�@
�G�w�̐��E�E��l�@�@�@


| ���X�͊� (ice age) 1 | |
|
�n���̋C�����ɂ킽���Ċ��≻������ԂŁA�ɒn�̕X����R�n�̕X�͌Q���g�傷�鎞��ł���B�X�͎���(�Ђ傤��������)�A�X��(�Ђ傤��)�Ƃ��Ă��B�܂�ɕX�͋I�Ə�����邱�Ƃ����邪�A�n��������敪����P��(�I)�ł͂Ȃ����ߐ������Ȃ��B
�X�͊w�I�ɂ́A�X�͊��Ƃ������t�́A�씼���Ɩk�����ɕX�������鎞�����Ӗ����鎖�������A���̒�`�ɂ��A�O���[�������h�Ɠ�ɂɕX�������݂��錻��A��X�͖����X�͊��̒��ɂ��邱�ƂɂȂ�B�ߋ����S���N�Ɋւ��Č����A�X�͊��Ƃ������t�͈�ʓI�ɁA�k�A�����J�ƃ��[���b�p�嗤�ɕX�����g�債��������ɂ��ėp������(�A�W�A�n��͕X�������B��������Ȓn�тł������炵��)�B���̈Ӗ��Ō����A�Ō�̕X�͊���1���N�O�ɏI�������Ƃ������ƂɂȂ�B���̖�1���N�O�ɏI������o�������A�����ɂ���Ắu�Ō�̕X�͊��v�ƋL�ڂ��Ă��邱�Ƃ����邪�A�Ȋw�҂̑����͕X�͊����I������̂ł͂Ȃ��A�X�͊��̊��������u�X���v���I������Ƃ��A���݂�X���ƕX���̊Ԃ́u�ԕX���v�ƍl���Ă���B���̂��߁A�ŏI�X���I���ォ�猻�݂܂ł̊��Ԃ���X���ƌĂԂ��Ƃ�����B �����ł́A�X�͊��͕X�͊w�I�ȈӖ��Ŏg�p���A�X�͊��̒��̊���������X��(�Ђ傤���Aglacial)�A�X�͊��̒��̂��Ȃ�g�����������ԕX��(����Ђ傤���E����҂傤���Ainterglacial)�ƌĂԁB �ߋ����S���N�́A4���N����10���N�̎����ő����̕X�����N����A����ɂ��Ă͌�����������ɍs���Ă���B�e�X���ƊԕX���ł͂��ꂼ�ꕽ�ϋC�����قȂ�A�ŋ߂̕X���ł͔N���ϋC����7-8���ȏ�ቺ�����Ƃ����f�[�^�����邪�A�u�C�����x����X���v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���̊Ԃɂ����X���A���ԕX�����F�߂���B���[���b�p�ł͌Â�������u�M�����c�v�A�u�~���f���v�A�u���X�v�A�u�E�����v��4�X���ɋ敪����Ă���B �����N�P�ʂȂǂ̒Z���I����ł͂Ȃ��A����ɑ�ǓI�E�������I�Ɍ���Ɖߋ��n����ł́A���Ȃ��Ƃ�4��̑�X�͊����������B�ߋ��܉��N�̎����}�ɂ��đ�\�I�ȕX�͊��̍��ڂŌ�q����B ���̒����u�X�͎���v���d�v�Ȃ̂͐l�ނ̐i���ɕ��s���Ă��邩��ł���B�X�����K���ƊC�ݐ����ɒ[�ɉ��ނ��A����̑啔�����X�ɕ�����B���̂��ߓ��A�����������A���A����H���Ƃ����̏W�����̐l�ނɂƂ��ẮA�傫�ȑŌ��ł������B�l��(���l)�ɂȂ�O�͎��㐶���ł������炵�����A�X���̊��Œn�㐶�����n�߁A2�����s���J�n���l�ނƂȂ����Ƃ����̂��ʐ��ł���B �@ |
|
|
���X�͊����_�̋N��
���[���b�p�̎R�x�n�тɏZ�ސl�X�ɂƂ��āA�ߋ��ɂ͕X�͂����L�����Ă����Ƃ����͈̂�ʓI�Ȓm���ł���(Imbrie and Imbrie 25�y�[�W�ɂ͖R�����X�C�X�̃O�����[���X�͂̉ߋ��̍L����ɂ��� Jean de Charpentier �Ɍ�������Ƃ����p����Ă���)�A�N�������̃A�C�f�A�����o������ł͂Ȃ��BJ. Charpentier �͂��̐����x������؋����܂Ƃ߂������B1836�N�ɂ͗��_�����C�E�A�K�V�[�ɔ[�������A�A�K�V�[�́AÉtude sur les glaciers ��1840�N�ɏo�ł����B ���̍ŏ��̒i�K�Ō������ꂽ�̂͌��݂̕X�͊��̒��ʼnߋ����\���N�ɋN�������X���ɂ��Ăł���A�X�ɉߋ��̕X�͊��̑��݂ɂ��Ă͑z����������Ȃ������B �X���̏؋��͗l�X�Ȍ`�œ�����B�₪�����ꂽ����ꂽ��(�C��)�₻�̂悤�ȐZ�H��p�������Ă����Ɠ��̌`��̊�(�r�w��Ȃ�)�A�X�̖͂��[�≏�ӂɑ͐ς����p�I(�����[��)�A�Ɠ��̕X�͒n�`(�h���������A�X�͒J�Ȃ�)�A�u�e�B���v��u�e�B���C�g�v���̕X�͐��͐ϕ��ł���B�������J��Ԃ��N����X�͍�p���A����ȑO�̕X�͍�p�̒n���w�I�؋���ό`�E�������邱�Ƃʼn��߂������Ă���A���݂̗��_�ɓ��B����܂łɂ͎��Ԃ����������B �ߔN�ł͕X���R�A��C��͐ϕ��R�A�̉�͂ɂ��A�X���ԕX���̉ߋ����S���N�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B ����\�I�ȕX�͊� �ߋ��n����ł́A���Ȃ��Ƃ�4��̑傫�ȕX�͊����������B24���N�O����21���N�O���̌����㏉���ɍł��Â��X�͊�(�q���[���j�A���X�� Huronian glaciation)�����������Ƃ������Ƃ��čl�����Ă���B �؋����c���Ă�����̂ň�ԌÂ��̂�(�����㖖��)��7��5�疜�N�O����̕X�͊�(�X�^�[�e�B�A���X�� Sturtian glaciation(�`7���N�O)����у}���m�A�X�� Marinoan glaciation(�`6.4���N�O))�ŁA�ߋ�10���N�̂Ȃ��ł����炭�����Ƃ����������̂ł���A�X���ԓ��܂ŕ��������X�m�[�{�[���A�[�X(�S�n�������A�S������)�����o�����B���̕X�͊��̏I�����������N�����J���u���A�����̌����ɂȂ����ƌ����Ă��邪�A���̐��͂܂��V�������݂��_���̓I�ł���B �Ð���ɂ́A4��6�疜�N�O����4��3�疜�N�O�ɂ����ď����ȕX�͊�(�A���f�X−�T�n���X�� Andean-Saharan glaciation)������A�������Ð����3��6�疜�N�O����2��6�疜�N�O�ɂ����Ăɂ��X�͂̊g���(�J���[�X�� Karoo Ice Age)������A���̂Ƃ��ɂ͐����̑�ʐ�ł��N���Ă���B ���݂̕X�͊��́A4000���N�O�̓�ɂ̕X���̐����ɂ��n�܂�A300���N�O����N�����k�����ł̕X���̔��B�ƂƂ��ɋK�͂��g�債���B�X�V���Ɍ������ɂ�čX�Ɍ������Ȃ�A���̍�����X���̊g��ƌ�ނ̌J��Ԃ��ɂ��4���N��10���N�̎��������E���Ō�����悤�ɂȂ����B�Ō�̕X��(�ŏI�X��)�͖�1���N�O�ɏI�����B ���X���ƊԕX�� ���ꂼ��̕X�͊��ƕX�͊��̊Ԃɂ͐��S���N�������g�Ȋ��Ԃ�����������B�X�ɕX�͊��̊��Ԓ��ɂ�(���Ȃ��Ƃ��ŋ߂̕X�͊��ł�)��芦��Ȏ����Ƃ�艷�g�Ȏ���������B��芦��Ȏ������u�X���v�A��艷�g�Ȏ������A�Ⴆ�u�G�[�~�A���ԕX���v�̂悤�ɁA�u�ԕX���v�ƌĂ�Ă���B �ŋ߂̕X�����I������̂́A1���N�قǑO�ł���B���݂͓T�^�I�ȊԕX����1��2000�N�قǑ����Ă���ƍl�����Ă��邪�A�X���R�A�f�[�^�ɂ�鐸���Ȏ����̒f��͓���A���E�I�Ȋ��≻�������炷�V�����X�����Ԃ��Ȃ��n�܂�\��������B���̂Ƃ���u�������ʃK�X�v�������Ă���l�דI�ȗv���̕����A�~�����R�r�b�`�̋O�������̂ǂ̉e�������d�����낤�ƐM�����Ă��邪�A�n���O���v�f�ɑ�����ŐV�̌����́A�l�Ԋ����̉e���������Ƃ��Ă��A���݂̊ԕX���͏��Ȃ��Ƃ�5���N�͑������낤�Ƃ��������Ă���B �X���ƊԕX���̕ϓ��Ɋ֘A���āA�A�����J���h���Ȃ����ƂɈ˗����č쐬�����n�����g���̉e���ɂ���K�͂ȋC��ϓ���z�肵�����S�ۏ�ɂ��Ă̕�(Schwartz, P. and Randall, D. 2003)�̑��݂�2004�N�ɖ���݂ɏo�Ē��ڂ��W�߂��B����ɂ��ƁA�n�����g���ɂ��C���̕ω��������ŁA�k�����ł�2010�N���畽�ϋC����������n�߁A2017�N�ɂ͕��ϋC����7�`8��������Ƃ����B�t�ɓ씼���ł́A�}���ɉ��x���オ��A�~���ʂ͌���A��鯂Ȃǂ̎��R�ЊQ���N����Ƃ����B �@ |
|
|
���X�͊����N���錴��
�����3�̗v�� �Ȃ��u�X�͊��v���N����̂��B����͑傫�ȃX�P�[���ŋN����X�͊��ɂ��Ă��A�X�͊��̒��ŋN�����菬���ȕX��/�ԕX���̌J��Ԃ��ɂ��Ă��A���܂��c�_����Ă�����ł���B��ʓI�ȑ��ӂƂ��ẮA��C�g��(���ɓ�_���Y�f�ƃ��^���̃t���N�V����)�ƁA�u�~�����R�r�b�`�E�T�C�N��(�p���)�v�Ƃ��Ēm����A���z�����n���̋O���v�f(�����炭��͌n����鑾�z�n�̋O�����W����)�A�嗤�̔z�u�̑g�ݍ��킹�A��3�̗v�f���g�ݍ��킳�ꂽ���̂����̌����Ƃ���Ă��� ����C�g���̕ω� 3�̗v���̂����A�ŏ��́u��C�g���̕ω��v�͓��ɍŏ��̕X�͊��ɂ��ďd�v�Ȍ����Ƃ���Ă���B�X�m�[�{�[���A�[�X�����ł͌��������̑�K�͂ȕX�͎���̎n�܂�ƏI��́A��C���̓�_���Y�f�Z�x�̋}���Ȍ����ƁA�}���ȏ㏸�������ł���Ǝ咣���Ă���B�c��̓�̗v�f�ɂ��ẮA���ݍł��c�_������ɍs���Ă���B ���嗤�̔z�u �k�Ɍ��Ɠ�Ɍ��ɑ嗤���ǂꂾ���z�u����Ă��邩���A�X�͊����N����ۂɏd�v�ł��邱�Ƃ��킩���Ă����B���ɁA�V����X�͊����n�܂��������͑嗤�̔z�u�̕ω��ɂ��Ƃ��낪�傫���Ƃ����B����́A�嗤�̑��݂ɂ���Ċ�����ɐ��X���W�ς��邱�Ƃ��\�ɂȂ�A���̌��ۂ̓A���x�h���ʂ̂悤�Ȑ��̃t�B�[�h�o�b�N���ʂ̈������ƂȂ邩��ł���B�܂��A�嗤�̔z�u�͊C�m���C�̏z�V�X�e���ɂ��傫�ȉe����^����B ���V����X�͊��J�n�̌��� �V����̕X�͎��オ�n�܂��������̑傫�Ȃ��̂Ƃ��ē�ɑ嗤�̈ړ�������B������ɃS���h���i�嗤�̈ꕔ�ł�������ɑ嗤�̕���Ɠ�ւ̈ړ��ɂ���ē�ɑ嗤�̊��≻���n�܂�A����Ɠ쉺�ɂ���Ĕ��B������Ɋ�����ɑ嗤�ւ̔M�A�����Ղ�悤�ɂȂ�X�Ɋ��≻��i�߂��B4000���N�O�ɂ͓�ɂ̕X���̐������n�܂�A3000���N�O�ɂ͋���ȕX���ŕ�����悤�ɂȂ����B���̌�A300���N�O������k�����ł��X���̔��B���n�܂������A���̌����Ƃ��ẮA�k�A�����J-���[���V�A�嗤�̔z�u�ɉ����āA�p�i�}�n���̌`���ɂ���K�͂ȊC���̕ω��A�q�}�����R���̗��N�ɂ���C�V�X�e���̑傫�ȕω�������Ă���B ���n���O���v�f�̕ω� �n���O���v�f�͒����ɂ킽��X�͊��ł͑傫�Ȍ����Ƃ͂Ȃ�Ȃ����A���݂̕X�͊��̒��Ō��݂ɋN�����Ă��铀���Ɨn���̌J��Ԃ��̃p�^�[�����x�z���Ă���悤�Ɍ�����B�n���O���ƃA���x�h�̕ω��̕��G�ȃp�^�[���ɂ���āA�X���ƊԕX���̓�̃t�F�[�Y���N����悤�ł���B �X�͊��ɂ��Ă͌��݂̕X�͊��A���ɍŋ�40���N�Ԃɂ��ďڂ����������ꗝ�����i��ł���B�ŋ�40���N�̃f�[�^�́A��C�g����C���A�X���ʂ̎w�W���L�^����Ă���X���R�A�̕��͂��瓾�邱�Ƃ��ł��邩��ł���B���̊��Ԃ͕X��/�ԕX���̌J��Ԃ����~�����R�r�b�`�̒�������(�~�����R�r�b�`�E�T�C�N��)�Ƃ悭�ĉ����Ă���̂ŁA���̐����Ƃ��ċO���v�f����ʓI�Ɏ�����Ă���B���z����̋����̕ω�(�O�����S��)�A�n���̍��^���A�n���̌X��(�X�Ίp)���������āA�n��������˗ʂ̕ω��ɉe����^���Ă���B���ɏd�v�Ȃ̂͋G�ߐ��ɋ����e����^����n���̌X���̕ω��ł���B���Ƃ��A�k��65�x�ɂ�����7���̑��z���̓��˗ʂ͌v�Z�ɂ��ő��25%(1����m������400W����500W)�ω�����Ƃ���Ă���B�Ă����������A�O�̓~�ɐς������Ⴊ�n���ɂ����Ȃ�̂ŕX���͑O�i����Ƃ����͍̂L���l�����Ă��邱�Ƃł���B���˗ʂ̂킸���ȕω��́u�O�̓~�̐Ⴊ���S�ɗn������āv�Ɓu���̓~�܂ŗn�����Ɏc��āv�̊Ԃ̃o�����X�߂���B���l���̌����҂́A�O���v�f�͕X���̊J�n�̈������ɂȂ�ɂ͎�߂���Ƃ��Ă��邪�A��_���Y�f�̂悤�ȃt�B�[�h�o�b�N�@�\�ł���͐����ł���B ���~�����R�r�b�`���̖��_ �~�����R�r�b�`�����́A�n���O���p�����[�^�[�̎����I�ȕω����X�͍�p�̋L�^�ɕ\������Ă���ł��낤�Ɨ\���������A�X��/�ԕX���̌��ɂǂ̃T�C�N���������Ƃ��d�v�ł���̂��ɂ��Ă͍X�Ȃ���������߂��Ă���B���ɉߋ�80���N�̊ԁA�X��/�ԕX�����J��Ԃ�������10���N���x�z�I�ł���A����͒n���O���v�f�̗��S���ƋO���X�Ίp�̕ω��ɑΉ����Ă��邪�A�~�����R�r�b�`�ɗ\�����ꂽ3�̎����̒��ł͂͂邩�ɂ����Ƃ��ア���̂ł���B300���N�O�`80���N�O�܂ł̊ԁA�X�͍�p�̎x�z�I�ȃp�^�[���́A�n���̌X��(�X�Ίp)�̕ϓ���4��1000�N�����ɑΉ����Ă����B��̎��������̂��̂���z���闝�R�͂܂���������Ă��炸�A���ݏd�_�I�Ɍ������s���Ă��镪��ł��邪�A���̉́A�����炭�n���̋C��V�X�e���̒��ŋN���鋤���ۂƊW����Ɨ\�z�����B ���ŐV�̌��� �]���̃~�����R�r�b�`�̐��ł�10���N�������x�z�I�Ȏ������ߋ�8�������Ƃ̐���������BMuller �� MacDonald ��̌����ł́A����͋O���̌v�Z��2�����I�Ȏ�@�Ɋ�Â��Ă��邩��ł���A3�����I�ȉ�͂��s���ΌX�Ίp�ɂ�10���N�����������Ǝw�E���Ă���B�ނ�́A�����̋O���X�Ίp�̕ω������˗ʂ̕ω����Ă���Əq�ׂĂ���A���l�ɑ��z�n�̃_�X�g�o���h�ƒn���O���Ƃ̌������e�����Ă���\���������B�����͏]������Ă������J�j�Y���Ƃ͈Ⴄ���̂����A�v�Z���ʂ́u�\������Ă����v�ŋ�40���N�Ԃɂ��ē����Ă���f�[�^�Ƃقړ������ʂ������Ă���BMuller �y�� MacDonald �̗��_�� Rial �ɂ�蔽�_����Ă���B ���ɂ� Ruddiman ��10���N�����������Ƃ��炵���������郂�f���Ƃ��āA2��3000�N�̍��^���̎����ɑ��闣�S��(�ア10���N����)�̕ϒ����ʂ��A4��1000�N��2��3,000�N�̎����ł����鉷�����ʃK�X�̃t�B�[�h�o�b�N���ʂƌ��т����Ƃ������������Ă���B �܂��A���̗��_�ł� Peter Huybers �ɂ�錤�����i��ł���A4��1000�N�����������D���Ȃ̂ł��邪�A���݂�2�Ԗڂ�3�Ԗڂ̎��������ł��X���ւ̃g���K�[�ƂȂ肤��C�[�h�ɓ����Ă���Ƃ������Ƃ��c�_���Ă���B���̌����ł́A10���N������8���N��12���N�̎��������ς���Ă�����̂�{���͍��o���Ă���̂ł͂Ȃ����ƈÎ����Ă���B���̗��_�͔N�㑪��̕s���m�������݂��邱�ƂƐ������������̖������̂ł��邪�A���݂̂Ƃ���L��������Ă���킯�ł͂Ȃ��B �@ |
|
|
���ŋ߂̕X���E�ԕX���ƍŏI�X��
��k�̑嗤�X���̔��B�ɂ��A�ŋ߂̕X���ԕX���ł͊C�������傫���ϓ��������Ƃ��m���Ă���(�����������k��ƒn�k�ϓ��̉e���������ł��Ȃ��Ȃ�)�B���������C�������ɂɕX���Ƃ��ČŒ肳��邽�߁A�n��̊C���̑̐ϑS�̂��������A���ʂƂ��Đ��E�I�ɊC�������ቺ����B���ɕX���̏I���ɔ����ėZ�𐅂��C�m�ɊҌ������ƊC�����͏㏸����B�_�f���ʑ̔�Ȑ��ɂ���Ď������X���ʂ̕ϓ��́A���ɐV��������ɂȂ�ɂ�āA���E�I�ȊC�����̕ϓ��f���Ă���Ƃ����ėǂ�(��L�u�ߋ����悻5�S���N�Ԃ̕X���ԕX���̕ϓ��v�O���t�Q��)�B���̕ϓ����͍ŋ߂̕X���ł�100m�ȏ�ɂ���ԁB ���{�ߊC�ł́A�����m�Ɠ��{�C�����ԊC���̐[�x�����߁A���Ȃ��Ƃ��ߋ����\���N�̊Ԃ̕X���ł́A�C�����̒ቺ�ɔ����đΔn�g���̗������~�܂�A�C��ɑ傫���e����^�����B�X���ɂ͊��≻�̂��߂Ɉ����їт������{�܂ŕ��z���Ă����B�܂��A�Δn�g�����������Ȃ�����(���݂̓��{�C���̍~��͑Δn�g���̏����ʂɉe������)�X�͓͂��{�A���v�X����іk���{�̍��n�ɂ킸���ɔ��B����݂̂ł������B����ł��A�����̕X�͂��ŏI�X���Ɍ`�������J�[������[���Ȃǂ̕X�͒n�`�͌��݂̓��{�A���v�X������R���Ŗ��ĂɊm�F���邱�Ƃ��ł���B �ł���̕X���͍ŏI�X���Ƃ��Ă��B�ŏI�X���̏I����A�l�ނ���Z���_�Ƃ����W����Ƃ����o�������N�������B���̂��Ƃ͔_�Ƃ̔��B���l�ނ̐����l���Ɛ[���W������Ƃ������Ƃł��낤�B �����X���ƈ��ԕX�� �X���������͊ԕX���������ԂɁA�X�ɍׂ��ȋC��̕ϓ��������邱�Ƃ�����B�������������X�� (stadial)�A���g�Ȏ��������ԕX�� (interstadial) �ƌĂԁB�ŏI�X���I���O�ォ�猻�݂ɂ����Ă̓��[���b�p�̓D�Y���n�Ŕ������ꂽ�ԕ��w���������Ηp�����A���݂ł͍ŏI�X���I���`��X���ɂ����Ă̋C��ω���\������ۂɕ��L���g���Ă���B �@ �@ |
|
| �����݂͑�4�X�͊��̊ԕX�� | |
|
����ȏ�ɒg��������ł��������Ɏc�������Ẩi�v���y���A�J�i�_�k���Ō��������B�k�Ɍ��ɍL����i�v���y�͒n�����g���ʼn�����ƁA��ʂ̓�_���Y�f�����o���ꈫ�e�����S�z����Ă���B�g���Ȏ���ł������Ȃ����y�����݂��邱�Ƃ́A���g���ɔ����e���]���̌������ɂȂ���\��������Ƃ����B���������̂̓J�i�_�E�A���o�[�^��̌����`�[���B
�ăA���X�J�B�ɋ߂��n��ŁA���̎��ӂ͔����ȏオ�i�v���y�ɕ����A�X�̌����͐��\���[�g���ɋy�ԁB�����`�[����7�N�O�A���̉i�v���y���������B ����A���y�Ɋ܂܂�Ă����ΎR�D����ː��N��@�ő��肵�A��74���N�O�ɂł������Ƃ�˂��~�߂��B�n���̋C��́A�C���������ԕX�����10���N�Ԋu�ŌJ��Ԃ��Ă���B���ɁA��12���N�O�̊ԕX���͍����C�������x�������A�C�ʐ��ʂ�8���[�g�����������Ƃ����B �����`�[���́u�i�v���y�͊C�X��X�͂ɔ�ׂāA�z���ȏ�ɉ����ɂ����B���g���e�����ł��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����A�����̋C��ϓ��̗\�����x�����コ���邽�߁A����ɒ������K�v���v�Ƃ��Ă���B ���g���Ŗk�Ɍ��̉i�v���y�������A��������Ȃǂ̉e�������O����Ă���B�������A�A���X�J�ł̊ϑ��ł͗\�z�ȏ�ɉ����Ă��Ȃ��B����̔����܂��A�e���]���̐��x�����߂邱�Ƃ����߂���B �@ |
|
|
���V�x���A�̉i�v���y�����^���K�X����o
�������ʃK�X�̈��ő��z�M�̕ߑ���������_���Y�f����20�{�ȏ㍂�����^�����A�V�x���A�̉i�v���y������o����Ă���B�i�v���y�͊�{�I�ɐ��S�N���琔��N�ȏ�P��I�ɓ������Ă���y��ŁA���̑�����1���N�O�ɏI�������ŏI�X���ȍ~�A��������Ԃ�ۂ��Ă���B�����A�V�x���A���݂̊C���ʂ͌��݂������悻100���[�g���Ⴂ�ʒu�ɂ���A��C�ɂ��炳�ꂽ��n�͒n��500�`700���[�g���܂Ōł�����t���Ă����B�n���S�̂̕��ϋC���͎Y�Ɗv���ȍ~���悻0.7�x�㏸���Ă��邪�A���V�x���A�k�ɗ��I�ł͏t�̋C�����ő�5�x�㏸���Ă���B�C��̉i�v���y�w�����^���n�C�h���[�g��V�R�K�X������߂�t�^�ƂȂ��Ă������A���^���������ɂ���R��o�����Ƃ͂Ȃ��Ƒz�肳���B�������A�n�����g���̉e���ɂ��A���^������C�ɕ��o����n�߂Ă���\��������B��ʂɁA�ԓ����痣�ꂽ�n��̕������g���̉e�����傫���A���ɖk�ɂł͉��g�����}���ɐi�s���Ă���B �@ |
|
|
��6��3500���N�O�ɋN�������g���̌����̓��^���H
��6��3500���N�O�Ɂu�X�m�[�{�[���A�[�X(�S�n������)�v���I������U���́A�������ʃK�X�ł��郁�^���̑�ʕ��o�������Ƃ������������\���ꂽ�B�X�m�[�{�[�����_�ɂ��ƁA���Â̒n���ɂ͕X�����ԓ��܂ŕ����s�����ꂽ��Ԃ̕X�͎��オ�������B�u�X���̉��ɕ����߂�ꂽ���^���́A���̉��x�ƈ��͂̉��ł͕X��ɂȂ��Ĉ��艻����v�ƁA���̌������s�����J���t�H���j�A��w�̒n���w�ҁA�}�[�`���E�P�l�f�B���͏q�ׂ�B�������A�X���͖{���I�ɕs����ł���A���̑傫���ɒB����ƕ��n�߂�B�ԓ��̕X�����������ƂŁA�����߂��Ă������^�����������Ēn���̉��x�������グ���B���̉��x�㏸�ɂ���Đԓ�����⍂���ܓx�̕X�����n���n�߁A���^���̕��o�ʂ��������āA�n���̉��g�������������B�P�l�f�B���̃`�[���́A��6��3500�N�O�ɂ͐ԓ��t�߂Ɉʒu���Ă�����I�[�X�g�����A�B�̊C�m���琔�S�̑͐ϕ��̃T���v�������W���ĕ��͂������ʁA�X���̗Z���ƃ��^���w�̕s���艻�𗠕t���邳�܂��܂ȉ��w�I���Ղ������B����A�J���t�H���j�A��w�X�N���b�v�X�C�m�������̌Ð����w�҂ł��郊�`���[�h�E�m���X���́A���݂̃��^�������ʂ͖c��ł���A�C��ϓ��Ɗ֘A�����Ėڂ����点��K�v�����邱�Ƃɂ͓��ӂ�����̂́A�P�l�f�B�����咣����悤�ɑ��Â̒n���ƌ���̉��g�������ѕt���鍪���͎ア�Ƃ��w�E���Ă���B �@ |
|
|
�����݂͑�4�X�͊��̊ԕX��
�X�͊����̊��������Ɖ��g�Ȏ���(�ԕX��)�̊Ԋu�ɂ͎�����������A���炩��10���N�����̋@�B�I�ȃ��J�j�Y���������Ă��邪�A����̓~�����R�r�b�`�E�T�C�N���ƌ����V�̉^���̎������ɂ���������Ă���B�b�n2���g�����ō����E�݂̂�Ȃ��呛�����Ă��邪�A�Ō�̑�l�X�͊����n�܂����̂�10���N�O�Ȃ̂Ń~�����R�r�b�`�������������Ȃ�A���̑�ܕX�͊��͂��n�܂��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�~�����R�r�b�`�̐��́A�n���̌��]�^��(�n���̌X���◣�S��)�̕ω��ŁA���z����n���ɓ͂��t�˗�(�M��)���ω����邽�߂��Ƃ������̂ł��B�b�n2�n�����g�����́A�n�\����F���ɓ����Ă����t�˗�(�M��)�������l�������ŁA���g���ŊC���ʂ��g�߂��_�ʂ�������Ƒ��z����̒n���ɓ����Ă����t��(�M��)������Ƃ����悤�Ȏ��͍l���Ă��Ȃ��悤�ł����A�܂��Ă⑾�z����n�������M�ʂ̕ω��Ȃǂ͑S���l���Ă��Ȃ���G�c�Ȃ��̂ł��B�ߋ��̐l�ނ̗��j�ŋN�������w���≻�x�́A��ԎR�̑啬�̂悤�ȑ�ʂ̕��o�������グ��V�ϒn��(���z������t�˔M�̌���)�Œn�������≻�����\�L�̑�Q�[�������N�����Ă����B�j�푈�ł̑��(��ʂ̂b�n2����o)�⊪���オ�������o�Łw�j�̓~�x���N����Ƃ����J�[���E�Z�[�K���̍l���������ۂɂ������ߋ��̗��j���Ȋw�I�Ɍ����ďo���オ���Ă���̂ł��傤�B �@ |
|
|
���~�����R�r�b�`�E�T�C�N��
�Z���r�A�̊w�҃~�����R�r�b�`(1879�N�`1958�N)�́A�n���̎��]���̌X������]�O���̕ω����A���z����̓��˗ʂ̕ω��������A���ꂪ�X���̌����ƂȂ�Ƃ�������������(1920�N)�B�n���̎��]���͍��Ƃ�����U��^�������Ă���B���̎�����26000�N�ł��邪�A���~�ł���n���̌��]�O���̒���������22000�N�����ŕω����邽�߂ɁA���˗ʕω��̎�����23000�N��19000�N�ɂȂ�B�܂��A���݂̒n���̎��]���͌��]�ʂɐ����Ȍ����ɑ���23.4���X���Ă��邪�A���ꂪ41000�N������22���`23.5���̊Ԃŕω�����B����ɁA�n���̌��]�O���̗��S����10���N��40���N�̎����ŁA0.005�`0.0543(���݂�0.0167)�ƕω�����B���������ω����g�ݍ��킳���āA�n������鑾�z�G�l���M�[���ω����邱�ƂɂȂ�B1970�N�ォ��n�܂����[�C��̑͐ϕ��̌�������~�����R�r�b�`������������邱�ƂɂȂ����B����͕��ː����ʌ��f��p�����N�㑪��̐��x�̌���A�_�f���ʑ̔��p�����ÊC�����̐���Ȃǂɂ���āA�������Ƀ~�����R�r�b�`�̗\�z�ʂ�̎����ł̋C��̕ϓ���������悤�ɂȂ����̂ł���B �@ |
|
|
���X�͊��̃~�����R�r�b�`����
�n���̎��]�͈��ł͂Ȃ��A���]���̌X�����A�����N�̎����ŕω����邵�A�n�������z�̎���������]�O��(�ȉ~�`)���A��10���N�̎����ŕω�����B�����̕ω��ɍ��킹�A�n���Ƒ��z�Ƃ̋������ω�����B���̕ϓ����͂��悻10���N�����ŕϓ����A�@�����41���N�ł��ϓ����Ă���B�n���̌X����O���̗��S���ɂ��n���̓��˗ʂ��ϓ�����B�����āA���̕ϓ�������4�D1���N�ł��鎖������o�����B�ŐV�̕X���Ő����́A1�D8���N�O�ŁA8���̓��{�t�߂̊C�����́A���݂��7�x�ʒቷ�ł������炵���B�q�v�V�T�}�[��(������)�́A���{�ł͓ꕶ����̑O�������悻�A3�E4��N�O�̎����ŁA�{�B���k���ŖL���ȓꕶ�������h�������p�̓�����t�߂ɑ��ʃT���S�����炵�Ă����B���݂ɐ��E�ł́A���̖L���ȍ����̎����ɃG�W�v�g�≩�͓��̐��E�̎l�啶�������܂�Ă���B�܂��C�ʂ����݂��5�b�߂������A���̍��ՂƂ��ēꕶ����̊L�˂��������ő�����������Ă���B�����E��セ�̑��̓s�s���A�قƂ�NJC�̒�ɂȂ邪���݂����ɓs�s������Ƃ������́A�n��������������Ăї₦�n�߂Ă���؋��ł���B�n���K�͂ł̑傫�ȉ��x�ω��́A�e�n�Ɉُ�C�ۂ�p�ɂɋN��������B |
|
|
�����݂͕X�͎���
�Ȋw�I���ނƂ��Ă̕X�͎���Ƃ́A�ɒn���ɕX�͂����݂��Ă��鎞��̂��ƂȂ̂ŁA��165���N�O���獡���݂܂ł̒n���́A�n���̗��j�̒��ł͊���Ȏ���(�X�͎���)�Ƃ���Ă���B���݂͑嗤�̕X��(�X��)�����n��10���ł��邪�A�͂邩�ɍL�����n��30�����X�͂ɂ�����ꂽ�X��(�X�͎���̒��ł��Ƃ��ɋC�����ቺ���Ă��鎞��)���傫�Ȃ��̂�4��K��Ă��������킩���Ă���B�X���ɂ͒n����̐����X�Ƃ��đ�ʂɌŒ肳��邽�߂ɁA�C���ʂ��ő��150m���x�Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ�����B�X���ɂ͒n���S�̂�4���`5�����x�C�����ቺ���āA���{�͂قƂ�ǃA�W�A�嗤�Ɨ������ɂȂ�B���E�I�Ɍ���ƁA�X�J���W�i�r�A������k���[���b�p�A�k�A�����J�ܑ̌�Εt�߂܂ł��X���ɂ������Ă��āA�C�ݐ������݂�肩�Ȃ��ނ��Ă����B�X���ƕX���̊Ԃ��ԕX���Ƃ����A�Ō�̕X���͖�1���N�O�ɏI���A���݂͎��̕X���܂ł̊Ԃ̊ԕX���ł���ƍl�����Ă���B�n��������ɂȂ�A�ɒn���ɕX�͂����B�����̂͌��݂���ł͂Ȃ��A�ߋ��ɂ����������B��J���u���A�����23���N�O�A8���N�`6���N�O�A�Ð���̃I���h�r�X�I(4.4���N�O)�A�Ð���̃f�{���I�`�ΒY�I(3.77���N�O�`2.7���N�O)���X�͎���ł������B�����N�̒������Ԃ̊ԂɁA�X�͎��オ�Ȃ��K��A�܂��Ăђg�����Ȃ�̂��ɂ��ẮA���z�����̕ω��A�n���̎��]�E���]�̕ω��A�v���[�g�̉^���ɂ��嗤�̔z�u�̕ω��A��C���̓�_���Y�f�̗ʂ̕ω��Ȃǂ��l�����邪�悭�킩���Ă��Ȃ��B�~�����R�r�b�`�E�T�C�N���͕X�͎���̒��̕X���|�ԕX���Ƃ��������N�`���\���N�Ƃ����X�P�[���ł̕ϓ����l�����ł͏d�v�����A��K�͂ȕX�͎��オ�K�ꂽ��A�܂����X�͎���(�ɒn���ɂ��X�����Ȃ�����)�ɖ߂�����Ƃ����ω��͐����ł��Ȃ��B �@ |
|
| ���X�͊� 2 / �C��̈ڂ�ς�� | |
| ���X�͊� �@ | |
|
���[���b�p�ł͕X�͂̐i�o�������オ���������݂��Ă��邱�Ƃ��A��������m���Ă��܂����B�C��ω��̗���̒��ŁA�V����Ɏn�܂����A����߂Ċ���Ȃ������̊��Ԃ�X���ƌĂт܂�(��ʂɂ͕X�͊��Ƃ������Ă��܂�)�B�܂��X���ƕX���̊Ԃ̊��Ԃ��ԕX���Ƃ����܂��B���ꂼ��̎���̕X���̌Ăі��ɂ͂��낢�날��܂����A�����ł̓��[���b�p���ŌĂԂ��Ƃɂ��܂��B��v�ȕX���́A��ʓI�ɉ��Ɏ�����4���L���m���Ă��܂��B�X���̖��̂ƁA���̂����悻�̊��Ԃ��܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
���M�����c�X���FGunz glaciation(410,000�N�`310,000�N�O) ���M�����c���~���f���ԕX�� ���~���f���X���FMindel glaciation(240,000�N�`220,000�N�O) ���~���f�������X�ԕX�� �����X�X���FRiss glaciation(125,000�N�`100,000�N�O) ���G�[�~�A���ԕX��(���X�����������ԕX��) �����������X���FWurm glaciation(70,000�N�`18,500�N�O) ���̂����M�����c�X���ƃ��������X���͒����āA�O���ƌ���ɓ��Ɋ���Ȏ���������A���ꂼ�ꏉ���X���A��v�X���Ƃ��Ă��܂��B�ŋ߂̕X����18,500�N�O�ɏI���������������v�X���ł����A������ŏI�X���Ƃ����ΌĂԂ��Ƃ�����܂��B���݂͂���ɑ����A�ԕX���ɂ����鎞��ł���ƁA��ʓI�ɍl�����Ă��܂��B �����̕X���́A�~�����R�r�b�`�T�C�N���ƌĂ��n���̓����̕ω��̎��������������ƂȂ��āA���������̂ƍl�����Ă��܂��B�n���̌��]�̋O���͑ȉ~�ł����A���ꂪ���Ⴐ����^�~�ɋ߂��Ȃ�����̕ϓ�������Ԃ��Ă��܂��B���̋O�����ւ��Ⴐ��قlj����_�ł̑��z����̓��˂͂��Ȃ菭�Ȃ��Ȃ�܂��B�܂����]�̒n������������ŌX�����藧�����肵�܂��B���̂����鉩���X�Ίp���}�ɂȂ�A�܂�n�������]�ʂɑ��ē|�ꍞ�ނقǁA�Ă��~���������Ȃ��āA�G�ߕϓ��̃R���g���X�g���͂����肵�܂��B����ɍ��^���ɂ��ω��ɂ���āA�嗤�̑����k�����̓~���A���Ƃ͋t�ɉ����_�ɏd�Ȃ�ƁA�k�����̑嗤�ɂ͕X�������B���₷���Ȃ�܂��B���̕X���͑��z����̌��̔��˗��A�܂�A���x�h���������z����̕��˂��悭���˂��܂����A�������g�͗n���ɂ������̂Ȃ̂ł��B���z����̕��˂��������˂����قǒn���ɓ��鑾�z�̃G�l���M�[���������A�n���̊��≻���������ƂɂȂ�܂��B�����Ă���Ȃ�X���̔��B�ւƂȂ����Ă����܂��B�~�����R�r�b�`�T�C�N�����������A���̂悤�Ȑ��̃t�B�[�h�o�b�N�����������Ƃɂ���āA�X�������������̂ƍl�����Ă��܂��B ����ɕX�������B�������߁A�C�ʂ͍�����100m�A���邢�͂���ȏ�ቺ���Ă����ƌ����Ă��܂��B�X���́A���Ƃ��A�����J�嗤�Ȃ�Ό��݂̃J�i�_�̍��y���������ۂ�ƕ������炢�ɍL�����Ă��܂����B���̌�����3km�ɂ��y�Ƃ������Ă��܂��B�A�����J���O�����͓암�������Ă��ׂĖk���тŕ����A�암���j�t���ђn�тƂȂ��Ă������Ƃ��킩���Ă��܂��B ���{�͂ǂ����Ƃ����܂��ƁA�k�C���̔����ȏ�ɂ̓c���h�����L����A�G�]�}�c��g�E�q�Ȃǂ���Ȃ鈟���ѐj�t���ёт����k���琼���{�̎R�n�ɂ܂ŕ��z���Ă����Ƃ݂��Ă��܂��B�֓����琼���{�̕��n�̍L���͈͂ɂ͗≷�ї��t�L�t���ёсA�܂�u�i�Ȃǂ��ǂ��܂ł��������Ă����Ƃ݂��܂��B�V�C�A�J�V�A�N�X�m�L�A�^�u�m�L�Ƃ����������Ō�������t��N�������͏Ɨt���ƌĂ�Ă���A���݂͐����{�̎��R�тɑ��������܂��B�������ŏI�X���ł��������̂���́A��q���E���v��������ɍׁX�Ƃ������ɉ߂��Ȃ������悤�ł��B���݁A���Ƃ��Α�\�I�ȏƗt���ł���^�u�m�L�̖k���̒n�́A�H�c���̓암�́A��ɒT���ŗL���Ȕ������т̌̋��ł���A���Y�Ƃ�����(���E�ɂ��َs)�ł��B�悭�l���Ă݂܂��ƁA���̍ŏI�X�������́A��B�̓�̒[���A���݂̏H�c���̓암������̋C��ɑ��������ƁA�P���Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B�Ȃ��A�����͊C�ʂ��Ⴍ�Ȃ��Ă��邽�߂ɁA�����̓��{�͒��N�����A�����ăT�n��������đ嗤�Ƃ��n���ł������A���˓��C�����݂��܂���ł����B �@ |
|
| �������K�[�h�D���A�X�� | |
|
12000�N�O�ɂȂ�ƁA�Ă̑��z����̕��˗ʂ�7���������C��͉��g���̕��Ɍ������܂����B�A�����J��[���b�p�Ȃǂ̕X���͗n���A�A���͖k�ցA�k�ւƈړ����Ă����܂����B��_���Y�f���������A�����I�ȉ��g�Ȏ��オ13000�`11000�N�O�Ɍ����܂����B���̉��g���̂��Ƃ��A�k���ł͂Ƃ��ɃA�����[�h(Allered)���Ƃ��������ł��B
�Ƃ��낪���̂��ƁA�}���ɉ��x��100�N�Ԃŕ���6�����x���������������������܂����B���̊������11000�`10720�N�O�̂킸��280�N�Ԃ̊Ԃɐ������Ƃ���Ă��܂��B���̎����̓����K�[�h�D���A�X(Younger-Dryas)���ƌĂ�Ă��āA���{�ɂ����݂��Ă������Ƃ��������Ă��܂��B���̎����ɂ͍ĂѕX�������������B����ȂǁA�X���̏�Ԃɋt�߂肵�܂����B�Ƃ��낪���̃����K�[�h�D���A�X���̖���(10720�N�O)�ɂ́A�Ȃ��50�N�Ԃ̊Ԃ�7���̉��g���������A���̊�������I������Ƃ���Ă��܂��B ���̌������߂����āA�Ȃ��炭�_��������܂����B�n���̓����A�ΎR���A�������ʃK�X�Z�x�̕ω��A�C���̕ω��Ȃǂ��낢�댾���Ă��܂������A���݂̂Ƃ���A�C���̃p�^�[���ω����Ђ��N�������Ƃ������Ɯa���̂悤�ȓV�̂��n���ɏՓ˂������Ƃɂ��_�X�g�E����ɂ����˂̎Օ���2�̐��ɍi���Ă���悤�ɂȂ�܂����B �܂��͊C�����ɂ��āB�C���ɂ́A������e���Ƃ��Ēm����悤�ȊC�ʕt�߂ɑ��݂��闬��̑��A�C�ʂ���800m�ȏ�[���ꏊ�𗬂��[�w�C���Ƃ�����̂�����A����2�̗��ꂪ�g�ݍ��킳�邱�Ƃ���āA�C���͗��̓I�ɏz���Ă��܂��B�O���[�������h�ߊC���X�m�ŊC�X���ł���ۂɂ́A�C���̂������̐����̕�����ɓ���A����Ȃ������c��̉����̍����C�����A���x���Ⴂ���Ƃ������Ĕ�d���傫���Ȃ�A����ɊC�̒�[���ɒ��ݍ��݂܂��B���̉����̔Z���ė₽���C���͊C����悤�Ɉړ����A�O���[�������h���̊C��𗣂�Ė�1200�N��Ɉ�x�m�C��ցA�܂�2000�N��ɑ啽�m�C��ɒB���܂��B�����ŕ����������ׂ̈ɊC��̊C�������㏸���A�C�ʋ߂��ɕ����オ��B�����Ă��̊C�����g�߂�ꂽ��ɁA�C�ʋ߂��̊C���ƂȂ��Đԓ��t�߂̔M�G�l���M�[����݂₰�ɍĂѓ�ɁE�k�ɂA���čs�����܂��B���̏z�͈�ʂɃR���x���[�x���g�ƌĂ�܂��B �X���ɂ͖k�đ嗤�ɕX�����傫���L�����Ă܂������A���g������ɂ�Ă��ꂪ�n���A���̐������ܑ̌�Εt�߂ɗ��܂��ċ���Ȍ��`����Ă��܂����B�Ƃ��낪������13000�N�O�A���������������ΐ��ɑς����˂Č̎��ӂ����ׁA��ʂ̐^�����k�吼�m�E�O���[�������h�ߊC�ɗ��ꍞ��ł����܂����B�����Ȃ�ƊC�������܂�A�����Z�x���Ⴍ�Ȃ�܂��B���ꂪ���������ŗ₽�������C��ɒ��ݍ��܂Ȃ��Ȃ�A�n���S�̂̃R���x���[�x���g�����サ�Ă����A����ɂ���2000�N��ɂ͊��S�ɂ��ꂪ��~�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ���܂����B�R���x���[�x���g����~����ƁA�k�ɁE��ɂɌ������āA�ԓ��߂�����̔M�G�l���M�[���^��ɂ����Ȃ�A�ɂɋ߂����ܓx�n���͓��R�����Ȃ�܂��B�����Ȃ�ƕX�������B���A�n���S�̂ł݂��A���x�h�������Ȃ��čX�Ɋ��≻���A�Ƃ������X���Ɠ��l�̈��z�ɗ������Ƃ݂��Ă��܂����B ����̜a���̏Փ˂̐��ɂ��āB�a�����Փ˂���ƒn�\�̂��̂������グ��ꂽ��A�Ђɂ�蔭�������X�X�Ȃǂ��������A���ꂪ���z����̓��˂��Ղ邱�ƂŊ��≻���Ђ��N�����܂��B�ǂ��m��ꂽ��Ƃ��ẮA������6500�N�O�Ƀ��L�V�R�̃��J�^�������t�߂ɔ����������V�̂̏Փ˂ƁA����ɂ���Ĕ��������}���Ȋ��≻�ɂ���ċ����𒆐S�ɂ�����ʐ�ł��������܂��B�Ƃ��낪12900�N�O�ɂ����V�̂̏Փ˂��������Ƃ���_����2007�N�ɏo����A���ꂪ�c�_����т܂����B���V�̂��Փ˂��邱�ƂŁA���̂Ƃ��̃_�X�g�ɃC���W�E���Ƃ����������܂܂�邱�ƂɂȂ�̂ł����A�k�Ă𒆐S�ɂ��̕�����12900�N�O�̒n�w���瑊�����Ō���������A���̑w�ɃX�X�Ȃǂ���ʂɑ��݂��邱�Ƃ���A���̏��V�̂��A�n�\�ɏՓ˂܂��͋������N���������Ƃ́A�قڊԈႢ�Ȃ��Ƃ����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�Ƃ������ƂŁA�ŋ߂͂�����̏��V�̏Փ˂������K�[�h���C�A�X�����Ђ��N�������Ƃ����悤�ɁA������Ђ�����Ԃ邱�ƂɂȂ�܂����B �����K�[�h�D���A�X���ł́A�C��̊��≻��6���^100�N�A���g����7���^50�N�ƁA�}���ȕω����������Ƃ����Ă��܂��B���̂���n����ɐ����Ă���A�������܂������̂ł͂���܂���B�����K�[�h�D���A�X���ɓ���ƁA�k�����[���b�p�ł͂���܂Ő����Ă����g�E�q��V���J���o���A�����Ƃ����ԂɁA��芦��Ȓn���ɐ��炷����{�ɒu����������ƌ����Ă��܂��B�A�����J�ł����≻�Ǝ��������āA�L�t���̎�ނ��������A�����ăg�E�q��~�A�V���J���o�Ȃǂ��܂������Ԃɑ����������Ƃ��ԕ����͂��疾�炩�ɂȂ�܂����B����ɑ��A�����K�[�h�D���A�X�����I��������10000�`9800�N�O�ɂ́A�c���h���ɍĂуg�E�q�Ȃǂ̐A���������Ă����悤�Ɍ�����܂����A����͉ԕ������ɂ���ĉ^�ꂽ���Ƃɂ���F�̉\��������܂��B ���{�ł��A�����K�[�h�D���A�X�����I����Ă��ł�1000�N�o����9000�N�O�ɂ́A��㕽��▼�É��ߕӂ��A�g�����̎w�����猩��Ƃ��łɏƗt���т������Ă��ǂ������ƂȂ��Ă���̂ɁA���ۂ̐A���͋I�ɔ����̂������k�㒆�ł��������Ƃ��ԕ����͂��疾�炩�ɂȂ��Ă��܂��B����������A�C��̋}���ȉ��g���ɐA���̔���(�ړ�)���S�����Ă����Ă��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B�ԕ����͂ł́A���Ƃ��I�ɔ����암������܂ŁA���̌�A�Ɨt���ьQ�����g�傷��̂�3000�N���������Ƃ������ʂ������Ă��܂��B�܂�����ł͑�ォ�狞�s�܂ŁA�Ɨt���т��L����̂�100�N���������Ƃ����Ă��܂��B�w���V��������O���ցc�c�x�̋�����}�Ȃ�30���ő��蔲���鋗���ł��A���ꂾ���̔N����K�v�Ƃ���Ƃ������Ƃł��B���s�E���Ԃ�40km�Ƃ����ꍇ�A��ォ�狞�s�ւ̐A���̈ړ����x�͖��N400m�A�����ɒ�����4cm/h�B�x���悤�ł����A�A���̈ړ����x�Ƃ��Ă͈ٗ�̑����ł͂Ȃ��ł��傤���B �Ƃ͂����Ă��A�}���ȋC��̊��≻�ɂ͐A���̕��z�̉����͑z���ȏ�ɑ����̂ɑ��āA�}���ȉ��g���ւ̐A�����z�̉�����100�`1000�N�I�[�_�[�ŁA���Ȃ�������ƌ����Ă��܂��B���ɁA�k�C���̍������t�߂ɂ���u�i�̖k���́A���Ȃ��k�㒆�Ƃ���Ă��܂��B�@ |
|
| ���q�v�V�T�[�}����(�C��œK��) | |
|
6000�N�O�܂łɁA�S�n���I�ɉĂ̋C�������݂��2�`4���������Ԃ��n�܂����B���̍��A�Ă̑��z����̕��˗ʂ͌��݂��4�������A�~�͋t��4�����Ȃ��Ȃ�܂����B���_�����猩�����z�������A���̎����A���Ɋ����ł����B7000�`5000�N�O�܂ł̂��̉��g�Ȏ������q�v�V�T�[�}��(hypsithermal)���A���邢�͋C��œK(postglacial climatic optimum)���ƌĂт܂��B���̂���̕X���̒������k���ɂƂ��Ȃ��āA�X���ȗ��Ⴍ�Ȃ��Ă����C�ʂ͈�C�ɏ㏸���A���݂�萔m�����Ȃ�܂���(������ꕶ�C�i�ł�)�B���Â̖��v��(�x�R�p)�̂悤�ɁA�嗤�I���A������Ƃ����v�����ꏊ�������܂��B�A�t���J���璆�ߓ��͌��݂�葽�J�ŁA���݂̃T�n�������͐X�тɕ����Ă����Ƃ����Ă��܂��B���M�э��C���͖k�ɕ�A���ܓx�͌��݂�芣�����Ă����悤�ł��B
���{�ł͂��̍��A�N���ϋC����2�����x���������ƕ]������Ă��܂��B���{�ɂ�����q�v�V�T�[�}�����̋C��т����Ă݂܂��ƁA6500�N�O�ɂ͏Ɨt������������̂��\�ȁA�g�����̎w��85�ȏ�̒n��(�Ɨt���ыC��)���H�c�����݂܂ŒB���Ă��܂����B�܂��R�i���ɑ�\�����g���ї��t�L�t���ыC������k�n���̂قƂ�ǂ��܂ōL���邱�ƂɂȂ�܂����B���Ⓦ�C�n���̎R�ɂ���G�ؗт����k�Ō���ꂽ�킯�ł��B�A���̊g��E�k��͂��̉��g���ɂ͂Ȃ��Ȃ��t���Ă����Ȃ������悤�ł����A����ł�6500�N�O�ɂ͏Ɨt�����A�����{�̒�n�Ŕ����I�ɍL���邱�ƂɂȂ�܂����B���ɏƗt���ьQ���̊g�傪���B�����̂����̍��ł��B�܂��A�C���Ō����X�ь��E��300�`400m�㏸�����Ƃ���Ă��܂��B�@ |
|
| ���q�v�V�T�[�}����̊���� | |
|
�q�v�V�T�[�}���̌�A5000�`4000�N�O�ɂ͋C��͗���E���������A�~���ʂ��������܂����B���̏㒬��n�ȊO�̕�����A���É��̏���C��������ɂ�����L���n��͂��̎��܂ŊC�ł������A�~���ʂ̑����̂��ߎ��R�̖��ߗ��Ă��i�݂܂����A���ϕ���͂��̎����ɂł����Ƃ����Ă��܂��B���{�C���ŐV�����ł������ϒ�n�ɂ̓X�M�����ɑ������B���Ă������B�X�M�͎���������(�N�~���ʂŖ�1800mm�ȏ�)�Ŏ�������A���ł���B���܂͉J�̑����R�n�ɂ���݂̂ł����A�����A����ɂ��������Ƃ����̂ł�����A�����ɂ��̎����ɉJ�������������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B
���̌�A4000�`3000�N�O�ɂ͈�U���g�ƂȂ邪�A���̂���2500�`2000�N�O�ɂ́A���ɖk���{��R�A�A�k���ŗ���ȋC�����܂����B�@ |
|
| ��������� | |
| ���{�⒆���ł�3���I�`7���I�̊ԁA�V�������A������A�~���ʂ̑����������܂����B���̎����͒�������{�̗��j�̒��ł��헐�������������������ł��邪�A���̌��������������C��̗�������_�@�ƂȂ����Ƃ�������������܂��B�헐�A�����A�����ł͎O���u�̎���A���{�ł͘`���嗐�̎���ɂ����鎞��ł��B���{�ł͂��̎������Õ�������ƌ����ꍇ������܂��B����́A���z�������s�����ɂȂ��������ɂ���������v���܂��B�@ | |
| ���������g�� | |
|
����800�`1300�N�́A���ݕ��݁A���邢�͂���������鉷�g�Ȏ����ł����B���̌��ۂ͑S�n���I�Ɍ���ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B���̎����A���[���b�p�ł̓m���}���l���吼�m��n���ăO���[�������h�ɓ��A���܂����B�܂��A���̍��̑吼�m�ɂ͗��X���قƂ�nj����Ȃ������ƌ����Ă��܂��B�����̃A�C�X�����h�ł̓G���o�N�Ȃǂ̔��ނ��͔|�\�ł����B���̉��g���𒆐����g��(Middle Ages warm epoch)�ƌĂт܂��B���̂Ƃ��̑��z�����́A����1100�`1300�N�ɂ͌��ݕ��݂Ɋ����������Ƃ���Ă��܂��B100�N�I�[�_�[�ŋC�������ƁA���z�������ł��e�����Ă���悤�Ɍ�����B
�܂��}1�͐̂̓��L��N��L�ɂ���Ă킩�����T�N���̖��J��������v�Z�����A���s��3���̕��ϋC���̐��ڂł��B���̎���̓f�[�^�̐������Ȃ��̂Ő��x�͈������A����ł�����1200�N�𒆐S�ɁA�C���̍����������オ���������Ƃ��萫�I�ɂ킩��܂����B ���肵�����̎���͓��{�̕�������B�̂�т�Ƃ������オ�������̂��A���̒������g���̂��A�������̂�������܂���B���������A�����̋M���̊ق́w�Q�a����x�ƌĂ��A�����ɂ����ʂ��̂悳�����ȁA�Ƃ������͊������ȗl�������Ă��܂��B����Ȓ������g������������A�M���������ɑς���ꂽ�̂�������܂���B�@ |
|
| �����X�� | |
|
���z�̍��_�����Ȃ����Ƃ͑��z�������s�����Ȃ��Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B����1300�N�ȍ~�A���̑��z�̍��_���}�ɏ��Ȃ��Ȃ葾�z�������s�����Ȏ������J��Ԃ��Ă���Ă���悤�ɂȂ�܂����B���̎�����1320�N���A1460�`1550�N�A1660�`1715�N�A������1800�N�O��ł���B1320�N���̋ɏ������E�H���t�ɏ����A1460�`1550�N�̂�����X�y�[���[�ɏ����A�����ĂƂ��ɐ���1660�`1715�N�̂��悻70�N�Ԃ̑��z���_���قƂ�ǖ����Ȃ��������ȍ��_�ɏ����Ԃ��}�E���_�[�ɏ���(Maunder minimum)�A�܂���ԍŋ߂�1800�N�O��̒Z���ɏ������h���g���ɏ����ƁA���ꂼ��Ăт܂��B
����4�̎����́A�T�N���̖��J�����琄�肵�����s�̋C��(�}1)�̒Ⴉ���������Ƃ��Ȃ�V���N�����Ă��܂��B�T�N���̖��J���ɂ��3���̋��s�̋C���͓~�G�̋C���ɂ��Ȃ莗���X���������Ǝv���܂����A��͂�A���̑��z�����̕s�����Ȏ����́A���E�I�ȋC���A���≻������ꂽ����ƁA�S�ʂɈ�v�����悤�ł��B����1300�N�Ȍ�A1850�N�܂ł̂��̊��Ԃ��A���X��(Little Ice Age)�ƌĂт܂��B���̎����ɂ͊e�n�ŕX�͂̑O�i���N���܂����B���{�ł�����1300�N���߂���ƋC�����N����A�~���ʂ������āA�Z������Ȃǂł͉͓��ω����J��Ԃ����悤�ɂȂ�܂����B ���Ƀ}�E���_�[�ɏ����Ƃ��̎��̃h���g���ɏ����ɂ�����1600�`1850�N�̊����̒��x�͂��̂������A���X�������̎����Ɍ��肷��ꍇ������܂��B���̎����A���{�ł͑��A��Ă��������܂����B���삪���ߕӂŊ��S�ɕX���������Ƃ�����܂��B���͓̉��n���ł͂���܂Ő���ł������ȍ삪�A�C�≻�E�~���ʑ����ɂ��߂ɃC�l�E�i�^�l�ɓ]���]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ������Ă��܂��B���������A���̎����̑���オ��̌������ώ@�A�G�ɂ��Ă���Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B����Ȃ��ƁA����ł͖k�C���ł����ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�Ƃ�����A���̎����A�Ƃ���19���I�����͊��������悤�ł��B���{�ł͏��X���̂����ł��ł�����Ȋ��ԁA���Ƃ���1830�N���1980�N����ׂ�Ɠ~��t�̕��ϋC����2�����x�A���s�Ɍ����3.4�������݂����Ⴉ�����Ɛ�������Ă��܂��B�@ |
|
| ���ŋ߂̋C�g���͉��̂����H | |
|
���݁A�C�������19���I�̑O��(�O�߂ŐG�ꂽ�h���g���ɏ���������)�ȍ~�A�m���ɒg�����Ȃ��Ă��܂����B���A�ɊW�����@�ւł���IPCC�ɂ��ƁA�ŋ�100�N�ԂɁA�n���\�ʑS�̂ŕ��ς���0.6���قNjC�����オ�����ƕ���Ă��܂��B�����������g�����A�ʂ����ĂȂ����������A����̋C�ڂ͂ǂ��Ȃ邩�A����ɂ��ẮA�ŋ߁A�c�_���������Ă���悤�ł��B�l�܂鏊�A�w�n�����g���ɉ������ʋC�̂̔Z�x�㏸���ǂ�قNJ֗^������̂Ȃ̂��H�x�w���z�����̐������C��ϓ��ɋy�ڂ��e�����A����܂ōl�����Ă����ȏ�ɑ傫���̂ł͂Ȃ����H�x�Ƃ���������ŋc�_������ɓ��킳��Ă���Ƃ����邩������܂���B�Ƃ��ɍŋ߂ɂȂ��āA���z�����̐������y�ڂ��n����C�ւ̂��܂��܂ȉe�������X�Ɩ��炩�ɂȂ�����A���Ƃ��ďo���ꂽ�肵�Ă��܂��B
�Â�����A���z�����������ɂȂ�Ɠ��˗ʂ��������A�C�g���Ɍ��т��A�ƁA�����ė��܂����B�������A���̓��˗ʂ̕ϓ��̕��́A��������2���b�g�����Ē��x�A���z�萔��0.�����ɉ߂����A���ꂾ���ł͑傫�ȋC��ϓ��ɂȂ���Ȃ��Ƃ�������������܂����B�ŋ߂ɂȂ��āA���z�̐����ɂ���Ď��O���ʂ��ő�8�����ϓ����邱�Ƃ��킩��A���ꂪ��ܓx�E���ܓx�̂��ꂼ��̏㕔���w�����璆�Ԍ�������(��������50km���x)�̋C������傫���ϓ������邱�Ƃ��킩��܂����B�Ⴆ�Α��z�����������ɂȂ��āA���ŋz������鎇�O���������A�ܓx�ɂ��C�������傫���Ȃ�ƁA���x���A���̏ꍇ�͏��̃W�F�b�g�C���̋����������܂��B�����������̐������Ɍ��ꂽ�Ⴂ�����菄���āA�n��t�߂̋G�ߕ��̐����p�x�A�M�ѕt�߂̉_�̔��B�̂��₷���ȂǁA���܂��܂Ȗʂɉe�����o�ė��邱�Ƃ��킩���Ă��Ă��܂��B��������A���z�����������ɂȂ�ƋC���g�ɂȂ�����ɋ@�\���Ă����܂��B ���z�����ƒn���̋C��Ƃ̊֘A�ɂ��āA�ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B�܂����̒i�K�Ő����ɔF�߂�ꂽ�킯�ł�����܂��A�F�����̍~���ė���ʂ��ϓ����A�_�̗ʂ̕ϓ��Ɍq����A�Ƃ������̂ł��B���z����͑��z���Ƃ�����������v���Y�}�̗��q(�z�q�Ƃ��d�q�Ƃ�)���o�Ă��܂��B����͒ʏ�A�n��t�߂ɂ͍~���ė��܂���B�n���C�̂����Ŗk�ɁA��ɂɏW�߂��A�I�[�������������肷��݂̂ł��B�Ƃ��낪�F���ł͂����ƃG�l���M�[�������A��͂̒��S�t�߂���͂�����ė���Ƃ������͉F�����Ƃ������̂�����܂��B����̓G�l���M�[�������A���ʁA�n��߂�(�Η���)�܂ō~���ė��܂��B���̉F�����͑�C���q�ɂ�����ƕ��q���דd���A����ɂ���Ċ��W�܂�����C���q�̉�(�N���X�^�[�ƌ����܂�)���j�Ƃ��Ė����������܂�(�������āA���Z�̕����ŏK���܂������)�B���z�������s�����Ȏ��ɂ́A�n���̊O�̎��C�_���`�����鑾�z���̐��������ォ������A���z����̎��ꂻ�̂��̂��キ�Ȃ邭���Ƃ����Ȃ����ʁA�d�ׂ�тт���R�̋�͉F�������A���₷���n����C�A��������w�̑Η����܂ł���Ă��₷���Ȃ�A�_�𑽂�����������A�Ƃ������Ƃł��B�܂��t�ɑ��z�����������ɂȂ�ƁA���C��тт����z������R�ł���A���z���甭�����鋭������̂��߂ɁA�d�ׂ�ттĂ����͉F�������U��������悤�ɂȂ�A��͉F�������n����C�ɍ~���Ă��Ȃ��Ȃ�A�_�̂ł���ʂ����Ȃ��Ȃ�A���z���˂��n�ʂɓ͂��₷���Ȃ�����~���ʂ����������肵�Ēn��t�߂̋C�����㏸����Ƃ���Ă��܂��B���A���E�̂��܂��܂Ȍ����҂����z�⎥��E�F�����̊ϑ��A������Ȃǂ��g�������؎����A�Ê��̒������͌��ʂȂǂ�ʂ��āA���̃X�x���X�}���N�̐��̌����i�߂��Ă��܂��B �����܂Ōl�I�ӌ��Ƃ��āc�c �������ʃK�X�Z�x�㏸�����g���A�ƁA��ʂɂ̓C���[�W���ꂪ���ł����A���m�ȂƂ��낱�̔Z�x�㏸���A���ɋN���Ă��鉷�g���ɂǂ̒��x��^���Ă��邩���ʓI�ɍ������x�œ˂��~�߂���ؖ������l�͒N�����܂���B�������ʃK�X���ƂĂ��Ȃ��n�����g���������炷�Ƃ����̂́A���J�j�Y���̐��������ɊȒP�Ȉ�̐��ɉ߂��Ȃ��̂ł����A�������ʂ̐��������ɊȒP�ł����������ɁA���ی���т̌���Ɍf���Ắw�[�ցx�Ɏg�p���₷���A�܂���ʂւ̐Z�������������̂ŁA���݂̂悤�ȏɎ������ƌl�I�ɂ͍l���܂��B�ŋߋN���Ă����C��̉��g�����A�����ӖړI�ɉ������ʃK�X�Z�x�㏸�̂����Ƃ���̂łȂ��A��̓I�ɁA�ȑO�ɂǂ̒��x�̋C��ϓ����������̂��A���ꂪ���ɂ���ĂЂ��N�����ꂽ�̂��A����A�ǂ̒��x�̋C��ϓ��̃��X�N������̂��A�����𐳊m�ɒ��ׂ邱�Ƃ���X�A�C�ۊw�E�C��w�A����ɂ͒n�������Ȃǂ���Ƃ��Ă���҂̐Ӗ��ł���A�Ə����ɍl����������Ă��܂��B���R�Ȋw���u������҂Ȃ�A�������Đ^����m�肽����̂��{���̐���Ȏp���Ǝv���̂ł��B�@ |
|
| ���s�s���������炵������ | |
|
�O�ɏq�ׂ����X���Ƃ���ׂ�ƁA���݂́A�s�s�łȂ��Ƃ���ł�2�����x�̋C���㏸�ōς�ł���̂ɁA�s�S�ł͂���ȏ�㏸���Ă��邱�Ƃ������݂��܂��B����͓s�s�̍\����A�l�Ԋ����A��C�����Ȃǂ̂��߂ɓs�s�̑�C���g�߂���(���ɖ�Ԃ�)�ł���w�s�s�q�[�g�A�C�����h�x���A�C��l�ɂ����炵�����Y�ƌ�����ł��傤�B�������ċC���Ȃǂ̔N�X�̐��ڂɓs�s�̏������e�������ʂ���I�ɂ͓s�s�o�C�A�X�ƌĂт܂��B��Ԃ̃q�[�g�A�C�����h�͎�ɁA���ɋ��������ڂ������łł���ƌ����Ă��܂��B
���s�s�̌����ɂ�鑽�d���˂̂��A�ŁA�����A���z���������Ղ�z�������B ���s�s�̌����⓹�H���M�𗭂߂₷���B ����ʁA�Y�Ɗ����ɂ�����ꂽ�G�l���M�[���M�Ƃ��ĕ��o�����B ����C�����A���ɐo�Ȃǂ��s�s����̔M�̕��˂��z���E�Ւf�B�~�j�������ʂ��N����B ��������艺�̃��x���ł݂�ƁA�����Ԃ̊X�H�ɔM�����܂�Ղ��B �����̐ςݏd�˂��N�X�̋C���̈ڂ�ς���傫�����E���܂��B�܂����̉e���̓x�����N�X�ŕω����邱�Ƃ��A�b�G�ɂ��Ă��܂��B�����ɓs�s���Ȃ������Ɖ��肵���ꍇ�̋C��(���R�l)�ƁA���ۂ̓s�s�̂Ȃ��̉��x�Ƃ̍����w�s�s���ʁx�ƁA�Ȍ�A�ĂԂ��Ƃɂ��܂��B ���s�ł�3���̋C���̓s�s���ʂ�����ƁA�}2�ɂ���悤�ɁA�����I�ɓ����Ăǂ�ǂ��A1970�N������Ƀs�[�N�ɒB���܂����B����͑�́A�ǂ�ȓs�s�ł������錻�ۂ̂悤�ł��B�s�s���ʎ��̂��G�߂⎞�Ԃɂ���ĈقȂ�܂��B�ď���~��A�܂����Ԃ���Ԃ̂ق����s�s���ʂ��傫���o��X���ɂ���܂��B 1970�N�ȍ~�́A�s�S�ł̏����͈�i���Ƃ������悤�Ɍ����܂��B�Ƃ��낪�J��������Ȏ��ӂ̉q���s�s�ł͓s�S��ǂ�������悤�ɏ��������Ȃ��i��ł��܂��B���������ׂČ����̂ł����A�s�S�̋C���̎��R�l���x�[�X�ɁA���Ӓn�_�̋C���Ɣ�ׂČ���ƁA1910�`30�N��ɂ͓s�s�����i�݂͂��߂�������V�����ŏ������n�܂��Ă���A1970�N���ɂ͊ݘa�c�s�ő��ΓI�ȏ������݂��n�߂܂����B�܂����݂ł������s�̕В����Óc�w�߂��ɂ���A���_�X�̓~�̋C���̒l�́A�s�S��ǂ�������悤�ɁA���ΓI�ɏ㏸�������Ă��܂�(�}3)�B�@ �@ |
|
| ��������Ɖ��g���̌J��Ԃ� | |
|
������Ɖ��g���͒���I�ɌJ��Ԃ��Ă���A�ŋ߂̉��g���X�������R�̃T�C�N���ƌ�������Ȋw�I�ł͂Ȃ��̂ł����B�܂��A�����������̊����������̂ł͂���܂��B
�ߋ��ɕX���ƊԕX�����قڎ����I�ɌJ��Ԃ���Ă��܂���(��1)�B���̋C��ϓ��́A��Ƃ��Ēn������鑾�z�G�l���M�[��(���˗�)�̕ϓ��ɋN������ƍl�����Ă��܂��B�������A20���I�㔼����̉��g���́A���˗ʕϓ��݂̂ł͐����ł����A��C���̉������ʃK�X�Z�x�̐l�דI�ȑ���������ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B�܂��A2���`10���N�X�P�[���̓��˗ʕϓ��͗��_�I�Ɍv�Z�ł��A���˗ʕϓ��ɂ�鏫���̕X��������3���N�ȓ��ɋN����m���͒Ⴂ�Ɨ\������Ă��܂��B�߂������Ɋ�������n�܂�Ƃ͍l�����Ă��܂���B �����˗ʂ̕ϓ��͋C���ς���d�v�Ȉ��q�ł��� �n���̗��j���݂�ƁA�X���ƊԕX������10���N�̎����ŋN�����Ă������Ƃ��킩���Ă��܂��B���̋C��ϓ��ɂ́A�����̌������w�E����Ă��܂����A���ł��k�����ċG�̓��˗ʕϓ����d�v�Ȉ��q�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B�܂��A������ߋ�2000�N�Ԃɒ��ڂ���ƁA��r�I���K�͂ȋC��ϓ������������Ƃ��킩���Ă���A����ɂ��Ă����˗ʕϓ����e�����Ă����ƍl�����Ă��܂��B�ȉ��ł́A������̎��ԃX�P�[���̎��R�̋C��ϓ��ɂ��Đ������܂��B ��2���`10���N�X�P�[���̓��˗ʕϓ��ɂ��C��ϓ� �}1(a)�́A�ߋ�80���N�Ԃ̓�ɂ̋C���ϓ��������Ă��܂��B���̃f�[�^�́A��ɕX���̉ߋ��ɂ���ꂽ�X(�X���R�A)�͂�����(����)�������̂ł�(��2)�B�C���������ɍ����ԕX���̊Ԋu�͖�10���N�ł���A�����X�P�[���̕X���ƊԕX���̌J��Ԃ������Ăɂ݂��܂��B���̋C��ϓ��̌����́A�n���̎��]���̌X����n�������z�̎�������O���������������ĕϓ����邱�Ƃɂ���Đ�����2���`10���N�X�P�[���̖k�����ċG�̓��˗ʕϓ��Ɩ��ڂɊW���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂�(���̎����ϓ����~�����R�r�b�`�T�C�N���Ƃ����܂�)�B�ڍׂȕϓ��@�\�̐����͊������܂����A���̓��˗ʕϓ������������ƂȂ�C�����ω����A�C���ω����X�����_���Y�f�Z�x�̕ω����C���ω��Ƃ����悤�ɋC���ω��̑���(��3)���J��Ԃ��Ȃ���A�C�J�ڂ����ƍl�����Ă��܂��B�܂��A�X������ԕX���ɑJ�ڂ���Ƃ��̋C���㏸�́A20���I�㔼����N���Ă���C���㏸�ƈقȂ�܂��B�Ⴆ�A�������2��1000�N�O�̍ŏI�X�����玟�̊ԕX���ɑJ�ڂ����1���N�Ԃł�4�`7���̑S���C���㏸�ɔ�ׂāA20���I�㔼����N�����Ă���C���㏸���x�͖�10�{�������̂ł��B�ȏ�̂��Ƃ���킩��悤�ɁA�~�����R�r�b�`�T�C�N���ɋN������C��ϓ��ł́A������������̉��g���̌X����������邱�Ƃ��ł��܂���B�@ |
|
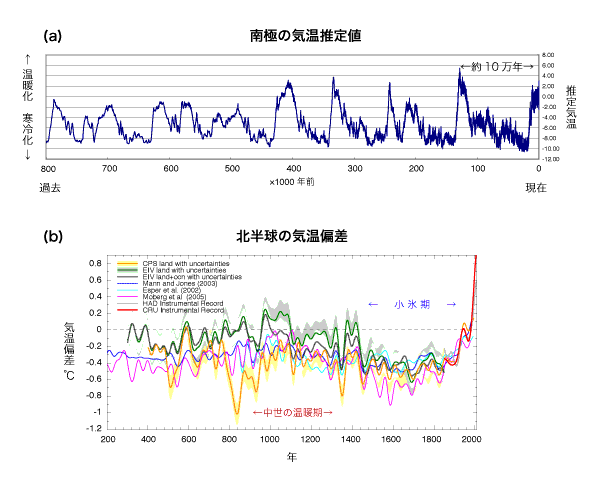 |
|
|
(a)�ߋ�80���N�Ԃɂ������ɂ̋C���̐���l�̎��n��B��10���N�X�P�[���ł̋C���̕ϓ����݂��A�X���ƊԕX�����J��Ԃ��C��ϓ����N�����Ă������Ƃ��킩��B (Jouzel et al. [2007] �̃f�[�^�����Ƃɍ쐬)
(b)�ߋ�1800�N�Ԃ̕������ꂽ�k�����̋C�����̎��n��B1961�`1990�N�̕��ϋC���̕��Ƃ��Ď���(�����̐���@��p�������߁A�l�ɂ͕�������܂�)�B �����̉��g��(��900�N�����1400�N)�⏬�X��(��1400�N�����1900�N)�ƌĂ��悤�ȋC��ϓ������������Ƃ��킩��B�܂��A��1970�N��(20���I�㔼)����C�����Z���Ԃŋ}���ɏ㏸�����A�ŋ߂̉��g�����݂���B(Mann et al. [2008] PNAS, 105, 36, 13252-13257)(Copyright [2008] National Academy Science, U.S.A.) ��������ߋ�2000�N�Ԃ̎��R�̋C��ϓ� ������ߋ�2000�N�Ԃ̋C���̐��ځm�}1(b)�n���݂�ƁA�u�����̉��g���v��u���X���v�Ƃ���A�k�����C���̕ϓ�����1�������̋C��ϓ�������܂���(��4)�B�����ɂ͐��S�N�X�P�[���̑��z�����̋���ɂ����˗ʕϓ����e�����Ă����ƍl�����Ă��܂��B�Ⴆ�A�����ɂ͑��z��������r�I�����ł��������߂ɉ��g�ł������Ɛ�������Ă���A�����15�`19���I���ɂ͑��z�������ቺ�������߂ɏ��X���������炳�ꂽ�ƍl�����Ă��܂�(��5)�B�������A20���I�㔼�ɂ͑��z�����̊������݂͂��Ȃ����Ƃ���A20���I�㔼�̉��g���z�����̕ω��݂̂ɂ���Đ������邱�Ƃ͂ł��܂���(��6)�B ��20���I�㔼�̒n�����g���̎���͉������ʃK�X�̑����ł��� �}1(b)���݂�ƁA20���I���Έȍ~�A�Z���Ԃŋ}���ȋC���㏸���N�����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�������A��q�����悤�ɁA�~�����R�r�b�`�T�C�N���␔�S�N�X�P�[���̑��z�����̋���ɔ������˗ʕϓ��ł́A20���I�㔼����̋C���㏸������ł��܂���B�ł́A20���I�㔼����N�����Ă���n�����g���̎���͂����������Ȃ̂ł��傤���H ����ׂ邽�߂ɁA�C�f�������҂�́A20���I�̋C��ω��Ɋ�^����ƍl�����邳�܂��܂Ȉ��q(�������ʃK�X�Z�x�̑��������łȂ��A�l�N���̗��_�G�A���]���r�o�̕ω��A�I�]���w�̕ω��A�ΎR���A���z�����ω��Ȃǂ��܂܂��)���l�������C�f������(20���I�Č�����)���s���܂����B���̎����ł́A�������q�����ׂčl�������v�Z�ɉ����A�������̈��q���l�����Ȃ��Ȃlj��z�����ł̌v�Z���s���A�����̌��ʂ��ϑ��f�[�^�Ɣ�r���邱�Ƃɂ��A20���I�㔼�̋C���ω��ɑ���e���q�̊�^�x���������Ă��܂��B���̌����̌��ʁA�������ʃK�X�Z�x�̑������l�����Ȃ����20���I�㔼�̉��g��������ł��Ȃ����Ƃ�������܂����B�������IPCC��4���]�����ł́A20���I�㔼�̉��g���̎���͉������ʃK�X�Z�x�̐l�דI�ȑ����ł���\�������ɍ����ƌ��_�t���Ă��܂��B ������3���N�ԂɕX�����n�܂�m���͒Ⴂ ���z�����̕ϓ��̏ڂ������J�j�Y���͂܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ����߁A���㐔�\�N����100�N�̊Ԃ̑��z�����̕ω��ɂ��C��ϓ��\���͍���ł��B�������A���z�����̕ω����ߋ�2000�N�ԂɋN���������x�̋���ŌJ��Ԃ����Ɖ��肷��Ȃ�A���̉e���ɂ��C���ϓ����͏��������Ƃ���A����100�N�ŗ\�������l�דI�ȉ��g����ł������Ċ��≻���邱�Ƃ͍l�����܂���B �~�����R�r�b�`�T�C�N���Ő��������A�����X�P�[���̋C��ϓ��ɂ��ẮA2���`10���N�X�P�[���̓��˗ʕϓ��͗��_�I�Ɍv�Z�ł��A�X��������3���N�ȓ��Ɏn�܂�m���͒Ⴂ�Ɨ\������Ă��܂��B�܂��A���݂̍�����C���̉������ʃK�X�Z�x�ɂ��X���̊J�n���x���\��������Ƃ��w�E����Ă��܂��B �����_�ŁA���㐔10�N�`100�N�̊��Ԃł���ꂪ�D��I�ɑΉ����l����ׂ��́A���R�̋C��ϓ��ł͂Ȃ��A�l�דI�ȉ��g���₻�̉e���ł���Ƃ�����ł��傤�B �� (��1)�R�R���m�肽�����g���u�X���R�A����킩�邱�Ɓv���Q�� (��2)�����ł͓�ɂ̋C���̐���l�݂̂������܂������A�e�n�̋C��ω��������w�W(�v���L�V�[�f�[�^)����A�}�Ɏ������悤�ȋC��ϓ����n���K�͂ŋN���������Ƃ��킩���Ă��܂��B (��3)�R�R���m�肽�����g���u�X���R�A����킩�邱�Ɓv���Q�� (��4)�����̓��[���b�p�ł͌������������A�S���I�ɂ͌����Ȍ��ۂłȂ�������������Ȃ����Ƃ�����Ă��܂��B (��5)�Ȃ��A�ʂ̊��≻���J�j�Y���Ƃ��āA�ΎR���̊��������l�����܂��B (��6)�R�R���m�肽�����g���u���z�̍��_���̕ω������g���̌����H�v���Q�Ɓ@ �@ |
|
| �����z���_���̕ω������g���̌����H | |
|
���z�̍��_���̕ω��ƋC���̕ω��Ƃ̊Ԃɋ������ւ�����ƕ����܂����B�Ƃ������Ƃ́A���z�����̊����������g���̎�v�Ȍ����Ȃ̂ł͂Ȃ��̂ł��傤���B
���z���_���̕ω��́A���z����n���ɍ~�蒍�����˃G�l���M�[�̕ω��������炷���߁A�n���̕��ϋC����ω�������\���͂���܂��B�������A�n���̕��ϋC���́A���z���������łȂ��A��K�͂ȉΎR���A�������ʃK�X���C���������̑����Ȃǂɂ���Ă��ω����邱�Ƃɒ��ӂ��K�v�ł��B�ŐV�̊ϑ��f�[�^�����܂��ƁA20���I���Έȍ~�A�����I�ɂ͑��z���_���͂قډ����������X���������Ă���A���z���������������Ă���Ƃ͍l�����܂���B���z�������n���̕��ϋC���ɋy�ڂ��e���ɂ��ẮA�܂��悭�킩���Ă��Ȃ��_������܂����A�������ʃK�X�̑������ŋ߂̉��g���̎�v�Ȍ����ł��邱�Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ��Ƃ����܂��B �����z���_���͑��z�����̂悢�w�W�A���_���̕ω��͋C���̕ω��������炵���� ���z���_�͑��z�\�ʂɌ����鍕�����݂̂悤�ȗ̈���w���A���͂������x���Ⴂ���߂ɍ��������Ă��܂��B�����̍��_���܂Ƃ܂��Ĕ������邱�Ƃ������A���̂܂Ƃ܂�����_�Q�ƌĂт܂��B���z���_���̒�`�ɂ͕�������܂����A��ʂɂ悭�g���Ă���̂͑����_���ƌĂ����̂ŁA���_�Q�̐��ƌX�̍��_�Q�Ɋ܂܂�鍕�_������Z�o����A���z�����̕ω����悭�\�������w�W�Ƃ��Ēm���Ă��܂�(�ȍ~�A���_���������_���Ƃ��܂�)�B ���z�\�ʂɂ́A���_�̑��ɂ������ƌĂ����͂�艷�x������(�����邢)�̈�����݂��A���_�̋߂��ɂ悭����܂��B���z�̖��邳�́A���_�ɂ��Â��Ȃ���ʂƔ����ɂ�薾�邭�Ȃ���ʂ̃o�����X�ɂ���Č��܂�܂����A�����̌��ʂ��킸���ɏ��邽�߁A���z���_����������Ƒ��z�̖��邳���������܂��B���́g���z�̖��邳�h�͒n���ɍ~�蒍�����z���˃G�l���M�[�ɑ������A�n���̋C��V�X�e���̋쓮���ƂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A���z���_���̕ω��ɉ����Ēn���̕��ϋC�����ω����邱�Ƃ͏\���l�����܂��B ���C����ω�������v���́A���z����̕��˃G�l���M�[�̕ω������Ƃ͌���Ȃ� ����ŁA�n���̕��ϋC����ω�������v���́A�������z�G�l���M�[�̕ω������Ɍ����Ă���킯�ł͂���܂���B��_���Y�f���͂��߂Ƃ��鉷�����ʃK�X�̑������C���̏㏸�������炷���Ƃ͂悭�m���Ă��܂����A��K�͂ȉΎR���ɂ�萬�w���ɂ܂ʼn^�ꂽ�ΎR���K�X(�����_�K�X�◰�����f�Ȃ�)���琶������闰�_�G�A���]��(���_�t�H�̔����q)�́A�n�\�ʂɓ͂����˂��Ղ邱�ƂŋC���̒ቺ�������܂��B���l�̌��ʂ́A�l�Ԋ����ɔ�����C���������̕��o�ɂ���Ă������N������܂��B�t�ɁA���Ȃǂ͓��˂��z�����邱�ƂŒn���̑�C��g�߂���ʂ������Ă��܂��B�I�]���w�̕ω���X�єj��(�k��n�̊g��)�Ȃǂ��n���̋C���ɉe����^���Ă��܂��B�܂��A�����̗v�����Ȃ��Ă��A���R�E�̒������Ԃ̒��ŕϓ�����g�C��̗h�炬�h(��1)�����݂��A����ɂ���Ă��C���͕ϓ����܂��B�n���̕��ϋC�����ϓ����錴�����l����ۂɂ́A�����̂��܂��܂ȗv���ɂ��Ă��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃɒ��ӂ��K�v�ł��B ��20���I���Έȍ~�̍��_���͂قډ����A�ŋ߂̉��g���͉������ʃK�X�̑��������� ���z���_���ƒn���̕��ϋC���̌o�N�ω� �@ |
|
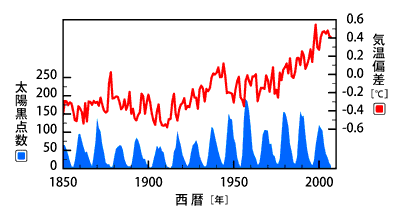 |
|
|
���z���_��(���h��ꂽ����)�ƒn���̕��ϋC��(�Ԑ�)�̌o�N�ω��B(Solar Influences Data Analysis Center �̑��z���_���̃f�[�^����сAClimatic Research Unit �̒n���̕��ϋC���̃f�[�^�����ɍ쐬)�n���̕��ϋC����1961�`1990�N��30�N���ϒl����̕��������Ă���B
�ȏ�܂�����ŁA���ۂɊϑ����ꂽ�ߋ�150�N�Ԃ̑��z���_���ƒn���̕��ϋC���̕ω��m�}�n�����Ă݂܂��傤�B���z���_���͖�11�N�̎����������đ������J��Ԃ��Ă��܂����A���̍ő�l�͕K���������ł͂Ȃ��A�������ƂɈقȂ��Ă��܂��B���̍ő�l�̕ω��ƒn���̕��ϋC���̕ω����r���܂��ƁA19���I�㔼����20���I�O���ɂ����ẮA�������ɗ��҂̑��ւ������悤�Ɏv���܂��B�������A���̎����ɂ͂��łɉ������ʃK�X�����X�ɑ������n�߂Ă���A����ɔ����C���㏸���l�����Ȃ���Ȃ�܂���B���́A���̎����Ɋϑ����ꂽ�C���ω��̌����ɂ��Ă͂܂��悭�킩���Ă��Ȃ��̂ł����A���z�����̒����I�ȕω������ł͐���������Ȃ��ƍl�����Ă��܂��B ����ŁA20���I���Έȍ~�ɂ́A���z���_���̒����I�ȕω��͂قډ������ނ��댸���X���������Ă���A�����������z���������������Ă���Ƃ͎v���܂���B�܂�A���z�����̊��������ŋ߂̉��g���̎�v�Ȍ����ł���Ƃ͍l�����܂���B�ڍׂ͏Ȃ��܂����A�C����ω�������\���̂��邳�܂��܂Ȍ��ʂ��ł��邾���l���ɓ��ꂽ�ŐV�̌����ɂ��A��_���Y�f���͂��߂Ƃ��鉷�����ʃK�X�̑������l���Ȃ���A20���I���Έȍ~�Ɋϑ����ꂽ���g����萫�I�ɂ���ʓI�ɂ������ł��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B �����̑��z�����w�W�Ɖ��g���Ƃ̊W���w�E����Ă��邪�A���i�K�ł͐M�ߐ����Ⴂ �n���̕��ϋC���̕ω��ɉe�����y�ڂ��\���̂��鑾�z�����w�W�Ƃ��āA���z���_���̑��ɂ���������₪�������Ă���A�ŋ߂ł́A�n���ɓ��B����F����(�F����Ԃ�Y���Ă���d�C��тт����q�j)�̋��x�����ڂ���Ă��܂��B���z�����������Ȏ����ɂ͎��ꂪ�傫��������邽�ߒn���ɓ��B����F�������������܂����A����ɔ����Ēn�����Ă���_�̗ʂ��������A�n�\�ɓ��B������˗ʂ��������邽�߂ɋC�����㏸����A�Ƃ�����ł��B�����ł̃|�C���g�͉F�������x�ƒn���̉_�ʂ̊W�ŁA���̐��ɂ��A�F�����ɂ���C���ɐ������ꂽ�C�I������ƂȂ��ĉ_������A�Ƃ���Ă��܂��B�������ɁA�萫�I�Ȑ����Ƃ��Ă͂��蓾�邩������܂��A���̂悤�ɂ��Đ��������_�͒n���S�̂̉_�ʂ̂ǂ̂��炢�̊������߂�̂��A�ȂǁA��ʓI�ɂ͂܂��܂������̕s���ȓ_���c����Ă��܂��B�������ʃK�X�̑����ɔ����C���㏸�Ɋւ��āA��C���̓�_���Y�f��2�{�ɑ������Ƃ��ɂǂ̂��炢�C�����㏸���邩�A�Ȃǂ̒�ʓI�ȋc�_���s���Ă��邱�ƂƔ�r���܂��ƁA���z�����|�F�����|�_�̕ω��ɂ�鉷�g�����́A���i�K�ł͐M�ߐ����Ⴂ�ƌ��킴��܂���B����̌�������ł́A���z�����|�F�����|�_�̕ω��ɔ����C���㏸�̒�ʓI�ȋc�_���\�ɂȂ邩������܂��A����ɂ���āA�������ʃK�X�̑����ɔ����C���㏸����������邱�Ƃ͍l����ꂸ�A�������ʃK�X�̑������ŋ߂̉��g���̎�v�Ȍ����̈�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B �� (��1)�C��̗h�炬�F���z����̕��˃G�l���M�[�̕ω����K�͂ȉΎR���A�l�Ԋ����ɔ����������ʃK�X�r�o�ʂ̑����ȂǁA�C��V�X�e���̊O������̋�������Ȃ��Ă��A��C��C�m�A��X�Ȃǂ����ݍ�p���邱�Ƃɂ�萶����ϓ����w���܂��B�G���j�[�j�������łȂ��A��Ă�g�~�Ȃǂ̔N�X�ϓ����C��̗h�炬�̈ꕔ�ƍl�����܂��B�@ �@ |
|
| ���X���]�ԕX���T�C�N���ɂ������CCO2�Z�x�ϓ��̖��� | |
|
�X���|�ԕX���T�C�N���́A�l�ނ��i�����Ă�����l�I(�ߋ�258���N��)�Ƃ������������Â���C��ϓ��ł���B���ɁA�ߋ���80���N�Ԃ̕X���|�ԕX���T�C�N���́A��10���N�̎����ŌJ��Ԃ��A���̐U���͕��ϋC����5���ȏ�A�嗤�X���̊g��ɔ����C�����ϓ���120m�ɋy�ԁB�X���]�ԕX���̌J��Ԃ��́A�n���O���v�f(���]�O�����S���A�n���̌X���A�n���̍��^��)�̎����I�ω��������N�����n���ւ̓��˗ʂ̈ܓx���z��G�ߕ��z�̕ϓ�(������~�����R�r�b�`�E�T�C�N��)�ɋN�����邱�Ƃ��A���ɖ��炩�ɂ���Ă���B�������A���������n���O���v�f�ɔ������˗ʂ̕ϓ��́A�n���S�̂��N�ԂɎ���˂̑��ʂ��قƂ�Ǖω������Ȃ����߁A�ËC��L�^�Ɏ������悤�ȁA�X���|�ԕX���T�C�N���ɔ����S���K�͂̑傫�ȋC���ϓ��������N�������߂ɂ́A�n���̋C��V�X�e���ɓ��݂��鉽�炩�̑����ߒ����K�v�ƂȂ�B�������Ȃ���A�����������˗ʕϓ����ǂ̗l�ɂ��đ��������̂��A���̃��J�j�Y���͖����Ɋ��S�ɂ͉𖾂���Ă��Ȃ��B�����āA����������J�M�́A�X������ԕX���ւ̈ڍs�ߒ��ɂ����āA�����ǂ��������Ԃŕω����Ă����̂���m�邱�Ƃɂ���ƍl�����Ă���B
��ɂ̕X���R�A���ێ�����ËC��L�^�́A���̖��̉𖾂Ɍq����d�v�ȏ���^���Ă����B����܂ł̌����ŁA�X������ԕX���ւ̈ڍs��(�Z�X���ƌĂ��)�ɂ�����X���̗Z����萔��N��s���āA��ɂ̋C������ё�C����CO2�Z�x�̕ω����N�����Ă����������炩�ɂ���Ă���A�X�ɁAMonnin et al. (2001)�̌����ɂ��(���Ȃ��Ƃ��ŏI�Z�X���ɂ����Ă�)��ɂ̋C���̏㏸���ACO2�Z�x�̏㏸�ɐ��S�N��s���Ă����Ƃ���Ă����B����ɑ��A�{�����́A��茵���ȑΔ���s���A��ɂ̋C��������s���Ă���悤�ɂ������邪�A�ނ���A���҂͌덷(100�N���x)�͈̔͂œ����ł���A�����J�b�v�����O���Ă���ƌ���ׂ����Ǝ咣���Ă���B �X���R�A�̋L�^�ɂ����āA��ɂ̋C���̎w�W�ɂ͕X�̐��f���ʑ̔䂪�p�����Ă���A����A��C����CO2�Z�x�́A�X�Ɋ܂܂��C�A�ɕێ����ꂽ��C�̕��͒l��p���Ă���B�����ŁA���҂̎��ԍ��̕]���Ɍ덷��������̂́A�X�̐��f���ʑ̂́A���̑w�����n�\�ɂ��������̍~��̐��f���ʑ̔���L�^���Ă���̂ɑ��āA�C�A�́A�X���\�ʉ�50�`120m�ʂ̂Ƃ���ŁA�����ŋC�A���������_�ł̑�C��CO2�Z�x���L�^���Ă��邽�߂ł���B�]���āA�C�A������[�x(Lock-in Depth��LID)���ǂ̂��炢���m�ɐ��肷�邩���A���ԍ��̐���덷������������J�M�ƂȂ�B�{�����ł́A�C�A����N2�̒��f���ʑ̔�𗘗p����LID����萳�m�ɐ��肵���B�C�A�����݂ɒʂ��Ă���LID�������ł͕��q�g�U�ɂ�蓯�ʑ̕��ʂ��N����ALID�̐[���ɔ�Ⴕ��N2�̒��f���ʑ̔�͑��傷��B���̐����𗘗p����LID�𐄒肵���̂ł���BLID�́A�ϐᑬ�x���̈������x�ȂǗl�X�ȗv���ŕω�����B�{�����ł́ALID���e�w�����Ƃɍׂ������肵�A���̎���ω����l�����邱�ƂŁA����w���ɂ�����C����CO2�Z�x�L�^�̎��ԍ�����萳�m�ɐ��肵���B �{�����ɂ����������̍H�v�́A��ɑS����J�o�[����5�n�_�ł̋C���f�[�^���d�˂ĕ��ω����邱�Ƃɂ��A��ɋC���ϓ��f�[�^�̃m�C�Y�����������������Ƃł���B���̌��ʁA�C����CO2�Z�x�̎��ԍ��̐���덷��90�`160�N�ɂ܂ŗ}���邱�Ƃ��o�����B�������ɁA�ŏI�Z�X��(2�`1���N�O)�ɂ�����C����CO2�Z�x�̕ω����r�������ʁA�덷�͈̔͂ŗ��҂̕ϓ��̃^�C�~���O����v���Ă������Ƃ������ꂽ�B�܂��A���҂̕ϓ������W��0.99�ȏ�ő��ւ��Ă��鎖�������ꂽ�B�����̌��ʂ́A�ǂ��炩�ƌ����킸���ɋC������s���Ă�����̂́A��ɂ̋C���Ƒ�C����CO2�Z�x�������J�b�v�����O���Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B��U�ω����n�܂�ƁA���ҊԂ̐��̃t�B�[�h�o�b�N�ɂ��A�ω�����������đ傫���Ȃ��Ă䂭�̂ł���B �{�����̌��ʂ́A�X������ԕX���ւ̕ω��ɂ����āA�ǂ��ɂ�����ǂ������ω����Z�X���̂��������ƂȂ����̂��A�Ƃ������̓�����^����ɂ͎����Ă��Ȃ��B�������A��ɂɂ�����C�����邢�͂���ɒ��ړI�ɉe����^����C�X���z��\�w���ɂ����鉔�������̕ω����������ɂȂ��Ă���\���������������Ă���B���ꂪ�{���Ȃ�A�X���ԕX���T�C�N�����k�������ܓx��ɂ�����Ă̓��˗ʕϓ��ɂ������N������Ă���A�܂�A�k�������ܓx�ɂ�����ω����������ɂȂ��Ă���A�Ƃ���~�����R�r�b�`�̉����Ɋ�Â�������܂ł̍l�������C������K�v�����邩������Ȃ��B�@ �@ |
|
| ���X���|�ԕX���T�C�N���̎����́A���A�ǂ̗l�ɕς�����̂��H | |
|
���݁A�������́A��3400���N�O�Ɏn�܂����n���j�̒��ōł��V�����X�͎���̒��ɂ���B�X�͎���́A�����A���≻���ĕX�����g�債���X���ƁA���ΓI�ɉ��g�ŕX�����k�������ԕX���̌J��Ԃ��A������X���|�ԕX���T�C�N���œ����Â�����B�����Č��݂́A��300���N�O�̖k�����X���̏o���Ŏn�܂�A���ꂪ�g�傷��ߒ��Ō��݉������X��-�ԕX���T�C�N���̒��̍ł��V�����ԕX��(��X���ƌĂ��)�ɓ�����B
�X���|�ԕX���T�C�N���́A�n���O���v�f�̕ω�(�n���̌��]�O���̗��S���ω��⎩�]���̌X���̕ω��A�����Č��]�O���ɑ��鎩�]���̃S�}�X���^��)�ɂ���Ĉ����N���������˗ʂ̈ܓx���z����ыG�ߕ��z�̏������I�ϓ�(��ʂɁA�~�����R�r�b�`�T�C�N���ƌĂ��)���A�n���V�X�e�����ő�������邱�Ƃɂ���Ĉ����N������Ă���B�X���|�ԕX���T�C�N�����~�����R�r�b�`�T�C�N���ɓ������Ă��鎖�͊��Ɏ��m�̎����ŗL�邪�A�������125���N�O�ȑO�ɂ́A���悻4���N�̒n���X�������ɓ������Ă����X���|�ԕX���T�C�N�����A���悻70���N�O�ȍ~�͂��悻10���N�̗��S���ϓ������ɓ�������悤�ɂȂ������́A���ƈȊO�ɂ͗]��m���Ă��Ȃ��B���̎����̕ω��́A�X�V��(Pleistocene:258���N�O�|��1���N�O)�̑����ɋN���������߁AMPT(Mid Pleistocene Transition)�ƌĂ�Ă���A���̌�����ω��̏ڍׂ𖾂炩�ɂ��鎖�́A�~�����R�r�b�`�T�C�N���������ɂ��ĕX���|�ԕX���T�C�N���������N���������ƌ����A�������̑喽���������ł̏d�v�Ȏ�|�����^���Ă����Ɗ��҂����B MPT�ɂ��ẮA����܂ŁA�u�ꐶ�L�E���ƌĂ��C��ɐ��ޒP�זE�����̐ΊD���Ȋk�̎_�f���ʑ̔䂪��ɊC���̓��ʑ̔�f���A�C���̓��ʑ̔�͑嗤�X���̑̐�(=�C����)�f����v�Ƃ̉���̂��ƁA���E�̐F�X�ȊC�悩����ꂽ�ꐶ�L�E���k�̎_�f���ʑ̔�̕ϓ����d�ˍ��킹�ĕ��ω������f�[�^�Ɋ�Â��Ă��̓������c�_����A125���N�O����70���N�O�ɂ����āA�X�������X�ɑ傫������Ƌ��ɁA4���N������10���N�����ɒu��������čs�����ƌ����Ă���B����ɑ��Ē��҂�́A�ꐶ�L�E���k�̎_�f���ʑ̔�́A�C���̓��ʑ̂����łȂ��k�𒾓a���������̐����̉e������̂ŁA�X���̐ς̎w�W�Ƃ��Ă͕s���S�ł���Ǝw�E���Ă���B�����āA�쑾���m�j���[�W�[�����h���̐��[3290m�̐[�C�ꂩ�������ꂽ�@��R�A���番�悳�ꂽ���v1485�̎������̒ꐶ�L�E���k�ɂ��āA�_�f���ʑ̔�Ɠ����ɐ����̎w�W�ł���Mg/Ca��𑪒肵�A�k���_�f���ʑ̂���荞�ލۂ̐����̉e������菜�����Ƃɂ��A�C���̓��ʑ̔�̕ϓ����ߋ�150���N�Ԃɓn���ĕ��������B �������ʂ́A�]���̍l�������̂ŁA���X�̎����ɕx��ł���B�����A�X���̐ς̕ω��́A�]�������Ă����悤�ɐ��\���N�����ď��X�ɋN�������킯�ł͂Ȃ��A95���N�O����87���N�O��8���N�Ԃŋ}���ɋN�������������炩�ɂȂ����A����A��w�����̕ϓ��l���́A�X���R�A�ɋL�^���ꂽ��ɂ̋C���̕ϓ��l���Ƃ悭���Ă���A��ɂ̋C���f���Ă��鎖���������Ă���B�����āA�X���ɑ����̐����́|1.7���O��ƒႭ�A�ߋ�150���N�ԗ]��ω��������Ȃ����������ꂽ�B����A�ԕX���̐[�w�����́A45���N�O�ȑO�ɂ́A1����Ⴉ�����B�X�ɖʔ����̂́A�ԕX���ɑ�������̐[�w�����ቺ�́A�X���̐ϑ����ɐ�s���Ă���A�ԕX������X���Ɍ������v���Z�X�̑O���ł́A��ɐ����ቺ���L�E���k�̎_�f���ʑ̔䑝���Ɋ�^���Ă���A�㔼�́A��ɕX���̐ς̑�������^���Ă��鎖�ł���B�����āA���Ȃ��Ƃ��������ꂽ�n�_�ɂ����ẮA�[�w�����̕ω����L�E���k�̎_�f���ʑ̔�ϓ��̔����߂���������Ă���B ���҂�́A�X�ɁA�������������ŁAMPT�ŕX���̐ϋ}�����N���������ɂ��Ă��l�@���Ă���B�����A�_�f���ʑ̔�X�e�[�W24�ŕX��������������A�X�e�[�W23�ŕX�����]��قƂ�ǗZ���Ȃ����������A���̃X�e�[�W22�ōX�ɕX�����g�傳���邱�ƂɂȂ����Ǝ咣���A���ʑ̃X�e�[�W23�ŕX�����]��Z���Ȃ����������́A���̎��ɁA�씼�����ܓx��̉Ă̓��˂��]��㏸���Ȃ��������炾�Ƙ_���Ă���B(�����āA�M�҂͂��܂蒍�ڂ��Ă��Ȃ���)����́A40���N�����ŗ��S�����ɏ��ɂȂ��������ƈ�v���Ă���B)���̉��߂́A�씼�����ܓx�̉Ă̓��˗ʕϓ����A�X���|�ԕX���T�C�N���ɉe����^���Ă���Ƃ����咣���܂�ł���_�ł��d�v�ł���B����́A���݁A�X���|�ԕX���T�C�N���̃y�[�X�����߂Ă���̂��A�~�����R�r�b�`�������悤�ɖk�����̉Ă̓��˗ʂȂ̂��A����Ƃ��씼���̓��˗ʂȂ̂��Ő���ɋc�_����킳��Ă��邩��ł���B Elderfield�́A70�ɋ߂������҂ł��邪�A������Nature ��Science�ȂǁA�g�b�v���x���̎G���ɘ_�������������Ă���B���̃A�N�e�B�r�e�B�[�̍����ɂ́A����������ł���B �@ �@ |
|
| ���~�����R�r�b�`�� | |
|
���X�͊�
�n���ɂ͉ߋ��ɉ��x���X�͊��Ƃ���C���̒Ⴂ����������܂����B7���N�قǂ܂ł̕X�͊��͒n���̂��ׂĂ̕\�ʂ��X�ɕ���ꂽ�u�S�������v�Ƃ������X�͊����p�ɂɂ��������Ƃ��킩���Ă��܂��B���̂悤�Ȓn�����u�X�m�[�{�[���E�A�[�X�v�Ƃ����܂��B��6���N�O�̃J���u���A�I���O�ɃX�m�[�{�[����E�����n���͂��̌�����x���̕X�͊����o�����܂������A�S�������͂������Ă��܂���B���̌����͑��z�̐i���ɂ���ĕ��˂����M�G�l���M�[�̑��ʂ������������߂ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B������(�J���u���A�I�ȍ~���݂܂�)�ɂ͑S�������͂�����܂���ł������A�Ð��㖖�ɂ͐������90���ȏオ��ł�����ł�������܂����B���̌����ɂ��Ă͓V�̂̏Փ˂Ƃ����l����������܂����A�X�͊��̓����ɂ��X�͂̔��B���C���̌������嗤�I�̏������A���v�����N�g���̎��Ł��_�f���R�@�Ƃ������������l�����Ă��܂��B������ɂ͖ڗ������X�͊��͂���܂��A�V����ɂȂ��ċ����X�͊������x���������Ă��܂��B�ߋ�200���N�̑�l�I�͕X�͊������ʂŁA�X�͊��ƕX�͊��̊Ԃł���ԕX���̂ق����Z���A���݂͖�1���N�O�ɏI������X�͊�(���������X��)�Ǝ��ɗ���X�͊��̊ԕX���ƍl�����Ă��܂��B�������ԕX���Ƃ͌��킸��X���Ƃ����܂��B ���X�͊��ɂȂ�� �X�͊��̒��x�ɂ����܂����A�X�͊��ɂȂ�ƊC�����嗤�X�͂ƂȂ邽�߁A�C��(�C�ʂ̒ቺ)��������܂��B��1��2��N�O�ɂ͊C�ʂ��ő�130���ቺ���܂����B���{�t�߂ł͒��N�����E�����E�V�x���A���������ŁA���{�C���ƂȂ��Ă��܂����B���{�̂悤�Ȓ��ܓx�n���ł́A���R�n�тŕX�͂����B���A�L�t���ёт�j�t���ёт̓������ɉ������Ă��܂��B�܂��G�߂́@�t�|�H�|�~�@�ƂȂ�Ă��قƂ�ǖ����Ȃƍl���Ă悢�ł��傤�B �@ |
|
|
�������ƍl�����鏔��
�Ȋw�I�Ȃ��̂����Ȋw�I�Ȃ��̂܂ʼnߋ��ɑ����̕X�͊��̌������l�����܂����B�Ȋw�I�Ȃ��̂ނ���Ǝ���3�ɕ��ނł��܂��B ���n���ɋN��������� �n�����̂��X�͊��������Ă���Ƃ����l�����ł��B�~�����R�r�b�`���������Ɋ܂܂�܂��B�n���̌��]�⎩�]�ɂ��Ă̂��܂��܂Ȃ��Ƃ����A�v���[�g�e�N�g�j�N�X��v���[���e�N�g�j�N�X�ȂǂŐ������悤�Ƃ�����̂�����܂��B�܂��ΎR�̕��ɂ��`�������w���ɑؗ����Ēn�\�ɓ͂����˗ʂ��������A�ُ�C�ۂ��p�����邱�Ƃ����x������܂����B19���I�ɂ��������V���̋Q�[�Ȃǂ͐�ԎR�̕��ɂ��G�A���]���������ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����A1991�N�̃s�i�c�{�ΎR�̕��ł��C���ቺ���ϑ�����Ă��܂��B����ȉΎR�������A������ΕX�͊��̈������ɂȂ邱�Ƃ��l�����܂��B �����z�ɋN��������� ���z�͊j�Z�������ɂ���ăG�l���M�[�Y�E���o���Ă���̂ł����A��Ɉ��Ƃ����킯�ł͂���܂���B���_�̑����ȂǂɎ�����������܂����A����ɒ����ϓ����ϑ�����Ă��܂��B�܂��}�E���_�[�ɏ���(1640-1715�N��)��V���y�[���[�ɏ���(1410-1540�N��)�Ƃ����č��_���قƂ�nj���Ȃ�����������܂����B���ۂɂ��̎����ɂ͊��≻��������u���X���v�Ƃ��Ă��܂��B���X�����X�͊��̏��K�͂Ȃ��̂��ǂ����͕s���ł����A���z�������ڂŌ���ƕό����ł���\���͎̂Đ�܂���B���̕ω��͍P���Ƃ��Ă͔��X������̂ł͂��邯��ǁA�n���ɑ���e���͑傫���ƍl�����܂��B �����z�n�O�ɋN��������� ���z�n�͋�͂̒���g�ł��Ȃ����2���N�Ō��]���Ă��܂��B���疜�N���Ƃɋ�͖ʂ�ʉ߂��܂����A���̂Ƃ�����ȕ��q�_�̒���ʉ߂��邱�Ƃ�����܂��B���̂Ƃ��@���z���������q�_�ɂ���ĎՂ����˗ʂ��ቺ����\��������܂��B���z�n�̋ߖT�ɂ͕��q�_������A�����N�O�ɒʉ߂��I������Ƃ����܂��B �@ |
|
|
���~�����R�r�b�`��
�n���̕X�͊���n���̋O���ʂ̕ω��ƍ��^���A�n���̌X�Ίp�Ő������悤�Ƃ�����̂��Ƃł��B���[�S�X���r�A�̃~�����R�r�b�`(Milankovitch)�ɂ����1930�N�ɏ������܂����B���݂ł͎嗬�ƂȂ��Ă���l�����ł����A�܂��܂����Θ_�������悤�ł��B ���n���̊C���̕��z �n����̑嗤�͖k�����ɏW�����Ă��܂��B���[���V�A�嗤�E�k�A�����J�嗤�݂̂Ȃ炸�A�t���J�嗤�̔����ȏオ�k�����ɂ���܂��B��A�����J�嗤���ꕔ���k�����ł��B�}�͗������Ƃ���嗤��������Ă��܂��B���ɓ쑾���m�𒆐S�Ƃ��镔���ɂ͗��n��10����������܂���B�嗤�͊C�m�ƈ���ĔM�e�ʂ��������̂ŁA�M���₷����߂₷���Ƃ��������������Ă��܂��B�܂�n�\�ɓ͂����z�G�l���M�[�̕ω����C�m�ɔ�ׂĂ�茰���ɕ\��܂��B�܂���U�嗤�X�͂��`�������ƁA�A���x�h(���˔\)���ɒ[�ɕω����܂��B�y�̒��F��A���̗ΐF�͑��z�̌����z�����܂����A�X�͔��˂��Ă��܂��܂��B�~�ɍ~�����Ⴊ�����ĉĂ��z���ƁA���N�ɂ͂���ɋC�����ቺ���Ă���ɍL���n��Ɋg����܂��B����ɂ�鐳�̃t�B�[�h�o�b�N�ŕX�͂���������ƍl�����܂��B���̋t�̌��ۂ͕X�͂̏��łɂ��K���ł��܂��B������ɂ���A�k�����ɑ嗤�������܂��Ă��錻�݂̏́A�k�����ł̓��˗ʕω������Ƃ������ł��X�͊��̈������ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B ���O���̌`�̕ω� �n���̋O���͑��z���œ_�̈�Ƃ���ȉ~�O���ł��B�n�����ł����z�ɋ߂Â��_���ߓ��_�A�ł���������_�������_�Ƃ����܂��B���z�ƒn�������Ȃ���O���̌`�͕ω����܂��A�n���̋O���͑��̘f���̉e������(�ؐ����ł��傫��)�A��10���N�����ŕϓ����܂��B���������z�ƒn���̕��ϋ����͂قƂ�Ǖω����܂���B�������ϋ������ω�����Εω����~�ς���Ēn���͌��݂̋O���ɂ͑��݂��܂���B���̂悤�Ȍ`�̕ω��𗣐S���̕ω��Ƃ����܂��B���]�O���̌`���ł��Ђ��Ⴐ��ƁA�ߓ��_�Ɣ��N�u�Ă������_�ŁA���z�̓��˗ʂ̍���20���ƂȂ�܂��B�ł��ۂ��Ȃ�ƁA���̍���4���B���݂��̍���7���ł��B �����^���Ƌߓ��_�ړ� �n���́A���]����k�ɐ��Ɍ������܂܁A���]�ƌ��]�����Ă��܂��B���̎��]����23.5�x�̌X����ۂ����܂܂ŁA2�D6���N�̎����ŋt��]���Ď�U��A�݂�����^�������܂��B��������^���Ƃ����܂��B������1���N�قǂ���ƃx�K(�D����)�̕����Ɏ��]���������āA���ƍ��̃x�K(�D����)���k�ɐ��ƂȂ�܂��B�n���O���̌`���ς��Ȃ��Ƃ���A���݂͑��z���o��286�x(1��7����)�ɋߓ��_��ʉ߂��܂��B�k�����̐^�~�ɒn���͑��z�ɍł��߂Â��܂��B�Ƃ��낪1��3��N��ɂ�1��7���͖k�����̐^�ĂɂȂ�Ƃ������Ƃł��B����ɁA���ۂɂ͒n���̋ߓ��_�͑��̘f���̉e�����Ċɂ₩�ɑO�i���܂��B���^���Ƌߓ��_�O�i�̌��ʁA�ߓ��_�ʉ߂̋G�߂���2���N�̎����ŕω����܂��B���ߓ��_�ʉ߂́A�k�����̓~�ɁA�씼���̉ĂɋN�����Ă��܂���1���N�̂��ɂ͋ߓ��_�ʉ߂͖k�����̉ĂɁA�씼���̓~�ɋN����悤�ɂȂ�܂��B ���n���̌X�� ���݂̒n���̎��]���́A���]�O���ʂɑ��Đ�������(�X�Ίp)23.5�x�X���Ă��܂��B��k�ܓx65.5�x(90�x�}�C�i�X�X�Ίp)�ȏ�̋Ɍ��ł́A���z�̒��܂Ȃ�����ƈÍ��̋ɖ邪���N�Â����܂��B���]���̌X���́A(�n�������łȂ��G���Ȃ̂�)���Ƒ��z�̏d�͂̈��͂ŁA21.8�x����24.5�x�܂�4��1��N�ʂ̎����ŕω����܂��B�X�Ίp���傫���Ɣ����ɖ�͈̔͂��L���Ȃ�G�ߕω����傫���Ȃ�܂��B ���嗤�ړ� ��ɏq�ׂ����Ƃ���ɂ���āA�k�����ւ̓��˗ʂ́A���Ƃ����z�̑S���˗ʂ������ł������N���琔�\���N�̋K�͂ŕω����邱�Ƃ��킩��܂��B�����̊��≻���������ƂȂ��đ嗤�X�͂������������Ƃ܂��܂����≻���i�݁A�����̑嗤�X�͂��Z���o������ɉ��g�����i�ނƂ����ɂȂ�悤�ł��B���݂̒n���̑嗤�͖k�����ɑ����C�͓씼���ɑ����̂ł����A����͍ŋߐ��疜�N�̏o�����ʼnߋ��ɂ����Ă͑嗤���씼���ɏW�����Ă��������o���o���ɂȂ��Ă���������������͂��ł��B�嗤�̓v���[�g�^���ɂ���ė����W�U���J��Ԃ��Ă���̂ŁA�X�͊��͌��݂̑嗤���z�����Ƃ������܂��B �@ �@ |
|
| ���X���E�ԕX���T�C�N���̊�b | |
|
��Milankovitch cycle
�V�̗͊w�I�ϓ��ɂ����˗ʕϓ��̌��ʂŏd�v�Ȃ̂́A�ȉ���2�B ���ԓ��X�p (obliquity) ���F�ԓ��ʂƉ����ʂ̂��ꂪ���ԕω����邱�Ƃ��� ����������ʁB���ܓx�n���̓��˗ʂ̋G�߂̃R���g���X�g�ɉe����^����B obliquity �́A�� 4 ���N(�ʏ� 41000 �N�ƌ�����)�����ŁA 22���` 24�����炢�̊Ԃŕω�����B ���C��I�����F���S���̕ω��ƍ��^���Ƌߓ��_�̈ړ��̑g���킹�ŁA �k�����̉Ă��ߓ��_�ɂ��邩�����_�ɂ��邩�Ƃ������Ƃ��ω�����B ���ʂƂ��ċG�߂̃R���g���X�g�̑召�ɉe������B���̎����� 23000 �N �� 19000 �N�ł���B���̎����́A���̎��� 26000 �N�� ���S���̕ω��̎���(10 ���N�A40 ���N)�Ȃǂŕϒ����ꂽ�Ǝv���Ηǂ��B ���˗ʕϓ��� 10 ���N�� 40 ���N�����̕ϓ��͂Ȃ��B �ǂ���̌��ʂ��G�߂̃R���g���X�g�Ɋւ�肪����B�k�����ŋG�ߕω����������Ȃ�ƕX��������Ƃ���Ă���B�Ƃ����̂́A�ė������ƕX���Z���ɂ����Ȃ�A�~�g�����Ǝ����ɂȂ��ĐႪ�����邩�炾�B�@ |
|
|
��10 ���N�����̕ϓ�
80 ���N�O�ȍ~�̕ϓ��� 10 ���N�����ł���B������o�����@�͂������l�����Ă���B �����炩�̔���`�� �C��I�����ɂ� 2.3 ���N������ 1.9 ���N����������A����2�����킹�����n��� envelope �� 1/(1/1.9 - 1/2.3) = 10.9 ���N�����ŕϓ�����B��������炩�̔���^���Ŏ��o���Ηǂ��B ��Paillard (1998) �̃��f�� �ԕX��(i)������(g)���X��(G)���ԕX��(i)���c�Ƃ���3��Ԃ��J��Ԃ��T�C�N���ł���Ƃ��邨�����Ⴢ�f���B���� g ��Ԃł͂������X�����������Ă��̊Ԃ͓��˂ɉ�������X�C�b�`����Ă������Ƃ��|�C���g�BG��i, i��g �́A���ꂼ����˂�����l���������Ƃ��Ɖ�������Ƃ��ɋN���邱�Ƃɂ���B����ƁA�����͔�r�I�Z������(�C��I����2���N���x)�ŋN���邱�ƂɂȂ�B g ��Ԃł́A�X���\����������܂œ��˂ɉ������Ȃ��Ȃ�B�\����������� G ��ԂɑJ�ڂ�����̂Ƃ���B�X���\����������ɂ�5���N���x�̎��Ԃ�������Ƃ��A���������˗ʕϓ������Ȃ�����(10 ���N������ envelope �̐߂̎���)�ɕX���̐������N���₷���悤�ȃ��f�������B����ƁAg��G �́Ai��g ��7���N���x��ŁA���� envelope �̐߂̎���������ɋN����悤�ɂȂ�B���̂悤�ɂ��āA���ۂ̋C��ϓ����Č��ł���悤�ɂȂ�(���������f���ɂ͂��낢��ȃl�W������)�B�@ |
|
|
�����ԕω��̋�����̔�Ώ̐�
�傫�ȕX���͂�����蓀�葬���Z����B���̗��R�́A���̂悤�Ȃ��̂ł���ƍl�����Ă���B����� ���X���f�M�ނɂȂ邽�߁A�X���̒�͒g�܂��ėZ���₷���Ȃ��Ă��邱�ƁB ���X�̏d���Œn�ʂ������邱�ƂƁA�n�ʂ̉������x�����ƁB���̂��� �\���X�������B���Ă���Z���n�߂�ƁA �@���n�ʂ��������č��x���������Ă��镪�A�X���Z����̂��e�ՂɂȂ��Ă���B �@���n�ʂ��������Ď��͂̐������ꍞ�݂₷���Ȃ��Ă���A���̐��� ���ꂪ�M��D���ĕX���Z���₷���Ȃ��Ă���B �ł���B�@ |
|
|
���X���E�ԕX���T�C�N���Ɖ������ʃK�X
�X���E�ԕX���T�C�N���Ƒ�C���̉������ʃK�X�̗ʂ̕ω��͘A�����Ă���B�ȉ��Ő�������悤�ɁA�C���Ɖ������ʃK�X�̗ʂƂ̊Ԃɂ͐��̃t�B�[�h�o�b�N�����݂��邱�Ƃ��l�����A���ꂪ�C���Ɖ������ʃK�X�̊Ԃ̑��ւ����������ł��낤�B�����āA�V�̗͊w�I�ȓ��˗ʂ̕ϓ��Ƃ������ׂȂ��ƂŁA�C��ω����N���錴���Ȃ̂ł����낤�B�ȉ��A�e�_�F �������C �u���g�ɂȂ�Ǝ����ɂȂ�A�����C�ɂ�鉷�����ʂ�������v �Ƃ������̃t�B�[�h�o�b�N�����邾�낤�B�������A���ړI�ȏ؋��� �͐ϕ��ɂ����ɂ��X�R�A�ɂ��c��Ȃ��̂�(���Ƃ��Ƃ����̂��̂� �����𑽂��܂�ł���)�A�ߋ��̕ϓ��͂��܂�悭�킩���Ă��Ȃ��B ����_���Y�f �X�R�A�̋L�^���ƁA�������ɕX���E�ԕX���T�C�N���Ɠ������ĕϓ����Ă���B �X���Ő����� 200 ppmv ���炢�A�ԕX���� 270 ppmv ���炢�B �ω��̗��R�͂悭�킩���Ă��Ȃ����A�C�ɂ͑�C���� 50 �{���̓�_���Y�f�� ���邱�Ƃ���C���֗^���Ă���ƍl������B���̃t�B�[�h�o�b�N�������� �\���Ƃ��Ĉȉ��̂悤�Ȃ��̂��l������B(1) �����Ȃ遨 ��_���Y�f�̗n��x���オ�遨�C�ɓ�_���Y�f����������n���đ�C���� ��_���Y�f�����遨�������ʂ������Ă܂��܂������Ȃ� (2) �����Ȃ遨��k�̊��g�̍������������������Ȃ遨������C�։h�{�� ������������Ă��遨�C���̐���������������ɂȂ遨���Ƃ����`�� �Y�f���C��͐ϕ����ɌŒ肳��遨�������ʂ������Ă܂��܂������Ȃ� �����^�� ������C���ɑ��Đ��̃t�B�[�h�o�b�N���l������F �����Ȃ遨���n�E���n���������邩���遨���n�E���n�ɂ����� �o�N�e���A�ɂ�郁�^�����������遨�������ʂ������Ă܂��܂������Ȃ�B�@ �@ |
|
| ���X���E�ԕX���T�C�N���ƒn���̋O���v�f | |
| ��1. ���_�@ | |
|
�ËC��̌����͐}1�̂悤�ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł��悤�B�C�m�E��C�E��X�E���ʂ����킹���u�C��V�X�e���v���l����B����͑����̕ϐ������݂ɊW���ĕω�����n�ł���B�ϐ��̗�Ƃ��ẮA�X�̑��ʁA�[�C�̐����A��C���̓�_���Y�f�Z�x�Ȃǂ�����B���ۂɊϑ����邱�Ƃ̂ł���C��w�W(�}1�̉E�[)�A���Ƃ��ΊC��͐ϕ��̗L�E���̎_�f���ʑ̑g���Ȃǂ́A���̋C��V�X�e���̕ϐ��f���Ă��邪�A���ꎩ�̂ł͂Ȃ��A�Ȃ�炩�̕ϊ� (�u�ϑ��ϊ��v�ƌĂԂ��Ƃɂ���)�������ʂł���B�C��̕ϐ��̕ω��́A�C��V�X�e�����̑��ݍ�p�����ŋN������̂����肤�邪�A�V�X�e���O����̓��͂ɂ��ˑ����Ă���\��������B�O�͂Ƃ��ẮA���z���˂̕ϓ��A����щΎR�����Ȃǂ̒n����������̍�p���l������B�ËC��̌����͈�ʂɂ͋C��w�W�̊ϑ��l���^�����Ă��邾���ŁA���͂��킩��Ȃ���A�u�C��V�X�e���v���u�ϑ��ϊ��v���u���b�N�{�b�N�X�ł���Ƃ����Ƃ��납��o�����āA���ꂼ��̓��e��m�낤�Ƃ����Ƃ��ł���B�������A�O�͂̂����A�n���̋O���v�f�̕ω��ɂƂ��Ȃ��Ēn����̊e�ܓx�A�e�G�߂Ɏ����˂��ς����ʂ������A�V�̗͊w�ɂ��ƂÂ��āA�قڌ���_�I�ɐ��S���N�̉ߋ��ɂ����̂ڂ邱�Ƃ��ł���B���������āA�����C��V�X�e���̕ϓ������̊O�͂ɑ��鉞���Ƃ��Đ����ł���Ƃ���A�������猋�ʂւ̏������ɍl���邱�Ƃ��ł���̂ʼnȊw�̉ۑ�ɂȂ�₷���B���ہA�u��l�I�v�ƌĂ��ŋ�200���N�Ԃ̕X���E�ԕX���T�C�N�����A�n���̋O���v�f�ɑ��鉞���Ƃ��Đ������悤�Ƃ����ϓ_�ŁA�������i��ł���B
������1���N�قǑO�܂ŁA�k�A�����J�ƃ��[���b�p�̂��Ȃ�L���n��ɑ嗤�X��(����ȕX��)���L�����Ă������ƁA����ɁA�X���͐���̊g��E�k�������肩�����Ă������Ƃ��A19���I�ɂȂ��Đl�ނ͔F������(���Ƃ��� ���сE����A1982�Q��)�B���̏������I�ω����O���v�f�̕ω��Ő�������l���́A�X���̓V���N�����A���邢�́A�uMilankovitch���_�v�Ƃ��Ēm���Ă���B���̗��_�ɂ��Ă̓��{��̉���Ƃ��ẮA ����(1938)�A�y��(1974, 75, 78)�A ����(1981)�A �X�R(1987)�Ȃǂ�����B Berger�ق���(1984)�͂�������Ƃ����V���|�W�E���̋L�^�ł���A�֘A����b���W�]����̂ɂ悢�Ǝv����B���̗��_�̗��j�ɂ��ẮA Berger (1988)�ɗv�̂̂悢�܂Ƃ߂�����A�܂� Imbrie and Imbrie (1979) �̓ǂݕ�������̂ŁA�����ł͂����ȒP�ɂӂ��B Milankovitch��1879�N���܂�A1958�N�v�A���[�S�X���r�A(�Z���r�A) �̗��H�w�҂ł���A�Z���{�E�N���A�[�g��̂Â��Milankovic[c�̏��'] �炵�����A����̂Â�ɏ]���Ă����BMilankovitch���g�̒���� 1920, 1930, 1941�N�̂��� ������A�ŏI�łƂ�����1941�N�̂��͍̂ŋߓ��{��o�ł��ꂽ�B�X���̌����Ƃ��ċO���v�f�̕ω����l�������҂Ƃ��ẮA Adhemar[1842�N�o��]�ACroll[1857�N�o��]�����邪�AMilankovitch�̋Ɛт͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��悤(�����ł� 1930�N�̒�����Q�Ƃ���)�B ��C��[�ɓ��˂�����˗ʂ̈ܓx�E�G�ߕ��z���Ɍv�Z�����B �O���v�f�̕ω��ɂƂ��Ȃ����˗ʂ̕ω����Ƃ��Ă͔��ɏڂ����v�Z�����B �X���E�C��̕ϓ��ɑ���O�͂Ƃ��āA�k�������ܓx(���ɖk��65��) �̉Ĕ��N�̓��˗ʂ��d�������B�X���̌`���ɂ͉Ăɉ��x��������Ȃ����Ƃ��d�v���ƍl��������ł���B Milankovitch�̊w����1930�N�ォ��1950�N��ɂ͒n���E�n�`�w�҂ɏd�����ꂽ�悤�ł���B����͈�ɂ͑��ɐ�ΔN��ړx���Ȃ�����ł������B���ː����ʑ̔N�オ�o��悤�ɂȂ�ƁA�N��ړx�Ƃ��ē��˗ʋȐ����g���K�v���Ȃ��Ȃ�A�܂��A���˗ʋȐ��ƒn���I�؋��Ƃ̂��������������ɂ����悤�ɂȂ����B�O���v�f�������Ȃ�Γ�k���������݂ɕX���ɂȂ�͂����Ƃ������ (Croll�̌����悤�ɍ�����v�ȊO���ł���A�������������C�����z�ɂ��܂���Ȃ��Ƃ���Ίm���ɂ����ł��邪)������A��l�I�C��ϓ��̌����_���O���v�f���ɂ��ƂÂ��ēW�J����l�X�͂ނ��돭���h�ƂȂ��Ă������B �������A�C��͐ϕ��̃{�[�����O�R�A�����n��Ƃ��ĉ�͂���ƁA�O���v�f�̕ω��Ɠ������������ϓ����C��w�W�ɂ������邱�Ƃ��������ꂽ�B��\�I�_����Hays, Imbrie and Shackleton (1976)�ł���B����́ACLIMAP (Climate: Long-range Investigation, Mapping, Analysis and Prediction)�Ƃ����v���W�F�N�g�ŁA�ŏI�X���̍Ő���(��1��8��N�O)�̊��̑S���E�K�͂̋�ԕ��z���܂Ƃ߂� (CLIMAP, 1976, 1981)�̂ƕ��s���Đi�߂�ꂽ�����ł���B���̐�����������Imbrie���SPECMAP�Ƃ������ŊC��R�A�̎��n���͂̃v���W�F�N�g�𑱂��A���������ꂽ���ʂ��o���Ă���(Imbrie��A1984, 1989)�B�ŋ߁A��l�I�̂��̂Ɍ��炸�A�͐ϕ��Ɍ����鏀�����I�Ȋ��ϓ������߂���ꍇ�ɂ́A�u�~�����R�r�b�`�T�C�N���v�̔��f�ł���\�����l����͓̂��R�ƂȂ�����������B Hays��̎d���͐}1�́u���́v�Ɓu�ϑ��f�[�^�v�̎��n��ɂ����̋��ʐ������邱�Ƃ��w�E�����ɂ����Ȃ��B���҂̋��ʓ_�Ƃ����Ⴂ�Ƃ�������������ł���悤�ȁA�u�C��V�X�e���v�̃��J�j�Y���͂ǂ�Ȃ��̂��͖������ł���B���̖��ɂ��ẮA����܂ł̌�����W�]���Ă݂邱�Ƃ����̎̕��ƂȂ�B�@ |
|
| ��2. �n���̋O���v�f�̕ω��Ƃ���ɂƂ��Ȃ����˗ʂ̕ω� | |
|
�����ōl����O�͂́A��C��[�ɂ͂����Ă�����˗�(���z���˂̃t���b�N�X���x)�ł���B����́A���z�̏o�����˃G�l���M�[��(���x)�ɁA�ܓx�ƋG�߂̊��ł���w�I���q�������ċ��߂���B���̈��q�́A�n���̌��]�Ǝ��]�̃p�����^(�ӂ��u�O���v�f�v�ƌĂ��)�̊��ł���B��̓I�ɂ́A���]�O���̗��S��(�O���̑ȉ~���~���炸��Ă���x����) e�A�����t���_����Ƃ����ߓ��_�̉��o _pi_(�n���E���z�Ԃ̋������ǂ̋G�߂ɍł��߂��Ȃ邩)�A�n���̌X��(�n���̎��]���ƌ��]���̂Ȃ��p) �Â����ƂȂ�O���v�f�ł���B�t�^A�ł��������ڂ�����������B�����̃p�����^��1���N�̎��ԃX�P�[���ŕω����Ă���A���ꂪ���̂悤�Ȍ`�œ��˗ʂɌ����Ă���B
�����Łu_pi_�v�ƕ\�����������́A�M���V�������̃�(�p�C)�̎��̂̂ЂƂ����A�~������\�킷���̂Ƃ͋�ʂ����B�M���V�������̃ւ̏�ɔg�`���̂����悤�Ȍ`�̎��ł���B (a) �܂��A�n���ɓ��B������˂�1�N�ԁA�S���̑���(�܂��͔N���ρA�S�ܓx����)���l���Ă݂�B�n���Ƒ��z�̋���r�̕��ς�a�ň��ł��邪�A���˃G�l���M�[�t���b�N�X��r��(-2)��ɔ�Ⴗ��B���������ĔN�ԁE�S���̓��ˑ��ʂ́Ar��1�������ςɁA�܂�1 / sqrt (1 - e2)�ɔ�Ⴗ��B e���̂��̂���������������2���̍��Ȃ̂ŁA�G�ߕʂ��邢�͈ܓx�ʂ̓��˗ʂɑ��Ă�(b), (c)�قnj����Ȃ��B�������A���S���̕ω��̌��ʂ͂��ꂾ���łȂ��A(b)�ɂ�������B (b) ���ɋG�ߕʁE�ܓx�ʂ̓��˗ʂ��l����B���S��e��0�łȂ���A���z�E�n���Ԃ̋����̔N�����ω�������̂ŁA�e�G�߂̓��˂̈ܓx�ɑ��镪�z�̌`�͕ς��Ȃ������̑傫���͕ς��B�ǂ̈ܓx�ł������ɁA�ߓ��_�ɋ߂��G�߂ɓ��˂������A�����_�ɋ߂��G�߂ɓ��˂��������B�������A�u�āA�~�v�Ƃ���������������ƁA��k�����ŋt�ɂȂ�B���݂͋ߓ��_���k�����̓~���t�߂ɂ���̂ŁA�k�����ł�(�~�O���̏ꍇ�ɔ�ׂ�)�Ă̓��˂��������A�~�̓��˂��傫���B�씼���ł͂��̋t�ɂȂ� (�}2a�A�}7a�Q��)�B���̌��ʂɂ����˗ʂ̔��ɒ������Ԃ̕��ς���̕���e sin _pi_�A e cos_pi_�̐��`�����ŕ\�킹��B�Ď��A�~���̓��˗ʂ̕���e sin _pi_�����ɔ�Ⴗ��B�t���A�H���Ȃ��e cos _pi_ �ɔ�Ⴗ��B_pi_ �̕ω��܂�u�C��I���v�ɂ��ܓx�ʁE�G�ߕʂ̓��˂̒����ϓ��̓����͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B�씼���Ɩk�����̂��ꂼ��̉Ă̓���(�܂��͂��ꂼ��̓~�̓���)�̋ɑ傪�t�ʑ��ɂȂ�B���Ƃ��Ƃ̓��˗ʂ̈ܓx���z�̌`�f���ĕ��̐U������ܓx�����ܓx�����傫���B (c) �n���̌X���Â��傫���ƁA���ܓx�̉Ă̓��˂��傫���Ȃ�B(���݂̑�C��[�ł̓����ϓ��˂́A�Ď��ɂ͋ɂ̂ق����ԓ����������Ȃ��Ă���B���̒������������߂ł���B����Ƀ� = 0 �������Ȃ�A�ɓ_�ł�(���B) ���˂�0�ɂȂ�͂��ł��邱�Ƃ��l����A���ꂪ�Â̂������ł��邱�Ƃ��킩�邾�낤�B) �n���ɓ��B����S���˗ʂ��ς��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�㏞�Ƃ��āA�~�����̓��˂��������Ȃ�A�N���ςł́A��ܓx�̓��˂��������Ȃ�B (�}2b�Q��)�B�Â̕ω��ɂ���ċN����A�ܓx�ʁE�G�ߕʂ̓��˂̒����ϓ��́A(b)�Ƌt�ɁA�씼���Ɩk�����̂��ꂼ��̉Ă̓���(�܂��͂��ꂼ��̓~�̓���)�̋ɑ傪���ʑ��ɂȂ�B�܂��A���̐U���͍��ܓx�ő傫���B���̍��́A�e�ܓx�̔N���ς̓��˂��ϓ������邪�A����͐ԓ��Ɋւ��ē�k�Ώ̂ɋN����B �}3�ɁA�O���v�f�̍ŋ�80���N�E����20���N�̎��n�������(Berger, 1978, 1979���^���Ă���O�p���W�J�̌W�����g���A���̋L�q�ɏ]���ĕM�҂��v�Z����)�B�܂��}4�͉ߋ�80���N�̎��n��Blackman-Tukey���O�����U�@�Ōv�Z�����p���[�X�y�N�g���ł���B Berger(1984)�ɏ]���āA�ߋ�5�S���N�̋O���v�f�̎��n��̓������q�ׂ�Be (����0.0167)��0.0005��0.0607�̊Ԃ��9.5���N�̎����ŐU�����Ă���B���̃p���[�X�y�N�g���ɂ́@41���A9.5���A12���A10���N�����̃s�[�N��������B�� (����23.45��)��22����24.5���̊Ԃ��4.1���N�ŐU�����Ă���B_pi_�͕���2.17���N��1������(2�ӂ���)���A�X�y�N�g���ɑ�z�������������2.3���N�t�߂Ɓ@1.9���N�t�߂ɏW�����Ă���Be sin _pi_ (����0.01635)�́A-0.05��+0.05�̊Ԃ��A��2.17���N�������u�����g�v�A e�̕ϓ����u�M���g�v�Ƃ���U���ϒ�(AM)�̂悤�ȕϓ������Ă���B �G�߂��Ƃ̓��˗ʂ̎��n��Ƃ��ẮAMilankovitch�ȗ������̕������Ĕ��N�E�~���N�̓��˗ʂ̒������ς���̕��������Ă���B�n���̌��]�p���x�����łȂ��̂Łu���N�v�̒�`�͂��낢��l�����邪�AMilankovitch�̎g�����u�M�ʓI�Ĕ��N(���邢�͓~���N)�v�͎��Ԃ�2�����������̂ŁA���˗ʂ����̒����l�����傫��(���邢�͏�����)���Ԃł���B Blatter��(1984)��1�N��4�ɕ������e�G�߂̓��˗ʂ̕��������Ă���B�����ł́A���ۂ̓����ϓ��˗ʂ̒l��\�����Ă݂��B�}5�ɁA�������̍��ܓx(65��)�ƒ�ܓx(20��)�́A�k�����̉Ď��̂���(6��21��=����) �Ɠ~���̂���(12��22��=�j��)�̓��˗ʂ́A�ߋ�80���N����э��� 20���N�̎��n��������B�������A���t�͏t����3��21���Ƃ������ΓI�Ȃ��̂ł���B�~���̓��˗ʂ��t�̔����̉Ď��̂��̂Əd�˂Ď������B�~�̍��ܓx (�ʼn��i)�̓��˗ʂ͂��Ƃ��Ə������̂ŁA�ϓ��̒l���傫���Ȃ����A��k�������̎��n��͂قƂ�Ǐd�Ȃ��Ă���A�Âf���Ă���B����ɑ��ĉĎ��̉�A���t��(�ォ��2�i��)�̓��˗ʂ�e sin _pi_ �f���Ă���A��k�����ł��ꂢ�ɋt�ʑ��ɂȂ��Ă���B �Ȃ��A�����ł͉Ď��E�~���̓��˂����������A�ĂƓ~�̓��˂ɂ������ڂ���悢�Ƃ����ۏ�����킯�ł͂Ȃ��B�ԓ��n���̓��˂̋ɑ�E�ɏ��͉Ď��E�~���̎����ł͂Ȃ��B Short��(1991)��2�����G�l���M�[���x���f�����g���������̘_���ł͂��̂��Ƃ��d�����Ă���B�܂��A���E���ܓx�ł��C��V�X�e���̊��x���G�߂ɂ���ĈႤ�\��������(���Ƃ��ΐϐ�핢��C�X�̔N�����ω��̒��̂���ʑ��ŕq���ɂȂ邱�Ƃ��z�������)�B �}6�͐}5�̉ߋ�80���N�̎��n��v�Z�����p���[�X�y�N�g���ł���B�܂��A �}7�ɂ́A���݂����9��N�O(���݂Ƌt�ɋߓ��_���k�����̉Ď��t�߂ɂ�����)�̓����ϓ��˗ʂ̈ܓx�E�G�ߕ��z�������B�@ |
|
| ��3. �C��R�A�̎��n�� | |
|
���ɁA�ϑ������C��w�W�̂����ŁA�[�C��̑͐ϕ��̃{�[�����O�R�A���璊�o��������������悤�B�g����ϐ��̈Ӗ��� �t�^B�ł��ڂ����q�ׂ�B
�����ł͌ÓT�I�ƂȂ��� Hays��(1976)�̘_���ɏ]���Č��Ă������Ƃɂ���B���̌����ł́A��C���h�m�́A�ǂ̑嗤����������[�C��2�̃R�A����͂����B��v�ȕϐ��̈�́A�L�E�����̎_�f���ʑ̔�ł���B�_�f���ʑ̔�̑��Βl��18O���傫���Ƃ������Ƃ́A�S���E�̕X�̗ʂ������������ƁA��̓I�ɂ͖k�A�����J�ƃ��[���b�p�̕X�����傫���������Ƃ������Ɖ��߂���Ă���B������́A�v�����N�g���̕��U���̎�\������v�Z�������̏�̊C�ʐ����ł���B�܂�A�����T���v������k�����Ɠ씼�����ꂼ��̋C��̓�����\�킷�Ǝv����ϐ����Ƃ����B��������n��Ƃ��ĉ��߂��邤���Ŗ��ɂȂ�͎̂��Ԃ̂߂���ł���B��ΔN�オ���ː����ʑ̂�n���C�t�]����킩���Ă���w�������������Ȃ��̂ŁA���̊Ԃ͉��ɑ͐ϑ��x�����Ɖ��肵�Ă����B �ނ�̎d���̓����́A�����̎��n����X�y�N�g����͂��Ď��g���̈�Ō���Ƃ������Ƃɂ���B����ȑO�̋c�_�̑����́A�������̈ܓx�̓��˗ʕϓ��Ȑ��ƒn���E�n�`�I�؋����A���ԗ̈�Ŕ�r������̂������B���g���̈�Ō��邱�Ƃɂ���āA�u�ǂ̈ܓx�������̂��v�Ƃ����c�_�����Ƃ܂킵�ɂ��āA�u�ǂ̋O���v�f�������̂��v�������ɍl���邱�Ƃ��ł���B����́A�C��R�A�Ƃ����A�����̂悢�L�^�̏o���ƁA�X�y�N�g����͎�@�̐i���Ƃɂ��������Ăł������Ƃł���B MEM�@(maximum entropy method)�ŋ��߂�ꂽ�p���[�X�y�N�g��(�}8)���݂�ƁA�s�[�N�͋O���v�f����ѓ��˗ʂ̃X�y�N�g��(�}9)�Ƌ��ʐ��������B���̈�v�͋��R�ł͂Ȃ��A�O���v�f���Ȃ�炩�̉ߒ����ւĕX�̗ʂ�C�ʐ����ɉe�����y�ڂ��Ă���̂��낤�Ɣނ�͍l�����B�������A���S���̃X�y�N�g���̃s�[�N�ł͂��邪�A���˗ʂ̃X�y�N�g���ł͖��m�ȃs�[�N���Ȃ�10���N�������C��R�A�ł͂�����ڗ����Ă���B �ނ�̔F���ł́A�C��R�A�ƋO���v�f�̎������̈�v�́A�C��R�A�̎��Ԗڐ���̐��x����������Ă���Ǝv��ꂽ�B�����ŗ�����t�]���āA�C��R�A�̎��n��2���N�O���4���N�O��̎����������f�B�W�^���t�B���^�Ŏ��o�����Ƃ��A���ꂼ��̐����̈ʑ��͑Ή�����O���v�f(e sin _pi_�A��)�̈ʑ��Ƃ��ꂼ����̊W�ɂ���͂����Ƃ����̂ł���B�͐ϑ��x�������肵�������܂ł̌��ʂł́A�ߋ��ɂ����̂ڂ�قNjO���v�f�Ƃ̈ʑ��̂��ꂪ�傫���Ȃ邪�A����͎��Ԗڐ��肪�������Ȃ����炾�Ɖ��߂����B�����āA�ʑ��̂�����ŏ��ɂ���悤�Ɏ��Ԗڐ����(tune-up)�����B�������݂̎��Ԗڐ���ŊC��R�A�̎��n���\�������̂��}10 (a���_�f���ʑ̔�Ab���C�ʐ����A���ꂼ�ꒆ�i���S�̂̒l�A�㑤��2���N�����сA������4���N������)�ł���B���i�ɂ͗��S��e�����킹�Ď����Ă���B���S���ɑ��Ă͒������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�R�A�̎��n��ɑ�z����10���N�����́A���S���ƈ��̈ʑ��W�ɂ���悤�ł���B ���ԗ̈�ɂ��ǂ��Đ}10���i�̋Ȑ������Ă݂�ƁA�����͎��̂悤�ɂ܂Ƃ߂���B �_�f���ʑ̔�A�����Ƃ��ɁA��10���N�̏������I�ω�����z���Ă���B �_�f���ʑ̔�Ȑ���10���N�����͑������Ώ̂łȂ��A�̂������̌`�����Ă���B�������琄�肳���S���E�̕X�̗ʂ̕ω��́A�������ƒ~�ς��A�}�ɏ�����Ƃ������̂ł���B ��C���h�m�̊C�ʐ�����10���N�����́A�����ቷ���ƒZ���������̂��肩�����Ƃ����`�����Ă���A�������͕X�̏��Ȃ������ƈ�v���Ă���B (����͗������̋C��ϓ�����{�I�ɂ͓��ʑ��ł��������Ƃ𗠂Â���B) �������A�_�f���ʑ̔�Ȑ��ƈႤ�̂́A�ቷ���̐������x�����قڈ��ł���A�̂������łȂ��_�ł���B 10���N�̂ق��ɁA�����ɂ����2���N����4���N���x�̕ϓ����d�Ȃ��Ă���B�������A���n������̂܂܌����̂ł́A����������F�����邱�Ƃ͂ނ��������B�܂��A2�̕ϐ���2--4���N�̎��ԃX�P�[���ł����ʑ��ŕω����Ă���Ƃ͕K�����������Ȃ��B �ȏ�́A�ŋ�70���N��(�n���C��Brunnhes�����Ɋ�)�̊C��R�A�̉�͌��ʂł���B���[���͐ϕ��̒������i�ނɂ��������āA������Â�����̓����͂�����Ă��邱�Ƃ��킩���Ă����B2�S���N�O����70���N�O�܂ł̎���̊C��R�A�ɂ́A�ڗ�����10���N�����ω��͌���ꂸ�A�ނ���4���N��������z���Ă���(Ruddiman��A1986)�B�܂��A��l�I�̑O���́A�㔼�����A�_�f���ʑ̔䂩�琄�肳���X�̗ʂ����ϓI�ɏ��Ȃ��A�܂����̕ϓ����������߂������B���̕ω���90���N�O����ɋN���������̋C��W�����v�ƍl����l������(Maasch, 1988)�B �Ȃ��AHays�炨��т���Ȍ�̂قƂ�ǂ̌����ł̃X�y�N�g����͂�MEM�@�ɂ���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������BMEM�͎����I���ԕω��𒊏o���邱�Ƃɂ͂�����Ă��邪�A���̐����̕ϓ������n��̑S���U�̂ǂꂾ�����߂Ă��邩�𐳊m�Ɍ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�n�����̕ϓ��ɂ͋O���v�f�Ƃ����u���v�������v�Ɏ��������킹�����̂�����炵���A�Ƃ������Ƃ͍��ł͂قڋ^���Ȃ��Ȃ��Ă���B�������A���ꂪ�����̈��łȂ��ϓ������|����قǂ̂��̂��ǂ����A�͂�����Ɗm���߂��Ă͂��Ȃ��悤�ł���B�@ |
|
| ��4. ��Ƃ��̕��@�_ | |
|
�u�C��V�X�e���v�Ƃ����u���b�N�{�b�N�X�̒��ɂǂ̂悤�Ȃ����݂��܂��Ă���̂����𖾂��邽�߂̕��@�_�́A�傫�����̂悤�ɕ�������B
(A) �����I(�M�������_�I���邢�̓V�X�e���H�w�I)�ȑԓx�B���͐M���Əo�͐M���̐������r���A���̊Ԃ̕ϊ��̐����ɂ��\���͂ǂ�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ������l����B (B) �����I�ȑԓx�B�C��V�X�e���̒��łǂ�ȕ����I�v���Z�X���N���Ă���̂����l����B �������A�ŏI�I�ɂ́A�����Ƃ��Ă��A�����I�v���Z�X�Ƃ��Ă������̂Ȃ����߂����߂�킯�ł���B���ۂ̌����ł́A�������I�ɂł��邱�Ƃ͌����Ă���B�����I�l�@�ɂ���ă��f����g�ݗ��āA���̂ӂ�܂��𐔗��I�ɂ��������錤���������B���̒��ł��A (��) ���ۓI�ȓ��͂���ꂽ�Ƃ��A�ϑ��ɍ����o�͂��o�Ă���悤�ȃ��f�����������A���̒��ŋN���Ă��邱�Ƃׂ�B (��) �����I���f���̐����I�\������͂��A�Ȃ�ׂ��K�p�͈͂̍L�����Ƃŕ\������B �Ƃ�����̍s������������悤�ł���B �X���E�ԕX���T�C�N���̖��Ɋ֗^���Ă������ȕ����ߒ��ɂ́A (1) ��C�ƊC�m�ɂ��G�l���M�[�A�� (2) ��C�ƊC�m�ɂ�鐅(���C)�A�� (3) �C���̕ω��ɔ���(��X�A�A���A�y��Ȃǂ��o�R���Ă�)�A���x�h�̕ω� (4) �ϐ�Ƃ��̕X���ւ̔��B�A����(�����A�Z���A�X�R����) (5) �X���̏d���ɂ��ő̒n��(���ɃA�Z�m�X�t�F�A�ƌĂ�镔��)�̕ό` (6) �C�m�̉h�{���Ɛ��������̕ω� (7) ��C���̓�_���Y�f�Z�x�̕ω� �Ȃǂ�����(�����ɂ���Ă�����̂����邾�낤)�B ����5�߂ł͐����I�l�@���A6-8�߂ł͕����ߒ��Ɋ�Â������f�����Љ��B6�߂ł͏�L�̕����ߒ��̂���(1)�A(3)�������l�����G�l���M�[���x���f���A 7�߂ł�(4)�A(5)�𒆐S�Ƃ����X�����f���A 8�߂ł͑��̃v���Z�X���֗^���������f���ɂ�錤�����Љ��B���ꂼ��̃��f���̂ӂ�܂��̐����I���߂ɂ��Ă͕M�҂̗͕s���Œf�ГI�ɂ����q�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̖ʂɋ�������l�� Ghil and Childress (1987)�� 10-12�͂��Q�Ƃ���邱�Ƃ������߂�B�@ |
|
| ��5. 10���N�������o�����߂̐����I���f�� | |
|
�܂��A�����I�ȗ���ŁA���˂̎��n�����͂Ƃ��X�̗ʂ̎��n����o�͂Ƃ���u���b�N�{�b�N�X�Ƃ��ċC��V�X�e�����l���Ă݂悤�B���͐M�����d�ˍ��킹�����̂ɑ��鉞�����ʁX�Ɍv�Z���������̂������킹�Ɠ������悤�ȃV�X�e������`�n�Ƃ����B���`�n�ɂ͐U���̕ω��A�ʑ��̂���̂ق��A���ԂɊւ����������A�ϕ����삪�܂܂�Ă��悢�B���Ƃ��ΐϕ�����́A���͐M�������g�������ɕ���(�t�[���G�W�J��)�A�������قǐ�Βl���傫�ȕ��f���̏d�݂����Ă������킹�����̂ƍl���邱�Ƃ��ł���B�Ƃ������A���`�����ł������A�o�͂̑�z�����͓��͐M���Ɋ܂܂ꂽ�����łȂ���Ȃ�Ȃ��B
���̏ꍇ�A���͂ł�����˗ʂɑ傫�ȃp���[�̂Ȃ�10���N�������o�͂ł���_�f���ʑ̔�̃X�y�N�g���ɑ傫�ȃs�[�N�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����ł���B���͐M���ɂ�10���N����������e��2���̍��Ƃ��Ă��邱�Ƃ͂���̂ŁA (a)�C��V�X�e���͓��͐M����10���N���������ɋ�����悤�Ȑ��`�n�ł��� �ƍl����Γ��˂ƕX�̗ʂ̊W������ł��Ȃ��͂Ȃ��B�������A2���N�A4 ���N���邢��40���N�̐M���ɔ�ׂ�10���N�����ɂ��Ĉ��|�I�ɑ傫�ȑ���������������悤�ȕ����I���J�j�Y�����l����̂�����ł���B �����ŁA (b) 10���N�����͓��˂ɑ��鉞���ł͂Ȃ��A�C��V�X�e���̒��ŋN���鎩��U���ł���B ���邢�� (c) ���˂ɑ��鉞�������A�C��V�X�e�����̔���`�����l����K�v������ �Ƃ����悤�ɔF�������悤�ɂȂ��Ă����B(c)������ɕ�����ƁA (c1) ���Ƃ���10���N�����̎���U������������n�ɊO�͂������A����U���̈ʑ����O�͂ɂ���ČŒ�(phase lock)���ꂽ���̂ł���B (c2) �n���̔���`���ɂ���Đ������A���͐M���̎����̐����{�̎����̐U���ł���B (c3) e sin _pi_�̍��̎��n��̕�炭��(envelope)�A���邢�́A���̍�������1.9���N������2.2���N�����̊Ԃł����邤�Ȃ� (combination tone, ������)���n�̔���`���ɂ���Ď��o�����B (c4) e��2���̍��ɑ������`�������ł���B (c5) ���̑��̌^�̓��˂ɑ��鉞���B���Ƃ��A2���N������ 4���N���������̈ʑ��W�ɂȂ����Ƃ��A�X�����邢�͊C�m�ɋ}���ȕω����N����Ƃ��� (Ruddiman, 1987)�B �Ȃǂ̍l��������B �����ł͔�r�I���ςɑi���₷��(c3)�ɂ��čl���Ă݂�Be sin _pi_ �̎��n��(�}3)�����āAAM (�U���ϒ�)�̃��W�I�̌����̐����}���v���o���l�͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���BAM�ϒ��ɂ����낢��ȕό`�����邪�A��{�͎��̂悤�Ȃ��̂ł��� (Connor, 1982)�B�p���g��(= 2�~���g��) ��m�A�U��Vm�̐M��(�}11a)���A�p���g����c�A�U��Vc�́u�����g�v�ő���ꍇ�A�ϒ����ꂽ�M��(�}11b)�� (Vc + Vm sin ��mt) sin ��ct = Vc sin ��ct + (Vm/2) cos (��c - ��m) t - (Vm/2) cos (��c + ��m) t �ƂȂ�B�p���[�X�y�N�g���͐}12a�̂悤�ɁA�����g�̃s�[�N��c (= 2 �� fc)�𒆐S�Ƃ��ė����Ƀ�c�������ꂽ�Ƃ���ɓ����傫���̃s�[�N���o��B�p���g����m�̂Ƃ���ɂ̓s�[�N�͂Ȃ��B�������͂Ƃ��Ă��Ƃ̐M���g�`�����o���̂ɂ́A�悭�m���Ă���悤�ɁA���͂��u�����v���A���������Ă��悢�B�����̗��z�I�Ȍ`�ɂ́A���͂����̕����������c���A���̕�����0�Œu��������u���g�����v�ƁA���͂̐�Βl���Ƃ�u�S�g�����v������B�������ꂽ���n������g�����͂���A�M���g�̎��g����m�Ɣ����g�̎��g����c�̗����Ƀs�[�N������B�������́A��c�t�߂̎��g�������̃p���[�� (��m�t�߂ɔ�ׂđ��ΓI��)���Ƃ����߂̂��̂ł���B e sin _pi_�̎��n��́A�T�^�I��AM�ϒ��Ƃ͈���Ă���Bsin _pi_ �������Ƃ��Ă�1.9���N�A2.3���N�̎�����������Ȃ��Ă���A�P���ȁu�����g�v�Ƃ݂͂Ȃ��Ȃ��B�������A�}9�̔j���Ɠ����悤�ɁAe sin _pi_ �̋Ȑ��̕�炭�����Ƃ�A�ق�e�̋Ȑ������o����_�ł́A����AM�ϒ��Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B���������āA������Ɏ����Ȃ�炩�̔���`�t�B���^�������e�̐M�������o�����Ƃ��ł���B���ہA Wigley (1976)�́A�u���͐M����2�悷��v�Ƃ����t�B���^������g���A1.9���N��2.2���N�̏d�ˍ��킳�������n�����͂Ƃ��āA�o�͐M���̃X�y�N�g����10���N�������܂܂�邱�Ƃ��������B �ł͂��̂悤�Ȕ���`���ʂ����o�����J�j�Y���͂Ȃ낤���B Imbrie and Imbrie (1980)�́A�X���̐����ɂ���ׂĂ��̕���͑����Ƃ����C��R�A�̎��n��ɂ݂��������w�i�Ƃ��A�X���͐������ƕ�����ŊO�͂ɑ��鉞�����Ԃ��Ⴄ�ƍl�����B �ނ�̍l����0�������f���͎��̂悤�Ȋɘa�^�̂��̂ł���(�\�L��ς���)�B dI/dt = �|(�h�@�|�@�heq )/ �� I�͑S���E�̕X�̗ʂ�z�肵���ϐ��ł���BIeq�͊O�͂ł���A�{���͓��˗ʂ�z�肵�Ă��邪�A�����ł͓��˗ʂ��Œ肵�ė^���Ē����(d I / d t = 0) �ƂȂ����Ƃ��̕X�̗ʂƂ����`�ɂ��Ă���B�т͌n�̉����̎��萔�����A������Ad I / d t �����̂Ƃ��ƁA���̂Ƃ��ňႤ�l�̒萔�Ƃ���B�ނ�́A Ieq�Ƃ��āA����ܓx�̓��˗ʋȐ�(��K���Ȓ萔�{��������)��^���A�o�͂��Ȃ�ׂ��C��R�A�̃�18�n�Ȑ��ɋ߂��Ȃ�悤�ɁA�p�����^�т�K���� tuning�������ʂ������Ă���B�܂��A Snieder (1985)�́A�������f���ŁA 1.9���N��2.2���N�̐����g����10���N���������邱�Ƃ��������B��������_�Ƃ��ẮA (�A)Imbrie and Imbrie�́u�悢�v�Ƃ��錋�ʂ邽�߂ɁAI�̐U�����1���߂��傫���ϓ�����O�͂heq��^���Ă��邱�� (�C)�ߋ�100���N�̓��˗ʋȐ�����͂Ƃ��Čv�Z����ƁA�Č����ꂽ�X�y�N�g����10���N���ނ���40���N�t�߂̃s�[�N�������o�邱�� (��蒷���C��R�A�̃f�[�^�̉�͂ɂ���40���N���������݂���悤�ł͂��邪�A10���N���������傫�ȃp���[�����Ƃ͍l���ɂ���) �Ƃ������Ƃ�����B2�����̎��萔�̃��f���ł̓X�y�N�g���̓����̑S���͐���������Ȃ��悤�ł���B�@ |
|
| ��6. �G�l���M�[���x���f���ɂ����� | |
|
���͂��G�l���M�[�t���b�N�X�ł��邱�Ƃ���A�C��ϓ����G�l���M�[���x�̃v���Z�X�����Œ�ʓI�ɐ����ł��Ȃ����Ƃ������҂��������B Milankovitch (1930)�͋Ǐ��I�Ȓn�\�ʂ̕��ˎ��x���l�����B���̒��Ő�X���������߂ɓ��˂𑽂����˂��A�n�\�ʂ̎��G�l���M�[�����������邽�߂���X���ێ����₷���Ȃ�A�Ƃ�����X�A���x�h�t�B�[�h�o�b�N���l�����Ă���B���������ォ��݂�ƁA Milankovitch�̃��f���́A��C����̒��g���˂̈����ɂ���肪���邵�A��C�̉^���ɂ��G�l���M�[�A���������E�����Ƃ��v�Z�ɂ���Ă��Ȃ��Ƃ����A�s���Ȃ��̂ł���B
��k1�����G�l���M�[���x���f��( ��6��2�ߎQ��)�̒��Ő�X�A���x�h�t�B�[�h�o�b�N�̖������l���� Budyko (1969)�� Sellers (1970)�́A���̃��f�� (�N���ς̕��t���f��)�̉����n���̌X���Âɔ��������˂̈ܓx���z��ς����ꍇ�ɂǂ��ς�邩�ׂ����A�����͏����������BBudyko�͏ڂ������ʂ��q�ׂĂ��Ȃ����A�O���v�f��ς����̂ɑ��Đ�X�̌��E�̕ω��͈ܓx1���ȉ��������Ƃ����BSellers�̏ꍇ�A�Â�21��55�f����24��24�f�܂ŕς����̂ɑ��āA���x�̈Ⴂ�͑S�����ς�0.6 K�A�ő�ƂȂ����ԓ�������10���̈ܓx�т�0.8 K�ł������B�O���v�f�ɔ����N���ϓ��˗ʂ̕ω��͂�������S��e�̒��ڂ̌��ʂ����邪�A�����e��2���̍��ł���A���z�萔�� 1 / 1000�̕ω��Ɠ����Ƃ݂Ȃ��邩��A��͂艞���͏������͂��ł���B �������A�G�ߕω�������ƁA�O���v�f�ɔ������˗ʂ̕ω��ɑ���C��V�X�e���̉����́A�X���E�ԕX���T�C�N�����������قǂɑ傫���Ȃ肤�邱�Ƃ�Suarez and Held (1979)�� Budyko and Vasishcheva [1971�N�A Budyko 1980������p]�ɂ���Ď����ꂽ�B�܂�A�C��V�X�e���͂ǂ̋G�߂̓��˂ɑ��Ă��������x�ʼn�������킯�ł͂Ȃ��A�q���ȋG�߂����邱�ƂɂȂ�BBudyko��Sellers�̃��f���ɔ�ׂ������͎��̂Ƃ���ɂ���B (1) �G�ߕω����l�����BSuarez and Held��1�N�����ŕω�������˂�^���āA�����Ԑϕ����邱�Ƃɂ��A1�N�����ŌJ��Ԃ��L���Ӗ��̕��t�������߂Ă���BBudyko and Vasishcheva�̂́A�ĂƓ~�̉��x�����ꂼ��ϐ��ɂƂ��ĘA����������탂�f���ł���B (2) �C�m�����w�̔M�e�ʁA����ї��̔M�e��(�C��菬����)��^�����B����͋G�ߕω��̐U���������I�ɂ��邽�߂ɕK�v�ł���B �Ȃ��ASuarez and Held�̃��f���ł́A (3) �n�\�ʉ��x�Ƒ�C�̉��x����ʂ��A���̂������̔M�̌�������̓I�ɕ\�������B (4) ����ɁA��C��2�w�ɕ����A�C���̉������z�̕ω��̈ܓx�ɂ��Ⴂ��\�������B (5) �n�\�ʂ̃A���x�h�����x�����Ɉˑ�������̂ł͂Ȃ��A1�N�ȉ��̎��ԃX�P�[���ł̐ϐ�̎��������l�����Č��߂��B�������A�Ⴊ�X���ƂȂ邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B �Ȃǂ̂��ӂ������Ă���A���ꂼ��ɋC�x�ɂ��e����^���Ă��邪�A�N���σ��f���Ƃ̈Ⴂ���l���邤���ł̖{���ł͂Ȃ��Ǝv����B Suarez and Held �́A�ĂɎc���X�̍L���肨��ёS�����ϋC���ɒ��ڂ��Č��ʂ��܂Ƃ߂Ă���B���̃��f���C��V�X�e���͖k�����̉Ă̓��˂̉e��������������B�������͂Ƃ��S�����ϋC�����o�͂Ƃ���ƁA�o�͂̒������ς���̕��͂قړ��͂̕��ɔ�Ⴕ�Ă���B���˗ʂ̕ω������������ɕ����ė^���A���ʂ����v���Ă��A�����������˗ʕω���^�����ꍇ�̌��ʂƂقƂ�Lj��Ȃ��B ���̂悤�ɐ��`�ɋ߂��n�ł́AHays�� �̌������X�y�N�g���̎����̂���2���N��4���N�͐����ł��邪�A 10���N��e��2���̍��ɂ��Ԃ������o�Ȃ��B���������āA�C��R�A��10���N�������������ɂ́A���̃��f���Ɋ܂܂�Ă��Ȃ����J�j�Y����lj�����K�v������ƍl������B�@ |
|
| ��7. �X�����f���ɂ�鎞�n��̍Č� | |
|
���˗ʕω�����͂Ƃ���10���N��������郁�J�j�Y���Ƃ��āA�X���̃_�C�i�~�N�X���l����͎̂��R�Ȃ��Ƃł���B�X�̂���{(�~��)�A���Ղ̂ق��X�̗�������т��̏d���ɂ��ő̒n���̕ό`��������x�l�������͊w���f�������̖��ɓK�p�����̂́AWeertman (1976) �����߂̂悤�ł���B���ꂩ�� Oerlemans (1980), Birchfield�� (1981)�̎d�����o�āAPollard (1982)�Ɏ����āA�ϑ����ꂽ�_�f���ʑ̔�Ƃ��Ȃ�߂��X�̎��ʂ̎��n��̍Č��ɐ��������B�������A�����̌����ł́A���͂Ƃ��ẮA�X���̋ύt�� (�X�̂���{�ʂƏ��ʂ���v����ʒu)���k�����̂���ܓx�̉Ă̓��˗ʂ̕ω��ɔ�Ⴕ�ĕ��s�ړ�����Ɖ��肵�Ă���B
�ނ�̃��f���́A���������ɂ͈�l�ȏ��l���A�X�̉^���������Ɋ�Â��āA��k1�����̖��Ƃ��āA�X���̍����ƕX���̒�(��Պ�Ɛڂ���Ƃ���)�̍�����\����̂ł���B�������A�ŏ��� Weertman (1976)�́A�X�����S�Y���̂Ɖ��肷�邱�Ƃɂ��A�X���̌`�́A���t���ł���A�f�ʂ��������ƂȂ�`�ƂȂ�A���ꂼ��̎��_�ł̕X�̑��ʂ����܂�ƒx��Ȃ��ɂ��̌`�ɒ��߂����Ƃ����BOerlemans (1980)�� Pollard (1982, 83)�́A�X�̉^�����������g���Ă��邪�A�ό`���x�Ɖ��͂̊W�͉��x�Ɉˑ����Ȃ��Ƃ����A�u�ȒP�ȗ����v�^ (��6��4�ߎQ��)�̂��̂ł���B�e�ܓx�̕X���̍�����ϐ��Ƃ��A�������������ϕ����āA���̔���`�g�U�������̌`�ɂ������̂�p���Ă���B�X�ɂƂ��Ă̊�Պ�ł���ő̒n���̉����ɂ��ẮA Weertman (1976)�͑����ɃA�C�\�X�^�V�[(�d���̋ύt)�����藧�Ɖ��肵���B Oerlemans (1980)��1���N���x�̎��萔�̒x����l�����BBirchfield�� (1981)�͂�茻���I�ƍl������3��N���x�̎��萔���l�������A10���N�����̉����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B Pollard (1982)�́A�A�Z�m�X�t�F�A (�㕔�}���g���̂�����r�I�Y���I�ȕ���)�𔖂����̑w�ŋߎ�������@�ŁA���`�g�U�^�̎��ŕ\�������B �܂�Pollard (1983)�́A Pollard (1982)�̃��f�����C�̊g�U�^�G�l���M�[���x���f���ƌ������āA���˗ʂ̈ܓx���z����͂Ƃ��ė^���A�O�̘_���Ɠ��l�Ɋϑ��Ɏ������n����Č������B�O�̘_���̓��͂Ɋւ��鉼�����蕨���I�����̂�����̂ɂ������������ƂɂȂ�B�X�����f�����ܓx�����̊��ł����k1�������f���ł���̂ɑ��A��C���f���͓����̎�����������2�����g�U�^���f���ł���A��◝�z�����ꂽ�C�����z�����B���̂悤�ȍ\���ɂ������R�́A�����炭�A�����I�ȐU���̋C��ϓ������̂ɁA�C�Ɨ��̗������K�v�ł���A�C��̋�C�Ɨ���̋�C�̔M������\������̂ɂ́A���ڂɁu������v�Ƃ����\�����K�����ƍl�������炾�낤�B�C���ƒn�\�ʉ��x�̋�ʂ͂��Ă��Ȃ��B�܂��A�X���̂���{�ɂ��ẮA��C���f���������C�Ƃ����ϐ����܂܂Ȃ��̂ŁA�~���ʂ����݂̊ϑ��l�ŌŒ肳��A���ꂪ��ɂȂ邩�ǂ������C���Ō��܂�Ƃ��Ă���B �_�f���ʑ̔�Ȑ��ɂ���10���N��������т̂������g�`����邽�߂ɁA�Ȃ�炩�̔���`���������Ă���͂��ł���BPollard�����낢��ȃv���Z�X����ꂽ�蔲�����肵�Ē��ׂ��Ƃ���ɂ��A (a) �X�̒~�ςɂƂ��Ȃ��Ēn��(�X�̖�)�������Ȃ�A���x��������ƂƂ��ɐ����C�����ɂ����Ȃ� �Ƃ������Ƃ����������x�̔���`���͏o�Ă��邪�A�ނ���A (b) �X�̏d���ɑ���ő̒n���̉������x��邱�� (c) �C�ʂ�ɐڂ��������ŕX�R�̕���(calving)�ɂ������悭�X�����Ղ��邱�� ��2�̌��ʂ��Ȃ��Ɗϑ��Ɏ����X�̗ʂ��Č�����͍̂���ł���B�������A (c)�̌��ʂ͒�ʂ��ނ��������A���f���ł̕\�������������l�ŗ^����Ƃ���������ۂ����̂ł���B���̂ق��A���̃��f���ł͎�����Ă��Ȃ����A Ruddiman�炪�w�E���Ă��� (d) �X���̂Ƃ������C�̕\�ʂɍL����A�C�X�����₷�����āA�C�����C�ւ̐����C���������Ȃ����A�X���̂���{�ƂȂ�~�������Ȃ����Ă��܂� �Ƃ������ʂ�(c)�̑���Ɍ����Ă���\��������Əq�ׂĂ���B Hyde and Peltier(1985, 1987) �́Acalving��C�X�̂悤�Ȃ悭�킩��Ȃ��v���Z�X���l���Ȃ��Ă��A��L��(a)�A(b)������10 ���N�����������Ǝ咣���Ă���B�ނ炪�d�_��u���Ă���̂͌ő̒n���A�Ƃ��ɏ㕔�}���g���̗͊w���f��( Peltier, 1982�Q��)�ł���B�X�̏d���ɑ���ő̒n���̉����̒x����A��̎��萔�ŕ\������͖̂���������A�����X�P�[���ɂ���Ĉ�����������Ԃ��l����K�v������A�܂� Pollard�̂悤�ɃA�Z�m�X�t�F�A����̑w�ŋߎ�����̂��悭�Ȃ��A�Ƃ����̂��ނ�̎咣�ł���B���̂��ߌő̒n���͑S���̈�ŋ��ʒ��a���œW�J���A�e���[�h���ƂɈႤ���萔�̉������v�Z���ďd�ˍ��킹�Ă���B�X�̕����͎��Ώ�(2�̈ܓx�~�ɂ͂��܂ꂽ�֏�)�����肵�A��k1�����̔���`�g�U�������Ɏ������ށB��C���̉ߒ��̓��f���Ɋ܂܂�Ă��炸�A�O�͂Ƃ��Ă�Weertman�Ɠ��l�A�ύt���̈ܓx���w�肷����@�ɂ���Ă���B 1�߂̘_���ł́A�����I�O��(���Ƃ���2.3���N����)����ł�10 ���N���x(���Ƃ���9.2���N)�̎���������邱�Ƃ��������B 2�߂̘_���ł́A�k�������ܓx�̓��˗ʋȐ��ւ̉����Ƃ��āA�C��R�A�̎��n��Ɏ����X���̕ω����Č��ł��邱�Ƃ��������B Hyde and Peltier�̃��f���Ɏ����I�O�͂�^����ƁA���͂̎����̐����{�̂��̂̂����A10���N�����ɋ߂����̂��I���B 5�߂�(c2)�̃��J�j�Y���ł���BPollard�̃��f���ł��A�����I�ȊO�͂�^���āA��10���N�������o�邱�Ƃ��m���߂Ă���( Pollard, 1984)�B�����̃��f���͊O�͂Ȃ��Ŏ���U�����N�������( 5�߂�(b)��(c1) )�ł͂Ȃ��悤�ł���B(���������̓_�͊m�F���Ă��Ȃ��B)�@ |
|
| ��8. �����C�����Ɠ�_���Y�f�̕ϓ� | |
|
6, 7�߂̋c�_���G�l���M�[���x�A�X�̎��ʎ��x���������ׂ��������Ă����̂ɑ��āA��葽���̃v���Z�X���ɍl���悤�Ƃ���Ghil�A�X�R�A Saltzman��̌���������B�������A��������A��ԕ���\��0�����ŁA�S�����v�̗ʂŋc�_��g�ݗ��Ă悤�Ƃ������̂ł���B��������ԕ��z���{���I�ł��荇�v�ʂŘb�����܂Ȃ��\��������̂����A����������Ǝ��R�x(�����I�ȕϐ��̐�)���ӂ��āA�l���邱�Ƃ��ނ��������Ȃ邩������Ă���̂ł���BSaltzman (1987)�ɏ]���ċc�_��i�߂�ƁA1���N����10���N�̎��ԃX�P�[���̕ϓ���������邽�߂ɂ́A�\��ϐ�(�A���������Ɏ��ԕω����̂͂����Ă���ϐ�)�́A���Ȃ��Ƃ�1��N�ȏ�̎��ԃX�P�[�������������̂��l����悳�����ł���B����Ɋ܂܂��ʂɂ́A�X�̗ʂ̂ق��A�C��n�S�̂̕��ω��x(���ʂ��l������Ɛ[�C�̉��x�Ƃقړ���)�A��C���̓�_���Y�f�Z�x�A�ő̒n���̕ό`�Ȃǂ�����B
��C����ъC�m�����w�̉��x�́A��N�ȏ�̎��ԃX�P�[���ł́A�X�̗ʂȂǂ̒x���ϐ������܂�A�����̉��Ƃ��Đf�f�I�Ɍ��܂���̂ƍl���Ă悳�����ł���B�������A�[�w�܂ł̊C�̉��x�́A�X���̔��B�Ɠ������x�̎��ԃX�P�[���ŕω�����Ǝv����̂ŁA���������߂�Ƙb�͕��G�ɂȂ肤��B���ɁA���x���Ⴍ�Ȃ�ƕX�̐��������܂�������悤�ȕ��̃t�B�[�h�o�b�N���l����ƁA�O�͂Ȃ��ɐU�����鎩��U���n����邱�Ƃ��ł���B���ہA�X��������{���邽�߂ɂ͐�ƂȂ鐅���C�̋������K�v�ł���B���x���Ⴍ�Ȃ肷����ƁA��ɂ͖O�a�����C���̉��x�ˑ����̂��߁A������ɂ͊C�X���C����̏��������܂����邽�߂ɁA�����C���������邱�Ƃ͂��肻���ł���B(��ɕX���̕X�R�A�̉�͂ɂ��A������̂ق����X���̂���{�����Ȃ������炵���B) ������d�����Ĕ��ɒP��������A���̂悤�ȃ��f��������B �bI(dI/dt)�@���@a�s �bT(dT/dt)�@���@�|b�h (*) ������I�͕X�̑��ʁAT�͋C��n�S�̂̕��ω��x(��Ƃ��Đ[�C�̉��x�f����)�����ꂼ�ꖳ�������������̂Ƃ��ACI��CT�͂��ꂼ��X���̃_�C�i�~�N�X(��Ƃ��ė���)�̎��萔�A�C��n�̔M�e�ʂɑΉ����鎞�萔�Ƃ���B a��b�����̒萔�Ƃ��ACI��CT���قړ������Ƃ���ƁA���̌n��TT��I�͊O�͂Ȃ��ɐU�����AI��T���1 / 4�����x���B�Ȃ��A���̐U���n�͐��`�ł���A�U���̐U���͏����l�������Ŏ��R�ɂƂ��B�������A�����ɏ��a�����ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�킯�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ������B6�A7�߂őO��Ƃ����悤�ȁA���x���オ��A�X�̏���(�Z�������)���ӂ��邱�ƁA�Ⴊ�J�ɕς��A����{�����邱�Ƃ�2�́Aa�ɂ�����ʂ��������Ă��邩��ł���B �ϐ����u���x�v�Ɓu�X�̗ʁv��2�����ɂ��Ȃ���A�p�����^�ɂ������������I�Ӗ��Â������A����ƂƂ��ɔ���`���ʂ��������� Kallen, Crafoord and Ghil (1979) �̃��f��������BGhil and Le Treut (1981)�ALe Treut and Ghil (1983)�͂���Ɍő̒n���̉����̒x����������A���낢��ȓ��͂ɑ��鉞�����c�_���Ă���B�����̃��f���ŐU�����N���邵���݂͖{���I�ɂ͂����ɏq�ׂ��悤�Ȃ��̂ł���B�������A����`���̌��ʁA(I, T)�̋�� (�����)�ł�����̌o�H��"limit cycle"�Ƃ��Č�����B�܂�A�����̃��f���̂��������ł́A���x��X�̗ʂ̕ϓ��̐U�������R�ɂƂ��̂ł͂Ȃ��A�ϓ��̉ߒ������܂��Ă��܂��B���̎��ӂ̏�Ԃ���o������ƁA�������Ԃ����Ƃ��̎����ϓ��ɋ߂Â��B5�߂Łu����U���v�ƌ������ꍇ�A���̂悤��limit cycle��(*)���̂悤�Ȑ��`���R�U������ʂ��Ȃ��������A���̐��w�I�\���͈�������̂ł���B ������A��_���Y�f�Z�x�̖�肪����B���ꂪ�X���E�ԕX���T�C�N���̗v�����Ƃ����l���͌Â����炠�������A�ŋߓ��ɒ��ڂ����悤�ɂȂ������������̈�́A�O���[�������h���ɂ̕X���R�A�̋C�A�̕��͂���A���ۂɕX���̑�C����CO2�Z�x���Ⴉ�������Ƃ��킩��������( Neftel��A1982; Lorius, 1989)�ł���B�܂�������́A��C��z���f���ɂ��ŏI�X���Ő����̃V�~�����[�V����( Manabe and Broccoli, 1985a, b, Broccoli and Manabe, 1987)�ŁA�k�����ɕX����u�������ł͓씼���̋C������������ʂ��Ȃ��A���ۓ씼���������������Ƃ��������̂͂����炭CO2�ł��낤�ƌ��_�������Ƃł���B (����͊C�m�������f���ł͂Ȃ��̂ŁA�u�C�m���ԓ����z���ĔM���^�Ԍ��ʁA��k�����������Ɋ����Ȃ�v�Ƃ����\�����ے肳�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�������A�X���̐[�w�z�͌��݂����ォ�����炵���̂ŁA�C�m�̔M�A���ɂ������͍���ł���B) �X�R�A�ɂ݂����C����CO2�Z�x�̕ω��ƁA�����X�̎_�f���邢�͐��f�̓��ʑ̔䂩�琄�肳�ꂽ���x�̕ω��Ƃ̊ԂɈʑ��̂���͂Ȃ��悤�ł���B CO2��ω�������v���ɂ��āA���ƂɁA��X���ɋ}����CO2�������������R�ɂ��āA���낢��Ȑ��������݂��Ă��邪�A�܂�����͂Ȃ� (Broecker, 1982; Broecker and Peng, 1987a, b, Martin, 1990)�B��̐�(Knox and McElroy, 1984�A�ق�)�́A�C�m�̐A���v�����N�g���̌����������������ł���Ƃ������̂ł���B�������͎�Ƃ��ĉh�{��(�����A���f�A���邢�͓S)�̕��z�ɂ���Đ���Ă��邪�A���˗ʕω��ɔ����Ă�������x�̕ω�������A���ꂪ�h�{����ʂ��ĕʂ̋G�߁E�ꏊ�̌����������ɂ��e�����āA�C�m�̂Ƃ肱�� CO2�ʂ��S�̂Ƃ��ĕς��Ƃ����_�ɂȂ��Ă���B������ɂ���A CO2�͉������ʂ�ʂ��ċC���ɂ͂˂�����B�Ȃ��A���˂ɑ���CO2�̉������ǂ���̔����ł������悤�ɋN����Ƃ���A�����e sin _pi_�̋Ȑ����u�S�g�����v����e�̐M�������o�����J�j�Y���ƂȂ邱�Ƃ����҂ł���B�������A���ۂɌ��̗ʂ��������ʂ�傫�����Ă���ꏊ�͏��Ȃ��A���̌��ʂ��d������͖̂���������炵���B �X�R��Saltzman�͂��ꂼ��ɐ����ECO2�t�B�[�h�o�b�N�����Ă��邪�A���ʂƂ��ċN����C��n�̐U���ɑ��邻�̖����͈���Ă���B Moriyama (1986)�̃��f���͊�{�I��Ghil and Le Treut�̂��̂Ɠ����ł���B����������U���̎�����Ghil��̃��f���ł�1���N�̃I�[�_�[�������̂��A10���N�����ɂȂ�悤��CT��1��N����1���N�ɑ傫�����Ă���B (Saltzman�̃��f���ł����l�ɑ傫��CT���̗p���Ă���)�B���ꂾ�����ƁA���˗ʂɑ��鉞����10���N��������z�������̂ɂȂ�B����ɓ��˗ʂ����_���Y�f��ʂ��ĉ��x�ւ̃t�B�[�h�o�b�N��������ƁA2���N�����ɑ�����`�I���������܂��āA�X�̗ʂ̎��n��̓������ϑ��ɋ߂Â��A�Ƃ����咣�̂悤�ł���B�������A�X���̔��B�Ɍ����̂��k��10���̉Ă̓��ˁACO2�Ɍ����̂��k��65���̓~�̓��˂��Ƃ�������ɔ��ɔC�Ӑ�������B Saltzman (1987)�́A�X�̗�I�A�C�m�[�w�̉��xT�A��C����CO2�Z�x�ʂ�3�̗\��ϐ��������f�����l�����B�C����C�m�\�w�̉��x�͂���炩��f�f�I�Ɍ��܂�Ƃ���B���̃��f���ł́A��10���N�̐U��������I�ɋN����B�܂��A�O���v�f�̂�����`�������O�͂Ƃ��ė^�����Ƃ���I�̕ϓ��́A�C��R�A�̃�18O�Ƃ悭�����̂��������������BT�͂قƂ��I�ƕ��s���ĕϓ����Ă���(�X�̑����Ƃ�����)�A���������������ʂ̑��݂��U�����`������̂ɖ{���I�ł���B�Ȃ��f�f�ϐ��ł���C���͂قڃʂƘA�����Ă���悤�ł���B�֘A����_���Ƃ��āA Saltzman and Sutera (1984), Saltzman��(1984), Saltzman and Maasch (1988), Maasch and Saltzman (1990)������B ������0�������f���̖�����́A�u����ȃt�B�[�h�o�b�N�����肤��v�Ƃ������ƁA����ѕ����̃t�B�[�h�o�b�N�������������ꍇ�ɂǂ�Ȃ��Ƃ������肤�邩���Ƃ��Ď������Ƃł���B����g�ݍ��킹�ɘ_���I���������邱�Ƃ��������Ƃ͂��܂ɂ͂ł��邪�A�����̃��f���̂ǂ��炪�������������邱�Ƃ͂ނ��������B���Ƃ������I�ȊO�͂̂��ƂŃV�~�����[�g�������ʂ��ËC��w�W�̎��n��Ɣ�r���Ă��A���̈�v���悢���f���̂ق����������Ƃ������Ƃ͕K�����������Ȃ��Ǝv���邩��ł���B�@ |
|
| ��9. �X���E�ԕX���T�C�N���͂�����n�܂����̂� | |
|
��l�I�Ɍ�����悤�ȁA�嗤�X���̏������܂ދC��̏������I�ϓ��́A���� 1���N�̂����ŁA���ɂ͊m�F����Ă��Ȃ��B�n������敪�Ƃ��Ă̑�l�I�̏���(��200���N�O)�́A����̏ꏊ�̒n�w�Ō��߂����Ƃɂ����Ȃ����A�قڂ��̂��납��A����ȑO���傫�ȐU���̏������I�ϓ����N����悤�ɂȂ����炵���B�܂��A��l�I�̒��ł��̐��̕ω����������悤�ł���B 3�߂ŏq�ׂ��悤�ɁA10���N�������ڗ��͍̂ŋ�70���N�قǂł���A���̑O�͂ނ���4���N�������ڗ��B�n���̋C��̍\���v�f�����{�I�ɕς�����Ƃ͎v���Ȃ��̂����A�U���^�̕ω����N��������N����Ȃ������肷�邱�ƁA�܂���z�������ς�邱�Ƃ��ǂ̂悤�ɐ���������悢�̂��낤���B
Moriyama (1987)�́A Kallen��(1979)�̃��f���̃p�����^�ˑ����ׁA�p�����^�̂�����肵���ϓ��ɑ��āA�U�����Ȃ��C��U������C��ւ̋}�ȑJ�ڂ��N����\�������邱�Ƃ��w�E�����B��́A�[�C�܂Ŋ܂߂��C��V�X�e���̔M�e�ʂ��猈�܂鎞�萔CT�ƕX���̗����̎��萔CL�̔䂪�ς��Ɖ��̍\�����ς�肤��B������A�X�������B������嗤�̈ܓx���z�̕ω��f���āA���f���̎��̌W��( 8�߂�(*)����a�ɑ����������)���C������邱�Ƃɂ���Ă����̍\�����ς�肤��BMoriyama�͑嗤�ړ��ɂƂ��Ȃ���҂̕ω����X���E�ԕX���T�C�N�����J�n�������Ɛ������Ă���B North��(1983)�́A�G�ߕω����܂� 2�����g�U�^�G�l���M�[���x���f���ɂ�錤���̎咣�́A���݂̃��[���V�A�̂悤�ɑ傫�ȑ嗤�ł͉Ăɗ���̋C���������Ȃ�̂ŕX�����ł��ɂ����Ƃ������Ƃł���BCrowley��(1986) �͂���̉��p�Ƃ��āA�O���[�������h�̈ܓx�̕ω����X���̔��B�ɏd�v�Ȗ�������ʂ������ƍl���Ă���B �嗤�ړ������Z�����ԃX�P�[���ł̋C��V�X�e���̊O���p�����^�̕ω��Ƃ��Ē��ڂ���邱�ƂɁA�`�x�b�g�����E�q�}�����R����10���N�Ԃ� 1 km���x�̑��x�ŗ��N���Ă���Ƃ������Ƃ�����B���̂Ԃ��ߋ��ɂ͎R���Ⴉ�����Ƃ���A��C�̉^���̌`���A���邢�͐�X�̕��z������Ă��Ă����������Ȃ��B Kutzbach��(1989), Ruddiman and Kutzbach (1989)�́A��C��z���f���ŎR�Ȃ��������s�Ȃ��A�~�̕ΐ����̒J�̈ʒu���ς��A�k�A�����J�X���̒��S���ƂȂ������u���h�������t�߂̓V�ς�����\�����q�ׂĂ���B����A�`�x�b�g�E�q�}�����̗��N�͂܂��Ẵ����X�[���z���傫���ς����͂��ł���( �����A1980)�B Maasch and Saltzman (1990)�͔ނ��0�������f���̃p�����^�̂��₩�ȕω��ɔ����ĐU���̂��悤���}�ɕς�邱�Ƃ��������BMoriyama (1987)�Ɠ��l�Ȕ����ł��邪�A�ނ�͂�����90���N�O�̋C��̐��ω��̐����Ɏg�����Ƃ��Ă���B �����ł͈��ƍl���Ă����A���˂Ɍ�����C�����A���邢�͑��z�G�l���M�[�t���b�N�X���̂���(���z�萔)�̕ω����l�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��ΎR�n�̗��N�ɔ����ĕ�����p�������ɂȂ�A��C�g���ɉe�����邾�낤�Ƃ����c�_������Ă���B��C�g���̕ω��̎��Ԃ́A�͐ϕ��̓��ʑ̕��͂��i�ނƂ킩���Ă���Ɗ��҂ł���B ��l�I���Â�����̑͐ϕ��ɂ��A�O���v�f�̎����Ǝv����2���N�A 4���N�A10���N�����������邱�Ƃ�����( Fischer, 1986; Berger, 1989)�B�Â�����̑͐ϕ��̎������̉�͂Ɏg���Ă���ϐ��́A�܂��C��ϐ��Ƃ̑Ή������Ă��Ȃ����̂������B�C��ϓ��̑傫���͑�l�I�ɔ�ׂ�Ώ����������Ƃ����̂��펯�ƂȂ��Ă��邪�A�����ړx�Ŕ�r���Ċm���ɂ����Ȃ̂��m�F����K�v������B ������̖��́A��l�I��10���N�����̐����̂قƂ�ǂő嗤�X�����s���̕��i�Ƃ���Ă��邱�Ƃł���B���E�ɑ傫�ȕX�����Ȃ������ƍl�����Ă��锒���I����Ñ�O�I�̎����10���N�����ϓ����������Ƃ���ƁA�ʂ̃��J�j�Y�����l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A���� 10���N������������Ƃ������A����e sin _pi_ �̋Ȑ��Ɠ��l�� 2���N������10���N�ŐU���ϒ�����Ă���Ƃ����Ӗ��Ȃ�A ���邢�� �ϑ��l�̃X�y�N�g����10���N�����������Ă��A���ꂪe sin _pi_ �ɔ�Ⴕ���C��ϐ��̕ω����A����`�́u�ϑ��ϊ��v��ʂ��Č������̂ł���A �u10���N�����̋C��ϓ��ɂ͑嗤�X�����K�v���v�Ƃ����c�_�͂�����Ȃ��B ������ɂ��Ă��A���̂悤�ȋC��̑̐��̕ω��̌����́A�؋��̖ʂł��A���_�I�ʂł��A�܂������I�i�K�ɂ���ƌ����邾�낤�B�@ |
|
| ��10. ����ւ̖�� | |
|
�X���E�ԕX���T�C�N���ƋO���v�f�̊֘A�̋c�_�ŁA���낢��ȃ��f���̂����ꂪ�������̂��̌������邽�߂ɂ́A�����̒~�ς��܂��܂��s�����Ă���B�m���ɊC��R�A�̎��n��I��͂͐i���A���鎞�Ԓf�ʂł̑S����ԕ��z���܂Ƃ߂�ꂽ�̂́A1��8��N�O( CLIMAP, 1981)����ш�O�̊ԕX���ł���12���N�O( CLIMAP, 1984)�����ł���B�嗤�X���A��_���Y�f�A�C�X�ȂǂȂǂ́u�ǂ��炪�悩�v�Ƃ������ɓ����邽�߂ɂ́A�����Ƃ�������̎��Ԓf�ʂł̐��E�����ق����B��ɂ͑�l�I�͈̔͂Ŏ��ԕ���\���ׂ������邱�ƁA������ɂ͂��Â�����ɂ킽���đ�l�I�ƒ�ʓI�ɔ�r�\�Ȍ`�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃł���B�ϑ��������܂Ƃ߂邾���ł��A�����̐l�̎Q���A���������݂̂��Ƃ̓����K�v�Ƃ���A��v���W�F�N�g�ɂȂ肻���ł���B
�܂��A�S�̑��邽�߂ɂ́A�ϑ��̂Ȃ��Ƃ���͂Ȃ�炩��(�o���I�Ȃ��̂��܂߂�)���f���Ŗ��߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B��C�̑�z���f��(�\�f��) ���g��������̋C�ۃf�[�^�́u4���������v�͂��Ȃ�̐����������߂Ă���B�܂��ACLIMAP�֘A�ł́A��C�������邢�͂���ƊC�m�����w��ϐ��Ƃ��A�X���Ȃǂ��Œ肳�ꂽ���E�����Ƃ���1��8��N�O�̋C��̍Č��������s�Ȃ�ꂽ�B����A�ő̒n���̃��I���W�[�̃��f���ł́A�O�͂Ƃ��ĕX���̏d���̂ق��C���̏d���̕��z�̕ω����l�����A�e�n�_�ł̒n�k�ƊC�ʂƂ̑��Εψʂ��V�~�����[�g���āA�C�ݒi�u�̍����Ȃǂ̒n�`�w�I�؋��Ɣ�r���錤�����s�Ȃ���悤�ɂȂ���(���c�ELambeck, 1988)�B���Ɋ��҂����̂́A�X���A�[�C�A�ő̒n���Ȃǂ̂������n�̎��Ԕ��W��\��^���f���Ŏ��ԊO�}���邱�Ƃɂ��A�ϑ��f�[�^�����Ă����A�ËC��f�[�^��4���������ł���B����ɓK�����X�����f���A�ő̒n���̃��I���W�[���f���̌��݂͂��ꂩ��̉ۑ肾���A�C�m�A���ɐ[�w�z��C�X�̃��f���ɂ��Ă��o����ς܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�A��C�́u�����v���Z�X�v�Ȃ̂łȂ�ׂ��������čl�������̂����A��C��[�̓��˗ʂƊC�����z�A�n�`�A�X�̕��z��^����ꂽ�Ƃ��A��C�̏�ԁA���Ƃ��Β��v���l�^���[�g�̒J�̈ʒu�A�_�̕��z�A�~�����z�Ȃǂ��ǂ����܂邩������悤�ɂ͂܂��Ȃ��Ă��Ȃ��B��C�̃��f�����O�̌������A�܂����̃p�����^�����߂邽�߂̊ϑ����A�K�v���͌����Ď����Ă��Ȃ��B 1992�N7���NjL: �l��(1992)�́A�C��R�A�̎��������琄�肵����l�I�̒n���C���x�̎��n���������邽�߁A�X���̏���(�܂藤�ƊC�Ƃ̐��̎��ʔz���̕ω�)�ɔ����n���̊������[�����g�̕ω����A�n���̎��]�̕ϓ���ʂ��Ēn���̃R�A(�j)�̗��̂̉^���ɉe������Ƃ�������������B�Ƃ��낪�A���˗ʂɊW����O���v�f�́A���͌��]�Ǝ��]�̃p�����^��g�ݍ��킹�����̂ł���B�X���̕ϓ������]�̃p�����^��ς�����Ƃ������Ƃ́A�O���v�f���C��V�X�e���ɂƂ��đS���̊O�͂ł͂Ȃ��A�O���v�f�ƕX�̗ʁE���z�Ƃ̊Ԃ̃t�B�[�h�o�b�N�����肤��Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B Rubincam (1990)�́A�ΐ��̏ꍇ�ɂ��āA��X�̎��ʈړ�����O���v�f�ւ̃t�B�[�h�o�b�N���c�_�����B�n���̏ꍇ���܂߂��v�Z�͌��݁A���嗝�w���̈ɓ��F�m�ɂ���Đi�s���ł���B�@ |
|
| ���t�^A / �n���̋O���v�f�ɂ��Ă̕⑫���� | |
|
�܂����]���l����B�V�̂Ƃ��Ă̒n���̉^���́A���_�̗͊w�ł悭�ߎ��ł��邪�A����ɍ�p����͂́A���z�̏d�͂̂ق����̘f���̏d�͂�����B���������Ă��̗\�����͑��̖��ƂȂ�A�����ɂ͂Ƃ��Ȃ��B�������K���A���z�̎��ʂ��f���̎��ʂ��������Ƒ傫���̂ŁA�n���̉^���͒Z���I�ɂ͑��z�E�n����2�̖��̉��ł���Kepler�^���ł���A���̃p�����^�����̘f���̉e���ł������ƕω�����Ƃ�����舵��(�ۓ��@)���ł���B�@Kepler�̖@���ɏ]�����^���Ƃ����Ă����R�x������A1�̋�̓I�ȉ^�����w�肷��ɂ́A6 �̃p�����^���w�肷��K�v������B���Ƃ����鎞���̘f���̈ʒu�Ƒ��x�̂��ꂼ��3�����x�N�g���̐������w�肵�Ă��悢�B�������V���w�ł́A���̗v�f���g���K��������Bi�ȉ��́A�}13�̂悤�ɁA���z�𒆐S�Ƃ���V��(�P�ʔ��a�̋�)�̕\�ʂł̈ʒu�̎w��ł���B�Ȃ��AKepler�^���͑o�Ȑ��A���������܂ނ������ł͑ȉ~�̏ꍇ�Ɍ���B
a�@�ȉ~�O���̔����a(�����ق��̑Ώ̎��̒��a�̔���)�B Kepler�^���ł͂���͑��z�Ƙf���Ƃ�(���Ԃɂ��Ă�)���ϋ����ɓ������B e�@�ȉ~�O���̗��S��(eccentricity)�B���Z�a��b�Ƃ���ƁA e = sqrt( a2 - b2 ) / a�B ���@�O���X�p(inclination)�B�����ʂɑ���A�O���̊܂܂��ʂ̂Ȃ��p�x�B ���@����_���o�B�O���ʂ���ʂƌ����_�̂����A�f���̉^������ʂ̉�������㑤�Ɍ������_������_�Ƃ����B�V����E��ʏ�Ŋ����(�ӂ��t���_���Ƃ�)���珸��_�܂ł̊p���������Ƃ���B �ց@�ߓ��_�������B�ߓ��_�͑��z����f���܂ł̋������ŏ��ƂȂ�Ƃ���ł���A���a��ɂ���B�V����E�O���ʏ�ŁA����_����ߓ��_�܂ł̊p�������ւƂ���B T�@�ߓ��_�ʉ߂̓����B �Ȃ��A�� + �ւ��ߓ��_���o�Ƃ����B(i = 0�̂Ƃ����A�ւ͒�`�ł��Ȃ��Ȃ邪�a�ɂ͈Ӗ�������B)�@���xy���ʂƂ��Ă͒n���̋O����(������)�Ax�����Ƃ��Ă͏t���_(�V�����̂Ȃ���ŁA�n������t���̂Ƃ����z��������������̂悤�ɌĂԁB���z����A�n�����H���ɒʉ߂���_�Ɍ����������ƌ����Ă��悢)���g���̂��ӂ��ł��邪�A�n���̋O������ю��]�̕ω��̂��߁A�����������B�����ŁA�V�̗͊w�̌v�Z�ɂ́A�����n(��]���Ă��Ȃ��ƍl�����Ă�����W�n)�ŁA���鎞�_(���Ƃ���1950�N����)�̋O���ʂ�xy���ʂƂ��A����_�̏t���_��x�����Ƃ��āA�ʒu���w�肵���ق����悢�B���̗���ł́A�u�Œ肵���t���_�ɑ���ߓ��_���o�v�����g����B �����ۂ��A�n����̋G�߂����߂Ă���̂͊�{�I�ɒn�������]���ɑ��ČX���Ă��邱�Ƃł���B���������ċC��ɑ��ẮAi�����ڌ����̂ł͂Ȃ��A�n���ƌ��]�O���̎��̂Ȃ��p�� (obliquity: �����ł́u�n���̌X���v�ƌĂ�ł����B�ԓ��ʂƉ����ʂ̂Ȃ��p�ƌ����Ă��悢)�̕ω���ʂ��Ė��ɂȂ�B�܂��A�ߓ��_���o�ɂ��Ă��A�����n�ɑ�������ł͂Ȃ��A�n���̌X�������f�������̂Ƃ��ǂ��̏t���_����Ƃ����ߓ��_�̕�����\�킷�u�����t���_�ɑ���ߓ��_���o�v_pi_�����ɂȂ�B _pi_�A�Â̕ω��ɂ͒n���̎��]�̕ω����W���Ă���B���]�͊p���x (����)�x�N�g����3�����A���邢�́A�p���x�̑傫���ƁA���]���̊�� (���Ƃ����鎞�_�̎��]�̎�)����̌X���ƕ��ʊp��3�v�f�Ŏw��ł���B�����̗v�f�����z�A������ё��̘f���̈��͂ɂ���ĕω�����B���ۂ̎��]���́A�n���̌`�Ō��܂銵�����[�����g�̎��̂܂������Ă���̂ŁA�����̕ω���_����ꍇ�ɂ͂��́u�`�̎��v(�����ł͒n���ƌĂ�)�̓������L�q����悢�B���z�ƌ��̏d�͂̌��ʂɂ��n���̕����̕ϓ��́u�͓��v�ƌĂ�A���N�A1�N�A18.6�N�Ȃǂ̎����������A���������ς��Ă��܂��Ǝc��̂́u���v(precession)�ƌĂ����̂ł���B����́A�n�������]�O���̎��̂܂����A�X�������Ƃ��āA������ς��Ă������̂ł���B���̌��ʁA�t���_�̊����n�ł̕���������Ă����A��2.58���N�� 1������B���ꂪ����_pi_�̍������B�����t���_����Ƃ����ߓ��_�̉��o_pi_�͖�2.17���N��1������B����̓��̕ω��ƍ��̑g���킳�������ʂ����A���̂ق����ʓI�ɑ傫���̂ŁA������u�C��I���v�ƌĂԂ��Ƃ�����B����Â̕ω��́A���]�O���ʂ̌X��i�̕ω����A���ɂ���ē����ԓ��ʂɓ��e���ꂽ���̂ł���B(����̊ϑ��ɂ��Â̕ω��ɂ́A����Ő����ł��Ȃ��c�������邪�A���̌��������炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�����ϓ��̌v�Z�Ɋ܂߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B) ���ۂɁA�O���v�f�̒���(���]�����ɔ�ׂĒ������ԃX�P�[��)�̕ω��������ꍇ�ɂ́A�O���̓��Řf�����ǂ̈ʒu�ɂ��邩�Ɉˑ����鑊�ݍ�p�̍��ς��Ă��܂������Ōv�Z����u�i�N�ۓ��@�v���g����B����́A��̂s�Ɋւ�������������Ƃɑ�������B�Ȃ��A�����n���ƈ�̂łȂ����ƁA����ё��Θ_�I���ʂ́A��1�ߎ��ł͖����ł��邪�A�ߎ��̐��x�����߂�Ƃ��ɂ͖��ɂȂ�B�f���̐ۓ��ɂ���ẮAa�͕ω����Ȃ��B���߂�ׂ��ϐ��́oe�C�ցCi�C���p�ł��邪�A�v�Z���x�Ȃǂ̗��R�ŁA {e sin ���Ce cos ���Csin i sin ���Csin i cos ��}�̎��ԕω��̎��ɂ��Ă����A����4�̕ϐ��̎��ԕω������ꂼ���r�I�����̎O�p���̍��̘a (e sin ������ Mj sin (gj t + ��j) �̂悤�Ȍ`))�ŕ\�킹��Ɖ��肵�Ă��̌W�������߂�Ƃ������@���Ƃ�B���߂�ꂽ4�̕ϐ��̎���ό`���āA���˗ʂ̎��Ɍ�����oe�Ce sin _pi_�Ce cos _pi_�C�Áp���O�p���̍��̘a�̌`�ŋ��߂�B(���������āA���ꂩ��v�Z�����G�ߕ��ϓ��˗ʂ̃p���[�X�y�N�g���͌����I�ɁA��r�I�����̐��X�y�N�g���̏W�܂�ɂȂ�B�����̘_���Ŏ�����Ă��镝�̂���X�y�N�g���́A�L�����Ԃőł������T���v����ʏ�̎��n���͂ŏ����������ʂł���B) Berger(1988)�̌��ς���ɂ��A Berger(1978)�Ɏ������O���v�f�̌v�Z�́A���n��Ƃ��ẮA���݂���e sin _pi_�Ee cos _pi_�ɂ��� 150���N�Ae�ɂ���3�S���N�A�Âɂ���4�S���N���x�����̂ڂ��ĐM���ł���B�܂��A�O�p���ɓW�J����������_����(�ʑ�������Ă��悢) �ꍇ�́A���Ȃ��Ƃ�5�S���N�O�܂ł̋c�_�Ɏg����Ƃ������Ƃł���B��������Â�����ɂ��ẮA����܂ł̌v�Z�Ŗ������Ă����A�����̘f���̕�������(�ؐ��Ɠy���̗L����930�N�����͍l���ς݂����A����ȊO) ��A�W�J�̍����̍��������Ă���\��������Ƃ������Ƃł���B�@ |
|
| ���t�^B / �C��R�A�̃f�[�^�ɂ��Ă̕⑫ | |
|
�C��͐ϕ��͗���ɔ�ׂĐN�H����邱�Ƃ����Ȃ��A���ɐ[�C�̗����牓���Ƃ���ł͑͐ϑ��x�����������߂ɁA�{�[�����O(�@��)�ɂ��R�A�̔�r�I�Z�������ɁA�����Ԃ̊��ϓ����A���I�ɋL�^����Ă���Ɗ��҂����B�������C�m��g��E���ݍ��݂̂��߁A2���N�ȏ�͂����̂ڂ�Ȃ��B�܂��A�ꐶ�����ɂ���Ă����܂����邱�Ƃ�A�[�C��̔������x�̒n��ł͒Y�_�J���V�E�����n�����邱�ƂȂǂɂ��A�L�^�̉��߂��ނ��������Ȃ邱�Ƃ�����B�����牓���[�C��̑͐ϕ����\�����Ă���̂́A��Ƃ��Đ����̊k�ł���B���������ƁA�Y�_�J���V�E�����听���Ƃ���k����鐶���Ƃ��āA�L�E��(����)�A�R�b�R���X�t�H���b�h(�A��)�A�]�_���听���Ƃ���k����鐶���Ƃ��āA�]��(�A��)�A���U��(����)�Ȃǂ�����B�����̑����͊C�̕\�ʋ߂��ɕ��V�������(�v�����N�g��)�ł��邪�A�L�E���Ȃǂɂ͒�ɂ��ނ���(�x���g�X)������B�����̐������̎�ނ���̏�ł���A����̈��蓯�ʑ̂̍\���䂪������̏�ƂȂ�B
�L�E���Ȃ�L�E���ƈ���Ɍ����Ă��A�������ނ́u���v��u��v�̃��x���ł͑��l�Ȏ�ނ��܂�ł���A���ꂼ�ꂪ���x�A�����Ȃǂ̈�������ɓK�����Ă���B���̊W���t�Ɏg���āA�������ΌQ�W���̎�̍\���䂩��A���x�A�����Ȃǂ̊��v�f�𐄒肷�邱�Ƃ��ł���B��l�I�̂��̂��ƁA��̂قƂ�ǂ����ݐ����Ă�����̂Ȃ̂ŁA���݂̐������Ŋr�����邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ȌÊ��̌����͌Â�����s���Ă��邪�AImbrie��́A���q���͂Ƃ������ϗʓ��v�w�̕��@�ŁA�����Ȃǂ̐���l���q�ϓI(���̐l�ł������菇�ɏ]���Γ������ʂ��Č��ł���Ƃ����Ӗ�)�ɏo�����Ƃɐ��������B ���ʑ̂Ƃ��Ă͎_�f18�������g���Ă���B����͂ӂ��̎_�f���q (�_�f16)�����d���̂ŁA�������N���Ă���Ƃ��́A���C�̂ق��ɂ͏��Ȃ��A�t�̂̐��̂ق��ɑ����Ȃ�X��������B�������A���̎��ʕ��ʂ́A���x�������Ȃ�ɂ��������Ė����ʂɂȂ��Ă����B�嗤�X���͌ő̂ł͂��邪�A��������C�����������������ƂȂ��č~�������̂ƍl�����邩��A�X��(�X���̑����ʂ�������������)�ɂ́A�C���ɂ͏d���_�f18�������A�ԕX���ɂ͏��Ȃ������͂��ł���B�ߋ��̊C���͎c���Ă��Ȃ��̂ŁA���ۂɑ��肳��Ă���C��R�A�̎_�f���ʑ̔�͗L�E���Ȃǂ̊k�̒Y�_�J���V�E���͂������̂ł���B�������k������ߒ��ŊC������Y�_�J���V�E���𒾓a������Ƃ����A���ʕ��ʂ��N����B���̒��x�͉��x�A��������ѐ����̎�ނɈˑ����A�����ő��肷�邱�Ƃ��ł���B���ẮA�C��͐ϕ��̃R�A�Ɋ܂܂�鉻�̎_�f���ʑ̔�̕ϓ��́A�C���̉��x�̕ϓ������̒��a�����̕��ʉߒ���ʂ��Č���ꂽ���̂��ƍl����ꂽ���Ƃ��������B�������A��ʓI�Ȍ��ς�������Ă݂�ƁA��l�I�Ɋւ��ẮA�X���ƊC���̕��z�̌��ʂ̂ق����A���̏�̉��x�̌��ʂ����傫�������Ă���A�_�f���ʑ̔�̎��n��́A�S���E�̕X�̗ʂ̎w�W�ł���Ƃ����l�����A���݂ł͏펯�ł���B�������A���n��ׂ̍����Ⴂ����A���x�̏������o����Ƃ����l��������(��Ⴊ Broecker and Denton, 1989�ɂ���)�B �Ȃ��A�_�f���ʑ̔�́A�ӂ� ��18O(��)��((�T���v����[18O] / [16O]) - (�W���C����[18O] / [16O]))/(�W���C����[18O] / [16O]) �~ 1000 �Ƃ����`�ŕ\�������B�@ |
|
| ���t�^C: ��C��z���f���ɂ�錤�� | |
|
�����ł́A�b���O���v�f�ɑ��鉞�������Ɍ���B�ËC��̎����Ƃ��ėL���ȁA CLIMAP�̍ŏI�X���Ő����̋C��̍Č������́A����Ɋ܂܂�Ȃ��B
���ݑ�C��z���f���ōs�Ȃ�������́A���f���̒��̌o�ߎ��Ԃ����\�N����S�N���x�ł���B�悭�s�Ȃ�������ݒ�Ƃ��Ă� (��) �C�m�����w��M�e�ʈ��̔Ƃ��đ�C�ƌ��������A�G�ߕω�������˂�^���Đ��\�N�ϕ����� (��) �C�ʐ��������E�l�Ƃ��ė^���A�G�߂��Œ肵�����˂�^���Đ��S���ϕ����� ��2�ʂ肪����B������ɂ��Ă��A�X���E�ԕX���T�C�N���ɔ�ׂ�Ώu�Ԃ� "snap shot"�ł���A�X���Ȃǂ͂��ꂼ��̎������ƂɌŒ肳�ꂽ���E�����Ƃ��ė^���邱�ƂɂȂ�B�����̈ʒu�Â��Ƃ��ẮA 6�߂ɏq�ׂ��A�G�l���M�[���x���f���ɂ�����(���m�ɂ�1�N������)�̌����ɐ��z�Ȃǂ̉ߒ������������̂ƍl�����邾�낤�B Kutzbach and Guetter (1986)�́A 1��8��N�O���猻�݂܂ł�3��N�����݂ɂ������ꂼ��̎����̋C����z���f���ŃV�~�����[�g���A�ԕ����͂Ȃǂ̏؋��ƑΔ䂵�悤�Ƃ����B���ꂼ��̎���̋O���v�f�ɂ����˗ʂ�^�����B�n�\�ʂ̋��E�����́A���Ȃ��ϓI�ł͂��邪�A1��8��N�O�ƌ��݂̊Ԃ���}�������̂�^�����B�X���̂����������̌��ʂɂ͕X���̉e���������o�Ă��邪�A���̎��ɖڗ������̂́A�k�����̓��˗ʂ̍ő�ł�����9��N�O�𒆐S�Ƃ�������́A�k�����̗���̉Ă̋C��ł���B�C���h��L�V�R�p�݂Ȃǂł͍~�������������B����́u�C���̉��M�����傫���Ȃ������߁A�M�у����X�[���z�����܂����v�Ɖ��߂���Ă���B�����ۂ������X�[���̋�C���N�����Ȃ��������ł́A���˗ʂ̒��ڂ̌��ʂŁA���x�������A�������� (�~���Ə����̍����������Ȃ���)�B����͉ԕ����͂�̐��ʂȂǂ̏؋��ƑΉ����Ă���B�ËC��̏؋�����́A�q�v�V�T�[�}��(hypsithermal) �ȂǂƌĂ�鉷�x�̋ɑ��5�炩��6��N�O�Ƃ���Ă���B9��N�O�ɂ͕X���̈ꕔ���c���Ă����̂œ��˂̌��ʂ��ł�������āA�ɑ傪���ꂽ�Ɖ��߂���Ă���B���̌����̉����� Kutzbach and Gallimore (1988), Prell and Kutzbach (1987)�Ȃǂ�����B��҂͉ߋ��̊ԕX��(����12���N�O)�ɑΏۂ��L���Ă���B Rind��(1989)�́A�ŏI�X���̎n�܂�̎����̋O���v�f��^�������������āA�k�A�����J�X���̐����͋O���v�f�Ő����ł��Ȃ��ƌ��_����(���͎c��B ��6��4�ߎQ��)�B Oglesby and Park (1989)�́A�X���̂Ȃ����������I�̏ŁA�͐ϊ�̂��܂��悤�̐������ӎ����āA�~���E�����̕��z���O���v�f�ɂ���Ăǂ��ς�邩�ׂĂ���B�@ �@ |
|
| ���n���͕X�͊��ɓ˓����� | |
|
�����^�_...
���̂������N������A9�K���Ẵr�����̐�ɖ�����Ă邾�낤�B�X�͊��Ƃ����̂͌����ɁA�[���}�C�d�|���̂悤��11500�N�̎����ł���Ă���B�C�Â�����ŏI�X����11500�N�O�ɋN���Ă܂�... ���Ȋw�I�m��... CO2�ɂ�鉷�g�����ʂ́A�O���̕ω���(�Ⴆ�}�E���_�[�ɏ�����)���z�����̕ϓ��Ɣ�ׂāA�����Ƒ傫���ł��B �ق�̐����I�O�A�n���́u���X���v�ƌĂ���r�I���₩�ȕX�͊����}�����B���X���̈ꕔ�͑��z���_����������������������(�}�E���_�[�ɏ���)�ƈ�v���Ă܂��B���z�����̒ቺ�ƉΎR�����̕p���Ƃ̑g�ݍ��킹���傫���v�����A���[���b�p�n���ł͊C�m�z�̕ϓ������ʂ��������Ƃ���Ă�B�@ |
|
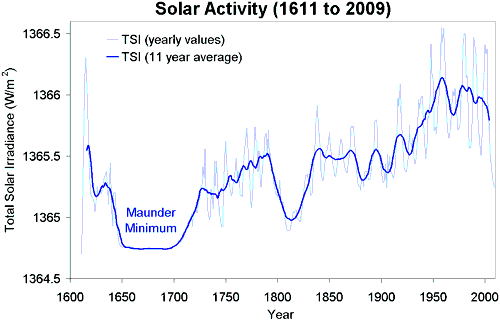 |
|
|
�}1�F���z���˗�(Total Solar Irradiance | TSI)�B1880�N����1978�N�܂�Solanki�B1979�N����2009�N�܂�PMOD�B
�����݂̎���Ƀ}�E���_�[�ɏ�����̌�����\���͂���̂��H���z�����͌��ݗ�p���̌X���������Ă��܂��B2009�N�̊����ʂقǒႭ�Ȃ����͈̂ꐢ�I�ȏ�O�ł��B�������A�����̑��z������\������ɂ͖�肪����܂��B�O�����h�ɑ��(e.g. 20���I�㔼)����O�����h�ɏ���(e.g. �}�E���_�[�ɏ���)�̎����͖������ŗ\������͓̂������ł��B �Ⴆ�}�E���_�[�ɏ�����21���I�ɋN�����Ƃ��܂��傤�B�n���̋C��ɂǂ�ȉe����^���邩�H�}�E���_�[�ɏ����܂ő��z�������������������A�ǂ�ȋC���������邩�V�~�����[�V�������Ă݂�ƁA���z�N���̉��x�ቺ���A�l�N���������ʃK�X�̉��x�㏸�̕����f�R���������B���z�����̒ቺ���痈���p����0.1��������Ɛ��肳��Ă���(�}�b�N�X0.3��)�A�������ʃK�X����̉��g����3.7�`4.5���Ɛ��肳��Ă܂�(�r�o�ʂɂ���ĈقȂ�)�B�@ |
|
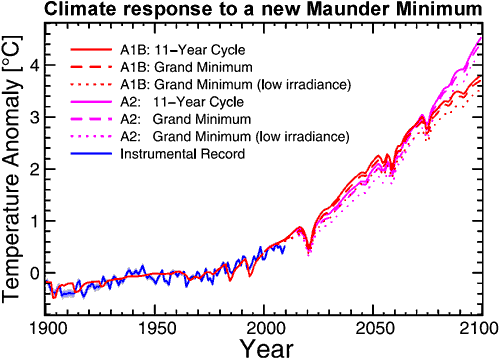 |
|
|
�}2�F1961�`1990�N���x�[�X�Ƃ���1900�`2100�N�̒n�����ω��x���BA1B�r�o�V�i���I(��)�AA2�r�o�V�i���I(�}�[���^�F)�B���z�����V�i���I�͎O�F����(����)�A�}�E���_�[�ɏ���(�j��)�A�}�E���_�[�ɏ������炳��ɕ��ˏƓx��ቺ(�_��)�BNASA�̊ϑ����ꂽ���x�f�[�^(��)�B
�������A�ߋ��̋C��͏��X����������Ɍ��I�ȕω����o�����Ă܂��B�ߋ�40���N�A�n���͉��x���X�͊����o�����A10���N�����ŁA�Z���Ԓg�܂��Ă܂��B�����������X���ƕX���̊Ԃɗ��鉷�g�Ȋ��Ԃ͊ԕX���ƌĂ�Ă���A���1���N�����B���݂̊ԕX����1.1���N�O�n�܂�܂����B������ԕX�����I��鍠�Ȃ̂��H�@ |
|
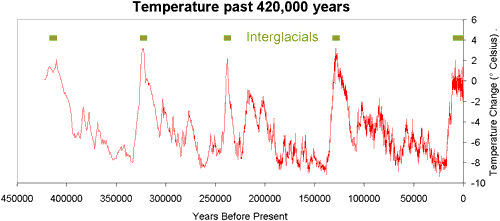 |
|
|
�}3�F�{�X�g�[�N�A��ɂł̋C���ω��B�ΐF�̖_�ŊԕX�����}�[�N����Ă܂��B
�X�͊��͂ǂ�����ċN������̂��H�n���̋O�����ω�����A�k�����֓���������͉Ăɒቺ����B�k���̕X���͉āA����n���Ȃ��Ȃ�A����N�������Ĕ��B����B����͒n���̃A���x�h�������A�X���̔��B�Ɨ�p����苭����������B���̉ߒ���1���`2���N���炢�p�����A�X�͊��ƂȂ�B �ԕX���̒����͊F�قȂ�܂��B��ɂɂ���h�[��C�̕X�R�A���g����72���N�O�܂ł̒n���̉��x��ˌ��ł��܂��B42���N�O�A�n���̋C��͌��݂̏�ԂƂ��قǕς��Ȃ������̂ł��B���̊��ԁA�ԕX����2.8���N�������̂ŁA���݂̊ԕX�����A�l�Ԃ̉�������O���Ă��������炢�̒����ɑ����\��������܂��B 40���N�O�ƌ��݂̎����悤�ȏ͒n���̋O���ɂ����̂ł��B���ԕX���Ƃ��A�O���v�f�̕ω����痈�鋭���͂͑��̊ԕX���Ɣ�ׂď��Ȃ��̂ł��B�V�~�����[�V�����ɂ��A���݂̊ԕX����CO2�r�o�Ȃ��ł�1.5���N������p�������Ƃ̎��ł��B �������A�l�Ԋ��������O�����ԕX���̐���͗��_��̂��̂ł��B�厖�Ȃ̂́A�l�Ԃ��������ƕX�͊��N���̃^�C�~���O�͂ǂ��e�������̂��B���̎���ɓ������ꌤ���ɂ��ƁACO2�Z�x��������������A�X�͊����N������u�������v�A���˗ʂ͒Ⴍ�Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B �}4�͗l�X�Ȕr�o�V�i���I�Ɋ�Â��ċC�������������̂ł��B�ΐ���CO2�������u���R�v�ȉ����B���͐l�N��CO2��300�M�K�g���r�o�������̃V�i���I�ł�(��X�͂������ɒ����Ă܂�)�B�I�����W����1000�M�K�g���̔r�o�A�N�����13���N�X�͊���h���Ƃ����v�Z�ł��B5000�M�K�g���̔r�o(�Ԑ�)���N����A�X�͊������50���N�x�点�鎖���ł��܂��B���̏�ԁA��r�I�ア�O�������͂ƒ���CO2�̎����A���������킹�l����ƁA�ߋ�260���N�A�Œ��̊ԕX���ɂȂ�\��������܂��B�@ |
|
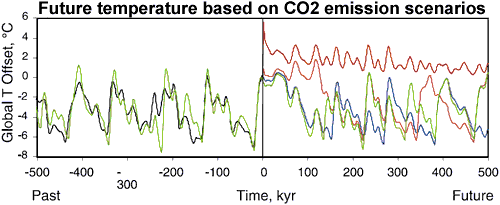 |
|
|
�}4�F�����̒n�����ω��x�ɑ���CO2���ʁBCO2�r�o����(��)�A300Gton(��)�A1000Gton(�I�����W)�A5000Gton(��)�B
�X�͊����ԋ߂Ƃ������O�͒u���Ă����Ă����ł��傤�B�X�͊����{���ɐؔ����Ă�ƌ����Ȃ�A�k���̕X���ɖڂ��Ă��������B�X�������B���Ă�A1���N������X�͊��̉ߒ����n�܂��Ă�̂�������܂���B�������A���݂̖k�ɂ̉i�v���y�w�͍픍�A�Z�������߂Ă��܂��B�k�ɂ̊C�X�͗Z���A�O���[�������h�̕X���͑̐ς̏k�����������Ă܂��B�X�͊����N��������Ƃ��Ă͂��܂����ł��B�@ �@ |
|
| ���X�͊� 3 | |
|
�n���͍��A�i���X�p���ł݂�ƁA�X�͊��Ɍ������Ă���A�Ƃ������Ƃł��B�����m�������A���͈Â��C�����ɂȂ�܂����B�ǂ������̍��͎��͑��݂��Ȃ�����A�ǂ��ł������悤�Ȃ��̂́A���̒n��������ɗ₦�ĕX�͂ɕ����Ă����A�Ƃ����C���[�W�͋C�����̂������̂ł͂Ȃ������B
�Ƃ��낪�A�ŋߒm�����̂ł����A�n����ł͕X�͊��̕����A�ނ��됶���̖L���Ȏ��ゾ�����悤�ł��B �Ƃ����͕̂X�͊��ɂ͑�C���̐����C�������Ēn��ɒ~�����A�������Z���ď펞�K�x�ɒn�ʂɐ��������������̂ŁA�X���L���ɍL����A�������傢�ɔɐB�����̂������ł��B �X�͊��͋�C���������Ăނ���Ⴊ���Ȃ������̂ŁA�n�\�̑������H�Ղ������B �X�͊����I���ƁA�n��̕X���Z���A�ǂ�ǂ��C�ɂȂ��ď��ɋ���A�n�\�͊����A�X�����荻���������܂����B�n��̊����Ƃ͋t�ɁA��C�͎���A�Ⴊ�����ē����̐H���̑����B���A���ꂪ�}�����X�̐�ł̈���ɂȂ����ƍl�����Ă��܂��B �n�\�̊����Ɛ�̑����Ƃ͖������邶��Ȃ����A�Ǝ�����قɎv���܂������A�܂�A�����������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ����̐������ɂƂ��ĕs���ȁu�^���v�́A�n����̂��ׂĂ̐��̈ꁓ�������݂��܂���B �Ƃ���ŁA�F�����猩��ƁA�n���̑S�ʐς̌܁Z������ɉ_�ɕ����Ă��܂��B�������A���̂Ƃ��J�̍~���Ă��镔���͂��̎O���ɂ����߂��܂���B�J���~�炷�_�͗�O�I�ȉ_�Ȃ̂ł��B �����b���A���݂̂悤�ȉ��g���ɂ́A�n����̐^���̑啔���͐��̌`�łȂ��A�_�̌`�A�܂��͖ڂɌ����Ȃ������C�̌`�ő��݂��A���̂����̗�O���n��ɍ~���ė���̂ł��B �������A���̂Ȃ��Ȃ��̐^�����A�����������ł����܂������C�ɂȂ��ċ�ɖ߂��Ă��܂��B�����Ȃ���A�͂ƂȂ��ė��ꋎ���Ă��܂�(�����čŏI�I�ɂ͊C�ɗ��ꍞ��ʼn����ɂȂ��Ă��܂�)�B �Ƃ��낪�A�X�͊��ɂ́A���̗�O�I�ɒn�\�ɍ~���Ă����^���́A�����ɕX�̌`�ɂȂ��Ă��̏�ɒ��~����܂��B�����������A�͂ɂ��Ȃ�܂���B �o���ς���ΎR�ƂȂ�B�ǂ�Ȃɔ��X����ʂ̐^���ł��啔��������ꂸ�ɂ��̏�ɒ~�����Ă����A�����͕X�R�ɂȂ�B�܂�A�X�R�Ƃ͐^���̒������Ȃ̂ł��ˁB �n��ɐ^����������A���ɂ͐����C������B�]���ċ�C���������ĐႪ����A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B �������ĕX�͊��́A�������ɕK�v�Ȑ^�����A���g�������n�\�ɑ������݂��A�������̑傢�ɔɐB����L���̎���ɂȂ�A�Ƃ����킯�ł��B �����A�X�͊��̑�\�I�ȓ����Ƃ����A�����m�̒ʂ苐��ȃ}�����X�ł���ˁB �Ƃ���ŁA�}�����X���Ȃ�����Ȃɋ���ɂȂ������A�Ƃ����A������܂��A�X�͊��̂������A�Ƃ̂��Ƃł��B�������X�͊��͖L���̎���ŁA��H���̐}�̂�{����قǐH���̑����L�x����������A�Ƃ������Ƃ�����܂����A����Ȃ�̂͏������Đ��������Ă��悩�������ł��B ����Ȃ̂ɂȂ�����ȂɃ}�����X������ɂȂ������A�Ƃ����A�������ɂ͑傫�������L��������ł��B ���w�̎��ԂɁA�u�ʐς͒����̓��ɔ�Ⴕ�A�̐ς͒����̎O��ɔ�Ⴗ��v�ƏK�������Ƃ��v���o���ĉ������B �����̐g����2�{�ɂȂ�ƁA�\�ʐς͎l�{�ɂȂ�A�̐ς͔��{�ɂȂ�܂��B�����܂ő����Ȃ��Ă��A�̐ς�2�{�ɂȂ��Ă��\�ʐς͈�E�Z�{���x���������܂���B �������ɂ͕\�ʐς��傫���قǍP�������̑̉��͑�R�����܂��B�����瓯���̐ς�������\�ʐς������������L���ł��B�Ƃ��낪�A�̐ς�������Α�����قǕ\�ʐς̑����������Ȃ��Ȃ��Ă䂭�B�����犦�����ɂ͐}�̂��傫���قǗL���Ȃ̂ł��B������}�����X�͂���Ȃɋ���Ȃ̂ł��B�����A������ł��傫���قǗǂ��A�Ƃ����킯�ɂ������Ȃ��B�K�v�ȐH����������Ƃ��A���낢�둼�̃f�����b�g�Ƃ̌��ˍ����ŁA���̑傫�����œK�A�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��傤�ˁB �l�ނ̔��W�ɂ��A�X�͊��͑傢�Ɋ�^���Ă���悤�ł��B ��k�A�����J�嗤���S���h���i�嗤���番���������ɂ́A�܂��l�ނ͔������Ă��܂���ł����B�]���ăA�����J�嗤�ɂ́A�l�ނ͂��܂���ł����B�쒷�ނ���k�A�����J�ɂ́u�����ށv��������ł��܂���B �₪�ĕX�͊������āA�x�[�����O�C��������A�A�W�A�嗤�ƃA�����J�嗤���n�����ɂȂ�܂����B���̎��ɂ͊��Ɍ����l�ނɂ܂Ői�����Ă��������̂���c�́A���A�Ŏ����̑��ŕ����ăA�W�A����A�����J�ɓn���čs���܂����B�A���X�J���X�ɕ����Ă����̂ŁA�p���đ��ꂪ�������肵�Ă��āA�ړ��ɍD�s���������悤�ł��B �x�[�����O�C�����z�����l�ނ��A��A�����J��[�̃}�[�����C���܂ŒB����̂ɗv�������Ԃ́A�����̐l�ނ̕����i�K���l����Ƌ��ٓI�ȒZ���������悤�ł��B �Ƃ�����A�X�͊����Ȃ�������A�l�ނ̓R�����u�X�̐V�嗤�����܂ŁA��k�A�����J�嗤�Ɉ�������ݓ��ꂽ���Ƃ������܂܂������ɈႢ����܂���B(����ȃA�����J�嗤��������ƌ��Ă݂��������C�����܂�����) ����Ȃ킯�ŁA�X�͊��Ƃ������̂́A���Ď����C���[�W���Ă����悤�ȍr�����鎀�̐��E�ł͂Ȃ��A�܂��ɂ��̐����́A�L���Ɣ��W�̃_�C�i�~�b�N�Ȑ��E�������悤�ł��B �n���̐����ɂƂ��ẮA�ނ���u���g���v�̕����A����ۂǍr���Ǝ��ɋ߂����E�Ȃ̂ł��傤�B�@ �@ |
|
| ���n���̔閧 | |
| ��1�@�ΎR�@ | |
|
�������̐��A�n���B���̉F���ł��������܂�Ȃ�f���́A46���N�̍Ό��������A�n�\�̌i�F��ς������A���������ł����B���̃V���[�Y�ł́A�n���w�҂̃C�A���E�X�`���A�[�g���A�n�����`��������R�̗͂�4�̐������Љ��B��1��̃e�[�}�́A�u�ΎR�v�B
���낵���j��͂����ΎR�B���́A����͒n���ɂƂ��Č������Ȃ��͂��ƌ�����B�ΎR�́A���E�̎p����ɕς������Ă����B�n���ɐ��������܂�錮�ƂȂ�A�X�͊��Ƃ��������ő�̊�@����n�����~�����̂��ΎR���B�����āA�����̏u�Ԃ��A�_�f�Ɠ�_���Y�f���z�����邱�ƂŁA�����Ƌ��͂��A�������Z�߂���𐮂��Ă���B ����ȉΎR�̔閧���������������߁A�i�r�Q�[�^�[�ł���A�C�A���E�X�`���A�[�g�́A�G�`�I�s�A�A�A�C�X�����h�A�j���[�W�[�����h�A�I�[�X�g�����A�Ɛ��E�e�n�𗷂���B����͓����ɒn��46���N�̗��j���삯�����闷�ł�����̂��B���|�I�Ȕ��͂̉f���ł��͂����锎�m�̎�������`�����A�嗤�����A������a���������ܔM�̐_��̐��E�֗U���B �n�����܂ő�����ʂ̍r��B����1�{�����Ă��Ȃ��D�F�̒n�ɁA���������Ɣ��������������߂�B����f���o���Ă���̂́A���E�ł��L���̊��ΎR�A�G�`�I�s�A�̃G���^�A���ΎR���B���̉Ό��ɂ���ė����C�A���E�X�`���A�[�g�̊z�Ɋ����ɂ��ށB�����̐藧�������̐�ɂ́A�Â��Ɏς����n��̌B�n��̓����������Ƃ悭���邽�߂ɂ́A����₷���������[�v��30���[�g���������ɍ~��čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �E�C���N�����A�Ό��̂ӂ��ɍ~�藧�����C�A���́A�n�₪�ł���������������҂B�����ē����e�͂Ȃ��Ƃ���Ă������z���R�A�ɒ��ނƁA�ቺ�ɐ^���ԂɔR����n��̌̎p�������яオ�����B�܂��ɑ����̂ތ��i�B�܂�ŎܔM(���Ⴍ�˂�)�̂��܂ǂ��B���̑s��ȔM�G�l���M�[�́A���������n���ɂǂ�ȕω��������炵���̂��H �ΎR�̔閧��T��C�A���̑s��Ȗ`���̗����n�܂����B����́A�n�������̔M�̗͂ɂ��Ēm�邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B46���N�O�A�n�����a���������ɕ����߂�ꂽ��ʂ̔M���A�ΎR�����̌��ɂȂ��Ă��邩�炾�B�n���̔M�́A�嗤�����A�n�\�̌`��ς������A����ȎR�������قǂ̗͂������Ă���B�C�̒��ōŏ��̑�C��������̂��A�n���ɐ��������܂����𐮂����̂��A�n�������̔M�̗͂��B��������46���N���̒����N���������A�ω��������Ă����n���̗��j�́A���E�̊e�n�ɍ��܂�Ă���B �A�C�X�����h�ɂ́A�嗤�̕���ɂ���Ăł����u�n���̗ځv������B�j���[�W�[�����h�ɂ́A�������a����������̑��Â̒n���̊��Ƃ悭���������̒r�����݂���B�C�A���͎��ۂɌ��n�֔�сA����2�̏ꏊ����n���̔閧���킩��₷������B����ɁA�X�͊��̒n����̌����邽�߁A���Ⴊ�r���^�~�̃A���v�X�ցB�I�[�X�g�����A�ł́A�ΎR���X�͊�����n�����~������̐����̌��I�Ȑi���̉ߒ���ڌ�����B �C�A���E�X�`���A�[�g�Ƌ��ɁA����������ɏo��A�ΎR���n���̖��̌��ł��邱�Ƃ������ƕ�����͂����B�@ |
|
| ��2�@��C | |
|
�������̐��A�n���B���̉F���ł��������܂�Ȃ�f���́A46���N�̍Ό��������A�n�\�̌i�F��ς������A���������ł����B���̃V���[�Y�ł́A�n���w�҂̃C�A���E�X�`���A�[�g���A�n�����`��������R�̗͂�4�̐������Љ��B��2��̃e�[�}�́A�u��C�v�B
��C�͖ڂɌ����Ȃ����̂��Ǝv���Ă��Ȃ����낤���H�@��������͑傫�ȊԈႢ���B��C�͂��܂��܂Ȍ`�Ŏ������̖ڂ̑O�Ɏp�������A���݂̏���n����ɍ��ݑ����Ă���B���̌��ۂ̐��X���Ƃ炦���f���́A�܂��ɋ����̘A�����B�����Ă������番�����Ă���̂́A��C�������ʼnQ�����Ă���Ƃ������ƁB�C��ݏo����C�́A�n�\�̌`��ς���قǂ̋���ȃp���[�������ʁA�ƂĂ��@�ׁB�����Ɏ_�f���������A�F���̗L�Q�����������Ă���Ă���B����Ȏ������̐����ɕK�v�s���ȑ�C�ɁA���A�傫�Ȋ�@���K��Ă���c�B ����̒n���w�҃C�A���E�X�`���A�[�g�̗��́A��C�����w�c�A�[���疋���J����B�������̃W�F�b�g�@���_���A�����Ƃ����ԂɑΗ������A���x15�L���̐��w���ցB����ɍL����Â��F������������́A�͂邩�ޕ��̉F�������������Ɋ���������B����ɁA���w������̃_�C�u�A��̏�̃T�[�t�B���Ƌ������̉f���̌��ցB��C���D��Ȃ��A���������r�X�����C�ی��ۂ̐��X��ڂ̓�����ɂ���B��ɑł����g�̂悤�ɁA�I�[�X�g�����A�ɕ����n���ő�̉_�B�A���f�X�̗L���Ȉ�Ȃ́A����҂����|�B�A���]�i�Ō����A�傫�����˂�Ȑ��̂��ܖ͗l���`���ꂽ��́A��������グ�����R�̋��咤�����B46���N�O�A�n�����a�����ĊԂ��Ȃ����܂ꂽ��C�ɂ́A�_�f�͑��݂��Ă��Ȃ������B�����ς����̂��A20���N�قǑO�ɒn��Ɍ��ꂽ���n�����̃X�g���}�g���C�g���B�X�g���}�g���C�g�́A���������͐ς��Ċ�Ώ�ɂȂ������̂ŁA���߂Č��������s���Ď_�f����o���������́B���݂ł��I�[�X�g�����A�̊C�݂ɌQ�����Ă���B�����̑�C�͐��\���N�������āA�����ƌ����ȃo�����X�W��ۂ��Ȃ������Ă������̂Ȃ̂ł���B ���������A���̃o�����X���l�Ԃ̊����ɂ���ċ�������Ă���B�V�x���A�̉i�v���y�ɋC��ЊQ�̈������������Ă���ƌ����C�A���́A����������s�����B����́A�������ΖʂɌ����@��A���߂Â���Ƃ������́B����ƁA�Ȃ�ƌΖʂ̂��������ŕX���牊�������o�����B�X�̒��̃��^���K�X���������̂��I ��ʂ̃��^���K�X�����܂��Ă���L��ȃV�x���A�̉i�v���y�B���^���K�X�̉������ʂ́A��_���Y�f��23�{���B�n�����g���̉e���ŃV�x���A�̉i�v���y�������A��ʂ̃��^���K�X�����o�����ƁA�������ʂ͂܂��܂��i�݁A�C��Ɍ��I�ȕω��������炷���낤�B ���łɃV�x���A�̉i�v���y�͉����n�߂Ă���B���܂��ɒn���Ɋ�@���K��悤�Ƃ��Ă���̂��B�@ |
|
| ��3�@�X | |
|
�������̐��A�n���B���̉F���ł��������܂�Ȃ�f���́A46���N�̍Ό��������A�n�\�̌i�F��ς������A���������ł����B���̃V���[�Y�ł́A�n���w�҂̃C�A���E�X�`���A�[�g���A�n�����`��������R�̗͂�4�̐������Љ��B��3��̃e�[�}�́A�u�X�v�B
�X�͂����̓��������ł͂Ȃ��B�l�ނ��n���Ɍ���Ĉȗ��A���E���`����ōő�̖������ʂ����Ă����ƌ����邾�낤�B�X���a�������X�͊��ȍ~�A�X�͑�n�����A���Ɏ��R�̖҈Ђ�U�邢�A�n���̋C���傫���ϓ������Ă����B���̋O�Ղ����ǂ邽�߁A�A���v�X�̕X�ǁA�J���t�H���j�A�B���Z�~�e���������A�m���E�F�[�̃X�o���g�C�X�X�́A�O���[�������h�̃��R�u�X�n�u���X�͂�K��A���̎c���ꂽ���X�̋����ׂ����ۂɏo��B �����āA�X�̗͂͐l�ނ̐i���̓��܂ł��ς��Ă����B���E�e�n�̕X���A�n�����g���ɂ������n�߂Ă��鍡�A�X�͎������̖����̌��������Ă���B ����̒n���w�҃C�A���E�X�`���A�[�g�̗��́A�A���v�X�R������n�܂�B���S�ɓ����ĕX�ǂƂȂ�������悶�o��ނ̎��͂ɍL����̂́A�藧������ƕX�̐��E�B�X�͂͒a���ȗ��A��n�̌`��ς���قǂ̑傫�ȗ͂��������Ă����B�X�͂ɍ���Ăł����R�̒��ł��A���ɑf���炵���̂��J���t�H���j�A�̃G���E�L���s�^���B�X�ɖ����ꂽ�ݕǂ́A���b�N�N���C�~���O�̖������B �ł͂Ȃ��A�X���ł����������悤�ȗ͂������Ă���̂��H�@���̋���ȗ͂̓�ɔ��邽�߁A�C�A���̓m���E�F�[�̃X�o���g�C�X�X�͂ցB�����ł͕X�͂̓����𒆂��猩�邱�Ƃ��ł���̂��B�X�͊w�҃~���A���E�W���N�\���Ƌ��ɐ��͔��d���̃g���l����i�ނƁA�X�͂̍Ő[���A�X�Ɗ₪�Ԃ���ꏊ�ɂ��ǂ蒅���B�g���l���̉��ɑ҂��Ă����̂́A���z�I�ȃA�[�g�̂悤�ȕX�͓����̐��E�B�X�Ɋ܂܂���̑͐ϕ��ƁA�X�̎����������Z�H��p�ݏo�������Ƃ�������B �O���[�������h�A�A�C�X�o�[�O�E�A���[�ł́A�X���C��ɂ����炵���e���ɂ��ĒT������B�X�͑��z�̌��ƔM�˂��邱�Ƃɂ���āA�C���ω������Ă����B�X���L�͈͂ɍL�����Ă����X�͎���ɂ́A���Ȃ�̗ʂ̑��z�G�l���M�[���F���ɔ��˂��ꂽ���߁A�n���̋z������G�l���M�[�ʂ��������A�s����ȋC��ƂȂ����B�����āA���̋}���ȕω��ɏ����ł����킾���������c�����Ƃ����_�ɂ����āA�X�͐l�ނ̐i���𑣂����Ƃ�������B ���݁A�n���̉��g���ɂ�萢�E���̕X�͂������n�߂Ă���B�Ō�ɖK�ꂽ�O���[�������h�̃��R�u�X�n�u���X�͂ł́A�X�̗͂��ꋎ�鑬�x�������Ȃ��Ă��Ă���B�R�����h��w�̃R�����b�h�E�X�e�t�F�������́A���̌����́A���������������X�͂̒�ɓ��B���A����₷���Ȃ��Ă��邽�߂��ƍl�����B�C�A���́A�����̌����`�[���ɓ��s���A�X�͂̕\�ʂ̌�"���[����"����J���������ĎB�e�����݂邪�A��܂œ��B�ł����A���͎���ɂ���������邱�ƂɂȂ����B �X�̗͂����I���āA�C�A���͌��B�u���E���̕X���n���ĕ��A�X�������Ȃ�Ƃ���������A����͎������̕����A�n�����傫���ς�鎞�Ȃ̂�������Ȃ��v�B�@ |
|
| ��4�@�C | |
|
�������̐��A�n���B���̉F���ł��������H�Ȃ�f���́A45���N�̍Ό��������A�n�\�̌i�F��ς������A���������ł����B
���̃V���[�Y�ł́A�n���w�҂̃C�A���E�X�`�����[�g���A�n�����`��������R�̗͂�4�̐������Љ��B��4�b�̃e�[�}�́A�u�C�v�B �C�́A�r�X�����͂ŊC�ݐ������݁A�G�l���M�[��n���S�̂Ɉړ������A�n���̎p�ƋC���ς��Ă����B�܂��A�C�ɐ�������A���v�����g���ƊC���̃l�b�g���[�N�͐����̐����Ɍ������Ȃ����̂ł���B�����̊����邽�߂ɃC�A���͒n���C�̃V�`���A�����A�j���[���[�N�B�O���[�����C�N�A�C�^���A�̃h���~�[�e�B�A�C�M���X�̃V���[�����A�p���I������K��A�≖�̌@��̃`���y���A���ĊC�ꂾ�����n�w�ȂNj����[���f���Ƌ��ɁA�C�̌��݂Ɖߋ���������B���ĊC�̐��������ɐ₦������̈╨��T�����A�����ʼn����N�����Ă������������������Ă����B�����āA�n���̂��ׂĂ̐����̊�Ղł���u�C�v�����߁A�����́u�C�v�̂�����Ɏv�����߂��炷�B �n����4����3���C�́A40���N�̊ԑ��݂��A�C�ݐ������A�C���ϓ������A�����̉^�������E���Ă����B �C�ɂ́A�G�l���M�[��߂炦�A�ۑ����A�`��������͂�����B���̗͂ɂ���Ĕg�����܂�A���̈��͂���������������B �܂��C�A���E�X�`���A�[�g�̓n���C�̊C��K��A�g�̍\����������A�C���ǂ̂悤�ɂ��Ēa������������₷����������B �a���ȗ��A�嗤�̈ړ��ɂƂ��Ȃ��A�p��ς������Ă����C�B600���N�O�ɂ́A�n���C�������������Ƃ��������B���̌��I�ȏo�����̍��Ղ��V�`���A���̒n��500���[�g���̏��Ō��邱�Ƃ��ł���B�≖�̌@���K�ꂽ�C�A���́A�n���C�����オ���ďo�����c��ȗʂ̊≖�̑w�ƁA�C���ƒn������̔M���Ō��������p�̓��A��T������B�n���C�̏����́A�����ɂ����L�̐i�����y�ڂ��A�V�`���A���Ŕ������ꂽ���M�قǂ̑傫���̏ۂ̉����Љ��B �V���[�����ł́A���L�V�R�p����̊����Ȃ���A�C������ԑ傫�ȗ́A�C�m��z�ɂ��ĉ����������B�����m�R���x�A�x���g�́A�n���̔M���z�����A�C��ɉe����^���A�����̐����Ɍ������Ȃ��_�f��h�{�����^��ł���B�������ꂪ�@�\���Ȃ��Ȃ�A�n���̐����͂قƂ�ǐ�ł��Ă��܂����낤�B�C�A���́A2��5��N�O�Ɏ��ɐ₦���������͐ς����A�h���~�[�e�B�R���ɂ��鍕����̑w��K�ˁA���Ă��ꂪ�������������Ƃ�������B �����Č��݁A�C�͐V���Ȋ�@�ɒ��ʂ��Ă���B�l�ނ���C���ɕ��o���Ă����ʂ̓�_���Y�f���A�������㏸�����A�C�����_���ɂ��Ă���̂��B�Ō�ɖK�ꂽ�̂́A���̉e���������Ɍ�����쑾���m�̃p���I�����B�����ɕq���ȃN���Q��A�_���ł͐����Ă����Ȃ��X�肪���ł̋��Ђɋ�������Ă���B�܂������̌��ŁA�_�f�����o���Ă���A���v�����g�����_���Ɏキ�A�C�̌��N�͒��������Ȃ��Ă���B ����Ȓn���́u�C�v���݂߂��C�A���́u�l�ԂƊC�̓����ŁA�l�Ԃ������Ƃ͂Ȃ��v�ƌ��B �l�ނɂƂ��āA�u�C�v�̌��N��ۂ��Ƃ́A�d�v�ȉۑ�Ȃ̂��B�@ �@ |
|
| ���X�͊������́u���̖߂�v�͓V�̏Փ˂������H | |
|
������1��2800�N�O�A�X�͊����牷�g���Ɍ������r���̈ꎞ�I�Ȋ�����u�����K�[�h���A�X���v�́A�V�̏Փ˂ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ƃ�����������B�����̒n�w�Ɏc���������̂�đ�w�̌����`�[�������͂����Ƃ���A���̐��𗠕t���錋�ʂ��o���ꂽ�B
��6500���N�O�ɋ����Ȃǂ̐�������ʐ�ł����̂́A���a10km���x��覐��n���ɏՓ˂��ċ}���Ȋ��≻�������N���������炾�Ƃ����������L�͂��B�������Ƃ��A�����������K�͂Ȃ���A��r�I�ŋ߂��N�����Ă�����������Ȃ��B �Ō�̕X�͊����I����Ēn�������g���Ɍ������Ă��������ɂ��A���x���u���̖߂�v�ƌĂׂ�悤�Ȋ���������݂����B���ł�1��2800�N�O���炨�悻1000�N�����������K�[�h���A�X���͊��≻�������ł������悤���B�}�����X�Ȃǂ̋���ٓ��ނ̑������k�A�����J�嗤���������������A�������k�A�����J�嗤�ōL�܂��Ă����Ί핶���ł���N���[���B�X�����̏I���Əd�Ȃ邱�Ƃ�������ڂ���Ă���B �����K�[�h���A�X���������炵�������Ƃ��ẮA�C�m�z�̕ω��ɂ���Đԓ��t�߂̒g�����C�����k�֓͂��Ȃ��Ȃ����Ƃ����������L�͂������B����A�ߔN���ڂ����悤�ɂȂ����̂��V�̏Փː����B2007�N�ɁA�N���[���B�X�����̈�Ղ��瑊�����ŒY�f�𑽂��܂ލ��y�����������Ƃ������\������A����͏��f�����a�����k�A�����J�嗤�ɏՓ�(�܂��͏Փ˒��O�ɋ���)�������ƂŒn��̐A�����Ă������Ղ��ƍl����ꂽ�B�������A�Ђ̑����͐l�דI�Ȃ��̂��ƍl������̂ŁA���y�͓V�̏Փ˂������炵�����̂Ƃ͌�������Ȃ��B���ɂ��l�X�Ȕ��_���������Ă���B �J���t�H���j�A��w�T���^�o�[�o���Z�̃W�F�[���X�E�P�l�b�g���_������͐V�����؋����������B����₪�����ŗn���Ă���Ăьł܂������ƂŌ`�����ꂽ�A���a1mm�ɂ������Ȃ��r�[�Y��̕��̂��B�������������͉̂ΎR�̕��○�̗����ɔ����č���邱�Ƃ����邪�A�P�l�b�g���_�������700�߂������̂̐����⎥���͂��ēV�̏ՓˈȊO�̗v�����Ă����B �����͖̂k�A�����J�嗤�����ł͂Ȃ��A��A�����J�̈ꕔ��[���b�p�A�����ɂ����z���Ă���B�V�̗̂����n�_�𐄒肷��̂͂܂�������A�P�l�b�g���_�����́u���̏؋��́A�A�����J�̑�^�����̑唼���ߌ��I�ɂ���ł��Ă��܂�����Ȍ�������K�͂ȓV�̏Փ˂ł��邱�Ƃ����������Ă��܂��B���x���̕X�͊��������������z�������A���̓V�ϒn�قł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��v�ƃR�����g���Ă���B �@ |
|
| �����{�ƕX�͊��ɂ��� | |
|
�������200���N�O�̐V�����4�I�X�V���O������A��1���N�O�̊��V�������܂ł̊ԂɁA���Ȃ��Ƃ�4��̕X��������A����ȑO��2��̕X���������Ėk�����ł͍��킹��6��̕X�����������ƌ����Ă��܂��B���ꂼ��̕X���̊Ԃɂ͔�r�I�C��̉��₩�ȊԕX��������܂����B
�����̕X��������Ă���ȑO�̖k�����̒n��͋C��͉��g�ŁA���t�L�t���тɂ������Ă����ƌ����Ă��܂��B�������A�X�͊��̖K��ɂ���Đ�ł�����A���邢�͓�ւƈړ������ƌ����Ă��܂��B ���݂͖k�����ł͕X�͂������܂����A�����͗��n��10�����������Ă���ɉ߂��܂���B�Ƃ��낪�Ō�̕X�͊��ɂ͑S���n��27�����X�͂ɂ������Ă����ƌ����Ă��܂��B���{�ł̓��������X���̏I��荠(������1���N�قǑO)�ɂ́A����̍���������肨�悻1000���[�g���Ⴍ�A�k�C���̓����R���Ⓦ�k�n���̍��R�A�k�A���v�X�ɂ͕X�͂��������Ɛ��肳��Ă��܂��B�����̕X�͂̑��݂́A�X�͂̐Z�H��p�ɂ���Č`�����ꂽ�ƍl������t���J�̓����ɃJ�[��(���J)�����邱�ƂȂǂŕ�����܂��B �X�͊��ɂ́A�C�ʂ͑啝�ɒቺ���܂����B�n���̊��≻�ɂ���ĕX���n�����A��ƂȂ��ĊC�ɗ��ꍞ�ސ��̗ʂ������������߂ł��B���̌��ʊC��̈ꕔ�͊C��Ɏp���������n�������ƍl�����܂��B���������X���ɂ͊C�ʂ�140m���ቺ�����ƌ����Ă��܂��B���̂��߁A���{�͒��N������T�n�����Ɨ������ɂȂ��đ����̓��A�������{�ɂ���Ă��܂����B���݂̃x�[�����O�C�������������X���ɂ͗��n�����āA�A�W�A�嗤�Ɩk�đ嗤���������ɂȂ��Ă��܂���(�x�[�����O����)�B��X�͊��ɂȂ�Ɠ��{�͓��{�C�ɂ���Ċ��S�ɃA�W�A�嗤����u������Ă��܂��A���{���L�̐��������������肵�܂����B�@ �@ |
|
| �����[���b�p�嗤 | |
| ��1�@���[���b�p�嗤�̒a�� �@ | |
|
�n���̖k�����Ɉʒu���郈�[���b�p�嗤�B���̋���ȑ嗤�́A5���N�O�A��ɂ̋߂��ɗ���Ȃ�̏�Ԃő��݂��Ă����B�ł́A���[���b�p�嗤�́A�ǂ̂悤�ɂ��Č��݂̎p�ɂȂ����̂��낤���H5���N�O�̒n�k�ϓ��A3���N�O�Ƀ��[���b�p���s�������M�щJ�сA������2���N�O�ɑ嗤���x�z���������B���[���b�p�嗤���a��(����)����܂ł�5���N�ɂ킽��s��ȕ��ꂪ�A�_�C�i�~�b�N�Ȃb�f�f���ɂ���đN�₩���S��B
���݁A���[���b�p�嗤�ɂ͑����̓s�s�����݂��A7���l���̐l�X���Z��ł���B���̑嗤�����̎p�ƂȂ�܂łɂ́A�����N���̒����N�����������s��ȕ��ꂪ�������B �����炨�悻5���N�O�A���[���b�p�͈�̑嗤�ł͂Ȃ��A����Ȃ�̏�Ԃœ�ɂ̋߂��Ɉʒu���Ă����B����Ȃ�̗��n�́A�n���𗬂��}���g���Ɉ��������ď������ړ����A�₪�ďՓ˂����B��������ĉ��S���N�������Ĉړ��ƏՓ˂��J��Ԃ������ʁA���n���Ȃ���A��̋���ȑ嗤���a�������̂ł���B�����āA���̎��̏Փ˂ŁA�J���h�j�A�R����E�����R�������܂ꂽ�B���[���b�p�嗤�͂��̌���ړ��𑱂��A3���N�O�ɂ͐ԓ��t�߂ɒB����B�ԓ��t�߂̒g�����������C��̂��ƁA���E�ŏ��̐X�����܂�A���̐X�́A�₪�đ嗤�S�̂��s�������B �������A���̋���ȔM�щJ�т́A2��5�疜�N�O�ɂ̓��[���b�p����p���������ƂƂȂ�B���̍��A�n����ɑ��݂��Ă����S�Ă̑嗤����ɂȂ�A"�p���Q�A�嗤"�ƌĂ��A�ƂĂ��Ȃ�����ȑ嗤���a�������B���̃p���Q�A�嗤�̈ꕔ�ƂȂ������[���b�p�嗤�́A�C���牓������A�J���~��Ȃ��Ȃ�A�M�щJ�т͑S�Č͂�ʂĂĂ��܂����̂ł���B ���疜�N���̊ԁA�����Ɖ����Ă������[���b�p�嗤�Ɍ��I�ȕω����K�ꂽ�̂́A���悻2���N�O�B�p���Q�A�嗤��������n�߁A���[���b�p�ɍĂъC���a�������B���𐁂��Ԃ������[���b�p�嗤�B�₪�āA�����ɂ��x�z���n�܂�B����Ȓ��A�ړ��𑱂��Ă������[���b�p�嗤�́A���݂̖k�A�����J�ɓ����镔����藣���A���̌��ʁA�吼�m���a�������B ���悻6500���N�O�B���J�^��������覐��Փ˂��A���̉e���ŋ����͐�ł���B���̑���ɒn��Ŕɉh�����̂��A�ٓ��ނł���B �����N�������ď������`������Ă������[���b�p�嗤�B���̊������߂Â��Ă����B���[���b�p�嗤���ŏI�I�Ɋ����������̂́A�A�t���J�嗤�ɂ�鈳���ł������B�A�t���J�嗤�ɂ�鈳���ŁA�s���l�[�R���A�J���p�`�A�R���A�A���v�X�R�����a�������̂ł���B �����āA550���N�O�ɒn���C���a�����A���[���b�p�̓�̋��E�����`���ꂽ�B���ꂪ�A���[���b�p�嗤�`���̍ŏI�i�K�ƂȂ�B�@ |
|
| ��2�@�X�͊��̃��[���b�p | |
|
������200���N�O�A�X�͊����K��A���[���b�p�嗤�͋���ȕX�͂ŕ����s�����ꂽ�B���̕X�͊��́A���̌�A���[���b�p�̒n�`��傫���ς��邱�ƂƂȂ�B���V�A�ɂ��郈�[���b�p�ő�̌A���h�K��A�m���E�F�[�̃t�B�����h�A�����ăA���v�X�R���̐[���k�J�Ȃǂ́A�ǂ���X�͊��ɂ��e���Ő��܂ꂽ�B
�ԑg�ł́A�ŐV�̂b�f�Z�p����g���Č���2000���[�g���ɂ��y�ԋ���ȕX�͂��Č����A�X�͊������[���b�p�̒n�`�����ւ��Ă����l�q�ɔ���B ���悻200���N�O�A���[���b�p��X�͊����P�����B���z�����n���̋O�����ω����A���z����̋����������Ȃ������߁A�n�����鑾�z�̌��̗ʂ������Ă��܂����̂ł���B���̌��ʁA�C���͋}���ɉ�����A����ȕX�͂����[���b�p�嗤���s�������B���̕X�͊��́A���̌�A���[���b�p�̒n�`��傫�����ւ��邱�ƂƂȂ�B�����ĕX�͊��́A�n�`�����ł͂Ȃ��A���[���b�p�ɏZ�ޗl�X�Ȑ����������ɂ��傫�ȉe����^�����B �X�͊��A�C�����X�͂̒��Ɏ�荞�܂�ē��������߁A�C�ʂ͌��݂��100���[�g���ȏ���Ⴍ�A�����͖k�C���x�[�����O�C�������n�������ƍl�����Ă���B�k�C�Ń}�����X�̍��������������Ƃ���A�k�C�����ė��n���������Ƃ����炩�ƂȂ����B ���悻4���N�O�A�������X�͊����������A�l�ނ̑c��ł���N���}�j�����l�́A�A�t���J���烈�[���b�p�����ė����n�߂��B���̍��A���[���b�p�嗤�ł̓l�A���f���^�[���l���������тĂ������A�l�A���f���^�[���l�́A���悻3���N�O�ɐ�ł��Ă��܂��B����A�N���}�j�����l�̓��[���b�p�̊��ɂ��܂��K�����A�ɉh���Ă����B �����āA�����炨�悻1���N�O�A�Ăђn���̋O�����ω����A�����������X�͊��͏I�����������B100�N���炸�̊ԂɋC����10�x���㏸���A�X�͈͂�C�ɗn���n�߂�B�����N�����̐�������Ń��[���b�p�嗤�̐�͐����𑝂��A��̔×��ɂ���đ����̌����܂ꂽ�B���V�A�ɂ��郈�[���b�p�ő�̌A���h�K�����̈�ł���B�܂��A�n���������X�͂�����̏d�݂Ŋ���悤�ɂ��Ĉړ����A�i�݂Ȃ������̊��n�ʂ�����āA�A���v�X�̐[���k�J��m���E�F�[�̃t�B�����h��������B�t�B�����h�Ƃ́A�X�͂��n�ʂ�����ďo�����[���J���A�X���n���ĊC�ʂ��オ�������ƂŐ��v���A�`�����ꂽ����]�ł���B �嗤�����Ă����X�͂��n�������ƂŊC�ʂ̐��ʂ�100���[�g���ȏ���㏸���A�V���ȊC�ݐ������܂ꂽ�B����ɂ���āA���[���b�p�嗤�̗֊s���A���݂Ƃقړ����ɂȂ����̂ł���B���[���b�p�̋C��͒g�������₩�ɂȂ�A�嗤�͍ĂѐX�ŕ����A�����ɖ�����ꂽ�B�X�͊��̓����ƏI�����A���[���b�p�嗤�̒n�`�Ɛ��Ԍn��傫���ς����̂ł���B�@ |
|
| ��3�@�l�ނƊg�傷�镶�� | |
|
1���N�O�ɕX�͊����I�������A�����ׂ������Ŕɉh�����l�ށB8000�N�O�ɂ͔_�Ƃ��n�܂�A4000�N�O�ɂ͐������H����Z�p�����B�A�l�ނ̓��[���b�p���̐X�т̂���悤�ɂȂ�B�����āA���[�}�鍑�̒a���B���[�}�鍑�̔ɉh�́A�����I���������B18���I�㔼�ɂ͎Y�Ɗv�����n�܂�A�l�ނ́A���ĂȂ��قǑ�ʂɐX�т̂����B�����܂��������ŕ����W�����A���[���b�p�̎p��ς��Ă����l�ނ̗��j�ɔ���B
�����炨�悻1���N�O�A�X�͊����I���A�C���₩�ɂȂ������[���b�p�嗤�́A��ʐX�ŕ����s������A�����ɖ������Ă����B���̂���l�ނ́A�X�Ŏ������ĐH���Ă����B �������A���悻8000�N�O�A���[���b�p�嗤�̓쐼���ŁA�V���������l�����n�܂�B���[���b�p�̓��������Ă����l�X���A�n���C���݂Ŕ_�Ƃ��n�߂��̂ł���B�_�Ƃ͏u���ԂɃ��[���b�p���ɍL����A�l�ނ͔���q���n����邽�߂Ɏ��X�ƐX�т̂��Ă������B����ɁA4000�N�O�ɂ͓���������H����Z�p�����B���A���������H����Ƃ��̔R���ƂȂ�؍ނ邽�߁A�l�ނ͑�ʂɐX�т̂���B �����āA���[���b�p�嗤�̊e�n�ɖ�������Ă���������A���ׂĎ�ɂ������Ƃ����~�]���A��̋���ȍ��ݏo�����B���ꂪ���[�}�鍑�ł���B���[�}�鍑�̓��[���b�p�嗤�S�̂ɓ��H�菄�点�A�鍑�̎v�z�ƕ����́A���̓��H��ʂ��ă��[���b�p�̋��X�ɂ܂œ`����ꂽ�B�����I�ɂ��킽���Ĕɉh�������[�}�鍑�́A���̌�A���X�ɐ��ނ��A�ŖS����B 11���I�ɓ���ƁA���[�}�E�J�g���b�N�����X�I�ȏC���@�̌��݂��n�߂��B�C���m�����͍L��ȐX�т��J���A���X�ƏC���@�����݂���B�����āA�X�т̂�����ɁA�傫�Ȓ�������ꂽ�B���̌�A�l�ނ́A�x�d�Ȃ�s�K�Ɍ������邱�ƂƂȂ�B14���I�ɂ́A�`���a�E�y�X�g�����[���b�p�S�̂ŗ��s���A�����̋]���҂��o�����B����ɁA19���I�ɂ́A�W���K�C���点��W���K�C���u�a�ۂ��A�C�������h���烈�[���b�p���ɍL�܂�A���[���b�p�j��A�ň��̑�Q�[�������N�������B�������A�l�ނ͂��̓x�ɍГ�����z���A�����W�����A�����g�債�Ă����̂ł���B ����Ȓ��A�C�M���X�ł́A���E���ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂƂȂ�A���邱�Ƃ��n�܂��Ă����B�Y�Ɗv���ł���B���C�@�ւ���������Ĉ�x�ɑ�ʂ̐��i�Y���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���X�ƍH�ꂪ���Ă�ꂽ�B19���I�㔼�ɂ́A�H��̉������[���b�p�嗤�S�̂����B �����܂��������Ŕ��W���A���X�ƐV���������ݏo���ă��[���b�p�̎p��ς��Ă������l�ށB���̌��I�ȗ��j�ɔ���B�@ |
|
| ��4�@���[���b�p�嗤�̖��� | |
|
21���I�̃��[���b�p�嗤�B����܂Ŏ��R��j�����A�쐶�����������łɒǂ�����Ă����l�ނ́A�悤�₭���R�̑���ɋC�t�����B���[���b�p�ł͌��݁A�쐶������ی삷��v�悪�i�߂��Ă���B�ʂ����āA����ꂽ���R���S�点�邱�Ƃ͏o����̂��B�ԑg�ł́A�쐶�����Ƃ��܂��������邽�߂ɗ͂�s�����l�X�̎p��ǂ��Ȃ���A���[���b�p�嗤�̖������l����B
���݁A���[���b�p�嗤�̐l���͂��悻7���l�ɂ܂Ŗc��オ��A�嗤�̂�����Ƃ���ɑ傫�ȓs�s�����݂��Ă���B���������l�ނ̔ɉh�ƈ����ւ��ɁA���R�͔j��A�쐶���������͋��ꏊ���Ȃ����Ă��܂����B �C�^���A�A���[�}�B���̊X�ɂ́A���N�A�~�ɂȂ�ƁA300���H���̃��N�h�����k�̕��������Ă���B�X�ł͑����̔M���������邽�߁A���[�}�̂悤�ȑ�s�s�͍x�O�����C���������A���N�h�������́A���̒g�����ɏW�܂��Ă���̂ł���B�������A���N�h���̌Q��͂Ƃ���\�킸��t���̉J���~�炷���߁A���[�}�̐l�X�͑傫�Ȕ�Q���Ă���B �I�[�X�g���A�̃E�B�[���ɂ��A���ꏊ���Ȃ������쐶���������������B�E�B�[���̃V���{���̈�A�V���e�t�@�����@�ɂ́A�n���u�T��A�C�^�`�̒��Ԃ̃e�����Z�ݒ����Ă���B�܂��A�X�y�C���k���̒��A���t�@���ł́A�R�E�m�g�����吹���̏�ɑ������A�C�M���X�̃����h���ɂ́A���悻1���C���̃A�J�M�c�l���������Ă���B�X�ɏZ�ݒ������A���̂悤�Ȗ쐶�����������A���Ă̂悤�Ɏ��R�̒��ŕ�炷���Ƃ��ł���悤�A�l�X�͎��R�Ɩ쐶���������̕ی�ɏ��o�����B ���݃��[���b�p�ł́A�嗤���ړ����悤�Ƃ���쐶�����̑������A��ʎ��̂ɂ���Ė��𗎂Ƃ��Ă���B�����ŁA�l�X�́A���H�̏�ɓ��������̒ʂ蓹�����A���������������ԂƐڐG���邱�ƂȂ��������邱�Ƃ��o����悤�ɂ����B �܂��A�Y�Ɗv�����n�܂��Ĉȗ��A���\�N�ɂ��킽���ĉ������ꑱ���Ă����h�i�E���C����̏ɂ����肷��B�����āA�����ɂ���Ē������ƃ��C���삩��p�������Ă����A�g�����e�B�b�N�T�[�������������Ƃ����v����n�߂��B�ĂɁA���S���Ƃ����T�[�����̎q�������C����̎x���ɕ�������̂ł���B���N�A�ق�̂킸���Ȃ���A��l�ɂȂ����T�[�������C����߂��Ă���悤�ɂȂ����B ���������l�Ԃ����̓w�͂ɂ���āA���[���b�p�̎��R�́A���������𐁂��Ԃ��Ă���B�������A�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����͂܂���������B�O����̓�����A���ُ̈�ɐB�A�����ċ}���ɐi�މ��g���B�悤�₭�Đ��������R����邽�߂ɁA���l�ނ�����ׂ����Ƃ͉��Ȃ̂��A���[���b�p�嗤�̖������l����B�@ �@ |
|
| ���k�O���[�������h�̕X���R�A���� �@�ŏI�ԕX���ɂ�����C��ƕX���̕ϓ��� |
|
|
�����ɒn���������Q�������k�O���[�������h�X���[�w�@��v��(North Greenland Eemian Ice Drilling�FNEEM�v��)�ɂ���Č@�킳�ꂽ�X���R�A����A�G�[���ԕX���ƌ�����ŏI�ԕX��(13���N�O�`11��5��N�O)�̋C��ƕX���̕ϓ�����������܂����B�k�O���[�������h�ł́A�ŏI�ԕX�����n�܂��������12��6��N�O�����ł����g�ŁA�C�������݂�����8���}4�������������Ƃ�������܂����B���̌�A�C���͏��X�ɒቺ���܂����B12��8��N�O��12��2��N�O�̊Ԃ�6��N�Ԃɖk�O���[�������h�̕X���̌�����400�}250���������A12��2��N�O�ɂ͕X���\�ʍ��x�����݂���130�}300m�ቺ���Ă��܂����B�܂��A���݂ł͖w�ǗZ�Ⴊ�����Ȃ��k�O���[�������h�������ł��A12��7��N�O����11��8��N�O�ɂ́A2012�N��7���Ɠ��l�A�ĂɕX���\�ʂŗZ���������Ă��܂����B���̌������ʂ́A�n�����g���ɔ��������̃O���[�������h�X���̕ϓ���\�����邽�߂ɏd�v�ȏ���^���Ă���܂��B
�������̔w�i ����܂Ŗk�����̕X���R�A���瓾���Ă��Ȃ������ŏI�ԕX���̋C��E���ϓ��̋L�^�邽�߂ɁA�k�O���[�������h�X���[�w�@��v��(������NEEM�v��)�̉��ŕX���R�A�@�킪���{����܂����BNEEM�v��́A�R�y���n�[�Q����w�����[�_�[�Ƃ��ē��{���܂�14�J�����Q���������ۋ����@��v��ł��B�@��n�_�͖k��77.45�x�A���o51.06�x�A�W����2450���̃O���[�������h�X����ŁA�@��v��̖��O�Ɉ����NEEM�ƌĂ�Ă��܂��B2008�N�ɊJ�n���ꂽ�@��́A2010�N7�����Ɋ�Ւ����2537m�̐[���܂ŒB���܂����B���̌�A�X�Ɗ����������������w�𐔃��[�g���@�킵����A2012�N�̉ĂɌ@��v�悪�I�����܂����BNEEM�Ō@�킳�ꂽ�X���R�A(NEEM�R�A)��NEEM�v��̎Q�����ɕ��z����A���݁A�l�X�ȕ��͂��s�Ȃ��Ă���Ƃ낱��ł����ANEEM�v��S�̂Ƃ��Ă̍ŏ��̌������ʂ�1��24�����s�̉Ȋw��Nature�ŕ���܂��B�@ ���������@ NEEM�R�A�̕X�̎_�f���ʑ̔�̕��͂ƁA���R�A���璊�o������C�̗ʂƐ����̕��͂��s�Ȃ��܂����B�����̌��ʂƃ��f���v�Z��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA�ŏI�ԕX���̋C���A�X�����x�A�X���\�ʗZ���ɂ��Ă̏��邱�Ƃ��ł��܂����B ���������� NEEM�ł́A��Օt�߂ŕX�̑w�����Ȃ��Ă������߁A���݂���ŏI�X���Ɏ���܂ł̘A�������X���@�킷�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�w�����Ȃ��Ȃ��ꍇ�A�[���Ƃ���قnjÂ�����̕X�����݂���͂��ł����ANEEM�ł́A�X�̐[���ƔN��̊W���t�]���Ă�����A��������̕X��3�ꂽ�肷��ȂǁA�w�̗��ꂪ����܂����B�����ŁANEEM�R�A�̎_�f���ʑ̔���C�̐����̕��͌��ʂ��A�O���[�������h�̑��̒n�_���ɂŌ@�킳�ꂽ�X���R�A�̕��͌��ʂƔ�r���邱�Ƃɂ��A���Ȃ����X�̊e�w�̔N������߂܂����B���̂悤�ɂ��āANEEM�R�A���瓾��ꂽ�f�[�^��N�㏇�̃f�[�^�Ƃ��ĂȂ����킹�����ʁA�ŏI�ԕX���̑啔���͘A�������w�Ƃ��ĕۑ�����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A�ŏI�ԕX���̋C��E�����قڊ��S�ɕ������邱�Ƃ��ł��܂����B �}2��NEEM�R�A���畜�����ꂽ�ŏI�ԕX���̋C���ƕX�����x�̕ϓ������������̂ł��B�}2a�̍����͕X�̎_�f���ʑ̔�ŁA�Ԑ��͎_�f���ʑ̔䂩�琄�肳�ꂽ�C���ł��B�C���́A�ŋߐ�N�̕��ϒl����̂���Ƃ��ĕ\����Ă���A���̒l�͌��݂����������������Ƃ��Ӗ����܂��B�}2���̎����͊ܗL��C�ʂ̃f�[�^�ŁA��_�����͕X���\�ʗZ�����Ȃ��ꍇ�̊ܗL��C�ʂ̐���l�ł��B���ۂɂ͕X���\�ʗZ���������Ă������߁A�ܗL��C�ʂ̃f�[�^�͈�_��������͂���Ēl���傫���ቺ���Ă��܂��B�Z�����Ȃ��ꍇ�A�ܗL��C�ʂ͕X�����x�̕ω��ɔ����C���ω��Ɠ��˗ʕω��̉e�����ĕω����܂��B�}2���̐F�̈�_�����́A����Ɋ�Â��A�Z�����Ȃ��Ƃ����ꍇ�̊ܗL��C�ʂ̐���l(���̈�_����)������˗ʂ̕ω�(�ΐF��)�ɂ��e���ƕX�������̉e��(���F��)�����������āA�X�����x�̕ω��𐄒肵�����ʂ��A���݂���̍��Ƃ��Ď��������̂ł��B �}2����A�k�O���[�������h�ł́A�ŏI�ԕX�����n�܂��������12��6��N�O�����ł����g�ŁA�C�������݂�����8���}4�������������Ƃ�������܂��B�܂��A12��8��N�O��12��2��N�O�̊Ԃ�6��N�ԂɕX���̌�����400�}250���������A12��2��N�O�ɂ͕X���\�ʍ��x�����݂���130�}300m�ቺ���Ă������Ƃ�������܂��B �}2�̔����D�F�ň͂܂ꂽ����(11��8��N�O�`12��7��N�O)�́A�X���\�ʂ̗Z���������Ă�������ł��B�}3�́A�ܗL��C�ʂ����łȂ��ANEEM�R�A���璊�o������C�̊�K�X�̑��ݔ�(��Kr/Ar�A��Xe/Ar)��^��(CH4)�Z�x���ɒ[�ɑ傫�Ȓl�ɂȂ��Ă���[�������邱�Ƃ������Ă���A���̎���ɕX���\�ʂ��Z�����Ă������Ƃ𗠕t���鋭�͂ȏ؋��ł��B ������̓W�] ���݂�NEEM�ł́A�Ăł��C�����Z�_���邱�Ƃ���ł��邽�߁A�ߔN�͕X���\�ʂ̗Z�����w�NJϑ�����Ă��܂���ł������A2012�N��7���͗�O�I�ɒg�����A�����ȗZ�����ϑ�����܂����B����A�n�����g�����i�s����A�ŏI�ԕX���Ɠ��l�ɖk�O���[�������h�������ł���K�͂ȗZ�����N����ƍl�����܂��B �ŏI�ԕX���͌��݂������Ȃ艷�g�ŁA�O���[�������h�X���̓������ł���K�͂ȕ\�ʗZ�����N���Ă����ƍl�����܂����ANEEM�R�A�̌������ʂɊ�Â��ƁA�ŏI�ԕX���ɂ�����O���[�������h�X���̕X�̗ʂ́A�Œ�ł����݂�90���͂������Ɛ��肳��A�]���̐���l�����傫���Ȃ�܂����B�ŏI�ԕX���ɂ͊C���������݂���4�`8m���������Ɛ��肳��Ă��܂����A�O���[�������h�X���̏k�������ł͂��ꂾ���̊C�ʏ㏸�͐����ł��܂���B�{�����̌��ʂ́A�ŏI�ԕX���ɓ�ɕX�����k�����A�C�ʏ㏸�ɑ傫����^���Ă������Ƃ��������Ă��܂��B NEEM�R�A�͌��݊e�������͓I�ɕ��͂�i�߂Ă���A���{���G�A���]���A��C�����A�������A���������Ȃǂ̌��������{���Ă��܂��B���{�̓h�[���ӂ��R�A�̌��������{���Ă���A���ɂ̕X���R�A�̔�r�����ɂ���āA�S���K�͂̋C��E���ϓ����J�j�Y���̉𖾂�ڎw���Ă��܂��B ���������@ NEEM�R�A�̕X�̎_�f���ʑ̔�̕��͂ƁA���R�A���璊�o������C�̗ʂƐ����̕��͂��s�Ȃ��܂����B�����̌��ʂƃ��f���v�Z��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA�ŏI�ԕX���̋C���A�X�����x�A�X���\�ʗZ���ɂ��Ă̏��邱�Ƃ��ł��܂����B�@ �@ |
|
| ���ꕶ����Ɍ���n�����g�� | |
| ���ߋ��̒n���@�|�J��Ԃ����C��ϓ��| �@ | |
|
�n���͎l�\�Z���N�̗��j�̒��ŁA�_�C�i�~�b�N�ɋC��ϓ����J��Ԃ��Ă��܂����B�n�����X�̉�ɁA���邢�͋t�ɃT�E�i�̂悤�ȏɂȂ�Ƃ��������x�̑�ω����������̂ł��B���̂��тɐ����͐�łƑ��l�����J��Ԃ��A�i�����Ă��܂����B
�����āA���݁B�����炭�n���͐V�����ǖʂ��}���Ă��܂��B����͉ߋ����瑱���S�̗̂�����Ƃ炦�A���̒��ɍ��̒n�����ʒu�Â��邱�Ƃł��N���ɂȂ�ł��傤�B �����n��(�X��)�ƒg�����n��(�ԕX��)���J��Ԃ����Y�����A���݂̈ʒu�Â���m��q���g�ł��B�X������ԕX���ւ̋}���Ȓn�����g���́A���̐��\���N�Ԃɉ��x������܂����B�N�O�̕X���̍Ő����ȍ~�A��ꖜ�N�O�ɊԕX���ƂȂ�A�Z��N�O�ɂ͉��g�̃s�[�N���}���Ă��܂��B ���̈ꖜ�N�O�ȍ~�̋}���ȊC�ʏ㏸��������"�ꕶ�C�i"�ł��B�_�ސ�ł͌��݂��C�ʂ��l���[�g���قǁA�C�����͖��x�����Ȃ�܂����B���݂ł͓�̒g�����C�ɂ��ފL���A�����̒n�w���猩����悤�ɁA�L�����̉��������Ă̋}���ȉ��g���̗l�q��m���|����ƂȂ��Ă��܂��B ���݂̒n�����g���́A�l�ނ̊����ɂ��v�����������̂ł��B�������ʃK�X�̓�_���Y�f�̑��������̈�ł��B���̓�_���Y�f�Z�x�́A�ߋ����\���N�ɒm����l���͂邩�ɒ����Ă��܂��B����A�n���̃V�X�e�����ǂ̂悤�ɍ�p����̂��͗\���s�\�ł��B �n���������l����Ƃ��A�X�̏��̒~�ςƂƂ��ɁA�����̏������Ƃɂ��đ��ʓI�ɒn�����Ƃ炦�邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B����ł��������́A�n���̂����ꕔ�����Ă���ɂ����܂���B���ꂩ�玄�����͂ǂ������邩�A�ߋ��̒n����m��A���݂��Ƃ炦�A�������l���Ă������Ƃɂ��܂��傤�B |
|
| ���X���ƊԕX���@�|�召�̃��Y���ŕϓ��| | |
|
���ʂł͋�C�������A��\�ܓ����Ƃɒ��Ɩ邪�J��Ԃ���邽�߁A��J���̂����ɕ\�ʉ��x����}�C�i�X�ꎵ�Z�`���Z�x�͈̔͂ŕω����܂��B����ɔ�ׂ�Ƌ�C������A�\�Ԃ��Ƃɒ��Ɩ邪�K���n���̕\�ʉ��x�́A���Ɉ��肵�Ă���Ƃ����܂��B
�������A�l�\�Z���N�ɂ���Ԓn���j�̒��ł́A�C��͑傫�ȃ��Y���⏬���ȃ��Y���������ď�ɕϓ����Ă��܂����B���悻��\�N�O�Ǝ����N�O�ɂ́A�n�\�̂قƂ�ǂ��X�ɕ���ꂽ�S�n���������N����܂����B ���ꂪ����������ɂ͔��ɔM�т̂悤�ȋC�K�ꂽ�悤�ł��B�������h����������͑S�ʂɏ�������ł������A���ɔ����I�ɂ͏������オ���疜�N���������悤�ł��B ��ʂɕX�͎���ƌĂ��̂́A���悻�S���\���N�O����n�܂�V�����l�I�ł����A���≻�͎O�S�\���N�O������n�܂��Ă��܂��B���̊ԁA�n���͊��g���J��Ԃ��āA�O���t�̓m�R�M���̎��̂悤�ł��B �ŋߕS���N�̕ω��ɒ��ڂ���ƁA���悻���\���N�O�ȍ~����́A��\���N�����̋C��ϓ��������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����������܂��B����̓~�����R�r�b�`�E�T�C�N���Ƃ��Đ�������Ă��܂��B �������A�C��ϓ����N���錴���́A���z���˂̕ϓ��⑾�z����̋����̕ϓ��Ƃ������A�G�l���M�[�̓��͂���n�܂��āA�嗤�̔z�u�ɂ���ĕω�����C�m���C�̏z�Ȃǂ̃G�l���M�[�̈ړ��A����ɒn������̕��˗ʂ����E����X���̏����A��C�̑g���A�G�A���]��(��C���ɕ��V��������q)�̗ʂȂǂ��݂��ɉe���������Ă��܂��B ����瑊�݂̂������͑�ςɕ��G�ŁA�����ƌ��ʂ��͂�����ƑΉ������邱�Ƃ͔��ɍ���ł��B �@ |
|
| �������g���@�|12.5���N�O�ɂ����g���| | |
|
��Z��N�O�Ƀs�[�N���}�����ꕶ�C�i�����̖̂���E�ܖ��N�O�A�ꕶ����������g����������������܂����B���̎����͉����g��(���������悵��)�ƌĂ�A���̊C�i�͉����g�C�i(���������悵��������)�Ɩ��t�����Ă��܂��B
����͉��l�s�ߌ���̉����g�n��ɂ��Ȃ��O�ł��B�����g�C�i���ꕶ�C�i�Ɠ��l�ɓ��{�e�n�Ŋm�F����Ă��܂����A�_�ސ쌧�ł͓����p���A���͘p������C�����荞�݁A��|������|��剪�n��ŁA�O�Y���������낤���ĂȂ����Ă����Ƃ����قNjK�͂��傫���C�i�ł����B �����g�C�i�̂Ƃ��ɂ��܂����n�w�́A�����g�w�܂��͉����g�w�����w�Ƃ����A�_�ސ쌧�����ɂ悭�ۑ�����Ă��āA�����ł͂��܂�m�F�ł��Ă��܂���B���A���l�n��ł́A�e�n�ōs��ꂽ���H�H�����n�J���̂��тɁA�����g�w���m�F����A�����̊C�̗l�q���ڂ����������Ă��܂��B �����g���̊C�ɐ������Ă����L������A�����̗l�q��������܂��B�����p���̍`�k��e���t�߂���́A�o�J�K�C�A�i�~�K�C�A�n�}�O���A�C�^���K�C�Ȃlj��ݍ���ɂ��ފL�̉����������Ă��܂��B�˒˂ⓡ��ł̓J�L�ʂ̉����������Ă��āA�p�����������Ƃ�������܂��B �܂��A����ɉ��܂�����扪�Ò��Ȃǂł́A���ݗL���C�Ȃǂ̊����ɂ��ރn�C�K�C�̉����������Ă��邱�Ƃ���A���������B���Ă������Ƃ��z���ł��܂��B�n�C�K�C�͌��݂̊֓��n���̊C�ł͊����Đ����ł��܂���B�n�C�K�C�̉��������������Ƃ���A�����g�����g�����������Ƃ�������̂ł��B ����A���̗l�q������Ă��܂����B���݂ł͐�ł����i�E�}���]�E�������������Ă��āA���l�A���{��A����Ȃǂ��牻����������Ă��܂��B �@ |
|
| ���ꕶ�C�i�@�|�߉������{���܂ŊC�| | |
|
���q�̋��s�X�n�͊���̒�n�ɍL�����Ă��܂��B��n�͓�����R�Ɉ͂܂�A�삪�R��P�l�̊C�ɖʂ��Ă���A�߉������{�_�Ƃ���A�قړӎO�p�`�ƂȂ��Ă��܂��B���̊����n�ɂ͍��ƓD�̓��ȉ��ϑw���ς����Ă��āA�����ɂ͓ꕶ�C�i�������ۑ��̗ǂ��L�����܂܂�Ă��܂��B
�ȑO�A�����{�����Ɍ����ߑ���p�ق����݂��ꂽ�Ƃ��A�n�������ʂ̊L�����o�܂����B����Ɋ��q�s����ق̎����ق��ł����Ƃ��ɂ��A�L����̂̊C�݂������n�`���݂���܂����B�����̏������ƂɎs�X�n�̓ꕶ�C�i�Ő���(�Z��N�O)�̒n�`������ƁA�����n�͓��p�ƂȂ��Ă������Ƃ�������܂����B �p�����R��P�l�ŕ����L���A�p�����߉������{�̓����ɒB���Ă��܂����B�p���܂ł̒����͖�O�L���ƂȂ�A�p���̍L�����ɉ��s���̐J��������]�ł����B�p�̍ł��������q�{�t�߂ɒB���A�����ƂȂ��Ă��āA�n�}�O����V�I�t�L�A�C�{�L�T�S�Ȃǂ��������Ă��܂����B �p���ɋ߂��߉������{�����ł́A��C�`���E�̂���Βi�̉��܂ŊC������A�g���ł��邫�ꂢ�ȍ��l�ƂȂ��Ă��܂����B�����ɂ͌��݂̑��͘p���݂ɂ͐������Ă��Ȃ��^�C�����V���g����V�I���K�C�A�q���J�j�����ȂǔM�т��爟�M�т̒g�����C�ɂ��ފL���������Ă��܂����B �܂��A���q�啧�̂��钷�J�̒J�͕��̋�������]�ƂȂ�A�����ɂ��D�w�������ς����Ă��邱�Ƃ��啧�̒n�����疾�炩�ɂȂ�܂����B���̓D�w������M�тɂ��ރJ���m�A�V�K�L�̂ق��A�C�{�E�~�j�i�A�J���A�C�Ȃǂ̊L�����݂����Ă��܂��B �@ |
|
| ���L����ǂށ@�|�p�݂̌Ê����| | |
|
�����p�⑊�͘p���݂ɂ݂��鉫�ϒ�n�́A�D�⍻�w�������ς����ē��ȉ��ϑw�ƂȂ��Ă��܂��B�傫�ȍH���ȂǂŁA�����̉��ϒ�n���@��N�����ƁA�ۑ��̗ǂ��L�����͂��߁A�C�ɂ���ł������낢��Ȑ������̉����݂���܂��B
���ł��D�w���ɂ͓̊k�����킳�����L�������܂��Ă��邱�Ƃ������݂��܂��B����͊L�������Ă�����Ԃ̂܂܉��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B���̊L�̎�ނƐ��ԁA���̎�̕��z��������A�L�������Ă��������̊C�ݐ���C��̊���m�邱�Ƃ��ł��܂��B ���̓_�ɒ��ڂ��āA�����ɕ��z���Ă��鉫�ϑw���̊L�����L�ތQ�W�Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă݂�ƁA���p���版�݂ɂ������z���鉫�ϑw�ɂ́A�傫���\��̃O���[�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B �Ⴆ�A�ߌ����n��剪��̒�n�̉��܂����n�_����Y�o����}�K�L��n�C�K�C�A�I�L�V�W�~�́A���p�̉��̓D�����ɐ�������L�ŁA���̒n�_�܂œꕶ�C�i�ŊC���������ē���]�ƂȂ��Ă������Ƃ������Ă��܂��B�n�}�O����A�T���A�J�K�~�K�C�͓��p�ł����D��̍L���銱���ŁA���n�ɐ����Đ������Ă��܂��B ���̉������ϑw����݂���A�����͂��ē��p�̍��n�̔��B���銱���ƂȂ��Ă������Ƃ������Ă��܂��B�`���E�Z���n�}�O����_���x�C�L�T�S�A�x���P�C�K�C�̉������ϑw����Y�o����A���̉��ϑw�͏Ó�C�݂�[���̋�\�㗢�l�̂悤�ɊO�C�ɖʂ������݂ɑ͐�(��������)�����n�w�ł��邱�Ƃ�m�邱�Ƃ��ł��܂��B �T�U�G��A���r�A�g�R�u�V�Ȃǂ̊����L�������I(���ꂫ)�w����Y�o����A�O�C�ɖʂ�����ʊC�ݕt�߂ő͐ς����n�w�ł��邱�Ƃ������Ă���܂��B���̂悤�ɊL���̎������A�ꕶ�̊C�̌Ê������邱�Ƃ��ł��܂����B�@ |
|
| ���C�ʕϓ��@�|100�N������2���[�g���㏸�| | |
|
�Z��N�O����A�_�ސ�ł͊C�ʂ���������l���[�g�������A�ꕶ�C�i�̃s�[�N���}���Ă��܂����B�N�O�̕X���Ő����̊C�ʂ͕S��\���[�g���Ⴉ�����̂ł�����A�킸���ꖜ����N�̊Ԃɋ}���ɏ㏸�������ƂɂȂ�܂��B���̋}���ȊC�ʏ㏸�ɔ����A�ς����Ă������͐�(��������)�������≡�l�Ȃǂ̒�n�����鉫�ϑw�ł��B
���ϑw���猩����L������A�L�������Ă��������̊C�ݐ����ł��܂��B���Ƃ��A�}�K�L�͒��̖���������ꏊ(���ԑ�)�ɂ��ފL�ł��B���̃J�L�ʂ̉���������A���̏ꏊ�����Ă̊C�ݐ��ł������؋��ƂȂ�܂��B�܂��A���ː��Y�f(�Y�f14)�����̑��x�ʼn��邱�Ƃ𗘗p�����N�㑪��(14�b�@)���牫�ϑw���̊L�k�̔N���m�邱�Ƃ��ł��܂��B ������E�ߌ����n�ł́A���ϑw�̊L�������������Ă��܂��B���̊L�����������[���ƔN�㑪��̒l����C�ʕω��Ȑ���`���܂����B���ԑтɂ��ގ�̓_�����Ȑ����A�C�ʂ̍����̕ω���\���Ă��܂��B0���[�g���͌��݂̊C���ʂ̍����ł��B�����͔N��A�c���͍���(�[��)�������Ă��܂��B �ꖜ�N�O�ȍ~�A�C�ʂ��}���ɏ㏸�����l�q���悭������܂��B�}���̔��甪�S�N�O�A�[���}�C�i�X�O�����[�g���̐_�́A�H�c��`�n�����猩�������}�K�L�ɂ����ł��B���甪�S�N�O�́A���ꂾ���C�ʂ��Ⴉ�����؋��ł��B ����N�O���玵��ܕS�N�O�ɂ����ẮA�O�\���[�g�����C�ʂ���C�ɏ㏸���Ă��܂��B����͕S�N������A���悻�[�g�����㏸�������ƂɂȂ�܂��B�}���ȊC�ʏ㏸�̌�A�Z��N�O�ɂ��悻��l���[�g���̍����܂ŊC�ʂ��B���܂����B �_�ސ�̉��ϑw����̊L���g���āA�ߋ��ɋN�������n�����g���ɂ��C�ʏ㏸����̓I�Ɏ������Ƃ��ł��܂����B�X���ɂ͑��ʂɂ�������ɂ̕X���A�n�����g���ɂ���C�ɉ����ĊC�ʏ㏸�������炵���̂ł��B�@ |
|
| ���ꕶ�̊C�@�|���������u���g��v�| | |
|
�[�������암���瑊�͘p���݂̉��ϒ�n�߂Ă��鍻��D�w�ɂ́A���݂̓�֓����݂ł͑S���������Ă��Ȃ��n�C�K�C��V�I���K�C���͂��߁A�^�C�����V���g���A�J���m�A�V�K�L�A�x�j�G�K�C�ȂǁA�M�т��爟�M�т̒g�����C�ɂ��ފL(���g��)���Y�o���܂��B
�����̉��g�킪�����둊�͘p���݂܂Ői�o���Ă��������ׂĂ݂�ƁA���ɕ�����Ă���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�ŏ��ɂ���Ă����O���[�v�̓n�C�K�C��V�I���K�C�A�R�Q�c�m�u�G�A�q���J�j�����A�J�j�m�e���V���K�C�ł��B �ꕶ�C�i���n�܂������悻���ܕS�N�O�ɏo�����A�C�i�Ő����́A�C�ʂ����݂��l���[�g���O��������Ȃ����Z��N�O�ɂ����Ƃ��ɉh���Ă������Ƃ�����܂����B���̌�A���̉��g��͐������Ă����������C�ʂ̒ቺ�ɂ���Ď����Ă����̂ɂ�A���͘p���݂�����ł��Ă����܂����B ���ɂ���Ă����O���[�v�̓^�C�����V���g����J���m�A�V�K�L�A�`���������L�K�C�A�x�j�G�K�C�̔M�ю�ŁA�[���َR�̏���O�Y�̖���Œm����ʃT���S�ƈꏏ�ɘZ��ܕS�N�O�ɍ����ɏ���āA�[���암���瑊�͘p���݂܂Ŗk�サ�Ă��܂����B ���̎����͒n�����g�����ł��i�݁A�C�ʂƊC�����������Ȃ�܂����B�M�ю�̊L�ƏʃT���S�������������Ƃ���A��֓��ł͊C���������݂���x�قǍ����������Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B���̌�A�����̉��g��͎l���S�N�O�܂Ő������Ă��܂������A�C�����ƊC�ʂ̒ቺ�ɂ���đ��͘p���݂��犮�S�ɏ��ł��Ă��܂��܂����B ���Ȃ݂ɁA�^�C�����V���g���̓^�C�����̖������Ă���悤�ɔM�т̊L�ł��B���ݐ������Ă���Ƃ���́A��p�ȓ�̔M�т̊C�ŁA����ł��ꂢ�ȍ��l�C�݂ɂ݂��܂��B�@ |
|
| ���Ò����p�@�|���N�����ꕶ���̊C�| | |
|
�Ò����p�́A���u�˓쐼���̏��c���s�Ɠ�{���̋��𗬂�钆����(�͌��t�߂ł͉��ؐ�)�̒�n�ɂł������p�ł��B�ꕶ�C�i�ɂ���āA����N�O���璆����̒J�֊C������͂��߁A�Z��ܕS�N�O�ɂ͌��݂̊C�ݐ����炨�悻��D�܃L�������܂ōL����Ò����p�ƂȂ��Ă��܂����B
��N�A�����여��̑����H���ɂ��Ò����p�ɂ���ł����L�����݂���܂����B���̒��ɁA���݂͋I�ɔ�������̒g�����C�ɂ��ރn�C�K�C�A�V�I���K�C�A�R�Q�c�m�u�G�Ȃǂ������܂��B��Z��ܕS�N�O�̑��͘p���݂́A���݂�肸���ƒg�������������̂ł��B ���āA���̌Ò����p�̊L���܂ޒn�w�́A���݊C����\���[�g���t�߂܂ŕ��z���Ă��܂��B���̂悤�ɘZ��ܕS�N�O�̌Ò����p�̒n�w����n�̏�̍����ɂ܂ŕ��z���Ă���̂́A�n�k�ɂ�闲�N���J��Ԃ��Ă������߂ł��B���ɑ��͘p�p����k���Ƃ��鋐��n�k�ɂ���āA���u�˂��傫�����N���邱�Ƃ��������Ă��܂��B �n�k�ɂ�闲�N�̌��ʁA�Ò����p����C�����ނ��A�l���̂悤�ȊC���ƒW��������������Ă���D���̌Ò��������a�����܂����B���̔N��͖�Z��ܕS�`�Z��O�S�N�O�̊Ԃł��B�Ò������ɂ́A����܂ł̌Ò����p�ɂ��ފC�̊L�����ɑ���A�D����ɂ��ރ��}�g�V�W�~�����ɂ��݂����ƂɂȂ����̂ł��B �����āA�ꕶ�O��(��ܐ玵�S�`�ܐ�O�S�N�O)�ɂ́A�H�����L�˂��Ò������̐��݂ɂ����܂����B���̌Ò��������A���̌�ɑ���������n�k�ɂ���Ď��n�ւƕω����Ă����܂����B ���̒n��ł́A�ꕶ�C�i�ɂ��C�ʂ̏㏸������n�̗��N�ʂ��傫���A�ꕶ�C�i�̃s�[�N�O�ɊC���ނ����ƂƂȂ�܂����B���u�˂Ɍ�����C�ʂ̕ϓ����l����Ƃ��ɂ́A���g���Ȃǂɂ��n���K�͂̊C�ʕϓ��̓��������łȂ��A�n��̒��~�◲�N�Ƃ������n�k�ɔ�����n�̓��������킹��K�v������̂ł��B�@ |
|
| �����T���S�w�@�|�k���Q���n�ɔM�ю�| | |
|
�[��������[�َ̊R�p�ɂ́A���݁A�K�͂͏������Ȃ��琅�[��Z���[�g���O��̊C��ɃT���S�̌Q���n������܂��B�����ł͓�\��ނ̃T���S���������Ă��āA���E�ōŖk�̌Q���n�_�Ƃ��đ�ϋM�d�ł��B
�Ƃ��낪��Z��ܕS�N�`�ܐ�ܕS�N�O�̓ꕶ����ɂ́A���̊C�Ɍ��݂��͂邩�ɋK�͂̑傫�ȌQ��������A���\��ވȏ���̃T���S���������Ă������Ƃ����Β����ɂ�蕪�����Ă��܂��B���łׂ͍��ȑg�D�\�����̕��������Ă��܂��̂ŁA��ނ����߂�͓̂�����Ƃł����A����ł�����Ȃɑ����������Ă��܂��B �����A���ۂɂ͂����Ƒ����̎�ނ������Ƒz���ł��܂��B���̂��ʂ́A�َR�p���ӂ̏�(�ʂ�)�n��ɕ��z���鉫�ϑw�ɉ����ʂƂ��Ďc���Ă��āA�u���T���S�w�v�ƌĂ�Ă��܂��B�܂��A���̒��ɂ́A���݂ł͎��������ȓ�ɂ������Ȃ���ނ��܂܂�Ă��܂��B �T���S�͈�N�ԂŐ����ł��鑬�����C�����ɂ���ĈႢ�܂��B���̂��Ƃ��L�N���C�V�Ƃ����T���S�ł݂܂��ƁA�ɓ������]�m�Y�̌�����ł͎O.�Z��~���A�����哇�ł͎l.����~���A�����ď��w���ł͎l.�Z��~���ł��B���w�Y���̔N�Ԑ������́A�����哇�̒l�ɋ߂����̂ł��B�T���S���ƈꏏ�ɂ݂���L������́A�x�j�G�K�C�A�����C�K�C�A�I�n�O���K�L�ȂǁA���݂̓�֓��ɂ͕��z���Ă��Ȃ��M�ю킪�������Ă��܂��B ���̂悤�ȓ_��������ʂ����z���Ă�����Z��ܕS�N�`�ܐ�ܕS�N�O�َ̊R�p�̊��𐄒肷��ƁA���݂̋I�ɔ����ȓ�A���B���牂���哇�قǂ̒g���ȊC���̐��p�ɂȂ��Ă����ƍl�����܂��B�@ |
|
| ���L�ˁ@�|���ω��m��w�W�Ɂ| | |
|
�y��̎g�p���n�܂����ꕶ���㑐�n���A�l�X�͋��Ί펞��Ɠ��l�Ɏ��̏W�ɗ��鐶�����c��ł��܂����B
�₪�ēꕶ���㑁��(����N�O)�ɂȂ�ƋC���g�����A�C�ʂ̏㏸�ɂ��C�ݒn�тɂ��ڂ�J�̒n�`�����B���āA���p�����]������o����A����̍��l�⊱�����g�傳��܂����B���̂��납��C�Ɛl�ԂƂ̐[�����т����n�܂�A�l�X�͉͌������]�ɏo�ċ���L�̕ߊl���s���悤�ɂȂ����̂ł��B �H���ɗp����ꂽ���Ƃ̋��̍���L�̊k�́A�ނ�̏Z�܂��̎��ӂɎ̂Ă��܂����B�����ɂ̓C�m�V�V��V�J�̍���p�A�y��̂�����A��肩������(����)��ނ�j�A�܂ꂽ�Ί�Ȃǂ��������Ă��܂��B�����͒������Ԃ��o�đ͐�(��������)���A�L�˂��`�������̂ł��B ���{��s�g��L�˂͓ꕶ���㑁�������璆���Ɏ���A���悻�Z��ܕS�`�l��ܕS�N�O�Ɍ`�����ꂽ�L�˂ł��B�㉺��̊L�w����Ȃ�A�����͊C�i�ō����ɁA�㕔�͊C�ފ��Ɍ`������܂����B�����L�w�͓��p�̒��ԑт̍��n��D�n�ɐ�������}�K�L�A�n�C�K�C����̂ɁA�I�L�V�W�~�A�n�}�O���Ȃǂ̓L�����������A��������͑������̓y�킪�o�y���Ă��܂��B �㕔�L�w�̓}�K�L�A�n�C�K�C�Ȃǂ̓L���������A�C�V�_�^�~�A�X�K�C�A�N�{�K�C�A���C�V�K�C�A�T�U�G�Ȃǂ̔g�ł��ۂ̊�ʒn�тɐ������銪���L�����������A��������͒����㔼�̓y�킪�o�y���Ă��܂��B ���̂��Ƃ́A�������̊C�i�ō����ɔ����Ĕ��B�������p���A�����ȍ~�ɂȂ�Ǝ���ɏk������A�}�K�L��n�C�K�C�̐����ł�����������Ă��������Ƃ������Ă��܂��B ���̂悤�ɁA����ꏊ�ɂ�����L�w�̗l���̈Ⴂ�́A�����ɂ���āA���R�����ω����Ă��������Ƃ�m���|����ɂȂ��Ă��܂��B�@ |
|
| ���������ʁ@�|�Z�x������_���Y�f�| | |
|
�n���S�̂ł̕��ϋC���́A���悻��l�x�ł��B����͒n���̕\�ʂ��u��C�v�̓����ɂ����̂ł��B������C���Ȃ���A�}�C�i�X�ꔪ�x�ɂȂ��Ă��܂��ƍl�����Ă��܂��B
���z����̌��́A��C��f�ʂ肷��̂Œn�\���g�܂�܂��B�g�߂�ꂽ�n�\�͉F���֔M�����̂ł����A���̓����Ă����M�̈ꕔ����C��g�߂܂��B���̗l�q���_�ƂŎg���u�����v�̃K���X�����̖����Ɏ��Ă���̂ŁA�u�������ʁv�Ƃ����܂��B ��C�̐����̒��ŁA�������ʂɑ傫�ȉe����^����̂́A�����C�ł��B�������ʑS�̂̔����ȏ�������Ă���Ƃ����܂��B�����C�̗ʂ́A�G�߂�ꏊ�ł̕ϓ����������A��C���̔Z�x��0.1�`5���ƕ�������܂��B ���̂ق��ɂ͓�_���Y�f��^���A�t����(�n���J�[�{��)������܂��B�����́u�������ʃK�X�v�Ƃ��Ēn�����g�����̌��������Ƃ��Ĉ����Ă��܂��B���̉������ʃK�X�́A�ϑ��̌��ʁA�ʂ������Ă��Ă��邱�Ƃ�������܂����B �}�́A��_���Y�f�Z�x�ƋC���Ƃ̊W�������Ă��܂��B�C���͎��F�̖_�O���t���e�N�̒l�A�Ԃ��܂�����ܔN�Ԃ̈ړ����ς������Ă��܂��B��_���Y�f�Z�x�́A�g��ł��Ă��鐅�F�̐����ϑ��l�ŁA�����̐������ܔN�Ԃ̈ړ����ς������Ă��܂��B �C���̏㏸�ƁA��_���Y�f�Z�x�̏㏸�̃J�[�u�����Ă���Ǝv���܂��H�@�������ʃK�X�Z�x�̑����́A�C���̏㏸�������ƍl�����Ă��܂��B�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l��(IPCC)�����\���������\���ł́A���̂܂܉��̑����炸�ɂ���ƁA�S�N��ɂ͍ő�ŋ�Z�Zppm�܂œ�_���Y�f�����債�A�C�����l.�ܓx�㏸����ƌx�����Ă��܂��B�@ |
|
| �����Y���@�|�������H���g�̎����| | |
|
�n���̋C��ω��ɂ͈��̃��Y��������悤�ł��B�ߋ���U��Ԃ�ƁA�g���������Ɗ��������͌��݂ɂ���Ă��Ă��܂��B���͒g�����������I���A�����Ȃ��Ă��������ɂ�����͂��ł��B
�}�́A�����ŋ߂�(�Ƃ����Ă��A�n���̗��j�̒��ł̂��ƂŁA�������̊��o�ł͂����Ɛ̂̂��Ƃł���)���̕ω����C���[�W�������̂ł��B���́A�C����C�ʂ̍����Ȃǂ̕ω��̌X����\���Ă��܂��B�ۊ�́A�_�ސ�̑�n�̕ω��������Ă��܂��B�ۂ̏㑤�ɂ���ΐF�̕����͗��n�ŁA�����̐��F�͊C�ł��B���̊��W�ł́u���Ȃ��킭��v�ƌĂ�ł��܂��B �C���̍��������A���Ȃ��킭����������Ă��܂��B���̎����ł́A�����ɂ���C�̕����������Ă��܂��B���������A���Ȃ��킭��͐k���Ă��܂��B�g���������ɔ�ׂ�ƊC�������Ȃ��Ă��܂��B ���̕ω��ɂ����ڂ��Ă��������B�g�����Ȃ�ω��͋}���ɐi�݁A�t�Ɋ����Ȃ�ω��͂������i�݂܂��B�_�ސ�ł́A�ꖜ�N�O����Z��N�O�ɂ����Ă̓ꕶ�C�i���ɁA�C�ʂ���C�ɁA���悻�l�\���[�g�����㏸�������Ƃ��������Ă��܂��B�����炭�A�g�����Ȃ�ƁA����ɂ��̒g�����Ȃ邱�Ƃ�������d�g��(���̃t�B�[�h�o�b�N)�������̂ł��傤�B �܂����̖��́A��C���̓�_���Y�fCO2�Z�x�̕ω��������Ă��܂��B�Ԃ��_���́A�Y�Ɗv���ȑO�̉ߋ����\���N�Ԃł̓�ɂł̔Z�x�̍ō��l(��Zppm)�ł��B���݂́A���̔Z�x���Ă��܂��Ă��܂��B ����͉����Ӗ�����̂ł��傤���HCO2�Ȃǂ̉������ʃK�X�̔Z�x�́A�C��̕ϓ��ɑ傫�ȉe����^����Ƃ����܂��B�C��ω��̃��Y������݂�Ί����Ȃ��Ă����͂��̋C��B�t�ɒg�����Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤���H�@ �@ |
|
| �����n��1���N��A10���N��̎p | |
| ��1�A�g�Ɗ���10���N�T�C�N���@ | |
|
�M�҂��o�ł����w�����Ɨ��Y�̓����n�v�ł́A���̒a������A���n�s�̒a���܂ł��������B
�M�҂̖{�̒��߂�����́A���n�����̏I��(�I��)���l���Ă����B����͂܂��l�ނ̎��ł��������ƂɂȂ�B�C�̏d���b�ł���B �M�҂́A�u�E�E�E���n�v�̖{�̒��ŁA�X�͊��̂��Ƃ��������B�~���f��(40���N�O)�A���X(20���N�O)�A���G����(7���N�O)�Ƃ̐��ɏ]���āA���n�n���̐l�ނ̗��j���������B ���̐l�ނ̖ŖS��\�����邱�Ƃ͂����ē�����Ƃł͂Ȃ��B�Òn���w�A�ËC��w�A�����w�A�Ð����w�Ȃǂł͐l�ޖŖS��̂���Ɏ���đ��铮�A���̃V�i���I���ł��Ă��� ��̎킪���ł���ق��̎킪����ɂƂ��đ���̂ł���B �ŋ߁u2���N��̐������E�v�Ȃ�{���o�ł��ꂽ�B �w�҂̊w����Ȋw�I�f�[�^�[�Ɋ�Â��A���n���̖����Ⓡ���̖����������c���Ă������ƂƂ����B �܂��ԈႢ�̂Ȃ����Ƃ́A���̒n����50���N���炢�ŏ��ł���Ƃ���Ă��邩��A���n�����i�v�ɑ��݂��邱�Ƃ͂Ȃ��B�܂��l�ނ́A500���N�����݂��邱�Ƃ͂Ȃ��A100���N���Ɏ��ł���ł��낤�B���̕ӂ܂ł͂قڊԈႢ�̂Ȃ����_�ł���B�@ �����ŁA�M�҂͐l�ނ̑�ʎ��ł͂ǂ̂悤�ȏꍇ�ɁA�ǂ̂悤�ȏŋN����̂��ɂ��Đ��_�����݂�B ���_�����ɏq�ׂ�ƁA�l�ނ́A4000�N�Ȃ���5000�N��̒n���̋ɓx�̉������ɂ���Ď��ł̑��x�𑬂߁A1���N�Ȃ���2���N��̕X�͊��̓����ɂ���Ăقڎ��ɐ₦��B�ԕX���ƕX�͊��́A�ʏ�10���N�����ŌJ��Ԃ����B�܂艷�g��1���N�A�X��9���N�̃T�C�N���́A�n���a������J��Ԃ���Ă��Ă���B ���݂̃E�����X�͊���6000�N�O�ɊԕX���ɓ���A�n���͉��g�����A���݂Ɏ����Ă���B���̉��g���X���͌�4000�N�͑����A���̌�9���N�Ԃ̕X�͊����҂��Ă���̂ł���B����9���N�̕X�͊���l�ނ��������т邱�Ƃ͂قƂ�Ǎ���ƕM�҂͍l����̂ł���B���ꂩ��Ȃ����̂悤�ɍl���邩�ɂ��ďq�ׂ�B�@ |
|
| ��2�A�l�ނ��n���Ɍ��ꂽ�̂́A1���̂�����1������ | |
|
�n���̒a�����猻�݂܂ŁA50���N�Ƃ�������������Ă��邪�A�l�ނ͒n���w��̐V����ɂȂ��Č��ꂽ�B���܂���400���N�O�ɉ��l������A80���N�O�ɃW������k���Ɍ��l������A����15���N�O�Ƀl�A���f���^�[�����l�A3���N�O�ɃN���}�j�����V�l�����ꂽ�B
���̂��Ƃ���A�l�ނ炵�����̂��n����Ɍ��ꂽ�̂͂�������400���N�O�ł���A�n���̒a�����猻�݂܂ł�1���o�߂����Ɖ��肷��A�l�ނ́A�ق��1���O�Ɍ��ꂽ���ƂɂȂ�B �l�ނ�����Ă���400���N�ԂɁA10���N�T�C�N���̕X�͊��́A40��N�������B����200���N�O����1���N�O�܂ł̕X�͎���(�n���w��X�V��)�́A�X�͂̔��B�A��ނ��J��Ԃ��ꂽ�B����̓��G�����X�͊��̂����̉��g���̂����ތ�X���ɑ�����B��ɏq�ׂ�����4000~5000�N�͂��̉��g���X���������̂ł���B |
|
| ��3�A�l�ނ͒n���������ʊ������т�邩 | |
|
���ݒn����ł́A�������ʂ̗}��������A���E�e�����Ζ��̏�����팸���邽�߂̏���鋞�s�c�菑��������悤�Ƃ������A�A�����J�̔��ɂ����Ă͂ł��Ȃ������B���̌��ʋ�C���̓�_���Y�f�A�L�ŃK�X�A����̗ʂ������Ȃ�A���E�e�n�Ɏ_���J���~��A�A���⓮�������ł�����B
�l�ނ͊j����̎������J��Ԃ��A�푈�ő�ʂ̔�����g�p���Ă���B�����͑�C�����������Ă���B �܂��M�҂̒����u���n�v��144�y�[�W�ł��w�E�����Ƃ���A�A�_��A���w�엿�A������܂Ȃǂ̊E�ʊ����܂���ʂɉ͐삩��C�֗�����A����ނ��o�Đl�Ԃ̌��ɉ^��Ă���BDDT�A.PCB�A.LAS�A�_�C�I�L�V���Ȃǂ̊��z����������̂���َ��ւƎp����Ă���B�����̊��z�������́A�����坘�������ł���A�q�����Y�߂Ȃ������A�l�Ԃ̐���Ȓm�\������j�Q����B �_���J�ɂ�鏼�͂ꌻ�ہA���q�����ہA�����̎E�������̕p���ȂǁA�M�҂̋���Ă����l�ނɂ��n���j��̒�����͂��߂Ă���B �v���[�g�e�N�X�ɃN�X�̗��_�ɂ��A�₪�đ嗤�̈ړ��ɔ����C�◤�̉ΎR�����������ɂȂ�A����ɐl�דI�ȃt�����K�X�̕��o�A�K�\�����Ȃǂُ̈�ȏ���Ȃǂɂ��A��C�̏�w�́A����ƊD�ׂ̍������q���[�����A���z����̕��˔M����������B ���̌��ʋC����������A�����͎��Ɏn�߁A�A����������͂��߂�B �M�҂͖{�̒��Łu�����H���~�߂�肾�ẮA�l�ނ���������̂āA�����Ɏ��R�ƌ������������Ƃ��ł��邩�ǂ����ɂ������Ă���v�Əq�ׂ��B �l�ނ̑����́A���̒n�����������ۂ�ΎR�����A�������ȂǂŎ��ł������A����ł����l���̐l�ނ͐������тĂ����̂ł���B�@ |
|
| ��4�A10���N��̐l�ނ̎��� | |
|
�ԕX���̉��g�������4000�N~5000�N�ŏI��A����ɑ����āA10���N�T�C�N���̕X�͊����A9���N�����̂ł���B�����Ă��ԂƂ��l�ނ��A���̕X�͊����c��邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ł������B
������1���N��ɂ���Ă����X�͊��́A�l�ނɂƂ��Č��������̂ƂȂ����B �k�A�����J�̂قƂ�ǂ͕X�̉��ɂȂ����B�k���[���b�p�X�̉��ɂȂ�A���̕X�̌����́A3�L���ł������B�A�}�]���여��ɂ������̟T���Ƃ����M�щJ�т́A�������������ɕς�����B��ʂ̐����X�ɂȂ�A�C�ʂ�150���[�g���ቺ�����B �l�ނ̃G�l���M�[����A�n����h�邪����œI�Ȍ��ʂ������炵�����߁A���Ԍn�����������ɂȂ����B�~�̖�͋C���͐ێ��}�C�i�X60�x����������B�\�y�̉��ɂ���A�i�v���y�w�́A1�N���������܂܂ŁA����ʂ��Ȃ������B �k���[���b�p�ɂ��t�͖K���B�\�y�͂��݁A�c���h���͐����肪�_�݂���A���n�ƂȂ����B ���̂悤�Ȍ������������������߁A�l�ނ͍앨����邱�Ƃ��ł����A�Q�̂��߂Ɏ��X�Ɏ���ł������B�܂��H�p�̓����A���Ƃ����Ƃ��A�Ƃ����邢�͋Q���Ɗ����Ŏ��ł��A���ނ̑唼�́A�X�̊C�ɕ����߂��A���ł��Ă������B���̂��߂��l�ނ́A�H�p�̐A���Q�A�H�p�̓����Q�������A��ł̓������ǂ��Ă������B 100���N�̊ԂɁA�ԕX���ƕX����10�N�T�C�N����10����K�ꂽ���߁A���̌J��Ԃ��ŁA�l�ނ݂̂łȂ��A�l�ނƂƂ��ɓ����ɐ��������A����������A���Q�����ł��Ă��܂����B �l�ނ͐�ł������A��������ł����킯�ł͂Ȃ��B�ł�Ō����������̑���ɁA���ɓK�������ʂ̓�����A�����a�����Ă����̂ł���B ����500���N�̑��������ɁA�l�ނ͖ŖS����Ɨ\��������̂�����(�h�E�[�K���E�f�B�N�\��)�B �M�҂́A1���N����n�܂�X�͊�����l�ނ͎��łւ̓�����݁A�X�͊��̃s�[�N�̗���10���N��܂łɂ͑S�l�ނ͎��ł���Ɛ�������B �l�ނ����ꂽ�̂́A��������400���N�O�ŁA�����n���̗��j���猩��A�ق�̈�u�ł���B�����Ă��ꂩ��̒n���́A�嗤�̈ړ��A�ΎR�����A�����A�X�͊����J��Ԃ��Ȃ���A50���N�Ƃ����ƂĂ��Ȃ��N�������ݑ����邱�ƂɂȂ�B�@ |
|
| �@ | |
|
���߂��@�@���߂�(�ڍ�)�@�@�@�� Keyword�@�@�@�@ |