■2020 / 2020/12・2020/11・10/31・10/20・・・10/10・10/9・10/8・10/7・10/6・10/5・10/3・10/2・10/1・・・2020/9・2020/6・2020/5・2020/1・・・2019〜・・・
■諫言 / 諫言・諫言に耳傾ける・忠言耳に逆らう・史記にみる諫言の作法・龔遂の王への諫言・諫言を受け入れる度量・・・
■杉田水脈 / 発言・杉田水脈1・杉田水脈2・・・





 2021/3
2021/3 2021/2
2021/2学術会議の会員定数は210人で、第1部(人文・社会科学)、第2部(生命科学)、第3部(理学・工学)に70人ずつ所属する。これに対し、自民党のプロジェクトチームは昨年12月にまとめた提言で「実際の科学者総数の割合に比し適切か議論の余地がある」と指摘。井上信治科学技術担当相も学術会議の梶田隆章会長に、各部の会員比率の見直しを検討するよう求めた。
オブラートに包んでいるが、端的に言えば「文系が会員の3分の1を占めるのは多過ぎる」ということだ。実際、閣僚経験のある自民党議員が学術会議について公然と「文学とか歴史とかは要らないよね」と口にするのも聞いた。
しかし、政府は昨年、科学技術政策の根幹をなす科学技術基本法を改正。人文・社会科学を新たに振興の対象に加え、重視する方向にかじを切っていた。井上氏の求めに、学術会議第1部幹事の小林傳司(ただし)・大阪大特任教授(科学哲学)が「法改正で人文・社会科学は大事だとメッセージも出ている中、数の議論だけがいきなり進むのは理解しがたい」と困惑したのも当然だ。
私は背景に、経済成長の原動力となる技術などの革新「イノベーション」に一見して寄与しない学問を軽視する政府の姿勢があると考える。
実は法改正では「イノベーションの創出」が目的に明記されたことも大きなポイントだった。これに伴い、法律名も「科学技術・イノベーション基本法」に改められた。この源流をたどると、学術会議が2010年に政府に出した「勧告」に行き着く。勧告は、世界が直面する21世紀的な課題に対応するには文理の連携が必要だと指摘。人文・社会を科学技術基本法で振興するよう、法改正を求めていた。
そのため昨年の法改正に際し、当時学術会議の副会長だった三成美保・奈良女子大副学長は「改正は私たちが求めてきた方向性に沿っている」と評価した。ただ印象的だったのは、「人文・社会科学がイノベーションの『しもべ』とならないかという危惧もある」とも話していたことだ。
任命拒否された6人は全員が1部の会員候補だった。軍事研究や安全保障関連法に批判的な研究者を排除したい意図もあったのだろうが、科学技術政策に関わる政府関係者は、学術会議の1部が「イノベーションのためにも社会のためにもなっていない」と厳しく批判。井上氏は学術会議改革の論点として「『世界で最もイノベーションに適した国』を目指すためには、アカデミアは必要不可欠な存在だ」と強調してきた。
こうした背景を踏まえると、任命拒否と1部会員を減らそうとする動きは、人文・社会科学をイノベーションの手段と位置づけ、役立たないなら不要だとする姿勢が露呈したものと言わざるを得ない。三成氏が危惧した状況が今まさに起きようとしているのではないか。
しかし、イノベーションは技術革新にとどまらず価値観の転換も含めた広義の言葉で、どんな人文・社会系の研究が寄与するか判断するのは難しいはずだ。すぐに役立つ研究を重視する一方、国立大への運営費交付金を削減するなどして基礎研究を軽視し、結果的に研究力の低下を招いた痛い教訓を思い出してほしい。
学術会議にも改善すべき点はある。政府への提言では、理念が先行し、政策としての実現性に乏しいものもある。実効性を持たせるため、政治と学術が互いの意見を共有する場があってもよい。工学系研究者でつくる日本工学アカデミーと国会議員の有志は昨年、意見交換の場を設ける取り組みを始めた。自民党内には「政治と学術の分断が一番良くない」との声もある。歩み寄りはできると思う。
ただ、政府方針に従わない者を排除することで改革議論を巻き起こす手法は民主主義的ではない。ましてや今回は、過去の法解釈を覆し、独立性の高い組織の人事に介入した。6人を任命してはじめて、菅首相の言う「未来志向」の対話が可能になる。私は首相の決断に期待したい。その上で、文理を問わず、多くの研究者が所属したいと思える学術会議を目指してほしい。
有馬氏をめぐっては昨年10月に菅義偉首相が番組に生出演した際、当時、臨時国会で焦点となっていた日本学術会議問題について直接質問。この時、菅首相が不快そうな表情で答えたこともあって、このやりとりについて、週刊誌が「事前の打ち合わせにない質問をして官邸を怒らせ、今年度で番組降板か」と報道。「官邸の圧力があるのか」と話題となっていた。
正籬(まさがき)聡放送総局長は会見で「そういった指摘のような人事はしていない。自主自律を堅持している。それだけはハッキリとさせておきたい」と強い口調で話した。後任は元ワシントン支局長の田中正良氏が務める。
今春の有馬氏の去就が注目を集めていた。昨年10月に菅義偉首相が番組に生出演した際、当時、臨時国会で焦点となっていた日本学術会議問題について直接質問。この時、菅首相が不快そうな表情で答えたこともあって、このやりとりについて、週刊誌が「事前の打ち合わせにない質問をして官邸を怒らせ、今年度で番組降板か」と報道。「官邸の圧力があるのか」と話題となっていた。
そうした中で決まった降板。NHK関係者は「実は降板報道以前に内々では決まっていたことで、官邸の圧力によって降板したわけではない」と語る。別の関係者は「前任の大越健介キャスターは5年、さらにその前の河野憲治キャスターは2年。有馬氏は2017年から4年だった。BS国際報道、ニュースチェック11を含めると有馬氏は7年キャスターを務めており、本人と局側の話し合いで今年度で“任期満了”の形になっていた。菅首相への質問は今回の降板には関係がない」としている。
共演する和久田麻由子アナウンサー(32)は続投。有馬氏の後任には、国際報道に携わっていた元ワシントン支局長の田中正良氏が就くもようだ。
 2021/1
2021/1
 2020/12
2020/12「学者の世界でも、それ以外でも嫌われている」と話す竹中氏。「学術会議は問題点だらけ。私も学者の端くれだが、学術会議の人選とかにも関わらせてもらってないし、学会のボスのような人たちが非常に遠い所で何かやってるいるというふうに見ていた。あの人たちが10億円も使っているということが明らかになって改めてビックリしたし、政策提言もいくつか見てみたが、経済学を勉強した人間の常識からするとあり得ないだろうという、ひどい提言もある。誰が責任を持ってやっているか分からないが、明らかに特定の省庁の言い分を聞いてそのまま書いているような提言もあった」と厳しく批判した。
「僕は“文系学者とは肌が合わん”と文句ばっかり言っているが」という橋下氏は、竹中氏の強い口調に驚きながらも、「東日本大震災の時に復興増税を提案したのが学術会議だった。色々な意見があっていいが、国債を発行するという考えもあるはずなのに、増税の方だけで固まるのはどうなんだ、と僕は思った」とコメント。
その上で、「ただ、僕らみたいな人間が批判しても、“お前、学者じゃないのに”と思われてしまう朝日新聞、毎日新聞系は“学者が重要だ。学問の自由を保障しろ。絶対にここには政治は手をつけるな”という声ばかりを拾う。“学術会議には問題点が山ほどある”という学者は少数なのだろうか」と尋ねた。
すると竹中氏は「復興増税の話も、あり得ない。100年に一度の震災だったら、100年で分担すべきだった。しかも経済が悪い時に増税するというのは、経済学者の常識ではあり得ない」と回答。そして「学術会議が問題だと思っている学者は、決して少数ではないと思う。メンバーだって、私たちに選ばせればいいのに、自分たちだけでやっている。よく覚えているが、小泉内閣の時に、学術会議については“ヨーロッパのように政府から独立したアカデミアになることが望ましい。そして10年後に再びレビューして議論しよう”という答申が出ている。しかしあれから17年経っているのに、何もやっていない」と指摘していた。
 2020/11
2020/11日本学術会議の任命拒否を巡り、多くの識者・表現者が声を上げた。当初は「学問の自由の侵害だ」という学者からの声明や談話が続いたが、時間を経るにつれ、この問題の影響は社会の広範囲に及ぶことが見えてきた。ジャーナリストや作家など、「大学」に所属する学者ではない表現者が声を上げていることには当然の理由がある。
憲法23条「学問の自由」は、「大学の自治」を中心的な要素としているが、専門的な学問の世界は学会などを通じてその外にも広がっている。中でも日本学術会議は、「学術」の名にあるとおり、学問にたずさわる人々の見識を政府のために提供するべく設置され、法的にも認められた公的機関である。大学や影響力のある学者は狙い撃ちされやすく、その心理的影響は広く社会に及ぶ。戦前には政府が大学に特定の教員(学者)の休職を強いたことがあった。滝川事件では、文部大臣が大学に学者の罷免を要求し、学者のほうが反発して辞任という流れとなり、矢内原事件では、辞職させることに決まったことを受けて学者が自ら身を引く、という形だったが、政府の圧力によって失職に追い込まれている点では共通している。
ところで、この種の事例としてもっとも有名な「天皇機関説事件」は、直接には大学内で起きた問題ではなかった。すでに大学を退任し名誉教授になっていた美濃部達吉が国会で非難されたのだが、これが「見せしめ」的な効果を持ち、大学内の学問内容や一般社会、公務員人事にまで影響した。このような影響は、当然に「表現」の世界にも波及する。学者の見解も出版やメディア上の発言など「表現」を通じて社会に認識されるものだから、ここが萎縮すれば、一般社会の市民が学識者の考えに接する機会も減っていく。市民にとっては思考や言論の足場が得にくくなっていく。筆者は、この種の事柄を「シンボルの政治」という観点から見ている。日本学術会議任命問題は、結果的にまさに「シンボルの政治」の問題へと発展してしまった。
憲法に「学問の自由」が明記され、政治と学問は距離を置くべきだとされてきたのは、こうしたことを繰り返さないためだった。日本学術会議法に定められた人選の方式も、日本学術会議自身が次期の会員候補者を選び推薦し(同法17条)、内閣総理大臣がこれに「基づいて」任命する(同法7条2項)こととなっているが、これは多くの識者がすでに指摘しているとおり、実質の人選が日本学術会議に任され、内閣総理大臣の任命は形式的なものにとどまると読むべきである。さらに最近の研究や報道で、日本学術会議の設立は、そもそも「学問の自由」制定の背景理念と切り離せない関係にあり、学術研究者が戦争協力を余儀なくされてきた流れを断ち切るという決断が込められていたこともわかってきた(これについては、推薦を受けながら任命されなかった当事者である加藤陽子教授の論説が毎日新聞に掲載されている)。
したがって、日本学術会議が2017年に、この会議としては軍事研究は行わないという姿勢を確認し、軍事研究を圧力的に要請する動きをけん制する声明を出したことも、同会議のもともとの設立趣旨からして筋の通ったことだと言える(これは日本という国でおよそ軍事研究を行うことができないように禁止することを求めているのではなく、同会議としては行わないという姿勢表明である)。
一方、最近の報道で、この任命拒否は日本学術会議に軍事研究協力を要請したいという政府の意向から発したものだったとの取材や読み解きもある。こうなると、政府の振る舞いは、日本学術会議設立の理念・含意に真っ向から反することになる。関連して、筆者は2016年に「天文学者と憲法学者のシンポジウム」でこの問題の発言者として登壇したことがあり、その時にこのシンポジウムのテーマソングを作成したことがある(音楽活動が研究活動の傍らのライフワークなので、こうした活動も行っている)。この動画は、スライドで問題を解説する内容にもなっているので、参考にご視聴いただければと思う。
●アラート機能を取り払った建物は・・・
なぜ、政府・政治からの自由という形での《学問の独立性》が重要なのだろうか。それは必要なときに政治に対し警鐘、警報(アラート)を鳴らす役割が期待されているからである。日本学術会議法では、政府から日本学術会議に諮問すること(同法4条)とともに、日本学術会議から政府に勧告すること(同法5条)の両方ができる。こうした役割は、常に政府の見解や政策を相対化し、是々非々で熟慮をつくすことによって初めて、果たすことができる。
憲法には裁判官の身分保障や違憲審査制など、本来、こうしたアラート機能が随所に組み込まれている。学術会議も同じ役割を託された組織といえる。「表現の自由」や「請願権」も、社会の中から起きてくるさまざまなアラートを塞いではならない、というルールである。一般社会から発せられるアラートには、「私はこのままでは生きていけない、助けてほしい」というSOSもあるだろうし、国策や地方自治への批判や提言を含むものもあるだろう。学識者の会議は、こうした一般社会の声をキャッチして、国政上見るべき問題に注目を促し、解決の方策を提案する役割も果たす。また、マスメディアも「表現の自由」を保障された表現主体だが、SOSの声が存在することを社会に知らせたり、識者の見解を知らせたり、自らが見解を示したりする中で、必要な時にはアラートを鳴らす役割を担っている。
これに対して政府は、こうしたアラート機能を次々に無効化しようとしてきた。警鐘を鳴らす基礎となる情報公開の仕組みも、公文書の管理のおかしさから、機能不全を起こしている。2017年から2018年にかけて起きた南スーダンでの自衛隊の日報問題もそうである。筆者の関心から言えば、昨年に起きた「あいちトリエンナーレ2019」の補助金不交付問題も、決定過程が不透明なため同根の体質的問題があるのではないかと思わずはいられない。いま、森友・加計学園問題にこうした機能不全問題をみている国民やメディアも少なくない。そうした背景から行われた国会議員による臨時国会召集要求(憲法53条に基づく正式なもの)が無視され続けてきたことも、同根の問題の一環と言える。
そして、任命人事の実質が掌握されることによって「アラート機能」が塞がれたものの最たる例が、裁判所と憲法81条(違憲審査権)ではないだろうか。憲法81条がわざわざ明文で裁判所に違憲な国家行為を「違憲だ」と判断する権限を与えているにもかかわらず、裁判所は事実上、重要な政治的問題を含む案件については判断しない(統治行為論)という自己拘束を続けている。1959年の砂川事件最高裁判決以来、この状態が決定的となってしまったのだが、2008年以降、当時の田中最高裁長官(故人)が最高裁判決前に駐日米大使と面会し、公判日程などを伝えたとする米公文書が見つかり、この判決が政治的圧力のもとに書かれた判決だったことが広く知られるようになった。こうした事柄について少しでも知っていれば、さまざまな領域で同じようなことが起きつつあるという連想が働くのが自然で、もしも「そうではない」としたら、政府はそれなりの筋だった説明ができなくてはならないはずだ。
これらの状況を総合して考えると、いま私たちは、火災報知機を「うるさいから」と作動不能にしてしまった建物の中で――しかも多くの火器を扱っている建物の中で――寝起きしているようなものである。火災報知機を止めてしまった建物で火災が起きたときに、どれほどの惨事が起きるかは、1982年のホテルニュージャパン事件が示している。
「ボヤで大騒ぎをして、後で社長の横井に叱られることを恐れていたのです。そのため最初に消防に通報したのは、従業員ではなく、燃え盛る炎を見たタクシーの運転手だったそうです。従業員が通報したのは発見から20分も後だった。・・・」
現在の政府が、とてつもない独裁欲求にかられているのかどうか、筆者には確かめるすべがない。しかし、もっとも善意に解釈したとして、「こっちだって忙しいんだ、些細なことで煩わされたくない」とトップが思い、これを忖度した周囲がここに書かれている「社長と従業員」と同じマインドに陥っている、ということは十分に考えられる。そしてタクシー運転手の役割を担おうとしているのが、学識者や市井の人々だが、その声までも抑えたり排除したりしようとしてはいないだろうか。
●言論空間の歪みあるいは傾斜
政治から「自由」な立場で学者が発言し、裁判官が法的判断を行うということの意味は、ときに結果的に政府方針と違う内容になったとしても恐れなくてよい、ということである。つまりその時々の政治的趨勢に翻弄されないこと、忖度しないこと。行政はその時々の政治的決定(立法)に従うもので(法治主義)、この「政治的中立」の中では出せないアラートを出せるのが「政治からの自由」を保障された機関である。この「自由」の保障があってこそ、行政組織の内部からは出にくい辛口の提言や勧告(学者の場合)、そして法的な判断(裁判官の場合)ができる。だからこそ、これらを公金を使って支える意味がある。
たとえば2013年に設置された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)のように、政府の人選・指名による有識者会議というものもありうる。そういうものとは異なり、学術の世界の有識者を、学術の世界の推薦によって選出し任命するところに、日本学術会議という組織の「公的」意味がある。
今回、トップレベルの学者が政府から名指しで疎まれるという出来事を、人びとは目の当たりにした。とりわけ、この一連の流れからは、安全保障や平和国家といった問題領域で発言をしたら、社会の主流から承認されず不利益を受けるかもしれない、という萎縮が広がることが懸念される。萎縮が社会に広まれば、社会全体の思考力が麻痺し、機能不全に陥っていくおそれがある。
任命拒否の理由の説明は今のところ筋だったものとは言えず、いくら理由を読み解いても推測の域を出ない。このことが、さらに萎縮の余波を広げかねない。こうした中で「この領域で発言すると目を付けられる」といった言説が広まっていけば、その正確な真偽は不明なままでも、その方面の社会的発言は萎縮していくからである。日本学術会議は、学者がほぼ手弁当で時間と労力を提供しているのが実態だと伝え聞いているが、それでも社会的信用や名誉という人格的利益は大きいはずである。この会議メンバーになれる見込みの高い学識者が、先々のことを考えてこの方面の発言を控えてしまうことは十分に考えられ、おそらくそれはすでに十分に起きている。このように、負のシンボル効果はすでに「表現の自由」問題へと飛び火している。
また、任命が行われなかったことの理由が釈然としない状況では、責任ある発言は行いにくい。学識者や、それに準じる論説を書くメディア関係者は、「ねつ造」などの指弾を受ければ社会的信用を失う、あるいは社会的バッシングを受ける。そのため、事実確認ができていない事柄には、慎重にならざるを得ない。その一方で、人気のある人の発言ならば信ぴょう性に問題があっても大丈夫、というマインドから出てくる発言のほうは、傷つくリスクが少ない分、幅を利かせやすい。デマが浸透しやすい下地ができてしまっているのである。テレビとネットでは、そうした状況が顕著に見られた。言論の環境がそのように傾斜や歪曲をこうむっていることも、法による治療がしにくい分、社会が自己修復を目指さなければならない問題である。
私たち一人一人が「萎縮しない」という矜持を持つと同時に、政府には任命がなかったことの理由について、もっと率直な説明を行ってもらう必要がある。おそらく説明できない事柄なのではないかということは百も承知で、やはりここを明らかにしてもらう必要がある。
 10/21-31
10/21-31この日本学術会議の会員任命問題については、すでに新聞、テレビ等のマスコミで盛んに報道されている。学問の自由の危機であるとか、首相や政権が説明責任を果たしていないとか、この任命拒否は日本学術会議法に違反するとか、様々なことが言われている。
しかし、ここでは、菅首相が「国の予算を投じる機関として国民に理解される存在であるべき」とか「政府の機関であり年間10億円の予算を使っている」という趣旨の発言をしていることを考える。つまり、日本学術会議には多額の税金を使用しているので、国民にとって良い組織でなければならない、ということについて考察する。
確かに年10億円という金額は巨額だが、巨額のお金が投入されているのは、何も学術会議だけではない。例えば、国会議員が所属する主要な政党にも税金が使用されている。それは政党助成制度と言われるもので、総務省HPによると、「国が政党に対し政党交付金による助成を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とした制度です」とある。
この制度に基づく政党交付金について、同HPでは「政党交付金の総額は、最近の国勢調査の人口に250円を乗じて得た額を基準として、国の予算で決まります」とある。政党交付金についても国の予算つまり、税金が使用されている。主要な政党の最新の2020年分の交付状況は同HPによると、以下の通りである。自由民主党には17、261、364、000円(172億6136万4000円)、立憲民主党には4、290、207、000円(42億9020万7000円)、国民民主党には4、648、376、000円(46億4837万6000円)、公明党には3、029、325、000円(30億2932万5000円)が交付される。なお、HPの資料は17、261、364、000という表記で分かりにくいので、( )内に通常表記される億、万、という形に直した。
自民党には日本学術会議の約10倍の約172億円もの国の予算が投じられているが、国民に理解されている存在なのか、また政党交付金制度についても様々な問題点が従来から指摘されているが、それらを改革する意図があるのか、学術会議の場合と異なり、現時点では我々には見えてこない。
また、「国民」といった場合、与党支持者を指すだけなく、野党支持者など与党を支持しない人も指すと考えられるが、現在の政治は、このような人のことも考慮した政治が行われているのだろうか? 総務省HPの「民主政治の健全な発展」に寄与する政治が行われているのだろうか。
ここ最近の政治をみていると、そのように思えない。与党が、数の力に任せて、一方的に決定しているように見えてしまう。さらになぜそのような決定をしたかについても説明も足りず、取り残されている感じになってしまう。つまり、支配者が権威を振るっていて、生身の権力を振りかざして自分のやりたいようにやっていて、批判されても正面から答えずに説明責任も果たそうとしないように見えてしまう。菅首相は「広い視野に立ってバランスの取れた活動」とこの任命問題について述べたが、同じことは政治の世界にも言えるのではないか。多数決の原理で与党が物事を決定していくのは当然であるが、もう少し少数者の意見を反映する形で柔軟に政治を行って欲しい。
 10/11-20
10/11-20そんな日本学術会議問題だが、私が総括すると、問題は次の3点となる。
問題の第1は、同会議関係者とそれを擁護する学者、文化人の非論理性だ。もっとはっきり言えば、およそ学者とも思えないおバカっぷりである。
当初、一部メディアと学者らは、政府による任命見送りが「学問の自由の侵害」につながると騒ぎ始めた。この弁法は、昨年の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」とそっくり。不適切な公共事業の問題を、「表現の自由の侵害」という、いかにも高邁(こうまい)な話かのように捻じ曲げた、あれと同じ、悪質な詭弁(きべん)である。
そもそも、日本学術会議は「学問をする場」ではない。同会議のサイトにも「科学者の意見をまとめ、国内外に対して発信する日本の代表機関」とある。つまり、学者各人は大学や研究機関、自宅などで思う存分、自由に学問・研究をする。その中の、業績秀でた人たちが集まって、政府に「勧告」「答申」「提言」をする場。それが日本学術会議のはずだ。
だから、同会議の会員になろうがなるまいが、学問の自由に何ら影響はない。いや、学問の自由は、学者でなくとも、わが国においては、すべての人に等しく保障されるものだから、はなから同会議とは無関係だ。
しかし、そんな理屈すら分からないのか、学者出身として知られる静岡県の川勝平太知事などは、「学問の自由」弁法をふりかざし、揚げ句、「菅(義偉)総理の教養レベルが露見した」とまで言って、首相をこき下ろした。同県出身者の一人としては、来年の知事選で川勝氏が再選されないことを祈るばかりである。
第2は、前述の「勧告」「答申」「提言」絡みの問題だ。驚くべきことに、同会議の「職務」と法律で定められている「勧告」「答申」が、この10年まったく行われていない。年10億円超もの公費をつぎ込みながら、10年間職務を果たさない集団が、それでも人事は自分たちの好きにさせろと言う。そんな団体は、この際、解体すべきだ。
第3の問題点は、同会議関係者の悪辣(あくらつ)さにある。法定の職務は蔑ろにしながら、その傍らで2017年には「軍事的安全保障研究に関する声明」なるものを発出。「軍事研究に慎重であれ」と宣言することで、各地の大学の研究者らが、防衛装備庁などから研究費を受け取ることを阻止した。それでいながら、15年に、軍民一体の独裁国家・中国の「中国科学技術協会」とは、協力覚書などを結んでいる。
東日本大震災後の復興増税やら、レジ袋有料化やら−。とにかく日本学術会議が出した「提言」類は、学術的にデタラメのトンデモ提言ばかりだ。中でも、私が特に腹立たしいのは、11年に出た「報告 アイヌ政策のあり方と国民的理解」なる文書である。
「政府はアイヌ民族が先住民族であるとの認識の下にこの問題への取組を始めているものの、一般の国民にあってはこの問題への関心が薄い。日本の近代化の過程において不利益を蒙ったアイヌの人々への対策や保障は本来全国民の理解のもとに進められる必要がある」
アイヌが先住民族だという「政府見解」には、いまも複数の学者から異論や疑義の声がある。折しも来年度予算に60億円超もの案が上げられる「アイヌ関連事業」だが、この巨額利権の創出を後押ししたのが日本学術会議だったのだ。「学問の自由」重視の点から言えば、同会議が、異論を廃して一方向への流れを作ったことは不適切ではないか。
日本学術会議は誰を利するものなのか。その検証を急ぐべきだ。
東京大学の大西隆名誉教授は平成29年までの6年間、日本学術会議の会長を務めました。
大西元会長は14日、NHKのインタビューに応じ、政府が学術会議が推薦した会員候補6人を任命しなかったことについて「会員は優れた研究または業績のある科学者の中から選ぶという選考基準が法律で明確に定められている。
学術会議が選んだ方々がなぜ適格性を満たしていないのかが問われるわけで、はっきり理由を言っていただかないと非常に大きな疑問が残る。
6人を任命拒否した責任が総理大臣にあることは間違いなく、なぜ任命しなかったのか国民に明らかにする必要がある」と述べました。
そのうえで自民党が「会議」の在り方を検討し直す議論を始めたことについて「それぞれの政党が学術会議の問題について考えるのは必要なことだが、いまは、現行の制度のもとでの任命拒否の理由がはっきりしないのが問題なのであって、学術会議の在り方は別の問題だ。この1週間ほどでにわかに行政改革論が出てきており、あたかも問題をすり替えるように組織の在り方が議論されるのは大変奇異だ」と述べました。
また日本学術会議の在り方については自身が会長を務めていた平成27年に内閣府の有識者会議による報告書がまとめられていることを挙げ「独立した国の機関という現在の設置形態がいちばんよいという有識者会議の結論が出ており、われわれはそれを尊重している。今後、会議の在り方を議論するのであれば、過去の経緯を十分に踏まえて将来のあるべき姿を検討してもらいたい」と述べました。
そして大西元会長は「科学アカデミーは国の発展の基礎になるものであり、政治家の皆さんは本質論に立ち返ってもう一度考えてほしい。学術会議に対する攻撃的な観点だけで科学アカデミーを考えると大きな国の方向の誤りにつながるおそれがある」と述べました。
日本学術会議の在り方は過去にも議論されています。
平成9年、省庁再編の議論を行った行政改革会議では一部から廃止論が出て、平成13年から内閣府の総合科学技術会議で学術会議の在り方が検討されました。
総合科学技術会議が、平成15年2月にまとめた報告書には「運営体制などの改革を早急に行うことにより、ふかん的な観点に立ち、科学の進展や社会的要請に対応して、柔軟かつ機動的に活動しうる体制に変革しなければならない」としたうえで、「設置形態については、欧米主要国のアカデミーの在り方は理想的方向と考えられ、今後10年以内に改革の進捗状況を評価し、より適切な設置形態の在り方を検討していく」と記されています。
これを受けて日本学術会議法が改正され、平成17年10月に現在の会員の選出方法や70歳定年制が導入されました。
この改革の評価について、10年後の平成27年に内閣府の有識者会議が報告書をまとめ、「迅速な助言・提言活動を行う仕組みを整備し、活用してきている」と評価しています。
そして組織の形態については「国の機関でありつつ、法律上独立性が担保されており、かつ、政府に対して勧告を行う権限を有している現在の制度は、日本学術会議に期待される機能に照らしてふさわしいものであり、これを代える積極的な理由は見いだしにくい」と結論づけています。
先ほど述べたように、筆者は文系と理系の両分野に博士の学位があり、限られた範囲ではあるが、ある程度の造詣があると考えている。その視点でみると今回の話題になっている委員候補が、すべて文化系の学者である所は非常に興味深い。
ここからは、筆者の意見が中心なので、気分を害される方もおられるかもしれないがご容赦いただきたい。非常に単純に言えば、理科系は何らかの理論を生み出したり、あるいはその理論を応用するといったところに力点が置かれる傾向がある。もちろん文化系も理論はあるし応用もあるのだが、最も理科系的な学問といわれる経済学でも、さまざまな学説がみられるように、理科系の物理学のようにクリアカットに白黒を出しにくい。
筆者が以前に、「入門医療経済学」(中公新書)でも解説させてもらったように、例えば「合理的経済人」といった前提を置いて分析が始まる。どうしても、このような前提条件が多くなるので、前提次第で結果が異なってしまう。
一方、理科系の学問は、本来であれば、前提が多くないはずであり、地球には重力がある、というように真実は一つであるということになる(もちろん、これも地球上でということを前提とみればそうだが、非常に大きな前提なので、この前提に異論がある人は少ないであろう)。
しかし先ほど述べたように、文科系の場合はさまざまな前提があって理論が構築されることが多い。つまり前提を置くところに研究者の主観が入らざるを得ない。行動経済学ではないが、研究者も自分の思想や主義といったものを排することが難しい。
例えば地球環境が「ペケペケ」だった時にはこのような事実があり、地球環境が異なる「ペけぺけ」だったとしたら、また違う事実がある、というのでは理科系的にはとても真理を探究したとはいえないであろう。
●コロナ禍の状況では理系でも結論は明確に出せない
少し学術会議から離れて、コロナ禍の状況を振り返ってみたい。
そもそも医学の場合も、基礎研究といわれる、例えば試験管内で行う研究においては、もちろん条件設定は行われ、かなり狭い範囲の研究になることも多いが、実験で誰が行っても同じ結果が出る「再現性」も問われる。そこで、正しいか正しくないかがはっきりする。
今でも論争がないわけではないが、数年前に「STAP細胞というものがあるかないか」という話のときに、「再現性がない」ということが大きな問題になったのと同じである。
しかし、今回のコロナ禍のような、原因は感染という医学的な事象であっても、広く社会問題になっている場合には難しい。現在でもそうであるが、コロナ禍においてはさまざまなエビデンスが出現した。これらがまさに先ほど述べた経済学と同じように、さまざまな前提や主義主張が理科系の学問である医学にも入り込んだからである。
このような現象のエビデンスについて再現性を問うことは難しい。
もちろん、医学研究もすべてが再現性で担保されるわけではない、例えば、一番アカデミックな手法は、薬剤などが承認される際に行うランダム化したダブルブラインドテスト(RCT)といわれる手法である。これは対象にプラセボといわれる偽薬あるいは対象薬を置き、同じ条件下で新しい薬剤と比較を行い、その効果が優れているかどうかを確認するものである。
もちろん、これとてサンプルを選び出すときのバイアス、例えば高齢者は避けるとか、子どもを避けるとかいったことはあるが、一応この方法で得られた結果が最高のエビデンスとされている(専門的には、複数行われたRCTをまとめて解析するということもあるが)。
もちろん、コロナ禍においてはこういった研究は行いにくいので、そこにシミュレーションとかさまざまな手法が導入され、将来を予測することになる。典型的なものは、コロナ禍での死亡者数予測であるが、前提をどう置くかで全く結論が変わってしまう。
●もう一つの視点は「ガバナンスの視点」
ここまで考えれば、コロナ禍に対してのさまざまな意見が、後から見ると正しかったり正しくなかったりすることがよく分かるであろう。
話を学術会議に戻す。文化系の場合、特に今回、学術会議で論争に出ているような非常に文科系的な研究の場合は、主義主張がダイレクトに出る。しかし実はエビデンスをまとっているように見える医学、あるいは理科系の学問においても前提の置き方でどうとでもなる部分がある。
コロナ禍のような場合では、文化系の学問と同じである。例えば、PCR検査を多くすべきかどうかといったことにこういった論争点が現れる。
もちろん筆者も、PCR検査が必要なときに必要なだけ行われることには賛成だが、例えば全国民に行うべきかといった話になると、中国のような管理的思想が入ったりする可能性も否定できない。そういったことを考えると 、学術会議において文化系の学者だけが話題にあげられているが、直接表現に現れない理科系の学者も同じであって、やはり個人の思想というものに入り込むことは非常に難しい。
その意味で筆者は、逆説的ではあるが、このようなネット社会においてはなおのこと、何らかの基準を持って、その人が学術会議のような場に適するか適さないかを判断することは極めて難しいのではないかと考える。
もう一つの視点は、「ガバナンスの視点」だと思われるので、最後に少し触れておきたい。
●日本の場合 「透明性」を求める相手は…
法的な部分はわからないが、庶民感覚、あるいは経営者あるいは経営学を学んだ人に多い論点としては、誰が学術会議のお金を出しているかという点がある。学術会議には、国がお金を出している、従って、任命権もお金の出し手である政府が持つべきだ、あるいは介入してしかるべきだという理屈である。
これは「会社のガバナンス」という点で日本が今まで弱かった点でもあり、現在改善のためにさまざまな努力がなされている部分であるから、そことの類似性でこういった意見になるのはよくわかる。
ややこしいのは、投入されているのが、個人や会社のお金ではなく税金を原資としているということである。そこで、国民の意見が反映されるべきだとなるのだが、ただ難しいのは、今回は元がわれわれ、国民のお金であっても、1クッション政府が入っているというところが隠された論点になる。
税金のもともとの出し手は国民であるから、国民の意見を聞くべきだという議論もあろう。しかし、一方では国民から付託されている政治と政治家の裁量に委ねているのだから、最終的には会社のガバナンスと同じではないかという考え方も出てくる。
ことほどさように、この問題は難しいが、台湾のオードリー・タンIT担当大臣の言葉が至言だと思うので、私の解釈を含めて、ここにのせて原稿を締めくくりたい。
中国では「政府が国民に対して、透明性を求める」、台湾では「国民が政府に対して、透明性を求める」。
この問題をスクープしたのは1日の「赤旗」だった。
任命拒否された6人のひとり、立命館大学大学院の松宮孝明教授の談話を紹介し、菅総理が学術会議の人事に介入、学問の自由を侵害している、と報じたのだ。
「この6人には共謀罪や安保法案に反対した過去がある人もいて、それを嫌った官邸が任命しなかったといわれています。しかし、官邸はその理由を一切説明していません」(政治部記者)
3日朝に都内で記者相手に行われた菅総理の「パンケーキ懇談」でも多くは語られず、批判は日増しに高まるばかりだ。
しかし、「学者の国会」といわれる日本学術会議の内情を追うと、学問の自由を声高に叫ぶのとは、また別の側面も見えてくるのだ。
日本学術会議は1949年設立。戦時中に科学者らが戦争に協力させられた反省に立って、政府から独立して政策提言等を行う組織だという。ただ、内閣府の特別機関という位置づけで、
「210人の会員と約2千人の連携会員で構成、予算は国費で賄われ年間約10億円です。会員には名だたる学者が揃い、非常勤の特別職国家公務員という扱いで約2万円の日当も支給されます」(同)
注目されたのは、3年前である。防衛省が創設した研究助成を批判し、「研究者は軍事研究を行うべきでない」とする声明を発表。この声明を受け入れ、研究をストップした大学もあり、その権威を見せつけたのだ。
元連携会員である、国際政治学者の篠田英朗東京外国語大学教授は、
「このことに加え、使用済み核燃料の処理についてなど、日本学術会議は政府の方針と反する声明や提言を出しています。もともと大学コミュニティは思想的に左に傾いている人も多い。左翼的カルト集団ではありませんが、学術会議はほとんど野党のようなもので、だから政府・自民党と対立するのではないでしょうか」
もっとも、大学に与える影響力については、
「大学では文系よりも、学術会議の声明が研究内容に直結する理系の方が影響は深刻だと思います」(同)
旧帝国大学の理系学部で教鞭を執る教授が明かす。
「特に理系の研究分野では学術会議の推薦がなければ大型プロジェクトは進みません。例えば、岩手県と宮城県の山間部に作られる予定だった素粒子の大型実験施設・国際リニアコライダーは、学術会議が最近ネガティブな評価をしたことで政府が及び腰になり、ほとんど計画が頓挫してしまいました」
一度目をつけられれば、研究者も蛇に睨まれた蛙になってしまうというわけだ。実態も「学者の国会」とはかけ離れているそうで、
「新規の会員は選挙ではなく、別の会員に推挙してもらうことで初めて国に任命される。決め方は非民主的です。自然、思想的にも似た人が集まるので、とてもじゃないですが、学者を代表する組織とはいえません」(同)
そして、今回の騒動についてはこう断ずる。
「学問の自由の侵害ではなく、単に学術会議の自由が侵されただけですよ」(同)
果たして本当の鬼は官邸か、それとも学術会議か。
自民党の森山裕国対委員長は14日、立憲民主党の安住淳国対委員長と国会内で会談。森山氏は杉田氏招致について「事務の副長官を国会に出す例はあまりない。そういうやり方がいいのか検討したい」と述べるにとどめた。
●任命されたメンバーにも「政権に批判的」な人はいる
科学や学問的知見を社会に反映または浸透させることを目的として設立された「日本学術会議」——その新会員候補者のうち6名の任命を菅首相が拒否したことが、大きな波紋を呼んでいる。
立憲民主党や共産党などの野党、あるいはマスメディアや大学でもこの一件は厳しく批判されており、なかには「憲法で示される『学問の自由』に違反している」といった指摘もある。これに対して菅首相は「学問の自由の侵害には当たらない」と反論し、6名の任命を拒否した理由については「総合的かつ俯瞰的に判断した結果」だと述べた。むろんこのような、ほとんどなにも言っていないに等しい釈明で野党もメディアもアカデミアも納得するはずがなく、批判の声はますます大きくなり、議論は紛糾している。
今回、菅首相によって任命を拒否された6名は以下のとおりである。
芦名定道:キリスト教学者、京都大教授。
宇野重規:政治学者、東京大教授。
岡田正則:行政法学者、早稲田大教授。
小澤隆一:憲法学者、東京慈恵会医科大教授。
加藤陽子:歴史学者、東京大教授。
松宮孝明:刑事法学者、立命館大教授。
任命を拒否されたメンバーになんらかの共通点を見出すとすれば、自民党政権やそのポリシーに対しておおむね批判的であったこと、とりわけ安全保障関連の法案や、共謀罪など治安関連の法案に反対してきたことなどが挙げられるだろうか。しかしながら、任命されたメンバーにも、任命拒否されたメンバーと同じような見解を持っていた人がまったくいないわけではない。
●「トップ・エリート」だからこそ、拒否された
単純に「安倍政権および安倍政権が打ち出してきた外交・安全保障の方向性を踏襲する菅政権に対して批判的・否定的だったから」ということが理由だったのであれば、任命を拒否されるはずの対象者はもっと多くなければつじつまが合わないだろう。
また、今回任命を拒否されたメンバーが、学術会議のメンバーとして不十分な資質の持ち主だったということはまずありえない。一部ネットでは「学術評価ツール『スコーパス』で調べたところ、拒否されたメンバーの実績は低く、任命拒否の首相判断は妥当だった」と評する向きもあるようだが、スコーパスは日本の人文学者を評価するツールとしては不適当であり、これは誤情報といえるだろう。
拒否されたメンバーは学術的実績や資質に欠けるどころか、むしろ「錚々そうそうたる顔ぶれ」と表現する方が適切なほどの実績とキャリアを長年にわたって積み上げられてきた、日本の人文知におけるトップ・エリート層である。「学問的知見を社会に反映または浸透させること」を目的とした組織であれば、彼・彼女たちは適任だったはずである。
では、彼・彼女らの任命が拒否されたのは、菅義偉というひとりの人間として個人的な好悪に基づいて、あるいはまったくの気まぐれで適当に——というわけでもない。そうではなく、菅首相はアカデミアのだれもが認めるたしかな実績を持つトップ・エリートだからこそ、あえてこの6人の任命を拒否したのである。言い換えれば、菅首相にとって任命を拒否するのは、ぜひともこの6名でなければならなかったのだ。
●任命拒否騒動で、一気に学術会議の知名度が上った
菅首相があえてこの6名の任命を拒否した理由——それは、彼・彼女たちの任命を拒否することが、ほかのだれかを拒否することよりも、社会的にはるかに大きな「反応」を引き出すことができると確信していたからだ。
6人の任命を拒否したことが明るみに出たことで、マスメディア以外にもさまざまな領域から、菅首相の意思決定を非難する声が一斉に聞こえはじめた。すでに100近い学会からは抗議の声明が発表されているし、菅首相の母校である法政大学からも抗議声明が出された。自身も経済学者である静岡県の川勝平太知事が、きわめて厳しい論調で菅首相を非難したことは記憶に新しい。
「菅義偉という人物の教養のレベルが図らずも露見したということではないか。菅義偉さんは秋田に生まれ、小学校中学校高校を出られて、東京に行って働いて、勉強せんといかんと言うことで(大学に)通われて、学位を取られた。その後、政治の道に入っていかれて。しかも時間を無駄にしないように、なるべく有権者と多くお目にかかっておられると。言い換えると、学問された人ではないですね。単位を取るために大学を出られたんだと思います」静岡朝日テレビLOOK『学者の静岡県知事、菅総理を痛烈に批判「教養レベルが露見した」 日本学術会議問題で』(2020年10月8日)より引用
だが、こうした「反応」こそ、菅首相が期待したとおりの結果だったのかもしれない。
一般大衆には、この騒動が起きる前までは「日本学術会議」の知名度はほとんどなかったに等しい。今回の任命拒否によって多くの界隈からの「反応」が喚起されたおかげでマスメディアに取り上げられ、世間的な知名度が一気に上昇した。同時に「まともに学問をしたことのないような人間には、学問の価値はわからない(のだから口を挟むな)」という、知的エリート層の本音をどうにかして引き出すという狙いも菅首相にはあっただろう。
●菅首相は「エリートの反応」を利用するつもりではないか
その意味においては、川勝知事のような言明は、菅首相にとっては願ってもないものだった。知事の発言はあくまで菅首相に向けられた非難ではあったものの、その言明の射程圏内には多くの一般大衆が含まれており、少なからず違和感や批判の声が挙がっていた。
川勝知事の会見から2日後の10月9日正午までに、約100件の意見が県に寄せられ、その多くが知事の言動を問題視するものだったと報じられている(テレビ静岡『「菅総理の教養レベルが露見した」静岡・川勝知事発言に批判の声相次ぐ 学術会議巡り』2020年10月9日)。学問の価値は学問を十分に収めた人でなければわからない——という指摘はまったく的外れではなく、もっともな側面もある。だが、もっともな事実であることと、そのようなあけすけな物言いが大衆的な支持や共感を得られない(むしろ反感を買う)ことは両立する。川勝知事をはじめ、菅首相に厳しい声を寄せる人びとは、アカデミアの援護射撃をしたつもりかもしれないが、しかし実際には菅首相によってまんまと利用されてしまったように見える。
菅首相はこのようなエリートたちの「反応」を次のステップへの足掛かりとして利用するつもりだったのではないだろうか。あえて乱暴に表現すれば、菅首相による「釣り」ではないか——と。私は当初からこうした疑念を持っていた。現在の動向を見るかぎり、どうやらそれは私の勝手な思い込みというわけではないようだ。というのも、すでに菅政権からは私の疑念を裏付けるような「次の一手」が示されつつあるからだ。
●「日本学術会議のあり方」再検討がゴールだったのではないか
こうした世間的注目を受け、菅首相をはじめ自民党は即座に「反応」を返した。
日本学術会議のあり方それ自体も再検討するべきだ——という認識のもと、作業チームを設けて議論を進めることになったのである。そうした議論のなかでは、抜本的な改組や民営化、ラディカルな意見では廃止論さえも飛び出しているとされる。
「日本学術会議」の会員候補6人が任命されなかったことを受け、自民党は、「会議」の在り方を検討し直す必要があるとして、来週にも作業チームを新たに設けて議論を始めることになりました。自民党の下村政務調査会長は記者会見で、「日本学術会議」について「法律に基づく政府への答申が2007年以降提出されていないなど、活動が見えていない」と指摘しました。NHK NEWS WEB『日本学術会議の在り方 作業チーム設けて検討へ 自民』(2020年10月7日)より引用
自分たちが強権的に自由を侵害しながら「大ナタ」を振るったと印象づけることもなく、今回の騒動で世間的な注目が集まり、日本学術会議のあり方を再検討するという流れに自然に持っていくことに成功したように見える。さらには、大衆的に「改革を断行する実行力のあるリーダー」として印象付けることにも一定の成果を得たようだ。
最初からこのゴールありきで、演繹えんえき的にシナリオを描いていったのではないだろうか。このシナリオを成就させるためにもっとも重要な役者が「6人の学者たち」だったというわけだ。菅首相を侮っていたのかもしれない。
●今回の騒動は「蟻の一穴」となるかもしれない
日本学術会議は「軍事研究(間接的に軍事に利用されうる学問研究も含む)」に対して、学問はみずから距離を取り、慎重であるべきだとの見解を戦後から一貫して示してきた(自民党としてはこうした「平和的左派」的な彼らのスタンスが疎ましかったというのは否定しえない)。しかしながら、近年ますます緊張が高まる国際関係・安全保障上の問題に関して「平和的左派」的スタンスへの世間の共感が少なからず低下してきたことも、菅首相のこうしたシナリオを実行に移す奇貨となっただろう。
菅首相は「学問の価値がなにもわからない無知蒙昧の徒だから」、日本学術会議の人事に介入したわけではないし、学問の自由に挑戦をしかけたわけでもない。その逆だ。学問には政治的にも社会的にもきわめて重大な役割や影響があるからこそ、そこになんとかして行政の権力を食いこませたいと考えたのだ。今回の騒動は、その「蟻の一穴」として、のちの歴史には記録されることになるかもしれない。
菅首相は、安倍前首相のような政治ショー的な派手さはないし、一見すると平和的で温厚そうな外見や「苦労人」を思わせる来歴からはまるで想像がつかないものの、しかし前首相よりもラディカルで、なおかつ「強したたか」な人物であるように私からは見える。
あえて喩えるならば「物静かなドナルド・トランプ」である。
前川氏によると、16年8月ごろに委員のリストを杉田副長官に提出したところ、1週間ほど後に呼び出され、2人の差し替えを命じられた。前川氏は「杉田氏から『こういう政権を批判するような人物を入れては困る』とお叱りを受けた」と証言し、実際に別の人物を選び直したと説明した。
首相は9日のインタビューで、会議側が提出した105人の推薦リストを「見ていない」と発言。99人のリストを見ただけだとして6人の排除に具体的に関与しなかったかのような説明をしたため、一連の経緯や理由、誰が判断したのかが焦点となっていた。首相が6人の除外を前もって知っていたプロセスが明らかになったことで、さらなる説明責任が求められる。
今回の人事を首相が最終的に決裁したのは9月28日。関係者によると、政府の事務方トップである杉田副長官が首相の決裁前に推薦リストから外す6人を選別。報告を受けた首相も名前を確認した。首相は105人の一覧表そのものは見ていないものの、排除に対する「首相の考えは固かった」という。
首相が105人のリストを見ていないと発言したことを受け、政府は12日、釈明に追われた。加藤勝信官房長官は記者会見で「決裁文書に名簿を参考資料として添付していた」と明らかにした上で、「詳しくは見ていなかったことを指しているのだろう」と説明。実態として把握していたとの認識を示し、首相発言を軌道修正した。
同時に「決裁までの間には首相に今回の任命の考え方の説明も行われている」と繰り返し、人事は首相の判断により決まったことを強調した。
日本学術会議法は会員について「(会議側の)推薦に基づいて首相が任命する」と定めている。政府が軌道修正したのは、首相がリストも見ていなかったとすれば、この規定に抵触しかねないとの指摘が出たのを意識したものとみられる。
立憲民主、共産両党などは12日、合同ヒアリングを東京都内で開催。首相発言について「明確に法律違反だ」と批判した。
 10/10
10/10東京大は9日、五神真学長名でメッセージを出した。「問題に端を発した混迷と相互不信は学術が持つべき本来の力を大きくそぐ」と強調。「日本学術会議からの(説明を求める)要請に対する真摯な対応を政府に望む」とよびかけた。
国立大学協会の永田恭介会長(筑波大学長)は現状、学術会議への政府対応を静観するとしたうえで「個人的には過度に(政府を)忖度(そんたく)することがあってはならず、会議の姿勢が変わってもらっては困る」と述べた。
同協会副会長を務める東京外国語大の林佳世子学長は「人文社会系は自由な発想で主張するなかで、ある種の調和が生まれる」として、学問の発展に必要な自由な発言につながらなくなると懸念した。金沢大の山崎光悦学長は「政府がやっていることは直接おかしいと思わない。最後は法解釈だ」との認識を示した。
法政大の田中優子総長は5日に発表した声明で「首相が研究の『質』によって任命判断するのは不可能」と強調。「もし研究内容によって学問の自由を保障あるいは侵害するという公正を欠く行為があったとしたら、断じて許してはいけない」としている。
日本物理学会や生物科学学会連合など自然科学系の93学会は9日、「混乱を大変憂慮している」との声明を発表した。この規模での共同声明は異例で「多様な科学者の真摯な意見に耳をふさごうとしているのではないかと危惧している」と述べ、対話を進めて事態を収束するよう求めた。
英科学誌ネイチャーは8日付で、政治と科学の関係性を巡る社説を掲載した。学術会議の問題について「日本の菅首相が政府の科学政策に批判的だった6人の任命を拒んだ」と指摘。米大統領選やブラジル国内の問題も引き合いに「科学と政治の関係が脅威にさらされている。黙ってみていることはできない」とした。
米科学誌サイエンスは「日本の新首相は学術会議との戦いを選んだ」との見出しで記事を掲載。新会員の任命プロセスを「混乱させた」と指摘し「研究者たちは学問の自由の侵害であると主張している」と紹介した。
 10/9
10/9これまで日本学術会議会員候補者は、私ども科学者の代表として学術上の業績を中心に、性別や地域、専門分野など種々の観点から多様性を重視して選出されてきました。このことにより日本学術会議は、政府からの審議依頼案件も含め、社会の様々な要請課題について、学術の見地から様々な意見を戦わせ、その結果を提言等にまとめています。
今回の任命拒否は、多様な科学者の真摯な意見に耳をふさごうとしているのではないかという危惧を持ちます。従来の運営をベースとして対話による早期の解決が図られることを希望し、自然史学会連合、日本数学会、生物科学学会連合、日本地球惑星科学連合、日本物理学会、他90学協会は共同声明「日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する緊急声明」を2020年10月9日(金)18時にオンライン記者会見にて発表いたしました。
 10/8
10/8第25期日本学術会議会員の任命にあたって、内閣総理大臣は日本学術会議が推薦した105名の候補者のうち6名の任命を拒否し、現在までその明確な理由を説明していません。これは、日本学術会議法第7条・第17条に定められた、日本学術会議が優れた研究・業績がある科学者から会員候補者を選考して推薦し、この推薦に基づいて内閣総理大臣が会員を任命するという法の主旨に反するものであり、第3条にある日本学術会議の独立性を脅かすとともに、首相による任命権の恣意的な行使に道を開くものです。また、今回任命を拒否された6名がいずれも人文・社会科学分野の候補者であることは、政府の人文・社会科学に対する態度への深い懸念を生じさせ、看過することができません。
関西学院大学大学院社会学研究科委員会は、人間と社会についての研究と教育を進める研究者の組織として、学問・研究の基盤であり、日本国憲法第23条で保障された学問の自由を侵害する今回の決定に対して、速やかに首相がその理由を開示するとともに、6名の候補者を会員に任命することを求めます。
 10/7
10/7「学問の自由の侵害に当たるはずがない。むしろ、『学問の自由』を侵害してきたのは日本学術会議だ」
門田氏はこう語り、日本学術会議が1950年と67年、2017年に、「軍事目的のための科学研究を行わない」という声明を出したことを問題視した。
「17年といえば、北朝鮮が弾道ミサイルを相次いで発射し、『どのようにして国民の生命と財産を守るか』が重要な課題となっていた。ところが、日本学術会議は、その研究の禁止を打ち出した。学問の自由を阻み、国民の命をどう守るかという課題も阻んだ」
菅首相は5日の会見で、「省庁再編の際、(日本学術会議の)必要性を含め、あり方について相当の議論が行われた。結果として、総合的・俯瞰(ふかん)的な活動を求めることになった。まさに総合的、俯瞰的活動を確保する観点から、今回の任命も判断した」と語った。
門田氏はこの判断について、「日本学術会議は15年に、中国科学技術協会と協力覚書を署名している。つまり中国の軍事発展のために海外の専門家を呼び寄せる『千人計画』には協力している。日本国内では軍事研究を禁じておきながら、中国の軍事研究には協力するという、非常に倒錯した組織だ」と言い切った。
左派野党やメディアは、任命されなかった6人が「安全保障関連法や特定秘密保護法などに反対した人物」として、あたかも菅首相が意にそぐわない人物を排除したとの批判を展開している。
これに対し、門田氏は「任命された99人の中にも安全保障関連法や特定秘密保護法に反対していた学者は大勢いる。6人の任命見送りは、別の理由と考えるべきだ」といい、「今回の騒動で、国民は日本学術会議がどのような組織であるかを理解したはずだ。当然、民営化を含めた行政改革の対象だ」と指摘した。
これに対して、野党から批判が集まった他、Twitterでは「#日本学術会議への人事介入に抗議する」というハッシュタグで抗議の声が集まり、映画監督・是枝裕和氏などが抗議声明を出す事態となっている。
一方で、フジテレビ報道局解説委員室の平井文夫上席解説委員が、学術会議と日本学士院を混同した上で、「死ぬまで年金をもらえる」と誤った説明をおこなったり、自民党の長島昭久議員が「年間10億円の税金が投じられる日本学術会議の実態」を明らかにすべきと主張するなど、学術会議そのものへの批判も集まっている。
日本学術会議とは何であり、問題の争点はどこにあるのだろうか。
日本学術会議は、下記の日本学術会議法にもとづいて存在する内閣府の機関だ。
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。
現在は、2015年にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏が会長を努めており、210名の会員と約2000名の連携会員によって構成されている。会員の任期は6年で、3年毎に約半数が任命替えされる。
今回、菅首相が任命しなかったのは、この3年毎の任命替えにあわせたもので、はじめての出来事となる。
●誰が会員に任命されるのか
学術会議の会員は、現会員・現連携会員によって推薦され、首相がこれを任命する形をとっている。日本学術会議選考委員会によれば、推薦の基準は「優れた研究又は業績がある科学者」であり、会員になると特別職の非常勤国家公務員となる。
繰り返しとなるが、「学術会議で6年働けば、学士院で死ぬまで年金250万円」は誤りだ。BuzzFeedが述べるように、「日本学術会議と日本学士院はそれぞれ独立した異なる組織」であり、「前者が『学者の国会』として政策提言などをする組織で内閣府の管轄にある一方、後者は学術上大きな功績を残した学者の顕彰を目的とした組織で、文部科学省の管轄になる」。
なぜ菅首相は、6名の研究者を任命しなかったのだろうか。政府は「個別の人事に関することについてコメントは控えたい」と直接的な理由を明らかにしていないものの、いくつかの理由が指摘・推測されている。
●前例主義の打破
まず、菅首相自身は内閣記者会のインタビューにおいて「推薦された方をそのまま任命してきた前例を踏襲してよいのか考えてきた」と答えている。菅首相は、自身の就任会見で「悪しき前例主義を打破」すると述べているが、今回の問題においても前例主義と絡めた説明がされている。
しかし「前例主義の打破」とは、その前例が問題を有していることが大前提である。法的根拠があったり、政府解釈が示されてきた手続きを「前例主義を打破するため」という理由で変更することは、そもそも前例主義の打破ではない。
菅首相は「推薦された方をそのまま任命」することを悪しき前例主義と認識している可能性があるが、なぜこれが「悪しき前例」であるのかは不明だ。少なくとも、法にもとづいた公務員の任命を「悪しき前例主義」と括ってしまえば、多くの法的手続きが糾弾されることになってしまう。
●「優れた研究又は業績」の欠如
より原理的に考えるならば、学術会議の推薦基準が「優れた研究又は業績がある科学者」であることから、菅首相が6名について「優れた研究又は業績」が欠如していると判断した可能性もある。
しかしながら、これはまずありえない。そもそもこの6名については、数多くの研究実績を有しており、そこに疑いを挟む余地はない。個々の論文や研究に異論がある人もいるかもしれないが、それは6名の高い研究水準とは全く別の話であり、純粋に学術論争の問題だ。NHKがまとめた研究内容や経歴を見ても、それは自明である。
加えて、菅首相に「優れた研究又は業績」を判断する能力はない。なぜなら、学者の能力というのは基本的には研究業績や論文によって判断されるためだ。分野によって個々のプロセスや考え方は異なるものの、基本的には査読(ピアレビュー)を通じておこなわれる。政治家や首相であっても、こうしたシステムの外から、ある学者の能力や業績を判断する力は持ち得ない。
●政治的意図
菅首相の判断について、もっとも多く聞かれる説明は、政治的意図があるというものだ。今回、任命が拒否された6名は以下の通りとなっている。
•小沢隆一、東京慈恵会医科大学(憲法学)
•岡田正則、早稲田大学(行政法学)
•松宮孝明、立命館大学(刑事法学)
•加藤陽子、東京大学(歴史学)
•芦名定道、京都大学(キリスト教学)
•宇野重規、東京大学(政治学)
この6名について、例えば毎日新聞は「安全保障関連法や『共謀罪』を創設した改正組織犯罪処罰法を批判してきた学者が複数含まれている」ことを指摘し、政治的意図があるという見解を示唆している。また東京新聞は直接的に、「政府の意に沿わない人物は排除しようとする菅政権の意図が浮かぶ」と解釈している。
とはいえ、現時点で政府が任命拒否の理由を明示していない限りにおいては、この理由についてもあくまで憶測の域を出ない。
●政治介入の重要性
しかしながら、政治的意図は別としても、政権が政治介入の重要性を認識していた可能性は高い。それは前回の推薦に際して、105名の候補を決定する前に、それより多い候補の名簿を示すように安倍政権時代の首相官邸が求めていたためだ。
これを報じた朝日新聞によれば、官邸側は「こちらが判断する余地がないのはおかしい。ある程度、任命権者と事前調整するのは当たり前だ」と説明しており、推薦・任命のプロセスにおいて政府を交えた事前調整が必要だと考えていることが分かる。
すなわち、なぜ菅首相は任命しなかったのか?という問いに対しては、
•菅首相が個人的に「悪しき前例主義」を嫌ったり、「優れた研究又は業績」が欠如していると考えたわけではなく、
•安倍政権時代から本プロセスに対して「何らかの理由」で政府による介入が必要だと考えていた連続的な動きがあり、
•それが今回の人事において表出した
と解釈することが妥当だろう。
その「何らかの理由」が、安保法制に反対する学者の排除という政治的意図であるか、あるいはより広範に、安倍政権が重視していた「官僚主導から政府(官邸)主導へ」という動きの一環であるかは、現時点では明らかではない。
では、こうした任命拒否にどのような問題があるのだろうか。現時点では、いくつかの方向から首相の判断が批判されているが、大きく3つにまとめることができる。
具体的には、憲法違反(学問の自由)に関する批判、政府解釈に関する批判、手続きの正当性に関する批判だ。
●憲法違反(学問の自由)
まず、憲法違反、すなわち日本国憲法第23条にある学問の自由の侵害だとする声がある。
任命拒否された6名の1人である立命館大学の松宮孝明教授は、「任命権があるから拒否権があるという理屈はなく、理由もなく拒否するのは憲法違反である」と述べている。また、日本共産党の志位和夫委員長は「今回の任命拒否はまさに日本学術会議法に反し、憲法23条の『学問の自由』を脅かす違憲、違法の行為だといわなければならない」と述べている他、法政大の田中優子総長も「任命拒否は憲法が保障する学問の自由に違反する極めて大きな問題」だと指摘する。
ただし、学問の自由を争点とすることは危ういとの指摘もある。例えば、 ハドソン研究所Japan Chair Fellowの村野将氏は「学問の自由を説くのに、政府に認められるかどうかを争点にしたら、自己矛盾するのでは」と指摘する。
また、東京工業大学の仙石慎太郎准教授も、学問の自由を主張する人々は「日本学術会議での活動も学術活動の一環と捉えている」とした上で、「ここの認識が学者によってかなり異なる」と述べる。東京大学の玉井克哉教授も、「むりやりに憲法論で行こうとするから、そんな理屈になる。ちゃんと根拠法があるんだから、それに照らして適法か違法かを議論しましょう」と指摘する。
学問の自由の侵害や憲法違反という批判は、多くのメディアやネットの主張で見られるものの、任命拒否を批判する人々からも疑義が呈されている状況だ。
●政府解釈の変更
過去の政府解釈との整合性を指摘する声もある。1983年の政府答弁では、政府が以下のように述べている。
「私どもは、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません。確かに誤解を受けるのは、推薦制という言葉とそれから総理大臣の任命という言葉は結びついているものですから、中身をなかなか御理解できない方は、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないかという感じが最近私もしてまいったのですが、仕組みをよく見ていただけばわかりますように、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったりを出していただくということにしているわけでございます。それでそれを私の方に上げてまいりましたら、それを形式的に任命行為を行う。この点は、従来の場合には選挙によっていたために任命というのが必要がなかったのですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ません。そういうことで任命制を置いておりますが、これが実質的なものだというふうには私ども理解しておりません。」
すなわち過去に政府は、学術会議の会員を任命することは「形式的」なものであり、「総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません」と明言している。
政府解釈の変更について、例えば宇都宮健児弁護士は「今回の菅義偉首相による日本学術会議が推薦した新会員候補6人の任命拒否がこれまでの政府解釈を無視した違法な決定」だと述べている。また、三浦義隆弁護士は「検察官勤務延長や学術会議会員任命拒否については、法律の心得のある人で延長可能説や裁量的任命説を採る人はほぼいなそう」と指摘する。
こうした批判に対して、加藤勝信官房長官は「憲法との関係を含めて整理した。構造的な仕組みを変更しているわけではない」と述べて、日本学術会議法の解釈変更はしていないという立場を示している。
●監督権の行使
また加藤官房長官は「会員の人事などを通じて、一定の監督権を行使することは法律上可能になっている」と述べているが、日本学術会議法には監督権について明記はない。
実際、1983年の内閣法制局による「法律案審議録」の「日本学術会議関係想定問答」には、首相の権限について「指揮監督権を持っていないと考える」と記載されている。
しかし、2018年に内閣府日本学術会議事務局が作成した新たな文書では「推薦の通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」とした上で、人事を通じて「一定の監督権を行使することができる」という見解が記されている。しかし、その文書は公開されておらず、政府は「秘密裏に対応を変更する形となったが、解釈変更ではないので非公表としたと主張」している。
監督権を含め、従来の政府解釈が変更されたにもかかわらず、十分な説明責任が果たされていないことを問題視する声は多い。
●手続きの正当性
政府解釈の変更とも関係するが、この問題は広く「手続きの正当性」がポイントだとする指摘もある。例えば、神戸大学の木村幹教授は以下のように述べる。
「この問題の本来の焦点は、内閣による任命拒否を巡る手続き的な正当性にある。日本学術会議法では、この点について「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」ものとしており、この内閣総理大臣の「任命」に纏わる権限の範囲について、様々な議論が巻き起こっている。」
すなわち、日本学術会議法における「任命」の範囲をどこまで広げて解釈することが可能かが焦点であるという指摘だ。
この点について、たとえば堀新弁護士は「総理に任命拒否の裁量権があるかどうかについて、日本学術会議の存在する意義、役割、目的などから総合的に考えていく必要」があるとした上で「『日本学術会議が推薦した候補者を、内閣総理大臣は原則として拒否することはできず、任命しなければならない』と解釈するのが妥当」だと結論づける。
その根拠としては「総理が自分の裁量で任命を拒否することができることになると、日本学術会議の会員の構成が総理の意向に左右されることになり、本来、総理の指揮監督を受けてはならないはずの日本学術会議が、総理によって実質的に指揮監督されることになってしまうから」という点が挙げられている。
また「任命」について、どのような解釈が取られていたとしても、問題は政府解釈が検証可能な状態にないことだという指摘もある。元厚生労働省の千正康裕氏は「問題は、ルールの範囲内だとしても、プロセスや判断が適切だったかどうかということで、それを最終的に国民が判断できるようにしておくこと」だと述べる。
手続きに論点があると指摘する論者は、立教大学の安藤道人准教授や慶應義塾大学の松沢裕作教授など数多く、日本学術会議も10月2日に公開した要望書において「推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい」と、任命拒否の明確な理由を求めている。
実際、現時点での菅首相をはじめとする政府関係者による発言は、「総合的・俯瞰的観点から」任命権を行使したとする発言に留まっており、6名の任命によって、なぜ学術会議の目的が毀損されるか具体的な説明はない。
●民意は全権委任を意味していない
以上のように、大きく3つの方向から批判される任命拒否だが、最も説得力を持っているのは、手続きの正当性に関する批判だろう。
憲法違反はさておき、従来の政府解釈を変更するのであれば政府に説明責任が生じるし、解釈が変わらないと主張するのであれば、過去の「形式的な任命」という説明を否定する論理が必要となる。あるいは、解釈を変えないまま任命権を行使することが可能だとしても、その具体的理由を明らかにしなければ、不透明なプロセスによって恣意的な決定がなされる懸念は払拭されない。
手続きの正当性がなぜ重要であるかは、言うまでもなく、民主主義下の全ての政治家は、国民から全権委任を受けたわけではないからだ。もし仮に、政府解釈の変更が妥当であり、「任命」の範囲に首相による拒否が含まれていたとしても、その理由が明らかでなければ、国民は政治家による決定が妥当性を持っているかを判断できない。
「選挙で選ばれた政治家は何をしてもよく、その決定は常に正しいものである」という考えは、現在の日本社会に蔓延する大きな誤解であり、アカウンタビリティ(説明責任)こそが、民主主義の根幹をなす重要な概念だ。
またこの問題と合わせて、日本学術会議そのものの動きを指摘する向きもある。たとえば、下村博文政調会長が「政治と学術の関係」について党内で議論することを明らかにしている。
この点について明らかなことは、学術会議も問題を抱えており、その中には、内閣府の1機関として議論されるべき論点もあるだろうが、今回の問題とは全く別の話だという事実である。そのため、学術会議そのものの在り方や問題、過去の提言に関する懸念は、本問題とは独立した事象として扱われる必要がある。
最後に、この問題はどこに向かっていくのだろうか。現時点では、学術会議が「任命されていない方について、速やかに任命していただきたい」という要望を出しているが、菅首相は「判断の正当性を強調」しており、事態は収束に向かう気配は見えない。
大きく2つのシナリオが考えられ、最も可能性が高いのは政府の主張が押し通されることだろう。自民党の船田元議員や石破茂議員など、党内からも批判が出ているものの、問題の発覚直後も高い支持率を誇っている菅首相が、いま立場を翻すことは考えづらい。
もう1つのシナリオは、検察庁の定年延長問題のように政府が立場を変えて、6名の任命を認めることだ。検察庁の定年延長問題では、#検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグがTwitterなどで話題を集め、今回の学術会議のような動きを見せた。しかし、菅政権の高い支持率や学術会議という機関の特殊性などから、今回の問題が同様の経緯をたどる可能性は、決して高くないだろう。
とはいえ、今後の抗議の広がりや党内からの懸念によって、状況が変わる可能性は十分にある。
筆者は、安倍政権の評価について、経済や外交・安全保障などで高い支持率を誇ったが、モリカケ問題や桜、定年延長など主要な政策とは異なる部分で国民からの信頼を毀損したと主張した。菅政権はスタートしたばかりで、主要な政策について実績が出ていない段階にあり、安倍政権ほどの安定感は見られない。開始早々、本来であれば直面する必要のなかったスキャンダルを引き起こしたことで、政権にとっては早くも打撃となる可能性もある。
 10/6
10/6声明は「立憲デモクラシーの会」のメンバー5人が、東京都内で記者会見を開いて明らかにしました。
この会は6年前、集団的自衛権の議論をきっかけに発足し、今回、任命が見送られた東京大学大学院の加藤陽子教授と東京大学の宇野重規教授が、それぞれ呼びかけ人となっています。
声明では、日本学術会議法は会員の人事について独立性や自律性を強く認めており、それは自律性が保障されてはじめて、学術会議の目的である「科学の向上発達を図り、行政、産業および国民生活に科学を反映浸透させる」ことが可能になるからだとしています。
そのうえで「各専門領域での研究者による評価を政府が『広い視野』という名目に基づいて覆すことは、学問の自由の侵害そのものだ。首相は今回の権限行使を直ちに撤回し、6人全員を任命すべきだ」としています。
日本学術会議の元会員で、法政大学の杉田敦教授は記者会見で「多くの研究者が政策の妥当性に関わる発言をしないほうがいいと考えれば、政策の検証や助言はできなくなってしまう。波及効果はかなり大きく、学術会議だけの問題ではない」と指摘しました。
日本学術会議の会員の任命をめぐって6日夜、総理大臣官邸前で抗議活動が行われ、任命されなかった1人で東京慈恵会医科大学の小澤隆一教授が「学術会議の意向を無視した人事で許されない。日本の学術、そして国民全体の問題として起きたことだということを訴えていきたい」と話しました。
総理大臣官邸前には主催者の発表でおよそ700人が集まり、「学問の自由を侵害するな」などと書かれたプラカードを持って、抗議の意思を示しました。
抗議活動には任命されなかった1人で東京慈恵会医科大学の小澤隆一教授も姿を見せ、「推薦に基づいて任命することこそ総理大臣の責務なのに、法律の解釈を変更し、今回のような暴挙に出た。学術会議の意向を無視した人事で許されない。政府から独立し学者が意見を述べることで国民の幸せが実現すると考えており、日本の学術、そして国民全体の問題として起きたことだということを訴えていきたい」と話しました。
参加した40代の女性は、「学術会議はいろんな考え方を持つ専門家が集まって議論する場だと思うので、政治が人事に介入するべきではない。任命しない理由を説明しないのもおかしいと思います」と話していました。
「日本学術会議」の複数の元幹部によりますと、平成28年の夏、3人の会員が70歳の定年を迎えたため、欠員の補充が必要になり、幹部らでつくる選考委員会で候補者を選んだということです。
その過程で、総理大臣官邸側から選考状況を説明するよう求められ、会議の事務局が推薦することが有力になっていた3人の候補者を挙げたところ、このうち2人について、官邸側から難色が示されたということです。
理由については明らかにされなかったということです。
会議側が候補者の差し替えに応じなかったため、翌年の秋まで、3人の欠員の状態が続いたということです。
元幹部の1人は「候補者の選考の途中で官邸側に『この2人は違うんじゃないか』と言われたが、推薦する候補者を差し替えたりすれば、圧力に屈したことになるので、結果的に空席になってしまった。選考途中で圧力をかけ、学術的な観点から会員を推薦することを不可能にしたわけだから、許せないことで、当時から公表するべきだと思っていた」と話しました。
また、当時の日本学術会議会長で、東京大学の大西隆名誉教授は「候補者は、選考の審議を積み重ね、学術会議として合意を得て選出しているので、官邸側に難色を示され驚いた。候補者は人物的に申し分ない人だと思っていた。苦い経験だ」と述べました。
日本学術会議の会員は昭和24年の設立後、全国の科学者による大がかりな選挙で決められていました。
しかし、組織票による会員の選出など選挙制度への批判が高まったことなどから昭和59年、日本学術会議法の改正によって研究分野の学会ごとに候補者を推薦し、その推薦に基づいて総理大臣が任命する仕組みに変わりました。
法律の改正案が審議された昭和58年の参議院文教委員会で、当時の中曽根総理大臣は、「政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております」と答弁しています。
その後、学会の仲間うちで会員を引き継ぐなれ合いなどが問題視されるようになり、平成17年、再び会員の選出方法が変更されました。
学会ではなく、210人の現役会員とおよそ2000人の連携会員が、「優れた研究又は業績がある」科学者を、それぞれ推薦し、その後、選考委員会を経て学術会議が最終的に推薦する候補者を絞り込む仕組みで、総理大臣が任命する規定は維持されました。
日本学術会議は「学者の国会」とも呼ばれ、政府から独立した専門家の立場で、社会のさまざまな課題について提言を出してきました。
1954年には米ソの核兵器の開発競争が加速し、太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で、第五福竜丸の乗組員が被ばくするという時代背景のもと、日本学術会議は、原子力の研究と利用について平和目的にかぎり、「民主、自主、公開」の三原則が十分に守られるべきであるとするいわゆる「原子力三原則」の声明を出しました。
この原則が翌年に制定された「原子力基本法」にも盛り込まれるなど、日本学術会議の提言は政府の政策に一定の影響を与えてきました。
日本学術会議の提言は、政府を拘束するものではありませんが、提言の内容をめぐって、政府与党の方針と対立することはこれまでにも起きています。
日本学術会議は、先の大戦で科学者が協力したことへの反省から、1967年に「軍事目的の科学研究を行わない」とする声明を出していて、この声明から半世紀となる2017年、軍事的な安全保障の技術研究との関わり方について、新たな声明をまとめました。
これは、防衛省が大学などに研究資金を提供する制度を始めたことを受けてまとめられたもので「将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿って公募や審査が行われ、政府による研究への介入が著しく、問題が多い」と指摘し、それぞれの大学などに対して、軍事的な安全保障の技術研究と見なされる可能性のある研究について、その適切性を技術的・倫理的に審査する制度を設けるなど、慎重な対応を求めています。
この声明がまとめられる前の段階で、当時の菅官房長官は、防衛省が始めた制度について、参加は研究者の自由意思によるもので、懸念はあたらないという認識を示しました。
一方で、日本学術会議は、政府から求められて政策への提言を出すこともあります。
2012年には原子力発電に伴って出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のゴミ」の処分について、国の原子力委員会から見解を求められ、「国の計画は行き詰まっていて白紙に戻す覚悟で見直すべき」などとする提言をまとめました。
このほか、日本学術会議は、時代に応じて幅広い分野で提言を出しています。
3年前には遺伝子を自在に書き換えることができる「ゲノム編集」の技術で、ヒトの受精卵の遺伝子を改変することなどについて、国が指針を作って規制すべきだとする提言や、LGBTと呼ばれる性的マイノリティーの人たちの権利を守る取り組みの遅れを指摘し、同性どうしの結婚を認める、法改正を行うことなどを求める提言を出しています。
ただ、提言の多くは国の政策などに十分生かされていないという指摘もあり、日本学術会議では3年前から各省庁や経済界など、研究者以外からも意見を聞いて提言を作成するなど、より具体的に政策に生かされやすい提言を増やす取り組みを進めているということです。
「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を菅総理大臣が見送ったことをめぐり、6日開かれた野党の会合には、内閣府の担当者が出席し、おととし、政府内でまとめられた総理大臣による会員の任命権に関する見解についての文書を公表しました。
この中では「日本学術会議」について、国の行政機関であることから、総理大臣は、会員の任命権者として、人事を通じて、会議に一定の監督権を行使することができると明記しています。
そのうえで、会員の任命について公務員の選定などは、国民固有の権利であることを定めた憲法15条にある国民主権の原理からすれば、総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えないとしています。
また、内閣総理大臣が適切に任命権を行使するためには、定員を上回る候補者の推薦を求めて、その中から任命することも否定されないとしています。
一方で、科学者が自主的に会員を選出するという基本的な考え方に変更はないなどとして、総理大臣は会員の任命にあたって、会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとしています。
これについて、出席者から法解釈の変更ではないかという指摘が出されたのに対し、内閣法制局の担当者は「法解釈の変更ではない。憲法15条の規定で、公務員の任命権などは国民にあり、最終的に内閣総理大臣が、その責任を負っている。かつての国会答弁も、その前提のもとにされている」と述べました。
日本学術会議の会員の任命をめぐって、政府が「総理大臣に、会議の推薦通りに任命すべき義務があるとまでは言えない」とする文書をおととし、まとめていたことについて、ことし9月まで日本学術会議の副会長を3年間務め、会員の選考にも携わった科学技術振興機構の渡辺美代子副理事は「在任していた期間、そうした文書は見たことがなく文書が存在していることも全く知らなかった。日本学術会議の会員や幹部はそうした文書を見たことはないのではないか」と話しています。
渡辺副理事は「公平、公正で中立な立場から将来の科学、学術分野の発展を支えてくれるふさわしい人物を長い時間をかけて選んでいる。私たちが選んだ人を総理大臣が文句なく選べとまでは言わないが、実質的な任命権は私たちにあるという認識だった。総理大臣が学術会議の推薦通りに任命すべき義務があるとまでは言えないなどという表現には違和感を覚える。国内の科学、学術の発展のため考え抜いて選んだ方々を、政府側の思惑一つで何の理由も示さずに任命しなくてもよいのだという認識であれば非常に問題で、とても受け入れられない」と述べました。
自民 下村政調会長「政治と学術を議論へ」
自民党の下村政務調査会長は党の会合で「今回の人事案件とは別に、政策決定におけるアカデミアの役割という切り口から議論していく必要性がある。今後、政務調査会内のしかるべき機関で議論を進め、政治と学術の関係について前向きなものを打ち出していきたい」と述べました。
加藤官房長官「人事に関わりコメント控えたい」
加藤官房長官は閣議のあとの記者会見で、記者団が「日本学術会議に定員よりも多くの推薦候補を示すよう求めたことはあるのか」と質問したのに対し、「学術会議からは、これまで定員どおりの推薦が上がっていた。その間に、いろいろなやり取りがあったと思うが、人事に関わるプロセスでありコメントは控えたい」と述べました。また、日本学術会議に関係する令和元年度の予算について、会員に対する手当の支給総額がおよそ4500万円で、事務局の常勤職員50人の人件費として、3億9000万円が充てられたと説明しました。
自民 世耕参院幹事長「総理はきちんと説明」
自民党の世耕参議院幹事長は記者会見で「菅総理大臣は、きのうの内閣記者会とのインタビューで人事の判断について極めてきちんと説明した。単純な前例踏襲を認めないのが、菅総理大臣の政治姿勢そのものであり、それが国民にも伝わったのではないか。その説明で、しっかり国会対応をしていけばいい」と述べました。
立民 枝野代表「理解不能 具体説明を」
立憲民主党の枝野代表は党の役員会で「今回の会議のメンバーの選定は、法的にもどう説明するのか理解不能だ。きのう、菅総理大臣がいろいろ言ったようだが、『総合的』とか『ふかん的』とか、全く何の説明にもなっていない。こうした恣意的(しいてき)な運用は間違いなく萎縮効果をもたらす。任命しなかったことを正しいと言うなら、わかるように具体的に説明していただかなければならない」と述べました。
立民 安住国対委員長「国家として下の下の下だ」
立憲民主党の安住国会対策委員長は、記者団に対し「慣例を壊したのだから、説明が必要だ。野党が国会に参考人を呼んで自由かったつに議論することを封じるために意図的にやっているとも思える。いま、文化人や映画界からもメッセージが発せられているが、自由な雰囲気がなくなったら、戦前の検閲と同じで、暗黙のプレッシャーをかけることは、国家として絶対やってはいけない。下の下の下だ」と述べました。
国民 玉木代表「過去答弁と矛盾 説明を」
国民民主党の玉木代表は記者会見で「『総合的、ふかん的な活動を確保する観点から判断した』という菅総理大臣の説明は、過去の国会答弁と照らし合わせても矛盾がある。理由が明確に示されなかったことで、何をしたら推薦が認められないか予測できず萎縮効果が働く。憲法が保障する学問の自由にも影響を与えかねない問題で、しっかりとした説明を求めたい」と述べました。
加藤官房長官「解釈に変更加えたものではない」
加藤官房長官は午後の記者会見で、おととし、政府内でまとめていた文書を6日、明らかにしたことについて「解釈に変更を加えたものではなく、内閣法制局と日本学術会議の事務局が内部で考え方の確認した文書だ。もし解釈が変わるということがあれば、公表もあったのだろうが、そうした形ではなかったので、直ちに公表する必要がなかったと当時、判断したのだと思う」と述べました。
立民 福山幹事長「6人の拒否理由 個別に説明を」
立憲民主党の福山幹事長は、記者会見で「6人がなぜ任命を拒否されたのか、それぞれ個別に理由を説明してもらいたい。『ふかん的、総合的判断』などということでは、なぜ6人が対象になったのか見えない。7日、8日の内閣委員会での政府側の答弁を注視していきたいと思う。今回の意思決定に関係する行政文書は、すべて公開してもらいたい」と述べました。
 10/5
10/5この中で菅総理大臣は、「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を見送ったことについて、「法に基づいて、内閣法制局にも確認の上で、学術会議の推薦者の中から、総理大臣として任命しているものであり、個別の人事に関することについてコメントは控えたい」と述べました。
そして、「日本学術会議は政府の機関であり、年間およそ10億円の予算を使って活動しており、任命される会員は公務員の立場になる。人選は、推薦委員会などの仕組みがあるものの、現状では事実上、現在の会員が自分の後任を指名することも可能な仕組みとなっている」と指摘しました。
そのうえで、菅総理大臣は、「推薦された方をそのまま任命してきた前例を踏襲してよいのか考えてきた。省庁再編の際に、必要性を含め、在り方について相当の議論が行われ、その結果として、総合的、ふかん的な活動を求めることになった。まさに総合的、ふかん的な活動を確保する観点から、今回の任命についても判断した」と述べ、今後も丁寧に説明していく考えを示しました。
一方、菅総理大臣は、昭和58年の参議院文教委員会で、政府側が「形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」と答弁したことについて、「過去の国会答弁は承知しているが、学会の推薦に基づく方式から、現在は、個々の会員の指名に基づく方式に変わっており、それぞれの時代の制度の中で法律に基づいて任命を行っているという考え方は変わっていない」と述べました。
また、菅総理大臣は、記者団が、任命の見送りは、学問の自由の侵害ではないかと指摘したのに対し、「学問の自由とは全く関係ない。それはどう考えてもそうではないか」と述べました。さらに、記者団が、今回の人事について、かつて政府が提出した法案への態度と関係があるのかと質問したのに対し、「全く関係ない」と述べました。
みずからの外交政策について、菅総理大臣は、「機能する日米同盟を基軸に政策を展開し、国益を守っていく必要がある。『自由で開かれたインド太平洋』を戦略的に推進し、中国やロシアを含む近隣諸国と安定的な関係を築いていきたい」と述べました。
また、ミサイル阻止に関する新たな方針について、「9月11日の総理大臣の談話を踏まえ、防衛大臣に対し、年末までにあるべき方策を示し、速やかに実行に移すよう改めて指示を行った。今後、与党ともしっかり協議していきたい」と述べました。
一方、菅総理大臣は、携帯電話料金の値下げについて、「政府としては、競争の一層の促進を通じて、利用者にとって、わかりやすく、納得できる料金やサービスを実現できるよう、しっかりと取り組んでいきたい」と述べました。
●日本学術会議 組織と予算は
日本学術会議は、全国におよそ87万人いる日本の科学者を代表する機関で、科学を行政や産業、国民生活に反映、浸透させることを目的に昭和24年に設立されました。
総理大臣のもとに、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として、210人の会員とおよそ2000人の連携会員が、政府に対する政策提言や国際的な活動、科学者の間のネットワークの構築などを行っています。
組織や会員については、日本学術会議法に定められています。
会員は、日本学術会議からの推薦に基づいて、総理大臣が任命する仕組みになっていて、任期は6年で3年ごとに半数が任命されます。
特別職の国家公務員となる会員には、本来の職業の収入とは別に、手当が支給され、任期にかかわらず、70歳に達した時に退職することになっています。
また、会議に関係する経費として、毎年およそ10億円の予算が充てられています。
その内訳について、加藤官房長官は記者会見で、今年度分として、
▽事務局の人件費と事務費が5億5000万円、
▽人件費を含む、政府や社会などへの提言に2億5000万円、
▽各国のアカデミーとの交流など国際的な活動に2億円、
▽科学の役割の普及・啓発に1000万円、
▽科学者の間のネットワークの構築に1000万円を
それぞれ計上していることを明らかにしています。
立憲民主党など野党側は、任命が見送られた6人の教授のうち、3人と個別に面会し、意見を聞きました。
このうち、憲法学が専門の東京慈恵会医科大学の小澤隆一教授は、「任命の拒否は、『日本学術会議法』にもとるやり方だ。その理由が明らかにされなければ、いつ何時、このようなことがまかり通るかわからず、研究者の学問・研究活動が阻害される」と指摘しました。このあと小澤氏は、記者団に対し、「もし仮に私が、専門家の立場からかつて衆議院の中央公聴会で安保法制について、『憲法に違反する』と言ったことが、実質的な理由になっているとすれば受け入れがたく、学問の自由の重大な侵害だ」と述べました。
刑事法が専門の立命館大学大学院の松宮孝明教授は「この任命拒否の問題は、まさに学術会議の存在意義に関わる大問題だ。しかし、政府側が全く理由を説明しておらず、菅総理大臣は記者会見すら開いていない。ちゃんと会見を開いてもらいたい。政府の対応は、法律を理解しているとはとても思えないと感じている」と述べました。
行政法が専門の早稲田大学の岡田正則教授は、「日本の学術自身が攻撃され、外堀を埋められているような状態だ。6人が排除されたことが、日本の学術に今後、どういう影響をもたらすかだが、やはり萎縮効果のようなものは、当然働く」と指摘しました。
野党側は、5日のヒアリングなども踏まえて、国会などで政府への追及を強める方針です。
加藤官房長官は、午後の記者会見で、「日本学術会議の会員は特別職の国家公務員だ。任命権のある総理大臣が、その責任において任命するということは、これまでも変わっていない。法律上、学術会議からの推薦に基づいて会員を任命するという構図の中で、憲法との関係を踏まえ、これまでも対応してきた」と述べました。そのうえで、「公務員の選定任命権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる総理大臣が、推薦のとおり、任命しなければならないというわけではないという趣旨の整理が2018年になされた」と述べました。
共産党の小池書記局長は、記者会見で、「これまでの国会答弁と全く違うことをやった以上、法解釈を変えたとしか言えない。学問の自由や法治国家としての在り方にも関わる極めて重大な問題だ。閉会中審査も含め、徹底的にこの問題を解明するとともに、拒否された6人の任命を求めていきたい」と述べました。
この問題で、映画に携わる監督や脚本家などの有志が、「表現の自由への侵害であり、言論の自由への明確な挑戦だ」などとして撤回を求める抗議声明を出しました。この抗議声明は、映画監督の是枝裕和さんや脚本家の井上淳一さんなど、映画に携わる22人が5日、連名で出しました。声明では「日本学術会議が推薦した候補を首相が拒否するのは本来あってはならないことです」としたうえで、「この問題は、学問の自由への侵害のみに止まりません。これは、表現の自由への侵害であり、言論の自由への明確な挑戦です」と記しています。そして「私たちはこの問題を深く憂慮し、怒り、また自分たちの問題と捉え、ここに抗議の声を上げます。私たちは、日本学術会議への人事介入に強く抗議し、その撤回とこの決定に至る経緯を説明することを強く求めます」と結んでいます。
国公立を含む日本の大学は、防衛のための研究に協力することを拒否し、自衛隊員の大学や大学院への入学まで排除・制限するという暴挙を平気で行っている。一方で、外国の軍事研究への協力には無警戒である。
自民党の甘利明税制調査会長は8月6日のブログで、中国が世界から技術を盗み出そうとしていると、米国で大スキャンダルになっている「千人計画」に、日本学術会議が積極的に協力していると批判している。北朝鮮の核開発にも、日本の大学の研究者が貢献したと疑われているくらいだ。
文科省をはじめとする政府機関は、この状況を放置してきた。だが、米国と中国の対立が激化するなか、日本の企業、大学、研究機関、さらには研究者個人に至るまで、無神経でいると世界の研究網から排除されたり、留学や学会のためのビザも拒絶されかねない。
日本学術会議は「軍事目的のための科学研究を行わない」という声明を1950年と67年、2017年に出した。これが、大学などでの不適切な方針を後押ししてきた。
これらの活動は、学術会議の本来の目的から逸脱している。時代にも合わないし、組織運営も時代に合わなくなっており、制度の全面見直しをすぐ行うべきところだ。
こうしたなか、政府が学術会議の自浄作用を期待するために、内閣法制局の意見も踏まえて、新会員候補の一部の任命を見送ったのは、何ら問題とされることではない。
ただ、東京高検検事長の定年延長問題でも「司法改革の必要性」を国民に訴えずに、人事でだけ控えめに政府の意見を反映しようとするから、「司法介入だ」という見当外れの批判を受けた。
今回も「学術会議の問題点」を国民に訴えずに、先例と違う人事のやりかたをしたので、守旧派の付け入る隙を与えている。
元文科事務次官の前川喜平氏は、政府の専権事項である審議会委員の任命について、官房長官時代の菅首相に事務方の案を覆されたと批判している。仲間内で後任者を決めることができるのでは、時代に合う改革はできなくなるし、「国民の意思を政策に反映する」という民主主義の根幹も維持できなくなる。
官房長官の立場では、人事をテコに意見を反映させるのも合理性があるが、いまや首相なのだから、国民に考え方を示し訴える方がいいのではないか。今回の件もまず、学術会議の現況を先に批判してから同じことをすれば、国民のほとんどは支持した案件であるし、すぐにでも正々堂々の説明をしてほしい。
日本学術会議は1950年と67年に、「軍事目的の研究を一切禁じる」とする声明を出し、科学者が軍事技術に協力するのを抑制してきた。さらに、2017年に防衛省が軍事応用できる基礎研究に費用を助成すると発表したことに反発し、「国家安全保障の研究と学問の自由が緊張関係にある」として、前の2つの声明を引き継ぐ意向であるとした。
自民党・長尾敬議員は自身のブログで10月3日、日本学術会議の声明を引用して批判している。議員は、同会は「学問に応じて学問の自由にガイドラインを設けている、とも受け取れる」と政治的な偏向性を疑っている。
こうした日本の安全保障技術に対して非協力の姿勢を示す日本学術会議だが、2015年9月7日、中国科学技術協会と、両機関における協力の促進を図ることを目的とした覚書を締結した。 中国科学技術協会は、中国全土すべての学会と科学館を管理し、国内の科学技術知識の広報に大きな役割を果たす組織だ。
中国は2050年までに科学技術における世界のリーダーになることを目指している。党が民間の技術を軍事に利用することを定める「軍民融合」政策を実践しており、軍事改革のひとつと考えられている。このため、共産党体制の中国では政治目標と学術研究および軍事開発の境目が曖昧だ。
このため、中国の学術機関との連携にはリスクがあると議員らは指摘する。自民党・佐藤正久議員は、ツイッターで、「日本の軍民複合と言われる分野の基礎研究にさえ反対なのに、中国軍と縁のある研究は反対せず許容している。このことは、自民党内では保守系にかかわらず批判が多い。仮に同会議が中国と縁を切っても困るのは中国の方で日本ではない」と書いた。
近年の中国の軍事拡張とインド太平洋地域の拡張主義には、防衛省は「力を伴う現状変更」として危機感を示している。2017年の防衛白書には、中国の戦力の近代化について「具体的な将来像や必要性を明確に示さないまま軍事力の急速な近代化を進めている。わが国周辺を含む地域および国際社会の安全保障上の強い懸念」と表現している。このため、防衛省は費用助成などを通じて、日本の軍事研究を後押ししたい考えだ。
いっぽう、日本の学術機関のすべてが、安全保障技術の協力を全て否定している訳ではない。日本学術会議は2018年、国立・私立大学、研究機関の183からアンケートをとったところ、防衛装備庁が2015年度から開始した「安全保障技術研究推進制度」に申し込みしたのは、全体で30%に及ぶことが明らかになった。
読売新聞は5月、経済安全保障の強化策を練る自民党の「ルール形成戦略議員連盟」甘利明会長による関連会議内の発言を報道している。それによれば、「日本学術会議は軍事研究につながるものには一切協力しない、させないとしながら、中国との研究に協力するのは学問の自由だと主張し、政府は干渉するなと言っている」とその矛盾を指摘した。
甘利議員は8月、自身の公式ウェブサイトで、さらに日本学術会議を強く批判している。「軍事研究には与しないという(日本)学術会議の方針は一国二制度なのか。そもそも民生を豊かにしたインターネットが軍事研究からの出自に象徴されるように、機微技術は現在では民生と軍事の線引きは不可能だ」と書いている。
甘利議員は重ねて、日本学術会議と中国共産党が国家的に率いる海外ハイレベル人材スカウト計画「千人計画」との協力があると指摘しているが、明確な関連資料を公表していない。
米国は千人計画をはじめとする中国の人材招待計画に危機感を示している。米国議会上院の小委員会が2019年11月に公表した報告によると、千人計画に参加する研究者が中国に渡ることで、米国政府の研究資金と民間部門の技術が中国の軍事力と経済力を強化するために使われる。連邦捜査局(FBI)は近年、中国研究者および中国共産党のプログラム参加者を虚偽申告、ビザ詐称、電信詐欺などの容疑で逮捕している。
米国のクリストファー・フォード米国際安全保障・不拡散担当国務次官補は2018年、ホワイトハウスの会議で「軍民融合」について語った。このなかで、外国技術の取得手段は外国企業や大学から技術移転させるための共同開発、連携があると指摘。外交の失策は国家安全保障を脅かすと警鐘を鳴らした。
米下院共和党議員15人からなる政策提言組織「中国タスクフォース」は2020年9月、400あまりの政策提言を作成し、政府および主要業界に対して対中政策の強化を訴えた。このなかでも、米大学や一流の研究機関における機密性の高い研究の保護を強化するため、連邦政府のすべての職員を含む公的関係者に、外国の人材プログラムへの参加を制限させる必要性を提言している。
日本学術会議の新会員候補のうち、6人の任命を首相が拒否したとして日本学術会議や野党、メディアが反発している。
立憲民主党、共産党など一部の野党は、学問の自由が侵害されると発言している。また、過去の1983年の国会での政府答弁を根拠として、「首相の任命権は形式的なので、日本学術会議の推薦どおりにしなければならず、裁量の余地はない」としている。
一部メディアも社説で反発しており、論旨は一部野党と同じだ。
(朝日新聞)「学術会議人事 学問の自由 脅かす暴挙」
(毎日新聞)「学術会議6氏任命せず 看過できない政治介入だ」
(日経新聞)「なぜ学者6人を外したのか」
(東京新聞)「学術会議人事 任命拒否の撤回求める」
一方、産経新聞社説は、論調が異なり、日本学術会議のほうに問題があるとしている(産経新聞「日本学術会議 人事を機に抜本改革せよ」)。なお、読売新聞は社説はなく、一般記事で事実のみを報じている。
では、改めて日本学術会議とはどのような組織なのか見ていこう。
●予算10億円を国が負担している
日本学術会議は1949年に設立された。現在内閣府の特別の機関であり内閣総理大臣が所轄し、その会員は国家公務員(特別職)である。その経費は国の予算で負担され、会員210名に対し10億円強の予算になっている。
かつて会員は研究論文をもつ全ての研究者による公選制だったが、今では年長研究者が推薦される縁故的なものになっている。
学術会議は、国内87万人の学者の代表、「学者の国会」とも言われるが、はたしてそうだろうか。
そもそも、身内推薦により会員が構成されているので、日本の学者の代表でもなく、まして、学術会議が国会というわけではない。
2000年はじめのころ、日本学術会議を行革対象という議論があった。その当時、筆者は直接の担当でなかったが内閣府にいたので、日本学術会議幹部からかなり陳情を受けた。
その際の議論のポイントは、従来のまま国の機関とするか、独立の法人格の団体とするかであった。政府に批判的な提言をするためには、後者の独立の法人格の団体のほうが望ましいという議論もあったが、結果として、日本学術会議の要望通りに、国の機関とされた。
●海外のアカデミーはどうなっているか
ただし、本来は独立の法人格の団体のほうが望ましいので、中央省庁等改革基本法に基づく2003年2月総合科学技術会議の最終答申「日本学術会議のあり方について」では、「設置形態については、欧米主要国のアカデミーの在り方は理想的方向と考えられ、日本学術会議についても、今後10年以内に改革の進捗状況を評価し、より適切な設置形態の在り方を検討していく。」とされている。
ただし、これがまともに検討された形跡は見当たらない。なお、欧米諸国のアカデミーは、ほとんどが独立の法人格の団体である。政府から一部財政補助は受けているが、独自の財政基盤(会費徴収、寄付、調査受託など)を持っており、政府からの独立性を維持している(2002年7月31日 日本学術会議のあり方に関する専門調査会 )。
筆者は、その後、国家公務員を退官し、アカデミアに転じた。そこでは、日本学術会議は一部の貴族のようなもので、研究の最盛期を過ぎた引退間際の豪華なポストでお小遣い付きにみえた。筆者のような中途でアカデミアに参入した者にはまったく無縁な世界だ。
日本学術会議は、国内87万人の学者の代表、学者の国会とも言われるが、はたしてそうだろうか。そもそも、身内推薦により会員が構成されているので、日本の学者の代表でもなく、まして、学術会議が国会というわけではない。
その役割である政策提言を見てみよう。
2017年3月「軍事的安全保障研究に関する声明」では、軍事研究を禁じた過去の声明を継承している。つまり、憲法で規定されている「学問の自由」に反することを言い続けているわけだ。
●本当に権威ある組織なのか?
その一方で、日本学術会議は、中国の「外国人研究者ヘッドハンティングプラン」である「千人計画」には積極的に協力しているありさまだ。そのために、日本学術会議は、中国共産党軍と関係の深い中国科学技術協会と協力覚書を結んでいる。
日本政府の軍事研究はダメと言いながら、中国政府の軍事研究はいいという国益に反する二枚舌だ。
次のケースを見てみよう。
2011年4月「東日本大震災への第三次緊急提言」では、復興財源として日銀引受を否定し、復興増税を勧めた。実際に、この提言は民主党政権で実行され、災害時に増税という経済理論にも反し古今東西見られない悪政が行われ、多くの人が今でも苦しんでいる。この意味で、日本学術会議の提言の責任は大きい。
日本学術会議会員の推薦要件として「優れた研究・業績」があるが、こうした提言を見ていると、提言を書いた学者のレベルのお里が知れてしまう。
こうした日本学術会議の体たらくを見ると、政府が漫然と日本学術会議会員を任命し税金投入するのは問題だ。
しかし、一部野党と一部メディアは、冒頭に述べたとおり、今回の日本学術会議人事を問題としている。
ただし、学問の自由を奪うというのは、大げさであることが一般人にもすぐわかる。87万人のうち210名の会員に選ばれない人はほとんどだが、誰も学問の自由を奪われたとは言わない。筆者の感覚からいえば、会員「貴族」でなくても、普通に研究ができるので、学問の自由は十分にある。
●「任命権」の問題も大きい
では、1983年の国会での政府答弁からみてどうか。日本学術会議の推薦があるのに任命しなければいけないのか。裁量的人事をしないという国会答弁は、日本学術会議の行動が適切との前提での当面の法運用指針である。
条文を読めば、裁量的な任命権がある。しかも、日本学術会議の実態が不適切になれば、条文通りの任命権を行使しないと不味い。
実際、政府は事情変更により1983年の国会答弁を修正したのだろう。それは可能だし、そうせざるを得ないのは、上に上げた日本学術会議の不適切事例を見れば納得できる。
もっとも、政府の人事である以上、任命しなかった理由を明らかにできない。これは、どのような組織であれ、人事であればその理由を明らかにできないのと同じだ。
この問題について、抜本的な解決を図ろうとすれば、日本学術会議を政府機関として置くことが適切でなくなるはずだ。
2003年に、日本学術会議の設置形態については「10年以内に欧米主要国のアカデミーの方向で再検討することになっている」から、この際、政府として検討したらいいだろう。
●あまりに虫がよすぎる主張
それは、もちろん国の機関ではなく、国から独立した法人格の団体である。なお、こうした方向の設置形態の改革は、一般的に「民営化」といわれているものだ。
日本学術会議が「民営化」すれば、その会員は国家公務員でなくなるので、首相による任命権はなくなるので、今回のような問題はない。今の時代、国に提言するために、国の機関である必要はない。実際に、民間会社のシンクタンクは数多くある。
「国の機関でいたい、国に全額費用してほしい、国家公務員のままでいたい、しかし人事は自分達で勝手にやらせてほしい」というのが、今回の日本学術会議の主張であり、あまりに虫がよすぎる。
欧米主要国のアカデミーのように「民営化」すれば、人事は自分達に勝手にでき、国にとやかく言われることはないので、そうしたらいいのではないか。
学術会議のメンバー選出にについては、政府が1983年の日本学術会議法改正に際し、首相の任命は「形式的」との見解を示したことが分かっている。法改正の審議の中で、首相の任命は実質的かとの問いに「推薦に基づいて会員を任命することとなっており、形式的任命である」と答えていた。この審議があったことで、任命拒否が「学問の自由に反する」と問題視されている。
高橋氏は「1983年の国会審議。学術会議はまともな活動するのが前提だろ」ときっぱり。83年の答弁を根拠に、推薦を拒否できないとするのは「ナンセンス」とし、「そんな議論がまかりとおるとは、そんな学者も楽なもんだ。憲法9条を唱えておけば世界平和になるというお花畑論みたいだな」とバッサリ切った。
さらに、内閣府に籍を置いていた経験から「学術会議は一部の貴族のようなもの。引退間際の豪華なポストでお小遣い付きだよな」と実情を吐露。「そのうえ、中国の千人計画賛成で防衛省の研究反対、復興増税賛成みたいなおバカな提言をやっている」とした。
「千人計画」とは、中国が科学技術強国を目指して海外から優秀な人材を集める国家プロジェクト。中国は「軍民の深い融合の推進」を明言しており、日本から中国に渡った研究者の技術が軍事転用される可能性は否定できない。その一方で学術会議は、2017年3月に、「軍事目的のための科学研究を行わない」とする過去2回(1950年、67年)の声明の継承を決定している。
高橋氏はこの“矛盾”があることを前提にについて「おバカな提言」と表現。「まともな活動」が行われていないと指摘した。
 10/3
10/3小澤隆一東京慈恵会医科大学教授(憲法学)は、日本学術会議は独立して運営されるべきであり、新型コロナ危機の対応で明らかになったように、専門家の意見は国民の生命、安全にかかわると指摘。任命拒否は、学問の自由への侵害だと述べました。
岡田正則早稲田大学教授(行政法学)は「理由のない行政処分はない」として、首相の説明責任を果たしてほしいと語りました。
松宮孝明立命館大学教授(刑事法学)は、「首相に任命権はあるが、任命拒否権は事実上ない」と強調し、憲法6条で、天皇による総理大臣への任命権はあるものの任命拒否権はないのと同じと考えていいと語りました。
一方、内閣府と内閣法制局へのヒアリングで、野党は、1983年の日本学術会議法改定の際の審議で、政府が「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない」と答弁したことを示し、法解釈の変更の有無をただしました。
内閣法制局の担当者は「法解釈を変えたわけではない」と回答。任命拒否の法的根拠は答えませんでしたが、2018年に同法7条の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」の解釈をめぐる合議を内閣府と内閣法制局で行ったことを明らかにしました。
また、任命拒否の判断はいつ、だれがしたかについて、内閣府の担当者は今年8月31日に日本学術会議から105人の推薦名簿を受理し、菅政権発足後の9月24日に任命の起案をし、同月28日に99人の任命を決裁したと説明。任命を拒否した経緯については、「人事に関する事柄」だとして答えませんでした。
●政府からの独立が重要 / 東京慈恵会医科大学教授(憲法学)小澤隆一さん
日本学術会議は「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)であって「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」(同法3条)などを職務として、独立して運営されるものです。学術の専門家の立場から政府に対してさまざまな意見を述べます。これがこの間のコロナ危機に対する対応でも明らかになっています。きわめて国民の生命や自由、安全に直結する重要な役割を果たしています。(学術会議人事への介入によって)本来の政策がゆがめられます。
今回6人の任命を拒否されたということは、学術会議の全体の問題として極めて重要だと考えるべきです。問題について、要請書を携えて学術会議の総会を傍聴しました。梶田隆章新会長に要請書を渡し、会長は重要な問題として受け止めて取り組んでいくと言っていただきました。
政府からの独立性を確保する取り組みとして、今後とも取り組んでいきたい。
●被害者は日本国民全体 / 立命館大学教授(刑事法学)松宮孝明さん
政権が日本学術会議の会員の推薦を拒否した問題の当事者は学術会議そのものです。同時に、この問題の被害者は、日本の学術によって恩恵を受ける人々全体です。任命されなかったわれわれ自身は被害者だとは考えていません。日本の学術がきちんとこれから伸びていけるのか、日本と世界の人々にその恩恵を与え、成果を還元することができるのかということに関する影響が一番大きいと考えています。
推薦名簿に基づいて内閣総理大臣は(会員を)任命するとなっています。法の精神からすれば、内閣総理大臣には任命権はありますが、任命拒否権は事実上ないと考えざるをえません。
加藤勝信官房長官は任命権があるから拒否権もあると思っているようですが、憲法6条1項は、内閣総理大臣は国会の指名に基づいて、天皇が任命するとしています。任命権はありますが、任命拒否権はないと当然考えられています。学術会議の会員の任命もほとんどこれと同じ仕組みだと考えられます。
●学術にゆがみもたらす / 早稲田大学教授(行政法学)岡田正則さん
日本学術会議は日本の科学者を内外に代表するという性格を、日本学術会議法で与えられています。
「内外で代表する」ということですから、国内においては行政に対して、学術界を代表していろいろな提言をするという役割を担っています。ここから、「学者の国会」と言われています。その「国会議員」にあたる会員を、提言される側の行政が左右するということはあってはいけないことです。学術会議法の中で、独立性が定められているのはそういうわけです。他の行政機関とは全く違うということです。
内閣総理大臣は、そういうことをきちんと理解して対応しないといけません。
さらに、学術会議法には、1983年と2004年に大きな改正がありました。その際の国会審議で、内閣総理大臣が学術会議からの推薦を左右することはあってはならないし、やらないと繰り返し言いました。それは、学術会議の会員が日本の社会で果たすべき役割から当然出てくる内閣総理大臣の対応です。今回の任命拒否はそれを踏みにじりました。今後の日本の学術にとって大変大きなゆがみをもたらすと思います。
今後の日本の学術の発展のために、きちんと法の趣旨に沿って手続きを進める必要があります。
 10/2
10/2「6人の方が新会員に任命されなかった。初めてのことで、大変驚いた。菅首相あてに文書で説明を求めたが、回答はなかった」
オンラインを含め、会員ら230人が出席して開かれた1日の日本学術会議の総会。会長を退任した山極寿一・京都大前総長は、あいさつの冒頭でこう切り出した。
同会議は8月末、政府に105人を推薦していた。しかし、6人が任命されないことを山極氏が知らされたのは9月28日の夜。総会後の取材に、「私たちは理由を付して新会員を推薦したのに、理由をつけずに任命しないという事実がまかり通ってしまったことは大変遺憾。学術にとって非常に重大な問題だ」と話した。
新会長に選ばれたノーベル賞受賞者の梶田隆章・東京大宇宙線研究所長も、「極めて重要な問題で、しっかり対処していく必要がある」と述べ、6人を任命しなかった理由について菅首相に説明を求めることを検討する、とした。
6人のうち、小沢隆一・東京慈恵会医科大教授、岡田正則・早稲田大教授、松宮孝明・立命館大教授は1日、梶田会長に、任命拒否の撤回に向け、会議の総力をあげてあたることを求める要請書を手渡した。
松宮氏には9月29日夕、会議の事務局から突然、「名簿から落ちている」と電話があり、「政府に問い合わせたが、理由は言えないということだった」という趣旨の説明をされた。
要請書で3氏は、首相から理由の説明がなく、「私たちの研究活動についての評価に基づく任命拒否であれば、憲法23条が保障する学問の自由の重大な侵害」「(任命が首相の意のままになれば)会議の地位、職務上の独立性、権限は、すべて否定されてしまい、学問の自由はこの点においても深刻に侵される」などとしている。
小沢氏は取材に「私は2015年、安保法制をめぐる国会での中央公聴会で『憲法違反だ』と述べた。仮に、学問上の意見を国会で述べたことが任命拒否につながっているのだとすれば、学問の自由の侵害だ」と話した。
立憲民主党・山井衆院議員:「昭和58年の国会答弁では、実質的には総理大臣の任命で左右されない、拒否権はないと答弁しているが、それは変えたのか」
内閣法制局担当者:「解釈変更ではございません」
内閣府担当者:「私が申し上げられるのはきのう、官房長官が会見で申し上げている通りだ。推薦人が上がってきたものをその通りにする義務的な任命まで課されているものではない」
野党側は、安倍政権のもとでこれまでの政府答弁の解釈を変更し、拒否権を持てるようにしたのではないかと追及しました。「学問の自由への侵害」だとして、次の臨時国会の予算委員会などでも徹底追及する方針です。
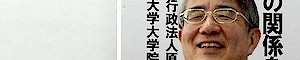

 10/1
10/1●東京大社会科学研究所教授の宇野重規しげき教授(政治思想史)
2013年12月に成立した特定秘密保護法に対し、「民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と批判。「安全保障関連法に反対する学者の会」の呼び掛け人にも名を連ねていた。07年に「トクヴィル 平等と不平等の理論家」でサントリー学芸賞受賞。
●早稲田大大学院法務研究科の岡田正則教授(行政法)
「安全保障関連法案の廃止を求める早稲田大学有志の会」の呼び掛け人の1人。沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設問題を巡っては18年、他の学者らとともに政府の対応に抗議する声明を発表。
●東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)
15年7月、衆院特別委員会の中央公聴会で、野党推薦の公述人として出席。安保関連法案について「歯止めのない集団的自衛権の行使につながりかねない」と違憲性を指摘し、廃案を求めた。
●東京大大学院人文社会系研究科の加藤陽子教授(日本近現代史)
憲法学者らでつくる「立憲デモクラシーの会」の呼び掛け人の1人。改憲や特定秘密保護法などに反対してきた。10年に「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」で小林秀雄賞を受賞。政府の公文書管理委員会の委員も務めた。
●立命館大大学院法務研究科の松宮孝明教授(刑事法)
17年6月、「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法案について、参院法務委員会の参考人質疑で、「戦後最悪の治安立法となる」と批判。
●京都大の芦名定道教授(キリスト教学)
「安全保障関連法に反対する学者の会」や、安保法制に反対する「自由と平和のための京大有志の会」の賛同者。
●退任の会長「学問の自由への介入」 官房長官は否定
9月30日に学術会議会長を退任した山極 寿一氏は取材に「退任直前に知らせを受け、理由も言われていない。(政府の行為は)学問の自由への介入だと言われても仕方がない」と批判した。
一方、加藤官房長官は「推薦された人を義務的に任命しなければならないというわけではない」とし、学問の自由の侵害には当たらないとの認識を示した。
●事務局「選考過程は答えられない」
学術会議事務局によると、新会員候補は学術論文やこれまでの業績を踏まえ、8月末に内閣府人事課に105人の推薦書を提出。同課からは9月28日、99人の発令案を事務局が受け取った。
事務局は翌29日、6人が任命されなかった理由を問い合わせたが、同課は「選考過程については答えられない」と明かさなかった。学術会議側は30日、任命しない理由の説明を求める菅首相宛ての文書を、内閣府に提出した。
●首相に選任する権利はなし
日本学術会議法では「会員は同会議の推薦に基づき、総理大臣が任命する」(7条2項)とあり、首相に任命権はあるが、選任できる権利はない。政府側は1983年11月24日の参議院文教委員会で「学会から推薦したものは拒否しない、形だけの任命をしていく、政府が干渉したり中傷したり、そういうものではない」と答弁している。
日本学術会議は定員210人。任期は6年で3年ごとに半数が交代する。学術会議は1日、新会員99人を発表し、定員より6人減となった。
関係者によると、任命されなかったのは立命館大の松宮孝明教授(刑事法学)や京都大の芦名定道教授(キリスト教学)、東京大の加藤陽子教授(歴史学)ら人文・社会科学系の研究者6人。
加藤勝信官房長官は同日の会見で候補者の選考過程や理由について「人事に関すること」と言及を避ける一方「専門領域の業績にとらわれず、広い視野に立って総合的、俯瞰的観点から学術会議の活動をしていただきたい。そういう観点から任命した」と述べた。
会員は日本学術会議法により同会議の推薦に基づいて首相が任命する。10月1日改選の今回は、7月の臨時総会で全会員の半数に当たる105人が候補者に選ばれ、8月末に首相に推薦書を提出した。9月28日に政府から内示があり、6人だけ外れていたという。
同法には職務の独立性を記した条項があり、9月末で退いた山極寿一前会長(京都大前総長)は1日の総会で「(1949年の)創立以来自立的な立場を取っている。説明もなく会員の任用が拒否される事態は会議の存立に大きな影響を与える」と懸念を示した。
学問の自由への侵害との指摘について加藤官房長官は「会員の人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能だ」と述べ、侵害にはつながらないとした。
松宮氏は2017年に「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法の成立を批判。松宮氏ら3人の法学者は1日、任命拒否の撤回に総力を挙げるよう連名で梶田隆章新会長に要請した。
加藤官房長官は、日本の科学者の代表機関として国が設けている「日本学術会議」の新たな会員について、「日本学術会議の推薦に基づいて、総理大臣が任命する仕組みになっている。8月31日に会議から会員候補推薦書が総理大臣に提出され、きょう、99人の任命を行った」と述べました。
そして、今の仕組みとなった平成16年度以降初めて、菅総理大臣が、会議側が推薦した候補の一部の任命を見送ったことを明らかにしました。
そのうえで、これまでと同様に法律に基づいて手続きを行ったと説明し、「これまでは、推薦された人をそのまま認めていたが、今回は、そうではなかったという結果の違いであり、対応してきた姿勢が変わるものではない」と述べました。
一方、加藤官房長官は、記者団が、「菅総理大臣の政治判断だとすれば、学問の自由の侵害にあたるのではないか」などと質問したのに対し、「会員の人事などを通じて、一定の監督権を行使することは法律上可能になっている。直ちに学問の自由の侵害にはつながらないと考えている」と述べました。
●「しっかりと精査するのは当然」
また、加藤官房長官は、午後の記者会見で、会員を任命する基準について「専門領域での業績にとらわれない広い視野に立って、総合的、ふかん的に科学の向上と発展を図り、行政や産業、国民生活に科学を反映、浸透させることを実行していただくという観点から考えていく。任命する立場に立って、しっかりと精査していくのは当然のことだ」と述べました。
一方、今回、会議側が推薦した候補の一部の任命を見送ったことについて「お一人お一人がなぜそうなのかということは、これまでも、いろいろなことがあったと思うが、具体的なコメントはしていない」と述べました。
また、記者団が「日本学術会議の独立性に問題はないのか」と質問したのに対し、「あくまで、総理大臣の所轄に関わるものであり、任命についての仕組みもあるので、それにのっとって対応している」と述べました。
●学術会議委員の任命手続き
日本学術会議の会員は、日本学術会議法という法律によって、任命の手続きが定められています。
この中では、「日本学術会議は規定に定めるところにより、優れた研究または業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣総理大臣に推薦するものとする」と推薦の手順を定めています。
そして、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」としています。
任期は6年として、3年ごとに半数を任命することも合わせて決められています。この法律は平成16年度に改正され、現在の手続になっています。
●一部当事者が撤回求める要請書
日本学術会議の新しい会員について、総理大臣が、推薦された105人のうち6人を任命しなかったことについて、学術会議が推薦した人が任命されなかった例はないということで、一部の当事者は撤回を求める要請書を提出しました。
日本学術会議は総理大臣のもと、政府から独立して政策の提言などを行う日本の科学者を代表する機関です。
3年に1度、会員の半数を新たに決めるため、学術会議が推薦し、総理大臣が任命することになっていて、日本学術会議によりますと、1日付けで任命する新しい会員として、105人の候補を推薦するリストを提出しましたが、6人が任命されなかったということです。
推薦した人が任命されなかった例は平成16年度に今の制度になって以降、ないということです。
任命されなかった6人のうち東京慈恵会医科大学の小澤隆一教授と早稲田大学の岡田正則教授、それに、立命館大学の松宮孝明教授の3人は連名で会長に宛てて、「研究活動の評価に基づく任命拒否であれば憲法が保障する学問の自由の重大な侵害です。また、学術会議の地位や独立性は、会員の任命が総理大臣の意のままになれば深刻に侵されます。任命拒否の撤回に向けて会議の総力を挙げてあたることを求めます」とした要請書を提出しました。
1日、新たに会長に選出された東京大学の梶田隆章さんは記者の質問に対して「重要な問題なのでしっかりと対応する必要があると考えている」と話しています。
●任命されなかった候補の人たちは
日本学術会議の新しい会員に任命されなかった東京慈恵会医科大学教授の小澤隆一氏がNHKの取材に応じ「日本学術会議は科学の振興などについて政府に勧告できるため、独立性が担保されなければならないが、総理大臣が会員を恣意的(しいてき)に任命できれば、会議そのものの地位や独立性、権限が損なわれてしまう。会員の任命拒否は大変大きな問題だと受け止めている」と述べました。
そのうえで小澤教授は、平成27年7月の衆議院特別委員会の中央公聴会で安全保障関連法案について反対する意見を述べたとしたうえで、「学術の立場から意見を述べたが、これが任命拒否につながったのであれば、研究活動についての侵害であり、日本学術会議の存立自体を脅かすものだ。今回の任命拒否は官邸による人事への介入が、独立性が担保されるべき学問にまで及んだということだ。政府に都合の悪い人たちを総理大臣の意のままに排除すれば国がとんでもない方向に進んでしまう」と述べました。
また、同じく新しい会員に任命されなかった立命館大学大学院の松宮孝明教授は、「おととい、日本学術会議の事務局長から、総理大臣の任命名簿に『名前がない』という話があり、大変な騒ぎになった。政府の意向次第で本来に踏み込んではいけないところに踏み込めることを示した形になり、非常にゆゆしき事態だ」と述べました。
刑法が専門の松宮教授は、3年前の平成29年6月に「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐって参議院法務委員会で行われた参考人質疑で法案を批判していました。
松宮教授は「日本学術会議法では、会議が優れた研究や学問の業績に基づいて推薦した人を総理大臣が任命する決まりになっていて、任命は本来、機械的に行われるものだ。総理大臣は学問の研究者ではないので、推薦の基準を満たしているか、会員にふさわしいかどうかは分からないはずだ。『嫌だから任命しない』というのであれば法律違反だ」と述べ、今回の対応を批判しました。
東京大学大学院の加藤陽子教授はNHKの取材に対し、「当方が任命に至らなかったことは事実です。担当の内閣府の側もまさに寝耳に水のことだと思います」などとメールで回答しました。
メールには「内閣総理大臣が学術会議の決定を経た推薦名簿の一部を拒否するという、前例のない決定の背景を説明できる協議文書や決裁文書は存在しているのでしょうか。この決定の経緯を知りたいと思います。有識者として、有識者懇談会から公文書管理法の成立までを見届けた人間として、この異例の決定の経緯に注視したいのです」と記されています。
そして「新会員の推薦は極めて早くから準備がなされ、内閣府から総理大臣官邸には今年8月末に新規就任予定者の名簿と写真があがっていたはずです。それを1か月間もの間、店ざらしにして、新しい学術会議が発足する2日前、9月29日夕刻に連絡をしてくるというのは、学術会議会員の、国民から負託された任務の円滑な遂行を妨害することにほかならないと思います。総理大臣官邸において従来通り、そのまま承認しようとの動きをもし最終盤の確認段階で止めた政治主体がいるのだとすれば、それは、『任命』に関して、裁量権の範囲を超えたものです」と批判しています。
●「外した理由開示を」立民 安住国対委員長
立憲民主党の安住国会対策委員長は、記者団に対し「異例なことだと思う。特定の人間を外した理由を開示してもらいたい。日本学術会議の会員を選ぶ際に、過去に政府が提出した法案に対する賛否を参考にするような、政治的意図を持っていたとすれば看過できないので徹底的に国会で追及する」と述べました。
●共産 志位委員長「学問の自由を脅かす違憲の行為」
共産党の志位委員長は、記者会見で「日本学術会議は、1949年の発足以来、日本学術会議法に基づき、高度な独立性が大原則で、任命拒否は違法だ。憲法23条の学問の自由を脅かす違憲の行為だ。菅総理大臣に対して、違憲で違法な任命拒否を直ちに撤回するよう強く求めたい。野党で共闘して追及していく」と述べました。
加藤教授は小泉純一郎政権での政府の公文書管理についての有識者懇談会に参加し、公文書管理について政権にアドバイスをしてきた日本の第一人者だ。2010年に設置された内閣府公文書管理委員会委員だったほか、現在は「国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議」の委員を務める。皇室にも熱心な読者を持つ、日本近代史の有力な研究者でもある。
今、多くのメディアは、任命されなかった私たち6人に「なぜ任命されなかったのか」を尋ねている。いかなる研究者の、いかなる研究内容が官邸に忌避されたのかを、国民の知る権利についての付託に応えるために探るのは、もちろん理解できる。
しかし、「なぜ任命されなかったと考えているか」を被推薦者に尋ねる思考回路は本末転倒でもある。首相が学術会議の推薦名簿の一部を拒否するという、前例のない決定をなぜしたのか、それを問題にすべきだ。この決定の背景を説明できる協議文書や決裁文書は存在するのだろうか。
私は学問の自由という観点からだけでなく、この決定の経緯を知りたい。有識者として、小泉政権で福田康 ・・・
―任命されなかったことについて率直な気持ちは。
率直にはほっとした。仕事が一つ減ったな、と。個人的にはそういうところで、別になりたいと思ってたわけでないので、まずはそれを理解してほしい。それを抜いて率直に言うと、「とんでもないところに手を出してきたなこの政権は」と思った。学術会議というのは、まず憲法23条の学問の自由がバックにあり、学術は政治から独立して学問的観点で自由にやらなければいけないということでつくられた学者の組織だ。もちろん内閣総理大臣の下にはあるが、仕事は独立してやると日本学術会議法で定められている。そこに手を出してきた。
しかも法律の解釈を間違っている。日本学術会議法では会員の選び方について、学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると書いてある。推薦に基づかない任命はない代わりに、基づく以上は「任命しない」もないのだ。
どのような基準で推薦しているかというと、結局その分野の学問的な業績、そして学者として力があるということを見て決める。これも日本学術会議法17条に書いてある。推薦に対して「不適格だ」というなら、それは研究者としての業績がおかしいと言わなければ駄目だ。ところが、その専門家ではない内閣総理大臣に、そのようなことを判断できる能力はない。だから結局、機械的に任命するしかないのだが、今回それをしなかった。任命をしないのならその理由を問われるが、総理には言うことができないだろう。
―官房長官は「個々については人事に関わるのでコメントは差し控える」と答えている。
差し控えるというより、コメントができないし、できるわけがない。「この先生の分野で評価したところ、こういう点でおかしいと思う」と言わなければならないのだから。一番大きな問題は、これは学問の自由に対する挑戦で、それを大胆にやってしまったな、という話だ。
―先生を含めて6人が任命されなかった。
これがどれだけ重大な問題であるのか、あまり分かっていないのではないか。
まず、一般公務員の任命と同じだと思ってるようなところがある。菅さんは首相就任の時、「言うことを聞かない者はクビにする」というようなことを言った。学術会議の会員というのは建前上公務員ではあるが、選考基準がはっきり決まっているので、任命権者だからといって自由にクビにするとか任命しないとか、できるわけがない。なぜできないかというと、憲法23条の学問の自由を保障する必要があるからだ。
―政権側は、先生を任命しなかった理由についてコメントを避けているが、ご自身はなぜ外されたと考えるか。心当たりは。
個人的な話をすれば、共謀罪の時に「あんなものをつくっては駄目だよ」と、参議院の法務委員会に参考人で呼ばれたので言ったことがある。治安立法として最悪だということよりも、「そんなものをつくっても多分使えない」と言ったのだ。つくるだけ無駄なもののために政治的空白を大きくするのは、本当に無駄。こんなところにエネルギーを注いだらいけないと言ったのだ。結果、できて3年だが、一度も使われたことがない。政権にとって有益な助言をしてあげたと思っていたのだが、向こうはそう思っていなかったようだ。
しかし、私個人の問題ではなくて、むしろ学術会議や大学を言うがままに支配したいということの表れだと思っている。何が問題かと言うと、防衛省が多額の研究助成予算で持っている。ところが大学や学術会議は、3年前に確認したが軍事研究はやらないということを言って、あまり応募していない。その代わりに普通の研究経費を上げろと言っているのだが、政府は言うことを聞かない。政府にとってみたら、軍事研究をしろと言っているのに言うことを聞かないのが学者だと思っているはず。ここが多分、本当の問題だと思う。
―官房長官会見では学問の自由については「法律上、内閣総理大臣の所轄であり、会員の人事を通じて一定の監督権を行使するのは法律上可能。その範囲内で行っているので、ただちに学問の自由の侵害にはつながらない」としている。
学問を監督しようと言っているが、それが自由の侵害ではないか。もう一つ言うと、ほとんど同じ構造をもっている条文が憲法6条1項にある。天皇の国事行為だ。「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する」とある。日本学術会議法では「学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」。主語と述語は入れ替わるが、同じ構造だ。ということは官房長官の言い方だと、国会が指名した人物について天皇が「この者は駄目だから任命しない」と言えることになる。同じ理屈だ。つまり任命権があることを、「任命が拒否できる権限もある」というふうに思うのは間違いなのだ。
拒否権があるかどうかというのは、結局どういう基準でその人を選んで任命することになっているかという法律全体の構造をみないと駄目なのだ。日本学術会議法は第3条で独立を宣言している。3条をみると、まず柱書きで、「日本学術会議は独立して左の職務を行う」とはっきり独立と書いている。「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること」となっていて、学術会議の職務は独立なんだと書いてある。
総理の下にあるけれど、総理からは独立してる。学術会議は学術行政について政府に勧告権もっているが、独立性がなくなれば、政府がこう言ってくれということしか言わなくなってしまう。だから存在意義がなくなり、学問自体の独立や自由が公的機関では保障できなくなる。だからこの法律は、「任命しない」ということは考えていないのだ。
―任命から外れたと日本学術会議事務局長から電話で聞いた時のやりとりは。
事務局は「ミスで落ちたんじゃないかと思って内閣府に問い合わせた。そしたらミスではないとのことだった」と話していた。「しかし、落とした理由は言えないと言われた」とも。事務局は多分とても困惑したと思う。私もそう感じた。「これは大変なことですよ」と言ったら「大変なことですね」と言われた。


 2020/9
2020/9●ふるさと納税に反対「飛ばされた」
―かつてふるさと納税を担当する総務省幹部だったが異例の人事で転出した。
「官房長官だった菅さんから2014年に、寄付金の上限額の倍増や手続きの簡素化などを指示され、返礼品競争の過熱や、高所得者への過度な優遇になるという課題を指摘したら、反対したということにされて飛ばされた。『逃げ切りは許さないぞ』と圧力をかけられ、最終的には従ったが、異を唱えたのが気に入らなかったのでしょう」
―菅首相は官房長官の時に左遷を否定した。
「菅さんは国会で『事実無根』と答弁したが、官邸が私の人事を止めたのは事実だと思う。当時の高市早苗総務相が官邸に人事案を上げたら、私だけバツを付けられたということで『ふるさと納税で菅ちゃんと何かあったの』と心配されたことがあった。菅さんが内閣人事局をブラックボックス化してしまった」
―菅首相は政策の方向性に反対する官僚には「異動してもらう」と述べた。
「これまで以上に物を言いにくくなり、首相やその周辺の意見で物事が決まるようになる。『おれが言っているからやれ』では、法治国家ではなく、人治だ。(政治家の)各閣僚が中心となって(官僚に)指導力を発揮するのが本来の政治主導。閣議決定などで方向性を決めていないのに、官邸の有力者の意向だから従えというのでは行政が混乱する。内閣法の趣旨を理解せず、政治主導を履き違えている」
―ふるさと納税では最近、問題が相次いだ。
「菅さんは当初『お世話になった古里への恩返し』と説明していたが、懸念した通り自治体の返礼品競争で全然違う状況になった。止めておけばよかったと忸怩たる思いだ。高所得者は税控除の優遇が大きく、肉や魚などを食べきれないほど受け取れるという問題は今も残っている」
●「官僚に忖度させる恐怖政治は勘弁を」
―菅首相に言いたいことは。
「官僚が選挙で選ばれた政治家の決定に従うのは筋ではあるが、忖度させる恐怖政治のようなやり方はもう勘弁してもらいたい。これまでの政権でもあったが、官邸で首相周辺が『首相はこう言っている』と指示することがまかり通っては困る」
―後輩の官僚に期待したいことは。
「役人としてやるべきことをやって良心に恥じない行動を取ってもらいたい。私はふるさと納税で最終的に言われた通りにやって後悔しており、あまり偉そうなことは言えないが。もし妥協したら、後々歴史で裁かれるでしょうから」


 2020/6
2020/6リスク・コミュニケーションを効果的に行なうためには、コミュニケーションを行なう者の専門的な知識や能力が十分にあり、信頼されていることが大事です。リスクの扱いを失敗し、信頼を失ったり、疑いの目を持たれている場合は、効果的なリスク・コミュニケーションは不可能になります。
このことは、2009年のパンデミック・インフルエンザや、2011年の東日本大震災とその後の原発事故でとても問題になりました。両例共に、「専門家」と呼ばれる集団が、いつしか「御用学者」と批判されるようになったのです。
信頼を失うのは、実にあっという間です。しかし、いったん失った信用は、取り戻すのが大変です。圧倒的な世論の支持を得て成立した民主党政権は、震災以降、その信頼が失墜し、現在では野党としてのプレゼンスすら脅かされるようになりました。
個々の専門家がいかに誠実にリスク・コミュニケーションに努めても、組織内の別の人間が信頼を失ってしまえば、組織内のみんなが総じて「御用学者」などのレッテルを貼られ、信用されなくなることもしばしばあります。信用とは、歴史的伝統的な、多くの人の積み上げによって成立するのです。もっとも、その積み上げも、ひとつの不祥事によって木っ端微塵に崩れ落ちてしまうのですが。
ですから、リスク・コミュニケーションにおいては、なるたけ失敗しないことが大事です。信用を失うことがないよう、妥当性が高くプロフェッショナルなリスク・コミュニケーションを行なわねばなりません。
とはいえ、人間が完全に失敗ゼロでい続けることはできません。それが可能なのは、リスク・マネージメントという業務を完全に放棄したときだけです。誤診をしない医者とは、患者を診ない医者のことなんです。しかしこれでは、本末転倒ですね。
自分の前任者の失敗のために(自分とは関係なく)信頼が揺らいでしまうことがあります。厚生労働省は、1990年代の三種混合ワクチン(MMR)の副作用のために、厳しくメディアと世論から糾弾されました。そのトラウマはとても大きく、その後、担当者が交替しても、長い間、予防接種政策を改善させようというインセンティブが高まりませんでした。
2000年代後半になり、麻疹の流行や先天性風疹症候群(CRS)の問題などが起き、「予防接種をしないのもまたリスクなのだ」という理解が少しずつ広がってきました。医療者や官僚を叩いていればよかったメディアも、少しずつ見方が変わってきました。長い時間をかけて、予防接種行政にはようやく追い風が吹くようになりました。
●過去の失敗からどう学べばいいのか
過去を変えることはできません。しかし、過去の失敗から我々が学ぶことはできます。過去のコミュニケーション事例を分析し、何が有効で、何がまずかったのかを検討し、将来同じ間違いをくり返さないことが重要です。
最悪なのは過去の失敗から学ばないこと。官僚がときどき陥る、「俺たちは間違っていなかった」の無謬主義に陥ること。
リスク・マネージメントにおいて、「自分たちは間違っているかもしれない」という正当な自己への疑念は非常に重要です。「俺たちは間違っていない」「間違っているはずはない」という自己正当化のロジックが強すぎると、いざプラン通りにいかなかったときも、「想定外だった」「だから仕方なかったんだ」という自己正当化が起きます。そもそも、想定していなかったということ「そのもの」が問題だったことには思いが至らなくなるのです。そうして過去の間違いに対する反省は消え失せてしまいます。同じような失敗がくり返されます。
2009年の「新型インフルエンザ」の流行時には、厚生労働省が総括会議を行ないました。そのとき、包括的な予防接種意思決定機関の日本版ACIP(予防接種諮問委員会)の設立や、国立感染症研究所と厚労省の二重構造について改善を求める意見が出されました。
その後、予防接種制度についてはだいぶ改善しましたが、日本版ACIPはまだできていませんし、できる見込みもありません。国立感染症研究所と厚生労働省の二重構造は改善されないままで、例えば本書執筆時に流行しているエボラ出血熱についても、厚労省からと、国立感染症研究所から、二重に情報が流れています。
アメリカであれば、CDC(疾病予防管理センター)のホームページを見ればOK、という情報の一元化がなされていますが、こういうシンプルな仕組みも日本にはありません。何年も前から改善を求められていますが、一向に改善は実現しません。
同様に、「新型インフルエンザ」の総括会議においては、個々の医療現場における臨機応変な対応が大切で、霞が関の官僚が机上の空論で一意的に診療のあり方を決定してしまうのはよくない、と私は意見しました。
これに対する異論は出なかったのですが、2014年8月に、海外渡航歴のないデング熱の症例が発表されると、デング熱の診療マニュアル(案)が作られました
マニュアルとは、一意的にそう行なうと決定しているものを指すのであり、診療現場がこのような「マニュアル」に拘束されるのは問題です。過去の失敗から学習していないのです(これは、ぼくらの批判を受けて、後に「ガイドライン」として改まりました。
自己を正当化ばかりして、改善に対するハードルが高い組織は、いざ間違いを犯しても、失敗し信頼を失っても、そこから学ぶことができません。
そしてこういう体質では、リスク・コミュニケーションは絶対に上手くいきませんし、それはリスク・マネージメントの失敗そのものにも直結しているのです。
●リスクを効果的に伝える3つのポイント
リスク・コミュニケーションはただ行なうだけではダメです。必ず結果を出さなければなりません。リスクを減らし、かつ不要なパニックを誘発しないような形でのリスク・コミュニケーションでなければなりません。
では、どのようにすれば、そのような効果的なリスク・コミュニケーションが可能になるのでしょうか。
まずは3つのポイントに留意しましょう。それは、
だれが聞き手なのか
状況はどうなっているのか
なんのためにやっているのか
です。まずは、「だれが聞き手なのか」 について説明します。
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」と孫子は言いました。もちろん、リスク・コミュニケーションにおいて聞き手は「敵」ではありませんが、対峙する相手ではあります。相手のことを理解せずに、一方的にこちらからメッセージを発信しても、コミュニケーションはうまくいきません。それは一般的なコミュニケーションにおいて、相手を知らずに一方的に情報発信しても、うまくいくはずがない事実を考えれば、自明ですね。
聞き手の科学や医学に対する理解や知識、聞き手が懸念している問題、などを十分に理解することが大事です。科学の知識が十分ある聴衆に、
「インフルエンザ・ウイルスはとっても小さくて、目には見えないんだよ〜」
なんて言えば「バカにすんな」と怒られるでしょう。逆に、小学生の健康教室みたいなところで、
「インフルエンザ・ウイルスは、エンベロープを持つマイナス鎖の一本鎖RNAウイルスで……」
と説明しても、チンプンカンプンでしょう。両者を入れ替えれば、適切なコミュニケーションが可能になりますね。
相手の懸念事項を把握するのも大事です。これは後述する「メンタル・モデル」で詳しく説明しますが、
「今度、海外旅行に行くから心配」「子どもの健康が心配」「なんだかよく分からないけど心配」
と、人はいろいろな理由で心配しています。人によって心配の力点の置き方が違うのです。例えば、エボラ出血熱について考えてみましょう。
海外に行くのであれば、「どこでどの感染症が流行している」という「場所」の情報が重要になります。「今、シエラレオネでエボラ出血熱が流行していて……」という感じです。ざっくりと「アフリカ」では不十分で、より正確な情報が必要とされているかもしれません。
でも、「子どもの健康が心配」な場合には、「お子さんが感染する可能性は極めて低いですよ」というメッセージで十分かもしれません。「シエラレオネ」ではチンプンカンプンかもしれませんから、単に「アフリカで流行してます」でも十分な場合もあるでしょう。
このように、聞き手によって重要度の高いメッセージは変わり、メッセージの出し方もそれに応じて変わってくるのです。


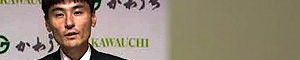 2020/5
2020/5●ワイドショーのMCみたい
「安倍さんの官邸での会見は、なんだかニュース番組のキャスターとかワイドショーのMCみたいになっていますよね。安倍さんがいて、一応は語りますが、細かいところとか数字の点はぜんぶ尾身さんに振る。まあ、記者に突っ込まれても科学的に根拠のある数字を安倍さんが答えられるとは思えないので、仕方ないスタイルではありますが……。異例のことばかり起こるこのご時世の中で、やはり異例中の異例でしょう」 と話すのは、永田町関係者。
「MCの安倍さんから話を振られる側の尾身さんは、いわゆる御用学者でないといけないわけで、それはもちろん尾身さんにも了解してもらっている。政府の方向性や主張、展望とは外れないようになぞるように尾身さんが話すということですね」
尾身副座長は、1949年生まれ。受験の年に東大入試が紛争で中止になって、慶応大法学部に入学。在学中に医学を志し、慶大を中退して地域医療充実のために新設された自治医大に入学した。へき地医療に携わった後、厚生省の技官となり、WHO(世界保健機関)に派遣され、西太平洋地域事務局長として、ポリオ撲滅に尽力した。
「尾身さんは2003年、SARSの流行を水際で防いだ立役者と言われていますね。鳥インフルエンザの脅威を世界にアピールしたことでも評価を受けている。ただ、SARSに関しては、矢崎義雄さんの貢献も非常に大きいものでした」 と、事情を知る関係者。
「矢崎さんは東大の元医学部長で、現在はスキャンダル続きの東京医大立て直しのために理事長を務めています。その矢崎さんが国立国際医療センターの総長時代、小泉さん(純一郎首相)に請われて、SARS対策に奔走したんですよね」
「2006年に当時のWHO事務局長が急逝した際に、日本代表として擁立されましたが、結果は中国が推薦した香港出身の候補に敗れました。アピールが足りないから在外公館を増やそうとか、色んな議論が起こりましたね。今もそうですけれど、あの頃から中国の息のかかった人がトップに立っていたわけですね。尾身さんはその後母校の自治医大教授になって、6年前から今のポジションに就きました」
専門家会議に対しては、緊急事態宣言が延長され、「新しい生活様式」なる行動スタイルの提案がなされるに至って、国民の不信感は増幅して行く。当然、表の御用学者である尾身副座長も様々な批判にさらされたわけだが、一方で、裏の御用学者が、厚労省の鈴木康裕医務技監である。
「首相動静」を確認すると、事務方のスタッフで連日のように官邸を訪ねているのが、今井尚哉首相補佐官、北村滋国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官らに加えて、この鈴木氏だ。
●アビガン推しだった
「鈴木さんは現在、新型コロナウイルス感染症対策本部の事務局長ですね。政府の政策のとりまとめを担当しています。医務技監は事務次官級のポストとして2017年に新設され、保険局長だった鈴木さんが初代として昇格しました。医師免許を持つ医系技官の最高位です」 と、取材を担当する記者。
「当時の塩崎恭久厚労相が決めた人事ですね。なかなかドラスティックでした。鈴木さんは慶応大医学部出身で、1984年入省。WHOでの勤務経験もある国際派とされている。塩崎さんは国際医療に注力したいという思いがあって、鈴木さんを引き上げたんです。塩崎さんの後の加藤勝信さんにもうまく取り入って、その頃からなかなかの御用学者ぶり(笑)。2年務め、2019年に再任・続投しています」 と、担当する記者。
「バランス感覚に秀でた人物という評価がある一方で、何か功績があるのか?と忌み嫌う人もいて、それが相半ばしている印象です。鈴木さんと言えばアビガンですね。石田純一やクドカン(宮藤官九郎)が効いたと公言したり、あの岡田晴恵白鴎大教授も医療従事者にはアビガンを持たせるべきだという主張をしていましたが、ご存じのように催奇形性がある。厚労省には薬害のトラウマがあり、アビガンにはネガティブな空気が強かったのですが、その中で、鈴木さんは“アビガンは良い薬”という考えの持ち主で、実際にこの薬を推していました。ただ、厚労省のトップとなった現在は、アビガンについては慎重な姿勢を取ったりしているようで、なかなかの“政治家”かもしれません」(先の関係者)
厚労省、WHOでキャリアを積んできた2人の御用学者に、コロナ禍の日本の運命が託されていることは間違いない。


 2020/1
2020/1私が福島県と関わるようになったのは、知人の紹介で相馬市の仮設住宅健診に参加したことがきっかけだ。この健診で驚いたのは、人々の口腔衛生状態だった。皆口の中が乾ききっていて、歯周炎や口臭が非常に多かったのだ。口腔衛生は精神的ストレス、血糖、飲酒や喫煙など色々な要因に影響を受けることを考えれば、口の中だけ見ても被災地の健康被害が放射能以外の様々な要因で起きていることが窺われた。
当時は世間で福島といえば「放射能が危険か否か」の議論ばかりがされていた頃だ。放射能以外の健康影響については、精神的ストレスと高齢者の運動不足が時折話題になる程度だったと記憶している。仮設住宅の生活習慣病、高齢者の孤立、医療崩壊、除染作業員の健康問題、外部労働者の大量流入による社会不安、失業や自殺…。健診に訪れた方々から聞く現在進行形の重大な社会問題・健康問題は、「放射能とがん」にかき消されているように見えた。
このままでは多くの健康被害が見捨てられてしまうのでは、という危機感を覚える一方で、そんな被災地でもしなやかに、したたかに暮らす人々たちが復興を実現していく姿にも感銘を受けた。色々な顔を持つ「福島」について学びたい、という気持ちの赴くまま、ご縁のあった相馬市に2013年から移り住んだ。「敵は放射能ではない」という発信に始まり、診療を続ける傍ら健康被害や復興の状況など、学んだ出来事を手当たり次第に発信して今に至る。
発信を始めた直後から私はネット上で「御用学者」と呼ばれ、たくさんの批判をいただくことになった。国から金をもらうでもなく「自分でも気づかず御用学者をやっている可哀そうな学者」という意味を込めて、「エア御用」と呼ぶ人もいた。「エア」であるだけに証拠を挙げて反論することが難しく、うまいネーミングだな、とむしろ感心したものである。
私が(エア)御用学者と言われる理由は主に二つあるだろう。一つは、「国立環境経済研究所」「原子力産業新聞」のコラムなど、世間で「体制側」「原発推進派」と見做され得る媒体に発信を行ったこと。もう一つは、原発の賛否や福島における放射能の影響等につき、「正解はない」というどっちつかずの発言しかしなかったことだ。
発信媒体で派閥を決められてしまう、というのは、私が相馬市に住むまで全く知らなかった世界であった(だからエア御用と言われるのだろう)。しかしそれを知った後でも、発信媒体を変えようと思ったことはない。それは主義の問題ではなく、 ・・・


 2019-
2019-昨年に連載記事「放射能恐怖という民主政治の毒」を書き出して以来、私がポスト・研究費のために記事執筆をしているという根拠のない中傷を何度か受けた。実に馬鹿げているが、一部の人々はいまだにそうした煽りに騙されてやすいようにみえる。そしてこれ自体が、われわれの社会の未熟な点、さらにはひとつの病理を照らし出しているように感じる。
基本事項を確認するが、日本も含めて、科学の世界はブログ記事やツイッターの呟きを書いて職や研究費がもらえるような甘い世界では全くない。こんな自明なことを言わなければならないのは、やはり2011年に起きた「御用学者追放運動(パージ)」という異常な事態の余韻だろう。
●学者パージ
2011年福島第一原発事故後に、行政の不透明さ・無能さに人々が不信を抱き、批判したのは当然だったと思う。しかしなぜか「御用学者」というレッテルを貼る動きが科学者・専門家全体に拡大し、本来的検証の動きを阻害した。御用学者騒動は人々の怒りを盗んだのである。
この「御用学者」叩きは、以前の記事で詳説したように、1)クリス・バスビー氏関連と思われる団体が「御用学者発言撤回訴訟」を準備、2)専門家を吊るし上げる「御用wiki」サイトの出現、匿名あらら氏らが「エア御用」という言葉で全ての科学者に対する不信を煽ったこと等に始まる。
もっともこの御用学者パージに関わった人々のあいだでは、自分たちが科学者・専門家全体を攻撃している意識はなかったことだろう。ごく一部の「専門家」は、「市民の側に立った人々」という、これまた根拠のない思い込みに基づいて喝采・歓迎される一方で、本来的な専門家や社会へ科学を可能な限り正確に伝える仕事をする科学の翻訳家とでもいうべき科学者たちは言論空間から排除されていった。そうして生まれた言論に真空空間に、クリス・バスビー氏やヘレン・カルディコット氏らに象徴されるようなきわめて政治的な人々が入り込み、そこに科学の衣をまとった似非科学を据えた。
この似非科学運動が結実したのが、震災地からの瓦礫の持ち込み・焼却に反対する瓦礫忌避運動である(放射能恐怖という民主政治の毒5:「真実を語る人」 とチェルノブイリの亡霊を参照)。そしてこの瓦礫忌避運動は、もともとが似非科学に依存していただけあり、科学的ではない放射線への恐れ=すなわち穢れとしての排除=そのものであった(3)。この運動は狭い日本を「穢れた被災地」と「穢れていないその他の地域」の二つに分け、そうして日本社会を分断した。
いまなおこのような幻影を標準と考え、誤った知識を科学と信じている人がいることは、実に大きな社会問題である。
今から考えるとこれら学者叩きの動きは、まるで初めから社会の分断とデマの固定化を意識的に目指していたかのようである。放射線問題で、科学者・専門家が萎縮してしまうと、社会はその問題に対応する専門的能力を失う。全ての専門家に敵意と不信をもつことは、人々が自らの右腕をもぐ作業に等しかったのである。
●社会における科学者
それでは本来、社会にとって科学者に存在はどういう意味をもつのだろうか。科学者にとって社会で生きていることにはどんな意味があるのだろうか。
そもそも社会からみれば科学者とは、我々の社会が科学的問題に対応する能力を持つために投資して育成した人材である。すなわち科学者は、科学的問題に対する社会の分業機能であり、社会の専門能力を体現する。そうした専門家全般への不信を煽ることは、社会の問題解決能力を麻痺させ、文明を退行させる行為なのである。長い歴史の中でようやく築かれ、社会が多大な投資をして日々維持している機能をみずからゴミ箱に捨てる行為なのである。
科学者からみれば我々は社会に恩義がある。自己の人生を科学の探求に費やす機会を社会からもらっている。我々科学者が権威主義にあぐらをかき努力を忘れてしまったら、科学者としての内実を腐らせ、自らの堕落によって社会の専門機能を低下させる。だから権威主義による怠慢は、社会に対する背信なのである。科学者は、それぞれの持分で科学者としての使命を果たさなければならない。
「博士」という言葉はまるで到達点のように思われることがあるが、実のところ科学者の一生にとって博士課程における修練ははじまりに過ぎない。科学者として大成するためには、独自の研究分野を見つけ作り出し、研究成果を出し科学の発展に寄与し続けることで世界の同業者内での評判(reputation)を積み、やがて学会内のリーダーとして研究を牽引する立場になっていかなければならない。これが科学者として地に足がついた進むべき道だろう。そしてこれは数十年かけてたどる道のりなのである。
原発事故で旧来の権威主義は死んだ。だがこれでよかった。我々が科学者として研鑽を積み道を極めるために権威主義は邪魔だ。今後の科学者は、科学の世界で自らの立場を確保するのと同じようにして、社会において自らの使命をまっとうする努力によって社会からの信頼と尊敬を勝ち取るべきなのだろう 。
こうした専門家と社会のあいだの健全な関係のためには、相互の信頼関係が必須である。社会にとっては、科学者を活用することで科学の力を使って問題解決に当たらなければならない。それができる社会になるために、科学の専門家を養成して、自らの右腕としていかなければならない。科学者にとっては、社会における自らの役割を自覚して、自分の持分においてプロの仕事をしなければならない。こうしてこそ社会は専門分化した機能を獲得し、より効率的に問題に対処できることになるはずだ。だから相互の信頼関係を崩そうとするものに対しては=それが専門家の側であれ、社会の側であれ=毅然とした態度で臨み、一線をひくべきところは迷いなく一線を引く必要がある。だからこそ私は「御用学者」というレッテルをはることで正統な学者を追放する誤った運動を、未開への退行として強く批判するのである。

福島原発事故以降、「御用学者」という言葉がはやった。バズワード(意味の曖昧なイメージの強い言葉)だが、「政府べったりで金と権勢欲のために人々を苦しめる悪徳学者」という意味らしい。今は消えたが2012年ごろまで「御用学者リスト」(写真)がネット上にあった。卑劣にも、発表者は匿名で名前を羅列した。それを引用し攻撃を加える幼稚な輩もいた。(消されたが小規模に再開されている。匿名のまま・リンク)
私も大物ではないのに「御用ジャーナリスト」として名前があがった。私は原発を活用すべきという意見だ。また2011年から原発事故問題で福島に健康被害はないと繰り返した。そのためか今でも罵倒される。私は反骨心をたたえられる記者という職業で、性格もあるのだろうが、批判には逆に闘志がわいた。
ところが、ここに掲載された組織、学者に聞くとショックを受けたそうだ。そういう知的エリートは、程度の低い人にののしられる経験がないため、ネットの罵声に恐怖を覚えたらしい。これをはじめとした感情的な反発に、専門家は沈黙してしまった。それが理性的な意見を潰し、福島のパニックを長引かせた一因だ。はやりの言葉を使えば「反知性主義」が原子力・放射能問題で広がった。
そして原子力規制の分野では「御用学者」を排除した結果、大変な状況になっている。これはあまり一般に知られていない。
●規制委は批判をまったく受け付けず
規制委員会では、活断層の判定問題が混乱している。規制委の新規則では活断層が原子炉の下にあったら使えないとする。工学的対応は可能なので、この規則も問題だ。
規制委は有識者会合をつくり、そこに集めた地質学者に活断層の存在の判定を委ねた。日本原電敦賀発電所2号機では、13年初頭にそれが原子炉の下にあるとした。同原子炉は廃炉に追い込まれそうな状態だ。
この学者の選定には問題がある。規制委員会は12年9月の発足直後に、活断層調査になぜかよく分からない情熱を示した島崎邦彦委員(現在退任)の要請で、関係学会から推薦を求めた。そこで「これまで国の規制にかかわらなかった人」という条件を付けた。「御用学者」批判を避けるためだろう。
呼ばれなかったある学者は人選に次のように述べた。「地質学は地震国日本で行政の防災活動と密接にかかわる以上、国と関係のない学者は何か問題のある人、もしくは政治活動家の可能性が多い」。
これが地質学会全体の意見か、そして事実かは分からない。しかし非御用学者の主導した活断層の判定問題は現在、混乱中だ。日本原電は猛反発している。このままでは行政訴訟になりかねないだろう。
ピア・レビューという、新しい視点から専門家が再評価する取り組みが学術論文などで行われる。そこでは修正もされる。今回規制委は2回ピア・レビューを行った。そこでは専門家から判定に疑問が噴出した。「科学的でも技術的でもないですよね。それはもう明らかに何らかの別の判断が入っている」(国の研究機関の研究者)「(資料の不備を指摘して)現場でちゃんとチェックされたんですか」(京大名誉教授)などの批判があった。ところが規制委はこれを参考にしないという。
日本原電は海外の2チームに調査を委託。いずれも「原電の主張が正しい」「日本では専門家と事業者の対話が必要だ」とした。調査メンバーで、活断層研究の世界的権威である英国シェフィールド大学のニール・チャップマン教授は、地球物理学研究では世界の中心的な学会誌である米国地球物理学連合学会誌「EOS」95号(14年1月発行)に、同趣旨の論文を掲載した。ところが規制委はこれも無視した。
ある研究者は、「チャップマン教授は言外に、日本の規制委員会は無能、判定を下した学者はおかしいと言っている。こんな論文を書かれたら、私なら学者生命が終わるので、蒼くなって反論をするか意見を修正する。『日本ガラパゴス』にいる活動家は、自分のおかしさに気づかないし、学者生命に関心がないのだろう」と嘆いていた。
●「穴掘りおじさん隊」の正体
なぜ頑迷な判断をするのか。規制委の有識者会合に参加した地質学者たちの政治信条が影響している可能性がある。「御用学者」と騒ぐ人のように、レッテルを貼って人を批判したくないのだが、事実を示そう。
敦賀の判定にはかかわらなかったが、別の認定にかかわる東洋大教授のW氏は反原発派の集会に参加。活動家の小出裕章氏と共著を出していた。そこには「六ケ所再処理施設に津波が襲い施設が壊れる」という趣旨の文章があって筆者は吹き出した。筆者は現地にいったが、再処理工場は高台につくられ標高は50メートル程度あり、海から3キロほど離れ、地盤も堅固で、そんな事故は起こりそうもない。現地を見ないで書いているのか、想像力が大きすぎるのか。
敦賀の判定の座長の名古屋大教授S氏の名前をネット検索すると、社民党の福島みずほ氏の勉強会、懇談会、集会に頻繁に呼ばれ、原発の危険性を福島事故前から強調していた反原発派だ。敦賀判定メンバーの学芸大准教授F氏の名前を検索すると「高校無償化措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教授の要請書」「会見に反対する大学人ネットワーク呼びかけ人」「教育基本法改正案の廃案を求める声明」などに署名している。左翼的な政治活動の好きそうな人だ。
彼らの政治信条が、理性的に行うべき地質学上の判断をゆがめている可能性が高い。彼らは活断層調査で、原発周りに巨大な穴を電力会社に掘らせ、全国を見回っている。電力業界内では「穴掘りおじさん隊」と呼ばれている。電力会社は彼らが活動家であると知って、この言葉の裏には敵意と軽蔑を込めているようだ。理性的に話し合うべき事業者と行政が感情的な対立状態になっている。
●「反プルトニウム」の政治信条
実は田中俊一規制委員会委員長にも疑惑がある。旧原燃で左派色の強い組合活動をしていたという週刊誌報道があった。これよりも問題は、彼が原子力の研究者のコミュニティで、昔から「反プルトニウム」を公言していたことだ。各国の物理学者の間では、反核・平和運動に熱心な人たちが、核兵器の原料になるプルトニウムの利用に反対してきた。そして日本政府はプルトニウムの利用を行う核燃料サイクル政策を採用している。それを以前から、止めようとしていた。
田中氏は発言を見るとしっかりした見識を示すこともあるのだが、原発の再稼動で混乱を放置している。「おかしな人ではないはずだ」と、そのちぐはぐな行動を不思議がる関係者が多い。
原子力政策の知識のある人には分かるのだが、田中氏の意向なのか、核燃料サイクル政策を妨げる、細かい決定が次々と行われている。六ケ所再処理施設の安全基準見直し、もんじゅの急な検査などだ。そして田中氏は電力会社と非常に対立的だ。彼の政治信条が、判断をゆがめている可能性があると、筆者は思う。
●「御用学者」批判を超えて
「御用」という変な言葉に、人々が2011年から今まで人々が踊っている。その悪影響が原子力規制の分野で、醜い形で現れている。「御用」を追い出したら、政治色の強い人が入ってきた。さらに感情で動く政治家が民主党政権下でこの問題に介入したために、さらに混乱を広げた。
確かに原子力の専門家は福島原発事故で失敗した。それは批判されるべきだ。そして日本のような高度な産業化社会では、専門家が産業界と結びつくし、経済的利益で社会的に重要な判断がゆがめられる危険は常にある。原子力では癒着と形容できるものもあっただろう。だからといって排除という行為は、紹介した実例を見れば、新たな混乱を生んでいる。
原子力で起こった問題は専門性が進む現代社会で、どの分野でも起こりかねない問題だ。知識を持つ層と一般人の乖離が深まると、さまざまな危険がある。専門家は実は無能である可能性がある。しかし、専門家の否定をすれば、ポピュリズムが意思決定に入り込み、それが反知性主義や政治活動に毒され、これも適切な判断をゆがめるかもしれない。
私たちは今、こうした問題を原子力規制で体験している。数人の地質学者の問題の多い判定で日本原電はこのままなら倒産に追い込まれかねない。原発は1プラントの工事費は約2000億円。それが潰されれば、国の行為である以上、国が責任を負う。その負担は国民の税金だ。そして代替電源が必要になる。結局、一部の反原発活動家が満足するだけで、国民の誰もが損をする。
潰されかねない敦賀原電2号機。今作れば2000億円程度するだろう。
当たり前の事を述べるが、解決法は「御用学者」と叫んで、専門家を排除することではない。検証と修正の仕組みをつくることだ。それには情報の公開、そして批判を受け止める仕組みの整備と、社会全体の知性と判断力の向上が必要だ。
そもそも私が述べたように、日本の原子力規制行政が、左派色の強い一部の人の政治信条でゆがめられているという事実は、右派の人、いやどの立場の人も当然、問題視するはずだ。しかし、この情報はあまり知られていない。だから是正の動きが強まらないのだ。情報の流通を自由に、そして質の高いものにすることが必要な理由はここにある。
感情を可能な限り遠ざけ、理性的に未来を選択することを、私たちは忘れていないだろうか。

2011年3月11日の東京電力(株)福島第一原発のシビア・アクシデント(以後、簡単に3.11事故と記す)ほど科学や技術が社会において大きな役割を果たしていることと共に、また同時にそのあり方に問題を抱えていることを示したものはない。事故後、テレビ等のマスコミに登場した殆どの日本の原子力専門家は、欧米の専門家等とは異なって事故規模はたいしたことはないとか、「メルトダウン」などはあり得ないと従来の「絶対安全論」的視野からの解説に終始し、政府関係者と足並みを揃えるかのように「風評被害」論に重点を置いていた。ある専門家は、現実に炉心溶融が起きていた時点でもそれを否定し、テレビ司会者の「メルトダウン」という語の使用の仕方にまで専門用語を駆使して反駁し、事態が深刻な状態に陥った現実自体を直視することから眼をそらせようとさせた。
欧米の専門家やメデイアが事態の深刻さを指摘する中での、事態の過小評価や「想定外」を口実にする専門家たちの反応は、当然ながら一般の反発を受け、「御用学者」や「原子力ムラ(村)」の用語がメデイアや巷にあふれた。インターネットでは、「御用学者リスト」が飛び交った。リストの中には、とても「御用学者」とは思えない人名まで含むものもあり、科学者の主張や意見が正確には社会に伝わっていないことも伺わせた。しかし、3.11事故後の諸科学者団体の諸声明もまた、科学・技術(者)に対する国民の期待に応える精神からほど遠く、科学的精神からも疑問を寄せられ、科学者の倫理的問題と、その事実実態に関する「専門的知識」の正確さが鋭く問われることとなったのは確かである。
事故直後のSPEEDIによる放射性物質の拡散予測が住民に秘匿され、本来は受けなくともよい放射線被曝を被ったことをはじめ、事故後3年を迎えようとしている現在もなお避難解除の放射線量や被曝線量をめぐって住民は翻弄されている。科学者は低線量の被曝の有害性が「科学的に未知」であることを理由に、現行の住民翻弄の行政体制を容認して良いのであろうか。科学者は突きつけられた問題解決に向かって、「解決のための研究体制」をどのようにとっているのであろうか。
総じて、科学や技術、そして科学者技術者が現代社会内でどのように機能しているのか、どのような状態になれば国民の期待に応えられる科学と社会の相互関係を築けるのが鋭く問われている。事態の打開を見いだす視点をさぐる作業として、科学・技術の社会的存在形態の視点と科学者技術者の二重性について視点を向ける必要があることを述べたい。
●2.近年の科学・技術と社会の関連に関する2、3の議論をめぐって
科学・技術が社会の中でどのように発展・展開していくかという問題や、その社会との相互関係問題は、科学史技術史研究にとっては根本問題の一つであり、科学・技術の内的或いは外的規定性や外的(社会的経済的)基盤、技術ウクラード、帽子のかぶり直し論、パラダイム論、相対主義、ストロング・プログラム(科学知識の社会学SSK)、諸々の社会構成(構築)主義論、東洋の科学西洋の科学論等々多種の議論が展開されてきた。
そして今日、東京電力の3.11事故以後は、A.ワインバーグが1972年に展開し、2007年に小林傳司氏に紹介された「トランス・サイエンス」論が盛んである。
トランス・サイエンスとは、「科学に問うことはできるが、科学だけでは答えることができない問題群」と言われ、ワインバーグが問題にした原子力発電所の多重防護の安全監視システムについて科学ではどの程度まで徹底すべきかの答えは科学だけでえられないというように、原発の安全性の問題はトランス・サイエンスの代表的な問題として「科学だけでは解決しない原発震災〜トランス・サイエンス問題」というようなフレーズが諸処で話題にされている。
トランス・サイエンス論では、科学では「決められない」から、市民の声を反映させなければいけないという論理になる。これと同じく、「現場」の科学・技術に「外」から規制する必要があるという論に、ガヴァナンス論がある。これはS. Fullerの議論等が元になっているが、科学・技術のあり方を外的(社会的)に、あるいは中から統治すべきだというもので、例えば、「チッソの技術、技術のチッソ」と、かっては日本における先進的な技術開発の旗手チッソ(株)の起こした最悪の公害病である水俣病も、「ガヴァナンスに失敗した典型である」とされる。
確かに、現実の技術実態はすべて科学的に、あるいは科学理論に基づいて成り立っているわけではない。3.11事故当時の原子力安全委員長の班目春樹・東大教授(当時)は、浜岡原発をめぐる裁判のなかで「非常用ディーゼル2個の破断も考えましょう、こう考えましょうと言っていると、設計ができなくなっちゃうんですよ。(中略)だからどっかでは割り切るんです」との証言(2007年2月静岡地裁)のように、現実の技術実態には、科学的には説明できていないことが含まれている。科学的には説明できるが、科学的には実際は処理できていないものや、班目教授が言うように原発初期には応力腐食割れの問題は知られていなかった問題もある。
しかし、ガヴァナンス論やトランス・サイエンス論で事故を解明するには大きな問題がある。一つには、「科学が答えを出さない(出せない)」というのは何も今に始まったことではないし、もう一つは「科学が答えを出さない」から事故になったのであろうか。答えはノーである。前者について言えば、例えば科学技術社会論者の好む「科学技術」が始まる時代の前の産業革命時でも、新しい機械の採用については何も科学(者)が「可とか不可とかの意思表示」(つまりは答え)をしたわけではない。しかし、新しい「ジェニー機械が採用される毎に5人から6人の労働者が馘首され」生活の手段を失ったのである。蒸気機関は既成の道路運輸業者や水上運輸業者の生活の糧を奪い、機械に基礎をおく工場制度の進展によって深刻な社会問題が発生した。機械の採用、不採用は科学の論理ではなく、資本(資本家)の論理が下したものであった。
そして、「昔」から現実の技術には、科学的理論に基盤を置いている部分はあるにしても科学的には、説明できていない部分、経験に依拠している部分、未知の部分がある。班目氏の言うように、「だから、安全率」をかけているのである。該当委員会や組織が責任を果たしたかどうかは別にすれば、現実の技術は氏の言うとおりである。
しかし、班目氏の誤算は、「安全率」を超えれば、氏が2005年のビデオで発言しているように、単に「原発が停止」するだけではなかったことである。3.11事故発生後、首相から爆発の可能性を問われて「ない」と答えてまもなく水素爆発が起きたとされるが、そのときに氏が意味不明の感嘆詞を発した反応は、3.11事故に至るまでの日本の原子力関係学者の特質を象徴的に表したもので、まさに原発史を象徴する一瞬であった。
彼らに欠けていたものは、技術は体系的なものであるとの認識と、その現実の体系に関する知識(科学的知識)であった。「原子炉は、格納容器に囲まれ、さらにコンクリートで防御、そのうえに建屋で覆う深層防御構造になっている、中性子反応特性もマイナスであるので安全。これを疑うのは非科学的」と学生に繰り返したさる教授には、格納容器が破壊されていないのに大量の放射性物質が放出される事態を説明すべも無かろう。
他方、科学のガヴァナンス論がいう「水俣病は、科学のガヴァナンスの失敗の典型」という断罪の仕方は、見当違いもはなはだしいと言わざるを得ない。科学的には水俣病の原因は徐々に明らかにされていったし、たとえ科学的に原因説明が無理であったとしても、漁業禁止あるいは汚水である工場排水放出の停止をすれば拡大を食い止めることはできたはずである。科学的な説明を隠蔽あるいは排除し、拡大を防ぐための行政処置が石油化学工業育成のために通産官僚たちによって確信犯的に妨害されたことによって水俣病が拡大されていったことが事の真相であったことは、当の官僚たちの回想によってさえも明らかになっている。正しい理論は間違った理論によって「中和」され、東工大清浦雷作教授(当時)や田宮委員会などの有名有力教授を動員して真なる因果関係の発見や実験結果は隠蔽されたりで、科学は彼らと工場経営者によってガヴァナンスされていたのである。彼らにとってはうまくいったのであり、これを「ガヴァナンスの失敗」と総括するのは、国と企業の犯罪的行為を隠蔽するに等しいといわなければならない。
●3.原発訴訟や公害と科学者・専門家
科学・技術の社会的問題に関する議論が混迷している根本は、単に科学が自然現象すべてを説明できていないことに諸問題の原因を求めるやり方だけでなく、科学と技術を一緒くたにし、それらの社会的存在形態、そしてそれらに関係している科学者・専門家たちの社会的存在形態を直視しないことに起因している。科学者や技術者は社会的な存在であり、社会的な属性をもつ。そこから社会的な諸関係を結ぶことも、また社会的な「評価」を受ける面が生まれる。
他方、現実の科学(技術)が、社会内において機能する過程は、科学的な活動であると同時に社会的な活動でもある、すなわち社会的な諸関係にも規定されている。だが、第一に社会との関わり方、規定関係は、科学と技術では異なっている。科学は、例えば資本との関わりが必ずしも直接的ではなく相対的に独立している場合が多いが、技術の活動は資本的活動そのものである。第二に、科学・技術の諸分野や個々の科学的知識・個別技術の社会的諸関係は異なった社会的諸関係を結んでいる。農民を鉱毒から守るかどうかということでも近世の政治関係は、農業・農民をより重視したが明治以降の富国強兵体制は、科学(医学者)が足尾銅山に鉱毒の原因があることを明らかにしたにも拘わらず、農民より銅山業(者)を守ったのである。科学者でも、医学者は原因解明を厭わなかったが、政府行政に強く包摂された当時の直接的専門家の鉱山冶金技術者は沈黙を余儀なくされるか、あるいは因果関係を正面から受け止めず鉱山(業者)の立場に立った。今日も、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門をめぐっては、漁業者と営農者という異なる社会的関係者を巻き込ませているが、本問題はそもそもの国の公共事業における失政に端を発しており、いずれも「科学が答えられない」から問題となったわけでもなく、科学のガヴァナンスに失敗したからでもない。
利害関係経済関係の絡む諸社会的の中に身を置く人間が自分の活動に必要な「科学」的知識を活用し、また科学者を動員しているところの構造把握が必要であろう。その際、既存の科学的知識では、社会関係でいうところの執政側と住民側ないし被害者側に仮に分けた場合に、被害者側のいう真実を明らかにし得ない場合が多い。科学的活動は、科学文化行政や研究体制、さらには人間の諸活動自体の中にあり、したがって科学的活動の成果たる科学諸理論・科学知識は、「偏在的」で「不均等発展」している面も多いからである。1960年代の三島石油コンビナート計画においては政府委嘱の産業調査団(黒川調査団)がコンビナート推進の立場から展開した「科学的知識」に対して、住民は当初は対抗する科学的知識を持たなかった。しかし、医療分野をベースにした松村調査団や住民自らの調査によって、黒川調査団の非科学性が明らかにされていった経緯もある。
そもそも、いわゆる四大公害といわれる水俣病、新潟水俣病、四日市大気汚染、イタイイタイ病において、企業側を支援した科学者の理論が、いずれも誤謬であったのはなぜか、またそれは何を意味しているのか。しかも、企業側からは、「駅弁大学の先生」のいうことを信ずるのか、「中央の有名大学の先生」を信ずるのかという人身攻撃的中傷が絡められたのも特徴的であった。
こうした社会の中での科学と科学的知識を鳥瞰するならば、科学・科学的知識の社会内における存在形態問題が浮揚するであろう。そこには、どんな科学・科学的知識が誰によって「所有」し「利用」されているかの問題も付随している。
●4.3.11事故後と科学(知識)の社会的存在形態
科学(科学的知識)とその利用方法が、政治的社会経済的に規定され、科学の利用は万人に平等に与えられてはいないことは、3.11事故後にも過酷事故、事故後の処理、住民の避難や安全確保をめぐって明瞭になった。その象徴的事例として、SPEEDIによる放射性物質拡散予測は、住民に知らされず拡散方向に避難した人々を無用の被曝に晒したことが知られる。SPEEDIの運用者・所有者の、後のいかなる弁解も、その正当性を見いだすことはできまい。
帰還区域の線量値設定の妥当性をめぐっても1 mSvから20 mSvの間で諸種の議論が交わされているが、これも低線量被曝の人体有害性が科学的に明確でないから線量値の設定が揺れているのではなく、実際の議論の順序は逆で、(経済的政治的に見て)どの程度で帰還させるべきかの政治的判断が先にあり、そのあとで、「その値で安全である」と「科学的に説明」されている。そのために科学」と科学者が動員されているのが実情である。そもそも一般人の被曝「許容量」は、ICRPの勧告では計画時は1 mSv以下であるはずで、現行の政治はこれを緊急時の20 mSvに置こうとしている。まさに、許容量とは、科学的な判断によるものではなく社会的な許容量であるとは、かって武谷三男が喝破したところである。科学者が、こうした政治的要請に応じるところからいわゆる「御用学者」が生まれたり、御用学的な活動に組み込まれたりする。
科学的知識は本来、断片的に発生し、最初は論文になっていない場合も多い。にもかかわらず、既成の理論や過去の権威を笠に着て最先端の現場で住民を守ろうとしている若手研究者を否定したり、長崎での被曝治療に貢献した経験をもつ科学者(医学者)でも、多くの間違いを犯したのは否めまい。既成の知識でもって、初期データ段階の新たな経験的知識に対して、「書かれた論文」がなければ科学的でないと抹殺排斥したり、現場での実際の被曝値を知らず頭から被曝量は少ないので甲状腺被曝を防ぐためのヨウ素服用を否定した「長崎から来た重鎮」も目に余った。
こうした3.11事故後の科学者と政治の動きからは、トランス・サイエンスとして捉えるより、まず社会内で科学と科学者がどのような社会的関係にあるかを分析することの方が本質的である。すべての科学的知識は、原子力三原則にも拘わらず、私有物であったり、公共的性格を有していても公開的ではない。東電の事故時の運転作業手順書は、国会関係に公開されたときでさえ黒塗りであったし、事故調査委員会の調査に対し、重要な部分を暗く危険であるからという虚言でもって隠蔽した。知識が私有物性は科学的な分析を制約しているのである。特許も、知的財産すなわち私有物とされ、大学でさえ特許取得と知的財産保護が推奨される。かってウラン研究の先陣をきったキュリー夫人は、科学知識は万人のものであるべきということから特許を申請しなかったが、科学の公的性格・普遍性と私有制度が、どのように調和すべきかを検討することは今日の焦眉の課題の一つであろう。
●5.科学の社会的存在形態と科学者の二重性
科学的知識が、誰もがアクセスできる公共財産的性格や私的財産として、あるいは公共的といわれるものの軍隊や特定政治家のみがアクセスできるもの、あるいは公共的であるが特定の科学的手段がなければアクセスできないもの等様々な形態をもち、それらが総体として現代科学を形成しているように、科学者研究者もまた先に一部触れたように社会的に規定される側面を有する。たとえば、彼らは大学の研究者であったり、企業内部の研究者であったりするように社会内での存在形態、簡単に言えば社会的な地位と身分が異なっている。そして、その社会的属性が、科学者研究者の評価に影響を与えることがことを複雑にする。本来、科学者研究者は、彼らの研究業績で評価されるべきであるが、この社会的評価が研究面での評価と絡み合い、科学者研究者は、研究面での評価と社会的位置での評価という二重性を体現することになる。「駅弁大学の先生を信用するのか、中央有名大学の先生を信用するのか」という水俣病をめぐっての企業側の言い草がまさに、このことを表している。
新しい事件や自然現象には既成の理論では説明できないかもしれない新しい未知のデータが含まれており、それを発見することが科学者の仕事であることを忘れ、頭から余所(チェルノブイリ)のデータを押しつけ、福島での多量の被曝線量に目をつむり、被曝線量の現実実態を明らかにし、被曝線量を少しでも減らす方策をせず、ただ「ニコニコする」ところに福は来る式の姿勢がどの程度の科学性を持つのかに、医学者はなぜ批判を向けられないのかが最も大きな問題である。科学者医学者の社会的存在(身分)形態と科学(科学的知識)がどのような結びつきを持つのかが問われる。
チェルノブイリでは、個々の科学者が果たして信頼に値する知識を有するかどうかは別にして「ナガサキから来た」といえば信頼されたというが、これは個々の科学者が看板を背負っている、すなわち社会的な存在からの規定が機能していることを示すものでもある。
ことがさらに複雑なのは、先に述べた様に四大公害裁判で、企業側に立った「中央有名大学」の教授たちがことごとく誤謬論を振り回したことである。
もちろん、中央の有名大学の科学者たちが常に間違った理論を振り回していると言うものではない。だが、それらに相互関係があるのかないのか、どんな時に公害裁判の例のような事象が発生するのか、検討に値するものがあるのではなかろうか。
一定の社会的結合関係の中にある科学者が、科学性を貫くには何が求められるかが根本的問題であるが、被災者被害者の立場に立つことが、事実を徹底的に明らかにする一つの試金石であったことは、多くの犠牲者を出した公害の歴史が示したところである。
諸論が、「原子力ムラ」を論じる中で、田中原子力規制委員長は、この言葉は安易に使うべきでないと嫌う(朝日新聞)が、確かに「レッテル張り」では事を解決しないし、むしろ本質を隠蔽する。ただ、いわゆる「御用学者」が、科学的な誤謬説を振り回し、加害企業を擁護してきたことも歴史の事実である。行政においても科学者を利用した「審議会」を多用するが、ここにも科学(科学者)のガヴァナンスが機能している。
現代科学者技術者に問われている倫理は鋭く、そこには、科学活動行為における倫理性だけでなく、現行研究体制では未知未解決の問題に対する科学・技術研究体制が必ずしも構築されていないことへの科学者技術者としての能動的責任、さらには自己の社会規定性に関する省察もまた問われていることを肝に銘ずるべきであろう。

これまでは一般には脱原発派の宣伝用語とされてきた「原発安全神話」が、福島原発災害という未曾有の事態を経て、国民の間で日常語として公式に認定されることになった。同時に、この神話を語る神官の役割を果たしてきた「御用学者」たちがやり玉にあげられ、批判されている。当然の成り行きだが、しかし「御用学者」とは何か、われわれ一人一人にその要素はないのか、と考えると、幅広く深い問題提起でもあることが分かる。
「御用学者」とは、権力や権益のために科学的真理や良心をおろそかにする学者、と仮に定義してみよう。そうすれば「御用学者ではない」と自信を持って断言できる人は少ないのではないか。つまりは程度問題ということだろう。
あるいはそれほど意図的でなくても「組織の論理」によって、また人間としての弱さから、科学的妥当性や良心に百パーセント一致しないことも不本意ながら実行せざるを得ないこともあるだろう。そのような局面ではある意味で「御用学者」として振る舞っている可能性がある。つまり、これはすべての研究者にとっての、またすべての活動の局面に関わる問題である。古文書『葉隠』も「又学問者は、才智・弁口にて本体の臆病・欲心などを仕隠すもの也。人の見誤る所也(聞書第一)」と学者の狡さと弱さを見抜いている。
本稿では前半で、当面最も問題とされるべきと考える「御用学者」への批判を試みる。次に後半では、それが生み出される背景や同僚からの批判もなく放置される原因など、現在の国立大学が抱える構造的要因について、特に国立大学の独立行政法人化に伴う問題について論じる。
●1 新たな「安全神話」と御用学者
「原発安全神話」は決して消滅したわけではないが、福島県を中心に多くの住民が被曝を強いられ、また食品汚染は全国的に心配されるという状況では、これに取って代わって出現した「放射能・放射線安全神話」が国民にとっての現在進行中の脅威である。原発問題と同様に集団間の利害対立に深く関わるため、また「ただちに健康に影響しない」場合が主であるため、その神話性は公式に認定されていない。それどころかこれから猛威を振るおうとしている。したがって、この問題こそが現在のせめぎ合いの中心であり、研究者の批判活動は当然この問題と、この新しい神話の媒体となっている「御用学者」に集中されなければならない。原発安全神話のように、大惨事を経験しなければ社会に認知されないということを繰り返してはならない。
この「放射能・放射線安全神話」で最も重大な役割を果たしている学者の一人が、長崎大大学院教授の山下俊一氏である。原発事故後まもなく福島県知事の要請で福島県放射線健康リスク管理アドバイザーに就任し、ただちに県下を巡回して、放射線に対する住民の警戒心を解除するような講演を行った。そのあと福島県立医科大学副学長に就任した。
山下氏が不当に住民の警戒心を解除し、そのために被曝を拡大することになった彼の発言はいくつも知られている。講演を聴いた人による書き起こしなど、ネット上には多数の発言が報告されている。ここでは、公的な機関のものを拾ってみよう。
「1度に100mSv以上の放射線を浴びるとがんになる確率が少し増えますが、これを50mSvまでに抑えれば大丈夫と言われています」
「原発から10kmから20kmの圏内にいて避難した人は、放射線量で1mSv程度浴びたかもしれないが、健康に与える影響は、数μSvも100mSvも変わりがない、すなわちがんの増加頻度に差がないのです」
(いずれも一般社団法人サイエンス・メディア・センター、3月22日の記事)
このように、「100mSvまで安全」と言いふらしたため、「ミスター100ミリシーベルト」とあだ名されることになるが、実際には100mSv以下でもがんのリスクが存在することは、ラドン222の影響についてのWHOやICRPの見解1-2)で明らかである。
これらの文書によると、このがんのリスクに対応する線量のレベルは1 mSvのオーダーである。このような事実を山下氏が知らないはずはない。また、外部被曝に限ってということでもない。「こども健康倶楽部」の昨年6月29日のインタビューで、「外部被曝も内部被曝も基準が一緒」と答えている。それとも、アルファ線やラドン222は例外とでもいうのだろうか。
仮に「100mSv以下は安全」が彼の個人的見解だとしても、それをわが国の放射線安全管理の法律とその前提とを無視して、公的立場で発言することが許されるはずはない。学会発表とはわけが違うのだ。わが国の法律はICRPの「閾値なしの線量―効果比例関係」、いわゆるLNT仮定に基づいて、公衆の追加的被曝の限度を年1mSvと定めている3)。このことを無視した住民への「アドバイス」活動は違法性の疑いさえあるだろう。(実際、氏は広瀬隆、明石昇二郎の両氏によって刑事告発されている)。
このような事実や文脈に照らせば、同氏の「放射能の影響は実はニコニコ笑っている人には来ません。クヨクヨしている人に来ます」という言葉も、決してたとえ話や精神訓話とみなすことはできない。山下氏は、副学長に就任した福島県立医大の入学式のあいさつで学生に、放射線について「世界一の学識」が得られると述べたと伝えられる。もし、避難者を少なくすることでより多数の被曝データを得たいという意識が彼にあったとすれば、現代の「731部隊」と呼ばれることになるだろう。
住民の追加的被曝の罪に連座する学者たちは他にも多数いる。12月22日に長瀧重信氏らを共同主査とする「有識者会議」は、年間20ミリシーベルトを避難区域の設定基準としたことを追認するだけの報告書をまとめたが、この会議メンバーも該当するだろう。(避難のリスクと被曝によるリスクとの競合を考えることは当然だが、この報告書には突っ込んだ議論はまったく見られない)。
●2 「科学僧官」宣言?
はじめに述べたように、分野内外を問わず、科学者の間での相互批判の欠如が問題だが、しかし前記の「有識者会議」の長瀧重信氏はこれとまったく反対のことを主張しているようだ。業界誌『医学のあゆみ』239巻10号(昨年12月3日)は「原発事故の健康リスクとリスク・コミュニケーション」と題する特集を組んでいるが、長瀧氏による「はじめに」の文章には、放射線の影響についての国連科学委員会などの「国際合意」について次のようにその至高性、独占性を主張している。
「この科学のみ(個人的、政治的、社会的主張にではなく)に基づいた国際的な合意に間違いがないとは言えないが、この合意に対抗できる研究結果をもつ、あるいは反対の論拠をもつ個人の専門家は世界のどこにもいない。したがって科学者は、個人の主義主張とは別に、この国際的な純粋に科学的な合意を一致して社会に説明する義務があるのではないかと考える。」
学者の組織であれば、集団や個人の社会的背景などから完全に独立して、論理的・科学的な要因だけでその合意や結論が出てくるとでもいうのだろうか。もしそうなら科学者は聖人ということになろう。さらに彼はこの「合意」を絶対化し、
「様々な主張が科学の名前で社会に直接に伝わることで混乱をまねく状況下では……社会に対して発せられる科学者からの提言は、一致したものでなければならない」
と述べる。そしてこれに異議を唱える者を次のように排撃する。
「非専門家が、様々な自分達の政治的、社会的、その他もろもろの立場からの主張を科学という衣を着せて発表し、その間違った科学をマスコミ(一部の)が宣伝しているようにみえる。」
「科学という衣を着せて発表」するという「非専門家」が具体的に誰を指すのか訊いてみたいものだが、この、権威付けられた科学者の組織とそれが出す結論とを絶対化する態度は「科学神官」、「科学僧官」と名付けられ、これによるシステムは「科学者独裁」、「専門家独裁」と呼ばれるのがふさわしいだろう。
古代においては、王の権威を理論づけ、祭式のプロトコル(儀典)を独占する神官や僧官が知識人として支配の不可欠の道具であった。専門的・科学的な知識なしには成り立たない現代の国家・社会では、国家によって認証され、権威づけられた科学者集団がこの役割を果たしていることは疑いない。
つまり「科学者独裁」、「専門家独裁」の要素はすでに社会に組み込まれているのであり、もし民主主義を信奉するのであれば、これが実質的独裁にならないような歯止め、対抗策を常に準備し、実行しなければならないはずだ。「すべての科学者は“合意”に従え」という長瀧氏の論理はこれとは逆に、まさに独裁徹底宣言そのものである。
もしこの「科学神官」、「科学僧官」制度に与しないのであれば、今回のような論争的課題では科学者間で激しい議論が起きてしかるべきである。ところが実際には、山下氏のような学者の言動に対し、大学社会からのあからさまな批判がまったくといっていいほど見られない。いわば“ピア・レビュー”の不在である。放射線防護など同一の専門分野の人たちの責任が最も大きいが、核物理や放射線医学など隣接分野も同様だ。
●3 「安全神話」問題からの一つの教訓
このような批判不在の状況や「御用学者」発生の原因や背景について議論する前に、原子力問題についての日本と米国の物理学会の対応の大きな違いについて指摘したい。物理に限らず学会一般のありかたを考えるうえでも示唆的な事例と思われる。
米国物理学会は1975年と1985年に、原発の炉心溶融事故について研究し、詳細な報告書を公表している。アメリカの物理学者は、原爆開発の一環としての原子炉開発に当初からかかわり、むしろそれをリードしてきたという歴史が背景にあるのだろうが、それから30年以上も経てば「業界」ごとの専門化は相当進んでいたはずだ。
これに対してわが国では、個人としては多くの物理学者が批判や分析に関わってはきたものの、物理学会としての公的な関わりはまったくなかった。もし物理学会が違った政策を取っていたら「フクシマ」は防げたかも知れない。
米国物理学会の事例と併せ、「原子力安全神話」の経験からの重要な教訓の一つは、大勢の人びとの安全など社会に大きな影響を及ぼすような技術では、同業者はもちろん、隣接分野からも活発な批判活動が行われる必要があるということだろう。
大学に関しては、1998年の「ユネスコ高等教育世界宣言」は、その批判的機能を「高等教育機関およびその職員と学生の役割」の一つとして掲げている(2条c項)。
●4 なぜ批判がないのか―劣化する相互批判の環境
このような批判活動が活発に行われ、実際的な影響力を持つためには、大学や研究者のコミュニティーが民主的でなければならず、また個々の研究者が幅広い視野を持たなければならない。しかし1970年前後と比較すると、他分野への関心はもとより、自己の専門分野に関してさえ、その社会的影響について研究者が自問自答したり深く考えたりすることが非常に少なくなっているのではないだろうか。
一方、公式スローガンとしては、大学と教員の「社会貢献」が盛んに喧伝されるようになって久しい。「社会貢献」には、研究成果の還元などでいわばポジティブに社会に関わっていくことだけでなく、ウオッチドッグとして社会に危険を知らせる「ネガティブ」な関わり方も重要なはずだ。しかしこれが公式に強調されることはまずない。むしろ、京都大学の「熊取六人衆」のように、そのような立場の学者は大学で冷遇されてきた。
「ネガティブ」な発言をする「反体制派」が社会から歓迎されないどころか、排斥ないし迫害されるというのはありふれたことかも知れない。しかし大学でそれが行われるとなると、一般社会とは違った深刻さを帯びる。なぜなら大学は「学問の自由」の砦として、とりわけそのような扱いから保護されていなければならないからである。
しかし現実には、その「砦」は、2004年に実施された国立大学の「法人化」(独立行政法人制度と類似性が大きいため以下では「独法化」と略)を境として急激に劣化のスピードを上げているように思われる。
もちろんこの「砦」が昔は強固であったわけでもないし、むしろ「砦」と言えるものであったかどうかも疑わしい。独法化が深刻なのは、学問の自由の「砦」としての大学自治が名目としても失われたということである。
●5 国立大学の「法人化」と大学自治
国立大学の法人化=独法化は、大学の「批判的機能」の重大な阻害要因である。この制度は、衆院での法案審議の冒頭で山口壯議員が指摘したように、「戦前の日本にも存在しなかった、文部科学省が大学をコントロールし得る仕組み」であり、「憲法二十三条の学問の自由及び大学の自治を侵しかね」ない制度である。この制度では、文部科学大臣が各大学に「中期目標」という、およそ何事も包括できるような命令を与え、大学はその実行を迫られる。大学を政府の一行政機関のように扱うという信じ難いような暴挙が、肝心の大学人によるさしたる抵抗もなく強行されてしまった。
独法化問題を論じるのが本稿の主眼ではないので、この問題についての筆者の分析と態度については過去の文章を見ていただければありがたい。しかし簡単にこの制度の問題点をまとめると、大きく次の3点に集約されるだろう。
(1) 文科省から大学への直接支配を可能にした制度であり、明白に憲法23条に違反する。
(2) 不透明な評価制度(実質は文科省による評価)によって各大学への予算がコントロールされる。予算審議権が国会から官僚に移行した。
(3) 文科大臣が各大学の廃校の権限までも持つ。
このシステムに変わってから教員が日常的に感じるのは、会議や書類の果てしない増大と、それによる本来の教育と研究に割くべき時間の浪費だ。一例を挙げれば、筆者の大学で2008年5月に配られた「年度計画進捗状況管理表」のエクセルシートは8列1245行に及ぶ。しかしもっと重大なのは、教授会の権限縮小による教員たちの大学運営に関しての無気力化、すなわち「エンパワーメント」ならぬ「ディスパワーメント」だろう。かつての大学教員特有の気難しさは消え失せ、何事も「上で」決められるものとされる。
このように、「自治」への意欲の希薄化によって視野を広げる機会も奪われ、また高まる研究業績へのプレッシャーも背景に、物事を、あるいは自らの研究の意味について、根本的、哲学的に議論したり思いをめぐらせるということがますます少なくなっているように思われる。
●6 「法人化」に無抵抗だった国立大学
政府による独法化の動きに対し国立大学は最終段階ではほぼ無抵抗にこれを受け入れた。実際、この法案にたいして公然と反対を表明した教授会は一つもなく、国大協は最終的には推進側に回った。
また国立大学などの教職員の組合「全大教」(全国大学高専教職員組合)も本気で阻止するという態度ではなかった。それは組合員全体の意識を反映したものでやむを得ない面もあるが、必要とされるリーダシップを東京の本部が発揮したかどうかは疑問が残る(そのために筆者らは「全国ネット」12)なる任意団体を設立した)。
あるパーティーで全大教の幹部と話したとき、筆者のことを「どうしてそんなに熱心に反対運動するのか不思議だ」と訊ねられた。不思議の対象が筆者のことを指すのか、つまり「私」がなぜ熱心なのか不思議だというのか、それとも「熱心さ」が不思議なのか、いずれかははっきり断定できないが、後者の意味も含まれていたという印象だ。
もう一つの、日教組大学部の後継組織「UIPセンター」は労働基本権が得られることを主な理由に、独法化をむしろ支持していた。
この10年ほど前の「教養部解体」キャンペーンが、これもさしたる抵抗もなく容易く行われたが、これは独法化のためのいわば予行演習だったのかも知れない。独法化を推進した側は、国立大学の教員の抵抗など口ほどにもないと思ったのであろう。
教養部解体という中身もさることながら、この「改革」の最大の問題点は、国民的議論はおろか、大学内でも自由で掘り下げた議論がないまま、それどころか、問題点があるとしても初めから「抵抗しても無駄」というような、大学関係者、特に当の教養部在籍の教員の当事者意識の欠如の上に進行したということである(このあたりの状況については、拙文「文部省の違法行為・従順な大学」を参照いただければありがたい)。
教養部解体の評価もまだきちんとなされていないように思われるが、しかし独法化に関しては今やそのデメリットが誰の目にも明らかではないだろうか。推進した者の責任、容認した者の責任が当然問われなければならない。同時に、このように権力の操作に対して烏合の衆でしかあり得なかった大学人とは何かが問われなければならない。
●7 知識人論、大学論の不在
「科学独裁制」に歯止めを掛け、この社会が少しでも民主主義に漸近するためには、当の科学者コミュニティーの中に、とりわけ大学社会の中に総合的な批判精神と批判力とを高めなければならない。しかし上に述べたように、独法化など制度的圧力のもとでそれはますます困難になっている。
したがって、なぜ大学人はこの何十年もの間、政府の大学介入と変質に抵抗できなかったのか、その原因をも問わなければならない。そうしなければ自らの砦であるはずの大学の自由を「防衛」できず、ますます「侵略」を許し続けることになるからだ。
少なくとも、大学論、知識人論を練り上げる必要がある。説得力ある「大学かくあるべし」の理論を持たなければ、文科省詣での大学首脳部も、この国の伝統的な官僚優位の文化の中では東京官僚の圧力や洗脳の前にひとたまりもないはずだ。
一般の大学教員も同様で、東京の密室で行われたやりとりの詳細を知るよしもなく、学長や学部長が巫女となって告知する「社会の要請」や「厳しい情勢」にただひれ伏す他はない。あるいは、中教審など「御用学者」が作ったであろう方針を「先読み」するのが関の山だ。わが国では、本格的な大学論は、このほぼ半世紀の間、ほとんど更新されていないのではないか。
大学論について国外の状況を見てみよう。といっても筆者の乏しい文献学では三つの書籍を紹介するのみだが、フランスでは著名な社会学者P。ブルデューによる大学論「ホモ・アカデミクス」が1984年に出版されている(日本語訳は1997年)。
アメリカでは、トップクラス2大学の軍学共同の実態を暴いた“Cold War and American Science”が出たのは1993年である。日本の大学を扱った“JapaneseHigher Education as Myth”という本もいくつかの興味ある視点を提供している。
わが国の大学においても、大学自身の組織の中にこのような分野の研究者を増やす、あるいはそのような部門を創設ないし拡充しなければ、理論的な蓄積は期待できないかも知れない。創設された部門がたとえ権力に都合の良い「御用学問」としてスタートしたとしても、それを担うのが「科学」者であれば、それはすぐに「反逆」を起こし「科学」として成長する可能性がある。
●おわりに― ラディカリズムの再生を
同僚による「御用学者」批判の欠如という問題を「独法化」制度への批判に、さらには大学論にまで拡大させてしまったが、もちろんこれ以外にも、今なお幅広く、かつ根深く大学社会を覆っている封建的後進性の問題も大きい。しかもそれは独法化と「負の相乗効果」を生むのでタチが悪い。
国立大学をおかしくした「独法化」を是正していくことが批判力を高めるうえで重要だ。しかし世の中の実質は日々の些細なことがらの集積である。最終的にはその中で個人個人がどう振る舞うかが問われるのであり、たとえどんな暴政であろうとも、自らの怯懦をすべて「客観情勢」のせいにするわけにはいかないだろう。
大学人はその職業柄「観察者」という習性が強いが、こと大学コミュニティーの問題に関しては自らがアクターであり、「現象」を担う存在そのものである。その行動パターンを決めるのは文化であり、個人の姿勢つまり「心の持ち方」である。
強気と弱気、信念の強弱という人びとの広いスペクトルのすべての部分で、それぞれが可能性を信じ、少しでもアクティブな方向へシフトすることが重要だ。単に研究を進めるだけでその社会的な意味を深く考えず想像力をめぐらせることがなければ、研究成果は社会に重大な害を及ぼすということを「フクシマ」は教えている。
あるいは、67年前にロスアラモスで成し遂げられた、科学的・技術的には驚異的に素晴らしい成果が、広島と長崎の人びとに何をもたらしたかを考えるだけでも十分だろう。マンハッタン計画に携わった科学者による「フランク報告」は、「過去において科学者は、彼らの純粋な発明の利用方法については直接的な責任を否認出来たが、今日同じ姿勢を取ることはできない」と述べていることを想起しよう。







●(古くは「いさめこと」) 禁じたこと。禁じたことば。禁制。諫言(かんげん)。書紀(720)用明元年五月(図書寮本訓)「皇子乃ち諫(イサメコト)に従ひて止(や)みぬ」
●目上の人の欠点や過失を指摘して忠告すること。諫(いさ)めること。また、その言葉。太平記(14C後)五「雖レ不レ献二諫言(カンケン)一世人豈其無レ罪許哉」 〔北周書‐憑景〕。いましめること。きびしく注意すること。太平記(14C後)二二「三千余騎の兵共、大将の諫言(カンゲン)に力を得て、十六騎の敵を真中にをっ取り籠め」。
●「諫言(かんげん)」とは、「いさめること」または、「いさめる言葉」を意味します。「諫」の訓読みは、「いさ-める」です。「諌める」は、「(おもに目上の人間に対して)まちがいや良くない点を改めるように言う」「忠告する」という意味の言葉です。したがって、「諫言」とは、上司や主君の言動の悪いところを指摘し、改善を求めること、あるいはその言葉、という意味になります。
● ・・・中国で君主をいさめる五つの方法。専制政治では君主の一方的な意志に終わりがちであるので,これを是正するために君主の心情に応じた臣下の諫言が必要となる。五諫は孔子が〈諫に五あり云々〉と述べたという伝えによるもので,その内容には諸説がある。・・・
● ・・・士道と武士道とは主従関係のとらえ方においても異なる。主君に対する諫言(かんげん)について,士道は諫言をいれない主君,つまり道を実現する可能性のない主君の下にとどまるべきでないという。これに対して武士道では,諫言をいれないときにも,いよいよ主君の味方となり,主君の悪が外部にもれないようにし,主君の悪を己にひきかぶりつつ諫言をつづけるべきであるという。・・・

「諫言を聞く」 / 指導者が物事を進めて行くに当たって、みなからいろいろな意見や情報を聞くのは当然の姿である。そしてその場合、大事なのは、自分にとって都合のいいことよりも、むしろ悪いことを多く聞くことである。つまり、賞賛の言葉、順調に進んでいる事柄についての情報よりも、“ここはこうしなくてはいけない”といった諫言なり、悪い点を指摘する情報を努めて聞くようにしなければならない。ところが、そうした情報はなかなか指導者の耳に入ってきにくいものだ。だから、指導者はできるだけ、そうした諫言なり、悪い情報を求め、みながそれを伝えやすいような雰囲気をつくることが大切なのである。(松下幸之助一日一話より)
私はこれまでに諫言を聞くことの重要性について、連ツイなどを通して何度か述べさせて頂きました。これは、中国古典の大家である守屋洋先生にご教授頂いたものが大半ではありますので、私自身もまだまだ身になるまでは至っておりませんが、要約しますと中国古典のひとつであり今から約1400年前、唐王朝2代目皇帝であり名君として名高い「太宗」の時代に政治の要点をまとめた書物である「貞観政要」があります。「貞観政要」の貞観とは、平成と同じ太宗の時代の元号のことであり、つまりは貞観の時代に政治の要点をまとめた書物ということになります。
その貞観政要には、大別すると次の6つの教えがあります。
「わが身を正す」
「緊張感を持続させる」
「諫言に耳を傾ける」
「自己コントロール」
「謙虚にそして慎重に」
「初心忘るべからず」
その中でも、3つ目にある「諫言に耳を傾ける」ことについては松下翁の「諫言を聞く」と通ずるところがあります。
リーダーの中には諫言すら好まない人もいますが、仮にリーダーがどんなに口を酸っぱくして「諌言してほしい」と呼びかけたところで、それだけでは部下をその気にさせることはできません。部下の諌言を引き出すためには、自らが実行して示さなくてはなりません。具体的な行動としては次の2つになります。「普段から部下が上司に対して何でも自由に物が言えるように組織の風通しを良くしておくこと」、そして「リーダー自身が部下の意見に喜んで耳を傾ける懐の広い人間であることを示しておく」ことが必要になります。部下の立場から見て、親しみの感じられるリーダーであるならば、更に良いと言えます。
リーダーに「諫言の聞き方」の心得が必要であるのと同様に、部下にもまた「諫言の伝え方」に対する心得が必要とされます。
「諫言の伝え方」に関して孔子は、次のように述べています。
「諫に五あり。一に曰く、正諫。二に曰く、降諫。三に曰く、忠諫。四に曰く、戇諫。五に曰く、諷諫」
五諫についての解釈は諸説あるそうですが、
正諫・・・正面からいさめる。
降諫・・・いったん君主の言に従ったうえでいさめる。
忠諫・・・真心を表していさめる。
戇諫(とうかん)・・・愚直をもっていさめる。
諷諫(ふうかん)・・・遠まわしにいさめる。
という意味になります。
その中でも、5番目の諷諫の大切さについて「吾それ諷諫に従わんか」と説き、それとなく遠回しにほのめかし、わが身の危険を避ける姿勢が望ましいとしています。
更に孔子は論語にて次のようにも述べています。
「君子に侍(じ)するに三愆(さんけん)あり。言(げん)未(いま)だこれに及ばずして言う、これを躁(そう)と謂(い)う。言これに及びて言わざる、これを隠(いん)と謂う。未だ顔色を見ずして言う、これを瞽(こ)と謂う。」(論語)
君子にお仕えする時にしがちな過ちが三つある。言うべきで無い時に余計な事を言うのを “躁(そう:落ち着きが無い)” と言う。言うべき時に必要な事を言わないのを “隠(いん:隠し事をする)” と言う。君子の顔色も見ないで自分勝手に言うのを “瞽(こ:盲目)” と言う意です。
更に、礼記(らいき)には以下のようにあります。
「人臣たるの礼は、顕わには諌めず。三諌して聴かれざれば、則ちこれを逃る」(礼記)
君主に過ちがあったら、それとなく遠回しに諌める。三回諌めて聴き入れられなかったら、そんな君主には見切りをつけて逃げなさいという意です。
「見切りをつけて逃げる」という行動は終身雇用の根付いていたこれまでの日本ではあまり好まれないことではありますが、要するに「そういうダメな君主にいつまでも仕えていたのでは、わが身まで危うくなる危険性が高くなるので、さっさと見切りをつけてもっと優秀な君主を探した方が良い」ということを中国古典は教えているのです。
翻って、貞観政要には理想的な君臣関係についても述べられています。
「惟(はなは)だ君臣(くんしん)相遇(あいあ)うこと魚水(ぎょすい)に同じきあれば、則ち海内(かいだい)安かるべし。」(貞観政要)
所謂、「君臣水魚」と言われる言葉です。君主と臣下、或いはリーダーや上司と部下の関係は、水と魚のような関係性が望ましいという意味です。
同様に孟子は
「君臣、義あり」(孟子)
とも言っています。両者の関係は義が必要であるという意になります。更に、 性善説を説く孔子や孟子とは逆に性悪説を説く韓非子は
「上下(しょうか)一日に百戦す」(韓非子)
とも言っています。韓非子によると君主の利益と臣下の利益は全く異なるという前提であり、上司と部下では大きく利害が対立するという意味です。
私は右手に論語を持ち、左手には韓非子を持っていますが、基本的には右利きですので、孟子のいうように義という信頼関係を構築した上で、論語にある諫言の仕方を実行する必要があると考えます。
「君子は信ぜられて後に諌(いさ)む。未だ信ぜられざれば、則ち以って己を謗(そし)るとなす」(論語)
君子というものは信頼を得た後に諫言をする。信頼を得られていない時に諫言をすると、侮辱しているように思われるという意味です。
貞観政要の中で太宗は、自分(君主)に過ちがあると見るやはばかることなく諌言を呈する臣下(争臣)を敢えて求めたとされますが、太宗の臣下のひとりであった王珪は「争臣七人あり」の体制が望ましい姿であるとも諫言しています。諫言というものは、聞く側にとっても、伝える側にとっても難しいことであり、難しいことだからこそ有意義な結果をもたらすともいえ、そこには義、即ち何が正しいか否か、更には信、お互いがお互いに対する信頼や信用が不可欠なものであるということを心得ておきたいものであると私は考えます。

「忠言は耳に逆らう」という言葉があります。忠言とは忠告のことですが、中心の心を言うと書きます。その忠言に諌める心が伴ったものが諫言になります。
忠言や諫言は、する側もされる側もいずれもが不完全な人間同士のすることですので、慎重さを要します。相手に良かれと思ってすることも、こちら側の伝え方や相手の捉え方次第では、以前の状況よりはるかに険悪な修羅場を招く危険があります。強固な信頼関係で結ばれた君臣の関係でも、一言の諫言で崩れた例も数多くあります。
茶の間のドラマで人気がある水戸の黄門様は、実に見事に悪人を成敗し、その後その地の殿様に忠告をなさいます。この場合、天下の副将軍が格下の若い殿様にする忠告ですから、スムーズに受け入れられるようです。
しかし忠言や諫言はその逆で、格下の者が格上の者に忠告することになりますから、大きな勇気と困難が伴います。このため中国では『諫義大夫(かんぎだいふ)』と呼ばれる君主に小言を言う専門役職までありました。いかに名君といえども臣下からの諫言なしでは治世の持続は困難であり、いかに信頼を得た名臣でも簡単には主君に諫言できない難しさがあるからこそ、このような役職が設けられたものだと思います。
一般的な忠言・諫言に関する名言は、受けた側の心の素直さを説くものが多いのですが、掲句は忠告する側の気配りの心構えを説くものです。
普通は意にそぐわない部分があるから忠告するわけですが、この感情を忘れ虚心坦懐で行えというのです。人間は相手に対して面白くない感情があると、どうしても心の底に怒りや押しつけの気持ちが生れますが、これでは虚心坦懐の忠告にはなりません。でき得るならば、いかに正論の忠告であっても一呼吸を置いて、こちらの面白くない心を整理した後に行う配慮が必要ということです。
天下の大聖人の孔子様も、「信じられて後に諌む。いまだ信じられざれば己を謗ると為す」と忠告に対して慎重さを求めています。
信頼感がない状態での諌めは、非難と受け取られるだけで相手の反発心を起こし、時には思い掛けない反撃を招くことになります。
韓非子にも「人主も亦逆鱗有り。説者能く人主の逆鱗に嬰るること無くんば、則ち幾し」とあります。逆鱗とは龍のあごの下の逆さの鱗(うろこ)ですが、その逆鱗に触れると怒り心頭の凶暴な龍に変ります。君主や社長も似たような逆鱗がありますから、具申の際にはこれに触れないようにしなければなりません。
とは言っても、反撃を恐れて正論を吐くことを躊躇し、甘言や佞言(いずれもオベッカ)が飛び交う組織や社会でも困ります。やはり勇気を以て正論を心掛ける一方で、相手に理解してもらう心遣い(虚心坦懐もその一つ)が必要だと考えます。

主君や目上の人に対し、その過ちを指摘し改めさせるのは大変難しいことです。諌(いさ)める時は諷喩(ふうゆ)と言って遠回しに指摘する方法と、ストレートに指摘する直諌(ちょくかん)の方法がありました。相手を傷つけず恥をかかせずに悟らせることができれば、諷喩は優れた諫言(かんげん)の手法と言えるでしょう。
●三年飛ばず鳴かず
中国の春秋時代(前770〜同403)、長江の中流域を中心とした楚の国でのこと。のちに有力諸侯の「覇者」に数えられた荘王は、即位してから3年もの間、何の号令も発せず、淫楽に耽(ふけ)っていました。しかも「もし自分を諌める者がいたら死罪に処す」との命令まで出したのです。
これを見かねた家臣の伍挙(ごきょ)は宮中に入ると王に言いました。「なぞなぞをしたいと思います」
鳥有り阜(おか)に在り、三年蜚(と)ばず鳴かず。これ何の鳥ぞ。
1羽の鳥が丘にいます。3年間も飛ぶことも鳴くこともないのです。何という鳥でしょうか――。これは日本でも使う「三年飛ばず鳴かず」あるいは「鳴かず飛ばず」という言葉の由来となった問いかけですが、これに荘王は答えます。「3年も飛ばないのか。ひとたび飛んだら天まで昇るであろう。3年も鳴かないのか。ひとたび鳴けば人を驚かすであろう。伍挙よ、下がれ。私はお前の言うことはわかっている」と。ところが数カ月たっても、王の淫楽はやむことがありません。
今度は蘇従(そしょう)が宮中にやってきます。今度は直諌でした。王は言いました。「お前は命令を知らぬのか?」。蘇従は答えました。「私は死んでも、王が名君になっていただけるならば本望です」。これを聞いた王は直ちに淫楽をやめ、政務に就いたのです。数百人を処分し、数百人を引き上げました。無論、伍挙と蘇従とは重用され、政務を任されました。「国人大いに説(よろこ)ぶ」と史記は伝えています。
国のため考え抜かれた諷喩と、保身とは無縁の直諫。荘王は臣下の忠誠を確認するために3年を費やしたことになりますが、彼が本当のことを知るためには必要な歳月だったのかもしれません。これは諫言の士が出世する話ですが、同じ楚の国で、逆のこともありました。
●讒言と諫言のゆくえ
時は移って平王の時代。平王の子で太子(王位継承者)である建(けん)の教育係に伍奢(ごしゃ)と費無忌(ひむき)がおりました。太子が秦の国から嫁を迎えることになり、費無忌が使いに行ってみると、それが大変に美貌の女性。費無忌は一計を案じます。一足先に平王のもとに戻り「秦の女性は絶世の美女です。これほどの美女ならば王がご自分で娶(めと)られ、太子には別の女性を迎えればよいでしょう」。平王はこの意見を聞き入れてしまいます。
この時、費無忌が上位職の伍奢を差し置いて出過ぎた行動をとったのはいかにも不自然です。おそらく費無忌は太子に嫌われていたのでしょう。しかしこんなことをしたら、今度は平王に万一のことがあったらと、費無忌は気が気でなくなります。彼は太子に謀反の計画があるとでっちあげて讒言(ざんげん)し、平王も太子を遠ざけてしまいます。王は伍奢を呼び、問責します。全てを知る伍奢は懸命に王を諌めました。
王、独りいかんぞ讒賊(ざんぞく)の小臣をもって骨肉の親(しん)を疎んずるか。
王よ、なぜあのような小人物の言うことを信じて実の子である太子を疎んじるのですか――。私はこの言葉こそ、史記の中で最高の名言のひとつと思いますが、王は逆に伍奢とその子、伍尚(ごしょう)と伍子胥(ごししょ)を捕えるよう命じます。伍子胥のことは別の機会に詳しく触れるつもりですが、この時は伍子胥のみ逃れ、父と兄は処刑されてしまいます。費無忌も無事ではいられませんでした。平王が没すると、彼の悪行を知る楚の重臣によって殺されます。ここでも史記は、人々が大いに喜んだことを書き添えています。
史記にある諫言のエピソードを並べましたが、その著者である司馬遷自身も諫言の士でした。北方の異民族、匈奴(きょうど)との戦いに敗れ、捕虜となった将軍の李陵を弁護し、それが時の皇帝である武帝の逆鱗に触れて宮刑を受けました。司馬遷の何が悪かったのでしょうか。正しいことを言えばそれでよかったのか、これはいつの時代にも通じる大問題です。
李陵は皇帝に近い他の将軍と比べたら小さな存在であり、司馬遷もまたひとりの役人にすぎませんでした。群臣の多くは司馬遷よりも高い地位にいたはずで、彼らからは出過ぎた行為とみられて当然です。さらに司馬遷の意見が正当であればあるほど、唯一無二の存在であるはずの皇帝が逃げ道を塞がれ、メンツも失います。どれだけ弁舌がすばらしくとも、周囲から支持されるものではなかった。つまり、その時点では何も変えられなかったのです。
諫言の難しさは、周囲から賛同が得られなければ何も変わらない点にあります。賛同を得るためには、「自分を棚に上げて」と言われぬよう、まず自分がクリーンでなければなりませんし、自分の立場も心得ていなければなりません。「何を述べるか」と同時に「だれが述べるか」も重要だからです。いま風に言えば空気を読む必要もあるでしょう。そして最も大切なことは、相手の逃げ道を塞いではいけないということではないでしょうか。諌言が批判のための批判になってしまってはいけない、そんな気がするのです。
もちろん、上に立つ人物が暗愚か否かも大きな分かれ道になります。荘王は粗野であっても名君でした。平王は救いようのない暗君であったと言わざるを得ません。前漢の最盛期を築いたとされる武帝は、どうでしょうか。
私の30年のサラリーマン生活を振り返ると、上役を諫める資格も能力もないことの自覚が欠如していたがゆえの多くの間違いが思い当たります。もし、それをわきまえてもう一度やってみろと言われたら、やはり同じ間違いを繰り返すことになるかもしれません。

●誠心を持って王に諫言する
儒教の経典に精通する龔遂は昌邑国(しょうゆうこく)で郎中令(官職名)を務め、昌邑王(しょうゆうおう)の劉賀(りゅうが)に仕えました。劉賀は品行が修まらない寛闊者(※1)で、龔遂は彼のことをとても心配しました。龔遂は太傅(天子の師)と国相(宰相を指す)が劉賀を正道に導くことが出来なかった事に対して厳しく非難し、彼本人もいつも経典を引用して、是非善悪を痛切に述べ、悲しいところに話が及ぶと、涙を流しました。
龔遂は大きな事に関しては決して曖昧にせず、お世辞を言わず、いつも劉賀の過ちを率直に指摘し、彼を大変困らせました。一回、龔遂が話をしている最中に劉賀は耳を覆って、「郎中令の言葉は本当に人に恥をかかせるものだ。聞いていられない」と言って、逃げてしまいました。
昌邑国では上から下まで皆が龔遂のことをとても尊敬していました。
しかし、劉賀は悪習を直さず、依然として酒食遊楽にふけり、湯水のごとく金を使いました。龔遂は両膝を地面につけて前へ進み出て、宮殿に入って直諌しました。彼が涙をほろほろと流している姿を見て、周りの人も感動して涙をこぼしました。しかし、劉賀はなんと「郎中令はどうして泣くのですか」と無神経な言葉を発しました。
龔遂は「このままでは国が危ういので、私は悲しんでいるのです! 王には落ち着いて、臣下の愚見を聞いてほしいと願っています」と言いました。劉賀は仕方なく、周りの人を退場させ、龔遂の話を聞くことにしました。そこで、龔遂は「膠西王(こうせいおう)が悪事を働き、滅ぼされたことをご存じですか?」と聞くと、劉賀が茫然として「知らない」と言いました。
龔遂は引き続き、「膠西王には、非常におべっかを使うのが上手な臣下がいて、名前は候得と言います。膠西王は夏桀殷紂(かけついんちゅう 暴君の代名詞)と同じように乱行や悪事を働きましたが、候得は彼の事を尭と舜(ぎょうとしゅん:徳をもって理想的な仁政を行ったことで、後世の模範とされた帝王)のように喩えました。膠西王は綺麗事を聞くのが好きで、ますます侯得の嘘偽りを信じ、最後に自分が死んで国を滅ぼしました。王は今、小人と親しくなっていますが、それは膠西王の後塵を拝している事です」と言いました。
劉賀は大変驚きました。龔遂はチャンスを掴んで「国を滅ぼしたくなければ、儒学に精通し、品徳の高尚の人を推薦させていただき、彼らと一緒に暮らすようにお勧めします。時間があれば、「詩」、「経」を読まれ、礼儀を演習してください。そうすれば初めて国をしっかり治めることが出来るのです」と言いました。
劉賀は嫌々ながら仕方なく賛成しました。龔遂は学問が優れ、品格の素晴らしい張安などの10人を選出し、劉賀に仕えさせました。しかし劉賀は愚かなもので、数日も経たないうちに、彼らを追い出してしまいました。
その後、王宮の中では度々不思議な現象が起きました。劉賀はよく犬の頭を持った人間や、熊、鳥の怪物などが見え、しかし、周りの人は誰も見えませんでした。一回、劉賀の座席に血痕が現れました。怖くなった劉賀は龔遂に理由を聞きました。
龔遂は「これは天帝の警告です。王は『詩経』を読まれましたが、その中の礼儀規範をやり遂げたのでしょうか? あなたは王ですが、あなたの言行は百姓よりも不潔ではありませんか? このままではきっと災いを招くだけです! 血は災難の相です。間もなくこの国には大きな災いがやって来るでしょう。早く反省してください!」と諫言しました。しかし、劉賀は依然として真剣に聞き入れてくれませんでした。
●劉賀が廃位される
ちょうど昭帝(しょうてい 前漢の第8代皇帝)が崩御し、大臣の霍光と朝臣たちは劉賀を皇帝として擁立しました。すると、劉賀は彼の無学無能な随従と部下を連れて、上京して即位式に行きました。途中、劉賀は女性を襲い、京城の近くに到着しても、跪いて国喪の礼を行ないませんでした。
宮殿に入った後、劉賀はさらに魚が水を得たように、法律を無視し、横暴で傲慢に振舞いました。龔遂は焦って居ても立っても居られず、長楽宮の衛尉(えいい 宮門を守衛する兵士を管轄する職)の安楽に「王は即位してから、日に日に贅沢三昧の生活を送り、諫言をまったく聞き入れてくれません。今はまだ先帝の喪に服す期間なのに、彼は随従達と酒を飲み、騒ぎ立て、9色の旗を立てている馬車に乗って、あちこちを走り回り、これは天道と国法に反し、民衆を裏切り、正道から離脱している事です」と言いました。
「古代の法制は寛大で手厚く、もし大臣達が悪逆無道の君主に遭った場合、避けて引退しても構わないとしました。正直なところ、私は官を辞めて引退したいと思いますが、しかし、そうすれば、将来、きっと天下の人々に笑われるでしょう。ですから、私は辞職することはできません。あなたは昔皇帝の宰相になった経験がありますから、あなたからも早く忠告をしてあげてください」と言いました。
残念ながら、忠実で正直な龔遂は劉賀の心を変えることが出来ず、結局、即位して27日目に、劉賀は朝臣たちによって追い落とされました。この僅か1カ月の間、劉賀は毎日40の過ちを犯していました。
劉賀が廃位されてから、昌邑国から来た臣下や随従たちも王の非道を放任する罪で、すべて処刑されました。ただ龔遂と中尉の王陽は何度も劉賀に諫言し、自らの職責を果たしたため、死罪は免れました。
●宣帝への対策
劉賀が廃されてから、宣帝が即位しました。漢宣帝が即位してからしばらくの間、渤海郡およびその周辺地域では飢饉が起き、盗賊被害が多発し、庶民生活は不安定となりました。そのため、飢餓した民衆は造反を起こしました。しかし、当時の郡太守は反乱を制圧する力がありませんでした。
宣帝は事態を収拾する人を探し、渤海郡の太守に就任させたいと考えました。丞相と御史大夫は皆「龔遂は責任感があり、危機に陥った今、彼こそこの任務を引き受けるもっとも適任者です」と龔遂を極力推薦しました。そこで、皇帝は早速任命書を出し、龔遂を渤海郡の太守に任命しました。
その時、龔遂はすで70歳を過ぎて、体も一回り小さくなっていました。宣帝は龔遂を引見した時、彼の容貌を見て、心の中で多少失望感があり、重臣達が推薦してくれた人のイメージとかなりかけ離れていると思いました。
宣帝は龔遂に、「渤海郡地域では混乱が起きており、法律と規律が緩み、民衆生活が不安定で、あなたには何かいい策があるか?」と聞きました。
龔遂は落ち着いて、「渤海郡は辺鄙な場所にあり、民衆が皇帝からの恩恵と教化を受けていません。しかし、民衆たちが飢えと寒さに迫られているにもかかわらず、地方官吏は彼らを救済しようとしませんでした。そのため、怨みが積りに積もって本日の状況となりました。今、民衆は武器を盗み、ひどく騒ぎたてていますが、しかし、彼らが本気で反乱を起こしたいわけではありません」と言いました。
宣帝は龔遂の話にも一理あると思い、とても嬉しくなりました。龔遂は皇帝に「陛下は私に彼らを掃討させるつもりなのか、それとも彼らを落ち着かせて慰めるつもりなのか、どちらでしょうか」と聞き返しました。
皇帝は「朕は才徳兼備の人を渤海に行かせるのは、当然、彼らを落ち着かせ、慰めるつもりである」と言いました。そこで、龔遂はさらに自分の施政方針を話し、「秩序を失った民衆を管理する事は、絡まっている糸を整理することと同じで、性急に事を運ぼうとすればかえって失敗します。時間をかけてじっくり対応すれば、初めて目的に達成することが出来るでしょう。私が着任した後、丞相と御史に私の仕事を制限しないようにしてほしい、それに、現地の実情に合わせて適当に処理させてほしい、この二つをお願いしたいのですが」と申し出ました。
●平和に反乱を治める
宣帝は龔遂の要求を承諾し、彼は黄金を賜り、馬車を増加してくれました。龔遂は皇帝から賜った馬車に乗って、渤海郡の地域に入りました。郡府の官吏達は新太守がもうすぐ着任すると聞き、兵隊に列を作らせ、出迎えてくれました。龔遂はそれを見て、兵隊を全部解散させました。そして、すぐさま公文書を出して、各県の治安を管理する官吏とその持ち場を撤去するようにと命じました。
また龔遂は良民と盗賊を区分する方法を案じました。農具を持つ人が良民で、官吏らが彼らに罪を問う事が出来ないように決め、兵器を持つ人を盗賊と見なすようにしました。そして、龔遂は随従を連れないで一人で馬車に乗って郡府に来ました。龔遂の仕事ぶりは人々から評価され、郡中の民衆が次第に安定し、盗賊被害も少なくなりました。かつて仲間を組んで略奪した人達は、龔遂の教令を聞いて、自ら解散し、兵器を棄て農具を持って農作業を始めました。
こうして、龔遂は一兵卒も使わずに反乱を治めることが出来ました。そのため、民衆も安心して生活し、生業に励むことができるようになりました。
龔遂はまた穀倉を開き、食糧を貧しい民衆に貸し出し、さらに清廉な官吏を抜擢しました。龔遂は渤海地域の人々が耕作を重視せず、贅沢好きで、商品販売するのを好む傾向があることに気付き、そこで、彼は自ら手本を示して節約を断行し、民衆に農業に従事するように勧めました。彼は1人に1本の楡の木を植えさせ、100株のラッキョウ、50本のネギ、1畦のニラを作らせ、そして、一戸では豚を2頭、鶏5羽を飼うように命じ、民衆に農業生産の基礎を教え、耕作するように手助けをしました。
民衆の中にはまだ刀や剣を持っている者がいると見て、龔遂は彼らに刀と剣を売却して耕牛や子牛を飼うように勧め、そして、ユーモアのある口調で「耕牛と子牛を身に付けてはいけないよ」と言いました。春夏の季節になると、彼は民衆に畑仕事を奨励し、秋冬になると、収穫に行くように促しました。
龔遂はまた人々に果実や菱角(リンジャオ)などの農産物を貯めるように励ましました。その結果、渤海郡では、どの家にも食糧の貯えができ、官民ともに豊かになり、そして、揉め事や犯罪も随分減少しました。
●優れた人材を推挙する
数年後、漢宣帝は龔遂を京城に召還しました。議曹(郡太守に属する官吏)・王生もついて行きたいと言いました。功曹(こうそう 郡太守の主要官吏)は王生が酒好きで節度がないと思い、彼がついて行くのはふさわしくないと言いました。龔遂はいろいろ考えた末、やはり王生を京城に連れて行くことにしました。
京城についてから、王生は毎日ベロンベロンになるまで酒を飲み、龔遂にまったく会いに行きませんでした。ある日、龔遂は皇帝に召されて宮に行く途中、ちょうどひどく酔っ払っていた王生に会いました。龔遂を見ると、王生は大声で、「もしも皇帝があなたにどうやって渤海を管理したかと聞かれたら、『私の能力ではなく、すべて皇帝の威徳によるものだ』と言いなさいよ」と言いました。龔遂は王生が自分に功績を鼻にかけないように注意していると受け止めました。
宮中、皇帝から渤海の情況を聞かれると、龔遂は王生の言葉通りに答えました。皇帝は龔遂の謙虚さと礼儀正しさを大変評価し、「あなたはどうしてこんなにも正直で温厚で謙虚でいられるのか?」と聞きました。
龔遂は皇帝に「臣は賢くありません。すべては義曹の王生が戒めてくれたのです」と言いました。
皇帝は彼が部下の功労を独占せず、優れた人を推挙する度量と雅量にいっそ敬服しました。龔遂がもう高齢になったため、皇帝は彼の体を配慮し、彼を自分のそばに残し、祖廟祭事を管理させ、王生を水衡都尉(すいこうとい 前漢の官職名)に任命し、それによって2人に対する奨励の意を表しました。

甲斐の戦国大名武田信玄の一代記といってよい『甲陽軍鑑』という本がある。信玄の重臣の一人だった高坂弾正(こうさかだんじょう)昌信が、信玄死後、そのほとんどを書き、そのあと、昌信の甥 春日惣次郎らが書きつぎ、それを江戸時代のはじめ、軍学者の小幡勘兵衛景憲(かげのり)がまとめたといわれる本である。
もっとも、この『甲陽軍鑑』は、40年ほど前までは偽書扱いをされていた。というのは、その頃までは架空の軍師だった山本勘助のことが、かなり書き込まれていたからであった。
ところが、その後、山本勘助が、たしかな文書の出現によって実在が証明され、偽書というレッテルを貼られていた『甲陽軍鑑』の見直しが進められた結果、今日では、「史実と合致しない部分もあるが、使える部分も多い」といったとらえ方となっている。
その『甲陽軍鑑』に、日常、信玄がしゃべっていた言葉が随所に筆録されており、よく知られるものとして、七分勝ちといったものがある。これは、「ゆミやの儀、勝負の事、十分を六分七分のかちハ、十分のかちなり」というもので、合戦では、六部か七部くらいの勝ち方が理想的だといったくだりである。その理由について、信玄は、「八分のかちハあやうし、九分十分のかちはみたま大まけの下つくり也」といっている。
完勝してしまうと、奢り(おごり)の気持ちや、油断が生じ、つぎの戦いで負けてしまうので、七分くらいの勝ちを理想的な勝ち方と考えていたことがわかる。
私が『甲陽軍鑑』に採録されている信玄のいくつかの名言の中で、一番注目しているのは次の言葉である。原文は、
国持つ大将、人をつかふに、ひとむきの侍をすき候て、其そうきやうする者共、おなじぎやう儀さはうの人計、念比(ねんごろ)してめしつかふ事、信玄は大きにきらふたり。
とある。漢字交じりで現代風に書けば、「国持大将、人を使うに、一向きの侍を好き候て、その崇敬する者共、同じ行儀・作法の人ばかり、念比して召し使う事、信玄は大いに嫌いたり」となる。
「一向きの侍」とは、自分と同じ方向を向いている家臣のことで、自分のことを崇敬し、しかも同じような行儀・作法をする者を自分のまわりに置きたくないという意味である。いま風ないい方をすれば、「イエスマンばかりでまわりを固めたくない」といったところであろうか。
上に立つと、下からあまり苦言をいわれたくないと考えがちで、どうしても、反対意見をいう者を遠ざけてしまいがちである。信玄は、寵臣(ちょうしん)に取りかこまれた大名が没落していったことをよく知っていたのであろう。諫言(かんげん)がいえる、すなわち、自分を諌(いさ)めてくれる家臣を側に置くよう心がけていたのである。
●補佐役の重要性を物語る晩年の秀吉
諫言がいえる家臣となると、どうしてもある程度限られてくる。下っ端の家臣では、立場上、諫言などできない。いえるのは重臣クラス。しかもそのトップの方で、ナンバーツーとかナンバースリー、すなわち補佐役ということになる。つまり、諫言がいえる補佐役がいるかいないかが、戦国大名家の存亡に大きく関係していたといってよい。
そこで思いおこされるのが豊臣秀吉である。秀吉には、二人の軍師、「二兵衛」などといわれる黒田官兵衛孝高(よしたか)(如水)と竹中半兵衛重治がいた。竹中半兵衛の方は、早くに死んでしまい、また、伝説的な話が多いが、黒田官兵衛は文句なく秀吉の補佐役であった。
そしてもう一人、秀吉には補佐役がいた。弟の秀長である。やや極端ないい方をすれば、秀吉はこの黒田官兵衛と弟秀長という二人の補佐役がいたおかげで天下を取れたといってもいいくらいであった。
秀吉はこの二人だけでなく、妻のおねの意見にも耳を傾けていたことが知られている。秀吉がはじめて長浜城の城主になったとき、早く城下町を作りたいと考え、「長浜城下で商売をする者には税を取らない」とお触れを出した。その効果は抜群で、またたく間に城下町ができた。すると、秀吉は、「これから税を取る」と方向転換しそうになったのである。
それを知った妻おねが横槍を入れた。「それでは商人たちをだましたことになりませんか」という。まさに正論で、秀吉もそれ以上のゴリ押しはしなかったのである。
秀吉が黒田官兵衛や秀長、さらに妻おねの諫言を受けいれている間はよかった。ところが天下を取ったあたりから、秀吉は聞く耳をもたなくなったのである。一つは、黒田官兵衛が遠ざけられたこともあるが、もう一つ、決定的だったのは、弟秀長の死である。
秀長は天正19年(1591年)1月22日に亡くなった。病死である。そのとたん、秀吉の暴走がはじまる。私は、秀吉晩年の不祥事とか暗黒事件といっているが、それまでの秀吉では考えられないことが次からつぎへおこるのである。
まず、秀長の死の直後、茶頭(さとう)でもあり、腹心でもあった千利休を切腹させている。そして、無謀な朝鮮出兵をはじめ、さらに、一度は養子に迎え、関白まで譲った甥の秀次を高野山に追って切腹させ、その正室、側室、子供、侍女まで全部で39人、京都の三条河原に引きだし、虐殺といってよい殺し方をしているのである。
これは、単に秀吉が老人になって耄碌(もうろく)したというレベルの問題ではない。ブレーキ役でもあった助手席に座っていた弟秀長の死で、運転手秀吉の暴走がはじまったのである。補佐役の重要性を極端に示す事例ではないかと思われる。






















