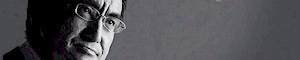■河野太郎・規制緩和・安倍政権の功罪・行政改革の方針2004・・・







 2020/7-12
2020/7-12野党時代、自民党の谷垣禎一総裁が唱えていたキャッチフレーズとそっくりだったからだ。同党は2010年1月に決めた新綱領に「自助自立する個人を尊重し、その条件を整えるとともに、共助・公助する仕組を充実」と書き込んだ。
有権者に自己責任を意識させる「自助」をなぜわざわざ明記したのか ・・・
全府省に要請したハンコ廃止の経過も報告した。年間1万件以上発生する手続きのうち、押印を求めているものは820種類あったという。9月末時点で存続を希望するのは4%にあたる35種類だったと説明した。
天皇陛下の印章である「御璽(ぎょじ)」は廃止の対象としない考えを示した。河野氏は「(ハンコ存続の理由で)法令に押印を求めると書いてあるというのがあったが、法律を変えれば済む。それは理由にならない」と強調した。
古賀:注目されている河野太郎行政改革担当相は、激務のキャリア官僚の仕事を「ホワイト化する」と言っていますが、難しいでしょうね。今後も意欲的で優秀な人ほど若いときに辞める傾向が続くでしょう。
前川:河野さんが本気で行政改革をしようと思うなら、まず、国会議員を100人減らせばいい。そうすれば、300人は官僚の人員を増やせるはずです。あと、官庁にも仕事ができない50代が相当な数います。そして東大法学部卒が多い(笑)。しょうがないから、「情報分析官」といった役職名を与えて、新聞や週刊誌の“情報”を分析してもらっていました。疲弊している若手官僚をまず救ってやらないと、仕事ができる者が辞めて、仕事ができない者ばかり残ることになる。
古賀:河野さんはもともと脱原発派ですから、行政改革をやるなら電力改革に手をつけるべきです。一方、派閥談合で総理になった菅さんが電力改革をサポートするのは難しい。河野さんは次の総裁候補で菅さんのライバル。今は総理と大臣という上下関係にありますが、河野さんが次の総裁選に向けてどこで戦いの狼煙(のろし)を上げるか注目です。
──衆院の任期が残り1年となり、いつ総選挙があってもおかしくない状況です。
古賀:前川さんは、選挙に出ないんですか? 立憲民主党が新しくなったといっても、幹部は民主党政権のときと顔ぶれが同じで、国民からは政権担当能力がないと思われている。前川さんのように行政組織を動かしてきた人が入れば、野党への期待が高まると思うのですが。
前川:古賀さんも行政経験あるじゃないですか(笑)。
古賀:私は、野党からは声はかからないんですよ。実は、17年に希望の党ができたとき、小池百合子東京都知事周辺から「菅さんの選挙区(神奈川2区)で出ない?」って誘われたんです。希望の党ができて野党が一つにまとまるという話だったので、それならと思ったけど、結局、野党が分裂したのでやめました。
実力のある人が出てこないと、野党に未来はないんです。前川さんは南関東比例単独1位で100%当選できる形にして、菅さんの選挙区から出てみてはどうですか?
前川:これまでも立憲民主党から共産党まで選挙に出ませんかという話はあったんですが、全部断っているんです。選挙に出るつもりはまったくないんですよ。
古賀さんも、タスキをかけて自分の名前を連呼するのはイヤでしょう?
古賀:それについては小池さんが、「大丈夫よ。『I am not ABE』のプラカードを持って歩けばいいのよ」って(笑)。政治家はいい加減だから、気をつけないといけませんね。
──古賀さんと前川さんは、麻布高校から東大法学部を卒業してキャリア官僚になりました。ただ、かつては3人に1人を占めた東大卒のキャリア官僚の割合は、20年度の合格者で14.5%まで激減しています。
前川:役所という組織では、ポストと権限がないと自分のやりたい仕事はできないんですよね。下積み期間が長くて、今の若い人には耐えられないというのはよくわかります。しかも、今は人員削減で人が少ない上に、肥大化する内閣官房や内閣府に各省庁の人材が併任という形で取られてしまう。若い人が物事を深く考えたり、勉強したりする時間もなくなっています。
古賀:私は、東大を優秀な成績で卒業した人ばかりが官僚になるべきだとは思わないし、いろんな大学から人材が集まるのはむしろいいことだと思います。官僚以外にも大切な仕事は世の中にたくさんありますしね。
ただ、公務員の仕事が「やりがいがない」と思われているとなると、別問題です。食いっぱぐれがないから官僚になったという人が増えると、日本の官僚システムが今より悪くなります。
全府省に原則廃止を要請した行政手続きのハンコの大半を廃止できるとの見通しを示した。年間1万件以上発生する手続きのうち、押印を求めているものは約800種類あったという。
9月末時点で「廃止」か「廃止の方向」と示せないものは4%にあたる35種類だったと説明した。河野氏の指示を受け、内閣府は9月24日付で行政手続きで求める押印の原則廃止を全府省に書面で要請した。
医療や介護、労働など幅広い分野の政策を扱う厚労省を巡っては、組織を再編すべきだとの意見もある。
河野氏は「厚労省は新型コロナウイルスで様々な業務が発生している」と主張した。「省庁再編で厚労省をまな板の上にのせるタイミングではない。優先順位は上げていない」と語った。
規制改革に関しては「大きなテーマもあれば細かなテーマもある。やれるところからどんどん動かす」と強調した。「世の中から見て新しい価値を生み出す規制改革をしっかりやる」とも述べた。個別分野の明言は避けた。
平井卓也デジタル改革相との連携について「DXを邪魔する規制を取りのぞかないと平井氏が動けない。優先順位を高くやる」と表明した。
オンライン教育やオンライン診療を巡っては「文部科学相や厚労相に入ってもらい、(平井氏を含め)3人で打ち合わせをする」と力説した。
オンライン診療の推進をはじめとする規制改革は、菅政権の主要施策の一つだが、日本医師会からは慎重な検討を求める声が上がっている。
河野大臣は、規制改革等の担当大臣就任は2回目であり、「前回は行政の無駄をそぎ落とすための規制改革を行ったが、今回は新しい価値を作り出すための改革を真ん中に据えたいと考えている」との抱負を表明。就任直後、自身のサイトに開設した行政改革目安箱「縦割り110番」については、「想定を超える件数だった。非常に多くの方から、悩んでいたり、困難に直面していることを赤裸々に切々と書かれたメールがたくさん来た」と明かし、政府としてこれらの声を受け止める必要性を指摘するとともに、規制改革、行政改革については、内閣府のホットラインに統合して、アイデア募集を継続していく方針を説明した。
主な質疑応答は以下の通り。
――規制改革担当等の大臣として、どんな抱負で臨んでいくのか。
この担当は2回目だ。前回は行政の無駄をそぎ落とすための規制改革を行ったが、今回は新しい価値を作り出すための改革を真ん中に据えたいと考えている。
――規制改革や行政改革を進めるため、10月1日に大臣の直轄チームを発足させた。その狙い、意図は。
大きな規制改革のテーマもあれば、細かな規制改革のテーマもある。とりあえず、来たものをやれるところから動かしていくという意味で、直轄チームを立ち上げた。いずれ大きなものをやってもらうことになるが、とりあえず今まで寄せられたものを直轄チームに渡し、実現できるものはどんどんやってもらいたい。
都道府県、市町村から職員を派遣してもらった。国の側から見て気付いていないが、自治体から見て「この規制、何とかしてくれ」というものが、たぶんたくさんあるのだろう。自治体から来た皆さんにも、直轄チームに一緒に入ってもらって、国と自治体との間での規制改革の先頭に立ってもらいたい。
――デジタル改革担当の平井(卓也)大臣と連日、打ち合わせを行っているが。
平井大臣がデジタル・トランスフォーメーションを進めていく上で、その邪魔をしている規制を取り除かないと進まないので、どの分野に焦点をあてるか、どの分野に優先順位を付けてやるかについて、緊密に連携をしながら、打ち合わせをしていきたい。オンライン教育やオンライン診療については、文科大臣、あるいは厚労大臣に入ってもらい、3人で打ち合わせをしてやっていきたい。
――受診歴のない初診からのオンライン診療について、日本医師会からは慎重な意見が出ているが、その受け止めについて。またそれ以外に医療分野で規制改革は考えているのか。
世の中から見て、新しい価値を生み出すと思われる規制改革については、しっかりやっていきたい。まだ個別のものについて評価をしている段階ではない。
――規制改革推進会議の進め方について。例年なら毎年6月に答申をまとめるが。
会議のメンバーには、昨日も連絡をした。どんどん知恵を出してもらって、作業を手伝っていただきたいと思っている。とにかくやれることは、どんどんやってもらいたい。フォーマリティ(の会議)にかかわらず、進めていきたい。悠長なことは言っておられず、毎日でも会議を開催したいくらいだ。
――行政改革について。厚労省の分割などはどう考えているのか。
省庁の組織再編云々は当面、後回しにしようと思っている。例えば、厚労省は今、新型コロナウイルス感染症対応で、いろいろな業務が発生している最中なので、省庁再編ということで、厚労省を「まな板の上」に載せるのは、あまりいいタイミングではない。省庁再編の優先順位はそれほど上げてはいない。
――行政事業レビューは今後、どう実施していくのか。
行政事業レビューは、行政の無駄なところをそぎ落とすために、やらなければいけないと思っている。それ以外にも、本来なら手が届いていないところがあれば、今やっている事業で適切なのかどうかという視点で、物を見ていきたい。
――社会、経済のデジタル化について。
デジタル化、オンライン化の利便性と安全性は表裏一体だと思う。防衛省でも、安全性をいかに担保しながら、最新の技術を使っていくかに直面していた。トレードオフではなく、利便性をいかに高めていくかを考えていかなければいけない。100%の安全性がないなら、いかに復旧力を高めていくのか、あるいは被害を最小限にするための冗長性のようなものを高めていくことを考えていかなければいけないだろう。デジタル化は、平井大臣の担当だが、規制の観点から必要であれば支えていきたい。
――先日、テレビ番組で「邪魔な規制を外して、経済を成長させたい」と発言されていたが。
いろいろな分野があるのだろう。経済を前に進めるのは、政府ではなく、民間の知恵と努力であり、政府が事を決めて動かせるものではない。例えば、保税地域で、美術の展示はできるが、売買はできない。保税地域で、海外から美術品等を持ってきて、オークションを実施し、海外の方はそのまま税金の還付などをしなくて済み、持ち帰ることができれば、新しいビジネスができるようになるのではないか。恐らくそうしたネタはたくさんある。それを民間がいかに拾い、こちらに投げてくれるか。投げてきてくれたものは、こちらで対応していきたい。
――規制改革の担当大臣として初めて取り組んだのが、押印の廃止。ほとんどが廃止できそう、とのことだが、手応え、受け止めは。次は「紙とファクスの廃止」と言っていたが、具体的な指示を出しているのか。
行政手続きで印鑑を押す行為がなくなるのは、それだけで利便性は上がるのだろう。押印が要求されなくなれば、紙で打ち出す必要もなくなってくるだろう。押印をなくすことだけが目的でやっているわけではなく、その次がある途中のステップ。果たしてその手続きそのものが必要なのかどうかまで、全部とは言わないが、いずれは考えていくことになるものもある。またいろいろなものが上がってくる時に、今のルートで果たして適切なのかも考えていかなければいけないと思う。「400メートルリレーの第一走者がスタートをきった」程度のところだと思ってもらえればいい。
――行政改革目安箱「縦割り110番」ホットラインについて。
規制改革のアイデアを広く集めようとして設置をした。想定をはるかに上回るメールをいただいた。規制改革については直轄チームに渡していく。非常に多くの方から、悩んでいたり、困難に直面していることを赤裸々に切々と書かれたメールがたくさん来た。「自分の思いを聞いてくれて、ありがとう」という感じのメールが多かった。世の中で、それだけ困っていること、困難に直面していることが多いことを改めて実感した。そうした声がたくさん寄せられて、読んでいて胸を打つようなものもあった。この機会を利用して、思いを寄せてくださった方には感謝を申し上げたい。年配の方から、高校生くらいの若い方まで、経済的な悩みから病気の悩みまで、さまざまな悩みに接することができ、ありがたい。想定を超える件数だったので、これ以上、私が全て目を通すわけには物理的にいかないと思って、一度止めたが、こうした思いを政府としてすくい上げていかなければいけないと思う。いろいろな方に向かって開いている窓口があり、そうした窓口をお知らせすることも一つのやり方だと思う。社会の中の困難、あるいは悩んでいることをすくい上げて、国、自治体がどう対応していくかをしっかりと考えていかなければならないことを認識した意味でもありがたいと思う。内閣府のホットラインに統合して、規制改革、行政改革のアイデアを募ることは続けていきたいと思っている。それとは別に、非常に多く寄せられたことについては、今、名案があるわけではないが、何か考えていかなければいけないと思っている。
――Twitterなど、SNSで積極的に情報発信していることについて。
ひまつぶしでやっているものなので、あまり肩に力を入れずにやっていきたい。フォロワーの方に楽しんでいただければいい。似顔絵などを送ってくださり、私も喜んでいる。楽しいものは紹介していきたい。あまり難しいことは考えずにやっていきたい。
河野大臣は「銀行印が必要なものや法律で押印が定められているものなど、検討対象は若干あるが、大半は廃止できる」との見方を示した。
河野大臣は9月24日に行政手続きでの押印を原則廃止するように各省庁に要請。はんこが必要な場合は、その理由を9月末までに回答するよう求めていた。
7月に閣議決定した規制改革実施計画では、押印の廃止を含む手続きの見直しを年内をめどに求めており、今回3カ月ほど前倒しした形となる。
河野行政改革担当大臣は、規制改革や行政改革をスピード感をもって進めるため1日、みずからの直轄チームを発足させ、内閣府のほか、愛知県や高知県といった地方自治体の職員など合わせて9人に辞令を手渡しました。
そして、河野大臣は「菅内閣は、『国民から見て価値を作り出す規制改革を内閣の1丁目1番地としてやる』と言って スタートした。遠慮することなく、規制改革を着実に進めなければならず、全身全霊をかけてやってもらいたい」と訓示しました。
直轄チームでは河野大臣のウェブサイトなどを通じて寄せられた規制改革や、行政改革についての提案を精査したうえで、関係省庁と連携して、実現に向けた取り組みを急ぐことにしており、今後、さらに態勢を拡充していく方針です。
河野行政改革担当大臣は、すべての府省庁に対し、行政手続き上の押印を可能なかぎり不要とするよう求めていて、年間の利用が1万件を超える手続きについては、先月30日までに検討結果を報告するよう要請していました。
これについて河野大臣は1日、報道各社のインタビューで「800種類ぐらいの手続きのうち、廃止の方向と言えないものが35種類ほどあったが、『法律などが押印を要求している』というものは、変えればいいだけのことだ」と述べました。
そのうえで、河野大臣は「理由があれば相談に応じるが、『全部、押印はいらないのでは』と思って押し戻している」と述べ、年間の利用が1万件を超える行政手続き上の押印については、法改正などで廃止できるのではないかという見方を示しました。
また、河野大臣は国家公務員の働き方をめぐり、すべての府省庁に対し来月までの2か月間、職員の職場での滞在時間を調査するよう指示したことを明らかにし、調査結果をもとに業務の見直しを進める考えを示しました。
保税地域は、これまでも美術品の展示場などとしては使われていた。外国人が売買品をそのまま海外に持ち出せば、税金の支払いや還付手続きが簡素化できる。法改正などは不要といい、河野氏は「日本での美術品などの売買が盛んになり新たなチャンスになるだろう」と述べた。

朝日新聞などのインタビューに答えた。平井氏は「私と河野氏+1で政治家だけで話し合う機会を設ける。十分に話し合った上でターゲットを決めて、ロックオン(追跡)するやり方になる」と述べた。近く田村憲久厚生労働相、萩生田光一文部科学相とそれぞれ会合を持つ予定だという。
オンライン診療は、新型コロナウイルスの流行期に限って初診から特例的に認めているが、菅義偉首相は恒久化したい考えだ。平井氏は医師のなりすましを防ぐために「マイナンバーカードと医師免許の連携が必要だ」との認識を示し、政府として日本医師会と調整していく考えを示した。
教育については「学校で1人1台の端末の配備が進んでいるが、配布することで終わってはいけない」と指摘。オンライン教材の活用や学習データの分析について「議論を先導していきたい」とした。オンライン授業を正式な授業日数に含められるようにすることなどを萩生田氏と議論する意向だ。
朝日新聞の報道によれば、“自らのHPに「行政改革目安箱」を開いたが、4千件を超える情報や意見が殺到して停止していた。自らがすべてに目を通す方針も見直す。 ”という。〈参照:縦割り110番は内閣府に 河野氏「全部読む」も修正:朝日新聞デジタル〉
「行革目安箱(縦割り110番)」とは、河野太郎氏が個人サイトに設置した投稿フォームだ。当初、すべての投稿を河野大臣が読むとしていたものの、投稿が殺到したため内閣府に開設することとなった、という。
“目安箱をつくった17日段階では、届いたものを「全部読む」と明言していた。ただ、想定を大きく上回り、翌日には停止。25日の会見では「物理的に続けていくのは正直厳しい状況」としたうえで、今後は「役所のプロセスにまず乗せ、必要なものには目を通していきたい」と軌道修正した。”〈参照:縦割り110番は内閣府に 河野氏「全部読む」も修正:朝日新聞デジタル〉
もちろん、行政の長たる大臣が直接いろいろな意見を受けるのは良いことである。
しかし、問題はこの縦割り110番の投稿フォームが、当初河野太郎氏個人のWebサイト上に設置されていたことだ。
かつて、金子恵美参院議員が公務以外で公用車を利用していたことが発覚し、問題になったことがあった。〈参照:保育所送迎に公用車「ルール上問題ない」 総務政務官|日本経済新聞〉
あるいは、舛添要一都知事の公用車利用は、直接的に都知事交代の引き金となっていた。〈参照:舛添知事、公用車で別荘通い 年に48回「全く問題ない」|産経新聞〉
公用車利用の是非についてはここでは明言を避けるが、「議員」という立法府の役割と「大臣・副大臣・政務官」という行政府の役割、あるいは私人としての立場は分けなくてはいけないということは明らかだろう。
例えば、ドナルド・トランプ氏個人のTwitterアカウントと、アメリカ大統領のアカウントも分けられているように、公と私を分けることは一般的に日本に限らず、重要なことだ。
ヒラリー・クリントン氏は、公務で個人のGmailを利用したことを批判されている。〈参照:ヒラリー氏、公務に私的メール使用 波紋広がる 国務長官時代|ウォール・ストリート・ジャーナル〉
私が河野氏のサイトに設置されたフォームを見た時点では、そもそもプライバシーポリシーなど、送信した情報がどのように使われるかは明示されていなかった。
縦割り110番に対してメッセージを送った方は、「大臣として」の河野太郎氏にメッセージを送ったわけだろうと思うが、政治家個人のメールというものは、個人だけが見るということはありえない。秘書や事務所の関係者などは必ず閲覧することになる。
もちろん、例えば特定のメールアドレスにフォームの内容を送信し、第三者が絶対に見られないという前提であれば、一定の秘匿性は担保されるかもしれないが、明示されていない以上、その解釈を取ることは無理があるだろう。
しかも、例えば大臣が読んだあとにそのメールがどうなっているのか、適切に破棄されたのかなどの情報は一切ない。
極論すればフォームを送信した人に対して、「ご意見をお寄せいただきありがとうございました。なおこのあとの進捗はメールマガジンにご登録ください」など、フォローアップと宣伝のメールを送ることも不可能ではない。
以上のことを考えれば、河野太郎氏個人のWebサイトに行政改革担当大臣としてのフォームを載せるのは到底ありえない話で、そもそも内閣府に設置することがすぐできるのであれば、最初からそっちでやれば良いのである。
極論すれば大臣としての地位を利用して、Webサイトのアクセスと、メールアドレスのリストを入手したという解釈もできなくもない訳で、問題が大きい。まさに字義通りの「公私混同」と言えるのではないか。
内閣府や参加者によると会合では、放送をインターネットで同時配信する際、映像などの使用許諾が別々に求められるため事業者の権利処理の負担が大きく、コンテンツ産業の成長の妨げとも指摘されている問題を巡り、関係省庁や有識者が議論した。
その席上、文化庁の担当者は庁内で検討した際、「タイトなスケジュールで多くを追求し過ぎると虻蜂(あぶはち)取らずになる」などと指摘する意見があったと紹介。著作権などに関する制度自体の改正が必要な点は来年の通常国会に向けて準備する一方、運用面での改善も探る方針を説明した。
それに対し、有識者からは「制度改正を進めるべきだ」「議論の先延ばしに見える」などの異論が噴出。河野氏も「文化庁の方針ではダメだ。国民の利便性を考えていない」と一蹴し「心を入れ替えて、スピード感をもって対応すべきだ」とたたみかけた。
さらに河野氏は、他のWGでの検討も含めて「1回目の節目は10月だ」と述べ、来月中に方向性を示すよう求める考えを表明した。通常は各WGでの結論を同時期にまとめて発表するが、案件ごとに随時結論を出させ、議論を加速させる意向とみられる。
しかし、結果的には、「異次元緩和」はマイナス金利の弊害が言われ、財政政策はいつの間にか「消費増税」及び「財政大盤振る舞いのステルスでの手じまい」となり、「規制緩和」は「加計学園」や「IRに伴う収賄、国会議員の逮捕」とか尻すぼみになり、盛り下がってしまった…。
そこへ、コロナが襲いかかり、経済は縮小し、東京2020も寂しいものになるのは必定な状況となった…。
菅さんとしては、何とか「デジタル」を突破口に、省庁縦割りを打破し、もう一度「規制緩和」へと、舵を戻したいところだろう…。ある程度の成果を上げることができれば、「本格政権」も視野に入ってくるはずだから、ここは頑張ってほしいところだ…。
●
一大事件の発生時など、新聞各紙が同じ日に同じテーマの社説を載せることがある。題材が共通しているだけに、読み比べるとそれぞれの社論の特性がつかめる。今のように新しい政権が船出したときは、その機会がたびたびある。
17日、主要紙がこぞって菅義偉政権の発足を社説で論じた。日本経済新聞は「新首相は『安倍政治の継承』を掲げて自民党総裁選に勝利したが、前政権と全く同じではないはずだ」と前置きしたうえで「迅速と丁寧が両立した政治主導」を求めた。
朝日新聞は「菅『継承』内閣が発足 安倍政治の焼き直しはご免だ」という見出しで、冒頭から「政策のみならず、人事・体制においても、安倍政権の『継承』は歴然だ」と決めつけた。記事中に「安倍改造内閣」なる表現も登場する。菅内閣を安倍亜流内閣と皮肉った立憲民主党の枝野幸男代表と同じ見方である。
●原則毎月第4水曜日に掲載します
スガノミクス(菅首相の経済政策)はその実、どちらに近いのか。成長戦略の面から考えてみる。
16日夜の首相就任記者会見で日経記者に規制改革の具体策について問われた菅氏は、ダム管理を担当する役所の縦割り行政や携帯電話3社による長年の寡占体制がもたらした弊害に触れ「規制改革を政権のど真ん中に置く」と語った。経済的規制だけではなく社会的規制を含めて変革させ、民間企業の創意工夫を引き出しやすくし、消費者の利便性を向上させ、成長につなげたいという政権戦略がみえてくる。
規制改革を成長戦略の柱に据えたのは、安倍政権も同じだ。2014年1月、雪深いスイスの山岳リゾートに飛んだ安倍氏は、世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)でのスピーチで、地域を限って規制改革を推し進める国家戦略特区が始動することを紹介し「向こう2年間、いかなる既得権益といえども私の『ドリル』から無傷ではいられない」と豪語し、岩盤規制改革を果断に推し進める姿勢を示した。
●菅首相は参入障壁の打破に強いこだわりを持つ
じつは「岩盤規制」は政府の規制改革会議議長を長くつとめたオリックスのシニア・チェアマン宮内義彦氏の造語だ。2004年に筆者が宮内氏にインタビューした際、公共サービスの民間開放や海外から高度人材を受け入れるための日本版グリーンカードの創設を例示し「岩盤に少し動意がみえた」と語っていた。
「ドリルから無傷ではいられない」はコンセプチュアル(概念的)なメッセージの発信に長(た)けていた前首相ならではだろう。しかし安倍政権の規制改革は、宮内氏が活躍した小泉政権の頃に比べると、成果は「中くらいなり」だった。
農協改革にはみるべき点があるが、雇用市場改革は道半ばだった。たとえば企業の経営側が従業員に相応の対価を払うことで解雇をめぐる争いに終止符を打つ「解雇の金銭解決」は、岩盤規制の象徴だが、労組団体の抵抗に遭って制度化を断念した。ダボス会議で紹介した国家戦略特区は加計学園問題のあおりで失速し、勢いを取り戻せずじまいだった。
規制改革は推進しようとする側にとって、骨が折れる政治的な難題だ。業界団体など特定勢力が有する既得権益は規制や保護政策によって生み出される。それを打ち破るのが本来の規制改革だが、権益を守ろうとする側は「推進側が新たな利権を手にしようとしている」などと反論することが往々にしてある。加計学園問題の本質は獣医師の業界団体が持つ権益だったが、論点はいつの間にか加計学園幹部と前首相との関係にすり替わっていた。
しかも、改革によって業界団体が失う既得権益は大きく外からみえやすいのに対し、多くの人が手にするメリットは1人あたりにすると小さく外からはみえにくい。参入規制を緩和・撤廃すれば競争原理が働き、新参者にとっては努力が報われやすい。半面、競争という言葉には他人を蹴落とすことで痛みを強いるニュアンスがある。こうしたこともあって、世論はどちらかというと権益を失う側に味方しがちだ。仮にこれを「規制改革のパラドックス」と呼ぶことにしよう。
●国家戦略特区は加計学園問題のあおりで失速した
筆者は、安倍前首相はこのパラドックスに敏感だったのではないかと考えている。加計学園の事例は自身がかかわる問題なので別にしても、自助と市場原理を掲げる新自由主義より、アベノミクスの「第2の矢」と称して財政赤字をさほど気にすることなく政府主導で財政資金を分配する「疑似左派的」な政策をいとわなかったのがその傍証になろう。安倍氏の疑似左派的な政策については、気鋭の政治思想家である宇野重規・東京大学社会科学研究所教授が朝日新聞の言論サイト「論座」に明快な論考を寄せている。
一方の菅首相は自民党総裁選などでの発言を総合すると、新自由主義的なスタンスを前面に出そうとしているとみて差し支えなかろう。めざす国家像として「自助、共助、公助」を提示し、政府が張るセーフティーネット(安全網)はラストリゾートとして機能させると示唆したのが、それを裏づけている。
菅首相の規制改革にかける意気込みは前首相より強い。官房長官のときに携帯寡占の問題に切り込んだ実績からも、自由な競争が消費者の利便を高める原理を熟知しているのがわかる。新政権発足で政策の立案・実行過程がどう変わるか。これは、有権者はもちろん、首相に仕える霞が関官僚にとっても一大関心事だ。
新首相の発言とそこに秘められた意図を吟味することなく「前政権の継承は歴然だ」と断定する社説は、少なくとも成長戦略の観点からは参考になるまい。
これまでは初診時の対面義務といった規制に縛られ普及が進んでいない。パソコンやスマートフォンで医師がいつでも対応できれば、患者の利便性は高まる。せっかく新首相がゴーサインを出しても厚生労働省の中からは「オンラインは対面より診療の質が落ちる」といった声が漏れる。
「拙速に一律に進めるのではなく、丁寧な合意形成を」。17日の記者会見で日本医師会の中川俊男会長はけん制した。安全確保には対面が必要と主張する。地方の診療所などにはオンライン診療が広がれば都市部の病院に患者をとられるとの危機感がある。
菅義偉首相は17日午後、首相官邸に河野太郎行政改革・規制改革相を閣僚のなかで最初に呼び「しっかりやるように」と指示した。河野氏は同日午後、自身のツイッターで「行政改革目安箱(縦割り110番)」を新設した。本人がすべての意見に目を通すという。
長年維持される「岩盤規制」は簡単には崩れない。国民が得られるはずの利益を規制が奪うケースはいくつもある。
ネット企業のBotExpress(東京・港)は10日、総務省を相手に東京地方裁判所に訴えを起こした。同社が4月に始めたLINEアプリで住民票を取り寄せられるサービスに「待った」をかけられたからだ。
総務省は「国が求める電子署名で本人確認をしていない」として全国の自治体に導入しないよう通知を出した。しかしLINEは広く国民に普及し、新サービスでは顔認証など最新技術も導入している。
中島一樹社長は「国の規制は民間のアイデアや技術を阻害する。規制を解いてくれればイノベーションはもっと前進するのに」と憤る。
政府はコロナ対策で大規模な財政出動に踏み切り2020年度の歳出総額は160兆円超に達する。公的債務の国内総生産(GDP)比率は21年度には250%を超える恐れがある。財政を立て直す原資は成長戦略で作り出すしかない。
「日本は潜在成長率を今より1.5〜2ポイント程度高められる」。世界がリーマン・ショックに揺れていた08年、ペンシルベニア大学のクライン教授ら日米の経済学者がこんな共同研究をまとめた。米国のように規制緩和を進めてIT(情報技術)革新を進めれば3%成長を達成できると提言した。
その後、日本の潜在成長率は1%未満に落ち込み欧米各国を下回って推移した。この結果を見れば、革新を起こす努力を怠ったといわざるをえない。世界銀行が毎年公表するビジネスのしやすさに関するランキングで日本は29位にとどまる。
九州大学大学院の篠崎彰彦教授は「取り逃がした成長力を取り戻すには、今からでも医療や教育など公的サービスをもっと民間に開放すべきだ」と強調する。
アベノミクスが掲げた「3本の矢」のうち成長戦略は尻すぼみに終わった。菅新政権が取り組むべき政策を検証する。
成長戦略の一丁目一番地とされたのは、「岩盤規制」改革だった。
当初の安倍晋三首相の意気込みは強かった。2014年のダボス会議では自ら「これから2年間で、ドリルですべての岩盤規制を砕く」と表明し、世界の注目を集めた。しかし、残念ながら成果は乏しく、課題は新政権に積み残された。
成果が全くなかったわけではない。
農協制度は60年ぶり、漁業制度は70年ぶりの大改革がなされた。国家戦略特区では、37年ぶりの医学部新設、52年ぶりの獣医学部新設もなされた。国家戦略特区の都市計画手続の特例を活用し、東京都内では30カ所以上の再開発プロジェクトが進んだ。
だが、多くの分野で規制改革は停滞した。
とりわけ、世界で急速に進むデジタル変革への対応は出遅れた。医療や教育のオンライン対応など、部分的には前進しつつも、厚い壁をなかなか突破しきれなかった。そうこうするうち、コロナ禍で図らずも改革の遅れが露呈した。
行政手続のオンライン化も、スローガンは何度となく唱えられたが、現実は進まなかった。せっかく設けられたマイナンバーは利用目的が限定され、10万円の給付に利用できなかった。全国自治体で、職員が申請と住民台帳をつきあわせる膨大な事務作業に追われることになった。もうちょっと早く規制改革を実現していれば、と悔やまれることが多かった。
●「岩盤規制」が経済成長を阻む
「岩盤規制」がもたらしているのは、「オンラインで診療や授業を受けられない」といった利便性の問題にとどまらない。
経済社会全体で生産性の低迷、ひいては1人当たりGDP(国内総生産)の低迷をもたらしてきた。日本の1人当たりGDPは、OECD(経済協力開発機構)加盟36カ国中18位(2018年、購買力平価ベース)。米国やドイツには遠く及ばず、OECD平均よりも低い。2012年末以降の安倍政権で、株価は大幅に上がったが、1人当たりGDPの順位は上がらなかった。むしろ、主要先進国との差は広がった。
大きな要因は、デジタル変革の遅れをはじめ、古い仕組みの維持、イノベーションの欠如だ。そして、古い仕組みを強いているのが、「岩盤規制」だ。だから、成長戦略の一丁目一番地は「岩盤規制」改革でなければならなかったのだ。
古い仕組みが随所に残る代表的分野が、「電波」である。
電波は、これからのデジタル社会で重要度が飛躍的に高まる。人と人のコミュニケーションだけでなく、あらゆるモノがネットワークでつながるための基盤だからだ。
問題は、電波の帯域は限られ、使い勝手のよい帯域は古くから使用されていることだ。このため、たとえば米国では、地上波テレビの帯域を逆オークションで買い上げ、より高い利用ニーズを持つ事業者にオークション売却するなどの仕掛けを導入している。未来の成長産業にスペースをあけるため、いわば電波帯域で“都市再開発”を行っているわけだ。
安倍政権下ではこうした議論もなされ、取組が一部進んだが、電波オークションはいまだに実現せず、放送制度改革も前進は小さかった。むしろ本筋から外れた「放送法4条(放送局に「政治的公平性」を義務付ける)撤廃」論などで大混乱の起きた経過は、拙著『岩盤規制』で詳述したとおりだ。
前掲の表では、主要分野の岩盤規制をあげた。実はこれ以外に、細々した分野の規制が膨大にある。
たとえば、『岩盤規制』でも取り上げた「クリーニングの無人ロッカー」がその一例だ。コロナ対応で「非接触」への転換が諸分野で進む中、クリーニングでも、ロッカーで洗濯物の受け渡しを行う無人店舗があってもよさそうなものだ。ところが、厚生労働省の通達では、洗濯物の受け渡しはカウンターでの対面でなされる必要があり、無人ロッカーは不可とされる。衛生管理ならばロッカーでも徹底可能なので、理屈はよくわからない。しかも、マンションの宅配ボックスを利用した「ネット宅配クリーニング」は規制対象外で野放しにされているのだから、厚労省の対応はおよそ筋が通らない。
こんなことが起きるのは、無人ロッカーの設備投資ができるのは比較的大手の事業者であり、資力の乏しい零細クリーニング店にとって解禁が好ましくないためだ。零細クリーニング店といえども業界団体など政治力はあるので、無意味な規制維持を政治・行政に強力に求め、これがまかり通っているのが現実だ。
現に、規制改革推進会議でこの議論をした際、自民党の某長老議員が直ちに事務局に電話をかけてきてストップをかけた。残念ながら、そんな電話一本で止まってしまうのが今の規制改革の実情だ。
こうした1つ1つは小さな、しかし不合理な規制が積み重なり、日本のそこら中でイノベーションを阻み、日本経済の生産性を低迷させているのである。
●「新・利権トライアングル」
「安倍一強」とも言われた強力な政権で、「岩盤規制」改革はなぜ進まなかったのか。答えの1つは、安倍政権は決して「官邸主導」ではなかったことだ。詳しくは経済学者・高橋洋一氏との共著『国家の怠慢』でも書いたが、外交・安保は別として、内政は概ねコンセンサス重視だった。
そして、もう1つの、より重要な答えは、前掲の表の中に隠されている。
各項目の実現時期をみると、右半分の国家戦略特区での規制改革が2017年でぱったりと止まった。2017年通常国会で「加計問題」の疑惑追及がスタートして以降だ。
「首相の友人への利益誘導」
「首相への忖度で規制改革」
などと、国家戦略特区での獣医学部新設を巡って、マスコミや国会での追及が長く続いた。国家戦略特区ワーキンググループの委員を務めていた私から見れば、根拠不明の“疑惑追及”だが、ともかく、追及が続くうちに、関係者の多くは「規制改革をやって、またあらぬ疑惑追及を受けたら堪らない」と、新たな規制改革に及び腰になってしまった。
これが、安倍政権後半に「岩盤規制」改革をストップさせた「壁」の正体だ。
これも詳しくは『国家の怠慢』で論じたが、マスコミや国会での“疑惑追及”は、実はデタラメだらけだ。
伝統的な「鉄のトライアングル」で一角を占める与党族議員の代わりに、マスコミと野党議員が登場。その裏側に隠れて、利権を守りたい役所と業界が規制改革にストップをかける。しかも、マスコミと野党議員は、事実かどうかにかかわりなく、国会で“疑惑追及”したらマスコミで報道、マスコミで“疑惑”を報じればそれを国会で追及、と“証拠なき追及”を無限サイクルで回し続けることができる。
私はこれを「新・利権トライアングル」と呼んでいる。
これを正さない限り、どんなに強力な政権でも「岩盤規制」改革は難しい。そして、これを放置する「国家の怠慢」による、我が国の地盤沈下を止めることも難しいのである。



 2020/1-6
2020/1-6国税庁が5月1日、1本の通達を出した。アルコール度数の高い酒を手の消毒用として出荷する場合には酒税を課さないとしたのだ。新型コロナので蔓延で消毒用のアルコールが不足し、ドラッグストアなどの棚から姿を消して久しい。酒造メーカーは度数60度以上の「酒」を作ることが可能で、それならば消毒用に使える。一升瓶に入れて近隣の病院などに納めたいという声が上がったが、「飲むことが可能なアルコール」は酒税法で「酒」と定義され、酒税がかかるという難題が生じた。蒸留酒はアルコール度数に応じて酒税が上がる仕組みのため、高度数のアルコールだと、1升(1.8リットル)あたり1100円から1400円前後もの酒税を納めなければならない。
そんな杓子定規の規制に批判が集まり国税庁はしぶしぶ非課税を決めたが、今回の措置はあくまで「臨時的な特例」という立場だ。「飲用不可」などとラベルを貼って消毒用として出荷することを求めている。一方で、無免許での製造や販売は酒税法違反に問われると、国税庁は注意を呼びかけるのも忘れない。
新型コロナへの対応を機に、本当に必要な規制なのかを示す結果となった。消費税が導入されているのに、なぜ「酒」だけに高税率を課すのか。酒税が明治以来、国の税収の柱だったことが理由で、それが脈々と続いているにすぎない。ところが今や酒税収入は税収全体の3%を切っている。地ビールや地酒がブームになっても新規参入には高い壁が設けられ続けてきた。新型コロナ禍は、そんな「岩盤規制」自体を問い直すきっかけになっている。
「予備費を使ってパソコンを支給したらどうか」。ある省の事務次官が厚生労働省の幹部にそんな苦言を呈していた。加藤勝信・厚生労働相が「テレワークの推進」を呼びかけている足元で、厚労省の課長補佐が、自宅に持ち帰れる業務用パソコンを支給されていないため、テレワークができないということが話題になった。パンデミック対策を考えてきたはずの厚労省ですら、交通が途絶し役所に通勤できなくなる事態を想定していなかったわけだ。
首都圏のある自治体でも、緊急事態発令後も全職員が登庁して勤務に当たっていた。4月下旬になってようやく、職員の半数を在宅にすることを決めたが、「実際には自宅でできる業務はごく一部だ」とその自治体の幹部は話す。従来、業務に当たって、個人のパソコンを利用することは禁じられてきたからだ。在宅勤務で役所のホスト・コンピューターに接続できる権限を付与設定したパソコンは、1万人以上の職員に対してわずかに60台だという。情報流出などの防止を優先するあまり、テレワークせざるを得ない事態はこちらも「想定外」だった。
霞が関や一部の伝統的企業のカルチャーは、「責任が問われかねないリスクはとらない」というもの。必要だと分かっていてもなかなか見直しには着手せず、前例踏襲で済ませてきた。岩盤規制と呼ばれる規制の裏には、それを守る既得権者がいるケースもあるが、規制自体を見直した場合に受ける「批判」や「責任追及」を恐れるという役所文化がある。
安倍晋三首相は、アベノミクスを掲げる中で「規制改革が一丁目一番地だ」と繰り返してきた。ところが、政府の特区諮問会議が出した資料では、2017年6月を最後に特区法改正はなされず、岩盤規制改革は放置されているとして次のように書かれている。
「この2年余りの間、新たに決定・制度化された規制改革措置は、すべて法律事項以外であり、かつ僅か一桁(9件)に止まっており、その前の約3年間の82件に比べ、改革は著しく停滞している」
要は、規制改革はピタリと止まってしまっていたというのだ。
●放置されてきた岩盤規制 今こそ必要な改革
それが新型コロナ対策で、動き出さざるを得なくなっている。4月7日には政府の規制改革推進会議が、受診歴のない患者も含め、初診からオンライン診療を認めることを決めた。また、オンライン服薬指導についても規制を大幅緩和した。これまでは医師会や薬剤師会の反対で、オンライン診療は進んでいなかった。当面新型コロナ対策での「時限措置」ということになっているが、おそらくこれが「ニューノーマル」となり、元に戻すことはできないだろう。
●大企業にも迫られる トリアージ(選別)
「中堅に資本支援1兆円 地方企業の破綻防ぐ」―─。5月1日付の日本経済新聞は1面トップで、新型コロナ蔓延による営業自粛などで経営危機に陥っている中小企業に官民ファンドを通じて資本注入することを政府が検討していると報じた。1件あたり100億円規模の出資も認めるとし、「地域の雇用と経済を支える中核企業の破綻を防ぐ」としている。
経済がまさに「凍りついた」ことで、観光関連の旅館やホテル、外食産業など地域の産業は崩壊の危機に直面している。4月の新車販売台数が速報で28.6%減となるなど、今後、裾野の広い自動車メーカーの減産が本格化すれば、経済への打撃は計り知れない。企業が倒産して経済システムが壊れてしまえば、新型コロナの蔓延が終息しても、経済が復活することができなくなる。資本注入は不可避の選択と言える。
経済活動の凍結が長引けば、中小企業のみならず、大企業にも資本注入が必要になり、「実質国有化」されるところも出始める。米国のドナルド・トランプ大統領は早い段階から航空会社への支援を想定して経済対策を打ち出している。
だが、すべての企業を国が資本注入して救うことは現実には難しい。そうなると企業を選別することが必要になる。新型コロナ後の経済社会で絶対に必要な企業を残すために「トリアージ」しなければならなくなる。
テレワークの進展に伴う業務のオンライン化やデジタル化で、社会は間違いなく大きく変わる。新型コロナが終息しても「元の世界」には完全には戻らないだろう。そうなると求められる産業や企業も大きく変わる。ここで構造転換を進められるかどうかが、コロナ後の成長を可能にするかどうかの分かれ道になるだろう。
●大恐慌の教訓 危機を変化のきっかけに
実は、現代では当たり前と思われている制度や仕組み、生活習慣などが、1929年に始まった世界大恐慌をきっかけに出来上がったものがいくつもある。未曾有の危機を乗り越えようと、様々な改革が検討され、実行された結果だ。例えば「週40時間労働」が基準になったのも、大恐慌後の改革から始まった。最低賃金や16歳未満の児童労働の禁止なども、今流で言うワークシェアリングを実行するために導入が求められた。
1930年代にはオフィスの光景も大きく変わったと言われる。「個人秘書にかわって速記者のグループが最新の口述録音機を使って仕事をする光景が見られた」(秋元栄一著『世界大恐慌』講談社学術文庫)という。つまり、1920年代に一気に花開いた技術革新とそれに伴う働き方の変化は、大恐慌以降、元に戻るどころか、むしろ加速したわけだ。
5月4日、政府は緊急事態宣言の延長とともに「新しい生活様式」を打ち出した。テレワークやオンライン会議、時差通勤などが「新しい働き方」とされ、食事もテイクアウトや宅配へのシフト継続を求めている。やはり、新型コロナが終息しても、生活は元には戻らない、ということだろう。
「新しい働き方」が求められれば、企業の行動も変わる。昨年あたりからDX(デジタル・トランスフォーメーション)が叫ばれるようになった。紙とハンコで進めてきた業務をデジタルに置き換えるだけでなく、すべての業務をデジタルで行うことを前提に見直し、業務全体を効率化するという動きだ。2020年に入ると先進的な企業の間では部門横断的にDXに取り組む責任者である、CDXO(チーフ・DX・オフィサー=最高DX責任者)を任命する例が相次いだ。
つまり、時代の変化が始まっていたところに、新型コロナ禍による「新しい生活様式」が加わり、変化を加速させつつあるのだ。新型コロナに伴う経済凍結は、このままでは90年前とは比べものにならない経済収縮をもたらし、社会の仕組みを根本から見直すことが突きつけられることになる。




 2019
2019こんにちは、税理士法人YFPクレア 営業部の越尾です。
11月も中旬に差し掛かり、税理士法人YFPクレアではいつも以上にあわただしい毎日を過ごしております。毎日のように年末調整のご相談のお電話を頂戴し、人数や精算するお日にちを伺い、可能かどうかを社内に確認したりする毎日です。
一時は「こんなに沢山の年末調整をとれるだろうか…」「スタッフにちゃんと仕事を行き渡らせることができるだろうか…」と営業部的には心配をしたのですが、頑張ったかいがあり、12月精算の年末調整は既にご契約いただいているお客様でいっぱいにすることができました。
残りは1月精算!そして、確定申告の目標件数だけだ!と、スタッフより少し先に営業部は意気込んでおります。
さてさて、そんな中、天皇陛下御即位のパレードも無事に終わり、大変お美しい皇后陛下と優しく温かいほほえみの天皇陛下のパレードの中継を見ては、令和の時代は日本の勢いを盛り返したい!と思ったものです。
日本が先進国だったのは今は昔…となりつつあり、貧富の差や少子化など問題盛りだくさんの昨今、日本が豊かな国って胸を張って言えない人も多いのではないでしょうか?
最近では「NHKをぶっつぶす!」という名文句をNHKの政見放送で繰り返して訴える立花議員が何かと話題に上がっていますね。私はテレビがない生活を送っているので、NHKにお金を払う義理はないと考えているので、スクランブル放送にしてもらって、早くテレビを見ない自由を手にしたいです。
第一、生きていくのに必須なはずの電気やガスや水はお金払っていないと止められるのに、電波は押し付けてくるって相当に迷惑なお話です。NHKの存在は否定しないし、見たい人は見ればいいと思うけど、私はNHKどころかテレビがいらないのでその拒否権をちゃんと認めてほしいです。昔、パリに行ったときにミサンガを押し売りしている現地のヤンキー?ヤクザ?がいましたが、それと同じくらい迷惑です。
NHKの高給取りからすると、月額3,000円は高くないつもりらしいですが、毎日の食費を切り詰めつつ、健康的な食事や食べたいものをモリモリ提供できるように家計簿とにらめっこしている私からすると「はぁぁぁぁ????3,000円あったらどんだけお野菜買えると思ってんの!?」と思います。キャベツ1玉100円として30玉も買えます!毎日1玉!レタスが200円でも15個も買えます!
我が家はテレビがないので、夕食は夫婦二人、今日あったこととか、今後の作戦とか、色んな会話が優先されます。土日の朝には、カフェミュージックを流し、一緒にホットケーキを焼いて食べ、のんびりとした時間を過ごします。テレビを何となく見て、ダラダラと時間を消耗してしまい、気が付いたら夕方!ってこともありません。
住民税だって、住民票があれば払う義務が発生しますが、ホームレス(住民票がない)になれば、住民税を払う義務は無くなります。テレビだってなければNHKに払う義務はないはずなのに、こんなに揉める理由がイマイチわかりません。
話は変わりますが、結局、消費税増税を見ても、新聞は軽減税率の対象になりました。
これは、事実を見極めるためにも重要な観点です。5%や8%にするときは私の記憶が正しければ、ほぼほぼ、どのメディアも反対の声が大きかったはず。
なのに10%になるときは各メディアは賛成というか、中間の立場というか、反対の声を大きく取り上げることはありませんでした。それはなぜか。
【自分たち(マスコミ)は軽減税率だから懐は痛まないから】
それを考えると、NHKとマスコミと政府は全部つながっていることが伺えます。政府もうまいことマスコミを買収したものです。マスコミってお金を出してくれるところに簡単になびくんだなーってよくわかります。そんなマスコミに正義面されても、何が真実か分かりません。
吉本興業の闇営業のときも、どう考えても犯罪者集団の詐欺集団に目隠しをするのはおかしいですよね。犯罪者なのですから、犯罪抑止のために受け子の顔出しするべきだし、「こうやって顔さらされるようなことは安易に引き受けてはいけない!」と犯罪抑止につながるはず!それに、芸人たちはグレーでも、犯罪者集団の詐欺集団は黒です。ハッキリ黒とわかっている人たちを守り、グレーな芸人たちを叩く姿勢は「叩きやすいところを叩く」というありかたがよく見えます。
そんなマスコミに正義ヅラされとうないわ!!って思います。
また、司法も落ちたもので、未成年の女性への暴行事件への判決や、NHKの裁判においても時代遅れの法律に則った判決しか出せないようなので、そのレベルならもうAIに任せたほうがいいと思います。多分、AIの方が過去の判例を判断できるのではないでしょうか?民意に任せた司法も困りものですが、時代遅れの司法も困りものです。被害者になっても守られないと感じるので、常々、犯罪に巻き込まれないように注意しなければなりません。本当に…被害者の人権を守ってほしいです。この国は誰を守っているんだろう・・・って思います。
令和の時代、こんなのんびりと法令を整えているようでは日本はますます先進国から落ちぶれてしまうのではないかととても心配です。他国は次々に法令を整えて、新しいことにチャレンジできるようにしているのに、日本は一部の既得権益者を守るばかりで国益は失っているように見えます。これでは優秀な人達から海外へ行ってしまうでしょうよ・・・
私自身も脱出できる準備をしておかなければ…と思いつつも、やっぱりこの国が好きだから、この国が落ちぶれてしまうのなんて嫌!!
私にできることと言えば、今日も中小企業が頑張って儲かるように仕事を通じて応援したいと思います。
さて、今週も頑張ろう!

安倍:「NHKのスクランブル化」という、個々人の家計に直接響く政策が国民の支持を集めたとの見方があるが。
立花氏:「(NHKの受信料という)目先のお金よりも、既得権益に挑んだことが評価されたと思う」。
安倍:NHKから国民を守る党はどのような政策を掲げているのか
立花氏:「NHKのスクランブル化。それから、税率を(5%に)下げて税収を上げる。増税すれば消費が冷え込み、税収は下がる。これは江戸時代からわかっていることだ」。
安倍:国民民主党代表の玉木雄一郎氏や、れいわ新選組代表の山本太郎氏も減税を訴えている。主張に違いはあるのか。
立花氏:「玉木さんは、いろいろな政策を言い過ぎて分かりにくい。」
安倍: 国民民主党玉木代表に対し自公連立与党入りを打診したというが、その意図は何か。
立花氏:「安倍首相の懐にあえて飛び込む方が良い。野党は弱い。本当に国民のことを考えているのか。政権がやろうとしていることと世論との乖離を追及することで、中道保守として何某かの貢献ができると考えている」。
「玉木さんは、NHKから国民を守る会の政策を受け入れようとしている。彼には先を読む力がある。YouTubeを使った情報発信もすでに行っていた」。
安倍:立花氏も最近YouTubeの配信を盛んに行っている。
立花氏:「NHKから国民を守る党は、投票に行かない人から票を取る。投票に行かない人は、テレビを見ずにYouTubeを見る人が圧倒的に多い。投票に行かない世代は、何を求めているか。消費税増税は嫌。そしてスマートフォンの負担。スマートフォンは国民の生命や財産を守るために必要だ。だから、スマートフォンの購入費や維持費を税金で保障する。これが響く。YouTubeで有名なタレントとタイアップするだけで、拡散力が相当違う。新聞やテレビより安価にCMが打てる」。
「玉木さんは、お金の使い方が下手。なぜなら、背後に既得権益の塊・連合があるから。『しがらみのない小池百合子』も、連合とくっついた後、失敗した。玉木さんは、これからの選挙でいかにしがらみが不利になるかを分かっている。連合と手を切ることのできる民主党系の人が10人ほど集まれば良いのではないか」。
●
安倍:野党勢力の大同団結についてはどのように考えているか。
立花氏:「大同団結は世界の潮流が許していない。左派ポピュリズムには限界がある。お金のない人たち向けの政策は伸びない」。
「山本太郎さんのれいわ新選組は、前回の参院選で、議席は1から2に増えたに過ぎない。立憲民主党の票を取っただけだ。今でこそ応援されているが、立憲民主党の枝野さんが2年前にもてはやされたのと同じ。山本太郎さんの情熱は素晴らしいが、政策は実現されていかない。支持者に実益が出ない。一過性だろう」。
「れいわ新選組は、次の衆議院選挙で、20億円を寄付で集めようとしている。自民党が経団連と竹中平蔵に忖度することと同じことをやろうとしている。NHKから国民を守る党は、政党助成金を10億円借りる。お金は必ず返す。返すあてがちゃんとあるから、忖度しない。人にお金はもらわない。借りて、利息をつけて返す。利息が忖度。それ以上のことはしない」。
安倍:与党に対しては、どのようにアプローチしているか。
立花氏:「まだおこがましい。自公と合流するには、参議院で少なくとも5議席くらい持っていないといけない。次の選挙、その次の選挙でどれくらい議席を伸ばすかを考えている。ゆっくりと国民に、政治、選挙、民主主義を発信することが自分の仕事だと思っている。今は、注目を浴びるような言動をしてヒール役になって、知ってもらう。民主主義は慌ててはいけない」。
「参議院で確実に票を伸ばしていくこと、新しい政治、選挙にお金をかけないという戦術を使うということ。国からもらう政党助成金や議員報酬の原資は、税金。税金を使って政治活動や選挙運動をする。そうすれば誰に忖度しなくてもいい。そういう新しい支持のやり方を、ゆっくり浸透させていくことが大事。直ちに何かをしようとは思っていない」。
安倍:今後、どのような候補者を発掘するか。
立花氏:「政治家が一番嫌がるのは盆踊りに行くこと。忘年会や冠婚葬祭。一般大衆に頭を下げなくてはいけない。それを取り除けば、多くの人が政治をすると思う。熱いのに、寒いのに駅前に立ってビラを配るのは、はっきり言って頭が悪い。頭の悪い人がが政治家をやっているから、官僚の言いなりになる」。
「今の日本の国会議員は、頂点の少し下の人がやっている。年収3000万くらいで喜んでいる。経営者って年収億超える。そういう人に降りてきてほしい。金銭不祥事の心配がない経営者や、法律に明るい弁護士が政治家になると良い」。
「行政は、国民の生命・財産を脅かすことができる。立法府はそれを縛る必要がある。国会議員は、法律を作らなくてはならない。ところが、立法府の人間は、行政府の人間の法律改正をほとんどそのまま受け入れている。法律知識があって、行動に移して、実現できるか。既得権益が潰しに来るのをはねのける力があるのか。ということ」。
「それがこれからYouTubeで発揮される。これまでの政治家はポスターのイメージ(で選ばれてきた)。これからは、YouTubeを使わないと、喋れないと思われて、有権者に選ばれなくなる。自分の言葉で抑揚をつけて説明できるかどうかが大事」。
「一部の賢い人たちが国を富ませて、一般大衆を養っていく。中国やアメリカはこれをよくわかっている。自分たちは一般の大衆であり、超一流の人を選ばないと国が滅びる、とわかっている。しかし、日本の場合は、有権者が自分を有権者様だと思っている。国を引っ張る人と自分たちは対等だと思っている。だから、共感を買う人に票が集まる。だから本当に頭のいい人たちは政治をしない。根底から変えなくてはいけない」。
「ドナルド・トランプさんも、『あなたたちのいうことをまともに聞いていたら国が衰退するから、俺に任せておけ。そのかわりあなたたちの生活はしっかり保障する』と説明すれば、『そうか、この人についていこう』となる。誰だって強いリーダーについていきたい。それをメディアが曲げてきたから伝わらなかった。だからTwitterやYouTubeを使って直接国民に訴えている」。
●
立花氏は、東京メトロポリタンテレビジョンとマツコ・デラックス氏に対して、集団訴訟を組織した。その目的は何か。
立花氏:「『戦うときはエネルギーを一点に集中させろ』と、NHK時代で学んだ。裏切り者が10人いた時、1人を攻撃すると残りの9人はビビる。マツコ・デラックスさんは、既得権益の表現者。テレビ局をたたくよりも分かりやすい。一番ぶち壊さなくてはならない敵はメディアだ。」
立花氏:「裁判は約1000件行った。現在進行しているのは50件ほど。」
安倍:安全保障や憲法改正の問題については、どう考えているか。
立花氏:「そろそろ日本もある程度の武力を(持たねばならない)。自衛隊自体がすでに相当な武力であるとは思う。竹島で自衛権が行使できていないことを見ると、政治家が誘導するのを好ましいとは思わない。政治家は憲法に縛られているから。9条については、『日本国を守るのか、戦わず植民地になる可能性をはらんだ状態でいるのか』広く国民に議論してもらいたい。交戦権を認めないという条文は、自衛権を否定している。NHKから国民を守る党は、直接民主主義を謳っているので、国民投票を含む改憲の発議には同意する。ただし、NHKのスクランブル放送の実現が伴わなければ、反対する可能性もある。」
安倍:NHKの受信料の問題については、様々な提案がなされている。受信料を廃止し、その分を税金で賄う案。立憲民主党の中谷一馬衆議院議員は、受信料を半額にする代わりに全世帯から徴収する案を提示している。これらについて、どう考えるか。
立花氏:「経費や番組内容を考えない意見だ。庶民の味方として権力を監視するのがNHKの役割。受信料が収入に関係なく均一であることがミソ。所得の高い低いにかかわらず、同じ圧力をNHKに対して持つようにする、本来庶民側につくような受信料制度。NHKを国営放送にするなら、いらないのではないか。公共放送をもう一つ作って国民が選べるようにし、切磋琢磨させる方法もとりうる」。
「労働組合や連合、その他のいわゆる既得権益、何もしない人たちがたくさん給料をもらっていて、今の制度を守ろうとしている。改革しようとする人間を、それ自体既得権益であるメディアを使って攻撃する」。
安倍:NHKのスクランブル化は、どのように実現するか。
立花氏:「過半数を取るのが一番確実だが、時間がかかる。あとは自民党との交渉ごとになる。現在はどの党も、スクランブル化をするかどうか、明確な答えをマニフェスト上で出していない。どこかの党が出して、自民党が票を奪われると危機感を持った時に、実現するのではないかと思う」。
「NHKのスクランブル化が実現すれば、NHKはつぶれる。その時には、他の既得権益も必ずつぶれる。消費税を0にすることや、政権交代をすることよりも難しい。実現するには、相当の回り道、裾野をひろげることをしなければいけない」。
「キーワードは『ゆっくり』。焦ってはいけない。今、戦後に計画されたような道路がやっとできてきている。一般大衆は目の前のことしか考えない。政治家は50年後、100年後の未来を考えて先行投資をしていかなくてはいけない。反発を受けても、これが正しいんだ、黙ってついておいで、という信頼をどこまで勝ち取ることができるのか。一般大衆は結果でしか判断しないから、説明せずに結果を見せる。そういう形でやっていかないと、国の舵取りはできない」。
「だから私は、目先の票にこだわっていない。それでも、同じように日本全体、子々孫々のことを考える人たちが、ある程度の数はいる。それを信じて毒を吐き続けるしかない」。
――韓国では環境と国土保全の要の一つである農業の多面的機能を憲法に明記し、食料安全保障の視点に立った農政の実行を政府に求める「1000万署名運動」が2018年7月に活発化したと聞きました。
米国と自由貿易協定(FTA)を結んでいる韓国では、米国産品への関税率はコメを除けば、実質ゼロの状態です。そんな米韓FTA締結に農業関係者は猛反発し、今回の署名運動には多くの市民が参加しました。韓国がFTAの締結に踏み切ったのは、国内総生産(GDP)に占める輸出の割合が日本の約8倍という事情があるからですが、このまま工業製品の輸出を最優先する状況が続けば、韓国の農業が滅びしてしまうという強い危機感を抱いていることの証しだと思います。
目下のところ、米国と韓国の間には競合するような農産物はありません。日本同様、すでに米国産の飼料穀物などは大量輸入されていますが、韓国が市場開放に応じたくないニンニクやキムチの原料となるハクサイなどは米国からは入ってきていません。こうしたなか、韓国が絶対にFTAを結びたくないと考えているのが中国です。
中国からはニンニクもハクサイもどんどん入ってきてしまう恐れがあり、「それだけは絶対に許さない」というのが韓国のポリシーで、日本とは違って「守るべきものは守る」という姿勢を貫いています。とにかくすごいのはニンニクの関税が「360%」で、パプリカの関税は「270%」という点です。さらにパプリカの輸出には補助金を投入し、国を挙げて輸出促進に力を入れています。
●EUと米国は農業所得を公的助成
――諸外国が採用している関税以外の農業保護策についてはどうですか。
2006年の時点では農業所得に対して公的助成が占める割合はスイスが「95%」、フランスが「90%」、イギリスが「95%」でした。それが2013年にスイスは「100%」、フランスは「95%」、イギリスは若干下がって「91%」になっています。それぞれ農業所得の9割以上が税金で賄われているのです。
イギリスやフランスの主食は小麦ですが、両国の小麦農家の平均経営面積は200ヘクタールで収穫量も多くなります。そうなると小麦の小売価格は安くなりますが、それでは農家は肥料や農薬代を十分に賄えません。そこで政府が補助金を支出し、農家は肥料や農薬の代金を払っても所得が手元に残る仕組みを機能させています。ヨーロッパの小麦農家は政府が投入した補助金でコストの持ち出し部分を補てんし、所得をきちんと得ながら国際競争力を高めているのです。
対して、日本では野菜や果物の農家の所得に助成金が占める割合は、せいぜい「10%」くらいでしょう。フランスでは野菜や果物の農家所得の4割、5割が補助金です。しかし、2006年の時点で日本の農家所得に占める補助金の割合は平均「15.6%」でした。民主党政権が導入した「戸別所得補償制度」が入る前の話です。
その後、米価は下がり、相対的に日本の農家所得も減り、若干補助金の割合は増えました。しかし、2016年の時点でも「30%」そこそこ。ヨーロッパは90%以上ですし、米国は「40%」ですから、日本の農家所得に占める助成金の割合は先進国で断トツに低く、その構造は現在も変わっていないわけです。
米国は「40%」と申し上げましたが、かの国の仕組みは、市場価格の状況によって変わります。たとえば米国の農家が1俵(60キロ)4000円でコメを販売しているとして、生産に12000円のコストが必要としましょう。米国では、その生産コストを政府が自ら計算し、販売価格の差額の8000円を政府が補助金で全額負担しています。だから、米国の農家は政府が提示する生産コストを目安に、安心して作付け計画が立てられるのです。
ただし、最近はコメ、小麦、トウモロコシ、大豆の国際価格が高値安定で推移しています。実際の販売価格が高ければ生産コストとの差額は小さくなりますから、政府が農家に支払う補助金は少なくなります。それでも米国の仕組みはすごいのです。生産コストと販売価格の差額を全額政府が穴埋めし、多い年には輸出向けの小麦、トウモロコシ、大豆の3品目の差額補填だけで1兆円規模の国家予算を投入した年まであるくらいです。
しかし、日本は米国の様な仕組みを持とうというそぶりさえ見せず、国会では議論すらしていません。日本の政治家には、欧米のような農業保護のための補助金制度ができたら「困る」という人が多いようです。自国農業保護のために本質的に必要な補助金制度については常にあやふやにしておいて、いざ生産者が窮したら自分が出て行って、「緊急対策費をとってやったぞ」と訴えて票につなげたいということでしょうか。この繰り返しですから、日本の農家が日常的に安心して作物づくりに励めるはずがないのです。
●「聖域」の確保は当然。だが日本は――
――欧州連合(EU)と米国の動きはわかりましたが、環太平洋連携協定の参加国であるオーストラリアやカナダはどうなのでしょうか。
カナダは穀物生産については助成措置を一切講じていません。ただし、自国の酪農と畜産を徹底的に保護し、とにかく酪農にはだれにも指一本触れさせないという姿勢を貫いています。まさに聖域であり、EUも米国も酪農は聖域です。彼らは守るべきもの、攻めるべきものを使い分けながら主張を巧妙に使い分けて実利を得ようとします。だから、かの国々は日本のようにチーズの関税の全面撤廃などという愚かな選択はしないのです。
オーストラリアとニュージーランドは酪農大国ですから、この分野では貿易相手国に徹底した自由競争を求め、関税を盾に使いません。しかし、両国は「隠れた輸出補助金」という農業保護を続けています。彼らは乳製品や小麦を日本には高く売り、中国に安く売っているのです。これは中国に自国産品を安く売るための補助金を日本の消費者が負担している「消費者負担型輸出補助金」と同じことで、紛れもなく世界自由貿易機関(WTO)の取り決めに反する問題です。
その点については日本政府の要請を受け、私も英文のペーパーを作成し、スイスのジュネーブにあるWTO本部に提出しました。しかし、オーストラリア政府は、この「価格差別」を小麦に適用していたAWB(独占的な輸出機関)が「すでに民営化されたため、政府の手元にデータが残っていない」として、かの国の農産物輸出における「価格差別」を輸出補助金としてカウントするのを阻止する姿勢を示し、いまも同様の措置を取り続けています。いわば「灰色」のままの放置状態に置かれたままなのです。
また、米国の差額補填の仕組みについても輸出補助金にあたるからやめるようにWTOの裁定が下りましたが、かの国も言うことを聞こうとしません。かたや日本の輸出補助金はゼロです。実はWTO合意をまっすぐに受け止め、深刻に解釈し過ぎ、過剰なまでに農業保護予算の削減を徹底してきた日本は哀れな「世界一の優等生」です。欧米各国は、国にとって必要な制度は死守しています。
ちなみにカナダ、EU、米国の乳製品への関税は数百パーセントです。子どもの命に関わる一番の食材である牛乳・乳製品の供給を「外国に依存することなどまかりならん」というのが彼らの考えで、それは「電気やガスの供給と同じように公共事業の一翼を担う分野だ」と言い切ります。
おまけにカナダでは「酪農家の再生産に必要な生産コストに見合う価格」を政府が決めています。その価格に基づき、独占禁止法適応除外の強力な生産者組織である「指定団体」が、メーカーへの納品価格を通告できる仕組みが機能しているのです。だから、原乳が過剰生産になったときには、政府が最低限の価格を守るために無制限に乳製品を買い上げます。それはEUも米国も同じで、同様の仕組みをやめてしまったのは日本だけです。
どうですか。これでも「日本の農業は世界一過保護」と言えますか。前回は「日本の関税率は高い」という主張の “ごまかし” についてお話しました。そんな言葉を巧妙に操り、日本の第一次産業を衰退に追いやり、食料安全保障を求める私たちの権利をないがしろにする政官財の動きを今後も注視し、安直かつ性急な自由貿易の推進に「NO!」を言い続ける必要があるとは思いませんか。

●世界は自国農業を「保護育成」
――環太平洋連携協定(TPP) など諸外国との自由貿易協定(FTA) をめぐる協議の際、あたかも決まり文句のようにてくるのが「日本の国内市場の閉鎖性」という表現です。特に「農業分野」は突出して “やり玉” にあげられ、「日本農業は世界一保護されている」とも言われます。
これらの言葉が本当に的を射たものなのかどうかについて伺いたいと思います。
鈴木さんは「国民の生命と財産を守るのが国民国家の責務であり、そのために最優先すべきは自国の農林水産業の保護育成だ」と常々指摘されています。そうした国家の責務と果たすべき役割を諸外国はどう捉え、どんな政策をとっているのですか。まずは、この点からお話いただけますか。
欧州連合(EU)諸国はもとより、中国やロシアも一次産業の価値を重視していますし、国民の生命の「礎」といえる食料を生産する農業をとりわけ重視しています。彼らは農業を中心とする一次産業が国民の生命はもちろん、環境と資源、地域コミュニティと国土を守ってくれている重要な産業だと考えているからです。
だから、政治家も官僚も国民から託された血税を投入し、自国農業をしっかりと支える政策を真剣に講じます。それは単なる「農家保護」の問題ではなく、自分たちを含めた国民の「生きる基盤」を支える重要な仕事であるという認識の表れといってもいいでしょう。
このように他国の政治家や官僚たちが国の政策として農業保護を続けているにもかかわらず、日本の永田町と霞ヶ関の住人たちは「農業だけを特別扱いするわけにはいかない。自動車や鉄鋼、その他の製造業一般と同じように扱うべし」と頑迷に言い張っています。この背景には現政権中枢と “お友だち” 関係にある企業さえ利益をあげればいいとの “おもんぱかり” があるのではないかという思いが、現政権にまつわる一連のマスコミ報道を見聞きするたびにこみあげてきます。
「農林水産業を工業製品中心の製造業一般と同列に扱う」と豪語する日本の政治家と官僚は「食料自給率」という言葉を死語にしつつ、日本農業をさらに痛めつける政策を実行し、自らの「既得権益」は死守しようとしています。そんなことを許容する国家は世界的に見ても、実に異様で特異というしかありません。
●「天下り先」確保に懸命な省庁の意向?
こうしたなか、日本農業は世界で一番過保護な状況にあるという話が、あたかも正論であるかのように、まことしやかに語られているのです。その発信元は電力に石油、鉄鋼、自動車といった大手資本でしょうね。彼らは米国をはじめとする他国の余剰作物の「売り先」として日本の国内市場を差し出し、見返りに自分たちの販売商品の販売市場を手に入れる皮算用の最中です。
その実現には「日本は農業に過保護であり、これに甘んじているから日本農業は駄目な産業なのだ」という考えを日本国民に刷り込み、農業保護政策を後退させ、農業分野への予算支出を削減させる必要があるわけです。そうしておいて、日本の農産物市場を大資本の餌食として与え、もっぱら自動車産業が利益を得る構造を定着させようというのです。
まるで時代劇の悪代官と悪徳商人のやりとりを聞いているような気分になりませんか。「お前も悪よのぉ」といやらしく耳障りな声音でつぶやくのが、だれで「ヒッヒッツ」と下卑た笑いを返しているのは、どの業界のだれかはご想像にお任せしたいと思います。そんな当節の悪徳商人は政治家と徹底的にタッグを組み、マスメディアを使って「日本農業過保護論」を社会に浸透させることに見事に成功しました。だから「日本農業は補助金漬けの過保護状態。おまけに世界で一番過保護というのだから、とんでもない」と言う人がほとんどになったのです。
まさにお見事というしかないくらいに、彼らは「日本農業過保護論」を浸透させました。これで十分な利益を手にしたのは経済産業省の役人でしょう。これまでも彼らは天下り先という「おいしい実利」を自動車業界などから手に入れようと政治をうまく利用してきましたし、いまが一番絶好調。陰で「経産省政権」と呼ばれるほど、現官邸では経産省の意向が隅々まで働いていると聞いています。
日米物品協定(TAG) の名を借りた日米FTA も、自分たちの天下り先を確保せんとする経産省の「総仕上げ」と呼べるものです。彼らはうまく官邸に取り入り、米国の思惑通りに日本の農産物、すなわち国民の生命の糧を差し出す動きを徹底しようとしています。こうして日本は、国民の生命と財産を守るという国家の責務を放棄し、大手資本と霞ヶ関の “お友だち” の利益を守ることを最優先する、世界でも例のない奇妙きてれつな国になってしまいました。
●スイスと韓国は食料安全保障を重視
――諸外国の農業政策はどうなっているのですか。具体的にお話しください。
まずは輸入品の急増から国内の農作物を守るための関税率からお話ししましょう。
「日本の農産物の関税は高い」と報じるマスコミは圧倒的に多いのですが、実は日本の農産物の関税率は経済協力開発機構(OECD) のデータでは「11.7%」。米国よりは高いのは事実ですが、EU は「20%」なので、その半分です。タイやブラジルは大変な農産物輸出国ですが、これらの国々も「35%」から「40%」の関税率を設定しています。そうした農産物輸出国と比べ、日本の関税は4分の1 という低水準なのです。
ではなぜ、「日本の関税率は高い」と言われるといえば、コンニャクに1700%の関税が設定されているためです。コメも300%を超えていますから、コンニャクとコメばかりが “やり玉” にあげられるのですが、キャベツなど他のさまざまな野菜の関税率は大半が「3%」程度。実際のところ、日本の農産物の9割は低関税率の品目なのです。そんな国は世界でも非常に珍しいということを覚えておいてください。
ですから、ほんのごくわずかに高関税の品目があり、そこだけを強調すれば「日本の関税率は高い」と思う心理が巧妙に利用されているというしかないのです。まさに、どなたかがお得意の「印象操作」というしかありません。繰り返しますが、日本の関税率は平均「11.7%」。対して韓国の平均関税率は「62%」、スイスは「51%」となっています。スイスは改正前の憲法にも「食の安全保障」を国家目標として盛り込んでいましたが、先の憲法改正で、それを明記しました。
韓国では憲法改正まではいきませんでしたが、農業界が中心となって「農と食料の安全保障」と国土・環境保全といった「農業の多面的機能」という公共的な価値を条文として明記しようという国民的な運動が起き、約1200 万人の署名が集まったそうです。
そういうスイスや韓国は関税率が無茶苦茶高い。平均で5割、6割というのはすごいことです。関税だけでも1.5倍とか、1.6倍という貨幣価値になってしまうわけです。このように関税制度を活用し、輸入産品の過剰な流入から自国産業を保護する正当な権利の行使を主張するのは、国民国家としての最大の責務ですよ。それができていない、いや、そんな食料安全保障を重視した政策は不要といわんばかりの日本という国家はまさに砂上の楼閣といっていいかもしれません。

そうした状況から安倍政権も「働き方改革」を進めているが、本来、労働者を守るはずの労働組合はどのように機能しているのだろうか。最新刊『働き方2.0vs4.0 不条理な会社人生から自由になれる』(PHP研究所刊)も話題の作家・橘玲氏が解説する。
●
日本型雇用慣行の最大の「不都合な真実」は、正社員と非正規社員で「同一労働同一賃金」の原則がかんぜんに無視されていることです。給料の格差、解雇の容易さから社宅や住宅手当・家族手当などの福利厚生まで、あらゆる面で非正規は劣悪な労働条件に置かれており、これほど搾取されている労働者は先進国ではまず考えられません。
労働組合も同じで、彼らが守っているのは「労働者の権利」ではなく「正社員の既得権」です。派遣社員や契約社員の雇い止めが大きな社会問題になったときも労働組合は見て見ぬふりをしていましたが、これも当たり前で、非正規の「人権」を守ると自分たちの既得権が「破壊」されてしまうことを知っているからです。
「働き方先進国」といわれる北欧の雇用制度を視察に来た日本の労働組合関係者が、最初は意気揚々としていても帰国するときには「見なかったことにしよう」になるという話は、北欧在住の日本人研究者のあいだでは広く知られています。世界標準のリベラルな制度には「正社員」は存在せず、自分たちがこれまでバカにしてきた非正規と「平等」になってしまうことがわかったからです。
なぜそんな重要なことが報道されていないかというと、その理由はものすごく単純で、「リベラル」を自称する新聞社や出版社などでも非正規雇用は当たり前で、「同一労働同一賃金」の原則などまったく守られていないからです。テレビ局の制作現場にいたってはさらに悲惨で、同じテレビ番組をつくっているように見えても、局の正社員と下請けの待遇は主人と奴隷ほど異なりますから、「働き方改革」のまともな報道などできるはずはありません。
こうした「リベラルの欺瞞」の象徴が、つい最近まで連合が主張していた「同一価値労働同一賃金」です。
安倍晋三首相が2018年の施政方針演説で「同一労働同一賃金を実現し、非正規という言葉をこの国から一掃する」と宣言してから「働き方改革」は一気に進み、裁判所でも非正規の原告の主張を認める画期的な判決が相次いでいます。
「同じ仕事をすれば、身分や性別、人種などのちがいにかかわらず同じ賃金が支払われる」というのはリベラルな社会の大前提ですが、「リベラル」を自称する労働組合はこれまで同一労働同一賃金に頑強に反対し、「日本には日本人に合った働き方がある(外国のことなど関係ない)」として「同一価値労働同一賃金」を唱えてきました。排外主義(ネトウヨ)と見まがうようなこの奇怪な論理では、「正社員と非正規は同じ仕事をしていても労働の「価値」が異なるから、待遇がちがうのは当然だ」というのです。
これは要するに、正社員と非正規は「身分」がちがい、人間としての「価値」がちがうということでしょう。ところが(一部の)労働経済学者を含むリベラルな知識人はこのグロテスクな論理を批判しないばかりか、保守派とともに「日本的雇用を守れ」と大合唱し、非正規への身分差別を容認してきました。
「人権」と「平等」を金科玉条とする労働組合は非正規などという「身分」を認めず、親会社と子会社の「身分格差」もなくし、海外で採用した社員を「現地採用」として「本社採用」の日本人と「国籍差別」するようなことはぜったいに認めないはずです。
ところがこれらはすべて日本企業が当たり前に行なっていることで、そこには必ず労働組合があります。だとしたら、彼らのいう「人権」や「平等」とはいったい何なのか?
マスコミも含め日本の企業や官庁、労働組合などを支配しているのは「日本人、男性、中高年、有名大学卒、正社員」という属性をもつ“おっさん”で、彼らが日本社会の正規メンバーです。そんな“おっさん”の生活を守るためには「外国人、女性、若者、非大卒、非正規」のようなマイノリティの権利などどうなってもいいというのが「平成」の30年だと考えれば、日本がなぜこんな社会になったのか理解できるでしょう。



 2018
2018規制改革、安倍政権になってからは「岩盤規制」(緩和や撤廃が簡単にできない規制の意味)という言葉まで登場し、「規制改革推進会議」を推進母体として積極的に進めてきている(とされている)。
その安倍政権、現在、森友学園問題に続いて加計学園問題でも、元総理秘書官の関与を裏付ける文書が発見、公表され、さらに厳しい追及を受けるに至り、「断末魔」と評せるような様相を呈している。
元総理秘書官である柳瀬経産審議官の国会への証人喚問を巡る与野党の綱引きや、財務省の福田前次官のセクハラ疑惑への対応で迷走し、野党の追及は少々膠着ぎみではあるが。一方で、国会の空転は、新たな事実が出てくることを恐れる与党側にとっては願ったりかなったりになったようではある。
これらの問題自体の詳細については別稿に譲るが、森友学園問題の本質が国有財産の不適切な処分に関する問題であるのに対して、加計学園問題は本質的には「国家戦略特区制度」という、国の制度の乱用に関する問題である。
この国家戦略特区制度は、地域を限定して規制改革の実験を行い、規制改革、なかんずく「岩盤規制」とされているものをなくすか、緩和することを通じてわが国の経済成長に寄与することを目指すものとされている。
その意味で、加計学園問題は規制改革の乱用、恣意的運用の疑いに関する問題であると言える。
この点を間違えると、加計問題の何がどう大問題なのか正しく理解できなくなるのだが、一方で、規制改革というもの自体についても正しく理解されずに、イメージだけでその当不当や賛否が語られているようである。
筆者は、国家公務員として規制改革の要望を受ける立場および規制改革に関する制度や提案、特例措置を評価する立場だけでなく、民間企業の職員としても規制改革の提案や要望を作成し、規制所管府省と協議する立場も経験している。つまり、「官と民」という「立場の全て」を実務で経験している。
そうした経験や蓄えられた知見に基づき、規制改革とは一体何なのか、どのような意味があるのか、さらには規制改革を巡る昨今の議論は何が問題なのかについて、簡単に解説してみたい。
●規制改革は「イコール規制緩和」ではない
規制とは、法令やそれに基づく告示や通達において規定された、許可、認可、届け出等(以下、「許認可等」という)、設備や構造に係る基準、使用や輸入を可能とする物質等の特定または範囲、許認可等において添付すべき文書等、長さや重さ、面積、分量のような数値の範囲(定量的規制)、特定の名称の使用、妥当性についての基準(定性的規制)といったものの総称である。一般的にイメージされる許認可だけが規制というわけではないし、許可や認可、届け出と法律に書いてあっても、全てが同じ法律効果、意味を持っているわけではない。後者については、詳しくは行政法の教科書を参照されたい。
規制改革とは、簡単に言えば、規制を「経済社会の実情」に見合ったものとなるよう改めていくことである。
注意すべき点は、この「改める」とは既存の規制を緩和したり、なくしたりすることだけを意味するわけではなく、規制を新設したり強化したりするものも含まれるということだ。
筆者は「改める」方向性を、おおむね、「新設」「強化」「緩和」「簡素化」「廃止」の5つに分類してきている。
ちなみに、筆者がこれまで拙稿や講演等で用いてきた規制改革の定義は「あらゆる規制および規制類似の行為について見直しを行い、不用な規制については緩和または廃止し、必要な規制については維持し又は強化することを通じて、行政の活動を社会経済の実情に合った適正なものとすること」というものであり、規制を行政の活動と結びつけて考えてきている。
このことを直近の分かりやすい事例で言えば、いわゆる民泊に関する規制の新設がある。
ちまたではよく「民泊解禁」などと言われるが、「解禁」とは禁止されていたものを解除して可能とすることを意味するところ、既存の法律で捉えきれていなかった新たなサービスについて、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の新設と旅館業法の改正によって捉えることを可能としたのであるから、「適正化」とするのが妥当であろう。
加えて、こうした規制改革は、その根拠たる法令の改正によって行われるのだが、改正の内容は緩和や強化、新設を同時に含むことが多い。
●規制改革にも程度がある イチかゼロかではない
さて、規制改革の議論が行われる時、決まって出てくるのが規制の徹底した緩和を求める意見と、現行規制を是が非でも守るべきとする意見という、両極端な意見である。安倍政権下では、後者は「既得権益」や「抵抗勢力」とされ、打破されるべき、排除されるべき対象とされている(「既得権益」打破を叫ぶという点に限って言えば、程度の差や対象の違いこそあれ与野党変わらないところはあるが)。
規制改革については、規制の強化にせよ緩和にせよ、さまざまなやり方、程度があり(例えば緩和であれば、禁止の解除である許可を条件を満たせば可能となる認可に緩和する、提出書類を簡略化する、数量の基準をなくす等)、当然それは規制の対象なっている分野の実情や保護法益、いわゆるステークホルダーの在り方等を総合衡量した上で決められるもの。
従って最初から「とにかく緩和する」と決めてかかることができるものではない。
また、地域を限定して緩和する(特例措置と呼ばれている)とか、まず地域で緩和する社会実験的なことを行った上で、その結果次第で全国一律で緩和するといったことになじむ規制もあれば、それになじまず最初から全国一律でその在り方を考えるべき規制もある。
前者の「地域限定」で規制改革を考える制度が国家戦略特区制度や構造改革特区制度である(民主党政権時代には総合特区制度というものも創設されたが、現在ではその立場は国家戦略特区制度に奪われていると言っていい)。
もっとも「国家戦略特区制度」と「構造改革特区制度」は似て非なるもので、後者が特区とは言うものの、特例措置の最終的な全国展開(全国一律の緩和)を前提としているのに対し(筆者が総務省で担当し、全国の管区行政評価局や事務所を総動員して行われた規制改革の評価は、まさにこの特例措置の全国展開に関する課題についての調査・評価であった)、前者は、全国展開は念頭に置きつつも、特例措置の特区内での限定適用をある程度の期間維持し、特区内で特例措置を活用した事業者の利益を保護しようというものである。
少なくとも国家戦略特区制度創設時や創設から間もない時期はそのように説明されていた。ちなみに、国家戦略特区法が国会で審議され、可決成立したのは筆者が衆議院議員の政策担当秘書をしていた平成25年の臨時国会である。
加計学園問題で焦点となった大学への学部の設置の在り方に関する規制は、特区となれば特定の学部の特定の地域への偏在を招くことになるし、そもそも無用な大学間競争による共倒れや、研究、学生の質の低下等を防止する観点から置かれてきた規制であると考えるのが妥当であり、まさに「全国一律」で考えるべきものの典型例であると言える。
従って、特区になじむものではないし、特例措置の適用がある程度の期間、特定の地域に限られてしまう国家戦略特区制度であればなおさらである。
一方、地域差が許容可能なものであれば特区にもなじむ。筆者が評価や提案で担当したものとしては、例えば、コンビナート規制やエネルギー関係の規制がある。もっともこちらは構造改革特区制度を活用したものであったので、最終的には全国展開され、コンビナートの高コスト構造の是正に大いに貢献したようだ。
●「規制=悪」「規制の緩和=善」ではない 岩盤には岩盤なりの意義がある
こうした規制改革の性格や特質からすれば、規制改革は「諸刃の剣」ではあるが、使い方さえ間違わなければ、経済社会をより良い方向に導くことが可能ということになる。
しかし、特に規制の緩和を主張する側には、規制の緩和は善であり、規制を守ろうとするのは悪だという、まるで岩盤のような先入観、固定観念があるようだ。
具体的には、先にも述べたように、規制を守ろうとする側は規制があることによって既得権益を得ており、それを守るために規制を死守しようとしている抵抗勢力で、日本の成長や発展を阻害する害悪である、というものだ。
だから抵抗勢力を排除して規制緩和を進めるべき、といったものである。そして緩和への抵抗が特に強いものを「岩盤規制」と呼んでいる。
しかし、規制が存在するのにはそれ相応の理由や背景があり、守られるべき公の利益、すなわち公益がある。これは保護法益と言い換えることができるが、だからこそ法令において定められているわけであって、それを一律に「既得権益」と決めつけるのは議論の飛躍であり、極めて乱暴な議論であると言わざるをえない。
「岩盤規制」には「岩盤」であるそれなりの理由があり、それがなくなることによる利益がある一方で、それ以上の損害や弊害が想定されるからこそ「岩盤」のように維持されてきたのである。
また、規制を必死になって守ろうとする人たちのことを悪の抵抗勢力と決めつけるのは、悪者と闘うヒーローのような単純な構図を作り、その内実は守られてきた公益を是が非でもむしり取りたいという意図、意識の表れのように見える。
もっと言えば、既得権益=公益を死守する抵抗勢力を排除し、保護するための規制もなくして、自分たちに都合のいい新たな既得権益を創りたい、そのための手段として規制改革や特区制度を利用しているのではないか。
ここが「国家戦略特区の乱用」という加計学園問題の核心ではないかと思われてならない。
実際、筆者が霞が関のある幹部と話していて話題が規制改革に及んだ際に、規制改革推進会議等の民間委員は、かつては一私企業や業界の利益のための規制改革の要望でも、“公益の衣”に包んでそれ相応の理屈や大義名分をつけていたものだが、今や「私利私欲むき出しになっているのは嘆かわしいことである」としていた。
規制改革を進めること自体、総論として問題はないし、積極的に評価されるべきであろう。しかしそれは、あくまでも特定の利益のために規制改革を悪用したり乱用したりしないで、公益を考え、経済社会の状況を踏まえて、丁寧に議論を積み重ねた上で、新設するのか、強化するのか、緩和するのか、簡素化するのか、はたま廃止するのか、適切な方向性に進める場合の話である。
政府も与党も野党も、地方公共団体も、そして経済界、市民団体等の非営利セクターも、そろそろ規制改革について冷静な議論を考えるべきではないだろうか。

突然だが、もしもみなさんの職場にこんな人がいたら、どう思われるだろうか。
職場を良くするためだと、とにかく人のミスや不正を見つけては言いふらす。口を開けば「職場のためにもっと言いたい放題言わせろ」と文句ばかり。ただ、時にデタラメを広め、無関係の人を傷つけるなどトラブルも続いたため、「自由もいいけど、少しは遠慮したら」と同僚たちがそっと諭した。
すると、その人は顔を真っ赤にして「言論の自由が侵害された!」と大激昂。その迫力に身の危険すら感じた周囲は、これまで以上に言いたい放題できるよう、職場内で最低限守るべしと定められていた「発言ルール」を取り払うと持ちかけた。
当然、飛び跳ねて大喜びするかと思いきや、なんとその人の怒りはさらにヒートアップ、発狂しそうな勢いで、耳を疑うような恫喝をまくしたてた。
「そんなことしたらデタラメを言うやつが増えるだろ!さては、俺を潰すための策略だな!」
完全なモンスター社員だと呆れる方も多いだろう。こんなのが現実にいたらサイコパスだよ、と冷笑する方もいるかもしれない。
だが、驚くなかれ、このような方たちが現実にちゃんと存在している。テレビ局や大手新聞社などの「マスコミ幹部」だ。
●放送法の「政治的公平」を巡る 大手マスコミの詭弁
先月、政府が放送制度改革を行うという話がちらっと出た。今やニュースはスマホで読むのが当たり前となっているように、テレビもネットと同列にして何が悪いということで、放送と通信の垣根をなくし、新規参入を促すように規制緩和を進めようというわけだ。そのなかのひとつとして検討されているのが、放送法4条にある「政治的公平」の撤廃だ。
少し前、高市早苗総務相(当時)が、この条文に違反すると電波停止もあり得ると発言したことで、テレビ局がこの世の終わりのような大パニックになったことからもわかるように、この「政治的公平」という縛りによって、報道が萎縮するというのがマスコミの主張だった。
それをなくすというわけだから当然、みんな諸手を挙げて大歓迎かと思いきや、テレビ局をはじめとしたマスコミ各社が猛烈な反対キャンペーンを開始した。
思う存分に報道ができる規制緩和に、なぜ彼らは腹を立てているのか。テレビ局幹部、総務省、マスコミが引っ張り出してくる専門家など、反対派の主張を端的にまとめると、ざっとこんな感じになる。
「政治的公平を撤廃して自由にしてしまうと、偏向報道やフェイクニュースを垂れ流すロクでもないテレビ局がたくさん増えて、それをヒトラー安倍みたいな権力者が悪用するので絶対ダメ!」
こうした意見に賛同し、「そのとおりだ!これは政治のメディア支配だ!」と、今すぐデモでも始めそうな方たちも大勢おられるかもしれないので、ちょっと申し上げづらいが、残念ながらこれは、第2次大戦中くらいの、かなり前時代的なメディア観と言わざるを得ない。
確かに、新聞やラジオなど限られたメディアしか社会に存在していなかった時代は、大手マスコミを掌握してしまえば、権力者はフェイクニュースで世論誘導ができたということもある。
が、今では状況がまったく違う。むしろ今の日本では、テレビや新聞のように閉鎖的な既得権益業界の方が、自ら進んで「フェイク」の罠に陥っている。
●マスコミのフェイクニュースを ネット民たちが正す時代
最近、オフィス北野のお家騒動で、「グッディ」(フジテレビ)に「偽社員」が出演したと話題になったが、ホラッチョ川上ことショーンKさん、佐村河内守さんなどなど、テレビは定期的に「フェイク」をつかませられる。これはなぜかというと、閉鎖的な世界ゆえ、多くの人たちのチェックが働かないからだ。
そういう既存マスコミの弱点は、ネットで克服できる。たとえば、大相撲の女人禁制問題における春日野親方の「トイレ騒動」がわかりやすい。
当初、マスコミは行司が「女性の方は土俵から下りてください」とアナウンスした際、親方はトイレに行っており、会場にはいなかったと報じた。が、会場にいた観客が、親方が会場にいるところをスマホで撮影していて、その画像がネットで拡散されたことで、トイレ発言が「嘘」だということがバレてしまったのである。
つまり、マスコミが図らずも広めてしまった「フェイクニュース」を、一般人たちが検証して誤りを発見し、それをネットに拡散したことで是正したのだ。
もし仮に、テレビ局幹部などが心配するように、安倍首相が懇意のネットTVを悪用して、「信者」に対して事実と異なるデマを触れ回ったとしても、同じような検証が働く、というのは容易に想像できよう。
仮想通貨における「ブロックチェーン技術」を想像してほしい。よく「改ざんができない台帳」というたとえがなされるように、この技術はネットワークにつながる不特定多数のPCが相互に確認と検証をおこなうので、改ざんや不正な取引ができない。
それと同じように、「報道」というものも、ネットというオープンスペースに多種多様なメディアが乱立した方が、不特定多数の個人が相互に確認と検証をおこなえるので、「フェイク」や「偏向」を防げるのだ。
●「政治的公平」は一握りの知的エリートしかわからないものか?
「テレビの規制を緩くしたら、アヤしいマスコミがたくさん誕生して国民が洗脳される!」と騒ぐ人たちは、このあたりの視点がごそっと抜けている。「政治的公平」のジャッジができるのは、永田町、霞が関、そしてテレビ局など大手マスコミの、ほんのひと握りの知的エリートだけであって、読者や視聴者にはできっこない、とハナから決め付けているのだ。
要は、大衆を「下」に見ているのだ。
こういう「政治的エリートとマスコミが日本人を良き方向へ導く」みたいな選民思想は、昭和の高度経済成長期くらいまでは当たり前のように存在していたが、もはや明らかに時代錯誤である。
なんてことを言うと、マスコミのみなさんからお叱りを受けるかもしれないが、みなさんが「時代」を捉えていないということが、「朝日新聞」の3月31日付け社説に如実にあらわれているので、以下に引用させていただく。
「安倍内閣は従来の自民党政権にもまして、4条を口実に放送に介入し圧力をかけてきた。だがその強権姿勢は厳しい批判を浴びた。一方で首相は、バラエティー番組や政治的公平性を求められないネットテレビには進んで出演し、自らを宣伝する。4条撤廃の衣の下からは、メディアを都合良く使える道具にしたいという思惑がのぞく」
個人的には、お前はとにかくムカつくから息をするな、というのと同じくらい理不尽な言いがかりのような気もするが、問題はそこではなく、「政治的公平性を求められないネットテレビ」というくだりだ。
こういうもの言いをされると、ピュアな朝日読者は、「うんうん、そうだよな。法律で政治的公平性の縛りがないネットテレビなんてありえないよ」と誘導されるが、世界的に見ると、国がテレビを規制して「政治的公平性」を求めている方が、はるかに「あり得ない」のだ。
よく言われるように、アメリカでは大昔、テレビ局を管轄する連邦通信委員会が「報道の政治的公平」を求めていたが1987年にこれをスパッと廃止した。
当たり前だ。白人社会の「公平」と、ヒスパニック系の「公平」はまったく違うし、トランプ支持者とワシントンのエリート層の「公平」は絶対に相容れない。この中で、何が「公平」なのか政府がジャッジを下したら、本気で内戦が起きる。
●「政治的公平」は法律でコントロールできない
日本のマスコミがなにかと手本にしたがるBBCがあるイギリスも同じだ。
NHKも安倍政権を叩けみたいな文脈の時によく出るが、BBCはかつてフォークランド紛争を「中立」に報道し、サッチャー政権から厳しく批判されても屈しなかったことで知られている。では、こういう硬骨の姿勢を貫けたのは、法律でちゃんと「政治的公平」が指導されていたからかというと、かの国にはそんな規制はない。
当時のBBCのガイドラインには、「公平性は、絶対的な中立性を意味するのではない」という趣旨の記述がある。BBCの言う「公平」とは、自分たちが信じる「公平さ」であり、報道機関として自らを厳しく律するポリシーでもある。役所や法律でああだこうだと指図されるようなものではないのだ。
まだ記憶に新しいかもしれないが、2年くらい前、テレビ・新聞は「ヒトラー安倍によって報道が萎縮している」という一大キャンペーンを張った。そのよりどころとなっていたのが、国連人権理事会が任命した「表現の自由」に関する特別報告者だった、米カリフォルニア大アーバイン校のデビット・ケイ教授である。
この方は2016年4月に来日し、1週間に及んで日本のマスコミ、ジャーナリストのみなさんにヒアリングをおこなった結果、こんな素晴らしい「提言」をしている。
「やはりこの放送法は一部改正する必要があるというふうに考えております。例えば、4条そのものを取り消すということです。政治的公平性を判断するということは非常にオープンな議論を要求するものであります。公平なのか・公平ではないのかというのは本当に大きな議論を要するところであって、それを政府がコントロールするということであってはならないというふうに考えています」(ログミー2016年4月19日)
あれから2年。国連に対して「安倍政権に恫喝されてます、助けてください」と、子犬のように怯えて訴えていた日本のマスコミが、「政府のコントロールがないとフェイクニュースが増える」と怒り狂っていると知ったら、ケイ教授はどう思うか。
やはり冒頭でみなさんが感じたように、「サイコパス」だと失笑するのではないか。
大臣は「政治家」であるから、行政事務職員から報告を受けていなかったら責任がないのか、形式的な謝罪をすればそれで済むのか。「行政の長」が政治家であることは、「聞いていなかった」「報告しなかった」ならば、結果責任はすべて行政職員が負うことになるのか。それならば、責任者としての行政職員以上に高い報酬と役割を与えられている「政治家」の存在なんて必要なくなってしまいます。これは、地方自治体の「首長」においても同じ議論が必要となるのです。
まず、国政レベルの話でいえば、これは現政権だけの問題では全くなく、政権交代が起こった時代でも同じ課題がありました。ある大臣が「私は本当はこのような政策を進めたいんだけど、官僚が動いてくれないからしょうがないのよね」という話を大臣室で聞かされたことがありました。よく政治家をいさめることができる「優秀な官僚」などという美談めいた話がでますが、既得権益がらみの話以外で「優秀な政治家」が官僚をいさめて方向転換させたという話はあまり聞きません。官僚にとって、微々たる方針転換をすることで政治家に花を持たせることは多々あっても、本質的な財政論や国家システムの構造改革にメスが入れることができないのは、本来「行政の長」であるはずの大臣や政務官が「単なる一人の政治家」でしかなく、具体的な「実務」をみていないことが大きな原因だといえます。
どの政権においても、大臣や政務官が女性問題や失言、政治的配慮によってころころ変わっても大きな問題が生じないのは、所詮「行政の長」が「単なる政治家」としてしか行政職員から見られておらず、役割も満足に果たせる状況でなければ、逆に責任も負わされることもない、負うこともできない状態なのが、今の国の政治家と官僚の関係であるといえるでしょう。真に「行政の長」でもあり、「政治家」でもある人材であるならば、隠蔽するシステムを変えることが出来なかった責任も、報告があがらない組織の責任も、財政再建を進められない責任も、現場とともに動いてきたという自負があれば、自分自身が責任をとるという気持ちが当然のようにわき上がることでしょう。
地方自治体では、「県」というレベルにおける知事職はほぼパフォーマンス職となっており、実務よりは既得権益との調整や新規事業の旗ふり役に過ぎず、市民の現実に関わる行政的手腕を発揮できないのは中間自治体としての「県」という不必要ともいえる中途半端な役割上、国政の政治家以上にしかたがないともいえる部分もあります。実際に、都道府県知事できめ細かな行政マネジメントに関わる人をみたことはありません。
一方で、基礎的自治体である「市町村長」の首長と職員の関係性においては、首長の汗の流し方と職員のトップに対する信頼のあり方によるといえます。通常の自治体においては、国における大臣と官僚と同じように、重要案件だけを報告連絡をして、予算の協議においても大きな20件ぐらいの市政の課題案件だけをピックアップしてそれ以外は行政内部の権限で処理をしてしまうというシステムが多くなっています。ただ、基礎的自治体においては、すべての案件の判断が直接市民の幸せにも痛みにも、次の世代の課題にもつながることになってしまい、本来ならば市民から責任を持って選ばれた「政治家」としての判断をしっかりと行うことが求められるといえます。もちろん、「行政の長」である以上、どんな細かいことであっても責任と役割を持っていなくてはならないともいえます。当然、一人の人間ができる役割は限られています。だからこそ、組織として、トップが責任と役割を担えるシステムを創ること、そして、組織全体で現場とトップをつなぎながら、みんなで責任を共有しあえる体制を創ること、それこそが、本当の意味での政治家が行うべき役割であるといえます。
行政職員は、立場的に「匿名性」を持ち、そして「持続可能性」を重視するため、成功するためのリスクを冒すよりも失敗するリスクを過度に恐れます。だからこそ、市民の幸せを増進し、痛みを解決していくためには本来「政治家」がリスクをしっかりと負えるシステムを創らなくてはいけない、でもそのためには「政治家」が行政職員と同様の「現場」をしっかりと知るためのシステムも創っていかなくてはいけないのです。

対談の前編では、人口減少が進んだとしても、考え方を変えれば日本はまだまだ成長できるという点で意見が一致した。後編では、定期採用の見直しや移民の受け入れなど、痛みの伴う労働市場の改革についても議論が及んだ(司会は日本経済研究センターの斎藤史郎参与が務めた)。
斎藤史郎氏(=司会、 以下斎藤):世界経済の拡大にも恵まれ、景気には明るさが広がっています。日本経済がダイナミズムのある経済成長を続けるには労働市場改革が必要との指摘が少なくありません。
小林喜光氏(以下、小林):そう、そこがカギですね。
八田達夫氏(以下、八田):私も、そこがカギだと思います。
小林:世界は一流の選手をそろえてプロフェッショナルの戦いを挑んでくるのに、日本だけが、プロも、一般人も、その分野の適性がない人も、みんな均一の条件で戦うというのは、いわば社会主義国のようなものです。会社は新陳代謝をしており、しなければ生きていけません。ところが、新陳代謝をした暁に、社内失業者のような人がたくさん出てしまう。これはその人にとっても、会社にとっても不幸です。そういう人にも自分に合った仕事が見つかるミスマッチのないような労働市場をつくる。そんな仕掛けが必要です。多様な人たちが、それぞれ多様な方向で生きていく。やたら働く人もいるし、ほとんど働かずに暢気にやっている人もいる。それぞれ受容しながら、最終的なところでみんなある程度、エンジョイできる社会にすることが大切だと思います。
八田:労働市場の流動性を高めることができれば、どんどん新しい体制に移っていけると思います。ところが、今は、例えば仮に本当に優秀な人材がいて、中途採用したくても、年功序列でポジションが空いていないからできない。これでは何もできません。もちろん、解雇されないという条件で雇われた人を解雇してはまずいですが、高い給料を得る代わりに解雇されてもいいんだ、というような条件で人を雇うこともなかなかできないというのは問題だと思います。日本では法律上、解雇が非常に制約されています。
小林:今、働き方改革が盛んに言われていますけれど、IT企業の経営者たちは、「会社を立ち上げるときは24時間働いた」と口をそろえます。 直接金融の最先端に関わっているような人は、3週間で1兆円の資金調達をまとめ上げたりします。そういう人たちの労働は、一般的に見れば想像を絶するでしょう。グローバルな戦いに勝つためにはハングリー精神も必要です。企業のコンプライアンス問題や不祥事にはしっかり目を配っていかなければなりませんが、同時にガッツがなければ戦えません。世界で勝ち抜いていくという思いがなければ、競争力を高めることなどできません。今の日本ではここが、ものすごく失われていると思うんですよ。海外を見渡すと、欧米でも中国でもアジアでもハングリーな人たちばかりです。
斎藤:本質的な問題ですね。社会全体に働きすぎを是正しようという動きがある中で、ハングリー精神とどう折り合いをつけていくか。デリケートではありますが、忘れてはならない論点ですね。八田先生はどう思われますか。
八田:私も全面的に小林さんの意見に賛成ですが、働く人の中には「クビにだけはなりたくない」「そんなに給料が高くなくてもいいから、とにかく早く帰りたい」「人間らしい生活をしたい」という人がいるのも当然だと思います。だから、そういう労働契約を結ぶのならば、きちんと法律を定めて、執行するような仕組みがあるべきだと思います。つまり、様々な契約があってもいいと思うんです。「4年間は一生懸命働きますから、そこで評価してください」とか、「労働時間は自分で管理します」とか。様々な選択を許すことが必要なんじゃないかと思うんですね。
小林:誰も彼もが同じように給料の高い企業を目指す、そういう同質的な風潮や評価システムは、僕は間違いだと思うんですよね。そんなことをやっていたら、日本の優位性のみならず、国内の産業、特に知的産業の競争力、あるいは大学の競争力は伸びていきません。格差の問題は大きな問題ですが、単純に働き方を均一にするのはいかがなものかと思います。多様な働き方を認めたうえで、別の政策的な工夫で格差を解消していくよう考えるべきではないでしょうか。
斎藤:解雇に伴う金銭補償ルールの制定も抵抗が強く、なかなか進みませんね。何か工夫の余地はありますか。
八田: 労働市場改革を、いったん退職した人や定年を過ぎた60歳以上の労働者を対象に先行させたらどうでしょうか。そこでは解雇も自由、優秀な人材であれば契約の継続も自由、という形にすれば、会社としては高齢者を雇う時のハードルが下がるのではないでしょうか。
斎藤:まずは高齢者の雇用改革ですか。
八田:そうです。高齢者の労働に対して革新的な改革を行えば、その後、全体の労働改革も進めやすくなると思います。非正規雇用の改革についても言えるでしょう。例えば、非正規雇用者は5年間雇ったら、雇い止めになってしまう可能性があります。そういう制度は、やはり非正規雇用者にとっては非常に不利ですから、いくらでも再契約をしてもいいという仕組みが必要です。今の日本では、正規雇用者の利権を守るために、非正規雇用者に対して様々な不利な条件を強いています。労働改革のもう一つのブレイクスルーになると思います。
斎藤:労働市場改革には他に何があるでしょうか。
小林:「通念を破壊する」という意味では、定期採用の問題もあると思います。昨年(2017年)10月にパリを訪れたとき、ルノーの元会長であるルイ・シュバイツァー氏とお会いしたのですが、「日本の競争力が弱い原因は、(4月の)定期採用である」とおっしゃっていました。そんなことをやっている国は、世界中のどこを探してもありませんよ、と。一部の日本企業、IT企業や一部の製造業では既に通年採用をしていますが、一般的に見れば定期採用をしている企業が非常に多い。毎年決まった時期にしか採用しないというお仕着せのルールです。そうした「通念」は間違いだと思いますね。優秀な人材だったら、どの時期であっても来てもらうといった雇用の流動性が大事です。これまでずっと続いてきた規制の中でやってきたものだから、何も変えようとしません。そんなことをしていると、外国人も雇えないし、海外留学している人のハンディキャップも非常に大きくなってしまいます。労働改革は、企業が柔軟に動けるように、きめ細かく議論していかなければなりません。働き方改革は大事だが、ただ残業時間を減らすだけというのでは、あまりに寂しい改革だと思いますね。
八田:今、小林さんがおっしゃったことは、大学の競争力にも繋がります。日本の仕組みは、4月に就職したら、その後はよほどのことがない限りクビになりません。採用試験は一度に集中しますから、実力をすべてチェックするのは限界があります。そこで企業は、どこの大学の学生かを最も重視するようになります。正確ではないけれど、優秀な人材かどうかを見極める一つのチェックポイントになるだろうと。すると、若者は「いい大学に行こう」と考えます。それは、単に資格証明のためです。学生は入学した段階でそれなりの企業に就職できることが決まってしまうわけです。そうなると(大学同士も)競争しなくなる。そこで、もし、小林さんのおっしゃるように、通年採用が実現すれば、大学も実力のある人を育てることが重要になってくるわけで、競争するようになります。
斎藤:労働問題として、移民の問題もありますね。
小林:これも重要なテーマだと思いますが、日本人のメンタリティーとしては、複雑なところでしょう。日本は島国で長い間隔離されてきましたから、人種のるつぼみたいになることには抵抗があるでしょう。しかし、人材の質を上げるという点で、非常に強い刺激剤になるのではないかと思います。海外の高度なプロフェッショナルを、高い給料を提示して採用するのは意味のあることだと思います。既に一部の企業は海外企業を買収していますから、マネジメント層には結構多くの外国人がいます。その結果、日本に移り住む、そんな自由度があってもよいのではないでしょうか。そのレベルならむしろ必要でしょう。
斎藤:八田さんはどう思われますか。
八田:その通りですね。ダイバーシティということは非常に重要です。海外から大卒の高度人材をどんどん入れることは必要だと思います。大学の話になりますが、私は政策研究大学院大学の学長を務めていた時のことです。外国人を雇わなければいけないことになり、私は米国の経済学会に毎年行って、何人もの方にインタビューをし、日本でセミナーを開催したりして、多数の外国人を採用しました。ところが、「この人にぜひ来てもらいたい」という人が、給料の差によって、結局、米国やカナダ、シンガポールの大学に行ってしまうというケースがありました。この給料の差というのは、多少の差ではありません。少なくとも、倍の差があります。日本の大学も、賃金設定を自由にしなければならないと感じましたね。つまり、しょうもない研究をしている人の給料は余り上げない。実力のある人の給料は実力に応じて上げる。その自由は大学にあるという形にすることが必要だと思いましたね。
小林:しょうもない研究をしている人でも辞めさせられない。そこが難しいところですね。
八田:そうですね。まあ、その人の能力に原因があることもありますが、研究自体が時代の流れから遅れてしまっている場合もあります。
小林:企業はスクラップ・アンド・ビルドをしないと生き残れないけれど、大学は昔からあるものを維持したまま新しいことをやろうとする。それでは、経費は膨らむ一方じゃないですか。
八田:そうです。その点はかなり危機的なことだと思います。日本のノーベル賞受賞者が多いのは、やはり60年代以降、政府が科学技術促進のために大学に多額の予算を配分したからなんです。そして今、ITの時代が到来し、まさにその部分に予算が必要になりました。ところが、既に工学部には昔の人たちがいるわけです。彼らが抵抗勢力となり、肝心の新しい分野に予算を十分に配分できないのが実態です。それは大きな問題だと思います。
斎藤:まさに、既得権ですね。
小林:そういう大学教授を辞めさせることが、一番重要だと思いますね。そして、新しい分野の研究をしている優秀な若者を採用するのです。
斎藤:まさに、新陳代謝ですね。
小林:おっしゃる通りです。
斎藤:新陳代謝がない上、大学教育を無償化しようという動きもありますね。
小林:無料にしたところで、レベルの低い大学ではしょうがないと思いますがね。
八田:お金をかけるなら、(学生数という)需要を増やすよりも、(教授たちの)供給の質を上げることを考える方が先です。
小林:そうそう、間違いなくその通りです。
斎藤:もう一つ、長期的な日本経済の姿を考える場合、今急激に進んでいるデジタル革命をどう捉えるかが極めて重要だと思います。小林さんはそうした変化をにらみながら、国の豊かさを測るモノサシに問題があり「国家価値、あるいは国民の幸せをGDPで捉えられる時代は終わったのではないか」とおっしゃっていますね。
小林:まあ、既存の統計(設備投資関連や家計調査など)については政府も修正すべき部分に気が付いて、ここ1、2年だいぶ改善されてきたと思います。GDPを推計する場合に支出面、生産面、分配面からそれぞれはじいても一致するという「三面等価」の法則も、ぜひきちっと達成されなければならないとは思いますが…。ただ、私が最も強く問題意識として持っているのは、デジタル革命が進む中で(既存の)GDPでは本質的に人々の効用、満足度を捉えきれなくなっているのではないかという点です。GDPは、貨幣価値で測定できる要素に基づき計算します。「人々が物質的に満たされれば幸福になる」という時代ならば適切な道具でしょう。しかし、物質的には既に満ち足りている経済、あるいはイノベーションによってより良いサービスや製品が安く供給される状況では、GDPで人々の幸福度、快適度を測るのには限界があると思うのです。例えば、利便性は高まっているのに価格は下がっているものがたくさんあります。かつてコンピュータは何百万円も出さないと買えなかったのに、今の時代では同じような機能を持つスマートフォンは数万円になっている。あるいは、昔は音楽を聴く時にCDを買わなければならなかったけど、今は「YouTube」などで何でも聴くことができる。この価値がほとんど価格に反映されていないんです。このように「測れないもの」が、若い世代の間では「価値」になっています。シェアリング・エコノミーもその一つです。米ウーバー・テクノロジーズのカーシェアサービスが話題を呼んでいますが、人々は「所有」ではなく、「利用」について考えるようになっているわけです。昔は一カ月のうち3〜4%程度しか使用しないクルマがいつも車庫に置かれていました。それが、シェアされるようになれば、(一台当たりの利用率が高まり、台数で見た)自動車の需要は現在の一割程度まで下がってしまう可能性もあります。
自動運転車の時代に、みんなでシェアするようなサービスが普及すれば、明らかに自動車の販売数は減るでしょう。資産が要らなくなるわけです。するとGDPは落ち込んでしまう。しかし、人々の快適度や幸せ度はむしろ上昇します。このようにGDPと幸せ度が乖離している時代が到来していると感じるのです。ITやロボットの発達で世の中はすごく生産性が上がっているわけですが、GDPはそれほど上がっていない。この部分をどのように捕捉すればいいのか。経済学的にもそう簡単ではないと思いますが、大きな問題ではないでしょうか。経済同友会は2016年に「経済統計の在り方に関する研究会」(座長・稲葉延雄氏=リコー取締役)を立ち上げ、「GNI(国民総所得)プラス」という新たな指標を考えるべきだと提言しました。GDPばかりに着目するのではなく、一つは海外所得を含めたGNIも合わせて見ることが重要であると指摘しました。海外進出した企業の配当金や、有価証券の利益なども考慮するのです。海外進出する企業は今後ますます増えていきます。特に米国では法人税率が引き下げられますから、そのタイミングで進出を考えている企業も相当あるでしょう。一方で、愛国心のある会社は、日本に本社を置いて配当金などで利益を得ようとするかもしれません。八田先生も先ほどおっしゃっていましたが、人口が減っても業績を伸ばすことは可能です。ただし、(国家レベルで)経済を発展させようと考えるなら、GNIといったようなコンセプトを重視する社会にする必要があると思います。海外でどんなビジネスをやっても構わないけれど、最終的に利益は日本に戻してくださいということです。もう一つは非経済分野の指標も併せて考えていくということです。社会の持続性、安全性、健康や衛生、育児や教育などの分野も加味します。さらに、温室効果ガス排出量や犯罪発生率、介護施設充足率や年間の総労働時間などの指標も加えるのです。
斎藤:いろんな面から、GDPで国家の価値を測ることには限界が来ているということですね。八田先生はどうご覧になりますか。
八田:GDPに含まれるものというのは値段があるもの、市場で取り引きされているもの、あるいはそれと同等で値段が推測できるものです。確かに、その測定方法には限界もあります。ただ、モノにはそれぞれ役割というものがあるのです。GDPについて弁護させていただきますと、GDPは直截に様々なことを我々に教えてくれます。例えば、ロシアのGDPは日本の5分の1で、イタリアと同レベルだとか。それから、世界各国が経済成長を遂げていく中で、日本だけが25年間も伸びていなかったという事実を分かりやすく教えてくれます。
斎藤:比較したり大局的に判断する場合には、非常に分かりやすいモノサシということですね。
小林:「20世紀の大発明」とも言われたりもしますからね(笑)。
八田:一方で、小林さんがおっしゃるように、GDPには生活水準の上昇が必ずしも反映されていない。その点は、日本も米国もロシアもみんな同じですが…。これからは、人々の満足度を測るのに経済学でいう「消費者余剰」を組み込めとか、色んな考えがあります。効用、満足度に焦点を当て、所得換算したらどうなるかなどを考えていくことも必要です。
斎藤:小林さんは、GDPでは国家の価値は測り切れないというお話をされる時に、「三次元で考えると捉えやすい」と言われますよね。
小林:ええ、最初は、「企業の価値って何なんだろう」と考えたことがきっかけでした。企業価値は三次元に分解できる。X軸、Y軸、Z軸に分けて考えると捉えやすいと考えたのです。企業を経営する場合に最低限必要なことは、絶対に儲けを出さなければならないということです。これが企業ベースでみたX軸で、利益、付加価値です。二つ目に企業に求められるのは次の時代を読んで新しいテクノロジーを研究開発することです。これがY軸でイノベーションです。今、世の中ではビッグデータ、IoT、ロボティクス、AI、バイオ・サイエンスなどあらゆる分野で急激なイノベーションが起きています。企業はこれに対応しなければなりません。三つ目は不祥事が起こらないようにどう徹底させるかとか、自社の技術を社会に向けてどのように役立て、社会にどう貢献していくのかということです。これがZ軸です。CSRとか「心」です。自らの企業活動が、環境問題、社会問題にどのように貢献していくか。まさに、サステイナブル・デベロップメント・ゴールズ(持続可能な開発目標、SDGs)です。この三つがない限り会社というものは潰れます。長期的に持続可能ではありません。まあ、以上の三つをよくよく考えてみると、武道などでよく言われる「心・技・体」なんですよね。これは企業だけではなく、国家もまったく同じです。国家価値も同じように測ることができます。X軸の利益は国レベルで考えれば、GDPやGNIに相当します。Y軸のイノベーションは、新しい時代を見据え、大学を中心に次世代の知的産業を開拓する。Z軸の持続可能性とは財政の持続可能性、あるいは環境問題、人口問題、エネルギー問題などにしっかり対応していくこと。それらが国家の価値という気がしています。企業も国家も価値というのはすべて「心・技・体」なんじゃないかと思うのです。
斎藤:八田先生は、今の考え方をどうご覧なりますか。
八田:経営の理念として、非常に優れたものだと思います。国に当てはめた時の私の解釈は、あまりに教科書的で申し訳ないのですが、X軸がGDP。これは必ずしも需要だけではなくて生産もすべて含まれるGDPです。Z軸は、小林さんがおっしゃったようになかなか測れないものですが、例えば東京の井の頭公園の水がきれいになったとか、隅田川の水がきれいになったとか、そういった外部経済の分野です。これは、必ずしもGDPに含まれていません。価格がゼロだから。逆に言うと外部不経済として地球温暖化への取り組みのようなことも含まれます。こういう外部経済、不経済がZ軸に入ります。では、Y軸とは何かというと、国内の資源を、現在の消費と将来の生産のためにどう分割するか。これは、言ってみれば投資と消費の分割のようなものです。技術進歩も、「今」という時間を犠牲にしてどれだけ投資するかという話になります。
小林:時間軸。
八田:そうです。だからY軸というのは、時間という視点から見て今を幸せに過ごすのか、あるいは将来をもっと幸せにするのかという選択だと解釈しているんですね。
斎藤:小林さんはX軸、Y軸、Z軸について、少し違った意味で時間の概念と対応させておられますね。
小林:ええ、X軸は一か月とか四半期単位で考える。Y軸は10年単位で考える。Z軸は1世紀単位、そんな風に考えるのが妥当かなと思っています。
斎藤:分かりやすい整理ですね。
斎藤:時代がどう変わろうが、構造改革、規制改革は常に大事ですね。お二人とも日本経済が活力を高めるには構造改革、規制改革が重要と認識されていると思います。国家戦略特区制度のワーキンググループの座長でもある八田先生は、どう進めれば良いと思っていますか。
八田:色々な切り口があると思うんですけれども、構造改革を妨げている問題を整理してみると、やはり選挙制度の問題があると思います。ひとつのポイントは地方です。これからは人口移動を(生産性の高い)外に向けて促進しなければなりません。その点では既存の政治力が流動化を妨げる面があります。 もう一つは、高齢者、老人が力を持っているということです。高齢者の投票数が多ければ、どうしてもそちらに偏った政策が強くなってしまいます。政治家だって、高齢者が多いですから。
斎藤:一票の格差とか「シルバー民主主義」の問題ですね。
八田:そうした障害を解決できるのは、政策研究大学院大学特別教授の井堀利宏氏(東京大学名誉教授)が提唱している「世代別選挙区制」の導入です。年齢別に選挙区を分け、地方の影響をなくし高齢者の影響をなくすという選挙制度です。
斎藤:私もインタビューしてお話を伺いしましたが、びっくりするようなアイデアですね。
八田:もう一つの障害は、各官公庁と業界との結びつきによるしがらみです。ここが、様々な構造改革を抑制してしまっている面があります。そこで、国家戦略特区でやったような総理主導の仕組みが必要ではないかと考えています。最後は総理が決めるんだから役所は譲るべきだという議論をしながら、どんどん改革を進めていくのです。そんなに数多くのテーマをやることはできないでしょうから選択的にやる。労働問題のような非常に重要な課題については、総理主導で改革を進める仕組みがどうしても必要になると思います。
斎藤:最近、しばしば言われているのは「総理が様々な意見に耳を傾けず、結論ありきでやっているのではないか」という見方です。国家戦略特区制度に批判的な声も巷にはありますが。
八田:それは、既得権を守りたい人がそう言っているだけの話でしょう。
斎藤:やはり、もっと総理主導でやるべきだと。
八田:それしかありません。各省に任せてしまうと、しがらみがあって改革などできないですよ。構造改革が今までできなかった理由はそこにあります。
小林:僕もかなり近い意見なんですけど、日本は少し前まで一年ごとに首相が交代していて外交的には非常に大きなハンディキャップを背負っていました。しかし、5年もやると非常に強いリーダーシップを握ることができる。安倍首相は2021年の秋までやられる確率は高いですよね(注:2018年9月の自民党総裁選で安倍氏が選出された場合、総裁任期は2021年9月までとなる)。消費増税に絡んで少子化対策費の一部として3000億円を経済界から調達するなど、安倍首相は自民党にも相談なしに決めてしまったと言われています。まあ、今までの民主主義というか、ああでもない、こうでもないいうところから比べると、ちょっと異例の早さでしたね。それに対して、あまり国民が大騒ぎはしてない現状を見ると、何が正義かと判断するのは極めて難しいということですね。確かに、プーチン大統領や習近平国家主席の体制は、政策を遂行するには効率がいい。中国なんか、「中国製造2025」を打ち出して、鉄などのコモディティー産業に見切りをつけ、次世代のIT、航空宇宙技術、先進的な交通インフラ技術、エコカー、新素材などに重点を置こうとしている。
小林:今の時代は、米国のトランプ大統領、イスラエルのネタニヤフ首相、トルコのエルドアン大統領など、もうみんなディクテーター(独裁者)的じゃないですか。ある意味でポピュリスト(大衆迎合)的であり、なおかつディクテーター的です。日本は今、政治が安定していますから、従来の既得権をぶっ壊すチャンスです。農業に限らず学界も含め既得権をぶっ壊す。世界の中で日本が優位性を持つためには、規制改革が何としても必要です。何が正義かは一番大事ですが、いま、日本は世界のディクテーター的なリーダーがいる国々と勝負しているという面もあるのです。最終的な目的は何なのか。もちろん、財政の健全化や持続可能性は、当然のことながら最重要なポイントの一つです。しかし、もっと懸念すべきは、若者も含め日本にはガッツがあってクリエティビティーのある人材がいなくなっているのではないか、という問題です。最近の日本の若者たちからは、強い活力を感じないんですよ。眼の光を感じません。幸せで何となく出来上がった「幸せな人間」ばかりです。「幸せの代償」があまりに高すぎると感じますね。これから日本はどんどん衰退していって、「5流国」になるという話もある。かつて「日の沈まぬ国」だったスペインのような衰退国家です。非常に怖いな、と感じます。衰退を止めるのは今しかありません。安倍政権には、そういう部分をやっていただきたいと思いますね。
八田:おっしゃるように、改革にはある種の強さが必要だと思うんですが、日本が中国やロシアとまったく違うのは、やっぱり基本的に民主主義だということです。だから、もし安倍政権がダメだと思えば、有権者が拒否できる。そういう条件の下で総理が強い力を発揮するということは、非常に意味のあることじゃないかなと思います。
斎藤:グローバリズムが進展する中で、国家と企業との関係はどうあるべきだと考えますか。
小林:企業と国家は、そもそもの目的や支えられているものが違います。企業は儲けることを主とし、株主に支えられています。当社(三菱ケミカルホールディングス)では既に半分が外国人投資家です。例えるならば私どもの選挙民というのはグローバルな株主なんですね。一方、国家はシルバー民主主義じゃないけど、国内の地方の高齢者たちがメインに支えている。つまり、国と企業はよって立つところが違うのです。お互いにその違いを認識しながらやっていかなきゃいけないと思います。法人税競争みたいなことになってくると、企業はますます外で展開することになりますね。理論的には、国民はシンガポールやオランダなどに移り住んでしまいます。簡単にそうはならないでしょうが、理屈ではそうなるのです。既に一部の企業は本社をシンガポールに移しています。しかし国というものは愛国心を持った「私」の集合体とも言えます。だとしたら、ここに住み、四季を楽しみながら、周辺国の脅威、北朝鮮の脅威から国を守ることも考えなければならない。みんなが、移民しちゃえばいいということにはならないと思います。結局、最後に残るのは「大和魂」なんですよ(笑)。日本人は多神教ながら、日本教という独特の愛国心がある。これは、必要ないという人には必要ないかもしれないけど、僕は体に染み込んだ日本教を信じて、日本のために企業活動をしています。ここが原点なんじゃないかと思いますね。
八田:国防の最大の道具は、経済だと思います。経済力がなかったら、どんな国防もできません。私は経済発展が必要だと思います。それから、小林さんが終始一貫しておっしゃっているように、日本は財政再建が必要です。そこで私がちょっと心配しているのは、今、安倍政権が進めようとしている「幼稚園や保育園の無償化」「大学の無償化」などの政策は、かなりばらまきの方向に向いてしまっているんじゃないかということです。
小林:確かにそうですね。
八田:政権を維持するためには、総理主導で岩盤規制を破っていくことが必要です。特に労働の規制を破ることは、自分が「爆死」してでもやるくらいの気概が大切なのに、今、何の意味もないばらまきを始めているように感じます。しかもそれは、財政再建には真っ向から反している。それはちょっと心配しているところです。
小林:安倍政権は、もうここまで勝ったんだから、あとは正義に向けた政策を実現して欲しいね。
八田:同感です。
斎藤:長時間ありがとうございました。



 2017
2017麻生太郎副総理・財務相は総選挙の直後、こんな発言をした。
「立憲民主党を左翼として計算すると、共産、社民両党を合わせても全議席の2割を切った。そこに今度の総選挙の意味がある」
「左翼の衰退」を強調したいのだろうが、保守派からは左翼と共にリベラル派も衰退の道を歩んでいるとの指摘が続く。
保守派の論客として知られる佐伯啓思・京都大学名誉教授は、立憲民主党を含むリベラル派について、こう指摘している。「彼らは、戦後のこの「体制」をできるだけそのまま続けようと言っているに等しい」(朝日新聞11月3日付)
佐伯氏は「日本社会を大きく変えていかなければならない、というのが安倍首相の基本方針である」とも述べている。安倍晋三首相が「変革」を打ち出しているのに対して、リベラル派は既成の秩序を守ろうとしているという。
リベラル派には展望がないのだろうか。
まず、今回の総選挙の結果をながめてみよう。自民党は284議席を獲得して大勝したが、政党名を書く比例区の得票は1856万票で、政権を失った2009年の1881万票を下回っている。立憲民主党は今回、1108万票を獲得、希望の党は968万票だった。自民党が圧倒的な支持を得ているとは言えない。むしろ、立憲民主党を拠点として、リベラル派は総崩れの一歩手前で踏みとどまったともいえる数字だ。
問題は今後の対応だ。そこで、リベラル派に求められるものを考えてみよう。
従来、保守とリベラルの対抗軸は「保守=既得権を守る、金持ち優遇・弱者切り捨て、憲法改正など。リベラル=既得権見直し、金持ち課税強化・弱者救済、護憲など」といったくくり方をされてきた。
ところが、小泉純一郎氏が首相時代に郵政民営化を進めたことにはじまって、保守派による「既得権打破」がアピールされ、リベラル派には「現状維持」というレッテルが張られるようになってきた。佐伯氏が指摘する安倍首相の「変革」も、そうした流れに沿うものだ。
しかし、小泉、安倍両氏の「変革」は本物だろうか。小泉氏は「郵政を民営化すれば、社会保障も外交も良くなる」と胸を張ったが、実際にはそうならなかった。小泉政権下では不良債権処理などが進んだものの、消費増税には手がつけられなかった。安倍氏にしても、2012年に政権に復帰してから5年が経つが、現在の日本が抱えている最大の問題である財政再建や社会保障について抜本的な「変革」が行われたわけではない。保守が既得権打破勢力であるというのは、政策の実質というより印象の問題ではないだろうか。
では、リベラル派はどうすればよいのか。まず、既得権にしがみついているというイメージを払拭することが必要だ。国会議員や官僚の特権を洗い出して「身を切る改革」を進める。労働組合を含めて、さまざまな業界団体の権益にメスを入れる。「弱者救済」の名で行きすぎた支出があれば、大胆に見直す。憲法改正論議にも、逃げずに正面から向き合う。そうした「変革の姿勢」を見せることで、保守派との「改革競争」をリードすることが何よりも求められる。
かつての社会党は、自民党との対抗軸として「護憲」を掲げて自民党政治の暴走を阻んだが、労組などの支持基盤にとらわれて、経済や社会保障の改革路線を打ち出せなかった。永田町での合従連衡に巻き込まれて、先細りとなった。
立憲民主党の枝野代表が「永田町の中の議論ではなく、国民の目線での議論が大事だ」というその方向性は間違ってはいないだろう。ただ、ある民主党の代表経験者が「立憲民主党が改革に正面から取り組まず、反自民の旗印を掲げているだけでは政権は取れない」と言うように、自民党に対抗する改革路線をどう打ち出していくかが、今後の課題である。
リベラルは立憲民主党の専売特許ではない。民進党出身者が多い希望にも、リベラル派はいる。自民党でも、池田勇人、大平正芳、宮沢喜一各氏らが率いた宏池会の会長を務める岸田文雄政調会長は、「リベラル派」を自認する。公明党・創価学会にも「立ち位置は宏池会とあまり違わない」という幹部は少なくない。
グローバル化が進んで経済の格差が拡大し、国際的には排他主義が広がる中で、格差縮小や国際協調主義を掲げるリベラル派が果たすべき役割はむしろ、大きくなっている。リベラル派には再興の努力が求められる時である。

政府の国家戦略特区諮問会議が今週ようやく再始動した。諮問会議が開かれたのは5月以来で、それまで改革論議が停滞したのは極めて残念である。
背景には、特区を使った学校法人「加計学園」(岡山市)による獣医学部新設をめぐる問題があった。加計学園の理事長は安倍晋三首相の友人だ。そのため、政治の圧力や官僚の忖度(そんたく)があったか否かをめぐる議論に政府や国会は長い時間を費やした。
政府は引き続き政策判断の経緯を丁寧に説明していく必要がある。省庁間のやりとりで「言った」「言わなかった」といった誤解を生まないように議事録をつくったり、議事公開のルールをつくったりするのは妥当だろう。
同時に、これまで以上に改革の本丸である規制の緩和や撤廃を加速させなくてはならない。
特区はこれまでも一定の成果をあげてきた。都市再開発のための容積率緩和や、一般の家に旅行客を泊める民泊を実現した。
都市公園に保育所を設置できるようにしたり、高齢人材の労働時間を柔軟にしたりするなど、特区発の政策を全国展開した例もある。問題は改革が徹底していない分野が残っていることだ。
例えば、一般の運転手が利用者を運ぶライドシェア(相乗り)や、テレビ電話を使った薬剤師による遠隔服薬指導はすでに特区で解禁されたのに、これまでの利用実績はゼロだ。自治体や民間への周知が不足しているのではないか。
新政策についても政府と自治体はもっと大胆に提案していく必要がある。東京都と豊島区が介護保険と保険外サービスを組み合わせた「混合介護」のモデル事業を計画しているのは前進だ。
ほかにも外国人受け入れや、企業の農地保有の拡大など、今ある政策をさらに深掘りする余地は大きいはずだ。関連法改正などスピード感を持って実現すべきだ。
人事異動もあり、特区の事務局の機能が低下しているのではないかと心配だ。必要なら人員を増やしたり、規制改革推進会議と事務局を統合したりするのは一案だ。将来の成長の種をまく規制改革の足踏みは許されない。

アベノミクスが掲げる3本の矢のうち、最も期待されながらも「道半ば」と批判され続けてきたのが「第3の矢=投資を喚起する成長戦略」だ。安倍晋三首相も、常々「規制改革が一丁目一番地だ」と言い続けてきた。
その規制改革の方向性や内容を協議する組織が「規制改革推進会議」である。前身の「規制改革会議」を踏襲する形で設立された諮問会議。同推進会議が検討してきた「答申」が、この5月23日に安倍首相に提出された。
提出された答申の内容については新聞等で細かく報道されたため詳細は省くが、「規制改革 新味乏しく」(日経新聞)あるいは「規制緩和 踏み込み不足『混合介護』見送り」(朝日新聞)といった具合に、メディアでの評価はあまり芳しくなかった。実際に「労働基準監督署の業務の民間開放」や「行政手続きコストの2割削減」など、一部で目新しいものもあるが、次のような項目で具体策が先送りになるなど、中途半端なものが多かった。
・保険外サービスなど「混合介護」の本格解禁
・勤務地や仕事内容を限定して働く「限定正社員」の雇用ルールの明確化
・自家用車でのライドシェア(相乗り)の解禁
・不動産登記情報のネットでの無料公開
規制緩和がどんどん進んでいく海外諸国に比べて、日本の規制緩和は遅々として進まない。金融業界に限っていえば、規制の大半を撤廃した香港やシンガポールが、かつて3大金融市場といわれた東京市場を凌駕する「国際金融センター」に成長してしまった。
アベノミクスをスタートさせるにあたって、安倍首相自身も「岩盤規制にメスを入れる」「聖域なき規制緩和を行う」と宣言してきた。しかし、森友学園や加計学園といったスキャンダルを見ると、安倍首相がやったのは岩盤規制を放置して、お友達の「倫理なきビジネス」の手助けをしたようにしか思えない。
自民党政権は、長期にわたって規制緩和を掛け声に選挙を有利に戦ってきた。しかし、その実態は諸外国に比べて遅々として進んでいない現実もある。今回の規制改革推進会議の答申を機に、日本の規制緩和について考えてみたい。
●規制は本来「政治家」と「官僚」の利権だった?
もともと今回の規制改革推進会議は、首相官邸が主導してきた一連の「規制改革会議」がベースにある。自民党政権時代、民主党政権時代ともに、同様の会議が、名称などを次々に変えながら延々と続けられてきたものだ。
システムとしては、首相の諮問会議という形式にして、どんな規制緩和が適切かを審議して首相に答申する仕組みになっている。最も有名なのが森喜朗内閣、小泉純一郎政権時代に設置された「総合規制改革会議」(2001年4月1日〜2004年3月31日)で、オリックスのCEOだった宮内義彦議長が、「製造業における労働者派遣事業の解禁」と「郵政民営化」などを答申した。
正規社員を激減させて、パートやアルバイトばかりを増やすことになった労働者派遣事業の解禁も、もともとは規制緩和の一環だったわけだ。結果的に、国民を苦しめる規制緩和になったと言っても過言ではないだろう。
また、郵政民営化の議論では3年間の議事録が作成されておらず、会議でどんな議論がなされたのか詳細が不明で、議長の説明責任が問われたものの、2004年3月に閣議決定されて推進された。周知のように、郵政民営化は国会を解散して国民に信を問うた。小泉政権は大勝し、その流れで第1次安倍内閣も誕生した。
その後も、「規制改革・民間開放推進会議」(第2次、第3次小泉内閣)、「規制改革会議」(第1次安倍内閣、福田康夫内閣、麻生太郎内閣、鳩山由紀夫内閣)と続き、第2次安倍政権時代にも「規制改革会議」の名で引き継がれた。2016年7月に規制改革会議の任期が終了し、現在の「規制改革推進会議」がスタートしたわけだ。
こうした一連の規制改革会議の議題や答申内容を見るとわかるのだが、おおむね自民党の支持母体である大企業などが、よりスムーズにビジネスを展開するための規制緩和が主であって、国民や納税者が主となる規制緩和は少ない。
国民が選挙で自民党を選択しているのだから仕方がないと言えばそれまでだが、そもそも同会議のメンバーの選別からして、企業サイドの人間が多い。
●突破口として作られた「国家戦略特区」が狙われた?
安倍首相自身が指摘するように、日本にはまだ数多くの「岩盤規制」が残っている。岩盤規制とは、規制を担当する官庁(役所)や族議員、業界団体などが「三位一体のスクラム」を組んで「緩和されること」を阻止している規制のことだ。医療、農業、教育、雇用などの分野に多いといわれるが、解禁されて自由化されてしまえば、各省庁やお役所の役割がなくなり、仕事を失うことになる。政治家もまた「利権」を失うことになるわけだ。
その岩盤規制が、いまだ「道半ば」であることはさまざまなメディアでも紹介されているが、そもそも首相自身が岩盤規制の存在を認めていることにも違和感がある。岩盤規制があるとすれば、その主犯格は行政であり、そのトップが他人事のように「岩盤規制」などと発言することは、自分の至らなさを認めているのと一緒だ。
たとえば、いま世間を騒がせている加計学園の獣医学部新設問題の舞台となった「国家戦略特区」は、首相を議長として内閣府に設定された「国家戦略特別区域諮問会議」が提唱したものだ。岩盤規制を突き崩すための切り札として、全国9カ所に特区を制定して、既存の省庁が介入できないようにした。
そもそも規制緩和は、民間の有識者などを集めて諮問会議をつくり、公平かつ公正な立場で、どの分野のどの部分の規制を緩和すればいいのかを審議させ、そのうえで規制緩和の推進をしていくというのが普通のプロセスだ。その点、国家戦略特区は首相が自ら議長となって、自分の意図する分野の規制を実施していこうというプロセスをたどっている。これまでのボトムアップスタイルとは真逆の「トップダウン」方式のプロセスが採用されている。
そういう意味で言えば、加計学園のスキャンダルが噴出した背景には、岩盤規制を守っているスクラム側の反撃と言えなくもない。とはいえ、「お友達」を優遇したのではないかと疑われるような方法で、数百億円もの資金が動くプロジェクトを推進してしまったところに問題がある。
いずれにしても、日本の規制が綿々と守られ続けている背景には「縦割りの行政機構」があり、省庁が握っている「許認可」の数に問題があると言われてきた。かつて、英国のマーガレット・サッチャー政権や米国のロナルド・レーガン政権時代に「規制緩和(ディレギュレーション)」が景気回復の方法として断行され、それなりの成果を上げた。
ところが、日本では大胆な規制緩和と呼ばれるものが、なかなか実現してこなかった。さすがに携帯電話などの通信事業やIT事業といった、技術革新による時代の変化には対応せざるをえなかったようだが、それでも日本の規制緩和はさまざまな分野で進んでいない。
私事で恐縮だが、私は1994年に日本の規制緩和をテーマにした『官僚統制列島 日本が危ない』(ごま書房)を上梓している。当時の政府が抱えていた許認可数は1万1402件(1993年3月時点)で、年々増える傾向にあったのを覚えている。
当時はまだ政府の財政赤字もわずか220兆円程度で、財政に対する危機意識は低かったが、それでもすでに行政機構には岩盤規制があって、日本の成長を妨げていると指摘する人が多かった。省庁の許認可と族議員や業界の利害関係が一致していて、英国や米国がやったような大胆な規制緩和が実現できない状態だった。
その書籍の中で、私はわかりやすいケースとして、当時の写真集や雑誌でのヌード写真の「ヘア」が突然、解禁されたことを取り上げ、「いったい誰が、どんな権限で、どんなプロセスで解禁にしたのか、不透明すぎる」と批判した。米国では、きちんと最高裁が「人間の体には猥褻(わいせつ)な部分などどこにもない」という判決を出して、その瞬間にオール解禁になった。
言い換えれば、日本の司法はつねに判断を避けてあいまいのまま放置し、代わりに行政が勝手に判断している状態だ。結果的に日本は規制緩和が進まず、経済の成長を阻害しているわけだ。
ちなみに、現在の省庁の許認可数は1万4908件(総務省行政評価局、2015年4月1日現在)。近年ずっと1万4000件台で横ばい状態だ。許認可というのは、許可、認可、免許、承認、検査、登録、届け出、報告等といったもの。最も多くの許認可を抱えているのは、国土交通省で2699件に達する。なお、1993年3月時点で最も多くの許認可を抱えていたのは通商産業省(現経済産業省)で1986件だった。
●日本の規制緩和が遅れているのは「司法」の怠慢だ!
さて、日本ではなぜこうも規制緩和が進まないのだろうか。綿々と続けられている規制緩和のための諮問会議も、高い税金を使って有識者を集めている割に、大胆な案はさっぱり出てこない。
岩盤規制を守っている三位一体のスクラムを組んでいるグループに対して、「忖度(そんたく)丸出し」「配慮だらけ」の答申しか出てこない。政府があらかじめ作った原案をそのまま踏襲するだけの答申しか出せない。そんな会議や制度が必要かどうか疑問だし、官僚や政治家の干渉を受けない抜本的な規制改革を打ち出せるような仕組みに変えたほうがいいだろう。
そもそも規制緩和は何をもたらすのか。簡単にピックアップしてみると、
・業界全体のパイが拡大する(経済成長をもたらす)
・民営化の進展で新規雇用が創出される
・業界全体のグローバル化が進む(外国資本の流入、市場の国際化)
事業の設立状況や資金調達の環境などで、その国の規制緩和や国際化の進捗状況を評価したランキングに「世界銀行ビジネス環境ランキング」というのがある。2017年の総合ランキングで日本は世界ランキング34位となっている。
ちなみに1位はニュージーランド、以下シンガポール、デンマーク、香港、韓国と続く。78位の中国よりはましだが、日本はなぜかくも遅れているのか。その中身を見ると、事業設立分野では89位、資金調達部門で82位、建設許可取得で60位と大きく遅れが目立つ。
つまり、外国企業にとって日本は市場参入しにくい存在であり、日本企業にとっては逆に海外進出する意味があまりないともいえる。日本の規制緩和の遅れが日本企業の海外進出も阻んでいるし、いずれは決断しなければならない外国人労働者の大量受け入れといった、本当の意味のグローバル化も遅くなる一方といってよい。
●日本の成長戦略にもマイナスに
なぜ、岩盤規制が残り、強固な規制を突き崩せないのか……。前述したように、その責任の一端は「司法」の怠慢にあると私は思っている。日本の司法制度は、地裁から最高裁判所までそろって行政に遠慮して、その方向に沿った判決や判断しかしないことで知られる。司法の怠慢は、日本経済全体の勢いにブレーキをかけ、日本の成長戦略にもマイナスになっている。
混乱させない、という理由で、違憲状態の総選挙やり直しを命ずることもなく、国民主権を守ろうという姿勢がほとんど感じられない。企業も国に逆らってまで新しいことにチャレンジしようという気概が感じられない。
たとえば、今までまったく想定していなかったような新規事業を展開する場合、海外では政府や役所の意向とは関係なしに民間企業がどんどん事業化に突っ走る。もし、そこで行政によるブレーキがかかった場合は、訴訟も辞さない覚悟で突き進むケースが多い。
その背景には、米国や英国では司法が的確な判断をしてくれるはずという安心感があるからだ。司法が正しい判断をしてくれる、という安心感があるから、莫大な投資も可能となり、新しいイノベーションに突き進むことができる。
日本の場合、100%とはいわないが、ほぼ行政側が勝訴する。司法に対して、まったく信頼感がない。そんなリスクを抱えている市場では、投資家も大切な資金を出せない。日本の司法は行政の方向性を逸脱するような判断をしないし、判断をする場合も時間をかけて、恐る恐る進めていく。その結果、憲法判断でさえ行政が勝手にしてしまう状況が続く。
裁判官の多くは、自分の地位や高額の報酬、厚遇された職場環境は、行政が与えてくれていると考えているのかもしれない。しかし、本当はその報酬も快適な職場環境も国民がコストを負担していることを忘れないでほしい。主権は国民なのだ。



 2016
2016「左巻き」の人々は、どうしてウソのニュースを報道したり、間違った知識で議論をしてしまうのだろうか。
メディア関係者や、公務員、教員、大学教授などはそれぞれマスコミ、役所、学校、大学という既得権にまみれた環境に安住している。日々厳しいビジネスの世界で緊張感ある働き方をしていれば、どうやって儲けて、いかに生きていこうか必死になるはずだが、そういった切迫した危機感がない状況だから、左巻きの考え方をしていても平気でいられるのだ。
マスコミの中でも、新聞はとくに左巻きがのさばっているメディアだ。そうして的はずれな記事を平然と報道している。
新聞の報道が嘘八百になる原因が4つある。まずは、日刊新聞紙法という法律だ。もう1つは再販規制。そして3番目は最近新たに生まれた軽減税率だ。この3つで新聞はすべて守られている。
それにプラスして、これは実体の話だが、新聞社屋のための国有地の売却という問題が絡んでくる。日本の新聞社の多くが、総務省から国有地を安く払い下げてもらって、社屋をそこに建設している。ある種の優遇措置を受けてきたと言っていい。大手町や築地、竹橋などの一等地に新聞社が立ち並んでいるのには、そのような理由があるのだ。
ここから、新聞を既得権まみれとしている法律について見ていこう。
まず日刊新聞紙法というのはどういう法律か。すごく変わっている法律で、実は世界にこんな法律は日本にしかない。ポイントは、新聞社は全国紙のすべてが株式会社で、地方紙も株式会社が多いのだが、その「株主が誰か」ということだ。
商法の大原則だが、株式というのは譲渡制限がない。これは株式会社の株式会社たるゆえんと言える。譲渡制限がないからどんな時にもオーナーが代わり得る。この「オーナーが代わり得る」ということが重要だ。
要するにオーナーはのうのうと安住できないということだ。そうすることで会社の緊張感が保たれ、きちんとした経営をするということになる。
しかし新聞社の株式は、日刊新聞紙法によってなんと譲渡制限が設けられているのだ。
制限があるとどうなるか。
たとえば朝日新聞を例にとってみよう。朝日新聞は、村山家と上野家が代々ずっとオーナーとして存在する企業だ。株式の譲渡が制限されているのだからオーナーが代わることがない。このように完全に経営者が代わらないと、オーナーがどんな意見を言うか言わないかで、経営方針をはじめとする会社のすべてのことが決まってしまう。
ただし、新聞社のオーナーは現場に意見を言わないケースがほとんどだ。するとどうなるかというと、現場の社長が経営のすべてを握ってしまう。そうして、絶対にクビにならない社長になるというわけだ。
もう1つの例として、読売新聞を見てみよう。渡邉恒雄代表取締役兼主筆がなぜ、あれだけの権力を持ち続けられるか考えてみて欲しい。読売は従業員持ち株会もあるのだが、結局会社はオーナーのものだ。
●そして新聞社が「既得権益集団」になる
株式が譲渡されない安泰な経営のなかで、オーナーが口出しをすることがないので経営陣にはなんのプレッシャーもかからない。そうして経営トップが大きな顔し続けることになる。
日経新聞などは企業の不祥事を追求する記事で「コーポレートガバナンスが重要」とよく書いているが、自分の会社が一番コーポレートガバナンスが利かないのだ。なぜなら、株式の譲渡制限があるからだ。それではガバナンスなど効きようがない。
新聞社の株式が譲渡されないということは、つまり絶対に買収されない仕組みになっているということだ。さらに、その新聞社がテレビ局の株を持つ。朝日新聞ならテレビ朝日、読売新聞は日本テレビといった具合だ。そうすると、テレビも新聞社と同じようにまったくガバナンスが利かなくなる。
そうして新聞社を頂点として構成されたメディアは、既得権の塊になってしまう。
以上のような仕組みになっているため、一度新聞社の経営陣に加わってしまえば絶対安泰だ。クビになることはまずない。これは、他の業界では絶対にあり得ない既得権を守る規制なのだ。
●一番ガバナンスがないのは、新聞社だった
世界基準で見てもこの日本のメディア構造は異常である。普通の国ではメディアも普通に買収される。経営者が代わることもあるので、これが会社としてメディアとしての緊張感につながるのだ。
たとえば2015年の11月に、日経新聞が米フィナンシャル・タイムズを買収したことは記憶に新しい。日経新聞が、米フィナンシャル・タイムズの親会社だった英ピアソンから株式を買収して自らのグループに組み込んだのだが、これはごく普通の企業買収と言える。しかし、日経新聞のほうは株式が譲渡できないから、決して買収されない仕組みになっている。
そんなものは商法違反でないか、と憤る人もいるかもしれない。この状態を商法の適用除外にしているのが「日刊新聞紙法」なのだ。
日刊新聞紙法はすごく短い法律で、正式には「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律」という。名前に書いてあることがこの法律のすべてで、「株式は譲渡されない」ということしか書いていない。新聞の既得権の最大のものと言っていい。
普通に働いている人たちには馴染みがないが、新聞社に務める人間ならみんな知っている法律だ。
しかし、新聞社の人間でこのことを堂々と記事で書く人間はいない。新聞は企業の不祥事があった時に「コーポレートガバナンスができていない」「社内制度が悪い」などと書き連ねるが、一番ガバナンスができていないはその新聞社なのだ。記者も、それが分かっているから日刊新聞紙法について恥ずかしくて書けないのだろう。
この法律が、新聞社を堕落させていることに、記者も早く気がつくべきだ。自分だけ安泰な身分では、他者に厳しいことがいえるはずない。自分には甘く他者に厳しいのはありえない。言論で勝負する人は、やせ我慢が必要なのだ。
●テレビ局も既得権の塊
ここでテレビ局に話題を移したい。新聞社が子会社のテレビ局を支配しているという構造的な問題は、前段で触れたとおり。さらに、そのテレビ局が既得権化している理由は、地上波放送事業への新規参入が実質的に不可能になっていることにある。
総務省の認可を受けた場合にしかテレビ放送事業はできない。「放送法」によって免許制度になっているわけだが、このことがテレビ局を既得権まみれにしている最大の原因だ。
はっきり言おう。「電波オークション」をやらないことが、テレビの問題なのだ。電波オークションとは、電波の周波数帯の利用権を競争入札にかけることだ。
日本では電波オークションが行われないために、電波の権利のほとんどを、既存のメディアが取ってしまっている。たとえば、地上波のテレビ局が、CS放送でもBS放送でも3つも4つチャンネルを持ってしまっているのもそのためだ。
電波オークションをしないために利権がそのままになり、テレビ局はその恩典に与っている。テレビ局は「電波利用料を取られている」と主張するのだが、その額は数十億円程度といったところだ。もしオークションにかければ、現在のテレビ局が支払うべき電波利用料は2000億円から3000億円は下らないだろう。現在のテレビ局は、100分の1、数十分の1の費用で特権を手にしているのだ。
つまり、テレビ局からすると、絶対に電波オークションは避けたいわけだ。そのために、放送法・放送政策を管轄する総務省に働きかけることになる。
その総務省も、実際は電波オークションを実施したら、その分収入があるのは分かっているはずだ。それをしないのは、テレビ局は新規参入を防いで既得権を守るため、総務省は「ある目的」のために、互いに協力関係を結んでいるからだ。
●放送法の大問題
そこで出てくるのが「放送法」だ。昨今、政治によるメディアへの介入を問題視するニュースがよく流れているので、ご存じの方も多いだろう。話題の中心になるのが、放送法の4条。放送法4条とは以下の様な条文だ。
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
これを根拠に、政府側は「放送法を守り、政治的に公平な報道を心がけよ」と言い、さらに電波法76条に基づく「停波」もあり得るというわけだ。
一方で左巻きの人々は、放送法4条は「倫理規範だ」とする。つまり、単なる道徳上の努力義務しかない、と反論をしている。
しかし、筆者から見ればなんともつまらない議論だ。
そもそも、世界ではそんな議論をしている国はない。「放送法を守れ」「これは倫理規範だ」なんてつまらない議論をするのではなく、「市場原理に任せ、自由競争をすればいい」だけの話なのだ。
電波オークションによって放送局が自由に参入して競争が起これば、質の高い報道や番組が生まれるはずなのだ。おかしなことを言っていたら人気がなくなるし、人気があれば視聴者を獲得しスポンサーも付く。そうやって放送局が淘汰されれば、放送法など必要ないはずだ。
繰り返すが、電波オークションをやると一番困るのは既存の放送局だ。だから、必死になって電波オークションが行われないように世論を誘導している。
総務省はその事情を知っているから、「放送法」をチラつかせる。「テレビの利権を守ってやっているのだから、放送法を守れよ」というわけだ。それはテレビ局も重々承知。言ってしまえば、マスコミは役所と持ちつ持たれつの関係になっている。
●マスコミをダメにする「悪魔の一手」
最近では右派の人たちが、左巻きのメディアに対して「放送法を守れ」と息巻いている。筆者からするとそれはつまらないやり方だ。言葉は悪いが、もしマスコミを「潰したい」のなら、電波オークションで新規参入させるよう促せばいい。
「放送法は守らなくてもいいから、電波オークションにして誰でも意見を発信できるようにしろ」と言えばいいのだ。そうなるのが、テレビ局にとっては一番痛い。
この電波オークションの問題は、当然ながらテレビ界ではタブーとされている。電波オークションについて必要性を語る論者は、テレビ局にとっては要注意人物。筆者もそのひとりだ。
もし地上波で「実は電波利用料は数十億しか払ってないけど、本当は3000億円払わなければいけないですよね」などと言おうものなら、テレビ局の人間はみんな真っ青になって、番組はその場で終わってしまうだろう。テレビでコメンテーターをしているジャーナリストも、その利権の恩恵に与っているので大きな声で指摘しない。
電波オークションをすれば、もちろん巨大な資本が参入してくるだろう。ソフトバンクなどの国内企業をはじめ、外国資本にも新規参入したいという企業はたくさんある。
既存のテレビ局は巨大な社屋やスタジオを所有しているが、これだけ映像技術が進歩している現在では、放送のための費用はそこまでかからない。今では、インターネット上で自由に放送しているメディアがたくさんあるのだからそれは明らかだ。
既存の放送局の権利を電波オークションで競り落とすと考えれば費用は膨大に思えるが、電波だけではなくインターネットを含めて考えれば、放送局そのものは何百局あってもかまわないのだから、新規参入するのに費用は数百億円もかかるものではない。
資本力がある企業が有利ではあるかもしれないが、技術が進歩しているために放送をする費用そのものはたいしたものでなないのだから、誰にでも門は開かれている。
多様な放送が可能になれば、どんな局が入ってきても関係がない。今は地上波キー局の数局だけが支配しているから、それぞれのテレビ局が異常なまでに影響力を強めている。影響力が強いから放送法を守れという議論にもなる。しかし放送局が何百もの数になれば影響力も分散され、全体で公平になる。そのほうが、健全な報道が期待できるだろう。
しかし、筆者などが「既得権をぶち壊そう」と提言すると、いつも激しい反発を食らう。マスコミや、教員、公務員の既得権を批判すると、すぐに左派の学者が出てきて共闘を始める。
経済問題への無知さ加減はもちろんだが、それにも増して、こういった既得権にまみれながら厚顔でいるところも、筆者が「左巻きはバカばかり」と言いたくなる理由だ。



 2015
2015検察の言い分は「あのような大きな津波が発生することを確実に予測することはできなかった。従って、東京電力の備えが不十分だったとは言えない」というものです。確かに、東京電力はそう主張しています。規制官庁の原子力安全・保安院も右へならえです。しかし、本当にそうだったのでしょうか。大津波を予測し、警告した人はいなかったのか。東電と保安院はなすべきことをきちんとしてきたのか。
福島の原発事故を考える際に、つい見落としてしまいがちなことがあります。それは、2011年3月11日に東北の沖合で巨大地震が発生し、大津波に襲われたのは福島第一原発だけではない、ということです。大津波は宮城県にある女川原発にも福島第二原発にも押し寄せました。なのになぜ、福島第一原発だけがこの悲惨な事故を引き起こしたのか。しかも、福島第一に6基ある原子炉のうち、なぜ1?4号機だけが全電源の喪失、原子炉の制御不能、炉心溶融と放射性物質の大量放出という大惨事を招いてしまったのか。それには、しかるべき理由と原因があるはずです。
その点をとことん突き詰めた本があります。昨年の11月に出版された添田孝史氏の『原発と大津波 警告を葬った人々』(岩波新書)です。添田氏は朝日新聞の科学記者でしたが、2011年5月に退社してこの問題の追及に専念し、本にまとめました。実に優れた報告です。とりわけ、女川原発と福島第一原発の設置時の津波想定を比較している序章が秀逸です。
原発の設置申請は福島第一の1号機が1966年、女川原発の1号機が1971年でした。まだ地震の研究が十分に進んでいない時期で、津波の研究はさらに立ち遅れていました。そうした中で、東京電力が福島第一原発の設置申請をする際に想定した津波は、1960年のチリ地震の津波でした。この時、福島第一原発に近い小名浜港で記録された津波の高さは3.122メートル。これに安全性の余裕を見て5メートルほどの津波を想定し、海面から30メートルあった敷地を10メートルまで削っで原発を建設したのです。当時はこれで十分、と判断したのでしょう。
これに対して、女川原発では明治29年と昭和8年の三陸大津波に加えて、869年の貞観(じょうがん)地震による大津波をも念頭に置いて津波対策を施し、原発の敷地を14.8メートルに設定しました。東電が調べたのはわずか10数年分の津波データ。それに対し、平安時代まで遡って津波を考えた東北電力。その結果が海面からの敷地の高さが10メートルの福島第一と14.8メートルの女川という差となって現れたのです。この4.8メートルの差が決定的でした。
添田氏は、女川原発の建設にあたって、東北電力がなぜそのように慎重に津波の想定をしたのかを詳しく調べています。そのうえで、同社の副社長だった平井弥之助氏の存在が大きかった、と結論づけています。宮城県岩沼市出身の平井氏は、三陸大津波の記録に加えて、地元に伝わる貞観大津波のことを知っていたのです。そして、部下たちに「自然に対する畏れを忘れず、技術者としての結果責任を果たさなければならない」と力説していました。(前掲書p12)。平井氏の思いは部下に伝わり、女川原発を津波から守った、と言うべきでしょう。
東京電力の大甘の津波想定がその後もそのまま通用するはずがありません。地震と津波の研究が進むにつれて、東京電力は「津波対策を強化すべきだ」という圧力にされされ続けます。1993年の北海道南西沖地震では、奥尻島に8メートルを超える津波が押し寄せ、最大遡上高は30メートルに達しました。これを受けて、国土庁や建設省、消防庁など7省庁が「津波防災対策の手引き」をまとめ、「これまでの津波想定にとらわれることなく、想定しうる最大規模の地震津波も検討すべきである」と打ち出しました。
1995年の阪神大震災の後には、政府の地震調査研究本部が「宮城沖や福島沖、茨城沖でも大津波が起きる危険性がある」と警告を発しました。2004年のインド洋大津波の後にも、津波対策を急がなければならないと問題提起した専門家は何人もいたのです。
それらに、東京電力はどう対処したのか。2008年には社内からも「15メートルを超える津波が押し寄せる可能性がある」という報告が上がってきていたのに、上層部が握りつぶし、ほとんど何の対策も取らなかったのです。それどころか、意のままになる地震学者を動員して、警告を発する専門家や研究者の動きを封じて回った疑いが濃厚です。東電はこの間、度重なる原発の事故隠しスキャンダルで逆風にさらされ、中越地震で損壊した柏崎刈羽原発の補修工事にも追われて赤字に陥り、経営的にも厳しい状況にありました。巨額の費用がかかる津波対策を先送りにせざるを得ない状況に追い込まれていたのですが、そうした事情を割り引いても、許しがたい対応と言わなければなりません。
添田氏は地震の研究者や原子力規制の担当官、電力会社の幹部らに取材して、その経過と実態を白日の下にさらそうとしています。経済産業省や保安院が東電をかばって資料を見せようとしないのに対しては、情報公開制度を駆使して文書を開示させています。彼の本はそのタイトル通り、津波に対する警告を葬った人々に対する弾劾の書です。
日本の検察は「有罪にできる自信がない限り、起訴しない」というのを鉄則にしています。いったん起訴されれば、被告の負担は大きく、たとえ無罪になったとしても取り返しのつかない打撃を受けるおそれがあるからです。それはそれで立派な原則ですが、それを権力を握り(地域独占企業である東京電力は限りなく「権力機関」に近い)、中央省庁を巻き込んで都合の悪いことを隠そうとする組織の幹部にまで同じように適用しようとするから、おかしなことになるのです。
11人の市民からなる東京第五検察審査会が東京地検の不起訴処分を覆して、東電の勝俣恒久・元会長と武黒一郎・元副社長、武藤栄・元副社長の3人を業務上過失致死傷の罪で強制起訴する、と決めたのは極めて健全な判断と言うべきです。検察は「大津波を確実に予測することはできなかった」と主張しているようですが、そもそも数千年、数万年、数十万年というスパンで動く地球の動きを地震学者が「確実に予測する」ことなど、昔からできなかったし、今でもできはしないのです。できることは「自然に対する畏れを忘れず、謙虚に研究を積み重ね、できる限りの対策を施す」ということに尽きます。東北電力はそれを愚直に守り、東京電力は「小さな世界」に閉じこもって姑息な手段を弄し、大自然の鉄槌を浴びる結果を招いたのです。
「小さな世界に閉じこもる」という点では、検察も同じです。日本で現在のような法体系ができたのは明治維新以降で、まだ1世紀半しか経っていません。そういう小さな枠組みで、東日本大震災という未曽有の事態に対処しようとするから、おかしなことになるのです。突き詰めれば、法の淵源は一人ひとりの良心と良識、その総和にほかなりません。そういう大きな枠組みに立ち、未来を見据えて、東電の幹部は司法の場で裁かれるべきかどうか判断すべきでした。有罪か無罪かはその先の問題であり、最終的な判断は裁判所に託すべきだったのです。
検察審査会が東電の旧経営陣3人の強制起訴を決めたことに関する新聞各紙の報道(8月1日付)も興味深いものでした。原発政策の推進を説く読売新聞が冷ややかに報じたのは理解できますが、朝日新聞まで1面に「検察と市民 割れた判断」と題した解説記事を掲載したのには首をかしげざるを得ませんでした。中立的と言えば聞こえはいいのですが、それは検察の言い分をたっぷり盛り込んだ、他人事のような記事でした。
中央省庁や電力会社の人間に取り囲まれ、その言い分に染まり、既得権益の海に沈んだ検察。その検察の取り巻きのようになって、一緒に沈んでいく司法クラブの記者たち。朝日、毎日、読売の3紙を読み比べた範囲では、「予見・回避できた」という検察審査会の主張を1面の大見出しでうたった毎日新聞が一番まともだ、と感じました。「法と正義はどうあるべきか」を決めるのは検察ではありません。三権のひとつ、司法の担い手である裁判所であり、最終的には主権者である私たち、国民です。その意味で、検察審査会のメンバーは立派にその職責を果たした、と言うべきです。

人口減少・高齢化や地域経済の疲弊等が進む中、厳しい財政制約の下での行政サービスの提供範囲や内容等のあり方を見直す必要性が高まっている。全ての公的サービスを行政に求めることが難しくなっており、国民・企業等が主体的に参画し社会課題解決に向けて協働することへの時代の要請も強い。同時に、グローバル化や国際競争の激化等により、規制や公的負担率等が国の立地競争力、さらには企業の競争力に影響を及ぼしており、国際的なイコールフッティングの確保が不可欠となっている。
政府においては、行政改革推進法等に基づき、掲げられた個別課題の改革を進め、一定の進展があったことは評価されるところである。2001年の省庁再編から15年、2006年成立の行革推進法から10年近くが経ち、消費増税等により国民に一層の負担を求められている中、行政も自己を改革し、行政のスリム化・効率化を断行するとともに、自立した参加型社会を構築すべき時期を迎えている。
●(2) 目指すべき方向性
1.必要な行政サービスの見直しと民間・地方の活力向上(小さな政府の実現)
国民に対し最低限保障すべき行政サービス・水準を見極め、民間にできることは民間に、地方にできることは地方に委ねることで、小さな政府を実現する。その際、規制改革等を通じた民間活力の活用や国民参加を図るとともに、道州制への移行も含め、国・地方の関係の一体的な改革を推進する視点も重要となる。
2.ICTデフォルトの業務改革と行政サービス向上(効率的で質の高い行政の実現)
許認可や行政サービスに係る業務プロセスを国民の利便性向上の観点から一から見直し、ICT等の技術革新を所与のものとした業務改革により、国民本位の効率的で質の高い行政を実現する。併せて、行政のオープン化・双方化を推進することで、行政情報の民間活用の促進、国民の声の行政への反映にもつなげる。
3.政策立案機能の強化とPDCAサイクルの深化(行政ガバナンスの強化)
2001年の中央省庁等改革の評価を踏まえ、内閣機能の強化や行政需要に応じた組織改革により、機動的かつ戦略的な政策の企画・立案を可能とする体制を整備する。併せて、Evidence Based Policyを基本とし、情報公開や政策評価、人事評価、予算編成等を一体的に運用することで、行政のPDCAサイクルの適正化を図る。
●(3) 行政改革の推進体制
2006年の行政改革推進法の成立から10年近くが経過したこともあり、その間の改革の成果と今後の課題について検証を行い、同法で掲げた重点分野および各重点分野における改革の基本方針等を見直すことを含め、同法を行政改革の基本法として抜本的に改正することにより、行政改革を国政の最重要課題の一つとして恒久的に推進する。また、重要性の高い改革項目について集中的に改革を推進する観点から、臨時行政調査会の仕組みを活用することも一案である。併せて、行政に対するガバナンスを確立する観点から、行政改革推進本部や行政改革推進会議の位置づけを、法定化することも視野に、強化する。
1.規制改革
政治のリーダーシップの下、規制改革会議を中心に、農業や雇用等の岩盤規制をはじめ、地道な取組みにより改革の成果が上がっており、また、国家戦略特区や企業実証特例制度等、新たな仕組みも創設されたことは評価される。
しかしながら、公務員に規制改革のインセンティブが働く仕組みがなく、下位規制も含め規制の体系が複雑化しており、長期にわたり見直しが行われていない規制も少なくない。また、特区等の制度についても、制度間の重複、その後の全国展開が不明瞭といった問題も指摘される。
政府は各省の規制権限に固執するのではなく、「経済的規制は原則廃止、社会的規制は必要最小限度」との原則の下、国際的なイコールフッティングを確保する観点からも、改革の手綱を緩めることなく全力で取組むことが求められる。とりわけ、2016年3月には規制改革会議が設置期限を迎える機を捉え、政府としての規制改革の体制の強化、規制の見直しルールの整備、特区制度等の改革ツールの検証・見直しを推進する必要がある。
2.官民競争入札・民間競争入札(いわゆる「市場化テスト」)
公共サービスの不断の見直し、質の維持向上、経費削減等を基本方針とした、競争の導入による公共サービス改革が進められている。対象公共サービスの選定にあたり、行政は民間に対して業務に関する情報を積極的に公表することが期待されるが、行政には情報開示インセンティブがなく、例えば、老朽化が進む社会資本の維持管理・更新業務をはじめ対象業務が十分に拡大していない。また、官民が競争環境下に置かれるが故に両者のノウハウ交流が行われにくいとの指摘もある。
民間ができる業務は民間が担うことを徹底し、指摘した課題に対応しつつ、民間開放を一層推進する必要がある。併せて、PPP/PFIといった手法も活用することが求められる。
3.独立行政法人等改革
独立行政法人の整理統合、ガバナンスやPDCAサイクルの強化をはじめ種々の改革が進められている。また、本年4月には、省庁の縦割りの弊害を排し医療分野の研究開発に係るファンディングを一元的に管理する日本医療研究開発機構の創設も予定されている。
独立行政法人の本来の趣旨に立ち返り、組織・事務・事業の廃止・縮減等について市場化テスト等の実施により推進するとともに、政策目的の実現に向けて府省の壁を越えて一元的に業務を執行できるよう組織改革を進めるなど、不断の見直しが求められる。その際、組織の民営化や公設民営等の可能性も排除せず、当該事務・事業を担うべき主体について、費用対効果を最大化する観点からの検討も必須である。また、独法に限らず広く公的機関についても、同様の検証を行うべきである。
●(2) 国民本位の効率的で質の高い行政の実現
1.行政の電子化と業務改革の一体的推進
わが国では、行政手続の電子化、オンライン化は進んだものの、利用者視点が徹底されておらず、また、業務プロセスの抜本的な見直しを伴ったものではなかったことから、行政サービスの質・利便性の向上や業務の負担軽減・効率化、組織・個人の生産性向上等の点で十分な結果が出ているとは言いがたい。
ICTはもとより、マイナンバー等の制度も最大限活用し、全政府的に業務プロセスを一から見直すとともに(行政版のBPR)、政府として一体的なシステムを構築していくことが求められる。特に、国民とのインターフェースにおいては、電子決済をベースとした決済状況の可視化、マイナンバーや政府内における情報連携をベースとした手続きのワンストップ化が重要となる。バックオフィス機能についても、業務プロセスの共通化・標準化、民間への業務委託等が検討されるべきである。業務改革の推進に際しては、企業のBPR専門家を積極的に活用するとともに、公務員のインセンティブ付与、国民の利便性の向上や事務コストの削減等を踏まえたKPIを設定することが有用である。
2.調達改善
契約形態の見直しや共同調達の推進等、着実に成果が出てきているものの、効率的な調達を実現できた事例(ベストプラクティス)の共有やスケールメリットの活用等を通じた政府全体としての効率的な発注の実現には至っていない。
こうした課題に対応しつつ、適切なインセンティブの付与、KPIの設定等を通じて、不断の改善が図られるようすべきである。また、受注企業が財・サービスをより効率的に提供できるような発注のあり方(納期や搬入方法等)を検討することや、PPP/PFIの一層の活用が求められる。
3.行政のオープン化・双方向化(含む:行政手続・救済)
政策情報の提供の充実、国民の政策形成過程への参加、公共データの民間活用等の観点から、行政情報の提供範囲の拡大・オープンデータ化、パブリックコメントやノーアクションレター制度、グレーゾーン解消制度等の整備が進められてきた。
引き続き、公共データの産業利用を一層促進すべく、障害となりうる法制度の見直しや未公開データの早期公開等を推進するとともに、個人情報保護法に留意しつつ、オープンデータの活用効果の説明等を通じ、オープンデータに対する国民理解を醸成することが重要である。
また、政策評価や予決算に係わる情報をより国民に分かりやすい形で適時開示することで国民による政策検証を容易にするほか、パブリックコメントの実態調査も踏まえ、同制度の改善や提出意見の取り扱いに対する説明の強化等、国民の政策形成への参加を促進する必要がある。
●(3) 行政ガバナンスの強化
1.政策評価・行政事業レビュー
政策評価制度に加え、行政事業レビューが行われるなど、アウトプットを評価し、政策のPDCAサイクルを回す枠組みが整備されてきたことは評価される。しかしながら、依然として、評価の質の確保や、予算要求や政策立案への評価結果の反映、評価の妥当性確保等、課題も多く指摘されている。
政策・事業の評価の活用を予算編成や政策形成プロセスにより強固に位置づけるとともに、政策目的に即した測定指標の定量化の一層の推進、外部評価の強化、事業等の廃止基準の導入、公会計のさらなる見直し、人事評価との連動等に取り組む必要がある。併せて、行政に対する国民や国会のガバナンスを強化していくことも求められる。
2.内閣機能の強化
中央省庁再編時、省庁横断的な政策を縦割りの弊害を排して官邸主導で進めるため、内閣官房の機能を強化するとともに内閣府が新設されたが、近年、両者の役割の拡大・業務の増大により、官邸主導による重要政策の機動的な決定が困難になっているとの指摘がある。そうした中、今般、政府が、内閣官房と内閣府の業務を見直す閣議決定を行い、「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案」を国会に提出したことを評価する。
法改正に加え、政府方針に基づき改革を着実に実施するとともに、内閣の重要課題に対して各省大臣が総合調整機能を果たすことで、わが国の重要課題にこれまで以上に機動的に対処していくことが期待される。また、特命担当大臣の所掌が広がっていることも踏まえ、大臣官房機能の強化等も検討される必要がある。
3.中央省庁再編
2001年の中央省庁再編から15年近くが経過し、わが国を取り巻く状況も大きく変化してきている。その後、外局の廃止・新設が行われたものの、中央省庁再編の効果や行政需要の変化等に伴う新たな縦割り行政の弊害等の検証は十分に行われていない。
省庁再編には法改正や膨大な事務量が発生するものの、中長期的な観点から国家的課題に取り組むことができるよう、2001年の中央省庁再編の検証を行うとともに、必要な体制について定期的に検討を行うことが重要である。
4.公務員制度改革
国益のために使命感・意欲を持った優秀な公務員が疲弊することなく、能力を向上・最大限発揮することを可能とする公務員制度の確立が不可欠である。これまで人員削減や再就職管理等が中心であったところ、全政府的観点からの国家公務員の人事行政や幹部職員人事の一元管理等を推進する内閣人事局が創設されたことは評価される。
今後は、業務改革と一体となった公務員の働き方の見直しや、公務員の能力・業績に関する人事評価制度の一層の改善、生産性向上、人材の流動化等に向けた不断の取組みが求められる。また、官民の労働条件のイコールフッティングの確立、身分保障のあり方の見直し、職員の採用・人事管理・再就職管理等の一元化についても検討を進めていく必要がある。



 2014
2014●組織温存でなく農家・農村を守る
「医師会はTPP反対をトーンダウンしたから混合診療の解禁はあの程度で収めた。農業組織はまだ抵抗しているから解体だ。されたくないなら反対をやめろ」との指摘は、いまの政権があらゆる側面で見せている陰湿・巧妙・卑劣な手口を象徴している。
TPPは、4月のオバマ大統領の訪日での日米「実質合意」が「ちゃぶ台返し」となって、「決まらなくてよかった」のではなく、いま明らかなことは、TPPを決着するには牛肉・豚肉・乳製品などの関税を限りなくゼロに近づけるしかない(冷凍牛肉では38.5%→19.5%→9%→まだ下げ足りない)という重大な事態に陥っているということである。国外からの日本の農産物関税は「撤廃しかない」との圧力もさらに強まっている。
ここで、JAなどの農業関係組織が目先の組織防衛に走れば、思うつぼにはまり、墓穴を掘る。農業が崩壊して、地域が崩壊して、組織だけが生き残れるわけがない。「組織が組織のために働いたら組織は潰れる。拠って立つ人々のために働いてこそ組織も存続できる」ことを忘れてはならない。
全農の株式会社化についても、「株式会社にすることが全農のビジネスに損か得か」を議論してはいけない。「農家、農村を守れるか」でなくては、最終的に組織も持たないことを肝に銘じるべきである。
●「対等な競争」誰のため?
食料・農業、医療、雇用もすべてそうだが、規制緩和し、equal footing(対等な競争条件)を実現すれば、みんなにチャンスが増えるかのように見せかけて、国民の命や健康、豊かな国民生活を守るために頑張っている人々や、助け合い支え合うルールや組織を、「既得権益を守っている」と攻撃して、それを壊して自らの利益のために市場を奪う、あるいは、人々をもっと自由に「収奪」して儲けようとしている「1%」の人々の誘導に乗せられてはいけない。
某国首相が国際会議で昨年秋に述べた「私がドリルになって規制という岩盤を打ち破る」「いかなる既得権益といえども私のドリルから無傷ではいられない」に続き、この6月30日付の英紙フィナンシャル・タイムズに、「私の『第3の矢』は日本経済の悪魔を倒す」と題した論文を寄稿し、「規制の撤廃の他、エネルギーや農業、医療分野を外資に開放することを言明した」と産経新聞が報じた。いよいよ「暴走極まれり」である。
ヘレナ・ノーバーグ=ホッジさんは、『いよいよローカルの時代?ヘレナさんの「幸せの経済学」』(ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ、辻信一、大槻書店、2009年)の中で、概略、次のように述べている。「多国籍企業は全ての障害物を取り除いてビジネスを巨大化させていくために、それぞれの国の政府に向かって、ああしろ、こうしろと命令する。選挙の投票によって私達が物事を決めているかのように見えるけれども、実際にはその選ばれた代表たちが大きなお金と利権によって動かされ、コントロールされている。しかも多国籍企業という大帝国は新聞やテレビなどのメディアと科学や学問といった知の大元を握って私達を洗脳している。」やや極端な言い回しではあるが、これはグローバル化や規制改革の「正体」をよく表している。そして、某国首相の浅はかな発言が、誰に踊らされたものかもよくわかる。
少数の者に利益が集中し始めると、その力を利用して、政治、官僚、マスコミ、研究者を操り、さらなる利益集中に都合の良い制度改変を推進していく「レントシーキング」が起こり、市場が歪められて過度の富の集中が生じる。この行為こそが「1%」による「自由貿易」や「規制緩和」の主張の核心部分である。
●相互扶助精神、協同組合はじゃま
こうして、自己の目先の利益と保身しか見えない総合的、長期的視点の欠如した「今だけ、金だけ、自分だけ」しか見えない人々が国の将来を危うくしつつある。人々の命、健康、暮らしを犠牲にしても、環境を痛めつけても、短期的な儲けを優先する、ごく一握りの企業の利益と結びついた一部の政治家、一部の官僚、一部のマスコミ、一部の研究者が、国民の大多数を欺いて、TPPやそれと表裏一体の規制改革、農業・農協改革を推進している。これ以上、一握りの人々の利益さえ伸びれば、あとは顧みないという政治が強化されたら、日本が伝統的に大切にしてきた助け合い、支え合う安全・安心な地域社会は、さらに崩壊していく。
「日本が伝統的に大切にしてきた助け合い、支え合う安全・安心な地域社会」を守るために頑張ってきた人々や協同組合などの相互扶助組織を追いやり、助け合い支え合う仕組みを壊すことこそが、彼らの利益拡大に不可欠なのである。地域社会を守るためにTPPにも反対するから邪魔で仕方ないのである。
●農業・農村からさらなる収奪
農協組織は農産物の「共販」、生産資材の共同購入、JAバンク、JA共済、医療、葬祭事業まで、地域の信頼を得て、地域生活全体を支える様々な事業を展開しているが、これを崩すことで農村での様々なビジネスチャンスを広げようとしている。
JAバンク、JA共済の「JAマネー」の強奪は日米金融・保険業界の「喉から手が出るほど」ほしい分野で、これを実質的に切り離されたら、代理店の手数料だけでは、営農指導などの非営利(本来的に赤字になる)部門を持つ個々のJAは存立不能である。
共同販売、共同購入が崩されたら、「対等な競争条件」どころか、さらに農産物を買いたたき、資材販売で価格つり上げをしようとする企業の独壇場にしてしまう。それは農協組織のない途上国の農村で、いまも現実に起こっている事態であり、農村の貧困が解決されない根本的要因である。森島賢先生が本紙でも書かれているとおり、戦前の日本も同じだ。そこに逆戻りすることなる。独占禁止法の適用除外のミルク・マーケティング・ボードが解体された英国の農村が「草刈り場」と化し、EUで最低の乳価に暴落した事実も忘れてはならない。
農業委員会組織を骨抜きにして、農業に自由に参入して、儲からなければ農地を自由に転売して儲けるようにしたいLファームやPファームを展開している人々が政府の会議のリード役の立場を利用して露骨な自社の利益追求をしているのも、人材派遣業のP社の会長が「雇用の短期化・解雇自由」の雇用改革を進めているのと同様、情けないほどわかりやすすぎる。
●「日本の農協は世界の成功例」
ある農水省幹部OBは、「日本の農協は世界の協同組合運動の最大の成功例だ」と話してくれた。「バブル崩壊の際も、破綻した信連はなかった。リーマンショック時の農中による資金運用の失敗についても、組織自体の中で自律的に処理を済ませた。これまで公的資金の投入は一切なかった。」
また、「販購事業においても、巨大化したのは偏にこれまでの努力の積重ねの成果であり、また他分野からの参入は常に自由だ。ある程度の系列取引は、日本の企業グループなら、どこにでも存在する。」
こうした視点からも、JA攻撃が、市場強奪を目的とした「なりふり構わぬ」人々によるいかに理不尽なものであるかがわかる。
●食と農犠牲に N省のスタンス
「N省はなぜ農協を庇ってやらないのだろうか。たとえば、Z省なら銀行をあくまで守るだろうに」との声もある。長らくN省は、米国を喜ばせることが私益・省益・国益になってしまったG省と、企業の経営陣を喜ばせることが私益・省益・国益となっているK省と対抗し、貿易自由化の流れから食と農を守ろうとしてきた。官邸を取り巻くパワーバランスが崩れ、「米国と企業のために食と農を犠牲にする」構図が強くなってしまっているのが、いまの危機的事態の根底にあるが、そのN省までが、農業組織改革については、誰の味方かわからないと言われる。
一方では、各省庁の幹部人事を官邸が決めるようになり、N省も、G省やK省のように、米国と企業を喜ばせなくては出世できなくなってしまうと、誰も暴走を止められなくなってしまう。内閣改造人事やお金をちらつかせて国会議員を恫喝する手法といい、どこまでも悪質・巧妙な策略が目に余る。
厳しい状況だが、目先の組織防衛は墓穴を掘ることを肝に銘じた関係者の踏ん張りと、滋賀県知事選挙のように、世論の力で、こうした暴走に歯止めをかけるしかない。



 2013
2013●
—ここのところ途上国支援やビジネスの関係でインタビューをすると、「インクルーシブ(inclusive)」という言葉をたびたび聞きます。全員を戦力化していく、という文脈です。
そうなのですか。我々が共著『Why Nations Fail』で使う以前は、inclusiveなど、そのような文脈ではあまり聞かなかった言葉でした。聞いたことがあったなら、ジェームズ・ロビンソン教授と一緒に「本当にこの言葉でいいのかな?」と悩んだはずですからね。著作権マークでもつければよかった(笑)。どの国のどのような立場の人たちも経済的困難に直面し、新たな視点を模索しているのでしょうね。
—インクルーシブは、ダイバーシティー(多様性)と同義でしょうか?
同義といえば同義なのですが、多様性は全員参加を実現する最初のステップにすぎません。多様性が大事だと言う時は、単に(既成の枠の中に)多様な人々をまず増やすのが目的でしょう。そうではなく、全員をテーブルにつけ、幅広い人々を(意思決定に)巻き込んで新しいものを作り上げていける制度が、インクルーシブという言葉で言いたいことです。
●収奪的な成長と、インクルーシブな成長は違う
—つまりは「全員参加」でしょうか。共著作『Why Nations Fail』では、国家が栄え続ける発展段階で、まず特定層のための中央集権的で収奪的な制度ができ、それから創造的破壊を起こすために「全員参加型(inclusive)」の制度に変わっていく必要があるとしていました。そうしますと、国の成長には制度が一番重要なのですか。
国が長期的に、持続的に成長するためにはそうです。創造的破壊を通じて最高の技術が生まれ、その技術を使って最高の制度にするわけです。その時に、「全員政治」の制度と「全員経済」の制度、双方を同時に実現することが望ましい。政治と経済の一方が中央集権的・収奪的なままで、特定層に権限が集中すると一時は成長したとしても、やがて停滞するでしょう。
たとえば、旧ソビエト社会主義共和国連邦がそうでした。ウラジミール・レーニンが率いたボリシェビキによる徹底的な中央集権体制によって、国がすべてを管理して最初はうまくいきましたが、結局、誰も創造的破壊を起こそうというインセンティブを持たなくなり、成長が止まりました。技術キャッチアップ型経済、あるいは(石油など)特定資源の利用による収奪的な成長と全員参加型の成長では違うのです。構造的に創造的破壊を必要としない前者はやがて行き詰まり、長続きしません。
英国が産業革命で劇的に成長したのは、それに先立つ1688年に名誉革命があり、創造的破壊が生まれる素地があったからです。だから産業革命が波及しても、近隣諸国では必ずしもすぐに劇的な成長につながらなかった。経済だけでなく政治制度も中央集権型から全員参加型に移行しないと難しいのです。
「近代化仮説」という理論があります。経済が変われば政治も変わる、という説です。しかし、現実は全くそうではない。アフリカ諸国、中国、シンガポール、サウジアラビア、ロシアなどどこも経済は高成長ですが、政治システムは不変です。ただこうした国々はまだ、創造的破壊が必要ではない段階にある。
●キャッチアップ型は結局は長続きしない
—中国経済について、共著書で「今の権威主義的な政治体制が続けばやがて停滞する」と予測しています。
中国がこれまで発展したのは「技術キャッチアップ型経済」、すなわち他国をモデルにしてエリートが牽引して追いつく「収奪的な成長」だったからです。まだしばらくの間は成長すると思いますが、1950年代、60年代に順調に成長していたラテンアメリカ諸国で、70年代に成長が止まったのと似たような未来を思い浮かべます。中国はまだ低中所得層中心の国ですし、技術的キャッチアップの余地も当面まだまだありますが、それが尽きた時、創造的破壊、技術進歩が起こるオープンな市場に移れるのかどうかがカギです。
政治がより幅広く多様な人々の手で運営されるようになれば、成長が続く可能性は高いでしょう。中国は準全員参加型の政治体制に移行しようとしている最中ですね。制度に必要なのは、土地の私的所有権が認められること、適切な法規制が機能すること、そして適切な税制などでしょう。つまりは創造的破壊を起こすためのインセンティブが制度的に重要だということです。
—官僚や銀行は、先進国の収奪的なエリート層と言えるでしょうか。
そうですね。銀行や官僚は収奪的になりやすいと言えますね。以前はそうではなかったのですが、近年は自分たちの分け前を増やすために政治力を行使しています。そして公的部門は多くの国で強い実権を握り、かつ肥大化しており、政治に守られています。銀行は20世紀を通じて国家繁栄に大きな役割を果たしてきましたが、政治力が増し、リスクを必要以上に取るようになりました。
日本のことは詳しくありませんが、たとえば米国において、国の制度がもっと強力で、銀行がロビー活動などを通じた影響力の行使ができない状況だとしたら、米国における銀行の収奪的な役割を減じる効果があると思いますね。とはいえ、先進国における金融業界は多くの業界の1つに過ぎません。カリブ海の西インド諸島内にある立憲君主制国家バルバドスのように、一握りの家族が政治、軍隊、司法、経済を握っているような社会とは明らかに違います。
—しかしやはり、先進国でもどうしても既得権は生まれていきますね。資本主義のもとで、本当に全員参加の発展は可能なのでしょうか。格差はなくなるのでしょうか。
そもそも私は「資本主義」という言葉があまり好きではありません。日本も米国もグアテマラも資本主義です。しかし、3者とも全く違う「生き物」です。グアテマラは残虐な独裁社会で、人口の半分以上が抑圧されている国です。市場主義を標榜してはいますが、市場は操作されています。政治権力が収奪的な一部の層に集中し、人口の半分を抑圧的に支配しているというわけです。
ですから、あなたの質問をこう言い換えましょう。「全員参加型の市場経済は格差なしで存在し得るのか、あるいは平等であっても限界があるのか?」と。
経済的な格差は、人々が成長するためのインセンティブなので、ある程度は社会に必要です。全員のニーズがすべて満たされるという共産主義的な発想は、神話にすぎません。それに、人は報われたい生き物です。すべての報酬がお金である必要はありませんが、お金が重要な時もある。
技術がすべてを変えるカギです。過去30年、技術によりグローバル化が進み、技術依存型の社会になりました。技術革新のおかげで以前より多くの「スーパースター」が活躍できる土俵ができました。バスケットボール選手のマイケル・ジョーダンが数千万ドルを稼ぎ、そのジョーダンを広告に使った代理店社長が大儲けして何か問題があるでしょうか?問題は、とても裕福だからとジョーダンとその代理店社長の子女だけが最高の教育を受け、政治的実権を握り、例えば国が戦争する意思決定などをするようになることです。政治力を一部の人間が握る独占状態は望ましくない。
すなわち、経済的な格差は大した問題ではないのです。重要なことは2つ、まず全員参加型の政治制度の実現による、政治的な平等です。これが最終到達点です。もう1つは経済的な「機会の不平等」を解消することです。全員が等しく活動できる環境作りが重要です。よその地域の子供たちと、同じ土俵で競争する機会すらない子供が大勢いるのが、今の米国です。町の中心部に生まれると、豊かな郊外に生まれた人と同じような機会に恵まれることがなくなってしまう。この機会の不平等は大問題です。経済的な格差よりも、機会の不平等のほうが問題です。もちろん、機会の不平等は経済的な格差と密接にかかわっているので、経済的格差は指標として注視しなければいけないのですが。
—教育の平等が至上命題であるということですか。
まったくその通りです。次のアインシュタイン、次のマーク・ザッカーバーグ(フェイスブック創業者)、次のセルゲイ・ブリン(グーグル創業者)がどこにいるかなど、誰にも分からないのです。もし、平等な教育機会を設けることができないとすると、言ってみれば我々は人口の10%にしか機会を与えないことになります。残りの90%に、ザッカーバーグやアインシュタインがいるのかもしれないのに。
●長期的繁栄には全員を巻き込む制度が必要
—貧困の削減に必要な条件は何でしょうか。制度改革でしょうか。あるいは、新しい雇用を作ることでしょうか。
格差の原因として制度は大きいです。ただし、そのほかにも技術、グローバル化、人的資本(の質)に原因があります。原因は様々に絡み合っていますが、稼げる社会は質の良い人的資本に恵まれた社会です。教育の質が低いことが格差につながります。そして教育のまずさは制度に原因があることが多いのです。失業はその結果であって、原因ではありません。
一番の解決策はやはり経済成長です。過去50年でそれを劇的に実現したのが中国です。1億人以上の人々が貧困から脱して中産階級になりました。インセンティブに欠け、不合理で収奪的で、経済的成功には制裁すら加えていたような経済制度を、少しずつですが全員参加型の制度に変えることで実現したのです。最初は、農業セクターで市場向けに生産を始め、次に都市セクターで、働いて稼ぐことができるようになった。結果として数百万もの人々が、30年前よりはるかに稼ぐようになった。次のステップは本格的に全員参加型の経済制度にすることと、政治制度を全員参加型にすることです。これからの課題です。
—創造的破壊を起こしていくには制度改革が重要とはいえ、既存のエリート層による制度改革にはどうしても限界があるのではないでしょうか?
確かに、エリート層は本質的な変革を嫌い、現状維持を好みます。既得権益を維持したがるものですね。例えば、エジプトのムバラク政権が自ら変革することが期待できたでしょうか? 市民から始まった「アラブの春」はとても不確実性が高くて問題が多いですが、何もせずに待っていたら、20年経っても何も起こらなかったでしょうね。本来は、ボトムアップの改革が望ましいと思います。
●日本はマクロ政策に頼りすぎる
—日本は欧米へのキャッチアップ型の発展を終えた後、創造的破壊を起こせる全員参加型社会に向けての改革がうまくいかず、過去20年経済の停滞に苦しんできたように思えます。
いくつかの要因があると思います。もっと開かれた経済への変革がうまくいくかどうかは、「どれだけ社会が『全員参加型』か」次第です。スターリン主義のようなモデルでさえも基本的な成長は可能なのですが、やがて息切れするのです。日本は第2次大戦後、多方面でそれ以前に比べればまずまず全員参加型の仕組みを築きましたが、部外者の目から見るとまだ問題が多いように見えます。
まず政治制度が(参入障壁が高く)全く競争的ではありません。その結果、経済制度も競争力を失いました。自動車業界や電機業界のような国際的企業は別ですが、国内の経済が(インフラなど)独占的な企業に支配され、競争がなかったからでしょう。また日本は経営のプロよりは同族による経営が多く、企業統治が不十分です。ここは制度的な問題ですね。
競争が激しい電機業界の調子が悪いですが、世界中の電機メーカーが「世界的な大変化」に巻き込まれて苦戦している状態です。ドイツでもアメリカでも同じです。これはソニーや他の日本企業だけの問題ではないのです。
キャッチアップ型の時には、大企業を基盤にしてうまくやっていくことができました。投資をして、既存の技術に適応していけばよかったからです。しかし、米国のソフトウエアやバイオ技術、ナノ技術などのように動きが激しい業界においては、カギとなるのはベンチャーです。果たして国内の環境、経済制度が、新しいプレイヤーが入れ代わり立ち代わりやってきて、容易に資金調達ができ、必要な支援を受けられるものになっているかどうか。そして、一緒にアイデアを実現しようとあちこちからやってくるような人々を雇用できる環境を整えているかどうか。日本はおそらく、米国や他の国々に比べ、そこでつまづいているのでしょう。
—日本では自民党の安倍晋三政権が「アベノミクス」として、金融緩和や成長戦略を打ち出しています。
まずは推移を見なければいけません。今、世界中が不景気です。金融緩和は重要ですが、構造的な問題の方が大きいと思います。私見では、日本は昔から構造的な問題が本質なのに、マクロ政策に頼る傾向があるように思えます。国内で独占的な経済が続き、技術革新のダイナミズムを阻害しています。
流動性を高めて政府支出を増やすだけではやはり限界があります。新規事業が生まれやすい環境を整備し、一握りの大企業が支配することによる弊害を、すべてのセクターでなくすことではないでしょうか。往々にしてベンチャー企業が技術革新の牽引役なのですから。
—初めから理想的な制度を作った都市「チャーター・シティー」を作ってしまうという、ポール・ローマー米スタンフォード大学教授の提言について、どう思われますか。
ホンジュラス共和国で一時検討された話ですね。ある程度までは、とてもいいことだと思っていました。ローマ―教授は大変優れた研究者ですし。ローマ―教授は成長理論の構築で大変重要な役割を果たされました。我々が専門としてきた制度とインセンティブの問題に、成長理論を専門とするローマ―教授が取り組んでいらっしゃるというのは大変斬新なことだと思います。チャーター・シティーのアイデアには魅力的な要素を多く含んでいます。経済問題については全員参加の要素が大きく盛り込まれています。しかし、政治問題に関しては排他的なままです。
そこで、3つの懸念があります。1つは、チャーター・シティーはモデルとしてシンガポールや香港をイメージしているようなのですが、マダカスカルやホンジュラスのような国でそうした貿易に根差した町づくりが可能なのかどうかという点です。シンガポールも香港も、起業家にとって絶好の立地にあるからこそ発展したわけです。しかしホンジュラスなどは国そのものに何もインフラがない。しかしこの点については大した問題ではありません。
2番目にもっと本質的な問題は、現地の政治家が信用ならないという点です。大体、ああいった国では政治家は自分の利益を追求し、腐敗し、やりたい放題です。もし彼らがチャーター・シティーを作ることを認めたとして、全く介入しないなどということが果たしてあるでしょうか。ローマ―教授も途中で気付いたわけですが、結局アイデアをもて遊ばれて、実現せずに終わってしまいましたね。
●制度改革は、歴史的な条件がそろって初めて実現する
3番目の懸念は、このアイデアがデモンストレーション効果を持ってしまうことです。ある国に作られたチャーター・シティーが繁栄したとする。すると他の地域に住む国民が、「そうか、我々が貧しいのは政治家のせいなんだ」と気づいてしまう。そこで、改革を求める声が高まる可能性が高い。指導者に問題があるということをいつまでも覆い隠せるものではない。アラブの春を見てください。最後の10年、国民は皆、ムバラクとその一族が問題の一部なのだということを見抜いていました。単に、力がなかっただけでした。最初から良い制度で作られたチャーター・シティーが役に立つ可能性もある半面、これも貧困削減の特効薬にはならないのです。
—貧困削減の研究で知られるエスター・デュフロ教授とアビジット・バナジー教授は、著書『貧乏人の経済学』の中で、貧困削減も国の政治経済制度がすべてだとするアセモグル教授とロビンソン教授の議論を「悲観的だ」と批判していました。
そうですね、確かに私たちは悲観的かもしれません。制度改革はすぐには実現しないのも事実です。結局それは、歴史的な文脈で条件が揃って初めて達成できるものなのですからね。しかし、(国の繁栄で)制度を重要視することは、地理的条件や文化を原因とするよりは楽天的ではないでしょうか。




 2012
2012そんな中で日本の代表は、城島財務相。前国会対策委員長、重要ポストではあっても、財務大臣にふさわしい人材かどうかというと首をひねってしまう。日本の銀行には国債リスクがあると指摘されるぐらい危なっかしい状態だというのに、わずか1年で財務大臣を交代させるというのは、外国諸国に対してどういうメッセージになるのだろうか。「日本政府は債務問題に本気で取り組む姿勢がほとんどない」と受け止められても文句は言えまい。先進国が財務大臣にはプロをすえる傾向が強まっているというのに、アマチュアの財務大臣がそれも1年でくるくると交代すれば、「まともに話し合えない相手」とレッテルを貼られる。
救いは消費税増税が決まっていることだろうが、目先は相変わらず「決められない政治」からまったく進歩していない。何と言っても今年の年末には国庫が空になってしまうというのに、その法律を通すための臨時国会さえまだ予定が立っていない。もっとも国会を開いたところで、このままでは赤字国債の発行法案や国会議員定数是正が実現する見通しもない。
自民党や公明党は、赤字国債の発行を人質に解散を迫る方針だし、民主党もできれば任期満了まで引っ張りたいというのが基本戦略だ。民主党の輿石幹事長は、憲法違反の状態は当然、国会議員が自らの身を切らずに(定数削減)選挙するのは国民に申しわけが立たないという主旨の発言をする。違憲状態を解消する0増5減だけではなく、定数削減ということになればこれはそう簡単にまとまる話ではない。それを見越して、選挙を遅らせようとする姑息な主張のようにしか見えない。まるで自民党から民主党へ「歴史的政権交代」をする前の麻生内閣のようだ。
麻生内閣は「さっさと解散せよ」と民主党から迫られながら、ずるずると任期満了まで引っ張った挙げ句、歴史的大敗を喫した。はっきり言ってしまえば、有権者はうんざりしている。民主党ではダメだということは火を見るよりも明らかだが、かといって自民党に戻すというのもいかがなものか、ということだ。しかも自民党は、一度、病気で政権を投げ出した安倍元首相を再び総裁に選んだ。健康リスクのあるリーダーを選ぶなどということはあってはならない。それが普通だと思う。
健康リスクがあれば、いざという時に判断を誤るリスクも高くなる。健康状態が悪くなったときに、後継者をめぐって権力闘争が起きる可能性もある。そうなったら場合によっては国の指導部に空白が生まれるということだ。それが社会的な混乱をもたらすこともありうるだろう。それでも日本は官僚組織がしっかりしているから大丈夫だと言う人もいるが、そうでもないかもしれない。
民主党政権の「政治主導」ですっかり嫌気がさしてしまったかのような官僚組織は、復興予算の中にいろいろ紛れ込ませて恥じるところがない。まるで野田政権になって、官僚主導へ戻ったのをいいことに、復興とはおよそ縁のなさそうなものまで屁理屈をこねて入れてしまった。しかも政治家はまるでそれをチェックできなかった。
その復興予算ですら執行は遅れている。被災地ではまだまだガレキの山が残ったままだ。神戸の時とは違って、被災地の小さなコミュニティを再建するのは難しい。仕事もなくなり、生活を支えるために他県へ移動すれば、元にはなかなか戻れない。だからこそ政治が主導してビジョンを描かなければならないのに、肝心のときに政治主導が機能しない。
泥沼に足を取られたようになっている日本の政治を見透かすかのように、北方領土にロシアのメドベージェフ大統領が行き、竹島には韓国の李大統領が上陸した。そして尖閣である。石原東京都知事の「買収宣言」に慌てた国は、国有化に踏み切って「棚上げ」になっていた問題に火をつけてしまった。その一方で、普天間基地の移転問題はまったくらちがあかず、オスプレイの配備についても沖縄を説得できないままに既成事実を積み上げている。
事態がどう動くのかまったく見通しのつかないままに、政治は漂流する。悪いことに復興予算で一息ついていた経済も息切れしかかっている。円高で輸出が青息吐息になっているだけでなく、生産そのものが減っているからだ。東南アジアでの日本車の生産は増えても、日本国内での生産が落ちる。空洞化だ。
政治にビジョンとリーダーシップがなければ、いくら成長戦略を描いてもそれは絵に描いたもちにすぎない。なぜなら、新しい成長戦略は必ず既得権益を損なうことになるからだ。無駄を排除しなければ新しいことにカネは使えない時代だ。既得権益層を説得し、日本を変革する政治家、その顔が思い浮かばないところが日本国民の不幸である。



 2011
2011 2010
2010 2009
2009民主党はこの8月の選挙で、衆議院では絶対多数を得たが、参議院では過半数にわずかに足りないままだ。だから、左派の社民党、右派の国民新党の支持を得ないと、参議院で過半数を握って法案を通すことができない。次の参院選挙は来年夏だが、民主党はそこで過半数を得ることを当面最大の政治課題としている。だがそれまでは、左派イデオロギーに基づく反米的立場を貫く社民党、右派の既得権益層を基盤とする国民新党と連立政権を維持せざるを得ない。鳩山総理は、民主党の内部で絶対的立場を有しているわけではない。8月の選挙の勝利の功労者は小沢幹事長で、10月26日から開かれる国会での戦術を指揮するのも彼だと言われている。「国家戦略担当」の菅副総理、岡田外相、前原国土交通相は以前民主党党首を務めたことがある。まるで明治維新直後のように、彼ら「元勲」達はめいめい勝手な発言をし、それらはよく調整されていないように見える。そして、国民はまだそのような民主党政権に対して寛大な気持ちを失っていない。鳩山政権は、国民にとってみれば「自分の手で選んだ」政権で、この政権を通じて国民は自ら政府を運営している気持ちになれているのだ。
一部の新聞は民主党政権への批判的態度を隠さないが、今民主党政権を批判すれば、国民を敵に回すことになるだろう。この「蜜月」は、通常国会が本格化する来年2月頃までは続くのではないか?革命や政権交代では、大衆はその熱狂を利用されるだけで、そのあとには既得権益勢力がまた権力を簒奪する例が多い。フランス革命しかり、1991年のソ連崩壊しかりである。日本でも、小泉総理による郵政民営化によってその勢力を弱められていた郵政労組が、先週の郵政関連4企業の再統合で実質的な再国有化を実現し、勢力回復の機運にある。もともと民主党の大きな基盤は労働組合にあるのだ。しかも、統合された郵政の新しい社長は元大蔵次官であり、「官僚主導でなく、政治主導で」という民主党のこれまでの政策に反する人事が行われたのである。小泉自民党が、都市の中産階級という政治的には頼りにできない層(きまった支持政党を持たず、選挙のたびに気分で支持政党を変える)にその軸足を置き、既得権益層を敵に回したことが、今回の政権交代の背景にある。
繰り返すが、国民は世直しを求めて政権をひっくり返すが、実際には既得権益層に利用されるだけという、古い革命の公理が今回も機能しつつあるのでないか? 医師会など、これまで自民党の票田だった圧力団体は、次々に支持を民主党に切り替えつつある。恵まれた終身雇用の、大企業・公営企業の従業員たちが作る労働組合も含めて、既得権益層による政治が、日本に復活しつつあるのでないか?日本人の生活を再び良くする方法は、経済を良くすることにしかない。雇用が海外に流出しすぎたので、中小企業を中心に新しい産業を国内に起こすことが必要だ。それは規制を緩和し、若者たちの年金負担を軽減することにより、社会の活力を解放する方向で行うのだ。経済が良くならないゼロサム社会では、民主主義は果てしのない利権の奪い合いに堕落する。日本で待望された「二大政党制に基づく政権交代」は8月の選挙で実現したが、これも効果を生まないことがわかるだろう。来年春頃には、日本でも治安状況が悪化して、昭和前期のようなテロが起きやすくなるのではないか。他方では、一度豊かになった国の富というものはそう簡単には減少しないので、日本経済には実はもっと余裕があるという見方も可能だ。まだ社会が荒れてくる兆候は見えない。どちらになるのか、自分にはまだわからない。
 2008
2008 2007
2007これらの課題について、まず、国・地方を通じた財政状況は、緒に就いたばかりの段階とはいえ、徐々に健全化に向かいつつある。
道州制については、政府の「道州制ビジョン懇談会」が設置され、また与党においても鋭意検討が進められるなど、次第に議論が深まりつつある。
また、本年6月に閣議決定された「経済財政改革の基本方針(基本方針2007)」において、「2007年秋以降、税制改革の本格的な議論」を行うこととされている。
こうした状況を踏まえ、本提言では、中長期的な財政健全化目標ならびに国・地方の税・財政関係のあり方について、経済界としての考え方を改めて示すこととする。
わが国では、過去数年にわたり、国・地方を通じた基礎的財政収支を黒字化させることを目標に、財政健全化に向けた取り組みが進められてきた。歳出面においては、政府・与党の真剣な取り組みにより、各分野にわたり、着実に削減努力が続けられている。他方、歳入面においても、官民双方の努力によって日本経済が活力を取り戻し、法人税をはじめとした税収が大幅に拡大している。国・地方を合わせた税収額は90兆円を上回り(2007年度当初予算ベース)、かつてのバブル期並みの水準にまで高まっている。今後の経済情勢や歳出削減努力にもよるが、当面の目標である2011年度における国・地方を通じた基礎的財政収支の黒字化達成は必ずしも不可能ではなくなっている。
しかし、楽観は許されない。わが国においては、1980年代後半にも税収が大幅に拡大し、バブル経済末期の1989年度には、かねてからの目標とされてきた特例国債(赤字公債)脱却に成功した。経済が過熱気味だったこともあり、これを機に本来は歳出抑制策がとられるべきだったにも関わらず、歳出は拡大を続け、また、その後のバブル経済崩壊により税収も減少に転じた結果、わが国財政は極端に悪化することとなった。この過ちを二度と繰り返してはならない。
そのような観点を踏まえれば、現在目指されている基礎的財政収支の黒字化は、政府債務残高対GDP比のさらなる上昇を避けるという意味にとどまるものであり、財政健全化に向けての一里塚に過ぎない。実際、2006年7月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(基本方針2006)」では、小泉内閣における財政健全化の取り組みを「財政健全化第一期(2001〜2006年度)」とし、「第二期(2007〜2010年代初頭)」における基礎的財政収支の黒字化はあくまで「財政健全化の第一歩」と位置づけられている。その上で、「第三期(2010年代初頭〜2010年代半ば)」に向けては、国・地方を通じ収支改善努力を継続し、基礎的財政収支の「一定の黒字幅を確保する」ことを通じ、「債務残高対GDP比の発散を止め、安定的に引き下げることを確保する」こととされている。
もちろん債務残高対GDP比の発散は何としても回避しなければならないが、それで十分という訳ではない。わが国財政の足もとの状況を見ると、国・地方合計の長期債務残高は、2007年度末で773兆円、GDPの約1.5倍と、先進国中最悪の水準に達している。債務残高の内訳を見ると、地方の債務残高は約200兆円(2007年度末)と高水準にあるとはいえ、その増加傾向には歯止めがかかりつつある一方で、国の債務残高は607兆円(同)と極めて巨額な上に、増加傾向に歯止めがかかっていない。これを税収との対比で見た場合、国は税収(交付税等移転後)の15倍超の債務を抱えており、第二次大戦末期に匹敵する状況とされる。このように、わが国財政は依然として危機的な状況にあり、中長期的な持続可能性は全く確保されていない。
とくに、今後のわが国財政を見通した場合、懸念されるのは債務の利払費の問題である。わが国では、長年にわたり超低金利政策がとられてきたこともあり、政府債務残高の急増にもかかわらず、これまでは、利払費の水準が抑制されてきた。1990年代を通じて利払費(一般会計)は10兆円前後で推移し、2000年代に入ってからは、債務残高の拡大傾向とは逆にその額は緩やかな低下が続いた。利払費の急増による財政収支の悪化という事態が避けられてきたことは確かであるが、このことが、債務規模が先進国中最悪の異常ともいえる状況にあるという事実を覆い隠してきた面も否めない。こうした中、2006年7月にいわゆるゼロ金利政策が解除され、金利水準が引き上げられており、また、市場金利も上昇傾向にある。この結果、利払費も、2005年度の7兆円(決算)をボトムとして2007年度には9.5兆円(当初予算)と再び増大に転じている。このまま債務規模が抑制されなければ、わが国財政は、金利負担が新たな債務につながる、すなわち借金が借金をよぶという状況に陥りかねない。
財政の中長期的な持続可能性を確立する観点から、国・地方を通じた基礎的財政収支の黒字化を一つの通過点として、さらに目指すべき財政健全化目標を速やかに設定し、歳出・歳入両面にわたる財政構造改革を継続的に進めていかなければならない。
●(2) グローバル化・少子高齢化に対応した財政の確立
わが国は、経済のさらなるグローバル化に伴う国際競争の激化と、人口減少下における高齢化の進展という、内外の大きな潮流変化に直面している。その中で、わが国が引き続き経済の活力を維持し、豊かな国民生活を実現する観点から、それに対応した財政構造を確立する必要がある。
わが国が本格的な少子・高齢社会に突入する中で、社会保障受給者数は確実に増加していく。このため、社会保障制度等を現状のまま放置すれば社会保障給付が大幅に拡大し、これに伴って社会保障に係る公的負担が増大し、財政を大きく圧迫する要因となる。具体的に見ると、今後、高齢者(65歳以上)人口は年3%程度の早いペースで増大し、それに応じて人口に占める高齢者の割合も年々上昇していく。これにより社会保障給付も、足もとの90兆円(2006年度)から2025年度には141兆円(厚生労働省推計)と大幅に拡大する見込みである。とりわけ高齢者医療と介護に係る給付が、経済成長を上回って増大することが見込まれている。
このような社会保障費の増加は、歳出構造の硬直化を招くだけでなく、成長力にも悪影響をもたらす。社会保障費の増大により、税と社会保険料負担からなる国民負担率が増大すれば、経済の活力が削がれることとなる。経団連が本年6月に公表した意見書「豊かな生活の実現に向けた経済政策のあり方」における分析によれば、国民負担率の上昇は、家計貯蓄率の低下と民間総固定資本形成の抑制などの経路を通じて、経済成長率を引き下げる。このままでは、新興途上国をはじめ世界経済が拡大を続ける中で、日本のみが低成長を余儀なくされ、グローバル競争の中でとり残されることになりかねない。
今こそ、社会保障制度の抜本的改革を中心に、国・地方を通じて可能な限り小さくて効率的な政府を実現することによって、国民負担率の上昇を抑制していかねばならない。
●(3) 道州制移行を見据えた税・財政制度
経団連は、本年1月に公表したビジョン並びに3月に公表した意見書「道州制の導入に向けた第1次提言」
今後、それぞれの地域が自らの知恵と責任において、自立的に発展・成長していくうえで、地方政府の役割がより一層重要となるが、それは地方において「大きな政府」を作ることを意味するものでは決してない。これから、国・地方の税・財政関係の見直しを進めていくことになるが、これを国対地方の財源争いに矮小化してはならない。必要なことは、国・地方間の役割分担を抜本的に見直すことにより、行政の無駄を省き、民に委ねるべきは民に委ねるとともに、国・地方の事務・事業や人員の重複を排除し、国・地方を通じて「小さくて効率的な政府」を確立することである。同時に、民間の活力を最大限引き出し、地域の活力につなげていくことこそが、今後のわが国が目指すべき方向である。
道州制の導入は、明治期以来100年以上続いたわが国の地方体制を刷新する言わば「究極の構造改革」であり、国民的な議論を通じて腰を据えた検討が求められる。国・地方の税・財政を考える上でも、常に道州制というゴールを見据えつつ、そのあり方を議論していく必要がある。
当面の目標とされている国・地方を合わせた基礎的財政収支が、引き続き財政健全化努力を進めることによって黒字に転じたとしても、現在の傾向では、マクロで見た地方財政は一定の基礎的財政収支黒字を維持する一方で、国の一般会計は依然赤字が続く見込みであり、国の財政についての持続可能性は担保されない。政府債務残高の大宗は国が発行する国債により占められており、国の財政の健全性が確保されない限り、国債に対する市場の信認をつなぎとめることはいずれ不可能となる。わが国の国債は、現状ではその過半が公的部門(郵便貯金、日本銀行、公的年金等)により保有されているものの、個人や海外部門の保有割合が徐々に増大するなど、国債の保有構造が次第に変化しつつある中で、万が一、国債に対する信認が失われるようなことがあれば、国債価格の暴落、長期金利の高騰という事態につながりかねない。前述のように、わが国財政は長期金利の高騰に対して極めて脆弱な構造となっていることから、利払費の上昇がさらなる財政収支の悪化を招くという悪循環が生じることも容易に予想される。さらに、わが国財政の持続可能性への懸念が、わが国経済そのものに対する信頼性の低下につながれば、円の暴落とインフレ亢進により経済が立ち行かなくなる事態さえ生じかねない。
したがって、国・地方を通じた基礎的財政収支を黒字化した次の段階において、国の一般会計についての健全化目標を早急に設定し、歳出入改革努力を着実に継続していくことが求められる。
他方、地方財政については、マクロ的には基礎的財政収支黒字を維持している。これは、ここ数年、国と歩調を合わせて歳出抑制に努めてきた成果ではあるが、歳出の長期的推移を見ると、国の一般歳出の水準は、1975年度を100とした場合に2006年度には293であるのに対し、地方の一般歳出は330と国の水準を上回っている。とりわけ地方単独事業(一般行政経費及び投資的経費)の水準は426と、500を超えていたピーク時に比べれば削減が進んだことは事実ではあるが、依然として肥大化が否めない状況にある。他方、歳入面を見ると、地方交付税については、三位一体改革の過程においてスリム化が図られ、また、算定方法を大幅に簡素化した新型交付税の導入が行われるなど、一定の改革が進められている。しかし、本来はナショナルミニマムを保障すべき地方交付税に対し、依然として大多数の地方自治体が財源の多くを依存する状況が続いている。長期にわたる景気回復が続いているにもかかわらず、地方交付税の不交付団体は、都道府県ではわずか2団体(2006年度)に過ぎず、市町村では約1,800団体のうちの1割程度に過ぎない(同)。しかも、過去、地方財政計画上の地方交付税額と法定率分との不足額を補填するために、交付税特別会計の借入金が拡大してきた。それにもかかわらず、個別自治体の財政状況を見ると、厳しい状況に置かれたところが相当数にのぼることも事実である。地域による財政力の格差は、根本的には企業立地が都市圏に集中するなど、地域が自立して発展していくための基盤が不十分であることによるものである。道州制という抜本的な制度変更を通じて、地方においても小さくて効率的な政府を確立するとともに、全ての地域が自らの足で立つことのできる税・財政制度を形作っていくことが、最も重要な課題であると言えよう。
●(2) マクロ経済との整合性
財政を中長期的に健全化していくためには、経済成長を維持することが不可欠の要件である。バブル経済の崩壊後、経済が長期にわたり低迷する中で、税収も低落傾向が続いてきたが、日本経済が活力を取り戻し、税収も2003年度を底として拡大に転じている。こうした足下の経験で明らかなように、経済が持続的に成長してはじめて税収も改善し、また一定の範囲でマクロ経済が歳出入改革によるインパクトを吸収することも可能となる。逆に、経済が失速すれば、税収が落ち込むばかりでなく、何よりも国民の支持を得て歳出入改革を継続することも不可能となる。
近年の財政改革においては、公共事業費の削減をはじめとして、歳出面の合理化が厳しく図られてきたが、それと同時に、所得税・住民税の定率減税の段階的廃止、配偶者特別控除の原則廃止など、実質的な増税が進められてきたことも事実である。また、厚生年金保険料率も、2004年の制度改正によりそれまでの13.58%から、2017年にかけて毎年0.354%ずつ引き上げられることとなっている。こうした国民負担の上昇はやむを得ないものであったとしても、その影響を軽視することは許されない。
わが国の危機的な財政状況を踏まえれば、財政の建て直しが急がれることは当然であるが、今後、歳出入改革を続けるにあたっては、マクロ経済運営に対して、細心の注意を払うことも欠かせない。
財政健全化に向けた取り組みは、長期にわたる努力が求められる。わが国財政は1990年代を通じて悪化の一途を辿った。これと対照的に、多くの先進国においてはこの間、財政改革が進展し、財政の黒字化に成功した国も多い。ただし、2000年代に入ると、オーストラリアやスウェーデン、オランダなど、健全性を維持する国がある一方、アメリカやイギリス、ドイツなど、再び財政収支が悪化した国もある。
各国の財政パフォーマンスの変動要因は、各国固有の事情によるところも大きいが、注目されるのは、1990年代以降、各国において、中期的な財政ルールの設定など、財政健全化に向けた様々な仕組みが整備され、発展を見せていることである。
例えば、アメリカでは、裁量的支出に対する支出キャップや義務的経費等に対するpay-as-you-go(財源の手当てなしに支出増は認めない)原則が導入され、90年代後半には財政収支の黒字化に成功した。ただしその後、国防費等の支出増加により、財政収支は再び悪化に転じており、現在、2012年度までの連邦政府の財政収支の均衡が目指されている。
イギリスでは、1997年に誕生したブレア政権下において、「財政安定化規律」が策定され、これを受けて借入れを投資的経費に限定する「ゴールデン・ルール」と、公的部門の純債務残高対GDP比を40%以内とする「サステナビリティ・ルール」が導入されている。
EUでは、1993年のマーストリヒト条約において、ユーロによる通貨統合への参加基準として、フローの財政赤字対GDP比を3%以内、ストックの政府債務残高対GDP比を60%以内とすることが決められ、これに向け、各国で財政健全化のための努力が進められた。ただし、ユーロ参加後、ドイツ、フランス、イタリアなどでは、再び財政収支が悪化している。
オーストラリアやニュージーランド、スウェーデン、オランダ、カナダといった国々は、1990年代に財政収支の改善に成功し、現在に至るまでその健全性を維持している。これらの国々においては、財政を中期的に管理するためのルールが整備されてきている。たとえば、オーストラリア、ニュージーランドでは、4年間の経済見通しに基づいて歳出を抑制するメカニズムを導入しているほか、スウェーデンは、3年間の歳出総額のシーリングを設定し、景気循環を通じて平均的に財政収支の対GDP比を2%の黒字とすることとされている。オランダも、4年間の実質純支出にシーリングを設定するルールを1994年に導入している。
わが国財政の基本的なルールとしては、財政法第4条において「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」とされ、同条ただし書において「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」とされている。これは、イギリスにおける「ゴールデン・ルール」に相当する。しかし、わが国では、1975年度にいわゆる特例国債(赤字公債)が発行されて以降、バブル経済により税収が拡大した一時期を除き、特例国債からの脱却を果たせず、むしろ特例国債への依存が進んでしまっている。
近年の取り組みとしては、1997年には「財政構造改革法」が制定され、2003年度までに国・地方の財政赤字の対GDP比を3%以内に抑制することなどが目指されたものの、同法は翌年凍結される結果となった。これは、日本経済が1997年末以降、マイナス成長に落ち込む中で、同法が経済の動向に柔軟に対応する仕組みを欠いていたことも一因となった。
その後、2001年6月の「経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(いわゆる骨太の方針)」や2002年1月の「構造改革と経済財政の中期展望(改革と展望)」などにおいて、2010年代初頭に国・地方の基礎的財政収支を黒字化するとの方針が示され、以降、それに向けた取り組みが着実に進められている。さらに「基本方針2006」では、2011年度において基礎的財政収支を確実に黒字化すべく、社会保障、公共事業、公務員人件費、その他(ODA等)、各分野における5年間の歳出削減プログラムが、数値目標も含めて設定された。
このように、わが国においても、一定の目標を目指して、財政改革を継続的に行う取り組みが進められていることは評価できる。しかし、歳出削減プログラムについては、2011年度までの「基本方針2006」で定められたものしかなく、2012年度以降においても削減を着実に進める道筋は明確となっていない。また、2007年1月の「日本経済の進路と戦略(進路と戦略)」においては、「各年度の予算が目標の確実な達成と整合的であるかどうかを確認しながら、予算を編成する仕組みが必要」とされているものの、経済成長率などマクロの経済動向や歳入見通しを踏まえつつ、複数年を通じて予算をコントロールする仕組みにまではなっていないのが現状であり、わが国においても、諸外国の例も参照しつつ、中期的な財政健全化ルールの整備を図っていく必要があると考えられる。
●(2) 財政健全化目標の設定・共有
当面の財政健全化目標である基礎的財政収支の黒字化が視野に入りつつある現在において、次に目指すべき健全化目標を設定することは重要である。ただし、何らかの数値目標を掲げるとしても、財政赤字3%(GDP比)、グロス債務残高60%(同)と、フロー・ストック両面の目標を持つEU、景気循環を通じて財政収支を2%黒字とするスウェーデン、ネットの債務残高をGDP比40%以下とするイギリスなど、フローとストックいずれかないし双方の目標設定が考えられ、また、数値の置き方も各国の経済事情などにより様々であり、裁量の余地が大きい。また、前項で見たように、健全化目標及び歳出入改革を進める手法については、経済の変動に対して柔軟性を持って考えることが重要である。
わが国においては、2011年度における国・地方の基礎的財政収支黒字化の次の段階としては、「進路と戦略」などにおいて、2010年代半ばにかけて基礎的財政収支の「一定の黒字幅を確保する」ことを通じ、「債務残高対GDP比の発散を止め、安定的に引き下げることを確保する」とされているが、一定の黒字幅について具体的な数値目標が示されるには至っていない。
債務残高対GDP比を一定水準へ抑制していくために、基礎的財政収支の一定の黒字幅の確保を中間目標とする考え方は、一国経済の規模と政府債務残高との相対的なバランスをとっていくというものである。債務残高の絶対額が増大したとしても、その増加率と同等かそれを上回って経済が拡大すれば、債務残高対GDP比は一定の値以上には増大しないことは確かである。しかし、わが国の政府債務残高は800兆円近くと未曾有の規模に達し、先進国中最悪の財政状況にある。また、借換債を含む国債発行額は年100兆円を優に超えている。たとえ、経済に対する債務の相対的規模が一定水準に維持されたとしても、今後も安定的な市中消化が可能かどうかは甚だ心許ない状況にあると言わざるを得ない。
こうした状況に鑑みれば、債務残高対GDP比を現在の水準で維持することは適当ではなく、目指すべき明確な目標を設定し、安定的に引き下げていくことが不可欠である。経団連意見書「成長と財政健全化の両立に向けて(2007年1月)」における財政試算#1によれば、2007年度末時点で約116%と見通される国の長期債務残高対GDP比について、歳出入改革を着実に進めれば、遠くない将来において100%以下まで低下することは視野に入るものと考えられる。
このように、債務残高対GDP比を安定的に引き下げる方向で、財政健全化への取り組みを着実に進めていく必要があるが、各年度の歳出入を管理する観点に立った場合、債務残高対GDP比は将来のGDPの見通しによって大きく変わる可能性があり、その結果必要とされる基礎的財政収支の黒字幅も変化すること、また、そもそもSNA(国民経済計算)ベースの基礎的財政収支の値は事後的に作成・判明するものであり、予算編成時に用いることは技術的に困難であること、などの問題が存在する。そこで、債務残高対GDP比の値については中期的に目指す一種の目安目標と置いた上で、これを実現していくために、各年度の予算編成上の基準を置いて管理していくことが考えられる。予算編成上の基準について、まずは、その年の税収により政策経費を賄う基礎的財政収支の黒字化が考えられる。その次の段階としては、債務の利払費までをカバーする狭義の財政収支の黒字化が考えられる。さらには、債務の償還費までを含めた一般的な意味での財政黒字(広義の財政収支黒字化)がある。このうち狭義の財政収支の黒字化が達成されれば、債務残高の絶対額の増大に歯止めがかかり、一定の成長を続ける経済においては、債務残高対GDP比は年々減少していくこととなる。したがって、マクロ経済との関係も勘案した上で、基礎的財政収支黒字化後の次の目標として、狭義の財政収支の改善に向けた赤字縮減を目指すことが選択肢として考えられよう。
なお、上記の考え方は国の一般会計について適用されるものであり、地方自治体の財政健全化については、当面、先に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(地方財政健全化法)」等を踏まえ、適切な基準の下に管理を行っていく必要があり、また、より根本的には、道州制の導入によりそれぞれの地域が経済的に自立可能な税・財政制度を確立していく必要がある。
#1 原則として「基本方針2006」に沿って歳出削減を行うとともに2015年度までに段階的に消費税率を引き上げる(第一段階2%、第二段階3%)ことを想定
その後も引き続き、歳出入改革を継続的に行うことが重要であり、前項で述べたように、中期的な財政再建目標を掲げた上で、2012年度以降についても、実効性のある歳出削減プログラムを策定すべきである。
●(1) 社会保障制度の一体的改革
わが国が本格的な少子高齢社会に突入する中で、社会保障関係費は、歳出を圧迫する最大の要因となっている。小泉政権下における歳出改革が開始された2001年度から足もとの2007年度までの間の一般会計歳出の変化を見ると、公共事業をはじめ社会保障以外の歳出は計5.2兆円の削減が行われた一方、社会保障関係費については、制度改革を含む削減努力が重ねられたにもかかわらず、計3.5兆円の増加となっている。すでに社会保障関係費は国の一般歳出の45%を占めるまでになっており、今後も年1兆円というペースでの増大が見込まれる。公的年金制度については、2009年度を目途に基礎年金国庫負担割合を1/2に引き上げることとされているが、そのためにはおよそ2.5兆円の財源が必要とされる。また、医療ならびに介護についても、今後給付が増嵩していくことが確実であるが、現役世代に対する保険料負担を可能な限り抑制していくためには、公費負担の役割を維持・拡大していかざるをえない。
こうした状況を踏まえ、医療・介護・年金を中心とする社会保障制度を一体的に見直すことにより、経済の身の丈に合った持続可能な仕組みとしていく必要がある。社会保障制度の持続可能性を確保することは、国民の将来不安の軽減につながり、消費拡大ひいては経済成長にも好影響を及ぼす。そこで、まずは、「基本方針2006」で定められた、5年間で国・地方を合わせた社会保障関係費を自然体に比べ1.6兆円削減するとの目標を、着実かつ計画的に実現していかなければならない。さらにその後も、社会保障給付の伸びを「高齢化で修正した成長率」(名目成長率に公的年金のマクロ経済スライドを考慮した上で高齢化の進行率を加算したもの)以下に抑制すべきである。
具体的な課題として、第一に、かねてより経団連では、医療・介護・年金等の社会保障制度全体の共通基盤として、社会保障番号と社会保障個人勘定を早急に導入し、制度の透明性を高めるとともに、給付の重複排除、事務の効率化、コスト削減を図るべきことを主張してきた。この点については、「社会保障カード」を2011年度を目途に導入するとの方針が示されるなど、政府・与党の取り組みが進展しつつある。今後、こうした検討を加速させ、国民にとって使い勝手が良く、また、社会保障制度の効率化、コスト削減に資するシステムの構築を急ぐ必要がある。
第二に、公的年金制度についてはマクロ経済スライドの導入により基本的には給付と経済成長との整合性が図られる見込みである一方、医療・介護については、現状のままでは、経済成長を上回るペースで給付が増加する見込みである。このため、療養病床の再編と平均在院日数の短縮、包括払い化の一層の拡大や診療報酬の見直し、後発医薬品の使用促進、レセプトの完全オンライン請求化を含む「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を着実に具体化する必要がある。加えて、保険者による医科レセプトの直接審査実施のための要件緩和、保険免責制の導入の可能性、さらには終末期医療のあり方などについても検討を深めるべきである。また、介護保険制度についても、現役並所得者の自己負担の適正化や、要介護度の改善に役立つ給付への重点化などの見直しが必要である。これらの取り組みにより、「基本方針2006」で定められた5年間での社会保障関係費削減目標を確実に達成しなければならない。
第三に、公的年金制度についても、給付時に一定以上の所得・資産を有する者に対する基礎年金給付の逓減や公費部分の支給停止、報酬比例部分の支給乗率の逓減に加え、所得代替率の下限の引き下げ、基礎年金の財源方式のあり方などを含め、制度の根幹に踏み込んだ見直しを検討していく必要がある。
●(2) 公務員人件費を中心とする行政経費の削減
財政の健全化を進めるために、行政改革を聖域なく推進し、「小さくて効率的な政府」を確立しなければならない。
第一に、行政経費の大きな割合を占める公務員人件費については、「行政改革推進法」や「基本方針2006」などにおいて、5年間で公務員の定員を5.7%以上純減することなどにより、国・地方の公務員人件費を5年間で2.6兆円程度削減(自然体比)することとされているが、本年6月の「基本方針2007」で明記された通り、これをさらに上回る削減を行うことが不可欠である。国民生活に大きな影響を与える歳出入改革を進める以上、外部情勢に関わらず、人件費の抑制方針は貫かれなければならない。とりわけ、地方公務員の給与水準については、地域の民間給与水準との乖離、技術労務職の過大な給与水準、国家公務員給与との比較などの問題を踏まえ、厳しく抑制していく必要がある。
同時に、先に行われた国家公務員法改正を踏まえつつ、採用から退職までの人事管理、能力と実績に基づく賃金・処遇制度のあり方、定員のさらなる見直しなど、パッケージとしての公務員制度改革を推進し、総額としての人件費の抑制と公務員の能力発揮の両立を図っていく必要がある。
第二に、「官から民へ」の原則に基づき、政府の業務を必要最小限に絞り込み、筋肉質の政府としていくべきである。したがって、官民の役割分担をゼロベースで見直し、民間から提案がある事業については、原則として市場化テストや民間開放の対象事業とすべきである。とくに、「基本方針2007」でとりあげられたハローワークや統計調査関連業務については、市場化テストの導入・拡大をより一層積極的に進める必要がある。同時に、現行の独立行政法人についても、全ての法人を対象に、民営化や民間委託の是非を検討し、合理化を進める必要がある。
●(3) 公共事業の効率化
公共事業については、過去数年来、削減努力が続けられ、補正予算を含む公共事業費はピーク時の半分の水準と、財政の健全化に寄与してきている。ただし、先進諸外国に比べれば、GDP比で見た投資水準が依然として高いことも事実である。したがって、経済活性化に資する事業への重点化など対象事業の優先順位の明確化や、コスト削減、入札・契約制度改革などの取り組みを通じて、さらなる効率化を進めていく必要がある。
●(4) 地方財政の改革
国と地方の税・財政関係については、かねてより、地方交付税交付金、国庫補助負担金により国から地方への巨額の財政移転が行われ、地方の行政ニーズへの対応が図られる一方で、このことが国の財政を圧迫する大きな要因ともなってきた。近年、国・地方を通じた歳出削減が続けられる中で、交付税特別会計の特例借入れの解消が図られている。また、三位一体改革の一環として、国庫補助負担金の改革とそれに伴う国から地方への3兆円規模の税源移譲、約5兆円の地方交付税改革が行われるなど、改革努力が進められている。しかし、地域ごとの財政力の格差は依然として大きい。国の財政も危機的な状況にある中で、かつてのように中央から地方への財政移転の拡大により、これを解決することは望むべくもない。また、交付税特別会計借入金の償還を計画的に推進していく必要もある。地方税、地方交付税、国庫補助負担金、地方債のあり方も含め、道州制の導入を見据えつつ、各地域が自立し、自らの責任と選択の下に地域経済の発展と地方行政の効率化、合理化を進められる税・財政の仕組みを設計していくことが何よりも求められる。
●(5) 経済成長戦略ならびに少子化対策への重点配分
財政を着実に健全化していくためには、持続的な経済成長が欠かせない。わが国経済の成長は、イノベーションと生産性の向上に支えられており、歳出全体を厳しく抑制していく中にあっても、先端技術や、宇宙・海洋開発などの国家プロジェクトを推進するための研究開発投資、経済全体の生産性向上に資するインフラ整備などに対しては、重点的な資源配分を行っていく必要がある。
同時に、わが国の長期的発展・存立を考えていく上で、人口の減少傾向に歯止めをかけることが極めて重要な課題である。景気の着実な回復もあり、足もとでは出生率の低下傾向に歯止めがかかる兆しも見られるが、予断は許されない。出生率を長期的に反転・上昇させていくために、必要な一般財源を確保しつつ、次世代育成支援のための施策を効果的に展開していく必要がある。
●(6) 歳入改革
財政健全化に向けては、歳出・歳入両面にわたる見直しが要請される。これまで見てきたように、まずは各分野における歳出削減を徹底して行わなければならない。しかし、高齢化のさらなる進展、とりわけ、今後団塊世代が次第に引退し、社会保障を受給する側にまわることを勘案すれば、社会保障給付が傾向的に増大することは不可避である。社会保障制度全体を通じた改革によって公費負担増を可能な限り抑制する必要があるが、それでもなお必要な負担については、将来世代への先送りをすることなく、歳入面の改革により対応していかなければならない。
一方、歳入面の状況を見ると、わが国では、かねてより直間比率の見直しが目指され、かつて7割以上あった直接税の割合は、一旦は50%台まで引き下げられたものの、ここ数年でその傾向が逆転し、足下では再び60%を超えている。逆に、間接税比率は40%台半ばから、30%台に低下している。
間接税の大宗をなす消費税は、国民一人ひとりが広く負担を分かち合うことが可能であり、また、経済活動の国際競争力に与える影響も中立的であることから、これから増大する社会保障費用を賄っていく上で最も相応しい税目といえる。
今後、国・地方を通じて、少子化対策費を含めた社会保障費用を賄うために消費税を拡充するという対応関係を明確にしながら、歳入面の改革を進めていくことが重要である。
図1:歳出入見直しイメージ
●(7) 資産・債務改革
財政全体の構造改革を進める上で、フロー面のみならず、政府が保有する資産・債務というストック面の改革も並行して行い、資産売却等による歳入面での寄与を目指すとともに、政府のバランスシートの改善を図る必要がある。
「行政改革推進法」などにおいて、2015年度末における国の資産規模を対GDP比で半減することが目指されており、まずはこれを着実に達成するとともに、独立行政法人、国立大学法人、さらに地方自治体などの資産・債務改革も併せて推進する必要がある。
●(8) 公会計整備とPDCAサイクルの強化
中長期的な財政再建目標の実現に向けて、歳出入改革を着実に進める上で、予算編成、予算の執行、決算、翌年度予算への反映の各段階を通じて、透明性の向上と厳格な政策評価を行うことにより、一連のPDCAサイクルとして確立し、財政資金の有効活用を図ることが重要である。企業会計の考え方を活用した財務書類については、これまで、省庁別財務書類、特別会計財務書類、国の財務書類と順次整備が進められてきている。これらを財政状況に関する単なる事後的な説明資料に止めるのではなく、予算の編成段階から適切に活用し、財政活動の効率化・適正化につなげていくために、歳入歳出決算と同時並行的に財務諸表を作成し、翌年度予算編成への活用を可能とした東京都のような先進的取り組み事例も参考としつつ、国においても財務書類の作成・公表時期の早期化など、さらなる改善を図る必要がある。また、政策単位での予算の効率化・適正化を図っていくために、省庁別財務書類の一層の活用、政策評価との連携を進めていくことも必要である。
1.受益と負担の不明確さと地方財政の改革の遅れ
戦後わが国では、社会保障や教育、インフラストラクチャーなどの整備を全国的に進めるため、国から地方への財政移転を行う仕組みが築かれてきた。こうした仕組みは、わが国の戦後復興、高度成長による成果を全国に行き渡らせ、豊かな経済社会を実現する上で有効性を発揮した。
しかし、わが国が成熟社会化し、また、さらなるグローバル化や少子高齢社会の到来という環境変化の中で、今後は、各地域の自立的発展を国全体の豊かさに結びつけることが求められる。これに対し、現状を見ると、各地域がナショナルミニマムを超えるナショナルアベレージまでの財源保障を求める中で、地方財政の肥大化が進み、現行の国・地方間の税・財政の仕組みは、持続可能性を喪失している。
地方自治の基本は、地域住民の主体的な選択に基づき、必要な行政サービスとそれに伴う負担のあり方を決定し、効率的に行政を進めるところにある。この点、わが国においては、地域における受益と負担の関係が明確に認識されない結果、財政面での規律が働きにくい状況にある。
2.規模の経済性の欠落
わが国では、47都道府県からなる地方体制が、基本的には明治期以来変わることなく維持されているが、こうした体制は、通信・輸送などの飛躍的進展や、経済活動の拡大・グローバル化など、経済社会情勢の変革に対応したものとはもはや考えられない。国・地方間や、地方相互間での事務・事業や人員の重複、無駄の排除も十分とはいえない。
現行の国・地方の財政関係においては、前述の通り、国からの地方交付税による財政移転を受けず、財政的に自立した団体は47都道府県のうち現在わずか2団体に過ぎず、地方自治体間に大きな財政力格差が存在することは確かである。しかし、総体としては世界第二位の経済規模を有するわが国にあって、それぞれの地方ブロックは欧州主要国と同等の経済規模を持ち、経済的自立を図ることは本来、十分可能と考えられる。
市町村レベルにおいては、かねてより「平成の大合併」として、1999年時点では約3,200団体あった市町村数が、いまや約1,800団体まで集約が進められてきている。現行の都道府県体制についても、国と地方の役割分担、税・財政関係を含めた抜本的な見直しを行い、経済的に自立可能な「広域経済圏」を確立することが、今後の重要課題である。
3.中央への依存体質
各地域が自らの知恵を働かせ、産業の振興・誘致を図り、雇用と所得の涵養、税収の増大につなげることが、地域経済の自立的発展への道筋である。
しかし、現行の国・地方の財政関係においては、地方交付税制度によって不足分が補填される仕組みがとられていることにより、それぞれの地域が自らの努力により税収を涵養し、財政的に自立を図るというインセンティブが失われている。
●
経団連では、本年1月に公表したビジョンにおいて、2015年を目途に、「究極の構造改革」として「道州制」を導入することを主張している。その基本的な考え方は、わが国の地方体制を10程度の「道州」によって構成される形に再編成し、各地域が競い合いかつ連携を深めつつ、主体的に「地域経営」を展開し、地域の経済社会の発展に自らの責任で取り組むことである。
地域の成長力の強化という観点からは、各道州は、高成長を続けるグローバル経済とのリンケージの中で、地域経済を支える産業の育成・誘致を図ることが考えられる。中央への陳情を通じた産業やプロジェクトの誘致合戦という従来型の発想では、日本全体ではゼロサムゲームに陥ることを免れないが、道州ごとの広域経済圏を構築し、それぞれの強みを活かしながら海外経済との結びつきを強め、グローバルに活動を展開する企業の投資や海外企業のグリーンフィールド投資を引き付けることにより、日本経済全体がプラスサムの発展を遂げることが可能となると考えられる。
道州のスケールメリットを活かして、国公立大学及び国・地方の研究機関の再編・統合・連携を行うことを通じて、国際水準の知的クラスターを形成し、地域の産業・企業の生産性向上と新産業創出につなげていくことも重要である。
その際、道路や空港・港湾などのインフラストラクチャーについても、道州が一つの広域経済圏として有機的に結合され、道州内の企業・産業の競争力の強化につながる形で、効率的に整備していく必要がある。
さらに、行政や地方議会のあり方についても、国・地方間あるいは地方相互での重複や無駄の排除が徹底されれば、相当程度の合理化が進むことが期待される。
国・地方の税・財政関係のあり方についても、道州のこのような努力を支える仕組みへと抜本的に見直していく必要がある。その基本的方向としては、各道州が自らの責任において地域経営を行うという考え方に照らせば、財政面における受益と負担の関係を、各道州を単位として貫徹していくことが望ましい。したがって、国・地方の「もたれあい」(「地方分権改革推進にあたっての基本的考え方」(地方分権改革推進委員会))とも評される現行の財政調整の仕組みは可能な限り簡素化・スリム化していく必要がある。また、道州内における基礎自治体に係る財政調整は、基本的に、それぞれの道州の責任において行われることになる。
●
道州制にあっては、国・地方の役割分担は抜本的に見直され、国の役割は国家の存立と国民生活の安心・安全の確保などに集約される。道州は、地域住民の生活向上のため、産業振興・知的基盤の確立、インフラ整備など、自らの知恵と責任に基づく地域経営を通じて、自立可能な広域経済圏を構築していくこととなる。
国・地方の税・財政のあり方は、原則として、国・地方が果たす役割に即して、再設計する必要がある。その際、行政サービスの遂行を確保する上での財政的責任と税源とが整合性を持つ形に整理することが重要である。この点は、今後増大が予想される社会保障負担に歳入増で対応する場合において、とくに留意する必要がある。地方消費税の拡充を求めるのであれば、社会保障給付における地方の責任が増大することは避けられない。
以上の点を踏まえ、今後、道州制への移行に向けて、地方財政の自立と合理化を進める観点に立ち、また、国・地方の役割分担を踏まえつつ、税・財政のあり方を見直していく必要がある。
まず第一に、地方の基本的な税源としては、地域による偏在が少なく、地域の住民が自ら担うことのできる税目が適当と考えられる。個人住民税、固定資産税については、現行でも制限税率は存在しないが、今後、地方自治体と地域住民とが真剣に向き合い、地域における受益と負担の関係のあり方を決定していくことが非常に大切となる。
第二に、地方交付税は、現行においても地方の固有財源とされているが、地域における受益と負担の関係を希薄化させる、法定率分で財源が不足する場合に加算を行うことにより財政規律を弛緩させる、財政調整を国が行うことから国の財政面における裁量的関与を強めている、などの問題点がある。そこで、地方税源の充実・強化の観点に立ち、現行の地方交付税は廃止することとする。その上で、地方交付税の担ってきた財政調整を水平的に行うものとして、例えば地方共有税を設け、従来の法定率相当分を財源とし、交付税特別会計借入金(地方負担分)の計画的償還を進めつつ、道州間での自主的財政調整に委ねることも考えられる。ただし、地方共有税は、各地域の自立的発展が図られる中で、将来的には縮小していくことが予想される。なお、現行の地方法人二税(法人住民税、法人事業税)については、地域間の偏在が大きいことなどに鑑み、全体の規模の縮小を図った上で、基本的に国税の法人税への一本化を図りつつそれに対応する形で地方共有税財源を積み上げることも考えられる。
図2:地方税源見直しイメージ
第三に、社会保障や教育など、全国的に一定水準を保障すべき費用については、国からの財政移転が維持される必要がある。そこで、使途を特定したシビルミニマム交付金として、対象事務事業により、道州または基礎自治体への財政移転を行うことが考えられる。
第四に、地方債については、道州制移行後は、道州が自らの責任の下に自由に道州債を発行し、地域のインフラ整備等を推進することが考えられる。それまでの間、地方債の発行の自由度を段階的に高めていくとともに、あわせて、地方財政の開示制度の拡充・強化、先に成立した「地方財政健全化法」を踏まえた現実的な債務調整の導入の是非などについて、検討を進めていく必要がある。
 2006
2006 2005
2005 2004
2004 2003
2003 2002
2002 2001
2001 2000
2000多くの方々との議論の中で考えさせられたことは、タイトルの通り、「私は誰のために政治を行うか」ということだ。半期の総括も兼ねてここに記しておきたい。
まず政治理念は、客観的な社会科学であるべき
よく、「私は恵まれない人達のために政治をします」、とか、「○○党は高齢者のための政治を考えます」というようなフレーズが言われる。今更言うまでもないことだと思うが、政治は基本的に全ての国民のために行われるべきだ。特定の誰かのために政治が行われることがあってはならない。かつては、労働者による政治(プロレタリアート)独裁によって現体制を否定し、別の体制を実現するという革命思想的政治理論も存在しえたが、冷戦構造崩壊後、現在の資本主義体制を否定する政治思想が生まれていない以上、現体制下で全ての人々が幸せになるためにはどうすべきか、という命題こそがあらゆる政治理念における共通基盤であらねばならない。欧州における福祉国家モデルも、経済との調和が絶対の条件と考えられるようになってきている。そういう意味で、政治理念とは、現在の資本主義体制とは何か、という客観的な社会科学であるべきだ。世界先進諸国でいわゆる政治の中道化といわれる現象が見られるが、結局のところ、これは全ての政治思想が、「経済・市場とは何か」という共通の命題を共有してきたがために起こっている現象だろう。所謂「第三の道」論も、「市場を否定する」ことも、「市場を盲目的に肯定しない」ことでもない「第三の道」と解釈される。
しかしながら、政治理念は同時に「行動の科学」でなければならない。
しかし、単なる自然科学的な「認識の科学」であれば、客観性は容易に保持されるが、政治理念は単なる観察の道具ではありえず、現実の諸問題を解決する「主体の科学」「行動の科学」である以上、「客観性の名のもとの無為」は肯定されえない。例えば、仮に自然科学的な知で我々が生物界を観察すれば、「食物連鎖」という自然の客観的法則が見える。我々が単なる観察者であれば、人間は、魚を食べ、その人間は更に強い肉食動物に食べられる、と客観的に語っていられる。しかし、我々がその肉食動物に食べられつつある現実の人間であったならどうか。我々の知は、その状況を如何に変革するかという方向で活かされるべきだ。我々は、「食べられるべき人間」という客観性を受け入れることはできない。「生きなければならない」という主観に基づく知は、食物連鎖という客観的知に挑戦する。ここで、「認識の科学」と「行動の科学」「主体のための科学」との間に緊張関係が生まれる。政治理念はまさに「行動の科学」「主体の科学」であり、客観性と、その客観性が前提とする現状を変革するための意志との緊張関係のもとに成立する、アンビバレントな知のあり方である。かのJ・M・ケインズの有名な言葉、「IN THE LONG RUN, WE ARE ALL DEAD」の言葉は、この政治的知の緊張を見事に表現する。客観的に肯定されうる現状況に対し、我々の主観はその改革を求める。しかしその主観もまた客観的であらねばならない。あらゆる政治理念は常にそんな緊張を内包する。そこにこそまた社会の発展の源泉があるのだろう。私は将来、国政にたずさわりたいと考えている。全ての日本国民のために政治をするつもりだ。しかし、私は同時に変革しなければならない。誰のために、何のために変革するのか?
現在の政策思想論争への懐疑
選挙の度に論点が見えないと揶揄される我国の政治シーンだが、幾らかの論争は存在する。構造改革か、景気対策かという論争の名を借りただけの低次元な政争は論外として、一般的に見られるのは、我国にも、世界的な潮流となりつつある市場原理を導入すべきという構造改革論と、それとは別の道を模索すべきだというアンチ市場主義論に整理されると思う。しかし、それらを聞いていて常に疑問を感じるのは、それらは双方ともに市場というものを観念的に捉えて、それを善玉と捉えるか悪玉と捉えるか、という観念的な思想で全てを判断しようとしていることだ。個人的には、市場がうまく機能しているか否かは、市場毎に異なるわけで、全てを混同すること自体に問題があると思う。例えば、ミクロの個別産業の市場を考えた場合、日本程の経済力になれば、国内産業の保護といった視点はあまり重要でなく、基本的には市場の持つダイナミズムを肯定すべきだ。食糧安全保障的観点から考えると等一次産業には若干の問題があるが、2次・3次産業の分野においては積極的に世界の市場化の動きを促進こそすれ反対するべき立場ではない。しかし、マクロな経済政策、例えば、通貨・金融政策というマクロレベルで見ると、日本の経済基盤は極めて脆弱で、かつアジアの通貨危機等連発する世界の経済危機を見るに、安易な市場万能主義は危険だ。グローバリゼーション・市場主義の名の元に思考を停止すべきではなく、積極的な政治のリーダーシップにより我国経済の自立性を高めるべきだと考える。現在の政治論争は非常に安易な誤りを犯しているように見える。アジアの通貨危機を見て所謂「アンチ市場主義」が力をつけると、すぐにミクロのレベルにおける規制緩和や市場統合の動きにブレーキがかかる。もしくは、所謂マネーファンド悪玉論もしくは国際資本悪玉論のような大雑把な観念的議論ばかりが幅をきかせる。肝心の通貨政策や金融政策には議論が至らない。逆に、アジアの通貨危機は、急激な資本の自由化のせいだ、と安易な魔女狩り理論が横行し、通貨政策・金融政策の誤りを隠蔽する。ミクロレベルとマクロレベルも区別できない安易な観念論では、現実の諸問題を解決しうる政治理念にはなりえない。構造的に諸問題を把握して現実的な解決のストラテジーを描く、という構想力が今の日本には必要だと思う。
「日本らしさ」への懐疑
現在の日本の改革を阻む勢力の理論は、いわゆる「アンチ市場主義」という所にその根拠を求めている。そして多くの場合、市場主義を、所謂弱肉強食をも肯定する「アングロサクソン・モデル」と強引にカテゴライズした上、自身の立場を、いわゆる「日本らしさ」の維持に置く。護送船団方式や終身雇用など、いわゆる「和の精神」に代表される日本人の集団性が強調された制度や慣行の維持を主張する。しかし、現実的にはそれらは単なる既得権益層の隠れ蓑になっているだけではないか。終身雇用という安定的雇用が、社員の会社へのロイヤリティを高め、生産性の向上につながるという理屈は理解できるが、現実的には、過去に蓄えた膨大な資産を食い潰しつつ、既得権益層たる中高年を保護し、諸問題を次世代へと先延ばししているだけではないのか。雇用の確保という名の元に、競争力のない企業に公共投資を投入し続けることは、将来膨大な財政赤字を補填する次世代から、現在の中高年という既得権益層への利益移転ではないのか。そして、本来雇用政策として取られるべき、雇用の流動化政策や技能研修制度、生涯教育制度等への投資を奪っているのではないか。膨大な財政赤字は、すぐに来る大インフレの中で、次世代に繰り越される前に全国民、特に年金生活者等に負担を強いるという形で解決されるという意見を聞くが、それこそ年金生活者という弱者への皺寄せ政策であって社会正義にもとる上、超インフレで弱体化する円は、国際経済に相当の悪影響を与え、日本経済の国際的な地盤沈下と為替切り下げ=近隣窮乏化政策によるアジアの分裂という事態を招き、世界に夢をはせる若者の道を阻むことになる。昨今勃発する少年犯罪に対し、最近私はシンパシーすら覚えている。無能な政治家を選び、現在の既得権益層を守ることで改革のチャンスを奪いつづける今の日本社会に、若者は絶望させられている。
「護送船団方式」が本当に日本らしさなのだろうか。例えば、作家の邱永漢氏は、中国人との比較から日本人の特質を「職人気質」とする。職人は、自分の腕に自信と誇りを持って、独立して生計を営む。商売には疎いかもしれないが、良いものを作るのでお金には困らない。江戸っ子は「宵越しの金は持たない」と言われるが、それは何故かというと、夜が明けても、必ず自分の腕さえあれば仕事があってお金に困ることがないという誇りと自信があったからだ。「日本人らしさ」というと、すぐに集団思考・安定志向を思い浮かべてしまいがちな気がするが、独立心あるクラフトマンシップこそが、日本人の特質であるとも言えるのである。雇用の流動化や起業が日本人にあわないなどということはないはずだ。
政府は、経済波及効果の少ない公共投資も、適当に「ケインズ理論」を持ち出して正当化している。しかし、ケインズは、決して社会主義者ではない。国家社会主義者の巣窟と化した自民党にケインズを語る資格はない。ケインズは自らを「自由主義者」と規定している。日本のケインズ経済学第一人者の伊東光晴氏は、ケインズの哲学を以下のように位置付けている。
〜「彼の主張したものは経営者資本主義であるといっていいであろう。経済的効率、社会的公正、個人の自由、この三つこそ求めなければならない。そして社会的公正を最も強く主張したのは社会主義者である。これと経済的効率と個人の自由、この三つを鼎立させるとき、ケインズはイギリスの階級社会にかわるメリトクラシー(能力主義)の社会を夢想したと言っていい。能力ある人間が経営者として登場する。そこには経営者と労働者としての差異を、能力のあるなしということで識別できるとする、ケインズ特有のビジネスデモクラシーの考え方がある。〜
今の日本の公共投資を見たとき、ケインズは何と言うであろうか。またアングロサクソンであるケインズのこの思想は、アングロサクソンのみならず、日本の「職人気質」の文化にも適合できるのではないか。「能力」を「技能」に置き換えれば、日本型クラフトマンシップ資本主義ができあがるのではないか。
では私は誰のために、何のために政治を志すか
先に、「政治理念は客観的社会科学でなければならない」と述べたが、それと同時に現実の政治は、「選択」である。「全ての国民のための政治」を大前提として心に刻みつつも、我々は行動しなければならず、多くの場合、政治的行動とは、「選択」だ。個別の政策、特に私のテーマである外交・通貨・通商政策に関してはまた別の形で具体的に論じていくので今回は、やや観念的になるかもしれないが総論的な話をしたい。
我々の直面する時代の潮流は、大きく2つに分けられると認識している。1つは、国内問題、眼前に迫りつつある少子高齢化現象だ。この問題に関しては政経塾同期の畠中氏が研究しており、いつも議論している。畠中氏がいつも言うのは、常に少子高齢化問題は、高齢者の生活をどう守るかという視点ばかりが論じられるが、我々は、少子高齢化社会で生きる我々若者の立場こそを考えるべきということだ。国民皆保険もしくは税金による最低限での高齢者保護は必要だし、世代を超えて支えあうことにこそ、即時的な概念では位置付けようのない、歴史的概念としての国家の意義があると考える。過去を未来をつなぐ事こそ国家の役割のはずだ。しかし、それが安易な、若年層から高齢者への所得移転になってはならない。少子高齢化問題において、我々にとって高齢者のことを考えることが重要であるのと同じ位、我々の次世代のことを考えることは重要なはずだ。老人の世話ばかり考えて、子供やそのまた子供のことを考えられない家は潰れてしまう。急速な少子高齢化の第1段階で高齢者となる層は、比較的裕福な層であるわけで、本当の問題は、少子化により我国が活力を失うことにあるはずだ。特に国際的な経済基盤が弱いわが国の場合、人口の減少は深刻な問題となる。労働力という観点だけであれば、女性の社会進出の促進や、高齢者の社会参加で補うという考えもあろうが、市場の縮小と、今の日本の資本を支える高齢者層の資産が減少していく中で、資本不足が深刻な問題になるのは避けられないのではないか。国際化に関しては2つめの問題として上げるが、やはり外国人及び外資の受け入れを促進する方向を考えるべきではないか。このままでは日本は過疎の国になってしまう。多くの地方が過疎対策として雇用問題に取り組むが、雇用対策は一時的な気休めにしかならない。特に公共投資による雇用創出もしくは維持は、経済の社会主義化を招くだけで到底サステナブルなものではない。過疎を防ぐには、その場所を外部から見ても魅力的な場所にして、人やマネーを惹きつける場所にしなければならない。また現在潜在的にかなりのレベルにまで高まった来ている日本の雇用問題だが、長期的観点では少子化の中で逆に労働力不足の方が問題となろう。
2つ目は国際化の問題だ。再三今まで主張してきたが日本は孤立している。これだけ世界から孤立しつつあるにも関わらず、日本らしさを強調して国際化を嫌うのは、変化を恐れる生活保守主義者的思考でしかないのではないか。我々が古き良き日本に住んでいたい、とワガママを言う前に、最低限、次の世代、もしくは次の次の世代の人々が、「極東で孤立しつつ、しかし旧来の日本的雰囲気を保った閉塞した国」か、もしくは「世界に開けた、アジアのセンターとしての希望に溢れる新しい日本」なのか、そのどちらかを選べる権利を残すことを考えるべきだ。かつての成功を生んだ世代(戦前生まれ世代)の蓄えを食いつぶしつつ、日本らしさという名の元で国際化の努力を回避しようとする生活保守主義者の安易な政治判断は国を滅ぼしかねない。我々は我国の自立・自律を高め、ポジティブに国際基盤の拡充に務めるべきだ。敗戦を引きずる隷属的・自虐的な外交姿勢を改め、国際社会における意志をもった大人の国家として、米国とのより高度なパートナーシップとアジアでのリーダーシップを求めるべきだ。米国と並ぶ超大国であるという現実を受け入れて、それに相応しい責任と品格ある行動が求められるはずだ。
我々の世代が、我々とそして我々の子供たちの世代のために声を上げて行かなければ、生活保守主義の蔓延する日本の未来はない、と感じている。政経塾入塾以来、指導官から度々、「我々はあらゆる観念・イデオロギーに囚われてはならない」と教えを受けてきた。あらゆる観念・イデオロギーに対し常にリベラルでありつつ、自分の感性を磨きつづければ、自然と方向は定まってくると感じている。耳を澄ませば、一遍の小説にも、電車内の一高校生の表情にもメッセージが溢れている。過去の成功に安住する中で、我国は未来を失いつつある。この国には希望がない。頻発する17歳の犯罪は、未来を失いつつある我国へのレジスタンスと解すべきではないだろうか。
 〜1999
〜1999「規制緩和」がもたらした恩恵の例として、電々公社の民営化に伴う電話機メーカーの指定が解除され、価格と性能の競争が生じて、高性能な電話機が低価格で購入できるようになった事例をあげることができる。また、最近の電気事業法の改正にともなう電力供給の多角化も関連する技術開発に好ましい影響をもたらすことが期待できる。問題は他の産業分野でも、「規制緩和」が引き金になって、技術開発が刺激され、消費者がその恩恵に浴することになるか否かである。
最近の「規制緩和」の動きは、外国政府(特に米国)と日本の経済団体の要望ないし圧力によってもたらされている。これらの要望ないし圧力の動機は、外国政府にとっては「自国の企業の日本参入の障壁の撤廃」であり、日本の経済団体にとっては「傘下の企業の既存事業の制約の除去」である。一方、同様に様々な規制のために事業の展開に支障を来している「新規事業者」の要望事項はほとんど緩和の対象となっていないし、議論の対象にもなっていない。
具体的な「規制緩和」要求の例として、住宅・建築分野の例を取ると、外国政府は日本の建築基準法をはじめとした建築システム全般にかかわる規制、日本の材料関するJIS、JASなどの規格、耐震性および耐火性に関する過度の規制の撤廃を主張している。外国政府の要求は概して妥当なものが多いが、一部には日本の実情をあまりにも無視したものも含まれている。日本の経済団体の規制緩和要求は「容積率、用途地域などの建築規制の緩和」、すなわち、一定面積の土地により多くの建築物を建てることを可能にすることが主眼となっている。一方、この分野で新規事業を展開しようとしている事業者は、建築基準法ばかりでなく、これに付随する告示、複数の省庁にまたがる規制、法に裏付けられない様々な行政指導、市町村レベルの規制など、過度の官僚統制に起因する多くの規制を障害と感じている。このような新規事業者の「規制緩和要求」は公の場で殆ど議論されることはなかった。
このような状況を踏まえると、現在の「規制緩和」の議論の延長線上にある新規事業、新産業とは外国企業および日本企業の既存の事業の幅がやや広がったものに過ぎない。新しい技術開発を誘発するような市場は期待できない。
現在の規制緩和の流れが契機となって、新規の市場と新規の事業が発生し、新しい技術開発の目標ができることを期待することは幻想に過ぎない。むしろ、新しい技術の開発とこれにともなう新規の事業の開発こそが「規制緩和」の原動力である。また、産業分野の中には、本来もっと強い規制があってしかるべきであるのに、現実には関連する技術が未熟であるため、十分な規制が行われていない分野がある。公害、環境問題にかかわる分野など、人類の生存に係わる分野がこの典型的な分野である。このような分野では規制の内容を実質的に決定するのも技術開発であると言える。