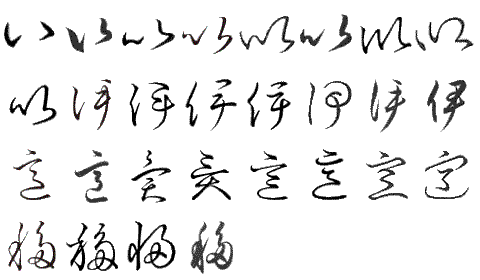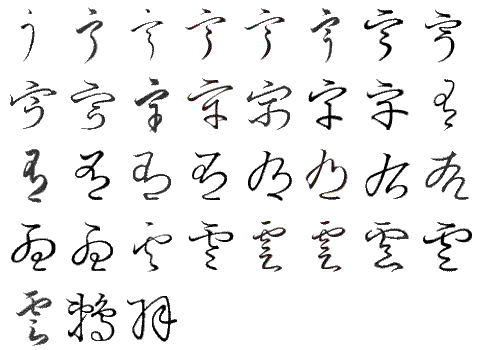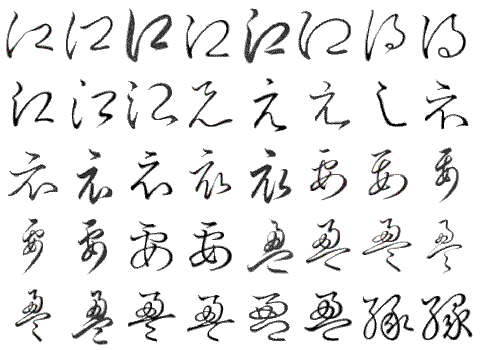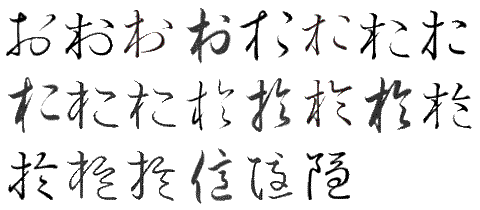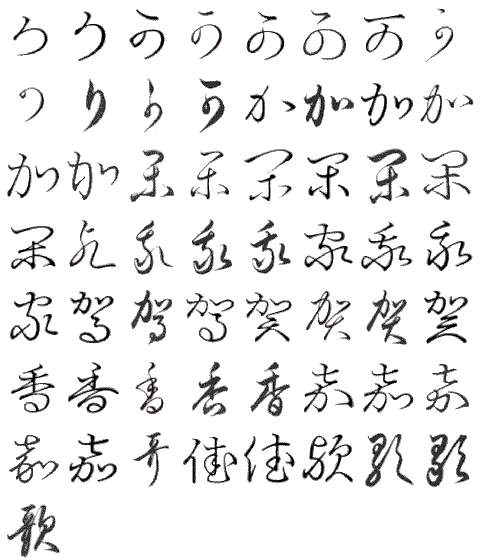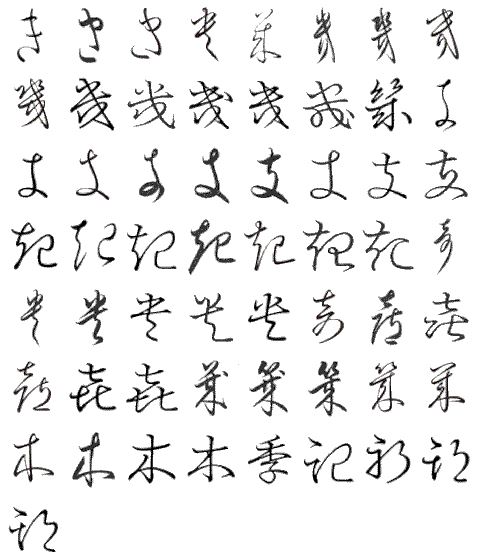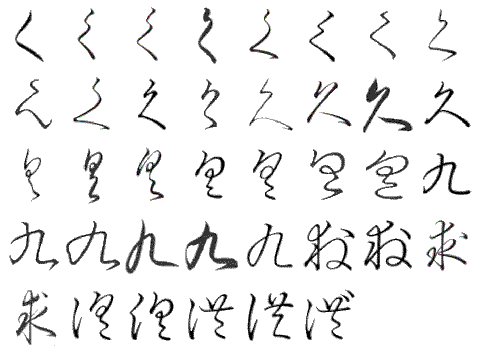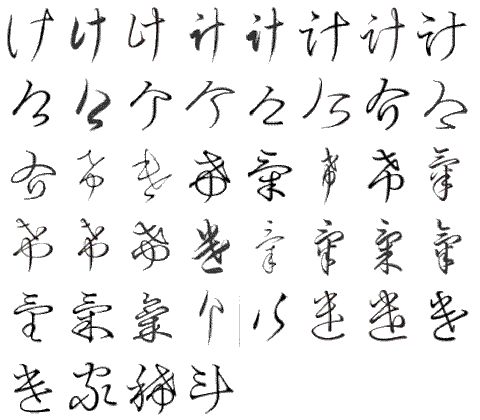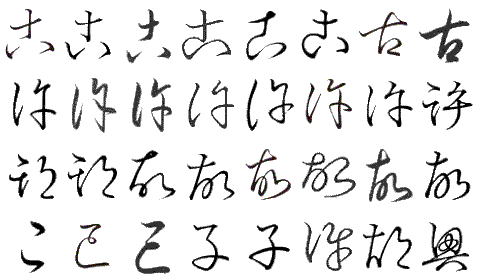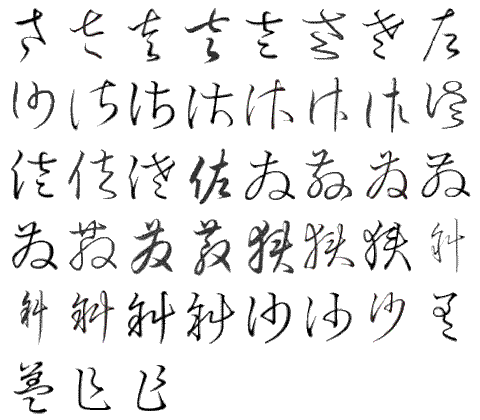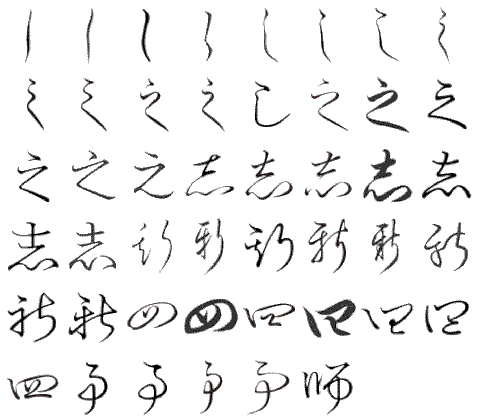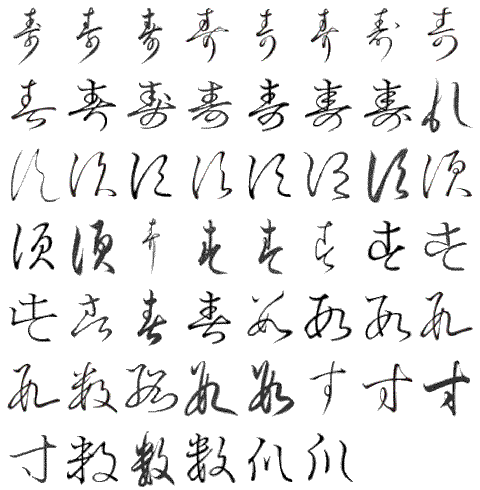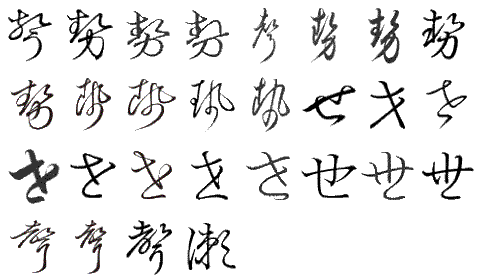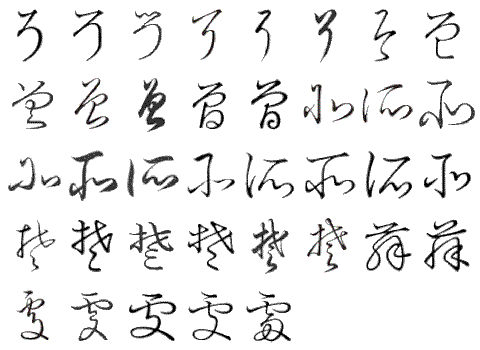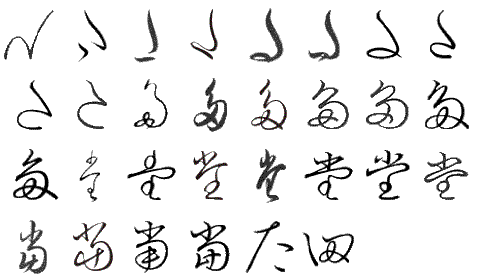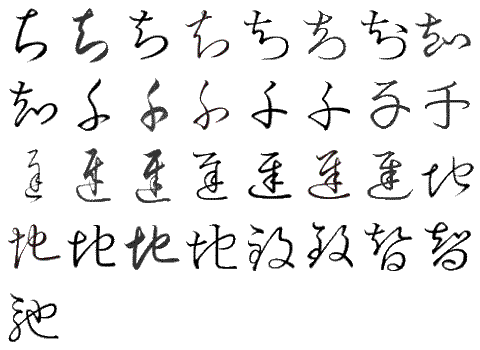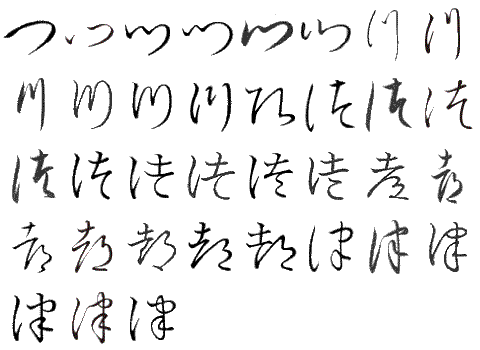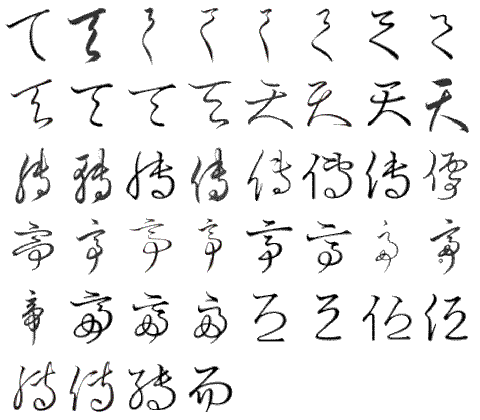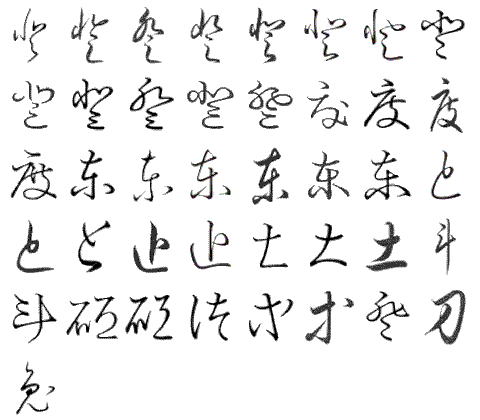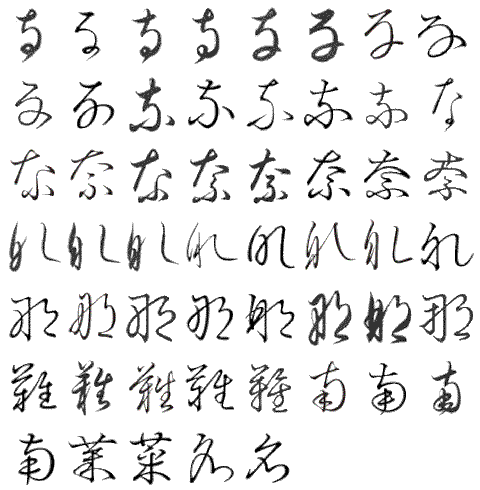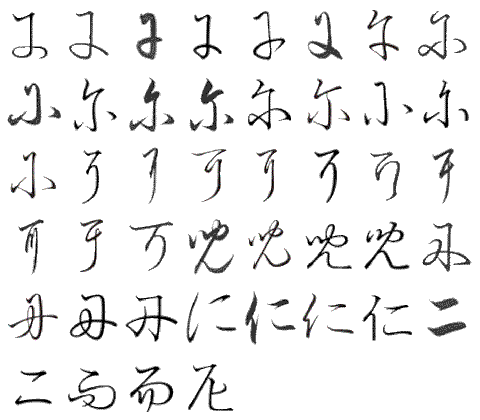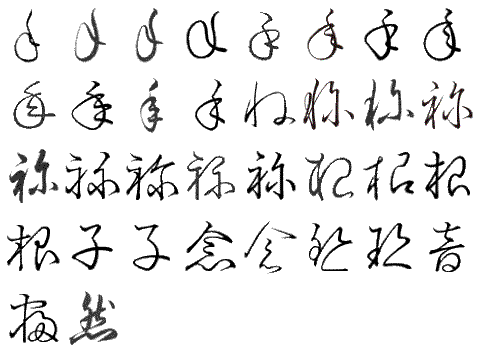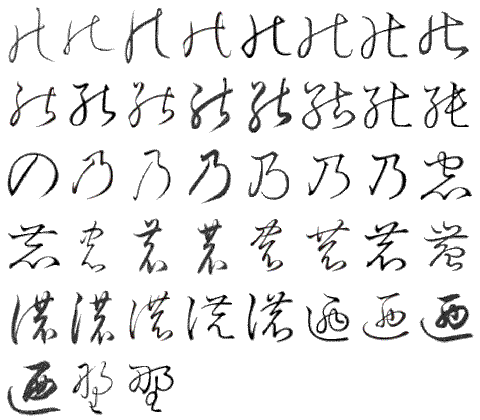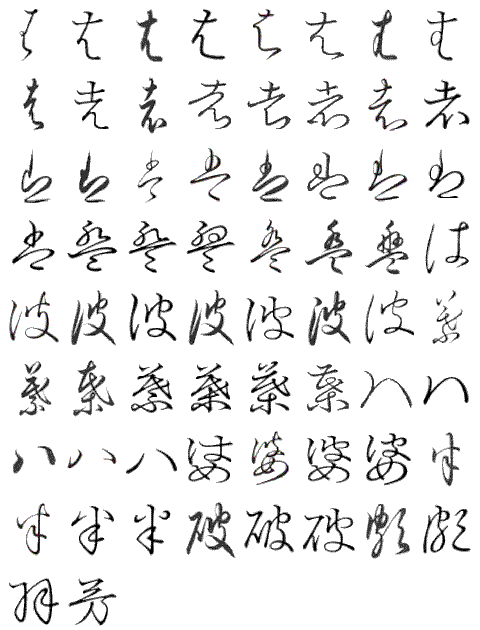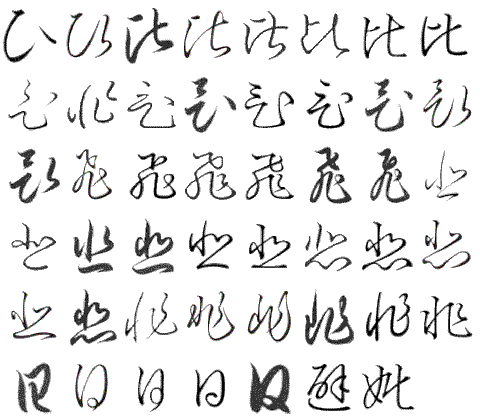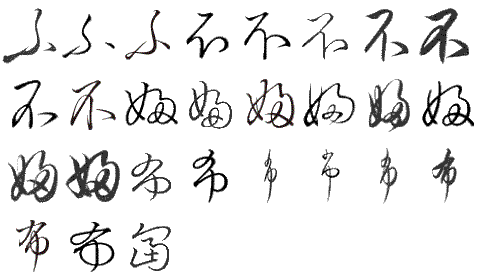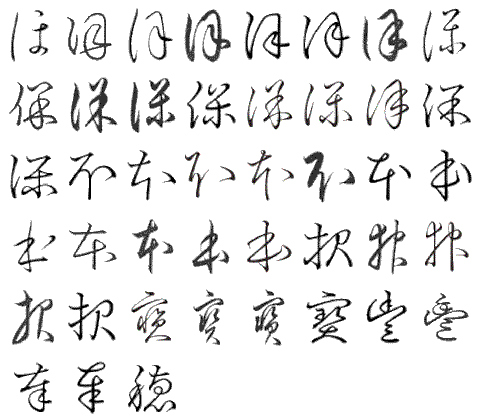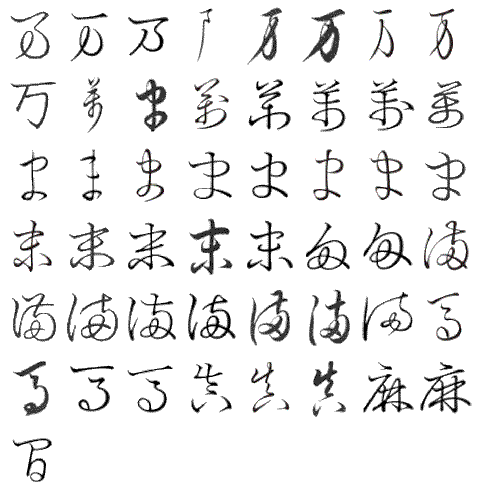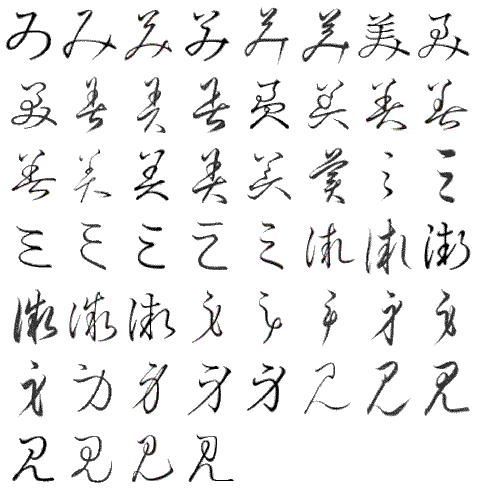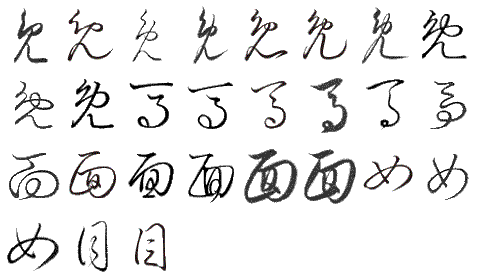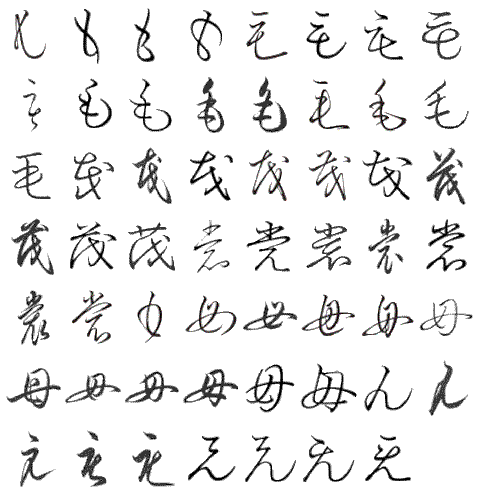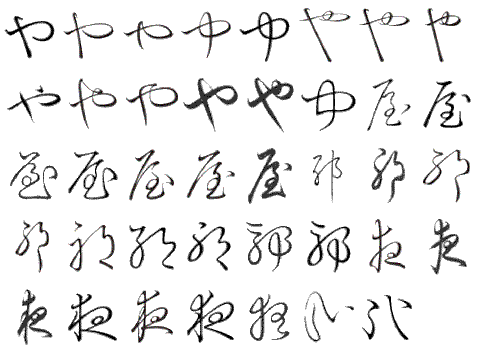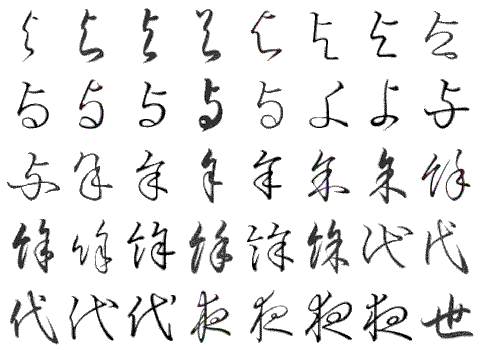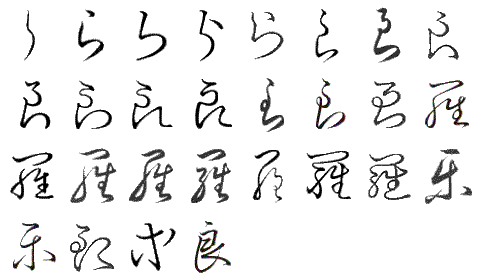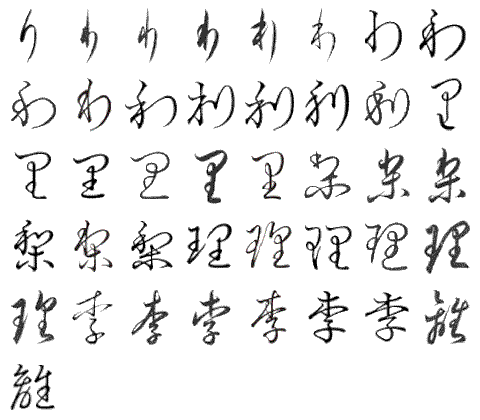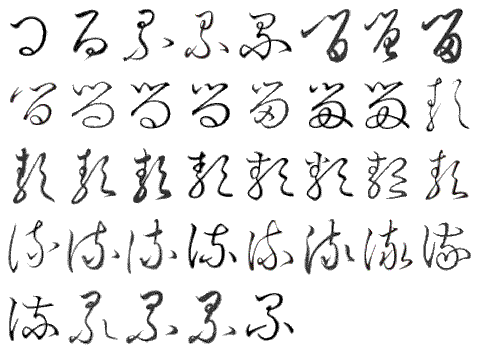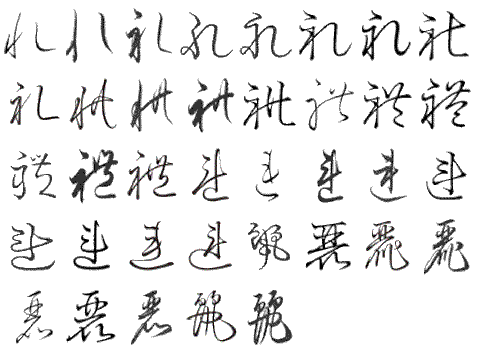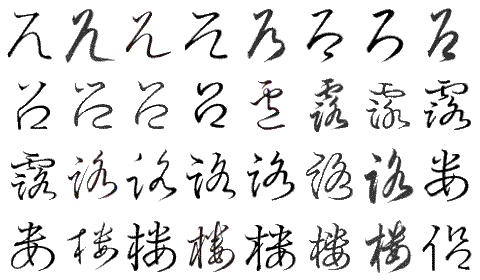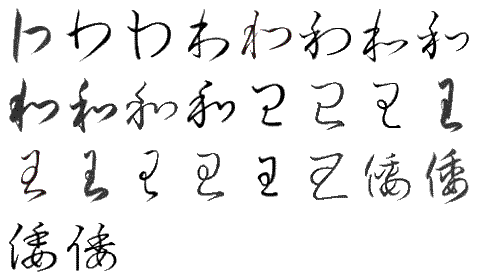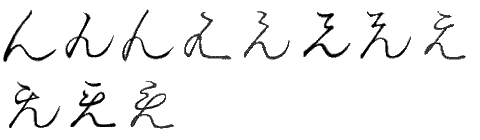�@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
���̒m��@ ���������u�ʌ��v�r���@���{�Ё@
�ړ]���I���@��̍H�����n�����̂ł��傤
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�E�S�V�b�N��
�E������
�E�ۃS�V�b�N��
�E�ܑ�(������/�s����/⽏���/�ꏑ��/������)
�E�v����
�E�^�C�|�X����
�E�t�@���e�[������
�E�菑������
�E��������
�c��Ȑ��̃t�H���g�����݂��Ă��܂����A�Œ���S�V�b�N�̂Ɩ����̂�2�����͊o���Ă����܂��傤�B�S�V�b�N�̂͑������Ȃ������ɂ��������Ȃ��V���v���ȏ��́B�����̂͐��̋���A�[��p�̑����A���̂͂炢������̂������B�S�V�b�N�̂��g�����A�����̂��g�����ɂ���ė^�����ۂ�ǂ݂₷�����傫���ς��̂ňႢ����������ƈӎ����Ă��������ł��B
���S�V�b�N��
�S�V�b�N�̂͑������Ȃ����ߑ������Ă����F���Ȃ�Ȃ��A��������ł��ǂ݂₷���t�H���g�B�ڂ������₷���͋�����ۂ�^����S�V�b�N�̂́A���̓�������L���〈�o���Ȃǂɑ������p����Ă��܂��B�܂��A�����̃S�V�b�N�̂͐������قڋψ�ɂȂ��Ă��܂��B�p��ł� Gothic �ł����C�O�ł͎g���Ă��炸�A�����̂Ȃ��t�H���g�Ƃ����Ӗ��̃T���Z���t�̂����{�Ō����S�V�b�N�̂ɑ������܂��B
��������
�����̂́u���낱�v�Ɓu�͂炢�v�ɂ���ď���t������A�����̉���p����������Ă���̂������B���낱�͕K���E���ɂ����ߕ������E�オ��Ɍ����A�E�オ��̕����������������̂ɒʂ��镔��������܂��B���ׂ͍����̗̂v���͂��낱�ɂ���ċ������邽�ߍׂ������ł��n�b�L���Ɠǂނ��Ƃ��ł���̂Œ����ɓK�����t�H���g�ƂȂ��Ă��܂��B
���ۃS�V�b�N��
�ۃS�V�b�N�̂͐��̒[��p���ۂ��Ȃ����S�V�b�N�̂̂��ƁB�S�V�b�N�̂��x�[�X�ɂ��Ă���̂Ő��̕��͋ψ�ŃS�V�b�N�̂̎��o���̍����������Ă��܂��B�[��p���ۂ��Ȃ邱�Ƃł��炩����ۂɂȂ肨�����������Ȃ��Ȃ�܂��B
�������ܑ�
�����ܑ̂Ƃ͉��L��5�̏��̂̂��ƁB
�E������
�E�s����
�E�ꏑ��
�E������
�E⽏���
���݂ł͞����̂ƍs���̂���ʓI�Ɏg���Ă���A�ߋ��̕����̓������������Č��㊿���Ƀf�U�C�������t�H���g�����݂��Ă��܂��B�ܑ̂́u�a���v�u�`���v�u���j�v����������^�C�g���〈�o���ɗ��p����邱�Ƃ������ł��B
�@�@�@���������̂̔��W
�������͈̂ȉ��̗���Ŕ��W���Ă��܂����B�������̔��W�̐��ڂ́A�b�����������́�⽏��́��ꏑ�́������́E�s���́������́A�ł��B
�@�@�@��������
�����̂͊������̂ł���ܑ̂̂Ȃ��ł͂����Ƃ��V�����A���ׂĂ̏��̂��p�����Ă����{���̂ƂȂ��Ă��܂��B�����̂�s���̂Ɣ�ׂ�Əȗ��◬�������Ȃ��u�����v�u�����v�Ƃ�������ۂ�����A�ǂ݂₷�����ߔF���r�W�l�X�����ł悭�g���Ă��܂��B
�@�@�@�������̂ƍs���̂̈Ⴂ�́H�@
�s���̂ƞ����̂̍ő�̈Ⴂ�͕����ď������A��������~�߂邩�̈Ⴂ�ł��B
�E�s���́F�M�ŗ����悤�ɏ������߁A�q�����ȗ�������
�E�����́F�����A�M�𗣂��ď���
�@�@�@�������̂Ɩ����̂̈Ⴂ�́H
�E�����̌X���F�����̂͒������������̂͌X��
�E�����̕��F�����͉̂������ׂ��������̂͂قړ�����
�E���낱�F�����̂͂��낱���n�b�L�����Ă��鞲���̂̓n�b�L�����Ă��Ȃ�
�@�@�@���M����
�M���͉̂ǐ��┻�ʐ����Ⴂ���̂́A���{�̓`���I�ȕ��͋C�⍂�������o������A�C���p�N�g���������̂Ń^�C�g���ȂǂɌ����Ă��܂��B�M���̂̑����������ܑ̞̂����̂�s���̂��x�[�X�ɂ��Ă��܂��B
�@�@�@����������(�f�U�C���t�H���g)
�������̂͗͋������̂���₳�������̂܂ŁA����f�U�C�����̋������̂ŁA�X�̎咣���������̂Ń^�C�g����S�Ɏg�p����邱�Ƃ������ł��B�f�U�C�����̂̓C���p�N�g���L�邽�ߖڂ������܂����A�ǐ����Ⴂ���̂������̂ő��p����ƃS�`���S�`��������ۂɂȂ�̂Ŏg���ۂɂ͒��ӂ��K�v�B�����g�������Ȃ��Ă��܂��������̂ł����A�����ۂ������₷���̂ŏ��S�҂͎g��Ȃ��ق�����������肵�܂��B�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�����A���ȂɎg���鏑�̂ŁA�]������(�A�W�A���̏��̂Ɋ܂܂��A�����₩�ȂƓ���̕����Ƃ��ẴA���t�@�x�b�g)�Ƃ��ăS�V�b�N�̂̃A���t�@�x�b�g�����݂��邱�Ƃ�����B�������A���m�ɂ����āuGothic�v�Ƃ����ƒP�Ɂu���[�}�����̈ȊO�̕����v�Ƃ����Ӗ������Ȃ��A�u���b�N���^�[�Ȃǂ��܂܂�邩�Ȃ�L���T�O�ł��邽�߁A���m�ł͒ʗp���Ȃ����t�ł���B�u��������r���Ă���v�Ƃ����Ӗ��ł́A���m��sans serif(�T���Z���t)���̂ɑ�������B
������
�c���̑������ϓ��Ȃ̂��S�V�b�N�̂̓����B
�����Ƃ��Ȃ����݂�����{��ł́A������(�A���`�b�N��)�̂��ȂƃS�`�b�N�̂̊�����g�ݍ��킹���A�u�A���`�S�`�b�N(�A���`�b�N)�v�Ƃ����g�������ł���B
���Ăѕ�
���{�ɂ����Ă͏c��Ɖ���̑������ϓ��ŋN�M�A�I�M�_�ɂ�����̂Ȃ����̂��w���B�������̂ɂ�����T���Z���t�̂ɑ�������B�p��ɂ����ăS�V�b�N�� (Gothic Script) �Ƃ����ƒʏ�͒������̃u���b�N���^�[���w���̂Œ��ӂ�v����B�����g�łɂ����ẮA���l�̊������̂��u����(�w�C�e�B)�v�ƌĂ�ł���B
(���{��)�S�V�b�N�̂́A�u�S�W�b�N�v�u�S�`�b�N�v�Ƃ��Ă�A�����ɂ͓��Ď��Łu���|�́v�Ƃ��\�L����Ă����B����ƊE�ɂ����Ắu�S�`�v���邢�́u�S�v�Ɨ������B�g�Ŏw���C���w���ɂ����ẮA��M�ɂ���āw�S�x���邢�w�S�`�x�Ƃ����L������A���Y�ӏ����S�V�b�N�̂ɂ���A�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�B��b�ɂ����Ắu�S�v�݂̂ł͕�����Â炢���߂��A�u�S�`�v�Ƃ����\�����p�����邱�Ƃ̂ق��������B�܂�Ɂu�S�V�v�Ɨ�����邱�Ƃ�����B
���g�p���
�̂��������ł͖����̂��g�����Ƃ���ʓI���������A����Ȃǂ̎��̈������ɑ�ʂɈ�����������ł́A�����ׂ̂̍��������ׂ�₷���Ƃ������_���������B���̂��߁A��ʓI�Ȗ���G����P�s�{�ł́A�����������S�V�b�N�́A���ȕ����𖾒���(�A���`�b�N��)�ɂ������A����ʓI�ɍs���Ă���(������u�A���`�S�`�b�N�v�A�����ăA���`�S�`�Ƃ�����)�B�܂��A�e���r�ԑg�w���j���̏����w�x�ł́u���킲�Ƃɏ��̂��قȂ邱�Ƃɂ���a�������܂�A����ɂ��l�Ԃ������Ă���悤�ȗ}�g���ł��邽�ߎg���Ă���v�Ƃ����ӌ������グ��ꂽ�B�f�W�^������ɂ����Ă͂��łɍ��A����Ă���t�H���g���g���Ă���B
�����Ԃ̃i���o�[�v���[�g�ɗp�����鐔�����̂́A�u�S�W�b�N�́v�ƒ�߂��Ă���B��������ɂ͐��菑�̂�����킯�ł͂Ȃ��A���i�̎��`�̋K�肪�Ȃ��B
�@�@�@���R���s���[�^
�R���s���[�^�̐��E�ɂ����ẮA�S�V�b�N�͕̂W���I�Ȓn�ʂ��߂Ă���B
�����̃f�B�X�v���C�̕\���𑜓x�̖�肩��A�c�扡��̑����̍��ق�E���R(�����̂ł����ΎO�p�`�ɂȂ��Ă��镔��)�̂��鏑�͓̂ǂ݂Â炭�Ȃ�A���ɂ���Ă͂ɂ���œǂ݂Â炢����A�S�V�b�N�̂͏����̃f�B�X�v���C�ł��K�ɕ\���ł������߂ł���B
�W���ŃC���X�g�[�������MS �S�V�b�N�ƌĂ��t�H���g�́A�}�C�N���\�t�g�ɂ��Ǝ��J���ł͂Ȃ��A�ʐ^�A���@�J���̓`�����������[�r�̃S�V�b�N-B���x�[�X�ɁA���R�[���J�����t�H���g�f�[�^�Ƃ��Ďd�グ�����̂ł���B���̌�A���_�C�i�R���E�F�A�ɂ�郊���[�r�̃S�V�b�N�̂��o�ꂵ�����AMS �S�V�b�N�Ƃ͎��`���킸���ɈقȂ�B
�����j
�^�C�|�O���t�B�Ƃ��Ă̘a���S�V�b�N�̂́A���o���Ȃǂł̋�����ړI�Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂Ƃ����B
�S�V�b�N�̂����m�ɂ��o���������͖��炩�łȂ��B�������A�w�����V���œǂ�20���I�x(1999�N1��1�����s�́w�m�b���x�̕ʍ�)�Ɍf�ڂ���Ă��钩���V���̋L����ǂނƁA1919�N1��1���t�̃��F���T�C�����ɂ��ĕ�L���Łu�u�a���v�̕������������Ȃ�����S�V�b�N�̂ŕ\�L����Ă���̂��m�F�ł���(p38���)�B�܂��A1936�N8��12���̃x�������I�����s�b�N�ɂ����鐅�j�̋L���ŏ������Ȃ�����S�V�b�N�̂Ō��o����t���Ă��邱�Ƃ���A���̍��ɂ͎g����@������Ă������Ƃ��M����B
�����Ă��̈�����ɂ����āA�{���������̂őg�܂�A���̒��Ō��o��������A�����������Ƃ���ɃS�V�b�N�̂��g��ꂽ�B����ɂ́A�c��Ɖ���̍����傫���A�����̃��[�}���̂ɂ��[�����閾���������{���p���̂Ƃ��ĉǐ��ɂ�����Ă�������A�C���L�̂��ʂ��L�����o�I�i�����̍����S�V�b�N�̂̓������������B
�����������������̎���ɂ́A���{��ȂNJ������g������ɂ����Ă̓A���t�@�x�b�g�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǑ����̊��������낦�˂Ȃ�Ȃ����߁A�������ň���̂悤�ɑ���̏��̂����A���邱�Ƃ͓���A��قǑ傫�Ȉ�����ȊO�ł͖����ƃS�V�b�N�̂݁A�Ƃ����Ƃ��낪���������B���̂��߁u�{���̓~��(����)�A�����̓S�`�v�Ƃ������{��g�ł̗��������̂悤�Ȃ��̂�����(��������u�����̂悤�ɑ��ʂȏ��̂��g�������v�Ƃ������v�͂�����)�A���オ�����Ďʐ^�A����DTP�������������̏��̂����݂Ɉ�����悤�ɂȂ��Ă��A���̃V���v���ȃ��[���͕ς�邱�ƂȂ������Ă���B
DTP���t�����ɂ����Ă��A������t�H���g�͎�����̃����E�~��L�ƒ��S�V�b�NBBB�����ł���A�f�U�C�i�[�����͂��̐���̒��ňӏ������炵���B����͊m���ɎʐA�̑��ʂȏ��̂��猩��ΐ���ł͂��������A��������������čH�v���Ă�����Ԃɔ�ׂ��ꡂ��ɑ傫�ȗ����Ă����B���݂ł͈�����t�H���g���͑I���ɖ����قǂɑ������Ă��邪�A����ł���͂薾���ƃS�V�b�N�̑g�ݍ��킹�͉����Ƃ����B�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
������
�����Ƃ��Ē������邽�߂ɁA��{�ƂȂ鞲���̏��v�f��P�����������̂��蒅���Ă���B�c��Ɖ���͂��ꂼ�ꐂ���E�����ŁA�����ނˏc��͑����A����ׂ͍��B�������u�S�v��u���v�Ɍ�����ɂ₩�ȓ]�܂ł́A�ǂ�����قړ��������ƂȂ�B�ق��ɂ́A����̎n�߂̑ł����݂�I���̃E���R�A�c��̂͂ˁA�܂����E�̂͂炢�Ȃǂɞ����̓������c���Ă���B���߂��ւ�₵��ɂ傤�ȂLjꕔ�̕����ł́A�ꏑ�Ɨގ��������̂�������B
�����Ƃ��Ă̗������玚�`�������`�ɋ߂Â������߁A�M���̂Ƃ͗v�f�̂܂Ƃߕ����قȂ�A���ʂɂ����ē_�悪�\�Ȍ���ϓ��ɔz�u�����B�����������ʂ���t�ɑ傫���g����@�́A�������T�C�Y�ł̉ǐ������シ�邾���łȂ��A���͂��c��������ɑg�ނ��Ƃ��s����悤�ɂȂ�����́A������̕����֑g��ł����R�Ƃ������ʂ���Ƃ����_�ŁA����ɗL���Ȃ��̂ƂȂ����B
�@�@�@�����̖��
�����̂͊����̏��̂Ƃ��Đ����������߁A���������������̂��Œ艻���₷���B�l�����̂��߂Ɏ菑�����̂Ő����Ȃ��̂Ƃ��ꂽ�����Ƃ̎��̂̑��Ⴊ���������B�����āw�Nꤎ��T�x�ɔ����鎚�̖̂�肪����A�����̂̎��̂��߂�����͂���炪���킳���ċN�����Ă���B
�ؔň���⊈���ɂ�銈�ň���ɂ����������̂Ƃ��Đ����������̂́A�����̒ʗp���̂܂��͐����̂f���ėl�������ꂽ���̂ł������B�Ⴆ�ΕM�������͞����ł͉^�M��Ōy���Y���邾���̂��̂ŁA�����̂̂悤�ȗl�������ꂽ���̂ł͂Ȃ��B
���̂ق��ɂ���������ނ�(艹)��3��ɂ��閾���̂́A�����̂������Ƃ���4��ɂ���̂ƑΗ������B�����Ă����̂���(禸)��1��ڂ̎n�߂̈ʒu��2��ڂ̎n�߂̈ʒu�������ł��閾���̂́A1��ڂ�2��ڂ�����Ō���点�鞲���̂ƑΗ������B�w�Nꤎ��T�x�ɂ����āw���������x�Ȃǂɑ���V���ɒ�߂�ꂽ�����͂����Ƃ͈قȂ��Ă����B����܂ł́u�B�v�Ɓu誁v�̂悤�Ȏ���̍\���v�f�̕s���Ő���܂��͐������̂���ʂ��Ă����̂ɉ����āA���̂̕ϑJ�Ƃ��Ēʗp���Ă����u�]�v�̓_��̌������w�����x�̏�⽂̂��̂ƈقȂ�̂���Ƃ��āu�\�v�𐳎��Ƃ���ȂǂƂ����B
����������ł���ʓI�ȏo�łɂ����Ă͒ʗp���̂��嗬�̂܂܂ł��������A�����։��Đ��͂�����A�������������̊J�����n�߂����A�w�Nꤎ��T�x���Q�Ƃ��Ċ��������삵���B�ꕔ�ɂ����Ēʗp���̂��g���邱�Ƃ����������A����Ȃǂ��w�Nꤎ��T�x�̂܂܂ł������B�����̊����Z�p���]���̋Z�p�Ɏ���đ���A���������ɂ��Ɩ����̂�����Ō�������̂ƂȂ�ƁA����܂ł̒ʗp���́E�����̂Ƃ̊u���肪�傫�Ȗ��ƂȂ����B�Ⴆ�Ξ����̂ł́u�g�v�̏㕔�́u�y�v�ɂ���u𠮷�v�Ƃ��āA�u���v�́u�͂�����(��)�v�������������A�V���ɓ����Ă��������̂̎��̂𗝗R�ɂ���炪���Ƃ����ȂǁA�M�L���̂ɑ傫�ȉe����^�����B
�M�������Ȃǂ́A����������ŕK�v���Ȃ��Ƃ���邱�Ƃ�����B�������p�̋K�͂ł͂������Ȃ����ꍇ������A�������ɉ��߂����̂�������Ă���B���{��1949�N4���ɓ��p�������̕\���������ꂽ�ہA�菑���̕\�ł��������ߕM�������Ȃǂ��Ȃ������B���������āA�Ȃ��̂��������Ƃ��āA��������蒼���Ǝ҂�A�V���̂ň������̂ɂ�����s�v�Ƃ���ڋq���������B���������p�����\�O�̊�����A�ꕔ�����Ǝ҂ł͕M�������Ȃǂ͎c���ꂽ�܂܂ł������B����Ȃǂł͐��������̂̎w������ɂȂ�Ƃ��Ė����̂��g�p���Ȃ�������A�g�p�����Ƃ��Ă��u��v��u���v�Ȃǂ̐܂�Ȃ���̕����A����ɂ傤�������ƈقȂ�Ƃ��ē��ʂɕς����肵���B
��������p�����Ȃǂł́A���̂悤�ȕM���������̌`��ɉ����A�_��̕t��������邩�Ⓑ�Z�ȂǂƂ����ׂ������ق��u�f�U�C�����v�ƌĂсA��瓝��Ȃǂ���܂ł��Ȃ��u���v�Ƃ��āA����͋����łȂ��Ƃ��Ă���B���{�Y�ƋK�i(JIS)�Ȃǂł�����ɏ]�����A����̏�Ȃǂɂ����ďȂ݂��邱�Ƃ͏��Ȃ��B
���g�p���
�����͎̂�Ɉ���ɂ����āA�{�����̂Ƃ��Ďg���A��r�I�������T�C�Y�ł̎g�p�������B����A���̃f�U�C����̓��������āA�傫���T�C�Y�ł��g����B���ɑ����E�F�C�g�̂��̂́A�R���g���X�g�������C���p�N�g���v������錩�o����L���Ȃǂ̏�ʂŎg�p����邱�Ƃ�����B
20���I�I�Ղɂ̓S�V�b�N�̂Ŗ{����g�ގG���Ȃǂ̏o�ŕ��������Ă͂��邪�A���ȏ��̂��g���鋳�ȏ��ȊO�̏��Ђ́A�قƂ�ǖ����̂̓Ɲ���ƌ�����B����ăt�H���g�𐧍�E�̔�������(�Â��͊�����^�ƎҁA�̂��ɂ͎ʐA�@���[�J�[�A�����ăt�H���g�x���_�[)�́A�قڕK�����C���i�b�v�̒��j�ɖ����̂𐘂��Ă���B�����������Ƃ���A�����̂͊��������̏ے��Ƃ��đ������邱�Ƃ�����A���Ă͖����̂őg�܂ꂽ���́E���ʂƂ́A���Ȃ킿��������o�R���Ă������̂ł������B
1980�N��̓��{�ꃏ�[�v���̕��y�A�����p�\�R���̕��y�ɂ��͕ς���Ă���B�p�\�R���ŕ����������ɍۂ��Ă������̂̃t�H���g��OS�ɕt�����邽�߁A�����������@��E�\�t�g�E�F�A���g�p����N�����������̂őg�܂ꂽ�������쐬�E����ł���悤�ɂȂ��Ă���B����ŃE�F�u�u���E�U�ȂǁA�����ς��ʏ�ŕ����������ꍇ�ɂ́A�����̂͂��܂�p����ꂸ�A����̂��V���v���ȃS�V�b�N�̂��L���p������B����͉𑜓x�̒Ⴂ��ʂł́A�E���R�Ȃǖ����̓Ɠ��̑������M�U�M�U�ɕ\�����ꂽ��A�c���̐��̕����s����ɂȂ肩�����Ȃǂ��ĉǐ��˂邽�߂ł���B
�S�V�b�N�̂قǑ����͂Ȃ����A�S���ݔ�(�w�E�ԗ���)��LED�\���@�ł��L���g���Ă���B
�����j
�����͖̂ؔň���⊈���ɂ�銈�ň���ɂ��������p���̂Ƃ��Đ������Ă���A1670�N�ɂ͂��łɑ��݂��Ă����Ƃ݂���B�ؔň���́A���������ŕ������Ă������A�����͋Ȑ��������A����̂Ɏ��Ԃ������邽�߁A�k�v����̈���̗����ɂ��A����ɒ������̂̕����������v���̂ւƈڂ��Ă������B�v���̂�����ɗl�������A���ォ�琴��ɂ����Ė����̂Ƃ��Đ������A���T��A�l���Ȃǂ̈���ŗp����ꂽ�B����ɓ���Î��̌������ʂ��Ƃ�܂Ƃ߂�ꂽ�w�Nꤎ��T�x�͖����̂ō����A���̖����̂̏��̂̓T���Ƃ��ꂽ�B�w�Nꤎ��T�x�́w���������x�Ȃ�⽏��̂�ꏑ�̂ŏ����ꂽ�����𖾒��̂ŏ������������߁A�`���I�ȏ������`�Ƒ傫���قȂ������`���Ȃ��ꂽ�B
19�����ɐ�������̉����A���[���b�p�����������ɐi�o����悤�ɂȂ�ƁA�܂������ւ̋�������A���̕��K�ȂǂƋ��ɕ������Љ�ꂽ�B�����i�o���֎�����ړI�������āA�i�|���I��1���ƃp���}���ɂ���Ă��ꂼ����ꂽ�w��̋F��x�Ƃ����{�Ɏg��ꂽ�����̓t�����X�����������W�����o�b�e�B�X�^�E�{�h�[�j(�C�^���A���)�̈�����Ȃǃ��[���b�p�̈�����Œ���ꂽ���̂ł���B���̌㒆���������n�܂�A������̎��T�╶�@���Ȃǂ̈���̂��߂Ɋ��������̊J�����K�v�Ƃ��ꂽ�B���̎���͒��ڂ̕z��������������Ă��Ȃ������������⏬���q�ł̕z���͋�����Ă������߁A�鋳�t�ɂ��|�n�߂�ꂽ�B���A�W�A�Ɋ��ɑ��݂������ŋZ�p�𗘗p�����A���������̋Z�p����������Ŏg�����B�����Ă�����������������ɂ���ɓ������Ė����̂�I�������B����͉����̈���ŕ��ʂ��������[�}����(���������̊J���͎�ɉp���Ă̐��͂����S�ł�����)�ƃe�C�X�g�������Ă������߂Ƃ�����B�鋳�̏�ʂł́A�����̓��[���b�p�Ŏg���Ă������̂��g�p������A���n�Ŏg�p����̂ɖȂǂɊ����ɒ����Đ��삵���B
���[���b�p�Ŏg�p����Ă������̂ŁA���߂Ă܂Ƃ܂����ʂ����ꂽ�̂̓��C14���̖��ɂ��t�����X����������̖؊���(1715–42�N)�ł������B���̊����͂̂��A�i�|���I��1���̒����ꎫ���Ҏ[�̂��߂Ɋg�[���ꂽ�B���̌�W�������s�G�[���E�A�x�������~���U�́w�����[�ցx�Ŏg��ꂽ�����́A���������ł������B�؊����������������Ƃ��ɖ����̂ł������B19���I���t�A����������̃}���X�����E���O���� (Marcellin Legrand) �͒����̌ÓT�̈����ړI�Ƃ��Ċ���������˗�����A�����̂̕��������삵���B���O�����̕��������ł́A�Νӊ��r�����ꂼ�ꕪ�����āA��菭�Ȃ���������ő�����d�����Ƃ������f�U�C���͗ł������B
�L���X�g���鋳�ł́A��Ƀv���e�X�^���g���`����S�����B�ނ�͓`������n��̌���œ`�����邱�Ƃ��d�����A���̂��߂Ɋ��������̊J�����d�v�������B���[���b�p����A�Ⴆ���O�����̕��������Ȃǂ̊��������邱�Ƃ����������A���n�Ŋ������J��������̂������������B�T�~���G���E�_�C�A (Samuel Dyer) �ȂNJ��Ⴉ�����邪�A���̑�\��͏�C�́u�p�؏��@�v��u���؏��فv�ł���B�p�؏��@�� London Missionary Society Press �̊��ŁA�ϓ֓`���� (London Missionary Society) �̐鋳�t���ݗ��������̂ł���A���؏��ق� American Presbyterian Mission Press �̍Ō���̊��ꖼ�̂ŁA���k���V��� (American Presbyterian Mission) �̈�����ł������B���Ɍ�҂ł́A6��ْ��ɃE�B���A���E�M�����u��(�������)������A�X���[���E�p�C�J(small pica = 11�|�C���g�B���ʂ̃p�C�J(pica)��12�|�C���g)�̃T�C�Y�Ȃǂ̊����̉������s�����B�����̃~�b�V�����v���X�̊����͉��Ă��痈���Z�p�҂��w�����Đ��삳�ꂽ���������ŁA�T�C�Y�������̊����T�C�Y�Ɋ�Â����̂ł������B�����̑傫���́A����̑傫���݂̂����A�傫�������珇�Ɂu1���v�A�u2���v�c�c�ƌĂ�ł����B
���؏��ق͈ꎞ��C�ŗ������ւ������A���؏��ق̊�����̔����鏤���قȂǂ̋Ǝ҂�����A�p�Ƃ���B
�@�@�@�����{
���{�ɖ����̂������Ă����͖̂�����ɕ��T��l���Ȃǂ�A���������̂��Ĕł������Ƃɋ���B���ɑ�K�͂Ȃ��̂́A���@�@�m���E�S�ᓹ���T�t�ɂ���،o�̊J���ł������B���̌�������̗p�r�ł͖����͎̂g���Ă������A�������g����ق��������A��ʂɂ������Ắu��Ɨ��v�ƌĂ��A�ȑ̂̈�킪�嗬�ł������B
�咹�\��ɂ�閾���̂ł̊����J���͂��������A���������ɂ����閾���̗̂��j�͈�ʂɖ{�؏���������S�H���ɊJ���ꂽ���œ`�K���ɂ����āA���؏��قɗ��Ă����E�B���A���E�M�����u�������ق��u�K�����ہA�M�����u���������Ă��������̂�{�����̂Ƃ��Ďg�����������ƂɎn�܂�B�����A���؏��ق̊����ɂ����������͑��݂��������܂�N�I���e�B�������Ȃ��������߁A�{���u��z�V�m�����������v(��̓����z�n���Ő�����)�𗧂��グ�A�A�ȑ̂ł��������������ꕶ�����藣�����������J������B
�����������珺�a�ɂ����Ċ����̃T�C�Y���A�����J���E�|�C���g���ֈڍs�����B�x���g����^�����@�����ĐV���Ɋ������������鎖�Ⴊ�o�������B�ꎚ���ɕ��^��A�d�ٖ@�ŕ�^�Ă������犈�������X�^�d�ٖ@�Ƃ͈قȂ�A�x���g���͈ꎚ�������p�^�[���𐧍삵�������ɋ@�B�I�ɏk�ڂ��s���ĕ�^����̂ł������B�x���g���̓����̍ہA���ׂ����`��������B
���a�ɓ����Ďʐ^�A���̊J�����s���A����ƂȂ�ʌ��̐Έ䖾���̂͒z�n���ł�12�|�C���g�����𗘗p���č��ꂽ�B�Ȍ���ʐA�ł͊�������̖|�����̂��J���E���p����邱�Ƃ��������B�ʐA�ł̓t�@�~���[���`������A���ɑ����E�F�C�g�̎��`�ł́A�������ɒ[�ɍׂ��A�c�����ɒ[�ɑ������ꂽ�B
1949�N�ɓ��p�������̕\�����������ƁA�e�Ђ͐V���̂ɂ�������̂ɕύX���n�߂��B���̎��A���p�������̕\�̎��̂ɕM�������Ȃǂ̃G�������g���Ȃ������̂��A��������̕ύX�̂����Ɣ��f���A�V���̂ւ̕ύX�Ɠ����Ɏ�菜����邱�Ƃ��������B����������͓��p�������̕\�̎��͎̂菑���ł��邽�߂ɕM���������Ȃ��̂ł���A�M�������Ȃǖ����̂ɓ��L�̃G�������g���Ȃ��͉̂������Ƃ̔ᔻ���������B
���{��f�W�^���t�H���g�̏����̓r�b�g�}�b�v�t�H���g���g���Ă����B���̂�JIS�ɏ������邱�ƂɂȂ邪�AJIS X 0208��2���K�i(�ʏ�JIS83)�ɂ��A�����̎��̕ύX�����ւ����s��ꂽ���Ƃō������������B�A�E�g���C���t�H���g�����p�������ƁA�����T����PostScript�t�H���g�Ƃ��ă����E�~���𓊓��������Ƃ��͂��߁A�����̉�Ђ������̕����E�|�����̂�V�K���̂��J�����Ďs��ɓ��������B
�@�@�@������
���{�Ŋ��ň������������ꍇ�A�����̒������K�v�ƂȂ�B
����20�N��A�����̂̉����̏o���_�ł��蓌���z�n���Ő������ɂ�鏑�́A�u�z�n�̑O���܍��v�����������B�������A����7�N�ɂ͎g���Ă������̂Ƃ���������݂���B�����ɍ��킹�邽�ߎ菑���̃j���A���X���O���L���������߂Ă���B����30�N��ɂ́u����܍��v���������A�����̂̊�{�ƂȂ����B
����Z�p�̌���������̎��̗ɔ����A1910�N�����當�����ׂ�����X�������܂��B��ʂ��V���[�v�ɍ��肠����Ƃ������Ƃ���n�܂����B�����ē����푈�Ɍ������ɂ����p�����ɂȂ�A����܂ł̕����ł͟���Ŏg�����ɂȂ�Ȃ��Ƃ����̂����̌X���ɔ��Ԃ��������B�����ƃJ�i�����h�́u�����̎��F���̌���v�Ȃǂ̓�������A����������傫���`��鏑�̂����܂��܂Ɏ��݂��A����܂ł̏��Ԃ�Ȏ�(�����̒��̔�����������������������)����A�����L���u���邢�v�����쐬�����悤�ɂȂ����B
1929�N�Ɏ��p�����ꂽ�ʐ^�A���@�ƁA1950�N��ȍ~���{�̋��������̐����ň�ʉ������x���g����^�����@�ł́A��̌������畡���̃T�C�Y�œ������`�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B����ɂ��A�ʐA����ɓ������`�ő������قȂ鏑�̌Q(�t�@�~���[)�����������B
1951�N�A�ʌ��ɂ��Έ䖾���̂̃j���[�X�^�C�����Ȃ��������ꂽ�B���̍�҂̐Έ�g�̒킪���ȏ���Ђɋ߂Ă������Ƃ�����A���ȏ��̗̂���������̂ƂȂ��Ă���B�܂��A���̏��̈ȍ~�����̂̉����Ƀj���[���Ȍn�����������B
���{��̕\�L�ɂ����ĉ����̔�d�������ɂ�āA�����t�H���g�̏d�v�������܂�A����������ς��Ďg���Ƃ�������������B��Ƃ��ẮA�����T���̃t�H���g�����E�~���̉������u�����E�~�� �I�[���h���ȁv�ɒu�������Ďg�p������̂Ȃǂ�����B�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
1963�N�̐Έ�g�v��A�����I�ȏ�ɂ킽���ĎВ��Ƃ��ČN�Ղ����O���̐Έ�T�q(1926�N9��28�� - 2018�N9��24��)�̃����}���o�c�̂��ƁA�ʐA�S������1980�N�㔼�ɂ͊֓���8���A����6���̏��̐�L�����ւ�A�����̉��i�Ŏ蓮�ʐA�@��1��1000���~�A�d�Z�ʐA�@��1�䐔�疜�~����1���~�](SAPTRON-APS5H�A1981�N)�Ɠ��Ƒ��Ђɔ�ׂĂ������ŁA����ɑg�ł���o�͂܂ł̐�p�@��ꎮ��̔����邲�Ƃɉ��P�ʂ̔�����m���ɓ����鎩�Ћ@��̔̔��ŔN����300���~���A�]�ƈ���1200�l�������ƂƂȂ��� �B
������1990�N��A�ʐA�ɂȂ����쐫�̗ǂ��ƒ�R�X�g�ōL�����y����Macintosh�ɂ��DTP�ɂ͔w�������A��1�������ƂɃ��[�U�[����g�p�����ł��A���z�Ȏ��А��@��̔��ɂ�锄�オ�����߂鎩�ЌŗL�̓d�Z�ʐA�V�X�e���ɌŎ��������ߋƐт͋}���Ɉ����B�ߋ��̗��v��~�������S���~�ɏ�鑽�z�̓������ۋ������������܂܁A2003�N�ȍ~�A�傫�����ƋK�͂��k������ �B
��������̃��g���o�g��1963�N����30�N�]�ɂ킽�蕶������ӔC�҂Ƃ��Ďʌ��̐��X�̏��̂̐����ďC����|���A�̂��������[�J�[���̂Ƃ���C���^�G���W�j�A�����O(���E�C���^)�Ō���w���ɂ����蓯�Ђ������L���̃f�W�^���t�H���g�x���_�[��1�ЂɈ�Ă����̐v�m���{�a�v(�C���^�ږ�)�̂ق��A�ʌ����\���鑕�����́u�X�[�{�v�݁A�̂��Ɏ����H�[�В��Ƃ��āu�q���M�m�����́v(1993�N)�Ȃǂ𑗂�o������ؕ�(1998�N�v)��A���c�ӈ�(�ӊ쓰)�A���я�(�ƃ��m�^�C�v)�ȂǁA����̃f�W�^���t�H���g���ɍv�����钘���ȏ��̃f�U�C�i�[��y�o�������Ƃł��m����B

 �@
�@
���������g�ł̌��������z���邱�Ƃ��ł����A��ɒ[���p�Ƃ��Ĉ���ꂽ�蓮�ʐA�@�̌��_���R���s���[�^�ŕ₤���ƂŁA�{���g����������D�����Ƃ�ڎw�����ʐ^�A���@�u�d�Z�ʐA�v�́A���z�Ȑݔ����������[�U�[�ɉ\�ł��������x�o�ϐ����̒ǂ����̂��ƁA�ʌ��́uSAPTON�v�V�X�e������������`�ŁA���̐V���Ђ�o�ŎЁA�����Ђ��ڋq�̒��S�Ƃ���1970�N�ォ�畁�y���{�i���B�u�ʐA�v�͓o�ꂩ�甼���I���o�Ă悤�₭�g�ł̎���ƂȂ������A�n���̈����Ђł͌o�c�K�͂ɔ�ו��S�����܂�ɂ��ߑ�Ȃ��߁A1971�N�̒��쌧����ɁA�����Ђ������Ŏ������o�������ēd�Z�ʐA�V�X�e�������L����u�d�Z�ʐA�����g���v���ݗ������قǁA���z�̔�p���ʐA�@���[�J�[�Ɏx�����K�v���������B

1980�N��A�č��̃x���`���[��ƃA�h�r�V�X�e���Y(���E�A�h�r)�́A�p�[�\�i���R���s���[�^�œ��{��g�ł��s��DTP���\�z�ɕs���ȓ��{��PostScript�t�H���g�̐����ڎw���Ă����B�A�h�r��1986�N�A�����g�b�v���[�J�[�ł������ʌ��ɒ�g�������|�������A�Ⓒ���ɂ������ʌ��͂�������ہB�ŏI�I�ɃA�h�r�͋ƊE2�ʂ̃����T���ƒ�g���A1989�N�A�����T���́u�����E�~��L-KL�v����сu���S�V�b�NBBB�v��PostScript�t�H���g�����ē��ڂ����v�����^�[�uLaserWriter II NTX-J�v���A�b�v���R���s���[�^�W���p�����甭�����ꂽ�B�����1990�N��ȍ~�̋}���ȓ��{��DTP���y�̒[���ƂȂ����B
����A���̂���̎ʌ��͓d�d���Ж��c��(1985�N)�ɔ����d�b����̃f�[�^�ʐM�[���@��J�����A1987�N�ȍ~�A�e�o�͑��u��d�b����Ŏʌ��̃T�[�o�ƌ��сA��1�������ƂɃt�H���g�����^����������]�ʉۋ������B���̉ۋ������V�X�e���̐����ƁA���z�ȓd�Z�ʐA�@�̐����̔��ŁA1991�N�ɂ͔N�Ԕ��オ�ߋ��ō���350���~�ɒB���� �B
�������o�u������̒��A�֘A�@����܂߂��ꎮ�̓����Ɉ����Ă����疜�~���牭�P�ʂ̓������������Ȃ��d�Z�ʐA�ɔ�ׁA���|�I�ɒ�R�X�g�Őݔ��𐮂��邱�Ƃ��ł��A�@�푀����̃I�y���[�^�[����邱�ƂȂ��f�U�C�i�[���g�̎�ɂ������I�ȍ�Ƃ��\�ŁA�t�H���g���邽�߃����j���O�R�X�g���Ⴂ�Ƃ������X�̗��_������DTP�́A���̕W���v���b�g�t�H�[���ƂȂ���Apple���p�[�\�i���R���s���[�^�uMacintosh�v�ƂƂ��ɋ}���ɕ��y���A�ʌ��̋Ɛт͏u���ԂɈ��������B
�ʌ��̓t�H���g�����^���������ɉ����A�g�Ńf�[�^��PDF�o�͂���V�@�\�ɂ��]�ʐ��̍��z�Ȏg�p�����ۂ��Ȃǂ��Ĕ���ێ���}�������A���[�U�[�̎ʐA�����Macintosh�ւ̈ڍs�̗���͂Ƃǂ܂�Ƃ����m�炸�A1998�N�ɂ͔���175���~�̎ʌ��ɑ��APostScript�t�H���g���Ƃɒ��͂��郂���T��������187���~�ƂȂ�A�����T�����N���x�[�X�Ŏʌ����� �B

���̊ԁA1989�N�ɂ͗�ׂؕ⏬�я͂ȂǁA�����J�����̎�̓f�U�C�i�[����ĂɑގЂ��A���̌��1990�N�㖖�ɂ����ăf�U�C�i�[�̑ގЂ����������B
�n�ƎҐΈ�g�̎O����1963�N���烏���}���o�c�𑱂��Ă����В��̐Έ�T�q���g�́A�v����܂ŏ��̐���ɂ͈�x���g��������Ƃ͂Ȃ��������A�����J���̃f�W�^�����ɔ������[�N�X�e�[�V������ł̌����C����Ƃ��\�ɂ������Ƃ��镶���J�����̗v�]�����ۂ��A�f�W�^�������������f�[�^���ēx�A�i���O�o�͂����ƂŏC������]���̍H������𖽂����B�n��70���N��1995�N�Ɍ����ĊJ�����������{���S�V�b�N�t�@�~���[�́A�Έ�̗v���Ńf�U�C���R���Z�v�g�̑�ύX��]�V�Ȃ����ꂽ���Ƃ��d�Ȃ�A70���N�ɂ͊Ԃɍ���Ȃ������B�Έ�͂܂��A���̎����ɒ�Ă��ꂽ�ʌ����̂̎��ЃV�X�e���ȊO�ł̎g�p�J���Ă��p������ �B

�ʌ���2000�N�A�d�Z�ʐA�V�X�e����p�̐V���̂Ƃ��Ė{���S�V�b�N�t�@�~���[���̗\�肩��5�N�x��Ŕ��\�������A���ʂƂ��Ă��ꂪ�ʌ��Ō�̐V���̂ƂȂ����B����͑ΑO�N��Ŗ��N��10〜30%�̗������݂����������߁A2003�N�ɑ����ސE��W���s�������ʁA�g�ŃV�X�e���J���ɂ�����\�t�g�J�������56�l����3�l�A���i�̔�����|����c�ƕ����46�l����1�l�ɂ��ꂼ�ꌃ�����A���Ƒ̐��͗�ׁE����ƕ��݂̋K�͂ɓ]�������B
2006�N�̔���͋@�B�̔�5500���~�A�@�B�t���i�̔�1��4800���~�A����S�̂�7�����߂�t�H���g�����^��������9��1700���~�ɂƂǂ܂�A�N���K�͂�1990�N�㖖�̂��悻10����1�ƂȂ������A�ʌ��̖{���̎��ƂƂ͖��W�ȃA���o�C�g���x�̓��E�d�����ЊO����W�ߐE��ŏ]�ƈ��ɏ]�������Ȃ�����A��ƂƂ��Ėڗ��������ƓW�J�͍s��Ȃ��܂܁A�Ő����ɒ~����400���~���������ۂ����͎���������������Ƃ����ٗl�Ȍo�c�𑱂����B2007�N7�����_�̏]�ƈ�����109�l�ŁA�����H�ꏊ����40�l(��ʍH��30�l�A��z�H��10�l)�A�n���c�Ə�������9�l�ƁA�Ő�����10����1�ȉ��ƂȂ�A�܂��Ȃ�100�l�����荞�B������i�݁A���N5�����݂ŏ]�ƈ��S�̂�7���ȏオ50�Έȏ�ł����� �B
�Ȍ�A�p�[�\�i���R���s���[�^�ɂ��e��o�͂���ʉ����A�@��V������ʐA�p��掆�̋����I��(2013�N10��)�Ȃǂɂ������ʐA�@�Ƃ̒u���������i���ƂŁA��ʏ��ƈ���A�����ƊE�ɂ�����e���r�ԑg�̃e���b�v�A�e�퉮�O�f�����ȂǂōL���g���Ă����ʌ����̂̂قƂ�ǂ͎p���������B
2018�N�A�����I�ȏ�ɂ킽���\������В��̍����߂��Έ�T�q���ݔC�̂܂�92�Ŏ��������B��C�В��ɂ͎��Y�Ǘ����s���Ă���ږ�ŗ��m�Ŏ�����̓쑺���Ƃ��A�C���A����ԂƂȂ��Ă������H��Ȃǂ̗V�x�n�������������ɊJ�n�����B���N�ɂ͋���z�H��(��ʌ���z�s)�̎{�݂���̂��Ē߃����s���̏��L�n�ƍ��킹�ďZ�F�����ɔ��p���A���Љ^�c�̕����{�݁uSOSiLA��z�v(2019�N2���v�H)���i�o�B2020�N�ɂ͋���ʍH��(��ʌ��a���s)���ʌ��������҂ƂȂ��ĉ�̍H�����J�n�����B�Ւn�͐H�i�X�[�p�[�̃��I�R�[�֒��݂���A2021�N10���Ƀ��I�R�[���Ǘ��E�^�c���鏤�Ǝ{�݁uthe marketplace �a���v�ƂȂ����B2020�N8���ɂ͓쑺�ɉ����A�O�N7���Ɏ�����ɉ����������̊}���`������\�����擾���В��ɏA�C�����B
 �@
�@ �@
�@
������OpenType���̌��f�[�^�ƂȂ���C�t�H���g��^�V���j���t�H���g�́A1980�N�㏉���̌Â��Z�p�Ɛv�����Ő��삳�ꂽ���̂ŁA�e�Ђ̌��s�f�W�^���t�H���g�ɔ�ׁA�����ɑ���A�E�g���C���̐��x���Ⴉ�������߁A�ʌ���1�������f�[�^���C�������Ƃɒ��肹����Ȃ��Ȃ�A2011�N�����߂��Ă��̔���������̏�Ԃ������� �B
����ɎʐA����̊������������ł�Adobe-Japan1-3(OpenType Std)�����ɂ����Ȃ�Ȃ���肪����A�ʌ�������ƊE�̎��Ѓ��[�U�[�ɕ��������s�����Ƃ���A�Œ�ł�Adobe-Japan1-4(OpenType Pro�A2000�N3�����\)�ȏ��K�v�Ƃ��錻��̏��ƈ���ł́A�v�����[�X�ɗp����ɂ͓���Ƃ̎w�E���Ȃ��ꂽ�B����ƊE�����߂�AJ1-4�ȏ�ɂ���ɂ́A�ʐA����ɂ͂Ȃ������s�����̕������e���̂��ƂɐV�����f�U�C�������Ƃ��������Ȃ�����A�ʌ����珑�̊J���̃f�U�C�i�[�����������Ċ���10�N���܂�̔N�����o�߂��Ă���A����2016�N������Ō�Ɂu�ʌ��t�H���g�v����悤�Ƃ��铮���͂�������r�₦���B

2021�N1��18���A�����T���͎ʌ��В��E�}���`������у����T���В��E�X�V���F�̑o���̃R�����g�ƂƂ��ɁA���Ћ������ƂƂ��Ďʌ����̂�OpenType�t�H���g�J����i�߂邱�Ƃɍ��ӂ����Ɣ��\�����B�蓮�ʐA�@����1���@�J������1924�N�ɐΈ�g�ƐX�V�M�v���s�����M���ʐA�@�����\��100���N�ɓ�����2024�N���珇������Ƃ��Ă��� �B
���̊J���̓����T���Ɠ��Ўq��Ђ̎����H�[�������ōs���A�ʌ��o�g�̏��̐v�m�A���C�C(�����H�[)���S�̊ďC���s���B�N���E�h�^�t�H���g�T�[�r�X�uMorisawa Fonts�v��2024�N�ɒ���\��̏��̂́A�w�Έ䖾���x�t�@�~���[(�u�j���[�X�^�C���v����сu�I�[���h�X�^�C���v�A�E�F�C�g�e4��)�Ɓw�Έ�S�V�b�N�x�t�@�~���[(�E�F�C�g5��)�̌v13���̂Ƃ��Ă��� �B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�ʌ��͍��z�ȓd�Z�ʐA�@�̔̔����}�L���Ă���1975�N(���a50�N)���납��1988�N(���a63�N)�ɂ����āA���Ђ̎���̂قƂ�ǂ������⏬�؎�ōs���Ă������Ƃ𗘗p���A�c�ƕ���̔��ォ���菜���������N10���~�O��A�o���S���������n���q�ɂ̋��ɂɉ^�э��݁A�����Ƃ��Ē~�����Ă����B����ɋ}���ȋƐш������n�܂���1992�N(����4�N)����́A�Ԏ����Z������悤�ƁA������N��5�A6���~���x�o���ɖ߂��A�������̂ňꎮ�̉��i��1��5000���~�̈���@��Ȃǂ�̔��������Ƃ��A�ˋ�̗��v���v�サ�Č��Z�����Ă��� �B
���o���_�ŒE�łɊւ��Ă͎������������Ă������߁A���Œ��͔������ꂽ����������Ў��Y�Ƃ��ČJ������悤�w������ƂƂ��ɁA�������Z�̎������̗������ɑ��Ă̂ݒǒ��������Ƃ��� �B
 �@
�@ �@
�@
�ʌ��́u�������g�ł̂��߂ɕ���(����)�Ƒg�ŋ@��E�\�t�g�E�F�A��藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������A���҂�������킹���`�Ԃł����̔����Ȃ������B
�@�@�@���^�V���j���R�[�h
�ʌ��V�X�e���ł͏��̂��uMMAOKL�v�uMNAG�v�Ȃǂ́A�A���t�@�x�b�g�������̋L���u�^�V���j���R�[�h�v�ŊǗ������B�u�����̂��j���j�b�N�����ăR�[�h�ŕ��ނ������́v�̈ӂł������B��{�I�ɖ���=M��S�V�b�N=G�Ȃǂ̗���\�L�ƁA���ꂼ��̃t�H���g�t�@�~���[�ɂ�����E�F�C�g(�����̑���)�A�����̃X�^�C��(NKS=�j���[�X�^�C�����ȃX���[���AOKL=�I�[���h�X�^�C���m�z�n�̃x�[�X�n���ȃ��[�W)�Ȃǂō\������邽�߁A�K�����𗝉�����Β����I�ɔc�����₷�������B
�@�@�@���f�W�^���t�H���g
���w���ł͈��x�Ɍ��E�����邽�߁A�d�Z�ʐA�ł�1977�N��SAPTRON-APS5�^����A���u�����ɑg�ݍ��p���^CRT�Ƀt�H���g�̃f�W�^���f�[�^��\�����Ĉ�掆�ɏĂ��t��������ɂȂ����B�����͐����r�b�g�}�b�v�t�H���g���g�p���ꂽ���A1983�N��SAPLS-N�^�ŁA�̂���DTP�ɂ�����f�W�^���t�H���g�Ɠ��l�ɕ����̗֊s���𗘗p�����A�E�g���C���t�H���g���������ꂽ�B�����C�t�H���g�Ƃ����Ǝ��`���̃t�H���g�ŁA�����R�[�h�͓Ǝ���SK�R�[�h(SK72/78��2��B�Ⴂ�͓���R�[�h�Ԃł̃O���t�̈Ⴂ)�ŊǗ�����A��2�����������B�ِ̍���R�}���h�ɂ��e�[�u����������̎w����s���W��A�����ʏ�Ŏg�p�ł��鏑�̐��ɐ����������A1993�N�ɂ̓^�V���j���R�[�h�Œ��ڏ��̂��w�肷�邱�Ƃœ����ʏ��100���̂܂Ŏg�p�\�ɂ����u�^�V���j���V�X�e���v���o�ꂵ�A���V�X�e���ɑΉ�����A�E�g���C���t�H���g���u�^�V���j���t�H���g�v�ƌď̂����BWindows NT��œ��삷��ʌ��̐�p�g�ŃV�X�e��Singis(�V���M�X)�ɂ�Illustrator��Photoshop���C���X�g�[������Ă������A�ʌ��̃A�v���P�[�V�����ȊO����C�t�H���g�E�^�V���j���t�H���g���g�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�@�@��SAPCOL
�ʌ��̓d�Z�ʐA�@�ł� SAPCOL(�T�v�R��)�ƌĂ��y�[�W�L�q�����p�����B���{��g�łɍœK�����ꂽ���̂ŁA�o�ŎЂ��ƂɈقȂ镡�G�ȑg�ŋK��(�n�E�X���[��)�ɂ��Ή��ł����B1969�N�Ƀ~�j�R����ŕҏW���������邽�߂ɍ��ꂽ�\�t�g�E�F�A��30�N�ɂ킽���čX�V���č\�z�����v���O�����ŁA�u���ɂ̑g�Ńv���O�����v�Ƃ��Ăꂽ�BDTP�Ŏ嗬���߂�PostScript�̓f�[�^�̌�ɖ��߂��L�q����`�������ASAPCOL�́u�t�@���N�V�����R�[�h�v�Ƃ����R�}���h�����őg�ŏ���ݒ肵�e�L�X�g�f�[�^�ƍ��݂�����}�[�N�A�b�v�����ƂȂ��Ă���B������PostScript�ƈقȂ�A�v���O��������ɕs���ȌJ��Ԃ�������ϐ�/����`�Ȃǂ̋@�\�͎����Ă��炸�A�C�ӂ̒l�𑊑ΓI�ɕω����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̓_�ł�SAPCOL�͏_��Ɍ����A���Ƃɑ����ăp�[�\�i���R���s���[�^�ȂǂŃt�@���N�V�����R�[�h�������}������v���O������g�ޗႪ�悭����ꂽ�B
�@�@�@���V�X�e���̓Ǝ���
�ʌ��̓d�Z�ʐA�V�X�e���́A���̂قƂ�ǂ��Ǝ��d�l�ł���ADTP�V�X�e���Ƃ̓f�[�^�̌݊������قƂ�ǂȂ������B1990�N�ォ�炵�炭�̊Ԃ́A�܂��ʌ����̂ɑ�����v�������������߁A���Ђ̓d�Z�ʐA��DTP�őg�ł����f�[�^���ʌ��̏o�͋@�ňł���`���ɕϊ����鑼�А��̃R���o�[�^�\�t�g�E�F�A���p����ꂽ�B������DTP�ɂ����đ��p����Ă���QuarkXPress�ɂ��AXTension�Ƃ��đg�ݍ��߂�R���o�[�^�����݂����B

����1���@(1925�N)
����2���@(1926�N)
���p�@(1929�N)
�^�C�g����p�@(1931�N)
�Έ䎮�ʐ^�A���@(A�^�A1936�N)
�Έ䎮��Z�Z�l�N�^(SK-1�^�A1943�N)
MC�^(1950�N)
�@�@�@��SK�^
SK-2�^(1954�N)
SK-3�^(1955�N)
SK-3R�^(1957�N)
SK-4�^(1957�N)
SK-4E�^(1958�N)
SK-T1�^(1959�N)
SK-3RY�^(1960�N)
SK-16TV�^(1961�N)
�@�@�@��SPICA�^
SPICA-S�^(1963�N)
�X�s�J�e���b�v(1964�N)
SPICA-L�^(1965�N)
SPICA-Q�^(1966�N)
SPICA-AD�^(1968�N)
SPICA-QD�^(1969�N)
SPICA-A�^(1973�N)
SPICA-AP�^(1975�N)
SPICA-APU�^(1976�N)
SPICA-AH�^(1979�N)
�@�@�@��PAVO�^
PAVO-8�^(1969�N)
PAVO-9�^(1981�N)
PAVO-10�^(1981�N)
�@�@�@��J�V���[�Y�@�����@��B
PAVO-J�^(1969�N)
PAVO-JP�^(1977�N)
PAVO-JL�^(1979�N)
PAVO-JV�^(1979�N)
�@�@�@��K�V���[�Y�@���@�\��ʋ@��B
PAVO-K�^(1973�N)
PAVO-K2�^(1977�N)
PAVO-K6�^(1977�N)
PAVO-K3�^(1978�N)
PAVO-KL�^(1979�N)
PAVO-KS�^(1981�N)
PAVO-KV�^(1983�N)
PAVO-KVB�^(1983�N)
PAVO-KY�^(1987�N)
�@�@�@��B�V���[�Y�@�r�W�l�X�t�H�[���p�B
PAVO-B�^(1975�N)
PAVO-B2�^(1978�N)
PAVO-BL�^(1981�N)
�@�@�@��U�V���[�Y�@�V���g�ŗp�B
PAVO-U�^(1971�N)
PAVO-KU�^(1975�N)
PAVO-UP�^(1979�N)

�@�@�@��SAPTON�V���[�Y
SAPTON����@(1960�N)
SAPTON-F(1962�N) - �h�q�����������\�쐻�p������p�@�B
SAPTON-N3110(1965�N) - ���̎��p�@�B�V���_�g�p�B�����ʐM���ꕶ���R�[�hCO-59���̗p�B1967�N�ɒ����V���k�C���x�Ђɑ���2�Ԗڂɓ�����������V���Ђł�1968�N3��5���t���ʂœ��{���̓������S�ʎʐA���Ɗ����S�p��B���B
SAPTEDITOR-N(1966�N) - SAPTON-N�p�V���p����E�e�[�v�ҏW�@�B�L���I���W�i���e�[�v�ƐԎ������w�߃e�[�v��ǂݎ��A�ҏW�g�ŏ����ς݂̎��e�[�v���o�́B
SAPTON-P(1968�N) - ��ʈ���p�_�g�S�����ʐA�@�B1���@�͏o�ŎЃ_�C�������h�Ђɔ[���B
SAPTEDITOR-P(1968�N) - SAPTON-P�p����E�e�[�v�ҏW�@�B
SAPTON-H - �V�����o���쐬�p�B
SAPTON-A5260/A5440(1969�N) - ��ʈ���p�_�g��p�@�B�]���̂���E�e�[�v�̑����DEC�А��~�j�R���s���[�^PDP-8���g�p�����ҏW�g�ŗp�\�t�g�E�F�ASAPCOL-D1�Ƒg�ݍ��킹�Ďg�p�B
SAPCOL-D1 - ��ʈ���p�g�����\�t�g�B
SAPTON-N5265(1970�N) - �V���_�g�p�B�V���p�g�����\�t�gSAPCOL-D3�Ƒg�ݍ��킹�Ďg�p�B
SAPCOL-D3 - �V���p�g�����\�t�g�B
SAPCOL-D5 - ��ʈ���p�g�����\�t�g�B
SAPCOL-H6 - ��ʈ���p�g�����\�t�g�B
SAPCOL-H3 - �V���p�g�����\�t�g�B
SAPTON-N12110(1972�N) - �V���_�g��p�A���̃X�^���h�A�����^(�n�[�h�E�F�A��W�������A�~�j�R���s���[�^SAILAC�Ōڋq���̃J�X�^�}�C�Y���s������)�B���^���E�ቿ�i���ڎw���B
SAPTON-N7765(1972�N) - �V���p�X�^���h�A�����^�B
SAPTON-Spits�V�X�e��(1972�N) - ��ʈ���p�X�^���h�A�����^�B�S�����ʐA�@�ŏ��߂ăy�[�W�g�łɑΉ��B
SAPTON-Spits7790 - ���ނ̃��[���o�b�N�@�\�𓋍ڂ��C�ӂ̈ʒu�ւ̈A�X�|�b�g�r�������\�ɁB
SAPCOL-HS - �y�[�W�g�����\�t�g�BHITAC-10���g�p�B���{��g�ł�JIS�K�i���̊�{�ƂȂ����B
SABEBE-S3001 - Spits�V�X�e���p��������E�@�B�u�ꐡ�m�Ў����茩�o���L�[�v���̗p�B
SAPTON-NS11(1975�N) - �V���p�B�Ԏ����������@�\�t�B���ڃ~�j�R����HITAC-10�U�ɕύX�B
SAPTON�����\�g�ŃV�X�e��(STC�A1976�N) - ���{��ʌ��Ќ����B
SAPTON-NS26D(1977�N) - �V���p�B�����ʐM�����R�[�hCO-77�ɑΉ��B
SAPTON-Somanechi6812(1977�N) - ��ʈ���p�B
SAPNETS-N(1977�N) - �V���p�ҏW�E�Z���E���C�A�E�g�V�X�e���B�Z���p��VDT�\���p�����������u���ځB
SAPTON-NS26DF(1981�N) - �V���p�BSAPTON-NS26D�Ƀf�[�^���o�͗p�t���b�s�[�f�B�X�N���g�p�ł���悤�ɂ����B
SAPTON-Somanechi6812S(1981�N) - ��ʈ���p�BSAPTON-Somanechi6812�Ƀf�[�^���o�͗p�t���b�s�[�f�B�X�N���g�p�ł���悤�ɂ����B
�@�@�@��SAPTRON�V���[�Y�@���𑜓x��CRT��ɕ������o�͂��Ċ��ނɘI����������ň������B
SAPTRON-G1(1977�N) - �����~�Ղ𓊉e����A�i���O�t�H���g����CRT�ʐA�@�B�V���p�B
SAPTRON-APS5(1977�N) - �ăI�[�g���W�b�N�Ђ�APS5�^CRT�ʐ^�A���@��a���d�l�ɂ����r�b�g�}�b�v�t�H���g���e�̃f�W�^���t�H���g����CRT�ʐA�@�B
SAPTRON-G8N/G8S(1979�N) - 8���̓��ڃA�i���O�t�H���g����CRT�ʐA�@�B
SAPTRON-APS5H(1981�N) - �����L�����������ǂ��Ĉ��x����1��3200������������������CRT�ʐA�@�B���i1��300���~�B
SAPTRON-APS��5(1981�N) - APS5�^�̈��x��3000���ɃX�y�b�N�_�E�����ĉ��i��������CRT�ʐA�@�B���i�͖_�g�d�l��6000���~�A��y�[�W�g�d�l��7000���~�B
SAPTRON-Gelli(�W�F���[�A1983�N) - �v���@��p5�C���`CRT���g�p�����ʌ��Ǝ������̃f�W�^��CRT�ʐA�@�B
SAPTRON-APS��5S(1983�N) - �ҏW�g�ŗp�~�j�R���s���[�^��APS��5����̂ɂ����X�^���h�A�����^CRT�ʐ^�A���@�B
SAPGRAPH-L(1983�N) - APS5/APS��5/APS��5S�p�}�`���̓T�u�V�X�e���B
SAPTRON-Gimmy S1040/SS1040(1985�N) - SAPTRON-Gelli���x�[�X�ɓ��e�t�H���g���r�b�g�}�b�v����C�t�H���g�ɕύX�B��ʈ���p�B
SAPTRON-Gimmy N1440/N1425(1985�N) - Gimmy S1040�̐V���pC�t�H���g�o�͋@�B
SAPGRAPH-L61(1985�N) - CCD�X�L���i�����Ȃ�SAPGRAPH-L���ǂ̐}�`���̓T�u�V�X�e���B
SAPGRAPH-G(1987�N) - �ʐ^�摜��������悤�ɂ����}�`���̓T�u�V�X�e���B
�@�@�@��SAPLS�V���[�Y�@�A�E�g���C���t�H���g(1985�N�AC�t�H���g�Ɩ���)�𓋍ڂ����[�U�[�Ŋ��ނɘI����������ŕ����摜���ꊇ�o�͂���C���[�W�^�C�v�Z�b�^�[(���ŋ@)�B
SAPLS-N(1983�N)
SAPLS-Laura/Michi(1987�N) - SAIVERT-H202�p�o�͐�p�@�B
�@�@�@��SAIVERT�V���[�Y�@SAPNET-N���x�[�X�ɂق�WYSIWYG�������������C�A�E�g�^�[�~�i���ŁA�o�͋@�Ƃ��čZ���p�v�����^�[SAGOMES�V���[�Y��C���[�W�^�C�v�Z�b�^�[SAPLS�V���[�Y���ʂɕK�v�B��掆�o�͂ɋ߂��C���[�W����ʕ\�����邱�Ƃ��ł����B�y�[�W�������Ƃ��ꂽSAIVERT-S��SAIVERT-P�A�[������Ɉ����P�y�[�W�p��SAIVERT-H���������B
SAIVERT-N(1983�N) - �\���p20�C���`CRT�𓋍ڂ����V���p�Z���ҏW���C�A�E�g�^�[�~�i���B
SAIVERT-S(1984�N) - �\���p15�C���`CRT�𓋍ڂ�����ʈ���p���C�A�E�g�^�[�~�i���B
SAZANNA-SP313(1985�N) - �������͂ƂƂ��ɑg�オ���Ԃ��m�F�ł���g�\���t���͍Z���@�BSAPCOL-HS��SAIVERT-S�p�e�L�X�g�f�[�^���o�́B
SAIVERT-H101(1985�N) - �o�͗pC�t�H���g���g�p���C�o�͎��Ɠ����̍ق�CRT��ʏ�ɕ\������[���p���C�A�E�g�^�[�~�i���B
SAIVERT-H202(1987�N) - �����^����30���̃t�H���g�p�b�N�𓋍ڂ����߂Ĉ̏]�ʉۋ������������C�A�E�g���[�N�X�e�[�V�����B���[�U�[�o�͐�p�@SAPLS-Laura/Michi�Ƒg�ݍ��킹�ĉ^�p�B
SAIVERT-P(1989�N) - ��}�@�\��摜���͕ҏW�@�\�Ȃǂ�lj����\���g�ʼn\�����T�C�Y���g���B
�@�@�@��SAMPRAS�V���[�Y�@
SAMPRAS-C(1997�N) - WYSIWYG���C�A�E�g�A�v���P�[�V�����B���i780���~�B�o�͋@���ʂɕK�v�B�n�[�h�f�B�X�N�h���C�u�S�̂̃t�@�C�������Ƃ�������{���삪�ł��Ȃ��Ȃǂ̐��������B���������[�N�X�e�[�V�����ʼnғ��B
�@�@�@��Singis
Singis(�V���M�X�A2000�N) - �ʌ��ʐA�@�̎�����̍ŏI�@��B�o�͋@���ʂɕK�v�B�J���[�Ή��A���y�[�W�Ή��B���C��21�C���`CRT�f�B�X�v���C�̂ق��ɁA�p���b�g�ޕ\���p15�C���`�t���f�B�X�v���C��W����������B�ʌ��@�ł͂��߂Ĉ�ʓI��PC/AT�݊��@(����FLORA)���x�[�X�}�V���Ƃ��č̗p���AWindows NT��œ��삷��\�t�g�E�F�A�ƂȂ����B���i500���~�BPC�p�̉摜�f�[�^��荞�ݗp��Adobe Illustrator9.0��Adobe Photoshop5.5�����ځB
�@�@�@��TELOMAIYER�@�����p�d�q�e���b�v���o���u�B
TELOMAIYER-T(1983�N) - ����e�����C���B�f�B�X�v���C��p���ă��C�A�E�g���s���A�摜�������ɒ~�ς����f�[�^�����n�ɔ������̊��M���ɏo�́B
TELOMAIYER-TG(1985�N) - �e���b�v�J�[�h�o�͂̂ق��A�r�f�I�o�͂ɂ��Ή��B
TELOMAIYER-C(1989�N) - PC-9800�V���[�Y��ʼnғ����A���M���v�����^�E�X�L���i���ڑ��\�BC�t�H���g���ځB�t�H���g�f�[�^��1����35���~�B
TELOMAIYER-C1 - ���������[�N�X�e�[�V�����ʼnғ��B�g�p�t�H���g�ɐ�����C�t�H���g�ɑ���^�V���j���t�H���g���ځB
TELOMAIYER-C1 HD - C1��SD�掿���A�b�v�R���o�[�g���邱�Ƃ�HD�o�͂ɋ[���I�ɑΉ��������́B

�ʌ��́A���А��i�Ή����̂̂قƂ�ǂ��Г��Őv�E�J�������B�����ɔ�ʐA�����Ղ�1���̂�����̐�L�ʐς����Ȃ��A�������������{��ł������̏��̂��������Ƃ��\�ƂȂ������߁A���Ђł͐ϋɓI�ɐV���̂��J�������B1969�N�ɂ͏܋�100���~(��1��)�̐Έ�ܑn��^�C�v�t�F�C�X�R���e�X�g��݂��ĊJ��������B�S�i��X�[�{�A�i�[���A�{�J�b�V�C�ȂǁA���j�[�N�������x�̍����f�U�C�����̂��������\���ꂽ�B
�ʌ��̎�Șa�����̂̔��\�N�͎��̒ʂ�ł���B
1932�N - �Έ䑾�S�V�b�N�A�Έ䞲��
1933�N - �Έ䒆����
1937�N - �Έ�t�@���e�[��
1951�N - �Έ�ז���
1954�N - �Έ䒆�S�V�b�N
1956�N - �Έ䒆�ۃS�V�b�N
1958�N - �Έ�ۃS�V�b�N�A�Έ䑾�ۃS�V�b�N�A�Έ䒆���ȏ�
1959�N - �Έ䑾�����A�Έ䉡�������A�Έ䑾���ȏ�
1960�N - �Έ���������A�Έ���ȏ�
1961�N - �Έ�����S�V�b�N
1964�N - �V�����������A�V�������S�V�b�N
1967�N - ��c�V������(��c��^������������)
1968�N - ��c�ז����A��c���S�V�b�N(��c��^������)
1970�N - �Έ䒆���S�V�b�N�A��c�V���S�V�b�N(��c��^������)
1972�N - �]���ꏑ�A�t�@�j�[
1973�N - �i�[��
1974�N - �X�[�{�A�i�[��D
1975�N - �{������L�A�嗖�����A�Έ�V�׃S�V�b�N�A�S�iU�A�i�[��L�A�i�[��M�A�i�[��O�A����s��
1976�N - �X�[�{O
1977�N - �i�[��E
1979�N - �S�iE�A�S�iO�A�X�[�V��L�A�X�[�V��B�A�W��
1981�N - �G�p����(����{���������)�A�Έ䒆���S�V�b�NL�A�S�iOS�A�S�[�V��E�A�t�@����B�A������
1982�N - �S�[�V��O�A�S�[�V��OS�A�t�@����O�A�t�@����OS�A�C�i�u���V��
1983�N - �S�iL�A�S�iM�A�S�iD�A�S�iDB�A�S�iB�A�t�@����E�A�{�J�b�V�BG�A��A���s���A�i�J�t���[L�A�i�J�t���[B�A�C�m�t���[
1984�N - �X�[�{OS�A�D�c���������A�C�_�V�F
1985�N - �{������M�A�{������D�A�{������DB�A�{������B�A�{������E�A�{������H�A�S�iH�A�S�iIN�A�~���J�[���A�J�\�SL�A�g���מ����A�g���������A�������A���s���A�D�c�������A��]�ˁA�C�i�Ђ��A�C�{�e�A�i�~��
1987�N - �i�[��DB�A�n����E�A�i�[�J��
1989�N - �S�[�V��U�A�]�����ꏑ�A�C�i�N�Y���A�C�i�~��E�A���܂�イD
1991�N - �L�b���~���A���ꏑ�A�i�J�S�����A�i�J�~���_B-S�A�i�J�~���_B-I
1993�N - �u�������A�n����L�A�n����M�A�n����B�A���vM�A�C�i�s�G��M�A�C�i�s�G��B�A�C�i�s�G��U-S
1995�N - �i�[��H�A�i�[��U�A���܂��傤D
1996�N - �Έ䒆�������ȏ��A�Έ䒆�����ȏ�
1997�N - �S�J�[��E�A�S�J�[��H�A�S�J�[��U�A�X�[�V��H�A�����X�[�V��U�A�S�[�V��M�A�͂��t���[�~��B�A�͂��t���[�~��E�A�͂��t���[�~��H�A�g���������A�g�����������A�c�s���A�������ꏑ�A�i�J�~���_M-S�A�S�i���C��U
2000�N - �{���S�V�b�NL�A�{���S�V�b�NM�A�{���S�V�b�ND�A�{���S�V�b�NDB�A�{���S�V�b�NB�A�{���S�V�b�NE�A�{���S�V�b�NH�A�{���S�V�b�NU�A�C�_�T�C��M
�����̖���2001�N���_�̌ď́B�����A�{������L�́u�{���ז����v�t�@�~���[�W�J�O�́A�S�iU�̓S�i�A�n����(���݂̑n����E)�Ȃǂ̓E�F�C�g�\���̂Ȃ����̂Ƃ��ă����[�X���ꂽ�B
 �@
�@ �@
�@
1926�N - �ʐ^�A���@�������ݗ��B�����s�k��x�D���ɖ{�Ђ�u���B
1944�N - �����s�L���摃��(������)�Ɉړ]�B
1948�N - �X�V�M�v�A���Ђ𗣒E���ʐ^�A���@���슔����Ђ�ݗ�(�̂��̃����T��)
1950�N - ������Ўʐ^�A���@�������ɉ��g�B
1963�N - �Έ�g�̎O���E�Έ�T�q���В��ɏA�C�B
1972�N - ������Ўʌ��Ɖ���
2018�N - �Έ�T�q���В��ݔC�̂܂����B��C�Ƃ��ē쑺���Ƃ��A�C�B
2020�N - �쑺���Ƃ���ɏA�C�A�����Ɋ}���`�����В��ɏA�C�B �@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
����Ɨ��O
�g���̂��郆�j�[�N�ŖL���ȏ��́h�ŎЉ�ɍv������
����ЊT�v
���� ������Ўʌ�
�n�� 1926�N(�ʐ^�A���@������)
�ݗ� 1950�N(������Ўʐ^�A���@������)
�@�@ 1972�N(������Ўʌ��ɖ��̕ύX)
���{�� 97,200��~
�{�Џ��ݒn �����s�L������˓�35��2��
��\������ �쑺����
��\������� �}���`��
���Ɠ��e �f�W�^���t�H���g�̊J���y�є̔��A�s���Y���y�ъǗ�
�����v
1924�N(�吳13�N) �Έ�g�A�X�V�M�v⽒�ƖM⽂�ʐ^�A���@�̓������o��
1925�N(�吳14�N) �ʐ^�A���@�����ꍆ�@���\
1926�N(�吳15�N) �ʐ^�A���@��������n��
1936�N(���a11�N) �Έ䎮�ʐ^�A���@�̔̔����J�n
1950�N(���a25�N) ������Ўʐ^�A���@���������⽴���Έ�g���В��A�C
1952�N(���a27�N) �Έ�g�u�����势�a�v��������J�n�@�u�����J�́v���
1956�N(���a31�N) �d�Z�ʐA�@�uSAPTON�v�J���J�n
1960�N(���a35�N) �Έ�g�u�����势�a�v���̊����@�u�e�r���܁v���
1963�N(���a38�N) �Έ�g�����A�Έ�T�q�В��A�C
1965�N(���a40�N) �d�Z�ʐA�@�uSAPTON-N�v���\
1970�N(���a45�N) ��1��⽯��ܑn��^�C�v�t�F�C�X�R���e�X�g�J��
1972�N(���a47�N) ������Ўʌ��ɎЖ��ύX ��1��u�����ǂݏ������v�J��
1983�N(���a58�N) �Έ�T�q�u�����J�́v���
1985�N(���a60�N) ���Ζ����Ɏʌ��u�[�X���o�W
1988�N(���a63�N) �����^���t�H���g�p�b�N�̔��J�n
1991�N(����3�N) �u�����ǂݏ������v20��J�ÂŖ��A���N����u���{��ƗV�ڂ���v��
1996�N(����8�N) �����̑Ή��̃����^���t�H���g�p�b�N�uN�p�b�N�v�̔��J�n
2004�N(����16�N) �u�����̐��Ԍ��J�����_�[�v�ŐΈ�T�q�Ɛ��Y�N�������A���Łu����
�h�V��܁v���
2018�N(����30�N) �Έ�T�q�����A�쑺���ƎВ��A�C
2020�N(�ߘa2�N) �쑺���Ɖ�A�C�A�}���`���В��A�C
�@�@�@�@�@��ʍH������A�Ւn����H�i�X�[�p�[�E������Ѓ��I�R�[�֒��݊J�n
2021�N(�ߘa3�N) ������Ѓ����T���Ƃ�OpenType�t�H���g�������Ƃ\
2023�N(�ߘa5�N) �V�{�Ѓr���v�H�A2�`3�K�ɖ{�Ђ��ړ]
�@�@�@�@�@4�`10�K���w�����^�c��Ђ֒��݊J�n �@ �@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@