���퍑�����̒m�b / ���c�����E�k�𑁉_�E���c�M���E�D�c�M���E�L�b�G�g�E�Γc�O���E����ƍN�E���c�@���E�]�ˎ����E�E�E
���j���� [�D�c�M��]�E[�L�b�G�g]�E[����ƍN]
�퍑����ƉƖ��E���Ǝ�
�@
�G�w�̐��E�E��l
�@�@�@


|
�퍑����̏I���E�쒆���̐킢�E���c�̐킢�E�{�\���̕��E�փ����̐킢�E���Ă̐w�E���c�M���E�㐙���M�E�D�c�M���E�L�b�G�g�E����ƍN ���퍑�����̒m�b / ���c�����E�k�𑁉_�E���c�M���E�D�c�M���E�L�b�G�g�E�Γc�O���E����ƍN�E���c�@���E�]�ˎ����E�E�E ���j���� [�D�c�M��]�E[�L�b�G�g]�E[����ƍN] �퍑����ƉƖ��E���Ǝ� �@ |
|
|
�G�w�̐��E�E��l �@�@�@  |
| ���퍑����̏I�� | |
|
�@���퍑�喼 �@���V������ |
|
| �@ | |
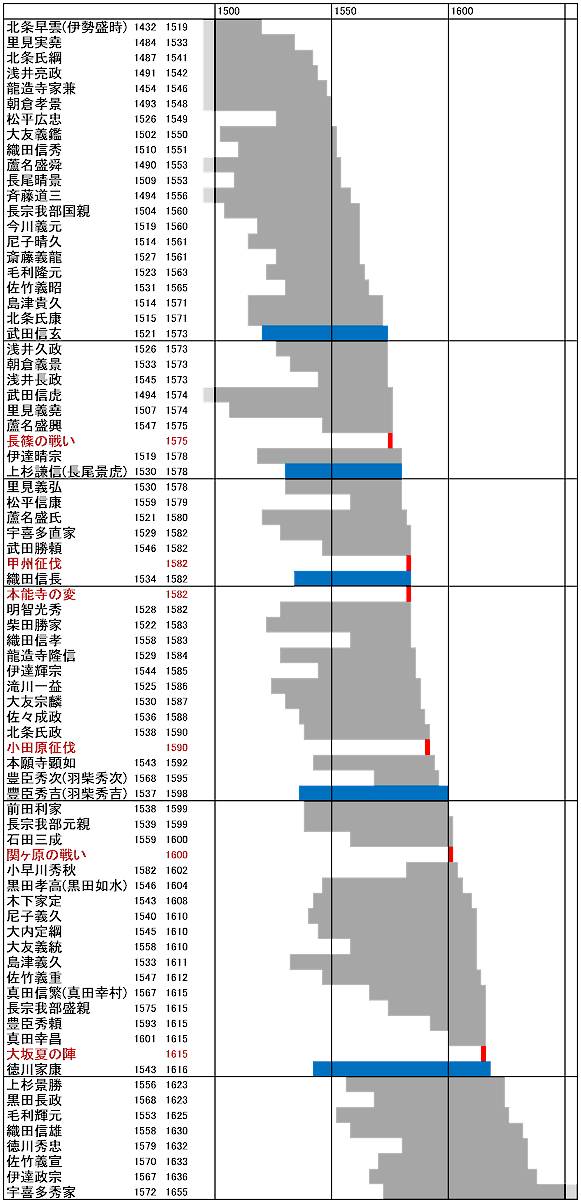
| ���쒆���̐킢 | |
|
�@���쒆���̕��c�㐙���� �@�����k�����̌n�� |
|
| �@ | �@ |
| �����c�̐킢 | |
| ���O�������̐킢�@�@�@�@�@�@1573 | |
|
���ɔ\����(���̂�����)
���c�M�������q�`�i�ɑ�����������e�Ȃǂ��L���������B�D�c�M����͖Ԃ�����ɉ����ė��E�����`�i��M�������Ă���B �Ȏg�m������A�����ӌ�A���V�����o�Ҍ�ԁA���O�B�w�V��A �ƍN�o������V���A������������������������A�������A �O�������V���k��V�����O��]�l���߁A�B�{�ӌ�ԁA��S�Ռ�A ���@�J���ҁA���V�O�ߔ��A���V�R������A�e�J���ܘ_�� 嫑R�A���ߐM���ŖS�������ҌA�B�����G�V����J��������b�A �s�ߌ䕪�ʌ�A�P���o�ތ����A���X�ތ��A �E�������@ �@ �M���@ �ԉ� �ޏ�@ ���q���q��a �g���̑m���b�͎f�����B��̕������ɁA����ƍN���ƌ��A����22���O�������̐킢�ŏ������A�O�́E���]�����̌R���ƐD�c���̉���1000�]������A�{�ӂ�B�����̂ł����S�������������B�l�ÂĂɕ������̂����A�M���̕��̑唼������𗣂�ċA���������ɂт����肵�Ă���B�����������͓̂��R�����A�D�c�M����ŖS�ɒǂ����߂�D�@�������������ɁA���̂悤�Ȋ��e�Ȕ����ł��Ă��A�J����݂̂Ō��Ȃǂ͖����B���f����邱�ƂȂ���B�Ȃ��A�g�҂Ɍ����^�����̂ł�����������Ă������������B���X�ތ��B�@ |
|
|
�����̐킢 �@�@�@�@�@�@�@�@1575 ���b�B����(�V�ڎR�̐킢) 1582 �@ �@ |
|
| �����E���q�̐킢 | �@ |
|
�����J��̐킢�@ 1573/7 (�V�����N)�@���q�`�i�R�ŖS �����J��̐킢�@�@ 1573/9�@�@�@�@�@�@�@�@��䒷���R�ŖS �@ |
|
| ���{�\���̕� | |
|
�@���{�\���̕� �@���D�c�M���́u���v/�K�ᕑ ���y �\�y �@�����q���G |
|
| �����q�E���v��̐킢 | �@ |
|
1584 (�V��12�N) �H�ďG�g�w�c�ƐD�c�M�Y�E����ƍN�w�c�̊Ԃōs��ꂽ�킢 �@ |
|
| ���փ����̐킢 | |
|
�@���փ������� �@���Γc�O�� �@���א�K���V�� �@�����쏫�R�Ƃ̒a�� |
|
| �@ | �@ |
| �����@�~�̐w�E�Ă̐w | |
|
�@�����̐w �@���^�c�K�� |
|
| ���R�t�G�b | |
|
���G��̏M�S�C
�s���q�́A���̂܂ܕ��Ƒ��ɂЂ��݁A�����̂��ɏo���B�߂́A�ʏ��Ƃ̉Ɛb�A�튯�łȂ��Ƃ������Ƃŕs��ɕt���ꂽ�B�G��̏M�S�C���A���̂܂܍�����݂ɂȂ����̂́A�w���҂̎s���q���A���̔C��������������Ƃɂ���邵�A�܂��A�틵�͂���ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B�s���q�����Ƒ��ɓ�����������l���ڂɁA�{�ہA��m��ƂƂ��ɘA������V�邪�A��̂��߂ɂ������̂ł���B �V�����N�����\�ܓ��A�ʏ������́A����̋Q��̎S����v���A����ȏ�Ɛb�A���l�ɋ�Y��^����͍̂߂ł���Ƃ��āA�ߎ��F��E�q�卲�ɏ�����������A�G�g�̕������핺�q�����̐w�ɍ~����\�����ꂽ�B���̏����͗ނ������Ȃ������B �u����\�����\�̍��A�����A�g�e�A�F�V���傱�Ƃ��Ƃ��ؕ��d��ׂ���B�R��ǂ��A����̎m���G�l�͕s�{�ɂ��A�ꖽ��������������A���������̉x�тƑ�����v �G�g�́A�u�ʏ����]�������m�̊ӂł���v�Ƃ��Ă��̐\���o����邵�A�����ɖ����Ď���𑗂����B�\�Z���A�����͏���̎m���̂��ׂĂ�{�ۑ�L�Ԃɂ��߂Ė�ʂ��A�\�����A�s���O�\��̋q���ɍ���݂��A�����̕~�������ɐ��߂Ď��Q�����B �R���g�e�A�F�V�i�F�V����ɂÂ��A����ɁA�����̕v�l�͒j����l������l�������Ɉ����悹�Ďh���A�Ō�ɂ݂�����̂ǂ��т��Ď��B�g�e�̕v�l�Ƃ��̎q�͂��Ƃ��A�����̎ɒ�F�V�i�F�V�̐V�Ȃ��\�܍̎Ⴓ�ł��̕v�ɏ}���Ă���B �u���܂͂�������݂͂��炶���l�̖��ɂ��͂�킪�g�Ǝv�ւv�Ƃ����̂��A�����̎����ł������B�v�l�̂���́A�u����Ƃ��ɏ����͂邱������������旧�K�ЂȂ鐢�Ɂv�G��s���q�̐S�������ꂳ�������̏��v�Ȃ̔������́A�ӂ��̎����̂Ȃ��ɋÌ����Ă����B���d�̖����Ƃ��āA�𐢏\�l��̉Ɩ���ق������ʏ��Ƃ́A�����ɂق�B �J���A�`�ςƎs���q�́A�ΎR��ɂ��ǂ����B���x�V�`�ς͂��̌�A�ΎR��ŕ������A�d�B�ɉB�ꂽ�B�`�ς��J��Ƃ��鎛�@�����܂ŕ��ɂ̂ǂ����ɂ���͂��ł���B�ΎR�̗����A�G��s���t�́A��������ċI�B�ւ��ǂ����B���Y���̓c�������A����Ƃ��Õ��q�̎R�c�ɂ��߂����́A�܂т炩�ł͂Ȃ��B |
|
|
���L�̂悤�Ȏ���
�Ƃ��낪�A�����̘\���͈ˑR�Ƃ��Đ�������B �m�s�����߂�Ƃ��A�G�g�́A�u�����͓a���璸�Ղ����Ɨ��䂦�e���ɂ͂��ʂ��A�\���͐����B����ȏ�͂��ʁB���[�ǂ̂ɂ����������āA��Α����̂��������������Ɛ\���������Ă������悢�v�����́A�����s���������B���Q���甆�b�ɂȂ����̂ɁA�\�����ӂ��Ȃ��Ƃ����̂́A�肭�ɍ���Ȃ������B ���̌�A�����́A�ےÂ̐ΎR�U�߁A���������A�R��̍���Ȃǂł��������̕��������Ă����A�G�g�͂��̂Ǎŏ��̂��Ƃ����肩�������B �u�����ɂ͒m�s�͂��ʂ��B���Ƃǂ�������v�������}���Ă�m�s�͂���Ȃ����������̂ljߕ��Ȃقǂ̋������Â��݂Ō��ꂽ�B���̂ق����A�����ɂ���A�m�s�n�������߂�ʓ|���Ȃ��A�l���������������鐢�b���Ȃ������B�ނ��A���~�ɂ��Ă����̂ق����悩�����낤�B �Ƃ��낪�A���̂��������Ƃ����̂́A�������m��Ă���B����̂��Ƃɔq�̂������͑��ɐς܂�Ďg������Ȃ��Ȃ�A���ɒ��܂邢���ۂ��ɂȂ����B ���l�ɋ����ڂ��Ă���\��N�������B �V���\��N�Ƃ����A�����̎l�\���̔N�ł���B ���̐�������A�����͂�������a�C���Ȃ������Ƃɑ����͂��߁A�ӂ����قǐQ�āA�͂�s����悤�ɂ��Ď��B�Ō�̖����Ƃ������l�̒��オ�A�u���Ⴂ���납��̐�ꂮ�炵�̂��������A����������̂ł�����܂��傤�v�Ƃ������B�������ɂ���ẮA���[�Ƃ����L���ɂ��������Ă��ɝˎ������L�ł������B �����͎����A���ꂪ�����ƂЂ������Ɉ�ォ�����Ăӂ₵�����₾���͎c�����B ���Ă�Ƃ̊Ԃł��܂ꂽ�����̎q�́A�����q���F�Ƃ������B ���N�̂��납��ˋC���������B�����̎���A���~�Ƃ��Ă�͑��k���āA�����q�ɂ͕��m����߂����A���̒��̋�������ƂłɁA���l�Ō��̂����Ȃ����������B ���̉ƂƂ��̈ꑰ�́A�̂��ɂ܂ŋߍ]�̏��ƂƂ��ĉh�����B�ߍ]����o�����܂̈ɓ����A�ɓ����Ȃǂ̏��Ђ́A�����̉ƌn�ƂȂɂ��̂Ȃ��肪����̂��낤���B���킵���͒m��Ȃ��B |
|
|
���̂ĎE���̍���j��
�ƍN�́A����ł��܈�A�u�̂ĎE���v�̐헪�I�ȏW�c���c���Ă����B��������Ă���ƍN����̕��������F�E�q��ȉ��甪�S�l�ł���B�O���I�N�̂������͂����͂₭�ׂ���ł��낤�ƉƍN�͊o�債�A�Ƃ��ɍ������ނƂ����钹���F�E�q����珫�ɂ���B �F�E�q��́A�ƍN�����N�̂��납��d���Ă����j�ŁA�ƍN���O�N��ł���B�ƍN�͓����̓r��A������Ɉꔑ���A�u���m�v�ƂȂ�ׂ��F�E�q��ƂقƂ�ǖ閾�������Đ̘b�Ȃǂ����A���x���܂��Ȃ������B���̓_�A�V�Q�҂̍j�����◯�狏�ɖ������Ƃ��Ƃ́A�܂�őԓx���������Ă����B �u�l�����A�������t���Ă�낤���v�ƉƍN�͂��������A�F�E�q��͂���₩�ɂ��Ƃ��A�u�ǂ������ʐg�A���p�̂��Ƃł������܂��B���l�Ȃ��l����������̂Ȃ�A����ׂ��升��ɂ��g���������܂��v�Ƃ������B�ƍN�͂���ɁA������h�q��̕��@�Ȃǂɂ��Ă����킵���w�������B���Ƃ��A�u���̕�����͌̑��}���҂������Ēz���ꂽ�邾�B�V��t�ɂ͖L�b�Ƃ̋���Ȃǂ������܂��Ă���B�S�ۂ�����Ȃ��Ȃ����𒒂Ԃ��Ēe�ۂƂ���v�Ƃ܂ł������B����قǂ̍����́A���鐼�m�ۂ̎����������j���ɑ��ẮA�тقǂ��Ȃ������B �j���̏ꍇ�́A�����ǂ���́A�u�u���̂āv�ł������B�F�E�q��͕���A�j���͐V�Q�A�Ƃ����e�a�̍��ʂ����ł͂Ȃ������낤�B �Ȃ��Ȃ�A�S�����˂���������̂����Ƃ������A���̍j���̎g���͂��ꂾ���ł͕ЂÂ��Ȃ������B���ǂ������A�Ƃ����ނ��������v�f������A����ɂ͉ƍN�ł����A�u��������v�Ƃ������Ă͗N���Ȃ������̂ł��낤�B���ׂĂ͍j���́u�ˊo�v�ɂ܂�����Ă����B (����͉����悤�̂Ȃ���X����)�Ƃ����A�����ɁA�����\�ܓ��A��s��(�Ɠ����͂����Ă����B�Ηp�O����d��Ƃ��鐼�R)�́A�ɂ킩�ɑ���Ƒ��鉺�ɉ����߂�z���A�ƍN�]�R�̏���̉��~���~�Ɏg�҂𑖂点�A�u�G���l�̂����߂ł�����B�������̊F�X�l�͂����\�֗����̂���܂��邱�Ƃ͑�����܂��ʁv�ƌ��������B�ނ��l���ł���B���̒i�K�ő�����Ɏ��e����܂݂�����B ���̂��߁|�܂菔��̍Ȏq�E���ɂ��Ȃ��邽�߂ɁA�s���̌x���͌��d������߂��B ���̏o���A���X�������A����ꂽ�B���Ƃ����틴�͍��c�L���A���쒬���͋{�{�O�g��A���㋴�͐���C�����A�ؒ��؋��͎��c�����A�V�������͉��l��������A�ʑ����͑���o�_��A�Ƃ������������ɂ����ƎO��l�̐��R���m���s���̌x���ɂ��������B �E�������҂������B ���c�����̕�Ɖł͐��D�̒�ɂ�����ĖؒÐ������E�����A�L�n�L���̍Ȃ́A���≮�̗p����ӑD�ɓ�d��������Ă���ɔE�сA�����E�o�����B����ɐ��Ԃ����ǂ납�����̂͋ʑ��ɉ��~�����א�Ƃ̏ꍇ�ł���B ���`�v�l�������͗��狏�̉ƘV���}�����ւɋ����Ƃ����낰�Ďh�����A�����~�ɕ����āA�v�l�A�Ɨ��O����Ƃ��Β��ŊD�ɂȂ����B (�������)�ƁA���̖�A���鐼�m�ۂ̏��V��t�̏ォ��ቺ�̋ʑ��̉Ђ��݂Ă�������j���́A�킪�g�Ƃ��Ȃ��������̎��Ԃ����Ɋ̂��X�̂悤�ɗ₦���B �u����v�Ƃ���������}�g�������B�j���͑��Z���̂��Ƃ䂦�A�Ɨ���������B �Ɨ��������߂��Ă��āA�u�����g�Q����Ƃ̂��Ƃł�����܂��v�ƕ��������B (���ɂ��Ă₪��)�ꍇ���ꍇ�����ɋC�������Ă�������A�������̍j���������Ƃ��āA�u�������l�ɂ��`�������B��B�͂��̐��m��ۖh�q���l���̎�z��ł����������B��p��������Ȃ�A������l���痈��A�Ɛ\���v�Ƃ�߂����B (���Ȃ�����l�ł͂Ȃ���)�����v���̂��B�������́A�ƍN�̐����Ȃ����͎�l���l�ł���B�߂����Ȃ�Ζ@�I�ɂ͕���l�ł���A�j���Ƃ����Ȃ��B�������ƍN�̎q��ł��Ȃ�����A�u���ܗl�v�Ƃ�������Ȓn�ʂł��Ȃ��̂��B (�[�̉������鏗����l������قLĵ��āA�|��Ƃ镐�ҕ���̂���́A���̂��Ȃ��ǂ��̊{�ł�����قǂɉ��ڂ�)���f�Ȃ�u�N�����������v�Ƃ������ƂŔ[���̂������Ƃ����A�����ƂȂ��Ă͂���Ȑ����̒ʔO�������Ȃ��Ȃ����B |
|
|
��������������j�������喽�ɔw�����̂ŏ��̖v��
���ɂ́A�����̐��U����������錠��������B���̂��߂ɂ́A�喽�ɂ��w�����Ⴊ�Í���������Ȃ��B���̖�ځA��߂���ƐS����ł߂��B �����A�Ɨ����c���A�j���͂��̎l�Y���q�剮�~����p������܂��Ă���B �����ɓ���A���������Ă��炢�A������m�ۂɕ��������Ă����A������\�O������J�n���ꂽ������̍U�h��ɎQ�����A�����������̓��A���킵�Ă��ɑ������āA�e���Ƃ�A�e���l�߂����l�߂������Đ키�����ɂ���܂��ē�d�ɑ����B��������ƉΖ�̉ߏ�̂��ߏe�g���剹���ƂƂ��ɔj�A�葫���l�U�����Ď����������B �փP���̖���A�ƍN�͑���ɐi�o���A�����ɒ������Đ��R�̏��̖v���Ɩ����̏����m���̘_���s�܂������Ȃ����B ����j���͏��̖v���ł���B���쟀���̂Ȃ��ł͗B��̗�O�Ƃ����Ă����B �u����͂��܂�Ɉ���ȁv�ƁA���h��������u�`�l�v�Ƃ����Ă���{�����M�ł������A���Ȃ����B �j���͎����o�債�ĕ�����ɓ���A�G���ł����]�����قǂ̑s��ȓ����𐋂��Ă���ł͂Ȃ����B �ƍN�́A�����Ȃ������B �u���̎҂͈ꌩ�A�����Ɏ��Ă���B�������킵��������������a���ɂ��A����𑼐l�̎�ɂ������n���A���Ԃɕ������Ă����Ď��Ԃ̎��𐋂��Ă���v�j���̕s�K�́A���A�_�l������o�Ă����������炪�A�ƍN�Ɍ�������߂čj���̈��������������Ƃł������B �u�킽�����ǂ��O�l�A���x���Q���悤���Ǝv���܂�����قǂɐS�ׂ��������܂����v�Ƃ������������̌��t���A�ƍN�̐S�ɂ悢�e�����������A���̉Ս��ȁA�ٗ�̏��f���������B |
|
|
�����叫�̋���
�����q�́A�߂���H���͂��߂��B��Â݂�ł��A�傫�ș������āA���Ă��Ă��s���Ȃقǂ̐����ŐH�������ƁA�u���v�u�͂��A����Ɂv�R�I�́A�����q�̘o�ɒ����������ł��Ȃ���A�u�ȁv�ƌĂB �u�ȁB���Ƃɂ���܂��鏬��Ɛ\���҂��A�n�ӗl�́A�s��ǂ̂ɂȂ���܂����ȁv�u����H�m��ʂȁv�Ƃ����Ă���s�ӂɎv���������炵���A�u�����A���ꂩ���v�u���ꂩ���A�ł́A�Ђǂ��������܂��傤�B���������Ɏs��ɂȂ���܂��������ɁB���Ȃ����̐g���A�������ł������܂��v�u�����q�́A�ނ肶���ɂ��Ȃ���ɂ߂����ƂȂǂ͂Ȃ��B���̂Ƃ��A�܂��˂ނ�ق����Ă��Ă悭�o���Ȃ��A����Ƃ̔��������Ȃ��ł������B�����O����A���ɎO�x�A�V���������������邲�ƂɁA���̎s��́A�����q���Ƃ���H���R�̎҂������イ�v���Ă���Ă���l�q�ł������䂦�A�����A���������d�V�ɂȂ����v���A�Ƃ��������B�����q�́A�R�I�Ə�����ԈႦ�Ă���炵���̂ł���B�т̉��ɂ߂����������ꂽ�B ���̂Ƃ��A�R�I�����������߂��Ă���A�R�I�͓��Ƃ��o����Ȃ��͂߂ɂȂ������Ƃ��낤�B�R�I�́A�Ȃ�قǐQ�Ă��銨���q�����炩���͂����B����������͂����܂ł��u���S�v�ƌv�Z���Ă̗V�тŁA����݂����Ă܂ł��ĕv�łȂ��w���҂ƒʂ��悤�ȂǂƂ����s��̋C���́A�тقǂ������Ă��Ȃ����肾�����B |
|
|
���������ՂƓn�ӊ����q
���̏d��Ȉ�u�ŁA�����Ƃ̍��Ղƕ����Ƃ̊����q�Ƃ̂������ɒv���I�ȐH�����������ł����B�����q�͍��Ղ��t���ė��ʂ̂��݂�Ƃ������ň����������A�u�a�́A�̂ɂȂ����v��̘\�����߂�Ƃ��ɖ����R�z�̂��Ƃł���B���Ղ͗�����B �u�킳���V���̎d�u�̈���B���ʂ�ɉ����킩�낤�B�������֍s���v�u�킳�͏��Ă悢�̂���B�G�������ɂ���̂Ɍ���̌�{�w�̊�F���݂Ēx�^����n�����ǂ��ɂ���v�u��l�ɂނ����Ĕn���Ƃ͉�������v�u�n���͔n���Ƃ��������悤������܂��v�����q���ڂ��������A���̎蕺�O�S�͍������̂悤�ɂȂ��Ē��]�䕔���ɒǔ����A�v�Ō��˂��ČܕS�ɂ��܂�G�̌�q������ב������A����ɒ��낵�ĕ���܂Ői�o���A���������ʂ���s�����Ă�������̎c���̗�𐡒f���Ă���ɔj�����B ���R�̏����̂����A�����q�قǂ̍L��Ȑ������܂Ȃ��킯���҂͂��Ȃ������B�ےÁA�͓��̖�����C���̂悤�ɋ킯�܂���������q�̓����́A���R����̐��������������A��l�̍��Ղ����݂͂Ƃ߂Ȃ������D �F�߂Ȃ��̂��A���R�ł��������B���̓��̊����q�́A�������Ƃ͉��̊W���Ȃ��y�삵�Ă����ɂ����Ȃ���������ł���B �킢���I���Ă��犨���q�́A�����Ԃ��̂����w�H�D���ʂ����āA���炠�炵�����Ղ̖��c�ɓ����Ă��āA �u�a�A�Ȃ��킵�ɕt���ĎQ���Ȃ��B�����킵�̎�ɎO��̐l����������A���̂Ƃ��A���]�䕔���^�c���ї�������ɑދ�����������şr�łł������ł������B����A�������̕��E�ő����U�߂��Ƃ����Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����v���Ղ͉����ނ�������Ԏ������Ȃ������B ���̐�����A���̐��ł��Ȃ��G�Ɛ������ɒ��F���A���ՂɁA�u��ƒ���⥂̎w���͉��҂ł����邩�v���Ղ͒��ق����B�������̂��Ƃł���������ł���B �u���̎w���̕���́A�k����G���a��Ȃт��葫�̂��Ƃ��R�������m���Ă����B�����ς�卄�̎m�Ƃ݂܂������A�������ł͂�����Ȃ��v���ƂŊ����q�͂��̘b�������A�u���Ƃ̑叫�ɒm��ꂽ�����ł����҂Ƃ��Ă��߂Ă��̎d���킹�ł�������v�ƁA�ɉ�A�w��A�ɂ킩�ɘ\��ԏシ��ƁA�����Ƃ�ޓ]���Ă��܂����B |
|
|
�����Ă̐w�E�����q�̍Ŋ�
�u�^�c�́A���ʂ��B�|�v�����q���A��s�Ƃ͒m����v�킸�⋩�����̂́A���̂Ƃ��ł���B���܁A�^�c�R�ꖜ���̌�l������A����➃��ł����Ɨ\�����𓊓����Ĕ�J���ƌ�ւ����A����ɎR��ɖL�x�ȏe�w��z���ēG�ɗ��˂���A���R�ב��͕K���ł������B���A�R��ɏ��{�𐘂��Ă��閔���q�́A�ӊO�Ȃقǖ��邢������Ă����B (���������ł͂Ȃ���)���Ă��A�ł���B����Ō��Ăǂ���^�c�R������A�����̏����ɂ͂Ȃ邪�A��������p�Ƃ��Ă��̐������������ꂽ�B (����ł���)�ǂ����ق�т�̂��A�L�b�Ƃ́B�����q�Ƃ��̔z���̘S�l�ɂ���A���m�炵�����U�������ʼn₩�ɏI�邾���ł����B �����ڂ����B �����q�̎蕺�͔�J�������Ă������A����ł�����̂Ȃ����悭�삯�܂���Ă���B���A���R�́A����̑��R�����łȂ��A���R�̖{�������ܐ�A��l�R�̈ɒB���@�ꖜ���A���łɐ��ɓ������������B �����q�́A����͂悵�A�ƌ��ď��{��|���ė���������A�킸���O�\�R�̊��{�ƂƂ��Ɉ�c�ɂȂ��ĎR���삯�~��A��j���\���ɂ���H��ɂƂт���悤�Ƃ����u�ԁA�e�e�ɋ����˂ʂ��ꂽ�B���A���n���Ȃ������B �����Ĕn���Ă������{�̋��n���E�q����Ƃ̏ォ������Ƃӂ肩����A�u���E�B���łāB�G�Ɏ�炷�ȁv���������āA�Ə�ɕ������B���łɁA�����₦�Ă���B �����q������قǑ҂��ʂ����^�c�K���̑��R�́A�\���莵���Ԓx��Đ��ߑO�A�悤�₭���䎛���̎�O�ɓ��������B�锼�N�̊��ɓV���������o�������Ƃ�������A�s�����x�́A�ꗢ���O���Ԃ������������Ă���B�K���قǂ̐_���ȍs���͂������������̂��̂��ǂ낭�ׂ��x���́A���Ȃ����A�Z���̂�������Ƃ͂����Ȃ����낤�B �K���́A�����炭�A�����Ƃ͂��A���A��͂蕺�������������ƁA�r���v�����������̂ł��낤�B�^�c�R�͈ꖜ���ŁA�����ő�̗V�����͂ł���B���ꂪ�A�ނ��ނ��㓡���Ă̍����̉@�y���ő��Ղ���A�K�����g�A�X�������ꌤ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B (�����q�͖����q�̎��ꏊ�Ŏ���)�K���́A�v�����ɂ������Ȃ��B�ׂɕs�l��ł��Ȃ��A�����q�Ƃ����R���Ƃ�����ɂӂ��킵���D�݂̐��Ŏ��Ȃ��A�����Ƃ����R���Ƃ��܂��A���̌R���������Ǝv���ꏊ�ŁA������ �����v�����ɂ������Ȃ��B �K���́A�����������䎛���܂Ői�o���������R�Ə������������������ł����ދp���A�������A����̌R���������Ƃ���������匈���ł����O�l�V�����̑�n�ŁA���R�\�����Ɛ킢�A�����Γ˂������A�ЂƂ��т͉ƍN�̖{�c�ɂ܂œ˂�����A�Ǖ��̖��Ƃ��Ă͂قƂ�Ǘ��z�I�Ƃ����Ă�������������A�ߌ�A�l�V��������𓌂ւЂ��������������V�_�̋����ʼnz�O�������m���q��Ɏ���������B��◎��́A���̗����ł���B�G���͂��ɏ����o�Ȃ������B |
|
| �@ | |
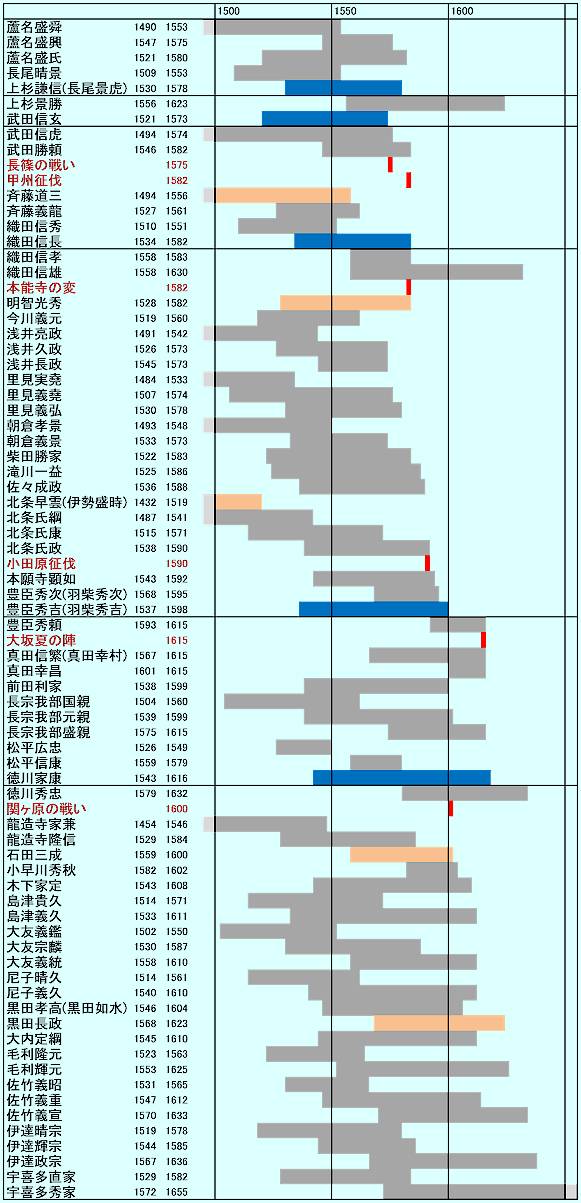
| �����c�M�� | |
| �@���R�{���� | |
| �@ | �@ |
| ���㐙���M | |
| �@�����]���� | |
|
���㐙���M�ƓD��������V
�u��������V�Ǝv���v�A�z��̌ՂƌĂꂽ�R�_�E�㐙���M���������L���Ȍ��t�ł���B49�N�̐��U��70��킢���s���A�������̂͂�����2�x�����Ȃ��A������95.6���Ő퍑�喼�̒��ł̓g�b�v�B�퍑�ŋ��̕����ƕ]������Ă���B���̌��M���c���̍���������M���Ă����̂�������V�ł���B���M�͔�����V�𐒔q���Ă����݂̂Ȃ炸�A����������V�̉��g(���܂�ς��)�ł���ƐM���Ă����B �w�������s�^�x�ɂ́A���̂悤�ȏے��I�ȃG�s�\�[�h���L�^����Ă���B�㐙�Ƃł͖�������킷�Ƃ��A����E�t���R����̔����哰�ōs���̂���Ƃ��Ă����B������V�����J���Ă����ꏊ�ł���B���M���܂��A�����߂āA�d�b�ƈ�Ƃ̎҂����ɕ��Ԃ��ƂɂȂ��Ă����B���鎞�A���ɈꝄ���N����A�}篁A�Ԓ�(�X�p�C)������ƂɂȂ����B�������A���M�́u�}���˂Ȃ�ʁB�o���ɂ������Ă��̎҂�����哰�܂ŘA��čs���A������V�ɐ�����Əo�����x���Ȃ�B������̑O�Ő��킹��v�ƌ������B�V�b�����͈ٗ�Ȃ��Ƃ��Ǝv���A���ɏ]��Ȃ������B���M�́u�䂠�����������V���p������B��Ȃ��Δ�����V�����肦�Ȃ��B��������V�Ǝv���āA��̑O�Ő_��(����)������v�Ƃ����Đ_���������Ƃ����B����Ɍ��M�́A�u�䂪������V��S�x�q�߂A������V�����50�x��30�x�q�܂�����悤�v�Ƃ������A������V�Ƃ̈�̉���M���Ă����B ���M�͐퍑�����̐킢�����������A���肷�邽�߂ɁA�z��̋���ł���t���R����ɔ����哰�����ĂāA������V���J��A�����̂悤�ɂ������Ă�njo���A�F�O���Ă����Ƃ����B����ɏo�w�O�ɂ͐����ԁA�Ă葱���ď������F�肵�āA���̐_�͂悤�Ƃ����B ���̔����哰���J���A���M�����q���Ă���������V�����A�đ�ˏ㐙�Ƃ̕�E�@�����Ɉ��u����Ă���B���̕������ǂ̂悤�ȗ͂��߂āA���M�͂ǂ̂悤�ɂ����J���Ă����̂��A�@�����̍����Nj��Z�E�Ɏ�ނ�\�����B �@ |
|
|
���D��������V�͍���33�Z���`�̐����̕����ōd���ȏd�������Y���Ă���
4�����{�A�܂������炭�O�œ��A�ɐႪ�c���Ă���đ�s��K�ꂽ�B�đ�w����^�N�V�[�Ŗ�10���B�đ�ˎ�㐙�ƌ�_���Ɨאڂ��Ă���@������q�˂��B�㐙�ƌ�_���ɂ́A����S�N�̐��̖Ɉ͂܂�āA���M�̗�_�𒆐S�ɁA���̍��E�ɗ��ˎ�̗�_�������ɕ���ł����B �@�����̖{���ɓ���ƁA�����Ɍ��M�Ə㐙�Ƃ̌�쏊������A�������ĉE�ɑP�����@�����A�����ĖړI�̔�����V���͍������J���Ă����B �g�̏��33.5�Z���`�B�����̕����ŁA�d���ŏd�X�������͋C���Y���Ă���B��҂Ɛ���N��̋L�^�͂Ȃ����A���q����̖��H�̍�Ɠ`�����Ă���B����̏�ɓk(�j�����o)�Ɣ����k(�r�����o)�̓�S�݂��ė����A�S�͋��̕\����ׂĂ���B���ɂ͕A�g�ɊZ�����A�E��͍��ɓ��āA����ɕ������A�����̕��l�̎p�Ő��ʂ��������\����ɂ݂��Ă���B ��������������V�Ƃ́A�u�@���v�u��F�v�u�����v�u�V�v�ɑ�ʂ���镧���̂����A�u�V�v�̃O���[�v�ɑ�����B�u�V���v�ɑ����鏔���́A���@�̎��_�Ƃ����Ӗ����������B�u�V���v�̐_���\����҂ɁA���������l�V��������B������k�̕��ʂ����_�Ƃ��āA�u�����V(�������Ă�)�v�u�L�ړV(���������Ă�)�v�u�����V(�������傤�Ă�)�v�u�����V(������Ă�)�v������B ���̒��Ő��R�ł���{��R�̖k�������̂��A�����V�B�T���X�N���b�g��Ń��@�C�V�������@�i�Ƃ����A������V(�т������Ă�)�Ɩ��B�k�͋S��ɂ����邱�Ƃ���d�v������A�����V�͎l�V���̃��[�_�[�ōŋ��Ƃ����B���̎O�V�������������������Ȃ��̂ɑ��āA�����V�͎O�̏�����B���̒��S�I�Ȉʒu���߂邱�Ƃ���A�l�V���̒��ł��P�Ƃ��J���āA�M�����悤�ɂȂ��Ă������B�l�V���̂ЂƂ�Ƃ��ẮA�u�����V�v�ƌĂ�邪�A�Ƒ��Ƃ��Ắu������V�v�ƌĂ��B �u����v�̖��O�̒ʂ�A�����̋����̑������āA�l�X�ȋS�_���]���āA���������A���Ȃ��̂��t���Ȃ��B������V�̕���������ƁA�S�̊炪�t���Ă���B�ʏ̓V�S�Ƃ�����S�_�ŁA�����͐��_�̖��ł������B�����̋����Ƃ��̐M�҂ɊQ�������炷���̂̏ے��ł���B������V�́A���̐l�ԍő�̓G�ł���ϔY�����ނ��Ă����_�Ȃ̂ł���B �܂��A���Ƃ��ƃC���h�_�b�ł́A����_�N�x�[���ƌĂ��x�ƍ���̐_�ł��������Ƃ���A�n�R�_��ǂ������͂�����Ƃ���A�������㖖���Ɏ����_�M���L����ƁA���̒��̈�_�ł��镟��������u�����傳�܁v�Ƃ��ĐM�����悤�ɂȂ����B �@ |
|
|
��������V�������M�̐��܂ŏo�����ĉ����������Ղ��A���Ɏc���Ă����c�c
�ł́A�Ȃ��@�����̔�����V���́u�D���v�ƌĂ�Ă���̂��H�����Nj��Z�E�ɁA���̂����������������B�����Z�E�́A�������ƁA���ɂ킩��₷�����������n�߂��B�u���鎞�A���M�����������Ă�A���O���ċF�肵�Ă����Ƃ���A�����A�얀�d(���Đ_���ɋF��C�@�̂��߂̒d)�̏ォ��O�Ɍ������āA�_�X�Ɣ�����V���̓D�̑��Ղ��c���Ă��܂����B����͌��M���̐�w�܂Ŕ�����V���o������āA�����삯���������ꂽ�Ղł���A�Ƃ������ƂŁA�ȗ��A�㐙�Ƃł͂��̑��Ɂw�D���x�����āA�D��������V�Ƒ��̂��ČĂԂ悤�ɂȂ����̂ł��v ���̐킢�����ł������̂��A�L�^�ɂ͎c����Ă��Ȃ����A�����A�퍑�����̊Ԃōŋ��ƐM�����Ă���������V�ƌ��M����̉������p�́A���m�����̎m�C�ɑ傫�ȉe����^���āA�s�s�_�b���d�˂邲�ƂɌ��M�Ɣ�����V�ɑ���M�����߂Ă��������Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B �@ |
|
|
���얀���A���Ŕ�����V�̐^���������Ȃ���A��̂ƂȂ�C�s������
�u�������A���M���͋�̓I�ɂǂ̂悤�ɂ��āA�����A������V�ɋF�肵�Ă����̂ł��傤���H�v�����^��Ɏv���Ă����̂́A���̕��@�_�ł���B�����Z�E�͂��̎���ɑ��āA�u���M�����A�˂��Ă����@���͐^���@�ł��B�^���@�͖����ł��̂ŁA�\�ɏo���Ȃ��̂ł����v�ƑO�u�����Ȃ�����n�߂��B �u��C���J�c�ł���^���@�̋F���̊�{�́A�O���ɂ���܂��B�O���Ƃ͕��l�̐g�E���E�ӂ�3�ŁA�l�Ԃ����̎O���̏�ԂɂȂ�悤�ɏC�Ƃ��邱�Ƃɂ���Ė{���ƈ�̂ɂȂ邱�Ƃ��ł��A���g�����̋��n�֓��B������̂ł��B�܂�A���M���̏ꍇ�͔�����V�ƈ�̂ƂȂ邱�Ƃ�ڎw���Ă����킯�ł��B��̓I�ɂ́A�얀���ĐS�Ŕ�����V���F�O����B�����āA���Ő^���������܂��B�������Ƃɐ^�����Ⴂ�܂��̂ŁA���M���͔�����V�̐^�������x���W�����ď����Ă��܂����v�^���͐��ɏo���Č����Ƃ��������A�S�ŏ�����̂��Ƃ����B �ł͔�����V�̐^���Ƃ͉����H�u�I���E�x�C�V���E�}���_���E�\���J�v(�I�[���A���B�V�������@�X�̌�q��A�g�ː��A)���̐^���������邱�ƂŁA����ɒ��ړ��������邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă���B �u��̓I�ɂǂ̂悤�ɂ��Ĕ�����V�ƈ�̉�����̂ł��傤���H�v����ɐq�˂��B�u�^���������邱�Ƃɂ���āA���l�̒��Ɏ����������Ă�����Ƃ������ƁB�����ɕ��l�������ɓ����Ă��Ă����B���̏�Ԃ��w�������x�Ƃ����܂��B�����ƕ��l�����݂��Ɉ�̂ƂȂ�悤�ɏC�s����̂ł��v����ȏ�́A��l��l�̑̌��ƏC�s�̐��E�Ȃ̂ŁA���t�ŗ������邱�Ƃ�����Ƃ����B �������A�^���@�ɂ����Ă͎����ƕ��Ƃ̈�̉��́A��ʐM�҂ɂƂ��Ă����R�̖ړI�ł��邱�Ƃ��킩��B�܂�A���M�����u��͔�����V�̐��܂�ς��ł���v�ƐM���āA�������邱�Ƃ́A�^���@�̗��ꂩ�猩��Ƃ���قLj�a�����Ȃ����ƂȂ̂��B �@ |
|
|
���o�w�̍ۂɁA�u���v�̊���Ɓu����������V�v�̉摜���f���Ă���
����Ɍ��M�͏o�w�̍ۂɁA�㐙�R�̊���Ƃ��āu���v�̈ꎚ��p���u����(�Ƃ��͂�)������V�v�̉摜���f���Ă���B���́u����������V�v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A�����Z�E���܂Ƃ߂��w�@�����̗��j�ƕx�ɋL����Ă���B����ɂ��ƁA�u���v�͔�����V�̔����̂��̂ł���A�u����������V�v�̎p�́A��g�ܖʏ\�]�ō��E8�{�̓��������A����2�{�̘r�ɂ͕����ƌ�(����)�Ƃ����镐�����ɂ��āA�����ɂ͎��q�܂��Ă���B�u�����v�Ƃ́A���Ƃ��ƒ�������́u�p�덑(�Ƃ�)�v�ɉ������̐_�Ƃ��ĐM����Ă����B���̎v�z�����{�ɓ`���A�u�p��v���u�����v�Ƃ��������ɕϊ�����āA������V�ƍ��̂����J����悤�ɂȂ����Ƃ����B�����Z�E�́A���́u����������V�v����ɁA���M���Ƌ��ɂ������ƌ��B �����āA���M�̔�����V�M���悭�\��Ă��āA�����̊�����p��������̂Ƃ��āu��禘���v(�ԂĂ�����)�Ƃ����o�w�̋V�������邱�Ƃ����������B���̋V���ł́A�͂����Ăǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��s���Ă����̂��H�����̏@���Ɛ_���`�����̑��l�҂ŁA�퍑���������̎�p�ɂ��Ă܂Ƃ߂��w�퍑�̎��@�x�̒��ҁA������ێ��Ɏ�ނ�����@����B �������ɂ́A�V�h�̋i���X�ł�����邱�Ƃ��ł����B�������p�ɐ��ʂ��Ă���Ƃ����C���[�W���������������A�퍑�̌R�z�҂͂������̂悤�ȕ��e���낤(����I)�Ǝv����Ɠ��̕��͋C���������B ��禘���̑O�Ɍ��M�́A�܂��t���R����̌얀���ɓ���A�u�ܒd�얀�v���s���Ă����A�Ɠ������͌��n�߂��B�u�ܒd�@�́A�^���@��V��@���s���Ă����傪����Ȍ얀�C�@�ŁA�C���h�`���̓`���I�ȋV���ł͂Ȃ��A��������ɁA���{�ō��ꂽ�C�@�ł��B�㐙���M�����ł͂Ȃ��A���̕����ł����ɂ悭����Ă��܂����B�����̒d�ɂ͕s�������A���d�ɍ~�O��(��������)�����A��d�ɌR䶗�(����)�����A���d�ɑ�Г�(�������Ƃ�)�����A�k�f�ɋ����鍳�����ܑ̌呸���A���̐��ɍ~�Ղ����āA�����ĉ���Ɖ��G�������F�邽�߂̋V���ł����v���S�ɂȂ�͕̂s�������ŁA6�l����8�l�̈�苗�(�������)���s�������̋V�����s���B�����āA����4�d�ɂ͂��ꂼ��4�l����6�l�̑m�������āA�e���̖@���C����Ƃ������̂��B �����͓V�c�ƂȂǂň��Y�F��̖ړI�ōs���Ă������A����ɁA�����S�����A�����āA�퍑����ɂȂ�ƓG��|���A����������̂ɕω����Ă������Ƃ����B �܂�A������ێ��ɂ��ƁA�ܒd�얀�͐_���̉���邾���ł͂Ȃ��A�G��|�����߂̋V���Ȃ̂��Ƃ����B���̑��ɂ��A�M���⑼�̕����������s���Ă��������̎�p�ɂ��āA���낢��Ռ��I�Șb�����f�����邱�Ƃ��ł����B�������A����̃e�[�}����͗���Ă���̂ŁA�܂��@����݂Ă��̕��������̎�p�̑S�e�ɂ��ďڂ����Љ�Ă��������B ���āA���̌ܒd�얀���I����Ă���A���̋V���Ɉڂ�B�u�����哰�Ɉڂ�A���_�ł��������V���q���āA�폟���F�肵�܂��v�������炪��禘���ƌĂ����̂ɂȂ�B�u������V�Ɍ����Ă������_��(�ܟ����E���Ă�)�������ɋ���ŁA�����폟�F��̐_���Ƃ��ď��������ɕ����^���Ă����܂��v���Ɍ��M�͒�ɏo�ď��{�ɍ����A�R��s���o�w�̂��߂ɑS�R�̏W���������āA�叫�N���X�������Q�W����B�u���̎��A�ŏ��ɓ��ꂷ��̂��w���x�̊������������叫�ŁA���ɓ����Ă���̂��㐙�R�̏d��ł���w�����̌�|�x����������ԑ叫�A�����āA�֓��Ǘ̏㐙�Ƃ̕ł���V���̌���������ē���܂��v�����ďo�w�̍ۂɁA�R�_�����̖@���L���������B���̌�A���M�͔n�ɏ��A���̌R����擪�ɂ��āA�t���R��̑��傩����ɏo�w���Ă������Ƃ����B���ꂪ�A���M�̕�禘���ƌĂ��o�w��@�ł������B �Ȃ��A���̕�禘���͌��݁A���y�����ƂȂǂɂ��₩�Ȃ��Ղ�Ƃ��čČ�����āA���N5��2���ɍs���Ă���̂ŁA������������͊ςɍs���Ƃ������낤�B ���̂悤�Ɂu���v�̊���́A�㐙�R�S�̂̃V���{���Ƃ������ׂ����̂������̂ł���B �@ |
|
|
�����M�̔�����V�M�́A�c���̍�����|���Ă�����
�ł́A���M�̔�����V�M�ƕ����ւ̐M�S�́A��̂�������A�ǂ̂悤�Ɍ`������Ă������̂��H���M�̗c���̍��ɂ܂ŁA�k���Ă݂Ă������B �㐙���M�́A���\3�N(1530)1��21���A�z����㒷���i(���߂���)�̖��q�Ƃ��ďt���R��Œa�������B�ДN���܂�̂��߁A�c�����Ր��Ƃ����B��͐��g��(�����s)�咷�����̖��ŌՌ�O�ł���B�㐙���M�Ɋւ��錤�����Ёw�V�����l���`�@�㐙���M�x(�V�����Ǝ�)�ȂǑ����̌��M�����̒������o���Ă���ԃ��O�������ɂ��ƁA��́A�M�S�Ȑ^���M�҂ŁA�ϐ�����F��M���Ă����Ƃ����B�ϐ�����F�́A����ɔ@���̘e���Ƃ��Ĉ��u����邱�Ƃ����邪�A�Ƒ��Ƃ��ĐM�����ꍇ�́A�������v�I�ȐM�������B������l�X�́A������肢��������Ƃ����B ���M���[���^���@�ɋA�˂��邱�ƂɂȂ�̂́A���̕�̉e�����傫���������̂Ǝv����B �����āA�V��5�N(1536)�ɏt���R�鉺�ɂ��鑂���@�̒����Ƃ̕�ѐɗa����ꂽ�B�����Ė��m�V������(�Ă�������)�T�t����14�܂ł�7�N�ԁA�������T�̏C�s�����Ƃ���Ă���B���M�̑f�{�́A���̌���ɂ���Ĕ|��ꂽ�ƁA�ԃ��O���͎w�E���Ă���B���̂܂ܑ傫�Ȕg�����Ȃ���A���M�̏����͗ѐ̑m���ƂȂ��Ă����͂��ł���B �������A�헐�̐��͌��M�ɂ��̂܂ܑm���̓���i�ނ��Ƃ������Ȃ������B�Z�̐��i���a��ŁA�����͂��Ȃ��������ߍ����������������N�����z�㍑���������Ă����̂��B�V��12�N�A���M�͌Z�������邽�ߊґ����ēȔ���ɓ���A���i�ɔw�������c�G���̈�R���A���w�Ō����Ɍ��ނ���B�܂��A�Ȕ���ł̐l�]���������ɍ��܂�ƁA���ɏt���R��ɌĂі߂���āA���㒷���Ƃ𑊑������B���M��19�̎��ł���B �Ȍ�A���M�͍����ƍ��O�̗l�X�Ȕ��������߁A�킢�ɖ������邱�ƂɂȂ�B�֓��Ǘ̏㐙�����̎x���A������24�̎��ɂ͕��c�M���ɂ���ė̓y��D��ꂽ�M�Z�����������片�������߂��Ă����B���M��8000�̕��𗦂��ĐM�Z�쒆���ɏo�w�����B���ꂪ��1��쒆���̍���ł���B ���̂悤�ȍŒ��A���M�̔�����V�ւ̐M�����悢��[�܂��Ă����B�w�㐙�N���x�ɂ��A���M�͐M�B�쒆�����ɂ������^���@�̎��@��掛���A�t���R��̖k�̊ۂɈړ]�����B��掛�̒��C�a������^�������̉�����������ꂽ�B���̉����̂Ȃ��ɂ͏��Ɖ��A���H�ȑщ��Ȃǂ������āA��������邽�߂ɕ�������얀���āA�u�s����Ă���߂�C�@�v���s���Ă����Ƃ����B �@ |
|
|
�����M�͔�����V�ɑ����ď㗌�@����R�̈�苗������Ɏt������
�����Č��M�́A�^���I�Ƃ�������s���ɏo���B�ԃ��O�������́w�㐙���M�x(�V�l��������)�ɂ��ƁA�u���M�͔�����V�ɑ����ď㗌���A����Ɩ��{���ċ��������Ƃ����傫�Ȗ��������Ă����v�Ƃ����̂ł���B �V��22�N(1553)�A���M�͏]�܈ʉ��e�����J�ɏ��C���ꂽ���Ƃւ̂���𖼖ڂɁA��2000�𗦂��ď㗌�����s�����B��ޗǓV�c�ɔq�y���āA�V�u�ƌ䌕���������B�����āA�V�c����u�Z���Ȃ�тɗ��̓G�����A�Ж����q���ɓ`���A�E����Ɏ{���A���悢�揟��痢�Ɍ����A�����꒩�ɐs�����ׂ��v�Ƃ��d�|(���)�����B����ɂ���āA�헐����肷���`�������o�������ƂɂȂ�B ����ɁA���M�̐M�S�ɂƂ��Č���I�ȏo�������A���̋@��Ɏ������āA�ݑ��̂܂ܗL���̑m�ƂȂ������Ƃł���B�@���́u�@�S�v�ł���B�����āA�ȑO����O�肵�Ă�������R�֎Q�w���Ă���B����R�ł͖��ʌ��A�̏Z�E��苗�����(��������)�ɉ�A�����̋��������B�����͌��M���8�ΔN��ł���A�����z��o�g�ł��邱�Ƃ���A���҂̌𗬂͐[�܂�A�Ȍ�A���M�͐^�������̎t�Ƃ��Đ����Ɏt�����A�����̐^�������߂Ă����̂ł���B �i�\2�N(1559)4��3���A30�̌��M�́A��2��ڂ̏㗌���ʂ����Ă���B��106�㐳�e���V�c�ɔq�y���Đ��X�̕��������サ�āA��1��ڂ̎��Ɠ��l�ɓV�c����V�u�ƌ䌕���������B���R�����`�P�ɂ͌܃����̐������C�߂āA�����𐾂��Ă���B�����āA����R�ɓo��A���ʌ��A��苗������ɉ�ɍs���A���������C�̐^�M��{������ꂽ�B �@ |
|
|
��45�̎��ɓ`�@���āA�@�̂ƂȂ�A��苗��̈ʂɏA��
���M�̐^�������ւ̌X�|�́A�����܂ł��1�i�K�Ƃ���ƁA���x�͐^�������̐����ȑm���Ƃ��Ă̈ʂ邽�߂ɁA4�i�K�Œ��_�܂ŏ��l�߂Ă����B ���̕ӂ̏ɂ��ẮA�����������w�_�ɂȂ����퍑�喼�x�̒��Ō�������A�܂Ƃ߂��Ă���B�^�������Ő����Ȏ��i��������V���Ƃ��āA�u��(���傤)�v�ƌĂ����̂�����B���ɐ����(����)���ŁA�������䶗��Ɖ������сA���̎��i������邽�߂̏d�v�ȋV���ł���B�ɂ́A����(��������)�A��(����݂傤)�A�`�@�Ȃǂ̎�ނ�����B�������ɂ��ƁA���M���ŏ��Ɏ��́A�i�\5�N(1562)�A33�̎��A�ܒq�������Č����ɖ��ʌ��A��苗������������čs�����A�ł���ƍl���Ă���B���̌����́A��ʂ̍݉ƐM�҂��ΏۂƂȂ�V���ŁA�����������邽�߂̏����I�Ȃ��̂ł���B�́A��q�Ƃ��Ă̎��i�āA���������A�C�@�����H���鋖�邱�Ƃ��Ӗ�����B�܂茪�M�́A�����ɐ������t�Ƃ��āA�����̏C�@�����߂铹�i�ނ̂ł���B �����đ�3�i�K�́A�V��2�N(1574)12��19���A45�̎��A�z��։������Ă����������}���āA�l�x���s�Ɠ`�@���������B�l�x���s�Ƃ́A�\�����A�����E�A�얀�A�ّ��E�̎l�x�̏C�s����Ȃ�B�����̏C�s���s���A���M�͖@��(�m���̎p)�ƂȂ��ďo�Ƃ����B�����Ė@���a��(�ق����������傤)�Ƃ����ʂ����������B���M�͂��̎��ɒ䔯�������ƂɂȂ�B �����2�N��A���M�͟��A��������^�������̔�V�����Ƃ��Ƃ��������āA���Ɉ�苗�����m�s�ƂȂ�B���̓`�@�͖����̟̒��ł��ł��d�v�ȋV���ł���ƁA�������͐�������B��苗��Ƃ����w���҂̈ʂāA���`�Ȃǂɂ���q�������w�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B��苗��Ƃ������i�́A�����̏C����[���ς҂ɂ����^�����Ȃ��B���M�̔�����V�M�́A�^�������̑m���ւƓ����A���Ɂu�키�m���v�̎p�́A�����Ŋ�������̂ł���B �@ |
|
|
��������V�̑��ɁA���M�͐��J�s�����ƑP�����@�������J���Ă���
�����܂ŒǐՂ��Ă����悤�ɁA���M�̒��S�I�ȐM�͔�����V�ł��邪�A���́A������V�̑��ɂ����M���鏔�����������B�퍑�����̕��_�ɑ���M�́A���M�̂悤�ɏ@���S�����ɋ��������ł����Ă��A�B���̕����݂̂ɋA�˂��邱�Ƃ͂Ȃ������B���{�̐_�l�╧���ɂ͓��ӂƂ���W������������A���������̓P�[�X�o�C�P�[�X�ŖړI�ɉ����ėl�X�Ȑ_����M���āA���̉�����F���Ă����̂ł���B �����Č��M�̏ꍇ�A������V�̑����J���Ă��������Ƃ��āA�đ�s�̖@�����Ɉ��u����Ă���s������������B�����ōĂэ����Nj��Z�E�ɓo�ꂵ�Ă����������B�u���M�������_�Ƃ����J�������l�́A�@������3�`�����Ĉ��u����Ă��܂��B�ЂƂ́A�D��������V�ł��B���̑��ɁA���J�s�����Ɛ�Δ镧�̑P�����@����������܂��v����ł́A���J�s�����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȏp�����Ă���̂��H �u���̕����́A���q����ɐ��삳�ꂽ�Ɠ`���ؑ��ŁA���̍�����28�Z���`�̕s�������ł��B�V�����k�����S���J�ɖ����썑���Ƃ����A��O��l�ɂ���đn�����ꂽ�^���@�̂����ɂ���܂����B���Ɋ�a�����̖����g���J�s�����h�Ƃ��đ����̎Q�w�҂��W�߂Ă��܂����v����5�N(1253)�A�������ŏĎ��������A�s�����ɒr�̂��ɂ����t�����āA�ޏĂ��܂ʂ��ꂽ�Ƃ����`�����c���Ă���B���M�����̑��ɐ[���A�˂��Ă����̂ŁA�㐙�ƂƋ��ɕđ�Ɉڂ���āA��X�J���@�����Ɉ��u����Ă����Ƃ����B ����ɐ�Δ镧�ƂȂ��Ă���P�����@�����ɂ́A�퍑�喼���������̔@��������ɓ���悤�ƌ��������D�킪�s���Ă����Ƃ����Ռ��I�ȃh���}���B����Ă����B �N����H���Ă����ƁA�C���h����S�ς��ւāA552�N�ɋԖ��V�c�Ɍ��������{�ɂ킽���Ă����B���̌�A�h���ڂɎ��������A�ێ�h�̕������`�ɂ���ē�g�x�]�Ɏ̂Ă��Ă��܂��B���ÓV�c�\�N(602)�A�M�Z���l�ᖃ�ѓ��l(�킩���݂��Â܂܂�)�������M�Z���J�����̂��A�M�Z�P�����@�����ł���B�����āA�O�����N(1555)7���A��2��̐쒆���̍���̎��A���̖{���������Č��M�ƐM���̑��D�킪�������̂��B���̎��̖͗l�ɂ��āA�w�퍑�������x�����M�x�̒��ҁE�����h�ꎁ���A���̂悤�ɋL���Ă���B�P�����͑S���I�ɗL���Ȗ����ł������̂ŁA���̎���M���閯�O�����ɑ��������Ƃ����B�퍑�喼�����́A���S�����̂��߂ɐM�̑Ώۂł������O���̔@��������ɓ���悤�Ƃ����Ǝw�E����B����O���Ƃ́A��̌���̒��ɎO�̂̕�������`�ŁA��ɁA�ω��A�����̎O���������Ă���B�������ɂ��ƁA���̔@�����͈�U�A�M�����l�����āA��ɐM���A�����ďG�g�ȂǓ]�X�Ƃ����Ƃ�����������Ƃ����B �������A�@�����Ɏc����Ă���L�^�ɂ��ƁA���̂悤�ɂȂ�B�u1555�N�A�M�B������̍��������́A�퍑�̕�������邽�߂ɁA���{�������M���ɕ܂����B���M���́A�t���R�Ɍ䓰�����ĂāA���{�������d�Ɏ�삵�܂����v(�����Z�E)�����āA�㐙�Ƃ̍��ւ��ɔ����A�D��������V�ƂƂ��ɕđ�̒n�Ɉڂ���A�@�������J��ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B �c�O�Ȃ����Δ镧�ł��邽�߁A���̑P�����@�����̎p��q�ނ��Ƃ͏o���Ȃ������B�����A���N5��15���t�܂�̖@�v�̓��ɁA�O���̕�������J�������B �@ |
|
|
�����M������̍ۂɐM���Ă����l�X�ȕ��_�Ƃ́H
����Ɏ�ނ�i�߂Ă���ƁA���M�ɂ͂��L�����_�M���s���Ă������Ƃ����������B���M���M���Ă��������ɂ��āA�����h�ꎁ�́w�퍑�������x�����M�x�̒��ŁA5���グ�Ă���B�ω���F�A����@���A���R�n���A�����x�V�A�эj���_������ł���B �܂��A�ω���F�͂��łɏЉ���悤�ɁA���M�̕ꂪ�M�S�����������v�̕��ł���B2�Ԗڂ͐^�������̖{���ł������@���B���M�͐��ɏo�w����Ƃ��ɁA����2�̑��������h��̐~�q�ɔ[�߂Đ�n�ɕ������Ƃ����B �����đ�3�̕����E���R�n���́A��F�̕��_���������̂ŁA�g�ɍb�h�����A�R�n�ɂ܂������Ă���p�����Ă���B��4�͖����x�V�ŁA���V�q(����)�ɏ]��������͂������_�B�퍑���������ɂ悭�M�����_�ł���B �����čŌ�́A�эj���_�ł���B�M�B�эj�R�ɍՂ�ꂽ�R�x�M�̔эj�匠���ŁA���̖{�̂̓_�L�j�V�ł���B���̎p�͔��ςɂ̂����������V������Ă���B���M�́A���̔эj���_�̑������̑O���Ăɂ��Ă����B���̊��O���́A���݁A�đ�s�㐙�_�ЂɎc����Ă���B�эj���_��M����҂́A���U�s�Ƃ�ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������������������������A���M�����U�Ɛg�ł������̂́A���̔эj���_��M���Ă������Ƃɂ��Ƃ�����������B ���M�͏o�w����ۂɁA�_�ЂɎQ�q���Ċ蕶��[�߂Ă���B�Ⴆ�Ό��T���N(1570)12��13���A���M���t���R�̊Ōo���ɔ[�߂��蕶�̒��ŁA���M���u�肢�ǂ���ɉz������ɓ���邱�Ƃ��ł����痈�N1�N�Ԃ͕K���Ōo���܂��v�Ƃ��āA���̂悤�Ȋ���(����)�𐾂��Ă���B�����Ƃ����̂́A�o����^�������ꂾ���̉��������܂��Ɛ_�ɐ����ژ^�ł���B���ӂ��Ă������������̂́A�����ɓo�ꂷ��_���̎�ނł���B �� ����ɕ��\�^���O�S�ҁA�O�����S�ҁA�w�m���o�x�ꊪ �� ���ω��\�^�����S�ҁA�w�m���o�x�� �� �����x�V�\�^�����S�ҁA�w�����x�V�o�x�ꊪ�A�w�m���o�x�ꊪ �� ���V�@�@�@�|�^�����S�ҁA�w�m���o�x�� �� �ٍ��V�@ �|�^�����S�ҁA�w�m���o�x�� �� �������R�\�^�����S�ҁA�w�m���o�x�� �� �s�������\�^�����S�ҁA�w�m���o�x�� �� ���������\�^�����S�ҁA�w�m���o�x�� ���̂悤�Ɍ��M���s�������u�̐��̑����ɋ�������邪�A���ɑ����̐_���ɉ�����F�肵�Ă����̂ł���B �������A���M�̐M�S�̍���ɂ������̂́A�u���`�v�Ƃ����l�����ł������B�����Z�E�́A���̓_�ɂ��Ď��̂悤�ɋ�������B�u���ʂ̐퍑�����̏ꍇ�́A�̓y���g�債�A�V�������Ƃ��A�����̗~�̂��߂ɐ���Ă��܂������A���M���̏ꍇ�́A�헐�̐����I��点�A�V�c�_�ɂ��ĕ��a�ȍ��ɂ������Ƃ������`�̂��߂ɐ키�Ƃ����l�������M�̍���ɂ���܂����B���炪������V�ƂȂ苞�s����݂Ėk���̓y�n���ɂ������A�Ƃ����z����_���ɐ����A����Ă����̂ł��v �_���ƈ�̉��������M�́A��苗�����m�s�ƂȂ��Ă���4�N�ڂ�49�ŁA�s�A�̋q�ƂȂ����B �@ |
|
| �@ | |
| ���D�c�M�� | |
| �@���ē����O | |
| �@ | �@ |
| ���L�b�G�g | |
|
�@�����z�ƏG�g �@���|�������q �@�����x�Ō�̎莆 �@���ŏ�`���Ƌ�P �@�����N �@���k�����˂� |
|
|
���G�g�̕��e�͒N��
������h���}�ŕ`�����G�g�̏��N����͂����ނˎ��̂悤�ȋ؏��ł��B �c���͓��g�ہB���_�̑��y���������e�̖�E�q���c�����Ď����A���̌�A��e���č�����B�G�g�̂܂ܕ�(�p��)�ƂȂ�|����́A�D�c�Ƃ̓����O���Ȃ킿��l�߂̒��V�傾�������A�č���������A���̎d���͂�߂Ă����B�G�g�ɂ͒�A�o�A�����ЂƂ肸����B�G�g�͒|����Ɛ܂荇���������A�Ƃ��яo���A�����A�O�́A���B����Q����B�y���W�c�̃{�X�I�{�ꏬ�Z�Ƃ̏o��A�l���ł̕��ƕ���Ȃǂ̃G�s�\�[�h���o�āA�D�c�Ƃւ̎d�������Ȃ��A�o���ւ̎��������ބ����B ���������������G�g���͎j���Ɠ`�������͂����Ăł������������̂ŁA���j�I�Ȏ����Ƃ��Ă̏G�g�ɂ��Ă͍��Ȃ������̓䂪�̂����ꂽ�܂܂ƂȂ��Ă��܂��B ���̂ЂƂ��A�G�g�̕��e�͒N���Ƃ������ł��B���Ƃ��]�ˎ���̂͂��ߓy���m��Ƃ������b���������Ƃ����w���}�f���L�x�ł́A�؉���E�q��Ƃ������ŁA�D�c�ƂɎd����S�C���y�ł������Ƃ���܂����A��������́w���}�L�x��A�w�c������(��������)�x�ł́A�|������G�g�̎����ƋL���Ă��܂��B��������͓��ڂ̖L�b���֔��ƂȂ����G�������̑O�c�ƂɎd������t�A��w�҂ŁA�w���}�L�x�͏G�g���L�̚���Ƃ��������i�ł��B �G�g�͍c���A���ƂȂǍ��M�Ȑl���̗����ł��邱�Ƃ��������镶�͂��A�G�g�̂����O�̑呺�R�Ȃɂ���ď����ꂽ�G�g�`�L�w�V���L�x�A�����ȉ̐l���i�哿�́w�Չ��L�x�Ȃǂɏo�Ă���A�G�g�͕�e������m���Ɩ��ʂ��Đ��܂ꂽ�s�`�̎q�ǂ��Ƃ�����������܂��B �G�g�̏o�g�K�w�A���Ƃ̐������x���ɂ��Ă��A���ƎЉ�Ƃ̐ړ_�͂�����̂́A�����ėT���ł͂Ȃ������ł��낤�Ƃ����̂�����̌����̂悤�ł��B�R��o�ŎЂ̓��{�j�̋��ȏ��ł́A�u���̒n���̉Ƃɐ��܂ꂽ�v�ƋL�q����Ă���A���̂����肪����̏펯�I�ȏG�g���̂悤�ł��B �������A�^��_���ł��L���ȁw������b�x�ł́u����(�ނ炨��)�v�A�C�G�Y�X��̋L�^�ł́u�n�����S���v�Ƃ���Ă���A���l���A�E�l���A����ɂ͔퍷�ʖ����A�T���J���܂ł����ĕS�Ƒ��̂��肳�܂ł��B �@ |
|
|
���Ȃ��A�L�b�́u��v�ɂ͌��Ђ�����̂�
�G�g�̎����Ƃ�����E�q��A�p���Ƃ����|����͂Ƃ��ɁA�u���v�v���Ƃ�����������܂��B���v�Ƃ́u���ˎ�ƍ������Ă��̕v�ƂȂ邱�ƁB�܂��A���̕v�v(�L����)�ł��B���ꂪ�j���ł���A�G�g�̐��Ƃ̌ˎ�(�ƒ�)�́A���e�ł͂Ȃ��A��e���Ƃ������ƂɂȂ�A�L�b�ꑰ�͏G�g�̕�e�𑰒��Ƃ��錌���W�c�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����������͂��߂Ƃ��鑤�߉Ɛb�̑���������̉��҂ł��B���̗��R�͕s���ł����A�L�b�ꑰ�ɂ͕�n�����߂������̂��������܂��B ��E�q��A�|���킪�ق�Ƃ��Ɂu���v�v�ł��������ǂ����͕s�ڂł����A���̓�l�̕��e�̉e���������Ƃ͂܂�����Ȃ������ł��B�V���l�ƂȂ����G�g���A���e�����{������A���������肵�������L�^�͂Ȃ��A��̏��ݒn��ꑰ�I�Ȕw�i���͂����肵�܂���B��e���吭��(�ې��A�֔��̕�e�̂���)�Ə̂���A�V���l�̐e�ɂӂ��킵���h�ӂ������Ȃ���G�g�̑��ŕ�炵�Ă����̂Ƃ͐����ł��B �G�g�Ƃ��˂̊Ԃɂ͎q�����ł��Ȃ������悤�ł����A�ꑰ�ł�����������A�����������c��������茳�ɂ����ė{�炵�Ă��܂��B��������͂̂��ɏG�g�q�����̑喼�ƌĂ�܂����A���˂���e����ł����B�G�g�̎�������˂́A�ЂƂ̐������͂ł���A�e���͂������Ă��܂����B �G������̑���͗��a��������̍ō����͎҂ŁA���̂��ɂ��鏗�������Ƃ��̎q�����G���藧�Ă܂����B�u���Ȃ��珗�̏�ł������v�Ƃ����Ό����鏊�Ȃł��B���ˁA���a�͂�����ċC�������A����Ȃ�̔\�͂��������Ƃ��������̘b�Ȃ̂ł��傤���B�������吭���Ƒ��̂��ꂽ�G�g�̕�e�̑��݊��Ƃ��킹�čl����Ȃ�A���ˁA���a�������Ă������Ђ����R�Ƃ͎v���Ȃ��Ƃ��낪����܂��B �����j�����̑������A���Q��}���́w��n���̌����x�ɂ��A�Ñ�̓��{�͕�n�ɂ���Ĉꑰ���`������Ă������A�j�n����{�Ƃ���嗤�����̓����ƂƂ��ɁA��n�I�ȓ`���͎Љ�̔w��ɑނ����Ƃ����܂��B����܂��ЂƂ̉����Ƃ����ׂ����̂ł����A�ߌ���ɂ����Ă����{�ł͕��n����Ƃ��Ȃ���A��n�̓`�������݂����l��������Ǝw�E����Ă��܂��B �G�g�̈ꑰ�����̂�����̕����`���Ƃ������̂��B���̂Ƃ���s���Ƃ���ق�����܂��A�G�g�̕��e���͂��߁A�ꑰ�̒j�����̉e�̔����͋C�ɂȂ�܂��B�Ȃ��A�L�b�́u��v�����ɂ͌��Ђ��������̂ł��傤���B�G�g�̈ꑰ���߂���傫�ȓ�̂ЂƂł��B �@ |
|
|
���u���}�f���L�v�ƍb��P
�����_�����珬���A�Q�[���Ɏ���܂ŁA�G�g�̉Ƒ��W�̂قƂ�ǂ́A�w���}�f���L�x�Ƃ��������ɂ���ĕ�������Ă��܂��B�������x�̒Z�����l�\�ӏ��قǏ����A�˂�ꂽ���̂ŁA�����Ƃ��������A�f�Ў����Ƃ������C���[�W�ł��B��҂͓y���m��Ƃ������쎁�Ɏd���������̕��m�ł������Ƃ���Ă��܂��B �y���m��̗{�ꂪ�A�G�g�̏o���n�ł��閼�É��̒����̑㊯�����Ă��������̖��ŁA���傤�ǏG�g�Ɠ����N���ł������Ƃ����܂��B���̗{�ꂪ��҂Ɂu��ɐ��ꂷ�v�Ƃ���܂�����A�`�����Ȃ���A������x�͐M�p�ł��邾�낤�ƍl�����Ă���悤�ł��B�����ꂽ�����͓��肳��Ă��܂��A�ǂ���ɂ���G�g�̎����琔�\�N���Ƃ̂��Ƃł��B �G�g�̏o���ɊW�������ȂƂ�����A�����ɋ����Ă݂܂��B(���艼���A��Ǔ_�ȂǁA�ǂ݂₷���悤�ɉ����Ă��܂�) ���B���m�S�̓��ɏ㒆���A���X���A�������Ɖ]�Ӎݏ�����B�G�g�͒��X���ɂďo���B ���͖؉���E�q��Ɖ]�Ӓ��X���̐l�B�M�����̐e���M�G �D�c���O�� �S�{���y��@(����)�ܑ̊��킸���X���ֈ������ݕS���Ɛ���@(����)�@�G�g���̎��A����E�q�厀���B �M�G�D�c�����Ƃɒ|����Ɖ]�ӓ�������B���X���̐���̎҂Ȃ�B�a�C�́A���X���ֈ������ށB���̎ҁA�����K�ɖ؉���E�q���ƏG�g��̕��֓���B �G�g������������������Ɖ]�ӏ��ɐ���Ė؉���E�q�及�։ł��A�G�g�Ɛ����@�Ƃ������A�؉���E�q�厀���̂̂���ƂƐ��ē�l�̎q���͂����ݒ��X���ɋ���B �G�g��͓����������̐��܂�B��A�吭���ƍ����B���\��N�����B���}�\���̔N�B ��e�̏o�g�n�Ƃ����u���������v�Ƃ́A��폊�̂��Ƃł��B���݂����É��s���a��ɂ́A��폊�A��폊���Ƃ����n�����c���Ă���A�n���S�̍��ʐ��ƒߕ����̌����Ƃ���Ɍ�폊�w������܂��B�n���S�ł���A���É��w����\�ܕ��قǂ̂Ƃ���ł��B �y���m��̑c���������Ƃ����A�b�㍑�̕��c�M�Ղ��Ȃ킿�M���̕��e�Ɏd���Ă����̂ł����A�M�Ղ����q�̐M���ɂ���ďx�͍��ւƒǕ����ꂽ�Ƃ��A����ɓ��s���Ă��܂��B���̐l�̕�e�����c���̖��ł������ƋL����Ă��܂��B�E��(��ʌ��s�c�s)�̐��c���́A�f�扻�����ꂽ���㏬���w�̂ڂ��̏�x�ł�������L���ɂȂ�܂������A���e�̏����҂Ɠ`���b��P�͂��̏��A���c�����̖��Ő킢�̂��ƁA�G�g�̑����ƂȂ����̂͂����m�̂Ƃ���ł��B�Ƃ�������ł���̂ŁA�u���}�f���L�v�̍�҂́A�b��P�ƌ���������Ƃ������Ƃł��B �m��̕��͕a�̂��ߎ������A���s�̖��Ō��Z�ƂȂ��Ă��܂��B�w���i���ƌn�}�`�x�ɂ��ƁA�փ����̐�̒��O�A�Γc�O���͚��s�̈ꑰ���֓��ɑ�������̂��A���̍Ȏq����ɑ���悤���т��э����������A���s�͂����������肩�A�����̐l���ƂȂ��Ă������c���̈ꑰ�̎҂����𖧂��ɏ����o�����Ƃ����̂ł��B���������p���Ă݂܂��B �Γc��������O���A�d���̂Ƃ��A�g�𗌒��ɂ��͂��A�ꑰ�̊֓��ɂ���҂����邵�č������B���s���ꑰ�����֓��ɂ���āA���s�ɋđ��Ȏq����ɂ��͂��ނׂ��|���x�ɋy�ԂƂ��ւǂ��A���s�������B���܂��֚��s���ꑰ���B�E�̏�听�c���A�l���ƂȂ�đ��ɂ�����A���s�Ђ����ɂ����Џo���Ă������u���B ���s�́A�䉾�O�Ƃ��č��쎁�A�k�����A����ɂ͓���ƍN�ɋߎ����Ă����Ƃ����܂��B�_�҂ɂ���ẮA�G�g�̌䉾�O�ł��������Ƃ����l�����܂����A�悭�킩��܂���B�y���m��͑��~�̐w�A�Ă̐w�ɏ]�R���Ă���A�w�y�������q�m�厄�L�x�Ƃ����L�^���c���Ă��܂��B�L�b������ё���̐l�тƂɂ��āA�l���݈ȏ�̏��������Ă����̂͊m���ł��B �y���m��̐�c�́A�������������œ|�̊����グ���Ƃ��ɋ��͂��������@���̎q�A�y���@���Ƃ���Ă��܂��B�_�ސ쌧���c���s�ɒ����Ƃ�������������A�@���͂��̑��i(�Ǘ���)�ł������Ƃ����܂��B�����̑��߂̂ЂƂ�ŁA���{�̏d���ƂȂ�y������͓�j�ł��B �y�쎁�̎x���A�����쎁�͍L���ɈڏZ���āA���n�̖����ƂȂ�܂����A�ї����A�̎q�A���i��{�q�Ɍ}�������ƁA�����I�ɂ͖ї��Ƃ̕��Ƃ̂悤�ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�G�g�̐��Ȃ��˂̉����{�q�ɓ����ď�����G�H�Ɩ����A���x�͖L�b�Ƃ̕��Ƃ̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂��B ��ʂ̐��c���̖��A�b��P�������ɂȂ������ƂƁA�G�H�������쎁�̗{�q�ɓ��������Ƃ̂������ɂ͈��ʊW�͂Ȃ��͂��ł����A�w���}�f���L�x�̓y�����ɂ���ă����N����Ă��܂��B�܂��A����͋��R�ł��傤�B�y�������A�����쎁(�y�쎁)���{�Ƃ͑��͍��̒������ł����A�G�g�̐��܂ꂽ�͔̂����̒����ł��B�����ȂǁA����ӂꂽ�n���A�c���ł����A����Ƃ����Ȃ����Ƃ�����܂���B �@ |
|
|
���G�g�̐��܂ꂽ����
�G�g�̐��܂ꂽ�����E�����́A���݂̖��É��s������̈ꕔ�ł��B�i�q���É��w�͒�����ɂ���܂����A���傤�Nj�̋��ł���A�S�ݓX��I�t�B�X�̗������ԔɉȊX�Ƃ͔��̂ق��������ł��B�M�c�_�{�̐_�̂��������Ɠ`����Ă��܂��B �G�g�̐��܂ꂽ����A�����E�����́A�㒆���A�������A�������̎O���ɂ킩��Ă���A�G�g�͒������̐��܂�ł���Ɓw���}�f���L�x�ɂ͏�����Ă��܂��B�������]�ˎ���̂��̂��납�A�����E�����͏㒆���A�������̓ƂȂ������߁A�G�g�̏o���n���ǂ��ł���̂������������A���݁A�o���̔肪����A�L���_�Ђ��J���Ă���̂͏㒆���ɂ�����n��ł��B �����Ɏc��`���ɂ��ƁA�L�b�����ŖS�������̐w�̂��ƁA�����E��������́A�G�g�ɂ䂩��̂���_�ЁA���Ȃǂ����Ƃ��Ƃ��ړ]�������A���邢�͋K�͏k���������Ă���Ƃ����̂ł��B�W���镶���L�^����������ꂽ�`�Ղ�����Ƃ����܂��B���É��ݏZ�̏G�g�����ҁA���n�����̒��N�ɂ킽�錤���ŁA���̂�����̎�����炩�ɂȂ��Ă��܂����B ���̓T�^�I�ȃP�[�X�́A���̋{�_�Ђł��B�����ɑ傫�Ȑ_�Ђł������Ƃ��`����Ă��܂����A�]�ˎ���ɔj�p���ꂽ�Ƃ����A���݂͌����̂��݂ɏ������K�����邾���ł��B�n���ɂ́A�G�g�̕�e�͂��̐_�Ђɓ��Q���āA�G�g�����������Ƃ����`��������A�����̓��g�͂���ɗR������Ƃ����̂ł��B �_�������̎���ł���A���̋{�_�Ђ��Ǘ����Ă����̂́A�������̐������ł����B���̎��̏Z�E�̓�j���A�튊�s�̐��̏Z�E�ɂȂ��Ă���̂ł����A���̋��G�Ƃ����l�͐������̉ߋ����Ɂu�ꑾ�}�G�g���V���v�Ə�����Ă��܂��B��e���G�g�̖��Ƃ������Ƃł��傤�B���G�Ƃ��������G�g�Ƃ̂��������������Ă��܂��B �u���v�Ɂu�A�l�v�Ƃ����ǂ݂��Y�����Ă��܂��B�G�g�ɕ����̖������Ă��̎o�̂ق��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤����A�G�g�̎o(�Ƃ�)�̖��Ȃ̂ł��傤���A���邢�͗{���̖��ł��傤���A��������܂����A�������̂܂܂ł��B �@ |
|
|
���c���͒b�肻��Ƃ��_���H
�G�g�̕���̑c���ɂ��Ă͂������̏��`������̂ł����A�N�䐬�A��(�R�w�@��w�����ȂǗ�C)�̕����n�}�ł́A�u��폊���̔H�X�@�����v�Ƃ���Ă��܂��B�G�g�����̑�ƁA�n�Ӑ��S���́w�L���}�̎��I�����x(�u�k�Њw�p���ɂȂ�)�ł́A�G�g�̕���c���ɂ��āu���Z(��)�̒b��@����v�Ƃ��Ă���A�w���n���x(��������}���ُ���)�ł͌�폊�ݏZ�̒b��̎q��(���邢�͒b��H)�Ƃ��Ă��܂��B�G�g�̐��܂ꂽ���É��ɂ́A�G�g�̕���c���ɂ��āA�b��ł������Ƃ����`���Ɛ_���ł������Ƃ����`��������悤�ł��B �w���n���x�́u���}����n�v�Ƃ����n�}�ł́A�G�g�̕���̐�c�͑�a���̓��b��ł���A�n���n�̍��g������̎q���Ƃ���Ă��܂��B���̌�A���Z���ɈڏZ���đ�X�A�b����c���ƁA�����ɈڏZ�����Ƃ������e�ł��B�G�g�̑c���͓V����\��N�����Ƃ���̂ŁA���ꂪ��������ΏG�g���\��㔼�̂���܂Ő����Ă������ƂɂȂ�A���R�Ȃ���𗬂��������͂��ł��B ���`�͒b����Ɛ_�����ɂ킩��Ă���̂ł����A�������ĘB���p�߂����d��������b��t�́A�m�̓������킸�A��p����J�ɐ[����������Ă���̂ŁA�ӂ��̏��`���܂��������W�Ƃ������Ȃ��Ƃ��낪����܂��B������ɂ���m���Ȏj���͂Ȃ��A�f�ГI�ȓ`�����c���Ă��邾���ł��B �w�������Ə��n�}�x�͏G�g�̕�ɂ��āA��폊���́u�����v�v�Ƃ����l�̖��ł��邪�A���̖��ł͂Ȃ��u�p�q�v���Ȃ킿�Ȃ̘A��q�ŁA���̕��e�͎������[���ۜA(�ۗ��H)���ł���Ə����Ă��܂��B�������[���Ƃ́A�s�ō߂����āA�����ɔz���ƂȂ��Ă������ƂŁA�k�R�̂��܂�A���n�̏����ɂȂ���ŏo�������̂��G�g�̕�ł���Ƃ����؏����ł��B ���܂�ɂ��r�����m�ł����A�G�g�̕���c���͌��ƂƂ������Ƃł��B�������A���̂悤�Ȍ��Ƃ͋L�^����Ă��܂��A���̖��O�͏G�g�̓`�L�ɂ����Γo�ꂵ�܂��B�G�g�̑��߂ɂ����Č䉾�O�Ƃ�����呺�R�Ȃ́w�֔��C���L�x�ɂ��A�u���̒��[���v�Ƃ��ďo�Ă���A�`���̔w�i�ɉ�������������Ă���̂�������܂��A�悭�킩��܂���B �@ |
|
|
����̂ӂ邳�Ƃ͓y��̎Y�n
�w���}�f���L�x�Ȃǂɂ��ƁA��e�̏o�g�n�́u���������v�A���݂̖��É��s���a��̌�폊�A��폊��������̂��ƂŁA�n���S�̍��ʐ��ƒߕ����̌����Ƃ���Ɍ�폊�w������܂��B�n���S�ł���A���É��w����\�ܕ��قǂ̂Ƃ���ł��B �]�ˎ���ɏ����ꂽ���y���w�����u�x�ł́A�u���n�͌�(���ɂ���)�A�M�c�{��_�̂ɂāA�_���ɗp��y��i����̂Ɍ�폊�Ɩ�������悵�v�ƋL����Ă��܂��B �M�c�_�{�ɂ����߂邽�߂ɍ��J�p�̓y��A������J�����P���Ă��Ă����Ƃ����̂ł��B�]�ˎ���ɂ́A������p�i�̓y�킪�����Ă����Ƃ����L�^������܂��B��������ȍ~����폊�ɂ͂₫���̂̓`�����p������A�y��Â���̊G�t���l�`(���É��y�l�`)�����D�Ƃ̂������ł͂悭�m���Ă��܂��B�����l�`�̗ނ̑f�p�Ȑl�`�ł��B �n���S��폊�w�O�͑�s�s�ߍx�ɂ��肪���ȃ`�F�[���X�̕���ʂ�ł����A���}�ȕ��i�𗐂��m�C�Y�̂悤�ɁA�\���[�g���߂��S�̃|�[��������A�H�`�̑�^�I�u�W�F���f�����Ă��܂��B �Z�����֖�ŐF�Â����ꂽ�A����|�p���̂₫���̍�i�ł��B�����ɂ�����ꂽ�p�l���ł́u�y�v�ƃ^�C�g�����ӂ��āA�u�Â�����y��Ɗւ��̂���X�B�y���e�[�}�Ƃ���B�Â�����g���Ă��铩�y�ƊD�ւ�p���c�c�v�ƌ�폊�̗��j�ƍ�i���e���Љ��Ă��܂��B �G�g�̕�e�̂ӂ邳�Ƃ́A�u�y��̂܂��v�Ȃ̂ł��B ��폊�w��������ď\�ܕ��قǂ̂Ƃ���ɁA�G�g�̕�e�̕�炵�Ă����Ɠ`�������y�n������A�����p�l�������Ă��Ă��܂��B �\������̋n�����邾���ł��B��폊�ŏG�g�ɂ������̂́A���̓`���n�����ł����A�L�b�G�g�̃��[�c��T�邤���ŁA�������ƂƂ��ɏd�v�ȏꏊ�ł��B �@ |
|
|
����̂ӂ邳�Ƃ̌Õ��Q
�G�g�̕�e�͖��É��́u���������v�Ő��܂ꂽ�ƋL�^����Ă��܂��B���݂̏Z���\���ł́A��폊�A��폊���A��폊�ʂƂ����n������ђn�̂悤�ɓ_�݂��Ă��܂����A���傤�ǂ��̎O�̒n�_�̐^������ɁA�ߕ������Ƃ����傫�ȓs�s�������L�����Ă��܂��B�Ԃ���L�x�ŁA��O�X�e�[�W�A�}���فA�����z�[��������Ƃ���ȂǁA����J�����Ƃ悭���Ă���̂ł����A��{�v�҂������l�������ł��B �L��ȕ~�n�͓��ɂނ����Ċɂ₩�ȌX���Ȃ��Ă���̂ł����A���̑�n�̒���ɁA���o���t���ɂ����悤�ȋu��̔����R�Õ�������܂��B���a���\�[�g���A�����\���[�g���B���͂ɕ��\���[�g���قǂ̖x�̐Ղ�����A�ܐ��I�̑��c�Ɛ��肳��鍑�w���Ղł��B�ۂ��u��������u�~���v�ƕ��ނ����Õ��Ƃ��ẮA���C�n���ōő�̋K�͂ł��B �~���Ƃ��đS���ő�̂��̂��A��ʌ��s�c�s�̍�ʌÕ��Q�̂Ȃ��Ɍ������Ă��܂����A�����͗L���ȔE�鐅�U�߂̂Ƃ��A�Γc�O�����{�w�Ƃ����ꏊ�ł��B �����R�Õ��Ƃ���̂́A��폊�����_�Ђ̉��{�ɂ����邩��ŁA�Ղ�̂Ƃ��ɂ́A�~���̂����œ����Đ_��������s��ꂽ�Ƃ����܂��B �ߕ������ɗאڂ��鍑�����É��H��̃L�����p�X���ł́A�O����~�������邱�Ƃ��ł��܂��B���̂�����ɂ͈�Q�̌Õ������������Ƃ��m���Ă��܂����A�s�s���ɂ���ĂقƂ�ǂ����ł��Ă��܂��B��폊�ł͔M�c�_�{�ł�������J�p�̓y��(�J�����P)���Ă���Ă����Ɠ`���܂����A�M�c�_�{�̂��ɂ͓��C�n���ōő�K�͂̑O����~���u�f�v�R�Õ��v������܂��B �����R�Õ�����͏��ւ��o�y���������ł����A�펞���̍����ŏ��ݕs���ɂȂ��Ă��܂��B�O����~����~����Ƃ�����J�ł́A��ʂ̏��ւ�y�킪�p����ꂽ���Ƃ����炩�ɂ���Ă��܂�����A��폊�̓y��Â���̓`�����A�Õ�����ɂ����̂ڂ邱�Ƃ͏\���ɍl�����邱�Ƃł��B �@ |
|
|
���L�b���̌n�}�@
���Ă̐w�ɂ����Ē��n�̈ꑰ���ŖS�����Ƃ������������A�L�b���̐������n�}�͂܂������`�����Ă��܂���B�G�g�͍ō��ʂ̊֔��ɂ܂łȂ��Ă����Ȃ���A���̕��e���N���Ƃ������Ƃ����m�肳��Ă��炸�A���̏o�g�K�w�ɂ��Ă��_���A���m�A�E�l�A���l����A�V�c�̂��������A�퍷�ʖ����܂ł����ď������X�Ƃ��Ă��܂��B�T���J�A�R�̖��̈ꑰ�Ƃ�����܂ł����āA���n�̎q�����������Ă��Ȃ��Ƃ����C�y�������邽�߂ł��傤���A�����������肪�܂���ʂ��Ă��܂��B �������G�g�ɂ������n�}���܂������Ȃ��킯�ł͂���܂���B��������}���ق���������w���ƕ��x�A�{�������˕��ɂ���w�������Ə��n�}�x�Ȃǂɂ́A�G�g�̐�c���L�������Ԃ����n�}���������܂܂�Ă��܂��B�܂��A�G�g�̐e�ނƂ������������A���Ȃ̂���(�k����)�̈ꑰ�ɂ������n�}���w���Z�����ƌn���x�Ȃǂɑ��݂��Ă���A�ꑰ�̃o�b�N�O���E���h��m��肪����ƂȂ�܂��B �w�������Ə��n�}�x�ɂ��镃���̌n�}�ɂ��ƁA�G�g�̑]�c��(��b�R�̑m�������@�t���ƍ��g)���ߍ]�����S(���ꌧ���l�s)��������ɈڏZ�������ƂɂȂ��Ă��܂��B�w���n���x�ł��A�ߍ]�����S�̐l�������ɈڏZ���āA�G�g�̑]�c���ƂȂ��Ă��܂��B �V��M�i�̖��������M�w���K�x�ł��ȗ��Ȃ��̂ł����A���l�̌n�}���f�ڂ���Ă��܂��B�j���ł���Ƃ����ۏ͂���܂��A�n�}�j���̂����ł́A�G�g�̃��[�c�͋ߍ]�ł���Ƃ����L�q���ڂɂ��܂��B ���������L�q���j���ɋ߂��Ƃ���A�G�g�ꑰ�̔����E�����ł̈ꑰ�̗��j�͕S�N������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����ɏZ�ޏG�g�̐e�ނ͈ӊO�ȂقǏ��Ȃ��A���ꂪ�L�b�����̐Ǝコ�̂ЂƂƂȂ��Ă��܂����A���É��ɂ����ďG�g�̈ꑰ�͗]���҂Ƃ܂ł͌����Ȃ��Ƃ��Ă��V�Q�҂Ȃ̂�������܂���B �@ |
|
|
���������̖����
��������}���ُ����́w���n���x�̌n�}�ɂ��ƁA�G�g�̕����̐�c�͋ߍ]�����S(���݂̎��ꌧ���l�s)�̐l�ŁA�ߍ]�̑喼�A��䎁�̎x���Ƃ���Ă��܂��B�G�g�̑]�c���ɂ�����l���u�����v�Ƃ��Ă���A�喼���Ƃ��m��������䗺���̑c���̒�Ƃ��Ă��܂��B �����̗��a�͐�䎁�̖��ł�����A�ߍ]�Ɣ����ɕ�����Ă����Ƃ��A�G���̏o���ɂ���čĂь��т������Ƃ����̂͂������o���߂����b�ŁA�j���ƌ��Ȃ��l�͂��܂肢�Ȃ��悤�ł����A�������낢���`�ł͂���܂��B �����A���A�L�b�̓����������S�ɐ�̂Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂́A��䎁�̌n�����܂����ׂƂ��Ă��邩��ł��B �ߍ]�̐퍑�喼�Ƃ͂����Ă��A�����A�v���A�����̎O��̑O�ƂȂ�Ƃ͂����肵�Ȃ����Ƃ������̂ł����A��䎁�̏o���ɂ��Ă͏]���A��̐����L���ł��B�ЂƂ͔z�����ꂽ�������̌��ƁA���e���O�����j����͂��܂�n���ŁA�����ЂƂ͌Ñォ�炱�̒n�ɐ��͂������Ă����������̖���Ƃ�����̂ł��B ��䎁�����̖���Ƃ�����͍]�ˎ��ォ��悭�m���Ă���A�w���c�w���`�n�x�Ȃǒ����Ȏj���ɂ��L�ڂ���Ă��܂��B �G�g����䎁�̉��ʂł���A��䎁���������̖���ł���Ƃ�����̐��������A�j���ł���Ȃ�A�G�g�́u�ߍ]�����_�Ƃ��Ă����������̖���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��̉����ςݏd�˂��b�ł͂���܂����A�C�ɂȂ�Ƃ���ł��B �@ |
|
|
���G�g�Ɛ_��
�G�g������̕����̏@�h�A���c�ɋA�˂����Ƃ����`�Ղ͌����܂���B�G�g�̕����Ƃ̂������͂��̏ꂵ�̂��Ƃ������A�x���ŗ�ŁA������G�g�̋��{�̂Ȃ��A�炿�̈����Ɨ�������l�͏��Ȃ��Ȃ��悤�ł��B�ق�Ƃ��ɁA�����Ȃ̂ł��傤���B �G�g�͎���A�V�����Ƃ����_�����J���邱�Ƃ�]��ł����悤�ł����A����͒���ɔF�߂��܂���ł����B�L���喾�_�Ƃ����_���āA���s�̖L���_�Ђ��J���A�_��������ɂ����܂����B �G�g�ƕ����E�̊W���Ɍ�����̂́A�_���̗��V�ő����̋V�炪���s���ꂽ���Ƃ�����ł��傤�B�G�g�̐M�͐_�������Ƃ����Ă��܂����A�_������ւ̌X���������ł��B �Ȃ��ł���אM�Ƃ̂�����肪�悭�m���Ă���A�S���e�n�ɏG�g�ɂ䂩�������א_�Ђ͋����قǑ������݂��Ă��܂��B���É��s�̔M�c�_�{�̐ێЂł��鍂������q�_�Ђɂ́A�G�g����e�ɂ���Ă��Q������Ă����Ƃ�����ׂ��K������܂��B���s�̏o����א_�ЁA�����s�̕Z�\�R��א_�Ђ��L���ł��B �G�g�̕���c����H�X(�_�Ђ̐_��)�Ƃ����������A����̐e�ނ̏��o���A�o�̉ł���̎O�֎��A�ƘV�i�̖I�{�ꎁ���_���ɂ������Ƃ��Ƃ������`������܂��B�G�g�̐l���ɂ́A�_���Ƃ̂�����肪�ڂɂ��܂����A���̔w�i�ɂ͉�������̂ł��傤���B �@ |
|
|
���؉���E�q�� (�G�g�̎����H)
�w���}�f���L�x�ł́A�G�g�̎����̖���؉���E�q��Ƃ��āA���ꂪ����ƂȂ��Ă��܂����A�����m�̂Ƃ���A���̐l���ق�Ƃ��Ɍ�����̕��e�ł��邩�ǂ����͊m���ł͂���܂���B��������́w���}�L�x�w�c������(��������)�x�͒}����(�|����)�Ƃ�����e�̍č�����Ƃ����l���G�g�̎����Ƃ��Ă����Ă��܂����A��E�q��ƒ}����̓���l���܂ł���܂�����b�͍��ׂƂ��Ă��܂��܂��B �G�g�̎������؉���E�q��Ƃ������O���Ƃ����̂��m��I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�w�������Ə��n�}�x�ł͒�����E�q�叹�g�A�w���K�x�́u�L�b�G�g�n�v�ł͒����폕���g�Ƃ���Ă��܂��B�G�g�̌�����̕��e�ł������Ƃ��Ă��A�؉��Ƃ����c���ł��������ǂ����͕s���Ƃ������Ƃł��B �w���}�f���L�x�ł́A�؉���E�q��͐D�c�ƂɎd����S�C���y�ŁA�G�g�����̂Ƃ����ƋL����Ă��܂��B��E�q�傪���������Ƃ�����l�O�N�͓S�C�`���̔N�Ȃ̂ŁA�S�C���y�ł������͂����Ȃ��Ƃ����咣�����Ă͎�����Ă��܂����B�������w���}�f���L�x�͏G�g������Ő��\�N��ɏG�g�̌����ł����߂ł��Ȃ����b�̓y���m�傪�������Ƃ������̂ŁA��E�q��̖v�N�͕K�������M�p�ł�����̂ł͂���܂���B �܂��A�ŋ߂̘_���ł́A�S�C�͂��܂��܂ȃ��[�g��ʂ��āA��l�O�N�ȑO������{�ɓ����Ă����Ƃ��������L�͂ɂȂ��Ă���̂ŁA��E�q�傪�S�C�ɂ������d�������Ă����\�����Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �w���n���x�̐������n�}�ɂ��ƁA�G�g�̐��Ȃ��˂̕��e�A�����藘(����)�́u�S�{���H�v�ł������ƒ��߂���Ă��܂��B�S�C�Â���Ɋւ���Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�����A���ꂪ�j���ł���Ȃ�A�G�g�A���˕v�Ȃ̕��e�͂�����ēS�C�W�̎d���ɂ�������Ă������ƂɂȂ�܂��B �G�g�̕�n�A���������̉Ƃ���X�̓��b��ł���Ƃ������`�͂悭�m���Ă��܂����A�S�C���Y���{�i������܂��A���R�Ȃ��瓁�b��ƓS�C�b��͖������ł����B����������ƁA���������l���̂Ȃ��ɖ�E�q��͂����̂�������܂���B ��̂ЂƂ́A�G�g�̑��߁A�Ɛb�c�ɁA��E�q��̌����҂��قƂ�ǂ��Ȃ����Ƃł��B�B��Ƃ��������O�͕��������ŁA�����̕��͖�E�q��ٕ̈��ł���ƁA�w���n���x�w�������Ə��n�}�x�w����W�x�ɂ͏�����Ă��܂��B���������̘b�͊m���Ȃ��̂ł͂���܂���B �V���l�ƂȂ����G�g����E�q������{������A���������肵���`�Ղ��Ȃ��悤�ł��B��E�q��͏G�g�̖{���̕��e�ł͂Ȃ��Ǝ咣����l�����́A���̂������L�͂ȏ؋��Ƃ��Ď����Ă��܂��B �@ |
|
|
���吭���A�Ȃ� (�G�g�̕�)
�G�g�̏o���ɂ����Ċm���Ȃ��Ƃ́A�u�Ȃ��v�Ƃ������̓`��鏗������e�ł��邱�Ƃ��炢�ł��B�����A���ꂪ���̖��ł��邩�ǂ����͕s�ڂł��B �G�g�͔������̒����̏o�g�Ƃ���Ă��܂����A�����̒����͏�A���A���̎O�����ɕ�����Ă���A�G�g�͒������̐l�ł��B�����̒n���ɂ��Ƃ��N�����A�u�G�g����@�������̐l�v�Ƃ������͂����āA�G�g�̕�e�́u���v�Ƃ������O�Łu�����v�ɏZ��ł���̂��Ɠǂ��A�G�g�̕�́u�Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ����Ƃ�����������܂����A�����ɂ����肻���Ȃ��Ƃł��B �����̒����̐l�Ȃ̂ŁA�L�b�����̌�{�ŁA�u�Ȃ��v�Ƃ����ď̂��������Ƃ�����������܂��B���Ȃ̂��˂̕�e�͒�����(�����Ђ̂ڂ�)�Ƃ����h�̂Œm���Ă��܂����A����͂��˂����܂ꂽ�����̒������ɂ��Ȃ��̂ł��邩��ł��B �`���Ƃ��������Ȃ��̂ł��傤���A�G�g�̕�e�͔z�����ꂽ����(�������[��)�̖��Ƃ����b������A�n�}�w�̌��ЁA���c�����m�́w�����ƌn�厫�T�x�ɂ��A�w���������L�x�����p����Ƃ����������ł����A�Љ��Ă��܂��B �G�g�M����̔��[�́A�䉾�O�̑呺�R�Ȃ��������w�֔��C���L�x�ł�����A�G�g�������̒Ⴂ�o�����B�����߁A�ˋ�̌������������Ƃ��������肪����ƂȂ��Ă��܂��B���܂�ɂ��E�\���ۂ��̂ŁA������������̂ł́A�������ق̂߂����Ă���̂ł͂Ƌt�ɋC�ɂȂ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���É��s���a��ɒ��������폊�����_�Ђ̋߂��ɁA�u�L�b�G�g���Ձv�̕\��������A�������������[���Ƃ������Ƃ��Z��ł����u�䏊���~�v�̓`���n�ł���Ə�����Ă��܂��B ���É��ɂ́A�G�g�e�q�ɂ䂩��̎��Ђ��������m���Ă���A�������낢�`�����c���Ă��܂��B�M�c�_�{�̐ێЂł��鍂������q�_�Ђɂ́A�G�g����e�ɂ���Ă��Q������Ă����Ƃ�����ׂ��K������A�q��ĂɌ䗘�v�̂���_�ЂƂ��Đl�C������܂��B �G�g�̏o���n�̒������ɁA���̋{�Ƃ����傫�Ȑ_�Ђ��������Ɠ`����Ă��܂����A���܂͏������K�Ƃ��ē��g�����̕Ћ����J���Ă��邾���ł��B���̐_�ЂɋF�肵����e���A���z���ٓ��ɓ��閲���݂ĉ��D�����̂��G�g�ł���Ƃ����`�����n���ɂ͎c���Ă��܂��B���̋{�͓��g�_�Ќn���̐_�Ђ������̂ł����A�G�g�̗c���Ƃ������g(���g��)�Ƃ̂��������w�E����Ă��܂��B ���ŏЉ�Ă���悤�ɁA�G�g�̕�e�ɂ��ẮA�b��(���b��)�̖��A�H�X(�_��)�̖��Ƃ������`������܂��B������̕����j���炵���͂���܂����A�m���Ȏj���͎c����Ă��炸�A��߂����Ƃ��낪�����̂͏G�g�̕��e�Ɠ��l�ł��B �@ |
|
|
���|���� (�G�g�̌p��)�H
�w���}�f���L�x�Ȃǂɂ��ƂÂ��ʐ��ɂ��ƁA�G�g�̕�e�́A�؉���E�q��ƌ������A���̌�A�|����(�}����)�Ƃ����D�c�Ƃ̓����O���Ȃ킿��l�߂̒��V��ƍč������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�G�g�����l�l�̎q�ǂ��̕��e���ǂ���Ȃ̂��ɂ��Ă������������āA�w���}�f���L�x�ł͏G�g�Ǝo���E�q��̎q�A��G���Ɩ���|����̎q�Ƃ��Ă��܂��B �Ƃ��낪�A�������(�L�b�G����O�c�ƂɎd�������)�́w���}�L�x�A�����̓`�����L�^���Ă���w�c������(��������)�x�ł́A�G�g�͒|����̎q�Ƃ���Ă��܂��B �G�g�̕ꂪ�P�Ȃ�S�����ł������Ƃ͍l���ɂ����Ƃ������Ƃ́A���˂Ă����Ƃɂ���Ďw�E����Ă��܂����A���̍����̂ЂƂ͍č�����Ƃ����|����̓����O�Ƃ����E�Ƃɂ���܂��B�����O�̐E���́A���R��喼�̑��ɂ����āA���̓��A�A�́A����Ǘ��ȂǕ����̈�̑��ߋƖ������Ȃ����Ƃł��B����Ă��Ɍ����A�����̃C���e���ł��B�����Ƃ����s�ׂ́A�����ɂ����Ă��ߋ��ɂ����Ă��A�������x���̎Љ�K�w����z��҂�I�Ԃ��Ƃ���ʓI�ł��B�n�����S�����̌������肪�����O(�������O�H)�Ƃ����̂͑����Ɉ�a��������܂��B �����O�𒃖V��Ƃ������̂́A�䔯���đm�̂Ȃ�����A�������Ŕ|�ł���������ŁA�����O�̂Ȃ�����u�v���̒��l�v�Ƃ����ׂ��l�������o�����Ă��܂��B�m���Ȍn���ł͂���܂��A�痘�x�̑c���͑������R�ƂɎd����爢��Ƃ��������O�������Ƃ����܂��B�V���l�ƂȂ����G�g�͒��̓��̐��E�ɒ^�M���Ă��܂����A���̍ŏ��̎t���͒|����ł�������������܂���B ���R�A�喼���߂Ƃ��āA�㗬�Љ�ł̎Ќ����̂������O�̎d��������A�喼��̎��I�A�����I�ȋɔ���ɐڂ��邱�Ƃ������A�P�Ȃ鋋�d�W�ł͂���܂���B�|����͐D�c�Ƃ̓����ɒʂ��A���R�A�M���Ƃ��ʎ����������͂��ł����A�G�g���D�c�Ƃɏo�d����Ƃ��A�|���킪�Ȃ����Ƃ����b�͎c���Ă��܂���B���̂����A�G�g�Ƃ͕s���ŁA�G�g�����ɒǂ��o������A�Əo�����G�g���O�͂��������Q����Ƃ����`���������āA�����╨��ł͂�����̘b���蒅���Ă��܂��B�G�g�ƒ|����̕s�����Ɏj���Ƃ��Ă̕ۏ�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�L�ۂ݂ɂ��Ȃ��ق��������̂�������܂���B �|����͖�E�q��ȏ�ɓ�̐l���ŁA�{�����ꑰ�w�i���s�ڂł��B�����̂Ȃ��ɂ́A�؉���E�q�傪�o�Ƃ��Ē|������̂����Ƃ������A�|����Ƃ����l���͎��݂��Ȃ��Ƃ�����(�w�L�b�ꑰ�x����f��)�����邭�炢�ł��B�����A�n�}���܂������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A��������}���ُ����́w���n���x�Ƃ����n�}�W�ł́A�����E�m�������̖����A���쎁�̗���Ƃ���n�}���ڂ��Ă��܂��B���̌n�}�ł́A����ƍN�̕���c���̐��쒉���ƒ|����͓����Ƃ���Ă���̂ł����A����ȏ�͎j�����Ȃ��A�܂������킩��܂���B �{�������˕������́w�������Ə��n�}�x�ɂ���؉��n�}�ł́A�؉������q��(��������)�Ƃ����l�ɍ��A�Ƃ����q������A�|����Ə̂��A�D�c�M�G(�M���̕�)�Ɏd�����Ə�����Ă��܂��B�ɂ킩�ɂ͐M�����Ȃ��n���ł����A�������ꂪ�^���ł���A�G�g���Ⴂ����ɖ�����Ă����؉��Ƃ��������͒|����ɗR�����邱�ƂɂȂ�܂��B �@ |
|
|
���k�����A���� (�G�g�̐���)
�G�g�̐��ȁA�k����(����)�͏G�g�Ƃ̂������Ɏ��q���ł��Ȃ������ɂ�������炸�A�L�b���������ŋ��������͂������Ă����悤�ł��B������̂��˂̑��߂ɂ̓L���V�^���̏������������Ƃ�����A�C�G�Y�X��鋳�t���C�X�E�t���C�X�́A�ޏ����Ƃ����ďG�g�ɒ�邱�Ƃ������A�l�ƂȂ�����̂悤�ɍ����]�����Ă��܂��B �u�ޏ��͂���߂Ďv���[���H�L�̑f��������Ă���A���̕w�l�����͂��̑��v�l�ɏ]���A�֔��͂��܂�ɂ��吨�̏������������Ă���̂Ŕޏ��Ɛ������c�܂Ȃ��ɂ��Ă��A�ޏ��������ƔF�߂Ă���v(���ɔŁu����t���C�X���{�j�v�l��150�y�[�W) �G�g�̐��Ȃ��˂́A�����⎞�㌀�ɂ������Γo�ꂵ�܂����A������l���̘b�ɂ܂Ō��������͂��݁A���ɂ͏O�l���̂Ȃ��G�g����荞�߂Ă��܂��܂��B���l������Ђ�ӂ��V���l�������Ȃ܂�̌Ï��[�ɂ����͓����オ��Ȃ��B����ȏ�ʂ�ʔ����������`���̂������܂�̃p�^�[���ƂȂ��Ă��܂��B����͂�����x�A�j���ł������悤�ł��B �u�喼�����������Ԃ̐����͓��{�ł͔N��(���N�喼�̐�����⍲���Ă������S)���s�����̂ŁA���[���b�p�Ƃ͈قȂ�A�����͕\�����̂��Ƃɂ͌����o���Ȃ��̂����ʂ������B����́A�����̒j�����ڎv�z�̉e����������Ȃ��B�������A���̎���A�ǂ��̐��E�ɂ���O������悤�ŁA�L�b�G�g�̍ȁE�k�������˂͂悭�G�g�Ƃ������������A���̃J�J�A�V���Ԃ���������A���喼�̂��˂ɂ��Ƃ��˗����邱�Ƃ��悭�������悤�ł���v(�N�䐬�A�w���{�j�E����̓�x26�y�[�W) �n���̂����ŋC�ɂȂ�̂́A���˂̕���c�ꂪ�吭��(�G�g�̕�)�̎o�ł���Ƃ����n�}��L�^���U������邱�Ƃł��B�������ꂪ��������A�G�g�Ƃ��˂͈ꑰ�̂Ȃ��ł̍����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���˂��L�b�����̂Ȃ��Ŏ����Ă������Ђ́A���������������w�i�ɂ���̂�������܂���B �����A���˂̌n�����͂����肵�Ȃ��_�������A�j���Ɗm��I�ł���n�}�͂ǂ��ɂ�����܂���B��ʓI�ɂ͐����藘(����)�̎q�Ƃ���Ă��܂����A�w������b�x�n���̓`���ł́A�D�c�M���̑R���͂ł�������q��̐D�c�ɐ���M���Ɏd�����і펵�Y�̈⎙�ŁA�������ɗ{�炳�ꂽ�Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��B ���������Ƃ��́A��쒷��(�L�b�����ܕ�s�̂ЂƂ��쒷���̕�)�̗{�q�ɂȂ��Ă����悤�ł��B����ɂ��ẮA�G�g�Ƃ̌��������˂̕�e(����)�����������߁A���v�Ȃ̐�쎁������āA���˂�{�q�ɂ��������ŏG�g�ɉł������Ƃ����b���`����Ă��܂��B���˂̎��Ƃ̖؉���(������)�͍]�ˎ���ɂ��喼�Ƃ��đ������܂����A���̂����̂ЂƂ��o��(�啪���ɏ���)�̊W�҂������c�����w�؉��ƌn�}�����[�x�ɏ�����Ă��邱�Ƃł��B �@ |
|
|
������ (���˂̕�)
�����Ƃ����͖̂{���ł͂Ȃ��A������ڊy��̌�{�ɂ�������ƕ��̌ď̂ł������悤�ŁA�u�����̋�(�ڂ�)�v�Ə����ꂽ����������܂��B�����Ƃ́A�������������ɕ��e�̏��̂����������ƂɗR������Ƃ����A���݂̏Z���\���ł����A���m�����{�s�����̂��ƂŁA�������H�̐��{�W�����N�V�����̂�����ł��B ���̒n�ɂ���u������Ձv�́A�퐶����̊��W���̐ՂƂ��ėL���ŁA���Z�̓��{�j�̋��ȏ��ɂ��悭�Љ��Ă��܂��B���Z��̂܂���x���߂���A���̊O���ɂ͋t�Ζ�(��������)�◐�Y�Ȃǂ̖h��{�݂�����Ă���̂ŁA���{�̏�Ƃ��Ă̌��^�ł���Ƃ����Ă��܂��B���˂̈ꑰ���퐶���ォ�炱�̒n�ɏZ��ł����Ƃ͎v���܂��A�G�g�̈ꑰ�A�Ɛb�ɂ͏���̖��肪���������ɋC�ɂȂ�Ƃ���ł��B ���˂̎��Ƃł��鐙��(�؉�)���͍]�ˎ���������ȑ喼�ƂƂ��đ������A���̂ЂƂ��o��(�啪���ɏ���)�̉ƘV���L�^�����w������������n�}�����x�ɂ��ƁA�����Ɨ��ɂ͒j�q�������ɂ�������炸�A����𑼉Ƃɗ{�q�ɏo���āA�����̒����ɏ���(�����藘�A����)���}���ĉƓ��p�������Ƃ����܂��B���̐l�����˂̕��e�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���������炩�ǂ����킩��܂��A�ǂ����e�̔������݂ł��B �������`����L���ȏ��`�ɁA�u�����͎����̖�(����)�ƏG�g�̌����������A�������Ƃ��Ȃ��������߁A���̕v��(��쎁)�����˂�{�q�Ƃ������Ƃɂ��ďG�g�Ƃ̌����𐬗��������v�Ƃ������̂�����܂��B���̃G�s�\�[�h�ɂ����Ă��A���˂̕��e(����)�̈ӎu�͖��Ƃ���Ă��܂���B�喼�؉����̕�ł��鏼����(�啪�����o��)�ɂ́A�����̕��͌������܂����A���̕v�̓����̂��̂͊m�F����Ă��܂���B�@�@ ��������}���ُ����́w���n���x��G�g�����̑喼�ł������؎��ɓ`��镶���ɂ��ƁA�����̕�e�͑吭��(�Ȃ��A�G�g�̕�)�̎o�ł��B�������ꂪ��������A�G�g����݂������͕���̂��Ƃ��ɂ��āA�`���̕�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���R�Ȃ���A���˂ƏG�g�͐e�ނƂ��������������܂��B �{�������˕�����������w�������Ə��n�}�x�́A�����ɂ��āA�u��J�Y������g����]�폗��v�ƋL����Ă��܂��B��J�Y���̕�͒����̂��Ƃ��̖��ł���A�Ƃ����Ӗ��ł��傤���B�փ����̐�ɂ�����Γc�O���̖��F�Ƃ�����ۂ����܂�ɋ���ł����A���̋L�q��M�p����Ȃ�A���˂̕���̐e�ʂƂ������ƂɂȂ�܂��B���˂ƏG�g�͌����Ƃ����\��������̂ŁA�����ł���A��J�Y�����G�g�̈ꑰ�ł��B�g���́u�g�v���v���ӂł��B �@ |
|
|
���؉��藘�A���� (���˂̕�)
�ЂƐ̂܂��܂ŁA���˂̕��e��؉��S�v�Ƃ����M�����b�̕�s�Ɠ���l���ł���Ƃ݂āA�u�G�g�͂��˂Ƃ̌����ɂ��؉��̖������g���悤�ɂȂ����v�u�G�g�͕n�����o�������A���˂̕��e�͒����N���X�̕��m�������v�Ƃ����悤�Ȑ������Ȃ���Ă��܂����B�������A�w�D�c�M���Ɛb�l�����T�x(�������N��)�ŒJ�����L���͂��˂̕��e��؉��S�v�Ɠ��ꎋ���錩���ɋ����^�`��悵�A���݂͕ʐl���̂ق����x������Ă���悤�ł��B����ɂ���Ă��˂̕��e�̐l�����͕s���ƂȂ��Ă��܂��܂����B ���˂̎��Ƃ́A�������Ȃ�����喼�Ƃ��đ������Ă���̂ŁA���{�Ҏ[�̌n�}�W�w�����d�C���ƕ��x�ɁA�����͖؉��A���͖L�b�Ƃ��ċL�ڂ���Ă��܂��B��Z��ܔN�̑��Ă̐w�ŖL�b���͖ŖS�����Ƃ����܂����A���Ƃ��Ă̖L�b���͂��˂̈ꑰ�ɂ���Čp������Ă���Ƃ����܂��B �w�����d�C���ƕ��x�ɂ����āA���˂̕��e�͑喼�؉����̎n�c�Ƃ���Ă�����̂́A�u�^�v�Ƃ��Ė��O�A�o���Ƃ��ɕs�ڂ̈����ł��B�����q��Ƃ����ʏ̂Ɠ������́u�����v�̂L����A���Ƃ͕����Ő������ł��������A�G�g����u�L�b������і؉��̏̍���^������v�Ɛ�������Ă��܂��B�w�����d�C���ƕ��x�́A�e�喼�����{�ɒ�o�����n�}����{�����ɂȂ��Ă���̂ŁA�؉��Ƃ̐l�����́A�n�c�̓������ǂ̂悤�Ȑl�ł�������������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��傤���B���邢�͌��\���͂���悤�Ȃ��Ƃ��������Ƃ����\��������܂����A�悭�킩��܂���B �؉����̓��o��(�啪���ɏ���)�ɓ`���w������������n�}�����x�ł́A���������e�����Ȃ킿�T�n�ł���Ƃ��A�u����ɗю��Ɖ]��v�ƋL����Ă��܂��B�������ł���̂͊m���̂悤�ł����A�n���I�ȂȂ���͂͂����肵�܂���B ��������}���ُ����́w���n���x�ł͓����ƍȂ̒����͕����̑c���������A�w���Z�����ƌn���x(����j���Ҏ[���̃T�C�g�ʼn{����)�ł͑]�c���������l���ƂȂ��Ă��܂��B �M���Ɛb�̖؉��S�v�Ɠ���l�������ے肳�ꂽ���Ƃɂ��A���˂̕��e�����m�g���ł��������ǂ��������s�m���ɂȂ��Ă���̂ł����A�w���n���x�ł͓����̐E�Ƃ��u�S�{���H�v�Ƃ��Ă��܂��B���̋L�q�𗠕t����j�����Ȃ��̂ŁA�ِ��̂ЂƂƂ����ׂ����̂ł����A�G�g�̑c���A���������̕��A�c���𓁒b��Ƃ��鏊�`�����邱�ƂƂ��킹�čl����A�u���킹�Ĉ�{�v�Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ă��A�L�����Z����̔���͂ł邩������܂���B�ڍׂ͂܂������s���ł����A���˂̕��e���S�C�Ƃ����Ő�[�̕�����ɂ�������Ă����Ƃ������͖��������������̂ł��B �V���l�G�g�̐��Ȃ̕��e�ł���Ȃ���A���O�̋L�^�͂��܂�Ȃ��A�o���A�v�N���͂��ߐl�������͂�����Ƃ��܂���B�����Ƃ��āA���˂̕�̒����ƌ������Ă��邩��ł��傤���A���݊��̊���������ۂɎc��悤�Ȑl�ł��B�G�g�̂܂��ɂ͓�̐l���������̂ł����A���˂̕��e�����̂ЂƂ�Ƃ������Ƃ͊m���ł��B �@ |
|
|
�������Ɨ� (���˕���c��)
���˂̈ꑰ����c�ł���Ǝ咣�����������́A�ɐ������̗�������ޔ��ˎ�����ɂ͂��܂�L�͎����ŁA�������{�ł������n�ʂĂ��܂��B���얋�{�Ҏ[�́w�����d�C���ƕ��x�͈ꉞ�A���̌n�����f���A�^���悵�A���˂̕���c���ƂȂ鐙���Ɨ��̑O�̐���͕s���Ƃ���ł��B�Ɨ��ɂ��ẮA�c���̂Ƃ�����������ɏZ�ނƂ̂L����Ă��܂��B�����������̎x�����ǂ������܂߁A�Ɨ�����͕s�ڂƂ����Ƃ���ł��傤���B ��������}���ُ����́w���n���x�ł́A�G�g�̕�͎l�l�o���̓ŁA�����̌������肪�����Ɨ��ƋL����Ă��܂��B�G�g���̑喼�ł������؎��ɓ`��镶�������l�ł��B���˂ɂƂ��Ă͕���c���ŁA���������n�����^���ł���ΏG�g�Ƃ��˂͕���łȂ��錌���҂Ƃ������ƂɂȂ�܂�����A�G�g�̌n�����l����Ƃ��̏d�v�l���̂ЂƂ�ł��B �������͔��㍑(�L��������)�����_�Ƃ����Y���ł����A�w���Z�����ƌn���x(����j���Ҏ[���̃T�C�g�ʼn{����)�ł͔��Z�����S������{�ђn�Ƃ��鐙�����̌n�����ڂ��A�Ɨ��A���˂ɂȂ��Ă��܂��B������̕����\���͂���Ƃ�������������܂����A����I�ȏ؋��͂Ȃ��悤�ł��B �����Ɨ����ɐ������̖���A�������̎x���ł��邱�Ƃ��A�G�g�̏f�ꂪ�Ȃł��邱�Ƃ��m���ł͂Ȃ����̂́A�G�g�̕�̐��Ƃ����m�߂����ƕ��ƍ������ނ��ׂ郌�x���ł��������Ƃ𐄗ʂ�����f�[�^�ł��B�G�g�̕�̂��Ɠ�l�̖����A�؎��A�������Ƃ��������A�������ł������m�߂����Ƃɉł��Ă��܂��B�������A�o���Ƃ���邱�̎l�l�̏����ɂ��Ăِ͈��������A�{���Ɏo�����������ǂ����͕s�ڂł��B���炩�̌����͂������悤�ł����A���̂�����̐l�ԊW�����𖾂̓䂾�Ƃ����܂��B �@ |
|
|
����쒷�� (���˂̉���)
��쒷���͐D�c�M���ɋ|�O�Ƃ��Ďd���Ă�����쒷���̎o�̎q�ŁA���{�q�ƂȂ��Đ��Ƃ��p�����Ƃ����Ă��܂��B�G�g���Ȃ̂��˂������̗{���ɂȂ��Ă���̂ŁA�����͂Ȃ����̂́A���傤�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��쒷���̕������͐����Ɨ�(���˂̕���c��)�̖��A����(�ȂȂ���)�ƌ������Ă���̂ŁA����ɂ���Đ����ꑰ�Ƃ̊W���[�܂����悤�ł��B �G�g�ɂ͐g���Ƃ��ċ�����A�L�b�����ɂ�����ܕ�s�Ƃ��āA�Γc�O���A���c�����A�O�c���ȁA�������ƂƂƂ��ɏd�v�Ȑ�����S���Ă��܂��B�Γc�O���Ƃ̐܂荇�����悭�Ȃ��������߂��A�փ����ł͓��R�ɂ��A���̎q���͍]�ˎ���̏I��܂ōL�����n���̑喼�Ƃ��Đ����c��܂����B�����̎q���Ɂu���b���v�̎����̔��[�A���̘L���̘T�S�ŗL���Ȑ����������邪���܂��B�����Ԃ��ɂ�����������͐��Ƃ̕��Ƌł��B �]�ˎ���A�喼���Ƃ͂��̐�c����Z�����̓y�ɋ��߂Ă��܂����A��쎁�ɂ͓��e���قɂ���n�}������ނ������Ă��̌n���͍��ׂƂ��Ă��܂��B�����n��̕��ƁA�ЉƂȂǂ̌n�������W���A�w�����Q���n�}���W�x(������N��)�ɂ܂Ƃ߂������������́A�u��얔�E�q�咷���ȑO�̌n�}�͑S���s�ڂł���A����̐��n�}�͓`���̈��E���Ă��Ȃ��v�Əq�ׂĂ��܂��B �@ |
|
|
���؉������q (���˂̉�)
���Ȃ��˂̌Z�ƒ�̒��j�ŁA�����(���Ɍ�)�A���l��(���䌧)�̏����Ƃ߂�L�b�ꑰ�̑喼�ł������A�̐l�Ƃ��Ė������A�u�ߐ��a�͔̂ނ���n�܂����Ƃ����Ă悢�v(�w���j�厫�T�x)�Ƃ����]��������قǂł��B ���͕Ӓ����Ƃ����]�ˏ����̊w�҂́A���w�݂̂Ȃ炸�ߑ㍑���w�̎n�c�I�ȂЂƂ�Ƃ����܂����A�؉������q�̉̕���炢�A���̋������������Ƃ����`��������܂��B���͕Ӓ����́A�����q�����t�W�����ǂ��Ă������Ƃɉe������A���t�W�����ɓ��ݍ��A�Ƃ����b������܂��B���ˉ���Ƃ��ėL���ȓ����������˗�����A���t�W�S��\���̒��ߎ��ƂɂƂ肭���Ƃ��悭�m���Ă��܂��B���̎t��W�̎��Ԃɂ͕s���Ȃ��Ƃ������̂ł����A�����q�̉̐l�Ƃ��Ă̕]�����蒅����������A���͕Ӓ�������̐�^�ɂ���̂͊m���Ȃ悤�ł��B �փ����̐�̂Ƃ��A�����q(���̂���͖؉����r�Ƃ������̕��m�ł���)����ƍN�ɕ�����̎���𖽂���ꂽ�̂��ď��ɎQ�������A��𗣂ꂽ���Ƃ��Ƃ��߂��Ď��r�A���̌�A���s�ɉB�����ĕ��l�����𑗂�܂��B�B���Ƃ͂������̂́A�f��ł��邨�˂��A���䎛�����Ȃ��狞�s�ŕ�炵�Ă����̂ŁA���̎��������ɂ���Ă��Ȃ肺�������Ȑ����ł������Ƃ����܂����A���\�Έȏ�̒������������߁A�ӔN�͍��������Ƃ��`����Ă��܂��B�����q(���傤���傤��)�Ƃ͕��l�Ƃ��Ă̍��ł����A�̂��Ⴘ�钷���ƚ}�̊|���ŁA�喼����]�������̚}��(���傤���傤)���Ȃ��琶���Ȃ��炦���킪�g�����s��������肾�����ł��B �����q�ɉƓ������i������������˂͒�̌����ɂ���ĂÂ��A�����Ɏ����Ă��܂��B�����h�ɑ������吳���̉̐l�A�؉������͑���ˎ�̌��Ȃ̂ŁA���˂̌����҂���́A���w�j��ɒ����Ȃӂ���̉̐l��y�o���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�����m�Ԃ����̐��q�҂ł������Ƃ����A���s��K�ꂽ�Ƃ��A �����̕���߂��邩���@�� �Ƃ��������q�̍�����`�[�t�Ƃ�������r��ł��܂��B�u�V���{�ÓT���w��n�v(��g���X)�ȂǂŎ�v��i��ǂނ��Ƃ��ł��܂����A�`�{�l���C���玛�R�C�i�A�˖{�M�Y�Ɏ���u�R���N�V�������{�̐l�I�v(�}�ԏ��@�A�S�Z�\��)�̈���Ƃ��Ė؉������q������A��Z���N�ɏo�ł���Ă��܂��B���l���̍�ƁA�ΐ�~�́w�]�˕��w���L�x (�u�k�Е��|����)�ɒ����q�ɂ��Ă̘_�l�����߂��Ă��܂��B �@ |
|
|
�����������͖��q���̎q���H
���������͗c�������A�G�g�̐g�߂ŗ{�炳�ꂽ���߁A�q�����̑喼�ƌĂ��ɂӂ��킵�������ł��B �������������c�Ƃ��A�������Ƃ��n�c�Ƃ���n�}���悭�m���Ă��܂����A�����������́w�����Q���n�}���W�x(������N��)�ɂ����āA�u�S���M����ɑ��炸�v�Ɛ�̂ĂĂ��܂��B ��������}���ُ����́w���n���x�ł́A�G�g�̕�͎l�l�o���ŁA���������̕�Ƃ���Ă��܂��B����ɕ���c��(����)�ɖ������Đ����̑c���̍ȂƋL�ڂ���Ă���A���ꂪ�����ł���A�G�g�Ɛ����̉Ƃ͓��ɂ킽�荥���W�������ƂɂȂ�܂��B �������A���Љ��͂���Ă��܂��A�w�������Ə��n�}�x�Ƃ����j�����{�������˕��ɏ�������Ă���A�����̕��𐴒��Ƃ��āu�b����ƂƂ��v�ƋL���A����G�g�̕�̏]��(���Ƃ�)�Ƃ��Ă��܂��B���̂悤�ɁA�G�g�̕�A�����̕�ɂ��Ă͏]�o��(���Ƃ�)�ł���Ƃ��f��ƖÂł���Ƃ���������A�o���ł��邱�Ƃ͊m��I�ł͂���܂���B �w���Z�����ƌn���x�ł́A�y�̎x�����q������{�q���}���A���̐l�������̒��ڂ̐�c�ƂȂ��Ă��܂��B���q���G���j�[����g���Ă������Ƃ͗L���ł����A����͓y�̉Ɩ�ł��B�������j�[��p���Ă���A���̌n���ƕ������܂��B ���̂悤�ɉ��������ɂ��ẮA�G�g�̕���̉��҂炵�����ƁA�b��ɂ������Ƃł������炵�����ƁA���q���Ƃ̌���������炵�����ƂȂǂ����`�Ƃ��ĎU������܂����A��������m���Ȏj���ł͂Ȃ��A���̎����͂��܂��ɑ����̓���͂��ł��܂��B �@ |
|
|
����������
���������̌n���͏������X�Ƃ��Ă���A�͂Ȃ͂������������Ă��܂��B�o���ɂ��Ă͌����Ƃ������Ƃ��������Ƃ������܂����A�n�����E�l�K���ł���Ƃ�����������܂��B���`�Ŗڂɂ��̂́A�G�g�̕��ƈٕ�̌Z��Ƃ�����ŁA�w����W�x(�u�G�g���̕��؉���E�q��ƕ��ւ�̌Z��̗R�A�������L��v)�A��������}���ُ����́w���n���x�Ɍ����܂��B �{�������˕������́w�������Ə��n�}�x���A�G�g�̕��Ɛ����̕��͈ٕ�Z��ł���Ƃ��Ă���̂ł����A���a�����̌n�}�ƂȂ��Ă���A���]�̕�������ڂ̑c�ɂ����Ă��܂��B �w�������Ə��n�}�x�ł́A�����Ƃ����l�̑�Łu���B�Z�B���Ԃɗ��v�Ƃ���̂ŁA���̂��땐�Ɛg�����������悤�ɂ��ǂ߂܂��B�����̎O�゠�Ƃ������̕��Ƃ���Ă���A�u���͒����퍶�q��A�ʕ��ɒ�B���B���{���ɏZ�݁A�M���������v�ƋL����Ă��܂��B�����̕��e���A��H�ł������Ƃ��A�M�E�l�ł������Ƃ������`�͂����Ζڂɂ�����̂ł��B ���������̌�����̕��e�͐��쐬���ŁA�������ɗ{�q�œ������Ƃ�����������܂��B �]�ˎ���̒n���w���������}�G�x�ł́A�x�{�̑喼���쎁�̏d�b�ł������������̌����Ƃ���Ă��܂��B���̕������́u�����܁v�Ƃ��ǂ݁A�v���A�㓇�Ə�����邱�Ƃ�����܂��B���Z���˒n�Ƃ��鐴�a�����̎x���ŁA���̑�\�i�����]���ɗ���č��쎁�̏d�b�ƂȂ�A���V�_��(�É����|��s)������Ƃ��Ă��܂����B ����Ƃ̉Ɠ����A������ԑq�̗��ɂ����āA����̊������������ł����B�V���ܔN(��O�Z)�̂��ƂȂ̂ŁA���傤�ǏG�g�̐��܂�邱��ł��B���̂��Ƒ����ŕ������͕����g�ƂȂ�A�ꑰ�͉�ł��Ă��܂��B���Ƒ����̏��҂��A�����Ԃ̐�œ������ɂ�������`���ł��B ���쎁�̗̍��ɋ��ꏊ�̂Ȃ��Ȃ����������̎c�}�̂����A���c���̖k�����Ɏd�����l�����܂��B�喼�k�����j�̖��{�q�ƂȂ����j���ŁA���̉ƌn�͖��{���{�Ƃ��ĉƖ��𑶑������Ă��܂��B���������͏��N�̂���A���Ől���E���A���c���ɓ����Ėk���j���̂��Ƃɐg���Ă����Ƃ����̂ł��B ���{�Ҏ[�́w�����d�C���ƕ��x�ł́A�����Ƃɂ��āu�͂��߂͕����ł��������������ɉ��������v�Ƃ��������ŁA���������̕�́u�L�b���}�G�g�̔���؉����v�Ə�����Ă���A������������e�ł��B���R���߂̎�w�ҁA�V�䔒�̏������w�ˊ˕��x�ɂ́A�u�����͖L�b�Ƃɂ䂩��̐l�Ƃ��ӁB���܂��ڂ炩�Ȃ鎖��m�炸�v�Ƃ���܂��B �@ |
|
|
���؋I�Ɏ�G��
�؏G��(���A�I�Ɏ�)���G�g�̕���̏]�킾�Ƃ����܂����A����܂����m�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�w�퍑�l�����T�x�ł��u�L�b�G�g�̈ꑰ�v�ƌ��t���ɂ����Ă��܂��B���̐؎��̉ƌn�͕��䌧�łÂ��Ă���A�n�}�Ȃǂ̊W�j���������O�\�N��A����j���Ҏ[���ɂ���ē��ʂ���ĕۊǂ���Ă���̂ŁA���݂͎j���̑������C���^�[�l�b�g�̃T�C�g�ʼn{���ł��܂��B���̂ЂƂł���u�،n�}�v�̏G�Ȃ̍��ɂ́A�u��@�L�b�G�g������v�ƋL����Ă��܂��B����(��̎o)�Ƃ���܂����A���ۂɂ͏f��(��̖�)�ł��傤���B �w���n���x�ɂ���u���}����n�v�ł́A�G�g�̕���l�l�o���̓Ƃ��Ă��܂����A�؏G�Ȃ̕�͎O���Ƃ���A�u���Z�����S�K�㏯�ɏZ�ސ؊����q�ꓟ�̍ȁv�Ə�����Ă��܂��B�K�㏯�Ƃ́A���݂̊��K��S�K��쒬�ɕ������ォ�玺������ɂ����Ă����������ŁA�{���͌��Ƃ̑����������̂ł����A�y���n���ƂȂ��Đ��͂������Ă��܂����B �؏G�Ȃ́A�͂��ߖL�b�G���Ɏd���āA�V���\��N���˃��x����ɏ]�R�A�l�������̂Ƃ��̌��ŋI�ɓ��R���ƂȂ�A���̂Ƃ��G�g�̒��b�ƂȂ��Ă��܂��B���̌�A�d�����Ώ��A�z�O�����A���{�����ƂȂ��āA�c���l�N�A�z�O�k����̏��ƂȂ��Ă��܂��B���̂���ɂ͓�\����̂��Ă����Ƃ������̂ŁA�L�͂ȑ喼�̂ЂƂ�ł��������Ƃ��킩��܂��B �������A�փ�������ł͕a���ɂ����Ďv���悤�ɓ������A���R�ɑ����k������ď�h��̐��𐮂������̂́A���R�̑O�c�����ɍ~�����A���̔N�̏\���Ɏ������ĉ��ՂƂȂ��Ă��܂��܂��B���̗P�q�A�r��(�G�Ȃ̒�)�͉z�O�œ�̂��Ă��܂������A�{���Ɠ��l�A�փ��������ɉ��ՂƂȂ�A�O�c�����̔�̂��Ƃɂ����Ď������Ă��܂��B���̒��q�A�v����փ��������ɘQ�l�ƂȂ�O�c���̋q�l�ƂȂ��Ă��܂������A�L�b�G���̏����ɉ����đ���ɓ���A���Ă̐w�œ������Ă��܂��B�v��̒�̉ƌn���A�z�O��(���䌧)�ŕ������Ƃ��������ŎƂ��c�݁A�؎��֘A�̎�����`�����邱�ƂɂȂ�܂����B �@ |
|
|
������
�G�g�̕���c���������Ɠ`����Ă���̂ŁA�ւ̕c�������ڂ����̂ł����A�G�g�̈��O�ɂ͌�������܂���B �����Ă�����A�����W������Ƃ͕����܂��A�����Ƃ������������܂��B�V���\��N�̒��v��̍���̂Ƃ��A�X�����璷�ɑ����Đ킢�A�Ƃ��ɐ펀�����l�ł��B �ʏ̂͏��\�Y�E�q��сA�֒����Ƃ��B����j���Ҏ[���w���Z�����ƌn���x�ɂ���֎��n�}�A�]�˖��{�̕Ҏ[�����w�����d�C���ƕ��x�ł͓����G�����Ƃ��Čf�ڂ��Ă��܂��B����A�w�����Q���n�}���W�x�ł́A�ɐ������̌n���Ƃ���A���e�̊֒��d�ɂ��ẮA�u��{���A�^���c�_�А_��v�Ƃ��Ă��܂��B�^���c�_�Ђ͈��m����{�s�ɂ���ÎЂŁA�������̈�̋{�ł��B ���̊֎��ƏG�g�̉ƌn���Ȃ��鍪���͍��̂Ƃ��날��܂��A�G�g�̑c���A�����ɂ��Ă͔�������폊���̔H�X(�_��)�Ƃ������`������̂ŁA�����̈ꑰ���^���c�_�Ђ̐_��ł��������Ƃ͏����C�ɂȂ�܂��B �����̐��Ȃ́A���Z���R���A�X���̖��B�L���ȐX���ۂƂ͋`���̌Z��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�k�������˂̉��ł���؉����r(�����q)���X���̖����ȂƂ��Ă���̂ŁA�����̊W�ł��B�w�����Q���n�}���W�x�̊֎��n�}�ł́A�����̒j�q(���͕s��)�͖؉����r�̗{�q�ƂȂ�A�̂��ɏo�Ƃ���ƋL����Ă��܂��B���̂悤�Ɋ֎��͖؉����r��ʂ��āA�L�b�ꑰ�Ɖ��ʊW�ɂ͂���܂����B �X���̕ʂ̖��͐؏G�d�Ƃ��������ɉł��ł���A����ɂ��ƁA���̕�e���؎��ł���Ƃ����܂��B�G�g�̕�̖������Z�̐؈ꓟ�ɉł��A���̎q�̋I�Ɏ�G�Ȃ��喼�ɂȂ��Ă��܂����A�G������̑���̏d�b�ɂ͐؈�d�����āA�؎��͖L�b�̈��O�ƂȂ��Ă��܂��B�؏G�d�̂��Ƃ͖������ł����A�G�g�̉��ʂł���؈ꑰ�ƂȂ����Ă���̂ł��傤���B �֎��͂̂��ɑ喼�ƂȂ�X���̉Ɛb�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�X���Ɗ֎��Ƃ͉���ɂ��킽�錌���W������A�����I�ɓ��������Ă��܂��B �@ |
|
| �@ | |
| ������ƍN | |
|
�@�����Ƌ{����I(������I) �@�����c�@�� �@�����c���� |
|
|
������̕�
1 (�������̂����A���\���N- �c��7�N / 1528-1602)�@�����L���̐����ŁA����ƍN�̕�B�ӔN�͓`�ʉ@�Ə̂����B�����́u��v���́u���v�u�����v�B�Ȃ��A�Éi3�N(1850�N)10��29���ɏ]��ʂ̑��ʂ�����A���̈ʋL�ł́A恂��u��q�v�Ƃ��Ă���B �������m���S�̍������쒉���Ƃ��̕v�l�ؗz�@(���x)�̊ԂɁA�����̋��鏏���(���m���m���S���Y������)�Ő��܂ꂽ(�R���M�̖��Œ����̗{���ł������Ƃ���������)�B ���E�����͏��삩��قNj߂��O�͍��ɂ����̂������Ă���A�����O�͂Ő��͂�U����Ă����������N�̋��߂ɉ����ĉ��x�̕��𗣉����Đ��N�ɉł��������A�������Ƃ���ɗF�D�W��[�߂悤�ƍl���A�V��10�N(1541�N)�ɉ���𐴍N�̌���p���������L���ɉł������B���V��11�N12��26��(����1543�N1��31��)�A����͍L���̒��j�|���(��̉ƍN)���o�Y�����B �����������̎��㐅��Ƃ��p��������̌Z�M�����V��14�N(1544�N)�ɏ����Ƃ̎�N����ƂƐ≏���ĐD�c�Ƃɏ]�������߁A����͍���ƂƂ̊W�𗶂����L���ɂ�藣������A���Ɛ���Ƃ́E�O�͍����J��(���J�s)�ɕԂ��ꂽ�B����͓V��17�N(1547�N)�ɂ͐M���̈ӌ��Œm���S���Ë���(���v�䒬)�̏��E�v���r���ɍĉł���B�r���͌��X����Ƃ̏������ȂɌ}���Ă������A���̍Ȃ̎���ɐ���ƂƏ����Ƃ̊ԂŋA������܂炸�A�������Ƃ̑R�セ�̊W���������R�ƍl������B�r���Ƃ̊Ԃɂ͎O�j�O������������B���̊ԁA�ƍN�Ɖ��M��₦����葱�����B �����Ԃ̐킢�̌�A����Ƃ��玩�����D�c�ƂƓ��������ƍN�́A�r���Ɖ���̎O�l�̑��q�ɏ�������^���ĉƐb�Ƃ��A������Ƃ��Č}�����B����͏r���̎���A�䔯���ē`�ʉ@�ƍ������B �փ����̐킢�̌�̌c��7�N(1602�N)�ɂ́A����@���z���V�c�ɔq�y���A�L���_�ЂɌw�łē���Ƃ��L�b�ƂɓG�ӂ��Ȃ����Ƃ��������B���N�A�ƍN�̑؍݂��錻�E���s�{���s�s������̎R�镚����Ŏ����B�⍜�͍]�ˏ��ΐ�̙B�ʉ@�ɖ������ꂽ�B�@���͙B�ʉ@�a�u�_���x�q����T���B�ޏ��̕�͊e�n�Ɍ��Ă�ꂽ�B �������L���Ƃ̊Ԃ̎q ����ƍN ���v���r���Ƃ̊Ԃ̎q �����N�� / �����N�r / �����菟 / ���������v�l(��ɏ������g(��������)�E�ۉȐ����ɍĉ�) / �����N���v�l / �����Ɛ��v�l �@ |
|
|
������̕� 2
������ƍN�̐���u����̕��v ����ƍN�̐���u����̕��v�́A14�̂Ƃ��A�����叼���L���ɉł����N�|���(��̉ƍN)���Y�݂܂����B���̌㐭���I�ɗ��ʂ������A�╔���v���r���ɍĉł��܂��B����̕��́A�ƍN��15�N�Ԉ��v��̒n�ŕ�炵�܂����B�ƍN�ɑ��Ă͉��M���₷���Ƃ͂Ȃ��A�S�̂�����Ԗ�̕i�𑗂葱���A���N���̉ƍN�̐S�̎x���ƂȂ�܂����B�܂��A�ƍN�����쎁�z���̕����Ƃ��Ĕ����ɏo�w�̂���A�╔��ɗ������u����̕��v�ƍĉ���ʂ������Ɠ`�����Ă��܂��B�c��5(1600)�N�A�փ����̍���ʼnƍN���������V���̎�����������2�N��A�c��7(1602)�N8��28�����s������Ŗv���܂����B�Ȃ��┯�͈��v�䓴�_�@�̕揊�ɕ��[����Ă��܂��B ���O�� �V��16(1547)�N�̏��āA�����╔�̏�O�ł́A�����킵���O��(����Ղ�)�����悻��ƈ�c�𐁂��n���Ă���܂����B �u�̂��A���a�l�����삩��V���������l���t��ɂ��}���ɂȂ��āA�������ꂱ��O���ɂȂ邩�̂��B������l�̂��Ƃ������āA�Ȃ�ƂȂ��₩�Ȃ�������₽��������ꂽ���A���̂���ł́A����������A���₩�ɗ��������āA�킵��܂łȂ���ł�����B�v �u������̂��B��������x�̉����l�̂��l����ɂ��̂��������āE�E�E�B�v �u�����l���A�����Ƃ���ɂ��ƁA�����킢�����Ȃ����������ȁB���߂Ă��łɍs���ꂽ����̂���֒|���l�Ƃ���3�ɂ��Ȃ�ʂ��킢�����q���c���ċA���ꂽ����Ƃ��� ���Ƃ��v �u�킵�牺�X�̎҂ɂ́A���̎���͂悤�킩��A�������Ƃ������̂͂ނ������̂�̂��E�E�E�B�v �u���s���ɂȂ�ꂽ��17�Ƃ������Ⴓ�ł�A����̂��Ɨ��O���吨�����Ȃ��瑗���� ����ꂽ�����Ȃ��A�����ŊF�A����A���̕S���O�ɗ`�����������Ƃ������Ƃ��B�`���̂�����悤�ɗ������ꂽ���o��l�𑗂��Ă���ꂽ���X�����J�ŊF�E���ɂ���Ȃ������̂Ƃ͑�ςȈႢ���ƁA�O�͂ł́A���炢�]���������ȁB�v �u���Ⴂ�̂ɁA����悤�S���������������̂��B�E�E�E���a�l���A ���̂���͐���₩�Ȃ�����������邵�A�O�̂��q�A���Y���܂��͂��Ⴌ�܂���Ă�����Ƃ������Ƃ��B�v �u�ق�ɁA���ꂵ�����Ƃ��̂��B�����Ȑ��̒��ŁA��ł͐킪�n�܂��Ă��邪�A�������ł����́A�悢�����ꂪ�o���������B�v �u���A����Ŏv���o�����B�悲�떼�傳�܂�����Ăяo����āA�������܂���ǂ̎������������Ă���ꂽ�B�Ȃ�����Ėa���ƌ����ĂȁB�v �u���������B����͂��肪�����B�Ȃ��Ȃ���ɓ���ʂ��̂��E�E�E�B�ق�ɂ��S�̐[����������B�킵��������o���˂̂��B�v ���ʉe ����̕��́A�܂��̍��̕Y���ꎺ�ɂЂ�����ƍ����Ă���܂����B�₩�Ȓ��x�Ɉ͂܂ꂽ���̕����́A�������O�̍���̂Ȃ܂߂��������c�����A���̉����̏Z�܂��Ƃ��Ă̗��������������n�߂Ă���܂����B �v�A�╔���v���r���́A�łĂ����悤�ȉ���̍L���Ƃ͈Ⴂ�A�����ł������肵�������ł������A�����ɏ��S�̐V�Ȃ��������D�����S�z��������A����̕������肩������ĘA��A���������ݎq�̕P���A���̏�ֈ������悤�v����Ă���܂����B����̕��́A�r���̍L�������܂����������ł�������������������Ă����v���ŁA�g���S���A���̍ȂƂ��ĐV���������悤�Ƃ��Ă��܂����B �Ƃ��낪�A�V������ɂȂ��A�܂����Ă͑S�g�Ō�肩���Ă���M�r�̎p�ɁA�܂����Ă�����֎c���Ă����|���̖ʉe�����Ă��܂����̂ł��B �Z����M���̖��ɍR���ꂸ�A���N���J�̞�����(��傤����)�ɍďo���𐾂��Ă��̏�։ł��A�K�� �����݂����Ɍ������ޏ��ł������A���ꂾ���ɁA���_�}�������鉪��̌ǎ����v���A ���ׂ����𗎂Ƃ��āA�܂ɂނ��Ԃ̂ł����B ���a�Ȉ��v��̗��́A�����g�ł���̏H���}���Ă���܂����B �u������B��厖�ƂȂ肻������B�}�g�ɂ��A�M�c�ɕ߂��̒|���ǂ̂�����O���D���Ԃ����Ƃ��铮��������A �D�c�M�G�ǂ̂́A�������������Ƃ̂��ƁB�|���ǂ̂̐g�ɂ������̂��Ƃ������Ă͂Ȃ�ʁB���Ȃ��̑��O������B�v �u�a�̂��S�ɊÂ��āA����v���ǂ̒|���v�Z�ǂ̂ɁA�M�c�ւ̐S�Â���͂������Ă����� ���܂����B���̏�̏d�˂Ă̂킪�܂܂ɂ�����܂��邪�A�ǂ����A�킪�g�ɑウ�Ă̖���ɐ��F�֎Q�邱�ƁA��������������܂��B�v �u�����A�悭���\���ꂽ�B�킵���������ĎQ�낤�B�}���x�x���������B�v �u�͂����E�E�E�B�v ���ĉ� �u�����l���E�E�E�B�����l���E�E�E�B�v ���łЂ��₩�ł͂��������A��������ŌĂԐ��ɁA����̕��͕M������~�߂܂����B ���J���玝���Ă��������̑O�ɂ́A�낤�����̉��������ɂ�炬�A���̐���������A ���₩�ɗ����オ���Ă��܂����B���̑O�ɂ��炦���o���Ɍ������āA����̕��́A���̂�����ۂƂ��Ă��錌���̎ʌo��i�߂Ă���Ƃ���ł����B�����̏��M�ɂ́A�����̏`�ŗn���ꂽ�ޏ��̎w���炵�ڂ����N�����A�c�菭�Ȃ����܂��Ă��܂����B�ꎚ�O��A����Ɍo���ʂ��Ȃ���A���K�̎q�A����̒|���ƁA �v�r���̂��߂ɁA�킪�g��ウ�ĂƋF���Ă����̂ł��B���̎ʌo���㏭���ł��B �u�E�E�E���̐��͋v���ǂ̂��B�����ł���܂����B�v ���́A�i�\3�N5��17���̒�������A�╔��͐�_���͂��ŁA�҂���ƒ���l�߂���C�ɕ�܂�Ă��܂����B �u�����l�A�a���̓��X�̌䉺�m�ł�����B�������A����̌��N���܂��������ɂȂ��܂����B�v �u�������A�|��オ�E�E�E�B�v ����̕��́A�v�킸�����オ���Ă��܂����B �╔���v���r���ɓY���āA����̕��͂��ł�33�B3��2���Ɍb�܂�A�v�Ɍ�ڂ̗J����^���Ȃ��A���h�ȏ��̍ȂƂȂ��Ă���܂����B �������A���̔ޏ��ɂ��A���K�̎q�̖ʉe�������܂Ԃ��̗��ɏĂ����ė���܂���ł����B�܂̕ʗ�����A���ł�16�N�B�M�c����x�{�ցA�v�Z�E�v����A������(����̂���)�ƂȂ����ꂨ�x�̕���ʂ��āA���܂��܂ȕi��͂��Ă͂������̂́A�����N���A��x����A�������Ƃ̂Ȃ������킪�q���A�헐�̓G�n�ł��邱���ւ��̂�ŗ��Ă��ꂽ�B�܂̂��ӂ��܂Ԃ��̗��ŁA�ӂƌZ�M���̊炪�悬���ċ���܂����E�E�E�B ���N�́A�������ɂ����܂܁A�����Ђ������̊�����߂Ă��܂����B�x�{�Ő��b�ɂȂ����c��̊炩��z�����Ă����Ƃ���̕�̊炪�ڂ̑O�ɂ���B ����`���̖��߂ŁA����̖ڂɂ������ƍl����ꂽ�卂��ւ̕��Ƃ̉^�ѓ���𐬂��� ���A�����̑��U����O�ɁA�ЂƖڂł��悢�A�܂Ԃ��̕�ɕʂ�����������ƁA�G�����ƕ� �ꂽ�����̂͂��炢�ŁA�킸���Ȏ蕺�Ƌ삯�Ă������N�������̂ł��B �悿�悿�����ɁA�悭�]��ł͋������A����Ƃ����̂Ŋۊ�̒|��オ�A����Ȃɂ�肵���ᕐ�Ҍ��N�ƂȂ��Ď����̑O�ɂЂ����Ă���B ����̕��́A�̂������݂ɐk�킹�Ȃ���A �u�E�E�E���q�����܂�܂��������ȁE�E�E�B�v ���������������ŁA�����ƌ��邵�������A �G�̏�Ōł����肵�߂���ɂ������点�܂����B ���̔�����q�́A���t���Ȃ��A���������Y��āA�������ߍ�������ł����B ���Ԃ��Ȃ��E�E�E�B����̕��́A��S�ɂ킪�q�̐H�����A���N�́A�ق��Ă�����������݁A����ق��Č��߂Ă���܂����B ���̂Ƃ��A�ʊԂ���A�ނ����苃�������ݎq�̐����������܂����B �u���A���N�ɂ͌Z�킪������������B�ǂ����A���q����������ցB�v ����̕��́A�͂��߂Ă��ɋA��A�Ί�ł��Ȃ������N�ɂ���Ƃقق��݂����āA���������Ɨ����オ��܂��B �Z����͂��łɓ��̋u�̗ː����������ɐ��ߎn�߁A����_�@�ł��炷��������Ƌł������Ă���܂����B ���N�́A���U���ɗՂޒ���߂��S�ŁA�S�����Ȃ����𗣂�悤�Ƃ��Ă��܂����B�����āA�Ђ�����Ƃ�������ŁA���܂ł��R�e���������Ă��邨��̕��̖T��ɂ́A���ł͖��������đ��키���ƂɂȂ����m��ʏr���̂����܂����̂��A�����Ɗ��Y���Ă���܂����B �����e �c��7�N8��28���A����̕��́A�����钆�̍��Ȉꎺ�ɁA�Â��ɉ�������Ă���܂� ���B �ւ����̐킢�ɂ���Ė������ɓV���̓����ƂȂ�A����b�ɔC����ꂽ�킪�q�ƍN��2���ɏ�����ċ���K��Ă�������̕��́A����b�̐���Ƃ��Č�z��(���悤����)�V�c�ɉ{���A����@ (������������)(�G�g�̐����˂�)�ɂ���A�q�⑷�Ɏ���Ƃ��ċ����̌������y���̂ł������A7���̔��ɕa��̐g�ƂȂ����̂ł��B �ƍN�͂��߁A���ꂼ����̎�ƂȂ��Ă���q�ǂ��≙�����̕S�����s�����Ă̈�ÊŌ���A����̎v�������ɂ��Ў��ł̕����F�� ���A�ޏ���75�̒薽���������Ƃ͂ł�����������܂���ł����B �����Ƃő����l�߂Č�����Ă���l�X�̖ڂ��悻�ɁA�Â��ɓ�����Ă��邨��̕��̔]���ɂ́A�ޏ��̔g���ɖ������l�������n���̂悤�ɂ悬��܂��B ����`���̓������Ɍ�A���������߂����ƍN�́A���S(�ɂ�������)���ƂȂ����v�v���r���⒉����Ȃ�����O�̌����̓����ŁA�r�ꋶ��������Ꝅ���b�B���̓{�����蔲���A����ɓ��p�������Ă������E�E�E�B �������A�V����������M���́A����̊肢���悭�����Ă��ꂽ�Z����M�����A���Ƃ����낤�ɁA�킪�q�ƍN�ɖ����ĎE�����A�܂��A���̎q�Ƃ��Ď����݁A�㎖��������v���M�r�������l�V�����Őؕ��������B�c����l�̑���ۂ�ŏĂ������Ă������╔��E�E�E�B �����āA���܂�ɂ������Ȃ邪�̂ɁA�M���ƉƍN�̎d�ł���{��A�������Q�̖��ɕ��������v�̏r���E�E�E�B�������ɍ������ �āA�`�ʉ@�ƍ����A������v��S���l�X�̖������F�낤�Ƃ����킪�g�E�E�E�B ���̌�A���x���̎��n��蔲���Ă����ƍN�Ɍ���A����E�l���E�x�{�ƁA����Ƃ��ċ����ڂ��čs�����̂����A���̉ƍN�����ł́A�V���̑�䏊�Ƃ��Ă̊ј\������Ă��Ă���B �����A���̎�̓͂��ʑ��݂ƂȂ����B�╔��Ő��N���͈�����A�菟�͉B���ɁA���̐��쏟�͓�����ƁA�F�ꍑ���̎����B �����A���͗p�̂Ȃ��g�ƂȂ����B �v���A15�N�̒Z���Ό��ł͂��������A ���S�̐g��v�̗��ɕ�����A�����̗c�Ȏq�Ɉ͂܂�Ȃ���A�K���ɂȂ��ĉ���Ɏc�����q���v���A�d����𑱂��A�����܂ł��Ă����A ���̂��낪�A���̈��v��̗����A���ɂƂ��ẮA������Ȃ������E�E�E�B �����ЂƂ��Ȃ��a���̖����q�ɁA�ג��� ���������Ă�����̏��̎}�e���A�Ђ��Ɨh�� ���Ƃ��A����̕��͐[�X�ƒ���ōs���ӎ��̒��ŁA�v���o�[���╔��̈ꎺ�ɁA�v�r���� ���Y���A�c�Ȏq�����₵�A�ᕐ�Ғ|���ƒk���Ă��鎩���̎p�����āA�ɂ��Ƃقق���ł���܂����B�@ |
|
|
�������L���@ (�܂����� �Ђ낽��)�́A�퍑����̕����B�O�͍��z�c�S������B�����@��8�㓖��B�������N�̎q�B����ƍN�̕��B �u�����听�L�v����i6�N4��(1��)�Ƃ��u�O�ƍl�v����сu��㑰�L�v(����3�E1743�N����)�͓��N4��29���Ƃ��Ă���B�u�����O�͌㕗�y�L�v(�㊪)�u������I�v(1��)������P���Ă���B�u���싌��裒�m�v(1��)�u���얋�{�ƕ��v�͑�i6�N�ƋL���ɂƂǂ߂Ă���B�u�����L�v��u�O�͋L��S�v�͓V��18�N��24�Ŏ����Ƃ���̂ŁA���N�͓����ɂȂ�B���̂ق�25�Ƃ������(�u�n�ƋL�l�فv����������ɂƂ���24�ƋL��)�܂�27�Ŏ����Ƃ������(�u�O�B����L�Ó`�W�v)������A�����̋L�q����t�Z�ł���L���̐��N�͑�i3�N(1526�N)�ł���B�u�O�͕���v��23�Ƃ��邪�N���̋L�q���Ȃ��B ������ �ؒ�i�̖��Ƃ���Ă��邪(�u���얋�{�ƕ��v�u������I�v1��)�A���N�̎��ł����������M��̖��Ƃ���ِ�������(�L�����u�e�����q��v�M��̎����Ƃ���w�V�҉���s�j6�x�����́u��ю��R���v�܂��u���싌��裒�m�v1���u�������R�����v�����|)�B ���Z�� �������M�N(�����Y) / �V��9�N(1540�N)6��6���A���˂ɂ����ē���(�u��㑰�L�v)�A���N���ځB �������@ / �g�Nj`���̎�(�u�������v2��)�B�����M���̖��u���˂̑�[�v�̗{���ƂȂ�(���O�B�܂��@���́u��㑰�L�v�ɂ��B ���O��P / ���������̍�(�u�������v1���u����v)�B�̂����䒉���ɍĉ�(�u���v2���u����v)�B�u�O��P�v�̖��́u��㑰�L�v����сu�������v2���u����v�ɂ��B�܂��u��㑰�L�v�ɂ����\2�N(1529�N)���܂�A�c��10�N(1605�N)10��17�����A77�A�@���͌����@�������S�܂��͑�������_����(�}�})�Ƃ���B�����s�␣���ɑ��u�@�����R�����v�ł͌c��17�N10��17�����A�����@�a��S������o�ƂȂ��Ă���u�������v�́u�@�����̋L�^�ɏ]���v�Ƃ��Ȃ��瓯�N11��27���Ƃ��Ă���B �����_��l / �����14���Z���B�V��3�N(1575�N)4��25����(�u��㑰�L�v)�B ���c�� �|���A�珼�ہA����ȂǏ����ɂ��قȂ�B���Ï��@���w���싌��裒�m�x�ɂ��Έȉ��̂Ƃ���B �u�n���v���|���܂��͐珼 �u�����啈�n�v���珼�� �u�ʖ{��n�}�v������ �w�O�͕���x�ɂ́A������l�A�E�O�ɃV�e�E�E�E�ƋL�ځB�w�V�҉���s�j�x�����u�M�����������v�V��6�N10��23���t�������ʂ��ɂ́u�珼�ہv�Ƃ���B�ʏ͎̂��Y�O�Y�ł������Ƃ���(�u�O�͕���v�u�����听�L�v1��)�܂��u����O�Y�v�Ə̂������Ƃ������������m�F����Ă���(�w�V�҉���s�j�x�����u����������v�V��16�N12��5���t������������̊�i��) ���o�� �u���얋�{�ƕ��v�̋L�q�����Ƃ��Ď��� ���V��4�N(1535�N)�̐��N�̎����ɂ��A��f���̏����M��́u���ɏ��āv���艟�̂�f�s�B�M����Ђ߂ʂǂ��납�ٔF�Ƃ����B���̑\�c���E���{(�������e)�̎p��������A����䂦�u�����̐��@�M�莟��v�Łu���Ђ悭�Ȃ�A�������ɑ����v���A��6�N�ɂ͏��̂��������̂��ĕ���̏O���Ђ����A�܂��L�����E�Q���悤�Ɗ�Ă�悤�ɂȂ����B ���������爢���呠��g�̓����ɋ~����B�܂��V��8�N(1539�N)�A�呠�ɂ���ċg�ǎ��L�̔�Ĉɐ����E�_�˂܂œ���A���̒n�ɓ�(������)����B1��11���ɂ͌������A���L���ꎚ��q�̂��āg��Y�O�Y�L���h�Ɖ��߂��B���������N9���̎��L�̎�����A�{�k�q�E�g�Nj`���̐D�c�����S�Ŕ�҂������ƁA�呠�ɔ����ĎO�͂֍ē��S�B��������A�Q�͊���ʂ��߁A���̖��𗊂�Ŏb�������B��������A����A�Q������`���Ɏ��萬���Ă��炤�ׂ��x�͂֕������呠��ǂ��悤�ɁA���B�u�|�ˁv�Ɏ~�h�B����ɏx�͂֓n���ė�9�N�H�܂ő؍݂���B ���V��9�N(1540�N)�`���̌v�炢�ŎO�́u���C��v�Ɉڂ����B�L���̋A���]�ޕ���O�̓����ŁA��11�N5��31���A�����M�F�E�����N�F�̋��͂ĉ���A��B���N6��8���ɐM��͍~�Q�����B ���V��14�N(1545�N)�⏼����ɂ�鏝�Q�������N������A���N�u�����v�ɂ����ĐD�c���ƍ���A������B��16�N9���u�n���쌴�v�ł͐M�F�Ɛ킢�A�{�������̌��тɂ�肱���j��B���N�A�D�c�M�G�ɂ��O�͐i�U�ł͍��쎁�։���������A���Ԃ�ɒ|����l���Ƃ��đ��邱�ƂƂȂ����B ���V��17�N(1548�N)3��19���u�x�B�v(�}�})������ɂ����ĐD�c���Ƒΐw�������A����Ƃ���̉��R2���]�������đ叟���A4��1���ɂ́u���������q�d�O�v�Z��̎R��������Ƃ����B�����u�O�B�h�R�v�ɂĐM�F�Ƒΐw�B�u�����쌴�v�ŐM�F������Ő펀����Ǝc���͔s�k�����B��18�N2��20���ĂѐD�c���Ƒΐw�A�����ĐD�c�M�L��ߗ��Ƃ��A����Ƙa���Ē|���ƌ����A26���ɍ���ƂƂ̖ǂ���l���Ƃ��ďx�{�ֈڑ��B ���V��18�N(1549�N)3��6���A24�Ŏ����B ���Q�l���L / �u�������v2���͋g�ǎ��L�̗{�q�Ƃ��ċg�Nj`���ƋL���B �@ |
|
|
���L���@�X�R����ƈ�c�썇��
�u�O�͕���v�͐��N�̎��Ɋւ��āu�X�R����v�ƌĂсA�����͂��̌�ɐD�c�M�G�ɂ��O�͂ւ̐i�U���������ƋL���B ���u�����L�v / ������t�߂ɕz�w�����D�c���ɑ��A�������́u�����\�Y�O�Y�v��叫�Ƃ���700�]�l�ň�c���ɐw���Ƃ����B�����͕�����ɕ����č��킵�A�u�����̎��O �������v�������A�M�G���u����O������� �Ȃ��Ȃ��\�����Ȃ炸�v����Ƙa�r���A�w�����B���N�̎���V��4�N12��5���Ƃ��邪��c�썇��̔N���͋L����Ă��Ȃ��B ���u�O�͕���v / �u�X�R����v�́u10�����߂�����Ɂv�Ƃ��Ĉ�c�썇����L���B�u�O�͂ɂĈɓc����Ɛ\������͐��Ȃ�v�Əq�ׂ�B��������N���������B����800�̎G���ɂ������M�G�̕�8,000�Ƃ��A�o�������ɂ킩��Đ�����Ɛ����B�u�N������Ɖ]�l�͂Ȃ��ꋤ �\�`���ɂ́v�Ƃ̕������݂���B ���u�ƒ����L����v / �M�G������������8,000�]��ƋL���A�������ɂ킯���Ƃ���B�������N���Ȃ��B ���u����̎�ËL�v / �V��4�N12��27���u�D�c�Ƃ�葽���ɂĎO�B�ɓ����v�ƋL���B ���u���i���ƌn�}�`�v6���u���́v / �V��4�N10�����N�����̌�A�D�c�����O�͂ɏo���A�ɓc���ɂč��͏d�������������Ƃ���B ���u�O�B����L�Ó`�W�v / ���N�̎���V��2�N12��5���Ƃ��A��������u100�������߂����Ɂv�D�c���̐i�U���������Ƃ���B�u���싌��裒�m�v�͔N���ɂ��ē��������Ă���B�u������I�v�͓V��5�N2���Ƃ��Ă���B ���Q�l���L / �u�����L�v�̏����\�Y�O�Y�͐��N�A�M�F�̌Z��E�����N�F��(�u�������v)�B�u���싌��裒�m�v�́u�O�͍��Õ��l�v�ق��������ēV��11�N3��18�����Ƃ��Ă���B �@ |
|
|
���ɐ��ւ̕��Q�Ɖ���ҏZ
���L���̉���A�҂܂ł̌o�܂��u�����Ɩ�����v�͎��̂悤�ɋL�� �V��4�N�u�Ɍ�5���v�ɐ��N���u�䕠��������v���B�ɐ��֑D�������āu�呠�a�v�ɐ\�����킹�ĉ��B�ւ̉��������߂��B�u�������v��3��17���Ɂu���q�v�ɉ�A�V��5�N�̉Ă̂��������u���� ���������v�ɂ����B��8��5������u�����v�u����v�u�`���v���o�āA9��10���Ɂu�ނ���v�ɂ������A�[10��7���ɂނ�����u���₫�v���āu�����v�֑ނ����B�u�呠�a�v�͍Ăяx�͂֕����A���N6��1���ɉ���ɂ����Ė{�ӂ��Ƃ��A�x�͂}������������25���Ɂu���q�v�����邵���B ���u�O�͕���v�͂����ł��� �u�ɓc����v�̌�u���O�v�͍L�����u���o���v�A���̂��߁u�����V�呠�v��13�̍L���ɋ����Ĉɐ��֓��ꂽ�B14�܂ő؍݂�����ɏx�͂֓n��A15�̏H�ɋ`���̉��R�āu�ΘC�̏�v�֓������B�u���O�v�͑�v�ېV���Y��7���̋N�������������A�ΘC���U������B��v�ۂ́u�L�ԁv�֓����ɍs���Ƃ̐M�F�̐\���o���A���̊ԂɍL���������֓��ꂽ�B���̌�u���V�a����l��������āv�o�d�����B ���u�����L�v�͎��̂悤�ɋL�� �M�G�Ɖ��҂ł������u���V�v�́u��B�������܂�����m�s�����́v���L�����u���X�ɂāv�Ǐo�����B13�̍L���́u�ɐ����֘Q�l�v�̐g�ƂȂ�A�����呠������ɏ]�����B�z�N��Ɍ������A�g�ǎ��L�́u��̐��v�ō���`���֏��͂̐\�����ꂪ�Ȃ��ꂽ�B�L���͏x�͂ɕ����A�`���̉����ĎO�͂́u����̏�v�Ɉڂ�B����̉Ɛb�͓����ɍL���̋A�҂����Ȃ������A��������M��́u��v�ېV���v���Ăсu�ɉꔪ���v��7���̋N��������������B��v�ۂ�͂����j���āu�������l�v��ɑ��k�A�u�{��v(�����)�̗��狏�ł������M�F���u�L�n�v�֓����ɂ��A���̊ԂɍL������ɂ��ꂽ�B�L���̎O�͋A���͓V��6�N6��1���ŁA�������͓�25���A���̎�17�B����O�u�F�X����������\ ���X����o���Ȃ炸�v6��8���u���V�v�͘a�r���A����ɏo�d�����B ���u�����听�L�v�͔N�����Ď��̂悤�ɋL�� �V��4�N12��5�����N���u���B��R�v�Ŏ����A10�̍L���͈����呠����]���Ĉɐ��E�_�˂ɂ����B���V���M��́u���Ƃ�D���u����� ���e�N�����Ԃ炩���v�D�c�Ƃ֓��ʂ����B�L���͑�v�ے��r��̗v���������A��5�N3��17���Ɉɐ��_�˂��o�ĉ��B�u���ˁv�ɏ㗤�A�u150�����萀���v�����̂��u�����v�ɋ��Z�A�����Ɂu����v�u�`���v�u���ˁv�Ȃǂցu�ʂ��āv�M�F�E�u�����`�\�Y�v�ƘA�����Ƃ�B�[10��10�������͏x�͂ŋ`���ɉ�A���N�~�ɍL���́u�Q�B���C�v�ɓ���B�M��͍U���������A�܂���v�ے��r��7���̋N��������������B��v�ۂ畈��̏O�ƐM�F�͒k�����A�M�F�͓����Ə̂��āu�L�n�v�֍s���A12�̍L���͓V��6�N5��1������ɋA�҂����B �� �u�����L�v�͐X�R�����V��4�N�Ɩ��L������ł��̎��̍L���̔N���10�Ƃ�(��)�A�܂��ɐ��s����13�Ƃ��Ă���B�V��6�N�ƋL������ւ̋A�҂ɂ�2�N�����Ȃ��A����䂦�N���ƔN��̋L�q����������B�u�����听�L�v�́u�����L�v�ƔN���������ł��邪�A6�N�̉���A���12�Ƃ��Đ��N�Ƃ��ꗂ�����Ă���B �u���싌��裒�m�v�͓V��6�N(1537�N)6���ɍL���̉���ҏZ�����������Ƃ��Ă���B�܂���L�u�珼�ہv�̖�������w�V�҉���s�j6�x�u�M����������16�v�̓V��6�N10��23���t�������ʂ��́A�����r�Z�Y�A��E�V���Y(�}�})�A���������Y�A�匴���߉E�q��A�ѓ����ɑ��āu���x�����V�V ���ߖ���ތ�v�Ƃ���15�ѕ��̉�����Ă���A�w�V�� ����s�j2�x�͂��������A�҂̌��тɂ����̂ƍl���Ă���B��v�ۂ�5���ւ̉����ɂ��Ắu�O�͕���v�u�����听�L�v�ɋL�q������B �ِ��Ƃ��āu��N�������v(����3�E1646�N����)�͉��艟�̂������M�F�ɂ����̂Ƃ��A�����V��7�N(1538�N)�ƋL���B�܂��`���ւ̉���ҏZ�̗v����8�N��Ƃ��A�x�{�s����9�N�t�A�u�ΘC�v����͓��N�H�A����ҏZ��V��10�N(1541�N)�ƋL�q����B����ɂ��āu���싌��裒�m�v�́A�M��̉��艟�̂�V��7�N�Ƃ���̂́u�����L�v�����̔N���13�ƋL�������߂ɐ��������ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���B ���Q�l���L / �u���O�v�u���V�v�������M��(�u�������v1���u����v)�A�u�������l�v�������M�F(���u�O�v)�A�u�呠�v�u�����V�呠�v��������g(10���u�����v�B���̒效�u��g�v�ɂ���A�Ƃ���)�A�u��v�ېV���v����v�ے��r(11���u��v�ہv)�A�u���C��v�������ɂ��\�L����肵�Ȃ����w�V�� ����s�j2�x�͐����s�����ɔ�肵�Ă���B �@ |
|
|
���L���@�D�c���̎O�͐i�U�Ə�����̐킢
�L���̌㔼���͎O�͂i�U����D�c���Ƃ̐킢�ɔ�₳��Ă����悤�ł���B �����ˏ���߂���U�h �u����̎�ËL�v�͎��̂悤�ɋL���B �V��9�N(1539�N)�u���B�� ���ˏ�֎�|�v���A6��6���ɍ���ƂȂ����B�u���˕�������ׁv���ď��u�������n�Ɓv���ؕ������B���ɏ����r�Z�A���E�����Y�A�ѓ����A�����P���q��A�ߓ��^�s�A������s�A���ؓ����������A�u�������� �D�c�Ƃɓn��v���ƂƂȂ����B��10�N8��10���A�x�͐������˂Ɋ��āu���˓�v�ɂ����Đ킢�ƂȂ����B �����͂��̌�A�V��12�N(�u�{���g���G�哢���v)�Ɠ�14�N�̌v4��̈��ˍ�����L���Ă���B �u���i���ƌn�}�`�v�ɂ��D�c�Ƃɂ����ˍU�߂̋L�q�����邪(�N���͓V��9�N6��6��)���������炪�h�킵�ēG���ނ����ƋL���Ă���(�u�������v1���u����v)�B�܂���1���͏����������Q�킵���Ƃ��邾����(�N���Ȃ�)���̌��ʂɂ��Ă̋L�q���Ȃ��B�u�������v�̒����̋L���́u�M�G���ɗ��������Ĕs���v�����Ƃ������̂ł���(1���u�܈�v)�B �������u�����听�L�v�͓V��9�N�̐킢���u�D�c�M�G����������߂Ĉ����ނ��v�Ƃ��A�V��13�N�ɂ͏镺�̖h��ɂ��D�c�����s�R�����ƋL���B��14�N�̂��ƂƂ��āu�L��������̔s���J�āv�Ƃ��邱�ƁA�܂��L���̎���A���삩��̉����Ĉ��ˏ���ח��������Ƃ̋L�q�����邱�Ƃ���A�邪�D�c���̎�ɓn�������Ƃ͔F�߂Ă���B���������̎�����o�܂ɂ��Ă̋L�q���Ȃ��B ���Q�l���L / �u�������n�Ɓv���������ƁB�u����̎�ËL�v���u�e����䑧�v�ƋL���ق��u�������v1���͏����e���̎q�E���鍶�n���u���Ɓv�Ƃ��A�V��9�N6��6������ɂ����Ď����ƋL���B ��������̐킢 �u�M�����L�v�́u8����{�v�̂��ƂƂ��ď�����ł̐퓬�����̂悤�ɋL���B�N���̋L�ڂ͂Ȃ� �x�͐��͎O�́u���c���v�Ɏ��i�ɐw���\���u�x�̗͂R���挜���ɂ� ��������l���������v���˂�����֏o���D�c���Ɛ킢�ɂȂ����B�D�c�����A�ɒ�u�^��Y�v�u���O�Y�v�u�l�Y���Y�v�܂��u�D�c������v�����킵�A���������B�u�O�x�l�x�����荇�� �e�蕿�Ɖ]�����v����Ȃ��A���쐨�͕����u�ł��[��v���B �������������u�M���L�v�͓V��11�N(1542�N)�̂��ƂƂ��ċL��(���L���s�{�㊪)�B �V���p��8��10���A����`����4���]�R�𗦂��āu���c���v�ɏo�w���A������ɕ����ď�����ɉ������B����D�c���̕��͂�4,000�]�R�ň���֏o���A�D�c�u���O�Y�v��叫�Ƃ��ēG�w���������B�D�c���͍�̓r���Ŗh�킵�A�͐K�^�l�Y�����쐨�̑��y�叫�u�R���v�̎��������B�����ɂȂ��ĐD�c���͍�̉��ւƒǂ��l�߂�ꂽ���A�D�c������A�������߁A���c���E�q��A���X���l���A���E�����A���얔���q��̊���ō��쐨��ǂ��Ԃ��A���ǂ����������B �����͂��̐킢�ɂ��āA���Ԃł́u�������̏��R�v�Ƃ����Ă��邪�u���ɂ������ɂ�����͑O�㖢���v�ł������Ƃ��A���������u������̎��{���v�ƌĂ�Ō��p�����ƋL���Ă���B�u�R���v�펀�ɂ��āu�M�����L�v�͂�����L�����A�t�Ɂu�R���v���u�ߌÖ��ܘY�v�̎��������Ƃ��Ă���B �Q�l���L / �D�c����灨�D�c�M�G�A�u���O�Y�v���D�c�M��(�u�������v8���u�D�c�v) �����u�O�͕���v�͏�����̐킢�����̂悤�ɋL���B�N���͂Ȃ��B ���쐨�̐i�o�����M�G�́A���˂��o�ď�a�c�ɒ����u�n���̌��v�w���Ƃ邽�ߐi�������B���쐨�͓��삩���a�c���߂����Đi�R���A�������������Ƃ���ŗ��҂��������A�킢�ƂȂ����B�D�c���͏�a�c������˂֑ސw���A���쐨������֖߂������A�u�X�Ƃ͐\���� �e���V���V���͓�x�NjA����\ �l�����łꂽ��� �x�͏O�V���v�ł������Ƃ����B�܂��u�O�͂ɂď�����V����Ɛ\�������͍��̎��v�ł���B �u�����L�v�͔N�����Ă��̂悤�ɋL���B �V��17�N(1548�N)3��19���A�D�c���͉�����Ƃ��Ƃ��Ĉ��˂�i���A������������x�͐��́u�Սώ���ցv��叫�Ƃ��ď�a�c�ɐw���Ƃ�A��������̂ڂ����B�D�c���́u�D�c�O�Y�ܘY�叫���ɂāv��̓r���ł��肠���ƂȂ����B�u����ޓ��O�Y�v������O�ɉ��m���āu�O�Y�ܘY�v��ǂ������A�܂��D�c��������Ԃ������߁u�ѓ��ܘY�v�u���ь��V���v��u�悫�҂��܂������v�����B�u�����ܘY���q��������v�Ă��肩�����A�u���O�ʁv���u���q��V���v���g�ݓ����A�D�c���́u�����s�R�v�����B �����̋L�q�͎��̂Ƃ��� ���u����̎�ËL�v / �V��17�N3��19���A������ɂ����č��킪����u�R�����������v�A���쐨�́u����v�ɁA�D�c���͈��˂ɑނ����B ���u���i���ƌn�}�`�v / 1���u�����E�אe�����v�B�V��11�N8��11���A�����⍇��ɂ����ē`�\�Y�u�^�v���펀�����Ƃ���B ���u���v / 9���u��v�ہv�B�V��11�N�A�Սώ��̒��V��ւ��u����`���ɂ����āv���˂����߂��Ƃ��A��v�ے������u�����̍���v�ɂ����đ����������ƋL���B ���u���v / 3���u���v�B�V��17�N������ɂ����č��ؐ��G���������A�����m�����D�c�M�G������̊����ɂ������Ƃ����B ���u���v / 14���u�R���v�B���Ȃ����V��17�N�R������(�R���d���̎���)���������A�����D�c�M�G�Ɍ��サ���Ƃ���B ���u�ƒ����L����v / �V��17�N3��19���u�L���N�R������̏��蔭���x�B�̕��ƍ����v�Ƃ��Đ킢�ւ̊֗^�������A����̕������쐨�Ɓu���Ɠ��������i�ĕ���v�A���䐳�e���u�C��w���v��������Ƃ���B���e�͑O�����u�����L�v�Ɠ����ł��邪�A�㔼�Ɏ����āu�D�c������v�A�����A���X�A����炪�D�c�M�L�Ƌ��ɕ��킵�u�x�B�̕��������Ĕs�S���v�Ƃ���B�܂��u���l�����ĎO�B������̎��{���Ə̂��v�Ƃ�����ŁA��Ɂu���萨�ܘY���q�щ��������v�D�c����ǂ����������ƁA�u���q��V���v���u���O�ʁv�������Ƃ����L���Ă���B ���u�D�c�R�L�v(�����L) / �V��17�N3���A�D�c�M�G��4,000�̕��𗦂����˂ɓ���A�u���c���v�ɐw���\�������쐨��3��12���ɏ�����Ő킢�ƂȂ����B�D�c���͑叫�u���O�Y�v�M�����u�D�c������v���⍲���A�͐K�����쐨�̐�w�u�������[��v��������B�[���ɂȂ��āu�����̐킢���v�ƂȂ������A�����A���c�A���X�A����炪����ĕԂ��A�G�w���������B���쐨�́u�����v���͂��߁u�O�B�v�́u�сv�u���сv�炪��������s�R���u�����ܘY���q�v���u���������v��a�ƂȂ��ďx�֑͂ދp�����Ƃ���(���L���s�{)�B ���u�O�͋L��S�v / �V��16�N8���A�D�c���̑叫�O�Y�M���A���쐨���u�эێ���֒��V�v�Ƃ��ď�����̐킢���L���B�u�ƒ����L����v�Ƃ��Ȃ����A�D�c������炪�����Ԃ����Ƃ�������������������ē˂��Ԃ����Ƃ���B�܂��u�����L�v�ɂ����āu����O�v�Ƃ��ꂽ�сE���т������̉����ɂ���ē������ꂽ�Ƃ���ȂǁA���e�ɍ������݂���B ���u�����听�L�v / �V��11�N�A��17�N��2��ɂ킽���ď�����̐킢���L���B �w�V�� ����s�j2�x��17�N3����11�N8���Ɍ�`�����\����Ⴍ�݂�2������x�����A���a�c�N�j�u�x�� ����ꑰ�v�͍���`���̓��O�͐i�o�͓V��12�N����ł���Ƃ��āA11�N�̐킢�͂Ȃ������Ƃ�������Ƃ��Ă���B ���Q�l���L �`�\�Y�u�^�v���u�������v1���ł́u���̒效�ɏ��g���邢�͐M���ɍ��v�Ƃ���Ă���B�܂��u���i���ƌn�}�`�v�ɂ͋L�q���Ȃ����u�������v�ł͕��u�M�g�v���펀�����Ƃ��Ă���B �u�D�c�O�Y�ܘY�v���D�c�M�L(�u�������v8���u�D�c�v) �u�����ܘY���q�v����������(�u�������v14���u�����v)�������j�̌Z��Ƃ���Ă���B��6���u����v�A�u�����O�͌㕗�y�L�v�㊪���������u�����v�ƋL���B�u���싌��裒�m�v1�������2���j���ɌܘY���q�u�^�K�v�Ƃ��邪�A����́u�����ҔN�W���v�㊪�̕\�L�ɂ�������̂Ǝv����B�w�V�҉���s�j6�x�́u�O��Õ����v��������20�E�V��21�N8��25���t�E�����ܘY���q���āu����`������ʁv�̌ܘY���q�̖��Ɂu���M�v�ƒ��L���č̘^���w�V�ғ��Y���� ������3�x�͍����������ّ��u�Í������W�v��������2-88�E�i�\3�N6��8���t�̉����ܘY���q���āu���쎁�^�����v�̌ܘY���q���u�������M�v�̂��ƂƂ��ĉ�����Ă���B �u����ޓ��O�Y�v���u�����听�L�v1���́u����ޓ��O�Y�ה\�v�ƋL���Ă���B�@ |
|
|
���L���@�����Ɨ���
�u�����听�L�v�͉���(�`�ʉ@)�Ƃ̍����͓V��10�N(1540�N)�Ƃ��Ă���B�ƍN�o���̌�ɗ������邱�ƂɂȂ邪�A�����͂��̗��R�ɂ��āA�V��12�N�̐��쒉���̑����ɂ��A�Ɠ��p��������M�����D�c�Ƃɗ^�������Ƃɂ������Ƃ݂�B�����͉ƍN�a����V��11�N�̐��܂�Ƃ�����ŁA�`�ʉ@�Ƃ̗����͉ƍN3�̎��̂��ƂƂ��Ă���B �u����̎�ËL�v�͉���Ƃ̍������u�V��9�N�̎����Ɖ]�v�Ƃ��A�܂���13�N�ɗ��ʂƂ���B ����Ƃ̊W�ł����A�ޏ��̍č�����ł���╔���v���r����ʂ��Ĕ������m���S�ɉ�������`�Ղ��݂��邱�Ƃł���B�u���i���ƌn�}�`�v1��202�ł͓V��15�N(1545�N)�u�L����������Ɍ䂠�������肵�́v���(�튊�s�k��)�̍����ƂƂ̘a�r�����������Ƃ��Ă���B�w�V�҉���s�j6�x1171�������́u�v�����Y�v���Ă̍L������ʂ��Ɂu��썟���A�\�䓯�S �O�����V �{�]���Ɍ�v�Ƃ��邳��Ă���B�@ |
|
|
���L���@��
�L���͓V��18(1549�N)3��6���Ɏ��������Ƃ���Ă���(�u�ƒ����L����v�u�n�ƋL�l�فv�u����̎�ËL�v�ق�)�B�������w����s�j�ʊ��x�㊪��3��10���Ƃ��Ă���B���������̎j���ɏ������Ȃ��A��A�ƍl�����Ă���(�w�V�� ����s�j2�x)�B �����Ɋւ��Ă����������� ���a���Ƃ�����́��u�O�͕���v�u�����L�v�Ȃ� ���⏼����(�Жږ픪)�ɂ���ĎE�Q���ꂽ�ƋL�����́��u����̎�ËL�v ���Ꝅ�ɂ��E�Q���ꂽ�Ƃ�����́��u�O�͓���L�v�B�V��18�N3���A���̍ۂɁu����̕� �n�����̈Ꝅ���Q�Ȃ����v�ƋL��(���L�����{15����)�B�܂�������u���B�D�c�e�����̕����v�Ƃ��Ă���B�w����s�j�ʊ��x�㊪�ɍ̘^����Ă���B �u�����听�L�v�̂ق��u�ƒ����L����v�u�n�ƋL�l�فv�u��c���сv�Ȃǂ�������a�������̂�B�u������I�v�u���싌��裒�m�v�������B�w���싌��裒�m�x�̘^�L���͎��̂Ƃ���(1��737���ȉ�) ���u�����L�v / �V��18�N�t���u��ς���v�A��3��18�������B24�� ���u���{�O�͋L�v / �������u18�N�t�L���a�C�v�A3��6�����A24�� ���u�ƒ����L����v6�������A24�� ���u�O���L�v / �u��a�C�v3��6�����B�u�a�C�A�N�v�g�]�X�v�Ƃ���B �u�����L�v���L�������́w�O�͕����W�� �����ҁx�Ɏ��߂�ꂽ�|���A����э����������ُ����̎ʖ{2���͂������3��6���ƂȂ��Ă���u���싌��裒�m�v�̋L�q�͌�ʂƎv����B�w����s�j�ʊ��x�㊪�͊⏼����ɂ��E�Q�����Ƃ�A���ꂪ�w�V�� ����s�j2�x�ɓ��P����Ă���B �����n�Ɩ@���A������ ���n�͈��m������s�̑����(�u���싌��裒�m�v1�����ځu�������R�����v�B�u��㑰�L�v����сu���얋�{�ƕ��v�ɓ���)�B�@���́u�����@�a�v�������́u���_�@�a�v���������勏�m(�u��㑰�L�v�u���얋�{�ƕ��v19��)�ŁA�����̌�u������a�v�ƂȂ����Ƃ��铯���̋L�^������Ƃ���(�u���싌��裒�m�v1��738�����ځB�u��㑰�L�v���Ȃ�)�B ���ݑ�����ɉ����A��ю��E�������E�@�����E�L������5�̕揊������s�ɂ���B �܂�����A�c��16�N3��22���]��ʑ�[���̊��ʂ��Ă���(�u���얋�{�ƕ��v19���́u�ƍN�� �䎷�`�v�Ɉ˂�Ƃ���)�B�u��N�������v�́u���匠���{��v�Ƃ��ď]�O�ʑ�[���ƋL���u��㑰�L�v�͐���ʌ���[���Ƃ��Ă���B�Ȃ��A�Éi���N10��19���ɂ́A������b����ʂɒǑ�����Ă���B �����L���@��������b����ʐ閽(����G�L) �V�c��ٗǖ��~�A���]��ʞܑ�[�����A�����b���ٔ{�~���������H�~��A�|��鞬�u������m�u氐�^���A���m��氐��S�L�P�N�A���������v�m�u�сA���Ƌ���A�����{���ҁA��T�q�ޗ��~�ޖ��A���H�{�����m������ҁA�q�m����A�q�m������ҁA�M���m�y�ҁA�ÔT�T�ޗ��A�R�m���g�T�s�����V����氐�A�d�V���ʌ��㋋��氐�A������b����ʐm�����䑡���z�A�V�c�䒺���������H�~��A�Éi���N�\���\��������L�������b�\�A (�P�Ǖ�)�@�V�c��ٗǖ��~(�F���V�c�A���߂炪���ق݂��Ƃ�܂�)�A���]���(���Ȃ��ӂ��̂����)����[��(����̂��ق����̂܂����̂���)���L�����b�ɏٔ{�~(�̂�ւ�)������(���ق݂��Ƃ�)���H�~��(�������߂��Ƃ̂�)�A�|��鞬(��Ԃ���)�ɂ�������(����)�ɂ��Ă�荡�Ɏ���ē�S�L�]�N�A���̐������v(����)�ɂ����A���ߋ��А������ւ�́A���̎q�Ȃ�ƂȂށA���H(��������)�����̕��Ɍ�����A�q�ɉ�(��)���A�q�Ɍ�����M���ɋy�Ԃ͌�(���ɂ���)�̓T(�̂�)�Ȃ�A�R��Ɍ��g(����₤)�̕s�������V�����ЂāA�d�˂Ċ��ʂ���(�̂�)�����ЂāA������b����ʂɎ��ߎ��Б��莒�ӁA�V�c(���߂�)������(���ق݂���)�������������H(��)���Ɛ�(��)��A�Éi���N(1848�N)10��19���A����L��(��)��(�������A�]�l�ʉ�)���b��(�������܂�)��Đ\���A ���]�� ��ʂɖ}�f�A���邢�͋����ł���ƕ]����Ă���B�������Ȃ��炻��͕��e�ł��鐴�N�⑧�q�̉ƍN�́A�P���������тƔ�r���Ă̎��ɉ߂��Ȃ��B�m���ɎO�͓���𐬂����������N�ɔ�ׂ�A���쎁�̔�ɂ���Ă悤�₭�������𑶑��������L���́A���܂�ɏ�Ȃ��ƌ����悤�B�������Ȃ���Ȃ𗣉����A���邢�͑��q�E�|����D�c���̐l���Ɏ���Ȃ�����A�����܂ō��쎁�ɒ�����s�������L���̔��f�͐����������ƌ�����B���쎁�͐D�c�����U�߁A�D�c�M�L���߂�ɂ��Đl�������Œ|����D�҂��A�L���̒��`�ɕĂ���B����ɂ��L������̏������͖ŖS���܂ʂ���鎖�ɂȂ�B�@ |
|
|
���L���@�Ȏq�Ɋւ���`��
���ȂɊւ��� �u���c�w���`�v�͎O�l�̎����L���Ă���B�����E�����̕ʂL����j���͂Ȃ��B�܂����̎q�Ɋւ��Ă���j�ꏗ(�u�����听�L�v1��)��j��(�u�Q���`�v��1)��j�O��(�u�����O�͌㕗�y�L�v�㊪����сu������I�v)�O�j�O��(�u��㑰�L�v��1)�Ə����ɂ��L�q���قȂ�B ���q���Ƃ��̐��� ����ɂ�蕪�ނ��Ĉȉ��Ɏ������A����ɂ��đ����̂�����́A�L���̎q�Ƃ��đ����̂�����̂͂�����u����Ɂv�Ƃ����B���������݂��̂��̂��^���Ă���A�����A�b�ŁA�ƌ��ɂ��Ă͂��̂�����ł͂Ȃ��A�P�ɏ��`�̂�����̂Ƃ��ė����B ���`�ʉ@�Ƃ̊Ԃɂ��܂ꂽ�q / ����ƍN�E�����P(�����) ���勋�������搳�̖��u���v�̕��v�Ƃ̊Ԃ̎q / ���������E���Ìb��(�m) ���������E���Ƃ̊Ԃ̎q / ��c�P(�����N���̍�) ���^��P�Ƃ̊Ԃ̎q(�����) / �s��a(�r��`�L�̍�) �����̑� / �O�Y�ܘY�ƌ��E�����M��(�����)�E�����e�� |
|
| �@ | �@ |
| ���퍑�����̒m�b | |
|
���M���A�G�g�A�ƍN ���݂̈��m�����������o�������O�l�̓V���l���Ȃ킿�D�c�M���A�L�b�G�g�A����ƍN�́A���ꂼ��́A�u�����Ǘ��@�v�͈Ⴄ�B���[�_�[�V�b�v�Ƃ����̂́A�u�g�b�v���邢�͑g�D�ړI���B������悤�ȁA�H�v������v�Ƃ������Ƃł���B�O�l�̓V���l�̖ڕW�́A��̎��̂Ƃ��ɐ�������Ă���B �� �D�c�M���̖ړI�́A�����l�Љ�̔j�� �� �L�b�G�g�̎��ƖړI�́A�V���l�Љ�̌��� �O ����ƍN�̎��ƖړI�́A��l�̐�y�ɂ���čs�Ȃ�ꂽ���Ƃ̐����ƁA�����ێ� �����Ă݂�́A �� �M���͔j�� �� �G�g�͌��� �O �ƍN�͈ێ��Ǘ� �ł���B�����Ȃ�ƁA����Ȃ�Ƀ��[�_�[�V�b�v�̂Ƃ�����قȂ��Ă���B �� �M���́����ԂƂ̐킢�����d�A�������[�_�[�V�b�v�͕����Ɂ����|�������������邱�ƂɂȂ�B �� �G�g�̏ꍇ�́A���݂��ړI������A�����̐l�тƁA���ɒ�ӂɂ��铭����̃����[���E�A�b�v(���C�N����)����̂ɂȂ�B����ɂ́A�g�b�v�Ƃ��Ă̏G�g�̐l�C�����߁A�u�G�g�l�̂��߂Ȃ�v�Ƃ����C�����N�������邱�ƂɃJ�_���������B �O �ƍN�̏ꍇ�́A�����ɘj��ێ��Ǘ����ړI������A�������[�_�[�V�b�v�̂Ƃ�����u���f�x�z�v���d�A�u�������݊Ԃɂ�����^�S�ËS�̔O����������v�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�u�^���̋C�����v��g�D�^�c�̃o�l�ɂ���B�Ƃ����悤�ȕ��́E���ނ��\���낤�B ������O�c���Ƃ�����Ƃ���A�M���͏�ɁA�u�R���Ă���ɂ��ė����v�Ƃ����^�C�u�̃g�b�v���[�_�[���������A�G�g�́A�u�݂�Ȃ̋C������t�x���Ȃ���A���C���N��������v�Ƃ����g�b�v���[�_�[�������B���������Ƃ̌���Ƃ���A�G�g�̏G�g����䂦��́A���������A�u�����̋C�������C�ɂ��Ă���v�Ƃ����g�b�v���[�_�[�ł͂Ȃ������B�M���͂��ė��Ƃ�����k���ɔh�������Ƃ��ɁA�u����̂�������֑��������ĐQ��ȁv�ƌ��������B���̂��Ƃ͌��t��ς���A�u����قǂ���𐒂߂�v�Ƃ������Ƃ��B���̌����ɁA�M���̕����͑S�����|�S�������A�u���Ȃ������猵���ɏ������v�Ǝv�����ށB �ӔN�Ɏ������G�g���ܐl�̑�V�ɑ��A�u�����@�ɔw���悤�ȘV��������A�C�t�����҂͕��������ɗ����ŏo�|���čs���A���肪�ӌ������ɓ����ė������������������ȁB���̂܂a���Ă��܂��v�Ɩ������̂́A�u�a��ꂽ�҂́A����Ɏa��ꂽ�̂ł͂Ȃ��A���̏G�g�Ɏa��ꂽ�̂��Ǝv���v�Ɩ��Ȏ蓢�_��W�J���Ă���B���邢�́A�u���������ւ̏}�����Ǝv���v�Ƃ������Ă���B�`���ɂ��́A�u�ՏI�̍ۂ́A�G�g�͎��ւ��Ȃ���A�ܑ�V�����ɗ��ݐ\���A���ݐ\���ƏG���̂��Ƃ����肵���v�Ɠ`�����Ă��邪�A���������S�߂ŏ�Ȃ��G�g�̗L�l����l����ƁA���́A�u�@��j�����ҁv�ɑ���A�Ǖ��E��蓢�o��̈ӌ��E�Ќ��̋��ߕ��́A����O�ɂ����g�b�v���[�_�[�́A�u���肬�茜�R�ɗ������҂̈�P�v�Ƃ��āA�������P��������Ă���B ���������āA�\����̘a�k�����̌�ɁA�O�c���Ƃ�����ƍN��K�ˁA���̌�œ���ƍN���O�c���Ƃ�K�˂�Ƃ������Ƃ́A�G�g�̈�P�ɂ��A�u�����E��蓢�o��́A�ٌ��\�����āv�̎��s�ł������B�P�ɁA�u���ꂩ��͒��ǂ����܂� �傤�v�Ƃ����A�e�P�K��ł͂Ȃ��B �@ |
|
| �����c���� | |
|
�����Ƃ̕��������s����
[ ���c����(1432-1486)�@��������̕����B��������A��J�㐙�Ƃ̉ƍɁB�ےÌ����̗�������ޑ��c���B恂͎���(�����Ȃ�)�B��J�㐙�ƉƍɁE���c����(���^)�̎q�ŁA�ƍɐE���p���ŋ����̗��A�����i�t�̗��Ŋ����B�]�ˏ��z�邵�������Ƃ��ėL���ł���B ] ����́A�u�����S�v���A�u��Ƃ���������l�ԁv�Ƃ��āA���̐l�Ԑ��Ɏ����_�ƗD�����Ɖ�����������Ƃ邩�炾�낤�B����́A�u����ƍN�̂�������ƂȂ�F�߂Ȃ�����ǁA���c�����̂�������ƂȂ炷�ׂď��F����v�Ƃ����A"������������ł͂Ȃ����ꂪ�������"�Ƃ����|�l�̕]�����@���A�����Ƃ��͂�����\��Ă���Ⴞ�B �ł́A�����͂��������ǂ�Ȃ��Ƃ�������̂��낤���B�ꌾ�ł����A�u���Ƃ̕������v�ł���B���݂ł��悭�u�s���̕������v���邢�́u�����s���v�ȂǂƂ������t���g����B���҂͈Ⴄ�B�u�����s���v�Ƃ����̂́A�s�������ۂɕ������Ƃ������Ȃ����Ƃł���B����ɑ��u�s���̕������v�Ƃ����̂́A�u�s���ɕ�������^���āA�i���⍁������A������Z���ɉ������킩��₷�����̂ɂ���v �Ƃ������Ƃ��B �ȒP�ȗ��������A�Z���ɑ��o�����̈��Ė����u�a�v�Ȃǂ��g�킸�Ɂu�l�v�ɉ��߂邱�Ƃł���(�u�a�v�́u�l�v���h�ӂ��y���A���݂ł͂����I�ȗp��)�A�܂��Z�����炢�낢��₢�|�����o���Ƃ��ɂ��A�u�����������܂��v���́u�P���������܂��v�ȂǂƂ����������͂��Ȃ��B�������Ɓu����͕K�����s���܂��v���邢�́u����͂ƂĂ��ł��܂���v�ƁA���m�ɓ����邱�Ƃ��s���̕������̂ЂƂ��B�Ȃɂ����A�����̕������Ȃ킿���������A�u�����ɂ킩��₷������v�Ƃ������Ƃ��A�ł���u�s���̕������v�ł���B������A�{���Ȃ當�����Ƃ����Ă����Ă��A�����͂܂��s���̕������ɓw�͂��ׂ��Ȃ̂��B�@ |
|
|
���l���������̌̂ɎE���ꂽ
���l�̑��������ς�̂ɁA�悭�g������@�́A�u���̐l�Ԃɂ��āA���]�𗬂��v���邢�́A�u�L�͎҂ɒ��ڈ����������v�Ȃǂ��B �O�҂́A�Ђǂ��̂ɂȂ�ƁA�Ȃ����Ƃ܂ŝs�����ė����B ��҂́A���Ƃ��ΐl�������E�ł��闧��̐l�ԂɁA�u���݂́A������ǂ��v�����v�ȂǂƂ������ꍇ�ƁA���i����܂��邲�Ƃ�"�����"�𐁂����ޏꍇ�ƁA�ӂ�����B �L�͎҂ɂ���ẮA��������"�l���̂��ӌ���"�����Ă����āA�̐S�ȂƂ��ɂ͕K���A���̂��ӌ��Ԃ̈ӌ��������A�Ƃ������@���Ƃ��Ă���B ���̃V�X�e���ł́A���R���ӌ��Ԃ̈ӌ��������łȂ���Ȃ�Ȃ����A���ꂾ���ł͂��߂��B�ӌ��������L�͎Ҏ��g�������łȂ�����߂Ȃ̂��B �L�͎҂��l�Ԃ������ނ����Ȃ��̂����A�L�͎Ҏ��g�A���łɏo�����������Ӓ��̐l�Ԃ�����B���A���̐l�Ԃ̕]�������܂����p�b�Ƃ��Ȃ��B�����ŁA���ӌ��ԂɈӌ��������B �����A���̂Ƃ��̂��������́A�����̈ꖕ�̕s�����S�O����������悤�ȓs���̂����ӌ������߂Ă���B�q���Ȑl�Ԃ́A���̂ւ������ʂ��Č}�����邪�A�����Ȑl�Ԃ͂���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���X�Ɛ��_���͂��B �����������������Ƃ́A�K���k���B����͗L�͎҂��Ӓ��̐l�Ԃ����ŁA�u���܂����o�������Ă�낤���Ǝv�������A���ꂪ�������v�Ƃ������炾�B���܂������Ȃ������C�����ӌ��Ԃɓ]�ł��Ă��܂��B ���R�A�������ꂽ�l�Ԃ́A���ӌ��ԂɁA�u�����́A����̑��������ς�₪�����v�Ƃ���ށB���l�ł���قǂ���ށB���ӌ��Ԃ̈ӌ��������ł����Ă��A�����͍l���Ȃ��B ������A���������l�Ԃɂ����炸�A���ӌ��Ԃ��A�u���̐l�Ԃ͂��߂ł��v�Ƃ������l�Ԃ́A���ׂĂ��ӌ��Ԃ����������ς������ƂɂȂ�B���̂ւ�́A���܂��ς��Ȃ��B�l�Ԃ̐l�Ԃ���䂦�B�����Đl�����ق�Ƃ��Ɍ�����������A�T�����[�}���͋t�ɂ܂�Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����B�h���}���ْ��������̔R�Ċ����Ȃ��Ȃ�A���ꂱ�����{�b�g�̎Љ�ɂȂ��Ă��܂��B ���c����́A��������"�l���̂��ӌ���"�ł������B�����������B�������A���������āA���ꂪ���������ς����҂���A���������ς��A���ɎE���ꂽ�B�@ �@ |
|
| ���k�𑁉_ | |
|
���D�ꂽ���o�c
��������Ăꂽ�Z�p�҂⏤�l�ɂ́A�R�C�̒����A�ՁA��A���A��A���H�A�����i�Ȃǂ̕����I�|�p�i��悤�ȏ��l���W�߂�ꂽ�B �Z�p�҂Ƃ��ďW�߂�ꂽ�̂́A�b��A�����t�A��H�A�����A�����A�\��t�A�勘���A��H�t�A�����t�A�D���t�A�������A���t�A�}�؎t(�����◓��������Z�p��)�A���̕����t�A���X�t�A��t�A�H�Ȃǂł������B �������낢�̂́A�����̎}�p�҂𑩂˂�̂͂��ׂ�"�E�т̎�"�ł��������Ƃł���B �����̘A���́A"����"�A"���g"�A"�����"�A"�f�j"�ȂǂƌĂꂽ�B�܂Ƃ߂āA�u�����ҁv�Ƃ����Ă����B�k�𑁉_�́A�������ɐ퍑����̕����ł����������ɁA�����̏p�ɒ����Ă����B�����̍��{�͉��Ƃ����Ă��A�u�����W�߂邱�Ɓv�ł���B�t�ɁA�u�K�Z�l�^�𗬂����Ɓv�Ƃ������Ƃ��B�K�Z�l�^�𗬂��ēG������������B���邢�́A�j�Z�̏���M�������ė���҂����肾���B�����̂��Ƃ́A�퍑�喼�̒N�����s���Ă����B���̈Ӗ��ł́A�u�����ɗ��z�������肽���v�Ǝu�����_�ɂ��Ă������������B����A���z����퍑����ɂ��낤�ȂǂƂ������Ƃ͓���s�\�Ȃ��Ƃ���������A�悯���A�u�����v���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B���̓_�A�k�𑁉_�́A�u�E�҂̊��p�ҁv�Ƃ��Ă����ꗬ�l�ł������B ���_�͂���ɁA�u�y�n�̐l�X�̐S�̌��菊�v�Ƃ��Ă̐M�̑Ώۂł���_�Е��t�ɑ��Ă͎�����ی���������B��ꂽ���Ђ͏C�����A���ꂼ��K�v�o��̖ʓ|���݂��B���ꂪ�܂����_�̕]�������߂��B ���������s�s�o�c�̒��ŁA���_�����ɗ͂���ꂽ�̂��A�u��Ƃ̕ی�v�ł���B ��Ƃ̒m���͑O�ɏ������悤�ɁA���_�͕��Q���ォ��g�ɂ��Ă����B ���������āA�u�a�C�ɂȂ����l�ɂ܂��K�v�Ȃ͖̂v�ƍl���Ă����B �u��Ƃ����X�X�̊j�ɂ��悤�v�Ȃǂƍl����퍑�����͑��_�̑��ɂ��܂肢�Ȃ��B ���̖ړI��B�����邽�߂ɁA���_�͋��s����F�쓡�E�q��莡�Ƃ����l�����������B�i����(��܁Z�l)�N�̂��Ƃł���B �F�쓡�E�q��莡�Ƃ����l���́A���{���𖼏���Ă͂��邪�A���͒���������{�ɋA�������n���l�ł���B�F�쓡�E�q��́A���Ƃ̖�����S�Ƃ������B���̐l�ł���B���ł͏d�����ɂ��āA�畔���O�Y�Ƃ����|�X�g�ɂ������B���A�������ɖłڂ��ꂽ���ɖS�����A���{�̒}�O�����ɂ��ǂ�����B���̎��ɁA�u�O�Y�v�ƁA�����̐E�������̂܂ܖ��ɕς��A�������{�ɋA�������B ���̒O�Y�̑��q���A�����`���̖����Ė��ɂ킽�����B�����`���͎O��̏��R���������A���Ƃ̖f�Ղɗ͂𒍂��ł����B���̎��O�Y�̎q�����������ʂ̊�����������Ă������A���̖��s�䏊�̌��Ƃ����̕]���ɂȂ����B���̒��ɂ���āA���̏L�C��h���ȂǂɎg��ꂽ���߂ɁA�u�������v�Ƃ������������B��������ʓI�ɂ́A�u�O�Y�̖�v�ƌĂꂽ�B�������͒P�ɍ����Ƃ��Ďg��ꂽ�����ł͂Ȃ��A���A�P�A�ݒ��A���ŁA�敨�����A�߂܂��A�S�����̑��̋}�a�̓�����Ƃ��Ă��L���ɂȂ����B �O�Y�́A�₪�āA������㏫�R�`������A�u�F�쌹���̖����p���ł悢�v�Ƃ�������������āA�F��Ɛ������߂��B�����ď��オ�F�쓡�E�q��莡�ł���B ���������A�O�Y�Ƃ͍���t�̊֓�����(�֓��̎x�z�ӔC��)�������B���������āA�����̏��ɖ��邢�B�܂��e�n�̍���t���x�z���Ă��邩��A���̃l�b�g���[�N�͌v��m��Ȃ������B���_�͂����ɖڂ������B �����ɁA�u�F��Ƃ��ɂ���A���s����Ƃ��Ȃ��肪�ł���v�ƍl�����B�܂�A��Γ̖��肾�����B ���̍��k�𑁉_�̖��͋��s�ɂ��苿���Ă����B �u���ɂ₳�����������s���A���l���ɕی삵�Ă���v�Ƃ����]�������������B�u���̒��S�ɂȂ��Ă������������v�Ƃ������_�̒��d�ȗU���́A�F�쓡�E�q���������B�F�쓡�E�q��͏��c���ɂ���Ă����B���_�͍L��ȕ~�n�Ɖ��~��^�����B�����āA�u���S�̂̉^�c�ɂ��J�𑁂����Ă������������v�Ɨ��B�@ |
|
|
�����x�̍������_
�k�𑁉_�́A������̕��������̂�����u�K�o�i�r���e�B(�����J)�v��A�u���[�_�[�V�b�v�v�ɂȂ����̂������Ă����B �u�l�ԓI���́v�ł���B�܂肩��̏ꍇ�́A�u���_�l�̂��߂Ȃ�A�������Ŏd�������悤�v�u���_�l�̂��߂Ȃ�A�����Ő펀���Ă������͂Ȃ��v�Ƃ����A�u���_�l�̂��߂Ȃ�v�Ƃ���"�Ȃ�"���������B���������悤�ɁA���l��"�Ȃ�"�Ǝv�킹�鎑�����A�����ł́u���x�v�ƌĂ�ł���B�x�Ƃ������t�����Ă��邩�炱��͈��̖ڐ��肾�B���x�Ƃ����x�Ƃ������̂Ɠ����Ӗ��ł���B �u���o�������v�Ƃ����A�u���̐l�̂��߂Ȃ�v�Ǝv���l�Ԃ���������Ƃ������Ƃ��B�u���x���Ⴂ�v�Ƃ����A�u���̐l�̂������ƂȂ�A��ɐM�p���Ȃ��v�Ƌt�Ȕ������������Ƃł���B ���̂悤�Ȑ��̒��ł́A���낢��Ɨ����������Ȃ��Ă���̂ŁA�l�Ԃ̋C�������ؖڂ����Ė��C���Ȃ��B�������l�Ԃ͉��Ƃ����Ă����̑��݂��B�u�l���ӋC�Ɋ����v�Ƃ��A�u�ȐS�`�S�v�Ȃǂ̋C��������B �u���E����̌ċz�v���������Ă���B�u���v�Ƃ����͓̂f�����ł���A�u����v�Ƃ����̂͋z�������B�܂�A�u�ċz���s�b�^�������v�Ƃ����l�ԊW�ł���B�@ |
|
|
�����ւ̗D��������
�������A���_�����������n��͕K���������_�̏o���肵�Č}���Ȃ������B�ނ��닰��Ă����B����́A�u�ɐ��V��Y(�k�𑁉_)�Ƃ����j�͍��d�Ƃ��B����������ė��āA���̊Ԃɂ�����Ƃɓ��荞�݁A����̐M�C������������v�Ƃ����\������Ă�������ł���B���̐l�X�́A�u����Ȗ����ȍ�����j�ł́A�������邩���Ȃ��v�Ƙb�������āA�R�̒��ɓ�������ł��܂����B���̊��Ɏc����Ă����̂́A�a�V�l����ł������B���_�͊S�Q�����B�������A����̐S�̒�ɂ͂����T�̐��_������B�����̋C����������B�������C���������畱�����������B����͑��̒������܂Ȃ��_��������ɁA�������W�߂āA�����������B �u��l�̕a�l���A�O�l�̕��������Ŋŕa����v�������Ă��ꎩ�g�́A�R�̒��ɓ������B���ė����������������B �u�����Ȃ����Ă�����̂ł����v�u��T���Ă���v�O��������̂���ɂ́A�������Q�������������B���̕��Q�̗��ŁA����͎R���ɖ����������Ă��邱�Ƃ�m�����B���ł����A�u������̍��Y���v�ł���B���̒m���ƋZ�p�������Ă����B���܂Ȃ����̒���������āA�V�l�����̕a���f������́A�u���̘V�l�̕a�C�ɂ͂������������B�����āA���̘V�l�ɂ͂��������������낤�v�Ƒ����ɓ��̒��Ŕ��f�����̂ł���B�̌��{������ƁA����͕����ɖ����āA���̑�ʍ̏W�𖽂����B�����Ďς��花�����蕲���������肵�āA���������B�����V�a�l�����ɗ^�����B���ʂĂ��߂�ŁA�a�l�����͎��X�Ǝ������B���������V�l�����͘b���������B �u���_�l�͌����Ĉ������ł͂Ȃ��B�ނ���A���̂悤�ȉ������C���������������B�R�ɍs���āA���̂��Ƃ�b�����v�����ʼn��������V�l�����͎R���ɍs���A�ޔ����Ă����l�X�ɂ��̂��Ƃ�b�����B�͂��߂͋^���Ă������l���A�₪�Ă͐M���ė��ɉ���Ă����B���̓����ɑ傫�ȍ��D�������Ă����B �ꂽ�Ƃ��Ƃł��A����ɒ��ɓ����Ē��x�i�Ɏ�������Ă͂Ȃ�Ȃ� ��܂��āA���x�i���O�Ɏ����o������A���蕥���ċ��Ɋ�����悤�Ȃ��Ƃ����Ă͂Ȃ�Ȃ� �ꑁ�_�̕������A���l���A���̕t���珟��ɒE�o���Ă͂Ȃ�Ȃ� ����ȓ��e�������B���_�͖߂��Ă������l�̒�����A���Ă̑���l��I�яo���A�u���܂łƓ����悤�Ɏd�������Ăق����v�Ɨ��B����I�Ȃ̂́A���ꂪ�N�v�̗����A�u�l�Z�p�[�Z���g�Ƃ���v�Ɛ錾�������Ƃ��B�����́A�u�܌��ܖ��v�Ƃ����āA�܁Z�p�[�Z���g���펯�������B����������Ȃ��Z�p�[�Z���g�����������B���ꂪ���l��������B �u���_�l�͐����������v�ƁA�݂�ȑ��_�̎x�z����B ���_�́A�������Ē��X�Ɨ̓y���L���Ă������B���ɑ��Ă͗D�����������A���͎҂ɑ��Ă͌������B�܂����ґ�ȕ�炵�����A�����ꂵ�߂Ă��錠�͎҂ɑ��ẮA����͗e�͂Ȃ����d����g���āA�����łڂ����B�@ |
|
|
���ї����A / �O�{�̖�A�{�Ƃ�⍲����悤�ɗ��� (-1571)
�ӂ��`����ꂫ���u�O�{�̖�v�̘b�́A���ɖʂ������A���A�O�l�̑��q���Ă�ŋ��P��^�������ƂɂȂ��Ă���B�ŏ��A���A�͈�{�̖��܂����B�����āA�u�����{���Ƃ����܂��v�Ƃ����āA���ɎO�{�܂Ƃ߂Đ܂낤�Ƃ����B�Ƃ��낪�܂�Ȃ��B���A�́u��O�{�W�܂�A�e�Ղɂ͐܂�Ȃ��B���܂��������Z��O�l���S�����킹�Ă��̖�̂悤�ɋ��͂��Ăق����v�Ɠ`�����Ƃ����B �����A�O�ɂ��������悤�ɁA���j�̗����͋}�����Ă��Ă��̐Ȃɂ͂��Ȃ��B�����Ɏ��j�̌��t���������풆�ŁA���̎��ɂ͑����Ȃ������Ƃ����B�����Ȃ�ƁA���A�̎����݂Ƃ����̂́A�O�j�̗��i�������B����ł͂��̘b���̂��������Ȃ��̂����A�^���͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��Ƃ����B ���j�̗����Ɏ��Ȃꂽ���A�́A�������̐Ղ𗲌��̎q�A���Ȃ킿�����̑��ɓ�����P���Ɍp�������B�������A�P���͂܂��q�ǂ��Ȃ̂ł��ڂ��Ȃ��B���A�́A�P���̌㌩�l�ɂȂ������A���ꂾ���ł͂����S�ł��Ȃ��B����́A���A���g���V��Ȃ̂ŁA�������K��邩������Ȃ�����ł���B �����ŁA������A���A�͋P���̑O�ɋg�쌳�t�Ə����엲�i���W�߂��B�����ĎO�{�̖�ɂȂ��炦�āA���t�Ɨ��i�ɁA���̋P����⍲����悤�ɗ��B���ꂪ�A�O�{�̖�̎��b���Ƃ����B �����炭�����ł������ɈႢ�Ȃ��B���������A���A��l�̎q�ǂ�����яW�߂���ẮA�����Ɛ[���ȗ��R���������B����́A�{�Ƃ��z���āA�g��ƂƏ�����Ƃ��������ɂ߂͂��߂Ă�������ł���B �Ƃ��ɁA������Ƃ̐L���������܂��������A�����엲�i�́A�q�ǂ��̂��땃�̌��A�����������悤�ɁA�����s���d���̎g����ł��������B���̂��ߌ��A�́A���i�ɖї��Ƃ̏O�S���𖽂��Ă����B���i�͂��̕��ʂł������ȍˋC���������B ���R�͏�ɑł��ďo��B���̂��ߗ��i�̍s�����A����ɑ�����������x���������B�܂��A�ގ��M���d�����������낭�Ă��������Ȃ��B�ނ̐��͕���͂ǂ�ǂ�L�����Ă������B��������Ă����A�͐S�z���ĂɈႢ�Ȃ��B���܂ł����A�{�Ђ𗽂��Ŏx�Ђ��ǂ�ǂ͂�L���Ă��������ƂɂȂ邩�炾�B�@ |
|
| �����c�M�� | |
|
�������Ȓ����A�傫�Ȍ���
���c�M���́A����ɑ��̐퍑�����Ƃ͈���ĉ���I�Ȃ��Ƃ��s�����B����́A����͍b�{�ɑ傫�ȏ�����Ȃ��������Ƃ��B����̋��ڂ̐Ղ́A���ݕ��c�_�ЂɂȂ��čb�{�s�ɂ���B�b�{��Ƃ����̂��c���Ă��邪�A����͍]�ˎ���ɍ��ꂽ���̂ŁA�M������������̂ł͂Ȃ��B �܂�M���͎����̕����ɑ��āA�u�l�͏�l�͐Ί_�l�͖x�v�Ƃ��������ȏ�A�����̋��قƂȂ�傫�ȏ�͌����č��Ȃ������B�܂�A�������S����ł���A�Ί_�ł���A�x�ł���A����Ȃ��͕̂K�v�Ȃ��Ƃ����l�����B ����������͒P�ɂ������������ōςނ��̂ł͂Ȃ��B�M���̍s�������Ƃ́A���݂ł����A�u�����Ȗ{�ЁA�傫�Ȍ���v�Ƃ������Ƃ��B���t��������A�u�g�D�̊Ǘ������@�\�͋ɗ̓R���p�N�g�ɂ��ď������s��`�ł����B�����ŗ]�点���q�g�E�J�l�E���m�́A����ɂ܂킷�v�Ƃ������Ƃ��B �q�g�Ƃ����̂͐l�ނ��B�J�l�Ƃ����̂͗\�Z���B���m�Ƃ����͎̂��ނł���B �M���́A�u���Ƃ����Ă����ۂɎd��������̂͌��ꂾ�B�����ŕK�v�Ƃ���l�Ԃ�\�Z���ނ��A�{�Ђ̕����S���D������Č����������悤�Ȃ��Ƃ�������A�t�O�p�`�ɂȂ��Ă��܂��B�g�D�Ƃ����̂̓s���~�b�h�^�̈��肵���O�p�`��ۂׂ����v�ƍl���Ă����B ���̂Ƃ���ŁA�g�D�Ƃ����̂̓r���~�b�h�^�ɍ\�������B�����Ďd���ɉ����ĎO�̑w�ɕ������B�g�b�v�E�~�h���E���E�ł���B��]���E���ԊǗ��E�E��ʂ̓�����Ƃ������Ƃ��B�����炢���A���R���ɂ����ɂ��������đ����Ă���B�Ƃ��낪�S�̂ɁA�Ǘ������@�\���剻�����A�����̂܂��ɂ�������l���W�߂ăE�n�E�n���ł���g�b�v�������B �M���͂�������߂��B���݂ł����Ί��E�l���E�����E�L��Ȃǂ̃Z�N�V�����́A�ɗ͐l�����炵���剻�����Ȃ��Ƃ������j���Ƃ����B���̍l���𑍍��I�ɂ���킵���̂����Ȃ킿�A�u�l�͏�l�͐Ί_�l�͖x�v�Ȃ̂ł���B�@ |
|
|
�������ɂ݂���헪
�������A�M���̌o�c�̍˂��������̂Ƃ��ẮA�u�b�B�@�x�V����v���́A�M�҂��u�M�������v�ƌĂ�ł�����̂̂ق����D��Ă���悤�Ɏv���B���̃����́A��������b��̍��ɂ���Ă������l�̏����L�������̂ł��邪�A�M�������̕����ƈقȂ�̂́A��̏��ӐM���邱�ƂȂ��A����ɃN���X�`�F�b�N���Ă���_���B ���Ƃ��A����������������l�ɍ�����A�����������ƁA����ɕʂ̗����l���畷���ď���������B���̏�ŕ��͂����A����f����̂ł���B �M���́A���̂悤�ȏڍׂȏ����W�����Ă�������e�n�̏��ɂ͂��Ȃ萸�ʂ��Ă����B���̂����A�Ɛb�����Ƃɕ�������A��������e�n�ɍs���l�Ɏd���ĂĔh�����A������������܂ł�������O�������߂��Ƃ����Ă悢�B�������A���̍s����ʂ��čb��═�c�Ƃɂ��Ă̋U�ԏ��𗬂��ēG���̐헪�����������鍂����p�܂ŗp���Ă���B��͂�A���ɂ��Ă͕��X�Ȃ�ʊ��o�ƍ˔\�������Ă����D�c�M���������A�M���̃j�Z���ɂ͂ӂ�܂킳�ꂽ�Ƃ����B ���������Ƃ��ẮA�m���̍ȑт����������ɁA�ȑт����m�ɂ͐V���Ȑł��ۂ�����A�x�m�o�R�҂ɓ��R�����ۂ��ȂǁA���j�[�N�Ȕ��z�����Ă���B����ɁA�䒺�g��Ɗ�����ɑ�K�͂Ȏ����H�������{�����M����X��z���A���Q�h�~�����łȂ��V�c�J���������߂���A�b�B���̋��R�J���������߂Ă�����B�@ |
|
|
���l�̘b�̕������ŁA4�ʂ�̔������瑊���
�u����̘b�����鎞�ɁA�Ⴆ�Ύl�l�̎�҂������Ă����Ƃ���B�����������ꂼ��Ⴄ�B��l�́A�����������܂ܘb����ł���킽�����W�c�Ƃ݂߂Ă���B��Ԗڂ́A�킽���Ɗ�����킹�邱�ƂȂ��A��₤�ނ��Ď������𗧂ĂĂ���B�O�Ԗڂ́A�b����ł���킽���̊���݂Ȃ�A���X���Ȃ�������j�b�R�������肷��B�l�Ԗڂ́A�b�̓r���ŐȂ𗧂��ǂ����ɂ����Ă��܂��v�M���͂����̕������ɂ���Ď��̂悤�ɕ��͂���B �������|�J���Ƃ����Ă킽���̊���݂Ă���҂́A�b�̓��e���܂������������Ă��Ȃ��B���ӎU���ŁA���������l�Ԃ͈�l�����ł��Ȃ��B �����ނ��ăW�c�Ǝ��𗧂ĂĂ���҂́A���������킹�邱�ƂȂ��b�����ɏW�����悤�Ɠw�͂��Ă���؋����B���ܕ��c�Ƃł킽���̕⍲���Ƃ��Ċ��Ă���A���̂قƂ�ǂ��A�Ⴂ���ɂ��������b�̕��������������̂��B ���b����̊���݂āA���X���Ȃ�������j�R�j�R�����肷��̂́A�u���Ȃ��̘b�͂悭������܂��v���邢�́u���������Ƃ���ł��v�Ƃ������͂�ł��Ă���̂��B�������A����͘b�̓��e���~�߂�����A���̎Ќ𐫂��֎�������ɃJ��������Ă���B�]���āA�b�̖{�������S�ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B ���b�̓r���ŐȂ𗧂��Ă��܂��̂́A���a�҂��A���邢�͎����Ɏv��������Ƃ��낪�����Ă������O�T���Ƃ����ꂽ�̂ŁA�������܂�Ȃ��Ȃ����؋����B �t���C�g�畉���̉s���l�ԓ��@�͂ł���B�M���͂������A�u������Ƃ����āA���a�҂⒍�ӗ͂��U���Ȏ҂����̂܂܌��̂ĂĂ͂����Ȃ��B���ꂼ�ꌇ�_�������Ă��t�ɒ���������B�������������ĕʂȖʂɐU�������A�͂����B�����͂��߂��Ƃ����悤�Ȍ��߂�������Ԃ����Ȃ��v�Ƃ����Ă���B���́A�u�ǂ�Ȑl�Ԃɂ��K���ЂƂ͒���������v�Ƃ����ԓx���A����������ɑ��āA�u���̑叫�̂��߂Ȃ�A�쒆���Ő펀���Ă������v�Ǝv�������S�̂ɈႢ�Ȃ��B �b�̕������Ɏl�ʂ�̔�����������҂����̎g�����ɂ��āA�M���͎��̂悤�ɂ����B ���l�̘b������̋�ŕ����Ă���҂́A���̂܂ܕ����Ă����������������ĂȂ����A�܂��ӌ�������҂��o�Ȃ��B�ꏊ�������`��s�����Ă�����ɉ����Ă���Ȃ����A�܂��ӌ������Ă��g�ɂ��݂Ă����Ȃ����炾�B�]���Ă��������l�Ԃɑ��ẮA�ʂ�Ƃ��Ē�������悤�Ȏ҂�e�ɂ��邱�Ƃ��K�v���B��������A�{�l�������̌��_�ɋC�Â��A������߁A��p�̕��m�Ɉ�͂����B ����ԓ��̂��ނ��Đl�̘b��g�ɂ��݂ĕ����҂́A���̂܂ܕ����Ă����Ă����h�ȕ��m�Ɉ�B���������l�Ԃ̑��݂��A��ԓ��̐l�̘b��g�ɂ��݂ĕ����Ȃ��҂ɋ����Ă�邱�Ƃ��厖���낤�B ���O�ԓ��́A���Ȃ��̘b�͂悭������܂��A���������Ƃ���ł��Ƃ��������������҂́A�����O���̎d���Ɍ����Ă���B�����̔C����^����A�K����������ɈႢ�Ȃ��B�����A�������Ȃ̂Ŏd���ɐ�������Ƃ��������C�ɂȂ錇�_������B�����Ȃ�ƁA���Ѝ����Ȃ��Đl�ɑ��܂��\��������̂ł��̂ւ�͒��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���l�ԓ��̐Ȃ𗧂҂́A���a���A���邢�͐S�ɂ�܂����Ƃ��낪������̂�����A��Ă�҂͂��̐l�Ԃ��f���ɂ��̌��_�����獐�����āA�C���y�ɂȂ�悤�ɂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������邱�Ƃɂ���āA���̐l�Ԃ��������C�ɂ��Ă��邱�Ƃ@���A���߂ĕ������ɈႢ�Ȃ��B���������҂ɑ��ẮA�ӂ߂�����ނ��뉷�������ł�邱�Ƃ��K�v���B ���������悤�ɁA�u�ǂ�Ȑl�Ԃɂ��K������������v�Ƃ���M���́A�V�����l�Ԃ����������鎞�ɂ��A�u�S�_���_�̊��S�Ȑl�Ԃ��̗p����ȁB�l�Ԃ͏������_�����������������v�Ɩ������B�܂��A�u���m�ŁA�S�l����\��l�ɖJ�߂���悤�Ȑl�Ԃ͂낭�Ȃ�ł͂Ȃ��B����͌y���Ȏ҂��A�������Ȏ҂��A���邢�͕������҂ł���v�Ƃ������Ă���B�@ |
|
|
�������̃��[�_�[�V�b�v
�����ڂ̂Ƃ�ׂ����������ꂽ���� �Ƃ��ɁA�����ɑ��邢�낢��Ȑ���A���q�̐M���𑊑��l�Ƃ��A�����͂��̌㌩�l�ł���ׂ����ƁA���邢�́A�R���̎g�p���ɂ��Ăׂ̍������ӁA����Ɉ�̂̎n���A���V�̂����A�܂��A�u�O�N�ԁA�����̎��͑��ɍ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����Ȃ���A�u�z��̏㐙���M�Ƃ́A�}篘a���ނ��ׁv�Ƃ����A�閧�R�k�����܂Ƃ��悤�Ȑ헪�܂ō������B (�����ƐT�d�ł����ė~��������)�����͂��Â������v���B �������A�M���̒����⌾�ɂ���āA�����̗���͌���I�ɂȂ��B���ꂪ�݂Ă��A�u�����l�́A�M����������҂���Ă��Ȃ����ځv�Ƃ������b�e����S���Ă��܂����B �������ɕ��c�M���͖����Ƃ����鑶�݂������B���̍s���́A�����̂Ȃ��Ȃ��y�ԂƂ���ł͂Ȃ��B�Ƃ��ɁA�u���̎��W�J�ƕ��͗́v�u���f�ƍs���́v�u�����𖣂�����l�]�v�Ȃǂ́A�������ɂ͋t�������Ă��ǂ����Ȃ����Ƃ��B (������)�Ə����́A�����Ȃ�ɍl����B (�l�Ԃ́A����Ȃӂ��ɖ������ЂƂ��߂ɂ��āA���̐��ɋ���Ă����̂��낤��)�����́A�Ղ��p���҂Ɏc���Ă����ׂ��ł͂Ȃ��̂��B���ꂪ�A���̈���Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂��B �����̋��̒��ɂ́A���������������X�ƗN�������Ă����B ���c�M���̈⌾���A���㕗�ɂ����A�u���ڂ̂Ƃ�ׂ����v���A�͂�����Ǝ������Ƃ������ƂɂȂ�B ���܂ł����������A��オ�����ꂽ�n�Ǝ҂ł������ꍇ�ɂ́A���ڂ̖�ڂ́A�u�琬�v�ł���Ƃ�����B �琬�Ƃ����̂͂��̕����ʂ�A�u���A���点��v�Ƃ������Ƃ��B���Ƃ����̂́A�u�����ꂽ��オ�c���Ă������n�ƓI���Ƃ���������Ǝ�蔲���v�Ƃ������Ƃł���B ���M���͖�����������J�����������͔p�~ �M���͖�����������J�����B�o�Ȏ҂͂�����A�u���c��\�l���v�ƌĂꂽ�ʁX���B���̐ȂɎ��g�̓����������ׂĂ��炯�o���A�u���c��Ƃ́A��������ǂ̂悤�ɐ�����ׂ����v�Ɠ��_������B���̓��_�ɂ���Đ��܂ꂽ���̂��A����́A�u�헪�v�Ɩ��Â����B�헪�����ӂ����Ƃ����������B �u���̐헪�����ꂼ�ꎩ���̐E��Ɏ����ċA��B�����Đ헪���ǂ����s���邩�Ƃ�����p�����߂�B��p���m�肷�鎞�ɂ́A��ʂ̕����ɂ��Q��������v�ƍ������B�܂�A�u�����X�P���g���v�͊�����c�Ō��肷�邪�A�u�ׂ������s���@�͌���Ō��߂�����v�Ƃ������Ƃł���B����͌��ݍl���Ă����Ȃ薯��I�ȕ��@���B �����ĐM���́A�[���ɂȂ�Ƃ�����x�~�[�e�B���O���J�����B �u�������߂��헪���A���ꂼ��̐E��͂ǂ�������p�Ŏ��s����������v�Ƃ������B���ɂ͎��s�����E�������B�������M���͙�߂Ȃ��B���R�́A�u�헪�͏��ɂ���đg�ݗ��Ă��B��Ń`�F�b�N����Ə��ɊԈ���Ă��镔�����������B���������Ă��̐헪�͊Ԉ�������ɂ���đg�ݗ��Ă�ꂽ�̂ł��̐E��̒����̂��̂ɐӔC�͂Ȃ��B�����������͓�x�Ƃ���Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�Ɂv�T�d�ɂ������B���̂��߂ɁA�����̌��ʂ������̂��B���������ďW�܂����A�����A���s�����E��̒�������������A�����C�����A�ȂǂƂ����Ă͂����Ȃ��B���������������߂����������Ȃ��悤�ɂ��悤�Ƃ��������̔O�����ׂ����v�ƍ������B ����͌��݂̎d�g�݂ł����A�E���̋��L�Ǝw�����߂̓O��A�Ƃ����u�g�b�v�_�E���v�E������̈ӌ����p�ɐ��������Ƃ���u�{�g���A�b�v�v�Ƃ����A��{�̃R�~���j�P�[�V�����̃p�C�v��p�ӂ��Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B�����āA���̃t�B�[�h�o�b�N���������c��Ƃ̊�Ɖ^�c������������ƐM���͍l���Ă����B (�������A�퍑����̕����ł��镐�c�M���ɁA����قǂ̌���ӎ��͂Ȃ������ʂƂ��Ă͂����Ȃ�)�����āA�����������̊�����c�ɂ����A���ڂ̏����ɑ��A�u�傢�Ȃ���J���v �������͐V��̒z��Ə鉺���̒n���܂ʼn��� �u�悵�A�B��ɐV����������낤�B�ł��邾�����łȂ��̂����肽���B�����ĐV��̏��ݒn��V�{�Ɩ��t���悤�v�ƁA�V��̒z��𖽂����ق��A�鉺���̒n���܂ʼn��������B �b�{�Ƃ����̂́A�u�b�㍑�̕{���v�Ƃ����Ӗ��ł���B����͓��{�̌Ñ㍑�Ƃ�����o�������x�ŁA���{�̍��͐퍑������Z�\�Z�̍��Ɠ�̓��ɕ�����A���v�Z�\�������������B���ꂼ��̍����A�����̌Ñ㍑�Ƃ̖��߂ŁA�u���ɂ�����������v�Ɩ�����ꂽ�B�b������̂ЂƂł���B �Z�\���J���ɂ͂��ꂼ��u���{�v���u���ꂽ�B���̍��{�̏��ݒn��{���Ƃ������B���������čb�{�Ƃ����̂́A�u�b�㍑�̕{���v�Ƃ����Ӗ����B������������A�u�V�{�v�Ɩ��t����̂ɂ́A�u�b�㍑�̍��{�͔B��ɒu���B����ĔB���V�{�Ɩ��t����v�Ƃ������Ƃł���B�����ԍb�{�ɋ��_��u���Ă������c�Ƃ́A�����̑�ɂȂ��ĔB��ɖ{�����ڂ��Ƃ����錾�ł���B �������͍b�㍑�̒����W������ڎw���� ���ꂪ�A�Ƃ�����Ύ����̗��v�ɑ����ē������������ɂ������Ȓn����y�������𑩂˂Ă����傫�ȃJ�ɂȂ��Ă����B�M���͎��������������n��̐l�Ԃ����������āA�u�I�[�_�[���[�h���v�͂��Ȃ������B���ꂼ�ꂪ�ۂ��Ă����A�u���f�B�[���[�h�v�����̂܂ܔF�߂��̂ł���B���ꂪ�q���̂���ΎЋƂɑ���Q���ӗ~��~�����Ă��B�܃��A�u�q���̎��含�E�������̑��d�v�������Ȃ�ꂽ���߂ɁA���������A�����A�u�d���ɑ���[���������A��т������Ďd�����ł����v�Ƃ���"���������̔F��"�ɂȂ����Ă����B ���c�����͂�����A�u���̍ۑS�����~����v�Ɛ錾�����B �����ɂ���A�u����ɂ͕��e�قǂ̊�ʂ͂Ȃ��v�Ƃ������Ȕ\�͂ɑ���F��������������A�u����͂��ꗬ�̊Ǘ����@�ł����v�ƍl�����B ���ʘ_�ɂȂ邪�A���c�����̂��̂ւ�̂����́A�ǂ����D�c�M���I�Ȃ��̂ɕς���Ă����B�Ƃ������Ƃ́A�؋��͂Ȃ������c�����̓��̒��ɂ́A�D�c�M���̍s�����ЂƂ̋K�͂Ƃ��Ă������̂ł͂Ȃ��낤���B����͂��̕���������i�߂Ă��������ɂ����������炩�ɂ������ł���B����肾�����`�����Ə����A���c�����ɂ́A�u�̍��o�c�̋ߑ㉻�v�ƁA�u�b�㍑���ɂ����钆���W�����v�Ƃ�����]�Ƃ������u���������悤�ȋC������B�B��ɐV�{����������̂͂��̕\�ꂾ�B �������͐D�c�M�����l�ɒn���������̒��b�Ƃ��� �D�c�M���͈�����B���ׂāA�u�����̒��b�v�ɂ��Ă����B����œV���������܂킵�Ă���B ���c�������Ђ����ɁA����Ɠ��l�̂��Ƃ��l���Ă����Ƃ�����B���ꂪ����̍b�㍑�ɂ����钆���W�����̖�]�ł���B�����́A�u�������Ȃ�����̍��͂܂Ƃ܂�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����̂ق���������n����y���̎��含���d�Ė���I�ɂ��Ƃ��^�ڂ��Ƃ��Ă��A�D�c�M���⓿��ƍN�������F�߂Ȃ����낤�B�k������Ȃ��v�Ƃ����l�͂ɑ���F��������������ł���B �������͓������邽�߂ɂ�ؕ|�S�����͎������悤�Ƃ��� �����������т����������������ɋ��|�S��^���A�u�M���l�͋��낵�������v�Ǝv���悤�ɂȂ����B���������ĕ��c�����݂̂�Ƃ���A�u�D�c�R�c�̓����͑叫�̐M���ɑ��镔���̋��|�S�ɂ���ĕۂ���Ă���v�Ǝv�����B�����́A�u�����͂����܂ł͂��Ȃ��B�����������ɑ���ؕ|�S�����͎������悤�v�ƍl�����B �����Ȃ�ƕ��̐M�������s���A�����̊Ԃŕ]���̂悩�����A�u�w�ƒ���̋��������������Ă���d����ɏo�Ă���x�Ƃ������݂ł���"�t���b�N�X�^�C��"�Ƃ����̂́A��������ɕ��m�̋C���������܂��邾�����B�����p�~���悤�v�����͂����v���������B ���Ƃ��ƕ��̐M���������Ă��������珟���͂��̃t���b�N�X�^�C����ᔻ���Ă����B����̍l���ł́A�u����Ȃ��Ƃ��葱���Ă����A����ɂȂ܂��҂��肪�o�Ă���B�ƒ�ɉ����������Ă��Ȃ��̂ɁA��������������������܂��A�ƉR�����ďo���ł���߂ɂ��錴���ɂȂ�B�I���͂���Ȃ��Ƃ͔F�߂Ȃ��B���ׂČ��߂�ꂽ���Ԃɂ͕K���S�������낤�悤�ɂ�����v�ƍ����āA�t���b�N�X�^�C���̔p�~��錾�����B����͈�ʁA�����������̎Ⴓ�ɂ܂����A�����̎��Ƃ��}�����߂ɁA�u�I���̌��݂̍ő�̉[�͎̂��ԂƂ̐킢�ł���v�Ƃ����F���Ɋ�Â��Ă����Ƃ�����B���ԂƂ̐킢�Ƃ����̂́A���ꂪ�A�u�b�㍑���̒����W�����v���Ȃ킿�A�u����ł���I��(���c����)�Ɍ����̈���W��������v�Ƃ����l���ɔR���Ă������炾�B �������ĉƒ��̐�������ɂ��т����Ђ����߂������́A�V����N(����l)�A�O���̑�R�𗦂��Ĕ��Z�ɓ˓������B���M��������ł���܂���N�����Ă��Ȃ��B�V�b�����͔������B���A�f�łƂ��āA�u���Z�ɓ˓�����v�Ƃ����鏟���ɁA�V�b�����͂�����߂��B �����j�͌����Ȏw���Ԃ�����M�������Ƃ��Ȃ��������V�T��𗎂Ƃ��� �u�����������Ƃ͐�ɂ��Ă͂Ȃ�܂���v�Ƃ����Ēf�łƂ��Ĕ����ׂ��ł���B���������c�Ƃ̘V�b�����͕K�����������͂��Ȃ������B �u���ڂ����������Ă���̂������ނ����܂��v�Ƃ�����߂Ă��܂��̂ł���B���������V�b�����̑ԓx�����c�Ƃ��������ɂނ���ł����v���c�Ƃ������̎���ɖłт����Ƃ����ׂāA�u���ڂ��}�f���������炾�B���M���Ɏ����s�т̑��q���������炾�v�Ƃ����邪���������̐ӔC�ł͂Ȃ��B �������ӊO�Ȏ��ɕ��c���j�͌����Ȏw���Ԃ�������B���Z���ɓ˓��ȗ��A�����܂����q����͂��ߏ\���̏�𗎂Ƃ��Ă��܂����B�V�b�����͖ڂ��݂͂����B��������킹�A�u���ڂ͂�邼�v�u�ĊO���ȁv�Ƃ����Ȃ���A���X�Ƃ���������U�ߗ��Ƃ����B�����Ȃ�ƒe�݂����B ���������ƂɁA�V����N�܌��ɂ́A���܂܂ŕ��̐M������ɗ��Ƃ��Ȃ��������]�̍��V�T��𗎂Ƃ��Ă��܂������Ƃł���B����ɂ͕��c�R�c�����������ɐ��������ď������̂����B �u��叫�͂������I�v�u���M�����ł����s�\��������𗎂Ƃ����I�v�����@���Ăق߂��₵���B�����͂ق����B�S�̒��ŁA(�ǂ����H�I���̃J��)�ƂԂ₢���B�����āA(����Ȃ�M���ɕ����Ȃ��J��{���邩������Ȃ�)�Ǝv�����B����������͎v���オ��ł���B���M�����悭�����̌Â����@����ǂ�ł́A�u�G�ɏ����߂ɂ́A�G�̎��͂��ǂ̒��x�̂��̂ł��邩��m��A�����ɂ܂��������̎��͂����m�ɒm�邱�Ƃ��v�Ƃ������B���V�_��𗎂Ƃ��ē��ӂɂȂ��������́A���̕��̌��t�́A ���G�̎��͂�m�� �������̎��͂�m�� �Ƃ�����̎����ɂ����āA�u���ɐ��m�ȔF�����Ȃ������v�Ƃ����Ă����B�Ƃ������Ƃ́A�u�G�̃J���ߏ��j���A�����̃J���ߑ压�����v�Ƃ������Ƃł���B �����̑�s�k�A�D�c�R�̊v���I��p �D�c�E����A���R�̑��y���́A�A�q��ɂ������n�h��̊J���瓛��������Ă���B��͑O�ɏ������悤�ɍL���[���̂ŁA�ȒP�ɂ͓n��Ȃ��B�߂��܂ŏo�����c���̏�n���҂����́A�o�^�o�^�ƌ������Ƃ��ꂽ�B���ꂪ�y�n�̌����҂�������悤�ɁA�u���̒n���т͑傫�Ȏ��n�т������v�Ƃ������Ƃł���A������������O���炷�łɎ��n�т̒��ɔn�������ꂳ�����Ƃ������Ƃ��l������B��������������́A�D�c�̒��ł������Ȃ���A�u�₠�₠�v�ȂǂƂ�߂��Ă����̂�������Ȃ��B������_�������ɂ��ꂽ�B ���c�����͋������B�Ƃ����̂́A����Ȃ��Ƃ͂��܂܂Ōo���������Ƃ��Ȃ���������ł���B���A���������̖���肪���܂Ȃ�����ɂ����Ȃ�S�C������������͔̂ڋ����B �u�푈�̍�@���m��ʁv�����͓{�����B�������D�c�E����A���R�́A����Ȃ��Ƃ͂����܂��Ȃ����B �݂Ă���ƁA�����ɕ����y���́A�S�C����x���Ƃ��̂܂܃^�c�^�c�^�Ɛ��R�ƈ�Ԍ��ɉ������Ă����B�G�̑��o���͎O��ɕ���ł����B��ԑO�����B���ƈ�Ԍ��̗�ɉ�����B�Ȃɂ�����̂��Ƃ݂Ă���ƁA�����Œe���߂�����B�����̓S�C�͈ꔭ�����e�����ĂȂ����炾�B�e�����߂�ƑO�֏o�Ă���B���̎��͓��ڂ���ԍőO��ɏo�Ă���B�����Č��B�e���߂̏I������O��ڂ͓��ڂɈڂ�A���ڂ������I����Ĉ����グ��ƌ�ւ���B���̌�ւԂ肪���ɑN�₩���B�����͖ڂ��݂͂����B �u���������A����͂ǂ��������Ƃ��I�v�Ƌ��������łȂ��A�Ō�ɂ͕��ꂽ�B�����炭���c���������łȂ��A����Ȗڂɑ������瑼�̐퍑�������݂�Ȗڂ��݂͂��ɈႢ�Ȃ��B�D�c�M���́A�퍑�̍�����@����ς����B�v���I�ȕ��@���Ƃ����B ���܂܂ł́A�n�ɏ�������ԊǗ��E����v�퓬�͂ł������̂��A���̏ꍇ�͈�ʂ̕��m����͂ɂȂ��Ă���B���������ꂼ�ꂪ���⑄��U��܂킵�āA�l�ŏK���������p�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����S�C�����Ƃ����A���܂̌��t���g���`�[�����[�N�����Ő푈�����Ă���B�܂�M���R�c�͂��łɁA�u�d���͌l�ł����Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�g�D�ł����Ȃ����̂��v�Ƃ����l���������s���Ă����B �����́A��O�̌��i���݂āA(�A���R�́A������ȗ��K�������̂��낤���H)���`�����B�����͖��q�ȕ�������������A�D�c�E����R�c�̕ώ��������@�m�����B���̐퍑�����ɂ͂Ȃ��w���Ԃ肾�B (����͕�����)���������B���̂Ƃ��肾�����B�O�ʂɏo���R�n���҂̂قƂ�ǂ��A�S�C���ɂ���Ď��X�ƌ����|����Ă����B ���M���͍�����Ȃ������߂ɑ��푦���ŏ��Ă�R�c�������� �u�ق�Ƃ��ł����v�����͎v�킸�G�𗧂Ă��B�������삪�����̂́A�u�M���́A���̍����獇����Ȃ������߂ɁA����ɏ����@�����ݏo�����̂��v�Ƃ������Ƃł���B����Њ�͂��Ȃ������B�����ĐÂ��Ȋ�ŏ������݂߂��܂܁A�����������B �u���ꂪ�M���a���������Ă���̂ł��B�܂�A���̍����獇����Ȃ��������Ƃ����u�����邩�炱���A����͎����̂����Ȃ��펯�͂���ȍs�ׂ����ׂĎ��琥�F���Ă���̂ł��v���͑������B����Њ�̘b������Ɠ��̒��ɃX�g���Ɨ������B (�����������Ƃ����̂�)�����͋C�Â����B����Њ�̂����̂́A ���M���́A�Ⴂ������������ŏ鉺����ʂ�l�Ԃ����ɓ��G���A���ܐ����Ă���l�Ԃ��������������Ȃɂ����߂Ă���̂���T�����B �������������ʁA���̊肢�̍ő�̂��̂����̍����獇����Ȃ������Ƃ��ƋC�Â����B�܂�A���܂��̍��ɐ����Ă��閯�O�́A�������������̂Ȃ����ɂ��ė~�����Ɗ���Ă���̂��B �����̊肢����������ƂȂ�A���܂��̍��̑喼�����������ȂĂ���悤�ȍ�����@�𑱂��Ă����̂ł́A�S�N����S�N��������B�����Ǝ��Ԃ�Z�k����K�v������B �������ŁA�M���͍���̕��@��啝�ɕς��A���푦���ŏ��Ă�悤�ȌR�c������A�V������̗p�����B �����̑�K�͂Ȏ������A���Ȃ킿�݊y�P���̍���ł������B �����͓��̒��Ő����������Ƃ�����Њ�Ɍ�����B����Њ�͂��Ȃ������B �u�悭�����C�����ꂽ�B���̂Ƃ���ł��v�u�M���́A�u���������邽�߂ɁA���̂悤�ȏ펯�͂���Ȑ�@���Ƃ����Ƃ��������̂ł����H�v�u�����ł��B���܂̐��ɐ�����喼���ɂƂ��āA�u�����邩�Ȃ������傫�ȕ�����ڂɂȂ�܂��傤�v �����c�̔s�k�͉Ɛb�c�\���̌Â� ����������A���R�́A�{���̂��Ƃ��b�{�֍b�{�ւƐi�������B ���c�����́A���ɐV�{����̂Ă�B�����āA�s���̗̎�ł��鏬�R�c�M�ɏ�����A���̋���ł����a�R�Ɍ��������B �Ƃ��낪�A���R�c�M�͑O�����Ђ邪�����A�u�s���ɂ��Ȃ��������ꂷ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƌ��B �����͂�ނ��A������ς��V�ڎR���_���̂ӂ��Ɠc��(�R�������R���S��a��)�܂œ��ꂽ�B���A�O���\����D�c�R�̐�w�ł������v�̎w�����鐔��̌R������s���P�����B�Ō�܂ł�����̂ĂȂ��������b�����̖h����ނȂ����A���ɏ����͎��E�����B �V���O�Y�`���ȗ���"�b�㌹��"�̖���ł��������c���́A�������Ėłт��B���c�M��������ł���A�܂��\�N�o���Ă��Ȃ������ł���B �w�R�����̗��j�x�̒��ɂ��������ꕶ������B �u���c���͂ǂ����Ă���Ȃɂ��낭�łы������̂ł��낤���B�����̓����J�̌��@�A�Ɛb�c�ǂ����̓��ւ��߁A�����̏d�łƌR���ߏd�ɂ�閯�S�̗������X�A�����͂��낢��l�����邪�A���F�͉Ɛb�c�\���̌Â��ɋA�����悤�B�Ӌ��^���m�c�𑽂��������Ă������Ƃ͕��c�̌R�̎�_�ŁA�L��ȗ̓y�������͐��͔͈͂Ƃ����ɂ������A�����邭�Ȃ�A���ł��Q�Ԃ��ł����댯���������B���̓_�A���_�������Ȃ��Ƃ��A�Ɛb���鉺�ɏW�߂ď펞�P�����Ȃ������A�D�c�̌R�ɑ����ł�����̂͂ނ������������B�����ŗ�́w�l�͏�A�l�͐Ί_�]�X�x�̉̂ł��邪�A���͕��c�̌R���g�D������ȏ�s���\�z����K�v�����o����i�K�ɁA�܂������Ă��Ȃ������Ƃ���ɁA�ߌ��̂��Ƃ��������Ƃ������悤�v �Ƃ���B�d��Ȏw�E�ł���B����́A�V�����u���������傤�Ƃ�����ڏ����ɁA�V�������߂ƂȂ�������ފՍւ����߂����Ƃƈ�v����v ���ꂵ�����ɂ͔��Ȏd�ł������҂͕��镉�̈�Y���p���� �݂�Ȃ̊Ⴊ�O�������Ă���Ԃ͂悢�B�����A����ȗ]�T�������Ă���ƁA�ǂ����Ă��ߋ��̕s���Ȏd�ł��≅�O���A���̎��Ƃ���ɗ����Ԃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B �~�������҂�Ɛb�����ɓ������������Ƃ������Ƃ́A�ЂƂ��эs���l�܂��āA�Ȃɂ��������܂��s���Ȃ��Ȃ������ɂ��������Ă���B�ꂵ�����ɉ���������������ׂĂ��ꂽ�Ƃ����v�����A���̐l�ׂ̈Ȃ�Ƃ����C���������B �����A���ɍ����d�ł����̌�������Ȃ��������Ă����҂����́A���̎��Ƃ���ɍ��݂̖���������Ă���B��������Ă��炦�Ȃ������A�������ɂ��Ă���Ȃ������ƂȂ�A�S�͗e�Ղɗ���Ă��܂��B����ǂ��납�A�̑Ώۂɂ���Ȃ��Ă��܂��B���ڂɂ�����ڂł���B �����́A���������`���̐S��ǂݐ�Ȃ������B���M���̎d�ł������Ƃ����ł킩���Ă����ɂ��Ă��A�����̎�ł����Ȃ������ƂłȂ������ɏ����ɓǂ߂Ȃ������Ƃ��Ă������͂Ȃ��B �n�Ǝ҂Ƌ�y�����ɂ����҂̋C�����́A��p�҂ɂ͎����Ƃ��Ă킩��悤���Ȃ��B ���l�ɁA���O��s�����A������ė����߂��Ă��邱�Ƃ��A�Ղ��p�����҂ɂ͗����ł��Ȃ��B�����A���������S�̒�ɖ����Ă����v����ǂݐ邱�Ƃ����A�n�Ǝ҂ɂ��܂��āA��p�҂ɂ͕K�v�ƂȂ��Ă���B ���g���[�����炷�ׂĂݏo�����̂ł͂Ȃ���p�҂ɂ́A�n�Ǝ҂̕��̈�Y���������p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������h�����D�ނƍD�܂���Ƃɂ�����炸�w���킳��Ă���B �l�Ԃ́A���Ă��ĉ��b��^���Ă��ꂽ���Ƃ͖Y��Ă��܂��ɂ��Ă��A�����������Ȏd�ł���s���ȏ����ɑ��ẮA������ĖY��邱�Ƃ͂Ȃ����炾�B ����p����n�Ƃ� ���̌���F���Ǝ���F���͐������B�����A������Ƃ����āA�����Ȃ��オ�z���Ă������̂��A�����S���Ă������b��������Ƃ��ے肵�A�V���ȑn�Ǝ҂̓��ɓ��ݏo���Ȃǂ͂ǂ��ł��낤�B �܂������̃[������o������ȏ�ɂ���͓�����Ƃł���B�V�����n�Ǝ҂Ƃ��ẴX�e�[�^�X���m���������̂ł���A�������̂��Ǝ������O�ɏo�āA����сA�܂������Ⴄ���ꂩ�炻����ʂ����ׂ��ł���B ���̏ꍇ�A���Ȃ�Ƃ͂����A�ꂩ��M���ł���ғ��m���W�܂��āA�ꂩ�玖�ƂW�����čs���o�傪�K�v�ł���B �T���̂�����݂≅�O�����A�n�Ǝ҂Ƌ�J�����ɂ��Ă����҂�����ς킵���v���̂ł���A��p�҂̒n�ʂɗ��ׂ��ł͂Ȃ��B ���������͂����Ă��A��p�̗���������������o�����Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ�����ǂ����B ���_�����ɂ����A����F�����ǂ��ł���A�܂������̑��������߁A����������������ݏo���Ă������Ƃ�S������ׂ��ł��낤�B �n�Ǝ҂��z���グ�Ă������тƂ������܂��\���������A���̗��_�ƌ��_��o���B���̒��ŁA����ɍ���Ȃ��Ȃ������̂���C�ɔr������̂łȂ��A�ً}���Ƒ��ւ̉e���x���l���A���P���Ă������Ƃł���B ���l������̂͋ɗ͂�����Ɉ����A�����Čy�����Ȃ����Ƃł���B�Z���I�A�l�I���l���f�݂̂ɕ炸�A�Ȃɂ��L������ɗ����āA�q�ϓI�ɔ��f�������Ă����B ��p�҂��Ȃɂ��y�����A�Ȃɂ��d�����邩�ɁA�܂��̎҂͏d��ȊS����B����ɂ���č���̕��j�������Ă��邩��ł���B�D���̊�����o���ɂ����肷��ƁA�^�ɉ��l������̂ł��A�����܂��y������Ă����B���ꂪ�V�����C���A�Е����Ӑ}���Ȃ��܂܂ɂ��������B�@ �@ |
|
| ���D�c�M�� | |
|
��������l�̃j�[�Y����������
�K������Ƃ���u�y�s�E�y���v���o���������B�y�s�E�y���̖ړI�́A 1 �K�����ɘa����B���ꂪ�ǂ�ȏ������c��ł��悢(���̓����́A���̂�������̔�����̂ɂ́A���������ʓ|���������ƁA��[�����K�v������)�B 2 �i�o���H�Ǝ҂ɂ́A�ŋ��������Ȃ��B 3 �֏���D�ԏ���p�~���āA���╨���̖W���ɂȂ���̂�S���p�~����B 4 �lj݂𗬒ʂ�����B �Ȃǂł���B�����ނ����悵�Ă����Ȃ����B �u���_�����v�̌��ʁA�v�����������m���鉺���ɏZ�܂킹�āA�����̃X�s�[�h�A�b�v���͂��������ƂɋN������B�����āA���́u�v�Ƃ����͓̂��{�̂ǂ��ɂ��Ȃ��A�����̒n�����B �����̐��k���ɟ͐��Ƃ�����(���͂̏㗬)�������āA���̐�̂قƂ�Ɋ�R�Ƃ����R������B���̎R�̘[���狻�����̂��L���ȁu���v�Ƃ��������B�������͕̂����Ƃ������ł���B���͕����B���̐����ɂ��ẮA�E�q���Ўq���J�߂�������B����́A�u�����̐����������Ȃ������炾�v�Ƃ����B �M���̓��̒��ɂ́A�����炭���̂��Ƃ��������ɈႢ�Ȃ��B�����ŁA�u��������̕����̂悤�ȋƐт��c�������v�ƍl�����B���̕����̂悤�ȋƐтƂ����̂́A�ނ��������ォ��c�������A�u������l�̃j�[�Y����������v�Ƃ������Ƃł���B����́A�u���a�ɐ��������v����u���肵�����v�ɂ����鎵�̗v�]��������{�Ɏ������邱�Ƃ��B����ɂ͂܂��A�u�Ȃɂ������̒c�̐푈��Ԃ��I��点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƁA�u���{�̕��a���v�ɗ͓_���������B �ނ͎����玟�ւƋ��_���ڂ��B ���F�邩�疼�É���ցA���É��邩�珬�q�R��ցA���q�R�邩�猢�R��ցA���R�邩���ցA�邩����y��ցA���y�邩�狞�s�ցB�����Ĕނ��Ō�ɋ��_�ɂ����������̂��A�����炭����@�̑��{�R�ł���ΎR�{�z��(���)�������͂����B�ނ̖ڂ͂��łɊC�O�Ɍ������Ă����B�@ |
|
|
�����œ�����l�̃j�[�Y�c��
�D�c�M���́A�푈�̓V�˂���A�푈�D���Ƃ����Ă��邪�A�����Ă����ł͂Ȃ��B�t���I�Ȍ�����������A�u�D�c�M���́A�푈�𑁂��I��点�邽�߂ɁA�V�����푈�̕��@���l���o�����v�Ƃ������Ƃ��ł��邾�낤�B ���̂��߂ɐ푈�𑁂��I��点�����Ǝv�������Ƃ����A�M���͐��܂���̏��d���_�҂ł�������ł���B���ꂪ���ɑ����Ìx�C�����������Ă������Ƃ́A���X�̃G�s�\�[�h��������Ă���B �D�c�M���́A�Ⴂ������A�����A���킯�A�o�T���ȂǂƌĂ�Ă����B�Ȃ������Ăꂽ���Ƃ����A���ꂪ��ɔ����̏鉺����������܂���Ă�������ł���B���̂��߂ɂ�����܂���Ă������Ƃ����A����͗��l�ɐϋɓI�ɐڐG�����B����ɂ��킹��A���̌��t���g���ƁA�u�V�����A�C���^�[�l�b�g�A�g�ѓd�b�A�e���r�A�����ԂȂǂ��Ȃ�����ɁA�l�����鍑���炠�鍑�֕����Ă����Ƃ������Ƃ́A���̂܂�����Ă����Ƃ������Ƃ��B��������܂��Ȃ���͂Ȃ��v�ƍl���Ă�������ł���B �ł́A�u���̂��߂ɗ��l�ɐڐG����̂��v�Ɩ₦�A����͂������������낤�B�u���ܐ����Ă��铯����l�̃j�[�Y(���v)��m�邽�߂��v ����͂₪�āA�u�V���z���v�Ƃ����͂��g���B���̈Ӗ��́A�u�V���ɕ����������v�Ƃ������Ƃ��B�����Ƃ����̂́A�u���Ƃ������������Đ������s���v�Ƃ������Ƃł���B���̗��ɂ́A�u����(�M��)�����̓_�����v�Ƃ��������肪����B�����Ă��̎��D�c�M�����u���Ɛ����v�Ƃ݂��̂́A�������R�ɂ�鎺�����{�̐����ł������B�M������݂�A�u���Ƃ��Ƃ͕��m�̂͂��Ȃ̂ɁA�����Ƃ͂��̂܂ɂ��M�������Ă��܂����B����Ă��邱�Ƃ͂��ׂČ��Ƃ̕�炵���B����Ȃ��������ȕ�炵�����Ă����̂ł́A��ʖ��O�̃j�[�Y�͔c���ł��Ȃ��v�ƒf�肵�Ă����B���ł�������́A�u�����̂Ă�A���ɏo�悤�v�Ƃ������R�C�i����̌��t�����s���Ă����Ƃ�����B �u��̒��ɂ��āA�������������ƍl���Ă��Ă͖��O���������߂Ă���̂����ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B��������������鉺���ɏo�Ă����Ė��O�Ƌ��ɍs�����邱�Ƃɂ���ăj�[�Y��c�����邱�Ƃ��ł���B���������{�S�̂̃j�[�Y��c������̂ɂ́A���Ƃ����Ă����l�ɐڐG���邱�Ƃ��v�ƍl���Ă����B�M���ɂƂ��ė��l�́A�u���������炷�}�́v�ł������̂ł���B�@ |
|
|
���M���ƏG�g / �|�p�Ɛ����̂����
�D�c�M���̎��Ƃ��p�������L�b�G�g�́A�V���l�ɂȂ�ƌ|�p�Ƃ��s�҂����B�s�҂����Ƃ��������A�u�|�p�Ƃ��������͂̂��Ƃɋ������ׂ��ł���v�ƍl�����s�����B�痘�x���E���ꂽ�̂͂��̂��߂��B���x�́A�u�D�c�M���l�́A���l�Ƃ����|�p�Ƃh�����B�܂�|�p�̕���́A�����̕���Ɨ���������̂ł����āA�㉺�W�͂Ȃ��Ƃ��l���ɂȂ��Ă����B�����Ă݂�Ό|�p�̕���̓T���N�`���A��(���̃J�̂܂������y�Ȃ�����)�Ƃ��l���ɂȂ��Ă����B����Ȃ�ɂ킽���������l�ɂ����h���Ă����������B�Ƃ��낪�L�b�G�g�l�͈Ⴄ�B�G�g�l�͂��ׂĂ̕��삪�������͂ɋ������Ȃ���C�����܂Ȃ������B�킽���ɑ��Ă��A�Ɛb�Ƃ��Ďd���邱�Ƃ����߂��B����͂킽���ɂ͂ł��Ȃ��B�킽���͒��̐��E�ɂ����鉤�҂�����ł���v�Ƃ������B ���̐痘�x�̍l�����ɂ��悭������Ă���悤�ɁA�D�c�M���ƖL�b�G�g�Ƃł͐l�Ԑ����܂������Ⴄ�B�G�g�͂�͂�_���̏o�g�œV���l�ɂ܂ł̂��オ��������A�u�V���l�Ƃ����͍̂ō��̌��͎҂ł���B���������łȂ��A�|�p���x�z����v�Ƃ���遂荂�Ԃ����l�����������Ă����B �M���́A���̎���ł́A�u�\�͎�`�v���Ƃ�Â����o�c�҂��B�g�b�v���[�_�[�����������l���������Ă�������A����̂��Ƃɂ͗L�\�Ȑl�Ԃ������W�܂����B�M���́A�u�g���ȂNJW�Ȃ��B�I���̓V���̂��߂ɂǂ������J�������ł��邩�A���̔\�͖{�ӂɂ���ĕ]������v�ƍ������B ����������́A�u�I���́A�V�˂͍D���ł͂Ȃ��B���������J���Đg�ɂ����w�͂ɂ��\�͂������]������v�ƍ����Ă���B�V�˂������M���ɂ��Ă͂������낢���������B����������͎����A�u�V�˂����w�͉Ƃ������]������v�Ƃ��������̕]�����@���Ƃ����B����ɂ���āA�L�b�G�g�▾�q���G���̂��オ���Ă����̂ł���B �����͐M���̂����A�u������(���l�A���������Ε��Q��)�v�̏o�g�ł���B�M���̉E�r�E���r�ƂȂ������q���G��H�ďG�g�́A�܂��ɗ����ҏo�g�ł������B�M���ɂ��킹��A�u���̂ӂ���͗����ҏo�g�ł��邾���ɏ��ʂł���v�Ƃ������Ƃł���B���q���G�͓����̑喼�₻�̏d��������w���ɂ����邭�A�G�g�͏o�g�̂��������̏��ɂ��킵�������B�M���͋��Ȃ���ɂ��āA�u��Ɖ��̏��v�ɒʂ��邱�Ƃ��ł����B�@ |
|
|
�����������^���x�Ɏ�肱��
�����M���ɂ͑傫�ȔY�݂��������B����͕����ɑ��鋋�^�ł���B���^�͂��ׂēy�n�ŗ^�����Ă����B�������A���Ƃ��g�傷�����قǓ��{�͋����̂œy�n�Ɍ��E���������B (������ǂ����邩)�M���͔Y��ł����B�䂫�Â܂肪�����Ă������炾�B����́A�O�G�ɑ����@�ł͂Ȃ��A�����ɐ�������@���B ������ǂ��Ǘ����˔j���邩�B�Y�ݔ������M�������H�������̂́A�����痘�x����������"����"�̑��݂ł������B�M���͎v�킸�A�u���ꂾ�I�v�ƕG��@�����B����̉s�����̒��ɁA���锭�z����������ł���B�ꌾ�ł�������́A�u�y�n�ɑ��鉿�l�ς��A�����Ƃ������l�ςɕς���v�Ƃ������Ƃ������B��̓I�ɂ́A�u�����ɓy�n��^���Ă����̂��A����ɕ����Y�i��^���邱�Ƃɐ�ւ��悤�v�Ƃ������Ƃł������B ����������ɂ́A�M�����g�͂������̂��ƁA�����������V���������������l�ς����悤�Ɉӎ���ϊv���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �u���������������s���傤�v�M���͂����l�����B ����͂��̔��z�������́A�u�m�I���Y�v�ƍl�����B�����̓��{�l�ŁA���������^���x�̒��Ɏ�肱�����Ȃǂƍl�����l�Ԃ͑��ɂ��Ȃ��B����͊��S�ɐM���̓Ƒn�ł���A�����ɂ��̔��z���̂��̂���̉��l���������B �M���́A�u���̉��l�ς��A�����̃p�e���g�ɂ��悤�v�ƈӋC���B ���̌�̂���́A�����̑喼�����ɑ��āA�u���܂��͓y�n���~�������A����Ƃ����̕����~�������H�v�ƕ������B�����̑喼�����́A���̍��̐M�������̓����ɂ��A���낢��ƗL���Ȓ�������W�߂邱�Ƃ�m���Ă����B �����ŕ��������́A�u����A�y�n�͂������\�ł��B��������A���Ȃ�����ɂ��Ă��钃�q������������܂��B���A�L���Ȓ��q������������ƁA�킽�����̃X�e�[�^�X���オ��A�����̐S���x�����܂�܂��v�����������������܂�Ă����B���ꂪ�M���̑_���ڂł������B�@ |
|
|
������厖�ɂ���
�M�����A����o�āA���s�Ɍ����������Ƃ��������B�Ƌߍ](���ꌧ)�Ƃ̋��ɂ���R���Ƃ����Ƃ����ʉ߂������A��l�̕���������B�܂�ŃT���̂悤�Ȏp�ɂȂ��āA�M���Ɏ�������o���A��������Ƃ������B�M���͂��̒j�ɂ������B �u�Ȃ��A����ȎR�̒��ł��܂��͕���Ȃǂ��Ă���̂��H�v�j�͉������B �u�́A���̎R����ʂ闎�l�̏����̒������A�����Ă������i��S���D�������Ƃ�����܂��B���̌�A���̏������ǂ������̂��C�ɂȂ��āA�����ꂵ��ł��邤���ɁA����ȃT���̂悤�Ȏp�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����炭�A�V�̔������������̂ł��傤�B�ł�����A���֍~�肸�ɁA���̏����ւ̍߂��������߂ɁA�������ĕ�������Ă���̂ł��v ���̎��A�M���͂����������Ɨ̂��������ŁA�ʂ�߂����B���A���s����̋A�蓹�A�܂��T���̂悤�Ȏp����������ɑ������̂ŁA�M���͕��߂̑��l��S���W�߂��B�����Ă��������o���Ă����������B �u���̋��ŁA�Ƃ̒j�ɉƂ����ĂĂ���Ă���B�����Ďc��Ŕ����A�������������炻�̈ꕔ�����̒j�ɗ^���Ă���Ăق����B�c��́A�S���F�ŕ����Ă���Ă���B���̒j�͎ꏟ�ȋC���̎�����Ȃ̂ŁA�F���D�������Ă��A�₪�Ă̓T�����������x�l�Ԃɖ߂邱�Ƃ��ł��邾�낤�v �M���̗D�����C���ɂق�����āA���l�����́A�K���������܂��Ɛ������B��N��A�M�����܂��R����ʉ߂������A�ӂ�͌��Ⴆ��悤�ɂȂ��Ă����B�����āA�����ݐ[���\���������l�̒��N�҂�����o�āA�M���̑O�Ɏ�������B �u�N���H�v�����ƁA�j�́A�u���̃T���̕���ł������܂��v�Ƃ������B�M���͋������B �u���Ⴆ�����B��́A�����N�������̂��H�v�u���Ȃ��l�̂����ł������܂��B���̐l��������ω��������Ă�������A���܂͂������đ��̂��߂ɂ��낢��Ɠ������Ă��������Ă���܂��B����ƁA�������b�������������𓐂����������A���̊Ԃ��܂��܂�����ʂ肩����܂����B���́A���̎��̂��Ƃ�l�тāA����������S���Ԃ��܂����B�����́A����Ȃ��Ƃ͂����Y�ꂽ�Ƃ����Ă���܂������A�C�����X�b�L���v���܂����B����Ȃ���ȂŁA���̋C��������A������x�l�Ԃɖ߂邱�Ƃ��ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂����v ������ƁA�M���͊��������ɏ����B�����Ēj�ɁA�u�悩�����ȁv�Ƃ������B �M�������߂�����y�́A���H�⋴���������ꂽ�B���܂ł����A�s�s��Ղ��������ꂽ�B���ꂾ���ł͂Ȃ������B�M���̎��߂鍑�ł́A��ɋ�����l�E�����o�Ȃ������Ƃ����B ������A�Ăł��Z�ސl�X�͑���˂��������܂ܐQ�邱�Ƃ��ł����B�܂��A���l���̉A�ŐQ����ł��܂��Ă��A�����Ă���ו��𓐂ގ҂͒N�����Ȃ������B ����ȂƂ���ɂ��A�M���̈ӊO�Ɛl�ɑ���D������ʂ�����������B�@ |
|
|
�����̒��Q�ɗ�܂����
�u�����͂Ƃ�ł��Ȃ���ł��I�v�u�Ȃ����H�v�n���~�߂��M���������B���m�͂����������B �u���̍��̗̎傳�܂��������̐킢�ɏo�čs���Ƃ����̂ɁA�����͓ۋC�ɒ��Q�����Ă��܂��B�����܂���v�u����͔_�����B�����͕��m���B���ꂼ��d���ɖ������S������B���͂����ƉɂȂ̂��B���傤�͗z�C���g��������C�����悭�āA�����Ă��܂����̂��낤�B�����Ă����v�u�����͂����܂���v���m�̓{��͂����܂�Ȃ��B�o���o���Ɣ��̒��ɋ삯�������Ƃ����B �u�ǂ�����C���H�v�M�����J�����B���m�͐U��Ԃ��Ă������B �u���Ղ�ɎE���܂��I�v�u�o�J�Ȃ��Ƃ͂悹�v�M���͏��ĕ��m���~�߂��B �M���́A���m�Ɍ������Ă������B �u����͑O�̋��_�̊ɂ����Ƃ��ɁA���m�Ɣ_���̋敪���s�����B����܂ł́A�_���m�Ƃ��ē������Ă����B���̑喼�́A�܂��������Ă���B���ꂪ�A���m�Ɣ_�������̂́A�_���͔_���ɂ��čŌ�܂Ŕ_�Ƃɐ�O���Ă��炢�����������炾�B���m�Ƃ��ē������Ă��܂��ƁA�_�Ƃ����낻���ɂȂ�B�����ɁA������_�Պ��ɂ����s���Ȃ��B�_�Ɋ��ɂȂ�Ɩ߂��ė��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����炨��͔_�ƕ��������̂��B���̓y�̔��ŐQ�Ă���_���́A�����̎d����ӂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�d�����I���������A���Q�����Ă��邾�����B�����Ă����v �u����Ȃ��Ƃ������Ă��A�������܂�܂���v ���m�͂������B�M���͂��Ă��܂����B�������A�����Z�C�ȐM���Ɏ����킸�A���̂Ƃ��̓j�R�j�R���Ȃ��炻�̕��m�ɂ������B �u����́A����̍��ł����������i������͍̂D���Ȃ̂��v �u�c�͂��H�v �����肽���Ă��镐�m�����łȂ��A�܂��ɂ������m�������݂�ȐM���������B���b�ȕ\������Ă���B�M�������������t�̈Ӗ����悭�킩��Ȃ���������ł���B �u�����������i������͍̂D�����Ƃ́A�ǂ��������Ƃł����H�v�_�����E���Ƒ������Ă��镐�m���������B�M���͓������B �u�������������悤�ɁA�_���ƕ��m�Ƃ͕ʂȖ������S�����Ă���B���ꂽ�����m�́A�_�������������悤�ɁA�Ƃ��ɂ͓ۋC�ɒ��Q���ł���悤�ɂ��Ă��ׂ����B�������O�[�O�[�����т��ŐQ�Ă���̂́A���ꂽ�����m���������ʂ����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B�̎�Ƃ��Ă̂����M�������Ă��邩�炱���A�������������肪�ł���̂��B����͂����̒��Q�ɋt�ɗ�܂�����B����������ĊԈ���Ă͂��Ȃ��Ƃȁv �u����H�v ���m�͔������B�l�����B����ɐM���̂������Ƃ��킩���Ă����B�܂��������B�݂�Ȃ��Ȃ����Ă����B�j�R�j�R���Ă���B�M���������B �u�悵�A����ł͐i�����v�M���͑S�R�Ɍ������Ė��߂������ƁA���X�ɂ������B �u���̔��̏�ŐQ�Ă���_�������̂��߂ɂ��A���ꂽ���͍��x�̐�ɏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ȁH�v �u�͂��I�v �S�R�����������ɐ����グ���B�M���̂������A���̍��ł͔_���̒��Q�����m���܂��Ă���Ƃ������t�����m�����S����傫���E�C�Â����̂ł���B�M���̈ӊO�ƒm���Ă��Ȃ���ʂ��B����͖��ɑ����������������ł���B�@ |
|
|
���I�n��т��đT�Ɋw��ł���
�D�c�M���Ƃ����A�������畑������́w���̕����x���L�����B���́u�K�ᕑ���v�̈�ŁA�M�����D��Ō��ɂ����̂��B �l�Ԍ\�N���V�̂���������Ԃ�Ζ����̂��Ƃ��Ȃ� �ǂ�Ŏ��̂��Ƃ��A�܂��ɁA�u�l�Ԃ̙R���A���튴�v���̂������̂ł���B���V�Ƃ����̂́A����Ȃ��L�����Ԃ̂��Ƃ��B�u����ɔ�ׂ�A�l�Ԃ̈ꐶ�Ȃlj��ƒZ���S�����̂��낤���v�Ƃ����Ӗ����B�M���͂قڂ��̂Ƃ���l�\��Ŏ���ł��܂��B����ȗ\�������Ă����킯�ł͂Ȃ��낤���A������ɂ��Ă��A�u�l�Ԃ̈ꐶ�͒Z����������A�������⊶�Ȃ�������R�Ă����Đ�����̂��v�Ƃ����[�����Ƌْ����������Ă������Ƃ͊m�����낤�B�M���́A�����y��Ƀ��[���b�p���痈���L���V�^���鋳�t���������B�����ĊC�̌������̕����݂̍�����A������I�ɐ����ɍ̂���ꂽ�B���y���z�������ɂ́A�n����ɂ������n���̎��S�����Ƃ��A��������z���ނƂ��Ďg�����Ƃ������B����Ȃ��Ƃ��l����ƁA�u�M���́A���������ł���A�T�Ƃ������������̂ł͂Ȃ����v�Ǝv����B�Ƃ��낪�Ⴄ�B�M���́A�I�n��т��đT�Ɋw��ł����B�������͖̂��S���n�̂����ꂽ�T�m��F�ł���B �Ⴂ���̐M���́A�u�����̂����ҁv�Ƃ����Ă����B���邢�́����Ԃ��ҁ�������ҁ��Ƃ�����ꂽ�B���Ԃ��Ƃ����̂́A���Ƃ��Ƃ́A�u�X���v�Ƃ������t���炫���B���̒����߂ɐ����āA�ɍ\���A���ł��l�̂������Ƃɔ����A�D������Ȃ��Ƃ�����l�ԂƂ����Ӗ����B�@ �@ |
|
| ���L�b�G�g | |
|
�������[���������閼�l�A�j�R�|���ƖJ���̂�܂�
�u�ًg�Y�͌���ɂ������B�����Ď����̊�ŕ��̉�ꂽ�ӏ��ׂ��B�₪�čH���ɏ]������J���҂������ĂB��S�l�����B���g�Y�͂���Ȃ��Ƃ��������B �u�V�������̏C���𖽂���ꂽ��s�̖؉����B�������I���͑S���̑f�l�ŁA���������d���̂��Ƃ͕�����Ȃ��B�S�����܂������ɔC�������B�����A�����C����ɂ��Ă��菇���������߂Ă������B���ܕ��̉�ꂽ�����݂Ă������A�����͑�̂ǂ��������ŁA����ӏ��������A����ӏ����y���������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�����ł��̔j���ӏ����\�J���ɕ�����B������C�����邽�߂ɁA���܂��������\�g�ɕ�����B��g����J����S�����ďC�����Ă��炢�����B���ꂪ�ǂ̑g�ɂ������́A�I���ɂ͕�����Ȃ��B���܂������ɂ͂�͂�C���������荇��Ȃ�������A�D�����Ƃ��������Ƃ��Ƃ������Ƃ����邾�낤�B�����ł��ꂪ�ǂ̑g�ɂ������́A���܂������ő��k����B ���܂��̕��𑁂������Ȃ��ƁA�G���U�ߍ���ł���B�I�������͒j������A���������Đ키���A���q���͂����͂����Ȃ��B��̒��ňꏏ�ɕ�炵�Ă��鏗�q���́A�����I�������������Ă��܂��A�G�̓z��ɂȂ�����E���ꂽ�肵�Ă��܂��B�Ƃ��ɏ��́A�S���G�̈Ԃ݂��̂ɂȂ�B���܂������͎����̏��[������Ȗڂɑ����Ă����C���H�q�����z��ɂȂ��Ă����C���H�����������Ƃ��l����ƁA���̕��̏C���́A������Ȃ�������ɂ͂ł��Ȃ��B�����ȁH������x�J��Ԃ��B���������ŋC�̍������Ԃň�g������A���̑g����J�����C���ӏ���I��ōH���ɗ�߁B���܂������́A���̕��̏C��������ړI���A���邢�͐M���l�����̂��߂��Ǝv���Ă����̂����m��Ȃ����A�����Ă����ł͂Ȃ����B���܂������̉Ƒ��ɂ��ւ�肪����̂��B���̂ւ���悭���̒��ɂ��ݍ��܂���B�����ȁH�v �b���I��������g�Y�́A�u�I��������ȏ�����o���ƁA���܂������̎d��������낤�B���ꂪ�ǂ̑g�ɓ��邩�A�ǂ��̔j���ӏ���S�����邩���܂�����A�ɂ����v���������ƃT�b�T�Ƃ��̏ꂩ�狎�����B�c���ꂽ�S�l�]��̘J���҂����́A�݂��Ɋ���݂��킹���B����Ȃ����͂͂��߂Ă���������ł���B���ɂ̓v�c�v�c����������҂������B �u�V��������s�͖��ӔC���B�I�������ɂ݂�Ȏd�������������āA�����͂ǂ����s���Ă��܂����v���A�݂�Ȃ̓��̒��ɂ͋��ʂ����V�����v�������������B����́A�u���̏C���́A��̎�ł���M���l�����̂��߂ł͂Ȃ��B���̏�Ɉꏏ�ɏZ��ł���Ƒ��ɂ��W������̂��v�Ƃ������Ƃ������B�����Ă݂���̂Ƃ��肾�B�J���҂����̉Ƒ������̏�Ɉꏏ�ɏZ��ł���B�G�ɍU�߂���A�G�̕��͂��ꂪ���m�Ȃ̂��J���҂Ȃ̂��������͂��Ȃ��B�J���҂��������̎��͕���������Đ키�B�����Ȃ�A�G�ɂ����͂�E���ΏۂɂȂ�B���g�Y�ɂ����āA�J���҂������͂��߂Ă��̂��ƂɋC�������B�K���K���Ƙb�����Ă��鎞�ɁA���g�Y�̎g�����Ƃ����āA��M���������܂ꂽ�B��M�������Ă����҂́A�u����œ��₩�ɘb�������Ă���ƁA�؉��l�̍�������ł��v�݂�Ȉ�ĂɃ��[�Ɛ����グ���B���̂ւ�͓��g�Y�̍I���Ȑl�g���ł���B���g�Y�͑S�̂ɁA���̐��U��ʂ��āA�u����̓j�R�{���ƖJ���̂�T���̖��l�������B�j�R�{���Ƃ�T���Ől�̐S��ނ����v�Ƃ�����B�M���̂悤�ɐ��܂����̎�̑��q�ɐ��܂ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�g���̎����ĒႢ�Ƃɐ��܂ꂽ���g�Y���̂��オ���Ă������߂ɂ́A�l�̐S��͂ޏ�łǂ����Ă������Ēʂ�Ȃ������������̂��B �J���҂����͑��k�����B�J���҂̒��ɂ����[�_�[�i������B���̃��[�_�[�𒆐S�ɁA ������Ƃ��ꂪ��g�ɂȂ邩�B ���ǂ��̏C���ӏ��������B �Ƃ������Ƃ�b���������B����������Ȃ��Ƃ͂�����b�������Ă����͂����Ȃ��B�l�Ԃ̍D�������͗����ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����炾�B���ǁA�u�N�W�����ɂ��悤�v�Ƃ������ƂɂȂ����B�N�W��������āA��\�l������g�ɂȂ����B���ɂ͋C�̍���Ȃ����m���ꏏ�ɂȂ����g������B���A�N�W�����͌������B����͂����Ȃ��B �u���܂��͋C�ɂ���Ȃ����ǁA�܂��ꏏ�ɂ�邩�v�Ƃ������ƂɂȂ����B���ꂪ���g�Y�̑_�����`�[�����[�N�̒a���ł���B�����āA�H���ӏ����N�W�����ɂ����B����g�Y�̏��ɕɂ����ƁA���g�Y�́A�u���������B�悭����Ă��ꂽ�B���ꂵ�����B�ԍŏ��Ɏ����̎������H���ӏ����C�������g�ɂ́A�I�����M���l����J�������Ă��v�Ƃ������B���g�Y�ɂ�������������ǂ��낾�����B�Ƃ����̂́A�O�̕�s�͘J���҂����ɒ����l�グ��v������A���܂������Ȃ��Ď��s�����B���g�Y�͂���Ȃ��Ƃ͌��̒[�ɂ��o���Ă��Ȃ��B��������X�́A(���������肽�����A�����l�グ��v�������獢���)�Ǝv���Ă����B���������́A�u���̏C���́A���܂������̉Ƒ��ɂ��ւ�肪����v�Ƃ������Ƃʼn������Ă��܂����̂ł���B���������ꂾ���ł͘J���҂����̃����[���͏オ��Ȃ��B�����ł���́A�u��ԍŏ��ɍH�����I�����g�ɂ́A�M���l���J�����o���v�Ƃ����G�T������������̂ł���B�@ |
|
|
���G�g�ɍ~�����O�c���ƁA�l�Ԃ̒ɂ݂�Y��܂��Ƃ���
���Ђ���H�I���ƁA�ނ͗����オ�����B�����āA�u�����A���܂������B�܂a�̘r�͂��悢��Ⴆ�Ă���B�Ƃ���ŁA�O�c�a�v�Ɖ��C�Ȃ��U��������B �u�͂��߂Ă̓y�n�Ȃ̂ŁA�k�m����ɂǂ��s���Ă�����������ʁB�ē��𗊂ށv�u�E�E�E�v���Ƃ́A�G�g�����Ԃ����B���̗��Ƃ̊���A�G�g���s�����Ԃ����B���̒ꂪ�����Ă����B����́A�u���x�́A�����������Ȃ����B�͂�����A�����ł���Ƃ����������Ă���v�Ƃ����F���������Ă����B���Ƃ́A�ӎv�\�������Ȃ��܂܂ɁA���܂ł��G�g�����Ԃ��Ă����B �G�g�́A�₪�Ăӂ��Ǝ��������炵�A�܂ɂ������B �u�܂a�A�˂˂���A���ꂮ�����낵���Ƃ̂��Ƃ��������v�u������܂����v����������b�ɂȂ�̈Ӗ����������̂��A�܂́A�傫�����Ȃ������B���Ƃ́A��l�̉�b�̈Ӗ���������B�G�g������ƁA���Ƃ͂܂ɂ������B �u���悢��A���S���Ȃ���Ȃ�܂��ȁH�v�u���̂Ƃ���ł������܂��B���炢�ł������܂��傤���A�˂˗l�̒U�ߗl�̂����������Ă��������܂��v�u���������v���Ƃ��ӂ��������B���̌��f�́A���ƂɖK�ꂽ��O�̊�@��˔j���邽�߂̂��̂ł���B���Ƃ́A�S�̈ꕔ�ɒɂ݂��o���Ȃ�����A�H�ČR�̐擪�ɗ����āA�k�m����Ɉē����čs�����B �G�g���A���ƂƂ�����y�ɂƂ�����́A�ł��Ս��Ȃ��̂ł������B����́A�����̌R�̐�N�߂���������ł���B�G������A�������R�͐^����ɂ����B���������댯�Ȗ������A�G�g�́A���ƂƂ�����y�ɗ^�����̂ł���B�������A���̂���̗��Ƃɂ͋t�炦�Ȃ������B�͊W�ŏG�g�̂ق����A�͂邩�ɑ傫������Ă�������ł���B ���Ƃ̌��f�́A�u���ꂩ��́A��y�̗�����̂ĂāA���̒j�̕����Ƃ��Ďd���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������̂������B���̌��f������ɂ������āA�܂̃J���傫����p�����B�܂́A����ɂ˂˂ւ̗F�������A�����̕v���G�g�ɖ����������킯�ł͂Ȃ��B�܂��܂��A�퍑�ɐ������喼�̍ȂƂ��āA�ǂ�����ΐ����c��邩�A�Ƃ������Ƃ�ޏ��Ȃ�ɍl���Ă����̂ł���B�����āA���̔��f�͐����������B ���シ��k�m����߂Ȃ���A���Ƃ��ǂ������C�����ł������́A�͂���m��Ȃ��B���Ă̐�y�ł���A�܂����l�ł�����A�悫���[�_�[�ł��������Ƃ����̒��Ŏ���ł������܂��A�ނ͂����ƌ������Ă����B�����āA�u���̂��Ƃ��A���U�����ĖY��܂��v�Ǝv�����B����́A�G�g�ɑ��č��݂𐰂炷���Ƃł͂Ȃ��B�����������Ƃł͂Ȃ��A���̎�����l�Ԃ̒ɂ݂Ƃ��āA�o���Ă����Ƃ������Ƃł���B �u�ɂ݂�m��Ȃ��l�Ԃ́A�l�Ԃł͂Ȃ��v�@ |
|
|
���ēc���� / �������Ƃ������
�u�O�c�a�A�꒷�N�킽���̗^�͂߂Ă��������đ傢�ɏ��������B���������łɐM�����͍��͖S���g���B�M������������ꂽ���ʂ��̗^�͂̐E���A���R�M�����̎��ɂ���ď������B�˃P�x�Ŕs�ꂽ�킽���́A�k�m����ɖ߂��ďG�g�Ƃ������\����B���A���ʂ��͂��łɎ��R���B�i�ނ͎v���܂܂ɂ��Ăق����v ���Ƃ͎v�킸���Ƃ̊�����Ԃ����B���̕\��̒�ɂ́A���Ȃ��Y�̐F�������Ă����B����͂��̏�ɗ����Ƃ�����܂ɍ��X�ƁA�u���̂����́A�G�g���܂ɂ������Ȃ����v�Ɣ����Ă�������ł���B�܂ƏG�g�̍Ȃ˂˂Ƃ͊`���̂悤�ɋ������B����Ȃ��Ƃ������āA�܂́A�u�O�c�Ƃ̏����̂��߂ɂ́A�G�g���܂ɖ������ׂ��ł��v�Ɛ����Â����B���Ƃ͗��`�Ȑ��i������A�u����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��B����͐M�����܂���A�ēc�a�̗^�͂𖽂����Ă���g���B���Ƃ��˃P�x�̍���ɔs�ꂽ�Ƃ͂����Ă��A�ēc�a�����̂Ă邱�Ƃ͕��m�̓��ɔ�����v�Ɣ����Ă����B�܂͌����I������A �u����Ȍł����Ƃ������Ă���ƁA���̐��̒��ł͐����ʂ��܂����v�ƒ������悤�ɂ����B�������������悤�Ȃ������͂��Ă��A�S�̒��ł͖{�C�ŁA�u�ēc���܂����̂ĂĂق����v�Ɗ���Ă����B����ȑO�c�v�Ȃ̗���́A�ēc���Ƃɂ͂悭�킩��B���ʂ̍l���������镐���Ȃ�A�u�����G�g�Ɉ��邽�߂ɁA�����ɖ�������҂͑S���k�m����ɘA��čs�����v�ƍl���邾�낤�B�Ƃ��낪�A���Ƃ͋t�������B�u�������Ƃ�������v�Ƃ������Ƃ������̐l���M���Ƃ��Đ����Ă����B �u�ł��邾���g�y�ɂȂ��āA���l�ɖ��f�������܂��B��ї������A�����̍��܂ł����������ꂢ�ɑ|�����čs���悤�Ȃ��̂��v�ƍl���Ă����B������A���ꂩ�珫���̂���O�c���Ƃ������Y���ɂ��āA�����ƈꏏ�ɖk�m����ŎE���悤�Ȑ^���͂������Ȃ��Ǝv���Ă����B (�k�m����ł́A����ƒ����ȕ������������˂���)�ƍl���Ă����̂ł���B�@ |
|
|
�������엲�i / �S�������Ƃ͂�����菑�� (-1597)
���҂��ׂ�₷�����i�̍ő�̂��̂��A�u���ȓ����v���B�܂�A�l�����Ă̂��炵���Ɏ��琌���Ă��܂��āA�u�������̂��Ƃ𑼂ɒm�点�����v�Ƃ��������肪�o��B���̂����肪�A��揑�������Ƃ��Ɍ���������B�܂�A�}�������镶�͂������Ă��܂��̂ł���B�����ɂ���́A���������킩���Ă���Ƃ������ׂށB �����엲�i�́A�ї����A�̑��q�����A�L�b�G�g���ł��M�����������ł���B�G�g�̎Q�d�͍��c�@�������߂Ă����B�Ƃ��낪�A�@���͓��{��s�����]�̎����傾�Ƃ����Ă����ɂ��ւ�炸�A�G�g�ɂ͌x������Ă����B�J���̂����@���͎n�I���̂��Ƃ��C�ɂ��Ă����B����Ƃ��A�����엲�i�̂Ƃ���ɗ��Ă������B �u�����ł����̂������������A�킽���͂܂��������������Ǝv���Ă���B�Ƃ��낪�A�ǂ�����l(�G�g�̂���)�ɂ͂��C�ɏ����Ȃ��炵���B�Ƃ����莶���܂��B�����ł��ǂ����Ă������킩��Ȃ��̂ŁA���Ȃ��̂��m�b��q�������v����������ė��i�͂قق��B�����������B �u����́A���c�a�̔��f�ƌ��f���������邩��ł��B�킽���́A�}�l�Ȃ̂ŁA�ЂƂЂƂ����Ȑ�ς݂�����悤�ɂ��āA�Ă����܂��B�����炭���̍��ł��傤�B���Ȃ��́A���f�͂�������Ă��邽�߂ɁA�����Y�o���ƕ����������߂ɂȂ�B�Ƃ��낪�A�킽���̓O�Y������A���Ȃ莞�Ԃ������ĂЂƂ̌��_�ɓ��B����B���̍��ł͂Ȃ��ł��傤���v�u�Ȃ�قǁv�@���͂��Ȃ������B���̂Ƃ��A���i�͂��܂������̈Ă����q���āA�����ɕM�L�����Ă����B �Ƃ��낪�����́A���c�@���Ƃ������{�ꓪ�̉s���l���̑O�ŁA�M�L�������Ă���̂ŁA�������Ă��܂��Ă����B���̂��߂ɁA�����Ώ����Ⴆ���B�����A�T������B�����A�g�b�v�̌��q��M�L��������Ƃ������Ƃ͂����ւ_�Ȏd���������B���̂��ߊX�C�������āA������͂��悢�救���������Ă��܂��B���̗l�q�����Ă������i�̓j�b�R�������B�����ď�����ɂ������B �u�����A�}���ł���Ƃ��͂�����菑���v�����͎v�킸���i�̊�����Ԃ����B�����āA�͂����������ɂ��Ȃ������B�u�킩��܂����v���i�́A�����������Ƃ��������B�u���ꂪ���܉���b���Ă��邩�𗝉����Ă��珑���B�킩��Ȃ����Ƃ́A�����Ԃ������������B�킩��Ȃ��܂܂ɂ��ď����Ă��܂��ƁA���ǂ͂���̈đS�̂̈Ӗ����Ƃ炦�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������H�v�����͂��Ȃ����āA�M��u�����B�����āA�������ɗ��i�̂������Ƃ��n�߂��B���̒��Ŕ��t����B�����āA�킩��Ȃ��Ȃ�ƁA�u��������������Ƃ́A�ǂ������Ӗ��ł������܂��悤���H�v�Ǝ��₵���B����ɑ��āA���i�͐e�Ă��˂��ɓ������B�\�\���A���݂������悤�ɂ��ď�����ɓ`�����B������́A���i�����q���Ă���Ԃ͕M���Ƃ�Ȃ������B���q���I���ƁA�j�b�R�����āA�u���b�͂悭�킩��܂����B�������Ă��������܂��v�Ƃ����ĕM���Ƃ����B�₪�ď������������͂�ǂ�ŁA���i�͖��������B �u�悭�������B����̂������Ƃ����S�ɂ��O�͗������Ă���B�����ł���v�Ƃق߂��B���̈ꕔ�n�I�����c�@���͂����ƌ�����Ă����B�r������ނ͖җ�ɔ��Ȃ����B (����͂͂��������B���̍������ւ��ċ}���������B�����āA�����̔��f�͂⌈�f�͂�M���������B���ꂩ��́A�����Ǝ������^���Ă����낤�B��������A�G�g���ɂ��������Ă��������邾�낤)���̒ʂ�ɂȂ����B�Ȍ�A�@���͓�x�ƏG�g�ɋ^���邱�Ƃ͂Ȃ������B�@ |
|
|
�������엲�i / �}�����Ƃ͂�����菑���A�l�ɍD����Ȃ��Ə��ɑa���Ȃ�
�u�}�����Ƃ͂�����菑���v ����́A���i������Ƃ��}���̕������������߂ɁA����ɂ��������Ɍ��q�����Ƃ��̂��Ƃ��B �Ƃ��낪�����͍Q�ĂāA�M���k���A�܂��M�̐悩��n���ۂ��ۂ��Ǝ��̏�ɗ��Ƃ��B�����ŁA��������Ă������i���u�}�����ƂقǁA���������ď����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɨ@�����Ƃ����B�܂��A�u���m�́A�ǂ�Ȃɍ˔\�������Ă��A�l�ɍD���Ȃ���A���Ԃ̏��ɂ��a���Ȃ�v�Ƃ����Ă���B ���i�́A�ɂ�����Ƃ悭�����̉Ƃ̑O��������Ƃ����B�����āA�Ђ�����Ƃ��Ă���Ƃ�A���₩�ɐl��������Ƃ�����ׂ��B��ɖ߂�Ɣނ͂����������B �u�ǂ�Ȃɍ˔\�������Ă��A�l�ɍD���������ꂸ�A���q�����Ȃ��悤�ȕ��m�͂��߂��B����́A�l���W�܂�Ȃ���A���ꂾ������炸�A���Ԃɑa���Ȃ邩�炾�v�Ƃ������B����ɁA�u�l����b���āA�����ɕ��������Ƃ����l�Ԃ͂��߂��B�l�̘b���Ă��A���������̒��ŁA�����ł��Ȃ������ł��Ȃ��A�Ƌc�_���A���������������Ƃ������̂��A�Ɣ[������܂Ől�̘b���ᖡ����悤�łȂ���A���̖̂��ɗ����Ȃ��v�Ƃ��������Ƃ����B����́A��������܂ł��Ȃ��낤�B ����ɁA�u�����̍D���Ȃ��Ƃ́A������ł���ł��Ǝv�����ق��������B�t�ɁA�����̂���Ȃ��Ƃ́A��������Ă�Ǝv���ׂ����B�l�Ԃ̈ꐶ�͔��ɒZ���B������A�l�ɂ悭������͓̂�����A����������Ȃ����x�̂��Ƃ͂ł���͂����v�Ƃ��B�@ �@ |
|
| ���Γc�O�� | |
|
���^���ɕĕU�����p
���������̐������������ĂȂ��Ȃ����܂�Ȃ��B�G�g�͂��痧�����B�e�ɂ����O���ɁA�u�O���A���Ƃ�����v�Ɩ������B�O���͐����������ƌ��߂Ă������A�₪�Ă����������B �u����Â߂�̂ɁA���q�̕ĕU��q���Ă���낵�イ�������܂����H�v�G�g�́A�������B�u�ĕU�����Ɏg���̂��H�v�u�y�U�̑���Ɏg���܂��B������y�U����点�Ă��A����Ԃɍ����܂���v�u�Ȃ�قǁv����Ȃ��Ƃ������o���ꂽ��A���ʂ̐l�Ԃ������炢���Ȃ�A�u�����o�J�ȁI�v�Ɩڂ��ނ��ɈႢ�Ȃ��B�u�����ɉ��ł��A��ȕĕU���A�y�U�̑���Ɏg���Ƃ͉������I�v�Ɠ{�邾�낤�B �������G�g�̊�ʂ͑傫���B�����ɎO����M�����Ă����B�G�g�͑����ɁA(�Ȃ�قǂ����͓��������B�y�U�̑���ɕĕU�𗘗p����ȂǂƂ����̂́A�Ȃ��Ȃ����̐l�Ԃɂ͎v�����Ȃ�)�����v��������A�u�킩�����B�g���v�Ƃ������B �O���͂������������āA�u��̂��q��A�������̂��q�ɕۊǂ���Ă���ĕU���^�т����B�����āA�J���҂�����������̌���ꏊ�ɐς߁v�Ɩ������B�݂�ȋ������B �u�y�U�̑���ɕĕU���H���������Ȃ��b���v�����v�������A�O���̂��т����\�������Ƌ}���Ŏ��X�Ƒq����ĕU��S���o�����B �Ջ@���ς̍ˊo�ɂ���āA����ꏊ�ɕĕU���ς܂ꐅ�͎��܂����B�G�g�͎O���̍ˊo�Ɋ��S�����B�������O���̍ˊo�͂���ŏI�������ł͂Ȃ������B��̗��ꂪ�Â܂�ƁA�O���͍��D�𗧂Ă��B ���D�ɂ́A�u��v�ȓy�U����U�����Ă����҂ɂ́A�����ɐςĕU�ƌ������Ă��v�Ə�����Ă������B�܂�A�u�V�����y�U�������Ă����҂ɂ́A��̌���ꏊ�ɐς�ł���ĕU����U�^����v�Ƃ������Ƃ��B �t�߂̏Z�������́A�u�{������H�v�Ɗ�����������B�������A�����ɓy�U��S���ł������Z�����A�����G�ꂽ�ĕU��U��S���Ŗ߂��Ă����̂�����ƁA�݂�Ȃ́A�u�{�����v�Ɩڂ��P�����A�����玟�ւƓy�U��������B �������Γc�O���́A�Z���������S���ł����y�U�������ĕU�ƌ���������ł͂Ȃ��B���ꂪ�擪�ɗ����āA�y�U�̂ł�����\���ɒ��ׂ��B����������ȍ��������Ă����҂ɂ́A�u����ȕU�ł͖��ɗ����ʁB��蒼���Ă����v�Ɩ������B�Z�������́A�u�Γc�l�͂���������ȓy�U�ł͕ĕU����������Ȃ��B�I�������������������Ă������肵���U�����Ȃ���_�����v�Ƃ������B����������ȓy�U�������Ă����҂ɎO���͂����������B�u��v�ȓy�U�����߂�̂̓I���ł͂Ȃ��B���܂��������g���A�^�����玩����������邽�߂ɕK�v�Ȃ͂����v���̂������͐����͂��������B�Z���������l���������B �u�~�������ŕU������Ă��_�����B���������̑��͎��������Ŏ��Ƃ����l�����Ȃ���_�����B�����Γc�l�͋����Ă����������v�������ĔG�ꂽ�ĕU�͑S���V������v�ȓy�U�ɑウ��ꂽ�B�@ |
|
|
����Ŏ��s������U��
��Ȃ��Ƃ��N���������́A���̐��U�ߍH���ɁA�O�����t�߂���_������ɓ��������Ƃł���B�������A�^�_������������̂ł͂Ȃ��A���������ƕĂ�ɂ������Ȃ��^�����B���܂܂ł̒����Ƃ͂������̂ŁA�_���͂�낱��ŎQ�������B����������āA��̒����炽������̕����_���ɉ����ĉ�������B�����Ă��̕Ă͂��̂܂钆�̐H�Ƃɂ��A���͕Ăɂ����āA�������Ɏ������B�O���̕���������ɋC�������B �u����̓G�����H���ɉ�����Ă��܂���v�ƎO���ɕ����B�O���͏����B�u�����̏���U�߂�H������`���A�Ƃ����̂͂������낢�ł͂Ȃ����H�v�u����B������œn���Ă�����A�G���ď�������邱�ƂɂȂ�܂��B�E���܂��傤�v�u����Ȃ��Ƃ�������A �ق��̔_�������킪���Ă��Ȃ��Ȃ�B�ق��Ă����B�H������������A�镺�͂ǂ������̃G�W�L���v���҂̊��e�̂悤�Ȃ��Ƃ��������B����łȂ��Ă��m���̎O���́A���i����A�u���̐l�͗₽���v�Ƃ����Ă�������A�����͈�ԁA�u����A�ӊO�Ɖ��������v�Ƃ���ꂽ�������̂��B �����a����̂͂������A�O���ł͋t�Ɏm�C����߂�B�ْ��������ށB ���������A�������������b�g�[�ɁA�G���l�v�ɂȂ��ċ��ƕĂ��������̂��ٔF���邭�炢������A�S�ʓI�ɂ���C���x�z�����B����́A�y��̊e���̊ēA�_���ɂ������ꂽ�B���ɁA�G�̐l�v�̂���Ƃ���́A�̂ɂ��Ƃ��܂��A�Ƃ����悤�ȋC��������邩��A����ڂɌ���B �u�����낤�A�����낤�v�Œʂ肷���Ă��܂��B���ꂪ�O���̍ő�̎��s�ɂȂ����B�G�̕��͏�֖߂�ƁA�Γc�R�̊��e�����A�u�܂ʂ��߁I�v�Ƒ�����Ă����̂ł���B �H���͊��������B�Γc�R�͕�͂̑Ԑ��ɓ������B�J���~��͂��߂��B���������̒��̐������������͂��߂��B���̕����ƁA�G��������H���ŕĂ����������Ƃ��Ă��A�₪�Ă͐H�Ƃ����邾�낤�A�Ǝv��ꂽ�B�⋋�̒ʂ��₽��邩�炾�B ���A�����A���J�������B�������J�ŁA��̒��̐��ُ͈�ɐ��肠�������B�u����ł́A�������邷��v���т����ɂȂ����邩��́A�����炭�~�Q�̎g�҂�����ɂ������Ȃ��A�Ƃ����\�����A�Γc�R�̒N�����������B�O�����g���A�u���͐��������B������m�����畐���ɂȂ��v�Ƃ͂����B �ǂ��낪�A�ˑR�A�炪�����B���̐�����ĂɐΓc�R�����������B�Γc�R�͑�A�����҂����o�����B����Ăӂ��߂����Γc�R�̕�͑Ԑ����߂��Ⴍ����ɂ����ꂽ�B ����ꏊ�́A�G�����H�������Ƃ���ł������B�ߓx�̉���������āA�����J�b�R�������O���̌�Z�ł������B�m���́A��͂聍�m���ŃP�W�������Ȃ�����߂Ȃ̂ł���B���ɂȂ�����������ƁA�����ǂ��聍�����̕挊���@��"���ƂɂȂ�B�@ �@ |
|
| ������ƍN | |
|
�����f��
�ԂƎ����o���o���ɂ���Ƃ����̂́A�ꌾ�ł����Ό����̓Ɛ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�܂茠���̏W�������Z�[�u����Ƃ������Ƃł���B�ƍN���s�����̂́A�u�������Č����́A�ˑR�Ƃ��ĕ��ł���O���R�ƍN�����B�]�˂̃t�H�[�}���Ȗ��{�́A�����܂ł����s�@�ւɓO����v�Ƃ������Ƃɂ����B�ނ͂��̗��O�����s���邽�߂ɁA�u�����������̂̋��^�͈����}����v�u���^�̑������̂ɂ́A�������������Ȃ��v�Ƃ����������Ƃ����B�����Ă��̕����ɂ���ĕ������喼�̂����A���{�̘V�����͂��ߏ���E�ɂ���̂͂��ׂĕ���喼�Ⓖ�Q�ł�����{�ɂ��������B �O�l�喼�͂ǂ�Ȃɋ��^�������Ă���ؖ��{�̎d���͂ł��Ȃ��B����S���A���Î��\���A�א�\�l���ȂǂƂ����傫�ȑ喼���A�����܂Ő�ɖ��{�̖�E�ɂ����Ƃ͂ł��Ȃ������B ����A�V���Ƃ���N��A��ڕt�A���邢�͏���s�Ȃǂ̃|�X�g�ɂ��喼����{�̋��^�́A�������ĒႢ�B���������\���Β��x�ŁA���ʂ͌ܖ����Z���̑喼�����̃|�X�g�ɂ����B�ƍN�́u���f��v�́A�Ō�܂Ŏ��ꂽ�̂ł���B �����Ă݂�A���ꂪ�ƍN���퍑����Ɍo�������������́u��@�v��蔲���邽�߂̍I�݂ȁu�w�����@�v�������B�@ |
|
|
�����f�x�z
�u�N�A�N���炸�Ƃ��A�b�A�b����v�Ƃ����A�g�����ɂƂ��Ă͔��ɓs���̂����_�������҂��邱�ƂɂȂ�B���̘_����"���m��"�Ƃ��āA���{�̑S���m�ɓK�p���ꂽ�B�g�����̌��͈͂�i�Ƌ����Ȃ����B�g���鑤�́A���ǂ͏�������ɉ����茩��悤�ɂȂ�B ����́A�M���E�G�g�̗���y���c���Ă��������{�Љ���A���[�����O(�C��)�������Ȃ��璷���ێ��Ǘ����邽�߂̉ƍN�Ƃ��ẮA�ǂ����Ă������Ȃ炴��Ȃ������B�ƍN�̓��ӂȑg�D�Ɛl���̊Ǘ��@�́A�u���f�x�z�v�ł���B�ƍN���g�A�u�ЂƂ�̐l�Ԃɂ��ׂĂ̔\�͂����Ȃ���Ă���ȂǂƂ������Ƃ͍l�����Ȃ��B�l�Ԃɂ͕K�����������邪�A���_������v�ƍ����Ă����B���������āA�u�d���́A�����̐l�Ԃ̑g�ݍ��킹�ɂ���Ă͂��߂Đ�������v�Ƃ����l�����т����B����͏��N���ォ��N����ɂ����āA�x�͂̍���Ƃ̐l���ɂȂ��Ă����B�l�Ԃ̎��Ԃ��悭�݂��B���̂��߂ɂ���̐l���ς͗L���ȁA�u�l�̈ꐶ�͏d���ׂ��ĉ��������䂭�����Ƃ��B�K���}���ׂ��炸�v�Ƃ������C�������̂ɂȂ�B�����ɂ��̂��납��́A�u�l�ԕs�M�̔O�v�@ |
|
|
�����a�����̒����ێ������_���E�{��
���ꂪ����̗��j�ɑ���A�u���a�����̒����ێ��v�Ƃ����܂��āA�Ɠ��ȁu�g�D�Ɛl���̊Ǘ��^�c���@�v�ށB���ꂪ�u���f�x�z�v�ł���B���邢�́u�D��̘_���v�Ƃ����Ă������B�D�̒�́A�������̃p�[�g�ɕ�����Ă���B���낢��Ȏd�������邩�炾�B�������A���ʂȂǂ̃A�N�V�f���g���N�������Ƃ��ɂ́A���i�݂͌��ɍs���������ł���e�p�[�g�ɂ́A�ˑR�����Օ��ǂ��~�낳���B��Q���������ɐZ�����A�ɒ[�ɂ����Ă����ɐ����Ă���l�Ԃ����Ă��A�Օ��ǂ͊J�����Ȃ��B���̏�ɂ����l�Ԃ́A�M�ꎀ��ł��܂��B���A��������̂ĂȂ���ΑD�S�̂�����ł��܂��B���ꂪ�u�D��̘_���v�ł���B�ƍN�̑g�D�Ǘ��@���݂Ă���ƁA���̂��Ƃ�ɐɊ�����B ���ꂪ����̓Ɠ��ȁA�u�Ǘ��E�|�X�g�̕������v�ł���Ƃ��ꂪ����Ƃ̐l������������ēƗ������̂́A�D�c�M���������Ԃ̍���ŋ`�������������̂��Ƃ��B��������������Ƃɑ����Ă����ƍN�́A�`���̘�ɁA�u���̋w�Ƃ��v�Ƃ������������A���q�̓E���Ƃ���Ȃ������B�����ʼnƍN�͓Ɨ������B����������͐N�喼�Ƃ��Ă��łɁA�u����͖��������������v�Ǝv���Ă����B�����ʼn����s��C�������B���A�P���ł͂Ȃ��O�l�̕��������Ƃ����B����s�������͑I�ꂽ�O�l���݂āA�����͂₵���Ă��B �u�z�g�P���́E�I�j�썶�E�ǂ��ւ�Ȃ�(�ǂ����ł��Ȃ�)�V��N�i�v�Ƃ������̂ł���B���͐����̓z�g�P�̂悤�ɐS���₳�����������B�{���썶�q��d���́A�I�j�̂悤�ɕ|���B�������A�V��N�i�͂��̂ǂ����ł��Ȃ������ȍق��������Ȃ��Ƃ����Ӗ����B���̂ւ���ƍN�́A�u�e�l�̒����ƒZ�����݂ʂ��������ł̑g�ݍ��킹�v�̗Ⴊ�Ƃ�ꂽ�B�����ɁA�u���ԁv�Ƃ������x���Ƃ��āA��J����ւŎd����������B��������ق��ɂƂ��ẮA����͂����炩�ɁA�u�h�b�O���[�X�v�ł���A�܂��s�����́A�u�ᔻ�ɂ��炳��鑶�݁v�ɂȂ�B�܂�s�������́A�挎�̕�s�̂ق����悩�����Ƃ��A����A�����̕�s�̂ق������҂ł���Ƃ���r���邩��ł���B���������A��s�ɑI�ꂽ�O�l�͋����S����������A�����ɂ˂ɋْ��������錋�ʂށB���ꂪ�̂��̓��얋�{�̐E���ɉ��p�����B�@ |
|
|
�����_���n���܂ŐÂ��ɑ҂�
�ƍN�͏����Ȏ����瑼�l�̉Ƃ̔т�H���Ă�������A�l�̐S�̓������Ԃ��Ɍ������Ă����B ����̐l���ς́A���̒�ɂ����Ă��Ȃ���₩�ł���B�����炱���A����͐T�d�Ɖʊ��̐▭�ȃo�����X��ۂ��Ƃ��ł����̂��B �����āA���̃o�����X��ۂ����ɂȂ����̂��A�u�E�ϐS�v�ł���B����������̔E�ϐS�͒P�Ȃ�A�u�䖝�v�ł͂Ȃ��B�͂����肢�����̔E�ϐS���x���Ă����̂́A�u���_�v�������B����ƍN�قǐ퍑����̕����ŁA���Ԃ̕]�����C�ɂ����l���͂��Ȃ��B ���ꂪ�V���l�ւ̓�������Ă䂭�ߒ������Ă���ƁA�K�����_�ɂ���Č��f�������Ă���B�܂�A���_���������x���Ă����܂ł́A�Â��ɑ҂B�T�d�ɑ҂B�����āA���_�������̕����ɕ��������ς�����ƌ���A�����܂��ʒf�ȍs���ɏo�Ă䂭�B���̊ԁA���̐T�d�Ɖʊ��̊Ԃɂ����āA���W���x�G�̂悤�ɂ��̐U�q���x����̂��A�E�ϐS�ł������B �����Ă��̐��_���`�����邽�߂ɂ́A���ɂ͂���͏�O���킵���s���ɂ��o��B�܂葼���猩��ƁA�u���̍s���́A�����T�d�������̂ł͂Ȃ����B�ʊ��Ƃ����Ă��A����ł͒��˂��v�Ƃ�����悤�Ȃ��Ƃ��s���B �Ⴆ�A�O���P���̍��킾�B�s���߂������c�M���̑�R���A����ƍN�����̍����_�Ƃ��Ă����l����̂͂邩�k����ʉ߂��悤�Ƃ����B�����m�����ƍN�́A�U�����悤�Ƃ����B���������͔������B�܂��A�s���̔����Ƃ��ĐD�c�M�����h�����������R���������B �M�����g���A�u���܁A�ƍN���ł��ďo��ΕK�����ӂ����B�����Ȃ�ƁA�ƍN���s�ꂽ�エ��́A����̔��M���R�ƐM���̋������ɂȂ�v�ƌx�����Ă����B�ƍN�͂���Ȃ��Ƃ͕S�����m���B �������A���̎��͑ł��ďo���B�Ă̒�A����͑�s���Ă��܂����B���̎��̏�Ȃ��\��̏ё��悪���݂��c���Ă���B �������A�s��Ă��ƍN�͖����������B�Ƃ����̂́A���̎����琢�_���������B����́A�u���`�ȓ���a�v�Ƃ����]���ł������B���`�ȓ���a�Ƃ����̂́A�u���Ƃ��s��Ă��A����a�͐D�c�M���a�Ƃ̓�������蔲�����B������ƕ������Ă���킢�ɂ��E���ɑł��ďo�Ă������B�������v�Ƃ����^�̐��ł���B�ƍN�͂ق������A�M���͋�����B (�^�k�L�߁A��肨���)�ƂԂ₢���B�@ |
|
|
������ƌ� / ���コ�ꂽ�c��A�����G�s�\�[�h
�����̎Ⴂ���R�͗����������Ǝv��������ł���B�喼�������A�ƌ��̗c���N�����m���Ă����B�����ĕ���ɑa�܂�A�낤�����R�̍����ɒD����悤�Ȋ�@�Ɋׂ������Ƃ��m���Ă����B�����˔j���Ă������R�����ɁA��N�Ȃ��炱�̂悤�ȑ�錾�������̂��Ɨ��������B �������ƌ��͂��̂܂܂ɂ͂��܂��Ȃ������B����͂��̃n�b�^���錾��������A��Ȃ��Ă����喼����l�ЂƂ莩���ɌĂB�����̒��ɂ́A�����ȓ����R�Ɛς܂�Ă����B�ƌ��͌Ăэ��喼�ɁA���̒������{�����グ�ēn�����B�����āA�u���g�������ߊ肢�����v�ƌ����Ă��̑喼�ɓ��������B���ׂČ����グ��ꂽ�����a���悤�Ȍ���������B�������ƌ��́A�g�ɐ��S�����тĂ��Ȃ��B�����̓��͂ǂ����֕ЂÂ��Ă���B�܂薳���ł���B �ƌ��ɂ���A�喼�ɓ���^���āA�u�����V���R�ɔ��S������A�������Ɏa��v�Ƃ����p�����������̂ł���B��L�ԂŃn�b�^���錾�����܂��ꂽ�����ɁA���x�͂ЂƂ肸�Ăэ��܂�ē���n����A�u�a�肽����Ύa��v�Ƃ������d���ƌ��̑ԓx�ɁA�喼�����͂��Ƃ��Ȃ������B �����̎ᑢ�ɂ͂ƂĂ����Ȃ�Ȃ����Ɗ������B�������ĉƍN�ƏG���̎���ɂ́A�Ɛb�Ƃ������������I����Őڂ��Ă����O�l�喼�����́A���̓��������Ċ��S�ɓ��쏫�R�Ƃ̉Ɛb�̍��Ɉʒu�Â����Ă��܂����B �������ƌ��́A�O�l�喼������b�]����������Ƃ����āA������U�炷�悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������B����͐A���D���������B���̂��Ƃ�m�����喼�����͐�𑈂��āA�ƌ��̂Ƃ���Ɏ����̗̍��œ���ꂽ�c�����X�Ƒ���͂����B��낱�ƌ��́A�A�ؐE�l�ɍ]�ˏ�̒�ɐA���������B������A�ƌ�����ɏo�Ă݂�ƐA�ؐE�l���A�喼�̌������c�̈ꕔ���̂ĂĂ����B�݂Ƃ��߂��ƌ����������D�u�Ȃ����̕c���̂Ă�H�v�u�}�Ԃ肪�悭�������܂���̂ŁB�������܂̂���ɂ͂ӂ��킵������܂���v���Ƃ������ĔC����A�ؐE�l�͓��ӋC�ɂ����������B�ƌ��͓{�����B �u���Ȃ��Ƃ������ȁD�S���A����v�u�������A����ȋW�Ԃ�̈�����A�����̂ł́A���������̂���̕�����܂����v�A�ؐE�l����ł��B ������̎d���ɊԈႢ�͂Ȃ����Ɛ��ƂƂ��Ă̎��M�������Ă���B�ƌ��͐A�ؐE�l���������Ȃ��炱���������B �u�������A���̕c�͑喼�������킽���Ɍ����Ă��ꂽ���̂��B���܂����A���Ă���̂͒P�Ȃ�A�ł͂Ȃ��B�喼�����́A�킽���ւ̒����S��A���Ă���̂��B�킩�邩�H�v�u�H�v�A�ؐE�l�͎v�킸�ƌ��������������B�����āA���܉ƌ������������Ƃ̒��Ŕ�䍂����B�₪�āA�n�b�ƋC�����A�u����͋������܂����B�킽�����Ƃ������Ƃ��A�Ƃo�߂������Ƃ��������܂��Đ��ɐ\�������܂���v�ƁA�n�`�}�L����肻�̏�ɐ������Ď�������B�ƌ��͂������B �u�킩�����ł����B�S���A���Ă���v�u�͂��v���������b���喼�����ɉk��Ă����B�喼�����ɂ��Ă��A�u���������サ���c���A�コ�܂͐A���Ă������������낤���v�Ɗ��҂��č]�ˏ�ɂ���Ă���B�`�����ƒ�𓐂݂݂�B���サ���c�͂������ɐA�����Ă����B�喼�����͂�낱�B���̉ƌ��́A�u��ɐA���Ă���̂͒P�Ȃ�c�ł͂Ȃ��B�喼�����̒����S���v�Ƃ������Ƃ́A���̌㒷���喼�����̕]���ɂȂ����B�ƌ��́A�n�b�^���Ɠ����ɁA�喼�����̐S��͂ލI�݂Ȑl�S�����p��g�ɂ��Ă����̂ł���B���N�Ƃ����Ă����B�@ |
|
|
���V�����s���͂��ׂđT�m�Ɋw��
���̈Ӗ��ł́A�u����ƍN�̓V�����s�����A���ׂđT�m�Ɋw�v�Ƃ����Ă������낤�B�����Ȃ�ƁA���N����Ɋw��ŋ�����ۂ����w��ϐ��v�x���w��ȋ��x���A���Ɩ��Ē��̂��̂ƂȂ�B�͂����肢���A�ƍN�͂����c���N����Ɋw��������{�̌ÓT���A�u�����̓s���̂����悤�ɉ��߂��A��(��)�p����v�Ƃ������ƂɂȂ�B���������ꂪ�ǂꂾ�������̓s���̂����悤�ɗ��p�����Ƃ��Ă��A�ƍN�̍��{���_�́A�u����͏�ɓV���̂��߂ɕ������s���Ă���̂��v�Ƃ������M�����邩��A�������Ƃ��Ƃ͔��o���v��Ȃ��B�₪�Ă��ꂪ�A���낢��Ȗ@��������ēV�c����Ƃ̐��������𐧌�������A���{�̑m���@�������ɍi������A���邢�͑喼�Ⓖ�Q�Ȃǂ̕��m�����𐧌䂵����A��ʐl�̍s���ɂ�������������̂́A���ׂč����ɁA�u�Ўq�̋����̎��H�v�Ƃ����M�O�����������߂��B�����̑T�̋����́A�K���������������ł͂Ȃ��B�L�����Ђɂ���Ċw�v�z�⑼�̍l������������荞�܂�Ă���B�����Ă��̔��w�Ԃ�́A���̕����v���p�[�̏@���҂����A�ނ���T�m�̕���������Ă����B���������āA�퍑���ォ�瓿�쎞�㏉���ɂ����Ă̂�����A�u�m�I�w���ҁv�́A�����đT�m�ł���B���ꂪ�A������o��ɂ��������āA�w�҂ɕς���Ă������B���̊����̉ˋ��ɂȂ����̂��A����ƍN�������Ƃ����Ă����B�@ |
|
|
�����헪
���_���Ђ������Ƃ����̂́A�ƍN�͍Ō�܂ŏG�g�v�l(����@)��厖�ɂ��A�����Ȕh���Ƃ��čs���������Ƃł���B���ꂪ�A���N�A�G����Ղ��Γc�O�����������l�h���ɔ����������Ă��������A�����A�����A���A�א�A�I�{���́A�����ǂ���G�g�̎q�����̕�����S�������ɂł����B���{�ł͂ǂ������Ȃ̍��͂Ȃ��Ȃ������悤���B������Γc�O���̔s�k�Ƒ�◎��́A�����l�h���̔s�k�������̂��B�ƍN�̐��_���������Ⴊ�������������̂��B �����ЂƂB�ƍN�̏��헪�ł��܂��̂́A���̓��́A�o�͂̎g���������B���������A�Ƃ肱�ޏ��͐^�����A�O�ɏo�����̓f�}���A�Ƃ����̂��ƍN�̍L��p�ł������B ���́A�܂�����Ă������^���ɂ����Â��邽�߂ɂ́A���̏��̂����炵�肪�A�{�C�ŏ�����肵�A���x���������߂ĉƍN�ɒ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A������������Ƃ��͎E����邩���m��Ȃ��Ƃ����A�s�f�ْ̋����炵������Ȃ��B�ƍN�����̃l�b�g���[�N�ɁA�������������ْ����������点���̂́A�ŏ��ɏ��������s�����Ɓ��s�����A�������ꍇ�ɂ���Ă͎E����邩���m��Ȃ��A�Ƃ����h�c�O���[�X�𑱂����������Ƃ���ł���B����ɁA������������`���Ă��A�t���ƕ@�̐�ŏ����肵�āA�����炵��Ɏ��M�����킹�A�t�ɕs��������������S�����̖����B �l�b�g���[�N�Q�́A���悢�恍�^���̏�T���ɗ�ނ̂��B �t�ɁA�ƍN�M��̂ɂ�����͑����Ƀf�}�������B ���Ƃ��A�ƍN���G�g�Ɗ��x���܂��������q�푈(�V�����N�E��ܔ��l)�̗��N������A�ƍN�͔w���Ƀf�L���̂��ł��Ď�������A���̂Ƃ��A�u�ƍN�͎�����v�Ƃ��������ӎ��I�ɗ������āA�W�҂̓������݂Ă���B ���c�M���ɑ�s�����O���P���̍���̎�(���T�O�N�����)�ɂ��A���̂����炪��l����ɓ������މƍN�́A�r���ŖV�哪�̓G�̎���v�������Ă��镔�����݂���ƁA�u��ɏ�ɖ߂��āA���c�M���̎���Ƃ����ƐG��܂��I�v�ƁA�镺�̃����[���A�b�v�̂��߂ɁA���������Ȃ��Ƃ����킹�Ă���B ���̐w�����ׂăf�}�Ƃ���������̖d����ł��������Ƃ͂��킵�������܂ł��Ȃ��B���̂���ɂȂ�ƁA�ƍN�͂����z���l�ƃ^�e�}�G��p�����������Ɏg�������������̐����̓J�P�����Ȃ��A�z���l�ނ������̚ʊ��ȃ�����k�A���̂��̂��B�O���P���̍ۂ́A���̒���A�M���͖{���Ɏ���ł��܂�������A�ƍN�͊�@��E�����B�l�ׂ��������c�L���������B�@ |
|
|
���h�����Ɓ����́���藣�����u���f�v�헪
�܂�A�����Ƃɂ�����b�h�͂����܂ł��u�M������邱�Ɓv�ł���A�����ێ����邽�߂̐헪��ނ͋�g�����̂��B �헪�Ƃ����̂́A ���������ԂɗN�����u����ƍN�͐M�p�ł���v�Ƃ����]�����A�ƍN�����łȂ��A�ƍN�̕����S���������̐ӔC�Ƃ��ĕێ����Ă������ƁB ������Ƃ��ǂ�Ȋ�@�Ɋׂ��Ă��A�M���������悤�Ȃ��Ƃ����͐�ɂ��Ȃ����ƁB �����̂��߂ɂ́A�Ɛb�c���ق��̑喼�ƂɌ����Ȃ��悤�Ȍ����͂������ƁB�܂�A�Ɛb���m�������M�����ŃX�N������g�ނ��ƁB �Ȃǂł������B�������A�M���̔j����A�G�E�g�̌��݊��́A�����Ƀ��[�_�[�V�b�v�����₷���B�M���́A�_�\�v�J�[�̂悤�ȊǗ����s�Ȃ��A���̃��[�_�[�V�b�v�́����|�����g�����B�G�g�́A����̃����[�����グ�邱�Ƃɗ͓_��u���A���������A�j�R�{����p(���Ȃ��猨��@���A�I�݂ɖ����Ɉ�������邱��)��J���̂�܂��ŕ��������̃����[�������߂��B�����ւ����ƁA�ێ��Ǘ����̐헪��[�_�[�V�b�v�͓���B�@ |
|
|
���F���q��͒x�ꂽ�����̓T�^
�O�͂̂����܂����y���̑��q���A���܂͓r�����Ȃ���]�������Ă��̍��ɌN�Ղ��悤�ȂǂƎu���Ă��邱�Ƃ��A�F���q��͘I�قǂ��\�z���Ȃ������B�ƍN�̕ώ��ɋC�Â��Ȃ������B�]�˂ɓ����Ĉȗ��A�Ȃ��\���o�\����ɖ��邢�V�������������Ɠo�p�����̂��A�F���q��ɂ͂킩��Ȃ������̂ł���B��l�̉ƍN���A�u�]�ˌo�c�v�̔w�i���ǂ��ɒu���Ă���̂��A���b���ȂĔC���Ă��Ȃ���A�����t�x���Ȃ������̂́A�F���q��̑Ӗ��ł���B�Љ��̕ω��ɔ����A�g�b�v�͎Љ�牽�����߂��Ă���̂��A�܂��A�����Ȃ����Ƃ��Ƀg�b�v�͕����ɂǂ������\�͂����߂邩�A�����ɒ��ڂ��Ȃ������F���q��́A���ꂾ���Œ��b�̎��i���������B (��l�́A�������������Ă��邩)�Ƃ������Ƃ́A�����ȕ����Ȃ瓖�R�A�ȐS�`�S�Ō��Ȃ���͂Ȃ�Ȃ������B���̉�H��F���q��͉ƍN�Ƃ̊Ԃɐ݂��Ă��Ȃ��B������A�F���q��́A�ƍN�ɂƂ��āA�������Ď����Ō����قǂ̒��b�ł͂Ȃ������B�̑�����R�̂���Ȃ炢���m�炸�A���Ȃ��Ƃ��ƍN���]�˂ɓ����Ă��炠�Ƃ́A�ނ���A�x�ꂽ�����̓T�^�ł������B�@ |
|
|
�����S�̋��߂ɉ�����
�����������̂́A�ƍN�͓V���\���N�̍]�˓���̒i�K�ł��łɁA�̌n�I�E�����I�ȍ]�ˌo�c��������Ă����킯�ł͂Ȃ��B�ӊO�ȂقǁA�ƍN�͎����̍s������A�u���_�̓����v�ɒu���Ă���B�܂�A���g�S�̋��߂�����ɏ]�킹��̂��B�ƍN�̐����ɑ���ԓx�́A�u�������Ƃ͓V���̎��A���邱�Ƃ͓V���̓��A���͓V���̐S�B���̎O���Ƃ��Đ�����ɂ��A�g��E�݂Đl�̒ɂ݂�m���āA��������P���Ȃ�B��X�����̍����ƒm��ׂ��v�Ƃ������Ƃɂ������B�ꌩ�A��̖����`�I�����Ƃ��v�킹�邪�A�������ƍN�͂���ȊÂ��l�Ԃł͂Ȃ��B �ނ̋����ɂ͓���Ƃ̐����S���̍P�v�������Ȃ��B�������A���̂��߂ɂ́A���S�̋��߂ɉ����邱�Ƃ������Ƃ��ߓ��ł��邱�Ƃ�m���Ă����B�ȒP�Ɍ����́A�u���́A���̉ƍN�ɉ������߂Ă��邩�v��I�m�ɒm��A�m���ɂ���ɉ����邱�Ƃł������B�����ƍӂ����\��������́A���̗~��������̂�^����Ƃ������Ƃ��B�傫�������́A���̍��̖��͉��m�̗��ȗ��A���a�����߂Ă���B���T�E�V������́A���̕��a�ɁA�Љ���̈��肪��������B�M���ƏG���́A���̎Љ�����ꉞ�͈��肳�����B���A���a�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�ӂ���Ƃ��A���̖ڂ��猩�Ă͂Ȃ͂��s���������B�ӂ���͖��炩�ɊO���N���ɒu���Ă������A�G���͌����ɒ��N�ɍU�߂��B�ƍN�́A���m�ȗ��܂���������Ă��Ȃ��A���̖��̕��a�ɉ����邱�Ƃ����C�����l���Ă����B�F�A�Y��Ă��邪�A���̂ق��͖Y��Ă��Ȃ��B����ɖ��͔��Ă����B�x�����~���������B�ƍN�͂��̐��_�ɏ]���Ȃ���A���g�̌����~���I�݂ɑg�D�����邱�Ƃ��v�������Ă����B �u�l�̒ɂ݁v��m��Ƃ́A������ׂ�������Ƃ������Ƃ��B������ׂ�������Ƃ������Ƃ́A������n��̎��Ԃ�m��A�����ɍ����l�Ԃ̗~�]��c�����邱�ǂł���B�@ |
|
|
���F�l�������Ȃ����R
�ƍN������܂ŗF�������������Ď����Ȃ������̂ɂ͗��R���������B�ƍN�̐l���N�w���炷��ƁA�F�����قǂ��ĂɂȂ�Ȃ����̂͂Ȃ����炾�B (�F�����Ƃ͂��������Ȃ낤�H)�ƉƍN�͂悭�l����B����́A�l���ɂȂ��Ă����q�����ォ��̌o���ł���B�����Ĕނ́A���ɑݎ؊W������ނƁA�F��Ƃ����̂́A�������Ȃ�����Ă��܂����Ƃ����x���o�������B�₪�Ĕނ́A�u�K�v�Ȃ͕̂����������B������A��l�Ƃ��ė��Ă�l�Ԃ͕K�v�����A�F�����ȂǂЂƂ������Ȃ��B�F�����Ƃ����̂́A�Q�����ĉv�Ȃ����̂��v�Ƃ����ɒ[�ȍl�������悤�ɂȂ����B������ނ̌o�c���@�̒��ł́A�F�����������Ŕς�Ƃ������Ƃ͂������ĂȂ������̂ł���B �������A���������K�v���Ȃ̂ł����ā��M�p������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�@ |
|
|
���g�����킸�\�͂̂���҂͓o�p���� �l�Y���Y�ɉƍN�́A�u���D�f�Ղ�S������v�Ɩ������B�㓡���O�Y�Ɠ���앺�q�ɂ́A�u�V�����ݕ��̒����𖽂���B�㓡�͋��݂��A����͋�݂�S������v�Ɩ������B���J�썶���q�ɂ͒����s��C�����A�u�����Ƌ��Ɏ��D�f�Ղ������v�ƍ������B���������l�������Ă���ƁA�㐢�A�u�g�����Ƃ���ɐl�̉��ɐl���������͉̂ƍN���v�Ƃ����Ă��邪�A�K�������������͂Ȃ��C������B�g�������Œ艻���A����ɐl�̉��ɐl��������悤�ɂȂ�̂͂����Ƃ��Ƃ̂��ƂŁA���邢�͉ƍN������ł��܂������Ƃ̂��Ƃ����m��Ȃ��B���̕ӂ͖��{�̘A���������ېV�܂ʼnƍN�̂��Ƃ��A�u�_�N�A�_�N�v�ƕ�����̂ŁA�������Ƃ��������Ƃ����ׂĉƍN�̂����ɂ���Ă��܂����悤�ȋC������B���Ȃ��Ƃ��A���̍��̉ƍN�͂��Ȃ�����ŁA�u�g�����킸�\�͂̂���҂͓o�p����B���̒m�b�����v�Ƃ����ԓx���Ƃ��Ă����B�����łȂ���A���J�썶���q�̂悤�ȏ��l���s�Ƃ������Ƃ������{�̗v�E�ɂ���͂����Ȃ��B�t�ɂ����ΉƍN�́A�u�@�\��`�v���̂��Ă����̂ł����āA�g���ɂ�����炸��������������Ă���A���̔\�͂������̂��߂ɏ\�ɔ���������Ƃ������������Ă����B���ꂪ�ƍN�̐l���̓������B�Ƃ����̂́A�x�{��ɏW�߂����j�[�N�ȃu���[�������͂��ꂼ������������Ă͂������A��͂蓖���Ƃ��Ă̈��̃����N�t��������B�@ |
|
|
���B�����L�b�ƖŖS�̈��d���Â炵��
�u����A���Α叫�R�E�͓���Ƃ̐��P�Ƃ���v�Ɛ錾���Ă݂Ă��A�����Đ����͈��ׂł͂Ȃ��B�ނ���傫�ȑ����̎�q��A�������悤�Ȃ��̂��B �u������A���ƈ�匈�킪�s����v�Ƃ������Ƃ́A���ܑ喼�����̏펯�ɂȂ��Ă���B�����A���ꂪ�����Ƃ������ʂ��������Ȃ��������B������A�x�{��ɂ��������ƍN�ɂ͍]�ˏ�ȏ�ɑ喼�����̎������W�܂��Ă���B�܂�A�u���Ƃ̎��̎��������߂�̂͏x�{��ɂ����䏊�l���v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邩�炾�B���������������ƍN���悭�m���Ă��邩��A�I舂ɂ͓����Ȃ��B�ƍN�̂��܂̈ꋓ�����́A�K���Ӗ������B���̈Ӗ��ł͉ƍN�̍s���͐��Ԃ̒����̖ԂɈ���������A������߂ɂȂ��Ă����B �������ƍN�͂�����߂Ȃ��B�t�ɂ����������ɂ����Ă����A�u�L�b�ƖŖS�̈��d���Â炷�v���ƂɈ����I�ȉx�т������Ă����B�ƍN�ɂ���A(���ꂪ�B����������̍ő�̖ړI�Ȃ̂�)�Ƃ����C����������B���������āA�x�{��ɏW�߂����ʂȃu���[���̖����́A�u���m�b�̌�����i��o�����Ɓv�Ȃ̂��B�����Ă��̍s�������Ƃ���͂��ׂāA�u�L�b����ŖS������v�Ƃ������Ƃł���B�����Ǝ����葁�������A���B�̖L�b���Ƃ̊ԂɎ���鍐���A�升����d�|���邱�Ƃ��B�����Ă��̍���ɂ���ĖL�b�G���̎����邱�ƂȂ̂ł���B�@ |
|
|
���G���̐V�@���E�Ǝ���
�G���̍]�˂ł̌o�c�́A�������ɉƍN���x�{�ł������Ă����s���邱�Ƃ������B�������A�G���͂��̎��s�ߒ��ŁA���̂悤�Ȃ������̐V�@�����������B �����̕����ɂ́A������������ƍN�̖��͎g��Ȃ��B���ׂē���G���̖��ŏo���B ���x�{����̎w���͌����ł���B���Ԃɑ����āA���������Ƃ���͏C������B ���C���́A���얋�{�̈З͂������悤�ȁA���t�����l���̑n���킹��B �����{�͌������|�Ƃ��A����ɋ��ꂽ�����݂��Ȃ��B �����ƌ���́A�Ȃ�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B���A���̕��j��Ⴏ�͖Ⴍ�قǁA�V���ɏオ��̂́A���얋�{�̈А��ł���A���R����G���̖��ł���B�ƍN�̖��ł͂Ȃ��B �����ЂƂA�G�����ƍN�Ɠ��āA�Ǝ��ɍs�Ȃ������Ƃ�����B����́A �����b�c�̗{���B �ł���B�G���ɂ́A�ƍN�̂������t�I�u���[���������������A����͂���Ƃ��đ��d���Ȃ���A�G���͎q���̂Ƃ�����́����w�F���𒆐S�ɁA�u�G���ɒ��`��s�����Ɛb�v�̗{����S�������B�@ |
|
|
���������g���̂ł͂Ȃ��A�����Ɏg����̂�
�u�������g���̂ł͂Ȃ��B�����Ɏg����̂��v �ƍN�́��l���g�����̂����܂��������A�l���́��l�̐S�����ށ��̂����܂������B �ڂ̑O�ŋْ����������������փ}����炩���ƁA�ˑR�A�������������A�����A�u�������g���̂ł͂Ȃ��B�����Ɏg����̂��v�ƌ��������肵���B�܂��A�u��x�M���������́A�ǂ�Ȉ��]�𗧂Ă��悤�ƐM�������v�ƌ����Â��A���s�����B �ׂ������ӂ���́A�����̂��ׂĂ͕��ƍN�̂����Ƃ͔����B�ƍN�فA ���܂��A�l�Ԃ��^���Ă�����B ���������m�A�^�S�ËS�Ō���������B �Ƃ��������f�x�z�h�̖��肾�B�G���̊Ǘ����@�ɐl�C���o��͓̂��R���B���ĉƍN�Ɏd���Ă����V���A�G���̕����ɂȂ��āA�u���������ڂ̂ق����D�����v�ƌ����o���҂������B���G���l�C���͊m���ɏ㏸���Ă����B�@ |
|
|
�����f�A�D��̘_��
�u�����������Ǝv�����A�D�̒�q�͏����Ȍ��ɕ�����Ă���B�@�\�ʂɂ��ꂼ�ꕪ�f����Ă���B������A�u�D��̘_���v�Ƃ����B�D��̘_���Ƃ��A�̂́A���Ƃ���A�AB�AC�AD�Ƃ����悤�ɋ@�\�ʂɐE�ꂪ������Ă������A�s���̎��Ԃɂ���āAA���������j��ǂƐ��������ė��邱�Ƃ�����B���̎��A����A����B�AC�AD�̋��ڂ̔������B����́A�u�D�S�̂��~�����߂ɂ́AA�������Ƃ������ɂ��Ă��A���̉��\�̈��S��ۂv�Ƃ����_���Ɋ�Â��Ă��邩�炾�B���������āA���Ƃ��ΐ��̓����Ĕ���A���ɂ����œ����l�Ԃ������Ƃ��A���̕����Ƃ̋��ڂɐ݂���ꂽ���f�ǂ��~��Ă��܂������A�K���K���Ƃ��̔������������āA�u�����Ă���I�v�Ƌ���ł��A���̎��͂�������E���ɂ���B�����J���āAA���̐l�Ԃ�������A�����ɏ[�����Ă��鐅�����̕����ɂǂƗ��ꍞ�ނ��炾�B�����A���ꂪ�A�u�D��̘_���v�ł���B����ƍN�͂��̐���̘_����̊��p�̖��l�������B���������āA�u�i�j�i�j�����A����H�v�ƊJ���A���肪�������Ɠ�����ƁA�u�N�����ɘb�����ǂˁv�ƌ������Ƃ́A�u�����̃p�[�g�́A�N�̐ӔC�ɂ����čŌ�܂Ŏ�蔲���v�Ƃ����Ӗ����������߂Ă���B ����ƍN�͕��c�M���h���Ă����B�M���Ƌ������ĕ��c����ł�������A����͐M���̌R�@��A�R�c�̕Ґ��@�A�l���Ǘ��p�Ȃǂ𑽕��ɍ̂���ꂽ�B�܂����c��\�l���Ƃ���ꂽ�E�҂ȐM���̕����̈�l�A�R���O�Y���q���i�́A�����̕����̌R�������ׂāh�Ԕ����h�Ƃ��āA����������F�ɑ����Ă����B�ƍN�͂����l�V���Ƃ���ꂽ��ɒ��̂ɁA�u�����ɌR�|�́A�Ԕ����Ƃ���v�Ɩ����āA�R���̌R���������p�������B �M���ɗL���Ȍ��t������B�u�l�͏�l�͐Ί_�l�͖x�v�Ƃ������̂��B����͂��̌�ɑ����A�u��͖����w�͓G�Ȃ�v�Ƃ������t�ɂ���āA�u���c�M���͕����̏�ЂƂ�d�����Ϗ�[�������ł������v�@ |
|
|
�������q�����_�ɓ���̐V����������
�ƍN�̋���A���Ƃ͐������̂悤�Ȃ��̂��B���M�͍���͕s���ӂ����������������͑哾�ӂł���B�������������ɘb����v�ۏ\���q���Ăяo�����B��v�ۏ\���q�͎l�\�܁A�Z�̒��N�҂������B���M�͂����Ǝ����̍\�z��b�����B�܂�A�u�k��F�̋����������̐�������_�Ƃ��āA�����q�n���W�I�ɂ������v�Ƃ����Ăł���B�����Ă݂����͋��k��̓��ɂ���h����n�̐V�����v�܁h�ł���B �u�V�������͐V�����v�܂ɐ���v�Ƃ����Â����t������B���M�͂�������ɂ��āA�u�����q�n�悩��A����Ƃ����V�����������肽���B����ɂ͌Â�����S�������K�v������v�����������B��v�ۏ\���q�͖ڂ𐘂��Ă����Ɛ��M�̘b�ɕ��������Ă����B���Ď�l�̕��c�M��������Ȃ��Ƃ����������Ƃ�����B �u���ꂪ�b������ƁA�����͎l�ʂ�̔���������D�|�J���ƃ����J���Ă���ҁA����̘b�̐߁X�ł��������̂�����A���Ԃ��ҁA�r���ŐȂ𗧂ҁA�����Ă���̍A�̂���������l�߂Ă����Ƙb�ɊJ������ҁB�|�J���ƌ����J���Ă���̂́A����̘b�̓��e�ɋV���Ă���҂��B�̂���������肵�Ă���҂́A���Ȃ��̂�������鎖�͂��ׂĂ킩��܂��Ƃ������ۏ��Ȏ҂��B�r���ŐȂ𗧂҂́A����̘b�̒��ɉ����g�Ɋo���������Ă������܂�Ȃ��Ȃ����҂��B�A�̂���������l�߂Ęb�ɊJ�������Ă���҂́A����̘b�����Ƃ����������ᖡ���A�������Ă���҂��B���ꂪ��Ԗ��ɗ��v �����ł���͏�i�̘b���J�����͕K�����̊�������ɁA�A�̂����������悤�ɂ��Ă����B�������ƕ\��C�ɂȂ��āA�b�̓��e����S������Ă��܂�����ł���B (�M�����͂����܂Ől�̐S�ɒʂ��Ă���ꂽ)�Ə\���q�͂��܂��ɐM���h���Ă����B�����獡���ԐM�̎��̏d�含�ɋC�t���A�d�M�̕\������Ȃ������D���M�̍A�̂���������ƌ��l�߂Ă����E���M�̘b���I���ƁA�\���q�͗̂����B �u���b�͂悭�킩��܂����B�ŁA�킽�����̖����́H�v�u�����q�����_�ɂ��āA�����n���т̖k��F�������Ă��炢�����v�u����ł������܂��ȁv�u���ʂ��������Ǝv���B��v�ے��ד��̂��������v�u�������v��v�ۏ\���q�̓j�����Ə����B���A���̏��������Đ��M�́A(���̒j�͂��łɍ�������Ă���)�Ɗ������B�����ŁA�u����Θb���Ă���v�Ƙe�̕��������������B�������r��g��Ŏ˂�悤�Ȏ������\���q�Ɍ����Ă����B�\���q�͂����났�����Ȃ������B �u�ł͐\���グ�܂��v���̎���v�ۏ\���q���b������Ƃ����͎̂��̂悤�Ȃ��̂������B ���D�c�M���E����ƍN�A���R�ɂ���ĕ��c�Ƃ��ł��ꂽ���A�M���̕��c�����͔��ɉߍ����������A�ƍN�̏����͊��傾�����B���Ƃ��A�P���̎�����ɍۂ��Ă��A�M���͂܂�ŏ����̎��ڂŒ@���悤�ȑԓx�����A�l�����B����ɑ��ƍN�͒n�̏�ɐ������A����ɏ����̎�Ɏ�����킹���B���������āA���c�Ƃ̈�b�����͓���ƍN�ɂЂƂ����Ȃ�ʕq���̔O�������Ă���B ���ƍN�́A���c�̈�b�̒������S�\�l��I�сA����������l�g�Ɩ��t���Ď��̂ƂȂ����b�㍑���̊Ǘ��ɂ����点�Ă���B �����̂����l�g��������������q�Ɉڂ��A����ɕ��c�̋��b���{�\�l�̗p���Đl�����ܕS�l�ɑ��₷�B�V�̗p�҂̓�{�\�l�̒��ɂ́A�b�B�X�b�p���قƂ�lj�����B ���V�����Ґ������ܕS�l���ɏ���āA�����n���т�O��I�ɑ{������B�l��ɕ��ݍ��ގ��́A���̂悤�Ȍ|�\�����p����B ���Ƃ��ɕW�I�͕��o�����Y�̗����鑊�B���g�Ȃ̂ł��̖o�łɗ͂�s�����B����ɂ́A�����ꑰ���A����Ƃ̓�������悤�Ȉ�@�s�ׂ�����悤�Ɏd������B �Ƃ����悤�Ȃ��̂ł���B���M�͕��������Ɗ�������킹�Ėڂŗ̂��������B��v�ۏ\���q�̍s���͂�����Ɋ��S��������ł���B���M�͌������B�@ |
|
|
�������q��l���̂͂��܂�
���������Y�|����ǂ��Ă��邤���ɁA�{�����M�͕������_���v�ۏ\���q�Ƒ��k���ĕ��j���ĂяC�������B����́A�u�����q�ɏW�߂��ܕS�l��������ɌܕS�l���₵�A��l�Ƃ��A���̒��ɂ͖k���Ƃ̈�b�������悤�v�Ƃ������Ƃł������B����͓���ƍN�̔��f�������B�ƍN�͐��M�����v�ۏ\���q�╞�����������̊���Ԃ���J�������A�K���������̐��ʂ��v�킵���Ȃ����Ƃ�m��ƁA�u�����ɖ��ʂȔ\�͂���������͍̂T���悤�B�������������������v�ƌ������B����͉ƍN�́A�u��̒n��̈�b�ɑ�����_��v�ł����ē��ӂƂ���Ƃ��낾�B���M���ƍN�̂��̕��j�͂悭�m���Ă�������]�����B �₪�Ĕ����q�ɂ́A���g�D�̌ܕS�l���ɁA�V����5�S�l���������ꂽ�B���̎傽����̂́A���k���Ƃ̈�b�����������B�����ƒ�R���邩�Ǝv�������A�k���Ƃ̈�b�����͊����ɑf���ɎQ�������B��͂�A�ďA�E�̊�т͐[�������̂ł���B�������Đ�l�ɂȂ����g�D�́A�u�����q�������S�v���邢�́A�u�����q��{���O�v�ƌĂꂽ�B�����͉��~��^�����A�}������������B�������͍ō��ܕS�̒m�s�����B�قƂ�ǂ̑��m�͓��S�����������A���̓��S�E�Ƃ͈���āA�����q�ߕӂ̑����ɋ��Z�����B�����ĕ��i�͔_�k�ɓk�������B����͂��̂܂ܑ�v�ۏ\���q�̒�Ăɂ���āA���c�M���̎���ɂ������A�u�R���_�����v�ɂȂ�������̂ł���B�����q��l���S�́A���̌㒩�N�ł̐킢�A�փP���̍���A����ɑ��~�̐w�E�Ă̐w�ɏ]�R����B�܂��A��v�ۏ\���q�̓��ӂƂ���u�鑢��v��u�s�s�Â���v�̎葫�ƂȂ��āA���s�̓����E������̍Č��āA�x�{��̑��z�A�]�ˏ�̏C�z�Ȃǂɏ]�����Ă���B �����̏�̌��z��C�z�̑��w���́A�������Ղ������Ă����̂ŁA�����q��l���S�͂��̎w�����ɓ������B�@ |
|
|
���L�b�n�喼�̓O��I�ȑ��E�̂��߂ɖ����ꑰ���g��
�ƍN�͂��̎����łɁA�u���̂Ȃ������ł���L�b������ł����Ƃ́A�����Ĕ��t�ł͂Ȃ��B�L�b�Ƃ�ł��Ă��A����͎�l�E���̍߂ɂ͖���Ȃ��B���̂��Ƃ́A���ꂪ�V���l�ɂȂ�����ɁA���̂��鐭�����s������ōςށv�Ƃ������_���Ă��s���Ă����B�����������Ȃ�L�b�G���Ɍ��܂�킯�ɂ͂����Ȃ��B�L�b�Ƃ�ł��̂͂���������ɂȂ�B���̑O�ɂ�邱�Ƃ�����B����́A�u�L�b�n�喼�̓O��I�ȑ��E�v�ł���B ����ɂ́A���܍��a�R��ŋސT���Ă���Γc�O����������x��������o���A����ɖd���̕������������邱�Ƃ��K�v���B����ɂ͚�������B�ƍN�̓��̒��͂��邭��Ɖ�]�����B����͂��̎d�|���ɁA�����ꑰ�����p�������ł����B�����ɂ��āA����͖����ꑰ�̗L�p�������݂��݂Ɗ����Ă����B���������Ƃ͂��������{���̔E�т̏p����g��������@���̈ɉ�ҁE�b��҂̊��p�@�́A���̎��̉ƍN�̍l���Ƀs�^���Ɠ��Ă͂܂��Ă����B�@ |
|
|
���ƍN�͏�E���̏�E�A�L�b�Ƃ�P�l�Ƃ��A����Ƃ����l�ɂȂ�\���T����
���̓�A�O�N�̊Ԃɂ�����ƍN�̖d�����͂܂��ɁA�ɉ�l��b�ꖼ�̂����u��䏊�l�͏�E���̏�E���v�Ƃ����{�̂��⊶�Ȃ��������Ă���B��E�Ƃ����͔̂E�Ғ��Ԃɂ����A�u���]�l�v�̂��ƂŁA������𗧂Ă���𒆔E�≺�E�Ɏ��s������Ƃ�������ɂ���E�҂̂��Ƃ��B �ƍN�����̍���E�Ƃ��đ����̒��҂����ɖ������̂��A�u�܂��Ȃ��푈�ɂȂ�Ƃ�����C����藧�Ă�v�Ƃ������Ƃł������B�푈�u���̕s������A���t����Ƃ������Ƃł���B�����Ă���ɁA�u�R�̑m�̕��L���d�ɑ�����߂��A�����t��̐��ł���A���̔w��ɂ͓���Ƃ̂��艟��������Ƃ����\���T���U�点�v�Ɩ������B����́A�L�b�Ƃ�P�l�Ƃ��A����Ƃ����l�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B���������}���𐢊Ԃɗ^���āA���悢��L�b�Ƃ̐�ӂ���낤�Ƃ������Ƃł������B �L�b�Ƃ͂���ɏ�����B�܂�A�u���_�͂����̖������v�Ƃ����F���ɗ������B�����ŁA���鉺�̕Ă�S������ɉ^�э��B�܂��ߗׂ�����ƐH�������B�����ɁA�̖L�b�G�g���ڂ̑喼�����ɗ����𐿂�������ɏo���B����͎�Ƃ��ĖL�b�G���A���N�A��쎡���A�D�c�L�y�֖ϔ��Ȃǂ��A���ꂼ�ꏐ���҂ƂȂ��ė��������B�����ɁA�փ����̍���ʼnƂ�Ђ��ꂽ��A���邢�͐Γc�����R�ɖ����������߂ɐE�������Ă���Q�l���m�����X�ƍ��\�ŏ����������B�������A�L�b�����當������������喼�����̂قƂ�ǂ��A�u�Ƃ�ł��Ȃ��v�Ƃ����C�����ŗv���ɂ͉����Ȃ������B�t�ɁA�u����ȕ���������������m�ꂽ�瓿��Ƃɑ��܂��v�ƈĂ��A�����ƂƂ��ɁA�u���쏫�R�Ƃɑ��ِS�͖ѓ��������܂���v�Ɛ������o���҂����X�Ƒ������B�փ�������œ���R�̐�N�ɗ�������������(�L�����͂��ĖL�b�G���������P�ƌ����������ɂ́A�����̑S�喼�ɁA�u�G�����ɈِS�̂Ȃ����Ƃ��v�Ƃ����Č��������o�����邭�炢�̈����������B�@ |
|
|
�������m�œ~�̐w�̘a�r����i�߂�
�u��i�͂��邩�H�v�Ɩ{�����q�ⓡ���̕����������B�������Ղ���������{�����q�̖����������ƁA�T���߂ɂ���Ȃ��Ƃ������o�����B �u����ɂ͂������퍂�@�l�������ł��Ǝv���܂����v�u����܂��v�����ǂ��̂����B�퍂�@�Ƃ����͎̂����ɍ����̍Ȃ����̂��Ƃ��B�����͂����遍���O�o�����̐^�̏����ŁA���a�̖��ŏG���̍Ȃ��]�^�̎o�ɂȂ�B���ĖL�b�G�g�̊��߂ɂ���āA�ߍ]�̖������ɍ����̍ȂɂȂ����B �����͋M���q�R�Ƃ��Ă��āA�����̐��̒��ɋ@�q�ɑΉ��ł��Ȃ��B���������������B���̂��߂����̓C���C�������B�L�b�ƂɍD���������A�փP���̍���̂Ƃ����ŏ��͐Γc�O���ɖ������傤�Ƃ����B�����͎������B �u����ȂɁA���̐�X�����ʂ��Ȃ��悤�ł͖{���ɗ���Ȃ��Ďd�����Ȃ�܂��ʁB����a�ɂ��������Ȃ����v�Ǝ��B���サ�ĉƍN�ɖ����������B���̂Ƃ��̍����͑�Ï�傾�����B�����Ώ���Ɍ������܂��C�e�̐��܂����ɋ����āA�����͓����o�����Ƃ����B������܂�������A�����̓M���M���܂ŏ��ۂ������B�������㌎��l���ɂ��ɍ~�����Ă��܂����B���A�叟���ƍN�́A�u�悭�M���M���܂ŏ���x���Ă��ꂽ�v�Ƃ����āA�ዷ(���䌧)���l���ɂ����B�₪�č����͎��ʁB�����Ƃ������q���������A�����͖��������ɂȂ�퍂�@�Ə̂��āA�Ȃ������̍�������ɂ����B��͂蒷�o�̗��a�𗊂�ɂ����̂����m��Ȃ��B�����ɂ���A�u�j�͂��߂��B�����m�̕�������b�オ����v�Ɗ������̂����m��Ȃ��B���q�̋��ɒ����͑�������ƍN�ɐb�]���A���܂͍����̐w�ɂ����đ���ւ̍U�����߂�҂��Ă����B �ƍN�́A�u�����a���E�E�E�v�Ƙr��g��ŋ���ɂB�ƍN�̓��̒��ɐl�Ԃ̊W�}���`�����B��{�́A���Ȃ葁�����玩���ɐb�]���x�{��ɂ����Ă܂߂܂߂����d���Ă�������玡���̐����B�����̌Z�͑�쎡���ł���A���̕�͑呠���ǂ��B�呠���ǂ͐��Ǝ��ォ�痄�a�̓��ꂾ�����B ������{�������ɐw��u�����ɒ����̐����B�ꂪ�퍂�@(����)�ł���A�퍂�@�̎o�����a�ɂȂ�B����ɂ�����{�̐����G���̖���P���B��P�̕v�͖L�b�G���ł���A�G���̐���͗��a���B ������̐������a�Ɍ��т��Ă����B�ƍN�����܍l���Ă���̂́A(�ǂ̐����A��Ԙa�r����i�߂�̂ɗL����)�Ƃ������Ƃł���B�����ň����ǂ������B �����ǂ͉ƍN�̋C�������@���Ă����������B �u����Ȃ���A�����瑤����͂킽���������g���������Ă��������܂��傤�B���ܓ����l��������������A�퍂�@�l��������ɂȂ�K�����Ƒ����܂��v�u�킩�����v�܂��ɁA���E����̌ċz���B�ƍN�͖{�����q�Ɠ������Ղ����Ă������B �u����ɂ͐D�c���v�a�ƐM�Y�l��������B���̂���l�ɘb�����āA����̑�\���퍂�@�a�ɂȂ�悤�Ɏd�����Ăق����v�u�������܂�܂����v�{�����q�Ɠ������Ղ��A���E����̌ċz�ŗ̂����B�D�c���v�͕����l���B�M���̖���ł���B�M�Y�͐M���̑��q���B�M�Y�͍ŏ��L�b�G�g����A�u���k��̂������グ��v�Ƃ���ꂽ����Ȃɂ�������B���̂��߂��̍������Ă���������ɐ��̏��̂��v������Ă��܂����B ���v�͂��Ƃ��ƗL�y�ւƏ̂���悤�ȕ����喼������A���܂荇��ȂǂɊS�͂Ȃ������ӂł��Ȃ��B�������Ăĕ�炵�Ă����B�ӔN�̖L�b�G�g�ɏ�����đ�����ŗI�X�ƕ�炵�Ă����B�����炭�A(���}�a�������������������Ă�����A����ɗ]�����y���߂����̂�)�Ǝv���Ă���ɈႢ�Ȃ��B���������Q���������ɂȂ�ƁA�g�̒u���ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă܂��܂�����B���������Ă��̕s����ȐS��˂��āA���̘b������������ΕK�����ɗ����Ă���邾�낤�Ƃ����̂��ƍN�̌v�Z�������B �u������̊�]�ǂ���A�����̑�\���퍂�@�a�ɂȂ����łɁA���̏���ǂ��ɂ���H�v�ƍN���������B�����ǂ��Ԕ�����ꂸ�ɓ������B �u�ǂ��ł��\���܂��ʁB���Ƃ�����ł����Ă��킽�����͏o�|���Ă܂���܂��v�ƍN�͖ق��Ĉ����ǂ̊�������B�����O���������ǂ��A�u��䏊�l�̂��߂ɂ����ɗ����Ƃ��������܂�����A���Ƃ����̐g�ł������̂ĂĐs�����܂��v�Ƃ��������Ƃ�����B�@ |
|
|
���ߒ��ɑS�͂𒍂������ʂɂ͎����������Ȃ�
�u�킵�͔n��V����������B�����������͔n����~��čs���v�ƁA�u�������V���v�̗��z���͂�����f�����B ��A�̎葱�����I�������A�ƍN�͖{�����M�ɂ������B �u�����A����ł���̖����͏I��������v�u����J�l�ł������܂����B���Ƃ͂�����肨�x�݂ɂȂ邱�Ƃ����ł��ȁv�u�������B�킵�����������������v��l�̘V�l�͏����B ���a��(��Z��Z)�N�l���\�l���ɉƍN�͎��ʁB���\�l�ł������B ���̂Ƃ��{�����M�͏}�����Ȃ������B����œ��߂�҂������B�Ƃ��낪���M�͂����������B �u����́A�Ƃ����Ɏ���ł���v�������[�Ƃ��Ă̓��X�𑗂������M�́A���̔N�̘Z�������Ɏ��ʁB���\��������B ���M�ɂ���A�܂��ɉƍN�����l���̓��ɁA���̐��ɂ����邨�̂�͊��S�ɏ��ł��Ă����B���������āA�킴�킴�����K�v�͂Ȃ������B�����̐��Ƃ͂����A���܂����N�b�̒��������Ƃ����Ă����B �����[�����Ƃ́A���s�̕��L���̏������B�u���̐w�v�̌����ɂȂ�Ȃ�����A�ƍN�̈�ʑ�G�c�Ȑ��i�������������̂ŁA���͂��ɔj��邱�Ƃ͂Ȃ������B���݂��u���ƈ��N�N�b�L�y�v�̔�������������ƍ��݂����܂܌��݂��B���N�Ƃ̍����̂Ƃ����������������A�ƍN�ɂ͂������������炩�����������B�܂肩��́A�u����������ߒ��ɂ͑S�g�S��𒍂����A���ʂɑ��Ă͂��܂获���������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��B���������āA�u���̐w�v�ł���ꎟ(�~�̐w)�ɂ����āA�{�ۂ������c���ė���ɂ���Ƃ����a�r����������������Ƃ��ɁA�ƍN�̊�]�̂قƂ�ǂ��R�Ă��s�����Ă����B ���������ĉĂ̐w�́A���̉������ɂ�������߂�����ł����āA���x�͂��ꎩ�炪���w�����Ƃ��āA�U���̐擪�ɗ����Ƃ͂Ȃ������B���ꂱ���A�u�n�����`�������Ă���̂�ق��đ҂v�Ƃ������Ƃł������B�䏊�`�͂��ɗ����Ă��؉��̏E���Ƃ���Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B�E�����̂͗��Ƃ���̓���Ǝ��g�ł������B ���̗�����v���o���āA�L�b�G���Ƃ��̕ꗄ�a�̎�����m������A�ƍN�͈�l�ŃR�g�R�g�Ə����B��C�ɔ�ꂪ�o���B�ƍN�́A����̏G�g�ɍ������B �u�G�g��A�V���Ƃ������̂͂ȁA�傫�Ȏ��������œ������̂ł͂Ȃ��B�l�̏����Ȃ�����肪���̒��������Ƃ�����̂��B�L�b�Ƃ��łт��̂́A���̓����ڊy��ł̂����܂̘������ɂ���̂��B�v���m�������E�E�E�v�����I���ƁA(�ǂ�A�����ł������������Ŕ��������)�ƙꂢ���B�@ |
|
|
���G���͏x�{�@�ւ������]�ˏ���ɉA�����������
�u�킽���͓����ʂ����]�ˏ�u�����ē����Ȑ����]��ł͂��邪�A���ꂪ�オ�����������Ƃ����āA���������s�ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B���܂��������A�̕����⍕�������͈ˑR�Ƃ��č]�ˏ���ɍ����Ă���B�����炻����������������A�̕����ɑΉ����čs�����߂ɂ́A�������������������\���i�������Ƃ��K�v���v�u�����܂ł��킩��Ȃ̂ɁA�Ȃ��x�{��ɂ����A����S�����قȂ����܂����v�u���肪�����������炾�v�u����H�v�u�������v�G���͗̂����B�����͌������B �u�悭�킩��܂��ʁv�u������A�킩��ʂӂ������ȁB�����x�{��ɂ��W�߂ɂȂ��Ă������������A�A�̕����͍��x�͂��܂������������肷��̂��v�u�͂��I�v���x�����{���ɋ����ė����͏G�������Ԃ����B�G���̓j�R���Ə����B�����������B �u�x�{��̘A�������ق��邱�Ƃɂ���āA������x�͋@�ւ͏������B�x�͋@�ւ��������Ƃɂ���āA����͖��{�̐���`���Ƃ�������s����葫�Ƃ͍]�ˏ���ɂ����Ĉ�̉������B���������āA�������ĂɌg�����̂́A���������s���`�����B���̂��Ƃ͍��킹�āA�A�̕����A�����������������������̗p�𑫂��Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ��v�@ |
|
|
���V������
�u�㔒�͖@�c�͂��̗��o�鏴�����҂݂ɂȂ邽�߂ɁA���s�̒����甒���q��V���܂ŋ��s�䏊�̒��ɂ��ĂтɂȂ����B�����Ă��ܒ��ŗ��s���Ă���̂͂ǂ��������̂��A�Ƃ������ɂȂ��Ă��̖{������ꂽ�̂��B�킽�����������B���y�X�ɂ͐l�Ԃ̊�{���y�����ׂċÏk���Ă���B�l�Ԃ̏L�����v���v������B�F���A���܂ɂ͈����쒬�̗V�����������̏�ɌĂ�ŁA���낢��Ȉӌ������Ă��炦�܂����v�u���Ƃ������Ƃ������܂����v�F��̓s�b�N�������B�������ƍN�́A�u�{�C����v�Ƃ������B ���̌�A�F��͉ƍN�ɂ���ꂽ�Ƃ���A�����쒬�̗V�������ɁA�u�a�l�ɗx����݂��Ă����Ă���v�Ƃ������ڂŁA�������ɘA��Ă����B����̕��m�݂͂�ȃs�b�N�������B�V���̒��ɂ́A�u�܂��A���Ƃ�����v�Ɗ����݂ɐ��𓊂���҂������B����������ꂽ�҂͍Q�Ăē������B����Ȍ��i���ƍN�̓j�R�j�R���Ȃ��猩����Ă����B����������͂��̕��@�ŁA�V����������A����鉺�ŕ�炷�l�X�̖{���̎p��m�낤�Ƃ����̂ł���B���ꂪ�����ɖ𗧂Ǝv���Ă������炾�B�����炩��͌����āA���y�X���ߐ[�����̂Ƃ��A���邢�͉��ꂽ���̂Ƃ͍l���Ȃ������B ���������ƍN�̐S��m���āA����̕��m�������䂫�߂�����V�т�T�ނ悤�ɂȂ����B�ނ���t�ɁA�����������ɏo�|���Ă����āA�u������������̖�l�Ƃ��ĉ������Ȃ�������Ȃ��̂��v��m�邱�Ƃ̂��������ɖ𗧂Ă��̂ł���B�ƍN�̗V������͎��ʂ܂ł��̕��j���т����B�@ |
|
|
����ϐ��v���e�L�X�g�ɁA�����𐅂ɂ��Ƃ���
�ƍN���w��ϐ��v�x�̂��Ƃ�m�����̂́A���̂��납�킩��܂��A��������Ƃɂ����āA�u�����̃e�L�X�g�v�ɂ��Ă��܂����B ���̖{�͒����̓��̎���(�Z����Z�l��N)�̑��@�̌��s�������Ƃ������j�Ƃ��L�^�������̂ł��B���e�́A�u�������߂�҂̐S���܂��v�ł��B���̒��ł����@�͂Ƃ��ɁA�u�����̐��_�d���v�u�g�b�v�͂����ɕ����̊Ђ߂��������v�Ƃ����ӂ��̓_�����x�����肩�����Ă��܂��B �L���ȁA�u���͂悭�M���ׁA�܂��悭���������v�Ƃ����̂����@�̂��Ƃł��B���@�́����h�Ƃ����͍̂����̂��Ƃł��B�܂�A�u�����̎x���������Ȃ��ƁA�鉤�����̍���ǂ���v�Ƃ����Ӗ��ł��B ����ƍN���悭���̂��Ƃ��g���܂����B�Ƃ��낪�ƍN�͂��́����h���������h�Ƃ��Ă��܂��B�܂�u�����͎�l���x���邪�A�ꍇ�ɂ���Ă͂��炬��v�Ƃ����Ӗ��ɂ��Ă���̂ł��B�q�ǂ��̂Ƃ������J�����ƍN�́A�S�̈ꕔ�Ɂ������s�M�h�̋C�������������̂ł��傤�B �������c���ܔN�Ƃ����A�܂��փP������̎��P�����O�ł��B���̂��낷�łɉƍN�ɁA�u�V���ւ̎u�v(���邢�͖�])���������Ƃ����܂��B�@ |
|
|
����ϐ��v�����ǁA�Ќ��͈�ԑ������ނ��������A�l�Ԃɂ͕K����蕿������
���͂悭�M���ׂ܂��悭�������� ���Ƃ��Ƃ͒����́w��ϐ��v�x�Ƃ����Â��{�̒��ŁA���̑��@�Ƃ����c��̂��������Ƃł��B���@�́����������l���̐��_���ƍl���܂����B���̖{�͉ƍN�̈��Ǐ��ł��B �ł��ƍN�́����������������ɂ��������܂����B���x�������ɂ��炬��ꂽ���Ƃ�����������ł��B ���Ќ��͈�ԑ������ނ������� �u��l�������߂邱�Ƃ́A���Ŏ蕿�𗧂Ă�����ނ��������v�Ƃ����Ӗ��ł��B���ɒɂ����Ƃ̓g�b�v������������܂��A�����������܂���B���ǃg�b�v�͗��̉��l�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�������둽����Ƃ̕s�ˎ����A�����蕷�����肷�邽�тɉƍN�̂��̂��Ƃ��v�������܂��B ���l�Ԃɂ͕K����蕿������ ��蕿�Ƃ����̂͒����₷���ꂽ�\�͂̂��Ƃł��B�ƍN�͂����u���̒��Ɋ��S�Ȑl�ԂȂǂ��Ȃ��v�ƁA�l�Ԃ̕s���S��`�������Ă��܂����B�ł����瓿�얋�{�̃|�X�g�͂��ׂĕ������ł��B ���������ق�ڂ��҂͕����ŁA���q���ق�ڂ��̂͊��q�� ���Ƃ͌����ɂ���Ăق�ڂ���܂����B���̌������O��łق�т܂����B�ƍN�͂��̏��A�u�ŖS�̌����͑�����̗͂ɂ����̂ł͂Ȃ��A�����ɂ������v�ƕ��͂��܂��B ���܂ł����ΎВ���Ј����u�����̉�Ђ͗D�ǂň��肵�Ă���v�ȂǂƎv���A��@�ӎ��������Ȃ���A���łɉƍN�̂�������������̕����͂��܂��Ă���A�Ƃ����Ă����ł��傤�B�@ |
|
|
���C�k�̌Q��𑀂�^�k�L���₶
����ƍN�̐l�Â����̓����́A�ꌾ�ł����u���f�x�z�v�ɂ���B�ƍN�́A�˂ɁA�u�ЂƂ�̐l�Ԃ����ׂĂ̔\�͂������Ă���Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��v�ƁA�l�Ԃ̔\�͂̊�������ے肵�Ă����B �����炩�ꂪ���{���J�����Ƃ��A���̊����͂��ׂāu�����C���v�ł������B�ƍN�ɂ���A�u�ЂƂ�̐l�Ԃ��A���ׂĂ̔\�͂�����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B���R���ׂ�����B���̌��ׂ𑼐l���₤�B�܂�A���{�̉^�c�́A�����̔\�͂̑��ݕ⊮�ɂ���Ă����Ȃ���v�ƍ����Ă����B ���������������銲���̒��ɂ́A�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B����̔\�͂͊��S���v�Ǝv�����̂��������ɂ������Ȃ��B�������ƍN�͂��������l�Ԃɑ��Ă����A�u���ʂڂ��ȁB�����ƌ����ɐ�����v�Ɩ�����B �ƍN�́A�u�ЂƂ�̐l�Ԃ��\�͂̂��ׂĂ����˔����Ă��邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��v�Ƃ����l�����́A�����������čl����A���M�����Ղ�Ȑl�Ԃɑ��ē������␅�����Ԃ���悤�Ȃ��₪�点�ł�������������Ȃ��B�����A�ƍN�̗͂͑傫���B�����ł́A�u����͊��S���v�Ǝv���l�Ԃ��A���ǂ͂��́u�������C�����v�ɊÂ�������Ȃ������B�����Ă݂�A���S���Ǝv���Ă���\�͂̈ꕔ���A�ƍN���u�s���S���v�Ɣ��肷��A���������͎����ł������v���悤�Ɏ��ȗ}����������ꂽ�̂ł���B���̎��ȗ}����������ꂽ�����͓��R�A���́u�s���S�R�āv���N�����B�������A���̕s���S�R�ĕ����͌����āA�u�ƍN�ւ̕s����s���v�Ƃ����`�ɂ͂Ȃ炫�������B �ނ���A�u����̔\�͂����S�Ȃ��Ƃ��A�ƍN�l�ɔF�߂Ă��炨���v�Ƃ����C�����ɂȂ�B���̂ւA�ƍN�����l�Â����̖��l"�ƌĂ��䂦��Ȃ̂��B����A�Ɛb���ׂĂɁu�h�c�O���[�X�v��������B�h�c�O���[�X�ł́A���̕@��ɃG�T���Ԃ牺���āA�����ɑ��点��B�����G�T�ɂ�������Ƃ͉i���ɂ��肦�Ȃ��B�������A�C�k�͏��m�ő���B����Ɛb�c�͂܂��ɂ��������C�k�̌Q��ł������B���ꂪ�ƍN�́A�u�^�k�L���₶�v�ƌĂꂽ�^�̗��R���낤�B �܂��ƍN�́A�u�f�[�e�B�[(����)�̕����v�́A�����Ď������w����Ȃ������B�����ɉ�������B������A�����̂ق����������炷����Ń_�[�e�B�[�ȕ�����w�����悤�Ȏd�������������B���̈�Ԃ����Ⴊ�A�փP�������̐Γc�O���̈������B �փP���̍���Ŕs�ꂽ�Γc�O���́A�u���_�ł���ߍ](���ꌧ)���a�R��ɖ߂��āA�ċN���͂��낤�v�ƍl�A���A��ꂩ�痣�E�����B�ӂ��̑叫�Ȃ�A�킢�ɔs�ꂽ�̂����猉�������ɂ���Ƃ��낾���A�O���͂����͂��Ȃ��B �������A�r���ł��Ă̖��F�ł������c���g���ɂ���ĕ߂炦���A�ƍN�̖{�w�ɘA�s���ꂽ�B���R�A�O���͌���ɔ����Ă����B�Ƃ��낪�ƍN�́A�e�̎҂Ɂu��������v�Ɩ������B���̑ԓx�ɂ͖��炩�ɁA�u���Ƃ��s���Ƃ͂����A�叫����҂�����ɔ���グ��Ƃ͉����Ƃ��v�Ƃ������m�̖ʖڂ��d��F���������B�e�̎҂�����ĂĎO���̓���������B�ƍN�͍��~�̒��ɂ������A���ɓ˂��o���ꂽ�O���ɁA�u��ւ�����Ȃ����v�ƌ������B�O���͂��������B�ƍN�͂��݂��݂ƍ������B �u����Ƃ����̂́A���^�����邩�Ȃ����ɂ���Ďx�z�����B�c�O�Ȃ���A���ʂ��ɂ͕��^���Ȃ������B�����������ʂɂȂ����̂͐��Ɏc�O���v�ƍ���ɂ���������B�܂��̎҂���݂�A(�ƍN�́A�����i�D������)�Ɗ�����B�������ƍN�͐^�ʖڂɂ��������ԓx���Ƃ����B�����āA�O���̐g����{�������ɓn�����B �{�������́A�ƍN�̈�������X�����v���Ă�������A�Ăэ��菬��ɔ���グ�āA��������O�Ƀ��V����~���A�ʍs�l�̂��ׂĂ��O�����݂���悤�ɎN�����B����ƍN�ɏ]���������̖L�b���̕������A���X�ƒʉ߂���B�n�̏ォ��O���������������B�������O���́A�u�����܂���������������A�����������ʂɂȂ����̂��B�������G���������o�n�Ȃ����Ă�����A����͋t�ɂȂ��Ă����͂������v�Ƃ̂̂���Ԃ����B ���̃P�[�X�ł����A�ƍN�́A�u�����i�D�����v�ŁA���̂Ƃ���͎����̎d���ɂ��邪�A�O�����s�҂��A�����V���ɂ��炵�Ēp����������Ƃ����_�[�e�B�[�ȕ����͖{�������ɂ�点�Ă���B�������{�������́A����ȉƍN�����邢�Ƃ͎v��Ȃ��B�u���ꂪ����̖�ڂ��v�Ɗ�����āA�ނ��낻�ꂪ�ƍN�ւ̒����S�̔�U�ł��邩�̂��Ƃ��ӂ�܂��B���o���ƍN�ւ̕s���s���͂Ȃ��B�Ȃ��ƍN�͉Ɛb���������������C�ɂ�����̂��A���ɕs�v�c���B�@ |
|
|
�������̍ˊo���������� �ƍN��"���U�ő�̊�@"�ƌĂ��悤�ȏ�ʂɉ��x���������Ă���B�Ȃ��ł��A�V���\�N�Z������A���F�̐D�c�M�������q���G�ɖ{�\���ŎE���ꂽ�Ƃ��������Ƃ��댯�������B����͂킸������̋�����ď���֗��s�����������A�L���Ȉɉ�z�������s���A�����炪�牪���ɓ����A�����B���̂Ƃ��̋��̒��Ɉ�ɒ�����������Ă���B �b��̕��c���́A���̑O�ɖŖS���Ă����B�҂��\���Ă����悤�ɁA�����c�̂Ɏ���o�����̂��ƍN�Ə��c���̖k�����ł���B ���҂͏Փ˂��A������P���ɂȂ����B�~��O�ɂ��ė��҂́A�u�a�r���悤�v�ƕ��݊�����B���ꂪ�A�V���\�N�\����\����̂��Ƃł���B�a�r�̑S����ւƂ��āA�k�𑤂���͈��̖k�����K�A���������͈�ɒ������I�ꂽ�B���̂Ƃ��A�����͎㊥��\��������B �������ɉƍN�̏h��������������������B �u����ȐV�Q�̎ᑢ�ɁA��Ȍ��̎g�҂𖽂��Ă����̂��낤���v�����̔\�͂��^���������ł͂Ȃ��A�V�Q�҂ɑ���Î�̎��i�Ƒ����̔O���������B�Ƃ��낪�����͗��h�ɂ��̖����ʂ������B �ƍN�͓V���́��l�Â����̖��l���ł���B����͂悭����Ȃ��Ƃ������Ă���B �u�ЂƂ�̐l�ԂɁA���ׂĂ̍˔\��������Ă���͂����Ȃ��B����Ȑl�Ԃ͂��̐��ɂ��Ȃ��B���������āA���ꂼ��̒�����L�������Z����₤���Ƃ��K�v���v����́A�u�l�Ԃ͂��ׂČ��ו��������邩��A�����₢�����v�Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��B�ƍN�̕����Ǘ��̊�{�́����f�x�z���ł���B���������̑O��Ƃ��ĉƍN�́A�u���̐l�Ԃɂ́A�ǂ���������������A�����������ǂ̂悤�Ɏ�����⍲���Ă���邩�v�Ƃ����A���̐l�Ԃ̒���(�\��)��������ƌ��ɂ߂Ă���B �������\�܍ł͂��߂Ă������Ƃ�����A�ƍN�͒����̃I���̒��ɁA�u���E�����łȂ��A�����̍˒m�������ɂ���v�ƌ������Ă����B �k�����ƍu�a�������ƍN�́A�����c�̂̂قƂ�ǂ��x�z���邱�ƂɂȂ����B���̂Ƃ��ƍN�́A�u���c�Ƃ̈�b�����́A�₽���˂��Ƃ������ނ���A�������������ق��������v�ƍl���āA��ʂɋ����c�Ɛb�c���Čٗp�����B���c�ƂŗE����y���Ă����A�y���A���A�R���A����Ȃǂ̏��O���R�c�ɑg�ݍ��̂ł���B �l��g�ݍ������ł͂Ȃ��A���c�Ƃł���炪�g���Ă�����������荞�B�Ȃ���"���c�̐Ԕ���"���������B ���c�̐Ԕ����Ƃ����̂́A��Ƃ��ĎR�����i�̌Z�A�ѕx�������p���Ă��������̂��Ƃł���B�ѕx���́A�����S�����Ԃ��b�m�𒅁A�w���A�n�̈ƁA�ڂɂ�����܂őS���Ԃ��h���Ă����B�ѕx�����Ȃ����ƁA�����吭���Ђ������B���̕������O�ʂɗ����āA�����������Ȃ���˓����Ă���ƁA����͎v�킸�Ђ�ށB�u���c�̐Ԕ����v�͂���قǗL���������B �ƍN�͒����ɁA�u���܂��̌R�c�́A�����O���p�����A�Ȍ������Ԃ�����v�Ɩ������B�����͏��m���A�ѕx���̐Ԕ������A��ɌR�c�Ɏ�荞�B�Ȍ�A�����̌R�c�́A�u��ɂ̐Ԕ��A���v�Ƃ��Ė������߂�B �ƍN�͂܂������ɁA�u����̂Ƃ��́A�˂Ɉ�ɐ�����w������v�Ɩ������̂ŁA��ɂ̐Ԕ����͂��̂܂܁A�u����R�c�̐�w�v�̖������ʂ������ƂɂȂ����B�@ |
|
|
�������ɒ����S�����������j�����
��v�ے��ׂ͎�Ԃ�ʼnƍN�̂Ƃ���ɂ������B�����āA�u�����������Ĉ��S���Ă���܂�����A�V��̂�͂܂��ǂ����ւ����Ă��܂��܂����B�����Ɍ�������˂܂��������ɔ����ł��܂���ł����B�����߂��������v�ƌ������B�N�i�ƌ�荇�������e�ɂ��Ă͂Ђƌ��������Ȃ����B �ƍN�́A�u�������v�Ƃ��ނ��A�u���������̒��b���������B���ꂪ���������v�ƌ��ɂ������ɂԂ₢���B���̉ƍN�̎p���v�ے��ׂ͂����Ƃ݂߂Ă����B ���ׂ̋��̒��ł́A�N�i�́A�u�����������߂�A��l�̉ƍN�����߂���Ƃ������ƂɂȂ�B�����V���ɂ��炷���ƂȂǂƂ��Ă��ł��Ȃ��v�ƌ��������̌��t���A������ɉQ�������Ă����B ��v�ے��ׂɓ���ꂽ�V��N�i�́A�c���\��(��Z��O)�N�Ɏ��B���\�Z�ł������B �u����قǐl�̎g�����̂��܂��l�Ԃ͂��Ȃ��v�Ƃ��ʂڂ�Ă����ƍN���A�V��N�i�̂悤�ɃV���v���Ő����ɒ����S�����������j�́A�{�S�����Ɍ��������Ƃ��ł��Ȃ������̂ł���B ����������͓V��N�i�̃P�[�X�����ł͂Ȃ��B�����I�Ȓ����S�����O�͕��m�́A�N�i�̂ق��ɂ����������B�������A���Ă��Ă����������m�͂��܂藧�g�o���͂��Ă��Ȃ��B�ƍN�̐S�̒��ɂ́A�����������m�����Ƃ��A�ǂ����ނ���悤�ȕ��G�ȐS�����������̂��낤�B�v�@ |
|
|
���{�����M / �ƍN�ւ̈��l����g�Ɏ~�߂�
����قǑ�v�ەF���q��́A�{�����M�E�������q��ł����B�����炱�̌��e�̍ŏ��ɏ������A���M���A�u�ƍN���ɓ��������鈫�]�≘���̂��ׂĂ��A�������ٌc�̂悤�Ɏ~�߂悤�v�ƍl����"�Ԃ�"�́A��v�ەF���q��ɑ�\����鑤����̂����������l�ł������B���M�͂���𐳖ʂ���~�߂��̂ł���B �������A�F���q��̓�������ԂĂ̑����́A�{���Ȃ�ƍN�ɓ���������ׂ����̂ł������B�܂�ƍN�̐������A�������ς��ɂ�Ăǂ�ǂ�ώ����Ă��������炾�B�����Ȃ�ƁA�ƍN�������̉Ɛb�c�ɑ��Ď��A�u���ꂩ��̊��҂����Ɛb���v�Ƃ����̂��ǂ�ǂ�ς��B �ƍN�͐l���Ǘ��̖��l����������A������Ƃ����Ă��ꂪ�I���ɂ݂���悤�Ȑ�̂ĕ��͂��Ȃ��B�{�l���A�u�m��Ȃ������ɐ�̂Ă��Ă����v�A���邢�́u�C�����Ȃ������ɑ��ۑ��ɂ���Ă����v�ƁA����C�����悤�Ȃ������Ƃ�B ����������͉ƍN�ЂƂ肪������킯�ł͂Ȃ��A���R�e�ɐ��i��������B�{�����M���ϋɓI�ɂ��̐��i���������ďo���Ɛb�������B ��v�ەF���q�傪�����{�����M�̓��������㕗�ɂ����A�u�o�c���o�ɂ�����A�Z���̏p�ɂ��I�݂ł������v�Ƃ������ƂɂȂ�B ���������̓I�ɂ́A�u���m�͐H��˂Ǎ��k�}�v�Ƃ����C�����܂��܂��݂Ȃ����Ă������ゾ����A�\���o������ɂ����ʂ����悤�ȕ��m�͓��R���ɂ����B �������A���M�ɂ���A�u�ƍN���́A�Ȃɂ������̍��̕��a��������Ă�����B����ȂƂ��ɂ��܂ł��A�₠�₠�������҂͉��ɂ������Ȃǂƍ����̂�߂������グ�Â�����A���̍���ł͂���Ȏ蕿�𗧂Ă��ȂǂƁA�v���o�b�ɂЂ����Ă���悤�ȕ��m�ł͍���B����́A�ǂݏ����\���o������������ł��镐�m�łȂ���A�ƂĂ��ƍN���̗��O����{�Ŏ��s���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƁA�}�N���Ȑ������O�̎��s�҂Ƃ��Ă̎��o�������Ă����B ���̐��M�̂悤�Ȏ��ȕϊv�������Ȃ��镐�m�������A�ƍN�̊��҂���Ɛb�c�ł������B���ꂪ��v�ەF���q��ɂ͗����ł��Ȃ������B��������炸�A�u����͏��w�̓P���R�łǂ��̂����́v�Ȃǂƌ����Ă���B ����͂��܂��ɁA�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����R��������Â�ŁA�W�܂��Ă͎�������ŁA�u�����܂Ƃ���Ƃ͓����̍��v�ȂǂƁA�R�̂��̂��Ă��肵���̒lj��ɂЂ���̂Ɠ������Ƃł���B �{�����M�ɂ́A���������Z���`�����^���Y���͂Ȃ��B�h���C�Ɋ����B���M���g���܂荇��͓��ӂł͂Ȃ������B�����𗧂Ă����т��Ȃ��B ���������M�́A�Ⴂ����̂悤�ɁA�u����(�푈)�Ȃ�Ēm��Ȃ���v�Ǝ��������̎Ⴓ���ւ�悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ������B�����h�̌��т�A�S��͂悭�������Ă����B���A�u���ꂩ��́A���������lj������ł͂���Ă����Ȃ��v�Ƃ����挩���������Ă����B�@ |
|
|
���q���d / �x�{����s�𖽂���ꂽ���ɍȂɑ��k
�����ŏ��d�́A�u���傤�A�a(�ƍN�̂���)����x�{����s�𖽂���ꂽ�B����������̔\�͂�����C������A���ސ\���グ���B���A�����ĂƂ������b�ł���B�����ŁA����͈ꉞ�Ɠ��Ƒ��k�������Ă��������܂��Ƃ����Ė߂��Ă����̂��B���܂��͂ǂ��v���H�v�Ƃ������B �Ȃ́A�u�ƒ���̂��Ƃł�����A�킽�����ɂ����k�Ƃ������Ƃ�����ł��傤���A�����̂��Ƃ��A�������a���܂��璼�X�ɂ������������b���A�Ȃ�ł킽�����ɂ����k�Ȃ���K�v������܂��傤���B����ڂ��܂邩�܂�Ȃ����́A���Ȃ����܂̂��S�ЂƂł������܂��B���̂悤�Ȃ��o���ɁA�Ȃ�ł킽�������Ƃ₩���\�����Ƃ�����܂��傤���B�ǂ������Ȃ��̂��ꑶ�ł����߂��������v�Ɠ������B �ꏟ�ȑΉ��������B�����炭�Ȃ��A�v�̕\��̕ω����݂āA(���܂���)�ƁA�����̏o�������ӂ�܂��Ȃ����ɂ������Ȃ��B���d�͂��̍Ȃ��Î����Ă����������B �u����B�K�����������ł͂Ȃ��B�x�{����s�̂���ڂ��܂邩�܂�Ȃ����́A���܂��̐S�ЂƂɂ���B�ނ��������s�ȂǂƂ��������߂āA�g�������Ƃ�łڂ����҂������Ԃ�Ƒ����B�����̍Г�̌����̑����͉Ɠ��̏�������͂��܂��Ă���B���Ԃɂ́A�ٔ���L���ɂ��Ă��炢�������߂ɁA��s�ł͂Ȃ����̉Ƒ��Ƀ��C��������A���낢��Ȃ��Ƃ𗊂݂ɂ���҂��₦�Ȃ��B�e�ߎ҂́A���̂���������������������肷��ƐS���h�炮�B�����āA��l�ɗ]�v�ȍ����o��������B����͂��������߂���Ƃ������Ȃ��B ���������āA�����x������s�E���������Ȃ�A���܂��͂܂��܂��g��T��ŁA�o�����邱�ƂȂ��A�܂����������������Ԉ���Ă��邩��������Ƃ킫�܂��A����̐g�ӂɂǂ�Ȃ��Ƃ��N���낤�Ƃ��A�����o�����Ƃ�����Ȃ��Ƃ������S�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�ł��邩�ǂ��������Ȃ̂��B�ł��邩�H�����ł���Ȃ�A����͂��̖�ڂ�������v �Ȃ����ł͂Ȃ��B�����ƕv�̌������Ƃ������Ă����B�₪�Ċ���グ�Ă����������B �u�������Ƃ��Ȃ����t�ł������܂��B�킽�����͐_���ɐ����Ă��܂̂��Ȃ��̂����t�����܂��v���d�̓j�b�R�������B �u����ł͂����Ă���B�a�͂��҂����B������x��ɖ߂낤�v�ƌ����āA�畞�ɒ��ւ��ďo�Ă������Ƃ����B�Ȃ���납��݂�ƁA�т̍����悶��Ă����B�����ōȂ͂Ȃɂ��Ȃ��A�u���Ȃ��A�т̍����悶��Ă���܂���v�ƌ����Ď��Y���Ē������Ƃ����B ����ƁA���d�͌����������ł��̎��U��͂炢�A���낵���`���ōȂ�U��Ԃ����B �u���ܐ\��������ł͂Ȃ����B����̐g�ɂǂ�ȕω����N���낤�ƁA�������������o���͂����Ȃ��ƌ��������肾���B���̐�����Y���悤�ł́A�ƂĂ����̂����͋܂��B����͎��ނ���v�ƌ����ė畞��E���ɂ��������B �Ȃ͂��ǂ낢���B�u�\�������܂���ł����B���������������Ƃ������j��悤�ł́A���������Ƃ���ł������܂��B�ǂ����A���������������B���ꂩ��͓�x�Ƃ��̂悤�Ȃ��Ƃ͂������܂���v�Ɨ܂Ȃ���Ɏӂ����B ���d�͂悤�₭�@�����A�u���̌��t��Y���ȁv�ƌ����ď�֖߂��Ă������B�@ |
|
|
���q���d / �N������J�߂��閼���i��
�@�x�̎�|�́u�V�c�ƌ��Ƃ́A���ア���������{�̐����Ɋ֗^���Ȃ��B�����܂ł��A���{�̍��������̕ێ��Ɛ_���ɐ�O����v�Ƃ������Ƃł���B ���d�́A���N�̖���Ƃ��Ă��̂��Ƃ��c���⏔���Ƃɍ������B�����āA�u�����F�̂����A������Ă������������v�ƌ����āA�u���̖@�x�Ɉًc�Ȃ��v��\�����鏐�������������B �������A����������҂������B�������A���剻��������ƍN�̌R���͂̑O�ɂ́A���s����������Ȃ�ɂȂ�ق��͂Ȃ������B ���̖@�x���ł����ƁA���d�̐E���ɂ́A�u���s����W�҂��A���̖@�x������Ă��邩�ǂ����Ď�����v�Ƃ������Ƃ������B�����Ă݂�A�u���얋�{�̋��s�x�В��Ƃ��āA�V�c�Ȃ�тɌ��Ƃ̓������݂܂���v�Ƃ������������̂��B ���d�́A���������Ȓj������A����ɑ��Ă��ʂɈ��ӂ������Ă����킯�ł͂Ȃ��B�P���ɁA�u���쐭�������ׂ̏�ɂ������߂ɂ́A���ɐ������͂������݂��c���Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��v�Ƃ������z���炻�������܂łł������B �ƍN�ɂƂ��Ă��̏��d�̑��݂͂��肪���������B�܂�A�������玩���������ׂ��ᔻ����̂ԂĂ��A���d�����s�ɏ�荞��ł����ē��X�Ǝ���~�߂Ă��ꂽ����ł���B�����Ă݂�Ώ��d�́A�u�Ռ��ɓ����ČՎ����v���݂ł������B ���d�͂��̌��\�N�ɂ킽���ċ��s���i����߂�B�₪�āA�u�q�l�͖����i�ゾ�v�Ƃ�����悤�ɂȂ�B����́A��Ƃ��ċ��s�s������オ�����������A���ꂾ���ł͂Ȃ������B������ł��A�V�c����Ƃ��A�u�q�͂���ςȕ��m���v�ƕ]�����͂��߂Ă����B�܂�q���d�́A�u�N������J�߂��閼���i��v�Ƃ�����������ɂ����̂ł���B ����ɂ͏��d�̂Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʎ�r�Ǝ��т���^���Ă���B�@ |
|
|
���V�C / ���q�b�u���ƈ��N�N�b�L�y�v
�u��m�����������v���悷�B���̖����͂����ƒZ���A�v�_�������q�ׂ��낵�����Ǝv���܂��v�u�������A������Ă̖��m���؍����������ɂȂ��������B�]�v�Ȓ����͂��܂��v���������Ȃ�����ƍN�͕��͂̍Ō�̕��ɂ����Ǝ����𒍂��ł���B�V�C�ɂ͉ƍN���ǂ����C�ɂ��Ă���̂��悭�킩��B�Ƃ����͕̂Ћˊ��������̕��Ă������Ă����Ƃ��A�V�C���������ē��ꂳ�������������������邩�炾�B�Ō�́A�u���ƈ��N�A�l�C�ɉ����{���A���ɖF��`�ӁB�N�b�L�y�v�Ƃ����\�Z����(�����͊����Ȃ̂�)�͓V�C�����ꂳ�������̂Ȃ̂��B�V�C�ɂ���A�u�S�̂ɁA������傪�������Ĉ�ۂ������v�Ǝv��������ł���B���������p���`���������Ȃ���Αʖڂ��Ɣ��f�����B�����Ŏv�������܂܍��ƈ��N�ȉ��̏\�Z��������ꂳ�����̂����A�Ћˊ����ɓn�������ƓV�C�̓��ɑM�����̂��������B����́A(���̏\�Z�����́A�������ɂȂ�)�Ƃ����\���ł������B���̎���������܂����B�ƍN�́A���͂��l�ɕԂ����B�����āA�u���̕��Ă��A�G���a�̕��͏��ɖ��Ƃ��Ē��荞�̂��ȁv�ƔO���������B��l�̑��͗̂����B�ƍN�͉������Ă悢�Ƃ������}�������B�����肩���ēV�C���A�u��䏊�l�A������Ƃ�낵�イ�������܂����v�Ƃ������B�ƍN�́A�u�ǂ����v�Ɨ̂����B�������������B�V�C�Ɛ��`�͂����A�ꗧ���čs�����A�܂��z���W�߂đ��k���Ă��邩��A�V�C�������c��Ƃ������Ƃ͂�����ƈӊO���������炾�B�Փ`���������Ƃ��������̂��낤���A�L���֏o�����ɂ���ƓV�C��U��Ԃ��Ĕ������B�������V�C�͂����܂ł��c��p���������Ă����̂Ő��`�͋������B �u�Ȃɂ��v�ƍN�������������B�V�C�͎����Ă��������̕��Ă�������x�ƍN�Ɏ����A�u����\���A���̏\�Z�����͂��ꂪ���̍ˊo�ɂ���Đ��ؓa�ɐi���������̂ł������܂��v�u�ق��A����Ȃ��Ƃ������̂��v�ƍN�͏�ڂÂ����ɓV�C�������B�V�C�͗̂����B�ƍN�͓V�C���������������ēǂ����B�����������͉ƍN���g���������������������ӏ����B���ɁA�u���ƈ��N�N�b�L�y�v�̔������͋C�ɂȂ�B�N�����Ă��A�u����ƍN�̖��f���A�L�b�Ƃ��h����v�Ɠǂ߂�B�ƍN�͕��ꂽ�B����͓V�C�̈��m�b�ɑ��Ăł����������A���������`���������Ă���V�C�̓x���ɂ��������̂ł���B�ƍN�͂ɂ��Ə����B�����āA�u��V���Ȃ��Ȃ��̒m�b�҂��ȁv�Ƃ������B�V�C�́A�u������A���̉ӏ��������Ė��Ƃ������܂��傤�v�����������B�ƍN�́A�u���ށB�������A�킵�͒m��ʂ�v�����������B�V�C�͂ɂ���Ə����B �u�������ł������܂��B���Ƃ����Ƃ����ǂ��A���̓V�C��������q���Ă���܂��̂Łv�����������B�ƍN�͗̂����B�����āA�u�����߂�ꂽ�����悢�B���`�a�����J��ƈ���v�u�͂��v�ƍN�̌��t�ɓV�C�����X�ɗ����オ�����B�������V�C�͐S�̒��ŁA(����ŁA���`�a������O�ɏo��)�Ǝ��Ȃ̗���̗D�ʊm�����艞���Ƃ��Ċ������B����͎����̏����Ƃ��Đ��ɑ}���������u���ƈ��N�N�b�L�y�v�̔������́A�K������������N�����Ƃ����\��������������ł���B��������m�œV�C�͉ƍN�ɕ����̂��B �{���������A�ƍN�̖������������Ɉ����A�L�b�Ƃ��h����ȂǂƂ����l�����ɂ������{�l�������Ȃ̂ɁA�V�C�͂���ɓq���Ă����B���ꂪ����ƂȂ�A�L�b�Ƃɑ�����z���̌����ɂł��Ȃ�A�ƍN�͂��ꂪ���Ƃ��Ƃ͓V�C���l�������ƂȂǂƂ������Ƃ͖��ɂ��Ȃ��B�t�ɖJ�߂Ă���邾�낤�B���������ڎZ���V�C�ɂ͂������B�������L��������Ȃ���V�C�́A(����ɂ��Ă��A�킵�͒m��ʂ�Ƌ������䏊�l���A�Ȃ��Ȃ��̒K�a�ł���������)�ƂЂƂ�ق������B�����āA(���Ƃ��Əx�{��͂��������ꏊ�Ȃ̂�)�Ɖ��߂Ďv�����B�����ɂ͈��m�b���i��o���A�����Q�Ƃ��ďW�߂��Ă���B�@ |
|
|
���ї��R / �u���ƈ��N�v�Ɓu�N�b�L�y�v�ɃC�`������
���̒���ɁA��̕��L���̏����ɃC�`��������������B�C�`�������̘_�����l���o�����̂͋��n�@���`�Ɨї��R�ł���B�����̂Ȃ��Ɂu���ƈ��N�v�Ɓu�N�b�L�y�v�Ƃ������������u���ƈ��N�v�Ƃ����̂́A�ƍN�̖����Y�^�Y�^�ɐ荏���̂��v�Ƃ����A�N�b�L�y�ɂ��ẮA�u�L�b�Ƃ��N�Ƃ��Ċy�������A�Ƃ����Ӗ����v�ƌ������B ����Ȃ������́A�{���Ȃ�ʗp���Ȃ��B�������A�����ƍN�̎���ɂ����V�C�␒�`�����w�m�����R�̐����x�����A���䍂�ɂȂ��ĖL�b�Ƃ��U�������B �L�b�Ƃ͘T�������B�u�����Ă̂ق��̌���������v�ƒ�R�������A�ƍN���͋����Ȃ������B���������L�b�Ƃ͑ԓx���d�������A����ɕ����W�߂͂��߂��B�������āA���~�̐w���N���A���̌�̉Ă̐w�ɂ���ĖL�b�Ƃ͖ŖS����B���̂����������������̂͗ї��R�ł���B���̂��߂ɂ���́A�u�Ȋw�����v�̓k�ƌ㐢�ɉ������c�����B �������]�ˎ����{�Z�\�ܔN�ԁA����̏������h�q�w�́A���얋�{�́u���w�v�Ƃ��Ĉʒu�Â����A����̎��m�͂₪�āA�u���얋�{�̊�����w�v�ɏ��i����B �����܂ł̑ҋ����A���R����悤�ɂȂ����̂́A�퍑�̎v�z�ł���u�N�A�N���炴��A�b�A�b���炸�v�Ƃ����v�z���A�u�N�A�N���炸�Ƃ��A�b�A�b����v�Ƃ������������h�̐��_�ɕρA���A���{�́W���m�ɐA���������Ƃɂ��B���̈Ӗ��ł��A���R�́u�Ȋw�����v�̓k�Ƃ����Ďd�����Ȃ���������Ȃ��B���{�̕��m�̊�{�I�l���₻�̎�̐��E���R�E��������傫���D�����������ł���B�@ |
|
|
���y�䗘�� / ���������͎��߂��G�s�\�[�h
�G���͗������ĂB�u�߂���A�֗߂ɂ�������炸�]�ˏ���ʼn������B����݂���҂�����Ƃ������B�����܂�v�����́A�u�������݂ɑ��A�ꋓ�Ɏ����܂�����т������邱�Ƃ͂ǂ����v�Ǝv�������A�G�������܂�ɂ����������������Ȃ̂ŁA�u�������܂�܂����v�Ƃ����V�����Ă��̏���������B �G���͗�����M�p���Ă��Ȃ������B�����̔����ɁA������Ƌ^�킵����C������������ł���B����͐��l�̕��S���ĂB�����āA�u���܂������ɁA����ʼn����̉B����݂����Ă���s�͂��ȘA���̔����𖽂���B���������Ƃ��́A�������ɂ킽���ɕ�v����v�ƁA����u�������t�v�̂悤�Ȗ���V�݂����̂ł���B ���̖ڕt����������܂�������ʁA�u����̓����ݏꂪ�A�����̉B����݂�����A���̏W�܂�ꏊ�ɂȂ��Ă���v���Ƃ��킩�����B�ڕt�͂��̂��Ƃ��G���ɕ����B �G���͗������Ă�ŁA�������B�u���������\���������B�ق�Ƃ����ǂ����m���߂�B�����ق�Ƃ��������ꍇ�ɂ́A���т���������v�����́A�������܂�܂����Ƃ����V���������A�S�̒��͗J�T�������B ����́A�������݂ɓ���Ă����B�܂�A�����D���͈��̒��ŏǏ�ɂȂ��Ă���̂ŁA�����Ȃ肱����ւ���Ƌ֒f�Ǐ���N�����Ă��܂��B�g�̂Ɉٕς���B�����ɂ���A�u�ꏊ�Ǝ��Ԃ����߂āA���R�ɋz�킹�Ă�����ق��������̂ł͂Ȃ����v�Ǝv���Ă����B����������Ȃ��Ƃ������ΏG������A�u���ҁA���܂��͂킵�̉����������킩��Ȃ��̂��v�Ɠ{����Ɍ��܂��Ă���B�����ŗ����͂�ނ����������ݏ�ɂ������B������A�����̉�������Ă����B �����̓j�����Ə����B�u����Ă₪��v�u���邼�v�����f���āA�����Ȃ蓒���ݏ�ɓ������B ���ɂ������l�̎��͂т����肵���B����ĂĎ�ŁA���ɂ����悤����ǂ������A����Ȃ��Ƃł͊Ԃɍ���Ȃ��B�S���A���Ȃ��ꂽ�B�ǂ�Ȃ���߂����邩�ƁA���ꂽ�̂ł���B�Ȃɂ���y�䗘���́A�钆�S�̂̎�����ӔC�҂��B �Ƃ��낪�����́A�u�ǂ����A���܂����v�ƃj�R�j�R���Ȃ��琺���������B���m�����͎v�킸��������킹���B�����͌������B�u����ɂ��z�킹��v�u�͂��H�v���m�����͂т����肵���B�����͌����B�u����ɂ��z�킹���v���M���^�ŗ����̊���݂Ă������m�����́A�������������{�C�炵���̂ŁA�L�Z���ɉ������l�߂ĉ��������o�����B�����L�Z�������̊Ԃɂ͂������́A�v���艌���z�����ނƁA�₪�ăt�[�c�Ɠf���o���A�u���܂��B�����́A�B����݂Ɍ���ȁv���Č������B ���m�����͂܂��x�����Ă����B�����������́A���m�����Ɂu�����d���ɖ߂�v�ƌ����ƁA���̂܂܋����Ă������B ���̌��i��ڕt���������݂݂��Ă��āA�����G���ɕ����B �G���͓{���ė������ĂB�����āA�u�钆����̔C�ɂ���҂��A�ꏏ�ɂȂ��ĉB����݂�����Ƃ͉������v�Ɠ{������B�����͈ꉞ�́A�u�\�������܂���v�Ǝӂ������A�ӂ������Ď����̍l�����q�ׂ��B �u�������݂́A�コ�܂̂��l���ɂȂ�悤�ȊȒP�Ȃ��̂ł͂������܂���B������ւ���A�g�̂Ɉُ���܂��B�ǂ����A����ɁA�K���ȏꏊ��݂��āA���������ނ��Ƃ��������������������Ƒ����܂��v�^���ȗ����̗l�q�ɁA�G�����l�����B�Ȃɂ���Ԃ�V�̂Ƃ����琢�b�ɂȂ�A�����ƐM�����Â��Ă��������̌������Ƃ��B��������B�G���́A�₪�ĕ\���a�܂���Ƃ��Ȃ������B �u�킩�����B�킽���������s���߂�����������Ȃ��B���܂��̂����悤�ɂƂ�͂���A���v���̂��Ƃ��A�ڕt�����̃�����]�ˏ���ɂ��ꂽ�B�����̉B����݂����Ă����A���͊��������B������ė����̂Ƃ���֎ӂ�ɂ����B�܂莩�������̌�������������������Ȃǂ����ɁA�G������O��I�Ɏ���ꂽ�Ƃ������Ƃ��A���t���炫�������炾�B���t�������A�������������ɑ��h�̔O�������͂��߂Ă����B�������āA�]�ˏ���ɂ́u�i�����v���݂����A���������͎��܂����B ���������悤�ɁA�������ア�҂̗���ɗ����Ă��̂��l����悤�ɂȂ����̂��A���ׂē���ƍN�́A�u�ɑ��w�̌P���v�ɂ����̂ł���B�@ |
|
|
���G�� / �����̎���������
�u�G���l�͂����i�����a�ł�����B���ꂩ��̐��̒��́A��������ɕ��͂��ւ�悤�Ȑl���ł͂Ȃ��A���]�ɂ���Đl�X�𖣂����鎑�����K�v�ł��v�Ƃ����������������B�G���͂���𗘗p���傤�ƍl�����B�Ƃ������Ƃ́A�u���������܂�������Ă���ƌ����铿�ʂ��A����ɑ��₵�Ĕ������邱�Ƃ��v�Ƃ������Ƃł���B�ނ͎����̐����������̈�_�ɏW�������B �u���ꂪ�A���ڂƂ��Ẳ��̐������Ȃ̂��v�������߂Ă��܂��ƁA�傫�������J�����C�������B �ȉ��́A���ʂ��Đ��Y���t�����l���邱�Ƃɂ���āA�����O�̓��]��l�X�Ɉ�ۂÂ��悤�Ƃ����B�@ |
|
|
�����ˌ��� / ����{�j
�����́A�����̐���\�����B 1 �������d�����A�_���̕�炵��L���ɂ��� 2 �w����{�j�x�̕Ҏ[�s���� 3 �̓��ɐ��������݂��� 4 �悱���܂ȏ@�����֎~���� 5 �_���̕��S���y�����邽�߂ɁA�G�ł̂�������p�~���� �Ȃǂł������B �����čł��˓������������̂́A�����l���߂���@�ł���B�����́u����A���˓���Ƃ̑����́A�l�������̏����ƂƁA��ւōs���v�Ɛ錾�����B�݂�Ȗڂ����������B���͎͂��s�����B���Ȃ킿�A�Z���d�̑��q�ł���j����{�q�Ɍ}�����B���d�ɂ́u�킽���̑��q���A�����̐��q�ɂ��Ă��炤�v�ƍ������B���d�́A�u�����܂ł��Ȃ��Ă������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��������A�����͏��m���Ȃ������B�\���̂Ƃ��ɓǂw�j�L�x�́u���Γ`�v�̏Ռ����A�����Ƌ��̒��Ɏc���Ă����B�O�j�̎������A�Z�̗��d�������u���Đ��˂̓���ɂȂ������ƂɁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ�������߂����������Ă����̂ł���B ���˗̓��̖������d�����āA���̕�炵��L���ɂ������Ƃ����̂��A��������������߂����̗��Ԃ��ł������B�����Ɂw����{�j�x�̕Ҏ[�s����Ɛ錾�����̂��A���̂��߂ł������B�w�j�L�x�́u���Γ`�v�Ɋ������������́u���{�ɂ��A�T���Ă݂�����������Ⴊ��������̂ł͂Ȃ����B������@��N�����Đ������A�㐢�ɓ`���悤�v�Ǝv���������̂ł���B�w����{�j�x�Ҏ[�̊�ẮA���ꂪ����ɂȂ�O�̖���O�N(��Z��)����s���Ă����B���ꂪ�O�\�̂Ƃ��ł���B�]�ˋ�̒����~�Ɏj�ǂ�݂��A�Ҏ[�ɏ]��������̊w�҂������W�߂��B���ʂȗ\�Z���p�ӂ����B���̎��Ƃ͑����ȋ��H�����ł������̂ŁA�ᔻ�����������B�����������́A�ˎ�ɂȂ��Ă����̕Ҏ[�͑�����Ɛ錾�����̂ł���B���������A���́w����{�j�x�̕Ҏ[�͖����O�\��N(���Z�Z)�܂ł�����B��S�\�N�ɂ킽���K�͂ȏC�j��Ƃł������B����́A�w�j�L�x�ɂ���Ċw�u�l�ς̓��v���Ȃ킿�u��`�𐳂��v�Ƃ������Ƃ��A���˔˓������łȂ��A���{�S�̂̃R���Z���T�X�ɂ����������̂ł���B�@ |
|
|
������g�@ / ���g�D���������v
����g�@�͌��݂ł������X�g���N�`�������O���邢�̓��G���W�j�A�����O�������Ȃ������R�����A�Ȃ�Ƃ����Ă������������v�𐄂��i�߂�̂͑g�D�Ɛl�Ԃł���B�g�@�ɂ���A�]�ˏ�̖�l�������B�]���āA���v�����̐l���ɂ͑����Ȉӗ~�����߂���B���ʂ̉��v�҂�������A�u���ܖ��ɂ��Ă���l�Ԃ͑S�����\���B�����炱������ȍ�����N�������̂��B����������芷���Ă��܂����v�ƍl����B�Ƃ��낪����g�@�̐l���ɑ����{���j�͈�����B����͂��̂悤�ȍl������������B ���啝�ȓ���ւ��͂����Ȃ�Ȃ��B ������Ă����i�N�ٗp����N�����͏d��B ��������͂����Ȃ�Ȃ��B���������B ������`���ɍ����̂悤�ȑ��݂͒u���Ȃ��B ���������A���܂����l���������̂܂܂̎d���̎d�������Ă����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�܂������ł��J�����Ă��Ȃ��\�͂������o������B �Ƃ������Ƃł������B�͂����肢���A�u���ݍ]�ˏ�ɋΖ����Ă��镐�m���������p���A�悻����啝�ɐV�������𒍓����Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B���̕��j�����Ă�ꂽ���߂ɁA����͋I�B�a�̎R�����荞��ł����̂ɂ��S��炸�A�a�̎R����]���Ă������m�������]�ˏ�̏d�����ɂ͂��Ȃ������̂ł���B �g�@�͉��v�҂̃^�C�u�Ƃ��ẮA�u�ƍٌ^�̃g�b�v�v�ł���B�ƍٌ^�̃g�b�v���悭�Ƃ�̂́A�u�����̑��߂������d�p����v�Ƃ������@���B������h���S��������ɂ��A���ł����̏����҂Ƒ��k�����Ď���i�߂�Ƃ����������B����̎҂̂قƂ�ǂ�ɂ��Ȃ��B�Ƃ��ɌÂ����炢��҂�ɂ��Ȃ��B �������g�@�͂���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������B����͂����܂ł��A �����݂̓��얋�{�̑g�@���d��B �����̑g�D�ɐg��u���Ă���l�Ԃ͊��p����B ���������������玫�߂�Ƃ����҂͎~�߂Ȃ��B ���������߂��ꍇ�ɂ͂��̕�U�Ɏ����̑I�l����o�p����B �Ƃ������Ƃł������B�]�˒���s�ɑ剪�z�O�璉����o�p�����̂͂��̗Ⴞ�B�O�C�̍]�˒���s����荞��ł����g�@�̐���������āA�u����킽�����ɂ͖��܂�Ǝv���܂���̂ŁA���C�����Ă��������܂��v�Ǝ��\���o�����̂��B�g�@�́A�u�������B�����Ԃ���J�������v�Ƃ����Ď��\��������B���̍]�˒���s�ɂ���A���邢�́A(�������玫�\���o���A���邢�͏�l(�g�@�̂���)�͈ԗ����Ă���邩������Ȃ�)�Ƃ��������������������̂�������Ȃ��B�������g�@�͂���Ȏ�ɂ͏��Ȃ������B(���߂����҂͂ǂ�ǂ߂Ă��炤)���R�������~�߂Ȃ������B�@ |
|
|
������g�@ / �܂��̂�ŏ���̂Ă�
�g�@�͋��ۏ\�Z�N(�ꎵ�O��)�Ɏ��j�@�c�����A�����ܔN(�ꎵ�l�Z)�Ɏl�j�@�������ꂼ��Ɨ��������B�]�ˏ�̖�̖����Ƃ��ēc���A��ȂƖ��̂点���B���Ƃ��͒��j�̉Əd�Ƃ��߂Ă����B�Ƃ��낪�Əd�͕s�т̎q�ŏ��N�̂Ƃ������F�ɂӂ���A�������r��Ă����B����ɂЂ�������j�̏@���͉p���ŁA����ł́A�u�c���@���l�����A���̏��R�ɂӂ��킵���v�Ƃ��킳����Ă����B���܂ł����Ă��Əd�̍s����Ȃ��̂ŁA�Ƃ��ɂ₵��������W�́A������g�@�ɒ��������B �u������Ȃ���Əd�l�����p��ɂȂ�A�c���@���l�������q�ɂȂ����܂��悤�Ɂv����������Ƌg�@�͉��Ƃ����킸�A���Ə�W���Î���삻�̖ڂ��݂�݂�߂������������B��W�͂т����肵���B�₪�ċg�@�͔ߒɂȐ��ł����������B �u��W�A�l�̐e�Ƃ��Ă̋g�@�́A���܂��̂����Ƃ���@�������Ƃ��ɂ������B���������R�Ƃ��Ă̋g�@�͒��q�Əd�����Ƃ��Ƃ���B���R�͗����т��B��͎̂Ă˂Ȃ�ʁB�������A���܂��͂��łɉƏd���x����C���Ȃ��B���O�����v �܂�Ŏ����Ɏ�����܂ꂽ���̂悤�ȔߒɂȌ��t�ł������B��W�͂��܂���Ȃ���g�@�̋��d�����r����C�����ɋ���ł��ꂽ�B�����̂����͂������`�����B ��������肩�����͂��Ȃ������B��W�͔�Ƃ��ꂽ�B �V���E���Ƃɂ͂������A�g�@�͂��̌�̏�W�̕�炵�ɂ����S���������B��W����߂�Ƃ����A���S�̒�Ԃɂ���ƂȂ��T�点���B��Ԃ́A�u�����E��A���F�l�̑喼�Ƃɂ���H����Ă���܂��v�ƕ����B �u�ȂɁv�g�@�͂��ǂ낢���B�Ȃ����Ƃ����ƁA�u���̂����ȂȂ����i�䂦�A���ݐE�����C���������������Ƃ�ɂȂ�܂���B����\�͂����̂��߂ɂ��ׂĂ��g���ʂ����ɂȂ�܂����B�s���ł́A�����̉Ƃ����Ăʃo�J�҂�Ƃ��������Ă���܂��v�u�������E�E�E�v�g�@�͈Â��\��ɂȂ����B�����d�����ĂсA�u��W�����Ȃ䂦�ɏZ���ɂ����ƌ����Ƃ́A���܂̐��ɒ������H��̖��b�ł���B�s���R�̂Ȃ��悤�Ɏ蓖���Ă��킹�v�Ɩ������B���̌����Ԃ���A�u�����l�͂�������������邤�������܂��v�Ƃ����A���������̎厡���h�����Ċŕa�������B�������ɂ́A�u����𒅂�悤�ɓ`����v�ƖȂ����͂��������B���̂��тɏ�W�͊������A�u�s���̐b�ɂ��̂悤�Ȃ�����������ꂢ��܂��B���ꂮ�����l�ɂ���т̂قǂ��v�ƕ��������B���������g�@�͖ڂ��Ȃ��܂��āA�u��W���Ƃ����̂͏��R�Ƃ��Ă̗��ł���B�l�ԋg�@�Ƃ��ẮA���܂���W���D�����v�ƌ�����B���̌��t�͂�����W�ɓ`�����A��W�͍]�ˉ�����p�ɓ���������̂ł������B �@ |
|
|
������g�@ / �{���̋g�@��
���쏫�R�Ƃ͏\�ܑ�Â������A����ڂ̋g�@�͂��낢��ȖʂŃ��j�[�N�Ȑl���������B�g�����S���\��Z���`�������Ƃ����B �]�ˎ���̒j���̕��ϓI�Ȑg���͕S�\�Z���`���炢�������Ƃ�������A�g�@�͈��|�I�ɔw�������B�ǂ�Ȃɑ����̐l�̌Q��̒��ɂ��Ă��A�u���A�g�@���܂��v�Ƃ����킩�����Ƃ����B�F�͍��������炵���B�����ēV�R���̂��Ƃ��c���Ă����B ��̓h���}(���㏫�R�g�@)�̎�������c�q�s���ƕ����āA�u���A�z���g�H�v�Ǝv������������ꂽ�͂����B�������A�L�^�Ɏc��g�@�̎������炷��A�܂��ɁA�u�z�����m�̋g�@�͂��������l���������v�Ƃ����C���[�W�ɑ����߂��B �g�@�͈Ќ������������A����ɂł��D�����l�Ȃ������������Ƃ����B���Ɏq�ǂ��ɍD���ꂽ�B�q�ǂ��ƃC�k��l�R�ɍD�����l�ԂɈ��l�͂��Ȃ��B �g�@�͑��l�╔�������s�����Ƃ��A��ɑ吺���o�������Ƃ��Ȃ��������B�₳�����������B ���ł��������������遍���ƂƁ��{�遍���ƂƂ͈Ⴄ�B����Ƃ����̂͑���Ɉ���������A����ł���\�͂������o�����Ƃ���s�ׂ��B�{��Ƃ����̂́A���s�̐ӔC�������������̂��C���Ȃ��̂�����A�u���܂��͉�������Ă���̂��I�v�Ƒ����݂̊����I���ɂ��邱�Ƃ��B����͎����������Ă���̂��{���Ă���̂���q���Ɍ������B�g�@�͐S�̂₳�����l���������B�@ �@ |
|
| �����c�@���E���c���� | |
|
���ٌ���A���f������̂̓g�b�v�̐ӔC���|�߂�@��
��҂̂������Ƃ��ڂ���E���R�𗎂Ƃ��悤�ȓ��e����������ł���B�����Ȃ�Ǝ�҂͓��X�Ǝ����̍l����������B��҂̌��t�͍��������������B�b���I���ƒ������^����ɔ��肵���B�����āA�u�N�̈ӌ��͔��ɂ����B���������̎����q���ɂƂ炦�Ă���B�ǂ����݂�ȁA����̈ӌ��ɏ]�����ł͂Ȃ����H�v�Ƃ������B�S�����u�����������܂��傤�v�ƈٌ������ɂ������B ���܂ʼn������킸�ɘe�ɂ��ĕ����Ă����@���͎v�킸���̒��ŁA�u�`�b�v�Ɛ��炵���B���������̏�Œ������Ƃ����߂��ɂ͂����Ȃ��̂ŁA�ق��č��𗧂����B�����͂т����肵���B����Ȃ��Ƃ͏��߂Ă���������ł���B�����͕q���ɁA(����͂��C�����������ꂽ)�Ɗ������B �����ŋ}���ŁA�u�����̉�c�͂����܂łƂ���v�Ɛ錾���Ĉٌ��������B�����Ă����@���̉B�����}�����B�ނ���ƕs�@���Ȋ�����Ă��镃�ɂ������B �u����A�������܂ٌ̈���ʼn������C���������˂�悤�Ȃ��Ƃ��������܂������H�v�u�����A�������v�u���ł������܂��傤�B�킽����������������������܂����ł��傤���H�v�u�����v�@���͂Ԃ�����ڂ��ɓ�����B �����͂т����肵���B�����ɂ���A�ŋߎ����̋c���Ԃ�͌����ł݂�Ȃ̕]���������B�܂�A�u����̔@�����ƈ���āA�������͓ƒf��s�����Ȃ��B�����݂�Ȃ̈ӌ�����������Ō��_�����o���ɂȂ锨�ǂ�ȉ����ς̈ӌ��ł��悭�������Ƃ�ɂȂ�B���ɖ���I�ȋc�����v�Ƃ����Ă����B�����璷���ɂ���A�u�����ٌ̈���̉^�c�͌����ĊԈ���Ă��Ȃ��B���͂ǂ��炩�Ƃ����Ύ����̍l�����ɉ����t����Ƃ��낪���������A�����͂����������Ƃ����Ȃ��B����͕��̎���͐퍑����ł������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������ŁA���͕��a���B���a�Ȏ��ɂ́A���c�����d�݂�Ȃ̈ӌ��������Ȃ���A�ЂƂ̌��_���o���Ă����l����Ȃ̂��B�܂荪�C�Ǝ��Ԃ�����B�����͂�����\���ɂ킫�܂��Ă�����肾�v�ƁA�����̂�邱�ƂɎ��M�������Ă����B��������ł��A�u�������͔��ɖ���I�ȓa�l���v�ƍD����������Ă����B �Ƃ��낪�����̃I���W�͂��ꂪ�C�ɂ���Ȃ��炵���B(���������ǂ�Ȏ��s�������̂��낤�H)�����Ɏv��������Ƃ��낪�Ȃ������B �����ŁA�����́u�ǂ������������̂��A����������Ă��������܂��H�v�Ƃ������B�@���͐U������ăM�����Ƒ��q���ɂ�݂����B �u�ł͂������B����͑O�X����C�ɂ��Ă������Ƃ��B���������Ă�����v�u�͂��B�f���܂��v�����Ɏ����A�����̕�����������I�������B(�킽���̂ǂ��������̂ł����H�Ƃ����悤�ȕs�����A��������悤�Ȍ��t�ɕ\�ꂽ�B�@���͂����������B �u���̏�̒��Ɉٌ����݂����̂́A�m���ɂ��܂����l���Ă���悤�ɁA��ɋ߂镐�m�S�̂��炢�낢��ȍl���������A�������Ƃ��Č��f���������̎Q�l�ɂ��邽�߂̂��̂��B�ٌ��Ƃ������ʂȎ����g�����̂��A�l�Ɠ������Ƃ������ȁA�Ⴄ���Ƃ������Ƃ����C���������������炾�B�Ƃ��낪�ŋ߂͂������B�݂�ȓ����悤�Ȃ��Ƃ��肢���Ă��āA���݂��Ɏ����̂����������Ƃ�ʂ����߂ɐl�̈ӌ������̂܂܂��݂̂ɂ���Ƃ����X���������Ȃ����B�����čł������̂́A��c�𑩂˂邨�܂����A�}������悤�ɂȂ������Ƃ��B�{����Ƃ����̂́A���������f���邽�߂̈ӌ��������狁�߂�Ƃ������Ƃł����āA���̈ӌ��ɂ��̂܂]���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B���˂��˂킽���͂��̂��Ƃ�S�z���Ă����B�������܂��͂��ɂ��̉߂������������B�Ƃ����̂́A���N����������̐V�Q�̎Ⴂ���m�����������ƂɁA���܂��́A���̈ӌ��ɏ]���܂��傤�Ƃ������B�����̂������Ƃɏ]����l���ǂ��ɂ��邩�B�܂�킽�������������̂́A�݂�Ȃɂ͂ǂ�Ȃ��Ƃ����킹�Ă������B���������߂�̂͂��܂����Ƃ������Ƃ��B���f�Ƃ����͎̂�l��l�̂��̂ł����ĕ����ɓn�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂�A�����ɓn���Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���f�������Ƃ̐ӔC�͐�Ɏ�l������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���̂ւ�����܂��͂͂��������Ă���B���̂܂܂��ƍ��c�Ƃ͔��Ɋ�@�Ɋׂ邼�v�u�E�E�E�v ���e�̘b�������������͐^���ɂȂ��Ă����B�ڂ���オ���Ă���B���͌ۓ��ő�����ł悤���B�������o�J�ł͂Ȃ��B���̂������Ƃ͂킩�����B(������Ƃ��肾����)���Ȃ̋C�������킢���B�����ɐ�]�̔O���킢���B(�I���̓_�����q���B����I�m���W�ɂ͂��Ȃ�Ȃ�)�Ɗ������̂ł���B�@ �@ |
|
| ���]�ˎ��� | |
|
���ɒB���@ / �s�������̂悤�ȐS�Ŋ�@��E����
�u����Ă͂Ȃ�܂��ʁB�s�������́A���̐��̈��ɑ���{���ގ����ׂ��A�����̑̂��牊�𐁂����ĂĂ���̂ł������܂��v�Ɛ��������B�����āA�u��N���A��NJ��p���Ă͂Ȃ�܂��ʁB���̕s�������̂悤�ɁA����ގ����邨�l�ɂ��Ȃ肠�����v�Ƃ������B���̈ꌾ�ɂ���Đ��@�͂���ȑO�̎����Ƃ͕ς�����l�ԂɂȂ������Ƃ��������B �܂�A�u���̓����炨��͐��܂�ς�����v�Ƃ������o�����Ă��B����ʖ���A�����R���̒�q�̈ꎺ�ő���Ȃ���A���@�͐U�]���������B�s�������̎p��������ē��̗����痣��Ȃ��B���@�͔��Ȃ����B (���̓��A�ՍƏ@���t�ɋ�����ꂽ���S���A����͂����Ǝ��������Ă����̂��낤��)�Ƃ����^�₾�B�t�m�́A�u���̈���ގ����邽�߂ɁA��NJ�������p�Ȃ����v�ƍ������B����͊m���ɂ��̓��ȗ��A�͂��炢�̋C�������̂ĂāA���M���������Ƃɕς�����B���������̊����̓��e�́A�ʂ����Ďt�m�̂������A�u���̐��̈���ގ�����v�Ƃ������ƂɏW�����Ă����̂��낤���B �u���ꎩ�g�̖�S�E��]�̒B���ɂ������̂ł͂Ȃ��̂��v�Ƃ����v�����N���Ă����B����Ȃ��Ƃ͍��܂łȂ��B����͖ړI��B�����邽�тɁA����Ɏ��M��[�߂��B���A���A�u�ł́A���̖ړI�͒N�̂��߂̂��̂��v�ƊJ�����A�͂��Ɠ����ɖ����B���@�́A�u���܂ł̍s���́A���ׂĂ��ꎩ�g�̂��߂ł͂Ȃ������̂��v�Ǝv���͂��߂Ă����B���̋��낵���s���������A���𐁂����Č����B����āA�����ɔ����ė���悤�ȋC������B�s�������͋��ԁB �u���@��A���܂��̓G�͂��܂������v���̎O�������@�̔]�V��ł��ӂ����B�Ռ��͍�������Ȃ��B�������A���̏Ռ������@�́A�u�����肽���v�Ƃ����Ђ�����Ȏv�����Ւf�����B���@�͌Ȃ����߂����B�O�c���ƂƓ���ƍN�͊m���ɖL�b�G�g�̑��߂ł���L�b�����̎��͎҂��B�������A�����ŒQ��̎p��������āA���������̂͂��₾�����B (�Ō�܂ŁA�������т��ʂ�����)���ꂪ����̕��m���Ȃ̂��Ɖ��@�͎����Ɍ������������B�@ |
|
|
���ɒB���@ / �~�������̂͏G�g�A�ƍN�A�ƌ��ł͂Ȃ�����ɑ��Ăł�����
���ڏG�����珫�R�E������ꂽ�ƌ����A���s������ōs�Ȃ������R�錾�͗L���ł���B���̂Ƃ��ނ́A��Ƃ��ĊO�l�喼���W�߂Ă����������B �u�킪�c���ƍN���ƁA�킪���G�����́A���Ȃ������O�l�喼�̂����͂ď��R�ɂȂ����B���������͈Ⴄ�B���͐��܂�Ȃ���̏��R�ł���B�������̉ƌ��̐錾�ɕs���̂���҂́A�����A���֗����߂��č���̏��������ꂽ���B���������ƌ��������Ɍ������ł��낤�v �����ւ�ȑ�n�b�^���ł���B�������ƌ��͖{�C�������B�Ƃ����̂́A���R�ɂȂ�ɂ��āA�u�ɒB���@�������x�����Ȃ����v�Ƃ����Ă�������ł���B���̓��̐錾�́A�O�l�喼�̑S���ɑ��Ăł͂Ȃ��A�ނ��됭�@��l�ɑ��čs�Ȃ�ꂽ�̂��Ƃ݂Ă����B ���̂Ƃ����@�͂ǂ��Ή��������낤���H�ӂ��A���̂悤�Ȏ�m�ɁA����������n�b�^�������܂���ẮA�퍑�����c��喼�Ƃ��āA�����炭�ق��Ă͂����܂��B�u�����������A���m�߁v�Ǝv���āA�Ȃ��R���Ăč��ɋA������������Ȃ��B���A���̓��̐��@�͈���Ă����B ���@�́A�ƌ��̐錾���I���ƁA�����Ȃ莝���Ă����G���J���āA�����Ɖƌ������B�����āA�u����A�����ς�A�����ς�I���ɗ����������R�Ƃł�����v�Ƃ����Ă��B ���ꂾ���ł͂Ȃ������B�ނ͐i�ݏo��ƁA�ƌ��̑O�ɕ������āA�u���܁A�����ɂ���܂��喼�����̒��ɁA���Ȃ��̂悤�ȗ��������V���R�ɔw���ȂǂƂ������낵���l���������͈̂�l������܂��܂��B�����A���̂悤�ȕs�S���҂�����܂����Ƃ��́A���̈ɒB���@���A�擪�ɗ����Đ������s�Ȃ��ł���܂��傤�v�Ƃ������B ����ɑ������̂��A�������Ղł���B���Ղ��܂��A�u�����ɒB�a�Ɏ^���ł������܂��B�����R�̐擪�ɂ́A�ɒB�a�Ɣn�̌D����ׂ�ł���܂��傤�v�Ƃ������B �퍑�����c��̍r�喼��l���A�^����ɍ~�����Ă��܂�������A���̑喼�����͂��������ׂ����Ƃ��Ȃ������B���̂܂ܑS�������������B�ƌ��́A�������Đ錾�����Ƃ���A�u���܂�Ȃ���̏��R�v�̍����A����̎�ɂ����̂ł���B �Ⴂ���̐��@����A���悻�z�����ł��Ȃ��~���Ԃ�ł���B���@�́A���͂⑈���C�͂Ȃ������B����́A���������̂��ƂɎQ�����āA���̐��������܂��g���Ȃ���A���Ȋ�Ƃ̑������͂��邱�Ƃ��A�ł��������Ǝv��������ł���B �����������̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă��A����̗���ł������B���@�͏�ɂԂ₢�Ă����B �u���ꂪ�~�������̂́A�G�g��ƍN�ł͂Ȃ��B�܂��ĉƌ��ł͂Ȃ��B���ꂪ���������Ă���̂́A�����き�Ȃ̂��B���̗���ł���A���̒��Ȃ̂��B����ɂ͏��ĂȂ��v �ނ��Ȓ�R������A�ɒB��Ƃ͂Ԃ�Ă��܂��B����́A���k�ł������N�������B������Ƃ����X�ƖłтĂ������B���傾�Ƃ��`�����Ƃ��́A���̂�����Ȃ��B�ނ���A�����������̂��t�ɍ�p���ė��ڂɏo�邱�Ƃ�������B����̂��˂�ɂ͋t�炦�Ȃ��̂��B ���̂��߂ɂ́A���ł��A���ɑ���ْ���������Ȃ����Ƃ��B���X���X�ƕς�鐢���ɑ��āA�ْ��̖ڂ������A���𗧂Ă邱�Ƃł���B���@�́A���U�A���������ْ������т��đ������B �ɒB���@���̂������̂́A�����́A�u���B�T��v�Ƃ����A�Ƃɑ����Ă������ڂ���蔲���āA���k�̎����������Ƃ������B���@�͂��̋��т�����������߁A��������ɋ��������̂��B�������A����͂���Ȃ�����ł͂Ȃ������B�������������o�����������Ƃ����āA���k�̒n�ɁA�u�ߐH����ĕ�����m��v�̋C��������o�����̂ł���B �����ʂ�Ƃ���Ƃ���ꂽ���k�ɁA���������㇗��ƉԂ��J���͂��߂��B����𐭏@�͓����Ɍ��т����B�����Ă܂����@���̂��Ƃ���́A���X�Ƒł肪���ڂɏo�Ă��A�����ė������݂��ςȂ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��������Ƃł���B�����A��݂��������B���N�����B���̔ނ̊��͂��A����̐l�X��E�C�Â����B �ނ́A��������ɑ���ނ����ł������B�ɒB��Ƃ͌������āA���̑n�Ǝ҂̎w���ɏ]�����B�@ |
|
|
���ɒB���@ / ���k�ɒz���������A�ɒB�҂̗R��
�̂��Ɂ��ɒB�ҁh�Ƃ�����悤�ȃ_���f�B�Y���́A���ׂĐ��@�������������̂��B�ނ̌R���͍s�i����Ƃ��A��ɂ���т₩�ȕ����������B�ނ̌R�����㗌����ƁA�s�������́A�Ƃ̒������яo���Č�������̂��y���݂ɂ����B �h�ɒB�O�h�̖����N�������B��������Ă��ɒB�̌R���̓p�t�H�[�}���X�����ɗ�B���@���A������͂ɑR���Ȃ���A�������A�t��킸�ɐ����Ă��������h�ɒB�C�Y���h�ł������B����́A�D�c�M���ɔ�����u�ߐH����ĕ�����m��v�̎����ł������B ���y�E���R���_�͐��@�ɂ���Ē����ɁA���k�̈�p�ɍ��Â����̂ł���B�������A����͒P�Ȃ�͕�ł͂Ȃ��āA���@�����k�̒n��������ӂ܂��Ȃ���A���y�E���R�����Ȃ������Ȃ�̕t�����l�������������ł������B���̕����́A���܂����X�Ɛ����Â��Ă���B�@ |
|
|
���א�H�� / �������喼�ɂȂ������Ƃ͂Ȃ��ꑰ�ɉh�̊�Ղ�������
[ �א�H��/�א쓡�F(1534-1610)�@�퍑���ォ����y���R����ɂ����Ă̕����E�퍑�喼�A�̐l�B���͗H���|�B��ʂɑ����̓��F�Œm����B�܂��ꎞ���A�̒n�̒����𖼎��Ƃ��Ă������Ƃ��璷�����F�Ƃ��������B�������R�Ƃ̘A�}�E�O�����̐��܂�B����O�E�O�������̎��j�ŁA��͎�w�E���w�҂̐����錫�̖��E�q�c�@�B�����̎��Z�̘a�����E�א쌳��̗{�q�ƂȂ����B����13�㏫�R�E�����`�P�Ɏd���A���̎����15�㏫�R�E�����`���̗i���ɐs�͂��邪�A��ɐD�c�M���ɏ]���O��{��11���̑喼�ƂȂ�B��ɖL�b�G�g�A����ƍN�Ɏd���ďd�p����A�ߐ��喼�E���א쎁�̑c�ƂȂ����B�܂�������Ƃ̉̓����p����𗬂̉̓��`���ҎO�𐼎��}����Í��`�����A�ߐ��̊w��听����������ꗬ�̕����l�ł��������B] �����āA�`���ɊЌ����Ă����������ꂸ�A����������Ă������Ƃ́A�H�ւɂƂ��Ă��ŏ��ɖK�ꂽ��@�˔j�̗Ö@�ɂȂ����B���G�́A���łɋ`�������̂āA�D�c�M���̂��Ƃɑ������B �M�����A�����������G���ǂ��Ƃ߂Ă������͕�����Ȃ��B�u�����͂��܂܂łɂ����Ύ�l��ς��Ă���B�`���������Ԃ��ƁA��������̂Ƃ���ɑ����Ă���B�����Ȃ�ƁA���ꂪ�����Ԃ��A�����́A��������̂Ăđ��̑喼�̂Ƃ���ɑ��邩������Ȃ��B�����������f�̂Ȃ�Ȃ���Ȃ̂��v�Ǝv������������Ȃ��B ������ɂ��Ă��A�퍑����́u��]�E����v������A�]�E���̂��͕̂ʂɒ��������ۂł͂Ȃ����A�g�����Ƃ��ẮA���낢��Ȏv�������������Ƃ��낤�B �����ւ����ƁA�H�ւ̐i�ނ͂��ꂢ�������B���̔��w���������B�M���́A�H�ւɖڂ������B����́A�`�����ŏ��Ɏ����ɉ�킹���Ƃ����A���G�ɔ�ׂ�A�H�ւ̂ق����A�͂邩�ɐ��ӂ��������Ă�������ł���B�M���́A�H�ւ̂Ƃ���Ɏg�����o�����B �u���܂��́A�`���ɏ\���s�������B�����A�ߋ���Y��āA������x���Ăق����v �H�ւ́A�M���̗U���ɉ������B�V�����N(���O)�����\���A�R��(���s�{)�̒������Ȃ킿�A�j�삩�琼�̒n��S���̓y�n��^����ꂽ�B�����ŗH�ւ́A�א�Ƃ��������Ɖ��߂����Ƃ͑O�ɏ������B�܂�A�����ɂ��H�ւ̂��܂����S�z�肪����B����́A�א�Ƃ��������̂ĂĒ����Ƃ������𖼂̂邱�Ƃɂ���āA�u�����͂����A�`���̉Ɛb�ł͂���܂���B�M�����̉Ɛb�ɂȂ����̂ł��v�Ƃ������Ƃ�\���������ƂɂȂ邩�炾�B �M���́A�Ȍ�A�`���̖����ɂ���āA�������U�߂悤�Ƃ����喼�������A�Ђ��[���瓢�����ڂ��B���q�������A���邢�͐ΎR�{�莛���A���ׂčU���ڕW�ɂȂ����B�����n���̖ї��ꑰ���^�[�Q�b�g�ɓ����Ă����B �H�ւ́A���������M���ɂ��ē]�킵�A���X�̕����𗧂Ă��B�H�ւ́A����Ȃ镶���l�喼�ł͂Ȃ��A�퓬�ɂ��܂������ꂽ�͗ʂ��������̂ł���B�ނ��������̂́A��Ƃ��ĒO�g(���s�{�E���Ɍ�)�E�O��(���s�{)�̍��X�ł���B����ɁA�M���̖��ɂ���Ē������ʂ��U�߂Â��Ă����H�ďG�g�ɋ��͂��A���X�̕�����������B�ĂђO�㍑�ɖ߂��āA���̕��ʂ𐧈������B ���̌��J�ɑ��āA�M���́A�u���܂��̘�A�����̖��`�ŒO��\��^����v�Ƃ������B�H�ւ͂͂��߂āA�傫�ȍ������喼�ɂȂ����̂ł��邪�A���`�͂����܂ł����q�̒����ł����āA�H�ւł͂Ȃ��B �����ŁA�Y��Ȃ������ɏ����Ă����A����͏d�傾�B�܂�A�H�ւ͍Ō�܂ŁA�傫�ȍ������喼�ł��������Ƃ͈�x���Ȃ��B�ނ́A���s���x�̒����ɗ^����ꂽ�B���������O��̊��{�ɂ����Ȃ������B���ʂ܂ŁA�ނ����\���Ƃ����������喼�ɂȂ��������͂Ȃ��B������H�ւ̌o�c�҂Ƃ��Ă̐��������݂�ꍇ�ɏd�v���B �܂�A�H�ւ́A�u�א��Ƃ������̊�b���m�����A���������ł��錩�ʂ������Ă���A�����Ȃǂǂ������g���������Ă������v�ƍl���Ă����B���������āA�`���̂悤�ɁA�u�����`����Ɓv���m������Ȃ���C�����܂Ȃ��Ƃ����^�C�v�ł͂Ȃ������B �u�א��Ɓv���m�����������̂ł���B���̑�\�҂͒N�ł����Ă������B���`�l���N�ł��낤�ƁA���Ԃ̌���Ƃ���́A�N���u����͍א쒉����Ƃ��v�ȂǂƂ͎v��Ȃ��B�M���Ƃ̊W���炢���Ă��A���R�A�u���`�l�͑��q�����A�����܂ł������͐e���������Ă���v�Ƃ݂�B �u����ł����̂��v�ƗH�ւ͎v���Ă����B���������_�A�������Ƃ������Ƃ��o�c�҂̌o�c�ԓx�ɑ傫���e������Ƃ������Ƃ���Ă���B�܂蕶�����́A���̐l�Ԃɂ�Ƃ��^����B�܂��A�l�������_��ɂ���B�S�̂Ƀ\�t�g�v�l�őΉ����邩��A�M�X�M�X���Ȃ��B�|�̂悤�Ƀs���ƒ�������Ȃ��B������A�N�����Ă��鎖���ɑ��ẮA�ނ���o�c��_����̐l�Ԃ����A�]�T�������đΉ����邱�Ƃ��ł���B �u��Ɛl�́A��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ƕ�������g�ɂ���v�Ƃ�����̂́A�����������Ƃ��B���Ӑ�̐l�ԂƉ���āA�݂��Ɏ����荇������d�������܂������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B����������̐��Ƃł͂Ȃ��āA�܂荪���ɂ����ĕ�����������o�c�҂́A�ǂ�ȏꍇ�ɂ���Ƃ�������đΉ��ł���Ƃ������Ƃ���Ȃ̂��B �H�ւ́A�܂��ɂ��������^�C�v�̌o�c�҂ł������B������M���ɁA�u���܂��̘�ɏ\��邼�v�Ƃ����āA�u����A��łȂ����ɂ��������v�ȂǂƂ͂���Ȃ������B����́A�M�����A�����ɗH�ւƂ����l�Ԃ��悭�m���Ă����������̂��B �H�ւ́A���Ȃ��Ƃ��`���̉Ɛb�ł���A�ނ����R�ɂ��邽�߂ɐM���ɒ�����˗������B�����āA���̋`����M�����Ǖ������B �H�ւɂ���A���܂�Ȃ��o�����ł������ɈႢ�Ȃ��B�Ƃ��낪�M�����݂āA�H�ւ͌����ĐM��������ł͂��Ȃ������B�ނ���M���̍s�ׂR���Ƃ݂Ă����B���������H�ւɐM���͍D�����������B�����āA�u���������A���̒j�͋ꂵ��ł��邱�Ƃ��낤�v�Ɠ�����B ���̓���A�u�����A���̒j�ɒ��ڏ\�̍������A����ɋꂵ�ނ��낤�B����́A����̈ƂŁA�̂т����S�������𑗂��Ă���`���̂��Ƃ��v���o�����炾�B�������邱�Ƃ́A����ɂ��̒j�������邱�ƂɂȂ�v�ƍl�����̂��B�����ŁA���q�̒�����喼�ɂ����̂ł�B�@ |
|
|
���א�H�� / �c�ӏ�����炵�����V�c����̒��g�Řa�r���ꂽ
���悢��c�ӏ�����邩�ƌ��ӂ������A�H�ւ́A���̔����{�Ɏ莆�𑗂����B����ɂ́A�u���Ȃ��ɁA�Í��`���̏؏���S�������肢�����܂��v�Ə����Ă������B�Í��`���Ƃ����̂́A��̃p�e���g�ł����āA�N�ɂ����������̂ł͂Ȃ��B�H�ւ́A��������}��������Ă����̂ł���B��������x�͖�l�ł������c�픪���{�ɏ��낤�Ƃ����̂��B�����{�͋����āA���̂��Ƃ��Z�̌�z���V�c�ɘb�����B �����āA�u�א�H�ւ̂悤�ȕ����l�����Ȃ��邱�Ƃ́A���{�̕����̂��߂ɑ傫�ȑ����ɂȂ�܂��v�Ɛi�������B�V�c�����Ȃ����A�u����ł́A���܂������g�Ƃ��ēc�ӏ�ɍs���A������͂�ł��镺�������g��������悤�ɂ���v�Ɩ������B �����{�́A�ނ�Œ��g�ƂȂ�A�����Ċ�̑叫�ɂ��̂��Ƃ����������A��̑叫�͏��m���Ȃ��B�u���̍���́A���m�̑����ł����āA�䏊�������o�����Ƃł͂������܂���v�Ɠ˂��ς˂��B�V�c�̖��ɂ���������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B ���f���������{�͋��s�ɖ߂����B�������A�H�ւ����̂܂܂ɂ���C�͂Ȃ������B�����ŁA�ĂѓV�c�ɗ��B�V�c�͂���ł͂������悤�Ƃ������ƂŁA���s���i��̑O�c���Ȃ���B ���̂���A�܂��L�b�����͌`�̏�ł͑��݂��Ă����B�����āA����ƍN�͖L�b�����̑�V�ł���A�Γc�O���͕�s�ł���B���������āA�փP���̍���́A��V�ƕ�s�̌��܂��Ƃ������Ƃ��ł���B���Ȃ́A���̖L�b�����ɂ����鋞�s���i��̃|�X�g�ɂ��Ă����̂��B �V�c�͒��g�Ƃ��āA���ȂɁA�u���s���i��̐ӔC�ŁA�c�ӏ�̈��݂���������v�Ɩ������B���Ȃ́A�c�ӏ�̕�͌R�ɑ��āA���g��`�������A��͌R�͂�����A�����ق��ɏR������B�u�悯���Ȃ��Ƃ�����ȁv�ƒǂ��Ԃ����̂��B �ق��ق��̑̂ŁA���s�ɖ߂������Ȃ́A��ނ������A�c�ӏ���̗H�ւɎg���𑗂����B�g���ɂ͎����̑��q�����Ă��B�����āA�u���ꂱ��̎���ŁA��͌R�ɒ�����`����������Ȃ��B���̏�́A�V�c�̌�S������邽�߂ɂ́A���Ȃ�������J���ĊO�ɏo���肵�������Ȃ��B�c�ӏ���J�邵�Ăق����v�Ƃ������B ����ɑ��A�H�ւ́A�u����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�����܂ł��������Ď��ʁv�ƕԎ��������B ���ǁA�V�c�����o������������܂��������A�c�ӊ��X��̓������悢�攗���Ă����B �������A�����Ȃ�ƁA�䏊���Ӓn�ɂȂ����B�V�c�͌��Ƃ��O�l�I��Œ��g�Ƃ��ēc�ӏ�ɍ����������B���x�́A�u�c�ӏ���Ă���̂��A�c�ӏ�����͂�ł�����̂��A���̖��ɂ���Ęa�r�𖽂���v�Ƃ������̂ł���B ���܂܂ł́A��͌R�Ə���̗H�ւɑ��āA���ɘa�r�����������̂����A����ǂ͂����ł͂Ȃ��B�����Ȃ藼�R�ɑ��āA�u�a�r����v�Ɩ������̂ł���B�����Ȃ�ƁA�H�ւ͋Ή��Ƃ�����A�V�c�̌�S�ɑ��Ă��܂ł��w���͕̂s���̐b�ɂȂ�Ǝv�����B�����ŁA��͌R�̂ق��̓����͂ǂ�����A�u����J���܂��v�ƕ����B �c���ܔN(��Z�Z�Z)�㌎�\����A�H�ւ͂��Ɍ|��̖���J�����B�����āA�ܕS�̕��𗦂��āA�����͒O�g(���s�{�E���Ɍ�)�T�R��Ɉڂ����B�Ȃ�ƁA�����\��������㌎�\����܂ŘZ�\���]����ď�ł������B�������ܕS�̕��ŁA���ꂾ����������̂ł���B �����āA���̂��Ƃ��A�ƍN����������傫�ȗv���ɂȂ����B����́A�փP���̍��킪�͂��܂����̂͋㌎�\�ܓ������A�H�ւ��c�ӏ�Ɋ��ܐ�̕����������Ă������߂ɁA���ꂪ���ǂ͍���ɊԂɍ���Ȃ������̂ł���B ���傤�ljƍN�̑��q�G�����A�M�Z(���쌧)��c��̐^�c�ꑰ�ɐU���āA�l�]��̌R���𑫂ǂ߂��ꂽ�̂Ɠ����ł������B �l���Ă݂�A�����ĉƍN�́A�փP���̍���Ɋy�������킯�ł͂Ȃ��B�ގ��g�����낢��ƃs���`�Ɋׂ����B���̈Ӗ��ł́A�H�ւ̌��т́A�ƍN���[���܂���Ƃ���ƂȂ����̂����Ȃ�����B �փP���̍��킪����ŁA����ʼnƍN�͏��喼�Ɖ�����B���̂Ƃ��H�ւɂ́A�Ƃ��ɂ˂�ɉ����A�ƍN�́A�u�V��ɂ�������炸�A�Z�\���]����悭��������������Ă����������B�������ŁA���̉ƍN���O���ɏ����Ƃ��ł����B���̂����́A�]�݂̓y�n������A�ǂ��ł��^���悤�v�ƍ������B �������A���̂Ƃ��̗H�ւ̑ԓx���܂������ł���B�ނ͒f�����B �u����قǂ̂��Ƃ͂������܂���B�ǂ����A���̘V���ڂ�̂��Ƃ͂��Y�ꂭ�������v�������A�ƍN�͏��m���Ȃ������B�u�ł́A�ʂȂ������ŖJ����^�������B�Ȃ�ł������Ăق����v�u���悤�ł������܂����v������ƍl�����H�ւ́A�����������Ƃ��������B �u����\���܂��ƁA��Ƃ��ĐΓc���ɐȂ�u���Ă������̂̂Ȃ��ɂ��A����Ď����U�߂��A���ꂾ���łȂ��A���낢��ƐΓc���̏����k�炵�Ă��ꂽ���̂�����܂��B��������܂��̂ŁA�ł�����̂��̂����̍߂�Ƃ��āA�̒n�����g���Ă���Ă���������A�K������ɉ߂�����̂͂������܂���v �ƍN�́A�H�ւ����߂��B�u�����������̂��v�Ǝv�����B�����ɖJ���͂���Ȃ�����A�������U�߂����̂̂Ȃ��œ��ʂ������̂̍߂������Ă���Ă���A�Ƃ����̂ł���B �߂����������łȂ��A���̘A���������Ă����y�n���A���̂܂������Ă���Ă���Ƃ����̂��B�ƍN�͂��Ȃ������B�u���Ȃ��̂���|�ɂ����������B���̂��̂����̖��������o���Ăق����v�Ƃ������B �H�ւ́A�ƍN��M���āA�����Ɏu��ʂ��Ă������̂����̖��������o�����B�ƍN�͖�������B����ł��ƍN�́A�C�����܂Ȃ������炵���B���c���Z�N�ɂȂ��āA�z�O(���䌧)�̂Ȃ�����O���H�ւɗ^�����B�@ |
|
|
���������� / ��Ԏ��`
[ ��������(1556-1630)�@�퍑���ォ��]�ˎ��㏉���ɂ����Ă̕����E�喼�B�ɗ\�������ˎ�B��Ɉɐ����Ô˂̏���ˎ�ƂȂ�B�����Ə@�Ə���B���x����N��ς����퍑�����Ƃ��Ēm����B����͔ގ��g�́u���m������̎��x��N��ς��˂Ε��m�Ƃ͌����ʁv�Ƃ��������ɕ\��Ă���B�z��Z�p�ɒ����A�F�a����E������E�R��E�Ï�E�ɉ����E�V����Ȃǂ�z�邵���B���Ղ̒z��͐Ί_�������ςݏグ�鎖�Ɩx�̐v�ɓ���������A�����z��̖���ł��Ί_�̔�����d��������������ƑΔ䂳���B ] ���Ղ̓�Ԏ��`���A�u�����̗��O���������Ă�����l�͒N���v�Ƃ���"��l�߂���"�Ɏv���Ă���B �ӂ��Ȃ�A�˂�"��Ԏ�"�𑖂��Ă���擪�O���[�v�̎�l��I�Ԃ��낤�B���̂ق������g�o�����������炾�B���������Ղ͌����Ă���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������B�˂ɓ�Ԏ��`��I�Ƃ������Ƃ́A�u��Ԏ�ɂ����l�́A�ŖS�������v�ƍl���Ă������炾�B�ŖS�̑�����l�Ɏd����ƁA���ꂾ�������̐��U���p�A�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B���Ղɂ���A�u�����̗��O�́A�꒩��[�ł͎����ł��Ȃ��B�N����������v�Ǝv���Ă����B �܂�A����̏�Â���E���Â���̗��O�́A�����܂ł������a������ՂɂȂ��Ă��邩��A���{�����ꂳ��A���̍�����푈���������������Ȃ���ڎ����ł��Ȃ��B�����Ȃ邽�߂ɂ́A �����������������邱�� �������̖����������Ă����悤�Ȍ��͎҂Ɏd���邱�� �����̌��͎҂��A������������悤�ł͍��邱�� �����̂��߂ɂ́A���������҂Ƃ��āA����������ƂƂ��ɑ���Ȃ�����A�����Đ擪�ɂ͗����Ȃ����� �Ƃ����l�������т����Ƃ�����B�@ |
|
|
���������� / ���͂Ƃ̘a��厖�ɂ����Z�p��
�㉺�W�̂Ȃ��Łu�^���v�����܂ꂽ�Ƃ��̐S�� �ӂ��Z�p�҂Ƃ����̂́A�����ɑa���Ƃ�����B�܂�A���܂�l�̂������Ƃ������Ȃ��B���̈Ӗ��ł́A�l�Ԃɂ͓�̃^�C�v������B (1)�`�^�C�v�[�l�����X�g�Ƃ������ʓI�Ȏd���Ɍg����Ă���l�X�B�d���̊W����A�l�ԊW���d������B������E��ɂ����Ă��u�l�̘a�v���d������B (2)�a�^�C�v�X�y�V�����X�g�Ƃ�����Z�p�I�E���I�Ȏd�������Ă���l�X�B�d���̊W����A�����̒m����Z�p�Ɏ��M�������Ă���̂ŁA���܂�l�ԊW�ȂǂƂ������Ƃ��l���Ȃ��B �܂�A�`�^�C�v���A�����܂Łu�l�̘a�v�u�E��̘a�v���d�����Ȃ���d�������Ă����̂ɑ��āA�a�^�C�v�́A�u�����̒m���ƋZ�p�v�𒆐S�ɂ��āA�d�������Ă����B ������`�^�C�v�́A�a�^�C�v�ɑ��āA�u�E��ɑ��ċ��������Ȃ��A�����𗐂����A��������Ȃ��Ƃ�����v�Ɣᔻ����B�Ƃ��낪�A�a�N�C�v�̂ق��́A�t�ɂ`�^�C�v�������ᔻ����B�u�l�̘a���Ƃ��E��̘a���Ƃ��A����Ȃ�����Ȃ����Ƃ���ɐ_�o��G�l���M�[���g���Ă��āA�̐S�̎d���͑a���ɂȂ��Ă���B���܂������͂����̌Q�ꂾ�v�Ƃ����B �����Ƃ����̂́A�{���ė��ł������͂��̂��肪�A��̒��ł����Ǝς��āA���Ȃ̃A�C�f���e�B�e�B�[�������Ă���Ƃ������Ƃ��B���������āA������ӔC���B���ɂȂ��Ă���B�����āA�����N�����Ă��A���̐ӔC�̏��݂��悭������Ȃ��悤�ȍI���Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă���A�Ƃ������Ƃ��B ������A�a�^�C�v�́A�u���ꂽ���͈���тł���A�܂��I�[�P�X�g�����v�ȂǂƂ����B����т́A�����Ă��Ă��A�ꗱ�ꗱ�̕Ă��u����͕Ă��v�Ƃ����A�C�f���e�B�e�B�[��������Ǝ����Ă��邩�炾�Ƃ����̂��B�܂��A�I�[�P�X�g���ł́A�`�[���v���[���K�v�����A����ȏ�ɁA�l�v���[��������Ƃ��Ă��Ȃ���A���������łĂ��Ȃ��A�Ƃ����̂��B�Љ�ŁA�ǂ��������������A��T�ɂ͂����Ȃ��B�����Ƃ����������B �������Ղ��ڎw���������炢���A�Z�p�҂ł���B�����獂�Ղ��A�Z�p�ғ��L�́u���ȐM�v�������āA�ق��Ƃ̋������������悤�Ȑl����������Ȃ��B����������͈Ⴄ�B���ՂقǁA�l�̐S���������A�܂��A���͂Ƃ̘a���������ɂ����喼�͂��Ȃ��B���ꂪ�܂��A�ނ𐬌��������傫�Ȍ����ɂȂ��Ă���B ���ՂɁA�������̃G�s�\�[�h������B���̍ő�̂��̂́A�ނ������A�u�����Ȃ��Ƃ͑傫�Ȃ��ƂƁA�傫�Ȃ��Ƃ͏����Ȃ��ƂƐS����v�Ƃ����Ă������Ƃ��B�܂�A�������厖�̃t�B�[�h�o�b�N�ł���B�����Ȃ��Ƃ��Ǝv���āA���f���Ă���ƁA�ӊO�Ƒ厖�ɂȂ邱�Ƃ�����B �����͑厖�ƍl����B�t�ɑ厖�ɂԂ���ƁA�a�苯�肵�Ă��܂��āA�t�Ɏ��s���Ă��܂��B�u����Ȃ��Ƃ́A�����������Ƃ͂Ȃ��v�Ǝv�����Ƃł���B��������ƁA�ӊO�Ƒ厖���݂��Ƃɉ������邱�Ƃ��ł���B�@ |
|
|
���א쒉�� / �C��ꂷ�镔���͐�
[ �א쒉��/��������(1563-1646)�@�퍑���ォ��]�ˎ��㏉���ɂ����Ă̕����A�喼�B�O�㍑�{�Ï����o�āA�L�O�����q�ˏ���ˎ�B���א�Ə���B�������̎x���E�א쎁�̏o�g�ł���B�����͖��b�E�א쓡�F�B�{���͈ꑰ���B�Ƃ̍א�P�o�B�����͖��q���G�̖��E�ʎq(�ʏ̍א�K���V��)�B�����̖��͐D�c�M���̒��j�E�M�������恂������̂ł���B���R�E�����`���Ǖ���͒��������̂��A���̌�͉H�Ď����̂��Ă������A���Ă̐w��ɍא쎁�֕������B�����`���A�D�c�M���A�L�b�G�g�A����ƍN�ƁA���̗L�͎҂Ɏd���āA���݂܂ő������א�Ƃ̊�b��z�����B�܂����E�H�ւƓ������A���{�l�E���l�Ƃ��Ă��L���ŁA���x���N�̈�l�ɐ�������B�����̗��h�O�֗��̊J�c�ł���B ] �����͂������B�u�������炢���A�Ƃ������Ƃł����H�v�u���������B���A����́A���R�̈ꕔ���B�ނ���A���܂��̂ق�������������Ă���B���邢�͔n���ɂ��Ă���A�Ƃ����Ă��悢�v�u�c�c�v�u�������B���́A��̕��j�����܂����������ɕ����ɓ`���Ă���B����l�ɂ���Ĉz����ȂǂƂ������Ƃ͂��Ȃ��B�����̕����́A���܂����������̂Ɠ����ʁA�������̏��ŏオ���߂�Ƃ���̎d�������Ă���B ���܂��́A������ς��悤�Ƃ���C�������Ȃ��B�����͂��ׂĐ������Ǝv���Ă���B�����̂͑��l�ł���A���ɏ�i�̎����Ǝv���Ă���B����Œ�ϔO�����邩�炾�B����Œ�ϔO�Ƃ����̂́A�������炢���Ƃ������Ƃ��B �d���ɑ���ӌ��̂������Ȃ�A���݊���B���A�D�����炢�͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���܂��͎������炢�A�������܂������炢���D�����E��ɂ���̂͂��݂��ɂ悭�Ȃ��B�ʂꂽ�ق������݂��ɍK�����B���̂܂܂��ƁA������Ȃ��C����K���āA���Ă��������Ȃ��B���d���ɐg������Ȃ��B�ǂ��ł��D���ȂƂ���ɍs���B�����ɂ͒u���Ȃ��v�u�c�c�v�����͂܂������ɂȂ����B�����̕@���ւ��܂�ꂽ���炾�B �ӂ��Ǘ��p�̖ʂł́A"���҂�����i��"���苁�߂��āA"���҂���镔����"�Ƃ������Ƃ͂��܂�_�c����Ȃ��B�Ў藎���ł���B�������A����������莙���g�����Ȃ��Ȃ��ƁA���ԊǗ��E�͔\�͕s��������B �������A�����ɂ́A�����������Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��҂�����B�܂��āu���炢���v�Ƃ���������݂��Ɏ����Ă�����A�ړ_�͂Ȃ��B�����ɕʂ��ׂ����B�א쒉���́A������т����ƍs�Ȃ����D���ꂪ�g�D�̂��߁A�ق��̎Ј��̂��߂��A�ƐM��������ł���B |
|
|
������r�ܘY / �ᒠ�{�ɕt�����l������������ (-1675)
�r�ܘY�������܂�����͍̂]�˂̘H�n���ł���B�������Z��ł���n�悾�B�����������X�́A�܂��������Ȃ��A�̂ł�����ɉႪ�o�Ă����B���������́A�����������Œǂ�����A��Œ@���ׂ��Ȃ���Q�ꂵ���ɑς��Ă����B�r�ܘY���t�b�Ǝv�����̂́A(�ᒠ�����̐l�����ɔ�������ǂ����낤���H)�Ƃ������Ƃ������B���z�͌����ĊԈ���Ă��Ȃ��B���A�X�̎҂����́A �u�ᒠ�Ȃ���Ă��A�ނ�ɂ͔�������������܂����v�ƖҔ������B�r�ܘY�͓������B�������A�ᒠ�͔���Ȃ������B������̂́A�����F�̉ᒠ�������B�r�ܘY�͍l�����B�������Ԉ���Ă���Ƃ͎v���Ȃ���������ł���B (�����́A�ᒠ���~�����͂����B�������A������ᒠ������Ȃ��̂́A�ᒠ�Ɍ���������)�Ǝv�����B����Ȏ��A�ߍ]�̖{�X�ɗp�������āA�r�ܘY�͗��ɏo���B�����āA���C����ʂ��Ĕ����̎R���z�����B�����̎R�̒��ɓ���ƁA��ꂽ�̂ŁA�傫�Ȗ̉��ŋx�B�v�킸�A����������Ă��܂����B�ڂ��o�߂��Ƃ��A�ނ̖ڂ�ł������̂�����B����́A���z�̌��ɋP����t�̗������B�L���L���Ɨz�����Ƃ�Ԃ��̗t�̔������́A���Ƃ������悤���Ȃ��B����ɁA�ƂĂ�������������^����B�t�̌Q����݂߂Ă��邤���ɁA�r�ܘY�͎v�킸�A(���ꂾ�I)�Ƌ��̒��ŋ��B (�ᒠ������Ȃ������̂́A�F�����������̂��B�F�����̗������ΐF�ɂ���A�K�������I) �����m�M�����B �����ŁA�ߍ]�ɖ߂����ނ́A�e�������ߕ��҂��Ă�ŁA�u�������ł��A�������̐F�ʼnᒠ����߂�H�v�����Ă���v�Ɨ��B�����t�́A�r�ܘY�̌�������M�ɋ���Ȃ�����A�d���ɂ��������B ������������F�ɐ��߂��ᒠ�́A��Ԃ悤�ɔ��ꂽ�B�r�ܘY�̍�킪���������̂ł���B�ނ͋����ƂŃS���S���Ɖ�ɐH���Ȃ���A��������߂������̐g�ɂȂ��Ă݂��B (�����������A���������߂�͉̂����낤���H)�ƍl���������̂ł���B�������{���ɋ��߂Ă���̂͒P�ɁA���ǂ�����Ƃ��Ẳᒠ�����ł͂Ȃ��B�������̂͂����B�����Ȃ�ƁA�ᒠ�̐F���������Ȃ�����߂��B �����Őr�ܘY�͉��ǂ������łȂ��A�������������炷�ᒠ�����낤�Ǝv�����̂��B���ꂱ������������ł����A�u�{�̂Ƀ\�t�g�ȕt�����l��������v�Ƃ������Ƃ������B�ᒠ�Ƃ����{�̂ɁA�������Ƃ����t�����l��������q���[�}�j�Y���ɂ���āA�r�ܘY�̏����͑傫�����������̂ł���B�@ |
|
|
���F��R / ���b����Ă��u�F�v�̎v�z
[ �F��R(���܂���� 1619-1691)�@�]�ˎ��㏉���̗z���w�҂ł���B恂͔��p�A���͗���(����ɂ͗lj�)�A�ʏ͎̂��Y���A�㏕�E�q��Ɖ��ށA�R�ƍ����A�����V���ƍ������B ] �������������̂́A�u�F�v�ł���B�����͂��������D�u�F�Ƃ����̂́A�e�ɑ��Ă����łȂ��A�n��ɑ��Ă��F�������B��(���̏ꍇ�͔�)�ɑ��Ă������B����ɓV�ɑ��Ă������B�������邱�Ƃɂ���Đl�Ԃ̐��̒����L���Ŏv�����̂�����̂ɂȂ�v�R�͊��������B�R�͍Ăђr�c�����̑��Ŏd����悤�ɂȂ�A�����͔R�����]���|����w��ł������Ƃ��A��̔ˎm�����ɂ��`����悤�ɖ������B���̋������������ɍL�܂�A���̑喼�Ƃ���A�u�r�c�Ƃ̕��m�͈Ⴄ�v�Ƃ�����悤�ɂȂ����B�Ⴆ�A�Q�Ό��ł́A�喼�������s��������ďh��ɔ��܂�B���̏h���Ԃ���h��̐l�����͔�r�����B�����Ƃ��]���̂悩�����̂��r�c�Ƃ̕��m�����ł���B����͂������B ����ɂȂ�ƁA���̑喼�Ƃł͎�Ȃǂ����đ呛�������邪�A�r�c�Ƃ̉Ɛb�����͐Â��ɏh�����A�����̕��m���Ǐ������Ă���B �����m����������ɂ��ƁA���ŔԂ�����B�̌��ɋC��������A�z�c�������Ȃ����Ă������ȂǁA�����������Ȃ�������B ���r�c�Ƃ��h��𗧂Ƃ��́A�e�����͂��ꂢ�ɑ|������Ă��Đo�ЂƂ����Ă��Ȃ��B �u����́A�F��R�搶�̋����������n���Ă��邩�炾�v�ƁA�h��̐l�����͌�荇�����B �������R���A�r�c�Ƃ̕��m�����̂��ׂĂ����}���Ă����킯�ł͂Ȃ��B�����͂܂��퍑����̋C�����c���Ă����̂ŁA�r�X�����l���������m���c���Ă��āA�������������B�R����̈ꎺ�ŁA�M�S�ȕ��m�����Ɋw��������Ă���ƁA�����Ȃ肻�̕����Ɋ��荞��ł���B�����Ăǂ����ƌӍ��������ƁA�R���ɂ�݂Ȃ���܂��̕��m�����ɑ吺�ł�߂����B �u���̂���́A���̏�̂Ȃ��ɂ����P�b�R�E�Ƃ������Ȓ�����������ł��āA���낢��Ƃ܂�ʂ��Ƃ��������ĂẮA���m����킹�Ă���B���P�b�R�E�ǂ��납�A�����ւ���f�Șb���B����Ȓ��́A�͂₭�E���Ȃ���_�����v �Ƃ��낪�R�͂ɂ��ɂ�����ł���B����ȔR�̑ԓx�ɁA�{�荞���m�̂ق������������Ă��܂��A���������ƕ�������o�Ă����Ă��܂��B����ƔR�́A�u�ł́A������b�����v�ƌ����āA�������Ȃ��������̂悤�ɍu�`�𑱂����B��l�����́A�R�̑ԓx�Ɋ��S�����B�@ |
|
|
���͑����� / �č������Đ��� (-1699)
�吨�̌����l���W�܂��������A�����͂�������̕ĉ���A��Ă���Ă����B�ĉ��݂͂�ȕĕU��S���ł���B�݂�ȃs�b�N�������B��̉����͂��߂�C�Ȃ̂��H�Ɩڂ����������B�����͕ĉ��������w�����āA���������̑��ɂ܂��ĕU����i�ɕ��ׂ������B�����āA�ĉ��������w�����āA�������̕ĕU�̏�Ɉڂ������B�����ĕU�̏�ɏ��ƁA���x�͔��Α��ɕĕU���i�̍����ɐς܂����B�����āA�܂��J�����킹�ď����������ֈڂ��B���x�͂������ɎO�i�A�����Č��������Ɏl�i�Ƃ����悤�ɕĕU�����p���Ȃ���A����ɂ߂��ɂ��܂����掟��ɏ�ɏグ�čs�����B�₪�āA���͌��ɖ߂����B����ɂ́A�����l�������������B���Ǝ҂��l���ڂ����������B�͂��߂͈��ӂ������Ă������̘A�����A�Ō�ɂ͔��肵�āA �u���������I�͑��͓��������v�Ɗ��S�����B �Ƃ��낪�A�����̒m�b�͂���ŏI�����킯�ł͂Ȃ��B�ނ͕ĉ������ɂ������B �u���̕ĕU�́A��������������������̂����A�����K�v�Ȃ��Ȃ����B�����łǂ����낤�H���߂Ă��܂���������������Ă���Ȃ����H��������������l�̔��l�ł����v�ĎY�����̓��b�Ɣ�т��āA��揟���ɕĕU���߂����B ����������{�̏d����������B�����āA�u�����̓z�͂��邢�v�Ƃ������B�Ȃ��ł����Ƃ��������ɁA���̏d���͂����������B �u�������ĕU�������́A�͂��߂��疋�{�������\�Z�̒��ɓ����Ă���B������A�z�͓�d�ɖׂ����̂��v���̂Ƃ��肾�����B�������āA�����͂��̏d���Ƌ߂Â��ɂȂ�A����ɓ������Ƌ{�̏C���Ƃ�����H���܂ň�����悤�ɂȂ����B�@ |
|
|
���m�ȏ��� / ���J�g�̎����������ɕς���
[ �m�ȏ���(1737�`1769)�@�đ�˂̔ˈ�B�Əm�u��䮊فv���J���A�|���E䬌ˁE�ؑ��Ȃǔ˂̗J���̎m���W�߂��B���́u��䮊فv�O���[�v���X���E�q���n�E�Ɣː����v�̒��j�ƂȂ�B�����O�̎���(��R)�Ɋ��҂��A�䕽�F���R�̎t�ɐ��E���Ă���B���������a6�N�A33�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ����B ] ��ɂ���āA�����ɏW�܂��āA�{�Бg�̈����������Ă���]�ˍ��J�g�̂Ƃ���ɁA�����������Ă����B�u���ς�炸���ȁv�Ƌ���A�������A����Ȃ��Ƃ��������B �u�������낻���߂�B�l�̈����͂����ꂵ�����A�����Ă��邨�܂����������Ɩ��������낤�H�����Ɗy�����b������v�u�����Ƃ����v�|���������������B �u�搶�������m�̂悤�ɁA�����͑S���A�{������Ƃ��ꂽ�҂��肾�B�����炭��x�Ɩ{���ɏ����߂���邱�Ƃ͂���܂��B����ȏŁA�ǂ����Ċy�����b�Ȃǂł��܂����v�u�������ȁv�����͏����B �u�l�̈����������Ă���ق����y�������H�v�u�y�����ł��ȁB������������܂��v�u����A���ꂾ�����B�����̒�����͉������܂�ʁv�u�H�v�u�������̓{��͂킩��B���A���̓{��͎��S���B�Ȃ����S�ɕς��Ȃ��̂��H�v�u���S�H�v�u�����B�����킢�A�������͍]�˂ɂƂ��ꂽ�������ŁA���Ԃ����͂����Ղ肠��B���^���x������Ă���̂�����A�H���S�z���Ȃ��B�Ȃ�A���܁A���𗧂ĂĂ���đ�ː��̂ǂ��������̂��A�������Ȃ̂��A�����āA�ǂ�����Ή����ł���̂��A���������c�_�����邱�Ƃ������ă��_�ł͂���܂��H�v�u�������A����ȋc�_�����Ă݂Ă��A���������A�����ɗ��̂ł����H����ꂪ�{���Ŗ��ɂ����Ƃ͓�x�ƂȂ��v�u���Ƃ����ɂ����Ƃ��Ȃ��Ă��A�c�_�������Ƃ��ɂ܂Ƃ߂Ă��������ł͂Ȃ����B�N�����̎m��������A�ڂɂƂ߂Ȃ��킯�ł͂Ȃ��c�v�u�c�c�c�v���J�g�͕p�������킹���B���Ƃ��Ǝd���D���ŁA�ː���J���Ă����l�Ԃ��肾�B �����̂������Ƃ͂킩�����B�����͂��������Ă����B �u���J�l���ƁA�{���A��Ђɂ����ׂ��Ӗ��Ƃ͕ʂ��B�������āA����Y���ȁv�ƁB �����āA�����ɂ͂��łɁ����̎m���̖ڎZ���������B ���q�̎��R�ł���B���R�͍��J�g�̎t�A�䕽�F�Ɋw�����������B���̐��ŁA���̗{�q�a�݂͂ǂ��낪����A�Ǝv���Ă����B ������A���J�g�̔����̋@����A��R�ɂ����Ă��炨���ƁA�S�Ђ����Ɏv���Ă����̂��B ���������J�g�ł���B���A���J�g���܂��������ɂ��Ă��A���J���ꂽ�Ƃ��̂܂܂̐l�Ԃł͂��߂��A�Ǝv���Ă����B �ϐg�Ȃ������ȕϊv���K�v���A�Ǝv���Ă����B���A�������g�A�ЂƂ�ł͎�����ς����Ȃ��B�ς���̂ɂ́A����͈����Ȃ��A�Ƃ������M���ז�������B�O���[�v�Ȃ�ǂ����낤�A�Ƃ���͍l�����B �u�l�Ԃ��l�Ԃɉe����^����B����Ȃ�Ες����邾�낤�v�����āA��������̃O���[�v�ɓ��낤�A�����v���Ď����������߂��B�]�ˍ��J�g�̑�����ʂ��˂�����B����ɁA���J�g�̓}�C�i�X�l�Ԃ��B���A�}�C�i�X�ƃ}�C�i�X��������v���X�ɂȂ�B�����v�����B ������A�{�q�a�������̌������ʂ����p���Ă����ɂ��Ă��A����ꂪ�̂̂܂܂�"�g���u�����[�J�["�ł́A�{���̑ԓx�͍d������B ���̂����A�{�q�a�ɂƂ��Ă������ăv���X�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B �u����Ȃ��ɂ��܂���āv�ƁA�{���l�͔w���ނ���B �u�����������ɕς��悤�v�Ƃ����̂������̍l���ł������B ���̍l���͐��������B�ɓx�̍�����ɔY�ޏ㐙�Ƃ̓���ɂȂ������R�́A"�C�G�X�}��"����������B�����āA���̃O���[�v�ɖڂ����A���̌������ʂ��̗p�����B���̂���́A�O���[�v��������ς��Ă����B�㐙��R�̉��v�𐬌��������̂́A���ɂ��̍]�ˍ��J�g�ł������B |
|
|
���א�d�� / ���v�܂����ꂩ��ҋ����P
[ �א�d��(1721-1785)�@���F�{��6��ˎ�B��4��ˎ�E�א��I�̌ܒj�B�F�{�ˍא��7��B�I�B�ˑ�9��ˎ�E���쎡��Ɓu�I�B���i�فA���̖P���v�ƕ��я܂��ꂽ���N�ł������B ] �d���́A�u���͔�펞�Ȃ̂�����A���ʂ̐l�Ԃł͖��ɗ����Ȃ��v�ƍl���Ă�������ł���B�Ăяo���ꂽ�x�������q��́A�א�d���̘b�����B�����Ď��ނ����B �u����킽�����ɂ͖��܂�܂���v�u����Ȃ��Ƃ������ȁB�킽�������܂���������ŗ��ނ̂��B�ǂ������v�̑��w�����Ƃ��Ă��炢�����v�u�ł��܂���v�u�Ȃ��ł��ʁH�v�u�d��l�ɂ̓{���N���������A�̐S�ȏ����������w�������̕��Ɏ����Ă���܂���B���̂悤�ȏł͂킽������l�łǂ�Ȃɂ�����Ă��A�����ł��܂���B�ł����炨�f�肷��̂ł��v�u���̂ւ�����߂悤�B���܂����v�������Ă𗧂Ă�킽�����w�����Ď�点��悤�ɂ���v�u�{���ł����H�v �x�͊���グ�ċ^�킵�����ɐ����̕��������B�d���͖x���܂��������Ԃ��傫�����Ȃ������B �u���܂��̂������Ƃ͂悭�킩��B�킽�����������Ƃ������Ă���B�{���Ȃ�g�b�v�̂������Ƃ��~�h����ʂ��ă��E�ɓ`�����A�d�����͂��ǂ��Ă����B���Ă���Ƃǂ����^�̃~�h���̂Ƃ���ŏ���܂�A���邢�͉�����̈ӌ��������Ă���B �܂�A�g�b�v�ƃ��E�̊Ԃɗ��ׂ��p�C�v���Ȃ����Ă��邩�A�S�~�����܂��Ă��邩���Ă���̂��B������܂����������Ȃ���A���v�͐i�܂Ȃ��B���܂����܂����������Ă��l����v�u�킩��܂����v �x�̕\��͕ς���Ă����B�����̘b���āA(���̓a�l�͖{�C��)�Ɗ���������ł���B�����ɁA(���̓a�l�Ȃ�A���������܂ōl���Ă������Ƃ����s���Ă���邩������Ȃ�)�Ƃ�����]�̌��������܌������̂��B�����Ŗx�͏d���ɂ������B �u���v�ɂ͓��R�A�܂��匐����s�����ƂƂ��̎��ɑ������W�J���邱�ƂƁA�l�Â�����s�����ƂȂǂ����ɂȂ�܂��B�������匐��Ƃ����͓̂��R��̒��̎d����S���������K�v������܂��B�������Ƃ������Ƃ́A���Ȃ�������Ȃ��d���͂���ɐl��������A���Ȃ��Ă������d���͎v�����Ă�߂Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B�l����𑝂₳���Ƃ���͊�т܂����A�d�������グ����Ƃ���͓{��܂��B�l�ԂƂ����̂͂�͂�ێ�I�Ȃ��̂ŁA���_�^���E�e�_���̃N�Z������܂��B�����̎d�����Ȃ��Ȃ�����E�ꂪ�p�~�����̂���Ԏ҂͒N������܂���B��������������A���ɋ��͂�����ɂ́A���Ƃ����Ă����v�̖ړI��O��I�ɒm�点�[�������Ȃ���Ȃ�܂���B���Ɍ���̔[�����K�v�ł��B�܂��A�a�l���獡�x�̉��v�̂���|���A�����ɂ��đS���ɍ����Ă��������v�u����͂������@���ȁv �d���͎^�������B �d�����S�̒��ŁA(�����̐V�����o�c���j��S�ˎm�ɓO�ꂵ����)�ƍl���Ă�������ł���B ���������M���Ȃ������B �܂肻��Ȃ��Ƃ����Ă��A�u�V�����a�l�́A���悾���ʼn��v���s�����Ƃ��Ă���B���v�͂���ȊÂ����̂ł͂Ȃ��B���ۂɒɂ��v��������̂͌���̕��Ȃv�Ƃ��������N�����Ă���Ǝv���Ă����B �d�����g�͎�������͂������Č����ɓ������ł������A�����ɂ���ẮA�u����Ȃ��Ƃ͂�����܂����v�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B �������A���x�������q�傪�A�u���Ȃ��̍l����S���ɒm�点�ė~�����v�Ƃ����Ă��ꂽ���Ƃɂ͊��ӂ����B�����ŏd���́A�����̍l�����ɂ܂Ƃ߂��B�א�d���́u�܂����̌P�@�v�ƌĂ�Ă�����̂ł���B �P�@���o���ɂ��Ă͖x�������q��́A�u�ɗ͉������m���[������悤�ȌĂт��������Ă��������B���Ƃ����Ă����v�������ɐ��i����̂͂����Ȃ̂ł�����v�Ƃ������B�܂��A�u�P�@�͂������ςȂ��ł̓_���ł��B�������m���������C���N�����悤�ȑҋ����P���l���Ă��������B���͔˂��n�R�Ȃ̂ŏォ�牺�܂ňꗥ�p�[�Z���g�ŋ��^�����炳��Ă���܂��B���߂ĉ��̕������ł����ɖ߂��Ă��������B�������p�[�Z���g���Ƃ����Ă��d��l�̉��p�[�Z���g���Ɖ������m�̉��p�[�Z���g���Ƃł́A�ɂ݂��Ⴂ�܂��B�d���̕��͂��̂܂ܐ����u���A�܂��������m�̕����猳�ɖ߂��Ă������������Ǝv���܂��v �d���͊��S�����B�Ȃ��Ȃ�����Ȃ��Ƃ͂���Ȃ��B�x���㋉���m�̈�l���B�������x�́A�u�킽�����͉��v�̑S�̎w�������̂ł�����A�킽�����̋��^�����͌��ɖ߂��Ă��������v�ȂǂƂ����Z�R�����Ƃ͂���Ȃ������̂ł���B�@ |
|
|
���㐙��R / �������v�̌��ߎ�͐S�̉��v
���ꂪ���ڂ̂Ƃ��ɁA���Z���Ɍ���A����ɊփP���̍���œ���ƍN�ɓG�������ߎO�Z���Ɍ��炳�ꂽ�B�l��ڂ̑����l���ŃS�^�S�^���N����A���̎��ɂ܂���ܖ��Ɍ��炳�ꂽ�B�̂����ׂ�ƈ�Z���̈�ȉ��̋K�͂ɏk�����ꂽ�B �ɂ�������炸�A�đ�˂ł̓��X�g�����s��Ȃ������B�܂茪�M����̐l���A�s���A���Ƃ��낢��ȏK�킵�Ȃǂ��ׂĎ������B����ł͂���Ă�����͂����Ȃ��B���������āA��R�����ڂ̔ˎ�ɂȂ����Ƃ��́A���S�ɍ����j�]�𗈂����A�����ǂ���̎Ԃ̏�ɏ���Ă����B���炩�����Ă�����R�́A�܂��A�u�ˍ����̗��Ē����v���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B ��R�́A�����Č��ɑ��Ă����l����(�p��͌��㕗)�B �u�����Č��́A�P�ɒ���ʂɕ\��ꂽ�Ԏ���������������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�O�o�u������̈��e�����āA���́A���̍��ɏZ�ސl�X�͑��l�̂��Ƃ��l�����A�����̖ڐ�̗��v�����Nj����Ȃ��B����́A�����Ă݂�ΐl�Ԃ̐S�ɐԎ��������Ă���Ƃ������Ƃ��B���̍��������Ȃ���A��̒���̐Ԏ������������Ƃ���ʼn��̖��ɂ������Ȃ��v �����đ�R�́A�_��́u���͕��~�̊�ɏ]���v�Ƃ������t�ŁA�����Z���A���~�̊�����ƍl�����B �u�Z�����S�ɐԎ����Ă���̂́A���������������炾�v�Ƃ������Ƃł���B��������l�Ԃ̏Z�ޗe��ƍl�����̂ł���B �����ł���́A �������Č��̋��ɂ̖ړI�́A���̍��̐����������コ���邱�Ƃ��B �����̂��߂ɂ́A�v�������d���̌������Ƒ匐�K�v�ɂȂ�B ���������A���������ӓ|�ł͓����l�X����]�����ĂȂ��B��������K�v���B ����������s���̂ɂ́A���̒n��̎莝���̎��Y���ő�����������Ƃ��B�莝���̎��Y���������Ƃ������Ƃ́A���Y�Ɋ܂܂�Ă���\�����O���o�����Ƃ��B ������łȂ��Ă��đ�͓��k�Ȃ̂ŁA�k���̓K�p����B�g�������łł���ؖȁA�݂���A�����A�n�[(���[�\�N�̌���)�Ȃǂ��ł��Ȃ��B�����͗A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �������Ȃ�ƁA�����łł���i���������l������H�v������B �����l��������́A�u����������A�̂��ƂȂ݂��ł���̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă��l�Ԃ��B�l�����ߎ肾�v�ƍl�����B�������A����"�l�����ߎ肾"�Ƃ������Ƃ��킩���Ă��A�l�Ԃ̍s����W����ǂ��O����B �������I�ȕ�(���m�̕�) �����x�I�ȕ�(�d�g�݂̕�) ���ӎ��I�ȕ�(������̕�) �ł���B���̂����A�ł��ς���̂��O�ԓ���(������̕�)���B��ᑸ�d�A����ρA�Œ�ϔO�Ȃǂł���B�����ő�R�́A�u�o�c���v�͂܂��A��l�ЂƂ�̐S�̉��v���X�^�[�g�ɂȂ�v�ƍl�����B����́A�u������̕ǂ�j�邽�߂ɂ́A���Ƃ����Ă����C���K�v���v�Ƃ����āA�����قƂ����w�Z���������B�˂̌��C���ł���B���ʃ��X�g���Ƃ����A�OK�Ƃ����āu��c��E�L����E���C��v�Ȃǂ�ߖ邪�A��R�͋t�������B �u������̂Ƃ������A���C���������ׂ����v�Ƃ������B�`���قƂ����̂́A�u����Ƃ����l�Ԃ̔�����������x�������v�Ƃ������Ƃł���B�u��w�v�Ƃ����Â��{�ɏ�����Ă���B����́A�Ɛb�S���ɂ����������B ���g�b�v�͕Ăł���B ���~�h���͊��ł���B �����E���[(��ʂ̏]�ƈ�)�͐d�ł���B �u�ǂ�ȂɕĂ�������ނł��낤�ƁA�܂��d���I�N�^�������������S�R�Ă��Ă��A�̐S�̊�������Ă�����A�����Ă��܂��Ă͐����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��ł������B�@ |
|
|
�����c���� / �]�����x�z���Ă���g�D�����l�ƗZ������
[ ���c����(1806-1855)�@�]�ˎ������Ɋ������˔˂̐����ƁA���ˊw���c�h�̊w�ҁB���ΐ_�Ђ̍Ր_�B ] �u�����B���䂳��̈����𗬂�����͌��������Ă��܂��B�ЂƂ�ЂƂ��т����āA�w��E���e���A�O������������������������̂ł��B������܂Ƃ߂āA�ˌ��ɂ��͂�����A���䂳��̈ٓ������l���Ȃ�����������ł��傤�v�u�l���ٔ��ŁA�������c�v���͋�����B�����āA�u���܂������̋C�����͂悭�킩��B���A�������ĂƂ��������Ȃnj��ʂ͂Ȃ��B�����͂����O�����Ђ邪�����v�u���̂Ƃ��͎a��܂��v�u����Ȃ��Ƃ�������A�ˎm�̑啔�����a�邱�ƂɂȂ�v���̂������Ƃ́A����ɐď��Ɏ��Ă����B�N�����͕s���������B �u���߂ł����H�v�u���߂��B�I�N�͂�邳�ʁv���͂��������ĉƂɖ߂����B���J�Ɏ�(�H���ˎm�B�w�������s�^�x�̒���)���A����K�˂Ă��Ă������B �u�Ⴂ�l�����̖I�N�����Ƃ߂ɂȂ��������ł����H�v�u�����v�u�Ȃ��ł����H�v�u���l�ɂ͂Ƃ��Ă����Ȃ�Ȃ�����ł��v�u�́H�v���ȓ����ɁA���J�͓����̊�������B �u�悭�킩��܂��v�u���`�h�́A�������������Ǝv���Ă��邩����̂̍l�����e���ł��B���������Ƃ����Ă���Ƃ����v��������ŁA���܂������ƂɋC��K��Ȃ��̂ł��B�Ƃ��낪���l�́A������܂��ŋْ����Ă��܂�����A�ǂ�ȏ����Ȃ��Ƃ��e���ɂ��܂���B�e���Ȑ_�o�ƁA�k���ȑT�o���k���Ȑ_�o�����ɂ��܂��Ă��܂��B����ɏ��l��������Ƃ����Ă��A�����������A�܂����邱�Ƃ�����܂���B���Ȃ�ʐ킢�ł��v�u�ł́A���Ȃ������l�ɋ�����̂ł����H�v�u����A������̂ł͂Ȃ����������̂ł��B�������y�̂�����A���肷��̂łȂ��A�ЂƂ�̐l�ԂƂ��Č��������̂ł��B�Ȃ݂�ƁA���ɂ́A�͂��߂��炩���ւ̃A�����M�[���������悤�ł��v�u����ςł��ˁA�������ł��v�u�Ƃ��낪�v�����͏����B�u���̂��Ƃ́A�ˌ��ɋ�����ꂽ�̂ł���v ���͎����̂��Ƃ����s�����B���l����炸�A�����ƗZ�������B���̕]���͂������đg�D�ŁA�����]���������]�����A�Ƃɂ���"�]���̐����H�ꁍ�́A�˂ɑg�D�����l���x�z���Ă���B���̂��Ƃ��Ǘ��҂͖��L���ׂ����B���A�����˂����肨�������g�����Ƃł͌����ĂȂ��B�@ |
|
|
���g�c���A / �킽���͎t�ł͂Ȃ��w�F�ł���
[ �g�c���A(1830-1859)�@���{�̕��m(���B�ˎm)�A�v�z�ƁA����ҁA���w�ҁA�n�挤���Ƃł���B��ʓI�ɖ����ېV�̐��_�I�w���ҁE���_�҂Ƃ��Ēm����B ] �v�ۏm��������p���ꂽ��l�̈�l�ɁA�g�c�h���Y������B�f���̌ܘY���q�傪�o�c���Ă����v�ۏm�́A�w�������������ނ���A�u�����ɖ𗧂ǂݏ����Z�Ղ�������v����j�Ƃ��Ă����B�g�c�h���Y�̉Ƃ͕n���������B�����ŕ�e�́A�u�v�ې搶�̂Ƃ���֍s���āA�ǂݏ����Z�Ղ��K���Ă����Łv�Ƃ������߂ŁA�h���Y�͋v�ۏm�ɒʂ��Ă����B�Ƃ��낪�A���A���m�������p���Ƌ�����j�̓K�����ƕς�����B���A�͏f���̂��߂Ɂw�������m�̋L�x�����������A�f���͕K���������̗��O�����s���Ȃ������B�����ŏ��A�́A�u�w�������m�̋L�x���A�����̎�ɂ���Ď������悤�v�Ǝv���������̂������B�Ƃ��낪�g�c�h���Y�́A�����܂����A�̗��ƂȂ����B �u���ꂱ���A���������߂Ă����{���̊w�₾�v�Ɩڂ��P�������B��e�͋������B�����āA�i�����B �u���A�搶�͊댯�Ȑl������A�������m�ɂ͍s���Ȃ��łق����v �������h���Y�͊J���Ȃ��B�g�c�h���Y�͌�ɁA�����Ɩ��̂��āA�ߌ��ȉ^���ɐg�𓊂��Ă������B����͂Ƃ��ɁA�˓��̍��ʂɋꂵ�ސl�X�̉���ɓw�͂����B�|���^���ɂ��Q�����A�W�����̋��s�̒r�c���ŐV�I�g�ɏP���āA�������B���B�˓@�܂Ŗ߂������A�Ȃ��ɓ���Ă��炦���A���ɖ�O�Őؕ����ĉʂĂ��B�ߌ��̎u�m�ł���B�Ƃ���ŁA�g�c�h���Y�́A�Ƃ��n���������̂ŁA�u�]�˂̔˘Y�ɍs���A�����͋��^���グ�Ă��炦�邩������Ȃ��v�ƍl�����B���ꂪ�����ꂽ�B�����h���Y��炤���N���O�l�����B��쉹�O�Y�A�s�V�i�A�a�O�Y�ł���B�O�l�Ƃ��A���̏鉺���ł͎��ė]���҂������B���܂ł���"��s���N"�ł���B�h���Y���\���A��쉹�O�Y���\���A�����Ďs�V�i�ƍa�O�Y�͏\�l�������B���O�Y�͔˂̐g���̒Ⴂ���m�̎q���ŁA�c�����땃�������Ă����̂ŁA��̎�ň�Ă�ꂽ�B���̂��߂�����ɐ��i���c�B�s�V�i�����e�����Ȃ��ꂾ���̉ƒ�ň�����B����Ȏ�����e���Â₩�����̂��낤�A�킪�܂܂����ς��̏��N�Ɉ���Ă����B�a�O�Y�́A���̏鉺���̍������̎q���B�������A���e�ɁA�u�ƋƂ����v�ƌ���ꂽ���Ƃɔ������Ă����B�a�O�Y�̌������́A�u�q�Ƀy���y�������V���肵�Ă��āA�����Ƃ������̂��܂������Ȃ��B��Ȃ��l�Ԃ��v�Ǝv���Ă����B�O�l���ꂼ��Ɂu��������s���N�ɂȂ������R�v�������Ă����B�����ĕs�v�c�Ȃ��ƂɁA�O�l�Ƃ��g�c�h���Y�����Ă����B�������h���Y�͍]�˂ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������A�ɁA�u�搶�A�킽�����͍]�˂ɍs���܂��̂ŁA���̎O�l��a�����Ă��������܂��v�Ɨ��B���A�̓j�R�j�R���āA�u�������낤�v�Ə��m�����B�O�l�͊�������킹�āA���A�����낶�댩�Ȃ���A�S�̒��ŁA(���܂�Ⴆ�Ȃ��搶����)�Ǝv�����B���A�͂܂���\���������B�������m�ɓ��債���O�l�̔�s���N�ɑ��A���A�́A�u���݂����͉��̂��߂ɕ����������̂��H�v�ƕ������B���O�Y�́A�u�Ƃɂ������Ȃ�����ł��v�Ɠ������B�s�V�i�́A�u�������܂�������������ł��v�Ɠ������B�a�O�Y�́A�u�ƋƂ̍����������̂����₾����ł��v�ƌ������B�J������������A�͗̂����B �u�킩�����B�������A�w��Ƃ����̂͐l�̂��߂ɁA�˂̂��߂ɁA�V���̂��߂ɍs�����̂��B���̕ӂ���悭�b���������v���A�͂����������B�����āA�u���͎t�ł͂Ȃ��B���݂����̊w�F���B������A�킽���ɂ��ׂĂ�u���킩��Ǝv��Ȃ��ł��炢�����B�킽�����ꏏ�ɕ�����B�킽���̒m��Ȃ����Ƃ��A���݂����͂�������m���Ă���͂����B����������Ăق����B�c�_�����悤�v�����������B���A�́A�u�킽���͎t�ł͂Ȃ��w�F�ł���v�Ƃ���������������ɂ������B�܂������̂��Ƃ�"�l"�Ƃ������B�܂菼�A�́A�u�����͊w��̖l�ł���B�w�l���B��l�Ɨ���͂Ȃɂ��ς��Ȃ��B��������l�ɋ����邱�Ƃ����邩������Ȃ����A�������܂���l����w�Ԃ��Ƃ�����v�ƍl���Ă����B�@ |
|
|
����{���n / �����v�����u��
[ ��{���n(1836-1867)�@�]�ˎ��㖖���̎u�m�A�y���ˋ��m�B恂͒��A�A�̂��ɒ��_�B���n�͒ʏ́B���ɍ˒J�~���Y�Ȃǂ̕ϖ�������B�y�����m�ɐ��܂�A�E�˂�����͎u�m�Ƃ��Ċ������A�f�Չ�ЂƐ����g�D�����˂��T�R�В��i��̊C�����j�����������B�F�������̈����A�吭��҂̐����ɐs�͂���ȂǓ|������і����ېV�ɉe����^�����B�吭��Ґ�����1������ɋߍ]�������ňÎE���ꂽ�B1891�N(����24�N)4��8���A���l�ʂ�Ǒ������B ] �t���C�M�̎u���p�������n�́A����T�R�ɖf�ՃO���[�v������B�u�T�R�В��v�Ə̂����B���̑��݂�m�����y���˂����o���āA�u�y���C�����v�ɔ��W������B���������n�́A�C�����̎��含���咣�����B 1 �C�����ɓ���҂͒E�ːl(���R�l)�Ɍ���B 2 �C�����́u�˗�(���v�Nj��̉c�ƍs��)�v���s���B 3 ���̗��v�ɂ���āA�C�����̔�p��d���B 4 �C�����m�̋��^�͑S�������Ƃ���B���������̌���ł͂Ȃ��B �����Ƃ��Ă͒�������Ђ������B���A��ړI�͒��G�̉����𒅂Ă������B�˂̂��߂ɁA�C�M���X����͑D�S�C�����ނ��Ƃ������B����A���A��Ђł��蓯����"���̏��l"�G�F�ʂ������Ă����B���̊C�����̊Ǘ����s�����߂ɓy���˂��璷��o���𖽂���ꂽ�̂͌㓡�ۓ�Y�ł���B���n�͌㓡�ɁA�L���ȁu�D������v����������B����́A�u���얋�{����̂��V���{������B�V���{�́A������𒆐S�ɂ����喼�̘A�������Ƃ���B�c�������B�V�c�����̒��_�ɂ��������v�Ƃ����悤�Ȃ��̂��B�����āA�u���̂��߂ɂ́A���R���܂����悵�đ吭��҂������Ȃ��ׂ��ł��v�ƍ������B���̍\�z�́A�u���a�̖����v���v�ł���B�@ |
|
|
�������W�� / ���{�̎匠�ێ��ɑ傫�Ȋь�������
[ �����W��(1839-1867)�@�]�ˎ������̒��B�ˎm�B�����ɒ��B�˂̑������̎u�m�Ƃ��Ċ����B����ȂǏ�����n�݂��A���B�˂�|���ɕ����t�����B恂͏t���B�ʏ̂͐W��A����A�a���B���͒��v�B���͏��ߓ���A��ɓ��s�Ɖ��߁A���s�����A���C�ꋶ���A���m�ꋶ���Ƃ���������B ] �W�삪������A���s�Ɩ�������̂͂��̒���ł���B���������āA�u���R�ȗ���ŁA���悢��|���s���Ɉڂ镠�Ȃ̂��낤�v�Ǝv��ꂽ�̂����R���B ���v�O�N�܌��\���A���B�˂͊J��C����ʉ߂���O���D��Ђ�������C�������B���͓V�c�̖��߂��B���������ď��R���A���{�Ƃ��Č܌��\������Ί����Ƃ��ĕ����̂́A�����炩�Ɍ����ɂ���āA�u���Ί����������ɐݒ肳�ꂽ�v�Ƃ������ƂɂȂ�B���B�˂͐������B���B�˂����얋�{�ɏ��𔗂����̂́A�����W�삽���ɂ���A�u���{�ɂ���ȗ͂͂Ȃ��v�Ƃ݂Ă�������ł���B�����W��́A�O�N�ɒ����̏�C�ɍs���āA�O�����ɂ�鍑�y�̊����ƁA���̊������ꂽ�y�n���ɂ����āA�����l�����܂�œz��̂悤�ɂ����g���Ă���l���܂��܂��ƌ����B�W��͕��S���A�u���{�́A��ɒ����̓�̕��ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ɛ[���S�Ɍ������B�������A���̓��{��S�����얋�{�͗�ゾ�B���ԉ҂����肵�Ă���B �u���̂܂܂ł́A���{�͖S���̗J���ڂ��݂�B�V�������{���K�v���v�Ƃ���͎v�����B�W�쎩�g�́A���łɊJ���_�҂ł���B �u���܂ł����������Ă��ẮA���{�͍��ێЉ����c�����v�Ƃ������Ƃ͏\���ɔF�����Ă����B���������{�ɂ͂��̔��Ȃ��Ȃ��B���x�̝��Ί������A�u�����̐ݒ肾���͂��Ă������v�Ƃ������܂�������ɈႢ�Ȃ��B�����Œ��B�˂́A���悵�ĊJ��C����ʉ߂���O���D���A���ۂɍU�����͂��߂ĝ��̎����������̂ł���B����́A�u��ɂł���͂��̂Ȃ���{�ɒǂ��āA���{������ɋ��n�ɒǂ��������v�Ƃ����A���B�˗L�u�̐헪�ł��������B �������A�C�����ꂽ�O���D�͖ق��Ă��Ȃ������B�C�M���X�A�t�����X�A�A�����J�A�I�����_�̎l�����A���͑���Ґ����āA���B�ɕɂ���Ă����B���B�˂��悭��������A�Ȃɂ���l���̐V�s����ɂ͂��Ȃ�Ȃ��B���ɘa�r��\������邱�ƂɂȂ����B���̂Ƃ��g�҂ɗ������̂������W��ł���B�����āA�������o�����ă����h���ɗ��w���Ă����ɓ��r�オ�}�����ǂ��Ă����̂ŁA�ɓ���ʖ�Ƃ��đѓ������B���x�ɂ킽����̌��ʁA���̏����Řa�c�����������B ��A���ꂩ��O���D���C����ʉ߂���Ƃ��́A�e�Ɏ�舵�����ƁB ��A�ΒY�A�H���A���ȂNJO���D���K�v�Ƃ���i���́A���B�˂ŗp�ӂ��L���ŋ��^���邱�ƁB ��A���������`�ɔ����Ƃ��́A�O���D�̏�g�������֍`�ɏ㗤���邱�Ƃ�F�߂邱�ƁB ��A�V�������B�˂ɖC��͒u���Ȃ��B�Â��C����C���͂��Ȃ��B ����A���������̂����A����͕��a�ȗF�D�W��z�����Ƃ������̂ł���B�W�������ȏ����Ȃ�ʂɈًc�͂Ȃ��B�S�����m�����B�l�����́A�u���������v�Ƌ����v�������̂����A�W��͂����Ȃ������B �u���Ζ��߂́A�V�c�Ɩ��{����o�����̂ł����āA���B�˂͂��̖��ɏ]�����܂ł��B�Џ������Ƃ肽����A���{����Ƃ�v�Ƌ��s�ɓ˂��������̂ł���B����ɂ́A�l�����������Ԃ��Ȃ������B�̂��ɖ��{�����B�˂ɑ����Ĕ���Ȕ��������x�������ʂɂȂ�B��������{�̗͂���߂��B���̂Ƃ��C�M���X�������Ђ����ɁA���B�ˎg�߂ɑ��A�u�֖�C����ɂ���F����L�N�ԑd�������v�Ɛ\�����ꂽ�B�C�L���X�͂��łɁA���`�������ɂ���Ē�������d���Ă����B�W��́A�f�ł�������ۂ����B�������W��ɁA��C�̌��i���m���Ƃ��ĂȂ��A�����ɗɑ���ڋ��Ȑ��_�������Ă�����A���m���Ă��܂�����������Ȃ��B�����Ȃ�ƁA�S�N�ԕF���́A�u���{�̖@�̂���Ȃ��n��v�Ƃ��āA���`�A�X�y�C���̃W�u�����^���̂悤�Ȉ����ɂȂ��Ă��܂������낤�B�W��̂��̋��ۂ́A�u���{�S���v�̈�[�ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��A�O���̓��{���y�d�������ɂ͂˂̂��A���{�̎匠�ێ��ɑ傫�ȍv���������̂ł���B�@ |
|
|
���͈�p�V�� / ��ݐ��̊�@�ӎ�
[ �͈�p�V��(1827-1868)�@�������̉z�㒷���˖q��Ƃ̉Ɛb�ł���B�u�p�V���v�͗c���E�ʏ̂ŁA�ǂ݂́u���̂����v�B恂͏H�`(�����悵)�B���͑����A�B ] �������ɁA�V���{�R�Ɛ�����z�㒷��(�V���������s)�̕��m�ŁA�͈�p�V���Ƃ����l���������B�z���w���w�сA�u�m�s��������H���Ă����B���ꂪ�d�����Ƃ͕���喼�̖q��Ƃ��������A���̖q��Ƃ̉ƌP�ɁA�u��ݐ��(��ɐ��ɍ݂�)�v�Ƃ������t������B����̊�Ƃɂ������@�ӎ��͂��́A�u��ݐ��v�Ƃ����C�������A�������������邩�ǂ������낤�B���̊�ƎЉ����ꂾ�B�����Љ�ł���B�ڂ�ڂ₵�Ă���A�����܂��Ԃ����B���̍����~�߂���B��������Ȃ����߂ɂ́A�u��ɁA���ɍ݂�Ƃ�����@�ӎ��������Ƃ�����v�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B ���̖�́A�����܂��Ƌ��ɂ��̃g�b�v�Ƒ����ɕ����������b�������B �u��@�ɋ����m�b�҂Ƃ́A�ǂ������v�����K�v���v�ȂǂƂ������Ƃ��b���������B�܂��A�u��@�ł��A���̊�@���܂������������Ȃ��m���l�̎�_�v�ɂ��Ă��A���Ȃ�h煂Ȉӌ������������B ���̃g�b�v�ɂ��킹��ƁA�u�g�D�̒��ɂ́A�����Ȃ��Ă��킩��^�C�v�̐l�ԁE����������킩��^�C�v�̐l�ԁE�����炢���Ă��܂������킩��Ȃ��^�C�v�̐l�Ԃ̎O�Ƃ��肪����v�Ƃ������Ƃł���A�u����Ȃ��Ƃ��킩��l�ԂƁA���������킩��l�Ԃ��m�b�҂ł���A�����炢���Ă��킩��Ȃ��̂͒m���l���v�ƁA���т������ނ����Ă����B�킽���͏��������B |
|
|
�����l�̋C�T���������G�s�\�[�h
�u���p�����́H�v�u��l�ɉ�����v�����܂ł�����ł���B���͂Ƃ���B��������l�́A�u�҂����Ă����v�Ƒ���ɂ��Ȃ��B �ƘV�͓X�̈���ő҂����ꂽ�B���̂��ƂȂ̂œX�͖Z�����B�F�A����܂���Ă���B���A�N���ƘV�ȂNjC�ɂ��Ȃ��B�ƘV�̓W���W�����Ă����B�G�w���Ƃ��A�E�t���Ƃ��P�炢���āA�����̑��݂��֎����邪�A�X�̎҂͒m���炾�B��l���炻�����������Ă���B�X�ɂ͂ق��̋q���o���肷��B�ςȖ������ĉƘV������B�ƘV�͋��J���ƕ���ŁA�����j�ꂻ���ɂȂ����B ��ɂȂ��ēX�͕���ꂽ�B����Ǝ�l���o�Ă����B �u���҂������܂����v�ƃj�R�j�R���Ă���B�������ɓX�̎҂̓n���n�����ĉ����猩������B�����������ȋC�����������āA�ƘV�͂������B�u����́����˂̉ƘV���B������ɁA�킴�킴�����Ƃ���]�˂ɏo�Ă����v���ɒ�����悤�Ȍ������B��l�͖����ŃL�Z���Ƀ^�o�R���߁A�����āA�[�X�Ƌz�����݁A�ӂ����Ɖ����ƘV�̊�ɐ��������B �ƘV�̖ڂɓ{��̐F������A���炾�������Ƌْ������B���Ɏ肪�s�����܂����B�������A���l�͕��R�Ƃ��Ă���B�C�������߂��ƘV�́A������x�u������ɂ킴�킬�]�˂֎Q�����v�Ƃ��肩�������B��l�͉��������Ēm���炾�B ���܂肩�˂��ƘV�́A�u�Ԏ�������I����҂߁I�v�ƂǂȂ����B����Ǝ�l�̓W�����ƉƘV�����߂��B �u���ꂪ�������l�̑ԓx�ł����H�v�u�ȂɁH�v�u�������̂ɁA����Ȃɂ���l������܂����B�肽����A���˂��Ă��݂̂Ȃ����v�u�c�c�v���ɂ���X�̎҂͈�Ăɐ��Ȃ�B�ƘV�͊���\�F�ɕω����������A�₪�ĉƘV�͎��˂����B �u���̂ށc�c�v�Ƃ������B �u���̂ށA����Ȃ��A���݂̂܂��A�ł��v�u�c���݂̂܂��v�u���ӂ��������Ă��܂���ȁB���₢�₾�B��͓˂��Ă��A���͂������A�ڂ������ɂ��ł���B���̂ق��́A�ʂɂ��݂����Ȃ��Ă�������ł���v�u���݂̂܂��I�v�u�吺���o���Ȃ��ł��������v�u�����A������ċA��Ȃ���A���͂Ԃ��̂��B�݂��Ă���Ȃ���A�����ŕ����v�u���ꂪ����Ȃ�ł��B���Ȃ��͕�����āA���Ƃ��ǂ��Ȃ����ł����H�����C�Ƃ������̂ł��v�u�����S�A����͉��������Ƃ���킺�사�v�u���́A�킴�킴�Ƃ����l�������͂��炢�Ȃ�ł��B���̂ق��ŁA�����ł��������Ƃ��肢�����킯�ł͂���܂����v �����˂��ԓ����A���ɋ��̕�݂������ďo�Ă��āA��l��˂������B���₪�点�������̂��A��l�͉ƘV�ɋ���n�����B�����ĉƘV���A�������ƁA�u���Ȃ����͂ɂ́A���̂��炢�̋C�T�������Ȃ�����߂��B�����킴�킴�]�˂ɂ����A���v�Ɠf���̂Ă�悤�ɂ������B��l�͂��̂������ŁA�X�̎҂ɏ��l�̈Ӓn���������̂ł���B �]�k�����A���̂Ƃ��̉ƘV�́A���ɖ߂�ƁA���m���̂ĂċA�_�����Ƃ����B������܂����̐������������Ȃ����̂��B�@ |
|
|
���l����� / ��ː��̎v�z (-1885)
����͈��̃j�q���Y���ɋ߂��B���������₽���H���l���̋��̓��ɗ������̂��B�����āA���̒M�ɂ͂��Ƃ��Ɨ₽���H�����܂��Ă����B ����́A�˂̕��m�K���ɂ��A�₦�Ԃ̂Ȃ����͓����ł���B�������B���s�݂̐����̖������́A���������l�������肳���Ă����B���v�Ƃ����Ƃ������Ă��A���ǁA���܂܂ł̂���́A�ː��{��ˎm���x�ނ��߂̂��̂ł���A�N�v��[�߂�_���▻��������[����s���̂��߂̂��̂ł͂Ȃ��B �����������肪�A��]�ƈ����܂��ɂȂ��ĕl���̋��̒M�ɗ��܂��Ă����B �l����˂́A�������甽�������B����́A���������_�ɁA����܂Ŏ����ł����C�����Ȃ��������g�̐挩�����A�s����̂ɐ������A������s�����_�ɂ����B���̋Ïk���؍����F��̍j�̂ł������B�j�̂Ƃ�����蓯�F��̐ݗ����̂��̂ł������B �l���̔��z�́A�����Ȃ�A�u��ː��̎v�z�v�ł���B�P���̎v�z�Ƃ����Ă������B�[����˂̐��́A����ł����ΐ������ɂ���ׁA�������������B ���Ƃ��A�������͓~�₽���A�Ă͂Ȃ܉������B��ː��͋t�ɓ~�������A�Ă͗₽���B���A��ː����g�ɍۗ����������̕ω�������킯�ł͂Ȃ��B����P���ɋ߂��B�l�Ԃ��������Ƃ�܂��G�߂̕ω��ɂ���āA�₽���Ǝv������A�������Ǝv�����肵�Ă��邾�����B �u����ōs�����v�ƁA�l���͎v�����B�s���I����ł��̂��l���邱�ƁA���̗�������������ɂ������߂ɂ́A��ː��̍P���̎v�z�ōs�����A�Ƃ��߂��̂��B �����āA�������邱�Ƃɂ���āA�����A���O������ŁA���ꂩ��̎Љ��\���ł���A�ƐM�����B�@ |
|
|
������@�g / �K���Nj���������w�� (-1901)
�u��l�ЂƂ�̐l�ԂɁA�K���Nj���������w�₪���w���v�Ƃ����Ƃ���ɂ���Ƃ݂Ă������낤�B���ɁA�u��l�ЂƂ�̐l�Ԃ��A�s�K�ɂ���悤�Ȋw��͊w��ł͂Ȃ��B���w�ł��莀�w�ł���v�Ƃ������ƂɂȂ�B �����ېV�O�̎��w�́A�قƂ�ǂ��A�u�o���ϖ��v�����b�g�[�ɂ��Ă����B�Љ�̑O�ɂ́A���Ȃ��咣���Ȃ������B����A�t�Ɍ����̂��߂ɂ́A���Ȃ�s�K�ɂ��]���ɂ��邱�Ƃ��������߂邩�Ŏ��̔��w�X���������B ���m�ŁA���l�̑��������݂Ă����@�g�ɁA����ȍl���͒ʗp���Ȃ��B �u�l�́A���ۂ̂����Ȃ�ɂȂ�l�Ԃ̎��Ђł͂Ȃ��B�t���B���Ƃ́A�߂��߂��l�̑͐ς̏�ɂ��������v�Ƃ����l�����B �������A������Ƃ����āA�l�����o���A����������������Ƃ����āA���ꂪ���ׂĐ������A���ɂ�������Ƃ͂�����Ȃ��B���̒N���������������Ȃ��悤�ȍl���́A����܂����w�ł͂Ȃ��B�����Ŕނ́A�m���ɁA�u�����̍l���𐢂ɖ₦�B���̂��߂ɁA�����̍l���������̌��t�Ō��\����v�ƁA�����������߂��B����́A���̍l���ւ̈�ʂ̔������݂āA���M����������A���Ȃ����肷�邫�����������낤�A�Ƃ������Ƃ��B����t�B�[�h�o�b�N���u�ł���B�������Ȃ���A�ЂƂ�悪��̂��ʂڂꉮ���萶�ނ��ƂɂȂ�B���ꂪ�@�g���̎Љ�Ƃ̐ڐG���@�ł���A�������ɂ��Ă̍l�����ł��������B�@ �@ |
|
| �����j���� [�D�c�M��] | |
| ��1 �F�����̏t�H�@ | |
|
��(1) �D�c�M���́u�V���z���v�����ӂ���
�퍑����Ɖ]���̂́A���j�w��ł͉��m�̗����I���������\�N(��l����)����n�܂邪�A�R���^�̌��l�͌��T�A�V��(*1)�Ȍ�ł���B�D�c�M���������`��(*2)��i���ď㗌���A�s�̋��Z���{�������Ă���l�S���̓y�q(*3)�̑唼����b�R�̊ґ��m�ł���A�E����~���瓌�C�A�k���ɂ͂т���Ꝅ(*4)�����̎�ɔN�v�����߂��{�莛�Ɏ��߂Ă��鎖���ɜ��R�Ƃ����B �u���̂܂܂ł͕��m�͖łсA�R��(���)��{�莛��̏@�卑�ƂƂȂ��Ă��܂��B�ʐ��ɍӂ��O�ꂵ���@�����v��f�s���˂A�ł������헐�̐��ꂷ�鎖�͂ł��Ȃ��B�v �M�������̂悤�Ɂu�V���z���v�����ӂ������T���N(����Z)�����^�̐퍑����̎n�܂�ƍl����̂��������ƐM����B �� (*1) ���T��1570�`1573��4�N�ԁB�V����1573�`1592��20�N�ԁB (*2) �������{�̑�\�ܑ㏫�R�B�Ώ�P�ۏ���Q�ƁB (*3) ���q���エ��ю�������̋��Z�ƎҁB���݂̎����̂悤�ɕ��i�������Ƃ��ĒS�ۂƂ��A���̎����ɑ���������z�̋��K�������őݗ^�����B (*4) �Ꝅ(�A���A����)�͌��X�A�S����ɂ���Ƃ����Ӗ��B�y��(*4-1)���x�z�ғ��֗v���������s���Ƃ��A�Ꝅ�����������B �y���ɂ��Ꝅ��y�Ꝅ(��������)�Ƃ����B�����������������߂Ƃ������A�y���̎����ӎ������܂������߁A�咣���ׂ�������v�����Ĕ��������B �قƂ�Ǔ�����(*4-2)�̔��z��v���������A�x�z�҂ł�����̉Ɛb�̍��O�ދ���v�������y�Ꝅ(�d���̍��Ꝅ)�A�s��ɂ��N�v�̌��Ƃ�v������Ꝅ���������B�y�����猩��A�����͎���̌�����v�����鐳���ȍs�ׂ������B �퍑����ɁA�퍑�喼�ɂ���~�x�z����������A�y���̎����I���i�����܂�A�y�Ꝅ�̔��������������B (*4-1) �S���̎����I�E�n���I�����ɂ�鋤���g�D(�����`��)�B�y(����)�Ƃ������B (*4-2) �����A�V�c�⏫�R�̑�ւ��ɁA�y�n�E���i�����̏��L�҂֕Ԃ�ׂ��Ƃ���v�z���L���Z�����Ă���A������ƌĂ�ł����B [�Q�l]���{�̓y�n���x�̕ω� ��(1)��������(�����������`���q���㒆��)�܂� ���̓����̑������̐��ɂ����ẮA 1 ���̗̎�(�S�i�A���i�A�ێi�Ȃǂ̎��i������) 2 ���̗̎�Ƃ������Ώd�����鑑�� 3 �ꕔ�̗L�͂Ȗ���S�� ��L�̎O�҂��A���U�C�N��ɍ��݂���u��(*4-3)�v���Ǘ������B�S���A���邢�͂��̐g�����玝���Ȃ���ʂ̔_�ƂȂǂ̗�ׂȎY�Ə]���҂�́A���ꂼ��̗̎�▼��(�݂傤����)�Ɂu�Ɛl�v�A�u���l�v�ȂǂƂ��ď]�����Ă����B�S����̐����E�o�ϊ����̓��U�C�N��́u���v�𒆐S�Ƃ��Ă������߁A�ނ�̏Z���͂܂�ɎU�݂��Ă���A�Z�������W���鑺���Ƃ����`�Ԃ͂Ȃ������B ��(2)���q������� �u�n���v�������E���̂̎x�z��i�߂��̂ŁA�u���v�𒆐S�Ƃ��������o�ς͎p�������A�]���̑������̐����ώ����n�߂��B�S����́A�����z���␅�H�E���H�̏C�z�A���E�����E�헐�ⓐ������̎��q�Ȃǂ��_�@�Ƃ��Ēn���I�Ȍ��������߂��B�܂��E���E�ߋE���ӂŁA�k�n����Z�����������ďZ��m���W������u�����v���`�����ꂽ�B�u�����v�́A���͈͓̔��ɏZ�ޑy��(���ׂ�)�̍\�����Ō`�����ꂽ�̂ŁA�u�y���v�܂��́u�y�v�ƌĂꂽ�B ��(3)��k������ �S���I�ȓ������o�āA�E���ɔ��������u�����v�͊e�n�֊g��B�x�z�P�ʂł��鑑�������(���E�ۂȂ�)�͈̔͂ŁA�����̑y��������Ɍ�������u�y��(�������傤)�v�A�u�y��(��������)�v���`�����ꂽ�B�y����y���́A�S���̒c���E�����̌X���������A���ł��y�������B���Ă����E���ɑ����o�������B�E�����牓�����k�E�֓��E��B�ł́A�y�������L���͈�(�����E���̒P��)�ŁA���₩�ȑ����������`������A������u����(��������)�v�Ƃ����B ��(4)�������� ���̌�������������A���ɂ�鑑���E���̎x�z�ւ̉���������B�y���͎������m�ۂ̂��߁A�����̎�E���̗̎�ł͂Ȃ��A���⍑�l(*4-4)�ƊW�����Ԏ������������B(���̍���) �y���̗L�͎҂̒��ɂ́A���⍑�l�Ǝ�]�W������ŕ��m�ƂȂ�҂����ꂽ�B������u�n��(�����ނ炢)�v�Ƃ����B�y�����Ő������}�����͎̂������㒆��(15���I)����ł���A���m�̗��Ȃǂ̐헐�ɑΉ����邽�߁A�����\�͂����ɍ��܂����B ��(5)�퍑���� �퍑�喼�ɂ���~�x�z�����܂�A�y���̎�����������ɒD���Ă������B�ŏI�I�ɂ́A�L�b�G�g�ɂ��u���_����(����)�v�Ɓu�y�n���L�m�F(���}���n)�v�̌��ʁA�y���Ƃ��������`�Ԃ͏��ŁB�]�ˎ���ɑ����ߐ��������`�����Ă������B�y���̎����Ă��������I���i�́A���J�ʂ␅���ʂȂǂ𒆐S�ɋߐ������ւ��������p������A�������x(*4-5)�╪��(*4-6)���ɂ����鑺�̓���ێ��ɑ傫�Ȗ������ʂ������B (*4-3) �݂傤�B���c(�݂傤�ł�)�B�������̐��ɂ�����x�z�E����(����)�̊�b�P�ʁB (*4-4) ��������B���q����̒n���w���甭���A��k�����ォ�玺������ɏ����̊J���𐄐i�������m�w�B���l�̎�B�u�ݒn�̎�v�̈�ʓI�ď́B (*4-5) �N�v�����P�ʂő��S�̂̐ӔC�Ŕ[�߂鐧�x�B�����̒n�d�����ő������x�͉�́B (*4-6) �Ԃ��B����(�������イ)�Ƃ��B�ߐ����ɂ�����̒m(*4-7)�̈�`�ԂŁA��̑����ɕ����̗̎傪�����ԁB��(��)���������ꂽ���߂ɕ����Ƃ��������B (*4-7) �̎傪�s�g�����y�n�ɑ���x�z����A�����ɏ�������Z���ɑ���x�z���ȂǁB�@ |
|
|
��(2) �����̋����͉p�Y�̏o���ɂ���č��E�����
���j�ォ�猩�Ă������̋����͉p�Y�̏o���ɂ���č��E�����̂���ł���B���{���������A�W�A�ɂ��̊��F��N���ɂ���������V�q�A�V���V�c�̐�(�����I)�ł���B ����ɑ����̂����y�A���R(*1)�̎���ŁA �u�Ƒn�I�Ȕ��z�A����Ȏ���Ɓw��͐_�̎q�Ȃ�x�̐M�O�A�����Ȃ��ȋ^�S�Ɛ����~�ɂ���Ė����̓ƍَ҂ƂȂ�A�₪�Ă͍��O�ɐi�W����v���ꂪ���E�̏퓹�ł���B ���������A�L��Ȓ����嗤���n�߂ē��ꂵ���`�̎n�c��B�Â����̎x�z���Ɏ��߁A�₪�Đ��E�ő�̑�鍑�����������`���M�X�n�[���B���X�A�����ɉɂ��Ȃ��B ���̃`���M�X�n�[���̑��ł���t�r���C�������̍��W�p���O���x�ɋy��ŐN�U���Ă����B�����������̋����͐_���ɂ���Ēזł����B���̗��j�����{�����̐M�O�ƂȂ��Đ_���v�z��a�������A�₪�Ċ��͂̌���ƂȂ�X�����J�Ԃ���B �������̂��M���ł���G�g�Ɏp���ꂽ���y�E���R����Ȃ̂ł���B �� (*1) ���y���R����(���Â�������܂�����)1568�`1603�B�D�c�M���ƖL�b�G�g���V���l�Ƃ��ē��{�̓������������Ă�������B�D�L����(���傭�ق�������)�Ƃ��B�@ |
|
|
��(3) �㐢�̊�ɂ���Ď����_���鎖�͂ł��Ȃ�
�m�̓������킸������H����Ƃ����Ñ�̐��E�j�͌㐢�ɐ��܂ꂽ����(�)�ɂ���Ę_���鎖�͂ł��Ȃ��B�u�͂͐��`�v�Ȃ̂ł���A�M���V�������ɂƂ��ăA���L�T���_�[�A���[�}�l�ɂƂ��Ă̓V�[�U�[�A���������ɂ͎n�c��A�Ö����ɂ̓`���M�X�n�[���A�����ē��{�����ɂ͐M���A�G�g�����p�Y�Ȃ̂ł���B �M���́u�e���ʂȂ�@�E���Ă��܂��@�����B�v�̋�Œm����B�ނ̓V�n����삯��悤�Ȑ��U���ڂ݂āA�����ƌ܌��̌O���̂悤�ȑu�₩����������̂́A������������Ƃ����a�{�P���Ă��Ȃ������̂�鍑�����ł��낤�B�@ |
|
|
��(4) ���q���G�͋ߍ]��{��Z���̗̎�ƂȂ�
���āA���͌��T�O�N(����O)�̏t�B��R�ēy�Ɖ�������b�A��ǂ̂����������ɎR�����]�юn�߂鍠�B�T�䓛�̈�ˉƒ����̑c�E�ዷ��ǍO���A�ߍ]��{��Z���̗̎�ƂȂ������G�̏����ŁA��̊��H�j���ɎQ�����B�ēy�̏���ނ���O�w�̓V������ł��̈Зe�ɑł���A����ɏ���A���ė𑝂��A ����Ȃ�Ł@�N���͐A��ށ@����@�S���Đ����@����̉Y�� �Ɖr���āA�P���ɓw�߂���G�����ĐS����A�]�ɂ����Ȃ������B ���̎O���A���i�e�����Ăє�����|�����B�`����M��(*1)�ƌv���ĐM���œ|�ɎQ�������̂̍����U�ߗ��Ă��ċ��n�ɗ����A�c����l��l���Ɏ����̑����E�Œm��ꂽ���m���̑���������サ�č~������B �� (*1) ���c�M��(������ ����)�B�{���͕��c���M(������ �͂�̂�)�B1521�`1573�B�]��ɗL���Ȑ퍑�����B�b��̎��喼�E�퍑�喼�B�Η������z��̏㐙���M�Ɛ쒆���̐킢���s�Ȃ��M�Z���قڕ���B�㗌�̓r��A�a�v�B�w�b�z�R�Ӂx�ɂ��u���щΎR�̌R���A�b��̌ՁA�㐙���M�̍D�G��v�̃C���[�W���`���B�@ |
|
|
��(5) ���c�M�����O�����œ���ƍN��j��
�M�����Q���㗌�̑�R�����B�ɐi�߉ƍN���O����(�݂������͂�)�Ŋ��s�������̂����̔N(����O)�̕�ł���B�M���̖��ɂ�艇�R�ɎQ�����ǍO�Ɠ����߂�E�������c�R�n�R�c�̏d�����G�Ԃ�����āu��������o�Ȃ������v�炵���B �ɂ������M���͏㗌�r��ŕa�v����̂����A���c�Ƃ͂��̑r���߂��B�@ |
|
|
��(6) �������{�͖������
�M���̎��ɋC�Â��ʋ`���͑����ς炸���d�𑱂������猳�T�l�N(����l)�����A�M���͏\�����̏��R����̐≏���@�������B�����A�`���͎l��߂�����O�Ɍ���ē���䏊���o��ƉF��ꠓ���(*1)�ɓ���M���œ|�̌䋳�����ď������������B ����Ǘ���ɂ����M���͊��ɐ��ɖS���A�{�莛�����A���q�������Ȃ��B�Ɛb�̍א�����q���M�����ɎQ���čU���R�ɉ����L�l�ŁA�ܖ��̑�R�Ɉ͂܂�Ă͂ǂ��ɂ��Ȃ炸�A�c�q��l���ɂ��č~�������B �M���͋`�����E������ł��������A���G�ƏG�g���u����ł͏��R�E�t�̉��������Ԃ�v�Ɛ������ĉ͓���]�̎O�D�`�p�̏�ɒǂ����B���̖V��ɕς�A���R���x�Ɖ��߂��`���͌lje���R��ꠓ���𗎂��A��S�N�̑������{�͂����ɖ�������B����ɏ}����悤�ɔ����ɂ͒��q�A��䂪�ŖS�����B �� (*1) ������͏d�v���_���������A���݂͏�Ղ̐Δ肾�����F���s�����ɂ���B�@ |
|
|
��(7) �M���́A���q�A���A�����Ꝅ��łڂ�
���R��Ǖ������M���͓V�c�ɔ����ēV���A�u���������炩�Ȏ҂��V���̎x�z�҂ƂȂ�v�Ɖ]���Ӗ������N���ɉ��߂������R�E�A�C��v���������A�u���Ȃ��v�ƒ���͂����F�߂��A�V����N(����l)�O���A�M�����]�O�ʎQ�c�ɏ��C�����������ł������B �M���͕s���ɑς����A���q�@�̖����A������(��Ⴝ��)���������������ɒ��������A�V���ɂ��̔e�҂Ԃ���֎������͕̂s痂Ƃ����]���l���Ȃ��B�ނ͋ߐ�����V�ˎ��ł���A���̔�ނȂ��n�����␔�X�̊v���I����͏G�g�A�ƍN��̉����y�ʑ��݂ł������B ���G��ǍO�́A���������l���Ŗ����ɒW���ȕ��������̕��l�ł���B���ꂾ���ɁA�M���������_����������ʋH��̓ƍَ҂ł��鎖��m��ƁA���S���̐M���ɑ��ďG�g�̂悤�ɖӏ]�ł��ʂ͓̂��R�������낤�B �R���e�҂Ƃ��Ă̐M���̕��^�͋����A���q�A���A�����Ꝅ�Ǝ��X�ɉ�ł������B�V���O�N(�����)�ɂ͒��ő��s�d���݂̎O�i���e�ΖԂ�蕐�c�R�n�R�c��S�ł��ĊM�̂����������B�@ |
|
|
��(8) ���q���G�͐ΎR�{�莛��j�ꂸ�A�M���ɏ��������߂�
���ɂ͌��G��叫�Ƃ���O�g�����R��Ґ����Đi�U�����B���c�A�ǍO�����̑g���ƂȂ��ďo�w����Ɛ��X�̎蕿�𗧂āA�N���ɂ͋v���Ԃ�ɋA���B �V���l�N(����Z)�̐����A���c�͑�a���Ƃ��ĉF��ꠓ���ɍ݂��������b�E���c�����������ďt���_�ЂŊϐ��A�����A���t�̎O���̐d�\���Â����B�ǍO���M���ɋ�����ė�Ȃ���ƁA�q���Ƃ��]���ׂ�����̎���_�Ђ̊ϐ�����̐l�X�Ƃ��Ȃ��₩�Ȉꎞ���߂��Ă���B ��a����̔ނ�ɂƂ��ĉ����O��Ƃ���̂͐����V�c�̐�����n�܂����H�̎�{�����(*1)�̗��L�n�▜���L�y�̍ՓT���啧�ĖS�ȗ��A���₳�ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���̂��Č����鎖�������B �R���ї��𗊂����`���̍����ɂ���āA�l���ɓ����G��R�c�����X�ƓS�ǂ̎����ւ�ΎR�{�莛�ɓ������B�����m�����M���͖��q�R�c�ɏo���𖽂���B ���c�ɗ�����ꂽ���c���͖ؒÂ�ҍU�������A�_������Č��c�͓����A���c�͐h�����ēV�����ɔs������B�����ɏ悶���ΎR���̒nj��ɂ������̌��G�� �u�}�����R������˂ΑS�ł����Ȃ��v�Ƒi�����B �� (*1) �t����{����ՁB�t����Ђ̐ێЂł����{�_�Ђ̂��Ղ�B��������̕ۉ���N(1136�N)�Ɋ֔��������ʂ��܍��L���A�������y���F�肵���̂��n�܂�B��a�ꍑ�������Đ���Ɏ���s����B�@ |
|
|
��(9) �M���͏��c�ɑ�a�������
�����m�����M���͎���S�R���炸�̐e�q���𗦂��ċ킯�����B�e�e�ɏ����Ȃ��畨�Ƃ�������]��(*1)�𗎂��Ə��c���ĂԁB �u��������������a�̎��Ɏ旧�Ă悤�B���������������ĉ��Ƃł����Đؔ�����v��������������ނ� �u���ꂼ������̐��ˍہA�\�܂���Z�\�܂ł̒j�͂��ׂďo�w�����v�ƌ������ĕK���ɓ����ɂ��藧�Ă�B �R�����X����� �u����̐g�Ő��ɂ͍s���ʁB�s���s�x�Ő폟�F��̓njo�ɗ�ނ���v�Ƌ�������č���ʂĂ��B����������ǍO�͈ꑰ�����𓊂��A���߂����͂œV�����ɒy������B�ʍӊo��œG�̑��w��˂��A���ɓG��{�莛���ɉ��Ԃ����̂ŁA���̗͐�������M���͑傢�Ɋ�B �� (*1) ���{�����s��]�쒬2-9-2��]�������فB���݂͏�Ղ̐Δ肾��������B�@ |
|
|
��(10) �M���͈��y���z��
�����ēV���l�N(����Z)���t�A���y�ɑs��Ȏ��w�̓V��t�������邪��������B �����œ��{�̏�ɂ��Ē��߂Č��悤�B��ؐ����̐瑁��͕ʂƂ��Đ퍑����ɓ����Ă���̒z��Z�p�͂����Đi�܂��A�����グ�y�ǂɍ������ƌĂ��E���x�̖ؑ��Ɖ��ł����Ȃ������B���������T���N(��܌ܔ�)�����R�P�ۏ�̎O�K�E���������i�e�����ޗǂ̑������M�M�R��Ɏn�߂ēV��t������ď��������������B �V���O�N(�����)�A�M���͏��i���瑽��������グ�ďڂ������̓��e�ׂ�Ɠ����A�z��̖��l�Ƃ��]��ꂽ���q���G�ɐv�����A�O�H���G�̎w�����ɒ��ˊэH���ŏo���������̂����y��(*1)�ł���B �S�C�U�������鑍�Ί_�͋ߍ]�̌����O(*2)�̖�ʐ�(*3)�Z�p���̗p�����B��V��t�́A�����嗤����`��鎛�@���z���ؕ����v�����Ď����ꂽ���؈�ࣂ��錚���ł���B�O�l�鋳�t(*4)�������u���[���b�p�ɗ�����ʑf���炵���|�p�I�ȏ�I�v�Ƌ��Q�����B ���̐鋳�t�ɂ��ƁA��K�̐Α��̏�Ɍܑw���K�̐v�ŁA�ŏ㕔�͓��O���⊢�����ׂċ����B���͍����ŁA�����ɋ��̊�����t���A�����[���ɂ���ƋP���Č������B�Z�K�͔��p�`�œ����͋��B�O���͎�h�ŁA�����ɂ��͂◴�Ղ��悩��Ă����Ɖ]���B�\���߂������̈Зe���ւ�l�������G�g��ƍN�́A�₪�Ă������{�ɁA��苐��ȏ��z���グ�鎞�オ��������B �� (*1) ��Ղ͎��ꌧ���y���B�ʌ���(�ՍϏ@)�̎��L�n�B2006 / 9 / 1��茩�w����l500�~�A�����w��100�~�B�J�R����9�F00�A�ŏI��t16�F00�B�߂��Ɂu�M���̊فv�u���y��l�Ô����فv������B (*2) ���̂����イ�B�D�L����Ɋ���B���@���s�Ȃǂ̐Ί_�{�H���s�����y�؋Z�p�ҏW�c�B���ꌧ��Îs��{������(*2-1)�o�g�ŁA�Õ��z���Ȃǂ��s���Ă����H�̖���ł���Ƃ����B���y��̐Ί_���{�H�������ƂŁA�M����G�g��ɂ���ď�s�̐Ί_�\�z�ɂ��g���B�]�ˎ��㏉���ɂ����đ����̏�̐Ί_�������O�̎w���̂��Ƃō���A�ނ�͑S���̔˂ɏ���������ꂽ�Ƃ����B ���݂ł��A��{�̒��ɑ����������ԁu���V�v�Ƃ��鉄��̖��[�̎��@�Q�́A�ނ�̑g�Ί_�ň͂܂꒬���݂ɓ�����^���Ă���B (*2-1) �����̗��B��b�R�̎R�[�̍�{�̋ߍx�B��{�͉���Ɠ��g��Ђ̖�O���B (*3) �̂Â�Â݁B�Ί_�̐ςݕ��B�ق��ɁA�u�ō��݃n�M�v�u�؍��݃n�M�v�u�Z�ؐς�(���Â�)�v�u�z��(�ʂ̂Â�)�v���A��������B (*4) ���C�X�E�t���C�X�B�Ώ�P�ۏ���Q�ƁB�@ |
|
|
��(11) ���䏇�c�͑�a���ɁA��˗ǍO��ꠓ����ɂȂ�
��������̉�������̖��������ė��������y��ɂ��u�V���z���v�̓��ɑ傫�������i�߂��M���́A���q���G�̐i���œ��䏇�c���a���ɗǍO��ꠓ����ɔC����B ���i�e���ɂ���Ē����ꂵ�߂��Ă������c�͍����a�l�\���̗̎�ƂȂ����B�����������P�ۏ�ŋ�l�����ǍO�́A�����`���ƉƐb��ꠓ����ď邵�A��a���̌��c���Z��ł����F��ꠓ���^����ꂽ�B�ǍO�͏���F�����Ɖ��߂ĉ䐢�̏t���}����B �F���Ɖ]���ΐ̂��狞�ւ̓��֖̊�Ƃ��Ēm��ꂽ�v�n�ŁA�����͒��̖{��ŗL���ƂȂ��Ă����B���͊��q����̑T�m�h��(*1)�������������R���̖��b(*2)���V������ďグ���̔������F���������ɈڐA���Đ��ꂽ�����ŁA�����Ȍ�͍ō��Ƃ���Ă����B �i�R���N(��ܘZ��)�ɏ��i�e������m���x�������A�F�����̒����ɐ݂����O�̊Ԃ��狂�ݏグ�������ōÂ�������L���ł���B�������{�͐����Ǝ҂�ی쉺�ɓ���Đ��Y�ɗ͂����Ă����B �M���̐��ɂȂ�ƐX�A�㑺���𒃓���Ƃ��ď��������S�l�̐E�l���g���đ��Y���ċ���B���̒n�̗̎�ɂ͒����ɂ��ڂ������������̕������K�v�ŁA���̓_���猩�ĐM�����ǍO��I�̂͐l�����閾���������Ɖ]����B �ǍO�́A���莅��_�Ђ̊y���E(*3)�������ϐ��ꑰ����H���\�u�䓛�v�ɂ��Ȃ�ő���ꂽ����Ă̈�i�g�T�䓛�h�������Ă����B���x�̈�m��q�ł���R��@��(*4)����������āu��˒��q�v�Ǝ^���A�������l�̊Ԃɑ�]���ƂȂ����̂������ł��낤�B �X�ɂ͐V�̎�ƂȂ����ǍO���́A��a�Îs�ł͂�����ĕ��C�Ɠl��(*5)��g�������u�ҊԒ���(*6)�v�̗V�т�����ꂽ�̂����s���Ĉ�i�ƌi�C�����߂��悤���B �� (*1) ���������B�悤�����B1141�`1215�B�ՍϏ@�̊J�c�B���m���̊J�R�B�i���̏K������{�ɓ`�����B (*2) ���O�̗����Q�ƁB (*3) ���y���\�̌����B (*4) ��܂̂����̂������B1544�`1590�B��̍����Œ��l�B�����Ƃ��ĖL�b�G�g�Ɏd���Ă������A�V��12�N�Ɏ����O�̌��̈�������G�g�̓{����A�Q�l�B�O�c���ƂɎd���邪�A��14�N�ɍĂяG�g��{�点�č���R�֓����B���̌�A���c���̖k�����Ɏd�����B��18�N�̏G�g�̏��c���U�߂̍ۂɂ́A���x����ďG�g�Ɩʉ�B�܂����G�g�̓{����A���ƕ@���킪��đł���B���N46�B (*5) �Ƃ�����B�����Ƃ��B��X�̒���_�ĂāA�����̐l�ɋ����A���̎Y�n���ނȂǂĂ钃�Z�B�����`���̍�����ɂȂ�A�����Ԃ���A�����ɔ��W����悤�ɂȂ����Ƃ�����B (*6) ���C���Ƃ��Ȃ������B |
|
|
��(12) �M���́u�S�b�D�v��A�����`���͍ċ��Ɍ����ƂȂ�
����Ȓ��ɂ������Ă��K���B �ς炸�D�c�R�̖{�莛�U�߂������Ă������A���s�̓S�C���ɑ����̏��m������������łȂ��A�ΎR�ɕ��Ƃ�A�����ė����ї����R���P�������D�c���R���V����u�ق��낭�e�v�ɑ�s�����B���X�ƕ����H��������ɓ͂��A�{�莛�@�k�̎u�C�͑傢�ɋ������B �M���͉��������Ƃ����炪������ɂȂ肩�˂ʁA�Ɛ틵�������B�ނ͗���w���ɗ����ē킵�Ȃ���A�ї����R����ł�����ׂɁu�D�̂�S������C��������͑���Ґ�����v�Ɖ]���V��@���v�����A��S�×�(*1)�Ɍ����𖽂����B���̓V�˓I���z�ɐ���܂����×��͒����ɒ��H�ɋA��A�ˊэ�ƂŎ��ǂ̑����D(*2)�̌����Ɍ����ƂȂ�B �V���l�N(����O)�̏H�A��˗ǍO��ꠓ����Ƃ��ė̖��̐M�����W�߁A�F���̒����H�Ղ�œ�����Ă������B�`����ꠓ������狌�b�Ƌ��ɉ͓���]����I�ɗR�ǂ̋��~���Ȃǂ�]�X�Ƃ����炢�ċ��Ɍ����ƂȂ��Ă����B�₪�Ėї��𗊂��Ĕ�����ւɓ@��Ⴂ�A�����������ɏ㐙�E���c��ɋ��s�i��������A�X�Ɉɐ��O���J�ɉB�����Ă���k���(*3)�ɖ��g��h�� �u�ɐ��F��̍����B���������ĐM���œ|�̕��������A�ї��A���c�Ƌ�������W�J����v�Ƃ̌䋳���������炵���B��͕��S�̘V�b�Ɩ��d�̖��A�x�����P(*4)�� �u�ɉ�E�ҋ��ƐԉH�̉������ɋ��͂�����́A�����������M���̑��͂������Ē������U�ߎ��A��������͒����̂͂��ׂĂ��Ȃ��ɗ^���悤�v�Ƃ̖����𑗂����B �� (*1) �����悵�����B�퍑�����E�喼�B��S���R�𗦂����B��S���̑�8�㓖��B�u���̍��l�̈���Ƃ��Đg���N�����A�M���E�G�g�̂��������R�Ƃ��Ċ���B3��5000�̘\���B��Ɋփ����̐킢�Ő��R�ɗ^���A�s��Ď��Q�B (*2) �����������ԂˁB�R�D�B����D�̑�^�̂��̂�����ƌĂԁB�L���ȐM���́u�S�b�D�v�͖ї����̐��R����������Ί�̍U���ɂ��ޏĂ�h�����߁A�����A���E�I�ɂ݂Ă��������S���肾�����B��C�Ƒ�S�C�ő���������p�Ŗї�����G��O�̐��R�Ɛ�����B (*3) �������� �Ƃ��̂�B�ɐ����i�ł���k���Ƃ̑�8�㓖��B1528�`1576�B�ɐ����Z�S���x�z���Ă������쎁�Ɛ킢�A��̎��j�E�����쎁�̗{�k�q�Ƃ��Đ��͊g��B�M���̐N�U���A�~���B�M���̎��j�E�M�Y��{�k�q�Ƃ��Č}�����ꂽ�B�o�Ƃ��ĎO���J(���C�S��䒬)�ɉB���������A�E�Q�����B���N49�B (*4) �ق�̂��������悵�B1549�`1615� �F��ʓ�� ���[�硁@ |
|
|
��(13) �M���A�k����̖d�E�𖽂���
�k����̖��������ėE�ݗ������x�����P�͏������W�߂�ƁA�����D�c�����Ē�������͂��A���̑��͂ŖҍU�����B ���̉����r�ܘY�͕K���̍R������������A�\�����̗��̖�A�ɉ�E�ґ�����ɐ������ĕ������B���̉������đ����̖x�����Ɍĉ����A���Â����̝��肩��ԉH����ܕS����ĂɍU�߉����������ǂ͈�ς����B��Ɖ^�������ɂ���o������߂������͏���́u�e�G���v�ƌĂ�鏬���ɉ������A�͂��ȕ��S�B�ƕʂ�̔u�����������n���ĉʂĂ��B ����悭�����𗎂��A���̏��ɉ����V�V���C�������P�͋щY��т܂ł��x�z���ɓ���A��ɐ��X�̍v�������ĐV�{�ɋA�����B�������A���ꂩ��͂���J����A���c�����ɑ�������̖�������ɓ��ꂽ�M���͌��{���āA�M�Y�ɋ�̖d�E�𖽂����B �V���l�N(����O)�\�ꌎ���A��₻�̈ꑰ�d�b��\�]�l���M�Y�ɂ����ߐb�B�ɂ�����x��������A���̖���Œm��ꂽ��������̖��ɖ��S�ȍŌ���Ƃ���B �����m�����k���ƒ��͑呛���ƂȂ����B���N(����l)�����ɂ͓ޗNj���������@�傾������̖��킪�ґ����Ėk����e�Ə̂��A�Ƃ̍ċ��Ɍ��N�����B�ɉ�̋g�����Ă�ɏ������Ĉɐ��ɐi�U����B �k���ꖜ�]�̉Ɛb�Q�͏d��̎�Ƃɏ}���ċ`���т���Ƃ��钉�b��A�M�Y�ɂ��Ĉ��������Ɩ�]��R�₷�A���œ�����ԂƂȂ����B��e���͑��C���R����n�߁A�e�n�ŕ������d�˂��A�吨���Ȃ��A�Ō�Ɏc���ꂽ��ҒJ�̐X�邪�������A�`�Ɍł��ɉꍋ���̐s�͂ňɉ�_�˂̉�R(*1)�Ɋق�z���A�k���ċ��ɓw�߂��B�������A���ꂪ�M���̓{����ɉ�̑嗐���������ΐ��ƂȂ�̂ł���B �� (*1) ��R��͎O�d���ɉ�s��_�ˎ���R�B�Ŋ��w�͋ߓS�ɉ�_�ˉw�B�ق��ɁA�O�d�������s�ފ_�Ɉɉ�k����e��ՂȂǂ�����B�@ |
|
| ��2�@�V���ɉ�m���@ | |
| ��2.1�@�M�̕� �@ | |
|
��(1) �m�ؒ����͐M���ɏ]��
�w�ɗ��L�x�ɉ]���B �u����ɗz�͌ŕ̏����Ȃ�Nj����͂��\�����A���͑��̗���тсA���͓��R�̛ӂɌb�܂ꗀ��J���Č܍��L���B�R���Đl��~�p�ɂ��ĉؔ��ɗ��ꂸ���ɓV�{�Ƃ��̂�����鑠�̍��Ȃ�v �����ʼn��߂Ĉɉꕽ���̗��j��H�낤�B�d�m�Y�ň�去���ŖS�����悤�ɉ]���Ă��邪�A�����͂����łȂ��k�ɉ�ɂ͒��c�A�����A�ѐA�̈ꑰ�����������c��A�ɉ�E�҂Œm��ꂽ�Z�\�Z�Ƃ̑唼�͂��̗���������Ɖ]���Ă��ǂ��B ���ł��A�L���ȕ�������������ƍN�Ɏd���g�S�̔����h�ƈ�����Ă����@���A��E�Ɖ]����S�n�A���сA���n�Ƃ͊e�n�̑喼�Ɍ���ėb���_������B���ɓS�C�n����͎G��A�����ɂ����ʖ��l�A��肪�����Ă����B �ɉ���̔ނ�̓���͌�̎F�����l�̔@���A�ߑO���͉ҋƂɗ�݁A�ߌ�͔E�т̒b���ɐ�O���c�����ł߂��B�����̑喼���̉�����������A �u�ɉꎘ�͗Ⴆ�b�S�̖Ԃ��߂��点����ɂ����X�Ɛ������A�����ǂ�[���x�����̔@���ɔ�щz���Ҏґ����v�Ƌ����ꂽ�B �R���M�����ɐ������ɏ��o����A�����̕�������@�������̌����A�m�ؒ���(*2)�͉i�\�\��.�N(��ܘZ��)�����A�i��ŐM���ɋA�������B�M������������ �u����Ƃ��ɉ�̓������Ԃ��ɒm�点�Ē������߂Ό����đe���ɂ͂��ʂ��v�ƖĂ���B �� (*1) ����B����7�N(1679)�ɋe���@��(*1-1)���ҏq�B�V��9�N�̐M���ɉ�U��(�V���ɉ�̗�)�ɁA�ɉ�̏������c�����ė������������T�v�������L�������́B�����̏����炪�قƂ�ǖԗ�����Ă��茤�������Ƃ��Ă��]���������B (*1-1) ���������ɂ傰��B1615�`1703�B�ɉ��앟�������܂�B�o���͐��a���������̗�������݁A�������e�������N�������Ɠ`���B�@���͈ɉ���Ŏ������c�ޗT���ȏ��ƋƂ��p���A�w����D�݁A�a�̂��悭�����B�u�ɗ��L�v�̑��ɁA�r�ؖ��E�q��̋w�������^�u�E�@�@�L�v�A�ɉ�̒n���u�ɐ�����(����������)�v�A���b���W�߂��u���I���q(�����肻����)�v�A�咘�u�����ꓝ(150��)�v�Ȃǂ킷�B�܂��A�u�ɉꍑ�E�p��@�v��u�ɉ�E�ҍl�v�Ƃ����A�ɉ�E�p�����̘_�l������B 79�Ŗv�����@���̕揊�́A�ɉ�s��i���B�e���@�����a�Ƃ̑O�ɐΔ肪����B (*2) �M���̖k���U�߂ɐ�A����v����ĐM���ɍ~��w�V�ÏG�O�N�������x�B |
|
|
��(2) �ɉ�V���̗� / �O�� ��N��A���T��N(�����)�ɂȂ�Ƃ����������ɂ��Ƃ������B���M���̐M�������m�؋`��(*1)���ɉ���ɕA�\��l�̗L�͍�����]�c�O�ɑI��ō����ɎQ�悵�A�V���O�N(�����)�A�k���M�Y(�M���̎��j)������ƂȂ�₻�̎P���ɎQ�����B ���ꂾ���ɍŋ߈ꕔ�̍����B���ɉ�_�ˁE��R�̖k����e�������A���M���h�̘Z�p����(*2)�̖����ȂɌ}�������čċ��ɐs�͂��Ă��鎖������ΐM���̐N�U���ĂԎ��͕K���ł���B�m�؋`�������Ƃ��v���~�܂点��Ƃ����͓̂��R�ł��낤�B ���˂Ęa���h�Œm��ꂽ�����E��ޒm�̍����E���R�b���A�ѐA�̊���(*3)�E���n�ɗ\���͓V���R������(*4)�̒��V�B�Ɏ����̗������� �u���̂܁T�ł͌ܕS�N�s�����ւ�_���̗��ɉ�̋��y���K����ɐN�����͕̂K��ł��艽�Ƃ��a���̓����v�Ɨv�������B ���V�B�� �u��ɋ��c�̍ۂɐ\���グ���ʂ�A�����͗����ł���̂ɍŋ߂̎Ⴂ�҂͕��ɕЊ���ČȂ̖����������ʎ҂�A�m�̂����ɖ�����ꑄ�Ⓛ��U�Čo����ǂ߂��P�ǂȗ��l����@�܂݂ɂȂ��Ă���̂��ڂɗ����ĉ��Ƃ��S�z�łȂ�ʁv�ƐF�X�ƌ��C�̍r�m�⋽�m����Ԃ߁A�M���̓{���ʂ悤�ɓw�߂Ă����B �K���k���̖S�V���l�N(����Z)�͎��Ȃ��ςB �� (*1) �ɂ��悵�݁B�ɉ���Ƃ��āA���T��N(1571)�D�c�M���̎x�����A�ɉ�ɓ����B�������A�����Ɋ�������y�����܂Ƃ߂��ꂸ�ɁA�V���Z�N(1578)�ɉ��Ǖ�����b��ɓ��ꂽ�B�M���̉Ɛb�c�ɂ́u�����v�̖������邪�A�m�؋`���Ɠ���l�����͕s���B (*2) ����������傤�Ă��B�B����̖��O�B�{���͋`��(�悵����)�B��ߍ]�̎��喼�E�퍑�喼�B�ω������B��13�㏫�R�E�����`�P��������ĎO�D���c�Ɛ킢�s��B�`�P�����s�ɖ߂��Ėʖڂ�ۂB�]���Ă�����䒷�������R����s�B�d�b�S�E�����ň�x�ω����邩��ǂ��Ă���B�M���̉��R�v�������₵�đ�s�B�b��ɓ����A�Z�p�Ƃ͖ŖS�B�����`�����M����͖Ԃ��`������ƁA�`���͋w�G�̐�䒷����ƌ���Ő키���s��č~���B�ċւ���邪�M�y�ɓ��S�B���̌�͕s�������A�G�g�����N�ɋ`���������B���N78�B (*3) �W�c�𗦂���ҁB�͂�������B (*4) �V���R�������B�O�d���ɉ�s�_�ˁB�ێR��Ղ��߂��B�Ŋ��w�͋ߓS�ێR�w�B�Ȃ��ێR��Ղ͎O�d���ɉ�s���_�ˎ���c�B�Ŋ��w�͋ߓS�ێR�w�܂��͏�щw�B�@ |
|
|
��(3) �ɉ���̐m�؋`�����Ǖ������B
�V���Z�N(�����)�ɂȂ�ƍd�h�̑�\�Ƃ��]���ׂ����c�̕S�c�����q���Əd��̉ƕ�ł��镧����m���Ԃ��Ȃ��̂ɕ��𗧂Ċقɉ������Ēǂ������Ɖ]���������u�������B �����m���ď�약�y��(*1)�ɏW�����]�c�O�͖����̑��\�Y�A���c�̕S�c�A�����̕���c�A�؋��̒���A�͍��̓c���A���H�E���J���̕x���A�˓ߋ�̏���A��y�̒����A���m��̉Ɗ�A�z���E�����g�̐A�c�̖ʁX�ł���B��������m�̉��������ɕ��𗧂ĂĕS�c�ɖ������āA���V�B�̔�������A �u�Ȍ�͐D�c�̑��̂����������i�Ȃǂ͖��p����I�v�Ǝ���Ɨ��̐��ɖ߂��Ă��܂����B����͉��Ƃ�����̗����m��ʋ���ł������ƌ��킴��Ȃ��B �����炪��ɉ��E�o�����m�͒����Ɉ��y�ɎQ�サ�ĐM���Ɉɉꋽ�m����遖���F�X�Ɛj���_��ɑi�����ɈႢ�Ȃ��B�M�������{�����낤���A�ނ��抪�����͂̏���猩�āA�I舂Ɏ���o���ĕ^���ŕ������ɉ�E�ҋ��ɖ����ׂ����߂Ă͎Z�Ղɍ���ʂƊ������炵���A�b���͉��̓����������Ă��Ȃ��B �� (*1) �������̔���Ō��Ă�ꂽ�Ƃ����B�V���ɉ�̗��ŏĎ��B�V��13�N(1585)�ɉ�ꍑ�̗̎�Ƃ��Ĉڂ��Ă�����a�S�R���E����莟���A���y����ɉꍑ���E�m�؎��̊ق̂������ՂɐV���z�����B�@ |
|
|
��(4) �G�ꑷ�s���M���ɏ���
�������łɎO�S�����z���鏊�̂Ă����M���ɂ͈ɉ�\���͖��ł͂Ȃ������B��������A�ΎR�{�莛�̓�U�s���Ԃ�Ɏ���Ă������� �u����ς���͂̍����ł���G��}��������鎖���挈�ł���v�Ƒ��c�}(*1)�⍪���̐��m�V(*2)�������������Ė����ɂ����B �V���ܔN(�����)�A�M��(�M���̒��j)�A�G�g�A����̖������镐�����ܖ��̕��𗦂��ċI�ɂɐi�U�����B �O���ɂȂ�ƐM�������c�}�̐擱�ŋI�O�䎛�R�[�ɐw��i�߂�B��c�A�����O�̗����m�������s�͐��ȗ��̉����[���x����F��O�ɋ}�g�����ĉ��R������B�x�����P�̏����̒��j�E�����������~�D�ɏ悶�ĎG���ɓ���A�O���O���A��[�͋I�m��̎x���G���Ő��ė����ꂽ�B ���˂đ��s�͎G���т̏�X�̎����ł߂�Ƌ��ɁA�G���ɑ�M�ߗ��Y��߂��炵�Ă����B��R�𗊂�ŋ��s�n�͂ɂ��������D�c�R���͒��Œɑł����̂ŁA�������̐M��������ȖڂɈ����h�����đ�c��ɓ������ނƉ]����s�k���i�����B �u���s�߂���苏���I�v�ƌ��ɂ��������Ɖ]���B ����̉����ɑ��s�͖����̎u�C�����߂�ׂ��Y�y�_�̖�m�l���@�G�_�Ђ̎БO�ő�j�����J���A�����̐��m�V�Ƃ̈�R�����ŏ��������Œ��т͂˂Ȃ��� �u�A���L��������ȁA�@�G�łя@��͖��L����Ɍ�ɏ��A��̑����Ђ�����Đ�q����������x��B�v�Ɖ̂��A �u��������������@��������ɋ|�A���e��ł��ӂ���������������ĕ����v�Ɓw�I�ɖ����}��x�͉]���B �� (*1) �G��O�̈ꕔ�O���[�v�B�G��O�́u�S�C�b���W�c�v�ł��邪�A�u����@�v�̐M�҂������A�{�莛�̗v�����ĐD�c�Ƃ̌R���Ɛ�����B�������ꕔ�̎G��O�Ɛ^���@�́u�����O�v�͐D�c�����x�������B�܂�G��O��1�u�G�ꑷ�s�v��������{�莛�h�ƁA2�u�����O�v�ɋ߂��D�c�h�̎G��O�ɕ��Ă����B1���u�G��}�v�A2�́A���c��v�Ƃ��̈ꑰ�����[�_�[�ƂȂ��Ă������߁u���c�}�v�ƌĂԁB (*2) �Ώ�P�ۏ���Q�ƁB�@ |
|
|
��(5) �G�ꑷ�s���M���ɕ�����
�R���Ȃ��瑷�s�̏�@���������͑����Ȃ������B���Ɖ]���Ă��G�g�ȉ��B�X���镐����i����ܖ��̐D�c���Ƒ�c�A�����̓S�C���Ƃ̘A���R�ł���B�O���\���ɂ͋I�m�썶�݂̗v�ՁE���Ï邪�����A�����čb��A���T���̊e������X�Ɋח������B�����J�����ї��̏����엲�i(*1)���x�����P���� �u���x�M�����G��ɑł��ďo�ď���͂���ɏA���A���R�`���������e�������𗦂��Đs�͂���悤���m����A�P�����o�w����o��Ȃ�M�a�ɂ���ӂɉ����G��Ɉ�i�Ɨ͂ւ�ꒉ�`��s����鎖���̗v�B�v�Ƃ̈ꏑ�𑗂��Ă���B �R����ǂ͈�i�ƈ������ĎG��{����낤���Ȃ�A���������{����ւ����G��S�C�W�c���u���̂܁T�ł͉�Łv�Ǝv��ꂽ���ł���B���˂Ĕނ̐l���ɍ��ꍞ��ł����L�b�G�g�������� �u�����͈ꎞ�J�邵�Ďl�C�ɖ������������G��}��V���ׂ̈ɖ𗧂Ă�v�Ɛ������B�F��ꠓ����Ƃ��čU���ɉ�����Ă�����˗ǍO�����˂đ��s�Ƃ͌�F�������������炻��ɐs�͂��u��x�Ɣ����Ȃ��v�Ɖ]�������ō~���������B���s�����̈��g����Ă���̂́A�M�����g�����s�̍����Ȓj�Ԃ������������Ǝv����B �� (*1) ���₩�� ���������B�ї����A�̎O�j�B���i�̏����쎁�ƁA���t�̋g�쎁�̗��Ƃ��A�{�Ƃł���ї������x�������Ƃ���A���Ƃ́u�ї��̗���v�ƌĂꂽ�B���������i�̎���A��p�҂������A�ƒ��̕���Ɗփ����̐킢�s��s�ɂ��A�h��2���ւ̌����ƂȂ�B�@ |
|
|
��(6) ���i�e������������
�M���̎��͉͂����I�B�ܖ��̑啺��������������������B��������Ĉɉ�̎x�z�҂�́u�Ȃđ��R�̐Ƃ��ׂ��ł������v�̂ɂ��̍D�@���킵���͎̂c�O�����A����ɂ͑�a�̏��i�e���̔������N�����ׂł�����炵���B ���i�e�����O�x�ڂ̔�����|�����̂��V���ܔN(�����)�̉Ăł���B�M���͎O�x��������Ȃ���A����ł��e�����ꂪ���炸�����g���o���Ă���B�M���͈ĊO���l�D���̖ʂ��������悤���B ����ǂ��e���͊�Ƃ��ĕ������A��ނȂ��M���͗c���l���̌Z���Z���͌��Ŏa�肷�Ă�B���N�\���ɂ͐M����叫�ɉH��(�G�g)�A���q�A����A��˂�ܖ��������ނ����B�ǍO��͖k����̕Љ���(*1)���Ă�G��������ŗ����A�e���̂���M�M�R�Ɍ������B �M�M�R��͎O�N���ď�ɑς��镺��e��H�Ƃ��Ă����Ɖ]����B���c�́A�e�����ΎR�{�莛�ɉ��R����g�҂𑖂点���̂�m���āA���S�̎萨�����R�ɋU�����ē��邳�����B�����ď\���\���̖�ɕ������ׂɍ����Ȕ����哰���n�߂��ׂĂ��������B ����͊�����e�����啧�a���Ă����\�N�O�Ɠ������ł���A�m���ŎE���ꂽ�����t�P�̏\������ɓ���B�����m�����ǍO�́A�u���ʂ͏���v�̎��������݂��߂Ȃ����i�ƖҍU�𑱂����B �e���͋͂��\�������ۂ��Ȃ�������̔߉^��Q���Ȃ�����A�M���� �u���w偂̊������o���Ζ��������悤�v�Ɖ]�������ɂ��� �u��ɋ�\��֎q���܂��グ��ꂽ���������͂����̂��B�킵�����̐��܂Ŏ����Ă䂭�킢�v�Ƃ�������A�a�������̋��������ēV�����Ƃ����������̂͗L���ł���B ���̉߁A�ǍO�͉��߂Ė��̐������F�������Ƃ��낤�B �� (*1) �ޗnj��k����S��q�����q�B�Ŋ��w�͂i�q�a�̎R�����c�w�B�ē��̖k���ɂ���G�ؗтƔ�����ՁB�Љ���́A��������ɕЉ������z���B�Љ����́A���䎁�Ƃ����ΐ키���A���䏇���̖���W��A������ɁB��A���i�v�G�Ɛ킢����B���i���D�c�𗠐�ƁA���q���G�ɂ���čU�߂�ꗎ��B�@ |
|
|
��(7) �k���M�Y�A�ɉ�ɊێR���z��
�V���ܔN(�����)�̏\�ꌎ�ɂ͋v���Ԃ�Ő�o�������������䏇�c������Ȏ�{�Ղ���Â����B ����ɂ�ꠓ��̈�˗ǍO�������ꂽ�B�ޗǂ̒��͕����Ԃ�A�l�X�͐̉���������L�n�ɂǂ�߂��A���ɂ͐d�\���㉉����Ċϐ��A�̖���Ɍ���A���c��ǍO�����ꂼ�꓾�ӂ̋������ċ����������ƋL����Ă���B ���˂Ďq�̂Ȃ����c�͌��G�̎��j�E�����ۂ�{�q�ɂƖ]��ł������A �u���j���c���ア�ł̂��v�ƒ��X���m���Č���Ȃ��̂ŕ��Z�Ƃ���莟���}�����͍̂����ł���B �����ēV���Z�N(�����)�̐V�t�A�ɐ��c�ۏ�(*1)�̒뉀�̔~�Ⓧ���������炫�������ɐV����E�k���M�Y�ɖڒʂ�������ꂽ�����E��ޒm�̍����E���R�b��͂Ԃ��Ɉɉ�̎�������� �u�܂��Ƃɋ��E�����ׂ��Ƃ͉]���A��̒��̊^�̔ނ�ɐM�����̑�u��m�点��ׂɂ���N�������������Ă����ێR��(*2)���������ɉ����̋��_�ƂȂ����܂��B�g���y���Ȃ�����ƂȂ�܂��傤�v�Ɛi�������B �M�Y�����N�F�쐪���Ɏ��s���Ă��邾���ɑ傢�ɏ�C�ƂȂ�A�����ɒz��Ɏ�肩�������B���̑叫�ƂȂ����̂��k�����ł���Ȃ���D�c�̉ƘV�E����v�̖��ƂȂ��đ��O�Y���q�Ɩ����ˎq�̌���@(*3)�ŗ��̋��m�B�ɂ� �u�ɉ�̕��a�ƈА��������v�Ə̂��Đ���ɑK���܂��B������Ƃ�ʓˊэ�ƂŁA�Z���ɓ���ƍ��ȎO�w�̓V��t���p�������n�߂��B �� (*1) ���܂邶�傤�B�O�d���x��S�ʏ钬�c�ێ���s�B��k������ɓ쒩���̋��_�Ƃ��Ėk���e�[�A�k�����M�ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ�����B�퍑����A�D�c�M�Y�̋���Ƃ��ēV��3�N(1575)�ɉ��z����A�O�w�̓V����������ւƐ��܂�ς�邪�A5�N��ɉЂœV����Ď��B���̌�A�������A��t���A�������Ǝ���ڂ��A�ŏI�I�ɋI�B����Ƃ̎��߂�I�B�˂̏��̂ƂȂ�B���Ă̏���ɁA�ʏ钬���ꂨ��ыʏ钬���ʏ钆�w�Z������B (*2) �ێR��Ղ͎O�d���ɉ�s���_�ˎ���c�B�Ŋ��w�͋ߓS�ێR�w�܂��͏�щw�B (*3) ���傤����B�͂��߂͌���@�区�B�m���Ƃ��Ėؑ��ƂɎd����B����v�ɍ˔\�����o����Ċґ��A��v�̖����E���Y��(�������킩�Ƃ�)�ƂȂ�B�M���̖��ŐD�c�M�Y�Ɏd����B�k����ÎE�A�V���ɉ�̗��Ɋւ��B�V���ɉ�̗��̍ہA�ɉ�̍������������͂���߁A�D�c�R�̑叟���ɍv���B�@ |
|
|
��(8) �ɉ�̏������A�ێR���������
�ɐ��喩�ŁA�M���̔��Ă������E�ŏ��̓S���͂����X�ɏv�����Ă������ł���B�S����\�A���O���A��C�O���������V�s�͘Z�ǂ��C�������ĈЕ����X�Ƒ����߂����i�q���čs�����B�����ɉ�̋��d�h�����̖ڂŌ���l�����ς�����������Ȃ��B��C��m��ʋ��m�B�͉\���āu�S�̑D�Ȃ��Ԗ��邩���v�ƋC�ɂ������Ȃ������炵���B ����̖ї��։��R�˗��̗�����A�����k����e�́A����ɈЗe�𑝂��ێR������� �u���ꂱ���D�c�̈ɉꐪ���̈���I�v�ƌx����炵���B�邻���Ɏ������ɏW�܂����]�c�O�� �u�����E����E���A���̖��ɂȂ��Č�����遂錹��@�̐��L�V��߂ɁA���c�̒n���������Ă͂Ȃ�ʁB��̊������ʑO�Ɉ�C�ɏ�����v�ƌ��c�����͎̂��̐����ł������낤�B �\���̑��ŁA�S�c�����q��叫�Ƃ��_�˂̒��l�A��y�̒����A���c�̐X�c�ꑰ���җ�ȍU�����J�n���B�ɐ��ł��E���Œm��ꂽ��C�F�E�q��ⓒ����唼����č��炩�ɊM�̂���������B �u�����m�ꂽ��c�ɋ��m�߁v�Ƃ��Ȃǂ��Ă������O�Y���q(������@)�͏���̂ĂĐ������炪��ɐ��H�������A�����ɏ悶�����m�B�͊�����������̊ێR����Ă������ĉ��Ƃ����B �]�c�O�� �u��͂��ׂďĂ����������H�ƒe��͌����ɕ��z����B���̏�����遂炸���̏������߂�v�ƕz�����Ă��邪�A�e�ҐM���ɐ킢�ȏ�͖��S�̔����𐮂��˂Ȃ�Ȃ��B����Ȃ̂ɖh��̋��_�ƂȂ����ނ��ނ��Ă��Ă��܂����B ���̎�����������̕]�c�O�ɗD�ꂽ�헪�Ƃ������������ɂ��܂�ĂȂ�ʁB�@ |
|
|
��(9) �r�ؑ��d���A�M���ɖd������Ă�
����ɂ��Ă��V���Z�N(�����)�͐M���ɂƂ��ĕs�^�ȔN�ŁA�t�ɂ͔d���̕ʏ������������Ē��������Ɍ������G�g�̑����������B�H�ɂȂ�ƐےÎ��ɔ��F�����ɒO�̍r�ؑ��d(*1)�� �u�邻���ɖ{�莛�ɓ��ʂ��Ă���v�Ɖ]����א쓡�F�������������A�������̐M�����u�Q���ɐ��v�Ƌ��������낤�B �����Ɉɉ�V���m���̏��ȂƂ��]���ׂ��ێR��ח��̔ߕ��m��������A���O�̊q�{�ȂɏP��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B �R���r�ؑ��d�̒��j�Ɍ��G�̒������ł������̂͐M���ł���B �u���������Ǝ�Ԃ������ʑ嗐�ɂ��Ȃ肩�˂ʁv�ƁA�M���͋}���㗌���Č��G�� �u�\�Ƃ��Ă͑��d������ȕs���Ȏ������锤���Ȃ��Ǝv�����m���߂ė����v�Ɩ������B ���G�������ĈɒO��ɋ}�s���A�G�g�̕���������c�����q(*2)���킯���Đ����ɓ������B����ōr�����l���Ƃ��Ĉ��y�ɎQ�シ��|�𐾂����B���G�����ŐM���ɕ����̂��\����\���ŁA��������M�����z�b�Ƃ����炵���B �R���Ȃ��瑺�d�͒��쐴�G(*3)���� �u�M�����͌T�̂悤�ȕ�����A���N�̌��b�ł��ӂɏ]��ʎ��͗e�͂Ȃ��a�肷�Ă�̂���ł���v�Ɣ�������ĂыC���ς����B �ΎR�{�莛�ɂ� �u�M���̏��Ƃ͋����ʁB�䂽�Ƃ���l�ɂȂ낤�Ƃ��K���n���ׂ��v�Ƃ̏��𑗂�A�ї��ɂ� �u�L����œ�J���͎x���邩�瑁�X�ɒe��ƕ��Ƃ𑗂��Ė]�����v�Ɩ������o���ď�̖h�����ł߂�B �� (*1) ���炫�ނ炵���B�����E�喼�B���x���N�̂ЂƂ�B���q���G���4�N�O�ɐD�c�M���ɔ��t���������Ƃ��ėL���B��c�͓����G���B (*2) �{���͍��c�F��(���낾 �悵����)�B�����E�喼�B�L�O�����Ï��B�ʏ̂̊����q�A���тɏo�ƌ�̔@���̍��ŗL���B�L�b�G�g�̑��߂Ƃ��Ďd���A�����⑼�喼�Ƃ̌��ȂǂɊ����B�h���E�V���I���Ƃ������疼�����L���V�^���喼�ł��������B (*3) �Ȃ����킫��ЂŁB�����B�q�ɏG���A�G���A���P(�r�c�P���̐��)�B���͌Óc�D���̍ȁB�o���͐��a�����������̑��c�����̌���ł���Ə̂����B�@ |
|
|
��(10) �r�ؑ��d�̈ꑰ�͖ŖS����
�����Ƃ͒m�炸�M���́A�܂����S���̋�S�͑����a�W�m�ւŖ{�莛���̐��R����R���č�`�ɓ��`�����̂�m���đ傢�Ɋ�сA�����B�����A��Č����ɏo�����Ă���B �₪�ď\�ꌎ�Z���A�ї����R�Z�S�ǂ��ؒÐ���ɐڋ߂��A�{�莛�֕���ƐH���⋋�ɂ���ė����B�����m������S���͒����ɏo������ƁA�G�̓��ӂƂ���u�ق��낭�e�v�ȂǕ��Ƃ������A�͂��Z�ǂ̓S���͂ɔ������\����̑�C�ł��̖w�ǂ����������B���������j���ւ鐣�˓��̑��㐅�R(���ї����R)����F�Ȃ�����Ăӂ��߂��s�����Ă������B �S���͂̉�����m�����l�X�͖ڂ��ނ��ċ������B�O�l�鋳�t�������E���̓S�͑��̏�����{���ɋ}�A�V�ˎ��E�M���T�}�̈̋Ƃ��r�b�O�j���[�X�Ƃ��āu���ɂ������F��C���̎��������P�������V����̋��Ёv���^���Ă���B �₪�đ��d�̐S�ς���m�����M���́A�����ɑ��d�̗��r�ł��钆��ƍ��R�ɏ��𑗂�A�g�Ԃ蒉�h������A�ےÈꍑ���B����Ƌ��ɁA�鋳�t�I���K���`�[�m���ĂсA �u�L���V�^���̋���������N�ɔ����Ă͂Ȃ�ʂƐ��������v�Ɩ������B �ʂ��邩�ȗ��l�͍����~�����A���d�ꑰ�͈���ꓬ�̖��ɖŖS�B�ЂƂ葺�d�����������ɓ����Đ��p�����炷���ʂƂȂ�B �������d�����G�̐Ȃ邷���߂����Ό㐢�܂Ő�ڂ̉������c���A�߂��Ȃ����[�q�����P��̏����Łw�M���L�x���`���� �u�S�]�̏��[�炪�߂����Ԑ��͓V�ɂ��������������l�O�\���̊Ԃ͐g�ɖY���炸�B�X�ɂ��̏��[�Ɏd�����ܕS�]�l�������ɕ����߂đ�ŔM�ɂނ��ыꂵ�ޗl�͒n���̍����̙�ӂɂ�����Ăӂ��ڂƌ���l���Ȃ��v�Ƃ̎S���͋N���Ȃ������낤�B �����Č��G�ɂƂ��Ă����d���^�͂ł���A�{�\���̕ό�������̒���A���R��̓͑����Č��G���ɎQ�����ɈႢ�Ȃ��V���R�̏��҂͔ނł����������m��ʁB�@ |
|
|
��(11) �ɉ�̏������A�M�Y�ɏ���
����ɂ��Ă��G�g����N�̐��E�I���������p���đ�͑���Ґ����A��̒��N�̖��ɗp����A�W�A�̗��j�͑傫���ς��������m��Ȃ��̂ɂƐɂ��܂��B ���E�C��j���ʂ�ؒÐ�ɉ������S���R�̊������E����~�ɂ��L���`�����Ă����V�����N(�����)�̏t�A�������̈���V�勤�����u�������Č������̂ŐM���͋v���Ԃ�ɐM�Y�̌R�����Ƃ��ċA���������B �n�k�A���A�Ύ����S�{�������e���̖ڂ�ď��K���ŘA���V�����y���ݐ�o�𗎂����M�Y�͈ꑧ�����Ƌ��N�̈ɉ�ێR��Ŏ�ɂ��S�s���i�������ɂ������v���o���A���̋@��Ɉɉ�ꍑ���䂪���Ő����ĕ�������Ă�낤�Ǝv���������B �������Č��C�Ɉ��M�Y�� �u���x�����ɉ�E�҂ŕ����������k�����F�E���ɂ���v�ƗE�ݗ����A�ꖜ�]�̕��͂������ēc�ۏ���o�w�����B��̐킢�͓V�����N(�����)�̏H���Ɏn�܂����B �M�Y�̍��͑S�R���O��ɕ����M�Y�{������͒��쓻����A�E������ܕS�͒ѐA�O�Y���q�傪�匴����Sᎉz���Ɍ����A������O�S�͏H�R�E�߂������ĐR�����珉���X�����߂����Ɖ]���v�悾�����B �������x���O��ɖ����ʈɉꐨ�̎v�������ʊ�P�┽���ɑ�s���A�ѐA�ȉ�����̎������o���A�����炪���ɓ����A��Ɖ]����S�s�ł�������M���͌��{���� �u�����������l�ȑ���\�Ɉꌾ���m�点������ɂ��Ƃ͉�������ʁB��炪���ʂ��ċ���ےÕ\�̐킢�͓V������ׂ̈̑厖�Ȉ��ʼn�������ɂ���ɋ��͂���̂�����Z�ɑ�����̕���ł���B�������������ւ̏o�w�͓�V���Ⴉ���߂Ȉɉ�Ŏ蕿�𗧂āA������������Ɖ]�����_����C�̎���Ƃ͉]�����Ƃ��v���̑���ʓz��Ɩ��O���ɂłȂ�ʁB���̏�ɒѐA�O�Y���̔@����ȗE���������A�Ȃ����X����������Ƃ͑S�����ꓹ�f�̐U���B����ł͈ꐶ�e�q�̉����O�͂���܂����I�v�Ɛ痋�̗�����悤�Ɏ��ӂ��ꂽ�B���̏�A������������̓c�ۏ邪�A�g�����݂̂��̂����ꂽ����s�̕��őS�Ă���A�Ɖ]���Г���ɁA�M�Y�͂��傰�����ċސT�����B�@ |
|
|
��(12) �ΎR�{�莛���A�M���ɍ~������
�₪�ēV�����N(�ꔪ�܁Z)�O���A���݂Ƃ���G��O�Ɩї����R���s��ĕ⋋��f���ꂽ�ΎR�{�莛���͐��� �u�M���̗v���ɋ����ĐΎR�����鎖���@��̐��������B��̓��ł���v�ƌ��������A�������@(*1)�͂���ɂ��Ă������ɉ�����M���̔ڋ��ȍs�����猩�ēV�c�̒����������ĊJ�邷�鎖�����S�ƁA����(������)��v�������B �R�����j�̋��@�� �u�ΎR�{�莛�͘@�@���l�ȗ��̗��ŏ\��N�ԕ��G�Ɉ�������܂��Ă��Ȃ��B���ɂȂ��Ă�����̂Ă鎖�͑S�������̏}���҂̎��ʂɂ��鎖�ɂȂ�]��ɂ����O�ł���B�Ⴆ���|�������Ă����S�͏o���ʁA�K���M���̖d���ɂ�������Ԃ��̂��Ȃ����ʂƂȂ鎖�͖��炩�Ő�ɏ����o���܂��ʁv�Ɨ͐����Ă�܂Ȃ��B �₪�Ē��g���������A���u�ɋ��������@�͗܂Ȃ���ɋ��@���`�₵�Ē�̟̔@�����𒄎q�Ƃ��ĐΎR���������B �����ۂ����@�͂����܂ŐΎR���ď邵���������A�R��h�̐M�k�B�͎���ɓ���ČǗ���ԂƂȂ�A�V�����N(�ꔪ�܁Z)�������ɐΎR������B���ہA���������{�莛���S�Ă��Ă��܂����̂œ{�����M���͌��������̍s����Nj������B ���@�͊e�n��]�X�Ƃ��Ȃ��珮���ċ����v�������A���ɐi�ނɋ����A���߂̎ҒB�Ƃ��ʂ�đ���l��H�V��̂悤�Ȏp�ŎG��ɐ�������ƁA���s�ɋ~�������߂��B �������A���@�v�Ȃ⎟�j�E�̔@�����̈�s�����s�Ɍ}�����ċI�ɂɗ����A��m�X��V�ň��炩�ȓ��X���߂����Ă���B���@���痊����ƍ������͂ɛZ�тʔ������ւ鑷�s�����ɔނ���G���̑鑃���A�ɂ����܂��ǎ肩���蔲�����B�����炱�������̓��A���{�莛�������̂ł���B �Q���\�N������Ŗ{�莛���~���������M���͂��̐ӔC���ƘV�̍��v�ԐM��(*2)���q��ɂ���Ɠ�\�ܖ���v�����č���R�ɒǕ��B�����̉Ɛb�����X�Ɣނ�ǂ��̂����āA�X�ɂ������������A�ނ�͂�ނȂ��F��ɓ�����B���̈��ꂳ�����Đl�X�͐M���̔��B �� (*1) ����ɂ�B1543�`1592�B�{�莛��11�����B恂͌����B (*2) ������ �̂Ԃ���B1528�`1582�B�����B�D�c�M���̉Ɛb�B���v�Ԏ��̓���B�o�H��A�E�q��сB�q�ɍ��v�ԐM�h�A���ɍ��v�Ԑ����A���v�Ԉ����A�ēc�����A���v�ԏ��V�B�@ |
|
|
��(13) �M���͏��c�Ɏw�o���n�𖽂���
���̉āA�v���Ԃ�ő�a�ɋA�������c�͐M������ �u�S�y�̒ޏ������S�C�����v�Ƃ̌����ɑ����� �u�S�R��̑��̏�͂��ׂĂ��킹�A���ׂĂ̓c�����w�o���n�����ׂ��v�Ƃ̖��ɓ���������悤���B ����ǂ��u���n�A�銄��A���_�����v�͐M���̊�{����Ŕۉ����Ȃ��A�₪�Ė��q���G���s�Ƃ���R�������{�����B�w�o���n�Ƃ͏��ނŒ�o����̂����A�Ⴕ�U����������̂�����Ɨe�͂Ȃ��v���A�F�E���Ɖ]���̂ő�a��~�͑勰�Q�������B �K�����̌��ʂ͏����ŁA���c�Ƃ��̈��̏\�Z���A�O�l�喼�\�O���A���З̎O�A�������l���A�v�O�\�Z�����F�߂�ꂽ�B ���З̂ɂ��Ă͐M��������u���ɓK���ɂ��v�Ƃ̎w�����������B�������ꖜ�ܐ�A���厛�������̂܂ܔF�߂�ꂽ���A����R�̂�ꠔ���(*1)�͋��ۂ��ďĕ���ꂽ�B����R�͓V�c�ɑi�������ǂ��ɂ��Ȃ炸�A�����m�����M���͓{���č��쐪�����v�悵���B�叫�ɐM�F�A�Q�d���͖x�G���Ɖ]�������o�[�Œ��X�Ə������i�߂��Ă����B �����H�ɓ���������������������̂� �u�R�܂��R�̍������������\���������Ȃ��ɉ���ɂ��ׂ��v�ƕς����炵���B�ɉ�ɂƂ��Ă͑�Г���A�R�������Ȃ�͓̂��R�Ƃ��]���悤�B �]���Ă��ꂪ�������V�����N(�ꔪ�܁Z)�H���痂�N�Ă܂ł��ɉ�ɂƂ��Ă͍Ō�̍u�a�̃`�����X�ł������B �� (*1) �{����(���ӂ���)�B�u�܂����ł�v�͒ʏ́B�V��@�B���{�a��s�Bꠔ��R�̎R���ɂ���B��C�̔��̖т�����ꏊ(������)�₻�̔��̖т������Ă����K������B�����ɂ͈������������͂�ŋΑ��Ƌ�C�̑������u�B�D�c�M���ɏĂ����O�͎R�x�����̈��C�s�n�ŁA�s����C�s���s�����B���݂̖{���͖L�b�G�����Č��B�@ |
|
|
��(14) �M���́A��̔M�a�Ɉɉ�U�߂�j�܂��
�������A����Ƃ��m��ʈɉ�̗��ɂ͐̂Ȃ���̒��ՂȓV����N(��ܔ���)�̏��t���K���B�����ēɓ���ƈ��y�ł͍����ȑ�n�������G�̎w�����ŋ��s���ꖼ�n���A���������\�]���œ�������B �V�c�͂��̍������ɐ���܂��A�����I��Ɓu����b���i�v�̒��g��h���������A�M���͊�ԏ����A �u���˂Ē�Ă��Ă���c���q�ւ̏��ʂ�����������܂��傤�B�v�Ɩŕ@�����������悤�ȑԓx�ɒ�����͑呛���ƂȂ����B ����𑼐l�ڂɐM���́u�ɉ�̂ȂŎa��v���������錈�S���ł߂��B�Ƃ����͔̂邩�ɑ�n���������������ɉꍋ���̕��n�ɗ\�A���{�펟�Y�炪������\���o�����炾�B��������ނ̓j���}���Ə��A�l��ƎZ�肵���u�ɉ�I�̎����n�ꂽ�悤�ȁv�ɉꎘ�̏\�{���z����啺�͂ň�C�ɒ@������Z������������B �o�w�͌܌��n�߂Ɨ\�肳��Ă������A�M��������o��Ɖ�ɔM�a�ɏP���A���]���|�̏d�ԂƂȂ�A�s�̖���������Đf�@�����Ă��a�̐��̂��悭����Ȃ��B �������̐M�����C�͂������A���߂̐X���ۂ� �u������A����Ȏ����]���̂��C���i�܂ʂ��A���͈ɉ�U�߂����߂Ă�薈�ӂ̔@���鍳�ɂ��������߂������ɗ�������āw�ɉ�U�߂��~�߂�x���ɂ݂�������B�w�����ق����I�x�ƈꊅ���悤�Ƃ��Ă�����������Ɍܑ̂�������ɂȂ萋�ɂ͋C�������Ă��܂��L�l�ʼn�Ȃ����Ȃ�����v�Ɖk�炷���ƂȂ����炵���B ����������ۂ́u��������Ȃ炸�v�Ɗ����āA�L���Ȑ�t�ɋF�������a���ގU�ɐS���ӂ������A�����ɂȂ��đQ�����N�ɂȂ����̂ōĂш��y���o�w�����B �R���������i�܂ʂ����ɖ�����唭�M�Ŏ��_���Ĉ��y�Ɉ��Ԃ��Ɖ]���n���ł���B�@ |
|
|
��(15) �ɉ��m�{�����_�Ђ���������
����ʂĂ��Ɛb�B�͋߉q�֔��ɍ������Ē���̐_�_��������ł���g�c�Ƃ̕M�����߂�蕔���b�ɋF������������ʁA���͈̂ɉ��m�{�����_��(*1)�̎�_�炵�������������B �����Œ����ɐ_��̓{�����Ñォ��̔�@���u���鎖�ƂȂ�A�������ɒ��g�ƂȂ����蕔���b���ɉ���߂����ďo���B����Ȕ��z�S����n�ɂ�s�������_�Ђɓ��������̂͗��H�����̎n�߂ł������Ɖ]���B �����}���o���{�i�B�� �u������̒����ł���v�ƁA�̏䍂�ɋ�������B��߂�ꂽ�C�@�ʂ蔒�z�Ő_�a����d�ɂ���ݍ��ނƁA�q�a�́Y���_��ꎮ�������A�R���[���Ñ���(*2)�����[�ɒ݂��Đ_�Е����̋V�����s�����B ���X�����C�@�ɉ����m��ʐ_���⎁�q�����͑��X��������ނ݂̂ł������̂� �u�����̊Ԃ͂�����������ɂӂ�Ă͂Ȃ�ʁA���������j��ΐ_���ɂ�荚���ꖽ���������͕K��B�v�Ƌ������ēs�ɋA�����B�蕔���b�͗��ۂ����� �u�C�@���I����������͂�S�z�䖳�p�Ǝv���邪�A���Ƃ����叫�͗]�l�ɖ�������ق������S�ł��낤�v�Ƃ����߂�B ��������M���͏�X �u�Ȃ̖ڂŌ��ʌ��艽�����M���ʁv�ƍ��ꂷ��̂���ς��Ď���o�n����v��𒆎~�����B�㌎�n�߁A�M�Y�ɓ`�Ƃ̖����u���l�Y�v�̒Z���������āA���t�ɔC����|���������Ə����ɓo��𖽂����B �� (*1) ���ւ��ɁB�O�d���ɉ�s��V�{877�B��Ր_�́A��F���A���F�����A���R�Q���B (*2) �ӂ́A����B�@ |
|
| ��2.2�@����� �@ | |
|
��(1) �M���́A�S�R�ܖ���z�u����
�V����N(��ܔ���)�㌎����A���y��̑�L�ԂɊ����̏������Q�W�����M���͙z�R�Ƃ��� �u���˂Ĉɉ�̋��k���͗]�̓V���z���̑�u�����܂���������肩�A��X���遚����ɂߖ����̍��������߂ʐU���͐��Ɋ�����ɂł���A���x�����͒f�ē��ł���B�}���m���A�j���̋�ʂȂ����ׂč��ł��R����҂͂ȂŎa��ɂ��A��l���e�͂���ׂ��炸�B�S�y���Ă������V���ɂ��̏V���������v�ƏH������̏o�w��߂��A�S�R�̔z�u�����̔@�����炩�ɂ����B (1) �ɐ����c���叫 / �k���M�Y(���́E�ꖜ) (2) �ѐA���c�Q�d�� / �O�H���G(���́E�ꖜ�l��) (3) �b����c�� / ��������(���́E����) (4) ��a���c�� / ���䏇�c(���́E�O�玵�S) (5) ���������c�� / �x�@�G��(���́E���O�S) (6) �����������c�� / ��쒷��(���́E�ꖜ) ���v�@�l������l �����̓V���z�����߂����M���̎x�z�̓y�͎l�S�����z���A�����͂͏\�O���l�Ɖ]���邩�炻�̎O���̈�𓊂�����ł���B�ނ��@���Ɉɉꕐ�m�������]�����Ă�����������A�t�ɘa�����߂�Ηe�Ղɓ��͊J�����Ɖ]���悤�B ���Ԃ̐������ɉꋽ�m�B�����ɐM�����̗��U�͂��̏t�ȗ��L���`�����ċ���A���ł��b��̑��������r����A���N�̉Ĉȗ��A�[���Ȃ���̂��铇�������m�O�ɑ吨����������Ȏ莆���͂��A�a�c�ɍ��͂�v������Ă����炵���B �R�����d�h�̑������A�����̋��m�B�́A�D�c�̎�́E�ēc�͖k���A�H�Ă������A���q�͒O�g����ɋ�l���Ă��錻�݂̏���ő勓�P���̋���Ȃ��ƊÂ����Ă����悤���B�@ |
|
|
��(2) �ɉ�O�͏�약�y���ŌR�c���J��
�u�D�c�R�ܖ��A�������i�U�J�n�v�̑勥�ɉ�ɓ͂����͓̂��N�㌎�����ŁA�����ɏ�약�y���ŕ]�c�O�̌R�c���J�����B �\�̕]�c�O�̕M���ɉ����ꂽ�����̑��\�Y�������̉���ɒ��ɂȐF�ׂēG�̏����ƁA��X����d�h�Œm��ꂽ���c�̕S�c�����q��X�c�A�����A�v�Ă̋e������������ɘr�����݁A�V����ɂނ����ł������B �]�c�̍ו��͎c����Ă��Ȃ����A�������̑�\�ł���x�������q��͈ꓝ�̍��c�Ƃ��� �u��狽�m�͖�������̂����̖�ڂł���A���Ăʐ킳�͂�����ׂ��v�Ƙa������Ă��A�^�J�h�͏����O��R������� �u���s�͓x�O�����Ė���܂ʼnƖ����������v�Ɠ{�����_���͐[��܂ő��������ʁB �u�M�����Ɖ����ׂ�㋍�Ɉ�т̑卷������A���Ɉ�̏��Z���Ȃ����A�`�����č~������Ƃ͕��c�̖����������̂ł���B����Đ��X���X�Ō�̈ꕺ�܂Ő킢���������ڂɎ~�߂�B��������̐킢�ł��邩��e�X�v���̂܂܂ɐS�u���Ȃ�����ĉԂ̔@���U��ׂ��v�Ɖ]�����c�ƂȂ����B ���̈ӋC�����ɑs�Ȃ�Ƃ͉]���A���q�̉]�� �u�����k���ɂ��č��̑厖�A���S�̊�@�Ȃ�B�}���G��m��Ȃ�m���ď��߂ď��s��m��B���̊�{�͎��̎������܂т炩�ɂ��ׂ��B��N�̓��`�S�B���̔\�́A�V�n�̗��A�@�߂̌��A�����̑召�A�����̗��x�A�ܔ��̖��炩�Ȃ邱�Ƃ���Ȃ�B�މ���r���āg���Z�h�Ȃ��A�f���Đ키�ׂ��炸�B�v�̑匴���ɂ��ނ��Ă���B����Ɂu�`�v�ׂ̈ɐ키�ƌ������ȏ�́A���ׂ��헪�����グ�A�S�R���ꎅ����ʍ��v��ɏ]���ď����ւ̌��H���J����ƕ����w�͂��˂u��邾��������I�v�Ƃ͉]���Ȃ��B���Đ��������A�����R�瑁��̛ӂɂ���z�V�O�Ȑ�@��W�J���Ă˂苭���킢���������炱���A�͂���]�̕��Ŗk���\���̑�R�����j�������̂ł���B ��ɏ\�{�̑�G�ɑ��A�e�����D������ɐ���Ă͈ɉꐨ���@���ɗE�҂Ȃ�Ɖ]���Ă����F�����͖]�ݓ��Ȃ��̂�m��������Đ킢��]���̐S��͔ߑs�Ƃ����]���Ȃ��B�@ |
|
|
��(3) �M�Y�́A�ɐ��H��蓌�T������̂���
�������ēV����N(��ܔ���)�㌎��\�����A�V�����n����H�������ė��̐D�c�R�ܖ��̏����͕S�A��̔n����Ȃт����A����т₩�ȍb�h�̋����炵�A�������J�ɋ}���_�̂悤�Ɋ��ۓ��X�Ǝ�������ɉ�̍���������B �悸�����ɐ��H�̐�ǂ߂�A���叫�M�Y�̈ꖜ�]�͑S�R��ۂƂȂ��đ��ޓ��X�Ƒ哻���z���A�[���ɂ͈ɐ��H�̓��T������̂��Ă���B������{�c�Ƃ��A������������z�u���� �u���������͓�N�O�̉��𐰂���v�ƋC�����������B ����ɑ��Ĉɉꐨ�́A�O��̏����̍��ʂ�A�����̊|�c��̕x���A�����̖{�c�A�ʕ{�̏�A���c�A���n�̏��A������̉H�Ă̗E����͎v���v���ɕ��c�`���̍Ԃɗ��Ă����B�h�����ł߁A�Ў��͎̕R���ɖ��߂ēG�̔���̂�Ҏ�B ���{���ƂȂ����V���R�������ɂ͋��m�A�m���̑��ɑ����̏��A�q����V�l�B�����Đ��o���A����e��̕⋋�Ɍ����ƂȂ��Ă����B���ɂ͈ɐ��H�ɓ��������G�̗]��̑�R�ƈ��y����h�����ꂽ�S��B���̌R�ĒB�̐v���Ȏw�������� �u��������Ɍł܂��ƁA�ƂĂ�����Ȃ����ǂ��ɂ��Ȃ�v�Ə���ɍԂ��̂Ăđ����ɑދp����҂��A�t�ɂǂ������ʂȂ畃�c�̒n�łƍőO���ɋ킯����҂Ȃǂ����藐��đ卬����悵���炵���B�@ |
|
|
��(4) ����v�́A�ɐ��H��艜����`�V��`�퐶���Ă��s����
����\���������A�ɐ��H�̖{�w�ł͈ꖜ�̌R���O�����đ��̗�����O�炪�����삩��V��A�퐶���ʂɌ����B���u�A�����̎O�炪�䎩��A�ێR��ցA�c��̎l��͐M�Y���������Ĉ��ۂ�������̎Q�{���𐼐i���A�O��Ƃ͂����ĕς����������l�u�ŏP��������B �����ɂ��Ċ|�c�Ԃ͕S���̍����悤�ȏe���ɕ�܂ꂽ�B������̋v�����͖҉ɏĂ������A�呺�_�Ђ�V���R�ɂ�����Ă������l�⏗�q���B�܂ł��e�͂Ȃ��E�������B�_�Ђ⎛�̓��w�A�O�V����뉀�A�܂ōg�t���U�炵���悤�Ȍ����ɍʂ�ꂽ�B ���̐������ɒ��c�_�Ђ�����Ă��������ꑰ�͈�Ăɔ䎩�R�ɑދp���ĔL�̎q��C���������A�����}�����͂��̂܂ܐi�̂Ŋ�ՓI�ɐ��Ƃꂽ�B�܂��V��Ɋy���̖{�������̎�ŏ��K����ɐ험�i�Ƃ��ĉ^�ꂽ�ׂɐ�������鎖���ł����B�������A����ȊO�̂��ׂĂ��D�o�ƋA���߂��Ȃ��_���m���܂ł���������͂˂�ꂽ�B�@ |
|
|
��(5) �O�H���G�́A�k�ɉ�������`�ѐA�����ɐi�݁A�����𗎂Ƃ�
�����Ėk�ɉ�ɖڂ�]����㌎��\�����A�ꖜ�l��̑�R���ւ̒n���ɏW�����Đw�e�𐮂����D�c�R�̎Q�d�����E�O�H���G�́A�����������n�ɗ\��̈ē��ŁA���X���ւ̐w���Ȃ��A��������ɉ�B��̐Ί_����̕��n��֓���B�u��R�ɐ؏��Ȃ��v�̌��ʂ�ꕺ���������ѐA�����ɐi�o����B ���˂Ă���a���_�҂ł������ѐA�̕��n��썇�̎��{�ɑ��Ă͍d�h�̓c���|����Ɖ��H���Z�炪 �u�ǂ����D�c�̊Ԏ҂炵���s���l��������Əo���肵�Ă���v�Ƃ̉\�Ō������Ď��̖ڂ����点�Ă����B�������A���ɂ��y���G�ɍ~������Ƃ͎v��Ȃ������炵�������ɏW�܂�����ѐA�̕x�c�A���c�A�����A���ѐA�̐��c�A���A���ѐA�̏��R�A����̋��m�B�͒Ǖߓ�(*1)�ŏ�ɓ���ƌ����ɐ�������A���F�͏O�ǓG�����������炸�ŗ���B �ӋC�g�������͗�R���̑剾���ɕ����A���l�͋͂��ȐH�Ƃ��������ɂ��ĎR���ɓ����������́T���ʖ�h�ɕa���ƂȂ�̍��A��p�ɗ͐s���ē|���҂��Z�𗐂����炵���B �� (*1) �����Ƃ肪���ȁB���m����}�̏ꍇ�ɓ���e�ɍ����]�T���Ȃ��A��Ɏ������܂܂̏�Ԃ������B�ً}�̏ꍇ�Ɏ����̂��Ƃ肠�����삯����l�q�B�@ |
|
|
��(6) ����v�́A�t���R���U�߂����˂đ�R�c�ɉI��
�����𗎂�������v�͏t���R�Ɍ����A�O�g���͈ɉꍑ�{�̒u����Ă������A�V���i�ށB�y���̒������͋��m�̕]�菊��S�C���K���̂������R�����_���������猃��ƂȂ����B���c�؍H�V���Ɖ]�����E�̎m�͐D�c���\�]�l���Ȃ��|���ĕ����A���͓V���ł����Ɖ̒��ŊD�o�ɋA�����B���̎��A�m�Ԃ̑c�������������Ɖ]��� �������т�A���q���ȂƁ@�b�����ށB �̋傪�c���Ă���B ���̂߂������t���R�ɂ́A���̒����O����叫�ɁA���̑�̉Ɗ���ɂ��Đ쓌�̐����A�{��A�쐼�̕����A�J���B�O�R�̓��R��V���̍��X�A���q��̖Ҏґ����ł������B�����ő��͑S�R�ɑ��� �u�������Ă����z��͗�������������Ă������̗E�m�̎q��������A��l�c�炸�F�E���ɂ��Ė���܂ł̉Ђ̎�������v�Ɛ擪�ɗ����čU�ߗ��Ă����A�镺�͕]�c�O�ł��s�J��̒����Ɏw�����ꂽ�������������ɁA�������̑����U�߂����B ��ނȂ���R�c�ɉI�A���c�P�������Ĕw�ォ��U�߂鎖�ɂ����ׂɒO�H�E��쐨�͔䎩�R����ɏo�x��鎖�ɂȂ�̂ł���B�@ |
|
|
��(7) ���������́A�b������F�c�J���R��A�c���̍Ԃ𗎂Ƃ�
���Ėk���̍b�������쉺�����̂͐D�c�����Ă̗E�����������ŁA���{�펟�Y�̐擱�ŋʑꎛ�ɖ{�c��u���A�e��A�R������Ď���̑��͂������ĖҍU�����B ����ɑ���ɉꐨ�́A�F�c�J���R��ɏW������E�E���ђ���ɎR�卶��A�R���P���q��E�������ł���B�D�c�R������(*1)�̑�S�C���̓���𑵂����X�Ǝ˂��܂����Ă��Ђ�܂��A������炵�Ĉ�����ނ����h��������B ����Ǔ��������鍠�ɂȂ�Ɩ�e�����A�҉̒�������ł���c���̍ԂɏW�����čċ����v�����B�������A�������Ă��s���Ή��̒��Ŏ��X�Ɉꑰ�͑S�ł��A���q�����e�͂̂Ȃ��D�c���̐n�ɂ�����B�㐢�u������������I�v�ƕ�����A�����q���ق����Ɖ]����S���ƂȂ����B �� (*1) �Ȃ����B����Ŕ�(�Ȃ��������)�̗��B���`�͉̕��ꌀ��̕\�ŔB�]���āA�u�L���ȁv���̂�\�����t�B�@ |
|
|
��(8) �x�G���́A����������蓇�����ɓ���
�X�ɐ����̑�����������i�������x�G���A���������O��̓��O�S�͍b�ꏬ�싽�œ��ɕ���A�x���͌�ē������H���������߂������B���̒n�̋��m�B�͌��O�ʗ���(*1)�̒��j�E���j(*2)��c�Ƃ���B���錳�O�m��(*3)�ɍۂ��Ă͊}�u�R�ɒy���Q���Ē�����s�������c���ւ�Ƃ���l�X�����ɁA�u�V���z���v�����Ƃ���E��b�E�M���ɔ��R���鎖����`�ł���Ƃ͎v���Ȃ������悤���B ����Z���A������Ƃ͉]���ɉ���̐m�؋`�������̊قɎp�������A���X�Ɉɉ�]�c�O�������ĐM���́u�ɉ�ȂŎa��v�̈ӌ���`���A���Ƃ��a�������ɐs�͂���Ɛ��������B���̍ۂɓ��������O�\���Ƃ͈�v�c�����A�a���Ɍ��������ɑ�ǂ�����ڂ��������B �R����\�̕x�c�����q�͓O��R��h�ŁA���y���ł̕]�c�ɂ͈ꉞ�a������������̂́A����Ƃ��܂���їE��ŒP�ƂŔ䎩�R�ɋ킯���Ă���B �D�c�R�ł��M���Ɉ����ꑤ�߂̈�l�������x�G���͕����E���������炻�̕ӂ̎���͏[�������Ă����炵���A�W�����S���̌�ē����z���Ă����ΊJ��𖽗߂����T�d�ɕ���i�߂��炵���B �� (*1) �V�{��̊J����Q�ƁB (*2) ���j�̎��j���L�j�B�����̗��j���D�ƁE�g�{��ꎁ�̘b���Q�ƁB (*3) ���O�̗����Q�ƁB�@ |
|
|
��(9) �x�G���́A���������~��
����������]�Ɍ��铻�ɒB�������A�H�T�ɕ��������\�Z���̐l�i�ڂ�����ʋ��m���ۍ��̂܂ܒ��d�ȑԓx�Ō��t�������Ă����B �u����́A����́A�x�Ƃ̕��X�Ƃ����v���B�g���͓��������̒n���E���n�������A����ɍT������́A��������R���������ꓝ�ɂČ�叫�E�x�G���a�ɒQ��̋V���ꂠ��A���Ƃ����Ȃ�������v��������G�����q�y�������Ƒ��n�͐����Ȗʎ��ŕِ�����₩�� �u���n��~�ɂ͐����V�c�̒���ɂ���ēV����N(���O�Z)�n�����ꂽ��ϕ�������𒆐S�Ƃ��鎵�������\��m�V���n�߁A���X�̖��ЌÎ����c����ċ���܂��B���������ēy�Ɖ����A�߂Ȃ�����h�Y�̋ꂵ�݂Ɋׂ������͒n��������̖{�ӂɂ��炸�B�ꖽ�ɂ����Ă��i�ʂ̂�������肽���A���O�ȗ��A�e��̊�������肽�镃�c�̌ւ��E��Ō�肢�d��B�v�Ɨ܂Ƌ��Ɍ��シ��A�������͐M�����߂̑��̐l���Ƃ��ꂽ�G�������� �u���̐S�ꑊ�������B���ɐ_���ł���v�Ƒ����ɏ��m���A�����ɑS�R�� �u���n��~�̎��Ж��Ƃɂ͈�ؗ��\����ׂ��炸�v�ƌ������������B �R�������藧���������̏��m�B�͊��ɗї����鉾���A�m�V�ɗ��������n�߂ċ���A�Q�Ăď��ɓw�߂��B�h�����Ė{���A�O��Ɩ{���m�������͏Ď���Ƃ��ꂽ�̂ŁA��s��u���Ď����ێ��ɓw�߂��Ɖ]���B ����ǂ����l�ȏ��u�͔ތl�̓ƒf�ł��锤���Ȃ��A���˂ĐM���͓��������m�̘a���_��m���� �u�R����҂͏��q���Ƃėe�͂��ʂ��A�~������ҋ��͊���Ɉ�������ȗ��\�͋����ʁv�Ɠ������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�@ |
|
|
��(10) �x�G���́A���R�����Ă��s�����`���q�_�Ђ̕s�v�c�`
����̂ɓ��������琼�R���ɓ����x���͂��̑ԓx����ς��āA���{�ŏ��̉w�Ɖ]����u�V�Ɓv���n�߁A�����ܔN(���O)�ɒz���ꂽ��ɗ����ւ̒��ΊX���ɗ������ԎЎ��A���Ƃ����X�ɉ̊C�Ɖ������B �����Đ��a�V�c�̒�ώO�N(���Z��)�n�����ꂽ�Ɖ]���_������⍲���Č����ɑ���������F�썂�q�������Ղ鍂�q�_�Ђɑ��Ă��R��̎đ����W�߂ĕ������B�Ƃ��낪�A���V����N(����l)�Ɏ��E�m�ؒ����̊�i��������̐_�a�ɔ���⍚�R�ƌ��ꂽ���q���q���q���Ɣ����ĉ������~�߂Ă��܂��B �{�������̈�l�A�юO�Y�Ɖ]���r���҂��啀���������Ďa�����ƁA���͉�g�ɂ͂˕Ԃ��č��������B����������ҎҒB���_���ɐk������Ď�����킹��Ɠ����������Ɖ]����B�_�a�͕��Ղ��~�߂��܂܁A�����������Ă���͕̂s�v�c�ŁA�������͕��_�E�������̍��c�E���q�����≞�_�V�c�̌�_���Ɖ]���悤�B�@ |
|
|
��(11) ���䏇�c�́A��a�����E���A�Z��A���c�����Ă��s����
�Ō�Ɉɉ�암�̗v�Ֆ������ӂ̐틵������B ��a����i���䏇�c�A�莟���q�̗�����O�玵�S�̌R���́A�㌎��\�����A�}�ԓ��̒���ŕ��𒓂߂��B�������ʂ̈ɉꋽ�m�̓��Â��m���߁A�w���˂���鋰��Ȃ��ƒm����C�ɑE���A�Z��A���c���̑��X�ɗ�������B ���̒n�̋��m�B�͂��˂ĕM���]�c�O�A���\�Y�̍��v��ʂ�A�v�Q�̒n�E������ɏW�����Ă����̂ʼn��̔������Ȃ������B���䐨�͖��l�̖���s�����@���A�����̑�Ж����͌���苒�_�ƂȂ肻���ȉƁX�͕Ђ��[���痪�D�����A���߂����Ėk����J�n�����B ���̔w���݂��悤�ɏ����X�����O�ցA�F�ɕ��ʂ���i�����ė����H�R�A�F��A���̈ꖜ�]�́A�F�ɐ�̍��݉����Ɉ��{�c�A��������ѐ��A���c���i�B�O�l�́A�G�g�̍ȁE�˂˂̎��Ƃ̐�쒷�����叫�Ƃ��A�u�g��O�l�O�v�Ɖ]��ꂽ�B�ނ�͔�����̈ɉꐨ�ɔ����Ė��������̉F���z�u���_�Еt�߂ɐ�w��u�����B �����Ĕ�������Ă����G�̊�P�ɑ��閜�S�̕z�w���ł߂A��쐨�̎�͔͂n���̍������������H�����߂������B���䐨�Ƌ��Ɍj�̗�������A�����ĉԊ_�]��̈ɉ��E�̈�l�A���n�ꑰ�̍ԂɏP��������A������̂��č��炩�ɊM�̂�t�����B�@ |
|
|
��(12) �M�Y�́A���g�c�Ԃ𗎂Ƃ�
�ȏオ����ɉ����闼�R�̐틵�ňɉꐨ�ɂƂ��Ă͐��Ɏl�ʑ^�̂̎v���ł������낤�B �����̍Ԃ����炵�ċʍӂ��������͋��炭��ɋ߂��A�S�R�̎O���߂������ł�����S��B���̗E���ґ�����ł���B���˂Ă����S�ňɉꎘ�ɑ傫�ȋ��|�S������Ă����D�c�R�� �u�F�ł�����Έɉꎘ�ƂĈĊO�ɂ��낢���I�v�Ƒ傫�Ȏ��M�ƗE�C��^���Ă��܂����̂́A�헪�ォ������炩�Ɏ��s�Ɖ]����B ���ɖk��(�D�c)�M�Y�̈ɐ����� �u�O���̒p�J�𐰂��͍̂����v�ƈ��ۈ�~�̑呺�_�Ђ�����̖��������X�ɏēy�Ɖ����A�ɐ��X�����}�i����B�H���̗�������g�c����̔n�˂ɖ{�c��u���ƁA�ψ�������グ�̒n�Œm���鏬�g�c�Ԃ̍U���ɂ��������B �����ɂ͊��A�|�����n�ߕ��E�M������u�K��������v�Ɩ��w�����ꂽ���̏��g�c�Z��A���͑����L�ł��m��ꂽ���E�E�������Y�̌����Ђ������������� �u�������j�̎��ꏊ���A����ɂ��܂��A����ɂ��܂�v�ƌł����������Ď��q���v�̓������������O�ǓG�������X�ɋʍӁB�H���̖�ɂ͑��X���Ă������������Ⴍ���Ȃт����ɘV��j���̗��l�炪�����܂ǂ��B����Ȓf�����̋��т����ɂ��Ȃ���A�����c�������m�B�́u�Ō�̎��ꏊ�v�Ƃ��߂��퐶������߂����ė����Ă������B�@ |
|
|
��(13) ���������́A��약�y���Ɍ���
�b�������j�|�̐����ŗF�c����̂������������͍��ދ�ɖ{�w��i�� �u�悸�͍K��悵�v�Əj�t���������A��\�����̖锼�ɐ�J�̈ӋC�ɔR�����ɉꐨ�̋}�P���đ卬����悵���B �R���������͖ҏ��A�����ɂ͍����w�e�𗧒����A����̑O�����ɂ���߂����I�X�Ɣn��L���ɏ��Ɍ����B �����̏��ɂ͕������̑n���Ɠ`�����鎛�̎��S�Ə̂��ꂽ���y�������܂�A��Z�̖{���𒆐S�Ɏ��������⋐��ȘO��A�\��̑m�V���ї����ĈЗe���ւ��ċ����B�O�傪��ɓh���Ă��鏈����l�X����g�Ԗ�h�ƈ��̂��ꂽ�ɉ���̑厛�ł���B���x�̗��ł��ɉꐨ�̍��{���ƂȂ��Đ��S�̑m���������߂����x���ɗ����A�u���y���̑m���v�Ɖ]���ΎO�q�������~��(*1)�A�Ҏҋ��m���r���ʼn�ΕK����������K���������Ɖ]���B �]���ĊJ��ƌ���������c�̐ȏ�ł͓��R���y�����ł́u���������_�Ƃ��Ď��点��v�Ƃ̈ӌ��ł������B ����Ǖ]��O�͗]��ɂ��L��ő�R��ɂ��Ă͎�肫��ʂ��� �u���c�̔䎩�R�ω����Ɉڂ�v�Ƃ������Ɍ������B�������A�m���B�͊�Ƃ��ď��m�����A��ނȂ������F�߂���Ȃ������炵���B �� (*1) �O�̎q���ł������~�ށB����قNj��낵�����ƁB�@ |
|
|
��(14) ���������́A��약�y���𗎂Ƃ�
�����A�e���D�c�����炪���{�펟�Y�Ɉē�����ĉ������A���ɂ͑m���Ɖ��l���킹�Ď��S�]�l������m���������̗v���X�X�ɕK���̎�q�w���ł߂ĖҍU����W�J�����B ��ɏ\�{�����R��Ɉꍏ�͂߂��܂������߂��킢�A�������̎���������Ă����B���A�����̌��l�����������ɑm���̒��ł��E�҂Œm��ꂽ�ʁX�͎��������B�ʓ��A�O�t�̂��ׂĂ��G�̕��ɂ���ė����̍ӂ��U��悤�ɕ���B�ŔM�n���Ɖ��������ō��m�A���V���珗�q���܂ň�l�c�炸�Ď��Ɖ]����B ���S�Ƃ�����Ƃ��䂦�悤���Ȃ��L�l���������A����ɉ����鈢�ۂ�V���R�ł̔ߌ��̍Č��ł����Ȃ������̂́u�Ȃ��m�炸�A�G��m�炴�钹�Ȃ����̉��Ƃ�(*1)�v�ŁA�o���ǂ܂��A�Z���������ėV�҂̒H��C�����ł������B ��������H�����Ƃ͉]����ہA���Ԃ��炩�����̂͌��̖���Œm��ꂽ�؋��̒��䍶�n�[�v�Ȃł���B�ނ͐V�c�`���c�Ƌ��ւ荂���ƌn�}�ƒ����̒������q�̐����q�ɗ^���Ĕ䎩�R�Ɍ��킹����u���Ɏ��ɂ����v�Ɩ]��ł�܂ʘY�}�����Ƌ��ɕ��c�`���̊ق��Ă��čD�@��_���G�̔w��Ɏa���܂�ƌ��߂Ă����B �R�����˂Ď��{���炻����Ă��������͈�����������Ċق��͂����B�����m���Ē���͈��Ȃ������Ă� �u���߂ĉ��e�q�̕����ׂɗ�����v�Ɩ��������A�ޏ��͊�Ƃ��ĕ������������ɐg���łߎ���̓㓁������ĕv�Ƌ��ɓ����ďo��ƁA�G��������|�����v�ɐd�Ȃ��ĝ˂ꕚ���A���̑s��ȍŌ���������� �u�ɉ�ɂ͐ɂ������Ԃ�v�Ǝ�����������Ɖ]����B �� (*1) �u���Ȃ����̂�������v�������Ȃ����ł́A����ׂ��啂��В���Ƃ����Ӗ��ŁA�D�ꂽ�҂����Ȃ����ł́A�܂�Ȃ��҂����𗘂����Ƃ������Ƃ̚g���B�@ |
|
|
��(15) ���䏇�c�́A�e���O�g�̍Ԃ𗎂Ƃ�
������������т𐪈��������A�����R�ɖ{�w��u�������䏇�c�́A����ƕ��я̂��ꂽ�v�Ă̋e���O�g�̍Ԃ֏P���������ĉU�߂ɂ����B�O�ǓG�����ނ͖҉̉������������Ĕ䎩�R�ɗ������т��B�����ĕ��ł̕]�c�̐ȏ�� �u�Ƃ������ɉꎘ�͐i�ނ�m���đނ�����m�炸�A���C�ɔC���Ď��ɋ}���K����������ň�O�Ȃ̂��Z���ł���B�ꎞ�̒p��E��ł��Ō�܂ł˂苭���킢���������^�̗E�҂Ɖ]����A�e�X���ǂ������̎����̂ɖ����A�Ȃ�Ƃ�̖����ɑ����đS�R�̔j��������@�����Ƃ͌ł��ނ�ŖႢ�����v�Ƌꌾ��悵���B����́A���������킢�����M�O����ł��낤�B �e���O�g���h�����Ĕ䎩�R�ɒH��������A�����m�����叫�̈�l�S�c�����q�� �u�悭���蔲���ė���ꂽ�v�ƌ�������Ċ�B ���@�Ƃ̋e���ƁA���d�h�̑�\�ł������S�c�ł����D�c�R�̋���ȕ��͂�m���� �u�O��̂悤�Ɋe��������̍Ԃ��Ă��Ă͑S�ł���̂݁B�k�ɉ�̖ʁX�ɂ͑��̗v�Q�ł���䎩�R�ɏW�܂�ł��Ĉ�ۂƂȂ邵���Ȃ��B�v�Ɨ͐������B ����́A���C�̑m����ӎւ̈ꕔ�̒��V��̔��ŋ��܂�A����w�����ł��Ȃ���������ł����낤�B����ł�����̕����m���Q�ĂĕS�c�̈ӌ��ʂ�킯���鋽�m���}�������B ���ł����c���̉��l�E�^���ƍ������A�܂����@�ɗ������{�펟�Y�̈����V�_�Ŕ������ďP��������A����悭���̎��y�Y�ɂ��ď�ɓ����Ă����B ���˂ĕS�c�犲���͏���̔s�k�����n�A���{��̗�����ƍl���� �u�ނ���͓̂G�̑叫�k��(�D�c)�M�Y��|���ɓ����������v�ƑS�R�ɕz�����Ă��������ɑ傢�ɕ����������B�����ɔނ��m���Ɏ旧�āu���R�r���v�̕�������������s�̊����^��������A�l�X�̎u�C�͈�i�ƍ��܂����B�@ |
|
|
��(16) �ɉ�O�́A�䎩�R�ω����ɏ��z��
�ɉꐨ�̑I�䎩�R�ɂ͈ɉꖼ����\�܍��̈�ω��������܂�B ���̎O�S�����R��ɗ����ē���]�߂A�ɉ��̋{������Ђ̒��삳����{�R�𒆐S�Ƃ��ĘA�Ȃ铌��͂��Ȃ���C�g�̂悤�ɂ���Ƃ��p�ׂ�B�R���痬�ꗎ����͐��┒���̐쌴�ɂ͓c�߂������A���X�Ɗg����c���Ɋg���閯�Ƃ��珸�鐆���͕s�V�s���̗�_�Ɏ��Ă����B ���]�߂Ώ�֖����X���ނ������āA�H�͍g�t�̒��ŗY���̍Ȃ�����鐺���ɂ��A�����ɂ͓`����t�n���ɂȂ鐼�@�������܂��Ă���B �����ɂ͎R�X���d�Ȃ钆�Ɉ���̛ӂ����R���������A���̏�Ɏ��̗����������Ă����̂ŕ��C���J�ƌĂ�A�������D�X(*1)���鏼��������߂��Ă����B �k�ӈ�т͒f�R��ǂ̉��ɓޗǁA���ɒʂ��ד����ʂ��Ă��邪�A�䎩�R���͔�Ԓ��ł�������ȓV�R�̗v�Q�ŁA�@���Ȗҏ��ł��u����������o���Ĕw�ォ��P���v�Ȃǂ͎v�������Ȃ������B �c�����璷�c�ɏZ�݁A���̒n���ݕv�s���̌���ł��鎖���n�m���Ă����S�c�́A���F�̏���ꑰ�⒩���̕���c�A��F�c�̋g�x�A���c�A���̏��ꑰ�A���H�̏�˂�̗E���B�� �u�����ƂȂ�ΐߖځX�X�̐����Ȉꑰ�݂̂ł��̏���Ă蒷���R��ɏo��A�����ȐD�c���ƂĔ��N�͎��v�\�v�ƐM���Ă����̂����R�ł��낤�B �]���ď���̔s�k��m���Ă��ނ�̎u�C�͏����������Ȃ������B�������̕]�c�O�������x���G�s�̂悤�ɁA���y���ŊJ��ƌ�����Ɨ����A���Ĉꓯ�ɂ����`�������u�����܂Řa�ł䂭�ׂ��v�Ƌ��܂���A���R�Ɓu���c�̖����������͂ł��ʁv�ƒP�g�y���������̎҂�����B�Q�W���������͕S�O�\�]�l�A�ꑰ�Y�}�͎O����Z�����Ɖ]����B �ނ�݂͌� �u���̗���킳�̒�Ƃ��鎖�͐��ɋ��ꑽ�����A�厜��߂̌䕧�̉���ɂ�����A����̓����������ĕ��c�̖����������v�ƐS�ɐ����Ă����悤�ŁA���̐S�������M������ł������B �����Ă�������l�X�͉������Ɣ䎩�R���߂����ďW�܂����B���q���܂ł��⊢���Ԃđ��ɏW�߁A�y���z����h����Ɋ����𗬂��A�͂����Ŏ��X�ƍH�����i�B�R���ɂ͒��c�ۂƒ����ۂ̖]�O��u�L�����v�ƌĂԐ�l�w���������������B �₩���Ƃ͉]���A�V�R�̗v�Q�ƓG�̐i���H�ɐ݂�����A���̗����ݔ��ɏ������āA�瑁��ɂ������ʂƎv���錘�łȐݔ��̎R�錚�݂����錓�s�ő�����ꂽ�B��Ӓ�����̐��̔@�����X�ƓV���ł��Ɖ��A���̐w�������Ɏ��悤�Ɍ������Ɖ]����B �� (*1) �����B�������𗧂ĂĐ������܁B�@ |
|
|
��(17) �䎩�R��̌���1�`�ɉ�O�ꏟ�`
������������������� �u�O�H�R�̓�����҂����A�������ł������ďo�����˂Ύ���Ă����v�Ɨ͐������B ���������ӂ��A�㌎�O�\���̒������A�������͖k�����������A����͒����̓������~�g�̐������܂����i�����J�n�B�������ꓝ���~���������x���͑��͂������Đ����̏o�邩��䎩�R�̔w��ɐi�ށB���������Ĉꖜ�ܐ�̑�R���u�䂱����ԏ��v�Ɠ{���̔@���H����˂��ĎR�[�ɔ������B ����������S�c�A����c�̗��叫�͏���A������l������ɑI��ŗv���X�X�Ɏ肮���ˈ����đ҂��\�����B�S�R�Ɍ}����騂̐�������������A����Ă����S���⏗�q���܂ł�������������Ƃ��苩�сA���̐��͎R�X�ɂ����܂��ĕS���̍����悤�ł������B �䎩�R��̑����ɔ���������Ɛ�쐨�̌ܐ�]�͏O�𗊂�ň�C�ɑ����ɔ��������J�̂悤�Ȗ�ɑł���č����ב������B ����̕��C�J�J�̋}���h���X���čU�ߏ�������������u����̋w�I�v���m��I�v�Ƌ��|�������i��������̖���Ď��X�Ɏ˓|����A�����Ă̖Ҏґ������Ђ��Ō������B �����Ă͂Ȃ炶�ƌR�āE�������Ă��u��ɑ����I�v�Ɛ�w�ɗ��������A�叫����c�ɋ}�����˂��ė��n������������������B�����������X�l�Y�A���c�����̗������̕���ŕ��C�J�J�͐l�n�̎r�Ŗ��܂����B �������̗E���E�����������u���̂܂܂ł͑S�ŁI�v�Ɗ��������A��R�𗦂��đ����ɓ]�����B�s�F�ɂЂ�ޓ���A��쐨�Ɂu���Ƃ��]���b��Ȃ��z���A��ɑ����v�Ǝ��B���Đw���ɗ��ĂA�Ⴂ�����ɕ������Ƃ��蓛��莟�����������Ď�����w���ɗ��B �u�����a���E���ȁv�Ɠ���̏��m�����ɂƑ�����킯�o�������A�叫�S�c�̌����ȍєz�Ŏ��X�Ɏ������o���čĂђǂ��������B����NJ��͑�R�����ɐV��X�X�Ɗ����A���䂪���݂ɌJ�o���A�ɉꐨ�ł����������g�Z�A���c�̑���������X�ɗ͐s�����������B �����Ǝv��ꂽ���A�x�G���́u���P�͖����v�ƈ������𗐑ł��đ��ދp�ɓ]�����B��Z���̐�����ӘH���悶�o�����x�����ɉ�̎d�|������ɐ�w�̑唼�������̂��������炾�B �E�����������O�̎���݂����Ȃ���U���𒆎~���č��ދ�Ɉ��g����B���䐨�������R�ɋA���ĒO�H�A��쐨�ꖜ�l��̎�͂̓�����҂��ččU���鎖�ƂȂ����B�@ |
|
|
��(18) �䎩�R��̌���2 / �ɉ�O�� �����܂��ċ����čs���������č��炩�ɊM�̂�t�����ɉ�O�͖{���̘_���s�܂��s�����B�S�c�A����c���䎩�R���{���Ƃ������A���ł��X�l�Y�ƍ��c�����A���R�r����̕����͌㐢�ɂ܂Ŏc�����B �����ĈӋC�g�����ނ�͒����R�̓��䐨�ɖ�P�������鎖�Ɍ������B���̖锼�ɒ��c���n���ĔE�ъ��A�ߑO�������Ĉ�Ăɏ����ɓ_���ēG�w�ɗ��������B ���c�͔����{�t�߂̖{�c�ŏn�����Ă��鏈�����R���ɕs�ӂ�ł��� �u���͂₱��܂Ō���������v�Ɖ]���̂��ɉ�o�g�̋ߏK�E�e�쐴��Y���K���ɂȂ��Đ�ɗ����R����E�o����Ƃ����B �܂������������镗�J�ɐ^�Èłł͂ǂ��ɂ��Ȃ炸�A�����{�ɉ����Đh�����ē��������������̈���œ��䐨�͕��͂̔����������Ɖ]������̑��킾�����B �����߂ƕ��щƒ������Ă̍��E��m��ꂽ���q�L����A���ƘV�E���V��ˎ�̒��j������́u��叫�����ȁv�ƕK���ɐ�������A���q�͗��n���čs���s���A���V�͏d�����ē|���S�s�ł������B ���̐��������P�͏��ւ����D�c�R��k����点�A���ł����q�̏�n�߂������R�̕����́u�S�R�ɔ�Ȃ��v�ƑA�]����Ă���B�@ |
|
|
��(19) �ɉ�O�́A�H�����Ȃ��A�䎩�R���E�o����
������ɂ߂��܂���������ɉꐨ�ł���̂ɍ��N�̊�����O�ł������̂ƕ��y���̐H�ƌɂ����サ���ׂɑS���̕������Ă�������Ă��܂����̂́A�E�͂����Ă������̊Â���Q�������Ȃ��B �����������������B���]�c�̖��Ɍ��߂��̂́A �u�G�̐V�肪�����ʂ����ɏ�����ĂĖ�����쐨�ƍ������čċ����v��v�Ƃ������Ƃł���A�\������̖锼�Ɏ蕉���⏗�A�q�����������v���v���ɗ����čs�����B �����Ƃ͒m�炸�������ŁA�O�H�A��쐨���������D�c�̑�R�͈�Ăɑ��U�������s�����B�O��̖Ҕ����ɋ�����ׂ��A��ԏ���_�����m���Ȃ��W���W���ƎR�[�ɔ��������A�Ԃ�⾉��ԁX�ƔR�������Ă���̂ɓG���̎p���Ȃ��Ԃ͖��ɐÂ܂�Ԃ��Ă���B �u����͂��������B�ɉ�҂̎����ች��㩂���������肩���m��ʁB���f����ȁv�Ɖ��ߍ����Ȃ���Q�����c�ۂɓ˓������B�����A�ꕺ���Ȃ����ʂ��̋��������������� �u�V�������������ɖ��������A������̓G������������̂ɋC�����Ȃ������Ƃ̓n�e���ĕ���Ԃ����ҋ���v�Ɛ���܂����炵���B ���̉��݂���������ƌ��߂Ă������c�͑傢�ɕ��𗧂� �u���̍��킯�Ă��T���o����l�c�炸�a��v�ƌ������ĒNj������̂ŁA�I�݂ɔ䎩�R��E���Ă�������ɒH������҂͏��Ȃ������B�蕉����Ƒ�������Ă���ƈɉ���o�đ�a�t���R�Ŗ�h�����Ă����ҒB���M���̌����Ŏ������Y����Ă���B�@ |
|
|
��(20) �퐶������́A�ʍӂ���
�\����{�A�䎩�R��т��D�c���̎�ɋA�������B�ɗz�̖삩���̎퐶������ɗ������ɉ�O�͂����ɏW�����Đ�J�������w�n���Ɍ����ƂȂ��Ă����B ���̒n�͑O�[����̏㗬�ɂ���B�R���ɂ͑��䎛�̎����������ї����������V�����Ղ̗��ŁA�k�R���ŗL���Ȍ��D�@�t�̕���c���ꂽ�v�Q���ł̏�ł���B �����ɏW�܂������m�̖ʁX�͎퐶�̑�|�A���|�A�����y�̒����A���g�c�̈ꑰ���R�̖k���̎c�}�ȂnjܕS�]�l�ł��̒��ɉ��R�b�オ�����߂ĉ�����Ă����炵���B �ނ͎����u�ƈ���ĐM�Y�̓{����ފ_���孋����鎖�A��N�ɋy��ł����B�����͔ނ̗\�z�����ʂ�ň��ƂȂ����B�ɉ�S���̊�@�̔���̂�m��� �u���y�̖S�т�̂���������ɔE�тʁA���߂Ă��ɉꕐ�m�Ƃ��Ĉꖽ���̗��ɕ����悤�v�Ǝ퐶��ɓ������̂ł���B �M�Y���퐶��̍U������A����A�Óc�ɖ����A�Z��߂���R���������̂͏\����{�Ǝv����B�ɉꐨ�͔�y�̒����A�����̗������w��������Č����ɖh�����ł߂������Ō�̎��ꏊ�ƒ�߂Ă����悤���B �ʂ��邩�Ȉɉꐨ�̗͐�͐��������̂��������A�ܕS�ΘZ��ł͍Ō�ɋʍӂƂȂ�͓̂��R�ł���B�����ւ����D�c�R�͍�����̈�p�Ɏ�a���݂��č~�l�₻�̉Ƒ��܂ŗe�͂Ȃ�����͂˂��B �������ɂ߂����䎛���Ă��҉��͐R���_�̔ޕ��ɂ��Ȃт��A���A�q���̋������Ԑ��͓c���ɂ����܂��ė���A���X�̔ߘb���������A���ӂ̑��X�Ɏc����Ă���B�@ |
|
|
��(21) ���\�Y�́A����������ŕ��ƍU�߂ɂ����
�u�퐶������A�ʍӁI�v�̔ߕ��������������̑��\�Y�͈ɗz�̊e�n�ɋ}�g�����ďW���𖽂����B������E���Ҏm�����X�Ɠ��邵�ē������͎l�S���z���A�����ꑰ�Y�}��Z�S�ɒB�����B �Q�d���ɂ͗L���ȕS�n�O�g���k�ɂ���y�����A����ӂ̗v�n�ɂ͕z���A���n�A�哹���A�g���A�g���A���R�̗E���B���ď邵�Ė��S�̎����ł߂��B �ނ�͉��Ƃ����ď��g�c�ɖ{�w��u���M�Y�̎��������ׂ�����@���_�����B�����m�����D�c�R�́A�ɉ�ł̓g�b�v���̑傫�����c���������������قƌĂ��Ԃ�z���āA�����P�ɔ�����B �k�ɂ𐪈������O�H�A��쐨���M�Y�R�ƍ������Ĕ�����̑��U�����J�n�����̂͏\�������Ɖ]���邪�A���{�ɋ߂������Ǝv����B�����O�����������R�̈�Ăɋ�����~�g�̐��͖���������ǂ�߂����������낤�B ����ɑ��Ĉɉꐨ�͑�쏬�O�Y�̗�����O�S�̗V�������o�ۂ���o�����ēG��U���o���A�h��ɍ\�����{������Ăɋ|�S�C�𗁂т�������B �R�t�S�n�̍ɔz�ɉ����Đi�ނ���z���B���䐨�̗E�҂��́A����������������܂����Ɖ]���A���������ł��D�c�R�̎����͐�ܕS�ɋ߂������B�V�I�̒O�H�͋����M�Y�ɐi���� �u�͍U�߂͒��~���A�e���͋}���h�q�����ł߂Ă݂���ɏo�����ւ���v�ƌR�߂�����ƁA�D�c�M�������y�ɑ��点�Đ틵��������B�@ |
|
|
��(22) ���\�̐X�c��_�A�{��ŋ����A�ʍӂ���
�M���� �u�J��\���ɂĈɉ�̑唼����ł��A�]���͓�ӂ̑���̂݁A�}����o�n����v�Ƃ̕�ɒ����Ɉ��y�����B �w�M�����L�x�ɂ��A�M�����ɉ��̋{������ЂɈ�������̂͏\���\���̗[���ł���B���g�c���疼�����ӂ܂ŋ��i�߂Đ틵�߁A�O�H�̐����u���ƍU�߁v�����m���A�\�O���ɂ͋A�H�ɂ��Ă���B ���̓r���_���ĎR������_���e����ё��߂͐F�����������A�K���e�͂���ĉ��̉�����Ȃ������B�M���͎���ɂ��������D�X�Ɣn�����ċ��������A�S�͓{��S���ɔ����đ������������炵���B �R���ʖڋʂ�ׂ��ꂽ�x��������͒����ɓO��I�ȑ{�����s�����B���̌��ʁA�Ɛl�͉��H�̏�ˁA�z���A���c�炵���Ɣ������A�ނ�̕�����т��l�Ԃ��ɑ|�����n�߂�B ���ׂ̈ɁA�X�c��_�ȉ����g�����̋��m���S�́A�s�{�ӂȋ��������邱�ƂɂȂ�B�X�c��́A�䎩�R����r�̔E�c�Ԃɗ����A�ɔ�ŋ{��̗v�Q�ɐV�������_��z���Ă����̂��B ������ƌĉ�����ǂ����߂ł���B�Ƃ��낪�_���ƒT���̂��߂Ɍ��ݒ��̍Ԃ���������鋰�ꂪ�o�Ă����B�X�c�炪�H�����̂܂܂ɋ���������Ȃ��Ȃ����͎̂c�O�������낤�B �\���\�ܓ������m���ċ������D�c�R�ł́A�g��O�ƌĂꂽ�H�R�A�O�炪�����ɍU�����J�n�����B���\�̐X�c�͏H�R�ƈ�R���̖��ɉX���������B�ꑰ�Y�}��������Ƌ��ɋʍӂ��A�����ɐ�͊�����Ђɔ��ő�F���ȗ��̓`�����ւ�Гa�����G�L�ɋA����(*1)�̂͐ɂ������ł������B �� (*1) ���䂤�ɂ�����B��������Ȃ��Ȃ�B���ɁA�ЂŏĂ��邱�Ƃ������B�@ |
|
|
��(23) �S�n�O�g�́A���������Ɍ��ʂ̏��𑗂�
������Ђ̉����m����������ł́u�ނ�̎��ʂɂ���ȁv�Ə\�Z���̖�A�D�c���̎��ӂ̎R�X�Ɉ�Ăɏ�����R�₵���B�G���������A���̌���˂��ĐM�Y�{�w���}�P����Ƃ������ł���B �R���܂����_�������ᧁX���錎���p���o���A�ׂɗ��̒O�H�A����� �u���ꂼ�U���̍�A��������ɑ������e���̎�����ł߂�v�Ɩ����Čx�����������������ׂɈłɂ܂���Ă̊�P���͎��s�B��Ɍĉ����ď������f���G���������������l�B�͕Ђ��[�������͂˂��A�]���҂͂��т��U�������ɒB�����Ɖ]����B �₪�ď\�������{�ɓ���ƒO�H�̗\�z�����ʂ蔐����̐H�Ƃ����˂����B��\�Z���̖�������čŌ�̓ˌ������s���鎖�Ɍ����A�S�n�O�g�͒m�F�ł���������Ƃ̔E�ҁE���������Ɍ��ʂ̏��𑗂����B �����m���������͉��Ƃ����ĎO�S�𐔂�����̔E�҂��Ƃɖ𗧂��������ƉƍN�Ɋ肢�M���ɔz������Ė����u�a�̓����J���ׂ��z�������炵���B�����Č��莅��_�Ђ̊ϐ����̐s�͂ő��Ɛe���̂�������q�ܘY���Ƃ������y�t���A����K�˂��̂���\�Z���̒��ł���B�@ |
|
|
��(24) �D�c�R�ƈɉ�O�A�u�a����������
���̓��͎叫��삩�甐������Ă����l�X�� �u���m�͍������o�ēG�w�ɓˌ����A��C�Ɏ��Y��������B�ؖڂ̘V�l�⏗�[�͏�ɉ������Ď����A�c���q���◢�l��͂��̌��Ɍ���̗��_�x�������Đ������т�v�Ƃ̌R�߂�����A�u�������Ōゼ�v�Ɣߑs�Ȍ��ӂ��ł߂����������Ɖ]���B �����������q�����������̖����ƐM�Y�̉ԉ��������� �u�J�邷��Έ�؍߂ɂ͖��ʁB�Ɩ��̑������F�߂悤�B�A�����\�Y���S����������Ĕ��R���ʖ�����o����q��l���Ƃ���v�Ɖ]���ӊO�Ɋ���ȏ����������B�����āA���̓����������̂ŁA�����S�n���^�킸�E�ҒB�������@�g�����m�����B�����u�a���������A���������ɗ�����ꂽ���S�̈ɉ�E�ҌQ����ɉƍN��V���l�ɂ��鋭���J�������B �V����N(����O)�\����\�����A�ɉ�ɂ͒��������t�̉��₩�ȓ��ɑ��\�Y�͈�q�T�V������Ėk�o�̖{�c�ɏo������ƐM�Y�� �u����ɍ����Ǖ����A�]�̉Ɛb�������E�����͖̂��@�̎���ł͂��邪�A��̒��̊^�̗Ⴆ������A���̑�u�𗝉���������������悤����B���㍑��ɒ�����s��������r�ɉҋƂɗ�ގ��𐾂��Ȃ�Έ�؍߂͖��ʁv���𖾂炩�ɂ��A�����ܖ��Ɩ��n�ꓪ��^���Ē����I�����B������ɂ͓��䏇�c���I��ď�ɓ������B���ƕS�n�͂��˂Ă̖ɂ��O�S�߂��E�҂���O�͂ɑ���ƕS�n�͐ӔC���Ƃ��āu����R�ɏ���ĕ���ɓ���v�Ə̂��A�₪�č����ɐ��炵���B �叫�̑��͈ɉ�e�n�ɋ}���̎g�҂𑖂点�Ė��̌���𖽂��A�d���̋��m�B�����X�ɏ��m���Ď��͏����ɐi�s���邩�Ǝv��ꂽ�B�@ |
|
| ��2.3�@�ɉ�T�䓛���b�@ | |
|
��(1) ���R���q��̔ߌ�
�Ⴆ�u�a�������ǂ�ȂɊ���ł��낤�Ƃ������ł͓l���F�E���ɂ��A�k���ł������l��e�͂Ȃ��ĎE�����Ɖ]����S���ȐM���̎��ł���B�����Q�d�̕S�c���܂̐�����g���u���̋N���ʂ悤�אS�̐S�����ӂ�Ȃ������B�������A�v�������ʎ����������̐Ԗڂ̑���Ŗu�������B �����萔���O�ɂ��˂ĐԖڍԂ���������R���q��ꑰ���ď锼���ɋy�Ԃ�A�H���ĐH�ׂ�Ƃ��Ȃ��G�̖ڂ������ނ��ׂɂ��P�ɎR�y�Ȃǂ����ċn�̉����₳�Ȃ������B ����ǂ��̂܂܂ł͉쎀���鑼�͂Ȃ����ɍԂ�E�o����B���ď��i���ɍU�߂�ꗎ�鐡�O�ƂȂ��Ă����F�ɂ̑Z�Y�ꑰ���~�o���āu���̐e�v�Ɗ�ꂽ���Ƃ��������B���̉��𗊂�ɗ����Ă䂭�r���̂��Ƃł���B �R�ӑ�����̗��ŁA�v�炸����������Ă����c��Ɖ�C��Ȕޏ����� �u���Ƃ߂߂����B�쒩�̗E�҂Œm��ꂽ���c�̖��������ʈׂɂ������ɋA���ď�ɓ�������v�Ƌ͂��ȐH����^�����A�ĂэԂ��߂������B���ꂪ�J�钼�O�̂��ƂŔނ�͉����m��Ȃ������B����q�n���̑O�܂Ő��s���Ă������A�s�^�ɂ��D�c�̏��ƂԂ����č������l�ƂȂ�A�G�������ʂ������Ɏ�]�\�]�l�������ʍӂ���Ɖ]���ߌ��ƂȂ����B ���˂ĕ����疽�����u������v�Ƒ҂��Ă����M�Y�͗�̔@�������藧���A����������ɒe������Ɉ�]�����B�����ȏ��c�̑��ɑ��O�Y���q��V�㊯�ɔC����Ƒ��A�S�c�ȉ����ׂĂ̋��m�����O�Ǖ��ɏ�����B�ɉ���o��Ȃ�Ђ��[���珢���߂�A���̍ߏ����������ď��Y�����炵���B�@ |
|
|
��(2) ���䉓�]�̍Ō�
���l�́u���j��ĎR�͂���v�Ɖr���邪�A�ɉ�̋��m�B�͌̋��ɏZ�ނ��Ƃ�������Ȃ������B���ĂǂȂ������������炤�Ԃɋ͂��ȘH����g���ʂ����A��ނȂ��Ȏq�����w�ɂ��Ă��̓������̂��҂������炵���B �ΐ�܉q��̔@���哐�Ɖ����҂�A��l��H�ƂȂ��č���R��I�B�������߂����r���ɕa�ɐN����Ė�ʂɋ�����҂������B�D�c�̂ƂȂ����ߋE�\�]���ɐ�����p�͂Ȃ��A�͂��ɓ���ƂɎd���镞�������ɋ~��ꂽ�E�ҎO�S���������H�����o���K�^�Ɍb�܂ꂽ�̂ł���B ���ł����ꂾ�����͉̂F�ɂ̑�Ƃɗ������l�X�ł���B�M�Y���� �u�ɉ�҂������܂��Ƃ͍����̌��肶��A���ׂĝ��ߎ���Ď���͂˂�B�����Ȃ��Α�Ƃ͒f�₳���邼�v�ƌ������ꂽ�B�w�ɕ��͕ς���ꂸ�A�Z�Y�͔ނ���鉺�̔n��Ɉ������Ăď��Y������Ȃ������B ���̒��ɑ��䉓�]�ƌĂԗE�m�������B�ނ͐l�X���d�u��ɒʂ������n��� �u�����A���ꂪ���̐��̓n��[�߂��c�v�ƒQ���̂� �u������Ȃ��B�Ⴆ���̎���a���悤�ƍ�鮂͂��̒n�Ɏ~�܂��Ė��邱�̋����щ�艶�m�炸�̑�߂ɁA���̉����ʂ��ł����ׂ����v�ƈӋC�������ɏA�����B�ʂ���Ƃ��̖邩���{��������̋ʂ�������щ�����Ɖ]���A���̉����炩�A�₪�đ�Ƃ͐M�Y�ɍU�߂��ď�͗����A�ꑰ�̑唼�͓��������Ɠ`������B�@ |
|
|
��(3) ���R���q��̈⌾
�h�����Đ������ѓ����l�X��䅋�ɖ��������X�ɂ�肫�ꂸ �u�����A���ɂ��Ďv���ΊJ��O�̕]�c�̍ۂɓ������O�̂悤�ɋ������a�̓���I�ׂΗǂ��������̂��v�ƒQ�� �u�`���d�āA����ɂ��܂��A����ɂ��߁v�Ɛ������e���O�g�̗Y�ق��v���o���� �u�V����̖����ŕ���������F�c�Ƃ̌������A�e���̐��O����������ׂ��v�Ƃ̌����c���Ă���B �⑰�̒��ɂ́A�ԖڍԂŕ��퓢���������R���q�傪�o���ɍۂ��Ă̌��t�A �u�×����當�������Ɖ]���B���x�̑������ӂɂ��ĕ��E��Ђ݂̂̍��O�̖����ʂ��珵�������̂���A���ɗ���҂͕��ɂ���ĖS�Ԃ̂����̏�B����Ƃĕ���ڂ��ݑו��ɓ��ĕ��݂̂ɂĂ��낤���A��ɐ��̈ꎚ���|�ɕ����̑哹���ӂ݊O�����̂���܂������B�v���ƌP�Ƃ��ĉi���㐢�ɓ`���Ă���Ƃ�����B ���̎�������A�a���_�𐳂����ƐM���Ȃ�����]�c�O�̌��_���d�Đ��ɎU�����m�����Ȃ��Ȃ������悤�ŁA���̐S��ɗ܂Ȃ��Ȃ��B�@ |
|
|
��(4) ���P�ƒ��m�V����
�Ō�Ɂg�ɉ�T�䓛���b�h�Ƃ��̂��ׂ��G�s�\�[�h�ɂ���Č��Ԃ��Ƃɂ��悤�B �\������̖�A����Ƃ̉ƘV�ŏ\���̏��w���}�������m�V�����́A�����R�ňɉꐨ�̋��P�����A��N������Č����ɐ�����B�������d���œ|��A������������Ƃ����B�q���̘Y�}�̕K���̓����ɂ��h�����Č˔ɏ悹���A����ؔ����đ�a�ɋA��r��ɌÎR������(*1)�̗��Ő��ɑ��₦�Ă���B ���l�͗܂Ȃ���ɂ��̒n�Ɉ�[�߁A�ߕ���S�R�̐V�ȁE���P�ɕ�B��������ޏ��͍�������C�ɂȂ炸�A��̒�������Ĉ���ɋ킯����ƕ�O�ŋ������ꂽ�B�ς�ʂĂ��v�̖S�[���Ă��ɔE�т��A���̖T�Ɂu���났���v�ƍ����鑐�������āA����̒Q���̂��������A���̂܂ܐ��U�����̒n�ő��邱�Ƃ����S����B�����m�������l�B�������𗣂�ĉ�����ƂȂ��ʓ|�������悤�ŁA�ޏ��͔O���O���̓�m�ł��̐��U���I�����Ɠ`������B ���P�͗c�������璉���̋��łŁA���̏j���́u���j�A�����̉Ԃ̉��v�Ə̂���ČS�R��~����A�]���ꂽ�Ƃ����B�����P�ۏ�̏t�P�ɂ��������̔��K�ȉ^���ɁA����܂ŔG�炳�ʐl�͂Ȃ��������낤�B �����疞�l�S�N���}�������a�\�Z�N(��㔪��)�̏H�A���X�̔ߌ��ɍʂ�ꂽ�ɉ�S�y�̐���q�˂��B �p�����A�v�炸������̃o�X��ɋ߂����̎j�Ղɗ����A�u���났���E���l�m��v���爻�P�䂩��̔��~�_�Ђ̎Гa�ɍ炭���ւ̌Ö������B�P�̐������ɂ��Ĕ߂�������̈��̑z�ɑł��ꂽ�B�Ⴋ���Ɉ��������u���ւ̉����v �������P���t�́@�Ԃ͗܂̑��蕨 ���ɗ҂��������G�ꂵ�@���ꉳ���̔��� ���̋��������āA�킢�̔���Ɋ����A�P�̗�̉i���Ɉ��炩�Ȃ鎖���F�����B ��Ƃ̎����Ƃ����t�P�̋��{�ׂ̈ɂ��B �� (*1) �ɉ�s����B |
|
| ��3 �{�\���̕ρ@ | |
|
��(1) �M���͍���R���U�߂�
�V����N(��ܔ���)�\���A�ɉ�S�y���D�o�ɋA���A�߂Ȃ��l�X��e�͂Ȃ��ȂŎa��ɂ����M���́A�����č���R�̐����ɂ��������B �O�N�A�M���͓��䏇�c���a���ɔC���ď��̂̐\���𖽂����ہA��������O�@��t�䂩���ꠔ������Ă����S�̑m��Ǖ������B�u�������Ƌ��ɎG��U�߂ɎQ����v�Ɩ������̂ɁA����R�͂���ɂ������ʂ��肩�A�r�ؘQ�l��b���Ėh�����ł߂Ă����B�M���͓{��A�ɉ�Ɍ����O�̔����A�s�t�߂����s���鍂�쐹��]�l�̎�˂Ă���B ���N�\�ꌎ�A�M�F(*1)��叫�ɔC���Ēf�Œ����Ɍ��킹���B ����ɑ��č���R���ł��R�t���ɋ������l�������A���ӎ����̗v�n�ɐ���l�����Ēz�邷��B�ѐ��R��(*2)�𒆐S�Ɉꖜ�ܐ�ɒB����m���A�n���A�Q�l�B�������W�߂Č����Ȗh�q����ł߂Č}�������B �D�c�̐�w�A�x�G���͔����R�ɏ��z���Ƃ��������_�Ƃ��čU���ɂ��������B�����ĐM�F�̗�����ꖜ�ܐ�̑�R���ѐ��R��ɔ���B�R�t�E������@��@��͍I�݂ȍ��ő傢�ɋꂵ�߂����̂̏O�ǓG�����A����͎��X�ɗ������B ���͂��ł͕K���Ǝv��ꂽ���A�M���͊��C�����܂�ƍU���𒆎~�����ėl�q����������B��������͂��A���G�ގU�̋F���ɂ������Ă���̂����āA���u�͗��N�ɂƍl�����炵���B �� (*1) �M���̎O�j�B�Ώ�P�ۏ���Q�ƁB (*2) ���������܂��傤�B���{�哌�s�y�юl����s�ɂ����B�W��318m�̔ѐ��R�ɒz���ꂽ�R��B ����k������c�m�����@�ɂ��z�邳��邪�A��ؐ����̍U���ɂ������邷��B�����N�ԁA�k�����̍��t�����l���덇��̐܁A���̒n�ɐw��z���B ���퍑����c�V���N�Ԃɔ��R�����͓�����̂���悤�ɂȂ�A�Ɛb�̖ؑ��ɖ����Ĕѐ��R�ɏ�s���\����B�i�\�N�ԁA�O�D���c���E���Ő��͂��g��B���������ƒ�߁A�C����Ƃ��s���B�i�\12�N�A�D�c�M���͓̉�����ɔ����A�j�p�����B�@ |
|
|
��(2) �M���́u�~�R(�ڂ�)�̊ԁv�Ő_�ɂȂ�
������ΓV���\�N(��ܔ���)�����A���y��ɂ͐V�N�̔N��q���E�����A�z�n�̍|�����̐������������B�M���͎Q��̑�Q�W�Ɂu�~�R�̊ԁv�ŕS�����ΑK������đs��ɂ݂Ȃ����w�̓V��t�������������B �����S���ŕĎO�����������Ɖ]�����猋�\�����ΑK�����A�₪�Ĉɐ��_�{�̑J�{��ɎO��ѕ�(��т͐當)����i���Ă���B�u���l����ő��o�����v�M���炵�������ł���B �o�e�����B�� �u���[���b�p�̂������̏�Ⓝ����ꡂ��ɋC�i�ɖ������ؗ�Ȃ��v�Ǝ]�������y��ɁA��˗ǍO���q���Q�ꂵ���̂͐����O���������B���y��̉����ɉf��鎵�w�̓V��t�������ɉf������߂��̂����Ȃ���A�S�X����n���č�N�v�H�����`�����ɎQ����B ��O�̐��D�ɂ� �u���̖{���͐M�����g�ł���A�n�҂��w�ł�Εx�҂ƂȂ�A�x�҂͈�i�ƕ��^�ƒ����Ɍb�܂��B�̂ɗ]�̐��ꂽ�����Ƃ��ĕK���Q�q����B�����M���Ď��s����҂ɂ͔��\�܂ł����������A�M���Ȃ����Ȕy�ɂ͌��������������X�ŖS����̂݁v�ƋL����Ă���B ����������ǍO�͎Ⴂ������u�l�Ԍ\�N�ЂƓx���������ł��ʎ҂̂���ׂ����c�v�ƐM�����M��������e���Ɖ������̂�m��A�u����ł͓V�����邩���H�v�Ɗ������͉̂Ƒ�X�������O�k�������ׂ��낤�B �R�������F�ɂ͏o�����A�����l�̉Q�ɂ��܂�i��ōs���ƁA�V��t�́u�~�R�̊ԁv�Ə̂��鈺࣋ɂ݂Ȃ���i�ɁA���Ȃ���_���̔@���M�����[�����Ă����B�Q��l�̍��o���ΑK���R�Ǝ���A��ɍT�����������Ƀp���p���Ɠ�����B �����B�����݂ǂ�ɂȂ��āA�R�̂悤�ɖ������ΑK�̐����ɑ������Ă���B��������ėǍO�́A�ї��̈������̑m�� �u�M���͂��̂��������ɂł��Ȃ邾�낤���A�����ƍ�����тɓ]��������ɈႢ�Ȃ��v�Ɨ\���������Ƃ�A�����`����ꠓ��邩��ދ�����ۂɌ��ɂ��C�� �u���Ɍ���I�����Ǝ����ɓ������݂������悤���v�Ɖk�炵���Ɖ]���b���v���o���āA�]�b�g���̊����Ȃ�̂��������悤���B�@ |
|
|
��(3) ���c�������q�A�U��
�V���\�N(��ܔ���)�����t�ɂȂ�ƐM���͎��M���X�� �u�M���́g�l�͐Ί_�l�͏�h�Ɖ]���ċ���ɍ��Ȃ������̂ɏ���(*1)�͐V���z�����Ɖ]���B�������b�B�U�߂̎����v�Əo�w��߂����B��w�ƂȂ������j�E�M��������������𗎂Ƃ����O�����{�A��؈ߏւ�����т₩�ɐM���{���͈��y�����B�ǍO�����G�P���ɉ����A�_�R�����̐��r�ɂ����B ���c���ɂ͂��ĎO�����ŗǍO�Ɠ����߂�����܂������̋R�n�R�c�̖ʉe�͂Ȃ��A�ꑰ�̌��R�~��(*2)�ɂ�������ꂽ�����Ɉ��z�����������m�͉_�U�������Đ�ɖ����Ȃ������B�͂��ɐ^�c���K�̍D�ӂ𗊂�ɏ�B�����Ƃ����r���ŏ��R�c�M�ɋ\����Ă��܂��B�O���\����A�V�ڎR��� �����ڂ�Ȃ�@���������Ɂ@�_�����݁@����čs���́@���̎R�̒[ �������ɎO�\���Ŋ����B���j�E�M�����t�\�Z�̉Ԃ��Q���U�炵���B �M���͂��̎��ѓc�̒��ɂ��炵���B�܂��A�l���O���A���G�̊Ђ߂�����ŁA�����҂�݂����b�ю��̉��썑�t��S�]�l���R��ɒǂ��グ�ďĎE�����B���̔��Ɓu�S���ŋp����Ή��܂������v�Ɗ��j���ď]�e�Ɖ���ɕ������G�s�\�[�h�͗L���ł��邪�A�����̌��i�́A�ǍO��̗܂�U�����ɈႢ�Ȃ��B ����ɏ����̏j���ŁA�������܂ʐM�������G�̌��t�Ɍ����Ė����̒��őł��@�����b���L���ł��邪�A�^�^�͔���Ȃ��B �� (*1) �����B���c�M���̎l�j�B���c���̑�20�㓖��B (*2) ���R�M�N(���Ȃ�܂̂Ԃ���)��͕��c�M���̎o�B���c�����̏]�Z��ɂȂ�B�ȁE�����@�͕��c�M���̖��B�s�N���ɏo�Ƃ��~��֕s���ƍ������B���c��\�l���̈�l�B�쒆���̍���ȂǁA�M���̎�v�ȍ���ɎQ���B ���M���̎���A�]�Z��̕��c�����Ƃ͑Η����₦���A���̐킢�̍ۂɂ͏���ɐ���𗣒E�B ���V��10�N(1582�N)�A�D�c�M���̍b��N�U�ɂ��y�d��Ɏ����ď����𗠐�A����ƍN��ʂ��ĐM���ɓ��������B ���{�\���̕ς��N�����āA�M�N�͋}���b��ɖ߂낤�Ƃ������A�R�鍑�Ԋ�S(���݂̖ؒÐ�͔ȁB���s�{���c�ӎs�̎R��勴�߂�)�ŁA�������Ҏ��̓y���ɎE�Q���ꂽ�Ƃ����B�@ |
|
|
��(4) ��˗ǍO�̎��j�E���G���A���q���G�̖��ƌ�������
�F���̗̖��Ɍ}�����ėǍO��ꠓ���ɊM�������͎̂l���ŁA���˂č���̐����Ă������j�E���G�̋������Â���A����͏j��̐F�ɖ������ӂꂽ�B ��ˎ������ƂȂ��Ă��瑁�������N�A���̏��͓̂ܐ�ŁA���đ�a�ł̏��̂Ƒ卷�͂Ȃ����A�L���Ȓ����̐Ŏ��͉_�D�̍����������B�X�Ɋψ���������n�̗̎�ŁA���c��X�\�y�ƒ������D�ޗǍO�̕��낳���A�����B�̐l�C�����߂Ă����B �����Ē��������ł͂Ȃ��A�g���ł�����G���s���ȓc�Ɏ�����̐D�c�Ƃɂ͏��Ȃ��ނ̐l���ɍ��ꍞ�݁A�������̎��j�̉łɂ��C�ɂȂ����̂ł���B����͐����I�ȈӖ������u�m�ȁv�ł���������ŁA����ɂ͐M���̑㗝�Ƃ��Ė�������(*1)���n�߉ƒ��̖�������𑵂��A�������u��t�ɂ��Ē����̗ΐ[���v�Ɖ]�������ł������낤�B ���ɒ���ȂɏA�������G�͎q���҂ŏ��̎q�������A�����͍r�؉Ƃ���߂���ĎO��핺�����t�ɉł��A���t�͖��q���n���G���Ɖ��߂��B�O���Ǝl���͐M���̐�������ōא쒉���ƐD�c�M���̍ȂƂȂ�A�������]�䕔���e�̒��j�E�M�e�ɉł��Ă���B�����Ė����������̉ԉłŁA��̖��Ɠ��������Ђ�ƌĂ�Ă����悤���B ���j�͏\���q���c�ŁA�鋳�t�t���C�X���u�����̉���Ƃ����܂����D���ȋM���q�v�ƕ]�����������A�����a�g�������炵���B���j�E�\���Y�͗c���������ۂƌĂсA���c���莟��{�q�Ƃ�������ĎO�������Ă�����̗D�ꂽ���N�������B �ȂɘA�Ȃ����l�X�͐S�����v�w�̑O�r���K��������ɈႢ�Ȃ��B�������u���̒��͈ꐡ�悪�Łv�̌��ʂ�ŁA���̌��G���������ɂ��v��ʌ����̗����s�̂�ƂȂ��ӂ肩��₩�ɐ������ė���B �R�����̐k���n����N�M���̂܂�����ł��낤�Ƃ͐_�o���Ȓ��̌N�q�l�ł�����G�ł����C�Â��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B �� (*1) �����d��(�܂�݂�������)�B1549�`1578�B�M���̏����B�V��6�N(1578)�r�ؑ��d�����t�A���̒����ɎQ�����邪�A�L����U�h��̍Œ��ɐ펀�B�����A�w�M�����L�x�V��9�N(1581)9��8�����A�M�����m�s��^����ꂽ�҂̒��Ɂu��������v������A�w�M�����L�x�M�҂̑��c����̌�L�łȂ���Ώd���̎q���Ƃ������ƂɂȂ낤�B�@ |
|
|
��(5) �{�\���̕ρA�O��
�V���\�N(��ܔ���)�l���A���c�𐪈������M���̐��͂Ɖ]���A����܂łɐ��������E���A�����A�����\��B�ɉ����čb��A�M�Z�A���C�A�֓��܃J�����P���ɓ���Ďl�S�����z���Ă����B �����Đ�ɋL�����悤�ɁA�l���O���ɂ́A���c�ɗ����Ă����Z�p�����A�D�c�M����������܂��Ă����y��ꑰ�̉��썑�t�E�����B�܂��A�O�֔��E�߉q�O�v(*1)���x�m�������������Ƃ̊肢���ɂׂ��Ȃ��u�ؑ]�H�֍s���v�Ƌ��݁A�Ȃ�Ƃ肪�O��̕x�m�̍��������ňӋC�������y�ɋA���Ă���B �M���ɑ�����ł͊��C�����L(*2)�g�Ƃ� �u�V�����悢��ו��ƂȂ��̖�����Ȃ��֔��A������b�A���Α叫�R�̂�����̊��ɂ��C���V�������{�̊J�݂������v�Ƃ��d�|���������B ����ǂ��M���́A���˂Č��Ă̒�̏��ʂƌȂ̗P�q(*3)�ł��鐽�m�e��(*4)�̑��ʂɏA���ĉ��̘b���Ȃ��̂ŁA�ŕ@�����������l�ȑԓx�Œǂ��Ԃ��Ă��܂��B 䑂��������g�ɑ���M���̒�Ђ������ԓx�͍����S���钩�b�B�����{�����A�邩�Ɂu�������c���̑������낤���v�Ɠ���S�̂��i�����炵���B �� (*1) �߉q�O�v(���̂������Ђ�)�B1536�`1612�B���ƁB�߉q�Ɠ���B�֔�����b�E������b�B ���i�\2�N(1559�N)�z��̒����i��(��̏㐙���M)���㗌�����ہA�����̋N���������킵�Ė�������ԁB ���i�\8�N(1565�N)�̉i�\�̕ςŏ��R�����`�P���E�Q�����O�D�O�l�O�E���i�v�G�͏��R�E�Q�̍߂ɖ���鎖���뜜���đ����đO�v�𗊂����B�i�\11�N(1568�N)�D�c�M���������`����㗌���ʂ������B�`���͌Z�`�P�̎��ɑO�v�̊֗^���^���B�O�v�́A�{�莛�̌��@�𗊂��đ��ΎR�{�莛�ɁB���̎��A���@�̒��j�E���@�������̗P�q�Ƃ���B ���V��3�N(1575�N)�M���̑t��ŋA���B��A�M���Ɛe����[�߁A����Ƃ������ʂ̎�ɂ��A��l�͂悭�݂��̐��ʂ��������������ƌ�����B�ȍ~�A�M���ɗv������A��B�ɉ������āA��F���E�ɓ����E���ǎ��E���Î��̘a�c��}������A�{�莛�̒�����s�����肷��B10�N�߂��������Ă��U�ߗ��Ƃ��Ȃ������ΎR�{�莛���J�邳�������ɑ���M���̕]���͍����A�O�v�����q�ɂ��Ă��莆�ɂ��A�M������u�V������̋łɂ͋߉q�Ƃ�1�������シ��v���Ƃ����B ���V��10�N(1582�N)6��2���{�\���̕ςɂ���āA�M�����S���Ȃ�A���ӂ̑O�v�͗��������R�ƍ�����B�������A�u���q�ɖ��������v��槌��ɂ����A���x�͓���ƍN�𗊂�A���]�l���ɉ��������B��N��A�ƍN�̈����ɂ�苞�s�ɖ߂邪�A�V��12�N(1584�N)���q�E���v��̐킢�ŗ��Y�����˂������߁A�܂����◧�ꂪ�낤���Ȃ����O�v�͓ޗǂɐg���A���҂̊Ԃɘa�c�������������Ƃ����͂��Ă���A�������B ���ӔN�͈���I�ɋ�t����苒���ĉB�������B�c��17�N(1612�N)�I���B���N77�B (*2) �����イ���͂�Ƃ�B1544�`1603�B���ƁB���Ɠ`�t�߁A�D�c�M���A�L�b�G�g���ƌ𗬂��������B���̒����w���L���L(���L�L)(���X�L)�x�͐M����{�\���̕ςɊւ���L�q�������A�j�����l�������B�{�\���̕ς̑O���A�{�\����K��M���Ɖ�B�ϒ���Ɍ�����������䏊���̏��L�^�B�R��̍����A���q���G�̖���ی삵���Ƃ����B (*3) �P�q(�䂤��)�Ƃ́A�����ȑO�ɂ����đ��݂����u���l�̎q���������̎q�Ƃ��Đe�q�W�����ԁv���ƁB�������A�{�q�Ƃ͈Ⴂ�A�_��ɂ���Đ������A�q���̐��͕ς��Ȃ��ȂǁA�u�@�I�ȁv�e�q�W�Ƃ����Ӗ������������B (*4) ���˂ЂƂ���̂��B1552�`1586�B106�㐳�e���V�c�̑�܍c�q�B�D�c�M�����牮�~������ȂǗD�����ꂽ�B�{�\���̕ς̍ہA�M���̒��q�E�D�c�M��������䏊(�����̑O�g)�ɑ؍݁B�M���͖��q���G�R�ɓ���䏊����͂���钼�O�ɋx�틦�������Ő��m�e����E�o�������B�q�ł���M�c�e���͐D�c�M���̗P�q�B���m�e�����M���̗P�q�Ƃ����������邪�A���m�e�����M�c�e������������u�܋{�v�ƌĂ�Ă����̂������̌�`���B�@ |
|
|
��(6) ���q���G / ����1
���j��͉i���̓䂾���A�����N���ւ�s�ɏZ�ޒ�b�A��Ў��A��A�����̕x���B�̊ԂŊ��邩�k�����J�Ԃ��ꂽ���ɁA���̊�@���~�����b�Ƃ��đI�ꂽ�̂����q��������G�������悤���B �����Ǘ̂̓y��Ƃ̗�������ޔ��Z���q�̖���ɐ���Ȃ���A�킳�ɔs��ĕ��Q�̗��ɏo�Đh�_���Ȃ߂��ނ́A�₪�ēS�C�p�Œ��q�Ƃ̋q���ƂȂ�B �i�\�\�N(��ܘZ��)�����`�����א쓡�F�ɒ��q�𗊂����ہA�`���̉Ɛb�ƂȂ�M���ւ̌����Ƃ��Ĕ��Z�Ɉڂ����B �����Ă��̏H�A�M���͎O�D����Ǖ����ē������A�`�����\�ܑ㏫�R�E�ɏA�C�����A���G��D�c�Ƃ̋��s���ݖ��ɔC�����B���G�͓�l�̎�Ɏg���鎖�ɂȂ������A����̊�ʂ����ׂĎ���ɐM���Ɏ䂩��Ă������炵���B �V�����N(����O)�A�`�����M���̓ƍق�{���ċ��������ۂ͐M���ɎQ����ꠓ��̋`�����U�߂Ă��邪�A�ނ͋�����u���R�U�t�̉�����������ׁv�Ə̂��ď����Ǖ�����A���̖����~���Ă���B �M���͐D�c�̕����ɂ͖����[�����{�ƕ����Ɋ��҂��āA���G�����s�Ǘ̂Ƃ��]���ׂ��d�E�ɔC���Ă���B�܂��A�ߍ]��{��ƒO�g�T����\���̑��Ƃ��A���������B�Ƃ̌����Ƃ����B �����Č��G�ɐڂ����������B�����̐l���ɍD�������� �u���G�a�����������Ȃޏ��͕��|�݂̂Ȃ炸�A�O�ɂ͌�(*1)����ɂ��A���ɂ͉Ԍ��������Ď��̂��w�ԁv�Ǝ]���Ă�����ŁA����ƍ����� ���Ă͍����A��������s���@�Ȃ݂̂��ȁB ���̐��X�̖�����c���Ă���B �� (*1) �ŁA�l����Ɏ��ׂ����̂Ƃ���܂̓��B�m�E�`�E��E�q�E�M�̌܂�(����)�B�@ |
|
|
��(7) ���q���G / ����2
�����I�Ȓm���l�ł��������G�ɂ͐M���̋ʐ��ɏĂ������͐S���ς�����̂��������ɈႢ�Ȃ��B �Ƃ͉]���A�u���I�̂悤�ȕY���̐g���珢���o���ꔜ��ȗ̓y�Ə�����a���Č��ꂽ�M���v�ɑ�����G�̒����S�͂��̌R�߂̒��ɂ����炩�ł���B �ނ̋����̍��{�́A�M���̎��̂悤�Ȗ�]�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ������ł������낤�B �M���̑��c�͖�����ł���B�����̖�]�����ׂ̈ɑ������Ă��邾�����B �M���́A���q�A���A�{�莛�A�b�R�Ƃ̋���E���邽�߂ɁA���R��V�c�𗘗p���Ă����B �����ēG�����Ȃ��Ȃ������A�M���͓V�c�ɏ��ʂ𔗂��Ă���B ����͐M�����A�������⑫���`���̔@���A�����ƂȂ�c�ʂ̏�ɗ��ƍَ҂����Ƃ��Ă��邩�炾�B �����Đ��e���V�c�� ���J�����Ƃ��ā@�N����������@�䂳����A�S�̂܂܂Ɂ@�Ȃ�ʐg�Ȃ�B �ƒQ����Ă��鎖��m�����B �u�V�c�͓V���ł��蕐�͂�q�d�ŐN���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ɖ]���×�����̓`�������̂�����ɍ݂�҂̔C�ƒɊ����Ă�����ɁA�ߔN�ɉ�����⍓�Ȉ������A����̏o�w�Ŗʖڂ��������\�����d�Ȃ� �u�Ⴆ�A�剶�����ł����Ă��A�^�̎�N�͓V�c�ł���A������X����Ƃ���҂����t���ł���v�Ƃ̐M�����犣���ꝱ�I�{�\���̋��ɏo�����̂ɈႢ�Ȃ��B �����ďG�g���܂����S�ł͐M���̖�]���Ƃ��Ă������́A����˃��x����ɍۂ� �u�����M�F�A���ƂɓV������点��ΕK���c�ʂ��X����Ƃ���͕K��Ȃ�A�V���ׂ̈ɂ������������v�Ɖ]���A�ގ��g�͂����܂œV�c�̐b���̊֔��Ƃ��ēV��������v�����̂����Ă����炩�ł���B ���G�͏�X�e�����d�˂Ă�����������̒Q���Ɣނ̌��N��ؖ]����Ă���̂�m�����B�����ĔY���A�M����遂��ċ͂��ȋߐb�݂̂ŋ��ɓ���\���m���A�܌���\�����A�����R�ɎQ���Đ_����₤���B���Ɍ��ӂ��ł߂��̂� �u��(�y��)�͍��A�V�����Ȃ�܌����ȁv�Ɣ��債�A �u���X�͂Ȃ��@���ՂȂ鎞(�y��)�B�v�ƌ����ɂ���Ă����炩�ł���B�@ |
|
|
��(8) �M���̍Ō�
�V���\�N(��ܔ���)�Z������A���ꂪ����̈��y�Ƃ��v�킸�A�M���͋ߐb�͂��Z�A���\�����]���������̌y���œ��������B�{�\���̏h�V�Ɉꔑ����Ƒ�������A���X�Ɖ��������ė�������⍋���B�ɓV���̖���Ə̂���钃���̈�i���܊コ����B ���̓��K�ꂽ�����A�a��l�l�\�]�l�ɂ��˂Ď咣�́u���ʂƕ��Ɨ�̗̍p�v�̍����s�����B���̖�́A���j�E�M���⋞�s���i��E���䒷����Ɛ[�X�܂Ŏ������݁A��@���Ŗ����̎Q���̍\�z�����Ȃ��疰��ɏA�����B���̖�A�ꖜ�O��̏��m�𗦂������G���u�G�͖{�\���ɍ݂�v�̌��ӂ��߂ċ}�i�����J�n���Ă��悤�Ƃ͐_�Ȃ�ʐg�̒m��R���Ȃ������B �����ĘZ������̑��ŁA�n�����Ă����ނ͂Ȃɂ�瑛�����������ɖڂ��o�܂� �u���y�������܂ł��n�߂��̂��v�ƐX���ۂɒ��߂�����Ƃ����B����͕s�v�c�ɂ������Ԃō���`�����M���̋}�P�ɍۂ��������̂Ɠ����ŁA�������H��̍K�^���ɂ��V�^�̐s����������Ă����̂��낤�B �����̐M���̐��͊O�ɂ���E�����ӂ̓G�Ɖ]���A�͂��I�ɒ��암�̒n�����ɉ߂��Ȃ��B���ꂾ���ɉ�Ƃɂł��A��悤�ȋC�����œ��������̂����A�Q�����A���ė������ۂ��� �u�G�͐��F�j�[�̊���|������R�ɂāA���G�̖d���Ǝv���܂��v�ƒm�炳����A�������ɐM������u��R�Ƃ��������A�������G�̋����������� �u��Ȃ��甲��������I�v�Ɗ����� �u����ɂ͋y���v�̑��ꌾ�A�ꂢ�������ŋ|������ė͐�B����g�������� �u���͂₱��܂Łv�Ɗقɉ������A�G���@���ʼn���𐴂ߔR����鉋�̒��Ŏ��n���A��Ђ̈⍜���~�߂Ȃ������̂͌����ł���B ���l�Ԍ\�N�@���܂ڂ낵�́@�@���Ȃ�B �̋�̒ʂ�A�l�\��Ō㐢�Ɍ��c���ׂ����X�̔E�ё����~�߂Č����������̂͑����̎����B���q�E�M���������ʼnX��������ĕ��ɏ}�����̂͌ߑO�㎞�O�������Ɖ]���B �V�ڎR�ŏ������q���ؕ����ċ͂��ɎO�J����ł����Ȃ��B���Ɉ��ʂ͏��鏬�Ԃ̔@���h���Ɖ]����B�@ |
|
|
��(9) ���q���G�A���n���v���Ƃǂ܂�
�u�M�����q�����I�v�̋���̓A�b�Ɖ]���Ԃɗ������O��y���߂������B����������A�M���̖����Łu�I�B�G��̖{�莛�����F�E���ɂ��ĉЍ���f����v�Ɛ�ܕS�̕���i�߂Ă����O�H���G�͋����Q�ĂĈ��Ԃ����Ɖ]���B ����R�ł́u���͂╧�̉�����F����Ȃ��v�ƑS�R�������āu�M����E�̑�C�@�v���n�߂Ă������A�s�v�c�ɂ��g��͖���̓�������������에�����ĕ����Ɋ��ӂ����炵���B ��b�R�Č��ɑS�����s�r���Ă����F��O�R���n�߁A�S���̎��@����ĂɁu�V���I�v�ƕ����������l�͍����̑z���ȏ�ł��낤�B���m���ꐢ�I�������f�s���ꂽ�M���̎S���ɂ܂�@���v���̍��܂����Ĕނ炪��͓̂��R�Ɖ]���悤�B �܂��Ă�A�M���̖��Őe�A�Z����S�E���ꂽ�ɉ��~�̈⑰�炪�u����������I�v�Ƌ��C�̔@������������͓̂��R�ō����呛���ƂȂ����B�������ւ��Ă����ѐA�̕��n�ɗ\���͉����ɓ�����B�������̊ϕ�ł��u�V���Ȃ�v�ƕ��������Ă��邪�A��ɂ͖k���M�Y�̐�w�ƂȂ������O�Y���q(*1)��ɂ���đS�������Ă�����ꂽ�B�{���O��Ă������̂́A�K���{���͐_���̐X�ɂ������Ė����������炵���B������Ԗڂł����G���~����̂��Ƃ����l�X�����������悤�����A���̌��G�͗��O�̖��S���ɓ����Ĕ����u�������q�v�Ɖ��߂��B�S����̕�������ɒ����Ɓu����v���c�����Ƃ��Ȃ��v�ƕʎ��ɓ���A�Â��Ɏ������������ߕ�����Ƃ����炵���B ����ǂ����m������m�̋}��Ō��t��ē��A���c��d�b�������Ă����� �u���Ƃ��V�����V���l�Ƃ��Ē�Ɩ����ׂ̈ɕ��N���ĖႢ�����v�ƍ��肵�Q���v���~�܂����Ɖ]����B �� (*1) ����@�B�M�̕҂��Q�ƁB�@ |
|
|
��(10) ���q���G�A�����ċߍ]�Ɍ���
�Z������̌ߑO�B�d�b��̐i���ʼn��߂ēV������̐헪�����グ�����G�́A�����ɏG�g�Ƒΐ풆�̖ї��ɁA���C���H����}�g���ċ��͍���v�������B����Ƌ��ɁA������ۂɂ������R�`���ɏ�Ă���B����͋���ɖї����Ƌ��ɏG�g��|�����A�������ď㋞���ꏫ�R�E�ɕ��A�肢�A���̉��Ŋ���Ƃ̐����������낤�B �����ɂ��ēc�ƌ�풆�̏㐙�Ƃ�A�g���喼�Œ����e�����d�˂��א쓡�F�A��a�̓��䏇�c�A�ےÂ̍��R�E�߂⒆�쐴�G��Ɏ��X�Ǝg�҂𑖂点�ĎQ�w�����߂�ƁA�ߌ�ɂ͋����ċߍ]�Ɍ��������B ����͈��y����U�����A�O�H�̍��a�R�A�G�g�̒��l�𗎂��āA�ߍ]�A���Z��B�ēc���Ƃ̐i�U��h�����Ƃ����킾�������A����͖����̌��t��R�t�E�ē����O�ɔC���A�ގ��g�͑�R�𗦂��ĐےÂɐi�ݓ���A���R�A��������������Ǝ蒆�Ɏ��߂�ׂ��������B ���ɓ���͖{�\���̕ς�m�����̐M�F����̋~���ɂ��������A�o�O��ꑰ��h�����Č��G�ɋ��͂��A���̈�˗ǍO�Ƌ��ɋߍ]�ɏo�w���Ĉ��y��U���ɎQ�����Ă���B �������G����R�ŐےÂɐi�ݑ���ɔ��鐨�������Γ���A���R�A�����ꖜ�ܐ�̕��͂͑��X�ƎQ�������ɈႢ�Ȃ��B������肩�A�����Ɖ]��ꂽ�����̐D�c�M��(*1)�����̎�����ɂ����̂����獇���������낤�B�M���̎���m���ē��S�҂����o���A�r���ɕ��Ă����M�F(*2)�͑��b�Ƌ��ɍs��������܂��������m��ʁB �� (*1) �̂Ԃ��݁B�D�c�M���̎���E�D�c�M�s�̎q�B�����͖��q���G�̖��B���E�M�s�������E�M���ɎE���ꂽ�B�c���̂��߁A�M���ƐM�s�̐���ł���y�c��O�̏����Q��������āA�ēc���Ƃ̋��ŗ{�炳���B�{�\���̕ς̌�A����5���ɐM�F�ƒO�H���G�̌R���ɏP������đ���ŎE�Q�����B��͍�ŎN���ꂽ�B���N28�B (*2) �M���̎O�j�B�Ώ�P�ۏ���Q�ƁB�@ |
|
|
��(11) ����ƍN�A�ɉ�z���̓����s
�V�^�̐�D�̋@����G�g�������Ƃɏd�_��u�������G�̍��̎��s�͌�ɒv���I�Ȃ��̂ƂȂ�B�������A�_�Ȃ�ʐg�̒m��R���Ȃ��A���������R��ɋ͂��ȕ���u���������ōQ�����k�i�����B�Q�����y��ɓ������̂͘Z���ܓ��ő��ԂɉƍN��s�������킵�Ă���B �ƍN���{�\���̕ς�m�����̂́A�䌩�����I���ċ��ɖ߂�ׂ��ѐ��R�[���}���ł����Z������̌߉߂��ŁA�攭���Ă����{�������Y�������ŕ����Q�ĂĈ��A���ċ}����B �v�������ʑ厖���ɂ������̉ƍN���������A�ꎞ�͓r���ɕ��u�{�\���Ŏ��n����v�Ɖ]���o�����炵���B �R������l�V����A�S�̔����ƌĂꂽ�ɉ�o�g�̕��������ȉ��̌\�]���̗E�m�ƁA�M���Ɍ������O�痼�̂����痼�����A��̌������Ƃ��ĕԂ���Ă����̂��������K�^�������炵���B�M������ē����ɂ���ꂽ���J��G��̐s�͂ő�a�̍����E�\�s�������B�ɂ��āA�Ꝅ���ɏP���Ȃ�����K���ɐ蔲�����B �b��M�y�̑��������r�̓@�ɒH��������A�o���ꂽ�Ԕт���Â��݂ŕn�ڂ�H�����Ɖ]������@���ɓ�s�R������������B �Z������̖�͑�������ňꔑ����ƍb��E�ҌQ�Ɍ���Č�ē�(*1)���z���ɉ�ɓ���Ɣ����̗v���ɉ������ѐA�O�V����S�]�l���y�����Č��ꂽ�B ����͋��N�M�����ɂȂŎa��ɂ���A�����ēy�Ƃ��ꂽ����łȂ��A�h�����đ����ɓ������т��҂܂ŗe�͂Ȃ����Y���ꂽ�̂ɁA�ƍN�̓������͎�����ی삳�ꂽ���Ԃ��ł������B��s�͒ѐA�A�����A�Ɛi���A�����z���̎R���ł͖��q���̓G�P���A�������o�̋�l�������������ɐ蔲�����B �Z���l���ɂ͈ɐ��喩�̑D��s�E�g�약���̐s�͂Ŕ��q�l���o�����A�����ɎO�͕l�ɓ����������͗]�������������炵���A������g��Ɉ����̗���F�߂Ă���B �� (*1) ���Ƃ��Ƃ����B�W����630���B����E�O�d�������Ɉʒu�B���̖��͊��q����ɗՍϑT�̍��m�E�������t���ɉ�O�c�̋R���ɗ���ꂽ�Ƃ��ɁA���l�������ō�(�Ƃ����H���̐ڑ�)�����������ƂɗR������Ƃ����B�@ |
|
|
��(12) �L�b�G�g�A�u������Ԃ��v
�ƍN�������ɉ����ɓ����ĉƐb�B�����삳���Ă����Z���ܓ��A���G�͈��y��Ɏc���ꂽ���������C�O�悭�Ɛb�B�ɎU���A���ɍ��������Ƃ��Ē��l����A���c�����ɂ͍��a�R����U�������ċߍ]�A���Z�肵���B �����ɂ͋g�c�����������g�ƂȂ��Ĉ��y��K�ˁA��̉b���ɂ�萪�Α叫�R�����́u���s���E�v�ɔC����Ƃ̌��h��`����ꂽ�B����G�͈��y�̎������t�ɑ����ċ��Ɍ����B ����ɂ͒���ɋ�ܕS���A�R�Ƒ哿���Ɋe�S���������A���s�s���ɂ͒n�d�Ə���z�����đP����Ă���B �R���Ȃ��炻�̓��̌ߌ�A�G�g�����������ї��ƍu�a���āu������Ԃ��v�Ɩ��Â��������ׂ��҃X�s�[�h�ŕP�H�ɋA��u��E���̋w����v�ƈӋC���������߂����Ă���Ɖ]����������B �\�������A�܂����ƐM�����˂Ȃ�������G�͋������B�j�R�������瓴�����ɕ���i�߂ē���R�̓�����҂������A����Ɏp�������ʁB�d�b�E���c�`�܂��S�R�ɑ��点�ē��������B����Ƃł́A���G�������u�{�q��Ă������j�E�\���Y��l���Ƃ��ď��c�ɋI�B�����S����^����v�n�t�������B�����߂�ҏ��͑傢�ɒ��������A�ƘV�M���̏��q���Ҕ��Łu�����Ə������ׂ��ł���v�Ɨ͐��B�d�b�B�̈ӌ����Η����Č��܂�Ȃ������̂͏G�g���̗\�z�O�̋}�i�����傫�ȗv���������B�@ |
|
|
��(13) ���G�A�R��ɕz�w
���G�ɂƂ��čő�̕s�^�͖ї��Ƃɑ��点���g�҂��C�H�͊C���r��đD���o���A���H�̖��g�͎������낤�ɖї��̐w�ƌ���ďG�g���ɔ�ł��܂������Ƃ��B�G�g�͈ꎞ���]��������R��ʗl�Ɍ������x�����ł߂�B�����āA���˂Ĉ�����(*1)����Đi�߂Ă����a�c��������ʊ�ŋ}���Ő����������B �Z���Z���̒��ɂ͍������o�����A�������ɂ͕P�H��ɓ����B�����ň���x�ނƁA������ɂ͍ĂіҍU����W�J�����B �ނ����ɓ��������̂͏\����̒��ŁA�r���ł����X�ɒO�H�A�r�c�A����珔���Ɏg�҂𑖂点�āu��N�̒�������ɎQ������v�悤�v�������B�l�\���߂�����������\��(�O�\����)�Ɖ]������(���a�̗��R�͈���O�\��̂����x)�ő��j�B���̐����������ɗU��ꏔ���͎��X�ɎQ�����A���䏇�c���\����g�҂𑖂点�ğ����ɎQ����|�̐������o���A�ꖜ�̑啺�������痄��Ȃɐi�߂�Ƃ����B ������@�������G�͂�ނȂ��������A�j�R�̕���]���A����E�݂̎R���~�ɏW�����ďG�g���ƌ��킹��Ƃ����B�����m����ꠓ���̗ǍO�� �u��炪��������͌��G�a�̂��A�Ȃ̂ɕ����Ƃ��Ă���܂����s�`�v�Ɠ{��B �u�V�����ڂ̑��Ȃ�ΐg���͗���̔ԓ����Ƌ��ɗ������萸�����𗦂��D�ɂďG�g�̑����ɓːi����o��ł���B����ēa�͗��썶�݂ɕ����~�߂ċ@��҂��A������Ԃ̐؏��Ɉꋓ�ɓn�͂��ďG�g�{���̔w����P����Ώ����͕K��Ȃ�݂̂��A����̋`���͓V���ɍ�����B�v�Ɨ�X����f���悤�Ȗ����𑗂����B����ŏ��c�͖������낽���A�����߂Ƌ��c���ė��썶�݂Ō`�������鎖�ɂ����炵���B �� (*1) �������b��(������������)�B1539�`1600�B�T�m�A�喼�B�����͕��c���ŁA�u�������v�͏Z��������(���|������[�s���@])�̖��B�ї����̊O��m(���Ƃ̑ΊO���̔C�߂��T�m)����A�ŏI�I�ɂ͑m���̐g���̂܂ܑ喼�ƂȂ����B�@ |
|
| ��4�@�V���R�̐킢�@ | |
|
��(1) �z�w
�V���\�N(��ܔ���)�Z���\����A���G�͓�����(*1)���~��Ēj�R���牺���H�ɖ{�w���ڂ��ƎR��A�����̕���P�ނ����A���Ə�����(*2)�����_�Ƃ����B�����X����ːi���ė���G���R��̊X�͂���𗬂��~�����쉈���Ɍ}��������ɕς����̂ł���B �l�I�̌R�t�E�ē����O�� �u�l���̏G�g�R�ɎO���̈���x�̕��͂Ō���ނ͕̂s���B�����͈ꎞ�������ċߍ]�e�n�ɎU�݂��Ėk�ɔ����Ă���E���E���t�ȉ��ܐ�̕��ƍ������A��{�A�T�R��ɂ���Đ키�ׂ��ł���v�Ɨ͐����Ă����G�� �u���s���̒������������͏o���ʁv�ƕ����Ȃ������S���͏[���@������B �u�����A�r�ؑ��d��ꑰ�����݂ł�������v�Ɠ��S�ɒQ���Ă����ɈႢ�Ȃ��B �����ĘZ���\�O���A����̓��͒����狭���J�������B ���G�͈��y��������t��ɋ}���Q��̋}�g�𑖂点���B�J�̒��������H���珟�����̑O���Ɉʒu�����V��(*3)�ɖ{�w��i�߂����A���̔z���� �����ɐē��A���A�ēc�A���q�Β���̋ߍ]���A �E���V���R�[�ɂ͏��c�A���͂̒O�g���Ɉɐ��A�z�K�A��q�狌���{����O�A �����ɂ͒Óc�A����炪���쉈���Ɏ����ł߂��B ���G�{�w�ɂ͓��䂩��A�������c�`�܂��\�����Ƃ��čT���A���̑����͈ꖜ�Z��]�Ɠ`����B���G���ł����݂Ƃ���E���E���q���t�ȉ��O��̐��s�̎p�������Ȃ������̂́A���Ƃ��Ă��ɂ��܂�ĂȂ�Ȃ��B ����ɑ���G�g�R�́A �����ɍ��R�A����A�x�B �E�������ɒr�c�A�����A�ؑ��B �����V���R�[�ɂ͏G���A���c���z�w�A �����ďG�g�{�w�A�I�J�A�O�H�A �a�R�͐M�F�ŁA�`�R�O�����]���т����藼���X���߂Ă����B ���G�Ɛe���̂������g�c�����������̓��ɉ����H����R��߂��܂ŗ��Ċϐ킵�Ă���̂͒�̓��ӂ��u���Ƃ����G�������Ă���ʂ��v�Ɛ_�ɋF��C�����������낤�B �� (*1) ���s�{�����s������R�B���ē�����X���̒��p�n�B���݂͂��̏�����������1��(�����o�C�p�X)���ʂ�A�����_�̖��O�Ƃ��āw�����������x������B�������A�Ȃ��肭�˂������͂Ȃ����`�̗ǂ����H�B (*2) ���傤��イ�����傤�B���s�{�������s�ɏ��݂����B�閼�́A�t�߂̓����Ù��ɗR���B�{�ۂ���я��c���䂪1992�N(����4�N)�ɏ�����������Ƃ��Đ������ꂽ�B (*3) ��V��(����Õ��Q)�́A���s�{��R�蒬�̓��k�[�Ɉʒu����B�T���g���[���s�r�[���H��̗���ɂ���A��V��(����Õ��Q)�ƌ��G�{�w�Ղ̕W��������B�@ |
|
|
��(2) �J��
��[����ꂽ�̂͌ߌ�l���߂��V���R���ʂ������Ɖ]����B��͂�V���R����ǂ����E����d�v�n�_�ƂȂ����B�Ǖ��ł͂����Ă����R�ɒn�̗���I�ׂ����q�������ɁA�����D�c�R�̒��ł��u���q�̓S�C���v�Œm��ꂽ���s�O�炪�E���E���t�ɗ������ĊX�����������V���R�Ɍ��w��z���ċ���ΐ�ǂ͑傫���ς����ɈႢ�Ȃ��B ����͐킳���Œm��ꂽ�ē������������킳�Ԃ�ō��R�w�������ėD�����������B�ɐ��疋�{����O���\�z�O�ȕ�����������̂� �u���̈��ɏ��ĂĂя��R�`�������Ɍ}���Ė��{�ċ��������o����v�Ɖ]�����Ҋ����炾�낤�B ����̕s�����������G�g�́A��E�G���ƍ��c�A�x�R�� �u���Ƃ��Ă��V���R���U�ߎ��v�Ǝ��B���A�{�w�ꖜ�̐��s�̂��ׂĂ��R���襘H�ɓ�����B����Ƌ��ɉE���̑����̖ҏ��B�� �u��C�ɉ~������˔j���ė��쉈���ɓG�̍������͂���v�ƌ���B�ҏ��E�r�c�����Ă�������ׂ炪���������Đē����ɏP�����������B ���̒��A���䏇�c�́A�G�g�A���G���� �u�����Ɩ�����A�M�F�l�ɏ]���ė���ۂɐw�����f�Ȃ��~�U����v�ƌ�������Ă����B���������̎��A���䐨�ꖜ����������A�˔@�����n�͂��ďG�g�{���̔w���˂��A�҂��\���Ă����ǍO��͗E��Ɍĉ����A��ǂ͈�ς����낤�B �c�O�Ȃ�����ɓ���̔~���̔n��͎p�������Ȃ������B�@ |
|
|
��(3) ���q���G�A��������ɑނ�
���ɖ����ʐē����͕�͂���ĕ���n�߂�B�\�����ƂȂ������q�̖ҏ��E���c�`�܂�����̉������ۂ��������ĖҔ�����W�J���A��ǂ͈�i��ނ��J�Ԃ��B�������A�R�m��̖��q�̗E���E���c���Y���q��炪���������ׂɁA���ɓV���R�͏G�g���̎�ɋA���A�j�ǂ͂�������n�܂����B �����Ԃɂ��Ė��q�̑����ŕ���������Ă����ē��A���c�����������o���ĕ��ꂽ�B����O�̌�q�������{�w�ɋ}�g�𑖂点 �u�킳�͑�����܂łł�����B�g���͎c�鏫�m�Ƌ��ɓG�w�ɓ˓����ē����d��Γa�ɂ͈ꍏ�������������ɑނ���}���v���܂��悤�v�Ɛi������B ���G�� �u���Ȃ��ɂ��v�Ǝc����{���̑S�͂𓊂��čŌ�̈������s����Ƃ������A�V�b�E��c�ѓ�����̌��_�ɂ�������A �u������Âȓa�ɂ����ʂ��U���A�Ⴆ����͔j��Ă����y�A��{�A�T�R�ɂ͌��t�a�n�ߌܐ�̖��������݂ł���A�ċ��͌����ĕs�\�ł͂���܂��ʁA�����͐悸�������Ɉڂ��܂��v�Ɩ����������g���������B�@ |
|
|
��(4) ���q���G�A������
���G���v�������ď�ɑނ������A���q�R�̓����͎O����z�����҂�������Ζ��ɋ߂��ނƋ��ɓ��邵�������͐�ɖ������A�@���Ɏ��͂�s���Ă�����͎��Ԃ̖��Ǝv��ꂽ�B �Q�����R�c���J����A�ߍ]���ƍ������Đ�Lj����v�鎖�ƂȂ�B���G���a�������q�A���q�Β���Ɛ��\�R�Ƌ��ɔ邩�ɏ���o���̂͂܂��G�g�����������͂ޑO�������B�G�g���͏������Ƃ͉]���A���m�̎��҂͎O��O�S�A���҂͐��m�炸�Ɖ]������A��(�M��)���E�������G�ɖ��q�̏��m�͂����܂Œ��߂�s������ŁA��]���̋������Â��B ����o�����G�̈�s�͋v����̊ԓ��`���ɕ����A�[����T�J��k�サ�ĘZ�n���ɓ��������A���������玵���߂��Ö�̉J�����s�ɔ�J���ނ������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�R���ނ���������ڂƕ@�̐�ɂ���F�����ɓ���A�ǍO���q�͕K������͂������Ə�ŋC�͂�{�킹�����낤�B�����ė������ɉF���썶�݂̋ߓ���n������Đ��c�ɒ��s�����ɈႢ�Ȃ��B������}��m���Ĉ��y�������t�ȉ��O��̏��m�ƍ����ł����낤�B ����njN�q�̌��G�͔s��̉Q���Ɉ�ˈꑰ���������ދC�ɂȂꂸ�A�Z�n�����瓹�����ɂƂ菬�I���Ɍ������B����͐l�͂̋y�ʓV�^�̐s���鏈�A�Ɖ]����������܂��B �`���ł��ǍO�琔�S��ꠓ���ő҂���тĂ���̂��@�����A���G�͗₽�����_�̑���܂܂ɉF����푺�̏��I���ɓ������B�����{�̎БO�Ő_������Ɣ�ꂫ�����ܑ̂ɕڑł��ē��@�@�{�o���̗��̒|���ɂ������������B �܂�����̒��̏��������鏬��̔Ȃ�ŁA���l���ň�ׂ�����ƖԂ��Ă����y���E�����q�̌J��o�����|�����^�������Z�̘e�̌��Ԃ��牡����[���т����B�@ |
|
|
��(5) ���q���G�̍Ō�
�b���͏��̒ɂ݂ɑς��Ȃ���n���}�����Ă������G���₪�ė͐s���ė��n�����B�������ߐb�Ɉ͂܂�Ȃ���Ō�̋C�͂��ӂ�i��Ɩ��S���ł̎����ɕM���������Ǝv����B ���t��喳���@�哹�͐S���ɓO���@�\�ܔN�̖��@�o�ߗ���ꌳ�ɋA�� �u���{�̕��m�̐^�̏��t�͒�Ɏg����哹�ɂ��݂̂ł���A���̎��͂��˂ĐS���ɓO���ċ���A�G�g����Ⴆ��E���̉������������悤�Ɓg��`�e��ł��h�Ɖ]���A�������p���鏈�͂Ȃ��B�Ƃ͉]���A��ƓV�������ׂ̈ɖ𗧂���Ɩz�������\�ܔN�̗��z�����₳�߂āA�H���̐��E�ɋA������K�ꂽ�炵���B�v ���̎����c���ƍa�������q�� �u��[�͐[���������Č�����ʂ悤�ɂ���v�Ɩ������B �����ʼnƐb�B�͗܂Ȃ���Ɉ�̂͋߂��̖��̍a�ɖ��߁A���͈ƕ����ŕ��Ŋ��C���ɋ߂��D�c�̈�p�ɖ��߂�B���ꂩ�爽�҂͎�ɏ}���A���҂͍�{����߂������B�@ |
|
|
��(6) ���q���t�̍Ō�
�\�O���̖锼�A���n����t�ȉ��A�O��̐��s�͈��y���Ă����B���G����́u�R��Ō���v�Ƃ̋}�g���r���œG�ɎՂ��Ēx�ꂽ�ׂł���B��镨���抸���A���c�ɂ��������������A�b��E�ҋ������q�̔s�k��m���Đ��������A�勓���ďP�����������B ������ӂ蕥���đ�Âɓ���ƓV���R�ŕ��킵���x�G���炪�u��炶�v�Ƃ��藧���ǂ����Č���ƂȂ����B�L���ȁu�ΐ��n��v�̖���ʂ����܂ꂽ�͍̂����ł���B���̓��A�ނ͗��R�̒��A���i�Β��𓂍�P�l�܂Ŗ�ꗢ�A���n�̖��Z�����ē˔j�����B�G�����Q�����A����̏��Ɉ��n���Ȃ��ŕʂ��������B ���Ă̒��ɍȎq�̑҂�{��ɋ킯����ƁA���G�̈��D�����M�d�Ȍ|�p�i�����̂܂Ď�������͍̂��Ƃɑ��Ă��\��Ȃ��Ɩx�G���ɏ��n�����B���̌�ɍŌ�̈���S�c��Ȃ�����Č��G�v�l�ȉ���去������Ɖ^�������ɂ����B����͐M�M�R�ł̏��i�e���Ɣ�ׂ悤���Ȃ��u�₩���ł���A���q�̉ƕ����Â��B �V���\�N(��ܔ���)�Z���\�l���A���i�ΔȂ��g�ɐ��߂ēy����̒����ł��������q�ꑰ�� �u�Ƃ��͍��A�V�̉��m��@�܌����ȁv�Ɖr���Ă���͂��\�O���ŋ�������������ɖS�ы������B �]�k�Ȃ���A���{�z��j�ɋP�������������������������y�邪�D���ɋA�����̂������ł���B�ɉꂩ��i�k���M�Y�����������������A���̋M�d�Ȉ�i�Ƃ��]���ׂ����̋�����ނ��ނ��Ă������Ă��܂����Ɖ]������_�O�ł���B����Ȕn���a�Ɉɉ����ł�����ꂽ���Ǝv���Η܂��~�܂�Ȃ��B�@ |
|
|
��(7) ��˗ǍO�A���
�X�ɓ�����A�邩�ɉF�����K�ꂽ���䏇�c�͗ǍO�̒��q�E�o�O�Ƌ��Ɍ��������ĊJ��~���������߂��B ����ƗǍO�͎��j�E���G��T��ɂׂ͂点�āA�����ނ�ɂ��̐S����q�ׂ��炵���B �� �{�\���̕ς�m�������A�َ҂͌N�q�l�Ƒ��h���Ă�����G�a�����ɂ���ɂ͕K���[���������ɈႢ�Ȃ��B������Ă킪�s���������߂悤�ƍQ�����n�������B �����ĕ�ł����闌�O�̖��S���ɂ����ނ�K�˂�Ɣ��Ɋ�� �u����ɂ͂��ׂĐ^������낤�B�v�ƒ�̈ӌ���璩�b�A�Ў��̒��V���狞�̒��N���̓������v�����ڂ����q�ׂ���� �u�䍑���_���ƌւ�R���͐_�����n�̓V�q�����A��͓V���ɂ��ĕ��͂�q�d�̔e���ɂ���Ė]��ł͂Ȃ�ʂ̂������Ƃ��Ă�������ł���B �M�������H��̉p�Y�ł��鎖�͂悭�����Ă��邪�A���̗��j�Ɠ`�������Ē�̏�ɗ�����Ƃ̖�]������ꂽ�̂͐b�Ƃ��ċ����ׂ��炴�邱�ƂŁA���邩�Y�ݔ��������Ɂg��`�e��ł��h�Ɨ܂�ۂ�ł����Ւv�����B ���S�m��ʁ@�҂͉��Ƃ��@�]��Ή]���A�g�����ɂ��܂��A�������ɂ��܂��B ���̋��������A����Ȃ��炱��͎��̕��������t�Ȏ�N�E�@�����������̂Ɠ����Ŏ�E���Ɖ]���Ɛb�Ƃ��Ă͑�߂�N�������̂ŁA���˂Ă�莖�����A�̍ۂɂ͐b����S�����ē������A�ؕ�����o������߂Ă����Ƃ̂��ƁB �Ƃ��낪�A���t���n�ߏd�b��� �w�a�������܂Ŏ��������Ȃ�َҋ����������d��B�Ȃ�ǁA���̐����Ȃ��S���ȂĈ��������ׁ̈A�V�������ׂ̈ɉ����ɂ��ނ��ʐV�����V���l���߂����̂��^�̑�`�Ɖ]�����̂ł͂���܂��ʂ��B�ǂ������S�����������ꎖ�̐��ۂ͓V�ɔC���āA�v���̂܂܂�邾����蔲���g�������炸��s������h���������ɕ��������Ēn���̉ʂ܂ł����v���܂��傤�B�x�Ɨ܂Ȃ���ɂ�����������Ďv�����������悶��B �Y������ʓV���O�N(�����)�H�A�O�g�̕ی���Ŕg����ꑰ�ɋ\����A�㎀�Ɉꐶ���w���ł��Ȃ��Ɂg��l�̓V���z�������������ɂ͑卑�͖����ł��ꍑ�̎�Ȃ�K���h�Ɩ����Ƃ͍����Y��Ă͋���ʁB �ǂ��ł��낤�Ƒ��q�B�ׂ̈ɂ��g�Ɛ��������ɂ��Ă͖Ⴆ�܂����B�v�Ɛ^���f�I���ꂽ�̂ɓ����g�l���ӋC�Ɋ����h�Ɖ�����������ł���B ����ƌ��G���͗܂����点�A���������グ������̖ї��A������a�ւ̎��̂悤�ȏ���������ꂽ�B �u�����Ɣ�����ȂČ��シ�B���x�G�g������ɂė��\����āA���R������o���A�ї��Ƌ��Ɍ�ΐw�̗R�A���ɒ���̎���Ɍ�B�R��Ό��G�A�ߔN�̐M���̐U���ɓ{��A������A�{�\���ɉ��ĐM�����q���n���A�f����B����B�c�c�����ɏ��R�{�ӂ��グ����̏��A��c����ɉ߂�����낵�����I�ɗa����ׂ����̂Ȃ�c�c�v �����Đ��X�̐��헼��������A�L���Ȗ��q���C�ɂ��������ĖႢ�A�t�����킵�đO�r���j���K���������ċ������B �܂����y�U����̏\���ɂ́A��������Ώ��R�̓��|�������A�`��������� �u����悭�㗌�̍ۂɂ́A�g�����R�ɔC���āA����ɒ����ȑ������{���J�݂��ēV���ו���������v�Ƃ̕ԏ����͂����R�ɂďG�g�Ƃ͋����̍���������Ƃ��A�����ċ����̂Ɂc�B�R��ɓV�^�������A��\�]�N�̒m�F�ł������א�ꑰ��g���喼�̒���A���R�A�r�c����Őh�_�����ɂ����F�Ɍ����Ă��A�ʂ͑�a�l�\���̑��ɔC����ꂽ�M�a�ɂ܂Ŕw����悤�Ƃ́c�\�H���}����g����ɂ͎v�������ʂ��Ƃł������B �� �ƌ���f���悤�ɉk�炵���̂ŁA�O�\���̏��c�͑����Ȃ���āA�ꌾ�̕Ԃ����t���Ȃ������Ɖ]���B�@ |
|
|
��(8) ��˗ǍO�A�F��ɗ�����
�R���ǍO�͂���ȏ�͉����]�킸 �u�c�c�Ƃ͉]���V�͎��Ƃ��Ĕ��Ȍv�炢���������̂͊����̗��j�̎������ʂ�ɂĖ}�v�̐g�̋y�т����ʏ�����v�ƙꂫ�A�n�����Ɠ��Ђ����Ɗ��ɔ��͗����ĎR���p�ƂȂ��ċ����B �u����͌��͂ɓ����A�ςɉ����ď��R�鉺�͋����Ă����̐ӂ�ʂ̂��K�킵�ł���A���x�̂��Ƃ����ׂĂ͌��G�a�̓ƒf�Ƃ��ď�����悤�B����͕S�����m�̏�ʼn߂������A���S���œ�������g�������q�h�Ɖ��߂�ꂽ���G���ɏK���g�����g���[�đP���h�ƍ����B�Ⴆ���l�����Ɣl�낤�Ɛَ҂̌��ɑ��鑸�h�ƐM�`�͂����������ς�ʁB���͂��x�Ɛ��ɏo��]�݂͂Ȃ��A���U���̕������ƂɌ��߁A�邩�ɌF��ɗ��������ł������B����ǁA�����g�����p�����������Ƃő��q�B�ⓛ��Ƃɍ߂��y�ڂ��悤�Ȃ炱�̏�ŕ����d�낤�B�悵�ȂɌv���ĉ�����B�v�ƌ����]���������B ��������Ĉꓯ�� �u���ꂼ�g�m�͌Ȃ�m��҂ׂ̈Ɏ����h�̌��ʂ肶��B���ʊ���(�G�g)��������遂��ĉ��Ɖ]�����Ƃ����Ŏ��Ȃ��Ă͑�a���m�̒j��������v�ƍ���̑�����c�̖��� �u���q�ɎQ�����ӂ͗ǍO����g�ɕ����A����J���n���đm�ƂȂ荂��A�F��ɓ���B��ˉƂ͒��j�E�o�O������ƂȂ�A�㌩���͍��܂Œʂ���\�Y���߁A���c�͍߂��ނ�ɋy�ʂ悤�������i��s���v�Ɗm�āA�����邱�Ƃɂ����炵���B �V���\�N(��ܔ���)�Z���\�l���̖锼�A�ǍO�͎��j�E���G�Ƌ͂��ȘY�}�Ƌ���ꠓ����邻���ɔ����o�Ďp���������B�@ |
|
|
��(9) �킢�̌�
���\�ܓ����ɓ��䏇�c���x��y���Ȃ�����̏G�g�{�w�Ɏp��������B�����ʂō��ɂ����̗������C�ȏG�g�ɁA���c�͓������ɏo�������̂͑�R�ł��鎖��ى������B���̏�ŗL���ȁu�T�䓛�v�̈�˒��q�������o���A�ǍO�̖��q�ɎQ��������𖾂炩�ɂ��Ęl�т��B�G�g�� �u������Ȏ����I�v�Ƒ劅���������ŁA��͉����Nj������@�������Ɖ]���B�g��������肷�鎖�Ɛl���炵�̖��l�h�Ɖ]��ꂽ�G�g�����ɁA���c��ǍO��ӂߗ��Ă鎖�����A���̈�˒��q�𗘋x(*1)�Ɍ����悤�ƍl�����̂��낤�B�����ė��x�𒃓�(*2)�Ƃ��Ď��̓V���l������R�����A�₪�Č����N����ēc��Ƃ̓V�����ڂ̑���ɑ�a�O�𖡕��ɂ���̂������B�c�ƁA�f�����Z�Ղ��͂������ɈႢ�Ȃ��B �����Č���A�g�c����(*3)�����G����喇�̋�q�������������炩�ƂȂ��Ă� �u�r����������ʎ��v�Ǝ��������̂́A���̋���ԋp�����A�s��ɂ��Ă���̂��������R����ł��낤�B �Ñ�V�c�̐e���̐��͂Ƃ������A���v�̗��⌚���̒����Ȃǂ̒ɂ��o������V�c�͎��猠�͂����炸�A���̌��͎҂̈ӂ��}������u�����ƓV�c���쎝�v�����߂�̂����̓`������ł������B �]���āu�s����Α��v�̌��ʂ���G�������ɂ܂݂ꂽ�̂����R�Ɖ]���悤�B �� (*1) �痘�x(����̂肫�イ)�B1522�`1591�B���l�B���������̂��Ȃ��Ƃ���܂Ŗ��ʂ��Ȃ��āA�ْ��������o���Ƃ����u��ђ�(�����̒�)�v�̊����҂Ƃ��Ēm����B���\�̂Ƃ��A���x�́A�ˑR�G�g�ɋ��s���ڊy���~���Őؕ��𖽂�����B����A���x�̎�͈��ߋ��Ş���B���߂̗��R�͒肩�ł͂Ȃ��B�u�l�����\�@�͈͊��@�ᔇ�����@�c�ŋ��E�@��(�Ђ�����)��䓾��̈ꑾ���@���������V�ɝe(�Ȃ�����)�v(�����̋�)�B (*2) ���ǂ��B�u�����v�u�����v�Ƃ������B�M�l�Ɏd���Ē����������ǂ������̎t���B���y���R����ɐ�@��(���x)�E�Óc�@�y�炪�M���E�G�g�̒����߁A�]�ˎ���ɂ͊e�˂ɂ��������Ƃ����E�����ł����B (*3) �悵�� ���˂݁B1535�`1610�B���s�̋g�c�_�А_��̐_���ƁB�w�������L�x�̒��ҁB�@ �@ |
|
| �����j���� [�L�b�G�g] | |
| ��1�@�ǍO�F�엎���@ | |
|
��(1) ��˗ǍO�A���q���G�̖������F��
�V���\�N(��ܔ���)�Z���\�l���̖�[���A�ǍO�͎q�̎��G�ƘY�}�����Ƌ���ꠓ���𗎂���B�ޗǂ̐���(*1)�ɂ��鋻�����̖����ɐ���ŋ@���_���A���߂ČF��ɓ���O�Ɍ��G�ꑰ�̗���Ԃ߂悤�ƁA�R���p�ŕ����̑�펛�O��@(*2)�ɓ������悤���B ���G�I���̒n�͎��̋߂��ŁA�����ɂ܂���Ē|���̒��Ɂg�������q�h�̔�ƐS����̓njo���������Ƌߍ]�̍�{�Ɍ����B���G�v�l�►�B�����Q�����ΔȂ̏ĐՂɗ������͉̂Ă̐���Ɍ��������̎n�߂ł������Ɖ]���B �ǍO���n�߂č�{���K�˂��̂́A�\�N�O�̂��ƂŐV���̓V��̈Зe�� �u�킵�����Ƃ����̎�ɂȂ낤�v�Ɠl�u��R�₵���̂��A������̂悤�ɎÂ�ĂȂ�Ȃ��B���ɘI���ׂ����G�Ƌ��Ɏb���Ȃނ����A�܂������͑������b�R�̐��ɒ��݂����A�Ό����Âт������ɉf����B�����t���Ă����������ǂ��������āA��������̓��̏�i�̂悤�Ɍ�����B �Ⴍ�n�����������A�Ȃ��������ĕv�̗F�����ĂȂ����ɂ����Ɖ]����߂Ȍ��G�v�l�B �t���C�X����u�ތ��Ń��[���b�p�̉���̂悤�ɗD��ȋ��{���ӂ�镐���v�Ə̂��ꂽ���G�B ���̂ɓy���̒|���Ŕ߂������𐋂��˂Ȃ�ʉ^����V����^����ꂽ�̂��낤�B �l�Ԃ̉��l�͎����}�����ۂ̑ԓx�ɂ���Ƃ���Η]��ɂ��ߎS�ł���B �u�D�c�����A�H�Ă����˂��V���݁c�v�Ɖ̂��邪�A���G�ƂČ����ɐM���̉��Ŗ݂����グ�A�G�g�ɗ��ʕ������d�˂Ă���B �͂��\���ɉ߂��ʓV���l�Ƃ͉]���A�ނ̍s��������Ό����Ĕe����`�ł͂Ȃ���������Ƃ����q�I�����ł������ׂɁA�Ԃ��Ă��̔ߌ����������Ƃ����v����B ���߂Ă��̈Ԃ߂͌��t�̊���ł��낤�B�����悤�Ɏ�E�`�P���E�������i�ɔ�ׂ�A���ɉ_�D�̍��Łu���̈���v��m�镐�l�Ɖ]���悤�B �����l���Ė������F���Ă���Ɨ���̐X�Ŕ��������̉��������A�t�g ���قƁT�����@�ѐX�́@�̊Ԃ��ȁB �Ƃ̌��G�̈�r���v���o�������B�M����G�g�Ƃ͒i�Ⴂ�̕����������A�������^�Ɍb�܂��A���{�̗��j�͑傫�ȓ]���������������m��Ȃ��Ɗ�����B �R���V�͔���ɂ��A�G�g�Ɖ]���u�l���炵�̖��l�v�Ɖ]����p�Y�𐢂ɑ������B�ǍO�͟��X(���݂���)�ƓV�̔��������Ȃ��� �u���͂�s�ɖ����͂Ȃ��v�Ɖ_�R�����̌F����߂������B �� (*1) �ޗǎs���咬�B�������̖k���A���厛�̐��BJR�ޗljw�����2km�B (*2) ���s�s�������퓌��H��22�B���G�I���̒n(���s�s�����揬�I��)�܂ŁA��2km�B��펛�͐�����t�����16�N(874)�ɏ���R��ɏ����F�������B�y��A�@�ӗւ̗��ω��������u�B�^���@���여�̒��S���@�B�O��@�͉i�v3�N(1115)�n���B�@ |
|
|
��(2) �ǍO�A�|���̗��ɗ�����
�ǍO�̗��H�̏͗ǂ�����Ȃ��B���炭�g�쉺�s�̋����������ŁA������(*1)�̓V��A�������h�̎x�z���ɑ����̊�i���s���A���ʂ̋�����ɓ���铙�̔z�����蔲����Ȃ��������낤�B���l���̑���R��̓���ɓo��ƎR����Ɍ����āu���삯���v��쉺���A�ʒu�R(*2)�Ɍ������Ǝv����B �×�����C�����ɂ́A���s�҂��J�c�ɋ��O�䎛�~�鎛(*3)�̉~����́u�V�䖧���h�v�ƁA��펛�O��@�̐���(*4)��c�Ƌ��u���������h�v������B ����͉��鎛��n�������O���V�c�̎q���ŋ�C�̒�E����̒�q�ƂȂ�A�V�{�_�q�ŏ\��N�ԏC�s�����B�₪�ĕ����̑�펛��n���������m�ŁA������t����포��@�h(�^���@���여)�̑c�Ƌ����B �ނ�͖��N�g������R��������Ƃ��ďC�s���A�g�삩��F����߂����̂���Łu���R�h�v�ƌĂꂽ�B ����ɑ��ēV��h�̎R���B�͌�Ɍ��Z�E���_(*5)���V�c�A��c�̐��Ȃ�g�����u����@(*6)�v��n�����A�F�삩��g��Ɍ����̂����ł���Ƃ��āu�{�R�h�v�ƌĂꂽ�B �ǍO�́A�C�s�̘`���_�Ђ̐_�{����������J�c�Ƌ��Ƃ������j�I�ȗR���ƁA���G�̍Ō�̒n����펛�ɋ߂��Ƃ���������A���R�h�ɉ�������炵���B �ނ�͋ʒu�R�܂ł̎��\�܍s��������ďC�Ƃɗ�ށB�ǍO�̈�s�͓r���A�u�O�S�v���琹���l�����s�҂����ꂵ�߂�ꂽ��ւ�ގ����ꂽ�Ɖ]����u�r���v�ɉ��肽�B�����āu�Y���v����s�������z�����u�|���v�̗��ŁA�쒩�̒��b�ŗL���Ȓ|�����Y��˖앺�q�̎q���ƌ����[�߂��炵���B �Ɖ]���̂́A����_�Ђ̊y���E�������ϐ��ꑰ�Ƃ������[�������������g�c�̒|����o�͂��̗��̏o�g�Ƃ��]���邩��ł���B �b���؍݂��d�˂邤���A�u�쒩���������̓V�q�v�Ƃ̐M������쒩�ؖڂ̋��m���ւƂ���d���̌Õ��m�炵�������������āA�傢�Ɋ��������B�������A�]��ɂ�������m��ʐ������Ɋ�Ԃ݂������B �� (*1) �����R���{���������B (*2) �ޗnj��g��S�\�Ð쑺�B (*3) ���ꌧ��Îs���鎛��246�B��ʂɎO�䎛�ƌĂ�邪�A�����ɂ́u�V�䎛��@�@���{�R�@�~�鎛�v�B�p�\�̗���A667�N�ɑ�F�^����(�s�ꂽ��F�c�q�̎q)���A���̗�����ߑn���B�V���V�c����u����v�Ƃ������z����������̂ʼn~�鎛�ƌĂ��B (*4) �펁�Ɗϐ��ꑰ���Q�ƁB (*5) ������B1032�`1116�B�V��@�̑m�B���鎛(�O�䎛)�̏扄�Ɏt���B���R�E����R�ŎR�x�C�s�B��������쌱���������B���́A�x�͗��V�c�̌쎝�m�Ƃ��Ă�����B����4�N(1090)���͏�c�̌F��Q�w�̐�B���Ƃ߂čŏ��̌F�쌟�Z�ɁB�����ɐ���@�������B����2�N(1105)�V�����ɔC�����邪�A����̔��ɂ�藂�����C�B85�Ŗv�B (*6) ���傤������B���s�s�����搹��@�����B�{�R�C���@���{�R�̎��@�B���@�h�ݗ��ȑO�͓V�䎛��@�ɑ������B�J��͑��_�B�{���͕s�������B�ߐ��ȍ~�A�C�����͍]�˖��{�̐���������āu�{�R�h�v�u���R�h�v��2�ɕ�����A����@�͖{�R�h�̒��S���@�B��X�A�@�e��(�c���j�q�ŁA�o�ƌ�ɐe���鉺������)�����������Վ��@�Ƃ��č����i�����ւ����B�]�ˎ������ɂ�2�x�ɂ킽�艼�c���ƂȂ����B�@ |
|
|
��(3) �ǍO�A�č�����
������A�ǍO�͉��F��̗��E�ʒu�R�ƁA�V�{�̖x�����ɂ��߂��Ñ�F��̍��{�ł������{�{���ꌩ�������Ǝv���������B �|��������g�F��͗��l�̋Ɋy�h�Ƃ̌��ʂ�̈��������A�ނ�̈ē��Ŗk�R��������ē����̗�����ʒu�R���m�@�ɎQ�w����B�ʓ��E��ؖڂ̋��m�B�ƌ�F��[�߁A��쒩�̔ߎj���w�B�C�s�̌����𑗂邤���ɁA�u���v�̗��̋��m�Ō˖�ꑰ�̗�������ސl�X�̐��b���A�����ŐV���������̊�Ղ�z������ɂȂ����炵���B �Ƃ͉]���A�O�\���̑喼���������v�ԐM��(*1)�����A���N�A�\�Ð�ŎR���ɎE���ꂽ�Ƃ��A�쎀�����Ɖ]���Ă��闎�l�邵�����ɁA�C�z�����ς������낤�B �����ŗǍO�́A�ʒu�R�̕ʓ�����R���̔�`���������ĖႤ�B�R��Ɏ�������A���A�R�܂��R�ƌk�J�ɌQ������F�ƘT�≎�A����玭�A�R����⋛�̋��ނ���āA���̑̓��������������o���āA���l�̕a�������Ƃŋ������v�낤�Ǝv���������B �Ɖ]���̂��A��ˉƂɂ͐̂��琻��̐[���m�����`����Ă������炾�B�ǍO�����̊o��ō���ɑς��Ă���̂����Č˖�̎�͊�B�ނ͂��̐�c�����Ƃ̗��l�ŁA���ɍ��q�厁�i�ƌĂԎ��叫�̉ƕ��������B���ꂾ���ɁA�����F����c�Ƃ����a��ˎ��̒����̌������̒n�ɐ������āA���ɔɉh���v�肽���ƍl�����炵���B ���N���肪�߂����N�̕�̂��ƁB�ǍO�����c�̖��ɂȂ�Ȃ�S�����Ɛg�ł���̂��K���A�˖�͖p�˂Ȍ����Ő�o�����B����̎o�́A�N�͎l�\�ɋ߂����A��������v�ƕʂ�Č�Ƃ�ʂ��Ă����B���l�ŕ����������̐l�� �u����Ƃ�����ĖႦ�܂����v�ƌ����̂ł���B�ǍO�� �u�������̔N�ōȂȂǁv�Ǝ��ނ����B�������A�Ɖ]���喼�ł������g���ւ炸�A�l��[�����������̕��l�ł���l����m�����o���g���܂������ɍ��ꍞ�炵���A�b�̓g���g�����q�Ői�B �V���\��N(��ܔ��O)�ǍO�����\���}�����t�A�R�X�̐�������ė��ɂ͔��~���]�юn�߂����A�߂ł������炪�Â����B �� (*1) �M�̕҂��Q�ƁB�@ |
|
|
��(4) �G�g�͎ēc���Ƃ�|���đ����z��
�s�ł͖��q��œ|�����G�g���A���F��c�Œ��V�E�ēc���ƂƐM�F(*1)�̈ӌ����������āA�M��(*2)�̒��j�E�O�@�t�𐳒��Ƃ����̌㌩���ƂȂ����B�V���l���߂������Y�̑����͍���������ʏ�Ɛ����Ă����B �V���\��N(��ܔ��O)�l���A�G�g�͑�_�̐M�F���U�߁A�}�]�k�サ���˃��x�ŏ��Ƃ�ב�������Ɩk�̏����͂�Ŏ����������B�����ĐM�Y(*3)�ɐM�F���E������B �u�ނ�͓V�c�̍c�ʂ�D���Ƃ����A�̂ɒ�ƓV���ׂ̈��n�����v�Ə̂��A�Z���ɂ͑����z���Ď��̓V���l�����Ƃ����B �V���\��N(��ܔ��O)�\�ꌎ�A�G�g�͔��N�Ԃ��D�c�����ꂵ�ߑ������ΎR�{�莛��тɋ���ȑ����z���n�߁A�H����s�͐�쒷��(*4)�Ƒ��c�����ŁA����O�`�l���l�̐l�v���Q����W�����B �����ė��N�����ɂ͈����ǂɂ��y�ԐΑD�ɂ��ɂ���Ċ��������{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ̐Ί_�̒����͏\��̂ɂ��B�����B���̏�ɍ����͈��y�Ɠ����\���������A�\�{������L��ȓV��t���o������B �ܑw���K�̍ŏ㕔�ɂ͉��L���߂��炳��A��ɂ͒߁A���ɂ͌Ղ̋������ƍ����̏d���ȑ����Ŋ��͐��A�����ɂ͋��ŋ˖䂪�P���Ă���B ����������l�X�́u����v�Ƃ��u�я�v�Ƃ��Ă�Ŏ^���A���̕����B�����ʊ��҂Ƌw�������G�g�̒�m��ʌo�ϗ͂ɖڂ��ނ����B ���܂ł͕��͂̕\����������͍���o�ϗ͂������̍����ł��邱�Ƃ������A���̓V���l���N���Ɖ]�������������B �����Ďq���̉����A�����̕�����Γc�A���c�̕��������Ăɉ����ƍ����h��̖����z���ēV���ɖL�b����̓�����������B �� (*1) �M���̎O�j�B�Ώ�P�ۏ���Q�ƁB (*2) �M���̒��j�B�{�\���̕ς̍ہA�����Ő펀�B (*3) �M���̎��j�B�k���M�Y�B (*4) �����̂Ȃ��܂��B1547�`1611�B�����͖L�b�G�g�̐����˂�(����@)�̋`��ŁA�L�b�����ł͌ܕ�s��1�l�B���ʁF�]�܈ʉ��A�e�����J�B ���D�c�M���̋|�O�����Ă����f���̐�쒷���ɒj�q���Ȃ��������߁A�����̖��̂��̖��{�q�Ƃ��Đ��ƂɌ}����ꂱ��𑊑��B�����̗{���ƂȂ��Ă����˂�(�̂��̖k�����A����@)���؉����g�Y(��̖L�b�G�g)�ɉł������Ƃ���A�����͏G�g�ɂ����Ƃ��߂����ʂƂȂ�A�M���̖��ŏG�g�̗^�͂ƂȂ�B ��1573�N(�V�����N)�̐�䒷���������͂��߂ɁA1583�N(�V��11�N)���˃P�x�̐킢�A�M���̎���ɏG�g�����ꎖ�Ƃ��p������ƒ��N�o���Ȃǂŕ����������A�܂����̑�z�����s����r���đ��}���n�⋞�s���i��Ƃ��Ă̔C���𑬂₩�ɐ��s����ȂǁA�l�X�Ȍ��������āA1593�N(���\2�N)�ɂ͍b�㍑22����^����ꂽ�B ���ܑ�V�̓���ƍN�Ƃ͐e�����W�ɂ���A�G�g����͓����ܕ�s�ł���Ȃ���Γc�O���ƌ����̒��ɂ������Ƃ����(����ɂ͋ߔN�ɂȂ��ċ^�������Ă���)�B1599�N(�c��4�N)�A�O�c������ƂƂ��ɉƍN����ÎE�̌��^���������āA�b�㍑�ɋސT�𖽂���ꂽ�B ��1600�N(�c��5�N)�H�̊փP���̐킢�ł͉ƍN�̎q�̓���G���ɑ����A���͒��j�E�K���ɉƓ������ĉB�������B�ƍN�͍]�˂ɕ��Ɛ����𐬗������A1606�N(�c��11�N)�ɂ́A�����͍K���̏��̂Ƃ͕ʂɁA����̉B�����Ƃ��ď헤�^�ǂ�5�����x�����ꂽ�B1611�N(�c��16�N)�A�^�ǐw���ɂĎ����B���N65�B�揊�F��錧����s����̓V�ڎR�`�����B�܂��A�a�̎R�����쒬�̍���R���n�@�B ���Ȃ��^��5���͎O�j�E���d���p���A���̎q�E�������ԕ�ֈڂ��āA���̉ƌn���猳�\�ԕ䎖���ŗL���Ȑ����������邪�o�Ă���B�@ |
|
|
��(5) �G�g�ΉƍN / ���q���v��̐킢 ��������āA�������V���l�ɂȂ��ƍl���Ă����M�Y�́u�b���Ⴄ�v�ƕ��𗧂Ă��B�ɐ��A�ɉ�������Ƃ��A����ƍN�⍲�X�����ɍ������Ė����ɉ����A�X�ɋI�B�̍�����ɂ��Ăт����ĉ��Ƃ����܂�Ƃ����B �V���\��N(��ܔ��l)�O���A�悸�M�Y�������������B�����ĉƍN�����F�ɓ����ċ�������W�J����Ƌ��ɁA�I�B���ɂ́u�a��A�͓��ɐi�����đ�����������ĖႢ�����v�Ɨv�������̂ŁA�����O���悸�������B �����m�����G�g�́A�}���ݘa�c��̎����ł߂�ƁA���˂Ēm�F�̎G�ꑷ�s���S�×������ĉ��F��̖x�����P�獋���𖡕��ɂ���ׂ��ވꗬ�̊O�𐭍��i�߂��B���̂��ߖk�I�͉ƍN���ɎQ�������A��I�͓����Ȃ��B���P�͏�����ďG�g�ɉ�����I�ꂷ�ׂ��A�̂͋q���Ƃ��ė{���Ă����G���̉Ɛb�E�������Ղ̏��֎q�̎����𑗂����B�e����[�߁A��I����̋@���҂����̂ł���B ��͗L���ȏ��q���v��̑ؐw�ƂȂ�B�����}�����r�c������(*1)�̗v���ŎႢ�G��(*2)�叫�Ƃ���O�͋}�P��킪���s���Ď��v��ƂȂ�B�G�g���̘e�������������U�߁A���O�Y���q(*3)�͈ɐ��ɖz��B �� (*1) �r�c�M�P�B1536�`1584�B�P���Ƃ��B�������ď����Ə̂����B�ꂪ�M���̓���B�N�����M���̑��߂ƂȂ�B���E�P�����D�c�M�G�Ɏd�����B�M�G����A�M���ɏ]���A�e�n�ɓ]��B�M���̒�M�s�̖d���̂Ƃ��A�M�s�B�����ԂŌR������A���R���ƂȂ�B�r�ؑ��d���M���ɔ����ƁA������B�ԌG����U�߁A�M����葺�d�̋��̐ےÂ�^�����A�ۏB���ɋ�����ڂ��B�{�\���̕ςŐM�������G�ɓ������ƁA�G�g�ƌ��сA�R��̍���ŕ���B���F��c�ł́A�G�g�E���ƁE�O�H���G�ƂƂ��ɁA�D�c�Ƃ̎l�h�V�̈�l�ɁB�G�g�̖��F�Ƃ����˃��Ԃ̍���ɂ��Q���B���̌��ŐD�c�M�F�̋��̂āA���Z��_���ɁB���q�E���v��̐킢�ŁA�����ꂽ�B49�B��A���j�̋P���͑�喼�ƂȂ�Ɩ����������B (*2) �L�b�G��(�Ƃ�Ƃ݂Ђł�)�B1568�`1595�B�喼�E�֔��B�L�b�G�g�̎o�E���G�̎q�B�͂��ߎO�D�N���ɗ{�q����B��ɏG�g�̒��j�E�ߏ��������������߁A�G�g�̗{�q�B�֔��E���p���B�ڊy��ɋ��Z���A�G�g�Ƃ̊Ԃɓ������Ђ��B���̌�A���N�����ɐ�O����G�g�̑���ɓ������i��B�G�g�Ɏ��j�E�L�b�G�������܂��ƁA�G�g����a�܂�A��s���J��Ԃ��B���̂��ߍ���R�ɒǕ�����o�ƁB��A�ؕ��𖽂�����B���N28�B��͏G�g�ɂ���ĎO���͌��ɔ����ꂽ�B (*3) ����@�B�M�̕҂��Q�ƁB�@ |
|
|
��(6) ���䏇�c�A����
�G�g���ɎQ���ď��q�ɂ������䏇�c�͂��˂Ă̈ݕa�����������B�莟�ɔC���ċA���×{�ɓw�߂����A�����ɂ͍ċN�̖]�݂���Ԃ܂���ԂƂȂ�B �������o�������c�́A���̗�ɂȂ炢�F��ɐ���ł����ǍO�ɋ}�g�𑖂点���B�������ǍO���邩�ɌS�R��K���B�O�w�̓V������V��ɋ����Ȃ���A�v���Ԃ�ɉ���c���������\�]�˂��N���Ȃ̂ɂ������萊�����̂ɐS��ɂ߂Ȃ���A��܂��������B �����\����ɂȂ�ƁA���c�͖����ɕ�̑���m�ǂ╟�Z�A�������A��˂�ꑰ�ƁA���q�A���m�V�A���̉ƘV�B���W�߂��B�k�q�E�莟�ւ̋��͂𗊂݁A�₪�đ��������Ƃ����B ���ɒj����̎O�\���ŁA�J�c�E��������l�\����𐔂������䎁�̐����͐₦�A���̑�����ɂ��܂ʐl�͂Ȃ������Ɖ]���B ���c�́A�M�S�Ɍ����A�_�w�A���A�̓��ɂ��ʂ��Ă����B�܂��A�̖��ɑ��Ă͏�Ɏ��߂��ȂĐڂ����̂ŁA�[�����h�������Ă����B �܂��������D�݁u���t�v�ƌĂ�錨�Ղ��̒���(*1)�͒m��ʐl���Ȃ�����̖��i�Ƃ��đA�]���ꂽ�B�\�y�ɂ��B�l�Ɖ]���A���́w�S���x�͂ƂĂ��喼�Y�Ƃ͎v���ʌ������ł������Ǝ^�����Ă���B ����ȑ��V���Â��ꂽ�̂͏\���\�Z���ŁA��Ԃ̉�擪�ɉԁA���āA�n�A�品�A�`�A���V�Ȃǂ̑呒��\��Ԃ܂Œ��ւ̗���ׂ��B�ǍO�͌ܔԖڂɕ��сA�V���R����ɍۂ��čł��s�͂��Ă��ꂽ�m�F�̓����߂ƌ���A�˂Ă���B��������Ă������̔ނ̕]�����@������B �����m�͉~暎�(*3)�̖��m�E���͂ŁA�����̕z�{�������тɒB���Ă���̂����Ă����̐��傳�������a���̖��ɂӂ��킵�����V�ł������悤���B �� (*1) �������Ă������߂̗e��B���ɒ��̓��ŁA�Z��(��������)�p�̖���������e��B��ɓ���ŁA�`������(������)�E�֎q(�Ȃ�)�E����(�Ԃ���)�Ȃǎ�X�̌`������B (*2) �w�S���x�̂��炷���c����j���E�������N��A��ċ��s�̍���ɁB����͑�O���̍Œ��B���̖�O�Œj���O���������Ă���ƁA��������Đl�X�̔O���̔��q�����肾�ƌ����A���特�������(�ԔV�i)�B���͂ЂƂ�q�����������ƂŐS������A�ÉG�X�q�����Ԃ������ɂ��ċ��������Ă���(���V�i)�B�_�X�ɕ�����Ƃ����ċȕ����B���͎q�̍s����K�˂ď������������g�̏�b(�N�Z)�B�Q�O�̒��ɉ䂪�q��T�������A�j�ɘA�ꂽ�q���䂪�q�ƒm��A���C�ɖ߂�B (*3) ��暎��B�^�����@�B�ޗnj�����s�㒬4713�B�\���ł͔q�ςł��Ȃ��B0743-79-1170�B ��890�N���A��a���䏯(����a�S�R�s����)�ɑn���B��A�퍑�����̓��䏇�������䎁�̊O�قƂ����ޗǎs�я��H��(���ޗǃr�u��)�ɉc�ʉ@�B�V��19�N(1550)�������v������A���q�̏��c�����ɉ��߁A�������̕�Ƃ��Ď��Ђ��ڂ��B���a60�N(1985)������ӂ̎s�X�n���w���ɂ����Q�����k�����̔�Q���o�āA�������ی�p���̂��ߐ���s�̌��ݒn�ɑJ���B�������ꂽ�d���́u�{���v�́A���������̓��F���悭�����������B ���u�{���v�̒����E���ɉԛ���ō���2.6���A�d���́u�Α��ܗ֓��v�B�n�֕��Ɂu�����h�w�V�A�V��19�N(1550)�M���Z�������v�̍���������B���̌ܗ֓����u�~暎��v�����n�̓���ł��������䏇��(���䏇�c�̕��e)�̋��{���B ���u�{���v�̎ߑO���A���a60�N(1985)�J���̎��ɐV�z���ꂽ�u�����@(�q�a�A�����V)�v�B���̈�Ԃɂ́A�V��13�N(1585)����莟(���c�̗{�q)���ɉ�̏��ɂȂ��ďW�߂��Èɉ�Ɖ]���ɉ�Ă̐^����`���閼���������݂����Ă���B ���u�q�a�v�̑O�ʂ��u�Β�(��R�̒�)�v�B��̖��́A���߉ނ��܂����܂ꂽ��x�̕��Ճ����r�j�[�ւ̓�������A��Â̔�����ēV����ނ���q�}�����Ɉ���Ŗ��t����ꂽ�B�͑�p�̉��n�A�Ԙ@�R����Z���̋��͂ɂ���ĉ^�яo���ꂽ�u��材v�ŁA�����Ԑ[������ŐN�I���ꂽ��B�����āA�����u�_�썻�v�̏�̐́A��x�u��h�R�v��蓞���B�@ |
|
| ��2�@�G�g�̋I�B���� �@ | |
|
��(1) ���䏇�c�̖v��
�V���\��N(��ܔ��l)�����B��a�l�\���̑�炾�������c�̐Ֆڂ́u�莟��N�ɏA���g���s�����v�Ɖ]���b���o�Ė��ƂȂ����B���A�M���Ɉ�����ė{�q�ƂȂ������̒莟�����ɁA�G�g�ْ̍�ŏ��̂͑�a�\�Z���Ɖ͓��Όv�\�����ɔ����ŔF�߂��B �R�����̏��u���ƒ��ɋy�ڂ��������������łȂ������̂́A�������ɂ��ꂽ�T�����[�}���ȏ�ł������낤�B �O�l�喼��͓���Ƃ��痣��ĉH�ďG��(*1)�Ɏd�����҂������������A���╈��Ɛb�Ƃ��Ȃ�������䂩���A�\����������Ă��a�X���m������Ȃ������悤���B ��ˎ��ɏA���Ă��o�O�A���G�A���O�O�l�ŕ����ē��Β��x���F�߂��Ă��邪�A��a�𗣂ꂽ�ǍO�ɏA���Ă͂ƂĂ����̂�F�߂��Ƃ���Ȃ������B�ǍO�ƂĂ���ȋC���Ȃ����V���I����ƍĂьF��ɋA���čs�����B�ǍO���Q�������u�R�[�ɋ}�����̂́A���˂Ēm�F�������א�H�ĂɌĂ�Ē���ɏo���ہA�G���Ƃ����ȂƂȂ� �u�Z���ƍN�ɖ������đ����_���Ă���I�B���̑ԓx�ɓ{��A�₪�Ęa�r����ƋI�B�𐪔����Č�̊�����f���ӂł���v�ƕ������ꂽ��A �u�\�Ð�A�k�R�̋��y�B�ɓV���̑吨������A�a���̓����J���ĖႦ��Έɉ�̔@���S�Ђ͂������A���ɍK�r�ł��邪�v�Ɨv�����ꂽ����ł���B �V���\��N(��ܔ��l)�H�A�ǍO�͍Ăї��A���u�R�̉p�p��������F����̗��ɋA�����B�ʒu�A�{�{��~��˖�A�����A�|���̋��m�����ɏW���肢�A�����ɉ�����G�g�̓������ڍׂɐ���������ŁA �u�G�g�͕K���M�Y�A�ƍN�Ƃ̘a�r�𐬗������A���݂̋E���Ɏc���ꂽ�I�B������f�s���ēV���l����̒n�ʂ��m������ɈႢ�Ȃ��B�D�c�Ƃ̒��V�E�O�H���G����w�G�g�̊�ʂ����Í��ƕ��ł���A�ނׂ̈����͑�O������Ȃ��]���B��O�̋A���鏈�͓V���̋A���鏈�ł���A�]���V�̐S�ɏ]���x�ƌ���Ă���B�M�a����G�g�̐g�����˂�����g���ʊ��ҁh�Ȃǂ̈����ɂ܂�킸�A�퍑�����̐���ו��̐��ƂȂ���Ƃ̓V�̐S�ɑf���ɏ]���ׂ��Ƒ�����v���x�X�Ɛ������炵���B �R�����u�R�[�̐l�X�͂Ƃ������k�R(*2)�̌����̋ؖڂ��ւ�A���́A�ɉ�}�̔ߌ���ڂł݂Ȃ���A�g���Ȃ����̂�������(*3)�h�̌��ʂ� �u�y�S�����ɋ����Ă͐�c�ɑ��ς܂ʁB��˓a�̍D�ӂɂ͊��ӂ��邪�A���������́v�Ɗ�Ƃ��ď��m�����M�Y�A�ƍN�̌��Ԃɏ�����炵���B �� (*1) �ЂłȂ��B1540�`1591�B�ʏ́A��a��[���B�L�b�G�g�̒�B�G�g�̕Иr�Ƃ��āA�������ʂŊ���B�V������ɍv���B �����T���N(1570) �z�O�����ȍ~�A��v�ȗ��ɎQ���B�V��13�N(1585)�̋I�B������A�G�g����I�ɁE�a��Ȃǂ�64���̏��̂�^������B ���V��13�N(1585)6���A�l�������ł͑��叫�B���т��܂���āA��a�������B�S�R��ɓ���A116���̑�喼�ɁB ���V��19�N(1591)1��22���A�S�R��ŕa���B���N52�B (*2) �a�̎R���k�R���B�O�d���Ɠޗnj��Ɉ͂܂ꂽ�S���B��̔�ђn�̑��B�ǎ��̐��Ɍb�܂�ыƂʼnh����B���̂��ꂽ�؍ނ͐V�{�܂Ŕ��ʼn^�ꂽ�B����22�N�Ɏ��F�A�|���A����A������A������5�̑����������A�k�R���Ɖ��́B (*3) �u���Ȃ����̂�������v�������Ȃ����ł́A����ׂ��啂��В���Ƃ����Ӗ��ŁA�D�ꂽ�҂����Ȃ����ł́A�܂�Ȃ��҂����𗘂����Ƃ������Ƃ̚g���B�@ |
|
|
��(2) �G�g�A�I�B���������ӂ���
�V���\��N(��ܔ��l)���q���v����ɂ݂����Ă��邤���ɁA�G�g�́A�a��ɓˏo���������A�G��O�̑��i�U�̓����������B�����ŏG�g�͋}���ŐM�Y�Ƃ̒P�ƍu�a���v��B�\�ꌎ�ɂȂ�ƈɐ��ɐi�o���A�M�Y�Ɖ���čI�Ɍ������������B�����ĉƍN�Ƃ��u�a�����ԂƁA�ɐ��Ɋ��������A���H�ɋ�S�×��A�����đ�a�̓���̏�ɒ�E�G����z���Ė��S���������B �����ēV���\�O�N(��ܔ���)�O���n�߁A�G�g�͑��������������I�ɂ̒��������ӂ��A�\���̑�R�������B����ɍ������𑄉��ɋ�����ƁA�G���A�G��(*1)�ɂ͘a��̐�Ζx�Ԃ��A�א�A�����ɂ͐ϑP���ԍU���𖽂���B �G���̐�w�ƂȂ�������莟�� �u�����𐢂ɍ������͍������v�Ɠ`�Ƃ̖�������ۂ��������Ĉ�C�ɐ�Ζx���U�������B�G�g�͊��� �u�������̐�w�����ɗ��ށv�Ɛ��藧�Ă�B�莟�͗E��ŕ�����(*2)���z���č������U���̑̐����Ƃ����B�G�g�́A���̐��\���A�m�V��S�A�m���O�����ւ�ނ�� �u�̎��̂�^���邩��c��̎��̂�Ԕ[����v�Ɛ\�����ꂽ���A���{��̓S�C�W�c���ւ�m���B�͓����瑊��ɂ����A�O�����Βf�ĂƂ��Đ�[���J���K���ɐ�����B �R���G�g�̑�R�̑O�ɂ͖��ł͂Ȃ��A�͂������ʼn�ł��S�R�����サ���B���͎��������G�L�ɋA���A�O�����ɂ͑��������R�吭(*3)�̏邪������A�����ւ����G�g�R�͑��X�Ƒ��c(*4)�A�G��}�̉��ɔ������B �����c��m���ŎG��S�C���Ɍ}�����ꎀ�����o�����A�G�g�͍͗U�߂��������B���\���l�����ċI�m������~�߁A���ӂ̐��U�ߍ���W�J����B�����������Œm��ꂽ���O�{(*5)�𒆐S�Ƃ��鑾�c�}����̑ł��悤���Ȃ��A�l�����ɂ͑��c��\�l�����n���ďZ�����~�����B �G�g�͗I�X�Ƙa�̉Y�̕������܂łȂ���A���ɂ͍���R�Ɏg�҂�h������B �u�m�ł���Ȃ���L��Ȏ��̂������A�Q�l����b���āA�V���̈��ׂ����܂�����Ƃ͈ȂĂ̊O�v�Ƌ����A�����̎S�����������R���́A�ؐH(*6)����\���č~�������B �� (*1) �G�g�̉��B�ǍO�F�엎�����Q�ƁB (*2) �����ӂ��Ƃ����B�a�̎R����o�s�B�W��200m�B�I�ɍ��Ƙa�����ԍ����X���̓r���ɂ���B���݂͑��{���E�a�̎R����63�����o�����ʂ�B�ߕӂɍ�����������B (*3) ���R��(�͂�����܂�)�͕����������S�ɋN���������m�̖����B�Ⓦ����������o�������d�O�̎q�E�d�\�����R���̂������ƂɎn�܂�B ����k������ɂ́A���������ɏ]���A�������{�n�����̌��тɂ���āA�z���A�͓��A�I�ɂ̎��ƂȂ����B ����������A���R����(���{)�́A�א쎁�A�R�����Ɲh�R���鐨�͂��ێ������B�������A�����̎q�E���R�`�A�Ɨ{�q�E���R�������Ɠ��߂����Č����������A���m�̗��̌����̂ЂƂɁB���m�̗��̏I����A���R���͐��ނ̈�r�����ǂ�B ���V��4�N(1576)�A�Ō�̓���E���R�������������ĖŖS�B�������R�吭(�����̒�E�����̎q)���]�˖��{�̍��Ƃ̈�l�ƂȂ�B (*4) ���c�}�B�M�̕҂��Q�ƁB (*5) �ɂ������B�����{�Ƃ��Ă��B�a�̎R���a�̎R�s�B��̋����ɓ��O�_�{�E�����_�{(�Ђ̂��܂����E���ɂ���������)��2�̐_�Ђ�����B�Ŋ�w�͘a�̎R�d�c�M�u������O�{�w�B�����A�I�k�ɂܑ͌吨�́A1.����̌Ë`�^���A2.���͂̓V��A3.�����̐^�`�^���A4.���c�̓��O�{�A5.�G��̈���@���������B���c�}�̓��O�{�͂��̈�B (*6) �ؐH����(��������������)1536�`1608�B�^���@�̑m�B�ߍ]���̏o�g�B �����Ƃ͕��m�ł��������V�����N(1573)38�̎�����R�ŏo�ƁB����R���R�̂���A�\�����ؐH�s���s�����Ƃ肵�Ă���B ���S�����s�r���A�V��13�N(1585)�L�b�G�g���������ɍU�ߍ��ۂɂ́A�G�g�Ƃ̘a�c�ɗՂB���ʁA����R�̕���������B�ؐH�������G�g�̕��L�����c�ɋ��́B ���V��15�N(1587)�G�g�Ɠ��Î��Ƃ̘a�r�����͂�s�����B ���փ����̐킢�ŖL�b�ƂƂ̉�����A�ߍ]�̑�Ï�(�珫�F���ɍ���)��ɐ��̒Ï�(�珫�F�x�c�M��)�ɂ�����J����ɂ�����B �����͋ߍ]���ѓ����ɉB���B�@ |
|
|
��(3) �G���A��I�ɐi�U����
�V���\�O�N(��ܔ���)�܌��ɓ���ƁA�G�g�͎���(���)�a�̎R��̓꒣����s���g��R�h�Ɩ��Â���B�G�������ɔC���A���R�𑱂���n�����̓����𖽂����B�G�g���g�́A��m�X�̖{�莛���@�ɑ��V���̒n��^���ĕz���������ƁA�������ƋA�サ�ĘZ���ɂ͎l���U�߂ɒ��肷��B �����ۂ��G���͌K�R�d������R���ɔC���Ėk�I�𐪈�����ƁA�����⑾�c�ƘA����������čR�킵������C��(*1)�A�L�c(*2)�A����(*3)����F��(*4)�̍����B�̐����ɂ��������B ���̑N�₩�������ďG�g�̓V���l�����ʂɍ��ꍞ�x�����P(*5)�́A��������(*6)�̋q���ƂȂ��Ă��钷�j�E�����̐s�͂ł��������b�]���ċ����ꂽ�B�\������̖{�̂����g���ꂽ���A���ɖ{�{�A�k�R��~�̋t�k�����ɏo�w�𖽂���ꂽ�B �a�̎R(��R)������G���R�̐�w�́A�I�{��A�����A�A��畷�����E���̗����鐔��ł���B�L�c�⑺��̔��R�萭�A�s��̋{���A�c�ӕʓ��n�̖ڗǏ�����X�ƍU�����ē쉺����B ���Ƃ̎q���ł���a�����̋ʒu���a�́A�����S�̊����ł��镐�c�����̓��쒼�t�̖��������A�G���R�ɐb�]���ĉƂ̒f���h����Ƃ����B�{�������쒼�t�͍�m���Ō����W�J����B�ʒu���a�̋}��ł����m�����G���R�͈ꋓ�ɓ��쒼�t�̖{���T�R��(��V�s)��ҍU���A���I���̏��̓ܐ���ւ������쒼�t���F�{�̔���ɗ������B ���̏�������F�{�̐���z���͏G���ɍ~�������B�U���R�̈ē����ƂȂ��ӘH��쉺���ēc�ӂɗ����A�l�{�_�Ђ��n�ߖ��Б厛�����X�ɏĎ�������B���������ڗǎ���_���O�k��͐��܂�����P�����s���āA���̊̂��₵���B �Ƃ͂����A���̏��������ɔ����ē��u��R�₵�A�Ǖ��̌F�쐨�͎���Ɉ��|�����B�R�{��V�͎s�m���̗����R�A���쒼�t�͓c�ӂ̗��_�R����Ă�A���A���𓊂��ĕK���ɐ�����B��������ǂ͔s�F��[�߂���肾�����B �����m���Ė{�{�A���C�u�A�����A�|���̍����B�������ɉ����ɒy���������A�O�ǓG�����B���ӘH�̗v�Ղ͎��X�Ɋח����A�^���A�ߘI�̗E���B���{�{�ɔs������B �� (*1) �a�̎R���C���S�B (*2) �a�̎R���L�c�s�B (*3) �a�̎R�������S�B (*4) �a�̎R���c�ӎs�Ɣ��l���̒��Ԓn�_�ŁA�F��Ó����u���ӘH�v�u��ӘH�v�ɕ�����镪��_�B�c�ӂ���C�����𗣂�ĎR���ɓ��邽�߁A�u���F��(�������܂�)�v�ƌĂꂽ�B (*5) �F�����̏t�H���Q�ƁB (*6) �Ƃ��ǂ� �����Ƃ�B�ɗ\�����ˎ�B��Ɉɐ��Ô˂̏���ˎ�B���x����N��ς����퍑�����Ƃ��Ēm����B�ގ��g�u���m������̎��x��N��ς��˂Ε��m�Ƃ͌����ʁv�Ɣ����B�z��Z�p�ɒ����A�F�a����E������E�R��E�Ï�E�ɉ����E�V����Ȃǂ�z��B���Ղ̒z��͐Ί_�������ςݏグ�邱�ƂƖx�̐v�ɓ���������B��N�ϑJ�c��䒷�������吪�����������D�c�M�����L�b�G�����G�ہ��G�g������ƍN���G�����ƌ��B�@ |
|
|
��(4) �G���͑�a����������A����莟�͈ɉ�Ɉڂ�
�V���\�O�N(��ܔ���)�����ɓ���ƁA�C�H�V�{�ɓ��������K�R�A�������͖x�����P���w�ɌF������A���ӘH��i�H�Đ��ƌĉ����Ė{�{�S����𗎂����B�X�ɓG��ǂ��āA���C�u�̕��`���Ō���̖��ɖ쒷�����߈ȉ��S�Z�\�l�����Y�����Ɖ]������A�F��{�M�뉤(*1)�̌��������ނ�Ƌ��ɓ�ɑ���ꂽ�����m��Ȃ��B �����ւ����������͐��R�̐Ԗɖ{�i�I�ȏ��z���Ėk�R��т܂Ői�U���A���a�ȎR�����r��������B��������(*2)�Ɏ~�܂��ĐN�U�R�Ƃ̒��ɗ������ǍO�̐s�͂ŁA�{�{��~�͉��̔�Q���Ȃ�������̂ł����B ������{�A�l����������A�����G���� �u�ɐ��Ɏ����F��̗�n�������蓾���̂͑���ł���v�Ɗ��ŗǍO�ɗ̎�ɔq�{�ł���u�n�m�v�̐g�������g���āA����̋��͂�v�����Ă���B ���āA�G���Ƌ��ɊM����������莟������ɏ�����A�֔��ɏ��C�����G�g������������ē�\����F�߂�ꂽ���̂� �u��a�͑���������֖̊�ł��邩��G���ɏ����Ă��B���Ȃ��͈ɉ�Ɉڂ��ē����ւ̖h�q�̉��ƂȂ��ĖႤ�B�v�Ɖ]��ꂽ����A���ɐV�����̂������낤�B �R�����߂ǂ��Ȃ邩�͖��炩�ł���A��勦�c�̖��ɁA��a�֎c�肽���҂͏G���Ɏd���鎖�ɂ��āA���������̋����̂Ă��悤���B �莟�Ƌ��Ɉɉ�A�ɐ��Ɉڂ�̂͏\�s�A�����A���Z�A�ݓc�A��˂̈��ƉƘV�E�̏��q�A���A���m�V�A��m�M���E���ȉ��̕���Ɛb��O��]�l�B�������{�ɁA�ނ�͏����X�����疼�����߂����ďo�������B ��������č����͎����閈�ɓ���̑P�����^���A��ƈ��ׂ̋F���Ȃǂ��Â��Ă��������@(*3)�Ȃǂ� �u��������a�͏t���_�̂ł������̂ɓ���畐�m��������ɂ킽���ĉ��̂������Ȑ������s���Ă����B���x�A�֔��a�̖��ɂ���ė���ǂ�������̂����R�̕ł���A���ɂȂ��đ��l������ł��x���v�ȂǂƓ��L�ɏ����Ă���͎̂Ў��̖{���ł��낤���A����ɂ��Ă��������������ʂ̔�ł���B �莟�̐V�̓�\���̓���͈ɉ�\�A�ɐ��ܖ��A�R��O���ƂȂ��Ă���B����ǁA�ɉ�͎O�N�O�̑嗐�ɂ���čr�p�������Ď����͏\���ɂ��������A�O�C�̑��O�Y���q(*4)�A�e��������������Ɏ���Ă��Ă������ł���B����Ƃ̊����B���O�r�̑����\�z���ĐS�ׂ�����ł������ɈႢ�Ȃ��B���̑������g�{�g�{�Ɨ���Ȃ��u�r�Ƃ̌��̔@���v�Ȃǂƕ]����Ă���B �� (*1) �����˂̗����Q�ƁB (*2) �a�̎R�V�{�s�F��쒬���B�ʒu�R�̓�B (*3) �Ώ�P�ۏ���Q�ƁB (*4) ����@�B�M�̕҂��Q�ƁB�@ |
|
| ��3 ��a�S���@ | |
|
��(1) �G���A����ƎR�{�̈�s��ŎE����
�V���\�O�N(��ܔ���)�����̖��A���䐨�́A���c�`�����S�N�Z�ݓ�ꂽ��a�_���ƌւ�u�܂ق�̗��v��ǂ����Ă��A���R�Ɛ�̓V���m���Ŏ�ɂ�������ւ����ɉ�Ɍ������B ����āu��a��[���v�Ƌ���ĉ���ɏ��������������Ă����H�ďG���ȉ��̏����̎u�C�͐��Ɉ����̂悤�ɍ��������B�Ƃ͉]���A���ӘH(*1)��т̗v�Q�̒n���Ă铒��A�R�{�̔����͌������V�̎�E�G���̋�J�����X�Ȃ�ʂ��̂��������B �G���͐V�������̑叫�ɐ���z���C���A�O��̕���^���ė����R���Ă�R�{�����O�����ɓn���ĖҍU�������A�͂��O�S�̓G�ɋꂵ�߂��Ăǂ��ɂ������Ȃ��B �c�ӑ��̍���E���_�R�̓��쐨�����l�ŁA�y�n�s�ē��̏G���R�͌������Q������ɔY�܂�������B��ނȂ��ƒ������Ă̍��r�A�������Ղ��I�݂Ɏ�����{�̈��g������đQ���a�r�J��ƌ������̂͂����N���������B �V���\�l�N(��ܔ��Z)�̏t�A�����R�{��s����a�S�R��ɎQ���ďG���ɉy�������B���c�`���̖{�̂����g����A���S���ē����@�ɋA��A�����Ŋ��𗬂������ł��鏈�𑄂Ŏh�E���ꂽ�Ƃ��������ɓŎE���ꂽ�Ɖ]���Ă���B �l��ƂŒm��ꂽ�G�������ɔނ���M�p���Ă����̂��낤���A���˂ďG�g���A�鎞 �u�����I�B�͐̂��甽���̋������ߓ�y�n�Œm���ċ���A���O�̂悤�ɏ�̌����j�łȂ��Ǝ��܂�ʁB�R���̂���̗̎�ƕS���B�̌��т��͋ɂ߂Čł�����Â₩������ł�������A�n���̓�����͎�i��I���v�����������ɏ����ďO�̉��߂Ƃ����B�v �ƍ��X�Ɩ����Ă��������炾�낤�B ���a�ȏG���͂��̉]���������A�����̒�Ăł��̋��ɏo���̂��낤���A���Ƃ��c���ȏ��u�ł���B���E�ŕ���������A�R�{���n�߈ꑰ�Y�}���\�l�́A�ߕ��̓{��ɔR�����O�̍Ō���Ƃ����ɈႢ�Ȃ��B �� (*1) ���ӘH�B�@ |
|
|
��(2) ��˗ǍO�A�G�ꑷ�s��T��
�����ē����A�|���A�쒷�����Ƌ��ɓ쒩���Ƃ��Ċ�������ƎR�{�̗��Ƃ��v�������B�͂��ɐ������т����쒼�t�̒�E���d��͌F���Ȃ̓����̔\��(*1)�ɐ���ŋA�_�����B ������̌��ɂ���ē������Ղ͕���(*2)�ňꖜ��^�����đ喼�ɗ��B�G���͋I�ɁA��a�A�a��S�\�]���̑�X���Ƃ��āA��R��(�a�̎R��)�ɌK�R�A�c�ӂɐ���A�V�{�ɖx����u���Ď�����i�߂�B�x�����P�̏��͓̂�������A����͐\�����Ǝv���A�����͂��̔{�͂������悤���B ��˗ǍO���G���ɏ�����A�̓��̌��n�ɐ旧���ċ��m�B�����C�̐U���Ȃ��悤���H��ɖk�R���ʂɕ������̂͂��̏H�������Ɖ]���B�ނ��C�ɂȂ�͈̂ꐢ�̉��j���E�G�ꑷ�s�̑��݂ł���B ���s�́A��N�A�M���̎G��U�߂ɏ���J�����B���̐ӔC�ォ��A�Ƃ������s�Ə̂��ꂽ���j�E���O�Y�ɏ����ĉB�����A�G�g�̋q���ƂȂ��Ď��R�ȓ��X���߂����Ă����B�R�����x�̋I�B�U�߂ɍۂ��ẮA���}�Ƃ̏�`��������A��B�ɏo�w���A�ϑP����(*3)�ɓ����Ă����B�l�����A�G�g�̊J��v���ɉ����Ă�������Ə���o��ƁA������(*4)���z���Č̋��ɋA�����B���ɑ��s�͒j����̎l�\�Ɖ]���A�Ȍ�A�j�ォ��B�Ƃ��Ă��̏��������Ă��܂��B�F��Ɏc��`���ɂ��A�ނ͖x�����P�Ɍ���ĐV�{��ɓ���A�I�X���K�̐����𑗂��Ă��邤���A���P�̎��j�E��V��Ƃ���L�n�Ƃ̋q���Ƃ��āA���̎����ɐs�͂��鎖�ɂȂ����悤���B �G�����͂G�g���ɏ����s����������ƍ~�����A�G���ɐb�]���Ă���̂��A���s�̏���f�ɏ]�����̂��낤�B�i��ŏG�g�Ɏd����Α喼�i�̈�������̂͊m���Ǝv���邪�A�V�����R�C�܂܂ȑ��s�����Ɍ��ꂵ���{�d��������C�͂Ȃ������炵���B �� (*1) �a�̎R���V�{�s�F��쒬�ɔ\��R�{�Ƃ����y�n������B (*2) �a�̎R�����͒��B�a�̎R�s�̓����Ɉʒu����B (*3) ���Ⴍ�����傤�B���{�L�ˎs���{�B (*4) �����ӂ��Ƃ����B�a�̎R����o�s�B�G�g�̋I�B�������Q�ƁB�@ |
|
|
��(3) ��˗ǍO�A�G�ꑷ�s�ɉ
��˗ǍO�͑��s���k�R�ɓ������ƕ����āA���b�ɂȂ����|����˖�ꑰ���ނ������ňꝄ���N�����Ă͈�厖�ƍl�����B�}���ŊC�H�A�F��V�{��̖x�����P�A���̐��Ȃŋ�S�×��̖��̐����j�E���O(��̐V�{�s��)�Ɖ�A�G���̈ӌ���`�����Ǝv����B ���˂ėǍO�̂��Ƃ��Ă����x�����q�͂��̐l���ɍ��ꂱ�݁A���O�����Œ�E�L�n��V�̏�Ɉē�����B�܂����k�R����A���Ă������s�̘b�������A����ɂ��Ζk�R�̋��m��͓V���ɕ����������������s�̒��S����̘a�r�̂����߂ɂ����������ʕ@���łǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ������炵���B �������Z�ȗL�n(*1)�����̔������Ɉ͂܂ꂽ�����ŁA�傢�ɈӋC���������O�l�͖�ӂ��܂Ō�荇�����Ɖ]����B�ǍO�͐��̂������̎h�g���M�ɐ���グ�Ă����߂Ȃ��� �u�g�N�ƐQ�悤���A�ܐ�Ƃ납�B���̌ܐ�@�N�ƐQ��h�Ƃ̍��l���̂��悤�ɁA�َ҂͂����{�d���͌�Ƃ���A�c��̐��U�͎��R���܂܂Ɋy����ő�������v�ƍ����ɏ���������s�ɂ������蓯��������ꂽ�炵���B �� (*1) �O�d���F��s�L�n���B�Ԃ̌A���߂����Ƃ��납��u���K�͌��܂ł����Ə��т������B�@ |
|
|
��(4) ��˗ǍO�A��a�ɋA��
����ł��ǍO���A�k�R�Ԓm(*1)�̗��ɒ|���l�Y��K�˂��͓̂V���\�l�N(��ܔ��Z)�̓~�ɓ��������ŁA�����Ŏn�߂ĕ��`���ōs��ꂽ�ڗ�ȍ��d��m�����B���d�Ƃ̓����́A���炵�����鋽�m���Ɏ���Ă������ɁA�a�r��\������ �u������̂ď���J���Έ�؍߂ɂ͖��ʁB�������m���˂Ίe���X�̘V�c�j�����F�E���ɂ���v�Ƌ��������̂ŁA���˂ėǍO���畷������A�G���̐l�]��M���ĊJ�邵�����m�S�\���l�̂��ׂĂ�Ђ��[�������͂˂��Ɖ]���̂ł���B �u����Ȕڋ��Șb��������̂��I�悵�g�������ɑ�[���a�ɉ�m���߂Č���v�Ǝn�߂Ă����m�������`���̋����ǍO�͕��𗧂Ă�ƁA�}���S�R��ɎQ���ďG���Ɏ����i����Ƃ����B�������܈������G���͕a���ɕ����Ă��ē����オ��ʂ炵���B�����Ɂu��ڌ����n�m�v�̔ނł�����Ƃ�����Ȃ������B��ނȂ��x�����q�ɂ��̏�����ċ��c�̖��A�b���͍ȂƐ��܂ꂽ����̗c����A��đ�a�ɋA��A��͖x���ɑP���肤���ɂ����B ���܂ق�́@���̗[�ӂɁ@�A��Ȃ�A⾉���@�F��̎R�B �Ɖr���Ė��c���ɂ����A�ӔC���̋������i�����ɁA���̎��͐��ɐS�O�������ɈႢ�Ȃ��B �ǍO�����ɏo��C�����Ă��̂́A���q���G����X���Ȃ̂悤�� �u�V��̉R�͕��ւƉ]���A���m�̉R�͍����Ə̂��Ă��܂����B����ƂĕS���͈���ɂ����䂫���̂Ȃ�v�ƒQ���A���s�� �u���܂������̂͋{�d����v�ƁA�����Ԃ��āA�l�ӂ̑����ɖ��������Đ��n���y����ł���̂����āA���Â��A�܂����Ȃ����̂��낤�B �ǍO���G������ɂ������̒n�m�ƂȂ����̂͊Ԃ��Ȃ��ł���B�F�삩�町���ė����Ȏq�Ɛm��c���̊قŏZ�݁A�F�삩�瑗���Ă��銿����̔��ƂƂ��Ȃ��炻�̖T��ɒ����Ɣ\�y�ɕ���̗]�����y���ݎn�߂�̂ł���B �� (*1) �F��s�_�쒬�ɉԒm�_�Ђ�����B�Ԓm�_�Ђ̈ē��ɂ́A����V�c�̍c�q�ł����ǐe�����F�엎�������ہA�����Ŏ����̊قɌ}��������̂��|�����Y�ƋL����Ă���B�@ |
|
|
��(5) �������ՁA��ۂ�{�q�ɖ]��
���̍��A�S�R��ł͏G���̎k�q�E���(*1)�����˂ŏ]�܈ʉ��{������ɔC�����Ă���B��ۂ͒O�H���G(*2)�̎O�j�ɐ��܂ꂽ���A�V����N(��ܔ���)�ɏG�g�̍��]�Œj�̎q�̂Ȃ��G���̗{�q�ƂȂ����B�G������a����̔N�ɂ͎��ŋ��ɓ��������A���̉��Ȏp�������B�̖ڂ��䂫 �u���Â��l���q�̂��P�l�̖��ƂȂ�A���̑�a��[���l�ƂȂ������v�Ƒ�]���ƂȂ��Ă����B �����m�����G�g�͉₩�� �u�O�H���G���������������ł͖L�b�Ƃ̈��ׂ��v��ォ����ꑰ����k�q��I�ڂ��v�Ǝv�������A���̏G��(*3)�ɑ�点��Ɖ]���o�����B �R���G���� �u�S���O�H�a�ɑ���`���������v�ƒ��X���m���Ȃ������̂ŏG�g�͍���ʂĂĂ����炵���B�����m���� �u�����͈�G�g���̋C������낤�v�Ɣ��ڂȂ����ɓ������̂��ƘV�̓������Ղ� �u�g�������q������܂��ʁB���Ƃ���ۗl��{�q�ɉ�����v�Ɖ]���o���A���̍��_�����������Ă���̂ŏG���͔��ɓ{�����炵���B ���̍��Ղ͏G�g�Ɏ��ĉz�O���q�Q�l�̎q�ŁA�\�܂ʼnƂ��o��Ɛ�䒷���̑��y�ƂȂ��Ă�萶�U�Ɏ��x����l��ウ���Ɖ]����B�V�{�̖x���Ƃɂ��S�ŕ������Ă�����������炵���B �G���ɂ͒����U�߂̍��Ɍ��o���ꂽ�Ɖ]������A�܂��\�N�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂����A������ċI�B�U�߂̌��ɂ���ēV���\�O�N(��ܔ���)�ꖜ�̑喼�ɐ���オ��������ł���B����Ȃ̂ɔ��������ƁA��̗{�q������Ɖ]���o�����̂�����A�G�����{��͓̂��R�Ɖ]����B ���Ղ����������ƍl���A���S�R��̊g���Ɏ�r��U�����̋@�������ɓw�߂��悤���B���䏇�c���M���̈ꍑ���߂ɉ����āA���݂̌S�R����a�B��̏�Ƃ��đ���C���n�߂��͓̂V����N(��ܔ���)�Ɖ]����B�V��t�����������͓̂V���\��N(��ܔ��O)�l�������A���ꂩ��͂���N�l�J���ŏ��c�͂��̐��U������B �G�������邵���V���\�O�N(��ܔ��O)�������炱�̏�͑�a�A�I�B�A�a��̎O�����x�z�����s�Ƃ��Ėʖڂ���V���ׂ��H�������肳�ꂽ�B�V���\�ܔN(��ܔ���)�ɂ͍������̎R�傪�ڂ���đ���ƂȂ�A���N����ޗǒ��̉Ɩ��ɑ�̋������舶�Ă��n�܂�A�Ў��ɂ��e�͂Ȃ����o��������ꂽ�B�����A��ǂ̏��X�Ɍ�����Ε����A�y��͂��̎��̍Q�������E���邪�A�ޗǂ̏��Ƃ��ڏZ���ď鉺�����`�����ꂽ�̂͗��A�V���\�ܔN(��ܔ���)�Ǝv����B �� (*1) ���� ���g(�Ƃ��ǂ� �����悵)�B�O�H���G�̎O�j�B�H�ďG���A�����ŁA�������Ղ̗{�q�ƂȂ����B (*2) �D�c���̉Ɛb�B���̐킢��z�O����Ꝅ�����ȂǁA�e�n��]�킵�Č���������B�����ʂɂ����Ă��D�ꂽ��r�����A�M������ߍ]���a�R���ዷ�ꍑ��^����ꂽ�B ���ƘV�̐ȏ��Ƃ��Ă͎ēc���Ƃɑ�����ԉƘV�̐Ȏ����^����ꂽ�B�D�c�Ƃ̎ēc�E�O�H�̑o���Ƃ����邱�Ƃ���A�����u�؉��v���������L�b�G�g���o���̎�������āu�H�āv�̐���M���ɐ\�����A���G���G�g�ɑ��D�ӂ����Ƃ����G�s�\�[�h������B���̂��Ƃ������v�����O�H�́A�ēc�Ƃ͑ΏƓI�ɏG�g�̕ی�҂ƂȂ�A���̌�̏G�g�̓V������ɑ傫����^����B (*3) �L�b�G��(�Ƃ�Ƃ݂Ђł₷)�B�L�b�G�g�̎o�ł�����G�̎q�B��a���[���B�f���G���̗{�q�ƂȂ�A�V��19�N(1591)�ɏG�����v����Ƒ�a�L�b�Ƃ��p�����B�������ՂƌK�R�d�����G�ۂ̌㌩���ɔC�����ꂽ�B �����\4�N(1595)�A�×{�̂��߂ɑ�a�\�Ð�ɂ������܁A�ώ��𐋂���B���N17�B�������vጂ̈����Ƃ���邪�A�G�ۂ̌㌩���̓����ƊW�̎j���ɂ́u�\�Ð�ɗV���ɏo�������Ƃ���A�������G�ۂɕ������A�Ƃ��ɍ��������э~��ē]���������v�Ƃ���B�������G���̗{�q�œ������Ղ̗{�q�̉H�č��g�ւ̑�a�L�b�Ƃ̉Ɠp�����F�߂�ꂸ�A��a�L�b�Ƃ͒f��B�@ |
|
|
��(6) �k�R���m�A���n�ɑ��ĖI�N����
���̔N(��ܔ���)�̏t�ɋ��̎O���͌��ňɉ�̕S�n�Ɏd�����炵���E�ҏ��̐ΐ�܉E�q��Ƃ����哐�����劘�ɖ������ĎώE���ꂽ��������]���ƂȂ��Ă��鍠�B ���˂Ă�����ƂȂ��Ă�����a�\�Ð�A�k�R��~�ł̌��n���f�s���ꂽ�B�����鑾�}���n�ł���B���̓y������V���l�ɐ���オ�����G�g�����O�̋ꂵ�݂�߂��݂��[���m��s�����Ȃ���u���n�A����v�̔_��������J�n�����̂������ł���B��B�������I����[���ɏ��i�����G���́A�S�R��ɋA��ƌZ�̐������j�𒉎��Ɏ���đ��}���n�ƌĂ��̓��̌��n�ɒ��肵�A�ꖇ�̉B���c���k��Ȃ���������ƌ��������B �u���m�̒m�s�͈ꎞ�A�S���͉i�v�v�Ƃ̏G�g�̈ӌ��ʂ�_���̈ڏZ���ւ��A�n���Ɣ_���̌��т���f�����ė̎�̎x�z�͂����߂��B�u����ꖯ�v�ƒ�߂�ƁA���ł͔r���A�������l�ȉ��͖��łɂ��A�_�����ł����g���������ւ��đP�����v���Ă���B �{�{��\�Ð싽���͗ǍO��̍H��������đf���Ɍ��n�����B���̏�ŁA��������̂܂ܒ��Ղ�����ɁA�v���Ƃ��Ė����l�\�ܐl�̔���肪�ޖ�V�{�܂ŗA�����鎖���肢�o��B�G���͂����F�߂���ɁA�l�v�̐H���Ƃ��ĔN���\���������鎖�ɂ����B ����ɑ��Ėk�R�����́A���n��l�̗���������� �u�����͐̂����c��X�p���ŗ����y�n�ʼn����̎傩���������̂���Ȃ�����N�v�Ȃǔ[�߂���̂��I�v�Ƌ��C�ɏo�ċ|�S�C���������o���������Ăǂ��ɂ��肪�����Ȃ��B ���n�㊯�𖽂���ꂽ����A�畐�����A���˂ē쒩�̍����n�Ƃ��Ď������{������o�������O�@���I�Ȉ������Ă����y�n�������ɁA�\�Ð쓯�l�͖̎ƒn�ɂ������ƏG���ɐ\���o���B�Ƃ��낪�A�ނ� �u�̎��͂Â��ŋ����Ɖ]���ԓx�͐��ɉ�������ʁv�ƌ��{���� �u���N�͂����~�ɓ����ᓙ�Ő��s�ł��Ȃ���A���N�Ȃ�Ƃ��k�R�҂͎�����˂�́A���̂���ō��ۂ͒��`����ɐS������v�Ɩ{�{�m�V�ɖ����Ă���B ��������k�R���m�B�� �u�����̉��ʊ��҂̒�߂������ʂ����v�ƕ��������A�k�R����_��A���R�A�����A���C�u�̑S���ɞ������Ԃ�z���Ĉ�ĂɖI�N�����B���`���̉��Ƃ͉]���A�����ɂ��Ƃ��u�ӎւɕ|�����v�̗ނł������낤�B�@ |
|
|
��(7) �g��Z��A�k�R���m��j��
�L�b���̋��傳��m���Ă���x�����P�͉��Ƃ��������ւɂ��܂���ƐF�X�z�������Ǝv���邪�A�d���̋��m�B�͊�Ƃ��ĕ����Ȃ��B�V���\�Z�N(��ܔ���)�̋㌎�ɂȂ�ƏG���̌��������g�약���A�O�U�Z�킪�O��̋����𗦂��ď�荞��ŗ�������A���P����ނȂ���w�ƂȂ�o�������B ���P�͗L�n�邩���ː�����n�J��i�ނƔ��̋��ɐh�ʂ����z���ċ��_�Ƃ����B�����ܕS���w���������P�́A�܂��̐_�R�A����A���n�A����A�喔�̑������W�߂Ď�������������ɉ�����ƁA�Ꝅ�����Ă������J�̑����╘�q�R�ԂɍU�ߊ��B �Ꝅ���̕��͓͂��ܕS�]�Ɖ]�������a�̖̂k�R�O�������Q�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B�ɉꋽ�m�̂悤�� �u�쒩�̒��b�Ƃ��ėE����y������c�̖���p�������߂�ȁv�ƈӋC�����}���������B����ǂ����̉H�Đ��ɖx���R�A����ɏ���m�������̖ҎҎO�S�]��������Ǝl��߂���R�ł���B �╘�q�R����邪�������̌~�g���������Ĉ�C�ɍU�ߗ��Ă��B�V���S�C���̈�Ďˌ��Ƌ��ɐ����s���ҍU��������A�ւ�͍����Ƃ�����ʈꝄ���͎������o���ĕ��ꗎ���l���̎R�X�ɓ������B����͗D�ꂽ�w���҂������ʔ߂����ł����낤�B �叟�ɖ��������g��Z��͓��O�㑸�뉤�䂩��̐_�R�������Z�E����G�����ւ̌���i�Ƃ��ĕ��ې����p�̐Ԑ�q��������ꂽ�B�Z��́A�ЂƂ܂��V�{�Ɉ��g���ē~���߂��A���t�čU�ƌ��߁A�M�����R�̈А��������R��Ԃ����B�@ |
|
|
��(8) �g�약���A�_�q���コ���A�����I���ɂ�菈�Y�����
���̋g�약���́A�ƍN�̈ɉ�z���������ɐ��喩�̑D��s�ł���B��ɏG���Ɏd���A����̑�g�����ɁA�V�{�؍ݒ����\�ᖳ�l�̐U���ő��ʑ�Ђ̐_��������グ�Ă���B�_�q���̐��~���������A���n�E�V�m�֏��ɓo���Č����̎������Â����̐ꉡ�Ԃ�ɁA���܂肩�˂��C���҂炪�ÎE���v�����炵���B�F��N��L�� �u�V���\�Z�N�\���\�Z���_�q����A�O�U�A�������Ă��ɁA��a��[���a�̌�p�ɂď\�Ð�k�R�֎Q�肽��ؕ�s�ɂė��l��؎E���B�v�ƋL���Ă���B ���̐^���́A�u����������o���Ă͂Ȃ�ʁv�Ǝ~�߂�̂��U����ēo������l���A���B���P���O�U���a��̂Ă��B����ɋ����������͖{���ɕ����đ��������炵���B�Аl�B���Q�Ăċ삯�o�������Ԃɍ��킸�������サ�Ă��܂����B�c�ƁA�������Ƃ炵���B �����B�͂��̑O�N�ɂ��G���̖��ŌS�R�錚���p�؍ޏW�߂ɖk�R�ɂ���ė����炵���A�r�����_�̐_�����̂��ނ�Ɖ]����B�_���B�ɂ́u�G�����̗�����v�Ə̂��Č�����U���A�]��ō���̓��������𖽂���ꂽ�悤���B �_�q���㎖���́A���炭�匟�Z���鎁�P�̕ɂ���ďG���̎��ɂ��������炵���A�����͑����ɏ������ꂽ�B�������F�c�̌��ʁA�ނ��F��ނ�����ɔ���A���Ŕ��蕥���Ď������₵�Ă��������I�������B�����́A���̏\�ɓޗǐ��厛�O�Ŏa�߂ɏ������Ă���B ���ɏG���炵�����ȓ������ʑ�̎�炵���ٌ��ł��������A����ɂ͗ǍO���傢�ɐs�͂��Ă���悤���B�@ |
|
|
��(9) ��k�R����
�R��������ɖ��N�ȏG�����A�����N�A�Z�E�G�g�̍���������A�������Ղ̐����Ɋ��҂��āA�������ۂ�ނ̗{�q�Ƃ����B�{�痿�Ƃ��Ĉꖜ���������ĕ���ɑ����Ă���B ���ɋ{�����㍂�g�A�\��˂̗c�N�ł���B���Ղ��}���}�Ɠ̑喼�ƂȂ����͎̂���������ɕq�Ɖ]���悤�B�R���ނƂ������g�̐l���͌����čK���Ȃ��̂Ƃ͉]�����A��ɂ͖����Ő��U���I����̂����A�ڂ����͔N��ǂ��ďq�ׂ鎖�Ƃ��悤�B ���V���\���N(��ܔ���)�A�G���́A��̕��`���̔ڗ�Ȃ��܂��������엪�Ə̂��鍂�Ղ�̌���M���Ėk�R�\�k�����𖽂��A�S�R��ł͒��X�Ɛ킳�������i�߂�ꂽ�B �t�l���ɓ���ƁA�������ՁA�H�c�����疼������E���������R�̑叫�ɔC�����ĐV�{�ɓ������A�x�����P�Ƌ��ɍ���������B �������A�G�g�����n�Ɍ�����쒷���ɑ��� �u���R����̎�͏�ɒǍ���ŊF�E���ɂ���B�c�����B���悤�ȕS�����͏��q���܂Ŏc�炸�ȂŎa��ɂ��Ă��܂��A���ׂ̈ɍ���S���r��ʂĂĂ�����ɂ��܂�ʁv�ƌ������Ă���̂͐M���ɏK�����̂��낤�B ���炭������������悤�� �u�����̒�����A�쒩�ɒ��߂�s���������Ƃł��낤�ƓV�c�̖��ɂ���ēV�������߂�\�ɔ��R����ҋ��͈�؏�Ȃǖ��p�v�Ɖ]��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B �Ñォ����{�̓`���������V�c���x�����Č����̏�ɗ��ƍَ҂����Ƃ����M���̑ԓx������̌��������������G�̔������������B�����m���Ĕz�������G�g���A���͂�Ύ�����Ŗ����̍K�����͊ᒆ�ɂȂ������Ƃ͔߂����B ���O��l������J�n���ꂽ�����A�H�c�̑�k�R�����͉Ս����ɂ߂��B�_�m��v�Q����Ă������Ꝅ����s�������Đ��R���ɐi�݁A�����m���ɐi��œ������̓����F���ȉ��̒n�����������X�ɓ������Ɩk�R��~����������B�@ |
|
|
��(10) �k�R�Ꝅ�̎c�}�A�c���q���ŋs�E�����
�R���Ꝅ�̎c�}�B���R��ɐ��ݑ��X�ɂ�����ėe�Ղɕ߂炦���Ȃ��B����ɋƂ��ς₵�A������͕��`���Ɠ�������l�����B���R�̐Ԗɖ{�i�I�ȏ��z���グ��Ƒ��X�ɕz������ �u���x�A�����ɏ邪�o���オ�����̂Ő���ȏv�H�j�����Âق����ɂ����B�A���Ă͊e�������l�c�炸�j���ɎQ�ス�摽���̏j�V�����킷���v�ƍI�݂ɌĂяW�߂��B�����m�炸�ɏW�������l�̒����炩�˂ĈꝄ�̎�d�Ɩڂ����Ă����A������ԑŐs�ɂ���ߕ߂����B ���̐��͎O�S���\�l�Ɖ]�������ɏ�����B��e�͂��Ȃ��c���q���ŋɌY�ɏ������͓̂����̔��ĂƂ͉]���A�����ȑ��Œm��ꂽ�G���Ƃ��v���ʗ⍓���S�Ȃ����ŁA�����m�������X�ł͋A��ʕ���v������炢 ���s����߂�ʁ@�Ԗ̂���A�g�̎̂ď��́@�c���q����B �Ɖ]���߂������̂��q�X���X�܂ʼn̂��p���A���̉��݂͖ȁX�Ɛ��S�N�ɋy��ł���B ����ɔ�ׂāA�x���̒z�����嗢����ł́A�n���̎傾���ɂ���Ȉ�煂ȍ��d�����炷�����Ȃ��A���n�������ɂ���Ŗ��S�͈��肵�Ă����B������`��f�s�����Ԗ؏�̓����ɔ�ׂĊi�i�̎����������Ă���B �����m�����G���͖��̕�������ɂ���ƎO���x���ɉ������A�����ďG�g�����N���c���U�߂̏���������ĎO�R�ɉ����S�\������i�Ƃ��Ă���B�����̋��ꖇ�͏\���ŏ\�܊ѕ��ɂȂ邩��A�ꖜ�ܐ當�Ɖ]�������ł���B�Ĉꏡ���O�\�����x������A���z�ł͎���ܕS�ƂȂ�B�O�R�����тŁA���c�ɒ��H���ďG���̑P�����^���A�\�Ð�ł͌�̓��쎞��܂� ���g���Ə\�Ð�@��͖Ə��A�N�v�v�炸�́@�����A �Ɖ̂��Ă��̑P�������ł���B����ɔ�ׂāA�k�R���̋��m��_���B�͑�����㊯�̈����Ɋ�����ꂸ�ɁA�k�R�A�|���O�͍Ăш��c�a���ʂɗ��P���đ㊯�E���c�������ꂵ�߂Ă���B�����̂܂������ʂ̎�́A���ăm�w�̌�܂ł��F��̗��l�ɔߌ��������炵�Ă��邪�A���̎j�����a�A�ɉ�̐l�X�͉���m��Ȃ��B�@ |
|
|
��(11) ���`������Ԗ؏�
�V���\�O�N����ܔN�ɋy�ԖL�b���̋I�B�U�߂͊����̔ߌ��������炵�����A���ɌF��A�k�R��~�ɂ��āw��I�Îm�`�x�͎��̂悤�ɋL���Ă���B �u�V���\�O�N�āB�쒩�ȗ��̖��ƂŒm��ꂽ�쒷�����߂��a�c�Ƃ��܂��ĐԖ؏�ɏ����������^�E�q��͂Ȃ������R���ӂ݉z�֖{�{�_���̔����S�Z�\�l�`��ɂėe�͂Ȃ�����͂˂�B���N�t�ɂ͗����R��ɂė͐킵�����a�����̒����ł��铒��A�R�{���a�c�̎g�҂ƂȂ��čI�݂ɐ������A�S�R��ɏ�����ƁA��Ó��쒼�t�ꑰ���G�����ɔq�{�����{�̈��g�Ŋ������ɓ@�Ŏ������Âق��ŎE����B����ƒm�����R�{��V�A�����l��\�O�����鉺��E�o�����̂��I�a���������y���őҕ����A���d�Ȉ����ňꔑ�������߂ĉ���A�ނ�M���V�݂̓��a�ł��낮�R�{��ljz���Ɏ��{�̒����Ŏh���E���A����]�҂����ׂ��x���������B�����ēV���\�Z�N�ɖu�������k�R�Ꝅ�ł͎傾���m��O�S�]��c���q���Ŏa�ĉ��݂̗��S���㐢�Ɏc�����v �R���A㩂ɂ����薳�c�Ɏa�ꂽ���l�̎��̂͒������Ƃ������ꂸ�A�[���J�ԂɏR���Ƃ���A���T��̉a�H�ɂȂ����Ɖ]���A�����J�ꂩ�琁���グ�Ă���╗�͒��ɂ��݂�B ���̉��݂��炩�A�����Ȑl���ŖL�b�Ƃ̑单���ł������G�����͂��̗��N�A���ڂ̏G�ۂ��₪�ĕώ����A��a�S���͐₦��B �������A������������Ղ͍I�݂ɏ����n�ɏ�� ���ɐ��͒ÂŎ��c �Ɖ̂��閼�N�Ƃ��č������A�����]�����Ă���̂�����Ƃ��Â� �u���j�͏��҂̂��̂ł����Ȃ����v�ƒQ���A�R���~�����B �� (*1) �a�̎R���V�{�s���1����9-29�B (*2) �r�ؓN�@���B�S������\�����Z�E�B�����Q����Ă��Q�ƁB�@ |
|
| ��4�@�ɉꔒ�P��̒a���@ | |
|
��(1) ����莟�A�ɉ�����߂�
����莟���ɉ�ɍ��ւƂȂ����͓̂V���\��N(��ܔ��l)�̔������ŁA���̎��ނɏ]�����҂͎��̂悤�ł���B 1�D���e��(�\�s�A��A�����A���Z) 2�D�ƘV�A�d�b(���q�A���m�V�A���A���c�A�����B���A��� (��)�ނ�͂��������a����̌܊����x�Ɍ��\���ꂽ�B �����̈ɉ�͎O�N�O�̑嗐�ɂ���Đ_�Е��t�̖w�ǂ͏ēy�Ɖ����Č���e���Ȃ������B�莟�͏��̎��E�m�ؗF�~�̓@�Ղɑ��ق����ĂāA�����������̒����Ƃ��A����E��t���̍r�n�ɒz����J�n�����B ���˂ďG�g�͔ނɋC��z���ĉH�Ă̐��Ə]�܈ʉ��ɉ��ɔC������� �u�ɉ�͑��̏o��Ƃ��Ă��鑠�̒n����A���������ɗ�݂v�Q���łȑ���z���v�Ƌ��z�̎��������������B�]���āA�z��̎����͖L���ŁA��v����l���W�߂Ĉ���܍��̕Ă��x�����A�ˊэH�������s�����B����͓���ƍN�A�D�c�M�Y�Ƃ̑ΐ풆�ł����������炾�B ���̔N���A�u�a���������Ă���͎����ɋC��z��A���q�𖼒�����A�ݓc�Ɉ��ێO��A�����ɕ��c���ܕS��^���ė̖��̌i�C�ɓw�߂Ă���B �����Ď�s�Ƃ��]������ɒ��m�V�A���̉ƘV�E���n�߈��̕��Z��\�s��z���ĊX�̕����Ɍ����ƂȂ�A���̍����E�p�q���ӂ��N�p���Ĉɉ��̐��H���@�킵�ĕ����A���̕ւ��v�����B �莟���e��������m���x�⒃�l�喼�E�Óc�D���Ɏt�d���āu�j��܁v�Ɩ������������▕����Ȃǂ点��]���ƂȂ��Ă��邠����A�@���ɎY�ƂW���ďZ���̐��v�̏[���ɔz�����������@������B ���݂ł��������ɂ߂�V�_�Ղ́A�ނ������̍ۂɗ������̐_�Ƃ��ĕ��Ă������̂ł���B�H�̑�Ղɂ͗̎厩��\�ʂ����A����т₩�Ȏ�߂ōs��̐擪�ɗ����č��N�̖L�N�� �u���P�̖��ɂӂ��킵���G�̂悤�ɔ������A���ɂ��D�������a�l�v�Ƃ��ď鉺�̐l�X�̓���̓I�ł������Ƃ��Ŕ��P��Ɖ]���������ꂽ�炵���B�@ |
|
|
��(2) �Γc�����A�����߂���������
�������X�̓V���\�O�N(��ܔ���)�t�A�����̎�̏��q���d���a�v�������A���j�E�d���͂܂��\��˂ʼnƓ��p�����A�M���ƘV�͒��m�V�G�S���A�C�B��ԉƘV�ɂ͓������̎q�E���ߖҏ����o�p���ꂽ�炵���B ���̖V�A���̐V�ƘV�͂���������Y�Œm��ꂽ�d���������Ɏv���ʂ������B�Ⴂ�莟�͂��ꂪ���������āA�V���������������J�A�͑�������Ă낭�ɉ�����ʂƉ]����ԂƂȂ���������A���̎���������n�߂��B �V���\�l�N(��ܔ��Z)�A�悸���q�d�����Q�l���A����������Ăčs��������܂��B�����ē����c��ƘV�̒��m�V�G�S�ƕʂ�̉����J���A�݂ɍ��̐�s���Ă��A�q�ɏ����ċߍ]��c�S�ɑސg����B �V���\�Z�N(��ܔ���)�ɂȂ�ƐΓc�O�������̘Q�l��m��O���̏��̂̔�����^���ď��������̂���]���ƂȂ����B��������G�g�� �u��]�������\���Ɖ]���͕̂����������Ȃ��B���g�͂�������C�҂�v�Ə^�����Ɖ]���A���ɓ��͎O�\���ˁA�O���͏\�ˉ��̓�\���˂������B ����ɂ��Ă����������ďG�g�͈ɉ�̎�肪��̉�����̂�����A��쒷�����g�҂Ƃ��Ĉꖜ������������� �u���ɑ����Ĉꑰ�̕��Z�A�X�܂ł����Ȃ�������̓��ɓM��߂���ƈ��z�������đ�a�A���������ȁB�c��z�{�A�\�s�A��˂�ɕ��z���čs������߁A������z����}���ő��̊O�邽���ڂ��ʂ����v�Ǝ����Ă���B�@ |
|
|
��(3) �R��v��A�G�g�ɏ��Y�����
�R���Ȃ����U�A���ɏo��ƒ莟�̗E�҂��͗L���ŁA��B�̓��ÍU�߂ł͖L�b�̐���������A�V���\���N(��܋�Z)�̖k���U�߂ɂ͈ꖜ�̕������w�������ɎR��U�߂ŕ������P�����Ă���B ���̐킢�ł͏G�g�̌������Ő���������ꂽ��ˊo�O�Z��̊���͂߂��܂������̂��������Ɖ]�����A��ˉƂɂƂ��Ă͖Y��Ă͂Ȃ�ʒɂ܂����o�������N�����Ă���B �Əd��̉ƕ�Ƃ��Ă���������䂸��̍��풃�q����ڌ��� �u�����A���ꂼ��������˒��q�v�Ɛ��ɒm�炵�߂��͎̂Ⴋ���̐�m�@�Ղ̈�m��q�̎R��v��ł������B �{�\���m�ς̌�ɏ��c�����サ����˒��q�͏G�g�̒����ɂ�������ʕi�ƂȂ��Ē���ɂ͕K���p�����B�@�Ղ̂����߂ɂ��k��̑咃��V���̕]�������߂Ă������A������^��ł�������������Ċ����Ă��܂� �u�����ؕ��I�v�Ǝv��ꂽ���A���ɂ����א�H�Ă� ������ÁT�@�܂Ɍ������@��˒��q�B�߂��Ή�Ɂ@�����ɂ��炵�ȁB �ƈɐ�����ɂ���ƕ��́u�T�䓛�v�̋�ɂ��Ȃ������r���A�����G�g�̋@�������������~�����b�͓����m��ʎ҂��Ȃ��]���ƂȂ��Ă���B ���x������ڒu�������̂��̎R��v�A�t���ɗ��ʒ����Ȃ��� �u�̂ђ��̐��_�ɂ��Ƃ鐬�������v�ƏG�g��ᔻ�����ׂɒǕ�����Ċe�n����Q�������ɁA�V���\���N(��܋�Z)�ɂ͖k���Ƃ̒������ƂȂ��Ă����B ���ꂪ���ƂȂ蒷�w�ɂ������G�g���v��̘b���ď��������A�v��� �u���̓��͖k���Ƃ̒�����邩��Q��ł����˂�v�Ƌ��ׂɒf�߂ɏ������Ɖ]���������u����������ł���B �v��͌��������Y�ɂ����ꂸ�A���m��������܂��̍����ȑԓx�Ő����������B���̎��͍����s�ɔ�сA���l�̊Ԃɂ͏G�g�̔�{�鐺���邩�ɉQ�܂����͓̂��R�Ɖ]����B ��a�̗��[�Ăƍ������ǍO�̒����ł��A�v��𓉂ސl�X�����߂₩�ɒǑP���{�̒�����J�����B�ǍO���₪�ď@�Ղ���Ƃ̎��ɂ���Ęǒ��̐��E����������������Ȃ��̂��������̂́A�ގ��g�����}�̉����̒����ɒ��l�Ƃ��Ĉ�����ނ��ʊo�������Ă������炾�낤�B �����Ă��̗\���͂₪�Č����̂��̂ƂȂ�B�@ |
|
|
��(4) ���x�A����
�V���\��N(��܋��)�����A�G�g�͉��B�𐪈����ēV��������ʂ��A�����đ嗤�ւ̖�]��R�₵�Ă����B���̔ނɂƂ��Ē��Ƃ��̂��ׂ�����l�̒�E�G�����\��˂Ő������������͉����ɂ��ウ��Ō��������낤�B �G���Ɨ��x���L�b�Ƃ̑单���ł���A�G������������F���Ă������͋�B�̑�F�@�ق�����Ŕނɉ�����ہA �u���V�ɂ��Ă͐g���������ċ���A���X�̎��͏@�Ղɂ��C������v�ƌ�������Œm���Ă���B���̏G�����������������Ƃŗ��x�ɉЂ��y�Ԃ͕̂K���ŁA�ʂ��ė����ɂȂ�� �u�V��������������Ŕ������A�哿���̎R��ɌȂ̖ؑ����f�����v���̍߂ŒǕ������B�吭����˂˂�������� �u���l�т�����v�Ƃ����߂Ă��A����͏o���ʁA�ƊΎ��Ƃ��Ď��U�葱�����ׂɁA���ɂȂ�Ɛؕ��𖽂���� �u�l�����\�A�͈͊��A�፟�A�c�����E�A�v �g���\�N�Ɖ]���M�����ɔ�ׂ��ꡂ��ȍΌ���͈�t�ɓw�߂����A������f�����̒�������̂͗e�Ղł͂Ȃ������B�R��������̊֓��ɗ����A����グ�����̕�U���A�c�t�����ɂ����ɒf�����āA���Ɂu���x�v���������������Ă��V�ߖ��D�̐l�ԂƂȂ낤�ƐS�ɐ������B�h �Ɖr���ĉ��썑�t�ɂ����ʌ����ȍŌ���Ƃ����B�����̒����ɏ���g��сh �Ɓg���сh�ɖ��������������������A�Ǝ����ȂĎ����Ē����̒n�ʂ�s���̂��̂Ƃ���B�@ |
|
|
��(5) �G�g�A�����U�߂�
���ēV�˓I�Ȑl���炵�̖��l�Ɖ]��ꂽ�G�g�́A���̓ƍَ҂ł������M���̌p���҂���F�ʂ����߂Ă������B����́A�L�b�������x���Ă����G���Ɨ��x�̎��ɂ��K�R��������Ȃ��B�M���̓��F�ł��������_�����ɂ���Đ��̕��m���a�������B�X�ɍH���A�n�d���A�o�����Z���琬���āA���{�S�y�ꂵ���G�g�����A�V���ו�����ނ�̐��b���������ׂɍX�ɐ킢�����߂���Ȃ������͈̂��ʂƉ]���悤�B �X�ɂ͓V���\��N(��܋��)�̉āA�u���͂��҂͕K������v�̊i���ʂ�A�V�̏����̋ʂł��������j�E�ߏ������������S�������ƁA���}�͑S���Ɂu������v�̏����ƌR�D�����߂����B ���a�R�\�㖜�̗̎�ƂȂ����Γc�O���́A�����߂��s�Ƃ��đ���̐��k�̎����ł߂錘�銮����簐i���Ă������A�����m���� �u���̑O�ɂ��ׂ���������v�Ƌ��Ɖ]���B �����߂��� �u�ƍN��������������āA�₪�ēV����_���ׂ�����̑g�D�I�Ȉɉ�R���̊m���ɓw�ߎn�߂��̂́A�M���̈ɉ�U�߂ɂ���ĘH���ɖ������E�ҒB���A���ɏ������o���Ĉȗ��̖�]�ł���B���������č��ۂ͖����̑ו����ł߂�ׂɂ��A�����Ȗ������ߊ댯�ȊO���R��h������O�ɁA�֓���܁Z���̓����łڂ��Ēu�������L�Ƃׂ̈ɐ挈�B�v�Ɛi������Ă�������ł���B �R���@���ɒ��b�E�O�����u�������m�v�̋w���ʂ�G�g�̓{��ɂ����ꂸ�����͐����Ă��A�u�喾�����菟��v�̗~�]�ɔR�������f�h�̑喼�B��A���c���U�߂ɍۂ������z���グ�������̍H���R��A�ĎO�\�������ꖜ���ł����W�߂ĐH�ƗA���ɑN�₩�Ȏ�r����������v���Z�B��V���Ă͒u���Ȃ��B�܂��ނ�Ə\�ܖ��߂������ȏ�̍ŐV���̏��e��������N���R���̐�w������Ȏ��Ԃ��n�߂�B ����ɂ����ʏ\�Z���̋���Ȗ��쉮�邪�����ɂ��ďo�����A�����E��x�܂ł��x�z����Ƃ��鑾�}�̖�]�͉ʂĂ����Ȃ��R���g�����Ă������B�@ |
|
| ��5�@�ߌ��̒��N�o���@ | |
|
��(1) �G�g�A���U�߂̏���������
�G�g�̑嗤�����̖�]�͐M���Ɏd���Ă���������v�����O�肾�����B�֔��ɏA�C�����V���\�l�N(��ܔ��Z)�ɂ͐鋳�t�����ɌĂт��A �u���˂̐g����ō��̒n�ʂɏA�����\�́A�V���ꂵ�đו��������点�A��E�G���ɔC���A���N�Ƒ喾�𐪕����āA���̖����㐢�Ɏc�����S�ł���B��R��n�C������ׂɑ����̌R�D��p�ӂ����Ă��邪�A����͏[���ɕ��������m�D��ǂɗ��B�̐��v��p�ӂ���B�ܘ_���̑㉿�͖]�ݒʂ�ɗ^����B�v�Ɩ����Ă��鎖�ł�����A�Ȍ㒅�X�Ƃ��̏�����i�߂Ă���B �G�g�͕��ʍ��ӂƂ��A��ɓG�̓�{�ȏ�̕��͂�p�ӂ���̂���ł������B�܂��P�ɕ��݂͂̂łȂ����U�߂Ⓑ����͍��ŏ����ė����B��������n�Ɛl���������s���A�S���ł���Ȃ����ǎd���ɐ����o���ʑӂ��҂͑��̘A�ѐӔC�Ƃ��A���Q�l�͂��ׂĒǕ����s���铙�������B �e�喼�� �u�C�����̔˂͏\���ɂ���D��ǁA�Y�S�˂ɐ��v�\����p�ӂ���A�o�����␅�v�̓c���͑����ōk�삳���čr�ꂳ�����A���v�ɂ͓�l�}�m�ƉƑ��蓖���o���B�A�����S�����҂͈ꑰ�܂Ō������߂�₤�v�Ɖ]�����ו��ɋy�Ԃ��̂ŁA�R�̑m��ʖ�Ƃ��A���a�җp�̌R��Q�s�����铙�ׂ̍��Ȕz���܂Ō����Ă���B �G�g�̒��̂ɂ͏\���ő�D�O�ǁA���D�ܐǂ̌����𖽂��Ă��邩�炻�̐������ł���D�S�ǁA���D�S�\�ǂɒB����B�D�ꂽ���D�Z�p�����F�쉈�݂̍`�X�ɂ͒������E�����ĐV�{�`�����ł��S�ǂ��z������������B�@ |
|
|
��(2) ���{�R�A����̏���
���\���N(��܋��)�����A�����R�̕Ґ����������A��w�͏����A������\�l���A��w�͉F�쑽��Z���A���쉮�{�w�ɂ͓����\�����ݐw���A�����O�\���ɒB�����B �R�����R�́A��S�A�x���A������̊C���o�g�͏��Ȃ��A�����A�e��痤�����Ă��ꖜ�ɖ����Ȃ��̂��v�����������B��S�R�̓��{��(�S�h)�̂悤�ɑS���O�Z���~�Ј�Z���A����S���\���C�Z����������D�ł������A���̓��e�͐�͂Ɖ]�����A���D�ɋ߂������Ɖ]����B���E���̓S���͑������������M�����t�Ɏ����Ȃ���A�G�g�͂�͂�R���̊k���甲���o���Ȃ������炵���B �O���ɓ���ƏG�g�͖��쉮�Ɍ����B�l���n�߁A�H�Ƃ͌\���l���̗p�ӂ��������B����������� �u�嗤�ɉ��ē�\�����q�̂����ށv�Ɖ]���G�g�̌��t�ɗE�ĊC��n�������A�����s�����n�߁A�o���ɕs���̏������������B �x�����P�͌x�őD�𗦂��A���t�i�̋�S�×��̕Иr�Ƃ��Ċ���B����̒|�����̊C��ɂ́A�l�c�����炪�G�͌ܐǂ߂������ɂ����O�����̖���������A�C���̐킢�ɂ͔��h�̐��ÁA�Í��̍��݁A���R�B���������������B ��G�g�́A���P�ɖk�R�ܐ�������A�����Ɋ���������ď܂��A�͂���\���Ŏ�s���邪�������ƕ�����L���V�ƂȂ� �u�V�c��k���Ɍ}���A�G����哂�֔��Ƃ��A���{�̊֔��ɂ͏G����C���ė\�͔J�g�Ɉڂ�v�Ƒ����ł���B ���N�R�̔s���͉����B���{�R�̐����ƕ���̗D�G���ɔ�ׂāA�������̕��s�Ɩ��\�ɕ���A�u�����̈����ɋꂵ�ނ����{�ɂ��v�Ɖ]���҂��ߗ��ƂȂ����G���̒��ɂ͂����炵���B�]���āA�����G�g�Ɉٖ��������Ɋւ��鍑�ۓI���o���D��ċ���A���Ɏɑ��閯���I�M�d����A�O�r�ɂ����Ɩ��邢���Ԃ����܂ꂽ�����m��Ȃ��B �R���c�O�Ȃ��瓖���̓��{�Ńg�b�v�̎�Ƃł������������|�Ȃǂ� �u���{�ł͎͈炽���A���Ă�����ŁA��i�Ȃǂ͖��ł͂Ȃ��v���ɐ�]���Ċ؍��S�������l���Ă����悤���B�@ |
|
|
��(3) ���{�R�A�s�킪����
���w�̉������������R�ɏ㗤���A�l����\���A���̐V���̎�s�������c�B�ɓ������B������w�̏��������蓖�莟�早�D������Ă���̂����ē{�����B �u���Η��\�����ׂČ��ւ���B��ʖ�������ɐl�v�Ɏg�������Ȃ�ʁv�ƕz�����A���ڍs���ɋ����R�c���Ă�����ł���B ���̐����ł����؍�������u�S�㊯�v�Ƌ����ꂽ�B��M����z���̈��h�z���ƌĂԏ��Ȃǂ͐�]�̕����Ƌ��ɓ��~���A���{�̐V�����e�����n�Ő������ēG�̐�͏[���ɋ��͂����B���̖��������P�Ɖ��߂ċA�����A������M��(����)�������ꂽ���ŁA���݂����̎q������緂̗F�����Ŕɉh���Ă���炵���B ����́u�_���v�ƌĂ����{�R�̉��i���������B�������킢�͑����B���̑�R���؍�����������B�܂��؍����R�̗��w���Ɖ]���������A�S���̋T�b�͂���͂Ƃ���S���\�ǂ̑�͑����o�����Ė҈Ђ�U���n�߂��A��ǂ͈�ς����B ���ϓ����o�������ނ�͂₪�āA�ʉY�ɏ㗤���Ă��������A�x�����̌\�]�ǂ����Ē������̑D���ɖҗ�ȖC����������B�s�ӂ�ł��ꂽ���{�R�͑�}���őD�ɋA��ƕK���ɐ�����B����ǂ��T�b�̖͂C�Ɏ��X�ɉ��サ�A�n�߂Ĕs��Ɖ]���ɑł𗁂т��B���P�͎��̟��쉫�C��ɂ͋T�b�̖͂C��������ēːi���A���C�u�`���q��̗͓��ɂ���ēG�����܂ł���������Ɖ]���P���W�J���Ă���B �R���Z���̓��Y�̐킢�ł͋T�䐨����s�B���㐅�R�̍��Y�E�����ʔV���펀���Ď��\�]�D�������A�S�Ő��O�ɑh�삩��삯�����x�����ɐh�����ċ~����Ɖ]���S�s�������B�G�g�͑傢�ɋ��� �u���R�P�Ƃ̐킢�������A�K�����C�����Ő킦�v�ƌ��������B�T�b�D�ɑR���ׂ���C���S��ƒe�ۂ𒋖錓�ƍs�Ő������A������n�C���Ďw������Ƃ����B �����ɂ́A�ՎR���C�킪�W�J���ꂽ���A��C���͂��ʏ�ɏd�Ȃ�s��Ɍ����ł����e���������S�A������Ƌ��������Ƃ炸�P�Ƃœˌ������B���ׂ̈ɕ�͂���ĒזœI�ȑ��Q��ւ�A�~���Ɍ�������S�R�����͓��{�ۂ̔�����܂������ŕS�]�ǂ������B����Ő��C���𗛏w�b(*1)�Ɉ����Ă��܂��A��ނȂ��A���{�R�͊��R�Ƌ��ϓ��ɓ��n���瑱�X�Ƒ����ė����O�S��̋��C�Q��z�����ĂЂ�����琨�ɗ��B�J��ȗ��̖��l�̍r����s���}�i���Łu�_������v�Ƌ����ꂽ����R���⋋��ŊJ�邩�������i�߂Ȃ��B �� (*1) �肵���B���\�E�c���̖����̗������N�̏��R�B���N���R�𗦂��ē��{�R�Ƃ̐킢�Ɋ��A���{�R���ꂵ�߂��B���̌��т���؍��ł͍����I�p�Y�ƂȂ��Ă���B�@ |
|
|
��(4) ���{�R�A������
�܂������̑�R���쉺���ĕ��߂��U�����A��ǂ̕s�����Ă��������s�������̒��Ҍh�Ɣ邩�ɘa�����ɓ������B����͋��炭�n�߂��狤�ɏo���ɔ��������Γc�O���̈ӌ������Ă̎��ł��낤�B �㌎�ɓ���ƁA���ւ������R�͕S�Z�\�]�ǂŊ��R�ɔ�����{�R�͐�痤��C��œG�̎i�ߊ��瑽���̏��m�ƕS�]�ǂ����j�������A���{�R���`�ɂȂ��ł����D���̔��������Ĕs�F��[�߂�B �܂���G�g�̖���Ƃ��ċ���ɓ��������O�����J��́A���{�ŕ������i�C�̗ǂ��Ƃ͑�Ⴂ�̌��n��ɁA�O�r�ɗe�ՂȂ�ʂ��̂��������B�����ŏ���������ɏW�߂ČR�c�̌��ʁA�i���͕��߂Œ��~���������ł߂鎖�Ƃ����B ���̏�ōs���ɖ��Ƃ̍u�a�𑣐i���������A���\��N(��܋�O)�̐����ܓ��A�˔@�Ƃ��ė��@��(*1)�̗������w�ܖ��̖��R�������̑�C���J�o���ďP�����A �u�킢�����f�ՂŐe�����v��ׂ����v�Ƃ̐M�O���������Ə�Ɍ��_�𑱂��Ă��������͕��߂��̂ċ���ɑދp�A�ɒ��قɐw���������B ����ɂ����O���͎叫�E�F�쑽�⏬����������č�����������A�����̌ܖ��ɑ��ނ͓�\���̑�R�ł���B���ւ������@���͓��{�R�͋��������������̂ƍl���A�ӋC������C�ɕɒ��ق̑����ɋ��i�߂�B ���{�R�͖ҏ��E���ԏ@���w�ɗE�҉ʊ��ɐ킢�A�����G�̐�N��זł������B�����������{���𓊓�����ƁB�����E�����엲�i�͍��E�����͂��A�F�쑽�{���͗��Ԑ��̌������P��������A���R�͘Z����z����呹�Q���ĉB���@���������炪�畽��ɒH������B ���̈��Ő�ӂ�r���������R�͍u�a��]�݁A�H��̎R�t�ł��钾�Ҍh�炪�u�a�g�Ƃ��Ė��쉮�Ɍ������B�������G�g���� �u��N�̊����B����̖�����{�̍c�܂Ƃ����N���q�Ƒ�b��l���Ƃ���v���̏�����˂������ق��ق��̑ԂŋA������B �� (*1) �肶�債�傤�B����̕����B���\�̖��Ŗ��R�𗦂��āA���{�R�Ɛ�����B�@ |
|
|
��(5) �L�b�G���̒a��
���{�R�͖��̉����閘�͐�����k�����A�����͌�ւŋA���x�{���Đ�͂̏[�����v�鎖�ƂȂ����B���Đ������ւ������S�\�̖x�������E���ґ��̑����������ČܕS�Z�\�Ɍ������A�h�����ċA�������������ɋꂵ�ގ҂����������A�Y�X�͈��D�̋C�ɂ݂����Ɖ]���B �X�ɑ����A���}�G�g�Ɗ֔��G���̊Ԃɂ͐[���a���ł��Ă����B�ƍَ҂������G�g�͑��}�ƂȂ��Ă����̌��͂���������ƈ���A�G���̘V�b�ؑ��헲��Ȃǂ� �u����ł͂܂�ŏ���l�`�ɉ߂��ʁv�ƌ��C����Ȋ֔�����藧�Ă�B �����A�G���͕��l�������l���Ȃ̂́w���{�L�x�w�O����^�x�w��������x����M�����Ē���Ɍ����Ă��鎖�ł�����A���N�o���d�Ƃ��Ĕ����A��̏��g�G�������N�Őw�v��������߂��݁A�ĎO�̑��}�̓n���ӌ��ɂ��]��Ȃ������B �����Ė�����̊֔��̒n�ʂɂ������炸�A����ɂ��̐��i���r��A���e����c�̑r���ɂ����⒃�m���A���Ɣ��i��瑊�o���s���Â��A������ɓ��X���܂��点�Ă����B ���X�̈��]���J�ɗ���钆�ɕ��\��N(��܋�O)�����A�G�����a�����Đl�X�͐�H�����j���� �u����Ŋ֔��a���ŖS�v�Ɲ������B�@ |
|
|
��(6) �G���̎�
���Ŗ��쉮����A���ė����G�g�͓��{�̓��G���ɗ^���A�G���̖����ȂƂ��Ď��̓V���l�ɂ����悤�ƍl�������A�G���͉����悤�Ƃ����ʁB �G�g�͏ł��ĕ��\�O�N(��܋�l)�t�ɂ͋��ɋg��̉Ԍ��ɗU�����Ƃ����m�����悤�Ƃ������A���͂�������e����L�b�Ƃ̕����_������̖{�����M�炪 �u�G���͑��}�̎q�ł͂Ȃ��v���Ɛ������邩��A����Ɖ]��Ȃ��B �܂������\�l�N(��܋��)�̏t�A�\�Ð쏄�����̑�a���[���G��(�G���̒�)���Ɛb�ɓ���n�̒J�֓˗��Ƃ���ĕώ����鎖�����u�������̂́A�����e���������炵���B�����ċA�����Ă����������Ղ͉����l�������u��N�̕����v�Ə̂��ďo�Ƃ��č���R�ɓ����Ă��܂����B ���Ǒ�a�S�����p���k�q���₦���B���쉮�ɑؐw���Ă�������莟�����X���ւ�ؖ]�������e���ꂸ�A�S�R�ɂ͓�\���ő��c�������������B�R������ŏG�g�̐g���͏G���ЂƂ�ɂȂ��Ă��܂��A�ꐧ�҂̏G�g�����߂���Ă�����ɏG���̗��s�͈�i�Ƃ̂萢�l�́u�E���֔��v�Ɖ\����B ���\�l�N(��܋��)���ĂɂȂ��Ė��̍u�a�g���k�����o���������A�G�����|���g�K���̐鋳�t�� �u�G���͎��q�ł͂Ȃ�����L�b�̐��k�͗]�����Ȃ��v�ƍL�������O���̎��ɓ������B �G���ɂ́A���˂ēV�c�ɒ��N�o�������~�߂ĖႢ�����Ƃ��A�ї��P����喼�ɐ������o�����Ē��������߂Ă��铙�̕s���ȏ������� �u���͂�����Ă͒u���ʁv�ƁA�O���͏G�g�ɕ����B���{�����G�g�́A���Ɋ��E�܂̏�������B �����ɓ���Ƌl��g�𖽂���ꂽ�O���Ƒ��c���ٖ��������A�G�g�ɂ��̏�������ʁA�G���͍���R�Őؕ��ƂȂ����B���x�̎����̎���́A���͏G�g�̑����������e���E��b�̖��E��̑�ŁA��������G���̑����ƂȂ��������ɁA���낤�������Ƌ��ɏG���̏��ɂׂ͂��Ă�������m�������炾�낤�B ��̔@���{�������}�́A�O�\�]�l�̍ȏ��c�����O���͌��Ŏ���͂ˁA���X�ɎE���˂ɓ������ނƉ]���M���ȏ�̑�c�s���������B�S����l�X�� �u��X�߂ł�����ׂ������ɂ��炸�v�ƖL�b�Ƃ̑O�r�ɕs��������n�߂�B ���Ă̏G�g�͐l���E�����������ŏo���邾����������������A�l������������B���ꂪ��̑�ꖺ�͂Ƃ��������̏��q���܂ŎE���Ƃ́A��q�������ɗ�ÂȔ��f���o���Ȃ������悤�ł���B���̎����͑傫�ȉЍ����c���A�O������ؕ�s�Ƃ��Ă�������l�C�𗎂����B���Ƃ��ׂ��������̂́A����ɓ����ďG�g������A�F�a�������̓Ɨ��喼�ƂȂ������Ղ݂̂Ɖ]����B�@ |
|
|
��(7) �G�g�̎�
���g���Ăї��������̂͌c�����N(��܋�Z)�㌎�ŁA���̍������G�g�̗v����������� �u�����ē��{�����ƈׂ��v�Ɖ]�����傾��������A�G�g�͓{���V�����L�l�ōĐ��𖽂���B ���喼�͐킢�ɔ����Ă������V���l����G�g�̖��ɔw�����͏o���Ȃ��B�c����N(��܋㎵)�ꌎ�A�����ƍs�����w�ɏ\�l���̏����͍ĂъC��n��A���P���V���̈���D�ɏ悶�Ă��̌x�łɓ����J���Ă���B ����͗��w�b�������̂킴�Ɨ������㗤�������^���ĉ����ɏ]�킸�s�ꂽ�B���w�b�͂��̍߂����Ĉꕺ���ɍ~������A����ĉ��a�Ȏ錳�ς����t�������̂���ɍK�������B���[�̓��A��̗����鐅�R�����R���P�������̂̐܂���̗��ɋꂵ�݁A�������ɏ㗤���������t�P����đ呹�Q���o���A��ӕs���̍߂Ŏ�͏�Y�ɏ�������B �����Ď����\�ܓ��ɂ͐�e���ɐi�U�������N���R��O��I�ɑ�s������C�킪�W�J�����B�����A�x�����͋��ϓ��̓��Ë`�O�ƊC���ĉ����ĖҔ�����W�J���A�Z�S�ǂ̐V�s�D�ŌF����o�����đ��P�����s�����B ���t�E��A�ȉ�����̏�������ł��A���{�R�͓�S�ǂɒB����G�D�߂�Ɛ폟�ɓG���̎����킢�ő���n�߂��B�S�s�ɋ����������͍Ăяw�b���N�p���������ǂ͈�������B��R�̑��Q���ܖ������Ɖ]���A���݂����s�̖L���_��(*1)�Ɏc�鎨�˂ɖ��߂�ꂽ�G���̐��͏\���ɋ߂��Ɠ`�����A�킢�͈�i�ƎS����ɂ߂��炵���B �����Ă��̔N�̏\�ꌎ�A�������̒��N���̖����E���w�b�����^�������A�I�×��̐킢�œ��Ð��Ƒ匃��̖��A�����ɑł������A��������d������v���� ���N���R�̃z�[�v�E���̎��͏��m�̎u�C�ɑ傫���������B�����A�����痤��R�̋��������͏_�炢�����A����ł����̒��ɂ� �u���߂ē��{�̔���������t�ۂ�ł��玀�ɂ����v�Ɖ]���c���đ��₦��҂����āA���̎����҂͔������z�����Ɖ]���B ���̂悤�Ȓ��Ɍc���O�N(��܋㔪)�̔N���������B���쉮�őѐw���ɕa�ƂȂ�A�A���×{�𖽂���ꂽ����莟�̕a���Q�������Ɍ������Ɖ]���̂ŁA���鉺���t�߂��Č������B��������N�̉��݂œB�Â��ƂȂ�A��킵�Ă��鏫���ɂƂ��Ă͐����̎G�ςǂ���ł͂Ȃ������B �܌��ɓ����ē����A�e��炪���R�����ׂ̈ɋA�����ׂɁA���P��̐h��͈�i�Ƒ����B�����Ĕ������A�S�R��������������ߕ����ꂽ�B�ƍَґ��}�G�g�̎��ł���B �� (*1) ���s�s���R���a��H���ʒ������B |
|
| ��6�@���}�A���Ə���@ | |
|
��(1) ���̓V���l�͒N��
�c����N(��܋㎵)�����A���˂āu�䂪��u���p�����͎̂O���v�Ɠ����������ė����Γc�������オ�ĎO�Ђ߂�̂��������A�ƍَҁE�G�g�͍Ăђ��N�o����f�s�����B���̏G�g���a�ɐN���ꂽ�̂́A���t�B�����ɂ߂����̉Ԍ��̌�ł���B ���˂̐g����V���l�ɐ���オ��܂Ō�铂����g����������ɁA�ƍَ҂ƂȂ����H�ƍr���̌����s�����������A���̋}���ȘV���������炵�����B�܂��́A���N�ɋy�Ԓ��N�o���̐S�J����i�ƏG�g�̎��𑬂߂��Ɖ]���悤�B �c���O�N(��܋㔪)�̔~�J������Ă�����ɉ����̒��������ʌܑ̂��܂��A���������̉p�Y���ĂыN�����Ȃ����o�̗��̖K����o��A�Ȃ̏d��Ȍ�Z�ɜ��R�ƂȂ����ɈႢ�Ȃ��B �u�l���炵�̖��l�v�Ə̂��ꂽ�ނ̎������ɁA���`�ʂ͂��Ă��Ă���̒�ɓV�����̖�]��R�₵�����Ă��铿��ƍN�̐S���́A��������悤�ɖ��炩�������B ���ƂȂ��āA�u�i�e�����đ���ς�v������̂菬�c�������ɉƍN��f�łƂ��ė͂Ő����ׂ��������Ƃ��A���N�o���𖽂��Đ�͂����Ղ�����Ηǂ������A���Ɖ���ł���̍Ղ�ł���B �u�V���͗͂���҂̓V���ŒP�ɓV���l�̎q�Ɖ]�������ŕۂĂ鐢�łȂ��v�Ɣ����Ă��Ă��A�G�g���֔��̍��ɏA���Ă����\�N�ɋ߂��A�ܑ�V�A�ܕ�s���̖L�b�����̑g�D���o���Ă���B ���Ƃ��G�������l����܂ł��̊����B�����͂��Đ����ɓ����Ă����A�����͈��ׂł���B�����ŏG�g�̖ڂ����������� �u�ƍN�����ނ����Ă��̎q�E�G�N���V�ɔ��F���A���̒�E�G���ɂ͓���Ƃ𑊑������A���̓�܁Z���𗼎҂ɂ킯��v ���̎��}�Ō�̖��Ƃ��Đ��s����A�Ɖ]���̂��O���̔��Ƃ��]����B ����G�N�͌����ŁA�O���Ƃ��e���������B��ɉƍN���G���ɉƂ��p���������A �u�Ȃ��Z�̎���u���Ē�ɏ���ꂽ���v�Ɩ₢�A �u���}�̗{�q�ɂ��������v�ƕ����� �u����ł͎��͖L�b�G���ƌZ��ł���A�Ⴕ�G�����E�����Ƃ���҂�����A���͑��ɓ��邵�A�����܂ł���������Ēf�Ő킢�܂��v�Ɖ]���������̐l���ł���B�G���̂悤�ɏ]�������ŁA���U�A���ɓ��̏オ��Ȃ������j�Ƃ͌�������Ă����B �G�g�S����A�V����]�ފ�ʂ̂�����̐l���͉ƍN�ł���A���͏G�g�̐M�������O���A�ނƊ̒_���Ƃ����㐙�̉ƘV�E���]�����A�G�g�̌R�t�Ƃ��Ċ��Ȃ��炻���v�Ⴓ�������������ꂽ���c�@���A�����Ă��̏G�N�������Ɖ]���B �ނ��ɉ�V���̗��Łu����������v�Ɖ]�������q���ق����Ƌ����ꂽ���������� �u�ƍN�͂����ʼnƐb����������̂�m���B����Ȋ�ʂœV����������̂��v�Ə����������B��Ë�\�ɕ�������� �u�����ƍN�������������炻�̐K�ɋ��Ēf���Ĕ������z�������ʁv�ƑO�c���ƂɌ�������x���N�Ŏ��l�B�R����̘_��D���̃L���V�^���M�k�Ɖ]�������E���������������Ă��������l�ӂ��悤�B�@ |
|
|
��(2) �G�g�A����
�R���c���O�N(��܋㔪)�̔��ɂ͏G�g�̋C�͂��s���ʂĂĂ��̍�𛉍s�ł��Ȃ������B�����������̂��܂��ĕ�����ɏ��喼���ĂсA�͂��Z�̎q�E�G���Ɉ�����������A�O���Ɍ��� �u���߂ďG�����\�܍ɂȂ��č����̓����}����̂U�̊y���݂ɂ��Ă������A�V���͂ǂ��ɂ��Ȃ�ʂ�v�Ɨ܂𗬂����B�����Ď��[�̓��ɂȂ�ƏG�g�͍ĂщƍN�ȉ��ܑ̌�V�A���V�A�ܕ�s���ĂяW�� �u�G���l�ɑ��ē�S������ʁv�|�̐������������B �W�c���ʼnƍN����������Ƃ����̂����A����ł����S�o���Ȃ��B�����ɂ͉ƍN���ɏ����� �u���̕��Ƃ��v���A�c���G���̖ʓ|�����Ă����悤���ݓ���v�Ɛ�P(*1)���G���̉łƒ�߁A�����̏�ɂ���Ė�]��������Ƃ����B �����Ĕ����\���� �u�Ԃ����������G�����ƁA���藧����悤�A�^�ɗ��ݐ\��A���c�ɂ�����v���M�ɘZ�\�O�Ő����������B������ ���I�Ƃ����@�I�Ə����ʂ�@��g���ȁc�c �Œm���Ă��邪�A���� ���I�ƎU��@��(������)�Ə����@���̒��ɁA���Ǝc���@�S�Ȃ���B �̋傪�������Ƃ̐�������B �q�ւ̖ӈ��ɋ������ނ̖��H�ɂ͉p�Y�̖ʖڂ͑S���Ȃ��B�V���l�Ƃ���遂�A���F�ɓM��āA��X����������鎖��Y�ꂽ�j�̈��ꂳ���g�ɂ��݂�B ���炭�G�g�͘V���̉ʂɃ{�P�Ă����ɈႢ�Ȃ��B�����Ȃ���ΑO�ɏq�ׂ��悤�ȖL�b�����̑���v��f�s���ĉЍ����������A����Ƃ��V���͗͂���҂̎x�z�ɔC���Ė����̑ו����v��̂��V���l����̔C�ƒB�ς��A �u�V���̎��͂��ׂĉƍN�ɔC����B�B�G�������l��͂��̊�ʂɉ����Đg�̗��悤�ɔz�����Ă���Ė]�����v�Ɖ]�������A���喼�͖ܘ_�A�k����(*2)�A���N(*3)����ĂяW�߂��ȂŖ������I�R�Ǝ����}�����ɈႢ�Ȃ��A���̎�{�͒O�H���G(*4)���g���Ȃċ����Ă���B �� (*1) ����Ђ߁B�L�b�G���E�{�������̐����B���͓���G���A��͐�䒷���ƐM���̖��E���s�̖��ł��鐒���@�B (*2) �L�b�G�g�̐����ł������˂ˁB (*3) �L�b�G�g�̑����B�{���͐�䒃�X(������ ���Ⴟ��)����ѐ��e�q(������������)�B��䒷���̖��B��͐D�c�M�G�̖��̂��s�B�D�c�M���̖Âɂ�����B���ꖅ�ɍ](�����@�A����G������)�A�q�ɏE(�G��)��������B (*4) ���G�̍Ŋ��́A�ɂޕ�����������ŁA��������o���Ƃ����s��Ȃ��̂������Ƃ��]����B��a�S�����Q�ƁB�@ |
|
|
��(3) ���j�͓�������炸
�c���O�N(��܋㔪)�H�A������������ɂ������ɁA���l���ǂɒB�����A��������萋���A�o���R���`�Ɍ}���ɏo���Γc�O�����ݑN���̘J���˂��炢 �u�����Ƃ͑����邪�A�܂���コ��G���l�₳�ꂽ��A�̍��ɋA���Đ�o�������A���H�Ɍ�㗌������B���߂͒���ł��݂��܂��傤�B�v�Əq�ׂ�Ɖ��������� �u�M����͒���ł����ł��낤�ƍD���Ȃ悤�ɂȂ����B���͖�펵�N�A�J�͂������s���ʂĂĒ��������Ȃ��L�l���Ⴉ��A�B���ł��i���悤�v�Ɣ�����ċ���B���}�̎r�₦�ʊԂɁA�q���̑喼�B�̊Ԃ̕����h�ƕ��l�h�ɑ傫�ȍa���o���Ă�����������B�X�ɑ吭��(�����˂�)�Ɨ��a(�������X)�Ɖ]���ȂƏ��̑Η�������ɖ��𒍂��ŁA���ɂ͖L�Ƃ̖ŖS�ƂȂ����Ɖ]����B �����̓�\���ɋy�ԏo�����m�̒��ł̎����͌܊��ɋ߂��Ɖ]���B��̓��{���R�̃��[���ł́u�S�Łv�ŁA���{�S���ɋA��ʕ���v��҂���тĖ���ʖ���߂������l�X���@���ɑ����������Ƃ��낤�B ���̒��Ɏ�ɑ���āA�M���̒����̊ɑ��E�G�M���ɉ��������ˊo�O�ꑰ�͐험�i�Ƃ��č��풃�q�\���ɓ��Ƃ������A�����B�����āA���炭�ǍO�̎w�����낤�B�L�b�G���A����ƍN�A����莟�̎�Ɋe�܌����サ�Ă���B �V���Ɉ�˒��q�ŕ���������̖{�Ƃ��I�i�����ɂ������������ȕi�������ɈႢ�Ȃ��B�����ƍN�́A���ɔz��Ƌ��ɁA���̈���u��ˁv�Ɩ����Ċo�O�ɕԂ����̂����ɑ�]���ƂȂ����炵���B ����������̍����B�͏��c���̒莟�̓@�ɉ������Đؖ]���A�G���Ɍ�ĉ������ꂽ�҂����āA�㐢�܂œV���̖���Ƃ��ė���ɂ܂Ŏ����������ƂȂ��Ă���B �R���A����͑S���̓���ŁA���N�o�����@���ɓ��ؗ������ɔߌ��������点�����͊��S�N���ւ������A�؍���K�˂�Ζ��炩�ł���B �G�g�����{�����̐��V�˓I�p�Y���������͊ԈႢ�Ȃ����A�ނ̑��݂ɂ���āg�ꏫ�����炸�����͂�h�Ɖ]���ߌ�����{�S���̒ÁX�Y�ɔg�y���������܂����j�I�����ł���B�u�×�������l����v�̎����S�ɂ��݂�B �����ČJ�Ԃ����A���E�j��W�]����Ζ����̋������ɂ͑�p�Y���o�����āu����Ȏ��Ȏ咣���ȋ^�S�A��͐_�̎q�̐M�O�ƁA�ʒm��ʖ����Ɛ����~�v�ɂ���āA�V����������@��g�D�I�ɋ�g���A�܂����Ƃꂵ�A���ɍ��O�ɐN�U����̂����j�̏퓹�ł���B �����ɂ͕K�������Ǝc�s�Ȏ�������������B���E�ő�̒鍑�����������`���M�X�n�[���͎l�\�̖�����łڂ��O�S���l���F�E���Ƃ��A���P�ܕS��D���ĉ䕨�Ƃ����Ɖ]����B���̑��N�r���C�́A�䍑���x�܂ł��N���A���̖��̂܂܁A�ցA���A�؏\�������Δn�A���A��B���P���Ė����E�������B�u�Í���v�̖��́u�ނ��肱���聁�ނ����v�Ɖ]���Ì�݁A�₪�Đ_���Ɖ]����䕗�ɂ���ĉ�ł����B �G�g�̐N�U�͂��̔����Ƃ��]���A������H����Ƃ���Ñ���j���㐢�ɐ��ꂽ�����Ř_���鎖�͂ł��Ȃ��B���j�͓�������炸�A��ɗ͂����`�Ȃ̂ł���B ���������A�l�핽����`�̐��܂ꂽ��ꎟ���E���Ȍ���A�X�^�[�����͎l�疜�l���E���A�q�b�g���[�͔��S���l�����Y�����Ɖ]����B ���������X�^�[�����ɂ���Ė��B�͒n���Ɖ����A�e�����߂đc����K��钆���c���ǎ������\�N�̌��݂����邱�Ƃ��Ȃ��A�܂�U���B�X�ɂ͕s�@�ɒD��ꂽ�k���̓y��肪�����������Ȃ̂�����A�Ƃ�G�g�݂̂�ӂ߂�͍̂��Ɖ]���悤�B�@ �@ |
|
| �����j���� [����ƍN] | |
| ��1�V�����ڂ̐킢�@ | |
| ��1.1 ���ߏ�̗͓l�@ | |
|
��(1) ���{�S�y�̑����͈ꔪ�܁Z����
�c���O�N(��܋㔪)�����A�G�g���c���G���̑O�r���v�������A���c��ɂ����������������A�u���}���n�v�ɂ����{�S�y�̑����͎��̈ꔪ�܁Z���ɒB���Ă���B ������� �\�� ���@�@�@�@ �\�ܖ��� �_�Ё@�@�@ �\�O���@(�v�@�l�Z����) ���� �@�L�b�@���Z���� �@����@��܌ܖ��� �@�ї��@���Z���� �@�㐙�@���Z���� �@�O�c�@�@ ���㖜�� �@�F��c�@������ �@������@�ܓ� �@���|�@�@ �l���� �@�ɒB�@�@ �ܔ����� �@���Á@�@ �܌ܖ��� �ȉ��O��Z�Ɓ@���O�Z���@(�v�@�ꔪ��Z����)�@[ ���v�@�ꔪ�܁Z���� ] �M�����{�\���œ|�ꂽ���A���̎x�z�n���l�S���Η]�ɉ߂��Ȃ����������v���A������̐퍑������ו��̐��ɂ�������́A��͂�G�g�������Ɖ]���悤�B �����ނ��嗤���e�ȂǂƉ]���M������̖���������A�����܂œV�c�̐b���ł���֔��Ƃ��Ė����̑ו����߂����A�L�b�ꑰ�Ǝq���̑喼�B�̈�v�c���ɐS��z��Ȃ���L�b�����̑g�D�����ɓw�߂�A�Ⴆ�G�����c���Ă��͂��O�N�ŕ���Ƃ����S�߂Ȏ��Ԃ��������͂Ȃ������낤�B�@ |
|
|
��(2) �O�c���ƁA����
�����Čc���l�N(��܋㔪)�ꌎ�A�⌾�ɂ���ďG������Ƃ��đ���Ɉڂ����O�c���ƂƁA������ɂ���Đ�����C���ꂽ�ƍN�h�̑Η����������B����͍��܂ŗ��`�҂Œm���Ă�����V�M���̉ƍN���A�����ɂ���Ē�߂��|�����X�j�������ׂł���B�����m�������Ƃ�� �u�ƍN�̉��\�����������͏o���ʁv�ƌ��{�����B ��X�_������� �u�ȂĘZ�ڂ̌ǂ�����ׂ��A�S���̖����ׂ��A��߂ɗՂ݂Ă͒D���ׂ��炸�A�N�q�l���N�q�l�Ȃ�v��M���Ƃ��闘�Ƃ� �u�G�g��������̍ۂɁw�G���̎��ЂƂ��ɂ��肢�\���x�ƌJ��Ԃ��ꂽ�̂������ĖY��͂��Ȃ��B�v�Ǝ��������ĕ����Ɍ��������B �R�����Ƃ̕a�d���ƌ����V�ԂȉƍN�́u�҂ĂΊC�H�̓��a�v�ƍl���A�t�Ɋ��҂��ċA�����B�G�g�̑��V�͕��A���Ő���ɋ��s���ꂽ���A������I���Ĉ��S�������A���Ƃ̕a�͈�i�Əd���Ȃ����B �[�O���O���A���Ƃ͉�S����O�N�ȓ��ɑ嗐�u����\������ �u�����A�����Z��͊e����̕��𗦂��đ��Ƌ���ɕ���ċl�߁A�G�����ɖd������҂������̕��͒����ɑ��ɒy�����A���ƂȂ�Ē������߁B�����͎O�N�Ԃ͑����ȁv�ƈ⌾���A�G�g�̎���͂��������ŗF�̐Ղ�ǂ��悤�ɐ����������B�@ |
|
|
��(3) �Γc�����A����_���A���a�R�ɋA��
���Ƃ����ʂƁA�҂��Ă��������A�����畐�f�h�� �u���N�ŎO�����̖ڕt�����s���ȕ��������瑾�}���玶�ӂ��ꂽ�B�z��ɕ���点��v�ƎO���ɔ���B ���`���̋����O���� �u���ł��Ȃ��\�������B�����͏�l�̖��ł���A�ڕt��̌��o����������ʂ��Ƃ͏��m�̔�����v�Ɠ˂����˂��B���̂��߁A �u�O�����E���Ă��܂��v�Ɖ]�������ɂȂ�B�̑��}�� �u���ƈ��������v�Ƌ����Ă����ɈႢ�Ȃ��B ���̌v���m�����O���̕��F�̍��|�A�F�쑽�A�㐙�������ċ삯�����B������������}�Șb�����ɗp�ӂ�����Ȃ��B�O���͐��Ɏ����o�債�ĉƍN�̓@�ɏ�荞�݁A�h���Ⴆ�Ă��L�b�̉Ѝ���f����Ƃ����B �����̍����������ƍN���܂����Ƌ������낤���A������K�̖{�������ĕ��l�h���������Ē��ɓ���A�O���ɂ͕�s�����E���č��a�R�ɉB������悤�ɖ�����B �O�����Ȃ̎��r�����A���̌�̂��Ƃ��C�ɂ��������̂��낤�B���������ɒ��]������㐙�i����ɑ��k�����B����ƁA�i���� �u�����������ÂɋA�邪���x�͗e�Ղɏ㗌���ʌ��ӂ���B�ƍN�͋��炭�����̕����N�������B�킵���苭������Ă��錄�ɋM���͑��ɏo�ėF���W�ߋ��������v�Ɨ͋������B ������ĎO�����傢�Ɋ�ьł���������Ԃƕ��������邪�A���̑O��A�����m��ʓ����߂� �u�������a�R�ɋA����A���Ɗ������ɂɓ��̕�����������A�ƍN�@���P��������������ǂ��߂ĕK����������Č����\���v�Ƌ����i�������B�������O���͏㐙�Ƃ̖��������ē��ɂ��k�炳���A�فX�ƍ��a�R�ɋA���Ă���B �A�����O�ɒ��]���������カ���Ă̊w�ҁE�������|��K�˂� �u�p��}�X(*1)�A�͌Ð��̌��ƕ����܂����A������������s�������o���܂��傤���v�Ɛq�˂��L���Șb������B����͐₦�X����Ƃ���L�b�Ƃ��~���Ɖ]���Ӗ��Œ��]��O����̔ߊ�ł����`�����ł��������B���A���|�͖ق��ē����Ȃ������Ƃ����B�������Ɖ]���Ζ��̂Ȃ��̂������Ă�������ł���B �� (*1) �������ӂ����B��ł���Ƃ��鉤����r�₦�������A�X�����鍑��������B�w�哂�V��(���\��)�x�L�b�Ƃ������A�����}���邱�ƁB�@ |
|
|
��(4) �㐙�i���ƐΓc�����A����
�c���l�N(��܋㔪)�㌎�ɂȂ�ƁA������䕨�Ƃ����ƍN�� �u�O�c�Ɛ�삪�ƍN�ÎE���v�����v�Ƃ̉\�𗬂��đO�c�����𑛂����Ă��B�����m�����O�c�����M�����̎��j�E�O�c�����͈⌾�ʂ茈������сA���a�ȗ������ꎞ�͂��̋C�ɂȂ����B �R���v�̈⌾��Y��A���Ƒ厖�̕�̌��t�ɏ]�����B�Ђ�����ӂ��A���l���ɂ��ĉ���S���̈��ׂ��v�����̂����A���Ƃ���Ȃ��b�ł���B ����ɖ������߂��ƍN�́A���c���ܔN(��Z�Z�Z)�ɓ���ƁA���͏㐙�����ɂ�����B�l���ɖd���̋���g��h�����������Ă����A���˂ĎO���Ƃ̖���ʂ蒅�X�Ɛ���𐮂��Ă����㐙���͌������͂˂����B �u�G�������������V���l�ƂȂ낤�Ƃ����l�̖��͓���܂�����v�ƌ㐢�ɓ��x�h��(*1)���A�փK����v�ɉ������ނȂ����������ƌ��܂������̎莆���ƍN�ɒ@�������B ���{�����ƍN�͘Z�����Α����o�w���Ėk�サ���B�����m�����O���� �u���ߓ����I�v�ƗE�ݗ����A��������A��ÍU�Ɍ����Ƃ���e�F�̑�J�Y�������a�R�ɏ����ĉƍN�œ|�̌v���ł������A�s�͂�����B ���カ���Ă̐헪�ƂŒm��ꂽ��J�� �u���������ɂ��ď��Z�Ȃ��v�Ƌt�Ɍ������߂����A�O���� �u�L�b�Ƃ̏������v���Ύ��͍������Ȃ��B�㐙�Ƃ̖�������茩�E���ɂ͏o���ʁv�Ə���Ȃ��B���ɎO���Ɛ��������ɂ���o������߂���J�͎��̓�𒉍����Ă���B �u��X�A�`���}�ɂ��������ȑԓx�����߁A����̋������ї��A�F�쑽��叫�ɕĎ����^�Ԏ��B�܂��q�b�ˊo�ɑo�Ԏ҂͂Ȃ����A�E�f�Ɍ�����_�Ȃ���v �����茵�������������̂��A���N�̐e�F�Ȃ�����ł������낤�B �O�����f���Ɏ����X����ƁA�邻���ɏ����Ă����ї��̐��m�E�������������ĖȖ��ȍ��v������グ���B �v���Ԃ�ɑ��Ɏp���������͎̂����\�Z���ŁA�v�炸�����������D��ŋʑ��̍א�@�����シ��̂�ڂɂ��Ĝ��R�Ƃ���B �� (*1) �Ƃ��Ƃ݂��ق��B1863�`1957�B�W���[�i���X�g�A���j�ƁA�]�_�ƁB���x�b�Ԃ͒�B�@ |
|
|
��(5) �א�H�ցA�h�킷
�����ē�����(�����\�Z��)�A���[�āE��˗ǍO�́A�א�K���V���v�l(*1)�̕v�ł���א쒉���̋����{�Ï�ɂ����̂��s�v�c�ȉ��ł������B �Ɖ]���̂́A���̔N�̓K���V���̕��ł��閾�q���G�̏\������ɂ�����A���˂ėǍO�� �u���}�ݐ����͉ʂ��Ȃ��������{���A�����悤�Ɍ��|(�א�)�A�P��(���)�Ɠ�����������l�ŐS�䂭�܂Œ����������v�ƕւ�����Ă������A�H��(*2)������ �u�V���̖����ł���V�m�����ŋ��{�̒�����J�������v�Ƃ̕Ԏ����͂����B ����ň�˗ǍO�́A�����q��(���q���G)�̖����ł���Z���\�O���ɗ\�肵�ė����ς肾�����B�����������Z�\�����߂����N�����ɁA�܈��������ׂɐN����A��J���x��̎����\�O���A�F�삩�����ė������q�̑O���ċ{�Â�K�ꂽ�B �҂����˂Ă����H��(�א쓡�F)�Ɨ������鏼�̍����ɒ�����݂��A�Ă̖����������G�̖������F��������ł������B �����Ĉ������߂���܂܂ɑ؍݂��邤���A���ʑ���˓@�ł̎����̋}�������̂͏\�����̖邾�����Ɖ]���B �u���R�̏����̍Ȏq��l���ɂ���v�Ƃ̎O���̖����������߂��ꑫ��ɑ��ɓ���A���X�����������A�ؒÐ�ɏM�ԏ���݂��Č����̐��������A�א�@���͂��ċ����ɕv�l�B������ɘA�s����Ƃ����B ���˂ĕv���� �u�܂����̏ꍇ�͌������A�א�̖��������ȁv�Ɩ������Ă����Ȃ̋ʎq�͂��������ŁA���狏���E���}�����Ăɋʍӂ𖽂��A�c����l�̎q�Ƌ��Ɏ��n���ĉʂĂ�B �}�ւɂ���Ă����m�����H�ẮA�{�Â�̏�����Ă��A�ܕS�̉Ɛb�Ƌ��ɕ��ߓc�ӂɂ���O��\�̖{����ď邷��B ���������Ă����̕����l�Ƃ��ċC�܂܂ȓ��X�𑗂��Ă����ǍO�́A����������ɖ�������C���Ȃ��������A���n�ɗ������ꂽ�V�F�����E���ɂ͂ł��� �u���܂ꂽ����ɂ�A�~�肩����̕���ɂ�Ȃ�ʁv�Ƒ��q�̑O��Y�}�B�ɂ����ʂ��܂߁A�H�Ă�⍲�����B�͂��ܕS�̘V�c����A�ߕӂ���y�������m�F�̑m���v���X�X�̔z�u�ɂ��A�h�폀���ɖz�������炵���B �� (*1) ���q���܁B���q���G�̎O���B�א쒉���̍ȁB�L���V�^�������Ƃ��ėL���B�������ɃL���X�g���k�炪�]���čא�K���V���ƌĂԂ悤�ɂȂ������A���̎����͕v�w�ʐ��ł���A�{���͖��q��ƌĂԂׂ��ł��낤�B (*2) �א쓡�F(�ق�����ӂ������A��̗H��)�ƒ���(���������A�א�K���V���̕v)�̕��q�́A�D�c�M���̖��ɂ��A���q���G�ƂƂ��ɒO���B�M������O�㍑��^�����A�{�Ï�Ɠc�ӏ�(���ߏ�)�����Ăĕ��q�͒O����B�{�\���̕ς̌�A���F�͔�����ĉB���ƂȂ�H���|(�䂤��������)�Ə̂��c�ӏ�ɏZ�ށB�א�H�ւ́A���@��ˌ��m�`�Ɋw�сA�g�X������O����|�p�̈���A�|�n�̎��c�M�x���瑊�`�����ȂǁA�����Ƃ��ďG�łĂ����B���ꂾ���łȂ��A�Ⴍ���ĉ̓���A�̂̓����w�сA�u�Í��`���v���Ęa�̂̓`�����p���A�����A�����A���ȁA�����Ӓ�A�L�E�̎��Ȃǂ�����w��A�|�\�̉��`���ɂ߂�B���㐏��̕��l�Ƃ��Ă��������A���|�Ɋւ��鐔�����̒��q���c���B�@ |
|
|
��(6) �א�H�āA�����������ɏo��
�Γc�O�����א�v�l�̔ߑs�ȍŌ���Đl���ɂ��鎖�𒆎~���A�ї��叫�A���c���ɐ����č���c���J�����͎̂����\�����ł���B �悸�\�O���ɋy�ԉƍN�̕s���ȍs�ׂ����e������ӏ����e�喼�ɔ����ċ`��Q�������߂�B�����Đl��������R�ɂ��͕̂K���Ǝv���镑�ߏ�̍א�H�āA����̑O�c��������܂߁A���̍������肵���B ��A���c�G�Ƃ����Ƃ��A�Γc�O�����Q�d���Ƃ����w�l���ŕ�����𗎂��A���Z�A�ɐ��ɐi�ށB ��A���ߏ�ւ͏����ꖜ�ܐ�A�O�c�ɔ�����J��O����k���ɐi�߂�B �O�A���叫�E�ї��P���A�Q�d���E���c������l���͑��ɍݐw���A����ƍN����̍ۂ͑S�R�𗦂��Ĕ��Z�ɐi���킷��B �����ɉ����ĎQ�W�����喼�͕S��\���A���̕��͂͏\�����l�B�\���ʼn]����S���ɒB���A�������V�����ڂ̑升��ƂȂ����B�͂���\���̕����E�Γc�O���̕K���̊������܂ő吨�������̂ł���B����͓����̑喼�B�̑唼���A���l�h�̉�����������āA�ƍN�̖�]�݁A�G�g�ւ̋`���тʂ���Ƃ���O���𐳘_�ƌ������炾�낤�B �����āA�O���ɂ�������ĕ��m�R���E����،�����叫�Ƃ���ꖜ�ܐ�̑�R���Ђ��Ђ��ƕ��ߏ���͂����B�C���̉J���~�炵�n�߂��͎̂�����\����������Ɖ]���B�����m���� �u�K���V�����L�b�G�����̖���f���ɕ�������Ȏ��ɂ��Ȃ�Ȃ������낤�ɁB���m�̎q�͋`�ɂ���Ď��ʂ̂���ł���ƁA�c�Ȏq���h���E���Ď�������Ɖ]�����A�G�����̖��ɏ]���̂����̋`�ł��낤�B�͂Ă��ċC�䂷����ł����������̂���A���G(�ǍO�̑��q)�̍Ȃɂ��悤�]���Ēu���ɂ�Ȃ��ȁv�ƁA�ǍO�͓��S�����v���Ȃ�����A���̑���̎w�����Ƃ�h��Ɍ����ƂȂ����炵���B ���R�̊��̒��ɂ͗H�Ẳ̓��̖�l������A�i�ʉ��݂̂���͂����Ȃ��B�܂����[�Ă̐e�����喼�������炵���A���ɂ͋�e�ł��`���Ő키�܂˂����Ă���������Ă���҂��������Ɖ]���B ����ł�������������ď邪�ꂵ���Ȃ�͓̂��R�ő叫�̗H�Ď��g�����n��̍I�݂Ȑl�������ɐF�X�Ǝv�Ă̖��ɒ���̔����{�ɑ� �u�Í��`���̉��`�����̂܂ܐ₦��̂��c�O�łȂ�܂��ʂ̂ŁA������\�������v�Ɖ]���g�҂��o�����B ����������e���͒��g�ƂȂ��ď��K�� �u�a�c������ŏ���J���v�Ɛ����ꂽ���A�H�Ă� �u���l�̖{�ӂɔv�Ƌ���ň����̂����v�����̂ŁA�������d�����R�ꖜ�ܐ炪�A���߂����������邱�ƂɂȂ�B�@ |
|
| ��1.2 �H���߂��@�փ��� �@ | |
|
��(1) �x�����P�Ƌ�S�×��́A���R�E�Γc�����ɕt��
�����Ŏ�����u���A�ɐ��̉��݂ɓ]���悤�B �×�����A�F��̊C���ŗL���ȌF��ʓ��̒����ł���x�����P�A��S�×���́A���˂Ă�葾�}�G�g�̉��`�Ɋ����Ă����B������ �u���}�͖��邭�Ă��l�D���ȊÂ������������A�ƍN���͑�K�ʼn��Ƃ��̂̒ꂪ����ʋ��낵���j��v�Ɗ��C�������Ă���̂�����ƁA��������̔������ނ��o���ĎO���̞����ɐU���������B�����F�씪���i(*1)�̎��Q����n(*2)�Ƌ��c���A���R�̐��R�w�����Ƃ��Ē����ɉ����D�c�ɏ悶�Ďu���A�ɐ����ʂɖk�サ���B���ꂪ������̍U�����n�܂����c���ܔN(��Z�Z�Z)�������{�ŁA���N�o���Œb����ꂽ�����̎m�C�͍��������B �₪�� �u�������E���������͗�ؑ��O�Y����������v�Ɖ]���N����B���s�̎q����蕿�𗧂Ă���ŁA��������x�����P�̒��q�E�s����͈�i�ƗE�ݗ����A��������ƍN�����̕�̋`���E��S�×��ɐs�͂�����ƒ��H�`�ɓ���B ���N�̏H�A���H�̉×��͍q�s�ł̎��ʼnƍN�ْ̍�Ɍ��{���A�吺�œ{��U�炵�āA���ɋA���Ă���B�����ĉƓ𒄒j�E�痲�ɏ���A�������ɂ�ł�������A���P�̗v�������������B�痲�̗����a���Ă�����ƘV���ꊅ���ď��D���ƁA�x���A�������q���Ɛ��R��Ґ����A��D�c��A�˂Ĉɐ��ɐi�ݒÏ���߂����B �� (*1) �펁�Ɗϐ��ꑰ���Q�ƁB (*2) �����݂���߁B�F�씪���i�B�Γc�O���Ɏd���A�}�g�Ƃ��Ă���ė����B�@ |
|
|
��(2) �Γc�����A���ӂ��r��
�����Ŗk�̉�Ð���߂�A���R�̍��͐�ÁA�㐙�i�����ƍN�̑�R�Ƃ����Ղ�l�ɑg��Ŏ苭������Ă���ԂɁA����ŎO�����������k�シ�閿�����B �i��������Ɋ�Â��A���͌��Ɏl���̕����W������B���|�`��͎O���̕��𗦂��ĒI�q�ɐi�݁A�ƍN���S�{����z������Ăɕ�͍U��������𗧂Ă��B ������\����A�ƍN�̖{�����]�˂����̂�m�������|�͂��̏��O���ɋ}��B �u�㐙���͗E��A���͏�̓�v�Č��Ō��킵�A���̍ہA��R�͓G�̑�����ɑł���v�Ƃ����|��`���ė����B ��������ĎO���͑傢�ɗE�ݗ����A�����ܓ��ɂ͐M�B�̐^�c���� �u�܂����Z�ɐi�݊��[���Ƌ��ɔ����ɏo���v������ł���v�ƕĂ���B���������ɂ͍��|�ɓ��l�A���v���`�� �u������ɂ��ƍN�����낽�������A�����ƎO�͂̊Ԃɂē����ʂ��ׂ���v�Ǝ��M���X�ł���B �R���o�w�O��̏j���ł� �u���K��A�]���s���ׂ̈ɓV�^�Ɋ��킸�Ƃ��A�L�Ƃ̒��b�Ƃ��ēV���ɖ��������Ď�������ւ����Ȃ��B�w�������ɂ��炵�A���l�݂̊Ɏ~�߂�x�Ǝv�����e�X�͔@���Ȃ���v�ƌ���� ���}���]��@���ԂɂƂڂ��@⾉ƁA���ɏ����䂭�@��g�Ȃ肯��B �Ɖr�����A�����Ɏ������߂� �����͖쌴�A�g�͋����Ȃ�́@�Z�Ƃ��ȁB �Ɖ����A�ꓯ�͑傢�Ɋ������Ăǂ�߂����Ɖ]���Ă��邩��A�ߑs�Ȍ��ӂł������悤���B�@ |
|
|
��(3) �Γc�����A��_��ɓ��邪�A�㐙�i���́A������
�������Čc���ܔN(��Z�Z�Z)���������A���a�R�ƌZ�ƎO��̏��m�Ɏ�点�A�O���͌ܐ甪�S�̕��𗦂��ďo�w�����B�����\���A���Z��_��ɔ���ƁA���E�ɓ������ɋ`�������ď�𖾓n������B�^�c���� �u�َq�����ƔZ�B�ɍݐw�v����A���̌��̋V�A�ƍN���̂��̏\�l�o���Ƃ���S������ׂ��A�����Ɠ����ʂ��\����v�ƈӋC���炩�ɕĂ���B �������k�̐�ǂ͔ނ̎v�������ʏƂȂ��Ă����B���R�̐��E����G�������㐙�̑����̒n�A���͂����Ɖ]���n�_�ɂ܂Ŕ�����������\�l���̂��ƁB���R(*1)�̉ƍN�� �u�����喼�A�����Γc�ɎQ���v�Ƃ̒��������̋}�g�����������B�����ċ}���A�]�i��������ꂽ�̂ł���B �F�s�{�Ɍ���G�N����c�������R�́A���������獋�J�����A���X�Ɛ���������Ĉ��g���n�߂��B�����m�������]�R��猓���⍲�|�`���́A�����ɒnj����Ĉ�C�ɏ��R�̉ƍN�{�w��˂���ƌi���ɔ������B �����ӊO�ɂ��㐙�i���� �u������G��ǂ��̂͏㐙�̉ƌP�ɔw���v�Ɣ������]�� �u����ł͎O���Ƃ̖���ɔ�����A�`����营��f�s���ꂽ���v�ƍ������A���|���܂������v���������i���͂ǂ����Ă����m���Ȃ��B �O�����A���]��i���̐������^�킸�A��_����ɐi�܂�Ƃ��Ă������B�i���͉�ÂɋA��A�`����Ɨ͂ł͏��Z�Ȃ��Ƃ�ނȂ����˂ֈ����g����Ɖ]�����ԂƂȂ��Ă����̂��B �� (*1) �Ȗ،����R�s������1����1-1�ɁA�u���R�]��Ձv�̐Δ肪����B�@ |
|
|
��(4) ����ƍN�A���]���A�ɐ��h�q�𖽂�
����Ƃ͒m�炸�x�����P��F�쐅�R�͈��Z�Âɔ���B������𗎂����ї��G����̗���R�̎O�����A���c����鎭�z���փm�n�����狴�{�܂Ői�݁A�S�ɖ����ʗ��琨�ɊJ��𔗂낤�Ƃ��Ă����B �����������Ώ�͊ȒP�ɗ����Ă����낤�ɁA���R�œ]�i���������ƍN�́A�����ɒÂ̕x�c�M���⏼��̌Óc�d����ɋA���h�q�𖽂����B �������{�A���R�������̔ނ�́A�O�͂��珬�D�S�]�ǂɕ��悵�āA���Z�Âɋ}�q���ė����̂ł���B �C��ꡂ��ɗ����Ɠ쉺���ė���x�c�����������R�́A�܂����ƍN�̔E�ҌQ���܂��U�炵�� �u�ƍN�}���㗌�I�v�̕����ɋ����Ă��������� �u����I�ƍN�̑�R������ė������v�Ƃ���Ăӂ��߂����B ��w�̒������Ƃ�������b��(*1)�͉��a���ɂƂ����A��A�ɏ悶�Ċփm�n���܂ő��ދp�B�����m�������P���� �u�s�b��Ȃ����������߁v�ƌ��{���ĊC�ォ��U�����J�n�����B����ɗ�܂��ꂽ���R���Q���U���ɓ]�����͔̂������ł���B �܂����O���͕�������(*2)�A���c����(*3)��ҏ��B�����X�Ɛ��F��ɏW�����n�߂��̂�m��A���̕����ɉ����𑗂�B����Ƌ��ɋ}�g���F�쑽�G�Ƃɑ��点�A�ɐ��H�̏��������}��_�ɏW��������悤�ɗv�������B���A�����ɒx�������B �� (*1) �{�\���̕ς��Q�ƁB (*2) �ӂ����� �܂��̂�B�ꂪ�L�b�G�g�̏f�ꂾ�������߁A�c�����G�g�Ɏd����B�˃��x���{���̕M���i�ŁA�L�b�Ƃ����Ă̗E���B ���Γc�O����ƒ��N�o�����_�@�Ƃ��Ă��̒�����C�Ɍ����ɁB�O�c���Ƃ̎���A���F�̉��������Ƌ��ɎO�����P������Ȃǂ̎������N�����Ă���B����ƍN�Ɉԗ�����A�፧�喼�̈�l�ƂȂ�B �����R�]��ł́A�ƍN�̈ӂ������c�����ɂ��炩���߉��_����Ă����������A���������ƍN�̖����ɂ����Ƃ�B���R�̐D�c�G�M������U�߂ł́A�r�c�P���Ɛ�N�𑈂��A���c������Ƌ����ŏ���ח�������B�փ����̐킢�{��ł́A�F�쑽���ƌ����B �����A���|�L���ˎ�(50����)�ƂȂ邪�A�ƍN����܂��Ȃ��̌��a5�N(1619�N)�A�L����̈ꕔ�f���C�������Ƃ���A�M�Z�����ˎ�(4��5000��)�ɉ��Ղ��ꂽ�B (*3) ���낾 �Ȃ��܂��B�փ����̐킢�ň�Ԃ̕�����������������A�}�O������52��3000��^�����A���̏���ˎ�ƂȂ����B���͖L�b�G�g�̌R�t�Ƃ��Ďd�������ŗL���ȍ��c�F��(���낾 �悵�����A�����q�A�@��)�B�@ |
|
|
��(5) ��͗����A�Γc�����A�����ɔ��Z�����W���Ăт�����
�������{�ɂ́A���ɕ�����Ėؑ\���n���������A�r�c��l���̓��R�͑勓���Ċ�ɔ���A���C�̐D�c�G�M(*1)���ď������V�b�B�̈ӌ��� �u�M���̒�������҂���������������Ă�̂͂��̖��������v�Ɩؑ\��݂Ɍ}���������̂̏O�ǓG�����s�����āA�O�q�w�̒|�K�@�⌢�R�����X�ɓ��R�̎�ɓn�����B �܂����ɐ��̐��R�͈��Z�Ï�U���̍Œ��ő匃��ƂȂ������A����̔����͌��������e�̕v�l�܂ł����n�̊Z�ɕЊ�����U���ĕ��킵���Ƃ����B �D�c�G�M���s�����������������{�A����Ɠ�m�ہA�O�m�ۂ𗎂Ƃ������A�L�b�т����̍���̖ؐH��l(*2)�����ɓ����ĊJ��ƂȂ�A��̎���͎��P��ɗa����ꂽ�B �����̏j�u��������ɂ��Ȃ��A��_�̎O������ �u���R�勓���Ċ�ɔ���B���R�͋}�����Z���ɎQ�W���ꂽ���v�Ƃ̋}�g���͂����B�F�쑽�G�ƈȉ��̏����͍Q������_���߂����ďo������B�O���͑��̋P���ɂ� �u�}���o�w���đ��w�����Ƃ��Ė]�����v�Ƃ����|�̎g�҂𑖂点�Ă���B�������A����͎g�҂ɔC������������ɒy�����ċP���̎�ɓ�����Ă�������o���ׂ��ł������낤�B �ƍN���O���̊��{�𗦂��č]�˂����̂͋㌎���������O�����O���𗣂�đ��ɋ}�s���P����������ċ��Ɋփ����ɓ�������ɂ͏[���Ԃɍ��������ŏ��s���ł��̋@���������̂����헼���ォ��傫�Ȍ�Z�ƂȂ�B �� (*1) ���� �Ђł̂ԁB�D�c�M���̒��j�A�D�c�M���̒����B�c���͎O�@�t�B���A���[���ł������̂Ŋ��[���Ƃ��Ăꂽ�B (*2) �G�g�̋I�B�������Q�ƁB�@ |
|
|
��(6) �ƍN�A�l���̌R�𗦂��Đ��F�ɓ�����
���āA���ߏ�͍א쐨�̗͓l�ŁA�J���J�����ւĂ���Ƃ��ď�͗����Ȃ������B�G�̕�͖Ԃ������߂āA�ǍO�͈ɉ�o�g�̘Y�}�ɔ��Z���ʂ̏���@�����A�H�ĂƐ헪����荇�����B �u�g���Ȃ�Ζk���̑O�c�Ɍ�������J���ƁA�������͂��Ă��鏬��ؐ��̍��v�O�����A�����ɌÑォ��̊X���̗v�n�g�s�j�̊ցh�ɏW�����ē��R��҂������邪�̂��v�ƒQ����A�H�Ă������� �u���l�X�X�B�����ĉ����̊���ɐ琬�Z�\�Ɨc���G�������o�n�肢�A�����̌��������Ȃ���̓V�����ڂ̑��Ɏ����߂Ή]�����͂Ȃ��B���������Ȃ���݂��ɔN�v�̔[�ߎ��ƂȂ낤�āB�n�b�n�b�n�b�v�Ɛ������킹�đ���A����ɂ����Ɖ]���Ă���B �H�Ă͂��̊o������Ɏ��߂Ȃ���A��̒�ɂȂ锪���{���Ɂu�Í��`���̉��V�v����i�̎�Ɏd�|�����̂�����t���A�͂��ȘV�㕺�œ�J���߂����~���J��������L���Ă����B���̂����A�V���̖���E�邪�A�b�Ɖ]���Ԃɗ������������R�̏����̉��a�������������B������𗎂Ƃ���������G�H(*1)�͈ꖜ�Z��𗦂��Ă����炢������B���N(*2)�̖����E���ɍ���(*3)����Ï���Ă��Ĕ�����|�������̂��㌎��{�������B �ƍN���߂̋L�^�ɂ����̍s���� �u�㌎�\���A�M�c���B�C�ӂ̑��X�l�A�܃P�����サ����A���ɂ͎��ɔ��˂̖��͂肽���S�×��̑�D�S�h�ۂ�I�R�ƕ��т���B����ĉƍN���͈�̋{�����Ԃ��A���F��ɓ����v�Ƃ���B �ƍN�͎l���̌R�𗦂��Đ��F�ɓ��������B���̕�́A��_��̖k���E�Y������ւ��Ă��ԍ�ɐi�o���Ă������R��w�̎m�C�����߂��B�������͊փ����̏h����Ă��ĉƍN�������B �� (*1) ���₪��Ђł���(�͂��ЂłƂ�)�B�G�g�̐����E����@�̉��B�����͖ї��P���̗{���B�H�ďG�g�̗{�q�ɂȂ�H�ďG�r�ɁB��A�G�g�̖��ŏ����엲�i�̗{�q�A�G�H�Ɖ����B ���փ����̐킢�ł͐��R�ɎQ��B����ɁA�������瓌�R�Ɠ��ʂ��Ă����Ƃ�������B���A���R�̉F�쑽�G�Ɨ̂ł��������O�Ɣ���Ɉڕ�����A���R��55���ɉ����B ��2�N���1602�N�Ɏ����B���N21�B���k�ɂ��A������Ƃ͒f��B (*2) ���}���Ə�����Q�ƁB (*3) ���傤�����������B�ߍ]�Ő�䎁�̉�������v���������勞�Ɏ��ɐ��܂��B ���L�b�G�g�̑����ł��閅(���q)��A���a�̖��ł����(��䏉�B�퍂�@)�̎�����ŏo������������u�喼�Ƃ����₩�ꂽ�B ���փ����̐킢�ł͋���̑�Ï�ɍȂƂƂ��ɘU����A�ꖜ���鐼�R�������t���փ����ւƌ����킹�Ȃ������B���̌��ɂ��ዷ���l�ւƕ������A���Ɏ��̍ċ����ʂ����B�@ |
|
|
��(7) �Γc�O���A�ї��P���ɑ����o�w���������
�l���̌R�𗦂��Đ��F�ɓ��������ƍN�ɔ�ׂāA�ї��P���͈���Ɏp�������Ȃ��B���R�̓��h�͉����ׂ����Ȃ��A�����⍕�c�̗U���Ŏ��X�ɓ��ʂ��鏫���o���炵���B �ł����O���́A�㌎�\���A���Q����n�ɍ��a�R���琅�H��Âɋ}�s���đ��ɒy������悤�������B�ї��P������ �u�ƍN����̕��������ς�Ȃ�B�}���G������ďo�n����S�R�ɉ��m����v�Ƃ̈ꏑ�������� �u�K�������ɏo�w�����悤�����v������v�Ƃ����O�������A��n�����̐ӔC�̏d�傳�ɐg�̈������܂�v�����������ɋ}�s�����炵���B ���˂ĎO���́A��J�̍��v��Ɋ�Â��A�փ����̓���ނ��鏼���R�ɖL�b�G���̖{�c��u���R����\�z���ł������B ���܂���_���ӂɏW�����������̐��R�ŁA���R�ƑΎ����Ă��̐i������~�߂�B �����ɕ��߂𗎂������m�R�̏���ؐ��ꖜ�ܐ�ƁA�ډ��A��Ï�U���Ɍ������ї����N�A���ԏ@�̈ꖜ�ܐ�𗎏鎟��A�փ����̐���ɓ�����B �������āA�₪�ē�������ł��낤�P���̕�G�����ȉ��l���ܐ�����̎R���тɕz�w�����A�铪�ɐ琬�Z�\�̑�n���|���Č����W�J����B �Ɖ]���̂����̑�헪�ł���B �O���́A�㌎�\����t�̎莆�ōĂё��c����(*1)���� �u�]�Z�̋��ɒz���������R��ɂ́A�����O(�ї���)�����u����ׂ��䕪�ʂ����A�ނ�������B�v�Ɨ͐����Ă���B ����͐���A���Q������ɑ��点�A�P���ɑ����o�w����킹�A�����������̂� �u�����_�����c���ƍN�ɓ�������炵���v�Ƃ̉\����сA������P���̍������Ȃ��������߂ł���B �u�P���A�o�n�Ȃ����A�ƍN��炴��Ηv�炴�邩�Ƒ����ǂ��A���X�͍��V�s�R�Ȃ�Ɖ\�������B�܂��M��(���c����)�ƉƍN�Ƃ̊Ԃɐl���͎E���ʖ���A�ׂɑ�R�𗦂���G�H�����ʂ���ƓG���͗E����R�A���̂܂܂ɂĂ͗�����ʂ����o���邩�Ǝv����ɂ��A���������u������v���ƐF�X���������Ă���̂ŁA�O���̋�J������B ����ɂ��Ă��ڂƕ@�̊ɉƍN�{�R���������Ă���̂�m��Ȃ��������R�̏��Ԃ̗���Ȃ����ɒQ�����B���ɂ��̕�������Â̓��R�ɒD���đ��ɓ͂��Ă��Ȃ��B���ɂ����āg�s�^�h�Ƃ����]���悤���Ȃ��B �� (*1) �܂����Ȃ�����B�L�b�����ܕ�s��1�l�B ���G�g���M���̉Ɛb�̍�����d���Ă����ÎQ�Ɛb�B�㐙�i���Ƃ̊O�����⑾�}���n�ȂǂŌ��т𗧂āA�G�g�ɑ�a���S�R���20���̏��̂�^������B���N�o���ɂ��]�R�B ���ƍN�ɎO���̋�������ʂ��A�փ����̐킢�ɂ͕s�Q���ŁA����̗��狏�߂Ă����B���A�ƍN���珊�̂�v�����ꂽ���A�ꖽ�͏������Đg��������R�ɗa����ꂽ�B ��1615�N(���a��)�A����`���Ɏd���Ă������q�̑��c���������̐w�ŏo�z���ĖL�b���ɗ^�������߁A���Q�𖽂���ꂽ�B���N71�B�@ |
|
|
��(8) �Y����̐킢 / ���R�ꏟ �㌎�\����A���ߏ邪�~���J��ƌ������B �����č��X�Ɗփ�����킪�����Ă����\�O���̑��ł���A�ҏ��E���ԏ@��(*1)��ꖜ�ܐ�̐��s�������Ă̑�Ï�}�P��킪�J�n�����B���̓��̂����ɓ�m�ہA�O�m�ۂ��ח��A�\�l���ɂ͍���̖ؐH��l(*2)�̐s�͂ō~���J��ƂȂ�B �R�����̘N��_�ɓ͂��ʋ㌎�\�l���A���˂Đ��R�����͑�J�Y���������ČR�c�̌��� �u�����Ȃ�ƍN���㌎���ɂ͏㐙�A���|�A�^�c��ɎO������U�ߗ��Ă��ď㗌�o���锤�͂Ȃ��B����ċ㌎�\�Z���������Đԍ�̓G��ǂ����đ����Đ��F�֍U�߉����v�ƌ��c�B�������}���ł���Œ��ɁA�㐙�⍲�|�ɂ���܂�Ă��锤�̉ƍN���ˑR��_�̑Ί݂ɂ���ԍ�Ɍ���ꂽ�B�����ė��̕����ɋP������̑�n�W��|��������A�O�������R�Ƃ����炵���B��������������߂́A�����̎u�C���g�ׂ̈ɂ��A�ƍN�̖ʑO�œG��ɑł���v����Ɛi���B �����߂́A�������ɂƋ��ɍY�����n��ƓG�O�ň���n�߂��B���������������h�A�L�n�L���炪����o�Ēǂ������Əo�����ė���B�����U���o���A�U�X�ɑł��j��Ɗ���S���\�]���������B�ӋC�g�X�ƈ��g���A�ƍN�̕@����������������͂����������߂ł������B �� (*1) �����Ȃނ˂����B�����I�q�ˎ�B�̂��ɒ}����͔˂̏���ˎ�B ����B���� / ����(�c��)�͒q�E�ɗD�ꂽ�����Ƃ��āA��F�@�ق����ĖL�b�G�g�ցA�u�`�����ɁA��������̎҂ł���܂���A���Ɛl�ƂȂ����܂��܂��悤�v�ƌ��킵�߂����̕����B�G�g����}������13��2,000��^�����A��F������Ɨ��������b�喼�ɁB �����c������ / �G�g�͏��喼�̑O�ŁA�u���ɖ{�������Ƃ����V�����o�̑叫������悤�ɁA���ɂ͗��ԓ��ՂƂ����V�����o�̑叫������v�ƁA�����J�ߏ̂����Ƃ����B �����\�̖� / ���Ōւ閾�R�����j���A�����엲�i���u���ԉƂ�3��͑��Ƃ�1���ɕC�G����v�ƕ]����قǂ̎��q���v�̊���A�G�g����������q�́B ���փ����̐킢 / ����ƍN���瓌�R�ɕt���悤�ɗU��ꂽ���A�u�G�g���̉��`��Y��ē��R���ɕt���̂Ȃ�A�������������ǂ��v�ƌ�������B9��15���̖{��ɂ͑�Ï���U�߂Ă������߂ɎQ���ł����A���R��ł�m���āA����Ɉ����Ԃ����B������Ă����ēO��R�킵�悤�Ƒ��叫�̖ї��P���ɐi���������A�P���͕������ƍN�ɋ����������߁A���̖̂���Ɉ����g�����B �������グ�鎞 / ���̋w�ł��铇�Ë`�O�Ɠ��s�B�փ����ł̐�ŕ��̂قƂ�ǂ������Ă������Ë`�O�ɑ��u���������N�̋w�D�@�Ȃ�v�Ƃ����藧�Ɛb�����̐i�����u�s�R�͕��Ƃ̗_��ɂ��炸�v�ƌ����đނ����B���Ë`�O�ƗF�b�����сA�����ɖ���܂ŋA��������A����������瓇���A���c�F��(�@��)�ɍU�߂��A�ƍN�ւ̋������������ߎ��g�͏�Ɏc���āA�Ɛb�c�����ŏo�w�B ���փ����� / ���Ղ���ĘQ�l�ɁB���̊�ʂ�ɂ���Ő�����O�c��������Ɛb�ƂȂ�悤�ɗU���邪�A����B�����͒��߁A�H�q�Ƃ��ċ������Ƃ����B����������ƍN����̔M�S�Ȉ��������͒f�������悤�ŁA�܂��Ȃ������I�q��1����^�����đ喼�Ƃ��ĕ��A�B�ŏI�I��3��5,000��m�s���A���̍�����@�Ɩ�����Ă���B �����̐w / �ƍN�͏@���L�b���ɗ^����̂�����āA���̐����Ɍ����ɓ��������Ƃ����B���̌��a6�N(1620�N)�A���{���狌�̂̒}����͂�10��9,200��^�����A�喼�Ƃ��Ċ��S�ɕ��A�B �������̗� / �헪�ʂ̎w���A�L�n��U�鎞�ɂ͐̓��̗E�p���������B���喼�͕��_�ė��ƒQ�܁B �����i15�N(1638�N)�A�Ɠ𒉖ɏ����Ēv�d�E�䔯�B���i19�N(1642�N)�A�]�˖����̔˓@�Ŏ����B���N76�B (*2) �G�g�̋I�B�������Q�ƁB�@ |
|
|
��(9) �Γc�O���A���Â̐\���o������
���R�͋v���Ԃ�ɋ��̂����v���������낤���A�\�����ʉƍN�̏o���ɎO���͋}���g�҂��J�ɑ��点�Ă��̈ӌ������߂�ƁA�Ăя����������ČR�c���J�����B ��_�ď���Ɗփ����Ŗ�팈��_���o�����A �u���R�͈�H���a�R���߂����Đi������炵���v�Ɖ]����������̂ŁA��팈��_�Ɉꌈ������œ��Ë`�O���� �u�ƍN�{�w�ł͉���̍s�R�Ŕ�ꂫ�����炵�������ł߂����肱���Ă���Ɖ]���B����P���ΕK���^���Ȃ��B��炪�����߂�̂��ЂƂ����s���ꂽ���v�Ƌ����v�����������B ��핐���̋`�O�̐\���o�ł���A��ɖn���Ŕނ̐i����e��Ȃ�������������O���͓��f�����B�����Ƌ��c�̏�A�Ăы���ł��邪�A���Q���� �u���ۂ͓��Â̊�𗧂ď��������ʼnƍN�{�w����P�����A���̗���ɏ悶�Ď�͈͂�H�փ����ɒ��s���ׂ��v�Ƃ̈ӌ��������炵���A���߂��Ȃ��^�����Ȃ�����������Ȃ��B ���̖鎵���A�܈������~��o������J�̒��A�邩�ɑ�_��������R�́A�Γc����擪�ɖq�c�����I�Ċփ����Ɍ������B������������(*1)�Ƌ��ɓD�H�ɔY�݂Ȃ���s�R���Ă������Q���� �u���Â炪�ƍN�{�w���P���A���͎R�H�ܗ�(��Z��)����蓙�����A�X���i����͂��ꍏ�Ŋփ����ɒ����g����ȂĘJ��҂Ă��h(*2)���̂��v�ƒQ���������悤���B �� (*1) �܂��Ђ傤���B�O�쒉�N(�܂��̂����₷)�B��ʓI�ɂ́u�����Ɂv�̖��Œm���Ă���B�Ȃ͖L�b�Ƃ̘V�b�E�O�쒷�N�̖��Ƃ���A���̉��œ����͖L�b�G���Ɏd���A��]���l�O�̈�l�Ƃ��Ċe�n��]��A����B �����\3�N(1593�N)�ɏG�����r���A�L�b�������G���������钆�A�u�G�������߁v�ƐM���A�Ō�܂ŏG�������ɓ������Γc�O���Ɋ����B�Ȍ�A�O���ƍs�������ɂ����B ���O�������������ȂǂɏP�����ꂽ�����A�O���𖽂����Ō�q�B ���փ����̐킢�ł͐Γc�O�����̑O�q�����Ƃ��č��c��������c���g�����ƌ���A���x�������Ԃ��Ȃǎ��q���v�̐킢���݂����B������G�H���̗���ɂ�萼�R���s�k�Z���ɂȂ�ƁA�O���̉��ɕ�ׂ��A�G�w�荞�݁A���j�ƂƂ��ɓ����B (*2) ���������Ă낤���܂B�Ȉ�ҘJ(���������낤)�B��͂��������A�G���J�����Ă���U������B�w�O�\�Z�v(�����̕��@���B��҂�������͕s��)�x�@�@ |
|
|
��(10) �Γc�O���A���J�̒��A�n�����đō���
�����ĎO���́A���J�̒����{�R�̖ї��G���A�������A�g��璆���O�ɍ���ō�����B�x�މɂȂ��A���̓�����Ɗփ����Ɏp��������������G�H�̕z�w���鏼���R��ɔn�������B ��ɏ��s�̕���ڂƂȂ鏬���쐨�������R��ɕz�w�������̂͑�J�Y�����̎���ƂȂ�B�������A�Y���Ƃ��Ă͗�����\�����G�H������ɔz��������R��ɒu���āA�܂����̎��̗p�ӂɂ��̎R�[�ɘe��A���A����A�ԍ��̎l�������z�����B���̏�ŁA���ڏG�H�ɑ��� �u���������������V���R�Ȃ�ΏG�g���̗�ɉ�����ׂ��v���Ƃ����X�Ƒi�����悤���B ���߂̈��珬���A�́A�O������ӂ̗g��ʏ������Ō�̓�Ɍ�������p�������� �u�a�͌������疋�̖d���A�J�����щ���ĕ��ׂł��Ђ���˂Ηǂ����v�ƈĂ��Ă��邪�A�s�K�ɂ����̗\�����I�����鎖�ɂȂ�B �I���R�̒��]�䕔�w�ŕ���⾉�ڂ����A�O���������ɔn�����Ă������B �ԍ�̉ƍN�͉��Ƃ����ӂ̖��Ɉ����ނׂ��A�킴�ƍ��a�R�U���̕�𗬂��A���������ɑ�_��̓����������������点��ƁA�����͍s���̔����x�߁A��ꍂŐQ����ł����B �u���R�A�邩�ɏ���o�Ċփ����Ɍ����I�v�̋}�������͖̂锼�ŁA���Ă������A�Ɣ�N�����ƍN�͒����ɏo���𖽂���B ���ɂ͕��������A���c������L�b�q���̛���I�̂́A�@���ɂ��ÒK�炵���z���ł���B �����҂̐����͗E�ݗ����āA�̂��悤�ɕ��������B���A�J�Ɩ��ɉ��钆�R�����}�i���n�߂��̂͌ߑO�������B���R�͒n�̗��͓������A�Z���Ԃ̍s�R�Ɂg����ȂĘJ��҂h����W�J���鎖�͂ł��Ȃ������B�x�X�̐i�������܂ꂽ���Ë`�O�Ȃǂ��A�������肨���ɂȂ����͓̂��R��������Ȃ��B ���������`���Œm��ꂽ�O�������ɁA�܂����L�Ƃ̈ꑰ�ł���A�G�����l�܂Ŋ֔���ꂽ�G�H���y�d��ʼnƍN�ɖ�������Ƃ͎v���Ȃ������̂����R�ł��낤�B�ƍN�̖ڕt���������R��ɔ邻��ł��铙�Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ�������J��O����ӂ߂鎖�͂ł��Ȃ��B�@ |
|
|
��(11) �J��O
�c���ܔN(��Z�Z�Z)�㌎�\�ܓ��A��J�����Ė�Ԏl���]�̎R�H��H��A�Γc�����փ����̏��ւɓ��������̂́A�锼�ꎞ�߂��������Ɖ]����B �r���ŎO�����P�R�A��{�R�[�������g�V���R���������}�h�ɐi�����A���R�̕��w��˂�����ō������B�x�މɂȂ������R�̏�����������˂ďG�����ւ̒�����͐��B��J�w����{�c�ɋA�����̂͒��̌��ŁA���т܂ł��ƂǂɔG��A�O�̐F���Ȃ������B �����ɖ��ɂ��ݍ��ޒɂ݂������Ȃ���A����ł��O���� �u���ׂ����͂�����B��͓V���ɏ]���݂̂���v�Ƃ̖������ɐZ��Ȃ���������ܑ̂ɂ̈�p�ɉ������A�ꍏ�قǃg���g���Ƃ܂ǂ�݁A�閾����҂����B ���łƋ��ɉJ�����B�[�������փ�����т߁A����R�[�̍����R�̐Γc���ɑ������ւ̓��ÁA�r���̏����A�����R�̉F�쑽�A���R������������J�A�����ď����R�A��{�R�ɕz�w�������������]�̐��R�B �����߂����Q����́A�����߂̗߂��� �u���`��h�ɌR�������A�K���̊o��ŕK����������v���ł������������B���A���̑��͊��ɐ��X�̎j�����o����Ă��邩��A�����ł͐��Γc���̊����ɏd�_��u���A���̊����ǂ����ɂ��悤�B�@ |
|
|
��(12) �����߁A���킷
�J��͌ߑO�����ŁA���R�̍ł������ɐw�����Γc�R�Z��̐�w�́A���쉈���ɓ����߁A�k���X�����ɂ͊������ɂ�z���A���̌���ɎO���̖{�w��u�����B ���߂͒��j�E�M���� �u�ƍN�̊��{�܂Ŏa�荞�ފo��œ����I�v�Ɨ�܂��A�蕺����Ĉ��������ɒu�����B��O�̈���͎����炪��������ɑ��A�E�ɍєz������ �u������I������I�v�Ɖ𐁂��悤�ɋ��ԁA���̎w���Ԃ�͐��ɋS�_�̔@���ł������Ɖ]���B ���R�̉E���ɐw�������c�����A�c���g���A�א쒉���A�����������͎O���̎�������Ό������Ƒ����𗊂݁A�W���U����W�J�����B���������̐i�ނ̌������͖ڂ�����݊̂��Ԃ����̐������ʼnƍN�{�w�ɔ��鐨���������B �u���̂܂܂ł͂����Ƃ�����|���˂v�Ɗ��������c�̓S�C�����̐���͖���\���𗦂��ĉE��̋u�ɎU�J���A�җ�Ȓe����߂��炵�č��߂̋r�ɏd����^�����B�������̍��Y���]���ɕ����āA�b���A����ɑނ����B ������������R�̓c�����͗E�ݗ����ēːi�������A�Γc�̑�C���̖Ҕ����ō������ނ���Ĕs���B���̋@�ɏ悶���������ɂ̕���ŁA��������A�ƌ������܁A��������~���ɎQ�����א�A�������̗͐�Őh����������������B�@ |
|
|
��(13) ���ÖL�v�A������
�O���͍��J���̊e�w���Ō����������ɏP���Ȃ��� �u���@�ɓ��R�̉E�����͂��Ĉ�C�ɉƍN�{�w��˂���v�ƑS�\�����𓊂��ĖҍU���A�ꎞ�͐Γc���̖C�e���ƍN�{�w�߂��Ɏ��X�Ɨ��������B�������ƍN�͓���U��ċߐb������������L�l�ŁA�{�������炪���킵�ĕK���ɋ�~�߂��Ɖ]����B �փ����R�L�� �u�G�������������ēS�C������A����т̐��V�n����邪���B�����ɓ������ÈłƂȂ�G�����������荇�������A�܂���A�U�ߐ킢�A���{�����ɕ����Ă�����F�x�ƌ����������v�ƋL���Ă���B �����R�̖{�w���璭�߂�A���F�E��J���́A�փm������z���āA�����A���ɑ��������܂����Ă���B�F�쑽���̐��E���ΑS�o�́A���������A����L�������l�A�ܒ������ނ���E��Ԃ�������Ă���̂ɁA�ׂ�̓��Ð������͖T�ς��Ă���B �O���͍ĎO�g�҂𑖂点�������ÖL�v(���Ë`�O�̉�)�͊�Ɠ����Ȃ��B���ɂ͎O�����g���n���� �u���ɓ��{�{�w��˂���v�Ɨv�����Ă� �u���͊e�����v���̂܂܂ɐ키�̂݁v�ƚ������B����͓x�X�̌��̗p����Ȃ��������������낤�B���Â͂��ĎO������������������ő剶���A���������Ċ��ӂ��Ă���B������ɑ厖�̏�ɗՂ�ŁA���̑ԓx�́A�`��m��҂Ƃ͉]���Ȃ��B �O���͖ق��Ĉ����Ԃ��Ȃ�����A��J�̒������g�ɂ��݂�v���ł������낤�B�@ |
|
|
��(14) �ї��G����������G�H������ɓ�����
����NJJ��ȗ��O���ԁA��ǂ͐��R�D���̂����ɐi��ł���B �u�������T���������ď�����G�H�A�ї��G���A���]�䕔���e���l���Z��ɉ��R�o�������A�ƍN�R�̔w���˂��ׂ��D�@�v�ƍl�����O���͒ɂޕ����������� �u�T�����グ��I�v�Ɩ������B���������R�̏�ɔ��ς̂悤�������V���������������B���ɌߑO�\�ꎞ�Ɖ]����B��ɔ{���铌�R�ɑ��A�P�트����W�J�������ɁA�����R�A��{�R����t�����Ɏl���̑�R���P��������A���R�͑܂̑l�ƂȂ鎖�͕K���������B �R��ɖї��������������ɓ����Ȃ��B�������Ƃ�������b���͖ї��Ƌ��ɐi���������ōāX���̎g�҂𑖂点���̂ŁA�G���͐�w�̋g��L�ƁA�����L�r�ɏo���𖽂����B�������A���˂ĉƍN�ɓ��ʂ��Ă����ނ�́u�����Ə�����āv�Ƃ��u��Õٓ������܂��āv���Ɖ]�����ĂĂ����ς蓮���Ȃ������B �܂������R�̏G�H�������̖��������A�ቺ�ɓW�J�����ǂ͐��R���D���Ȃ̂œ��a���I�ȑԓx�ɕς�A����ɔw���ɏo�Ȃ��B�ƍN�� �u���̏���߂Ɍv��ꂽ���I���ɂ��X�X�I�v�Ƃ�����Ɏw�����Ɖ]���B �����Đ��ɉ䖝���o�����A�ꂩ�����A�R��̏G�H�{�w�ɗU���S�C��ł����܂����B �u�����ԓx�����߂ʂƍU�ߍ��ނ��v�Ɖ]���d���ŎႢ�G�H�����C�Ȑ��i�Ȃ�t�� �u�������̋C�Ȃ��������v�Ɠ{���ē��R�ɍU�ߍ��낤�B �����ɂ�������G�H�͂���Ă� �u��J���̑��ʂ�˂��v�Ɩ��߂����B���������w�̏����n�� �u����Ȕn���Șb�����邩�A�킵�͕������ɓˍ��ށv�Ɖ]���ĕ������A���ɂ͊���܂�A�D�X�Ɛ����������Ɖ]���B�@ |
|
|
��(15) ������G�H�A����
������̈ꖜ����͐���̂悤�ɑ�J�g�p(�Y��)�����P�����B�g�p�͔��Η\�z���ꂽ�����ɘZ�S�̌������ł�������Ƌ~�߁A�t�ɂ��̑��ʂ�˂�������A�G�H���͍����l�S�߂��������A�ƍN�̖ڕt�E�����厡�����������ꂽ�B ���ꗧ�����쐨�����ē��������~���Ɍ�������A�u�G�H���v�ƒm���č����R����e�n�̐g�ɂ��͂����A�Q��������ɒy�����������߂̈������������B��J���̎��������̔��������������A���˂ċg�p���G�H�̗���ɔ����Ă����̂���̐�F�ł���e������A���،��j��ܐ�̕����A����܂��g���t���ɂ��đ�J���ɏP���ė����B ��J���������ɗE�҂Ƃ͉]���A�͂��O��ɉ߂����A�O������̓G���Ă͗͐�ʍӂ��邵���Ȃ��B�E�����˂� �����ׂ̈Ɂ@�̂閽�́@�ɂ����炶�c �̋���g�p�ɑ����ē����B�g�p�� ���_�肠��@�Z�̍J�Ɂ@�b���҂āA�x��旧�@���͂���Ƃ��B �ƕԂ��A�G�H���A�ؕ�����B �ł��E�҉ʊ��ɐ���Ă�����J���̋ʍӂ́A�F�쑽�R�ɔg�y�����B����������F�쑽�G�Ƃ� �u���叫����P�������Ⴆ�ďo�n���ʈׂɁA�ї��͑����A�G�H�߂͗��B�s���ǂ̂悤�Ȑ��ɂȂ邩�}���@���͂����B���l�ȉ������ɐ����Ƃ��͂Ȃ��B�l�ʏb�S�̏G�H�߂����o�̎�r�ɓ����ʂ��āA���}�̉��ɎQ����B���Ɏ��Ȃ�Ƃ���҂͑����I�v�Ɠ{�����A���n�ɕڑł��ďG�H�{�w���߂������Ƃ���B�����V���̏d�b�E���ΑS�o�� �u�叫����҂͍Ō�܂Ŏu���̂�ׂ��ɔv�ƈԂߗ�܂��A��ꂩ�痎�����B �O������ �u���ɓ��{�{�w�ɓ˓����v�ƍ�������Ă���Ɛ��Ȃ��������Ñ��́A�����̔s�������ڂɓG����˔j���Ĉɐ��H�ɓ����Ƃ����B�L�v�ȉ��̑唼�������B���Ë`�O�ƕ����\���h�����F���ɗ������тĂ���B�@ |
|
|
��(16) �Ō�Ɏc�����Γc��
�Ō�Ɏc�����Γc���͏����ƍN�{�w��˂��ׂ��͐핱���𑱂����B�����ւ铌�R�����x�����ނ��āA�������當���ƚ}���ꂽ�O���̖ʖڂ���ς����B���ɓ����߂̗E��͐��܂����A�ނ��e���������c���̐��쐳���Ȃǂ͌�X�܂Ŕނ��^�������� �u�S�_�����\���Ɖ]��ꂽ���߂̎��q���v�̗L�l�͍������A�قɏĂ����ė���ʁv�Ǝv���o�b�����Ă���B ���̓�����J�~���ɕ����ċA�炸�A��������(*1)�͐D�c�L�y��n�ォ��a�����Ȃ���G�̕�͉��ɓ����B�����m�������q�E��V�� ���҂Ďb���@�䂼�n��ā@�O����A��ݐ[�݂��@���ɒm�点��B �������ɓ��������B�卄�E�������ׂ�������̒��q�E�M���Ƌ��ɂ��̎���ɂ��܂��B �R�t�E�����ɂ́A�吨�@���Ƃ��ׂ���ƒm��� �u�����킵���Ō�̈�҂��v�Ə��ċ�Ɍׂ���A���Q���� �u�ꍏ��������N���ꂩ�痎���A�ċ����v����悤�i������v�Ɩ����Đ��ɓːi�����B �� (*1) ���Ƃ����B�փ����̐킢�ɂĐD�c�L�y����������A���̌㓢�����ꂽ�Ƃ����b�́A�����̕ʐl������������Ƃ̍����Ƃ��]���顁@ |
|
|
��(17) �Γc�O���A�s���
���Q���͒����ɖ{�w�ɎQ���A�O���ɕ��̈ӌ���`�� �u���˂Ė���̗p�ӂɂƉ����D���ǂȒ}���`�ɗp�ӂ����Ă�����B�ԓ����}���ΐ��X�l���A������Ώ��ˑ���Η[���ɂ͍��a�R�ɒ����܂��傤�B�����Ɍ�o�����I�v�Ɣ��������A�O���� �u�K���ɐ���Ă���Ɛb�B�����̂ė\�Ƃ肪�������邩�A���{�����ΐ�ǂ͈�ς���B�����͍Ō�̈�u�܂œ����Ă͂Ȃ�ʁv�ƕ������A���Q������ނȂ��O���ɖ߂��Ď��͂�s�����B ����njߌ���߂����A�V�Z�ɕڑł��đ��ł��畱�킵�A���c�̗E���E�㓡�����q�ƌ����S���̌�A���ɑ������ƂȂ������̍����E�n�ӊ����q���d���̐g�ŎO���ɖ��c��������ɋA��� �u�킳�͍ő�����܂ŁB�����������тčċ����v����v�ƔM�܂�H�点���B �n�ӊ����q�́A�O�����ܕS�̋ߏK�̍��A�S�z�𓊂��u�����͏\����^����v�ŏ����������E�������ɁA�O������ނȂ�������C�ɂȂ��� �u���˂Ă��Ȃ��ɏ\����^����Ƃ̖�����ɂȂ����̂��v�ƒɍ��Ȗʎ����ŕʂ���������B�����ċߏK��Ƌ��ɑ���R�Ɏp�������A���Q�����Ăі{�w�Ɏ���ċA�������ɂ͊��ɎO���̎p�͂Ȃ� �u�e���v���v���ɐ��𗣒E�����ɂčĉ�ׂ��v�Ƃ̖��߂݂̂��`����ꂽ�̂ŁA�ꑰ�\�]�l�ƒ��Ȓ}���`���߂����Ĕn�����A�K���G�Ɖ�����Ȃ���D����ƁA��H��Â��߂����E�o���Ă���B�@ |
|
|
��(18) �Γc�O���A�߂炦����
���a�R�ł͔s��ƕ����A��]�̌����̋~�o�����փ������߂����A�삯�������̂̐��Ɏ�N�̎p���ł��Ȃ������̂́A�O���̓V�^�̐s���鏈�ł������낤�B ���R�̎����҂͎O���]�Ɖ]����B����ꂽ�ƒu�n��ܕS���������������悤�ɑ����钆�ɁA�ߌ�l�������矏�R���鍋�J���~�肵����A�s�j�̐쐅�͐펀�҂̎��[�����������A���̐F����ɐ���Ō������Ɖ]���B �����Ĉ�邪���������� �u�Ō�܂ł��������Đ��������ɂ������v�ƍ��肷�����ߏK�� �u���ōĉ�悤�B�\�̂��Ƃ͈Ă���ȁv�Ə��đ��ЂƂ�R�H�ɕ����������O���͌Ë����̎O��@�ɉB��Ă����B���������l�̉\�ƂȂ����̂ŁA�X�ɎR���̓��A�Ɉڂ�A�S���^���Y�̐��b���Ă����B �R���ƍN�̌����ŁA���S���ɉi�㖳���̔���ȏ܋����q����ꂽ�̂�m�����^���Y�̖�������ɑi���o���B�O�S�]�̒ǎ肪���A���͂��A�������߂ċN�����܂܂Ȃ�ʎO���� �u���͂�V��������v�ƍ����S��m�����̓c���g���̐w�ɉg���ꂽ�B ���Ɍc���ܔN(��Z�Z�Z)�㌎��\����������B�@ |
|
|
��(19) ������G�H�̍Ŋ�
�c���g���͎O���̐��b�ŏG�g�Ɏd���o�������ԕ������ɎO���̊������� �u���x�V���̑�R�𗦂��đ����̍�����Ȃ��ꂽ�q�d�̒��́A�㐢�����������܂��傤�B���s�͓V���ɂĐl�͂̋y�ԏ��ł͂���܂��ʁv�ƈԂ߂�O���� �u�G�����ׂ̈ɑ�Q���������}�a���̌����ɕ���Ǝv�����������A���^���s�����̂ł��낤�B���R�̂܂ܐ킢�̐���s���G�����̓������肩�łȂ������́A�����ƌ���߂Ēn���̑��}�ɕ�Ƒ����A�����̑̂���v�Ɣ��݁A�G�g���玒�������@�̒Z������i�ɗ^�����Ɖ]���B �R����\�ܓ��ɑ�ẨƍN�̐w�ɘA�s������A�{�������̓@�̖�O�ɓ�t���̂܂N����A�S�Ȃ����R�̏����̗�𗁂т��B �O���͕��R�Ƃ���ɑς������A������G�H�����Җʂ����Č���ꂽ�������͕��ɂ������ˁA �u����I�����͂���ł��l�Ԃ��I���{���ɂ������炢�����̕������j�͓�l�Ƃ���܂��A�������ʂĂ����ҕ��m�߁I�v�Ǝ��B���A�G�H�͈ꌾ���Ȃ��ӋC�������ē����������Ɖ]�����A �u���̂�l�ʋ^�b�S�̏G�H�߁A�O�N���ԂɕK���l�̉��O�̂����Ȃ�����v���m�点�Ă����I�v�Ƌ���Ŏ���J��O�����M��ł��낤���B������G�H�͔��O�玵�\�O���̑��ƂȂ����̂����̊ԁA��N��ɂ͐��_�������ċ������A�Ր₦�Đ�N�̉��������炷�B �R������𖽂����͉̂��Ɩk����(�G�g�̐���)�ł������̂�m��l�͏��Ȃ��B�@ |
|
|
��(20) �Γc�O���A���Y����
�O�������Y���ꂽ�̂͏\������������B�O���͌��ɔ����A��ɂ͓S�ւ��͂߂��āA���n�ō�A��������A�����͗`�œs��H�𐔖��̌Q�W�̖ڂɂ��炳�ꂽ�B�O���炪�������������̂���ڌ��悤�Ɛ����̋M�G�Q�O�������ĉ��������A�쎟�n���� �u�������オ�V����������Ԃ�����v�Ƃ͂₵���Ă�ƎO���́A �u�킵����R�𗦂��ēV�����ڂ̑����ׂ������͓V�n�̔j��ʌ�����p����悤�B�����������Ă鎖�͂Ȃ�����v�ƗI�R�Ə����Ɖ]����B�r��ō����ɔ��������]�������A �u����Ȃ��̂͂Ȃ��B�`�ł��H���v�Ɖ]��� �u�`�͐g�̂ɓł���v�ƒf�铙�A�Ō�܂ŋB�R����ԓx�Ő��X�̈�b���c���Ă���B �u��`��]�ގ҂́A���̂�����薽��ɂ��݁A�{�]��B����Ɛs���ׂ��v�Ƃ̋��P����j��Ɏ~�߂��̂́A���l�̋T�ӂƂ��ׂ��ł��낤�B���̏�����������E�R�Ȍ��o�����L�� �u��������Z���͌��ɂĐ��Q�A��͎O�����Ȃɉ˂���錾�ꓯ�f�Ȃ�M�ˌQ�O�Ȃ�v�Ɣނ𓉂݁A�ƍN���n�߂Ƃ���S�Ȃ��쎟�n���ɕ������Ă���B�@ |
|
|
��(21) ���s�Ƃ�
���͓��{�j����ʂ镐���̒��ōł������ȉp�Y�Ɖ]���Ό��`�o�A��ؐ����A�Γc�O���A�^�c�K���A������F�̌ܐl�ƍl���Ă���B��������s�R�̏��ƂȂ��Ă���̂� �u�V�́A�p�Y�̖��H��ߌ����ȂďI�点�鎖�ɂ��A�����̐������b�ށv�Ɖ]�����l�̌��t�ʂ�ƐM���Ă���B ���A�l�Ԃ̐����ɎЉ�I�Ɛl�ԓI�̗��ʂ�����悤�ɁA�킢�ɂ������̏��s�Ɛl�Ԃ̏��s������A����f������̂͗I���ȗ��j�ł���B�`�o�A�����͒�ɏ}���A�O���͏G�g�ɏ}�����B���ĂΊ��R�ŁA���쎞��ɎO���͊��b�̎�@�Ƃ��ꂽ�B�ƍN�̎q���E���ˉ��傾���͂������� �u�O���͖L�Ƃ̒��b�Ȃ�Α��ނׂ��ɂ��炸�v�ƒf���A�N�l�吼���� �u���s���S�N�������܂�@���˂̐�N���_����B�v�Ɖr���Ă��̋`����^���Ă���̂͊������B�@ |
|
|
��(22) ��S���A����
�S�𐔂��鐼�R�喼�̒��ł����E�ŏ��̓S���͂Ŗ����グ�Ȃ���߉^�������̂͋�S�×��ł���B�x���ƐV�{�ɗ����A�F���~�Ɉ��Z�̒n�Ȃ��ƒm���A�Ăюu���̐Γ��ɓ��ꂽ���A�������낭�A�a��̖����̐R�L�O��@�ɐ��������B ���̍��A��S�痲�͉��Ƃ�����ɑウ�ĕ��̈ꖽ�������ꂽ���ƍ����������A�ƍN�͒��X�����Ȃ��B�����m������S�̉Ɛb�E�L�c�ܘY�q��͏���� �u�c�O�Ȃ���䏕���͍���Ǝv���܂��B���ۂ��Ƃׂ̈ɂ����悢��Ō���v�Ɛi�����A�×����o������߂ē��u���̒������Ɉڂ����B �₪�ď\���\����A�����ē��{���R�̗E���Ƃ��ĉ����嗤�ɂ܂ŕ����������������Y����S�ƂƎq���̔ɉh���v��ׂɁA�R�L�O�̉���ŏ]�e�Ǝ��n���āA�\��˂̐��U������B���ƍs�������ɂ����ܒj�A�Z�j�͌��ǂ��A���j�͒��F�R�����؎��ɓ����ďo�Ƃ��A���̕������ɂȂ����B �×��̎����̉ƍN�Ɍ�����ׂ��A�R���܂Ȃ���ɓ��u�����璹�H��ɋA��Ɛb�ꓯ�Ɍ������ďo�������B�ƍN�̏��������������痲�̋}�g�Əo������͈̂ɐ��̖��������������Ɖ]����B�Ɛb�E�L�c�̓ƒf��m�����痲�͌��{���āA���_���ŋɌY�ɏ������Ɖ]���B �ƍN�������������A�痲�̏��̂͌ܖ��ܐ�ƂȂ����B���������̎��𓉂痲�́A���u���̎R���Ɏ�˂����喾�_�Ƃ��čՂ�A�R�[�̓��˂Ɍܗ֓������ĂāA�[�����̖������F���Ă���B�����Ē��H��̗���ɂ��鍋�s�ȕ�E������̋�S�Ɨ�㓖��̕��̗ї����钆�ł������̑c�E�×��̌ܗ֓��͈�ۗ��h�Ȃ��̂ł���B�@ |
|
| ��2 ����Ɠ������@ | |
| ��2.1 ����Ɠ����� �@ | |
|
��(1) ����莟�A�Z��ؕ�������
�ƍN�Ɂu�O�������v�̑���𑗂������c����(*1)���S�R��\���Ƌ��⎵�疇��v�����ꍂ���孋������c���ܔN(��Z�Z�Z)�H�A�փ�������}篈ɉ�ɋA���Ă�������莟�͜��X�Ɗy���܂��A�����F�ɂӂ����Ă����悤���B�Ɖ]���̂��A�㐙�����ׂ̈ɎO��̏����𗦂��ďo�w������A�����n�߁A���R�ɎQ�������Ώ��E�V�������ȉ����]����씒�P����͂B��̗���������Ă����莟�̌Z�E�\�Y���[�́A�����߂̂����ߒʂ� �u�ƂĂ����ڂ͂Ȃ��B���v�Ɍ��𗬂�������J���ė̖�������~�����v�ƈ��ɂ��y������R�ɓ��������A�Ƃ����B�\�Y���[����]�킹��A�^�̎�N�E�G�����̖��ɏ]�����܂ŁA�Ɠ����邾�낤�B �����ܓ��A�Γc�O�����^�c���K(*2)�ɑ������莆�ɂ́u�ɉ�ݐw�̐��R�͎���]�l�v�Ƃ���B �莟�͂����m���ċ}�����A���ƌ�ē����z���Ĉꋓ�ɏ��D���Ɖ]����B�������A�u�ꋓ�Ɂv�́A�^��ł���B �������̏��R�ł̌R�c�ɂ��A�����A�r�c�A����A�����̏��������F��ɋA���Ă����̂������\�ܓ��ł���B���ꂩ��A���n�̍��킩��փ����̑�킪�W�J���ꂽ�̂��㌎�\�ܓ�������A�ǂ��l���Ă��莟�������Ԃ����̂͊փ����̑�킪�I�����㌎���{�Ƃ����l�����Ȃ��B�ƍN�̓����ł�ނȂ�����ɓ������Z�� �u���Ƃ��Z�ł��ӂ͎���Ė��˂Ȃ�ʁv�Ɛؕ��������̂͂���Ȍゾ�낤�B �� (*1) �H���߂��փ������Q�ƁB (*2) ���Ȃ� �܂��䂫�B�����E�喼�B ���M�Z����O�Ƃ��čb�㕐�c���̉Ɛb�ƂȂ����M�Z�̒n��̎�E�^�c���̏o���B���M����̕��c�ƂɎd���A���c���ŖS��Ɏ����B��A�k�����⓿�쎁�Ƃ̐Ղ��o�ĖL�b�������ɂ����đ喼������B ����c����œ�x�ɂ킽���ē���R�����ނ��A�㐢�ɂ͐퍑���カ���Ă̒m���A�d���Ƃ��Ă̐l�������t������A�u�k�⏬���ȂǂŒm����悤�ɂȂ�B�q�ɁA�M�K�A�K���B�@ |
|
|
����(2) ����莟�A��⏇�c���̓@�ŁA��F�ɗJ�𐰂炷
�V�����ڂ̈��Ŕs�ꂽ���R�̑喼�B�̏��̎��S����v�������ƍN�́A���̂��������R�̑喼�B�ɓ�{�`�O�{�̑�ՐU�������ēV���l�ʂ��ւ����B�G���ׂ̈ɐ�������ł������̂ɓ�S���\���̏G���̂͘Z�\�ܖ��ɍ���A�S���̋���z�R�͂��ׂē��삪�܂��グ�Ă��܂����B �G�g����^����ꂽ�莟�̘\���͓�\���������̂ɁA���̂��ɉ�ꍑ�ɂ������ʔ����Β��x�ɍ���Ă���炵���B�փ����ŁA�莟�̉ƘV�ł����������߂̖ҍU�ŁA�ƍN�{�w�����낤���������A�ƍN�̍��ɂ����莟���́A�F�쑽�̐i���Ŕs�������������ɂ܂����܂�A�փ����̏h��ɑދp�����B�ƍN�͂�������Ă��� �u���Ă͒莟�߁B�����O���ɂ���ė]���E�����A�Ȃ͓��K�������߂��ދC���v�Ƌ^���������m��Ȃ��B ���邪�����~������Ɖ]�����Ԃ����āA���ߏ�̗͓l�Ɋ��ōא�Ɏl�\����F�߂��ƍN�����ɁA�M�ܕK���̑ԓx�ɂł��̂��낤���B �c�����琳�`���̋����E���Ȕ����N�ŁA�M���Ɉ�����A�{���E�G�q�̕v�ɑI��A���̑��V�ɂ��\�ܔԖڂɏč����Ă�����̒莟�ł���B���˂Ē��삩��� �u���������͌����A�R���ɂ��G�ł���ɐl�i�����ɂ��Ċ��e�A�Ԃ̔@���e�e�̎���ł���A�M�Ղ͑��M�e���A��͐�M�ɂ��܂����͗ʂ�����A�\�y�ɂ��Ă͋��t�l���̑�v��菟��L���V�^���喼�Ȃ�v�Ɛ�^����Ă��������ɁA��⏇�c���̓@�Ŏ�F�ɗJ�𐰂炷���X�������Ȃ����̂������͂Ȃ��B ���̏�A�G���◄�N�ɂ��D����Ă����炵���A�u���������U���܂ő����v�̌��ʂ�K�e������i�Ɩڂ����炵�A�c���Z�N(��Z�Z��)�ɂ͋��s���i��Ɏq���̉Ɛb�E�q���d(�����\����)��C�����ď��喼�̓������������Ď������A�ނ͐e�L�b�h�̃u���b�N���X�g�̃g�b�v�ɒu���ꂽ�悤���B�@ |
|
|
��(3) ����莟�A�ƍN���ɂ܂��
�����œ���Ƃ̕M���ƘV���������q���d�Ɠ����̐l�����o�ꂷ��̂ł܂���킵�����A�q���d�͓��안��̐b�ŁA�V���\�O�N(��l�l)�`���i���N(��Z��l)�A���\�˂ŕa�����Ă���B ����ɔ�ׂď��q���d�́A�V���\�l�N(��ܔ��Z)�O���A�����Ŗv���A���̎q�E�d���́A�V�����N(����O)���ꂾ���瓖���\�O�˂ł���B �d���͉Ɠ����Ȃ��̂�{���Ă��������ŏo�Ƃ��A�₪�ĉƍN�ɏE���Č��̗̎�ƂȂ�A��ɓ����Z���̑喼�ƂȂ�B���̎q�E���q���Ƃ��L���ȓ����m�����Ђ��N�����B ���̒����Ɍ������̂��q���d�̎q�E�d���Ŋ��i�\�l�N(��Z�O��)�A�����œ����B���\�ܔN(��Z�O��)�ɂ́A���q���Ƃ��ӔC�����Đؕ����Ă��邩��A���͐[�����ʐl�ł���B �c�����N(��Z�Z��)�A�ƍN�́u�L�b�G���A�֔��A�C�߂��v�̉\�𗬂��āA�喼���̔����߂�ƁA�����N(��Z�Z�O)�ɂ͉E��b���Α叫�R�ɔC�����Ė��{���J�݂����B ���͟�X�Ɠ���̗�������߂Ă���̂ɁA���`���̂����܂ŋ����莟�́A���}�̈▽������āA���N�̔N�����ÏG���ɎQ�����B �����c���������珇�c���ƌĂ��قɁA���O�Z���������Ē���ȂǍÂ��A�e�r���v��̂��킾�����B ��������ƍN���u�莟�߂͂��̂܂܂ł͒u���ʁv�ƈɉ�̏�E�E���������d���̖d�����߂��点��B �����Ă������ǂ�Ŏ��ƂȂ����̂��A�փ����̐킳�Œ����݁A�F�a���������獡����\���̑喼�ƂȂ����������Ղł���B�c���Z�N(��Z�Z��)�ɁA�l�\�Z�˂Ŏn�߂Ēj�q���o�����Ă���́A�k�q�̍��g(*1)���ז��ɂȂ��Ă����炵���̂͏G�g�ƏG���̈����������炵���̂����m��ʁB �����A���g�͓�\��˂ŁA�n���ő傢�ɕ��킵�Ă���̂ɁA�`���E�G�����������ꖜ�̂܂܂Ő��u���ꂽ�B�₪�ĉ����Ö�(*2)�̉Ɛb�Ƒ����ɂȂ��A�ƍN�ْ̍�ŁA�����Ă���̂ɑ�F��孋��𖽂����Ă��� �� (*1) ��a�S�����Q�ƁB (*2) ���Ƃ��悵�����B�u�悵������v�Ɠǂސ�������B�ɗ\���R�ˎ�A�̂�������Ôˏ���ˎ�B�����ˉ����Ə���B�˃��x�̎��{����1�l�B�ʏ̂͑��Z�B�@ |
|
|
��(4) ����莟�A�u�킢�͂������Ȃ��v�ƐS�Ɍ��߂�
�₪�Đ��͌c���\�N(��Z�Z��)�ɓ���A�ƍN�͏��R�E���G���ɏ���B�c���\��N(��Z�Z�Z)�ɓ���ƁA��ɒ������F��������H�����A�����ĐV���R�E�G�����A�ƍN�̖��ŏ��喼�Ɏ�`���𖽂��A�]�ˏ�̑���z�ɂ��������B �G�g�������Ɖ����Ōւ����̂ɔ�ׂāA�ƍN�́A�����������̕ǂƓy���̑��ɉ��Ɩ�\�荇�����y���V�������̗p���āA�������\���������Z�\�����̑�V��t��z���グ�Ă���B �����̏�̗̈e�͖[������������������炵���A�֓���~�̐l�X�����������B�����m���Ďq���̈�ɂ͕F����ɁA�P�H�̒r�c�A�����̓��������x�ꂶ�A�Ƃ���Ɍ��K���A�����̗��s�F�ƂȂ�B ��������Ď��܂�Ȃ��̂́A����̗��N�B�ŁA�G���ɓV��������C�̂Ȃ����͖��炩�ł���A�ƌ��{���āA���̔w�M��l�����B �����ďG�����㗌���Ė��̏G���������Ă���ɍs������ �u�����ǂ����Ă��Ɖ]���Ȃ�A��q�S������v�Ƃ܂ʼn]���A�k����(�G�g�̐���)�� �u����͏G���ׂ̈ɂ͂Ȃ�ʁv�Ɖ����߂Ă���Ə��m���Ȃ������B �����m�����ƍN�͓��S�[���{�����B ����܂ŏ\�O�̏G���𐳓�ʉE��b�ɁA��\���̏G�������ʂ̏]��ʓ���b�ɕ�C���Ă����̂��A�c���\��N(��Z�Z��)�ɂ͏G���̉E��b���Ƃ�����ɁA�O�l�喼���ɏx�{��̉��C�ɁA�l�v�̒𖽂��Ă���B �u�ǂ����Ă��킢�͂������Ȃ��B���̎��͑��}�̉��`�ɕ�̂݁v�ƒ莟�͐S�Ɍ��߂Ă����悤���B �ɉ�ɓ`��铛��̎����͗ǂ��b�́A�ǂ�����ɓ������������̖��ł��������ꂽ�悤�Őr�����Ȃ��B �莟�́A�Ă͏��c����̖����Œ��̓����y���݁A���c�̂��т����ň����ɋ����A�ɉ��̗����ɎV�~��݂��ėH���̋C�ɂЂ���A�̕����Ȃœ��̂����̂��Y�ꂽ�Ɖ]����B �܂�����̔��l�Œm��ꂽ���Ƃ̏��[����ɌĂ�ň����Ƃ����̂œ{�����v���u�D�F���ނ̗̎�v�Ƃӂ������Ɖ]���b�����邪�A�L���V�^����M���Ă����ނ�����Ȏ��������Ƃ͐M����B�@ |
|
|
��(5) �ƍN�̛@�v�A����莟�ɔ���
���āA����c���\�N(��Z�Z��)�ɏ㗌�����ƍN���A���R�E���G���ɏ����ďG���ɓV����n���C�̂Ȃ����𖾂炩�ɂ������B ���̎��ɘA��Ă����鏠�����A������Ɉɉ�ɗ��āA�������A�c�����r�����B����œ{�����S�������̑���E���Ă��܂����B ����ƉƍN�́A�����ɏ��i��̌x���������Č������T�����A�{�l�����łȂ��ނ������܂��������܂ŏ��Y�����B����ő��l�B�� �u�l�Ԃ��邪��ȂǂƉ]���n���Șb��������̂��A�v�Ƃ����藧���A�d���̕��m�B�� �u�_����a�̓��̂ł���������Ƃ̒��n�������Ȃ���A�ꌾ�̕�����]���ʍ������a��v�ƉA�����������Ɖ]���B�ƍN�A���Ղ�́u�҂ĂΊC�H�̓��a����v�Ƃق��������낤�B �c���\��N(��Z�Z��)�ɂȂ�ƁA���炭���Ǝv�����ɂ���āA������X���s���Ă������đ呹�Q�ƂȂ�A��N�̓V�_�Ղ��ł��Ȃ������B�����̖͗��v���̒莟���A�w�ɕ��͕ς���ꂸ�A�d���N�v����藧�ĂāA��ق̏C�z�����s���A�̎傽��ʖڂ�ۂ��˂Ȃ�ʗ���ɒǂ����܂ꂽ�B ���悢��ƍN�̛@�v���f�s����鎞�������Ă����B�@ |
|
|
��(6) ����莟�A���Ղ����
�₪�Čc���\�O�N(��Z�Z��)�l���A�M���ƘV�E���V�G�C�̉Ɛb���A�]�ˉƘV�E�ٓc��V�̉Ɛb�ɂ��𐁂������A�o���Ɏ����҂��ł�Ɖ]���������N�����B ������u�������s�v����ł���B���������������Έ�厖�ɂ��Ȃ肩�˂ʁA�ƒ莟�͎��k�Ŏ��߂悤�Ƌ�S���Ă���ԂɁA���V�́A�ނ̖����ƍN�̈����ƂȂ��Ă������ɗ����āA���ډƍN�ɑi���o���B����́u���Ƃ�������X�ł��܂��悤�v�Ƃ����ׂƉ]���邪�A���炭�ƍN��㩂ł������낤�B �ƍN�ɂƂ��Ă͐������u���ʼnɓ���Ă̒��v�������B�Z���ɂȂ�ƁA�˔@�A�莟�A�ٓc��͖��{�]�菊����Ăяo����A�������撲�ׂ��n�܂�A���̐Ȃɂ͑�䏊�̉ƍN�̊���������炵���B �������A�莟�Ə]�Z����ٓc�͓��X�Ɣ��_�����B�����A���V���̏ؐl�Ƃ��ďo�����������A���A�z�{��́A���𑵂��Ď�N�̒莟����A���V���x�������Ɖ]�����獕�����N���͖��炩�ł���B �����Čc���\�O(��Z�Z��)�N�Z����\���ɂ͉ƍN�̖��� �u����莟�A�����V�́A�����������r���̏�ɁA�D�b�������A��⏇�c���̓@�ɏ�Z���A����쓹���Z��Ǝ��������ɂ��铙�A������ӂ�����肩�A�ݍ������V�b�̒����������Ėʐڒv�����B�R��ɗV���A�여�ɋY��A��������u���A�m�������p�������݂̂Ȃ炸�A��X���ւ̃L���V�^���@�k�̐M���̂Ă���s��A���ɋ�����A����Ĉɉ�\�A�ɐ��ܖ��A�R��̌v�\�㖜�����ׂĖv���̏�A���q�E���a�ۂƋ��ɉ��B�A�֏�̒����Ƃ�孋��ސT�𖽂��B�ƍN�ԉ��B�v�Ƃ̍������������ꂽ�B�ٓc��V�͐ؕ��ɏ�����Ă���B ����莟�́A�喼�Ƃ��Ă͒p�J����܂�Ȃ��ߖ����ɁA���ՂƉ]���߉^��H��̂ł���B ���̏��̂��\�㖜�Ȃ͕̂\���ŁA�����͔����������悤�����A����ĉƍN�̔z���Ŏl�����璅�C���铡���ɂ́A�ɉ�E�ɐ��E��a���ē�\���^�����Ă���B�@ |
|
|
��(7) ���V�G�C�A�E�Q�����
�B��̖L�b���喼�ƍl���Ă�������Ƃ̉��Ղ͑����~�ɂ܂ő傫�ȏՌ���^�����B���A���͂�L�b�Ƃł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ������B �ꌏ������ɁA���V��́A�ƍN����y��������Ƃ��� �u���̐S�ꗥ�V�ɂ��Đ��@��j�炸�A�F�~�𗣂�A��N�Ɍ����肵���ƌ��b����ׂ��B�v���������B �O��̓��쒼�Q�Ɏ旧�Ă��A�����A���A�z�{������̉��b�ɗ������B�킯�Ă����V�G�C�͓V�̂̓ޗǕ�s�ɔC������A���s���i��Ƌ��ɑ��Ď��̏d�C������ꂽ�悤���B ���������V�����̂Ƃ��]���������ɉ��~�� �u�w���̎q���t���ɕ����Ĕ�щ��҂������v�Ɖ]�������ŁA�J�ɂ� �����V��[�߂́@�Ɉ��ƘV�A��Ƃ��Ԃ��ā@�ޗǕ�s�B �ƁA����S�����ꂽ�A�Ƃ��]����B �ܘ_�O��߂��Ɛb�̒��ɂ́A�莟�̐^���m�鎘�������A��̑��w�Ŋ��������A�z�{�A����̒��b�� �u�����Ȃ�������A���J��̛@�b��A�ƍN�߂Ɏ�Ƃ������V��̂����ł���B���ɕK���a�̋w����v�Ɩ��O�̗܂𗬂����B ���ł��R���F�L�́A�ꎞ�͋�S�ƂɎd���������̂́A�ĂјQ�l���āA�c���\�l�N(��Z�Z��)�A���V�������ɕ����r���ł��̏h�ɔE�э���Ŏh�E�����B �����A�����̒����ɍ��D�𗧂� �u��͓���ƕ���̐b�ɂĎ�N�̍��𐰂���ƒ��V���n�����B���ɂ͂��̒��q�̌��Ղ�����Ď�������o��ł���B�v�Ə����c���đ�]���ƂȂ��Ă���B�����m�����S����Ɛb�B�́u�Ԃ�����I�v�ƕ����������ɈႢ�Ȃ��B �����̗��j����]���A�m���ɁA�莟�͐��Ԓm�炸�̈��[�a�l�ŁA�ꑰ��Ɛb�ɎS��������炵���B�R���g�`���т��h�l�Ԃ̗��j����_����A�����ɂ܂�킸���s�ɂƂ��ꂸ�A�Ђ�����Ȃ̐M�O�ɐ����Ĕ������S�т��N�q�l�ł������B �����ɒ莟���]���A���̔G�߂𐰂��A���������₩�ȍ��Ƃ��悤�B�@ |
|
|
��(8) �������Ղ̓���
����ł͔ނƂ͑ΏƓI�Ɂu���n�薼�l�v�Ƃ��]���铡�����Ղ̓������q�ׂ悤�B ���j�͏��҂̂��̂ł���A�s�҂̐��`�͂��ׂĂ���������Ă��܂��̂���ł���B�_����a�Ő�N�̔ɉh���d�˂�����Ƃ��A�r�ꋶ������̑�^���ɂ���Ĉ���~��(����̉Ɩ�)�͎U��B �c���\�O�N(��Z�Z��)�����ɓ���ƁA���悮�H���Ƌ��Ɉɐ��̈��Z�Ï�A�ɉ�A��a��ɗ\�ō��v��\�̑喼�ƂȂ����������������A�₪�ċj�[�̉Ԃ��炫�������ƂȂ�B �����Ŕ���Ղ��w���R��(����)���s�^�x����ǂ���� �u�w�I�B�A�F��A�k�R�̏����A���͋g��̎R���A�\�Ð싽�m�炪�I�N���ē��C���ɖ\���̍ۂ͓��n�Ŗh���x���ׂɂ���y�̕����ł͂ƂĂ��y�т������B�x�Ɛ_�N(����ƍN)�͔��f���ꂽ�B�܂����L�b���̋����ɍۂ���Ǖs���̏ꍇ�́A��䏊(����ƍN)�͏���A���R�Ƃ͕F����ɓ����Č��y�d����������Ƃ��āA�]�����̑�C�ɑI�ꂽ�B�Ɛb�ꓯ���悭�������@���ď[���o�傹��B�R���ĒÂ͕s���łȕ���ł��邩�瓖���̋x�����ƍl���A�g�ɉꂱ���鑠�̍��Ő�l�w���̍����n�Ǝv���h����͎����ɐS�������m�̐��Y�ƒ����ɓw�߁A��������̍ۂɕ��Ƃ̐s���ʂ悤�S������B���̎������łɂ��ׂɁA�����̎����ɗ�핐���̎��l�̓S�C����u���A�e�\���̓S�C��z�u����Ή��̐S�z���Ȃ��B�v �Əq�ׂāA���Ղ́A�^��ɓS�C�����E�~�����E�q��ɖ����̑�̂�^���A�O�S�\���̏e�����A���֖̊�ɔz���Ă���B�@ |
|
|
��(9) �����Ƃ̖萭
�����Ƃ̖萭�́w�v���j(�����˂̐��j)�x�ɏڋL����Ă���B�ڍׂ͂�����䗗�����Ƃ��āA���̓��F������������� ��A�����l�u�������Ȃ��v�c�ƌĂсA�����ł͂��邪�ƕ��ɂ���ĕ��m�̓�����F�߁A���̎��ɔ�����Ƌ��ɁA���̎x�z��N�v�̎旧�Ăɓ��点�Ă���B ��A���Ƃ̖�����Q�l���ʂɍ̗p���Đ�͂��[�������A��ɖ��{�̐��ƂȂ��Ă��́u�����v�ɕ邱�Ƃ���ƒ�߁A����ɋt�炤�҂͂��ׂĎa��A�Ɛ����Ă��� �O�A��E�̐��n�̏o�g�ʼnƍN�Ɏd���Ă����ۓc�Ï�(*1)��Ⴂ�A�����̖��������A�₪�ď��ƘV�Ƃ��ĔE�ҌS��g�D���āA��Ԋ����ɓw�߂����Ă���B �����Ĉɉ�̔E�҂ƉƍN�̊W�́A�V����N(����O)�̈ɉ�̗��ȗ��̉��ł���A���Ղ��Ï������������͎̂l���̗̎傾���������炾�B�ƍN�͑������瓛��̑��ɍ��Ղ����đ���U���̕t��Ƃ�����肾�����͖̂��炩�ł���B �� (*1) �������������̒��Z�E�ی��̑��B�@ |
|
|
��(10) �������ՁA���P����C�z
�₪�Čc���\�ܔN(��Z��Z)�ɂȂ�ƁA�z��̖���Ɖ]��ꂽ���Ղ͓��������ہA����̔��P��̌�����(*1)�̂��炵���ɐ���܂��A���̌���̑�C�z�ɂ�����B�莟����������ׂ̏o��Ƃ��ē��ɑ��Ĕ������̂ɑ��A���Ղ͑��ɍU�߂�ׂɐ��ɑ��Ĕ������̂ł���B �j���ɂ��A �u�E�ҒB��S���̕S�\��ɐ��������āA���̍\����������A���ɋЎO�Z���̐[���x�����A�����O�Z���̐Ί_���k�����Ēz���B��k�̗����ɘE������A���܂ł̖{�ۂƍ����ĐV�{�ۂƂ���B��ɖʂ��ē�̏o�������J���A���͌Â���x��p���B�����ɂ͐V������k�Z���̑�Ί_��z�������̍��ǂ͑�����������Ȃ�B�v�ƋL����A�{�ۂ̌����́A�@������H�̒����a���A�b�Ǒ�H�̍b�ǖL��炪�A�勓�����ɏW�܂����炵���B �A���G�g���喇�̋���莟�ɉ��������̂ɔ�ׂāA��ȉƍN�͒m���炾�����B �� (*1) �F�����̏t�H���Q�ƁB�@ |
|
|
��(11) ���m�ρX�A�������Ղ̉Ɛb
�G�g�͑�������t��ɁA���̈ɉ���ɓ���A���̕F���ɐΓc��u�����B����ɑ��āA�ƍN�͐�ÕF���Ɏl�V���̈�l��ɁA�����Đ���������A�O�l�A�̗E���̒����瓡����I��ňɉ���ɓ��点���B�ƍN�͓�����[���M�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B �u�l�͐Ί_�A�l�͏�v�Ɖ]�����̉Ɛb�c������ƁA�Γc�O���̏����E���A���\���B���]�䕔�̌K���A�����B���c�����̉ƘV�̕ۓc�A�n�ӁB����̈ꑰ��A�쑽(�\�y�̑c)�Ȃǐ��ɖڂ����������ł���B ���y�炿�̍��Ղ��A�n�߂Ďm��������ߍ]�A���삩��n�܂��āA�A�n�A�l���A�ɐ��A�ɉ�܂�(���ɂ͖x�����P�̒��j�E������V�{���E�ዷ�玁�O�ƌ���Ă�����̂����邪)���ɑ��m�ρX�ł���B �u�L�ׂȐl���Ɏv���������\��^���v�u����ɂ�����炸���͎�`�v�̂����͎O���Ɠ����Łu�ߍ]����̓��F�����m��Ȃ��v�Ƒ傢�Ɋ�����������B�@ |
|
|
��(12) �������Ղ̉ƌP��
���Ƃ��ẮA�����ߍ]�l�ł����Ղ̂悤�ɉ������u���������ė��ɑ���v�j�����A�O���̔@�� �u�E�q�͐m���]�����A�Ўq�͗����ɂ͋`����Ƃ���B�`�͕K���s�`�ɏ����A�`�݂̂����𐳂��������߂铹�ł���v�Ƃ̌��t��M����j�̂ق����D�����B�w�҂̍E�q�A�Ўq�ƌR�w�҂̑��q���l����ׂ����Ǝv���B ��J�Y���̂悤�ɁA��ɑ��q�̌������E�̖��Ƃ��A�O���̋����ɍۂ��Ă��u���q�ɐ����������ׂď��Z�Ȃ��v�Ǝ~�߂Ȃ���A���ČȂ�m��҂ׂ̈ɏ}�����u���n�艺��v�Ɏ䂩���̂́A�ǍO���̌��̗���ł��낤���B ���y���̋��������̈ɉ�̐l�̒��ɂ� �u�Ȃ̍D�������ŏ���ɂ��߂��Ă͍���B�l�Ԃ̒Z���͒����ł�����]���Ȃ�ɉꖼ�Y����ɂႭ�̗��\�ł������B����O�S�N�ɂ킽��ɉ�̕��a�Ɣɉh�ɍv�����������Ƃ����ƐS���邩�v�Ƃ�������邩���m��Ȃ��� �u���̕��͖��������Ƃ̐l�X�͑傢�ɍD���Ƃ�P���B�܂����ق��Ă������v�Ɠ����邱�ƂɌ��߂Ă���B ���āA����莟���A�G�g����u�`���d�A���������ɏG�ł�̎傽��v�Ƃ̋���������āA����łڂ�����Ⴊ����B ���Ղ́A�u��Ɏ��̗���ɋt��킸�`���ɓM��邱�Ƃ͂Ȃ����X�ꑰ�ƉƐb�̔ɉh���v�邱�Ɓv���|�Ƃ����炵���B ���̌��ʁA�����˂́A�O�\�̗̓y���i��n�Ƃ��āA�����ېV�܂ňꗱ�����炳�ꂽ��]������邱�ƂȂ��ɉh��������A�Ɖ]�����j���c���B ���H�����ł̐킳�ɓy�d��ŐQ�Ԃ�A���R��s�����������Ƃ���F�X���������邪�A����͕F���̈�ɂ������ł���B���Ղ́u��Ɏ����Ƌ��ɞ������ċt���ʁv�ƌP����蔲�����Ɖ]���悤�B�@ |
|
| ��2.2 �K�^�̈�˒��q�@ | |
|
��(1) �����ΏM�ĂƖ�������
�c���\�O�N(��Z�Z��)�̏H�A��F�ɋP���]�ˏ��x�{�邪�������A�����Ĕ����ɋ`��(*1)�̖��É���̓꒣����n�܂�A���̊�������i�Ɛ����𑝂����ɁA���̐����ւ铡�����Ղ��ӋC�g�X�Ɠ�������B ��������������߂Ȃ�����̘Q�l�ƂȂ�����ˊo�O�A���G�A���O��Z��͑�a�ɋA�����B���̗ǍO����`���A���k�J�ǂ̐����ɓ������ŁA�����@��(�ΏM��)�̒��j�E�����ɕʂ�������ɍs�����B���ĒC�s��̐킢�ɏ��i���ɎQ�����ďd�����A�������̐��؍�Ɉ�������ňȗ��A�e�������Ă����̂ł���B �ΏM�Ă͏��i���n��A���c�Ɏd���A���̋��̂�^�����ǍO�ꑰ�Ƃ��e�������Ă����B�������L�b�G���̑�a������A���n�ʼnB���c����������ď��̂�v�������� �����@�́@���͎��Ă��@���̒����@�n�肩�˂���@�̏M���ȁB �Ɖr���ĐΏM�Ăƍ����A���p������J�����B�₪�ĖL�b�G������S�̎̕}����Ⴄ�悤�ɂȂ�A���ɂ��喼�B���片�����ėI�X�ƕ�炵�ċ����B ���\�O�N(��܋�l)�Ɍܒj�̏@���A��ďx�͂ɕ����A�ƍN�ɓ��ӂ̖�������������������A�G���̎w��������ꂽ���u���N�g�Ȃ�v�ƁA����ĎႢ�@����d���������B �փK���ł͏@�邪�b��E�ҏO���W�߂Č���������������A�������̓�����������A���Q�O��̕��@�w��ԂƂ��ē��p�����������A�ΏM�ẮA�c���\��N(��Z�Z�Z)�A���\�Ő����������B �� (*1) ����`��(�Ƃ����� �悵�Ȃ�)�B�����˂̏���ˎ�ŁA��������Ƃ̎n�c�B����ƍN�̋�j�B�@ |
|
|
��(2) ��ˎO�Z��A������
�ΏM�Ăɑ���������́A����̓���v���ɔ����A�e����������ˈꑰ����a�ɋA���ĕS���ɂȂ�ƕ��� �u������̐l�����ɋ���������̂͐ɂ����B�����ŐV�̂̊Ǘ��𗊂݂����B�v�ƍ��]����������ɐV���������߂邱�ƂɌ��߂�ƁA���\�Z�˂ɂȂ������E�ǍO�̎���S�z���Ė����ڏZ�����߂��� �u�i�N���ݓ�ꂽ��a�𗣂�����͂Ȃ��B�Ⴂ���q�炪�ǂ����b�����Ă���邩��킵�̂��Ƃ͐S�z���p�v�Ɖ]���B �����Ŋo�O��O�Z�킾�������؍�Ɉڂ�ƁA����̐��b��N�v�W�ߓ��ɓ���A�q���Ƃ��Č��\���X�̂ǂ��ɉ߂����Ă����悤���B �c���\�l�N(��Z�Z��)�ɂȂ�ƁA�ƍN�́A����ƕ��Ԗ���̈�ˈꑰ�������̋q���ƂȂ��Ă���̂�m���� �u�����A��������Y��ċ������I�N�͂Ƃ肽���Ȃ����̂���B�o�O�ɂ͈�˒��q�ő傫�Ȏ肪�������̂�B�ނ͗ǍO�̌����Ђ��������ɁA�����ɂ������ς肵���������j��B����Ȑl����Гc�ɂɖ����ꂳ���Ă͂Ȃ�܂��A����Ƃ��G���Ɏd��������B�v�ƒ����ɏ@����Ă�Œ�����ɂ������B�@ |
|
|
��(3) ��ˎO�Z��A�֓���
���N�m�����瑁�����\�N�A�o�O���G���Ɍ������܌̈�˒��q�̂��Ƃ́A���̍����̊Ԃł��A�]�̓I�ɂȂ�A����͔ނ�̎�ɓn���āA�m��ʎ҂͂Ȃ��B�l�X�ȃG�s�\�[�h������Ă��邩�琳�Ɂu���q�̂����炵�������v�Ɖ]����B �d���̂��Ƃ��g���g�����q�Ői�݁A�₪�Ċo�O��O�Z�킪�����đ�a��K�˂��̂́A�c���\�l�N(��Z�Z��)�̕�ł������B ���[�ẮA���l�����O���F��ɋA�点�Đ���Ő��v�𗧂����A�Ȃ͍P�g�Ɛ��k�J�ǂ̒��ŁA���Ɣ\��̗F�Ƃ��ē��X�𑗂���B�҂������B���N�Z���ɂ͎R��A���I���A�㌎�ɂ͊փ����̌Ð��𗷂���̂��y���݂Ƃ��Ă����炵���B ���[�ẮA�����\���z�����o�O��O�\�O�̒��O�܂ő����ē���d���̘b�����B�����ȗ��[�Ăł͂����Ă��A���q�B����˂̌����֓��ɉh��������̂��V�̌b�݂Ɗ������炵���A�t���ɂł������ꂽ�悤�ȏ� �u���ɂ��g�n��œV���͐������Ă��A�n��œV�������߂鎖�͂ł��ʁh�Ƃ��]���B�G�����ɑ��鑾�}�̐e�S�͔��邪�A�v�͂��̊�ʔ@������B���藧�悤�ɔC����̂��V���ׂ̈ł����낤��B���ܓV���̖����́A���N�̖��A�փ����̑��Ɖ]����n�k�ɔ��ʂĂāA����蕽�a�ŖL���Ȑ��̒������߂Ă���B�����ɑ��}�̎q�Ɖ]���Ă��c���G�����ɓV�������߂��ʂ͂Ȃ��A�H�ēa�̂悤�ɐ��n����Ȑl�X�݂͂ȁA�g�l���炵�̖��l����������}���A���C�҂̂Ɖ]����ƍN���͏\�{�����낵���l���B�₪�ēV���͓���̐��ƂȂ�͕̂K��h�ƌ��Ă���̂́A�����̂Ă����̂킵�ɂ��悭����B����ȐV������ɖ]�܂ꂽ�̂���A���Ȃ��������t����Č���̂��ǂ��낤�B����A�킵���Ă��ċ���̂͂�����N�����B��孋��������Ă���莟���q�̎���B���Ƃ����߂ĉƖ��̗��悤�ɓw�߂�̂��A����ł���A���̂Ȃ�����[������́g�`�h�ł���̂�Y���ł��ꂢ�v�Ƃ��݂��ݖ]�݂��q�ׂ��B ���q�B���[�����m���āA���c���ɂ��݂A���H��������B�@ |
|
|
��(4) ��ˎO�Z��A�d������
�r���ŏx�͏�̉ƍN�ɌĂ�u���R�Ƃ̗͂ɂȂ��Č�����v�ƁA��X�̎���ʼny���ł����̂������@��̔z���������낤�B �]�˂ɒ�����A�G���ɖڒʂ��������A�o�O�͏헤�^�ǎO��B���G�A���O�����R�e�q���ł��鏑�@�Ԃ�q�����āA�]�˂̒���舕��ł��钼�Q���{�ܕS�̐g���ƂȂ����B�O�r�m�X����V�����D�o���}�����̂�����A�֓���ˎ�����˒��q���ƕ�Ƃ���̂����R�Ɖ]����B ����������[�Ă���тȂ�������G�Ɉ��� �u���m�͈ꓹ���Q�l�݂̂ƌł��ӎv������A����҂Őg�𗧂Ă悤�ȂǂƎv���Ă͂Ȃ�ʁv�Ɖ��߂Ă���B ����͓����悤�ɍ���Y�̑咃�q���������āA��q����̒�����J�� �u���ꂱ���^�ɑ喼�̎��ׂ����̂�v�ƑA�]����Ă����ےÎ��̍r�ؑ��d(*1)���v���o���Ă̐e�S���낤�B �߂����V���Z�N(�����)�A�r�ؑ��d���M���̖��Ŗ{�莛�ւ̍u�a�g�ƂȂ��ĕ��������̂̎��s���A �u���̂܂܂ł͐M�����牽���Ǖ�������画���v�Ɣ������N�������B ���̖��ɁA���d�́A����Ɛb�������A�k�M�܂ƕ]���ꂽ�Ȃ������a���Ȃ���A�ЂƂ�����ɓ������т�B �M���̎���A���O�Ɩ������߁A�������������O���ɕ�炵�Ă����̂ɁA�G�g�̑����O�ɏ�����A��x�ڂ̋{�d���ɏo���B �ꎞ�͕Ԃ�炢�����A�G�g�������ō��R�E�߂��ق߂�ƁA�r�ؑ��d�́A�̂̉E�߂̗����Y�ꂸ�A �u�ނ͌��s�s��v�Ȓj�ł�����B�v�Ƃ��Ȃ����B���ׂ̈ɖ�����Ǖ�����A��т����v���Ă���B �� (*1) ���炫�ނ炵���B���x���N�̂ЂƂ�B���q���G���4�N�O�ɐD�c�M���ɔ��t���������Ƃ��ėL���B ���D�c�M������C�ɓ����āA�V�����N(1573�N)�A��؏��ɁB���N�A�M���������`�����U�߂��Ƃ��A�F���U����U�߂Ō����������B�V��2�N(1574�N)�A�ɒO���B�V��6�N(1578�N)10���A���d�͗L����ɂē˔@�A�M���ɑ��Ĕ�����|�����B ���M�����{�\���̕ςʼn�������ƍ�ɖ߂苏�Z�B�L�b�G�g���e��������ƁA���Œ��l�E�r�ؓ��O�Ƃ��ĕ��A�B�痘�x��Ɛe�����������B�V��14�N(1586�N)�A��Ŏ����B���N52�B�@ |
|
| ��3 �܂ق�̗��� �@ | |
|
��(1) �א�H�ցA����
�c���\�ܔN(��Z��Z)�̔N��������ƁA�L�b�Ƃ̍��͂��X�����Ɖ]���鋞�s���L���̑啧�a�Č����i�ޒ��ɁA�����Ƃ̈ɉ����̉��C�H�����}�e���|�Ői�s���Ă����B ���������n��ƒz��̖��l�E���Ղ����ɁA�c����N(��Z�Z�l)���璅�H���ꂽ���̕F���̈�ɏ�Ƌ��ɁA���U���̓��̕t��ƂȂ鎖�͕S�����m�������B �u�Â͋x�����A�ɉ��삱����l�w���̔鑠�̏�v�Ɠ��{��̍��Ί_�̌��łȕ��R�邪�o�����āA�ɉ�̐l�X����������B �Ĕ����ɂȂ�ƁA���s�ԍ�(*1)�̓����ŕ���ȗ]�����y����ł����א�H�ւ��a�ɐN���ꂽ�B���[�ւƓ������A���q�E�������}�O�l�\�ꖜ�̑��ƂȂ��Đ��ɂƂ��߂��Ă��Ă��A������ւ͍s���Ȃ������B ���[�ւ́A�l�G�t�H�̕ς�ڂɂ́u��������ɗ����v�ƗH�ւɏ�����Ă����悤���B���n��͉���ȗ��[�ւ��A�����̓��ɂ����Ă͉����̗v��ʒm�Ȃ����ɁA�}�������ɕ������B������H�ւ̕a���Ɏ����A�߂����̎v���o�����A�݂ɂ��ꂩ���̐��̗�����Ă��������̗�������ɂ��݂ʂꂽ�B�H�ւ́A������\���A���s�O���ԉ����̎��@�Ŏ����B���N���\���B �����ėH�ւ̎���m�����o�O��́A�Ăэ]�ˈڏZ�������߂��B���������[�ւ͑��ς炸�u�킵�͑�a�̗[�邪�D�����Ⴉ��v�Ə��đ���ɂȂ�Ȃ������B����͖��m�̉]���u���X��ɂ̗��}��҂��A�[�X�Ō�̋߂Â��̂���ԁv�����߂����Ă����̂��낤�B �� (*1) �ԉ����̌�L���B�ԉ����́A���݂̋��s������͌����ʎO���B�ԍ㒬�́A���s�s������[���B�@ |
|
|
��(2) ��쒷���A���������A����
�₪�Čc���\�Z�N(��Z���)�̔N�ɓ���ƁA�₩�ɏ㗌�����ƍN���G���������u�Ăы��ނ悤�Ȃ�v�Ɗo������߂��B �����m�������������A���������A���K��(*1)��q�����̑喼��́A�a�闄�N��������āA�����ɑ̖ʂ����܂��A���A���̐l�X�����S�������B �ނ炪���݂ł������A�L�b�Ƃ͈��ׂ������낤�ɁA���̏t�A��Ð�쒷�����v��(*2)�A�����ĘZ���ɂȂ�Ɛ������a�ɕ����B �����m�����G���͋����đ�펛�̋`�~�ɉF������������A�a���͏d���Ȃ����ł���B �����Ĉ��[�A�������a���ɑ��q�������A����̘_������o���Č��ɂ́A �u�O�c���ƌ��̕a���d���ƕ����A(���A������)�����ɎQ�サ�����A�����łɒU�[�ɔ��������ƌ��́A�w���}�A���ɗՂ݁A�g��[��(����)�a�A�ЂƂ��ɏG���̂��Ƃ����ݐ\���h�ƌJ�Ԃ��ꂽ�B�Ȍ�킵�́A��ɁA���̖{(�_��)��S�̎x���ɐs���ė������A��������Ȃ��Ɍ�����B�[���n�ǂ���āA�b�߂�S��������A���X�����肢�\�����x�Ɨ܂𗬂��ꂽ�B�R�����̍��́A�Γc����(�Γc�O��)�߂������āA�{��ǂޏ��ł͂Ȃ��������A���ɂȂ��ēǂ�Ō���Ɂw�ȂĘZ�ڂ̌ǂ�����ׂ�(��)��߂ɗՂ�ŒD���ׂ��炸�B�N�q�l���B�N�q�l�Ȃ�(*3)�x�Ƃ̏͂��S�ɒɂ������݂�B����G�������A�͂��Z�\�ܖ��̐g��ɗ�����ꂽ�̂����āA���}�q���̎҂̓������A��Ƃ��X����v���������ƌ��A�Μ��Ɋ����ʁB���̏�͉ƍN�����A�ǂ����N�q�ł����Ė]�������̂���B�v�Ƃ��݂��ݒQ���Ȃ��琢������B(*4) �� (*1) �����̂悵�Ȃ��B1576�`1613�B�I�ɍ��I�B�˂̏���ˎ�B��쒷���̒��j�B ���V��18�N(1590�N)�Ɍ�k��������(���c������)�ɎQ���B���\�E�c���̖��ɂ����ƂƂ��ɌR�𗦂��ďo�w�A�c��2�N(1597�N)�ɉU�R�`��(���݂̉U�R�L��s��)���ď邵�A����B �����\2�N(1593�N)�ɕ��ƂƂ��ɍb�㍑�{��(�R�����b�{�s)��^����ꂽ�B���\4�N(1595�N)�A�֔��E�L�b�G���̎��r�ɘA�����A�\�o(�ΐ쌧����)�ɔz���B�O�c���Ƃ̂Ƃ�Ȃ��������Ă܂��Ȃ����A�B ���c��3�N(1598�N)8���̏G�g�v��́A���N�łƂ��ɐ�������������E���������畐�f�h�ɗ^���A�ܕ�s�̕����h�E�Γc�O����ƑΗ��B�c��4�N(1599�N)�̑O�c���Ɩv��ɂ͕����E������Ƌ��ɐΓc�O�����P���B ���c��5�N(1600�N)9���̊փ����̐킢�ł͓���ƍN�����铌�R�ɑ����A��{�R�t�߂ɕz�w���Ėї��G���A�������ƂȂǂ̐��R�������������B���ɂ͋I�ɍ��a�̎R��37��6���^������B�c��16�N(1611�N)�̓����ɂ�����ƍN�ƖL�b�G���̉�k�ŁA���������Ƌ��Ɍx�����s���B�c��18�N(1613�N)8��25���ɘa�̎R�Ŏ����B���N38�B�j���������������߁A��̐�쒷�����p�����B�揊�́A�a�̎R���̍���R���n�@�B�a�̎R�s����̑����R��B (*2) �L�b�����̌ܕ�s�̈�l�B�c��16�N(1611)4��7���v�B���N65�B�ǍO�F�엎�����Q�ƁB (*3) �Z��(�肭����)�̌ǂƂ́A�������������Ă݂Ȃ��q�ƂȂ������N�B��l���S���Ȃ��āA��p�҂��܂����N�ł��鎞�ɁA���̎ア���N���Ɏ��A��펞�ɗՂ�ł��A�����Ă��̌��͂�D��Ȃ��l�B���������l�����A�N�q�l(�^�ɑ��h���ׂ��l)�ł���A�Ɖ]���Ӗ��B�w�_��(�ה��攪)�x (*4) �c��16�N(1611)6��24���v�B���N50�B�@ |
|
|
��(3) �^�c���K�A����
�����ĊԂ��Ȃ��A��x�R�̐^�c���ł��u�ƍN�̋S��v�Ƌ����ꂽ���K���v�����A�Ɖ]���]�A��a��~�ɂ������B(�c��16�N6��4���v�A���N65) �����m�������[�ւ́A������Ə̂��ꂽ���s�ؗ�ȑ��邪�傫���X�����悤�ȑz���������B�����ƉƍN�߂́u�҂ĂΊC�H�̓��a����v�Ƃ������Ԃ��Ă��邾�낤�A�ƓV�̔��Ɋ������ɈႢ�Ȃ��B �u�^�c���K�a���S���Ȃ�ꂽ�v�Ƃ̔ߕF��{�{�̒n�ɗ��ꂽ�̂́A�c���\�Z�N(��Z���)�̎����ŁA�^�c�ꑰ�Ɠ��������˂̊Ď����ɂ������V�{�s��(*1)�͂�������R���p�ɂȂ��ď\�Ð��������B �Ɖ]���̂��^�c�ꑰ�ƐV�{���͐[���Ȃ��肪���邩�炾�B���Ȃ킿�A���}�ݐ����ɁA���ɐl���Ƃ��āA����ʼn߂������Ȃ̂ł���B�^�c�K���̐����Ȑl�������āA�N���̍s���͌Z�Ɏd����悤�ɐڂ����Ƃ����B �K���́A�G�g�Ɍ����܂�āA�g�]�܈ʃm���E���q�卲�h�ɔC�����A�L�b�̐��܂ŋ�����A��J�Y���̖����Ȃɂ��ĉƒ���������B���̍K���ɑ��āA�s���͂܂�Œ�̔@�����̉Ƃ�K��ĎG�p���Ƃ߁A�V�Ȃ���傢�ɗ���ɂ��ꂽ�B�K�����܂� �u���Ȃ��̌����ɂ͉��Ƃ��Ԃ����点�Ă��˂̂��v�ƍ���܂��Ă���A����悭�g���n��h�ɔC�����āA��(�x�����P)������Ă���B ����Ȃ��Ƃ���^�c(���g��)�Ɩx��(���[��)�̗�����̎�͐e����[�߁A�փ����ɂ͋��ɐ��R�̗E���ƂȂ��ĕ��킵���B���K�͏�c��ŁA����G���Ɩ{�����M��z�낤���āA�O������̑�R����ɒx�ꂳ���Ă���B ���P�͈ɐ��p��~��\�����Đ��C��������ƁA�Ï�̍U���ɑ���𗧂āA�������R�������ċ���Ώ\�����̑喼�Ƃ��ĈېV�܂ʼnh�����ɈႢ�Ȃ��B �����Ĕs���A�x���͌F��O�R�匟�̐_������A�^�c�͑��q�E�M�K�Ɖł̕��E�{�������Y�̐s�͂ŁA�������͏��������B ��B�̐�����(�x�����P)�ƋI�B��x�R(�^�c���K)�ŋ��ɉƍN�݂Ȃ��� �u���}�Ƃ̋`�ɔw���A�N�q���铹�ɔ������j�������܂ł��h���锤�͂Ȃ��B�K�����߂ĖS�ڂ����ɒu�����̂��v�Ɠl�u�ɔR�������Ă����̂ɁA�ɂ�������Î��P�A���x�͏��K�������������͖̂L�b�ɂƂ��đ傫�ȒɎ�ł������B �� (*1) ���� �䂫�Ƃ��B1596�`1645�B�����͖x�����O�B�I�ɍ��V�{���E�x�����P(*1-1)�̒��j(�Z�j�A�܂��͒�Ƃ�)�B���`(�������Y�`�Ƃ̓���)�̏\�j�E�V�{�s�Ƃ�c�Ƃ���B��̖��͎ዷ��B ���L�b�G�g���V���ꂷ��O�ォ�炻�̉Ɛb�ƂȂ�A�փ����̐킢�ł͐��R�ɑ����ĉ��ՁA�v���B �����K�����I�ɍ��a�̎R���ɕ�������ƁA�s����500�ŏ���������ꂽ���A�ҋ��ɕs�������ڂ��ďo�z�B �����̖��ł́A���̉̂���300�l�𗦂��đ�쎡�[�̊�R�ƂȂ�A����Ɉɓ������̕����ɑ������B���Ă̐w�̓V�����E���R�̐킢�ȂǂŊ��A�I�B�Ꝅ��������邱�Ƃɂ���ċ���E���Ƃ����������Ă���B �����邪���邷��ƈ�U���ꂽ���̂́A��a���ŏ��q�d���R�ɕ߂炦���ĕߗ��ɁB���̌�A�O��̖x�����v(����A�܂��͉��Ƃ�)�̐�P�~�o�̌��ɂ��͖ƁB�ɐ����Ôˎ�E�������Ղ̉Ɛb�ƂȂ����Ƃ����B�܂��A�ِ��ɂ͑�a�����c�ˎ�E�Ћˎ���70�Ŏd�����Ƃ��`���B (*1-1) �x�����P(�ق�̂��������悵)�B1549�`1615�B����Ƃ��B���[��B�I�ɐV�{�̎�B�x�����͌F��V�{�ʓ����X���߂��ƕ��ŁA�V�{�𒆐S��2��7000 ��(�����6����)�̒n���x�z���������ł������B �����P�͓V��13�N(1585)�ɖL�b�G�g�ɑ����Ė{�̂����g����A���N�̖��ɍۂ��Ă͐��R�𗦂��ď]�R�A�W�B�U�߂ȂǂɊ����B ���c��5�N(1600)�A�փ����̖����N��Ƌ`���ł����S�×��ƂƂ��ɐ��R�ɑ����Ĉɐ��N�U���邪�A������͂̔s������d�B����V�{������R�ɍU�ߗ��Ƃ��ꏊ�̂������A�I�ɉ��c����孋������B ���̂�������Ĕ�㍑��̉��������Ɏd��2000��m�s���A�F�y���a�����A�c��14�N(1609)�ɓ��n�Ŗv�����Ƃ����B�������A�v�N�ɂ��Ă͌��a���N(1615)��������B�@ |
|
|
��(4) �V�{�s���A�L�b�G������U����
�̂���^�c�Ƃɂ͑t�m�������`���A�F��R���B���҂ݏo�����Ɖ]���E�@����X�`���A���̓����E���B���E�q��́A���K�̖������A�]�ˁA���̓��Â���f�Ȃ��������Ă����B �����孋��������N���d�˂閈�ɁA���̐����͋ꂵ���A���̍��͕Č\�ł͂ƂĂ����肸�A�Ɛb�B�͋ߍx�Ŏ������A�^�c�R���s�����ē��X���x���Ă����悤���B �s�����^�c����K�˂��̂͘Z���̖��ŁA��K���́A�Ē��ƎR�ł��ĂȂ��A��ӂ��܂Ō�荇�����Ɖ]���B���ɗD�ꂽ��ؗ��R�w�҂����ɁA���̈�u���p����������Ȃ��������͂Ȃ��B �����čs�������̋A��ɑ�a�̗��[�ւ�K�˂��̂́A�邩�ɏG������ �u���邷��Ύዷ��ɔC���A�喼�i�Ƃ��Ĉ����v�Ƃ̓��ӂ��Ă����̂ŁA���c��X�ዷ��𖼏���Ă������[�ւ̗�������Ƌ��ɁA����b�������������̂��낤�B �s���Ɨ��[�ւ̐e���͑O�q�����悤��(*1)�\�N���̉��ŁA�s���͗��[�ւ̐l���ɓ��ꂳ�������Ă�������A�{�{�ɋ߂��n�ɕ邷�O(���[�ւ̎q)�Ƃ͌Z��̂悤�Ȓ��������B ����Lj������ɂ��āA���[�ւ̋������@�����s���́u�O�ꑰ�̕��a��j��悤�Ȏ��͌����Ă��ʁv�ƖāA�ʂ���������炵���B �� (*1) ��a�S�����Q�ƁB�@ |
|
|
��(5) ���[�ւ̈⌾1
������߂��镗�_����i�Ƌ}�������钆�ɁA�c�i�\���N(��Z���)�̐V�N���K��A���[�ւ͔��\�˂ɂȂ����B ��N�̂悤�ɔN��ɂ���ė����O��Ƃ�P�g��Ɉ͂܂�āA�̂ǂ��ȏ����𗁂тȂ���A�䂩��̋����䗅��˂̎ᐅ�ɐg�𐴂߁A����_�Ђւ̏��w�����܂����B ���ꂩ��C���悭�N�h�������������A�����������̂��B�R�Ƃ����ʎ��Řb���n�߂��B �v����ꡁX�Ɣ��\�N�̒����������悭���������čڂ������̂�ƁA�_���Ɋ��ӂ��鑼�͂Ȃ����A������̌�������B���C�ȊԂɁA���������Ă��鎖�����A���Ȃ���Ɍ���Ēu�����B��������Ƌ��Ɏ��߂Ēu���Ă���B �߂����V���O�N(��O�l)�߂̍A��a���苽�ɐ����������킵�́A�c��������w�t���_���̐��n�ɎY�ꂽ�҂́A���ɐ_���сA��c���h���A�������O�k�Ƃ��āB�܂��A����ɂ��܂�����ɂ��ޑ�a���m�Ƃ��āB���X����̋Ƃɗ�݂��A����̂����Ȃ݂�Y�ꂸ�A���̈����m��L�ׂ̐l���ƂȂ�v�x�ƌ������b����ꂽ�B �����ĕ��̓��ɏA���ẮA����_�Ђ̊y���E�ł������ϐ���傩��\�y���A�����A���ԁA�A�̂ɏA���ẮA����̗������������m�@�Փa�̈�Ԓ�q�ł���R��@��a�Ɏt�d���� �u����������A�a�h�Î���|�Ƃ��A�������̂Ƃ��т���Ƃ���v�Ƌ������Č��r�������肶��B�@ |
|
|
��(6) ���[�ւ̈⌾2
�R���Ȃ���A������������������t�̗����̒������ɁA�S�Ȃ炸���C���̍J���n�炴��Ȃ������̂́A���Ȃ�����悭�����ċ��낤�B ����Ȓ��ɁA�v�炸���M�����́u�V���z���v�̎P���ɉ������A���G�a�̗^�͂ƂȂ��Đ�w�����ɂ��A�ނ̐����N�b�̋`���d�鉤���v�z�Ɋ������u���������ɂ���v�ƌ��ӂ����B �c�O�Ȃ���A���̕��^�͂��Ȃ��u��E���v�̉����ɂ܂݂�錋�ʂƂ͂Ȃ��Ă��A�N�q�l�Ƌ��M���ɂ͕ς�Ȃ��A�R���ƂȂ��ČF��ɗ����Ȃ������ɐS�ɂ������̂� �w���m�̉R���Ɖ]���A�m�̉R�͕��ւƐ����B����ƂĕS���͉��䂫���̂ł����邼�x�ƈ₳�ꂽ���t�ł���B �킵���g���m�͈ꓹ���Q�l����A��x�Ɣe���͕��܂��h�ƁA�{�d���������A�����Ɏ������̂́A�Ђ�������Ƃ̐������ʂ��ׂł������̂�B �M�����͐��ɕs���o�̓V�ˎ��Ƃ͉]���A���̂߂������e���͂킪���̂ɂ͋����ꂴ����̂ł������B �����������G�g�́A�����܂Őb��������ČÍ��ƕ��̉p�Y�ƂȂ�A�V���ꂵ���̂͌����Ɖ]����B�������֔��ƂȂ��ĈȌ�́A���F�Ɩ������×~�̂܂܂ɁA�������Ƃ����v���ʔӔN�ł������B �����ĔނɎd���đ�V�M���ƂȂ�A�V����̗��`�҂�Ǝ^����ꂽ�ƍN���A���悾���� �w�V���͔n��Ő������Ă��A�n��Ŏ��߂邱�Ƃ͂ł��ʁB�V���̐l�S�����ߓ��Ă����^�̓V���l�Ȃ�x�Ə̂����ƂāA���̐S��̔ڗ͒f���ČN�q�l�Ƃ͉]���ʁB�₪�Ă͐M���ȏ�̔e���ƂȂ�A��̎q��S�ڂ��A���삳�����x�z���Ɏ��߁A�����A�����̂߂������@���A�Ȃ̌����Ђ���𗧂Ă�Ƃ����]�ނ��낤�B �o�O��͔ނ���N�Ƃ������̂ɁA�ۉ��Ȃ����̖��ɏ]�킴��ʂ��A����͕��̕������������A�����ċ{�d���͂����A��ɖ�ɍ݂��ĉҋƂɗ�݁g�����Ɛ����h���|�Ƃ���B�@ |
|
|
��(7) ���[�ւ̈⌾3
���[�ւ́A���N�Ŕ��\�Ƃ͎v���ʋC���œ�l������ �u�O��B���Ȃ��͌F��ŁA�킵�̑n�Ƃ̎u���p���ŁA���l�ɖ𗧂F���ˉƂ�z���̂���B�����čP�g�́A���c��X�̖���܂ق�̒n�ɍ݂��āA�����Ƃ̎k�q�ƂȂ�A��_�ꑰ�̔ɉh�ɐs���Ȃ�����A�{��������ˉƂ̕������낵�����ނ��v�Ɩ����ē�l�ɐ��X�̈�i���I��ƁA���͂�v���c�����Ƃ͂Ȃ��A�Ɖ]�����ʎ��� �u���ĕ���̓��ɂ��āA���͔\�ƒ����ɋ��߂����A��������݂̂ɂ�����炸�A�A�́A���ԁA�����A���悢����ɂ��悱�̓��͍L�傶��A������̍D���ɂ����B�Ȃ�ǁA�f���Č��͂▼���ɛZ�т��A�^�́g��тƂ��сh�ɊJ�Ⴗ�鎖�B����ɂ͉�Ƃ̉ƕ�ł���g�T�䓛�̍��풃�q�h���g�V����̈�˒��q�h�Ɛ��ɍL�߂Ă��ꂽ�R��@��a��A���̎t�E���x���m�a�̐��Ԃ���������Ɛg�ɂ���̂����������v �����]���Ȃ��痢�[�ւ́A���̒m�Ȃł������R��@�A�G�g���玨�A�@�����̎S�Y�ɂ��B�R�Ƒς������̐l���A�����āA���x���A����������O�̈��̒��m���҂Ƃ͉]���A�V���̖��l��搂��A�喼���������͂��ւ����ނ̐�R���n�̗E���ɏ��鍋���ȍŌ�������^�����B �u�������Ȃ���A�킵�ɂ͔���ʂ̂��A���x���m�́A���́A���}����O����̘\���������A�Ɖ]�����Ƃ�B���m����҂̏K���Ƃ��āA������ȏ�́A���E�^�D�̌�������o�傪�̐S����B ���x�a�́A �w�̂ђ��̐S�́A���̏����~�ɂ������B�Ƌ��̌��\��H���̒����Ȃǂ͑����̂��́B�Ƃ͉k�炸�A�߂͒g����Ηǂ��A�H�͋Q���˂Ώ[���ł���B�����^�сA�d�����āA�������A���𗧂āA���ɋ����A�l�ɂ��{���A����ۂނ̂݁B���Ԃ��̂݁@�҂��l�ɁA�R���́@�_�Ԃ̑��́@�t��������B�x�Ɖr�����B ���̔ނ��A���}�ɕ�����ꂽ�B������̑��}������A�������R�̒z�������t�A��t�ɗ��ʉ��������̐v�𖽂���ꂽ�͓̂��R�Ƃ��]����B �����܂Łg�̂ђ���h����ނȂ�A�{�d��������ׂ��ł͂Ȃ������Ǝv���B ���}�́A���x�����f����A����̋M���⍂�m��̍D�݂ɉ��������������������߁A�Óc�D���ɖ����ď��@����ƒ뉀���̍��s�ȑ喼������n�点���B ����Lj�N��ɂ́A���߂ɂ������x�̒��j�E�����Ǝ��j�E�����������Ă���B��������B�̍א쒉���ɁA��������Â̊��������ɁA�ĔC���������̂͌���������炾�낤�B ���̎����悭���L���āA���Ȃ���͂����܂Ŗ�ɂ����Ĉ�|�ɓO���A������Ƃ炷���z�̉��ɁA�厩�R�̒��́g��тƂ��сh��g�ɂ���悤�ɂ���B ���ꂪ������a�̗H���\�ɂ��ʂ��铹�Ȃ�A�Ƃ킵�͍l���ċ���B�v�@ |
|
|
��(8) ���[�ցA����
���X�ƌ�����͂�������̈ꌎ�ܓ��̗[���B ���[�ւ́A���R�ɒ��ޑ����ȗ��z�Ƌ��ɁA���R�Ɛ����������B ���[�ւ̑��V�́A�ꌎ�����A�{�������ŁA�m�Ȃ݂̂ł܂����Â��ꂽ�B���̗҂����L�l�������S�Ȃ��l�́u���ꂪ�̌��喼�̑������v�ƈ⑰�B�������Ɖ]����B ����ǂ���͔ނ̈⌾�Łu�֓��̌Z�B�̋{�d�������܂�����ȁv�Ƃ̌��t���������̂��낤�B ���̉������A�@�a�勏�m�ȂǂƉ]�����̂łȂ��u���[�֑P���v�̌��ɉ߂��Ȃ��̂����Ă��A���̐l�����Â�A������ł���������q�B���u�������Ɍ��͑����ʁv�Ǝ^����l�������B �g�l�͓Ƃ萶��āA��l�����Ǝ��ʁB���{������̂����܂��������ǂ��h�Ɖ]���̂����[�ւ̈�u�ł������͉̂]���܂ł��Ȃ��B�@ |
|
| ��4 �������L �@ | |
| ��4.1 �~�̐w�Ɩk�R�} �@ | |
|
��(1) �ї��R�A�ƍN�̈ӂɉ���
�c���\���N(��Z���)�āA�ƍN�́A�������|�̒�q�ŐV�i�C�s�̊w�җї��R���Ăт����B ��N�Ɠ��������ɍڂ� �u�\�͕�������N�����̂́w�t�揇��x�ł��舫�ł�����P�ł�����Ǝv�����A�ǂ�����v�Ɛq�˂��B ���|�Ɣ�ׂĖ�S�ɔR���A��p�w�҂̌��{�̂悤�ȗт́A�ƍN�̈ӂɉ��� �u�����v���܂��ɁA�����͓V���ɏ����A�l�S�ɉ��������̂ŁA�����Ĉ��ł͂Ȃ��A�ނ���V���𗐂��别�l�E�@�����������P�ƍl���܂��v�Ɠ����Ă���B(*1) ��������ƍN�́g��ӂ���h�Ƃق����B�Ȍ�͗т��A����V�V�C�A���n�@���`�瑤�߂̈�l�ɉ����A��ɑ�w�m���ɔC���A�v�̎�q(*2)�̊w���{�̊��w�Ƃ��Ă���B ���ɉƍN�͎��\���z���ċ���A���̓����ɂ������܂��� ���䏊�`�́@�Ƃ�n���ā@�����ɂ���A�̉��ɂ��ā@�E���G���B �ȂǂƉ]���������������A�����̐l�S���G���ɗǂ��A�����ł���̂��@����ƁA �u���R�̉]���悤�ɁA�V���ɏ����A�ڂ̍��������ɉ��Ƃ��G����S���ċ����˂A����̓V������Ȃ��v�ƒɊ����A����͎�i��I���A�킢�ތ��ӂ��ł߂��B �� (*1) �I���O1100�N����̒����́u�u�v�ƌĂ�A�@��(���イ����)�́A�u�̑�30��A�Ō�̒�B�h(����)�A��(����)�Ƃ��Ă��B�\�s�Ȑ������s�Ȃ����鉤�Ƃ���A���̕����ɖłڂ��ꂽ�B (*2) ��q(���サ1130�N - 1200�N)�B�����̓�v��̎�w�ҁB����(���カ)�̑��́B�̑̌n����}�����̒����ҁB�u�V�v�̎�q�w�̑n�n�ҁB ���������N(1199�N)�ɓ��v�����^���@�̑m�E�r?(����傤)�����{�֎����A�����̂����{�`���̍ŏ��Ƃ���邪�A�ِ��������B ������V�c���ؐ����́A��q�w�̔M�S�ȐM��҂Ǝv���A���q�ŖS���猚���̐V���ɂ����Ă̂����̍s�������́A��q�w�Ɋ�Â��Ă���Ǝv����ӏ�������������B �����̌�͒�B�]�ˎ���A�ї��R���A���̖����_�Ɛ����̊�b���O�Ƃ��čċ��B�]�˖��{�̐��w�ɁB�������A���̎�q�w�̑䓪�ɂ��u�V�c�𒆐S�Ƃ������Â��������ׂ��v�Ƃ��������^�����N����A��̓|���`�����ېV�q����B ����q�w�̎v�z�́A�ߑ���{�ɂ������e����^���A�R���̈ꕔ�ł͓��ɐS�����A��E��Z�����▞�B���ςɁA�����Ȃ�Ƃ��e����^�����Ƃ�����B�@ |
|
|
��(2) �ɉ���̓V��t�A���ɂ��ĕ���
�㌎�ɂ͈ɉ���̓V��t���o�����ĕ��_�͈�i�Ƌ}�𑝂��B�������A�ł�������ܑ̌w�̓V�炪���ɂ��ĕ��A���\�l�̎������o���Ɖ]���������u�����āA�ɉꒆ������������B ����͋㌎����̂��ƂŁA���܂������_�Ƌ��ɂ܂��N������w�̗����ɂ���āA�̍���������V��t���A���낭�������Ɖ]���邪�A �u�����������ɘV�m���鉺�Ɍ����w��_���g�����M��ɂ���Ă₪�ēy��(����)�ɂ���ēV��͕K������邼�x�Ɨ\�������v�Ɖ]���`��������B���́A�ƍN�̖��ŁA�������Ղ̎�ɂ���ĉꂽ�Ƃ̐�������A�i���̓�ƂȂ��Ă���B�@ |
|
|
��(3) �ƍN�A�푈����
����Ȓ��Ɍc���\���N(��Z��O)�ɓ���ƁA���{�͌��Ə��@�x�Ⓔ�����ߓ����߂ĖL�b�ƂɍD�ӂ��������M���̌����𐧌������B��c(��z���V�c)��㐅���V�c���Ђǂ��{�点���̂́A�����`����D�c�M���Ɠ������A�����̏�ɗ��ƍٓI�e�҂��߂���������ł���B ��X�w����(*1)�x���n�ǂ��āA��������k�{�̐������܂˂��ƍN�����Ɂg�V�q�͉̓�����ɂ��Đ����Ɋ֗^�������A�喼���Ў��Ƃ̌��т����ւ��A�h �Z�g���[��ɑ�鋞�s���i���z���ĊĎ��������B �X�ɁA�ƍN�͂��˂Ă��L�b�Ƃ̍��͂��͊�������ׂɁA�ɐ��A�F��A�j�R�A�Z�g��Ђ̑��c��i���S���G�g�̋��{�ׂ̈̕��L���̍ċ����������߂��B�����m��ʗ��N�͐_���̉���ɂ���ĖL�b�̔ɉh��ۂ���Ƃ��ĂЂ������i�𑱂����B�啧�a�̌��������ł����\�l�����A��O��сA�ē�\�O���𓊂��A���̑��v��ĂɊ��Z����ΎO�S���Ɖ]�����z�ɒB���Ă���B ���̈���ŁA�ƍN�́A���F�b���I�����_�D���甜��ȑ�C�ƒe����w�����āA�푈�������}���B�܂��A�ޗǕ�s�E���V����(*2)�ɖ����āA�܂����̎��ɂ͏\�Ð싽�m��]���������Đ�͂����߂����鏈�u���Ƃ����B �X�ɁA�c���\��N(��Z��l)�ɓ���ƁA���˂Ĉ�ˊo�O����v������Ă�������ƍċ��̎�i�Ƃ��āA�莟�ƕs�����������Z�ꑰ�̓����c�A��V�Z����S�R���Ƃ��Ĉꖜ��^�����B�܂��A��S�Ύ�̗^�͎O�\�Z�R��n�m����I�B�����āA�L�b���̓����Ď��𖽂��A��a�A�ɉ�̕��_�͈�i�Ƌ}��������B �� (*1) �w��ȋ��x(���Â܂�����)�Ƃ́A���{�̒����E���q����ɐ����������j���B�u���Ӂv�Ƃ������B�S52���A��������45���͌������Ă���B���q��������������ł̊�{�j���ł���B ���������̋�������4�N(1180�N)4���Ɏn�܂�A�����E���i�̗��A���q���{�����A���v�̗����o��13���I���ɏ@���e�����A�����镶�i3�N(1266�N)�܂ł�87�N�Ԃ��A���L�`���ŋL�q����(����)�B�k�����̗���ɂ�鎖���̘c�ȂƎv����ӏ������Ȃ肠��A���̎j�������킹�ĎQ�Ƃ���K�v������B ���㐢�̕����Ȃǂɂ����ǂ���A���ƌ�k�������������Ă����ʖ{(�k��{)��1603�N�A����ƂɌ��コ�ꂽ�B����ƍN�͌��������𑼂̑喼�Ƃ���W�߁A1605�N(�c��10�N)�Ɂw��ȋ��x��؊����Ŋ��s����(51���A�����łƌ�����)�B�ƍN�̍��E�̏��Ƃ��āA���{�^�c�̎Q�l�ɂ��Ă����Ƃ����B (*2) ���䏇�h�̉Ɛb�E���V�G�S�̎q�B���V���ߏG���B��ˎ�B�ƍN�Ɍ��o����ċ|�����{����ݐi���A���̖v��ɓ������ޗǕ�s���߂��B�@ |
|
|
��(4) �^�c�K���ƐV�{�s��
�����������x�R�̐^�c�K���́A������̑��U���̐ؔ���m�����B��x�R�ߍx�ɎU�݂��Ď������Ȃ��疽��҂��Ă���Y�}�B�ɐ킳�d�x�ƐM�B�e�n�̗L�u���U�ɏo���������̂͌c���\��N(��Z��l)�܌��ł���B �����čĂіK�ꂽ�V�{�s��(*1)���� �u���̍��v��Ɛ��ۂ̌��Z�͔@���Ɂv�Ɛq�˂��A���̂悤�ɓ������Ɖ]���B �u�L�b���ڂ̗E�������X�ɐ����������̂́A�V�^���L�Ƃ��������ꂽ���Ƃ��v����B���{��̋���Ɖ]���n�̗��͂����Ă��A���C�ȗ��a����̒������ʐD�c��傪�������ւ錻��ł́A�l�̘a�͖]�߂��A�����ɉ]���āA���Z�̌����݂͋ɂ߂ď��̂�������B �R���G���������}�̈�ǂƂ��Ă̌ւ�ɔR���A�ŖS���o��ŋ��������Ȃ�A��������ɉ����A�`���т��ĕ��킵�A�^�c�̕�����V���ɍ�������o��ł���A���炭�M�������̌��ӂƌ��āA��̓���Ŗ���������ł����邪�A�@�����ȁB�v �Ɣ����̕��e�ɂ͓N�l�̂悤�ȈЌ����사��A�n�߂Č�����K���̓V���̌R���ƂԂ�ɂ͍s���͐[�����������B �u�悭�Ŗ����ĉ����ꂽ�B�َ҂��F�쐅�R�̗Y�Ƃ��čL���m��ꂽ�x���Ƃ̒����Ƃ��āA�������̐܂ɂ́A���s�A���~�𗣂�đ��ɓ��邵�A�S�����E���[��̈⌾�ʂ�A�͂̌���킢�����A���s�s�Ȗ�]����ɂ���ƍN���q�Ɉ����ނ����A�����j�Ɏ~�߂ĎU��o��ł�����B������ɕ��v�̎��Ԃ��炩���\�����B�v�ƌł��j�̖����� �u�J��͍��H�܂łɂ͕K���Ȃ�A���ɐ��X��������v���ׂ��v�ƃJ���J���Ə��ĕʂꂽ�ƍs���͋L���Ă���B �� (*1) �܂ق�̗������Q�ƁB�@ |
|
|
��(5) ���N�A�����̗₽����m��
�����Čc���\��N(��Z��l)�����A����Ȕ�p�Ə\�N�̍Ό��𓊂��āA�Q�����L���啧�a���������A���c���{��҂���ƂȂ����B���̍��A���˂ĉƍN�̈ӌ������{�����M���q�����V�V�C�A���n�@���`�A�ї��R��̃u���[���B�́A�x�X�̖d�c���d�˂����ɁA���X�Ɩ������𐁂��������B����̉ʂɏ����ɕs�R����Ƃ��� �u������̂Ăč��ւ��邩�A�G�����]�˂ɋl�߂邩�A���N���l���Ƃ��č]�˂ɏZ�ނ��A�����ꂩ�Ɍ��߂�v�Ɣ���B������ƍN����ł͂Ȃ��A��⑤����\���o��A�ƕЋˊ���(*1)�ɖ������̂́A�J��̐ӔC����������ł���B�����m�������������� �u���̂܂܂ł͑��������{���ċ�������ɈႢ�Ȃ��A�����ĖŖS����͕̂K���ł���B���Ƃ����Ȃ���v�Ƌ}�g�𑖂点�A �u���̂��ܗl���A���]�˂ɉ����A�ƍN���Ɍ�Ζʂ��Č�l�ׂ̈ɍ]�˂ɍݏZ�����̂��G�����̌�^���v���v����B��̍�ŁA�����Ȃ��Ύ��ł̓������Ȃ��v�Ƃ����|��i�������A���N�͈�w���𗧂ĂĕԎ������Ȃ������B �G�����A���l���ɂ��Ă܂ň��ׂ��v����A���}�̎q�Ƃ��Ēf�Ő키�o������߁A�c��������[���M���Ă��������̓o������߂����A�a�Ə̂��ďo�d���Ȃ��B��ނȂ��Ǖ��𖽂����̂͋㌎���ł���B�\���n�߂ɂ́A�L�b�q���̑喼�B�ɁA����v���̎g�҂���Ăɔ�B �R�����݂Ƃ����喼�B�͈�l�Ƃ��ĉ�����҂͂Ȃ��A�]�˂Ŋċւ���Ă����������������˓@�̕Ĕ����� �u�ƍN�͏�U�߂����肾����A�Ō�܂Ŏ�蔲���A���}�̖���������܂��ʂ悤�v�ƌ���̖��g�𑗂��ė����B �ї��P���́A�Ɛb�̓������������쓹���ƕϖ������A�Ĉꖜ�A���ܕS�������Q���ē��邳����B���������̒��j�E���L�́A��D��ǂɐ������悹�ē���s�͂�����x�ł���B���N�͌����̗₽���Ɂu���m�炸���I�v�Ƃ����肽���������낤�B �� (*1) �Ћ� ����(�������� ������)�B�˃��x�̎��{���̈�l�B�ߍ]�����S�{��J(���ꌧ���l�s�{��J)�̐�䎁�z���̏��̎�E�Ћ˒���̎q�Ƃ��Đ��܂��B �����T���N(1570�N)����V�����N(1573�N)9��1���ɂ����Ă̐D�c�M���ɂ���䒷���ւ̍U���ɍۂ��Ă͏��J��̗���܂ň�т��Đ����Ƃ��Đ�����B����O��(8��29��)�̓��t�̐�䒷������Ћ˒���Ɉ��Ă�ꂽ�����݂��c���Ă���B ���V��7�N(1579�N)����A�����ߍ]���܂�̐Γc�O����Ƌ��ɒ��l�鎞��̉H�ďG�g(�L�b�G�g)�̉Ɛb�Ƃ��Ďd�����Ƃ����Ă���B�V��11�N(1583�N)5���A�M������ɑΗ������D�c�Ƃ̎ēc���ƂƂ��˃��x�̐킢(�ߍ]���ɍ��S)�ŕ������������������Ƌ��Ɋ��A�u�˃��x���{���v�̈�l�ɐ�����ꂽ�B �����̌�͑O���Ŋ��镐���ł͂Ȃ��A��s�l�Ƃ��Ă̌���x���Ȃǂ̊��������S�ƂȂ�B�G�g�̒��N�o��(���\�̖�)�ł́A���R(���݂̊��R�s)�ɒ��݂��A�W�B��U���ȂǂɎQ���B���\2�N(1593�N)�ɋA���B���\4�N(1595�N)�ɂ͐ےÍ���؏��A�c��3�N(1598�N)�ɂ͑���ԂƂȂ�A��l�߂ƂȂ�B ���������^����ꂽ���͔̂d���Ɉꖜ�قǂɉ߂��Ȃ��������A�G�g�̔ӔN�ɂ͖L�b�G���̘����̈�l�ɔC����A�H�Đ����^�����Ă���B ���G�g����͏G����⍲���A�c��5�N(1600�N)9���̊փ����̐킢��A�ܑ�V�M���̓���ƍN�����a���c��2��8��̏��̂�^����ꂽ�B���̌���G����⍲���A�L�b���Ɠ��쎁�̑Η�������邱�Ƃɐs�͂����B�c��19�N(1614�N)�A���L��������肪�N�����đΗ�����������ƁA�����͐푈������邽�߂ɕK���ʼnƍN�Ƃ̘a�����ɖz���������A�ƍN�ƌ����Ă���Ԃɑ�쎡����G������̗��a����ƍN�Ƃ̓��ʂ��^����悤�ɂȂ�A����𒀓d�����B���ꂪ������̓~�̐w�̐�헝�R�ƂȂ��Ă���B �����̐w���n�܂�ƉƍN�ɖ������Đ��A4���ɉ������ꂽ�B�������Ă̐w�ォ���\���قǂ��āA�˔@�̎��𐋂��Ă���B����ɂ͕a����������A�G�����~�����Ƃ��ł��Ȃ�����(�����́A���̐w�ʼnƍN�ɖ�������㏞�Ƃ��āA�G���̏�����Q�肵�Ă����炵��)���Ƃ���̐ӔC�������āA���E�����Ƃ������Ă���B����A�q�̍F������Ղ��p�����B�@ |
|
|
��(6) �Q�l
����ɔ�ׂđ����\���Ɖ]��ꂽ�Q�l�̒��Ōܐl�O�Ə̂��ꂽ���喼�́A �^�c�K��(�M�B�ܖ���)�\���Ίi��(���Z�璅��) ���]�䕔���e(�y����\�l����)��\���Ίi�@(���ܐ�V) �㓡�����q�@(��B����O����)�R�Ċi�@(���Z��V) �ї����i(���q���ܖ���)�R�Ċi�@(���l��ܕS�V) ���ΑS�o(���O��Ҏl���L���V�^���喼)�@(���ܐ�V) ���̑��ɖ���m��ꂽ���͔��c�E�q��(*1)�ƐV�{�s�����炢�ł���Ɓw�R���x���b(*2)�x�ɂ͋L����Ă���B �F��Z���̖x���Ƃ̒��j�E�V�{�s�����^�c�Ɍ���A�G���̎q�E�����N���̕��ŗ鎭���̐��c���l���A��a�O�l�O�Ɖ]��ꂽ�H�R�E�߂ƎO��l�߂��ɐ��A�ɉ�̖�����E�m���������̂��A�R���x���͒m��Ȃ������悤���B �c���\��N(��Z��l)�\�����܂łɎ��X�Ƒ���ɎQ���������͋㖜�ɋ߂������Ɖ]���A�L�b�Ɛb�c�̑�쎡���ȉ��O����������A�R��ꖜ���A�����Z���A�G���ܖ����v�\���Z���A�R��ꖼ�ɂ��|���������A�����ȉ��ɂ͉i�y�K���\�тɕ}���Ă������̎x�x���Ƃ��Ĕz��ꂽ�B �� (*1) �� ���V(�� �Ȃ��䂫)1567�`1615�B���c�E�q��̖��ŗL���ȗE���B ���o���͕s���B�͂��߂͐D�c�M���Ɏd���Ă����炵���B���i�͂��ƂȂ������i�Ȃ̂��A�������ނƖ\��o���Ƃ������Ȃ�����d�p����Ȃ������B�G�g�ɂ��d�������d�p����Ȃ������B ����ɉ����Ö��̉Ɛb�Ƃ��Ďd���A�S�C�叫�Ƃ��Ċ���B�Ö��ɏ]���Ē��N�o���ɂ��Q���A���̌��тɂ��350�̒m�s���B ���փ����̐킢�̂Ƃ��A�R�߈ᔽ�ɂ��Ö��ƑΗ����A���̂��Ƃ�������(��������)�B �����̌�A������G�H�⏼�����g�A�����ĕ���������Ɏd�������A�����������̉Ö��̕���\�ɂ��ז��������Ē����������A�ꎞ���͕���ɓ����Ă����B���~�̐w�ɖL�b���Ƃ��ĎQ�����Ċ���B���N�̑��Ă̐w�Řa�ɂĐ�쒷��̌R���Ɛ���Đ펀�B���̂Ƃ��̊���Ɂu���c�E�q��v�Ə����Ď��g�̖���V���ɒm�炵�߂��B�揊�́A���݂̑��{��s�쒆�~��(�݂Ȃ݂Ȃ�������)�n���A���{��64���a�̎R�L�ː�(�F��X��)�����ɂ���B (*1-1) ����Ɠ��������Q�ƁB (*2) �w���w�R���x����x�L�b�Ƃ̐b�E�R���x���������Ƃ��Đ�����ہA���~�̐w�ɉ�����镺�̓������q�ׂ����B�@ |
|
|
��(7) �V�{�s���Ɠn�ӊ����q
�V�{�s�����A�G���̖��Őԍ��Aꠓ��̏����Ƌ��ɍ��s���Ɍ������̂͏\���\�O���ł���B������̕�s�≞���ɒy�������Ћː���S��s�������A�ƍN�̐����E����@�O���q��߂��A���ʂ̕���e����������č���x�z���Ɏ�߂����B �R���\�����ɂȂ�ƁA�G��������g�̋}�g�����B���ŁA�����O�S�𗦂��č���o�����āA�Z�g��Ђ�����܂ŗ���ƊX�������ɐ�]�̓��������w���\���Ă����B ����͓��������Ă̗E���E�n�ӗ�(�킽�Ȃׂ��Ƃ�)�̈���ŁA�ƍN�̖{�w���Z�g��Ђɐ݂���Ƃ̖��������}����̂����̂ł���B�������A�Z�g��Ђ̎Гa�͏G������i�������̂����ɁA�s���͓��u�ɔR�����B�u���̂��ꂵ���v�Ƌ����F���Ȃ���C�ɐw�O���삯�������A�S�̒��ł́u�������̒��ɂǂ����Z�̎��������Ȃ��ł���I�v�ƔO���Ă����낤�B �V���O�����q(*1)�̈�l�Œm��ꂽ���̓n�ӂ́A���̊���������F�쐅�R�̗Y�Ƃ��Ė炵���x�����ƌ��āu�\���I�v�ƒǂ��Ƃ��镔���������� �u�͂��ȕ��ŗI�X�Ɖ�w���킯������͍̂�ɕ�����u���U������ň͂܂�Ƃ̍��ɈႢ�Ȃ��A�ǂ��Ă͂Ȃ�ʁv�ƌ��������B �l�X�́u�������a����������������v�Ɗ��S�������̂́A�₪�ĉ��̕������Ȃ��������������āA���˂���͏��A���Ղ͖ʖڋʂ�ׂ��B��쎡�[(��쎡���̒�)�������R�̏Z�g�i�o��m��A�u�V�{�������E���ɂ͏o���ʁv�ƍא쒉���̎q�E���H�A���c�E�q�����𗦂��ēV�������܂Œy���������A�s�����ꕺ���������Е����X�ƈ��g���ė����̂����� �u�������͌F��̍��Y�E�x�����P�̒�����������v�Ƒ傢�Ɋ��Q���A���̘b�͏G���̎��ɂ��B���āA����̎u�C�����߂����܂ɖʂ�ዷ��ɏ��i�����Ă��̗E���]���Ă���B �� (*1) �n�ӗ�(�킽�Ȃׂ��Ƃ�)�B�����q(����ׂ�)�̖��ŗL���B �����ߐ�䎁�̏��E���吪�Ɛb�B��Ɂu���̊����q�v�Ə̂����悤�ɑ��̖���B�D�c�M�����璼�ڏ̎^���ꂽ�قǁB���Ƃ������ēV��10�N(1582�N)������H�ďG�g�Ɏd���A2000�ŏG�g�̗{�q�E�H�ďG���t���ɁB�R��̐킢���˃��x�̐킢�Ŋ���B�Γc�O���Ɛb�̐��]�����q�A�c���g���Ɛb�̒Ҋ����q�ƕ���Łu�O�����q�v�ƕ]���ꂽ�B�V��13�N(1585�N)�ɏG�����v���āA�Q�l�B �������ꎁ��3000�Ŏd����B���c���̖��Œ������̐�N�Ƃ��ē����A�ɓ��R����U�߂ɂ����Ĉ�ԏ��B�G�g���u�̂ĂĂ��ꖜ�͎��ׂ��v�Ə^�B�ꎁ����̉���(�{��6000��)�ɕs���ŁA�ĂјQ�l�B �����c������4000�Ŏd����B�փ����̐킢�Ő��R�ɂ��������̏o�w���ɁA����̌S�R���C���ꂽ�B���A���ɒ��������̂�v������č���R��孋����Ă������u��N��������̖��ŏ������Ă���B����ȊO�̖��ɂ���ĊJ��͂ł��Ȃ��v�ƁA��ڎ��̓������ՁA�{��������ɒ�R�B�ƍN��ɂ���āA�����ɏ������������܂ŏ�����ʂ����B�����ɊJ������܂��A���̒��`�Ɨ͗ʂɎd���̗U�����������A�����̓������Ղ�2���̔j�i�̑ҋ��Ŏd����B���Ղ̋���ƂȂ����ɗ\���̍�����̕�����s�߂�ȂǁA�������ȊO�̍˔\��������B�����Ƃ��ɐ����Ɉڕ��ƂȂ�ƁA�ɉ�����ɁB �����̖��ł͓������̐�N�߂邪�A�~�̐w�ŁA�킢���Ŏ�N���ՂƏՓˁB�J�����̍U�h��ɂ����Ē��@�䕔���e�̕����ɏR�U�炳��āA���n���ĕ�������ȂǑ�s�B�Ă̐w�̔����̐킢�Ŗ��_�҉�ƍĂђ��@�䕔���e�E���c�����̕����ɏP���|����300�]�l����銈��B���A�ƒf��s�r�������A7��ɂ��y�ԓP�ޖ��߂����Ēnj����ē������́B�����������Q���傫���A���Ղ⑼�̏d�b��������a�܂�錴���ɁB���o�z���čĂјQ�l�B ���d���̓���T�����A�����Ƃ���u����\�v�̐G��(�d���𑼂̉Ƃɂ����Ȃ��悤�ɂ���肢)���o�āA���{������U���邪�A�K��Ȃ������B���Ղ́u������������(���ʊW�̂���)��Â̊����ƂɎd����v�Ɩ��������A�ނ͏��m���Ȃ������B���i5�N(1628�N)�ɂ͓V�C�𒇍ٖ��ɂ��ĕ���\�̉������肤�B�����Ƃ���o���ꂽ����I�Șa���̏��������m�ł����A�t�ɍ��Ղւ̕s���s����\�����Ă����߁A���͌���B ���Ղ̎�����A�q�̍���������\�̕��j���ێ��������ߎd���ł��Ȃ������B���̍˂�ɂ��א쒉���⓿��`����̎̕}�����ׁX�ƎA�u�����v�Ə̂��A���Ŗv�����Ƃ����B���N��\�B�@ |
|
|
��(8) ����c
�c��\��N(��Z��l)�\�����A�n�߂ďG���Ɨ��N�o���̏�ō���c���J�Â���A����̏��ɑ��O�Z���D�c�ꑰ�B�Q�l�g����͐^�c�K���A�㓡������(*1)��̌ܐl�O���Q�������B �R�t�i�̍K���͕��Ƌ��ɗ���グ�� �u�G�����͓V�����ɐi�o����A�㓡�͑�a�H��i�ݕ�������A�K���͎R�肩�狞�ɐi�ݓ����𗎂��ĉF���A���c�ɐw���\���A�����̘A����f���āA���}���ڂ̏��喼�𖡕��ɏ����Đ킢�A��s���ƂȂ����ꍇ�͏���Ă��ė͐킷��B�v�Ƃ����o�������������B ����ɑ��A���N�̈ӌ�������쎡���́A�F�X�Ɨ�������ׂāA�ŏ������ď����������B���ǂ���Ɍ������̂́A�א쒉��(*2)�����D����M����Ɛb�� �u�G�����͐킳�Ɋւ��Ă͓��ێq����A���̂��܂������Ă�ɐF�X�ƚ{��ˍ��ނ��瓝���킪��ꂸ�A����͑����v�ƒf�����ʂ�̏�ŁA�K���̌\���ΌR�t�ҋ���������ł������B �X���ď����ɏA���Ă��A�K����R�Ă̌㓡�炪 �u��c�A�����A�`�@���܂ōL���Ԃ�z������z���Ă���R�̓G�ɕ�͍U�����ꎟ�X�ɗ��������̎u�C�����킹�鎖�͕K��ł���B�V������ӂɗ��C���͂��[�����Čł����ׂ����v�Ɛ����Ă��̗p���Ȃ��B ����ł́u�`�ׂ̈ɔ��������Ȃ�v�Ə��s�◘�~��x�O�����ē��邵���K���B�����]������肾�����B���܂肩�˂��s�����A����̒��ł����s�h�̑�쎡�[�ɐi������ �u�ď��ӓ|�̏��ɍ�ł͔@���Ȗ���ł�����͕K���ł���A���Ƃ���O�ɗV������u���֓����̔w��𝘗������@���̗p���ׂ��ł���v�Ɨ͐������A����ŁA���˂Čv���i�߂Ă����I�ɌF��e�n�̋��m��R���ɈꝄ���N�������B�����āA�L�b�Ɛ[�����ʂɂ���Ȃ��疡���ɎQ���Ȃ���쒷��(*3)�̎�R��V�{����U������V���������肵���̂́A���߂Ă��̈Ԃ߂��낤�B �� (*1) �㓡 �(���Ƃ� ���Ƃ�)�B���c�F��(�@��)�E�L�b�G���̉Ɛb�B�ʏ͖̂����ʂƂ��ėL���B�d���ʏ����Ɛb�E�㓡�(�㓡������)�̎��j�B ���c���̍��A����S���������Ƃ���A���̗F�l�ł��������c�@���Ɉ������ꂽ�B�@���̉Ɛb�Ƃ��Ďd���A�������̌R���������A�u���c��\�l�R�v��u���c���Ձv�̈�l�ɐ�����ꂽ�B�������A�@�����r�ؑ��d�ɂ���ėH���ꂽ�ۂɁA�f����M�����̎q�̊�E��Z��(�����q�̂��Ƃ�)�ƂƂ��ɑ��d���ɑ��������߂ɁA�����q�͈ꑰ�̖d�����N���������ɂ��A�������j�ڂƂȂ�A�ꎞ�A���c�ƒ�����̑ދ���]�V�Ȃ����ꂽ�B ����ɍ߂�������āA�Ăэ��c���̉Ɛb�Ƃ��Ďd���A�L�O�F�s�{���Ƃ̐킢�A���N�o����փP���̐킢�Ȃǂɏ]�R�A�փP���ł͐Γc�O�����̍����g���勴�|������R�����Ŕj��Ȃǂ̕����ő�G��1��6000�̏��̂�^����ꂽ�B�������@���̎q�E���c�����Ƃ͔��ɐ܂荇���������A���̊m������@���̎���A�����q�͈�Ƒ����č��c�Ƃ��o�z�����B���������̎��A�����͖����q�ɑ��ĕ���\�Ƃ����[�u����������߁A�����q�̒q�E��ɂ���őS���̑喼(�א쒉���E���������E�O�c�����E����G�N�Ȃ�)���珢���o�������������ɂ��ւ�炸�A���������Ɏd�����ז�����A�Ƒ��ƂƂ��ɒ����Q�l������]�V�Ȃ������H�̐g�ɗ뗎����قǐ������N�������Ƃ����B ��1614�N�A���~�̐w���N����Ɠ���ƍN����@�O�ȉ��܂������ɗU��ꂽ���A�����q�͊����������������₵�đ���ɓ���B�u�G�����ɂ͐�w�߂邱�ƂŁA�ƍN���ɂ͍��평���Ɏ��ʂ��ƂŌ䉶�ɕ悤�v�ƌ�����Ƃ����B�~�̐w�ł͎���E�������ʂ�ؑ��d���Ƌ��͂��Ď�����A�㐙�y�э��|���Ƒ������B ��1615�N5���̑��Ă̐w�ł́A��a�H���ʁE�����ł̌}�����̐�N�Ƃ���2800�̕��𗦂��ďo�w�A�͓��u�������̐킢�v�œ�����̉��c����������A�Ǖ��Ȃ�������킵���B�������ɒB���@�R�Ƃ̗���̒��A�^�c�M�ɌR�����̔����ɂ��s�R�Ɏ�Ԏ���Ă���ԂɁA�Бq�d��(�Бq�i�j[���\�Y]�̒��j)������S�C���ɏe�����ꂽ�B������������s�s�\�ƂȂ�����͕����ɉ���𖽂��Ď��n�����Ƃ����B���N45�B (*2) �א쒉���́A�א�H�ւ̑��q�B���ߏ�̗͓l���Q�ƁB (*3) �����̂Ȃ�������B1586�`1632�B��쒷��(*3-1)�̎��j�B���K��(*3-2)�̒�B�����͍]�˖��{���R����ƍN�̖��E�U�P�B���ʂ͏]�l�ʉ��A���E�͒A�n��E���]�B ���ߍ]����{(���ꌧ��Îs)�ɐ��܂��B1594�N(���\3�N)����L�b�G�g�̉Ɛb�Ƃ��Ďd����3,000��^����ꂽ�B1600�N(�c��5�N)�̊փ����̐킢��A�]�˂ɕ��Ɛ����𐬗�����������ƍN�ɏ]���A����������˂�2��4,000��^����ꂽ�B1613�N(�c��18�N)�A�Z�̍K�����k�q�������ĕa���������߁A�I�ɋI�B�˂��p���Řa�̎R���ƂȂ����B���̐w�ɂ͓�����Ƃ��ĎQ�����A�Ă̐w�ł͓G���E�����V(�O�q)�Ƃ���������������B��1619�N�A�������������Ղ����ƁA���̌���Ĉ��|�L����42���ɉ����ڕ����ꂽ�B1632�N�Ɏ����A���N48�B�揊�͍L�����L���s�̍����B (*3-1) �ǍO�F�엎�����Q�ƁB (*3-2) �܂ق�̗������Q�ƁB�@ |
|
|
��(9) �ƍN�A������
�ƍN�������ɓ������̂͏\�����{�ŁA�V�c�ɏG�������̘_�|���������ĎO�v�������B�������A��͂Ђǂ��s�@���� �u�G���͏��R�̖��ł͂Ȃ����A���̍߂��������n���ȂǂƂ����̂��v�Ǝ���ꂽ�B ���{�����ƍN�́A��c�������ɏ�����ƓV�C��̈ӌ������߂��� �u����ł͓V���̐l�S�������v�Ɣ�����A�f�O����ƁA�Ћˊ����ɐ擱���𖽂��āA���X�Ƒ����߂������B �\�ꌎ�\�ܓ��A�ƍN�́A�ޗǂ̒��V�G��(�O�o)�̓@���h�Ƃ��A�ϐ�����̗w�ȂȂǂ��Ă��邪�A�@�̎��ӂɂ͏\�Ð����]�l���������x�����ł߁A���܂Ō�q���Ă���B ���R�G���́A��������͓��Ɍ����A�����ɔ������B�\�Z���ɂ͓V�����Ɍ��������A��N�l�ԑ��ɂ͓����c�炪������Ă���B�����ēa�R�̘V���E������M�̕⍲���Ƃ��Ĉ�ˊo�O�A�e�q���̒��Ɏ��G�A���O�炪�Q�����āA�����R�ł̉ƍN�Ƃ̉�̌�q�ɓ����Ă���B�@ |
|
|
��(10) �I�ɌF��̈Ꝅ
�J��͏\�ꌎ���{�ŁA��c��������D��Ɍ��킪�W�J���ꂽ���A�܂����k�R�O�S(*1)�����Ꝅ�����X�ƐV�{��Ɍ����A����Ɍĉ������R���Z�킪�a�̎R��Ɍ������B �V�{�U������]�̎�d�҂́A�O�S�̏C���h�ł���X�{�V(�܋S�p)�s�ҖV(�܋S�F)�s���V(�܋S��)�����V(�܋S��)�ł���B���ɁA�x���Ƃ̋��b�Ő�삩���S����������Ă����̂��đ��ɎQ�������@�E�q��A�Î�v���q�A�x����w�炪�A�㓡�̒��j�E��ӂ��쓹���̗v���ɂ���Č��N�����B���̍����́A�ƍN�̔ڗ��{������펛�O��@�⍂��R�A����@�̒��V��ŁA�R���B�������Q�����Ă����悤���B �ނ�͖�̔@���ɌF��k�����蒆�Ɏ��߁A�\�̏��߂ɂ́A�V�{����w�Ă̊Ԃɖ]�ޑΊ݂ɏP����������A�鉺��~�͑呛���ƂȂ�B �ӋC�����嗢�̋���(*2)��D���Ė{�w�Ƃ����ʏ́E�O�S�̒Ëv�́A�\�����������đ��U�������s�����B�F�����͂���Ō��킪�W�J����A�R���S�ܘY���O�ڌܐ��̖쑾���𐅎Ԃ̔@���U�A�w���ɗ����Ė\����A�I�����킪�������B ��ꑧ�Łg����I�h�Ǝv��ꂽ���A���h����̓S�C�����֑D�ɏ悶�ĉL�a�͌��ɏ㗤�B�쉺����C���ɏ悶�ďĂ����āA��ォ��͖{�{�̏�y�����P���A��l��R���B�𗦂��ďP�����������ׂɁA��ǂ͈�ς����B ���̒��A�嗢�������叫�̒Ëv�́A�݂݂����^�̊��ɍ����n�̊Z�����A�L�b�Ƃ̒����ꗬ��擪�ɎR�Ăɂ���� �u���������V�{��ɏ捞�܂�v�ƈӋC�����i�������B���������c�Ŕs�����ė��閡���ƂԂ��� �u���S�̓S�C����擪�ɉi�c�A�Ί_�疼���Ă̗E���B���nj����ė���v�Ƃ̎v�������ʕ�����B�Đl�����n�߁A���S�҂����o���A�Ëv���@���Ɏ��B�サ�Ă��A���a���ɂƂ���ꂽ�A���́A�Z�𗐂��Ĕs�����Ă��܂����B �������ɒËv�ꑰ��A�R���A���J���n�߁A�O�S�R����O�S�]�l�́A���C�u���`���ő̐��𗧒������B�������čU���̕��͂��W�܂炸�A�I�m��������Ď�R����͂����R�������镺�̔�����������킵�Ă����B �� (*1) �ޗnj��̉��k�R�O�S�͏C�����̏h�V�̂������ꏊ�B�����R���̂��߂̏h�V�u�����V�v��������1���c��(2007�N����)�B1300�N�O�A���̍s�҂ɋS�v�ȁE�O�S�ƌ�S(����)�Ƃ���5�l�̎q���d�����Ƃ����`�����c��B�����h�V�����̂́A���̎q���B5�l�̎q�Ƃ́A�܋S���E�܋S�p�E�܋S��E�܋S���E�܋S�F�ŁA���ꂪ�A���̂܂ܖ����ɂȂ��Ă���B�܋S���E�܋S�F(�����ǂ��E��������)���Ƃ́A�₦���炵�����A���3�ƁA�܋S���E�܋S�p�E�܋S��(��������E�������E�������傤)�͌��݁B (*2) ���̎O�d���어�K�S�I�嗢�ɂ��鋞��(�݂₱���傤)�@ |
|
|
��(11) ���N�������A�a�c������
�����́A���U�߂̐틵�����悤�B �{�w�𒃉P�R�ɐi�߂��ƍN���A��\���̑�R�����B���サ�ĖҍU�𑱂��Ă��A�������͑��}���z���グ�����邾���Ɋ�Ƃ��ė����Ȃ��B�����A����̖ؑ��d���A�㓡�����q�̕����A�^�c�ۂɉ�����K���̌����ɂ���āA���̎����͎O���ɋ߂������Ɖ]���B ���̐틵�������㐅���V�c�́A���˂ĖL�b�т��������ɁA��[���E����������g�ɔh�����āA���R�ɘa�r���Ă���A���Ƃ��L�Ƃ̑������v���Ƃ��ꂽ�B�������A�����܂ŖL�Ƃ̒f����߂����Ă����ƍN�́A�V�c�̒��|�ɂ���Ęa�c�����ׂΌオ���邳���ƁA �u���������̒��|�ł͂��邪�A�G���������Ȃ��ꍇ�́A��̈Ќ����������ɂȂ邩�玫�ނ���v�Ƒ̍ق̗ǂ������]���Ă���ɏ]��Ȃ������B���`�ʂ̕Ћˊ����̒�ĂŁA���O���ɔz�������\����̋��C���n�ߎO�S��̑�C���w�n����ҍU����W�J�B���̏\����̋��C�́A�I�����_�D����w�������ŐV���̌܊і�Ɖ]���e�ۂS�����������̂������B ���e���A�����������n�}�ɂ���Č����ɗ��N�̋��Ԃɖ��������B�V��t�̒����ӂ��A�������l����������̂����Đk����������N���A�g�����܂ōR��h���咣����G���ɋ��������B �a�c�����������̂͏\��\����ł���B���}���ꐢ�̒q�����X�|���A�^�c�A�㓡�ȉ��\���̖����A���Y��i�����V���̖��邪�A�J��͂���J���]��Řa�r���˂Ȃ�Ȃ������̂͂Ȃ����B����͐�̌R�c�� �u��̐�Ζh�q�����m�ۂ���ׂɂ�������ɐ���g����ȁA�v�ƍs�����������̂ɁA���Z��͑��p�̐��C���������܂��Ƃ��ċ�S���R�ɎS�s���A���ɓV�����~�̐��C���܂Ŏ����A�V��t���ԋ߂Ɍ�����O���ɒ���Ȏ˒������m���V�s���C��z����������ł���B�ɔ�̏���}�ʂ����o���āA���̌v���i�߂��̂��ˈ�t(*1)�ő咉�b�Ƃ���銎���������B ���Ă܂�܂Ƙa�c�����ƍN�́A��쒷����Ă� �u�̓��ňꝄ���N�������X�͒f�œ��ł��Č���̊����̍���f�āv�ƌ������čĐ�߂����A�F�ɂɓ��̕��𑗂��Ĕ��C�u�A�����A����ɐi�U�������B �Ëv�����r���̓�ɑ��݂�A���𗎂��d�|��݂��ĕK���ɍR�킵���B����|���n����̌���ł́A�F�ɂ��R���S�ܘY�ƈ�R���ƂȂ�A�낤�������ꂻ���ɂȂ����������A���ǂ͈Ꝅ�����O�ǓG�����s������B �a�̎R��ɔ������R�������A�ܕS�ɋ߂����Q��ւ�A�͂��Ƃ��Ĕs�������A�Ƃ̔ߕ�����ɂ��Ȃ���A�Ëv��͐h�����ď\���A�O�S�̗��ɒH����čċ����v�����B �� (*1) �������ɁA����Ƃ̒ؓ�疗y���j���w�ˈ�t�x�ɂ����Ē��b�Ƃ��Ă̊�����`�����B�@ |
|
| ��4.2 �ăm�w�̌��l �@ | |
|
��(1) �a�r
�~�̐w�Řa�r�Ă�����������A�^�c��s���� �u��ǂ͉�ɗL���ł���a�c�͋U���ł���v�ƍR���͐����A�G���������� �u�ƍN���V��Ȃ�Θa�����ю���҂��āv�Ɛ����� �u����͊����̉]�����ʂ�ł͂Ȃ����v�Ɗ�Ƃ��ĕ����������܂ōR������сA���[��㓡�� �u���̌���ŋ`������v���͂��Đ킦�Ή��N�ł���蔲����A�ꂵ��ł���͓̂G���ł���v�Ƙa�c�ɔ����V�ԂȉƍN�̎�ɏ���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɨ͐������B �R���ƍN�̃X�p�C�������L�y���q(*1)�́A�������������N�������A�a�r�����ɖz�������B�F�s�ȏG���͐��ɕ�̗܂ɕ����A����i�߂��B�����������ő��}�̈�ǂ���ւ�ɖ������G���͈�J���̎�����o�����A�����Ƃ��đ傫�����������B�����������̕�v���Ɛl���^���������悵�Ƃ��Ȃ����^���͂����ς���̂ł͂Ȃ���H�j�ǂ����Ă������B�@ |
|
|
��(2) ����
�����ɏ����ꂽ�a�r�̏����� �u�G���̗̓y�͍��܂Œʂ�A���N��l���ɂ͂��Ȃ��A�Q�l�B�Ɉًc�͉]��ʁv�̎O�J�������ŁA�O���߁A��m�ێO�m�ۂ����͋L���ĂȂ��A���悾���̖ɂ����̂��ƍN��㩂������B �ƍN�͏G���Ɠ����Ɉ���Ꝅ�Ɏ���Ă��Ęa�������� �u���@�͌��̂܂܁v�Ɖ]�������������̂ɁA���������A���������肪����ӂ߂�� �u���X���̂��������͖������������v�Ƃʂ��ʂ��ƚ��������̉ƍN�ł���B �����l�̐l�v��喼�B����o�����A�A�b�Ɖ]���ԂɊO���߂�� �u����`���v�����v�Ɠ�m�ێO�m�ۂ̎�Ɏ���o�������A�L�b���͒f�ł���ԓx�ŋ��ۂ��ׂ��ł������̂ɁA�a�c���j���̂����ꂽ���N�̖��ŁA�����Q����ƂȂ��Ă��܂����B ����������K���� �u�ƍN�A�G�����P���ē���肽���v�ƍ��������� �u�ɔw�����Ƃ͂ł��ʁv�Ƌp������Ă��܂��A��������U�s���̖��������ȗ���ƂȂ��Ă��܂����B ���̖����Ă̑��ē��ďo���̂��������ՂŁA�ˊэH���𖽂����̂ɐi��ł��Ȃ��̂����āA�ӔC�҂̐����E�q����Ăю������ƁA���̗��F�Ŋ≮��傾�������� �u�H�����H�����Ⴉ��̂��B�͂��ł�̂���낤�v�Ƃ��̔ڗ�Ȏd������ăj�����Ə����̂����� �u�փ����ŋ~���Ă�����̂�Y�ꂽ���I�v�Ƒ����Ɏ���͂˂Ă��܂����Ɖ]���B�ƍN�͂������ �u��ӂ���v�Ɗ�낤�B�@ |
|
|
��(3) �ƍN�A�Ē���
�L�b�т����̍J�̘Q�l�⏎���B�͌��X�ɓ���̔���ƂȂ��A�������]����҂͏��ɗ���ׂ����B�����m�������s���i��̔q���d�́A�����ɉƍN�ɋ}��ƁA�~�̐w�ɂ͓��R�ɎQ���������A�^�c�ۂł̔s��ŘQ�l���Ă��������ȌR�w�ҁE�����i�����ĂсA�ƍN����� �u�S�R�����ɎQ�W���閘�ɂ͌\���͂����낤�B���ԂɏG�������ɐi�����A��ɑi���ēV���ɋ`�R����Έ�厖�ƂȂ�B���Ƃ������j�݁A�Q�l�����U���������v�Ƃ̌�����`���A���̑����ނɈ�C���đ��ɑ��点��B �u���R�̌R�w�w��v�Ɖ]���a�ɂ��āA�����͉����ʊ�ő�쎡�[�̔z���ƂȂ�A���X�Ə��𑗂����B �O����{�A�����\���ɒB�����A�ƍN�͉�R �u���𖾓n���A��a���ɐ��Ɉڂ�B���ꂪ�}�Ȃ�Q�l���������Ǖ����A���̉ƒ������ɂ���A���ꂳ�������ʂƂ���Β����ɍU�߂����邼�v�Ɩ{����f���Ē��킵�ė����B�@ |
|
|
��(4) �����i���̖d��
�����m�������h�̑�쎡�[�́A�O�����A�V�{�s�����n�߁A�����A���A�z�{��̑��ɐV�K�������̏���������Ȃ����āA�R�c���J�����B �s���� �u���˂ė\�������ʂ�A�ƍN����͖L�b�Ƃ̒f��ɂ���B���ے����ɉE��b�E�G����ď㗌���A�����̔q���Ǔ����A��ɋ����̎����t�サ�āA�V���ɉƍN�̔𖾂炩�ɂ��A�}���̐����m�����ׂ��v�Ɛ����A�������^���������A���������� �u�S��B���̉ƍN�ɏ���o�Ĉ��ނ͖̂��Ɉ�̏��Z������܂��ʁB����Ă��Čł���莞��҂̂����ł���v�Ɣ��_���q�ח��Ă��B�b�B���̌R�w�҂Œm��ꂽ�ނ̈ӌ������ɔ@���ɂ��ނ��炵�����������B �R���s���͈�������炸�A���X�Ƙ_�j���Č��_��W�J���A���[�� �u�X�����A����ł͏G�����ɐi���������ɏo������v�Ə��m�������̍I�݂ȍs���̍����āA�����͓��S�ŗ⊾�𗬂��Ȃ�������_�����B ���̐헪�̌��_���w�E���� �u�悸���Ɉׂ��ׂ���́A�d�x���ڂ��Ă̕������̖��ɗ����������Ȃ��V�㕺��⿂ɂ����A�������s�̕��𑵂��Ă���㗌���v��ׂ��v�Ɨ͐����A���[�͎��������������ď��������������ɃR�������x����Ă��܂��B�@ |
|
|
��(5) �����i���̓��S
�a���h�̎����́A����ɂ���ĉƍN�̘Q�l�Ǖ��̗v���ɉ����鍰�_�������āA�\���̘Q�l�����Ђɐ������邱�ƂƂȂ�A�₪�āg�V�c����f���̒m��ʕS�����h��̑�ʉ��ق��n�܂����B �\���Ɖ]����S�R�̔��ɒB�����k�R�ŁA��쐨�̒��ł��E�҂Œm��ꂽ�����O�g��Ȃǂ́A��S���̑���������S�\�����Ǖ����Ă��܂��B��ő傢�Ɏc�O����̂����A�\�������ȏ�̏k�R���i�ނ̂����āA�����͓��S�ق�����ł����B�܂����A�G���ɐS���鋞�̖��S�����V��� �u�����͊Ԏ҂ł���v�Ƌ}�������B �u���܂����I�v�Ƌ����Ď��[�͒������ܒǂ���������������A�܂�܂ƕ�����ɓ������܂ꂽ�B�n�c���ӂ�Ō��ɂ������Ă��A���ׂĂ���̍Ղ�ł���B�Q�Ăďk�R�𒆎~���āA�ĕ�W����Ƃ������A�Z�̎����������s���𗝗R�ɂ���������Ȃ��B ����Ɉ�U�ǂ�����ꂽ���B�����̎d�ł��ɕ��𗧂đf���ɋA�锤���Ȃ��B�q���i����e�˂Ɍ������Ă����h���x������߂��点������A���̖ԂɈ����������Ďa��ꂽ���m�������A�~�̐w�̔����ɂȂ��Ă��܂����̂͒v�����Ɖ]���悤�B�@ |
|
|
��(6) �D�c������̓��S
�O�����ɂȂ�ƁA�ƍN�͓��R�ɍďo���𖽂����B���̐�N�Ƃ��č��Ղ�I����A�E��o�w�̖����ɉ�A�ɐ��͌���荡���̍��g�ɂ܂Ŕ�сA �u�l���ܓ��܂łɗ���ɓ��邹��v�Ɩ�N�ɂȂ��Ă���B ����ɔ�ׂĐ��R�̓����͓݂��A����Ǝl���O���ɂȂ��đ���璟�~�ʼnăm�w�̌R�c���J�����B �G���͏������W�߂�ƁA�O��Ƃ͂����đ�������u�ɖ������ԓx�ʼnƍN�̔ڗ���� �u�������Ɏ����Ă͍ő���ނʁB���悭���킵�āA���Y�𑈂��A���܂��s���ȂA���}�̎q�Ƃ��ď����Ƌ��Ɏr����ɂ��炷�o��ł���B�v�ƒf����B �K���������ė��� �u�G�������������R�𗦂��ď㗌�A�������U�����A�����̓G��ǂ������A�F���A���c�̋����Ă��ē����̘A����f�Ƌ��ɁA�L�b���ڂ̏����ɞ������A�₪�ď��ɒn�̗����߂đ匈����s���B�v�ƁA���N�O�̍s���Ǝ������v����Ă����B�㓡�A���]�䕔����̕����� �u���ꂱ�����ɒj�̎��ԁv�Ə���������Ď^�������̂����A�����������Ɉꕨ����D�c������ �u�R�ɂ͓����������̗v�ł���B���ہA�]�����i�ߊ��ɏA�C�������v�Ɖ]���o���A�~�m�w�ȗ��̔ނ̍s�������Ă��鏔���� �u����f�����g�̒���m��v�ƒN��l���m���Ȃ��B ����ƒ����� �u�M���̉��ł���]�����R���w������̂ɉ��̂����Ȃ����A����Ȃ�]����ɂ����Ă��d�l���Ȃ��v�ƌ��{�����ӂ�ŐȂ𗧂��A���̂܂܋��ɒE�������B�����ėL�y�A���v�������������痄�N�͔������ŏ��ɕ����L�l�ł���B �G���� �u����ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�ʁv�Ƌ��s�i���͌������A����\��n���ꏄ���ď����̎u�C�����߂邱�ƂɂȂ����B�@ |
|
|
��(7) ���Z������
�l���ܓ��A�O�q�Ɍ㓡�A�ؑ��A�����ċ��Z�̔n��Ɉ��n�����y�Ɍׂ����G�����B���R�ɂ͐^�c�A���]�䕔�B��q�ɑ��A�V�{�炪�Е����X�ƏZ�g�_�Ђ���V�����A���R��т̒n�`���������ċA�邵�Ă���B ���̖�͑S�R�ɍ����Ȏ��悪�U�����ď����͋C�����g�������A�~�m�w�ɔ�ׂ�Ɣ��ɂ������ʕ��͂ł͓��ꏟ�Z�Ȃǂ͗����Ȃ��B�ӔC��Ɋ��������[�� �u��`�e��ł��v�ƌZ�E�������ÎE���Ă������̓l�u���������Ă�Ƃ����͔̂ߑs�ł������B �G�������A�����������̂��낤�B��Ă̐e�̕Ћˊ����A�ꂪ��Ɍւ�Ƃ���D�c���Ɏ��X�Ɨ����A���͗͂Ɨ��ސ^�c�A�㓡�������Đ킢�̌����݂�q�˂�B �u��\���̊֓����ɑ��A����Ƌ͂��ܖ��̕��ł́c�c�v�Ɛ^�c�A�㓡�炪������������B��������āA�G���͎�����M�����A�̑��}�Ɖ��̐[�����ɎQ����v�������B�������ނ͉ƍN�̖��� �u���݂̑�̎�ƂȂꂽ�͉̂ƍN���̂����ł���B�v�Ǝg�҂��a�肷�Ă�n���B ����Ȓ��ɑ�a���R�O���̕�������(���������̒�)���A��q�E�������邳���A孋����̑��c���������q�E�����𑗂��Ă���B����͉ƍN�̂����̂Ђǂ��Ɏ�������������ł��낤�B�@ |
|
|
��(8) ���A�㗌�̍D�@���킷
�V�{�s���ɂ́A���Ɏd���Ă����Z�E��V��A�����ɐ�ŕ������Ă������C�u�`���q�炪�����o�債�Ēy�����Ă��ꂽ�B�����������ڑO�ɂ��Đ��̎�ɂ������ĉʂĂ��҂������A����ƎO�S���x�������B����ł͓����̋`�m���̂��Ă̊�P��@�����Ȃ��Ɣ��ԋ���̍���߂��炵�Ă����B �܂������ł́A��쎡��������̓r���Ŏh�q�ɏP���A���̎�d�҂����[���Ƃ��A�������Ƃ̉\���Q�܂��B �l���ܓ��A�������Ղ́A���Ɩ����̎����ł߂�ƁA�ܐ�̕��𗦂��Ĉ�H������߂����Đi�݁A�����������ɕ��߈�т̌x�����ł߁A���R�̓�����҂B �ƍN�������ɓ������̂͏\�����A�G���͓�\����ŁA���͐��ɏ㗌�̍D�@���킵���B �l�����{�A�ƍN�͑S�R����đ�a�A�͓��̗�����i�݁A�͓��̓������ō������āA��삩�瑍�U����������Ƃ����B �����m������쎡�[�� �u����Ƃ̏d�b�E����������叫�Ƃ���z�{�A������]�ɁA�Ó����z���A�S�R����U�������Ċ֓����̊̂�₷�Ƌ��ɁA��a�F��ɐ������Ă���L�b�}��{�{�R���B�ɑ��z�̌R�����������āA���N���Ăт��������v�Ƌ����G���ɑi�����B�@ |
|
|
��(9) ���A�S�R����U��
�~�m�w�̘a�r����A�ƍN����k�R�Ꝅ�̓O�ꓢ�ł��������ꂽ��쒷��́A�F�ɂɕ��h�����B�F�ɂ́A�N���܂łɖk�R�A���R����~�Ɏc�}��Nj��A�����̎��\����R�̒���ɑ����Ē���������B��������ƍN�͏�@���Ō˓c�A�F���ɉ��܂�^���Ă���B �R���A���A�Î��͍I�݂ɒǎ�̖ڂ���߂đ��ɋA��A�e�n�ɂ͏��������̓��u�̎c���Ă��鎖����B��쎡�[�͊�сA����ƏG���̋����Ă��̍������s�����B����͐�ɏ����Ɉ�t�H�킳��A�s���̈ӌ�����グ�Ȃ������l�̈Ӗ�����ł��������낤�B �₪�Ďl����\�Z���̖�A�˔@�A�Ó���삵��⾉Ŗ��߂ċ}�i���ė�����������S�R�̒�c��͍������a���ɐ�����A�������������Z��ɓ����������B�ꌂ�ŌS�R����U�������������́A��\�����ɂ͓��k�̑��X���Ă����āA�����ēޗǂɐi�܂�Ƃ����B�����m�����ޗǂ̒����B�͑傢�ɋ����A�����\�M�������� �u���Ƃ��䊨�ق��v�ƍ������t���R�ɓ�������ł���B�@ |
|
|
��(10) ���
���l�ȏ���l���Ă��A�l����{�A�G�����������R�𗦂��ď㗌����A���A�����A�ޗǂ��ꎞ��������͈̂ĊO�e�Ղ����������m�ꂸ�A���Ƃ��ɂ������������B ���ł��ޗǂ͓���ꑰ���v�����x�z���Ă����y�n�ł���B���̏t�A����孋��𖽂����Ă�������莟���A���q���Ɏ��n�𖽂���ꂽ�B�~�m�w�ɑ����˕�������̒��ɓ���̖�̓�������������Ƃ������R�ł���B�����m��A�[�������Ă�����ɁA�������̒��ł͍䕺�����n�߁A�����̓���Ƃ̋��b�����Ĕ����z����������ł���B �~�m�w�ł͂��������ޗǕ�s���ɒy�������\�Ð����l�́A����͖k�R���ɔ����Ă�������A��s�̒��V��͈��ɂ��y�����������B�����m��������̎��[��s���́A�E�ݗ����Ď��̍��ɂ��������B �Ɖ]���̂́A�G��������S�R�D��������Ă����A�l�����{�A���[�A�s���͋ɔ�Ō㓡�A�^�c�������A �u���x�̐�́w�v���������k�������˂Ζ��Ɉ�̏��Z���Ȃ��x�ƍl���A�S�R�U���̗��������A���͂���Ɉ������Ĉɉ���𗎂��A�X�ɂ͉ƍN�A�G���o�w��̕����A������ē��������ł�����B�v�ƑŖ������̂��A����Q�l�������Ƃ������̏ē��ł���B ���l�喼�̌Óc�D�������q�����m�����A�ƘV�E�ؑ��@������Ƃ���ܕS�]�l�ŗ���̕����A������Ă��B�o�w���čs�R���̉ƍN�A�G���������A���邩�琸���𗦂����㓡�A�^�c�̗��Y�ŋ��ݓ����ɂ���B�Ɖ]���ɉ��ȍ��ł������B ���˂ČÓc�D���̎��j�E�㔪�Y�́A�G���̒��b�Ƃ��ď�ɋ���A�s���̍Ȃ͌Óc�D���̖��ł���B���ꂾ���ɁA�Óc�D��������̉ƍN�̗]��ɔڋ��Ȃ����ɉ䖝���Ȃ炸�A�Óc�ꑰ�������đ��}�̉��ɕ邱�Ƃ���Ă��ꂽ�B���X�Ǝd�x�𐮂��Ă���A�Ɖ]���B �v��ʘN��ɗ��Y�����ł��Ċ�� �u�}�P���͐���Ƃ��g���̎�Łv�ƗE�ݗ����A�ł�����������ďo�w�����ɂ�����B�K���S�R���� �u�ĊO�e�Ղɏ����ɓ��ꂽ�B�������錈�s�̗\��ł��������܈�������J�ׂ̈ɓ�\������ɉ��������̂̐����͋^���Ȃ��v�̋g�������B�@ |
|
|
��(11) �I��
��i�ƗE�ݗ��������[��́A�����ē��R�̐�N�Ƃ��č�����߂����Ă���ܐ�̐�쐨��n�����m�ƌĉ����Ēזł����悤�Ƃ���B��\�������łɁA���A�V�{�s����̗E���Ƌ��ɏo�������B��Ɏc�����㓡�A�^�c�̗����́A�ƍN��̎�������A�ꋓ�ɏ�������ɓ����ƖȖ��Ȓ�@������W�J���Ă����悤���B �o���O��ɍs���� �u����҂͂��ׂċ������B���A�����̒c���͌ł��A�Y�S�܂��ɖu�X�I�v�ƋL���Ă�����ŁA����Ő�������ΐ�ǂ͈�ς����ɈႢ�Ȃ��B�������A�y�d��Ŕq�̃X�p�C�Ɍ������ꂽ�V���E��h�����q���A��q�̖����~�������ɖ�������A�Ɖ]���v���������ʎ����ɂ���đS�Ă��I�������B����͐��Ɂg�c�O�h�̈��ɂ���B �����̎�ŕҐ����ꂽ�ɉ�E�b��̖d�������́A���̏�Ő^�c�A���̔z���ɂ�������Ƃ͔�r�ɂȂ�ʍ����������悤���B�������q�̋}��ɂ��A�낤���o�w���O�ɂ����m���ĐF���߂��ƍN�́A�����ɏo���𒆎~�����B�ɉ�鉺�̓�\�]�l�A����A�������_���Ă����Óc���̌\�]�l����ԑŐs�ɂ��ׂ��������A��������������Ղ͖ڋʂ𔒍������Ĉ�������ɑ��点�A�h�����S����߂����B �Óc�Ƃ̉ƘV�E�ؑ��ȉ����Ԉꔯ�Ŏ�����������āA�Óc�D���� �u�V�^�����v�Ɩ��O�̗܂�ۂ炵���B�@ |
|
|
��(12) �~��̐킢�@�`��쒷��@�@��쎡�[�`
�����Ďl����\�����A�_�Ȃ�ʐg�̒m��R���Ȃ��A�S�R�̏���ɈӋC�g���������[�ƍs���͐܂���u�i���s���v�𐾂��Ă����B����ɂ��G���̎g�҂��a��̂Ă���쐨�̏o����m���A���̍���̋��m�B�ɔw���̏����𖽂���B�ňł�˂��A������O��̑O�q�𗦂��ĈӋC���炩�ɑ�����o�����A�I�B�X����쉺�����B ���̐�N�𖽂���ꂽ�V�{�s���A���c�E�q��A�������j��݂͌��Ɍ��������āA�L�˂ɖҐi���𑱂����B�܂�����쐨�̐�N�́A����̓���ɓ��������� �u�����A�勓��R����P���Ɠ쉺���v�Ƃ̕�ɋ����Ēn�̗����~��ɑދp�B����̉����Ɣ�����w�����ƂȂ��āA����◐�������������~��̍�ɍ����������A�n�`�������s���͗����ɒf�Ői���𒆎~�������B �u���̐�̗v�n�ɂ͕K���G�̕���������B�����ŖӐi�����A�{���̓�����҂Ƃ��v�ƌ����������������A�邪�������A���Ɖ����͖{���̓������҂����A�͂��Ȏ蕺�����Œ��˖Ґi���Ă��܂����B �ʂ��邩�ȁB�y����z�����A��쐨�̈�Ďˌ�����������A���C�Ȕ��͏����������A�Ґi���𑱂��Ċ~��̒��ɓ˓������B�������e���ɏe�e���������ē�����A�������d�����đދp�����B�s�����~��ɓ˓��������A�G�͑ދp���āA�����̎��̂��d�Ȃ��Ă������B�@ |
|
|
��(13) �����s����
�s���͎d���Ȃ��A�R���A���Q����V�������܂��āA���[�Ƒ��ɋA��� �u�ɉ���A�����ē��v�悪�I�����āA�ɉ�A�ؑ��ȉ��\�]�l���߂܂�A�����喼�̌Óc�D�����q�������ɉg���ꂽ�B�v�Ƃ̔ߕ�����ꂽ�B ����͏㗌�Ă����܂ꂽ�s�����A�Ō�̍�Ƃ��ċ`���E�Óc�D�����ɋ������͂�v�������g�N���̍�h�ł����������ɂ������R���Ƃ̍s���� �u���͂�l�͂ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�ʖL�Ƃ̕��^�̐s���v�ƒ��Q�����邵���Ȃ������炵���B ����������̂����S�R��̔������� �u���𒆎~���ċA�邹��v�Ɖ]���ߒɂȎg�҂���̂́A�l����\����������Ɖ]����B���̏��m�͒f���̑z���ňÓ����A�����ɈႢ�Ȃ��B�@ |
|
|
��(14) �㓡�����q�A����
���a���N(��Z���)�l�����A�틵�����G���͏������W�߂ČR�c���J��������������ʁA �u���߂�ꂽ������ď�͏o���Ȃ��B����ƂčL��Ȗ��ő�R��ɂ��ẮA���Z�͖R�����A�c��͒n�̗������Đ키��̂݁B�ƍN�͓~�m�w���l�ɑ�a�H���痈��Ǝv���̂ŁA��R�͍����̐�̓V�ӂŌ}�����ׂ��v�Ƃ̈ӌ��Ɍ������B �����đO�q�͌㓡�A���c��̘Z��B �{���͐^�c�A�ї��A������̈ꖜ��炪�������ցB �ʓ����Ƃ��āA�͓��X����쉺����G�ɔ����A��]�ɖؑ��̌ܐ�A�����֒��]�䕔��Z�炪�o�����đ��ʂ�˂����ƂȂ����B �����O���ɋ߂��A�S�R�̐������X���Ă̑�ꌈ��Ɖ]���悤�B �܌�����A��ÁA�㓡�����o�����A����ɏh�c���Ė{����҂��Ȃ���A���Ƃ��ƍN�A�G���̖{�w��P�������s�������A�Ɛ^�c�̔E�ґ��Ɣ����ɐˌ�𑖂点���B�������A�����͏���o���A�@����������B �܌��Z���̖锼�B�㓡����w�ƂȂ�A�����̕��̒n�̗����߂āA��a�H����i��ł���G��ב�������Ƃ����B �����ɂ͑������G�����i�o���Ă��鎖���������̂ŁA��@�������������ꂽ�㓡�͂�ނȂ��P�ƂŐΐ��n�͂��A�����R�̗v�n���m�ۂ���ƁA騂̐������܂������R�ɂȂ��ꂩ�������B�����͌ߑO�l���B �����ɂ��āA�G���E���c���������A���q������Ő��O�ɂ܂Œǂ����B�叫�E���q�d�����낤���������A�E���Œm��ꂽ�ނ��������� �u�m�ɋM�˂Ȃ��A���������ɂ���v�ƌ��Ĕтŋ��ɓۂ��Ă����Ɛb�B���g���ƂȂ��Ă��ꂽ�̂ŁA�h�����������т��Ɖ]����B�������͐�R���n�̌㓡�炵���B�@ |
|
|
��(15) �ؑ��d���A�Ȃɕʂ��������
�u�K��悵�I�v�ƑS�R�����炩�Ɍ~�g�������������B ����̉Ɖ]����ؑ������d�����܂��l�玵�S�̕��𗦂��A��a������o�����ċ��X��������Ă����B�n�`�ォ�猩�ĉ͓����̓��R�́A�K����(���)���c(�l����)���ւē쉺���A�������ő�a���ƍ�������Ɣ�������ɖk�i����ɈႢ�Ȃ��A�Ɣ��f�����B�����āA��͍���X���ɋ߂���]�ɐi�݁A�ꋓ�ɉƍN�{�w��˂��Ď��Ԃ��炩����A�Ɗo�債���B �������V�ȁE�����܂Ȃ���ɍ������߂��������Ԃ�A�Y�X�����ʂ������������v�E�d���́A�Ŗ�̒����𗊂�Ɉ�H���������]�ɐi�B�ʋ����O�ɐw���������̂͌ߑO���ŁA���������ʂ̖��̒����猃�����e���������ė���̂����ɂ��A�G��҂��Ă����B �͓����̓��R�͑����\�Ɖ]����R�ŁA�d���̔��f�ʂ�A�O��A�ƍN�͐��A�G���͍��c�ɔ����Ă����B�E��N�̓����͐�˂ɁA����N�̈�ɂ͊y�����ɐw���āA���̓��͑������瓹�����Ɍ����A�i�R����\�肾�����B �R���A�閾�O�ɍ������ʂŏe���������A�ˌ�̕ɂ��Δ����A��]���ʂł�������ɐl�n�̓���������Ɖ]���B���Ղ́A�G���̎w�߂����ׂ��A���c�Ɍ������B���̓r���Ŗ�������A�����E��]��т̓G�������ʂ�˂���Ƃ��Ă���̂�����B�����ɉE�擪�̓����Ǐ��A��̖������E�����g�⎁���A���擪�̍��Y��� �u�E�]�U���I�v�Ɩ������B �����̓������̐�͂́A�����A�R�m���Z�E�l�l�Z�R�A�S�C���m�E�܁Z�Z�A�|�E�܁Z���A���v�܁Z�Z�Z�l�Ɖ]����B�S�C�̐��́A�ؑ����̔{�͂������낤�B ��]�̖{�w���炱��������d���́A�����O�����āA�E�����͓������ɔ����A�{���ƍ������͏\�O�X����i��ŗ����ɑ����U�����鎖�𖽂����B�E�݂������E���͑傢�ɕ��킵�āA�����Ǐ��ȉ��̑唼���A�����i����]�B���A�d���͂�����~�߁A��]���ő��߂ɒ��H����点��ƁA�ߌ�̌���ɔ����ď[���x�܂����B�@ |
|
|
��(16) ���]�䕔���A����
�ؑ����ɑ����A�v���甪�����߂��������]�䕔���Z��́A����������̂����Ē������ɕ����A���𑵂��đ҂��\����B������т͓~�m�w�ő����ɏĕ����A�͂��ɉƍN�̎��m�E���n�`�䂩��̒n����(�����)�������c���Ă����B�킢�͒�����Ƃ��̓��𒆐S�ɓW�J���ꂽ�B ���]�䕔���̐�N��S�C���Ō��j�����������Y��́A�����ɏ悶�āA�nj������B�������A���ɕ����A��Ăɑ��œ˂��グ�����e���̗͐�ɁA���͐��e���̉Ɛb�������K����F���^��ɓ����ꂽ�B����ɍ��Y�A�����ȉ������������Ĕs���B���g��͖{�����牓�����ꂽ�n�����ŌǗ����Ă����B �������̖����鏫�Z�l�A�R�n�Z�\�A����S�]����������͏��������̉��R��Ŕj���A�������ŊM�̂����炩�Ɍߌ�̐킢�ɔ�����B�@ |
|
|
��(17) �ؑ��d���A����
�R���Ȃ��獑���ŏ�����������㓡�R�ɂ́A�ɒB���@���n�߂Ƃ���̓��R����������P��������A�㑱�̔��c��̓�����҂Ă��ɓ����B���c����e����̌`�ƂȂ��Ĕs���B�����m������]�A�������̓��R�͑����𗊂�ő��X�Ɛ���ɉ�������B �����ւ��Ă������R���A���X�Ɠ쉺���ė����R�̊֓����ɉ�����C���ƂȂ����B�ߌ�̏���ŁA��ɑ��̗E���E���A�R�������ĕ���𑱂��Ă����ؑ������\���Ԃ̌���ɁA����ɔs�F��[�߂��B�d�b��� �u�����͂���܂ŁB�����ɔ����ď�Ɉ��g�����v�Ɛi���������d���͊�Ƃ��� �u�ƍN�̎�����܂ł͒f���Ď~�߂ʁv�ƈ���������Ȃ������̂́A���������ꏊ�ƌ��߂Ă�������ł��낤�B�������������A�njR���l�Ɖ]�����p�Ő[�c�̒��ŗ͂��A��������Ƃ��������Ȃ���҂ɂ�������B �F���̕Y����������������ƍN�� �u�������Ēu���ΓV���Ȗ����ƂȂ����ł��낤�ɁB���Ƃ��ɂ�����҂����Ȃ������̂�v�Ɛ[���Q���]�����̂́A�a�c�̎g�҂ƂȂ��ė������牯���Ă����̂��낤�B�@ |
|
|
��(18) �������g�A���킷
�R���叫���������ؑ����̔s���́A�����쌴�ŗ͐풆�̒��]�䕔���ɂ��傫�������A�v�̑������߂Č����ɑ̐��𐮂���Ƃ����B�������A�������̒��ŁA�����A�����̓Ɨ��喼�Ƃ��ĉƍN�����������Ă������g���A�`���̋����~���Ɣ����n�����̕Ԃ苴�ɋj�[�̔n���|���ĕ��킵���B�����Đ��ɁA���̐������͐�ɒǂ������ꂽ�B �փ����Ő��R�̑��Q�d���Ƃ��]���ׂ�����ɂ���Ȃ���A����̉��������炵�����c�����̒��q�E�����ȉ����A���� �u���߂Ă����}�̉��Ԃ��ɁA�킵�ɑ���Đ킦�v�Ɖ]���ߑs�Ȍ��t�ɗ�܂���A�K���Ɏx�������̂́A�͂��ē������ꂽ���ł������B���q���ł��Ă���́A���g�ɐh�����鍂�Ղ��������ɕ���̂��悤���Ȃ� �u�����ւ�G���������͍̂��g�Ȃ�v�ƔF�߂Ă���B �G��ǂ��ĕ�����̂����n�ӊ����q�́A����������ދp���ė��鐼�R�����ďP������Ƃ������A���Ղ͊�Ə��m�����A�����ɌĂі߂����B�n�����̉��ɌܕS�]�̓G�̎����ׂĎ���������A��v�����̖������F���Ă��̖�͂����Œʖ���c��ł���B ���̐ȂŁA�����E�n�ӂ́A�ɒB����ב��������E�t�E�K���ɒ������Ƃ����������ꂸ�A����͂Ƃ������̖̂�����m�͂Ȃ��A�����ʂ����Ă����B���Ղ͂�������āA���͓����G���̉Ɛb�ŌS�R��ɂ��������ɋC�y�� �u����ከ���q��A���炭�ӂ���ċ��邪�̂��A�N���l���Ă�����B�݂��ɘZ�\�ɂȂ낤���A�킵���v���Ԃ葄������ēD�c�̒����щ�������R���A���̒ʂ肶��v�Ƌr�̑��������� �u�g�����͑厖�h�ƌ��ɂ��]���B�Ȃ܂������ւ��Ă������Č���A���̕������ƍN�������낤�������^�c�K������B�����͎��ł����ɈႢ�Ȃ�����B�v�Ɖ��߂��̂́A�S�g�������炯�ɂȂ����Ƃ����퍑�����̐��c��炵���������ɗ��h�Ȃ��̂ł���B ���ꂩ�畗���O�S�N�A�����ߓS�����w�ɋ߂��n������K�˂�A������̗��̕揊�ɂ́u���Ɏ�����v���������сA�������Y�ȉ����\��m�̕悪�c����Ă���B���Ղ������̎�������������̉��͍��������̓V��ɂȂ��Ă���Ɖ]������ɉ�䂩��̕��X�ɂ͂��ЎQ�q����Đ�c�̕����A���łɖ����̖~�x��ł��y����ŗ����Ă͂��������낤�B�@ |
|
|
��(19) �Ō�̌���
���a���N(��Z���)�܌������̒��B ����̓���������ŏ��ւ�ꖜ�]�̈ɒB�̔n�S�C�������s��������ɁA �u�֓��S���̕��̒��Ɉ�l�̒j���Ȃ����v�ƍ��ꂵ�ėI�X�ƈ��g�����^�c���́A�V�������P�R�̈�тɐԈЂ��̐w���\����B �K���͍���̌���̔����������A�w�n���ꏄ���ď��m�ɂ˂��炢�̌��t�������ċA��ƁA���i�ߊ��Ƃ��]���ׂ���쎡�����Q�����p�������āA�Ō�̍���c���J����A�����̈ӌ������߂��B �����͉��a�ȍK���������ɂȂ������������� �u���������Ō�̌���ƂȂ�\�����B�Ȃ�ǓG�͕S��B���̘V���ɗ�����ꂽ��ɎO�{����V���̑�R�����ɁA�e�ՂȎ��ł͏����͖]�߂܂��ʁB���ׂ̈ɂ͐���Ƃ��G�����̏o�n���肢�A��n����l�V�����̏铪�Ɍf���āA�e�������m�Ɍ�������鎖����ΕK�v�Ǝv���܂��B���炭�G�͓V����D�ꂩ��͍U�߂��A�S�R�������̕�����ʂ���P�����鎖�͕K��A����ĉ�R�͓V�����A���R���ɏW�����Ďv����G���茳�Ɉ������A�D��ɔz�������Γa�̐��s�����{����Z����ɐ��s���A���}�̘T�����オ��̂����đS�R��ĂɉƍN�A�G���̖{�w�����������A�����̎���������ȊO�ɏ��Z�͂���܂��ʁv�Ƌ����咣���A������������� �u�������͐^�c�a�̌R���A�m���ɂ��̑��ɕ���͂���܂��܂��B��낵���g���͂����蒼���ɋA�邵�K���G�����̏o�n���肢�\�����v�ƌł��ċA���Ă������B �������E�ݗ����Ď���ɋA�艪�R���̑��w������쎡�[�͒����ɔz���̕������W�� �u����̐킢�͗]��ɂ��邩�牓���i�݉߂����ׂɔs�ꂽ�B���������Ō�̌���Ȃ�Ό����Ē��P�R�A���R�����O�ɕ����o�����v����茳�Ɉ����Ĉ�ĂɖҌ����G�̖{�c��˂����Ɍ������B�����͂悭�R�@�����A�����ėE�Ɉ���Čy�͂��݂Ȕ����킯�͂��ʂ悤�����ɏ[���\���������A䑂������R�@�ɔw���҂͒����Ɏa���Ď̂Ă�v�ƌ������������B �s�����őO���̐w�n�ɋA��Ə��m�ɂ���������]���܂߂Đ�@�̓���̂�҂���т��B�@ |
|
|
��(20) �K�e��
���̓��̑��Ŏl���A�������o�������ƍN�͓�������Ղ����ĕ���ɒ������̂͏\���߂��ŁA�ł����Ǝv���钃�P�R�ɂ͎��������鎖�ɂ��ČK�ÂɌ������B�����āA���R�͑��ސ��R�ƊJ���҂��Ă��邪�G�����g�͖����o�n���Ă��Ȃ��A�ƕ�����A�g�҂���ɑ��点�u�u�a����Γ�J����^����v���ƌ������Ă���̂́A�Ō�܂ŒK�e���炵���d���Ɖ]���悤�B ���������Ȃ��Ă������ς�G�����̏o�n���Ȃ��̂ŁA�K���͑叕�𑖂点�čēx�v�����A�G����������o��Ɗ��{�O��𗦂��ēV�����Ɍ����Ƃ����B�������u�a�̎g�҂������̂�m�������N�Ɏ~�߂���B�����Ĕn�����g�ԂɎ������ċA�����̂́A���Ƃ��Ă����m�̎u�C�𐊂������鎸��ł������B�@ |
|
|
��(21) �ї����̗͓�
����ɔ�ׂē��R�́A�J���҂ĂƉ]���Ă����̂ɑO���̐킢�ŁA�ƍN���� �u���Q�ł����Ă������v�Ǝ���ꂽ�{��������A���}���G���A�z�O�����炪�����o��Ő�𑈂��Đi�����J�n�����B����͓G�������ƌ�������ł���B ���R�̕����A�g�c�������܂肩�˂ďe�����n�߁A�K�����}�g������ �u���̋R�n���̍��}�̘T���̂���܂ł͎˂��Ă͂Ȃ�ʁv�Ɩ��������A�R�Ղ̐����~�ߓ�A���ׂ̈ɖ��Α����o��ɏo���Ȃ��B ���̕����E�ї����������u�˕��~�߁v�𖽂������A�{��������������w���ɗ����ːi���ė���B��������āA��ނ������ɕ����A�{���������E����U�������B�E���͕��킵�ēG��ב������A�����͖{������������B ����l�V���̕M���Ƃ��ėE�������������{��������ł����ĈӋC�傢�ɗg�������ї����́A�����ď��}���G�����ɏP�����������B���������̗͓���������G�����q�������ɏ����̑唼����ł����A����ɐ����ɏ悶�ďH�c�A��쐨�����s�������A����̋C����f�����B ���̗͓��Ԃ�͌�ɓ��R�̗E���B��������܂��Ď]�������ɐ��������̂��������B�@ |
|
|
��(22) �K���A�����o�傷
�ї����ɕ������ƁA�����Ɏ��B���コ�ꂽ�z�O���ꖜ�O�炪�A�g�̂��̍炢���悤�Ȑ^�c�̐ԑ����l�R�ƕz�w���Ă��钃�P�R�ɓːi�����B ���˂čK���́A�V�����̒����O�ɏG�����̖{�w��u���A����O�ɏ����̐w���ꏄ���Č��コ��A�����猈���̊o��ł����������������ꂸ�A�틵�ɉ����ēK�ȍєz�������A�ǂ�Ȏ㕺�ł������ďG���������̂Ăē������锤�͂Ȃ��A�Ɗm�M���Ă����B �R��ɂ�����ɍ��������̂ɖ����Ɏp��������ꂸ�A���l�ȍ���ɓ����Ă��܂��Ă͍ő����̋@����Ȃ��B �̑��}���̕Z�̔n��������쎡�[�̐w�ɖ|���Ă���̂߂āA�K���͎q�̑叕�� �u����x��o�n����v�Ɩ����A �u����Ƌ��Ɏ��ɂ����v�Ɗ肤�q�� �u������Ɋ���Ă��o�n����ʂ̂́A���̖d�����^���ċ����邩�炶��A���Ȃ����l���ƂȂ��Đ���Ƃ��o�n���肤��������܂��B�������Ƌ��Ɏ��˂ΒN�����̋^���𐰂点�悤�B�s���I�s���ďG�����Ɛ��������ɂ���B���ꂪ���̍Ō�̖�����v�Ɨ܂��ӂ���Ď�����叕�𑖂点���B�T�ŕ����Ă����R�Ă̈ɖ؉��Y�� �u���������H���Ⴂ�A�ő��ǂ��ɂ���̑ł��悤���s�����悤�ł�����B���̏�͉ƍN�{�w�ɓ˓����ē�������O�͂Ȃ���������B�v�ƒQ���A�ɖ������ �u�ǂ���炻�̂悤�ł���܂��Ȃ��A�����̎v���o�ɉƍN�̔������_���Č��܂��邩�v�ƈ��n�ɂ܂��������B�@ |
|
|
��(23) �K���A�ҍU��
�������Č㐢�u�^�c���{��̕��v�Ǝ]������K���̐������ˌ����J�n�����B��ؐ������u�\���ꐶ�m��@�v�Ɩ��Â����O�R�c���˔j���ŁA�e���ɂ��ꂼ��K���Ɩ����E�������u�^�c�̂͂ˑ��v�Ƌ����ꂽ�\��������M������B �z�O�����̑�R��^�ꕶ���ɓ˂��j���Ă͍������A�Ăѓ˂��j���Ă͍������đ̐��𐮂���ƁA�{���̂悤�Ȍ~�g�œG�̊̂�₵�A�ƍN�{�w���߂�����@�ł���B �܂�����쐨�����{�ɋ}�i����̂����� �u��쐨���Q�Ԃ����I�v�Ɨ��������ēG�������낽�������A�����̔@���ƍN�{�w�Ɏa���ނ� �u��䏊�͂��������A�^�c�K�����Q�I�v�Ƌ���Ŗ\�������B �����̑O�R��˔j���Đ^�c�K�����{�w�ɓ˓����ė���Ƃ͍l���Ă����Ȃ��������{���͍����呛���ƂȂ����B����s�̕ۍ�A���c��́A�O�������ȗ��A���������̂Ȃ���n������o���ē�������B����s�̑�v�ەF���q����A����ɂȂ��ē����ė��������ɑ��݂ɂ�����B�{��������V���܂ł��A�������Ĕ����ɓ����U�����B �ƍN�̑��߂Ɏc�����҂͑�v�ۂƏ��I������ �u���͂₱��܂ł���B����낤�v�Ɖ]���ƍN��K���ɗ�܂��������������A�O�x�ɋy�ԍK���̎a���݂Ɋ낤�������ꂩ�����B ���v���̓`���ł́A�ƍN�͏d���̌�ɒËv��Ŏ��ɁA�邩�ɖ������ꂽ�Ɖ]���A���Ɉ��̖����̔肪�c����A��ɏG����ƌ��܂ŎQ�w���Ă���_������A�傫�ȓ䂪��߂��Ă���悤�ȋC������B �~�m�w�ŏ\�����z���������ăm�w�ł͌ܖ��ɖ����Ȃ��������́A�^�c�ۂŗE�������������K�����̌ܐ疼���V�����̌���ɎO�炵���Ȃ������̂����Ă����邪�A�K���̕���͖ڂ��܂����א쒉���� �u���̏P���ɗ��X�̏��Ƃē����ʎ҂͂Ȃ��A���씪���܂œ�����������҂͐����c����v�ƋL���Ă���B�@ |
|
|
��(24) ���[���A���킷
�����ۂ����R�ɖ{�w��u�����G���� �u�J��͑҂āv�Ƃ̉ƍN�̖�������đҋ@���Ă������A�V���������猃�����e�����������Ă����̂Ői���𖽂��A��N�̑O�c���ꖜ�ܐ炪�劽�����������ēːi�����B �R���s���ƕz�{���N�Ƃ��鐼�R�͗ǂ����̖�������āA�G���v���������ƁA�җ�Ȉ�Ďˌ��𗁂т��������B���̂��߂ɑO�c���̑��Q�͐r�����A���X�ɒǂ�������A��w�ɂ����������Ȃǂ́u�|�������|���ē����U�����v�Ɖ]���B ���̏�����āu���͍��v�Ɗ��������[�͈ꋓ�ɏG���{�c�̉��R�����P�B���@�ԂŏG���̑��߂ɂ�����ˎ��G�A���O��́A�ԓ��E�R���r�Ƌ��ɕK���ɖh�킵�A�V���E�����Δn���⍲�����o�O�́A�a�R����y�����u������A������v�Ɛ��炵�ĕ������B���A���Ƃ��~�߂�Ƃ����B �R�����[���̕���͌����ŁA�V���̓y��A����͌����A�������畐�����ւ������{���������̎q���U�炷�悤�ɓ������ꂽ�B���̕s�b��Ȃ��ɕ��𗧂Ă��G���́A�����瑄�����Ɠ����o��œːi����Ƃ����B����������b��҂̑啽���������ɔn�̌����������ĕ����Ȃ������B ���Ɋ�@�ꔯ���������A����s�̎O�}�������|���ꂽ�n���K���ŗ��������̂ŁA���ɓ��������Ă������{��������ƈ��A���Đh���������鎖���o�����Ɖ]���B �������[�������̍I���ɏ悹��ꂸ�ꖜ���z���Ă������������Ȃ�������A���R�E�G���͉��R�Õ��̈�p�œ��������낤�ɁA�ܐ�ɖ����ʕ��͂ł͏\�{�߂��G�������Ō�܂Œǂ��������͏o���Ȃ������B ����ł����ÌR�L�� �u���x�̑��̍���Ԃ�͌Í��ɂ���ނȂ��蕿�ɂĕM��ɐs����A���R�̏�������͂��U���͂̍��̂݁v�Ǝ]���A�s����̗͐�Ԃ���L���Ă���B�@ |
|
|
��(25) �G���A�o�n����
�g���{��̕��h�Ɖ]��ꂽ�^�c�����O�x�ڂ̓˓����ŏ����̖w�ǂ��������A�K�����g���d�����A�͐s���Ďr����ɖ��߂��炵���B ����ɗ͂��z�O�����^��ɒ��P�R�ɒ����̔n��𗧂Ă�ƁA��J�A��h�̏�����s�������A���̊����q�������Ȃ����Ɏ�����������̂͗���p���Ă̎��E�Ƃ��Ƃ��B �^�c�ƌĉ����ďG���{�w�̉��R���}�P���A������̏��܂Œǂ��߂��s���́A�������u�ɔR���Ĉ�ɂ̊���s�E�s�̈����˔j���A����̉ƘV�E�����ѓ��̎q�E�d�\���A�G���{�c�߂����čŌ�̖ҍU�����s�����B�ؑ��d���̈�b��͑f���ŏG���ɔ��������A�����h�����������@��ɂ���Ď����������ꂽ�Ɖ]���B �s���A���[���u�ő�����܂Łv�ƒ��߁A���Ɏ����������Ă��镔�����W�߂ċʑ����ɑދp���n�߂��̂́A�ߌ�̎O���߂��������Ɖ]����B �J��O�A�n�����ڌ��̎��[�{�w�Ɏ��Q������\�l�̎g�Ԃ��A�G�ɔ�ׂė]��ɂ������̕������ȉ߂���̂ŁA���܂肩�˂Ēy���߂����шɕ��q�����鋰�錾�サ�����A�G���͓����Ȃ������B �܂��畃�̖��Œy�������^�c���̕K���̍����ɁA����ƕ�̐��~��U�����G�����Ăэ�����o�ēV�����Ɍ������Ƃ������ցu�^�c���S�ŁI�v�̔s�͂����B �G���͍K���̊��҂ɓ������Ȃ������������ �u�ꎀ�͂��Ƃ��o��̏ザ��A�f�ŏo������v�Ƌ��i�߂����A�O������A���ė����V���E������ �u����Ȃ���r�𗐌R�ɂ��炷�͎̂叫�ׂ̈��ׂ��Ƃɂ��炸�A�ނ��Ė{�ۂ����͐s����܂Ő키�ׂ��v�Ƌ����Ђ߂�ƁA��������v���̋M���q�����ɑf���ɋ��Ԃ����B���ꂪ�����ւ̍Ō�̋@������킹���Ƃ��]���悤�B�@ |
|
| ��4.3 ���� ��P�~�o �@ | |
|
��(1) ��m�ۂ�������
�G���ƒ����̊��{�O�炪���ɂ��y�����{�ۂɈ��g���ĊԂ��Ȃ��A�˔@�Ƃ��ċl�̊�(*1)�̈�p�ɂ����䏊����g�@�̉�������������B�䏊���̑�Z�^���q�傪���˂ĕЋˊ����ɓ��ʂ��A�����ɂ܂���ĕ������̂ł���B ����O�Ɍ㓡�����q����������j�� �u��Z�͉������B�����ɏ�������v�Ǝ����ɐ\�����ꂽ�̂� �u����A����Ȕ��͂Ȃ��B�ނ͑��}�q���̗����l�ŁA�q�̌��Ȃǂ����ׂđ������p�厖�ɐ��サ�Ă�������҂���B�����ē�S�ȂǕ����j�ł͌�����v�ƕ����Ȃ������B ��Z�͑���Ŏa��ꂽ���A�͋����ɐ����ēV���ł����B����������z�O���� �u����邪�R���邼�I�v�Ɛ�𑈂��ēːi���A�O�m�ۂ̍����z���āA���@���n�߁A�Ђ��[��������A���D�Ɩ\�s���n�߂��B �V�����A���R���ɉ���������̓����͓Ɖ]����B����ł��G�������悵�ĎO�m�ی��܂ŏo�n���A�O��������g���ė��鏫�����܂��A������w���ɗ����Ėh��ɓw�߂�A�ǂ����������B�Ⴆ�x�͐Ƃ��A�L��ȓ�m�ۂ�����Ȃɑ��������鎖�͂Ȃ��������낤�B �^�c�K���͋ʍӂ��Ă��A�ї��A������̗E���������ɕ��킵�Ă���B����Ȃ̂ɁA�̐S�̏G��������̑���̉]���܂܂ɑ��X�Ɩ{�ۂɈ��g���Ă��܂����B���ꂪ���̔ߌ��������A����������V�{�s�����A���ւ�G���ɓ˓������܂����������B �� (*1) �{�ۂ̋K�͂��ӂ���A�{�a�����i�ނƁA�펞�̎i�ߕ��E�Ō�̘U�鋒�_�ƂȂ鏬�ȗ�(*1-1)���K�v�ƂȂ�A�{�ۂ̒��ɕʋ敪�Ƃ��č\�z���ꂽ�B������l�̊�(�߂̂܂�)�E�l�̏邠�邢�͓V��ȗւȂǂƌĂԁB (*1-1) �ȗ�(�����)�Ƃ́A���ꂼ��̖�����@�\�ɉ����ď���ŋ�悳�ꂽ�����̂��ƁB�s�E�f�̎������Ă邱�Ƃ�����B�ߐ��̏�s�ł͖{�ہE��̊ۂ̂��Ƃ��A��ʂɁu���ہv�Ƃ���B�@ |
|
|
��(2) �x�����v�A��P���~��
���A������͓����B�x�c�A��X���͎��n�B�ї���͂��ȏ��m�������h�����Ė{�ۂɓ������B �x�����v(*1)���Z�B�ƈ��A����ƍ����ɒH��������A����E�͋Ɖɕ�܂�Ă����B���̉A�ʼn������Ă����V������ �u�����I�����鏫�Ƃ������������B���͌Y�����m�ǂ���A���Ƃ�����Ȃ��䏊�l��̖{�c�܂Ō��쎒���ʂ��v�ƕK���̖ʎ��Ő�������������A���v�͋������B �u���Ɖ]����B��P�l���v�E�G���������̂ĂēƂ��𗎂����锤�͂Ȃ��B�U���\�����ȁv�Ƌl�₷��ƁA�ǂ� �u���������B����͑�쎡���a�̌v�炢�ŁA���Ƃ��G�����̖���ׂ̈ɎQ������̂���B�����ĉ�g�������ɗ�������̂ł͂���܂��ʁv�Ɖ�����т̑܂ɕ�܂ꂽ���������o�����B�����ŒԂ��������Ȉ��̖䂪�L�����ƌ����Č��������� �u���Ă������̌�䏊�l���v�Ƌ����Ȃ���� �u���m�d�����B�K�������ɑ���͂��Đi���悤�v�ƈ����B�܂��痈�������암����Ƃ��͂������A�Ɖ̉������������ď�O�ɒE�o�����B ������o�����ŁA���˂Đe�����������o�H��̈���Əo�����A�ނ̐s�͂Ŗ����ɒ��P�R�̉ƍN�{�w�ɑ���͂��鎖���o�����B���߂Ă��������̖����Ȏp�����Ċ�ƍN�́A�~�o�ɂ����J�̂������x�����v�ɒ��Q���{�ܕS�̉��܂�^��������łȂ��A���R�ɎQ�������s���ȉ��ꑰ�̍߂��������Ă���B ���R���ł͍őO���ŗ͐킵�A�G���{�w���P�����ĎU�X�Ȗڂɉ�킹���V�{���ł���B���Ƃ̉��݂��[���A�����тĂ��ɌY�͖Ƃ�Ȃ��������̖x���Z��ł���B���ꂪ���鐡�O�ɒ킪���Ă��v�������ʌ����ŏ��������B�v�������Ȃ��K�^���������̂ł���B�l�̉^�Ɖ]�����̂͐��ɕs�v�c�Ȃ��̂��B ����ɂ��Ă��A���v�炪�A��P���쑗���Ȃ��璃�P�R�����r���̏�́A�S�邽����̂������B���ւ������R�� �u�������҂����I�v�Ƃ���Ɏ蓖�莟��Ɏ��������B���R�͑��v�ňꖜ����̎���������Ɖ]������A�������l�̌������Ȃ��E�C���d�˂��悤���B �G���̏��@�Ԃɏ����ꂽ�o�O�̎q�E�ǍO�Ȃǂ��傢�ɕ��킵�Ď�����A�]���� �u�ƂĂ��d���Ď��Ă܂��ʁv�Ɖ]���̂ŕ@�������Ď����ɋ������������B����ł͕��m�����l���̋�ʂ�������Ȃ��B �� (*1) ���͋I�ɐV�{���E�x�����P(*1-1)�B��͋�S�×��̗{���B�Z���V�{�s��(�f���Ƃ������)�B�]�˖��{���{�B ��1600(�c��5)�N�̊փ����̐킢�ŕ����P�����R�ɑ����ĉ��ՁB��A�a�̎R�ɓ��������K���Ɏd���邪�A1614(�c��19)�N����̑��̐w�ł͑���ɓ������B���N�̉Ă̐w�ő��闎��̍ہA�m�荇�����������o�H�璼���w�܂ŁA��P����q�B���̂��ߐ��A�͂���ĉ���������500��^�������{�ɁB1657(����3)�N8��20�������B���N63�B���s�̓V�J���ɑ���ꂽ�B ���Ȃ����v�̌��ɂ��A�����������ɑ����Ċ����Z�s�����͂���A�������ՂɎd�����B�����Ŏ��ۂ̐퓬�ɎQ�������������A�w��ɑ喼�ɏ�������ꂽ��͔��ɒ������B (*1-1) �܂ق�̗������Q�ƁB�@ |
|
|
��(3) �G���A����
�����̖邪�����������̂��ƁB �Ћˊ����́A�Ă��������{�m�ۂɓ����āA�����������ׂĂ����B�����ĎR���ۂ̈��c��q�ɏG����q������ł���̂����A�E��ŏG���A�ƍN�ɋ}���B���̎��A�ꌾ��������Q�肵�Ȃ������Ɖ]��������B�ނ���\���قnj�Ɏ��͓̂V�������m��Ȃ��B ��쎡���⑬��(*1)�͍Ō�̖]�݂Ƃ��Đ�P��Ԃ��A�G���̏�����Q�肵���B�������D�_�ɒǑK�ŁA�ƍN���q�� �u�L�b�ꑰ��f�₳���Č�Q�������v���Ɍ��߂ċ���A��ɂ�����ɖ����A���c��q�Ɉ�Ďˌ��������Ď����𑣂����B �G���͖ї����i�̉���œ�\�O�˂�����Ƃ��ĉʂĂ��B ���N��A��쎡���A�������q�A�^�c�叕����̉Ɛb�̎q�ŏ����̐ӔC�����������؏�l(*2)�܂ŎO�\�]�l����q�̉��̒��Ő��U���I�����̂͌܌������̒��ł������B �ė����������ɋ��A��ܖ���(���l��S���~)������߂��ċ���A�ƍN�ɒD���Ă���B���a�R��Ƃ͑�Ⴂ�ŁA�Γc�O���������� �u���Ƌ��̎g�������m��ʋ����ҁI�v�Ƒ����������낤�B �� (*1) ���� ��v(�͂�� ����Ђ�)�B�L�b�G�g�Ɛb�B�͂��ߋߍ]�����S�̓y���ł���A��䎁�̉Ɛb�B��䎁�ŖS��ɏG�g�Ɏd���A�ߏK�g���A����ߏO�Ƃ��ċߍ]���l�ɍђn��B���q�E���v��̐킢�A���c�������Ȃǂɗ�킵�A���N�o���ł͔�O�����쉮��{�ۍL�ԔԏO�Z�ԑg����w�߂��B�����ɂ͏G�g�̐g�ӌx��ɂ����������B��s�Ƃ��Č��n�Ȃǂɂ����A1��5000��q�́A���4���܂ʼn������ꂽ�B ���G�g�v����G���ɂ悭�d���A���{�����̒��j��S��������g�̕M���ƂȂ�B�c��19�N(1614�N)�A���L��������肪�N����A�a�����ɖz�������Ћˊ������t�ɓ��ʂ��^����悤�ɂȂ�ƁA���̒���ɐs�͂���B���NJ����͑����ދ��������A���̌���������L�b�ƒ��̒���ɓw�߂��B �����~�̐w���n�܂�ƁA����̐킢�ŏ㐙�i���̌R������ɕ���B���l�ɉĂ̐w�ł͓V�����̐킢�Ő^�c�K����ƕ���œ������Ղ��R�U�炷�ȂNJ������̂́A�O�ǓG�����s�k�B ������ƍN�ɏG����̏�����Q�肷����̂̕���������邱�Ƃ͂Ȃ��A���Q����G���̉���߁A���̎��ɏ}�����B��v�̎q�ł���`�g(�o����)�́A��v�̒��߂��܂���ċ����ꂽ�Ƃ����B (*2) ���p����(�Ԃ���������)�B1568�`1621�B�ՍϏ@�̑m�B�ɐ����̏o�g�ŁA�����͒����d���B�o�Ƃ�����A���\�̖��ł͉��������ɏ]�����N�����ɁB1600�N(�c��5�N)�ɋ��s�������̒��V�A���̌��T���̒��V�ɁB�������ɏG�ŁA1614�N(�c��19�N)4���A�Ћˊ����ɖ�����ꋞ�s���L���啧�a�̍Č��H���ɂ����Ğ����̖������N���B���̖����ɕs�g�Ȍ�傪����Ɠ���ƍN�͈��������A�啧�J�ዟ�{�̒��~�����߂�(���L����������)�B���N8���ɂ͊����ɓ��s���ďx�{�ٖ֕��Ɍ������A�R�m�������Ă���B���Ԃ͏�����肩�瓿��ƖL�b�ƂƂ̑Η��ɔ��W���A���̐w�̉����ɁB���h���A�����A��T������Ǖ��B�Z�V�̓V���@�͈ꎞ�p��̗J���ڂɁB���p�͑O�q�������������Ƃ̊W�ŕ�����悤�ɖL�b���Ƃ̂Ȃ��肪�[���A������T���Z�m�œ���ƍN�̌ږ�ł��������n�@���`�Ɛ����I�ɑΗ��A�Ǖ����ꂽ�Ǝv����B孋����ɗї��R�ƒm�荇���A�̂����R�̎��Ȃ��Ȃǂɂ�苖���ꂽ�Ƃ����B�@ |
|
|
��(4) �G���Ǔ�
�����ʼn��߂ďG�g�v��̗��j��U�Ԃ��Ă݂�B ���ɍۂ��đ��}���J�Ԃ��G���Ɉ₵�����t�� �u�������Ƃ��āA�_���сA�����ɗ�݁A�\�܍˂ɂȂ�ΓV���l�ƂȂ�A�L�Ƃ̔ɉh�Ɩ����̑ו����v��˂Ȃ�ʗ����Y���ȁv�Ɖ]�����ŁA���N����ɂ��������A���߂ė����B �G�����A�����́A���ƁA�����A�̂悤�ȍ����ȕ������D���ŁA���e����ł����B�����āg���h�ɂ��ẮA�O��@�`����獂�m�̊����ŁA�[���M�S�ƕ��w���̂��������B �u����ɂ��܂��A����ɂ��݁A���̈����m�鎖�����^�̕��l�v�ƐM����M���q�Ɉ���Ă������悤���B �t���C�X(*1)�́u������ɂ�Ēq�E�����A�L���X�g���ɑ��Ă���������ԓx���������v�Ǝ]���A�\�N�Ԃ�ɏG���ƑΖʂ����ƍN�́A���̓��X����ԓx�ɐ�������u�ƂĂ����l�̉��m�Ȃǎׂ��l���ł͂Ȃ��v�Ɣ��f�����炵���B ����ǏG���̕s�K�́A����葾�}�q���̗D�ꂽ�l���͑喼�ƂȂ��đ��𗣂�Ă������Ƃ��B ���̏�ɁA�����́A�����A���f�h�őΗ����āA���N�Ɩk����(�G�g�̐���)���ɕʂ�A�����������Ă����B ����ɏG�g�ɂƂ��Ắg�T�䓛�̌N�h�ł��鐳�Ȃ˂�(�k����)���A�g�������h�̏��S����A�v�̈⌾�ɔw���āA���Ƃ̐����d���������Ƃł���B ����ɑ��߂���͂̂��A���C�œƍٓI�ȗ��N�ɁA�D�c�ꑰ��Ћ˂̂悤�ȋ`�S���������b�ƁA���������ÒK�ƍN�̑����ɂ��y�ʑ���̖}�������ׂ̈ł���B ����ȘA���ɕ⍲����Ȃ�����A�G���� �u�p�J�̒��Ő�����������}�̎q�Ƃ��Ĕ������S�т�v�Ƃ��铹��I�̂͂������ɏG�g�̎q�炵���B�������A�킳��m��ʏ���ȋM���q�����ɁA�d��Ȑ�@�ɕS��B���̐^�c�A�㓡��̖����A�R�t�����A�c��������e����ŗ�������̐b�̌��t�Ɏ䂩�ꂽ�B�叫�Ƃ��Ēq�E�m�E�M�E�E�A���̌ܓ��̂����̍ł���ȗE�f�Ɍ����A�@���킵�A���̎��ꏊ��������B���̂��Ƃ͉��Ƃ��Ă��ɂ����B�g���`�͔ߌ��ɂ���Ă����h���ɍʂ���h�Ƃ������Ƃ��B �H��̔e���������ƍN�ɑ��A���s�͘_�O�Ƃ��Č���G���B�c����蕶�M�ɏG�ŁA�����������闘�x�̈��r�A ���S���ā@���˂�������@�t�̖�́@�Ő��Ɍ���@�Ԃ̐F�X ������}�ȕM�ՂƐ����Ȑl�����猩�� �u�����������d�A���̈����m���č��Ԃ̂悤�ɎU������m�J�̓��ɂ�������叫�Ȃ�v�ƐM���A�V���Ȃ����я�(*2)���ӂ���A�L���_��(*3)�Ɍw�ŁA�ނ�ł��̖������F��݂̂ł���B �� (*1) ���C�X�E�t���C�X�B�Ώ�P�ۏ���Q�ƁB (*2) ����̕ʖ��B�V��t�́A����9�N(1997)�A����C�H���ɂ���āA�O�ǂ̓h��ւ�������i�̏C���A�����̉��������Ȃǂ��Ȃ���A���ǂƋ����̋P���ōʂ�ꂽ�������p���S�����B (*3) �ق������_�ЁB���s���������2-1�B�L�b�G�g�A�L�b�G���A�L�b�G������J����_�ЁB�@ |
|
| ��4.4 �Q�ԂT�䓛 �@ | |
|
��(1) ��ˑO
���a���N(��Z���)�܌������̌ߌ�A�L���}�����̒q�����ӂ�i���Ēz���グ�������鉩���邪�A�͂�����̐킢�ŁA�V�����ł��������̋Ɖɕ�܂�ĉ��サ���B ���̍��A��ˑO�ƍP�g��́A����A��̈Ó��̎R����䩑R�Ƃ���߂Ă����B ���̔N�̐������X�A�a�r�����������̂��A��(���[�āE��˗ǍO)�̎O�N�����c�ނׂ���a�ɂ���Ă����O�ł��邪�A�v����������_�͍Ăы}���������B�A��ɋA��Ȃ��Ȃ����O�� �u�悵�B���̋@��ɁA���̉]�����킢�̔����A���̖ڂŊm���߂Č��悤�v�Ǝv�������A��a��~���狞�A���܂ő���L���A�����ɋL�^�Ɏ~�߂Ă���B �����ĕ����Ⴋ�����߂����S�R�邪�����ɒD��ꂽ�̂����āA��������C�ɂȂꂸ�A�����c(*1)�̗v���ɉ����Č����Ƃ�����A����̗L�l����ڌ���Ƃ��̎R���܂ő����̂����肵���̂ł���B �u���Ɖ]���Ă��V���̑�邾�B�O����ܓ��ŗ������͂Ȃ��v�ƁA�Y�}�̈�˖���V���Ɏ������̐H�Ƃ��������Ă���ė����B �����A�܌������ɂ͑������V��t�͉e���Ȃ� �u�G�������n�I�v�̔ߕ��ꂽ�B����őO��͎R���~���B �� (*1) ����莟�ƕs�����������Z�ꑰ�B����莟�͓��䏇�c�̗{�q�B�~�̐w��A���q���Ɏ��n�𖽂���ꂽ���Ƃ́A�ăm�w�̌��l���Q�ƁB�@ |
|
|
��(2) ���l��
�O�炪�A���A�����X���ɏo��ƁA�e�͂Ȃ����l�낪�n�܂��Ă����B���ɕS�l�߂��������Ђ��[�������͂˂��Ėڂ��S��ł���B ����莟�̈�b��A�Óc�D�����ɎQ�����߉^�̐l�X�����Y���ꂽ���A�O�͂��̏��m���߂ɍs���Ă���B ���鉺�ł́A���n�ɏ悹���Ȃ���A�����͂�A�B�R����ӋC�������Ă���v�������Ȃ��A�������ɋ����܂点 �u���O�l�́A�܂��A��Ύ�蓙�Ɖ]�������Șb�ɂ̂����āv�ƒQ���ƁA���̕v�� �u�ق�I����ۂ�ŕ����ꂽ�a�̋w����낤�Ƃ����킵�̋C����������B��\�Z���̖�A��J���~��Ȃ�A���N�n�R�邵�̂��O����Ύ��̉����l�ɂȂꂽ��v�ƁA�Ō�̕v�w���������������ɏ�����p��������ꂽ�B ���̘Z���͌��ł́A�ƘV�E�ؑ��ȉ��O�\�]�l���A����������m�炵���Ō���������ĎU�����B����ɔ�ׂČQ�O�̒��Ɍ������⑰�炵�����A�q���̒Q���l�͌���ɔE�тȂ����̂�����A�O�́g���܂������̂͋{�d���h��Ɋ������B ���� �u�e�҂Ɏd����Δۉ��Ȃ��e������܂˂Ȃ�ʂ��v�Ǝc�������t���v���o�����悤�ł���B�@ |
|
|
��(3) ����Z��ƌÓc�D���A���n��
�ߌ��͑���̔s�҂݂̂ł͂Ȃ��B �S�R��Ŏ����������������ĕ��Z��ɗ����A�����c�͑Q���������S���W�߂��B�Ăѓl�u�ɔR���u�����D��I�v�Ɍ����r���ŁA�V���̖���Œm��ꂽ���邪�͂�����ŗ������̂�m�炳���B�툶�� �u���Ȃ��̉]���ʂ�ɂ���Ηǂ������B�ӂ͈�킵�ɂ���v�Ƃ̈⏑���c���ē����c�͎��n�����B�����m������� �u�߂͓������v�ƐՂ�ǂ��A���ꓛ��Ƃ͍Ăђf�₵�Ă���B �����X���߂��ꖜ����̎N����̐��������i�B�͂����̏G���̎q�E��������e�͂��Ȃ����Y����n���̋S���Ȃ���̎p�B�O�͂��������Ă� �u��������ȏ��ɂ͂������Ȃ��v�Ɩ]���̔O�ɂ����� �u�A��Ȃ��̉��܂��ɍr���Ƃ��v�Ƒ�a�����̂͘Z���������B�܂����J�ł͕��̒m�F�̈�l�ł������Óc�D�����撲�ׂɑ� �u�]��������������ǁA�ى����݂Č����炸�B���Ȃǐ낤�v�ƗI�X�Ǝ��n�����b������Ă����B ����̗���ɔC���ċ���A��m���x��Ԓ�q�̒��l�喼�Ƃ��ĕ�����n�邱�Ƃ��ł����낤�ɁA�`���т���Ƃ��āA�g��S�������ꂳ���A�̕��E���[�Ă͂ǂ����Ă����낤�B�O�͂����v���Ȃ���A�䂵������u�₩�ȋg��̎R�H��H�����B�@ |
|
|
��(4) �ؑ��d�� / �Q�ԂT�䓛
����ɂ��Ă������O�\���̗��R�̒��ʼnԂƎ^����ꂽ�ؑ��d�����D�u���鐶���l�ɁA�l�X�͋���ł��ꂽ�悤���B �~�̐w�̘a�r�ׂ̈ɕ������ǂ̎����ɉ����čs�������A�N��l�j�ƋC�Â��Ȃ���������v�ł���B�����ɒ���̑�����ʂ����̙z�X�����Ɉ�ڍ��ꂵ�����N�t���̐��Ɖ]���\���̉����������ł���ĕa�ƂȂ����B�Ȃ������̂����������ɁA�߂ł����v�w�ƂȂ����̂��A�~�m�w�̘a�r��ł������Ɖ]���B ���̂悤�ȓ��X�����̊ԁA�ăm�w�ƂȂ��ĕv�̏o�w�������A�ʂ�̔߂��݂Ɋ������˂��ޏ��͎����疽��f����Ƃ����B �����m�����d���� �u���̎q�����܂��܂ł́v�Ƌ����]�݁A�]�B�n���̗��̎��ƂɋA���A�₪�ďd���͎�]�̐킢�ŎU����B �Ȃ͌����ɕv�̈▽�̂܂܂ɐ��������āA�j�̎q���Y�ނƓ�ƂȂ�A�v�̈���������܂�����ɗ��e�Ɏq������A ������тā@���閽�́@��������@���Ă�����Ɓ@�]���l������ �������̋�Ƃ��ĕv�̐Ղ�ǂ����Ɖ]���B�@ |
|
|
��(5) �˂�
�O�́A�J�ɗ���鈣�̃G�s�\�[�h���Ȃ���A�փ����̍ۂ́A�˂�(�G�g�̐���)�̑ԓx�ɂ��ĕ��E���[�Ă����̂悤�Ɍ����Ă������Ƃ��v���o�����B �u�˂˓a�́A�]���Ȃ�A�G�g�́g�T�䓛�̌N�h�ł���A���G���̍ȁE�Ђ�a�������悤�ȗc����̕��ł������B�R��ɖ��q�a�͌N�q�l�ł������̂ɁA�G�g�͏������ŏ\�Z�l�̏�������Ȃ��珗������~�߂Ȃ������B�������߂Ȕޏ������z���������̂��낤�B�₪�Ắg�R�h�Ɖ]��ꂽ�����̐��q�̂悤�ɁA�q�����E���ɂ��Ď��Ƃ̔ɉh������厖�ɂ��A�L�Ƃ͕��^���ĖS�Ԃ����m��ʁB�O��A���ꂪ���̉]���w���ʉ���̗��x�ł��邱�Ƃ����ɍ��݁A�킪�Ƃ̗R������A�g�T�䓛�̐S�h��Y��܂����v ���̂悤�ɋ����r���߂Ă��������v���o���A�Y�}�̈�˖�ƌ�炢�Ȃ���A����������z���āA�O�͖k�R�̂ɓ������B�@ |
|
|
��(6) �I�ɁA�F��A�g��̖L�b�}�̍Č��N
�Ă̐w�̔ߌ����瑁��J���A�C���̗��ł���O�S�̏h�ɒʂ���썇�̗��ɂ͕��a�̌��͏������x���̕��B�̖ڂ��������B�������A�O�ɂ͏G�����ȗ��̒n�m�F����B ����ɍ���͗������ɍۂ��ē����ɌZ�B��K�˂ĕʂ�����������A�q���i�ォ��̓��ʏ����Ă�������X���̒ʍs�����R�������B�������A�r���A�Y���ɓ���⑺�X�̗l�q�͔ߎS���ɂ߂Ă����悤���B �Ɖ]���̂́A���̂悤�Ȏ������B�����ňꃖ���قǎ��Ԃ�k��B ���āA�ăm�w�̎n�܂����l�����A���R�̌S�R�U����m�����I�ɁA�F��A�g��̖L�b�}�͍Ăш�ĂɌ��N�����B ��R��U���Ɍ������͎̂R�������A���g�Z��ŁA�~��ł̏����A����ɓ����A�L�c�A�����S���̐��̉Ր��ɕs���������m�R���B�ɍL���Ăт����A���̑����͓��ɒB�����B �k�R���ʂł́A�|���V�l�Y�����邩��S�C���𗦂��Ēy�������B�܂��A���J�̋|�̖��l�Œm��ꂽ����O��ƍ��������_�쑺�̖x����w�A���R�������̐����y�E�q��A�ܖ��^�A�Ԓm�̒������Z�E�A������I���̌������Z�E���������ƂȂ��āA�L�b�Ƃɑ���`�����сA����������̏d�œP�p�����߂āA�Ăю��X�ɖI�N�����B �{�{��~�ł́A�R���_�E�̔~�m�V�A�ԍ�吆�V���A�r���ɓ��炪�ʒu�R�̑���s�ҒB�ƌĉ������B�����āA�{�{��Ђ����_�ɁA�L���\�Ð���ʂɂ܂œ��m����A�����̈��\�E��{�A�|�m�V�ꑰ��Ǖ�����ƌv���i�߂��B ���̊O�ɁA������̉F��A������͔����̊����q��ƌĉ����Ėm�{�㊯�����P���Ƃ��ċ���A�Ꝅ�̉̎�́A�L�������A�k�R�A���C�u���O�\�]�����n�ߑ�a�k�R�A�\�Ð��~�ɔ���Đ��ɑ呛���ƂȂ�n�߂��B �Ⴕ���邪�͂������ŗ����Ȃ�������Ꝅ���̎�͎͂�R����͂��A�ʓ����͑�a�k�R����g��ޗǂɁA���͏\�Ð�A�����Ȍ����Ęa��A�͓��ɐi�������낤�B���ɘa��R���ɂ͎��Q�����e�����@���҂��Ă����B�@ |
|
|
��(7) �L�b�}�̐킢�A�Z���ŏI����
����ɑ����˂ł͑O��̈Ꝅ�����Ɋ����F�ɂ����̕���嗢�����Ԗ؏�ɔz���āA�ނ̏��̂ł���k�R���l�S�̑��X�̖h�����ł߂��B �܂��A�ˎ咷��͋I�ɎR���ɖ{�w��u���A��R����߂����R���ꑰ�⏬�����g������ł��Ĉꍏ����������Ɍ����Ƃ����B �V�{��ł͖����ƘV�̌˓c�Z���q�傪�T���A�c�ӏ�ɂ���썶�q�卲����I�ꂽ�������̓�����f�Ȃ��ɂ�ňꝄ�̏P���ɔ����Ă����B����͓~�m�w�Ɏ�����z������쐨���A�V��������ɂ͋͂��l��ŋI�B�X���̍Ō���ɔz����Ă���̂����Ă����炩�ł���B �R���Ꝅ���̎m�C�������������̂́u�܌��������闎��A�G�������Q�v�̎v�������ʔߕ�ł������B�܂��������ŗL���ȕ��`���̍Ԃŋ@���_���Ă�����쐨�͐��������đ��U�������s����B����Ƌ��ɋt�k���n�łɑ��z�̉��܂���̂Ő킢�͒Z���ŏI�������B�V�{�˂��Z���\���ɂ� �u�F��ɂċ��N�Ȃ�тɓ��N�Ꝅ���Â��鍶�̎ҋ��A�����������s��\�������v�ƕz�����Ă���B ����ɂ��Ε��J�̕���O��́A�k�R�r���ɐ�������߂炦���A�̖{�A�k�R�X���̕���_�Ş���A�Ƒ��Z�l�����ƂȂ����B �x����w�́A�s���s���ׂ̈ɕ�Ǝq�����ɕ߂�ꂽ�B �|���V�l�Y�́A��◎���ɋA��R���ɐ���ł��鏈��߂���ꂽ�B �ނ���n�߁A�����O�S�Z�\�]�l���L�a�쌴�Ŏ����a�ꂽ�B �{�{�̔~�̖V��́A�������O�ɒ|�̖V�ɖ�������ĕ߂������A�_�E�̂��A�ŒǕ��B�y�n���Y�́A�ʂ�|�̖V�ɗ^����ꂽ�B �Ԓm�������A��I���������A�F��c�����̏Z�E�B�́A�m�E�Ƃ͉]���ߐ炸�A�Ǝa�߁B ��R���P�����R������ܕS���߂������Y���ꂽ�B �k�R��~�́A���{���͒��[�����������c�}�{�����s���A���̋]���҂�������Α�ςȐ��ɒB���A���̑�Õ�s�Ŗ���@���s��������@���q��̋L�^�ł� �u�k�R���Ȃǂ͑S���l�e�������ʗL�l�ŁA������������}�ɒ���㊯���A�]��̋���������˂āA�e�n�ɓ��S���Ă����ǖ��̒�����S�l��[���ɔC���āA���v�̗������ɐs�͂����B���˂ł��A�m�{�R���̗t�S������S�C��\�l�O��Ґ����Ċe�X�N�ܐ��x�����A�̓��̎����ێ��ɔC����Ȃǂ̔z���������Ă���B����͗]���̎��ł���B�v�Ƃ��Ă���B�@ |
|
|
��(8) ���J�|�����K�˂�
���Ă̐w����O�S���\�]�N��̕�����N(���㎵)�H�A���N�ɑ����ċI�a���̎j�Ղ�K�˂Ĉ�i�Ɛ������ꂽ�Ԗ؏邩�畽�J�̎O��n�����߂����B �k�R�A�������A�Ȃ鑺�͂���ɂ����ɂ��������d�ˁA�痧�����肩�łȂ��Ε��������Ă���B �������͕��{�O��ƌĂꂽ�悤�ʼnĂ̐w��ɖ����ɂ���č����ɉ˂���ꂽ�������m�������˂͗̓����J�ɏZ��ł������Z�l���u�͂����́v�ɂ������ƕ@�����Â��ɂ��ĐV�{�ɑ��点�Ă���B �L�a�쌴�ɂ͌F��e�n����W�߂�ꂽ����@�̑��ɕ߂炦��ꂽ�O�S�]�l�A�a�C�̏������`���q��͍߂��Ȃ��̂ɒ��ׂ��������ɂ���Ă��邩��A�܂��ɌF��n�܂��Ĉȗ��̑�S���Ɖ]���悤�B �O��n���ɂ��Q����ʂ����ĎR������k�R���n��Ƃ������~�̐w�̏\��\�����A�����ƂȂ����S�ѓ��ő����̖�����E�҂̌������ꂽ�B ���̏㗬�̒|���ɂ͌�쒩�̋`�m�|�����Y�̕�⏬�哃�{�̍��u�_�Ђ��Ղ��Ă���A�䂩��̉Ԓm������h�ɐ�������Ė����ƂȂ��Ă���B�R��ɗ͐킵���ł��낤�q���̐V�l�Y�ɂ��Ă͉����c����Ă͂��Ȃ��B ���Y�͈ېV��ɑ喼���݂ɑ��ʂ���Ă���̂ɐV�l�Y�͉��̈������Ȃ��Ꝅ���N���������k�̂܂܂ł���A����̈�p�̖L���_�Ђɂ͏G�g�A�G���Ƌ��ɏG�����_�Ƌ���Ă���̂ɔ�ׂĉ��Ƃ��C�̓łłȂ�ʁB �������̍�킪��������Β���̂߂��������������h��A�F��O�R�̐_�̂��̂ǂ���L���ɂȂ�u�����̍K���ƒ����v���b�ޑ�_�ւ̐M�͈�i�ƍ��܂�B�Ђǂ��N�v���������Ē|����k�R�}�̐l�X�́u�ǂ��̎�l�v�Ɛe���܂�A�₪�Ắu���������_�v�Ƌ���Č��݂������Ղ葱�����Ă���ɈႢ�Ȃ��B�����v�����Ɓu���̂܂܂ł͐��S�̋`�m��̍��������ł��Ȃ��v�ƒɊ����A���Î���N�@����Ƃ����k���āu�����₩�Ȉԗ�Ղł������悤�v�Ɖ]�����ɂȂ����B ����ɂ��Ă�������ɂ߂��̂͌F��̗��l��ŁA�s�ꂽ���̂ɐ��̌��߂��O�\�㖜�̏d���N�v�������̋I�B����ƂɎp����āA�����ېV�܂ł̐��S�N�Ԃ������ꑱ���A���l�̐�����L���ɂ���ڂ͂Ȃ������̂��C�̓łłȂ�Ȃ��B �A��́A�o���O�Ɉ��̗t����̊����Ŋ������炵�ē����Ă����u�叟�R�o���g�z�R�v�Ղɒa���������҉���ɓ��������A���������������Z�ȎR�̂��œ��ɐZ������A �u���`�̌R�͔s���̂����̏�Ƃ͉]���A�Ă̐w�ōs���̍�킪����������A���̒n�͐��ɓ������ƂȂ��Ă����낤�Ƀi�A�v�ƁA������ɗ������o���B�@ |
|
|
��(9) ��ˑO�̂��̌�
�O��́A���Ɛe���̐[�������|���ꑰ�̔ߌ�������ɔE�т��A�R�����������͂����Ă���B����͑O�q�����ʂ�A�������ɍۂ��ē����ɌZ��K�˂��ہA�q���i�ォ��̓��ʋ��s�����Ă�������ł������Ƃł���B���ꂪ������Ύc�}�̈ꖡ�Ƃ��ꂽ�����m��Ȃ��B �������ʒu�R�ɘA�Ȃ�䍂�R���ɐ^���ȓ����_�̕��������Ă��������A�O��́A�Q���ɂ��āA�K�����Ƃꂽ��ƂɋA�����B�ꑰ�����ďj�u�������邱�Ƃ��ł����͉̂����������������낤�B �������čĂюR��Ɏ����������e��̊���������A�F�A���A���A���A�T�Ȃǂ�����āA�����������B�����Ċe�n�ɔ̔����Đ��v���c�ނƉ]���O�̓��X���n�܂�B �×�����A�F��͗��l�̋Ɋy�Ɖ]����B���ꂾ���ɁA���̑��̌���A�{�{��~�ɂ͖x���ꑰ�A���h���ʂɂ͐^�c�ꑰ���A���C�u�ɂ͍�{�ꑰ���Z�݂����B��瓾�ӂƂ���ŕ�炵�Ă����炵������A�O�ɂ���A���\�����ɂȂ�������łȂ��A�����̗F�āA�ӔN�܂ŐS�L���ȓ��X�𑗂ꂽ�悤���B�@ |
|
|
��(10) �V�{�s���̂��̌�
�����đO���Z�Ƃ����V�{�s���͂ǂ��Ȃ������B�V������������g���ē�m�ۂ̖h�q�Ɍ����ƂȂ������̂́A���Ɖ]���Ă����邾���ɔ������甗���Ă͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ������B���R�̒���˔j���āA�͓��̌��ɏZ�ޒm�F�̑�ɐ���ł��邤���ɒe�����������ė��ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����B �̎�E���q�d���̕��ɕ߂����A�����ɉg���ꂽ�̂��܌����{�ł���B�����m������쒷��� �u������ċɌY�ɏ��������v�ƉƍN�ɍĎO������B�������A�ƍN�͒f�ċ������A���Q���{�Ɏ旧�Ă���E���v�ɓn���ė×{�������B ������������ɁA�s���́A���{�旧�Ẳ��������ނ��A���s�k��̗��ōȂƋ��ɌÓc���q�̕����Ă����B�����m������B�l�g�O���̑��ǒ������A�V�{�\�Y�ȗ��̌����̖��Ƃ��₦��̂�ɂ��B��k������ɓ쒩�̌�ǐe����i���ĕ��킵���V�{�s��̌����������ƘV�E�����������s���̗{�q�ɂƐؖ]���Ă����B�s���́A���̑u�₩�Ȑl�������ď������A���ɐl�g�̓��̗��ł̂ǂ��Ȑ��U���I���邱�ƂɂȂ�͍̂K�^�Ɖ]����B�@ |
|
|
��(11) ��ˉƒ����̂��̌�
����Ɋ֓��Ɉڂ�����ˉƒ����̏͂ǂ����Ɖ]���A����܂���Ƃ̏t���}���Ă����悤���B�Ƃ͉]���A���w����̍]�ˏ�͑呛���B�����듿�씪���R�����喼�̌��Ă���O�ŎO�����̑�s�����������̂ł���B �V�������Ŋ낤�����𗎂��������ƍN�͎�����u��ɓ������B��v�ەF���q�傪 �u���͓|��Ȃ������v�ƕK���Ɋ撣��ƁA��������@���� �u���̋���ҁI�����|�ꂽ�̂͗]�����̖ڂŌ��ċ���킢�v�Ǝ�������Ɖ]���B ���ǁA�O�͈ȗ��̒��Q���{����������s��͗̒n�v���̏�Ǖ������B�G�����������ɉ��R���̎撲�ׂɓ���A�e�q���S���Ɋ����ȉ��S���@�Ԃ̎��Ԃ𓊏��������B ����ƁA�V���y��吆��͐^��ɓ������̂Łu�����吆�v�A���䒉���́u�ǂ��������̉�y���v�Ɖ]����B�Ƃ�����Δn�炾���́A�⍲�̈�ˊo�O���u������v�Ǝ��B���Ēy�����A�G�����������̂Łu������Δn�v�ƕ]����Ėʖڂ��قǂ������B �o�O�͏헤�̑��ɉ���̂������ĎO��ܕS�B���j�E���G�͌ܕS�B���O�͏��@�Ԃ����ԓ���ƂȂ�A��ɂ͐�Z�S�Ώx�͏��ɗ��g����ƁA���Q���{�̒��ł��u���a�l�v�ƌĂ�鍂���E���ƂȂ�A���ŕ��������č]�˂̒���舕��ł��鎞���ƂȂ����B ��v�ەF���q��(��������)�̏����c�����w�O�͕���x�ɂ� �u�O�͕���̉Ɛb�Ƃ��āA���c��X�̐����킯����A�e���q�������������Ă��܂��A�Ƒ��͔���I�A�B�̊����������đς������Ă����B��Ƃ͍���V���l�ƂȂ��ē��{�S�y���x�z���Ă���̂ɁA����v�ۈꑰ�́A�{�Ƃ��L�b��ŖS������̂ɔ����ĉ��Ղ��ꂽ�̂��n�߂Ƃ��A�܂Ƃ��Ɉ����Ă��Ȃ��B���Q�̌ւ肾���͍����Ă��A�S�U���x�ł͂��̖̑ʂ�ۂ̂ɐ̒ʂ�̕n�R�邵�ŁA����c���������Đh�����Đ����ċ���A���ɂ͒Ǖ�����ď����𗬂���������ɉ쎀�����҂�����B���̓���Ƃŏo�����Ă���̂́A��Ƃ𗠐�����(�{�����M������)��A�v�Z�ɏڂ����������̏��ȓz�A�������痬��Ă��������q�҂���ł���B�v�ƕ��𗧂ĂĂ���B�������A����͕�����O�Ȕނ���A�����̔\�����K�v�Ƃ���āA�_���ɖ��邭�\�⒃���̂����Ȃ݂ɂ��[�����������̈�ˈꑰ�ɂ͈�z�����̎v���ł������悤���B�@ |
|
|
��(12) �ƍN�A�ƍٌR��������������
���đQ���h�]��B�����ƍN�́g�Ӌ���y�h���߂����A�Z���ɂ͈ꍑ���߂��đS���ɎU�݂���l�S�]�̏�̎�ׂ��𖽂����B �����ɂȂ�ƍ��߂̍ɑ��ƌ���ꂽ���S�̋��n�@�����ɋN���������֒��A���ƁA���ƁA���Ж@�x���ē��얋�{�̓ƍٌR�������������������B ���̑�j�́A���쎁��V���l�Ƃ��Ĉ�̉������e�����u�m�_�H���v�͖ܘ_�A����A���ƁA���Ђ��e�X���ɉ߂����s�����Ƃ�ʂ悤�A ���l�͗B�A�g�̒���m��@���̗t�́@�I���d���́@������̂��ȁB �Ɖr���Č��������߂�B ��������{�Ƃ��A�g�i�e�����đ���ς��h�̌��ʂ�A�������Ős�����Ă��ꂽ���l�h���������h�̔\�b���d�p���A�ꑰ���b�ł����Ă����{�g�D�𗐂��҂͗e�͂Ȃ���������B�܂��A���������̐����ʂ悤�A�O�㏫�R������I�ԂȂǁA�G���̓ƍق������ċ����Ȃ������B ���{�×��̓`���ł���u�V�c�͓V���ł���A���͂�q���Ō����č��E���ׂ����̂ɔv�Ƃ̐���ɂ�������߂��Ȃ����ݍ��B�������ʂ��Ȃ������g�����c�@�ɓ���č����ƂȂ�h��������ɐi�߁A�G���̖��E�a�q���㐅���V�c�̍@�ɓ��肳���铙�̐ꉡ�Ԃ�ŁA�V���Ɍ������ւ����B �G�g���������Ƃ��A�����܂œV�c�̐b�ł���֔��Ƃ��ēV���ו������������̂ɔ�ׁA�ƍN�͐M���ȏ�̔e���ƂȂ�A�V���{�̌��͉��Ɏ��߂��B�V�c�̌����Ɏc���ꂽ���̂͋͂��ɈʋL��^���鎖�݂̂������B�@ |
|
|
��(13) �ƍN�A����
���a��N(��Z��Z)�����A�L�b�����ŖS���Ĕ��N��ɁA�D���ȑ��ɏo���ƍN�͓������d���ꂽ��̓V�Ղ���������ܐH�߂��Ĕ��a�����B�₪�ĉăm�w�����N��̎l�����A�M��������A�G�g�������̎��\�܍܂ł��������ɐ������тĖv�����B �ƍN�̏d�a��m��������ł͑�����b�ɔC���A���セ�̕������Ɉڂ��ē��Ƒ匠���ƍ�����̂������Ă���B����̓u���[���̓V�C�␒�`�̓��q�b�ŁA�ɐ��̓V�Ƒ�_�ɑR���ē��Ɛ_�N�Ƌ����̂ł���B��������u�g�̒���m��v�����ȂƂ����ƍN�̌��s�s��v���r�����B ���{�̋����ɂ�ނȂ����������̂́A���˂��ˉƍN�̐����{���Ă�����z����c�́A���N�O���A�G�����㗌����ƋB�R����ԓx�� �u�ƍN�͈ꐶ�킢�̒��ʼn߂����ė��������ɓx�X�����ɔw���s�ׂ����������̂͒����⊶�Ɏv���B�R���G���A���͎����̏��Ƃ��Đ��ɏo���̂ł��邩��A�ƍN���L�b�Ƃɑ����悤�ȎE���͓�x�ƍs�킸�A���ɐm�����قǂ����A�Ȃɉ߂�����ƋC�t���Β����ɉ��߂�v�Ƌ����@���ꂽ���A�ɂ��������̔���������ꂽ�B ���̎j��������Ă��A�����̒��삪�ƍN�̔�{��A���Ƃ���������ēV���̑ו����v���Ƌ�S����Ă��������@������B���l�喼�E�Óc�D���̋����Ɏ����������ɂ͒���̉e���������A�����̉\�b�Ƃ��� �u�D���͕����A�������Ă��A�א쒉���Ƌ��ɓV�c��i���ĉb�R���ď邷��B�G���͐����O���𗦂��ĉƍN�A�G�������ݓ��B���x���N��̑�v��ł������v�Ɖ]���̂́A���X�R���S�ł��Ȃ����������m��Ȃ��B�@ |
|
| ��5 �s���ƌ����q �@ | |
|
��(1) �ƍN�̏\�j�̗���A�I�B�ɓ�����
�������Ό��͗��ꌳ�a�ܔN(��Z���)�A���˂Ė��{�����ɂ܂�Ă��������������������ɏC�������ƈ����������ĐM�B�ɒǂ�ꂽ�B���ɐ��Ƃ����w�̌��Ƃ��ĎO������������A�|�B�l�\�̑��Ƃ��ē]�����ꂽ�B �����ċI�B�ɂ͉ƍN�̏\�j�ŏ\���̗��邪�A�I�ɎO�\�����A�ɐ�����\�����A�v�\�ܖ��̌�O�Ɠ���Ƃ��ē�������B �I�B�͓�̍��Ɖ]���̂ŁA���Ɋ��ȘS�������ĂĈЌ����������B�����Ė��{�V�̂ł����a�\�Ð�Ƃ̗̊E�����߁A�̓��e�n�̗R�����鍋���ɒn�m�̐g����}���Ă�^���ĉƖ�̌ւ��F�߂Ă���B �����ċI�B�Ƃ̕t�ƘV�ɂ͓c�ӂ̈����A�V�{�̐���A�c�ۂ̋v�삪�Ɨ��喼�����ŔC�����ꂽ�B���ɒ��Q���{���^�͂Ƃ��Ē��C���A�����ɓ����ċ���A��ˑO�͒����̖{�{�̌�ڌ����n�m�ɑI�ꂽ�悤���B�@ |
|
|
��(2) ���T���Y�A��m�@�E�ɓ��傷
����ɂ��Ă����Ƃ�����̎j�����c���Ă��Ȃ����ƐF�X���ׂĂ��邤���ɕS�N�߂����ւ����۔N��(�ꎵ��܁`�ꎵ�O��)�ɋ������鎑�����������B�����Œ�����m�@�Ղ��߂��钃���n�}�ׂČ���Ǝ��̒ʂ�ł���(���\)�B �����ĕ\��Ƃ̒����ł��鏭���̎q�̏@�U�́A�c���̓�̕��������āA�ǍO�̉]�����悤�ɐ��U�m���������n�ɊÂ��B�u��H�@�U�v�ȂǂƉ\����Ȃ�����u�a�h�Î�v����蔲�������A���̎O�l�̎q�͕��ҏ��H�A�\�A���̎O��Ƃ������Ă���B �\��Ƃ͋I�B�ƒ����ƂȂ��Ă���B���̕t�ƘV�ł��鐅�쎁�̐V�{�O�ߏ�ɁA���̓����A���T���Y�Ɖ]���Ⴂ�������K���A�����Ȉ���G�p�ɒǂ��܂��������C�ɒ����C�s�ɐ��サ�Ă����̂��������B �ނ̕��͐��ܘY��Ə̂���˂̒����O�����钃�V��ŁA�T���Y�͂��̎��j�Ƃ��ċ��ێO�N(�ꎵ�ꔪ)�V�{�鉺�ɐ��ꂽ�B�c������g�̂�痂����q�\���D��Ă����̂ŁA�����������y���݂ɂ��Ă����B�����A�V��t�̔ԓ����߂Ă����V�؎��̉��ŏ\�܍��炨��ɏ��B��������A�s�����^�肵�Ȃ���A���ƉԂƔo��Ɍ����������炵���B �����ܔN(�ꎵ�l�Z)�A�T���Y����\��̏t�A��m���x����̐�����m�@�E���O�R�w�ɐV�{��K�ꂽ�̂� �u���̋@����ĂȂ邩�v�ƕK���ɓ����Q�肵���B �ꌩ���ď@�E�����̊�ʂ𗊕ꂵ���������炵�������������B�˂̏d���� �u���ɘA��A���Ē����̏C�Ƃɑō��܂���Ώ����͑��ƂȂ낤�v�Ɛ������Ă��̗����Ă��ꂽ�B �T���Y�͓V�ɂ�������ŁA�t�̔������ĐV�{�ƁA����ċ��̕\��Ɣ@�S�ď@�E�̖��Ƃ��ē���חサ���B�t�̉]���܂܂ɑ哿���̑嗴�a���̌��ɎQ�T���A�`���������_����Ƃ���T�̓����ɂ߂鎖�ɖv�������B�@ |
|
|
��(3) ���T���Y�A�u�Ǖ��s���v�̍�����
���ꐸ�シ�鎖�A�l�N�B�t�̔������Ęa�̎R�ɏ����ꂽ���A�@�E���� �u�����͖������Ȃ��ɔC���邪�A�w��x�̐S�\����Y���ȁv�Ɩ������A��Ӓ��ꐇ���������T�������A �u����S���ꓹ�Ȃ�v�Ƃ̌����J�����B ���������A����̒����ɍs���Č���ƁA���m�Ԃ̑嗴(*1)�̏��w���Ό��x�̎������̂����Ԃ��ɂȂ��Ă���B����������ނ̓\�b�ƕ\�ɒ����ė��h�ɒ�������ߏグ���B��������嗴�́u�Ǖ��s���v�̍��� �u���������R�̂܂�̐S������ʂ��Ƃ��������̋Ɉӂ��v�Ƌ������B �� (*1) �嗴�@��B�]�˒����̗ՍϏ@�̑m�B�哿���O�S�l�\�ꐢ�B���s���B�@���恁A�����͖����B�ɂ������A�ʗщ@�ɓ얾����n��B����4�N(1751)��A58�ˁB�@ |
|
|
��(4) �s���A�u�@��v�̖���^������
�₪�Ċ�����N(�ꎵ�l��)�A��m�@�E�͔ނɗ��x�����̍��{�Ƃ���u�^�̑�q�v��`�����āu�@��v�̖���^���A�剺���̍���Ƃ����B����\�N���炸�ł������͈̂ٗ�̎��������B �s���@��A���ɎO�\��̒j����ŁA��������l�X�������Ă��̗��R��q�˂�ƁA�@�E�� �u�I�E�@��͂ȁA�V�{��Ŗ���s���̖����莵�N���葱���ċ������̂ɁA���̂悤�Ɍ����ڂɂ͖���������V��ł����邪�ȁA��U�����ɓ���܂��Ƃ܂�Ől���ς��A�w�Q�����Ղ����ǂ�s���x�̍��̒ʂ�A�����̋Ɉӂ�g�ɂ�������l���ł�����v�Ə^�����B ��{�����������ꂽ�s���́A�ЂƂ܂��V�{�ɋA�����B�˂̏d���ɂ������b���A����͍]�˓@�Ɉڂ��ēa�l�Ɏd����T�A�u�]�ː�Ɓv��n���������Ɗ肢�ł�ƁA�]�˂��߂������B�@ |
|
|
��(5) �s���A��ƈ�q���`�́g���~�`�h��`�������
�܂���]�˂̒|�{���ł͒|�c�o�_�́w������{���b���x����]���ƂȂ��Ă����B����Ƃ̒����ɋ����\�����s���͂�����y���މɂ��Ȃ��A�]�˂ɐ�m���x�̘̒��̐��_���g�߂鎖�ɐ�O���A����ɂ��̖���m���n�߂��B �܂������̎t����}�ւ��͂����̂ōQ�����㗌�������A��������a�����ȏ�ɁA�q�̏@�����c���ł��鎖���Ă����@�E�� �u���ۂЂƂ܂��s���ɁA��ƈ�q���`�́g���~�`�h��`�����A��������@���ɑf������X�������肢�������v�Ɖ]���v�������ʎt�̌��t�ɋ��������B �ĎO���ނ������A�Ȃ�t�̈˗��Ɉꉞ�A�`�����A���ɉ�����\��ƈ��̐l�X��K�˂Ă��̌������ł߂Ă����B���̂������x�͍]�˂����N�E�������A�d�Ԃ̕������B ���ڂ����傾���ɒ����ɋA�鎖�ɂ������A���ʂ̒�����Â��Ă��ꂽ�@�E�͐S�����߂����Ȃ̏I���� ���H���Ɂ@���ċA���@���l�B �̋���͂Ȃނ��Ƃ��A�����čs���s���̌�p�ɁA���߂₩�ȑ���������ł��āA�ʂ��ɂ��Ɖ]���B�@ |
|
|
��(6) �s���A���͓I�Ȋ�����W�J����
��͂Œm�炳�ꂽ�ܑ�E�������v�����̂͂��̏H�ł���B�Z��ˎ�ɂ͒��������A���A�s���͐V�ˎ�Ɏd���Ȃ�������͓I�Ȋ�����W�J�����B�����S�����ւ����ΏB����ǂ��z���A�L�͂Ȑl�X��剺�ɉ����Ă������B �L���Ȑ̔�l���E�e�E�q����A�ނ̐l�����Đ���ɂ������肢�����ƍ����� �u�����ɂ͐l�Ԃ̍��ʂȂ��v�ƐM����s���͊��ŋ��߂ɉ������B���̎�����ꎞ�͍]�˒Ǖ��𖽂�����Ɖ]���ڂɈ����Ȃ���A�������Ђ�܂��A���x�̂߂��������l�����̔��W�ɓw�߂Ă���B�@ |
|
|
��(7) �s���ƑO1
���N(�ꎵ�܈�)�ɓ���ƁA�Q�Ό�ւŐV�{�ɋA���Ă��������́A�s���̊���Ԃ���� �u�����ɋA��������v�Ɩ������B���ƘV���A �u�s���͂��͂ⓖ�Ƃ̈ꒃ���O�Ɏ~�܂炸�A�V���̕s���@��ł���A�]�ː�Ƃ̑��������ɂނ������v�Ɠ�����ƎႭ���C�ŃJ�b�ƂȂ��������� �u�Ɛb�̕��ۂŗ]�̖�������ꍇ�͎�ɂ��Ă������A��v�ƌ��������B��ނȂ������`�������A�s���͋���� �u�����q�ƒn���ɂ͏��Ă܂��ʂȁv�Ɖ��悭�A�������������B �s�����]�˂𗧂����͈̂��̉p���E�g�@���������������N�̉ĂŁA�����̗����L���J���� �� ����Ɍw�ŁA��N�̌����A�v���Ԃ�Ɍ̉��V�{���߂��������A�r���ŌF�̒_�����߂�ׂɉ�蓹���ĉʖ��z(*1)�ɍ������������B�R�H�͗��l�̎p���Ȃ����܂ɖ؏���l���ʂ������̏����Œ��������͉_�������ꍞ�߂Ă���B ����b�����ߊ��ʒ��̋��낵�����ŁA���߂��Ȃ��Ă������������߁A��ڐ������ʗL�l�ɁA�R�ē��̗��l�Ƒ吺�ŌĂь��������ɎR�H��o��B����ȎR���ɂ������Q����A�ڕ@�ɔނ̂ŁA������ɑł������Ȃ����� �����[���A�����̊O�Ɂ@�J�������ȁB �Ɖr���B ����s����Ղ邪�@���u�R�Ȃ܂��v�ƌĂԓ�ڗ]��̑�g�����˂��˂Ɗ�Ԃ����ɂ����߂��ċ��� �u����ȓz�Ɏ����ꂽ��ǂ��Ȃ鎖���v �Ɣw������ ���������A����̖���@�R�Ȃ܂��B �Ɖr���A�}�����悤�ɓo��B �b���A�Q���R�̔����ɏo��������t���ޏ����Ȃ��B�����̔�势�����ɂ��������₦������ �u�q�˂�Ƃ͂܂����v�ƕ����� �u����������������v�Ɖ]�������� �u�����v�Ǝv���Ȃ�����������A�R�Ƃɂ��Ă͗R������C�Ȍ���������̑傫�ȉƂ����� �u����ȏ��Ɂv�Ƌ���������ƁA����ɖ������̐��召�̌F�̖є炪������A���X�����C�����Y���Ă���B �ē�����ƁA������̂͑����ʂ̖����镐�m�̎q���ƕ����l�i�ڂ�����ʐl�����o�ė��Ĉ��A�����킷�B��������X����ˌ����璼���̌�ڌ����n�m�炵����ʂ̎���� �u���͂Ƃ����ꐅ����t���]�v�Ɨ��ނƍ������������o���Č��ꂽ�B �V�̊ØI�ƐS���đՂ�������q�ז�����ĖႢ�����Ɗ肤�� �u�O�ɓۂ܂ꂽ���͂����邩�v�Ɖ]���B �u����n�߂ĂŁv�Ɠ������ �u�R��v�Ɖ��̒\�y����ق�̏���������ł��ꂽ�B �u���ɋ��k�Ȃ�ǁA�����Ƒ�R�킯�ĖႢ�����B�l�͂����ɍ����Ƃ����\�ł�����v�Ɖ]���Ă� �u����F�̒_�Ɖ]�����̂͋͂��ł����ڂ̂�����́A����Ƃĕa�ɂ���Ă͑��ʂɗp���Ă������ʎ�������B�܂����ꂾ���ۂ܂��ė����悤�Ȃ�A����͂�����ł��������v�����v�Ɠ����A���x����ł� �u���ꂪ��Ƃ̝|�ł�����v�Ƃ���ȏ�͔����Č��ꂸ�A �u�䖼�ʂɋL���āA����̏؋��ƒv���v�Ɖ]������A��ނȂ�����͂Ɩ₦�A�ق�̋͂��ł���B �l�������[�R�œ�l�����̎��������@�O�Ȓl�𐁂������Ă����ċ���҂����Ȃ��̂ɂƈ�i�Ƃ��̐S�̉��䂩�������������B ���̖�́A�傩��A�\�c�������x�̈��q�E�R��@��ƒm�F�ŁA�g��˒��q�h�̉��Ȃǂ���������A�u�ƂĂ����l�Ƃ͎v���ʐS�n�v�Ői�߂���܂܂ɎR�Ɨ����Ŏ������݁A�閾���߂��܂ŋ����������B �� �Ƃ���A���̎傪���ڈ�ˑO�������炵���B(�ȉ��A�O�ƕ\�L) �� (*1) �F��Ó����ӘH�@ |
|
|
��(8) �s���ƑO2
�����A�ʂ�ɍۂ��āA�s���͎�� ���_���Ɂ@������ʌ��́@�S���ȁB �̋���āA���c��ɂ��݂A�Ăт�������͐�M�ň�H�V�{�쌴�Ɍ����c�c�B �Ɨ����L�͏����I�݂ɓ����̐�����`���A���Ȃ����O�Ɍ���悤�Ȑ��X�̖�����c����ċ���A������ ���̋��́@�t��̂́@�[���B �Ō���ł���B �s���́A�������Ȃ�������Ɍ������A�l�ɂ͊���ŁA����͂Ȃ�ӂ���\��Ȃ������B�[��̍ޖ؏��̖���K�˂����Ȃǂ́A�X�̎�ォ��d����T���ɗ����l�v�ƊԈ���A�I���҂����ꂽ���A�ʂɓ{��������A�C�߂đ҂��Ă����Ɖ]���b��������B �s�����J�c�Ƃ���g�]�ː�Ɓh�͑����i�Ɨ������ɂ߂����A���O�N(�ꎵ�O)�A�t�̏@�E�v��́A�c���q���E�@������藧�ĂāA���̐����ɋC��z�����B �₪�Ĕ�`�g���~�`�h��ނɓ`�����ĕ\��Ƃ̓���Ƃ��ĕA�����͂����܂ł��̖剺�̒��b�Ƃ��Ďt�̈ӎv�𗠐�Ȃ������B �s���Ə@���̊W�́A�����ƍN�ƏG���̏ꍇ�Ǝ��Ă���B�������A���̑ԓx�͌����ŁA���ɂ��ނ��ʔ������t�툤���c���āA�����̌��Ђ������������Ȃ��B ���a�l�N(�ꎵ�Z��)�ɂ͕S��̒������Â��A���x�̕���������āA���Ɂg�S����̐[���h���M���Ƃ���̒��̐��_�������Ă���B �J�c�E���x�́g�́h�Ɓg��h�̊m���ɁA�s���s���̐��_���������āA�����������Ȃ������B���̒��l�����̔��W�ɐg��������̂́A���ɂ��̐��s���ł���B �s���́A�ӔN�A�_�c���_�̈�p�Ɂg�@�؈��h������ �u���萅�̒��ɏZ��ł������m��ʘ@�̐S�������@��l�̕s���S����B�����Ė������x�ސS���������̍��ł���Ɓg���x�h�ƍ����ꂽ�J�c�̐M���Ɠ������̂��v�Ɩ�������߂Ă���B ���̕s���@�Ⴉ��A�O�͏��Ζʂł���Ȃ���u�_���ɂ�����ʌ��̐S�̎���v�Ǝ^�����Ă��邱�Ƃ��A����ׂ��p�Ƃ��Ċo���Ă��������B �v���ɁA�O�́A�u�����Ɛ����v�̉ƌP���X�т��Ȃ�����u䑂��Ȃ�Ɛ����v����v�Ɠw�߂Ă������c�̐���������S�ł͑傫�Ȍւ�Ɗ����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�@ |
|
|
��(9) ��܂������q / ���܂�
���āA�O�́A�������A�F��e�n�̎�l�̒��ɂ��F�������悤�����A�m�Ȃ̈�l�Ɠ`������u��܂������q�v�̋`���̐��U�ɏA���ďq�ׂ悤�B ���R�g�@�́g���ۂ̎��h�̑S�����̍��A�F�쑊�ꑺ�֎R�ɒɉ��Ȉ�l�̋��m���Z��ł����B �������q����܂���@�G���ق�����B�O�x�Ɉ�x�́@�ǂ킸�Ȃ�܂��B �ƌ㐢�܂ʼni���̂�ꂽ�w�Y���x���߁x�̎�l���ł���B �ނ̕��́A���m�w�ŕ���̖��u���{��̕��v�v�Ǝ]����ꂽ������^�c�ꑰ(�叕�Ƃ��]��)�������܂��Ă��̒n�ɗ����ė����㑺�����d�v�Ɖ]����B���̑c��́A��k�������̖����N�Ԃɖ���m��ꂽ�㑺�p���q��d���Ȃ�E��������A�Â����炱�̒n�̋��m�������悤���B ����O�N(��Z����)�O���A�����͖v���A���T��(*1)�ɑ����Ă��邩��A���w�ł͎�҂������낤�B���R�Y�ɒ�Z������[���߂Ƌ��ɐ���E�Ԑg�ł������B �����q�����ꂽ�̂͌��\���N(��Z��Z)�Ɖ]���Ă��邩��A�����͔ނ̑c�������m��Ȃ��B������ɂ��敃�c��X���E�̉ƕ��������ɈႢ�Ȃ��B ���̌������������炾�낤�B�����q�́A��N���畐�|�ɏG�ŁA���ɓS�C�̖���Œm��ꂽ�B���d���ɂ͂����ς�������炸�A���S�C�����ɎR����킯����ĉ҂��ł�������A���l�̊Ԃɂ��̂悤�Ȗ��w�����ꂽ�̂��낤�B��Ԃ̉̎��� �������̏��R�́A�����̖؉A�Ɂ@�\�����c���@�o�ė��Ď菵���@�����Ύ̂ĂĂ��A�s�����Ȃ�܂��B �̋傩��@���ď����ɂ��Ă��炵���B �� (*1) �O�d���k���K�S�I�k���C�R��փm�R�@ |
|
|
��(10) ��܂������q / �����q�̑��
���N�̏H�ɁA���R�[�̊��J�œ������Ă��܂��A�����q�͑���̍����Ŗ�h�������A�锼�ɂȂ�Ɨ��͗l�ƂȂ��ė����B �u����͂��������Ɋ⌊�ł��Ȃ��낤���v�ƒT�������ɁA��w�̗Ƌ��ɁA�����l�̗l�Ȃ��̂����ŗ��Č����q�̐g�̂Ɋ��������B �������̌����q������ɂ͋��������A�s�v�c�Ȏ��ɐ��������ԉJ�����Ղ��Ă���A�������G�ꂸ�A�����Č���Ə_�炩�Ȗт̂悤�Ȋ��G������B �u���Ă͗d�����������A���̐��̂����͂���܂ł͉I舂ɓ����ʂ��v�Ƒ������炵�Ă��邤���ɑQ�������ƂȂ����B �悭����A�N�v���������Ă����ۂ����ɂ͂���Ĕނɂ܂��������̂������B���A�ň�Ӓ��A�z�c����Ɍ����q�������ł��ꂽ�����������B��ނ͑ۂ����̑��ɖ߂��ĎR�������ƁA���̘b�l�Ɍ�����B��������l�X�͔ނ̊̂̑����ɋ����āg�����q�̑�䭁h�ƌ��p���ł���B�@ |
|
|
��(11) ��܂������q / �S�C�̖��l�|
�܂��փm�R�̋߂��ɔn�z�R�Ƃ�����R������B�����ɂ͓����A���{�O�d�ςƏ̂��ꂽ�u�ɐ��̎ĘZ�v�u��a�̌���Y�v�ƕ��ԁu�F��̎O���Y�ρv���l�X��Y�܂��Ă����B�������A�������̌Ìς������q�Ɏ�ɂ��ڂɂ����Ă��牽�����֓����Ă��܂����B ��l�X�́A���X�Ɍ����q�̍��E�ƓS�C�̖��l�|���]���͂₵���B�܂���̓������ɗ���ꂽ�I�B�������̘b����� �u����Ƃ�������������v�Ƃ������ɂȂ����B �����Ō����q���ނ�ŏo������ƎR�̒��ォ��M��]���藎���A�܂�Œ��̑���悤�ɐ��������œ]�����ė���̂��O��_�����������A�e�͎����������ɓ��������ƌ����A�e���͈�J�������Ȃ������B�����ňꓯ�����Đ���܂��A�a�l���傢�ɖ�������A�ߕ��ȖJ�܋����������B �������猠���q�̖����͈�i�ƍ��܂�A���R�Y�ɏZ�ށA���m�w�őc���̐�F��������[���߂̈ꑰ���j���ɂ���ė��đ�ƂȂ����B��[���߂̈ꑰ���A���̖��l�|���]����ƁA�����q�̓j�����Ƃ��� �u�����b���Ⴊ�́A��̓͋�e�������̂�B����Ŗ�l���A���m�w�̕����������낤�v�ƍ��������B���̓x���̗ǂ��ɋ���������A�ނ����l�̎q�����ɋ��̗�������x�ɉ������Ɖ]����B ���m�w�̔s���A�ނ�̓���ɑ��鉅���@���ɐ[�����������@������B�@ |
|
|
��(12) ��܂������q / �I�B��炩��̒���
���l�����́A�����ɂȂ�ƁA���˂Č����q������܂��Ă��A��D���ł낭�Ɏ����������A�I�ɂ͋����␝�̉a�ƂȂ��Ă��܂��̂����āA �u�����q�̎�܂���J�������A��͂܂��Ă�����₹���A����G�̉a�ƂȂ�v�Ə��A�g��܂��a�h�Ƃ��A�ނ���ɑ�Ɏ����Ă���Y���x������g�Y���x���a�h�Ƌw�����Ă����̂����ɂ��Ȃ��Ȃ����B ���ꏈ���A���⎭�̊Q�Ɏ���Ă����e�n�������������ė��݂ɗ���l�X�����X�ɂ��̖��l�Ԃ���]����̂����āA�䑺�̌ւ�Ɛi��ōk��̎�`���⊠���ɋ��͂��Ă����悤�ɂȂ����B����ŁA�փm�R����̔ނ̉��~���ӂ̓c���͖L���Ȏ��n�������炵�A�Ȏq���ǂ��ɂ��т�H�ׂ鎖���o�����B ���̍����I�m�������������������ۂ̖��A�����q�̉��~�ɖm�{�㊯���珢�o�����������B �u�����Ȃ��v�ƎQ�サ���� �u�I�B��炩��̒����ŁA���˂Ĕn�z�R����̓V�q�R�̊⌊�ɉi�N���݂��āA�l�X�ɔ�Q�������炷�H��̑�ւ߂��A�����q�ɑގ�������Ƃ̂����t���������v�Ɖ]���B ���̑�ւ́A���˂Ĕ��h�̓S�C���ł���팠���q��Ɖ]���˂����Ă̓S�C�̖��肪�����ē����ׂ��_���������B�팠���q��́A�O�x���S�C��ł����������A�����ւ��֑̂͒e�ۂ��͂˕Ԃ��Ăǂ����Ă��|�������o���Ȃ������B �����Đ��Ɍ����q���I�ꂽ���̂ŁA��������ނ� �u�g�ɗ]����h�ł�����B�K���ގ��d���v�Ɩĉ�ƂɋA�����B�@ |
|
|
��(13) ��܂������q / ��֑ގ��ɏo��
���̖�A�Ȏq�ꑰ���W�߂������q�͉����ɂȂ��������ʎ��� �u�킵���i�N�̊ԁA����ƂƂ��A������͎�Ŗ��𗎂����ɂȂ낤�Ɗo������Ă������A���x�v�炸����a�l����̊i�ʂ̖��őގ����鎖�ɂȂ����B���̑�ւ߂́A�킵���x�X�o�������������邪�A���S�N���O����V�q�R�ɐ��ޑ喂�������ɁA�����́A�킵������邩���m��ʁB���A�����đ��ł͎��Ȃ�B�h�Ⴆ��o��ŗ����������肶��A��������͕ʂ�̉��ƂȂ����m���B���悭�������Ă���v�Ɖ]���A�p�ӂ��������u�ŌX����ƒ��j�A���j�Ǝނ����ĉ�����B �₪�Ăق됌���@���ŁA�ߍ����h�̑D�拤���̂��n�߂��g�Y���x���߁h���̂��A�y���C�ɐ����炸�̈����߂������B �����ė��������A�����q�́A���˂ĕ������ۂ� �u���̐ɂ킵�̈�O���h���Ēu���B�Ⴕ���̎��ɂ͈�S�ɔO��������B�K���쌱�����낤�v�ƈ⌾���Č��ꂽ�g�Y���x���h�ƁA��寂̔��p���č�����O�p�`�́g�������Ăъ�͂����鎭�J�h�������ɁA��Ƃ��o���B ���Ɍ������N(�ꎵ�O�Z)�̉ĂŁA�E��Ɉ��p�̓������Z�p�`�Ōo���荞�Z��̑�S�C�A���ɂ͐�c�`���̖����������݁A�ӋC�����փm�R����n�z�R���߂����������q�̎p�́A�o�w�̕������Ȃ���̗E�p�������낤�B �w�F��N��L�x�ɂ��A���̔N�̉Ă͑�J�������A�V�{�쌴���ł͏o���̓x�ɉƂ����ڂ��\�O����呛�����J��Ԃ��Ă���B����Ȓ��Ō����q�́A��ւ̒ʂ��H�ɂ���n�z��̋���̊�A�������Ƃ��āA������f�Ȃ��ҕ����Ă����炵���B �R�����X�D�@���Ȃ��A��ւ̑��A�̈�ł���V�q�R�Ɉڂ��āA�����ԁA��̓J�𐁂��������B�@ |
|
|
��(14) ��܂������q / ��ւ�ގ�����
�����Đ��ɁA���̖��Ǝv������ւ��U���o����Ă���ė����B����͔������̗[�鎞�ŁA�S���Ŋϐ�����F��O���A�l�ӂɖڂ����点�Ă��������q�̑O�ɁA���������ȑ�ւ��p���������B �D���̎��Ǝv���A���邷��Ɣ����ė�����ւ́A�̌҂ɏe�g���x���č\���Ă��錠���q�������A�{��ɔR���A�^�ԂȐ��M�߂����A�������J���Ă܂��ɔ�т����낤�Ƃ����B ���̏u�ԁA �u�_�_�[���v�Əe�����������A�ƌ����A�e�͌����Ɍ����ɖ����y���B�}���̒Ɏ�ɋꂵ�ޏ����A�葁�����̒e�U���������q�́A�������߂����đ����ē܂Ŏˍ��B����ŁA�������̑�ւ����ւǂ�f���Ȃ��瓦���������B ��ւ́A���h�ɒʂ���J��̔ȂŁA���ɑ��₦���B����Ől�X�͌�ɂ������g�ւ̉��h�ƌĂ�ł���B �Ƃ��낪�����q���ŋC�ɂ��Ă��đ���ŋC�������A�܂���e�����ċ킯�������l�̌˔ɏ悹���āA�Q����Ƃɉ^�ꂽ�B�@ |
|
|
��(15) ��܂������q / �����q�A����
�����q�͂₪�Đ��C�ɕԂ������A�ܑ͎̂��オ��A�g�������Ȃ�Ȃ��B�a���ɕ��������A�����m��������̗F�A�k�R���̎ˏꕺ�q���S�z���Č����ɂ��������B�ނ̑c��͎ˏ�e���Ə̂��A���K���ɏo�v����������(*1)�ƌĂԑ���b������E�m�̎q�������Ɍ����q���傢�Ɋ�� �u�킵�͍��x�̑�֑ގ�������Ɏ���~�߂���肶�Ⴉ��A�S�����Ă���x�ƓS�C�ɗp�͂Ȃ����A�Ⴕ�^�s���Đ�������悤�Ȃ�M�a�Ɉ�i�Ɍ����悤�B�v�ƍň��̋��e��ނɗ^�����̂́A���������C�Ȍ����q���Ȃ̎����̐s�����̂�\�����Ă̎����낤�B �����q��֑ގ��̘b�͒����ɔˌ��̎��ɂ��B���A����ȉ��܂��������ꂽ�B�������A��ւ̉���ɐ���ꂽ���A�����q�́A���̔N�̏\��\�Z�����ɂ��̐�������A��̈�p�Ɂu�@���c���v�Ƃ��đ���ꂽ�B ��\�ꐢ�I���߂������A���{�ɂ���ȑ�ւ��������Ƃ͐M�����Ȃ����A�w�F��N��L�x�̒��ɂ́A�x�X���̑��݂��L����Ă���B���h�A�ւ̉��ɂ� �u��ւ̍��̑����͈ꐶ���������������v�Ɠ`�����Ă���B ���ɓ�S�ɏZ��ł������̑\�c�����A�Ⴂ���A�R���ŏo���킵����ւ̋��傳�� �u���ۂ͎l�l�M���̓���肾�����낤���A���ɂ͓��P���炢�ɂ������������v�Ɖ]���b�����̎��ŕ������ꂽ���́A�����M���ċ^��Ȃ��B �����q���A���{���Ƃ����g�Y���x���h�́A�������A���T���Ɏc����Ă���B �w�Y���x���߁x�́A �����̈Â��̂ɔ�����������B �̒��H�Y�̖��w�ƁA����ˉƘV�E����� ���I�m���́@������̐���Ɂ@�����������́@�D�ʎR�c�c �̉S�Ƌ��ɁA��]�ˈ�~����S���ÁX�Y�X�ʼn̂������ꂽ���ł���B ���B�́A��܂������q���F��̍��Y�̈�l�Ƃ��č����]���A���̎j�Օۑ������̐���ɋ����i�������B �� (*1) �����������B�g��n���ɓ`���`���̉��فE�d���@ �@ |
|
| ���퍑����ƉƖ� | |
|
�`���̖���A�q�����́u�e�Ɓv�Ɩ����ېV�ł̒��j�m���́u���Î��v�Ƃ������ł���Ƃ̍����̂ЂƂƂ��āA�u�Ɩ�v������܂��B���Ƃ̉Ɩ�́u�ۂɏ\���v�ł��B�������A���̉Ɩ�ɂ͊ۂ��Ȃ��āA�B�́u�\���v�������̂ł��B
�\���ƌ����A�L���X�g��(���V���A��)���v���o���ЂƂ����邩�Ƃ������܂����A�L���X�g���̏\���˂́A�I���W�i���ł͂Ȃ��A���z�_�~�g�����̑��z�̃V���{���A�}���^�N���X(�\��)���������̂Ȃ̂ł��B �����āA�}���^�N���X�̃V���{����p����i���́A�L���X�g�����番�h�����l�X�g���E�X�h���Ƃ����Ă��܂����A����͋t�ł��B ���[�}�R�_�Ƃ��ă~�g���_(���e����ł̓~�g���X�_)���M����Ă����̂ɁA392�N���_�����̈�h�ł��锽���[�}�鍑�̃��V���A��(�M���V����ŃL���X�g��)���A�ˑR���[�}�鍑�̍����ƂȂ�A���̃��[�}�鍑�́A395�N�����ɕ���̂ł��B428�N�����[�}�鍑�ɂ����āA�l�X�g���E�X�h�́A�L���X�g(���V���A)�̐_����F�߂Ȃ��u�l�ԃL���X�g�v�̏@�_��W�J����̂ł��B����ɑ��āA�����[�}�鍑���e�Ŏx�z���鍑�ی��Տ��l�́A�L���X�g��_�i�����āA�L���X�g���z���̖��ڂňً����ւ̐N����i�Ƃ��āA�ً����x�z���v�悵�Ă����̂ł��B431�N�G�t�F�\�X�̌��J�c�ŁA�l�ԃL���X�g���咣����l�X�g���E�X�h�ْ͈[�ƌ��ߕt�����A435�N�����[�}�鍑����Ǖ������̂ł��B���̒Ǖ����ꂽ�l�X�g���E�X�h�L���X�g���k�B�́A�����[�}�鍑�ƑΗ�������T�T�����y���V���鍑(293�N�`642�N)�Ɏ������̂ł��B�����āA�l�X�g���E�X�h�L���X�g���k�́A�y���V�����Տ��l�Ƌ��ɁA�V���N���[�h�𓌐i���A�k�(�_�k�����̊������łȂ��A�R�n�����̑��땔���x�z�B���땔�͌����̌��B423�N�`534�N)�̓s���z�ɓn������̂ł��B���̂���A�k鰂ł́A����������ɂȂ�A�����͒e������Ă����̂ł��B ���̓����[�}�鍑�̋��c�ɔj�傳�ꂽ�L���X�g���l�X�g���E�X�h�Ƃ́A���z�_(�~�g���_)����c�����肵�����̂ł��B���z�𐒔q����i���́A���X�͑��z�_�~�g�����̋��`����荞�@���g�D�ŁA�����嗤�ł̕z������������ƁA�����������瑾�z���J��@���Ƃ������ƂŁA�i����(���z)�̋�(�s)�̏@���ƌ���ꂽ�킯�ł��B �R�n�����x�z�̖k鰁��@����(���{�ł́A�R�n�����x�z�̔��ォ��ޗǎ���)�ł́A���D�������߂�y���V�����Տ��l�����Ƃ̋��_�Ƃ��Ď�����������̂ł����A����́A�y���V�������l�X�g���E�X�h����i�����Ƃ����킯�ł��B(603�N�n���ƌ�����A�I�u���u��̍L�����v�͌i�����ł��B)�Ñ�ł́A�ً����Ƃ̏�����́A�_���Ȑ_�̉�(���E����E�끁�_���h��ꏊ)�ł����Ȃ��Ă����̂ł��B�����āA�~�g���_�͌R�_�����ł͂Ȃ��A�I���G���g�łً͈����Ƃ̏�����������u�_��_�v�ł��������̂ł��B �ł͉��́A�`���̖���A�e�ƂƓ��Î��̉Ɩ䂪�A�i���̃}���^�N���X�Ȃ̂ł��傤���B ���{�̉Ɩ�́A�\�Z���I���ΓˑR�ɐ퍑����̕���������R�c�́A����̐�`���̂悤�ɘI�o�x���グ��悤�ɁA�X�ɉ�������m�F�ł���悤�ɁA�R�c���Ƃ̓������Ȍ��ȃf�U�C���}�[�N�Ƃ��A���̌R�������̃V���{���}�[�N���{���������Ɍ����̂ł��B �Ɩ䂪���m�̍��펞�ɓG�������m�F����}�[�N�Ƃ��ĕK�v�Ȃ��̂ł���̂Ȃ�A���̏\�O���I�̌�������ŁA�����ƐԊ��ł͂Ȃ��A�Ɩ䂪�o�ꂵ�Ȃ������̂ł��傤���B ���q���㖖���A�����ɂ����̘_���s�܂ŁA�����o���̕��m�c�ɕ��Ȃ��S�ϖk�𐭌��́A���O�������̂ł��B(���́A�S�ϖk�������x�z���銙�q�̓s�őT�@���ی삳��Ă��邱�Ƃ�m���Ă����̂ŁA�T�@�m�����R�̎g�҂Ƃ��āA�k�𐭌��Ɍ��Ղ����߂Ă����̂ł��B�������x�ł��B�������A�k�𐭌��́A���R�̎��̑T�@�m�̖��g���x�Ƃ��S�E���Ă��܂��̂ł��B����ɑ��āA���R�́A���{��1274�N��1281�N�ɓ�x���P����̂ł����A���R�D�͓�x�Ƃ��\���J�ɂ���ł��Ă��܂��̂ł��B���R�̗��P�́A��j�D�̉ו��̒���������_������������ꂽ���߁A���{������{�C�ōl���Ă����悤�ł��B����́A���R�́A���{�ŋ��E�₪�����Y�o����邱�Ƃ�m���Ă�������ł��B���̏�A�}���R�|�[���ɂ�艩���̍��u�W�p���O�v�ƏЉ��邱�Ƃɂ��A���[���b�p�����̓��A�W�A�A���n����������������̂ł��B) �����ɁA����V�c(1288�N�`1339�N)���A���ʌ�A�@������߂�̂ł��B�����āA���S�ω����̖k�����q��������s��ǂ��Ă����������̈Ö�ɂ��V�c�e�����s���A�����āA�k�����ɂ��R���̕ƒn�ɒǂ��Ă��������ꑰ�̓퐳���A���������A�V�c�`��Ȃǂ̕S�ϖk�𐭌��ɕs�������n�������̕��͋��͂ɂ��A1333�N�k�����q���{��|���̂ł��B �ł́A���q�k�𐭌��ɔ�����|��������V�c�Ƃ́A�ǂ̂悤�ȏo���̓V�c�Ȃ̂ł��傤���B�n�}�ł́A��F���V�c�̑��c�q�Ƃ������Ƃł����A�u���v�̓V�c�����C�ɂȂ�܂��B �u���v�ƌ����A�������S������̕�������ɁA���������̐������^���ɕ{�ɍ��J���������S���̊�b��z�������V�c(885�N�`930�N)���݈ʂ��Ă��܂����B���͉F���V�c�ŁA��͓���b���������̖��A�������q�ƂȂ��Ă��܂����A�^�╄������܂��B����́A�u���v�̕����ł��B �u���v�Ƃ́A�������i�y����i�K�Ő����镨���ł���A��(�ɂイ)����(�炭)�����h�E��(���傤��)���n�h�E��(���キ��)�����́A�ܖ�(����)�̂��Ƃ������̂ł��B���́u���v�́A�n���������Ă��Ȃ��������{�ɔn��Õ����猻���l���I�ȍ~�A�I���G���g����n�������R�n�V�q�����ɂ��A���{�Ɏ������܂ꂽ���̂ł��B�܂�A�`�[�Y(���)�́A�R�n�V�q�����̂��y���ł���킯�ł��B�������A���(�`�[�Y)�́A�h�䉤���A�V����������ł���ƁA���i�Ƃ��Ă͑��݂��Ȃ��Ȃ�A�R�n�V�q�����̖���ł͂Ȃ��S�ω����E���������̕�������ł́A�u��햡�v�Ƃ��āA�u�ō��̔����v�̈Ӗ��̌��t�Ƃ��Ă̂ݑ��݂���̂ł��B �H�����ł��A�E�ޗǎ���̋M���ƕ�������̋M���Ƃٖ̈��������ؖ��ł���ł��傤�B����́A�E�ޗǎ���ł͋M���͓��H���R�n�ɂ��s�����Ă����̂ł��B����ɑ��āA��������̋M���͓��H�����A�R�n�������A���Ԃ���ʎ�i�Ƃ��Ă����̂ł��B ���̃`�[�Y(���)�Ɩ������ꂽ���V�c�̌��ɂ́A�R�n�V�q�����̌�������Ă����̂ł��B���V�c�́A���F���V�c���c�q�̎��A�R���Ō_�����R�n�����̖��̎q�ł������̂ł��B���́u���v�̖��������p������V�c�ɂ��A�V�c�Ƃ͓�k�ɕ��A��k�����n�܂�̂ł��B 1334�N�̌����̒����ł̉��܂̕s�����ɂ�鑫�������̌���V�c����̗����ɂ��A1336�N����V�c�́A�g��֓���A�����ɖk��(���s���쁁�����V�c)�Ɠ쒩(�g�쒩�쁁����V�c)�ɕ���̂ł��B�쒩�́A�k���̍U���ɂ���B(�`���̖��ᓇ�Î��̎x�z�n�ɓ������̖{���߉q�Ƃ͉B�����Ă����B)�ɓ���A�ꎞ�����Ԃ��̂ł����A1339�N����V�c���������A�쒩���x���Ă������������̐����玟�X�Ƌ��邱�Ƃɂ��A1392�N�����`���̈����ɂ���k���͍��̂���̂ł��B�������A����͕\�ʏ�ł��B�������A�S�ύc���A�V���n�������m�Ƃ̎O�b�̐킢�͍X�ɑ����̂ł��B ��B�ł́A��k���̐킢�������ېV�܂ő����̂ł��B�����āA�]�˖����A�������̗���ɂ���e�r���̖��ᐼ�������́A�k���̍l���V�c�E���āA�쒩�̍c���厺�ДV��(�F���˂ɂ��r�m�e���E���A�����V�c�ɐ�����B)���A�u�ʁv�Ƃ��Ė����ېV�ɉS���o���̂ł��B����͐��ɁA645�N�ɑh�䉤�����������ӒD�����Č����ł��B������A���������Ẩ����ӒD�����̖����V���{�́A�j�����B�����邽�߉������Â������A645�N�剻�̉��V(���\�̉��v)�����ȏ����j�Ɏ�荞�݁A�w�Z�Ő��k�ɍ��荞�̂ł��B 1394�N�����`���́A������b�ƂȂ�A�����Ɏ������{���m������̂ł��B �������͌����ꑰ�ł��̂ŁA���q����ɑG�����q�����Ȃ߂�ꂽ�R���Z�p�W�c�̐`���̖���͕\�Љ�Ɍ���A�����̋Z�p�����������ɔ��f����̂ł��B��������́A�E�\���E�|�\�����E���t�����ł��B���q����A�S�ω������敧������G�����Ȃ߂�ꂽ�E�\���E�|�\���B�𑫗������́A�ی�琬����̂ł��B���̂ЂƂ��A�\�y�ł��B������́A1402�N���p�ԓ`���̂ł��B�����āA�����T�@�̕����́A�������ƎЉ�Ɏ������ꏑ�@�����������A�����_��悪���{�ŎR����Ƃ��Ċ�������킯�ł��B���݂̓��{�����̑����̊�́A�����x�z�̎������ォ�狻��킯�ł��B �R�n�����́A���Ɩ����Ɠ����ł��B����́A�R�n�ɂ�蕨���Ǘ����s���A�����ւ��L�����Ղ������Ȃ�����ł��B�R�n��������̐V���n���{�l�́A�S�ϊ��q����̈������ŁA�R�n�ɂ����{�S���ɓƎ��̏��ƃl�b�g���[�N���\�z���Ă����̂ł��B �u�Љ�v�Ƃ́A��(�₵��)�ʼn���Ƃɂ��A�l�b�g���[�N���L���邱�Ƃł��B���q����A�S�ϖk�𐭌��ɑG�����Ȃ߂�ꂽ���q�����ꑰ�̏W����(�₵��)�Ƃ́A�������ɂ�艅�압�����߂̎{�݂Ƃ��ĊJ�����ꂽ�A�u�S�v�������߂̈يE�ł���_�Ћ����ł���킯�ł��B �_�ЂƂ́A�����ɂ��ߓ�����A���압�����߂́u���E�v�ł���킯�ł��B�����ɂ́A�퐪�������̉����u�S���G�_�v�Ƃ��ĕ������߂��āA�M������Ȃ��悤�ɒ��������Ă��鏊�Ȃ̂ł��B ���w�u�Ƃ����v�̉̎����v���o���Ă��������B�u�Ƃ����A�Ƃ����A�����͂ǂ��̍ד�����A�V�_�l(�������^�̉�������߂邽�߁A�V�_�Ƃ��ĕ������߂��B)�̍ד�����A������ƂƂ����Ă�������A���̎q�̎��̂��j���ɂ��D��[�߂ɎQ��܂��A�s���͂悢�悢�A�A��͕|���A�|���Ȃ�����Ƃ����A�Ƃ����v���́A���Q��̋A�肪�|���̂ł��傤���B����́A�u�_�Ёv���퐪����(�����͎ҁ��A�E�g���[)�̃l�b�g���[�N�Ԃ̋��_�ł���������ł��B�����ɏW���퐪�����̓������A���������T�����Ă�������ł��B ���̌��E�ł���_�Ђ����ƃl�b�g���[�N�Ƃ��āA�G���B�͓��Ƒg���ł���u���v��g�D����̂ł��B���̑g�D���d�������A�u�����E���N�U�v�ƌ����킯�ł��B����ɑ��āA��b�R�̓V��@�́A���̖�O�s�̏���(�����)�ł̏��Ƃ��d��̂ł��B���̖������d��u���v�ƕ����g�D���d��u�s�v�̏��Ɗ��������A�퍑����ɐD�c�M���́u�y�s�y���v�̐���Ŕj��̂ł��B ��������ɏ����̏��Ɗ����������ɂȂ����̂́A��������ɕ����������v�f�ՂŁA�v�K�𑽗ʂɗA�����Ă�������ł��B���̗���́A���q����A��������Ƒ����킯�ł��B�ł́A�v�K�▾�K�͉��̓��{���ɑ��ʂɗ��ꍞ��ł����̂ł��傤���B����́A���{����Y�o�������A��A����A�����Ȃǂ��A�v���l�A�����l�ɑ��ʂɎ����o����A���̑Ή��Ƃ��Ă̑v�K�ł���A���K�ł������̂ł��B ���̓��{����Y�o�����z�������ɖڂ��������[���b�p�l���A�u�W�p���O�v�̎������㖖���ɖK���̂ł��B���̖K����́A�@����(���)���a�@�ݗ����w�Z�ݗ������l�̓n�����R���ږ�n�����R���n�����A���n���ٍ̈��N�����������̂܂܂ł��B ���q���㏉������S�ω����⊙�q�k�𐭌��Ɋ���c���E���ƁE����z���̎��͍��ɗ̂�����o�c���邱�Ƃɂ��킪���̏t���̂��Ă������̂��A�������㖖���ɂȂ�ƁA�o�ϓI��Ղ̂Ȃ��������m�K���́A���Ƃ̓����@�\�ł�����E�n���ɑ����镐�m�B���A�n�����≺�n�����Ƃ��āA���̍��ɗ̂����N�H���n�߂�̂ł��B�����āA�n�߂͍��ɗ̂���̊Ǘ��҂ł��������m���A�₪�Ă��̓y�n�̎x�z�҂ƂȂ�A���Ɏ��喼�ƌĂ��悤�ɂȂ�킯�ł��B�������A�����g�D�́A�c������ƂƈقȂ�A���m�ɂ�鑑���N����ق��Ă݂Ă͂��܂���ł����B����́A�؏�Ȃǂ̍����݂��ɂ����͂ɂ��̂����킹�A�����g�D�̕��������X�ɋ�������Ă����킯�ł��B���̕����������̒��_����b�R�̉���ł��B ���̎��喼���A���{�ɑ��������ƁA�K�R�I�ɓy�n�����ɔ��W���Ă����킯�ł��B�����āA�R���͂̂��閼���m��ʏ����喼���A�R���͂̂Ȃ�����喼�̓y�n�𗪒D���Ă����킯�ł��B���ꂪ�A������̐��ł���킯�ł��B ���喼�������̂̓y�n�����ɂ́A���͂��K�v�ł��B�����ŁA�S���̎��喼�́A�R���͂ɗ͂����Ă����킯�ł��B���{�S���ł̓y�n�������p���ɋN����ƁA�R�l�═��̎��v�������Ă����̂ł��B�����ɖڂ����������̏��l���A1542�N��q���Ɂu�e�v�Ɓu�b���R�v�荞�݂ɗ���킯�ł��B����ł́A1543�N�|���g�K���D����q���ɕY���Ƃ���܂��B �|���g�K���́A1385�N�A���W���o���_�̐킢�ŃJ�X�`���R��j�芮�S�Ɨ����ʂ������̂ł��B�|���g�K�������͓������J�X�`��(1479�N�C�X�p�j�A�����ƂȂ�B)�ɗ}�����Ă��邽�߁A�o�ϊ������C�O�ɋ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B1498�N���@�X�R�E�_�E�K�}���C���h�q�H���J��������A�C�X�p�j�A�����ł́A1492�N�ɂ̓R�����u�X�ɂ��A�����J�嗤�ɓ��B���Ă����̂ł��B�����āA���̍q�C�p����g���Đ��C���h�ɐi�o���A�������x�z���Ă����̂ł��B�����ŁA�|���g�K���D�́A�d���Ȃ������Ŗk�サ��q���ɕY���������ƂɁA���j��͂Ȃ��Ă���悤�ł��B �������A��q���́A�|���g�K���D�ɂ����R���j��Ɍ��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��̂ł��B���̎�q���ɂ́A�o���s���̓������̓�������q���g������悤�ł��B ������q�̗��ɂ�葠�l����u�����O�N�A809�N�S�ώl��ڍ���V�c���݈ʂ������A��q���ɁA�������̎����ł��鋻�����̖��ЂƂ��āA�����������������̂ł��B����́A���������A�S�ϊ����V�c�̕������J�s�ɂ��A�ޗǂ̓s�ɕ���Ă��܂��Ă���15�N�ڂł��B���̎�q���̎����������́A806�N��C��������A�����A�^���@�����������ƂƂ̊W���������܂��B����́A�F�ɂ̐���E��̌��Ճ��[�g���A����R�E�������I�B�E����������q���E�������������R�������ƌq���邩��ł��B ���̓������́A�Ǔ��̎�q���Ɏ������������������ƌ����A�u���v�̕\�̋@�\���������u�ꏊ�Ƃ���A���̋@�\�́u�ԁ��遁����Ɂv������ł��B ��q���́A�A���r�A�C���C���h�m���ăX�}�g���C����k�シ��A���V�i�C�̍����x���g�R���x�A�[��Ɉʒu����̂ł��B�ł�����A�������㖖���A�y���V�����Ƃ̕������́A��ؖf�ՓƐ�̂��߂Ɏ�q����苒���A�\���̕��M��𓇎�Ƃ����̂ł��B ��������A�������́A���̓s�ƍ��ۍ`��g��S�ϊ��������Ɏx�z���ꂽ���߁A�����嗤�Ƃ̌��Ճ��[�g���A��q�����I�B�ɕύX�����̂ł��B�����āA�I�B�ɂ͋������̖����̍���������������̂ł��B�܂�A�������̍��ی��Ճ��[�g�́A�����嗤����q��(������)���I�B(������)�ƂȂ�킯�ł��B �������A���q���㏉���A�y���V�����Ƃ�łڂ������ƌ����̓����������ɂ��A�������̓��Ñ����́A�`���̖���ҏ@���v����������ƂȂ�A�ҏ@���v���ߓ��Ò��v�ƂȂ�A���Î��̑c�ƂȂ�̂ł��B�����āA�������́A�߉q�Ƃƕϐg����킯�ł��B�������A�������̖���߉q�Ƃ́A���������ӂ́u�����̏��v���g���헪�ŁA���Î��Ɖ��ʊW�����Ԃ̂ł��B�����āA�������疾���ېV�܂ŁA�߉q�Ƃ̃R���g���[���ɂ��A���Î�(�F����)�͍s������̂ł��B(����͐��ɁA�C�X���G���̃G�t���C�����̑���������A�J�b�R�E�E���_���̃��r���̍s���\�b�N���ł��B) ���q����̐V���@�����@�@�́A���q�ł͕S�ϖk�����ɂ��T�@�ی�̂��ߕz�����ł��Ȃ����߁A���ŕz�����n�߂�̂ł��B���@�@�́A�R�n�����̎��̖@�،o�����������ߑG���ɂ͎�����Ȃ��������A�������v�����������ߗ~�[�����̒��������ɂ��x�����������̂ł��B���̌������v�̓��@�@�́A��q��11�㓖�厞���ɂ�������A�������́A��n���̃l�b�g���[�N���[�g��̂ł��B����́A�]���̎��������������ƁA���������{�\��(���@�@)�ł��B�{�\���́A���@�@�̎��ł������̂ł��B���̖{�\���́A���Î�(������)�ɂ��A���������q���ɂ����ē�ؖ��f�ՂŎd���ꂽ�u�ɐ��Ζ�̌����v�̔閧�����ɂ������̂ł��B(�C�G�Y�X��鋳�t���C�X�E�t���C�X�̓��{�j�ɂ��A�D�c�M���̖{�\���ł̎��́A�u�����Ύ����傫�������̂ŁA�ǂ̂悤�ɂ��Ĕނ����������Ă��Ȃ��B��炪�m�蓾�����́A���̐������łȂ��A���̖������Ŗ��l���ɂ����l���A�є��Ƃ��킸���Ƃ��킸�D���������ł���B�v�Ɣ������Î����Ă��܂��B)�����āA1549�N�C�G�Y�X��̃t�����V�X�R�E�U�r�G�����A�ˑR�������Ɍ����̂ł��B �C�G�Y�X����{�Ɍ��ꂽ�̂́A���x�퍑����̐^�������ł��B���{�́A��B�̓��ËM�v�A�����̖ї��P���A�l���̒��@�䕔���e�A�����̐D�c�M���A����̕��c���M�A�ɓ��̖k�������A�M�Z�̏㐙�P�ՒB�̌Q�Y�����ł������킯�ł��B �����̕������\�̌R�c���Ƃ���ƁA���̌R�c�������R�c�ł��B�������c�́A�z�{�Ȃǂ̏W���V�X�e���ŏW�߂������A�؏�̍����݂��Œ~�����A���̍��͂őm���R�c��g�D���Ă����̂ł��B�퍑����̎�ȕ����R�c�͎O�ł��B�����́A�ő�g�D�̕S�ϋ��s�������x�z�����b�R�̓V��@�̉���ƁA���̒������x������{�\�����ԂƂ�����@�@(�@�؏@)�ƁA�����āA�G������������ČR�c��g�D������y�^�@�ł��B�����̎O�̕����R�c�����̓s�̎x�z���𑈂��Ă����̂��A�퍑����ł������̂ł��B�����̏@���푈�́A�������A�S�ύc���A�V�����ƌ����̊��q���ォ��̉Ύ킪��ł��B ���̏@���푈�Ɋ������܂�Ă��܂����̂��A���q�k�𐭌��ɂ��A�q�����Ȃ߂��Ă��܂����A���q���ƌ����̎c�}�Ɛ`���̖���ł��B��������̕��ƌ����̐��ɂȂ����̂����̊ԁA�������́A���̗���ɂ������Ƃ̏����g���āA�����������ɐH�����ނ̂ł��B�O�㏫�R�����`���̑�������Ǝq�A�l�㏫�R�����`���̑�������h�q�A�Z�㏫�R�����`���̑�������d�q�A���㏫�R�����`���̑�������x�q�ȂǁA��������ł̕S�ϋ��s�����ɓ����̏��𑤎��Ƃ����p���̂܂܂��g�����Ƃɂ��A��������̌������������A�M����(��������)�Ƃ���̂ł��B ���̓������̈ꑰ����L�͂̎q�����A1173�N(����3�N)�ɐ��܂ꂽ�e�a�ł��B�e�a�́A�@�،o�z���̌��c��b�R�̉���ŏC�w�ɗ�ނ̂ł��B�������A�������q�̖��̂��������A��y�@�̖@�R�̒�q�ƂȂ����ƌ������Ƃł��B�������A�e�a�̌����́A�ǂ����A���_�����̃��[�Z���v�킹�܂��B���̏�y�^�@�̋����́A�M�S�ɓO�ꂵ�A�M�������܂����Ƃ��ɕK�����ƂȂ�҂̒��Ԃɓ����B�܂�A��y����M����A��y�����ȑO�ɂ��̐��ŋ~�������A����A�Ɛ������̂ł��B�����āA��Α��͂̋��w��������̂ł��B �����āA�������̖���e�a���S�ϋ��s���x�z�����b�R�ɂ��A�ߍ��ȍU�����邱�Ƃɂ��(�G�̓G�͖���)�A���S�ς̑G���́A�u�P�l�Ȃ����ĉ������Ƃ��A�����∫�l����v�̃L���b�`�t���[�Y�ɂ��A��y�^�@�͑G���̖������Ƙf�킳��Ă��܂��̂ł��B �]�ˎ���A���̐e�a�̈�_���̂悤�ȁA�S�ϑ�敧���ւ̔r���I�v�z�ɂ��A�q���͍X�Ȃ鍷�ʂ��邱�ƂɂȂ�̂ł��B�e�a�́A�S�ϕ����ɍU�����d�|���镐�͂邽�߂ɁA���H��别�Ƃ��鋳�`�ő�敧���ɃC�W�����Ă���A�q���ɊÌ����q�ׂ�̂ł��B |
|
|
��
����́A�u�B�M�╶�Ӂv�ŏq�ׂ�ɂ́A �j�́A��낸�̂���������̂��A���낵�A�قӂ���̂Ȃ�B����́A��傤���Ƃ������̂Ȃ�B���́A��낸�̂��̂��A���肩�����̂Ȃ�A��傤���A�����l�A���܂��܂̂��̂́A�݂ȁA�����E�����E�ԂĂ̂��Ƃ��Ȃ����Ȃ�B�@���̌䂿�������ӂ�������Ȃ��M�y����ΐێ�̂Ђ���̂Ȃ��ɂ����߂Ƃ点�܂��点�āA���Ȃ炸�埸�ς̂��Ƃ���Ђ炩���߂��܂� �� ���́u�G�̓G�͖����v��p���A�퍑����̑G���⌹�������҂̖���́A�u�~���v�Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��킯�ł��B���̐e�a���q���ɕz������헪���A�]�ˎ���̗^�́E��{��V�����u���ؔ�L�v�Ŗ����ɏq�ׂĂ��܂��B �� ���̏��Ɍ�B�q���ǂ��l�Ԍ����̏o���ʂƂ��������A�ނ�̑��c�O�ɑ����鏈�ɂāA�e�a�Ƃ����q�d�V��A���̏����悭�ۂݍ���ŁA���̕��̏@��ɂĂ��q���ɂĂ����������Ȃ��A�M�̎҂͍��������q���Ȃ�ǁA��̐��ɂ͋Ɋy��y�̕��ɂ��Ă�낤�ƌ������A���Ƃ̂ق��L���v���A�{�莛���q���グ�邱���q���قǑ����҂͂Ȃ��B���S��̗L��Ƃ������Ƃ������ƒm��ʂ��Ƃ����A�l�ԕ��݂̕��ɂ���ƌ������A�������������Ȃ������邩��́A���������ɐl�Ԃɒv���Ă��킷�Ɛ\���A���̏�Ȃ��L����A�ɂ����ɂ������̂ē����ׂ��B �� �e�a����������y���E��M�����q���⌹�������҂̖���́A�S���ЂƂƂȂ��u����v�Ƃ��āA�S�ϋM������喼�̗̒n���U������̂ł��B�q���̑����́A���X���q��������܂ł͕��m�W�c�������̂ŁA���H�͂̂Ȃ��S�ϕ��m��_�����m�̑���ł͂Ȃ������̂ł��B�����āA����Ꝅ�͑G���̎������邽�߁A�퍑�喼�̗̒n��D�悷��ړI�ŁA�S���ɍL�����Ă����̂ł��B ���̈���Ꝅ������y�^�@�{�莛�̖{�w�́A���`�o�������̍���̎��ɏo�w�����n�ӒË߂��ł���킯�ł��B�n�ӒẤA�S�ϖS���M��������(663�N�V���ԘY�R�c�ɂ��{���S�ς��łڂ��ꂽ�B)���ƌ���(�V���ԘY�R�c�̖���)�̋��Z�n�ł������̂ł��B���݂̋ߋE�n���ł̖������ʂ̌��́A��1500�N�O�̒��N�����ł̕S�ςƐV���Ƃ̓����ł������̂ł��B ���̓n�ӒÎ��ӂ́A�퍑����ɂ͓��{�̍��ی��Ղ̒��S�n�ƂȂ��Ă����̂ł��B���̒Â̋߂��ɂ���㒬��n�́A��a��Ɨ���ɂ�鐅�^���ǂ��A���ی𗬂̗��j���Â����߁A�퍑����ɂ́A��������ɓ���邱�Ƃ͓��{�͂�����E�ւ̌��Ռ�����ɓ���邱�ƂƓ����Ӗ��ƍl�����Ă����̂ł��B�D�c�M���́A���̌����炵�̗ǂ��㒬��n�ɒ��ڂ��u�����������͂��悻���{��̋��n�Ȃ�B�v�Ə������قǂł��B���̏���(�����������������E���)�̑�n�̐�̂���Ă�W�c���A�C�̌��������猻���̂ł��B����́A�C�G�Y�X��ƍs���ɂ��鍑�ی��Տ��l�ł��B 1549�N�������ɓn�������C�G�Y�X��́A���̃L���X�g�z�����c�Ƃ͈قȂ��Ă����̂ł��B����́A�E��Ɂu�����v�A����Ɂu�e�v�����퓬�I�L���X�g���c�������̂ł��B�X�ɁA���ی��Տ��l�����s���Ă����̂ŁA�L���X�g���z�����ړI���A���Ǝx�z���ړI���͂����肵�܂���ł����B(���́A�F�ɂ̎R���ɁA���R�E�߃W���X�g�ɃL���X�g��������Ă������̂��́A�L���X�g���z���̂��߂����ł͂Ȃ��ł��傤�B�����ɁA�C�G�Y�X��̓��{�n���̗��̖ړI������Ă��܂��B) ���{�ɓn������܂ł̃C�G�Y�X��́A1509�N�f�B�E�̊C��ŃC���h�m�𐧔e���A1510�N�S�A�E�R�����{���̂���̂ł��B�����āA1511�N�C���h�l�V�A�����̃}���b�J��苒���A�e�̕��͂�w�i�ɃL���X�g����z�����Ă����̂ł��B�����āA���n�l����荞�ރV�X�e���Ƃ��ẮA�a�@�ݗ����w�Z�ݗ��ٖ̈��������v���Z�X�����A�����Ȃ�R���N�U�Ō��n�@���g�D��j�āA���n�l�ɂ����S�x�z�w���\�z���A�L���X�g�������ݗ����Ă����̂ł��B�����āA1542�N�C���h�ɃU�r�G���������̂ł��B �������A1548�N����ɕY�����C�G�Y�X��ɓ��M�������W���[������̏��ɂ��A���{���̓C���h��C���h�l�V�������̏Z���ƈقȂ�A�������R���͂��i�i�Ə����Ă��邱�Ƃ�m��A���K�ً̈����N���v���Z�X��H�邱�Ƃɂ��A���{�L���X�g������ژ_�ނ̂ł��B ���̂��߂ɃC�G�Y�X��ŏ��ɖK�ꂽ�̂��������̓��Î��ł��B���Î��́A���͐`���̖���ł��B�`���́A���z�_���J��i��(�~�g����)��M���Ă����̂ł��B�L���X�g���́A���̋��`�̊�{�̓~�g��������̎ؗp�ł��B12��25���̃N���X�}�X�̓~�g���_�̍Đ��a�����ł��B�\���˂͑��z�̃V���{���E�}���^�N���X�Ő`���̉Ɩ�ł��B�Ԃǂ����ƃp���̋V���́A�~�g���_�̉�����j��V������̎ؗp�ł��B �����̃L���X�g���ƌi���Ƃ̋��ʓ_��m�邱�Ƃɂ��A�`���̖���őG���g������A������ɂ��퍑�喼�ɐ���オ���������B�́A���X�ɃL���X�g���ɓ��M�A�L���V�^���喼�ƂȂ��Ă����킯�ł��B �C�G�Y�X��̖ړI�́A���{���L���X�g�������邱�Ƃł��B�������A�C�G�Y�X����o�ϓI�Ɏx�����鍑�ی��Տ��l�́A���{�ő�̌��Ւn�̏���(������)���x�z���邱�Ƃł��B���̖ړI���ʂ����ɂ́A�ǂ̕������R���I�Ɏx�����邩���l����킯�ł��B ����́A�n�ӒÂ���̒n�����ŁA�����͐V���ԘY�R�c�̖��ᕐ�ƌ����̒n�ł��B�����ɑR����R�������́A���R���Ƃł��B ���������̌�������Ŋ����A�y���V�����Ƃ̔��˒n�́A�ɐ��ł��B�ɐ��́A�Â�萅������߂鍑�ی��Տ��l�B�̌��Ւn�ł������̂ł��B���̓�Ƃ̐�����ՂŔ���ȍ��Y��z���āA�㔒��@�c�Ɏ��������̂��A�y���V�����Ƃ������̂ł��B�������A��������ŁA�y���V�����Ƃ́A���ƌ����ɔs��āA���{���疕�E���ꂽ���Ƃɗ��j��Ȃ��Ă���̂ł��B�������A�y���V�����Ƃ̕��ې��̖���́A�y���V�����Ɣ��˂̒n�A�ɐ��ɗ������ъ֎��ƂȂ��Ă����̂ł��B ���̃y���V�����Ɩ���̈ɐ��T�R���̊ֈꐭ�ɁA�C�G�Y�X��鋳�t�I���K���e�B�[�m�������n�l�R�m�c�W���o���j�E�����e�B�X���ė���̂ł��B�����āA�W���o���j�E�����e�B�X�́A�R���ږ�Ƃ��Ċֈꐭ�Ɏd����̂ł��B�����āA�W���o���j�E�����e�B�X�́A�ֈꐭ�v�l�̌Z�A�L���X�g���ɋA�˂�����������(1556�N�`1595�N�B���疼���I���̓��I��)�ɁA�R���ږ�Ƃ��ď���������̂ł��B���̊��������́A�D�c�M���̖����ȂƂ���A�D�c�M���̉Ɛl�������̂ł��B�����āA�D�c�M���ɉy�����邽�߁A�W���o���j�E�����e�B�X�́A���������ɂ��A�R�ȗ��v�C���q�叟���Ɩ��������̂ł��B��������A�����̎㏬�����ł������D�c�M���̉��i�����n�܂�̂ł��B �D�c�M���́A���̕����Əq�ׂĂ��܂����A���̐D�c���̏o�����͂����肵�Ȃ��̂ł��B�D�c���́A�n�}�ł́A����D�c�v�����~�聨�M�聨�M�G���M���A�ƂȂ��Ă��܂����A�~��ȑO���s�ڂł��B�܂�A�O��悪������Ȃ��̂ł��B �퍑�����ŏo����������Ȃ��̂͐D�c�M�������ł͂���܂���B�L�b�G�g�A����ƍN���A���̏o����������Ȃ��̂ł��B ���̕����̖L�b�G�g�̌n�}�́A�؉��������E�q��̎q�ƂȂ��Ă��܂����A���̖�E�q����s�ڂȂ�A����͂܂������̕s�ڂł��B�܂�A�o���n���a�������܂������s�ڂȂ̂ł��B������A�D�c�M�����L�b�G�g���A�����ł͂Ȃ��o���s�ڂ̂��߁A���̍ō��n�ʂ̐��Α叫�R�ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ł��B ����ɑ��āA���̌����̓���ƍN�̌n�}�́A�����L���Ɠ`�ʉ@�v�l�̎q�ƂȂ��Ă��܂����A����ƍN�̍s��(�퓬���A�`���̖��ᕞ���E�҂̃o�b�N�A�b�v����B�q�����e���q����]�˂ɏ����A�Ăɂđѓ����o��������B�L�b�G�g�ɂ��A����Ꝅ�ɂ����ĕ����͂Ŋ������ߏ���̗̒n��v������G���q�����ɗ��Ƃ��ꂽ�n粑����l���Ɋi�グ�����B���N�w�҂h����q�w���w�ԁB�L�b�G�g�̒��N�����ł̐l�Ԃɂ���܂����؍s�ɑ��Ē��N�����ɘl�т�B���������S�̖L�b�G�g�̕��\���j��B)�ɂ͑G���i��̎p���������o�Ă��邽�߁A���̏o�����G�������o�g�ŁA�������ł͂Ȃ��Ƌ^���Ă��܂��B(�]�ˎ���A�ƍN�������܂ł́A�G���B����炵�Ղ��������A�S�ς̌�������Ă���O�㏫�R�ƌ������O���S�ω����ŁA�e���q��͍Ă��q���Ƃ��ăC�W������B�����āA1687�N(�勝4�N)�S�όn����ܑ㏫�R�j�g�ɂ��A���ޗ��݂̗ߔ��z�ɂ��A���{�ŃJ�[�X�g���x�A�u�m�_�H���E�q���E��l�v����������B) ���̐퍑�����B�̏o�����s�ڂȂ�A���̐퍑����Ɋ������m�c�ɂ��s�v�c�Ȃ��Ƃ�����̂ł��B����́A�Ɩ�̏o���ł��B �Ɩ�̗��j��̏o���́A����قnjÂ��͂Ȃ��悤�ł��B�V�c�Ƃ̏\�Z�ٔ��d�\�e��́A1198�N�㒹�H��c���A�e���D�݁A����̈�Ƃ��Ĉ��p�Ƃ����̂��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B�����ɋe�䂪�c���̖�Ƃ��ꂽ�̂́A1869�N(������N)�̑������z���ɂ��̂ł��B ���̉Ɩ�̕s�v�c�́A���̐}�Ă̌��ƂȂ铮�A���Ȃǂ��A���{�×��̂��̂ł͂Ȃ��A�I���G���g�n���̂��̂������Ƃ������Ƃł��B�V�c�Ƃ̋e���A���{�×��̉Ԃł͂Ȃ��A�I���G���g����n���������̂Ȃ̂ł��B �ł́A���̃I���G���g�n���̓��A���������Ƀf�U�C�������Ɩ���f����퍑���m�c�̏o�����A�ǂ̂悤�ɂ��Đ���������悢�̂ł��傤���B ���{�ɂ�����R�l�̌Ăі��́A����̕�(�����)�A��������̕��m(���̂̂�)�E��(���ނ炢)�A���q����̕��m(�Ԃ�)�A�]�ˎ���̕��m(�Ԃ�)�E���|��(�Ԃ�������)�ȂǂƌĂ�Ă���悤�ł����A�����̓��{�ł̌R�l�͂ǂ̂悤�ɂ��Ĕ��������̂ł��傤���B ����̑�\�I�R�������̕������́A�`���ƃc���O�[�X���Ƃ̍����R�������ł��B��������̕��m�́A���압���̃L�������s���V���ԘY�R�c�̖���ł��B�����āA���́A�V�c�̌x��Ɣ鏑�Ɩ������˂�A�S�ϖS���M���̖���ł��B���q����̕��m�́A�����͐V���ԘY�R�c�̖���ŁA�y���V�����Ƃ͈ɐ��ɓn��������،R�������̖���ŁA�����́A�S�ϖS���R�c�̖���ł��B�Ɩ�̗p�r���A�퓬���ł̓G�����̎��ʃ}�[�N���Ƃ���Ȃ�A���́A�퍑����܂ʼnƖ䂪�o�����Ȃ������̂ł��傤���B �����ōl������̂��A�퍑����܂łɒ����嗤������{�ւ́A�I���G���g�R���̌R�������̓n���ł��B 642�N�T�T�����y���V���́A571�N���܂�̃��n���}�h�ɂ��C�X���[�����R�c�ɂ��A�j�n�[���@���h�̐킢�Ŕj��A�T�T�����y���V���鍑�͕���̂ł��B���[�}���E�O���X�ƌ��D���Ƃ̌��Ւ��p���ł���T�T�����y���V���鍑�̃��Y�f�M���h�O���́A�V���N���[�h���Ր�̓����������A�����֔s������̂ł����A651�N�ɈÎE����A�����ɃT�T�����y���V���͖ŖS����̂ł��B �������A���̃T�T�����y���V���鍑�c���̋M���A�R�c�A���l�̑����́A����(618�N�`907�N)�ɒH�蒅���̂ł��B����ɑ��āA�k����̋R�n�����˙�(�`�����N��)�̈��|�I�R���͂ɔY�ޓ����́A���̃T�T�����y���V���鍑�S���҂�삷��킯�ł��B�����ē����́A���̎c���T�T�����y���V���R�c�𓂌R�ɑg�ݍ��ނ��Ƃɂ��A���R�c�́A�p�~�[���̐��܂Ő��͂�L�����Ƃ��o�����̂ł��B �����́A�T�T�����y���V���R�c�̂ق��ɁA�����ЂƂ̕����ɓ��ꂽ�̂ł��B����́A�y���V�����l�̃\�O�h�ł��B �\�O�h�l�́A�I���G���g�ŋI���O���N���납�犈���A�����l��c��Ƃ��Ă���悤�ł��B���̃A�����l�͗V�q���o�g�̍��ۏ��Ɩ��ł������̂ł��B�������A�I���O�����I�ɃA�b�V���A�鍑(�I���O933�N�`�I���O612�N)�ɁA�A�����l�̐����g�D(�C�X���G���������܂�)�͖łڂ���܂������A���̃A������́A�I���G���g�ł̒ʏ���ƂȂ�A�X�ɒ����S��̋��ʌ�ւƔ��W���Ă����킯�ł��B���̃A�����ꂪ�\�O�h��A�A���r�A��A�����S����̊�ƂȂ�킯�ł��B �����̃C���[�W�Ƃ��ẮA���m�l�̊������̍��̂悤�Ɏv���܂����A���Ԃ́A���m�F�����A�I���G���g�F�������̂ł��B���̃\�O�h���l�́A���ۏ��l�ɑ��������A�������b�����Ƃ��ł����̂ŁA�e���̏����L�x�������̂ł��B(804�N���ɗ��w������C���A�A����A������̎������������̂́A�������̈˗��ɂ�萅����Ղ̂��߃\�O�h���l�ƐڐG��������ł��傤�B) 642�N�T�T�����y���V�����|��\�O�h���l���A�����Ɍ��ꂽ�������A���x���{�őh�䉤��(�˙Όn����)���A�o���s���̓������ɂ��|���ꂽ����(645�N)�ƕ�������̂ł��B �S���y���V���R���������ꂽ���R�́A657�N���˙𐧈����A663�N���E�V���A���R�ɂ��S�ς�łڂ��A668�N���E�V���A���R�ɂ�荂���ٖłڂ��̂ł��B�V���́A���X�~�g���R�_���J��M���V���E���[�}�R�ɂ�茚�����ꂽ���ł��B�ł�����A�V���ԘY�R�c�ƃ~�g���_���J��I���G���g����n���̓��y���V���R�c�Ƃ̌R���A�g�́A�\�������̂ł��B�����āA674�N�T�T�����y���V���S�����q�y�[���[�Y�������ɓn������̂ł��B ���̂悤�ȓ������A�C�X���[���R�c���I���G���g���x�z�������ƂƁA�k������̋R�n�R�c�̗��P�ɂ��ŖS���A�ܑ�\���̕�����o�āA960�N�v�������ւƂȂ�킯�ł��B ���̑v��(960�N�`1126�N�B�쒩�E��v��1127�N�`1279�N)���A�k�����痈�P�����R�n�������^�����W���ċ��鍑(1115�N�`1234�N�B)�ƂȂ�A���̌R���I������������̂ł��B ��v��(�쒩)�́A���鍑(�k��)�ƕ��a�������Ԃ̂ł����A���̌��Ԃ肪�A���鍑�ւ̌��D���Ƌ�̍v���ł��B��v�����A���{������A�v�K�����Ԃ�ɁA��E�����ӒD�����̂͂��̂��߂ł��B���̓�v�f�ՂŁA�������͈ɐ��̐���E��̖��A�ō���z���A1132�N���H��c�ւ̘d�G�ŁA�����a���������̂ł��B �₪��12���I(���1162�N)�ɁA���鍑�̖k���A�u���J���R�������́A�����S���Ƃ��������W�c�Ƀe���W�������܂��̂ł��B�e���W���́A�����S�����̂Ȃ��̍X�ɏ��A���̃{���W�M�����̉ƕ��������̂ł��B �e���W��(�`���M�X���Ə̂��B1206�N�`1227�N)�́A�����S���W�c�̃��[�_�[�ւƕ��サ������A���鍑�̃^�^�������������s���āu���v�̏̍������P���C�g���̃����E�J���̌��͂�ӒD���A�����̓����ƒ����̔e�҂Ƃ��Ă̂��オ���Ă����̂ł��B�`���M�X��(�e���W��)�����郂���S���́A�q���W�c��A���̂Ƃ��Ĕ�剻���Ă����킯�ł��B�������A1227�N�`���M�X���́A���Ă�łڂ��A�A�҂̓r�̘Z�ՎR�ɂĎ�������̂ł��B ��C�̃I�S�_�C(���@1229�N�`1241�N)�̉��ɔ�剻���A�R���͂𑝂��������S���́A���鍑�ɒ��ނ̂ł��B�����āA�Z�N�Ԃɂ킽��퓬�ɂ��A1234�N���鍑��|���������S���́A�u�僂���S�����v�Ƃ��Đ��E�鍑�Ɍ����č��͂��L���Ă����̂ł��B �ł́A���̎㏬���̃����S�����A�����S����鍑�ɂȂꂽ�̂ł��傤���B����́A���鍑�ɔs�ꂽ�R�n�������ƃL�^�C�ɒ鍑(907�N�`1125�N)�̌R���͂��z���������ƂƁA���ۏ��l�̃E�C�O���l�̏����W�͂ɂ��̂ł��B ���鍑�����鍑���A�����������Ƃ̉^�c�������̂ł͂Ȃ��̂ł��B���鍑�́A�R���̒��S�͖S���T�T�����y���V���R�c�ŁA���Ǘ��̓I���G���g�̃\�O�h���l�ł��B�����āA���鍑�́A�R���̒��S�͖S���L�^�C�R�c�ŁA���Ǘ��́A���ۏ��l�̃E�C�O���l�ł������̂ł��B�܂�A���E������̒����嗤�ɂ́A�I���G���g����n�������R���⏤�l�B�ň��Ă����̂ł��B ���̂悤�ȓ��A�W�A�ł̃����S�����A���͂𑝂��Ă��鍠�A1219�N�������́A�S�ϖk�����̉A�d�ɂ��A���łɂ��ÎE����A�����Ɋ��q���ƌ����O��̎��オ�I���̂ł��B�������A���̌������́A�ÎE�����O�N�O�A1216�N�ɓ�v��(1279�N���ɖłڂ����B)�̕��H�a�����������āA�n�v����āA��D�̐�����˗����Ă���̂ł��B���̂��Ƃ́A���j��ǂ̂悤�ɉ��߂�����悢�̂ł��傤���B �X�ɕs�v�c�Ȃ��Ƃ�����̂ł��B����́A1274�N�̕��i�̖���1281�N�̍O���̖��̌��R�̗��P�ł��B���̓�x�̌��R�̑�R�c�́A��x�Ƃ��u�_���v�ɂ���ł������ƂɁA���j��͂Ȃ��Ă���悤�ł��B���̐����Ƃ��āA���R�́A�C�m�����ł͂Ȃ��A�R�n�����̂��߁A���D�ɕs����Ȃ��߁A�ꐡ�������̖\���J�ł��S�ł����A�ƌ������Ƃł��B �������A���̐����́A�����ɂȂ��Ă��܂���B����́A�t�r���C(���c1260�N�`1294�N)���o�c���郂���S���鍑(1271�N���E�Ò鍑)�̎����m��Ȃ����߂̐����ł��B �����S���鍑�́A1260�N���������ɁA�O��ӂ��̃����S���ɕ����邱�Ƃ��o����̂ł��B�O�������S���́A����ɂ�����̒n�g��̎��ゾ�����̂ł��B�������A��������S��(1271�N�Ɍ����Ɩ���)�́A��v��(���������S������Ă���)��ڎ����āA��v���̊C�m�n�q�Z�p�ɂ��A���[���V�A�͂��Ƃ��A�k�A�t���J�܂ł����Ռ��ɂ����\�z�������āA�C�m�f�����𐄐i���Ă����̂ł��B ���̂��߂ɁA�����S�y���o�ό��Ƃ���ړI�ŁA��k��A�˂��^�͂̌��݂ɒ��肵���̂ł��B���̂��߁A�����̖f�ՑD�́A�����^�͖Ԃɂ��A��s�E��s(�k��)���ʏB������(�V��)��(�݊C�p���o�R)�������E���큨���{�ւƑ�^�C�D���q�s���Ă����̂ł��B �����łȂ��Ƃ��A�����嗤�ƊO�m�D�ɂ��A���u��C�����Ƃ̍��ی��Ղ́A�����I���炨���Ȃ��Ă����̂ł��B�����̃A���u�l�̑D�����A�������C�ݒn��ł̍`�p�s�s�ł̏o�����ꂵ���̂��A�V���h�o�b�h(�C���h�̕��𗘗p���đD��������C�m���l�̑���)�̖`������ł���킯�ł��B ���̂悤�ɁA�����I�ȍ~�̍q�C�p�́A�O�m�̍r�g�����z����Z�p�������Ă����̂ł��B�ł́A�����̓�x�́u�_���v�ɂ����{�j����������ł̎��̂́A�j���������̂ł��傤���B(�u�_���v�Ƃ́A�����̗��j�w�҂��n�삵���T�O�B) �����̋L�q�������Ȏ����́A�����܂��B���{�����u�����L�v�ŁA���푤���u�����ʊӁv�ł��B�����L�ł́A���i�̖��́A�u���ɂȂ�����G�͂��G�������ꂢ�����ς茩������Ȃ��Ȃ����̂ŋ������B�v�Ƃ���A�O���̖��́A�u�啗����A���������A�����M������v�Ƃ���̂ł��B�������A���푤�̎j���ł́A���i�̖��́A�u�锼�ɑ啗�J���������B�����̑D�����B�v�Ƃ���A�O���̖��́A���{���j���Ɠ������e�ł��B ���i�̖��ɑ���A���{���ƍ��푤�̋L�q�̈Ⴂ�́A�ǂ̂悤�ɉ��߂�����悢�̂ł��傤���B |
|
|
�X�ɁA�s�v�c�Ȃ��Ƃ�����̂ł��B����́A���i�̖��̗��N1275�N�A�����́A���Ղ����߂ēm�����𐳎g�Ƃ��đ��荞��ł���̂ł��B����ɑ��āB���q���{�́A���g�m�������ɕ{���犙�q�̌Y���m���֘A�s���ď��Y���Ă��܂��̂ł��B�X�ɁA1279�N���g�������A���Ղ����߂Ĕ�����K���̂ł����A�����͔����ŏ��Y����Ă��܂��̂ł��B(�푈��Ԃ̎����ɁA���h���̎g�߂��x�������Ă��邱�Ƃ�����̂ł��傤���B�������x�̎g�߂́A����R�Ŏa��Ă���̂ł��B�X�ɁA�m�����͎N����ł��B)
���̕s�v�c�Ȍ����Ɗ��q���{�Ƃ̌��ՊO�����̓�����́A�����̏��𑀍삷��u�T�m�v�ɂ�����悤�ł��B���q���{�́A�����̏����u�T�m�v���瓾�Ă����̂ł��B����́A�T�́A���X�����嗤�Ŕ������ꂽ�@���g�D����������ł��B �����āA���̊��q����ɓ��{�ɓy�������T�@�́A���{�ƒ����Ƃ̍��ی��Ղɐ[���g����Ă����̂ł��B���q���{�́A��v���Ƃ̌��Ղ��s�����߂ɁA���q�ɍ��ۖ���z���Ă����̂ł��B�����āA���q�T�@�g�D�́A�����Ɗ��q���{�Ƃ̒��ڌ��Ղ�]��ł͂��Ȃ������̂ł��B �����ŁA�ЂƂ̐��_�������̂ł��B����́A���i�̖��ł́A�u�_���v�͐����Ȃ������ƌ������Ƃł��B�ł́A�O���l���悹����S�ǂ̌��R�̑D�́A�ǂ������̂ł��傤���B���������A���̋�S�ǂ́A�{���ɐ��K�̌��R�������̂ł��傤���B 1274�N�A���鍑�ƂȂ����t�r���C���{�́A��v�������̏�������S�ʐi�R����̂ł��B�C�����R���A���]�����̗v�n���킸�ɊJ�邳���A��v���̖k�̎��A���]�̓V�������R�ɓ˔j�����ƁA��v���̏��s�s�͎��X�Ɠ��~�����̂ł��B ���̂��Ƃ́A�I���O334�N�́A�^�ɂ��z�̍U���̋L������݂����点�܂��B�s�ꂽ�z�̉����c�}�́A��^�O�m�D�œ��V�i�C�ɒE�o���āA�����x���g�R���x�[�A�ɂĖk��B�E���{�̓��k�ɓn������킯�ł��B 1274�N�̕��i�̖��̌��C�R�Ƃ����Ă�����̂��A��v���̉����S�����c���Ƃ���ƁA�k��B�ɏ㗤���邱�Ƃ����܂ꂽ�����A�ˑR��B���݂�����ɂ��āu�����Ȃ��Ȃ����v���R�������ł��܂��B��v�������S�����c���㗤���ő����̃C�U�R�U����������������܂��A����͐N���퓬�Ȃǂł͂Ȃ������ł��傤�B(���R�̎��҂̐M���ł���j���������ɑ��݂��Ȃ��B) �ł́A���j���ȏ���1281�N�̍O���̖��̓��H�R4���ƍ]��R10���̌����́A�ǂ̂悤�ɐ����ł���̂ł��傤���B 1276�N�Y�B�̓�v���{�́A���鍑�R�̃o�����R�ɑS�ʍ~������̂ł��B�������A�Y�B�J��ɔ�������v�R�̉����c�}���A�c��̌Z��������ŁA���쉈�C�݂��^�O�m�D�ŗ��S����̂ł��B�������A�L�B�p�������R�ŁA1279�N�ŖS����̂ł��B �ł́A�����̂��Ƃɂ��A1281�N�̍O���̖��͂ǂ̂悤�ɐ����ł���̂ł��傤���B���H�R��4���̌��C�R�́A�I���O�O���I�̏����̖H�����ւ̓n�q���v�킹�܂��B�����̓��H�R�̑唼�́A�����̑����ƂȂ��Ă��܂����ւ荂������R�������̂ł��B �����́A�`�n�c��ɕs�V�s���̐������ɂ����ƁA���j���O�疼�ƋZ�p�҂ƌR���Ǝ���Ɣ_�@���ςD�S�ǂŁA���{�Ɍ��������̂ł��B���ꂪ�`���n���̐挭���������̂ł��B �ł́A���H�R�n�����x��ė����]��R�͂ǂ̂悤�ɐ����ł���̂ł��傤���B����́A����v�R�ɂ��\������Ă���Ƃ����Ă��܂����A���̑����͓�v�������̖S�����c�������̂ł��傤�B ���������A�����ɑ��Ă̎j�����R�������܂��B�����ɂ��Ă��A�����L�ɂ��Ă��A���@�@�̎����ɂ��Ă��A�����E�T�@�W�̎����������̂͂ǂ����Ăł��傤���B���ȏ��ł��Ȃ��݂́u�|��G���G���v(�������������Ȃ������Ƃ�)�ɂ��Ă��A���n�q�S�R���z�w�����G�w�ɓ˓������A�ƌ��������A��v���⍂��̖S���ҏ㗤�̌����ɁA���f���ԈႦ����������R�Ŗ��d�ɂ��˓��������Ƃ��A��ŋ�z��őn�삵���G�ł��邩������Ȃ��̂ł��B���R�̋|�́A�{�[�K���̂悤�ɕS���S���ł��B�{���ɁA���R�ł������Ȃ�A��R�œ˓��������{�̕����͐▽���Ă������Ƃł��傤�B�������A�|��G�������́A�_���s�܂̌��̂��߂ɂ킴�킴���q�܂ŏo�����Ă���̂ł��B �����ŁA���ی��Ղ̎|����m��@���g�D�ɂ��u�����t�B�N�V�������v�������ł���̂ł��B �T�@�g�D�������K�Z������ɁA1263�N(�O��3�N)���@�������A�k�����q���{�ɒ�o�����u���������_�v�̗��_�W�J�̌��ʂł���u�×��P�̗\���v���A�u���\�̌����v���j���Ƃ���d�v�j���̂ЂƂƂȂ��Ă���̂ł��B �t�r���C�̌��鍑�́A1260�N����C�m�f������W�Ԃ��A�A���r�A�A�C���h�A�����ē��{���ƍ��ی��Ղ����邽�߂Ɏg�҂�h�����Ă����̂ł��B�������A���鍑�Ɩk�����q�����ƒ��ڍ��ی��Ղ��s���邱�Ƃ́A��v���Ɩ��f�Ղ����Ă������q�T�@�g�D�ɂ͋��Ђ������̂ł��B�����āA���E��������m��Ȃ�18�̖k�����@�́A�T�m���k�����̌�����܂܂ɁA�k��B�ɗ��ꒅ������v���E����S���R�c���A���鍑�C�R�ƐM���Ă��܂����̂ł��B 1281�N�ɖk��B�Ɍ��ꂽ�A��v���S���R���c�́A�\���J�ɏP��ꂢ�����Ƃ��Ȃ������Ă����킯�ł��B�������A�s�K�ɂ�����Ă��܂����D���������̂ł��傤�B���̓�j�D�̎c�������A�����̐��̂��ؖ����܂��B�����ƌ����Ă��錳�R�̓�j�D�̎c�����̑������A����ł͂Ȃ��A�P�ɋl�߂�ꂽ�u����v�Ɓu�_�@��v�ł������̂ł��B ���N�����œ�[�ɋ߂��V���S�̉������̊C�ꂩ������グ��ꂽ���D�́A1323�N�Ɗm�肳��܂����B����́A��x�ڂ̌������P�Ƃ����Ă���A�킸���l�\�N�قǂł��B���̑D�ɂ́A�_�ɋy�ԓ�����������A�����āA��O�\�g���߂��̓��K���݂��܂�Ă����̂ł��B���̌��ՑD�́A���N��������ǂ��Ɍ������čs�����̂ł��傤���B �ł́A�����Ƃ���ꂽ��v���E����̖S���R�c�D�́A�Δn�C���ɏ���Ăǂ��ɏ������̂ł��傤���B ����́A���̕����̗��j�����܂��B���{�ɂ����镐��̗���Ƃ��āA�ꕶ�E�퐶����̃T�k�J�C�g�̐Γ��A�Ζ_�A�|��Ȃǂ�����܂��B�ޗǎ������ɂȂ�ƁA�R�n�����̋R�m�ɑ�������̕���Ƃ��āA���_�ɂ���������㓁����������܂��B����́A�������̋������A�S�ϋ��s�̉���̑m���̕���ƂȂ�܂��B�ł́A�퍑�������g�p�������́A�ǂ̎���ɓ��{�Ɍ��ꂽ�̂ł��傤���B����́A���x�����̌�A���N�������Ō��鍑�Ɠ��{�Ƃ̍��ی��ՑD�����v�������A����V�c���݈ʂ�����k���̍��ł��B�����āA���j����H�ő����g�p���ꂽ�̂́A��k���ȍ~�̂悤�ł��B �ł́A���̓ˑR���{�ɑ����o�������̂ł��傤���B�����āA�퍑����ɂȂ�ƁA�Ȃ�Ə\���[�g�����̑����o������̂ł��B ���m�̗��j��ł̑��̏o���́A���[�}����̂悤�ł��B�L���ȃ����M�k�X�̑��́A�\���˂̃��V���A(�L���X�g)���h�������̂ł��B�����M�k�X�Ƃ́A���e����Ń��[�}�j���̌ď̂ł��B���[�}�鍑�R�̎�ȕ���́A�\���[�g���̒����������̂ł��B���̏\���[�g���̒����Ǝ������̂��A�D�c�M���̗b���R�Ŏg���Ă����̂ł��B ���̐D�c�M���R�̒����́A�ē����O���l�Ă������̂ƌ����Ă��܂��B�ē����O�́A�����̐퍑�����Ɠ����ɏo���s�ڂł��B���̖��̓��O�Ƃ͕ʏ̂ŁA�{���͗����ł��B����́A�����l���m�������m�ւ̐E�ƕ��ɂ��A�ē����O�ƌĂ�Ă����킯�ł��B �����l�Ƃ́A�_�Ѓl�b�g���[�N�ɂ�蓯�Ǝґg���̖������\�z����A�S���I���̐��̏��ƏW�c�̈���Ȃ̂ł��B�����āA���̖����́A645�N�܂Ő`�����x�z���Ă����R�鍑(�R�w��)�̎R�肪�{���������̂ł��B �ޗǎ���A�������ɂ��A�`���̐_(�����E��͂�)�́A�_�Ђɕ������߂��u�����E�͂��܂�v�Ƃ���A���̎��q�͑G�����Ȃ߂��Ă��܂��킯�ł����A�`���͌��X�I���G���g����n���̋Z�p�ҏW�c�������̂ŁA���̋Z�p����g���邱�Ƃɂ��F�X�ȏ��Ɛ��i�Y���A�يE�ł���_�Ђ��l�b�g���[�N�Ƃ��āA���ƎҏW�c�g�D�́u���v���\�����邱�Ƃɂ��A�S���ɏ��Ɛ��i�̔̔��Ԃ��\�z���Ă����̂ł��B 1017�N�A��������̂킪���̏t��搉̂��铡�����ꑰ�́A���̐_�Ѓl�b�g���[�N�̏��ƖԂ��x�z���邽�߂ɁA�{�n��瑐�(�����{�ƂŁA�_�͕���)�����A�_�Ђ��̎x�z���ɒu���킯�ł��B �����l�̏��i�����̃S�}�ɂ͓��ނ���܂��B����́A�`�Ӗ�(������)�ƌӖ��ł��B�`�Ӗ��́A�V�\�ȂŁA���Y�n�͒����암�ł��B���{�ւ̓n���́A�ꕶ����ł��B����ɑ��āA�Ӗ��̓S�}�ȂŁA���Y�n�́A�A�t���J�ł��B �Ӗ������j��Ɍ����̂́A�I���O1377�N�A�C�X���G�������̃G�t���C�����̑c�惈�Z�t���������A�G�W�v�g�̃C�N�i�g���̎���̂悤�ł��B�Ӗ��̗p�r�Ƃ��ẮA�~�C���̕ۑ��܁A�����̖��A�����Ĉ��i�ł��B�C�N�i�g���́A�Ӗ��ƃI���[�u���x�z�n�ō͔|�����邱�Ƃɂ��A�o�ϊ�Ղ�z���Ă����̂ł��B�������A�I���[�u�̓G�W�v�g�̋C��ɍ��킸�A�M���V����I���G���g�Ő���ɍ͔|����A�����Ɏ���̂ł��B�Ñ�G�W�v�g�ł́A�Ӗ�����I���[�u���́A���Ȃ��(�A���u�̕���ł̎����u�I�[�v���E�U�Z�T�~�^�J���S�}�v�Ɏg����قǁA�Ӗ��͖��͂����H�ו��Ƃ��ėp����ꂽ�B)�Ƃ��ċM�d�i�ł������̂ł��B���_�����ł́A�I���[�u���ɒ����ꂽ���͉̂��ɂȂꂽ���ł��B �����āA�Ӗ��́A�I���O�Z���I���A�G�W�v�g����C���h�֓n�����āA�A�����x�[�_��w�ł́A���߂��Ӗ������ɐ��ꗬ�����Ïp���J�������̂ł��B���̌Ӗ��́A�I���G���g�̍��ۏ��l�Ƌ��ɒ����ɓn�����A���N�������o�R���āA���{�ɂ�200�N���n�������悤�ł��B645�N�̓������ɂ��h�䉤���j���̕����ɂ��A����̌Ӗ��̗��j�͈ł̒��ł����A���{���j��Ɍ����̂́A�R�n���������̓V���V�c(672�N�`686�N)�ɂ��A�Ӗ����͔|����A�H�p���Ƃ��Ďg�p���ꂽ�悤�ł��B ���������ɁA�z�������̓ޗǂ���`�Ӗ����Z�p�҂��A�R�鍑(�R�w��)�̒����J�s�ɔ����ڏZ��(���X�R�w���́A645�N�܂ł͐`���̎x�z�n�ł������B)�A�����āA�F���������ɑJ���������A��R��{�̓����p�ɉ`�Ӗ���������悤�ł��B���̔���(��͂�)�Ƃ́A�`���̐_�l�ł��B���̐_�Ђ̐_�l(�_�Ђ̓z��)�炪�A�R�������g�D���A�������㖖�����玺������܂ŁA���̔��̓Ɛ�����Ă����̂ł��B �ƌ������Ƃ́A������̐ē����O�́A���̐����̂ЂƂł�����킯�ł��B���̒������l�Ă����ē����O�́A���̔Z�P��D�c�M���ɉł�����̂ł��B�ł́A�G���̖���W��D�c�M���Ƃ́A���̏o���́A���҂Ȃ̂ł��傤���B �D�c�M������O���A�܂�c���D�c�M��́A�e�����M��ƌď̂���Ă����̂ł��B�e�����M��́A�쒩�̎c�}�E�V�c�l�ƂƒÓ����}���x�z�������������̍`���̒Ó��̏����𗪒D���A���������_�Ƃ��ē�Ɛ���̖��f�Ղ��s���̂ł��B�����āA1543�N(�V��12�N)�e�����́A���f�Ղʼn҂����i�y�K�l��т�����̏C����Ƃ��Ē���Ɍ��シ��̂ł��B����͐��ɁA1132�N(����1�N)�y���V�����Ƃ̕��������A��ؖ��f�Ղʼn҂��������A���H�@�c�Ɍ��サ�āA�����a�������ꂽ���ƂƓ����s���ł��B �ł́A�D�c�M���̑c���́A�y���V�����Ƃ̖��Ⴉ�Ƃ����ƁA���̏o���͂܂������킩��Ȃ��̂ł��B�����A�������Ă��邱�Ƃ́A�e�����M��̕�́A���Y��߂��̏����̌䏊�_��(�����傩����)�ɂ���̂ł��B �_��(������)�Ƃ́A�ޗǎ��㖖���A�S�ω����ɔs��A�S�ω����ɂ܂��ʐ`����V���n���{�l���������߂�ꂽ�A�ߗ����e���ł��B��ɁA���ʕ����ƂȂ�킯�ł��B���̕����ɁA��������ɐ������q��������b�R�̉�����A�@�،o�Ő�`����A�����҂ƌ��߂���n���Z�����a�҂��������߂邱�Ƃɂ��A���̕������q�ꕔ���Ƃ����̂ł��B�D�c�M���ɂ��A��b�R����̕��m���A�u�V�呞�����U���܂ő����v�ƁA�S���ł���Ƃ��������̂ЂƂ́A����(�O�����ł���h��E�V���V�c�̓��H����R�n����������A�ؐH�̕������`�̖��̉����q�����Ȃ߂�����)�ɂ���̂�������܂���B �C�G�Y�X��́A�L���X�g������{���̒��S�ł��鋞�̓s�ŕz�����邽�߂ɁA���̋����b�R����Ɋ肢�o��̂ł��B�������A���̏��Ɨ�����������́A�Ȃ��Ȃ������܂���B����́A�����f�Ղɂ����āA������́A�C�G�Y�X��̃C���h�E����A�W�A�ɂ��������m���Ă�������ł��B��t�E�鋳�t�n�����n���~�ρ��a�@�ݗ��������̐鋳�t�n�����w�Z�ݗ������ی��Տ��l�n�����R���ږ�n�����R���N�U���A���n���̗���́A�C�G�Y�X��̕z�����j���̂��̂ł��B �C�G�Y�X��́A���ی��Ս`�ƂȂ����n粒ẤA�{�莛���������@�ł����y�^�@��k�̌R�c�ɂ��A�v�lj����ꂽ�����ŌR���I�Ɏx�z����Ă���̂ŁA�C�G�Y�X�������n���R�c�ł͉�łł��Ȃ����Ƃ�m���Ă�������A�ŏ��ً̈��R�c�̉�ŖڕW�Ƃ��Ĕ�b�R�����I�Ԃ̂ł��B ���̂��߂ɂ́A�C�G�Y�X��̘��S�R����{�S���ɑg�D����K�v������킯�ł��B�����Ŗڂ�t�����̂��A�������c�ɃC�W�����Ă���G���o�g�̕��������̐D�c�M���ł��B�D�c�M���̕��������́A�����̕����V�ŁA�Ւd�̈ʔv�ɐ����D�𓊂����A���V�ɂ��Q�����Ȃ��قǂł��B�m���Ɉ��Ԃ����͓̂��풃�ю��ł�����A�����E�̓G�ł���C�G�Y�X��ɂ́A�e�ߊ������͓̂��R�ł��傤�B�܂�A�G�̓G�͖����ƌ������Ƃł��B ����ɁA�����ƕ��m�Ƃ͑��e��Ȃ����݂Ȃ̂ł��B����́A�E���֎~�Łu���v���֊��Ƃ��镧�����`�́A�G�̎����邱�Ƃ��蕿�ƂȂ镐�m�̎v�z�Ƃ͑��e��Ȃ�����ł��B�܂�A������M���镐�m�́A���Ȗ����̑��݂ł���킯�ł��B�ł�����A���m���x�z�������q����ɁA���H����R�n������̎�����@�،o��z�����Ȃ��u�T�@�v���������瓱������A�u���ԂɑT�����ƎЉ�ɕ��y����킯�ł��B �������A���m�ƌ����Ă��A���q���m�Ɛ퍑���m�Ƃ͓����o���ł͂���܂���B���q�����O��ŖS��́A���q���m�͕S�ϖS���R�̖���ŁA�S�ϖk�𐭌��̉A�d�ɂ��A�V���n���m�̌����͓s����Ǖ����ꗎ�����҂Ƃ��Đ������т�킯�ł��B���ꂪ�A��k������������̉��m�̗����o�āA�퍑����̉�����̐��ɂȂ�ƁA�R���Ő������Ă��������������҂̖���́A���̌R���͂ɂ��퍑�喼�ƂȂ�킯�ł��B ���̐퍑�喼�ɑ��āA�C�G�Y�X��̐鋳�t�́A�L���X�g����z������̂ł��B���̕z�����菕�������̂��A�����i�@�t�ł������������\���ւł��B�g�̕s���R�̔��i�@�t�̗��ւ́A�C�G�Y�X��̎������Ís�ׂ��邤���A�����m����L���X�g�҂֏@�|�ւ������̂ł��B�����i�@�t���C�G�Y�X��ɓ��M���������Ƃɂ��A�C�G�Y�X��̘��S�R�c���}���ɑg�D����Ă����킯�ł��B����́A���i�@�t�͓��Ƒg���ł���u���v�̃l�b�g���[�N�ɂ��S�����s�r���邱�Ƃɂ��A�퍑�喼�̏o���⓮����ǂ��m���Ă�������ł��B �퍑�喼����L���V�^���喼�ɂȂ����҂̒��ɂ́A�C�G�Y�X��x������u�e�v�Ɓu�Ζ�v����肷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ����҂����Ȃ��炸������������܂��A�C�G�Y�X������A�u�l�������v�z�v�ɋ������҂����Ȃ�����܂���B����́A��������̋�C����������������炵���u���H�G���J�[�X�g�v�z�v�A���q���ォ��o���������̍��ʎv�z����荞�����g�D�ɂ�蔭�����ꂽ�A����I�ɓ��H�҂͈��ł���u�q���v�ƕ̏̂��ꂽ�҂ł��������ł��Ȃ��ł��̂ł��B�����āA�L���X�g�҂��A�R�n�V�q�����Ɠ����ɓ��H���邱�Ƃ��A���H����G�����琬��オ�����퍑�喼�ɂ͋����ł����̂ł��B �L���V�^���ɓ��M�����喼�═���́A�œ|�����R�c(�C�G�Y�X��́A�j�F���镧�m���Z�ޔ�b�R����������̊قƂ��A�����j�邱�Ƃ����`�Ƃ��Ă����B����Ă������ŁA�����̎Ⴂ�����Ɠ��q���a��Ă��܂��B���l���̕��̐��n�ɉ��̑����̏����������̂ł��傤���B)�Ō������Ă����̂ł��B���̎�ȕ����́A �� ���ΑS�o(�W���X�g�E�F��c�Ɛb)�A�L�n�`��(�A���h���E��O�����̎�)�A�L�n���M(�v���^�W�I�E�L�n�`���̎q)�A�L�n����(�T���Z�Y�E�L�n���M�̎q)�A�������(�h���E�p�E���E�y����������Ɠ���)�A�ɓ��`��(�o���g�����I)�A�F�v����(�h�����C�X�E�ܓ�����)�A�ؑ�����(�o���g�����I�E���{���̃L���V�^���喼)�A�ؑ���O(�t�����V�X�R�E�L��̎�)�A�D�c�L�y��(�W���A���E�D�c�M���̒�)�A�D�c�G�M(�D�c�M���̑�)�A�D�c�G��(�p�E���E�D�c�M���̑�)�A����R����(�f�B�G�S�E�א�Ƃ̉Ɛl)�A��������(���I���̓��I���E�D�c�M���̉Ɛb�B���[�}�\���R�̐����n�l�R�m�c�W���o���j�E�����e�B�X���R�ȗ��v�C���q�叟�����R���ږ�Ƃ��ď�������)�A�؉����r(�y�e���E�ዷ���l���)�A���ɍ��m(�L�b�G�g�A����ƍN�Ɏd����)�A�F�J����(�����L�I�[���E���|�ٌF�J��)�A���c����(�_�~�A��)�A���c�F��(�V���I��)�A������G��(�V�}�I�E�}�㍑�v���ď��)�A�����s��(�A�E�O�X�e�B�m)�A��������(�W���E�`���E�����s���̕�)�A�u��e��(�h���p�E���E��F�`���Ɛb)�A���R�F��(�_���I�E��ˎ�ʼnE�߂̕�)�A���R�E��(�W���X�g�E�L���V�^���喼�Ń}�j���ɂĎ���)�A�����@��(�W���A���E�}�j���Ŏ���)�A�I�{��Ɛ��A���R�����A���Y���M(�������Y28�㓖��)�A�ї�����(�L�㍲���̎�)�A�ї��G��(�}��v���ď��)�A���钉��(�A�����P)�Ȃǂł��B �� �퍑����ł̑����̐킢�́A�V�����ꂪ�ړI�ł͂Ȃ��A�����̗̓y�ۑS����ړI�������̂ł��B�L���V�^���b���R�c�őg�D�����D�c�M���̌R�c�������܂ł́A�퍑�喼�̌R���s���́A�G�̗̓y�N���ɑ��Ă̖h�䂪��ړI�������̂ł��B����́A�퍑�喼�����߂鑽���̍��́A�����𐔏\�{�ɂ����邱�Ƃ��\�ȏ��ƌo�ςł͂Ȃ��A�V��ɍ��E���ꏊ���{��������_�Ǝ�̌o�ςŁA���{�S����ł���퓬���R��������邱�Ƃ��ł���قǍ����L���ł͂Ȃ���������ł��B �ł�����A�����̍��ł́A�����̐��R�c�Ƒ命���̔_�ƌ����̕��m�c�ɂ��\������Ă����̂��퍑����̌R���g�D�������̂ł��B�ł�����A�o�w�̑����́A�U�߂�������_�Պ��ɂ����Ȃ��Ă����킯�ł��B�t����H�܂ł̔_�Ɋ��ɂ́A�傫�Ȑ킢���Ȃ������̂͂��̂��߂ł��B �������A�D�c�M���́A���̐퍑�喼�Ƃ͈قȂ�R����g�D���Ă����̂ł��B���ꂪ�b���ɂ��R���g�D�ł��B���̌R���g�D�͒N�̃A�C�f�B�A�Ȃ̂ł��傤���B�����āA���̐퍑����ł̗b���R�̏o���Ɠ����ɁA���ƉƖ䂪�o�������̂ł��B �b���R�̎n�߂̓��[�}�R�ƌ����Ă��܂��B�������͌R���ɓ���̂����݁A���̗͂ɂ��u�ق����v���ق��̂ł��B����Ɛ�����i�Ƃ��Ă̔_�n�������Ȃ��������A�R���Z�p�蕨�ɂ���킯�ł��B���ꂪ�b���R�c�̎n�܂�ł��B�b���R�c�́A���(�d����)�œ�������ڋq�ɃA�s�[�����邽�߂ɁA�R�������̃V���{���}�[�N�����āA���⏂�ɂ���̂ł��B�܂�A�R�c��͌R����������ڋq�ɐ�`���邽�߂̃}�[�N�������̂ł��B ���̌R�c����m�̕W���Ƃ��č̗p�����̂��A1095�N�ɑg�D���ꂽ�\��������Ɍf����u�\���R�v�ł��B�\���R�́A�L���X�g��(���V���A��)�̐��n�p���X�`�i�̂��߂Ƀg���R������ڎw���̂ł��B �l���I�̃p���X�`�i�̃G���T�����́A���[�}�鍑�ɂ��L���X�g���̐��n�Ƃ����̂ł����A�����I�ɃC�X���[���R�c�ɂ��G���T�����̓C�X���[�����̐��n(668�N��A���@����)�Ƃ����̂ł��B�������A�ً��Ɋ��e�ȃC�X���[�����́A�L���X�g����r�������A�G���T�����̓L���X�g���ƃC�X���[�������������鐹�n�ƂȂ��Ă����̂ł��B |
|
|
�������A���̃p���X�`�i�́A�Z���W���N�E�g���R(1037�N�`1157�N)�ɐ�̂���Ă��܂��킯�ł��B����ɑ��āA1095�N���c�E���o�k�X���N������������c�Ńg���R�x�z�̃G���T����������錾����̂ł��B1099�N�\���R�̓G���T�������̂��A�G���T��������(1099�N�`1187�N)�����݂��A�C�^���A�̏��l���G���T��������҂�ɂ���h�������×{�������˂�C���@�g�D���u�����n�l�R�m�c�v�Ƃ��āA�@���p�X�N���[���ɂ�萳���ɔF�߂���̂ł��B
�����āA�C���@�g�D�ł��鐹���n�l�R�m�c�́A���̓x�d�Ȃ�g���R�Ƃ̐푈�ŁA��R�c�̍U���ɑ���h��Z�p(��̌��Z�p)���m�����Ă����̂ł��B�����āA���̐����n�l�R�m�c�̖��Ⴊ�A�퍑����̓��{���Ɍ����̂ł��B �D�c�M�����x�z��������̈ɐ��T�R�̊ֈꐭ�ɁA���s�ŃL���X�g����z�����Ă����C�G�Y�X��̃O�b�L�E�\���f�B�E�I���K���e�B�[�m�������n�l�R�m�c�W���o���j�E�����e�B�X���Ă���̂ł��B �����n�l�R�m�c�́A�ꎞ�G���T�����Ŋ��Ă������A1291�N�̃A�b�R���ח��ɂ��G���T�����������ŖS���A�L�v���X���ɓ���A�̐��𗧂Ē�����1308�N���[�h�X���𐪕����A��������n�Ƃ��ăI�X�}���E�g���R(1299�N�����A1405�N�g���R�鍑�ċ�)�ƑΛ�����̂ł��B �������A1522�N�g���R�鍑�R�́A��\���̑�R�����[�h�X���ɍ���������̂ł��B����ɑ��鐹���n�l�R�m�c�͘Z��B�܃����ɋy�Ԑ킢�ŁA�����n�l�R�m�c�́A�s�ނ��A���[�h�X����P�ނ���̂ł��B�퍑����̓��{���ɓn�������W���o���j�E�����e�B�X�́A���̐킢�ł̎c�}�Ɛ�������܂��B�����ŁA�����n�l�R�m�c�c�}�́A�C�G�Y�X��Əo��������A���{���ւ̓n���ƂȂ�킯�ł��B(�C�G�Y�X��̏��Ȏj���ɂ��A�I�X�}���E�g���R�R�Ƃ̍Đ�̂��߂ɁA���{���ɗb���R�����߂ēn�������̂��A�����n�l�R�m�c�̎�ړI�������悤�ł��B) 1560�N(�i�\3�N)�����Ԃ̐킢�ł́A�x�{�̍���`���R�O���ɑ��āA���F��ɗ��Ă�����D�c�M���R�͎O��ł��B�퍑����̍����R�����ێ��ł��鐔�́A���̍��̔_�n�ʐςɔ�Ⴕ�܂��B�ł�����A�_�n�ʐς������D�c�M���R�̕��́A���R����R�������Ȃ��킯�ł��B�ł�����A�R�l�̏��Ȃ��㏬�D�c�M���R�̐�@�́A������ł͂Ȃ��A�Q������E��P��Ɍ�����킯�ł��B ���ꂪ�A1575�N(�V��3�N)�̒��̐�ł́A���c�����R�ꖜ�ɑ��āA�D�c�M���E����ƍN�A���R�͓ł��B�X�ɁA�D�c�M���R�ɂ́A���Ƃ��O��Ƃ�������S�C���������̂ł��B�����āA���̒��̐�ł̐݊y�����̍U�h��ł́A���{���̐퓬�ł͒������n�h����\�z���Ă���̂ł��B(1568�N�D�c�M���������B�{�\���߂��ɓ�؎������B1569�N�D�c�M�����A�C�G�Y�X��鋳�t���C�X�E�t���C�X�ɉy��������A�M���R�̌R�c�K�́A�R���A��p�����ς��Ă���悤�ł��B) �S�C��͕킷��̂͊ȒP�ł��B�������A���̏e�ŋʂ˂����邽�߂́u�Ζ�v�͂ǂ̂悤�ɂ��Ē��B�����̂ł��傤���B�Ζ�̌����̂ЂƂł���u�ɐv�́A���{���ł͖w��ǎY�o����Ă��Ȃ��̂ł��B�퍑����̏ɐ́A�X�y�C�����N��������Ẵ`�����A��ȎY�o���ł������̂ł��B(�퍑����̏ɐ������[�g�͓�B�ЂƂ́A�}�J�I���ɐ������s�E��؎��̃C�G�Y�X��[�g�B�ӂ��߂́A��C����q�����I�B(�G��S�C�O�̋��_)�����s�E�{�\���̓��Î��E���������[�g�B�{�\���́u���v�ƌ��������A�x����点���u�o��v�B�D�c�M���́A�{�\����苒���A���������ł̏h�����Ƃ����B�{�\���̕ς́A����ׂ����ċN�������B�D�c�M���́A�Ζ�ɂ̏�ŏh�����Ă����̂�����B) �Ζ�����A�����ƉΖ�U���A�����ĉΓ�ɉ����A�e�ۂ�I�ɂ߂����Ĕ��˂���Z�p�K���́A�����Ԃ̌R���P�����K�v�ł��B�D�c�M���R�́A���ӂ̍��X�ɑ��ċx�݂Ȃ��U�������Ă����̂ł��B�ł́A�D�c�M���R�̎O��Ƃ�������S�C���̎ˌ��P���́A�����ŒN���w�������̂ł��傤���B���̋L�^���Ȃ��̂́A�ˌ��Z�p���������b���R�c�̓n�����l�����܂��B �����Ԃ̐킢����A���̏\�ܔN�Ԃɂ�����D�c�M���R�c�̌����Ɛ��m�R����p�̕ϖe�U��́A�ǂ̂悤�ɐ����ł���̂ł��傤���B ����1560�N����1575�N��15�N�Ԃɂ́A�퍑�喼�Ƃ̐퓬�̑��ɁA�@���R�c�Ƃ̐킢���������̂ł��B �퍑�喼�Ƃ̐킢�́A�����Ԃ̐킢�̌����́A��P�U��������t���āA�Z���ԂŒ����A�����āA���̐�̓V���R�A�݊y�����̐킢�͎l���ԂقǂŌ����������̂ł��B����ɔ�ׂāA�O�́E��������Ꝅ�A�ΎR����Ƃ�����@���R�c�Ƃ̐푈�͐��N����\�N���������Ă���̂ł��B����͗��j��ǂ̂悤�ɐ����ł���̂ł��傤���B ���j���ȏ��̐����ɂ͏@���g�D�ƐD�c�M���R�Ƃ̐푈�́A���V�������f���L��|����Ƃ���_���R�c�Ƃ̃C�U�R�U���x�̂悤�ȋL�q�ł����A�D�c�M���R�͐݊y�����̐킢�ł́A���c�����R�ꖜ���l���Ԃقǂʼn�ł�����قǂ̔j��͂������Ă����̂ł��B�X�ɁA��ѓ���́u�S�C���v���������̂ł��B���̂悤�ȋ��͌R�c�Ƃ̒����푈�́A�B�̔_���R�c�ł͖����ł��傤�B�ł́A�Ꝅ�R�́A�ǂ̂悤�ȑg�D�ɂ��\������Ă����̂ł��傤���B 1570�N(���T���N)��ォ��̗����ނ��Ɩ�K��v������Ă����{�莛�Ƃ̐ΎR�\�N�푈�̏���E�O�D�O�l�O�Ƃ̐킢�B1571�N(���T1�N)���s�́u���E�s�v�o�ς��x�z�����b�R�Ă������Ƒm���F�E���B1573�N(�V��2�N)�u���v�̃l�b�g���[�N���x�z����G���ɂ��ɐ���������Ꝅ�����Ȃǂ̐푈������̂ł��B(�����̏@���푈�́A���̒�ӂɂ́A�؏�̍����݂��������Ȃ��A�u���v�Ɓu�s�v���o�ώx�z���A�֏���݂��Ēʍs�ł������b�R����_�Ƃ��镧���g�D����ł��A�D�c�M�������{�̌o�ς��x�z���邱�Ƃ��ړI�ł������̂ł��B����́A�C�G�Y�X��̍��ی��Տ��l�Ɠ����ł��B���{��̏��Ɠs�s�E���̒D��́A�D�c�M���ƃC�G�Y�X��̍��ی��Տ��l�̔ߊ肾�����̂ł��B) �����āA1570�N�Ɏn�܂�A�ї����̕���������G��O�S�C�������R����ΎR�{�莛�Ƃ̐퓬���A1580�N(�V��8�N)�܂ő����̂ł��B���̃L���X�g���S�R�ƕ����R�c�Ƃ̏\�N�@���푈�́A�퓬�����ł͌����ł����ɁA�D�c�M��������ɍu�a�̈������肢�o�āA�{�莛�ɕ������������Ă���ї��P���Ƙa�c�̌���i��肷��i�K�ŁA�D�c�M���̓ˑR�̘a�c�����̎��ނɂ��A�{�莛���͕����H���̉������ї�����蓾���Ȃ����߁A�틵�͐D�c�M���R�ɗL���ɂ����߂��A1579�N12��(�V��7�N)�{�莛�ƐD�c�M���͍u�a�𐬗�������̂ł��B �����āA�D�c�M���ɂ����̖{�莛�͏Ă������A���͂܂��ɐD�c�M���̎x�z�����O�ƂȂ�̂ł��B�����āA�D�c�M�����A�Ō�̎d�グ�ł���G��O�c�}���x������{�莛���@�̒��j���@����ł��邽�߂ɁA�u�{�\���v�Ő������Ă��鎞�A1582�N�{�\�����D�c�M���Ɣ��ɔ�������̂ł��B�����āA�{�\���߂��̓�؎��ɂāA������������Ă����̂��A�C�G�Y�X��̍��ی��Տ��l�t���C�X�ł��B �ł́A�D�c�M���́A�N�ɂ�蔚�E���ꂽ�̂ł��傤���B ���j���ȏ��ɂ��A1582�N�{�\���̕ς́A���q���G�̖d���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���悤�ł��B�������A�ꐡ���ׂ�A���q���G�����^�킵���҂�����悤�ł��B���̃q���g�́A�u�G�͖{�\���v�ł��B 1582�N(�V���\�N)�D�c�M�����A�{�\���Ŗ��q���G�̈ꖜ�O��̌R�c�Ɏ��͂܂�A�Q���݂��P��ꓬ���s���̂��@�m���āA�����������Q��������̊�́A���߂̑��c����́u�M�����L�v�ɂ����荞�݂������ł��B�������A���́u�M�����L�v�́A�{���Ɏj��������Ă���̂ł��傤���B �u�M�����L�v�́A�D�c�M���̑��ߑ��c����(���������イ����)�����X�������߂����L����ɁA�L�b�G�g�̍Z�{�̂��ƂɌ��ꂽ�����̂悤�ł��B�ł�����A�×���肻�̋L�q���e�ɑ��ċ^��𓊂�������l�����Ȃ�����܂���B�������A�{�\���̕ό�̖L�b�G�g�ɂ���g���߂╰���Ȃǂɂ��A�u�{�\���̈ÎE�v��m�邽�߂̐M�������j���́A�u�M�����L�v�ȊO�ɂ͑��݂��Ă��Ȃ��̂�����̂悤�ł��B ���j���ꍇ�A���̎j���ƂȂ���̂��A��Ղ�Õ����ł��B��Ղ��i�ɂ͌��t������܂���B�������A�Õ����͂��ꎩ�g�������ł���̂ł��B�����̌Õ����̑����̂��̂́A�Ў��ɕۑ�����A�����āA���Ƃɂ����L�Ƃ��ĕۑ�����Ă���̂ł��B���̗��R�Ƃ��āA�Ў��́A�؏�Ȃǂ̍����݂��̋L�^����ؗp���ނ̎j����ۑ�����킯�ł��B �ł́A���́A�����̌��Ƃ͓��L��t�����̂ł��傤���B����́A��������̔�b�R������A�����ōs���o�Z�Ȃǂ̓q���ɂ��؏�̎؋������Ƃɓ��ݓ|����Ȃ��悤�ɁA�u�����v�W�v�ȂǂŒn���v�z��z�����A�؋���Ԃ��Ȃ��҂�E�\�����҂��������߂ɔ��������A�E�\���̐���u腖��l�v�ɂ��̂ł��B���̎v�z�ɂ��ƁA�L���X�g����^�����u腖��l�ɂ��Ō�̐R���v�̎��A���̂ЂƂ̐��O�̍s���ɂ��A�n�����Ɋy���ɐU�蕪������̂ł��B �ł�����A�n���v�z�m�ɂ����荞�܂ꂽ���ƒB�͎���A�n���ł͂Ȃ��A�Ɋy�s����]�ނ��߁A���X�́u�ǂ��s�������v���L�^���A�Ō�̐R���̓��ɔ�����킯�ł��B���ꂪ�A�������ォ��̌��Ɠ��L�̎n�܂�ł��B�ł�����A���L�ɂ��鎖�����S�Đ^���Ƃ͌���܂���B����́A�ЂƂ́u�E�\�v�����铮��������ł��B �{�\���̕ς��A���j���ȏ��̋L�q�̂悤�ł͂Ȃ��Ƌ^�����Ȍ����Ƃ��ẮA�O����܂��B ��ڂ́A��������̎�ړI�͓G���̎����邱�Ƃł��B�Ď��⍜�ł���͎�ł��B�������A�M���̏Ď��̂����݂��Ȃ��̂ł��B(�ʏ�Ђɂ�荜���S�ĊD�ɂȂ邱�Ƃ͋^��B������u�ɂ��ď��ł���̂́A���炩�̉��w�I�R�Ă���������܂��B) ��ڂ́A���̖��q���G�́A�ꖜ�O��̌R�c���A���U���Ė��o���ɂ͌������ɁA����قǑ傫�Ȍ����ł͂Ȃ��{�\�������ɏW���������̂��B(�����V����{�C�Ŏ��̂ł���A�D�c�M���̑��q�̂��閭�o���������ɏP�����Ƃ͏펯�B���o���̖�Ԍ�̏P���͉��̂��B) �O�ڂ́A���̖L�b�G�g�R�́A�ї��R�ƈ���ŋx����𐬗������A�ےÂɎl����ɖ߂ꂽ�̂��B(�퓬��Ԃ̖ї��R�ƈ���ł̋x��͕s�\�B���̐ےËA�Ҏ��ŁA�̑�R�c�̐H�����B�����O�ɍs���Ă����̂��B) �u�{�\���̕ρv�Ɋւ��Ă̏؋��ɋ^�₪�����ɁA�X�ɐD�c�M���R�̍ō������B�ɂ��^�₪����̂ł��B���̍ō������B�Ƃ́A�ēc���ƁA����v�A���q���G�A�H�ďG�g�ł��B�����̕����ɋ��ʂ��邱�Ƃ́A�����̐퍑�喼�Ɠ����ɁA�S���o���s�ڂł���̂ł��B(�L�b�G�g�������āA���͒��N���ɗ��j��ɏo���B) �퍑����Ƃ͂����A�D�c�M���R�c�̍ō��ӔC�Ҏl�l�Ƃ��q�����̕����ł͂Ȃ��A���r�̗p�ł������o���s�ڂł���̂ł��B�u�N�v���A�o���s���̐l�����R�l�Ƃ��ĐD�c�M���Ɉ��������̂ł��傤���B �����҂Ƃ��čl������̂́A�C�G�Y�X��̋��s�S�����@�t�A���V�����h���E���@���j���[�m�ł��B(�C�G�Y�X��鋳�t�I���K���e�B�[�m���A�ɐ��T�R���ֈꐭ�ɏ\���R�̖��ᐹ���n�l�R�m�c�̃W���o���j�E�����e�B�X�u���{���F�R�ȏ����v���R���ږ�Ƃ��Ĉ���������Ⴊ����B)�܂�A�D�c�M���̍ō������̎l�l�́A��������C�G�Y�X��̗b���Ƃ��Ă̓n�����l�����܂��B����́A�{�\���̕ς̈�N�O�A1581�N(�V��9�N)�D�c�M���́A�V��������֎����邽�߂ɁA���̓s�ŁA���{���n�߂Ă̌R���p���[�h(�ܕS���̔n����)���A�D�c�M���R�̉e�̃X�|���T�[�ł���C�G�Y�X��̃��@���j���[�m����o�Ƃ��čs���Ă�������ł��B ���q���G�́A�\�O�㎺�����R�����`�P�̎���o�c(�`��)���O�D�O�l�O�ɂ�苞�s����Ǖ����ꌳ�����Ɛb�𗊂�A�e�n�𗬘Q���Ă��鎞�A�o�c(��̑����`��)�̐b���ƂȂ����̂ł��B����ȑO�̌o���͕s�ڂł��B�����āA���q���G���A�����`�����㗌�����邽�߁A�D�c�M���Ɍ㌩�l�̈˗����肢�o�����A�D�c�M���R�ɂ��̗p���ꂽ�̂ł��B�܂�A���q���G�́A��l�̎�Ɏd���Ă����̂ł��B ���q���G�̖{���̎�́A�D�c�M���ł͂Ȃ��A�����`��(1568�N�`1573�N�������{�łсA������Ǖ������B�ї������o�b�N�ɏ㗌��d��B)�������̂ł��B�D�c�M���Ɏd�����̂́A�����`����D�c�M���̌R���͂𗘗p���ď㗌�����邽�߂������̂ł��B���̂��Ƃɂ��A���q���G���u�V���l�v��]��ł����A�Ƃ��鍪���͔���܂��B����ł́A�N���D�c�M���ÎE�̐^�Ɛl�Ȃ̂ł��傤���B �^����m��҂��A�㐢�̐l�ɒm�点���i�Ƃ��āA���̏����̒��ɈÍ��Ƃ��Ďc�����Ƃ��A�×�����s���Ă��܂��B�Ⴆ�A�V���ɂ���p���X���̃��n�l�ɂ��A���r���̐�����₂�m�点��u���n�l�َ̖��^�v�́u666�̓�v�A�����āA��������̑��l���ɂ��A����������������ɑn�삵���u���{���I�v(720�N)���A��������ɍX�Ɋ����V�c�ɂ��A�h��E�V���n�����E���A�S�ω����L���ɓ��{���I����₂��ꂽ���Ƃ�m�点�邽�߂́u�Î��L�v(812�N)�Ȃǂł��B �ł́A�L�b�G�g�ɂ��u�{�\���̕ρv�̎j���B���̎����ɁA�N���A���̎�d�҂��ǂ̂悤�ɂ��Č㐢�̐l�ɒm�点�悤�Ƃ����̂ł��傤���B �L�b�G�g�́A���c����ɖ����āu�M�����L�v��n�삳���鑼�ɁA�u�{�\���̕ρv�̎l������ɁA�R�n�̎�m�呺�R��(�����ނ�䂤��)�ɁA�u�ҔC�ގ��L�v(����Ƃ���������)�̋L�^�����������Ă���̂ł��B�ҔC�Ƃ́A�D�c�M�����^�������ŁA���q���G�́A�ҔC������Ƃ������Ă����̂ł��B �L�b�G�g���A�u���q�ގ��L�v�Ƃ����ɁA�u�ҔC�ގ��L�v�Ƃ����Ӗ��́A���q���G���D�c�M���̒��b�ł��������Ƃ��u�����v����Ӑ}���~�G�~�G�ł��B�܂�A���b���Ɉ��l�u���q���G�v�̃C���[�W�n��ł��B�����āA���q���G�̓V�����̈ӎu�����鍪���Ƃ��āA�{�\���̕ς̑O���ɍs��ꂽ�ƌ����Ă���A�̂̉�ł̖��q���G�̉́A�u���͍��V���m��܌����ȁv���A���̏؋��Ƃ��Ă���̂ł��B��(�Ƃ�)�́A���q���̖{���y��(�Ƃ�)���Ɂu�������v���̂ƌ����Ă��܂��B ���́u�M�����L�v�Ɓu�ҔC�ގ��L�v�Ƃɂ��A�㐢�̐l�̗��j�I�펯�Ƃ��āu�D�c�M���E���́A���q���G�v�ł���A�ƐM�����Ă���̂ł��B�������A�D�c�M���̉Ɛb���c����́u�M�����L�v�̈�߁A���q���G�R�ꖜ�O�炪�V�m�₩��B�|�ɍ��������������A���q���G���������u�䂪�G�͖{�\���ɂ���v�A���Ӗ��������Ă���̂ł��B�]���̉��߂ł́A���q���G�R�̓G�́A�u�{�\���ɐ������Ă���D�c�M���v�ł���A�ƌ������Ƃł��B �������A�u�G�͖{�\���v���u�D�c�M���̐������Ă���{�\���v�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�u�{�\���v�����L���Ă����҂��{���́u�G�v�ł���Ƃ���ƁA�]���̈Ӗ��Ƃ͂܂���������Ă���̂ł��B ���@�@�ɂ�茚�����ꂽ�Ԃł���{�\���́A1536�N�u�V���@�̗��v�̋��s�����푈�ɂ���b�R����̑m���ɂ��j��A���̌�A�������̋������n�̎�q���̎������ƃl�b�g���[�N�����Ԃ̂ł��B��q������̏ɐ́A�I�B���������o�R���āA���s�{�\���։^��āA�퍑�喼�ɔ��肳����Ă����̂ł��B�܂�A�{�\���́A���Î�(������)�̌n�ł������킯�ł��B���̖{�\�����A1568�N(�i�\11�N)�����`����ē��������D�c�M�����ێ悵���̂ł��B�����āA�C�G�Y�X��ɋ��ł̕z���������A���̋߂��ɎO�K���Ă̓�؎��̌����������̂ł��B�����āA�D�c�M���́A1570�N�ߍ]�o��̐킢�Ő�䒷���ɏ�������̂ł��B ���̌�A�D�c�M���R�̌R�g���i�݁A���m����p�̉��i���ɂ��A�ߋE���Ӎ��͐D�c�M���̌R��ɉ������̂ł��B�V����_���镐���Ŏc��́A�D�c�M���Ɨ������������`�������������ї��������ł��B ���̖ї��U�߂��H�ďG�g�ɍs�킹�A���ɓV������O�̎��A�u�{�\���̕ρv�̑O���A�l�\�l���܂�̌��ƒB���W�߂đ咃����A�D�c�M���͖{�\���ōs�����̂ł��B�����̌��Ƃ́A�߉q���A������A������A������A����@�̋{�A��i���A�ۉƁA���؉ƁA�ȂǂȂǂł��B �߉q���Ƃ́A�������̖���ł��B���q����A�S�ϖk�𐭌��ɂ��A�s����ǂ����Ƃ��ꂽ�������́A�߉q�ƁA����ƁA�e�r�ƂȂǂɕϐg���Ă����̂ł��B ���̋߉q�Ƃ́A�{�\���̕ςŁA�s�v�c�ȍs�����N�����Ă����̂ł��B�u�{�\���̕ρv�Ƃ�����u�ÎE�v���s���Ă��܂�����ɁA�{�\���ɏW���������q���G�R�ꖜ�O��l�́A�㑱���W������܂ŁA�{�\��������߂��̏��őҋ@���Ă����̂ł��B�ꖜ�O��l�̌㑱���ړI�n�ɓ�������ɂ́A���Ȃ��Ƃ��Ԉȏ�͕K�v������ł��B ����́A���q���G�́A�D�c�M���ɂ��A���Α叫�R�̈ʂ�U�Ȃɋ��ۂ��钩����������߁A�����ɖ{�\���ɌR�c���W������悤�ɖ�������Ă����̂ł��B�������A�{�\���łٕ̈�(�����͈�u�̖җ�̂��߂Ɍ��^�𗯂߂��B)�ɋC�Â������q���G�R�́A���D�c�M���Ɗm�������鑧�q�M�����������閭�o���Ɍ������̂ł��B ����Ɩ{�\���łٕ̈ς�m�����D�c�M���́A���o����茘�S�Ȍ����ł���ׂ̓���䏊�ɔ���̂ł��B����䏊�ɗ��ĘU����A���R���삯����܂Ŏ����������邱�Ƃ��\������ł��B�������A����䏊�͕��C�Ȃ����q���G�R�ɂ��ח����Ă��܂��̂ł��B����́A����䏊�ɗאڂ���߉q�O�v�@�̉�������A���q���G�R�̓S�C������Ďˌ��������Ȃ�������ł��B ���́A�߉q�O�v�́A�t���̖��q���G�R��j�~���Ȃ������̂ł��傤���B�����āA�߉q�O�v�́A���̌�A�����瓦�S���A�O�͂̓���ƍN�ɕی�����߂Ă����̂ł��B ���̋߉q�O�v�̕s�v�c�ȍs���ɏ���s�v�c���A�H�ďG�g�̕s�v�c�ȏ��i�ł��B �ї��R�Ƃ̐킢���}篋x�~���ċ삯��������̌R�c�ɂ��A1582�N�R��̍���ŁA���q���G�R����ł����H�ďG�g�́A1584�N�ő�̃��C�o������ƍN�Ə��q�E���v��̐킢�Ŕs��܂����A1584�N(�V��12�N)�]�܈ʂɏ��݁A���̌��̓��ɏ]�l�ʉ��Q�c�̌���Ă��Ƃ肻�낦�A���N��1585�N3������ʓ���b�ƂȂ�A�����āA���֔��́u�߉q�O�v�v�̗P�q(���`��̎q�B���́A���`��Ƃ����ǂ��A�o���s�ځE�G���̉H�ďG�g�����{�×��̋M��ł��铡�����̈���ƂȂꂽ�̂ł��傤���B�����ɐ퍑����̑傫�ȓ䂪�B��Ă��܂��B)�ƂȂ�A7���ɂ͐���ʂɏ������A�����ɏo���s���E�G���o�g���̊֔��ƂȂ�̂ł��B |
|
|
�������A���̕����ł́A�������m�̍ō��ʂ̐��Α叫�R�Ƃ͂Ȃ�Ȃ����߁A�X�ɏo���s���ł͓������𖼏�邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A1586�N(�V��14�N)�ɑ�����b�ƂȂ�A��a�����̑O�g�����u�`�����v�̕ʖ��u�L���v����A�u�L�b�v�̎���������킯�ł��B�L���́A�����������i��ł��邩��A�L���̐b�ł���u�L�b�v�́A���������i��ł���Ƃ̗����ł��B
�L�b�G�g(���̕���)���V�������ƁA���L�b�̕����̖���(�����n���m)����@���Ȃ��L���V�^���喼(�`���n���m)�͑G���ƕ̂܂�A�q�������ɉ������߂���̂ł��B����́A���ɁA���ƌ����̖�����q���Ƃ��ĎЉ�I�ɖ��E�����k�����q�����̍Č��ł��B�����āA1590�N�A�L�b�G�g�̍ő�̃��C�o���A�����o�g�̓���ƍN(���̌���)�́A�֓��̂ЂƂ��Z�߂ʉ͌��A���̐����鎼�n�сu�q�y�v(���ǁ��]��)�Ɉڕ������̂ł��B�����āA�����Ɍ����̂��q�����̒e���q��̈ꑰ�ł��B �ł́A���̓������̖���̋߉q�O�v�ƖL�b�G�g�̕s�v�c�ȍs���Ə��i�́A�N�ɂ��A���̂����Ȃ�ꂽ�̂ł��傤���B���̓�l���u��v�Ƃ��āA�u�{�\���̕ρv�͂ǂ̂悤�Ɍv�悳��A�����Ď��s���ꂽ�̂��𐄗����Ă݂܂��傤�B�q���g�́A�D�c�M���R�ƍs���ɂ����L���V�^���喼�́A�D�c�M���ÎE������������L�b�G�g�ƌR���s���ɍs�����͉̂��̂��A�ƌ������Ƃł��B ���{�̌Ñオ�A�I���G���g�����ł̓����E�����̌��ʂł���A�R�n������V�q�����̓��i�̉e����傢�Ɏ��悤��(�I���O�O���I�`���̐�c�����̓n���A�u���}�g�v�̃`�����N���n���̑h�䉤���A�����āA645�N���̉����������������_���F���Y���������̓n���ȂǂȂǁB)�A�����E�퍑����̓��{�́A���[���b�p����(�|���g�K���E�C�X�p�j�A)�̉e��(�퍑����ɉƖ�E�G�W�v�g���˂̑ȉ~�̈�͂��o�������B)��傢�ɎĂ����̂ł��B 1347�N����1351�N�Ԃ̑S���[���b�p�ł́A�����a(�y�X�g)�̑嗬�s�ɂ��A�l�����啝�Ɍ������A�Ȃ��ɂ͑S�ł���s�s���������قǂł��B�X�ɁA1353�N�ɂ́A������g���R�R�̃��[���b�p�N�U���n�܂�̂ł��B �l���I���[�}�鍑�̍����Ƃ��ĕz�����ꂽ���V���A��(�L���X�g��)���A�������[���b�p�ł́A���ی��Տ��l�����ی��Ղɂ��x�傷��̂ɍ��킹��悤�ɁA���̏@���I���͂債�Ă����̂ł��B ���̃��[���b�p�̕x�̊�́A�y�X�g�a��h�~����ƐM����ꂽ�u���h���v�ł��B���H�̃��[���b�p�ł́A���̕��s��h�~����u���h���v�́A�u���v�Ɠ����̉��l���������̂ł��B�������A���̍��h���̌��Y�n�̃C���h�E���A�W�A�́A�C�X���[���̏��l�B�ɂ��x�z����Ă����̂ł��B �����ɂ����āA�L���X�g���̕z���͂𗘗p���Č��Ւn���C�O�ɍL���Ă������ی��Տ��l�́A���̍��h���ړ���(���D)���邽�߂ɁA���[���V�A�嗤�̓g���R�ƃC�X���[�����͂Ɍo�ϓI�Ɏx�z����Ă��邽�߁A�吼�m�̔ޕ��ɂ��関�J��n��ڎw���̂ł��B���̌��ʂ��A1492�N�R�����u�X(�C�X�p�j�A����)�̃A�����J�嗤�ւ̓��B�ƁA1498�N���@�X�R�E�_�E�K�}(�|���g�K��)�̃C���h�q�H�̔����ł��B���̓�l�̖`����(�H)�ɂ��A�u���h���v�̌��Y�n�̃C���h�E���A�W�A�́A�A���n�ւ̎���ɓ˓����Ă����킯�ł��B����Ɏ��݂��̂��A�J�\���b�N�̋���g�D�ł��B ���ی��Տ��l�ƌ�������J�\���b�N����g�D�́A���̌��͂𗘗p���āA1500�N�L���X�g(���V���A)�~�a�Ղ𗘗p���āA���c���́u�ƍߕ��v�������̂ł��B���́u�ƍߕ��v���w������A�N�ł��S�Ă̍߂���J�������Ƃ����̂ł��B����ɑ��āA1518�N�}���`���E���^�[��95�����̎�������c���ɓ˂�����̂ł��B���ꂪ�Ύ�ƂȂ��āA�@�����v�ɔ��W���Ă����킯�ł��B���̗��ꂩ��A�J�\���b�N�����E�ނ��āu�v���e�X�^���g�v�g�D�����܂��킯�ł��B(�L���p��́u�v���p�K���_�v�́A�������甭�������B�܂�A�J�\���b�N������A�v���e�X�^���g�z�������𝈝����āA�u�E�\�b�p�`�̕z���E��`�v�Ƃ��Ĕ������ꂽ���t���u�v���p�K���_�v�Ȃ̂ł��B) ���̃v���e�X�^���g�̐��͑���ɋ��Ђ����������[�}�E�J�\���b�N����́A���̊����Ԃ��ƁA�V���ȕz���n�����߂銈����͍�����̂ł��B���̂悤�ȃJ�\���b�N����g�̉��v�ƍ��V�������i�߂��Ă��鎞�A1534�N�C�O�i�e�B�X�E�f�E�������A�t�����V�X�R�E�U�r�G���A�s�G�[���E�t�@�[�u���A�e�B�G�S�E���C�l�X�A�A�����\�E�T���������A�V�����E���h���Q�X�A�j�R���X�E�{�o�f�B�[�����̎������A�u�C�G�Y�X��v��a��������̂ł��B ���́u�C�G�Y�X��v�Ƃ́A�u�C�G�X�̓��m�v�̈Ӗ��̑��ɁA�u�C�G�X�̌R�c�v�A�u�C�G�X�̐퓬�����v�Ƃ����Ӗ�������Ă����̂ł��B���́u�C�G�Y�X��v�̃L���X�g�z�����c�̓��ِ��́A���̃o�b�N�ɁA���[�}���c�ƃ|���g�K�������̔�ƌo�ϓI�����A�X�ɍ��ی��Տ��l�g�D���x�����Ă����̂ł��B �u�C�G�Y�X��v�̖ڎw���Ƃ���́A�u���ׂĂ͂��傢�Ȃ�_�̉h���̂��߂Ɂv��W�Ԃ��A�u���ׂĂ̕z����i�͐_�̊�ɋ�����v�A�u�n��̉��v�J�\���b�N�̐_�̋������ً��k�ɍL�߂邱�Ƃł��B�������A�|���g�K�������ƍ��ی��Տ��l�̍l���Ă��鎖�Ƃ́A�����Y�����������悤�ł��B ���̃��[���b�p��������ɁA���j�Ղɂ��O�m�q�C�p�Ƒ��D�Z�p�ƒn���w���K�������|���g�K���ƃX�y�C���Ƃ́A���ꂼ��̐����悪�A�����̃|���g�K���Ɛ����̃X�y�C���ƂɈقȂ��Ă����̂��A�n�����ۂ����ߍŏI�I�Ɉ�_�ɏW�邽�߁A�����n�̋A����肪�������̂ł��B���̉����̂��߂ɁA���[�}���c�̉��A�|���g�K���ƃX�y�C���Ƃ��ً����E����ɐ������鎖�Ɓu�f�}���J�V�I���v������킯�ł��B ���[�}���c�̓|���h�K���ɁA�|���g�K���̊C�O�N���ƕ������킹�ɁA�L���X�g���z����ژ_��ŁA�V�����n�ł̌��Z����z�ꉻ���錠���Ɩf�Ղ̓Ɛ茠��^����킯�ł��B�X�y�C���́A����ɑ��Ĉًc��\�����āA1494�N�g���f�V�[�����X�������сA�x���f��������370���O�A��ʂ�o������ɁA�����S����|���g�K���́A�����āA�����S����X�y�C���̂Ƃ���̂ł��B �܂�A�\�ܐ��I���̔�L���X�g�����E�́A���[�}���c�̋��̉��ɁA�|���g�K���ƃX�y�C���́u�����\��n�v�ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B�ܘ_�A�퍑����ɓ˓����鉺����̌Q�Y�����̓��{�����A�|���g�K���̐N���x�z�n�Ƃ��āA���[�}���c�ɂ��F�߂��Ă����̂ł��B �C�G�X�̐_�̎��̉��A�C�G�Y�X��(�|���g�K��)�́A1530�N�|���y�C�苒�A1536�N�C���h�̃f�B�E��苒�����A�������C�G�Y�X��̋��_�Ƃ��A1542�N�U�r�G�����C���h�Ɍ����̂ł��B���̔N1542�N�|���g�K���l(�C�G�Y�X��鋳�t)���悹�������}�J�I�D���A���{����q���ɗ��q����̂ł��B���̌Ǔ��̎�q���́A�������̓��Î�(���Î��͓������̖���߉q�ƂƐe�ʊW)�̓�ؖ��f�Ւn�ł������̂ł��B(���j���ȏ��ł̓|���g�K���D��q���ɕY��1543�N�Ƃ��Ă���B)����́A1549�N�U�r�G���̎��������q�ւ̉����ׂł������̂ł��B �����āA�C���h��苒�����C�G�Y�X��́A1557�N�����E�����x�z���鋒�_�Ƃ��Ă�苒����̂ł��B�������A�卑�̖����̓C�G�Y�X��n���R�c�����ł͑����ł��ł��܂���B�����ŁA���̃}�J�I�����_�Ƃ��āA���A�W�A���E�����헪�����̂ł��B���̂��߂ɁA�܂���n�߂Ƃ��ē��{�����L���X�g�����ɂ��āA���̌�A���{�L���X�g���R�c��g�D���Ė����𐪕�����A�ƌ����v��ł������̂ł��B �ł́A���̂悤�Ȏ��_�ɂ��A�C�G�Y�X��́A�ǂ̂悤�ȃv���Z�X�ɂ����{�����L���X�g�������Ă������̂����l�@���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B�����āA�����ɐD�c�M���̈ÎE�҂������яオ���Ă��邱�Ƃł��傤�B �z���Ƃ́A���z(�E�\)���Z�[���X���邱�Ƃł��B�ЂƂ́A����Ƃ����ӎ����l���������_����A�s���Ƌ��|�̊����ێ����Ă��܂����̂ł��B���̕s���Ƌ��|�̊�����A����̈ӎ��ŃR���g���[���ł���Ζ��͂���܂���B�������A�����ӎ��ɂ��A�s���Ƌ��|�͍�������Ă͂��܂���B���̌��߂�Z�p�̂ЂƂ��A�u�@���v�Ƃ������z(�E�\)�ł��B�܂�A�ЂƂ͌��z(�E�\)�����ɂ͐������Ȃ������Ȃ̂ł��B �z�����Z�[���X�Ɠ����ł��邱�Ƃ́A����̍L�����_�͑S�ď@���̕z����@��^���Ă��邱�Ƃ���������ł���ł��傤�B�L���E��`�𝈝����āA�u�v���p�K���_�v�ƌ����Ă��邱�Ƃ�����[���ł���ł��傤�B ����T�[�r�X�邱�Ƃ̎�n�߂Ƃ��āA�}�[�P�e�B���O�������Ȃ��܂��B�}�[�P�e�B���O�Ƃ́A����T�[�r�X�邽�߂́u�d�|�n��v�̂��Ƃł��B���̎d�|�n����s�����߂̍ޗ��W�߂��A�s�꒲���Ƃ������Ƃł��B �C�G�Y�X��̐鋳�t���A1542�N�����D�Ŏ�q���ɓn�������̂́A���{���̎s�꒲���̂��߂������̂ł��B���̏�����ɁA1549�N�}�J�I����U�r�G�����������ɓn������킯�ł��B �}�[�P�e�B���O���_���ǂ��Ă��A���镨��T�[�r�X���A���ڋq���]�܂Ȃ����͔̂��邱�Ƃ͂ł��܂���B ���������e�Ŏx�z���铡����(���q����A���������ߋ߉q��)�́A�ޗǎ��ォ��퍑����̍��܂Ŗ��f�Ղ������Ȃ��Ă������߁A�C�G�Y�X��̃U�r�G��������C���h�▾���̕�(�e�Əɐ�)��T�[�r�X(�L���X�g��)�ɐG���L���Ȃ������̂ł��B���X�������́A�h�䉤����|����645�N����u�C�G�Y�X��̂悤�ȑg�D�v�ł����̂ŁA�C�G�Y�X��̕z���헪�ɂ͏��Ȃ������̂ł��B���̏؋��ɁA�C�G�Y�X����S�R�ł���L�b�G�g�R���A1587�N(�V��15�N)��B�ōŌ�ɓ������̂����ÌR�������̂ł��B ����@���T�[�r�X�����߂�ЂƂ́A�n�R�l���a��҂̂悤�ł��B �C�G�Y�X��́A��̒n�������@�Ƃ��āA��t��h�����A��ҋ~�ς��s���A�V���p����āA�����ĕa�@��ݗ����A������z�����_�Ƃ��āA���ۏ��l����������A�w�Z��ݗ����Č��n�T���҂̎q�����]���A���̒�����D�G�Ȏ҂�I�яo���A�z���̌�p�҂Ƃ��Ĉ琬���Ă����킯�ł��B �C�G�Y�X��C���h�ł̕z�����Z���Ԃł����Ȃ�ꂽ�����̂ЂƂ́A�C���h�̃J�[�X�g���x�̂������ł��B�J�[�X�g�̍ŏ㋉�K�w����荞��ł��܂��A���̉��̃J�[�X�g�́A��J�[�X�g�ɖ���R�ɂȂт�����ł��B �C�G�Y�X��́A�C���h�N���̂��߂ɁA�J�[�X�g�v�z�ׂ����Ă����̂ł��B���̃J�[�X�g�v�z���A���{���ɂ����݂��Ă���̂��s�꒲���Œm��̂ł��B�����āA���̃J�[�X�g�v�z����敧���Ɏ�荞�܂�Ă��邱�Ƃ��m��̂ł��B �C�G�Y�X��鋳�t(���l)�̃t���C�X�́A�p���C��(�^�~����ŃJ�[�X�g�v�z�̕s�G�G���̂���)����{���ł́u�G�^�v�ƔF�����A�u�G�^�v�́u�͌��ҁv�Ƃ��Ă�A���y�A���X�A������(�|�H�E�l�A�痘�x�̒����Ɗ֘A)�A���@�A���i�@�t(�t���C�X�̏��胍�����\���ւ̑O�E��)�Ȃǂ̐E�Ƃɏ]�����āA�̐����獷�ʂ������Ă��邱�Ƃ�m��̂ł��B�����āA���̑̐����獷�ʂ��Ă���҂�T���o���̂ł��B���ꂪ�A��B����̑呺����(�o���g�����I)�Ƌ�B�啪�̑�F�@��(�t�����V�X�R)�ł��B���̗������A�����̏o�����s���Ȃ̂ł��B(�L��ɂ�1541�N�|���g�K���D���q) �C�G�Y�X��́A���̗���(����E�L��)���o�ϓI�ɔ敾���Ă��邱�Ƃグ�A�}�J�I���玝�����i�X���C�O�ǂ��U�����̂ł��B����́A���{���̎s�꒲���ɂ��A���{�l�͕��i���Ďn�߂čs�����N�����A�Ƃ������Ƃ�m��������ł��B�܂�A���{���ł́A���������̕��i��^���Ȃ��ƁA�������Ȃ����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B �C�G�Y�X��̑��蕨�ɑ��āA�����̓|���g�K���D�̖����\�z����킯�ł��B���̂��Ƃɂ��A�|���g�K���D�̌��Ճ��[�g���A�|���g�K�����C���h�E�S�A�������E�}�J�I�����{���E����E�L��ƌq����킯�ł��B�������A���������̓��{���̌o�ϒ��S�n�̑��͏�y�^�@�R�ɂ��x�z����A�����āA�����̒��S�n�̋��s�͔�b�R����R�ɂ��x�z����Ă���킯�ł��B �����R�c���x�z����s�N�U���邽�߂ɁA���Ȃ��n�����߂邱�ƂɂȂ�̂ł��B���̌�₪�A��ƈɐ��ł��B �C���h�ɋ��_���m�ۂ����C�G�Y�X��́A�C���h�Nj撷�ł��������@���A�[�m���A���@�t�ƂȂ��ē��{��������ɓ������āA�s�꒲������ɕz���헪(�|���g�K�������ɂƂ��Ă͐A���n���헪)�����̂ł��B���{�N���̃}�[�P�e�B���O�Ƃ��āA���{���̏d�v���_���O�n��Ƃ���̂ł��B ���n��̉��n��̒�����A�}�J�I�f�Ղ̕⋋��n�ƃC�G�Y�X��C���m�̓��{��{����n�Ƃ��邽�߂ɁA�G�Ώ@���g�D�̕����R�c����h�q���邽�߂ɌR���v�lj��Ƃ���B ���n��̖L��n��́A�C�G�Y�X��C���m�̂��߂̋���n��Ƃ��āA�R���W�I(�\������@�ւ̃Z�~�i���I�ŏC�w��A����������邽�߂̎{��)�ƏC���@(�C���m�Ƃ��Ă̓K�������ɂ߂�{��)�����݂��A�}�J�I����s�ւ̒��p��n�Ƃ���B ��O�̓s�n��́A���{���_�I�ɓ������Ă���V�c�ƌR���I�ɓ������Ă��鏫�R���L���X�g���ɉ��@���邽�߂ɁA�ؗ�Ȃ鋳���s�Ɍ��݂��A�L���X�g���̉ؗ�Ȃ鋳�T�V����s�Ŕ�I����B����ɂ��A�V�c�Ə��R���L���X�g�҂ƂȂ�A���{���̓L���X�g�������ƂȂ�B ���̂悤�ȖȖ��ȕz���헪�Ɋ�Â��ăC�G�Y�X��́A���{���ɃL���X�g����z��(�N��)���邽�߂ɖK��Ă����̂ł��B�������A���j���ȏ��ł́A�|���g�K���D�́u�Y���v�Ƃ��A�C�G�Y�X��u�ӂ��v�Ɠ��{�Ɍ��ꂽ�ƋL�q���Ă���͉̂��̂ł��傤���B ���n��A���n��̊�n���m�ۂ����C�G�Y�X��́A��O�n��́u�s�v�ɐN�U���邽�߂ɁA���̏㗤�n���́u��v���s�꒲������킯�ł��B �u��v�̖��̗R���́A�ےÍ��Ƙa�Ƃ̋��E�ɂ���Ƃ��납��ł��B�ޗǎ��ォ��A�F�ɂ̐������(�C�G�Y�X��ɓ��s���鍑�ی��Տ��l���F�ɂ̐���E��̒D�悪�ړI)�̂��߁A�ےÂ̓�g�ƋI�B�̍��ی��Ս`�����������߂ɓ��̖ڂ��݂Ȃ������u��v�ɂ��A�������㖖���́u���m�̗��v�ƁA���ł̈���@�R�Ɩ@�؏@�R�Ƃ̐퓬�A�����āA�@�؏@�Ɣ�b�R�Ƃ̏@�_�R���̉ʂẮu�@���푈�v�Ɍ��C���h�����s�̒m���l�⍋���Ȃǂ��A���������W�܂��Ă����̂ł��B����́A�u��v�́A�O�G��h���x����点���v�Ǔs�s�ł���������ł��B�����āA�����̓s�̗��ɂ��A��g��I�B�̖�������A�����D���u��v�����Ս`�Ƃ�������ł��B�X�ɁA�O�D�O�l�O�ɂ��R���I�ی���A���R�s�s�u��v���A�o�ς̔��Ƃ��Ă����̂ł��B �퍑����ɁA���̂悤�ȎЉ��ɂ��A�u��v�͈�ی��Փs�s�ƂȂ����̂ł��B�o�ϓI�ɗ]�T�����鏈�ɂ͕����̉��炫�܂��B�q���̈��ł������u���̂݁E�����v���A������ŁA�痘�x�ɂ��u�����v�ɂȂ����̂́A������������炳�ꂽ���Ȓ������i�ɂ��̂ł��B���́u����v���A�D�c�M���̖��𗎂Ƃ��u����v�ł��������Ƃ́A1582�N�܂ő҂��Ȃ���Ȃ�܂���B(�퍑����̒���́A���q����A�䉶�ƕ���̂��߂ɗ^����y�n�����q�����̖��{�ɂ͂Ȃ��Ȃ������߁A�q�d�҂��u����v�́A�y�n���������Ȃ��̂ł���ƍ��荞���Ƃɂ��A�y�n�������l������̂ƂȂ��Ă����B) �痘�x���J�������u�����v�́A�L���X�g���̐ԃu�h�E���̐��t������݂���V����^�������̂ƌ����Ă��܂��B���ɓY���邨�َq���p���̖����ł��B�������A���̃L���X�g���̐��t�V�����A�~�g�����̑��z�̃V���{���������A���z�̍Đ�������ēj�������̌�(�ԂԂǂ���)�Ɠ�(�p��)��ۂ邱�Ƃɂ��A���g�̍Đ����肤�V����^�������̂Ȃ̂ł��B �痘�x���A�L���X�g���̋V����^�����̂��A�~�g�����̋V����^�����̂��͕�����܂��A�痘�x�̎��ӂɂ́A���z�_�~�g�����������嗤�ŕϐg�����A�u�i���v��M����`������̑G���Z�p�W�c�u�q���v�̑��݂���������܂��B���̈��Ƃ��āA�痘�x���J�������ƌ�����A�O��̐�[����ɋȂ���`��́u��⤁v������܂��B��⤂́A�N�ł�������̂ł͂Ȃ��A�q�����̒e���q�傪�x�z����u������v�̌���E�l�łȂ���A���Ƒg�����d��u�����v�ɂ��d�u��������Ă��܂��܂��B �X�ɁA�u��v�ł́A�����ɃC�W�����Ă����i����M�����`������̑������A�L���V�^���ɉ��@���Ă���̂ł��B��˂̎R���ɕ邷�����\��Z�p�҂̍��R�E�߂��L���V�^���ƂȂ�A���̍��R�E�߃W���X�g�́A�痘�x�́u�����̒�q�v�ƂȂ��Ă���̂ł��B�������{�\�O�㏫�R�����`�P���A�O�D�O�l�O�Ɣ��ɏP�������i�v�G���A�痘�x�̒������O�ł������̂ł��B�u��сE���сv�Ƃ͈قȂ�A�u���ȏL���v�{���c���A�ʏ̗^�l�Y�̐痘�x�Ƃ́A�u����v(�G�����`������)�̗��x�ƌ������ƂȂ̂ł��B �痘�x���G���Ɛ[���W���Ă��鍪���Ƃ��āA�痘�x�̊J�����������ɋ����e����^�������̎t���ł���u����Љ��E�����̂��傤�����v�́A�u��v�̊X�ŏ���������u��v���v�̎q���Ȃ̂ł��B�Չ�ȑ����̒����A�̂т̒������n�Ă��A�����痘�x�ɓ`�����̂́A����E�̔琻�i�������G���̎q������Љ��������̂ł��B���q����A�S�ϖk�����q�����ɁA�u���킽�v�ƃC�W����ꂽ�R�n��������̐`���E�V���n�������m������A�퍑����ɂȂ�ƁA�R�������ł���u��v�v�́A�퍑�����̎��v�ɐ��Y���ǂ����Ȃ��قǂł������̂ŁA���̍��͕͂��݂̐퍑�喼�ȏ�ł������̂ł��B���̌R�������ł���u��v�v���A�V���s�s�u��v�ň����Ă������Ƃ́A�����u��v�ɂ́A�G���Ƃ�����Z�p�ҏW�c��������炵�Ă������Ƃ��������܂��B�u��v�����R�s�s�ƌ�����̂́A�u���E�s�v���x�z���镧���g�D���玩�R�ł���Ƃ������Ƃł��B ���݂ɁA�퍑����Ɍ��ꂽ�ȁE���w�Z�p����g����E�ҏW�c�́A�`������̌R���W�c�ł��B�����o�g�̓���ƍN�����E�ҕ����̕������́A�`���̖��Ⴞ�����̂ł��B �퍑����́u��v�̒��́A�����ƒm���l�ƕ����l�ň��Ă����̂ł��B���̂悤�Ȍo�ϓI�ɗ]�T�̂���l�ɂ́A�@���͕K���i�ł͂���܂���B�����������{�̂ЂƂł��B�������A�C�G�Y�X��́A�u��v�Œ������O(��������)�ƃR���^�N�g����ꂽ���Ƃɂ��A��̕����R�c��łƁu�{�\���̈ÎE�v�Ɍ��т��Ă����킯�ł��B �C�G�Y�X��̓s�x�z�̖ړI(�z��)�ƁA�|���g�K�������ƍ��ی��Տ��l�̓s�x�z�̖ړI(�����̍��W�p���O�ŋ��E��̒D�悪�ړI)�͓����ł͂���܂���B��҂̖ړI�́A���{���̒n���I�x�z�ƌo�ϓI�x�z�ł��B���̂��߂ɂ́A�Z�\�]���ɕ�����Ă�����{������ɂ܂Ƃ߂�K�v������̂ł��B���̐����I���S�͋��s�ł��B�����āA�o�ϓI���S�͑��ł��B���̓���x�z���邱�ƂŁA���{�������S�Ɏx�z�ł���̂ł��B���̂��߂ɂ́A�e�����x�z����퍑�喼�B��łڂ��āA���ꍑ�邱�ƂƁA�����āA�u���E�s�v�A�u�؏�̍����݂��v�A�u�֏��̒ʍs�Łv�ȂǂŌo�ώx�z�����Ă��镧���g�D����ł��邱�Ƃł��B �����ŁA�C�G�Y�X��́A�퍑����̓��{�����R�����ꂵ�A�����āA�����R�c����łł��镐����T���̂ł��B �퍑����̕����̐l�����́A�]�ˎ���܂Ő����c�����퍑�����̖��Ⴊ�A��c�̌��Ђ�t���邽�ߌn�}���ɑn�삳������A�u�ߎt�ɂ��n�삳�ꂽ���̂��啔���Ȃ̂ł��B�Ȃ��ɂ́A�q�ϓI�j�������Ўj������Ɠ��L�Ȃǂ����p���đn�삵�����̂����邩������܂��A�s�s���ȏ��ނ͕����E��₂����̂��j���̉^���ł�����A�퍑�����̕����̎j�����r��������ƁA�j���̂킯��������Ȃ��Ȃ�̂�����ł��B�܂�A�퍑�����̏o�����ؖ�����u�������k�v�ɍs�������n�}�́A�]�ˎ���ɒ����҂̓s���ɂ��킹�n�삳�ꂽ���̂�����ł��B�n�}��n��u�n�}���v�Ƃ́A�B��Łu�������t�v�̈Ӗ��Ȃ̂ł��B(���炭�A���m�̗�����o�����������̑����́A���q����A�����Ƃ���ꂽ��v��������̖S�����m�c�̖���ł��傤�B) �D�c�M���̐l���������̂ЂƂł��B�D�c�M���ɂ��Ă̎j���́A����قǑ����͂Ȃ��悤�ł��B����́A�Ӑ}�I�ɒN���ɂ�蕰������Ă���悤�ł��B���ɁA�C�G�Y�X��Ƃ̊W�����́A�t���C�X�̓��{�j���Ȃ���A�u���{���܂�̊v���Ɓv�̃C���[�W���v�������т܂��B(���S�ω����E��������B���S�ω����E�k�����q����B��O�S�ω����̓���ƌ��ȗ��̍]�˂ł́A�S�ς̎�쎛�̔�b�R�������ł����D�c�M���̕]���́A�ň��������悤�ł��B�D�c�M�����A���j��r���𗁂т��̂́A�����m�푈�s���̏��a�O�\�N���̂悤�ł��B��������j���D�c�M���̋Ɛт��A���̐��{�ɂ��u�v���ƐD�c�M���v�Ƃ��ė��p���ꂽ�̂ł��B) �������A�D�c�M���̍s���́A���{�l�̊��y���ɒ����Ă��܂��B�����́A���[���b�p���R���s���͂��Ƃ��A�]���̕����Ƃ͈قȂ��b�R�S�m�Ŏ�ƕ����M�ҕ����V��j�����c���܂şr�ŁA�������[���b�p�̃L���X�g�������������Ԃ肵���悤�ɐ��e���V�c���獑�t����ꂽ����a���̍��m���Ă��E�������ƁA�L���X�g�̏\��������^���˂ă����M�k�X�̑���^�������|���ł̌Y���A�y�s�y���̎��R�o�ώv�z�Ȃǂ�����܂����A���z�Z�p�A���ɒz��ɂ��ẮA���[���b�p�̒z��v�z�������o�Ă���̂ł��B�����́A�]���̕����ƈقȂ���{�I�ł͂Ȃ��v�z�s���E�Z�p�m���́A�N�ɂ��D�c�M���ɂ����炳�ꂽ���̂Ȃ̂ł��傤���B ���{������������ߑ�ɕϊv�����̂́A1568�N�D�c�M���������`����ċ��s�ɓ�������(���N�C�G�Y�X��鋳�t�t���C�X�Ɖy��)����ƌ����Ă��܂��B����́A��𒆐S�Ƃ����鉺���̂͂���Ƃ��Ă̈��y��̒z�邪���邩��ł��B |
|
|
���ݒm���Ă���V��t�̂���u��v�̒z��́A����قnjÂ��͂���܂���B���X�u��v�Ƃ́A�u�y�v���ł߂āu���v�����A�y���ň͂����w�n�ł������킯�ł��B
�l���I���N��������n�������R�c���A�퓬���̔��ꏊ�Ƃ��ĎR����y���ς�ň͂w�n���u���N���R��v�Ƃ����킯�ł��B�ޗǎ���ɂȂ�ƁA�C�O���Ղō��𐬂����������͋������́u���v���R���ԂƂ���킯�ł��B���q����ɂȂ�ƁA���S�őωΊ��̎������́A��x����炵�y��̕ǂň͂܂ꂽ�R�̎R���ɗ��Ă���킯�ł��B���ꂪ�A�R��ł��B�₪�Ď�������ɂȂ�ƁA���n�ɂ��x�Ɉ͂܂ꂽ�y��̕��ň͂܂ꂽ����^�������S�Ȍ����������̂ł��B���ꂪ����ł��B�퍑����ɂȂ�ƁA��s�́A�ĂюR����R�[�Ɍ��݂���A�Ɨ������ȗ�(�����)��v���v���ɔz�u����̂ł��B �����āA�퍑�����ɐD�c�M���́A�Ί_�̏�Ɂu�V��t���D�c�M���̏Z���B�������u�̌�����^���������v(���̍��A�D�c�M���́A������C�G�Y�X��̐_�������݂ƐM���A�D�c�M�����u�_�v�Ƃ��Ĕq�܂����B������A�D�c�M���̈��y��́u�V��t�v�ł͂Ȃ��A�u�V��t�v�Ȃ̂ł��B���̌��ʁA�C�G�Y�X��̎j���ł́A�u�f�E�X���D�c�M���̊��삪�\����ȏ�p�����邱�Ƃ������������Ƃ��Ȃ������v�ƋL�q����̂ł��B�����āA���{�����@�t�A���V�����h���E���@���j���[�m�́A�{�\���ł̐D�c�M���̎��ɑ�������̂ł��B)�����y������݂���̂ł��B���ꂪ���Ɍ���u��v�̊T�O�ł��B���̖x����炵�A���łȓy�ǂ̕��Ɉ͂܂ꂽ�Ί_�̏�Ɍ��݂��ꂽ�u���y��v�́A�C���h�Nj撷�E���{�����@�t�A���V�����h���E���@���j���[�m���A���[���b�p�̂ǂ̏�ɂ��y�т������Ȃ����h�ȏ�Ə^�����قǂł��B �ł́A���[���b�p�����z�邵�A���[���b�p���R���g�D�����D�c�M���́A�ǂ̂悤�ɂ��ăC�G�Y�X��ƐڐG�����̂����l���Č��܂��傤�B �C�G�Y�X��́A�|���g�K�����C���h���}�J�I�����聨�L��ƐN�U���A�X�Ɂu��v�ɂ����_��݂����킯�ł��B���̎�@�́A�f�ՂƂ����Â����ł��B���̖f�Ղ́A���葤�ɑ���ȗ��v�������邽�߁A�댯��`���Ă܂ł��̑g�D�̈���ɂȂ�Ƃ���]�ނЂƂ���������킯�ł��B�������A�C�G�Y�X��ƐڐG�����߂�ЂƂ́A�����v�̂��߂����ł͂Ȃ��ЂƂ������̂ł��B����́A�̐��ɃC�W�����Ă���G���ł��B�܂�A�����`�P�̐��]�������A�O�D���Ɠ��ʂ����̒������O�Ȃǂ̑G���g�D���A��̃C�G�Y�X��ЂɏW�܂��Ă���̂ł��B ���{���̊C�O�Ƃ̐������Ճ��[�g�͌Â���A�����嗤(�O���E���[����)�����N����(�y�Q�E���[����)������(�����E�͂��E�`)����g(�Q���E���[����)���ޗǁE���s�ƌ��܂��Ă��܂����B�������A�C�G�Y�X��́A���̐������[�g���O��āA�}�J�I�����聨�L�と��Ƃ����̂ł��B����́A���̃��[�g�ɁA�s��ǂ�ꂽ���̐��̖��Ⴊ���邩��ł��B �V�����ۓs�s��̌��Ր�́A�L��ł��B�����́A��F�@�ق��x�z���鍑�ł���̂ł��B�L��ɂ̓|���g�K���D���A��q���Ƀ|���g�K���D�����q�������N����A1541�N�ɂ͗��q���Ă����̂ł��B����́A�L�オ�A�×�����A��Ɩ��f�Ղ����Ă�������ł��B �����Ɛ������Ղ����Ă��Ȃ��u�`���v�́A���̖{���̎��Ԃ͖����̏Z������ŁA���̖{���n���ܓ��ł���킯�ł��B�܂�A�`���̌��Ճ��[�g�́A�������ܓ����L�と��ƂȂ�킯�ł��B���̐�́A���{�̌o�ς̒��S�n��g�`������̒n�́A��y�^�@�R�Ɏx�z����Ă���̂ŁA�䁨�G�ꁨ�ߒq���ɐ��ƂȂ�킯�ł��B���̃��[�g���A�`���ƌ�����u�C���v�̌��Ճ��[�g�������̂ł��B���̊C�����[�g���A�C�G�Y�X��A���{���N���ɗ��p����킯�ł��B�C�G�Y�X��̎��̋��_����́A�ɐ��ł��B �ɐ��́A�ꕶ���ォ��C�O����̌��Րl���n�����Ă����̂ł��B����́A�ɐ��ɂ́A�F�ɂƓ����Ɂu�鍻�v���Y�o���Ă�������ł��B����͓��R�ŁA�F�ɂƈɐ��́A�����\������Ɉʒu���Ă��邩��ł��B�X�ɁA�ɐ��p�ɂ́A���ł��ɗǎq���ɞ��q�̎������ꒅ���悤�ɁA������獕�������ꒅ���Ƃ���Ȃ̂ł��B�ł�����A�ɐ��ɂ́A�×�����A���u�A�C���h�̓������n�����镔�������������̂ł��B �����I�̐p�\�̗��ł́A�V���n�V���V�c�R�̏o���_�́A�ɐ��������̂ł��B�ɐ��ɂ́A�鍻�����߂钆���嗤����̍��ی��Րl�����̊C�l���������Z��ł����̂ł��B���̊C�l���̃V���{���̐Ԋ��𗧂ĂāA�S�ϖS���M�����x�z����ߍ]���A�V���V�c�R���U�߂�킯�ł��B�����āA���̐킢�̏��������ӂ��ĊC�l���̐_���J�����̂��u�ɐ��_�{�v�ł��B�ɐ��_�{�́A�V���n�V���V�c�ɂ�茚�����ꂽ���̂Ȃ̂ł��B�������A��������ɂȂ�ƁA�V���̓G���S�ϖS���M���̖��ኺ���V�c���������x�z����ƁA��b�R������z������R�n������̎�����(�E���֎~�E���̋֊�)�A�����L�����N�^�[�̐������q��n�삵�Ắu�@�،o�v�z���ɂ��A���H�E���H�̕����҂̏Z�ވɐ��́u�q�ꂽ�n�v���Ȃ߂��Ă��܂��킯�ł��B�ł�����A�S�όn�V�c�͑�X�A�ɐ��_�{�ł͂Ȃ��A�F�������{���J��킯�ł��B�S�όn�V�c�ŁA�ɐ��_�{���J�����̂́A���N��̖����V�c���n�߂ł��B �\�I�ɕ���������x�z�����y���V�����Ƃ��A���̈ɐ�����̏o���ł��B ���̈ɐ��ɓn�����������ɂ́A���̐��I�S�����悤�ł��B�������n�������x���K������(�x���K�����߂Ƃ́A�C���h�̃x���K���n������Y�o����S�K�̐Ԑ���)�̃y���V�����Ƃ̕������E�d�t�e�q�ɂ��A�D�c�M���Ɠ����ɁA���{�̐_�Е��t�ɂ͓G���S�������Ă����悤�ł��B����_����_�`�ɖ���ˊ|������A1180�N�ɂ͕��d�t�͓ޗǓ��厛�̑啧�ɉ�������Ă����Ă���̂ł��B ���́A�y���V�����Ƃ́A���̂悤�ɓ��{�̐_�����������̂ł��傤���B����́A�y���V�����Ƃ̋��ł̋��_�A�_���Ƀq���g������悤�ł��B�_�������s����ƁA���̌��ƒB�́A�q��_������ƁA�s��������̂ł��B�܂�A�y���V�����Ƃ̓y�n�_�́A�������̌��ƒB�ɂ́A�q��_�ł������̂ł��B����́A�_���̐_�́A�C���h�̒�J�[�X�g�̓y���_�ł���������ł��B ��������ɁA�������̌v�炢�œn���̋�C�ɂ��A���ɓn���̃C���h�m�̋����ɂ��A�������ʂ̃J�[�X�g�v�z���A���{���Ɏ������܂�Ă����̂ł��B���̋_���Ղ̋����V�c�Ƃ́A�C���h�ł��q��_�ł������̂ł��B �������A�y���V�����Ƃ��A�������}�ɒ���S�ύc���E�S�ό��Ƃɂ͕����Ă͂��܂���B��C�ɂ�蔭�����ꂽ�u���{�����v�̐_�X�̑S�ẮA�C���h�̃o���������E�q���Y�[���̐_�X�ł��邱�Ƃ��A�y���V�����Ƃ��m���Ă�������ł��B�X�ɁA��敧���̋V���ł���A�����F���A�아�A�����A�����Ȃǂ́A��C�ɂ�薧���V���Ƃ��Ĕ������ꂽ�킯�ł����A�����̋V���́A���X�o���������E�q���Y�[������̎蕨�ł��邱�Ƃ��A�y���V�����Ƃ͒m���Ă����̂ł��B �u�ޗǂ̑啧�v�́A��C�ɂ��u����@���v�ɕϐg�����킯�ł����A���̌��̖��́u�ՏƋS�v�ŁA�C���h�ł̓o���������̌n��O�̐_�ł������̂ł��B�ł�����A�y���V�����Ƃ̕��d�t�́A�S�ϕ�����������삷�邻�̑���@���̕ՏƋS(�ޗǂ̑啧)�ɉ����ĔR�₵�Ă��܂����킯�ł��B �y���V�����Ƃ́A�����╧�t��R�₵�Ă��܂��܂������A�D�c�M���́A�S�όn���e���V�c�̍��m�g�̂܂ܔR�₵�Ă��܂����̂ł��B���ُ̈�ȕ��������́A�ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂ł��傤���B����́A�D�c�M���̑c���̕悪�A�Y��߂��̊_��(������)�ɂ��������Ƃ������̂ЂƂ̂悤�ł��B�c���̎������́A�������ۂɊώ@�ł��܂��B���炭�A�D�c�M���͗c���̍��A�ɐ����q��n�ɏZ�ޑc�����A�����҂ɃC�W�����Ă����̂��o�����Ă����̂�������܂���B�u�O�q�̍��S�܂ł��v�A�ł��B �D�c�M���́A���R���镧���m��M�҂ɂ͏�e�͂����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ɁA�n���̐g��҂ɂ͎��߂̐S���������悤�ł��B����́A�D�c�M���̈�b�Ƃ��āA��̂��тɌ�������R���̕����߂��ɂ���畆�a�������Ă���g��҂�����Ɏv���A���E�тł��̕����ɍs���A���̕��������W�߁A���̐g��҂U�ʓ|������悤�ɕ������B�ɋ��������n���A�����Ȕ����𑽂��^�����A�Ƃ������̂����邩��ł��B �畆�a�҂́A�ޗǎ���ł͓��������x�z���钆�b�_���ɂ��A���b�P�́u���߁v���q��҂Ƃ���A�ޗǍ�̕����ɉ������߂��A�����āA��������ł́A�S�όn�����V�c���x�z�����b�R����ɂ��@�،o�ɂ��A�u�����ҁv�Ƃ��āA������̕����ɉ������߂��Ă����̂ł��B �Ñ�ł́A�a�C�Ƃ͖ڂɌ�������̂ŁA���̑�\���A�畆�a�ł������킯�ł��B���̑��̕a�C�́A����ɂ������N������Ă���ƐM�����Ă����̂ł��B�ł�����A�Ñ�ł́A���P����F���́A��Ís�ׂ������̂ł��B(���݂ł��A����ގ����r�W�l�X�ɂ��Ă���ЂƂ����܂��B) �퍑������A�@�،o�ɂ�蕧���҂Ɛ�`���ꂽ�畆�a�҂͉Ƒ�����Ǖ�����A�Љ����Ǖ�����Ă����̂ł��B���̔畆�a�҂��A�����ɔ��R�����`����V���n�������m�̖���̕����ɉ������߂邱�Ƃɂ��A�q�ꕔ����n��o���Ă����̂��A�����E�S�ω����������̂ł��B���̎Љ��Ǖ����ꂽ�畆�a�҂��~���g�D���A�퍑����̓��{���Ɍ��ꂽ�̂ł��B���ꂪ�A�C�G�Y�X��ł��B �C�G�Y�X��̕z����{�헪�́A�a��ҁE�n�҂��~����������n�܂�̂ł��B1557�N��B�̑啪(�呺�@�فE�t�����V�X�R�̎x�z�n)�ɂ́A�鋳�t�A�����C�_�����ȁE�O�ȕa�@��ݗ����āA���̈�p�ɁA�����҂ƌ�����畆�a�҂̎��e�{�݂����݂��Ă��܂��B1583�N�ɂ͒���(�呺�����E�o���g�����I�̎x�z�n)�Ƀn���Z�����a�҂̂��߂̕a�@���ݗ�����Ă����̂ł��B ���̂悤�ɁA���b�_�����敧���ɃC�W�����Ă����畆�a�҂́A�C�G�Y�X��̐_(�f�E�X)��q�ނ͓̂��R�ł��傤�B�X�ɁA�����E�S�ω����ɂ܂��Ȃ��������߂ɁA���b�_�����敧���ɂ��A�u�q���v�Ƃ��ĎЉ�I�ɒǕ�����Ă����A���M���⌳���m�K���₻��ɏ�����҂��A�C�G�Y�X��̕z�������ɋ����������Ă����킯�ł��B�����̃C�G�Y�X��ҒB�́A�_�Ѓl�b�g���[�N�́u���v�����_�ɁA�u�����v�̎d��ɂ��A���Q����V�|�҂�e��E�l�Ƃ��āA���q���ォ��퍑����܂ł��A�����̎v�z���Q���Ȃ��琶�����тĂ����̂ł��B �S�����A�{�n��瑐��ɂ�蕧���g�D�������E�_�Ђ��x�z���Ă����u���E�s�v�����_�Ƃ��āA���Q����V�|�҂�e��E�l�́A�퍑�̍��X�̏������W���邱�Ƃ��A�d���̈ꕔ�������̂ł��B�����ŁA�C�G�Y�X����A�퍑�̍��X�̏��邽�߂ɁA���Q�V�|�҂ƐڐG����킯�ł��B���ꂪ�A�g��҂̗��Q���i�@�t�ł��闹�ւł��B���ւ́A�L���V�^���ɋ����ă������\���ւƂȂ�A�C�G�Y�X��̂��߂́A���������ЂƂ̏��A���W��ƂȂ�킯�ł��B�������A�C�G�Y�X��ƐڐG�����̂́A�G���Ƃ����闬�Q�V�|�҂����ł͂���܂���B�������ɕs���������ƒB�������̂ł��B �C�G�Y�X��́A���E�z��(����)�𐋍s���邽�߂ɁA�����嗤�̖����z��(����)�̑O����Ƃ��āA���������̂��߂̃C�G�Y�X����{�R��g�D���邽�߁A�퍑����̓��{����ł���l���F����킯�ł��B���̂��߂̏�͎҂Ƃ��ẮA���ƕs�����q�A�C���A�R���A���Q�V�|�ҁA���f�Վ҂Ȃǂ̔��̐����q�ł��B�����āA���f�Ւn�̒��p�n�L��̑�F�@�ق���C�G�Y�X��ɁA�����̍��ɐD�c�M���Ƃ������������������邱�Ƃ��m�炳���̂ł��B �C�G�Y�X��́A�㏬���Ȃ��班���̌R�͂ŗ��̑�R�c�ƃQ��������s���Ă���D�c�M���̗͗ʂ����ɂ߂�ƁA�C�G�Y�X����{�R�̑叫���Ƃ��āA�L���V�^���ւ̎�荞�݂ɂ�����̂ł��B���̐�p���A�V�c�_�Ƃ��ĕ��͂œ��{������X���[�K���Ƃ���u�V���z���v�̐D�c�M���ւ̍��荞�݂ƁA�B��L���V�^�����ƂƓ���������̉A�d�ɂ�鐳�e���V�c����́A���G�����́u�����d�|�v�̏���ł��B �퍑�����B�ɂ́A�S������Ȃǂ̊T�O�́A�w��ǂȂ������̂ł��B���̖���{���c���𑼍�����̐N���̌��ƁA�����Ƃ̋��E���̊g�����A�퍑�����̐킢�̎�ȖړI�������̂ł��B�l�o�c�ł��鑑���o�c�ɂ��_�Ǝ�̂̌o�ςł́A���{���ꂷ�邽�߂̕��͂͗{���Ȃ������̂ł��B�܂�A�퍑����̐킢�́A�_�Ɋ��ł͂Ȃ��A�������̏I������_�Պ��Ɏ�ɂ����Ȃ��Ă����̂ł��B �����A�_�Ǝ�̂ł͂Ȃ��A�ɐ��ł̓�ؖ��f�Ղʼn҂��A�����̐D�c�M���R�͗�O�ł����B�D�c�M���́A�u�K�v�ŁA�R�l���W�߂Ă����̂ł��B�u�K�v�ŌR�l���W�߂邽�߂̐�`�Ƃ��āA�u�D�c�R�ɂ͑K�����邼�I�v��}�ĉ����āA���K������ɂ����̂��A�D�c�M���R�̑K�̊������̂ł��B�ł�����A�D�c�M���R�́A���̐퍑�����ƈقȂ�A��N��ʂ��ē������Ƃ��ł����̂ł��B ���{���́A���X�e�햯���������N�����o�ăI���G���g�E�����嗤�Ȃǂ���n�����A���ꂼ��̕���������{���Ɍ��݂��Ă����̂ł��B���ꂼ��̓n�������́A���ꂼ��̌���ł��ꂼ��̕��������Ă����̂ł��B���̍����Ƃ��āA�퍑���ォ���O�S�N��̖����ېV�̍ŏ��̉�c�ł́A�e�ˏo�g�҂̘b�����t�����݂��ɕ�����ꂸ�A�����ł��Ȃ����߁A�M�k�ʼn�c�������قǂȂ̂ł��B(���݂ł��A�n���𗷂��āA���n�̂��N��蓯�m�̉�b�����Ȃ����Ƃ́A�N������x�͌o�����Ă���ł��傤�B) ���Ƃ̓���́A����̓��ꂩ��n�܂�̂ł��B�ł�����A�����V���{�́A���{������̂��߁A�f���t����{�Ƃ��āu�W����v������킯�ł��B �퍑����ɑS�����ꂷ�邽�߂ɂ́A�R�~�j���P�[�V�������݂��ɐۂ邽�߂ɁA����̓��ꂪ�K�v�������̂ł��B�������A���{���ł́A�����ɂȂ�܂ŁA�e�˂͂��ꂼ��̕����Ő������Ă����̂ł��B �D�c�M�����A�����S�������{���Ɍv�悵�Ă����Ȃ�A�`�̎n�c��̂悤�ɁA���t����P�ʂ̑S������v������s���Ă����͂��ł��B(���{������̂��߂̍s���́A�D�c�M���ÎE��A1582�N����̓c���̌��n���@��v�ʊ�u6��3���E191��������ԁA��Ԏl����1���A�O�\�����ꐤ�A�\�����ꔽ�A�\�����꒬�^�Ă̗ʂ�́A���e�ɓ��ꂵ���B�v��S�����ɂ������}���n����ł��B���̌��n�ɂ��A���q���ォ��̑������x�����āA�C�G�Y�X��̖]�ދߑ���{�������������m�������̂ł��B) �ł��A�D�c�M�����A�s�����Ƃ��Ă����̂́A���ꌾ��̊J������{�S���̌��n�ł͂Ȃ��A��̕ύX�ŁA��������A���z����A�Ȃ�ƃ��[���b�p�̃O���S���I��(���[���b�p�ŋI���O46�N����g�p����Ă��������E�X���O���S���I��ւ̕ύX���߂́A1582�N2��24���������̂ł��B�ƌ������Ƃ́A�l�����قǂŁA���[���b�p�̍ŐV���́A�C�G�Y�X��̏�[�g�œ��{���ɓ͂��Ă����̂ł��B���݂ɁA���{���ł́A1873�N(����6�N)�ɁA���A��瑾�z��u�O���S���I��v�ɉ��߂�ꂽ�B)�Ɋ����悤�ƁA���e���V�c�ɋ��i���Ă����̂ł��B�D�c�M���́A�C�G�Y�X��̓��{�l�G�[�W�F���g����A���{����v�z�����ł͂Ȃ��A���[���b�p�̐F�X�ȍŐV�m�������荞�܂�Ă����悤�ł��B �C�G�Y�X��́A���[�}���c�A�|���g�K�������A�����č��ی��Տ��l�B�̌o�ω����̉��ɁA���{�������ڎw�����߂ɁA�����̎㏬�����̐D�c�M���ɁA���[���b�p���R���헪�A�R�����A����(�����M�k�X�̑�)�A�e�A�Ζ�A�����Đ`���E��������̃L���V�^���喼��e�̎g�p�Ɋ��ꂽ�b���R�c(�ꎞ�I�ɁA�I�B�G��S�C�O�b���R���Q�����Ă����B��̏�y�^�@�{�莛�h�Ƃ̏\�N�������ΎR����ł́A�G��S�C�O�͔��D�c�M���R�̓G�Ύ҂Ƃ��Ċ����B)����Ă����̂ł��B����́A���{�ꂵ�A�����ăC�G�Y�X����{���R�c��g�D���āA���̕��͂ɂ��A���[�}���c�E�|���g�K�������̍ŏI�z�����̒����嗤�̖������A��̂��邽�߂������̂ł��B 1580�N���{�C�G�Y�X��́A�|���g�K�����G�����P�̎���m��̂ł��B�C�G�Y�X��́A�ً����N���̂��߂ɁA���̑g�D�^�c�����̑������A�|���g�K���������片������Ă����̂ł��B �X�ɁA�|���g�K�����G�����P�̎��́A�C�G�Y�X��Ɍ��k�������炵���̂ł��B����́A�C�X�p�j�A�̃t�F���y2�����A�|���g�K�����ʂ����C���A�C�X�p�j�A�E�|���g�K�����N��(1580�N�`1640�N)�Ƃ�������ł��B �C�X�p�j�A�͐��E�����̎��Ƃ��āA�|���g�K���̃C�G�Y�X��ɑR���āA��C�����g�D���Ă����̂ł��B���̃C�X�p�j�A�́A1565�N�t�B���b�s���𐪕����A1571�N�ɂ̓}�j���ɃC�X�p�j�A�̓��m�f�Պ�n���\�z���Ă����̂ł��B�\�Z���I�̃}�J�I�̃C�G�Y�X��(�|���g�K��)�ƃ}�j���̑�C����(�C�X�p�j�A)�́A���ɒ����嗤�ւ̕z����ڎw���ē����Ă����̂ł��B �C�G�Y�X��ɂ͂������Ԃ�����܂���B�C�G�Y�X��D�c�M���ɌR���������n�߂������Ԃ̐킢(1560�N)����{�\���̕�(1582�N)�܂ł̓�\��N�ԂɁA�E���𒆐S�ɁA�퍑�����R�c�A��b�R����R�A�����ď�y�^�@�R����ł��A�����̒��S���s�E���Ƃ̒��S���̒n���A�C�G�Y�X����S�R�̐D�c�M������̂����̂ł����A�܂��S���̎O���̈���x�z�����ɂ����Ȃ������̂ł��B �������A�V�����꒼�O�̐D�c�M���́A�c��퍑�喼�̉�łɐ�O����̂ł͂Ȃ��A�V�c���R���g���[���ł���֔��̒n�ʂ�v�����āA���ł̌R���p���[�h���s������A��̕ύX�����߂��肵�āA�V�c�Ƃ���ƒB�ƐS����������Ȃ��Ă����̂ł��B�����̐D�c�M���̍s���́A���}�ɁA�����N����i�Ƃ��ẮA�V�c����S�Ƃ��ăC�G�Y�X����{���R�̑g�D�Ґ�����ށA�C�G�Y�X��̐헪����傫���O��Ă����̂ł��B�����ŁA�C�G�Y�X��͐D�c�M���Ɍ����t���āA�D�c�M���ɑ���C�G�Y�X����{�R�叫����I�Ԃ킯�ł��B����炪�A��������̖��q���G�Ǝ��̕����̉H�ďG�g�ł��B �����āA���e���V�c�Ɛ��m�e�����A��������v������D�c�M����a�܂����v���Ă����̂ł��B����́A�֔��̒n�ʂ�v������A�X�ɁA�V�c�̍��J���̍��{�Ƃ�������×�����̗���A���[���b�p�Ŕ��߂��ꂽ����̃O���S���I��ւ̉��ς����i����Ă�������ł��B �����ɁA�C�G�Y�X��ƓV�c���Ƃ̈Öق̌v�悪���s�����̂ł��B���ꂪ�A1582�N6��2���̖{�\���̕ςł��B���̎d�|���́A�{�\���ł̑O���̒���ł��B 1587�N�L�b�G�g�́A�F���̓��Î�������������ƁA���܂ŖL�b�R���o�b�N�A�b�v���Ă����L���V�^���喼�������A���@�𔗂�A�L���X�g���̋֎~�߂߂���̂ł��B����́A�C�G�Y�X����o�ϓI�ɉ������Ă����C�X�p�j�A���A�C���O�����h�̊C�O�i�o�̂��߁A�C�O���Ռ���D���A1588�N�ɂ̓C�X�p�j�A���G�͑��́A�C���O�����h�C�R�ɉ�ł���Ă��܂��̂ł��B�C�G�Y�X��̌R���͂͏��X�ɁA�C���O�����h�ɐN�H����Ă����킯�ł��B �{�\���̕ό�A���q���G���璼�X�ɉ����̗v���������A���̐\���o���ɒf�������R�E�߃W���X�g���A�L���V�^�����Q�̑Ώێ҂������̂ł��B���̍��R�E�߃W���X�g�̒����̎t�����A�痘�x�������̂ł��B ���̃L���V�^���e���̖L�b�G�g�̕ϐS�́A�ǂ����ċN�������̂ł��傤���B���̌����̂ЂƂƂ��āA1585�N�ɉH�ďG�g���A���֔��́u�߉q�O�v�̓�q�v�ƂȂ������Ƃ��l�����܂��B�܂�A�H�ďG�g�́A���p�ҐD�c�M����d���ɂ�薳�c�ɑ���(���E)�C�G�Y�X��̖{�S��m��A�Â���V�c�𗠂ŃR���g���[�����Ă��铡�������ɐQ�Ԃ��Ă����̂ł��B ���́A�o���s���̉H�ďG�g���A���咆�̖��員�����̗���ɓ��ꂽ�̂��́A�C�G�Y�X��Ƌ߉q�O�v��V�c�Ƃ��֗^�����D�c�M���ÎE�̎�݂������Ă�������ł��傤�B�D�c�M���Ɏd�����痘�x�́A�L�b�G�g�ɂ��A����(���Q�d)�Ƃ��Ďd���Ă����̂ł��B 1591�N2��28���A�������J�������ƌ����钃�l���A�L�b�G�g���X�ɐؕ��𖽂����̂ł��B���̒��l�Ƃ́A��̐痘�x�ł��B�J�ł́A�哿���R��̘O��Ɏ��g�̖ؑ���u�����Ƃ��A����̔����Ŗ\�����Â����Ƃ������Ă��܂����A�ʂ����āA���̎j���͂ǂ��������̂ł��傤���B 1568�N�㗌�����D�c�M�����A���f�Փs�s��ɖ�K(�R����)���ۂ��ƁA��̊X�͓�ɕ������̂ł��B�ЂƂ��R��h�ŁA�����ЂƂ��a���h�ł��B���̎��Ö��̂��A�a���h�̍�̕��폤�l�̒Óc�@�y�ƍ���@�v�ł��B�������A���̓�l�́A�L���V�^���Ƃ����ʂ��Ă����̂ł��B�����āA���̓�l�́A�������O�ł��������킯�ł��B���̓`�ŁA�����E���d��痘�x�́A�D�c�M���ƒm�荇���̂ł��B���̍��̐D�c�M���́A������W�ɖv�����Ă����̂ł��B�����ŁA��̒����̎w���Ґ痘�x�́A�D�c�M���̒����Ƃ��Ďd���邱�ƂɂȂ�̂ł��B �D�c�M���́A�O�\���̖�����������W���Ă������A��i���̐�i�ƌ�����u��āv���������肵�Ă��Ȃ������̂ł��B���̖���́A�����̕��폤�l�����@�������L���Ă����̂ł��B �����ɐD�c�M���ÎE�̂��߂̎d�|������������̂ł��B����́A����ɔ[�܂�قǂ̑傫���ł����A�ꍑ���������ł���ƐM�����Ă�������́A�A���̂��ߌ��d�ɍ���ꂽ���߁A��l�ЂƂ肪�������̍���ƂȂ��Ă��܂��̂ł��B 1582�N6���ɋ��s�ɗ��Ă��������@���́A6��2���ɂ͋��s�\�肾�����̂ł��B���̂��Ƃ��A�痘�x�͐D�c�M���ɓ`�����̂ł��B �����ŁA�D�c�M���́A6��1���ɖ{�\���ŁA�����@���ɖ���u��āv�̏��n��v�����邽�߁A���Ƃ������č�̕��폤�l�B(�Ζ�̌����ɐ́A�C�G�Y�X��Ƃ̖��f�Ղł͍ő�̌��Օi)�Ƃ̎l�\�l�قǂ̒���J�Â���悷��킯�ł��B���̒���̑O���ɂ́A�����̒�����ו����{�\���ɔ�������Ă����킯�ł��B �D�c�M�����A�ǂ̂悤�Ȏ����}�������͒m��p�͂���܂���B����́A�L�b�G�g�̎j�������ƌ������g���߁A�����Č��Ƃ̓��L��₂ɂ��A�j�����B����Ă��܂�������ł��B �������Ă��邱�Ƃ́A1582�N6��2�������A�{�\���͈�u�ɂ��đ傫�ȉ��ɕ�܂�A�A��u�̂����ɑS�Ă��Ă��܂����̂ł��B�����āA���̏Ă��Ղɂ́A�D�c�M���̈⍜�̌��Ђ�������Ȃ������̂ł��B �t���R�Ɛ�`�����A�ꖜ�O��̖��q���G�R���A�{�\���ɓ��������閾���O���ɂ́A���ɖ{�\���͏Ă������Ă����̂ł��B�@ �@ |
|
| �����Ǝ� (��o��) | |
|
���Ǝ��́A�����k�ƉF�s�{�����Ƃ����A�F�s�{���j�̎q���������썑�F��S���Ƌ���̂��A���Ƃ𖼏�������ƂɎn�܂�B�u�F�s�{�n�}�v�ɂ��A�����̒�ɂ�����l���Ƃ��ď��c���̑c�ƂȂ锪�c�m�Ƃ�����A���Ǝ��͑����i�K�ɉF�s�{�����番���ꂽ�Ƃł������B
��������O��̌o���̉��d�肪���q����̐����N��(1299�`1301)�ɉz���Ɉڂ�A��k�����㏉���̌����l�N(1337)���B�T��ɔC����ꂽ�z�g�����̎����Ƃ��Đ��s�����̂����B���Ǝ��̎n�߂Ƃ����B�]�ˎ���ɐ��������Ƃ����w���Z�������L�x�́u���Ƃ̂��Ɓv�ɂ��A�u���Ƃ̐�c�́A�z���̍��̏Z�l�Ȃ�B�������������獂�j�̗^�͂ɂ��āA���ƒ�����d���Ƃ����āA�����̂���A�k���̐�ɕ�������B��ɉ�����N�[��������A�z�O�����H�S�����̋��ɉ����āA�V�c�`��̎������āA���s�ɍ����グ����B�������R�A�������܂����āA���Z���ɂ�荏��̒n�𑽐������A����蓖���ɗ���A�ΒÌS���{�̏��ɏZ����v�ƋL����A���Ǝ��͉z���̏o�g�ƂȂ��Ă���B ���������獂�j�͑����z�g���o�̂��Ƃł���A���B���Ǝ��̏���Ƃ����d��̎q�d���͍��o�ɑ����Ċ���A�V�c�`��̎����������܂Ƃ��Ĕ��Z�ɗ̒n���������B�����āA�q���͑�X���Z�ɏZ���āA�퍑�����ɔ��Z�O�l�O�̈�l�Ƃ��Đ��͂�U�������Ɩm�S���o�Ă���B �����Ǝ��̉��B�����A���� ���ĉ��B���Ǝ��ł��邪�A��q�̂悤�ɏd�肪���߂ē����������ƂɂȂ��Ă��邪�A�����̏����݂Ă��̂܂܂ɂ͎~�߂��Ȃ��悤���B ��k�������̉��B�͓쒩�̐��͂������A�k���������ƕ��͐Γ��������S�ƂȂ��ē쒩���ƑR�����B���̌�A�g�ǁE���R�̗������T��Ƃ��ĉ��B�ɔh������A���a��N(1353)�Ɏ����Ďz�g�ƌ������B�T��Ƃ��ĉ��������̂ł���B�����āA�������N(1356)�ɑ��ƌ��͒��j�̒��������ď㗌�A���N�Ɏ��������B���B�T��E�Ǝz�g���Ɠ͒������������A��̌����͏o�H�@�g�ɔC������ďo�H�̓쒩���ɑΛ������B �������N�Ɠ��Z�N�ɁA���ƕF�\�Y�Ɠ��ɉ�炪�z�g��������{��S�]�ڋ����ق��̏��s�𖽂����Ă��邱�Ƃ��w���當���x�ɂ݂��Ă���B�����炭�A���Ǝ��͉ƌ��ɏ]���ĉ��B�ɉ���A�ƌ��̎���͒����Ɏd�������̂Ǝv����B���̂悤�ɁA���Əd�肪�����l�N�Ɏz�g���ɐ����ĉ��B�Ɉڂ������Ƃ́A��`�ł���ƒf����������Ȃ��B �d��(��������)�͎�N�̌����ɑ����āA�o�H�ɉ���o�H�n���̓쒩���ɑ���H��ɂ��������B�d��͂��łɑ����̘V��ł������Ǝv���邪�A�����̎����ƂȂ��đ��R�����ɋ��Z���A���n�Ŏ��������悤���B�����āA�q���͑�X�z�g�ŏ㎁�̎������Ƃߐ퍑����Ɏ������B �d�肪�o�H�ɋ��������Ƃ́A�ꑰ�̒e���F�p�����Ƃ��p�����Ƃ����B����ɂ́A���̑F�p���a�ܔN(1349)�ɑ���������艜�B�T��z�g��(�̂��ɑ�莁�Ɖ��߂遁�ȍ~��莁�ƋL��)�̊Ď����𖽂����ĉ��������Ƃ�������B�������A������̐����N��I�ɂ��ȂÂ��Ȃ����̂ł���A���B���Ǝ��̔��˂Ɋւ��Ă͂�����̐����^����`�������̂ł��邩�͂ɂ킩�ɔ��f���������B �@��k������̌o�߂��݂邩����A���Ǝ������B�ɓ������̂́A�z�g�ƌ������B�T��Ƃ��ĉ��B�Ɉڂ������a���N(1352)�ȍ~�̂��ƂƎv����B�����āA���̎��_�ɂ�����z�g���Ǝ��Ǝ��̊Ԃɂ͂̂��̂悤�Ȏ�]�W�͂Ȃ��A�������i�ƕ����Ƃ������W�ł������ƍl������B ����莁�A�M���̏d�b ���āA�o�H�Ɉڂ����d��Ƃ��̂��Ƃ��p�����Ƃ�����F�p�̊W�ł��邪�A�e�q�̂悤�ɂ��������邪�A���̂Ƃ��낻�̊W�͕K���������m�ł͂Ȃ��̂ł���B�d�肪�����������̂����̂͐�q�������A�F�p���܂������������̂��Ă���A����l�����Ƃ��v����̂ł���B�w���썑���x�Ɍf�ڂ��ꂽ�u���Ǝ��n�}�v�ɂ́A�d��̎q�ɏd�����L�����F�p�̖��͌����Ȃ��B����ɁA���n�}�̂ǂ��ɂ��F�p�ɑ�������l�������o���Ȃ��̂ł���B����ɁA�F�p�̖����͍����ɍڂ�n�}�̐l���Ƃ͈ٗ��̊������������̂ł���B �d��ƑF�p�͎��Ǝ��̐l���Ƃ��Ĉꑰ�̊W�ł��邱�Ƃ͋^���Ȃ����A�������Ǝ��ł������Ǝv����B�w�ɒB���b�����x�ɂ��A��o�R���Ǝ��Ɋւ��āu���Ƃ͐������A���̏o���ڂȂ炸�A��c�����Y�F�p�A��a�ܔN�A�������R�̖����A���Ďi�ƂȂ�A������ċʑ��S����V��ɏZ���A�q�����ɑ��Ɛb�ƂȂ�v�ƋL����Ă���B �厡�O�N(1364)�A�k���ꑰ�̉��c���M������̌R�𗦂��Ē_��ɐi�U�����B���̂Ƃ��A���ƑF�p����莁�̖���ƂȂ��ČR�𗦂��ďo�w�A���c�R��s�莞�M�ꑰ�ܐl�̎����芙�q�Ɍ������B���̂��납�玁�Ǝ��͑�莁�ɐb�]����悤�ɂȂ�A���O�Ƃ��ɑ��̉Ɛb�Ƃ��ĔF�߂��鑶�݂ƂȂ����悤���B ���Ǝ��͎������㏉���̉��i�N��(1394�`1428)�Ɋ�o�R���{���Ƃ��A���B�T��z�g��莁�̎����Ƃ��ĈА����ւ����B���R�͈ꖼ����Ƃ������A�w�������y�L�x�Ɂu����V��͎R��ɂ���A���Ɋ�o�R�Ɖ]���v�Ƃ݂��A�w�ϐ֕��V�u�x�ɂ́u���̖��A����������V�Ɖ]���B���Ɛb���ƒe���Ȃ�҂̋��قȂ�v�Ƃ���B����ɂ���Ď��Ǝ��͊���V���Ƃ��̂��Ă����B ����莁�ɑΗ����� ���B�T��Ƃ��ďd�����Ȃ�����莁�́A���B���m�̐��h���W�߁A�����S���V�c�E�����Ȃǂ������n�Ƃ��Đ��͂��g�債���B�����āA����������퍑����ɂ����Ďu�c�E�ʑ��E�����E���c�E�I���܌S���x�z���A�퍑�喼�ւƐ������Ă������B������̉��B�ɂ́A�ɒB�E�����E�����E�ŏ�E�암�Ȃǂ̏������������݂��ɍU�h���J��Ԃ����B ���Ǝ��͑�莁�̎����ߏh�V�ł��������A��莁�ƒ��ɂ�����嗬�h�ł���}����}�ƑΗ����A���嗬�h�Ƃ��đ�莁�ɔ������邱�Ɛ���ɋy�B �V���O�N(1534)�A�u�c�S���̎�V�c���|���������V�c�E���E�����̏�����U���Ĕ������N�������B���`���͐V�c���|�����ɏo�w�������A���̂Ƃ��A���ƒ��v�͌Ð�E����E�ꔗ�̏����ƂƂ��ɐV�c���|�ɉ��S���ċ`���R�ɑR�����B�`���͓Ɨ͂Ŏ��Ԃ̉������ł����A�������ł���ɒB�e�@�̏o�n�𐿂����B�V���ܔN�A�e�@�͈ɒB�R�𗦂��Ďu�c�S�t�R��Ɏ���A����𐮂����B�����ĘZ�����{�A�����R�̗����Ă�Ð����U�����āA������ׂ�A���ō����ȉ��̏���Ă��������B �������{�ɂ́A�`���ƂƂ��ɔ����R�̍Ō�̋��_�ł����o�R��ւ̍U�����J�n�����B��o�R��ɂ͎O��]�l�������Ă�A�ɒB�E���A���R�̍U���ɒ�R�����B�킢�͒�����ƂȂ�A�㌎���{�Ɏ����Ă��ɏ�����~���A���̎�d�҂ł���V�c���|�͏o�H�ɗ������тāA���N�ɋy���̂̓����͔����R�̔s�k�ɏI������B�������A��莁�ƒ��̍����͂��̌���₦�Ȃ������B ���̌�A���v�͉Ɠ𒄎q���p�ɏ���O���ڏ�ɉB�������B�ʑ��S�y�̎��Ǝ�������p�������p�́A�O�͎���̂��ėݑ�̊�o�����p�������B��o���͓V�����N(1573)�ɗ��p���z�邵���Ƃ������邪�A���n�ɂ͐�㒼�v�̍�����ڏZ���Ă������̂ƌ����Ă���B ����莁�̓��� ���p�̐Ղ��p�����g�p(���p)�͒e�������̂����B�V���O�N�̓����Ȍ�A��莁�ƒ��ł͌��͑����������A�V���\�l�N�ɂȂ�Ƃ��ꂪ���������B���̑���������I�Ȃ��̂Ƃ����̂́A���`���̒����ł���V��c�Y���ƈ���y���Y�Ƃ̑����ł������B �Y���͋`���̒�������g�ɏW�߂Ă������A�����֑y���Y������ċ`���̒�������悤�ɂȂ����B�Y���͋`���̒����Ǝ��Ƃ̕��͂�w�i�ɖT�ᖳ�l�ȐU���������������Ƃ�����A�y���Y�̍T���߂ȑԓx���ƒ��ɂ͍D�������v���Ă����B�ʔ����Ȃ��Y���́A���ƂɋA�����y���Y�v���i�߁A���ł̂��ƂɎ�N�`�����l�ߕ���点�悤�Ƃ����B����ɁA�Y����͈ɒB���@�ɕ���𐾂������𗊂����̂ł���B ����A�Y����}�ɖ���_��ꂽ�y���Y�͐i�ނɋ����āA���ƒe���g�p�𗊂����B�͂��炸���e���́A�y���Y�������ČY����}�ƑR����`�ɂȂ����B����ɑ��āA�`���͒���ɋꗶ�������A�Y���̊Ì��ɂ̂��Ă��̐g��V��c��ɍS������Ă��܂����B�`�����蒆�̂��̂ɂ����Y����}�͎嗬�h�ƂȂ�A���ƈ�}�ׂ������Ɍ��������B ���̊ԁA���ƒe���͋`���̎��⒄�q���ی삷��Ȃǂ��A�`���ɔ��R����C�͂��炳��Ȃ������B�Ƃ��낪�A�`����f�v�����Y����}�ɂ���āA���ƒe���͂��̂܂ɂ�甽�嗬�h�Ƃ��čU�����闧��ƂȂ����B���̎��ԂɎ����Ēe���g�p�́A�Бq�i�j�𗊂�ɒB���@�ɉ������肢�o���B���@�͐�ɌY����}���片���𗊂܂ꂽ���A�`����f�v�����Y����}�͐S�ς�肵�āA���@�Ƃ̖̂ɂ��Ă����B�Y����̐g����Ȏd�ł��ɓ{����������˂Ă������@�́A�e���g�p��h���������邱�Ƃɂ��đ��o�����������B ���̂悤�ɁA�V���\�ܔN(1587)���瓯�\�Z�N�ɂ����Ă̑�莁�̓����́A�V��c�E�ɏ��̏�����l�̊m�������������̌����ł������B�������A���嗬�h�̗̑��ƂȂ����e���g�p���ɒB���@�ɋ~�������߂����ƂŁA���`�͈ɒB���Ƒ�莁�Ƃ̍���ɂ܂ŘA���g�債�Ă��܂����̂ł���B ����荇��Ɛ퍑����̏I�� �ɒB���@�́A�l�c�ɓ��i����w��Ƃ��ďo�������A���琭�i�Ɛ�c�d����叫�ɁA���R�c�}�O���R��s�ɔC���A����ɁA���]���ӍցA�c��@���A�������N�A����@�j����̂ɐڂ��鏔���ɓ����߂����B���̐��A�ꖜ����Ƃ�����R�ł������B �����͒��V�c������Ƃ��āA�K��E�t�R��ɕ���z���ĈɒB�R���}���������B�ɒB�R�̖ҍU�ɂ���Ē��V�c��͖{�ۂ��c������ƂȂ����Ƃ��A��茴��ɑ�Ⴊ�~��o���A�ˑR�̓V��̕ω��Ƒ��ɂ�銦���ɂ���ĈɒB�R�͕���P�����悤�Ƃ����B�����ɍU��͋t�]���A��萨�͓�����ɒB���ɏP���|�������B�����ցA�K��̏鏫�ł��鍕�쌎�M�ւ̐��������A�ɒB�R�͎U�X�ɔs��ď��R�c�}�O���͂��ߑ����̕�����茴���_�ɐ��߂ē��������B ���Ǝ��͊�o��邩��o���������̂̈ɒB���ƍ����邱�Ƃ��ł����A�����������Ƃ����Ƃ�����}�����ƍ���ƂȂ����B����ƂȂ������A�����ƂƂ��ɑo�����������A���Ɛ��͊�o���ɓP�������B�̂��Ɂu��荇��v�Ƃ��邱�̐킢�́A�����̑叟���ɏI������B ����ɏ��������Ƃ͂�����莁�̗͂͂��łɌ��E�ŁA���LjɒB���Ƃ̊Ԃɘa�c�����ꂽ�B�����āA�V���\���N(1590)�A�L�b�G�g�ɂ�鏬�c���̐w�ɉƒ��s���̂��ߎQ�w�ł��Ȃ�������莁�́A�L�b�G�g�̉��B�d�u�ɂ���Ėv�������B������_�@�Ƃ��Ēe���g�p�͈ɒB���Ɏd�������A�V���\��N(1591)�ɕa�v����o�R���Ǝ��̒����͖ŖS�����B����ɁA��荇���̊Ԃ��Ȃ��V���\�Z�N�Ɏ��������Ƃ�����̂�����B �]�ˎ���A�ɒB�ƒ��̎��Ǝ��́A�g�p�̑�Œf�₵�����Ǝ����ċ��������̂ł���B���Ȃ킿�A���p�̖����x�c����ɉł��Ŏ�j�B��j�̖��͈ɒB���@�̏����Ƃ��Ďd�������������ɉł��A���@�͐����Ɏ��Ƃ̖��Ղ��p�������̂ł���B�����͎��Ǝ吅�Ɖ��߂āA�����O�N(1660)�ɐ甪�S�\�̘\�ƂȂ�A�q���A�Ȃ��Ė����ېV�Ɏ������B�@ �@ |
|
| �@ | |
|
�@���߂��@�@���߂�(�ڍ�)�@�@�@�� Keyword�@�@�@�@ |
|