10/1�E10/2�E10/3�E10/4�E10/5�E10/6�E10/7�E10/8�E10/9�E10/10�E�E�E10/11�E10/12�E10/13�E10/14�E10/15�E10/16�E10/17�E10/18�E10/19�E10/20�E�E�E10/21�E10/22�E10/23�E10/24�E10/25�E10/26�E10/27�E10/28�E10/29�E10/30�E10/31�E�E�E
11/1�E11/2�E11/3�E11/4�E11/5�E11/6�E11/7�E11/8�E11/9�E11/10�E�E�E11/11�E11/12�E11/13�E11/14�E11/15�E11/16�E11/17�E11/18�E11/19�E11/20�E�E�E11/21�E11/22�E11/23�E11/24�E11/25�E11/26�E11/27�E11/28�E11/29�E11/30�E�E�E
12/1�E12/2�E12/3�E12/4�E12/5�E12/6�E12/7�E12/8�E12/9�E12/10�E�E�E12/11�E12/12�E12/13�E12/14�E12/15�E12/16�E12/17�E12/18�E12/19�E12/20�E�E�E12/21�E12/22�E12/23�E12/24�E12/25�E12/26�E12/27�E12/28�E12/29�E12/30�E12/31�E�E�E
 ��O�����E����@
��O�����E����@ �v�[�`���哝�̂́u���v�@
�v�[�`���哝�̂́u���v�@ �푈�I���̓��@�E�E�E
�@
�푈�I���̓��@�E�E�E
�@ �Ǘ����郍�V�A�@
�Ǘ����郍�V�A�@ �v�[�`���̐V����@
�v�[�`���̐V����@ �ǂ��֍s���v�[�`���哝���@
�ǂ��֍s���v�[�`���哝���@ �v�[�`���哝�̂̓~�x�x
�v�[�`���哝�̂̓~�x�x �@
�@ �@
�@
���V�A�̃v�[�`���哝�̂��N�������푈�ɂ��A���X�́u�V��v���a�������B���ꂾ���A���E�Ɍ����̃j���[�X�����ӂ�A�E�N���C�i�ł͍��̖��^��l�̐��������X���ꂽ�Ƃ������Ƃ��낤�B��ɗ��j�Ƃ����łȂ��A�����ҏW�҂��Y�܂��邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B
���L�҂�������Ȃ������u���V�X�g�v
2�����{�̐N�U�J�n����A�ߋ��ɐ��b�ɂȂ�����s�L�[�E�̒m�l�ɃI�����C���Ŏ�ނ��Ă��āA������Ȃ����t���o�Ă����B��P�x��┚��������������Ƃ������A�ޏ��́u���V�X�g�v�ƌJ��Ԃ��ă��V�A�R������B
�v�[�`���́u���ꖯ���̌Z�퍑�v�ƌ��ɂ��Ȃ���A���炩�ɍ��ʊ���������ăE�N���C�i�l�̓��̏�ɔ��e�𗎂Ƃ��Ă���B�M�҂̓��C�V�X�g(�l�퍷�ʎ�`��)�̃X���u�Ȃ܂肾�Ǝv���ď���ɔ[�����Ă����B���A��ňႤ���Ƃ�m�����B���t�ɐ_�o���g���E�Ɛl�Ƃ��Ď��i���B
���̓��V�A(���̓I�ɉp�ꔭ���Ń��V���ƌĂ�)�ƃt�@�V�X�g�̑��ꂾ�����B�ƍَ҂��d�ˍ��킹���u�v�g���[�v�Ȃǂ́A�N���~�A�������������炠�������̂́A�����܂ŃX�����O�B�ΏƓI�Ɂu���V�X�g�v�͌��n�̎�v���f�B�A�ł����p����Ă�������A�V��Ɣ��ʂł��Ȃ������B���͂⎫���ɍڂ郌�x�����낤�B
����ȋ�ŁA�푈��ނ�E�N���C�i�e���œ�̒P�ꂪ�p�o������̂�����A�����܂ꂽ���A���s�ސT�Ȃ��狻���[�����������B�����Љ�̔��f�Ȃ̂��B
�Ȃ��u���V���v�̍ō��w���҂́A�A���t�@�x�b�g26�����̈�ɂ����Ȃ��uZ�v�ɂ����\���̂悤�ȈӖ���t�^���������ł��A���j�ɖ����c�����B
������͎������ɋ�����
�V��Ƃ������A�^�����B������́u���ʌR�����v�B100���ڂ�6��3���A�N�����鑤�̃[�����X�L�[�哝�̂�����ō��������ɉ��������B
���e�͂����̐틵�ƈقȂ�B�R���f�B�[�o�D�炵���A�ʂ�����̂��錾�t�ŏ������l�X����₵�A�E�C�Â�����́B�u�S���S��v�Ƒ肵�A�푈�Ő��܂ꂽ���t�A�߂��݂̌��t�A��]�̌��t�����Љ���B
�����ĕ��ՓI�Ȍ��t�Ƃ��āu���a�v�u�����v�u�E�N���C�i�v��B�u(2014�N�̌R���������)8�N���100���ԁA�����͂���3��̂��߂ɐ���Ă���v�Ƃ��������Ă����B
�|���āA�v�[�`���́H ����������2����풼��̗p��ł���u��i�`���v�ȂǁA����x��́u����v�������B�������ɂ����������ǂ����c�c�B���������t�̗͂ł́A���ď����V�A�ƌĂꂽ�E�N���C�i�ɕ����Ă���B�E�E�E�@
���V�A�́A�E�N���C�i�ւ̌R���N�U���n�߂Ă��珉�߂ĂƂȂ��K�͂ȌR�����K���A1�����烍�V�A�ɓ���k���̓y�A���{�C�Ȃǂōs���܂��B�N�U�̉e���ŋK�͂̏k����]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ��w�E����钆�A���V�A�Ƃ��ẮA�Q�����钆�����͂��ߊe���Ƃ̘A�g���A�s�[��������̂Ƃ݂��܂��B
���V�A���h�Ȃ́A�ɓ��n��Ȃǂ�4�N�Ɉ�x�s���Ă����K�͂ȌR�����K�u�{�X�g�[�N�v��1������7���܂ł̓����ōs���܂��B
���Ƃ��́A7�����̉��K��ŗ\�肳��Ă��܂����A�k���̓y�̑𑨓��ƍ��㓇���܂�ł���ق��A���{�C��I�z�[�c�N�C�̊C��≈�݂ł��s����Ƃ��Ă��܂��B
���V�A�͖��N�A��K�͂ȌR�����K���s���Ă��܂����A�E�N���C�i�ւ̐N�U���n�߂Ă���͏��߂Ăł��B
31���́A���C�n���̉��K��ŊJ����s���A���V�A�ɉ����āA���K�ɎQ������13�����̂����A������C���h�Ȃǂ̕������s�i���܂����B
����̉��K�ɂ́A���m5���l�ȏ�̂ق��q��@140�@��͑D60�ǂ��Q������Ƃ������Ƃł����A���ƂȂǂ���̓��V�A�R�͋ɓ�������E�N���C�i�ɕ�����h�����Ă��ĉ��K�̋K�͂̏k����]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ��w�E����Ă��܂��B
�����������ŁA���V�A�Ƃ��ẮA����̉��K��ʂ��āA�e���Ƃ̌R���I�ȘA�g���������A�Η�����A�����J����{�Ȃǂ�������ƂƂ��ɁA���ۓI�ɌǗ����Ă��Ȃ��ƃA�s�[������˂炢������Ƃ݂��܂��B
8��30���ɖS���Ȃ����S���o�`���t���\�A�哝�̂́A��p���ƂȂ������V�A�̃v�[�`���哝�̂Ƃ̊ԂŁA���݂���ᔻ����悤�Ȕ������J��Ԃ��A�₽���W�������ɂȂ��Ă����B�S���o�`���t�����v�[�`���������Ŗ��剻����ނ������Ƃ����グ�����ŁA�v�[�`�����̓S���o�`���t�哝�̎���ɋN�����\�A�����ے�I�Ɍ���Ă����B
���Y�}����}�ƍق𑱂����\�A�̍ō��w���҂߂��ߋ��������Ȃ���A�S���o�`���t���͂����Ζ����`�̉��l������Ă����B2000�N�ɑ哝�̂ɏA�C�����v�[�`�����Ə��߂ĉ�k�������N8���ɂ́u���V�A�ɒ����ƐӔC�����K�v�Ƃ���v�[�`���哝�̘̂H�����x������v�Ɩ��������B
�Ƃ��낪�v�[�`�����������̍ő�̔C���ł���2��8�N��S��������Ɏɉ����肵�����Ƃ���A�ᔻ�I�Ȕ�����R�炷�悤�ɂȂ����B11�N8���ɖ����V���Ɖ�����ہA���V�A�́u(�����ƍٍ�������)�A�t���J�̂悤�ȏƂ�����v�Ɣᔻ�B�v�[�`�����ɂ��Ă��u���Ȃ瑽���̋Ɛт��c�����l���Ƃ���(���E����)�ނ����Ƃ��ł���v�Ƃ�������B15�N12���ɍēx�A�����V���Ƃ̃C���^�r���[�ɉ������Ƃ����A3���ڂ̑哝�̂ɕԂ�炢���v�[�`�����ɂ�铝�����u�l�ɂ�錠�Ў�`�I�ȓ����Ɣ�����I�X���������Ă���v�ƕ]�����B
����ŁA�v�[�`�����ɂ��S���o�`���t���̕]�����茵�����B15�N7���ɕč��̉f��ēI���o�[�E�X�g�[�����Ƃ̃C���^�r���[�ɓ����A�S���o�`���t�����\�A�̍ō��w���҂ɏA���������́u���ɕϊv���K�v�ł��邱�Ƃ́A�S���o�`���t�ɂ����̑��߂ɂ����炩�������v�Ǝw�E�B�������S���o�`���t������ӂ��u�ǂ̂悤�ȕ��@�Ŏ������ׂ����͂܂�ł킩���Ă��Ȃ������v�u�����炱�����ɐr��ȃ_���[�W��^����悤�Ȃ��Ƃ����낢��Ƃ�����v�ƍ��]�����B
�v�[�`�����ɂ��S���o�`���t�ᔻ�́A���݂̃��V�A�̃E�N���C�i�N�U�̉����̈�Ƃ�������k�吼�m���@�\(NATO)�Ɋւ�����ɂ��y�ԁB�č���1990�N�̃h�C�c�ē����O�ɂ��āA�S���o�`���t���̓��ӂ����t���悤�Ƃ��āA�����̋��Y����NATO���������g�債�Ȃ��Ɩ����Ƃ����B������90�N��㔼�ȍ~�A���́u�v�͂ق��ɂ���āA����������\�A�ɑg�ݍ��܂�Ă����o���g3���Ȃǂ����X��NATO�ɉ����������Ƃ���A���V�A���Εĕs�M���点�����ƂȂ����B
�č��́u�v�ɂ��āA�v�[�`�����̓X�g�[�����Ƃ̃C���^�r���[�Ŏ��̂悤�ɐG��Ă���B�u�͏��ʂɂ���Ă͂��Ȃ������B���̌���Ƃ����̂̓S���o�`���t�����v�u�����̐��E�ł͉��������ʂɎc���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����S���o�`���t���̓y���y������ׂ��������ŏ\�����Ɣ��f�����v�B�������A�č��̌������ՂɐM�������ʁANATO�̓����g��������Ă��܂����Ƃ̌������������B
90�N�Ƀm�[�x�����a�܂���܂����S���o�`���t���́A���ď����ō����]�����ꂽ���A�\�A�����h���Ȃ��������Ƃ�����A���V�A�����̕]���͍����Ȃ������B����ŁA���V�A�����ł̓v�[�`�������\�A�����̍��������߂����ƂȂǂ�]������Ă������A���ď�������͋����I�ȓ������@����E�N���C�i�ւ̌R���N�U�Ȃǂ�ᔻ����Ă���B�����̃R���g���X�g�͑N�����B
�������S���o�`���t���͉��Ċ���ӓ|�̐����Ƃ������킯�ł��Ȃ��B�v�[�`��������14�N�ɃE�N���C�i�암�N���~�A�������ғ�����ƁA����Ɏx����\�������B�܂��\�A�����̃��g�A�j�A�œƗ��^�����������Ȃ�ƁA���͒��������݂����ʁA���҂��o�������Ƃɂ��ᔻ���c����Ă���B
30����91�Ŏ��������~�n�C���E�S���o�`���t���\�A�哝�̂́A�鐭���V�A�A�\�A�̍ō��w���҂ɂ��܂Ƃ��⍓�ȃC���[�W���Ί�Ə_���ɁA�d���������\�A�̓��O�����]�������B��2������A�����I�߂��ɋy���������I���ɓ������B�S���o�`���t���͍��ۓI�ɏ̎^�𗁂т����A1991�N�ɒ��卑�������\�A����������{�l�Ƃ��āA��p���ƃ��V�A�ł̕]���͒Ⴂ�B
��90�N�m�[�x�����a��
�S���o�`���t����85�N3���A54�Ń\�A�̍ō��w���҃|�X�g���������Y�}���L���ɏA�C�����B�\�A�͓����A�A�t�K�j�X�^���N�U���ŁA�\�A���u���̒鍑�v�Ɣ����č��ƌR�g�������J��L���Ă����B�S���o�`���t���̏��L���A�C���A���Ɨ\�Z�̖�40�����R����ɏ[�ĂĂ����Ƃ̎w�E������B���O����̓]���ɓ��ݐ����w�i�ɂ́A�\�A�̌o�ςƎЉ�̔敾���[���ʼn��v���}�����������Ƃ�����B
�ĉ��Ƃ̘a���ɂ���������u�V�v�l�O���v�ł́A85�N�Ƀ��[�K���đ哝��(����)�ƃX�C�X�E�W���l�[�u�ŏ���k�ɗՂ݁A�j�R�k�ɓ��������B89�N11���Ɂu�x�������̕ǁv�����A��12���ɂ͕ă\��]�ɂ����̏I���錾�A90�N�̓����h�C�c����̎����ɂ��v�������B���̔N�A�m�[�x�����a�܂���܂����B
���O�ł́u�S���r�[�v�Ƃ̈��̂��蒅���A���E���ތ��2000�N��ɂ̓t�����X�̍����u�����h�̍L���ɓo�ꂵ�����Ƃ�����B
�S���o�`���t�������Y�}�̍Č���ڎw���A86�N�Ɍf�����u�y���X�g���C�J(���Ē���)�v�͓��{�ł����s��ɂȂ����B���Y�}�̈�}�ƍق�������A90�N�ɑ哝�̐������������B
�\�A�\�����������E�N���C�i��86�N�ɔ��������`�����m�[�r��(�`�F���m�u�C��)���q�͔��d���̔������̂ł́A���̂��B���Ĕ�Q���g�債�����Ƃ�ᔻ����A�u�O���X�m�X�`(�����J)�v�������������B���_�̎��R�g��▯�剻�̐��i�́A�\�A�����̃��V�A�Ŗ��剻��l���^���̋@�^��������������܂����B
�S���o�`���t�����g��91�N12���̃\�A����Ɠ����Ɏ��r���A�����I�e���͂����邱�Ƃ͂Ȃ������B�I���c�e���r��8��31���A�o�ϊw�҂̌����Ƃ��āA�u(�S���o�`���t����)�������Ȃ��Ă��\�A��10�`15�N�͑����ł����v�ƕ��B�v�[�`���哝�̂��\�A������u20���I�ő�̒n���w�I�ߌ��v�ƕ]���Ă���B
�S���o�`���t���̐��G�ŐV�����V�A�̃G���c�B������哝�̂�2007�N�Ɏ��������ۂɂ͍������c�܂ꂽ�B�^�X�ʐM�ɂ��ƁA���V�A�̑哝�̕���8��31���A�S���o�`���t���̍���������s�����ǂ����ɂ��Ắu�܂����܂��Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ��B�������s��ꂽ�ꍇ�̃v�[�`���哝�̂̎Q��ɂ��Ă�����Ƃ����B�@
���V�A�哝�̕{�́A9��3���ɉc�܂��\��̃S���o�`���t���̑��V�ɁA�v�[�`���哝�̂��Q�Ȃ��Ɩ��炩�ɂ��܂����B
���\�r�G�g�̍Ō�̎w���҂œ��������I���ɓ������~�n�C���E�S���o�`���t����8��30���A91�ŖS���Ȃ�܂����B
�S���o�`���t������\�߂����c�ɂ��܂��ƁA���V�͍���3���A���X�N���s���̎{�݂ʼnc�܂��\��ł��B
����ɂ��āA���V�A�哝�̕{�̃y�X�R�t���́A1���u�c�O�Ȃ���v�[�`���哝�̂͌����̓s���ő��V�ɎQ��ł��Ȃ��v�Əq�ׁA�v�[�`���哝�̂��S���o�`���t���̑��V�ɎQ�Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�܂��A�w����A���V�͍����Ƃ��������ɂȂ邩�ǂ������₳�ꂽ�̂ɑ��Ắu���̗v�f�͂��邾�낤�B���{�́A���V�̎�z���x������v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂܂����B
���V��O�ɁA1���A�v�[�`���哝�̂́A�S���o�`���t�������u����Ă���a�@��K��Ĉ�̂ƑΖʂ��A���c�e���r�́A�v�[�`���哝�̂��Ԃ������A�����ň�̂��e�����߂����Ƌ��̑O�ŏ\�����A�S���o�`���t���ɕʂ��������l�q�����J���܂����B
�S���o�`���t���͋ߔN�A�v�[�`�������̓�����@�������I���ƌ��O�������A�E�N���C�i�ւ̌R���N�U�ɑ��Ă��J�����Ă����Ɠ`�����Ă��܂��B
�X�y�C�����h�Ȃ�9��1���܂łɁA�E�N���C�i�֑�C���~�T�C�������^����Ɣ��\�����B�X�y�C�������̎�̕���̈����n���ɉ�����̂̓��V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U���n�܂��Ĉȍ~�A���߂āB
�����ŁA��C�p�̒e��1000���A1000�g���K�͂̃f�B�[�[�����A�l�X�ȑ��b�ԗ���~�G�p�̌R��3����������ƕ\���B�N�U���甼�N���o�߂������ƂȂǂ܂��A���V�A�̐N���ɒ�R�����a�Ǝ��R�����킢�ɒ��ރE�N���C�i���x��������Ƃ̌��ӂ��������B
�X�y�C���͑�C�̑���ɕK�v�ȃE�N���C�i�R�̌P���������Ŏ��{������j�����������B�E�N���C�i��R���m�̌P�����s���Ƃ����B
�X�y�C���͍��N4���A�e��ޖ�200�g���Ƒ��̑����i�̃E�N���C�i�ւ̏��n�\���Ă������B
�k���X�E�F�[�f���̃A���f�V������9��1���܂łɁA�E�N���C�i��10���X�E�F�[�f���E�N���[�i(��130���~)�����̌R���A�������ʂł̒lj����������{������j���������B�����͌R���x���ɏ[�Ă�Ƃ����B
��s�X�g�b�N�z�����ɃE�N���C�i�̃N���o�O�����}������̋L�҉�ŕ\�������B�u�����͗͂̍s�g���邢�͐푈�Ō����ĕς��Ă͂����Ȃ��B�E�N���C�i�x���͉�X�̐Ӗ��ł��薼�_�̍s���ł���v�Ɛ������B
�N���o�O���́A�X�E�F�[�f���ɑ��֒e(��イ����)�C�A�h����葽���̖C�e�̋��^�����߂��B���R�͖��m�Ƃ��A�E�N���C�i���q�����łȂ����B�S�̂���邽�߂��Ƌ��������B
����A�E�N���C�i���ŋ߁A�d���K�₵���W�����\���p�́A6600���ăh�������̌R�������̎��{�\�����B�p���@�̕��\���ɂ��ƁA�E�N���C�i�R�ɂ�钷�����̊Ď��\�͂�G���͂̓�����c�����U���ɓ]����h��\�͂̌���ɂȂ��蓾�鉇���Ɛ��������B
���\�̉����ɂ́A�ŐV�^�̃h���[��(���l�@)�Ȃ�2000�@���܂܂ꂽ�B�G�̕��͂̈ʒu��m������A�U���ɓ]����h���[���Ȃǂ������Ă���B
�G���͂̑O�i���Ď��Ȃǂ��鏬�^�h���[���́u�u���b�N�E�z�[�l�b�g�v850�@������錩�ʂ��B���̃h���[���͓��ɒ������ł̓����Ɍ��ʓI�Ƃ��]�����B�m���E�F�[���h�Ȃɂ��ƁA�u���b�N�E�z�[�l�b�g�͓�����Ƃ��J���������̂ŃE�N���C�i�ւ̋��^�͉p���Ƌ����Ŏ��{����B
�W�����\���p�̐挎24���̃E�N���C�i�K��̓E�N���C�i�N�U�����N2�����{�Ɏn�܂��Ĉȍ~�A3�x�ڂ������B�p���̐��ςœ��͋߂��ޔC�̗\�肾���A�E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂̓W�����\�����̎x���������]�����A�u���R�M�́v�̎��^�\�����B
��IAEA�����`�[�� �U�|���[�W�������֓��� �C���̏���
�E�N���C�i�쓌���ɂ���U�|���[�W�����q�͔��d���Ɍ������Ă���IAEA�����ی��q�͋@�ւ̐��ƃ`�[����1���A���{���Ԃ̌ߌ�8���߂��ɓ������܂����B�����̎��ӂ̒n��ł͒�����C���̏�������A�ғ����̌��q�F��1�����S���u���쓮���Ē�~����ȂǁA�ٔ������������Ă��܂��B
���E�N���C�i�̌��q�͔��d���Ёu���S���u�쓮��5���@��~�v
�E�N���C�i�쓌���̃U�|���[�W�����q�͔��d�����߂���A�E�N���C�i�̌��q�͔��d���Ёu�G�l���S�A�g���v��9��1���A�u���傤�Ăу��V�A�R�ɂ��C��������A���S���u���쓮����5���@����~�����v�Ɣ��\���A�ғ�����2��̌��q�F�̂����A1���~�����ƃz�[���y�[�W�Ŗ��炩�ɂ��܂����B����ɑ����V�A���h�Ȃ�9��1���A�u�E�N���C�i�R�������s�ׂ��s���A������1���@����400���[�g���̋�����4���̖C�e�����������B�����́A�E�N���C�i�R�̍H�암����7�ǂ̃{�[�g�ɏ���āA������D�҂��悤�Ƃ��������ނ����v�ȂǂƎ咣���A�����̎��ӂ̒n��ł͐퓬�������Ă���͗l�ł��B
�����V�A�O�� �uIAEA�Ɋ��҂���̂͋q�ϓI�Ȓ����v
���V�A�̃��u���t�O����9��1���A��s���X�N���ōu�����AIAEA�����ی��q�͋@�ւɂ��U�|���[�W�����q�͔��d���̒����ɂ��āA�u����ꂪIAEA�Ɋ��҂���̂͋q�ϓI�Ȓ������v�Ƃ����܂����B�܂��u�E�N���C�i�R�͌����Œ����s�ׂ𑱂��邪�A�厖�̂ɂȂ���Ȃ����Ƃ��肤�B���V�A��IAEA�����S�ɔC����B���ł���悤������[�u���Ƃ��Ă���v�Əq�ׁA���V�A����IAEA�̔C����W�Q���Ȃ��Ǝ咣���܂����B
��IAEA�����`�[�� �U�|���[�W�������֏o��
8��31���A�E�N���C�i�쓌���̃U�|���[�W���s�ɓ�������IAEA�����ی��q�͋@�ւ̒����`�[����9��1���A�U�|���[�W�����q�͔��d���Ɍ����ďo�����܂����B�o����O�Ɍ��n���Ԃ̌ߑO8�������A�O���b�V�����ǒ��́u�傫�ȃ��X�N�����邱�Ƃ͔c�����Ă���B�����ɂ͒B������ׂ����ɏd�v�ȔC��������v�ƋL�Ғc�ɏq�ׂ܂����B����A�U�|���[�W���B�̒m����1���A�uIAEA�̒������s����悤�A���O�ɍ��ӂ��Ă��������܂ł̃��[�g�����V�A�����C�����Ă���B�����̓��V�A�ɑ��A��������߁AIAEA�ɂ�錴���̎{�݂ւ̗��������F�߂�悤���߂�v��SNS�ɓ��e���܂����BIAEA���A�����̈��S�m�ۂɌ������������n�߂悤�Ƃ��Ă���ɂ��ւ�炸�A���ӂł͖C���������Ă���Ƃ݂��A�����������ɍs���邩�ǂ������œ_�ƂȂ��Ă��܂��B
���č��h���� IAEA�̐��ƃ`�[���̒����J�n�����}
�A�����J���h���Ȃ̃��C�_�[����31���A�E�N���C�i�쓌���̃U�|���[�W�����q�͔��d����IAEA�����ی��q�͋@�ւ̐��ƃ`�[�����������n�߂邱�Ƃ����}����Ƃ��������ŁA�u���n�ł͎U���I�ȖC���������Ă���A�����͂��ׂĂ̓����҂Ɍ����̈��S���m�ۂ���悤�v������ƂƂ��ɁAIAEA�̃`�[������Ƃ��s����悤���V�A�ɋ��߂�v�Əq�ׂ܂����B�܂��E�N���C�i�암�̐틵�ɂ��āA�u�E�N���C�i�R���w���\���B�Ŏ�O�i���A�ꕔ�ł̓��V�A�R������֑ނ������Ƃ�c�����Ă���v�Ǝw�E���܂����B����ɗ��T�A�h�C�c�����ɂ���A�����J�R�̊�n�ŁA�I�[�X�e�B�����h�����炪��Â��ăE�N���C�i�ւ̌R���x���ɂ��Ċe�������c�������J���Ɩ��炩�ɂ��A�u���E50�����ȏ�̍��h����Ƙb�������A�E�N���C�i���Ƀ��V�A�̐N�����玩������邽�߂ɕK�v�Ȏ�i����邽�߁A���������ٖ��ɘA�g���Ă����v�Əq�ׂ܂����B�܂��A�z���C�g�n�E�X�̍�����31���A�L�Ғc�ɑ��A���㐔�����ɃA�����J�Ƃ��āA�E�N���C�i�ւ̐V���ȌR���x���\����Ɩ��炩�ɂ��܂����B
��EU ���V�A�l�ւ̃r�U�����葱���ȑf����~�ō���
EU�����[���b�p�A���͊O����c���J���A�E�N���C�i�ւ̐N�U�𑱂��郍�V�A�ւ̈��͂����߂邽�߁A���V�A�l�ւ̃r�U�̔����葱�����ȑf�����邽�߂̋���̗��s���~���邱�Ƃō��ӂ��܂����B���V�A�ɂ��E�N���C�i�ւ̌R���N�U���āAEU�͂��łɃ��V�A���{�̍�����o�ϊE�̗L�͎҂Ȃǂ�EU�ɓn�q���邱�Ƃ��֎~���Ă��܂��BEU��8��31���A�`�F�R�ŊO����c���J���A���V�A�ւ̈��͂�����ɋ��߂邽�߂Ƃ��āA��ʎs�����܂߂����V�A�l�ւ̃r�U�̎�舵���ɂ��ċ��c���܂����B���̌��ʁA�r�U�̔����葱�����ȑf�����邽�߂Ƀ��V�A�ƌ�����̗��s���~���邱�Ƃō��ӂ��܂����BEU�̊O���ɂ�����{�����㋉��\�͋L�҉�ŁA�u����A�����葱���͂�茵�����A��莞�Ԃ�������悤�ɂȂ�A�V���ɔ��������r�U�͑啝�Ɍ��邾�낤�v�Əq�ׂ܂����B�R���N�U���āAEU�����V�A�̍q���Ђ̏�������֎~�������ƂȂǂ��痤�H��EU����ɓ��郍�V�A�l�������Ă��āAEU�ɂ��܂��ƁA2��24������8��22���܂ł̔��N�Ԃ�100���l�߂��ɏ��Ƃ������Ƃł��B���V�A�ƍ�����ڂ���G�X�g�j�A��t�B�������h�́A���łɌʂɊό��ړI�Ȃǂ̃��V�A�l�ɑ���r�U�̔�����啝�ɐ�������[�u�̓��������߂Ă��܂����AEU�S��ł��������[�u���Ƃ邱�Ƃɂ͐T�d�ȗ���̍�������A���ӂɂ͎���܂���ł����B
�����V�A �k���̓y����{�C�Ȃǂő�K�͂ȌR�����K
���V�A���h�Ȃ́A�ɓ��n��Ȃǂ�4�N��1�x�s���Ă����K�͂ȌR�����K�u�{�X�g�[�N�v��9��1������7���܂ł̓����ōs���܂��B���Ƃ��́A7�����̉��K��ŗ\�肳��Ă��܂����A�k���̓y�̑𑨓��ƍ��㓇���܂�ł���ق��A���{�C��I�z�[�c�N�C�̊C��≈�݂ł��s����Ƃ��Ă��܂��B���V�A�͖��N�A��K�͂ȌR�����K���s���Ă��܂����A�E�N���C�i�ւ̐N�U���n�߂Ă���͏��߂Ăł��B31���́A���C�n���̉��K��ŊJ����s���A���V�A�ɉ����āA���K�ɎQ������13�����̂����A������C���h�Ȃǂ̕������s�i���܂����B����̉��K�ɂ͕��m5���l�ȏ�̂ق��A�q��@140�@��͑D60�ǂ��Q������Ƃ������Ƃł����A���ƂȂǂ���̓��V�A�R�͋ɓ�������E�N���C�i�ɕ�����h�����Ă��āA���K�̋K�͂̏k����]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ��w�E����Ă��܂��B�����������ŁA���V�A�Ƃ��ẮA����̉��K��ʂ��āA�e���Ƃ̌R���I�ȘA�g���������A�Η�����A�����J����{�Ȃǂ�������ƂƂ��ɁA���ۓI�ɌǗ����Ă��Ȃ��ƃA�s�[������˂炢������Ƃ݂��܂��B
�����V�A�E�C�����O����k ���Ă̐��قɑR����p���N����
�C�����̃A�u�h���q�A���O����8��31���A���V�A�̎�s���X�N����K�₵�A���u���t�O���Ɖ�k���܂����B��k��̋�����Ń��u���t�O���̓C�����j���ӂ�������ɂ��āu�C���������S�Ɏx������B���ӕ����̍ŏI�Ăɂ����͖������Ă���v�Əq�ׁA������l�߂��}���Ă���Ƃ����F���������܂����B����ɑ��A�A�u�h���q�A���O���̓C�����ƃ��V�A�����ԓS��������v��̂ق��A���Z��f�ՂȂǂ̕���ł̋��͂��c�_�����Ƃ��������Łu�߂������A�����I�ŕ�I�ȋ�������Ԃ��낤�v�Əq�ׁA�A�����J�Ȃǂ������ɐ��ق��Ȃ��Ȃ��A�������đR����p����N���ɂ��܂����B����A�E�N���C�i�ւ̌R���N�U�𑱂��郍�V�A�͖��l�@���s�����Ă���Ƃ݂��Ă��āA�A�����J���{�́A�C���������V�A�ɑ��A���S�@�̖��l�@�̋��^��i�߂Ă���Ǝw�E���Ă��܂��B�����͂����ے肵�Ă��܂����A���đ��̓C�����ƃ��V�A���o�ς����łȂ��A�R���ʂł̋��͊W���[�߂悤�Ƃ��Ă���Ƃ��āA�x�������߂Ă��܂��B
��IAEA 9��1������U�|���[�W�������̒����J�n��
�E�N���C�i�쓌���̃U�|���[�W�����q�͔��d���ł́A���S���̊m�ۂɌ�����IAEA�����ی��q�͋@�ւ̐��ƃ`�[�����A9��1�����猴���̒������n�߂錩�ʂ��ł��B�����A��������ӂł͖C���������Ă���Ƃ݂��AIAEA�̒����������ɐi�߂��邩���œ_�ƂȂ��Ă��܂��B�E�N���C�i�쓌���ɂ��胍�V�A�R����������U�|���[�W�����q�͔��d���ł́A�������C���ɂ���Ĉꕔ�̎{�݂ɔ�Q���o�Ă��āA�d��Ȏ��̂ɂȂ��肩�˂Ȃ��Ƃ������O�����܂��Ă��܂��B���̒������s�����߁A�E�N���C�i�ɓ����Ă���IAEA�̐��ƃ`�[����8��31���A��������60�L���قǗ��ꂽ�U�|���[�W���s�ɓ������܂����B�U�|���[�W���s�ŁA�L�Ғc�̎�ނɉ�����IAEA�̃O���b�V�����ǒ��́A�����̒�����9��1������J�n���Đ����ԍs�����Ƃ𖾂炩�ɂ��A�u���n�̏�]�����邽�ߋZ�p�I�ȍ�Ƃ��s���\��ŁA�]�ƈ��Ƙb���K�v������v�Əq�ׂ܂����B���̂����ŁA�uIAEA�̏풓����ڎw���v�Ƃ��Č��n�̏���ɔc���ł���d�g�ݍ��Ɍ����Ē�����i�߂�l���������܂����B����ɂ��āA�E�B�[���ɒ��݂��郍�V�A�̃E�����m�tIAEA��g�́u���V�A�͊��}����v�Ƃ��āA�F�߂�\���������܂����B����A��������ӂł̖C���ɂ��āA���V�A���h�Ȃ�31���A�u�E�N���C�i�R��IAEA�̔C����W�Q����ړI��30���������s�ׂ𑱂��A�����̕~�n���ɖC�����������v�Ǝ咣����Ȃǐ퓬�������Ă���Ƃ݂��܂��B�܂����V�A�R���A�����̏]�ƈ���ɑ��A�~�n���ɒ������镔���ɂ��Č��O���Ȃ��悤���͂������Ă���Ƃ��w�E����Ă��āAIAEA�̒����������ɐi�߂��邩���œ_�ł��B
���E�N���C�i�암�փ��\���B�ŃE�N���C�i�R�̍U������
�퓬�������E�N���C�i�ł́A�암�w���\���B�̃��V�A�R����̂���n��ŃE�N���C�i�R���V���ȍU���ɏ��o���Ă��܂��B���V�A���h�Ȃ�31���A�u�E�N���C�i�̍U���͎��s�����B�E�N���C�i����1700�l�ȏオ�E�Q���ꂽ�v�Ǝ咣���܂������A�C�M���X���h�Ȃ́A�u�E�N���C�i�R�́A���V�A���̖h�䂪�����n�_�ŕ�������ނ����Ă���v�ƕ��͂��Ă��܂��B�E�N���C�i�R�̍U���ɑ��A���V�A�R�͕����̍ĕ҂ⓝ����i�߁A�암�̖h�q�����Ɏ��g��ł���Ǝw�E����Ă��āA�암�ł̍U�h����i�ƌ������Ȃ�Ƃ݂��Ă��܂��B
���E�N���C�i �I�f�[�T�u���j�n��v���E��Y�o�^�\����
���l�X�R�����A����Ȋw�����@�ւ́A�E�N���C�i�암�̍`�p�s�s�I�f�[�T�́u���j�n��v�ɂ��āA�E�N���C�i���{����A���E��Y�ւ̓o�^��\��������j��`����ꂽ�Ɣ��\���A���l�X�R�Ƃ��Ă��E�N���C�i�����̕������̕ی�ɗ͂�����Ƃ��Ă��܂��B���l�X�R�ɂ��܂��ƁA���̕��j�́A�t�����X�̃p���ɂ��郆�l�X�R�{���ŁA�A�Y�������ǒ��ɑ��A�E�N���C�i�̃g�J�`�F���R���������8��30���A�`����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�I�f�[�T�́u���j�n��v�́A�N�U�������V�A�R�Ƃ̐퓬���s���Ă���O�����琔�\�L����������Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁA���Ƃ�7���ɂ́A���̒n��ɂ���19���I�Ɍ��Ă�ꂽ���p�ق̉����̈ꕔ�Ȃǂ��j�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B���l�X�R�́A�E�N���C�i���{�̕��j���āA�o�^�̐\�����ً}�I�ɐi�߂���悤�A�Z�p�I�Ȏx�����s�����Ƃ��E�N���C�i�ɔh�������Ƃ������ƂŁA���V�A�̌R���N�U�Ŋ�@�I�ȏɂ��炳��Ă���E�N���C�i�����̕������̕ی�ɗ͂�����Ƃ��Ă��܂��B
���V�A�R����̂��Ă���U�|���[�W���������߂����ă��V�A�ƃE�N���C�i�̂��荇���������Ă��܂��B����A��a��w�̍��X�ؐ��������ɂ��Ɓu�E�N���C�i�R���������}�P���A���������v�Ƃ̏����Ƃ������ƂŊm�F���҂���܂��B�܂����V�A��9��1������n�߂�w�{�X�g�[�N2022(�ɓ��R�����K)�x���k���̓y�ł��W�J����邱�Ƃɂ��āA���X�؋����́u���{�͔�F�D���ƂȂ�A�v�[�`���哝�̂ƈ��{�������̊W�����Ȃ��Ȃ������A���V�A�͂�苭�d�ɁA���U���I�ɂȂ�̂ł́v�ƌx�����Ă��܂��B�����Ėk�C���̖ڂƕ@�̐�̑𑨓��A���㓇�̌R�����K�ɒ����R���Q������\��������A�k���̓y�łɂ킩�Ɂu���I�Ƃ̕s���̎��ԁv�Ƃ����A�R���I���X�N�����܂���݂��Ă��܂��B
�\�\�\�ْ��������U�|���[�W��������IAEA(���ی��q�͋@��)�������ɓ���܂��B�E�N���C�i�암�̒��ŁA���B�ő勉�̑傫�Ȍ���������܂��B
(���X�ؐ�������)�E�N���C�i�͌����卑�ł��B�`�����m�[�r���������̂�����������A�G�l���M�[�~�b�N�X�̒��̃p�[�Z���e�[�W�������A�ł��傫�Ȍ��������̃U�|���[�W���ł��B
�\�\�\IAEA�����̎�������V�A���F�߂Ă���Ƃ������Ƃł���ˁH
�͂��B���V�A�ɂƂ��Ă��d�v�Ȋ�{�݂ł��B�Ȃ����Ƃ����Ɛ�̒n���암2�B�����A�N���~�A�����ɂ͑厖�ȌR�`������܂��B�����̃G�l���M�[���Ƃ��čł��厖�ȏꏊ�ŁA���V�A�R�������͎��������Ȃ��B�����Ă����������̂�����Δ�Q����˔\�R�ꂪ�A���V�A���ɂ�����Ă��܂��̂ŁA�����͐���V�A�R�����������Ȃ��A��S�����N���������Ȃ��Ӑ}������Ǝv���܂��B
�\�\�\���݂̓��V�A�R����́B�����ۂ��E�N���C�i�͌R�̊Ǘ����Ɋ��S�ɖ߂������B�o�����A�U���͑��葤�ɂ����̂Ǝ咣���Ă��܂��B���X�؋����ɂ��܂��ƁA�u���̌����͍����̔����ɓ�����d�͂ޑ厖�ȃG�l���M�[�����Ƃ������ƂƁA��������ɂ��čU�����ł����Ȃ����v�ƁH
�Ȃ��U�|���[�W�������̖C���������������ƌ����܂��ƁA�w�i�ɁA�암�̃E�N���C�i�R�̔��]�U���������ł��B6�`7���ɂȂ��Ă��狭�܂�܂����B�V�������V�A�̕�������ł����ǂ��A���V�A�̍��h�Ȃ����\������ł����A�U�|���[�W�������ɃE�N���C�i�R���}�P���Đ��������n�߂��Ƃ���������܂��B���V�A���h�Ȃ����\���Ă��܂��̂Ŋm�F�͂��������Ȃ��ł����ǂ��A�������ȏL����������܂��B
�\�\�\IAEA�̍��@�͂����炢�H
�����̑Ί݂ɃU�|���[�W���s������܂��āA�������o�������Ƃ���������A������Ό��n���Ԃ̌ߑO���ɂ͓����Ă���\��������܂����A�u�E�N���C�i�R�̋}�P�v�Ƃ�����������܂��̂ŁA���ۂ͎����킩��Ȃ��ł��B
���u���I�Ƃ̕s���̎��ԁv�R���I���X�N
�\�\�\�����ẮA���V�A�R�̑�K�͌R�����K�u�{�X�g�[�N2022�v�̘b�ł��B�Q���������m�A4�N�O��30���l��������ł����ǂ��A���N��5���l�Ƃ����K�͂ł��B
5���l�Ƃ������������͑傫����ł��B30���l�́A�����������鐔���ŁA���ۂ�10���l���炢�������̂ł͂Ȃ����B5���l�Ɍ��������R�́A��͂萼���ŃE�N���C�i�R�Ɛ���Ă��܂��̂ŁA����قǕ��m�̂�Ƃ�͂Ȃ��B
�\�\�\���K�ꏊ�ɂ́A�k���̓y�̑𑨓��ƍ��㓇���܂܂�Ă���Ƃ������Ƃł��B��F�D���ƂȂ������{�ɑ��A�k���̓y�̉��K���U���I�Ȃ��̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂��搶�̌��O�ł��ˁB
���N�A�����R�̊C�R���Q�����Ă����ł����A������������k���̓y�t�߂Œ����R���Q�����āA���I�̌R�����K����邩���m��Ȃ��B�����Ȃ�܂��Ɠ������𐳏퉻�A���N50�N�ɂȂ�܂��̂ŁA�����ɑ��Ă������a瀂����܂��B�����Œ����R���ǂ��Ȃ邩���Ă����̂���̒��ڂł��B
�\�\�\9��3���A���V�A�ł͑Γ��폟�L�O���ł��B����܂ł�9��3���ɑ�K�͂ȌR�����K�͂��Ă��Ȃ����������ł��B�Ȃ����A���{�������ƃv�[�`���哝�̂̊W��������������B
�u�W�O�v�u�E���W�[�~���v�Ƃ����W�����グ�āA���傤��9��3���t�߂ɂł��ˁA�E���W�I�X�g�N�œ����o�σt�H�[�������J����āA���{�����4�N�A���ōs���ăv�[�`���哝�̂ƌo�ϓI���т������߂悤�Ƃ��Ă����B�����Ŕz���Ƃ������ŏ���������āA9��3�������܂�A���V�A�����ł��v���p�K���_�Ƃ��ē��{�̌R����`���A�s�[�����邱�Ƃ͂Ȃ���������ǁA���{���S�����A����ɔ�F�D���Ƃ������Ƃł��̂ŁA�����炭�����I�Ȕ����A�R�����K��3���ɂԂ���\��������܂��B
�\�\�\�O�V����ψ��ɂ��܂��ƁA���{�̓��V�A�́u���̒����~�T�C���v�ɂǂ��Ή����邩�H
(�O�V������ψ�)�R�����K�̓��e�ɂ����Ǝv����ł����A���ۂɑ𑨓��ȂɁA�~�T�C����z�u���Ă��܂��̂ŁA���ۂɂ������������̂�ł����Ƃ��ɂǂ��Ȃ�̂��A��������p���ӂŌR�����K�����Ƃ��ɓ��{��EEZ���Ƀ~�T�C�����������܂����B�k�C���ɂ͂ƂĂ��߂��A�s���̎��Ԃ��N����Ȃ��̂��A���ɐS�z�ł��B����A�ߔM����Ɠ��{���~�T�C����k�C���Ȃǂɒu�����ꍇ�A�܂��a瀂��[�܂�\��������܂��B
(���X�ؐ�������)���N�͂܂��A�E�N���C�i�ւ̓��{���̎x���x�ɂ���āA�����炭�����9��3���̉��K�����Ǝv���܂����A���N�ȍ~�́A�����炭5��9���̑ΓƐ폟�L�O���̂悤�ȁA���{�ւ̐����I�A�s�[�������悤�ȓ��ɂȂ邩������܂���B
�����n���K���[�̃y�[�e���E�V�[���[���g�[�O���f�Ց���8��31���A���V�A�Y�V�R�K�X�̗A���ʂ𑝂₷���ƂŃ��V�A���ƍ��ӂ����Ɣ��\�����B�n���K���[�͉��B�A��(�d�t)�����������A�r�N�g���E�I���o���̓��V�A�̃v�[�`���哝�̂Ɛe���ȊW�ɂ���B�d�t���������ăG�l���M�[�̒E���V�A�ˑ���i�߂������I�悵�Ă���B
�V�[���[���g�[�����r�m�r�ɓ��e�����r�f�I�����Ȃǂɂ��ƁA�n���K���[�͘I���c�K�X��ЃK�X�v��������A9�`10���ɓ��ʍő�580���������[�g���̒lj���������B
�n���K���[�͓V�R�K�X�̑唼�����V�A�Ɉˑ����Ă���B��N�ɂ̓E�N���C�i���I��(������)����p�C�v���C����ʂ��āA�N�Ԍv45���������[�g����A�����钷���_������B�K�X�v������8���ɂ��A�g���R��ʂ�p�C�v���C���u�g���R�X�g���[���v�o�R�œ���260���������[�g����lj��������Ă����Ƃ����B
�d�t�͑ΘI�o�ϐ��قƂ��ĔN�������h�Ƀ��V�A����̐Ζ��A�����ւ�����j�����A�V�R�K�X�ł͂܂Ƃ܂��Ă��Ȃ��B�I���o�����́u�ꂵ�ނ͉̂��B�̕����v�Ƃd�t�̐��ٕ��j�Ɍ��R�ƈًc�������Ă���B
IAEA�����ی��q�͋@�ւ̒����c���A�E�N���C�i�암�̃U�|���[�W�������ɓ������܂����B
�h�q�Ȗh�q�������̕����T������ɕ����܂��B
(Q.�U�|���[�W�������̎��͂ł͖C���������Ă��܂����A���ۋ@�ւ̎��@�����邱�ƂŁA�����̈��S���͊m�ۂł���̂ł��傤��)
���q�F1��ً}��~����ȂǁA�댯�ȏ�Ԃ������Ă��܂��B�E�N���C�i�R�́A�A�����J�Ȃǂ�����ꂽ����ȂǂŁA���V�A���̌R�����_�����ʓI�ɍU�����Ă��܂��B���V�A�́A�������Ԃɂ����`�ɂ��Ă��āA�E�N���C�i�����U�����ɂ������낤�ƁB��������R���I�ȓ��������߂Ă����Ǝv���܂��B������AIAEA�̒����c���ꎟ�I�ɗ����������Ƃ��Ă��A���V�A���������𖾂��n���Ƃ������Ƃɂ͎c�O�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
����A���V�A�{���ł́A�{�i�N�U�㏉�ƂȂ��K�͌R�����K���n�܂�܂����B����̌R�����K�́w�{�X�g�[�N�x�ƌĂ�A���V�A��Łw�����x�Ƃ����Ӗ��ł��B4�N��1�x�s���Ă��܂����A����܂ł����啝�ɋK�͂��k�����Ă��܂��B���m�̐���5���l�ȏ�ŁA�O��̖�30���l����6����1�ɏk���B�܂��A�P���ꏊ��������13�J������7�J���ɂقڔ������Ă��܂��B����A�Q�����̓��V�A���͂��߁A�����A�C���h�A�x�����[�V�Ȃ�14�J���ŁA�O����������Ă��܂��B
(Q.�K�͂��k�������R�����K���ǂ��݂��炢���ł��傤��)
���܁A���V�A�R�̓E�N���C�i��6�`7���̕��͂𓊓����Ă���Ƃ݂��Ă��܂��B4�N�Ɉ�x�A�s����ɓ��n��̑�K�͌R�����K�ł����A����A���m�����Ȃ����A�P���ꏊ������������`�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���V�A���͖������Ă���Ă���Ǝv���܂��B�܂�A���ꂭ�炢�E�N���C�i�푈�ɕ��́E���������Ă��܂��Ă��������Ǝv���܂��B
(Q.�������Ăł��R�����K���s���v�[�`���哝�̂̎v�f�͂ǂ��ɂ���̂ł��傤��)
2����Ǝv���܂��B1�ڂ́A�E�N���C�i�푈���s���Ă��Ă��A���ێЉ��Ǘ����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�s�[�����邱�Ƃł��B�O��́A���V�A���܂߂�3�J���̎Q���������̂��A�����14�J���ɑ����܂����B�F�D���̒����A�C���h�݂̂Ȃ炸�A�j�J���O�A�Ȃǒn���I�ɗ��ꂽ���������W�߂��B�����āA���ێЉ��Ǘ����Ă��Ȃ��Ƃ����A�s�[������_��������Ǝv���܂��B2�ڂ́A����A�����̊C�R�����߂ĎQ�����Ă��܂��B���{�C�ʼn��K���s����Ƃ݂��Ă��܂��B����A�𑨓��Ń��V�A�R���R�����K�����\��������Ă��܂���̂ŁA���Ă�������_�������肻���ł��B
����A�啝�ɋK�͂��k�����Ă���Ƃ������̂́A5���l�K�͂ŁA13�J���������`�ŁA���ꂾ���̌R�����K���ł���Ƃ������Ƃ��A�s�[�����Ȃ���A����������E���͕s���ŃE�N���C�i�푈���ł��Ȃ��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ����ێЉ�ɃA�s�[������Ƃ����Ӑ}������Ǝv���܂��B�v�[�`���哝�̂͒������̍l���͕����Ă��Ȃ��Ƃ��낪����܂��̂ŁA���������A�E�N���C�i�ł̋]���҂̊g�傪���O����܂��B

���E�N���C�i�o�g�A�j���̐���
�n�[�o�[�h��w���҃C���^�r���[��3��ڂ́A�j���̐��ƁA�}���A�i�E�u�W�F����(Mariana Budjeryn)���m�̘b���Љ��B�ޏ��́A���V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂̎v�f��A�E�N���C�i�̈��S�ۏႪ����ꂽ�u�_�y�X�g�o���Ȃǂɂ��Č�����B
�E�N���C�i�o�g�̃u�W�F�������̓L�[�E�̑�w�𑲋ƌ�A�u�_�y�X�g�ɂ��钆�����[���b�p��w�Ŕ��m�����擾�A�ă^�t�c��w�ŖK�⋳���߂���A�n�[�o�[�h��w�P�l�f�B�X�N�[���̃x���t�@�[�Z���^�[��Ȍ������ɏA�C�����B
�E�N���C�i�̐N���푈���߂����ẮA6��24�����J�R�����ŏЉ���悤�ɁA�u�����ŕI�|���֎q�ɍ����Ă����m���̕]�_�Ƃ��A�E�N���C�i�l�ɑ��āw�������ׂ����A�������ׂ��ł͂Ȃ��x�ȂǂƎw�}���ׂ��ł͂Ȃ��v�Ǝ茵�����ᔻ���Ă���B
�\�\���V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂��j������g���\���͂���A�Ǝv�����B
�q���̌����Ăł́A�\���͂��邪�A����Ȃɍ����͂Ȃ��B�Ƃ͂����A�S�z�Ȃ̂́A�j�̗}�~�͂��ނ̌����W���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����_���B�E�N���C�i��1994�N�Ɋj����������B(NATO=�k�吼�m���@�\��)�g��}�~�ɂ��J�o�[����Ă��Ȃ��B���S�ۏ�̐^��n�тȂ̂��r
�q(�j�̗}�~�͂�)�v�[�`�����̌����W�����Ȃ��Ƃ���A�܂��A�ނ������I�łȂ��Ȃ�A�j���g����������Ȃ��B���Ƃ��A���C�Ŋj��������u�f�����X�g���[�V�����E�V���b�g�v�̋c�_������B�����A����ŁA�E�N���C�i�̐l�X�̐키�ӎv��ς����邩�ƌ����A���͕ς����Ȃ��A�Ǝv���B�Ƃ�킯�A�u�`���̎S���ȍ~�́r
�\�\�E�N���C�i�̐l�X�́A�키���Ƃ����łɌ��ӂ��Ă���B
�q�����A���ӂ��Ă���B���͏Ă���A���H���j�ꂽ�ȏ�A�킢�͂��炭�����r
���u�l�I�Ȏ��݁v�Ŏn�܂����푈
�\�\�v�[�`�������ǂ��]�����Ă��邩�B
�q���V�A�ɂ͐푈���ǂ��i�߂邩�A�͂����肵���r�W�������������B�����A���܂�v��ʂ�ɐi��ł��Ȃ��̂́A�����炩���B�ނ�͐헪��ς��A�E�N���C�i�ŒB�����悤�Ƃ��������ڕW�����ς��Ă���B����́A�I���W�i���̌v��ł͂Ȃ��r
�q���ɂ́A���̐푈���v�[�`�����̌l�I�Ȏ��݂ł���悤�Ɏv����B�v�[�`�����͔��ɏ����ȃO���[�v�ŊJ������肵���B���̓��V�A�̓����ƌ𗬂��Ă��邪�A�ނ�͔��ɋ����Ă����B�ނ�́A�{�i�I�ȐN�����N����Ɨ\�z���Ă��Ȃ������B�P�Ȃ鉉�K���A����I�ȍ�킪���邩�ǂ����A�Ǝv���Ă����̂��B�ނ�̋������A���ɏ����ȃT�[�N���Ō��肳�ꂽ���Ƃ���Ă���r
�q�����̌l�I�ȕ]����q�����l�����푈���n�߂��Ƃ��A���j�́u�w���҂Ƃ��ẴI�[���▼���A�M���x�̂��߂ɁA���ׂĂ�q����\���������v���Ƃ������Ă���B������A�G����2�����ӌ����قɂ��Ďn�߂��푈�����A����̓��X�N�������B�ނ��j���g���\���͂���r
�\�\�v�[�`�����͍����I���낤���B
�q����f����̂́A���ɓ���B�ނɂ͓���̖ړI������A�ړI��Nj������i�����Ă���A�Ƃ����_�ł͍����I���B�Ƃ�ł��Ȃ��v�Z�Ⴂ��E�N���C�i�l�ɑ����������邪�A���ɂ́u�E�N���C�i�Ƃ��������Ȃ������Ƃ����т����w�́v�ł���悤�Ɍ�����r
�q�ނ͋��Ђ������Ă����B�����A�E�N���C�i�R������A�܂��������Ђł͂Ȃ������B�E�N���C�i�͊j�ۗL���ł͂Ȃ��A�R�����Ƃł��Ȃ��B�ނɂƂ��ẮA�E�N���C�i�̑̐��ⓝ���^�����Ђ������̂��낤�B�������͖@�̓��������߂��B���������]���R�́A�v�[�`���������̍��ō�낤�Ƃ��Ă������̂ƁA���Ɉ���Ă����̂��r
�q�v�[�`�����̓E�N���C�i�ƃ��V�A�͈�̂ł���u�E�N���C�i�l�������̍��ƂƓ����������ׂ��ł͂Ȃ��B�@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���v�ƍl���Ă���B�ނ́A�������M���Ă�����̂��f�b�`���������A��`�Ɏg�����Ǝv�������A�̂ǂ��炩���B�u�E�N���C�i�S�̂��i�`�Ɏx�z����Ă���v�ȂǂƂ͌����Ȃ��B���́u�����Ă���v�Ǝv�����A���ꂪ�����Ȃ̂��r
�\�\�v�[�`�����̓E�N���C�i�l��������Ă����B
�q�ނ́A�E�N���C�i�̐l�X�ƍ����ǂ��������A�܂�����������Ă����A�Ǝv���B�ނ͊X�����V�A�R���s�i���Ă����A�l�X�����}���Ă����A�Ǝv���Ă����B���ꂪ�A��K�͂ȐN�U������̂ɏ\���ȌR�������Ȃ��������R���r
�q�R���̌o�����́A�U���Ɩh�䂪3��1���B�ނ�15���l���������A�E�N���C�i��10���l�����B�ނ́A�Ō�̒�R��\�z���Ă��Ȃ������̂��B����ŁA���ܐ헪��ς��āA�Ē������Ă���B�ނ͍����I�ɑΉ����Ă���r
���j�푈�͋N���肤��̂��H
�\�\�j������g���n�[�h���͉��������A�Ǝv�����B
�q�ނ͌J��Ԃ��A�j���g���Ƌ����Ă���B�j�������肵�āA���[�Y�g�[�N(�U���Șb)�ɂ��Ă��܂����B���V�A��NATO�̊j�}�~�̊W�͉��\�N�����݂��Ă����̂ɁA����̐푈�ł͋N���Ă��Ȃ��B�ނ́u��X�͈̑�ŋ��͂Ȋj�ۗL���v�Ƃ��u�N�����j�Ō������Ƃ��Ȃ��悤�Ȍ��ʂ������v�Ȃǂƌ��������A����Ȃ��Ƃ������K�v�͂܂������Ȃ������BNATO�́A�ނ��j����������Ȃ��Ă��A�����Ή����������낤�r
�q����ʂ��āA2�̓G�����j�̃G�X�J���[�V����������āA���ڑΌ������ꂫ�����j������B1956�N�̃n���K���[��x��������@�ł������������B�����̑㗝�푈�����������A�R���͒��ڑΛ����Ȃ������BYouTube���V���b�g�_�E��������A�p�C���b�g���E�Q�������A�����܂ł��B�z�����������̂��r
�q����́A���܂��K�p����Ă���B�N���j�푈��]��ł��Ȃ����炾�B�����A�ʏ�푈���j�푈�ɂȂ�\���͂���B���V�A������ȌR���͂�ۗL���Ă���̂́A���ɕs�����B�ނ�͒ʏ��͂ߍ��킹�邽�߂ɁA�j�J�[�h���g���Ă����r
�q���̏I����A��p�ړI�̐��j���g���������l�͒Ⴍ�Ȃ������A�č��͊؍��₻�̑��̒n�悩��A������P�������B�����A���V�A�͂܂�2000���̐�p�j��ۗL���Ă���B�����͖��z���ŁA���Ԃ�5�̒����ɂɂ��邪�A�Ĕz������̂ɑ債����Ԃ͂�����Ȃ��r
�q����A�č��ƃ��V�A�͊j����̖������ŏ����ɗ}���悤�Ƃ����B����ł��A���V�A�͌x���Ԑ����������Ȃ������B60�N�ォ��80�N��܂ŁANATO�ƃ\�A�ɂ͐��ł̊j�g�p�v�悪�������B�K���A�����N���Ȃ��������A�v��͂������B����A���ł̎g�p�͖��Ӗ��ɂȂ����悤�Ɍ������r
�q�����A���܂�j��肪�ĂсA�e�[�u���ɖ߂��Ă����B������A���͊j���g���n�[�h�����Ⴍ�Ȃ����Ƃ͎v��Ȃ��B�Ƃ͂����A�����炩�ǂ�����̈�Y������B���Ő�p�j���g���ANATO�����V�A���W�Ȃ��A�G�X�J���[�g����Ƃ������Ƃ��r
���u�_�y�X�g���ӂ́u�^���v
�\�\�č��Ɖp���A���V�A��1994�N�Ƀu�_�y�X�g�o���ɒ����B�j�����ƈ��������ɁA�E�N���C�i�ƃx�����[�V�A�J�U�t�X�^��3�J���͍��̈��S�����ꂽ�͂��������B�Ƃ��낪�A���ǁA����ꂽ�B�����������̂��B
�q�E�N���C�i���p������Y�́A�����j�}�~�Ɏg������̂ł͂Ȃ������B�����NATO�ƕč���}�~���邽�߂́A�ʂ̍��̊j�헪�̈ꕔ�ł���A�E�N���C�i�͊��S�ȍ�퓝�����������Ă��Ȃ������B���S�Ȋj�R���T�C�N�����Ȃ������r
�q�E�N���C�i�ɂ́A�\���ȉȊw�҂�Y�Ɣ\�͂����������A2�̏�Q���������B1�͂������B�\�A�������Ƃ��A���̓L�[�E�̊w�����������A�C���t������10000���ɒB���Ă����B1�x��5�h���ȏ�͌����ł��Ȃ������B�J�l���Ȃ��A�V���ɓ����ł��Ȃ������r
�q����1�́A���ۓI�Ȕ������BNPT(�j�s�g�U���)�ɉ����āA�č��͊؍���h�C�c�̊j�ۗL��j�~���悤�Ƃ����B�C������C���N�A�k���N�ɂ��Ă��������B�E�N���C�i���j��ۗL����A�č��⍑�ێЉ��D�ӓI�Ɏv���Ȃ��A�Ə\���ɗ\�z�ł����r
�q�������͓Ɨ���������̐V�������ŁA���卑�Ƃ�]��ł����B���ێЉ�̍D�ӂāA�ǂ����ێs���ł��肽�������B�k���N�Ⓦ���̂悤�ɁA�Ǘ��������Ȃ������B�������́A���m�Ȍ��t�Ō���ꂽ�B�u�E�N���C�i�ł��肽���Ȃ�A�j�����v��ɎQ�����ׂ����v�ƁB����ŁA�������́u������܂����A��������v�ƌ������B�������A�`�F���m�u�C���������̂̉e�����������r
�q����A�������ɂ͎�����錠�����������B1�͒e�����̊j�������������������㏞���B3000�̐�p�j�e����2000��ICBM(�嗤�Ԓe���~�T�C��)�Ə��q�~�T�C���Ɋ܂܂�鍂�Z�k�E�����ƃv���g�j�E�������������ɁA���V�A�͒�Z�k�E�����Ƀ_�E���u�����h���āA�����̔R���W���̂Ƃ��ăE�N���C�i�ɒ����r
�q����1�́A���S�ۏႾ�B�E�N���C�i�̓u�_�y�X�g�o���ō��̈��S�ۏ�����߂����A����͏�肭�����Ȃ������B���V�A�͋��͓I�łȂ��������A�č��ɂƂ��āA���S�ۏ�Ƃ͖k�吼�m���̑�5��(�W�c�h�q�̋K��)�̂悤�Ȃ��̂��B���{��؍��ANATO�������ɑ��鐾�r
�q�|�[�����h�A�n���K���[�A�`�F�R��NATO�����ł����A���c���������B�č���������S�ۏ�ɖ@�I�S���͂�����A�č��c����F����K�v������B�����I�Ȑ킢�ɂȂ�B�č��̓E�N���C�i�Ɉ��͂��������B���ǁA�������ɂł����őP�̑I���́A�����ɏ������邱�Ƃ������B����͐����I�ۏ�ɂ������A���A�̕�������R�s�y���������̂��̂������r
�q�����A�u�_�y�X�g�o���̓E�N���C�i��NPT�����ƂƂ��ɁA�j�s�g�U�̐��̈ꕔ�ɂȂ����B���́u�o���ɑ���ᔽ�́ANPT�̐��ɑŌ���^����v�Ɣᔻ���Ă���B���S�ȗ}�~�ł͂Ȃ����A�E�N���C�i���j�������������Ƃ��āA��j�ۗL���ƍ��ۓI�j�����̊Ԃō��ӂ��ꂽ����̈ꕔ�������̂��r
���V�A�̐Ζ���胋�N�I�C���̃����B���E�}�K�m�t�(67)��1���A���S�����B���X�N���s���̕a�@�̑�����]�������ƕ��Ă���B
���N�I�C���̓}�K�m�t��̎���F�߂����̂́A�u�d�a�̖��v�Ɛ������Ă���B���V�A�̃��f�B�A�́A�}�K�m�t���̓��X�N���̒����a�@�ł����̎蓖�Ă������A���a�@�ŖS���Ȃ����ƕ��B���V�A�ł͂��̂Ƃ���A����Ƃ̌o�c�҂Ȃǂ��������œ�̎��𐋂��Ă���B
�{�����ǂ́A����Ŏ����ׂĂ���Ɛ����B���c�^�X�ʐM����ނ����W�҂ɂ��ƁA�}�K�m�t����1���ߑO��6�K�̑�����]�������Ƃ����B�^�X�ʐM�͂��̌�A���������E�����ƕ��B
���N2���Ƀ��V�A���E�N���C�i�N�U���J�n�����ہA���N�I�C���̖�����͕����̑����I�������߂�ƕ\���B�u���̔ߌ��v�̋]���҂ɓ����Əq�ׂ��B
4���ɂ̓��M�g�E�A���N�y���t�В�(����)���A�N�U�ւ̑Ή��𗝗R�ɃC�M���X���琧�ق��Ȃ��ꂽ���Ƃ��A���C���Ă���B
���V�A�ł͂������J���ŁA�G�l���M�[��Ƃ̏d����I���K���q(�x��)���s�R�����Ă���B
�E4���ɂ́A�V�R�K�X���m���@�e�N�̑O�В��Z���Q�C�E�v���g�Z�[�j�����ƍȎq�̈�̂��A�X�y�C���̕ʑ��Ŕ������ꂽ
�E�����A�Ζ����K�X�v�����P���̋��Z�@�փK�X�v�����o���N�̃E���W�X���t�E�A���@�G�t�O���В��ƍȎq�̈�̂��A���X�N���̃}���V�����Ŕ������ꂽ
�E5���ɂ́A���N�I�C���̑啨�����A���N�T���f���E�X�{�e�B�������S�s�S�ŖS���Ȃ����B�ł́A�V���[�}��(�@���I�E�\��)�ɂ���ֈ�Â�T���Ă����Ƃ���
���N�I�C���́A���V�A�ő�̖��Ԋ�ƁB ���E�ő勉�̃G�l���M�[��Ƃɐ��������̂̓}�K�m�t���̌o�c��r�ɂ����̂��ƁA���Ђ͐����ŏq�ׂĂ���B
�}�K�m�t����1993�N�ɓ��Ђ��A2�N�O�ɉ�ƂȂ����B3�N�O�ɂ̓E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂��琶�U�̌��J����������M�͂����^����Ă���B
���V�A���E�N���C�i�N�U���J�n���Ă��甼�N���o�߂����B�����ɗ��āA�E�N���C�i�푈�̐�ǂ��傫�������o�����B
���́E�����̕s���ȂǂŌp��\�͂̌��ނ��ڗ����Ă������V�A�R�ɑ��A�哱�����������E�N���C�i�R��2022�N8��29���A���ɒn�㕔���ɂ��{�i�I�Ȕ��U���ɏ��o�����B���V�A��3�����琧������Ă���암�w���\���B�Ȃǂ̒D�҂�ڎw�������̂��B
�E�N���C�i�̃[�����X�L�[���������̎����ɔ��U���ɓ��ݐ����w�i�ɂ́A���N�~�܂łɑ傫�ȏ������������������ŁA�D�ʂȗ���Ń��V�A�Ƃ̒�����͍�����Ƃ����Z������̐헪������B
�A�����J�̃o�C�f���������E�N���C�i�����͂Ɏx���邽�߁A2022�N10���ɂ���K�͂ȌR�������̐���������\�����B����́A�A�����J���E�N���C�i�Ǝ�����́u�A�����v�̐����\�z���邱�Ƃ��Ӗ�����B
����A�v�[�`��������2022�N7���ȍ~�̋����A�푈��2023�N�ȍ~�ւƒ����������A�S�菟����_���헪�ɓ]�������B���������U���̊J�n���A��w�g�ɗ��������`�ƂȂ����B
�����U�����n�߂��E�N���C�i�R
2022�N8�������݁A�E�N���C�i�R�͔��U���̓��e�ɂ��Č�����⭌��߂�~���Ă���A�ڍׂ͕s�����B���ꂾ���d��Ȍ��ӂŗՂ�ł�����ł��邱�Ƃ��B�w���\���B�ɉ����A�U�|�����[�W��(�U�|���W�F)�B�ł��n�܂����Ƃ݂��邪�A���U��킪�ǂ��܂ł̗̓y�D�҂�_�������̂��͌����_�ł͂͂����肵�Ȃ��B
���U���̎������߂����ẮA����܂�2022�N6�������ȂǁA���܂��܂ȉ���������Ă����B�ŋ߂ł́u�{�i�I�Ȕ��U����������v�Ƃ̏���ă��f�B�A�ŗ���A���������L�����Ă����B���̂��߁A����̔��U�͈��̃T�v���C�Y�ƂȂ����B�E�N���C�i���̗z����킾�����Ƃ݂���B
���̊ԁA�E�N���C�i�R�͎����ɔ��U�ւ̏�����i�߂Ă����B�܂��A�w���\���B�̃h�j�G�v���쐼�݂ɔz�u����Ă��郍�V�A��������̉������邽�߁A�i�ߕ��A�e��ɂ��W���I�ɖC�������B
����ɁA�w���\���ւ̎�v�ȕ��������̏o���_�ł������̃N���~�A��������̕⋋�H�ɂ����X�ɖC�����������B���ł��⋋�H�̗v���ł���A�h�j�G�v����ɉ˂���4�̋����A�����J�����^���������\����ł��鍂�@�����P�b�g�C�n�C�}�[�X�Œ@���Ă���B���̌�����V�A�R�������C��������A����������邽�тɍU�����Ă���B���̌��ʁA���̕⋋�H�͂قڒf���Ԃ��B
�R���ɂ��ƁA���U����O�ɃE�N���C�i�R�͍I���ȖC���Ńw���\���̃��V�A�R���̂��ǂ�����ł����B
�����A1��2000�l�̃��V�A�R�������������A�E�N���C�i�R�̓w���\���ɂ���i�ߕ��ƒʐM�{�݂��n�C�}�[�X�Ō������C�������B���̂��ߎi�ߕ��͕������c�����܂܁A��200�L�����[�g�������ꂽ���݂̃����g�|���܂ł�������ƌ�ނ����B
�E�N���C�i�R�͂��̌�A�����g�|���̎i�ߕ��ɂ��ĎO�C���������Ă���B���̂��ߎi�ߕ��ƕ������ʐM������S�ɐ藣���ꂽ��ԂɂȂ����B�����ɂ͉����ɗ���3000�l�K�͂̕����������������A�i�ߕ��Ɛ藣���ꂽ���ƂŎm�C�r����ԂƂ����B
�⋋���ꂵ���Ȃ����ɂ�������炸���V�A�R���w���\���֕������������Ƃɂ��āA���V�A�̗L�͂ȌR���]�_�Ƃł��郆�[���[�E�t���[�h���t����2022�N8�����ɁA�E�N���C�i�́u�헪�I㩁v�ɂ͂܂�~�����邩�s�����邵�������Ȃ��Ȃ�\�����w�E���Ă������A�����ʂ�A�����Ȃ��Ă��܂����悤���B�n�C�}�[�X�́A��70�L�����[�g���̎˒��Ɛ��x�̍����A�g������̂悳�ŗD��Ă���A�E�N���C�i�R�ɂƂ��āu�Q�[���E�`�F���W���[�v�ƂȂ��Ă���B
�������^�̐퓬�ɏI�n���郍�V�A�R
����ɃE�N���C�i�R��2022�N8�����{����A�N���~�A�����̌R���{�݂��ʗv�Ղ�W�I�ɒn���̃E�N���C�i�l�Z���Ƌ��͂��āA�p���`�U���U�����p�����Ă���B���̌��ʁA�N���~�A����S���ŌR�������𑗂�o�����Ƃ���w����Ȃ����B�����Ƀw���\���Ȃǂł͏Z���̎��O�����i�߂Ă����B�E�N���C�i�l�Z���ɑ����̎��҂��o�������암�}���E�|���ւ̃��V�A�R�̐��S�ȍU����O���ɁA���U���ł̖��Ԑl�̎��҂��Ȃ�ׂ����Ȃ�����z���Ȃ̂��낤�B
���V�A�R�͑����̏����A���Ԑl�̎��҂��ڂ݂��ɖC������J��Ԃ��A���\�A�R�^�푈���̗p���Ă���B�R���́A�E�N���C�i�R������Ƃ͈�����悵���u�����g����21���I�^�̐V���Ȑ푈�v�����悤�Ƃ��Ă���Ǝw�E����B�E�N���C�i�R�́A���͏��Ռ^�̃��V�A�R�̏����ɂ��āu��C�̉a�v�Ɨ����ł���B
���U�J�n�ɓ�������2022�N8��30���Ƀe���r���������[�����X�L�[�哝�̂��A���V�A�R���m�ɑ��u����������Ύ���ɖ߂邩�A�ߗ��ɂȂ邵���Ȃ��v�ƕ������E���Ăъ|�����B����͂����ł����m�C�ቺ���������ƌ����郍�V�A�����̓��h��U���S����Ƃ݂���B
���U���J�n���A�틵�̍s���ƂƂ��ɏœ_�ɂȂ�̂́A�v�[�`��������2022�N9��11���̎��{�Ɍ����ŏI�I���������Ă����̒n�ł̏Z�����[���B�����h���o�X�n���̃��K���X�N�A�h�l�c�N�̗��u�l�����a���v�ɁA�암�w���\���B�ƃU�|���[�W���B��������4�n��ōs���ׂ��������i��ł���B�v�[�`�������Ƃ��ẮA�`�����́u�Z�����[�v���o�Ĉ�@�ɃN���~�A������錾����2014�N�́u�N���~�A�E�V�i���I�v���Č�����_���Ƃ݂���B
�������A�E�N���C�i�R���w���\���ȂǂŒD�Ғn����L���Ă���A�Z�����[�͎����㉄���A�Ȃ������~�����\���������B�����Ȃ���V�A�ւ́u�ғ��錾�v�ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ邾�낤�B
�[�����X�L�[�����͂Ȃ��Z������̐헪��I�̂��B���̑傫�ȗv���Ƃ��ẮA�푈���������������قǁA���V�A�ɗL���ɓ����Ƃ̔��f������B�D��������A���V�A�Y�V�R�K�X�̋����팸�ŃG�l���M�[��@�Ɍ������Ă���h�C�c���܂߁A���B����E�N���C�i�ɑ��A�s���ȏ����ł̒������߂鈳�͂��o���˂Ȃ��Ƃ̊�@�������邩�炾�B
����ɁA�l��1��4000���l�̃��V�A��4500���l�̃E�N���C�i�̍��͂̍�������B�����_�ŌR���͂��u�悤�₭������ׂ��v�Ǝ咣����E�N���C�i�R�����A��͂荑�͂̍����ӎ����Ă��邾�낤�B
�ł́A���U��킪�ڎw���̓y�D�҂̃S�[���͂ǂ��Ȃ̂��B�����_�Ń[�����X�L�[�����͔��\���Ă��Ȃ��B��������V�A�R�̓��h�������o���S����̈���낤�B�펯�I�ɂ́A�w���\���B��A�ꕔ����������Ă���U�|���[�W���B�̒D�҂��S�[���ƍl����̂��Ó����B
������������āA�N�U�J�n���̒n�_�܂Ń��V�A�R�������Ԃ����ƂŁA�Ƃ肠�����u�폟�v�Ɛ錾����\���Ƃ݂���B���ꂾ���ł��A�v�[�`�����ɂƂ��Ă͐��������ȗ��A�ő�̐����I�s�k�ƂȂ�B���̏������o�b�N�Ƀv�[�`�������ɑ��A�̗͂���Œ������Ăъ|����v�悾�낤�B����2�B�ƃN���~�A�̒D�҂͂�蒷���I�X�p���Ŏ�������2�i�K�헪�Ƃ݂���B
���N���~�A�D�҂����錾�����E�N���C�i
�������A�[�����X�L�[�哝�̂�2022�N8��24���A�암�݂̂Ȃ炸�A�唼�������x�z����Ă��铌���h���o�X�n��ƂƂ��ɃN���~�A���D�҂���錾���o�������肾�B�����̍�����������x�����Ă���B
����̐틵���悾�낤���A�N���~�A�ɂ���|����ȍU�����d�|����\���͂���Ǝv���B�[�����X�L�[����2022�N8��16���̃e���r�����Łu�N���~�A�Ȃǐ�̂��ꂽ�n��̂��ׂĂ̐l�X�̓��V�A�R�̎{�݂ɋ߂Â��Ȃ��łق����v�ƌĂт������B
���ʂ̏œ_�́A���V�A�{�y�암�ƃN���~�A���q���B��̗��H�A�N���~�A�勴���B�����_�ŁA�p���`�U���U���Ńp�j�b�N�ƂȂ�A�N���~�A���瓦��悤�Ƃ��郍�V�A�R�E��������l�ł������A����n���ă��V�A���ɓ������ق�������ƃE�N���C�i���͔��f���Ă���悤�����A���̔j���_�����ˑR�̍U�����ے�ł��Ȃ��B
�����܂Ń[�����X�L�[���������C�ɂȂ����w�i�ɂ́A�E�N���C�i�ɑ��A�A�����J���A��q����������́u�A�����v�̐��\�z�ɓ��ݏo�������炾�B���̑̐��̍��i�ɂȂ�̂�2022�N5���ɃA�����J�c������������u����ݗ^�@�v���B�u�����h���[�X�@�v�Ƃ��Ă�镐��ݗ^�@�́A2023�N9�����܂ł̊ԁA�葱�����ȗ������A�v���ɃE�N���C�i�ɑ�ʂ̌R��������ݗ^���邱�Ƃ��\�ɂ���@�����B
�u����ݗ^�@�v�͑�2�����E��풆�ɂ����肳�ꂽ�B�A�����J�̓i�`�X�E�h�C�c�Ɛ키�C�M���X�Ȃǂɑ��ĕ���������A���ꂪ�A���������̗v����1�ɂȂ����B���@�����ȗ��A�E�N���C�i���͑����̎��s���A�����J�ɋ��߂Ă������A�悤�₭2022�N10���ɂ������ɓ����o�����ʂ����B����ɂ��A�A�����J�ƃE�N���C�i��������́u�A�����v�I�W�ɂȂ�B���@�͑�풆�A�h�C�c�Ɛ�������\�A�ɂ��K�p���ꂽ�B���ꂪ����̓��V�A�Ƃ̐푈�œK�p����邱�ƂȂ�B���j�̔�����B
�E�N���C�i���ɂ��ƁA2022�N10���ɂ̓A�����J���h���ȓ��ɕ��틟�^�ƗA���Ɋւ���{�����ݒu�����\��Ƃ����B����܂ł͍q��@�ŕ�����^��ł������A�啝�ɗA���ʂ������邽�߁A�D���A������͂ɂȂ�Ƃ����B
����ɔ����ăA�����J���̍����\����̋��^���啝�ɑ����錩�ʂ����BF16 �ȂǃA�����J���퓬�@�̋��^�����߂Ďn�܂�\��������Ƃ����B���łɃA�����J�ł̓E�N���C�i���m��1���l���A�����J������̑���̌P�����Ă���A�E�N���C�i�R�̑����ʂł�NATO(�k�吼�m���@�\)����������i�ނ��ƂɂȂ�B
���������A�����J�̃E�N���C�i�h�q�ւ̖{�i�I�֗^�̎p���́A�E�N���C�i�����̐폟���ʂ������ƂŁA�v�[�`�������Ɍp���f�O������Ƃ̕ĉ��̐헪�Ɋ�Â����̂��B���R���ɂ��ƁA���Ƀ��V�A�Ƃ̊Ԃʼn��炩�̒�틦�肪����������A���V�A�������j��U�����Ă��Ă����Ԑ��\�z���Ӑ}���Ă���Ƃ����B
���������������Ȃ��A�����J�̎x��
�E�N���C�i�Ɨ��L�O����2022�N8��24���A�A�����J���{��30���h��(��4100���~)�K�͂̒lj��R���x���\�����B�N�U��A�A�����J��1��̔��\�Ŗ��炩�ɂ����R���x���Ƃ��Ă͍ő�K�͂��B���̒��ɂ̓E�N���C�i�������]��ł����h��V�X�e�������߂Đ��荞�܂ꂽ�B
���̉������\�̍ہA�A�����J���h���Ȃ̃J�[�����h����(�����S��)�́u�v�[�`���̐헪�́A�E�N���C�i������E�N���C�i�̓����������߂�̂�S�苭���҂��Ƃ��B����̉����͂��̃v�[�`���̗��_�ɒ��ڒ��ނ��̂��v�Ƌ��������B���ʃA�����J���{�Ɂu�x�����v�����肻�����Ȃ����Ƃ������������B
�������Ƃ��A���͌R���x���ɏ��ɓI�ƌ����Ă����h�C�c�ɂ����Ă͂܂�B�x���v��\���Ȃ���A�Ȃ��Ȃ����s���Ȃ��V�����c�ɑ��ăE�N���C�i�ɓ���I�ȍ������肩�A�A��������������ᔻ���o�Ă����B������2022�N7��������{�i�I�x���������o�����B�h�C�c���ᔻ���Ă����E�N���C�i���{�W�҂�����ᔻ���o�Ȃ��Ȃ����B
�t�����X�͑��ς�炸���ɓI�����A�p���͌R���x���ɂ��Ă͕ĉ��S�̂����[�h����قǂ̐ϋɎp�����B�`�F�R�Ȃǂ̓����������x���ɐϋɓI���B
����ɑ��A���V�A�R�͔��U�����R���I�Ɍ��ނ���Ƃ̋��C�̎p�����B�������A�ꂵ�������[�I�Ɏ������Ԃ�2022�N8��24���ɋN�����B���̓��͐N�U�J�n���炿�傤�ǔ��N�ŁA�����ɃE�N���C�i�̋��\�A����̓Ɨ��L�O���Ƃ�����d�̈Ӗ��ŐߖڂƂȂ����B
�[�����X�L�[�����͐����I�Ō���_���ă��V�A�R����s�L�[�E�̐��{���ɂȂǂɑ�K�͂ȃ~�T�C���U�����s���̂ł́A�ƌ����Ԑ���~�����B
���������̓��A���V�A�R���e���~�T�C���u�C�X�J���f���v�ōU�������͓̂����h�j�G�v���y�g���t�X�N�B�̉w�������B25�l���̎��҂��o�����A���q�����̈�ۂ͔ۂ߂Ȃ������B���n�̎���ɏڂ����R���͕M�҂ɑ��u�����U���~�T�C���̕s�������R���낤�B�����ւ̍U���ɉ��߃L�[�E�Ƀ~�T�C���������Ȃ������v�Ǝw�E�����B
�E�N���C�i�R��̔��\�ɂ��ƁA���V�A�R�̎�̓~�T�C���ł���J���u���^���q�~�T�C���̌��݂ۗ̕L���́u���ɏ��Ȃ��v�A�Z�������q�~�T�C���u�C�X�J���f��M�v�̏ꍇ�A�c���Ă���͕̂ۗL���̓�����20�������Ȃ��Ƃ����B�������������ق̂��߁A���V�A�ł̃~�T�C�����Y�\�͂͑啝�Ɍ����Ă���B��������̗A���������i�������g���Ă��邩�炾�B
�ΖC�̒e��ɂ��Ă��A���Ƃ���͂��ł�2022�N���ɂ͋ɂ߂ĕs������Ǝw�E����Ă���B���R���́u�V���ȕ����W�߂����܂������Ă��Ȃ��B���V�A�̐�͂͂���ƁA�N���Ōp��\�͂������邾�낤�v�Ǝw�E����B
�������v�[�`�������Ƃ��ẮA�E�N���C�i�Ɏ哱����D��ꂽ�܂܁A�N�U�����s���鎖�Ԃ������킯�ɂ͂����Ȃ��B���C�ȃv�[�`�����́A�g�ɂȂ�Ȃ�������Ƃ��S���ď�t�]�̃`�����X��_���͂����B���B�ւ̃K�X�������i���āA�ĉ��Ԃ̗������_���Ƃ݂���B
��������ւ̐��_�`�����}�����V�A
���̂��߂ɂ͍����ɒ����킪�K�v�ȗ��R��������A�����푈�x�������������ۂK�v������B�����ړI�ɃN�����������ŋ߁A���_�`���̂��߂ɍs���Ă���̂��A�푈�̑���̓E�N���C�i�����ł͂Ȃ��ANATO�S�̂��Ƃ̃v���p�K���_���B������A���c�e���r�ŕ��������g�[�N�V���[�ł�����`���Ă���BNATO����̐푈�����璷�����͎̂d���Ȃ��Ƃ����������B�����Ɋo������߂�_�����B
�����A�V���C�O���h����2022�N8��24���A���V�A�̐i�R���x��Ă���͖̂��Ԑl�̋]��������邽�߂̈Ӑ}�I�ȑI�����Ɛ��������B���̋ꂵ���ى��́A�����������肩�����ł��������B�v�[�`���������x���Ă����ێ疯���h������N���������ᔻ�̐����o�n�߂��B
���̂��߃V���C�O�����̗����A�v�[�`�����͂���Ăĕێ�h�����Ƀ_���[�W�E�R���g���[���̎��ł����B���V�A�R�̑������2023�N1�������14���l���₵�āA��203��9700�l�Ƃ���哝�̗߂ɏ��������̂��B�N������������̓I�ȑ������ł��Ă��邱�Ƃ������_�����B
�������A���̒���������ۂɕ��͋����ɂȂ���Ƃ̌����͏����h���B���V�A�̌R�����Ƃł��郋�X�����E���r�G�t���́u���������E���ŁA�����V�A�R�͑O��̂Ȃ��K�͂̒�����ꂪ�N���Ă���B�哝�̂̑����߂���ς���Ƃ͎v���Ȃ��v�Ɨ��₩�ɂ݂Ă���B
�ǂ������Ă��ŊJ�̎�������������Ȃ��v�[�`�������B���̒��ŋN�����암�U�|���[�W�����q�͔��d���ł̖C�������́A�N���������ɂƂ��ĕĉ����牽�炩�̏����������o�����߂́u���ˍۍ��v�Ƃ݂���B
�������A�������̂Ƃ������|����������郍�V�A�ɑ��A�ĉ��͗��₩���B���ː������Ƀ|�[�����h�̓��Ŋ��m������NATO�ւ̍U���Ƃ݂Ȃ��Ƃ̋��d�p���őΉ����Ă���B�N�U���݂̂Ȃ炸�A������@�����o����������p�ł����V�A�͍s���l�܂��Ă���B�@
���V�A�̐Ζ���2�ʁu���N�I�C���v��1���̐����ŁA��̃��r���E�}�K�m�t��(67)�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ����B
���V�A�̃C���^�t�@�N�X�ʐM���A���̘b�Ƃ��ē`�����Ƃ���ł́A�}�K�m�t����1�����A�����Տ��a�@�̑�����]�����A����ɂ�����Ŏ��S�����Ƃ����B
���Ђɂ��ƁA���N�I�C���Ђ́A��s�݂ƂȂ����ꍇ�A�������̕������̖������ʂ����Ƃ���Ă���B���N�̎�����̍\���͔��\����Ă��Ȃ����̂́A���X�N���B���@�ȑ�w�̊w��������ɍĎw�����Ă���Ƃ����B
���N�I�C���̓v�[�`���哝�̂̃E�N���C�i�N�U�̌���ɔ�������������ƂŁA�N�U�J�n����A�����́u�O��I��i�ɂ��A����ʂ��āv��������ׂ��Ƃ̐����\���Ă����B
�����Տ��a�@�́A�����E�̃G���[�g�����p���邱�ƂŒm���A�}�K�m�t�������S�������A�v�[�`���哝�͓̂��a�@�ŁA�\�A�Ō�̎w���҂�30���Ɏ��S�����S���o�`���t���哝�̂̒���ɖK�ꂽ�Ƃ����B
���C�^�[�ʐM�ɂ��ƁA���V�A�̃^�X�ʐM�͑{�����ǎ҂̏������ƂɁA���E�Ɠ`���Ă���B�}�K�m�t���͐S������������A�R���܂p���Ă����Ƃ����B
����A�E�N���C�i�N�U���߂����ăN���������ɔ������Ă�����̎��ɁA�l�b�g�ł́A���E���^���������e����Ă���B
�m�[�X�E�E�F�X�g�E�C���O�����h�̎�Ȍ��@���A�i�W���E�A�t�U�����̓c�C�b�^�[�Ɂu�v�[�`���̔ᔻ�I�Ȑl�X�̎���ł́A���ׂ̑����悭������v�ƈÎE�̉\�����w�E�����B
4���A���V�A�̓V�R�K�X��ƃm�o�e�N�̌������̃Z���Q�C�E�v���g�Z�[�j�����Ƃ��̉Ƒ����X�y�C���Ŏ��S���Ă���̂��������ꂽ�B�����A���n�̑{�����ǂ͉Ƒ����E�Q���āA���E���͂������Ƃ݂đ{����i�߂Ă���Ɠ`����ꂽ���A�m�o�e�N�Ђ͂�����^���p���������Ă����B�����A���V�A�O���s�̃K�X�v�����o���N�̌������A�E���W�X���t�E�A�o�G�t��(51)���A�Ȃ�13�̖��ƂƂ��Ƀ��X�N���̃A�p�[�g�Ŏ��S���Ă���̂����������B���n���f�B�A�́A�A�o�G�t������l���E�Q������A���E�����\��������Ɠ`���Ă����B
�挎14���A�v�[�`�����ɔᔻ�I�Œm��ꂽ���g�r�A�n�č��l�̎��ƉƁA�_���E���p�|�[�g��(52)���A���V���g��D.C�̍����A�p�[�g���痎�����Ď��S�����B�x�@�͑��E�̉\����ے肵�Ă�����̂́A�u�v�[�`���ő�̓G�v���ƃr���E�u���E���[���́A�|���e�B�R�̎�ނɁu���̏́A�ɂ߂ċ^�킵���v�Ǝ咣���Ă���B
���V�A�R�ɂ��~�T�C�����˂��u�厸�s�v�����u�Ԃ𑨂����Ƃ݂��铮�悪�A�C���^�[�l�b�g��ɏo����Ă���B
�E�N���C�i�R�̓��ǎ҂ɂ��A8��31���̖�A���V�A�R�͖k�����̃n���L�E(�n���R�t)�Œn��~�T�C���uS300�v6���˂������̂́A���̂���1�����O�����O��A�����ɋ߂����V�A�E�x���S���h�̏Z��X�ɒ��e�����B�x���S���h�̏Z�����l���A���̏u�Ԃ��J�����ŎB�e���Ă����Ƃ����B
�I�[�v���\�[�X�E�C���e���W�F���X�̃A�J�E���gOSINTtechnical���A���s�����~�T�C�����˂𑨂����Ƃ���铮��̈ꕔ�����L�B�u�U���V�X�e���ɉ����[���ȃg���u�����������悤���v�Ǝ��������B
19�b�Ԃ̂��铮��́A���̃~�T�C�����ł��グ��ꂽ��ɐi�s������ς��ċO�������A�ŏI�I�ɂ͒n��ɗ������Ĕ������N�����l�q�𑨂��Ă���B
���P�b�g�����e�������m�ȏꏊ�͂܂��������Ă��Ȃ����A���b�Z�[�W�A�v���u�e���O�����v�̕����̃`�����l���ɂ��A�x���S���h�쐼���̃R���\�����X�L�[���Ƃ݂���B
�x���S���h�B�̃r���`�F�X���t�E�O���g�S�t�m���͎���̃e���O�����̃`�����l���ŁA�s���ŕ����̔���������Ă���A���B�̖h��V�X�e�����쓮�����Ɛ����B���e���_�܂łɓ��������ɂ��A��Q��]���҂͏o�Ă��Ȃ��Əq�ׂ��B
���V�A�R�̐ݔ�����쓮�����Ƃ݂���̂́A�����߂Ăł͂Ȃ��B6���ɂ́A���V�A�̖h��V�X�e������쓮�����u�Ԃ��B�e�������悪�A�\�[�V�������f�B�A��ɏo������B
�~�T�C�������˒n�_�Ɉ����Ԃ��Ă���悤�Ɍ�����u�Ԃ𑨂���������������B�E�N���C�i�����̃��n���X�N(���K���X�N)�B�A���`�F�t�X�N���甭�˂��ꂽ�n��~�T�C�����A���ˌ�ɋO����ς��Ĉ����Ԃ��A���˒n�_�̋߂��ɒ��e�����̂��B
�e���O�����̃`�����l���uKyiv Operative�v���ŏ��ɓ��e�������̓���ɂ́A�~�T�C�������˂��ꂽ����Ɍ�����ς��ċt�߂肵�A���e���đ�K�͂Ȕ������N����l�q���f���Ă���B������ɂ́A�T�C������A���[���̉�����n�߂Ă���B
���̔����Ŕj�ꂽ�A���邢�͑��������ݔ�������̂��ǂ����͕s�����B��Q�҂̒��ɁA���V�A���x�����镪���Ɨ���`�҂��܂܂�Ă������ǂ������������Ă��炸�A���̊�Ȍ�쓮�̌�����������Ȃ������B
�܂�6���ɂ́A���V�A�R�����s�Ń~�T�C�����˂����݂����̂́A�E�N���C�i�̕@��24TV�̓����̕ɂ��A1���ڂ����ˌシ���ɋŔ������Ă��ɂȂ�A�Z��X���炳�قǗ���Ă��Ȃ��Ƃ���ʼnЂ������N�������Ƃ������Ƃ��B
�E�N���C�i�N�U���߂����ă��V�A�̓Ɨ��n�̐��_�����@�ւ́A���V�A�����ł͐N�U�̌p���Ƙa�����ւ̈ڍs�ňӌ������Ă���Ƃ��钲�����ʂ\���܂����B
���V�A�R�ɂ��E�N���C�i�N�U��A���V�A�̐��_�����@�ցu���o�_�Z���^�[�v�͖������{�ɑS����1600�l�]���ΏۂɑΖʌ`���Œ������s���Ă��܂��B
1���A8���̒������ʂ\���A���̒��Łu�R���s���𑱂���ׂ����a�������J�n���ׂ����v�Ƃ�������ɑ��āA
�u�R���s���̌p���v�Ɠ������̂�48���A
�u�a�����̊J�n�v��44���ŁA�ӌ����قړ��܂����B
���̂���40�Ζ����ł͉ߔ������u�a�����v��I��ł��āA�Ⴂ����قǘa�����ւ̈ڍs��]��ł��邱�Ƃ����������܂��B����18����24�܂ł̎�҂�30���́u���V�A�R�̍s�����x�����Ȃ��v�Ɠ����A��������܂钆�ł��A���悻3�l��1�l���N�U�ւ̔��Ύp�����������`�ł��B
�u���o�_�Z���^�[�v�͂�����u�O���̃X�p�C�v���Ӗ�����u�O���̑㗝�l�v�Ɏw�肳��A�����̈��͂��Ȃ�����A�Ǝ��̐��_���������╪�͂𑱂��Ă��܂��B
�E�N���C�i�암�̍`����8���ɔ_�Y���̗A�o���ĊJ���Ĉȍ~�A����܂łɗA�o���ꂽ�����Ȃǂ�100���g�������ƁA���A�����\���܂����B�����A�E�N���C�i�̔_�Ɛ��Y�҂̒�����́A�R���N�U�̉e���Ŏ��엿���������A���N�̎��n�̌����͔������Ȃ��Ƃ����������������o�Ă��܂��B
���C�ɖʂ���E�N���C�i�암�̍`�ł́A���V�A�R�ɂ�镕���ŁA�_�Y���̗A�o�����Ă��܂������A8���A�E�N���C�i�ƃ��V�A�Ƃ̍��ӂɊ�Â��ėA�o���ĊJ���A���A�́A����܂łɗA�o���ꂽ�����Ȃǂ�100���g��������8��27���ɔ��\���܂����B
�A�o�̍ĊJ���i�ވ���A�E�N���C�i�ł́A����̎��n���t���Ɍ��������ʂ����������Y�҂����܂��B
�X�R���j���R�E�����o�c�����荒����Ђ́A�E�N���C�i������12��7000�w�N�^�[���̔_�n�����L���Ă��܂������A���̂����A���悻7���͌R���N�U��Ƀ��V�A���ɏ������ꂽ��A���ɒn���߂�ꂽ�肵�āA�����Ȃǂ̎��n���ł����ɂ���Ƃ������Ƃł��B
����ɁA�����̔_�n�Łu�����Ɣ_�Ɨp�@�B�̂��ׂĂ�D��ꂽ�v�Əq�ׁA������������_�Ɨp�@�B�Ȃǂ̔�Q���z�́A���悻1���h���A���{�~�ɂ��āA���悻140���~�ɏ��Ƒi���܂����B
�R���N�U�̉e���Ŏ����J�肪�������Ȃ钆�A�X�R���j���R�E���́u���N�̍앨�̎���܂��������Ȃ��B�엿�������Ȃ��B���N�̎��n�ʂ͌��I�Ɍ������邾�낤�v�Əq�ׁA����̍�t���ւ̉e���͔������Ȃ��Ƃ��������������������܂����B
�E�N���C�i�N�U�ɉ����A���̌�A�t�����X�ɓ��ꂽ���V�A����JNN�̒P�ƃC���^�r���[�ɉ����܂����B���{�̌����Ă������Ƃ́u���S�ȃE�\���v�B���ӂ̍����ł��B
�N�U�J�n���甼�N���߂����E�N���C�i�B
���V�A�R�ɂ���̂������암�U�|���[�W�������ɂ�IAEA=���ی��q�͋@�ւ̃`�[����1���A�悤�₭�����ɓ���܂������A�������ɍĂю��ӂŖC�����`�����Ă��܂��B
����A�I���Ȃ��N�U�ɉ�����Ă����j���͍��A�ʂ̏ꏊ�ɂ��܂����B
���V�A�R���m �t�B���e�B�G�t����u�ڂɂ����̂́A�X���j��A���a�Ȑ�������Ă���l�q�ł��v
JNN�̒P�ƃC���^�r���[�ɉ������p�x���E�t�B���e�B�G�t����(34)�B���V�A�̐e�q���A���̑����ł������A�C�e�Ŗڂ���A���̓t�����X�E�p���ɂ��܂��B
��`�ɓ��������ۂɂ́A�����̃p�X�|�[�g��j��̂āA���V�A�ւ̋����s���������t�B���e�B�G�t����B
2���̃E�N���C�i�N�U�̍ۂ͓암�w���\���ɔh������܂������A�قږ��߂͎Ă��Ȃ������Ə،����܂����B
���V�A�R���m �t�B���e�B�G�t����u��X�͒N������ǂ����U������A�ړI�͉����A���߂��Ă��܂���ł����v
�܂��A�ߍ��Ȑ�n�̏ƕ��m�����̍s���ɂ��Ắc�B
���V�A�R���m �t�B���e�B�G�t����u�l�����Ȃ��X������A���ׂĂ̌R�l���X��ʂ肪���鎞�ɂ����A���A�H���𓐂�ł����܂����B�����ɂ�������肾�����̂ł��v
�����āA���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɕ��͕͂s�����R�̎m�C���ቺ�B�����̕��m�����̐�n�ɍs�����Ƃ����ۂ��Ă����Ƃ����܂��B
���V�A�R���m �t�B���e�B�G�t����u�R�̑唼�̓v�[�`���������Ă��邵�A9���͌R�ɋ߂����Ƃ��Ȃ����h�������Ă��܂��v
���V�A�ŌR�ւ̔ᔻ�́u�U���v�̗��z�Ƃ��Ĕƍ߈����Ƃ���܂����A��n�ꂽ�t�B���e�B�G�t�����SNS���141�y�[�W�ɋy�Ԏ�L�����\���A���V�A�R�̓����\�I�B
���̓t�����X�ɐ����S�������߂Ă��܂��B�ނ��v�����Ƃ́c�B
���V�A�R���m �t�B���e�B�G�t����u���̐푈�͒N�ɂ��K�v�ł͂Ȃ����A�P�ɖ��Ԑl������ł��邾�����Ƃ������Ƃ��F�킩���Ă��܂��B(���V�A���{�̌������Ƃ�)���S�ȃE�\�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��v
�R�̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��āu�푈���ꍏ�������I��点�����v�B�t�B���e�B�G�t����͂����i���Ă��܂��B
���V�A�̊w�Z�ŐV�w�����n�܂���1���A�v�[�`���哝�̂͐����J���[�j���O���[�h�B�̊w�Z�̋����őS�y����I������W�܂����q�ǂ������Ɩʉ�A���{���F�߂����j�������邱�Ƃ̏d�v���ɂ��Č�����B
�v�[�`������1���Ԃ̎��^�����̒��ŁA�E�N���C�i�����̎q�ǂ��������E�N���C�i�͂��ă��V�A�ƂƂ��Ƀ\�A�Ƃ����������̈ꕔ���������Ƃ𗝉����Ă��Ȃ����Ƃ�m��A�����̓V���b�N�������Əq�ׂ��B����𐳂����Ƃ��ɂ߂ďd�v�ȍ�ƂɂȂ�Ƃ��A���V�A��A�E�N���C�i�̃��V�A��̒n��Ŋw�Z�����V�A���{�̏��F�������Ȃ������邱�Ƃ��d�v���Ƌ��������B
�E�N���C�i�N�U��Ɉ������牻��傫�����i���Ă��郍�V�A���{�́A���̐V�w�����炷�ׂĂ̏��w�Z�ŏT���ɂ͎��Ƃ̑O�ɍ����Ȃǂ��f�g����Z�����j�[���s���A���̂����t���邱�Ƃ��`�����B�v�[�`�����̓\�A����̋��Y�}�N�c�u�R���\���[���v�⏭�N�c�u�s�I�l�[���v�ɂȂ�������{��ɂ̐V���Ȑ��N�g�D�̗�����g�b�v�ɂ��A�C�����B
���V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`��(Vladimir Putin)�哝�̂�1���A�o���g�C(Baltic Sea)���݂ɂ����ђn�J���[�j���O���[�h(Kaliningrad)��K�₵���B�V�w�����}�������k�Ɩʉ�A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U��o�ρA�F���T���Ȃǂ̎���ɉ������B
���B�A��(EU)�ɉ�������|�[�����h�A���g�A�j�A�����ɋ��܂ꂽ�J���[�j���O���[�h�́A�R�����_������Ă���B�E�N���C�i�N�U�J�n��A���V�A��EU�̊Ԃŋْ������܂�A���n�ɂ�8���ɋɒ������e���~�T�C���u�L���W����(Kinzhal)�v�𓋍ڂ����퓬�@3�@���z�����ꂽ�B
�v�[�`���哝�̂̓e���r�������ꂽ�f���̒��Łu�킪���̕��m�̔C���́A���̐푈���~�߁A���������A���R�Ȃ��烍�V�A����邱�Ƃ��v�ƌ�����B����Ɂu�E�N���C�i�͂킪���������������V�A�̔�ђn���\�z���n�߂��v�Ƃ��q�ׂ��B
���g�A�j�A��6���AEU�̐��ّΏۂƂȂ��Ă��镨�i��ς݃J���[�j���O���[�h���������V�A�̗�Ԃ̍����ʉ߂��֎~���A���V�A�͂���ɔ����BEU��7���A����������A���ّΏۂł����Ă����V�A�̉ݕ���ʉ߂�����`�������g�A�j�A�ɂ͂���Ƃ̎w�j�\�����B
���V�A���E�N���C�i�N�U���Ă��甼�N���߂����B�v�[�`���哝�̂̓E�N���C�i�Ń��V�A�n�Z�������Q����Ă��邱�Ƃ�N�U�̐������Ƃ��ċ������Ă��邪�A������@�Ƀ��V�A�ւ̈��͈͂�Ăɋ������ꂽ�B�č��𒆐S�Ƃ��鉢�ď����̓��V�A�ւ̌o�ϐ���(������V�R�K�X�Ȃǂ̗A����~�A���V�A�����̓����֎~�Ȃ�)���������A�}�N�h�i���h��X�^�[�o�b�N�X�Ȃǐ��E�I��Ƃ̓��V�A���犮�S�P�ނ����B���{�ɂ�鐧�ق��A��Ƃ̊��S�P�ނ⎖�Ək���Ƃ������吧�ق̕������ʓI�Ƃ̈ӌ����������A�����ɂ���ă��V�A�o�ς͑傫�ȑ������邱�ƂɂȂ����B
�܂��A���ď����͌R���ʂł��E�N���C�i�ւ̎x�����������A�����܂Ń��V�A�R�̍U����H���~�߂邱�Ƃɐ������Ă���B�N�U�����A�v�[�`���哝�̂͐������x�Ŏ�s�L�[�E�������ł���ƌv�Z���Ă������A�v�[�`���哝�̂��`���N�U�v��͊��Ƀt�B�N�V�����Ɖ����A���V�A�R�͈�i��ނ̍U�h��]�V�Ȃ�����Ă���B
�틵�����������邱�ƂŃ��V�A���̔�J��s�������܂�A�U�������v��A�����ʓI�Ȃ��̂ɂȂ�A�R���헪�Ɋ�Â��U�������E�����e���̗l�����悵�Ă���B�܂��A���V�A���g�p���鍂���\������ꕔ�̍ޗ��Œ��B�悪���ď����ƂȂ��Ă���A�o�ϐ��قɒ��ʂ��邱�ƂŌR���J���ʂł��傫�Ȑ������o�Ă���Ƃ����B���Ăƃ��V�A�Ƃ����\�}�݂̂ł݂�A���V�A�͌o�ϓI�ɂ��R���I�ɂ��傫�ȃ_���[�W����`�ɂȂ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�������A������x�����Ԃ��g�債�Ă���B���́A�E�N���C�i�ɐN�U�������V�A�ɑ��Čo�ϐ��ق����{���Ă���͉̂��Ă���{�Ȃ�40�������܂�ɗ��܂�A������C���h�AASEAN�⒆���A�A�t���J�̖w�ǂ̍��͓Ǝ��̃X�^���X���ێ����Ă���B
���V�A�ւ̌o�ϐ��قɂ���ă��V�A�Y�G�l���M�[���l�����肷�邱�ƂŁA�����̓��V�A�Ƃ̃G�l���M�[�f�Ղ���������X���ɂ���B�܂��AASEAN�⒆���A�A�t���J�ɂ͈�ш�H�ɂ���Ē������瑽�z�̌o�ώx�����鍑�������A���`�I�ɂ͉��Ăɒǐ��������Ă��A��������Όo�ώx�����~�A���z����邱�Ƃ��x�����Ă��鍑�����Ȃ��Ȃ��B���N�H��G20���J�Â���C���h�l�V�A�́A����c�Ƀv�[�`�������҂��邱�Ƃ\���A�C���h�͈����ȃ��V�A�Y�G�l���M�[�̗A���͔������Ȃ��Ƃ��A���V�A�Ƌ�����u���悤���߂鉢�Ă̗v������R�����B
�����������u�Đ��E�v�̊g��A�����̍��v����ɁA���v�����v������V�A�Ƃ������I�ڋ߂����݂�e���̎p�̓v�[�`���������㉟�����Ă���B���ꂪ���̔��N�Ńv�[�`�������������ő�̎��n�ƌ����Ă������낤�B
�Ċɂ��R�����K��8��22������n�܂����Ȃ��A�؍��R��23���A���V�A�̌R�p�@2�@���؍��̖h�ʌ��ɐi�������Ɩ��炩�ɂ����B���V�A���̈Ӑ}�͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ����A�Ċɂ��R�����K���Њd����_�����������\���������B���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U���甼�N���o�߂���Ȃ��A���ĂȂǂ̊Ԃł̓��V�A���ɓ��n��ŌR���I�����������������錜�O�����߂Ă��邪�A�؍��Őe�ēI�Ȑ������a���������Ƃ�����A����̓��V�A�Ɗ؍��Ƃ̊Ԃł����S�ۏ��ْ̋������܂�\��������B
���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U���甼�N�o���Ė��炩�ɂȂ������Ƃ́A���E�̕��f����w�i�݁A���������ꂪ����������l����悵�Ă��邱�Ƃ��B�v�[�`���哝�̂͋��d�ȑԓx������Ă��炸�A�u�Đ��E�v�w�c�͐�s�����邱�ƂŁA�����w���Ăɑ��ċ��C�̑ԓx�őR���Ă��邱�Ƃ��낤�B�O���[�o���������T�v���C�`�F�[���Ԃ̂Ȃ��A�o�ς̃f�J�b�v�����O(�藣��)�͔��I���B�������A���{�Ƃ��Ă̓E�N���C�i�N�U�ň�w�i���f�Љ�̂Ȃ��łǂ��o�ς��x���Ă��������l���Ă����K�v������B
��v7�J��(�f7)�̍�������2���J�Â����I�����C����ŁA���V�A�Y�Ζ�����ѐΖ����i�̉��i�ɏ����ݒ肷��[�u��������j�ō��ӂ����B�������i�̍�����������A�E�N���C�i�N�U�𑱂��郍�V�A�̐��B��j�ށB
�������A�o����������̉��i����ɂ��Ắu�Z�p�I�C���v�b�g�͈̔͂Ɋ�Â��v����l�߂�Ƃ��A�d�v�ȏڍׂ͐��荞�܂�Ă��Ȃ��B
�f7�������͐����Łu���V�A�Y��������ѐΖ����i�̊C��A�����\�ɂ���T�[�r�X�̕�I�ȋ֎~�����肵�A���{����Ƃ��������̐����I�Ӑ}���m�F����v�ƕ\�������B
���i������郍�V�A�Y�Ζ���Ζ����i�̊C��A���ւ̕ی��E���Z�T�[�r�X�Ȃǂ̒͋֎~�����B
�����͂܂��A�u���B�A��(�d�t)�̑�6�����V�A���قɊ܂܂��֘A�[�u�̃X�P�W���[���ɍ��킹�Ď��{���邱�Ƃ�ڎw���v�Ƃ��Ă���B�d�t��12�����烍�V�A�Y�Ζ��̋֗A���{�s����B
�č������Ȃ̍����ɂ��ƁA���V�A�Y�����ɂ��Ă͓���̃h���̉��i�����݂��A�Ζ����i�ɂ��Ă͕ʂ�2��ނ̏����݂��錩�ʂ��B���i�͕K�v�ɉ����Č������Ƃ����B
�c�����h�C�c�̃����g�i�[�������͉�ŁA���V�A�̐Ζ����i�ɏ����݂��邱�ƂŁA���V�A�̍Γ�����������ƂƂ��ɁA�C���t�����}�������Ƃ��A�u�����̓��V�A�̎����𐧌��������B����Ɠ����ɂ����̌o�ςւ̑Ō����y���������v�ƌ�����B
����ɁA�f7�͏���ݒ�ŃR���Z���T�X�`����ڎw���Ă���A�d�t�̑S���������Q�����邱�Ƃ�]��ł���Ƃ����B
�C�G�����č��������������Łu���E�̃G�l���M�[���i�ɉ��������͂�������A�E�N���C�i�ł̎c�E�Ȑ푈�̍����ƂȂ�v�[�`���哝�̂̎�����f�Ƃ���2�̖ڕW�v�B���ɖ𗧂Ƃ����F�����������B
���V�A�哝�̕{�̃y�X�R�t���͂f7�̐������A���E�̐Ζ��s���s���艻������[�u�Ƃ��������������A������i��ݒ肷�鍑���ւ̐Ζ��̔����~����Əq�ׂ��B
�f7�̍����́A���V�A�Y�Ζ����i�̏���ݒ������A����������Q���Ɍ����u�O�����ȃV�O�i��������Ă��邪�A�m�łƂ����R�~�b�g�����g�ɂ͎����Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ��B�����Ɂu�����̓��V�A�⒆���Ȃǂɑ��錋���̃V�O�i���𑗂肽�������v�Əq�ׂ��B
�E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂̃E�X�e���R�㋉�o�όږ�́A���V�A�̎��������炷���߂ɂ܂��ɕK�v�ȑ[�u�v�Ƃ��A�f7��������ł̌�������}�B���i�����40��60�h���̃����W�ɂȂ�Ƃ������ʂ����������B
�[�����X�L�[�哝�̂̓r�f�I�����ŁA���V�A�̓V�R�K�X�A�o�ɂ������݂���ׂ��Ƒi�����B

�E�N���C�i�N�U�̒������́A���������o�ς𒆐S�ɒᐬ���ƃC���t�����̏㏸�Ƃ����Â����ʂ��ɂȂ����Ă���B�������A���V�A�͌������G�l���M�[���i�̗A�o���������������A����̋@�q�Ȋ�@�������A�o�ς͗\�z�ȏ�Ɏ����������Ă���B���J���v���̑I������Ă���Ƃ̎w�E�����邪�A���Ȃ��Ƃ������Ԑ��Y�ɂ��Ă͑啝���Y�������A�M���v�ǂ̔��\���o�Ă���B���V�A�������������암�ł́A�H���Ƀ��V�A�ғ�������Z�����[���{�Ɍ����������i�߂��Ă���B�������A�E�N���C�i�̔����͕K���ł���A�����̓��͌����Ȃ��B������A�E�N���C�i���̐��E�I�ȐH�Ɗ�@�̌��O�������̂����ڂ���Ă���B
�����V�A�o�ς͑z��ȏ�Ɏ����������Ă���H
�E�N���C�i�N�U�������̌��O�������̂��̂ƂȂ�A���E�o�ςɈÂ��e�𗎂Ƃ��Ă���B�E�N���C�i�N�U�̃V���b�N�́A���V�A����̃G�l���M�[�A���ɑ傫���ˑ�����d�t�ɒ��ځE�ԐړI�ȑ�Ō���^���A�o�ς̒ᐬ���ƃC���t�����̏㏸�Ƃ����O���������Ă���B�G�l���M�[����ѐH�Ɖ��i�̋}���͐��E�I�ȃC���t�����͂����߁A�ƌv�̍w���͂��������A����܂őz�肳��Ă������������y�[�X�ł̋��Z����������߂Ɍq�����Ă���B
�h�l�e��2022�N7���̌��ʂ��ł́A������v���̂قڂ��ׂĂ������C�����ꂽ���̂́A���V�A�o�ς͌������G�l���M�[���i�̗A�o���\�z�ȏ�Ɏ����������A2022�N��6�D0���k���Ə���C�����ꂽ(�O��4�����ʂ��ł�8�D5���k��)�B���Z�Z�N�^�[�ւ̐��ق̉e�����ɘa����[�u�����A�J���s��̎�̉������O���ꂽ�قǂł͂Ȃ��A�������v�͊�����̋��x���������Ă���B
����Ƀ��V�A������A�i�C����͒�����������̂́A����܂ł̗\�z�قǐ[���ɂȂ�Ȃ��Ƃ���7���Ɍi�C���ʂ�������C�����Ă���B��Ɗ������A6���\�z���قǒ���Ă��炸�A���V�A��Ƃ��V���ȃT�v���C���[��s����J�A�i���������X�ɉ��Ă���B�f�c�o�̏k�������������Ȃ�Ɨ\�z���ꂽ�̂́A��ɗA�o�̌������z������������������߂ł���B���̌��ʁA���V�A����͋����T�C�h�̗v���ɂ���Ăf�c�o��2022�N��4�`6���k��(4�����ɂ�8�`10���k����\�z)������̂́A2024�N�ɂ͊g��ɓ]����Ɨ\�z���Ă���B
����A�h�l�e�́A�i�C��ނ̋K�͂͑����Ȃ��̂ł���A���V�A�̌o�ϐ�������2023�N�ɑO�N��}�C�i�X3�D5���ƃ��o�E���h�����҂͂ł��Ȃ��Ƃ݂Ă���B����ɕč��C�G�[����w�̒����ł́A���V�A�͑z��ȏ�ɐ��ق̉e�������Ă��邱�Ƃ����������Ǝw�E���Ă���B2��24���̐N�U�ȍ~�A���V�A�̓G�l���M�[���i�̍����ɂ��A�G�l���M�[�A�o�Ő��\���h���̗��v�Ă������A���̃Z�N�^�[�Ɋւ���w�W����́A�����̍����o�ϊ�������~���Ă��邱�Ƃ���������Ă���Ƃ����B
�������ł̓��V�A�����̐��Y�͊��S�ɒ�~���Ă���A����ꂽ�r�W�l�X�A���i�A�l�ނ𑼂ő�p����\�͂����V�A�ɂ͂Ȃ����Ƃ��w�E����Ă���B�܂��A���V�A�ł́A�A���͂قڏ��ł��A�l�ނ╔�i�A�Z�p���ɂ߂ĕs�����Ă���A�v�[�`���哝�̂𐭎��I�Ɏx�����Ă��钆������̏d�v�ȗA���ł����A�����ȉ��Ɍ������Ă���Ƃ������ʂ�������Ă���B���V�A�����̋Z�p�v�V�Ɛ��Y��Ղ̋��́A���i�̍����Ə���҂̕s���ɂȂ����Ă���Ɠ������͌��_�t���Ă���B
�C�O��Ƃ̓P�ނ������A�A�o���s�U�ɂȂ����Ƃ����������ʂ́A���V�A�o�ς��ˑR�Ƃ��Č����ł���A�u�o�ϓI���Ր�v�ɏ������Ă���Ƃ������V�A���{�̎咣�ɐ^��������Η�������̂ł���B�������A�C�O��Ƃ̓P�ނƂ����Ă��A�p�ĂƂ���ȊO�Ƃł͑傫�Ș���������B�C�G�[����w�̓��V�A����̊�Ƃ̓P�ޏɂ��Ă��N�U�J�n����p�����Ē������s���Ă���A����ɂ��u�ʏ�ʂ�v�̋Ɩ��𑱂��Ă���p����Ƃ�1�Ђ݂̂����A�d�t��Ƃ�100�В��ƑΏƓI�ł���B�t�����X�̃��R�X�e�A�C�^���A�̃A���}�[�j��x�l�g���A�I�����_�̃t�B���b�v�X�ȂǁA�����\����悤�Ȋ�Ƃ́A���V�A�s�ꂩ��̓P�ނ�Ɩ��팸�����߂鐺�ɂ�������炸�A����܂Œʂ�̋Ɩ��𑱂��Ă���B
�������Ԕ̔��s�U�̓��V�A���ǂ��F�߂���Ȃ��H
���V�A�́A�f�Փ��v���܂ތ����Ȍo�ϓ��v�̔��\���~�܂��͌��{���A���V�A�ɂƂ��ēs���̗ǂ����v�݂̂����\���Ă���ƃC�G�[����̒����ł͎w�E���Ă���B�������V�A���̓��v�ł����Ɏ����ԂɊւ���w�W�͑傫���������Ă��邱�Ƃ��ǂ݂Ƃ�A�������̎w�E���S�Đ������Ƃ�������Ȃ��B
���V�A�A�M���Ɠ��v�ǂɂ��ƁA2022�N5���Ƀ��V�A�ł̏�p�Ԑ��Y�͂قڒ�~���A�O�N��96�D7�����A���V�A�����Ő��Y���ꂽ��p�Ԃ͂킸��3�C700��ɗ��܂��Ă���B�܂��A�g���b�N�̐��Y���������Ă���A�d�ʃg���b�N�̐��Y��5���ɑO�N��39�D3�����ƂȂ����B�E�N���C�i�N�U������3�����߂ɁA��v�C�O�����ԃ��[�J�[�̑������A���V�A�����ł̊����̈ꎞ���~�\�����B���̂��߁A�H��ł̎����Ԑ��Y�͋x�~���A�����f�B�[���[�ւ̐V�ԋ������~�܂����B
����ɔ������V�A�̏�p�Ԕ̔��s������l�Ɍ����������������Ă���B2022�N7���̐V�Ԕ̔��͑O�N��74�D9����(32�C412��)�A1�`7���ł���60�D5����(368�C850��)�ƂȂ�A�l�C24�u�����h���܂ނقڑS�Ẵ��[�J�[�̐V�Ԕ̔����͋}���������Ă���B���̎���̓f�B�[���[�̂��ƂɐV�Ԃ���������Ă��Ȃ����Ƃł���B
�v�[�`���哝�̂�6�����ɃT���N�g�y�e���u���N�ŊJ�Â��ꂽ�����ԋƊE���W�Ɍ�������ŁA�����ԉ��i�̏㏸�Ɋ֘A���A�s��ɏ\���Ȑ��̎����Ԃ��������邱�Ƃ��K�v�Əq�ׂ��B�܂��A�����ԋƊE�����ݒ��ʂ����v�ȃ^�X�N�Ƃ��āA1�H�ꑀ�Ƃ��p�����A�K�v�Ƃ���镔�i���������A���l�ނ̌ٗp���m�ۂ��邱�ƁA2���i���}�����Ă��鎩���Ԃ̋�����啝�ɑ��₷���Ƃ��������B����ɖ��͏�p�ԂɌ��炸�A���p�Ԃł��m�F����Ă���Ǝw�E���Ă���B���p�Ԃ͔�����ł����Ƃ�A���ƊE���A�s����ȏ��ł̓������T���Ă��邽�߂ł���A���ɁA4�������牢�B�ւ̃��V�A�̗A���g���b�N�̓����E�؍݂��֎~����Ă��邱�Ƃ��傫���Ƃ����B�v�[�`���哝�̂́A���p�Ԏs��̌���ɂ��āA���v���s�����Ă���\��������ƔF�߁A���v���x����ׂ��l�X�Ȏx���v���O�������������邱�Ƃ��Ă����B
���Z�����[�ŃE�N���C�i�����Ɍ����͂��̂��H
����̃��V�A�o�ς�\�������ł��������Ȃ��̂��A�E�N���C�i�N�U���ǂ̂悤�Ȍ`�ŁA���I�����邩�̌��ʂ��ł��낤�B2��15���A���V�A���@���h�l�c�N�l�����a���ƃ��K���X�N�l�����a�������Ə��F�������Ƃ́A�����a���̃��V�A�n�Z���ی�̌��������V�A�ɗ^�����B����𗝗R�Ɏn�܂����E�N���C�i�ɂ����郍�V�A�̌R�������́A�L�[�E�U���̎��s��ɓ��������ւƏœ_���ڂ����B���킪�J��L�����A���V�A�R�̐������ɂ���n�悪���X�Ɋg�債�Ă���B�����a���ł́A���V�A�ւ̕ғ������₤�Z�����[�̏������i�߂��Ă���B���ɓ��[�̘g�g�݂͐����Ă���A�I���l������쐬����A�I���ψ��̔C�����ς�ł���Ƃ����B
�܂��A���[����1���ł͂Ȃ��A2���Ԃɂ���Ƃ̈Ă���������Ă���B7���ɗאڂ��郍�V�A�̃��X�g�t�B�̑I���ψ������̏����̂��߂Ƀh���o�X�n���ɔh�����ꂽ�B7�����_�œ��n���ɂ�77�J���̓��[�����ݒu����Ă���Ƃ����B8���O�̓��[���{����������Ă������A���V�A�R�������a���ƃE�N���C�i���Ƃ̍s�������ɂ܂œP�ނ��A(�E�N���C�i�R���N�U�ł��Ȃ�)���S�ۏ�]�[��������Ă�����{�����\��̂��߁A�R������̍��}�҂��̏�Ԃɂ���B�����a���̓��V�A�ł͈�̒n��Ƃ��ĔF������Ă���A���V�A���{���Ɨ����ɏ��F�������Ƃ���A�Z�����[��(�����a����)�����Ɏ��{�Ƃ����̂���{�I�ȍl���ł���B�Ȃ��A�����a���̐��_�ɂ����Ă̓��V�A�x�������m�����A�h���o�X�n���ł��E�N���C�i�N�U�J�n��Ƀ��V�A�x�z���ƂȂ����n��ł́A���������鐢�_�͈��ł͂Ȃ��Ƃ����B���m�ȓ��t�͐ݒ肳��Ă��Ȃ����A�����n��̐������i�߂ΏZ�����[��9��15���܂łɎ��{�����Ƃ̕�����B
�܂����V�A�R�̓E�N���C�i�암�ł����l�Ɍ���𑱂��Ȃ���A�����n����g�債�Ă���A7�����̎��_�ŃE�N���C�i�̓y�̖�20�������V�A�̎x�z���ɂ���ƕ��Ă���B����܂Ń��V�A�͓암���������������d������p�����݂��Ă������A7��20���Ƀ��u���t�O���͓암���I�Ɏx�z������j�m�Ɏ����Ă���B�ꕔ�ɂ��A�암�̎�v�s�s�A�w���\����U�|���[�W���A�k�����̃n���L�E�Ȃǃ��V�A�����n��ł́A�����ғ��x�������A���̑唼�͏��ɓI�Ȏx���Ƃ����B�܂�ϋɓI�Ȏx���͂���10�`15���ɂ������A2�������ɉ��\��������A�c��3���̓E�N���C�i�c����������炵�������y�ɂȂ�̂ł���Ƃ��������ł̎x�����Ƃ����B����͌����Ȑ��_�����ł͂Ȃ��A�Z�����[�̏����Ɍg����Ă���W�҂̌����ɂ����Ȃ��B7��23���Ƀ��V�A���C�������U�|���[�W���̎b��g�b�v�́A���V�A�ғ�������Z�����[�̑����ƂȂ�I���ψ����ݗ����邽�߂̐��߂ɏ������Ă���B���V�A�͓����A�����n��̕ғ��ł͂Ȃ��E�N���C�i����̕�����ڎw���Ă������A�����n��ɂ�����e���V�A�h�ւ̐M���������ꂽ���Ƃ����蒼�ړI�Ȏx�z�ւƐ헪�ύX�ɏo���ƍl�����Ă���B
���C�X�^���u�[������́A���E�I�ȐH�Ɗ�@������ł��邩�H
����ɐN�U�̒������ōł����O����Ă���̂��A�H�Ɩ��ł��낤�B�E�N���C�i�́u���B�̃p�������v�Ə̂����悤�ɁA������Ђ܂����̎�v���Y�E�A�o���ł���B�_�Ƃ̓E�N���C�i�̑S�A�o�z��4���ȏ���߁A�N�U�O�ɂ͌ٗp��15����S���Ă����B�A�t���J�⒆���̔��W�r�㍑����v�A�o��ł���A���C����{�X�|���X�C�����o�R���ăT�n���ȓ�ւƌ��������[�g����ʓI�ł������B�Ⴆ���o�m���ł͏����A���ɐ�߂�E�N���C�i�Y�����̊�����8���ɂ��y��ł����B�������A���V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɂ��A�g���R��o�m���A�V���A��\�}���A�Ƃ����������͂��ߐ��E�I�ɐH�Ɖ��i���������������A���V�A�����C���C�㕕���������߁A������ςA�o�D���o�`�ł����A�E�N���C�i�ɑؗ����Ă��鍒����2�C000�`2�C600���g���Ƃ݂��Ă���B�E�N���C�i�ő�̍`�p�s�s�ł���A�����A�o�̃^�[�~�i���ł���I�f�[�T�ł͂���܂Ŏ�v�Ȑ퓬�͉������Ă������A�`����邽�߂ɃE�N���C�i�͋@����~�݂��A���V�A���C�㕕���ɓ��ݐ��Ă����B
���E�I�ɐ��S���l���Q�[�̋���ɒ��ʂ���Ȃ��A���V�A���{�͂��̐ӔC���E�N���C�i��������ɕ��킹�悤�Ƃ����B�A�t���J�����̎�]�ɑ��A����珔���ł̐H�Ɠ�̓��V�A�̔_�앨�A�o�ɑ����������̐��ق��������ꂽ���߂��ƁA���U�̎咣��W�J���Ă������߁A���V�A�̂��̌�̓��������ڂ���Ă����B������7���ɍ��A�ƃg���R������A���V�A�ƃE�N���C�i���N�U�J�n�㏉�߂č��ӂ�������ɂ��A8��1����5�J���ɂ킽�郍�V�A�̍��C������������A�I�f�[�T����E�N���C�i�̍����A�o�D���o�`���邱�Ƃ��ł����B���̂�����C�X�^���u�[������ł́A�@�����~�݂��ꂽ�`�p�t�߂̊C��ł́A�E�N���C�i�̑D�������A���D��U�����A���̊ԃ��V�A�͗A���D���U�����Ȃ����ƁA�܂��E�N���C�i�Ɍ������A���D������𖧗A����̂ł͂Ȃ����Ƃ������V�A�̌��O����A�A���D���������邱�Ƃ����ӂ��ꂽ�B����������ɍ����A�o�D���E�N���C�i���o�`���A���肭�鐢�E�I�ȐH�Ɗ�@�̊ɘa�ɂȂ��邩�A����̌��ʂ����ڂ���Ă���B
�ؗ����Ă��������D�̖����ȍq�s�������A����ɑ���M���������܂�A�܂��C�O����ݕ��D�����`����X�y�[�X���m�ۂ���A����I�ȑD���̉������ĊJ����邱�Ƃ����҂���Ă���B�T�n���ȓ�̍`�p�͐������A���^�D�����p����邽�߁A�E�N���C�i���`���̌����ɂ͒��ւ̗ł���Ƃ݂��Ă���ق��A���}�ς���\��������ȏ�A�E�N���C�i���`�ɒ�R���o����D������Ȃ��Ȃ��B���̂��߁A�E�N���C�i����̍����A�o���N�U�O�̐����ɖ߂�A�H�Ɗ�@���ɘa�����ɂ͐��J��������ƁA�E�N���C�i�̃N�u���R�E�E�C���t�����͐T�d�Ȍ����������Ă���B�Ȃ��A���荇�ӑO�ɂ͂��̍��C����̃��[�g�ɂ��A�o�ĊJ�̌��ʂ���A���E�I�Ȍi�C��ނւ̌��O�A���V�A�ł̉ߋ��ō��ƂȂ�앨�̎��n�Ȃǂɂ��A�_�앨���i�̉��i�͉������Ă��Ă����B�������E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂����V�A�Ƃ̓O��R��̎p���������Ă��邽�߁A�N���ɒ������J�n�����\�����Ⴂ�B������A�E�N���C�i���̐��E�I�ȐH�Ɗ�@�̌��O�������̂����ڂ���Ă���B
�č����Ȃ̃I�u���C�G�����ْ�������2���A���V�A�����������ɂ��R���ړI�ȂǂɎg�p�����n�C�e�N���i�ւ̐��ق����������낤�Ƃ��Ă�����̂̎��s���A�C�O����̎������B�ɋꂵ��ł���Ƃ����F�����������B
�I�u���C�G�����́A���B�A��(�d�t)���ǎ҂Ƃ̉�̂��߂ɖK��Ă���u�����b�Z���ŋL�Ғc�ɑ��A���V�A���ق��u�@�\���Ă���v�Ƃ��A�u���V�A���@��⎑������肵�悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͔c�����Ă��邪�A���܂������Ă���Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v�ƌ�����B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂͂���܂łɁA���قɂ�郍�V�A�o�ςւ̉e����F�߂��A�����́u�o�ϓd����v�͎��s�����Ɣ������Ă���B
�ꕔ�̂d�t���ǎ҂́A������C���h���R���ړI�Ɏg�p�ł���@������V�A�ɔ̔����A���ى�����菕������\�������O���Ă���B�������I�u���C�G�����́A�����������V�A�̎��݂͎��s���Ă���Ƃ��A�u���V�A�͌��m��ʋƎ҂���s�m���ȉ��i�ŕi���̕s���ȋ@��̓�����������Ă���B���̂悤�ȕ���ł͋ߑ�o�ς͐��藧���Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�܂��A���������͍��㐔�J���Ń��V�A���{�ւ̈��͂����߁A���ق̔��������ӂ����Ɠ����Ƀ��V�A�o�ς́u�v�Ձv�ɏœ_�Ă�Ƃ����F�����������B�@
�����V�A�͈������狭�� �w�Z�ō����f�g�ƍ��̐ď��`���Â�
���V�A�̃v�[�`�������͈���������������Ă��܂��B
���V�A���{�́A�V�����w�N���n�܂����������爤���S����ނ��߂��Ƃ��āA���T���j���ɁA�w�Z�ł̍����̌f�g�ƍ��̂̐ď�����Ăɋ`���Â����ق��u��Ȃ��Ƃ�b�����v�Ƃ������̎��Ƃ�V���ɐ݂��A���V�A�Ǝ��̗��j�ςȂǂ������Ă����Ƃ��Ă��܂��B
����1���A��s���X�N���s���̊w�Z�ōs��ꂽ�n�Ǝ��ł́A���̂ƂƂ��ɍ����f�g���s���A�V�����������^���ȕ\��Ō��߂Ă��܂����B
���k��1�l�́u���̎���Ɉ����S����ނ��Ƃ́A�ƂĂ��d�v�ł��B����ɂ��Ă͂��܂��܂Ȉӌ�������܂����A�c���ւ̒����S�����������邱�Ƃ��K�v���v�Ƙb���Ă��܂����B
�v�[�`���哝�̎��g��1���A�e�n����W�߂�ꂽ�q�ǂ�������O�ɓ��ʎ��Ƃ��J���A�E�N���C�i�N�U���d�˂Đ������������ƁA�o�Ȃ����q�ǂ������ƂƂ��ɁA���̏�ō��̂�ď����܂����B
�v�[�`�������Ƃ��ẮA��҂̊ԂŌR���N�U�ɔے�I�Ȉӌ�����r�I����������钆�A�u�����S����ށv�Ƃ������ڂ̂��ƁA�q�ǂ��̂��납�琭�����̎咣���������ނ˂炢������Ƃ݂��܂��B
���U�|���[�W������ �g���V�A���̖W�Q��IAEA�͌����ȕ]������h
IAEA�̐��ƃ`�[���́A���V�A�R�̕������W�J����E�N���C�i�쓌���̃U�|���[�W�������ɍ���1����������Ē�����i�߂Ă��܂��B
�`�[���𗦂����O���b�V�����ǒ���2���AIAEA�̖{��������I�[�X�g���A�̃E�B�[���ɖ߂��ċL�҉���uIAEA������ʼn����N���Ă��邩���m�F���邱�Ƃ́A���Ԃ̈��艻�Ɍ����ďd�v�Ȍ��ʂ�����v�Əq�ׁA6�l�̐��Ƃ����n�ɂƂǂ܂�A2�l�����T�ȍ~���풓������j�������܂����B
����A�������^�c����E�N���C�i�̌��q�͔��d���ЃG�l���S�A�g����2���u���V�A���͕��m�̂����@�Ǘ��̎{�݂ɐ��Ƃ��������邱�Ƃ�F�߂Ȃ������v�Ƃ��āAIAEA�͌����ɕ]������̂�����ɒu����Ă���Ƃ��������������܂����B
����ɑ��ăO���b�V�����ǒ��́u�����Ăق����Ɨ��ꏊ�����邱�Ƃ��ł����v�Əq�ׁA�Ɨ������������ł��Ă���Ƃ����F���������A���T�O���ɕ����܂Ƃ߂�Ƃ��Ă��܂��B
���^�]��~�̃U�|���[�W������5���@ �^�]���ĊJ
�E�N���C�i�̌��q�͔��d���Ёu�G�l���S�A�g���v��2���A�O���̖C���ɂ��^�]���~���Ă����U�|���[�W�����q�͔��d��5���@�ɂ��āu���d�Ԃɐڑ����A�o�͂��グ�Ă���v��SNS�ɓ��e���A�^�]���ĊJ�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
����ŁA�ғ����̌��q�F�͍��킹��2��ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B
���ȃE�N���C�i�N�U�𑱂��郍�V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂��A�����ł͂��ߌ��ȁu���d�h�v�ɋ�������Ă���B�V�������I���K���q�W�҂̕s�R�����������A�u�v�[�`���̓��]�v�ƌĂ��v�z�Ƃ̖����E�Q���ꂽ�B�u�v�[�`�������ł�����鑶�݁v�̉e��������Ă���B
������]����
���V�A�̐Ζ���胋�N�I�C���́A���r���E�}�K�m�t�(67)���u�d�a�Ŏ��������v�Ɣ��\�����B���C�^�[�ʐM�́A1���ɕa�@�̑�����]�������Ɠ`�����B
�E�N���C�i�N�U�O�ォ��A�I���K���q�W�҂̕s�R���⎩�E���������đ����ɋN���Ă���B
���N�I�C����3���A�E�N���C�i�N�U���u�ߌ��I�o�����v�Ƃ��A����������ɂ����������Ăт����Ă����B���d�h�̕s�����Ă������Ƃ͊m�����B
8��19���Ƀ��V�A�̎v�z�ƁA�A���N�T���h���E�h�D�[�M�����̖��A�_���A�E�h�D�[�M�i�������E���ꂽ�����ł́A�E�N���C�i���ƈ��S�ۏ��c�̃I���N�V�[�E�_�j�[���t���L�����V�A�̒���@�ցA�A�M�ۈ���(�e�r�a)�̊֗^�����������B�u���V�A�ł͐푈�ւ̎x�����ቺ���Ă���A�N��������(�哝�̕{)�͍����̓�����K�v�Ƃ��Ă���B�e�r�a�̓��V�A�̓s�s�Ńe���U����g�D���A��ʂ̖��Ԑl�̎����҂��o���Ƃ݂��A�h�D�[�M�i���͂��̗�̍ŏ����v�Ǝw�E�����B
�������U����
�}�g�喼�_�����̒�����Y���́u�e�r�a���ɂ͔���h�Ƌ��d�h�o�������邪�A���d�h�̔ƍs�������ꍇ�A���튴���h���_����A���_�𐨂��Â��郁�b�Z�[�W�ɂȂ�v�Ǝw�E����B
�v�[�`�������f�����u���ʌR�����v���D��������Ȃ��A�S�ʓI�ȁu�푈�v�ɓ��ݐ�ׂ����ƈ��͂�������̂����d�h�̃X�^���X���B
�E�N���C�i�암�U�|���W�G�����ւ̍U���ɂ��Ă��A�u�j�U�����咣���鋭�d�h�̈��͂f���Ă���\��������B���ߌ��ȋ��d�h�̑��݂́A�v�[�`�����̔Y�݂̎�ɂȂ��Ă���v�ƒ������͕��͂���B
�v�[�`�����̑��߂ɂ̓E���W�[�~���E���W���X�L�[�哝�̕⍲����j�R���C�E�p�g���V�F�t���S�ۏ��c���L�狭�d�h�Ƃ݂���l���͑����B
�O�o�̒������́u�p�g���V�F�t���̑��q�A�h�~�g���[������p���ɉ\���ꂽ���Ƃ�����B���d�h�̎v���ʂ�ɂȂ�Ȃ��ꍇ�A�v�[�`�����̑ޏ�ɓ����\���͏\���ɂ���v�ƌ�����B
���V�A�R����������E�N���C�i�̃U�|���[�W�����q�͔��d���ɂ��āAIAEA�����ی��q�͋@�ւ̃O���b�V�����ǒ���2���A�����̈��S���m�ۂ��邽�߁A���n�Œ������s���������Ő��Ƃ��풓��������j�������܂����B����A�����ɋ߂��E�N���C�i�암�ł͍����������퓬�������Ă���Ƃ݂��A�����ɒ������������邩�͗\�f�������Ȃ���ł��B
IAEA�̐��ƃ`�[���́A���V�A�R�̕������W�J����E�N���C�i�쓌���̃U�|���[�W�������ɍ���1����������Ē�����i�߂Ă��܂��B
�`�[���𗦂����O���b�V�����ǒ���2���AIAEA�̖{��������I�[�X�g���A�̃E�B�[���ɖ߂��ċL�҉���u�����Ăق����Ɨ��ꏊ�����邱�Ƃ��ł����v�Əq�ׁA�Ɨ������������ł��Ă���Ƃ����F���������A���T�O���ɂ������܂Ƃ߂邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
���̂����ŁuIAEA������ʼn����N���Ă��邩���m�F���邱�Ƃ́A���Ԃ̈��艻�Ɍ����ďd�v�Ȍ��ʂ�����v�Əq�ׁA����2�l�𗈏T�ȍ~���풓��������j�������܂����B
�����A�C�M���X���h�Ȃ�2���ɔ��\�������͂Łu���V�A�R����������U�|���[�W�������ɋ߂��E�N���C�i�암�Ō������퓬�������Ă���v�Ǝw�E���Ă��āA�����ɒ������������邩�͗\�f�������Ȃ���ł��B
���V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂��A����܂łɃE�N���C�i�ł̐푈�Ŕ�����ł��傫��5�̑������A���킹��10���h���ȏ�ɂ̂ڂ邱�Ƃ����������B
�ăt�H�[�u�X���̌v�Z�ɂ��A���V�A�R�ɂƂ��čő�̒Ɏ�ƂȂ����̂́A���V�A���C�͑��̊��͂ł���~�T�C�����m�́u���X�N���v�̒��v���B4���ɒ��v�����u���X�N���v�̉��l�́A7��5000���h�������Ƃ���Ă���B�E�N���C�i���͎����������Ί̓~�T�C���𖽒������Ē��v�������Ǝ咣�������A���V�A���͊͏�ł̉Ђ������������Ǝ咣���Ă���B
�c��4�̏d�呹���́A8600���h�������̃C�����[�V��IL76�A���@�A7500���h�������̑�^�g���́u�T���g�t�v�A5000���h�������̃X�z�[�CSu30SM�퓬�@�A4000���h�������̃X�z�[�CSu34�퓬�@�ŁA���������v�����10���h��������v�Z�ɂȂ�B
�t�H�[�u�X�̌v�Z�ɂ��A�R���N�U���J�n����2��24������8��24���܂ł�6�J���ԂŁA���V�A�R��1��2142�_�̌R�������i�������A���̉��l�͍��v��165��6000���h�������ɂ̂ڂ�B�~�T�C���́A���̍��v�z�ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ��Ƃ����B
���u�v���ȏ����v�̖ژ_�������ꂽ
���V�A�ɂ��E�N���C�i�ւ̌R���N�U�́A�E�N���C�i�̓Ɨ��L�O���ł�������8��24���ɁA�J�n���甼�N�̐ߖڂ��}�����B���V�A���v���ɏ��������߂邾�낤�Ƃ����ꕔ�̗\�z�́A���������̎x�������E�N���C�i���̔S�苭����R�ɂ���đł��ӂ��ꂽ�B���̐��T�Ԃ́A�E�N���C�i���A�����J�̍��@�����P�b�g�C�V�X�e��(HIMARS=�n�C�}�[�X)�ȂǁA�����������狟�^���ꂽ�������g���āA���V�A���̕W�I�ւ̍U���𐬌������Ă���B
�E�N���C�i�������X�ƍU���𐬌�������Ȃ��A���V�A���{�͕������[���邽�߂ɋ������p���s���A�����镺�m�ɂ��A�m�C���グ�邽�߂Ɍ����x���̃C���Z���e�B�u��^���Ă���Ƃ݂���B
���ė��R�叫�̃o���[�E�}�b�J�t���[��8��22���A�c�C�b�^�[�ւ̓��e�ŁA�v�[�`���́u�����s���āv����A�ނɂƂ��Ă͍̏���A�}���Ɉ������Ă������낤�Əq�ׂ��B�}�b�J�t���[�͂܂��A���V�A�R�́u���ʂō���ȏɂ���v�A���V�A�S�̂Ɂu�R���I�ȑ����ƌo�ϓI�ȌǗ��̐[���ȂЂ��݂������n�߂Ă���v�Ƃ��w�E�����B
�����V�A�́u�ڕW�B���v�̋��C�p���������
�����}�b�J�t���[�̕]���Ƃ͑ΏƓI�ɁA���V�A�͂��́u���ʌR�����v�𐬌������鎩�M������Ǝ咣�������Ă���B���V�A�O���ȏ��o�ŋǂ̃C�����E�l�`���[�G�t�����́A18���̋L�҉�̒��ŁA�E�N���C�i�ɂ����郍�V�A�̖ڕW�͒B������邾�낤�ƌ�����B
�u���V�A�̖ڕW���B������ď��߂āA�n��̕��a�A����ƈ��S��ۏႷ�邱�Ƃ��\�ɂȂ�v�ƃl�`���[�G�t�͏q�ׂ��B
���V�A�R�Ɣ�r���āA�E�N���C�i�R������̐퓬�łǂꂾ���̑����������̂��́A�͂����蕪�����Ă��Ȃ��B�ċc����ǂ�6���㔼�ɔ��\�������̒��ŁA�E�N���C�i�R�������̔������������Ƃ����A�n�㕔������x���i�ߊ��E�H���f�B�~���E�J���y���R�y���̐�����Љ���Ⴊ���邮�炢���B
���V�A�Ńv�[�`�������ƈ�����悷�Ɨ��n���_�����@�փ��o�_�E�Z���^�[��1���A8�����{�Ɏ��{�������V�A�̃E�N���C�i�ł́u����R�����v�Ɋւ��鐢�_�����ŁA���p�����a�����c�Ɉڍs���ׂ����ǂ���������ӌ��������Ƃ̌��ʂ\�����B
���V�A�̃E�N���C�i�N���J�n���甼�N���o�߂��A�}��(����)���[�h�����킶��ƍL����n�߂Ă���\��������B
�����p�����ׂ����Ƃ̉�48���������̂ɑ��A44�����a�����c�̊J�n���x�������B40�Ζ����ł́A�a�����c�ւ̎x�������p�����������B
���ւ̎x�����̂�76���ƍ��~�܂肵���B�E�N���C�i�암�w���\���A�U�|���[�W�����B�̘I�R��̒n��̏����ɂ��Ă̒����ł́A45�������V�A�ւ̕������x�������B�v�[�`�������ɂ��v���p�K���_�̐Z�����������킹��B
�č��h���ȍ�����3���܂łɁA���V�A�̃v�[�`���哝�̂��ŋߖ��߂��������R�̋K�͊g��ɐG��A��������\���͏��Ȃ��Ƃ̌������������B
���V�A�R�̉ߋ��Ɍ��y���Ȃ���A�K�͊g��̖ڕW�l��B����������͂Ȃ��Ƌ��������B�v�[�`�����͐�ɁA���V�A�R�̋K�͂����s�̖�190���l����204���l�Ɋg�傷��哝�̗߂ɏ��������B���̑哝�̗߂͗��N1��1���ɔ�������B
�č��h���ȍ����́A�V�����W�߂邽�߂ɔN����̓P�p��Y�����̎�Y�҂̎�荞�݂Ȃǂ̑[�u���u���Ă��A���V�A�R�̐퓬�\�͂̌���ɂ͂Ȃ���Ȃ��\���Ɍ��y�B�����̐V���ȐV����W��ł��o�������̂́A��荂��ŌR���ɕs�K�i�Ȑl���̗̍p�A�s�\���ȌP���ɂȂ��������Ԃɒ��ʂ������Ƃ��l������Ǝw�E�����B
�E�N���C�i�ւ̌R���N�U�̑O�A���V�A�R�͖ڕW�Ƃ��Ă����l���K�͂Ɋ���15���l����Ȃ������ɂ������\��������Ƃ����B
�ٔ������������E�N���C�i�̃U�|���[�W������������A�g���R�̃G���h�A���哝�̂����V�A�̃v�[�`���哝�̂ɍĂђ������\���o�܂����B
�g���R�̃G���h�A���哝�̂�3���A���V�A�̃v�[�`���哝�̂Ɠd�b�ʼn�k���܂����B
�g���R�哝�̕{�ɂ��܂��ƁA�G���h�A���哝�̂̓��V�A�R���苒�𑱂���E�N���C�i�암�̃U�|���[�W������������A���Ԃ̑ŊJ��ڎw���Ē�������ʂ����ӌ���`�����Ƃ������Ƃł��B
�挎30���ɖS���Ȃ����S���o�`���t���哝�̂̑��V���s��ꂽ���ł�����A�G���h�A���哝�͈̂����̈ӂ��������Ƃ������Ƃł��B
����]�͍���15������E�Y�x�L�X�^���ōs�����C���͋@�\�̉�c�ʼn�\��ł��B
�g���R�͂���܂Ń��V�A�ƃE�N���C�i�̒�틦�c�̂ق��A�E�N���C�i�̍��C����̍����A���������Ă���������ʂ����Ă��܂����B
���V�A���E�N���C�i�ւ̌R���N�U���J�n���Ă���A8��24���Ŕ��N���o�߂����B�������퓬�͍��A�V���ȋǖʂ��}���Ă���B
���N�U�J�n���甼�N�@���݂̐틵
2��24���A�v�[�`���哝�̂��u���ʌR���������肵���v�Ɛ錾��������A���V�A�R���E�N���C�i�����ɐN�U�����B�v�[�`���哝�͓̂�������g�j�̎g�p�h����������Ă��āA���ĂȂ����Ԃɐ��E���Ռ������B
���݂̐틵�⍡��̌��ʂ��ɂ��āA���V�A�����ɏڂ����c��`�m��w�̜A���z�q�����ɘb���B
Q. �N�U�J�n����3�J����5����8�����݂ł́A���V�A�R�̐����n�悪�قƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B�Ȃ��ł��傤���B
�A���z�q����:�@�E�N���C�i�������ɑP�킵�Ă���Ƃ������Ƃ͋������܂��B���Ă̎x���╺�킪����t���Ă��āA���V�A�͑z��O��������R�ɂ����Ă��܂��B�܂��A���V�A�̕��͂�����Ă��܂���B�����ŕ��m���W�߂Ă͂��܂����A�P�����\���ɂ��Ȃ��܂ܑO���ɑ��荞��ł��܂����A�m�C���Ⴂ�B�⋋�����܂������Ă��炸�A���ߌn�������܂��@�\���Ă��܂���B���̂��߂ɐ틵���P��(�������Ⴍ)���Ă���ƍl�����܂��B
���N���~�A�ł̍U�h�������@�E�N���C�i�̍l����
����A8���ɓ����čU�h���������Ă���̂��A2014�N���烍�V�A�ɂ������x�z�������N���~�A�������B
9���ɂ̓��V�A�R�p��s��ő�K�͔����A16���ɒe��ۊǏ�A18���ɂ͔���������2�J���̔������N���A�����20���ɂ̓��V�A���C�͑��i�ߕ��Ƀh���[�������ĉ����̏�ɗ��������サ���B�����̍U���́A�����ȕ\���͂Ȃ����E�N���C�i���ɂ����̂Ƃ݂��Ă���B
Q. �A�������̓E�N���C�i���̑_�����u�N���~�A�����ł͂Ȃ��A����N�U���ꂽ�암�̒D�ҁv�ƍl�����Ă��܂����A�ǂ��������Ƃł��傤���B
�A���z�q����:�@���V�A��9����{�ɓ암�Ɠ��������킹�ďZ�����[�����悤�Ƃ��Ă��܂����B���̏ł͖����Ƃ����b���o�Ă��܂����A������ɂ���E�N���C�i���암�����Ԃ��A���V�A�ɂ��Z�����[�̎��{�͓���Ȃ�܂��B������A�E�N���C�i�͓암�����Ԃ����ƕK���Ȃ�ł��B�암�̐���ɂ��ẮA���V�A�̓N���~�A�����_�ɂ��Ă���̂ŁA���̋��_���U������Γ암�ւ̃��V�A�̍U��������Ȃ�Ƃ������Ƃ�����܂��B�Z�����[���s����A�N���~�A�������̂悤�Ƀ��V�A�����̂܂��������Ă��܂��\���������̂ŁA�E�N���C�i���烍�V�A�ւ́u�암���N���~�A�̂悤�ɂ͎�点�Ȃ���v�Ƃ����悤�ȃ��b�Z�[�W������Ǝv���܂��B
Q. 8��23���̉�c�ŁA�[�����X�L�[�哝�̂́u�S�Ă̓N���~�A����n�܂�N���~�A�ŏI���v�Ƃ����������������悤�ł��B�����ʂ�ǂ߂u�N���~�A��D�҂���܂ł��̐푈�͏I���Ȃ��v�Ǝ��܂����A����͖{���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����B
�A���z�q����:�@�����ɗ��āA�N���~�A�D�҂܂ł�����ɓ��ꂽ�������o�Ă��Ă���悤�Ɏv���܂��B���������ɂȂ�A���V�A�R���c�s�ȍs�ׂ���������s���Ă��܂��̂ŁA���̂܂܂݂��݂������Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B�����������̔��[�̓N���~�A����n�܂��Ă���Ƃ����̂�����܂��B�E�N���C�i�̕������̓]���Ƃ����̂��ŋߐF�Z�������Ă��Ă��āA���Ă��ĉ����Ă��铮��������܂��B
�A���z�q����:�@���Ă͍���̐N�U���n�܂������A�u�N���~�A�͒��߂ē���2�B�Ō������v�Ƃ��������͋C�ł������A�ŋ߂̓N���~�A�D�҂Ɍ����Ă����͓I�Ȏp���������Ă��Ă��܂��B�����A�N���~�A�����ɂȂ�ƁA���V�A�������ȋK�͂Ő퓬��W�J���܂��B���V�A���g�푈�錾�h�����č���̂ƂȂ��Đ���Ă���\���������B�����Ȃ�Ƒ�O�����E���A�j�g�p�̋��������܂��̂ŁA���Ă��u�N���~�A�D�҂܂Ŏx�����Ă��������v�Ƃ����v��������A�܂������܂Ō��ӂł��Ȃ��Ƃ����Ƃ��낾�Ǝv���܂��B
���|�C���g�́g���̓~�h�@���Ă̎x��������
Q. �퓬���������A�ǂ��炪�D�ʂɂȂ�܂����B
�A���z�q����:�@���V�A�ł��B���݁A���V�A�̓G�l���M�[�̗A�o�����Ăɑ��Ď~�߂Ă��܂��B���ł���G�l���M�[���i�͑��������Ȃ��Ă��܂����A�~�ɂȂ�ƒg�[�ŃG�l���M�[�̎��v�������̂ŁA���[���b�p���镉�S�͂�荂���Ȃ�܂��B�����Ȃ�ƁA�E�N���C�i�x���ɉ����グ�鍑��������\���������B���V�A�́g�E�N���C�i�x�����h��_���Ă��܂��B
���V�A�̃y�X�R�t�哝�̕���2���A�v�[�`���哝�̂���K�͌R�����K�u�{�X�g�[�N(����)2022�v��6���ɋɓ��E���W�I�X�g�N�Ŏ��@����Ɩ��炩�ɂ����B
�^�X�ʐM���`�����B�E���W�I�X�g�N�ŊJ�����铌���o�σt�H�[����(5�`8��)��7���̑S�̉�ʼn�������O�ɗ�����邱�ƂɂȂ�Ƃ����B
�v�[�`�����̃{�X�g�[�N���@��2��A���B�O��4�N�O�͕�����30���l���Q���������A����̓E�N���C�i�N�U�̉e���Ƃ݂���K�͏k���Ŗ�5���l�ɂƂǂ܂�B
����ł��哝�̎��王�@���邱�ƂŁA�R���ە�����ƂƂ��ɁA�E�N���C�i���돂�̐��������ւ̋��d�p�����A�s�[������_����������悤���B�܂��A�ΕĂŋ������钆���̂ق��A���V�A�̓`���I�F�D���C���h���Q�����Ă���A���č���4�J���̘g�g�݁u�N�A�b�h�v�ɂ����т�ł����݂����l���Ƃ݂���B�@
8��30����91�ŖS���Ȃ����~�n�C���E�S���o�`���t���\�A�哝�̂̑��V�E���ʎ���3���A���X�N�����S���ʼnc�܂ꂽ�B�\�A�Ō�̍ō��w���҂Ƃ��ē��������I���ɓ������̋Ƃɂ�������炸�u�����v�ł͂Ȃ��A�v�[�`���I�哝�̂������𗝗R�Ɍ��Ȃ����B
�^�X�ʐM�ɂ��ƁA�n���K���[�̃r�N�g���E�I���o�����Q�����A�ĉp��h�C�c�͒��I��g�ɂƂǂ܂����B���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�����e�𗎂Ƃ��Â��ȕʂ�ƂȂ����B
�I�哝�̕{�ɋ߂��J���g����فu�~���̊ԁv�ł̍��ʎ��͑哝�̕{�V�T�ǂ��x�����A�����ɏ�����`�ōs��ꂽ�B�I�����ł̓S���o�`���t����1991�N�̃\�A����������炵�����{�l�Ƃ̔ᔻ�����������Ƃf�����Ƃ݂���B�I���c�e���r���قڒʏ�ǂ���̕����������B
�S���o�`���t���̓��X�N���s���̃m�{�f�r�`��n�ŁA99�N�Ɏ����������C�T�v�l�ׂ̗ɖ������ꂽ�B��n�ɂ̓\�A�̌�p���ƃ��V�A�̃G���c�B������哝�̂璘���l����������Ă���B2007�N�Ɏ��������G���c�B�����́A�����������B
8��30����91�ŖS���Ȃ����S���o�`���t���\�A�哝�̂̑��V��3���A���V�A�̎�s���X�N���ʼnc�܂ꂽ�B�s���S���̗��j�I�ȃz�[���ō��ʎ����s��ꂽ��A�����Ƃ⒘���l����������m�{�f�r�b�`��n�ŁA���C�T�v�l(1999�N����)�ׂ̗ɖ����B�\�A����ɂ�鎩�R���������ގs���炪�������A�Ō�̕ʂ���������B
���V�͘A�M�x���(�e�r�n)�Ȃǂ��x�����u�����I�ȗv�f������v(�y�X�R�t�哝�̕�)�Ɛ������ꂽ���A�v�[�`���哝�̂͑��̍���������D�悳����Ƃ������R�ŎQ�Ȃ������B�^�X�ʐM�ɂ��ƁA���{�̏㌎�L�v�����V�A��g�̂ق��A�ĉp�ƕ��ƃX�y�C���̊e��g�A�n���K���[�̃I���o�����p���������B
���X�N����3���A8��30���Ɏ��������̃~�n�C���E�S���o�`���t���\�A�哝�̂̑��V���c�܂ꂽ�B�s���̍Î���ō��ʎ����s��ꂽ��A�Ђ��͕�n�ɉ^��A1999�N�ɐ旧�������C�T�v�l�ׂ̗ɖ������ꂽ�B�u�����v�ł͂Ȃ��A�v�[�`���哝�̂��E���𗝗R�ɎQ�Ȃ������B
�S���o�`���t����89�N�̗��I����90�N�̓����h�C�c�̓�����A���N�ɂ̓m�[�x�����a�܂���܂����B8��30���A�×{���Ă������X�N���̒����N���j�b�N�a�@�Łu�d�������̕a�C�v(���a�@)�Ŏ��������B91�������B
���X�N�����S���̘J���g����قʼnc�܂ꂽ���ʎ��ɂ́A�ԑ�����ɂ����s���炪�������K�ꂽ�B���ʎ��̌�A�G���c�B�����ネ�V�A�哝�̂��Ƃ̃j�R���C�E�S�[�S���瑽���̒����l�����郂�X�N���s���̃m�{�f�r�`��n�ɖ������ꂽ�B
���V�A�̃E�N���C�i�R���N�U�������Ȃ��A���Ď�]�̎Q��҂̓��V�A�ƗF�D�W��ۂn���K���[�̃I���o�������������悤���B�^�X�ʐM�ɂ��ƁA���ĉp�Ƃ̒����V�A��g���Q���B
2007�N4���Ɏ��������G���c�B�����͍����ŁA���{�͑��V�̓����u�������r�̓��v�Ɛ錾�����B�S���o�`���t���̑��V�́u�����̗v�f������v(�哝�̕{)�Ƃ���A���{�͋V��(�����傤)������Q��������ȂǑ��V���x�������B
�v�[�`������3���̑��V�ɂ͎Q�Ȃ������B�O���v�l�Ƃ̓d�b���c��5�`8���Ƀ��V�A�ɓ��ŊJ�������o�σt�H�[�����o�Ȃ̂��߂̏����ȂǐE��������Ƃ��Ă���B����ɁA�S���o�`���t���̈�̂����u����Ă���a�@��1���ɖK��A�Ђ��ɉԂ����������B
���Ăł́u�S���r�[�v�̈��̂Őe���܂ꂽ�S���o�`���t�����������A���V�A�����̊Ԃł�1991�N�̃\�A����������炵���Ƃ��Ĕᔻ�I�Ȍ����������B�\�A����ɂ��āu20���I�ő�̒n���w�I�ߌ��v�Ɣ����������Ƃ�����v�[�`�����Ƃ��a���������Ƃ݂��Ă���B

���V�A�̃E�N���C�i�ւ̌R���N�U�́A����E���ȗ��A���B�ōő�̗����������N�������B�R���N�U���n�܂���8��24����6�J�����o�߁B���A�̔��\�ɂ��ƁA�N�����ꂽ�E�N���C�i�ł�5000�l���̖��Ԑl��9000�l���̏������]���ƂȂ����B����A���V�A�R�̎����Ґ��Ɋւ��Ă͏������邪�A�č��h���Ȃ�7��〜8���l�Ɛ���B�E�N���C�i�ɂ����镨�I���Q���傫���A������p�ɂ�7500���h��(��105���~)������Ǝ��Z����Ă���B
���E�N���C�i�o�ς̕����R�X�g�A7500���h������
���A�̓E�N���C�i�푈�ŏ��Ȃ��Ƃ�5614�l�̖��Ԑl���E�N���C�i�ŎE�Q���ꂽ�Ɣ��\�������A�����ɍ��A�W�҂͎����͂����啝�ɏ���ƌ����B�A�]�t�X�^�[�����S�����߂����Č������U�h���������암�̓s�s�}���E�|���ł́A�ڌ��҂̏،���q���摜�Ȃǂ��疯�Ԑl�̎��҂�2��2000�l�ɏ��ƃE�N���C�i���{�W�҂݂͂Ă���B
��⍑�����ƂȂ邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�E�N���C�i�l�������B���A�ɂ��ƁA�O���ɓ����ē�ƂȂ����s����670���l�A��������660���l�ɏ��B����ɁA�퓬�n��œ��H�⋴���j�ꂽ��A�茳���s�@�ӂœ�����ꂸ�A�퓬�n��ɗ��܂��Ă���s����1300���l�ɏ��Ǝ��Z����Ă���B�Ď��j���[���[�N�E�^�C���Y���`�����B
����A�E�N���C�i�ł�2��24���ɐN�����n�܂��Ĉȗ��A���V�A�R�ɂ��C����~�T�C���U���ŁA18���˂̌������j�ꂽ�B���̒��ɂ�11��5000�˂̌l�Z��A2290�̋���{�݁A934�̈�Î{�݁A1991�̏��X�A27�̃V���b�s���O�Z���^�[�A715�̕����{�݁A511�̍s���{�݁A28�̐Ζ��������A18�̖��ԋ�`���܂܂��B����ɁA311�̋����j���A18��8000��̎��Ɨp�Ԃ��j�����邩�������͉�������A2��4800�L���ɋy�ԓ��H���j�������B�E�N���C�i�ɂ����錚����C���t���̔�Q���z��1136���h���ɏ��Ɛ��肳��Ă���B
�E�N���C�i���{�́A�Z���ւ̊�{�T�[�r�X���ێ����A�o�ς��Ă������߂ɂ͖���50���h���K�v���Ƃ��Ă���A���̐����͏H����~�ɂ����đ������A������E�N���C�i�o�ς̕����R�X�g��7500���h���ɖc��オ��Ƃ݂Ă���B
���R���x���͕ĉp���ˏo
�����������Ő��������̓E�N���C�i�ւ̌R���x�����p�����Ă���A���z�ł͕ĉp���ˏo���Ă���B�č��͍ŋ߁A29��8000���h���Ɖߋ��ō��ƂȂ�V�K�����\���A�v�z�͓��{�~���Z��1���~����B�p��������40���h���A3�Ԗڂ����B�A��(EU)���@�ւ�25���h���A4�Ԗڂ��|�[�����h��18���h���A5�Ԗڂ��h�C�c��12���h���ƂȂ��Ă���B�����A�����̓v�[�`���������ߓx�ɒǂ��l�߂Ȃ����߂ɁA���P�b�g�C�Ȃǂ̎˒������V�A�̂ɓ͂��Ȃ������ɐ���������A��Ԃ�퓬�@�Ȃǂ̋��^�͍T���Ă���B
�Ƃ���ŁA�푈�̓E�N���C�i�̔_����A�O���r�W�l�X��230���h�����̗��v�@��̈편��A�_�Ƌ@�B�̔j��A�]���̗A���R�X�g���S�ɒ��ʂ����Ă���B���V�A�R�ɂ�鍕�C�����ŁA�E�N���C�i�ł͖�2000���g�����̍������A�o�ł����ɍ`�p�{�݂Ȃǂőؗ����Ă���B���A�ƃg���R�̒���ɂ��A8�����߂��獒���A���D�̍��C�̍`����̍q�s���ĊJ����A8������100���g�����̍������^�яo���ꂽ���A������A���������ɐi�ނ̂��ǂ����\�f�������Ȃ��B
�E�N���C�i�푈���n�܂��Ĕ��N�A���B�ő���E����A�ő�K�͂̐푈�ƂȂ������A�틵���P����Ԃ������A�I���͌������A�����������O�����B�@
���V�A�̌R���N�U���߂���A�E�N���C�i�R�̓w���\���B�ȂǓ암�𒆐S�ɍU�������߂Ă��܂��B�E�N���C�i�哝�̕{�̌ږ�͓��ʂ̓��V�A�R�̕⋋�H��f���퓬�\�͂�ቺ�����邱�Ƃɏd�_��u���Ă���Ƃ˂炢�𖾂炩�ɂ��܂����B
���V�A�̓E�N���C�i������암�ōU���𑱂��Ă��܂��B
�����h�l�c�N�B�̒m����SNS��3���Ɏs��4�l�����S�����Ɠ`�����ق��A�암�~�R���C�E�B�̒m����4���A�[��ɑ�K�͂ȃ~�T�C���U��������A��Ë@�ւ⋳��{�݂Ȃǂɔ�Q���o���Ƃ��Ă��܂��B
����ɑ��ăE�N���C�i�R�́A���V�A�R�����������Ƃ���w���\���B�ȂǓ암�𒆐S�ɍU�������߂Ă��܂��B
����ɂ��ăE�N���C�i�哝�̕{�̌ږ�A�A���X�g�r�b�`���̓��f�B�A�ւ̃C���^�r���[�Łu�C���ɂ�胍�V�A�R�̍���̕�����̌n�I�ɔj�Ă���v�Əq�ׁA�E�N���C�i�R���x�z�n��̒D�҂Ɍ����A���ʂ̓��V�A�R�̕⋋�H��f���퓬�\�͂�ቺ�����邱�Ƃɏd�_��u���Ă���Ɩ��炩�ɂ��܂����B
����A���V�A�̃v�[�`���哝�̂̓E���W�I�X�g�N�ŊJ�����u�����o�σt�H�[�����v�ȂǂɎQ�����邽�߁A4������ɓ���K�₵�܂��B
������6���ɂ̓��V�A�R�̑�K�͌R�����K�u�{�X�g�[�N�v�����@����\��ŁA�R���͂ɗ]�͂����邱�Ƃ���O�Ɏ����˂炢��������̂Ƃ݂��܂��B
�`�F�R�̎�s�v���n��3���A��7���l���Q�����āA���������E�N���C�i�ɂ���S���Ă���Ɛ��{��ᔻ����f�����s��ꂽ�B
�f�����͕������ɉ����A�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���ڎ�A�ږ����ŕs����i���u�`�F�R�����t�@�[�X�g�v�ƘA�Ă����B�~�̒g�[������\�z����u�Z�[�^�[��2������v�Ɨv������v���J�[�h���������B
���V�A�R���苒����U�|���[�W�������ł̍��ی��q�͋@��(�h�`�d�`)�̒����ł́A�I�R��̒n�悩�甭�˂��ꂽ�Ƃ݂��郍�P�b�g�e�̎c�[�Ɋւ��A�I�����Ƃ��u�E�N���C�i�R�̃��P�b�g�e����ՓI��180�x��]�����v�ƒ����c�ɋ��ق��铮�悪�g�U���Ă���B���V�A�̓E�N���C�i�R���������U�����Ă���Ƃ̎咣��Z�������悤�Ɩ�N�ɂȂ��Ă���B
����ł́A���f�B�A�������A��Ē����c���ē������I���c���q�͊�ƃ��X�A�g��������1���A���P�b�g�e�̒��e�p�x�ɋ^����������h�`�d�`�̒����c�Ɏߖ����Ă���B���V�A�ʐM���摜��z�M���A�E�N���C�i�̃��P�b�g�e���Ƌ��������B
�E�N���C�i�̓������ږ��2���A���g�̂r�m�r�ɓ���𓊍e���u���ꂪ���V�A�̂������v�Ɣ�������B�Đ����@�ցu�푈�������v�́A���V�A�������c�̖K��ɍ��킹�A�����ɋ��Ђ�^���Ă���̂̓E�N���C�i�R���ƈ�ۂÂ�����g�݂����������邾�낤�Ǝw�E���Ă���B
���n����̏��ɂ��ƁA�~�����}�[���R�g�b�v�̃~���A�E���t���C�����i�ߊ���4���A���V�A�ɓ��E���W�I�X�g�N��5〜8���ɊJ�����u�����o�σt�H�[�����v�֏o�Ȃ��邽�ߎ�s�l�s�h�[���o�������B11���ɋA������B
3���t�̃~�����}�[���c���ɂ��ƁA���V�A������t�H�[�����̏��҂����B���i�ߊ��͌o�ϕ���Ȃǂ̋��͊W������ɋ������邽�߁A���{�W�҂Ɖ�k����\��B
��N2���̃N�[�f�^�[�ȍ~�A���R�̓��V�A�ւ̌X�����߂Ă���A���i�ߊ��̖K����3��ځB���N7���ɂ����V�A�����I�ɖK�₵�A���{�����⍑�c���q�͊�Ƃ̊�����Ɩʉ�����A�v�[�`���哝�̂Ƃ̉�k�͎������Ă��Ȃ��B
�g�v�[�`���̐푈�h���v�[�`����ǂ��l�ߎn�߂Ă���B���N���߂��܂��܂��I��肪�����Ȃ��E�N���C�i�N�U�B����������ɂ�E�N���C�i�̑O���ł��A���V�A�����ł��A�v�[�`���哝�̂ւ̕s���������Ă����B�v�[�`�����������ꂽ�g�ꋫ�h�A�l�X�Ȗʂ��炻�̌����������B
���u�R����߂����l���x������{�݂�����܂����A���͓����悤�Ƃ����R�l�̊č��v
�t�����X�ɖS������]���郍�V�A�R�l���A�t�����X�A�V�������E�h�S�[����`�Ŏ�����B�e�����f����SNS�ɃA�b�v���ꂽ�B
���V�A�E��56�e�q����P�����@�p�x���E�t�B���e�B�G�t����u��҂����̂��߂��ƐM���Ă������Ƃ��A���ۂɂ͉�X�𗘗p���đ����Ă��鐭���̂��߂������B�v
�ƌ����āA�ނ͋�`�̃g�C���Ń��V�A�����s���������̃p�X�|�[�g���א�ɔj��A�֊�Ɏ̂Ă��B�����Č����E�E�E�B
�u���V�A���D���ŁA���V�A�l���ׂĂ��D���ł��B�������v�[�`���⍡�̐����̓��V�A�ł͂���܂���B�v�[�`���A�������炦���B�v
��������]���郍�V�A���͌��₽�Ȃ��B����ɑ����V�A�͂���c�̂�ݗ����Đ��_�I�ɂ��x������Ԑ��𐮂����Ƃ����B�����������̎��Ԃ͑S���ʂ̂��̂������B
���V�A���l���ی�NGO�@�^�o���t��\�u1�����̐��ł̌R�����I��胍�[�e�[�V�����Ō��v���A�x�ɗv���ɂȂ�Ƒ����̌R�l���z�u�𗣂�A�_���j�����ČR�����߂Ă��܂��B�����������ꂪ���ɑ�K�͂ɂȂ荑�h�Ȃ͐_�o���点�Ă��܂��B(����)���n���V�N�l�����a���̃u�������J�ɂ͌R����߂����l���x������w�R�l�S���x���Z���^�[�x������܂����A���̓��V�A�ɓ����悤�Ƃ����R�l�̊č��ł����B�����ŕ��m�����͐S�����ւ��đO���ɖ߂�悤���̓I�ɂ����_�I�ɂ����͂��������܂����B���V�A�ɖ߂ꂽ�l�����܂����A�߂�Ȃ�������s����������Ȃ��Ȃ����肷��l�����܂��B�v
���������ł��Ȃ�����A���V�A���͐�ΐ�������Ȃ��Ƃ�����B�R�Ƃ��Ă͈�l�������������Ȃ��B�����A�͂��߂���m�C�������Ȃ����m�����́A���łɌ��E�ɒB���Ă����B�O�o�̖S����]�̃t�B���e�B�G�t����͎�L�ɋL���Ă���B�g�E�C��U��i���Đ퓬�Ԑ��ɓ���Ƃ����i�ߊ��̖ڂ��|�C�Â��Ă����B�R���̑命���͂����ŋN���Ă��邱�Ƃɕs���������A���{�̎w���ɕs���������A�v�[�`���̐���ɕs���������A�R���ɂ������Ă��Ȃ��������h��b�ɕs���������Ă���h�ƁB�@
���u�v�[�`���̖{���̓��x�����Ȑ��m��`�҂ł����A�����ނ������̖]�ނ��Ƃ��������n�߂���A�N������������ǂ��o�����ł��傤�v
�N�U�������͐�ꂾ���łȂ����V�A�����ł��l�X�ȉe���������炵�Ă���B�����ɂǂ��W���Ă���̂��͕s�������A�挎20���A���V�A�̋ɉE�v�z�Ƃ̖���������Ԃ����j���ꂽ�B�Ɛl�͂킩���Ă��Ȃ����A�������z�肳��Ă���Ɛl��������B
(1)�E�N���C�i�ƍs���B���ł�FSB���E�N���C�i���̗e�^�҂���肵���Ƃ���邪�A����̓E�N���C�i�̃����b�g���l�����Ȃ�
(2)���v�[�`�����͔ƍs���B�������a���R���ƍs�������o�����Ƃ���邪�A�������a���R�Ȃ�g�D�̑��݂���͂����肵�Ă��Ȃ��B
(3)���V�A�ɂ�鎩�쎩�����B�ړI�͉��Ȃ̂��B
����(3)�ł���\���������Ƃ������Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��B�����Ă��̗��R�́A�ɉE���͂��g���ʌR�����h�Ȃǐ��ʂ邢�Ή��łȂ��A�푈��錾���đ��������Đ푈������Ǝ咣���Ă��邱�Ƃ��v�[�`�����ɂƂ��ēs���̗ǂ��Ȃ����̂��Ƃ݂��邩�炾�Ƃ����B�ԑg�ł́A����܂ł��܂�m���Ă��Ȃ��ɉE�v�z�ƃh�D�[�M�����ɒ��ڂ����B
�X�^�W�I�Q�X�g�̒����V���A��ؖ��`���́A2018�N�A���̐l���ɃC���^�r���[���Ă���B�����Ńv�[�`�����ɑ��ӊO�Ȍ�����ނ����Ă��邱�Ƃ����������B
���V�A�ɉE�v�z�Ɓ@�A���N�T���h���E�h�D�[�M�����u�X�^�[�����Ƒ�Ⴂ�Ńv�[�`���͔��Ɏ����I�Ȑ����Ƃł��B�X�^�[�����͂܂��ɖ{���̑傫���ċ����ƍَ҂ł������A�v�[�`�����ǂ��炩�Ƃ����ƃv���O�}�e�B�X�g(���p��`��)�ł��B���x�����̏������ł��Ă��Ȃ����ł̓��x�����Y���͂��蓾�Ȃ��Ƃ������Ƃ𗝉����Ă���̂Ō��������̕ێ��`�����s���Ă���̂ł��B�v�[�`���̖{���̓��x�����Ȑ��m��`�҂ł����A�����ނ������̖]�ނ��Ƃ��������n�߂���A�v�[�`���̓N������������ǂ��o�����ł��傤�B�v
�N���~�A�����A���ĂƑR���A�E�N���C�i�ɐN�U�����v�[�`�������A�{���͐��m��`�̃��x�����Ȑl�����Ƃ����B��؎��̉��߂ɂ��A���ꂪ�{�S���͕s�������A�h�D�[�M�����͂������Ă���ƁB
�����V���Ё@��؋`���@�_���ψ��u�G���c�B���̌�p�҂Ƃ��ďo�Ă������͊m���Ƀ��x�����Ȃ��Ƃ������Ă����B�������A���V�A�̍������g�������V�A�h��]��ł���̂Ńv�[�`���͂����^���Ă���B�v�[�`���͗D�G�ȍL���}���ł���A�Љ�]�ނ��̂�^����ƁA�{���Ƃ͈Ⴄ���Ƃ�����Ă���ƁA�h�D�[�M���͌����Ă���B�v
�^�̃��x�����h����͓ƍَ҂Ɣ����v�[�`�����B�E�h����͐��m��`�A�L���}���Ɲ��������v�[�`�����B�ӊO�ɂ����݂̎��Ԃ������Ă����B
�h�q�������@�����T���@���������u���͌R�̒��ɂ��E�h�I�Ȏv�z�̐l�͂���Ǝv���B�v�[�`���͐��ʂ邢�ƁB���̂܂ܒ��������Ă̓��V�A���̋]�����ǂ�ǂ�g�傷��B�v�[�`���͂����Ƌ��d�ɑ����������Ă��ׂ������Ă����l�́A�����ɋ߂��l�ɂ������Ȃ����Ɓc�v
���̋��d�h�̐��́A���͔��Δh�̐��������Ƃ����͕̂����ϑ쎁���B
���V�ANIS�o�ό������@�����ϑ�@�����u�푈���̐��̓v�[�`���Ƃ��Ă͒e�����������ł����A���d�h�́g�����ƓO��I�ɂ��h���Ă����̂�e������͖̂������Ă���킯�ł��B�v
�Y�܂����v�[�`�����́A�ʂ����Ăǂ��������̂��낤��?���̃��V�A�ō��A�R���N�U�̕��������Ă���Ƃ����B�ǂ��������ƂȂ̂�?
���u���V�A�o�ς́A�n����1���ڂɍ����|�����Ă�B�v
�w�C�Y�x�X�`���x�Ƃ����V��������B�\�A����̐��{�@�֎��ŁA�����������̎p���𑱂��Ă���B���̐V���ŌR���N�U�Ɋւ���L���������Ă��Ă���B1�ʃg�b�v�ŃE�N���C�i���`�����𐔂����B����ƁA���N3��4����90�����E�N���C�i�֘A�������̂ɑ��A6����50���B7���ɂ�30��������B�����Ɍ����鐭�����̎v�f�Ƃ�?
�h�q�������@�����T���@���������u�������틵�ɊS��������A���x�����A�E�h�������炢����ᔻ�����B���܂ŌR���������̂��B�]���̎��Ԃ͓`���Ȃ��Ă����X�ɍ����̒m��Ƃ���ƂȂ�B���_�����N���Ȃ����߂ɕ����炵�Ă����Ȃ����c�v
�푈�ɖڂ������ǂ����ɓ]��ł��v���X�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�S���������Ȃ��ɉz�������Ƃ͂Ȃ��̂��B����ő����Ă��������B
�����V���Ё@��؋`���@�_���ψ��u�����g�����V�A�̃e���r�����Ă����ł����A�푈���̂��̂��j���[�X�ň���Ȃ��Ȃ��Ă����ۂ������Ă��܂��B�푈��������Ȃ��A�U�|���[�W���������E�N���C�i�R���U�������Ƃ��A���V�A�ւ̌o�ϐ��قʼn��Ă��������ō����Ă���Ƃ��c�B���V�A�o�ς������s���l�܂��Ă��邪�A�G�͂����Ƌ�J���Ă���Ƃ��B�v
�v�[�`�����Ƃ��Ă̓��V�A�����̕s���@���A���타�[�h��}���邱�Ƃ��ő�̉ۑ肾�B���N�ɂ͎�����哝�̑I���X�^�[�g����B�푈�̍s���ƂƂ��ɁA����A���V�A�����̌o�ς̍s�������E���邱�ƂɂȂ�B
���V�ANIS�o�ό������@�����ϑ�@�����u���͊ԈႢ�Ȃ����V�A�o�ς͂��ꂩ��ǂ�ǂ��Ȃ�Ǝv���B�n����1���ڂɍ����|�����Ă�B�v�[�`���Ƃ��Ă͑I���܂ł��܂����܂�����Ă�����ł��傤���ǁA�ǂ����̎��_�Ń{�����o�n�߂�B���̃{�����o��^�C�~���O�ƑI���̃^�C�~���O�Ɍl�I�ɂ͒��ڂ��Ă��܂��v
�g���R�̃G���h�A���哝�̂̓��V�A�̃v�[�`���哝�̂Ƃ̓d�b��k�ŁA�E�N���C�i�̃U�|���W�G���q�͔��d��������A��������������ʂ������Ƃ��ł���Ɠ`�����B�g���R�哝�̕{��3���A���\�����B
�哝�̕{�ɂ��ƁA����]�̓E�N���C�i�̍����A�o����b���������ق��A�g���R�̃A�b�N���������݂��v��ʂ�p�����錈�ӂ�\���B15��16���ɃE�Y�x�L�X�^���ōs�����]��c�̍ۂɂ����̖����ڍׂɋ��c���邱�Ƃō��ӂ����B
���V�A���E�N���C�i�ɐN�U����Ƃ܂��Ȃ��A�č��≢�B�e���͖�p�����Ƀ��V�A�Ɍo�ϐ��ق��Ȃ����B
������A���V�A���Ɠ��v�ǂ��͂��߂Ƃ��鐭�{�@�ւ́A���܂��܂Ȍo�ϓ��v�̌��\���~�����B�A�o���A���A�������Y�ʁA��s�A�q���Ђ��`�̗��p�Ґ��ȂǁA����܂Œ���I�ɕ���Ă����f�[�^�����X�Ɏp���������B
�����푈���������ɂ�A�s���Ȃ��Ƃ��N�����B���V�A�o�ς͗\�z�ȏ�Ɍ������ƃ��f�B�A���n�߂��̂��B4-6�����̍��������Y(GDP)���O�N������4�����ɂƂǂ܂������Ƃ�A���Ɨ���3.9���Ɖߋ��Œ���X�V�������ƂȂǂ�����𗠕t���Ă���Ƃ����B
���̃f�[�^�̏o�ǂ���́A�Đ��{�≢�B�A��(EU)�����ق̌��ʂ𑪂�Ȃ��悤�A�킸��6�J���O�Ɍo�σf�[�^�̌��\����߂����V�A���Ɠ��v�ǂ��B
���V���g���̍��ۋ��Z����(IIF)�Ŏ�ȃG�R�m�~�X�g�߂郍�r���E�u���b�N�X���́u�f�[�^�̎��͋}�~�����Ă���v�Ƙb���B
�푈���n�܂�܂łɁA�����Đ��������́u���͂��x��Ȃق�(���V�A�哝�̃E���W�[�~���E)�v�[�`���ɂ��܂���Ă����v�B�C�G�[����w�o�c��w�@�`�[�t�E�G�O�[�N�e�B�u�E���[�_�[�V�b�v�E�C���X�e�B�e���[�g(CELI)�̃��T�[�`�f�B���N�^�[�A�X�e�B�[�u���E�e�B�A�����͂����w�E����B�u����G�R�m�~�X�g��f�B�A�܂ł����V�A���Ɠ��v�ǂ̃f�[�^��M�p���A���܂���Ă���B�M�p����̂͂܂��������Ƃ����A������x���T�C�����o�Ă���ɂ�������炸���v
�e�B�A�����ɂ��ƁA�ނ�͌o�σf�[�^���z�ʒʂ�Ɏ���Ă���B���ꂪ�����ɂ��邩��A�Ƃ����̂����R�̈���Ƃ����B�u��ʃ��f���ɂƂ��ĕK�v�Ȃ̂́A���f���ɓ�����鎞�n��f�[�^�������v
���V�A���Ɠ��v�ǂ͓���f�[�^�̑��������\���Ă��Ȃ��ɂ�������炸�AGDP�Ǝ��Ɨ����Z�o���Ă���B���̐������G�N�Z���ɑł�����Ń`���[�g���쐬����ƁA�����̌o�ώ��k��2008�N�̐��E���Z��@���قǂЂǂ��͂Ȃ��悤�Ɍ�����B
IIF����ȃG�R�m�~�X�g�Ń��V�A�o�ϐ��Ƃ̃G���i�E���o�R�����ɂ��ƁA����͋��R�ł͂Ȃ��B�v�[�`�����͈ȑO����A���ې��قɑς�����o�ς��Ӗ�����u�v��(�悤����)���V�A�v���X���[�K���Ɍf���Ă����B�u���V�A�o�ς�2008�N�ȏ�ɗ�������ł���Ƃ����������A�s�k��F�߂����ƂɂȂ�v�Ɠ����͘b���B
�\�A����̌o�σf�[�^�͐M�҂傤�����ɂ߂ĒႩ�����B���T���������\�A�Ō�̍ō��w���҃~�n�C���E�S���o�`���t����1989�N�A�������R����̋K�͂��ߏ����Ă������Ƃ�\�I�B���ۂ͌��\�l��4�{���������A�\�A�̎w���҂̑����͎��Ԃ�m��Ȃ������B�����̑��߂͓����A�L�Ғc�Ɂu���������̎x�o�ɂ��ď��߂Ēm�����v�ƌ���Ă����B
���V�A���s��o�ςɈڍs���A���������Ƃ̊W���[������ɂ�A�o�σf�[�^�̎��͉��P�����B���V�A������s�ȂLjꕔ�̌o�ϋ@�ւ́A�v�[�`�����������œ��������߂钆�ł��A���̐�含�ƓƗ����������]������Ă����B
����Ń��V�A���Ɠ��v�ǂ́A�푈���n�܂�O����A�Ɨ����ƃC���e�O���e�B�[(������)���^�⎋����Ă����B�v�[�`������2017�N�A���ǂ��o�ϏȂ̊NJ����ɒu���Ĉȍ~�A���\����f�[�^�̎����^�⎋����邱�Ƃ������Ă������B�������\����Ă��鐔���Ȃ����v�ɂ��āA�f�[�^�����f����Ă������ƈȊO�ɂ��A�M�҂傤�����^���ׂ����R������B
���V�A�ɂ͐��x��́u�B�ꎸ�Ǝҁv�����邱�Ƃ��m���Ă���B�]�ƈ��̉��ق͖@�I�ɓ�����A��Ƃ͌i�C�������ɏ]�ƈ��ɖ����u�x�Ɂv�̎擾�������ł���B���̏ꍇ�A���̏]�ƈ��͎d�����������Ȃ��ɂ�������炸�A�A�Ǝ҂Ƃ��ăJ�E���g�����B���̐��͏��Ȃ��Ȃ��B2015�N�̎��Ɨ��́A�B�ꎸ�Ǝ҂��܂߂�Ɩ�2.5�|�C���g�����Ȃ�Ƃ̐��v������B
�O�o�̃e�B�A������ACELI�n�ݎ҂̃W�F�t���[�E�\�l���t�F���h�����7���̘_���ŁA���Ċ�Ƃ̓P�ނ�ق̓��V�A�o�ςɉ�œI�ȑŌ���^���Ă���Ƃ��āA���V�A���{�̃f�[�^�Ƃ͑������錩�����������B���V�A����P�ނ�����Ƃ�1000�Јȏ�ɏ��A���㍂���v�̓��V�A��GDP��40��������Ƃ����B
�P�ނ������Ƃ̈ꕔ�̓��V�A�l���o�c�������p���ł��邽�߁AGDP�ւ̑Ō���40���ɂ͓͂��Ȃ����낤���A�ԈႢ�Ȃ�4���ȏゾ�낤�B
CELI�̐��v�ł́A�P�ނ�����Ƃ̂�����500�Ђ����S�Ɏ��Ƃ���߁A���V�A�̘J���͐l���̍ő�12�������Ƃ����B�ꕔ�͂����炭�ďA�E�����Ƃ݂���B�e�B�A�����́u���Ɨ���12���Ƃ͌���Ȃ����A4�����͂͂邩�ɍ����v�Əq�ׂ��B

�E�N���C�i�ւ̌R���N�U���߂��艢�Ă����V�A�Ɍ��������ق��Ȃ��Ȃ��A���V�A�ɓ��̃E���W�I�X�g�N�ł�5���A�v�[�`���哝�̂��o�Ȃ��鍑�یo�ω�c���J�����܂��B�v�[�`�������Ƃ��ẮA�����ȂǂƂ̘A�g���������邱�Ƃō��ۓI�ɌǗ����Ă��Ȃ��Ɠ��O�Ɏ����A���ĂɑR����˂炢������Ƃ݂��܂��B
���V�A�ɓ��̃E���W�I�X�g�N�ł́A5������4���Ԃ̓����Ń��V�A���{��Ấu�����o�σt�H�[�����v���J�Â���A60�ȏ�̍��ƒn�悩���Ƃ̑�\��{�W�҂̎Q���������܂�Ă���Ƃ������Ƃł��B
���Ƃ��̃e�[�}�́u���ɉ����鐢�E�ւ̓��v�ŁA�t�H�[�����̊��Ԓ��A���V�A�́������ƃ��V�A���哱����g�g�݂̏�C���͋@�\��A��ASEAN������A�W�A�����A���ɉ�������e���Ƃ̌o�ϘA�g�̋����ȂǂɌ����ӌ������킷�\��ł��B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂͊J���ɐ旧�����b�Z�[�W�����J���u����x��̈�ɏW�����f���́A�V�������E�����Ɏ���đ����悤�Ƃ��Ă���v�Ƃ��āA�A�W�A�����m�n��A�Ƃ�킯�������d������p����N���ɂ��Ă��܂��B
�E�N���C�i�ւ̌R���N�U���߂��艢�Ă����V�A�Ɍ��������ق��Ȃ��Ȃ��A�v�[�`�������Ƃ��ẮA��c��ʂ��Ē����ȂǂƂ̘A�g���������邱�ƂŁA���ۓI�ɌǗ����Ă��Ȃ��Ɠ��O�Ɏ����A���ĂɑR����˂炢������Ƃ݂��܂��B
������ ���Y�}�̏���3�� �I�폑�ψ������o�Ȃ�
�������c�̐V�؎ВʐM�ɂ��܂��ƁA�E���W�I�X�g�N�ŊJ�Â����u�����o�σt�H�[�����v�ɂ́A�������狤�Y�}�̏���3�ʂőS�l�ぁ�S���l����\���̌I�폑�ψ������o�Ȃ���Ƃ������Ƃł��B
�I�ψ�����7���ɊJ�����u�����o�σt�H�[�����v�̑S�̉�ɏo�Ȃ��A���̌�A����17���ɂ����ă����S���A�l�p�[���A�؍����K���Ƃ������Ƃł��B
�����ł͏K�ߕ����Ǝ�Ȃ��͂��߁A���Y�}�̍ō��w�����̃����o�[�́A���ƂƂ��A�V�^�R���i�E�C���X�̊��������E�I�Ɋg�債�Ĉȍ~�A�C�O�ւ̖K����T���Ă��܂����B
�����Ƃ��ẮA�V�^�R���i�̊����g��ȍ~�A�����Ƃ���������̐l�������V�A�ɖK�₳���邱�ƂŁA��p��Ȃǂ������ăA�����J�Ƃْ̋������܂钆�A�Ƃ��ɃA�����J�ƑΗ����郍�V�A�Ƃ̊W���d������p���������˂炢������Ƃ݂��܂��B
���E���̐퓬�I���̊肢���������A�J�킩��7�J���ڂɓ˓������E�N���C�i�푈�B�����P����Ԃ��������̐푈�͂܂��A�n����̎��鏊�Ɂu�]�сv��\�o�����Ă���悤�ł��B����̃����}�K�w�Ō�̒��⊯�@���c�v�m�F�́w���G�̌��E�R�~���j�P�[�V�����p�x�x�ł͌����A�������⊯�̓��c���A�����]�т̐��X����e�X�ɂ��ďڂ�������B����ɓ��{���u����Ă��錵�������S�ۏ�����Љ��ƂƂ��ɁA���ꂪ�����ăE�N���C�i�푈�Ɩ��W�ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă��܂��B
���������ɂ߂鐢�E�ʼn����N���Ă��邩�H
��T�����A����܂ł��܂���Ȃ��������A���͂����Ƃ����Ԃ葱���Ă������O��������C�ɔ������A�\�o���Ă����C���������܂��B
�͂���ł����V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U���߂��������ł����A���̗��ł́A��T�A�G�ꂽ�R�\�{�����͂��߁A�C���N�E�C�����A�A�t�K�j�X�^���̍����Ɣߌ�����A����Ԃْ̋��̍��܂�A�R�����K��ʂ���������̊Ԃł̍j�����A�^�C�̃v�����b�g�����̗h�炬��q���M�������͂��߂Ƃ���~�����}�[��̍����ȂǁA����A���ۏ����C�ɋɌ��̍����Ɋׂ�A�܂��ɃJ�I�X�������N�������˂Ȃ���ނ������낢�ł��B
����炷�ׂĂ��J�o�[���邱�Ƃ͕s�\�ł����A���T���ł͂��łɏ����ꂽ���̂��s�b�N�A�b�v���Ă��`�����܂��B
�ŏ��́u�E�N���C�i��v�ɂ��Ăł��B
���̂Ƃ��뉢�Ă��狟�^���ꂽ���킪����t���A�E�N���C�i�R�����V�A�R�ɑ��Ĕ��U�������A�암�փ��\���B��N���~�A�����Ő��͂�҉Ă���Ƃ����j���[�X���`�����Ă��܂��B
�u���V�A�̒e����������n�߂Ă���v
�u���ď����ƗF�l�����ɂ�鐧�ق������n�߂Ă���v
�u�A�����J���狟�^�����n�C�}�[�X�Ȃǂ̕��킪�A�E�N���C�i�R�ɗ͂�^���A���ł̓��V�A�������Ԃ��Ă���v
���낢��ƃE�N���C�i�̑P���`������e�������炳��A���̐����ɏ�邩�̂悤�ɁA�[�����X�L�[�哝�̂́u�E�N���C�i�ɑ����邷�ׂĂ̗̓y�E���v�����߂��܂Ő키�v�ƍēx�A�E�܂����R�����g��z�M���Ă��܂��B
���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U���甼�N���߂��āA�E�N���C�i��ꂪ�ڗ������������A�ēx�A���ێЉ�̊S���E�N���C�i�Ɍ��������A�x�����x���������悤�Ƃ����_���������܂����A�������͏������������ď����ɂ߂�K�v�����邩������܂���B
���̈�Ⴊ�u���V�A�̒e��͒�����n�߂Ă���v�Ƃ������ł����A����ɑ��Ă�NATO�̈�p��S���A���V�A���d�p�������h�C�c�̘A�M�R�������u�E�N���C�i�R��NATO�̎x�����ă��V�A�R�������Ԃ��Ă��邪�A���V�A���̒e��A����ӂ�r�����Ă���Ƃ����̂͋��炭�������͂Ȃ��B���V�A�͈���������̒e����E�N���C�i�ɑ��ėp���A���̂Ȃ��ɂ͋����ł�����З͂����Ȃ�傫�����̂�����A�����ʍU���ɓ������邾���̗]�͎͂����Ă���悤���v�Ƃ̌����������Ă���̂́A��l�̉��l������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�n�C�}�[�X�Ȃǂ̎˒��������A�U���@�\���D��Ă��镐����A�g���R���狟�^����Ă���h���[���ɂ��ʒu�c���ƍ��킹�邱�ƂŁA�m���Ƀ��V�A�̒e��ɂ�j����A�⋋�H��f�����肷���ʂ͋����Ă��܂����A�܂��܂����V�A�͗ʂŃE�N���C�i�ɏ����Ă���A��C�ɃE�N���C�i�R�����n��҉�ł���قǎ��Ԃ͊Â��Ȃ��Ƃ������Ƃ���Ă���̂��ƍl���܂��B
�����č���A���V�A���̓����S�ɍēx�_����\�������鎖�Ԃ��A�N���~�A�����ւ̍U���ł��B
���v�[�`�����̓{��̉ɖ��𒍂��N���~�A�����ւ̍U��
2014�N�Ɂu���V�A�l���E�̌��������v�Ƃ�������̉��A�̐�ԕ����Ə���Ń��V�A����C�ɃN���~�A���������Ă��܂��܂����B���̌�A�u�N���~�A���������߂��v��NATO�₻�̒��Ԃ����̍����t�ɂȂ�A���v�[�`���哝�̐��͂̊���ɂȂ��Ă��܂����A���i����悭�ӌ����������Ă���X�g���e�W�X�g�����H���A�u�E�N���C�i�����̎��_�ŃN���~�A�ɐG���Ă��܂����̂́A�헪��A�����Ƃ͎v���Ȃ��v�Ƃ̂��ƂŁA�u������@�ɁA�܂Ƃ܂�������Ă��Ă������V�A�R�̖�����o�܂��A�E�N���C�i�ɑ��Č���I�ȍU���ɏo������@�^�����߂邱�ƂɂȂ���̂ł͂Ȃ����v�ƍl���Ă���悤�ł��B
2014�N�̃N���~�A�����̕����́A�v�[�`���哝�̂ɂƂ��Ă̓T�N�Z�X�X�g�[���[�Ƃ��Ĉ����Ă���A�܂������ɁA���\�A��̌��x�͋߂Â����Ƃ������ď����Ƃ̌��ʂ��Ӗ�����厖�Ȍ_�@�ƌ����A���ł����������x�����̊�ՂƂȂ��Ă��鎖�����ƍl�����Ă��܂��B���V�A�C�R�̍`�ł̑��������j�����́A���s�Ƃ͌��ɂ͂Ȃ��Ă��܂��A���炭�E�N���C�i�R�̓��ꕔ��(���F�p���ɌP������Ă���O���[�v)�ɂ��d�Ƃƌ����Ă���A�E�N���C�i���������ے肵�Ă��Ȃ����Ƃ���A�v�[�`���哝�̂Ƃ��̎��ӁA�����ă��V�A�R���ł̓{��̉ɖ��𒍂����ƂɂȂ����Ƃ��������ł��B
�l�I�ɂ̓N���~�A���������V�A������I�ɕ����������Ƃ͎�����Ȃ����Ƃł����A�헪�I�ɂ́A�u����̃��V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�̎��s����ەt���邽�߂̍Ō�̃g�h���v�Ƃ��Ďc���Ă����Ă��悩�����̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B
���Ȃ݂ɁA����ɂ���8��30���ɖS���Ȃ����S���o�`���t�哝�̂��A����܂ł̓v�[�`���哝�̂̕��j����Ă����ɂ�������炸�A2014�N�̃N���~�A���������ɂ��Ă͎x�����Ă����قǂŁA����̃E�N���C�i�N�U�ւ̔��Ƃ́A�����ĕ����Ă����Ƃ̂��Ƃł�����A�u���V�A�����ł����v�[�`���哝�̂̐��͂������Ă��Ă���v�Ɗ��X�Ƃ��ē`������e���ǂ��܂ŐM���ɒl���邩�͋^��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�y�X�R�t�哝�̕{���̂悤�Ƀv�[�`���哝�̂̃X�|�[�N�X�}���Ƃ��ĕ\�����Ĕ�������l�͕ʂƂ��Ă��A�N���~�A�����ւ̃��V�A�l�̎v������͕���܂��A���Ɏ���̃T�N�Z�X�X�g�[���[�ɓD��h�����E�N���C�i�ɂǂ̂悤�Ȉꌂ���v�[�`���哝�̂������悤�Ƃ���̂��A�ƂĂ��C�ɂȂ�܂��B
���ɔ��ɋC�ɂȂ�̂��E�N���C�i�암�ɂ���A���B�ő�̌����ł���U�|���[�W������������U�h�̍s���ł��B
���V�A�R���������ɒ������A���d���Ɗ֘A�{�݂��蒆�Ɏ��߂Ă��钆�A�U�|���[�W���������̎{�݂ւ̍U�����������Ă��܂��B���q�F����100���[�g���̈ʒu�ɖC�����c�Ƃ����w�����肻���ȏ�����������܂����A���ꂪ�N�̎d�Ƃ��A��������܂��^���͂킩��܂���B
����ɂ́u���V�A�R�͂��Ȃ�ǂ��l�߂��Ă���A��ނ����������ɃE�N���C�i����̍U������߂悤�Ƃ��Ă���v�Ƃ��������e��A�u�E�N���C�i�݂̂Ȃ炸�A�E�N���C�i���x��������Ӎ��A���B�e�����A�ꍇ�ɂ���Ă͊����Y����H�炤�Ƃ��������o���Ă���̂��v�Ƃ�����������܂����A����(���Ȃ���)�U��Ƃ͌����Ȃ��ł��傤���A������܂������Ƃ��قȂ�悤�ȋC�����Ă��܂��B
���������ւ̋����I�ȍU�������݂��˂Ȃ��e���́A������ꌴ�����̂̋L������у`�F���m�[�r��(�`�F���m�u�C��)�������̂̋L�����N���Ɏc���Ă��鎄�����ɂƂ��Ă͋��|�ȊO�̉��ł��Ȃ��A������퓬�Ɋ����������Ƃ��Ă��邱�Ƃ͍s���߂����Ǝv���܂��B
���ێЉ�̌��O�̍��܂���A���q�͂̕��a���p�̊m�ۂ��i��IAEA�̒����c(�O���b�V�[�����ǒ����܂�)���U�|���[�W�������̏����ׂ��E�N���C�i���肵�Ă��܂����A���̌��ʂ͖��m���ł��B
�����V�A���U�|���[�W�������ɒ����������Ă��闝�R
�ꉞ�A���V�A���{�͋��͂̎p���������Ă��܂����A��������̃��V�A�R�̓P�ނ́u����̎���̋c��ɂ͂Ȃ��v�Ǝ���Ȃ��p���ŁA���݁A�������R���g���[�����Ă��郍�V�A�R���ǂ�قNj��͓I���͂킩��܂��A���炭���قNJ��҂͂ł��Ȃ��ł��傤�B
��������ƁAIAEA�̒����c�ɂ�钲���̗L�����ɋ^�₪�悳��邱�ƂɂȂ�܂��B
����̒����͖{�i�I�ɂȂ�̂��H����Ƃ������̌��������Ȃ̂��H
����͂��ꂩ�猩���Ă���Ǝv���܂����A�e���̌��q�͂̐��Ƃ́u�{�C�Ȃ�A�����ɂ킽���Ē����c�̓U�|���[�W�������Ɏc��A���Ԃ����ɂ߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ɣ������AIAEA���v�悵�Ă��鐔���Ԃ́g�����h�̗L�����ɋ^���悵�Ă��܂��B
�Ƃ͂����A�����Ɍ������ɗ��܂�̂́A����������ƍ��ۓI�Ȑ��Ƃ���������̕����ɂ�����g�l�Ԃ̏��h�����Ă��܂����Ƃ��Ӗ����܂��̂ŁA����̒����c���g�����ɗL���I�Ɏg�����h��헪�I�ɍl����K�v������܂��B
���V�A�������ɒ������Ă���̂́A�؉H�l�܂��Ă��邩��Ƃ������́A�퓬�Ƃ͕ʂɃE�N���C�i�o�ς̐����C���t������ߏグ��Ƃ����ʂ̍��ł���Ǝv���܂��B
����́A������Ƌ�����������܂��A���V�A�ɏd�x�̐��ق��ۂ����B�e���ւ́g���Q�h�Ƃ��ăp�C�v���C���̃o���u��߁A���B�e��(�h�C�c�A�t�B�������h�Ȃ�)����ߏグ�Ă���헪�Ɏ��Ă���C�����܂��B
�����ă��V�A���؉H�l�܂��Ă��邩�ۂ��ɂ��ẮA4�N�Ԃ�ɊJ�Â�����K�͂ȌR�����K(��������Ή�)�̗l�q������킩���Ă��邩�Ǝv���܂��B
�����ɒ����݂̂Ȃ炸�A�������x�����A���V�A�Ƃ̓K�ȋ�����ۂ������C���h���Q�����A���ɃX�^���n�̍��X���܂߁A�v12�����̌R���Q������̂��A�������͂ǂ��]�����ׂ��ł��傤���H
���V�A�ɂ͂܂��]�͂�����̂��H���V�A�̊S�́A�����Ƌ��ɁA���ɂ��������Ă���̂��H���V�A�Ƃ��Ă͐��ق�}�����̂悤�ɁA����̎x���҂̑��݂����������̂��H
�����̖₢�ւ̓����́A���炭����ƌ����Ă���Ǝv���܂��B
���āA�����ŃE�N���C�i����痣��܂����A�E�N���C�i��ɑN���������]�т͎��鏊�ŕ\�o���Ă��Ă��܂��B
���̈�Ⴊ�A�C���N�Ŕ���������K�͂ȕ��͑Η��ł��B
��̑��I���ő����̎x���������T�h���h(�V�[�A�h)�͌o�ϓI�ɍ������閯����̎x���Ă���A���������A�����J�P�ތ�̃C���N�̏����P�ł��Ă��Ȃ����Ƃɔ������āA�h�̒��ł���T�h���t(����͋c���ł͂Ȃ�)���������̖��\���ɍR�c���邽�߂ɐ�������̈��ނ�\�����A����Ɍĉ������x���҂�������K�̓f�����N�����A���ꂪ���T�A���͂ɂ��Η��ɔ��W�����Ƃ����V�i���I�ł��B
�T�h���t�́g���ށh�錾�͎��ۂɂ̓T�h���h���x�����閯�O�����邽�߂̍�킾�Ǝv���܂����A���ʂƂ��āA�����ł���������Ղ��Ǝ�Ȍ������̖��͂����N���[�Y�A�b�v����A���X��莋����Ă��������ԁE�@�h�Ԃ̂��������ɍē_���āA����A�S�y�I�ȑΗ��ɔ��W���Ă��܂��B
�܂����������Ԃł��B
���ُ̈킳�́A��s�o�N�_�b�h�Ő��{�@�ւ��W�܂�A���O���̌��ق��W�܂�Green Zone(�C���[�W�ł́A�����̉i�c���E������!?)�܂ŕ����̉̕��͋y��ł���A���{�@�\���}�q���Ă��邱�Ƃ������O�Ɏ����H�ڂɂȂ��Ă��܂��B
�ُ�ȏ�Ԃ��A�C�����͍�������A�C���N�ւ̒��s�ւ��~�߂�Ƃ����[�u������Ă��܂����A�e������g�و������O�ɔ�����[�u��������悤�ł��B
���Ȃ݂ɁA�T�h���t�̓V�[�A�h�ł��̂ŁA�C�����̈Ö^��ꂻ���ł����A�T�h���h�̓C�����Ƃ��Η��W�ɂ���Ƃ���A�C�������{�������ɂ�������ɂ��֗^��ے肵�A�̕������ł��Ȃ��悤�ɋC��t���Ă���悤�ł��B
����x�͐��͂��������Ƃ����C�X��������������
���ꂪ���ނ��ƌ����A�c�O�Ȃ����x�͐��͂��������Ƃ����IS�̕����̒����ŁA����̓C���N�̍��Ƃ��Ă�integrity�����킹�A���Ӎ��ɑ��čēx�A���|�𓊎˂��邱�ƂɌq�����Ă��܂��B
�����Ă���́A�Œ��ꒃ�ɂ��邾�����ė����������A�����J���{�ƃA�����J�R�ւ̔��ɂ��Ȃ����Ă���̂ł����A���̉e���ɂ��ẮA�܂��̋@��ɁB
�A�����J����������AIS���䓪���n�߂��ƌ����A�A�t�K�j�X�^�����P���Ă���ߌ�����ڂ����炷�킯�ɂ͂����܂���B
8��30���ŕČR�̍Ō�̔�s�@���J�u�[�����ۋ�`���ї����Ă��炿�傤��1�N���o���܂����A�x�z�����߂����^���o�����͂́A���ۓI�ɐ����Ȑ��{�Ƃ��ď��F����Ă��Ȃ����肩�A���X�AIS�Ȃǂ���̃e���U���ɑ����A�A�t�K�j�X�^���Ɉ���������炷���Ƃ��ł��Ă��܂���B
�A�t�K�j�X�^������O�Ȃ��A�R���i�̃p���f�~�b�N�̉e�����A�����ɑ�n�k�Ȃǂ̍ЊQ�ɂ�������ꂽ���ƂŁA���������͔j�]���A�h�{�����̎q���̊������ُ�ȃ��x���ɒB���Ă���悤�ł����A�^���o�����͂ɑ��鐭�{���F���܂��قƂ�Ǒ��݂��Ȃ����A���A���ً}���ۗ���c���J�Â������̂́A���O���\������邾���ŋ�̓I�ȍu�����Ȃ��Ƃ������z�ɋꂵ�߂��Ă��܂��B
�^���o���ƌ����A�����̌������͂��D���Ă���Ƃ����_���悭���ΏۂŃN���[�Y�A�b�v����܂����A����ȊO�ɂ��܂������������ɂ������ẴL���p�V�e�B�[������Ă��Ȃ��_�����邱�Ƃ͂ł��܂���B
���ʓI��IS�ɂ��e���݁A�����}���邽�߂ɁA��x�͉�������͂��̃A���J�C�_�Ƃ̐ڐG���\�����ȂǁA�͈����̈�r��H���Ă��܂��B
�u�C���N�̏�A�A�t�K�j�X�^���̏̂Ђǂ��ɂ��Ă͕����������ǁA���ꂪ�E�N���C�i�Ƃǂ��W������̂��H�v�Ƃ������₪���邩������܂��A�����̃P�[�X�ł��A�E�N���C�i�ł̐푈�Ő��������ێЉ�̕��f���e�����Ă��܂��B
�C���N��A�t�K�j�X�^���̃P�[�X�ɑ��ẮA�E�N���C�i�O�́A�哱�������͑��݂��Ă��A���ď������A���{���A���V�A���������A�����Ď��Ӎ����A�o�ϓI�Ȍ��v�̊g��Ƃ����_���̉��Ɏx�����s���Ă��܂����B�����̎x���͍��A��ʂ������̂������A�K�����������I�Ɏx�����s��ꂽ�Ƃ͌����܂��A�܂��g��������h�Ƃ��������͎c���Ă��܂����B
�E�N���C�i�ł̐푈���͂��܂�A���E���O�ɉ����钆�A�C���N��A�t�K�j�X�^���A�~�����}�[�Ȃǂł̍�����ߌ��ɑ�����⌜�O�̕\���͍s������̂́A�x���Ƃ͒������A�����܂ł��g����̃T�C�h(��)�Ɉ����t���邽�߁h�Ƃ��������ړI���������ڐG�ɉ߂����A���̐���������Y���`�̎x���͍s���Ă��܂���(���Ȃ݂ɁA�~�����}�[�̃P�[�X�͕ʂƂ��āA���̊��Y���^�̎x�������Ȃ̂����͓��{�ŁA�x���͌p������Ă��܂�)�B
�u�ƂĂ��C�ɂ͂Ȃ邵�A���O�������Ă��邯��ǁA���͋�̓I�ȍ�͍u�����Ȃ��v
�E�N���C�i�ł̐푈���߂���g�w�n�����h�̉��A�C���N���A�t�K�j�X�^�����A���͍��ۋ�����x�����s���͂��Ȃ��ߌ��̏ے��ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B
����ɂ͂��낢��ȕ����炲�ᔻ������邩������܂��A�������̎v���߂��������ł���A�w�E���Ă��������ˁB
�������A���̒m�����ł́A�C���N��A�t�K�j�X�^���̎S��ɂ��ẮA�F�A�b�����тɂ��ߑ������A���O���q�ׂ�̂ł����A��͍����L�ׂ��Ă��Ȃ��̂�����ł��傤(�����āA��T���ŐG�ꂽ��3�ɂ̍��X�ɂƂ��Ă��A�C���N��A�t�K�j�X�^���͑ΏۊO�̂悤�ł�)�B
���U��グ������������^�C�~���O���킵�Ă��钆��
�C���N��A�t�K�j�X�^�����獑�ۓI�ȊS���̓I�ȍ��D���Ă���̂��A����ԂŖڗ����Ă����ْ��̍��܂�ł��B
�y���V�c���̖K��Ɏn�܂�A���̋L������������A8�����܂ł�4��A�A�����J�̘A�M�c��c���c����p��K��A�A�����J�̑�p�x���m�ɑł��o���Ă��܂��B
����̓y���V�c���̖K���́u��p�́A�A�����J�ɂƂ��Ė{���Ɏx�����鑊�肩�ǂ��������ɂ߂ɍs�������A�܂��ɒ����ɖʂ��A�����`����������F�l�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����v�Ƃ����������Ă̑傫�Ȕg�ł����A10��16����5�N�Ɉ�x�̋��Y�}�����T���A�����3���ڂ̏��F���T����K�ߕ����Ǝ�ȂƂ��̎w�����ɂƂ��ẮA�ʼn߂ł��Ȃ������o���Ă��܂��B
���e��p������K�͂��{�i�I�ȌR�����K�̎��{��A�o�ϓI�Ȑ��ّ[�u�Ȃǂ�p���đ�p�ւ̈��͂�������k�����{�ł����A�A�����J�̌�돂���ƐM���Ă�����p���������������ƍőO���ɕ����A�����ւ̓O��R���錾���āA�����o���A�U��グ������������^�C�~���O���킵�Ă���ɂȂ��Ă��܂��B
�ǂ��܂Ńo�C�f�������̑Β��E�Α�p����ƍ��v���Ă��邩�͐������K�v�ł����A�m����11���ȍ~�̉Ύ킪���܂�Ă��邱�Ƃ͊m���ł��傤�B
�����ŃJ�M�ƂȂ�̂��A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U���ĉ��ď��������V�A�ɉۂ����o�ϐ��ق��g�{���Ɂh�ǂ�قnj����Ă���̂��Ƃ������e�ɂ��Ă̐������ʂł��B
�S�����ʂ��Ȃ��Ƃ͌����܂��A���Ƃ����ē����A�\�肵�Ă����قǂ̌��ʂ͏o�Ă��炸�A�V�R�K�X�Ƃ����G�l���M�[�����A������؍ނ̎����A�����c�l�X�ȁg���́h��ɁA�����ق̕�͖Ԃ�������Ă���͎̂����ł��B
���B�e���ɂ��ẮA�G�l���M�[�Ƃ����C���t���������A�m���h�X�g���[���h�o�R�̃K�X�������e�R�ɁA�v�[�`���哝�̂Ƃ̉䖝��ׂ��������Ă��܂��B���ʂƂ��āA����ł͌����������ł��A���ۂ̐��ّ[�u�ɂ��Ă͋y�э��ɂȂ��Ă���NATO�̍�������܂��B
�����ɑ�3�ɂ̃C���h�����V�A�Y�̐Ζ��ƓV�R�K�X�������āA�����̏�A���ۃ}�[�P�b�g�ɗ����Ƃ����g���h�������Ă��܂����A�G�l���M�[���v�����������钆���������Ƀ��V�A���狟�����邱�Ƃʼn��b�����Ă��܂��B�����ăg���R�ɂ��ẮA�E�N���C�i�Ƀh���[���������Ȃ���A���V�A�Ƃ���������ƌ��Ղ𑱂��Ă��܂����AUAE���T�E�W�A���r�A���������V�A�Ɣ��ɖ��ڂȊW��ۂ��ƂŁA�o�ϓI�ȉ��b���Ă��܂�(UAE�ɂ��ẮA�h�o�C�����X�N���ԂŃG�~���[�c�q����7�֒��s�ւ��^�q���Ă���A�قږ��Ȃ��Ƃ�)�B
���̂悤�ȋ������́A�����Ƃ̋��������p�Ƃ̋������ɂ����ړI�ɔ��f����Ă��܂��B
�ȑO�ɂ����b�����܂������A�T�E�W�A���r�A������UAE���A�����̃A�t���J�������A�����Ƃ̊W���d�����āA��p�֘A�̍��ۈČ��ɂ͂��Ƃ��Ƃ����Ε[�𓊂��܂����A�������咣����g��p�ρh�ɑ��Ď^�����A���ď����𒆐S�ɁA��p�C���̖������ۈČ��ɂ��邱�Ƃɋ���������Ƃ������͂ƂȂ��Ă��܂��B
���̐��́A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�ɑ���e���̔������x�[�X�Ɍ����Ă�����O�ɂ̍��X�ƌ����Ɉ�v���܂��B
�������Ă݂����A������ƒ��Ӑ[���V�i���I������Ă݂Ă��������ˁB
���ɒ���Ԃŕ��͏Փ˂��N�����ہA�ǂ̂悤�ȏ�������ł��傤���H
�������ւ̑Λ��̍őO�����p�Ɠ��{�ɉ����t����č�
��ڂ͍��ۓI�ȑΒ����ق̔����ɂǂ�قǂ̍��X���^�����邩�ł����A����͂قځA����̃��V�A�ɑ��鐧�قւ̎^�����E�����E�������̃��X�g�ƈ�v���Ă�����̂Ǝv���܂��B
���܂��Ƀ��V�A�o�ς̋K��(���E��10�ʂ�11��)�ɔ�ׂ�ƁA�����̌o�ϋK�͂͂��Ȃ�傫���A�ǂ��܂Ő��E1�ʂ�2�ʂƌ����钆���o�ςɁg�|�˂����Ƃ��ł��邩�h���l�����ہA���V�A�ɑ���P�[�X�����A�o�ϐ��ق̌��ʂ͔����ł��傤�B
�����āA�C���h�͒m��܂��A���������́A������25�N�Ԃɂ킽��헪�I�p�[�g�i�[�V�b�v��������ԃC�������܂߁A�������o�b�N�A�b�v���邱�ƂɂȂ�Ɨ\�z����܂��B�䂦�ɁA�Β��o�ϐ��ق́A���قlje���������Ȃ��Ǝv���܂��B
��ڂ́A�R���I�Ȏ��_�ł��B����͍���̃��V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�̏�����Ε�����܂��B���V�A�̐N�U�ɑ��Ă͊e����������A���ď����ɂ��ẮANATO�̘g�g�݂�ʂ�������e��̎x�����s���Ă��܂����A���V�A�ƒ��ړI�ɌR���I�ȑΛ��͍s���Ă��܂���B
���̏Ɋӂ݂�ƁA���ɒ�������p�ɑ��ČR���N�U���s�����ꍇ�A�e������̔��͊���ł��傤���A�R���ʂł͒��ړI�ɑΒ���ɎQ�������A�����܂ł���p�x���Ɍ�����悤�Ɏv���܂��B
����������ƁA�A�����J�͑�p��S�ʓI�Ɏx������Ƃ������̂́A��p�L���̍ۂɌR������͂��Ă���Ȃ��Ǝv���܂��B
����Ȗϑz��������܂��A����������Ƀo�C�f���哝�̂Ƃ̊ԂŁu���{�̖h�q�͋����v�Ɓu�A�W�A�����m�n��ɂ���������̑���v�ɂ��č��ӂ���Ă��܂����A�����������l���������܂��ƁA��p�L�����u�������ہA�ɘ_�������A�ČR�͒��ړI�ɂ͓������A��p�Ɠ��{�ɌR���I�Ȏx�����s���āA�����ւ̑Λ��̍őO�����p�Ɠ��{�Ɂg�����t����h�悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B
�ȑO�A�����̌R�W�҂�X�g���e�W�X�g�Ƙb�����ۂɂ́u���{�Ɛ키�Ȃ�đ傻�ꂽ���Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B�����͒��z�푈�ȍ~�A������o�����Ă��Ȃ����A�܂��Ă␢�E��ɐ�������Ƃ͋ߑ�ɂ����Ă͂Ȃ��B�����Ă��A�����J�␢�E�Ɛ�������{�̋��낵���͂悭�m���Ă���v�Ƃ̂��Ƃł������A�L���̍ہA�������{���Ӑ}�����A�A�����J�Ɏx������`���őO���ɂ��āA�����ƑΛ����Ă����Ƃ�����ǂ��ł��傤���B
�����Ă����ɖk���N��������������o���ė�����H�����āA���̎��A�؍��͂ǂ��瑤�ɂ��Ă���̂��H�����āA�����4�N�Ԃ�̑�K�͌R�����K���g���h��Ώۂɂ��Ă��郍�V�A�͂��̎��A�ǂ̂悤�ɓ������H
���̂悤�ɍl������A�傰����������܂��A�䂪�����{����芪�����S�ۏ���͂ƂĂ��Ȃ����������̂ł��邱�Ƃ͑z���ł��邩�Ǝv���܂��B
�����āA����́A�����Č��ݐi�s�`�̃E�N���C�i�ł̐푈�Ƃ͖��W�ł͂Ȃ����Ƃ���������ɂȂ邩�Ǝv���܂��B
�܂Ƃ܂�̂Ȃ����e�ɂȂ�����������܂��A�˔��q���Ȃ��悤�Ȃ��b���Ƃ������ɂȂ邩������܂���B
�������A���ۏ����ՓI�ɒ��߂Ă݂��ہA���̂悤�ȕ��͂�����̂��Ƃ��l�����������A�F����̂��l���̈ꏕ�ɂ��Ē�����K���ł��B�ȏ�A���ۏ�̗����ł����B
���V�A�̓Ɨ��n���_�����@�ցu���o�_�Z���^�[�v��1���A�E�N���C�i�N�U�ɂ��čŐV�̐��_�������ʂ\�����B�v�[�`���������u���ʌR�����v�ƌĂԐN�U�ɂ��āA�u�p���v�Ɓu�a�����v�ňӌ������Ă�������炩�ɂȂ����B2���̐N�U�J�n���甼�N�ȏオ�o�߂��A����타�[�h���g�債�Ă���\��������B
����̒�����8�����{�Ɏ��{����A��1600�l��ΏۂƂ����B�������ʂɂ��ƁA�u�����p�����ׂ����v�Ƃ̉�48���������̂ɑ��A44���́u�a�����c���J�n���ׂ����v�Ɠ����A�u�قړ����v(���Z���^�[)�`�ƂȂ����B���̂���40�Έȏ�͍��p���x���������������A18�`39�ł͉ߔ������a������]��ł���A�Ⴂ����قǐ퓬�I��������Ă���X������������ƂȂ����B
����A�u���ʌR�����v���̂ւ̕]���́u�x���v��46���A�u�ǂ��炩�Ƃ����Ύx���v��30���ŁA7���ȏオ�R���s�����x�����Ă����B
���V�A�̐V�������������I���K���q�̎��S���~�܂�Ȃ��B���V�A�̍��c�^�X�ʐM��1���A���V�A�̐Ζ���胋�N�I�C���̃��r���E�}�K�m�t�(67)�����@��̕a�@�̑�����]�����Ď��S�����ƕ��B���V�A���ǂ͎��E�Ƃ��Ă��邪�A���N�ɓ����ăI���K���q�����͏��Ȃ��Ƃ�8�l���s�R���𐋂��Ă���A���E���Ŕ��v�[�`���h��_�����ÎE���^�������オ���Ă���B
���E�A��ƐS���A�����s���c�B���N�ɓ����ă��V�A�ł͂��܂��܂Ȍ`�ŃI���K���q�����̎��S���������ł���B���\�A�����A���݂̃v�[�`���哝�̂琭�{���x������`�ŋ}���������I���K���q�����Ƀv�[�`�����Ƃ͖����W���������A���N2���̃E�N���C�i�푈�u���ȍ~�A�}���ɊW���������Ă������B
���x�����Y���œ��{���S�ۏ��@�Ǘ��w��C���e���W�F���X����̖k�Ō����͂����b���B
�u�v�[�`�����I���K���q�̋}�������x�����錩�Ԃ�Ɏ����ʂʼn������Ă����̂͗L���Șb�B�������A�v�[�`���̓ƒf�Ŏn�܂����E�N���C�i�푈�ŁA���������̐��ق��闧��ɂȂ����I���K���q�́A�E�N���C�i�푈����\������悤�ɂȂ����B���ꂪ�v�[�`���ɗ���Ɖf��A���X�ɕs�R�����������ʂɂȂ��Ă���Ɖ��Ă̏��@�ւ͌��Ă���v
1���Ɏ��E�����Ƃ����}�K�m�t���͕\�����ăE�N���C�i�푈��ᔻ���Ă����I���K���q�̈�l�������B
4���ɂ̓��V�A����s�K�X�v�����o���N�̌����В����A���e�Ŗ����S�����͂��莀�S�����Ɠ��ǂ����\�������A�g��ꂽ���e�̓��V�A���ꕔ���̂��̂��������Ƃ����炩�Ɂc�B����ɂ��̗����ɂ̓G�l���M�[���m�o�e�N�Ђ̌�����������S���Ŏ��S�����Ƃ���A�ɂ킩�ɐM���������������A�����Ă���B
�u�v�[�`���������ł͏e��ŕ��̂ق��A���ː������܂Ŏg�p�����s�R���������������N�����Ă���A��A�̃I���K���q�̕s�R���̓v�[�`���̎w���Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��B�ߋ��Ƀv�[�`���͐l���E�������Ƃ����邩������A�w����́A�����̎�����������Ƃ����邩�A�Ƃ������Ƃ��H�x�Ɠ��������A���t�҂����邽�߂Ȃ牽�ł��A���Ȑl�Ԃ��v(�k�Ŏ�)
����Ŕ��v�[�`���h���u�ڂɂ͖ڂ��v�̋��d��ɏo�n�߂Ă���B�挎20���A�v�[�`�������x����ƌ�����ɉE�v�z�Ƃ����\�肾�����Ԃ���������B����Ă������v�z�Ƃ̖������������B
���Ȃ�߂��Ƃ����l����_�����ÎE���������ɁA�v�[�`�����ɂ��ÎE�̎肪�߂Â��Ă���̂��Ǝv������A�k�Ŏ��́u�������Ԑ���~���v�[�`����_���ňÎE���邱�Ƃ͕s�\�B�܂��Ō��������݂��邽�ߓŎE���ł��Ȃ��v�ƃv�[�`���ÎE�̉\����ے肵���B
����Łu������E�N���C�i�푈�ɔ�����I���K���q�����̈ÎE�͑����ł��傤�B�K�X�v�����o���N�̕��В��̎��S����Ƀ��V�A���ꕔ���̌��e���c����Ă����̂́A�w���ɔ��t�����炱���Ȃ邼�I�x�Ƃ����Î����v�Ǝ����B�܂��܂����������V�A���ȏ͑����������B
���B�A��(�d�t)���B�ψ���̃t�H���f�A���C�G���ψ�����2���A���V�A�̃v�[�`���哝�̂ɂd�t����̃G�l���M�[�s��𑀍삷�������݂�����A�����ڍ�������ɂ̓��V�A����p�C�v���C���ŋ��������V�R�K�X�ɏ�����i��݂���ׂ����Ƃ̍l����\�������B
�܂��A�K�X������@�ɂ���ēd�͉�Ђ��I�ڂ����ɓ������v�̈ꕔ�����A�ꋫ�ɂ���s�����Ƃ̎x����Ɋ��p���鐭������肷��悤�������B
�t�H���f�A���C�G�����́A�L�Ғc�ɑ��āu�p�C�v���C���ʼn��B�ɋ�������郍�V�A�Y�K�X�ɂ��āA���i�ɏ����݂��鎞���������ƌł��M���Ă���v�ƌ�����B
���̏�Łu���i����͉��B���x���ł̒�Ă��\�ł���A��@�I�Ȏ���ɋً}��Ƃ��Ĉꎞ�I���v������@�I���������B���x���ő��݂���v�ƕt���������B
���V�A�̃��h�x�[�W�F�t�O�哝�̂̓t�H���f�A���C�G�����̔������āA�d�t�����V�A�Y�K�X�̏�����i�ݒ��i�߂��ꍇ�ɂ͋������~����\�����x�������B�@
�E�N���C�i�̃w���\���B�Ŏ��{�\��̃��V�A�ғ��̐����₤�Z�����[�ɂ��āA���V�A���ݒu�����s�����ǎ҂�5���A������𗝗R�Ɂu�ꎞ��~�v���ꂽ�Əq�ׂ��B���V�A���c�ʐM�^�X�����B
�ɂ��ƁA�w���\���s�ߍx�̃h�j�v����ɉ˂���d�v�ȃA���g�j�t�X�L�[���́A���T�Ԃɋy�ԃE�N���C�i�̖C���Ŏԗ��̒ʍs���ł��Ȃ���ԂƂ����B
�w���\���B�́A���V�A�̐N�U�J�n��܂��Ȃ����V�A���ɐ������ꂽ���A�E�N���C�i�͐�T�A�D�҂�ڎw���{�i�I�Ȕ��U���J�n�����Ɣ��\�����B
�E�N���C�i�̃E�H���f�B�~���E�[�����X�L�[�哝�̂�4���̃r�f�I�����ŁA�E�N���C�i�R���암�Ɠ����h�l�c�N�B�ŘI�R����v3�����̏W����D�҂����Ɛ錾�����B�E�N���C�i�R��8��29���Ƀw���\���B�ȂǓ암�̗̓y�D�҂Ɍ������]�U���ɏ��o���Ă���A��ʂ��������邱�ƂŎm�C���ە�����_��������Ƃ݂���B
�[�����X�L�[���͓암��2�����A�h�l�c�N�B�ł�1�����̏W�����u��������v�Əq�ׁA�E�N���C�i�R�̕������̎^�����B�암�̏W���̓w���\���B���Ƃ݂���B�h�l�c�N�B�͘I�R���S�搧����ڎw���Ă�����̂́A�U���Ɏ���Ă��Ă���B
�哝�̕{�����╛������4���A���ꂼ��̂r�m�r�ɁA�������m�������̉���ŃE�N���C�i�������f����ʐ^�𓊍e�����B�哝�̕{�����́u�������v�Ƃ̃��b�Z�[�W��t�����B�ʐ^�́A�����h�j�v���y�g���E�V�N�B�Ɨאڂ���w���\���B�k���̏W���ŎB�e���ꂽ�Ƃ݂��Ă���B
�E�N���C�i�R�́A�I�R��3���ɑS�搧����錾�����w���\���B�𒆐S�ɑ����ʂŔ������������Ă��邪�A�̓y�D�ҍ��̐i�W�ɂ��Ă͏����~���Ă���B�[�����X�L�[�����r�f�I�����ŒD�҂����W���̏ڍׂɂ͐G��Ȃ������B
�I���h�Ȃ�4���̐틵�Ɋւ��锭�\�ŁA�E�N���C�i�R�̔������u�������Ȃ����݁v�ƕ\�����A�̓y��D�҂��ꂽ���Ƃ�F�߂Ă��Ȃ��B�I�R�̓~�T�C���U����C���őR���Ă���B
�E�N���C�i���c�ʐM�ɂ��ƁA�w���\���B�ɗאڂ���암�~�R���C�E�B�̍��������{�݂�4���A�C�����A��������g���̔�Q���o���B�E�N���C�i�R�Q�d�{����4���A�I�R���~�T�C��14���˂��A15��ȏ�̋��s�����Ɛ��������B
���V�A�Œ���������Ɉ����l���c�̂̊�����3���A���g�̂r�m�r�ŁA�v�[�`���I�哝�̂��E�N���C�i�N�����ɔh�����镺�����m�ۂ��邽�߁A�����̑��ƂȂǂ�ΏۂɌ_��R�l�Ƃ��Ďu�肳����]�ƈ����̃m���}�����蓖�Ďn�߂��Ɩ\�I�����B���c�̃��V�A�S����1���l���W�߂�悤�w�����ꂽ�Ƃ��Ă���B
���V�A�S���̓������Ƃ��āA�ҋ��Ȃǂ̏ڍׂ������ꂽ���������\�B�_��R�l�ƂȂ�A��Б��ƘI���h�Ȃ��v40�����[�u��(��92���~)�̈ꎞ�����x�����A�]�R���͌���30�����[�u����{�[�i�X�̎x���Ȃǂ���Ă���Ƃ����B�v�[�`�������́A���������ɂ�鍑���̔������x�����A�l�X�Ȏ�@�Łu�u�蕺�v���W�߂Ă��邪�A��q���`�����Ă���B
���V�A�ɓ��E���W�I�X�g�N��5���A��7���o�σt�H�[�������J�������B�E�N���C�i�N�U�ʼn��Ă̑��V�A���ق���������钆�A�o�ϊ����̈ێ���ď����Ƃ̋��͂ɂ��Ęb�������B�v�[�`���哝�̂�7���̑S�̉�ʼn������A���قɋ����Ȃ��p�������߂ċ������錩�ʂ����B
7���̑S�̉�ɂ͐e���V�A�I�ȃA�����j�A�̃p�V�j�����A�����S���̃I���[���G���f�l�A�����̌I�폑�E�S���l����\���햱�ψ���(����c���ɑ���)�A�~�����}�[���R�̃~���A�E���t���C�����i�ߊ��炪�Q������B2���ԉ�k���\�肳��Ă���B
����ɁA�C���h�̃��f�B�A�}���[�V�A�̃C�X�}�C���T�u�����r�f�I���b�Z�[�W����Ƃ����B�E�N���C�i�N�U�ŌǗ����郍�V�A�́A�����ɑ����ăC���h�ɂ��ڋ߂��Ă���A�C���h�����m�n����d������č������O���Ă���B
����̃t�H�[�����́u���ɉ����鐢�E�ցv���e�[�}�ɐ����A�č��̈�Ɏx�z�ɋ����ق������Ă���B�J���ɐ旧���A�y�X�R�t�哝�̕��̓^�X�ʐM�Ɂu���Ă̔�_���I�ł������s�������E�I�ȗ��������N���������A���V�A�̓}�N���o�ς̈�����ێ����Ă���v�Ǝ咣�B�����㏸��H����@�́A���قɋN������Ƃ̔F�����������B
�v�[�`������6���ɃE���W�I�X�g�N�ŁA������Q�������K�͌R�����K�u�{�X�g�[�N(����)2022�v�����@����B1���̍Ő��[�̔�ђn�J���[�j���O���[�h�K��ɑ����A5���͋ɓ��J���`���c�J�����ɑ؍݁B11���̓���n���I��O�ɒn���d���̗�����A�s�[�����A�����^�}�u���ꃍ�V�A�v���x������_���Ƃ݂���B
���V�A�ɋ��d�p���ŗՂރg���X�p�̒a�����v�[�`�������͌x�����Ă���B�^�X�ʐM�ɂ��ƁA�X���c�L�[���@�O���ψ�����5���A�u�g���X���̗���Ɍ��z��������Ƃ͂��蓾�Ȃ��v�Əq�ׁA�����I�ɑΉ�����l����\���B�u���V�A�����ŃG�l���M�[�E�H�����i�㏸�������ł���Ƃ��v���Ȃ��v�Ɣ�������B
���@�O���Ϗ����̃x���N�c�����A�W�����\�������Ő��܂ꂽ�����V�A�H�����g���X���ɂ���āu�p���E���������v�ƌ��������ʂ����������B
�C���^�[�t�@�N�X�ʐM�ɂ��ƁA�����A�W�A�E�J�U�t�X�^���O���ȕ���5���A�����̏K�ߕ�(�V�[�W���s��)���Ǝ�Ȃ�14���A�J�U�t�X�^����K�₷�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�V�^�R���i�E�C���X�ւ̊����������x�����Ă���Ƃ݂���K�������O�ɏo��̂́A�V�^�R���i�����g��O��2020�N1���Ƀ~�����}�[��K�₵�Ĉȗ��ƂȂ�B
�K���́A��15���ɃE�Y�x�L�X�^���̃T�}���J���h�ŊJ�������C���͋@�\(�r�b�n)�̎�]��c�ɏo�Ȃ�����̂Ƃ݂���B�r�b�n��]��c�ɂ́A���V�A�̃v�[�`���哝�̂��o�Ȃ��錩�ʂ��ƂȂ��Ă���B�K���ƃv�[�`�����́A���V�A���E�N���C�i�ɐN������O�̍��N2�����{�ɖk���őΖʉ�k���Ă���B����ȗ��A���߂ĂƂȂ�Ζʂł̒��I��]��k���J�Â����\��������B
�����͑ΘI���ق��s���ĉ�����Ă���B��p���������Ă��č��Ƃ̑Η����[�܂钆�A�K���͊O�V��ʂ��ă��V�A�Ƃ̘A�g����������l���Ƃ݂���B���I���哱����r�b�n�ɂ̓C���h��p�L�X�^���A�����A�W�A�e�����Q������B���ĂƂ͈�����悷����̍��X�Ƃ̋��͂��m�F���錩�ʂ����B
������10���ɁA5�N��1�x�̋��Y�}�����T���Ă���B�K�������̃^�C�~���O�ŊO�V�ɓ��ݐ�̂́A�ٗ��3���ړ���Ɍ������}���̒����Ȃǂ������ɐi��ł��邱�Ƃ̕\��Ƃ������������B
�J�U�t�O���ȕ��́A�K�����J�V���W���}���g�E�g�J�G�t�哝�̂̏����ɉ������Ɛ��������B�����́A�G�l���M�[�������L���ȃJ�U�t�Ƃ̊W�����߂Ă����B����o�ό��\�z�u��ш�H�v�̗v�ՂƂ��ʒu�Â��A�d�v�����Ă���B
�E�N���C�i�N�U�ɂ��o�ϐ��ٌ�����V�A�ł̃v�[�`���哝�̂̎x���́A��������Ă���B���N���ƂɌR���s�����N�����w���҂��Ȃ����V�A�����͎x����������̂��B
�{�e�ł͌����V�A�O�����ł���T�R�z�i�����w�n���w�Ɨ��j�œǂ݉������V�A�̍s�������x���A���V�A�����ƃ��V�A���E�C�f�I���M�[�ɂ��Đ�������B
�C�����E�C���C��(1883-1954�N)�́A�\�r�G�g�����ɔے�I�ł��������߁A�c����Ǖ����ꂽ�v�z�Ƃł���B�ނ͍݊O���n���V�A�l�̑g�D�ł���u���V�A�S�R�A��(ROVS)�v�̃C�f�I���[�O�Ƃ��Ă��m����B�X�C�X�Ŏ����A�\�A�����A���̈⍜�̓��X�N���ɖ������ꂽ�B
���݁A���V�A�ł��̒��삪���X�ɔ�������Ă���B�v�[�`���哝�̂����̉����̒��ł����C���C���Ɍ��y���Ă���A�v�[�`���哝�̂̐����v�z�ɑ傫�ȉe����^���Ă���l���ł���ƍl������B
��������̐M�́g���V�A�h���̂��̂ւ̐M��
�C���C���͔M�S�Ȑ�����̐M�k�ł���A�����M�����V�A���ƂɂƂ��čł��d�v�Ȏv�z���ƍl���Ă����B�C���C�����u���V�A�̃i�V���i���Y���ɂ��āv�Ƃ������̒��Łu��X�͂Ȃ����V�A��M����̂��v�Ɩ₤�Ă���B�C���C���̓\�A��ے肵�Ă������A�c���ɑ��鈤�͋��������Ă����B
�u��X���V�A�l�́A�ǂ��ɏZ�݁A�ǂ�ȏ�Ԃɂ������Ƃ��Ă��A�c�����V�A�ɑ���߂��݂�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����͎��R�Ŕ������������Ƃ��B���̔߂��݂͉�X�����̂Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A��������ׂ��ł͂Ȃ��B����͑c���ɑ����X�̐��������Ƃ�������ƐM�̌���Ȃ̂��v�Ə����Ă���B
�C���C���ɂ��A���V�A�l�ł���Ƃ������Ƃ́A���V�A���b�����Ƃ������Ӗ�����̂ł͂Ȃ��B�u���V�A��S�������A���������ă��V�A�̉��l����Ǝ��������āA���̓Ǝ��������V�A�l�ɗ^����ꂽ�_�̎����ł��邱�Ƃ𗝉�����v���Ƃł���B
�C���C���́A�`���b�`�F�t�́u���V�A�������M����̂݁v�Ƃ����t���[�Y�������A���V�A�ւ̐M�͕s���ł���A���V�A�ւ̐M�Ȃ����Ă͐����邱�Ƃ����V�A�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����B�����āA���V�A��M����Ƃ͐_�ɂ����ă��V�A�����邱�Ƃ��Ƃ���B
�C���C���͔�����`�҂Ƃ��āA���V�A�鍑�̍ċ���]��ł����킯�����A���̎v�z�ɂ̓��V�A���E�C�f�I���M�[�̊j�S���\������Ă���Ǝv����B�����ł������V�A���E�C�f�I���M�[�Ƃ́A���V�A�̗��j��ʂ��ă��V�A�̌��͂���э����̒��Ŏ��R�Ɍ`������Ă������V�A�ŗL�̃i�V���i���ȉ��l�ς̂��Ƃł���B
���V�A�̐����I�C�f�I���M�[�╶���I�C�f�I���M�[�A�����ď@���I�C�f�I���M�[�́A���̃��V�A�̊�ՓI�C�f�I���M�[�Ɍ��т��Ă���ƍl������B���V�A���E�C�f�I���M�[�������Ē�`����Ƃ���A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ƂȂ邾�낤�B
�g���V�A�h�Ƃ͈̑�ȑc���ł���A���̑c���g���V�A�h�ւ̈��ƐM�ɂ���āA���V�A�̈̑傳��i�삵�A���W�����悤�Ƃ��鈤����`�I���l�ςł���B���́g���V�A�h�Ƃ́A���y�A���j�A�����A�����ă��V�A�����ɂ���Č`�����ꂽ1�̕������ł���A�卑�ł���B�卑�ł���Ƃ́A���V�A�̈̑傳�̐����I�\���ł���A���E�̖��^�̌��������Ă��邱�Ƃł���B
�����傰���Ȃ悤�����A���V�A�l�̉��l�ςƂ������̂́A�܂��ɑc���ɑ���p�g���I�e�B�Y���ł���B2008�N�̃W���[�W�A(�O���W�A)�������A2014�N�̃N���~�A�u�����v���A2022�N�̃E�N���C�i�N�U���A���{���܂߉��Ă̎��R�����`�̉��l�ς��猩��܂����������ł��Ȃ��s���ł���B����ɂ�������炸�A���V�A�����̓v�[�`���哝�̂��x�����A�c�����V�A�̍s�����m�肵�Ă���B
����́A�v�[�`���l�ւ̐M���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����낤�B�����ł͂Ȃ��A���V�A�Ƃ����c���ɑ���M���ł���ƍl������Ȃ��̂ł���B
��2020�N���@�����Œ��ڂ��ׂ�����
2020�N�̌��@�����ɂ��ẮA�v�[�`���哝�̂�5�������6�����\�ɂ���C�����肪�N���[�Y�A�b�v���ꂽ���A�ނ���A���V�A���E�C�f�I���M�[�̒莮���Ƃ������ʂ������d�v�������̂ł͂Ȃ����낤���B
���̃��V�A���E�C�f�I���M�[�́A�c�����A�p�g���I�e�B�Y���ɗ��r������̂ł���A�i�V���i���ȉ��l�ςł���B�\�A�Љ�ɂ����Ďx�z�I�ł������悤�Ȑ����I�ȍ��ƃC�f�I���M�[�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ��K�v�ł���B����ɂ��ẮA�哝�̏A�C���O�Ƀv�[�`���哝�̂����\�����_���u��N�I�̋��ɂ��郍�V�A�v(1999�N12��30��)�Ŗ��L����Ă���B
�v�[�`���́A�u���V�A�I���O�v�Ƒ肳�ꂽ�͂ŁA���V�A�͓��I�����Ԃɂ��邪�A�����������I�����Ԃ�1917�N�̃��V�A�v���̎���A1990�N��̃\�A�����̎���Ɍ�������̂��Ƃ��A���V�A�̌�������V�A�v���̎���ɂȂ��炦��B
�����āA�����̐����Ƃ�w�҂��Ăт����Ă���u���ƃC�f�I���M�[�v�̑n�݂ɂ��āA���������p��͒m�I�A���_�I�A�����I���R���Ȃ������\�A�����A�z�����邽�ߓK�ł͂Ȃ��Ƃ��A���Ƃ̌����C�f�I���M�[�̕����ɔ�����̂ł���B�����āA�����Ȃ�Љ�I���ӂ������I�Ȃ��̂ł������肦�Ȃ��Ƃ���B
�v�[�`���ɂƂ��ẮA�������V�A�Љ�̓����ɕK�v�Ȃ��̂͐����I�Ȍ���(����)���ƃC�f�I���M�[�ł͂Ȃ��A�����I�œ`���I�ȉ��l�ςȂ̂ł���B�����āA���̂悤�ȉ��l�ςƂ��āA�p�g���I�e�B�Y���A�卑���A���Ǝ�`�A�Љ�I�A�т�������B
�������I�œ`���I�ȉ��l��4�̈Ӗ�
�p�g���I�e�B�Y���́A�啔���̃��V�A�l�ɂƂ��čm��I�ȈӖ���L���Ă���A�c���A���j�A�����Ĉ̋Ƃɑ���ւ�ł���B�p�g���I�e�B�Y���������A���V�A�l�͈̋Ƃ�B�����邱�Ƃ��ł��閯���Ƃ��Ă̎��Ȃ�r�����邾�낤�Ƃ����̂ł���B
�卑���ɂ��ẮA���V�A�͈̑�ȍ��Ƃł��������������葱����Ƃ����B�卑���́A���V�A�̒n���w�I�A�o�ϓI�A�����I���݂ƕ����������������ł���B�卑�Ƃ��Ă̔\�͂Ƃ́A�R���͂ł���ȏ�ɁA����̈��S���m�ۂ��A���ێЉ�ɂ����鍑�v��i�삷��\�͂ł���Ƃ����B
���Ǝ�`�ɂ��ẮA���V�A�̓A�����J��C�M���X�̂悤�Ƀ��x�����ȉ��l�ς����j�I�`���ƂȂ��Ă��鍑�̏Ă������ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����B���V�A�ɂ����āA����(����)�Ƃ́A���⍑���̐����ɂ����ċɂ߂ďd�v�Ȗ������͂����Ă����B���͂ȍ��ƌ��͂̓��V�A�l�ɂƂ��Ĉُ�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�����̕ۏł���A���v�̎句�҂ł����v�Ȍ����͂Ȃ̂��B
�Ō�ɎЉ�I�A�т����A���V�A�ɂ����Ă͌l��`�����W�c�I�`�Ԃ��D�悵�Ă����Ƃ���A���V�A�Љ�ł͉ƕ����I�ȌX�������t���Ă����Ƃ����B�����̉��P�Ƃ������̂����Ȃ̓w�͂������ƂƎЉ�̎x���Ɍ��т��čl�����̂ł���B���������X���͌��݂��x�z�I�ł���A������l�����ĎЉ����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���B
���̏�ŁA���V�A�ɂ͋��͂ȍ��ƌ��͂��K�v�ł���ƌ��_�t����̂ł���B
���������v�[�`�������̏����̃v���O���������߂ĐU��Ԃ�ƁA�����ɒʒꂷ��v�z�������Ă���̂ł���B�p�g���I�e�B�Y���A�卑���A���Ǝ�`�A�W�c���Ƃ������v�f�́A�X������`�҂̎咣�ɒʂ�����̂ł���B��ɒ莮��������ՓI�C�f�I���M�[�Ƃ��Ẵ��V�A���E�C�f�I���M�[�ɂ��Ó�������̂ł���B�����`�Ǝ��{��`�Ƃ�����������(���ՓI��)���l�ς�����͂��邪�A����͂����܂ł����V�A�̓`���ɑ������`�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
���V�A�̒����v�z�ƃA���N�T���h���E�h�D�[�M�����̖��_�����E�h�D�[�M�i�����A8��20���A���X�N���x�O�Ŏ����Ԃ��Ɣ��E���ꂽ�B���̎Ԃ��h�D�[�M���������p����\�肾�������Ƃ���A�ƍs�̓h�D�[�M������_�������̂Ƃ݂��Ă���B�h�D�[�M�����Ƃ͈�̂ǂ�Ȑl���Ȃ̂��B���V�A�v�z����Ƃ���t�����X�l�N�w�ҁA�~�V�F���E�G���`���j�m�t�̒����w�E���W�[�~���E�v�[�`���̓��̂Ȃ��x(�����)���Љ��\�\�B
���v�[�`����m���ŏd�v�ȁu���[���V�A��`�v�Ƃ�����]
�E���W�[�~���E�v�[�`�����܂����V�A�̑哝�̑�s������2000�N�A�u���V�A�@���������̐V�����W�]�v�Ƒ肳�ꂽ�L���ŁA���̂悤�Ɍ����Ă���B
�u���V�A�͎�������[���V�A�̍��ł���ƔF�����Ă����B�������̓��V�A�̑啔�����A�W�A�̒��Ɉʒu���Ă���Ƃ���������Y�ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B�������A������������܂ł��̎�����L���Ɋ��p���Ă��Ȃ��������Ƃ��m���ł���v
�܂�A���ꂩ��̃��V�A�̓��[���b�p�ł͂Ȃ��A�A�W�A�̕�������������ɐ�ւ��Ă����A�Ƃ����p���������Ŏ����ꂽ�̂��B�A�W�A�ւ̕��݊��͂���v��̎n�܂���Ӗ�����B
���[���b�p�ɑR����悤�ȐV���Ȑ��͂��A�W�A�Ƌ��͂��č��グ��A�Ƃ����v�悾�B���[���b�p�Ƃ��A�W�A�Ƃ��قȂ�V���Șg�g�݁A���V�A�𒆐S�Ƃ��ă��[���b�p�ƃA�W�A�ɂ܂�����n��A�܂胆�[���V�A�n������V�A���x�z����Ƃ����A�u���[���V�A��`�v�̂��Ƃł���B
���Ȃ��V�x���A��V�A�ɓ��n��̔��W���ŗD�悵���̂�
13�N��A�哝�̂Ƃ��Ă̑�3���ڂ��J�n�������A�v�[�`���͂��̐V���Ȉ���ݏo���ԓx��\�����Ă���B
�u�������͒�������ȓ������ɕ������Ƃ��Ă��܂��B�������͎������g�⎩�������̗͂Ɏ��M�������n�߂܂����B����܂Ŏ������͍���������ďグ�A�卑�Ƃ��Ă̌ւ�����߂����̂ł��B�S���E�����V�A�̕�����ڂ̓�����ɂ��Ă���̂ł��B(�c�c)�������͂�������s�����Ă���ɑO�i���Ă܂���܂��v
���������ނ͉���ڕW�Ƃ��đO�i���Ă����Ƃ����̂��B����́A�u���[�_�[�Ƃ��ă��[���V�A�𑩂˂Ă����v�Ƃ������Ƃ��B�������A���̌�v�[�`������̓I�ɂǂ̂悤�Ȍv���ł��o�����ƂɂȂ邩�ȂǁA�N�ɂ��\���ł��Ă͂��Ȃ������B
��l�v�[�`���݂̂�������ق̂߂����Ă����̂ł���B
�u���ꂩ�琔�N�Ԃ̂����ɋN���邱�Ƃ́A����ɂ��̐�A���\�N�̃��V�A�̍s��������肷��d�v�Ȃ��̂��Ƃł��v�B
�v�[�`���̑s��Ȍv�悪������邱�ƂƂȂ�̂́A���̔N�̏I���̂��Ƃł���B�v�[�`���͂��̎��A�V�x���A��V�A�ɓ��n��̔��W�������A�u21���I���V�A�ɂƂ��Ă̍ŗD�掖���v�ł���ƌ�����B
�������āA�����A�A�W�A�A�ɓ��E�V�x���A�Ƃ������[���V�A�n����܂Ƃ߂郊�[�_�[�ƂȂ��]�������ꂽ�̂��B
���u���V�A���������[���V�A����ɂ܂Ƃ߂Ă���v
���[���V�A��`�̒a����1920�N��ł���B
���V�A�v���̌�A�v���n��E�B�[���A�u���K���A�̃\�t�B�A�A�x�������A�p���Ƃ������s�s�ւƈڏZ���Ă������v�z�Ƃ����ɂ���č\�z���ꂽ�̂��B���̑�\�҂̈�l���A�n���w�҂Ōo�ϊw�҂̃s���[�g���E�T���B�c�L�[�ł���B
�ނɂ��A�E�����R���ɂ���ă��[���b�p�ƃA�W�A�Ƃ�����̂͌��ł���A���҂����킹�����[���V�A���A�����J�A�A�t���J�Ɏ����g��O�̑嗤�h�ƍl����K�v������B���̒n��͈�̂܂Ƃ܂�Ƃ��āA�u�n���I�Ɍ����ꍇ�̓Ǝ��̐��E�v���`�����Ă���B
���̂܂Ƃ܂肪�u���[���V�A�v�ł���A���V�A���������̒��S�ƂȂ�B
�T���B�c�L�[�͂��̍����Ƃ��āA�A���������ʂ��Ă��邱�Ƃ�������B���[���V�A�n��͓����琼�ɂ����āA�c���h���A�^�C�K�A�X�e�b�v�A�����Ƃ������n�т����ݍ����A�O�̕����������̃��[���V�A��т�k�����܂łȂ��ł���B
���̂悤�ȏ������ŁA���[���V�A�͐A�����̊ϓ_�������̒n��Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂��B�n���I�ȋN�����猾���Ă�(�E�����R�����X�I�Ƀ��[���b�p�ƃA�W�A���u�U��̋��E���v�ƂȂ��Ă���̂������āA���̒n��ɂ͑傫�ȋN���͑��݂��Ȃ�)�A�C�猾���Ă��A���̈�тɂ͋��ʐ����F�߂���B
���[���V�A�嗤���ł͑��l�ȗv�f���������邾���ł͂Ȃ��B�����炱���A���E�̒��Ń��[���V�A��n���I�Ȉ�̑傫�Ȃ܂Ƃ܂�Ƃ��邱�Ƃ��ł���Ƃ����킯���B�T���B�c�L�[�͂܂��A���V�A���������[���V�A����ɂ܂Ƃ߂Ă���Ƃ������B
�u���V�A=���[���V�A�́A�����E(�A�����J�嗤�����O�̐��E�A���[���b�p�E�A�W�A�E�A�t���J)�̒��S�ł���B���̒��S����蕥���Ă��܂��A���[���V�A�嗤�̕Ӌ��n��(���[���b�p�A�ߓ��A�C�����A�C���h�A�C���h�l�V�A�A�����A���{)�́w�G���ȑg�ݍ��킹�x�ɉ߂��Ȃ��Ȃ�v
�u���V�A�́A���[���b�p�̍��X�̓��ƁA�w�Â���`�ɂ�����x�A�W�A�̖k�ɍL����L��ȍ��ŁA���[���b�p�ƃA�W�A�Ƃ��Ȃ��d�v�Ȉʒu�ɂ���B���V�A���������[���V�A����ɂ܂Ƃ߂Ă���Ƃ��������͂���܂ł����炩�ł��������A�����A���d�v�Ȏ����Ƃ��ĔF������邱�ƂɂȂ邾�낤�v
���v�[�`���̋��c�E�h�D�[�M��
���[���V�A��`�̓\�r�G�g����ɂ͒��ڂ��W�߂邱�Ƃ͂Ȃ��������A���I����A1990�N��ɂȂ��āA�ĕ]������邱�ƂƂȂ�B
����ȐV���ȃ��[���V�A��`(�l�I�E���[���V�A��`)�̎v�z�Ƃ̒��ŁA�ł��L���Ȑl���̓A���N�T���h���E�h�D�[�M�����B
�ނ͂܂��A���܂��܂Ȍ���ɂ��炳��Ă���l���ł�����B�a���҂̂悤�ȕE�₵�A�^���ȓ��������e���炭���ۂ����܂��āA�v�[�`���́u���c�v�Ƃ��Ă�邱�Ƃ�����B2�l�̌l�I�𗬂͂���قǐ[���Ȃ��悤�����A�v�[�`�����l�I�E���[���V�A��`��M���I�Ɏ����グ�郁�f�B�A�̉e�������₪���ɂ��Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B
���l�I�E���[���V�A��`�̒��g
����ł́A�l�I�E���[���V�A��`�̑�\�҂ł���h�D�[�M���̎v�z�����Ă݂悤�B
�h�D�[�M���̎v�z�́A���[���V�A��`�ƋɉE�I�Ȏv�z�Ƃ��������킹�����̂��B
2009�N�ɏ����ꂽ�w��l�̐������_�̍\�z�x�Ƒ肳�ꂽ�{�̒��ŁA�h�D�[�M���̓��[���V�A�鍑�̗��z���f���A���������̎��R��`�▯���`�Ƒ����p����\�����Ă���B���e���Љ�悤�B
���̖{�̒��Ŕނ́A�u�O���[�o�����������R��`�v�����l�ς̑��l���������炵�A�u�|�X�g���_���I�ȕ���������N�����A���E��j�łւƓ����v�Ǝ咣����B
�u���E�̎�҂����͊��ɁA�j�ł̈����O�܂ŗ��Ă���B���R��`�ɂ��O���[�o�������A�l�X�̖��ӎ��ɓ��������A�K�����x�z���A�L���A��y�A�e�N�m���W�[�A�l�b�g���[�N�Ƃ��������܂��܂ȕ���ɐ[���Z�����Ă���B���̌��ʁA���E�̐l�X�͎����̍��╶���ɑ��鈤����A�j���̈Ⴂ��r�����A�l�ԂƂ��ẴA�C�f���e�B�e�B�܂ł���������Ă��܂��Ă���̂��v
�h�D�[�M���̗���́A���[���V�A��`�ƋɉE���͂̌f����u�V�����Љ���v�̗��_�Ƃ��|�����킹�����̂��B���ꂾ���ł͂Ȃ��A�_���`�ƃ��V�A�M�̍��݂����v�z���ނ̓����ł���B�Ⴆ�A�ނ̒���̂���͂ɂ͂���ȑ肪�t�����Ă���\�\�u���L���X�g�̉����Ƃ��ẴO���[�o���Ȗ����`�v�B
�ނɂ��ƁA���V�A�̐i�ޓ��͓�Ɉ���B�������O���[�o�����̔g�Ɉ��ݍ��܂�邩�A�O���[�o�����ւ̒�R�^�����哱���Ă������A�ł���B
���u�E�N���C�i���߂��萼���Ƃ̑����͔������Ȃ��v
2012�N�ȑO�̃v�[�`���͂܂��ǂ�����I�����Ă͂��Ȃ������A�Ɣނ͌����B
�u���V�A�̌��͎�(�v�[�`��)�͘I���Ȑ�����`����邱�Ƃ͂Ȃ��������A���Ƃ����ĕʂ̗���(�X���u��`�A���[���V�A��`)��I�����邱�Ƃ��Ȃ������B�ԓx�����߂��˂Ă����̂��v
�������A�u���܂ł�����扄���ɂ��Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��B����̐��������Ƃ̊W������Â���悤�Ȍ��f�𔗂����������Ă��邾�낤�v�B
���݁A���ă\�r�G�g�A�M�̈�����������X�����V�A�𗣂�ă��[���b�p��A�����J�̕��֕��݊�낤�Ƃ��Ă���B�����āA�����̍��X���߂����āA���V�A�͐��������ƑΗ����Ă���B�h�D�[�M���͂��̂悤�Ȏ��Ԃ𑁂�����\�����Ă����̂ł���B�ނ͌����B
�u�������E�N���C�i�ƃW���[�W�A���A�����J�鍑�̈���ƂȂ����Ȃ��(�c�c)���V�A�̐i�߂�̓y�g��̌v��ɂƂ��đ傫�ȏ�Q�ƂȂ邾�낤�v
�u���V�A�ɂ��E�N���C�i������j�~����Ƃ����A�A�����J�w�c�̖ژ_�������Ɏn�܂��Ă���̂ł���v
����A���V�A��2008�N�ɃW���[�W�A�N�U�����̂���ɁA���Ȃ����Ɍ����ď������ł߂��B�u�N���~�A�����ƃE�N���C�i�������߂����Ă̐��������Ƃ̑����͔����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�A�����ނ͌��_�Â��Ă���B
���h�D�[�M���������哝�̂̓��̒�
�ȏ�A�ȒP�Ƀh�D�[�M���̎v�z���Љ�����A���͔ނɒ��ڎ�ނ��s���Ă���B
�v�[�`���ɉe����^�����N�w�҂ɂ��āA�ނɘb�����̂��B�ނɂ��A�v�[�`���̒��ɂ́A�������̃C�f�I���M�[�̃��f�������w�ɂ��d�Ȃ��đ��݂��Ă���B
�u�܂��A�v�[�`���̓\�r�G�g����ɋ�����AKGB�Ōo����ςA�T�^�I�ȁw�\�r�G�g�l�x�ł��B�\�r�G�g�l�Ƃ��Ă̐S�����v�[�`���̓N�w�v�z�̑�1�̑w�ł��B
�\�r�G�g�l�Ƃ��Ă̔ނ́A���{��`���E���G�ł���Ƃ������E�ς������Ă��܂��B���̓y��ɏd�Ȃ�w�Ƃ��āA���V�A�v����̈ږ������ɂ���ēW�J���ꂽ���R�^���A�܂�鐭���V�A�ւ̉�A��ڎw���i�V���i���Y���E�ێ��`�v�z������܂��B
���̎v�z�̑�\�҂Ƃ��ẮA�C�����E�C���C�����������܂��B�C���C���̓��[���V�A��`�ƑΗ�����v�z�Ƃł��B�������A�ނ͓Ƒn�I�Ȏv�z�Ƃł���Ƃ͌����܂���B�V�����l�����������Ă͂��Ȃ��̂ł��B�N�w�҂Ƃ��Ă̔ނ͖��\�Ȑl���ł��B�C���C�����v�[�`���֗^�����e��������I�ł��B�C���C���͔����Y��`�҂ł������A�v�[�`���͂����ł͂���܂���B�C���C���̓v�[�`���Ɏv�z�I�ȉe����^�����Ƃ��������A�������܂Ƃ߂�Z�p������ɉ߂��܂���B�ނ̎v�z�͋��{�̂Ȃ��l�X�Ɍ������A���{�̂Ȃ��l�Ԃɂ���Đ��ݏo���ꂽ�v�z�Ȃ̂ł��v
�܂�A�C���C���̎v�z�͌��͂ɑf���ɏ]���l�X�ݏo�����߂̓���Ƃ����킯���B�h�D�[�M���ɂ����ꂪ�v�[�`���̓N�w�v�z�̑�2�̑w�ł���B
��3�̑w�Ƃ��āA�h�D�[�M���̓W�����E�p���r�����X�R�̒����A�W�����E�e�B���A�[�g�̊v���I�i�V���i���Y���^���Ƃ̌𗬂��瓱���o�����l�����I���Ă���B�L���X�g����y��Ƃ����ێ��`�A���ւ̖�]���B
�u�v�[�`���̓��[���b�p�̃L���X�g�������m�̘A�����������������Ɗ���Ă��܂��v
���̖�]�̌��ƂȂ����̂́A���V�A�̓N�w�҃E���W�[�~���E�\�����B���t�������Ƃ����u�ێ��`�I���[�g�s�A�v�Ƃ����T�O�ł���B
���̗��z�́A�L���X�g���̉��l���ĔF���������[���b�p�̓`���I�ȍ��X���W�܂�A�u���L���X�g�ɐ킢�ށv���Ƃł���B���ꂾ���ł͂Ȃ��A�u���V�A�������̍��X���哱���Đ킢��W�J���Ă����v�K�v������Ƃ������̂��B
���ł��d�v�ȁu��4�̑w�v
�h�D�[�M���ɂ��A���̑�4�̑w�������ł��d�v�Ȃ��̂ł���B
���ꂱ�������[���V�A��`�Ȃ̂ł���B
���[���V�A��`�́A�u���̃C�f�I���M�[�Ƃ͑S���ʂ̂��̂ł��B���̗��z�̓X���u��`�A���ɑ�2����X���u��`�ƌĂ��A�R���X�^���`���E���I���`�F�t��j�R���C�E�_�j���t�X�L�[�A�����č�Ƃ̃h�X�g�G�t�X�L�[�̎v�z�����ɂȂ��Ă��܂��B
�������A���[���V�A��`�̓X���u��`�����������ꂽ���̂ł��B���[���V�A��`�̎v�z�Ƃ����̓��V�A�̕�������藝�_�I�ɁA���m���I�Ɍ������Ă��܂��B���[���V�A��`�̓��V�A�̗��j�̍ł����[���Ƃ���ɂ܂ŋ����v�z�ł��B����͔��R��ԌR�A�鐭�x����Љ��`�A�ǂ�ȗ���ɂ����Ă͂܂�v�f�������Ă��܂��v
�ނɂ��ƁA���[���V�A��`�́A���j��̂ǂ̂悤�Ȏ���ɂ��L���Ȏv�z�ł���B
�u�A�����J�𒆐S�Ƃ������������ƃ��[���V�A�Ƃ̑Η����������𑝂��Ă��钆�ŁA���[���V�A��`�̎v�z�͍ł����㐫�̂�����̂Ȃ̂ł��v
�h�D�[�M���ɂ��A�v�[�`���́A�\�r�G�g�l�Ƃ��Ă̐S���A�C���C���̔����Y��`�E�鐭�x���A�L���X�g���Ɋ�Â����ێ��`�A�����ă��[���V�A��`�A�����̗v�f�������Ă���B
���E�N���C�i�N�U�̗��R
�܂��A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B
�����̎v�z�������Ȃ�����A�u���ە���ɂ����āA�v�[�`���͌��������������s��������Ă���A�Ƃ������Ƃł��B�����炱���A���V�A�Ƃ����������E�ɑ��ċ����e���͂��s�g���邱�Ƃ��ł��Ă��邵�A�^�C�~���O�ǂ��N���~�A���������邱�Ƃ��ł����̂ł��v
���[���V�A��`�̓v�[�`���̗��z��̌����邾���ł͂Ȃ��A���������������헪�Ȃ̂��B�A�����J�̐��͂ɑR���鐭���I�Ȑ헪�Ƃ��āu�v�[�`���̓��[���V�A�鍑�̌��݂�錾�����̂ł��v
����ɁA�h�D�[�M���̓��[���V�A��`���߂����āA���V�A�ƃE�N���C�i�̕��G�ȊW���w�E���Ă���B�u3�N�ȓ��Ƀv�[�`���́A�E�N���C�i�̈ꕔ�A�h�j�G�v����E�݂̒n������V�A�ɓ�������ł��傤�v(�C���^�r���[�̓E�N���C�i�N�U�ȑO�ɍs��ꂽ���߁A�h�D�[�M���̗\�z�͌����ƂȂ���)
�v�[�`���̓E�N���C�i����̍��ƂƂ��ĔF�߂Ă��Ȃ��B�v�[�`���ɂƂ��āA�L�[�E�𒆐S�Ƃ����E�N���C�i�̐e���[���b�p�n��́A�u���͂�E�N���C�i�Ƃ��������ے�����n��ł͂���܂���v
�u�����̒n��͖����w�I�ȈӖ��ɂ����Ă̓E�N���C�i�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���c���Ă͂���ł��傤���v�A���͂���I�ȓƗ���������Ă��܂����A�ƃh�D�[�M���͌����B
�܂胆�[���V�A�A���̎����ɂƂ��āA�E�N���C�i�̐e���[���b�p�n�悱�����A�傫�ȏ�Q�ɂȂ��Ă���A�Ƃ������Ƃł���B

���V�A�̃v�[�`���哝�̂��ق�̏��������������ŁA���B�̓G�l���M�[���S�ۏ�̖ʂŌ�߂肪�ł��Ȃ��n�_�ɒB�����B
�v�[�`�����́A�������o�ϐ��ق��������Ȃ�����A���V�A����h�C�c�ɓV�R�K�X�𑗂�C��p�C�v���C���u�m���h�X�g���[��1�v���~�ߑ�����\�����������B
���̌��ʁA���V�A�͂��͂�M���ł���K�X�����҂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������B���́u�^�O�v���u�m�M�v�ɕς��Ă��܂����̂��B����ʼn��B�e���́A�G�l���M�[��@������������Ɛ摗��ł��Ȃ�����ɒǂ����܂ꂽ�̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�m���h�X�g���[��1�̉ғ����͍ŋߐ��J���A500���������[�g�����Ƃ����N�ԗA���\�͂̂��悻20���Ő��ڂ��Ă���B����ł����B�̎w���҂́A���V�A���Z�p��̏�Q�Ɛ������Ă�����肪���������A�ʏ�̋����K�͂ɖ߂邾�낤�ƁA�킸���Ȗ]�݂��Ȃ��ł����B
�Ƃ��낪�A���ۂɂ̓m���h�X�g���[��1�͖������Œ�~����A���B�͍��N�K�v�Ƃ���K�X���v5700���������[�g���̖�2�����s�����鎖�ԂɂȂ����B
�����ɁA���V�A����ʃ��[�g�ő����Ă���N��500���������[�g�������A�������ɂ킩�ɕs��������Ă���B�����̕s�����́A���B������܂ʼn��Ƃ��Ђ˂�o������Őߖ�ł������v�Ɣ�ׂ�ƁA�͂邩�ɑ傫���B
�����āA�k�����̂��̓~�����N�ȏ�̊����ɂȂ�A���B�͐V����130���������[�g�����s���ɂȂ邩�����ꂸ�A1400���������[�g���̉t���V�R�K�X(�k�m�f)�����߂ăA�W�A�̔�����Ƃ̋������������邱�ƂɂȂ�B
�܂��N3���̐����Ɣ�ׂĊ��ɂ��ꂼ��14�{��10�{�ɒB���Ă��鉢�B�̃K�X�Ɠd�͂̉��i�́A���N�Ƃ���ȍ~�����~�܂肷��B
�o�[���X�^�C���̃A�i���X�g�`�[�������O����̂́A�h�C�c�̊e�ƒ�̔R����N�Ԃ�1�����[�����ƍ�N��4�{�ɂȂ�A�p���ł��G�l���M�[�x�o��3�{�]��c����6000�|���h���ɒ��ˏオ�鎖�Ԃ��B
�t�����X�A�h�C�c�A�p����3�J�������Ő��ѐ���1��������A�ނ炪������2�N�Ԃł��ꂼ��N��2000���[���]�v�Ɏx�����Ƃ���A���S�z��4000�����[���ɂ��Ȃ�B
����قǂ̕��S�������ɂ��̂܂ܔw���킹��Ƃ����̂́A�������������B������1�̑I�����Ƃ��ĕ��シ��̂́A�G�l���M�[��Ƃւ̎����Z���œ��ʂ̉��i��}���A�����̉��i�����グ��ʂ��č����ɕԍς��Ă��炤���@�ŁA�p���Œ�Ă���Ă���B
����ɁA�d�C�����ɏ����݂��A���p�҂��畊�ۋ�������Ƃ����X�y�C���Ŋ��Ɏ��{����Ă����@������B
�h�C�c���a�X���ꂽ�悤�ȁA�Ζ��E�K�X���Y�҂ƍĐ��\�G�l���M�[�̔��d���Ǝ҂������v�������Ȃ����v�ɉېł���Ƃ����̂����ʂ����邩������Ȃ��B���邢�͐��{���؋��𑝂₵�č����̕��S�̈ꕔ���z������̂���ɂȂ邾�낤�B
�Ƃ͂����A�e��������҂��s��̗͂�����Ƃ��Ă��A�G�l���M�[���v���̂����炷����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ͗Ⴆ�A�����I�ȓd�͂̊��蓖�Ă��K�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
������ɂ��扢�B�e���́A�G�l���M�[��@�Ő�������K�ʂƎЉ�I�ȃR�X�g��ނ荇�킹�邽�߂̂��܂��܂Ȃ����������o�����Ƃ��낤�B
���Ȃ��Ƃ��v�[�`�������A�������ׂ����Ƃ̍l���ɑ����̋^�S�ËS���������Ă��ꂽ�̂�����B
���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U���n�܂��Ă��甼�N�ȏオ�o�߂���Ȃ��A�p���̃E�H���X���h����5���A�p���@�ŁA���V�A���헪�I�ڕW������B�����Ă��Ȃ��Əq�ׂ��B
�E�H���X���́A���V�A���E�N���C�i�N�U�ő����Ɛl�����ʂɎ��������Ă���Ǝw�E�B���������������A���V�A�̏����I�ȌR����̗L�����ɒ����I�ȉe�����y�ڂ��Ƃ̌������������B
�E�H���X���́u���݂܂ł�2��5000�l���郍�V�A�������𗎂Ƃ����Ɛ��肳���v�Ǝw�E�B���̂ق��A�����҂�ߗ��ƂȂ������́A�����l�ƕ��Ă��铦�S���Ȃǂ�������Ύ����҂Ȃǂ�8���l����Əq�ׂ��B
�E�H���X���̓��V�A�̃v�[�`���哝�̂ɂ��āA�G�l���M�[���u���퉻�v���Ă���Ƃ��Ĕ��A�c���ɑ��Ă͗L���҂ɏ��������悤�������B
�E�H���X���́A�F�����ʂ��Ă�����ɕs�����ȏ́A���V�A�̑S�̎�`�I�Ȑ������Ӑ}�I�Ɋ�Q�������悤�Ƃ��A�G�l���M�[��p�̂��߂ɉ�X�̉��l���]���ɂ��邩�ǂ����������Ƃ��Ă��邱�Ƃ��������ƗL���҂ɓ`���邱�Ƃ��d�v���Ƃ̌������������B
���V�A�̐N���������E�N���C�i�ɁA��360�l�̏Z���قڑS�����n�����ɕ����߂��A�u�l�Ԃ̏��v�ƂȂ�����������B�ċւ�1�����߂��ɋy�сA10�l���Èł̒��Ŗ��𗎂Ƃ����B���l�����������͐[���A�N�����n�܂��Ĕ��N�ƂȂ鍡�������Ă��Ȃ��B(�E�N���C�i�k�����q�h�l�@�ɓ���)
����������C�A��
�u��C���Ђǂ�����A���ʂɑ����ł����Ԃł͂Ȃ������B�����ŁA��������̐l������ł��܂����v�B8�����{�A�`�F���j�q�E�B�̑��E���q�h�l�Ɉ�����Ȃ��w�Z�̒n�����ŁA�G�ݓX�o�c�X�r�g���[�i�E�~�l���R����(51)���d�������J�����B
���V�A�R��2��24���A�E�N���C�i�ւ̐N�����n�߂��B���q�h�l�ɍU�ߓ������̂́A3��3���B�X�r�g���[�i����͑��ɔ���C���̉����A�Ƒ���7�l�Ŏ���̒n�����֓��������A2����A�@�֏e�����������V�A���Ɍ��������B�X�}�[�g�t�H���݂��ĉ悤�������A���������_�Ƃ����w�Z�̒n�����ɍs���悤�w�����ꂽ�B
�����͕��i�A�q�ɂƂ��Ďg���A�������d�C���K�X���ʂ��Ă��Ȃ������B�召���̕����ɕ�����ꂽ�v200�������[�g���̋�ԂɏW�߂�ꂽ�̂́A���㔼�N����93�܂ł�347�l�B�X�r�g���[�i����̕����ɂ́A�Ԃ̃o�b�e���[�ɂȂ����k�d�c���Ƃ����Ă������A�ق��̕����͂낤���������������B�^���ÂȘL���ɂ܂Ől�����ӂ�A��l�͈֎q�⏰�ɍ������܂ܐQ���B
�O�͓�����悤�Ȋ������������A�n�����͏ꏊ�ɂ��������C�̂悤�ɏ����A����E���l�������B1���ɂ킸���Ȏ��Ԃ����O�ɏo��ꂸ�A�Z�������͕����̕Ћ��ɒu�����o�P�c�ŗp�𑫂����B
�H�ו��́A���V�A���������Ă���Ⓚ�̃p����2�l�ŃR�b�v1�t�̃X�[�v�����肾�����B�S���z���Ȃ���������A�u���Ȃ������������q�ǂ�����������̂���Ԃ炩�����v�ƃX�r�g���[�i����͘b���B
���u���V�A�������v
�ċւ�����������ɂ�A�Z���͎��X�ɑ̒���������B�Ӗ��s���Ȃ��Ƃ����юn�߂�ƁA���̐l�͂܂��Ȃ����B
�Z�������́A�ċւ��n�܂��Ă���̓��t�����������̉��̕ǂɁA�S���Ȃ����l�̖��O���L�^�����B���W�J�A���_�j�A�{�C�R�c�c�B���܂ꂽ�̂�10�l�ɏ�����B
����ȓ��X���I������̂́A3��30�����̂��ƁB�C���̉��Ɨh�ꂪ�ˑR��݁A�ӂ肪�Â��ɂȂ����B�O�ɏo�Ă݂�ƁA���V�A���̎p�͂Ȃ������B���̓��͒n�����ɂƂǂ܂�A��31���A�Z���̓E�N���C�i�R�ɂ���ĉ�����ꂽ�B
�F�X�������{�t�E�C���V�F���R����(50)�͊ċ֒��ɁA69�̕�i�f�B���E�u�h�`�F���R������������B�̂̂ǂ��ɂ��s���͂Ȃ��������A�n�����ł̐�����1�T�ԂقǂɂȂ�ƕ����Ȃ��Ȃ����B�Ƃ茾���J��Ԃ��悤�ɂȂ�A�����2���O�ɖS���Ȃ����B�u�ƂĂ������Ă����̂Ɂc�c�v�Ɨ܂��ށB
�����{�t���g���t���������Ȃ�A�T��3��A�a�@�œ��͂���悤�ɂȂ����B�u�������Ȃ���Ύ�������ł������낤�B��ɂ�����̂ł��Ȃ��A���R��D�����Ƃł���ȏ�Ȃ��قǂ̋��|�������炵���A���V�A���������v�ƌ��B
��w�I���K�E�}�g�r�G���R����(68)���v��2�l�ŕ�炵���w�Z���̉Ƃ́A�߂�ƏĂ������Ă����B�u�S�Ă��j��Ă��܂����v�Ɠr���ɕ���B���N�O�܂ŁA�q�ǂ������̂ɂ��₩�Ȑ�����ь����Ă����w�Z��ڂɂ��Ă��A�u���╔���ɂ��������Ȃ��v�Ƃ����B
�w�Z�͐N�����甼�N�������Ă��A�ĊJ���Ă��Ȃ��B�n�����̕ǂɂ́A�ċ֒��Ɏq�ǂ��������`�������z��ԂȂǂ̊G�Ƌ��ɁA���b�Z�[�W���c���Ă���B
�u�푈�͂���Ȃ��v
���u�l�Ԃ̏��v���ᔽ
���q�h�l�̏Z���ċւɂ��āA�S�����ۋ��͋@�\(�n�r�b�d)��7���ɂ܂Ƃ߂����Łu��퓬�����w�l�Ԃ̏��x�ɗ��p���Ă���A�W���l�[�u���ɔ�����v�Ǝw�E���Ă���B�����́A�퓬�̓����҂��U����j�~���邽�߂ɖ��Ԑl�𗘗p���邱�Ƃ��ւ��Ă���A���V�A����y�����B
�{���ɂ�����`�F���j�q�E�n���ɂ��ƁA�ċւ�3��3���`30����28���Ԃɋy�B�n���͑��l���300�l���璮�悵�A���ꂩ�烍�V�A���̖��O��K���Ȃǂ��L�^���ꂽ���L��ʐ^�Ȃǂ����W�B���Ȃ��Ƃ�9�l�̃��V�A�����ċւɊ֗^�����Ɠ��肵�����A����������V�A�ɖ߂��Ă���Ƃ����B�Z���q�[�E�N���v�R����(33)�́u���ۖ@�Ɋ�Â��ċN�i���A�@��ŗL�ߔ������o��A9�l�͍��ێw����z�����B���Ƃ��Ă��ߕ߂��A�ӔC��Njy�������v�Ƙb���Ă���B
���V�A���{�́A�k���̓y�̌�������ɂ��A������u�r�U�Ȃ��𗬁v�Ȃǂ̓��{�Ƃ̍��ӂ�j�������ƁA����I�ɔ��\���܂����B�E�N���C�i�ւ̌R���N�U���āA���{���{�����ق��Ȃ��Ă������Ƃɔ��������`�ł��B
���V�A���{��5���A�k���̓y�̌�������ɂ��u�r�U�Ȃ��𗬁v��A���������̋��̏W���Ȃǂ�K�₷��u���R�K��v�ȂǁA����܂łɓ��{�Ƃ̊ԂŌ��ꂽ���ӂ�j�������ƁA����I�ɔ��\���܂����B
���̂����ŁA���V�A�O���Ȃɑ��āA���̌������{���{�ɒʒm����悤�w�������Ƃ��Ă��܂��B
�u�r�U�Ȃ��𗬁v�Ȃǂ̌𗬎��Ƃ��߂����ẮA���Ƃ�3���A���V�A�O���Ȃ��E�N���C�i�ւ̌R���N�U���āA���{���{�����ق��Ȃ������Ƃɔ������āA��~����ӌ��𖾂炩�ɂ��Ă��܂����B
���̍ۂɁA�k���̓y�����܂ޕ��a�����𒆒f����ӌ���\�����Ă��āA�u���ׂĂ̐ӔC�́A�����V�A�I�ȍs�����Ƃ���{���ɂ���v�ƈ���I�ɔ��Ă��܂����B
�u�r�U�Ȃ��𗬁v�́A���{�l�Ɩk���̓y�ɏZ�ރ��V�A�l���r�U�̔��������ɁA���݂ɖK�₷��g�g�݂ŁA1991�N�ɍ��ӂ���A1999�N����́u���R�K��v�̘g�g�݂�����A�u�r�U�Ȃ��𗬁v�ƍ��킹�āA����܂łɑo�����悻3���l���Q�����Ă��܂��B
������ �Ί_�s���u�e�F�ł�����̂ł͂Ȃ��v
���V�A���{���A�k���̓y�̌�������ɂ�邢����u�r�U�Ȃ��𗬁v�Ȃǂ̓��{�Ƃ̍��ӂ�j�������Ɣ��\�������Ƃɂ��āA�k�C�������s�̐Ί_��q�s����6���ߑO�A�E���Ɍ����čs�����P���̒��Łu���̋���͓����̃S���o�`���t�哝�̂���̒�Ăł���A30�N�ȏ�A���v�̐j��߂��s�ׂ͗e�F�ł�����̂ł͂Ȃ��v�Ɣ��܂����B���̂����Łu��x�J�������͕��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��l���Ă���B�k���̓y�̗אڒn��Ƃ��Ĉ���J���邱�ƂȂ��A�Ԋ҉^�����_�̒n�̖�������������Ɖʂ����Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
�����슯�[�����u�ɂ߂ĕs�� ���V�A���ɉ��߂ċ����R�c�v
���슯�[�����́A�t�c�̂��Ƃ̋L�҉�Łu�ɂ߂ĕs���Ȃ��̂Œf���Ď�����Ȃ��B���݂܂ł̂Ƃ��냍�V�A������̒ʒm�͂Ȃ����A���傤�A���V�A���ɑ��A���߂ċ����R�c�����v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�����W�̌���́A���ׂă��V�A���ɐӔC�����邪�A�k���l���̌𗬎��ƂȂǂ��s���ɂ͂Ȃ��B�������A����ɂȂ����������̕��X�̎v���ɉ��Ƃ����������Ƃ����l���ɕς��Ȃ����A���̂悤�ȑΉ�����炴������Ȃ����Ƃɂ��āA�����������肽���v�Əq�ׂ܂����B
���ъO���u�ɂ߂ĕs�� ���߂ċ����R�c�v
�ъO����b�͊t�c�̂��Ƃ̋L�҉�Łu�ɂ߂ĕs���ł���A�f���Ď�����Ȃ��B���݂܂ł̂Ƃ��냍�V�A������̒ʒm�͂Ȃ����A���傤�O���Ȃ̉��B�ǎQ��������A�����V�A��g�ق̎��Ȃɑ��Ă��������l����`���A���߂ċ����R�c�����v�Əq�ׂ܂����B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂�5���A�u���V�A���E�v�Ƃ����T�O�Ɋ�Â��V���ȊO����j�����F�����B�O���ɉ�����ă��V�A�n�Z�����x������s�ׂ𐳓������邽�߂ɕێ�h�������Ă����T�O�ŁA�����ɖ����������B
�u�l�����j�v�Ƃ���31�y�[�W�ɋy�ԕ����ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B���V�A�́u���V�A���E�̓`���Ɨ��z�����A�ی삵�A�O�i������v�ׂ��ƋL���ꂽ�B
���V�A�̓E�N���C�i�N�U�ňꕔ�n��𐧈������ق��A�������I�Ɏ����x�z����e���V�A�h���x�����Ă���B�����̍s�ׂ𐳓������邽�߂ɋ��d�h�̈ꕔ�������Ă������V�A�̐�����@���Ɋւ���l���������荞�܂ꂽ�B
�u�C�O�ɏZ�ޓ��E�̌����s�g�A���v�ی�A�����I�A�C�f���e�B�e�B�[�̈ێ��̂��߂Ƀ��V�A�A�M�͎x�������v�Ƃ��A�C�O�̓��E�Ƃ̂Ȃ��肪�u���ɉ����E�̎����ɓw�͂��閯���`���ƂƂ��Ẵ��V�A�̃C���[�W�����ە���ŋ����v���邱�Ƃ��\�ɂ��Ă���Ǝ咣�����B
�܂��A���V�A�̓X���u�n���Ƃ⒆���A�C���h�Ƃ̋��͂��g�債�A�����A����āA�A�t���J�Ƃ̊W����i�Ƌ������ׂ����Ƃ����B
2008�N�ɋN�������V�A�ƃW���[�W�A�̌R���Փˌ�A���V�A���Ɨ���F�߂��A�u�n�W�A�Ɠ�I�Z�`�A�A���тɃE�N���C�i�����̈ꕔ�������x�z����e���V�A�h�u�h�l�c�N�l�����a���v�u���K���X�N�l�����a���v�Ƃ̊W����i�Ɛ[������K�v������Ƃ��L���ꂽ�B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂��u���o�Â鍑�̓��V�A���v�Ɣ����������Ƃ��A������SNS��Ŕ������Ă�ł���B
�^�X�ʐM�ȂǕ����̃��V�A���f�B�A�ɂ��ƁA�v�[�`������5���ɃJ���`���c�J�ŊJ���ꂽ���t�H�[�����ŁA�p�����̃��T�C�N���⏈���̖��Ɍ��y�����ہA�u�n���I�Ȃ��Ƃ������A��͂�J���`���c�J�ɂ��Ęb���ׂ����B��ʓI�ɁA�������̗��ł�����{�́w���o�Â鍑�x�ƌĂ�Ă��邪�A���̍l���ł́A�J���`���c�J���邢�̓T�n�����͓��{�������ɂ���B����ɓ��ɂ̓j���[�W�[�����h������A�j���[�W�[�����h�̂���ɓ��ɂ̓`���R�g�J������v�Ƃ��A�u���̈Ӗ��Ŗ{���́w���o�Â鍑�x�̓��V�A���v�Əq�ׂ��B
�������f�B�A�̊��Ԃ������`����ƁA�����̃l�b�g���[�U�[����́u���̒ʂ肾�v�u���{�́w���o�Â鍑�x�Ƃ̌ď̂��T����ׂ��v�u�͂͂͂́B���{������{���Ԃ�����C���ȁv�u���̒e�ۂ̂悤�Ȍ`���������{���w���o�Â鍑�x�Ƃ�(��)�v�u����ȂɈܓx��������Ίm���ɑ����������邾�낤���ǂ�(��)�v�u5000�N�̕��������؉�(����)�������^�́w���o�Â鍑�x�v�u�w���o�Â鍑�x���āA�������������̒n���I�ʒu����ɂ����Ăѕ��ł���v�Ƃ������R�����g���������܂ꂽ�B
�ҏW�����m�[�x�����a�܂���܂������V�A�̓Ɨ��n�V���u�m�[�o���E�K�[�[�^�v�ɂ��āA���X�N���̍ٔ����͐V�����s�̔F�����������f�������܂����B
�Ɨ��n�V���u�m�[�o���E�K�[�[�^�v���߂����ẮA���V�A�̒ʐM�ē��ǂ�7���ɁA�@�ւƂ��Ă̔F���������悤���߂�i�����N�����Ă��܂����B
�C���^�t�@�N�X�ʐM�ɂ��܂��ƁA���X�N���̍ٔ�����5���A�u�m�[�o���E�K�[�[�^�v�ɑ��A�V���s����F�����������f�������܂����B
�u�m�[�o���E�K�[�[�^�v�͐������o���A�u�V���͂��傤�E���ꂽ�B�ǎ҂͒m�錠����D��ꂽ�v�Ɣᔻ�B
�m�[�x�����a�܂���܂����ҏW���̃����g�t���́A�u���̌���ɂ͖@�I�������Ȃ��v�Əq�ׁA��i����l���������Ă��܂��B
�u�m�[�o���E�K�[�[�^�v�̓v�[�`�������ɔᔻ�I�ȕŒm���A�E�N���C�i�N�U���3������V���̔��s�Ɠd�q�ł̔z�M�̒�~�Ɏ�����A�ǂ����܂�Ă��܂��B
����A�@������R�炵���Ƃ��č��Ɣ��t�߂ɖ���Ă����L�͎��R�����T���g�̌��L�҃C�����E�T�t���m�t���ɑ��A���X�N���̍ٔ�����5���A����22�N�̔����������n���܂����B
�T�t���m�t���͌R���@����NATO���k�吼�m���@�\���ɘR�炵���Ƃ��āA���ƂƂ�7���ɍS������܂������A�������߂����Ă͓Ɨ��n���f�B�A��C�O����u�������Ȃ��v�Ɣᔻ���鐺���o�Ă��܂��B�T�t���m�t�����͏�i������j���Ƃ������Ƃł��B�@
���V�A�R����������E�N���C�i�̃U�|���[�W�����q�͔��d���ł�5���A�C���ɂ��Ђ̉e���ŊO���d���������܂����B���q�F�Ȃǂ��p����@�\�͈ێ�����Ă��܂����AIAEA�����ی��q�͋@�ւ����n���肵�����Ƃ����S�������O�����������Ă��܂��B
�U�|���[�W���������^�c����E�N���C�i�̌��q�͔��d���ЃG�l���S�A�g���́A5���A�C���ɂ��Ђ̉e���ŁA�ғ����Ă���6���@���A�O���̓d�͖Ԃ���藣����A�d�͋��������Ȃ��Ȃ����Ɣ��\���܂����B
6���@�͏o�͂������������ʼn^�]�𑱂��A�����{�ݓ��ŕK�v�ȓd�͂��������Ă���A���q�F�Ȃǂ��p����@�\�͈ێ�����Ă���Ƃ������Ƃł��B
IAEA�ɂ��܂��ƁA�����ƊO���d�������ԑ��d�����̂ɑ����͂Ȃ��A�G�l���S�A�g���́A���̂��߁A�Ӑ}�I�ɊO���̓d�͖Ԃ���藣�������̂́A�Ђ������~�߂�ꂵ�����A�Ăѐڑ����錩�ʂ����Ƃ������Ƃł��B
�G�l���S�A�g���́A�O���d����������̂͐挎25���ȗ����Ƃ��Ă��܂��B
����ɂ��āA�E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂�5���A��������J���u�U�|���[�W�������́A���V�A�̒����ɂ���ĕ��ː��ЊQ�̈����O�܂ł��Ă���v�Ɗ�@���������܂����B
�����āu�����ւ̖C���́A���V�A��IAEA�⍑�ێЉ���y�����Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����v�Əq�ׁA�e���ɑ��ă��V�A�ւ̐��ق���������悤���߂܂����B
���������n�s�̎s�� ���V�A�R�̓P�ނ��K�v�Ƒi����
�C�������������S���ւ̌��O�����܂��Ă���E�N���C�i�̃U�|���[�W�����q�͔��d�������n����G�l���z�_���s�̎s�����ANHK�̃I�����C���C���^�r���[�ɉ����u��̎҂̕������Ƃǂ܂邩����댯�Ȃ܂܂��v�Əq�ׂāA������s���̈��S�̂��߂ɂ̓��V�A�R�̓P�ނ��K�v���Əd�˂đi���܂����B
���V�A�R���苒����U�|���[�W���������ӂł́A�挎�ȍ~�A�C�����������ł��āA����1���ɂ́AIAEA�����ی��q�͋@�ւ̐��ƃ`�[�������n�ɓ��蒲�����s���܂����B
�������A5���ɂ́A�C���̉e���ŁA�ғ����Ă���6���@�̊O���d���������鎖�ԂƂȂ��Ă��܂��B
����̃U�|���[�W���s�őΉ��ɂ������Ă���G�l���z�_���s�̃h�~�g���E�I�����t�s����NHK�̃C���^�r���[�ɑ��uIAEA�̒������s��ꂽ���Ƃ͈���O�ɐi�ƌ�����v�ƈ��̕]���������Ȃ�����u�c�O�Ȃ���C���͑����Ă��āA�͕ς���Ă��Ȃ��v�Əq�ˑR�Ƃ��āA������s���̈��S����������Ă���Ƒi���܂����B
�������ӂւ̖C���ɂ��Ắu���ˉ���������������ɁA����������������B�C�������V�A�R�̐�̒n�������Ȃ͖̂��炩���v�Əq�ׁA�E�N���C�i�R�̐M�p���ĂȂǂ�_�������V�A���ɂ�钧���s�ׂ��Ɣ��܂����B
�܂��I�����t�s���́A�s���ɂ͍����A���悻2��5000�l�̎s�����c���Ă���Ƃ��������Łu�s�����U�������P�[�X�������Ă���B�g�ѓd�b�Ȃǂ�D��ꍉ�₳�ꂽ�l������v�Ǝw�E�����ق��A�H������i�Ȃǂ̎x�������𑗂낤�Ƃ��Ă����V�A�����F�߂Ȃ������Ɩ������܂����B
���̂����Łu��̎҂̕������Ƃǂ܂邩����댯�Ȃ܂܂��v�Əq�ׂāA������s���̈��S�̂��߂ɂ̓��V�A�R�̓P�ނ��K�v���Əd�˂đi���܂����B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂�6���A�I�ɓ����C�n���̃Z���Q�G�t�X�L�[���K���K��A�I���h�Ȃ����{���Ă����K�͌R�����K�u�{�X�g�[�N2022�v�����@�����B�^�X�ʐM�́A���K��ɓ��������v�[�`�������V���C�O���h���A�Q���V���t�Q�d�����Ɣ���J�̉�k���s���A���̌�A�j���ډ\�Ȓe���~�T�C���u�C�X�J���f���l�v�̔��ˉ��K�Ȃǂ��ē����Ɠ`�����B
�I���h�Ȃɂ��ƁA1������7���܂ł̉��K�ɂ́A������x�����[�V�A�C���h�Ȃ�13�̊O�����R������I�u�U�[�o�[��h���B���V�A�͉��K��ʂ��A�E�N���C�i�N�U�ō��ۓI�ɌǗ������Ƃ̈�ۂ@����_��������Ƃ݂��Ă���B�����Ƃ̌������֎����A�E�N���C�i���p���x��������ė������Ј�����_����������悤���B
���K�ł́A�T�n����(����)�ɏ㗤�������z�G�̕����𑽘A�����P�b�g�V�X�e���Ō��j����P����A�퓬�@�u�~�O31�v�ɂ��}���P���Ȃǂ��s��ꂽ�B���V�A���s�@�苒����k���̓y�̍���(���Ȃ���)���Ƒ�(���Ƃ��)���ł��㗤�j�~�P�������{���ꂽ�B���K�̈�Ƃ��āA���{�C�C��ŘI�C�R�ƒ����C�R�ɂ�鍇���ΐ��P����A���z�G�̊͒��ɑ��鍇���ˌ��P���Ȃǂ����{���ꂽ�B
�����A����̉��K�ɎQ�������̂͌v��5���l�ŁA30���l�����Q�������Ƃ����2018�N�̑O�K����͑傫���K�͂��k���B�E�N���C�i�N�U�ɂ͋ɓ����NJ����铌���R�Nj悩�������������h������Ă��邱�Ƃ��v�����Ƃ݂��Ă���B
�v�[�`������7���A�ɓ��E���W�I�X�g�N�ŊJ�Ò��̘I��Â̍��ۉ�c�u�����o�σt�H�[�����v�̑S�̉�ɏo�Ȃ���B�y�X�R�t�I�哝�̕��ɂ��ƁA�v�[�`�����̓E�N���C�i���ɓ��̔��W�ɂ��ĉ�������\�肾�Ƃ����B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂�6���A�ɓ��E���W�I�X�g�N�ߍx�ŁA��K�͌R�����K�u�{�X�g�[�N(����)2022�v�����@�����B�{�X�g�[�N���@��4�N�O�̑O��2��A���B�E�N���C�i�N�U�J�n���甼�N���߂��A�퓬���������̗l�����������A���V�A�R���ە�����ƂƂ��ɁA���ĂȂǂƂ̑Ό��p�����A�s�[������_��������B
�^�X�ʐM�Ȃǂɂ��ƁA�v�[�`�����̓V���C�O���h���A���V�A�R�����g�g�b�v�̃Q���V���t�Q�d�����Ɣ���J����J�����B���K��ł́A�j�e�����ډ\�Ȓe���~�T�C���u�C�X�J���f���l�v�̔��˂����@�����B
���K�ɂ́A�ΕĂŋ������钆���̂ق��A���V�A�̓`���I�F�D���C���h����C���͋@�\(�r�b�n)�������̗���ŎQ���B�v�[�`�������Ƃ��ẮA�����̌������֎����ē��ē�����������ƂƂ��ɁA���č���4�J���̘g�g�݁u�N�A�b�h�v�ɂ����т�ł����ގv�f������Ƃ݂���B
�k���̓y�́u�r�U�Ȃ��𗬁v������A���V�A��������I�Ȏ����\�������Ƃɂ��ėъO����b�́u�ɂ߂ĕs�����v�ƍR�c���܂����B
�ъO����b�F�u�ɂ߂ĕs���Ȃ��̂ł���A�f���Ď�����Ȃ��ƍl���Ă���܂��v
���̂Ƃ��냍�V�A������O�����[�g�ł̒ʒm�͂Ȃ����̂́A�O���Ȃ�6�����A�����������V�A��g�ق̃i���o�[2�ɑ��āA�d�b�ŋ����R�c�����Ƃ������Ƃł��B
�u�r�U�Ȃ��𗬁v�́A�r�U���������ɓ��{�l�Ɩk���̓y�ɏZ�ރ��V�A�l�Ƃ̑��ݖK����\�Ƃ��Ă��܂����A���V�A���̓E�N���C�i���������{���{�̐��قɔ������A3���Ɉꎞ��~�\���Ă��܂����B
�O���Ȋ����́u���������̔j���Ƃ͑����Ă��Ȃ��v�Ƃ��āA���@���݂čĊJ�Ɍ����������s�����j�������Ă��܂��B
���\�A�̏���ɂ��čŌ�̑哝�̂߂��~�n�C���E�S���o�`���t��8��30���A���X�N���̕a�@�Ŏ��������B�e���r�̃��C�h�V���[�Ȃǂ����Ă���ƁA�u����Ȏ��������炱���A���Ăق��������Ƃ������v�Ƃ��A�u���a�Ɩ����`��Nj������l�������v�Ȃǂ̔������R�����e�[�^�[���炵���Ε������B�v�[�`���Ƃ͑�Ⴂ�Ƃ����킯���B������a�����������B
�S���o�`���t�͎����܂����{���Y�}�ɂ���1985�N�Ƀ\�A���Y�}���L���ɏA�C���A�����`�̗v�f���������O���X�m�X�`(�J��)����A�o�ς̌�������}��y���X�g���C�J(�č\�z)����Ɏ��g�B���������̐���́A�A�����J�Ƃ̌R�g������A��}�ƍِ����̂��Ƃł̌o�ϓI�敾�A�����I�s���Â܂肩��A��ނ��s��ꂽ���̂������B�R�g�����ł��A�o�ϔ��W�ł��A�A�����J�E���{��`�w�c�ɕ������Ƃ��������̘b���B
�����̐��܂Ő��݂����卑��`
�������X�^�[�����ȗ��́u�卑��`�v(�R���͂�o�ϗ͂Ȃǂ�����ȑ卑���A�����⑼�����ɑ��Ď����̗����咣���x�z�I�A�����I�ɉ����t���邱��)�́A�S���o�`���t������܂������ς��Ȃ������B
�X�^�[��������̃\�A�̑卑��`�͐��E�ɂƂ��ėL�Q���̂��̂������B�q�g���[�E�h�C�c�����[���b�p�ւ̐N���푈���J�n���悤�Ƃ��邻�̎��ɁA�X�^�[�����̓q�g���[�E�h�C�c�ƕs�N�������B���̕s�N���ɂ́A�����������[���b�p�ƃo���g3���������閧����܂Ō���Ă����B�\�A�͐��A�t�@�V�Y���Ɛ�������Ƃ���A�v�[�`����������������Ă��邪�A���̃t�@�V�Y�������(����)�������Ă����̂��\�A�Ȃ̂ł������B
���̖��ł́A�S���o�`���t���X�^�[�����ƂȂ��ς�邱�Ƃ͂Ȃ������B�����Y�}�c���̕s�j�N�O���͒����w�V���ŃX�^�[�����Ƒ卑��`�x(2007�N5�����ŁA�V���{�o�Ŏ�)�Ŏ��̂悤�Ɏw�E���Ă���B
�q�S���o�`���t�����́A�o���g3���Ŗ����I�K�͂ł̋���ȉ^�����N����܂ŁA�q�g���[�ƌ������[���b�p�E�o���g3���ĕ����́u�閧�c�菑�v�ɂ��āA���ꂪ���݂��邱�Ƃ����拭�ɔے肵�܂����B���̑��݂�F�߂�������Ȃ��Ȃ�ƁA���x�́A�o���g3���̃\�A�ւ̉����́u�閧�c�菑�v�Ƃ͊W�Ȃ��A���@�I�Ȏ葱���ł����Ȃ�ꂽ�����Ȃ��̂��ƌ������葱���܂����B���̕���ł̃X�^�[�����̈����͔F�߂Ă��A�卑��`�̌��͔F�߂Ȃ��Ƃ����̂��A��p�҂����̈�т����g�M���h�������̂ł��B�r
�k���̓y�ԊҖ��ł��A�S���o�`���t�͎��G��̗ǂ������Ȃ��Ƃ͏q�ׂ����A������O�i�͂��Ȃ������B�X�^�[�����ɂ��瓇�⎕���E�F�O�̗��D�́A�����A���ۓI�ɂ����F����Ă����u�̓y�s�g��̌����v�ɔ�������̂ł������B�����S���o�`���t���Ԋ҂Ȃǖѓ��l���Ȃ������B
�X�^�[��������S���o�`���t�A�����ăv�[�`���ƁA���V�A�̑卑��`�͍��̐��܂Ő��݂������̂Ȃ̂��B
�����āA���ꂱ�����V�A�v���̎w���҃��[�j�����ł����ꂽ���Ƃ������B
���V�A�v���̒���A���V�A���Y�}���Ŗ��ɂȂ����̂��������̖�����������F�߂邩�ǂ����ł������B�����̎w���I�����͌��͂������Ă��Ȃ������ɂ͎�������F�߂Ȃ��Ƃ����ԓx���Ƃ����B���̎����[�j���́A�u�����̋��Y��`�҂����ނ��A�働�V�A�l�r�O��`���������v�u���̑働�V�A�l�r�O��`�҂͉�X�����̎҂̐S�ɐ���ł���A����ɑ��Đ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƌ��������B�����X�^�[�����ɂ���Ă��̎咣�͑����Ă��܂����B
���V�A�ɂ́A���j�I�ɐςݏグ���Ă������[���卑��`���A���݂����݂������Ă���̂��B
���E�N���C�i�N�����x��������
9��1���t�����V���ɕҏW�ψ��E�����p�����̃S���o�`���t�]�`���f�ڂ���Ă���B���̕]�`�ł́A�S���o�`���t�����ق߂Ă����S���o�`���t���c�����V�A�̃E�N���C�i�N���ɑ��āA�u���E�ɂ͐l�̖�����Ȃ��̂͂Ȃ��B���݂̑��d�Ƒo���̗��v�̍l���Ɋ�Â������ƑΘb�݂̂��A�ł��[���ȑΗ�����������ł���B��̕��@���v�ƌĂт��������Ƃ��Љ��A�u�Η��ł͂Ȃ�������͍����A�l�ދ��ʂ̗��v��D�悷�闝�O���A���̐����ɍ��߂��Ă���C�������v�ƌ���Ă���B
�{���ɂ������낤���B2014�N3���A�v�[�`���������E�N���C�i�암�̃N���~�A����������I�ɕ��������ہA�u�����v�[�`���哝�̗̂��ꂾ������A�܂������������Ƃ��������낤�v�ƑS�ʓI�Ɏx�����Ă���B�v�[�`���Ɠ����N���҂̗���ɗ����Ă����̂��S���o�`���t�Ȃ̂ł���B
�������̓S���o�`���t�̎v�z�̒��́A�u���݂̑��d�v�u�Θb�Ƌ����v�u�����v�z�̔�R�����v�Əq�ׁA�u�����I���l�ނ̎w�j�ɂȂ肤��v�Ȃǂƕ]�_���Ă���B�Ȃ������܂ŃS���o�`���t�������グ��̂��s�v�c�łȂ�Ȃ��B���Ȃ݂ɃE�B�L�y�f�B�A�ɂ��Ɛ��E���a����ƒ�A��(�����ꋳ��)�̎��������ɂ��S���o�`���t���c(�S���o�`���t�F�D���a���c)��ݗ����������ł���B
���������S���o�`���t�̓\�A�̕����]��ł����킯�ł͂Ȃ��B�����̖��剻�͐}�����Ƃ��Ă��A��{�I�ɂ̓\�A���Y�}�ɂ���}�ƍِ�������߂�C�ȂǂȂ������B�������A�����̎Љ��`���Ŗ��剻�̓��������܂�A�u���W�l�t����̂悤�ɎЉ��`���S�̂̂��߂Ɉꍑ�̎匠�𐧌��ł���Ƃ����u�u���W�l�t�E�h�N�g�����v�͕���������Ȃ��Ȃ��Ă����B
�v�[�`���̓S���o�`���t���u�ǂ�ȉ��v���K�v�ŁA�ǂ��Ȃ����ׂ��������Ă��Ȃ������v�Ɣᔻ���Ă��邪�A���̔ᔻ�͓I���˂Ă��邾�낤�B���ʂƂ��ė��̐����I�����A�\�A�����Ă��܂����Ƃ��������̂��ƂȂ̂��B
���\�A�̈ێ���ڎw�������Y�}�̃G���[�g
1991�N8���Ƀ\�A���Y�}�̉�̂�����I�ɂȂ����ہA���{���Y�}��C������́A9��1���t�Łu�卑��`�E�e����`�̗��j�I�����̓}�̏I�������}���鄟���\�A���Y�}�̉�̂ɂ������āv�Ƒ肷�鐺���\�����B�����ɂ́A���̂悤�Ȏw�E���Ȃ���Ă���B
�q�\�A���Y�}�́A7�����ɊJ���ꂽ�����ψ����Ō��肳�ꂽ�V�j�̑��Ăɂ����߂���Ă���悤�ɁA�Ȋw�I�Љ��`�̐��E�ς�������ĎЉ��}���̐錾�������Ȃ��ȂǁA�Ȋw�I�Љ��`�̓}�Ƃ��Ă̎��̂�����ے肵�Ă����}�ł������B�������A�������āu�]���v��錾�����\�A���Y�}�́A�V�j�̑��Ăɂׂ̂��Ă���悤�ɁA�\�A�����ł͂Ȃ����E���ł��͂�K��������v���͕s�v���Ǝ咣���A���E�̓}�ɂ������Ă��ϐ߂������エ������ԓx���Ƃ����B���E�ɑ卑��`�̋������ӂ�܂��Ă������̓}�́A����̑��݂���߂�Ō�܂ŁA����ɂӂ��킵���ے�I�Ȗ������͂������Ƃ����̂ł���B�r
�����ꂽ�b�ŁA�\�A���Y�}�́g���������͋��Y�}����߂邵�A�v����߂�B�����琢�E�̋��Y�}�������悤�ɂ��ׂ��h�Ƃ����̂��B
�Y�o�V��(9��4���t)�ɑO���X�N���x�ǒ��̉����lj�ɂ��u���������̎u�@������2�l�v�Ƒ肵�āA�S���o�`���t�ƃv�[�`���̕]�_���f�ڂ���Ă���B
�q�v�[�`�����ᔻ����S���o�`���t���܂��A�ڎw�����̂̓\�A�̈ێ��ł���A�E�N���C�i�̓Ɨ��͔F�߂������ƍl���Ă����B���̂��Ƃ�U��Ԃ�Ƃ��A�����Ɏ��郍�V�A�卑��`�̞~��(��������)���v���m�炳���B�r
�q�y���X�g���C�J(�Č�)�ɂ��\�A���剻�A�ă\�j�R�k�A�������̏I���\�B�S���o�`���t�����E�j�Ɏc��������ȑ��Ղ͌����ĉߏ��]�������ׂ��ł͂Ȃ��B�����A���Ƃ��Ƌ��Y�}�̃G���[�g�������S���o�`���t���O���ɒu���Ă����͎̂Љ��`�̘g���ł̉��v�������B���Ԃ��}�W�J���A�Ӑ}���Ȃ��\�A����ɋA�������̂͗��j�̔���ł���B�r
�܂����������ł���B

�E�N���C�i�R�́A���V�A���Ɏx�z����Ă����n��̒D�҂�ڎw���A�암�𒆐S�ɔ��]�U���𑱂��Ă��܂��B����A���V�A�̓E�N���C�i�̐퓬�ŕ�������i�̑������[�������Ă���Ƃ݂��A���ĂƑΗ�����C������k���N���畺��̒��B��i�߂Ă���Ƃ��w�E����Ă��܂��B
�E�N���C�i���R���N�U���郍�V�A�̍��h�Ȃ�6���A���q�~�T�C���u�J���u���v�ōU�����A�����h�j�v���y�g���E�V�N�B�ŔR���ɂ�j���Ɣ��\���܂����B
����ɑ��A�E�N���C�i�R�́A�암�w���\���B�𒆐S�ɔ��]�U���𑱂��A���V�A�Ɏx�z����Ă����암�Ɠ����̕����̏W������������Ƌ������Ă��܂��B
�C�M���X���h�Ȃ�6���A�w���\���B�Ń��V�A�R�̖��l�@�̏o�����挎�Ɣ�ׂāA�傫�������Ă���Ǝw�E���܂����B
���̗v���Ƃ��ĉ��Ă̐��قɂ���ă��V�A�Ŗ��l�@�̕��i���s�����Ă��邱�ƂȂǂ������u���l�@�̉^�p�������A���V�A�R�̍��ɉe�����o�Ă���v�ƕ��͂��Ă��܂��B
����A�A�����J���{�́A���V�A�ƗF�D�W�ɂ���C�������A���V�A�ɑ��Đ��S�@�̖��l�@�̋��^��i�߂Ă���ƌ��O�������Ă��܂��B
�܂��A�A�����J���{������6���A�L�Ғc�ɑ��u���V�A�͖k���N���琔�S�����̃��P�b�g�e��C�e�̍w����i�߁A�E�N���C�i�Ŏg�p���悤�Ƃ��Ă���v�Ɩ��炩�ɂ��܂����B
���̂����ŁA���̍����́u�E�N���C�i�ɂ��郍�V�A�R������̋����s���Ɋׂ��Ă��邱�Ƃ��������̂��B���V�A�͖k���N���炳��Ȃ镺��̍w����i�߂�\��������v�Ƃ��āA��������l���������܂����B
�܂��A�A�����J���h���Ȃ̃��C�_�[����6���A�L�҉�ŁA�u�����̓��V�A���C�e�����߂Ėk���N�ɐڐG�����Ƃ������������Ă���B����͕����̋�����ێ��̔\�͂ɂ��āA���V�A�̒u���ꂽ���������̂ŁA�k���N�ɐڐG�����Ƃ��������͉��炩�̉ۑ������Ă��邱�Ƃ̌��ꂾ�v�Ǝw�E���܂����B
�����������A���V�A�哝�̕{�̃y�X�R�t���͋L�Ғc�ɑ��u�E�N���C�i�ł̌R�����ւ̎Q����]�ގs���ɂ���܂Œʂ�̎d�����ۏ����悤�A�哝�̂͐��{�Ɏw�����邾�낤�v�Ɛ������܂����B
����ɂ��ăA�����J�̃V���N�^���N�A�u�푈�������v�̓��V�A�R�͕����s�����[�������Ă��āA�u�蕺�̊m�ۂɌ����ăv�[�`�������̒����ɂ�����哝�̕{�����ځA�����n�߂Ă���Ǝw�E���Ă��܂��B
���V�A���E�N���C�i�R���N�U���J�n���Ă��甼�N���o�߂����B�����̕����ƕ���𓊓����������̊Ԃ̐킢���P����ԂɂȂ����A���������錜�O�����܂��Ă���B�E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂�8�����{�A�u���V�A�̐N���Ƃ̐킢�ɏ������A�N���~�A���̂��������邱�Ƃ��K�v���v�ƕ\������ȂǓO��R��̎p��������Ă��Ȃ��B
���V�A��������������Ȃ��\���������Ă���B�����A�Z���ł̌�����ڎw���Ă������V�A�����A�N�U�̒������������A2014�N���畴���������������h���o�X�n���Ɠ��l�A�퓬�𑱂��邱�ƂŃE�N���C�i��B���ȗ���ɂƂǂ߂Ă������Ƃ��ł���Ƃ��������b�g�����������Ă���Ƃ̎w�E������B
���V�A��������Ɉڍs�ł����w�i�ɂ́A�����������Ȃ������������قɂ�������炸�A���V�A�o�ς̃_���[�W���������������Ƃ�����B���V�A�̍��N��2�l������GDP�͑O�N��4�����ƂȂ�A5���Ԃ�̃}�C�i�X�����ƂȂ������A�������ݕ��͗\�z���ꂽ�قǑ傫���Ȃ������B���V�A�o�ϏȂ́u���N��GDP��4�D2�����ɂƂǂ܂�A�����z�肵���قǗ������܂Ȃ��v�Ƃ̌��ʂ��������Ă���B�����Ȏ����A�o�����V�A�o�ςւ̐��ق̉e����a�炰�Ă��邱�Ƃɉ����A���V�A����̊O����Ƃ̓P�ނ����ƂȂ�A�A������Ȃ��Ȃ���������Ȃǂ̍�����ւ��i��ł��邱�Ƃ�����t�����`���B�y�ςł���ł͂Ȃ����̂́A�v�[�`���哝�̂́u���V�A�͒�����ɑς�����v�Ƃ̎��M��[�߂Ă��邱�Ƃ��낤�B
���V�A�ɂ͒�������u������ʂ̗��R������̂�������Ȃ��B�v�[�`���哝�̂́u�č��哱�̐��E�����͏I������v�Ƃ��˂Ă���咣���Ă������A�E�N���C�i�ł̕�����Ԃ��������Β������قǁA�č���ɏW������̏I���̉\�������܂��Ă��邩�炾�B
�E�N���C�i��@�͂���܂Łu���R�▯���`�����킢�v�Ə̂���Ă������A����������������ɂ�āA�u���ے����ɕϊv���N����v�Ƃ̔F�����L�܂����B�ăj���[���[�N�E�^�C���Y��8�����{�A�u���������̊S���E�N���C�i�ɏW�����Ă��邽�߁A���A�̐l���x���@�ւ͋L�^�I�Ȏ����s���ɒ��ʂ��Ă���v�ƕ��B�č����哱���鐧�ق̂����Ő[���ȑŌ����Ă��锭�W�r�㍑�̔����͍��܂���肾�B�E�N���C�i�N�U�ɒ�����ۂ��X�̐l���͐��E��3����2���߂邪�A�����̍��X�̍s����͖����`�̉��l���������ɂƂ��đ����������B
�Ď��i�V���i���E�C���^���X�g�̃R�����j�X�g��8�����{�A�u���V�A�ƃE�N���C�i�̂ǂ��炪�������Ƃ��Ă��A�헪�I�s�k���i����͕̂č����v�Ƃ̕��͂��������B�u���V�A�͒�����C���h�A�y���V���p�ݏ����Ƃ��ٖ��ȊW��z���A���������Ɖi���ɊW��f���낤�v�Ƃ�����Łu�č��͑��ɉ����i�ސ��E�̌����Ɍ������킴��Ȃ��Ȃ邾�낤�v�ƔߊϓI�Ȗ�����\�����Ă���B
���o�ϓI�ȗ��v���g�傳����g���R
�č��̉e���͒ቺ��K�ڂɍ��ێЉ�ő��݊������߂Ă���̂́A���C�̑Ί݂Ɉʒu����g���R���B���C������ŗאڂ��郍�V�A�ƃE�N���C�i�Ƃ̊W�̐[�������āA�������Η����闼���̊Ԃ���莝�����������Ă���B3���ɗ����̊O����k�������������g���R�́A8���̍����A�o�Ɋւ��郍�V�A�ƃE�N���C�i�Ԃ̍��ӂ����A�ƂƂ��Ɏ��������Ă���B����Ɏ��M���������炾�낤���A�g���R�̃G���h�A���哝�̂�9��3���A���V�A�R���苒�𑱂���E�N���C�i�쓌���U�|���[�W�����q�͔��d�����߂����Ċj�ЊQ�̌��O�����܂�Ȃ��A������ɖ������グ���B�����A�o�̍ۂɔ|�����o������������Ƃ����̂͂��̗��R���B
�E�N���C�i��@�̐[������������邱�Ƃɍv�����Ă���g���R�́A���V�A�≢�B�Ƃ̊W���������A�����Ă���B�g���R�͉��Ă̐��قŊ����ƂȂ������V�A�Y�����̗A���������Ă���B���N��2�l�����͑O�N�����ɔ��3�{�ɂȂ����B7���̎�]��k�ł̓G�l���M�[�f�Ղ̌��ϒʉ݂Ƀg���R���������p����Ă��c�_����Ă���B
���������̐��ى��ɂ��郍�V�A�̊�Ƃ̓g���R�����_�����铮�������߂Ă���B�g���R�͐��������̐��قɎQ�����Ă��Ȃ����Ƃ���A�g���R�����_�ɍ��ۓI�Ȓ��B��̔��𑱂��悤�Ƃ��郍�V�A��Ƃ��������Ă���B�g���R���H��c���A���ɂ��A���V�A��Ƃ̃g���R�����̐ݗ����͍��N1�`7����600�Ђ��A��N�ʔN��177�Ђ�傫������B
�g���R�̐����Ƃ͉��B�����A�o�����������Ă���B���E�I�ȃT�v���C�`�F�[��(������)�����̂����Œ��B��̋ߏ�V�t�g���i�݁A����܂ŃA�W�A���狟������Ă����ߗ��i��Ƌ�Ȃǂ����Y���邱�ƂŗA�o�z��71���h�������������Ƃ����Ă���(9��4���t���{�o�ϐV��)�B�������C���t���ɔY�܂����g���R�����A���ێЉ�ɂ����鑶�݊��̍��܂���e�R�Ɍo�ϓI�ȗ��v���g�傳����Ƃ������������������Ă���̂��Bgoogletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1635733543229-0'); });
���݃��V�A���苒���Ă���E�N���C�i�쓌���́A���Ƃ��ƃI�X�}���E�g���R����600�N�ɂ킽��x�z���Ă����n�悾�B�����������哱���鍑�A���@�\�s�S�ƂȂ�A���E���ĂьQ�Y�����̎���ɋt�߂肷�邱�ƂɂȂ������ŁA�n�̗����������ăg���R�̂悤�Ȓn��卑���e���͂����悤�ɂȂ��Ă���B
�E�N���C�i��@�̒������ɂ��A�č���Ɏ���̏I������������ттĂ��Ă���B���{�������������ې����̌��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�č��̃W���[�E�o�C�f��(Joe Biden)������6���A���V�A���u�e���x�����Ɓv�Ɏw�肵�Ȃ����j�𖾂炩�ɂ����B�E�N���C�i��ċc���炪�w������߂Ă������A�J���[�k�E�W�����s�G�[��(Karine Jean-Pierre)�哝�̕��́A�u���V�A�ɐӔC�킹��v��Łu�ł����ʓI�܂��͋��͂ȓ��ł͂Ȃ��v�Ƃ̍l�����������B
���V�A�̃e���x�����Ǝw����߂���A���������͐������ɂ킽���Ė��m�ȉ�����Ă����B����ɂ��ăo�C�f���哝�̂�5���A�L�Ғc�̖₢�Ɂu�m�[�v�Ɠ����Ă����B
���́A���V�A���e���x�����ƂɎw�肷��A���V�A�̐N�U�ōr�p�����E�N���C�i�̈ꕔ�n��ւ̎x�������̋������W����ꂽ��A���A(UN)�ƃg���R��������E�N���C�i�̍`����̍����A�o����Ɏx���c�̂��Ƃ��Q���ł��Ȃ��Ȃ����肷��\��������Ǝw�E�B�u(���V�A�̃E���W�[�~���E)�v�[�`��(Vladimir Putin�A�哝��)�ɐӔC����点���Ŕ��Ɍ��ʓI�ȑO��̂Ȃ�������(�A�g)����߁A������(����ʂ���)�E�N���C�i���x������\�͂����Ȃ����˂Ȃ��v�Ƃ����B
�i���V�[�E�y���V(Nancy Pelosi)���@�c���璴�}�h�̋c���O���[�v�́A�o�ϐ��ق��Ȃ��Ă������V�A�ւ̈��͂�����ɋ��߂邽�߂Ƃ��āA�o�C�f�����Ƀe���x�����Ǝw������߂Ă����B
�č��ɂ��e���x�����Ǝw��͂��܂��܂ȉe�����y�ڂ��B��Ƃ��s�Ƃ��ẮA���E��̌o�ϑ卑�ł���ē��ǂɂ��@�I�[�u���x�����A���X�N�����Ȃ��Ȃ�B
���ݎw�肳��Ă���̂̓C�����A�V���A�A�k���N�A�L���[�o��4�����݂̂ŁA��������o�ϋK�͂̓��V�A�Ɣ�ׂĂ͂邩�ɏ������B�@
���V�A�̃v�[�`���哝�̂́A�ɓ��̃E���W�I�X�g�N�ʼn������A���̒��ʼn��Ă����V�A�ɉȂ������ق��u���E�o�ς���̉��������v�Ǝ咣���A�Ό��p����N���ɂ��܂����B���̂����ŃG�l���M�[�̗A�o�Ȃǂ�ʂ��āA�������͂��߂Ƃ���F�D���Ƃ̘A�g����������p���������܂����B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂�7���A�ɓ��̃E���W�I�X�g�N�ŁA���یo�ω�c�u�����o�σt�H�[�����v�̑S�̉�ɏo�Ȃ��A�������܂����B
���̂Ȃ��Łu���ẮA���������ɂƂ��Ă̂ݗL�v�Ȑ��E�������ێ����悤�Ƃ��Ă��邪�A���ق��A���E�o�ς���̉��������v�Ǝ咣���A���Ă����V�A�ɉȂ������ق�ᔻ���܂����B
�����āA���V�A�R�̕����ő��Ă����E�N���C�i����_�Y���̗A�o���ĊJ���ꂽ���Ƃɂ��Ắu���̂قƂ�ǂ��A�n�����r�㍑�ł͂Ȃ��A���[���b�p�����ɉ^��Ă���B����ł͐l���I�ȑ�S���ɂȂ���B���[���b�p�ւ̍����A�o�𐧌�����K�v������v�Ǝ咣���A���V�A�ƑΗ���[�߂郈�[���b�p�������܂����B
�܂��A���V�A�Y�̃G�l���M�[�ɂ��āu���[���b�p�͒��N�A���V�A�Y�̓V�R�K�X�̉��b���Ă������A���̗��_�����͂�K�v�Ƃ��Ȃ��̂Ȃ�A����ł����܂�Ȃ��B���E�̓��V�A�̃G�l���M�[������K�v�Ƃ��Ă���B���V�A�͂ǂ�ȍ��Ƃ����͂��Ă����v�Əq�ׂ܂����B
�����āu�m���h�X�g���[���𗘗p���āA���V�A���w�G�l���M�[�퉻���Ă���x�Ɣᔻ���邪�A���قɂ���Ă݂������ǂ�����ł���v�Əq�ׁA���V�A���A�L�x�ȓV�R�K�X�𗘗p���ă��[���b�p�ɗh���Ԃ�������Ă���Ƃ����ᔻ�ɔ��_���܂����B
�܂��u�E�N���C�i�ւ̓��ʌR�������J�n���Ă���A���V�A�͉��������Ă��炸�A������������Ƃ͂Ȃ��ƐM���Ă���B���V�A�ɂƂ��Ă̗��v�Ƃ����ϓ_�ł́A�����͎匠���������邱�Ƃ��ł����B�m���ɁA���E�ł������ł������̓�ɉ����N�������A����͂����ɗ��v�������炷���낤�v�Ǝ咣���܂����B
���̂����Łu���V�A�̖ړI�́A�����h���o�X�n��̏Z���������邱�Ƃ��B�����͍Ō�܂ł������萋����v�Əq�ׁA�R���N�U���p������l�������߂ċ������܂����B
�܂��A�C�������������S���ւ̌��O�����܂��Ă���E�N���C�i�̃U�|���[�W�����q�͔��d���ɂ��āA�E�N���C�i�R���������U�����Ă���Ǝ咣���������ŁuIAEA�����ی��q�͋@�ւ́A��������R�̑�����P������悤�w�E���邪�A�����Ƀ��V�A�R�̑����͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
��c�̑S�̉�ɂ́A�����̋��Y�}�̏���3�ʂŁA�S�l�ぁ�S���l����\���̌I�폑�ψ�����A�~�����}�[�Ŏ���������R�̃g�b�v�A�~���E�A�E���E�t���C���i�ߊ��炪�o�Ȃ��A�v�[�`���哝�̂͗F�D���Ƃ̘A�g����������p����ł��o���Ȃ���A���ĂƂ̑Ό��p����N���ɂ��܂����B
���u�U�|���[�W�������Ƀ��V�A�R�̑����͂Ȃ��v
�v�[�`���哝�̂�7���A�E���W�I�X�g�N�ŊJ����Ă��鍑�یo�ω�c�̑S�̉�ɏo�Ȃ��A�E�N���C�i�̃U�|���[�W�����q�͔��d���Œ������s�����AIAEA�����ی��q�͋@�ւɌ��y���܂����B
�v�[�`���哝�̂́uIAEA�̕��͐M�����Ă��邪�AIAEA�̐��Ƃ́A�A�����J��[���b�p���爳�͂��A�E�N���C�i���������U�����Ă���Ƃ͌����Ȃ��̂��B���Đ��̕��킪�g���A�����̈��S���ɋ��Ђ������炵�Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁuIAEA�́A��������R�̑�����P������悤�w�E���邪�A�����Ƀ��V�A�R�̑����͂Ȃ��v�Əq�ׁA�U�|���[�W�������̔����ɔے�I�Ȏp���������܂����B
�����V�A �����Ƃ̘A�g ��w����
���V�A���{���A���V�A�ɓ��ŊJ�Â��Ă��鍑�یo�ω�c�ł́A�E�N���C�i�ւ̌R���N�U���߂��艢�ĂȂǂƂ̑Η����[�܂钆�A�����Ƃ̘A�g����w��������Ă��܂��B
���Ƃ��̃v���O�����ł́A���V�A�ƒ����̊Ԃ̖f�Ղ�A��҂̌𗬁A����ɒ����ƃ��V�A���哱����g�g�݁A��C���͋@�\�̏d�v���ȂǁA�����̘A�g�������e�[�}�ɂ����Z�b�V�������ڗ����܂��B
���̂����A7���ɍs��ꂽ����̒����̌o�ϋ��͂Ɋւ���Z�b�V�����ł́A�����ƍ�����ڂ���ɓ��̃A���[���B�̒m�����u�������ƌo�ϕ���ȂǂŁA���炵���W��z���Ă���v�Əq�ׂ������ŁA���Ƃ�6���ɁA�����ɐV���ɋ����J�ʂ������Ƃ�A�B���̌����w�Z�ŁA���Ƃ����璆����̎��Ƃ��n�߂����ƂȂǂ��Љ�A�����镪��ŊW����������Ă���Ƌ������܂����B
�܂��A�I�����C���ŏo�Ȃ������V�A�ɒ��݂��钆����g�́A���Ƃ�7���܂ł̗����̖f�Պz��977���h���A���{�~�ł��悻14���~�Ɋg�債�����ƂȂǂ������āu�������̊W�́A����܂ł̗��j�ōō��̎����ɓ˓������v�ƕ]�����܂����B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂�7���A�ɓ��E���W�I�X�g�N�ŊJ�Ò��̑�7���o�σt�H�[�����̑S�̉�ʼn��������B�i��҂̎���ɑ��A�v�[�`�����̓E�N���C�i�N�U�J�n���甼�N�ȏオ�߂�������F���ɂ��āu���V�A�͉��������Ă��Ȃ��B�ނ���匠�����������v�Ƌ����B���Ă̑��V�A���قɋ����Ȃ��p�������߂Ď������B
�܂��A�u�����͌R�������n�߂��̂ł͂Ȃ��A(2014�N�ȗ��̊�@��)�I��点�悤�Ƃ��Ă���v�Ǝ咣�B���͐e���V�A�������|�ꂽ�E�N���C�i���ςɒ[����Ƃ��āA���ێЉ��h�邪���N�U�������܂Ő����������B
�����ł́A���Ă̐��ق��u�S���E�ɋ��Ђ������炵�Ă���v�Ɣ����B�H���A�o�����V�A��W�I�Ƃ��邱�ƂŁu�l����@�ɂȂ���v�Ƃ̎��_��W�J�����B�����قɉ�����Ă��Ȃ�������C���h���܂ރA�W�A�����m�n��ȂǂƂ̂Ȃ����O���Ɂu���V�A���Ǘ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ�������B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂́A�������E�N���C�i�N�U���o�Ĉ�i�Ƌ����Ȃ��đ䓪����Əq�ׁA���ď����́u���كt�B�[�o�[�v������B
�v�[�`���哝�̂�7���A�E���W�I�X�g�N�ŊJ���ꂽ�����o�σt�H�[�����ŁA��c�i�s������E�N���C�i�N�U�Ɋւ��鎿����A�u���V�A�͉��������Ă��炸�A���̐����������Ȃ��Ɗm�M����v�Əq�ׂ��B�v�[�`���哝�͎̂���O�̉����ł̓E�N���C�i�ł̐푈�Ɉ�،��y���Ă��Ȃ������B�u��ɓ�������̂́A���V�A�̎匠�������v�Ƃ�������B
�哝�̂͂���ɁA�V�^�R���i�E�C���X�������炷�o�ςւ̉e���ɂ��āu�V�^�R���i�Ђ͕ʂ̖��Ɏ���đ���ꂽ�B����͒n���K�̖͂��ł���A���E�S�̂��������Ă���v�Əq�ׁA�u����͐��������̐��كt�B�[�o�[���B�����̍s���l���𑼍��ɉ������A�匠��D���A�ӂ̂܂܂ɏ]�킹�悤�Ƃ���U���I�Ȏ��݂��v�Ǝ咣�����B
���V�A���Ǘ������邱�Ƃ́u�s�\�v���Ƌ���������ŁA�u�����̓��X�N���������Ă���A���̒����𑱂���K�v������v�Ƃ��q�ׂ��B
���V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`��(Vladimir Putin)�哝�̂�7���A�E�N���C�i�N�U�𗝗R�Ƃ������قɑ���Ƃ��ă��V�A���G�l���M�[���u����v�Ɏg���Ă���Ƃ̔ᔻ�ɔ��_���A��~���Ă���V�R�K�X�p�C�v���C���ɂ��āA�^�[�r�������V�A�ɕԊ҂����Β����ɉғ�������Əq�ׂ��B
�v�[�`�����͋ɓ��E���W�I�X�g�N�ŊJ���ꂽ�����o�σt�H�[�����ŁA�u�ނ�(���B)�̓��V�A���G�l���M�[��Ƃ��Ďg���Ă���Ǝ咣���Ă���B���������Ƃ��B�����͗v���Ɋ�Â��āA�K�v�Ȃ����������Ă���v�Əq�ׂ��B
���V�A�̍��c�V�R�K�X���K�X�v������2���A���V�A�Y�V�R�K�X���h�C�c��������p�C�v���C���u�m���h�X�g���[���v�ɂ��āA�C���̂��߉ғ��ĊJ����������Ɣ��\�����B
���V�A�哝�̕{�́A�J�i�_�ŏC�����������Ɠd�@���V�[�����X���^�[�r�������������̐��قŕԊ҂���Ȃ��Ǝ咣�B�v�[�`�����́u�^�[�r�������A�����ɂ��m���h�X�g���[�����ғ�������v�Əq�ׂ��B
����A���V�A�ƃE�N���C�i�A���A(UN)�A�g���R�̍��ӂɂ��ĊJ���ꂽ�E�N���C�i����̍����A�o�Ɋւ��āA�u�E�N���C�i����A�o���ꂽ�����̑唼�́A�n�����J���r�㍑�ł͂Ȃ����B�ɑ���ꂽ�v�Ƃ̌������������B
����Ɂu���B�����͂������\�N�A���S�N�ƁA�A���n��`�҂Ƃ��čs�����Ă����v�Ƃ��A�u�ނ�͍��������悤�ɍs���������Ă���v�Ɣᔻ�B���B�����͓r�㍑���\���Ă���A�u����������@�����A���E�̐H�Ɩ��͂���ɐ[��������v�Ǝ咣�����B
�암�n��̗̓y�����߂��ׂ��A8��29���ɔ��]�U���ɏo���E�N���C�i�R�B9��4���ɂ̓[�����X�L�[�哝�̂������Ɠ암��3�̏W����D�҂����ƕ\�����܂������A���̐整���͂ǂ��W�J���Ă����̂ł��傤���B����̃����}�K�w���ې헪�R�����L���Łx�ł͓��{���ې헪��茤�������̒Óc�c�����A���܂��܂ȏ������틵������B����Ƀ��V�A�E�E�N���C�i�����̎v�f�ƁA���̐푈���N�������������̂ɂ��čl�@���Ă��܂��B
���E�N���C�i�R���w���\���s�ɔ���
�E�N���C�i�푈�̓E�R���w���\���s�̒D�҂�ڎw���A29����葍�������J�n�����B������������悤�B
�E�N���C�i�Ɨ��L�O����8��24�����29������암�w���\���B�̃h�j�G�v���쐼�ݒn��̒D�҂Ɍ����A�E�R�͑��������J�n�����B
���̔����ƂƂ��ɁA���������A�E�R�̓N���~�A������w���\���B�A�U�|���[�W���B�̃��R�̒e��ɂ╺⋋��_�A�i�ߕ��A��R��n�Ȃǂ����j���āA���R�̕⋋���Ȃ������������Ă���B
���R�́A�푈�������͊����Ă����̂ŁA�h���o�X���ʂɗD�G�������W�߂āA���̒n�_�ł̓˔j���u�����Ă���悤���B���̂��߁A���R�̓C�W���[�����̃m�o�E�t�T���t�J����ˑR�A�h�l�c��̋���j�āA�Ί݂܂œP�ނ����B
�C�W���[�����ӂ̗D�G�Ȑ��K�����h�l�c�N���ӂɈړ�������悤�ł���B���̐��K���̑���ɕ�W�����[������̂ŁA�h�q�̓���n�_���������悤���B���̕�W�������Ȃ��A���̒n��͎蔖�ɂȂ��Ă���B
���̂��߁A�E�R�͏��X�ɑO�i���Ă���B��@�����o���āA���R�̋n�т������āA�����ɐZ��������@�őO�i���Ă���悤���B
�v�[�`���哝�̂̓h�l�c�N�B�̊��S�����̊�����8��31������9��15���ɉ������āA���R�ɐ�Ζ��߂��o�����Ƃ����B���̂��߁A�h�l�c�N�ւ̕������������R���K�v�ɂȂ�A�C�W���[�����ӂ�n���L�E���ӁA�X���r�A���X�N�������瑽���̌o���L�x�Ȑ��K�����ړ������ĕ�W���ɒu�������Ă���悤���B
����2�T�Ԃ�����ƁA���R���O�i�ł����̂́A�h�l�c�N�ߍx�̃s�X�L�[�����ł���A��x�͉����߂����E�R�́A�ς����Ȃ��Ȃ芮�S�P�ނ����B
�������A�s�X�L�[�����ɍU���ł��Ȃ������R�����Ղ����悤�ł���B���̏��Ńv�[�`�����������\��������B�h�l�c�N�ɕ������W�߂�ƁB���n�w�����ƒ��ژA�����Ă���̂ŁA�S�̐�ǂ������ɁA�ꕔ�n��̐�p���x���œ����̖��߂��o�����悤���B
����Ɋ֘A���āA����ȋ]�����đO�i�����̂ŁA���R�͋x����E�R�ɐ\���o�����A���ԉ҂��̂悤�ȋC������B�h�l�c�N�ɕ������W�߂�����Ń��V�A�R�͓����Ă���̂ŁA��Ȃ��悤�ȋC������B
���̂悤�ȓ������猩��ƁA���R�̐헪�́A�암���̂āA�C�W���[���̂āA�h�l�c�N�s���ӂ��m�ۂƂ������ƂɂȂ�B
����A�E�R�́A�h�j�G�v����̃w���\���s�ƃm�o�E�J�z�t�J�̒��Ԓn�_�̃��{�O�̃|���c���E�t�F���[��j���B�A���g�m�t�X�L�[���₻�̕t�߂̃t�F���[�A�J�z�t�J����t�߂̑D�����U�����āA�h�j�G�v���쐼�݂ւ̕⋋���~�߂�U�����p�����Ă��邪�A�t�F���[�̔j����ł���悤�ɂȂ����悤�ł���B
����́A�˒�70km�A�덷1m�́u�{���P�[�m�vGPS�U���e���E�R�ɋ�������āAPzH2000��155mm�֒e�C����łĂ�悤�ɂȂ������ƂŁA���̒e�͍Ō�̒i�K�ŔM�ǔ����ł���̂œ����ڕW�ł��_���邩��ł���B����ŁA���R�̕⋋�͊��S�Ɏ~�܂邱�ƂɂȂ�B
�N���~�A�����ɕ⋋���Ă��镺��E�e��́A�w���\���B�ɑ��ꂸ�ɃU�|���[�W���B�̃g�N�}�N�t�߂ɒ~�ς������A������HIMARS�Ŕj��Ă���B�������A���R�̓h�j�G�v���쐼�݂ւ̑�ʂ̕⋋�E���R����߂āA�U�|���W���[�B�ŐV���ȍU��������̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă���B�V�����Ґ����ꂽ���R�̑�3�R�c���U�|���[�W���B�ɐ��K�����𑗂荞��ŁA��W���̓n���L�E�ߍx��C�W���[���ɑ����Ă���B
���̂��Ƃł́A�h�C�c�R�c�H�������Ă��A���V�A���R�ɂ͑�������J���]�n������Ƃ��A���������̓��V�A�̌R���͂��ߏ��]�����ׂ��łȂ��ƌx����炵�Ă���B�܂��A���V�A�R�͖L�x�ȕ���������Ă���Ƃ������Ƃ��B
�E�R�̎�͕���������암�w���\���B�ł́A29����葍�U���ɂȂ�A3�����Ŕ������Ă���B1�ɂ̓w���\���s�̖k���烍�R�ɐ�̂��ꂽ�u���z�_�g�l��D�҂��A�������HM14���꒼���ŃL�Z���t�J�A�����ăw���\���s�x�O�̃`�F���m�o�C�t�J�܂ōU�����y��ł���悤�ł���B
���̍U�����ɃE�R�͂��Ȃ�̐�͂𓊓����Ă���BHIMARS��������`�F���m�o�C�t�J�ւ̍U���Ɏg�p���Ă���B�������A�`�F���m�o�C�t�J�����̃w���\���s���ʂ͗v�ǒn�тɂȂ�A��������̍U���͗e�Ղł͂Ȃ����A�z���̃��R�������B�������A�E�R�̍U�������������ƂɃ��R�́A�r�b�N�������悤�ł���B
���̍U���Ɠ������āA�w���\���s���̓��ꕔ�����s���ŏe������J�n���Ă��邪�A�s���̏e����͎��܂����悤�ł���B
�w���\���B���k���̃��]�x�̋����ۂ��烍�R���U�����āA�X�N�C�[�E�X�^�{�N��D�҂��A�R�X�g�����J���D�҂�T2207�����ŗ��R�����풆�ł���B���R�̐�Ԓ��SBTG���W�����Ă���̂ŁA�����ł̓E�R�̑O�i���x�͒x�����ƂɂȂ��Ă��邪�����ɑO�i���Ă���B
�w���\���B�k�����ł́A�A���n���w���X�N�A�I���w�l��D�҂��āA�r�\�R�s���A�Ō���ɂȂ��Ă���B�������A�����̃E�R�͍U�����D�҂����n�_���ēx�A���R�ɒD����ȂǁA�������Ă���悤���B�������A���R���w���\���B�������̃]���C�E�o�N�J�ɖC�������Ă���Ƃ������Ƃ́A�E�R��10km���쉺�����\��������B
�������A���̃w���\���B�S�̂ŃE�R�����R��������Ă���̂ł悭�킩��Ȃ��B���R�̍U���n�_��SNS�̏�Ő������邵���Ȃ��B
�����āA����͗l�ł�����B�L���͈͂�1��8,000��̃��R�ł́A�_�������Ă��Ȃ��̂ŁA�E�R���i�����Ă��A���R�w�n�������A�O�i�ł���\���������B
�ǂ���ɂ��Ă��A�h�j�G�v���쐼�ݒn��̃��R30BTG��1��8,000�����̕⋋���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邪�A����ł��A���R�́A���܂łɒ��ߍ���C���ԁA�w���R�v�^�[�A�����C�ƒe����ʂɎ�������Ă���B�E�R���m�́u�z��̑����͖L�x�������m�͏��Ȃ��v�Ƃ����B
�⋋�́A�E�R�퓬�@�Ɍ�����Ȃ��悤�ɁA�N���~�A����A���w��2�@�ƌ�q�̍U���w��2�@��4�@�ґ��ōׁX�Ƃ��Ă���悤�ł��邪�A���ɏ��Ȃ��B�⋋�����ێ��ł����ɋ�̕⋋�ɂȂ��Ă���B����ƁA�Ǘ��������R���������݂��Ă���悤���B
���̂��߁A�����̐퓬�ɂȂ�ƁA���R�̑�ʓ��~�ɂȂ�\�����o�Ă����B���܂ŁA���R�������Ƃ������ɂȂ��Ă���B
�����A���V�A�̓Ɨ��n���f�B�AThe Insider�ɂ��ƃ��V�A�͂��łɗU���~�T�C�����قƂ�ǕۗL�����A�푈�����̂܂܈ێ������A�C�e�Ƒ��b�ԗ���2022�N���܂łɂقƂ�ǂ����ꂷ��Ƃ����B
�����āA��Ԃł����A���R�̎ԗ��������v��5,415�������A1,756��(31��)�����R�����ŃE�R���b�l�������̂��B������C�����Đ���ɑ���o���Ă���悤���B���R��Ԃ̃����e�i���X���Ȃ����ƂŌ̏ᗦ���������ƂɂȂ��Ă���B
�Ō�ɁA�s�����郍�R�́A�t�F���[����ɉ����邱�ƂɂȂ邪�A�h�j�G�v���쐼�ݒn��ł�3�P���̃t�F���[�⋴�����Ȃ��B��͐���j���œn�邵���Ȃ��B�d�Ί�͕������邱�ƂɂȂ�B
����ƁAAGM-88���[�_�[�~�T�C���Ń��R�̖h�[�_�[���j��āA���R��S300�͋@�\���Ȃ��Ȃ��Ă���B���̂��߁A�o�C���N�^��TB2����@������ΖC����ŁA���R�̉ΖC���U���ł���悤�ɂȂ��Ă����BTB2��T-72��Ԃ�j�铮����o�Ă����B
���Ƀh�j�G�v���썶�݂̃w���\���s�Ȃǂ̐����̈�тł́A�E�R�������m�ۂ����\��������A���̒n��Ń��R�퓬�@�̊����́A���ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă����B
���̂��߁A�E�R�U���@�����R�n�㕔�����ł���̂ŁA�E�R���㕔���́A�C���Ƌ�R�̎x�����āA���R���U�����Ă���B����ŁA�w���\���s�x�O�܂ŃE�R�͓��B�����͗l�ł���B
����ł��A���R�̑҂������U���ŁA�E�R��ԑ��Ȃǂ���Q���Ă���悤�ł���A�����ȋ]�����đO�i���Ă���B
�������A�S�̓I�ɂ́A���R���s���Ȑ킢�ɂȂ�A��ӂ̒Ⴂ�����́A�E�R�̍U���ł����ɓ��S���Ă���B�O���ɂ����h�l�c�N109�A���́A�E�R���U���J�n������A���P�ނ����B�������A������҂������U���̗U���̉\��������A���ӂ��K�v�ł���B
�p���ƕč��̃E�R�R���ږ�c���A�E�R�̑������̑O�i���x�𑁂߂�ƁA���Q�������Ȃ�A�p��\�͂�Ⴍ���邱�ƂɌx�����Ă���B�������Ƃ����N�U���x�ɂ��āA���R�̒e����͊�������ׂ��ł���Ƃ����B����ƁA�|�[�����h�̑S���PT-91���A�܂��͂��Ă��Ȃ��ł���A�U��������\���Ƃ͌����Ȃ����Ƃ��l�����Ă���悤���B
���݁A�I�����_���狟�^���ꂽ�����A�����b��YPR-765APCs�������AT-72�AT-64�Ȃǂ̐�Ԃ̑䐔�����Ȃ����Ƃ��l�b�N�ł���B���̐�Ԃ̑������w���\���s�D�ҍ��ɓ������Ă��邪�A����ł����Q�������Ɛ�������Ȃ��Ȃ�B
���̂��߁A�E�N���C�i�̃A���X�g�r�b�`�哝�̌ږ�ɂ��ƁA���{�͑����̃E�R���m�����𗎂Ƃ����Ƃ�]��ł��Ȃ��Ƃ��A�E�R�����R�ɑ��f�����������邱�Ƃ����҂��Ȃ��ŗ~�����Ƃ����B
�������A�E�N���C�i�̃��Y�j�R�t���h���́A�~�܂Ő푈�𑱂���ƁA�������ŁAEU����̎x�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�S�z���Ă���B���̃o�����X���K�v�ɂȂ��Ă���悤���B
����ɑ��āA�h�C�c�̃V�����c�́A�~�̔R���ɂ��āA�m�ۂł����ƌ����Ă��邪�A�����̍��ł͓~�̔R���̕s�����S�z�ȏł���B
�v�[�`���哝�̂́A���B�ւ̓V�R�K�X�������~�߂āA���B�ł̃G�l���M�[�s����������E�N���C�i�ɗv������̂�҂����ł���B���̂��߁A�m���h�X�g���[�����~�߂��B
�������A�암�w���\���B�̃E�R�������̌o�߂Ŏ��M���������[�����X�L�[�哝�̂́A�E�N���C�i�����̕��������̂��߂̌��O���[�v�ɂ����铯���̑�\�c��p�~���A�푈�Ō���������Ƃ����B
���̂��߁A�[�����X�L�[�哝�̂́A�h�C�c�ɑ��āA�E�N���C�i����d�C�̋������s���Ƃ��āA���B�̃G�l���M�[�s�����ɘa���āA�x���̌p����}�肽���悤�ł���B
�����āA���̃E�R�̑������ŁA��̒n�̃��A�M�ғ��̂��߂̏Z�����[�́A����n���I�Ɠ�����9/11�Ɏ��{����͕̂s�\�ŁA���̌���11/4�́u�����c���̓��v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă���B
����A�U�|���[�W�������ɂ́AIAEA�̍��@�c�����������B����ŁA���V�A�͎������苒���錴���ւ̍U�����T����ƁA���҂������B
���̖��������������o�Ă����BIAEA���u�Ȃ������ɔ��ł����~�T�C���̓��V�A���ł����悤�ȕ����������Ă���́H�v�ƌ�������ɑ��āA���V�A���̒S���҂́A�u���e����ۂɃ~�T�C����180�x�����]�����邩�炾�v�Ɛ^��œ������Ƃ����B
���̂悤�ȃ��R�̍s���Ď��ɁAIAEA�̃O���b�V�����ǒ��́A�U�|���[�W�������ɃX�^�b�t2�l���풓������Ɣ��\�����B
�����āA���V�A�R���苒����U�|���[�W�����q�͔��d���̈��S���Ɋւ������9��9���܂łɔ��\����Əq�ׂ��B
�V���C�O���h���́A�E�N���C�i���u�j�e���v�����s���Ă���Ɣ��A���V�A���������ɏd�Ί��z�������Ƃ����E�N���C�i�Ɛ��������̎咣��ے肵�A���A���ۗ��ł��A���V�A�͌����̈��S���E�R���j�Q�����ƁA�c���Ă�����AIAEA�̕���A�R�c����邱�ƂɂȂ�B���V�A�̉R���A���A���ۗ��ł��\����邱�ƂɂȂ�B
���V�A��9��1�������K�͂ȌR�����K�u�{�X�g�[�N�v���A���V�A�ɓ���k���̓y�A���{�C�Ȃǂōs���A���m5���l�ȏ�̂ق��q��@140�@��͑D60�ǂ��Q������B�����A�A���W�F���A�A�C���h�A���I�X�A�����S���A�j�J���O�A�A�V���A�A�A�����j�A�A�A�[���o�C�W�����A�x�����[�V�A�J�U�t�X�^���A�L���M�X�^���A�^�W�L�X�^�����Q������B
���̑_���́A�E�N���C�i�푈�ł��A���V�A�͒����ƂƂ��ɁB�ĉ�����{�ւ̑R���ł���ƌ�������_��������Ƃ݂��邪�A���ɁA�����͊͑D�̎Q���������āA��p�i�U���Ƀ��V�A�̎x����_��������悤���B
���V�A�́A�ɓ����R���E�N���C�i��70�����x�����Ă���̂ŁA�Q���l����1���l���x���̂悤�ł���B�P��̑剉�K���s�����ƂŁA���R���]�T���邱�Ƃ��������悤���B
���E�́A�m���ɓ����̕����ɂȂ��Ă��Ă���B��i���Q�Ɛꐧ��`��+�V�����{���W�r�㍑�Q��2�Ɋ���Ă���B���g���h�~�Ȃǂ̐�i���̋K���ŁA�V�����̔��W�͑j�Q����Ă���B
�����������V�����́A�����̒��ԂɈʒu���邱�ƂɂȂ�B���̂悢�Ⴊ�C���h���B�C���h�́A�u�{�X�g�[�N�v�ɎQ�����邱�ƂŁA���Ăɑ���s����\���Ă���悤�Ɋ�����B
�����A�ǂ��Ȃ�܂����H
�E�N���C�i�R���k�����n���R�t�B�̒��o���N�����Ŕ��U�̓����������Ă���B
�E�N���C�i�����̐e���V�A�h�������́u�h�l�c�N�l�����a���v������7���A�ʐM�A�v���u�e���O�����v�ŁA�u�o���N�������E�N���C�i�R�����̍U�����Ă���v�ƔF�߂��B
�o���N�����̓��V�A�������⋋���_�Ƃ����ʂ̗v�ՃC�W���[���̖k���Ɉʒu���A���V�A�R��3������苒���Ă����B�e���h�����́A�E�N���C�i�����ȑO����C���̏�����i�߂Ă����Ǝw�E�B�E�N���C�i���D�҂���A���V�A�R���n���R�t�B�ō���W�J�����őŌ��ƂȂ�B
�E�N���C�i���ǂ͔��U�ɂ��Ė���������Ă��邪�A���n�̋L�҂��e���O�����ȂǂɃo���N�����Ō�킪�N���Ă���Ƒ������œ��e�����B
�E�N���C�i�哝�̕{�̃A���X�g�r�b�`�ږ��7���A�e���O�����ւ̓��e�Łu�n���R�t�B�œd���Ή̕ω����N���A���V�A�R�͓����֑ނ��Ă���v�Ǝ咣�B�E�N���C�i�R�͓암�w���\���B�ł��U�������߂Ă���Ƃ���A�A���X�g�r�b�`���͍����u�������s�Ői�߂Ă���v�Ƌ��������B
�E�N���C�i�̃��f�B�A�ɂ��ƁA�n���R�t�B�̕ʂ̒��N�s�����X�N�̓��ǎ҂�6���A�r�f�I���b�Z�[�W�Łu�E�N���C�i�������߂��N�s�����X�N���������v�Ƒi�����B�@
�E�N���C�i�R��������2�̓s�s�n���L�E�̓��ɐi�R���Ă��邱�Ƃ����������B�b�m�m���ʒu�����m�F�����r�m�r�̓���ɂ́A�ŋ߂܂Ń��V�A�R�ɐ�̂���Ă������ɃE�N���C�i�̕��m������l�q���f���Ă���B
�����E�N���C�i�R�����̒��Œn�����ł߂邱�Ƃ��ł���A�אڂ���o���N�����ɒ������郍�V�A�R���͂��邱�Ƃ��\�ɂȂ�B
�E�N���C�i�A���V�A�o���̏��ɂ��ƁA�o���N�����ł͎��́u���K���X�N�l�����a���v�̖�����V�A���Ɛe�q���̕��m������ɏA���Ă���A�������������╺�m�̒u���ꂽ�͊낤���Ȃ��Ă���\��������B
�b�m�m�͂�����������Ǝ��Ɍ��ł��Ă��Ȃ��B���̒n��ł̃E�N���C�i�̍U���Ɋւ��ẮA���V�A���{���E�N���C�i���{�����y���Ă��Ȃ��B
�ăV���N�^���N�̐푈������(�h�r�v)��6���A�E�N���C�i�R���o���N�����ɔ���A���V�A�R���h�l�c��Ȃǂ̍��݂ɒǂ�����Ă���\���������Ƃ̕��͂��������B
���C�^�[�ʐM��7���A���V�A�R�̐�̒n��D�҂Ɍ����A�암�Ŕ��]�U���ɏ��o���Ă���E�N���C�i�R���A�����n���L�E�B�ł��������n�߂��ƕ��B�E�N���C�i�R��8��29���ɊJ�n�������U���L�͈͂ɋy��ł���\��������B�E�N���C�i�R��6���A�암�w���\���A�U�|���[�W�����B�ł��I�R���_�ւ̍U�������߂Ă���A�퓬�̎哱�����E�N���C�i�Ɉڂ�n�߂Ă���悤���B
���C�^�[�ʐM�ɂ��ƁA�����h�l�c�N�B�̐e�I�h�����W�c������6���A�r�m�r�ɁA�I�R���苒����n���L�E�B�o���N�����ɑ��A�E�N���C�i�R���������U�����n�߂��Ɠ��e�����B�o���N�����́A�I�R���h�l�c�N�B�U���̋��_�Ƃ��Ă���n���L�E�B�C�W���[���ɋ߂��A�D�҂����A�C�W���[����h�q���邱�Ƃ�����Ȃ�Ƃ����B�E�N���C�i�哝�̕{���������U��F�߂��B
�Đ����@�ցu�푈�������v��6���A�����ɔz������Ă����I�R�̐��s�������암�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�Ǝw�E�����B�I�R���암�̖h�q���������邽�ߐ�͂��ړ��������Ƃ��A�����ł��E�N���C�i�R�̔��U���\�ɂ����Ƃ̌������B
�E�N���C�i�R�Q�d�{����7���A��R���n�㕔���̍U���x���̂��߁A��40�����̘I�R���_�Ȃǂɔ�Q��^�����Ɣ��\�����B6���ɂ́A�U�|���[�W���B�x���W�����V�N�̐e�I�h�u�i�ߊ��v���Ԃ��Ɣ��E���ꂽ�Ƃ̏������ꂽ�B

�E�N���C�i�R�̃U���W�j�[���i�ߊ���7���A���V�A��2014�N�ɕ��������N���~�A�����̃��V�A�R��n�ɑ����A�̔����ɂ��āA�E�N���C�i�ɂ��~�T�C���������̓��P�b�g�ɂ��U���ƔF�߂��B���c�ʐM�ЃE�N���C���t�H�����ւ̊�e���疾�炩�ɂȂ����B
�N���~�A���������̃��V�A�R�̊�n�ł�8��9���A������̔������������B�E�N���C�i�́A����܂ōU���������ɂ͔F�߂Ă��Ȃ������B
����A�U���W�j�[���͊�e�ŃE�N���C�i�R���U���������Ƃ�F�߁A�U���ɂ�胍�V�A�R�@10�@���u�s���s�\�v�Ɋׂ����Əq�ׂ��B
����ɁA����̏ɂ����ă��V�A�R���j������g�p����Ƃ������Ђ�����Ǝw�E�B�E�N���C�i�푈�����N�܂ő����\���������Ƃ̌������������B
�E�N���C�i����߂��鍑�A�̈��S�ۏᗝ����̉���J����A���Ċe���́A���V�A���E�N���C�i�����ȂǂŎs�����S�������胍�V�A�����ɋ����I�Ɉڑ������肵�Ă���Ɣ��A���V�A�ɑ��č��A�ɂ�钲���������悤����܂����B
�E�N���C�i����߂���A���Ċe���⍑�ۓI��NGO�́A���V�A�R���x�z���ɒu�����E�N���C�i�����ȂǂɎs����q�₷��{�݂�݂��A���̌�S�������胍�V�A�����ɋ����I�Ɉڑ������肵�Ă���Ǝw�E���Ă��܂��B
����ɂ��č��A���ۗ���7���A����J����A���A�l�������ٖ����������̒S���҂����s���A���V�A�R���E�N���C�i�s����q�₵�Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ƃ��������ŁA�u�M���ł�����ɂ����̉ߒ��ő����̐l���N�Q���������v�Əq�ׂ܂����B
���̂��ƁA�A�����J�̃g�[�}�X�O���[���t�B�[���h���A��g�́u�������������̓��V�A�̎x�z�ɏ]��Ȃ��l����肷��̂��ړI�ŁA���V�A�ւ̕����ɔ�������̂��B���������̏Z�����[���s�����Ƃ��Ă���v�Əq�ׁA���V�A��������ڎw���n��ŏZ�����[���s���A�s���̂悢���ʂ��o��悤�������Ă���Ƃ��������������܂����B
���̂����ŁA�����I�Ȉڑ��Ȃǂ͍��ۖ@��̐푈�ƍ߂ɓ�����Ƃ��ă��V�A�����������A���A�ɂ�钲���������悤����܂����B
����ɑ��A���V�A�̃l�x���W�����A��g�́A���n�ōs���Ă���̂͐q��ł͂Ȃ��o�^�̎葱�����Ɣ��_���A���Ă̓��V�A�����Ƃ��߂邽�߂ɐV���ȋU�����L�߂Ă���Ǝ咣���Ă��܂��B
���یo�ω�c�ɁA�v�[�`���哝�̂��o�d���A�E�N���C�i�N�U�ɂ��āu�匠���������ꂽ�v�Ƌ��������B
�����o�σt�H�[�����ɓo�d�����v�[�`���哝�́B
�E�N���C�i�ւ̌R���N�U��ɁA���V�A����P�ނ�����Ƃ��������Ƃ��i��҂���w�E����A�v�[�`���哝�̂́u�����͉�1���͂��Ă��Ȃ��B���ꂩ������͂��Ȃ��B�����̎匠���������ꂽ���Ƃ����v���v�Ƌ��������B
�܂��A�����A���̍ĊJ�ɂ��āA�v�[�`���哝�̂́A�u�E�N���C�i���o��87�ǂ̂����A���W�r�㍑�ɂ�2�ǂ����͂��Ă��Ȃ��B���W�r�㍑�ւ̗��肾�v�Ɖ��Ă�ᔻ�����B
3�N�O�̃t�H�[�����ɂ́A���{�W�O�����Q������ȂǁA�����̌o�ϊW��[�߂��ƂȂ��Ă������A����́A���{�͑�\�c��h�����Ȃ������B
���V�A�́A�E�N���C�i�ł̕������瓾�Ă��邱�Ƃ�������A�����Ă�����̂͂Ȃ��\�\�v�[�`������7���A����������B���V�A�͍��ۓI�ȉe���͉Ɍ����A�V���ȓ������ł���Ƃ����B
���V�A�@�v�[�`���哝�́u�������͉��������Ă��Ȃ����A���ꂩ����������Ƃ͂Ȃ��Ɗm�M���Ă���B
������x�����Ă��������\�\����͂悭�����邱�Ƃ����A�S���������B�R���s���Ƃ����_�ł́A��X�������n�߂��킯�ł͂Ȃ��B��������ɏI�~����łƂ��Ƃ��Ă��邾�����B�v
���V�A�ɓ��̃E���W�I�X�g�N�ŊJ�Â��ꂽ�A�����o�σt�H�[�����Ńv�[�`�����͂����q�ׂ��B���̈���ŁA���̕��������E�ƃ��V�A�̑o���Ɂu�����̓�ɉ��v�������N�������Ƃ̔F�����������B
7���A�C�������E�N���C�i�E�n���R�t�̏Z���ɂƂ��ẮA������̂ȂǂȂ��������肾�B���̏����́A�����������E��������Ă��ꂽ�B��������̂��j�ꂽ�ƌ�����B
�����암�ő����Ă���D�ҍ��ɂ��āA�E�N���C�i���ǎ҂̌��͌����B�����փ��\���ł͒����Ȑ��ʂ�����Ă���B
����́A5��SNS�ɓ��e���ꂽ����B�E�N���C�i�R���D�҂����Ƃ���w���\���n���̃r�\�R�s�����ŁA���m���E�N���C�i�������f����l�q���B�e�����Ƃ����B���C�^�[�͂��B�e���ꂽ���̂��m�F�ł��Ă��Ȃ��B
������V�A���́A�E�N���C�i���̔��������ނ��Ă���A���V�A�R���P�ނ��������͂Ȃ��Ƃ��Ă���B
�����e���h�̎��́u�h�l�c�N�l�����a���v�̊W�҂̓n���R�t�ƁA���V�A������������C�W�����Ƃ̒��Ԃɂ��钬�A�o���N���A�Ő퓬���������Ɩ��炩�ɂ����B���̒���������ƁA�C�W�����ɒ������郍�V�A�R�͐Ǝ�ɂȂ�Ƃ����B
���C�^�[�͐틵�Ɋւ�����̐^�U���A�Ǝ��Ɋm�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
���V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂�7���A�������Ǘ������邱�Ƃ́u�s�\���v�Ƃ��A�����Y�Ζ��ƃK�X�̗A�����i�ɏ����݂��鍑�ɑ��Ă͋������~����ƌx�������B
���������ɂ���A�̐��ق��A�A�W�A�⒆���A�A�t���J�Ƃ̊W������͍�����v�[�`�����́A�ɓ��E���W�I�X�g�N�ŊJ���ꂽ�����o�σt�H�[�����ʼn������A�u���V�A���ǂꂾ���Ǘ����������l�����悤�ƁA����͕s�\���v�ƌ����B�V�^�R���i�E�C���X�̐��E�I�嗬�s�ɑ����āA�u���������̐��ٔM�v�Ȃǂ����E�S�̂��������Ă���Əq�ׂ��B
�܂��A���V�A�Y�̐Ζ���K�X�̗A�����i�ɏ����ݒ肷�邱�Ƃ́u�S�������Ȍ��f���v�ƒf�����A�����̌o�ϓI���v�ɔ�����ꍇ�́u��؉����������Ȃ��v�Əq�ׂ��B
2���ɂ͐�i7����(G7)���A�E�N���C�i�ɐN�U���郍�V�A�̌R����̎�������f���邽�߂ɁA�����Y�Ζ��̗A�����i�ւ̏���ݒ�𑁋}�ɐi�߂���j�ō��ӁB�����ɃG�l���M�[����傫���ˑ����Ă��鉢�B�A��(EU)�ł�7���A���B�ψ���̃E���Y���E�t�H���f�A���C�G���ψ������A���V�A�Y�Ζ��ƃK�X�̗A�����i�ɏ����݂���悤�������ɒ�Ă����B
�o���̌����Ȃ��E���C�i�푈�\�\�B�v�[�`���I�哝�̂̎�ɂ���Z�̔w�i�Ƃ��āA�������@�ւɂ��I�n�y�ϓI�Ȑ틵���ʂ������������Ƃ��A�ă��V���g���E�|�X�g�����ʃ`�[���ɂ�钲���ł��̂قǖ��炩�ɂ��ꂽ�B�N�U�̓��������O�@�m���A���E�Ɍ����Čx�����Ă����đ��C���e���W�F���X�Ƃ̎��I����������ɂ��ꂽ�B
�������ȏ�����A�͊y�ϓI�Ȃ��̂���
���V���g���E�|�X�g���͐挎�A�E�N���C�i�푈�����V�A�ɂ��R���N�U�J�n����6�J���̐ߖڂ��}����̂��@��ɁA�x�e�����L�҂������A�ĉ��A�E�N���C�i�ȂNJe�����{�A�R�E���W�҂𒆐S�ɐ��͓I�ȃC���^�r���[�A�w�i��ނɒ���A���̕��͌��ʂ𐔉�ɕ�����X�I�ɕ����B
���̒��œ��ɒ��ڂ����̂��A��펞��̍��ƕۈ��ψ���(KGB)�ɑ���A�N���������̐푈���āE���s�ɒ��S�I�����������Ă����u�A�M�ۈ���(FSB)�v�̑��݂��B
FSB��2019�N�܂ŁA�����́u�E�N���C�i�ہv��30�l���x�̃X�^�b�t��i���Ă������A���̌�A�v���������v�ɏ��o���A���N2���̐N�U���O�ɂ́A160�l�ɑ啝�������ꂽ�B�E�N���C�i�e�B�ɐ�]�v���𑗂荞�݁A�����イ�ɃX�p�C�l�b�g���[�N�菄�炵���B
�v�[�`���哝�̂��ЂƂ��сu�E�N���C�i�N�U�v�����f����ƁAFSB�́A�[�����X�L�[������R�����ɐ��������Ă����X�p�C�Ԃ�ʂ��A���V�A�R���W�J���ׂ���̓I�N�U���A�\�z�����E�N���C�i���̔����Ȃǂɂ��āA�N���������ɏڍׂɂ킽����s���Ă����B
���̊j�S�����́u����������(�N�U��)�Z���Ԃ̂����ɕ���v�Ƃ������̂������B
�E�N���C�i���̎��X�ȃ��W�X�^���X�̉\���ɂ��ẮA�قƂ�nj��y���Ȃ������B
�[�����X�L�[�����́u�Z������v��O��ɁA�u���S�����v���������������A������x����E�N���C�i���̒��S�l�������܂ō����Ă����B���̒��ɂ́A���ăE�N���C�i�哝�̂߁A���ς�2014�N�Ƀ��V�A�ɓ��S�����r�N�g���E���k�R�r�b�`���A�E�N���C�i��}�}��Ńv�[�`�����Ƃ��e����[�߂Ă����V�������̃r�N�g���E���h�x�`���N���炪�܂܂�Ă����B����A�E�N���C�i�������̏��@�ւ͂��łɁA�ނ�ɂ��ẮuFSB�����ҁv�Ƃ��ă}�[�N���Ă����Ƃ����B
�������AFSB�{���́A���������E�N���C�i���@�ւ̌x���Ԃ�ɋC�Â����l�q�͂Ȃ��A���V�A�R�N�U�J�n�u�ŏI�i�K�̐����ԁv�ɂ́A��s�L�[�E���ӂɐ�������H��v�������̂��߂ɗp�ӂ����u���Z�p�A�p�[�g�ē��v��u���S�����v������ɑ��X�ƃ��X�N������������\�z�����v�������̂��߂̎���Ɋւ���ׂ��Ȏw�������n�ɕp繫�ɑ����Ă����B
���V���g���E�|�X�g�������肵���E�N���C�i���̋@�����t�@�C���ɂ��ƁAFSB�̃E�N���C�i�ɂ�����傽��C���́A�u�����̓�������v�u�[�����X�L�[�哝�̒Ǖ��v�u�e�I���������v�ɂ���A�����������ɐ���������v�������̊���Ɋ��҂��Ă����B���̂����̉��l���͎w���ɏ]���A�E�N���C�i���h�Ȃ̍��W�Q�ɏ��o�������A���ɂ́A�閧�H�쎑���𒅕�������A�N�U�J�n����Ɍ��C�����Ėd�����N�������肵���҂������B
FSB�̐틵���ʂ����S�̂Ƃ��āA�y�ςɖ��������̂ł���A�[�����X�L�[�哝�̂̋��x�Ȕ��R�p����A���哝�̂ɑ���E�N���C�i�����̉䖝���������Ԃ�Ɋւ��ẮA�قƂ�nj��y���Ȃ��A�푈������ɒ��ʂ��A���������邱�Ƃɂ��ẮA�v�[�`���哝�̂ɂ܂Ƃ��ȕ��グ�Ă��Ȃ������B
���Ȃ����`�����Ȃ������u���ۂ́v���
FSB���A�Ȃ����ʂ�����������ɂ��ẮA���܂��~�X�e���[�ƂȂ��Ă���B
���ɁA�N�U����ɐ旧���AFSB�͂Ђ����ɁA�E�N���C�i������ΏۂɍL�͈͂ɂ킽��Ǝ��̐��_���������{���Ă����B
����ɂ��ƁA�҂̑命�����u���V�A�ɐ�̂��ꂽ��O��I�ɒ�R����v�Ɠ����Ă���A���V�A�R��������҇��Ƃ��Ċ��}�����C�͓������瑶�݂��Ȃ������B�ɂ�������炸�AFSB�W�]�́u�N�U�����͎s�����犽�}����A���݂₩�ɐe�I�̐��������v�Ƃ̊y�Ϙ_�ɗ����Ă����B
������FSB�́A�u��s�L�[�E�Ɍ������d�����ɂ��A�[�����X�L�[�����͐����Ԃœ]������A�哝�͎̂E�Q�A�g���S�����邢�͒��O�̍��O���S�ɂ��A�����������A�V�̐��������\�ƂȂ�v���Ƃ�O��Ƃ����푈�v��܂ō쐬���Ă����B
�Ƃ��낪�A���ۂɂ́AFSB�v�����������V�A�R�����ƂƂ��ɃL�[�E�ߍx�ɔ��������_�ŁA�������E�N���C�i�R�̔����ɒ��ʁA�P�ނ�]�V�Ȃ������Ɏ������B
���V�A�R�Q�d�{�����(GRU)���قځAFSB�Ɠ��l�̕��N���������ɋ����Ă����Ƃ����B
���̂悤�Ƀ��V�A���̃E�N���C�i�N�U���Ɋւ���C���e���W�F���X�������ɊԈႢ���炯���������́A���̌�̐틵���@���ɕ�����Ă���B
���V�A�R�͎�s�L�[�E������f�O��A�����̍���]���A�E�N���C�i�암����ѓ������B�U���Ɏ�͂𒍓����Ă����B�����Ă�������́A�h�l�c�N�A�w���\���e�B��苒�����Ƃ݂��Ă����B
�������A�E�N���C�i�R�́u��s�����v�Ƃ������V�A�R���̏o�@�������������肩�A����8��29���A�암�Ȃǂł��̓y�D�Җڎw���җ�Ȕ����U���ɓ]���A���Ƀw���\���B���ӂł́A�W�����������l�K�̘͂I�R��������ɍ��Ȃ��ܕ��ܕ��̐킢�𑱂��Ă���B
�E�N���C�i�R�́A�����h�l�c�N�B�̂������̏W���ɂ��Ă��A���łɒD���Ɠ`������B����ɁA�[�����X�L�[�哝�͍̂���4���̉����Łu�����͂��ׂĂ̗̓y���������v�Ƃ����Əq�ׁA���V�A�����������암�N���~�A�̒D�҂ɂ����o���p���𖾂炩�ɂ����B
����̃E�N���C�i���̎����E�ۈ��̐����A�����͌��łƂ͒�������Ԃł���A���V�A���̃X�p�C�����E���A�������H�����ɂ��Ȃ����Ă��Ă����B�������A�Ē�������(CIA)�A�p�閧���(MI6)�Ȃǂ���̏��x���āA����7���ɂ́A�[�����X�L�[�哝�̐w���w���̉��ɁA���w�Z���ォ��̗F�B�������g���̃C�����E�o�J�m�t�������ǒ���˔@��C�A���ɂ����ʎ҂̈�|�ȂǁA���[�u���Ƃ��Ă���B
������ɂ��Ă��A�v�[�`���哝�̂́AFSB�ɂ��u�������S���������v�Ƃ������ʂ���^�ɎĂ������ʁA����A�܂������o���̌����Ȃ���������������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
���u���V�A�N�U���v��`��������������͉��^�I�ԓx
����ƑΏƓI�Ȋ���������Ă����̂��A�ĉp�����̃C���e���W�F���X�������B
���ɁACIA�𒆐S�Ƃ���đ��e���@�ւ́A���V�A�̐N�U�J�n�ɐ旧��1�N�ȏ�O����A�N���������A�R���A���@�֓����ɃX�p�C����荞�܂��A�v�[�`���哝�̂����X�ƃE�N���C�i�N�U���̏����ɏ��o���n�߂Ă��邱�Ƃ��@�m���Ă����B
�����āA2021�N10���ɂ́A�W�F�C�N�E�T���o���哝�̕⍲��(���ƈ��S�ۏ�S��)�A�E�C���A���E�o�[���YCIA�����炪�A�o�C�f���哝�̂ɑ��A����̓I�ȃ��V�A���̐N�U����̂��߂́u�E�H�[�E�v�����v�ɂ��ċɔ�u���[�t�B���O���s�����B
������āA�o�C�f���哝�̂͑����A���l����Ȃ�C���e���W�F���X�E�`�[�������X�N���ɔh���A�v�[�`���哝�̂ɒ��ږʒk������A�u�킪���́A���łɃN�����������������悤�Ƃ��Ă��邩�A���ׂĔc�����Ă���B�N�U�ɓ��ݐ����ꍇ�A(���V�A����)�[���Ȍ��ʂ��������Ƃ�m��ׂ����v�ƌx�����Ă����B
�������A�v�[�`���哝�̂͌����ɂ͂�������āA�N�U�v������s�������ƂɂȂ�B
���V���g���E�|�X�g���̒����ɂ��ƁA�đ����`�[���́A�v�[�`���哝�݂̂̂Ȃ炸�A�p���ƂȂǐ�������������]�ɑ��Ă��A���l�̎��O�u���[�t�B���O���s���A���ꂼ��̊O���`�����l���ʂ��A�N���������ɃE�N���C�i�N�U���v���Ƃǂ܂点��悤���������𑣂��Ă����B
���̂����A�p�����{��MI6��ʂ��A���V�A�̐N�U�v��ɂ��ĕđ��Ɠ��l�̏���������x�܂Ŕc�����Ă���A�đ��C���e���W�F���X���m�x�̍������Ɠ˂���������ŁA���̓��������ɑ��Ă��A���V�A�R�ɂ�鑁���E�N���C�i�N�U�ɂ��Čx�����Ăъ|���Ă����B
�Ƃ��낪�A�h�C�c�A�t�����X������]�́A���V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɒ��O�܂ʼn��^�I�ԓx�������Ă����B
���ɗ������ǎ҂́A�����ɓ��������ď��@�ւ̃g�b�v�ł���A�u�����E�w�C���Y���Ə���ɑ��A���ăW���[�W�E�u�b�V������������ɕđ��C���e���W�F���X�ɂ��u�C���N�j�ۗL�v���ŐU��ꂽ�ꂢ�o���ɂ����y������ŁA�u����̏ꍇ���A���V�A�����ۂɐN�U�Ɋ����ē��ݐ�Ƃ͎v���Ȃ��v�u�킪���̏��@�ւ����������������@�m���Ă��Ȃ��v�ȂǂƔے�I�����ɏI�n���Ă����Ƃ����B
�������A�Đ��{���ǎ҂������A�u���V�A�R�N�U�ؔ��v��M�����܂���̂ɍł�����Ă����̂��A�[�����X�L�[�哝�̈ȉ��A�����҂ł���E�N���C�i���{���������B
���ɍ�N11���A�u�����P�������������[�����X�L�[�哝�̂��p�X�R�b�g�����h�̃O���X�S�[�ɂЂ����ɌĂяo���A���V�A�R�N�U�J�n�����Ԃ̖��ƂȂ���邱�Ƃɂ��āA�N�������������̓����A���V�A�R�̍��������̓W�J�ȂǏڍׂɂ킽����������Ȃ���A���d�Ȍx���𑣂������A���̂Ƃ����A�哝�̂́u�ߋ��ɉ��x���A���V�A�͎����悤�ȃt�F�C���g�������Ă����v�ȂǂƏq�ׁA���M���^�������B
���̐��T��A�哝�̂͑��߂̃h�~�g���E�N���o�O���A�A���h���[�E�C�F���}�N��ȕ⍲�������V���g���ɔh���A�����ł��đ����炳��ɍ����ȃu���[�t�B���O�����������A����ł��E�N���C�i���{���́A����2��24���̐N�U�J�n�̒��O�܂ŐM���Ă��Ȃ������B
�đ���ǎ҂͐N�U��A�ŋ߂ɂȂ��āA�u�E�N���C�i�����@�ւɂ̓��V�A���̇����O�������������荞��ňÖĂ��邱�Ƃ͌��������Ȃ̂ŁA����ȏ�̊j�S�ɐG���@�������O���邱�Ƃ͔������v�u�������A�N�U��́A�킪���͂��ϋɓI�ɃE�N���C�i���ɏ�����悤�ɂȂ����v�ƌ���Ă���B
���̌㋎��7���A�[�����X�L�[�哝�̂��������@�ւ̃g�b�v�ł���o�J�m�t���ǒ��̉�C�A�ǒ��ȉ��̎v�������l�����V�ɓ��ݐ邱�ƂɂȂ������A����͌����ċ��R�̂��Ƃł͂Ȃ��A�ď��@�ւ̌㉟�������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
����ɂ߂�ĘI����̒��ɂ����āA����KGB�Ŋ��A������ő�̕���ɂ��ă��V�A�ō��w���҂ɂ܂ŏ��l�߂��v�[�`�������A����̃E�N���C�i�N�U���ł́A���ʓI�ɕđ��̃C���e���W�F���X�Ɉ����~����A�v���Ă����Ȃ����������������Ă��邱�Ƃ́A�܂��Ƃɔ���Ƃ����ق��Ȃ��B�@
�č��̃g�[�}�X�O���[���t�B�[���h���A��g��7���A���V�A�������ɃE�N���C�i�l�������A�s���Ă���Ƃ��A�푈�ƍ߂ɓ�����Ɣ����B
���A���S�ۏᗝ����Łu�����̍��̓��V�A�������̎x�z�ɏ\���ɏ]��Ȃ��A���邢�͓K�����Ȃ��ƌ��Ȃ��l������肷�邱�Ƃ��ړI���v�Əq�ׂ��B
���X�N�����܂ނ��܂��܂ȏ����̐���Ƃ��āA���V�A���ǂ��E�N���C�i�N�U���90����160���l�̃E�N���C�i�l���u�q�₵�A�S�����A(���V�A��)�����A�s�v���Ă���Ǝw�E�B7��������1800�l�ȏ�̎q�ǂ����E�N���C�i�̃��V�A�x�z�n�悩��A�s���ꂽ�Ƃ������������Ă���Əq�ׂ��B
���̏�Łu��ی�҂��̒n�����̎҂̗̓y�����A�s���邱�Ƃ͐푈�ƍ߂��\������v�Ƃ��A�u�ł́A�Ȃ��ނ�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ�����̂��H����͕����Ɍ����������̂��߂��v�Əq�ׂ��B
����A���V�A�̃l�x���W�����A��g�́A���̈��ۗ���͎��Ԃ̖��ʂŁA�u�E�N���C�i�Ƃ��̐����x�������J��L����U���L�����y�[���̐V���ȃ}�C���X�g�[��(�W��)���v�Ɣ��������B
�Đ푈������(ISW)��7���A���킪�����k�����n���L�E�B�ŃE�N���C�i�R�����V�A�R�Ɋ�P���s���A��400�����L���̗̓y��D�҂����Ƃ̕��͂\�����B�E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂�������̉����ŁA�u�n���L�E�B����悢�j���[�X�������Ă����v�Əq�ׂ��B
ISW�ɂ��ƁA�E�N���C�i�R��6�`7���A��ʂ̗v�ՃC�W���[���̖k���Łu���Ɍ��ʓI�Ȕ����v�����{�B���R�����V�A�̎x�z�n���ɓ���A���Ȃ��Ƃ�20�L���O�i�����͗l���Ƃ��Ă���B
���C�^�[�ʐM�ɂ��ƁA�퓬���������̂́A�C�W���[���k���Ɉʒu���钬�o���N�������ӁB�E�N���C�i�哝�̕{�̃A���X�g�r�b�`�ږ�́u���V�A�̓o���N��������͂���Ă���ƌ����Ă��邪�A(�E�N���C�i�R��)����ɐ�ɍs���Ă���v�Ǝw�E�B�u�N�s�����X�N�ւ̓��H�������v�Ƃ��āA���V�A�R�̕⋋�H�ɑ��đŌ���^�����Ƌ��������B
�[�����X�L�[���̓r�f�I�����Ńn���L�E�B�ł̏����Ɍ��y���A�u����(�D�҂���)�W���̖��O�������鎞�ł͂Ȃ��v�Ƌ�̓I�Ȓn���͖��炩�ɂ��Ă��Ȃ��B
�E�N���C�i�R�̃������[�E�U���W�j�[���i�ߊ���7���A���V�A��2014�N�ɕ��������암�N���~�A��8���ɔ��������I�R�̃T�L�R�p��s��ł̑�K�͔������A�E�N���C�i�R�̍U���ɂ����̂������ƍ��c�ʐM�ւ̊�e�ŔF�߂��B�U���W�j�[���́A�I�R�Ƃ̃~�T�C����͂̍����k�܂�Ȃ���u�푈�͉��N�ɂ��y�ԁv�Əq�ׁA�퓬������������Ƃ̌��ʂ����������B
�N���~�A�ł�8��9���̃T�L��s��ł̔����ȍ~���A�ʂȘI�R��s��ȂǂŔ����������������A�E�N���C�i�R�͊֗^�������ɔF�߂Ă��Ȃ������B�U���W�j�[���͊�e�Łu�~�T�C���ōU�������v�Ɛ��������B
�U���W�j�[���̊�e�́u2023�N�̌R�����̓W�]�v�Ƒ肵�������_���ŁA���V�A�Ƃ̒������O���ɁA�N���~�A�̒D�ҍ��ɂ��ӗ~���������B
�����A�˒�2000�L���E���[�g���̃~�T�C���ŃE�N���C�i�̓y�̂ǂ��ł��U���\�ȘI�R�Ƃ́u��͂̕s�ύt�v���ς��Ȃ��ꍇ�A���V�A���N����f�O����Ƃ͍l���ɂ����Ƌ��������B�E�N���C�i�R��8�����ɓ암�w���\���B�ȂǂŒ��肵�����]�U�������ł͐N���I���ɂ͎������߂Ȃ��Ƃ̔F�����������������B
����A�E�N���C�i�̃E�H���f�B�~���E�[�����X�L�[�哝�̂�7���̃r�f�I�����ŁA�����n���L�E�B�̕����W����I�R����D�҂����Ɛ錾�����B
�^�X�ʐM�ɂ��ƁA���V�A�̐����^�}������7���A�I�R��̒n��̃��V�A�ւ̕����Ɍ������Z�����[�ɂ��āA���V�A�́u��������̓��v�ɂ�����11��4���̎��{���Ă����B�Z�����[�͓�����5���̎��{����肴������Ă������A�ĎO�A��������Ă���B
���V�A�R�Ɏx�z����Ă���̓y�̒D�҂�ڎw���A�E�N���C�i�R���암�Ŕ��]�U�������߂钆�A�A�����J�̃V���N�^���N�̓E�N���C�i�R�������n���L�E�B�ł����V�A�R�̕����������߂��������o�Ă���ƕ��͂��Ă��āA�E�N���C�i�R�ɂ�锽���̓����������Ă��܂��B
�E�N���C�i�R�́A�암�w���\���B�ȂǂŔ��]�U�������߂Ă��܂����A�A�����J�̃V���N�^���N�u�푈�������v��6���A�E�N���C�i�R�������n���L�E�B�ł��������A���V�A�R�̕����������߂����Ǝw�E���܂����B
�����āu���V�A�R���n���L�E�B�ȂǓ�������암�֕�����W�J���������ƂŁA�E�N���C�i�R�̓n���L�E�B�Ŕ����̋@����Ƃ݂���v�Ƃ��Ă��āA���V�A�R���암�ł̖h�q�ɒǂ��钆�A�E�N���C�i�R�������ł������ɐ��������ƕ��͂��Ă��܂��B
�E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂�7���Ɍ��J��������Łu���T�A�n���L�E���炢���j���[�X���������B���܁A�W���̖��O�͖��炩�ɂ��Ȃ����E�N���C�i�R���������̏W����D�҂����v�Əq�ׂĂ��āA�E�N���C�i�R�ɂ�锽���̓����������Ă��܂��B
�܂��A�E�N���C�i�R�̃U���W�j�[���i�ߊ���7���A�n���̒ʐM�Ђւ̊�e�ŁA���V�A������I�ɕ��������N���~�A�̌R�̊�n�Ő挎9���ɋN���������ɂ��āA�E�N���C�i���ɂ��U�����Ə��߂Č��ɔF�߂܂����B
���̍U���Œ������郍�V�A�R�̕����̍q��@���j��܂������A�U���W�j�[���i�ߊ��̓N���~�A�ɂ��āA���V�A�R�̕����̓W�J��⋋�A����ɃE�N���C�i�ւ̋̋��_�ɂȂ��Ă���Ƃ��ăN���~�A��D�҂���d�v�����������܂����B
����A���V�A�R����������E�N���C�i�쓌���̃U�|���[�W�����q�͔��d���Ǝ��ӂł͈ˑR�Ƃ��ĖC���������Ă��܂��B
IAEA�����ی��q�͋@�ւ͐����ŁA�����Ƌ߂��̉Η͔��d�������ԗ\���̑��d�����A6���C���ɂ���đ��������Ɩ��炩�ɂ��܂����B
IAEA�́A���̑��d���̑����ɂ�蒼���Ɍ����̉^�]�ɉe���͏o�Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��܂����u�{�݂����炳���d��Ȉ��S�̃��X�N������ɂ��Ă���v�Ƃ��āA�����ւ̊O������̓d�͋����ɉe����^����R���s������߂�悤���߂Ă��܂��B
�p���h�Ȃ�8���܂łɃE�N���C�i��Ɋւ����V�A�R�͐퓬���ɂ��m�C�̒ቺ��w�������̗���ɈˑR�Y�݁A���^�x�����̖��������Ă���Ƃ̕��͌��ʂ��������B
���Ȃ͂r�m�r��̐����ŁA���V�A�R�̓E�N���C�i�֑��荞���͂Ɋ�{�I�ȕ������p���I�ɕ⋋�o���Ȃ��ł���Ǝw�E�B����畨���ɂ͐����A����A�H���Ȃǂ��܂܂�A���^������������Ƃ����B���̌���x���Ԑ��̕s�������͂̑唼���P���n��Ȏm�C�ɂȂ����Ă���̂͂܂��ԈႢ�Ȃ��Ƃ������Ă��B
���V�A�͎��R�����ɒʏ�A�u�K�x�Ȑ����v�̊�{���╡�G�Ȏd�g�݂�����l�X�ȃ{�[�i�X����蓖���x�����Ă���Ǝw�E�B
���̏�ŃE�N���C�i�ł͑����Ȋz�Ƃ݂���u�퓬�{�[�i�X�v�����^����Ă��Ȃ��[���Ȗ�肪�����Ă���\��������ƌ��y�B�R���̂������d���A�E�N���C�i�N�U���u���ʌR�����v�Ə̂���ٗ�̖@�I�Ȉʒu�Â��⏭�Ȃ��Ƃ��i�ߊ����ł̉��E�̎����w�i�ɂ��邾�낤�ƕ��͂����B
�ĉ����ǎ҂͐挎���{�A�E�N���C�i�R�̓��V�A�R�̍U���ɑ��݊p�̏�����ł���Ƃ݂���Ƃ̐�ǔ��f�������Ă����B�ĉ��������n������[����̈З́A�D���Ȏm�C�̈ێ��A�����̒c���́A�@�q�Ȑ�p�̗p��D�ꂽ�Ջ@���ς��Ȃǂ����̗v���Ƃ����B
�č��h���ȓ��ǎ҂́A�E�N���C�i�N�U�Ń��V�A�R������������҂�7�`8���l�Ɛ��肵�Ă���B
���̒��ŃE�N���C�i�R��Ǔ��ǎ҂�8���܂łɁA���V�A�R�̐V���ȕ����̓�����11�����{�܂ŕs�\�̏�Ԃɂ���Əq�ׂ��B�P�������E�ƌR�l����i�̕s���������ɂ����B
�V���ȕ����ɂ͋��\�A����̕�������Ă����Ă���Ƃ��A�����̏ꍇ�A����ɂ͕s�K�i�Ȏ�ނƂ������B�����ǎ҂͂r�m�r��ŁA�E�ƌR�l�̕�[�����ƂȂ��Ă���A���̎��Ԃ����邽�߂̌P���ɂ�3�`4�J���v����Ƃ��q�ׂ��B
����Ƀ��V�A�R�͍��N��2�A3�����ɔ������K�͂ȕ��͑����Ő�[�I�ȑ����̂قڑS�Ă������Ă���ɂ���Ƃ������B���̂��ߐV���ȕҐ������ɂ͋��\�A����̌Âт����킪�^�����Ă���Ƃ��咣�����B�R������4���͐��ɓ����o�����Ԃɂ͂Ȃ��Ƃ��A�C���Ȃǂ��K�v�Ƃ������B
�Đ��{��8���A���V�A�̐N�U����E�N���C�i�ɑ��A�֒e(��イ����)�C�Ȃ�6��7500���h��(��970���~)�ɏ��lj��R���x�������{����Ɣ��\�����B
���C�h�E�I�[�X�e�B���č��h�����́A�h�C�c�쐼�������V���^�C���ɂ���ċ�R��n�ŊJ���ꂽ�E�N���C�i�h�q�Ɋւ���W����ɏo�ȁB�u�����͐��ł̋��ʂ̓w�͂̐��ʂ������Ă���v�Əq�ׁA�E�N���C�i�̓��V�A�R�ɒ�R���Ă���݂̂Ȃ炸�A�암�ł͔��]�U���ɏo�Ă���Ƃ̌������������B
�lj��x���ɂ́A105�~���֒e�C��A�W�I�𐳊m�ɍU���ł���U���^���A�����P�b�g���˃V�X�e���̖C�e�Ȃǂ��܂܂��B
�č����ŋ߃E�N���C�i�ɋ��^��������ő傫�Ȑ�ʂ������Ă���̂́A���@�����P�b�g�C�V�X�e���u�n�C�}�[�X�v�ŁAGMLRS�̖C�e�͍ő�80�L�����ꂽ�W�I�𐳊m�ɍU���ł���B
�����A�E�N���C�i�����^����悤�v�����Ă���˒�300�L���̒n�Βn�~�T�C���uATACMS(�G�[�^�N���X)�v�ɂ��ẮA�~�T�C�������V�A�̓��ɒ��e���Đ���g��̌��O������Ƃ��āA�Đ��{�͋��^������ł���B
�E�N���C�i���{�͐��������ɑ��A��苭�͂ȕ���̋��^���d�˂ėv���B�E�N���C�i�̃f�j�X�E�V���~�n����4���Ƀh�C�c��K�₵���ۂ��A���߂ĕ���̋��^�����߂Ă����B
���B�A��(�d�t)�̎��s�@�ցE���B�ψ���̃E���Y���E�t�H���f�A���C�G���ψ�����7���A�d�t����ɗA������郍�V�A�Y�V�R�K�X�̉��i�ɏ����ݒu����Ă𖾂炩�ɂ����B�K�X���i�̍����Ɏ��~�߂�������ƂƂ��ɁA���V�A�̃G�l���M�[�����ɑŌ���^����̂��_���̐��ق̈�ƂȂ�B
����ݒu�ẮA9���ɊJ�����d�t�e���̃G�l���M�[����ŋ��c�����B�t�H���f�A���C�G�����͋L�Ғc�Ɂu�E�N���C�i�ł̔Ȑ푈�̎������ł��郍�V�A�̎����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�`�e�o�ʐM�ɂ��ƁA���V�A�̃v�[�`���哝�̂�7���A�d�t�̔��\�ɐ旧���āu(����ݒu�Ă�)�ɂ߂ċ����Ȍ��f���v�Əq�ׂ��B�����������ꍇ�ɂ́A���B�ւ̃K�X���������S�ɒ�~����l�����������Ă���B����ݒu���K�X�̋����s���ɂȂ���A����Ȃ鉿�i�������������ꂪ����B
���B�ς́A�Đ��\�G�l���M�[�⌴���Ȃǂ̔��d�֘A���Ǝ҂ɂ��āA���ȏ�̗��v�ɑ��Ēlj��ېł���Ă����炩�ɂ����B�K�X���i�������d�C�����S�ʂ̒l�グ�ɂȂ���A�Ǝ҂����b���Ă��邽�߂��B�ېłœ��������͊e���̊�Ƃ␢�тɊҌ�����B
���V�A�̃v�[�`���哝�̂�7���A�����S�����o�R���Ē����ɓV�R�K�X���������邽�߂̐V���ȑ�K�̓C���t���v��ɂ��ċ��c���Ă���Ɩ��炩�ɂ����B
�v�[�`�����͍��c�e���r�ŕ��f���ꂽ�����S���̃I���[���G���f�l�Ƃ̉�k�Łu�����S���o�R�Œ����Ƀ��V�A�Y�V�R�K�X�K�X���������邽�߂̎�v�ȃC���t���v���W�F�N�g�̉\���ɂ��ċ��c���Ă���v�Əq�ׂ��B
�v�[�`�����͂��̂ق��A���V�A�̍��c�Ζ���Ѓ��X�l�t�`�������S�����{�ƐΖ����i�̋��������鋦�͂̊g��ō��ӂ������Ƃ����炩�ɂ����B
����]�̓��V�A�ɓ��E���W�I�X�g�N�ŊJ�Â��ꂽ�����o�σt�H�[�����ʼn�k�B�v�[�`�����͓��t�H�[�����ōs���������ŁA���V�A�Y�K�X�ւ̏�����i�ݒ���Ăт����Ă��鉢�B�́u�������v�Ƃ��A���V�A�Y�G�l���M�[�ɏ�����i���ݒ肳���A�K�X�E�Ζ��������~����ƕ\�����Ă���B
2019�N���ɉғ��J�n�������V�A�ƒ��������ԃK�X�p�C�v���C���u�V�x���A�̗́v�̔N�ԗA���\�͂�610���������[�g���B���V�A���c�K�X�v�����́A�����S�����o�R���ă��V�A�Y�V�R�K�X�𒆍��ɗA������V���ȃp�C�v���C���u�V�x���A�̗�2�v���݂̉\�������N���O���猟�����Ă����B
�K�X�v�����ɂ��ƁA��Ă���Ă���u�V�x���A�̗�2�v�̔N�ԗA���\�͂�500���������[�g���ƁA�h�C�c�����ɋ�������u�m���h�X�g���[��1�v��������B�����A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�����B���������V�A�Y�G�l���M�[�ւ̈ˑ��x��ቺ�����钆�A���������̐V���ȃp�C�v���C���̓��V�A�̏d�v�Ȏ������ɂȂ�Ƃ݂��Ă���B

�č��̃u�����P������������8���A�E�N���C�i�̎�s�L�[�E��K�₵�A�E�H���f�B�~���E�[�����X�L�[�哝�̂Ɖ�k�����B�E�N���C�i����ӂ�18�����ɑ��A22���h��(��3100���~)�̒����I�Ȉ��S�ۏ�x�����s�����j��`�����B
�E�N���C�i�ւ̌R���x�����߂����ẮA�h�C�c�쐼���̃����V���^�C���ċ�R��n��8���A�č��̃I�[�X�e�B�����h��������ɂ��鍑�ۉ���J���ꂽ�B�I�[�X�e�B�����́A22���h���̎x���Ƃ͕ʂɁA��イ�e�C��b�ԂȂ�6��7500���h��(��970���~)�����̒lj��R���x�����E�N���C�i�ɑ��čs���ƕ\�������B
��̊J�Â�5��ڂŁA�k�吼�m���@�\(�m�`�s�n)�������Ȃǖ�50�����̊t���炪�Q�������B
���V�A�̑E�N���C�i�푈�́A�E�N���C�i���ɂ킸���ɗL���ȓW�J�ɂȂ����悤���B���V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂��V���ȋ����������Ă��邱�ƂƁA���V�A���]���͕�������^���Ă������X����̕��풲�B�ɖz�����Ă��邱�Ƃ́A�����������̒��B
���V�A��2���̓d����킪�����̏����ŏI���Ɨ\�z���Ă������A�����͂�������ԂƂȂ�A�E�N���C�i�͌��݁A���V�A�̕������j�A�̓y�����߂����߂ɓ암�Ŕ��]�U���ɏo�Ă���B���V�A�͌R�������̔��~������������Ȃ��Ȃ����B���ɃX�}�[�g����̕�[�ɋ�J���Ă���̂́A���������ɂ�鐧�قŁA�ŐV����Ɏg����R���s���[�^�[�`�b�v�Ȃǂ̕��i�̑��A�o���֎~����Ă��邽�߂��B
�������āA���E�ň��̂Ȃ炸�ҍ��Ƃł���C�����Ɩk���N��ɂ����A���V�A���{�́u������v���n�܂����B�ď�ǎ҂��5���A�u�[���ȋ����s���v���ɘa���邽�ߖk���N�����V�A���x�����Ă���ƋL�Ғc�Ɍ�����B����́A�C���������V�A���{�Ƀh���[��(���l�@)���������Ă���Ƃ����挎�̕ɑ������̂��B�卑�̒n�ʂ��咣���鍑�͒ʏ�A�K�v�Ƃ��鍑�X�ɕ������邪�A���̋t�͂Ȃ��B
�v�[�`������7���A���V�A�̃G�l���M�[�A�o������Ɍ��炷�\�������������ق��A���C��ʂ����E�N���C�i�Y�̍����A�o��e�F����Ƃ����A���炪�����ӂ̔j�����������Ȃ��p�����������B���̂��Ƃ�����A�v�[�`�����̕s���̓x�����𑪂邱�Ƃ��ł���B���V�A�͍ŋ߁A�p�C�v���C���u�m���h�X�g���[��1�v��ʂ������B�ւ̓V�R�K�X�������~�����B�v�[�`�����͋�����~���������āA���̑ΏۂɐΖ��ƐΖ������i��������Ƃ̋������������B�����͊����~�Ɍ��������B�̎w���҂ɂ���Ȃ鐭���I���͂����������ƍl���Ă���B�������A���̂悤�ȋ�����~�͂ǂ�Ȃ��̂ł���A���ƂȂ郍�V�A���{�̎����ɂ��Ō���^����B
�����Ɋւ��Č����ƁA�v�[�`�����͍��āA���V�A�����E�̐H���s���̐ӔC�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA�E�N���C�i����̗A�o��e�F���鍇�ӂ���������B������7���A�����������r�㍑�ւ̐H�������������ɁA���܂��܂ȖʂŎ��������𗘂��邽�߂ɍ��ӂ𗘗p���Ă���̂́u�����炳�܂ȍ��\�v���Ɣ����B
�������A�v�[�`�����͐H���̎s�ꂪ�O���[�o���ł��邱�Ƃ�A�����A�o���ӂ̖ړI�̈���A�����g���ʂ����H�����i�̉����������������Ƃ����Ă���B���i���ቺ����A�n�������X�ɂ����b���y�ԁB�v�[�`�����̓E�N���C�i�Y�����̗A�o��{���ɒ�~������A���ꂪ�����N�������ɂ��āA�ӔC�����邱�ƂɂȂ�B
�v�[�`�������E�N���C�i�Y�����̗A�o��{���ɑj�~�����ꍇ�ɂ́A�č��̓v�[�`�����ɑ��A�E�N���C�i�Y�����A���D�̊͑D�ɂ���q���A�L�u�A���������������邾�낤�ƌx�����邱�Ƃ��\���B���l�̌v��́A1980�N��ɃC�����̋��Ђւ̑�Ƃ��ăy���V���p����Ζ����^�яo���^���J�[����q����Ƃ����`�ŁA���{���ꂽ���Ƃ�����B���V�A�R���l���ƕ����̕s���ɋꂵ�ޒ��A���a�I�Ȍ�q�C���𐋍s���Ă��鐼�������̑D���ւ̈Њd�ɁA�v�[�`���������C�ɂȂ�Ƃ͍l�����Ȃ��B
�E�N���C�i�ł̐푈�̏I���܂ł̓��̂�͉����B�����ăv�[�`�����́A�c�s�s�ׂƋ������G�X�J���[�g�����邩������Ȃ��B���������V�A���{�̂��瑛���Ԃ�́A�E�N���C�i���̒�R�ƃE�N���C�i�ւ̊O���̎x���̌��ʂ��\��Ă��邱�Ƃ������Ă���B�v�[�`�������N�U���p������Ȃ�A�E�N���C�i�ƍőO���Ɉʒu����k�吼�m���@�\(NATO)�����ɑ��邻�̍������~�߂邽�߂ɂ́A�ŐV����̋����𑱂��邱�Ƃ��ɂ߂ďd�v�ƂȂ�B�E�N���C�i�����łȂ��A���V�A���܂��ꂵ���ɂ���B�@
�E�N���C�i�R�͓암�ɑ����A�����̃n���L�E�B�ł����V�A���x�z���������̏W���̒D�҂ɐ��������Ɣ��\���Ă��āA���Ă̌R���x�����Ȃ��甽�]�U�������߂Ă��܂��B
�E�N���C�i�R�́A�w���\���B�ȂǓ암�ɑ����āA�����n���L�E�B�ł������Ɍ������R�����𑱂��Ă��āA�R�̎Q�d�{����8���A���V�A������̂����n��ɍő��50�L���U�ߓ������ق��A20�̏W������������Ɩ��炩�ɂ��܂����B
�܂��A�����h�l�c�N�B�̃N���}�g���V�N�ߍx�Ȃǂł��A���V�A����̂����n��ɍU�ߓ������Ƃ��Ă��āA���Ă̌R���x�����Ȃ���A���]�U�������߂Ă��܂��B
�[�����X�L�[�哝�̂�8���A�u9���ɓ����Ă��炱��܂łɁA���킹��1000�����L�����[�g���ȏ�ɋy�ԗ̓y����������v�Ɛ�ʂ��������܂����B
���V�A�R���A�암�̖h�q�̂��ߓ������畔����W�J�����钆�A�E�N���C�i�R�̔����ɂȂ������Ǝw�E����Ă��āA�A�����J�̃V���N�^���N�u�푈�������v��8���A�u�E�N���C�i�R���n���L�E�B�̔����ɐ����������Ƃɑ��A���V�A���h�Ȃ͒��ق��Ă���v�ƕ��͂��܂����B
���V�A���h�Ȃ�8���A�����̃h�l�c�N�B��n���L�E�B�A����ɓ쓌���U�|���[�W���B�ȂǂŁA�E�N���C�i�R�̕����e��ɂ�j���Ƃ��Ă��܂����A�R�̍��w���ɂ��āA���V�A���̈ꕔ�̌R���]�_�Ƃ�����^�⎋���鐺���������Ă��܂��B
�E�N���C�i�R�́A�����n���L�E�B�Ń��V�A���x�z���Ă��������̏W���̒D�҂ɐ��������Ɩ��炩�ɂ��A���]�U���𑱂��Ă��܂��B�����������A��s�L�[�E��K�₵���A�����J�̃u�����P�����������̓E�N���C�i�Ȃǂɑ��A���{�~�ɂ���4000���~�K�͂̌R���x����\������ȂǁA����Ȃ�̓y�D�҂Ɍ����Ďx������p�����������܂����B
�E�N���C�i�R�̎Q�d�{����8���A����܂łɓ����n���L�E�B�ȂǂŃ��V�A�����x�z���Ă���20�̏W����������A700�����L�����[�g���ȏ�̗̓y��D�҂����Ɩ��炩�ɂ��܂����B
�܂��A�����h�l�c�N�B�̃N���}�g���V�N�ߍx�Ȃǂł��A���V�A����̂����n��ɍU�ߓ������Ƃ��Ă��܂��B
�[�����X�L�[�哝�̂�8���A�u9���ɓ����Ă���A����܂łɍ��킹��1000�����L�����[�g���ȏ�ɋy�ԗ̓y����������v�Əq�ׁA���]�U�����������Ă��܂��B
�����������A�A�����J�̃u�����P������������8���A��s�L�[�E�����O�ɔ��\���邱�ƂȂ��K�₵�A�[�����X�L�[�哝�̂Ɖ�k���܂����B �u�����P�������́A�E�N���C�i�R��������암�Ŕ��]�U�������߂Ă��邱�Ƃ�O���Ɂu�����d�v�ȋǖʂ��B���V�A�̌R���N�U��6�����ȏ㑱���Ă��邪�A�E�N���C�i�R�̔����͍��������A���ʂ��グ�Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁA�C���Ɏg����イ�e�C��A���@�����P�b�g�C�V�X�e���̃��P�b�g�e�ȂǁA���킹��6��7500���h���A���{�~�ɂ��Ă��悻970���~�����̐V���ȌR���x�����s���Ɠ`���A����Ȃ�̓y�D�҂Ɍ����Ďx������p�����������܂����B
����ɑ��A�[�����X�L�[�哝�̂́u�A�����J���A�E�N���C�i�ƂƂ��ɂ���Ƃ������ɏd�v�ȃV�O�i�����B�����ɂƂ��ẮA�̓y�����߂���Ƃ����ۏ��v�Ɖ����܂����B
�܂��A�u�����P�������́A���̎x���Ƃ͕ʂɁA���V�A�̋��Ђɂ��炳��Ă���Ƃ��āA�E�N���C�i����̃����h�o�Ȃ�19�����ɑ��A22���h���̌R���x�����s���Ɣ��\���A����\�������x���z�̑��z�͓��{�~�ɂ���4000���~�K�͂ɏ��܂��B
���V�A�哝�̕{��9���A�O���Ɏ��������p���̃G���U�x�X�����̑��V�ɃE���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂��Q��\��͂Ȃ��Ɣ��\�����B
�h�~�g���[�E�y�X�R�t���͓����̒��L�҉�ŁA�u���V�A�l�͏����̉p�m�h���Ă����v�Ƃ����A�����̑��V�ւ̃v�[�`�����̎Q��́u��������Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�u�����ւ̃G�l���M�[�������ꍇ�ɂ���ẮA���S�ɒ�~����v�\�\�B�E�N���C�i�N�U�������ĉ��ĂƂ̊W�������������V�A�̃v�[�`���哝�̂ɂ�邱�����������́A���V�A�ɂƂ��Ă���n�̌��ƂȂ鋰�ꂪ����B
���B�A��(�d�t)��7���A���V�A�Y�K�X�̉��i�ɏ����݂���Ă�\���B���̒��O�Ƀv�[�`�����́A����������������������Ȃ烍�V�A�͋������~�߂�Ƃق̂߂����u�����ɂł���̂́A���V�A�̗L���Ȗ��b�̂悤��(�X�Ɍ����J���ĐK���ŋ���ނ��Ă���)�I�I�J�~�ɐK��������ƌx�����邱�Ƃ݂̂��v�ƌ����������B
�T�E�W�A���r�A�Ɏ������E��2�ʂ̎Y�����ŁA�����ɐ��E�ő�̓V�R�K�X�A�o���ł��郍�V�A���牢�B�ւ̃G�l���M�[�������r�₦��A���E���̃G�l���M�[�s��͈�w�������A���ۉ��i�͂���ɒ��ˏオ����Z���傫���B
���V�A���c�K�X��ЁE�K�X�v�����̃~�����ō��o�c�ӔC��(�b�d�n)��8���A���B�̃K�X���i�͍���1000�������[�g��������4000�h���܂ō�������\��������Ɣ������Ă���B7�����_�̉��i�͖�2200�h���������B
�����A�d�t���G�l���M�[���B�ŒE���V�A���v������̂܂ܐ��i���Ă����A���V�A���Ɏ���邱�ƂɂȂ�B
8��30���Ƀ~�V���X�`������Â�������J��ɒ�o���ꂽ�A���V�A�̃G�l���M�[�헪���܂Ƃ߂������ɂ́A�E�N���C�i�̐푈�ɕt������G�l���M�[�Z�N�^�[�́u�����X�N�v�̊T�v���L����Ă���B���C�^�[���S�̂̓��e���m�F���Ė��炩�ɂȂ����B
�u2030�N�܂ł̐V���ȏ���ł̎��Ɗ����̐헪�I�������ɂ��āv�Ƒ肳�ꂽ�����́A�O���ڋq�ւ̋��������炷�ƒቿ�i�ɐݒ肵�������̔��̑�����A�o�����ŕ₤�Ƃ����]���̎d�g�݂������Ǝw�E�B���̌��ʂƂ��āA�e�n��ł̃K�X�J���ɕK�v�Ȏ������s�����������Ƃ̌������������B
�������͂d�t��2027�N�܂łɃ��V�A�Y�K�X�A������߂�ƁA1)30�N�܂łɔN�Ԃ�4000�����[�u��(65��5000���h��)�̌����ɂȂ肩�˂Ȃ��A2)27�N�܂łɃK�X�A�o���N��1000���������[�g�������Ă����������Ȃ��\�\�ƕ��́B���̏�ŁA30�N�܂ł̃��V�A�̃K�X�Z�N�^�[���������͖�410���h���ڌ��肷��Ƃ݂Ă���B
���G�l���M�[����D
���V�A�ɂƂ��ĉ��B�ւ̐Ζ��ƃK�X�̔̔��́A�����Ǝ�ȊO�ݒ��B���������B�����āA1999�N���Ƀ{���X�E�G���c�B��������哝�̂̍��������p�����v�[�`�������ڎw���Ă����̂́A�����̃G�l���M�[�������D�Ƃ��āA���\�A�����Ɏ�܂������V�A�̗͂����߂����Ƃ������B
����̃E�N���C�i�����鉢�ĂƂ̑Η��ǖʂł��ĂуG�l���M�[��ɊO����W�J����v�[�`�����́A���̐푈�Ń��V�A�͐V���ȓ��ɓ��ݏo���Ă���̂ʼn��������Ă��Ȃ����A�ނ��듾�����Ă���Ƌ��C�̌��t���Ă���B
�v�[�`�������J��Ԃ��Ă���̂́A���B�����V�A�Y�Ζ��E�K�X�������Ȃ��̂Ȃ�A���邢�͉��i�ɏ����ݒ肷��̂ł���A���V�A�͒�����C���h�Ɏ�v�ڋq���ւ���Ƃ������b�Z�[�W���B
�����A��������s���邽�߂ɂ́A�����Ɍ������p�C�v���C���̌��݂����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ɠ������͎w�E����B
���݁A���V�A���璆���ւ̎�v�K�X�p�C�v���C���́u�p���[�E�I�u�E�V�x���A1�v�̂݁B���N�S�̂Ō����܂��A���ʂ�160���������[�g���ƁA�ʏ펞�ɖ��N���B�ɗA������ʂ�11���ɂƂǂ܂�B
���}�������ɂ���{�o�l���R�{�A�n���U�x�C���K�X�c���璆���ɂȂ���u�p���[�E�I�u�E�V�x���A2�v�͂܂��������Ă��Ȃ��B
���ň��V�i���I
���B�����V�A�ɑ���G�l���M�[�̒��B���������ꂽ�ꍇ�A���V�A�͑����傫�Ȏ����ɒ��ʂ���B
���������`���ň��V�i���I�Ɋ�Â��ƁA27�N�܂łɉ��B�����̓��V�A�Y�Ζ��ւ̈ˑ������S�ɒf���邱�Ƃ��\�ŁA�u�h���W�o�v�Ζ��p�C�v���C���ƃo���g�C���݂̍`���[���ȑŌ�����B
�h���W�o�͍�N3600���g�����^�сA�o���g�C���݂̍`��2019��21�N�ŔN��6000����8000���g���̌�������舵���Ă����B
�������ɂ��ƁA���V�A�̃G�l���M�[�ƊE�͍̌@�̓���Ȃǂɔ������Y�R�X�g�����Ƃ��������̉ۑ�ɁA�A�o���ւ��R�X�g�ƃ^���J�[���v�̍��܂�Ƃ����V���ȋt���������Ƃ����B
�܂��A���ɉt���V�R�K�X(�k�m�f)�ƐΖ������̕���ł́A�����̋Z�p�����p�ł��Ȃ��Ȃ邱�ƂŁA���V�A�̃G�l���M�[�ƊE�͌������I���𔗂��邾�낤�B
�������́A�k�m�f���Y�v���W�F�N�g����Z�p�ʂ̃p�[�g�i�[���P�ނ���ƁA�V�K�{�݂��ғ�������^�C�~���O���x���ƌx���B�Ζ����i�A�o�͍�N�̖�55�������A8000���g�������������A����������25��30���ቺ���č��������̏\���ȃK�\�������Y���m�ۂł��Ȃ��Ȃ�A�R�����i�������グ��ƌ��O���Ă���B
���̂Ƃ���͎��Ƃ������ŁA���N1��6���̗��v��2��5000�����[�u���̉ߋ��ō��������K�X�v�������A�����I�ɂ͈É_���������߂�B
�A�i���X�g�ɂ��ƁA���E�S�̖̂����ʂ̖�15���A���V�A�S�̂�68�������铯�Ђ́A������K�X�c�̑��Ƃ��~���邩�A�����p�K�X�̔R�ď������K�v�ɂȂ邩������Ȃ��Ƃ����B

���V�A�̃v�[�`���哝�̂�9���A���V�A���N����3000���g���̍�����A�o���錩�ʂ��ŁA�������5000���g���Ɋg�傷��p�ӂ�����ƕ\�������B
�v�[�`�����͈��S�ۏ��c�ōs�����e���r�����ŁA���A�ƃg���R�̒���ɂ���Ē��������E�N���C�i����̍����A�o�ĊJ�Ɋւ��鍇�ӂɂ��āA���V�A�␢�E�̒Ꮚ�������s���v�����Ă���Ƃ����l�������߂Ď������B
7���ɒ����������ӂ́A���V�A��E�N���C�i�������ō��ӂ��Ȃ���A11���Ɏ�������B
�v�[�`���哝�̂�7���A�E�N���C�i�Ƃ̍������ӂ��C�����A������A���ł��鍑�𐧌��������Ƃ̈ӌ��������Ă����B
���v�����[�O�^�Y������v�[�`���E���V�A��
���V�A(�I)��V.�v�[�`���哝��(69��)��D���Ƃ���u�v�[�`���E���V�A�v���́A�ړI�n�s���̗��j�Ղ̂Ȃ��q�C�ɏo�����ʁA���V�A�̍��Ɛ헪�ƃG�l���M�[���Y�����Ă��܂��B
���\�A�M�������āA���j�Ղ̂Ȃ��q�C�ɏo���u�v�[�`���E���V�A�v�����ǂ��ɓ����E�Y������̂�����ł͕s���ł��B
�������A���݂䂭�D����^����ɑl�������o�������Ƃ��A�l�͊��ɓ����n�߂Ă��܂��B
�Y���̓r���ŐH�����s����\��������A���ʂ��邩�A���l���ɕY�����邩������܂���B
��̓o�E���e�B���̂悤�ɁA�߂������A�D���������N���邱�Ƃ����蓾�܂��傤�B
�v�[�`���V���V�A�哝�̂�2000�N5���ɒa���������A�ނ̃X���[�K���͋������V�A�̎����Ɩ@�̓ƍقł����B
���V�A�̑哝�͎̂アB.�G���c�B���哝�̂��狭���v�[�`���哝�̂ɑ��A���V�A�����̓v�[�`���哝�̒a���Ɋ��҂��Ă��܂����B
�����T�n����(������)�ɒ��݂��āA����Łu�T�n����-1�v�v���W�F�N�g�ɏ]�����Ă����M�҂��A�V�哝�̓o��ɂ�胍�V�A�͕ς�邾�낤�Ɗ��҂��Ă���܂����B
����22�N���2��24���A���V�A�R�̓E�N���C�i�ɌR���N�U�J�n�B
���ʂƂ��āA�ア���V�A�̎����Ƒ哝�̌l�ƍق̓������ł���A�v�[�`���哝�͎̂��烍�V�A�̍��v��ʑ����邱�ƂɂȂ�܂����B
�������j�̔���ƌ��킸���āA���ƌ����܂��傤���B
�����V�A�̍��v��ʑ�����v�[�`���哝��
�{�e�ł́A�v�[�`���哝�̂������Ƀ��V�A�̍��v��ʑ����Ă���̂��A���V�A�͍���ǂ��Ȃ�̂��A�M�҂̓ƒf�ƕΌ��Ƒz���������ė\�����Ă݂����Ǝv���܂��B
�M�҂́A�v�[�`���哝�̂�3�{�̃��r�R�����n�����ƍl���܂��B
1�{�ڂ̃��r�R����̓��V�A�E�E�N���C�i�����A2�{�ڂ̃��r�R����͓V�R�K�X�p�C�v���C��(P/L)�𐭎��̓���Ɏg�������ƁA3�{�ڂ̃��r�R����͑哝�̗߂ɂ�胍�V�A�A�M�@��j�������Ƃł��B
���\�A�M�ƐV�����V�A�A�M�͉��B���K�X���v�ƂɂƂ�M���ɑ���V�R�K�X�������Ƃ��āA�ߋ�50�N�ȏ�̒����ɂ킽��A�V�R�K�X�����苟�����Ă��܂����B
�������A����͓��R�ł��B���Ɏ�v�O�݊l�������Ȃ��䂦�A�M���ɑ���Ζ��E�K�X�������Ƃ��Ă̒n�ʊm���͋��\�A�M�E�V�����V�A�A�M�ɂƂ荑�v���̂��̂ł����B
�Ƃ��낪�A�I�v�[�`���哝�̂͋��\�A�M�E�V�����V�A�A�M���ߋ�50�N�ȏ�̒����ɂ킽��c�X�ƒz���Ă����M��������ɂ��đr���B
�����ʂ�A�u�z��\�N�A�������v�ƂȂ�܂����B
���ɁA�v�[�`���E���V�A���̋ߖ�����\�����܂��B
�v�[�`���哝�̂ɑ����͂��|�����鑤�߂͂��炸�A�������W�̐g�������M�p���Ă��Ȃ��ƌ����Ă��܂��B
�䂦�ɁA���ӓ��t���������āA�����펞���t��g�t������̂ƕM�҂͗\�����܂��B
�������A���j�ՂȂ��q�C�̓����n�͖���E�s���ɂāA������Y���𑱂��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
��3�����������(2021�N1���`2022�N8��)
�ŏ��ɁA2021�N1������22�N8���܂ł�3����(�k�C�u�����g�E��WTI�E�I�E��������)�̏T�Ԗ������ڂ��T�ς��܂��B
������2020�N�㔼����2022�N2�����܂ŏ㏸��������܂����B
���V�A�̑�\�I����E���������́A���V�x���A�Y�y���E�X�E�B�[�g����(������0.5���ȉ�)�ƃ��H���K����̏d���E�T���[����(��1���ȏ�)�̃u�����g�����ŁA�����E�T���[�����ł��B
�䂦�ɁA�E���������͉p��ł́uURALs�v�ƕ����`��s���t���܂��B
���Ȃ݂ɁA���{���A�����Ă������V�A�Y������3���(S-1�\�[�R�������^S-2�T�n�����u�����h�^ESPO����)�݂̂ŁA���ׂČy���E�X�E�B�[�g�����ł��B
�������A���{�͍��N2022�N6���ȍ~�A���V�A�Y�����̗A�����~���܂����B
���N(2022)8��29���`9��2���̕��ϖ����͖k�C�u�����g$95.31/bbl(�X�|�b�g���i)�A��WTI $90.79(��)�A�E��������(���C���݃m���H���V�[�X�N�`�o��FOB)$74.34�ƂȂ�܂����B
�u�����g�ƃE���������ɂ͑傫�Ȓl��������܂��B
���̒����l�̘I�Y�����������Ă���̂������ƃC���h�ŁA���V�A�͌��݁A�A�W�A�����ɑ��s�ꉿ�i���3�����������ŃI�t�@�[���Ă���ƕ��Ă��܂��B
���n�}�X�R�~�ł͂悭�A�u�E�N���C�i�J���A�����͏㏸�����B���V�A�͖����㏸�����Ă���A�Ζ������͑����A���̖��͂Ȃ��v�Ƃ���������f�ڂ��ꂽ��b���ꂽ�肵�Ă��܂����A����͊ԈႢ�ł��B
��L�̃O���t���������������B���F�̏c�����̓��V�A�R���E�N���C�i�ɑS�ʐN�U����2��24���ł��B
���̓������Ƃ��āA�k�C�u�����g���WTI�̖����͂�������㏸���܂������A8�����̎��_�ł͐N�U�O�̖�������������܂����B
����A�I�E���������̓E�N���C�i�N�U��ɖ��������B
8�������݂ł́A�N�U�O�Ɣ�r���ăo������$20�Ⴂ�����Ő��ڂ��Ă��܂��B���Ȃ킿�A�I�E���������͐N�U�㉺�������̂ł��B
���v�[�`���哝�̂̎v�l��H
�\�A�M�͍�����100�N�O��12���ɒa�����܂����B
1917�N�́u2���v���v(����)�Œ鐭���V�A�����āA�P�����X�L�[���t�������B���̔N�́u�\���v���v�ŃP�����X�L�[���t���|��A���[�j������ǂƂ���\�r�G�g�������a�����܂����B
���̌ネ�V�A�͐ԌR�Ɣ��R�ɕ����ꂽ�����ԂƂȂ�A�\�r�G�g�A�M�����������̂�1922�N12��30���ł����B
�ł�����A���N(2022)12���̓\�r�G�g�a��100���N�L�O�̔N�ɂȂ�܂��B
���V�A��V.�v�[�`���哝�̂�����ڎw���ăE�N���C�i�ɑS�ʐN�U�����̂��l�X�Ȑ�������Ă��܂����A�{�l�̓��̒��ɂ̓\�A�M�����̖�(���z)���h���Ă������Ƃł��傤�B
�I�v�[�`���哝�̂�2000�N5��7���V�哝�̂ɏA�C�A7��8���ɑ�1��哝�̔N�������\���܂����B
�ŏ��̑哝�̔N�������́u���V�A�͕���̊�@�ɕm���Ă���v�Ɣߑs���ɂ��ӂ����e�ł���A�u�������V�A�̎�����ڎw���v�ƍ����ɑi���܂����B
���̌�A�v�[�`���哝�̂�2005�N4��25���̖{�l�ɂƂ��Ă�6��ڂ̑哝�̔N�������̒��ŁA�u�\�A�M�����20���I�ő�̒n���w�I�S���ł���v�Əq�ׂĂ��܂��B
���̍�����A�\�A�M�����̎v�l��H�ɃX�C�b�`���������̂�������܂���B
���V�A�R�̃E�N���C�i�S�ʐN�U����2022�N2��24���ɔ�������A���̋L�����J����9��10���ŐN�U�J�n��199���ڂƂȂ�܂����B
����7�����ڂɓ���A�푈�͒�����E���Ր�̗l����悵�Ă��܂��B
�N�U�J�n2����ɂ͎�s�L�G�t(���L�[�E)�𐧈����A���V�A���S���������\�z�ł�������A�v�[�`���哝�̂ɂƂ茻�݂̐푈�������E�D�����͑z��O�̑��Z�ƌ����܂��傤(��q)�B
�푈�D�����ɂ��v�[�`���哝�͍̂����}�X�R�~���������Ǝ����u�펞�o�ρv�ւ̈ڍs��]�V�Ȃ�����A�I�}�X�R�~�͑����m�푈���̓��n�}�X�R�~���l�A�u��{�c���\�v�ł��ӂ�邱�ƂɂȂ�܂����B
S.�V���C�O���h����8��24���A�u���V�A�R�͖��Ԑl�̋]����}����ׂ��A�i�R���x�𗎂Ƃ��Ă���v�Ɣ����B
���h�����N�ł�����������R��������Ȃ��Ƃ���ɁA���V�A�R�̋��E�ꋫ�������Č����Ă��܂��B
NATO(�k�吼�m���@�\)���i��j�~���ׂ��E�N���C�i�N�U�J�n�����̂ɁA�t�Ƀt�B�������h�ƃX�E�F�[�f����NATO������U���B
�]���͑m���E�F�[����170�L����NATO�Λ����ł������A�V����1269�L���̃t�B�������h������NATO�Λ����ƂȂ�A���ʂƂ���NATO���i�𑣐i�B
����̓v�[�`���哝�̂̐헪�I���s�ƌ����܂��B
�E�N���C�i�R�ɂ��N���~�A�����U���������B�]���A���ł͂Ȃ������ꏊ�����ƂȂ�A�N���~�A�����ɏZ�ރ��V�A�l���푈���ӎ�������Ȃ��ɂȂ�܂����B
�E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂̓N���~�A�����D�҂�\�����܂����̂ŁA���V�A�R�ɂ��E�N���C�i�S�ʐN�U���͐V�ǖʂɓ���܂����B
������A�v�[�`���哝�̂ɂƂ�s�s���Ȑ^���ƌ����܂��傤�B
�Z���S�ʐ�����ڎw���ăE�N���C�i�d���N�U�����J�n�����v�[�`���哝�̂ɂƂ�A�E�N���C�i�S�ʐN�U�㔼�N�o���Ă�����ړI��B���ł��Ȃ��Ƃ́A�N���z�������������Ƃł��傤���H
���V�A�R���E�N���C�i�ɑS�ʐN�U�����Ƃ��A�I�v�[�`���哝�̂́u�푈�v�ł͂Ȃ��u�R�����v�Ə̂��܂����B
�����{�R�������ɐN�U�������A���{�R�́u�푈�v�ł͂Ȃ��u���ρv�Ə̂��܂����B
�Ƃ���A����̐N�U�́u�E�N���C�i���ρv�ƌĂԂ̂����������A�v�[�`���ɂ̓E�N���C�i���ς��悭�������ƂȂ�܂��傤���B
���{�������푈�̓D�����甲���o���Ȃ��Ȃ����悤�ɁA���V�A�̓E�N���C�i�푈���甲���o���Ȃ��Ȃ�A���Ɛ��ނ̓�����ނ��ƂɂȂ邾�낤�ƕM�҂͗\�����܂��B
�����E�̎��ڂ��������v�[�`���哝��
���N(2022)6������8���ɂ����A���V�A�ł͐��E�̎��ڂ��������r�W�l�X�֘A������3���A���˂ɑ������܂����B
�@�@�@1�m���g�E�X�g���[��1(�Ȍ�ANS1)�V�R�K�X�A�����
�@�@�@2�u�T�n����-2�v���(�哝�̗�416��)
�@�@�@3�u�T�n����-1�v���(�哝�̗�520��)�ł��B
�{�e�ł́A���E�̎��ڂ����������A���V�A�ɂ�邱��3�̖\�����T�ς��邱�Ƃɂ��A���̖{���͉������l�@�������Ǝv���܂��B
���V�A����o���g�C�o�R�h�C�c�����V�R�K�X�C��p�C�v���C��(�Ȍ�AP/L)�A���ʂ����N6���A�ˑR�팸����܂����B
���R�́A�u�m���g�E�X�g���[��1�p�K�X�E�^�[�r�����C���ɏo�������A�߂��Ă��Ȃ��v�Ƃ̘I�K�X�v�����������ł����B
���̌��ʁA2022�N8���̒i�K�ł�NS1�̔N�ԗA���\��55bcm�ɑ�2���̓V�R�K�X�A���ʂɂȂ��Ă��܂������A�I�K�X�v�����͂���ɁA�u8��31������3���ԁA����C���̂���NS1��S�ʒ�~����v�Ɣ��\�B
3���Ԃ̒���C����ɂ͂܂��s������������Ƃ��āA2022�N9��8�����݁ANS1�̑��Ƃ͑S�ʒ�~����Ă��܂�(bcm��10������)�B
�������A���̃K�X�E�^�[�r�����ɂ��A�V�R�K�XP/L�A�����s�\�ɂȂ����̂ł͂���܂���B����́A�����܂ł������ɂ����܂���B
���ׂĂ̐Ζ�(�����E�Ζ����i)P/L��V�R�K�XP/L�͖��N�K���A�ێ�_�������C���̂��߈ꎞ�ғ����~���܂��B
�������A���O�ɋ�����(�A�o��)�͎��v��(�A����)�ɘA�����āA�I��H�ŋ���������A���~�{�݂���Z�ʂ�����A�ň����v�Ƃɋ����ʍ팸�Ŕ[�����Ă��炢�܂��B
NS1�̏ꍇ�A���V�A���o��n�ɂ͗\���܂ߌv8��̃R���v���b�T�[�X�e�[�V����������A���N���Ԃɕێ�_���E����C�������{���Ă��܂��B
�ł�����ߋ�10�N�ȏ�̒����ɂ킽��A���̖����Ȃ����V�A����h�C�c�ɓV�R�K�X����������Ă��܂����B
����A���V�A�͓V�R�K�XP/L�𐭎����p�����̂ł��B
�t������A���̃K�X�E�^�[�r���͉p���[���X���C�X���́uTrent60�v�Ƃ������f���ł��B
�{���͍q��@�p�W�F�b�g�G���W���ł����A�����n��p�ɉ��������̂��ƃV�[�����X�Ђ́uSGT65�v���f���ŁA���h���b�T�[���R���v���b�T�[�Ƒg�ݍ��킹�Ďg�p���Ă��܂��B
�����V�A�̐Ζ��E�K�X�Y��
���ă��W���[��������A�C�ۏ����̌������C�m�z��ɂ�����Ζ��E�V�R�K�X���Y�͎�������ł��B
�������C�m�C�ۏ������̌����E�V�R�K�X�z��̒T�z�E�J���E���Y�E�A���ɂ́A���ă��W���[�ƃV�������x���W���[��n���o�[�g���A�ƃW�[�����X��p���[���X���C�X�A�ăx�[�J�[�q���[�YGE(�[�l�����E�G���N�g���b�N)�ȂǁA���Ă̍ŐV�Z�p�ƃm�E�n�E�̑����͂��K�v�ɂȂ�܂��B
�T�n����-2�v���W�F�N�g�̏ꍇ�A�p�V�F����������ALNG�̌����ƂȂ�V�R�K�X���Y���̂�����ɂȂ�܂��B
���ʂ͈�C�T�̋Z�p�Ҍٗp�ɂ��Z���ԗ����܂����A�����I���Y�͕s�\�ł��B
�u���Ăɂ��ΘI�o�ϐ��ق͌��ʂȂ��v�Ə�������E�b�����肵�Ă���]�_�Ƃ����܂����A�����͐����ł��B
�ΘI�o�ϐ��ّ[�u�����͂Ɍ����Ă��邪�䂦�ɁA�v�[�`���哝�̂͊O���ɑ��āu���V�A����o�Ă����v�ƌ�������(�哝�̗�416��)�A�O�����o�Ă����ƐΖ��E�K�X���Y�Ɏx�Ⴊ�ł邱�Ƃ𗝉�����ƁA���x�́u�o�Ă����ȁv�Ƃ������������哝�̗�(�哝�̗�520��)�𗐔����Ă���̂ł��B
��L���A���ă��W���[���P�ނ�����V�A��LNG�\�z�͑S�ʕ���̉\����ƂȂ�A���V�A�̍��v��W�Ԃ���v�[�`���哝�̎��g���A�}�炸�����V�A�̍��v��ʑ����Ă��邱�Ƃ��������܂��B
���Ȃ킿�A���V�A�̐^�̓G�̓v�[�`���哝�̂��̐l�Ƃ̌��_�Ɏ���܂��B
���I�哝�̗�416���Ɛ���1369��
���V�A�̖@�̌n�̗D�揇�ʂ�1���@�@2�A�M�@�@3�哝�̗߁@4���߂ɂāA�u�����v�ɂ����đ哝�̗߂ɂ��A�M�@���C�����邱�Ƃ͂ł��܂���(�u�펞�v�͕�)�B
���̂��Ƃ�Ă�����n�}�X�R�~�͑��݂��܂��A���̖{���͘I�哝�̎��g���I�A�M�@�Ɉᔽ����哝�̗߂߂������Ƃł��B
�Ȃ��Ȃ�A�T�n����-1��2��PSA(���Y�����^�_��)�͎����A���V�A�̖@���ɂȂ��Ă��邩��ł��B
�哝�̂������̖@����j�鍑�ɐV�K���������Ƃ͊F���ƂȂ�܂��傤�B
�I�v�[�`���哝�̂̃G�l���M�[���Y�����Ă���A���N�ɓ���6��30���t���哝�̗�416����8��5���t���哝�̗�520���ƁA���������|�̑哝�̗߂𗐔����Ă��܂��B
�{�e�ł͂܂��A6��30���t���哝�̗�416����8��2���t���I����1369�����T�ς��܂��B
�v�[�`���哝�̂�2022�N6��30���A�哝�̗�416���ɏ������܂����B ����́A�T�n�������k���������̃I�z�[�c�N�C�ɂČ����E�V�R�K�X��T�z�E�J���E���Y���Ă���T�n����-2�v���W�F�N�g�ɑ��A���Ɖ�Ёu�T�n�����E�G�i�W�[�Ёv�̌��v���A����V�K�ɐݗ�����郍�V�A�@�l�u�T�n�����X�J���E�G�l���M�A�v�ɖ������n��������e�ł��B
��������L�̒ʂ�A���̑哝�̗ߎ��̂����V�A�A�M�@�Ɉᔽ���Ă��܂��B
�哝�̗�416�����A�I���{�͐V���V�A�@�l�u�T�n�����X�J���E�G�l���M�A�v�ݗ��Ɋւ���8��2���t������1369���z�B
�V���V�A�@�l�L���ӔC��Ёu�T�n�����X�J���E�G�l���M�A�v��8��5���A�T�n�����B�̏B�s���[�W�m�E�T�n�����X�N(���L��)�ɓo�L����܂����B
���{���{�͎O�䕨�Y�ƎO�H�����ɑ�S-2���v�ێ���v�����A�O��E�O�H��S-2�V��Ёu�T�n�����X�J���E�G�l���M�A�v�Ɍ��v�Q���p��������B���v�ێ����ׂ��A�V��Ђɐ\�����ċ�����܂����B
�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A���Ђ̌��v�ێ���S-2�u�T�n�����X�J���E�G�l���M�A�v�ɂ��Γ�LNG�����͕ʎ����̖��ł���A���ڂ̊W�͂���܂���B
LNG�����_��͓��{�̎��v�ƂƃT�n�����X�J���E�G�l���M�A�Ԃ̌_��ɂȂ�A�O��E�O�H��LNG�_��̓����҂ł͂Ȃ��̂ł��B
�O��E�O�H�����v�Q���p������ΑΓ�LNG�������p�������ƍl���Ă���Ƃ�����A����͑傢�Ȃ錶�z�ɂ����܂���B
�O��E�O�H��S-2���Ɖ�Ђւ̏o���҂ł���A���Ɖ�Ђ����v���o���Ό��v�ɉ����ė��v�z�����A���Ɖ�Ђ��Ԏ��ɂȂ�Ό��v�ɉ����ĐԎ����S���܂��B
LNG�H�ꎩ�̂͐V���V�A�@�l�u�T�n�����X�J���E�G�l���M�A�v�Ɉڊǂ���܂����A�p�V�F���͊���S-2�v���W�F�N�g����̓P�ނ�\�����Ă��܂��B
�p�V�F����������H��̕ێ�E�_����S������Z�p�҂����Ȃ��Ȃ�A����C���ɕK�v�Ȏ��@�ނ�����s�\�ɂȂ�A����LNG���Y�͒ቺ�E��~����ł��傤�B
���㌸�����Ă��^�]�����͕K�v�ł�����A���Ɖ�Ђ͐Ԏ��ƂȂ�A���v�Q���҂͐Ԏ����S���������邱�ƂɂȂ�܂��B
�M�҂́A1�`2�N��ɂ͂��̗l�Ȏ��Ԃ��\�ʉ�������̂Ɨ\�����܂��B
�����Əd�v�Ȃ��Ƃ�����܂��B
�T�n����-2�v���W�F�N�g�ł́A�T�n�������k���������̃I�z�[�c�N�C�T�n����-2�z��(���j�z��ƃs���g���E�A�X�g�t�z��)�ŐΖ��E�K�X��T�z�E�J���E���Y���Ă��܂����A�V�F����������ΐΖ��E�K�X���Y�͏��X�ɒ�E�������邱�Ƃł��傤�B
��������A���Ƃ�LNG�H�ꂪ�ғ����Ă��Ă��A�����ƂȂ�V�R�K�X���s�����鎖�Ԃ����ӏo�����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�M�҂�1�`2�N��ɂ͂����Ȃ�Ɨ\�����Ă���܂��B
���ɁA�u�p�V�F���������Ă��A�T�n����-2�̐Ζ��E�K�X���Y��LNG���Y�͖�肠��܂���v�ƌ����Ă���l�������Ƃ�����A����͂��̃v���W�F�N�g�̎��Ԃ�m��Ȃ����A���邢�́u�s�s���Ȑ^���v���B���Ă��邩�̂ǂ��炩�ɂȂ�܂��B
���{���{�͎O�䕨�Y�ƎO�H�����ɑ�S-2���v�ێ���v�����A�O��E�O�H��S-2�V��Ёu�T�n�����X�J���E�G�l���M�A�v�Ɍ��v�Q���p��������B���v�ێ����ׂ��A�V��Ђɐ\�����ċ�����܂����B
�Ƃ��낪���̌�A���Ԃ͋}�W�J�B9��7���t�����C�^�[�d�͈ȉ��̂��Ƃ��܂����B
�u�u�T�n����2�v�V��Џo���ɑ�K��LNG���Ƃ̌o���v�������V�A���{
���V�A���{��6���A�ɓ��̐Ζ��E�V�R�K�X�J�����Ɓu�T�n����2�v��S����Ђւ̏o���ɂ��āA�N�Ԑ��Y�\�͂�400���g������t���V�R�K�X(LNG)�v�����g�̑��ƌo�������鎖�Ǝ҂Ɍ���Ƃ��������@�߂Ŏ������B�v
�������A�M�҂͂��̃��V�A���V��͓��R���Ǝv���Ă���܂��B
��q�̂Ƃ���A�C�ۏ����̌������C�m�z��ɂ����ẮA���ă��W���[��Ζ��T�[�r�X��Ђ̎Q��Ȃ��ɂ͒T�z�E�J���E���Y�E�A���Ȃǂ͕s�\�ł��B
�V�F����������A�z�挻��ł̐Ζ��E�V�R�K�X���Y���ALNG�H��ғ������X�ɍ���ɂȂ�A�ŏI�I�ɂ͐��Y��~�K���ƂȂ�܂��傤�B
���V�A�����A�x����Ȃ������Ƃ��̎���𗝉������̂��Ǝv���܂��B
���ꂪ�A���V�A�����}篁A���v�Q�����ύX�����䂦��ƕM�҂͍l���܂��B
���V�A���ł͂�����A�ʔ����������o�Ă��܂����B
�T�n����-2����P�ނ�\�����Ă���V�F���ɑ��A�k�Ɍ��O�B�_�������ŁuArctic LNG 2�v�v���W�F�N�g�𐄐i���Ă���INovatek�Ђ��V�F���̌��v���n�����������|��\���o���ƕ��܂����B
�������A�INovatek�Ў��̂�LNG���ƌo��������܂���BLNG���ƌo���̂���̂́ANovatek�Ђ�10���̎��{�Q�����Ă��镧�g�^�[���ł��B
�ł�����ANovatek�Ђ̃T�n����-2���v�Q���́A���g�^�[���ɃI�y���[�^�[(�呀�Ǝ�)�Ƃ��ăT�n����-2�̉^�c�E���Ƃ��ϑ��������Ƃ����̂����V�A���ӌ��ł���A�ƕM�҂͐������Ă���܂��B
�ł́A���g�^�[�����T�n����-2�̉^�c�������邩�ǂ����Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����͌���s���ł��B
�E�N���C�i�푈�̐i�W����Ǝv���܂����A���炭�g�^�[���͎��ނ���ł��傤�B
�g�^�[�����T�n����-2�̃I�y���[�^�[�ɂȂ�A�č�����o�ϐ��ّΏۉ�ЂɎw�肳��Ă��܂��܂��B
�������āA�T�n����-2�v���W�F�N�g���Y���J�n���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
���I�哝�̗�520��
���E�ő�̐Ζ���ЁA�I���X�l�t�`��I.�Z�[�`���В��͉��ă��W���[�P�ނ̈Ӗ��𗝉����Ă��܂��B
�䂦�ɁA�ނ��v�[�`���哝�̂ɏo�������哝�̗߂���520���ɂق��Ȃ�Ȃ��ƕM�҂͍l���܂��B
�v�[�`���哝�̂�8��5���A�I�哝�̗�520���ɏ����B����́A�T�n����-1�v���W�F�N�g����O���P�ނ��ւ�����e�ł��B�ăG�N�\�����[�r����������A�T�n����-1�v���W�F�N�g������Ȏ�����}���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
���̑哝�̗߂̗L�������͍��N���܂łł����A�����ł��E����ł��L�����������\�Ƒ哝�̗߂̒��ɖ��L����Ă��܂��B
���Ȃ킿�A�O�����Ƀ��V�A����P�ނ����Ȃ��Ƃ̃��V�A���̋����ӎv���������܂��B
���E�N���C�i�틵
������102�N�O��2��24���A�h�C�c��A.�q�g���[�̓~�����w���̃r�A�z�[���u�z�[�t�u���C�n�E�X�v�ɂāA�i�`�X�}�̊��g���������s�B
����2��24���ɁA���i�`�Y����W�Ԃ���v�[�`���哝�̟����̃��V�A�R���E�N���C�i�ɑS�ʐN�U�J�n�����̂ł��B
�������j�̔���ƌ��킸���āA���ƌ����܂��傤���B
���̋L���̌��J��9��10���̓��V�A�R��2��24���E�N���C�i�ɑS�ʐN�U�J�n�ȗ�199���ڂƂȂ�A�E�N���C�i�푈�͊۔��N���܂����B
�Z���d�����̔���������E���Ր�ƂȂ�A��ԍ��f���Ă���̂̓v�[�`���哝�̂��̐l�ƕM�҂͑z�����܂��B
�Z���S�ʐ�����ڎw���ăE�N���C�i�d���N�U�����J�n�����v�[�`���哝�̂ɂƂ�A���̐푈�������E�D�����͑z��O�̑��Z�ƂȂ�܂����B
�E�N���C�i�S�ʐN�U�㔼�N�o���Ă��A�v�[�`���哝�͉̂���ړI��B���ł��Ă��Ȃ��̂ł��B
9��8���̃E�N���C�i��{�c���\�ɂ��A���V�A�R���E�N���C�i�ɑS�ʐN�U����2��24������9��8�����܂ł�187���Ԃɂ����郍�V�A�R�̗v���Q�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�E�N���C�i�Q�d�{�����\�F���V�A�R�v���Q�^2022�N9��8��������
�E�펀�ҁF��5��1250�l(�O����{640�l)
�E��ԁF2112�q(���{15)�^���b�ԁF4557�q(���{37)�^�ΖC�F1226��(�{32)�^�g���b�N�F3344��(�{24)
�E���A�����P�b�g���ˑ�F239��(�{2)�^��Ί�ǐ��V�X�e��159��(�{3)�^���q�~�T�C��214��(�|)
�E�R�p�@�F239�@(�{2)�^�w�� 210�@(�{2)�^�h���[�� 884�@(�{4)�^�R�� 15��(�|)
�E�N���C�i��{�c���\�ɂ��A7��27���Ƀ��V�A�R�펀�҂͐���4���l���A9��8���ɂ�5���l���܂����B
����A8��22���̃E�N���C�i��{�c���\�ɂ��A�E�N���C�i�R�̐펀�҂͖�9000�l�̗R�B���V�A�R�̐펀�҂Ɣ�r���ăE�N���C�i�R�̐펀�Ґ���5����1�A�Ƃ�����Ə��Ȃ����銴�������܂��B
�������A�E�N���C�i��{�c���\�ł����炱�̂܂�L�̐�����M���邱�Ƃ͊댯�ł����A�b�����Ƃ��Ă����V�A�R�̐펀�҂͊���2��5000�l�ȏ�ɒB���Ă��܂��B
�t�ɁA�E�N���C�i�R�̐펀�҂�2�{�Ɖ��肷��ƁA1��8000�l�ɂȂ�܂��B���̕ӂ����^���ɋ߂������ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ł́A�펀��1�ɑ��A�폝�҂�3�̊����Ŕ�������ƌ����Ă��܂��B���̏ꍇ�A���V�A�R�̐펀���Ґ��͖�10���l�ƂȂ�A����������͂̔����ȏオ�펀���҂ɂȂ�܂��B
�퓬������3���̐펀���Ґ��Łu�퓬�s�\�v�ƂȂ�A5������Ɓu�S�Łv�ƌ���邻���ł��B
�Ƃ���A���V�A�R�̑E�N���C�i����������͂́u�S�Łv�������ƂɂȂ�܂��B
�I�V���C�O���h����8��24���A�u���Ԑl�̔�Q��}���邽�߁A���V�A�̐i���͒x��Ă���v�Ɣ������܂����B
����͐}�炸���A���V�A�R�̐i������E�������Ă��邱�Ƃ�����F�߂����ƂɂȂ�܂��B
���n�}�X�R�~�ł͂悭�u���V�A�����͐푈�ɂ��ϖR�����Ɋ���Ă���v�Ƙb���Ă���l�����܂����A���̂悤�Ɏ咣���Ă���l�͏d�v�Ȏ������������Ă��܂��B
����́A�i�|���I���푈���h�C�c�̃\�A�N�U�����V�A���ɂƂ�c���h�q�푈�ł������_�ł��B���V�A�̑c���h�q�푈�ŕ������̂͐N���R�ł��B
�������A����̐푈�̓��V�A�̑c���h�q�푈�ł͂Ȃ��A���V�A�̑����N���푈�ł��B
���V�A���ɂƂ�A�E�N���C�i�N�U�͈Ӗ����Ӌ`����`���Ȃ��푈�ł��B
����A�E�N���C�i���ɂƂ��Ă͑c���h�q�푈�ɂȂ�܂��B���ꂪ�A���R�퓬�����̎m�C�ɉe����^���Ȃ��͂��͂���܂���B
�őO���͏��Ր�ƂȂ�A���s�̍s���͕�⋕⋋������ƂȂ�܂����B
�䂦�ɉ��Ă��E�N���C�i�R���x�����p���������E�N���C�i�R�L���ƂȂ�A���B���V�R�K�X�s���̍��~������A���V�A�ɂ͒����E�����E�Â��~���҂��Ă��邱�Ƃł��傤�B
�v�[�`���哝�͍̂����㏞�����ƂɂȂ�Ɨ\�����܂��B
�����V�A�R�ƃE�N���C�i�R�̐�͔�r
���Q�l�܂łɁA���V�A�R�ƃE�N���C�i�R�̐�͔�r�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�E�N���C�i�Q�d�{���̓��V�A�R�̔�Q�����\���Ă���A�M�҂͖����L�^���Ă��܂��B
9��8���̃E�N���C�i��{�c���\�ɂ��A���V�A�R���E�N���C�i�ɑS�ʐN�U����2��24������9��8�����܂ł�197���Ԃɂ����郍�V�A�R�̐펀�҂͐���5��1250�l�ɂȂ�܂����B
���\�A�M����̃A�t�K���푈��10�N��(1979�N12���N�U�`1989�N2���P�ފ���)�����܂������A���̎��̃\�A�R�펀�҂͖�1.5���l�ƌ����Ă��܂��B
�A�t�K���푈�ł�10�N�ԂŐ펀��1.5���l�ł������A�E�N���C�i�푈�ł͔��N��5���l���܂����B
����A���V�A�R�̎��R��Q�Ɋւ����{�c���\��3��25���ɔ��\�������V�A�R�펀��1351�l���ŏ��ōŌ�ł��B
����͂��Ȃ킿�A���V�A�R�펀�҂����܂�ɂ��������āA�������\�ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B
�������A���傹���{�c���\�ł����炻�̂܂ܐM���邱�Ƃ͂ł��܂��A�b�����Ƃ��Ă����V�A�R�͑��Q���Ă��邱�Ƃ������Č����Ă��܂��B
�Q�l�܂łɁA���V�A�R�̔�Q�����͈ȉ��̒ʂ�ł��B
������1�_�A���V�A�R�̐펀�Ґ��Ɋւ��t�L�������Ǝv���܂��B
���V�A�R�̏ꍇ�A���V�A���K�R�̐펀�ҏ����̈�̂��߂��Ă����ꍇ�̂݁A�펀�҂ƔF�肳��A�N���x�����ΏۂɂȂ�܂��B
��������A�s���s���҂�V�A���ԌR����Ѓ��O�l���̗b������(���[�O�i�[�Ɨ���A��)�A�E�N���C�i����2�B�̖����g�D�A�`�F�`�F�������R�c�̐펀�҂Ȃǂ̓��V�A�R�̐펀�҂ɓ����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�E�N���C�i���ɘI�R���������Ȃ��Ȃ����̂ŁA�v�[�`���哝�̂̓��V�A��ƂɐԎ����W�ߏ���o�����R�ł��B
�퓬���ꂩ�烍�V�A�R�����Ȃ��Ȃ�ƁA�v�[�`���͖��X��p�j���g�p���邩�A���邢�̓U�|���[�W�������Ɏ���o����������܂���ˁB
���G�s���[�O�^�u���V�A�͉��������Ă��Ȃ��v
�I�v�[�`���哝�̂�9��7���A�I�ɓ��o�σt�H�[����(���E���W�I�X�g�N)�ɂāu���V�A�͉��������Ă��Ȃ��B��������Ȃ��v�Ɖ������܂����B�{���ł��傤���H
��q�̂��Ƃ��A�E�N���C�i��{�c���\�ɂ��A�E�N���C�i�푈�ɂ����郍�V�A�R���Ґ��͊���5���l���Ă��܂��B�b�����Ƃ��Ă��A���Ґ���2��5000�l���Ă��܂��B
�č��h�ȋ̔��\�ł��A8���̎��_�Ń��V�A�R�̐펀���Ґ���7���`8���l�ƕ��Ă��܂��B
���V�A���C�͑��̌R�͂�15�ǒ��v���Ă��܂��B���̒��ɂ́A���C�͑����͂���~�T�C�����m�́u���X�N���v�����܂܂�Ă��܂��B
����ł��u���V�A�͉��������Ă��Ȃ��v�ƌ�����̂ł��傤���H
K.�}���N�X�́u���C�E�{�i�p���g�̃u�������[��18���v�̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�w�[�Q���H���A�u���j�͌J��Ԃ��v�B�������ނ́A�u1�x�ڂ͔ߌ��Ƃ��āA2�x�ڂ͒��Ԍ��Ƃ��āv�ƕt�������邱�Ƃ�Y�ꂽ�B
�������}���N�X�������Ă���A�ނ̓v�[�`���哝�̂��ǂ̂悤�ɕ\������̂ł��傤���H
�}���N�X�͋��炭�A���̂悤�ɋL�q���邾�낤�ƕM�҂͑z�����܂��B
�v�[�`���H���A�u���V�A�͉��������Ă��Ȃ��B��������Ȃ��v�B�������ނ́A�u�����̎v�l��H�ȊO�́v�ƕt�������邱�Ƃ�Y�ꂽ�B�@
���C�M���X���h�� �g�E�N���C�i�R �ő��50�L���O�i�h
�틵�͂���C�M���X���h�Ȃ�10���Ɂu�E�N���C�i�R�͍���6������n���L�E�B�암�ō����J�n���A���V�A����̂��Ă����n��ɍő��50�L���O�i�����B���V�A�R�͊�P�����v�Ǝw�E���Ă��܂��B
����ɃE�N���C�i�R�������h���o�X�n��̍őO���Ő키���V�A�R�̕⋋�H�ƂȂ��Ă���n���L�E�B�̃N�s�����V�N�ɔ����Ă��āA�D�҂ɐ���������V�A�R�ɑ傫�ȑŌ��ɂȂ�ƕ��͂��Ă��܂��B
���E�N���C�i�R�̍U���� ���V�A�́g�����������Z�����[�h������
���V�A�R���x�z���Ă���������암�ł́A���V�A��11���ɍs���铝��n���I���ɂ��킹�āA�����Ɍ������Z�����[�����{����v�悪�������Ƃ݂��Ă��܂��B�������A�����ɂȂ��ăv�[�`�������̗^�}�������Z�����[��11���Ɏ��{����悤��Ă��Ă��āA�E�N���C�i�R�̔��]�U�������[������������Ȃ��Ȃ����Ǝ~�߂��Ă��܂��B
���[�����X�L�[�哝�� �u�n���L�E�B��30�ȏ�̏W���D�ҁv
�E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂�9���A�V���ɓ�������J���u�E�N���C�i�R�������n���L�E�B��30�ȏ�̏W����D�҂��A�x�z���ɒu�����v�Ɩ��炩�ɂ��܂����B9���Ƀn���L�E�B�ɂ���D�҂����W����1�ŎB�e���ꂽ�f���ł́A�Z��⋳��Ȃǂ��C���ɂ���đ傫�����Ă��āA�E�N���C�i���̌x�@���Z���ւ̎x���̂ق��A���V�A�R�ɂ��푈�ƍ߂ɂ��đ{�����n�߂��Ƃ������Ƃł��B�E�N���C�i�R�͐挎���{����w���\���B�ȂǓ암�Ŕ��]�U�����J�n���A����8���ɂ͓����h�l�c�N�B�̃N���}�g���V�N�ߍx�Ȃǂł����V�A����̂����n��ɍU�ߓ������Ɣ��\���Ă��āA�e�n�ŌR������W�J���A�����ɓ]���Ă���Ƃ݂��܂��B�[�����X�L�[�哝�͓̂���̂Ȃ��Łu�������V���ȏW����D�҂��A�E�N���C�i�̍����ƈ��S�������̍����ɕԊ҂���v�Əq�ׁA�U���𑱂���p�����������Ă��܂��B
�����V�A���h�ȁu�������n���L�E�B�ɍĂѓW�J�v
���V�A���h�Ȃ�9���A�n���L�E�B���~�T�C���ȂǂōU�����A�E�N���C�i�R�̎w������j�A���m���E�Q�����Ɣ��\���܂����B����Ɂu���V�A�R�̕������n���L�E�B�ɍĂѓW�J���Ă���v�Ƃ��āA��Ԃ�R�p�Ԃ��ړ�����f�������J���܂����B�E�N���C�i�R�̔����ɑΉ�����p���������������˂炢�Ƃ݂��A�E�N���C�i�암�����łȂ������ł��������U�h�������Ă��܂��B
���v�[�`���哝�� �����Y�_�Y����엿�̗A�o�g��w��
�v�[�`���哝�̂�9���A�N���������ŊJ�������S�ۏ��c�ŁA���V�A�Y�̔_�Y���Ɣ엿�̗A�o���g�傷��悤�W�t���Ɏw�����u���قɂ���āA�A�t���J��A�W�A�A��Ăւ̃��V�A�Y�̔엿�̗A�o���W�����Ă���B����͍��ʂ��v�Ɣᔻ���܂����B�܂��A�E�N���C�i������_�Y���̗A�o���ĊJ���ꂽ���̂̑��������[���b�p�����ŁA�n�������ɓ͂��Ă��Ȃ��Ǝ咣���A�E�N���C�i��[���b�p�����̑Ή���ᔻ���܂����B�v�[�`���哝�̂͗��T�A�E�N���C�i����̔_�Y���̗A�o�ĊJ�̒�������Ƃ߂��g���R�̃G���h�A���哝�̂Ɖ�k���A���[���b�p�����̔_�Y���̗A�o�𐧌�����悤��Ă���l���������Ă��܂��B�v�[�`���哝�̂Ƃ��ẮA�H����@�ɒ��ʂ���A�t���J�ȂǓr�㍑�Ɋ��Y���p������������ƂƂ��ɁA���[���b�p�ɗh���Ԃ��������˂炢�Ƃ݂��܂��B























 �@
�@ �@
�@







 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@




















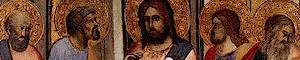


 �@
�@ �@
�@





























 �@
�@ �@
�@

 �@
�@




























 �@
�@ �@
�@