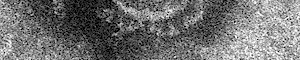 |


 �@
�@ |
���I�~�N�����ō����̓��{�������y����̍��{���@1/24
�I�~�N�������̊������}�g�債�Ă���B���{�����ŐV���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l��1��22�A23���̗����Ƃ�5���l�����B
�M�҂��f�@���Ă���i�r�^�X�N���j�b�N�V�h�ł��A1��������20�l�ȏ�̔��M���҂���f���A���̔������x���z�����B1�l�̊����҂��m�F����A�Z���ڐG�҂ɂ�����Ƒ�����������ƂƂ��Ɏ���Ö@���̊����҂�d�b�Ńt�H���[���A���̌��ʂ�ی����ɕ��邱�ƂɂȂ�B�����҂��}�����Ă��錻�݁A�N���j�b�N�̕��S�͋}�������B
�u�����}���ŕی������N���w�l�����ꏊ���x ���S���֎����̂��͍��v(�����V���A�s�^��1��19��)�ȂǁA�ی����̋���͑����̃��f�B�A���Ă��邪�A�R���i�f�Âɏ]������N���j�b�N�����l���B
��PCR������R�������̃L�b�g���s��
���́A���ꂾ���ł͂Ȃ��BPCR������R�������̃L�b�g���s�����n�߂��B�i�r�^�X�N���j�b�N�V�h���_�؎�b�@���́u���i�Ȃ甭������Ɨ����ɓ͂��R�������L�b�g���A1��18���ɔ��������������܂��͂��Ă��܂���(1��23������)�v�Ƃ����B�����L�b�g�������Ȃ�A�R���i�f�Â͂ł��Ȃ��Ȃ�B
�����A�����̏͂܂��܂����B1��23���A�_�ːV���́u���ɂ���Ō����L�b�g�s�� �����}���A�S���Ŏ��v���܂� �V�^�R���i�v�Ƃ����L�����f�ڂ��A���̒��ŁA�u�_�ˎs���ł́A�����̃N���j�b�N���APCR�����L�b�g�̓��ב҂��̂��߈ꎞ�I�Ɍ����𒆎~���A�L�b�g�s�����猟���ɉ������Ȃ���ǂ��o�Ă���v�ƏЉ�Ă���B����ɁA����ł͕ی����ɂ��s�������ł����A�����L�b�g���s�����A1�T�ԑ҂����B
���̏͗e�Ղɂ͉��P���Ȃ����낤�B�I�~�N�������̐��E�I�ȗ��s�ɂ��A���E���Ō������v�����܂��Ă��邩�炾�BPCR�������������o�C�I�j�N�X�̐{���K�O�В��́A�uPCR�����L�b�g�͑��t�̎�e��A�s�����t�ȂǕ����̃A�C�e���ɂ��\������܂����A�����͖�1�J���̓��ב҂��ŁA���ɂ̓��h�������Ȃ����̂�����܂��v�Ƃ����B
�ł́A�C�O�͂ǂ��Ȃ̂��B�}�������������������B1��21���̌o�ϋ��͊J���@�\(OECD)�������̐l��1000�l������̌�����(1�T�ԕ���)�������B���{��1.18���ŁA���L�V�R�Ɏ����ŏ��Ȃ��A�}���[�V�A(3.25��)��C���h(1.27��)�ɂ��y�Ȃ��B�����̍��́A�I�~�N�������̗��s���ł��A���{�Ƃ͌��Ⴂ�̌��������{���Ă��邱�Ƃ����킩�肢�������邾�낤�B
�Ȃ��A�����Ȃ�̂��낤���B�ǔ��V����1��19���t�L���Ŋړc�ꔎ�E���M��w�����ɂ��u�����I�Ȗ�������܂����A�����������鐻���Ƃւ̎x�����������ׂ��v�Ƃ����ӌ����Љ�Ă���悤�ɐŋ��̓��������߂�_�������邪�A���{�̌��������A��i���ōŒ�x���Ȃ̂́A����Ȃ��Ƃł͐��������Ȃ��B
�����{�̌������̓}���[�V�A�ɋy���ғ������Ⴂ
���{�̌������́A���������ڕW���Ⴂ�B���݂̓��{��1��������̌����\�͖͂�38��5000�����B�����A���̐��̌��������{�����Ƃ��Ă��A�l��1000�l������3.06���ɂ������AOECD�����ł̓R�����r�A(1.73��)�A�|�[�����h(2.62��)�A�j���[�W�[�����h(2.7��)���������B����A�W�A�ł́A���܂��}���[�V�A�ɋy�Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA��N8��27���ɂ�27��5680���̌��������{���Ă���B�f���^���̑嗬�s���o����������A�����̐����������Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B
���{�̌����̐��͌����\�͂��Ⴂ���Ƃɉ����āA�ғ������Ⴂ���Ƃ���肾�B1��21���̌������́A�����\�͂�39���ɂ����Ȃ��B�N�������čł�����������������1��14���ł���21��7291���ŁA�ғ�����56�����B
���́A�����J���Ȃ������ӎu�������āA������}�����Ă����ƍl���Ă���B�����łȂ���A���{�̌����\�͂���i���Œ�x���Ƃ������������Ȃ��B�ő�̗��R�͊����ǖ@�̓��@�K��̑��݂��B
�����ǖ@�ł́A�@��̊����NJ��҂ɑ��āA�m���́u���@������ׂ����Ƃ��������邱�Ƃ��ł���v�Ƃ���B���̏�����̂ɁA���@�������Ɏ���Ŏ��S����A�m�����ӔC��Njy�����B���̌��ʁA�m���͑S�����҂���@������B�y�ǂŊ����͂������I�~�N�������ł��A�����A�S�����҂���@�������̂́A���̂��߂��B
�����ǖ@�́A�R�����⌋�j��O���ɂ����ė��@���ꂽ�B���������l�̊����҂��o��R���i�͑z��O���B���ׂĂ̊����҂�f�f���Ă��܂��A�����ɕa���͂����ς��ɂȂ�B�a����p�ӂ���̂͌��J�Ȃ̐ӔC���B�����炱���A�R���i���s�����A�uPCR�����𑝂₳�Ȃ����Ƃ��A�킪������Õ��Ȃ����R�v�Ƃ����������J��Ԃ����B
�����A���̒��x�̖�D��ł́A�R���i�����҂̑������u�}���v���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���ɁA�����͂������I�~�N�����������҂���@������A�@�������͔������Ȃ������B����ł͉@���������������A��Õ��뜜���ꂽ�B
���̒i�K�ŏ��߂āA�m�����������@�̕��j���ɘa���Ă��A�Ɛӂ����悤�ɂȂ����B�����A�����ɕa�����N�����邽�߁A�܂h�~�錾���o�����ƂƂȂ����B���ꂪ�A���{�ł͏����̊����҂ŎЉ��Ⴢ��Ă��܂����R���B���̍\�}�́A��1�g���獡��܂Ŋ�{�I�ɕς��Ȃ��B
�����ǖ@�̋������@�K�肱���A�킪���̊����Ǒ�̖����ے����Ă���B�Љ�̖h�u�̂��߂Ɋu����D�悵�A�����҂̌����⎡�Ñ̐��̋����͌y������B��������ɓ����ȉq���x�@�����ǂ����`���a�\�h�@�̉e�����c���Ă���B
�����{�łȂ������̗���ɗ��Ăΐ��E�ƌނ���
�R���i�͖��m�̊����ǂ��B�����ǖ@��2�ނ�5�ނ̂悤�Ȋ��m�̗ތ^�ɖ�����肠�Ă͂߂邱�ƂȂ��A����ɑ����A�����I�ȑΉ����Ƃ�˂Ȃ�Ȃ��B���̍ہA�d�v�Ȃ̂́A���{�łȂ��A�����̗���ɗ����Ƃ��B�����̗���ɗ��ĂA���E�ƌނ����c�_���\�ɂȂ�B
�R���i�p���f�~�b�N�ŁA���E�͔�ڐG����]�����B���̌��ʁA�ݑ�����}���������B�Ⴆ�A��N3���A�A�����J�H�i���i��(FDA)�́A�A�����J�E�L���A�w���X�Ђ��J����������Ō����ł���ȈՊj�_�����ɋً}�g�p����(EUA)��^�����B��t�̏���Ⳃ��s�v�ŁA���p���Ԃ͖�20���ŁAPCR�����Ƃ̗z����v����97�����B
���ĂŌ������𑝂₷���Ƃ��ł����̂́A���̂悤�Ȏ���ŊȒP�Ɏ��{�ł��錟�����J������A�I�����C���ōw���ł���悤�ɂȂ������炾�B���̂悤�Ȍ����L�b�g�̔z������A��Ãf�[�^�Ƃ��ė��p����܂ł́A�Љ�V�X�e�����A����2�N�Ԃ̎��s����̖��A�m�����ꂽ�B�����炱���A�o�C�f���哝�̂́A��N12���A�S�����ɖ����Ō������邱�Ƃ��ł���Ɛ錾���邱�Ƃ��ł����B
���{�͑ΏƓI���B�m���ɁA���i��Ë@�푍���@�\(PMDA)�́A�u�̊O�f�f�p���i�v�Ƃ���50��ނ̌����L�b�g�����F���Ă���B�����A���̂悤�Ȑf�f�L�b�g�́A��ǂŖ�t���Ζʔ̔����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��ڐG�Ƃ͒������B����ɁA������A�z���ɂȂ����ꍇ�A�����҂̈ӌ��Ƃ͖��W�ɁA�������@�������Ă��܂��B
�����{�͐��E����w�Ȃ���Ȃ�Ȃ�
�����́A�����Ɛ��E����w�ԕK�v������B���ẮA�������t�����p���A�I�~�N�������̗��s���ł��Љ�����p�����Ă���B1��12���A�A�����J�̃o�C�f���哝�̂́A�Ζʎ��Ƃ��p�������邽�߂ɁA�w�Z�����ɔz�t���錟���L�b�g��1000���lj�����Ɣ��\���Ă��邵�A�p�����{�́A1��17���A�R���i������̎���u�����A�����A���̏ꍇ�Ɍ���A�]����7������5���ԂɒZ�k�����B1��20���A�C�X���G���ł̓R���i�����҂ƐڐG���������́A�T2��A�R���������A�A�����m�F����Ƃ����������ŁA�u���𒆎~�����B
�J��Ԃ����A�킪���̃R���i��̊�{�I�p���͊Ԉ���Ă���B�ŗD�悷�ׂ��͍��Ƃ̖h�u�ł͂Ȃ��B�u�����������v�u���Â������v�u�Ƒ��ɂ��������Ȃ��v�Ȃǂ̍����̊�]�ɉ����邱�Ƃ��B���̂��߂ɁA���E���ōݑ���A�I�����C���f�ÁA�u���{�݂��������ꂽ�B���J�Ȃ���{��t��A���̂悤�ȃV�X�e�����������߂��Ƃ����b���Ǖ��ɂ��Ēm��Ȃ��B���̌��ʁA���{�̓R���i�f�Ñ̐��ő傫���o�x��Ă��܂����B
�ݓc���Y�͑��}�Ɋ����ǖ@���������ׂ����B���̍ۂ̃|�C���g�́A���Ƃ̌������������A���ԕa�@�ɖ�����芴���҂������t���邱�Ƃł͂Ȃ��B�����A���ÁA����Ɋu�����錠���Ȃǂ������ǖ@�ŕۏႷ�邱�Ƃ��B��������A�����������āA�����J�����i�ށB���E�́A�����̌��N�d�����т��A2�N�ԂŃR���i�����ς������B���̌��ʁA�I�~�N�������̗��s�ł��Љ�K����v���Ȃ��u�����v�Љ��z���グ���B���܂����A���E����w�˂Ȃ�Ȃ��B
|
�����B�ŐV���ȕψّ́u�X�e���X�I�~�N�����v�A�p�����������@1/24
�p���̕ی����S�ۏᒡ(UKHSA)��1��21���A�uBA.2�v�Ƃ��Ēm���A�ꕔ�̉Ȋw�҂��u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ�ł���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̈�������Ă��邱�Ƃ\�����B
UKHSA��BA.2���u�������̕ψّ́v�Ɏw�肵���Əq�ׂĂ���B����́A�����̕�A���ɍ폜���ꂽUKHSA�̃c�C�[�g�𗠕t���铮�����B
�������A1��10���܂łɉp�����Ŋm�F���ꂽBA.2�̃T���v�����͂킸��53���ł���A�����_�ł͔��ɏ��Ȃ����Ƃ�UKHSA�͋������Ă���B
�ꕔ�̉Ȋw�҂́ABA.2��PCR�����Ŕ�������̂������`�q�\���������Ƃ𗝗R�ɂ��̈�����u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ�ł���B
�f���}�[�N�̕ی��ȎP���̌����@��Statens Serum Institut(SSI)�ɂ��ƁA�p���ł͂��̈���̊����Ґ��͂������������A�f���}�[�N�ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂̔����߂�(45��)��BA.2����߂Ă���A2021�N�̍ŏI�T��20������}�㏸���Ă���Ƃ����B
SSI�ɂ��ƁA�����̕��͂ł�BA.2�́A�I�~�N�����]������BA.1�Ɣ�r���ē��@�����ɍ��͂Ȃ��Ƃ������A���̈��킪�]�����������������͂������̂��ǂ����A���N�`���̌��ʂɉe����^������̂��ǂ����͊m�F���Ƃ����B
�܂��A�t�����X�A�C���h�A�m���E�F�[�̈ꕔ�ł�BA.2�����s���Ă���Ƃ̕��������ł���B
SSI�ɂ��ƁABA.2�͌���ł̓I�~�N�����̈���ɕ��ނ���Ă��邪�ABA.1�Ƃ̈�`�q�̈Ⴂ�͑傫���A���̍����A�d�Ǔx�⊴���͂Ȃǂ̋����̈Ⴂ�ɂȂ���\��������Ƃ����B�������A����𖾂炩�ɂ��邽�߂ɂ͂���Ȃ錤�����K�v���B
�܂��ABA.2�Ɋւ��Ă��u���N�`���̌��ʂ͊��҂ł���v��SSI�͕t���������B
BA.2�ɂ��ẮA�܂����𖾂ȕ����������A�ꕔ�̒n��ł��̈��킪���B���Ă���Ƃ�������ꂽ�؋��������ABA.2���Ɖu���������\�͂������̂��A�d�lj����₷���̂��ABA.1���������͂������̂��ȂǁA���̋����Ɋւ���f�[�^�͌����Ă���B
�I�~�N�����ɂ�3�̈���(BA.1�ABA.2�ABA.3)�����݂��邪�A�Ǘ�̂قƂ�ǂ�BA.1���B�u�������A�f���}�[�N�ł�BA.2���䓪���Ă��Ă���v��SSI�͌x�����Ă���A�p���A�m���E�F�[�A�X�E�F�[�f���ł����K�͂ł͂��邪�����X����������Əq�ׂĂ���B
|
�����������ҁA�T29���l�@���҂������@�V�^�R���i�@1/24
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�24���ߑO10�����݁A�N���[�Y�D�u�_�C�������h�E�v�����Z�X�v��D�҂��܂ߗv��218��1000�l�ƂȂ����B1�T�Ԃ̐V�K�����҂�29��5270�l�ŁA�O�T(11��8317�l)��2�D5�{�ɑ������B
�ψي��u�I�~�N�������v�̊g��ɔ����A�S���e�n�Ŋ����҂������B���҂�1�T�Ԃ�78�l�����A�v1��8522�l�ƂȂ����B
1�T�ԂɊm�F���ꂽ�V�K�����҂̓s���{���ʂł́A������5��5313�l�ōł������A���(3��9823�l)�A�_�ސ�(2��91�l)�ȂǂƑ������B��s���Ȃǂ�葁��9������܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă��鉫���8220�l�ŁA�������͑O�T(9666�l)����k�������B
���҂͍�N12���ȍ~�A1�T�ԓ�����10�l�����Ő��ڂ��Ă������A�O�T(30�l)���瑝���X���������Ă���B�S���Ŋm�F���ꂽ23�����_�̏d�ǎ҂�430�l�ŁA1�T�ԑO��235�l��1�D8�{�ɑ������B
|
���k�C�� �V�^�R���i 1�l���S �V����1589�l�����m�F �@1/24
�k�C���ł�24���A���킹��1589�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B
�����̈���̊����m�F��6��������1000�l���A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��A�D�y�s�͂���܂łɊ������m�F����Ă����A80��̒j��1�l��23���A�S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̉���4��4979�l���܂މ���7��5006�l�A�S���Ȃ����l��1480�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i �k�C������1589�l�����m�F 1�l���S�@1/24
�k�C���ł�24���A�D�y�s�ōėz����48�l���܂�880�l�A���َs��38�l�A����s��32�l�A���M�s��17�l�A�Ύ�n����201�l�A���H�n����111�l�A�_�U�n����105�l�A�I�z�[�c�N�n����48�l�A�\���n����40�l�A��m�n����28�l�A�n���n����26�l�A��u�n���Ə@�J�n����16�l�A�����n����7�l�A�����n����6�l�A���G�n����4�l�A���n����3�l�A�O�R�n����1�l�A����ɁA�����u���̑��v�Ɣ��\�����A���O��5�l���܂�10�l�́A���킹��1589�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�����̈���̊����m�F��6��������1000�l���A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��A�D�y�s�́A����܂łɊ������m�F����Ă���80��̒j��1�l��23���ɖS���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�4��4979�l���܂ނ̂�7��5006�l�ƂȂ�A�S���Ȃ����l��1480�l�ƂȂ�܂����B
�������������� ������10�l����
�I�z�[�c�N�C���ɂ��鏬�����������23���܂łɒ����⋳�璷�Ȃ�10�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B���ł́A�c��E�����悻70�l��Ώۂɂo�b�q������i�߂Ă��邽�߁A�����Ɩ����k�����Ă��܂��B������������ł́A����19������23���܂łɋv�ۍO�u�����⋳�璷�Ȃ�10�l�̊������m�F����A���͓Ǝ��ɃN���X�^�[�̔����\���܂����B10�l�͂�������y�ǂł��B�v�ے����͓��@���Ă��܂����A�a������I�����C���ŐE���ɑΉ��̎w�����o���Ă���Ƃ������Ƃł��B���ł́A�c�邷�ׂĂ̐E�����悻70�l��Ώۂɏ����o�b�q������i�߂Ă��܂��B���̂��߁A24����25���͒����W�ƐŖ��W�݂̂ɑ����Ɩ����k�����A���łɌ����ʼnA�����m�F����Ă���E���őΉ����Ă��܂��B������ł̓N���X�^�[�̔�����m�点��f����������A�h�앞�𒅂��E����������t�߂őҋ@���ė��������l������ɓ���Ȃ��悤�p�������肵�Ă��܂����B���ł͓��ʁA�A�����m�F���ꂽ�E���݂̂ŋƖ����s�����j�ŁA��������ۂ͎��O�ɖ���Ɋm�F���Ăق����Ƃ��Ă��܂��B���������̋v�ۍO�u�����́u���ׂĂ̐E�����N���X�^�[�������d���~�߁A�ҏȂ̂��ƂɊ�@�Ǘ��ӎ��̌������Ɗ����h�~��̓O���}��A�����̊F���܂̐M���ɓw�͂��܂��v�R�����g���Ă��܂��B
���w�W�ł݂铹��������
23�����_�̓����̊����ɂ��āA�V�^�R���i�E�C���X����������邽�߂̃��x�����ނ̎w�W�Ɋ�Â��Č��Ă����܂��B
���S��
�S���ł́A�a���g�p����22.7���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���168.1�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���194.2�l�ƂȂ��Ă��܂��B���̂����A�a���g�p���́A�u0�v����u4�v��5�i�K�ɕ����ꂽ��̃��x���̂����A�u���x��2�v�̎w�W�ƂȂ��Ă���u20���v���Ă��܂��B�V�K�����Ґ��ƁA�×{�Ґ����u���x��2�v�̎w�W�������Ă��܂��B
���D�y�s
�D�y�s�����Ō��܂��ƁA�a���g�p����16.7���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���246.4�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���269.6�l�ƂȂ��Ă��܂��B�V�K�����Ґ��ƁA�×{�Ґ��́u���x��2�v�̎w�W�������Ă��܂��B
���D�y�s�������n��
�D�y�s�������n��ł́A�a���g�p����25.3���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���121.0�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���149.0�l�ƂȂ��Ă��܂��B�a���g�p���A�V�K�����Ґ��A�×{�Ґ��͂Ƃ��Ɂu���x��2�v�̎w�W�������Ă��܂��B
��
�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑O��1�T�ԂƔ�ׂāA�S���ł��悻3.4�{�A�D�y�s�ł��悻4�{�A�D�y�s�������n��ł��悻2.8�{�ɑ�����ȂNj}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B���́A���̂܂܊����҂̋}���ȑ������������ꍇ�ɂ͈�Â��Ђ���������A�Љ�@�\�̈ێ��ɉe�����������肷�鋰�ꂪ����Ƃ��āA����21���A�����S��ő�̃��x�����u2�v�Ɉ����グ��ƂƂ��ɁA���{�ɑ��A�܂h�~���d�_�[�u��K�p����悤�v�����Ă��܂��B
|
���{���285�l�����@3���A��200�l���@�C����̈��H�X�ŃN���X�^�[�@1/24
�{�錧�Ɛ��s��23���A10�Ζ����`80��̒j��285�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B22�����32�l�����A3���A����200�l�����B�C����s�̎�ނ������H�X��23���܂ł�7�l�̊������m�F����A���̓N���X�^�[(�����ҏW�c)�����ƔF�肵���B
�V�K�����҂̓���͐��s185�l�A�Ί��s21�l�A����s12�l�A�ēc��10�l�ȂǁB�����_��163�l(57�E2��)�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B
�N���X�^�[�֘A�̊����҂͐��s�̌�y�{�݂�1�l����11�l�A�c�t����1�l����43�l�A���w�Z��3�l����9�l�A�ۈ�{�݂�10�l����21�l�ƂȂ����B
�ߌ�1�����_�̌����̗×{�҂�1262�l�B����͓��@72�l�A�h���×{619�l�A����×{323�l�ȂǁB�m�ەa��(510��)�g�p����14�E1���B��������\�a��(174��)�g�p����41�E4���ɏ㏸�����B��������Ì��͊m�ەa��(329��)��17�E6���A����\�a��(94��)��61�E7���B
�v�����҂�1��8090�l(���s��1��1254�l)�B1��6525�l���މ@�E�×{�����ƂȂ����B |
���Ȗ،� �V�^�R���i 1�l���S �V����422�l�����m�F �@1/24
�Ȗ،��ƉF�s�{�s�́A24���A�V���ɂ��킹��422�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�܂��A�Ȗ،��́A����21���Ɋ������m�F���ꂽ�Ƃ��Ĕ��\����2�l�ɂ��āA24���A���\����艺���܂����B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A�v��2��8�l�ɂȂ�܂����B���̂ق��Ȗ،��͐V���Ɋ���1�l�����S�����Ɣ��\���A�����Ŏ��S�����l��121�l�ɂȂ�܂����B
|
�������s �V�^�R���i 1�l���S 8503�l�����m�F ��T���j����2�{�� �@1/24
�����s����24���̊����m�F��8503�l��1�T�ԑO��2.3�{�ƂȂ�A���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s��24���A�s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v�܂ł̒j�����킹��8503�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�ߋ��ő�������1�T�ԑO�̍���17����肳��ɂ��悻4800�l�����A2.3�{�̑����ŁA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B���łɑ�5�g�̃s�[�N�������Ă���7���ԕ��ς�24�����_��8000�l����8585.3�l�ƂȂ�܂����B�O�̏T��2.6�{�ł��B
24���A�������m�F���ꂽ8503�l�̔N��ʂł�20�オ�ł�����2248�l�őS�̂�26.4���ł��B������30�オ1456�l�őS�̂�17.1���ł����B���̂ق�10�Ζ�����1068�l�őS�̂�12.6���A10�オ1001�l��11.8���ł��B10�Ζ�������30��܂ł��S�̂�7���߂����߂Ă��܂��B65�Έȏ�̍���҂�552�l�ł��B�܂�24���A�������m�F���ꂽ8503�l��4���]���3717�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��܂����B
����A�s�̊�ŏW�v����24�����_�̏d�ǂ̊��҂́A23�����1�l������12�l�ł����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ80��̏���1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B24�����_�œ����s���̕a���g�p����36.7���ƂȂ�܂����B23������1.4�|�C���g�㏸���Ă��܂��B�܂��d�NJ��җp�̕a���g�p����2.4���ł��B
|
�����m�� �V�^�R���i 3�l���S 2492�l�����m�F �@1/24
���m���͌����ŐV����2492�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�܂��L���s�́A22���̔��\�ɏd�����������Ƃ��āA���̓��̊����Ґ���1�l���Ȃ�192�l�ɒ���������23�����\���܂����B���̂��߈��m�����ł̊����m�F�͉���13��5981�l�ɂȂ�܂����B�����Ė��É��s�ƈ�{�s�͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��������3�l��22���܂łɎ��S�����Ɣ��\���܂����B���m�����Ŏ��S���������҂�1173�l�ɂȂ�܂����B
|
��1�T�O���1339�l���c�V�^�R���i ���m�̐V�K����2492�l�@1/24
���m���ł�24���A�V����2492�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��܂����B���Ȃǂɂ��܂���1��24���́A�V����2492�l(�ėz��39�l)���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��A���É��s��1023�l(�ėz��28�l)�A�L���s��134�l(�ėz��1�l)�A����s��134�l�A�L�c�s��81�l(�ėz��1�l)�A��{�s��69�l�A���̑��̎s����1051�l(�ėz��9�l)�ł��B���É��s�ł�2�l���S���Ȃ������Ƃ����\����Ă��܂��B
���m����1�T�ԑO�E1��17�����j���̐V�K�����Ґ���1153�l�ŁA1339�l�����܂����B1��23���܂ł�7���Ԃɂ�����1��������̕��ςł́A�V�K�����Ґ���2658.7�l�A���̂���70�Έȏオ135.3�l�A���@���Ґ���259.1�l�A�d�ǎҐ���2.1�l�ł��B1��16���܂ł�7���Ԃɂ�����1��������̕��ϗz�����́A14.1%�ł��B1��23�����_�ŁA���m���̃R���i��p�a���ɑ�����@�Ґ���353�l�ŁA�g�p����30.9���A�d�ǂ�3�l�A�����ǂ�96�l�A�y�ǁE���Ǐ�279�l�A����×{�҂�17069�l�ł��B
|
�����{ �V�^�R���i 1�l���S 4803�l�����m�F ���j�ł͍ő� �@1/24
���{��24���A�V����4803�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
��T�̌��j����2549�l��傫������A���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B����ő��{���̊����҂̗v��26��7486�l�ƂȂ�܂����B�܂��A1�l�̎��S�����\����A���{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l��3079�l�ɂȂ�܂����B����A�d�ǎ҂̐l����23�����5�l�����āA28�l�ɂȂ�܂����B
|
���V�^�R���i�e�� �ۈ珊�₱�ǂ����̑S�ʋx��327���� �ߋ��ő� �@1/24
�V�^�R���i�E�C���X�Ɏq�ǂ���E�����������S�ʋx���ƂȂ����ۈ珊�Ȃǂ́A�����J���Ȃɂ��܂��ƍ���20���̎��_��27�̓s���{����327�����ƂȂ肱��܂łōł������Ȃ�܂����B
�����J���Ȃ��S������̕��܂Ƃ߂��Ƃ���ɂ��܂��ƁA�{�ݓ��Ŏq�ǂ���E�����������S�ʋx���ƂȂ����ۈ珊�₱�ǂ����͍���20���̎��_��27�̓s���{����327�����ɏ���Ă��܂��B
�O�̏T�̍���13���ɂ�14�̓s���{����86�����ł������A1�T�Ԃ�3�{�ȏ�ɂȂ��5�g�̂��Ȃ����������N9��2����185�����������ĉߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��S�ʋx���̐��͍���6���ɂ�7�����ł�����2�T�Ԃŋ}���ɑ����Ă��āA�����̊g�傪�ۈ�̌���ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��Ă��܂��B
�����̔F�肱�ǂ��� ���������ŋx����
�����g�傪�������s�ł͐�T21���̎��_�ŕۈ珊�̂��悻7����1���x�����鎖�ԂƂȂ��Ă��܂��B24�����V���ɉ����̊������m�F���ꂽ�s���̕ۈ�{�݂ŕی�҂ɋ}����A���Ԃ𑁂߂Č}���ɗ��Ă��炤�ȂǑΉ��ɒǂ��܂����B
���悻200�l�̎q�ǂ����ʂ���� �s����̔F�肱�ǂ����u����c���ǂ�ۈ牀�v�ł�24���ߑO�A�ی�҂���̘A���ʼn������V�^�R���i�Ɋ������Ă������Ƃ�������܂����B���̂��ߒ��H��ɋx�������߁A�q�ǂ����}���ɗ��Ă��炤�悤�ی�҂Ƀ��[���ŘA�����܂����B�ی�҂����͎��X�ɖK��ĕۈ�m����ɂ��Đ����������Ǝq�ǂ���A��ċA��Ă��܂����B
���w�Z�ŋ��t�����Ă���Ƃ���40��̕�e�́u�Ζ���̊w�Z�ł��������L�����Ă���B�����Ɏ����b���Č}���ɂ������A�����g�傪��������ɑ�ςȂ��ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����S�z���v�Ƙb���Ă��܂����B
���ɂ��܂��ƁA�ی�҂̂��悻3������Â���A�ۈ�Ȃǂ̎d���Ɍg��邢����G�b�Z���V�������[�J�[���Ƃ������Ƃł��B���̉��ł͉����̃}�X�N���p�₨������̏��ł̂ق���_���Y�f�Z�x�̑��������ׂĂ̕����ɐݒu���Ċ��C�����܂߂ɂ���ȂǑ��O�ꂵ�Ă��܂����A�n��Ŋ������g�傷�钆�Ő�T�������̊�����������x���������肾�����Ƃ������Ƃł��B
�u����c���ǂ�ۈ牀�v�̍]��i���q�����́u�����^�C�~���O�ōēx�̋x���ɂȂ�炢�v���ł��B�ی�҂������₷���悤�ɂ��邱�Ƃƈ��S����邱�Ƃ̗����̂��߉����ł���̂����₢�����Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
|
����������2013�l�����@6���A��2��l���@�V�^�R���i�@1/24
��������24���A�V����2013�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B6���A����2��l�����B���ǎ����̕ʂ̊����Ґ��́A�����s686�l�A�k��B�s295�l�A�v���Ďs115�l�A��917�l�B
|
�������ŕی����Ђ����u�A���Ȃ��v��Ë@�ւɑ��k�ŐV���ȕ��S�� �@1/24
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�钆�A�����s�ł͊����҂ւ̘A���Ȃǂ��s���ی����̋Ɩ����Ђ������Ă��܂��B�s���̈�Ë@�ւɂ́u�ی�������A�����Ȃ��v�ȂǂƂ��āA�����҂�Ƒ�����Ή��𑊒k����d�b���������ł��āA�V���ȕ��S�ɂȂ��Ă��܂��B
�����s�ł́A�ی����������҂ƘA�����Ƃ�A���N��Ԃ̊m�F��×{��̈ē��Ȃǂ��s�����ƂɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ��낪�������}�g�傷�钆�A�����҂ւ̘A���Ȃǂ��s���ی����̋Ɩ����Ђ������Ă��āA�����s��t��ɂ��܂��ƁA�s���̈�Ë@�ւł́u�ی�������A�����Ȃ��A�ǂ��Ή����Ă������킩��Ȃ��v�ȂǂƊ����҂�Ƒ����瑊�k�̓d�b���������ł���Ƃ������Ƃł��B
���̂����A�������������̐f�Ï��ł́A��5�g��1���������������k�̓d�b���A��T�͑������ł��悻30���ɏ���Ă��āA���k�ɉ�������t�����N��Ԃ��ڂ����m�F������APCR������f�@�̓����������肷��ȂǁA�V���ȕ��S�ɂȂ��Ă��܂��B���̐f�Ï��ł́A���O�̘A���Ȃ��ɐf�Ï���K��Ĕ��M�₯��ӊ���i����l�������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�f�Ï��̖��c�_����t�́u���܂��܂Ȗ₢���킹���E�����Ă��āA�R�[���Z���^�[�̂悤�ȏ�Ԃł��B����ɂ���āA�Ζʂł̐f�@�ɏ\���Ȏ��Ԃ��Ƃ�Ȃ��Ƃ����ɂ��Ȃ��Ă��܂��B������Ƃ����đ��k���t���Ȃ��킯�ɂ��������A���ɑ��Z�ɂȂ��Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
|
�����[�����u15���{������܂h�~�K�p�̗v���v����������� �@1/24
�V�^�R���i�̊������������钆�A���{�͂܂h�~���d�_�[�u�̓K�p����3�{���Ȃǂɂ��g�傷����j�ł��B���슯�[�����͌����_�őS����15���{������d�_�[�u�K�p�̗v�����������Ƃ��������ŁA���₩�ɔ��f����l���������܂����B
�V�^�R���i�̊����̋}�g�傪�������A���A���ɁA���s�̊�3�{���̂ق��A�k�C����É����Ȃǂ��܂h�~���d�_�[�u�̓K�p��v�����A���{�͗v���̂����������̂ɓK�p���g�傷����j�ł��B
���슯�[�����́A�ߑO�̋L�҉�Łu�����_�ŁA�k�C���A�X�A�����A�ȖA���A�É��A�ΐ�A���A���s�A���ɁA���R�A�����A�啪�A����A��������15���{������v�������Ă���v�Ɩ��炩�ɂ��܂����B
���̂����Ŏ����̂���̗v�����āA���₩�ɔ��f����l���������܂����B
�܂�����̑�ɂ��āu�ݑ�A�h���×{���܂߈�Ò̐��̊g�[��}��ƂƂ��Ƀ��N�`���⎡�Ö�Ƃ������\�h���瑁�����Â̗�����������Ă������Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ܂����B
����d�_�[�u��K�p���A����31���܂ł̊���������������j�̉���A�R���A�L����3���ɂ��āA���슯�[�����́A����ł͕a���g�p����6����ƂȂ��Ă���ȂǂƂ��Ĉ��������������Ă����K�v������Ƃ����F���������܂����B
�܂����������A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�����24���ߑO�A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�����ɗv�����܂����B
|
���܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�g�� ���{ 25���ɐ�������� �@1/24
�V�^�R���i����߂���A���{�͂܂h�~���d�_�[�u�̓K�p����3�{���╟�����Ȃǂɂ��g�傷����j�ŁA24���A�ݓc������b���W�t���Ƌl�߂̒������s���A25���ɐ��ƂɎ����������Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�V�^�R���i�̐V���Ȋ����҂́A23���܂�2���A���őS����5���l���A�e�n�ŕa���̎g�p�����㏸���Ă��܂��B
�����������A���A���ɁA���s�̊�3�{���Ȃǂ���T�A���{�ɂ܂h�~���d�_�[�u�̓K�p��v�������̂ɑ����A22���ɂ͉��R�����v���������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
����ɋ�B�̕����A����A�啪��3���ȂǁA�����̎����̂��v����������ƂȂ��Ă��܂��B
�ݓc������b��23���A�㓡�����J����b��R�ېV�^�R���i���S����b��W�t���Ɖ�k���A�����̂���̗v���̓����܂��A����̑Ή������c���܂����B
���{�͗v���������������̂ɑ��Ă͏d�_�[�u��K�p������j�ŁA24�����ݓc������b���W�t���Ƌl�߂̒������s���A25���A���ƂɎ����������Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�܂��d�_�[�u��K�p���Ă��鉫��A�R���A�L����3���ɂ��Ă������Ȃǂ��l�����A����31���܂łƂȂ��Ă���������������邱�Ƃ��Č��肷����j�ł��B
����A�I�~�N�������̊����g����Č㓡��b�́A���݁A�ŒZ��6���ڂɉ��������A�Z���ڐG�҂ƂȂ����u�G�b�Z���V�������[�J�[�v�̎���Ȃǂł̑ҋ@���Ԃɂ��āA�K�v�ɉ����Č���������������l���������܂����B
���{�̓I�~�N�������̓����܂��A���������A�Љ�@�\���ێ����Ȃ��犴���g��h�~��}��A�o�ςւ̉e�����ŏ����ɂƂǂ߂����l���ł��B
|
���J�i�_�A�I�~�N�������s�s�[�N�A�E�g���@���@�Ґ��Ȃ��}���@1/24
�J�i�_�A�M���{�̃e���T�E�^�����O�q���ǒ���21���A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��I�~�N�����̗��s���s�[�N��ł����\��������������������Ƃ������A���@�Ґ��͈ˑR�Ƃ��ċ}�����Ă���A�a�@�ɋ������ׂ��������Ă���Əq�ׂ��B
�����O�ɂ́A�J�i�_�̐l���̂��悻61�����߂�I���^���I�B�ƃP�x�b�N�B�̓��ǎ҂��A�I�~�N�������s�̍ň����͋߂��I���\��������Ƃ̌����������Ă���B
�^�����͋L�҉�ŁA1��������̐V�K�����Ґ����O�T���28����������Ȃǁu�S�����x���ł͊������s�[�N��ł������Ƃ����������I�Ȓ�����v�Ǝw�E�B�u�������A���@�Ґ���W�����Î��̊��Ґ��͈ˑR�Ƃ��ċ}���ɑ������Ă���A�S���̕a�@�̑����ɂ͋������ׂ��������Ă�v�Ƃ����B
�^�����ɂ��ƁA�ߋ�1�T�Ԃ�1��������̓��@�Ґ��͕���1���l�ȏ�ƁA�ߋ��̊����g��̃s�[�N�����������Ă���B
|
���I�~�N�����������߂��s�[�N�ɒB���飂ƃt�@�E�`���@1/24
�č����A�����M�[�����nj�����(NIAID)�̃t�@�E�`�����͐V�^�R���i�E�C���X�ɂ��Ĥ�I�~�N�����ψي��ɂ��L�^�I�Ȋ����ҥ���@�҂̑������߂��s�[�N�ɒB����Ƃ̊y�ϓI�Ȍ������������B���������y�[�X�͒n��ňقȂ褈�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���B
�o�C�f���哝�̂̎�Ȉ�Ìږ�߂�t�@�E�`����23�����ߐM�͋֕�����������_�ł͐����������Ɍ������Ă���ƌ����飂�ABC�̔ԑg�Řb�����B
��A�t���J���a���Ȃǂł̃I�~�N�������̋O�ՂƓ��l��č��̖k�����ƒ������Ŋ����҂���}���Ɍ������n�߂Ă��飂Ɠ����͎w�E�B���Ȃ������Ґ����������Ă���암�Ɛ��������l�̌o�H�����ǂ錩�ʂ�����������y�[�X�̓��N�`���ڎ헦�ō��E�����ƌ�����B
|
���I�~�N�������g��A���@�Ґ��͌��������ĂŐ[���ȉe������ �@1/24
�č���22���A�V�^�R���i�E�C���X�����ɂ����@�Ґ���7���ԕ��ς�15��8788�l�ƂȂ�A2���A���Ō��������B�����Ȃ����炩�ɂ����B�܂��S���̐V�K���@���Ґ����������Ă���B
�����ꕔ�̏B�ł̓I�~�N�������̊����g��ɂ��e�����[�������A�����ɂ�鎩��×{�҂����S���l�ɒB���Ă���B���������ǂ�1����{�Ɏ��{���������ɂ��A�V�^�R���i�ւ̊������A�����̏Ǐ�����l�̊ŕa�Ŏd�����ł��Ȃ��Ƃ����Ґ��͖�880���l�������B���ǂ�2020�N���ɓ��l�̒������J�n���Ĉȍ~�ōł������A����܂ł̋L�^�ł���21�N1����660���l��啝�ɏ������B
���B�ł̓I�~�N�������̊����̔g���s�[�N���z�����������A�ꕔ���{�͓��퐶���Ɋ֘A����K�����ɘa���n�߂Ă���B�A�C�������h�ł�22���A�ڋq�Ƃ̉c�Ǝ��Ԃ��p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�ȑO�ɖ߂����Ƃ��F�߂�ꂽ�ق��A�\�[�V�����f�B�X�^���X(�Љ�I����)�̈ێ��Ɋւ���K�����P�p�B�����O�̃C�x���g�ɂ��Ă�����l���݂͐��Ȃ��ȂǁA���O�q���ʂ̂قƂ�ǂ̋K�����������ꂽ�B
�t�����X�ł͗����ɂ��I�t�B�X�Ζ��𑝂₷���Ƃ�A�i�C�g�N���u�̉c�ƍĊJ��F�߂�ɘa�����{��������A�V�^�R���i���N�`���̐ڎ�Ɋւ���V���Ȗ@����24������{�s����A���ڎ�҂�ΏۂɐV���ȋK�����u������B�����ł�22���̊����Ґ����ߋ��ō�������38��9320�l�ɒB�������A�W�����Î�(ICU)�Ŏ��Â��Ă���R���i���Ґ���1�T�ԑO�Ɣ�ׂ�3���������Ă���B |
���V�^�R���i�A���B�Ńp���f�~�b�N�������@WHO�����������@1/24
���E�ی��@��(WHO)�̃N���[�Q���B�n�掖���ǒ���23���AAFP�ʐM�̃C���^�r���[�ɉ����A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v���҈Ђ�U�邤���B�ŁA�p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�������Ɍ������\��������Ƃ��錩�����������B
�I�~�N�������̗��s���߂�����A�u���N�`���ڎ�A�����ɂ��Ɖu�l���A�܂������҂���������G�߂��}���邱�ƂŁA���T�ԁA�܂��͉��J���ԁA�L�͈͂ŖƉu���l�����ꂽ��ԂɂȂ�v�Ǝ咣�B�܂��A���B�ł�3���܂łɑS�l����60���������Ɋ�������\���ɂ����y�����B
�I�~�N���������߂����ẮA���N�`���ڎ�ς݂ł���Εψي��u�f���^���v�����y�ǂōςތX��������ƁA�����̌����ŕ���Ă���B����ɂ��V�^�R���i���G�ߐ��C���t���G���U�̂悤�ɑΏ��\�ȕa�C�ւƈʒu�t�����ς��Ƃ������҂����Ă���B
�N���[�Q���́u(�Ώ��\�ȕa�C�Ƃ�)�ǂ̂悤�ȏǏ\��邩��\���ł���Ƃ����Ӗ��B����܂ʼn��x���V�^�R���i�ɋ�������Ă����̂ŁA(��������)�\���ɋC��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƒ��ӊ��N�����B�@ |
���C�O�ŐV���ȕψّ̃X�e���X�I�~�N���������I�Ǐ�ƃ��N�`������ �@1/24
1��21���C�M���X�̕ی����S�ۏᒡ�͈ꕔ�̉Ȋw�҂�BA.2���u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ�ł���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̈�������Ă��邱�Ƃ\���܂����B�u�X�e���X�I�~�N�����v�Ƃ͂ǂ�ȃE�B���X�Ȃ̂ł��傤���B�Ǐ�͂ǂ�ȏǏ�Ń��N�`���͌��ʂ�����̂ł��傤���H
�u���B�ŐV���ȕψّ̃X�e���X�I�~�N��������
�I�~�N���������^BA.2�ŁAPCR�Ō��o���ɂ������ł��邱�Ƃ���X�e���X�I�~�N�����ƌĂ�A�f���}�[�N�ł̓I�~�N����������u������肻���ł��B�ψىӏ����]���̃I�~�N�������Ƃ��Ȃ�قȂ��Ă���A�d�lj����X�N�͂܂��s���v
BA.2�͌���ł̓I�~�N�����̈���ɕ��ނ���Ă���BA.1�Ƃ̈�`�q�̈Ⴂ�͑傫���d�Ǔx�⊴���͂Ȃǂ̋����̈Ⴂ�ɂȂ���\��������Ǝw�E���Ă��܂��B�܂�PCR�ɂ��������Ȃ��P�[�X������̂ł��傤���H������BA.2�Ɋւ��Ă��u���N�`���̌��ʂ͊��҂ł���v�Ƃ��Ă��܂��B
�ی����S�ۏᒡ�ł�BA.2���u�������̕ψّ́v�Ɏw�肵�Ă���悤�ł���1��10���܂łɉp�����Ŋm�F���ꂽBA.2�̃T���v�����͂킸��53���ɂƂǂ܂��Ă���悤�ł��B�����_�ł͔��ɏ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�@ |
 |


 �@
�@ |
������{�̓R���i�ł��܂Ŏ��s���J��Ԃ��̂�� �@1/25
�V�^�R���i�E�C���X�̊������Ăъg�債�A�u�܂h�~���d�_�[�u�v���e�n�ɓK�p���ꂽ�B��t�̑�a�c�����́u�V�K�����҂�}���邽�߂ɐl�X�̕�炵���]���ɂ���͖̂{���]�|���B�R���i���Ƃ͍Ăю��s���J��Ԃ����ƂɂȂ�v�Ƃ����\�\�B
���R���i���Ƃ����o���Ă������|���痣���ׂ�
���{�͊֓��Ⓦ�C�Ȃ�16�s���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�o���܂����B25���ɂ͖k�C������A���s�A���ɂ̊�3�{���Ȃnjv18���{���������錩���݂ł��B
���H�X�̎��Z�c�Ƃ�u�l�������v�����߁A��炵��o�ς��Ăя������n�߂܂����BWHO���n�q�K�����u�I�~�N�������ł͎��{���鉿�l���Ȃ��A�o�ϓI�E�Љ�I�ȕ��S���e���ɋ�����v�𗝗R�ɓP�p�����ɂ�������炸�ł�(��1)�B
���Ƃ����S�ɂȂ��ē��{�ōs���Ă����u���l�v�Ɓu���N�`���ڎ�v�ɕ����R���i��̃}�l�W�����g���s���A�I�~�N�������ɂ���ČJ��Ԃ���A���߂đN���ɂȂ�܂����B
���s�̌����͖��m�ł��B��͐V�KPCR�z���Ґ�(�����Ґ�)�ɍS�D���A�V�^�R���i����ŁE��݃E�C���X�������ɂ�������炸�A��̊�{�I�ȓ��e�����������Ƃ�ӂ������߂ł��B
�g����̉ʂĂ�2�ނ̂܂܁u��҂͌��������ɐf�f�v�Ɛ��Ƃ����������n�߂����ߌ���͖������J�I�X��ԂɊׂ��Ă��܂��B�h�앞�͕K�v�Ȃ�ł��傤���B��҂��ĉ��˂܂łł��傤���B�ӂ��肵�Ă��܂�(��2)�B
���ہA�u�d�_�[�u�v�̌��ʂɑ��Ď����̂̃g�b�v����͂��̌��ʂ��^�⎋���鐺���オ�蔻�f������Ă��܂��B�ޗnj��̍r�䐳��m���́u�܂h�~���d�_�[�u��ً}���Ԑ錾�͌��ʂ��Ȃ��v�Ɩ��m�ɕ\�����d�_�[�u��v�����܂���ł���(��3)�B
���łɏd�_�[�u�����{���Ă���n���ł͐l���}���ɂ��o�ϓI���������債�Ă��܂��̂�(��4)�A�s����������邽�߂Ɍ�����ÂɊώ@����Γ��R������锻�f�ł��B�����g��̋��|�Ɏx�z����钆�ł��Ȃ��ꂽ�A���������E�C�̂���K�Ȕ������ƌ�����ł��傤�B
�������ƐV�^�R���i�̕t��������2�N�ȏ�ɂȂ�A�K����������G�{�����݂̒v�����̍����E�C���X�ł͂Ȃ��A��N���炳��Ɏ�ʼn����ď�݃E�C���X�ɕω����Ă������Ƃ��ώ@����Ă��܂��B
�ɂ�������炸�����҂������邽�тɔ��o�����ً}���Ԑ錾��d�_�[�u�ŁA�������͕�炵��o�ς����댯�����������Ă��܂����B�{���̓R���i���Ƃ����̂��Ƃ𖾝��ɕ��͂��ĎЉ�s��������������ׂ��Ȃ̂ł����A���{�ł͎��������g���I�������Ȃ��Ɛ�����d���ȂǕ�炵�����ł����邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��ł��B
�����s�s�[�N���߂�������̃f�[�^
�����ŐV�^�R���i�E�C���X(�I�~�N������)���m�F����Ă������2�J���o�߂��܂��B�ǂ����������̂��̂������̂��A�L���ɐV�������ꌧ���ł̊�����U��Ԃ��Ă݂܂��傤�B
2022�N�N�n����̗��s�́A���ꌧ�ɂƂ��ĉߋ��ő�̂��̂ł����B���ꌧ�̔��\�����ɂ��ƁA������52�l�����������m�F���A15���ɂ͉ߋ��ő���1��1829�l�ɂ܂ŋ}�����܂����B���݂�1000�l�ȏオ�z���ɂȂ��Ă��܂����A�s�[�N�͉߂�����܂��B
���S�Ґ��͂ǂ��ł��傤���B11��12���̔��\�ȍ~��1��22���̔��\(399���)�܂Ń[���������܂����B1��24�����_�̏d�ǎҐ���5�l�A�����ǂ�251�l�ƂȂ��Ă��܂�(��5)�B
�S���W�v������ƁA�m�F���ꂽ�z���Ґ���1��5���l�����������܂������A���S�҂�1��10�l�O��Ő��ڂ��Ă��܂��B�ǂ̓s���{��������Ɠ����o�߂����ǂ�ł��傤�B1�̌���1�l�̎��S�҂����邩���Ȃ����ł��B
�I�~�N�������̖��Ǐ�҂�90���ȏ�ɂ̂ڂ�܂��B���Ƃ��ƃf���^���ł��A�p���I��7�`8�������Ǐ�ł����B�z���Ґ����ǂ�Ȃɑ����Ă��u���Ǐ�v�Ȃ�J�[�ł�����܂���B
���̗z���Ґ��̑����ƁA�d�lj��⎀�S��Q�̘���������́u�����N��v�A�C�O�ł́udecoupling�v(�f�J�b�v�����O�A��A��)�ƌĂ�܂��B���{�ł͍ŏ�����ώ@����Ă��āA�f���^���̊������L���������ɂ���ɖ��m�ɂȂ��Ă��܂����B
�������������Ƃ́A�݂Ȃ������̂Ƃ��胁�f�B�A�͕܂���B
����łȂ̂͐��E�I�ɓ��l�A���{�́u�����g�ȉ��v
���̌��ۂ́A�I�~�N���������ŏ��ɔ������ꂽ��A�t���J�̗��s�ł������ł��B��A�t���J�ł͍ő�̗z���Ґ����L�^���܂������A���Ƀs�[�N�͉߂��Ă��܂��B�s�[�N���s�������オ��A3�`4�T�Ԃقǂŗ��������܂���(��6)�B
���S�Ґ��͂�����(�}�\3)�ł��B�f���^���ɔ�ׂĂ͂邩�ɏ��Ȃ���Q�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B����Ŋώ@����Ă��邱�ƂƓ����ł��B
���x�͐��E�Ɠ��{�̔�Q�̎��Ԃł���100���l������̎��S�Ґ����r���Ă݂܂��傤�B���{�̏ꍇ�́u�R���i�����s���͂��߂��ŏ�����v���E�̗��s�ɔ�ׂ�Ɓu�����g�v�ł��B
���݂̗��s�́A���E��r�ł̓O���t��͎R���`���ł��Ȃ��قǏ����ł���(Our World in Data)�B���N�`��4��ڐڎ�������Ȃ��Ă���C�X���G���ł͗z���Ґ����������n�߂Ă��܂��B
�����Ƃƒn�������̂ɂ�閳�Ӗ��Ȗh���
���̐V�^�R���i�E�C���X���I�~�N�����������̂��s���Ȗ��m�̃E�C���X�ł͂���܂���B���{�Ŋώ@����Ă������ۂ͈ȉ��ł��B
1�D�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�z���Ґ��⎀�S�Ґ��͐��E�I�ɂ݂čŏ�����u�����g�v�������B
2�D�V�K�z���Ґ��Ǝ��S�Ґ��́A�f���^������A�����Ȃ����Ƃ����m�ɂȂ�u�����N��v���N�����Ă���B�I�~�N�������ł͂���ɂ��ꂪ�����ɂȂ�A����ł͎��S�҂͂قڃ[���������B���̌X���͐��E�I�Ȃ��̂ł���B
3�D���N�`���ڎ��p��ɂ����Ȃ��Ă��A�z���Ґ��͑�������B
4�D�E�C���X�̎�ʼn��ɂ���ă��N�`���̕K�v�����}���Ɏ����Ă���B�s�v��PCR�ǐՂƔZ���ڐG�Ҕr���ɂ���ĎЉ�����J��Ԃ���Ă����B�S�����Ɍ����ƃ��N�`���ڎ���w���������Ƃ���̕������n�߂��B
5�D�s�p�ӂȎЉ�l�����������{�o�ς͎��ł��Ă���B���E�ɔ�ׂĕ������x��Ђǂ����Â����Ă���B
�����ŋ������Ă����������Ƃ�����܂��B����́A�������������ׂ��͐V�^�R���i�����A�o�ς̒���ɂ���炵�����������Ƃ��������ł��B
������㎁(�݂��ً�s �`�[�t�}�[�P�b�g�E�G�R�m�~�X�g)�̓R���i��Ƃ��Ă̋K���������ǂꂾ����Ƃ�ƌv�ɉe�����y�ڂ����A�v���W�f���g�I�����C���̋L���u�w�ڐ�̐��_�ɂ͋t�炦�Ȃ��x�ݓc�������R���i�K���ɓ˂�����g�ߌ��I�Ȍ����h�v�Ŗ��m�Ɏw�E���܂���(��7)�B
�V�^�R���i��}�����ނ��߂ɘA������鎩�l��K���ɂ���āA�o�ς͈����������ł��B���{�̏ꍇ�̓R���i�ȑO���璷���I�ɒ�����Ă��܂�������A���E�ɔ�ׂĂ��[���ł��B���ꂪ�������̌ٗp�⋋���A���X�̕�炵�ɔ��f����Ă��܂��B
���l�X�̋��|���א��҂��ޏk�����鈫�z��
�`���ŁA�d�_�[�u�̌��ʂ��^�⎋���A�v���̌������\�������ޗnj��m���́u�E�C�̂��锭���v���Љ�܂����B
�Ȃ��u�E�C���v��v���Ƃ����ƁA�V�^�R���i���قƂ�ǖ��Q�ł���A��݂�����̂ɂȂ��Ă��u�R���i�͂����܂Ŋ������ׂ��v�Ƃ����ԈႦ���F���������̊Ԃ��略�@�ӂ����傭����Ȃ�����ł��B�Ƃɂ����ǂ�Ȃ��̂ł��R���i�̓_���ȂƂ����ӎ��ł��B
�ݓc���Y�́u��肷���̂ق����܂��v�Əq�ׂ�ȂǁA�I�~�N���������m�F����Ĉȍ~�A���ۑ����������Ȃǂ������ʁA���t�x�����͐�����������ߋ��ō��ƂȂ�܂����B�܂h�~�d�_�[�u�̓K�p�����̉������ł��B
1��23���ɓ��J�[���ꂽ���ꌧ����s���I��7���̎Q�@�I�ȂǁA���N�͏d��ȑI�����߂��뉟���ł��B�����͋��|�ƕs���ɂ����Ȃ܂ꑱ���鐢�_�̐��������Ė����ł��܂���B
�܂��A�������̈ӎ���ς��Ȃ���Ȃ�܂���B�O�q�̓������̔��������A�u�o�ςɗ^����_���[�W���N���[�Y�A�b�v����Ă���w���߂��̕����܂��x�Ƃ������݂̃R���i��̊�{�p���v���C������Ă������Ƃł��傤�B
���������u�R���i�͂����܂Ŋ������ׂ��v�Ƃ����F�����A���E����{�Ŋm�F���ꂽ�f�[�^����ɁA�������̈ӎ����A�b�v�f�[�g���Ă����Ȃ���Όo�ς���炵���悭�Ȃ�܂���B
������ŏ�����������āA���܂��Ɏ��l�ƃ��N�`����ӓ|�𑱂��Ă���̂��A�R���i���Ƃł��B�R���i�̊����g�哖������p������Ă���}�l�W�����g���s�̖{���Ɛl�Ђ̌������ƌ�����ł��傤�B���܂Ŋ����g��Ƃ��Z���ڐG�Ȃ�Č����Ă���̂ł��傤�B�{���Ȃ�R���i�̂���Ȃ��ŕω����A�h�o�C�X����̂́A���Ƃ̎d���̂͂��ł����B
���q���Ƀ��N�`���͕K�v�Ȃ̂�
���Ƃ̃}�l�W�����g�̎��s�́A���_�ȍs���ɂ��Ȃ����Ă��܂��B���Ǐ�҂�y�ǎ҂����|�I�����ł���ɂ�������炸�APCR�����ƔZ���ڐG�҂̒ǐՂ�ی����͋������A�@�\�s�S�Ɋׂ��Ă܂��B���{�o�ϐV���́u�Z���ڐG180���l���Z�A�Љ�@�\�Ɏx��@�l��s���[���Ɂv�Ƃ����L���ŁA���̌����Ă��܂�(��8)�B
�q�������ɂ����e�����o�Ă��܂��B
���͍ŋ߁A�N���j�b�N��K�ꂽ���q����u�搶�A�����āB�w�Z�̂ǂ����ɗz���ɂȂ����q���o�āA�x�Z�ɂȂ����������ł��B���낢��Ȋy���݂ɂ��Ă����Â������S���L�����Z���B���̂��q��������Ǐ�݂����Ȃ�ł��B���̂��߂̋x�Z�Ȃ�ł����v�Ǝ��₳��܂����B
���́u��݃E�C���X�����_�ɒ��ׂ邩�炾�Ǝv���܂��v�Ɠ�����̂��������ς��ł����B
���鏬���Ȃɋ߂�����u�Ƃɂ����s�����ʓ|�ł��B���Ǐ�̎q���ł��z�����Ɛ\��������A�Z���ڐG���u��������B�Ƃɂ������Ӗ��Ȃ��Ƃ̘A���ł��v�Ƌ����Ă���܂����B
�u�R���i�͂Ƃɂ�������������_���A����������I���Ǝv���Ă���e�䂳�����Ǝv���܂��B��`�qRNA���N�`�����������ǂ����A�q�����R���i�ŏd�lj����邩�ǂ����Ȃ�Ċᒆ�ɂȂ��Ǝv���܂��B�Ƃɂ����ł��Ȃ��ẮA�Ƃ����e�䂳���Ǝv���܂��v
�����A�E�C���X�������ǂ������ł͂Ȃ����E�ɂȂ��Ă��܂��B�K�v����L�������Ȃ��Ă��ڎ킷��Ƃ�����ÉȊw�������َ����̐��_�_�ł��B���܂��������̈�`�qRNA���N�`�����{���ɕK�v�Ȃ̂��A�f�����b�g���郁���b�g�͂���̂���Âɍl����K�v��������܂��B
�قƂ�ǖ��Q�ȃE�C���X�ŁA�O�o���T������A�x�Z�����肷��̂��i���Z���X�ł��B
�܂h�~�d�_�[�u�̍��ւ̗v���ɐT�d�Ȏp���������Ă��錧������܂��B���h�Ȕ��f���Ǝv���܂��B
2�N�O����J��L�����Ă������̂��i���ɑ����Γ��{�͎��ł��܂��B�ނ炪�A�܂h�~�d�_�[�u����������܂ꂵ�Ȃ����Ƃ���]�ɂȂ���܂��B
�����ꂩ�玄���������ׂ�����
����܂Ō��Ă����悤�ɁA�R���i���Ƃ̃}�l�W�����g�̎��s�́A�������ɋ��|�S�������A���l��K���ɂ���Čo�ς���������ɗ₦���܂��܂����B
�f���^���ȍ~�A�����Ґ��Ǝ��Ґ��́u�����N��v(���邢��decoupling�A��A��)���N���ɂȂ����ɂ�������炸�A��̃A�b�v�f�[�g��ӂ��Ă��܂����B
�ł͎������͂��̕s�𗝂ɂǂ����������������̂ł��傤���B
����́A���������ŗ��E���Ă����ق�����܂���B��ÂɁA�m�F���ꂽ�f�[�^����Ɏ��������ӎ����A�b�v�f�[�g���Ă������Ƃ��d�v���Ǝv���܂��B
���͊��҂����߂āA�I�~�N�������̊����g�傪�u�Ō�̕s�𗝁v�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B�����m�F�҂��}�g�傷��قǔ�Q�Ƃ́u�����N��v��udecoupling�v�𑽂��̐l�����A���Ȋώ@����鎖���Ƃ��ċ����F������ƍl���Ă��邩��ł��B
�������̃R�������J�n����2�N�O�́A���Ƃƃ��f�B�A���y���~��̉J���~�点��^���Èł̂Ȃ��u������m�点�Ċ�]�̓�����������Ȃ��Ắv�Ǝv���Ă��܂����B���ł͊��҂���Ƃ̉�b��E�F�u��̂��܂��܂ȃR�����g��q������ɂ�A���{�̕��X�̓��@�͂�d�����ƈȏ�ɐM�����ėǂ��Ɗm�M����悤�ɂȂ�܂����B
�u�R���i�͏I������B�ǂ���ł������v�Ƃ������Ƃ̔F�����d�v�ł��B���́A���̌�N���邾�낤���Ƃ�\�z����2020�N6���Ɂu���{�̃R���i�E�C���X�͏I������B�������ɂł悤�v�Ƃ����L���������܂���(��9)�B
�L���̍Ō�ɂ́u�����������́A������w�Ԃ��߂ɑ�ςȋ�J�Ǝ؋������Ă��܂����B�����̔��ƌo�ς̔�����₷���߂ɍ������s�ɂł����悤�B�o����ς�ŁA�V�������ɂł悤�v�Ƃ��Ă��܂��B
�u�v�͕��ׂ��Ђ������瓯���悤�ȕ��ׂ��Ђ��Ȃ��čςƂ��������̂��Ƃ��B�}�W�b�N�̃^�l�Ƃ����̂̓V���v���Ȃ��̂��v�Ƃ����`�����Ă��܂����B�}�W�b�N�̃^�l�͂��̌�A�����w�������⍑����`�w�������ɂ���Ė��炩�ɂ������܂�(��10�A11)�B
���p���f�~�b�N�����̏I���_�͂�����������Ă���
���̌�A�������͎��ۂ̌o����ʂ��Ċw��ł��܂����B���łɐ����̊�@���������R���i���s���̂��I�����Ă���Ƃ������Ƃł��B��݃E�C���X�𑽐����o���Ă����̈Ӗ�������܂���B���܂��ܗz���ɂȂ����l��f�߂���炵���Ӗ����������܂���B
�Ƃ��Ƃ������s�́u�Z���ڐG�҂ɂ͎����ŘA���v�ɂȂ�܂����B�ی����E������̂���܂ł̋�J�͂Ȃ����̂ł��傤�H(��12)
���N�`�����ڎ킵�����l�͐ڎ킷��Ηǂ����A����p���Ђǂ������l�͔����Ă������B�ڎ킵�Ȃ������l�͂��Ȃ��ł��܂��Ηǂ����A�E�C���X��Q�������ŕK�v�Ȃ��l�X�͐ڎ킵�Ȃ��Ă悢�Ǝv���Ă��܂��B
�E�C���X�����������}�ɕω����邱�Ƃ͂���܂���B�`���̍��۔�r�O���t�������ɂȂ��Ă݂Ă��������B�ȑO����ώ@����Ă����u�����N��v�Ȃǂ��A����ɖ��m�Ɋώ@����Ă������Ƃł��傤�B
������������M�܂�������Ă���Ύ���——�B���������R���i�̑��݂�Y��āu�ǂ����ł������v�Ɗ��e�ɂȂ邱�Ƃ��A���̈�A�̃p���f�~�b�N�����̏I���_�ɂȂ�ł��傤�B���������g���A�������̕�炵�Ɩ��������̂ł��B
�������́A���܂悤�₭����2�N�Ԃ̍����Ȏ��Ɨ��Ƌ]�����ĕ����Ă��������u���R�ɔ��f���鎩�����鎩�������v�݂�ȂŏI���悤�Ƃ��Ă���̂ł��B
���Q�l����
1�DWHO�A�R���i�n�q�����u���l�Ȃ��v�@�P�p�E�ɘa�����@���o�V��2022�N1��20��
2�D�����҂���ɋ}���Ȃ�u��҂͌��������ɐf�f�v�@���ƗL�u���ā@�����V���@1��20��
3�D�r��m��"�܂h�~���d�_�[�u��ً}���Ԑ錾�͌��ʂ��Ȃ�"�@NHK NEWS WEB
4�D�u�q�������v�u�Ⴂ�l���}�X�N���c�v�܂h�~���A�T���̊ό��n�@�����V���@1��22��
5�D���ꌧ�z�[���y�[�W�@�����ɂ����銴���ɂ��ā@
6�Dworldometer South Africa
7�D�u�ڐ�̐��_�ɂ͋t�炦�Ȃ��v�ݓc�������R���i�K���ɓ˂�����"�ߌ��I�Ȍ���" �����Ƃ̎x������Ōo�ς͑�Ō��c
8�D�Z���ڐG180���l���Z�A�Љ�@�\�Ɏx��@�l��s���[���Ɂ@���o�V���@1��20��
9�D������t�̒u���{�̃R���i�E�C���X�͏I������B�������ɂł悤�v �u���l�x�@�v����Ă����f�B�A�̍�
10�D�V�^�R���i�E�C���X�ɎE�����ʂ����L���Ɖu�L���[T�זE�@�|�̓��ɑ��݂��������̖h�䕔���|�@�����w������2021�N12��8��
11�D�f���^���A�C���\�͒ቺ�@�O���̍�����`�w���Ȃ� ������`�w�������@2021�N10��31��
12�D���V�^�R���i�����r�m���u�����҂���Ԃ悭�������v�@�{�l����Z���ڐG�҂ւ̘A���Ăъ|���@�����V��2021�N1��21��
|
�����܂����Ȃ��I�~�N�������̢���ǖ�裁@1/25
�ی����ǎ҂̑����́A�I�~�N������������܂ł̐V�^�R���i�E�C���X���ɔ�d�lj����ɂ������Ƃ��������鏉���f�[�^�ɗE�C�Â����Ă��邪�A�����ɕʂ̏d��ȋ^�₪�e�𗎂Ƃ��Ă���B
���N�`���ڎ튮���҂̃u���[�N�X���[�������܂߁A�I�~�N�������ւ̊������u�����R���i������(Long COVID)�v�ɂȂ���\���͂ǂ��Ȃ̂��A�Ƃ����^�₾�B�����R���i�����ǂƂ����̂́A��������ǂ̂��ƁB���J���ɂ��킽���đ����A���퐶���Ɏx����y�ڂ����Ƃ�����g�̓I�A�_�o�I�A�F�m�I�Ȉ�A�̏Ǐ���w���B
�I�~�N�������ƃ��N�`���ڎ�A�����Ē����R���i�����ǂ��߂���W���͂܂��Ȋw�I�ɂ悭�킩���Ă��Ȃ��B����܂łɍs���Ă��������ł́A����I�Ȏ肪���肪�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���̋L���ł́A�Ȋw�I�ɂ킩���Ă��邱�ƂƁA�܂��킩���Ă��Ȃ����Ƃ̃|�C���g���Љ��B
���I�~�N�������̌��ǃ��X�N�́H
�I�~�N���������ŏ��Ɋm�F���ꂽ�͍̂�N11���B���̂��߁A�Ǐǂꂾ���������\�������邩�����ɂ߂�ɂ́A�܂����炭���Ԃ�������B�܂��A����������ĉA���ɂȂ�����A����܂ł̃E�C���X���Ɠ��l�ɁA���ɂ��₪���������悤�ɂȂ�u���C���t�H�O��A���������ӊ��Ƃ������Ǐ�ɂȂ���\��������̂��ǂ������悭�킩���Ă��Ȃ��B
�I�~�N�������͂���܂ł̃E�C���X���قNJ��������ɏd�lj����Ȃ��Ƃ���f�[�^������Ă��邪�A��{�I�ȏǏ�͂���܂ł̃E�C���X���Ǝ��Ă��邽�߁A�����I�ȉe��������܂łƓ����悤�Ȃ��̂ɂȂ�\��������B
���������̏d�lj����X�N���ቺ�����Ƃ��Ă��A����̓I�~�N�������������R���i�����ǂ������N�����ɂ����Ȃ������Ƃ�K�������Ӗ�������̂ł͂Ȃ��ƁA�����̈�t�A�����ҁA���Ғc�̂͌x�����Ă���B����܂ł̌�������́A�V�^�R���i�Ɋ������������͌y�ǂ܂��͖��Ǐ����l�X�̑������A���̌�A���J�������������R���i�����ǂ����������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B
���N�`���Œ����R���i�����ǂ�h����̂��ǂ����́A�͂����肵�Ȃ��B
�d�lj��⎀�S��h�����Ƃ����N�`���̖{���̖ړI�����A����܂ł̃E�C���X���Ɋւ��Ă����A���N�`���ɂ���Ċ������X�N���̂��̂����������P�[�X���������Ƃ݂���B�����R���i�����ǂ������őP�̕��@�͂������A�ŏ����犴�����Ȃ����Ƃ��B���������N�`���ɂ�銴���\�h���ʂ́A�I�~�N�������ɑ��Ă͂���܂łقNj����Ȃ��A�u���[�N�X���[�������ȑO�ɔ�ׂ͂邩�Ɉ�ʓI�ɂȂ��Ă���B
���N�`���ڎ�҂ƒ����R���i�����ǂɊւ��錤���́A���̂Ƃ���f���^�����o�ꂷ��O�Ɏ��W���ꂽ�f�[�^�����S�ɂȂ��Ă���A���������ʂ�����Ă���B���N�`���������R���i�����ǂ̗}���ɂȂ���Ƃ��錤�����������ŁA�Ȃ���Ȃ��Ƃ��錤�������݂���Ƃ������Ƃ��B
�����N�`����łƌ��ǂ��a�炮�H
���N�`���̉^�p���n�܂����Ƃ��ɂ͂܂��A�����͂̋����f���^�����A�����肳��Ɋ����͂𑝂����I�~�N���������o�����Ă��Ȃ������B���A�����A�����R���i�����NJ��҂̒��ɂ́A���N�`���ڎ��Ƀu���C���t�H�O�A�ߒɁA����A���ӊ��Ƃ������Ǐ��P�����l�����������B����ł��A���N�`����ł��Ă��Ǐ܂������ω����Ȃ��Ƃ����l�͑����������A�Ǐ��������Ɗ�����l�������Ȃ��炢���B
2021�N2〜9���ɏǏ���Ɠ�����18〜69��ΏۂƂ����C�M���X���Ɠ��v�ǂ̒����ɂ��ƁA�����R���i�����ǂ̏Ǐ��i����m����1��̃��N�`���ڎ��13���ቺ���A2��̐ڎ�ł����9���ቺ�����B
�����R���i�����ǂ̌����͍������炩�ɂȂ��Ă��炸�A���Ƃɂ��ƁA���܂��܂ȏǏ�̔w��ɂ́A���҂ɂ���ĈقȂ錴�������݂���\��������Ƃ����B�L�͂ȉ����Ƃ��ẮA���������܂��ĉA���ɂȂ�����Ɏc�����E�C���X�₻�̈�`�q�����̎c�[���W���Ă���Ƃ�����́A���邢�͖Ɖu�̉ߏ蔽�����~�܂�Ȃ��Ȃ�A����ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���ǂ������͌��s�s�ǂƊW���Ă���Ƃ�����̂�����B
�C�F�[����w�̖Ɖu�w�ҁE��薾�q���́A�E�C���X�̎c�[�������ƂȂ��Ă���ꍇ�ɂ́A���N�`�����Ǐ�̒����I�ȉ��P�ɂȂ���̂ł͂Ȃ����Ƙb���B����́A���N�`���Ő��������R�̂ɁA���������c�[����菜���\�͂����邱�Ƃ��O��ƂȂ�B
���ʁA������Ɏ��ȖƉu�����Ɏ����������N�����A���ꂪ�����R���i�����ǂ̌����ƂȂ��Ă���ꍇ�ɂ́A���N�`���ł͈ꎞ�I�ɂ����Ǐ��P�����A���ӊ��Ȃǂ̖�肪�Ĕ�����\��������B
|
���g�}�X�N���p�������n��͊������Ⴂ�h �đ�w�Ȃǒ��� �@1/25
�}�X�N�̒��p���V�^�R���i�E�C���X�̊����\�h�Ɍ��ʂ����邩�������邽�߁A�A�����J�̑�w�Ȃǂ̃O���[�v���o���O���f�V���ő�K�͂Ȓ������s�����Ƃ���A�}�X�N�̒��p���������n��ł͐V�^�R���i�Ɋ�������l�̊������Ⴉ�����Ƃ��錤�����ʂ\���܂����B
���̌����̓A�����J �C�F�[����w�Ȃǂ̃O���[�v���s���A�Ȋw�G���́u�T�C�G���X�v�Ŕ��\���܂����B
�O���[�v�́A���ƂƂ�11�����狎�N4���ɂ����āA�o���O���f�V���̔_�����̂��悻600�̎����̂�ΏۂɃ}�X�N��z���Ē��p�̌[�����s���������̂ƍs��Ȃ����������̂ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����ɈႢ�����邩�ׂ܂����B
���̌��ʁA�}�X�N���p�̌[�����s��Ȃ����������̂ł̓}�X�N�̒��p����13.3���������̂ɑ��A�[�����s���������̂ł͒��p����42.3���ƍ����Ȃ�A�V�^�R���i�̊������^����Ǐo���l�̊�����11.6���Ⴍ�Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B
�܂��A�R�̂̌����ł��}�X�N�̒��p�������������̂͊��������Ⴂ�X�����݂�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�O���[�v�ł́A�}�X�N���V�^�R���i�E�C���X��ɖ𗧂Ƃ������m�ȏ؋�������ꂽ�Ƃ��Ă��āA�}�X�N�̒��p��������ɏオ��A������h�����ʂ���荂�܂�Ƃ݂���Ƃ��Ă��܂��B |
���|�\�E���瑊�����R���i�����@�X�Ȃ��A����I�t�@�[�ȂǑΉ��ǂ���@1/25
�A���A�V�^�R���i�E�C���X�����Ґ��̉ߋ��ő����X�V����钆�A�|�\�E����̊������������ł���B24�����A���~�薾����2�l��A�t�@�[�X�g�T�}�[�E�C�J�A�����p��A�����ڗ��q�A���X�T��A�f�B�[���E�t�W�I�J�A�Ȃɂ�j�q�̑吼�����A���������A�������Y��̊��������ꂽ�B
�����ґ��ɔ����A�e���r�ǂȂǕ�������ɂ����^�Ȃǂ̍H�v�����߂��Ă���BTBS�n�uN�X�^�v(���`���j�ߌ�3��49��)�ł́AMC���M���A�i�E���T�[�ƃz������H���X�^�W�I�ƕt���A�ɕ�����ďo���B���A�i�́u�����z���҂������Ă��钆�ŁA����������������ׂ����Ƃ�����Ƃ������ƂŁA�܂��́A�ԑg�X�^�b�t�̏o�Ύ҂����炷�Ƃ������Ɓv�Ɛ��������B21���ɂ́A���ǂ̓��䖃���q�A�i�������������Ƃ��A�����������A�i������烊���[�g��MC�߂Ă����B
�R���i��Ƃ��ăt�W�e���r�́u�A�N�����̐ݒu�A�X�^�b�t�̌����A�R�����e�[�^�[�Ȃǂ̃����[�g�o���Ȃǂ̑Ή������܂��v�ƉB�ʂ̕����NJW�҂ɂ��ƁA�܂h�~���d�_�[�u�̏o�Ă���n��ւ̃��P�n�����������A�X���P�ł̃}�X�N���p�A���P�o�X�ł̈��H�֎~�A���^���̊��C�̊Ԋu��Z������ȂǑ���u���Ă���Ƃ����B����������g�傪�����A�ԑg�o���҂ȂǂɊ����҂��o���ꍇ�A������I�t�@�[�����肷��P�[�X���o�Ă���ƌ��O���������B
����ŁA������|�\�������W�҂́A�^�����g�̑̉��v���⏜�ہA��A�������̓O��Ȃǂ͎��m���Ă��邪�A��{�I�ɂ́A����̑Ή��ɏ]���`�ƂȂ��Ă���Ɩ��������B�I�~�N�������̋}���Ȋg��ɔ����A�e���ł���܂ňȏ�ɓO�ꂵ���Ή��������Ă���B
|
���u��6�g�s�[�N�A�E�g���Ȃ������v�g2�{�̊����́h�̃I�~�N�����g����h�Ƃ́H�@1/24
�҈Ђ�U����Ă���I�~�N�������ɂ��āA�C�ɂȂ錤�����ʂ����炩�ɂȂ�܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψقׂ铌����w�̍������y�����́A��͂�i�߂邤���ɋC�Â����̂̓I�~�N�������̕ω��ł��B������w��Ȋw�������E�������y�����F�u�wBA�D1�x�ƁwBA�D2�x�́A�ǂ������I�~�N�����Ƃ������O�����Ă���B�ǂꂭ�炢�Ⴄ�̂��킩��Ȃ����A�]�����ƃf���^���̕ψق̐��̈Ⴂ�����A�wBA�D1�x�ƁwBA�D2�x�̕ψق̐��̈Ⴂ�̕��������B�����I�~�N�����̖��O���t���Ă��邪�A���Ȃ�Ⴄ�v
�wBA�D1�x�́A���݁A���{�Ŗ҈Ђ��ӂ���Ă���I�~�N�������B����ɁA�ψق��d�˂����킪�wBA�D2�x�ł��B�wBA�D2�x�̓����ɂ��āA�����_�ł킩���Ă��邱�Ƃ͑�������܂���B�������A����܂ł̃I�~�N���������A����ɏ��銴���͂��w�E����Ă��܂��B���́A���łɒu��������Ă��鍑������܂��B
�f���}�[�N�ł́A���N12�����犴���҂������n�߁A�������{�ɉ����x�I�ɑ����B21���ɂ͉ߋ��ő���4��6831�l���L�^���܂����B�֘A�ɂ��ẮA�܂��ڂ����킩���Ă��܂��A52�����wBA�D2�x�̊����ŁA���E�ł����������u������肪�i��ł��܂��B
�C�M���X�̕ی����ǂ́wBA�D2�x���g�������̕ψي��h�ƈʒu�t���܂����B����܂Ŋm�F���ꂽ�̂�426��ł����A���B������荂���\��������Ƃ��āA�x�������߂Ă��܂��B������i�߂�C�M���X�̐��Ƃ́wBA�D2�x�ɂ��āA�������Ă��܂��B�C���y���A���E�J���b�W�E�����h���̃g���E�s�[�R�b�N�����F�u�����̍��ň�т��āA�������Ă���Ƃ������Ƃ́A����(BA�D2)������܂ł̃I�~�N������(BA�D1)���A������x�����͂������\��������؋����B�C���h�ƃf���}�[�N�̂��������̃f�[�^�ɂ��ƁA����܂ł̃I�~�N������(BA�D1)�Ɣ�r���āA�d�Ǔx�Ɍ��I�ȍ��͂Ȃ��l�q���v
�wBA�D2�x���m�F����Ă���̂́A���ɂ��C���h��X�E�F�[�f���ȂǁA�S����48�J���ł��B�����ɂ͓��{���܂܂�܂��B�����J���Ȃɂ��܂��ƁA��`���u�Ŋm�F���ꂽ�I�~�N�������̊����҂̂����A�wBA�D2�x�������̂́A19�����_��198��B�C���h��t�B���s�����痈���l���������S�ł��B
�����y�����́A���{�ł�����E�C���X���wBA�D2�x�ɒu������蓾��Ƃ��������ŁA���̂悤�Ɏw�E���܂��B������w��Ȋw�������E�������y�����F�u��6�g�͍Ō�ł͂Ȃ��B��7�g�Ƃ����`�ł������������Ă��玟������̂��B��6�g�ɂ��Ԃ������`�ŁwBA�D2�x���A�������{�ɓ����Ă��Ă���B���ꂪ�����̎R�̐L�тɊւ���Ă���̂��͂킩��Ȃ��B���E�I�ɂ́wBA�D1�x�̎��ɁwBA�D2�x�����Ă���̂ŁA��6�g�ł͏I��Ȃ��v
1��19���܂łɋ�`���u�ŃI�~�N�������̗z�����m�F���ꂽ�Q�m����͂̌��ʂł��B1826��̂����wBA�D1�x�A���{�ōL�����Ă���I�~�N��������1626��B�wBA�D2�x�A�I�~�N�������̈����198��Ɩ�11���̐l����m�F����Ă��܂��B
�������y�����ɂ�铝�v�f�[�^�̉�͂ɂ��܂��ƁA�wBA�D1�x�̓f���^����2〜5�{�̊����́A�wBA�D2�x�́wBA�D1�x��2�{�߂��̊����͂ŁA����A���E�̎嗬�ɂȂ邱�Ƃ́A�\���ɂ��蓾��v�Ƃ����܂��B
�u������肪�i��ł���f���}�[�N�̌�������Ă݂�ƁA12�����{����A�f���^���������B����ƂƂ��ɁA���{�ŗ��s���Ă���wBA�D1�x���}�����Ă��܂��B�����x��āwBA�D2�x�������Ă����A16�����_�ŁA�����҂�52�����wBA�D2�x�ɒu��������Ă��āA�wBA�D1�x��47���������Ă��܂��B
�f���}�[�N�̌����@�ւɂ��܂��ƁA�����̕��͂Łu���@���ɂ͍����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂��B�����A�u�嗬�̃I�~�N�������ƈقȂ鐫���������ǂ����͏��͂Ȃ��v�Ƃ��Ă��āA�ڂ����Ǐ��A���N�`�����ʁA�d�lj����Ȃǂɂ��ẮA���݁A������i�߂Ă��邻���ł��B
��`���u��200��߂��m�F����Ă��邱�Ƃ܂��A�����y�����́u�s�������͏\���ɂ��蓾��v�Ƃ����܂��B�u�f���}�[�N�̗Ⴉ����A�wBA�D1�x�̌�ɁwBA�D2�x�����s�g�傷��ƁA��6�g���s�[�N�A�E�g���Ȃ��A�������́A�����ɁwBA�D2�x�ɂ���7�g�����鋰�ꂪ����B����x�A�C���������ߒ����āA���s�g��Ɏ��~�߂�������Ή����K�v�v�Ƙb���܂��B
|
�����g��u�I�~�N�������̓����ɍ��킹����p���v �@1/25
�V�^�R���i��Ő��Ƃł��镪�ȉ�́A�܂h�~���d�_�[�u��K�p����n��Ɋ�3�{���Ȃ�18���{����lj������Ԃ�27�����痈��20���܂łƂ���ƂƂ��ɁA����31���܂łƂȂ��Ă��鉫��A�R���A�L����3���̊����𗈌�20���܂ʼn������鐭�{�̕��j�𗹏����܂����B�u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή�́A��̂��ƕw�̎�ނɉ����܂����B
���g��͐��{�̕��j�𗹏������O��Ƃ��āu�I�~�N�������͂���܂ł̃f���^���ȂǂƂ͈قȂ�̂ŁA����܂ł̑�̓��P�ł͂Ȃ��I�~�N�������̓����ɍ��킹���ӂ��킵����p���Ƃ�ׂ����Ƃ������Ƃ��������B�L���Ȍ����݂̍���⑽���̌y�ǎ҂����钆�łǂ���Â�Љ�@�\���x���邩�Z���ڐG�҂��ǂ����邩�A������̐��Ƃ����łȂ��o�ς̐��Ƃ�m���Ȃǂ������V�^�R���i�̑����ȉ�ŋc�_���ׂ����v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŃI�~�N�������̊����g��ɂ��āu�N���X�}�X���琬�l���܂łɐڐG�̋@��傫���������������̂������������B����ɐE���ƒ�ɂ��L����A�Ⴂ�l���獂��҂ɍL�����Ă��Ă�����B�}�X�N���O������@�}�X�N�Ȃǒ��p���s�\���ȏł̊������v���Ă������͂邩�ɑ������Ƃ��������Ă���B�s�\���Ȋ��C���l���ł̉�b����H�A�吺���o�������Ŋ������N���Ă���v�Ǝw�E���܂����B
�����ċ��߂����ɂ��āu�O�ꂵ�Ă��炢�����̂̓}�X�N�̓K�Ȓ��p�ŕs�D�z�}�X�N�ŕ@�܂ł������蕢���Ăق����B���C�����ɑ���ƕ������Ă���B����Ɋ������X�N�̍�����ʂ�ꏊ�ւ̊O�o�͔����Ă��炢�����B�܂������ł��̒��̈����l�͊������^���O�o������Ă��炢�����B�����������ƂŊ�����������x�}������ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
����ɔ��g��́u�w�X�e�C�z�[������K�v���Ȃ��x�Ƃ����̂́w�ڐG��8���팸�x�̂悤�ɑS���A�Ƃɂ��Ă��炢�����Ƃ������ꗥ�ōL�͂ȊO�o���l�͕K�v���Ȃ��Ƃ����Ӗ����B�������X�N�̍����ꏊ�͕������Ă���̂ŁA���������ꏊ�ւ̊O�o�͂ł���Δ����Ă��炢�����B�܂��m���̔��f�ł���ɋ������łꍇ������A���̏ꍇ�͒m���̗v���ɏ]���Ăق����v�Əq�ׂ܂����B�@ |
���Z���ڐG�� �����Ȃ��ł��f�f�u��Â̕��א[���Ɂv���g� �@1/25
�����J���Ȃ́A�I�~�N�������̊���������ɋ}�g�債���ۂɂ́A�����̂����f����A�����҂̔Z���ڐG�҂ɁA���M�Ȃǂ̏Ǐo���ꍇ�A�������Ȃ��Ă��A��t�����������Ɛf�f�ł���ȂǂƂ�����j�������Ă��܂��B
����ɂ��āA���{���ȉ�̔��g�Ή�́A25���ɊJ���ꂽ���ȉ�̉�̂��Ɓu�I�~�N�������ɂ��Ă͎Ⴍ�A��b�����̂Ȃ��l�͂قƂ�Ǐd�lj����Ȃ��Ƃ����f�[�^������B��l�ЂƂ���P�A����͈̂�Â̍��{�ł͂Ȃ����Ƃ����c�_�����������A�������}���Ɋg�傷�钆�ŁA�قƂ�Ǐd�lj����Ȃ����Ƃ��킩���Ă���l�܂ō��̑̐��̂܂܁A�������Ă���ƁA��Â̐l�I����������Ȃ��Ȃ�A���ׂ��������Đ[���ȏɂȂ�Ƃ������Ƃ����Ƃ⌻��̎����Ƃ��Ă�����v�Əq�ׂ܂����B
����Ɋւ��āA���g�����Ƃ́A�I�~�N�������ɉ�������Ƃ��Ċ���������ɋ}�g�債���ꍇ�u�Ⴂ����͌������s�킸�A�Ǐ��Őf�f���邱�Ƃ���������v�Ƃ���Ă������J���Ȃ̐��Ɖ�ł������Ă��܂����B
���g��́u���ɓ����肾���A���Ƃ̊Ԃł́A�N��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����c�_���������B���ӎ��Ƃ��ē��������邱�Ƃ����Ƃ̖����ŁA���Ƃ����łȂ���ʂ̐l�����ɂ��l���Ă��炢�A�Љ�̔[����������A�o�����X���Ƃ���������邱�Ƃ��厖���v�Əq�ׂ܂����B�@ |
���k�C�� �V�^�R���i 4�l���S 1536�l�����m�F 7���A��1000�l�� �@1/25
�k�C���ł�25���A�D�y�s�ōėz����31�l���܂�620�l�A���َs��98�l�A����s�ōėz��1�l���܂�54�l�A���M�s��35�l�A�Ύ�n����218�l�A���H�n����116�l�A�_�U�n����107�l�A�I�z�[�c�N�n����91�l�A��m�n����47�l�A�n���n����38�l�A���n����26�l�A�@�J�n����17�l�A�\���n����16�l�A��u�n����15�l�A���G�n����11�l�A�����n����8�l�A�����n����7�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��3�l���܂�12�l�́A���킹��1536�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B �����̈���̊����m�F��7��������1000�l���A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��A���Ȃǂ͓����ł���܂łɊ������m�F����Ă���4�l�����S�����Ɣ��\���܂����B���Ȃǂɂ��܂��ƁA�S���Ȃ����͍̂���22����80��̏���1�l�A23����90��̏���1�l�A24���Ɉ���s��80��̒j��1�l�A�����25���ɎD�y�s��80��̒j��1�l�Ƃ������Ƃł��B����œ����̊����҂͎D�y�s�̉���4��5599�l���܂ށA����7��6542�l�A�S���Ȃ����l��1484�l�ƂȂ��Ă��܂��B�@�@ |
���{���192�l�����@���j�ōő��@���A���ŃN���X�^�[�@1/25
�{�錧�Ɛ��s��24���A10�Ζ����`90��̒j��192�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B���j���Ƃ��Ă͍�N8��23����162�l������A�ߋ��ő��ƂȂ����B�V���ɐ��s�Ƒ��s�Ōv4���̃N���X�^�[�����������B
�V�K�����҂̓���͐��s117�l�A���s26�l�A�Ί��s15�l�A�����s�Ɩ���s���e6�l�A�������s5�l�ȂǁB�����_��77�l(40�E1��)�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B
24���܂łɐ��s�̍���Ҏ{�݂ƍ��Z�Ŋe10�l�A���s�̕ۈ�{��2�J����20�l��13�l�̊������������A���Ɛ��s�̓N���X�^�[�ƔF��B���s�̕ʂ̍���Ҏ{��2�J���ł��e4�l�̗z�����m�F���ꂽ�B
�N���X�^�[�֘A�̊����҂͐��s�̌�y�{�݂�1�l���̌v12�l�A�ۈ�{�݂�2�l���̌v23�l�A�Ί��s�̕ۈ�{�݂�5�l���̌v46�l�A�ēc���̏��w�Z��1�l���̌v14�l�A���w�Z��1�l���̌v11�l�ƂȂ����B
�ߌ�1�����_�̗×{�҂�1437�l�B�m�ەa��(510��)�̎g�p����14�E3���ɏ㏸�����B��������\�a����185���ɑ��������ʁA�g�p����39�E5���ɒቺ�����B
�v�����҂�1��8282�l(���s��1��1371�l)�B1��6610�l���މ@�E�×{�����ƂȂ����B
|
���{��ōő�331�l�A�������214�l�A�Ί�20�l�@1/25
�{�錧�Ɛ��s��25���A10�Ζ����`90��̌v331�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B������1���̊����҂Ƃ��Ă͍�N8��25����301�l������A�ߋ��ő����X�V�����B�s�����ʂ̓���͐��s214�l�A�Ί��s20�l�A�C����s15�l�A�x�J�s14�l�ȂǁB����܂łɐ��s�ōł����������͍̂�N8��25����197�l�B�@ |
���I�~�N�������A�q�ǂ������}�g��@�������w�Z����A�אS�̒��Ӂ@1/25
�V�^�R���i�E�C���X�����̋}�g��ɔ����A�����̏����w�Z�ŃN���X�^�[(�����ҏW�c)�̔������������ȂǁA�q�ǂ��ւ̊������L�����Ă���B�����͂������Ƃ����V�ψي��u�I�~�N�������v�̉e���Ƃ݂��Ă���A���ɒ��w�Z�ł�3�N�������Z���T���A��������������^�C�~���O�B�e�w�Z�͊w�K�@����m�ۂ��邽�ߐ_�o���Ƃ��点�Ă���B
�����s�̐M�˒��ł́A�̉�������w�̏��ŁA��Ȃǂ�O�ꂵ�Ă���B���͗R�I�{�싳�@�́u�Z���Ŋ������g�債�Ȃ��悤�ɁA�����ł���������ꍇ�͋x�ނ悤�ɓ`���Ă���B�Z���ł͂ł������̑���u���Ă��������v�ƍאS�̒��ӂ��B
�����������̑O���I���̊菑�t���J�n��2��3���Ɣ����Ă���B�ڍ����Z���́A�s����̒ʒm��(�s���ς���)���Ă��Ȃ����ߑΉ��͖���Ƃ�����Łu���T����3�N���́A�F�B��搶�Ɗ�����킹�邱�Ƃŗ��������ĕ��ɗՂ߂邱�Ƃ�����B������͂�������A3�N���ɂ͎Ɏ��g�ރR���f�B�V�����Â�����C�Ɋ|���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƙb�����B
�s���ł́A���Ắu�܂h�~���d�_�[�u�v�ŁA�����w�Z�̍��Ȃ̊Ԋu���Œ�1���[�g���m�ۂ�����A�������X�N���������Ƃ͍s��Ȃ��ȂǍs����������������B
�l���������ꕔ�̊w�Z�ł́A�^�u���b�g�[���ł̃I�����C�����Ƃ╪�U�o�Z�ɂ����g�B�s���ϊw�Z����ۂ́u�����h�~���ŗD��ɁA�w�т̋@���ۏႵ�Ă��������v�Ƃ����B
24���܂ł�3�Z�Ŋw�N����w�������s��ꂽ��Îᏼ�s�ł́A�s���ς��s���w�Z�ɑ̈�̎��Ƃ╔�����ŁA�_���Ȃǂ̐ڐG�����Z���T����悤�ʒm���o�������ŏ����ɓ������B�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�����܂莟��A�����ɒʒm����Ƃ����B
����ŁA�w�N�E�w���������������Ă��w�K�̋@����m�ۂł���悤�A�����A���k��1�l1���z�����Ă���^�u���b�g�[�����ƒ�w�K�Ɋ��p���邱�Ƃ��������Ă���B�s���ς̒S���҂́u��������d�v�����A�w�K�w���v�̂ɒ�߂�ꂽ�J���L�����������{����K�v������v�Ɠ���Y�܂���B
�S�R�s���ς͍���̌��̕��j���Q�l�ɂ��A�����w�Z��`������w�Z�ɑ��A�����̃��X�N���������y�⒲�����K�A���������T����Ȃǂ̑Ή�����܂Ƃ߂��������o��������i�߂Ă���B�@ |
����錧 �V�^�R���i 1�l���S �V����611�l�����m�F �@1/25
�V�^�R���i�E�C���X�ŁA��錧���ł�25���A�V����611�l�̊��������\����܂����B
��T�̉Ηj�����355�l�����A2�{�ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A�v��3��0567�l�ƂȂ�܂����B����A���́A23�����\����������2�l�ɂ��āA���łɔ��\�ς݂������Ƃ��Ď�艺���܂����B�܂��A���͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������1�l�����S�����Ɣ��\���A�����Ŏ��S�����̂͗v��221�l�ƂȂ�܂����B�@ |
���Ȗ،� �V�^�R���i �V����584�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25
�Ȗ،��ƉF�s�{�s��25���A�V���ɍ��킹��584�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�����ň���ɔ��\�����V�K�����҂̐��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ŁA���߂�500�l���܂����B�܂��A����24���ɔ��\����������1�l�ɂ��āA23���̔��\���Əd�����Ă����Ƃ��āA��艺���܂����B����ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͗v��2��591�l�ƂȂ�܂����B�@ |
���I�~�N�����ɐ��ރf���^�Ɍx�����@�d�lj����X�N�ɈႢ�@������@1/25
��t�����ł�24���A�ߋ��ő��ƂȂ�2760�l�̐V�^�R���i�E�C���X������2�l�̎��S�����\���ꂽ�B�V�K�����҂̍ő��X�V��4���A���B���҂̂���40��j���͎���×{���Ă��ċ~�}��������A���S��Ƀf���^�������^�������������B�����Q�m����͂��Ē��ׂĂ���B���ȂNJe�����̂ɂ��ƁA�����̊����҂͌v12��1563�l(����1036�l)�ƂȂ����B
�����a��ۂɂ��ƁA���S����40��j����1�����{�ɗz���ƕ�����A�y�ǂƐf�f���ꂽ�B19���ɂ̓X�}�[�g�t�H���𗘗p�������N�ώ@�V�X�e���u�}�C�n�[�V�X�v�ɁA38�x��̔M�͂��邪����(����)���͂Ȃ��Ɠo�^�B�ی�����20���A�p���X�I�L�V���[�^�[��͂��邽�߂ɓd�b�����ۂ͘A�������Ȃ������B21���ߑO�ɉƑ��̗v���ŋ~�}��������A������Ŏ��S���m�F���ꂽ�B�j���Ɋ�b�����͖����A���N�`���͖��ڎ킾�����Ƃ����B
����1�l�̎��҂�90��ȏ�̏����ŁA����×{���Ɍċz���Ă��Ȃ���ԂŌ�����A�~�}������Ŏ��S���m�F���ꂽ�B
���ۂȂǂɂ��ƁA��c�s�̕ۈ珊2�J���A�s��s�̐�t���ȑ�Ǝ��������{��2�J���A���s�̍��Z�ŐV�K�N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F���ꂽ�B
���q�������������J���Ă���V�^�R���i�E�C���X�̃Q�m����͌��ʂɂ��ƁA20���̒������ʂɐ�߂�I�~�N�������̊�����92�E9���A�f���^���̊�����7�E1���������B�����ł�1����{�ȍ~�A�I�~�N�������ւ̒u������肪�قڏI����Ă��邪�A�f���^���̌��o���ˑR�����Ă���B���͓�������d�lj����₷���f���^��������ł�����x�����Ă������A�V�K�����Ґ��̑啝�ȑ����ő���Ȃ��Ă���B
�F�J�r�l�m���͍���13���̒��L�҉�ŁA�I�~�N��������9�����߂�悤�ɂȂ����Ƃ̌������������ہA�f���^���̏d�lj����X�N�Ɍ��y���u�f���^�����������Ȃ������������������Ă����v�Ɣ����B���͕ψي��̎�ނ�N�`���ڎ���̗L���ȂǏd�lj����X�N�𑍍��I�ɔ��f���A���҂̃��X�N�������ꍇ�͓��@��A�R�̃J�N�e���Ö@�Ȃǂ̎�i������h���×{�{�݂�I������l���������Ă����B
�������A���̌�ɐV�K�����҂��A���������A�ߋ��ő����X�V�B�V�K�����҂̕ψي��̎�ނׂ�͎̂�����s�\�ƂȂ�A�y�ǎ҂������I�~�N���������O��̑Ή��ƂȂ��Ă���B����f���^�������^������������40��j�����A�e�̋}�ό�̎��S���ĕψي��̎�ނׂ邱�ƂɂȂ����Ƃ����B
�����a��ۂ́u�����҂���������ł̓f���^������肵�đΉ��ɓ�����͓̂���A���Ӑ[�����N�ώ@����K�v������v�Ƃ��Ă���B
|
�������s �V�^�R���i 1��2813�l�����m�F �ߋ��ő��@1/25
�����s���ł�25���A�ߋ��ő���1��2813�l�̊������m�F����܂����B1�T�ԑO�̉Ηj����2.5�{�Ŋ����̊g�傪�����Ă��܂��B
�����s��25���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��1��2813�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B����܂ōł�������������22����1��1227�l���1500�l�ȏ㑽���Ȃ�A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂�1�T�ԑO�̍���18�����7600�l�]�葽�����悻2.5�{�̑����ł��B7���ԕ��ς�25�����_��9000�l����9675�l�ƂȂ�܂����B�O�̏T��2.5�{�ł��B
�������m�F���ꂽ1��2813�l�̔N��ʂł�20�オ�ł�����3126�l�őS�̂�24.4���ł��B������30�オ2257�l�őS�̂�17.6���A40�オ1876�l�őS�̂�14.6���A10�Ζ�����1562�l��12.2���ł��B65�Έȏ�̍���҂͉ߋ��ő���928�l�ł����B
�܂��������m�F���ꂽ1��2813�l��4���]���5938�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��܂����B����A�s�̊�ŏW�v����25�����_�̏d�ǂ̊��҂�24�����2�l������14�l�ł����B���S���m�F���ꂽ�l�͂��܂���ł����B�@ |
���V�^�R���i �s�������҂̖�99�� �I�~�N�������^�� �s�����@1/25
�����s�Ȃǂ�24���܂ł�1�T�Ԃɍs�����X�N���[�j���O�����ŁA���悻99���̐l���I�~�N�������Ɋ������Ă���^�������邱�Ƃ��킩��A�s�̒S���҂́u�s���ł͂قڒu����������ƌ�����v�Ƙb���Ă��܂��B
�����s�́A�s�̌��N���S�����Z���^�[�Ɩ��Ԃ̌����@�ւ��A24���܂ł�1�T�Ԃɂ��킹��4640�l��Ώۂɍs�����A�X�N���[�j���O�����̌��ʂ�25�����\���܂����B
���̌��ʁA����s�\������380�l�������Ă��悻99���ɂ�����4221�l���I�~�N�������Ɋ������Ă���^�������邱�Ƃ��킩�����Ƃ������Ƃł��B�s���ōŏ��ɋ^��������Ɗm�F���ꂽ�挎20���܂ł̏T�ȍ~�A�I�~�N�������̊����͑啝�ȑ����������A6�T�ڂł��悻99���܂ōL����܂����B�s�̒S���҂́u�s���ł̓f���^������I�~�N�������ɂقڒu����������ƌ�����v�Ƙb���Ă��܂��B |
���É��� �V�^�R���i �V����1336�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25
�É����Ȃǂ�25���A�����ŐV����1336�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����̊����m�F�Ƃ��āA����܂łōł�������������22����1160�l������A�ߋ��ő����X�V���܂����B����A�É��s�͍���21���Ɋ����m�F�\����������1�l�ɂ��āA��Ë@�ւ����艺���̕��������Ɣ��\���܂����B�É������̗v�̊����Ґ���3��8035�l�ƂȂ�܂����B�@ |
���q�ǂ��̃I�~�N�����Ǐ�A���M��2�����x�@���䌧�����\�@1/25
���䌧��1��24���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�ψي��u�I�~�N�������v�̉\�����������������҂̂����A12�Ζ����̌y�ǎ�110�l�̎�ȏǏ�ׂ��Ƃ���A37.5�x�ȏ�̔��M��34.7���ƍł����������Ɣ��\�����B���M�̕��ϒl��38.6�x�ŁA40�x����P�[�X�����������A�قƂ�ǂ͑�l�Ɠ��l��2�����x�ŕ��M�ɖ߂��Ă���Ƃ����B���̒S���҂́u�s�̂⏈���̉�M�܂������ꍇ�������̂ŁA�Q�Ă��Ώ����Ăق����v�Ƙb���Ă���B
5�`23����12�Ζ����̌���������(�f���^���A��)��134�l�ŁA����͌y��110�l�A���Ǐ�24�l�B
�Ǐ�͔��M�Ɏ����ŁA����15.7���A����12.8���A�̂ǂ̒ɂ݂ƕ@���E�@�Â܂�11.6���̏��B12�Έȏ���܂߂��S�N��ł́A��6����37.5�x�ȏ�̔��M�A�̂ǂ̒ɂ݂��݂�ꂽ�B
���ɂ��ƁA�f���C�╠�ɂ�i����q�ǂ��������Ȃ��炢���B�S���҂́u���M�����ɂƂ��ꂸ�A�q�ǂ��̑̒�������������Ɏ�f���Ăق����v�ƌĂъ|���Ă���B
|
���ΐ쌧 �V�^�R���i �ߋ��ő���354�l�����m�F �@1/25
�ΐ쌧��25���A����ɔ��\����鐔�Ƃ��ẮA����܂łōł�����354�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�ΐ쌧���ł̊����m�F��10267�l�ƂȂ�A���̂���140�l���S���Ȃ��Ă��܂��B�@ |
�����m�� �V�^�R���i 4�l���S �V����4120�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25
���m���͌����ŐV����4120�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�����ň���ɔ��\����銴���҂̐��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ŁA4000�l�����߂Ē����܂����B���m�����ł̊����m�F�͉���14��98�l�ƂȂ�܂����B�܂��A���m���Ɩ��É��s�A����Ɉ�{�s�͐V�^�R���i�Ɋ������Ă��������4�l���A24���܂łɎ��S�����Ɣ��\���܂����B�����Ŏ��S���������҂�1177�l�ɂȂ�܂����B�@ |
�����s�{ �V�^�R���i �V����1622�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25
���s�{�Ƌ��s�s��25���A�V����1622�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����̊����Ґ��Ƃ��Ă͂���܂łōł������A8���A����1000�l���܂����B�{���̊����҂̗v��5��1734�l�ƂȂ��Ă��܂��B�������ĖS���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�24�����_��7�l�ƂȂ��Ă��āB23�����1�l�����Ă��܂��B�@ |
�����{ �V�^�R���i 10�l���S �V����8612�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25
���{��25���A�V����8612�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����22����7375�l������A����܂łōł������Ȃ�܂����B���{���̊����҂̗v��27��6098�l�ƂȂ�܂����B�܂��A10�l�̎��S�����\����A���{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l��3089�l�ɂȂ�܂����B
�@ |
�������� �V�^�R���i ����l��3389�l�����m�F�̌����� �ߋ��ő� �@1/25
�������͌����ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�����l�ʼnߋ��ő���3389�l�ɏ�錩���݂��Ɩ��炩�ɂ��܂����B�@ |
�����ꌧ �V�^�R���i �V����1175�l�����m�F �ČR�����50�l �@1/25
���ꌧ��25���A�V����1175�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�����Ŋm�F���ꂽ�����҂�7��7102�l�ɂȂ�܂����B�܂��A�A�����J�R���牫�ꌧ�ɑ��A�V����50�l�̊������m�F���ꂽ�ƘA��������܂����B�@ |
��18���{���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�K�p ���{���傤���� �@1/25
�V�^�R���i�̊����̋}�g�傪�������A���{�́u�܂h�~���d�_�[�u�v��V���Ɋ�3�{���Ȃ�18���{���ɓK�p������j�ŁA25���A���ƂɎ����������ŁA�����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B����ɂ��d�_�[�u�̓K�p�n���34�s���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B
�V�^�R���i����߂���A���A���ɁA���s�̊�3�{����A�k�C���A�����ȂǁA���킹��18���{�����V���ɂ܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�𐭕{�ɗv�������ق��A����A�R���A�L����3���͍���31���܂łƂȂ��Ă���d�_�[�u�̊����̉�����v�����܂����B
������āA�ݓc������b��24����A�W�t���ƑΉ������c���A�v���̂�����18���{���ɑ��A1��27������2��20���܂ŏd�_�[�u��K�p����ƂƂ��ɁA����Ȃ�3���ɂ��Ă�2��20���܂Ŋ���������������j��\�����܂����B
���{�́A�����������j��25���A���Ƃł����{�I�Ώ����j���ȉ�Ɏ��邱�Ƃɂ��Ă���A������������A����ł̕Ǝ��^���o�āA�������̑��{���Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
����ɂ��d�_�[�u�̓K�p�n���34�̓s���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B
����A�ݓc������b�͍���̑�Ƃ��āA�d�ǂ⒆���ǂ̃��X�N������l�̓��@�̐��̐����A�y�ǂŎ���×{����l�ւ̑Ή��A�Љ�o�ϊ������ێ����邽�߂̕�����A��������l���������܂����B
�����āA�������g�債�Ă���n��Ŏ�ɓ���Â炭�Ȃ��Ă��錟���L�b�g�ɂ��āA�����������ۏ����āA���[�J�[�ɓ���1��80���܂ŋ����ʂ̈����グ��v�����Ă���Ɛ������܂����B
�܂��A���N�`����3��ڐڎ���y�[�X�A�b�v������ɂ̓��f���i�̃��N�`���̊��p���s�����Ƃ��āA����܂Ńt�@�C�U�[��2��ڎ킵���݂�������A3��ڂ̓��f���i��ڎ킷��ӌ��������ȂǁA�������i���u���āA�����̋}�g�傪�����I�~�N�������̗}�����݂ɑS�͂������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
|
���u�܂h�~�v �V����18���{���lj� ���{���ȉ���� �@1/25
�V�^�R���i��Ő��Ƃł��镪�ȉ�́A�܂h�~���d�_�[�u��K�p����n��Ɋ�3�{���Ȃ�18���{����lj������Ԃ�27�����痈��20���܂łƂ���ƂƂ��ɁA����31���܂łƂȂ��Ă��鉫��A�R���A�L����3���̊����𗈌�20���܂ʼn������鐭�{�̕��j�𗹏����܂����B�d�_�[�u�̓K�p�n���34�̓s���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B
25���ɊJ���ꂽ���{�́u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�ŐV�^�R���i���S��������t�{�̉���c����b�͖k�C���A�X�A�R�`�A�����A���A�ȖA�ΐ�A����A�É��A���s�A���A���ɁA�����A���R�A�����A����A�啪�A��������18���{������܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�̗v�������������Ƃ�������܂����B
���̂����Łu�������Â̂Ђ����x���������x��2�̒i�K�Ɣ��f����Ă��邱�ƁA�}���Ɋ����g�傪�����Ă��邱�ƁA���̂܂ܐ��ڂ����ꍇ�߂�������Ò̐��ɑ傫�ȕ��ׂ������肩�˂Ȃ����Ƃ��������A���}�Ɋ����g���h�~����[�u���u����K�v������v�Əq�ׁA27�����痈��20���܂�18���{���ɏd�_�[�u��K�p������j������܂����B
������ �R�� �L�� ����20���܂ʼn������j������
�܂�����31�����d�_�[�u�̊����ƂȂ��Ă��鉫��A�R���A�L����3���ɂ��āu���܂��ɑ����̗z���҂��������Ă��荡��̊����ɂ���Ă͈�Ò̐��ɂ���ɑ傫�ȕ��ׂ��������˂Ȃ����O������v�Ǝw�E���A����20���܂ʼn���������j������܂����B���ȉ�ł͂����������{�̕��j�ɂ��ċc�_���s��ꗹ������܂����B���{�͍���ւ̎��O�̕Ǝ��^���o�đ��{�����������ŊJ���A�����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B����ɂ���ďd�_�[�u�̓K�p�n���34�̓s���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B
�����J����b�u�K�Ȍ�����×{�ɂȂ��邽�ߕ��j���������v
�É�����J������b�͕��ȉ�̖`���u����A�����҂�����Ɍp�����ċ}�g�債���ꍇ�ɔ����A���҂̏Ǐ��d�lj����X�N�Ȃǂɉ����ēK�ȗ×{���m�ۂ����悤�����ɉ����Ēn��̔��f�Őv���Ɋ��҂�K�Ȍ�����×{�ɂȂ��邽�߂̑Ή������{�ł���悤�ɍ��Ƃ��Ă̕��j���������v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu���������I�~�N�������Ɋւ���Ȋw�I�Ȓm�������W���A���Ƃ̈ӌ����f�������̖��ƌ��N����邱�Ƃ��1�Ɏ����̂��ÊW�҂ƘA�g�E���͂��Đ����őS�͂Ŏ��g��ł����v�Əq�ׂ܂����B
�����[�����u�܂h�~ �I���͑����I�ɔ��f�v
���슯�[�����͊t�c�̂��Ƃ̋L�҉�Łu�܂h�~���d�_�[�u�̏I���͓s���{���̊������Ò̐��̂Ђ����Ȃǂ��l�����đ����I�ɔ��f����B���{����Ă���{��̌��ʂ��܂ߍ���̊����Ȃǂ��ő���̌x�����������Ē������A�m������ƂƋٖ��ɘA�g���đΉ����Ă��������v�Əq�ׂ܂����B�܂���Ò̐����m�ۂ��邽�ߎ����̂̔��f�Ō��݂̊O���f�Â݂̍�������������Ƃ��ł���悤�ɂ�����j�ɂ��āu�ꕔ�̒n��ł́w���M�O���x�̗\���Â炢�������Ă���A�����ɉ����Ēn��̔��f�Őv���Ɋ��҂�K�Ȍ�����×{�ɂȂ��邱�Ƃ��ł���悤�I�������L���邽�ߍ��Ƃ��ĕ��j�����������̂��v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�d�lj��̃��X�N���������͂���܂łǂ����f���Ă������������B�܂���]����ꍇ�͌����O�ł���Ë@�ւ̎�f���\�ł���A�Ǐd���ꍇ��}�ώ��Ȃǂɂ͑��₩�Ɏ�f����悤���킹�ČĂт��������v�Əq�ׂ܂����B�@ |
���I�~�N�������\���u�e���̏��݂Ă�3�����Ŋ������g�債�A�I���v�@1/25
�o�D�̒J���͉�i��߂�u�߂��܂�8�v(�t�W�e���r�n)��25���A���ې����w�҂ŎR�L����������\�̎O�Y�ڗ펁���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̊����g��ɂ��Č��y�����B
�ԑg�ł́A���C�^�[�ʐM�̕ɂ��ƁA�p���̕ی����ǂ�21���A�I�~�N�������̕ψق��d�˂�����u�a�`�D2�v�ɂ��āu�a�`�D1�v�ɔ�ׂđ��B���������\��������Ƃ��Ē��������Ă��邱�Ƃ��Љ�B�ꕔ�̌����҂��u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂԂa�`�D2�͉p����426���̈�`�q��͂����{�������Ƃ�A�f���}�[�N�ł͐V�K�����҂̂�����߂銄���͍�N�̍ŏI�T��20���������̂ɔ�ׁA������2�T��45���ɏ㏸���Ă���A�����@�ւ��u�a�`�D1�Ɋ��������l���a�`�D2�ɍĊ�������\���͔ے�ł��Ȃ��B�����g��̃s�[�N��2��\��������v�Ƃ��Ă���B���{�̋�`���u�ł��a�`�D2��261���m�F����Ă���Ƃ����B
�O�Y���́u���N�`�����ǂ�ȂɊJ�����Ă��������������̗l����悵�Ă��܂������A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂̓C���t���G���U�����N���s����Ƃ������ƂȂ̂ŁA���S�Ȃ�o������Ȃ������Ƃ��Ă��A�Ώ��ł��Ă��Ă���Ƃ������ƂŁA���邢�������҂������Ǝv���v
�㓡�ΔV���J����24���A�Z���ڐG�҂ɏǏo���ꍇ�A�������s��Ȃ��Ă���t�̔��f�Ŋ����Ɛf�f�ł���悤�ɂ��邱�ƁA40�Ζ����Ȃǂŏd�lj����X�N�̒Ⴂ�l�͈�Ë@�ւ���f�����A�����Ō������Ď���×{�ł���悤�ɂ���Ɣ��\�����B�����g��ɔ��������L�b�g���s�����Ă���B
�O�Y���́u�����L�b�g������Ȃ��̂͂��傤���Ȃ���Ȃ����Ƃ��v���B�d�lj����Ȃ��Ƃ����̂���ԑ厖�ł����āA���ׂȂ̂��A�R���i�Ȃ̂��A�����Ă��܂��Α債�����ł͂Ȃ��v�Ƃ��b�����B
�O�Y���̌����`�[�����܂Ƃ߂�����̓����s�̐V�K�����Ґ��̗\���ɂ��ƁA2�����߂�2���l���A5���Ƀs�[�N�ɒB���A���̌�͉��~����Ƃ��Ă���B
�O�Y���́u�d�v�Ȃ̂́A���Ȃ���������������A���~�����Ƃ��ɂ悭��������x���o�E���h�����Ȃ������Ƃ������ł����A�e���̏��݂Ă��A��������3�����Ŋ������g�債�A�I�����Ă����Ă���B�䕗�̐i�H�\���Ǝ����悤�Ȃ��́B����10���Ԃ��炢�䖝����A�Ȃ�Ƃ��Ȃ��Ȃ����Ɛl�X�͊�]�������ĊO�o���l�Ȃǂ��ł���v�Ɖ�������B |
���C�^���A�A�I�~�N���������̓s�[�N�z�����@�R���i�ӔC�ҁ@1/25
�C�^���A���{�̐V�^�R���i�E�C���X���ӔC�ҁA�t�B�O���E�I������24���A�����͂������ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�̗��s�́u�s�[�N�ɓ��B�����悤�ŁA�����҂͌����X���ɂ���v�Əq�ׂ��B�Ƀ��f�B�A�����B
�t�B�O���E�I�����́u����2���ԁA(�o�ϓs�s�~���m������)�k�������o���f�B�A�B�ł����@�Ґ����މ@�Ґ���������Ă���B����͗ǂ����v�ƌ�����B���B�͐V�^�R���i�̗��s�Őr��Ȕ�Q�����B���B�C�^���A�̐V�K�����Ґ���11���ɂ�22���l���Ă������A24���͖�7��7700�l�܂Ō������Ă���B |
���I�~�N�������̊����g�匜�O�A�M���V�X�e����Ԃց@�j���[�W�[�����h�@1/25
�j���[�W�[�����h�̃W���V���_�E�A�[�_�[����1��23���A�V�^�R���i�E�C���X������Ƃ��ē������Ă���M���V�X�e���ɂ��āA�����ߌ�11��59������S�Ă̒n����u�ԁv�Ɉڍs����Ɣ��\�����B�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�����^�ψي��̎s�������̊g�傪���O����邱�Ƃ���A�x�����x�����ō��ʂɈ����グ���B
���{�͂���܂ŁA�I�~�N�������̃��X�N���ŏ����ɗ}���邽�߁A1��������{�\�肾���������K���̒i�K�I�ɘa��2�����܂ʼn������Ă����B�܂��A�������̗v���ł���o���O72���Ԉȓ��̉A���ؖ���48���Ԉȓ��ɒZ�k���A���{�w��{�݂ł̊u�����Ԃ�7���Ԃ���10���Ԃɉ�������ȂǁA���ۑ���������Ă���(2021�N12��22���L���Q��)�B�������A�I�~�N�������̊����͋�`��u���{�݂̘J���҂Ɏn�܂�A1��24���܂łɍő�s�s�I�[�N�����h��k���̃p�[�}�X�g���E�m�[�X�A�쓇�̃l���\���E�}�[���{���n��Ōv19�l�m�F����Ă���B
�j���[�W�[�����h���������Ă���V�^�R���i�E�C���X������̐V���x�uCOVID19�v���e�N�V�����E�t���[�����[�N�v�ł́A�A�I�����W�A�Ԃ�3�i�K����Ȃ�M���V�X�e����p���Ă���B�Ԃ̏ꍇ�́A�ő�100�l�̐l�������Ȃǂ��ۂ������̂́A���N�`���ڎ�ؖ����̎g�p�ɂ���Ĉ��H�X�̗��p�Ȃǂ��\�ƂȂ�B
�A�[�_�[���́u�I�~�N�������̊����͂͋����A����܂ł����͂邩�ɑ����̊����҂���������Ǝv�����A�������X�N��}���邽�߂ɂł��邾���������N�`���̒lj��ڎ���Ăق����v�ƌĂъ|�����B�@ |
���؍����I�~�N�����嗬���@1/25
�؍����{��25���A�V�^�R���i�E�C���X��24���̊����҂�8571�l�ɏ�����Ɣ��\�����B1��������̊����҂�8��l����̂͏��߂āB�؍����f�B�A�ɂ��ƁA����܂ł̍ő��͍�N12����7848�l�B���̌�A�ꎞ�����X�����������A�ψي��I�~�N�����������̊�������T50���ȏ�ƂȂ�A�嗬�����Ă����B
���{�͂���Ɋ����҂�������Ƃ݂āA�����҂̗}���ɏd�_��u���Ă�������܂ł̑���A�d�lj����₷������҂�̌����⎡�ÂɏW��������j��26�����珇���]������Ɣ��\�B�����Ώۂ��i������A�u�����Ԃ�Z�k�����肵�Ĉ�ÁE�h�u�Ԑ��̕��S�y����}��B |
 |


 �@
�@ |
���X�e���X�I�~�N�����A�嗬��芴����18%�����\���@�����ł����o�@1/26
�C�O�̈ꕔ�ōL�����Ă���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̈��ɂ��āA�����J���ȂɐV�^�R���i�������������Ƒg�D��26���A�����̎嗬�n�����������͂�18%�����\��������Ƃ��錩�����������B�C�O�̈ꕔ�̌����ł̓I�~�N�������ǂ������ʂł����A�u�X�e���X�I�~�N�����v�Ƃ��Ă�Ă��邪�A������PCR�����ł͔��ʂł���Ƃ����B
�I�~�N�������́A�E�C���X�̈�`�q�̈Ⴂ�ɂ���āuBA.1�v�uBA.2�v�Ȃǂƌn�����������B����܂Ő��E�ōł��L�܂��Ă����n���́A���{���܂�BA.1�����A�ꕔ�̍��ł�BA.2���L�����Ă���B
���Ƒg�D�͂��̓��ABA.2���u���u�⍑���Ō��o����Ă���v�Ǝw�E���A�Q�m����͂̕K�v����i�����B��̓I�Ȑ��͏W�v���Ƃ��Ė��炩�ɂ��Ȃ������B
�����͂ɂ��ẮA�f���}�[�N�̏��A������1�l�����l�Ɋ������L���Ă��邩�������u�����Đ��Y���v���ABA.1����18%���������Ƃ����B���͂������Y���E���s�勳���́u��2�������́A�w�f���^�ƃI�~�N�����̍��x�Ō���ꂽ�قǂł͂Ȃ����A���̂Ƃ��Ă��Ȃ�傫�ȈႢ�v������Ǝw�E���Ă���B
�u������肪�i�f���}�[�N��C�X���G���ł́A�����̃s�[�N����x�z������ɁA�Ăъg�債�Ă���B�����̘e�c�����E���������nj��������́u�u�������ɂ���Ă���Ɋ����g�傪�i��ł���BBA.1���������͂��������Ƃ͌x�����ׂ����v�Ǝw�E�����B����A���@���͍����Ȃ��\��������Ƃ����B
|
���g�X�e���X�I�~�N�����h�ւ̒u�������Ɍx�� �����͂�2�{�Ƃ̎w�E���@1/26
�]���̃I�~�N���������u�����͂�2�{�v�Ƃ̕��͂��E�E�E�B�ꕔ�̉Ȋw�҂���X�e���X�I�~�N�����Ƃ��Ă��I�~�N�������̈���u�a�`�D2�v������A�����Ă����\�����w�E����Ă��܂��B����Ȃ��Â̂Ђ������������˂Ȃ��̂��E�E�E
������w��Ȋw������ �������y�����@�u����g�X�e���X�I�~�N�����h�g�I�~�N��������h�Ƃ��Ă�Ă���v
���[���b�p�ł͈ꕔ�̉Ȋw�҂���g�X�e���X�I�~�N�����h�Ƃ��Ă�Ă���V���ȕψٌ^�ł��B���ܓ��{�Ŋ������g�傳���Ă���̂́A�I�~�N�������a�`�D1�ł����A����ɕψق����̂��I�~�N�������̈���a�`�D2�ł��B�V�^�R���i�E�C���X�̈�`�q�z��͂��Ă��鍲���y�������w�E����̂��E�E�E
�������y�����@�u���ɂ���Ă���͂��邪�A�a�`�D1���a�`�D2�̕���2�{���x�A���s���₷���v
�f���}�[�N�ł�12�����{���犴���҂��}���ɑ����Ă��܂����A���V���g���E�|�X�g�͐��Ƃ̘b�Ƃ��āA�V�K�����҂̂����a�`�D2����߂銄�������悻65���ɂ̂ڂ�Ɠ`���Ă��܂��B�C�M���X�ł́A�ی����ǂ�����������荂���\��������Ƃ��Ăa�`�D2�����Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���O�����̂��E�E�E
�������y�����@�u�I�~�N�����̎����悤�Ȃ��̂ƈ�ۂ��������������A�]�����ƃA���t�@�����炢�ψِ��͈Ⴄ�B�`�d�͂����ł͂Ȃ��A�Ő��A�Ɖu�A��ɑ����R���A�a�`�D1�Ƃa�`�D2�ł͂��Ȃ�قȂ�\��������v
�a�`�D2�͌���ł̓I�~�N�����̈���ɕ��ނ���Ă��܂����A�a�`�D1�Ƃ̈�`�q�̈Ⴂ�͑傫���A���̍����d�Ǔx�Ȃǂ̈Ⴂ�ɂȂ���\��������Ƃ����̂ł��B���{�̋�`���u�ł́A����܂łɂa�`�D2��198��m�F����Ă��āA�x�����K�v���Ƃ����܂��B
�������y�����@�u�����炭�s���ł��L�����Ă���\���͂��Ȃ荂���B�a�`�D1�Ƃa�`�D2����ʂł���̐��������āA����ɔ����Ă����ׂ����Ɓv
|
���I�~�N�����h���^�A�����ł��m�F�@�����͍����Ƃ̕��͂��@1/26
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�̔h���^�̊����������ł�27��m�F����Ă��邱�Ƃ����������nj������̒����ł킩�����B�uBA.2�v�ƌĂ�A�I�~�N�����^�Ŏ嗬�́uBA.1�v�Ƃ͕ψق��قȂ�B���s��̐��Y��������͔h���^���]���̃I�~�N�����^��芴���͂�18%�����Ƃ̕��͂��������B
�h���^��40�J���ȏ�Ŋm�F����A���E�ی��@��(WHO)���D��I�ɒ�������悤�������Ă���B���������̘e�c����������26���A�h���^�Ƃ̔�r�ɂ��āu���@���Ȃǂ̈Ⴂ�͖��m�ɂȂ��Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ��B
����A�����J���Ȃ̏W�v�ɂ��ƌ��u�֘A�ł͔h���^��19�����_��198��m�F���ꂽ�Ƃ����B���Ȃ͎����̕��S�̌y���̂��ߕψٌ^���ׂ�PCR�����̏k���Ȃǂ𑣂��Ă���A���ۂɂ͂���ɑ����\��������B
���Ȃ̐��Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�̓����̉�ł́A�����̃R���i�����҂�97%���f���^�^����I�~�N�����^�ɒu����������Ƃ̃f�[�^�������ꂽ�B��c�ł́u�Z���I�ɂ͑S���Ŋ����g�傪�p������v�Ƒ����B�e�c���́u�ǂ̎��_��(�����Ґ���)�����Ɍ��������́A�܂������͂����肵�Ă��Ȃ��Ƃ̋c�_���������v�ƌ�����B
|
���I�~�N�����h�����A������27��m�F�@�����́u18�������v���v���@1/26
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̈��ŁA���ݎ嗬�̃E�C���X�Ƃ͕ʂ̔h�������A�����ŏ��Ȃ��Ƃ�27�ጩ�����Ă������Ƃ�26���A���������nj������̏W�v�ŕ��������B
���B��A�W�A�Ŋg�債�Ă���uBA�E2�v�ƌĂ��E�C���X�ŁA�����͖��𖾂ȕ������������A���s��̐��Y������(�����lju�w)��͓����A�����͂�����܂ł̃I�~�N���������18�������Ƃ̕��͌��ʂ��܂Ƃ߁A����̗��s�Ɍx�����K�v�ƌĂъ|�����B
BA�E2�́A�嗬�̃I�~�N�������uBA�E1�v�ƕψق̉ӏ��������Ⴄ�B�p�����{�̕��ɂ��ƍ�N11���ȍ~�A��40�J��������ꂽ�B�g�傪���ɖڗ��̂̓f���}�[�N�ŁA�V�K�����҂̔����߂����߂�B���E�ی��@��(WHO)��BA�E2�ɂ��āA�d�lj����X�N�Ȃǂ̒����������}���ׂ����Ƃ��Ă���B
�����ł́A��N12��27�����獡�N1��16���܂ł�27��m�F���ꂽ�B��`���u�ł��������Ă���A�C���h�A�t�B���s���Ȃǂɑ؍ݗ�������l���������Ă����B
BA�E2�Ɋ����������҂̐f�Âɓ����������ۈ�Õ�����̏��{�N�Ƌ���(�����NJw)�́u�l�l����������ł́A�Ǐ��a�C�̏d����(BA�E1�Ƃ�)�Ⴂ�͂Ȃ��Ƃ�����ۂ��v�Ƙb���B
����A�f���}�[�N�̃f�[�^�Ɋ�Â����͂��܂Ƃ߂����Y�����́u�����͂�2���߂�������Ƃ����Ⴂ�͑傫���v�Ƃ�����ŁA������{�ōL���邩�ǂ����𒍈Ӑ[���Ď�����K�v������Ǝw�E�����B
|
�����N�`��2��A�I�~�N�������Ǘ\�h52%�@�����f�[�^�ŏ��@1/26
�����w�Ȃǂ̌����`�[����26���A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�ɑ��郏�N�`���̌��ʂ������̃f�[�^�ŕ��͂����b�茋�ʂ\�����B�I�~�N�����^�̗��s���L���������Ԃɂ����āA�ăt�@�C�U�[�����ă��f���i����2��ڎ�̔��Ǘ\�h���ʂ�51.7%�ŁA�f���^�^���s���ł�88.7%���ቺ���Ă����B�I�~�N�����^�ւ̃��N�`�����ʂɊւ��鍑���f�[�^�͏��߂Ă��Ƃ����B
�S���I�ɃI�~�N�����^�̊������L�����Ă���1��1�`21���̌����f�[�^�͂��A�I�~�N�����^�ɑ��郏�N�`���̌��ʂ𐄒肵���B�����ȂǑS��5�J���̈�Ë@�ւŃR���i�̏Ǐ����Č�������417�l(16�`64��)�ɂ��ĉ�͂����B
���N�`�����ڎ킾����53�l�̂����z����24�l(45%)�������̂ɑ��A�t�@�C�U�[�������f���i����2��ڎ킩��14���ȏソ����346�l�ł͗z����88�l(25%)�ɂƂǂ܂����B�Ǐ����ėz���ɂȂ�䗦�v�����Ŕ�r���A2��ڎ�͖��ڎ�Ɣ�ׂĔ��ǂ�51.7%(2.0�`76.2%)���炷���ʂ�����Ɛ��肵���B�����A�܂��Ǘᐔ�����Ȃ��������͂ł��邽�ߐ���l�̕����傫���B
�f���^�^�����s����2021�N7��1���`9��30���̃f�[�^�̕��͂ł́A2��ڎ�̔��Ǘ\�h���ʂ�88.7%(78.8�`93.9%)�������B�����̐X�{�_�V�㋳���́u�I�~�N�����^�ɑ��Ă����N�`���͈��̌��ʂ����邪�A�f���^�^�Ɣ�ׂČ���肷��̂͊ԈႢ�Ȃ��B�ڎ킵�Ă��Ă����f�����Ɋ�����𑱂��Ăق����v�Ƙb�����B |
���S���̃R���i�����m�F ����7���l���� �ߋ��ő��Ɂ@1/26
26���͌ߌ�7���܂łɁA�S����7��1633�l�̊��������\����Ă��܂��B����̊������\��7���l����̂͏��߂Ăł��B�܂��A�����s��5�l�A��t����4�l�A���{��3�l�A���m����3�l�A��������3�l�A���s�{��2�l�A�k�C����2�l�A�O�d����1�l�A��ʌ���1�l�A����1�l�A�L������3�l�A�Ȗ،���1�l�A���ꌧ��1�l�A�Q�n����1�l�A��錧��1�l�A���쌧��1�l�A����������1�l�̍��킹��34�l�̎��S�̔��\������܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͋�`�̌��u�Ȃǂ��܂�235��9254�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��235��9966�l�ƂȂ��Ă��܂��B�S���Ȃ����l�͍����Ŋ������m�F���ꂽ�l��1��8604�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��1��8617�l�ł��B
��Ȏ����̂Ȃǂɂ��܂��ƁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͗v�Ŏ��̂Ƃ���ł��B
�����s��49��8549�l(14086) / ���{��28��5908�l(9813) / �_�ސ쌧��21��2273�l(4794) / ��ʌ���14��8159�l(3890) / ���m����14��4761�l(4663) / ��t����12��7419�l(2621) / ���Ɍ���11��18�l(4303) / ��������10��4065�l(3615) / �k�C����7��8633�l(2091) / ���ꌧ��7��8358�l(1256) / ���s�{��5��3950�l(2216) / ���L������4��3138�l(1252)
���̂ق���`�Ȃǂ̌��u�ł̊����m�F��9193�l(116)�A��������̃`���[�^�[�@�ŋA�������l�ƁA���̐E���⌟�u���Ȃǂ̊����͍��킹��173�l�ł��B
�����J���Ȃɂ��܂��ƐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�l�ŁA�l�H�ċz���W�����Î��ȂǂŎ��Â���Ȃǂ��Ă���d�ǎ҂́A26�����_��470�l(�{26)�ƂȂ��Ă��܂��B
����A�Ǐ��P���đމ@�����l�Ȃǂ�26�����_�ō����Ŋ������m�F���ꂽ�l��186��4355�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����659�l�̍��킹��186��5014�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A24����1���ɍs��ꂽ���匟��������PCR�����Ȃǂ̐��͑���l��11��60���ł����B
|
�������V����242�l�R���i�����@�X�|�[�c���ŃN���X�^�[�@1/26
�H�c���ƏH�c�s��26���A�v242�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�������\��25����245�l�Ɏ����ő����B�����ŊJ���ꂽ�X�|�[�c���ŐV���ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F���ꂽ�B�����̊����҂̗v��3110�l�B
�����҂̓���͕ی����ʂŏH�c�s103�l�A���24�l�A�k�H�c13�l�A�\��13�l�A�H�c����4�l�A�R���{��9�l�A���9�l�A����65�l�A����2�l�B����ی����Ǔ��̊����҂͏Ǐ�Ȃǂ����B�ق��ɏd�ǎ҂͂��Ȃ��B
�V���ȃN���X�^�[�͌����ō������{�ɊJ���ꂽ���Z���̃X�|�[�c���B�v11�l�̊������m�F���Ă���B
25���ɔ��\���ꂽ�X�|�[�c���̃N���X�^�[�́A�V����42�l�̊��������������B
���̂ق��A����܂łɔ��\���ꂽ�N���X�^�[�̐V���Ȋ����҂͔\��ی����Ǔ��̎��Ə�5�l�A���ی����Ǔ��̐E��2�l�A���암�̍��Z1�l�B�H�c�s�͏��w�Z11�l�A�X�|�[�c�C�x���g1�l�A�ۈ牀2�J���ł��ꂼ��7�l��5�l�B
�Y�������a�@(����s)�͐E��2�l�̊����\�����B���҂ƐڐG���Ă��炸�A�ڐG�҂̉A�����m�F�������ߋƖ��͒ʏ�ʂ�s���B
�H�c�s����ψ���́A�V���ɏ����w�Z�v5�Z���w���A�w�N���Ƃ���B����s���ς͏��w�Z1�Z��V���Ɋw�N���Ƃ��A���w�Z1�Z�̋x�Z��26������28���܂ʼn��������B
�H�c�s�ƌ��x�A�H�c�C��ۈ����̐E���e1�l�A�\��R�{�L����h�{���̐E��3�l�̊��������\���ꂽ�B
|
�������s �V�^�R���i 5�l���S 1��4086�l���� 2���A���ʼnߋ��ő� �@1/26
�����s����26���̊����m�F��1��4086�l��25������1200�l�ȏ㑽���Ȃ�2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�����̗z�����͂��łɑ�5�g�̃s�[�N������30�����A�s�̒S���҂́u���ɓ��ɐl�ƐڐG���邱�Ƃɂ�銴���̃��X�N�����܂��Ă���Ƃ�����@�ӎ��������ď\���ȑ���Ƃ��Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B�����s��26���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�̒j�����킹��1��4086�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B25�����1200�l�ȏ㑽���Ȃ�2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂����j���Ƃ��Ă͂���܂łōł���������1�T�ԑO�̍���19�����6700�l�]�葽��1.9�{�̑����ł��B7���ԕ��ς͏��߂�1���l����1��633.4�l�ƂȂ�A�O�̏T��2.3�{�ƂȂ�܂����B
���z���� 30������
�܂��s�͌����̗z������25�����_��30.5���ɂȂ����Ɩ��炩�ɂ��܂����B�z�����͍���20���ɑ�5�g�̃s�[�N������A���̌���㏸�������Ă��܂��B�s�̒S���҂́u�X�Ȃ��Ɋ������Ă���l�����Ȃ�̊����ł��邱�Ƃ������Ă���B���ɓ��ɐl�ƐڐG���邱�Ƃɂ�銴���̃��X�N�����܂��Ă���Ƃ�����@�ӎ��������ď\���ȑ���Ƃ��Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
10�Ζ�����10��A30�ォ��70��܂ł͂��ꂼ��ߋ��ő��ɂȂ�܂����B�܂�30��ȉ����S�̂�64.6�����߂Ă��܂��B65�Έȏ�̍���҂�7.4���ɓ�����1040�l�ŏ��߂�1000�l���܂����B�܂��S�̂�44.8���ɓ�����6305�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��܂����B
�����o�H���������Ă���̂�4892�l�Łu�ƒ���v��2642�l�ƍł������S�̂�54���ł����B�܂��u�{�ݓ��v��24.4���ɓ�����1192�l�ʼnߋ��ő��ɂȂ�܂����B�ۈ牀�Ɨc�t���ł��킹��394�l�A���w�Z��228�l�A����Ҏ{�݂�136�l���m�F�����ȂǕ��L���{�݂Ŋ������L�����Ă��܂��B�u�E����v�ł̊�����504�l�ł����B�u�ƒ���v�u�{�ݓ��v�u�E����v�Ŋ��������l�͂��ꂼ��ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
26�����_�œ��@���Ă���l��25�����222�l������3027�l�ł����B����×{���̐l��25�����4400�l�]�葝����4��2733�l�ƂȂ�A���߂�4���l���܂����B��Ë@�ւɓ��@���邩�z�e���⎩��ŗ×{���邩�������̐l��3��4620�l�ʼnߋ��ő��ł��B����A�s�̊�ŏW�v����26�����_�̏d�ǂ̊��҂�25�����4�l������18�l�ł����B����ɓs�͊������m�F���ꂽ40���70�ォ��90��̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���̂���3�l�͓������ʗ{��V�l�z�[���ɓ������Ă��āA���̎{�ݓ��Ŋ�������
�B
���s���̕a���g�p�� 40������
�����s���ŐV�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p����26�����_��40������42.8���ƂȂ�A�s���ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50���ɋ߂Â��Ă��܂��B�s���V�^�R���i�̊��҂̂��߂ɍő�Ŋm�ۂł���Ƃ��Ă���6919���̕a���g�p����26�����_��40������42.8���ƂȂ�܂����B�s���̕a���g�p���͍����ɓ����ď㏸�������Ă��āA����9����10�������8�����17����20���A����4�����21���ɂ�30�������ꂼ�꒴���܂����B������30�����Ă���5�����26���A40�����A�s�����{�ɑ��ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50���ɋ߂Â��Ă��܂��B����A�d�ǂ̊��҂�26�����_��18�l�Ńs�[�N���ɂ�297�l�ɏ������5�g�ɔ�ׂ�Ƒ啝�ɏ��Ȃ��a���g�p����3.5���ł��B�s�ɂ��܂��ƁA�d�ǂ̊��҂͏��Ȃ����̂̊����m�F�̋}���ɔ����ďd�lj��̃��X�N����������҂��b����������l�̓��@�������Ă��邱�Ƃ���A�S�̂̕a���g�p���̏㏸�������Ă���Ƃ������Ƃł��B�a���g�p����}���邽�߂ɂ͊����g��Ɏ��~�߂������A�V�K�z���҂������Ɍ��炵�Ă��������œ_�ɂȂ�܂��B
|
�������ŐV����1��4086�l�����A65�Έȏオ����1000�l���@1/26
�����s��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�1��4086�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����X�V�����Ɣ��\�����B�N��ʂł́A65�Έȏ�̍���҂�1040�l�ƂȂ�A���߂�1000�l�����B�܂�40��`90���5�l�̎��S���m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�������}�g�債��1���ȍ~�̔��\���ł͍ő��B���̂���70��A80��A90��̏�����3�l�̓N���X�^�[�����������������ʗ{��V�l�z�[���̓����҂ŁA�������1��22���Ɏ��S�����B80��̏����͓��A�a�A90��̏����͍������̊�b�������������B
�����s���̕a���g�p����42�E8���ƂȂ�A���r�S���q�m�����ً}���Ԑ錾�̗v������������ڈ��Ƃ���50���ɋ߂Â��Ă���B�s�͊����҂�1�����{�ɖڗ�������҂��獂��҂�ɍL�����Ă���Ƃ݂Ă���u�Ⴂ�l�́A�����̍s���͈͂ɍ���҂��b����������l������Ώd�lj����X�N�����邱�Ƃ��̂ɖ����Ăق����v�Ƙb���Ă���B
�s�̔��\�ɂ��ƁA���ݓ��@���Ă���d�NJ��҂͓s�̊��18�l�B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���26�����_��1��633�D4�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�231�D2���B�s���̗v�̊��Ґ���49��8549�l�ƂȂ����B
�N��ʂł�20�オ3225�l�ƍł������A10�Ζ���1829�l�A10��1600�l�A30��2442�l�A40��2213�l�A50��1334�l�ȂǁB
����×{��4��2733�l�A���@�E�×{����������3��4620�l�ɂȂ����B
|
�����{�A�d�Ǖa���������グ �y�ǂł���b�����d�ĉ� �@1/26
���{��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ɔ����A�a���m�یv��Œ�߂��d�Ǖa���̉^�p���������グ���B���a���d�ĉ������R���i���҂̂ق��A�d�lj����X�N�������D�w��l�H���͊��҂�����炩���ߏd�Ǖa���Ɏ��e���鎖�Ⴊ�����Ă���B�V�ψي��u�I�~�N�������v�̉e�����傫���A�g���m���m���́u�I�~�N���������L�̉ۑ肾�v�ƌx�������������B�{�ɂ��ƁA�R���i�͌y�ǁE�����ǂ����A�d�ĂȊ�b����������Ȃǂ��ďd�Ǖa���ł̎��Â�v���銳�҂�13�����_�Ń[���������B������25����40�l�ɋ}���A26����33�l�ɏ�����B
�g�����́u�ʼn߂ł��Ȃ����ɂȂ��Ă���v�Ƌ����B�a���m�یv���̉^�p�����t�F�[�Y1(170��)����t�F�[�Y3(330��)�Ɉ����グ���B���ۂ̉^�p����25�����_�̖�240������340�����x�܂ő����錩���݁B�{�ɂ��ƁA�f���^���܂ł̊�����ł͔x���Ǐ������A���@���銳�҂��唼���������A�I�~�N�������ł͔x���Ǐ�������P�[�X�̓f���^���ȂǂƔ�ׂď��Ȃ��d�lj����͒Ⴂ�B
����ŁA�R���i�͊�������Ί����ǖ@�Ɋ�Â��u������K�v������B�R���i�����̋^��������A��b�����������������҂͈�ʂ̏W�����Î�(�h�b�t)�ȂǂŎ��Â��邱�Ƃ�����B�D�w��l�H���͊��҂�����l�ŁA����I�ɃR���i�z������������P�[�X���������Ă���Ƃ����B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�������u����(�܂�)�h�~���d�_�[�u�v��27���A�k�C������{�A�������Ȃ�18���{���ɒlj��K�p�����B���Ԃ�2��20���܂ŁB���H�X�̉c�Ǝ��ԒZ�k�ȂǁA���̐��������߂�B�Ώےn���34�s���{���Ɋg�傷��B |
���A�����J�̃R���i���Ґ��A�f���^�����s���Ɠ����x�Ɂ@����҂Ɩ��ڎ�ҁ@1/26
�A�����J�ŐV�^�R���i�E�C���X�ɂ��1��������̎��Ґ����A�f���^���̊����g��̃s�[�N���Ɠ����x�܂ő����Ă��邱�Ƃ��A�ŐV�̓��v�Ŗ��炩�ɂȂ����B
�ăW�����Y�E�z�v�L���X��w�̏W�v�ɂ��ƁA1��������̎��Ґ���7�����ς́A����21����2000�l�߁B23����2033�l�ƂȂ����B����͍�N9���́A�f���^���̗��s�̃s�[�N���Ƃقړ������B
���҂̑唼�́A65�Έȏ�̍���҂��A���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l�����ƂȂ��Ă���B
�A�����J�͐��E�ōł�COVID-19�ɂ�鎀�҂������A���{����26���ߌ�܂ł�87��1937�l���S���Ȃ��Ă���B����ŁA�����Ґ��͓��������͂邩�ɑ����A���@���Ґ����f���^���̃s�[�N�����z���Ă���B
1��������̐V�K�����̕��ς́A����܂ł̊����̔g�Ɣ�ׂĂ����ɑ����B
�X�^���t�H�[�h��w�̊����ǐ��ƁA�A�u���A���E�J�������m��BBC�̎�ނŁA�I�~�N�������͈�ʓI�Ƀf���^�������Ǐy���A����̎��Ґ��̑����͓��@���̍����ɋN�����Ă���Ǝw�E�����B�u��芴���͂̋����E�C���X�̏ꍇ�A�d�NJ��Ґ��Ǝ��Ґ��͋}���ɑ�����B�d�lj�����m�����Ⴍ�Ă��A��ΐ������ɑ������炾�B���ɑ傫�Ȑ��ɑ���w���Ȃ��m���x�́A�傫�Ȑ��ɂȂ��Ă��܂��v�@�Ď��a��Z���^�[(CDC)�̃f�[�^�ł́A���҂�75���߂���65�Έȏ�ƂȂ��Ă���B
����ɓ��v����́A���N�`����ł��Ă��Ȃ��l�̎��S����m���́A���N�`���ڎ���������A�u�[�X�^�[(�lj��Ɖu)�ڎ�����l�̖�100�{�ɏ�邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B�ăI�n�C�I�B�P�[�X�E�E�G�X�^����w�̐l���E�ʓI���N�Ȋw�Ȃŏy�����߂�}�[�N�E�L�����������m�́A�u�I�~�N�������̗��s�ł͈�т��āA�d�lj��Ɠ��@���A���S���X�N�܂ŁA���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l�ւ̉e�����傫���v�Ǝw�E����B�u����͖��m�Ȏ������v�@�A�����J�ł͂���܂łɐl����63�������N�`���ڎ���I���A12����1���ڎ���Ă���B
�j���[���[�N�E�V���L���[�X��w�̉u�w�ҁA�f�C���B�b�h�E���[�Z�������ɂ��ƁA���N�`�������l�������A���̐l�����������K����ς��ĎЉ�𗬂𑝂₵�Ă��錋�ʁA���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l�X�̓��@���⎀�S�����オ���Ă���\��������Ƃ����B
���[�Z�������́A�u�{�X�g����j���[���[�N�Ȃǃ��N�`���ڎ헦�̍����n��̐l�X�قǁA�s���p�^�[����ς������ƂŃE�C���X�ɐڐG����\�����������A����قǑ厖�ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ɛ����B�u�����҂������钆�ł́A�E�C���X�����X�N�̍����l�X�ɂ܂œ��B���A���S���������Ȃ�ƌ���̂��Ó����v�Ƙb�����B
�܂��A�A�����J�̖��ڎ�҂̃��X�N�͔N��̂ق��A�얞�⍂�����Ƃ��������������Ȃǂɂ���Ĉ������Ă���Ǝw�E�����B�u�����̗v������������l�̃��X�N�͍��܂�v
�Z���I�ɂ́A1��������̎��Ґ��͍��������������Ƃ݂��Ă���B�L�����������m�́A�����Ґ��̃s�[�N�Ǝ��Ґ��̃s�[�N�͍ő��1�J�������ƌx���B���Ґ��͌��������T�Ԃ͑������邩������Ȃ��ƌ�����B�u�A�����J�͂܂��s�[�N�ɒB���Ă��Ȃ��B�I�~�N�������ɂ�銴���Ґ��̑����ɂ���āA�l��������̎��S���͌����ɓ]���Ă��Ȃ��v
|
���I�~�N��������99�D9���@�V�K�������������ґ����\�Ăb�c�b���v�@1/26
�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)��25���A�S�Ă�16�`22���ɐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊��������������l��99�D9�����ψي��u�I�~�N�������v�ɂ����̂��Ƃ���ŐV�̐��v�\�����B�č��ŏ��߂ăI�~�N�������̊����m�F�����\���ꂽ�͍̂�N12��1���ŁA2�J����ł���܂Ŏ嗬�������f���^������A�قڊ��S�ɒu����������Ƃ݂���B
�č��ł̓I�~�N�������̋}���Ȋg��ɔ����A�p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�ȍ~�A�ł��}���Ɋ����Ґ������������B�b�c�b�̏W�v�ɂ��A�������{��1��������̐V�K�����Ґ���7���ԕ��ς͖�80���l���L�^�B��25���l�ʼnߋ��ő���������N1����3�{�ȏ�ɑ������B
����A�����ɃI�~�N�����������s�����k�����⒆�����ł́A�s�[�N���z�������悤���B�j���[���[�N�B��1��������V�K�����Ґ��͍������{��9���l���Ă������A24���ɂ͖�1��2500�l�ƂȂ����B
�������A�S�Ă̎��Ґ��͑������A1���������2000�l(7���ԕ���)���S���Ȃ��Ă���B�I�~�N���������s������12�����{�ɔ�ז�2�{�ŁA�t�@�E�`�����A�����M�[�����nj���������23���A�`�a�b�j���[�X�ɑ��u���N�`���ڎ킪�\���łȂ��n��ł͓��@���ꂵ�݂���������������������Ȃ��v�ƌ�����B
|
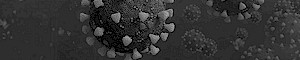 |


 �@
�@ |
���R���i�t��!?�@2�V�[�Y���A���ŃC���t�����Ґ����ᐅ���̃��P�@1/27
�N�����ƂƂ��ɐV�^�R���i�E�C���X�E�I�~�N���������҈Ђ��ӂ邢�n�߁A�����̓s���{���ł܂h�~���d�_�[�u�����{�����Ȃǂ̑Ή�������Ă��܂��B����œ������s���뜜���ꂽ�~��̋G�ߐ��C���t���G���U�����ɂ��Ă�2020/21�N�V�[�Y�����l�A2021/22�N�V�[�Y�������܂̂Ƃ���ɂ߂ď��Ȃ���Ԃ̂܂ܐ��ڂ��Ă��܂��B2�N�A�����ăC���t���G���U�����҂��g���j�I�ɏ��Ȃ��h���R�⍡��̗��s�̉\���A�I�~�N�������Ƃ̊֘A���܂߂������Ǒ�Ȃǂɂ��āA���l�ߌ����n�r���e�[�V�����a�@(���l�s�ߌ���)�̋g�c�����@���Ɏf���܂����B
���嗬�s�̊뜜���A���܂̂Ƃ��뗬�s�̂������Ȃ�
�I�~�N�������Ƃ݂���V�^�R���i�E�C���X�����̔����I�g��Ƃ͗����ɁA�C���t���G���U�̊����Ґ��͍��V�[�Y�����ɂ߂ď��Ȃ��̂悤�ł��B�u��N�H�̒i�K�ł́A���V�[�Y���ɃC���t���G���U�����҂����Ȃ��������Ƃ���w�Љ�S�̂̏W�c�Ɖu���`������Ă��Ȃ��x(���{�����NJw��̌���)�Ƃ��āA���V�[�Y���͑嗬�s�ւ̊뜜������܂����B��N�A�����̃C���t���G���U�����Ґ��́A�����1000���l�Ƃ����Ă��܂��B�Ƃ��낪���V�[�Y���́A�����J���Ȃ̐��v�ɂ���Ë@�ւ̎�f�Ґ�����1��4000�l�ɂƂǂ܂�A���s�̒������n�܂���1999�N�ȗ����߂āw���s�Ȃ��x�Ƃ���܂����v(�g�c)
���V�[�Y���ɂ��Ă��A�����J���Ȃ�1��21���ɔ��\�����u�C���t���G���U��_��������v�ɂ��ƁA2022�N��2�T(1��10���`1��16��)�̃C���t���G���U�w���Ë@�ւ���̕��́u54�v�ł����B��1�T(1��3���`1��9��)�́u50�v�Ƃ��܂�ω��͂���܂���B���V�[�Y���������̑����u65�v�Ɠ������A���N�����́u90,811�v��2018/19�V�[�Y���́u190,527�v�ȂǂƔ�ׂċɒ[�ɏ��Ȃ������ɂ���܂��B�u�w�����̕����̂Ƃ���قƂ�ǂȂ��A�C���t���G���U�̗��s�́A�w���V�[�Y�����A���܂̂Ƃ��딭���̂������͌����Ȃ��x�Ƃ�����ł��v(�g�c)
�����V�[�Y���Ɠ������R���i�����Ǒ�̓O�ꂪ�t��
�C���t���G���U�̊����Ґ������V�[�Y�������Ȃ��w�i�ɂ́A�������������ǑO�ꂳ��Ă��邱�Ƃ�����悤�ł��B
�u�C���t���G���U�E�C���X���V�^�R���i�E�C���X�Ɠ��l�ɁA�����A������݂Ȃǂɂ���(�Ђ܂�)�����ōL����܂��B�R���i��Ōp������Ă����}�X�N�̒��p���A�O�o���l�Ȃǂ̓O���A�C�O����̓n�q�����������Ă��邱�Ƃ��傫�ȗv���Ƃ�����ł��傤�v(�g�c)
�Ƃ͂����A��N�C���t���G���U���s��3�����܂ő����܂��B
�u����܂œ��{�ł�1�����{����2����{�Ƀs�[�N���}����̂���ʓI�ł����B�ނ��낱�ꂩ�炪���S�ł��Ȃ��������ƍl���Ă��������B���������������̎����ɂ��ƁA���E�̃C���t���G���U���x���́A�S�̓I�ɂ͒ᒲ�ł�����̂́A���ɉ��g�n��ő������݂��A���ɂ���Ă̓p���f�~�b�N�O�̐����܂ő������Ă���悤�ł��B���{�ł��A���s�̂������������Ȃ�����Ƃ����āA��������s�̉\�����Ȃ��킯�ł͂���܂���B�G�ߊO��̗��s�����肦�܂����A�Љ�S�̂̏W�c�Ɖu���`�����ꂸ�A�Ɖu����̉����Ă��錜�O���������Đ@�����킯�ł͂���܂���B�܂��A���߂Ċ����������c�����d�lj����₷���Ƃ����X���������܂��B���s���Ă��Ȃ������ǂقǁA���߂̗\�h����ł��B����܂œ��l�Ɋ����ǖh�~��Ƃ��ă}�X�N�̒��p�Ǝ��s�A�l���݂�ɉ؊X�ւ̊O�o���T����A�K�x�̎��x�ێ�(50�`60��)�A�\���ȋx�{�ƃo�����X�̎�ꂽ�h�{�ێ�Ȃǂ̌p���͕K�{�ł��v(�g�c)
���V�[�Y�����C���t���G���U���s�̂������������Ȃ��Ƃ͂����A������������~�ꂪ�����ǂɂ�����₷�������ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B�V�^�R���i�E�C���X�E�I�~�N�������Ɋ������Ȃ����߂ɂ��A�����̗\�h��͂�����Ƒ����Ă����悤�S�����܂��傤�B
|
���I�~�N���� �����}�g�� �V���ɂ킩���Ă������Ɓ@1/27
�I�~�N�������̊����}�g�傪�Ƃ܂�܂���B�S����1���ɕ���銴���Ґ��́A�f���^���̂Ƃ��̃s�[�N�̂��悻3�{�ɂȂ��Ă��܂��B�d�lj����X�N�͒Ⴂ�Ƃ͂����A���@���Ґ����������A�a���̂Ђ������e�n�������Ă��܂��B���̒��ŁA�I�~�N�������ł��قȂ�n���̃E�C���X�uBA.2�v���C�O�̈ꕔ�Ŋg�債�Ă���Ƃ��������o�Ă��܂����B���܁A���̏Ŋ�����h�����߂ɂǂ�����悢�̂��B�������Ă������Ƃ��܂Ƃ߂܂����B
���o���Ȃ������g��̃y�[�X
�V�^�R���i�̑S���ł̊����m�F�̔��\��2022�N1��27����7��9000�l�߂��ƂȂ�A�f���^���̎��̃s�[�N�A2021�N8�����{�̂��悻2��6000�l�̂��悻3�{�ɂȂ��Ă��܂��B�S���e�n�ŋ}���Ȋg��ƂȂ��Ă��āA�܂h�~���d�_�[�u��1��27�������34�̓s���{���Ɋg�傳��܂����B�u�ψي�PCR�����v�̌��ʂ��猩��ƁA2022�N1��23���܂ł�1�T�Ԃ̎b��l�ŁA�I�~�N�������̋^��������E�C���X�͑S��97�����߂�Ɏ����Ă��܂��B
���I�~�N���������h���H BA.2�Ƃ�
����ɁA�I�~�N�������̌n����1�ŁuBA.2�v�ƌĂ��ψكE�C���X�����ڂ���n�߂Ă��܂��B���݁A���E���Ŋ������L�����Ă���I�~�N�������uBA.1�v�ł̓E�C���X�̕\�ʂɂ���ˋN�����u�X�p�C�N����ς����v�̈ꕔ�Ɍ����Ă��镔��������܂����A�uBA.2�v�ł́A���̌����Ă��镔�����Ȃ����Ƃ��������Ă��܂��B���[���b�p�ł́A���̕�����ڈ�ɂ��ăI�~�N�����������o���Ă���Ƃ������ƂŁA�������Ȃ����Ƃ�����Ǝw�E����Ă��܂��B(���{�ōs���Ă��錟���ł͌��o�ł���Ƃ���Ă��܂�)�@���{�����ł́A�C���h��t�B���s���ɓn�q��������l����A���̃E�C���X�����o����Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A1��26���̌����J���Ȃ̐��Ɖ�ł́A���̃E�C���X���L�����Ă���f���}�[�N�̃f�[�^�͂������ʂƂ��āA1�l�����l�Ɋ������L���邩�����������Đ��Y�����uBA.1�v�ɔ�ׂ�18���㏸���Ă���\��������ƕ���܂����B�f���}�[�N�̕ی����ǂ̂��Ƃɂ��錤�����ɂ��܂��ƁA�uBA.2�v��2021�N�̔N����1�T�Ԃł̓f���}�[�N�����Ō��o�����V�^�R���i�E�C���X��20���قǂ������̂��A2022�N1�����{��1�T�Ԃł�45���قǂɂȂ����Ƃ��Ă��܂��B�����A�f���}�[�N���{�̂��Ƃɂ��銴���ǂ̌������́A1��20���ɏo���������ŁA�uBA.1�v�ƁuBA.2�v�œ��@�Ɏ��郊�X�N�͍����Ȃ��A�������̍�����N�`���̌����ɈႢ�����邩�ǂ����͒��������Ƃ��Ă��܂��B�C�M���X�̕ی����ǂ�1��21���A�����O�ő������Ă��邱�Ƃ���A�u�������̕ψكE�C���X�v�Ɉʒu�Â������Ƃ����\���܂����B�C�M���X�ł͏]���̃I�~�N�������uBA.1�v���D���ŁA�uBA.2�v����߂銄���͏��Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B�����A�E�C���X�̈�`�q�̈Ⴂ�ɂǂ̂悤�ȈӖ������邩������Ȃ��Ƃ��������A����ɕ��͂𑱂���Ƃ��Ă��܂��B
���������ԒZ���A�����L����T�C�N�����Z��
�I�~�N�������́A�������Ă��甭�ǂ���܂ł̐������Ԃ��Z���̂������ł��B���������nj������̎b��ɂ��܂��ƁA�I�~�N�������Ɋ��������ǂ���113�l�ɂ��ĕ��͂������ʁA���ϓI�Ȑ������Ԃ�3���]��ł����B�E�C���X�ɂ��炳�ꂽ���ƁA3����܂łɔ��������ǁB6����܂łɂ͂��悻90�������ǂ��A9����܂ł���98������l�����ǂ��Ă��܂����B�����āA�u����l���������Ă���ق��̐l�Ɋ���������܂ł̊��ԁv���u���㎞�ԁv���Z���Ȃ��Ă��܂��B�����J���Ȃ̐��Ɖ�̎����ɂ��܂��ƁA���㎞�Ԃ̓f���^���ł͂��悻5���������̂ɑ��A�I�~�N�������ł͂��悻2�����ƍl�����Ă��܂��B�Z�����Ԃ̂����Ɏ��X�Ɗ��������邽�߁A�}���Ɋ������L�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B����ŁA�I�~�N����������Ɋg�債����A�t���J��C�M���X�ł́A�����Ґ����}���Ɍ������A�A�����J�ł��������n�߂܂����B���{�����ł͂܂��}���������Ă��܂����A�s�[�N���ł��邾���Ⴍ���āA�����ł��e�������炷���Ƃ��厖���Ɛ��Ƃ͎w�E���Ă��܂��B
�����H�ȂǂŊ��� �g�@�}�X�N�h������
�ł́A���܁A�ǂ��ł���������\��������ŁA�ǂ���悢�̂ł��傤���H�|�C���g�́A�I�~�N�������ł��A�����o�H�͂���܂ł̐V�^�R���i�E�C���X�ƕς��Ȃ��_�ł��B��܂�u�}�C�N����܂v�ƌĂ�閧���ꂽ������Y�������Ȕ�܂���ŁA�E�C���X��������ŕ@����Ȃǂ�G�邱�Ƃɂ��ڐG����������܂��B���������nj�������1��13���ɏo�����I�~�N�������Ɋ��������P�[�X�̉u�w�����̌��ʂł́A�I�~�N�������ł��A���H�X�ł̐E�ꓯ���Ƃ̖Y�N���A����ł̐e���Ƃ̉�H�ȂǁA���H��ʂ��������������Ă��āA��܂����������Ȃ��Ă��܂��B�E��ł̖��Ȋ��ł̍�Ƃ�ʂ��Ċ�������P�[�X������Ă��܂��B����܂ł������Ă����u�}�X�N�𒅗p����v�A�u���C���s���v�Ƃ��������O�ꂷ�邱�Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă��܂��B���{���ȉ�̔��g��́A1��25���A���ȉ�̂��ƕw�̎�ނɑ��u�}�X�N���O������A�g�@�}�X�N�h�Ȃǒ��p���s�\���ȏł̊������A�v���Ă������͂邩�ɑ������Ƃ��������Ă���B�O�ꂵ�Ă��炢�����̂̓}�X�N�̓K�Ȓ��p�ŁA�s�D�z�}�X�N�ŕ@�܂ł������蕢���Ăق����v�Əq�ׂ܂����B�}�X�N���Ƃ�����b����H�̏�ʂŊ������郊�X�N�������A�����J���Ȃ̐��Ɖ�́A���N�`���ڎ�҂��܂߁A�}�X�N�̐��������p�A��w�q���A���C�Ȃǂ̓O����p�����邱�Ƃ��K�v�ŁA�u1�̖��ł��ł��邾�������������悢�v�Ƃ��Ă��܂��B
�����N�`���lj��ڎ�œ��@���X�N�啝��
�I�~�N�������ł��A���N�`���̒lj��ڎ�Ō��ʂ�����ƍl�����Ă��܂����A1��21���ɂ́A�A�����J��CDC�����a��Z���^�[�����@��h�����ʂ̓I�~�N�������ɑ��Ă�90���ɏ㏸����Ƃ������͌��ʂ����\���܂����B�t�@�C�U�[��f���i�́umRNA���N�`���v��2��ڂ̐ڎ킩��6�����ȏソ�����ꍇ�A���@��h�����ʂ́A�f���^�����D��������������81������������A�I�~�N���������D���ɂȂ��������ɂ�57���ł����B�������A3��ڂ̐ڎ�̂��Ƃł̓f���^���̎�����94���A�I�~�N�������̎�����90���ɏ㏸�����Ƃ������Ƃł��B�܂��A���N�`���̒lj��ڎ�����l�Ɣ�ׁA�Ă��Ȃ��l�͓��@���銄�����啝�ɍ����Ȃ�A50����64��44�{�A65�Έȏ��49�{�ɂȂ�Ƃ������͂����킹�Č��\���܂����BCDC�́A�Ǐ�̈�����h�����߂ɂ�3��ڂ̐ڎ킪�d�v�ŁA���ڎ�҂͂ł��邾���������N�`����ڎ킷��K�v������Ƃ��Ă��܂��B
���d�lj����X�N���� �a���g�p������
�I�~�N�������́A�����͂͋�������ŁA���������Ƃ��ɏd�lj����銄���͒Ⴂ�Ƃ������������܂��Ă��܂��BWHO�����E�ی��@�ւ�1��25���̏T��ŁA�u�I�~�N�������͊e���Ŋ����Ґ����}�����Ă���ɂ�������炸�A�d�lj��⎀�S�̃��X�N�͒Ⴂ�悤���v�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�I�~�N�������ł́A�@��̂ǂƂ�������C���̉��ǂ������N�����₷�����̂́A�ق��̕ψكE�C���X�Ɣ�ׂĔx�܂ŒB���ďd�lj����郊�X�N�͒Ⴂ�Ƃ��Ă��܂��B�����A�����Ґ������ɑ������߁A�����̍��œ��@�Ґ��͋}�����Ă��āA��Ñ̐����Ђ������Ă���Ƃ��āA�x�����Ăт����Ă��܂��B�C�M���X�̕ی����ǂɂ��܂��ƁA�I�~�N�������Ɋ������ē��@�Ɏ��郊�X�N�́A�f���^���̏ꍇ�ɔ�ׂ�3����1�ɂȂ��Ă���Ƃ��Ă��܂��B�����A�C�M���X�ł�3��ڂ̒lj��ڎ�����l��2022�N1��25���̎��_��64.4���ɏ���Ă���(12�Έȏ�)�A1��27�����_�őS�l����2.5���ɂƂǂ܂��Ă�����{�Ƃ͏��قȂ邽�߁A���ӂ��K�v�ł��B�����ł��e�n����y�ǎ҂������Ƃ������������ł��܂����A�����ōł����������Ɋ������L���������ꌧ�ł͏d�lj����X�N�̂��鍂��҂Ɋ������L�����Ă��Ă��܂��B���ꌧ�Ŋ����҂ɐ�߂�60��ȏ�̊����́A1��23���܂ł�1�T�Ԃł��悻16���Ə��X�ɏ㏸���Ă��Ă��܂��B�a���̎g�p���͓��ɓ��ɏオ���Ă��Ă��āA1��26�����_�ʼn��ꌧ�ł�63.8���A���{�ł�53.9���A�����s�ł�42.8���ȂǂƂȂ��Ă��܂��B�����ł͎��Ґ������Ȃ���Ԃ������Ă��܂����A�C�O�ł͊����Ґ��������Ă����Ґ������������Ƃ��낪����܂��B�C�M���X�ł́A1��18���܂ł�1�T�Ԃł̐V�K�����Ґ��͂��悻67��4000�l�ƁA�O��1�T�ԂƔ�ׂĂ��悻40�������������ƁA�قډ����ƂȂ��Ă��܂��B���Ґ��́A�����Ґ����s�[�N�A�E�g�����Ƃ݂�ꂽ1��18���܂ł�1�T�Ԃ�1900�l�]��Ƃ��悻15�������A���̌��1�T�Ԃł�1800�l�]��Ƒ�����Ԃ������Ă��܂��B���{�ł��A�������L���葱����ƁA�d�NJ��҂�S���Ȃ�l�̐��������邨���ꂪ����܂��B
���q�ǂ��̊����g�� �e���Ō��O
�I�~�N�������ł́A����܂ł͏��Ȃ������q�ǂ��ł̊����g��������Ă��܂��B�����J���Ȃ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��܂��ƁA10�Ζ����̐V�K�����Ґ��́A2021�N12��28���܂ł�1�T�Ԃł�149�l�ł������A2022�N1��4���܂łł�353�l�A1��11���܂łł�2238�l�A1��18���܂łł�1��2947�l�Ƌ}�����Ă��܂��B�A�����J�ł́A1��20���܂ł�1�T�ԂŁA�q�ǂ��̐V�K�����Ґ���115��1000�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����X�V�������Ă��܂��B�A�����J�����Ȋw��́A�q�ǂ��ŏǏd���Ȃ���@�Ɏ��闦��0.1����1.5���A���S����0����0.02���ƕ��Ă��܂��B���{�����ł́A���N�`���̐ڎ�Ώ۔N�5�܂łɈ����������܂����B�t�@�C�U�[�̗Տ������ł́A5����11�ł̔��ǂ�h�����ʂ�90.7���ŁA�ڎ��ɏo���Ǐ�������ނˌy�x���璆���x�������Ƃ��Ă��܂��B�����Ȉ�Ń��N�`���ɏڂ����k����w�̒��R�N�v���C�����́A�u�ǂ̎q���d�lj����邩���O�ɓ���ł����A���N�`���ڎ�Ŕ�����̂͑�Ȃ��Ƃ��B�I�~�N�������́A��C���A�@��̂ǂő�����ƌ����Ă��āA�q�ǂ��͂�����o���ɂ���������A�C���������������肵�āA��������������ċz����ɂȂ����肷�邱�Ƃ��l������B�q�ǂ��ɂƂ��Ă̏�C���̊����ǂ͕����Ă͂����Ȃ��B���炩���ߐe�q�Ń��N�`���ɂ��ė������āA�����b�g�ƃf�����b�g�A���������悭�l���āA�q�ǂ����e�q���[�����Đi�߂Ȃ�������Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B
������܂ł̕ψكE�C���X�Ƃ̔�r
�����͂�a�����ȂǁA���ܕ������Ă��邱�Ƃ�WHO�⍑�������nj������A�e���̌��I�@�ւȂǂ̏������ƂɁA�ق��́u���O�����ψي���VOC�v�Ɣ�r����`�ł܂Ƃ߂܂����B
�w�A���t�@���x(2020�N12���@�C�M���X�ōŏ��ɕ�)
�w�x�[�^���x(2020�N12���@��A�t���J�ōŏ��ɕ�)
�w�K���}���x(2021�N1���@�u���W���Ŋg��)
�w�f���^���x(2020�N10���@�C���h�œ����n�����ŏ��ɕ�)
�w�I�~�N�������x(2021�N11���@��A�t���J���ŏ��ɕ�)
�@�@�@��������
�w�A���t�@���x��
�w�x�[�^���x��
�w�K���}���x��
�w�f���^���x����
�w�I�~�N�������x������
�I�~�N�������̊����X�s�[�h�̑����������f�[�^���A�e���������Ă��܂��BWHO�̏T��ł́A�ƒ���ł́u2���������v�̓f���^����21���ɑ��A�I�~�N��������31���������Ƃ���A2021�N12���̃f���}�[�N�ł̕��͌��ʂ��Љ�Ă��܂��B�A�����J��CDC�����a��Z���^�[�́A�I�~�N�������̊����͍͂ő�Ńf���^����3�{�Ƃ���f�[�^������Ƃ��Ă��܂��B
�@�@�@���a����
�w�A���t�@���x�@���@�E�d�lj��E���S�̃��X�N�����\��
�w�x�[�^���x�@���@�̃��X�N�E���@���̎��S�������\��
�w�K���}���x�@���@�E�d�lj��̃��X�N�����\��
�w�f���^���x�@���@�̃��X�N�����\��
�w�I�~�N�������x�@���@�E�d�lj����X�N�Ⴂ
�I�~�N�������ł́A���@�Ɏ��郊�X�N��d�lj����X�N���f���^���ɔ�ׂĒႢ�Ƃ���Ă��܂��B����A�C�M���X�̕ی����ǂ́A�I�~�N�������͏d�lj����X�N���Ⴂ�Ƃ����Ă��A�����g��̃X�s�[�h�̑�����Ɖu���瓦��鐫��������A�K��������Ë@�ււ̕��ׂ����邱�Ƃ��Ӗ����Ȃ��A�Ƌ������Ă��܂��B
�@�@�@���Ċ����̃��X�N
�w�A���t�@���x�@�E�C���X��}����R�̂̓����͈ێ��A�Ċ����̃��X�N�͏]�����Ɠ�����
�w�x�[�^���x�@�E�C���X��}����R�̂̓����͌���A�E�C���X���U������זE�̓����͈ێ�
�w�K���}���x�@�E�C���X��}����R�̂̓����͂�⌸��
�w�f���^���x�@�E�C���X��}����R�̂̓����͌���
�w�I�~�N�������x�@�Ċ����̃��X�N�オ��
WHO�ł́A���N�`����ߋ��̊����ɂ���ĖƉu�����l�ł��Ċ������₷���Ȃ�ψق�����Ƃ��Ă��܂��B�C�M���X�̃C���y���A���E�J���b�W�E�����h���́A�I�~�N�������̍Ċ����̃��X�N�́A�f���^���ɔ�ׂ�5.41�{�ƍ����Ȃ��Ă���Ƃ�����o���Ă��܂��B
�@�@�@�����N�`���̌���(�t�@�C�U�[�E���f���i��mRNA���N�`��)
�w�A���t�@���x�@�����\�h�E���Ǘ\�h�E�d�lj��\�h�Ƃ��ɕς�炸
�w�x�[�^���x�@���Ǘ\�h�E�d�lj��\�h�Ƃ��ɕς�炸
�w�K���}���x�@�����\�h�E���Ǘ\�h�E�d�lj��\�h�Ƃ��ɕς�炸
�w�f���^���x�@�����\�h�E���Ǘ\�h�E�d�lj��\�h�Ƃ��ɕς�炸(�����\�h�E���Ǘ\�h�͉�����Ƃ�����)
�w�I�~�N�������x�@���Ǘ\�h���ʒቺ�E�d�lj��\�h���ʂ͂���Ƃ����� 3��ڐڎ�Ŕ��Ǘ\�h���ʁE�d�lj��\�h���ʂ��オ���
�I�~�N�������́A2��̃��N�`���ڎ�����������l�ł���������P�[�X������Ă��܂��B���Ǘ\�h���ʂ͐ڎ킩�玞�Ԃ��o�邲�Ƃɉ�������̂́A�d�lj���\�h������ʂ͈����x�ۂ����Ƃ����f�[�^���o�Ă��Ă��܂��B�܂��A3��ڂ̒lj��ڎ�Ŕ��Ǘ\�h���ʁA�d�lj��\�h���ʂ��オ��Ƃ������o�Ă��Ă��܂��B�C�M���X�̕ی����ǂ̃f�[�^�ł́A�I�~�N�������ɑ��ẮA�t�@�C�U�[��f���i��mRNA���N�`���ŁA2��̐ڎ킩��2�T�Ԃ���4�T�Ԍ�ɂ͔��ǂ�h�����ʂ�65�`70���ł������A20�T�����10�����x�ɉ������Ă��܂����B�t�@�C�U�[�̃��N�`����2��ڎ킵���l��3��ڂɃt�@�C�U�[�����f���i�̒lj��ڎ������ƁA2�T�Ԃ���4�T�Ԍ�ɂ͔��ǂ�h�����ʂ�65���`75���ɏオ��܂����B�����A5�T�Ԃ���9�T�Ԍ�ł�55�`70���ɁA10�T�����40�`50���ɉ�����܂����B�d�lj����ē��@���郊�X�N����������ʂ́A���ǂ�h�����ʂ�荂���Ȃ��Ă��܂��B�t�@�C�U�[��f���i�A����ɃA�X�g���[�l�J�̃��N�`����ڎ킵���l�ŕ��͂���ƁA���@�Ɏ���̂�h�����ʂ́A2��̐ڎ��2�T�Ԃ���24�T�Ԃł�72���A25�T���Ă�52���A3��ڂ̒lj��ڎ���������ƁA2�T�ȍ~����88���ƂȂ��Ă��܂����B
�@�@�@�����Ö�̌���
�d�lj���h�����߂Ɋ������������ɓ��^�����u�R�̃J�N�e���Ö@�v�́A���ʂ��ቺ����Ƃ���Ă��܂��B�����J���Ȃ̓I�~�N�������Ɋ����������҂ɂ́A���^�𐄏����Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B����ŁA�E�C���X�̑��B��h���d�g�݂̈��ݖ�ɂ͉e�����o�Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B������w�Ȃǂ̌����O���[�v�́A�y�NJ��җp�̈��ݖ�u���Q�u���I(��ʖ������k�s���r��)�v�𓊗^�������ɑ̓��ɏo�镨����A�����Ljȏ�̊��҂ɓ��^�����u�����f�V�r���v�̍�p�ׂ��Ƃ���A�I�~�N�������ɑ��āA�f���^���Ɠ������x�̌��ʂ�����ꂽ�Ƃ���������ʂ��Љ�Ă��܂��B�܂��AWHO�́A�d�NJ��҂Ɏg����Ɖu�̉ߏ蔽����h�����X�e���C�h�܂́A�����������ʂ����҂����Ƃ��Ă��܂��B
�����Ƃ�
�C�O�̊����ɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́A����ŋ��߂����ɂ��āA�u�I�~�N�������́wBA.1�x�ł����Ă��wBA.2�x�ł����Ă������͂��������Ƃ͕ς�炸�A��ʂ̍����ɂƂ��ĂƂ�ׂ���͕ς��Ȃ��B�I�~�N���������}���Ɋg�傷�錻��łƂ��Ă�����O�ꂵ�����邱�Ƃ������d�v���B����ŁA�����̂�������A�Ǐ�ɕω����������Ȃǂ��Ď����邱�Ƃ͍œK�ȑ���Ƃ��Ă�����ő�Ȃ��ƂȂ̂ŁA���������������Ă����K�v������v�Ƙb���Ă��܂��B
����͕ς��Ȃ�
���������ł����͂���܂łƕς��܂��A���Ƃ͍��̊����}�g��̏̒��ŁA������O�ꂷ��悤�Ăт����Ă��܂��B�s�D�z�}�X�N�ŕ@�܂ŕ����A�g�@�}�X�N�h������邱�ƁA���ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��āA�}�X�N���O���Ƃ��ɂ͂�蒍�ӂ��邱�ƁB�Ƃ��Ɉ��H�̏�ʂł̑d�v�ł��B�����J���Ȃ̐��Ɖ���A���N�`���ڎ�ɉ����āA���ɉ�b���Ȃǂł̃}�X�N�̒��p�A���ł��A���C�▧�������Ƃ�������{�I�ȑ�𑱂���悤�Ăт����Ă��܂��B
|
���R���i�R�E�C���X�� �I�~�N�������ւ̌��ʂ͑f���^���Ɠ��� �@1/27
�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������ɑ��鎡�Ö�̌��ʂɂ��ē�����w�Ȃǂ̃O���[�v���|�{�זE���g���Ď��������Ƃ���A���A�g���Ă���R�E�C���X��̓f���^���ɑ���̂Ɠ����̌��ʂ��݂�ꂽ�Ƃ��錤�����ʂ\���܂����B
���̌����͓�����w��Ȋw�������͉̉��`�T���C������̃O���[�v���A�A�����J�̈�w�G���u�j���[�E�C���O�����h�E�W���[�i���E�I�u�E���f�B�V���v�ɔ��\���܂����B
�O���[�v�̓I�~�N�������̃E�C���X��|�{�����זE�Ɋ��������A�����ɂ��܂��܂Ȏ��Ö�𓊗^���Ĕ����ׂ܂����B
���̌��ʁA�V�^�R���i�̍R�E�C���X��Ƃ��č����ł����F����Ă���u�����f�V�r���v�Ɓu���Q�u���I�v����ʖ��u�����k�s���r���v��2��ނ̖�́A�E�C���X�̑��B��}������ʂ���������f���^���ɑ��ĂƓ������x���������Ƃ������Ƃł��B
�܂��R�̂��g�������Ö�ɂ��āu�\�g���r�}�u�v�͏]���̃E�C���X�ɑ���̂Ɣ�ה�����14����1�ɒቺ�������̂̕K�v�Ȍ��ʂ͕ۂ���Ă��܂������A�����J���Ȃ��I�~�N�������ւ̎g�p�𐄏����Ȃ��Ƃ��Ă���R�̃J�N�e���Ö@�́u���i�v���[�u�v�͌��ʂ��قƂ�NJm�F�ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�͉����C�����́u�I�~�N�������͑����̕ψق��N�����Ă���̂ŗՏ�����Ŏg���Ă����̗L�����ׂ錤���͏d�v���B�Տ�����ł̎��Â̎Q�l�ɂ��Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B
|
���I�~�N���� �Z���ڐG�҂ɂȂ����� �m���Ă����������Ɓ@1/27
�������}�g�債�Ă���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������B����܂łɂȂ��K�͂̊����Ґ��ƂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ͓��R�A�����҂ɐڐG�����Z���ڐG�҂̐�������܂łɂȂ��K�͂ɂȂ�Ƃ݂��܂��B�������Z���ڐG�҂ɂȂ����A�܂��͋߂��ɂ���l���Z���ڐG�҂ɂȂ����Ƃ����l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Z���ڐG�҂ɂȂ�ƈ��̊��ԁA����ł̑ҋ@���K�v�Ƃ���Ă��܂����A�ǂ��܂ł��Z���ڐG�Ȃ̂��H���܂Ŏ���ҋ@���K�v�Ȃ̂��H���܂��܂ȋ^��ɂ��Ď�ނ��܂����B
�����������Z���ڐG�҂̒�`�́H�ǂ��܂ł��Z���ڐG�Ȃ́H
�Z���ڐG�҂́A���������l�Ƌߋ����ŐڐG������A�����ԐڐG�����肵�āA�������Ă���\��������l�ł��B�����J���ȂȂǂɂ��܂��ƁA�Z���ڐG�҂��ǂ����f����ۂ̏d�v�ȃ|�C���g�͎��̒ʂ�ł��B�ڐG�̊��Ԃ͊����҂��E�C���X��r�o���Ȃ��Ȃ锭�nj�10�����܂ł̊�(�����҂����Ǐ�̏ꍇ�͌����̂��߂̌��̂��̎悵�Ă���10��)�B�ڐG�̖ڈ��́A�}�X�N�Ȃǂ������Ɋ����҂Ɏ�ŐG�ꂽ��A���݂��Ɏ��L������͂�������15���ȏ�ڐG�����肵���ꍇ�B�����҂̑̉t�Ȃǂ��������̂ɒ��ڐG�ꂽ�\���̂���ꍇ�Ȃǂł��B�Ƒ��Ɋ����҂�����ꍇ�⊴���҂̉������Ă���ꍇ�Ȃǂ͂��̖ڈ��ɓ��Ă͂܂邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂����A��Ë@�ւ���{�݂ōs���Ă���悤�ɁA��������Ƃ��������\�h�Ƃ��Ă����ꍇ�͔Z���ڐG�҂Ƃ݂͂Ȃ���܂���B�܂��A15���ȏ�̐ڐG�Ƃ����Ă��A��b�����Ă������A�̂��̂�����吺���o�����肷�邤�悤�Ȋ����������A���C���\���ɂł��Ă������A�ȂǁA���̏�̋�̓I�ȏɂ���āA�Z���ڐG�҂Ɣ��f����邩�ǂ����͕ς���Ă��܂��B
���Z���ڐG�҂͂��܂Ŏ���ҋ@������K�v������H
�����J���Ȃł́A�I�~�N�������̐������ԂȂǂ̍ŐV�̉Ȋw�I�Ȓm���܂��A����14���t���ŔZ���ڐG�҂̎���Ȃǂł̑ҋ@���Ԃ�����܂ł�14������10���ԂɒZ�k���܂����B(1��27�����_)���̂��߁A�����҂ƍŌ�ɐڐG��������0���Ƃ��āA10���Ԃ͎���Ȃǂł̑ҋ@�����߂��邱�ƂɂȂ�܂��B�����s�ɂ��܂��ƁA�������Ă���Ƒ������������ꍇ�́A�����҂����@������A���Ɋu�����ꂽ��ԂɂȂ��������u�Ō�ɐڐG�������v�Ƃ���Ƃ��Ă��܂��B�����A���������̂��c���q�ǂ��Ȃǂŕʎ��Ɋu���ł��Ȃ��ꍇ�́A�����Ҏ��g�̗×{���I�������u�Ō�ɐڐG�������v�ƂȂ�Ƃ������ƂŁA��������10���ԁA�܂�ő��20���ԂƂȂ�܂��B�����A��Ï]���҂Ȃǂ̂�����u�G�b�Z���V�������[�J�[�v�ɂ��ẮA6���ڂ�PCR�������R����ʌ����ʼnA���ƂȂ邩�A6���ڂ�7���ڂɁA�����ŏ��F����Ă���R���萫�����L�b�g��2��A�A�����ĉA���Ɗm�F�����Αҋ@�������ł���Ƃ��Ă��܂��B
������ҋ@���Ă���Ԃ͂ǂ�������������H
����ҋ@�̍ۂɂ́A�s�v�s�}�̊O�o�͂ł������T���A��ނ��O�o����ꍇ�ɂ́A�}�X�N�̒��p���Ȃǂ̊�������s���āA�l�Ƃ̐ڐG������邱�ƂƂ���Ă��܂��B�ʋ�ʊw���T����K�v������Ƃ������Ƃł��B�I�~�N�������̗��s���嗬�ƂȂ��Ċ��Ԃ͒Z�k����܂������A�I�~�N�������ł����Ă��������N����d�g�݂��ʎ��͕̂ς��Ȃ��Ƃ���Ă��邽�߁A����ҋ@���̑�̓��e����{�I�ɂ͕ς��܂���B
�����s�̐V�^�R���i���S�����铌���s�̊����Ǒ����ł͎��̂悤�ɂ��Ă��܂��B
�E�@10���Ԃ͕s�v�s�}�̊O�o�͍T���A�E���w�Z�ɂ͍s�����Ɏ���őҋ@�B
�E�@�ҋ@���́A�����A���Ɨ[����2��A�̉��𑪂��đ̒��Ɉُ킪�Ȃ����m�F�B
�E�@���M�₹���Ȃǂ̏Ǐo���炩������ォ�A�V�^�R���i�̌�����f�Â��\�Ȉ�Ë@�ւ���f�B
�E�@�Ȃ�ׂ�������ʋ@�ւ̗��p�������B
�����A�����J���Ȃł́A������ꍇ�́A�K�C�h���C���Ɋ�Â��ĕK�v�ȑƂ�ꂽ���ȂǂŁA�������邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă��āA���̏ꍇ�͊O�o���F�߂���Ƃ������Ƃł��B�Z���ڐG�҂ɂȂ����ꍇ�́A���߂�ꂽ���Ԃ��߂���܂ł́u�����������犴�����Ă��邩���v�ƍl���čs�����邱�Ƃ��d�v�ł��B
���Ƒ��ɔZ���ڐG�҂��o���ꍇ�͂ǂ���������H
�Ƒ��ɔZ���ڐG�҂��o���ꍇ�ɂ��āA�����s�̊����Ǒ����ɂ��܂��Ɓu�w�Z���ڐG�҂̔Z���ڐG�ҁx�Ƃ����T�O�͂Ȃ����߁A�Z���ڐG�ƂȂ����l�������ĉƑ��S�����s���𐧌�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�s���Ƃ��Ă��s���͐������Ă��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�����A�Ζ����ʊw��ȂǂŌʂɃ��[�����߂Ă���ꍇ�����邽�߁A��Ђ�w�Z�Ƙb�������āA���ꂼ��̃��[���ɏ]���Ăق����Ƃ������Ƃł��B�������A�Z���ڐG�҂��ҋ@���ɔ��ǂ���Ȃǂ��āA���͊������Ă������Ƃ�������\��������܂��B�����ꊴ�����Ă����ꍇ�ɔ����āA�Z���ڐG�҂ƂȂ����Ƒ��̑ҋ@���Ԓ��́A�ƒ���ł̃^�I���̋��p���������A�H���̎��Ԃ����炵���肷��ȂǁA�ł�������Ԃ��Đ�������B�}�X�N���p�Ȃǂł����G�`�P�b�g�����A���A���R�[�����łȂǂ�S������B�h�A�m�u��e���r�̃����R���ȂǕp�ɂɐG�����̂̏��ŁA����I�Ɋ��C������Ȃǂ̒��ӂ����Ăق����Ƃ������Ƃł��B�I�~�N�������͏d�lj����銄�����Ⴍ�Ȃ����ƌ����Ă��邱�Ƃ���A��������܂ł����y���l���Ă��܂����Ƃ����邩������܂��A����ł�����҂��b����������l�Ȃǂ𒆐S�ɁA�d�lj�����l�����E���ŕ���Ă��܂��B���f�����ɁA���Ɋ�b��������������A��������肵�āA�d�lj��̃��X�N�������Ƒ�������ꍇ�͒��ӂ��K�v�ł��B
���c���q�ǂ����삪�K�v�Ȑl�����������ꍇ�A�Ƒ��͂ǂ�����H
�����҂��ЂƂ�Ő����ł���N��ł���A�ƒ���Ő����̋�Ԃ�����A�����������Ƃ����肷�邱�ƂŁA�Z���ڐG������邱�Ƃ��ł��܂����A�c���q�ǂ����삪�K�v�Ȑl�����������ꍇ�Ȃǂł́A���b������l���Z���ڐG�҂ɂȂ�̂������͓̂���Ȃ�܂��B1��27�����݁A���������ꍇ�A���������l��10���Ԃ̗×{���Ԃ��I�������u�Ō�ɐڐG�������v�ł��B���̂��߁A�Z���ڐG�҂ƂȂ����Ƒ��́A�������炳���10���Ԃ̎���Ȃǂł̑ҋ@���K�v�ƂȂ�܂��B�����Ҏ��g��10���Ԃ̗×{���Ԃ��I����Ă��܂�����O�o�Ȃǂ̐����͂���܂���B�����Ҏ��g�����Z���ڐG�҂̕��������ҋ@���ԂƂȂ邽�߁A�s�v�c�ȋC�����܂����A�E�C���X���L����̂�h�����߂ɕK�v�Ƃ���Ă��܂��B�����s�ɂ��܂��ƁA���ۂɂ�����������͑������ł��āA�ǂ��ɂ����đҋ@���Ԃ�Z���ł��Ȃ����Ƃ����₢���킹������Ƃ������Ƃł����A�����A20���Ԃ��K�v���Ɠ`���Ă���Ƃ������Ƃł��B
���Ƒ��̊������m�F �ق��̉Ƒ��͂ǂ���������́H
���������nj������Ȃǂ̒����ɂ��܂��ƁA�����̕��͌��ʂŁA�I�~�N�������̉ƒ���ł̊������́A30���`40�����x�ƂȂ��Ă��āA�f���^�����������\��������Ƃ������Ƃł��B�����A���̒����ł́A�I�~�N�������ł��A�����o�H�́A����܂ł̐V�^�R���i�E�C���X�ƕς�炸�A��܂�����A���C�̈����ꏊ�ł̂�����u�}�C�N����܂v(�G�A���]��)�ɂ�銴�������S�������Ƃ������ƂŁA�]������̊������O�ꂷ�邱�ƂŖh�����Ƃ��ł���ƍl�����Ă��܂��B�����J���Ȃ��쐬���Ă��钍�ӂ̌Ăт����C���X�g�ł́A�Ƒ��Ɋ����҂��o���ꍇ�Ɏ��̒��ӓ_�������Ă��܂��B
���Z���ڐG�҂̎���ҋ@���Ԃ̓I�~�N�������ŕύX ������ς��H
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́A����A�I�~�N�������̓����ɍ��킹�đ��ύX���Ă������Ƃ����蓾��Ƃ��Ă��܂��B�ړc�����́A�I�~�N��������50�Ζ����Ŋ�b������얞���Ȃ��l�ł͌y�ǂŎ��邱�Ƃ������Ƃ�����ŁA���̂悤�ɘb���Ă��܂����B�u�[�����X�N�����߂čs���������}�����Ă��܂��ƁA�����͌������邩������Ȃ����A�t�ɎЉ�@�\�̕�����Ⴢ��j�]���������Ă��܂������ꂪ����B������x�̃��X�N������Ȃ���A�Љ�@�\���ێ����Ă����悤�ȁA�o�����X�̎�ꂽ�Ή������߂��Ă���v�@����ɁA�I�~�N�������̊����҂������A�Z���ڐG�҂�����܂łɂȂ��y�[�X�ŋ}�����Ă��錻��ɂ��Ắ|�B�u�����A�S���Ŋ����Ґ��̍ő����X�V���Ă���悤�ȏ̒��A1���������Z���ڐG�҂ɑ���K�ł����ʓI�ȑΉ����l���Ă����Ȃ�������Ȃ��B�Ⴆ�Ηc���q�ǂ����������ė×{���I���10���ڂɁA�ʂ̉Ƒ����������Ă��܂����X�N�̓[���ł͂Ȃ��B�������A�\���Ɋ���������Ă���Ȃ�A�Z���ڐG�҂ƂȂ����Ƒ��ɂ��Ă��A�ǏȂ��A�����ʼnA�����m�F�ł���ꍇ�Ȃǂł́A�q�ǂ��̗×{�����Ɠ����^�C�~���O�Ŏ���ҋ@����������Ƃ����悤�Ȍ������K�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v
|
���I�~�N�������������͂ȕψي�������ė����c�g�X�e���X�ψفh���@1/27
�V�^�R���i�̃I�~�N�����ψي��̉��ʕώ�ł���uBA.2�v�̊������Ⴊ���{�ł��m�F���ꂽ�B�uBA.2�v�͈�`�q����(PCR)�����ő��̕ψي��Ƌ�ʂ��邱�Ƃ�����A�`���͂͏]���̃I�~�N�����ψي��́uBA.1�v��苭�����Ƃ�������A������g�X�e���X�h�ψقƌĂ�Ă���B
27��(���傤)�̓��{�o�ϐV���ɂ��ƁA���������nj�������26���ɊJ���ꂽ�����J���Ȃ̐V�^�R���i���Ǝ����c�ŁA���{�����ŏ��Ȃ��Ƃ�27���́uBA.2�v�������Ⴊ�m�F���ꂽ�ƕ����B
���J�����Ȃ̏W�v�ɂ��ƁA���{�����҂̒��ł�19���܂ł�198���́uBA.2�v�������m�F���ꂽ�B
�uBA.2�v�́uBA.1�v�ƂƂ��ɍ�N11�����犴�����s���Ă���A�p����f���}�[�N�ȂǁA40�J���ȏ�Ŕ�������Ă���Ɠ����͕t���������B
�؍������ł��C�O������������V�^�R���i�����҂̂����A4.5%���uBA.2�v�ψي��̊����҂ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�؍��E���a�Ǘ����̃`�����E�E���M����������27���̃u���[�t�B���O�Łu(�؍�)�����̊�������ł͂��̃^�C�v�̃I�~�N�����ψي��͊m�F����Ă��Ȃ��v�Ƃ��A�u���݂̐f�f����A�ψٕ���PCR����ł��̃X�e���X�ψق����ׂĊm�F���\�v�Ɛ��������B
�p���E�ی����S���͍���21���A�������̗D����́uBA.1�v�����A�����O�ŁuBA.2�v�ւ̊����������Ă���Ƃ������R�Œ����ψقɎw�肵���B���E�ی��@��(WHO)���uBA.2�v�ψقɊ������Ă��邩�ǂ�����D�悵�Ē�������悤�������Ă���B
�������͂ł͊����͂������\������N����Ă���B���s��w�̐��Y�������́A�f���}�[�N�ŕ���Ă���Q�m�����Ȃǂ͂������ʁA�uBA.2�v�̊����͂��uBA.1�v�ɔ�ׂ�18%�����Ƃ����������������B
�������A�uBA.2�v�̕a�����Ȃǂ��͂��߂Ƃ���ڂ��������͂܂��s���m�ł���A���@���ɂ��傫�ȈႢ�����邩�ɂ��Ă͊m�F����Ă��Ȃ��ł���B
�uBA.1�v�ƁuBA.2�v�̊Ԃɂ�20�ȏ�̈قȂ镔�������݂��Ă���A�����2020�N�����痬�s�����A���t�@�ψي��̉��ʕώ�Ԃ̈Ⴂ���������Ɠ��{�o�ϐV���͕����B
������`�w�������̍��쌰�����́u�f���^���ɂ��Ă��V�����ψق��������Ă���A����A�I�~�N�����ψي��̗��s�����É�����Ƃ��Ă��A�f���^�����܂����s����\��������v�ƌ��O���������B
|
���I�~�N�������u���ǂ́H�Ċ����̃��X�N�́H�v���Ƃɕ��� �@1/27
�X�^�W�I�ɁA�E�C���X�w�����̍L����w��w�@������������ɂ��z�������Ă��܂��B��������ɕ����������Ƃ��W�����Ƃ���A��������̎���������������܂����B
���u�I�~�N�������͏d�lj����X�N�͏������ƌ����Ă��܂����A���ǂ̃��X�N�ɂ��Ă͂ǂ��ł��傤���H�v
������� �u���ǂň�ԐS�z����Ă���̂����o��Q�A�k�o��Q�B���̃I�~�N�������͂��Ƃ��Ƃ���������Q�����Ȃ��B�Ȃ̂ŁA���ǂł��ꂪ�o��\���͒Ⴂ�Ǝv���v
���u�I�~�N�������̍Ċ����͂��蓾��̂ł��傤���H�v
������� �u��x������ƁA�����ɂ��̂��Ƃɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B�������ɖƉu�����B�������A�R���i�E�C���X�͖Ɖu�����܂蒷�������Ȃ��Ƃ������Ƃ��m���Ă���̂ŁA���N�A1�N�o�ƍĊ������Ă��܂���������Ȃ��v
�p�}�X�N�͓����A�������͂������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��H
������� �u���炭�����Ȃ��Ƃ����Ȃ���������Ȃ��v
�p���̌��ʂ��́H
������� �u���N�`����ł�����A��������Ƃ���d�lj����ɂ����Ȃ��Ă��邵�A����E�C���X�Ƌ����ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA������͊F�A�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�Ƃ������A���ʂ̕��ׂ̂悤�ȏ�ԂɂȂ�Ǝv���v
���u����͐V�K�����҂������Ă��܂������A�L���͖���������C�z�������܂���B����ƍL���̈Ⴂ�͎�̗L�������ł����c�v
����ɂ��ĕ⑫����������Ɓc�B���H�X�̎��̒Ɋւ��āA����ł͉\�����A�L���ł͌��ݒ�~����Ă�B�����n���̌��ł����f��������Ă���B�L���ł͔F�̗L���ɂ�����炸�A�܂h�~�̊��Ԃ͎��͈̒�ؕs�B���R�A�����A�����ė�������͎R������������u�����F�ؓX�ł͎��̒��\�Ƃ��A�����̓s���{���ł����l�̑Ή��ƂȂ��Ă���B
�p�u���̒̐����v�̌��ʂ͂ǂ����H
������� �u�܂��A���ꂪ�����čL���������Ă��Ȃ��Ƃ����̂́A�P���Ɏ����̖�肾�Ǝv���B����̕����������s���n�܂����̂ŁA���̕����������Ă���̂��Ǝv���B�����Ɋւ��ẮA�m���ɓ�����ŁA�������֎~���邱�Ƃ��͂�����ǂ��Ƃ����؋����A���͂͂����肵�����̂͂Ȃ��B����ǐ����ς���Ĕ����Ƃ����C���[�W���ƂĂ������Ƃ������Ƃ�����̂ŁA�֎~����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���v
|
���S���̐V�^�R���i�V�K������ 3���A���ߋ��ő� 8���l�ɔ���@1/27
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ���27���A�S����7��8920�l�̊��������\����A3���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�����s��27���A�V���ɔ��\���������҂�1��6538�l�ł����B��T�ؗj�̂��悻2�{�ŁA3���A���A�ߋ��ő����X�V���Ă��܂��B�a���g�p����44�D4���ŁA���@���҂�����389�l������ƁA�a���g�p����50�����A�s�Ƃ��āu�ً}���Ԑ錾�v�����ɗv�����錟�����n�߂��ɒB���܂��B
�s���{���ʂł́A�����s��k�C���̂ق��A25�̌��ʼnߋ��ő����X�V�B�S���ł�26���ɏ��߂�7���l���܂������A27����7��8920�l�ƁA3���A���ʼnߋ��ő����X�V���Ă��܂��B
�S���œ��@���Ă��銴���҂̂����A�d�ǎ҂��O�����67�l�����A���悻3�������Ԃ��500�l���܂����B�V���Ȏ��҂ɂ��Ă�47�l���\����Ă��܂��B
|
�������R���i2800�l���@�ő��X�V�@�D�y1590�l��ɋ}���@1/27
���Ȃǂ�27���ߌ�ɔ��\����V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂͑S����2800�l������A�ߋ��ő�������ɍX�V���錩�ʂ��ƂȂ����B���̂����D�y�s����1590�l��ɏ��A���߂Đ�l����B���َs�����ő����X�V����\��������A�I�~�N�������ɂ�銴����6�g�̋}�g�傪�S���I�ɑ����Ă���B
27���͑S���e�n�Ő[���Ȋ������������ʂ��ŁA26����143�l�Ɠ��ʂ̊����Ґ������߂�100�l�������َs������ɑ�����\��������B����s�⏬�M�s�ł������̊����҂��m�F����Ă���Ƃ݂���B
�S���̐V�K�����Ґ���19���ɏ��߂Đ�l��˔j���A26���ɂ�2��l��ƂȂ�ȂNj}���������B���͊��Ɋ�����̂قƂ�ǂ��I�~�N�������ɒu��������Ă���Ƃ݂Ă���B
�D�y�s���ł�4���ɃI�~�N�����������m�F�B�����̐V�K�����Ґ���9�l���������A13����100�l���A���̌�2�T�Ԃ�1500�l�ɒB���錩���݂ƂȂ����B����܂ł̍ő���26����953�l�ŁA1�E5�{�ȏ�ɖc��ނ��ƂɂȂ�B
�s���̕a���g�p����26�����݁A22�E5���B�d�Ǖa���g�p���̓[�����������̂́A�����{�݂�a�@�ł̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă���B�w�Z�̋��E����q�ǂ��̊������L�����Ă���A�s���̏����w�Z�A���Z�Ȃ�117�Z245�w����26���A�x�Z��w�N�E�w�����ƂȂ����B
�����҂̑������y�ǂ△�Ǐ�ŁA����×{�Ґ���26�����݁A4173�l�ʼnߋ��ő����X�V�����B�s���̈�Ë@��256�J���ōs���Ă��锭�M�O���ɂ͖₢���킹���E�����Ă���A�s�́u�{�����Â�K�v�Ƃ���l����f�ł��Ȃ����ꂪ����v�Ƃ��āA���Ǐ�̐l�͑��}�Ȏ�f���T����悤�Ăъ|���Ă���B
|
���H�c�����R���i�����A�ߋ��ő�266�l�@�H�c107�l����71�l�@1/27
�H�c���ƏH�c�s��27���A�V����266�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����܂ōő�������25����245�l���21�l�����A�ߋ��ő��ƂȂ����B�����̊����҂̗v��3376�l�B
�����҂̓���͕ی����ʂŏH�c�s107�l�A���21�l�A�k�H�c14�l�A�\��15�l�A�H�c����8�l�A�R���{��16�l�A���7�l�A����71�l�A����7�l�B����ی����Ǔ��̊����҂͏Ǐ�Ȃǂ����B�ق��ɏd�ǎ҂͂��Ȃ��B
�N���X�^�[(�����ҏW�c)�̐V�K�����҂́A25���Ɍ��\���ꂽ�X�|�[�c����55�l�A26�����\�̕ʂ̃X�|�[�c����9�l�B���̂ق��\��ی����Ǔ���2���Ə��Ŋe1�l�A���암�̍��Z1�l�A�H�c�s�̏��w�Z7�l�ƕۈ牀2�l�B
�H�c�s����ψ���͐V����7�Z���w�N�A�w�����Ƃ���B�R���{���s���ς͒��w�Z1�Z��V���ɋx�Z�A�X�|�[�c���N�c�╔�����̋x�~���Ԃ�30�����痈��6���ɉ�������B�����a�@�@�\(�H�c�s)�͖{�������ǂ̐E���ƌ����z��E�]�Ґ��Z���^�[�̊Ō�t�e1�l�A����s����X�a�@�͎����E��1�l�̊����\�B���҂�E���ɔZ���ڐG�҂͂��炸�A�ʏ�ʂ�Ɩ����s���B
�E���̊����͌���3�l�A����s4�l�B�\��R�{�L����h�{��2�l�B�H�c�A�j���A�R���{���A����A��ځA���Y���A����7�s�����e1�l�B
|
���{�錧�A��������u�d�lj����X�N�Ⴂ39�Έȉ��͎���×{�v�@1/27
�{�錧��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ŏh���×{�{�݂̕N��(�Ђ��ς�)���\�z�����Ƃ��āA�d�lj����X�N���Ⴂ39�Έȉ��̊����҂�����܂ł̏h���×{���猴���A����×{�Ƃ���V���[����28���ɓ�������Ɣ��\�����B����×{�҂̃P�A�ɓ�����u�t�H���[�A�b�v�Z���^�[�v�������ɊJ�݁B�ی����̋@�\���d�lj����X�N�̍������҂ւ̑Ή��ɏW��������B
�����̐V�^�R���i�����҂̗×{�̓O���t�̒ʂ�B�V�K�����҂�2���A���ʼnߋ��ő����X�V���A26���͑O�����165�l����496�l�B9��1580���̐��̏h���×{�{�݂ɂ͓����ߌ�1�����݁A771�l������g�p����48�E8���B
�V���[���ł́A�d�lj����X�N�̒Ⴂ39�Έȉ��̊����҂͎���ŗ×{����B40�Έȏ�܂��͏d�lj����X�N�����������҂́A�h���×{�{�݂ɓ���B
�O�o�֎~�����߂鎩��×{�҂ɂ́u�p���X�I�L�V���[�^�[�v��ݗ^���A�H���Ȃǐ����x���i��z������B���~���N�⎆���ނȂǂ̓��c���������p�ӂ���B
���̌��N�ώ@�A�v�������p���A�����_�f�O�a�x��̉��A�Ǐ�Ȃǂ���Ă��炤�B�Ή�����Ȑl�͓d�b�ł�������B���ǂ���10���Ԍo�߂��A���Ǐ�y������72���Ԍo�߂��Ă���Η×{�����B�Ǐ��������ꍇ�A�h���×{�{�݂����@�ɐ�ւ���B�V�݂̃t�H���[�A�b�v�Z���^�[��(1)1��1�A2��̌��N�ώ@(2)�Ǐ�Ɋւ���24���ԑ��k(3)��Ë@�ւ̎�f���K�v�ȏꍇ�̒���(4)�����x���i�̒lj��z�z�̎t���|�Ȃǂ�S���B
�ی����̕��S�y����Ƃ��āA�����o�H��Z���ڐG�҂�ǐՂ���u�ϋɓI�u�w�����v��{�l�ƏǏ�̂��铯���Ƒ���𒆐S�ɍi��B�{�݂̒����ł͊Ǘ��҂Ƀ}�j���A���ɉ����ĔZ���ڐG�҂���肵�Ă��炤�ȂǁA���͂��˗�����B
����24���A�h���×{�{�݂̎g�p����70�����A1���̐V�K�����҂�300�l���̓��������Ɨ\�z�����ꍇ�A�V���[���ɐ�ւ�����j�������Ă����B |
����t����3�l���S�A3802�l�����@�ő��X�V�A�w�Z�ȂǃN���X�^�[10���@1/27
��t������27���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������3�l�̎��S�ƁA�ߋ��ő���3802�l�̊������V���ɔ��������B����̊����Ґ���3��l����̂�2���Ԃ�ŁA�O�T20��(1596�l)�����2�E4�{�ɑ������B����Ҏ{�݁A���������{�݁A�w�Z�A�a�@�Ōv10���̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F���ꂽ�B
���́A90��ȏ�̒j��1�l�̎��S��2465�l�̊����\�B�S���Ȃ����j����1�����{�Ɏ���œ]�|���~�}��������A�o�b�q�����ŗz�����m�F���ꂽ�B�_�f���^������25���Ɏ��S�����B���N�`���ڎ���͕s���ŁA�z��n�̊�b����������A�����̓R���i�ȊO�̎����ɂ����̂Ƃ����B
�����s�̓��ʗ{��V�l�z�[���u���u���v�ł͐E���Ɠ����҂̌v34�l�A�䑷�q�s�̎��������{�݁u���ς�͂��������獪�ˋ����v�ŐE���Ɩ��A�w���E�����̌v14�l�A���s�̍��˕ۈ牀�ŐE���Ɖ����̌v41�l�A�s���s�̌����s�����Z�Ő��k7�l�A���s�̒鋞��w���Α�����ÃZ���^�[�ŐE���Ɗ��҂̌v35�l�A�s��s�̑�쒆���a�@�ŐE���Ɗ��҂̌v22�l�̃N���X�^�[�����ꂼ��m�F���ꂽ�B
��t�s�́A60���70��̒j���v2�l�̎��S��656�l�̊����\�����B���s�̐V�K�����҂�24����564�l������ߋ��ő��B60��j���́A�s����Ë@�ւ���f�����ۂɗz�����������A�s�O��Ë@�ւ֔������ɖS���Ȃ����B�����͔x���B70��j���́A�R���i�Ƃ͕ʂ̎����ň�Ë@�ւɓ��@���Ă����ۂɗz�����������A�����ǂƐf�f����_�f���^���Ă����B�����͐V�^�R���i�����ǁB���������b����������A���N�`����2��ڎ�ς݂������B
�D���s�́A401�l�̊����\�����B3�l�̏Ǐ��d���B�N���X�^�[���m�F����Ă���s���{�݂̂����A�Z�R���f�B�b�N�a�@�œ��@���҂ƈ�Ï]���҂̊���������8�l�����v85�l�ɂȂ����B�D�������a�@�ł�2�l���̌v23�l�B���t���L���V�l�z�[���u�j�`�C�z�[�����D���v��3�l���̌v12�l�ƂȂ����B
���s�́A280�l�̊����\�B���N�`��2��ڎ�ς݂�162�l�Ŕ������A3��ڐڎ�ς݂�1�l�����B�s�����w�Z4�Z�̊e1�w���ŃN���X�^�[�������B�����k���Ɠy�A�L��3���͎���5�l�A�������͎����ƐE���̌v6�l���������A��������w���������B
27���Ɍ����Ŋ��������������l�̋��Z�n�́A��t�s601�l�A���ˎs436�l�A�D���s426�l�A�s��s366�l�A���s269�l�A�����s166�l�A���R�s138�l�A�䑷�q�s125�l�A�Y���s121�l�A�s���s102�l�A���q�s99�l�A�K�u��s96�l�A�s76�l�A�؍X�Îs75�l�A�l�X���s70�l�A���c�s68�l�A���P�J�s43�l�A�Ό��s42�l�A�x���s39�l�A��c�s36�l�A�N�Îs27�l�A���P�Y�s26�l�A�����s24�l�A����s�A���s�A�x�Îs���e20�l�A�َR�s�A���������e19�l�A���X�s�A���q�s���e17�l�A��Ԕ����s15�l�A����s14�l�A�R���s13�l�A�����ݎs12�l�A��{���A���������e10�l�A��[���s�A�x���s���e9�l�A���X�䒬8�l�A����s�A���Ò��A���쒬���e7�l�A�r��6�l�A�h��5�l�A���Y�s3�l�A��\�㗢���A���q���A���������e2�l�A���Ō����A�ŎR���A�_�蒬�A�命�쒬���e1�l�A���O54�l�������B
|
�������s �V�^�R���i 3�l���S 1��6538�l�����m�F 3���A���ōő� �@1/27
�����s����27���̊����m�F��1��6538�l�ŁA26������2400�l�]�葽���Ȃ�A3���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂��A����×{���̐l�͏��߂�5���l����5��11�l�ɏ��A�s�̒S���҂́u����×{�҂́A�s��ی����ȂǂŘA�g���Ďx�����Ă��邪�A���̒i�K�Ɏ����Ă͌l���݂����玩�������s����O�ꂵ�Ă������Ƃ��K�v���v�Ƙb���Ă��܂��B
�����s��27���A�s���Łu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v�܂ł̒j�����킹��1��6538�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ�V���Ɋm�F�����Ɣ��\���܂����B26����肳���2400�l�]�葝���āA�����3���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂��A�ؗj���Ƃ��ẮA����܂łōł����������A1�T�ԑO�̍���20���̂��悻1.9�{�ł��B7���ԕ��ς�1��1762�l�ƂȂ�A�O�̏T��2�{�]��ƂȂ�܂����B�s���Ŋ������m�F���ꂽ�l��27���܂ł�50���l����51��5087�l�ƂȂ�܂����B
27����1��6538�l�̔N��ʂ�10�Ζ�����2048�l�A10�オ1750�l�A20�オ3775�l�A30�オ3000�l�A40�オ2594�l�A50�オ1661�l�A60�オ752�l�A70�オ504�l�A80�オ321�l�A90�オ127�l�A100�Έȏオ5�l�ŁA�N�オ������Ȃ��l��1�l�ł����B���̂����A10�Ζ�������90��܂ł͂�������ߋ��ő��ł����B����A65�Έȏ�̍���҂͑S�̂�7.7���ɂ�����1267�l�ŁA�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�܂��A����×{���̐l�͏��߂�5���l���āA5��11�l�ɏ���Ă��܂��B24����3���l�A������26����4���l�����ꂼ�꒴��������ŁA�����̋}���Ȋg��ɂƂ��Ȃ��Ď���ŗ×{����l�����ĂȂ��y�[�X�ő������Ă��܂��B�s�̒S���҂́u����×{�҂́A�s�̃t�H���[�A�b�v�Z���^�[��ی����A��Ë@�ւŘA�g���Ďx�����Ă��邪�A���̒i�K�Ɏ����Ă͌l���݂����玩�������s����O�ꂵ�Ă������Ƃ��K�v���B�̒��������Ȃ������́A�����Ɏx���@�ւɘA������ق��A�Ƒ���m�l�ǂ����ŘA������荇���āA���X�̌��N�Ǘ���O�ꂵ�Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B
27���̎��_�œ��@���Ă���l�́A26�����122�l������3149�l�ł����B��Ë@�ւɓ��@���邩�z�e���⎩��ŗ×{���邩�����̐l��3��9105�l�ŁA�ߋ��ő��ł��B
�����o�H���������Ă���̂�5662�l�ŁA�u�ƒ���v��3236�l�ƍł������S�̂�57.2���ł����B�����ŁA�u�{�ݓ��v��21.4���ɂ�����1212�l�ł����B���̂����ۈ牀�Ɨc�t���ō��킹��437�l�A���w�Z��271�l�A����Ҏ{�݂�207�l�A��Ë@�ւ�113�l�̊������m�F�����ȂǁA���L���{�݂Ŋ������L�����Ă��܂��B�܂��A�u�E����v�ł̊�����590�l�ł����B�u�ƒ���v�A�u�{�ݓ��v�A�u�E����v�Ŋ��������l�́A���ꂼ��ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
27����1��6538�l�̂������Ǐ�̐l��1446�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�s�̊�ŏW�v����27�����_�̏d�ǂ̊��҂�26���Ɠ���18�l�ł����B����ɁA�s�́A�������m�F���ꂽ90��̒j���ƁA70��̒j��2�l�̍��킹��3�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
���a���g�p��44.4�� �錾���o�v��������50���ɋ߂Â�
�����s���ŐV�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p�����A27�����_��44.4���ƂȂ�A�s���ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50���ɋ߂Â��Ă��܂��B�s���V�^�R���i�̊��҂̂��߂ɍő�Ŋm�ۂł���Ƃ��Ă���6919���̕a���g�p���́A27�����_��44.4���ƂȂ�܂����B�s���̕a���g�p���͍����ɓ����ď㏸�������Ă��āA����9����10������ƁA8�����17����20���A����4�����21���ɂ�30�������ꂼ�꒴���܂����B�����āA27���A40������26�����1.6�|�C���g����A�s�����{�ɑ��ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50���ɋ߂Â��Ă��܂��B����A�d�ǂ̊��҂�27�����_��18�l�ŁA�s�[�N����297�l�ɏ������5�g�ɔ�ׂ�Ƒ啝�ɏ��Ȃ��A�d�NJ��җp�̕a���g�p����3.5���ł��B
|
�����m�ŐV�K�����ҁA�ߋ��ő�5160�l�@1/27
���m����27���A�V�^�R���i�E�C���X�����҂��V����5160�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����҂͉ߋ��ő����X�V���A5000�l����̂͏��߂āB
|
���u�u�w�����v���ꂸ�c�I�~�N�������}�g��Ŏ����̊i���@�����@1/27
����Ë@�ւ�w�Z��D�悳���邽�߂Ƃ������c
�ی�������A�����Ȃ��c�B���A�����s�̕ی����̑Ή����g����L���Ă���B
�����s���̊�Ƃ̊W�ҁF�@1��18���Ɋ����҂��o���B�ی�������̃q�A�����O�������āA�����ŔZ���ڐG�҂��������Ă���̑Ή��Ǝv���Ă����B�ی�������̘A���͂Ȃ�����
�A���A1000�l���銴���҂��m�F����Ă��镟���s�ł͕ی����̑Ή����ǂ������A1��12�����犴���҂�����������Ƃɑ��A�Z���ڐG�҂���肷��u�w�������k�����Ă���B
�s�ɂ��ƁA�d�lj����X�N�̍�����Ë@�ւ⍂��Ҏ{�݁A�N���X�^�[���������₷���w�Z�Ȃǂ̉u�w������D�悳���邽�߂��Ƃ��Ă��邪�c�B
�����s���̏��w�Z�Ɏq�����ʂ���e�F�@�u���삳�ʂ��Ă���N���X�ŗz���҂��o�܂����v�ƁB�ی����̕������Ȃ��Ƃ������Ƃ݂����ŁA�Z���ڐG�҂̉\���������Ƃ����F���̌��Ɏ���ҋ@�Ȃǂ����Ă���������
�����s���̏��w�Z�ɒ��j�ƒ�����ʂ킹�鏗���B�����̃N���X�Ŏ����̊������m�F���ꂽ���A�ی����̋Ɩ��Ђ����𗝗R�ɁA�D�悳���͂��̔Z���ڐG�҂̒��������{����Ȃ������B
�������Ă��邩������Ȃ��Ƃ����s���@���邽�߁A�������{���Ă��閳����PCR�������悤�Ƃ������A�\��͂����ς��������B
�����s���̏��w�Z�Ɏq�����ʂ���e�F�@(�Z���ڐG�҂�)���肪�ł��Ȃ��̂ł���A�������猟���������Ƃ��Ɍ���������ꏊ�����������������Ƃ����̂͊�����
���q������L����ƒ�������������@�Ɩ��Ђ���
����A�v���Ďs�����̉�c���ł͒�����Ђ�����Ȃ��ɓd�b���葱���A�ی����̐V�^�R���i��`�[�����Ή��ɒǂ��Ă����B�����҂̋}���ő��Z���ɂ߂钆�A���܈�ԂЂ������Ă���Ɩ����A�����Ɏ������o�܂�Z���ڐG�҂Ȃǂׂ�u�u�w�����v���B
�ی����E���F�@�X�s�[�h�ł��ˁA�����͂ƁB�����A�{����(�����҂�)�����̂ŁA���܂Œʂ�̉u�w���ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���
�I�~�N�������̊����͂��������X�Ɗ����҂��m�F����邽�߁A�u�w�������ǂ����Ȃ����Ƃ����B
��T�A�������m�F���ꂽ�j���B�Z���ڐG�҂Ƃ��ĉƑ�6�l���������A4�l���z���Ɣ��������B
�ی��t�F�@17���ɕa�@�ɗ��Ă��������Č������ʂ��o�Ă����ł����A�z���҂̕��������m�F����Ă��āc�B�ǂ�����܂����A���������Ă���ɂ��܂����H �r���Řb�𑱂���̂��������ȂƎv������A���ł����d�b�ł��邩�炢���ł���
�j���̍Ȃ́A�������O�ꂵ�Ă����̂ɂ�������炸�ƒ���Ŋ������L���������Ƃ�m��A�����o���Ă��܂����B�z���ɂȂ������Ƃ�m��V���b�N����l�������A���Ԃ������ĕ������K�v������B
�ی��t�F�@(�q�ǂ���)�Ō�A���o�Z���Ă��܂����H 13���ł����B���̓���1���A�w�Z�ɂ��������ł�����
���̓d�b�����ŁA����1���Ԉȏ�B���������������l�͎��͂ɒm��ꂽ���Ȃ��Ƃ̐S�����������߁A�M���Đ��m�ȏ�����肷��ɂ́A�c��Ȏ��ԂƘJ�͂�������B�ɂ���ẮA1�l��1���ɕ�������̂͐��l�����E���Ƃ����B
�ی��t�F�@�ق��̓s���{���������ł���悤�ɁA�{�X�ő����Ă�������ǂ����Ȃ��B���ꂷ��悤�Ȋ���
�v���Ďs�ł́A���̉Ƒ��̂悤�ɉƒ���Ŋ������L����A�q�ǂ�����z�����Ɣ�������P�[�X�������Ă��Ă���B
�v���Ďs�ی��\�h�ہE�c���_�V�ے��F�@�N���N�n�ɂ����āA�����銴���g�債�Ă���n�悩��̉��������ɑ��������Ƃ������ƂŁA�ƒ�̒��Ŏ������܂�čL�����Ă���Ǝv��
�v���Ďs���̏������ł́A2022�N�ɓ����Ċ��ɐ��Z���x�Z�B�����E���k����������ƁA�N���X���[�g�Ȃǂ�Ώۂɂ�����x�ɑ����̒������K�v�ƂȂ�A�Ɩ��ʂ���C�ɑ�����B
���̂܂܂ł͉u�w���������ŕی����̋Ɩ����p���N���Ă��܂������ꂪ���邽�߁A�s�͐ϋɓI�ȉu�w�������k�����A���ʂ͊w�Z�⍂��Ҏ{�݂Ȃǂ�D��I�ɒ������邱�Ƃ����߂��B
�v���Ďs�ی��\�h�ہE�c���_�V�ے��F�@�Ⴆ�Ίw�Z�Ƃ��ł�����ꍇ�́A�L������������悤�Ή����Ă���܂��̂ŁA�ł�����芴�����L���Ȃ��悤�Ȍ`�Ō����ɂȂ�����
����t�ł����鏊���ɂ��ׂĂ̒������e���
�ʂ̎����̂ł��A�Z���̖�����邽�ߌ����Ɏ��g�ޕی����̐E�������̎p���������B�ߑO8���߂��A�����ی�����1�����n�܂�B
�����������ی����E�{���e�����F�@�����҂�1��17�����炤����35�l�B18����39�l�A21����46�l
��5�g�ł�1��������̊����҂́A�ł���������40�l�O�ゾ�����B���A����ȏ�̔g���₦�ԂȂ��P���Ă���B�h���×{�⎩��ҋ@�ƂȂ��Ă��銴���Ґ��́A1�T�ԑO����10�{�ȏ�ɑ����B���ɂ͓��@�̕K�v�Ȑl���o�Ă��Ă���B
���l�̓���3�A�x�����������Ƃ����Ⴂ����̊������n�܂�A�����҃��X�g�̔N����������ɂ́A20�Ƃ�������������ł���1��14���B����A�������X�g������ƁA�����҂̔N��w���L�����Ă��邱�Ƃ������Ă����B
�����������ی����E�{���e�����F�@20��̎q��������������̂����邯�ǁA���̒��ŌZ�킪����c�B���T�͏��w���Ƃ��ۈ牀�Ƃ��A���̊W�҂��o�Ă���B����҂��Ƃ�(�����҂�)�N��w���炯�Ă���
�����҂ɓd�b�������A���N��Ԃ�Z���ڐG�҂̗L���Ȃǂׂ�u�u�w�����v�B
�����ی����ł́A�u�w�����̓��e�����ׂĈ�t�ł�����{�������ɕ���B�Ƃ��ɂ́A�Z���̖��Ɋւ�锻�f�����߂��邱�Ƃ�����A�����ł��E���̐��_�I�ȕ��S�����炷���߁A�V�^�R���i�ւ̑Ή����n�܂���2�N�O���炱�̂����𑱂��Ă���B
���̂��ߊ����҂�������ƁA�Ђ�����Ȃ��ɐE�����{�������̌���K���B
�����������ی����E�{���e�����F�@�Ƃɂ����������������āA�L�����������āA�����Ċ����҂��Ȃ�ׂ��E�C���X���܂��U�炷�O�ɔ������āB���̐l���玟�ɍs���Ȃ��悤�ɁA�����Ŏ��~�߂������Ă����Ƃ������ƂŁA����2�N�Ԃ�葱���Ă���
���̈���ŁA�ی����̉u�w�������k�����铮���ɂ��Ă͔ے肵�Ă��Ȃ��B
�����������ی����E�{���e�����F�@����10�N���Ƃ��o���Ă݂Ȃ��ƁA���������ʼn����ԈႢ���͂킩��Ȃ��B��������ł́A���̂�������ԁA�����g���h���Ƃ�������
�E�����������I���āA�{�������̂��Ƃɑ��k�ɂ���Ă����B
�E���F�@�E��̂ق�3�l�̂����A2�l�������s�ƕ���
�����������ی����E�{���e�����F�@�Ȃ������(�����s)
�E���F�@�������Ȃ�ł����ǁA(�����s��)�E��ɗ��Ă�
�����������ی����E�{���e�����F�@�Ȃ炢���B��������
�����҂��o�������s�̉�ЁB�Z���ڐG�҂̋^��������]�ƈ�2�l�͕����s�ݏZ�ŁA�{���͕����s�Ō�������K�v�����邪�A�o���Ă������ߎ����ی����Ō��������邱�ƂɂȂ����B�Z���̂��߂ɁA��ɗՋ@���ςɑΉ�����B
�������A�ǂ��ɂ��ł��Ȃ����Ƃ�����B
�E���F�@1��18������Ǐ��邻���ł��B�s�����́A�d���ɂ����s���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�E�ꂪ�����s����̕��ɂȂ�܂�
�����������ی����E�{���e�����F�@��������E��̕��Ɂu�z���ɂȂ����̂ŁA�W������Ǝv����l�͎����ň�Ë@�ւɘA�����Č������Ă��������v���āB�ی�������A���������Ȃ��̂�
�����������ی����E�{���e�����F�@�����̊Ǔ���������A�������܂��ƂȂ�B�t�ɂ������͂����Ŕ����������ǁA�����s�ɐE�ꂪ���邩��{�l��(�E���)�����Ă��������ƁB�E��̔��f�Ō������K�v�ƂȂ�A�����œd�b���邩�����Ō����Z���^�[��������A��Ë@�ւ�������Ƃ����d�g�݂ŕ����s�͓����Ă���̂�
��6�g�ɂ�銴���g��ŁA�ی����̑Ή��ɑ傫�ȍ������܂�Ă����B
���u�w�����̏k���u�����Ă����Ȃ肽���Ȃ��v
�莞���߂��Ă��ی����̎d���͑����B���̎��Ԃ́A����̒��ň�ԁA�ْ�������B
�����������ی����E�{���e�����F�@�����ߑO���Ɍ�������200������Ƃ̌��̂̌��ʂ��A���������o�܂��B�����ŗz���҂��o����A���̗z���҂̐l�ɘA�������āB����������Ȃ��ƁA�{�l�����@���K�v��������Ȃ����A(�Z���ڐG�҂ɂ���)�Ƒ��̂��Ƃ��Ȃ��ƁB�ۈ牀�Ƃ����w�Z�Ƃ��ł���A�����̒��Ɍ������o���A�[���̎��ԂɌ������ʂ��o��B���̎��Ԃɗz����������A�w�Z�̂ǂꂭ�炢�̏W�c�̌��������邩�Ƃ����̂����߂�
�����҂�1�l�ł����炵�A�Z���̖������B�{���������l����ی����̖����������B
���ǂ��̓��A�����s���Ŋ������m�F���ꂽ�͉̂ߋ��ő���56�l�ƂȂ����B
�����҂�����������A�����u�w�������k��������Ȃ����͂���B�{�������́A���̉\���͔ے肵�Ȃ����A�����Ă����Ȃ肽���Ȃ��Ƙb���B
�����������ی����E�{���e�����F�@�Ȃ肽���Ȃ��B�����̎d����ے肷�邱�ƂɂȂ�B�l�I�Ȉӌ������ǁA������S�͂ł����Ȃ�Ȃ��悤�ɁB���肪�������ƂɁA�����̐E���݂͂�Ȃ����v���Ă���Ă���B�Ƃɂ���1�l�ł������҂𑝂₳�Ȃ��悤�ɂƁA�݂�Ȃ����v���Ă���Ă���B����͖l�͖{���ɍK���B�݂�Ȃ��A�����̏Z���̂��߂Ǝv���Ċ撣���Ă���Ă���
�����Ǒ�̍Ō�̍ԁA�ی����B�I��肪�����Ȃ����ł��A�E��������������x���Ă����B�@ |
�������������ŐV����544�l�@1�l���S�@1/27
�����������ł�27���A�V�^�R���i�̊����҂�544�l��1�l�̎��S�����\����܂����B�������m�F���ꂽ�̂́A�����\��284�l�A�������s���\��260�l�̂��킹��544�l�ŁA�����҂�3���A����500�l�����܂����B�����̗v��1��4391�l�ɂȂ�܂����B �܂��A����1�l�����S�����Ɣ��\���܂����B�����ł���܂łɔ��\���ꂽ���҂͍��킹��70�l�ƂȂ�܂����B
���̊����g��x����͌��݁A���x��2�ł��B�l��10���l������̐V�K�����Ґ���152�D62�l�A�×{�Ґ���168�D3�l�A���߈�T�Ԃ̂o�b�q�z������20�D9���ŁA����������x��3�����ł��B������567����R���i�a���̎g�p����25�����_��39�D3���ƂȂ��Ă��܂��B
��Ì��ʂł�33���̊̑���72�D73���A9���̑]����66�D67���A31���̏o����48�D39���A38���̓�F��42�D11���A80���̉�����36�D25���A79���̈��ǁE�ɍ���37�D97���A30���̐�F��40�D0���A234���̎�������37�D61���A33���̌F�т�9�D09���ł��B
�܂��A�����̎���ҋ@�҂�25�����_��1864�l�ŁA�O�����382�l�����܂����B��Ì��ʂł́A��������1082�l�A���ǁE�ɍ���412�l�A������140�l�A��F��76�l�A��F��62�l�A�̑���58�l�A�]����26�l�A�o����8�l�A�F�т�0�l�ł��B
|
���Z���ڐG�ҋ@����7���Ɍ������@���{�����@1/27
�����J���Ȃ�27���A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̔Z���ڐG�҂ɂ��āA����Ȃǂł̑ҋ@���Ԃ�10���Ԃ���7���ԂɒZ�k��������Œ����ɓ������B����14���ɑҋ@���Ԃ������������肾���A�����҂̋}���ɔ����ĔZ���ڐG�҂ɔF�肳���l�����o���A�Љ�@�\�̈ێ�������Ȃ��Ă��邽�߁B
�V�^�R���i�̔Z���ڐG�҂͓���14���Ԃ̑ҋ@�����߂��Ă������A���{�͍���14����10���ԂɒZ�k�B�܂��A�x�@����h�A���A�ۈ�Ȃǎ����̂����f�����E��ɂ��ẮA6���ڂ܂���7���ڂ̌����A���ʼn�������Ƃ��Ă����B���J�Ȃ�10���Ԃ�7���ԂɒZ�k����Ă����Ɍ������A�x�@��ۈ�Ȃǂ̐E��ɂ��Ă͂���ɏk�߂�����Ō������Ă���B
�S���ŘA���ߋ��ő��̊����Ґ����X�V���A�w�Z�̋x�Z��ۈ牀�Ȃǂ̋x�����������ł���B�Z���ڐG�҂ƂȂ����q�ǂ������e��10���ԏo�ł����A���Ԃ̌����������߂鐺���オ���Ă����B
�܂��A�����}�g��ɂ��R�������L�b�g�̕s��������A���J�Ȃ�27���A�Ǐ���l��Z���ڐG�Ҍ����̍s�������ȊO�����{���鎩���̂��Ƃɑ��A�K�v�ȏ�̔��������l����悤���߂��B���������邽�߁A��Ë@�ւ��ŗD��Ƃ��A�Ǐ���l�ɑ���s�������̂ق��A�Z���ڐG�҂̑ҋ@���Ԃ�Z�k���邽�߂̌������D�悵�����l�����B���͊���1��80���܂ł̑��Y�����[�J�[�ɗv�����Ă���A�]�����ꍇ�͍���������邱�Ƃ�ۏ���B
|
���p���A�R���i�K�����قړP�p �I�~�N�������s�[�N�߂����@1/27
�C�M���X�ł́A�V�^�R���i�̃I�~�N�������ɂ�銴���s�[�N���߂����Ƃ��āA�}�X�N�̒��p�`���Ȃǂ̋K�����قړP�p����܂����B�C�M���X�ł͌��݁A7���ԕ��ςň��6���l���܂�̐V�K�����҂��o�Ă��܂����A�A�����悻20���l�̊���������Ă����������{�ɔ�����Ă��āA�s�[�N�͉߂����ƌ����Ă��܂��B�u�[�X�^�[�ڎ���i��ł��邱�ƂȂǂ���A�C�M���X���{��27���A������ʋ@�ւ�X�܂ł̃}�X�N���p�`���ȂǃI�~�N��������Ƃ��čē������Ă����K�����قړP�p���܂����B
�����h���s���u�����Ń}�X�N������K�v�͂���܂���B(�C���͂ǂ��ł����H)�ō��ł��v
�����h���s���u�d�Ԃ�l���݁A�X���ł̓}�X�N���������ł��v
�L�ҁu���傤����K�������ƂȂ�܂������A������̂悤�ɓX�����}�X�N�̒��p�����߂Ă���Ƃ��������܂��v
�����A�K�����P�p����Ă��}�X�N���p��Ǝ��ɋ��߂�X�܂�����ق��A�����h���s���ł͒n���S��o�X�Ȃǂň��������}�X�N���p���`���t����Ƃ��Ă��܂��B
|
���؍��g�I�~�N�������h�҈Ё@�V�K�����҂�3���Ŕ{���@1/27
�V�^�R���i�̃I�~�N���������҈Ђ�U�邤�؍��ŁA�V�K�̊����Ґ����킸��3���Ŕ{�����鎖�ԂƂȂ��Ă��܂��B27���ɔ��\���ꂽ�؍��̐V�K�̊����҂�1��4518�l�ł����B25����8000�l�䂩��3���A���ʼnߋ��ő����X�V���A���̊��Ԃłق�2�{�ɑ����Ă��܂��B�I�~�N�������ւ̒u������肪�}���ɐi��ł��āA���ʂ̊ԁA����Ȃ鑝���͔������Ȃ��Ƃ݂��Ă��܂��B
���ݓ�(�����E�W�F�C��)�哝�̂�26���̑��c�ŁA���T�ɍT���鋌�����̘A�x���Ɉ�Ë@�ւ։ߓx�ȕ��S���|����Ȃ��悤����w�����܂����B����ŁA�u�������s���߂����s���������Ȃ����߂ɍ���҂ւ�3��ڐڎ킪�i�ݏd�Ǘ��ƒv�������Ⴂ���Ƃ��`����ׂ��v�Ƃ̍l���������Ă��܂��B
|
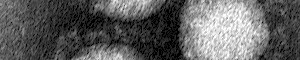 |


 �@
�@ |
���X�e���X�I�~�N������苭�łȁu�f���^�ψفv�����ɏo���@3���u��7�g�v�H�@1/28
�I�~�N���������҈Ђ�U�邢�A27�����S���̐V�K�����Ґ���7��8931�l�ƁA�ߋ��ő����X�V�����B���́u��6�g�v�͗�����{�ɂ��s�[�N���}���āA�����Ɍ������Ƃ������������邪�A�܂����S�͂ł������ɂȂ��B�������u��7�g�v����������\�������܂��Ă��邩�炾�B�V���ȕψي��̑��݂�2�����炩�ɂȂ����B
���݁A�f���}�[�N�Ŋ����g�債�Ă���̂��A�u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ��]���̃I�~�N�������̈��킾�B�I�~�N��������芴���͂������A�f���}�[�N�ł͋}���ɒu������肪�i��ł���B
�f���}�[�N�́u���ƌ����������v�̌����ҁA�A���_�[�X�E�t�H���X�K�[�h���́A�]���̃I�~�N�������Ɋ��������l������ɍĊ������鋰�ꂪ����Ǝw�E�A�����g��̃s�[�N��2��\���ɐG��Ă���B�f���}�[�N�݂̂Ȃ炸�č���t�����X�A�C���h�ȂǂŊ����Ⴊ�m�F����A���{�ł�27�ጩ�����Ă���B���s��̐��Y������(�����lju�w)�̕��͂ɂ��ƁA�]���̃I�~�N��������芴���͂�18�������Ƃ����B
�����łɍ����Ŋm�F
����ɏՌ��I�Ȃ̂́A�I�~�N���������Ő��̋����f���^���̕ψي����A�����Ŕ������Ă��邱�Ƃ��B�����[�Ȋw�Z�p�����Z���^�[�̎��ʗ��F���_�������A�h�o�C�U�[�߂�u�V�^�R���i�E�B���X�R�̑��苦�c��v��23���t�̃��|�[�g�ɂ��ƁA��N12�����{���瓌���𒆐S�ɔ�������Ă���Ƃ����B�����͂�d�lj����Ȃǂ͂܂��s�������A���c��́q���O���ׂ��r�ƌx����炵�Ă���B
�f���^���Ƃ����A���Ắu��5�g�v�ʼn���ނ��A�����̎��҂��o�����B��2�J���ɂ킽��A�A���A���\�l�̎��҂������B����҂݂̂Ȃ炸�A30��ȉ��̐���ł����҂��o���B����ŖS���Ȃ������o�����B�����A�f���^�ψي��������悤�ȋ��Ő��Ȃ�A���낵���b���B
��WHO�́u���N�ɏI������\���v
���E�ی��@��(WHO)�̃e�h���X�����ǒ��͍���24���A2020�N1�����ɐ錾�����u���ۓI�Ɍ��O�������O�q����ً̋}���ԁv�ɂ��āA�u���N�ɏI������\��������v�ƕ\���B�����A���N�ŃR���i�Ђ����������Ȃ�Ό��\�Ȃ��Ƃ����A2�̕ψي��̑��݂͕s�C�����B�u������肪�i�݁u��7�g�v�̏P���͂���̂��B���a���w���q�������̓�ؖF�l��(�Տ������NJw)�͂��������B
�u�E�C���X�͕����̍ۂɃG���[���N���邱�Ƃ��܂܂���̂ŁA����̔����͕s�v�c�Ȃ��Ƃł͂���܂���B���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���킪�ǂ̂悤�ȓ����������Ă���̂��A�Ƃ������Ƃł��B����̃I�~�N�������̈��킪�]��������u�������A��6�g�́w�R�x��傫�����鋰�ꂪ����ł��傤�B�܂��A�I�~�N�������̎��̕ψقɂ��v���ӂł��B����A��7�g���������邱�Ƃ��l�����܂�����A�܂��܂����f�͋֕��ł��v
20�N1���ɃR���i�������ŏ��m�F����Ĉȍ~�A��1�g�͈��N3���ɁA���{�ň�Õ������������4�g�͍�N3���ɔ��������B��7�g�P����2�J���ォ������Ȃ��B
|
���S�ݓX����A�I�~�N��������u�����ƈ�̂œO��v�@1/28
�I�~�N�����^�̐V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�Ă���B�S�ݓX�ł͍��Ắu��5�g�v�ŃN���X�^�[(�����ҏW�c)�����������B�����͂̋����I�~�N�����^�ւ̑Ή��ɂ��āA���{�S�ݓX����̑��c�P�Y�(�������В�)�́u�����A�����Ǝ҂ƈ�̂ŏ��i�̋����@�\���ێ�����v�Ƌ��������B
2021�N10���ɋً}���Ԑ錾���S�ʉ�������Ă���A�S�ݓX�ɂ͋q�����߂��Ă����B22�N1����16���܂ł̓X�����㍂�́A�O�z�ɐ��O�z�[���f�B���O�X�̎�s���X�܂ł�21�N�̓����ԂƔ�ׂ�44%�������B��������33%���ő�ۏ��≮�S�ݓX��26%�v���X�������B21�N1����2��ڂً̋}���Ԑ錾�����������߁A���̔������������B�������߂̃I�~�N�����^�̊����g��Łu�ڋq�̗���͓���ǂ����Ƃɏ��Ȃ��Ȃ��Ă���v(���c�)�B
�S�ݓX�]�ƈ��̊����҂������Ă���B������ʂ̈ɐ��O�V�h�{�X(�����E�V�h)�ł�27���܂ł�1�T�ԂŌv74�l�̊������m�F�B90�l�ȏ���L�^���Ă�����5�g�̊g������͏��Ȃ��������X���ɂ���B����3�ʂ̐����r�ܖ{�X(�����E�L��)��27��������12�l�̊����\�����B
��5�g�ł͍�_�S�ݓX�~�c�{�X(���s)���}���߂��{�X(��)�ŃN���X�^�[�������B�����ł��ɐ��O�V�h�{�X�������҂̑����ňꕔ�̔������x�Ƃ����B
����͎�v�ȕS�ݓX�Ŗڗ����������̋x�Ƃ͌����_�ł͂܂��N���Ă��Ȃ��B��5�g�͊����҂��n���H���i�����(�f�p�n��)�ɕ�X�����������B���c��́u����͊����҂��o��ꏊ�����U���Ă���B�o�H���ƒ���������ڗ��B�X�܂̖h�u�̐���(��5�g���)�����Ȃ��Ă���v�Ƙb���B
�S�ݓX�̖h�u�̐��ɂ��č��ۈ�Õ�����w�̘a�c�k������(���O�q���w)�́u�ł����͂��ׂ��͏]�ƈ����m�̊�����\�h���邱�Ɓv�Ƙb���B�S�ݓX�͋Ζ��҂̑唼���O���̎����Ј�����߂邱�Ƃ���u�������܂߂Ăǂ��h�u�̐����\�z���邩���v�Ǝw�E����B
���c��͑I�~�N�����Łu�S�ݓX�e�Ђ�������֊����h�~���ēO�ꂷ��悤���M�����v�Ƌ����B�u�̉�����Ȃǂ̏]�ƈ��̌��N�Ǘ��͂�苭�����Ă���B�Ј��H���ł��]�ƈ��͌H��ِH�����킢�����ȂقǓO�ꂵ�Ă���v�Əq�ׂ��B
�I�~�N�����^�͊����͂������B�]�ƈ��̊����ŗX�ǂ��x�~���A�����ԍH��̃��C������~�������o�Ă����B���c��́u������S��������T�v���C�`�F�[��(������)��S�������Ǝ҂̋Ɩ����܂Ђ��Ă͂����Ȃ��B(�H���i�Ȃǂ�)�����K���i�������ł��Ȃ��Ȃ�v�Ƙb���B����Ȃ銴���҂̑����ɔ����āu�{�Е���̂ق��A��H���i����̏]�ƈ����o�b�N�A�b�v����Ƃ���������K�v�ɂȂ�v�Ƃ̌������������B
|
���u�S�����R���i�ɂ�����B���������Ɉꐶ���I���邱�Ƃ͍���v�@1/28
�ăj���[���[�N�B�A���`�F�X�^�[�����a�@�̊����Ǖ����A�G�h�E�E�H���V����t�́A������̓R���i�Ɋ��������Ɉꐶ���I���邱�Ƃ́A�قڕs�\�ɂȂ�Ƃ̎��_��W�J�����B27���̕ĕ����ǂv�g�`�l�����B
�u���Ԃ����ĂA����ɑ����̐V�^�R���i�E�C���X�ψي����o�����A����ɑ����̐l�X���������邾�낤�B���̗\���ł́A�����ꂻ�̂����A�����S�������炩�̃R���i�ψي��ɂ�����v�B���̗��R�Ƃ��āA����t�́u���N�`���͂����Ȃ銴���ɑ��Ă��A100���̗\�h�ɂ͂Ȃ�Ȃ����炾�B���������Ɉꐶ���I���邱�Ƃ͍�����ɂ߂邾�낤�B�Ƃ����̂��A���̃E�C���X�͂�����(�n��ɍ�������)���y�a�ɂȂ邩�炾�B���̂܂����Ă��܂����Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ɛ��������B
���a�@�̃G�~���E���[�V���[�����ǐ�����A�I�~�N�������Ō�̕ψي��ɂȂ��Ăق����Ƃ̊�]�ɂ��āu����͂قڂ��蓾�Ȃ��B�I�~�N�������Ō�̕ψي��ɂȂ邾�낤�Ƃ�����������S��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ɠ��������B
���ہA�č��ł̓p���f�~�b�N����2�N��ŁA�S�l���̖�22���ɑ��������7300���l���������A��88���l�����S�B�Z���ڐG�҂ɂ������ẮA�l����9���ɂ̂ڂ�Ƃ����B
���݁A���E�Ŋ����̎嗬�ƂȂ��Ă���̂̓I�~�N�����������A����̈���A�ʏ́g�X�e���X�E�I�~�N�������h������������B�f���}�[�N��t�B���s���Ȃǂł́A���ɐV�K�����̔����ȏオ�]���̃I�~�N�������Ɏ���đ������ƕ��A�����͂��]���̊���苭���Ƃ̌����Ⴊ����B
|
�����@��6����2��ڎ�ς݁@1/28
���������nj�������28���A�ψق����V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������Ɋ��������@����122�l�̕��͂ŁA���N�`����2��ڎ���I�����l��63���ɏ���Ă����Ƃ̌��ʂ����\�����B2��ڐڎ킩��̎��Ԍo�߂�E�C���X�̕ψقŌ��ʂ���܂�ƕ���Ă���A���������e�����o���\��������B3��ڎ킵���l��2������A�V�^�R���i�̊�����������l�������B���ڎ��33���������B
��N11�����`���N1��12���ɍ����œ��@����0�`78�͂����B���@���ɉ��炩�̏Ǐ������l��76���A���Ǐ��24���B���@��ɏǏo���P�[�X������A�މ@���܂Ŗ��Ǐ����̂�20���ɂƂǂ܂����B�@ |
���{��ő�547�l�����A�������323�l�@�v2���l�����@1/28
�{�錧�Ɛ��s��28���A�v547�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B27����497�l������A4���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B���s��323�l�B�����҂̗v��2��153�l�ƂȂ����B
|
�������s �V�^�R���i 1��7631�l�����m�F 4���A���ʼnߋ��ő� �@1/28
�����s��28���A�ߋ��ő���1��7631�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ�V���Ɋm�F�����Ɣ��\���܂����B27�����1000�l�]�葝���A4���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂��A���j���Ƃ��ẮA����܂łōł����������A1�T�ԑO�̂��悻1.8�{�ł��B����A�s�̊�ŏW�v����28�����_�̏d�ǂ̊��҂�27�����2�l������20�l�ł����B
|
�������s �V�^�R���i 3�l���S 1��7631�l���� 4���A���ߋ��ő� 1/28
�������}�g�債�Ă��铌���s���ł�28���A1��7631�l�̊������m�F����A4���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B����×{���̐l�͈����1���l�]�葝���ď��߂�6���l���A�s�̒S���҂́u����A����ɑ����邱�Ƃ��\�z�����B�T�����ɊJ�݂����T�|�[�g�Z���^�[�Ȃǂ�ʂ��Ďx�����Ă��������v�Ƙb���Ă��܂��B
�����s��28���u10�Ζ����v����u100�Έȏ�v��1��7631�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ�V���Ɋm�F�����Ɣ��\���܂����B27�����1000�l�]�葝���A4���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂��A���j���Ƃ��ẮA����܂łōł����������A1�T�ԑO�̂��悻1.8�{�ł��B28���܂ł�7���Ԃ̕��ς�1��2895.1�l�ŁA�O�̏T��2�{�]��ƂȂ�܂����B
10�Ζ�������40��ƁA60�オ�A��������ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂��A����×{���̐l�͏��߂�6���l����6��1026�l�ɏ���Ă��܂��B26����4���l���A27����5���l�����ꂼ�꒴��������ł����A28����27�����炳���1���l�]�葝���Ă��āA�����̋}���Ȋg��ɔ����Ď���ŗ×{����l�����ĂȂ��y�[�X�ő������Ă��܂��B�s�̒S���҂́u�y�ǂ△�Ǐ�̕��Ɏ���×{�����Ă��������Ă��āA�����Ґ��̑����Ƒ��܂��Ď���×{�҂������Ă���B�������܂������ɓ����Ă��炸�A����×{�҂́A����A����ɑ����邱�Ƃ��\�z�����B�T�����ɊJ�݂����T�|�[�g�Z���^�[�Ȃǂ�ʂ��Ďx�����Ă��������v�Ƙb���Ă��܂����B
�����o�H���������Ă���̂�6167�l�Łu�ƒ���v��3789�l�ƍł������A�S�̂�61.4�����߂Ă��܂��B�����Łu�{�ݓ��v��18.5���ɂ�����1139�l�ŁA���̂����ۈ牀�Ɨc�t���ō��킹��372�l�A���w�Z��309�l�A����Ҏ{�݂�153�l�A��Ë@�ւ�111�l�̊��������ꂼ��m�F����܂����B�܂��u�E����v�ł̊�����597�l�Łu�ƒ���v�Ɓu�E����v�Ŋ��������l�́A��������ߋ��ő��ł��B28����1��7631�l�̂������Ǐ�̐l��1664�l�ŁA��������ߋ��ő��ł��B
�s�̊�ŏW�v����28�����_�̏d�ǂ̊��҂�27������2�l������20�l�ł����B���̂ق��A�s�́A�������m�F���ꂽ80��̒j��1�l��90��̏���2�l�̍��킹��3�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B�܂��A�s�́A����14���Ɋ������m�F���ꂽ�Ɣ��\�����l���ɂ��āA�������ʂ̋L�ڃ~�X������A4�l�A������Ɣ��\���܂����B����ɂ��14���Ɋ������m�F���ꂽ�l��4055�l�ƂȂ�܂����B
�����s���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l�̂����A����×{���̐l��28�����_�ŏ��߂�6���l���āA6��1026�l�ɏ���Ă��܂��B����24����3���l�A26����4���l�A27����5���l�����ꂼ�꒴��������ŁA�����̋}���Ȋg��ɂƂ��Ȃ��Ď���ŗ×{����l�����ĂȂ��y�[�X�ő������Ă��܂��B�@ |
���u�����Җ{�l���Z���ڐG�҂f���A�����v �V�������ی����̋Ɩ��������@1/28
�V�^�R���i�̊������}�g�債�Ă��邱�Ƃ��A�V������26�����炱��܂ŕی������s���Ă����Z���ڐG�҂̒����Ȃǂ̋Ɩ����������܂����B����́A�����Җ{�l���F�l�⓯���Ȃǂ̔Z���ڐG�҂������Ŕ��f���A�A�����邱�ƂɂȂ�܂��B�����������A���Ȃ��͔Z���ڐG�҂Ƃ����A����ҋ@�����ꍇ�A�Ƒ��Ƃǂ��ڂ�����悢�̂��H�܂��A�����Ō��������ėz�����o���ꍇ�͂ǂ�������悢�̂��H��z�ی����ɕ����܂����B���́A�ی����̋Ɩ����Ђ��ς����Ă������A�����ǂ�d�ǃ��X�N�̂���l�ւ̈�Â̒��ł��Ȃ��Ȃ�Ȃ��悤�A����܂ōs���Ă����Z���ڐG�҂̒����Ȃǂ̋Ɩ����������܂����B����́A���������l���A�����Ƒ��ȊO�̔Z���ڐG�҂������Ŕ��f���A�{�l�ɘA�����邱�ƂɂȂ�܂��B
���Z���ڐG�҂̒�`
�E�����҂Ɠ����Ⓑ���Ԃ̐ڐG���������B
�E1���[�g�����x�̋����Ń}�X�N��������ƒ��p�����A�����҂�15���ȏ�̐ڐG���������B
�E�ߋ����ň��H���Ȃ���̉�b��x�e����X�ߎ��ȂǂŃ}�X�N�����Ȃ��܂܂̉�b�Ȃǂł��B
�܂��A�ڐG�̃^�C�~���O�́A�����҂ɏǏ���ꍇ�͏Ǐo��2���O����A���Ǐ�̏ꍇ�͗z���ƂȂ������̂��̎悵������2���O����ł��B�����āA�����҂��炠�Ȃ��͔Z���ڐG�҂��ƘA�����������ꍇ�A�ǂ��s��������悢�̂ł��傤���H�܂��A���Ǐ�̏ꍇ�́A��������K�v�͂���܂���B���̏ꍇ�A10���ԁA����ҋ@���Ă��������B�����A���M�ȂǁA���ׂ̂悤�ȏǏ������ꍇ�́A���������A��f�E���k�Z���^�[�A�ی����̂����ꂩ�ɘA�����Ă��������B�ł́A���Ǐ�̐l���A����ҋ@���Ɏ����Ō������ėz�����킩�����ꍇ�͂ǂ�������悢�̂ł��傤���H��z�ی����ɂ����˂����A�z���������o���ꍇ�́A���������A��f�E���k�Z���^�[�A�ی����̂����ꂩ�ɘA�����������A�Č����ƂȂ�A���̌�̎w���ɏ]���Ăق����Ƃ������Ƃł��B���̏ꍇ�A�w�����o��܂ŁA�Ƃ̒��ł́A�ł��邾���Ƒ��Ɨ���ĉ߂����悤�ɂ��Ă��������B
���Z���ڐG�҂̔Z���ڐG�҂́c�H
�Ƃ���ŁA�F�l�⓯������A���Ȃ��͔Z���ڐG�҂��Ƃ���ꂽ�ꍇ�A�����̉Ƒ��Ȃǂ͂���Ȃ�Z���ڐG�҂ɂȂ�̂ł��傤���H������u�Z���ڐG�҂̔Z���ڐG�ҁv�ɂ��āA��z�s�̌��N�q��ĕ��A��R�m�����ɂ����܂����B
��z�s���N�q��ĕ� ��R�m�����@�u�Z���ڐG�҂ɋ߂��l�͍s���̋K���͂Ȃ��B�I�~�N�������͔��Ɋ����͂������B�̒��̕ω�����������O�o���T���A���������⑊�k�Z���^�[�ɘA������ȂǑ���v
|
���l���s�ŐV�K����315�l�@�ߋ�2�Ԗځ@����Ҏ{�݃N���X�^�[�g�� �@1/28
28���A�l���s�͐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�315�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂���(�֓c�s3�l�A�ΐ��s3�l���܂�)�B�l���s�̔��\���ł���܂ōő�������27��333�l�͉����܂������A�ߋ�2�Ԗڂɑ��������Ґ��ł��B315�l�̂���20��ȉ�����5�������߂Ă��܂��B28�����݂̕l���s���̕a�@�̓��@�Ґ���44�l�ŁA���������Ljȏ��12�l�ł��B
���N���X�^�[�g��
�E���t���L���V�l�z�[���u���N���X�L�W�f���X�v �E��1�l�̊������킩��A�N���X�^�[��14�l�ɂȂ�܂����B
�E���t���L���V�l�z�[���u����₩�͂܂܂فv ������1�l�̊������킩��A�N���X�^�[��13�l�ɂȂ�܂����B
�E���t�V�l�ی��{�݁u�G�[�f�����C�X�v ������1�l�̊������킩��A�N���X�^�[��7�l�ɂȂ�܂����B
|
�����{�̃R���i�����͑S�����[�X�g�c�@1/28
��������}�̐����l�������g�̃c�C�b�^�[�ɓ��e�����u�q�g���[�����v������A�A���g�����h�𑱂��Ă�����{�̋g���m���B27���̒���ł��A�u��������}�̑Ή���҂������v�Ɖ��߂ĎӍ߂�v�������B�������Ƃ���ɔᔻ���J��Ԃ��̂́A�I�~�N��������́g�厸�s�h���璍�ӂ����炵�������炩�B
�����̃L�b�J�P�́A���������{�ېV�̉��n�ݎ҂̋����O�����{�m���ɂ��āA�q�咣�͕ʂƂ��ĕِ�̍I�݂��ł͑�ꎟ����̍�������h�C�c�Ő���������������̃q�b�g���[���v���N�����r�ƃc�C�b�^�[��Ŕ��M�������ƁB�������͂������A�ېV�̕���\�߂�g���m�����u�Ƃ�ł��Ȃ������v�Ɛ��ɉ����A27���̉�ł́u�{���ɖ���}�������I����Ă悩�����Ȃ��ƐS����v���܂��v�u��x�Ɨ��Ȃ��ł������������v�����Ƃ܂Ō����������B
�₽�狭�C�Ȏp���������Ă��邪�A���}�ɃC�L���Ă���ꍇ�Ȃ̂��B�����̓{���{�����B
����27���̐V�K�����Ґ���9711�l�ƁA2���A����9000�l�����B�u�D�y���t�����e�B�A���Q�m����Ȋw�v�̃f�[�^�ɂ��ƁA�l��100���l������̓��@�E�×{���Ґ�(7���ԕ���)��26�����_��6892.5�l�ƑS�����[�X�g�B�����_�̐l��100���l������̐V�K�����Ґ��Əd�ǎҐ����S�����[�X�g�ŁA���Ґ��̓��[�X�g3�ʂ������B
���������S��̃V������̂́A����̐E���������B���������ɂ���Đl���̑������s���ł͘A���A�~�}�Ή��������������A�o���̐����N���B�I���̌����Ȃ������g��ɁA���{�W�E���J���g��(�{�E�J)�̌��ɂ͕ی����E������̔ߖ��E�����Ă���Ƃ����B
�u��5�g�Œ����ԘJ����������ꂽ�ی��t��́w�܂������̔g��������c�c�x�ƃg���E�}�ɋ߂���Ԃł������A��6�g�͂������S��ł��B���҂ւ̃t�@�[�X�g�^�b�`���x���A������w�ςݎc���x�����o���A�������o���琔����̘A����]�V�Ȃ������ȂǁA���S�ɃL���p�I�[�o�[�ł��B��Â�ی����ւ̕��S�y�����Ӑ}���Ă��A�{�͈�Ë@�ւ̎�f�����Ȃ��Ă�����×{���n�߂���w�݂Ȃ��z���x�̓������������Ă��܂����A����×{�ɂȂ����l��ی������Ǘ�����ƂȂ�ƁA���ǂ͕��S���ɂȂ��肩�˂Ȃ��B�m���ɂ͌���̐����悭�����ė~�����Ǝv���܂��v(�{�E�J�̏����N���ψ���)
�u�g���{�����I����Ă悩�����v�u��x�Ɨ��Ȃ��ăG�G�v�ƌ���������߂����B
|
���_�˂ŃI�~�N�����h�����m�F�@���Ɍ����ŏ� �@1/28
�_�ˎs��28���A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��I�~�N�������̈��ŁA���ݎ嗬�̃E�C���X�Ƃ͕ʂ̔h�����u�a�`�E2�v���s����2�ጩ�������Ɣ��\�����B�s���N�Ȋw�������̃Q�m����͂Ŕ��������B���Ɍ��ɂ��ƁA�����ł͏��m�F�Ƃ����B
2���10�`16���A�s�ɓ͂��o�������������҂��猩�������B���E�I�Ɏ嗬�́u�a�`�E1�v�Ƃ͕ψق̉ӏ����قȂ�B�s�ɂ��ƁA������1�l�����ω��l�ɂ�������\���u�����Đ��Y���v�͎嗬�����18�������B�����_�ŁA���@���̈Ⴂ�͊m�F����Ă��Ȃ��Ƃ����B
|
���I�~�N�������̈���u�a�`�D2�v�ɐ_�˂�2�l�����@���Ɍ��ł͏��@1/28
�V�^�R���i�E�C���X���߂���A1��28���A�_�ˎs�͏]���̃I�~�N���������������͂������I�~�N�������̈���u�a�`�D2�v��2�l�����������Ɣ��\���܂����B���ݍ����Ŏ嗬�̌n����芴���͂�18�������Ƃ����f�[�^������A���Ɍ����Ŋm�F�����̂͏��߂Ăł��B
�_�ˎs�v���s���u�R���i�E�C���X�Ƃ����̂͏�ɕψق�������B�ψق�������Ƃ������Ƃ́A���܂܂Œm���Ă��Ȃ����X�N����������Ƃ������Ƃ���X�͔F�����ׂ��ł͂Ȃ����v
�܂��A���Ɍ��ł͎���×{�҂�2���l�ɔ��钆�A28���Ɂu����×{�ғ����k�x���Z���^�[�v�̉^�p���n�܂�܂����B���Ǐ��y�ǂ̎���×{�҂���̑̒�����x���Ȃǂ̑��k�ɊŌ�t�炪24���ԑ̐��ʼn�����ق��A�K�v�ɉ����Ď�f�ł����Ë@�ւ��Љ��Ƃ������Ƃł��B �@ |
���|�\�E�̃R���i�����ҁA27���������� ���Ζ��߁Ehitomi�E�ԍ]�Ď��� �@1/28
���̂�27���̐V�^�R���i�E�C���X�����ҏ́A�����s����1��6538�l��3���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B�S���ł�7��8920�l�ƂȂ�A2���A����7���l���������ߋ��ő����X�V�B�|�\�E�ł��������������̊��������ꂽ�B
�|�l�ł́A�����R���r�E�W�����W�����̕����G��(38)�ƁA�����}�̃����[(37)�A���l�_2000�̈�(25)�B�̎��hitomi(46)��[�j���O���B�f22�̕��v�����A���R��ށA���t�@�N�g���[�̉͐����S�����������B
����ɁA���T�؍�46�ŏ��D�E���f���̔��Ζ���(29)�A�̕���o�D�̒����Ŋ�(56)�A���D�ł͉ԍ]�Ď��A�������ނ��z����B�e�E�Ŋ������L���葱���Ă���B
|
�������Ŋ�R���i�����@�ȁE�O�c���q�͔Z���ڐG�҂Ɂu�Y�������v�ƊE���R�@1/28
�̕���o�D�̒����Ŋ�(56)���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ�27���A���\���ꂽ�B
�Ŋ�͍���2�����瓌���E�̕�����̌����u��@���t��̕���v�ɏo�����Ă����B���|�ɂ��ƁA26�������̏I����A�̂ǂ̒ɂ݂Ȃǂ����������߂o�b�q�������A27���ɗz���Ɣ����B��H�y������27�������͑�������{�K�l�Y�����߂��B
���|�͓����A�����T�C�g�Łu���|�ɂ�钲���̂��ƁA�Z���ڐG�҂ɊY������҂͂���܂���ł����v�ȂǂƔ��\�������A����Ƀe���r�E���U�������B�ȂŃ^�����g�̎O�c���q(56)�͔Z���ڐG�҂ɓ�����Ȃ��̂��A�Ƃ����킯���B
�Ŋ�͍�N12���A3�x�ڂ̕s�ς���A�̂��ɖ{�l�������ے肵���B�����O�c�͎Ŋ�ɕ��S�����Ƃ����B
�u�����҂̓����l�͔Z���ڐG�҂Ɣ��肳��邱�Ƃ������B����ɓ�����Ȃ��̂ł���A�O�c����͎Ŋコ��ƕʋ����Ă����̂ł́H�ƌ����Ă����ł��v(���C�h�V���[�W��)
�Ŋ�̔Z���ڐG�҂̔��f�́A�ی����ł͂Ȃ��O�L�ʂ�u���|�ɂ�钲���v�������B�_�E���^�E���̏��{�l�u��25���A�c�C�b�^�[�Ɂu���͔Z���ڐG�҂ɂȂ�܂����B(�ی����̓p���N��ԂȂ̂ŁA���唻�f)�v�Ɠ��e�����悤�ɁA���ǂł͂Ȃ����唻�f�𐭕{���e�F����悤�ɂȂ����B
�u�O�c���ƒ���Ō��d�Ɋ���������Ă�����A�Ŋコ�����ɏW�����邽�߂Ƀz�e���h�����Ă����肷�邱�Ƃ��l�����܂��B�O�c�����27�����a�����B���̃^�C�~���O�ŎŊコ�V�^�R���i�Ɋ������Ă��܂��̂����̈��ʂ��c�v(��)
�܂��͂������×{���Ă��炢�����B
�@ |
���u�ً}���Ԑ錾�v�͏d�ǎҐ��ȂǐT�d�ɔ��f �V�^�R���i���� �@1/28
�V�^�R���i�̊����҂��}���������ŕa���g�p�����㏸���Ă��邱�Ƃɂ��āA�R�ےS����b�́A�u�ً}���Ԑ錾�v�o���邩�ǂ����́A�a���g�p�������ł͂Ȃ��A�d�ǎҐ��Ȃǂ��܂߂ĐT�d�ɔ��f����l���������܂����B
�V�^�R���i�̊����҂̋}���ɔ����A�����ł͕a���̎g�p�����㏸���Ă��āA27�����_��44.4���ƁA�s���u�ً}���Ԑ錾�v�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50���ɋ߂Â��Ă��܂��B
�R�ېV�^�R���i���S����b�͊t�c�̂��Ƃ̋L�҉�ŁA�����ɐ錾�o����K�v������ꂽ�̂ɑ��A�u�a���g�p������̗v�f�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�V�K�����Ґ�������ɔ����I�ɑ�����̂��ǂ�����A�d�ǎ҂̐����ǂ������Ă����̂����܂߂đ����I�ɔ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׁA�d�ǎҐ��Ȃǂ��܂߂ĐT�d�ɔ��f����l���������܂����B
���̂����ŁA�u�����s�Ɩ��ɃR�~���j�P�[�V���������A�����ǂ��R���g���[�����Ȃ���o�ώЉ�����p������Ƃ���2�̔��ɓ�����Ƃ��o�����X�����Ȃ���B�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
�܂��R�ۑ�b�́A27���a�̎R���̐m��m������d�b�Łu�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�̗v�����������Ă��邱�Ƃ�`����ꂽ�Ɩ��炩�ɂ��A�����ɗv��������ΓK�ɔ��f����l���������܂����B
|
���C�M���X �R���i�K�����قړP�p �I�~�N�������s�[�N�߂����@1/28
�C�M���X�ł́u�I�~�N�������v�ɂ�銴���̃s�[�N���߂����Ƃ݂��A�}�X�N�̒��p�`���Ȃǂ̋K�����قړP�p����Ă��܂��B����A���ׂ̊؍��͐V�K�����҂�4���A���ߋ��ő����X�V���Ă��܂��B
�C�M���X��27���̐V�K�����҂͂��悻10���l�ŁA�������{�̘A�����悻20���l�Ɣ�ׂ�ƌ����Ă��āA�s�[�N�͉߂����Ƃ݂��Ă��܂��B���N�`���̒lj��ڎ���i��ł��邱�ƂȂǂ���A�C�M���X���{��27���A������ʋ@�ւ�X�܂ł̃}�X�N���p�`���ȂǃI�~�N��������Ƃ��čē������Ă����K�����قړP�p���܂����B
�����h���s���u�����Ń}�X�N������K�v�͂���܂���B(�p�D�C���͂ǂ��ł����H)�ō��ł��v
�L�ҁu���傤����K�������ɂȂ�܂������A�X�����}�X�N�̒��p�����߂Ă���Ƃ��������܂��v
�����A�����h���s���ł́A�n���S��o�X�Ȃǂň��������}�X�N���p���`���t����Ƃ��Ă��܂��B
����A�؍��ł́A���傤���\���ꂽ�V�K�����҂�1��6000�l���A4���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B����4���ԂŔ{�ȏ�ɑ����Ă��āA�����g��Ɏ��~�߂�������܂���B�؍��ł͂������狌������5�A�x���n�܂�܂����A���x���́u�I�~�N�������g�U�̐������������v�Ƃ��āA�A�Ȃ��T����悤���߂ČĂт����Ă��܂��B
|
���J���{�W�A�@�I�~�N������������22�l���A�v675�l�Ɂ@1/28
�J���{�W�A��26���A22�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ����������B�S�����V���ȕψي��u�I�~�N�������v�̊����҂������B�I�~�N�������̗v�����҂�675�l�ƂȂ����B�N���[���E�^�C���Y(�d�q��)�������`�����B�����m�F���ꂽ�I�~�N�������̐V�K�����҂̂����s��������17�l�ŁA�v�ł�241�l�ƂȂ����B�V�^�R���i�̗v�����Ґ��͓������_��12��1,116�l�ɒB�����B
�����͂������Ƃ����I�~�N�������ւ̊����́A�J���{�W�A���܂ސ��E�Ŋg�債�Ă���B�����ی��Ȃ̃z�N�E�L���E�`�F���L�́A�u�I�~�N�������̏Ǐ�́A�]���́w�A���t�@���x��w�f���^���x�ɔ�ׂČy�ǂł���A�l�X�ւ̏d��ȉe���͊m�F����Ă��Ȃ��v�ƃR�����g�B�u�J���{�W�A�ł͊m���Ȋ������[�u���u�����Ă��邱�Ƃ���A�o�ς̍ĊJ��i�߂Ă����v�Əq�ׂ��B�t���E�Z����21����A�I�~�N�����������҂ɑ���u���`�����ɘa������j�\���Ă���B
|
 |


 �@
�@ |
���I�~�N�������̈���"BA.2"�u�X�e���X�E�I�~�N�����v �����_�ŕ������Ă��邱�Ɓ@1/29
�I�~�N�������̈���"BA.2"���f���}�[�N���͂��߂������̍��ōL�����Ă��܂��B���{�ł��s�������Ⴊ����Ă��荡��̊g�傪���O����܂��BBA.2�ɂ��Č����_�ŕ������Ă��邱�Ƃɂ��Ă܂Ƃ߂܂����B
�����ď������s�[�N�A�E�g���钆�A�f���}�[�N�ł͑������~�܂炸
���{������ɃI�~�N�������ɂ��V�^�R���i�̗��s���݂��Ă����C�M���X�A�A�����J�A�C�^���A�Ȃǂ̍��ł͊����Ґ��̓s�[�N�A�E�g�������ɓ]���Ă��܂��B�������A���̒��Ńf���}�[�N�͍��������҂����������Ă��܂��B1���̊����Ґ����l��100���l������7600�l���Ă���A����͓��{�ŗႦ���1��90���l�̊����҂��o�Ă���Ƃ������܂�����Ԃł��B�f���}�[�N�Ŋ����҂����������Ă��錴���̈�Ƃ��āA�I�~�N�������̈���uBA.2�v�̊g�傪�������Ă��܂��B
���I�~�N�������̈���uBA.2�v�Ƃ́H
���݁A�I�~�N������(B.1.1.529)�́A���̉��ʌn���Ƃ���
BA.1(B.1.1.529.1)
BA.1.1(B.1.1.529.1.1)
BA.2(B.1.1.529.2)
BA.3(B.1.1.529.3)
��4�̈���ɕ�����Ă��܂��B
���̂����A���{���܂ߐ��E�Ŏ嗬�ɂȂ��Ă���̂�BA.1�ł��B�������ABA.2�Ƃ�����������E�e���ŕ������Ă��Ă���A���{�ł�����܂łɌ��u�ł��ł�BA.2�͕���Ă��܂��B�܂�1��28���ɂ͓��{�����ł��s�������Ⴊ����܂������A�����_�ł͑S�������N�̂Ȃ��s��������͕���Ă��܂���B�f���}�[�N�ł́A2021�N12������BA.1���g�債�Ă��܂������A�ォ��N�����Ă���BA.2�����݂͂�����čL����A�����_�ŃQ�m����͂��s���Ă���E�C���X�̂���60�����߂Ă��܂��B�܂��f���}�[�N�ȊO�ɂ��A�t�B���s���A�C���h�A�C�M���X�Ȃǂ�BA.2�̊����҂̐�߂銄�����������Ă��Ă��܂��B
���u�X�e���X�E�I�~�N�����v�̈Ӗ��́H
���̃I�~�N��������BA.2�͊C�O�̕ł́u�X�e���X�E�I�~�N����(Stealth Omicron)�v�Ƃ��Ă�Ă���悤�ł��B�X�e���X�͢��������������s����Ƃ����Ӗ�������A�R�p�@�Ȃǂ̋@�̂�G�̃��[�_�[�ɕߑ�����ɂ�������Z�p�Ȃǂ��w���܂��BBA.1�Ȃǂ̃I�~�N�������ɂ́udel69/70�v�Ƃ����X�p�C�N�`���̌����ӏ�������A�����̃X�p�C�N�`���̌����ӏ���PCR�����Ō��o����uS gene target failure (SGTF)�v�Ƃ������@�ŃI�~�N�����������o������@���s���Ă��鍑�������Ȃ��Ă��܂����ABA.2�ł͂��́udel69/70�v�Ƃ��������ӏ����Ȃ�����SGTF�Ō��o����܂���B���̂��߁u�I�~�N�������Ȃ̂�SGTF�Ō��o����Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ŃX�e���X�E�I�~�N�����ƌĂ�Ă��܂��B�������A���{�ł̓f���^���ɓ����I�ȁuL452R�v�Ƃ����ψق��Ȃ����Ƃ������ăI�~�N�������̊ȈՌ��o�@�Ƃ��Ă��邱�Ƃ���A���{�ł�BA.2��BA.1�Ɠ��l�̕��@�Ō��o����܂��B���̈Ӗ��œ��{�ł̓X�e���X�ł͂���܂��A���̌��o�@�ł�BA.1��BA.2����ʂł��Ȃ����Ƃ���A�ނ��덡���BA.1��BA.2����ʂ��邽�߂�SGTF�Ȃǂ̕��@�ŊȈՌ��o�����ׂ���������܂���B
��BA.2�̊����͂́H
�C�M���X����̕ł́A�����Ґ��̑�����(growth rate)��BA.1�����������Ƃ�����Ă��܂��B�܂��A�Ƒ������ǂ����ꍇ�ɂ��̔Z���ڐG�҂��������銄����BA.2�̕�������ȊO�̃I�~�N������������������(13.4% vs 10.3%)�Ƃ̂��Ƃł��B���s��̐��Y���搶��̒����ł́ABA.2�̎����Đ��Y���̓I�~�N����BA.1���̂������18%�����Ɣ��\����Ă��܂��B�f���}�[�N�ł̊g�������ƁA���㑼�̍��ł�BA.2���L�����Ă����\��������܂��B
��BA.2�̏d�Ǔx�́H
�����_�ł�BA.2������܂ł̃I�~�N�������Ɣ�ׂďd�lj����₷���̂��ɂ��ď\���ȏ��͂���܂���B�f���}�[�N�̍�������������(Statens Serum Institut)����̔��\�ł́A�����_�ł�BA.1��BA.2�ł̓��@���ɍ��͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B
��BA.2�ɑ��郏�N�`���̌��ʂ́H
�I�~�N�������ł́A�]���̐V�^�R���i�E�C���X�Ɣ�r���ĐV�^�R���i���N�`���ɂ�銴���\�h���ʂ��傫�������Ă��邱�Ƃ������ł��BBA.2�ɑ��郏�N�`���̌��ʂ́A�����_�ł͏Ǘᐔ�����Ȃ����ߗ\���I�ȃf�[�^�݂̂����\����Ă��܂����A���Ǘ\�h���ʂ�
�E2��ڎ킩�甼�N�ȏ�o�߂������_�F13%(BA.1�ł�9%)
�E3��ڎ킩��2�T��F70%(BA.1�ł�63%)
�ł������Ƃ̂��Ƃł��B�傫��BA.1�ƃ��N�`�����ʂ��قȂ邱�Ƃ͂Ȃ������ł��B
��BA.2�ɑ��鍡��̑�́H
������{�����ł�BA.2���g�債�Ă����\��������܂��B���̓��{�����ł̈�ʓI�ȃI�~�N�������̊ȈՌ��o���@�ł�BA.1��BA.2�Ƃ̋�ʂ����Ȃ����Ƃ���ASGTF�Ȃǂ̕ʂ̕��@�ŋ�ʂ���K�v������ł��傤�B�{���́A����BA.2�����o���ꂽ�����҂̎��͂̔Z���ڐG�҂���肵�A��������Ɗu�������邱�ƂŊg��̃X�s�[�h��}����Ƃ����s���܂����A���݂̕ی����Ɩ��̕N������͓���ƍl�����܂��B��������l�ЂƂ�ɂł��銴����͕ς��܂���B���3�̖��������A�}�X�N�𒅗p����Ȃǂ̊����������܂Œʂ肵������Ƒ����邱�Ƃ��d�v�ł��B���Ƀ}�X�N���O������Ԃł̉�b���������X�N�ƂȂ�₷�����Ƃ���A��H��E��̒��H���Ȃǂِ͖H�E�}�X�N��H��O�ꂷ��悤�ɂ��܂��傤�B�܂��A����҂��b�����̂�����ɂ����Ă͐V�^�R���i���N�`���̃u�[�X�^�[�ڎ�ŏd�lj��\�h���ʂ��Ăэ��߂邱�Ƃ��d�v�ł��B�������A���N�`�������Ŋ�����h���邱�Ƃ͍���ł���A���N�`���ڎ�������܂Œʂ�̊�����͑�����悤�ɂ��܂��傤�B�@ |
���I�~�N�������s�[�N���H�@�����͋����ʌn���x���A�C�O�ł͍Ċg����@1/29
���ٓI�ȑ����Ŋ����g�傷��V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������ɂ�闬�s�̃s�[�N�͂����|�B�S���ɐ�삯�Ċ������i���ꌧ�ł́A�V�K�����҂̐L�т������ɓ]���A�����̒�������������B�S���œ��l�̌X�������ǂ�\�����������A�V���ɕʌn���̃I�~�N���������L��������������A���Ƃ͌x�����Ăъ|����B
�u����ł̓s�[�N���z���������������Ă��Ă���v�@26����A�����J���Ȃɑ������������Ƒg�D�̉�B�����̘e�c�����E���������nj��������͏I����̋L�҉�ŁA���ꌧ�̏��������͂����B
��̎����≫�ꌧ�Ȃǂɂ��ƁA�����ł�3���ȍ~�A�I�~�N�������ւ̒u�������Ŋ������}�g�債���B6���ɂ͐V�K�����҂�981�l�ƂȂ�A�ߋ��ő���������N8��25����809�l���X�V�B���̌�������������B�l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A13���܂ł�1�T�ԂŖ�654�l�܂ő�������A600�l��Ő��ځB18���܂ł�1�T�ԂŖ�679�l�ɒB���A�������s�[�N�Ɉ�]���ĉ�����n�߂��B25���܂ł�1�T�Ԃ͖�547�l�őO�T����0�E8�{�ƂȂ�A�S���ŗB��A�����X�����݂�ꂽ�B���Ƃ́A���H�X�̎��Z�c�Ƃ�l���̒��~�Ȃǂ̑����t�������Ƃ݂�B�����A�y���Ǐ�̊����҂��������Ă��Ȃ��P�[�X��A�s�������̕N��(�Ђ��ς�)�Ŋ����҂̕��x��Ă���\��������B�u�s�[�N�A�E�g���ǂ����A�܂�������Ȃ��v�B���ꌧ�̒S���҂͐T�d�ɘb���B
�u������A����2�T�ԑO��Ńs�[�N����������\��������v�B���{�ɑ������������Ƃ̔��g�Ύ���L�u��21���Ɍ��\�����ł́A2����{�ɂ��I�~�N�������ɂ��u��6�g�v���s�[�N���}����\�����������Ă����B�O���ɂ���̂́A�I�~�N�������̓������B�I�~�N�������͊��������̐l�ɂ���܂ł̓����������u���㎞�ԁv����2���ŁA��5�g�������炵���f���^���̖�5�����������ȉ��Ƃ����B���Ƃ̈�l�́u���㎞�Ԃ��Z���Ɨ��s�s�[�N�͑������邪�A�����҂�����ۂ��X�s�[�h�������A���s���Ԃ͒Z���Ȃ�v�Ƃ݂�B���ہA���E�ŏ��߂ăI�~�N�������𐢊E�ی��@��(WHO)�ɕ�����A�t���J�ł́A�����҂̊m�F����1�J����Ńs�[�N���z���A���s�͎����Ɍ��������B�p���ł��A��N11�����{��1��ڔ��\����1�J���]��œ����z���Ă���B�����Ƃ��A�����g��̃X�s�[�h�͓݂������A�����ł͊��������������B���g����28���̏O�@�\�Z�ψ���Łu����1�`2�T�ԂŃs�[�N�A�E�g���邩�ǂ����\�f�������Ȃ��v�Ƌ��������B
�V���Ȍ��O�ޗ��ƂȂ�̂��A�ʌn���̃I�~�N���������B�����ōL�������嗬�n���uBA�E1�v�ɑ��A�ψىӏ��̈قȂ�uBA�E2�v�ƌĂ��E�C���X�ŁA�����͂�18�������Ƃ������͂�����B�����ł͏��Ȃ��Ƃ�27�Ⴊ���������B�u���O�͓��������A�Ɖu�@�\�ɉe���������ȃA�~�m�_�̔z�傫���قȂ�BBA�E2�ɒu�������A��7�g�������N�����\��������v�B���s��̋�����������(�E�C���X�w)�͌x������B�f���}�[�N��C�X���G���ł́uBA�E1�v����uBA�E2�v�ɒu�������A�����X���������������Ċg�債�����Ƃ�����Ă���B���������́u�ʌn���ł���{�I�Ȋ�����͓����B�}�X�N���p��3���̉����O�ꂵ�Ăق����v�ƌ�����B
|
���I�~�N�����u�����������v2���̒Z���@�}�g��̔w�i�@1/29
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�̋}�g��̔w�i�Ƃ��āA�����̃T�C�N���������Ȃ����\�����o�Ă����B�p���̕��͂ł́A�����҂��瑼�̐l�ɂ���܂ł́u���㎞�ԁv���Z���Ȃ�2���O��ɂȂ����Ƃ����B��̌��ʂ��\���܂ł̊��Ԃ��Z���Ȃ�B�ڐG�@������炷�����₷�����ʁA�����҂�ڐG�҂̒ǐՁE�u���Ƃ������ǂ�������`�̑�͌��ʂ��o�ɂ������ꂪ����B
���㎞�ԂƂ́A���������l���瑼�̐l�ɂ���܂�(�ꎟ������������܂�)�̎��Ԃ̂��Ƃ��B���㎞�Ԃ��Z���Ɗ������A������T�C�N�������܂�A�}���ɗ��s���L����B�I�~�N�����^�͊������甭�ǂ܂ł́u�������ԁv����3���ŁA�f���^�^�̖�5�����Z���B�V�^�R���i�E�C���X�͔��ǂ̑O���瑼�l�ɂ��邽�߁A������̏�ł͐��㎞�Ԃ����ڂ����B
�p���̃f�[�^�͂��������̍��ǑO�̌����ŁA�I�~�N�����^�̐��㎞�Ԃ��Z���\�����o�Ă����B�u�f���^�^�͕���4.6���A�I�~�N�����^��2.1���v�u�f���^�^�͕���2.5�`4���A�I�~�N�����^��1.5�`3.2���v�Ɛ���l�͏����قȂ邪�A������̕��͂ł��f���^�^���Z���B
���㎞�Ԃ�������Ԃɂ́A�E�C���X�̑��B����ꏊ��X�s�[�h�Ȃǂ��e������B�ψقɂ���ăI�~�N�����^�͂̂ǂő����₷���Ȃ����ƍl�����Ă���B�������������̕ω��ŁA�����̋N����₷���Ȃǂ��ς�����悤���B
���㎞�Ԃ́A������̍��{�ƂȂ镪�͂ɉe������B���ۂ̎Љ�ŁA1�l�̊����҂��畽�ω��l�ɂ����Ă��邩�������u�����Đ��Y���v�͊����Ґ��̐��ڂƐ��㎞�Ԃ̐��l�����ƂɌv�Z���Ă���B����܂ł̕��͂ł̓I�~�N�����^�̐��㎞�Ԃ̓f���^�^�Ɠ������Ɖ��肵�Ă������A���㎞�Ԃ��Z���Ǝ����Đ��Y���̐���l�͏������Ȃ�B
�I�~�N�����^�̗��s���n�܂��������A�����Đ��Y���̓f���^�^��3�`4�{���x�Ƃ����Ă����B���㎞�Ԃ̒Z���܂��Čv�Z�������Ɖp���ł�2�{�O��ɂȂ�Ƃ����B�k�C����w�����̈ɓ����l����Ƌ��s��w�����̐��Y�������ɂ��f���}�[�N�̕��͂ł͖�1.6�{�Ɛ��肵���B
�I�~�N�����^�͖Ɖu�����蔲����u�Ɖu�����v�̐����������B���N�`���������Ȃ����ƂƁA�����T�C�N���̑����̗������e�����A�}�g�債�Ă���悤���B
�Ɖu���Ȃ��W�c�ł̃E�C���X�̖{���I�Ȋ�����(��{�Đ��Y��)���ׂ�ƁA�I�~�N�����^�̓f���^�^��菬�����\��������Ƃ̌������o�Ă����B�V�^�R���i�̕ψٌ^�̓A���t�@�^�A�f���^�^�ƍĐ��Y�����傫���Ȃ�A������1�l���炤��l����������`�Ŋg�債���B���㎞�Ԃ̒Z�k�͏��߂Ẵp�^�[�����B
��{�Đ��Y���͏W�c�Ɖu�̒B�����₷���ɂ������A��������Η��s���������₷���B��A�t���J��p���ȂǗ��s�̃s�[�N���������߂����Ƃ݂���n�悪���邱�Ƃ́A��{�Đ��Y���̏������Ɛ��㎞�Ԃ̒Z���f���Ă���\��������B
���㎞�Ԃ̕ω��͊�����̌��ʂɉe������B�����̃T�C�N����������A��̌��ʂ��\���̂������Ȃ邩�炾�B�p�����h����w�q���M�ш�w��w�@�q���������̉���������́u���㎞�Ԃ��Z����A�����҂������X���ɂȂ����Ƃ��Ɍ���̂������B�t�ɁA���s���g�傷��ǖʂő��摗�肵���ꍇ�̉e���͑傫���Ȃ�v�Ƙb���B
�܂h�~���d�_�[�u�̂悤�ȑ�ŐڐG�@������炷���Ƃ��ł���A���ʂ͂���܂ł����Z���Ԃŕ\���\��������B����A�T�C�N���������Ȃ������Ƃœ���Ȃ�������B��������́u�����҂�ڐG�҂̒ǐՁE�u�����Ԃɍ���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��l������v�Ǝw�E����B�u������O�ɑ��̐l�ւƊ������L����P�[�X�������Ă��܂��ƁA�g��j�~�̌��ʂɂ����Ȃ�B
�l�̃��x���ł́A���N�`���ŃI�~�N�����^�̊�����h���ɂ������A��{�I�Ȋ�����̈Ӌ`�͑傫���B�}�X�N�̒��p�⊷�C��O�ꂵ�A�u���v������A���ׂ̏Ǐ�ȂǏ����ł��̒���������ΊO�o���T���邱�Ƃ����������d�v�ƂȂ�B
��
��{�Đ��Y���@/�@���銴���ǂɑ���Ɖu�������Ȃ��W�c�̒��ŁA1�l�̊����҂��畽�ω��l�ɂ��邩�������A�����ݏo���{���I�Ȋ�����(�`�d��)��\���B�Ɖu�����l�������A�}�X�N���p�Ȃǂ̑��������ۂ̏W�c�̒��ł́A�����̕��ϐl���͎����Đ��Y���ƌĂԁB�Ɖu�����l�����ȏ�̊����ɂȂ�ƁA�W�c�Ɖu�ɂ���Ċ����̘A�����N���ɂ����Ȃ�A���s����������B�W�c�Ɖu�ɕK�v�ȃ��N�`���ڎ헦�̖ڈ��́A��{�Đ��Y������v�Z�ł���B��{�Đ��Y�����u3�v�Ȃ�ΐڎ헦��67%�A�u5�v�Ȃ��80%�ƂȂ�B
|
�������D�w���O����50�{�Ɂc�u��p�a���v���܂�A����×{�������@1/29
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̗��s�ɔ����A�D�w�̊����҂��}�����Ă���B�����s����ÊW�җp�ɂ܂Ƃ߂�����l�ɂ��ƁA1����20���܂ł�261�l�ƁA���łɑO���̖�50�{�ɏ��B�����D�w�p�̕a�������܂�a�@���o�Ă���A����×{�������A�}�ώ��ɓ��@�ł��Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ����B
�����D�w��������Ë@�ւ́A�R���i�f�Âɉ����A�D�P�E�o�Y�ւ̑Ή����K�v�Ȃ��ߌ�����B��t���ō�N8���A�����D�w�����@�ł����Ɏ���ő��Y���A�V���������S���������A�e�n�Ő�p�a�������铮�����L�������B
�^���a�@(�����s�n�c��)�ł́A28�����_��9�l�����@�B�����D�w��q�ǂ���p�̌v7���͖��܂�A�D�w�͈�ʂ̃R���i�a���ɂ������Ă���B�O�T�܂ł́A���M��̂ǂ̒ɂ݂̌y�ǎ҂������������A���T��2�l�ɔx�����m�F���ꂽ�B�R�c���b�E�Y�w�l�ȕ����́A�u�����D�w�̓��@�v���������Ă���A�������������邩�S�z���v�Ɗ�@�����点��B
���a�@�ɓ��@���̔D�P8�����̉�Ј�(20)�́A�v�����������������B���g�̃R���i�̏Ǐ�͐����Ōy���Ȃ������A�u���Y������ƕs���������B���@�ł��Ă悩�����v�Ƙb���B
��t��a�@(��t�s)�ł́A���������D�Y�w�p�Ɋm�ۂ���2���́A�������{����قڋ��Ƃ��Ȃ��B��t���̂܂Ƃ߂ł́A�����̊����D�w�́A��N10�`12���̓[�����������A1����20�����݂Ŗ�50�l�ƂȂ�A����×{�������B
�D�w����������ƁA�Ǐd���Ȃ�₷���Ƃ�����A���Y���X�N�����܂�Ƃ̌���������B�܂��A�D�P���َ͑��̂��߂Ɍ����_�f�Z�x��95���ȏオ�K�v�Ƃ����B
���{�Y�ȕw�l�Ȋw��Ȃǂ́A����ŗ×{����D�w�Ɍ����āA�̒����Ǘ�����ۂ̖ڈ����܂Ƃ߂Ă���B
�q1�r1���Ԃ�2��ȏ�̑��ꂵ����������q2�r�S������1���Ԃ�110��ȏ�q3�r���Î��̌����_�f�Z�x��93�`94������1���Ԉȓ��ɉ��Ȃ��\�\�Ȃǂ̏Ǐ���A��������̎Y�w�l�Ȉォ�ی����ɘA������B
���ꂵ���ŒZ�����t���b���Ȃ��Ȃ�����A�����_�f�Z�x��92���ȉ��ɂȂ����肵�����́A�~�}�Ԃ��ĂԁB
����͐l�E���{��ȑ命���i�R�a�@���́u����A����×{����D�w�͑����邾�낤�B�s�����A���������D�w���m���ɔc�����A�Y�w�l�Ȃ̂��������ƘA�g���āA�}�ς��������Ȃ����Ƃ��d�v���v�Ƙb���Ă���B
|
���S���̊�����2���A��8���l������@16���{���ʼnߋ��ő��@1/29
FNN�̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA�ߌ�5�������_�ŁA�S���ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă���̂��m�F���ꂽ�̂́A8���l112�l�ɂ̂ڂ����B1���̑S���̊����Ґ��Ƃ��āA2���A����8���l���������B�S���̊����Ґ��́A25��(��)��6��2589�l�A26��(��)��7��1613�l�A27��(��)��7��8911�l�A28��(��)��8��1808�l�ŁA4���A���ʼnߋ��ő����X�V���Ă����B
�����s�ł́A1��7433�l�̊������m�F���ꂽ�B2��������1��7000�l��ŁA�ߋ�2�Ԗڂ̑����ƂȂ����B���{�́A�ߋ��ő���1��383�l�ŁA2��������1���l���������B
���̂ق��ɁA1���̊����Ґ����ߋ��ő��ƂȂ����̂́A�_�ސ쌧��8686�l�A���m����5613�l�A��������4949�l�A���Ɍ���4634�l�A�k�C����3002�l�A���s�{��2754�l�A�Q�n����1099�l�A���R����877�l�A�Ȗ،���708�l�A�{�錧��554�l�A�啪����448�l�A��������443�l�A��������163�l�A��茧��156�l�ȂǁB16���{���ʼnߋ��ő����X�V�����B�S���ŁA����܂łɁA�����҂̂���33�l�̎��S������Ă���B
|
���R���i����8��4935�l�@������5���A���ő��@1/29
�����ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�29���A8��4935�l�ƂȂ�A5���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B����͓���1��7433�l�A���1��383�l�A�_�ސ�8699�l�ȂǁB
�嗬�ƂȂ����I�~�N�������͊������������A2�T�ԑO�̓����j���ɔ�ׁA�V�K�����҂�3�{�ȏ�ɑ����B�S���̎���×{�Ґ����ߋ��ő���26��3992�l(26���ߑO0�����_)�ɏ��A����܂ōő����������s�u��5�g�v�̃s�[�N����2�{�ƂȂ��Ă���B���҂͑��ƕ��ɂŊe6�l�A�����Ɛ_�ސ�ł��ꂼ��3�l�A�����ƌQ�n�A���m�A�L���A�R���A�����e2�l�Ȃnjv39�l�̕��������B
|
����t����1�l���S�A3365�l�����@��t�s�A�D���s�͉ߋ��ő��@1/29
��t������29���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������1�l�̎��S�ƁA3365�l�̊������V���ɔ��������B����̊����Ґ���3��l����̂�3���A���ŁA�ߋ�3�Ԗڂ̑����B�O�T22��(2296�l)�����1�E5�{�ɑ������B�V�K�N���X�^�[(�����ҏW�c)�͕a�@�A����Ҏ{�݂Ōv4���m�F���ꂽ�B
����1934�l�̊����\�B�V���Ɋm�F���ꂽ�N���X�^�[�́A���Y�s�́u��Ö@�l�r�g�h�n�c�`�@���c�a�@�v�ň�Ï]����8�l�Ɗ���7�l�̌v15�l�A�����s�̃O���[�v�z�[���u�I�X�₿��v�ŐE��6�l�Ɨ��p��5�l�̌v11�l�A���ˎs�̓��z�[���u�~���U�V���ˁv�ŐE��3�l�Ɨ��p��5�l�̌v8�l�A���s�̓��ʗ{��V�l�z�[���u�����˃q���Y�v�ŐE��2�l�Ɨ��p��11�l�̌v13�l�B
��t�s�́A80�㏗�������s���̎��S�ƁA�ߋ��ő��ƂȂ�793�l�̊����\�����B����܂ł̍ő���28�����\��708�l�������B���S���������͕ʂ̎����Ŏs����Ë@�ւɓ��@���Ă���A���M�Ȃǂ̏Ǐo�����ߌ������ėz���������B�_�f���^�Ȃǂ̎��Â��Ă����B�����͔s���ǂŁA���N�`����3��ڎ�ς݂������B
�D���s�́A�ߋ��ő���487�l�̊����\�B����܂ł̍ő���25�����\��445�l�������B2�l�̏Ǐ��d���A�_�f���^���Ă���B�N���X�^�[���������Ă����Z�R���f�B�b�N�a�@�ł́A�V���ɓ��@����5�l�ƈ�Ï]����6�l�̊������������A�����҂͌v110�l�ɑ������B���t���L���V�l�z�[���u�j�`�C�z�[�����D���v�ł́A������1�l�̊������������Čv13�l�A���V�l�ی��{�݁u�Ȃ݂̋��v�ł͐E���Ɠ����Ҋe1�l�̊������������Čv11�l�̃N���X�^�[�ƂȂ����B
���s�́A151�l�̊����\�����B���̂����A4�l�̏Ǐ��d���B
�����a��ۂɂ��ƁA�����̎���×{�҂�28�����_��1��3992�l�ɏ��A���Ă̑�5�g�̃s�[�N��������25������4���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
�܂��A27����28�����\���̊����҂����ꂼ��1�l��艺����ꂽ�B�����̈���̊����Ґ��̍ő���27����3801�l�ƂȂ����B
29���Ɍ����Ŋ��������������l�̋��Z�n�́A��t�s759�l�A�D���s498�l�A�s��s381�l�A���s164�l�A�s���s152�l�A�Y���s140�l�A���q�s139�l�A�����s107�l�A�l�X���s96�l�A��c�s80�l�A�؍X�Îs65�l�A�K�u��s59�l�A�s58�l�A����s45�l�A���c�s43�l�A���P�Y�s42�l�A�N�Îs41�l�A�Ό��s38�l�A�R���s37�l�A���X�s�Ɠ����s���e36�l�A���P�J�s28�l�A��Ԕ����s22�l�A���ˎs�A�x���s�A�َR�s���e20�l�A����s19�l�A�x�Îs18�l�A��\�㗢��16�l�A���s�A�����ݎs�A���Y�s���e13�l�A���X�䒬12�l�A���q�s�Ɗ���s���e11�l�A�h��10�l�A���Ò�9�l�A�x���s�Ɖ��Ō������e8�l�A��[���s6�l�A���R�s�A�䑷�q�s�A���쒬�A���q�����e5�l�A�命�쒬�A��{���A���������e4�l�A������3�l�A�ŎR���A�_�蒬�A��h�����e2�l�A�������A���쒬�A�r���e1�l�A���O27�l�A�C�O1�l�������B
|
�������s �R���i �V����1��7433�l�����m�F ��T�y�j���̖�1.6�{ �@1/29
�������}�g�債�Ă��铌���s���ł́A29���A�ߋ��ő�������28���Ɏ���1��7433�l�̊������m�F����܂����B����×{���̐l��28������3000�l�ȏ㑝����6��4000�l���܂�ƂȂ�܂����B
�����s��29���A�u10�Ζ����v����u100�Έȏ�v��1��7433�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ�V���Ɋm�F�����Ɣ��\���܂����B�ߋ��ő�������28���Ɏ�����2�Ԗڂɑ����Ȃ�܂����B�܂��A1�T�ԑO��22���̂��悻1.6�{�ł��B29���܂ł�7���Ԃ̕��ς�1��3781.7�l�ŁA�O�̏T�̂��悻2�{�ƂȂ�܂����B
50�ォ��70��ƁA90�オ��������ߋ��ő��ƂȂ����ق��A65�Έȏ���S�̂�7.4���ɂ�����1296�l�Ƃ���܂łōł������Ȃ�܂����B�܂��A����×{���̐l��28������3000�l���܂葝����6��4391�l�ɏ��A���������Ă��܂��B��Ë@�ւɓ��@���邩�z�e���⎩��ŗ×{���邩�����̐l��4��3453�l�ŁA�ߋ��ő��ł��B
�����o�H���������Ă���̂�5884�l�ŁA���̂����u�ƒ���v��3674�l�ƍł������A�S�̂�62.4�����߂Ă��܂��B�����Łu�{�ݓ��v��19.5���ɂ�����1147�l�ŁA���̂����A�ۈ牀�Ɨc�t���ł��킹��358�l�A���w�Z��308�l�A����Ҏ{�݂�203�l�A��Ë@�ւ�79�l�̊��������ꂼ��m�F����܂����B�s�̊�ŏW�v����29�����_�̏d�ǂ̊��҂�28�����2�l������22�l�ł����B���̂ق��A�s�́A�������m�F���ꂽ60���70��A�����80��́A�j�����킹��3�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s���̐V�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p���́A29�����_��48.0���ɂȂ�܂����B28�����炳���1.9�|�C���g�㏸���A������50���ɔ����Ă��܂��B����A�d�NJ��җp�̕a���g�p���́A4.3���ł��B
|
�������s�ŐV����1��7433�l�̊������m�F �d�ǎ�22�l ���S3�l �@1/29
29���A�����s���m�F�����V�^�R���i�̐V�K�����Ґ���1��7433�l�������B�a���̎g�p����48���ŁA�ً}���Ԑ錾�̗v������������ڈ���50���ɋ߂Â��Ă���B�������m�F���ꂽ�̂́A10�Ζ�������100�Έȏ��1��7433�l�B43���A���őO�̏T�̓����j�����������B
����7���Ԃ�1��������̕��ς�1��3782�l�ŁA�O�̏T�Ɣ�ׂ�192.9���������B�N��ʂł́A20�オ3893�l�ōł������A������30�オ3249�l�B65�Έȏ�̍���҂�1296�l�������B���Ȃ��Ƃ�8146�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��āA4409�l�͈�x���ڎ킵�Ă��Ȃ��B�d�NJ��҂̐��͑O�̓�����2�l������22�l�ƂȂ��Ă���B
�V�^�R���i���җp�̕a���̎g�p���́A�O�̓�����1.9�|�C���g�オ����48���ƂȂ����B�܂��A60�ォ��80��̒j��3�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
|
�����{ �V�^�R���i �V����1��383�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/29
���{29���A�V����1��383�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�����1���l�����̂�2���A���ŁA����܂łōł������Ȃ�܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��31��6014�l�ƂȂ�܂����B�܂��A6�l�̎��S�����\����A���{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l��3111�l�ɂȂ�܂����B
|
�������������V����483�l�@�N���X�^�[���@1/29
�����������ł�29���A�V�^�R���i�̊����҂��V����483�l���\����܂����B
�������m�F���ꂽ�̂́A�����\��246�l�A�������s���\��237�l�̂��킹��483�l�ł��B�����̊����҂͗v��1��5506�l�ƂȂ�܂����B 237�l�̓���́A�s����230�l�ƁA���ǎs��3�l�A�����s�A�o���s�A���V�\�s�A���v������1�l���ł��B
�Ȃ��A���͐V���ȃN���X�^�[���m�F���ꂽ�Ƃ��āA���̂��ƌߌ�6�������߂ǂɉ���J���\��ł��B
�����̊����g��x����͌��݁A���x��2�ł��B�w�W��27�����_�ŁA�l��10���l������̐V�K�����Ґ���188�D45�l�A�×{�Ґ���216�l�A���߈�T�Ԃ̂o�b�q�z������25���ŁA����������x��3�����ł��B
������564����R���i�a���̎g�p���́A27�����_��48�D8���ƂȂ�A�O�̓����5�|�C���g�������܂����B ��Ì����Ƃ̕a���g�p���́A33���̊̑���78�D79���ƍł������A������9���̑]����66�D67���A31���̏o����54�D84���A79���̈��ǁE�ɍ���51�D9���A38���̓�F��50���A30���̐�F��46�D67���A231���̎�������46�D32���A80���̉�����42�D5���A33���̌F�т�33�D33���ł��B
����ҋ@�҂�27�����_��2540�l�ŁA�O�̓����325�l�����܂����B ��Ì����Ƃł́A��������1542�l�A���ǁE�ɍ���530�l�A��F��135�l�A��F�A������94�l�A�̑���92�l�A�]����42�l�A�o����11�l�A�F�т�0�l�ł��B
|
������R���i979�l�@2�T�ԂŔ����@�ČR�͍��~�܂�225�l�@1/29
���ꌧ��29���A�V����979�l(�O��1073�l)�̐V�^�R���i�E�C���X�z�����m�F�����Ɣ��\�����B5���Ԃ��1000�l����������B2�T�O�̓y�j���ɂ͉ߋ��ō���1829�l�������������A������قڔ����A�O�T�y�j����1313�l���300�l�ȏ㌸�����B�v��8��1510�l�B
�݉��ČR�W��225�l�̐V�K�z���҂��m�F�����ƕ��������B��T�A��X�T�̓y�j����200�l��B�ČR�W�ґS�̂̐l���͉��ꌧ���̖�30����1�ɂ�����5���l��Ƃ݂��A�ˑR�Ƃ��č��~�܂��Ԃ������Ă���B�v��9505�l�B
�O�����_�ł̒���1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�z���Ґ���503.93�őS��3�ʁB���27����1�J���Ԃ�Ƀ��[�X�g��E���A3���A����3�ʂƂȂ������A�ˑR�Ƃ��ċɂ߂č������l�ɂȂ��Ă���B1�ʂ͓����s��652.05�A2 �ʂ͑��{��639.70�B
�a���g�p����70.8��(�O��70.0��)�ƁA�d�ǎҗp�̕a���g�p����41.1��(�O��40.4��)�Ƃ킸���Ȃ��瑝�����Ă���B
���ɂ��ƁA29�����_�œ��@�������̊��҂�1452�l(�O��1385�l)�A�h���×{�{�ݗ×{����491�l(��481�l)�A����×{����7036�l(��7264�l)�A�×{���̊��҂̍��v��9447�l(��9586�l)��1���l����������B���@����453�l(�O��448�l)�A�����d�ǂ�7�l(��8�l)�������B |
���I�~�N�������uBA.2�v �p�g���N�`���̔��Ǘ\�h���� �Ⴂ�Ȃ��h�@1/29
�C�M���X�̕ی����ǂ́A�V�^�R���i�̕ψكE�C���X�A�I�~�N�������̂����uBA.2�v�ƌĂ�錻�ݎ嗬�ƂȂ��Ă�����̂Ƃ͈قȂ�n���̃E�C���X�ɂ��āA���N�`����ڎ킵���ꍇ�̔��ǂ�\�h������ʂ́A2�̃E�C���X�ɑ傫�ȈႢ�͂Ȃ��Ƃ��鏉���̕��͂𖾂炩�ɂ��܂����B�I�~�N�������̂����A���݁A���s�̎嗬�ƂȂ��Ă���uBA.1�v�Ƃ͈قȂ�n���́uBA.2�v�ƌĂ��E�C���X�́A�f���}�[�N�ȂǂŊ������g�債�A�C�M���X�ł��u�������̕ψكE�C���X�v�ƈʒu�Â����Ă��܂��B
�C�M���X�̕ی����ǂ́A28���A�����h���̂���C���O�����h�ł́A����24���̎��_�ŁuBA.2�v��1072���m�F����Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B�����_�ł́uBA.2�v����߂銄���͏��Ȃ��Ƃ������Ƃł����A�����̃f�[�^�ł́uBA.1�v�����A�����͂͂킸���ɍ����Ƃ݂���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�����̕��͂ł́A���N�`���̒lj��ڎ���s���Ă���2�T�Ԍ�̎��_�ŁA���ǂ�\�h������ʂ́uBA.1�v��63���uBA.2�v��70���ő傫�ȈႢ�͊m�F�ł��Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B�d�lj��Ɋւ���f�[�^�́A���̂Ƃ���͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����A�ی����ǂ́A���������uBA.2�v�Ɋւ��镪�͂𑱂��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
|
���I�~�N�����h���^�u�a�`�D2�v�A�����͍������Z���p���ǁ@1/29
�p���ی����S�ۏᒡ(�t�j�g�r�`)��28���A�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������h���^�u�a�`�D2�v�ɂ��āA�I�~�N�����]���^�́u�a�`�D1�v���������͂������\��������Ƃ̌������������B
�t�j�g�r�`�ɂ��ƁA�C���O�����h�̑S�Ă̒n��ła�`�D2�̑��������a�`�D1�������������B�����A�a�`�D2�����̕����d�lj����邱�Ƃ������f�[�^�͂Ȃ��Ǝw�E�B�Ǐo���ꍇ�̃��N�`���̗L�����ɂ��Ă��A�b�茟�̌��ʁA�a�`�D1�Ƃa�`�D2�Ƃ̊Ԃɍ��͊m�F����Ă��Ȃ��Ƃ����B
�p���ł͍�N12���ɃI�~�N�����]�����̂a�`�D1�̊g�U�ɂ��A�V�K�����Ґ����ߋ��ň��̐����ɑ����B�������@���͔�Ⴕ�đ��������A�t�j�g�r�`�ɂ��ƁA��N11��24�����獡�N1��19���܂łɏW�����Î�(�h�b�t)�Ŏ��Â��Ă������҂̑命���̓I�~�N�������g�U�O�Ɏ嗬�������f���^���ւ̊����҂������B
|
���ċ����ԁA�I�~�N�����ō��������@�������ł��l�葫�肸�@1/29
�V�^�R���i�E�C���X�́u�I�~�N�����^�v�̂܂��Ċ�Ƃ̃T�v���C�`�F�[��(������)�ɐV���ȍ����������炵�Ă���B���H�ɂ������������������Ԃ̌��Y��C�݂̃R���e�i�D�̍��G���Ăіڗ����Ă���B�č��̊����Ґ��̓s�[�N��E��������̂̈ˑR�������ŁA������Y��S���l��s�����������Ă��Ȃ��B����������������Ί�Ƃ̃R�X�g����l�グ��ʂ���i�̃C���t�����������ꂪ����B����A�����Ґ��̌����ɔ����l��s���������Ɍ����������œ_�ɂȂ�B
���R���e�i�D�̑ؗ��A�Ă�100�ǒ���
�����Ȃǂ���̗A���̌����ł��郍�T���[���X�E�����O�r�[�`�`�B��N11������ɃR���e�i�D�������ɑؗ����鍬�G�͈ꎞ�ɘa�������A�����ł͍Ăё�����100�ǂ����B�����m�C������̃W�F�[���Y�E�}�b�P�i��́u�������T�Ԃō`�p�J���҂�g���b�N�^�]��ɐV�^�R���i���܂��A���G�����������v�Ɛ�������B���C�݂̍`�p�J���҂̊����҂�1��������1700�l�ɏ��A2021�N�ʔN�̊����Ґ����������Ƃ����B�g���^�����Ԃ�1���̖k�čH��̌��Y�䐔��4��5000��ƁA12����1��5000�䂩��3�{�ɖc����悤���B�k�Ă̌��Y�͍�N9����8������s�[�N��3�J���A���ʼn��P���Ă����B�g���^�͏ڍׂ𖾂炩�ɂ��Ă��Ȃ����A����̂���T�v���C���[�ɂ��ƁA�ԗ��̋�����G�A�o�b�O�̍쓮�Ȃǂ𐧌䂷��d�q���i�ɕs���������Ă���Ƃ����B�z���_��ă[�l�����E���[�^�[�Y(GM)�ł��A�����ŕ����̎ԑ̕��i���s�����Ă���Ƃ݂���B�d�C������(EV)���[�J�[�̃e�X����26���A22�N�ɗ\�肵�Ă����s�b�N�A�b�v�g���b�N�̐V�^�ԁu�T�C�o�[�g���b�N�v�̔�����23�N�ɉ���������j�𖾂炩�ɂ����B�C�[�����E�}�X�N�ō��o�c�ӔC��(CEO)�́u�����̂̐�����Ȃ��ŁA�V�Ԏ��lj�����Ӗ����Ȃ��v�Ɛ����B�����̕s����21�N�ɔ�ׂĊɘa������̂́A�u���������ő�̉ۑ�ɂȂ�v�Əq�ׂ��B
�������̓s�[�N�z���A�ꕔ�ɖ��邳
�ăW�����Y�E�z�v�L���X��ɂ��ƁA�č��̐V�K�����Ґ�(7���ړ�����)��1�����{��80���l�����B���̌�A�����̏B�Ō����X���ɂ���s�[�N���z�����Ƃ݂��邪�A�ˑR�Ƃ��č������ɂ���B�������ċƖ��ɏA���Ȃ�������Z���ڐG�Ŏ���ҋ@�𔗂�ꂽ�肷��l�������A���Y�╨���̍����������Ă���B�Ċ�Ƃł̓A�b�v���̃e�B���E�N�b�NCEO��27���A�����̕s�����ɘa�Ɍ������Ă���Ɩ��炩�ɂ���Ȃǖ��邢������������B��������ł̓u�����h�͂�w���͂̍����ꕔ�̑���ƂɌ����Ă���̂�����ŁA���L���Y�Ƃŋ������c��B���ޗ��╨����̍����͊�Ƃ̎��v����������B���p�i����P&G��21�N10�`12�����̑O�N������6%�̑����ƂȂ�������A�c�Ɨ��v��4%���������B�����f�ނ�z���g���b�N�̔R�������~�܂肵�A22�N6�����ʊ��ł�23���h��(��2600���~)�̌��v�v���ɂȂ�Ƃ����B���H�ɑS���i�ŕ���3%�̒l�グ�ɓ��ݐ������肾���A���N2����4���ɂ�����p��܂�q���p�i��lj��l�グ������j�����߂��B
�����܂�C���t������
�o���N�E�I�u�E�A�����J�̃X�g���e�W�X�g�A�T�r�^�E�X�u���}�j�A�����́u�I�~�N�����^�̊����g�傪�J���͂ƃT�v���C�`�F�[���̐�������������A�C���t�����͂����߂Ă���v�Ǝw�E����B�}�N�h�i���h�͏]�ƈ��ɃI�~�N�����^�̊������L����A12���ɑS�Ă̓X�܂ŕ���10%�̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�ɒǂ����܂ꂽ�B�t�����`���C�Y�X�̐V�K�̗p�𑝂₵��1�����{�܂ł�99%�̓X��ʏ�c�Ƃɖ߂������A�l�����10%�߂��㏸�����Ƃ����B22�N12�����͕č��Ŗ�500�X�̐V�K�o�X��\�肷�邪�A���ݍ�ƈ��̕s���ŏo�X�v��ɂ��x�ꂪ������\��������B��������^�[�Q�b�g�͐��C�݂ւ̉ݕ��̏W��������邽�߁A�����o�[�W�j�A�B�Ɠ암�W���[�W�A�B�̍`�p�ɃA�W�A����̉ݕ���U��������B���C�݂ւ̗A����͐��C�݂ɔ�ׂ�2�`3�����x�����Ȃ�A�R�X�g���̈ꕔ�͏������i�ɓ]�ł�����j���B�k���~�G�ܗւ��T���������́u�[���R���i��v���s�����v�����B���]�Ȃ̎�v�`�ł���J�g�`�Ȃǂł́A�o��Ƃ�q�ɂ̑��ƒ�~�����������B�H��ғ���^�����~�܂钆���̏t��(������)���܂����ŁA�����̒������ɐ[��������Ƃ̎w�E���o�Ă���B��ƃR���T���e�B���O�̃��b�Z���O���[�v�́u2���ɂ����Ċ�Ƃ����i�ɂ��m�ۂł����A����ҕ����̏㏸�ɂȂ���P�[�X���o�������v�Ƃ݂�B
|
�������N�o����A�I�~�N�������ōR�E�C���X�����@1/29
�ă����N���ă��b�W�o�b�N�E�o�C�I�Z���s���[�e�B�N�X�Ƌ����J�������V�^�R���i�E�C���X������(�b�n�u�h�c19)�o����u�����k�s���r���v�́A�Ɨ��@�ւ����{����6�̌����ŃI�~�N�����ψي��ɑ���R�E�C���X�������������B���Ђ�28���ɔ��\�����B
�p���{�́A�ăt�@�C�U�[���̌o����u�p�N�X���r�h�v�ɂ��āA����10������Ɖu�n���ア���Ҍ����ɒ��J�n����B���@�⎀�S�����炷���Ƃ��Տ������Ŏ����ꂽ���ݖ�����p���A��Ë@�ւ̕��S�y����}��B
�ăo�[�W�j�A�B�̃~�����X�i�@�����́A�B����w�ɂ��w���ւ̃��N�`���ڎ�`�����͖@�I�����������Ƃ̌������������B
�X�C�X���{�͗��T�ɂ��A�Z���ڐG�҂̊u���`����ݑ�Ζ��`�����I��点�邱�Ƃ����c����\��������B�x���Z�������L�Ғc�Ɍ�����B�A�C�X�����h�̓R���i�֘A�����̒i�K�I�ȉ����ɓ����B6�|8�T�Ԉȓ��ɑS�����[�u�̉�����ڎw���Ƃ��Ă���B
�W�����Y�E�z�v�L���Y��w�ƃu���[���o�[�O�̏W�v�f�[�^�ɂ��ƁA���E�̐V�^�R���i�����Ґ���3��6730���l�A���Ґ���564���l�����ꂼ��������B�u���[���o�[�O�̃��N�`���g���b�J�[�ɂ��A���E�̃��N�`���ڎ��100��������B�@ |
 |


 �@
�@ |
�����̕ψي��u�X�e���X�E�I�~�N�����v�H�@�����͂�18�����@��6�g���������O �@1/30
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̂����A���ݗ��s���̌^�Ƃ͕ψق̎d�����قȂ�^(���^)��������x���������܂��Ă���B�������u�ł͂��ł�300���ȏ�m�F�B���s���̌^��芴���͂������Ƃ���A��6�g�����������O������B���B�ł͕ψي��o�b�q���������蔲���邽�߁u�X�e���X�E�I�~�N�����v�Ƌ�����邪�A�����ł͌������@���قȂ邽�ߌ��o���\�Ƃ����B(���c�ɁA��c��H)
�����{�����ł͌��o�\
�I�~�N�������́A�h��̍זE�ƌ�������ۂɏd�v�Ȗ������ʂ����u�X�p�C�N�^���p�N���v�ɑ����̕ψق�����A�����͂�Ɖu����\�͂��f���^���Ȃǂ�荂���Ƃ����B���E�ی��@��(�v�g�n)�́A�I�~�N�������̂��������ŗ��s����^���u�a�`�D1�v�A���^���u�a�`�D2�v�Ɩ����B���̌^�̓f���}�[�N�A�t�B���s���A�C���h�Ȃǂő������Ă���B
�a�`�D1�ɂ̓X�p�C�N�^���p�N���̌���������B���B�ȂLjꕔ�̍��ł́A���̌�������ɃI�~�N�������ƃf���^������������ψي��o�b�q�������s���Ă���B�a�`�D2�ɂ́A���̌������Ȃ����߃I�~�N�������Ɣ���ł����u�X�e���X�v�ƌĂ�ł���B
�����ł̌����͂ǂ����B�����J���Ȃ̒S���҂�2�̌^�Ƃ��u����(�ɔ�������)���x�A�L�����͈ێ����Ă���v���߁A�V�^�R���i�̗z���A�A���̔���ɂ͖��͂Ȃ��Ɩ�������B�ψي��̋�ʂ͉��B�̂悤�Ȍ������݂���@�ł͂Ȃ��A�f���^���̓����I�ψفu�k452�q�v�̗L���Ŕ��肷�邽�߁A���^�Ƃ��I�~�N�������Ƃ��āu���o�\�v(������)�Ƃ��Ă���B�����A�^�̋�ʂɂ̓Q�m��(�S��`���)��͂��K�v���B
���������u�ł��ł�300�����m�F
�������ɂ��ƁA�s���ł͍�N12�����{����3�T�Ԃ�27���̂a�`�D2���m�F�B�������Ɋm�F���ꂽ�a�`�D1��0�D4���ɂƂǂ܂�B
���u�ł́A�a�`�D2�̓t�B���s���Ȃǂ̓n�q�҂���313�����������B���J�Ȃɏ���������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v��26���A�u�a�`�D2��������Ŏ������܂��Ă����̂��v�Ɩ�莋���鐺������u�p���I�ȃ��j�^�����O���K�v���v�Ǝw�E�����B
���O�͑����̊��������������N�����Ă���a�`�D1�^���A����ɍ����Ƃ���銴���́B���Ƒg�D�́A1�l�����l�Ɋ��������邩�����������Đ��Y����18��������Ɛ��v����B
���s�������������������������邱�Ƃ��s��
�f���}�[�N�ł́A��N12�����{�ɂa�`�D1�̗��s���s�[�N���}���A1���̐V�K�����҂���2���l�ɒB�����B���̌�A1��8000�l�܂Ō����������A�������{�A�Ăё����ɓ]�����B�s���̃E�C���X���a�`�D2�֒u��������Ă��邩�炾�B1�����{�ɂ�6�����A�V�K�����҂�4���l��˔j�B�����g�傪�����B
2�̌^�̏d�Ǔx�̈Ⴂ�͕���Ă��Ȃ��B������Ȏ��ȑ�̕��������y����(�E�C���X����w)�́u���ꂼ��ʂ̑K�v�Ȃ킯�ł͂Ȃ��v�Ǝw�E�B�u�����ō���A�f���}�[�N�Ɠ��l�ɂa�`�D2�֒u�������A��6�g�̗��s���������\�����ے�ł��Ȃ��B���s��\���ł���A���ň�Ñ̐����m�ۂł���B�Q�m����͐��𑝂₵�A�a�`�D2�̎s�������������������������邱�Ƃ��厖���v�Ƌ������Ă���B |
���g�X�e���X�I�~�N�����h�����g��̌��O�H�@1/30
�V�^�R���i�E�C���X�E�I�~�N����������}�����ꂵ���u�a�`�D2�v�A�ʏ́g�X�e���X�I�~�N�����h�B�]������������Ɋ����͂������Ƃ���钆�A����A���{�ł����s�������炷�\���͂���̂ł��傤���H
�V�^�R���i�������̕����Ō������Ă���2�N���܂�B�E�C���X�͕������Ɏn�܂�A�A���t�@�A�x�[�^�A�K���}�A�f���^�ȂǁA�v�g�n�����t�����ψي������ł��u13��ށv�ɂ̂ڂ�܂��B���̒��Ő��E�I�ȑ嗬�s�������N�����Ă����̂��u�A���t�@���v�A�u�f���^���v�A�����č��́u�I�~�N�������v�ł��B
���̃I�~�N�������ł����A���͕��������N���Ƃ��A���[���b�p�����o�āA���́A���N3���ɂ̓I�~�N�����̐e�ƂȂ�ψي����a�����Ă����Ƃ���܂��B�����āA���̊����炳��ɕψقɂ��}�����ꂵ�A���N11���A��A�t���J�Łg3�̎q�h�����܂�܂����B
1�͐��E�Ŗ҈Ђ�U���Ă���u�a�`�D1�v�B�����āA���㑝���Ă����\�����w�E����Ă���̂��u�a�`�D2�v�A�ʏ́u�X�e���X�I�~�N�����v�ł��B�u�a�`�D3�v������܂����A���̂Ƃ���ڗ������͂���Ă��܂���B��������I�~�N�������ł͂���܂����A�a�`�D2�͂a�`�D1�ƕψق̈قȂ镔����20�����ȏ������u�S���ʂ̊��ƌ���ׂ��v�Ƃ����w�E������܂��B
���Ȃ݂Ɂu�X�e���X�v�Ƃ́g�C�Â���ɂ����h�Ƃ����Ӗ��B�Ƃ����̂��A�a�`�D2�Ɋ��������l�ɑ��A�C�O�ło�b�q�������s�����ꍇ�A�R���i�̗z���͂��������̂́A�I�~�N�������ł͂Ȃ��ƌ딻�肳���P�[�X�����邱�Ƃ���A�X�e���X�I�~�N�����ƌĂ�Ă��܂��B
���̃X�e���X�I�~�N�������a�`�D2���m�F����Ă���̂́u56�̍��ƒn��v�ł��B���{�ł��A���łɋ�`���u��313��A�����ŏ��Ȃ��Ƃ�27�����Ă��܂��B���̓����ɂ��Ăv�g�n��24���A�e���ɑ��ꍏ���������ׂ�悤�����B�x�������߂Ă��܂��B
����Ȃa�`�D2�ł����A�ǂ�ȓ����������Ă����ł��傤���B�d�lj����X�N��N�`�����ʂɂ��āA�a�`�D1�ƍ��͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂����A�k���E�f���}�[�N�̕ی����ǂ́A�����͂ɂ��āA�u�a�`�D1�v���1�D5�{�����\��������Ǝw�E�B����ɁA���̍��̏��A1�l�̊����҂����l�ɂ������������u�����Đ��Y���v�ɂ��āA���s��w�̐��Y������̃`�[���́A�a�`�D1����18�������ƕ��͂��Ă��܂��B�f���}�[�N�ł́A�f���^���ɂ�銴���͂قڎ������Ă��āA�u�a�`�D2�v���ł�������߂Ă��܂��B���͍������{�ɂ́u�a�`�D1�v���t�]���Ă����ł��B
�u�I�~�N�����a�`�D1�v�ɂ�銴���g�傪�s�[�N���z��������n�悪�������A�u�X�e���X�I�~�N�������a�`�D2�v�ւ̒u������肪�i�ށA�f���}�[�N�A�����E�C�X���G���ł́A�V�K�����҂��Ăё����ɓ]���Ă��܂��B
���Y�����́A���{�̊��������̓��ɂ��Ă��u�a�`�D2�ւ̒u�������ŁA�ژ_��������Ă��܂��\�����\���ɂ���v�Ǝw�E�B�u������肪�i�ނ��Ƃɂ�銴���̍Ċg������O���Ă��܂��B���{���ȉ�̔��g��́A�u�a�`�D2�̏ɂ��Ă��Ď������Ă����K�v������v�ƌx�����Ăт����Ă��܂��B
���̂��A�S���̐V�K�����Ґ��͉ߋ��ő���8��4941�l�B�܂��s�[�N�������Ȃ����A�X�e���X�I�~�N�������a�`�D2���A���コ��Ȃ銴���g��́g�������h�ƂȂ蓾��̂ł��傤���B�@ |
���S���̊�����7��7701�l �@��ʁA��t�Ȃ�5���ʼnߋ��ő� �@1/30
FNN�̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA30���A�S���ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă���̂��m�F���ꂽ�̂́A7��7701�l�ɂ̂ڂ����B��T�̓��j��(5��25�l)�����1.6�{�������B
�S���̊����Ґ��́A25��(��)��6��2589�l�A26��(��)��7��1613�l�A27��(��)��7��8911�l�A28��(��)��8��1808�l�ŁA29��(�y)��8��4937�l�ƍ���܂�5���A���ʼnߋ��ő����X�V���Ă����B
�����s�ł́A1��5895�l�̊������m�F���ꂽ�B6��������1���l���A���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��������B���{��9135�l�œ��j�ő��������B
���̂ق��ɁA1���̊����Ґ����ߋ��ő��ƂȂ����̂́A��ʌ���5315�l�A��t����4258�l�A��錧��1086�l�A���R����924�l�A�R�`����257�l�B5���ʼnߋ��ő����X�V�����B�܂��A�S���ł���܂łɁA�����҂̂���30�l�̎��S������Ă���B����A�����J���Ȃɂ��ƁA29�����_�ł̑S���̏d�ǎ҂�767�l�ŁA�O�̓�����33�l�������B
|
�������R���i����7��8128�l�@�O�T��1.6�{�A����31�l�@1/30
������30���A�V����7��8128�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����҂��m�F���ꂽ�B7���l����̂�5���A���B�O������͌��������A�O�T�̓����j�������1.6�{�ƂȂ����B
�s���{���ʂł́A����1��5895�l�A���9135�l�A�_�ސ�6141�l�A���5315�l�ȂǁB�R�`�A���A��ʁA��t�A���R��5�����ߋ��ő��������B���҂͑��ƕ��ɂŊe5�l�A�k�C��3�l�A��ʂƈ��m�A�a�̎R�A�L���Ŋe2�l�A�ȖƐ�t�A�����A�_�ސ�A�A�R���A�����A�F�{�A�{��A�������Ŋe1�l�̌v31�l�����ꂽ�B
�����J���Ȃɂ��ƁA�S���̏d�ǎ҂͑O������33�l������767�l�ƂȂ����B |
���V�^�R���i ������2782�l���� �D�y�ƈ���ʼnߋ��ő��Ɂ@1/30
�����ł�30���A�V����2782�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă���Ɗm�F����܂����B������1���̊����m�F�Ƃ��Ă͉ߋ�3�Ԗڂɑ��������g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��������Ă��܂��B
�k�C���ł�30���A�D�y�s�ōėz����39�l���܂�1692�l�A�Ύ�n����238�l�A���H�n����112�l�A����s�ōėz����2�l���܂�109�l�A���َs�ƒ_�U�n���ł��ꂼ��108�l�A��m�n����73�l�A�I�z�[�c�N�n����60�l�A���n����59�l�\���n����46�l�A��u�n����44�l�A���M�s�ōėz����1�l���܂�37�l�A�����n����28�l�A�n���n����24�l�A�@�J�n����22�l�A�����n����10�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��7�l���܂�12�l�̂��킹��2782�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B
1���̊����m�F�Ƃ��ẮA�D�y�s��2���A���A����s��3���A���ł��ꂼ��ߋ��ő����X�V���A�����S�̂ł͉ߋ�3�Ԗڂɑ����Ȃ�܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂĂ�1200�l�߂������Ă��Ċ����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��������Ă��܂��B�܂����́A����܂łɊ������m�F����Ă���90��̒j��2�l��80��̏���1�l�̂��킹��3�l��29���܂łɎ��S�����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�5��2896�l���܂ނ̂�9��48�l�A�S���Ȃ����l��1502�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���e�n�ŐV���ȃN���X�^�[
�D�y�s�͎s���̈�Ë@�ւŁA����s�͎s���̒��w�Z�Ə��w�Z�ł��ꂼ��V���ȃN���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B���̂����D�y�s�ɂ��܂��ƁA�s���̈�Ë@�ւŃN���X�^�[��������50�ォ��90��̐E��4�l�Ɗ���21�l�̂��킹��25�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�s�͔Z���ڐG�̂����ꂪ����E��15�l�Ɗ���23�l�̂��킹��38�l�ɂ��āA�����o�b�q���������{���Ă��܂��B�܂�����s�ɂ��܂��ƁA�s���̒��w�Z�ŃN���X�^�[�����������k���킹��6�l�̊������A�s���̏��w�Z�ŃN���X�^�[������������7�l�A���E��1�l�̂��킹��8�l�̊��������ꂼ��m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�s�͊����҂���������w�����w�����ɂ��Ă��āA�Z���ڐG�̂����ꂪ����l�ɂ͏����o�b�q���������{���Ă��܂��B
�������̊����w�W
29�����_�̓����̊����ɂ��ĐV�^�R���i�E�C���X����������邽�߂̃��x�����ނ̎w�W�Ɋ�Â��Č��Ă����܂��B
���S��
�S���ł͕a���g�p����27�_5���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���295�_3�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���370�_1�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���D�y�s
�D�y�s�����Ō��܂��ƕa���g�p����28�_8���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���408�_2�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���472�_2�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���D�y�s�������n��
�D�y�s�������n��ł͕a���g�p����27�_0���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���227�_5�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���308�_8�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��
�a���g�p���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��A�l��10���l������̗×{�Ґ��́A�S���A�D�y�s�A�D�y�s�������n��Ƃ��Ƀ��x���u2�v�̎w�W���Ă��܂��B�܂��l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��́A�O�̏T�Ɣ�ׂđS���ł��悻2�_0�{�A�D�y�s�ł��悻1�_9�{�A�D�y�s�������n��ł��悻2�_0�{�Ɗ����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B
|
���V�^�R���i�@�{��ōő�554�l�����@1/30
�{�錧�Ɛ��s��29���A10�Ζ����`90��̒j��554�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B5���A���ʼnߋ��ő����X�V�B�m�ەa���g�p���͑S���Ɛ���Ì��Ƃ��ɁA�܂h�~���d�_�[�u����������u���x��2�{(�v���X)�v�̊�ƂȂ�20�������B
�V�K�����҂̓���͐��s357�l�A�Ί��s36�l�A�C����s32�l�ȂǁB�����_��339�l(61�E2��)�̊����o�H��������Ȃ��B����܂ŃN���X�^�[(�����ҏW�c)�����������{�݂̂����A�C����s�̍��Z��43�l���̌v98�l�A���s�̍���Ҏ{�݂�2�l���̌v17�l�ƂȂ����B
�ߌ�1�����_�̗×{�҂�2946�l�ʼnߋ��ő����X�V�B����͓��@109�l�A�h���×{1029�l�A����×{1093�l�ȂǁB���ɂ��Əd�ǎ҂�2�l�A�_�f���^���K�v�Ȓ�����2��8�l�B�m�ەa���g�p����21�E4���ŁA����Ì���26�E4���B�v�����҂�2��707�l(���s��1��2903�l)�B1��7286�l���މ@�E�×{�����ƂȂ����B
|
���I�~�N�����^���̍����2�l���S�@���������ŏ��@448�l�̊����m�F�@1/30
�������͌����ŐV�^�R���i�E�C���X�̐V�ψي��u�I�~�N�������v�Ɋ��������^���̂���2�l�����S���A448�l�̊������m�F���ꂽ��29���A���\�����B�I�~�N�������Ɋ��������^���̂��銴���҂̎��S�͌����ŏ��߂āB�I�~�N�������̊����͌y�ǂ△�Ǐ����Ƃ���邪�A���͍���҂�͏d�lj��A���S�̃��X�N������Ƃ��Čx�����Ăъ|���Ă���B�����̐V�K�����Ґ���3038�l�ɒB���A���ʂōł�����������N8����2950�l�����ɏ������B
2�l�̎��҂�90�Έȏ�j����80�㏗���ŁA�j����19���A������21���ɁA���@���Ă��������̈�Ë@�ւŖS���Ȃ����B�����⑰�̗����Č��\�����B�����҂̎��S���\�͍�N11��18���ȗ��A72���Ԃ�B�����̎��҂͗v178�l�ƂȂ����B
���͌����ŐV�^�R���i�������m�F���ꂽ�����҂̑S���̂�Ώۂɕψي����������{���Ă���B�X�N���[�j���O�����̌��ʁA�S���Ȃ���2�l�̌��̂̓I�~�N�������̉\���������Ƃ��Ă���B
���V�^�R���i���{���̒S���҂́u�I�~�N�������͍���҂�����ǂ̂���l����������Əd�lj����A���S���郊�X�N������v�Ǝw�E�B�y�ǂ△�Ǐ�̑�����N�w�������o�Ɋ������L����\�������邽�߁A�}�X�N�̐��������p�ȂNJ�{�I��̓O������߂Ă���B
��4�g�̍�N5����1179�l�������B�f���^�����҈Ђ�U�������5�g�̓�8���ɂ�2950�l�Ƌ}���B�����͂������I�~�N�������ւ̒u������肪�����ɓ���}���ɐi���ʁA���߂�3000�l�����B
�����ō������������N���X�^�[(�����ҏW�c)�̂����A�����\����29�����_��42���ɏ��B���̂����A�w�Z��13���ƍł������A�����{�݂�9���ő����A�q�ǂ��Ɋ֘A�����N���X�^�[���S�̂̔������߂�B�q�ǂ����m��ƒ��ʂ��ĎЉ�S�̂Ɋ������L�����Ă���ƌ��͕��͂��Ă���B
28�����_�̗×{�҂�2247�l�ʼnߋ��ő����X�V�B���̂�������×{�҂�1049�l�A�×{�撲������493�l�A�h���×{�{�ݓ����҂�399�l�ŁA��������ł������Ȃ����B
�×{�҂̂������@�҂�306�l�ŁA�������펞�Ɋm�ۂ��Ă���a��734���̎g�p����41�E7��(�O����4�E2�|�C���g��)�B���@�҂̂���3�l���d�ǂƂȂ��Ă���B
�S�×{�҂ɐ�߂���@�҂̊����������u���@���v��13�E6���Ɖߋ��Œ�ƂȂ����B����1�T��(22�`28��)�̐l��10���l������̗×{�Ґ���122�E58�l�A�������V�K�����Ґ���113�E19�l�ł�������ߋ��ő��ƂȂ����B
����29���ɔ��\�����V�K������448�l�̗z����28���܂łɔ��������B1��������̐V�K�����Ґ���4���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
|
�������s�̍��Z�ŃN���X�^�[�@���k7�l���V�^�R���i�����@�s�����\�@130
�����������s�͎s���̍��Z�Ő��k7�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������A�N���X�^�[(�����ҏW�c)������������29���A���\�����B
�����s�ɂ��ƁA25���ɒj��1�l�A27���ɒj��2�l�A28���ɒj��4�l�̗z�������������B2�̃N���X�Ŋ����҂��m�F����A25����26�����炻�ꂼ��w�����ƂȂ��Ă���B2�N���X�ɂ�64�l���ݐЂ��Ă���A�s�͂��̂���31�l�̂o�b�q���������{�����B�c��33�l�̌����ɂ��Ă͒������B
|
�����A���̐V�K������1000�l�����@��974�l�m�F�@1/30
��錧��30���A�V�^�R���i�E�C���X�����҂�V����974�l�m�F�����Ɩ��炩�ɂ����B���҂͊m�F����Ă��Ȃ��B1���̐V�K�����҂́A���ˎs���������\����112�l�ƍ��킹�A�����ŏ��߂�1000�l���B
|
����錧��1086�l�����@����1000�l�����A�����̊w�Z�ŃN���X�^�[�^�� �@1/30
��錧�Ɛ��ˎs��30���A�V����1086�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�V�K�����҂�1000�l�����̂͏��B28�����\��983�l������A2���Ԃ�ɉߋ��ő����X�V�����B�v��3��5254�l�ƂȂ����B
�V�K�����҂̋��Z�n�̓���́A���ˎs104�l�A���Ύs100�l�A�y�Y�s86�l�ȂǁB�d�ǎ҂�1�l�B
�N���X�^�[(�����ҏW�c)�̔������^���鎖��́A�����⌧���̏��w�Z�A����̍��Z�^�����̗��ȂǂŐV����10���m�F���ꂽ�B
���ɂ��ƁA30�����_�ŁA����×{���̊����҂�4855�l�A���@���҂Ȃǂ��܂߂��×{�҂̑�����5537�l�ŁA�������10���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
|
���ߋ��ő��A��t����4258�l�����@1�l���S�@1/30
������30���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������1�l�̎��S�ƁA4258�l�̊������V���ɔ��������B����̊����Ґ��Ƃ��Ă�27����3801�l������ߋ��ő��B�����ł̗v�����҂�14��2601�l�ɑ������B���������\���������̕ʂł́A����2644�l�A��t�s��784�l�A�D���s��326�l�A���s��504�l�B
|
����t����1�l���S�A4258�l�����@27����3801�l������ߋ��ő��@1/30
������30���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������1�l�̎��S�ƁA4258�l�̊������V���ɔ��������B����̊����Ґ��Ƃ��Ă�27����3801�l������ߋ��ő��B�V�K�N���X�^�[(�����ҏW�c)��6���m�F���ꂽ�B
���́A90��ȏ�̏����̎��S��2644�l�̊����\�B�S���Ȃ��������́A�̒��s�ǂň�Ë@�ւ���f�����ۂɗz���������B������Ë@�ւɓ��@���_�f�z�����Ă����B�����K���a��z��n�̊�b�������������B�����͐V�^�R���i�E�C���X�����ǁB
����s�̌����������A���P�Y�s�̏�Q�Ҏ{�݁u���P�Y�̂т�w���v�A���ˎs�̍���Ҏ{�݁u���V�l�ی��{�݁@������܂̋��v��3�{�݂ł͐V���ɃN���X�^�[���m�F���ꂽ�B�������ł͐��k29�l�A��Q�Ҏ{�݂ł͐E��7�l�Ɠ�����35�l�A����Ҏ{�݂ł͐E��7�l�Ɠ�����20�l�̊��������ꂼ�ꔻ�������B
�N���X�^�[���������Ă�����c�s�̉ԗ֕ۈ珊�ł͐V���ɐE��1�l�̊�����������A�����̊����҂͌v10�l�ƂȂ����B
��t�s��784�l�̊����\�����B29����793�l�Ɏ����ߋ�2�Ԗڂ̑����������B
���s�́A�V����504�l�̊����\�B���s�̐V�K�����҂�28����363�l������ߋ��ő��B���̂���9�l�̏Ǐ��d���B
�܂��A�����F�ۈ牀�u�R�R�t�@���E�i�[�T���[���̗t�����j�[�m�v�Ǝ����F�肱�ǂ����u����݂��ǂ����v�A�s�����t���3�{�݂ŃN���X�^�[�������B�F�ۈ牀�ł͐E���Ɖ����v9�l�A�F�肱�ǂ����͉���8�l�A���t��ł͓����w���̐E���Ǝ����v13�l�����������B
�D���s��326�l�̊����\�����B���̂���2�l�������ǁB�N��ʂł�20�オ63�l�ƍő��������B
�N���X�^�[���������Ă����Z�R���f�B�b�N�a�@�ł͐V���ɓ��@����1�l�̊����������B���a�@�ł̊����Ґ��͌v111�l�ɑ������B
30���Ɍ����Ŋ��������������l�̋��Z�n�́A��t�s760�l�A���ˎs679�l�A���s464�l�A�s��s369�l�A�D���s347�l�A���R�s214�l�A�䑷�q�s�ƍ��q�s���e128�l�A�s116�l�A�l�X���s98�l�A�Y���s95�l�A�s���s92�l�A��c�s59�l�A����s46�l�A����s45�l�A�؍X�Îs44�l�A�K�u��s�A���P�J�s�A���X�s�A�Ό��s���e40�l�A���c�s36�l�A�����s35�l�A�N�Îs26�l�A���P�Y�s�ƎR���s22�l�A�َR�s19�l�A�x���s�A���s�A���������e17�l�A���X�䒬16�l�A���q�s15�l�A�x�Îs�Ƒ��Ò����e14�l�A��Ԕ����s12�l�A�����s9�l�A���Y�s8�l�A�x���s�A����s�A��{���A�r���e6�l�A��[���s�A�����ݎs�A�ŎR�����e5�l�A�h���A���Ō����A�命�쒬���e4�l�A���쒬�A�_�蒬�A���q�����e3�l�A��\�㗢���A��h���A���������e2�l�A�������ƒ��쒬���e1�l�A���O47�l�������B
|
�������s �V�^�R���i 1�l���S 1��5895�l�����m�F ���j���ł͍ő� �@1/30
�����s����30���̊����m�F��1��5895�l�ŁA1�T�ԑO�̓��j���̂��悻1.7�{�ƂȂ�܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s�́A30���A�s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v��1��5895�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1��5000�l����̂�4���A���ł��B1�T�ԑO�̓��j���̂��悻1.7�{�ŁA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B30���܂ł�7���Ԃ̕��ς�1��4699.9�l�ŁA�O�̏T�̂��悻1.9�{�ƂȂ�܂����B
30���A�������m�F���ꂽ�l�̔N��ʂ́A�u20��v���ł�����3307�l�ŁA�S�̂�20.8���ł��B�����ŁA�u30��v��2774�l��17.4���A�u40��v��2516�l��15.8���A�u10�Ζ����v��2244�l��14.1���A�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B65�Έȏ�̍���҂�1213�l�ŁA�S�̂�7.6���ł����B����A�s�̊�ŏW�v����30�����_�̏d�ǂ̊��҂�29�����1�l������23�l�ł����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ70��̒j��1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
|
��30���̓����s�̐V�K�����҂�1��5895�l�@�O�T�����1.7�{�̑����@1/30
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA30��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�1��5895�l�B�d�ǎ҂͑O������1�l�����A23�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�1��5895�l(�s��1�l)�B�N��ʂł�20�オ�ő���3307�l�A������30���2774�l�A������40���2516�l�ƂȂ��Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�1213�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�1��4699.9�l(�ΑO�T��186.0��)�B�s���̑���(�v)��56��6050�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����48.5��(3353�l�^6919��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T23��(9468�l)����6427�l�����A�������͖�1.7�{�B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
�����ɂ�4450�l�����@�L���y�؎������ŃN���X�^�[�@�×{�Ґ���3���l���@1/30
���Ɍ���30���A�V����4450�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B�O����29���Ɏ����ʼnߋ�2�Ԗڂɑ����A1�T�ԑO��23��(2681�l)��1�E66�{�B���@�⎩��×{�Ȃǂ��܂߂��×{�Ґ��͉ߋ��ő���3��698�l�ŁA���߂�3���l�����B
���\�����̕ʂł́A�_�ˎs��1546�l�A�P�H�s��408�l�A���s��645�l�A���{�s��599�l�A���Ύs��252�l�A�����Ǖ�����l�B�����Ǖ��Ɩ��Ύs�Ōv3���̎�艺��������A�����̗v�����Ґ���12��7730�l�B�_�ˁA���A���Ύs�Ōv5�l�̎��S���m�F����A�����̎��҂�1423�l�ɂȂ����B
����1�T�Ԃ̕��ϊ����Ґ���3888�l�B30���ߑO0�����_�̕a���g�p����61�E8��(�����d�ǎҗp��14�E0��)�B�h���×{�Ґ���501�l�ŁA�×{�{�݂̎g�p����20�E7���B����×{�Ґ���2��4786�l�ƂȂ�A�ő����X�V�����B
���ɂ��ƁA�V���ɖL���y�؎������ŐE��5�l�̊������m�F����A�N���X�^�[(�����ҏW�c)�ƔF��B�ق��ɐE��4�l�����M�Ȃǂ̏Ǐ��i���Ă���Ƃ����A2��7���܂ŋƖ����k������B���쌒�N�����������Ǔ��̃T�[�r�X�t������Ҍ����Z��ł������҂ƐE���v11�l�̊������m�F���ꂽ�B |
���k���̃R���i�V�K�����ҁA�ߋ�1�N���ōő� �ܗ֊J���܂�5���@1/30
�k���~�G�ܗւ̊J����5����ɍT���������}�s�b�`�Ői�߂��钆�A�k���ł�30���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����ߋ�1�N���ōő����L�^�����B �����͋Ǐ��I���b�N�_�E��(�s�s����)�⍑�������A�����u���Ȃǂ́u�[���R���i�v����̈�Ƃ��āA�u�N���[�Y�h���[�v�v�ƌĂ��u�����u�o�u���v�̒��Ōܗւ��J�Â���B
�[���R���i�헪�ɂ��A�����͏��O���Ɣ�ׂĐV�K�����Ґ������|�I�ɏ��Ȃ��ێ����Ă��邪�A���݂͌ܗւ̃o�u���������łȂ��A�����̎s�ŋǒn�I�ȗ��s�̑Ή��ɒǂ��Ă���B�Ԃ��Ȃ�����ė���t��(Lunar New Year�A������)�ł͑吨���A�Ȃ��ĉƑ���F�l�ƌ𗬂��邽�߁A����Ȃ�ۑ肪�҂���B���Ɖq�����N�ψ���(NHC)�ɂ��ƁA30���̖k���̐V�K�����҂�20�l�ŁA�����2020�N6���ȍ~�ł͍ő��ƂȂ�B�s���ǂ͈ꕔ�̏Z��n�����A30���ɍł������Ґ��������������s�암�E�L��(Fengtai)��ł́A�Z��200���l�S����ΏۂƂ����������n�܂��Ă���B
�ܗւ̃o�u���ł͑��̑S�W�҂ƈ�ʂ̒����s���͕������A�������R��L����댯���}������B�o�u���ɓ��鐄��6���l�͖�����������B���g�D�ψ����30���A�ܗ֊W��34�l�̊����\�B����ō���4���Ƀo�u���̉^�p���n�܂��Ă���̊����Ґ���200�l�����B
�@ |
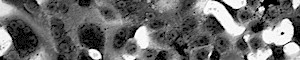 1/31 1/31 |


 �@
�@ |
���I�~�N������A�]���ʂ�́u�܂h�~�v���ʂ͂���́H�@�@1/31
�����ōł������V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̗��s���o���������ꌧ�ł́A1�����{�ɐV�K�����҂��ߋ��ő���1800�l���������B���@�҂̑����ɔ�����Ì���̕N����A�I�~�N�������̓������s���ł��������Ƃ���S���ɐ�삯�āu�܂h�~���d�_�[�u�v�����o���ꂽ�B�V�^�R���i�̉��ꌧ���Ɖ�c�ō����߂问����w��w�@�̓��c���Y�����́u�I�~�N�������̓C���t���G���U�Ɨގ��_�������A�d�lj����X�N���]�����ɔ�����Ȃ��B����܂Œʂ�̏d�_�[�u���p������̂ɂǂ̒��x�̈Ӗ�������̂��v�Ƌ^���悵�A�I�~�N�������̓����ɍ������o�����͍����Ă���B���ĂȂǂł͐V�K�����҂͌����X���ɂ��钆�ŁA�Z���ڐG�҂̋}���ŎЉ�C���t���ɉe�����o����A�������Ă��d�lj����X�N���Ⴉ������ƁA�K���ɘa��i�߂鍑���o�Ă���B���c�����́A���{�̔Z���ڐG�҂ƔF�肳�ꂽ��Ɏ���Ȃǂőҋ@������Ԃɂ��āu�I�~�N�������̐������Ԃ̒Z������l���Ă��A�Z���ڐG�̊T�O�͓���܂Ȃ��v�Ǝw�E����B�e���̃f�[�^�ƂƂ��ɁA�I�~�N�������̑����@��T���Ă݂��B
���Z���ڐG�҂̑ҋ@���ԁu5���܂ŒZ�k�\�v
�V�^�R���i���܂߃E�C���X�����ǂ̑�ł́A�u�������ԁv���d�v���B�������ԂƂ́A�E�C���X�������甭�M��A�̒ɂ݂Ȃǂ̏Ǐo����Ԃ̂��Ƃ��w���A���̊Ԃɂ��l�Ɋ���������\��������B���c�����́A�I�~�N�������̐������ԂƃE�C���X�̔r�o�s�[�N�̎����ɒ��ڂ����B
�V�^�R���i�̏]�����̐������Ԃ͕���5�`6�����������A�I�~�N��������2�����x�ŃC���t���G���U�Ƃقړ����������B�܂��A�R���i�E�C���X���̓��ő��B���ꂽ��ɑ̊O�ɔr�o����s�[�N�́A�]�����́u���Ǔ��v�ɑ��āA�I�~�N�������́u���Ǔ�����3�`6���v�ƂȂ邱�Ƃ������B���̌������ʂ���ǂ������������o�����̂��B
���c�����̍l���͂������B���݁A�����҂̔Z���ڐG�҂̔F��́A�ی����������҂���̕���������ɁA���Ǔ���2���O�܂ők���čs���Ă���B
�������A�I�~�N�������̔r�o�s�[�N�����Ǔ�����3�`6���Ƃ����O��ɗ��ĂA���Ǔ��O�܂ők��K�v�͂Ȃ��A���ǎ��_�Ŋ����҂Ƌߋ����܂��͒����ԉ�b�����l�Ȃǂ�Z���ڐG�҂Ƃ������������ɍ������Ƃ����B���{�͈�Ï]���҂�\�[�V�������[�J�[�������A�Z���ڐG�̑ҋ@���Ԃ���14������7���܂ŒZ���������u�I�~�N�������ł́A5���܂ŒZ�k�\�B��Ï]���҂̋x�E���s�[�N�̍��A������ɕK�v�Ȋ�������x�E���x�̍\�z�ȂǁA�[����������d�v���B�܂��A�w���Ǔ��x�Ɋ�Â���́A�����g��̗\�m�ɗL���ł���A���ʓI�ɐV�K�����҂̋}���ɔ����ی����̕��ׂ��ɘa�ł���v�Ɠ��c�����͎w�E����B�@
���d�lj��ɂ����@���X�N�́u�����v
�I�~�N�������̓����̈�Ƃ��ďd�lj��̂��ɂ�������������B���ۂɁA�p�ی����ǂ̕��ɂ��ƁA�f���^���ɔ�ׂăI�~�N�������̓��@�܂��͏d�lj��ɂ����@�̃��X�N�͔����ɁA�~�}��Â�����@�Ɏ���P�[�X��3����1�ɂ܂Œቺ�����B�����āA���N�`���ڎ킪�L�܂������ʂ��傫���A3��ڐڎ킩��2�`4�T�ȓ��̐l�͓��@���X�N��92�������A10�T�ȏソ�����l�ł�83���ቺ�����B����ŁA2��ڐڎ킩��25�T���o�߂����l��44���ƁA3��ڐڎ�����啝�Ƀ��X�N���㏸�����B
���ۂɁA�p���̑啔�����߂�C���O�����h�ł̓��N�`���̒lj��ڎ킪�i�ݐV�K�����Ґ��������������ƂȂǂ�w�i�ɁA�}�X�N���p�`�����Ȃ��Ȃ�A���N�`���ڎ�ؖ����s�v�ɂȂ�ȂǍs���K���̂قƂ�ǂ��������ꂽ�B�I�����_�ł����@�Ґ��������\�����Ă����������Ȃ��A���X�g������o�[�Ȃǂ̉c�ƍĊJ��������Ƃ������K���ɘa���i�ށB
���c�����͏d�lj����ɂ������R���u�I�~�N�������̓E�C���X����C���ł̑��B�ɂƂǂ܂�A�x�ɗ����Ă��Ȃ����ߔx�����N���ɂ����v�Ɛ����A�f���^���ȑO�Ɣ�r���ďd�ǎ҂̏��Ȃ�����������B������a�@�̓��@���҂̂قƂ�ǂ͍���҂����A�a�ȂNJ�b���������l�ŁA�u������x�얞�A����ҁA����ъ�b�����̂�����͐l�H�ċz�Ǘ��ɂȂ邱�Ƃ�������̂́A�����̕��͔x���̎��ÂƂ������́A���X�̕a�C�̊Ō���삪���C���ƂȂ��Ă���v�Ƙb���B
�V�^�R���i�̒v�����Ɋւ��ẮA���ꌧ���ŕ̂������I�~�N�������̊����Җ�27000�l�̕ꐔ�ɑ��āA�I�~�N���������ǂ����m�F�ł��Ȃ���������҂�1�l�ƁA�C���t���G���U�����Ⴂ�����������B�����u��7�g�ȍ~�̑���\�����Ȃ��瓯���ɑ���s���ׂ��ł���A�d�lj����₷���a�����̃E�C���X�����s���Ă��悢�悤�ɁA���N�`���ڎ�̂���Ȃ�������]�܂��v�B
�������̃X�s�[�h����������Łc
�����̐V�K�����҂͘A���ő����X�V���A1��28���ɂ�1��������̊����҂�����8���l��ƂȂ�A�����Ɋm�F���ꂽ534�l�����C��150�{�ȏ�����������B�������g�傷��X�s�[�h�̑����Ɂu���㎞�ԁv���W���Ă���Ƃ̌��������܂��Ă���B���㎞�Ԃ́A���銴���҂��瑼�̐l�ɂ���܂ł̓����ŁA���̊��Ԃ��Z����ΒZ���قǎ��X�ɃE�C���X���L�����Ă����B�f���^���̖�5���Ɣ�ׂāA�I�~�N����������2���Ɣ����قǂɂȂ��Ă���B
���㎞�Ԃ��Z���A�����X�s�[�h���������A�����҂̃s�[�N�A�E�g���}����̂������̂ł͂Ƃ̊ϑ����L����B�f���^�����҈Ђ�U����Ă������ẮA�p����1��������5���l�䂾�����̂�21���l���ɁA�č��͖�20���l��130���l������܂Œ��ˏオ�������A���̌�A�����҂͌����X���ɂȂ��Ă���B
���c���������E�ŏ��߂ăI�~�N�������������A�t���J�̊����Ґ��̐��ڂ������Ȃ���A�u����͊��Ƀs�[�N�A�E�g������B���ƌ��ł͋K�͂��Ⴄ���߁A����͂��R���p�N�g�ɒZ���ԂŎ�������ƍl���Ă���v�Ǝw�E�B���̔��ʂŁA���X�̊����҂ɒ��ڂ��������ɁA�u���{�⎩���̂̓I�~�N�������̓����ɂ��������łׂ��ł͂Ȃ����B��5�g�܂ł̂悤�ɉ�ꉻ���ꂽ�Ή����A�S���ɐ�삯�ĉ��ꂩ��ς��Ă����K�v������B�Ȋw�I�����Ɋ�Â��ӎv������s�����߂ɂ́A��������I�m�ɔc������u�w�����̎�@�Ƒ̐��̌��������߂���B�I�~�N�������̕a�����ł���Όo�ςƈ�Â𗼗ւŎ��s����ׂ��v�ƓW�]���������B |
���I�~�N�������}���ʼn��� ���E�̑Ή��� �K�v�ȑ�� �@1/31
�I�~�N�������̋}�g��ŘA���ߋ��ő��̊����Ґ����X�V���Ă�����{�B3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�i�܂Ȃ����A����ҁA�����Ďq�ǂ������ɂ��������L����A�e�������ɓ��ɑ傫���Ȃ��Ă��܂��B���N11�����{��WHO�����E�ی��@�ւ��u���O�����ψي��v�Ɏw�肵���I�~�N�������ɂ�銴���́A���̌�A���E�e�n�ŋ}�����Ă��܂��B���{��葁���I�~�N�������̋}�g��Ɍ�����ꂽ���ł͉����N���A�ǂ��Ώ������̂��B�ǂ̂悤�ȑ�ŏ��낤�Ƃ��Ă���̂��B�ڂ���������܂��B
���I�~�N�������e�n�ŋ}�� ���̎��Ԃ́H
�A�����J��1���ɕ���銴���҂̐����ꎞ�A100���l����ȂǁA�I�~�N�������͐��E���Ŗ҈Ђ�U�邢�A�V�^�R���i�̊����Ґ��͐��E�e�n�ŋ}�����Ă��܂��B���̒��ł��A100���l�������1���̊����Ґ�(7���ԕ���)�Ō���ƃA�����J��啝�ɏ���y�[�X�ő����Ă���̂��A�t�����X�A�����ăC�X���G���ł��B1��26�����_�ŃA�����J��100���l������1834�l�Ȃ̂ɑ��A�t�����X�͂��悻3�{��5418�l�A�C�X���G����8672�l��5�{�߂��ɂ܂łȂ��Ă��܂��B
���I�~�N�����������͂ǂꂮ�炢�����H
�ÎR(���[���b�p����)�F�t�����X�ł͂��Ƃ��ɓ�����1���̊����Ґ���30���l��������������A1��25���ɂ͏��߂�50���l���܂����B�f���^���̊������L���������N8���̊����Ґ��̕��ς�1�������肨�悻2���l���������Ƃ��l����ƁA�I�~�N�������̊����g��̃X�s�[�h�͊i�i�ɈႢ�܂��B�N���ȍ~�A���̗F�l���ސ�ł���ɒN�����犴�����Ă���Ƃ�������Ԃ������Ă��܂��B
�]��(�G���T�����x��)�F�l��900���l�]��̃C�X���G���ł�1���͂��߂�1��������5000�l�������V�K�̊����Ґ���2�T�Ԍ�ɂ�5���l���A1��17���ȍ~�͘A��7���l����ȂǁA���ٓI�ȃX�s�[�h�Ŋ������g�債�Ă��܂��B
���I�~�N�������}���ɂǂ��Ή��H
�ÎR�F���\���l�Ɗ����҂��o�Ă���t�����X�ł����A���݁A�O�o�����̂ق��A���H�X�Ȃǂ̉c�Ǝ��Ԃ̐����͍s���Ă��܂���B�ȑO�͌������O�o������ᔽ�҂ւ̔�����݂��Ă�������������܂������A����͂��������K���͂Ȃ��A���[�u�����p�ق�G�b�t�F�����Ȃǂ̎���ɂ͊ό��q�̎p���݂��܂��B
�]��F�C�X���G���ł��A������u���b�N�_�E���v�̂悤�Ȍ����������͍s���Ă��܂���B���N�`���̐ڎ�ؖ���A���ؖ�������A���X�g�����Ȃǂ𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�Z���ڐG�҂ɂȂ��Ă��A���N�`���ڎ�̗L���������Ō����̌��ʂ��A���ł���A�u���̕K�v�͂Ȃ��A���ʂ̐����𑗂邱�Ƃ��ł���̂ł��B
���Ȃ�����������s��Ȃ��́H
�]��F����͌o�ςւ̉e���������������ł��B�����A������\�ɂ��Ă���w�i�ɂ́A�f���^���̂Ƃ��Ɣ�ׂĂ��d�NJ��҂⎀�҂̐��̊��������Ȃ����Ƃ�����܂��B�C�X���G���ł�1��26�����_�̏d�NJ��҂�915�l�Ńf���^���̃s�[�N����100�l�]������Ă��܂����A�����������݂�1���̊����Ґ��͂��悻7�{�ł��B�܂芄���ɂ���A7����1���x�ɂƂǂ܂��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B����Ɏ��҂̐�������1��������20�l�O��ƁA�f���^���̂Ƃ��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�ÎR�F�t�����X�ł��d�lj����ē��@���Ă���l�⎀�҂̐����̂̓f���^���̂Ƃ�������܂����A�����Ґ����̂�20�{�A30�{�ƂȂ��Ă��邽�߁A�����Ō���Ƒ啝�ɒႭ�Ȃ��Ă��܂��B�t�����X���{�́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�n�܂������ƂƂ��Ȃǂɂ́A�c�Ƃł���X�܂����肵�A�O�o������甼�a1�L���ȓ��ɐ�������ȂǁA�ɂ߂Č������[�u���Ƃ�܂����B���̌��ʁA�o�ς��������ݍ�������͕s���̐������o�����̂ł��B���́A�ȑO�قǕa�����Ђ������Ă��炸�A�}�N�����哝�̂Ƃ��Ă��哝�̑I����4���ɍT���钆�A����ȏ�A�����̒ɂ݂��[�u�͂Ƃ肽���Ȃ��Ƃ����̂��{�����Ǝv���܂��B
���������Ȃ��Ă����͂Ȃ��́H
�ÎR�F�e���͏o�Ă��܂��B�����҂̋}���ƂƂ��Ɋu���ΏۂƂȂ�l���������A�l��s���̖�肪�\�ʉ����Ă��܂��B�S���͉^�s�{�������炵���H�X�̒��ɂ͋x�Ƃɒǂ����܂��X���o�Ă��܂��B�����āA�傫�ȉe�����o�Ă���̂��w�Z�ł��B�q�ǂ������̊ԂŊ������}�����A�t�����X�ł�1��21�����_�őS����1��8000�]��̊w�������ƂȂ��Ă��܂��B
�]��F�C�X���G���ł��I�~�N�������̋}�g��ŁA�u���[�u�̑ΏۂƂȂ����q�ǂ�(5����11��)�̐���1��15�����_��1��1000�l���A12����{�Ɣ�ׂ�Ƃ��悻4�{�ɑ����܂����B���t���u���[�u�ƂȂ��Ď��Ƃ��Ȃ��Ȃ��i�߂��Ȃ��Ƃ������P�[�X���������ł��܂��B
���w�Z�ւ̉e�� �ǂ��Ή����Ă���́H
�]��F�C�X���G�����{�͔Z���ڐG�҂̊u���[�u�̌������őΉ����悤�Ƃ��Ă��܂��B�w�Z���ꂾ���ł͂���܂��A�Z���ڐG�҂ɂȂ����ꍇ�A�C�X���G���ł�10���Ԃ̊u���[�u���`���Â����Ă��܂����B�������A�I�~�N�������̋}�����A1���ɓ����Ă���7���ɒZ�k����A�����5���ɂȂ�܂����B�w�Z�ɂ��Ă�5���Ԃ̊u���[�u�ł��e�����傫���Ƃ��āA�q�ǂ��̊u���[�u�͖Ə����Ă������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ă܂ŏo�Ă��Ă��܂��B
�ÎR�F�t�����X���{�̑Ή��͓�]�O�]���Ă��܂��B���Ƃ��ƁA���w�Z�ł̓N���X�̒��Ɋ����҂��o���ꍇ�A�w��������Ƃ����[�u���Ƃ��Ă��܂����B�������A������w�������������A1������͂ق��̃N���X���[�g���S���������ĉA���ł���Γo�Z���Ă��悢�ƃK�C�h���C����ύX���܂����B�������A���̌���K�C�h���C���͕p�ɂɕύX����A���{�̑Ή���ᔻ���鋳�t�ɂ��X�g���C�L��f�����N���Ă��܂��B�f���ɎQ���������t�́u�ύX�̏ڂ������e��������Ȃ��܂o������������A�ی�҂��玿��U�߂ɂ����Ă���v�Ȃǂƕs�������ɂ��܂����B
���ǂ�����ăI�~�N���������������������Ƃ��Ă���́H
�ÎR�F�t�����X���{�̑�̒��́g���N�`���ڎ�h�ł��B�t�����X�ł�1��26�����_��78.3���̐l��2��ڂ̃��N�`���ڎ���I���Ă��܂����A�ڎ�����ގs������萔���܂��B���{�͏d�lj�����l�̑����̓��N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l���Ǝw�E���A1��24������͂��ׂĂ̐l�Ɉ��H�X�Ȃǂ𗘗p����ہA�ڎ�ؖ��̒��`���Â��܂����B���̐��{�̕��j�ɑ��āA�u�I���̎��R��D�����̂��v�Ƃ��đS���Ńf�����s����Ȃǔ���������܂��B�}�N�����哝�̂́u���N�`����ڎ킵�Ȃ��l�����肳�������B�O��I�ɂ��v�Ƃ܂ŏq�ׁA�����܂ł����N�`���ڎ��i�߂悤�Ƃ��Ă��܂��B
�]��F�C�X���G����4��ڂ̃��N�`���ڎ��i�߂Ă��܂��B20�Έȉ��̐l�����S�̂�3����1���߂�ȂǁA����҂̊��������Ȃ��C�X���G���ł����A���łɑS�l����47.7��(1��26�����_)��3��ڂ̐ڎ���I���A4��ڂ̐ڎ��26���܂łɍ���҂𒆐S�ɂ��悻61���l���I���܂����B���̂����ŁA�C�X���G�����{����̒��Ƃ��Ă���̂��A�����ɂ�銴���҂̑�������ł��B�C�X���G���ł͊X�̂�����Ƃ���ɊȈՂ̌�����ꂪ�݂����A1����40�����ȏ�̌������s���Ă��܂��B�����1���őS�l���̂��悻4�������������Ă���v�Z�ɂȂ�A���̎���ł������N�����炪�������Ă��܂��B�܂��A�q�ǂ�1�l�ɂ������L�b�g3���Ŕz�z���邱�Ƃ����߂�ȂǁA���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��q�ǂ��̑���i�߂Ă��܂��B
���I�~�N���������ܕK�v�ȑ�́H
�ÎR�F�t�����X���{���A�I�~�N�������ɂ��d�lj���h���̂ɗL�����Ƃ���Ă���3��ڂ̃��N�`���ڎ���d�����Ă��܂��B2��ڐڎ�I����3������3��ڂ̃��N�`����ł��Ƃ�F�߂����Ƃ�����A26�����_�őS�l����51.5����3��ڂ̐ڎ���ς܂��܂����B�A���A���\���l�̊����҂��o�钆�A�s���̊Ԃł͎���Ɋ����҂��o�Ă��ᔻ����̂ł͂Ȃ�������邱�Ƃ��|�������̂�����̕��i�ɂȂ��Ă��܂��B���Ƃ�2���ȍ~�A�����Ґ��������Ă����Ƃ̌��ʂ����������A���{���e�����[�N�Ȃǂ̋K����i�K�I�Ɋɘa���Ă������j�������Ă��܂��B
�]��F�C�X���G���ł͂܂������g�傪���܂�C�z�͂���܂��A���ꂾ���������L����ƁA�}�X�N�̒��p��ݑ�Ζ��Ƃ�������{�I�Ȋ����\�h�����Ă���l�ł���������P�[�X������A��Ȃ̂͂����Ɋ������L���Ȃ����߂̑���Ƃ邩���Ɗ����܂��B�C�X���G���ł́A�����Ґ��̑��������ɂƂ����̂ł͂Ȃ��A���ʂ̐��������Ȃ�����o�ϊ������ێ�������@���͍�����Ă��܂��B
|
���I�~�N�����h�����u�a�`�D2�v�A�Ȋw�҂����������x���@1/31
�V�^�R���i�E�C���X�̋}���Ȋ����g��͈ꕔ�̍��Ŋ��Ƀs�[�N�A�E�g�������̂́A�Ȃ������ɂ͒������B�����āA���݂̐��E�ɂ����銴���̂قڑS�ẮA���͂Ȋ����͂����I�~�N����������߂Ă���B�����A�Ȋw�҂����x��������̂́A���̃I�~�N�����]�����u�a�`�D1�v�̔h������1�ł���u�a�`�D2�v���A���B��A�W�A�̈ꕔ�Łu�a�`�D1�v����u�������`�Ő����𑝂��Ă��鎖�Ԃ��B�u�a�`�D2�v�ɂ��Ă���܂łɕ������Ă��邱�Ƃ��ȉ��ɂ܂Ƃ߂��B
���u�X�e���X�I�~�N�����v
���E�I�ȉȊw�C�j�V�A�e�B�u�ł���C���t���G���U�E�C���X��`�q�f�[�^�x�[�X(�f�h�r�`�h�c)�ɍ���25�����_�œo�^���ꂽ�Q�m����̓f�[�^�Ɋ�Â��ƁA���E�̐V�^�R���i�E�C���X������98�D8���́u�a�`�D1�v���B�����A���E�ی��@��(�v�g�n)�ɂ��ƁA�u�a�`�D2�v�̊������ŋߑ������Ă���B
�v�g�n�́u�a�`�D1�v�Ɓu�a�`�D2�v�̂ق��A�����2��ނ̃I�~�N�����h�����u�u�a�`�D1�D1�D529�v�A�u�u�a�`�D3�v�����X�g�A�b�v�B���������`�q�I�ɂ͋ߎ����Ă��邪�A���ꂼ������ɕψق��������ɂ���ē���������Ă���\��������B
�t���b�h�E�n�b�`���\�������Z���^�[�Ōv�Z�Ȋw��p�����E�C���X���������Ă���g���o�[�E�x�b�h�t�H�[�h����28���A�f�h�r�`�h�c�̏��ƃI�b�N�X�t�H�[�h��w���^�c����f�[�^�x�[�X�u�A���[�E���[���h�E�C���E�f�[�^�v�܂���ƁA�u�a�`�D2�v�̓f���}�[�N�ɂ����銴���̖�82���A�p����9���A�č���8�����߂Ă���A�ƃc�C�b�^�[�ɓ��e�����B
�u�a�`�D1�v�͂���ȑO�̕ψي��ɔ�ׂČ��m�������ȒP�������B�u�a�`�D1�v�͈�ʓI�Ȃo�b�q�����ŗ��p�����3�́u�W�I��`�q�v��1���������Ă��邩��ŁA���̓��������E�C���X�����o���ꂽ�ꍇ�A�����I�Ɂu�a�`�D1�v���Ɛ��肳��Ă����B
����ŁA���Ɂu�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ��u�a�`�D2�v�́A�u�a�`�D1�v�̂悤�ȕW�I��`�q�̌�������������Ȃ��B���̂��߉Ȋw�҂�́A�f���^�����܂߂��ȑO�̕ψي��Ɠ��������A�܂�f�h�r�`�h�c�Ȃǂ̌��I�ȃf�[�^�x�[�X�ɓo�^���ꂽ�Q�m���̐���ǂ������邱�Ƃœ����𒍎����Ă���B
���Ƃ̘b�ł́A�u�a�`�D2�v�͑��̕ψي��Ɠ��l�ɉƒ�p�̌����L�b�g�ł����m�͂ł��邪�A�ǂ̕ψي����Ǐ�������N�����Ă��邩�͕�����Ȃ��B
�������͂͋��܂�����
�u�a�`�D2�v�͊����͂��A���ɔ��ɋ����u�a�`�D1�v������ɏ���\��������n�߂Ă���B�����Ƃ����̂Ƃ���A���N�`���̖h��@�\�����蔲����͂����܂����Ƃ����؋��͏o�Ă��Ă��Ȃ��B
�f���}�[�N�̕ی����ǂ́A�b��I�ȃf�[�^�Ɋ�Â��āu�a�`�D2�v�̊����͂́u�a�`�D1�v��1�D5�{�ɒB���锼�ʁA�d�lj����X�N�����߂����ɂ͂Ȃ��Ɛ��肵�Ă���B
�p�ی����S�ۏᒡ����N12��27�����獡��11���܂ŃC���O�����h�ōs�����ڐG�ǐՒ����̌��ʂ���́A�u�a�`�D2�v�̉ƒ�������䗦��13�D4���ƁA���̃I�~�N��������10�D3����荂�����Ƃ����������B������28���t���|�[�g�ɂ��ƁA���N�`�����ʂɍ��͂Ȃ��������悤���B
�m�[�X�E�F�X�^����w�t�@�C���o�[�O�E�X�N�[���E�I�u�E���f�B�V���̊����ǐ��ƁA�G�S���E�I�[�����́A�����Łu�a�`�D1�v�����҂��u�a�`�D2�v�ɂ͊������Ȃ��̂��Ƃ����d��ȋ^�₪���サ�Ă���Ƙb���B
�I�[�����́A�f���}�[�N�ł́u�a�`�D1�v�������[������������̒n��Łu�a�`�D2�v�����������Ă���Ƃ̕����Ă���A���̖��ɊS���W�܂��Ă���Ǝw�E�B�u�a�`�D1�v�����҂��u�a�`�D2�v�̊�����h���Ȃ��̂ł���A�����̔g�̓s�[�N��2�ł��鋰�ꂪ����ƌ��O���A�u�����N���邩��c������͎̂����������v�ƕt���������B
����ł������́A����܂ł̃��N�`���ڎ�ƒlj��ڎ�ɂ���Ĉ����������@�Ǝ��S�̃��X�N���}�����܂�Ă���̂́A�ǂ��ޗ����Ƃ̌������������B
|
���I�~�N������ �x���Ǐ�g�f���^�����y���h �n���X�^�[�Ŏ��� �@1/31
�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������ɂ��āA������w��Ȋw�������Ȃǂ̃O���[�v�����������n���X�^�[�̔x���ڂ������ׂ��Ƃ���A�f���^���ɔ�ׂĔx���̏Ǐ�Ȃǂ��y���Ȃ��Ă����Ƃ���������ʂ\���܂����B
���̌����́A������w��Ȋw�������͉̉��`�T���C������̃O���[�v���Ȋw�G���́u�l�C�`���[�v�ɔ��\���܂����B
�O���[�v�ł́A�I�~�N�������Ɋ��������n���X�^�[�ƃf���^���Ɋ��������n���X�^�[�ŁA�Ǐ�ɂǂ��������Ⴂ���o��̂����ڂ������ׂ܂����B
���̌��ʁA�I�~�N�������Ɋ��������n���X�^�[�́A3���ڂ̎��_�Ŕx�Ō��o�����E�C���X�̗ʂ��A�f���^���Ɋ��������n���X�^�[�ɔ�ב啝�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B
�܂��ACT���g���ăn���X�^�[�̔x�̉摜���B�e�����Ƃ���A�f���^���ł́A�q�g�̐V�^�R���i�̊��҂Ɠ����悤�Ȕx���������摜�ƂȂ�܂������A�I�~�N�������ł͌y�����ǂɂƂǂ܂��Ă��܂����B
����A�V�^�R���i�Ɋ������₷�������n���X�^�[�ł̎����ł́A�I�~�N�������ł����ʃP�[�X���������Ƃ������ƂŁA�O���[�v�ł́u�n���X�^�[�̎����ł́A�I�~�N�������̕a������B�\�̓f���^�����Ⴍ�Ȃ��Ă���B�����A�q�g�ł́A����҂�Ɖu���ቺ���Ă���l�Ȃǂ����邽�߁A�y�ǂ�������S�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��B
|
���H�c�����ŐV����83�l���R���i�����@1/31
�H�c���ƏH�c�s��31���A�v83�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�ی����ʂ̊����҂͏H�c�s40�l�A���7�l�A�k�H�c5�l�A�\��13�l�A�H�c����3�l�A�R���{��2�l�A���2�l�A����10�l�A����1�l�B
|
���{���372�l�����@�O�T�̌��j����2�{�߂��@1/31
�{�錧�Ɛ��s��31���A10�Ζ�������90��ɂ����Ă̌v372�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�O�T�̌��j��(24���A192�l)��180�l�������B���Z�n�ʂ̓���͐��s232�l�A�x�J�s27�l�@�Ί��s�Ɩ���s�A���{���e16�l�A�����s14�l�ȂǁB���s�̕ۈ�{�݂ŃN���X�^�[(�����ҏW�c)�����������B
|
����t����2�l���S�A3344�l�����@5���A��3000�l�����@1/31
��t������31���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������2�l�̎��S�ƁA3344�l�̊������V���ɔ��������B����̊����Ґ���3��l������̂�5���A���B�ߋ��̔��\�̎�艺��������A�����ł̗v�����҂�14��5943�l�ɂȂ����B
���������\���������̕ʂł́A����1883�l�A��t�s��919�l�A�D���s��368�l�A���s��174�l�B
|
����t�s919�l�������\�@�ߋ��ő����X�V�A�V�l�z�[���ȂǃN���X�^�[2���@1/31
��t�s��31���A�V����10�Ζ�������90��̌v919�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����\�����B���s�̐V�K�����҂́A29����793�l������ߋ��ő��ƂȂ����B��������y�ǂ����Ǐ�B
��t��̓��ʗ{��V�l�z�[���ƉԌ����̍���҃O���[�v�z�[���ł̓N���X�^�[(�����ҏW�c)�������B���ʗ{��V�l�z�[���ł́A�E��3�l�Ɠ�����19�l�A����҃O���[�v�z�[���ł͐E��7�l�Ɠ�����14�l�̊��������������B
|
������ �R���i 1�l���S 1��1751�l�����m�F ���j�ł͏���1���l�� �@1/31
�����s����31���̊����m�F��1��1751�l�Ō��j���Ƃ��Ă͏��߂�1���l���܂����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s��31���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1��1751�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j���̂��悻1.4�{�ŁA���j���Ƃ��Ă͏��߂�1���l���܂����B31���܂ł�7���Ԃ̕��ς�1��5163.9�l�őO�̏T�̂��悻1.8�{�ł��B�܂��s��12���A�������m�F�����Ɣ��\�����l�̂���18�l�͍Č����ʼnA�����m�F�����Ȃǂ����Ƃ��Ċ����҂���폜����Ɣ��\���܂����B
1��1751�l�̔N��ʂ́A�u20��v���ł�����2485�l�őS�̂̓_21.1���ł��B�����ŁA�u30��v��1963�l��16.7���A�u40��v��1884�l��16.0���A�u10�Ζ����v��1606�l��13.7���ȂǂƂȂ��Ă��܂��B65�Έȏ�̍���҂�909�l�őS�̂�7.7���ł����B����A�s�̊�ŏW�v����31�����_�̏d�ǂ̊��҂�30�����3�l������26�l�ł����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ90��̏���1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s���̐V�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p����31�����_��49.2���ƂȂ�܂����B30������0.7�|�C���g�㏸���A�s���ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50���ɔ����Ă��܂��B�s���̕a���g�p���́�1��21����30����26����40�������ꂼ�꒴�������ƁA����ɏ㏸�������Ă��܂��B����A�s�̊�ŏW�v�����d�ǂ̊��҂�26�l�ŏd�NJ��җp�̕a���g�p����5.1���ł��B
|
������494�l���V�^�R���i�����@2�l���S�@1/31
���Ɗs��31���A�����ŐV����494�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����ƁA2�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�����̊����Ґ��͌v2��8986�l�A���҂͌v225�l�ƂȂ����B
|
���d�Ǖa��40���ŋً}���ԗv���@�V�^�R���i�����ҋ}���@�g�����m���@1/31
���{�̋g���m���m����31���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g����A�{���̃R���i���Ҍ����d�Ǖa���̎g�p����40���ɒB�������_�ŁA���ɋً}���Ԑ錾��v������l���𖾂炩�ɂ����B�g�����͕{�����ŋL�Ғc�Ɂu�R���i���҂̍Ō�̂Ƃ�łł���d�Ǖa�������ӂ�鎖�Ԃ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƌ��������B
�{���ł́A�V�^�R���i�̏Ǐy���Ă����̕a�C�₯�����d�����߁A�d�Ǖa���ɓ��@���̊��҂�����B�g�����́A�����������҂��܂߂��d�Ǖa���̎����I�Ȏg�p����40���ɓ��B����ً}���Ԑ錾�����߂���j���B�{�ɂ��ƁA���̍l�����ɑ����ĎZ�肵���d�Ǖa���̎����g�p����30�����_��15�D4���B�@
|
���V�^�R���i�̢��6�g��ɍ����̔����͑��v���@1/31
1���ɓ����āA�I�~�N�������̑S���I�Ȋ����}�g��ɂ��A�V�^�R���i�E�C���X�́u��6�g�v�ɏP���Ă���B�V�K�����҂̋}���ɂ��A�܂�����ی����Ɩ��̐l��s���A�a���N����A����×{�ł̍������J��������ԂɂȂ��Ă���B�u��6�g�v�̊����Ґ��́A�ߋ��ő��������u��5�g�v���鐨�������A�����ʂł��ς����邾���̔������ł��Ă���̂��낤���B�u��5�g�v�̍ۂɂ́A�V�^�R���i�Ή��̕a�����m�ۂ��邽�߂ɁA���{�͑��z�̕⏕������Ë@�ւɏo�����B�������A�⏕�������Ȃ���V�^�R���i���҂�����Ȃ���Ë@�ւ��ꕔ�ɂ������Ƃ����b�����݉������B
��2020�N�x��11.5���~���̗\������v�サ��
2020�N�x�ɐV�^�R���i�����߂Ċ����g�債���ۂɂ́A3���ɂ킽���\�Z��g�݁A�ő��11.5���~���̐V�^�R���i�E�C���X���\������v�サ�đΉ��ɓ��������B
2021�N�x�ɓ����āA4�`5���ɒ��ʂ����u��4�g�v�A7�`8���ɒ��ʂ����u��5�g�v�ɑ��ẮA2021�N�x�����\�Z�ɐ��荞�܂ꂽ5���~�̐V�^�R���i�E�C���X���\����őΉ������B2021�N�x���ɕ�\�Z���g�܂ꂽ�̂́A�������ݓc���Y���t�ɕς�������11���ɂȂ��Ă��炾�����B
2020�N�x�ɂ́A�V�^�R���i���\�����11.5���~(�ŏI�I�ɂ�9.65���~)���p�ӂ��āA��3�g�܂ł����z�������A��4�g�Ƒ�5�g�́A���������͂邩�ɑ��������Ґ��ł���Ȃ���A5���~�̐V�^�R���i���\����ŁA�\���ɑΉ��ł����̂��낤���B
�V�^�R���i�Ή��ɔ�₵���\�Z�́A�ǂ�����ǂ̂悤�ɏo���Ă���̂��B�����I�ɂ͑�ϊS�̂���Ƃ��낾���A������o�����Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B����͎��̈��������Ă��Ă��킩��B
���������nj������́A�V�^�R���i�Ή��ł��őO���ɗ����̌����@�ւł���B��ΐE���̒��ɂ͐V�^�R���i�Ή��ɓ�����l�����邪�A���ꂾ������ɍs���Ă���@�ւł͂Ȃ��B��ΐE���́A�V�^�R���i�̊����g�傪�Ȃ��Ă��p���I�Ɍٗp����Ă��āA���̐l����́A���̈�ʉ�v�̒��ł͌����J���{�Ȏ������������ʔ�̒�����P�o����Ă���B���̌o��̂����A�����炪�V�^�R���i�Ή��ɔ�₳�ꂽ����蕪����͍̂���ł���B
���̈��́A�ꎖ�������ŁA�V�^�R���i�Ή��̂��߂ɂ������₵�����𐳊m�ɐ��v���邱�Ƃ͓���B
���Վ��I�Ɍv�サ���o��͂����炾������
�����ŁA�p���I�Ɍv�サ�Ă���o��̒��ŐV�^�R���i�Ή��ɏ[�Ă�ꂽ��p��蕪���邱�Ƃ͂�߁A�Վ��I�ɐV�^�R���i�Ή��̂��߂Ɍv�サ���o��ł݂āA2020�N�x��2021�N�x�ɂ����āA�ǂ̂悤�ɍ����ʂőΉ����������݂邱�Ƃɂ��悤�B
�V�^�R���i�Ή��̌o��́A��Â���o�ς܂ōL�͂�����A�����ł͈�Âɏœ_���i�肽���B�V�^�R���i�Ή��̈�Ò̐��������ʂ���x���Ă���̂́A�V�^�R���i�E�C���X�����Njً}��x����t���ł���B����́A2020�N�x�̕�\�Z�ŐV�݂��ꂽ�B�����A2021�N�x�����\�Z�ɂ͓���t����1�~���v�コ��Ă��Ȃ��B
����́A����t�����Վ��I�Ȍo��ƔF������Ă��āA�P��I�Ȍo����v�シ�邱�Ƃ���{�ƂȂ铖���\�Z�Ɍv�ス���A��\�Z�őΉ�����A�Ƃ����X�^���X�f�������̂Ǝv����B
��3�g�܂łɑΉ�����2020�N�x�\�Z�ł́A����t���́A�V�^�R���i���\�����9169���~���P�o����A�ʓr��\�Z�ł�3��6871���~���v�コ��č��v4��6040���~���p�ӂ��ꂽ�B�����āA���Z�i�K�܂ł̎x�o��3��0565���~�ƂȂ�A2021�N�x��1��5140���~���J��z���ꂽ(�\�Z�Ƃ̍��z�͕s�p�z)�B
2021�N�x�\�Z�ł́A�O�q�̒ʂ�A����t���͓����\�Z�ɂ͌v�コ��Ă��Ȃ��B���Z���o�Ă��Ȃ����߂܂����m�ɂ͂킩��Ȃ����A��4�g�Ƒ�5�g�ɍۂ��ẮA����t����1.5���~�]�̌J��z�����[�Ă��Ă����Ƃ݂���B�������A����ł�����Ȃ��Ɣ��f�����̂��낤�B2021�N12��20���ɐ�������2021�N�x��\�Z�ɂ́A����t���Ƃ���2��0314���~���V���Ɍv�コ�ꂽ�B����ŁA����t���͌J�z�ƍ��킹��3.5���~�]�ƂȂ�A2020�N�x�̌��Z�z����K�͂ɂȂ����B
2021�N�x��\�Z�ɂ́A�ق��ɂ��V�^�R���i�̊����g��h�~�̂��߂̗\�Z���������荞�܂�Ă���B�V�^�R���i���N�`���̐ڎ�̐��̐�����ڎ�̎��{�̂��߂�1��2954���~�A���Ö�̊m�ۂ�6019���~�A���N�`���E���Ö�̌����J���E���Y�̐��̐�����7355���~�A�\��s�v�̖��������̊g���3200���~��lj����Čv�サ�Ă���B����ɁA2021�N�x�����\�Z�Ōv�サ���V�^�R���i���\����́A�����_��1��8343���~���܂��c���Ă���B
���ۑ�͍���������������ɂ���
�����݂�ƁA��6�g��2021�N�x���Ɏ�������Ȃ�A�����ʂł͑Ή��]�͂��m�ۂ���Ă���Ƃ݂Ă悢���낤�B
�����ʂł͑Ή��ł������������Ƃ�������̂́A�����ʂł͌��O���c��BPCR�����L�b�g���s�����Ă�����A�Z���ڐG�҂ƂȂ��Č���𗣂�Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ï]���҂������o����A�~�}�������悤�ɂ���������Ë@�ւ����Ȃ������肵�Ă���B�����������W�X�e�B�N�X�ł̉ۑ�́A����܂ł̑�5�g�܂łł��w�E����Ă������A�����ɂ���6�g�ɂ͏\���ɑΉ��ł�����x�ɔ������Ȃ������B
����͈�Â����Ɍ���Ă���ۑ�ł͂Ȃ��B�|�X�g�R���i����������A���ޗ��̑�����A���ɗ���A���q���ŘJ���͕s���ɒ��ʂ�����{�o�ϑS�̖̂��Ƃ��āA�T�v���C�`�F�[���Ɍ���郍�W�X�e�B�N�X�̎�_���A��������ƂȂ��Či�C�̍D�z��W�����˂Ȃ��B�����x�o���o���������ł��Ă��Ă��A�������x��ƂȂ�A���̍����̔����͊�������Ȃ��B���̏��݂�������Ă͂����Ȃ��B
|
���ً}���Ԑ錾�A�I�~�N�������̓����l�������{�Ƃ��Ĕ��f���ݓc�@1/31
�ݓc���Y��31���ߌ�̏O�@�\�Z�ψ���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��܂����ً}���Ԑ錾�̔��߂ɂ��āA�I�~�N�������̓������l�����A���{�Ƃ��Ĕ��f����Əq�ׁA�����_�ł͕K�v�������Ȃ��Ƃ̌��������߂ċ��������B��������}�̍]�c���i�ψ��ւ̓��فB
�]�c�ψ��͓s���{���m�����ً}���Ԑ錾�̔��߂�v�]�����ꍇ�ɂ́A���{�Ƃ��Č������邩����B�́u�I�~�N�����̓����Ȃǂ���������l�����Ĕ��f����v�Ǝw�E�B�u�I�~�N�����͊����g��̌�ɒx��ďd�ǎ҂������邱�Ƃ��z�肳��A�����Ċy�ς���킯�ł͂Ȃ��v�Ƃ��t���������B�u�m���̈ӌ��������Ȃ���Ō�͐��{�Ƃ��đ������f����v�Ƌ��������B
�ً͋}���Ԑ錾�̓K�p�́A�u�a���̕N���x�ɏd�_��u�������x�����ނ��Q�l�ɑ����I�ɔ��f����v�Əq�ׂ��B�����s���ɁA������5�g�s�[�N���̍�N8���͐V�K��5900�l���̊����҂�����Ă����i�K�ŕa���͖����A����ɓ��@�ҋ@�҂����ӂ�Ă������u(���̌�)�a�����m�ۂ��ғ����������グ�����ʁA�a���g�p���͌���48�E5���A�d�Ǖa���g�p���ɂ��Ă��A37�D6���A�����Ǝ����4�D5���ɂƂǂ܂��Ă���v�Ǝw�E�����B |
���I�~�N�����́u�Q�[���`�F���W���[�v�c�C�X���G����ÊE�̌��Ђ����@1/31
�����O�ł̓}�X�N�s�v
���N�`����i���Ƃ����C�X���G���B�R���i�����g��̑����i�K���烏�N�`���ڎ��i�߁A����X�N�̍����l��Ώۂ�4��ڂ̐ڎ킪�s���Ă���B�������A�I�~�N�������̋}�g��͂��̍������������A�ŋ߂̐V�K�����҂�7���l��Ő��ڂ��Ă���B�����͓����K���ɘa���2022�N1�����{�A���n����ނ����B
�C�X���G���ł̓��X�g�����������ʋ@�ւȂǂ������A���O�Ń}�X�N�̒��p�͕s�v���B���̂��߁A�}�X�N�����Ă���l���قƂ�nj������Ȃ��B�M�҂͓����������҂̑����C�X�^���u�[���Ő������Ă��邪�A�g���R�Ɣ�ׂĂ��C�X���G���̃}�X�N���p���͒Ⴍ�A�ꌩ�A�R���i�������������ƍ��o����悤�Ȍ��i���L�����Ă����B
���n�ł́A�ǂ̂悤�ȃR���i�i�߂��Ă���̂��낤���H�C�X���G���̃R���i��̑��l�҂ŁA�����ő�̋~�}���Î{�݂ł���e���A�r�u�E�\�E���X�L�a�@�̉@���A���j�E�K���Y�����ɘb�����B
�K���Y�����̓R���i�����g�傪�n�܂���2020�N�A��ÊE�̌��ЂƂ��ē����̃l�^�j���t�����̃R���i��ɑ傫���v�������l�����B
�\�\���݂̃C�X���G���̏́H
���j�E�K���Y�����F�C�X���G���͍��A��5�̔g�ɒ��ʂ��Ă���B�c��Ȑ��̐l�X���������Ă��āA���̂قƂ�ǂ��I�~�N���������B���E���̑����̍��Ɠ��l�A�L�^�I�ȃ��x���̐l�����B�����A�ǂ��j���[�X������B�d�lj����ē��@����l�̐��́A�ȑO��8����1���炢�ɂȂ����B����ł��܂������̂ŁA�����͂��ׂĂ̏��Ď����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�d�v�Ȃ̂́A��Â̕N����������邱�Ƃ��B
�\�\���A�������߂��Ă���H
�K���Y�����F �s�������A����V�X�e���A�o�ς̊��������ێ����Ă����Ȃ�������Ȃ��B����炪�ő�̉ۑ肾�B�����������S�����̐l�X��10���Ԃ��u�����Ȃ�������Ȃ�������A�s�������͂܂Ђ��Ă��܂��B������z���҂̊u�����Ԃ�5���ɒZ�k�����B�O�i�������邽�߂��B
��4��ڐڎ�͑�5�g�h�~�ɂ��u�L���v
�\�\�C�X���G���ł�4��ڐڎ킪�n�܂����B����ŁA�C�X���G���̍����a�@(�V�F�o�E���f�B�J���Z���^�[)��1��17���A4��ڐڎ�̓I�~�N�������̊����h�~�ɂ͌��ʂ��s�\���Ƃ̏����������ʂ\�����B
�K���Y�����F�V�F�o�̌����͏����Ԉ���Ă����B�Ƃ����̂��A���̃V�F�o�ƕی��Ȃ����{�������͌���(1��23�����\)�ł́A4��ڐڎ킪3��ڂƔ�ׂĊ����̃��X�N�������邱�Ƃ��킩�����B�������Ă���̂Ɂu���ʂ͍ŏ����v�Ƃ͌����Ȃ����낤�B����ɏd�lj����X�N��3����1�܂Ō���B�܂�A4��ڐڎ�͌��ʂ�����Ƃ������Ƃ��B����4��ڐڎ�̑Ώۂ�50�Έȏ�̑S�s���ƁA���������Ȃǂ̃��X�N�̂���S�Ă̐l�ɂ��g�傷�ׂ����ƍl����B3��ڐڎ�(�u�[�X�^�[�ڎ�)�̓C�X���G������n�܂����B���̌�A�����̍��X���C�X���G���ɑ������B4��ڐڎ�(2��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ�)�������Ȃ邾�낤�B�m���Ɍ����_�ł�4��ڐڎ�̓I�~�N�������ɂ͑Ή����Ă��Ȃ����A��5�g��h���ɂ͗L���Ȏ�i���ƌ�����B
���q���ɂ����N�`���ڎ��
�\�\�C�X���G����5����11�̎q����ΏۂɃ��N�`���ڎ킪�n�܂��Ă���2�J���o���A�ڎ헦�͒�����Ă���B
�K���Y�����F�܂��A�e���R���i������قNj���Ă��Ȃ����Ƃ����R�̈���B�ʏ�A�q���͊������Ă��y�ǂł��邱�Ƃ���A�e���g���q���ɐڎ킳���邩�ǂ����f���Ă���B���N�`�����Δh�����ł͂Ȃ��A�����̐l�������悤�ȍl���������Ă���B�����A�^���h�Ɣ��Δh�őΗ�����ׂ��ł͂Ȃ��B�܂��A�ڎ�����Ȃ��A���������Ȃ��Ƃ����l��F�߂邱�Ƃ�����B���ɁA�u���������胏�N�`����ڎ킵�������ǂ��v�Ƃ������b�Z�[�W��`���Ă����B�������邱�Ƃɂ���āA�L���ڎ������Ă��炤�悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���͎�����5�Δ��̎q���Ƀ��N�`���ڎ���������B�����A���̓��N�`���ڎ�̋`�����ɂ͔����B
�\�\���{�ł�5����11�̎q���ւ̃��N�`���ڎ킪�n�܂낤�Ƃ��Ă���B
�K���Y�����F ���̃A�h�o�C�X�́u���������胏�N�`���ڎ킵�������ǂ��v�Ƃ������Ƃ��B�d�lj����郊�X�N�����Ȃ�����ڎ킵�Ȃ��Ă������A�Ƃ͍l���Ȃ��łق����B
�\�\5�Έȉ��̎q����Ώۂɂ����ڎ����������Ă���Ƃ����ꕔ������B
�K���Y�����F�܂��������܂��Ă��Ȃ��B�����A�q���͏o������c���܂ŁA�͂�����|���I�ȂǑ����̗\�h�ڎ���s���B�l�X�ȃE�C���X�����邽�߂��B�܂�A�R���i���N�`���������Ƃ��قLjႢ�͂Ȃ��B�C���t���G���U���N�`���Ɠ��l���B�������A�R���i�ɂ��Ă͌l�̌��N�����ł͂Ȃ��A�p���f�~�b�N�̊ϓ_����(�ڎ킷�邩�ǂ�����)�ӎv���肪�K�v�ɂȂ��Ă���B
���I�~�N�����́u�Q�[���`�F���W���[�v
�\�\���E�ŃI�~�N���������}�g�債�Ă���B�u�W�c�Ɖu�v�B���͂��蓾��̂��H
�K���Y�����F�I�~�N�������̊����g��ɔ����A�R���i�́u�Q�[���I�[�o�[�v���ƌ����l������B���̍l���͈Ⴄ�B�I�~�N�������̓R���i�́u�Q�[���`�F���W���[�v(�����ς������)���B�I�~�N�������͂����̎��R�ȏW�c�Ɖu�������炷��������Ȃ����A���܃C���t���G���U�̂悤�ɍR���s�A���ψ�(antigenic shift)���N����B���̕ψق͔��Ɍ����ŁA�傫�ȉe�����y�ڂ����Ƃ�����B����������͏�Ɍx�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���N�ǂ������ψق��N���Ă���̂��H�k�����Ɠ씼���ʼn����Ⴄ�̂��H�C���t���G���U�Ɠ��l�A1�N���Ƃ̐ڎ킪�K�v�ɂȂ邾�낤�B������u�Q�[���I�[�o�[�v�ł͂Ȃ��A�u�Q�[���`�F���W���[�v�Ȃ̂��B
�\�\�V���ȕψي��o���̉\��������Ƃ������Ƃ��H
�K���Y�����F����͏�ɋN���肤��B�E�C���X�͕ψق����ɓ�����Ԃł��葱���邱�Ƃ͂Ȃ��B���͂��̕ψي�����若�\�ɂȂ肤�邩�ǂ������B���ꂪ�N����Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��B�R���i�̓E�C���X�̒��Ԃ��B�܂��傫�ȁu�g�v������\���͏�ɂ���B
�\�\�y�ϓI�ɂȂ��Ă͂����Ȃ��H
�K���Y�����F����A�����̓E�C���X���������Ă������炱���A�y�ϓI�ɂȂ��B�E�C���X���ǂ������Ηǂ��̂��A�������Ă��邩�炾�B�g�̌�ɁA���̔g�Ɍ������������ł���B�����玄�͊y�ϓI���B�R���i�̔g�͂܂����邾�낤���A�����͒ʏ�̐��������߂��A�܂����E���𗷂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ邾�낤�B
��
���̃C���^�r���[�̒���(1��26��)�A�C�X���G���ی��Ȃ�4��ڐڎ�̑Ώۂ�18�Έȏ�̃��X�N�̂���l�Ȃǂɂ��g�債���B�K���Y���������{�̃R���i��ɍ����[���ւ���Ă��邱�Ƃ��킩��B���N�`����i���C�X���G�������ʂ��Ă���ۑ�ɂ́A�����ꐢ�E�����g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ���������̂��B�I�~�N�������̊����̐��ڂƋ��ɁA�C�X���G���̃R���i��Ɉ��������e�������ڂ��Ă���B |
���R���i�����̂g�h�u���ҁA�E�C���X��21��ψف|�ψي��̔����o�H���@1/31
�\���Ȏ��Â��Ă��Ȃ��G�C�Y�E�C���X(�g�h�u)�����҂ŁA�V�^�R���i�E�C���X������(�b�n�u�h�c19)��9�J���Ԝ늳(�肩��)������A�t���J���a���̏����̑̓��ŁA���Ȃ��Ƃ�21��̐V�^�R���i�E�C���X�̕ψق������������Ƃ��A�����Ŗ��炩�ɂȂ����B
�����ɂ��A����22�̏������g�h�u�̎��ÂɎg�p�����R���g���E�C���X�Ö@�ɏ]���A�Ɖu�V�X�e�������������ƁA6�[9�T�Ԉȓ��ɐV�^�R���i������邱�Ƃ��ł����B�����̓X�e�����{�b�V����w�ƃN���Y�[���[�E�i�^�[����w�̉Ȋw�҂��哱�����B���̌����͍��ǂ��Ă��Ȃ��B
�g�h�u���Ö�p���Ă��Ȃ��l�ȂǁA�Ɖu�s�S�̐l���V�^�R���i�Ɋ�������ƁA���E�C���X���}���ɕψق���\��������A���ꂪ�V���ȕψي��̔����ɂȂ��蓾��Ƃ����V���ȏ؋��������ꂽ�B�����Ώۂ̊��҂��������Ă����x�[�^�ψي��́A�I�~�N�������Ɠ��l�ɓ�A�Ŕ������ꂽ�B
�Ȋw�҂�͍���̌����ɂ��āu�ȑO�̑��̃P�[�X�Ɠ��l�A�V���ȕψي�����������o�H�̉\���������Ă���v�Ƃ�����ŁA�܂������i�K���Ƃ������B �u����������Ԃ�}�����錮�͌��ʓI�ȍR���g���E�C���X�Ö@���Ƃ̏]���̕��ʂ�⋭����`�ƂȂ����v�Ǝw�E�����B
��A�͂g�h�u�����Ґ������E�ő��ŁA�l��6000���l�̂���820���l���늳���Ă���B
|
���؍��A�R���i�V�K������1��7085�l�c�I�~�N�������g�U�@1/31
�؍��ł͐V�^�R���i�E�C���X������(�V�^�x��)�I�~�N�������̊g�U��3���A���ŐV�K�����҂�1��7000�l����L�^���Ă���B31���A�؍������h�u���{���ɂ��ƁA���̓�0����ŐV�K�����҂�1��7085�l�����ėݐ�84��5709�l�ɂȂ����B�O��(1��7529�l)�ɔ�ׂ�444�l���������A����͏T���ɂ�錟���������̉e���������̂Ƃ݂���B
�V�K�����҂̊����o�H������ƁA�n�攭����1��6850�l�A�C�O������235�l�ƂȂ��Ă���B�V�K�����Ґ��͍���26���ɏ��߂�1���l��(1��3009�l)���L�^����29����1��7526�l�Ńs�[�N�����Ĉȗ��A3���A����1��7000�l����p�����Ă���B�ŋߐV�K�����҂͋}�����Ă��邪�A�܂��d�Ċ��҂⎀�S�Ґ��̑����ɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��B
���̓�0����̏d�ĎҐ���277�l�őO���ƕς���Ă��Ȃ��B���S�҂�23�l���ŗݐ�6755�l�ɂȂ����B�ݐϒv������0�D80�����B |
���I�~�N�������̈���uBA.2�v�ɂ��Ă킩���Ă��邱�Ɓ@2022/1
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̊����g��ɉ����A���̈���ł���uBA.2�v�̌��o�����ꂽ2022�N1���B�uBA.2�v�Ƃ́A�ǂ̂悤�ȃE�C���X�Ȃ̂��낤���H �����g��ɂ���Ĉꕔ�̍��Ŏn�܂���4��ڂ̐ڎ�̗L�����Ƃ́H �����̍ŐV���Ƌ��ɁA����1�J���̐V�^�R���i�E�C���X�Ɋւ��铮����U��Ԃ�B
���E�ł�2022�N1���A�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̗v�ڎ��100����Ƃ����ߖڂ��}�����B�������A���̑啔���͕x�T���Őڎ킳��Ă���A�C�X���G���̂悤��4��ڂ̐ڎ���n�߂Ă��鍑������B�Ꮚ�����ŏ��Ȃ��Ƃ�1��ڂ̐ڎ���I���Ă���l�́A�l���̂킸����10���ɂ����Ȃ��B
���E�ł�1���ɖ�2,400����Ƃ����y�[�X�Ń��N�`���ڎ킪�i�߂��Ă���B�������A�I�~�N�������͂�������̂������ŁA����܂ł̕ψي���艽�{�������������g�債�Ă���̂��B�����́u�f���^�������y�ǁv�ƕ��Ă����I�~�N�������̏Ǐ���A����҂��b���������l�A���N�`�����ڎ�҂͏d�ǂ⎀�Ɏ���\�����������Ƃ��킩���Ă���B
�ŏ��ɃI�~�N�������̌��o�����\������A�t���J���͂��߁A�p����č��A�t�����X��C�^���A�Ƃ��������͑������V�K�����Ґ��̃s�[�N�A�E�g���}�����B����ł����S�Ґ��͂��肶��Ə㏸�X���ɂ���B�č��ł̓I�~�N�������ɂ�����̎��Ґ����A�f���^���̃s�[�N�������Ă���B
����A�������I�~�N�����n���̈���(BA.2)���o�����A���E�e���Ŋm���Ɋ����Ґ��𑝂₵����B�f���}�[�N�ł͍ŏ��̃I�~�N������(BA.1)����i������BA.2���V�K�����҂̑啔�����߂�悤�ɂȂ����BBA.2�̓I�~�N�����̖�1.5�{�����͂������Ɨ\������Ă��邪�A���̕a�Ő��͍ŏ��̃I�~�N�������Ɣ�ׂĂ��܂�Ⴂ�͌����Ȃ��Ƃ����B
�I�~�N�������̏o���ɂ���āA�ߋ��ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɏ��R�������������̐l�������Ċ������A���N�`���ڎ�҂̓u���C�N�X���[��������X����������悤�ɂȂ��Ă����B�Ɖu���������ψي��̏o���ɔ����A�p����f���}�[�N�ł̓��N�`���̋`������f�O���铮�����݂��Ă���B
���������Ȃ��A�킽�������͂��ꂩ��ǂ��s�����A���̃E�C���X�ƌ��������ׂ��Ȃ̂��낤���B�V�^�R���i�E�C���X�Ɛ��E��1���̓�����U��Ԃ�B
���I�~�N�������̈���uBA.2�v�Ƃ�
�u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ�邱�Ƃ�����I�~�N�������̈��^(BA.2)�́A2022�N���߂Ɍ��o���ꂽ�B�f���}�[�N���n�߃t�B���s����l�p�[���A�J�^�[���A�C���h�ł͍ŏ��̃I�~�N������(BA.1)���D���ɂȂ����B
�ƒ�������̕ł́ABA.2�̗z���҂������l������������m����39%�ł���ABA.1(29��)�����ƒ���Ŋ�������m�����������Ƃ��킩�����B�Ȃ��ł����N�`�����ڎ�̐l�Ɋ�������\�����ł������A���N�`���ڎ�҂���Ƀu�[�X�^�[�ڎ�(3��ڈȍ~�̒lj��ڎ�)�����l�́A���̊��Ɋ�������\�������Ⴂ���Ƃ�����Ă���B�Ȃ��A�d�lj��̒��x�͏]���̃I�~�N�������ł���BA.1�Ƃ��قǕς��Ȃ��Ƃ����B
���g�y�ǁh�ł͗L�v�ȖƉu�͓����Ȃ��H
���ǑO�̐V���Ȍ����ɂ��ƁA�f���^���ւ̃u���C�N�X���[����(���N�`���ڎ�����������l��COVID-19�ǂ��邱��)�œ�����Ɖu�����I�~�N�������ւ̖h����ʂ͌���I�ł���A�����Ɖu�����������Ȃ����Ƃ��킩�����B�܂�A�f���^�������œ�����Ɖu�̓I�~�N�������ɑ��Ă��܂���ʂ��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�܂������ׂ����ƂɁA�I�~�N�������Ɋ������Ă��y�ǂ������ꍇ�A�I�~�N�������ւ̗L�v�ȖƉu���U������Ȃ��\�������炩�ɂȂ��Ă���B
����̓I�~�N����������������ƁA���炭����Ɠ����I�~�N�������ɍĊ�������댯��������������̂��B���ۂɃC�X���G���ł͏]���̃I�~�N������(BA.1)�Ɋ�����A�قƂ�NJԂ�u�����Ɉ���ł���BA.2�ɍĊ��������Ⴊ����Ă���B
��4��ڂ̐ڎ�͕K�v�Ȃ̂��H
�I�~�N�������̗��s���g�傷��ɂ�A�����҂����炵��Â̂Ђ������y�������邽�߂ɁA�u�[�X�^�[�ڎ킪���������悤�ɂȂ����B����3��ڂ̃��N�`����ڎ킵�Ă����J���ōR�̗ʂ��ቺ����̂ŁA�����Ԃɂ킽��h����ʂ����҂ł��Ȃ����Ƃ��B
4��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ�Ɋւ��錤���ł́A3��ڂɌ���ꂽ�悤�ȋɒ[�ȍR�̗ʂ̏㏸�͌����Ȃ����Ƃ��킩�����B������60�Έȏ��ΏۂƂ��������ɂ��ƁA4�J���O��3��ڂ̐ڎ�����l�Ɣ�ׂ�4��ڂ̐ڎ�����l�́A�I�~�N�������ɑ���2�{�̊����\�h���ʂ�3�{�̏d�lj��\�h���ʂ��F�߂�ꂽ�Ƃ����B������ăC�X���G���̐��Ƃ����́A3��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ킩����5�J����������ɁA4��ڂ̃��N�`���̐ڎ�𐭕{�Ɋ��������B
���錤���ł́A3��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ�ł̓I�~�N�������ւ̊�����\�h����R�̂��ő�ł�4�J�������������Ȃ��\������������Ă���B����ɑ��đ̖̂Ɖu�����ׂ��ق��̌����ł́A�قƂ�ǂ̏ꍇ��3��ڂ̃��N�`���ڎ�ł�蒷���I�ȖƉu����Ƃ������ʂ��o���B�d�lj��ɑ���ی���ʂ͂�莝���I�ŁA���Ƃ������̍R�̗ʂ��ቺ���Ă��Ɖu�L����T�זE�ɂ���ďd�lj���\�h�ł���\��������Ƃ����B
����䂦�A4��ڂ���̃��N�`���ڎ�Ɋւ��Ă͊����\�h��ړI�Ƃ��Ă���̂��A����Ƃ��d�lj���}���ē��@�����ɍςނ��Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���̂��ɂ���ėp�r���قȂ邾�낤�B������ɂ��挤���҂̊Ԃł́A�����̕ψي��ɑ��Ă��L���h����ʂ���V�������N�`�����K�v�Ƃ����ӌ��������B
���i�ށu�I�~�N��������p���N�`���v�̊J��
�t�@�C�U�[�ƃ��f���i���I�~�N�������ɓ����������N�`���̗Տ��������J�n�����B�p���̕ɂ��ƁAmRNA���N�`����3��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ��2�T�Ԍ�ɂ�80〜95���ƈˑR�Ƃ��č������@�\�h���ʂ��ێ����Ă�����̂́A���Ǘ\�h���ʂɂ������Ă̓I�~�N����(BA.1)��63���A�I�~�N����(BA.2)�ł�70���قǂ̌��ʂ����Ȃ��Ƃ���Ă���B
�t�@�C�U�[�͂��łɃI�~�N�������p�̃��N�`���̐������J�n���Ă���A3���ɂ������������Ƃ��Ă���B���f���i�̃��N�`����2022�N�̉Ăɏo�ׂ���錩�ʂ����B
�����N�`���ڎ킪�g���ǁh�̂悤�ȏǏ���������Ƃ�
�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���ڎ��ɔ��ɂ܂�ɋN������ǂ��ACOVID-19�̌��ǂɎ����Ǐ���������Ƃ�����Ă���B�Ⴆ�A��J�⌃�������ɁA�_�o�ɁA�����̕ϓ��A�Z���L����Q�Ȃǂ��������邪�A�Ǐ�̕����ϓ����₷�����Ƃ��f�f�������Ă���Ƃ����B
�����������瓾��ꂽ�؋��ɂ��ƁA�Ɖu�����������N�����ړI�ő����̃��N�`�����g�p���Ă���SARS-CoV-2�̃X�p�C�N�^���p�N���Ɍ���������\��������B�X�p�C�N�^���p�N����W�I�ɂ���R�̂��A�g�D�ɉ��炩�̑����������N������������Ȃ��Ƃ����̂��B
�����ł́ASARS-CoV-2�ɑ��ċ��͂Ȍ��ʂ�����18�̍R�̂̂����A4���}�E�X�̌��N�ȑg�D���W�I�ɂ��Ă���\������������Ă���B���ꂪ���҂̎��ȖƉu������U�����Ă���̂�������Ȃ��B
���̌��ʂ́ASARS-CoV-2�ւ̊�����̐l�X�ł́A�����Ҏ��g�̑̍זE��g�D���U�����鎩�ȍR�̂̃����F�����ُ�ɍ����X�������邱�Ƃ��������������B���݁A�����`�[���͎��ȍR�̂��g�D�ɑ�����^���邩�ǂ����A�����Ď��ȍR�̂��ǂꂾ����������̂������Ă���B
���ݍ��ǒ��̘_���ł́ACOVID-19�̌��ǂ������l�̏��Ȃ��Ƃ�3����1�Ń}�E�X�̐_�o�זE��ق��̔]�זE���U�����鎩�ȍR�̂����������Ƃ����B�������A���̌����ł̓��N�`���ڎ�ɂ����ǂ͋ɂ߂Ă܂�ł���Ƃ��A�ΏƓI��COVID-19�̌��ǂ͊��҂�5〜30���ŋN���肤�邱�Ƃ���������Ă���B
��COVID-19�̌��ǂ̃��X�N���q�Ƃ�
COVID-19���҂̏��f�����(2〜3�J����)�ׂ��c�f�I�ȃf�[�^����ACOVID-19�̌��ǂɊ֘A���郊�X�N���q������Ă���BCOVID-19�̊���309�l�̗Տ��f�[�^�Ǝ��Ȑ\�����ꂽ�Ǐ�͂����Ƃ���A4�̗\�����q�������яオ���Ă����B
�����́u2�^���A�a�A������SARS-CoV-2��RNA�����F���A�����̃G�v�X�^�C���E�o�[(EB)�E�C���X��DNA�����F���A���ȍR��(���ȖƉu�����̌����ƂȂ�R��)�v��4�ł���B������COVID-19�f�f�̏����i�K�ő��肷�邱�ƂŁA���҂������I�ȃR���i���ǂǂ���\�������邩�ǂ�����\���ł���Ƃ����B
���̌����ɂ��d�v�Ȓm���́A�f�f��(���Ǐ���)�̃E�C���X�ʂ����J�����COVID-19�̌��ǂǂ��邩�ǂ����ɋ����֘A���邱�ƂƁA�̓��ŕs���������Ă���EB�E�C���X��COVID-19���nj㑁���ɍĊ��������A���ꂪ���ǂƊ֘A���邱�Ƃ��˂��~�߂����Ƃ��B
�Ȃ��A���N�`���ڎ�҂͒����I�ȐV�^�R���i�E�C���X���ǂ̔��Ǘ������ɒႢ���Ƃ��킩���Ă���BCOVID-19�Ƀu���C�N�X���[�����������S���N�`���ڎ�҂̓��N�`�����ڎ�҂ɔ�ׂē��ɂ�i����m����54���Ⴍ�A��J��i����m����64���Ⴍ�A�ؓ��E�ߒɂ�i����m����68���Ⴂ�Ƃ����B
�I�~�N�������̏o���Ƃ��̈���̓������������A�W�c�Ɖu�̒B���͎����I�ɕs�\�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B��������ǂƐl��s���ɂ���āA�Љ�͋@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���B
�I�~�N�����n���̕ψي��ɑ���h����ʂ���荂�����N�`������������܂ł́A�d�lj�����l����邱�ƁA�Ǝ�ȃO���[�v��ی삷�邽�߂̃u�[�X�^�[�V���b�g�A�����ďd�lj���������邽�߂̍R�E�C���X�܂̎g�p��D�悳���邱�Ƃ��A�킽�����������܂ł��邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B
|
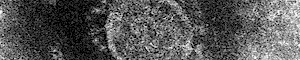 �@ �@
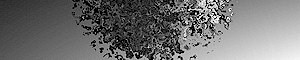 �@ �@
 |


 �@
�@ |
��5〜11�ւ̐V�^�R���i���N�`���ڎ�̌��ʂƕ����� �@2/1
5����11�܂ł̎q�ǂ��ւ̐V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���ڎ킪���N3������n�܂錩�ʂ��ƂȂ�܂����B�I�~�N�����������ٓI�ȑ����Ŋ����g�傷��Ȃ��A�����̎q�ǂ��Ƀ��N�`����ڎ킳����ׂ����ǂ����Y�ޕی�҂͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B���N�`���ڎ�̃����b�g�ƃf�����b�g�𐳂����������Ĕ��f���邱�Ƃ��d�v�Ƃ����܂��B
��10��ȉ��̐V�K�����҂������X��
���J�Ȃɂ��ƁA10�Α�ȉ��̐V�^�R���i�̐V�K�����Ґ��͍�N12�����瑝���ɓ]���A1��12〜18����10�Α�̐V�K�����҂�2��6,560�l�A10�Ζ�����1��3,050�l�ŁA�S�̂�24%���߂�܂łɂȂ��Ă��܂��B�I�~�N�������̗��s����s���鉫�ꌧ�ł́A1����{�܂ł�20��𒆐S�Ƃ��������I�Ȋ����g��͎��܂����܂����A�����⍂��҂֊����g�債�n�߂Ă��܂��B1��17〜23���ɂ͑S�N��w�̂Ȃ���10�Α�̊����A10�Ζ����̊��������ꂼ���15%���߂Ă��܂��B
5〜11�̐V�^�R���i�E�C���X�����NJ��҂̑命���͌y�ǂƍl�����Ă��܂��B���������Ì����Z���^�[�ƍ������ۈ�Ì����Z���^�[�������ōs���������R���i���҂̌����ł́A2020�N1��〜2021�N2���ɑS����570�{�݂ŕ��ꂽ�R���i�����ɂ����@����18�Ζ����̏�������1,038�l��ΏۂɌ����܂����B���̌��ʁA���Ǐ�̊��҂�308�l(30%)�A���炩�̏Ǐ��������҂�730�l(70%)�ŁA�Ǐ�̂��������҂̂����_�f���^��K�v�Ƃ����̂�15�l(2.1%)�A���S���0�l�ŁA�����͌y�ǂł��邱�Ƃ��킩��܂����B38���ȏ�̔M���o�����҂́A�Ǐ�̂��������҂̂�����10%�ł����B�������A���@���Ԃ�8���Ɣ�r�I�����ɋy��ł��܂����B�܂��A���J�Ȃ̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǔ����c���E�Ǘ��V�X�e��(HER-SYS)�ɂ��ƁA2021�N4��〜12����5〜11�̐V�^�R���i�����҂�6��1967�l�ŁA���̂��������x�ȏ��171�l(��0.3%)�A�d��25�l(0.04%)�A���S0�l�ł����B
�������̔��Ǘ\�h���ʂ͖�90%
�q�ǂ��ւ̃��N�`���ڎ�ɂ��ẮA��N5���ɐڎ�Ώۂ�12�Έȏ�ƂȂ�A���N1��21����5����11�܂ł��Ώۂɉ���邱�Ƃ������ɏ��F����܂����B5〜11�Ηp�̃��N�`���̓t�@�C�U�[���ŁA12�Έȏ�̂��̂Ƃ͈قȂ�L�������ʂ�3����1�ŁA3�T�Ԃ̊Ԋu����2��ڎ킵�܂��B�č���5〜11�̎q�ǂ���ΏۂƂ����Տ������ł́A�U��𓊗^����750�l�̂���16�l�����ǂ��܂������A�t�@�C�U�[���̒ʏ��3����1�ʂ�2�^���ꂽ��1,500�l�̂������ǂ����̂�3�l�ŁA���Ǘ\�h���ʂ�90.7%�ł����B�������A�Տ����������{���ꂽ�͎̂�Ƀf���^�������s���Ă����N�ŁA�I�~�N�������ւ̌��ʂɂ��Ĕ��f����Ă��Ȃ��Ƃ���܂��B
�C�X���G���̍ŐV�̌����ł́A���N�`����2��ڎ킵��5����11�̎q�ǂ������́A���ڎ�̎q�ǂ������Ɣ�ׂăI�~�N�������Ɋ������郊�X�N����2�{�Ⴂ���Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B�C�X���G�����{�����C�c�}���������A�w�u���C��w�A�V�F�o��ÃZ���^�[�E�Q���g�i�[�������Ƌ����Ŏ��{���������ɂ��ƁA��N12��25�����獡�N1��16���̊Ԃ�5〜11�̖��ڎ�̎q�ǂ���1�����ς�10���l�������260�l���������Ă����̂ɑ��āA�t�@�C�U�[�����N�`����2��ڎ킵���q�ǂ��ł͖�120�l�̊����ɂƂǂ܂�A���N�`���ڎ킪�I�~�N�������ɑ��Ĕ��Ǘ\�h���ʂ����邱�Ƃ��������܂����B
��16〜25�ɔ�ו������̏o���p�x�͒Ⴂ
���N�`���ڎ��̕������ȂLj��S���Ɋւ���f�[�^���W�ς������܂��B�č��ł́A2021�N11��3������12��19���܂ł�5〜11�̎q�ǂ��ɖ�870����̃t�@�C�U�[�����N�`�����ڎ킳��A�o�^���ꂽ��4��2,500�l�̕������ɂ��Č�������܂����B����ɂ��ƁA2��ڎ��1�T�Ԉȓ��̕������Ƃ��ẮA�ڎ핔�ʂ̒ɂ�55.8%(1��ڎ��52.7%)�A��J��25.9%(��20.1%)�A����19.8%(��13.9%)�A���M13.4%(��7.9%)�ؓ���10.2%(��7.2%)�Ȃǂł����B�ڎ��Ɋw�Z�ւ̏o�Ȃ�����ƂȂ�p�x�͍����Ȃ��A��ÃP�A���K�v�ƂȂ�P�[�X�͋H�ł����B�܂��A�������ɁA�č��̗\�h�ڎ���S�Ď��V�X�e��(VAERS)�ɂ́A4,249���̕������̋^���ǗႪ����A���̂���97.6%���y�ǂł����B�d�ǂƂ��ĕ��ꂽ100�������������͔̂��M29���A�q�f21���Ȃǂł����B11�����S�؉��Ɣ��f����܂������A�S�����܂����B5〜11�̏����ł�16〜25�̐l�Ɣ�ׂĈ�ʓI�ɕ������Ǐ�̏o���p�x�͒Ⴂ�Ƃ݂��Ă��܂��B�ł��������Ƃ��Ă̐ڎ핔�ʂ̒ɂ݂┭�M�A���ɁA���ӊ��Ȃǂ́A���̔N��ɐڎ킳��鑼�̃��N�`���Ɣ�ׂĂ��̔������͍����Ƒz�肳��Ă��܂��B
����b�����̂���q�ǂ��̏d�lj���h�~
�䂪�q�Ƀ��N�`����ڎ킳����ׂ����ۂ��A�v���Y�ޕی�҂͑����Ǝv���܂��B���{�����Ȋw��́u����A�S�N��ɂ����Ċ����҂����������ꍇ�ɂ́A���N�`�����ڎ�̏�������߂銄�����������A�����̒����ǂ�d�ǗႪ�����邱�Ƃ��\������A��b�����̂��鏬���ւ̃��N�`���ڎ�ŃR���i�̏d�lj���h�����Ƃ����҂����B�܂��A���N�Ȏq�ǂ��ł��ڎ�̈Ӌ`������v�Ƃ��A���ߍׂ��ȑΉ����K�v���Ƃ��Ă��܂��B�܂��A���{�����Ȉ��́u�N��Ⴂ�����ł����Ă��������Ă��܂����ꍇ�̑��҂ւ̊������X�N�̑���A10���ȏ�ɂ��킽��s�������̕K�v���ƍ���Ȃǂ��l������ƁA�q�ǂ������̐S�g�ւ̉e���͌v��m��Ȃ��v�Ƃ��A�\���ȋc�_�Ə����̏�ł̐ڎ�����߂Ă��܂��B���N�`���̃����b�g�ƃ��X�N�𐳂����������Ĕ��f���邱�Ƃ��K�v�Ƃ���܂��B |
���V�^�R���i�o����u�����k�s���r���v�A�I�~�N�������ւ̊������m�F �@2/1
�����N�E�A���h�E�J���p�j�[(MSD)�ƕăx���`���[��ƃ��b�W�o�b�N�E�o�C�I�Z���s���[�e�B�N�X��1��28��(�č�����)�A�V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�����o���R�E�C���X��Ƃ��ĊJ�����Ă���u�����k�s���r���v�ɂ��āA�V�^�R���i�E�C���X(SARS-CoV-2)�ψي��u�I�~�N������(B1.1.529)�v�ɑ��銈����in vitro�����Ŏ����ꂽ���Ƃ\�����B
�����ł́A��ʓI�ȃZ���x�[�X�A�b�Z�C��p���A�����k�s���r������т��̑��̐V�^�R���i�E�C���X�����ǂɑ���R�E�C���X��ɂ��āA�I�~�N���������܂�SARS-CoV-2�̌��O�����ψي�(VOC:variants of concern)�ɑ���R�E�C���X�����̕]�������{�����Ƃ����B
�x���M�[�A�`�F�R���a���A�h�C�c�A�|�[�����h�A�I�����_�A�č����܂�6�����̓Ɨ������@�ւōs��ꂽ��Տ������̃f�[�^�ɂ��m�F���ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA�����N�ł͏d�lj��̃��X�N�̍����y�ǂ��璆���ǂ̐V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̐��l���҂ɑ���d�v�Ȏ��Â̑I�����ƂȂ肤�邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ��Ă���B
�Ȃ��A�����k�s���r���͓��{���܂ޕ����̍��Ŏg�p�����o����Ă���A���{�ł�2021�N12���ɐ����̔��Ɋւ�����Ᏻ�F���擾���Ă���B
|
���R���i�ی��ɓ��邩�����l�ɒm���Ăق���3�_�_�@2/1
500�~�ʼn����ł���R���i�ی����b��ɂȂ��Ă��܂��BPayPay�ق���̏ꍇ�A3�J����500�~��PayPay�Ŏx�����ƁA��t�ɐV�^�R���i�Ɛf�f���ꂽ�ꍇ��5���~�̂��������������Ă��܂��B�u�őO���ŎЉ���x���邠�Ȃ��Ɂv�Ƃ����̔��R�s�[�̂Ƃ���A���̕ی��̎�Ȍ_��҂͏����A���H�A�����Ȃǂ̌���œ����Ă��āA�����R���i�z���ƂȂ��Ă��܂�����������r�₦�郊�X�N�������҂����������ł��B���āA�u�����̂͑�����B�Ȃ��Ȃ�300�~�̂������Ă����Ғl��150�~�ɂ����Ȃ�Ȃ�����v�Ƃ����b������܂��B�o�ςɏڂ������͂��������Ǝv���܂����A�ی��ƕ��͖{���I�ɂ͓������J�j�Y���̏��i�ł��B�ǂ������Ȃ̂��͂��ꂩ���������Ƃ��āA�������Ƃ�����R���i�ی��ɓ���̂����Ȃ̂ł��傤���H
���R���i�Ɋ�������m���́H
�����3�̃X�e�b�v�Ő������܂��B�X�e�b�v1 ���Ȃ����R���i�ɂ�����m���́H�I�~�N���������҈Ђ��ӂ���Ă���̂͊F�������̂Ƃ���ł����A�����m�����l�������Ƃ�����܂����H ��N9���Ƀf���^�����s�[�N�A�E�g���Ĉȍ~�A12���܂ł͐V�^�R���i�̐V�K�����Ґ��͔��ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���ꂪ1���ɂȂ��ăI�~�N�����ŋ}�Ɋ����Ґ������������킯�ł��B���{�̏ꍇ1���̐V�K�����Ґ����قڂقڃI�~�N�������̊����Ґ��ƌ����Ă������炢�̏ł��B����1���̐V�^�R���i�����Ґ��͖�100���l�ł��B���āA������ی��ɓ��邩�ǂ������l���邽�߂ɂ́A���������̃I�~�N�������̊����Ґ������l�ɂȂ邩��\������K�v������܂��B�܂������Ȃ��V�i���I�́H�ł��y�ϓI�Ɍ����u�������s�[�N�ŁA��������s�[�N�A�E�g���Ă����ꍇ�v�ł��B�V�^�R���i�̊����҃O���t�͊F���x�������ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A�����҂̑��������ƃs�[�N�A�E�g��̌��������̓O���t�����傤�Ǎ��E�Ώ̂ɂȂ�X��������܂��B�ł����牼��2��1�����s�[�N�ł������猸���ɓ]�����Ƃ�����A���ꂩ��R���i�ɂ�����l�̐��͂��傤��1���Ɠ���100���l���x�Ƃ����\�������藧���܂��B������y�σV�i���I�Ƃ��܂��B�ł́u�{���ɐV�^�R���i�������s�[�N�A�E�g����́H�v�Ƃ����ƁA�����͂�����Ɩ�����������܂���B�R���i���s�[�N�A�E�g���邩�ǂ����ׂ�ɂ͂ЂƂ�̗z�����҂����l�ɃR���i�����������邩�����������Đ��Y��������K�v������܂��B
�I�~�N�������͂���܂łɂȂ������قǂ̍��������Đ��Y���������ł��B�I�~�N���������}������1��9�����s�[�N�Ŏ����Đ��Y���͂Ȃ��5.9�A1��20�����܂ł�2���������������Ă��܂����B���ꂪ1�����{�ɓ����Ă悤�₭1.5�ȉ��܂ʼn������Ă��܂������A��5�g�܂ł̏ɔ�ׂ�܂��܂������Đ��Y���͍������x���ɂ���܂��B
��5�g�̂Ƃ��̃f���^�����s�[�N�A�E�g�̒������������N8��26���̎����Đ��Y����1.09�ł����B���̌�8��29���Ɏ����Đ��Y����0.98��1�������ăf���^���̃s�[�N�A�E�g�������ɂȂ������Ƃ��l����ƁA�I�~�N�������̃s�[�N�A�E�g�͍��ł͂Ȃ��B���Ƃ��\�z����悤��2�����{���ɂȂ�\���̂ق��������ł��傤�B�����������Ƃ���ΐV�K�����Ґ��̎R�͂������������������A�s�[�N���Č��݂̐l���ɖ߂��Ă���͍̂�����3�T�Ԃ��炢��ɂȂ邩������܂���B�V�K�����Ґ���8���l����������ꂩ���20�������Ƃ����炱�̐�̊����Ґ��̊T�Z�l�͐�قǂ�100���l�ł͂Ȃ�260���l���炢�̐����ɂȂ肻���ł��B����𒆊ԃV�i���I�Ƃ��܂��B�����Ă����Ɗ댯�ȃp�^�[����2�����{�ł̓s�[�N�A�E�g���Ȃ��P�[�X�ł��B���ہA���B�ł͐l���̔������V�^�R���i�Ɋ������郊�X�N������Ƃ����b������܂��B���{�͂������ɐl���̔����͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����A���N�`�����ڎ�҂�2400���l�K�͂Ŏc���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA1000���l�߂��܂Ŋ����҂�������Ƃ����ߊσV�i���I���l�����܂��B����͌��\�������\�������ŁA�v����ɂ��Ƃ����ԃV�i���I���Ƃ��Ă�����܂ŐV�^�R���i���������Ă���̗v�����Ґ���270���l�Ɠ��K�͂̊����҂��V����2����3���ɏo������\��������ƌ����Ă���킯�ł��B
���l����Ōv�Z����Ɩ�2��
���āA�m���Ɗ��Ғl�̘b�����Ă݂܂��傤�B���ɂ��ꂩ��260���l���V�K�Ɋ�������Ƃ����玄�₠�Ȃ�����������m���͎c�O�Ȑ����ł����l����Ōv�Z����Ɩ�2���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��������͎Z���̌v�Z�ł��B�u2���̊m����5���~�����炦�邭�����������Ƃ��܂��B���炦����Ғl�͂�����ł��傤�H�v�����5���~�~2����1000�~�������ł��B500�~�̕ی��ɂ͂�����Ғl��1000�~�Ȃ̂Łu�R���i�ی��͔���Ȃ���Α����v�Ƃ������Ƃł��B������ƈӊO�Ȍv�Z���ʂ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�����ŁA�u�ł͂Ȃ��PayPay�ق����500�~�ʼn����ł���́H�v�Ƃ����b�ł����A������l������\���́A�ی����i��v�����Ƃ��̑z����������ƃI�~�N�������̊g�傪�}�������Ƃ������Ƃł��傤�B
��N�̉Ăɖ҈Ђ��ӂ�����f���^���̐V�K�����Ґ���100���l�ł����B���̐������Q�l�Ɂu�ő�ł�100���l�̊����҂��o�邩�犴���m��0.8�����炢���o�債�āv���炢�̏��i�v�������̂ł���A�����قǂ̊��Ғl��5���~�~0.8����400�~�ł�����A500�~�Ŕ̔����Ă����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ł͂��̐Ԏ���������Ȃ��R���i�ی��͂��ꂩ��ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H ���͍�N�A�f���^�����}�����钆�ő�ꐶ���̊֘A��Ђ��̔����Ă����u�R���imini�T�|�ق���v��9��1���ɔ̔��ꕔ�x�~�ɂȂ��Ă��܂��B���Ƃ��Ə���������Εی����z����v�Ŋ֓������ǂɓ͂��o�Ă����̂ł����A���̏�����f���^���̑����X�s�[�h�������Ă��܂����̂ł��BTwitter��ł̓R���i�ی��ɂ��łɉ������Ă��郆�[�U�[����u�X�V�̈ē���������ی������т����肷��قǏオ���Ă���v�Ƃ��������Ă��܂��B�m�����Ғl���̔����i���������ی����i�́A���i�Ƃ��ĉi���͂ł��܂���B�܂�`���̃R���i�ی��Ɋւ��Č����A�u���A�����Ă����Ȃ��ƁA�Ђ���Ƃ���Ɨ��T�ɂ͂��̏��i�A�Ȃ��Ȃ����Ⴄ��������Ȃ����v�Ƃ����̂������ȃR���i�ی��ɑ��鎄�̖����\���ł��B
������1500�~�ɏオ���Ă��������ق��������l�Ƃ́H
�X�e�b�v2 �m�����Ғl���Ⴉ������ی��ɓ���Ȃ��ق��������H���āA���̃I�~�N�����̊������ŁA500�~�̕ی�����5���~�̂����������o��Ƃ����R���i�ی��́A�P���Ȍo�όv�Z�ł͉����҂ɂ����ȐԎ����i�̂悤�ł��B�ł́A���������ƕی���������������A�ی��ɓ���Ӗ��͂Ȃ��̂ł��傤���H���Ƃ��Ώ��i�̌������������āA�u1500�~�̕ی����ŁA�����R���i�ɂ���������5���~�̂����������o��v�Ƃ����������i(�H)���łĂ����Ƃ�����ǂ��ł��傤�H�����ǎ҂݂̂Ȃ��`���ł��������u�����A���H�A�����Ȃǂ̌���œ����Ă��āA�����R���i�z���ƂȂ��Ă��܂�����������r�₦�郊�X�N�������ҁv�Ƃ����ی��̎�Ȕ̔��Ώێ҂������Ƃ�����A����3�J��1500�~�̕ی������Ƃ��Ă����̕ی��ɓ���ׂ����ƒf�����܂��B���̗��R�́A�ی��ɓ��邩�ǂ����͊��Ғl�̑�������Ō��߂�ׂ��b�ł͂Ȃ�����ł��B���͂���40�N�ȏ�A�ΐl/�Ε����̂̔������Ȃǂ�⏞����C�ӂ̎����ԕی��ɓ����Ă��܂��B���N�����~�̕ی������Ă��Ă܂������������Ƃ͂���܂���B�ł��ی��ɓ����Ă��闝�R�́A�u������̎��ɐ��������ł��낤����Ȕ������Ȃǎ����̎��Y�ł͎x�����Ȃ�����v�ł��B
���{�l�ŎԂ̉^�]�Ƌ��������Ă���l��8216���l�B���̂���3�����y�[�p�[�h���C�o�[���Ƃ��Ă��Ԃ��^�]����l�͖�6000���l���܂��B����Ō�ʎ��̎��Ґ��͖��N��3000�l��B�ł����玀�S���̂��N�����m���͒P���v�Z��0.005�����x�B�߂����ɋN���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B�������������̐����ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A���̂߂����ɋN���邱�Ƃ��Ȃ��͂��̂��Ƃ������N������ǂ�����̂��Ƃ������Ƃł���A�ی��͂��̂��߂̏��i�ł��B2���~�̔��������K�v�ɂȂ�ꍇ�̊m�����Ғl��1���~���Ƃ��Ă��A�N�Ԑ����~�̕ی������ĕی��ɉ������Ă����Ȃ��Ɩ���̂Ƃ��ɐ������j�]����\��������̂ł��B����Ɠ����ϓ_�ŁA�R���i�ی��ɂ��čl���Ă����ׂ����Ƃ́A�R���i�ɂ������Ă��܂����琶�������藧���Ȃ��Ȃ邩�ǂ����ł��B�T�����[�}���̒��ɂ́A�����R���i�ɂ������Ă����^�͌��炸�A����ҋ@��\���t�����邾���Ŏd���͑��̎Ј��������Ă����Ƃ����悤�Ȋ��̕�������������Ǝv���܂��B�������������R���i�ی��ɓ���K�v�͂܂������Ȃ��ł��傤�B
���ی��͊��Ғl�ōl���Ă͂����Ȃ�
����ł����R���i�ɂ���������d�����ł��Ȃ��Ȃ�A���ꂪ�����̎����ɒ�������Ƃ����l����������Ⴂ�܂��B������������Ȃ��Ă��Ƒ�����������Ίŕa�Ŏd�����~�܂�Ƃ����l������ł��傤�B��قǂ̒��ԃV�i���I�ł����A�����Ȃ�m����2���ƁA���͂�����Ȃ��m��98���Ɣ�ׂ����قǍ����͂Ȃ������ł��B���������������Ȃ����琶���ɑŌ�������B���̂悤�ȕ��͂��̂Ƃ��̂��߂�5���~�̂��������̂��߂ɉƑ��S�����R���i�ی��ɉ��������ق��������Ǝv���܂��B�܂�X�e�b�v2�̂܂Ƃ߂Ƃ��ẮA�ی��͊��Ғl�ōl���Ă͂����Ȃ��āA�������̏ꍇ�̃Z�[�t�e�B�[�l�b�g�Ƃ��Ẳ��l�����邩�Ȃ����ʼn����f���ׂ����̂Ȃ̂��Ƃ������Ƃł��B�X�e�b�v3 ���͔���Ȃ��ق��������́H���āA�Ō�ɃR���i�ی�����͈ꌩ�b�������悤�Ɍ����܂����A�ی��ƕ��̊W�ɂ��Ă����_���o���Ă��������Ǝv���܂��B�`���ɕی��ƕ��͓������J�j�Y���̏��i���Ɛ\���グ�܂����B���ۂɔ�r���Ă݂�Ƃ悭���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B
�u3���~�̎����ԕی��ɉ��������0.005���̊m���Ō�ʎ��̂��N�����Ă��܂����ꍇ��2���~�̔��������ی��ŃJ�o�[�����B�ł��m���̊��Ғl��1���~�Ȃ̂ő唼�̐l�͑�������v���ꂪ�ی��ł��B�����āA�u�o�����^�C���W�����{�����ƁA0.00001���̊m����1��2���~��������B�ł�3000�~��10���Â���w�����Ă��m�����Ғl��1500�~�ȉ��Ȃ̂ő唼�̐l�͑�������v���ꂪ���B�������Ĕ�ׂĂ݂�Ƌ��Z���i�Ƃ��Ă͓����悤�ȃ��J�j�Y���ł��邱�Ƃ��悭�킩��܂��B�����Ă���������Ƃ����̂͌o�����Ƃ��Ă͎����ԕی��Ɠ������炢�������āA���̏ꍇ��10���Â��3000�~�ōw�����Ă�������̂�300�~1�{�����ł��B�m���v�Z�I�ɑ������邱�Ƃ������Ȃ��̕����Ȃ��������͔����̂ł��傤���H
���u������v�̎��̂��߂�
����͕ی��Ɠ����Łu������v���Ă���̂ł��B���������肵���T�����[�}���̓R���i�ی��ɓ���K�v���Ȃ����Ƃ��قǐ������܂������A����Ɠ����_���ŕ����K�v���Ȃ��l�́u3���~�͂�����҂���l�v�ł��B�ǎ҂̊F����̒��ŔN��1���~�̕���3�N�d���������3���~�҂��܂��B��������m�����Ғl�ő�������Ƃ킩���Ă���̂�3000�~�̕����K�v�͈����܂���B�����������ł͂Ȃ��ǎ҂́u������v�̂Ƃ��̂��߂ɕ����Ӗ��͏\���ɂ���܂��B�����������Ă��܂����玩���ł͓���҂��Ȃ���������Ȃ�3���~����ɓ���B���Ԃ�O��邯�ǂ���Ŏ���3000�~�͒ɂ��͂Ȃ��B���������ꍇ�͕����o�ϓI�ȈӖ��͕ی��Ɠ����Łu�A���v�Ȃ̂ł��B����������ꕶ�������ꂳ���Ă��������ƁA�ی����������͌o�ϗ��_�ł����{���e�B���e�B�[��̔����Ă��鏤�i�Ȃ̂ł��B������̃P�[�X�͂قƂ�NjN���Ȃ����ǁA������̂Ƃ��̋��z�����傾�Ƃ����̂��{���e�B���e�B�[�̈Ӗ�����Ƃ���ł��B����������Ƃ킩��₷�������Εی��̓��X�N��A���̓`�����X���Ă���킯�ŁA������o�ϗ��_�ł͓����u�{���e�B���e�B�[�v�Ƃ������t�Ő�������ƌ���������Ƃ��킩��₷����������܂���B�Ƃ������Ƃō���̋L���̌��_�́A�R���i�ɂ�����Ǝd�����Ȃ��Ȃ��Đ����Ɏx�Ⴊ�o��l�̓R���i�ی��ɓ���ׂ������A�R���i�ی��ɓ��肽���Ǝv��ꂽ�ǎ҂̕��̓o�����^�C���W�����{���������Ă������ق����u�o�ϗ��_�I�ɂ͂���ł����̂��v�Ƃ����b�ł����B
|
���I�~�N�����ʌn���A�x�������@������18�����A�s���������\�V�^�R���i�@2/1
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A���ݎ嗬�ƂȂ��Ă���ψي��u�I�~�N�������v�̈��ŁA�ʌn���́u�a�`�D2�v�ɑ���x�������܂��Ă���B�����͂͌��ݗ��s�́u�a�`�D1�v���18�������Ƃ̕��͂�����B�C�O�ł͈ꕔ�Œu������肪�i�݁A�����ł��s���������n�܂������ꂪ����B
���������nj������ɂ��ƁA���݂̐��E�I�Ȏ嗬�͂a�`�D1�����A�f���}�[�N��C���h�ł͂a�`�D2���������Ă���A�f���}�[�N�ł͊����ŋt�]�����Ƃ����B���҂ɂ͋��ʂ���ψق��������A�ꕔ�̍��ł̓I�~�N���������o�p�̌��������蔲���邽�߁u�X�e���X�I�~�N�����v�Ƃ��Ă��B���{�ł͌�����@���قȂ邽�ߖ��͂Ȃ��Ƃ����B
���{�ł͂a�`�D1���唼�����A�����J���Ȃɂ��ƁA�a�`�D2�͋�`�Ȃǂ̌��u��1��26���܂ł�313�Ⴊ�m�F���ꂽ�B�C���h�Ȃǂɓn�q���̂���Ⴊ�����B�_�ˎs�ł�1��10�`16���ɔ����͂��o���ꂽ2�l���猟�o���ꂽ�B1�l�͊C�O�n�q��������A����1�l�͓n�q�҂Ɛړ_���������B
1�����{�ɂ͓�����Ȏ��ȑ�̒����ŁA�����o�H�s���̊����҂�1�l���������B����̕��������y�����́u�֓����ł͎s�����������Ȃ��炸�n�܂��Ă���\��������v�Ǝw�E����B
���Y�����s�勳����ɂ��ƁA�a�`�D2�͊�����1�l�����ς��Ă����l���u�����Đ��Y���v���a�`�D1���18�������Ƃ����B���Y���͂��̈Ⴂ���u���Ȃ�傫���v�Ƃ�����ŁA���݂̗��s�s�[�N�̗\���ɂ��Ă��u�u�������ł�����݂������\��������v�Ǝw�E�B���ہA�f���}�[�N�ł̓s�[�N���}�����V�K�����Ґ����Ăё����ɓ]�����B�����A�C�O�̌����ł͓��@���X�N�̈Ⴂ�͌����Ȃ��Ƃ����B
���J�Ȑ��Ƒg�D��1�����{�A�a�`�D2�ɂ��āu�Q�m��(�S��`���)��͂ɂ�郂�j�^�����O���p������K�v������v�ƒB�����̘e�c�����E���������nj��������́u���@���ɍ����Ȃ��Ƃ̏������邪�A�����͍͂��̃I�~�N��������苭���x�����ׂ����v�Ƌ��������B
|
��1���D�y�s�̃R���i������1480�l�ȏ�̌����݁@6���A����1000�l���@2/1
1�����\�����D�y�s�̐V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�1480�l�ȏ�ƂȂ錩���݂ł��邱�Ƃ�������܂����B�D�y�s�̊����҂�1000�l����̂�6���A���ł��B�܂��A����s�ł͉ߋ��ő��ƂȂ�115�l�O��̊������m�F����錩�ʂ��ł��B
|
�����������c��̊g��[���@10���l�����芴���Ғ���1�T�Ԍ����ő��@2/1
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��I�~�N�������̊������}�g�債�A����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��������s�����ōő��ƂȂ��Ă��钖�c�㒬�B�ƒ�������Ȃǂ��������A���������̌��ʂ��������Ȃ����߁A����1��31���A�����̔F�肱�ǂ����Ə����w�Z�̗Վ��x�Z�̉��������߂��B�d�lj����X�N�̍�������҂ɂ��������L����B�\�h��ɓw�߂Ȃ�������������j���́u�N������������\��������v�ƌx����炷�B
���x�Z����
���c�㒬�ł͒���1�T��(24�`30��)�̐l��10���l������̐V�K�����Ґ�1549�E59�l�Ō����s�����ōł������A���S�̂�140�E85�l�̖�11�{�ɏ��B������1��3400�l�ɑ��A20�l�ȏ�̊����҂��A���m�F����Ă���B30���܂łɒ����ł͔F�肱�ǂ����Ə��w�Z�A���Z�A����Ҏ{�݂Ōv5�̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�������B����1�����܂łƂ��Ă������ǂ����Ə����w�Z�̗Վ��x�Z��2���܂ʼn��������B�E���͎{�ݓ������ł���Ȃǂ��Ċ��𐮂��Ă��邪�A�����̋��E�����������Ă���A�ĊJ�܂ł̓��͕s�������B�x�Z�ɔ������������т𒆐S�Ɉ玙�A�d���̗����ɋꗶ���钬��������B���H�X���c��50��j���́A�����̒ʂ����ǂ����ŃN���X�^�[���������A�����\�ł͉���8�l�A�E����2�l���������ċx���ƂȂ����B�Ȃ������̋Ζ��悩��߂�܂ŘA���A�����̐��b�����Ȃ���X�̎d���ݍ�ƂȂǂɓ������Ă���B�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p��悪�S���Ɋg�傳��A�j���͉c�Ǝ��ԒZ�k�ɉ������B���͋��͎x������邪�X�܂̒����Ȃǂ̎x�o�͂����ނ��߁A�x�Ƃ͑I�����ɓ���Ȃ��B�u��炵����邽�߁A�ł������̓w�͂𑱂��邵���Ȃ��v�ƔY�܂������̓������B
���ƒ������
������30��j����17������38�E3�x�̔��M������A��Ë@�ւło�b�q���������B�����A�z���������B�Q���������g�x�x���ς܂��ē��@�����B�����ȂǕ��Ǐ�̐l�͎��͂ɂ��炸�A�����o�H�ɐS������͂Ȃ��A�ی����̒����ł�������Ȃ��܂܂��B21���ɂ͓����Ƒ�7�l�̂����A5�l�̗z�������������B����������������j���ƍȁA���e�̓��N�`����2��ڎ�ς݂������B�Ǐ�͂���������ǏA���M���Ă������ɂ͕��M�ɖ߂����B�j���ȊO�̉Ƒ��͎���×{��]�V�Ȃ����ꂽ�B�ƒ���ŏ��܂߂Ȋ��C��h�A�m�u�ȂNj��p���������ł���ȂǑ��O�ꂵ���B�����A�c���Ǝ���3�l�̎q�ǂ��ƕ�炷���A�H���̏ꏊ������A�ڐG�����炵���肷���ɂ͌��E������Ƃ��������B�j���͊����͂̋����I�~�N�������̓����ɂ��āu�قƂ�ǏǏȂ��A���A�N���犴��������������Ȃ������v�Əq�ׁA�N�����������̉\��������Ǝw�E���Ă���B���V�^�R���i���{���̓R�b�v��^�I���ȂNj��L������A�����͌X�ɐ���t���ĐH�ׂ邱�ƂȂǂ��ƒ�������̑�Ƃ��ČĂъ|���Ă���B
|
�������s �V�^�R���i �a���g�p��50���� �d�NJ��җp��5.5���@2/1
�����s���̐V�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p���́A1�����_��50.7���ɂȂ�A�s���ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50�����܂����B�挎1����3.3���������s���̕a���g�p���́A�����g��ɔ������@���҂̋}���ŏ㏸�𑱂��A�挎17���ɂ�20�����܂����B�����̃y�[�X�͂���ɑ����Ȃ�A20�����Ă���1�T�ԗ]�肽�����挎26���ɂ�40�����Ă��܂����B������1���A�s���ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50�����A50.7���Ȃ�܂����B
����A�s�̊�ŏW�v�����d�ǂ̊��҂�1�����_��29�l�ł����A���̂����s���m�ۂ��Ă���a���ɓ��@���Ă���̂�28�l�ŁA�d�NJ��җp�̕a���g�p����5.5���ɂȂ�܂����B
|
��1���̓����s�̐V�K�����҂�1��4445�l�@8���A����1���l����@2/1
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA1��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�1��4445�l�B�d�ǎ҂͑O������3�l�����A29�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������90��܂ł�1��4445�l(�s��7�l)�B�N��ʂł�20�オ�ő���2824�l�A������30���2549�l�A������40���2279�l�ƂȂ��Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�1198�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�1��5397.0�l(�ΑO�T��159.1��)�B�s���̑���(�v)��59��2228�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����50.7��(3510�l�^6919��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T25��(1��2813�l)����1632�l�����A�������͖�1.1�{�B�V�K�����҂�1���l����̂�8���A���ƂȂ�܂����B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B |
���l���s�ŐV�K����430�l�ő��X�V�@�Ⴊ���Ҏ{�݂ŃN���X�^�[21�l���� �@2/1
1���A�l���s��430�l�̐V�^�R���i�V�K�����҂��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B (�֓c�s5�l�A�܈�s2�l�A���쒬1�l�A���O2�l���܂�)�@����܂ł̕l���s���\���̍ő�������29��345�l���A90�l�߂�����܂����B�����Ƒ����̊����܂��A��t�̔��f�ɂ�茟�����s�킸�Ǐ�ŗz���Ɣ��f����u�^���NJ��ҁv��25�l�܂܂�Ă��܂��B430�l�̂���30��ȉ�����6�������߂Ă��܂��B1�����݁A�l���s���̕a�@�ɓ��@����V�^�R���i�̊��҂�46�l�ŁA���������Ljȏ�́@11�l�ł��B
���N���X�^�[����
�Ⴊ���Ҏx���{�݁u�V��������@�ԏ����v�@���p��19�l�ƐE��2�l�̌v21�l�̊������킩��A�N���X�^�[�ɔF�肳��܂����B���p�҂�29����2�l�A30����12�l���M���A���p�ҁE�E��86�l�̌��������āA���p��14�l�ƐE��1�l�̗z�����������܂����B�����31���ɒlj�������Č��������ĐV���ɗ��p��5�l�ƐE��1�l�̊������킩��܂����B��������y�ǂł��B
���N���X�^�[�g��
���t���L���V�l�z�[���u����₩�͂܂܂فv�@�V���ɓ�����2�l�̊������킩��A�N���X�^�[��20�l�ɂȂ�܂����B���V�l�ی��{�݁u�G�[�f�����C�X�v�@�V���ɐE��2�l�Ɠ�����4�l�̊������킩��A�N���X�^�[��21�l�ɂȂ�܂����B
|
�����ɂ̊����ҁA��4900�l�@�ߋ��ő��X�V�̌��ʂ��@2/1
���Ɍ�����1���A�V���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�����҂͖�4900�l�ŁA�ߋ��ő����X�V���錩�ʂ��ł��邱�Ƃ��A�W�҂ւ̎�ނŕ��������B�����̐V�K�����҂�1��26�`30����4��l���A����܂ł̍ő��͓�29����4724�l�������B
|
���R���i��6�g�A����ŕ������S��@������������\�ց@�I�~�N�����������@2/1
���ꌧ��1��31���A�V�^�R���i�E�C���X�֘A�Ŗ����\�̎��S�Ⴊ���Ⴀ�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B1�����{�Ɏn�܂�����6�g�Ȍ�Ɋm�F���ꂽ���S��ŁA�⑰��ی����Ɣ��\���e�����Ƃ����B������A�����Ɍ��\����B�����̐V�K�����҂�480�l�ŁA7���A���Ő�T�̓����j������������B500�l�������̂�1��4���ȗ��A27���Ԃ�B�ČR�W�̐V�K�����҂�98�l�������B�@
��6�g�Ō������\�ς݂̎��S��́A1��9���ɖS���Ȃ���70��j����1��̂݁B����1��ȊO�ɁA���S�Ⴊ��������Ƃ����B�I�~�N�������̊����҂Ƃ݂���B���͌����_�Ŏ��҂̐l����N��A���ʂȂǂ𖾂����Ă��炸�u���S��̌��\�̗���ɉ����ď������Ă���B�菇��ő��₩�Ɍ��\����v�Ɛ��������B
�s�����ʂ̐V�K�����҂͓ߔe�s���ő���134�l�B�Ί_�s��2�Ԗڂɑ���47�l�������B�Ί_�s�͏����w���̊����������A10�Ζ�����10���39�l���߂��B
���S�̂̓��@���҂�440�l�ŁA����̏d�ǂ�6�l�A�����ǂ�280�l�������B���́u�V�K�����҂͌����X���ɂ��邪�����ǂ͌����Ă��炸�A���@�̃s�[�N�͌����Ă��Ȃ��v�Ɛ������A��ÕN��(�Ђ��ς�)�ւ̌x�����ɂ߂Ă��Ȃ��B
�ČR�́A��n�������݂̂���Ă���1��28�`30���̐V�K�����Ҍv448�l�ɂ��āA��n�ʂ̓�������\�����B1��30���̊����҂�89�l�ƕ��Ă������A88�l�ɒ��������B |
���w�Z�ȂǂŊ����g��g�I�~�N�������̓������܂������h�R�ۑ�b �@2/1
�R�ېV�^�R���i���S����b�́A�w�Z��ۈ�{�݂ȂǂŊ����������L�����Ă���Ƃ��āA�I�~�N�������̓����܂��������ƂɌ������Ă��炤�l���������܂����B
�V�^�R���i�̋}���Ȋ����g�傪�������A��ɃI�����C���ŊJ���ꂽ�S���m����̉�ł́A���݂̐��{�̑�̓I�~�N�������̓����ɍ����Ă��Ȃ��Ƃ��āA�ƒ��w�Z�A�E��Ȃǂł̑������ɋ������ׂ����Ƃ����ӌ����������܂����B
����Ɋ֘A���A�R�ېV�^�R���i���S����b�́A�t�c�̂��ƋL�Ғc�ɑ��u�I�~�N�������̓������Ԃ��Ɍ��Ă����ƁA�m�����w�E����Ă���悤�Ɉ��H�X���������Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu�w�Z��ۈ�{�݂Ȃǂő����L�����Ă���̂������Ȃ̂ŁA����܂��ĕ��ȉ�ŋc�_���Ă����������ƂɂȂ�Ǝv���v�Əq�ׁA�I�~�N�������̓����܂����w�Z�Ȃǂł̑����ƂɌ������Ă��炤�l���������܂����B
����A�����s�̏��r�m�����A�ǂ̂悤�ȏɂȂ�ً}���Ԑ錾�o����̂��Ƃ������l�����Ȃǂ��u��{�I�Ώ����j�v�ɖ��L����悤���߂Ă��邱�Ƃɂ��āA�u�����s�Ƃ͔��ɖ��ɃR�~���j�P�[�V�������Ƃ��Ă��邪�A�s���ȂƂ��낪����Ȃ�A�ǂ̂悤�ɑΉ����Ă�������������R�~���j�P�[�V��������葱�������v�Əq�ׂ܂����B
|
�����E�̊�����3��7504���l : �č�7433���l�A���E�S�̖̂�2����߂�@2/1
�ăW�����Y�E�z�v�L���X��w�̏W�v�ɂ��ƁA���E�̐V�^�R���i�E�C�������҂͓��{����31���A�ߌ�8�����_��3��7504.58�l�ƂȂ��Ă���B���E�ő�̊������ł���č��͗v7433.6���l�A���E�S�̂ɐ�߂銄����19.8%�B�č��̒���4�T�Ԃ̊����Ґ���1907.0���l�Ƌ��ٓI�ȃX�s�[�h�Ŋ������g�債�Ă���B�č��Ɏ����Ő[���ȏɊׂ��Ă���̂����B�ŁA���Ƀt�����X�͗v�����Ґ���1918.0���l�A����4�T�Ԃ�882.26���l�B�p���A�C�^���A�A�X�y�C���ł������Ґ��������I�ɑ����Ă���B�v�̊����Ґ���2�ʂ̃C���h��4130.2���l�A3�ʂ̃u���W����2536.1���l�B�C���h�͈ꎞ���A�����g��y�[�X�����������Ă������A�����ɂ��čĂы}���ɓ]���Ă���A����4�T�Ԃ̐V�K������638.0���l�ƂȂ��Ă���B
|
���č��@40�B�ŐV�K�����Ҍ����E�I�~�N�������s�[�N�z�� �@2/1
40�B�ŐV���Ȋ����Ґ��͌����Ă���B�I�~�N�����̓s�[�N���z���Ă���B�������č��ł͕��ς��Ė���54��3000�l�̐V�K�����҂��o�Ă���B�q�ǂ��̊����Ґ��͐�T���猸���Ă���B���ӍՂ��珉�߂Ă̌����B��������T������80��8000�l�̎q�ǂ������������B�ی����ǂ͎q�ǂ������N�`����ڎ킵���̐V�����ψكE�C���X�ɔ�����悤�Ăт����Ă���B
15�B�łh�b�t�̕a�����ˑR�s���B
�j���[���[�N�s�ł͐V�^�R���i�̎��Ö�Ƃ����V�����R�E�C���X�������ɓ͂���v��������������Ă��邪�A���̑��̒n��ł͂��̂悤�Ȗs�����Ă���B
|
���C���h�A��s�s�ŃI�~�N�������u�}���v�c�u�s�[�N�͉߂����H�v�@2/1
�V�^�R���i�E�C���X�����ǁg�I�~�N�������h�̊g�U�ɂ��n�܂����C���h�� �h��3�g�h���u�s�[�N���߂������̂Ƃ݂���v�Ƃ����������Ă���B
30��(���n����)�����p���V���u�C���f�B�A���E�G�N�X�v���X�v�ȂǃC���h���f�B�A�ɂ��Ɓu���������̊ԁA�C���h�̑�3�g���s�[�N�ɒB�����Ƃ݂���v�Ƃ��������X�Ɠ`�����Ă���B�u�����͂̋����I�~�N���������}���Ɋg�U�������s�[�N�ɒB������A�����ɓ]���闬����}�������v�Ƃ��������ł���B
�C���h�̐V�^�R���i�u��1�g�v��2020�N9�����������A��N��4�`6���ɂ� �g��g�U�h�ɂ��u��2�g�v�ɋꂵ�߂�ꂽ�B��2�g�̎��͈���̐V�K�����Ґ���41���l�܂ŏ㏸���A����̑�3�g�̎��͐挎(1��)21��34��7254�l�̊����҂����ꂽ�B
�����ŋ߁A�V�K�����Ґ����������n�߁A31���ɂ�20��9918�l�ƏW�v���ꂽ�B�C���f�B�A���E�G�N�X�v���X�́u�S�Ă̎w�W�𑍍����Ă݂�ƁA��3�g�͂��łɃs�[�N�ɒB�������̂Ƃ݂���v�Ƃ��u���㊴���Ґ��������邱�Ƃ͂��蓾�邪�A���ɍ����������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�v�Ɠ`�����B
���Ɏ�s�j���[�f���[�A�ő�o�ϓs�s�����o�C�Ȃǂ̑�s�s�̊g�U�́A�����ɒ��܂���݂��Ă���B�j���[�f���[�̏ꍇ�A�挎14���ɂ�2��8867�l�܂ő������Ă������A���̓�3674�l�Ɍ������Ă���B�s�[�N���߂�����A17���ԂŊ����Ґ���87%�قnj����������ƂɂȂ�B
�����o�C�����̓�1160�l�ƏW�v����A�ō��l���L�^�����挎8����2��971�l����傫���������Ă���B���Ƃ����́u���̂悤�ȑ�s�s�̏ꍇ�A�C�O����̗��s�q�Ȃǂ�ʂ��ăI�~�N����������ɗ����������A���̕��s�[�N���������B�������̂Ƃ݂���v�Ɛ��������B
|
�����]�ȍY�B�s�A�u�I�~�N�����v�����Ґ����v�u96�l�v�Ɂ������@2/1
���](��������)�ȉq�����N�ψ���̔��\�ɂ��ƁA1��31���̈���ş��]�Ȃɂ�����13��̐V�^�R���i�E�C���X�����Ⴊ���ꂽ�B13��̊����҂͑S�ğ��]�Ȃ̍Y�B(�������イ)�s�Ŋm�F����Ă���A���łɏW���u������Ă����l�����̒����猩�������B����Y�B�Ŕ��������u�I�~�N�������v�̊����́A1��26���`31���܂łŌv96�l�̊����m�芳�҂�����Ă���B
����29���ȍ~�́A�S�Ă̐V�K������(29���F19��A30���F24��A31���F13��)���W���u���A�O�o�����Ȃǂ̊Ǘ��[�u������Ă��钆���猩�����Ă���A���]�Ȃ͎Љ�I�Ȋ����g��̃��X�N�́A��{�I�ɗ}���ł������̂ƌ��Ă���B |
���؍��̐V�^�R���i�V�K�����ҁu1��8343�l�v�A�Ăщߋ��ő����X�V�c�@2/1
�؍��̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂��I�~�N�������̊g�U�ɂ��ߋ��ő��l��A���X�V���Ă���B
�����h�u���{���ɂ��ƁA1���ߑO0����̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�1��8343�l���������B�V�K�����҂�1��8000�l����̂͂��ꂪ���߂Ă��B�S���̂��������ŏW�c���������o���Ă���A�V�K�����҂�3���A����1��7000�l�ȏ���L�^���Ă���B
���������̐V�K�����҂�1��8123�l�A�C�O�����̊����҂�220�l�Ɗm�F���ꂽ�B���傤�܂ł̗ݐϊ����҂�86��4042�l(�C�O����2��5516�l)���B���@���̏d�ǎ҂�272�l�A���S�҂�17�l�A�ݐώ��S�҂�6772�l(�v����0.78%)���B
����A1���ߑO0����̐V�^�R���i�E�C���X���N�`��1���ڎ�҂�591�l�A2���ڎ�҂�949�l�A3���ڎ�҂�1��8987�l���B�ݐ�1���ڎ�҂�4464��1142�l�A2���ڎ�҂�4399��6241�l�A3���ڎ�҂�2725��4256�l���B
�@ |
���ΐ�Łu�܂h�~�v7������ĉ��� �X�̔����� 3/7
�܂h�~���d�_�[�u�͐ΐ���܂ޑS��18�̓s���{���ŁA7�����獡��21���܂ōĂщ�������܂����B�o�ϓI�ȑŌ����鉷��X����͔ߒɂȐ��������������ŁA����ł͎Ⴂ����𒆐S�Ɋό��q�̎p�����X�ɖ߂��Ă���ȂǁA�����͂��ȏ������Ă��܂��B
�܂h�~���d�_�[�u�̓x�d�Ȃ鉄���ɁA����s�R������A�n�Ɩ�60�N�̗������فu�Ӓ��v�̎В��E�O�J�C�i����͗��_�̐F���B���܂���B
�u�g�܂����h�Ƃ����̂������ȋC�����v(�O�J�C�i����)
�������R���i�ЂŁA�R������͒����g���l�����o�����ɂ��܂��B2019�N��42���l�߂������h���l�������̗��N��2020�N�ɂ�25���l�]��ɁB�����āA���N��17���l�������܂����B
�u�Ƃɂ����o�ς��Ă����A�����Đl�����Ă����B���������Ă��͖̂{���Ɍl�̓w�͂����ł͂Ȃ��Ȃ��������ɂȂ��Ă���v(�O�J�C�i����)
���̈���A���X�ɓ��킢�����߂�����̂͋���̒��S���ł��B
�s�L�҃��|�[�g�t�u�ό��q�͎Ⴂ�l�����������܂��B�݂Ȃ���ۖ�̑O�Ōg�т�Ў�Ɏʐ^���B���Ă��܂��v
�V���Ⓑ��Ȃ�13�̌���7������d�_�[�u�������B���̉e���������Ă��A�t�x�݂𗘗p���ė��s�ɖK���w���̎p���ڗ����܂��B
�u��������Ă��g�܂����h�Ƃ��������B�����������N�O���炢�������痷�s�����Ȃ��v�u�܂h�~�����������Ƃ�(�\��)�������ǁA���т�������̂ł��傤���Ȃ����Ǝv���āv�s��������̊ό��q�t
����s���̑䏊�E�ߍ]���s��B�������̏d�_�[�u���������ꂽ���N6���̗l�q�Ɣ�ׂ�ƁA���炩�ɐl�o�������Ă���̂��킩��܂��B
�u2��3���Ƃ���ς��w�����S�ɏT���͑����C������B�݂Ȃ������ς蓮����Ă���͓̂�����Ă���Ǝv���v(������Y�E�r�ؐꖱ)
�u1�T�Ԗ����̂悤�ɋ߂����痈�Ă������ǁA1�T�Ԉ�2���炢���������ɗ��܂���B(�ό��q��)���Ă����ȂƂ������Ȃ����c���̕�����������������ƋC�����Ă������Ƃ��Ă��Ă�������v�s�������q�̏����t
���ӂ̌��̑�������������钆�A�ΐ쌧���ł͂���2�T�ԑ����d�_�[�u�B���ʂ����邤���Ŋό������E�ΐ�Ȃ�ł͂̉ۑ�����肻���ł��B |
 |
���u�܂h�~�v18�s���{���ʼn����c���������g�����h�@3/8
�����Ȃ�13����7���A�u�܂h�~���d�_�[�u�v����������܂����B
����A��s������Ȃ�18�s���{���ł́A21���܂ł̂��悻2�T�Ԃ̉����ł��B
�u�܂h�~�[�u�v�����E���������F�u�����ɂ́A(������)������Ƒ������ȂƁv�u����Ŏ��܂��Ă����Ƃ����ł����ǁA����1���Ȃ����ȂƎv���܂����ǂˁv
7���A�����s�Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂́A��T�̌��j������4258�l����A5374�l�ł����B6000�l�������̂́A1��18���ȗ��A���悻1�J�����Ԃ�ł��B�s�c��ł́A���H�X�́g�s�������h�������āA���₪��т܂����B
�����}�E���c�s�c�F�u���R�ƍs���������s���̂ł͂Ȃ��A�ǂ�������c�Ƃ𑱂��邱�Ƃ��ł���̂���^���ɍl���Ē��������v
���r�s�m���F�u���R�ƍs�����K�����Ă���킯�ł͂���܂���B���Ǝ҂̉c�ƁA����̎��Ԃɑ������������̂���d�g�݂ƂȂ�悤�ɁA�s���猻��̐����܂߂āA�v�����Ă���Ƃ���ł���܂��v
|
���d�_�[�u�ĉ����@�o���헪��������̂��@3/8
�V�^�R���i�E�C���X��̂܂h�~���d�_�[�u���A���s�Ȃ�18�s���{����21���܂Ŗ�2�T�ԉ������ꂽ�B
�S���̐V�K�����Ґ��͌����Ă��邪�A�a���g�p���͓s�s���Ȃǂō��~�܂肵�Ă���B�[�u�̉����͂�ނȂ��B
�V�ψي��u�I�~�N�������v�̊g��ɂ�闬�s�u��6�g�v�́A����܂łƂ͗l�����قȂ�B��5�g�ł́A���N�`����2��ڎ�̐i�W�ƂƂ��Ɋ����Ґ����}���Ɍ��������A��6�g�̌����y�[�X�͊ɂ₩���B
���Ґ��͘A���̂悤��200�l���Ă���B�~�}����������ƂȂ鎖�Ă������Ă���A��Â�ی����Ɩ��̕N��(�Ђ��ς�)�͑����Ă���B��芴���͂̋����I�~�N�������̔h���^���m�F����Ă���B
���{�͓����A31�s���{���ɏo���Ă����d�_�[�u��������6���Ɉ�Ăɉ������邱�Ƃ��������Ă������A�ڎZ���O���`�ƂȂ����B
���̗v���̈�́A����̊����҂̑������B��b����������l���S���Ȃ鎖�Ⴊ���Ȃ��Ȃ��B
�a���g�p�����A���{�⋞�s�{�ł�2�����_��70�������B
���������̉��P�Ɍ����A3��ڐڎ�Ɋ��҂��W�܂邪�A���{�̎��g�݂͒x��Ă���B
�ݓc���Y�́u1��100����v�̖ڕW���f���Đڎ�����������Ă��邪�A3��ڂ��I�����l�͂܂��l���̖�2���ɉ߂��Ȃ��B
�t�@�C�U�[�А��ɐl�C����Ȃǂ̖��_���w�E����Ă���A�L�����╛�����Ɋւ��鐳�m�ȏ��Ǝ����̂ւ̎x���̋��������߂���B
�R���i�Ђ̒������ŁA�d�_�[�u�Ȃǂ̌��ʂƁA�o�ϊ����ւ̉e��������A���Ƃ⎩���̂̈ӌ���������Ă���B
����̍ĉ����ɍۂ��A���{�̊�{�I�Ώ����j���ȉ�ł́A�d�_�[�u�̉�����2�l�̈ψ����������B�d�lj������Ⴂ�Ƃ����I�~�N�������̓����ɉ�������ŏ\���A�Ƃ̌����������ꂽ�Ƃ����B
��B�̊e�{���ł́A�F�{��������v�������̂ɑ��A�����Ґ���a���g�p���Ȃǂ̎w�W����舫�������������ɓ��ݐ�ȂǑ����݂����ꂽ�B
10��ȉ��̊����������������Ă��邱�Ƃ���A���H�X�̎��Z�c�ƂƎ�ޒ����𒌂Ƃ���]���Ɠ��l�̑�ɂ��āA���ʂ��^�⎋���鐺������B
���{�́A���ݖ�̕��y��3��ڐڎ�̐i�W�Ȃǂ܂��A�V���ȉ������o���헪�������K�v������B������ւ̍����̗����Ƌ��͂�w�͂��������Ȃ��B |
�����c�Ǝ҂��{���Ă���@�R���i�d�_�[�u�����Łu�x�����Ȃ��v38���Ɂ@���_�����@3/8
1���A�ݓc�����ɂȂ��ď��߂āA�V�^�R���i�E�C���X�̊����h�~��Ƃ��Ắu�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����܂����B2���ɂ͓�������Ȃǂւ̉��������܂�܂����B�d�_�[�u���������A�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�Ȃǂ����߂��Ă�����H�X�ւ̑Ō��͑傫���Ȃ�܂��B�����V����2��19�`20���Ɏ��{�����S�����_�����ł́A�u���c�Ǝҁv�̕s�����ɂ��ݏo�Ă��܂����B
���d�_�[�u�����u�悩�����v6����
�u���c�Ǝҁv�ɂ͈��H�X�W�҂炪�܂܂�Ă���Ǝv���܂��B2���ɓ����A�����܂߂��S����30�قǂ̓s���{���ŁA���{���d�_�[�u�̉��������߂����Ƃɂ��Đq�˂܂����B����ƁA�S�̂ł́u�悩�����v�Ɠ������l��69���A�u�悭�Ȃ������v��21����傫������܂����B�����A�u���c�Ǝґw�v�ł́u�悩�����v��59����6���������A�u�悭�Ȃ������v��33���ŁA���̍��͏k�܂��Ă��܂����B
�@�@�@���u�܂h�~���d�_�[�u�v�̉���������c�c
�y�S�́z�悩����69���E�悭�Ȃ�����21��
�y���c�Ǝґw�z�悩����59���E�悭�Ȃ�����33��
���ݓc�����u�x�����Ȃ��v�����A�ł�����
���������s���́A�ݓc�����ւ̕]���ɒ������Ă��܂��B�ݓc���t���x�����邩�������Ƃ���A�S�̂ł́u�x������v��45���A�u�x�����Ȃ��v��30���������̂ɑ��A���c�Ǝґw�́u�x������v��34���A�u�x�����Ȃ��v��38���ł����B����̒����ł́A�ݓc����������A���߂ĕs�x�����S�̂�3����ɏ��܂������A�E�ƕʂł��̊������ł����������̂����c�Ǝґw�ł��B
�@�@�@���ݓc���t���c�c
�y�S�́z�x������45���E�x�����Ȃ�30��
�y���c�Ǝґw�z�x������34���E�x�����Ȃ�38��
�y�����E�Z�p�E�w�z�x������47���E�x�����Ȃ�29��
�y�����E�T�[�r�X�]���ґw�z�x������43���E�x�����Ȃ�30��
�y��w�w�z�x������46���E�x�����Ȃ�29��
�y���̑��E���E�w�z�x������48���E�x�����Ȃ�31��
���́u�w���́v�ł��ω����c�c
����ł́A���c�Ǝґw�̐����ɑ���]���́A����܂łǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă����̂ł��傤���B�����ł͐V�^�R���i�E�C���X��ɑ��Ắu�w���́v��₤������Ŕ�ׂĂ݂܂����B���{�W�O�ɂ���2020�N5���ɁA���`�̎ɂ���20�N10����12���A21�N1���ɁA�����Ċݓc�ɂ��Ă͍��N1����2���ɕ����Ă��܂��B����܂ōł��S�̂ƍ����J�����͍̂ŏ��ً̋}���Ԑ錾���o�Ă���20�N5���A���{�ɑ���]���ł����B�w���͂��u�������Ă���v�Ɠ������l�͑S�̂�30���ɑ��A���c�Ǝґw��17���ɂƂǂ܂����̂ł��B����͂���ȗ��̍����J���A�S�̂ł�34�����u�������Ă���v�Ɠ������̂ɑ��āA���c�Ǝґw�ł�21���ɂƂǂ܂�܂����B
�@�@�@���R���i��Ŏ��w���͂��u�������Ă���v�Ɠ����������́c�c
�y2020�N5/16�`17�z�S��30���E���c�Ǝґw17��
�y10/17�`18�z�S��26���E���c�Ǝґw23��
�y12/19�`20�z�S��19���E���c�Ǝґw24��
�y2021�N1/23�`24�z�S��15���E���c�Ǝґw 17��
�y2022�N1/22�`23�z�S��37���E���c�Ǝґw34��
�y2/19�`20�z�S��34���E���c�Ǝґw21��
�����Ă̎Q�@�I�ɉe����
������������͍��Ă̎Q�@�I�̕[�̍s���ɂ��e����^���邩������܂���B����œ��[���������}�����Ƃ���A�����}�Ɠ������l�͑S��34���ɑ��A���c�Ǝґw��23���ɂƂǂ܂�܂����B�M�ƂȂ��Ă���Ƃ݂���̂����{�ېV�̉�ŁA�S�̂�16���������̂ɑ���21���ƁA�����}�ɔ��鐨���ł����B���Ȃ݂ɖ�}��1�}�ł��闧������}��9���ł����B��N10���̏O�@�I�����ɍ��킹�čs���������ŁA�O�@�I����œ��[���������}�����Ƃ���A���c�Ǝґw�̎x���͗���13���A�ېV9���ł����B�c�Ȃ����炵���O�@�I�̌���A�����͋ꂵ����Ԃ������Ă��܂��B3��6������������������̏d�_�[�u�ł����A���{�͍Ăѓ����A�����܂߂�18�s���{���ɂ���21���܂ʼn������邱�Ƃ����߂܂����B���̌��f�����c�Ǝґw�̎x���ɂǂ̂悤�ȉe����^���邩�A���������݂Ă��������Ǝv���܂��B
�@�@�@�����ɂ��܁A�Q�@�I����ɓ��[����Ƃ�����c�c
�y�S�́z�����}34���A��������}12���A���{�ېV�̉�16���A���̑��̐��}18���A�����Ȃ��E������Ȃ�20��
�y���c�Ǝґw�z�����}23���A��������}9���A���{�ېV�̉�21���A���̑��̐��}25���A�����Ȃ��E������Ȃ�24��
�@ |
���R���i�j����A���H�Ƃ�500���ɔ���@�v�ł�3023���Ɂ@3/8
3��8����16�����_�Łu�V�^�R���i�v�֘A�̌o�c�j����(����1000���~�ȏ�)��8�������A�S���ŗv2882��(�|�Y2748���A�ٌ�m��C�E������134��)�ƂȂ����B
2021�N��2���ȍ~100�������������A9���ȍ~��4�J���A���ōő����X�V�A12���͉ߋ��ő���174�����L�^�����B2021�N�̔N�Ԍ�����1718���ɒB���A2020�N��843���ɔ�ׂĖ�2�{�ɑ��������B
2022�N1����113����5�J���Ԃ�ɑO��������������A2����153���ƑO����啝�ɏ���A13�J���A����100�������B3����8�����݂�55���ƍ������������Ă���B
�|�Y�W�v�̑ΏۊO�ƂȂ镉��1000���~�����̏��K�͓|�Y�͗v141�������B���̌��ʁA����1000���~�������܂߂��V�^�R���i�E�C���X�֘A�j����͗v��3023���ƂȂ����B
�u�܂h�~���d�_�[�u�v�K�p�n��̖����A�����̊������牄�������B�����Ґ������~�܂肵�A�S���I�ɉe��������������Ȃ��ʼnc�Ƌ@��������Ă�����H�Ƃ�A�O�o���l�Ȃǂɂ�����֘A��Ƃ̔敾���������Ă���B
����x���A���Z�@�ւɂ�郊�X�P�Ή��Ȃǂ͌p�����錩�ʂ������A�Ɛѕs�U�̒������ʼnߏ���Ɋׂ�����Ƃ��ڗ����Ă���B����₠����߂ɂ��E�������X�ɑ����A�R���i�j����͓��ʁA�������Ő��ڂ���Ƃ݂���B
�y�s���{���ʁz(����1000���~�ȏ�)�@�`100���ȏ��8�s���{���Ɂ`
�s���{���ʂł́A�����s��614��(�|�Y593���A������21��)�ɒB���A�S�̂�2����(�\����21.3��)���߁A�ˏo���Ă���B�ȉ��A���{297��(�|�Y283���A������14��)�A������141��(�|�Y134���A������7��)�A�_�ސ쌧(�|�Y127���A������4��)�ƈ��m��(�|�Y131��)���e131���A���Ɍ�129��(�|�Y124���A������5��)�A��ʌ�103��(�|�Y93���A������10��)�Ƒ����B8���͑��{��2���̂ق��k�C���A���쌧�A�����s�A���Q���A�L�����A���ꌧ�Ŋe1�����������B10��������2���A10�`20��������10���A20�`50��������20�{���A50���ȏ�100��������7���A100���ȏ��8�s���{���ɍL�����Ă���B
�y�Ǝ�ʁz(����1000���~�ȏ�)�`���H���ő���490���A���݁A�A�p�����A�H�i���A�h�������� �`
�Ǝ�ʂł́A���X�q�̌����A�x�Ɨv���ȂǂőŌ��������H�Ƃ��ő���490���ɋy�ԁB�u�܂h�~���d�_�[�u�v�K�p�n��ł͉c�Ɛ����������A�o�c�̗͂̏��Ղ₠����߂ɂ����H�Ƃ̐V�^�R���i�j������ɑ�������\�������܂��Ă���B�����ŁA�H���v��̌������Ȃǂ̉e���������Ƃ�307���A�����X�̋x�Ƃ��e�������A�p�����֘A(�����A�̔�)��226���B���̂ق��A���H�ƂȂǂ̕s�U�Ɉ��������Ă�����H���i�����Ƃ�130���B�C���o�E���h�̎��v�����◷�s�E�o���̎��l���e�������z�e���C���ق̏h���Ƃ�116���ƁA��ʂ��߂Ă���B
�y���z�ʁz(����1000���~�ȏ�)
���z����������2839���̕��z�ʂł́A1�疜�~�ȏ�5�疜�~�������ő���1073��(�\����37.7��)�A������1���~�ȏ�5���~������918��(��32.3��)�A5�疜�~�ȏ�1���~������526��(��18.5��)�A5���~�ȏ�10���~������167��(��5.8��)�A10���~�ȏオ155��(��5.4��)�̏��B����1���~������1599��(��56.3��)�Ɣ����ȏ���߂�B����A100���~�ȏ�̑�^�j�����6���������Ă���A���E���Ƃ�����Ƃ܂Ōo�c�j���L�����Ă���B
�y�`�ԕʁz(����1000���~�ȏ�)
�u�V�^�R���i�v�֘A�j����̂����A�|�Y����2748���̌`�ԕʂł́A�j�Y��2441��(�\����88.8��)�ōő��B�����Ŗ����Đ��@��122��(��4.4��)�A�����~������115��(��4.1��)�A���ʐ��Z��57���A��������12���A��ЍX���@��1���Ƒ����B�u�V�^�R���i�v�֘A�|�Y��9�������Ō^�̔j�Y����߁A�Č��^�̉�ЍX���@�Ɩ����Đ��@�̍��v��1�������ɂƂǂ܂�B�Ɛѕs�U�������Ă����Ƃ���ɐV�^�R���i�̃_���[�W���Ƃǂ߂��h���������ŒE������P�[�X���唼�B��s���̂߂ǂ��������A�Č��^�̑I����������Ƃ���������ƂȂ��Ă���B
�y�]�ƈ����ʁz(����1000���~�ȏ�)
�u�V�^�R���i�v�֘A�j����̂����A�]�ƈ���(���Ј�)����������2736���̏]�ƈ����̍��v��2��7479�l�ɂ̂ڂ����B2736���̓���ł͏]�ƈ�5�l������1561��(�\����57.0��)�ƁA�����ȏ���߂��B�����ŁA5�l�ȏ�10�l������535��(��19.5��)�A10�l�ȏ�20�l������332��(��12.1��)�Ƒ����A�]�ƈ��������Ȃ����K�͎��Ǝ҂ɁA�V�^�R���i�j���W�����Ă���B�܂��A�]�ƈ�50�l�ȏ�̔j�����2021�N�㔼��(1-6��)��17���A������(7-12��)��15���B2022�N��6���������Ă���B�@ |
���C�x���g�l���A����P�p�ց@�܂[�u���A�����s�v�� �@3/9
���{��9���A�V�^�R���i�E�C���X�Ή��̂܂h�~���d�_�[�u�̓K�p���Ŏ��{���Ă����K�̓C�x���g�̐l�������ɂ��āA�������o���Ȃ��ȂLj��̊������O��ɓP�p������j���ł߂��B����܂ł͏���P�p�ɂ͑S���������K�v���������s�v�Ƃ���B11���ɂ��J���V�^�R���i�����ȉ�Ő��Ƃ̗����āA���T���肷��������B
���{��2��25���ɊJ�������ȉ�ł����̈Ă������A�����Ɍ����Ē�����i�߂Ă����B
���݁A�d�_�[�u���̃C�x���g�ł́A�}�X�N���p��吺���o���Ȃ��Ȃǂ̑�荞�u�����h�~���S�v��v�̍���������ɁA2���l�̏�����ݒ肳��Ă���B
|
 |
���d�_�[�u�����n��Ȃ�15���őO�T��芴�����@�R���i���Ƒg�D�@3/9
�V�^�R���i�E�C���X��������J���Ȃɏ���������Ƒg�D��9���̉�ŁA�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ�ꕔ�n��ŁA�V�K�����҂̑����X�����݂��邱�ƂɌ��O���������B�����Ŏ嗬�̃I�~�N���������A�����͂���荂���Ƃ����ʌn���́uBA.2�v�ɒu������錜�O��A�l�̈ړ���������N�x�����}���邱�Ƃ������A�e�c�����E���������nj��������́u�����g��̗v���ɂȂ�v�Ƃ����B
�S���̐V�K�����҂͒���1�T�Ԃ�10���l������329�E02�l�ŁA�O�T��0�E90�{�B���ׂĂ̔N��Ō����X���������B����A2��20���ɐ�s���ďd�_�[�u���������ꂽ�R�`�A�����A�R���A����̊e����A����6���ɉ������ꂽ�����A���m�ȂǁA15���ł͑O�T�����������B���ꌧ�ł�2�����{���瑝���X���������B
���������nj������̐��v�ł́ABA.2��4��1�T�ڂ�78%�܂Œu�������\��������Ƃ����B���Y���E���s�勳���̎��Z�ł́A������1�l�����l���������Ă��邩�������u�����Đ��Y���v�������Ŏ嗬�̃I�~�N����������26%�����Ƃ����B
���Ƒg�D�͂���܂ŁA�I�~�@�E�E�E
|
������ ��T�䌸��1���l���� �S���̏d�ǎ҂͌����X�� �@3/9
�S���ł�9���A6��3,725�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�B
�����s�ŐV���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A1��823�l�ŁA��T���j�����1,870�l����A�s���̐V�K�����Ґ��́A4���Ԃ��1���l���������B9���̊����҂̂����A�݂Ȃ��z���҂�528�l�B�܂��A�S���Ȃ����l��28�l�������B�I�~�N�������̓������ӂ܂����w�W�ɂ��d�ǎ҂�208�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����25.9%�ƂȂ��Ă���B
���̂ق��A���{��7,080�l�A�_�ސ쌧��5,748�l�A���m����4,638�l�ȂǁA�S���ł́A6��3,725�l�̊����ƁA213�l�̎��S���m�F����Ă���B����A8�����_�ł̐V�^�R���i�E�C���X�̑S���̏d�ǎ҂�1,321�l�ŁA�O�̓�����27�l�������B |
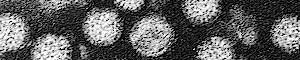 |
���V�^�R���i �V�K�����u�������ɂ₩�v�@�uBA.2�v5��1�T�ɂ�98���@3/10
�V�^�R���i�E�C���X��������J���Ȃɏ���������Ɖ���J����A�V�K�����Ґ��ɂ��āA�u�S���I�Ɍ���Ό����X���ɂ��邪�A�X�s�[�h�͊ɂ₩�ȏv�ƕ��͂����B
�e�c�����u�p���I�Ɍ����X��������ꂽ��N�̉Ă̊����Ƃ͈���āA�V�K�����Ґ��̌������ɂ₩�ɂȂ��Ă��܂��v�܂��e�c�����́A���ݎ嗬�̃I�~�N��������芴���͂������Ƃ����ʌn���́uBA.2�v�ɒu�������A�u�ēx�����ɓ]����\��������v�Ǝw�E�����B
��Ŏ����ꂽ���������nj������̐��v�ł́A�ŏI�I�ɑS�ẴE�C���X���uBA.2�v�ɂȂ邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�uBA.2�v��4���̑�1�T�ɂ�78���A5���̑�1�T�ɂ�98�����߂�Ɛ��肵�Ă���B
|
���I�~�N�����Łg�y�ǎ��h���}�����c��t�́u�x����莝�a�̈����v�Ǝw�E�@3/10
�u�V�K�����Ґ��������Ă��āA���̒��ɂ́w�I�~�N�������͏d�lj����Ȃ��x�w��6�g�̓s�[�N�A�E�g�����x�Ƃ������y�Ϙ_���o�Ă��܂����A�����ǂ�d�NJ��҂�f�Ă����Ì���ł́A��6�g�͂܂��I����Ă��Ȃ��B�}���Ɋ��Ґ�������������5�g�Ƃ͈قȂ�A���@���҂��܂���������Ȃ��Ƃ����̂�����ł��v
�������̂́A�R���i���Â̍őO���œ����A��ʈ�ȑ�w������ÃZ���^�[�̉��G���������B
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���2��11�����s�[�N�ɏ��X�Ɍ������Ă��Ă��邪(1�T�ԕ��ϒl)�A�d�ǎҁE���S�Ґ��́A�s�[�N���}�����Ƃ͌����(�O���t�Q��)�B
����ɒ��ڂ��ׂ��Ȃ̂��A�R���i��6�g�ɂ��u�v�����v���u�d�lj����v�����錻�ۂ��������Ă���_�B�����s�̃P�[�X�ł́A60��ȏ�̏d�lj�����0.35�������A�v������0.54���ɂȂ��Ă���̂�(������w�E���c�חS�y��������)�B�Ȃ����̂悤�Ȉُ펖�Ԃ��N�����Ă���̂��낤���H
�R���i�a���̂���A�ӂ��݂̋~�}�a�@�̎���W�@�����������B
�u�R���i�́w�d�ǁx�̊�́A�x�����N�����Đl�H�ċz��Ȃǂ�v�����Ԃł��B��5�g�܂ł̊��҂́A�ق�100���̐l���x�����N�����ĕa�@�ɉ^��A�l�H�ċz���ECMO(�l�H�S�x���u)�Ȃǂ̎��Â��o���g�d�NJ��ҁh�̏�ԂŖS���Ȃ��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�x�����N�����ɂ����I�~�N�������ɒu�����������6�g�ł́A�R���i�x���œ��@���銳�҂�10�l��1�l�قǁB�R���i�����ɂ�锭�M��̗͒ቺ�Ȃǂ��玝�a���������ĖS���Ȃ�P�[�X���}�����Ă���̂ł��v
�������̕a�@�ł́A���̎��Ԃ�ڂ̓�����ɂ����B
�u���N�ɓ�����60��1�l�A70��4�l�A80��2�l�̌v7�l�̊��҂��S���Ȃ�܂������A���S�f�f���Ɏ������g�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��x���h�Ə���������1�l�����܂���B�����́A�s���ǁA�x����A�뚋���x���A�}���t��Q�ACOPD(�x�C��)�̑����ȂǁB�R���i���҂Ƃ��Ă͌y�ǂł����A�����������̂͑S�ăR���i�������ł��B���Ƃ��Əd�x�̓��A�a�⍂�����A�]�����A����Ȃǂ̎��a������A�R���i�Ɋ����������Ƃ����������ŏǏ��������萊�サ���肵�Ĉӎ��������Ă��܂��B�܂��w�I�ɂ́w�d�ǁx�Ȃ̂ɁA�R���i���҂Ƃ��Ắw�y�ǁx�����ŖS���Ȃ��Ă��܂��̂ł��v(������)
���a���R���i�����ɂ���ďd�ĉ�����d�g�݂ɂ��āA��������w�����̈��m������w�Ō�w���̐����閾���������B
�u�S���a�A�������ǁA���A�a�A�t���a�A�ċz�펾���Ȃǂ͌��ǂ̏�Q���Ă��܂��B�R���i�E�C���X�́A���ǂ̍זE�Ɋ����������������A�����ŃE�C���X�������Č��ǂɃ_���[�W��^���܂��B�Ɖu���������Ƃʼn��ǂ��N���A�����̈����⌌�����ł��邱�Ƃ��B���Ƃ��Ǝ���Ă������ǂ̓������ቺ���Ď��a�̈����������̂ł��v
����Ɂu�뚋���x���v�Ŗ��𗎂Ƃ��l���ڗ��Ƃ����B
�u�뚋���x���Ƃ́A����̂ǂ̎G�ۂ��Ȃ�炩�̗��R�Ŕx�ɓ��荞�݁A�ۂ����B���ċN����x���B����҂̏ꍇ�A�I�~�N�������Ɋ������Ĕ��M�⌑�ӊ����N����ƁA�̂ǂ̋ؗ͂��ቺ���Đ���ɓ����Ȃ��Ȃ�A���̒��̎G�ۂ��H�ו�����t�ƈꏏ�Ɍ���ċC�ǂɓ����Ă��܂����Ƃ�����܂��BCT���B��ƁA�x�S�̂��^�����ɂȂ�R���i�x���Ƃ͈قȂ�A�E���̔x�̉����ɉ��ǂ��L����뚋�����L�̔x�����N�����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��v(����搶)
�@����̂ǂ܂ł̏�C���ő��B���₷���I�~�N�������B�{���A��C���ɂ͕a���̂Ȃǂ�f���o���h�q�@�\�����邪�A�̂ǂ̒ɂ݂���ɂ��A���̖h�q�@�\�ł���o���A�����Ȃ��Č뚋���x���������P�[�X������Ƃ����B
����Ɂg���a�̈����ɂ�鎀�S�h�Ƃ�����6�g�̓����ɂ���āA��Ì���ł͐V���Ȗ�肪�N���Ă���ƁA�������͌��B
�u��5�g�܂ł́A���@���҂̓R���i�x���������������߁A�d�lj�����ΐl�H�ċz����g���A�X�e���C�h�܁A�����f�V�x���Ȃǎ��Ö�őΏ����Ă��܂����B�Ώ��@�����肳��Ă��邽�߁A����Ӗ��A�����₷�������̂ł��B�������A�I�~�N�������̊����҂͂��܂��܂Ȏ��a���������邽�߁A���܂ł̂悤�Ȉ�ӓ|�Ȏ��Â��ʗp���܂���B�뚋���x���ɂ͍R���������g���A�S�s�S�̊��҂ɂ͌����������◘�A�܂��g�p����c�c�ȂǁA���a�ɍ��킹�����Â����߂���B�����ǂ̐��オ�t���A�S���A���A�a�̕���ɂ܂őΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ̂ł��B�w������È�x�Ƃ������݂����Ȃ��A���{�̏c�����Â̌��E���_�Ԍ����܂��v
�ł́g�R���i�y�ǁh�ɂ�鎀�S��h���ɂ́A�ǂ�������悢�̂��H
�u���S�Ґ������炷���߂ɂ��A���N�`���̗L������������A3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�d�v�ł��B��5�g���}���Ɏ��������̂́A�قƂ�ǂ̍���҂ւ�2��ڂ̃��N�`���ڎ킪�I����Ă������Ƃ��傫���B���݁A3��ڂ̃��N�`���̐ڎ헦���v���悤�ɏオ���Ă��Ȃ��Ȃ��A����Ҏ{�݂����łȂ��A����Ă��Ȃ���Î{�݂ł̃N���X�^�[�������p���B�\�f�������Ȃ��������Ă���̂ł��B������ł�3��ڂ̐ڎ�����āA���̈��������f���邱�Ƃ����߂��Ă��܂��v(������)
�I�~�N�������͕��ׂƕς��Ȃ��[�[���̖��f�̉A�ŁA�g�y�ǁh�ł��S���Ȃ�l�͑��������Ă���B
�@ |
���R���i��6�g�A���䌧���̈��H�X�u�m����ԁv�@3/10
�V�^�R���i�E�C���X�̗��s�u��6�g�v�ŋq���̗������݂ɒ��ʂ��镟�䌧���̈��H�X����́A��w�̌o�ϑ�����߂鐺�����ɓ��ɋ��܂��Ă���B�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�n��ł́A���Z�v���ɉ��������H�X�ɋ��͋����x�����Ă���A�s���������w�E���鐺�������B�u�S���̑����̒n��ł͋��͋������炦��̂ɁA�Ȃ����䂾���c�v�B���H�X���̑i���͐؎����B
�u��6�g����Ԍ������B�Ƒ����������������߁A���݂ɏo��l���܂����Ȃ��v�B����s�̔ɉ؊X�E�ʏ́u�В��v�ŃX�i�b�N���c��60�㏗���͒Q���B1��������̐V�K�����҂�100�l�ȏ�̓����A������1�����{���납��u�ς�����Ƃ��q���������B�Ȃ����͂܂h�~��v�����Ȃ��̂��v�Ɠ{��ƕs�M�����点�Ă���B
�։�s�̔ɉ؊X�u�{���v�ŋ������N�c�ޒj����1�������玩��I�ɋx�Ƃ��Ă���B�u�d�͉�Ђ̊W�҂炪��H���T���A�l�o�͂����܂�B�H�ނ��d����Ă��A���ݔ��s���ɂȂ邾���v�Ƙb���A�܂h�~�̗v���ɔے�I�ȕ��䌧�̎p�����^�⎋����B
�u�����̈��H�X�͕m����ԁB�܂h�~��v�����Ȃ��Ȃ�A���̂���Ɏ�����x�����K�v���B�Ǝ��̋����x�����ł��Ă������䃂�f���ł͂Ȃ����v�B�����̈��H�X���o�c����j��(42)���ߒɂȐ��ői�����B
�܂h�~���ĉ�������Ă���ΐ쌧�ł́A�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���ɉ��������H�X��1��2��5��`10���~�̋��͋����x������B���ƂȂǂł�1���̏����20���~�ɏオ��B
�u�ΐ�⋞�s�Ȃnj������܂������狦�͋���������Ă���̂ɁA����ł͎؋����ē��X�̌����߂����Ă���v�B��������}���䌧�A��2���A�܂h�~���d�_�[�u�����ɗv������悤���䌧�ɋ������߂��B�Ėؕ��u���A��\�́u�d�_�[�u�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ă��A���Ǝ��̌x��߂��Ă���ꍇ�ȂǂɁA���Ǝ҂����ɋ��͋��̎x���ڐ\���ł���悤�@����ς��邱�Ƃ��I�������v�Ƙb���B
�����A�h���Ǝ҂⏬���Ǝ҂Ȃǂɂ́u�d�_�[�u�Ɉڂ�ΐl�̗��ꂪ����Ɏ~�܂�v�ƐT�d�ȑΉ������߂鐺�������B
����s���̃V���b�s���O�Z���^�[�W�҂́u�x�����x���������グ����Ώ���}�C���h�͈�w�₦���ށv�B���s�̕В����ӂʼnc�Ƃ���^�]��s�Ƃ̏����^�]����u�܂�h�ň��H�X�͋��͋������炦�邯��ǁA�������͂���Ɍ������Ȃ�v�Ɣ��̍l�����B
���䌧�Ǝ��̃R���i������ʌx��Ɉ����グ��3��9���A���{�B���m���͕a���g�p���̒Ⴓ����H�ƈȊO�ւ̉e���܂��A�܂h�~�v���ɉ��߂Ĕے�I�ȍl�����������B����A�S���m����̉�Ȃǂł́u�d�_�[�u�n��ɓ���Ȃ��悤�w�͂��Ă��鎩���̂ւ̍����[�u�����܂�ɂ��������������Ă���v�Ǝw�E���A���̎x�������߂Ă���B�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���R���i�V�K������ 1�T�ԕ��� �S���Ō����������ꕔ�ő����X�� �@3/11
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł͊ɂ₩�Ȍ����X������������ŁA�܂h�~���d�_�[�u�����łɉ������ꂽ�n��̈ꕔ�ȂǁA�����X����������Ƃ��������܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S��
�挎10���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�ɔ�ׂ�1.11�{�Ƒ����X���ł������A�挎17����0.88�{�A�挎24����0.88�{�A����3����0.92�{�A����10���܂łł�0.86�{��4�T�A���Ŋɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻5��6700�l�ƈˑR�Ƃ��đ�����Ԃ������Ă��܂��B
���d�_�[�u�̒n��
����21���܂ŏd�_�[�u���������ꂽ18�̓s���{���ł́A��s�s���𒆐S�Ɋ����Ґ��������������Ă�����̂̂����ނˌ����X���ƂȂ��Ă��܂��B
�y�����s�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.84�{�A����3����0.91�{�A����10���܂łł�0.83�{��4�T�A���Ŋɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ���9402�l�Ƃ��悻1�������Ԃ��1���l�������܂������A����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���468.51�l�ƁA�S���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
�y�_�ސ쌧�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.93�{�A����3����0.91�{�A����10���܂łł�0.91�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻5733�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y��ʌ��z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.01�{�A����3����0.84�{�A����10���܂łł�0.89�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3878�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y��t���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.88�{�A����3����0.89�{�A����10���܂łł�0.92�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3289�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���{�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.80�{�A����3����0.86�{�A����10���܂łł�0.73�{�ƌ����X���������Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻5877�l�ƂȂ��Ă��܂��B����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���466.30�l�ƁA�����s�Ɏ�����2�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�y���s�{�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.87�{�A����3����0.82�{�A����10���܂łł�0.80�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1186�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���Ɍ��z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.89�{�A����3����0.85�{�A����10���܂łł�0.87�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3003�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���m���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.87�{�A����3����0.89�{�A����10���܂łł�0.81�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3680�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.80�{�A����3����0.92�{�A����10���܂łł�0.80�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻550�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�k�C���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.81�{�A����3����0.86�{�A����10���܂łł�0.81�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1675�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���̑��z�@�X���͍���10���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.06�{�A��錧��1.07�{�A�Ȗ،���0.76�{�A�Q�n����0.90�{�A�ΐ쌧��0.85�{�A�É�����0.88�{�A���쌧��0.97�{�A�F�{����1.12�{�ƂȂ��Ă��܂��B
���d�_�[�u �������ꂽ�n��
���łɏd�_�[�u���������ꂽ�n��̂����A�L�����╟�����A���ꌧ�Ȃǂ͉������ɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂����A�ꕔ�ő����X���ƂȂ��Ă���n�������܂��B
�y�L�����z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.83�{�A����3����0.96�{�A����10���܂łł�0.97�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻665�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�������z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.79�{�A����3����0.94�{�A����10���܂łł�0.86�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ���2550�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���ꌧ�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.02�{�A����3����1.41�{�A����10���܂łł�0.86�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻688�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���̑��z�@�R�`���͍���10���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.11�{�A��������1.28�{�A���쌧��1.01�{�A��������1.05�{�A�R������1.20�{�ƁA�����������X���ƂȂ��Ă���n�������܂��B
���d�_�[�u �K�p����Ă��Ȃ��n��
����A�d�_�[�u���K�p����Ă��Ȃ��n��ł������X���ƂȂ��Ă���Ƃ��낪����܂��B
�y���䌧�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.15�{�A����3����1.13�{�A����10���܂łł�1.22�{�Ƒ����X���������Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻389�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���Q���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.93�{�A����3����1.27�{�A����10���܂łł�1.08�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻282�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ɓu�N�x�ւ��̎��� �\�h�����v
�����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́u�����̃s�[�N���߂��Ă��邱�Ƃ͊m�������A���鑬�x�͂��Ȃ�������ŁA���ɂ܂h�~���d�_�[�u���������������̂͌��肪�~�܂��Ă���Ƃ��������悤���B3��ڂ̃��N�`���̒lj��ڎ킪�i��ł��Ȃ����Ƃ⊦���G�߂��Ƃ������ƁA����Ɏq�ǂ��ƍ���҂̊ԂōL�����Ă��邱�ƂȂǂ̗v�����l������B�q�ǂ��⍂��̐���ɂ͂��������ϋɓI�ȑK�v�ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂��B
�܂��A����21���������ƂȂ��Ă���܂h�~���d�_�[�u�̉����ɂ��Ắu�����Ґ��̌������ɂ₩�ȏ̒��ʼn�������ƂȂ�ƁA���傤�ǐl�̈ړ����������N�x�ւ��̎����ɓ�����B���ꂪ�����̍ĔR����������������邽�߁A�����̔��f�͔��ɒ��ӂ��Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�N�x�ւ��̎����͉Ԍ���s�y������ɂȂ邽�߁A�\�h����������邱�Ƃ��S�����Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B |
���Ăɂ��H4��ڃ��N�`�������@�u�܂h�~�v�����֕��j�ɘa�@3/11
������11���A�V����8464�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ȃ��A���{�͑�������̉Ăɂ�4��ڂ̃��N�`���ڎ���������Ă��邱�Ƃ�������܂����B�ɘa�֑傫��������낤�Ƃ��Ă��܂��B
����c���t�{����b�@�u����͎Љ�E�o�ϊ����̈ێ��Ƃ̃o�����X���ӎ����Ȃ���A�ǂ̂悤�ȑΉ����K�v���l���邱�Ƃ��d�v�v
11���ɍs��ꂽ���ȉ�B21���Ɋ������}����u�܂h�~���d�_�[�u�v�ɂ��āA�d�Ǖa���g�p����50�����Ă��Ă�����A�ቺ���錩���݂Ȃ��������l���������܂����B
���{���ȉ�E���g��@�u�a���g�p����50�����炢�ō��~�܂�ł��V�K�z���Ґ����������Ă���Ή������Ă����̂ł͂Ƌc�_�����B�قƂ�ǂ��^�������v
11���ɓ����s�Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�����҂�8464�l�ł��B4���̋��j���ɔ�ׁA2000�l�قnj���܂����B�����̊�Ƃ��ꂽ�d�Ǖa���g�p���͏����������X���ɂ������܂����A�m���̌����͈Ⴄ�悤�ł��B
�����s�E���r�m���@�u����̏Ƃ��Ă��܂����~�܂�B���͐V�K�z���Ґ�����w�A�}�����A��Ò̐��̕��ׂ��y�����Ȃ�������Ȃ��v
���s�{�ł́A��b�����̂Ȃ����A�w�������S�����P�[�X�����炩�ɂȂ�܂����B���̖��A�w���͐挎���{��38.8�x�̔��M������A�z���Ɛf�f����܂����B�ꎞ�A�ċz���r���Ȃ�܂������A���������ďǏ��P�B����×{���Ă��܂������A���̌�Ɏ��S���܂����B�����͕������Ă��܂���B4��ڐڎ�ɂ��Ă������n�߂�悤�ł��B3��ڐڎ킪�S����3���ɔ���Ȃ��A���{��4��ڐڎ�̌����ƃ��N�`���̊m�ۂ�i�߂���j�ł��B
�㓡���J��b�@�u4��ڂ̃��N�`���̌�����i�߂Ă����ɂ������āA���N�`���̊m�ۂȂnj��J�Ȃ̐ӔC�Ƃ��Ă���������g��ł����v
���{�͑�����ΉĂ���4��ڐڎ���J�n���邱�Ƃ��z�肵�Ă��܂��B
|
���d�_�[�u�����̐V��𗹏��@���ȉ�A�Љ�o�ςƂ̗����d�� �@3/11
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ��11���A�V�K�����Ґ������~�܂肵�Ă��Ă��A��Âւ̕��ׂ��ቺ����ƌ����߂�A�܂h�~���d�_�[�u�������ł���Ƃ���V���ȍl�����������ނ˗��������B�I�~�N�������̏d�lj����X�N����r�I�Ⴂ���Ƃ�A�d�_�[�u�̌o�ςȂǂւ̕��S���傫�����ƁA���N�`���̐ڎ킪�i��ł������ƂȂǂ𗝗R�Ɍ��������B
��������g�Ή�́u�Љ�ƌo�ςւ̉e���������܂Œ����Ȃ�ƁA�l�X�̐S���I�����o�Ă���v�Ƃ��Ċ�����ƁA�Љ�o�ϊ����Ƃ̗�����i�����B
���{�́A21���Ɋ������}���铌���A���A���m�Ȃ�18�s���{���̑[�u�̈����f����B |
����t�ɕ����@���쌧�̊����ҁg���~�܂�h�̗��R�@�����̎����́H�@3/11
���쌧�ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p���ꂽ1��21������3��11���A1�T�Ԃ�����̐V�K�����҂͂܂h�~�[�u���n�܂���������2100�l����2300�l�قǂŐ��ڂ��Ă��܂������A2�����{�ɂ�2800�l���܂����B���̌���V�K�����҂�2600�l�䂪�����A���~�܂肵�Ă��܂��B���~�܂��Ԃ��������R�A�����ĉ����̎����ɂ��Ĉ�t�ɕ����܂����B�����s���݂�Ȃ̕a�@�̊ݖ{�L�l��t�͍��~�܂�̗��R�Ɂu�ی����Ɩ��̂Ђ����v�������܂��B
�ݖ{���@���@�u����ɂ��Ĉ�Ԋ����邱�Ƃ͊��҂���̎���ɂ���Z���ڐG�ҁA���ꂩ��ڐG�ҁA���̐l�����̒����⌟�����\���]�͂��Ȃ��̂ŁA�ł��Ă��Ȃ��Ǝv���B�������Ă��邩���m��Ȃ����ǎ��o���Ȃ��l����������̂ŁA���������l���������Ă��ĕ��ʂɐ������Ă���B�����ł܂��L���Ă��܂��Ɓv�u�t�x�݂ɓ���Ɗw�Z�Ȃǂł̊����͗}�����܂��̂Ő��I�ɂ͌����Ă��邾�낤�Ǝv���܂��B�����A�ۈ牀�Ƃ��{�݁A���������Ƃ���ɂ͏t�x�݂͂���܂���̂ŁA�܂��܂�����������Ƃ������Ƃ͓�����ȂƎv���Ă��܂��v
���~�܂�̗��R�ɂ��č��쌧�̕l�c�m���́\�\�B
�l�c�m���@�u�ŋ߂̈�Ë@�ւɂ������K�͂ȃN���X�^�[�̔������A���̐V�K�����Ґ��̐��l�������グ�Ă���ƌ����܂����A���~�܂肳���Ă���v���ƂȂ��Ă���v
�����Ґ��������Ă������߂ɂ́\�\�B
�ݖ{���@���@�u���Ԃ��Ԃ��ܑ厖�Ȃ̂�3��ڂ̃��N�`���ڎ�B�C�O�̃f�[�^�����Ă��A3��ڂ�ł��Ƃɂ���ăI�~�N�������Ɋ������ɂ����Ȃ邾���̍R�̂�����܂��̂ŁA��͂�L�����Ǝv���܂��v
���쌧��10�����_�ł�3��ڂ̃��N�`���ڎ헦��24.7���B�S��43�ʂőS�����ς�3�|�C���g�قlj�����Ă��܂��B���쌧��3��12����13����2���ԁA������21�K�ŃG�b�Z���V�������[�J�[��18�Ζ����̎q�ǂ������e�Ȃǂ�D�悵���L��W�c�ڎ��O�|�����čs���܂��B�@ |
 |
���ݓc�� �܂h�~�[�u�́g18�s���{���������Ɍ����h�o���헪�Ɉӗ~�@3/12
�ݓc�����́A�u�܂h�~���d�_�[�u�v���o����Ă���18�̓s���{���ł������҂������Ɍ������n�߂��Ƃ��āA�o���Ɍ������Ή���i�߂čs���l���������܂����B
�ݓc�u(�g�܂h�~�[�u�h�����{����)18�̓s���{���ɂ����Ă������Ɍ��������n�߂Ă��܂��B�������������g��h�~��O�ꂵ�Ȃ���o���Ɍ����Ă̓�����i�߂čs�������v
�����}�̉�Ŋݓc�����͂��̂悤�ɏq�ׁA�g�܂h�~�[�u�h������������̎Љ�o�ϊ�����{�i�������邢����g�o���헪�h�ɂ��Ď��g��ł����l���������܂����B
����ɐ旧���ݓc�����́A���傤�ߑO�Ɋό��U����=GoTo�g���x���ɂ��āA�u�K�Ȏ����������Ȃ�ΐv���ɍĊJ�ł���悤���{�Ƃ��Ă������͐i�߂Ă��������v�ȂǂƍĊJ�Ɍ����ӗ~�������܂����B
���{�͏T������18�s���{���ւ́g�܂h�~�[�u�h���������邩�ǂ������f����\��ł��B |
���ɐ��_�{���ӂɑ����̉Ƒ��A�� �u�܂h�~�v�����㏉�̋x�� �@3/12
�O�d���ɓK�p����Ă����܂h�~���d�_�[�u����������A���߂Ă̋x�����}�����ɐ��s�̈ɐ��_�{���ӂł́A�l�o�������Ċ��C���߂��Ă����Ƃ���������������܂����B
����6���������������u�܂h�~���d�_�[�u�v�́A���C3���ł͈��m�Ɗ������ɂȂ�������A�O�d�͉�������܂����B
�����㏉�߂Ă̋x�����}�����ɐ��_�{�̓��{���ӂł͌ߑO�����璓�ԏ�͖��ԏ�ԂŁA�y�Y���X����H�X�����Ԓʂ�ɂ͑����̉Ƒ��A��Ȃǂ̎p�������܂����B
�l�͎Ԃ������Ă���40��̒j���́u���邩��ɐl�o���������悤�ȋC�����܂��B�ɂ��₩�����߂��Ă����悤�Ɋ����܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
�Q�q�҂̃K�C�h�����Ă���70��̒j���́u�d�_�[�u�̊Ԃ͊ό��o�X�������A�ǂ������C���Ȃ������ł��B���傤�͊��C���o�Ă��āA����܂łƈ������C������Ă���Ǝv���v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A��������K�ꂽ40��̒j���́u��������Ēg�����V�C���悩�����̂ł������ɗ��܂����B�C�������O�����ɂȂ�܂��������̎��̔g�����邩������Ȃ��̂ŋC���������ł��v�Ƙb���Ă��܂����B�@ |
 |
������ �R���i 9�l���S 8131�l�����m�F �O�T���j���1100�l�]�� �@3/13
�����s����13���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓��j�����1100�l�]�菭�Ȃ�8131�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ9�l�����S�����Ɣ��\���܂����B
�����s��13���A�s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v��8131�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����1100�l�]�茸��܂����B13���܂ł�7���ԕ��ς�8708.7�l�ŁA�O�̏T��79.2���ł����B�O�̏T�������̂�30���A���ł��B13���Ɋm�F���ꂽ8131�l��N��ʂɌ���Ɓu10�Ζ����v���S�̂�21.2���ɓ�����1720�l�ŁA�ł������Ȃ��Ă��܂��B65�Έȏ�̍���҂�473�l�ŁA�S�̂�5.8���ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A13�����_��12�����1�l������63�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70�ォ��90��̒j�����킹��9�l�����S�����Ɣ��\���܂����B�����s���̐V�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p���́A12������0.1�|�C���g��������13�����_��41.6���ł��B
|
���u��6�g�v�Ή��Ō��A���]�L�̊����g�叵���c����Ҏ{�݂̃N���X�^�[�����@3/13
����5�g�Ɣ������5�{�A����3�{
�V�^�R���i�E�C���X�Ŋ����͂̋����I�~�N���������L����A���{�ł͑�6�g(��N12��17���`)�̊����Ґ���12���܂łɖ�52���l�A���Ґ���1220�l�ɒB�����B��5�g(��N6��21���`12��16��)�Ɣ�ׁA�����Ґ���5�E2�{�A���Ґ���3�E4�{���B�����̃s�[�N�͉߂����Ƃ݂��邪�A�����Ґ��̌����y�[�X�͒x���A�V���Ȕg�̓��������O�����B�f�[�^��������ƁA�V�����ψي��ւ̑Ή��̒x�ꂪ���]�L�̊����g������������Ԃ������яオ��B
���܂h�~�ɐT�d���l���䊴���A�S���ň�
���̊����Ґ���1��2������A����1�E4�`2�E1�{�̃y�[�X�ő����n�߂��B����̓f���^�����嗬��������5�g��1�T�Ԃ�����̑����y�[�X�ɑ����B��7���̕{�̑��{����c�ł͂��ĂȂ������̋}�g����뜜�������Ƃ���A�l���̗}�������߂�ӌ����o���B
����ɑ��A�g���m���m���́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̗v���ɂ��Ắu��Â̕N��(�Ђ��ς�)�x�A�d�ǎҐ��܂��Ĕ��f�������v�ƐT�d�ȍl�����������B�o�ϊ����ɗ^����e���ւ̔z�����������Ƃ݂���B
�ŏI�I�ɕa���g�p�����A�{����Ƃ���35�����A�d�_�[�u���K�p���ꂽ�̂�1��27���B���20���Ƃ��������s���6���x�������B���̌�A�����g��̃y�[�X�͓���������A�l��10���l������̊����Ґ��́A�S���ň��̏�Ԃ�3�����߂܂ő������B
���H�X�ɉc�Ǝ��Ԃ̒Z�k�Ȃǂ�v������d�_�[�u�́A�����g��̏����قnj��ʂ������Ƃ����B����ȑ�̐��R��������(���O�q���w)�́u�d�_�[�u�͎s���ւ̐S���I�Ȍ��ʂ��傫���B�扄���������ʁA�w�܂��C�����Ȃ��Ă����x�Ƃ������b�Z�[�W�ɂȂ������\��������v�ƌ����B
��3��ڐڎ�i�܂������҂�93����70�Έȏ�
�I�~�N�������͏d�lj����ɂ����Ƃ���A���Ǐ�̐l�������Ƃ���Ă����B�������A�����Ґ��̕ꐔ�������I�ɑ��������ʁA���Ґ����啝�ɉ����グ��ꂽ�B
���҂̒��ł͍���҂̊����������A��6�g�ł�70�Έȏオ93��(2��26�����_)���߂�B��5�g�ł�68���ŁA�u��Õ���v�̊�@�ɒ��ʂ�����4�g(��N3��1���`6��20��)��85���ɋ߂���ԂƂȂ����B
����҂̎��҂��������傫�ȗv���Ƃ��ẮA�S���I�ȃ��N�`����3��ڐڎ�̒x�ꂪ����B��5�g�ł͑����̍���҂�������1�A2��ڂ̐ڎ���I���Ă����B�����g�傩���1������7��31���ɂ́A������65�Έȏ��2��ڂ̐ڎ헦��80�������B
����A�ڎ�2��̌��ʂ����ꂽ��6�g�ł́A3��ڂ̐ڎ헦�͊����g�傩���2�������2��25���ɂ����50�����A3��11�����_�ł�69�����B���̎��҂̂���73���͐ڎ�1�`0��(�s���܂�)�����A�ڎ�2���26���ɏ��B
����ɑ��ł͑������@�E���Â��v���ʂ�ɐi�܂Ȃ������B��5�g�ł́A�y�ǂ̒i�K����ϋɓI�ɓ��@�����ďd�lj���\�h����u�R�̃J�N�e���Ö@�v���t�������B��������6�g�ł́A�ی����̑̐��������҂̑����ɂ܂������ǂ������A�����҂ւ̃t�@�[�X�g�^�b�`(�ŏ��̘A��)�⎡�Â��x�ꂽ�B
���ɑ��ɉ��������Ҏ{�݂ł̓N���X�^�[(�����W�c)���������A�[���ȏɊׂ����B��5�g�Ō��ʂ��o���R�̃J�N�e���Ö@���A�I�~�N�������ւ̌��ʂ�1000����1�ɂȂ�Ƃ̕�����A�g���Ȃ������B����ɑւ��R�̖�͌����Ƃ��Ĕ��ǂ���7���ȓ��ɓ��^����K�v������A���ÊJ�n�̒x��Ŏg�p�ł��Ȃ��P�[�X���������B
�{�̓��@�t�H���[�A�b�v�Z���^�[�����@������Ă��鎞�_�ŁA�_�f�z�����K�v�ȁu������2�v�ȏ�̐l��1��6�`11����6������A2��25���`3��3���ɂ�62���܂ő������B
���������@15��
����҂ւ̊����g��͕a���s���ɂ��Ȃ������Ƃ݂���B����ɂȂ�قǓ��@�����͒����Ȃ�A�y�ǁE�����Ǖa����15���ȏ�̒������@�̊�����1��4����2������2��24���ɂ�15���ɏ㏸�B�y�ǁE�����Ǖa���̎g�p���͈ꎞ100�������B
�{�����E��`�ɊJ�݂����Վ���Î{�݁u���R���i��K�͈�ÁE�×{�Z���^�[�v(1000��)����삪�K�v�ȍ���҂̎��Âɂ͎g�����A�g�p��(12�����_)��6�E5���ɂƂǂ܂�B
���ی����v���x�ꁨ��Îx���O�Ɋ����g��
���ґ����̗v���ƂȂ�������Ҏ{�݂̃N���X�^�[�́A�Ȃ����������̂��B
�{�ɂ��ƁA�{�ݓ���5�l�ȏ�̊����҂��o���ꍇ�ɃN���X�^�[�ƔF�肵�Ă���B�N���X�^�[��1����57���A2����268���̌v325���������A��5�g(51��)��6�E4�{�A��4�g(��N3��1���`6��20���A105��)��3�E1�{�ɏ���Ă���B
�e�{�݂ł́A�Ƒ��Ɠ����҂Ƃ̖ʉ����E���̒���I�Ȍ����Ƃ���������u���Ă������A�I�~�N�������͏]���̃f���^���Ɣ�ׂĊ����͂������A3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�i��ł��Ȃ��������Ƃ������ăN���X�^�[�̌������}�������B
���u5�l�ȏ�v
�{�ݓ��Ŋ������L�������v���́A�x���̒x�ꂾ�B
�{�͒����ɊŌ�t���10�l�̎x���`�[����ݒu�B�ی�������̗v���Ɋ�Â��āA2�l1�g�Ŏ{�݂ɏo�����A�����̋��ꂪ������ƈ��S�ȋ�����u�]�[�j���O�v��h�앞�̒��E���@�Ȃǂ�����Ŏw�����Ă���B
�������A�ی������x���`�[���ɘA������̂́A5�l�ȏ�̊����҂��o�Ă��炾�B�{�ɋ��͂��A�{�݂ł̎x���ɓ����Ă��鍑���a�@�@�\�{���c�l�`�s�����ǎ����̎�䑏�q(�����̂�)��t�́u�قƂ�ǂ͊������L���肫���Ă��܂����{�݂���B�x���ɓ���̂��x���v�Ǝw�E����B
����t���ΏƓI�ȗ�Ƃ��ċ�����̂́A��6�g�ł��������������L���������ꌧ���B
���ꌧ�ł͖�2�N�O����A����Ҏ{�݂œ����҂�E���̊�����1�l�ł����������ꍇ�A�ی�������̏�����Ɉ�t��Ō�t��24���Ԉȓ��ɔh�����Ă���B���̒S���҂́u���₩�ɐ��Ƃ𑗂荞�ނ��ƂŁA�����g���}����̂ɖ𗧂��Ă���v�Ƃ��Ă���B
�d�lj����X�N�̂��鍂��҂ւ̊�����H���~�߂邱�ƂŁA���҂̗}���ɂ��Ȃ����Ă���Ƃ݂���B�ǔ��V���̏W�v�ł́A��6�g�̉��ꌧ�̎��S��(�����Ґ��ɐ�߂鎀�҂̊���)��0�E06���ŁA���{�̎��S��(0�E24��)��4����1���B�l��10���l������̎��Ґ����A����13�E66�l��啝�ɉ����2�E18�l�ƂȂ��Ă���B
���ۑ�Ȃ�
�����������A�{�����P�ɏ��o���Ă���B2��18������A�]���̎x���`�[�����g�[�����u�N���X�^�[�Ή������`�[���v��ݒu���A24���Ԏt���\�ȃR�[���Z���^�[���J�݁B�ی���������ɁA���f�⊴����̎w������]����{�݂���̘A��������悤�ɂ����B3��10�����_�ŁA���f�x��6���A������̏���32���ɑΉ������Ƃ����B
�����A�ۑ�͂Ȃ��c����Ă���B�`�[���̗v�����ĉ��f���s���Ă��銋����@(���s�����)�̏��ѐ��X�@��(39)�́A��ÑԐ����s�\���Ƃ̌����������B
����Ҏ{�݂́A���̎w�j�ŘA�g��Ë@�ւ��w�肷�邱�Ƃ����߂��Ă���B�������A�A�g��Ë@�ւ͋K�͂��������f�Ï��������A�\���ȃ}���p���[���Ȃ����Ŏ{�݂ł̑Ή��ɓ�����͓̂���Ƃ����B
���щ@���́u�A�g��Ë@�ւ����ɗ���̂ł͂Ȃ��A�g�D�I�ȉ��f�`�[���𑝂₵�Ă������Ƃ��d�v���v�Ǝw�E����B
|
���h�܂h�~�h������@���̏T���@���������̍s�y�n�Ȃǂɑ吨�̊ό��q�@3/13
�������ɏo����Ă����A�܂h�~���d�_�[�u���������ꏉ�߂Č}�����T���A�����̍s�y�n�Ȃǂ́A�吨�̊ό��q�̎p�������܂����B3��6���ł܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ�A�����L���̊ό��n�A
���ɕ{�V���{�̎Q���ɂ́A������吨�̉Ƒ��A��Ȃǂ̎p�������܂����B�u�l�̑����Ƃ������A�����܂ł���Ǝv��Ȃ��������A���C���ӂ��̂������ł��ˁv�u���Ɍ����痈�܂����B���Ɨ��s�Ȃ̂ŁA�܂h�~���I������̂ŁA���傤�ǂ������ȂƎv���ė��܂����v�Q���̔~���}�ݓX�́A���O����̊ό��q�������A���グ�̉ɂȂ���A�Ɗ��҂��Ă��܂����B
��������4��7���܂ł��u�����Ċg��h�~����ԁv�ƈʒu�Â��A���������A������̓O����Ăт����Ă��܂��B
|
�����{�̕a���g�p����61�D3���@���{�́u�܂h�~�v���� �߂����f�ց@3/13
���E���ɁE���s�Ȃǂɏo����Ă���u�܂h�~���d�_�[�u�v�B���{�͋߂��A�������邩�ǂ������f����Ƃ���Ă��܂��B
3��13���̑��{�̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�4897�l�ŁA1�T�ԑO�ɔ�ׂ�535�l���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����A�a���g�p����61�D3���ƍ��������ł����A���{�����ȉ�Ŏ������V���ȕ��j�ł́A50�����Ă��Ă������Ґ��������X���ň�Õ��ׂ̒ቺ�Ȃǂ������܂��ꍇ�͂܂h�~���d�_�[�u�������ł���Ƃ��Ă��܂��B
�[�u�̉����ɂ��āA13���A���E�~�i�~���s�������l����H�X�̓X����ɘb���܂����B�u(������)�^�������ǁA(�����҂�)�������炱�킢�v�u�t�x�݂��߂Â��Ă���̂ŁA���X�Ƃ��Ă͉������Ă��������̂͑������������ł��ˁv
���{�ȊO��13���̋ߋE�̐V�K�����҂́A�ߌ�5�������_�ŁA���Ɍ���2489�l�A���s�{��1131�l�A�ޗnj���738�l�A���ꌧ��584�l�A�a�̎R����198�l�ƂȂ��Ă��܂��B�������̐V�K�����҂�210�l�ł��B
|
 |
�����̐V�K�����ҁ@10���A���őO�T�䌸�@3/14
��2�{4����13���ɔ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂́A���킹��1���l�]��ŁA10���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B���A���ɁA���s�̂܂h�~���d�_�[�u�͍���21���������ŁA����e�{���͍��T�A�Ή����������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
��2�{4����13���ɔ��\���ꂽ�V���Ȋ����҂͑�オ4897�l�A���ɂ�2489�l�A���s��1131�l�A�ޗǂ�738�l�A���ꂪ584�l�A�a�̎R��198�l�̂��킹��1��37�l�ł����B�O�̏T�̓����j���Ɣ��1400�l�]�菭�Ȃ��A10���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B�ŐV�̏d�ǎ҂̐l���́A��オ174�l���ɂ�23�l�A�ޗǂ�20�l�A���s��7�l�A�a�̎R�Ǝ���ł��ꂼ��3�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A����12�l�A���s��6�l�A���ɂ�4�l�A�ޗǂƎ���ł��ꂼ��1�l�̂��킹��24�l�̎��S�����\����܂����B
�V���Ȋ����҂͌����X���������Ȃ��A���A���ɁA���s��3�{���ɓK�p����Ă���܂h�~���d�_�[�u�́A����21���������ƂȂ��Ă��܂��B
���{�̋g���m���́A���T�̒����ɕ{�Ƃ��Ă̑Ή������߂�l���������ȂǁA����e�{���́A���T�A�ŐV�̊��������ɂ߂Ȃ���܂h�~���d�_�[�u���߂���Ή��ɂ��Č������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�@ |
���܂h�~���d�_�[�u ���{ ����21�������őS�ʉ���������Ɍ����@3/14
���{�́A����21���Ɋ������}���铌���Ȃ�18�s���{���ւ́u�܂h�~���d�_�[�u�v�ɂ��āA�S�ʉ������邱�Ƃ�����Ɍ����ɓ���܂����B
�ݓc�����͂��̂��A�㓡�����J����b�ȂǃR���i�̊W�t����Əd�_�[�u�K�p�n��̊����Ȃǂɂ��ċ��c���܂����B
���݁A�K�p����Ă���18�s���{���̂����A����_�ސ�ȂLjꕔ�̎����͈̂ˑR�Ƃ��ĕa���g�p����5�����z���Ă��܂����A���{�W�҂ɂ��ƁA�u������̒n��������Ґ���a���g�p���Ɉ����X���͌����Ȃ��v�Ƃ��āA21���̊����������đS�ʉ������邱�Ƃ�����Ɍ������Ă���Ƃ������Ƃł��B
���{�́A���T�̊����Ȃǂ��悭���āA�����̂̈ӌ��܂��Ȃ��獡�T���ɍŏI���f���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
|
 |
���܂h�~�����@�u����͌��O������v�@�S���m�����E���䒹�挧�m���@3/15
14���A�S���m����̉�߂钹�挧�̕���m���͍��Ƃ̈ӌ�������ŁA�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̉�������ɂ߂鍑�̕��j�ɂ��āu�����Ɍ������̂��A����͌��O������v�Əq�ׂ܂����B
�S���m�����@����L���@���挧�m���@�u��{�I�Ώ����j�Ƃ��āA�܂h�~���d�_�[�u�ȊO�̗l�X�ȑ�Ƃ������̂����Ђ��l�����������Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ��N�x���A�N�x�n�߂Ől�������Ƃ��Ɏ����Ɍ��������ǂ����Ƃ����̂͌���ł͌��O�̂���Ƃ���ł������܂��v
�����́A18�s���{���ւ̏d�_�[�u��21���̊����ł��ׂĉ��������\���ɂ��āA�u���Ȃ�]���Ƃ͈������舵���ɂȂ�v�Ƃ��A���������ꍇ���A��6�g�̊����̒��S�ł���q�ǂ��⍂��҂ւ̑����������悤���߂܂����B����ɑ��A�R�یo�ύĐ��S����b�́u�����������F���������Ă��āA�Ċg��ɂȂ�Ȃ��悤�ɑ�ƌĂт�����O�ꂵ�Ă����v�Ƃ��܂����B
|
�������̂��O�����p���c�u�܂h�~�v21����ĉ����ց@3/15
�����s��14���A�V���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�4836�l�ł����B��T���j�����500�l�ȏ㏭�Ȃ��A���悻2�J���Ԃ��5000�l�������܂����B�܂��A�S���̐V�K�����҂�3��2471�l�ŁA1�T�ԑO�ɔ�ׂ��悻4600�l�������Ă��܂��B
���������Ȃ��A���݁A�����ȂǑS����18�s���{���ɏo����Ă���u�܂h�~���d�_�[�u�v���A21���Ɋ������}���܂��B���{�́A�V�K�����Ґ���a���g�p���Ȃǂ����P�X���Ɍ������Ă���Ƃ��āA��ĉ�����ڎw�����j�ł��B�����̂��A�����ɑO�����Ȏp���������Ă��܂��B
�_�ސ쌧�E����S���m���F�u�T�d�Ɍ��Ȃ���A�C�����Ƃ��Ă͉����������v
���m���E�呺�G�͒m���F�u�����ł��Ȃ����Ƃ��Ȃ���������Ȃ��B�T���ɂ́A���f���Ă��������v
���{�E�g���m���m���F�u�������̂��̂ɂ��ẮA�����X���ɂ���Ǝv���B�āX������v������̂��A�����ł�������I�������肢����̂��A���j���ɔ��f�������v
���{�́A�����̂���̗v�]�܂��A16���ɂ��ŏI���f���錩�ʂ��ł��B
|
���k�C���@�u�܂h�~�[�u�v21���I�����j ���H�X�ւ̎��Z�v�������ց@3/15
�k�C���̂܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āA���́A�����ǂ��荡��21���ŏI������j���ł߁A�ߌ�̑��{����c�Ō��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�����������Ĉ��H�X�ւ̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���͏I�����������ŁA��{�I�Ȋ�����̓O����Ăт�������j�ł��B
�����ł́A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑O�̏T�Ɣ�ׂ�1�{�������A�����X���������Ă���ق��A�ꎞ�A�D�y�s��50���߂��܂ŏ㏸�����a���g�p���������X���ɓ]���܂����B
���������܂��A���́A���Ƃ�1��27���̓K�p�ȍ~�A2��ɂ킽�艄�����Ă��������S��̂܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āA���{�ɉ����͗v�������A�����ǂ��荡��21���ŏI������j���ł߂܂����B
���́A���Ƃɂ��ӌ����������ŁA15���[���A���{����c���J���A���肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�������22���ȍ~�́A���H�X�ł̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v����4�l�ȓ��Ȃǂ̐l�������͍s��Ȃ����j�ł��B
����A�N�x������N�x���߂ɂ����Đl�̈ړ����H�̋@������A�����̃��X�N�����܂鎞�����}���邱�Ƃ���A�����⎖�Ǝ҂ɂ͊�{�I�Ȋ�����̓O����Ăт�������j�ŁA��̓I�ȑ�̓��e���������Ă��܂��B
|
�������s�� �V�^�R���i ��������10�Ζ�����������ԑ��� �@3/15
�V�K�z���҂���������Ȃ��A�����s���ł́u10�Ζ����v�̎q�ǂ��̊������N��ʂōł�������Ԃ������Ă��܂��B�����ɓ�����14���܂ł̓s���̐V�K�z���ҁA13��3166�l��N��ʂɂ݂�Ɓu10�Ζ����v���ł�����2��5242�l�ŁA�S�̂�19.0�����߂Ă��܂��B13.2���́u10��v�����킹��ƁA�����͐V�K�z���҂̂��悻3�l��1�l��20�Ζ����ƂȂ��Ă��܂��B�s���̐V�K�z���҂͌������Ă��܂����A��l�Ɣ�ׂĎq�ǂ��͌����̃X�s�[�h���x���A�S�̂ɐ�߂銄���������Ȃ��Ă��܂��B
��6�g�œs����7���ԕ��ς��s�[�N�ƂȂ����挎8�����_�ƁA14�����_���r����ƔN��ʂł́A20�オ38.8���A30���43.7���ƁA�s�[�N����4���O��܂Ō����Ă��܂��B�܂��A65�Έȏ�̍���҂�32.3���ƁA���悻3���܂Ō������܂����B����ɑ��A10�Ζ�����14�����_��63.5���A10���57.5���ŁA�����͂��Ă�����̂̃s�[�N����6���O��ɂƂǂ܂��Ă��܂��B
|
����6�g�́u�R���i���ҁv�A3���̎������R���i�ȊO�c����҂̎��a������V���@3/15
�V�^�R���i�E�C���X�����g��̑�6�g�ŁA�u�R���i���ҁv�Ƃ��Č��\���ꂽ�l�̂����A���ڂ̎������R���i�ł͂Ȃ������Ƃ݂���l��3���O��ɏ�邱�Ƃ��A�ꕔ�����̂̕��͂ł킩�����B�����҂����S�����ꍇ�A�����͎̂����ɊW�Ȃ��u�R���i���ҁv�Ƃ��Čv�サ�Ă���B��6�g�͍���̊����҂��R���i���L�̔x���ȂǂŖS���Ȃ�̂ł͂Ȃ��A���a�̈�����V���Ŗ��𗎂Ƃ��P�[�X���ڗ����Ă���B
�ǔ��V�����e�����̂̌��\�f�[�^���W�v�����Ƃ���A���N1���ȍ~�̃R���i���҂͑S���Ōv7885�l(3��14�����_)�ɏ��A��5�g���N������N8�`10��(�v3073�l)��2�E6�{�ƂȂ��Ă���B
�����J���Ȃ́A���҂̐������Ƃ��āA�u���ڂ̎����ɂ͂�����炸�A�����҂��S���Ȃ�w�R���i���ҁx�Ƃ��Čv�サ�Ăق����v�Ǝ����̂ɋ��߂Ă���B
�����������A��6�g��2�����܂ł�66�l���S���Ȃ������R���́A��Ë@�ւ����S�f�f���ɋL�ڂ���u���ڎ����v�̓��e��ی�������������ĕ��͂����B���̌��ʁA�u�V�^�R���i�E�C���X�v��68��(45�l)�ŁA�c���32��(21�l)�́A�뚋(������)���x����V���Ȃǂ������B
���t�̑�4�g�͒��ڎ������R���i�Ƃ��ꂽ������99��(90�l)�ɏ��A����ȊO��1��(1�l)�������B
���̒S���҂́u�]���̓R���i���ƌ����A�x���Ǐ������Čċz����Ɋׂ�P�[�X�Ȃǂ������������A��6�g�͏��Ȃ��Ȃ��Ă���B���̈���ŁA�����ɂ�鐊��Ŏ��a���������ĖS���Ȃ�w�R���i�ȊO�x�̎��Ⴊ�}�����Ă���v�Ƙb���B
��t���̕��͂ł́A�R���i�ȊO�̎��҂͑�3�g��10��(24�l)���������A��6�g��22��(39�l)�������B
���{�ł́A2��26�����_�̎���799�l�̂����A�R���i�ȊO��39��(314�l)�ɏ���Ă���B
�_�ސ쌧�ł��A���N1�`2���Ɍ����̕a�@�ŖS���Ȃ���������312�l(70�Έȏオ9��)�̂����A�R���i�ȊO��32��(100�l)�������B���s�ɂ��鐹�}���A���i��ȑ�̍����L�V����(�����NJw)�́u��6�g�ŗ��s�����I�~�N�������͏d�lj����ɂ������A����҂⎝�a������l�A�얞�X���̐l����������A�̗͂̒ቺ�Ŏ��S���郊�X�N�����܂�v�Ǝw�E����B
�R���i�Ɋ������Ă͂�����̂́A�u�R���i�ȊO�v�ŖS���Ȃ�l�������Ă��錻��ɁA�_�ސ쌧�̒S���҂́u�R���i�̏Ǐy���Ă����f�͂ł��Ȃ��B�x����i�s�����Ȃ����߂̎_�f���^�����łȂ��A���a�̈����Ȃǂɂ������Ή��ł���悤�A���X�N�̍����l�����ւ̌��N�ώ@�����d�v�ɂȂ�v�Ƙb���Ă���B�@ |
 |
���Z���ڐG�҂̒����E�o�ΐ����A�E��͕s�v�Ɂc�I�~�N�����ł́u���ʂ��ቺ�v �@3/16
���{�́A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̓����܂��A�����g��n��̈�ʎ��Ə��ł́A�Z���ڐG�҂���肹���A�o�ΐ����Ȃǂ����߂Ȃ����Ƃ����߂��B�Z���ڐG�҂̌����������A�Љ�@�\�ێ�������ɂȂ鎖�Ԃ�ی����̋Ɩ� �N���Ђ��ς� ���������_��������B
����܂ŕی����́A�����g���h���_���ŁA�����҂̔Z���ڐG�҂�ǐՒ������A����ҋ@�Ȃǂ̍s�����������߂Ă����B
�����A���ݎ嗬�̃I�~�N�������͊����g��̃X�s�[�h���������߁A�����J���Ȃ̏����@�ւ̐��Ƃ炪�u�Z���ڐG�҂̒����̌��ʂ��ቺ���Ă���v�Ǝw�E���Ă����B
�I�~�N�������̏ꍇ�A1�l�̊����҂���ʂ̊����҂ɂ�����Ԃ͖�2���ƁA�f���^���̖�5�����Z���B���ǂ܂ł̐������Ԃ͖�3���ŁA�ی������������J�n���鍠�ɂ́A���Ɋ������g�債�Ă���\���������Ƃ����B
�I�~�N�������͎Ⴂ�l�̏d�lj����X�N���Ⴂ���Ƃ����܂��A���{�́A�Z���ڐG�҂̒������A�d�lj����X�N�̍������҂⍂��҂��W�܂��Ë@�ւ⍂��Ҏ{�݂̂ق��A�������X�N�̍����ƒ�ȂǂɏW�����čs�����ƂƂ����B�������A�ی������Ή��\�Ȏ����̂ł́A�]���ʂ蕝�L���������s���Ă��悢�Ƃ����B
�����҂̓����Ƒ��ɂ͌���7���Ԃ̍s�����������߂邪�A4�A5���ڂɍR���萫�����L�b�g�ʼnA�����m�F�ł���Ή������\�Ƃ���B�ۈ珊�⏬�w�Z�Ȃǂɂ��Ē��������邩�ǂ����͎����̂̔��f�Ɉς˂�B
|
�����B�ŐV�^�R���i�����Ċg��@�I�~�N���������킩�@3/16
���[���b�p�ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N����������Ƃ݂��銴�����g�債�A�A�����J�ȂǑ��̒n��ł�����̊������ĂэL����S�z����Ă��܂��B
CNN�ȂǃA�����J���f�B�A�ɂ��܂��ƁA�C�M���X�Ő�T�̊����҂����̑O�̏T�ɔ�ׂ�48�������A���@�Ґ���17�������Ă��܂��B���ɂ��h�C�c�A�t�����X�A�C�^���A�ȂǂŊ����Ċg��̌X�����݂��܂��B
�C�M���X�ł͍������{�Ɋ����҂�68�D6�����I�~�N�������̈���BA.2�ɂ����̂ŁA�]���̃I�~�N��������31.1���ł����B�C�M���X���ǂƘb�����A�����J�̃t�@�E�`��Ȉ�Ìږ�́A�u�����͂̋���BA.2���̊g��A�}�X�N���p�`���̓P�p�ȂNjK���ɘa�A�l�������R�̂̌����v���Ċg��̔w�i�ɂ���Ƃ��Ă��܂��B
�j���[���[�N�ȂǃA�����J�̈ꕔ�n��ł�BA.2���̊����������Ă��āA���l�̊����g�傪�A�����J�ŋN���錜�O���w�E����Ă��܂��B
|
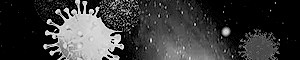 |
���S���V�K�R���i������5��3588�l�@�X643�l�ʼnߋ��ő��@3/17
17���A�S���Ŋm�F���ꂽ�����҂�5��3588�l�ł����B14���ԘA���őO�̏T�̓����j���̊����Ґ���������Ă��܂��B�X���ł�643�l�̊������m�F����ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�S���Ȃ�������171�l����Ă��܂��B
�d�ǎ҂́A16�����_�őO�̓�����50�l������1090�l�ŁA1�������Ԃ��1100�l�������܂����B
|
��18�s���{���u�܂h�~���d�_�[�u�v���{���ȉ� �������j���� �@3/17
��������A���m�Ȃ�18�s���{���ɓK�p����Ă���V�^�R���i��̂܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āA���Ƃł��鐭�{�̕��ȉ�́A���ׂĂ̒n��ō���21���̊����������ĉ���������j�𗹏����܂����B���{��17����A�����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�V�^�R���i����߂���A�����ǂȂǂ̐��Ƃł��鐭�{�́u��{�I�Ώ����j���ȉ�v���J����܂����B
���̒��Ő��{�́A��������A���m�Ȃ�18�s���{���ɓK�p����Ă���܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āA�e�n�̊������Ò̐��A����Ɏ����̂̈ӌ������܂��A����21���̊����������ĉ���������j������܂����B
�܂��A�Љ�o�ϊ������ێ����邽�߁A�n��̊�����ی����̑̐��Ȃǂɂ���ẮA�������X�N���Ⴂ��ʂ̎��Ə��Ȃǂł͔Z���ڐG�҂̓�������߂��A�ꗥ�̏o�ΐ������s��Ȃ��ȂǂƂ�����j������܂����B
�V�^�R���i���S��������t�{�̉���c����b�́u�����̖�����邱�Ƃ���ɁA����������Ò̐��̈ێ��E�����Ɏ��g��ł����ƂƂ��ɁA�Љ�o�ϊ����̉Ɍ��������g�݂�i�߂Ă������Ƃ��d�v�ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���ȉ�ł͂����������j�ɂ��ċc�_���s��ꗹ������܂����B
���{�͍���ւ̎��O�̕Ǝ��^���o��17����A�������̑��{���Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�d�_�[�u���ǂ̒n��ɂ��o����Ă��Ȃ��ƂȂ�̂́A���Ƃ�1��8���ȗ��A���悻2�������Ԃ�ƂȂ�܂��B
|
���܂h�~���d�_�[�u�A3��21���̑S�ʉ�����������@3/17
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̐V�K�����Ґ��������X���ɂ��钆�A���{�͌���18�s���{���ɑ��ēK�p���́u�܂h�~���d�_�[�u�v��2022�N3��21��(��)�̊����ʂ�������邱�Ƃ𐳎��Ɍ��肵���B
�ɂ��ƁA�K�p�����n�悪�Ȃ��Ȃ�̂͂��悻2�J�����Ԃ�B��{�I�Ώ����j���ȉ�̔��g�Ή�́A�u�����̃��o�E���h�����肦��v�Ƃ��w�E�A���ӊ��N���Y��Ȃ������Ƃ����B
3��16���ɂ͂��łɎ����ʐM���A���t������b�̊ݓc���Y�������̎��@�L�҉�ŁA�S�ʓI�ɉ���������j��\���A17���ɐ��Ƃ̈ӌ�������Ő����Ɍ��肷��|��Ă����B���{�Ȃǂ͉��������߂邩�ԓx��ۗ����Ă������A���{���܂ߍŏI�I�ɑS�s���{�������������߂邱�Ƃ͂Ȃ������B
���ݓK�p���̓s���{���́A�Q�n���A��ʌ��A��t���A�����s�A�_�ސ쌧�A���A���m���A���쌧�A�F�{���A�k�C���A�X���A��錧�A�Ȗ،��A�ΐ쌧�A�É����A���s�{�A���{�A���Ɍ���18�s���{���B
�K�p����18�̂����A15�s���{���ł͐V�K�����Ґ��͌����������Ă���B����ŁA10�����_�̕a���g�p���ɂ��Ă͐_�ސ쌧�A��t���A���m���A���s�{�A���{�A���Ɍ��œ��[�u�̖ڈ��Ƃ���Ă���50�����Ă�����̂́A���{�͍���͌�������Ɣ��f�����`���B |
���g�܂h�~�h�����u��ÊW�ψ�2�l�͏��ɓI�^���v���g� �@3/17
�u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή�́A��̂��ƕw�̎�ނɉ����A���ׂĂ̒n��ł܂h�~���d�_�[�u���������邱�Ƃɂ��āA�S�����^���������̂́A��ÊW�҂�2�l�̈ψ��͏��ɓI�Ȏ^���������Ɩ��炩�ɂ��܂����B
���g��́u�t�x�݂⊽���}��A�Ԍ��Ȃǂ̋G�߂��߂Â��A�I�~�N��������1�Ŋ����͂�����ɍ����Ƃ����wBA.2�x�����钆�ŁA�d�_�[�u�����A��������A�����҂�������̂͊ԈႢ�Ȃ��ƐS�z���鐺���オ��A�^�������ق��̈ψ���������o�E���h�ɒ��ӂ��ׂ����Ƃ����ӌ����ٌ������ɕ����ꂽ�B����ŁA�s�������ɂ��Љ�o�ςւ̉e���������������ŁA���ɖ߂��Ă����Ƃ����ӌ��Ɉًc���������l�͂��Ȃ������B�����҂͑����邩������Ȃ������ʓI�Ŗ����̂Ȃ�����Œ������Ă��炢�A�Љ�������Ƃ����c�_�ɂȂ�A�݂�Ȃ�������x�[�������v�Ɛ������܂����B
���̂����Ŕ��g��́A����ҁA�q�ǂ��A���̒��Ԃ̐���̂��ꂼ��ɉ�����������ׂ����Ƃ��āA��̓I�ɂ́A����҂ɑ��ẮA���N�`���̒lj��ڎ��A�����҂��o������Ҏ{�݂ł̌����Ȃǂ̑�������ɉ����āA�V���ȃ|�C���g�Ƃ��āA���a�̂���l�͊��������������ɁA�}�ɏ�Ԃ��������₷�����߁A���퐶���̓���̃��x���������Ȃ��悤�A���@�ł̑Ή������łȂ��A�ݑ��Â⍂��Ҏ{�݂ł̎x�����������ׂ����Ƃ��Ă��܂��B
�܂��q�ǂ��ɂ��ẮA����̑�l���̒��Ǘ������Ēlj��ڎ킷��ȂǁA��l����邱�Ƃ��厖���Ƃ����ق��A
�ق��̐���ɂ��ẮA�Ԍ��⊽���}��ȂǁA�������X�N�̍����s���̍ۂɂ͊y���݂Ȃ�����}�X�N�Ȃǂ̊�����ɒ��ӂ��邱�Ƃ�A�̒��������Ƃ��ɂ͉�Ђ��x�ނ��Ƃ��d�v���Ǝw�E���܂����B
���g��́u�d�_�[�u����������Ɗ����Ґ���������\���͂��邪�A�d�ǎҐ���������x�}���A��Â̂Ђ������������悤�ɂ��邱�Ƃ��厖���B���N�`���̐ڎ헦���������[���b�p�ł��A���S�Ґ�����������̍��ƁA�����Ă��鍑������A���N�`���ȊO�̑���������肵�Ă��鍑�ł͔�r�I�Ή��ł��Ă���B���N�`���͕K�v�����\���ł͂Ȃ��A������𑱂��Ȃ��ƃ��[���b�p�̈ꕔ�̍��̂悤�ɁA���S�҂������邱�ƂɂȂ�B���������Ȕ�܂A�G�A���]���ɂ�銴���������Ȃ��Ă���̂ŁA�}�X�N�͎�����l����邽�߂ɁA�܂������������悭�A������낤�Ǝv���Ă���v�Ƙb���܂����B
����ɔ��g��́A�����������������i�K�ŁA�܂h�~���d�_�[�u���Ñ̐��݂̍���ȂǁA�������I�ȉۑ�ɂ��Ă��c�_���Ă����K�v������Ƃ���F���������܂����B
|
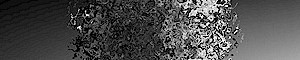 |
�������̃R���i�����ҁA�v600���l��˔j �@3/18
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�18���A�ǔ��V���̏W�v�ŗv600���l�����B500���l��˔j����2��28������18���Ԃ�600���l��ɒB�����B
�������s�@�V����7825�l�̊������\�@15���A���őO�T���j���������@3/18
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�����s�͂��傤�V����7825�l�̊����\���܂����B
��T���j����8464�l����639�l����܂����B15���A���őO�̏T�̓����j���̐V�K�����Ґ���������Ă��܂��B�����s�́u���������A��t�������Ɛf�f�����v�g�݂Ȃ��z���h�̊��҂������҂Ƃ��Ĕ��\���Ă��āA312�l���g�݂Ȃ��z���h�̊��҂ł����B�V���Ȋ����҂̂����A���N�`����2��ڎ킵�Ă����l��3644�l�ŁA1����ڎ�����Ă��Ȃ��l��2221�l�ł����B�V�^�R���i�̕a���g�p����34.7���ŁA�ő�Ŋm�ۂł��錩���݂�7229���ɑ��A2505�l�����@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�̕a���g�p���́A�O���̎��_��18.5���ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł́A10�㖢����1458�l�A10�オ1072�l�A20�オ1349�l�A30�オ1434�l�A40�オ1357�l�A50�オ628�l�ŁA�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂�389�l�ł����B���ݓ��@���Ă��銴���҂̂����A�����s�̊�Łu�d�ǎҁv�Ƃ����l�́A48�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��V���ɁA21�l�̎��S�����\����Ă��܂��B
����錧�ł̃R���i�����ҁA�ߋ��ő���1800�l�@���҂�4�l�@3/18
��錧��18���A�V����1800�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������A4�l�����S�����Ɣ��\�����B�V�K�����Ґ��́A����܂ōł���������12����1748�l���������B�v�̊����Ґ���9��8471�l(����356�l)�B
���X���̃R���i������656�l�@2�������ĉߋ��ő��X�V�@3/18
�X����18���A�݂Ȃ��z���҂��܂ߐV����656�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����Ґ��Ƃ��Ă�17����642�l���A2���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
|
���R���i�V�K�����Ґ� �ɂ₩�Ȍ����X�� �ꕔ�ł͑����X���� �@3/18
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł�1�����ԗ]��ɂ킽���Ċɂ₩�Ȍ����X������������ŁA����21���������ɂ܂h�~���d�_�[�u�̉��������܂����n��̈ꕔ���܂߂āA�����X�����݂���Ƃ�����o�Ă��܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��āA�O�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S��
�挎17���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T�ɔ�ׂ�0.88�{�A�挎24����0.88�{�A����3����0.92�{�A����10����0.86�{�A����17���܂łł�0.90�{�ƁA5�T�A���Ŋɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��́A�ł����������挎��{�Ɣ�ׂ��4���l�ȏ㌸��A���悻5��906�l�ƂȂ��Ă��܂����A���N�Ă̊����̑�5�g�̃s�[�N��2�{�ȏ�ŁA�ˑR�Ƃ��đ�����Ԃ������Ă��܂��B
���d�_�[�u ���������n��
����21���ł̏d�_�[�u�̉��������܂���18�̓s���{���ł́A�����Ґ��������������Ă�����̂́A�����ނˌ����X���ƂȂ��Ă��܂��B
�y�����s�z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.91�{�A����10����0.83�{�A����17���܂łł�0.87�{�ƁA5�T�A���Ŋɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ���8159�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���406.57�l�ƁA�S���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
�y�_�ސ쌧�z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.91�{�A����10����0.91�{�A����17���܂łł�0.92�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻5293�l�ƂȂ��Ă��܂��B����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���401.07�l�ƁA�����s�Ɏ�����2�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�y��ʌ��z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.84�{�A����10����0.89�{�A����17���܂łł�0.97�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3748�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y��t���z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.89�{�A����10����0.92�{�A����17���܂łł�0.91�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2987�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���{�z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.86�{�A����10����0.73�{�A����17���܂łł�0.82�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ���4804�l�ƂȂ��Ă��܂��B����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���380.51�l�ƁA�����s�A�_�ސ쌧�Ɏ�����3�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�y���s�{�z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.82�{�A����10����0.80�{�A����17���܂łł�0.88�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1038�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���Ɍ��z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.85�{�A����10����0.87�{�A����17���܂łł�0.80�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2412�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���m���z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.89�{�A����10����0.81�{�A����17���܂łł�0.80�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2943�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.92�{�A����10����0.80�{�A����17���܂łł�0.89�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻486�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�k�C���z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.86�{�A����10����0.81�{�A����17���܂łł�0.92�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1540�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���̑��z�@�X���͍���17���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.09�{�A��錧��1.03�{�A�Ȗ،���1.00�{�A�Q�n����1.07�{�A�ΐ쌧��0.98�{�A�É�����0.94�{�A���쌧��1.03�{�A�F�{����0.88�{�ƁA�ꕔ�őO�̏T��葽���Ȃ��Ă���n����݂��܂��B
�����łɉ������ꂽ�n�� �����X����
���łɏd�_�[�u���������ꂽ�n��̂����A�������≫�ꌧ�Ȃǂł͊ɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂����A�L�����ȂǑ����X���ƂȂ��Ă���n�������܂��B
�y�������z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.94�{�A����10����0.86�{�A����17���܂łł�0.89�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2268�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���ꌧ�z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.41�{�A����10����0.86�{�A����17���܂łł�0.91�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻625�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�L�����z�@����3���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.96�{�A����10����0.97�{�A����17���܂łł�1.09�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻726�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���̑��z�@�R�`���͍���17���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.05�{�A�V������1.31�{�A���쌧��1.15�{�A��������1.02�{�A�{�茧��1.12�{�ƁA�������瑝���X���ƂȂ��Ă��܂��B
������ �g���s�͉��P�� �܂���6�g�̂��Ȃ��h
�����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́A���݂̊����ɂ��āu�����Ґ������łȂ��A�d�ǎҁA���Ґ����s�[�N���z���Č����Ă��Ă��āA��Â̂Ђ�����������x��������Ă��邱�Ƃ���A�S�̗̂��s�Ƃ��Ă͉��P���Ă��Ă���ƌ����Ă����Ǝv���B�����A���͈��5���l�O��ƁA���N�Ă̑�5�g�̃s�[�N��2�{�̊����Ґ����o�Ă���B��6�g�͌����ďI������킯�ł͂Ȃ��A�܂����̂��Ȃ��ɂ��邱�Ƃ͖Y��Ȃ��ق��������v�Ƙb���Ă��܂��B����̌��ʂ��ɂ��āu���E�I�ȌX���Ƃ��āA�����Ґ���������x�o���Ƃ��Ă��A�d�ǎ҂̑�����a���̂Ђ������N���Ȃ���A�K�����ɘa���A�Љ�E�o�ς̍Đ��Ɍ���������ɂȂ��Ă���B���[���b�p�ł͂�芴���͂̋����wBA.2�x�̊g��͂��邪�A�K�����������ė��s���ĔR���Ă���Ƃ�������B���ꂩ��N�x�ւ��ŁA�����}���Ԍ��ȂǁA���낢��ȍs���Ŗ��ɂȂ�@������Ȃ�̂ŁA�����Ґ���������������\�����l������B�s���̍ۂɂ���{�I�ȗ\�h����s���A����ɂł��邾�������̐l�����N�`���̒lj��ڎ���Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B
|
���V�^�R���i�g��6�g�h �����Ґ������肫��Ȃ����R�́@3/18
�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N���������g�債���u��6�g�v�̓s�[�N���z���A�e�n�ɓK�p����Ă����܂h�~���d�_�[�u��2�����Ԃ�ɉ����ɁB�������A�����̌����X�s�[�h�͊ɂ₩�ŁA�����Ґ��͋��N�Ăɋً}���Ԑ錾���o����Ă����Ƃ��̃s�[�N����2�{�ȏ�ƁA������Ԃ������Ă��܂��B���̂܂܊����������肫��Ȃ��܂܁A���́u��7�g�v�ɂȂ����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A���O���鐺���o�Ă��܂��B�ǂ����Ċ����������肫��Ȃ��̂��B
���g��6�g�h ���������X�s�[�h�͊ɂ₩
���N�ɓ����Ċ������}���Ɋg�債����6�g�ł́A�S���̈���̐V�K�����Ґ���2��5���̂��悻10��5600�l���s�[�N�ƂȂ�܂����B1�T�ԕ��ςł݂�ƁA2��10���O���9��3000�l�������ƁA�����X���ƂȂ�܂������A1�������܂肽����3��17���̎��_�ł����悻5��1000�l�ŁA���悻45���̌����ƁA�����ɂ͎����Ă��܂���B���N�Ă̑�5�g�̃s�[�N�́A����̐V�K�����Ґ��ł�8��20����2��5992�l�A1�T�ԕ��ςł�8��25������2��3000�l���܂�ł����B1�������܂肽����9��29���ɂ́A1�T�ԕ��ς͂��悻2190�l�ƁA90�����܂茸�����Ă��܂����B��5�g�ł͊����͋}���ɒႢ���x���ɂ܂ʼn�����܂������A��6�g�ł͌����X�s�[�h�͊ɂ₩�ł��B3��15���ɊJ���ꂽ�����J���Ȃ̐��Ɖ�̂��Ƃ̋L�҉�ŁA�e�c���� �����́u�S���I�Ɍ����X���ł͂��邪�A���̌������x�͑��ς�炸�ɂ₩�ŁA�������x���ǂ�ǂ��Ȃ��Ă�����2021�N�̑�5�g�̎����ǖʂƂ͂��Ȃ�Ⴄ�ɂ���B���ꂩ��A�x��t�x�݁A�N�x�ւ��ȂǂŐl�̐ڐG�������邱�Ƃ��芴�����̍����wBA.2�x�n���̃E�C���X�ɒu������肪�i�ނ��ƂȂǂŁA�Ăъ����҂������X���ɓ]����\��������A�\�����ӂ����Ă����K�v������v�Ƙb���Ă��܂��B
�������x�����R
�����X�s�[�h���ɂ₩�ȗ��R�Ƃ��āA���Ƃ�������̂�
�E3��ڂ̃��N�`���A�lj��ڎ킪�x�ꂽ���Ƃō���҂ւ̊���������������
�E����܂łɂȂ��K�͂ł̎q�ǂ������ւ̊����������Ă��邱��
���傫���Ǝw�E���Ă��܂��B
�����N�`��3��ڐڎ�̒x�� ����҂Ɋ����g��
��5�g�ł́A�������}���Ɋg�債��2021�N7�����{�̒i�K��65�Έȏ�̍���҂�2��̐ڎ�����������l��70�����Ă��āA�Ⴂ����ōL����������������҂Ɉڍs���邱�Ƃ����Ȃ��������߁A�}���Ȍ���������ꂽ�ƕ��͂���Ă��܂��B����A��6�g��2022�N1����{�̒i�K�ł́A2��ڂ̐ڎ킩�玞�Ԃ������Ċ�����h�����ʂ��������Ă��������A65�Έȏ�̍���҂�3��ڂ̐ڎ�����l��1���ȉ��ł����B�ڎ헦�́A�����Ґ����ł���������2��5���̒i�K�ł����悻15���ɂƂǂ܂��Ă��āA�����������Ƃ���Ⴂ����Ŋ������g�債�����ƁA����҂Ɋ������ڍs�����Ƃ݂��܂��B����҂̊����͑����Ă��āA�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂ł́A����14���܂ł�1�T�Ԃł��S���̍���ҕ����{�݂Ŋm�F���ꂽ�N���X�^�[��341���Ƒ�����Ԃ������Ă��܂��B
��������w����� ����w ���ߌ��u �����u���{���ł͑����������ԕa���̂Ђ����������A����Ҏ{�݂Ŋ����҂��o�Ă����@�ł����ɁA�{�݂ŃP�A�𑱂�����Ȃ��Ƃ���������A���܂�����ɋ߂���Ԃ������Ă���B�{�ݓ��Ɋ����҂��Ƃǂ܂��Ă���̂Ŏ���Ɋ������L����B��Â̂Ђ����ō���҂����@�ł��Ȃ��Ȃ�A�{�ݓ��Ŋ����҂�������Ƃ������z�����܂�Ă���B���܁A���{���Ŕ�������N���X�^�[�̔������炢������҂ɊW������̂ŁA�������v�����悤�Ɍ������Ȃ��v����1�ɂȂ��Ă���v
�����J���Ȃ̐��Ɖ�ɂ��Q�� ���ꌧ�������a�@ ���R�`�_��t�u����ł͊����Ґ���������������ƂőS�̂͑����ɓ]�������A3����{�̒i�K�ł��łɍ���҂�6���ȏオ���N�`���̒lj��ڎ���I��点�Ă��āA����҂̊����͌����������Ă���B�S���ł��A���ɍ���҂ւ̃��N�`���̒lj��ڎ��i�߁A����Ҏ{�݂Ȃǂł̃N���X�^�[����x�����Ă������ƂŊ����̃C���p�N�g�����炵�Ă�����v
���q�ǂ��̊��� ����܂łɂȂ����� �����p��
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA10�Ζ����̊��������q�ǂ��́A��5�g�ł�2021�N8��31���܂ł�1�T�Ԃ��ł�����1��380�l�ł������A��6�g�ł͊����������ǖʂɂȂ��Ă���2022�N3��15���܂ł�1�T�Ԃł�6��5000�l���܂�Ƒ�����Ԃ������Ă��܂��B�����ґS�̂ɐ�߂�10�Ζ����̎q�ǂ��̊�����2022�N1����{�ɂ�5���قǂɂƂǂ܂��Ă��܂������A2�����{�ȍ~�͑S�̂̊����Ґ����������钆�A����15���܂ł�1�T�Ԃł͂��ׂĂ̔N��ōł������A�S�̂�21�����߂Ă��܂��B�q�ǂ��ɊW����N���X�^�[�������Ȃ��Ă��āA����14���܂ł�1�T�ԂŁA�ۈ珊�Ȃǂ́u���������{�݁v��229���ƑO�̏T����56�������A�ߋ��ő��ƂȂ����ق��A�u�w�Z�E����{�ݓ��v���O�̏T����59�������A318���ƂȂ�܂����B���Ƃ́A�I�~�N�������̓f���^���Ȃǂɔ�ׂ�ƁA�q�ǂ��ł��w�Z��c�t���ȂǁA�W�c�Ő���������ōL����₷���Ȃ��Ă��āA�q�ǂ��͂ق��̔N��Ɣ�ׂă��N�`����ڎ킵�Ă���l�̊������Ⴂ���Ƃ�����Ǝw�E���Ă��܂��B
�����J���Ȑ��Ɖ �e�c���� �����u�I�~�N�������͊����͂������̂ŁA����܂ł��܂�L����Ȃ������q�ǂ������ւ̊����������Ƃ��Ă͍����Ȃ��Ă���B12�Ζ����̓��N�`�����\���ɐڎ킳��Ă��Ȃ����Ƃ�����A���̐�������������������Ă��Ȃ����Ƃ��A�N��ʂ̊��������Ă��������Ƃ��ł���B���݁A�����������~�܂��Ă����艡���������肷��n�悪�������邪�A10��ȉ��̊��������������Ƃ���ł́A�����Ґ����Ȃ��Ȃ��������Ă��Ȃ��B�q�ǂ��̊������e�����Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�C���t���G���U�̂悤�Ɏq�ǂ������̔����I�Ȋ�������L�����Ă���킯�ł͂Ȃ����A�q�ǂ������l�֊ɂ₩�ɍL���������A�Ȃ��Ȃ������ɂȂ����Ă��Ȃ��v
���ꌧ�������a�@ ���R�`�_��t�u���H�X�̐����Ƃ�������̌��ʁA��Ґ���ł̊����͑傫������������ŁA�q�ǂ����m�̊�����ƒ���ōL���銴���ɂ͑�̌��ʂ͂��܂�͂��Ȃ������B�I�~�N�������́A��C���������N�����₷���A�q�ǂ������ł��������₷���Ȃ��Ă���B�܂��A�̂ǂ̒ɂ݂�i����q�ǂ��������ɂ��A�N�Z�X���₷���Ȃ��Ă��邱�Ƃ���A����܂ł��q�ǂ��̊��������o���₷���Ȃ��Ă��邱�Ƃ��v���ɋ�������̂ł͂Ȃ����v
�����J���Ȑ��Ɖ�����o�[ ���ۈ�Õ�����w �a�c�k�� �����u���{�ł�12�Ζ����̎q�ǂ����������N�`���ڎ킪�i��ł��Ȃ��w�|�P�b�g�x�ƌĂ��N��ɂȂ��Ă���B����0����5�͂܂��ڎ�����錩�ʂ����Ȃ��̂ŁA�������L����₷���Ȃ��Ă���B����A�q�ǂ������̊������c���Ă��܂����Ƃ͏\���ɍl������̂ŁA���ɐV�w������Ă���܂ł́A�q�ǂ������Ɋ������L����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ�������Ȃ��B�ۈ牀��c�t���A�w�Z��߂邱�Ƃ͂Ȃ�ׂ������āA�w�т̋@�����������Ɗm�ۂ���Ȃ�������Ȃ��B�Ǐ���l�͋x�܂Ȃ�������Ȃ����A�ǏȂ��ꍇ�͊���������Ȃ���^�c�ł���x�����d�v�ɂȂ��Ă���v
�����肫��Ȃ��܂܍Ċg�储�����
19�������3�A�x��A�N�x���̑��Ǝ��⊽���}��ȂǂŐl�Ƃ̐ڐG�@�������ƁA�����������肫��Ȃ��܂܁A�Ċg�傷�邨���ꂪ����܂��B���É��H�Ƒ�w�̕��c�W�������̌����O���[�v��AI���l�H�m�\���g���ė\�������Ƃ���A�����s���̊����Ґ���4����{��1��5400�l�]��܂ʼn����������Ƃ͂قډ����ɂȂ�Ƃ������ʂɂȂ�܂����B���c�����̃O���[�v�́A�l����ߋ��̊����A����Ƀ��N�`���̌��ʂȂǂ̃f�[�^�����ƂɁAAI���g���ė\���B
�E�܂h�~���d�_�[�u�̉�����A�l����2021�N�̓��������̐����܂ʼn����Ƒz�肷��ƁA�����s�̐V�K�����Ґ���4����{��1��5400�l�]��܂Ō����������ƁA���㏸���Ăقډ����ƂȂ�A4�����{�ł�1��5600�l�]��ɂȂ�Ɨ\�����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�E�l����2021�N�̓����������20���������ꍇ�́A4���̏�{�ȍ~�A�������Ƒ������A���{�ɂ�1��7700�l�]��Ƃ����\���ɂȂ�܂����B
�E�l���̑����ɉ����Ĉ��݉�Ȃǂ��N���N�n���ɑ������ꍇ�́A3�����ɂ͐V�K�����Ґ��������ɓ]���A4�����{�ɂ�1��1��3000�l�]��Ɨ\�����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�O���[�v�́A���N�`����3��ڐڎ�Ȃǂ̌��ʂ��l����Əd�ǎҐ����}������\���͒Ⴂ���̂́A�����̍Ċg���}���邽�߂ɂ͉�H�̐l�������Ȃǂ̑K�v�ȉ\��������Ƃ��Ă��܂��B
���É��H�Ƒ�w ���c�W�������u���̎����͐l�����l���ł̉���Ȃǂ�������X��������A�����Ґ�������ɂ��������ƌ�����v
���uBA.2�v�ɒu�������H
����1���O����Ă��邱�Ƃ�����܂��B�I�~�N��������1�A�uBA.2�v�n���̃E�C���X�ł��B3��15���ɊJ���ꂽ�����J���Ȃ̐��Ɖ�ł́A����̍����ł́uBA.2�v�̐��ڂɂ��Ă̗\����������܂����B���̒��ŋ��s��w�̐��Y�������́A�����s�̌����f�[�^�����ƂɁA�����s���ł�4��1�����_�ŃI�~�N�������S�̂�82�����uBA.2�v�ɒu�������Ƃ���\���������܂����B�܂��A���������nj������̗�؊���lju�w�Z���^�[�������������͂ł́A���Ԍ����@��2�Ђ�Ώۂɂ������o���������ƂɁA�S���́uBA.2�v�̊��������̂悤�ɗ\�z����܂����B4����1�T���_��70���B5����1�T���_��97���B�uBA.2�v�́A���ݎ嗬�ƂȂ��Ă���uBA.1�v�ɔ�ׁA��������20�����x�A���܂��Ă���ƍl�����Ă��܂��B�uBA.2�v�ւ̒u������肪�i�߂A����܂łƓ�����ł́A�\���Ɋ��������������߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂������ꂪ����̂ł��B
�����J���Ȑ��Ɖ �e�c���� �����u�wBA.1�x�n���̃E�C���X�����芴�����̍����wBA.2�x�ɒu������肪�i�ނ��ƂȂǂŁA�Ăъ����҂������X���ɓ]����\��������A�\�����ӂ���K�v������v
������̑Ή��͂ǂ�����Ηǂ��̂�
����A�傫�Ȋ����̔g���N�������A��Â̂Ђ�����h�����߂ɁA�������͂ǂ��Ή�����Ηǂ��̂��B
3��17���A�d�_�[�u�̉����̕��j�𗹏�������{�I�Ώ����j���ȉ�̌�A���g�Ή�́A�u�d�_�[�u����������ƁA�����Ґ���������\���͂��邪�A�d�ǎҐ���������x�}���A��Â̂Ђ������������悤�ɂ��邱�Ƃ��厖���B���N�`���̐ڎ헦���������[���b�p�ł����S�Ґ�����������̍��Ƒ����Ă��鍑������A���N�`���ȊO�̑���������肵�Ă��鍑�ł͔�r�I�Ή��ł��Ă���B���N�`���͕K�v�����\���ł͂Ȃ��A������𑱂��Ȃ��ƁA���[���b�p�̈ꕔ�̍��̂悤�Ɏ��S�҂������邱�ƂɂȂ�B���������Ȕ�܂A�G�A���]���ɂ�銴���������Ȃ��Ă���̂ŁA�}�X�N�͎�����l����邽�߂ɂ܂������������ǂ��A������낤�Ǝv���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
�ق��̐��Ƃ��A���������A������ɒ��ӂ��A�Ƃ��ɁA����A�l�Ƃ̐ڐG�������s���Ȃǂ�������G�߂ƂȂ钆�A���N�`���ڎ��i�߂�ƂƂ��ɁA�������X�N�������s�����Ƃ�ۂɂ͓��ɒ��Ӑ[����悤�Ăт����Ă��܂��B
���ۈ�Õ�����w �a�c�k�������u����A��������@���������̂ŁA���������łȂ��Ƒ���F�l����邽�߂ɂ��A�Ⴂ�l���܂߂Ăł��邾�������^�C�~���O��3��ڂ̐ڎ���Ă��炤���Ƃ��d�v���B�Ƒ��ȂǏ��l���ł̉Ԍ���A�H�����b�����Ȃ����Ǝ��ł���ΐe�̎Q����F�߂�ȂǁA�������������ł���Ύ��{�ł���B�s���͂܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ��A�s���Ǝ��Ǝ҂ɉ������߂�̂��`���邱�Ƃ��d�v���v
����w ���ߌ��u�����u�d�_�[�u�̉�����ɓ����s����{�ł��đ����Ɍ������\��������A���܂܂ł̊Ԋu��葁���^�C�~���O�Ŏ��̗��s�����邨���ꂪ����B���̔g������܂łɍ���҂ւ̃��N�`���̒lj��ڎ킪�s���n��悤�ɂ�����ŁA�����҂��o������Ҏ{�݂ɑ����ɉ�����Ď��Â��n�߁A������̎w���𑁂߂ɍs����悤�ɂ���ȂǁA�x���̐��𑬂₩�ɐ�����K�v������v
���ꌧ�������a�@ ���R�`�_��t�u�ߋ�2�N���t�x�݂̂��Ƃɗ��s���N���Ă���A��7�g���N����\���������ƍl���ď��������Ă����K�v������B����Ҏ{�݂Ŋ��������������ꍇ�A�Ȃ�ׂ�����������Ċg���h�����ƁA����Ƀ��N�`���̒lj��ڎ��i�߂邱�ƂŎЉ�S�̂ɑ傫�Ȑ����������邱�ƂȂ��A��7�g�����z���邱�Ƃ��ł����炢���ƍl���Ă���v�@ |
 |
��4��ڂ̃��N�`���ڎ�̌��ʂɂ���Ė��炩�ɂȂ��Ă����A�L�����̌��E�@3/20
���{�ł͌��݃u�[�X�^�[�ڎ�Ƃ��Ă��3��ڂ̐V�^�R���i���N�`���̐ڎ킪�i�߂��Ă��܂��B�C�X���G���ł͂��ł�4��ڂ̐ڎ킪�s���Ă���A���̌��ʂ̈ꕔ������Ă��܂��B�c�O�Ȃ���ڊo�܂������ʂ͊m�F���ꂸ�A���̌��ʂɂ���ă��N�`������͑傫�Ȋ�H�ɗ�������邱�ƂƂȂ肻���ł��B
��4��ڂ�mRNA���N�`���ڎ��A�R�̂͂ǂꂭ�炢�����邩
��Ï]���҂�Ώۂɂ����C�X���G���ł�4��ڂ̃��N�`���̌��ʂƈ��S����]����������������Ă��܂��B
1250�l�̈�Ï]���҂̂����A�t�@�C�U�[3��ڐڎ킩��4������ȍ~��154�l���Ƀt�@�C�U�[��4��ڂ̐ڎ���A120�l�����f���i��4��ڂ�ڎ킵�܂����B
�}�̓��N�`���ڎ��̃X�p�C�N�`��RBD�ƌĂ��A���ۂ̃E�C���X�𒆘a���钆�a�R�̗̂ʂf���₷���R�̉��̐��ڂ������Ă��܂��B
�c����2��ڂ���3��ځA3��ڂ���4��ڂ̌�̕����R�̉��͍����Ȃ��Ă��܂����A����قǑ傫�ȕω��Ƃ͌����܂���B
�������A3��ڂ̐ڎ��Ɏ��Ԃ��o�ƍR�̉��������Ă��܂����A4��ڂɂ���Ă��ꂪ�ď㏸����Ƃ������Ƃ͊m�F�ł��܂��B
���I�~�N�������ɑ��钆�a�R�̂�4��ڎ����s�\��
���N�`���ڎ��ɎY������钆�a�R��(���ۂɃE�C���X�𒆘a���邽�߂̍R��)�̗ʂ́A�ψي��̎�ނɂ���ĈقȂ�܂��B
���X�A�t�@�C�U�[��f���i��mRNA���N�`���́A�����Ō��������V�^�R���i�E�C���X(������쐶��)�̃X�p�C�N�`�����זE���ŎY�����A�Ɖu��Ƃ������̂ł��B
�������A�I�~�N�������ł͔��ɑ����̃X�p�C�N�`���̕ψق��N�����Ă���A�쐶���̃X�p�C�N�`���Ƃ͊�����傫���ς���Ă��܂��B
���̂��߁AmRNA���N�`���̐ڎ�ɂ���Ė쐶���ɑ��钆�a�R�̂͑����Y������܂����A�I�~�N�������ɔ������邽�߂̒��a�R�̗̂ʂ͏\���ł͂���܂���B
4��ڂ̐ڎ�ł͂ǂ��Ȃ邩�Ƃ����ƁA�������͂�쐶���Ɣ�ׂ��10����1�ȉ��̗ʂƂȂ��Ă���A�\���Ƃ͌����܂���B
���a�R�̗̂ʂ͊�����h�����ʂƊT�ˑ��ւ���ƍl�����Ă���A�I�~�N�������ɑ��ď\���Ȓ��a�R�̂��Y������Ȃ����Ƃ́A�\���Ɋ�����h�����Ƃ͓���Ɛ�������܂�(�d�lj���h�����ʂ͕K���������a�R�̗̂ʂƑ��ւ��܂���)�B
��4��ڂ̃��N�`���̊����\�h���ʂ�11〜30��
���̌����ł́A4��ڂ̃��N�`���ڎ�����Ȃ������l(3��ڂ܂Őڎ킵���l)�́A�ώ@���Ԓ���25�����I�~�N�������Ɋ��������̂ɑ��A�t�@�C�U�[�ڎ�Q��18.3%�A���f���i�ڎ�Q��20.7%���������Ă���A3��ڐڎ�݂̂̐l�Ɣ�ׂ������\�h���ʂ͂��ꂼ��30���A11���ƌv�Z����܂����B
���������̌����ł͎Q���҂̐l���������Ȃ����߁A���N�`���̌��ʂ��ߏ��]�����Ă���\��������܂��B
���Ȃ݂ɂ��̌����ŃI�~�N�������Ɋ���������Ï]���҂́A4��ڐڎ�Q�̕������nj����҂̊�������������(25〜29.2%)���̂́A4��ڂ�ڎ킵���Q���ڎ�Ȃ��̌Q�Ɣ�ׂăE�C���X�ʂ͑����A���������ꍇ�̎���Ɋ������L���郊�X�N�͂����炭�ς��Ȃ����̂ƍl�����܂��B
�Ȃ��A4��ڂ̐ڎ��ɐ������������́A3��ڂ܂ł̕������Ƒ傫�ȈႢ�͌����܂���ł����B
����܂Œʂ�ڎ핔�ʂ̎���ɂ݁A���邳�A�ؓ��ɁA���ɁA���M�A�����p�߂̎��Ȃǂ������Ă��܂��B
3��ڂ܂ł������ɕ������������Ȃ�A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ������ł��B
��60�Έȏ�̍���҂ł͊������X�N�������A�d�lj����X�N��1/4
�t�@�C�U�[�Ђ�3��15���Ƀv���X�����[�X�o���A�C�X���G���ɂ�����60�Έȏ�̍���҂�Ώۂɂ���4��ڂ̃��N�`���ڎ�̌��ʂɂ��Ĕ��\���܂����B
���̃v���X�����[�X�ɂ��ƁA3��ڂ̐ڎ킩��4������ȍ~��4��ڂ̃��N�`���ڎ����������҂ł́A4��ڂ�ڎ킵�Ă��Ȃ�����҂Ɣ�r���Ċ����҂������A�d�lj������l��4����1�ł������A�Ƃ̂��Ƃł��B
�����̃f�[�^�����ɁA�t�@�C�U�[�Ђ̓A�����J��FDA(�A�����J�H�i���i��)��65�Έȏ�̍���҂ɑ���4��ڂ̐ڎ�Ɋւ���\�����s�����Ƃ̂��Ƃł��B
��4��ڐڎ�̌��ʂŌ����Ă����������N�`���̌��E
�ȏ�̂悤�ɁA4��ڂ̃��N�`���ڎ�̌��ʂ���S���Ɋւ�����͌����Ă��܂����A3��ڂ�4��ڂƂł͑傫�Ȍ��ʂ̍��͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ��u�S����4��ڂ̐ڎ��������R���i�͏I������v�Ƃ������Ƃ͊��҂ł��Ȃ������ł��B
�I�~�N���������嗬�ƂȂ��Ă��錻��ɂ����ẮA4��ڂ̃��N�`���ڎ킷�邱�ƂŐڎ킵���l�̊������X�N�������邱�Ƃ͂ł���悤�ł����A���������S�ɖh�����Ƃ͂ł��Ȃ��悤�ł��B
����҂ł͎��Ԍo�߂ƂƂ��ɏd�lj���h�����ʂ��������Ă��܂��̂�4��ڂ�ڎ킷��Ӌ`�͂���ł��傤�B
�a�@���ł̃N���X�^�[�������ł��h���Ƃ����Ӗ��ł͈�Ï]���҂��ڎ�ΏۂɂȂ�Ǝv���܂��B
�������A���ł�3��ڎ���������ďd�lj����X�N���傫��������������ȊO�̐l�����ɂƂ��āA3��ڂ��炽����4�����̊Ԋu��4��ڂ̐ڎ���s���̂͌����I�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�����4��ڂ̐ڎ�̌��ʂɊւ���́A�L�������������Ƃ������͊����̃��N�`���̌��E���������Ƃ������܂��B
�u�����A�����A���ɔ����N�ɂȂ������E�E�E�ŗ������v�Ǝv��ꂽ��������܂��A���������킯�ł͂���܂���B
����܂ł�mRNA���N�`���Ȃǂ̐V�^�R���i���N�`�����ʂ��������т͂��܂�ɑ傫���f���炵�����̂ł��B���݁A�����͂��ɂ߂ċ����I�~�N�������Ŋ����҂������I�ɑ����Ă��܂��܂������A����ł����ꂾ���̏d�ǎҁE���S�҂ōς�ł���̂̓��N�`���ڎ�̉e�������ɑ傫���ł��B
�������A�����̃��N�`���͏d�lj��\�h���ʂ͕ۂ���Ă�����̂́A�Z���Ԃŏo�����Ă���ψي��ɑ��ď\���Ȋ����\�h���ʂ������I�ɕۂ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂�(����A�I�~�N�������������N�`���������₷���ψي����I�~�N����������u�������Ƃ������Ƃ��A����܂ł̕ϑJ���l������܂���҂ł��Ȃ��ł��傤)�B
�܂��A4�������Ƃɒlj��ڎ�����X�ƍs�����Ƃ́A�ꕔ�̖Ɖu�s�S�ҁE��b�����̂�����⍂��҈ȊO�̐l�X�ɂƂ��Ă͌����I�ɓ���ƍl�����܂��B
�����̃��N�`���̒lj��ڎ�͏d�lj����X�N�̍����l�Ɍ��肵�A����́A��蒷���Ԍ��ʂ��������郏�N�`����A�l�X�ȕψي��ɑ��ĕ��L�����ʂ������N�`���̊J���ɒ��͂��ׂ��A�Ƃ����ӌ��������Ă���ł��傤�B
���������Ӗ��ł́A�����4��ڂ̐ڎ�Ɋւ�����ʂɊւ���́A����̂���Ȃ郏�N�`���J���̕K�v�������߂ĔF����������̂ɂȂ����ƌ�����ł��傤�B
�����āA�����������N�`�����o�ꂷ��܂ł́A4��ڈȍ~�̃��N�`���́u�ǂ��������l�����ցv�u�ǂꂭ�炢�̊Ԋu�Łv�ڎ킷�ׂ��Ȃ̂��A�Ȋw�I�����Ǝ����\���̌��n���猟�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�Ȃ��A����҂��b�����̂�����ɂƂ��Ă�3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�d�lj����X�N��傫�������邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�܂������̐l�ɂƂ��Ă�3��ڂ̃��N�`���ڎ�̓I�~�N�������ɂ�銴����h�����ʂ��Ăэ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B |
���l�����ŃR���i��7�g�������c�����NJw�̐��Ƃ̌����@3/20
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ����E���Ɋg�傷�钆�ŃE�C���X�͕ψق�����Ԃ��A�����������Ȃ��ɂȂ��Ă���B���{�ł̓}�X�N�̏K����N�`���ڎ�ő������������g�傪�}�����Ă��邪�A�܂������҂͑��������Ă���B�����NJw�����̓��{��ȑ�w�̖k���`�_���C�����ɁA����̊����ǂ̓����\�z�Ȃǂ����B
�\�\��6�g�ł�1���̊����҂͂���܂ł��������ł��B
�u���������Ǝ�s���ł̊����҂͌����X���ɂ���A��6�g�̏I�Ղɂ͊����Ґ�����ԑ�����������10����1���x�܂Ō������邾�낤�B�����n���ł̊����҂̌���������ꂸ�A���ꌧ�ł͉����������k���n���ł͑����X���ɂ���B����͎�s���̐l�������n���Ɉړ����邱�ƂŊ������L�������Ƃ݂Ă���v �u����ŐV���ȕψي��̃X�e���X�I�~�N�������̊g�傪���O����Ă��邪�A��s���ōL�������Ƃ����͂Ȃ��B�l����������s���Ŋ������L����Ȃ�����A���{���Ɋg�傷�邱�Ƃ͂Ȃ��ƍl����v
�\�\3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�n�܂�܂����B
�u�V�^�R���i���N�`����1��ڎ킷��Δ��i�v�I�Ɍ��ʂ�����̂ł͂Ȃ��A���ԂƂƂ��Ɍ��ʂ���������B���̂��ߒ���I�Ƀ��N�`����ڎ킷��K�v������B�����̐l��3��ڂ̃��N�`����ڎ킷�邱�ƂŊ����҂����łȂ��d�����҂�����A�����g�傪���������Ɨ\�z�����v�@�u�O��ڎ킵����ނƈقȂ郏�N�`����łw���ݐڎ�x��������B�t�@�C�U�[�ƃ��f���i�Ō��ݐڎ�����Ă��������̈Ⴂ�������邪�R�̂̌��ʂ͕ς�炸�A�ڂ�����𗧂Ă�قǂł͂Ȃ��ƍl���Ă���v
�\�\��7�g�͗���Ǝv���܂����B
�u3�\4���͐V�N�x�ւ̐�ւ������Ől�̗��ꂪ�����Ȃ�A��6�g�����������^�C�~���O�ő�7�g������Ɨ\�z����B�����I�ɉԌ��q�⑲�Ɨ��s������l�������A��s���̐l�������n���ɏo�����@��������Ȃ芴�����g�傷��ƌ�����B�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ��A���N�`����ڎ킷�邱�Ƃ��K�v���낤�v
|
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���u�܂h�~���d�_�[�u�v������ �u��Â��肬��v����͊�@���@3/21
���{�́A�V�^�R���i�E�C���X��̂܂h�~���d�_�[�u��21���������ɑS�ʉ������܂��B�V�K�����Ґ��̃s�[�N�͉߂������̂̈ˑR�Ƃ��Ċ����Ґ��͍��~�܂肵�Ă��܂��B��Ò̐��ɗ]�T���Ȃ��������������ŁA��Ï]���҂�́A�����̍Ċg�傪�N����Έ�Õ���������Ɗ�@�����点�Ă��܂��B
�����s��17���ɊJ�����V�^�R���i�E�C���X�̃��j�^�����O��c�B���Ƃ���́u�V�K�����҂͊ɂ₩�Ɍ����X���ɂ�����̂́A���܂���5�g�̃s�[�N���̖�1�E7�{�̐��l���v�u����҂����@���Ґ��̖�7�����߁A��Ï]���҂ւ̕��ׂ����債�Ă���v�Ȃnj���������A�d�_�[�u������̈�Ò̐��ւ̉e�����뜜���܂����B���̂����ŁA�u�����}��₨�Ԍ��ȂǔN�x���O��̃C�x���g�ɂ��l�̈ړ��A�ڐG�@��̑����Ȃǂ̉e������A�������Ċg�傷�鋰�ꂪ����v�Ǝw�E���Ă��܂��B
�V�^�R���i���{�����̒J��q�s��t�́A�u��Ë@�ւ͐[���Ȉ�Õ���Ƃ�������悤�₭�E���A�K�v�Ȉ�Â��ł��邩�ǂ����́A���肬��̏ɂ���܂��v�Ǝw�E���܂��B
�q�ǂ���Ⴂ����̊������������������A�a�@�E��������������Z���ڐG�҂ɂȂ����肷�鎖��������Ǝw�E�B�u�����Ζ�����a�@�ł́A�E��ɂ���Ă͊Ō�t��1���ȏオ��ɋΖ��ł��Ȃ��ɂ���A�f�Â̏k����]�V�Ȃ�����Ă��܂��B������Õ���Ɨׂ荇�킹�ł��v�Əd�_�[�u�����Ɍ��O�������܂����B
�V�^�R���i�E�C���X��̂܂h�~���d�_�[�u�̉����ɂ��āA���ł��s���̐����������Ă��܂��B
���{�́A18�����_�̃R���i���Ґ���4449�l�őS���ő��B�����̐V�K�����҂�3865�l�ł��B
���s���ɂ�����ȁE��������ȁu���݂̂�N���j�b�N�v�@���ő��{�ی��㋦��̉F�s�{���O�������́u����͂悤�₭���������Ă��܂����v�ƌ����܂��B
���݂́A�R���i�Ή��Ƃ��Ĕ��M�̎�f�҂�1��1�l�f�@������x�ɂȂ��Ă����ƌ����܂����A��6�g��U��Ԃ�Ɓc�B
�u�o�����Ă�����ʗ{��V�l�z�[���ŏW�c�������N���܂����B�����҂���@���������Ă��a�@�̃x�b�h�������ŋ�J���܂����B�悤�₭1�l���@�����邱�Ƃ��ł�������ǁA���@��ŖS���Ȃ��Ă��܂��܂����v
���s�ł͕ی�����������Ȃ��A��6�g�ŋƖ��͂Ђ������K�v�ȑ[�u������Ȃ��Ȃ�܂����B�R���i�a�����Ђ������A�K�Ȉ�Â��ł��܂���ł����B
�F�s�{�������́A�����������Љ�ۏ�}������𐄂��i�߂钆�A�a���팸����l���s���Ɋׂ邱�ƂɂȂ����Ɣᔻ���܂��B���܂��Ɍ����̐��͕s�\���Ȃ܂܂Ŏ��Ö���m������Ă��Ȃ��Ƃ��A�u�N�x����5���̑�^�A�x�Ɋ����̍Ċg�傪�\�z����܂��B���{�̊W�҂��ÊW�҂݂͂ȁA�R���i���낻���Ȃ܂܂̏d�_�[�u�����ɕs��������Ă��܂��v�Ƌ������Ă��܂��B |
���u�܂h�~���d�_�[�u�v�����@���H�X��ό��n�ł͊��ґ�@3/21
���{��18�s���{���ɓK�p���Ă����u�܂h�~���d�_�[�u�v��21���ʼn�������B
��2�������ɂ킽���đ��������H�X�̎��Z�c�Ƃ��ޒ̐�������������A�R���i�������O�ꂵ�Ȃ���o�ϊ����Ƃ̗����Ɍ����ē����n�߂�B
�Ԍ��V�[�Y����O�ɁA���H�X��ό��n�ł͎��v�ւ̊��҂͑傫���B
�������A��������u������ł̍ĊJ�ƂȂ邪�A�ً}���Ԑ錾���������ꂽ��N���́u�@�l���v�̖߂�͒x�����̂́A�l�q�͖߂��Ă����v�����ɁA�N��������̂܂h�~�[�u�K�p�͒Ɏ�ƂȂ��Ă����B
����Ɩ��p���̃g�b�v�́u��N���̓��������Ă��Ă��A�O�H�ɑ��邨�q�l�̃j�[�Y�͍������B�������I�Ɏs��͖߂��Ă��R���i�O��7�`8�|�����x���낤���A���v�����ׂĎ���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�s���ł͂���1�N�ԁA�s�������Ȃ��ɉc�Ƃł����͓̂����ɂ���3�����x�A�{���Ɍ���������ς��E��ł����B���ς��A���q�l�͖߂��Ă���v�Ɗ��҂����B
|
���܂h�~���d�_�[�u�@���C�k����4���ʼn����Ɂ@3/21
���C�E�k���ł́A���m�E�E�É��E�ΐ��4���ɓK�p����Ă����V�^�R���i�E�C���X��̂܂h�~���d�_�[�u���A21���������ĉ�������܂��B�����A�V�K�����Ґ��͈ˑR�A���������ɂ���A�����̍Ċg���}���Ȃ���Љ�o�ϊ����Ƃ̗�����}��邩�����������ۑ�ƂȂ�܂��B
���C�E�k���ł́A���m�E�E�É��E�ΐ��4���ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă��܂������A21���̊����������ĉ�������܂��B
������A4���ł�22���ȍ~�A���H�X�ɑ��A�c�Ǝ��Ԃ���̒ɂ��Ă̐����݂͐��Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��B
����A�t�x�݂�N�x�ւ��̎����ƂȂ邱�Ƃ���A���m���ł́A���Ǝ�����w���Ȃǂ̍s���ł͊����h�~���O�ꂵ�Q���҂ǂ����̊Ԋu���\���Ɋm�ۂ��邱�Ƃ�A�����}���Ԍ��ł͑�l���E�����Ԃ̈��H�͔����邱�ƁA����ɑ��Ɨ��s�Ȃǂł͈ړ���Ŋ������X�N�̍����s���͍T���邱�ƂȂǂ����߂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�܂��A3��6���������ďd�_�[�u���������ꂽ�O�d���ł��A���Ǝ��ɐ݂��Ă���u�Ċg��j�~�d�_���ԁv��4��3���܂ʼn������A�����������H�̏�ʂȂǂł̊�����̓O����Ăт����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�����A�V�K�����Ґ��͈ˑR�Ƃ��č��������ɂ��邱�Ƃ���A���Ƃ���������Ґ����������邱�Ƃ����O���鐺���オ���Ă��āA�����̍Ċg���}���Ȃ���Љ�o�ϊ����Ƃ̗�����}��邩�����������ۑ�ƂȂ�܂��B
|
���܂h�~�[�u���傤���� 3�A�x�ŏI���Ŋό��n�͂ɂ��킢�߂�@3/21
3�A�x�̍ŏI���A�e�n�̍s�y�n�ł͓��킢���݂��Ă��܂����A�����u�܂h�~���d�_�[�u�v�������������ł͊��҂ƕs���̐���������܂����B
JR���w�O�́A�����烆�j�o�[�T���E�X�^�W�I�E�W���p���ȂǂɌ������Ƒ��A���ό��q��ō��G���Ă��܂��B����Ȓ��A���{�ł͂�������u�܂h�~�[�u�v�������ƂȂ�A���H�X�ւ̎��Z�v���Ȃǂ���������܂��B
��w���u�������܂�������Ȃ����Ɓv
��Ј��u���ꂩ�炨�Ԍ��Ƃ����̃V�[�Y���ɂȂ�̂ŁA���̕ӂ��S�z�Ȗʂ������ł����A���Ƃ����̂܂ܗ��������Ă������炢���ȂƁv
���{�̋g���m���́A�N�x�ւ��Ŋ����̍Ċg��Ɍx�����K�v���Ƃ��āA���������H�̐l�������Ȃǂ̗v���͌p�����܂��B
����A�k�C�����َs�̒��s�ł́A�֓��Ȃǂ��痈���ό��q�̎p�������A�������ɂ��킢���߂����܂��B
�X���u����3�A�x�͂��������܂ł�����Ƃ͗��Ă��ꂽ�v�u�F����A�V�тɏo�����ȂƂ�������������v
�k�C���͂������痈��17���܂ŁA���H�X�̗��p��Z���Ԃōς܂��ȂǁA�Ǝ��̊�������n�߂܂��B
���̊ό��n�E���R�s������3�A�x�́A�ό��q�łɂ��킢�܂����B
�n���̐l�u���������ł��ˁB�Ȃ��Ȃ������ɂȂ�Ȃ������ł�����ˁB����3�A�x�Ől�̗�����������o�Ă��Ă���āA���̂�����ԃs�[�N���ȁB���傤�������������������ł��q�����Ă���Ă��܂��v
�ό��q�u�����ȂƂ���ɂ��ꂩ��s�������ȂƎv���܂��B���܂ʼn䖝���Ă����v�u���������ʂ���ς肿����ƐS�z�ł���ˁv
|
���Ԍ��q�ŏ������卬�G�c���l�v�����g��̉���s�h�@3/21
18�s���{���ɓK������Ă���u�܂h�~���d�_�[�u�v��21���������Ĉ�Ăɉ�������܂��B�ό��n�ł́A������O�Ƀt�����C���O�ŊO�o����l�̎p�����������܂����B
�����ȁA�a�c�ɂ��키�ό��n�E���q
�O�A�x�̒����ƂȂ���20���B�l�C�̊ό��n�E���q�ł͐l�o������܂����B�����ʂ�́A�����̐l�Ŗ��ߐs������܂����B���̈��H�X�ɂ́g���ȁh�̒��莆���c�B
�u�}�U�[�X�I�u���q�v�]�F��������@�u(�q����)���\�����ł��ˁB����ȏ�l�߂��疧�ɂȂ��Ă��܂��āA�����犷�C��Ƃ������J���Ă��Ă��|���̂ŁB���傤�͂����܂łŁc�v
�ό������E�߉������{�ւƌ��������H���A�悪�����Ȃ��قǂ̏a�ł��B
��t�����痈���Ƒ��@�u(�܂�h�~��)�����Ă��炾�ƁA���x�͏t�x�݂ɂȂ�̂ŁB�ǂ��ɍs���Ă�����ł��鏊�ɍs���O�ɂƎv������A����Ȃɍ���ł����Ă����B�O�A�x�ł�����ł��˂��Ă����c�v
��GW�E���~���g����h�c�\��u1�T�Ԃ�4�{�v
�u�܂h�~���d�_�[�u�v������O�ɂ����A�g������v�h�͑��ɂ�����܂��B
���N12���A�ԑg����ނ������s��ЁB�I�~�N�������̊����g��ɂ��L�����Z���}���ɓ�������Ă��܂������c�B
�u�I�����C�����s�T�C�gena�v�o�R�K�T����@�u�����21���ɉ����Ƃ������ƂŁA���߂̈�T�ԂŔ�r���āA��4�{�V�K(�\��)�������Ă���v
��T�́A�������s�̐V�K�\��1000�����܂����B�������A���������łȂ��A�S�[���f���E�C�[�N�₨�~�Ȃǂ̗��s��\��g����\��h�������Ƃ����܂��B
�����N���4�������c�����Łg���̊J�ԁh
���������Ȃ��A�g�t�̕ւ�h���͂��܂����B
�����Nj�C�ۑ�E���@�u���傤��5�ֈȏ�A�m�F�ł��܂����B�����̍��̊J�Ԕ��\�ł��v
�C�ے���20���A�����ō����J�Ԃ����Ɣ��\�B���N���4�������A���̊J�ԂƂȂ�܂����B
�\���C���V�m�̖��J�͂܂���ł����A�������ł́A���炫�̍����y���ށg����Ԍ��h�œ��킢�܂����B
�s������������ɗ����l�@�u�R���i���͂���Ă���A���܂�O�H�ɍs���Ȃ��Ȃ�����Ƃ��B�Ƒ�������̂ŁA����ς�R���i�͕|���ȂƎv����ł����ǁB�������ď����ł��C�������邭�Ȃ�����ȂƎv���āv
���������s�c���������剹�ʂʼn��y
�R���i�ЂŌ}����O�x�ڂ̏t�B
���̉��ŏW�܂��Ď������މԌ��́A���N���ł��܂���B�������A��ɂȂ�ƁA�������Ɉٕς��c�B�ߌ�7������A���̖̋߂��ɍ��荞�݁A��������l�̎p������܂����B
�o�C�g�I���̒j���@�u�����͈���ł܂��c�B��������Ƃ����A�������Ɓc�B���傤�҂����������������Ŏg���������ł�������Ȃ��ł����v
���ɂ��A�O���l�Ƃ݂���j��4�l�g���V�[�g���L���g��̉���h���s���Ă��܂����B
����ɂ́A�x�������ق��Ă����܂���B�x�������璍�ӂ����j��4�l�g�ł������A���̌�A�����̍s���ɏo���̂ł��B���͂ɋ����n��剹�ʂʼn��y�������n�߂܂����B
�x��������Ăђ��ӂ��A����ƋA��x�x���n�߂܂����A�Еt���Ȃ���A�傫�ȉ��y�𗬂��Ă��܂��B
�����H�X��W�p���`�c�l��s�����H�ލ���
����A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̉e���������Ă������H�X�B�����ڑO�ł����A������ł�낱�ׂȂ��������Ƃ����܂��B
�u�����H���V���X�v���R�����X���@�u���ꂪ1���̃V�t�g�Ȃ̂ł����A���ۂ��̎��_�ł͑g��ł����̂ł����A��������v�����n�܂��āc�v�u(Q.�Ԑ��Ƃ����̂͂ǂ������Ӗ��ł����H)�Ԑ��Ƃ����̂͗\��őg��ł�������ǁA�v�����������̂ŐԐ��ŋx��ł�������v
�N�����̎��_��14�l�����A���o�C�g�X�^�b�t�́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̉����Ȃǂ�����A���X�Ǝ��߂Ă��܂�6�l�ɁB���ꂩ��}���銽���}��V�[�Y���Ɍ����A�l�肪����Ȃ��Ƃ����܂��B
����ɐS�z�Ȃ̂��A�E�N���C�i�N�U�̉e���ɂ��A�H�ނ̍����ł��B
���R�����X���@�u(�T�P1�C��)���4000�~����5000�~���炢�͂��Ă��܂��܂��ˁB�l�オ�肷��Ǝv���܂��B�ň�7000�~���炢�܂ŏオ���Ȃ��ł����ˁv
�X�ň����Ă���H�i�́A�قƂ�ǂ��k�C���Y�̂��̂ł����A���ۓI�Ȓl�オ��̉e�����A����A�d����l����������\��������܂��B
���R�����X���@�u�����[�h�ł͂Ȃ��ł���ˁB�K���ɂȂ��ĉƒ��������āA�l�ދ��炵�Ĉێ����āA�ǂ��ɂ����̓X����葱���Ă����邱�Ƃ�M���āA�X�^�[�g�n�_���ȂƁv
|
�������ŐV����3855�l�̊����m�F�@1�T�ԑO����981�l�����@3/21
�܂h�~���d�_�[�u��22����������铌���s����21���A�V����3855�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����܂����B
�����s���̐V���Ȋ����҂�3855�l�ŁA1�T�ԑO����981�l�������A18���A���őO�̏T�̓����j���̐l���������܂����B�����҂̂����u�݂Ȃ��z���v��101�l�ł����B
����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�7449.1�l�ŁA�O�̏T��86.3���ƂȂ�A38���A����100����������Ă��܂��B
����A�V����50�ォ��90��܂ł�6�l�̎��S���m�F���ꂽ�ق��A�]���̓s�̊�ɂ��d�ǎ҂͑O���ƕς�炸46�l�ƂȂ�܂����B
18�s���{���ɓK�p����Ă���܂h�~���d�_�[�u��22���A�S�ʉ�������܂��B�����s�͔N�x���Ɍ����āA���Ԍ��⊽���}��Ől���W�܂�@������Ȃ邽�߁A���������A������������Ȃ��Ăق����ƌĂт����Ă��܂��B
|
���S���R���i������ 3��9659�l ��T���1���l�ȏ㌸���@3/21
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��Ă��̂�(20��)�A�S���ŐV����3��9000�l���銴�������\����܂����B��T���1���l�ȏ㌸�����Ă��܂��B
�����s�́A���̂��V����6502�l�̊����\���܂����B��T�̓��j������1629�l�������A17���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B
�S���ŐV���ɔ��\���ꂽ�����҂�3��9659�l�Ő�T�̓��j�����1���l�ȏ㌸�����Ă��܂��B�܂��S���œ��@���Ă��銴���҂̂����A�u�d�ǎҁv�Ƃ����l�̐���955�l�ŁA�V���Ȏ��҂�66�l���\����Ă��܂��B�@ |
 |
���u�܂h�~�v���� �g��{�I�Ȋ����h�~���O����h �㓡���J�� �@3/22
�V�^�R���i��̂܂h�~���d�_�[�u�����ׂĂ̒n��ʼn������ꂽ���Ƃ��āA�㓡�����J����b�́A�N�x����V�N�x���}����ɓ�����s����ړ��������Ȃ�Ƃ��Ċ�{�I�Ȋ����h�~��̓O����Ăт����܂����B
��������A���m�Ȃ�18�̓s���{���ɓK�p����Ă����܂h�~���d�_�[�u�́A21���̊����������Ă��ׂĉ�������܂����B
�㓡�����J����b�͋L�Ғc�Ɂu�S���I�Ȋ����Ґ��̓s�[�N���̔������x�ɂ܂ŗ��������A�a���g�p���⎩��×{�Ґ����n�捷�͂��邪�A���m�Ȓቺ�X�����m�F����Ă���v�Əq�ׂ܂����B
����Łu���Ƃ���͍�������̃I�~�N���������wBA.2�x�ɒu������邱�ƂŁA�ēx�����ɓ]����\�����w�E����Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁA�N�x����V�N�x���}����ɓ������đ��Ǝ���t�x�݁A���w����Ԍ��ȂǑ����̐l���W�܂�s���ɉ����A�A�E��i�w���@��Ɉړ��������Ȃ�Ƃ��āu�������X�N�̍����s�����T���A�}�X�N�̒��p���ȂǁA��{�I�Ȋ����h�~��̓O���S�����Ăق����v�ƌĂт����܂����B
�܂�����̑�ɂ��āu�ēx�������g��ɓ]�����ꍇ���w�S�̑��x�ŏ������Ă����ی��E��Ñ̐����ғ������Ă������Ƃ���{�Ƃ��A���Ƃ̈ӌ����Ȃ���A�V���ȃE�C���X�⊴���ɉ������ϋɓI���v���ȑΉ����u���Ă����v�Əq�ׂ܂����B
���D�y�s���ł͊��}�̈���Ō��O���鐺��
�k�C���ɓK�p����Ă����A�܂h�~���d�_�[�u��21���ʼn������ꂽ���Ƃ��āA�D�y�s���ł́A�����̊ɘa�����}���鐺������������ŁA����̊��������O���鐺��������܂����B
22������w�̑��Ǝ����Ƃ���20��̏����́u�X�Ɋ��C���߂�Ǝv���Ƃ��ꂵ���ł��B�܂h�~���d�_�[�u�ŁA��w�̕���������������Ă����̂ŁA����Ō�y�������̂т̂тƊ����ł���悤�ɂȂ�v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A30��̉�Ј��̒j���́u�C���˂Ȃ��H���ɍs����悤�ɂȂ����̂��ȂƎv���܂��B����Ŏ��Ƃɂ��A�邱�Ƃ��ł��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
����A70��̏����́u�����ɂȂ����̂͂��ꂵ���ł����A���ꂩ��l����������X�ɏo�Ă��āA�������A�܂��L����̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A60��̒j���́u�����Ґ����Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ��̂ŕs�����傫���ł��B���ꂩ����Ƃɂ����邱�Ƃ͑����Ă����܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
����� �����̈��H�X����2�����Ԃ�ʏ�c��
�܂h�~���d�_�[�u�̉����ɔ����A���{���̑����̈��H�X�ł͂��悻2�����Ԃ�ɒʏ�ǂ���̉c�Ƃ��ĊJ���Ă��܂��B
���̂����A��� �吳��ɂ��鍇�킹��17�̈��H�X�������������{�݂ł́A�܂h�~���d�_�[�u���A���ꂼ��̓X�܂����S�ɋx�Ƃ�����A�c�Ǝ��Ԃ�Z�k�����肵�Ă��܂����B
�d�_�[�u�̉����ɔ����A�{�݂ł͂��悻2�����Ԃ�ɑS�X�܂ʼnc�Ƃ��ĊJ���A���̂����C�^���A�����X�g�����ł͊J�X�O����]�ƈ��炪�����̎d���݂�|�����s���܂����B
�����ČߑO11���̊J�X�Ɠ����ɑ����q���K��A��������ݕ��𒍕����Ă��܂����B
�X���̏�����炳��́u��Ì���̕��S�y����A���q�l�Ə]�ƈ��̈��S����邽�ߋx�Ƃ��Ă������A����グ���[���ɂȂ�e���͑傫�������B�ĊJ�ł��đ�ς��ꂵ���B�H�����y����ł��炢�A�����ł��Ί�ɂȂ��Ă��炦����Ǝv���v�Ƙb���Ă��܂����B
|
���u�܂h�~�v���������@���҂ƈꖕ�̕s���u�܂��L��������c�v�@3/22
�����s�̐V���ȐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂�3533�l�ł����B18�s���{���ɏo����Ă����u�܂h�~���d�_�[�u�v����������܂������A�Ԍ��V�[�Y�����T���čĊg��ւ̌��O���c���Ă��܂��B
�J�����ɕς��ȂǁA�����ԗ₦���s���B
����ł����X�X�͋v���Ԃ�ɑ����̒���������A�����Z�ȗl�q�ł����B�y�m�X���E�A������\�F�u�w�܂h�~�x�������Ɍ�����(���H�X��)���X���ĊJ����Ƃ����̂Ō��\�A�߂��Ă��Ă���̂Ŋ��҂��Ă��܂��v��Ƀo�[��X�i�b�N�Ȃǂ̌ڋq����X�̗\��C�ɑ����A����Ɋ��҂��c��ނƌ����܂��B
���̎����̊��t�ƌ����c�B�����L���̍��̖����̖ڍ��쉈���ɂ��郌�X�g�����B�i�F�̗ǂ��e���X�Ȃ͉J�̉e���ŊՎU�Ƃ��Ă��܂����B�����E�ڍ���ł͊������X�N������邽�߁A�C�x���g��C�g�A�b�v�̒��~������B�Ԍ��q�ւ�����̎��l��v�����Ă��܂��B�A���n�e�[�u�����ڍ��X�E���V�b�X���F�u���G�ȋC�����͂���܂��ˁv�{���͍�����Ԃ̔ɖZ���ł����c�B���͗��N�������ƍ炫�܂��B�A���n�e�[�u�����ڍ��X�E���V�b�X���F�u���ݍ����Ă��܂��̂ŁA���̕ӂ��C�ɂ��邨�q���������������̂Ŕz�����c�Ƃ��Ă��������v
�����E�`��̃I�t�B�X�X�ɂ�����H�X�ł�22���̂܂h�~���d�_�[�u�̉������A��̉c�ƂɌ������������i�߂��Ă��܂����B�����H���E���R�����X���F�u�d���A��Ɉ��S���āw1�t���݂ɍs�����x�Ƃ����悤�ȕ��͋C�A�����͂��傤����ς���Ă����������ȂƎv���܂��v�Ƃ͂����A�����ł͐Ⴊ�~�蓀����悤�Ȋ����ɉ����ēd�͕s�����N����ȂǓX�ɂƂ��Ă͋t���ł��B
����A�k���̐ΐ�̃z�e���͐l�C���H�X�Ƃ̃R���{��u��������v�ȂǂƂ������n���̃L�����y�[���ŁA�����ĂȂ��̑Ԑ��𐮂��Ă��܂��B����ʂ̒�z�e���E�e�c��������F�u(Q.�w�܂�h�x�̉����͖{���Ɋ�]�ł��ˁH)�����ł��ˁA�����������������Ă���ł��v�܂h�~���d�_�[�u�̑S�ʉ����Ŕ҉�̏t���}���闷�s�W�҂͐���e�܂��܂��B�����Ǒ��h���c�ƕ��E�㓡�ʉ���F�u(�ߑO)0�����璩�ɂ����Ă�(�l�b�g�ł�)���\��A���Ƃ͗\��̂��ύX�ł��ˁB���̂��炢�͗��܂����B�R�s�[�@���l�܂邭�炢�̐����ŗ��Ă���܂��v�X�̐l�o�͑�������܂����A���҂ƕs������������܂��B
���É��s���̈��H�X���[���J�X�֎d���݂̐^���Œ��B�r�[���T�[�o�[�p�̐V���ȒM���������܂�Ă��܂����B�a�H�̐X�X��E�X��v������F�u����ނ͂��傤��ʂɎd����܂������A�H�ނ����Ȃ葽���d����Ă��܂���l���͂Ȃ��Ƃ��Ă�3�A4�l�̕��Ń~�j�����}��Ȃǂ���Ē�����Ǝv���Ă��܂��v����܂Œ��̒�H�݂̂ʼnc�Ƃ𑱂��Ă��܂������A22���邩��A�����������r�[���̒��ĊJ�������ł��B
|
�����E���ɁE���s�Łu�܂h�~�v�����@���{�u�N�x�ւ��̏W���x�����ԁv�@3/22
���E���ɁE���s�ł͂܂h�~���d�_�[�u�����悻2�J���Ԃ�ɉ�������܂����B
���{�ł͂��悻2�J���Ԃ܂h�~�[�u�̓K�p�������܂������A22��������H�X�Ȃǂɑ��鎞�Z�v�����ޒ̐����͉����ƂȂ�܂��B�X�̐l�̎~�ߕ��͗l�X�ł��B
�X�̐l�́u��Ђ̕����V�������ɂȂ�̂ŁA�S�@��]�𗬂̏��݂��Ĉ���ł�����Ă�������ȂƎv���܂��v�u�O�H���S�R���Ă��Ȃ��̂ŁA���́B�����ɕω��͎����o���Ȃ����ȂƎv���܂��v
����A���悻2�J���ԋx�ق��Ă������s�E�_���̗��قł́c
������ ���̏h ��̏�u�T����5�`7���܂ŗ\�L�тĂ��邪�A�����͂قƂ�Ǘ\�����Ă��Ȃ����������Ă���B�R���i�O���͖��ɂȂ炸�����y���߂�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��v
���{�́A22������4��24���܂ł��A�u�N�x�ւ��̏W���x�����ԁv�ƈʒu�Â��Ă��܂��B
���{�E�g���m���u�w�Z�̐V�w�����n�܂�A��Ђł��N�x�ւ��̊����}�������Ǝv���B������Ƃ��̊�����̓O��肢�������v
|
���k�C���@�܂h�~���� �ό��n�E���H�X�͊��� �s������͌��O�̐����@3/22
�k�C���ɓK�p����Ă����܂h�~���d�_�[�u���A21���ʼn�������܂����B�ό��n����H�X������v�̉Ɋ��҂��鐺�������ꂽ����A�D�y�s���ł͍���̊��������O���鐺��������܂����B
���ܗŊs�^���[
�挎1������Վ��x�Ƃ��Ă������َs�̊ό������u�ܗŊs�^���[�v�B�܂h�~���d�_�[�u�̉������āA22������c�Ƃ��ĊJ���܂����B22�����͏]�ƈ��������W�܂��Ē��炪�s���A�u���悻50���Ԃ�̉c�ƍĊJ�Ȃ̂ŁA�~�X�̂Ȃ��悤���J�ɑΉ����Ă����܂��傤�v�Ɛ����|�������Ă��܂����B�����ČߑO9���ɉc�Ƃ��ĊJ�����Ƒ����A�ό��q���W�]�䂩��i�F�߂���ʐ^���B�����肵�Ă��܂����B�É�������Ƒ��ŖK�ꂽ�j���́u���N�O����k�C���̗��s���v�悵�Ă����̂ŁA�����ł��Ă悩�����ł��B�^���[����̌i�F�͂ƂĂ����ꂢ�ł����v�Ƙb���Ă��܂����B�ܗŊs�^���[�̉��R���A�V�X�^���g�}�l�[�W���[�́u���ꂩ����̃V�[�Y���Ŋό��q�������Ă���̂ŁA���̃^�C�~���O�ł̉c�ƍĊJ�͂��ꂵ���v���܂��B�������������S�Ɏ������Ĉ��S���Ċό��ł���悤�ɂȂ��Ăق����Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
������ ���̐쉷��
�܂h�~���d�_�[�u�̉����ɔ����A�����̓������s�ɂ������đ������������u�ǂ��݂v��A���َs���̃z�e���Ȃǂɔ��܂����l��Ώۂɏh�����⏕����u�͂����Ċ��v��22������ĊJ���܂����B���َs�̓��̐쉷��ɂ���z�e���ł͂��Ƃ�1��27���ɏd�_�[�u���K�p����Ă���͗Վ��x�Ƃ��Ă��܂������A�[�u�̉�����������ō���19������c�Ƃ��ĊJ���܂����B�z�e���ɂ��܂��ƁA�u�ǂ��݂v��u�͂����Ċ��v���ĊJ�������Ƃ��đ����A��^�A�x�ɂ����ė\����n�߂Ă���Ƃ������Ƃł��B�u������ؒ��v�̒r�c�����x�z�l�́u���ꂩ����̋G�߂ɂȂ�̂Ŋ��҂��Ă��܂����A���������������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�������O�ꂵ�Ă��q�l�����}���������v�Ƙb���Ă��܂����B
�����H �a���s��
�����̋���ނ����낤���H�s�́u�a���s��v�ł́A22���ߑO������s���̈��H�X�̐l���d����ɖK�ꏙ�X�Ɋ��C���߂��Ă��܂����B�܂��ό��q�̎p�������A�����́u���蘥�v�𒍕����A�D�݂̃l�^��I��ł��͂�ɐ�����ĐH�ׂĂ��܂����B�s��̊W�҂ɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�̊����g��O�Ɣ�ׂ�Ɣ������q��3���قǗ�������ł���Ƃ������Ƃł��B���H�a�������g���̊`�c�p���������́u�悤�₭�����̓����������Ƃ����v���ł��B�܂��������Ă��Ȃ�������܂Ŕ|���Ă�����������Ƃ��Ă���̂ŁA��������̐l�ɕ����Ă��炢�����v�Ƙb���Ă��܂����B����A�a���s��ł̓x�j�U�P��E�j�Ȃǃ��V�A�Y�̋���ނ������Ă���X�������A���V�A�ɂ��E�N���C�i�ւ̌R���N�U�̉e���ō���̓��ׂ̌��ʂ��Ȃǂɂ��ĐS�z���鐺���オ���Ă��܂��B�`�c�������́u���V�A����ǂꂭ�炢�̗ʂ������Ă���̂��A�ǂꂭ�炢���i���オ��̂����O���Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
���эL �k�̉���
2�����߂��x��ĊJ�X�̓����}�����l�����܂��B�эL�s�̉F�����G������́A�挎�A�эL�s�̒��S���ɂ��鉮�䑺�u�k�̉���v�ŐV���Ɏ����̓X���J�X����\��ł������A�܂h�~���d�_�[�u�̉e���ʼn��䑺���x�Ƃ������Ƃ��āA�J�X�ł��Ȃ���Ԃ������Ă��܂����B�d�_�[�u�̉������āu�k�̉���v�͉c�Ƃ��ĊJ���A�F��������̓X�ł�22���A2�����߂��x��ĊJ�X�̓����}���܂����B�F��������̓X�ł͏\���Y�̓̃^�����g�����V�`���[��A�\���̍L�����̎��ƂłƂ������z���g���������߂�Ȃǂ���邱�Ƃɂ��Ă��āA�ߑO������d���݂Ȃǂ̍�Ƃ�i�߂Ă��܂����B�F���������2�N�O�A�����̓����u���ċ߂Ă��������Ђ�ސE���A�����t�w�Z�ɒʂ��ēX�܂̊J�Ə�����i�߂Ă����Ƃ������ƂŁA�u�悤�₭���X���J����Ƃ������Ƃň��S�����B�܂��܂��菇�ȂǂŊ���Ȃ��������������A���q����ɂ����◿�����y����ł��炢�Ȃ��炢�낢��Șb���ł����炤�ꂵ���v�Ƙb���Ă��܂����B
���D�y �X�̐�
����A�D�y�s���ł́A�����̊ɘa�����}���鐺������������ŁA����̊��������O���鐺��������܂����B30��̉�Ј��̒j���́u�C���˂Ȃ��H���ɂ�����悤�ɂȂ����̂��ȂƎv���܂��B����Ŏ��Ƃɂ��A�邱�Ƃ��o���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B22������w�̑��Ǝ����Ƃ���20��̏����́u�X�Ɋ��C���߂�Ǝv���Ƃ��ꂵ���ł��B�܂h�~���d�_�[�u�ő�w�̕���������������Ă����̂ŁA����Ō�y�������̂т̂тƊ����ł���悤�ɂȂ�v�Ƙb���Ă��܂����B�����70��̏����́u�����ɂȂ����̂͂��ꂵ���ł����A���ꂩ��l����������X�ɏo�Ă��āA�������܂��L����̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B�܂��A60��̒j���́u�����Ґ����Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ��̂ŕs�����傫���ł��B���ꂩ����Ƃɂ����邱�Ƃ͑����Ă����܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
|
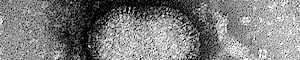 |
���p�f�H�@����H�@�ݓc��܂h�~������ő唎�� �@3/23
���{���命���̓s���{���ɓK�p���Ă����܂h�~���d�_�[�u���A3��22���ɑS�ʉ������ꂽ�B�Љ�E�o�ω��d������ݓc���Y�̌��f�ɍ����̎x���������B�������A�V�K�����Ґ��̍��~�܂�ő�7�g�ւ̌x�������������A1�`2�J���ł̊����Ĕ����ƂȂ�A�Q�@�I�ł̎����}�̏������h�炬���˂Ȃ��B
�ݓc�̈ӌ����đS�ʉ��������߂����{�R���i�����ȉ�̔��g�Ή���A�u���o�E���h�̉\���͍����v�ƌx���B�����X���������e�s���{���ʂ̐V�K�����Ґ��ł��A�ꕔ���ߋ��ő��ƂȂ�P�[�X���ڗ����Ă���A�Ȃ���5�g�̃s�[�N���ƕς��Ȃ��B
���̂��߁A����̐��{�̑Ή��ɂ��āA�u�͂��߂���S�ʉ������肫�v�Ƃ̕s�M���L����B�������A�ݓc�̌��f�ւ̕��䗠�ł́u���Ǘ��݂̎v�f�v���w�E�������������A�u�Q�@�I�Ɍ������A�̂邩���邩�̑�����v(��������)�Ƃ̐������Ȃ��Ȃ��B
�����{���y�d��ʼn��������߂Ȃ����j��\��
18�s���{���ɓK�p����Ă����܂h�~�[�u��3��22������̑S�ʉ����́A��16���̊ݓc�ƊW�t���̋��c�Ō��܂����B�ݓc�͓���̊��@�L�҉�ŁA�u���サ�炭�����ւ̈ڍs���ԂƂ��A�\�Ȍ�����퐶�������߂����ԂƂ���v�Ƃ��āA�o�ρE�Љ���ւ̈��e�������D�悵�����Ƃ����������B
�����Ċݓc��1�����h�~�Ƃ�ꂽ��ʎ��Ə��ł͔Z���ڐG�҂̓���͂��Ȃ�2�ό��x�����ƁuGo To�g���x���v�ĊJ�Ɍ����A4��1������u�������v���g�傷��A�Ȃǂ�\���B���Ċe���ɕ���āA�E�B�Y�R���i�ł̌o�ωɓ��ݏo�����ӂ�\���A�����̗����Ƌ��͂�i�����B
�������̎̌��f�́A��Õ���̊�@����E�p�ł����A�Ή������߂��Ȃ��������{���A�y�d��ʼn��������߂Ȃ����j��\���������Ƃ��A�|�C���g�ƂȂ����B�ݓc�́u���R�̂ł̌��f�v�������������A���f�܂ł̕��G�Ȍo�߂��A�������E�ł̐��ǓI�������������ʂƂȂ����B
�S�ʉ����̐�������́A�ݓc�̌��f���3��17����̐��{���{���B����܂œ��l�̎������`���̋��c�ŁA1����{�ȍ~�ő�36�s���{���ɓK�p���ꂽ�d�_�[�u�ɂ��āA2�J�����ŏI�~����ł��Ƃ��ŏI�m�F�����B
�\����ł̑S�ʉ����ւ̌o�܂��݂����A�ݓc�̌��f�́u���R�Ȑ���s���v(���@��)�ł͂���B���{�͓����A�I�~�N����������������3��ڃ��N�`���ڎ�̑啝�x��Ō��������ᔻ�������A3���ɓ����ĐV�K�����Ґ��⎀�ҁE�d�ǎ҂̌������i��ō����̌x����������A�ᔻ�����É����Ă������炾�B
�������A2��24���ɖu���������V�A�̃E�N���C�i�R���N�U���A�u���{�̃R���i�Ή��̖����ւ̍����̔ᔻ�����ɂ����v(���@��)���Ƃ��ے�ł��Ȃ��B�T�C�h���u�p���f�~�b�N�����鍑��ŁA�R���i�Ή��ᔻ���������v(����)�Ƌ����B
�����A�S�ʉ����ւ̌o�߂��݂�ƁA���{�͎��O�ɐ��Ɖ�c�ʼn��������̑啝�ɘa�����߂Ă���B�u�������肫�Ŋ�������i�߂Ă����v(�t���o����)�Ƃ����݂��Ȃ��B�������A���̒��ōŌ�܂ŕs�������������Ƃ̋��c�Ɂu�̂��������Ȑ헪���_�Ԍ������v(�t���o����)�Ƃ̎w�E������B
���g�����Ɂu���ǓI�ȗh���Ԃ���������v�Ƃ̌�����
���������A���̑Ή������ڂ��ꂽ�̂́A��Õ���̎w�W�Ƃ��Ȃ�d�ǎҐ��⎀�Ґ��Łu��オ���|�I���[�X�g�����v(�����ǐ���)���������炾�B���{�E�s�̍ō��ӔC�҂̋g���m���m���Ə����Y�s���́A�������}�E���{�ېV�̉�̕���\�Ƒ�\�ŁA���ɋg�����̓R���i�Ή��Łu��ヂ�f���v���f�������ƂŁA�S���I�ɂ��x���A�]������Ă��������Ƃ��B
���̂��ߍ���A��ゾ���d�_�[�u�K�p�̉����ΏۂƂȂ�A�u���R���r�̃R���i�Ή��̎��s���\�ʉ��v(��������)���āA�ېV�ւ̔ᔻ�g����m���������������B�^�}���ł́u�����ɖڂ�t�������A�g������Ɉӎv�\���𔗂邱�ƂŁA���ǓI�ȗh���Ԃ���������v(��������)�Ƃ̂��������������L�������B
����ɑ��g�����́A�^�C�����~�b�g���肬��̒i�K�Łu�����炩�牄���\���͂��Ȃ��v�ƁA���{�ɉ��ʂ�a����Ή��Ō��킻���Ƃ����B�������A�L�҉�ł̐����ɂ͏]���̎���悳�͌���ꂸ�A���ʓI�Ɂu�����ςȗh���Ԃ�ɁA����y�U���������v(�������V)�悤�ɂ��݂����B
����̊ݓc�̑S�ʉ������f�́A���̌�̊e�퐢�_�����ł�6���O��̍����x���Ă���B�����̈��|�I�������u����ȏ�䖝�͑������Ȃ��v�ƍl���Ă��邱�Ƃ��A�S�ʉ��������}���鐢�_���`���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
����ɁA��3�����E���ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��E�N���C�i��@�ւ̍����̋��|�����A�R���i���܂߂����{�̑Ή��ւ̊S�𔖂߂��̂��ے�ł��Ȃ��B���_�����ł��A�ݓc��G7�̈���Ƃ��ē��{�ւ̕Ԃ茌���o��ł̃��V�A�ւ̌o�ϐ��قɓ��ݍ����ƂŁA���t�x�������ď㏸���Ă���B
���̏��A�u��N10���̐��������ȗ������ݓc�̉^�̋����v(�������V)�Ƃ݂�����������B�m���ɃE�N���C�i��@�̒��A�ʏ퍑��O����̍ŗD��ۑ肾����2022�N�x���{�\�Z�Ă��A3��22���ɂ���Ȃ萬�����A�R���i�Ή�����X�L�����_���ł̖�}�e�}�̒Njy���A���ӂ��ɏI������B
���E�N���C�i��@�ł̎�]�O���ɐ��͓I�����c
�����^�c�ւ̎��M��[�߂�ݓc�́A�S�ʉ����̌��f��A�E�N���C�i��@�ł̎�]�O���ɒ���ł���B�܂��A19���Ƀ��V�A�ƊW�̐[���C���h��K��B���f�B�Ƃ̎�]��k�Łu���V�A�ւ̐퓬�̑�����~�v���v�ň�v����ȂLj��̐��ʂ��������B
����ɁA22���̗\�Z�������A��23���[�ɍs����E�N���C�i�̃[�����X�L�[�哝�̂̍��������Ƀx���M�[�Ɍ����o���B24�������G7��]��c�ɏo�ȁA�Ζʂł̋��c�Łu���ĂƃA�W�A�̋��n�������A�s�[������v(�O���ȋ�)���ƂɂȂ�B
���������ݓc����]�O���������̎x���g���_�������̂ŁA�\��ɂ��u���M�Ɨ]�T�v(����)���ɂ��ށB���{�Ǝ����}���A�g���Ă̍��������A���̎�荞�݂ŁA�u��}�̕��f�ɂ����������v(��������)�B����ɂ��u���̂܂܂Ȃ�Q�@�I�͕����悤���Ȃ��v(�����I��)�Ƃ̌������x�z�I���B
�����A�����ǐ��Ƃ̑����́A�u�������܂߂ĐV�K�����Ґ��̑S���I�ɍ��~�܂肪�������ł̑S�ʉ����́A�����̊��������ɂȂ���v(���{������)�Ɗ�@�����B���Ȃ��B�u�N�x����4��������̃S�[���f���E�B�[�N�őS���I�ɐl�̓����������ɂȂ�A�����A�S���̐V�K�����҂͐����l���x���ɂȂ�v(��)�Ƃ������͂��B
�T�C�h�́u�܂h�~�̍ēK�p�͂��Ȃ����j�v(����)�Ƃ���邪�A���̏ꍇ�A�����̕s����s�M�����{�ᔻ�ɂȂ��邱�Ƃ͔�����ꂻ�����Ȃ��B���̂��߁A�����}���ł��u����̎̑唎�Łv(����)�������̑�7�g�P���������A�u�Q�@�I�ł̗^�}���I�ߔ�������Ƃ����s�k�v(��)�ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��Ƃ̐������Ȃ��Ȃ��B�@ |
 |
�������s����8875�l�̃R���i�����Ҋm�F�c3�T�ԂԂ��1�T�ԑO������@3/24
�����s��24���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�s���ŐV����8875�l�m�F�����Ɣ��\�����B�O�T�̓����j������414�l�����A3�T�ԂԂ��1�T�ԑO���������B
|
���s���̃I�~�N�����h���^�A�V�K�����҂�4���Ɂ@3/24
�����s��24���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂̂����A��4�����ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�̔h���^�Ŋ����͂������Ƃ����uBA.2�v�Ɋ������Ă���Ƃ݂��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B2����{�ɏ��m�F���Ă���}���ɒu������肪�i��ł���A���Ƃ́u�x�����K�v�v�Ǝw�E�����B
���͌��ʂ͓����J�����s�̃��j�^�����O��c�Ŏ������B�s�͕ψٌ^�̌^�ׂ�PCR������Ǝ��Ɏ��{���Ă���B�uBA.2�v�����߂Ċm�F����2��8�`14����1.3%���������A1�J�����3��8�`14����38.5%�ɏ㏸�����B
�s��4�����烂�j�^�����O��c�̊J�Õp�x���T1�猎2��ɕύX����B�܂h�~���d�_�[�u���I���������ƂȂǂ����Ή��ŁA�����4��7���̊J�ÂƂȂ�B�������Ăш��������ꍇ�͖��T�J�Âɖ߂��B
|
���I�~�N�����������Ŏq�ǂ��́u���M�v�u�������v�����@�f���^����3�{�ȏ�@3/24
�V�^�R���i�̕ψي��̒��ł��A�y�ǎ҂̊����������Ƃ����I�~�N�������B�Ƃ��낪�A�q�ǂ��̏ꍇ�͂���܂łɗ��s�����ψي��Ɣ�ׁA���M��A����ɔ������������N�����������啝�ɑ����Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B
��ʌ��ɏZ�ޏ����ƁA1��1�����̒����B���T���j�A�ˑR�A�����̑̂Ɉٕς��N���܂����B
1��1�����̖��̕�e�u�}�Ɏ葫���k�������āA�ڂ����_�������������O�����ɂȂ��āv
1��1�����̖��̕�e�u�~�}�Ȃ�ł�����ǂ��v
�����119�Ԓʕ����ɎB�e�����f���ł��B�����́A��_�����߂��܂܁A�����݂ɘr��̂��k���Ă��܂��B���M�ɂ��u�M���������v�Ƃ݂���Ǐ�B
1��1�����̖��̕�e�u���Ȃ�|�������ł��ˁB�����Ɛk���Ă邵�A������A�����Ă銴���������v
�~�}�������PCR�����ŐV�^�R���i�ւ̊������������܂����B
1��1�����̖��̕�e�u�{���ɂЂ�Ђ₵�܂����B�ӎ����Ȃ��Ȃ�����Ƃ��A�ň��{���Ɏ��Ⴄ��Ȃ����Ǝv���܂����v
�������1��7�����̏��̎q�̏ꍇ���B
1�̖��������������e�u�M��40�x�߂��o�āA�{�l�������������痧���ē�������Ă��邪�A�t���t�����邭�炢�v
���ɓ��c���̏ꍇ�A�ˑR�A���߂Ă̍��M�ɁA�ǂ��Ώ����ׂ����e���˘f�����傫���Ƃ����܂��B
1�̖��������������e�u���߂Ă���ȕ\������̂ŁA�ǂ���������̂�������Ȃ��v
�q���͑�l�Ɣ�d�lj����Ȃ��ƌ����Ă����V�^�R���i�B����ɁA��5�g�̃f���^���ȂǂƔ���|�I�Ɍy�ǂ������Ƃ����̂��I�~�N�������ł����A�q���Ɋւ��Ă͂��̃I�~�N�������ŁA�u���M�v��A����ɔ����u�������v�̏Ǐ����Ă���̂ł��B�����ȃN���j�b�N�ł́E�E�E
�N���j�b�N��т��� ���c�͎j�@���u����܂�(��5�g�܂�)�͔M���������̃R���i�̕��͌o�����Ȃ��������A�����Ȃ�̍��M�ŔM�����������N�����悤�Ȃ��q����͂�o�Ă��āv
���ƂƂ��ɂ��A����ȏǗႪ�E�E�E
�N���j�b�N��т��� ���c�͎j�@���u���̗�͑O�̓�����38�x�㔼�̔M���o�āA���̓��ɋ}��40�x�܂ŏオ�����Ƃ���ŁA�M�����������N�����ꂽ��ł��ˁv
���{�����Ȋw�16�Ζ����̐V�^�R���i�����҂��悻5100�l�������Ƃ���A�����s�̏�����4���A���f���^�����s����6�����x�������u���M�v�̏ǏA���I�~�N���������s���ł́A���悻8���ɏ��܂����B�܂��A1��~4�Ύ��́u�������v�Ǐ�ɂ��ẮA�f���^��3%�������̂��A�I�~�N�����ł�3�{�ȏ��9.4%�ɋ}���B�����������c���̎���10�l��1�l�����������N�����قǂ̍��M���o���Ă���Ƃ����̂ł��B��t�́A�u�M�������v�̊댯���ɂ��āE�E�E
�N���j�b�N��т��� ���c�͎j�@���u(�������)�����ɂ킽��ƁA�ċz����N������]�ւ̃_���[�W���N���邽�߁A���ɂ͏d�lj�����Ⴊ����̂ŁA�M���������͒��ӂ��Ȃ�������Ȃ��v
�I�~�N�������ɂ��V�K�����҂����~�܂肷�钆�A�܂h�~�[�u�͉�������܂������A�q�ǂ��̊����ƏǏ�̊ώ@�ɂ́A���܂ňȏ�ɒ��ӂ��K�v��������܂���B
|
��2���̕S�ݓX���㍂ �܂h�~��������5�����Ԃ�}�C�i�X�@3/24
2���̑S���̕S�ݓX�̔��㍂�́A�܂h�~���d�_�[�u�̉�����5�����Ԃ�̃}�C�i�X�ƂȂ�܂����B
���{�S�ݓX������\����2���̕S�ݓX�̔��㍂�́A�O�̔N�̓������Ɣ�ׂ�0.7%����A3172���~���܂�ƂȂ�܂����B5�����Ԃ�̃}�C�i�X�ł��B
�܂h�~���d�_�[�u�̉�������Ȃǂ̓V��̉e���ŁA���q�������������Ƃ���ȗv���ł��B
���X�q���́A�O�̔N�̓������Ɣ�ׂ�2.9%���ŁA4�����Ԃ�̃}�C�i�X�ł����B
���i�ʂł́A���v�����i�ȂǍ����i�т̏��i���傫���L�т��ق��A�o�����^�C������ŃC���^�[�l�b�g�̔����D���ł����B
�Ȃ��A2020�N2���Ɣ�ׂ�Ɣ��㍂��11.7%���A���X�q����28.2%���ŁA�V�^�R���i�����g��O�̐����ɂ͖߂��Ă��܂���B |
 |
���R���i�V�K�����Ґ� ��1������ �ɂ₩�Ȍ����X�������� �@3/25
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł͂��悻1�������ɂ킽���Ċɂ₩�Ȍ����X���������A3��21���ɂ܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ18�̓s���{���ł��A�O�̏T��茸�����܂����B
�S���A2��24���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T�ɔ�ׂ�0.88�{�A3��3����0.92�{�A3��10����0.86�{�A3��17����0.90�{�A3��24���܂łł�0.76�{�ƁA6�T�A���Ŋɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂��B
���������̐V�K�����Ґ��́A�ł���������2����{�Ɣ�ׂ�ƁA5��4000�ȏ㌸����3��8830�l�ƂȂ��Ă��܂����A�ˑR�Ƃ��đ�����Ԃ������Ă��܂��B�n�悲�ƂɌ��Ă��A3��21���ɏd�_�[�u���������ꂽ18�̓s���{�����܂�44�̓s���{���ŁA�������猸���X���ƂȂ��Ă��܂��B
3��21���ɏd�_�[�u���������ꂽ18�̓s���{���ł́A�����Ґ���������Ԃ͑����Ă�����̂́A��������O�̏T���͏��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B3��21�����O�ɏd�_�[�u���������ꂽ�n��̂����A�L�����╟�����ȂǁA�قƂ�ǂ̒n��ł͊ɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂����A���ꌧ�Ȃǂł͑������Ă��܂��B
�����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́A���݂̊����ɂ��āu�����̃X�s�[�h�͏��������Ȃ��Ă���ƌ����邩������Ȃ����A�S���ł͈����4���l�O��̊����҂��o�Ă���B��6�g�̃s�[�N�̔�����菭�����������x�ő��ς�炸�����A�܂���6�g�̂��Ȃ��ɂ���B�܂h�~���d�_�[�u�͉������ꂽ���A���Ȃ��Ƃ�4�������炢�܂ł͑�𑱂��Ă������ƂŁA�Ȃ�Ƃ���6�g�����z���Ă����K�v������v�Ƙb���Ă��܂��B
����̌��ʂ��ɂ��Ắu���Ǝ�����Ў��A���ʉ�⊽�}��ȂǁA�l�ƐڐG����@������邱�Ƃ�A��芴���͂������Ƃ����I�~�N�������wBA.2�x������A����͊����Ґ�������X�s�[�h�����������ɂ₩�ɂȂ��āA�ň��̏ꍇ�A�đ������N���邱�Ƃ��\�z���Ă������ق����悢�B�����wBA.2�x�ɂ��ẮA���{�ł́A�ق��̃I�~�N�������wBA.1�x���L���������ł̒u�������ƂȂ�A�����҂�������x���]�������Ă��A���ꂾ���ŋ}�����Ă������Ƃ͍l���ɂ����Ǝv���v�Ƙb���Ă��܂��B
�܂��A���߂����ɂ��āu�����[���b�p�ł͋K���̊ɘa�ɂ���āA�������������Ă��邪�A�lj��̃��N�`���ڎ헦��5�����A�����҂͏o�Ă��d�lj�����l�����Ȃ�����A�K���̊ɘa���\�ɂȂ��Ă���B���{��3��ڂ̐ڎ헦��3�������i�K�Ȃ̂ŁA5���ȏ�Ɏ����Ă������Ƃ��A�܂��͑厖���B�}�X�N������A�l�Ƃ̋������Ƃ�Ƃ��������@�����܂��g���Ȃ���s�������{����ȂǁA����Ƃ����̐����ɖ߂��Ă������Ƃ��A����1�����̉ۑ肾�v�Ƙb���Ă��܂��B
|
��������7289�l���R���i�����@3/25
�����s��25���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����7289�l���ꂽ�Ɣ��\�����B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���6275�E4�l�ŁA�O�T���77�E8���B11�l�̎��S�����ꂽ�B�d�ǎ҂͑O����3�l����38�l�������B
�����҂̔Z���ڐG�҂ŁA�Ǐ�Ɋ�Â������Ȃ��ň�t���z���Ƃ݂Ȃ������҂́A�V�K�����҂̂���126�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�30�オ1333�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�330�l�������B�����҂̗v��120��5465�l�ƂȂ����B
|
�����ŐV����3783�l�̊����m�F�@������32�l�����S�@3/25
���{��25���A�V����3783�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̋��j���̊����Ґ��́A3865�l�ł����B���{���ł́A������32�l�̎��S���m�F����܂����B
|
���呺�m���u���ȕ��͋C�v�@�R���i�����ҁA���C3���ʼn����~�܂�X���@3/25
���C3���ł�25���A�v3731�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�B���m����2719�l�A��521�l�A�O�d��491�l�������B����3���A���ŁA���m�A�O�d������2���A���őO�T�̓����j��������A�����~�܂�̌X���ƂȂ��Ă���B
���m���̑呺�G�͒m���͓����̉�ŁA�u���o�E���h�Ƃ͍l���Ă��Ȃ����A�C������������������v�ƌ��y�B�܂h�~���d�_�[�u��21���őS�ʉ����ƂȂ������Ƃ��v���ł͂Ȃ����Ɩ���A�u�O�̂߂�ł͂Ȃ��������B���{�͓����s�̉������肫���������A�{���ɂ悩�������A�Ǝv���v�Ɠ������B���̂����Łu�K�����@���҂͌����Ă���B��Ì���͎�������������Ǝv�����A���ȕ��͋C���Y���Ă���v�Əq�ׂ��B
|
���V����825�l���R���i���� �O�T���207�l���� ���ꌧ�@3/25
���ꌧ��25�����\�����V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�825�l�ŁA2���A���őO�̏T�̓����j�����200�l�ȏ㑝���Ă��܂��B�l��10���l������̊����Ґ��������s�Ɏ����őS��2�Ԗڂ̑����ƂȂ��Ă��܂��B
���ꌧ�ɂ��܂��ƁA�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�825�l�ŁA��T�̋��j�����207�l�����܂����B�N��ʂł͑�������20�オ203�l�A10�オ138�l�A30�オ135�l�A40�オ129�l�A10�Ζ�����78�l�A50�オ77�l�A60�オ42�l�A70�オ15�l�A80�オ5�l�A90�Έȏオ2�l�A�m�F����1�l�ƂȂ��Ă��܂��B�n��ʂł͑������ɓߔe�s��231�l�A����s��98�l�A�X��p�s��67�l�A����s��57�l�A�Y�Y�s��56�l�A����s��45�l�A�L����s��42�l�A�����s��40�l�A�Ί_�s��17�l�A���s��15�l�A�{�Ó��s��14�l�ł��B���̂ق��̒����͕ی����̊NJ��ʂɁA�암�ی����Ǔ���71�l�A�����ی����Ǔ���53�l�A�k���ی����Ǔ���9�l�A�{�Õی����Ǔ���1�l�ŁA���O��8�l�A�m�F����1�l�ł��B
���肳��銴���o�H�͉ƒ����166�l�A�F�l�E�m�l��76�l�A�E�����27�l�A���H��15�l�A�{�ݓ���1�l�ȂǂƂȂ��Ă��āA����܂ł̂Ƃ���539�l�̊����o�H���������Ă��܂���B�l��10���l������̊����Ґ���24���܂ł�1�T�Ԃ�310.88�l�ƑS���œ����s�Ɏ�����2�Ԗڂ̑����ƂȂ�܂����B
���̎�������ËZ�ẮA�S����3�Ԗڈȓ��ɓ���̂�1��28���ȗ����Ƃ�����Łu�A�x�̉e�����傫���A1�T�Ԃ̊����Ґ���O�̏T�Ɣ�ׂ�ƈ�ԑ����̂�20�ゾ�B�܂���H�Ŋ�������l�͕��L������ŏo�Ă���B���̂܂܊����҂�������ƁA�w��7�g�x�̍ŏ��ɂȂ邩������Ȃ��ƌ��O���Ă���B�V�K�z���҂�}�����݂Ɍ����Č��������ӂ��Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
�����Ŋm�F���ꂽ�����҂͂��킹��11��7126�l�ɂȂ�܂����B����A�a���̏́A�V�^�R���i���җp�̕a���g�p����25�����݁A25.0���ŁA156�l�����@���Ă��܂��B���̊�ł̏d�ǂ�8�l�A�����ǂ�78�l�ŁA�l�H�ċz����g�������Â��錧�̊�ł̏d�ǎ҂�24���Ɠ���2�l�ł��B����×{�҂��܂߂��×{���̊��҂�5678�l�ł��B
���̂ق��A�A�����J�R���猧�ɑ��A�V����37�l�̊������m�F���ꂽ�ƘA�����������Ƃ������Ƃł��B
|
�����ӊ��A�v�l�͒ቺ�A�P�c�I�~�N�������̌��ǐ[���@3/25
�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̊����҂������X���ɂ��钆�A�y�ǂ△�Ǐ������҂̐[���Ȍ��ǂ����������Ă���B�����⌑��(����)���Ȃǂ����炭�����Ƃ̑i���͌��₽���A�Q������ɋ߂���ԂƂȂ�P�[�X�������B�]�������Z���ԂŏǏ��Ɏ���������݂��A�f�Ì���͑傫�Ȋ�@��������Ă���B
��ʌ���50�㏗����2����{�A�����ƍA�̒ɂ݂�����A�R���i�z���Ɣ��������B����Ɍ㓪�����A�w����]��(�������)�����ɂ��݂��ɂ݂�������悤�ɂȂ�A�N���オ��̂��炭�A�ɂݎ~�߂Ǝs�̂̕��ז������ł��߂������B
10���Ԃ̎���×{��ɐE�ꕜ�A���ʂ��������̂́A���ǂ���1�J�����߂��Ă������������A������w���ɂ����ċؓ��ɂ̂悤�Ȓɂ݂������Ȃ��B�d�����Z�����Ȃ�ƁA�����₽��̏o��ʂ����������Ƃ��C�ɂ�����B
�ӎ��I�ɐ������Ԃ��m�ۂ���ȂǑ̒��Ǘ��ɓw�߂Ă��邪�A�s���͂Ȃ��Ȃ����P����Ȃ��B�m�l�̒��ɂ�������A�u���邭�Ďd�����Ȃ��v�u�H�~���Ȃ��v�Ƙb���l������B�u�ȑO�̑̂̏�Ԃɖ߂邱�Ƃ͂ł���̂��v�B�����͕s����@������Ȃ��B
�R���i�̌��NJO�����J���u�q���n�^�N���j�b�N�v(�����s�a�J��)�ł͑�6�g�̃s�[�N���߂���2�����{���납��O�����҂������n�߁A��������100�l�߂���f��B�I�����C�����܂ߌߑO�����痂���܂őΉ����Ă��A���\�l�͐f�@��f�炴��Ȃ����������Ă���B
���҂̒��S��30��ŁA10���10�Έȉ��̎q��������B�I�~�N�����������̉e���Ƃ݂��銳�Җ�130�l�͂������ʁA��8�`9�����u���ӊ��v�u�v�l�͂̒ቺ�v�u�C���̗������݁v�u���Ɂv������ƉB�u�����v(��7��)�̏Ǐ�ł́A�����̂悤�ȏ�Ԃ̊��҂������B
�ł��[���Ƃ�����̂͏T�̔����ȏ�����ɂȂ��ĉ߂����u�Q������ɋ߂���ԁv��u�Q������ƂȂ����v���҂ŁA49�l(1��1���`����6��)�ɏ��B���ǂ���24�����x(���͊��҂̒����l)�ł��̏�Ԃ܂Ŋׂ�A�Ǐ��̃X�s�[�h�͏]�������2�T�ԂقǑ����Ƃ����B
��������@���́u�×{���Ԃ������A�d������̒x������߂����Ɩ��������Ċ撣���Ă��܂��ƈ�C�Ɉ������邱�Ƃ�����v�Ɛ����B�I�~�N�������͊������Ă��d�lj����ɂ����Ƃ���邪�A�u�����҂��������A���ǂɂȂ�l�������鋰�ꂪ����v�ƌ��O����B
���ǂ͍��{�I�Ȏ��Ö@���m������Ă��炸�A�ΏǗÖ@�����S�ƂȂ�B�Q������ɋ߂���ԂƂȂ�A�×{�������Ԃɋy�Ԃ��Ƃ�����A�����Ȃ��Ȃ�����A�w�Z�ɍs���Ȃ��Ȃ����肷�銳�҂�����������B
�u�I�~�N�������Ɋ������Čy�ǂ△�Ǐ�ōς�ł��A���킪�D��ꂩ�˂Ȃ����ǂ̋��ꂪ����B���ǂő̂��炢�̂Ɏ��̗͂���������ꂸ�A�ꂵ���v��������Ă���l���吨����B�����h��̎�������Ċɂ߂Ȃ��łق����v�B�������͂����i���Ă���B
|
���}�X�N�Ȃ��̓���͉����H�c�E�ъ��u�X�e���X�I�~�N�����v�̋��Ё@3/25
�V�^�R���i�E�C���X�̊����\�h��́A�����ƂɎ��g�ݕ����l�X�ł��B�{�L���ł́A�{�X�g���ɂ���_�i�E�t�@�[�o�[���������̌������ł���s�I�����A�A�����J��C�M���X���͂��߂Ƃ����e���̊����\�h��⌤�����ʂ�ʂ��āA���{�����ꂩ��ǂ�������ω����ׂ����A�܂��A���ݐ��ʉ��Ŋg�債�Ă��Ă���u�X�e���X�I�~�N�����v�̋��Ђɂ��ĉ�����܂��B
���I�~�N�������̏o���œ��퐶���́u�V���ȃt�F�[�Y�v��
���{��2022�N�������n�܂����V�^�R���i�E�B���X������(COVID-19)���s�̑�6�g�́A�V�K�̕ψي��ł���u�I�~�N�������v�̏o���ɂ��A����܂łɂȂ��L������݂��Ă��܂��B
�������A����̗��s������܂œ��l�ɁA2���͂��߂�10���l/���̐V�K�����Ґ����s�[�N�ɁA�ɂ₩�ł����������k���X���ɂ���悤�Ɏv���܂��B
����́A�����l�ނ�����܂Ŏ�����܂˂��Ď��Ԃ�T�ς��Ă�����ł͂Ȃ��A���N�`���⎡�Ö�J���ɉ����A�X�l���ł���}�X�N���p���͂��߂Ƃ����\�h���^���ɍu���Ă����ł�����܂��B
�Ƃ͂������̂́A�����_�ł͈�A��COVID-19�p���f�~�b�N�̐�s�����݂��Ȃ��̂������ł��B
�����ō���͉�X�̐������ǂ��ς��Ă����ׂ����l���邽�߂ɁA�A�����J��C�M���X���͂��߂Ƃ����e���̏A�}�X�N�ɂ�銴���\�h��̊ɘa�A�X�e���X�I�~�N������(BA.2��)�̊e���ł̕���эŐV�̌������ʂ��Љ�܂��B
���u�u�[�X�^�[�ڎ헦�v���Ⴂ�A�����J
�A�����J�ł̃��N�`���ڎ헦�́A2022�N2�����_�ɂ����Ă��Ƃ��~�Y�[���B�ł�55��(�u�[�X�^�[�ڎ헦22��)�A�R�����h�B�ł�69��(�u�[�X�^�[�ڎ헦34��)�ƒႢ�n�������܂����A���ƑS�̂ł�12�Έȏ�̐ڎ헦��73.3��(�u�[�X�^�[�ڎ헦44.9��)�ł����B
���Ȃ��Ƃ����N�`����ڎ킵�Ă���l�̊����͓��{�Ɠ����x�ł����A�u�[�X�^�[�ڎ헦���Ⴂ�̂������ł��B
�A�����J�ł̐V�K�����Ґ���1����30���l�ɒB�������ƁA3���ɂ�3���l�Ɍ������Ă��܂����A����ɂƂ��Ȃ��V�K���N�`���ڎ헦�̓��N�`�������������Ă���2020�N12���Ɠ����x�܂ŗ����Ă���Ƃ����Ă��܂��B
�u�[�X�g���N�`����ڎ킵�Ȃ��l�̂Ȃ��ɂ́A�uCOVID-19�Ɋ��������̂ŖƉu���l�����Ă���v�ƍl���Ă���l�����܂����AHarvard TH Chan School of Public Health�̉u�w������Bill Hanage�������悤�ɁA�������҂��l�������Ɖu�����͒ቺ���Ă������ߏd�lj����₷���Ȃ��Ă���\��������܂��B�u�[�X�g���N�`���͕K�v�ł��B
�����������\�h��ɘa��i�߂Ă���C�M���X
�C�M���X��2����COVID-19�ɑ���K�����ɘa�����܂����BBoris Johnson�͌����z���҂̎���u���v���A�ڐG�Ғ����A�����v���e�X�g�{�s�̎���߂\���܂����B
���́u�R���i�E�C���X�Ƌ��ɐ����邱�Ƃ��w�сA��X�̎��R�𐧌����邱�ƂȂ���X���g�⑼�̐l����������Ă����v�ƃR�����g���Ă��܂��B
�C�M���X�ł�12�Έȏ�̃��N�`���ڎ헦��84.9��(�u�[�X�^�[�ڎ헦65.7��)�ƍ������Ƃ��ɘa��̈���Ƃ��Ă��܂��B
���ɂ��f���}�[�N��I�����_�Ȃǂ����l�ɋK�����ɘa���Ă��܂����A���̈���j���[�W�[�����h�⍁�`�ł͂���܂łɂȂ��������s���݂��A�Ή��ɒǂ��Ă��܂��B
���A�����J�Ői�߂��Ă���u�}�X�N���p���R���v
�A�����J��CDC(The Centers for Disease Control and Prevention)�͐V�����K�C�h���C���̂Ȃ��ŁA�����ȏ�ɓ������`�����x�̃��X�N�̏B�Ń}�X�N���p�́u���͂�K�v�Ȃ��v�Ƃ��܂����B
����͂��悻70���̃A�����J�l���܂܂�邱�ƂɂȂ�܂����ACDC��Rochelle Walensky�����́A���N�`����������ɂ��Ɖu�l���A�����̌���A�V�K���Â̕��y�Ȃǂ���d�lj����X�N�������������Ƃ������Ƃ��Ă��܂��B
����Ńn�C���X�N�̐l�₻�̉Ƒ��̓}�X�N���܂߂��\���ȗ\�h�����邱�Ƃ����N���Ă��܂��B
�܂��A�����̊w�Z�ł̓}�X�N���p�����߂��Ă��܂����ACDC�́A�q���͏d�lj����X�N���Ⴂ���Ƃ���A�������s�n�̊w�Z�̂݃}�X�N���p�ł̐��������߂Ă��܂��B
���݁A�����ł̃}�X�N���p���`���t���Ă���̂̓n���C�݂̂ƂȂ��Ă���A���Ƃ̂������ł͑�������K���ɘa��Ɍ��O�̐����オ���Ă��܂��B
�����ʉ��ōL�����Ă���u�X�e���X�I�~�N�����v�̋���
�I�~�N�������̈��^�ł���BA.2����2022�N1��������Ɍ��o����܂����B���o������u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ�A�嗬�ł���BA.1�����������͂������A���N�`���⎡�Ì��ʂ��Ⴂ�\������������Ă��܂��B
�������A�����J�ł̓A�C�I���B�A���C���B�A�I�N���z�}�B�ȊO�̑S�y�Ō��o����Ă�����̂́u1,400����x�v�ɗ��܂��Ă���A����͑S�̂̕��0.5���ȉ��ɓ�����܂��B
��̂����Ƃ������J���t�H���j�A�B�ł�262��Ə����̂��߁ACDC�͂���܂ł̕ψي��ƗL�a���͑卷�Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
����ŋK���ɘa�������Ă����f���}�[�N�̂ق��A�u���l�C�A�W���[�W�A�A�l�p�[���Ƃ��������X�ł�BA.2�����[���ȃA�E�g�u���[�N�������N�����܂����B
���ہA�f���}�[�N��Staten Serum Institute�́ABA.2����BA.1���ɔ�����͂�30���㏸���Ă���A���N�`���ɂ��\�h���ʂɑ��Ă��Ɖu����\�����邱�Ƃ���Ă��܂��B
�������A�����[�����ƂɁA���N�`����ڎ킵���l�ł�BA.1����BA.2���������͂͋����Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
����ɓ��{�̍������搶�A�r�c�P���搶��̌����O���[�v��BA.2����BA.1���ɔ��40�������͂������A���ɔx�ł̃E�B���X���B�\���オ���Ă��邱�Ƃ���Ă���ȂǁA�d�lj��ɂ͒��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
���u�}�X�N�Ȃ��̐����v�͔��I
���N�`���ڎ헦�͓��{�Ɠ����x�̃A�����J�́A�u�[�X�^�[�ڎ헦���Ⴂ�ɂ�������炸�}�X�N���p�����R�����Ă���C�M���X�́A���N�`���ڎ헦�A�u�[�X�^�[�ڎ헦�Ƃ��ɍ������Ƃ���\�h����ɘa���Ă���\�h����ɘa���Ă����f���}�[�N�ȂǂŃX�e���X�I�~�N������(BA.2��)���A�E�g�u���[�N���N�����Ă�����{�̌����ł�BA.2���̊������̑����A�d�lj����J�j�Y��������Ă��邱���̂��Ƃ���A���܂��X�e���X�I�~�N�������̏��͏��Ȃ��A����܂ł̂悤�ɂ܂������}�X�N���K�v�Ȃ������ɖ߂邱�Ƃ͌����I�ł͂���܂���B
�������A���N�`���⎡�Ö�ɂ����ʂ����炩�ɂȂ��Ă��Ă���A�\�h����ɘa���邱�Ƃ͉\�ł��B
������e���̏��Q�l�ɉ�X�̐����X�^�C�������������邱�Ƃ��d�v�ƍl�����܂��B |
���u�܂h�~�[�u�v�����㏉�̓y�� ���r�m���g��������h�@3/25
�܂h�~���d�_�[�u����������ď��߂Ă̓y�����}����̂�O�ɁA�����s�̏��r�m���́u�F����̉䖝�����A�ɋA���Ȃ����߂ɂ��A���͂������������肢�������v�Əq�ׁA���H�͏��l���ŒZ���Ԃɂ���ȂNJ�����𑱂���悤�d�˂ėv�����܂����B
26����27���͍���21���ɏd�_�[�u���������ꂽ���Ə��߂Č}����y���ƂȂ�܂��B
�����s�̏��r�m����25���̋L�҉�Łu�����X�����m���Ȃ��̂ɂ��āA��Ò̐��ɂ������Ă��镉�ׂ�O��I�Ɍy�����Ă������Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu���������̂���܂ł̊F����̉䖝�����A�ɋA���Ȃ����߂ɂ��A���ЁA�����͂������������肢�������v�Əq�ׁA���T�A�V�N�x���}���邱�Ƃ����܂��A���H����́A�s�̔F�����X�𗘗p���A���l���ŒZ���Ԃɂ���悤�d�˂ėv�����܂����B�@ |
 |
���I�~�N�����n���a�`�E2�@4���ɒu�������@��6�g��荂�����@3/26
�V�^�R���i�E�C���X��œK�p����Ă�������(�܂�)�h�~���d�_�[�u������21���ʼn������ꂽ���A���Ɏ��̑�7�g�ւ̌x�������܂����B���݂̎嗬���ɔ�����͂������I�~�N�������̌n�����u�a�`�E2�v�ւ̒u������肪�i�݁A4�����ɍ����ł̌��o�������ق�100���ɒB����Ƃ݂��邽�߂��B�E�C���X�����̉𖾂��i�ނ��A���N�`���⎡�Ö�̌��ʂ͂���̂��B�e����T�����B(�L�N�R�M�q)
�����ŗ��s����I�~�N�������́A�����͌n�����u�a�`�E1�v�ƁA���̕\�ʂ̃X�p�C�N�^���p�N����1�J���ψق��������u�a�`�E1�E1�v�����������A�������L����ɂ�Ăa�`�E1�E1���嗬�ɂȂ����B
�I�~�N�������̉�͂��s���Ă��铌����̍�����(����)�y����(�E�C���X�w)�ɂ��ƁA�a�`�E1�E1�͂a�`�E1����⊴���͂��������A�����͂قړ����ƍl�����Ă���B����A�a�`�E2�̓X�p�C�N�̉���z�a�`�E1�Ƒ傫���قȂ��Ă���A��芴���������߂Ă���Ƃ݂���B���łɃf���}�[�N��p���ł͎嗬�����a�`�E2�ɂقڒu�������A�t�B���s���Ȃǂ̓���A�W�A�n��ł������ȑ����X���ɂ���B
�����y�����́u�a�`�E2�͂a�`�E1�E1��������Ɋ����͂������B�a�`�E2�̊����������Ă��鑼���Ŋ����̍Ċg�傪�N���Ă���悤�ɁA�u������肪�i�ޒ��Ől���������ɂȂ�ƁA���{�ł��������g�傷�邾�낤�v�Ǝw�E����B�����h�~���d�_�[�u�̉����ŊX�ɐl�g���߂�A�a�`�E2�̊����g�傪��6�g��荂���g�������N�����\�������O����Ă���B
23���ɍs��ꂽ�����J���Ȃ̐��Ƒg�D�̉�Ŏ����ꂽ�����ɂ��ƁA�a�`�E2�͂a�`�E1�E1���܂ނa�`�E1�Ɣ�ׁA������ɑ��̐l�ɂ���܂ł̓������������㎞�Ԃ�15���Z���A������1�l�����l�Ɋ������L���邩�����������Đ��Y����26�������B�܂��A���������nj������̗\���ł́A���o������4����1�T���_��72���A5����1�T���_��97���ɒB����B
�����̘e�c����(������)�����������͂a�`�E2�ւ̒u�������Ɋւ��A�u�����g��̈��͂ɂȂ邾�낤�B����A�����Ґ����ēx�����ɓ]����\��������v�ƌ�����B
�a�������߂���A�p���ی����ǂ͂a�`�E2������̓��@���X�N���u�a�`�E1��荂�܂��Ă���Ƃ͂����Ȃ��v�ƕ��Ă���B�����A����Ȃǂ̌����`�[���̓��������̌��ʂɂ��ƁA�x�g�D�ɑ����L����₷���A�a�`�E1�ւ̊����ɂ��Ɖu���a�`�E2�ɂ͌����Â炢�\��������Ƃ����B�C�O�ł͂a�`�E1�����҂̂a�`�E2�ւ̍Ċ���������Ă���B
����A���N�`�����ʂɊւ��ẮA�p���̃f�[�^�ɂ��ƁA���Ǘ\�h���ʂ́A2��ڎ킩��25�T�ȍ~�ła�`�E1��10���A�a�`�E2��18���B3��ڐڎ킾�ƁA2�`4�T��ła�`�E1��69���A�a�`�E2��74���ɍ��܂�A10�T�ȍ~�͂a�`�E1��49���A�a�`�E2��46���Ɍ�������ȂǓ��l�̌X���������Ă���B
�����ŏ��F����Ă��鎡�Ö�ɂ��ẮA����⊴�����Ȃǂ̌����O���[�v���A���a�R�̖�̌��ʂ��]���������Ⴂ���O��������̂́A�זE�����ň��̌��ʂ��m�F�B�����f�V�r������k�s���r���Ȃǂ̍R�E�C���X��͍������ʂ��ێ����Ă���Ɣ��\�����B
|
���S��������4���A��4���l�����@����10���A��1���l����� �@3/26
26���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂́A4��7,338�l�������B
�����s�ŐV���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�7,440�l�ŁA��T�y�j�����4�l����A10���A����1���l����������B�܂��A�S���Ȃ����l��18�l�������B
���̂ق��A�_�ސ쌧��4,848�l�A��ʌ���4,129�l�A���{��3,645�l�ȂǁA�S���Ŋm�F���ꂽ�����҂�4��7,338�l�ŁA��T�y�j�����炨�悻2,500�l�����A4���A����4���l�����B���҂�101�l�������B
����A�����J���Ȃɂ��ƁA25�����_�ł̑S���̏d�ǎ҂�707�l�ŁA2���A����800�l��������Ă���B
|
 |
���V�K�����҂́A�S����27���ߌ�5��10���܂łɁA3���l���Ă���B�@3/27
�����s�ŐV���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A7,844�l�ŁA��T�̓��j������1,342�l�����āA3���Ԃ�ɑO�̏T�̓����j�����������B
���̂ق��A�_�ސ쌧��3,553�l�A���{��3,493�l�A��t����2,515�l�ȂǁA�S���ł͌ߌ�5��10���܂łɁA3��5,335�l�̊����ƁA42�l�̎��S���m�F����Ă���B
|
�������s �V�^�R���i 9�l���S7844�l�����m�F �O�T��1300�l�]���� �@3/27
�����s����27���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓��j�����1300�l�]�葽��7844�l�ł����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ9�l�����S�����Ɣ��\���܂����B
�����s�́A27���ɓs���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v�̍��킹��7844�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����1300�l�]�葝���܂����B7���ԕ��ς�6466.6�l�ŁA�O�̏T��85.2���ł����B27���m�F���ꂽ7844�l��N��ʂɌ���ƁA10�Ζ������ł������S�̂�19.3���ɂ�����1511�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�323�l�őS�̂�4.1���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�27�����_��36�l�ŁA26�����1�l�����܂����B����s�́A�������m�F���ꂽ50��ƁA70�ォ��90��̒j�����킹��9�l�����S�����Ɣ��\���܂����B
|
��������7844�l�����A9�l���S�@�R���i�A�N��ʍő���10�Ζ����@3/27
�����s��27���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����7844�l���ꂽ�Ɣ��\�����B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���6466�E6�l�ŁA�O�T���85�E2���B9�l�̎��S�����ꂽ�B���@���҂͑O���ɔ��32�l����2013�l�A�����d�ǎ҂�1�l����36�l�B�I�~�N�������̓����܂����d�Ǖa���̎g�p����14�E2���������B
�����҂̔Z���ڐG�҂ŁA�Ǐ�Ɋ�Â������Ȃ��ň�t���z���Ƃ݂Ȃ������҂́A�V�K�����҂̂���68�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�10�Ζ�����1511�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�323�l�������B
|
�����{ �V�^�R���i 6�l���S �V����3493�l�����m�F �@3/27
���{��27���A�V����3493�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���������悻580�l�����Ă��܂��B����A���{��1��31�����獡��25���܂łɔ��\���Ă���9�l�ɂ��āA�d�����Ă����Ƃ��Ċ����҂����艺���܂����B����ő��{���̊����҂̗v��78��1081�l�ɂȂ�܂����B�܂��A6�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��4606�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�26���ƕς�炸96�l�ł����B
|
���V�^�R���i �������@3/27
��2�{4���ŁA27���ɔ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂́A���킹��7215�l�ŁA�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�900�l�ȏ�A�����Ȃ��Ă��܂��B
�{���ʂł́A��オ3493�l�A���ɂ�1748�l�A���s��864�l�A���ꂪ623�l�A�ޗǂ�345�l�A�a�̎R��142�l�ł����B����ŁA��2�{4���̊����҂̗v��142��6430�l�ƂȂ�܂����B �d�ǎ҂̐l���́A��オ96�l�A���ɂ�18�l�A�ޗǂ�11�l�A�a�̎R��3�l�A�����2�l�A���s��1�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A����6�l�A���s��5�l�A�a�̎R��1�l�̎��S�����\����܂����B ��2�{4���ŁA����܂łɖS���Ȃ����l��7969�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���܂h�~�����㏉�̏T�� �e�n�̔ɉ؊X�Ŗ�̐l�o�����@3/27
�܂h�~���d�_�[�u����������ď��߂Ă̋x���ƂȂ������̂��A�ɉ؊X�̖�̐l�o�́A�O�̏T�Ɣ�ׁA�S���I�ɂقƂ�ǂ̒n�_�ő������܂����B
��������Ȃ�18�s���{�����ΏۂƂȂ��Ă����u�܂h�~���d�_�[�u�v�����悻2�������Ԃ�ɉ�������Ă��珉�߂Ă̏T�����}���A�e�n�̔ɉ؊X�͓��킢���݂��܂����B���̂��ߌ�9����̐l�o��O�̏T�̓y�j���̓������ԑтƔ�ׂ��Ƃ���A�S����21��������ϑ��n�_�̂����A19�����Ől�o���������܂����B
�ł����������͍̂��쌧�����s�̊����w���ӂł��悻8���������A�����œ����E�Z�{�Ɛΐ쌧�̕В���5���ȏ㑝�����ق��A�k�C���̂������̂ł́A���悻3�������B���s�̍�������A�a�J�Z���^�[�X�A���s�E�͌����Ȃǂł�2���ȏ�̑����ƂȂ�܂����B
|
���V���ɂ��݂��q���@�܂h�~�[�u���� ���̏T���@�����A�ߐ{�@3/27
�Ȗ،��Ȃ�18�s���{����ΏۂƂ����V�^�R���i�E�C���X�܂h�~���d�_�[�u����������Ă���ŏ��̏T�����}����26���A������ߐ{�����̊ό��n�͓V��Ɍb�܂ꂸ�A�݂��q���̖߂�ƂȂ����B����19�������3�A�x�ȍ~�͏��������Ă���Ƃ����A�n���W�҂͍���̂���Ȃ�l�o�Ɋ��҂��Ă���B
���̓��ߌ�A�����s�͂����ɂ��̉J�V�ƂȂ����B���E��Y�u�����̎Ў��v���ӂ�Ў��ɑ�������119�������ł͉Ƒ��A����҂̎p������ꂽ���̂́A�l�ʂ�͂܂炾�����B
������(�͂���)���̂��X�u�����{�O���v�̓X��֓��S���q(�����Ƃ���݂�)����(56)�́u�{���̊��C�ɂ͂قlj������A(19�`21����)3�A�x����ό��q�͏����������Ă��Ă���v�Ƙb���B���⌧�̊ό����v���N��4��������{�����\��ł��邱�Ƃ܂��A�u�S�[���f���E�C�[�N(GW)�ɂȂ�Ί��C���߂�̂ł͂Ȃ����v�Ɗ��҂��Ă���B
���Ɨ��s�ŗF�l��2�l�œ������Ƌ{��K�ꂽ�A��t���D���s�A�Ō���w�Z3�N���c�[��(�ӂ����䂤��)����(21)�́u���o�͔��N�ȏ�Ԃ�B�����ƊO�o�����ɉ߂����Ă����̂ŁA���t���b�V���ł����v�Ƙb���Ă����B
�ߐ{�����s���̊ό��X�|�b�g�����V��Ȃǂ̉e���ŋq���͐L�тȂ������B���s���{�����̗��فu��������(���炩��)�v���c�ސ��R�x�l(������܂����Ђ�)����(54)�́u�����̐l�������Ȃǂ̗l�q�����Ă���̂��낤�v�ƕ��͂���B
����ł����[�u�����O�Ɣ�ׁAGW�̏h���\��͑����Ă��Ă���Ƃ����A�u�t�̖{�i�I�Ȋό��V�[�Y��������O�ɉ����ƂȂ��Ă悩�����v�Ƙb�����B�@ |
 |
���܂h�~�����ƍ����J�Ől�o������ �����҂�2���A���őO�̏T������@3/28
���̓y���́A�����Ȃǂ̂܂h�~���d�_�[�u����������ď��̏T���ƂȂ�A���̌������}�����n��𒆐S�ɑO�̏T���啝�ɐl�o�������܂����B���Ƃ���́A�C�x���g�ɂ�銴���̍Ċg������O���鐺���������Ă��܂��B
�������ɗ����l�u���ꂢ�������v
�����̍������̂��A���ɖ��J���}���܂����B
�������ɗ����l�u�܂h�~���������ꂽ���A������Ɖ��o���ėL���ȂƂ���s�������ȂƁv
�܂h�~�[�u����������A�t�炵���z�C�ƂȂ������傤�A���̖����A�����E�ڍ���́A�����ɂ�������炸�����̉Ԍ��q�œ��킢�܂����B���܂�̐l�̑����ɑO�ɐi�ނ̂�����Ƃ̏c�B
�������ɗ����l�u�l���݂ɂȂ��Ă����̂ŁA(����)���������ĕ����Ă��܂����v
�������ɗ����l�u�l����������̂ŁA���\���ѐH�ׂĂ���l��������ł����ǁA�}�X�N��肽���Ȃ��̂ł����������ȁv
���̓y���́A��������Ȃǂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v����������ď��̏T���Ƃ������Ƃ�����A���̌������}�����n��𒆐S�Ɋe�n�őO�̏T���啝�ɓ����̐l�o���������܂����B
���̂��ߌ�2����̐l�o��O�̏T�̓������ԑтƔ�ׂ��Ƃ���A�����E�������ł��悻1.7�{�ɁA�����E���c�����ł����悻1.9�{�ƂȂ�܂����B
�܂��A�ɉ؊X�ł͖�̐l�o���킸���ɑ����A���̂��ߌ�9����ł́A�O�̏T�̓��j���Ɣ�ׁA�����E�Z�{��1.1�{�A���E�Ȃ�Ήw���ӂł����悻1.1�{�ƂȂ�܂����B
���傤�A�����ŐV���ɔ��\���ꂽ�����Ґ���4544�l�B��T���j�����689�l�����A2���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
����A������́c
���������l�u�V�C���ǂ������̂ŗV�тɂ��܂����v
���m�����v��s�̈��E�n�����L�O�����B�������ɂ́A11���ɃW�u���p�[�N���I�[�v���\��ł����A�ꑫ��ɃW�u���̐��E�ς��Č���������������I�ڂ���A�T���͑吨�̉Ƒ��A��œ��킢�܂����B
�t�x�ݒ��A�e�n�Ől�o��������ƌ����܂�܂����A���Ƃ́u�Ԍ��Ȃǂ̃C�x���g�ɂ���ċ}���Ȋ����Ċg��ɂȂ��鋰�ꂪ����v�Ƃ��Ċ�{�I���O�ꂷ��悤�Ăт����Ă��܂��B
����A���m���ł͐�T�ؗj���ȍ~�A�����Ґ����O�̏T�̓����j���������Ă��܂��B�呺�m���́c
���m�� �呺�G�͒m���u���������āA��T�̎��_�Łw�܂h�~�x���������ėǂ��������B���͂�����Ɣ������ȂƎv���Ă��邪�A���S�ɍ��̕����O�̂߂�Łw��������x�Ɠ˂������Ă��܂�������A������Ƃ����������v
|
���u�܂h�~�v�S�ʉ����㏉�̏T���c���O�ό��q�łɂ��키�@3/28
�܂h�~���d�_�[�u���S�ʉ����ƂȂ��Č}�����T���E27���̓��j�́A�e�ό��n���吨�̌��O�ό��q�łɂ��킢�܂����B
�g���ȓ��������~�蒍�������捻�u�B������߂��̒��ԏ�͂قږ��ԂŁA���O�i���o�[���ڗ����܂����B
�������͏����₽���������̂́A�����ō��̊��G���y����A�n�������N���o���Ăł���I�A�V�X�Ő��V�т������肵�Ċy���ސl�B�y�b�g��A��č��u�ό��i����l�����̎p�������܂����B
�ޗnj�����̊ό��q�u���������C���˂Ȃ����₷���Ƃ������A�������}�X�N�Ȃǂ𒅗p���Ăł����A�l���������A�q�ǂ��������A�����ɂȂ��Ċy����ł��܂��B�V�C���ǂ����ō��ł��ˁv
���R������̊ό��q�u�l�͏C�w���s�Ƃ��Ȃ������̂ŁA���̋@��ɍs������Ǝv���āA���傤���܂����B���b�`���y�����ł��v
����A�Ďq�s�̖��R�����ɂ��A���̂������l�����肪�ł��Ă��܂����B�n���Y�i�̃}�[�P�b�g�C�x���g�A�u��Ȃ��E�}���V�F�v���J�Â���A�吨�̉Ƒ��A��Ȃǂœ��킢�܂����B�n���̎Y�i�̖��͂M���邱�Ƃœ��킢�ɂȂ��悤�ƕĎq���H��c���N�����J���Ă��āA���̓��̓J���[��X�C�[�c�ȂǐH�̃u�[�X�𒆐S�ɗl�X�ȏo�X������A1���Ŏ���5000�l���K��܂����B
�K�ꂽ�l�́u�V�C���ǂ��ċv���Ԃ�ɂ�������ďo����̂ŗǂ������ł��v�u�v���Ԃ�̂��o�����ŁA�q�ǂ����y�������ł��v�u�}�X�N���Ă��邯�ǁA��������Đl�̑������ɗ���ƋC�����Ⴂ�܂��ˁv
�K�ꂽ�l�͋v�X�ɊJ�Â��ꂽ��K�͂ȉ��O�C�x���g�i���Ă��܂����B
|
���g�܂h�~�h�������@���̏T���@�W�u���Řb��̌����␢�E��Y�̊ό��n�@3/28
27���́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̉�����A���߂Ă̓��j���B����Ԃ��L���������m�����v��s�́u���E�n�����L�O�����v�ł������炫�n�߁A�吨�̉Ƒ��A�ꂪ�y����ł��܂����B
�K�ꂽ�l�@�u�Ȃ��Ȃ��O�o���Â炩�����c�A�V�C���ǂ������̂ŗV�тɗ����v�@�u�v���Ԃ�Ɍ����ɗ����v
�H�����i�ޒ��ڂ́u�W�u���p�[�N�v�B���Ƃ�11���̃I�[�v���\��ł����c�B
���������L�ҁ@�u������Ɍ����Ă���̂���T���痘�p���ł���悤�ɂȂ����G���x�[�^�[���ł��B�����̕~�n���ł́A����ɃI�[�v���O�ł������̎{�݂����邱�Ƃ��ł��܂��v
��T���痘�p�ł���悤�ɂȂ����A������30���[�g���́u�G���x�[�^�[���v�B���Ƃ��Ƃ������G���x�[�^�[�����C���A�W�u����i�̐��E�ς��C���[�W���č���Ă��܂��B
�K�ꂽ�l�@�u�v�������A���������������v�@�u���ۂɌ��Ă݂�ƁA�������B�W�u���̐��E�ς��v
����A������́A�܂��Ⴊ�c�鐢�E��Y�A���́u���싽�v�B���ԏ�͒��O�ɂ͖��Ԃ̏�ԂɁB��������̉ƁX�����悤�ƁA�����̊ό��q�œ��킢�܂����B
�ό��q�@�u�_�ސ삩�痈���B�g�܂h�~�h�������Ė{���ɋv�X�ɗ����B�q�ǂ������ɁA���낢��ȏ��������Ă��������v��������̂Łv�@�u��ʂ��痈���B�����I�ɂ��t�ɂȂ�ƁA�ǂ��ƂȂ��o���������Ȃ�v
�v�X�ɑ����̊ό��q���K�ꂽ�y�Y���X�̓X��́c�B
�y�Y���X�̓X��@�u(�܂h�~��)���������B�n���̒��������B�������ċq�����Ă����Ƃ������Ƃ͐��ɂ��肪�����v
|
���ό��n�@����E���Z����7536�l�@�܂h�~������A���̓��j�@3/28
�V�^�R���i�܂h�~���d�_�[�u����������Ă��珉�̓��j�ƂȂ���27���A�ΐ쌧���͐L����A�ό��n�ɗ��s�q�炪�������B3�A�x��������T�ɑ����ɂ��킢�ŁA�t�x�݂ʼnƑ��A��̎p���ڗ����A�ό��W�҂͍s�y�V�[�Y���{�i���֊��҂����߂��B
���Z���ɂ�7536�l���K��A3�A�x�ŏI����21��(6815�l)���������B�s���N�F�̉Ԃ��炩�����~�̖̎���ł́A�ό��q���t�̖����̕��i�����߂悤�ƃX�}�[�g�t�H���̃J�������\���A�l�����肪�ł����B
�ߍ]���s��̂����X��C�N���X�Ȃǂ̑O�ɂ͒����s�ł����B��w���i���j���A��������k���V�����ŕ��e�Ƌ��ɖK�ꂽ��J������(19)�́A�C�̍K�����\���u���߂ċ���ɗ��ėǂ������B���͕��Ƃ��������n�����ނ��킵�����v�ƏΊ���������B
NTT�h�R���ɂ��ƁA�ߌ�3�����_�̍��іV�̐l�o�͊����g��O���3�E5�����ƂȂ�A�R���i�O�Ɠ������ɔ������B����w��16�E7�����������B
�֓��s�̗֓����s�⍑�����u����(������)�疇�c�v�ł͌��O�i���o�[�̎Ԃ���������ꂽ�B���s���s�g���̕y�����B(�Ƃ݂��E�Ȃ�����)�g�����ɂ��ƁA��T��3�A�x���珙�X�ɋq�����L�тĂ���Ƃ����A�u��^�A�x�ɂ����Đl�o���߂邱�Ƃ����҂������v�Ƙb�����B
27���̍ō��C���͋���14�E2�x�A�֓�12�E8�x�ƕ��N���݂��������������B����n���C�ۑ�ɂ��ƁA28���̌����͐��ꎞ�X�܂�̗\��ƂȂ��Ă���B
|
�������������u���f�ł����v�@�A���N�`���m�ېs�́@3/28
�ݓc���Y��28���̎Q�@���Z�ψ���ŁA�����̐V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������ɂ�闬�s�u��6�g�v�̒������Ɋւ��u�܂h�~���d�_�[�u�͑S���ʼn����������A�����Ė��f�ł��Ȃ��B���͂܂��Љ���������������Ă����ڍs���Ԃɂ���v�ƌ�����B�u��7�g�v�ւ̔����Ƃ��āA���N�`����4��ڐڎ���������Đ�����Ђƌ����A�m�ۂɓw�߂�Ƌ��������B
�́A�S���I�ɂ�1�J���ȏ�ɂ킽���ĐV�K�����Ґ����ɂ₩�Ɍ����Ă���Ɛ����B����Łu�����Ґ��������Ă��錧������v�Əq�ׂ��B��}�����A��6�g�̏o���͌����Ă���̂��ȂǂƎ��₵���̂ɓ��ق����B
|
 |
���č��ŃR���i�����Ґ��������~�܂�A�ꕔ�B�ŁuBA.2�v�������g��@3/29
�����X���ɂ������č��̐V�^�R���i�E�C���X�����Ґ����A�����ɂȂ��Ă���B���łɈꕔ�̏B�ł́A�Ăё����ɓ]�����Ƃ����B�ی����ǂ̊W�҂�́A���s�̒��S�ƂȂ��Ă���ψي��A�I�~�N�������̔h���^�uBA.2�v�ւ̒u������肪�����̍Ċg�������������\��������Ƃ��āA���O�����߂Ă���B
�Ď��a��Z���^�[(CDC)�ɂ��ƁA3��25���܂ł�7���Ԃɂ�����1��������̐V�K�����Ґ��́A����2��7594�l�B3��18���ɕ��ꂽ�l���Ƃقړ����ŁA1�����{���瑱���Ă��������X�����A����n�߂����Ƃ����m�ɂȂ����Ƃ�����B�����A�����ɂ����@�Ґ��Ǝ��Ґ��́A�S�ĂŌ����X���������Ă���Ƃ����B
�Ď��j���[���[�N�E�^�C���Y���܂Ƃ߂��f�[�^�ł́A�ߋ�2�T�ԁA��s���V���g���̂ق��P���^�b�L�[�B(106%��)�A�j���[���[�N�B(56����)�Ȃǂ�9�B�A�ė̃T���A�A�ė̃v�G���g���R�ŐV�K�����҂̑������ڗ����Ă���B
CDC�ɂ��ƁA���݂̂Ƃ��덑���̐V�K�����҂ɐ�߂�uBA.2�v�ւ̊����̊����́A35�����x�B�Ĉ�w���j���[�C���O�����h�E�W���[�i���E�I�u�E���f�B�V����3��16���Ɍf�ڂ��ꂽ�������ʂɂ��A�uBA.2�v�̓I�~�N�������̏����̏����ɑ唼���߂Ă����uBA.1�v�Ɣ�ׁA�Ɖu���������\�͂ɑ傫�ȈႢ�͂Ȃ����̂́A�����͂͂�苭���Ȃ��Ă���Ƃ݂���B
���E�ی��@��(WHO)�͂��łɁA���̔h���^�����E�I�ɗD���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������f�[�^�����\���Ă���B�����҂���̎悵���T���v���̃V�[�P���V���O(��`�q���̓ǂݎ��)���s�������ʁA99.8�����I�~�N�������ŁA���̂���86�����uBA.2�v�������Ƃ����B
WHO�ɂ��A1�����{�ȍ~�͌����X���ɂ��������E�S�̂̊����Ґ��́A���łɍĂё����n�߂Ă���B3��14���܂ł�7���Ԃɂ́A�O�T���9���߂����������҂��m�F����A�T��ł̑�����2�T�A���ƂȂ����B�܂��A���ɑ啝�ȑ������ڗ����B�ł́A3��7������14���܂łɃn���K���[��57���A�t�����X��42���̑������m�F���ꂽ�B
�Đ��{�̎�Ȉ�Ìږ�A�����A�����M�[�����nj������̃A���\�j�[�E�t�@�E�`�����́ABA.2�̍L����Ɗ�����̂��߂Ɏ��{����Ă����s���K���̊ɘa�ɂ��A�u�č��ł����B�Ɠ��l�ɁA�����҂��������邾�낤�v�Əq�ׂĂ���B�����A�u�}�����邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ̌������B
����A�z���C�g�n�E�X�̃R���i�E�C���X���������A�W�F�t�E�U�C�G���c�ɂ��ƁA�č��ł̓��N�`���⌟���A���Â̂��߂Ɍ������Ȃ���Õ������\���Ɋm�ۂ��邽�߂̎������s��������B
�u�A�M�c��s�����N�����Ȃ��v���Ƃɂ��A���łɊ����҂̎��ÂɕK�v�ȃ��m�N���[�i���R�̖�̊e�B�ւ̋����ʂ�35�����炷���Ƃ�]�V�Ȃ�����Ă���Ƃ����B
|
�������s�ŐV����7846�l�������A5�l���S�@�a���g�p��26.2�� �@3/29
�����s��29���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ�����7846�l��5�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�d�ǎ҂͓s�̊��33�l�B�a���g�p����26�D2%�B
�V���Ȋ����҂̂����A�����������Ɉ�t�̔��f�ŗz���Ƃ݂Ȃ��u����^���NJ��ҁv(�݂Ȃ��z����)��108�l�B 1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���29�����_��7181�D1�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�105�D1���B�s���̗v�̊��Ґ���123��3139�l�ƂȂ����B �����҂�10�Ζ������ł�����1524�l�B10��1262�l�A20��1454�l�A30��1287�l�A40��1169�l�A50��610�l�ŁA65�Έȏ�̍���҂�398�l�������B �S���Ȃ����l��70��`90��̒j��5�l�B
|
���u�I�~�N�������wBA.2�x�ւ̒u������肪�i��ł���v���r�m���@�����ґ����@3/29
�s���̊����Ґ���3���A���ŁA�O�̏T�̓����j�������������Ƃɂ��āA���r�m���́A�����قǁA�u�I�~�N�������wBA.2�x�ւ̒u������肪��ςȃX�s�[�h�Ői��ł��邽�߁v�Ƃ̌������������BBA.2�́A�]���̃I�~�N���������������͂������Ƃ���Ă���B
�����s�ł́A29���A�V����7846�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă������Ƃ����������B��T�̉Ηj��(3533�l)���2�{�ȏ㑝�����B1���̊����Ґ��Ƃ��ẮA3���A���őO�̏T�̓����j�����������B���݂̊����ɂ��ē����s�̒S���҂́A28���A�w�����~�܂�C����������Ȃ��x�Ƙb���Ă����B
����A29�����_�ŁA�I�~�N�������̓����܂����d�ǎ҂�108�l�ŁA�a���g�p����13.4���B���ґS�̂ɑ��Ă̕a���g�p����26.2���ɂƂǂ܂��Ă���B
|
�����{ �V�^�R���i 13�l���S �V����4340�l�����m�F �@3/29
���{��29���A�V����4340�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B3�A�x������������T�̓����j���Ɣ�ׂāA3000�l�ȏ㑝���܂����B
����A���{�͍���26����28���ɔ��\����2�l�ɂ��Ď�艺���܂����B����ő��{���̊����҂̗v��78��6559�l�ƂȂ�܂����B�܂��A13�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��4620�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�28������2�l�����āA84�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���܂h�~���d�_�[�u �S��������1�T�� �������ɓ]�����n��� �@3/29
�܂h�~���d�_�[�u�����ׂĉ�������Ă���1�T�ԂƂȂ�A28���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑S���őO�̏T�Ɣ�ׂ�0.86�{�Ɗɂ₩�Ȍ����X���������Ă��܂����A�������瑝���ɓ]����n����o�Ă��Ă��܂��B
NHK�̂܂Ƃ߂�28���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���O�̏T�Ɣ�ׂ�ƁA����21���ɂ܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ18�s���{���̂����A��s����1�s3���ł͓����s��0.88�{�A�_�ސ쌧��0.73�{�A��ʌ���0.93�{�A��t����0.80�{�A���ł͑��{��0.78�{�A���s�{��0.82�{�A���Ɍ���0.81�{�A���C�ł͈��m����0.88�{�ȂǂƂقƂ�ǂŊɂ₩�Ȍ����X���������Ă��܂��B
����ŁA�k�C���ł�0.99�{�Ɖ����Ȗ،��ł�1.03�{�A���ł�1.07�{�ƑO�̏T��葝�����Ă��܂��B
�܂��A�ق��̏d�_�[�u���������ꂽ�n���A�d�_�[�u�̓K�p���Ȃ������n��ł��H�c����1.07�{�A���挧��1.15�{�A�L������1.06�{�A���ꌧ��1.13�{�A�啪����1.20�{�A����������1.33�{�A���ꌧ��1.14�{�ȂǑ������Ă���Ƃ��낪����܂��B
�V�K�����Ґ��͑S���ł͊ɂ₩�Ȍ����X���������Ă��܂����A1�T�ԕ��ςł݂�ƁA���܂��ɋ��N�Ă̑�5�g�̃s�[�N�̂��悻1.7�{�ƂȂ��Ă��܂��B
�����J���Ȃ̐��Ɖ�͐�T�A��Ԃ̔ɉ؊X�̐l�o���d�_�[�u�̉����̒��O����p�����đ����Ă���n�悪����Ǝw�E������ŁA����͉Ԍ���N�x�ւ��̎����̊����}��ȂǁA�����̐l���W�܂�ڐG����@������邱�Ƃ�A�I�~�N�������̂����A�����͂���荂���Ƃ����uBA.2�v�ƌĂ��n���̃E�C���X�ɒu������邱�ƂŁA�������Ăё����ɓ]����\��������Ƃ��Ē��ӂ𑣂��Ă��܂��B
�����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́u�����3�A�x�Ȃǂ̉e���f���āA������������������X���������n�߂Ă���B�d�_�[�u�͉������ꂽ���A�����̑�6�g�͂܂��I����Ă��炸��b�̍ۂɃ}�X�N������A�����ł��Ǐ���ΊO�o���Ȃ��Ƃ������l�̑�̕K�v���͕ς��Ȃ��B�����ɂ��ă��N�`���̒lj��ڎ�̃X�s�[�h�������Ă��Ă���̂ł�����x�X�s�[�h���グ�A�܂��͐ڎ헦���C�M���X��t�����X�ȂǂƓ������x�A5������悤�ɂ��Ă������Ƃ��K�v���v�Ƙb���Ă��܂��B
|
���R���i�����ґ����̒����ɋ~�}�Ȃ̈�t����@���u���o�E���h�ɓ���E�E�E�v�@3/29
���C3���̐V�^�R���i�E�C���X�����҂������̒����������n�߂Ă��܂��B�f�Âɂ������t�́A�����̍Ċg������O���Ă��܂��B
�S���Łu�܂h�~���d�_�[�u�v����������A28����1�T�ԁB���ł́A1��������̐V�K�����Ґ����A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA6���A���̑����B���m���ƎO�d���ł�5���A���ő������Ă��܂��B������������ɁA���É���w�a�@�~�}�Ȃ̎R�{��ǒ��͊�@���������Ă��܂��B
�u���o�E���h�ɓ���v�f�͑����Ă�Ƃ����ӂ��Ɍ�����Ǝv����ł��ˁB������BA2�ƌĂ��I�~�N�����̐V�����^�C�v���������Ă��Ă��邱�ƁA�t�ɂȂ��Ċ����}��Ƃ����Ԍ��Ƃ��A���ꂩ��l�Ɛl���ڐG����@������Ă����܂��B���ɎႢ���𒆐S�ɂł��˂�͂肻���܂Ōx������������ƌ����Ă��Ă���Ǝv���܂��v(���É���w�a�@�~�}�ȁ@�R�{���͈�ǒ�)
�܂��A�܂h�~�̉����̃^�C�~���O�ɂ��Ắc
�u(������)�^�C�~���O�ƁA���ꂩ��l�̈ړ��������ɂȂ�^�C�~���O�A�����āABA2�������Ă���Ƃ�������3�̃^�C�~���O�������Ă��܂��Ă܂��̂ŁA���������Ӗ��ł͂�͂芴���҂��}���ɑ����Ă������X�N������Ẳ����ł͂���Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��ˁB������Ƃ����̂��ɂ߂Ă��܂��ƁA�������������Ă��܂��ɂ���Ƃ������Ƃ��A�܂��F����ɒm���Ă��������Ƃ������Ƃ��ƂĂ��厖���Ǝv���܂��v(���É���w�a�@�~�}�ȁ@�R�{���͈�ǒ�)
�@ |
 |
���V�^�R���i �����Ґ��͂Ȃ����� �u��7�g�v�� �@3/31
1�����ȏ�ɂ킽���Ċɂ₩�Ȍ����������Ă����S���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��͍��T�A�����ɓ]���܂����B�Ȃ��������Ă���̂��A�����āA�����́u��7�g�v���n�܂��Ă���̂��A���������ƂƂ��ɐ��ƂɎ�ނ��܂����B
��1�������Ԃ�ɑ���
�����g��́u��6�g�v�ł�2022�N1���Ɋ����Ґ����}���ɑ����A2����{��1�T�ԕ��ς̊����Ґ���9��3000�l�]��ƂȂ�����A�ɂ₩�Ȍ����������Ă��܂����B�������ANHK�̂܂Ƃ߂ŁA3��30���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑S���őO�̏T�Ɣ�ׂ�1.15�{�ƁA���悻1�������������������瑝���X���ɓ]���܂����B�O�̏T��葝�������n���42�̓s���{���ɏ��܂����B
�����s��1.21�{�A�_�ސ쌧��0.95�{�A��ʌ���1.17�{�A��t����1.07�{�A���{��1.11�{�A���s�{��1.23�{�A���Ɍ���1.11�{�@�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
���ɂ͏H�c����1.35�{�A�O�d����1.47�{�A���ꌧ��1.49�{�A�啪����1.45�{�A����������1.74�{�A���ꌧ��1.36�{�@�ȂǂƋ�B�𒆐S�ɑ����̕�����r�I�傫���Ȃ��Ă���Ƃ��������܂��B
���������ł�3��30���A����̊����Ґ���776�l�ƁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�����̑����̗v����
�ǂ����č��A�����Ґ��������Ă��Ă���̂��B3��30���ɊJ���ꂽ�����J���Ȃ̐��Ɖ�ŗv���Ƃ��Ďw�E���ꂽ�̂��A3��19�������3�A�x��A�N�x�ւ��ɂ�鑲�ƃC�x���g�⊽���}��ȂǂŐl�Ƃ̐ڐG�@����������ƁA�܂h�~���d�_�[�u��3��21���������ɉ�������Ĉȍ~�A�S���I�ɖ�Ԃ̔ɉ؊X�̐l�o�������Ă��邱�Ƃł��B�����āA�����������Ƃɔ�����20��̊����Ґ����������A���Ɉ��H�X�ł̊����̊����������X���ɂ���Ƃ��Ă��܂��B������������20��ł̊��������́A����܂ł������g�傪�N���鏉���Ɍ����A�������畝�L������Ɋ������L����X�������邽�߁A���ӂ���K�v������Ƃ��Ă��܂��B�܂��A���̈���ŁA��앟���{�݂��Ë@�ւł̍���҂̊������܂������Ă���Ƃ��Ă��܂��B
����7�g�H
���Ɖ�͌�������������3�A�x�̉e���ŁA3�����{�ł͑O�̏T�Ɣ�ׂāA���l�㑝���Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃɒ��ӂ��K�v�Ƃ͂��A���̑����X���������̍Ċg��A���o�E���h�ɁA�Ȃ���Ȃ����A��������K�v������Ƃ��Ă��܂��B����̐V�K�����Ґ��́A��6�g�̃s�[�N���甼�������Ƃ͌����A2021�N�Ă̑�5�g�̃s�[�N��2�{�߂��ɏ���Ă��܂��B���܂͂܂���6�g�̂��Ȃ����Ƃ����w�E������A���̂܂܁u��7�g�v�ɂȂ�ƁA����܂ł����傫�Ȋ����g��ɂȂ邨���ꂪ����Ɛ��Ƃ͎w�E���Ă��܂��B���Ɖ�̘e�c���� ������3��30���̋L�҉�Łu20��Ŋ����҂����������n�߁A���H�X�ł̊����̊����������Ă���B�܂��A��������Ō����̗z�������オ���Ă��邱�ƂȂǁA���o�E���h�̒������n�߂Ă���\��������B�����A���́A�����̊g����ɓ������Ƃ܂ł͌�����ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B�܂��A���Ɖ�̃����o�[�ō��ۈ�Õ�����w�̘a�c�k�������́u���܂��ɉߋ��ɂȂ��K�͂̊������N���Ă���Ȃ��ō�����g�傪�����A��6�g��荂���g�����邱�Ƃ��z�肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ǝw�E���Ă��܂��B
������͂ǂ��Ȃ�̂�
����̊����ɂ��Đ��Ɖ�́A������������v���Ɨ}������v��������A���̃o�����X�łǂ��炪�D���ɂȂ邩���e������Ƃ��Ă��܂��B����������v���Ƃ��Đ��Ɖ�́A��Ԃ̔ɉ؊X�̐l�o�̑����ƃI�~�N�������̂����A����Ɋ����͂������Ƃ����uBA.2�v�ւ̒u�������������Ă��āA������}������v���Ƃ��āA3��ڂ̃��N�`���ڎ헦�����サ�A����ɂ���܂łɊ������čR�̂����l�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ�A�C�����㏸���A���C���₷���Ȃ邱�Ƃ������Ă��܂��B
�������v��1 �u��Ԃ̔ɉ؊X�̐l�o�����v
�V�^�R���i�E�C���X�̓}�X�N�Ȃ��ł̉�b�Ȃǂ�ʂ��Ċ������L���邱�Ƃ���A��Ԃ̔ɉ؊X�̐l�o�������������Ɗ������g�傷��p�^�[�����J��Ԃ���Ă��܂����B�d�_�[�u�̉�����A��Ԃ̔ɉ؊X�̐l�o�͂����ނˑS���I�ɑ������Ă��܂��B���̒��ŁA�����������ȎႢ����̊����������Ă��Ă��āA�����ҏ����W������J���Ȃ̃V�X�e���uHER�|SYS�v�̃f�[�^�ɂ��܂��ƁA�V�K�����Ґ��ɐ�߂�20��̊����͑S���ł�2���ȍ~��13���قǂ������̂�3�����{�ȍ~�͏��X�ɏ㏸���A16������17���قǂƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���݁A�l��������̊����Ґ����ł��������ꌧ�̃f�[�^�ł́A20��̊����Ґ��͍���27���܂ł�1�T�ԂőO�̏T�Ɣ�ׂ�4���������A�S�̂ɐ�߂銄���ł͂��悻22���ɏ���Ă��܂��B
�������v��2 �u�wBA.2�x�ւ̒u������v
�I�~�N�������̂����A����Ɋ����͂������Ƃ����uBA.2�v�ɒu�������ƁA�����̑����ɂȂ��邨���ꂪ����Ǝw�E����Ă��܂��B���������nj������ɂ��܂��ƁA���Ԃ̌����@�ւōs��ꂽ�R���i�E�C���X�̌������ʂł́uBA.2�v��3��7�������1�T�Ԃ�20���O����߂Ă��āA���T3��28������̏T�ɂ͂��悻60���A4��25������̏T�ł�90���]��ɒB����Ɛ��肳��Ă��܂��B�C�M���X�Ȃǂł́ABA2�ւ̒u�������Ŋ����������ɓ]���A�d�ǎ҂�S���Ȃ�l�̐����������Ă���Ƃ��Ă��܂��B
���}���v��1 �u3��ڂ̃��N�`���ڎ헦�̌���v
3��ڂ̃��N�`���ڎ헦�́A2022�N1�����{�̒i�K�ł́A65�Έȏ�̍���҂ł��ڎ헦��1���ɂ������Ȃ��ł������A3��31���̎��_��65�Έȏ�̍���҂ł�80�����Ă��āA�l���S�̂ł�40�����A����A�Ⴂ����ł�����ɐڎ킪�i�ނ��Ƃ����҂���Ă��܂��B�����w�Ȃǂ��s���������ł́A�V�^�R���i�E�C���X�ɑ��郏�N�`����3��ڐڎ�Ŕ��ǂ�\�h������ʂ̓I�~�N���������L�����������ł�68.7���Ɛ��v����A���Ɖ��3��ڐڎ�ɂ���ėL����������Ƃ��Ă��܂��B����ɁA��6�g�Ŋ������傫���g�債���n��ł͐V�^�R���i�E�C���X�ɑ���R�̂����l�������x���āA����̊����g�傪�}�����邱�ƂɂȂ���\��������Ǝw�E���Ă��܂��B
���}���v��2�u�C���̏㏸�Ŋ��C���₷���v
�V�^�R���i�E�C���X�́A��ɔ�܂�u�}�C�N����܂v��u�G�A���]���v�ƌĂ�閧���ꂽ������Y���A���������Ȕ�܂�ʂ��Ċ������邽�߁A���C���d�v�ȑ�ƂȂ��Ă��܂����B���Ɖ�͍���A�C���̏㏸�ň��H�X�ȂǂŊ��C���₷���Ȃ邱�Ƃ�A�����ʼn߂������Ԃ����邱�Ƃ������g���}������v���Ƃ��čl������Ƃ��Ă��܂��B���Ɖ�́A�������������̑����v���Ɨ}���v���̕ω��������ɉe������Ƃ��Ă��āA������}���邽�߂ɂ́A���N�`���̒lj��ڎ�𒅎��Ɏ��{���邱�Ƃ�s�D�z�}�X�N�̐��������p�A���ł⊷�C�A���������Ƃ�������̓O�ꂪ�K�v���Ƃ��Ă��܂��B
�����Ƃ�
���ۈ�Õ�����w�̘a�c�����́u�Ⴂ����ł̃��N�`���lj��ڎ������ɐi�߂�ȂǁA�����̗}���Ɍ��ѕt���v�f���ǂ����}���ȑ������}������\��������B�lj��ڎ����@������A�Ȃ�ׂ������Ăق����B�̂ǂ̒ɂ݁A���M�ȂǑ̒��������ł����������Ƃ��ɂ͊������Ă���ƍl���Đl�Ɖ��Ȃ��悤�ɂ��Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B�����āA����̔����ɂ��Ắu�ǂ����̃^�C�~���O�ő�7�g�����邱�Ƃ�O��Ƃ����������K�v���B���Ɉ�ʂ̈�Ë@�ւł́A������a�C�Ŏ��Â��K�v�Ȋ��҂��R���i�Ɋ������Ă��Ă��Ή��ł�����𐮂��邱�Ƃ����ɏd�v���B�����̂Ƃ���őΉ����ł����]�@���܂܂Ȃ�Ȃ���~�}����������Ȏ���������Ă��āA���ꂪ��ʈ�Â̂Ђ����ɒ�������B��6�g�̋��P�܂��A�n�悲�ƂɈ�Ñ̐��̍ē_���Ɛ������}���K�v������v�Ǝw�E���Ă��܂��B�܂��A���Ɖ�̘e�c�����́u������ɂ͂��܂��܂Ȉӌ�������Ǝv�����A����܂œ��{�ł͏d�ǎҐ��⎀�S�Ґ������炷���߈�ÂɂЂ����̒�����Α���Ƃ��Ă����B�����A�s���������s���ƌo�ςւ̃_���[�W���傫���B�d�_�[�u�Ȃǂ��o����Ă��Ȃ�����ł́A�o�ϊ����͗}�������Ɋ������X�N�������s����3��ڂ̃��N�`���ڎ�Ȃǂ̑�������������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B�l�I�Ȉӌ������A����A�������g�債�Ĉ�Â̂Ђ������m���ɋN����Ƃ����悤�ȏꍇ�͊�����}����K�v���ƍl���Ă���B���̏ꍇ�́A���܂��܂ȊW�҂���������ƍ��ӂ����Đi�߂Ă����ׂ����v�Ƙb���Ă��܂��B
|
���R���i�����ҁA37�s���{���őO�T����c���[�����u���o�E���h�������v �@3/31
���슯�[������31���̋L�҉�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��������X���ƂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��āA�u���o�E���h(�Ċg��)�ɂȂ��邩�A�����𒍎����Ă����K�v������v�Əq�ׁA�x�������������B
���쎁�́A�u���炭�͍ő���̌x����ۂv�Ƌ������A�u��6�g�v�ŋ���������Ò̐����ێ�����l�����d�˂Ď������B�A�E��i�w�Ȃǂő����̐l���W�܂�@������邱�Ƃ���A�u�������X�N�̍����s�����T���A�}�X�N�̒��p�A��A3���̉���Ȃǂ̊�{�I�Ȋ����h�~��̓O������肢�������v�ƌĂт������B
�����J���Ȃɂ��ƁA�S���̐V�K�����Ґ��́A29���܂ł�1�T�Ԃł݂�ƁA�O�T��1�E04�{�ƂȂ�A37�s���{���őO�T���������B
|
���u�܂h�~�v�����Ŗ�̊X�͊��C���u�X�e���X�I�~�N�����v�ŃR���i�g��7�g�h���@3/31
3��31���ɓ����s�Ŋm�F���ꂽ�A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�8226�l�B5���Ԃ�ɑO�̏T�̓����j��������������A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�������Ĉȍ~�A���~�܂�̌X���������Ă���B�V�N�x��ڑO�ɍ��܂�A�h��7�g�h�ւ̊�@���B30���ɂ́A�����J���Ȃ̐��Ɖ���s��ꂽ�B
�����J���� �A�h�o�C�U���[�{�[�h �e�c���������F�@���o�E���h�̒������n�߂Ă���\���͂���Ƃ����ӂ��ɍl���܂�
29���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��́A�O�̏T�Ɣ�ׂ�37�s���{���ő��������B�S���̊����Ґ����O�T���1.04�{�ƁA2����{�ȗ��A��1�J���Ԃ�ɑ����ɓ]�����B
�����̎嗬�́A�]���̃I�~�N���������������͂������Ƃ����uBA.2�v���X�e���X�I�~�N�����ɁB���������nj������̐��v�ł́A���T���ɂ��X�e���X�I�~�N�����̊�����6���ɒB����Ƃ��Ă���B
�e�c���������F�@���ꂩ��A���Ԍ��A�Ӊ���A�����}��Ȃǂ̎������}���Ă���܂��̂Łc
���g�܂h�~�h�����Ŗ�̊X�͂ɂ��킢
�d�_�[�u�����������10���B�N�x�����}�����A��̓����E�V���̏ē��X�́A�Ƒ��A���E��̍��e��Ȃǂłɂ�����Ă����B
�E��̍��e��ŗ��X�����l�F�@�Г��̍��e��Ȃ�ł����ǁA�u�܂h�~�v���͂���ĂȂ������̂�(�[�u��)�����Ă���Ƃ�ꂽ�Ƃ�������
�X�����q�����������Ǝ������Ă����B
�ē��z����������� �V���X �؉��ʍؓX���F�@�X�[�c�́gTHE�E�V���h�݂����ȕ��������������Ă�ȂƁB���N�́u�܂h�~�v���ƍ����ׂ�Ȃ�A4�`5�{�͌��\�ς������Ȃ����ȂƎv���Ă܂�
�u�܂h�~�v�������A���C�����߂�����̊X�B
���ʉ�A��̐l�F�@with�R���i�ŃR���i�ƈꏏ�ɐi��ł����܂��B�R���i�ƌ���g��ł��������Ȃ��炢��
����ŊX�����n���ƁA�m�[�}�X�N�Łg�O���݁h������l�����Ȃ��Ȃ��B�����҂������Ă��邱�Ƃɕs�����Ȃ��̂����ƁA�u�S���Ȃ��ł��ˁv�u���ꂽ�Ƃ��������v�Ƃ��������������B
�����S����c�q�ǂ��̊����ɕs�����L����
�����̃��o�E���h�����O����钆�A�����ł�3��20���A10�Ζ����̒j�̎q���A����ňӎ��s���ƂȂ�A�~�}�������ꂽ�����S�B���̌�̌����ŁA�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B�����ł́A���t�̎��������������Ƃ������������A���O�ɂ͊�b����������Ƃ͒m��Ȃ������Ƃ����B3��31���̓s�S��5�����݂̗z�C�ƂȂ����B�O�o�������鎞�����}���A�q�ǂ��̊����ɕs�����L����B���s�̑����t�@�~���[�N���j�b�N�ł́A4�̒j�̎q��PCR�������Ă����B���M�O������f����4�����q�ǂ����Ƃ����B�N���j�b�N�̉@���͂����b�����B
�����t�@�~���[�N���j�b�N �勴�����@���F�@10�Ζ����̂��q����ł����ˁB���킶��ƍ������Ă��Ă�Ƃ����̂��������Ă܂��B��7�g�����錜�O�Ƃ����̂́A���͂���Ǝv���܂�
5����11��ΏۂƂ������N�`���ڎ�ɂ��āA���̃N���j�b�N�ł�30�l�قǂ̗\��g��20���قǂŖ��܂�Ƃ����B����ŃI�~�N�������ł́A�q�ǂ��̎��S��ɂ��Ắc�B
�勴�����@���F�@���q����ŏd�lj�������́A���̂Ƃ���A�I�~�N�����ł͋ɂ߂ď��Ȃ��̂�
�I�~�N�������ł̎q�ǂ��̎��S��́A���E�I�ɂ������Ȃ����߁A�ߓx�ɋ���Ȃ��悤���ӂ𑣂����B |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���I�~�N�����u�a�`�E2�v���� ����52���A����38���c�u�����S����9���v���v �@4/1
�����s��31���A�s���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂̂����A�I�~�N�������̌n���̒��ł������͂������Ƃ����u�a�`�E2�v�̋^���Ɣ��肳�ꂽ������52�E3���܂ŏ㏸�����Ɣ��\�����B���{�ł��A38�E5���ɑ����Ă���B�����A���̐V�K�����҂͑����X���ɓ]���Ă���A�a�`�E2�̊g�傪����Ƃ݂���B
�s��1�����ȍ~�A�ꕔ�̊����҂̌��̂ɂ��Ăa�`�E2�^���ʂ���o�b�q���������{���Ă���B����1�T��(3��15�`21��)�ł́A��������833���̂�����������427�����a�`�E2�^���Ɣ��肳�ꂽ�B�O�T��39�E6���A�O�X�T��17�E8���ŁA����܂Ŏ嗬�������u�a�`�E1�v����̒u������肪�}���ɐi��ł���B
���{�ł��A3��21�`27����1�T�Ԃ̌�������122���̂���4���߂�47�����a�`�E2�^���ŁA�O�T��18�E2������啝�ɏ㏸�����B
�a�`�E2�̊����͂́A�a�`�E1����1�E2�{�قNj����Ƃ����B
�����J���Ȃ̎����ɂ��ƁA�S���̂a�`�E2�̊����́A2����10���������������A3��14�`20���ɂ�21�E4���ɏ㏸�����B���������nj������́A4����1�T�ɂ͊����҂�60���A5����1�T�ɂ�93���ɒB����Ƃ̐��v�������Ă���B
���{���ł́A�u�܂h�~���d�_�[�u�v��3��21���̊����ʼn�������A���o�E���h(�����Ċg��)�̒��݂���B1�T�Ԃ��Ƃ̐V�K�����Ґ����݂�ƁA3��23�`29���͑O�T���1882�l����2��5678�l�ƂȂ�A7�T�ԂԂ�ɑ����ɓ]�����B
�N��ʂł́A70�Έȏ�̊�����1�����O�Ɣ�ׂ�4�E6�|�C���g���Ȃ�5�E2���Ɍ��������̂ɑ��A20�`30�Α��5�E9�|�C���g����32�E8���ɑ������Ă���B
3�`4���͉Ԍ��⊽���}��ȂNJO�o�@������鎞���ŁA�{�́A�Ⴂ���オ�����ɓ����ƈ�C�Ɋ������L���肩�˂Ȃ��Ƃ݂āA�x�������߂Ă���B
�����������{�̓Ǝ���u��ヂ�f���v�́A�a���g�p����3��29����7���ԘA����50�������ƂȂ�A�u�ԐM���v����u���M���v�Ɉڍs�������������A���ʂ́u�ԐM���v��_��������B
|
�������V�K�����ґ��ŐV�^�R���i��7�g�ɓ˓���������A�I�~�N�����uBA.2�v�@4/1
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂��}�����Ă���B30���̓����s�̐V�K�����҂́A��T�̐��j�����3090�l�������A9520�l�������B��T���j��(6430�l)��1.5�{�ł���B31����5���Ԃ�ɑO�̏T�̓����j���̐V�K�����Ґ�������������̂́A8226�l�̊����҂����\���ꂽ�B
1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���31�����_�ŁA�O�̏T�Ɣ�ׂ�118.5���ɖc���ł���B�z������32.0���ƍ����BWHO(���E�ی��@��)�͊�������f����ڈ��Ƃ��ėz�������u5�������v�Ƃ��Ă��邩��A�ُ�Ȑ��l���B�}���Ɋ����҂������Ă��邩�A������������Ȃ��\���������B
�u�܂h�~���d�_�[�u�v��21���ɉ������Ă���A������1�T�Ԃł̃��o�E���h�B���̂܂ܑ����ɓ]���Ă��܂��̂��B��ÃK�o�i���X�������������̏㏹�L��(���Ȉ�)�͂��������B
�u��7�g�ɓ˓������\��������܂��B��N�����̎����ɐV�K�����҂������Ă��܂��B�����A�t�̗��s�͒ʏ�A�R���������̂ŁA�傫�ȗ��s�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�S�z�Ȃ̂́A�����͂̋����I�~�N�����gBA.2�h���嗬�ɂȂ���邱�Ƃł��v
�I�~�N�����uBA.2�v�́A����܂Ŏ嗬�������I�~�N�����uBA.1�v�ɔ�ׂĊ����͂�26���������Ƃ����B4�����ɂ́A�����̎嗬���́uBA.2�v�ɒu�������Ɨ\������Ă���B���łɃf���}�[�N�Ȃǂł͎嗬�����uBA.2�v�ɒu������芴�����Ċg�債�Ă���B
�������A���{�͂��ꂩ��V�N�x���}���A�Ԍ�����w���Ȃǐl���������ɂȂ��Ă�������A�����Ƃ����ԂɊ������L���鋰�ꂪ����B
�����h�~�̃J�M�́A�Ƃɂ������C���悭���邱�Ƃ��B�悤�₭�u���������nj������v��28���A��C����(�G�A���]������)���邱�Ƃ��z�[���y�[�W�ŔF�߂��悤�ɁA��C��������Ȋ����o�H�ɂȂ��Ă��邩�炾�B
�uWHO�͈ȑO����A��Ȋ����o�H�Ƃ��ăG�A���]�������Ɣ����������Ă��܂����B�Ȃ̂ɁA���E����x�ꂽ�����������́A�G�A���]�������ɂ͔ے�I�ł����B�G�A���]��������O��ɂ���A����ς��܂��B��h�~���邱�Ƃ��K�v�ł����A���C��O�ꂷ�邱�Ƃ��厖�ł��v(�㏹�L��)
���̂܂܂ł́A�S�[���f���E�C�[�N���u�܂�h�v�̉��ʼn߂������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
|
�����ŃR���i�����҂������X���@������1.2�{�uBA.2�v�֒u�������@4/1
���{��4��1���A�V����3670�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̋��j���̊����Ґ��́A3782�l�ł����B
���{���ł́A������34�l�̎��S���m�F����܂����B�y�ǁE�����ǂ̕a���g�p��(����)��29.9���ŁA�d�Ǖa���g�p��(����)��14.7���ƂȂ��Ă��܂��B
���{��1�T�Ԃ̊����Ґ����v������ƁA��T�A3��19������3��25����2��2245�l�ł������A���T�A3��26������4��1���܂ł�2��4537�l�ƁA�����X���ɓ]���Ă��܂��B�����X���ɓ]���Ă���v����1�Ƃ݂��Ă���̂��A�]���̃I�~�N�������ɔ�ׂĊ����͂�1.2�{�Ƃ����A�I�~�N�������ւ̈���A�uBA.2�v�ւ̒u�������ł��B
���{�̊����҂̂����uBA.2�v�̋^���Ɣ��肳�ꂽ�����́A3��14������20���̊��Ԃł�18.2���ł������A����3��21������27���̊��Ԃ�38.5���܂ŏ㏸���Ă��܂��B
����̓����ɂ��č��������nj������́A�u5��1�T�ɂ͑S����93�����u�������v�Ɛ��v���Ă��܂��B
|
���t���ŏ��̃R���i�����ҁA��c���q�������z���c�t�c���Ȃ�����×{ �@4/1
���t�{��1���A��c���q�������V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1�����ɔ��M���o�����ߊt�c�����Ȃ��A�o�b�q�����ŗz���Ɣ��������B�t���̃R���i���������������̂͏��߂āB���t�{�ɂ��ƁA���{�W�҂ɔZ���ڐG�҂͂��Ȃ��Ƃ����B��c���͌���������߁A����×{���Ă���B
����c���̊�����45�l�ځB��c���̊����ɔ����A���{��������ł̐�����ڎw���u���ǂ��ƒ뒡�v�̐ݒu�@�Ăɂ��āA�^�}��7���̐R�c������}���ɒ�Ă��Ă������A��c���̕��A��ɂ��ꍞ�ތ��ʂ��ƂȂ����B
|
���I�~�N�����h���^�uBA.2�v�A���E�Ŏ嗬�@�č��ʼnߔ��Ɂ@4/1
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂̂����A�I�~�N�����^�̔h���^�uBA.2�v�̔䗦���}���ɍ��܂��Ă���B����܂ŃA�W�A�≢�B�ő����������Ă������A�č��ł������҂̔��������B���N�`���ڎ킪�i���Ƃ����莀�S���͗}�����Ă��邪�A�ʂ̕ψٌ^���m�F����Ă���B�e���͊�����ƌo�ϊ����̐��퉻�̗�����͍����Ă���B
�ăX�N���v�X�������̌����҂炪�܂Ƃ߂�f�[�^�x�[�X�uOutbreak.info�v�Ȃǂɂ��ƁA�C���h�ł͂��łɐV�K�����̂��ׂĂ�BA.2�ɒu����������B�p����x�g�i����9�����A�č���55%�A���{�ł�45%���߂Ă���B�d�lj��̂��₷���͏]���̃I�~�N�����^�Ƃ��܂�ς��Ȃ��Ƃ���邪�A�����͂��������������B
���E�ŐV�^�R���i�̊����Ґ��������������A���S���͒Ⴂ�����ɗ}�����Ă���B�V�K�̎��S�Ґ��������Ґ�(�Ƃ���7���ړ�����)�Ŋ����Ď��S�����Z�o����ƁA�č���2%���邪�A���{��p���Ȃǂł�1%�������Ă���B���N�`���ڎ킪�i�ق��ABA.2���܂߂��I�~�N�����^�̏d�lj������Ⴂ���߂��B
�č��ł�BA.2���嗬�ɂȂ����A�Ď��a��Z���^�[(CDC)�́A���㐔�T�Ԃő啔�����߂�悤�ɂȂ�Ɨ\������B�������X�L�[�����́u�]���^�����킸���Ɋ����͂��������̂́A���N�`����lj��ڎ킪�L�����B�]���^���d�lj����邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ǝw�E�����B
CDC�ɂ��ƁA����29���̐V�K�����Ґ�(7���ړ�����)�͖�2��5000�l�A�V�K���Ґ�����640�l�ƁA���ꂼ���N�Ĉȗ��̒ᐅ���ɂƂǂ܂�BBA.2�̊����䗦�����܂钆�ŁA����̓������œ_�ɂȂ�B
�o�C�f���哝�̂�30���̋L�҉�ŁABA.2�̊����g��ɂ��Č��y�������̂́u�p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�͐V���ȋǖʂ��}���Ă���A�������͐V�^�R���i�ɐ������x�z����Ȃ��Ȃ�B�l�X�����c�[��������v�Ƌ��������B�č��ł�29���A�t�@�C�U�[�ƃ��f���i�̐V�^�R���i���N�`���ɂ���50�Έȏ��Ɖu�s�S�̐l��Ώۂ�4��ڐڎ�(2��ڂ̒lj��ڎ�)���F�߂�ꂽ�B
�ꕔ�̎��Ö�ɂ��Ă͌��ʂ̒ቺ���݂��Ă���B�ĐH�i���i��(FDA)�́A�p�O���N�\�E�X�~�X�N���C��(GSK)�̍R�̖�u�[�r���f�B(�\�g���r�}�u)�v��BA.2�ւ̌��ʂ����҂ł��Ȃ��Ƃ��āABA.2�������Ґ��̉ߔ����߂�n��ł̏��F�����������B30���܂łɃj���[���[�N�B��J���t�H���j�A�B�A�}�T�`���[�Z�b�c�B�Ȃǂ����[�u�̑ΏۂƂȂ����B�\�g���r�}�u�͓��{�ł����F����Ă���B
BA.2�Ƃ͕ʂ̕ψٌ^�u�f���^�N�����v���ĉ��Ȃǂő������������Ă���B�����҂̑̓��Łu�f���^�^�v�Ɓu�I�~�N�����^�v��2��ނ̃E�C���X�̈�`�q�z�������Đ��܂ꂽ�B
���ƂɂȂ����ψٌ^�̖��O��g�ݍ��킹�����̂ŁA���E�ی��@��(WHO)�Ȃǂ������ɖ��������킯�ł͂Ȃ��B�p����t�����X�A�I�����_�A�f���}�[�N�Ȃǂ��班�Ȃ��Ƃ����\���̃f�[�^������Ă���B
�e���Ƃ����ۑ��s���K�����ɘa����Ȃǂ��Čo�ς�Љ���̐��퉻��ڎw���Ă���B�E�C���X�͕ψق��J��Ԃ����߁A������ɂ��ڔz�肷��K�v������B�����̋��͂ȕψٌ^�̏o���ɔ����邽�߂ɂ��A�Q�m����͂Ȃǂ̍��ۓI�ȊĎ��̐��̐������K�v�ɂȂ�B
|
�����S�ݓX4�� 3���̔���グ�O�N����������@�q���� �@4/1
�܂h�~���d�_�[�u�̉����Ȃǂ��A�S�ݓX�̔��オ���X�ɉ��Ă���B
���S�ݓX4�Ђ�3���̔���グ�̑���l�́A���N�̓������Ɣ�ׂāA��ۏ��≮�S�ݓX���P���Ɏ���J. �t�����g ���e�C�����O��6.8���A��������6.1���A�O�z�ɐ��O�z�[���f�B���O�X��8.3���A�������E������3.6���A���ꂼ�ꑝ�����B
���O�W���A���[�u�����h�����i�Ȃǂ̔��オ���������D�����������Ƃɉ����A�d�_�[�u���������ꂽ���Ƃ��A���X�q��������ɑ��������ƂȂǂ��v���Ƃ��Ă���B
|
 |
�������s �V�^�R���i �V����7395�l�����m�F �O�T�Ƃقړ����� �@4/2
�����s����2���̊����m�F��7395�l��1�T�ԑO�̓y�j���Ƃقړ��������ƂȂ�܂����B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ4�l�����S�����Ɣ��\���܂����B
�����s��2���A�s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v�܂ł�7395�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j���Ƃقړ��������ƂȂ�܂����B�܂��A2���܂ł�7���ԕ��ς�7622.4�l�ŁA�O�̏T��121.5���ł����B100������̂�5���A���ł��B
2���Ɋm�F���ꂽ7395�l��N��ʂɌ���ƁA�u20��v���ł������A�S�̂�21.5���ɂ�����1587�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�365�l�őS�̂�4.9���ł����B����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A2�����_��1�����2�l������32�l�ł����B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ60�ォ��90��̒j�����킹��4�l�����S�����Ɣ��\���܂����B
|
���u�V�N�x�̊������Ȃ��c�v �R���i�����ҍĂё����A���}��l�̏t�@4/2
�V�N�x���}�������j����1����A�������s�̊��y�X��Ԍ��X�|�b�g�̐l�e�͂܂炾�����B�����ł͍��T�A�V�^�R���i�E�C���X�����Ґ��̉ߋ��ő��X�V�������A�����̊�Ƃ����}������l���Ă���Ƃ݂���B�q���̏��Ȃ����H�X��K�˕����ƁA�u���̏t�͎d�����Ȃ��v�ƒQ���̐����R������A�s���̃R���i�Ή��ɋ^��̐��������ꂽ�B
���������������ߌ�7�������A�V���ق̕����ʂ���ӂ�1���ԂقǕ������B�X�[�c�p�̋q�͂قڌ������炸�A�Ăэ��݂̏]�ƈ������Ȃ��B�莝�������������ɂ��Ă����������̃X�^�b�t�́u��T�͂����������������B�R���i����C�ɑ������e�����o���v�Ƙb���B
������̋������ɓ������B��25�Ȃ̓X���ɋq�͒j��2�l��1�g�����B�X��(61)�́u�����҂��������āA���}��Ȃ��Ȃ�͎̂d���Ȃ��B�V�N�x���Ċ����͂��Ȃ��v�Ƃ��ߑ������B
���̌�40���Ԃŗ��X�����̂́A2�g�v3�l�B�u���ꂾ���q�����Ȃ��Ȃ�x�Ƃ��ċ��t�������炤���������B���ɂ͂͂����肵���Ή������Ăق����v�ƓX��B�u�ʏ�͐V���Ј��̌��C���I������犽�}��낤���ǁA���҂ł��Ȃ��ˁv
�X���o��ƁA�����ʂ�̉��������������Ă����B1������I�����l�������낤���B������2�l�ŕ����Ă������N�̒j����Ј��Ɂu���݉�ł����v�Ɛ����|����ƁA�u�H�������v�ƕԂ��Ă����B�Г��ň��݉�֎~����Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ����B�u���}��͉������邵���Ȃ����ǁA�o�ϊ������~�߂�̂̓�����������v�B���������A���̓X��T���Ė�̊X�ɏ����Ă������B
�s���c�̋q�̉���l�����߂�b�ː�͔ȁB�����ƂȂ�A�X���ɂЂ�����Ƃ炳�ꂽ�\���C���V�m���A���Ȃ��Ԍ��q���}���Ă����B
�x���`��Ő��ɂ́A3�A4�l�ŕٓ�����ݕ����L�����҂�Ƒ��A�ꂪ����ق�B��w����̗F�l��3�l�ŖK�ꂽ�s����20�㏗���́u���l���E�Z���Ԃƌ��߂āA���N�Ԃ�ɗ����B���H�X���ʏ�c�Ƃ��Ă��钆�ʼnԌ������������̂͋^�₪����v�Ɩ��J�̖�������グ���B�@ |
 |
���V�K�����Ґ����đ����ɓ]����@��7�g�̋K�͂�}���邽�߂ɂł��邱�Ƃ́H�@4/3
2����{���s�[�N�ɐV�K�����Ґ��͊ɏ��Ɍ������Ă��܂������A�N�x������ōđ����Ɍ���������܂��B��7�g�̋K�͂�}���邽�߂ɁA���㎄�������C������ׂ����Ƃɂ��Ă܂Ƃ߂܂����B
���S���̐V�K�����Ґ����đ����ɓ]����
�S���̐V�K�����Ґ��́A���߂�1�T�Ԃł�10���l�������240�l�ŁA���T��T�䂪1.04�ƂȂ�A�����X���ƂȂ��Ă��܂��B��s���A�����A�������A���̑��̒n��̂�����ł����l�̌X���ƂȂ��Ă���A����̂���Ȃ鑝�������O�����Ƃ���ł��B
�Ȃɂ��̊ԈႢ�ő������킯�ł͂Ȃ��A���ۂ̗��s�f����w�W�ł��錟���z������ڐG�s���Ґ��E������Ƃ������w�W�������s����{�ōđ������Ă���A���o�E���h�̉\�����������ł��B
�܂��e�n���20��E30��Ƃ���������̐V�K�����҂ɐ�߂銄�����������Ă��邱�Ƃ��A����܂ł̗��s�J�n�̏Ɠ��l�ł��B�u��7�g�ւ̔����v�Ƃ����L���ł������܂������A��6�g�̓s�[�N���߂�������A��5�g�̌�̂悤�ɂ͋}���ɂ͌��肫�炸�A�������x�͔��Ɋɖ��ł��B����́A�I�~�N�������ɑ��Ă̓��N�`���ɂ�銴���\�h���ʂ������Ă��芴���̘A����f���Ƃ�������ƁA��6�g�ł�10��ȉ��̎Ⴂ����ł̊����҂����������`�d���ێ�����Ă��邱�ƂȂǂ������ƍl�����܂��B�����ɁA
�E�܂h�~���d�_�[�u�̉���
�E�N�x���E�N�x�n�߂̃C�x���g�Ɋ֘A��������
�E�I�~�N������BA.2�̊g��
�Ƃ������v��������邱�Ƃōđ����Ɍ������Ă�����̂ƍl�����A���̂܂ܑ�7�g�̗��s���n�܂��Ă��܂��\�����������ł��B
����7�g�̋K�͂����������邽�߂ɂł��邱�Ƃ́H
�u���������A��6�g���I������Ǝv�����������7�g�Ƃ������Ă�̂���E�E�E�������E�Ȃ��ǁI�v�Ǝv���Ă�����������Ǝv���܂��B���ۂɁA��6�g�̒v�����͂���܂łƔ�r���čł��Ⴍ�Ȃ��Ă���A�l�l�ɂƂ��Ă̏d�lj����X�N�͒Ⴍ�Ȃ��Ă��Ă��܂��B���܂ł��u��H�_���IStay Home�I�v�Ƃ������Ă�i�K�łȂ��Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
����ŁA��6�g�̎��S�Ґ��͉ߋ��ő�ƂȂ�܂����B�S���Ȃ�l�̊��������������̂́A�ꐔ�ƂȂ銴���҂̐������|�I�ɑ������������߁A���̂悤�Ȍ��ʂƂȂ��Ă��܂��܂����B���ɍ���҂ɂ����鎀�S�҂����������Ƃ���A����͂����̏d�lj����X�N�̍������X�ւ̑�ɏd�_���u����邱�ƂɂȂ�܂��B��7�g�ɔ����Ċe�n��ł͍���ҁE��b�����̂�����̃u�[�X�^�[�ڎ��A����Ҏ{�݂̑���i��ł͂��܂����A��͂芴���Ґ����ǂ��܂ł����������邱�Ƃ����e�ł���ɂ͂܂������Ă��܂���B
���́A��͂�V�K�����Ґ����\�����肫��Ȃ��܂܍đ����ɓ]���Ă��邱�Ƃł��B����1��40000�l�ȏ�Ƃ����V�K�����Ґ��́A2021�N8���̑�5�g�̃s�[�N�ł�������25000�l���������Ƃ��납�瑝���Ɍ������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���傤��BA.1����BA.2�ւ̒u�������Ɠ����^�C�~���O�ōđ����Ɍ������Ă���A��6�g�ȏ�̗��s���N����\�������O����܂��B
�ł������Љ�@�\���ێ����Ȃ��獡��̗��s�̋K�͂����������邽�߂ɂ́A�����n���̂��銴��������̂�������p���I�ɍs���Ă������Ƃ��d�v�ł��B�قƂ�ǂ̊����҂͒N�ɂ������������ɉ��Ă������ŁA�ꕔ�̐l����������̐l�Ɋ��������ăN���X�^�[�������Ă���̂��A���̐V�^�R���i�̓����ł��B���́u1�l���炽������̐l�v�ւ̘A���������邱�ƂŁA�����҂̋}���ȑ����Ɍq����܂��B���Ƀ}�X�N���O���Ē����ԁA��������̐l�����H���s���悤�Ȋ��}��̂悤�ȏ�͂����������������₷���Ȃ�܂��B�e�����̂ɂ���ă��[�����قȂ�܂����A�Ⴆ�Α��{�͈ȉ��̂悤�Ȋ���������肢���Ă��܂��B
���ɁA�����}��A�Ӊ���A������Ƃ��Ȃ��Ԍ��A�Ȃǂ̊������X�N�̍�����H�ł͊����h�~���O�ꂷ�邱��
�E����e�[�u��4�l�ȓ�
�E2���Ԓ��x�ȓ��ł̈��H
�E�}�X�N��H�̓O��
�����h�~��(3���̉���A�}�X�N���p�A��A���܂߂Ȋ��C��)�̓O��
���̂悤�ɍ���́A�l���E���Ԃ�������x����������ʼn�H���y���ށA�Ȃǎ����\�ȓ�������̊�{�I�Ȋ�������s���Ă����Ȃ���A�܂h�~���d�_�[�u�Ȃǂ̋�������u�����ɂȂ�Ƃ��Љ�@�\���ێ����Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ�܂��B�܂��A�V�^�R���i���N�`���̃u�[�X�^�[�ڎ�ɂ���Ċ����\�h���ʂ��Ăэ��߂邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA�ΏۂƂȂ���͂��Аڎ�����������������B�������A���N�`�������Ŋ�����h���邱�Ƃ͍���ł���A���N�`���ڎ�������܂Œʂ�̊�����͑�����悤�ɂ��܂��傤�B
|
�������s �V�^�R���i 9�l���S 7899�l�����m�F �O�T��50�l�]�葝 �@4/3
�����s����3���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓��j�����50�l�]�葽��7899�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ9�l�����S�����Ɣ��\���܂����B
�����s�́A3���A�s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v��7899�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����50�l�]�葝���܂����B3���܂ł�7���ԕ��ς�7630.3�l�ŁA�O�̏T��118.0���ł����B100������̂�6���A���ł��B3���A�m�F���ꂽ7899�l��N��ʂɌ���ƁA�u20��v���ł������A�S�̂�21.4���ɂ�����1689�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�369�l�ŁA�S�̂�4.7���ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A3�����_��2�����1�l������31�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ60�ォ��90��̒j�����킹��9�l�����S�����Ɣ��\���܂����B
|
�����őO�T������葽��3760�l�����@4/3
�{��3���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�����҂�3760�l�������B�O�T�̓������j��(3��27��)���267�l���������B80��̒j��1�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
�R���i�ȊO�̎��a�ŏd�Ǖa�����g���K�v������l���܂߂��{���̏d�Ǖa��(612��)�̎����g�p����14�E1%�B�y�ǒ����Ǖa��(3302��)�̎����g�p����29�E7%�������B
�y�����҂̓���z���1471�A��275�A�L��186�A�����166�A����158�A���c130�A�ݘa�c�E����110�A��E�Q����94�A����86�A�哌75�A�a��71�A�r�c54�A���53�A����47�A����36�A��E�x�c�сE�͓�����33�A��^31�A����30�A�L�ˁE���27�A��㋷�R25�A���22�A�H�g��20�A�l����19�A����18�A�ےÁE�F��17�A����16�A���䎛14�A���12�A���{10�A�L�\�E����9�A�͓�5�A�c�K4�A���q3�A�{�O110�B
|
���u�܂h�~�v�S�ʉ����̕��䗠�@4/3
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̊��������ɔ����A���{�������̓s���{���ɓK�p���Ă����܂h�~���d�_�[�u���A3��22������S�ʉ������ꂽ�B���{�R���i�����ȉ�ł͈ꕔ�٘_���o�����A�ݓc���Y���ŏI���f�����Ƃ����B�́u���サ�炭�����ւ̈ڍs���ԂƂ��A�\�Ȍ�����퐶�������߂����ԂƂ���v�Ƃ��āA�o�ς��܂߂��Љ���ւ̈��e�������D�悵�����Ƃ������B�����A���g�Ε��ȉ����u���o�E���h�̉\���͍����v�ƌx����炵�A�e�s���{���ʂ̐V�K�����Ґ��ł��A�Ȃ��ꕔ���ߋ��ő��ƂȂ�P�[�X�����₽�Ȃ��B���̂��߁A�u���{�̑Ή��͏��߂���S�ʉ������肫�v(��������)�Ƃ̎w�E�������A���f�̕��䗠�ł́u���Ǘ��݂̎v�f�v(��)���w�E���鐺���o�Ă���B
��3��16���[�̊W�t���Ƃ̋��c���o�āA��������Ȃ�18�s���{���ɓK�p���Ă����܂h�~�[�u�ɂ��āA�����̓�21���܂łł��ׂĉ������邱�Ƃ����߂��B��Õ���̊�@�������A�Ō�܂őԓx���肾�������{���A�y�d��ʼn��������߂Ȃ����j��\���������Ƃ��A���f�̃|�C���g�ƂȂ����B����ɂ��A1����{�ȍ~�ő�36�s���{���ɓK�p���ꂽ�d�_�[�u�́A2�J�����ŏI�~�����ł��ꂽ�B17���̍�����o�ē���̎������̐��{���{������������̏�ƂȂ������A��16����̊��@�L�҉��(1)�����h�~���ꂽ��ʎ��Ə��ł͔Z���ڐG�҂̓���͂��Ȃ�(2)�ό��x�����Ɓu�f���s���g���x���v�ĊJ�Ɍ����A4��1������u�������v���g�傷�鄟���Ȃǂ�\���B���Ċe���ɕ���āA�E�B�Y�R���i�ł̌o�ωɓ��ݏo�����ӂ�\���A�����̗����Ƌ��͂����߂��B
���u���[�X�g���v�ւ̑Ή��͐��Ǘ��݁H
�S�ʉ����ւ̕\�ʓI�o�܂�U��Ԃ�ƁA���{�͓����A�I�~�N����������������3��ڃ��N�`���ڎ�̑啝�x��Ō��������ᔻ�����B�������A3���ɓ����ĐV�K�����Ґ��⎀�ҁE�d�ǎ҂̌������i��ō����̌x����������ᔻ�����É��������Ƃ�����A����̑S�ʉ����́u���R�Ȑ���s���v(���@��)�Ƃ�������B�����A���{�͎��O�ɐ��Ɖ�c�ŁA�����̏����̑啝�ɘa�����߂�ȂǁA�u�������肫�Ŋ�������i�߂Ă����v(�t���o����)���Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�������A���̒��ōŌ�܂ŕs�������������ւ̑Ή��ɁA�u�̂��������Ȑ헪���_�Ԍ������v(�t���o����)�Ƃ̐������Ȃ��Ȃ��B
���������A���̑Ή������ڂ��ꂽ�̂́A��Õ���̎w�W�Ƃ��Ȃ�d�ǎҐ��⎀�Ґ�������A�u��オ���|�I���[�X�g�����v(�����ǐ���)���������炾�B�����A���{�E�s�̍ō��ӔC�҂̋g���m���m���Ə����Y�s���́A�������}�E���{�ېV�̉�̕���\�Ƒ�\�ŁA���ɋg�����̓R���i�Ή��Łu��ヂ�f���v���f�������ƂŁA�S���I�ɂ��x���A�]������Ă����B���̂��߁A�����ゾ���d�_�[�u�K�p�̉����ΏۂƂȂ�A�u���R���r�̃R���i�Ή��̎��s���\�ʉ��v(��������)���A�ېV�ւ̔ᔻ�g�傪�m���������������B
�^�}���ł́u�����ɖڂ�t�������A�g������Ɉӎv�\���𔗂邱�ƂŁA���ǓI�ȗh���Ԃ���������v(��������)�Ƃ̉������L�������B�g�����͎��ԃM���M���Ɂu�����\���͂��Ȃ��v�Ɛ��{�ɂ�����a����Ή��ł��̂����Ƃ������A��ł͏]���̎���̗ǂ��͏������B���ʓI�Ɂu�̂��������Ȑ헪�ɈېV���y�U���������i�D�v(�������V)�ɂ�������B�����A�V�K�����Ґ��̑S���I���~�܂肪�������ł̑S�ʉ����́u�Q�@�I�Ɍ������̑�����v(��)�ł�����A�Q�@�I���O�̑�7�g�P���������A�����s�k�ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��̂����Ԃ��B
|
���g�܂h�~�h������2�x�ڂ̓��j���@�����H�X�u��̔���グ���c�v �@4/3
4��3���A�܂h�~���d�_�[�u����������Ă���2�x�ڂ̓��j�����}�������B�~�i�~�̊X�ł͑����̐l���s���������A�ĂѐV�^�R���i�E�C���X�̊������L���邱�Ƃ�S�z���鐺��������܂����B
�u�������ˁA�l�B�݂�ȑ�ς�ˁA���ɂȂ�̂킩���Ă��āc���������₯�ǁA�����A���v
�_�ސ삩��̊ό��q�@�u������ƐS�z�ł��ˁB�y���߂��͊y���߂��v
����A���H�X�ɂ��b���܂����B
���D�ݏĂ��u���ږx�ꖾ�v�@���c��������@�u���Ԃ́A���t�x�݂Ƃ������Ƃ������Ă��Ȃ葽���̂��q�l�������Ă��܂��B�݂Ȃ����A��̂��ȂÂ��Ă���̂ŁA��̔���グ���S�R�B���S�ɂ͖߂�Ȃ��ł��ˁv
4��3���̋ߋE�̐V�K�����҂́A���{��3760�l�A���Ɍ���1701�l�A���s�{��939�l�A���ꌧ��600�l�A�ޗnj���379�l�A�a�̎R����260�l�ƂȂ��Ă��܂��B�������̐V�K�����҂�81�l�ł��B
|
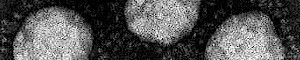 |
�����B�ɂ�����I�~�N�����ψي��̊����g��@4/4
���B�����̑����ł�2�����O�ɃI�~�N�����������͓����z�����A�Ɨ\�z�����B����ɑ���WHO�́u�����̉��B�嗤�����ł́A�e�퐧������蕥������ɕψي�BA.2.���R���g���[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�v�ƌx�����Ă����B
�킪���ł������s�𒆐S��1�T�ԕ��ςőO�T��v���X�ɓ]���ă��o�E���h�̌��O�������₩��Ă���B����́A����BA.2.�̊����g��̉\���������BBA.2.�͒ʏ�̃I�~�N�������Ɣ�ׂ��30���������͂���������ŁA���@��d�lj����X�N�͏��Ȃ��ƕ��͂���Ă���B
���B�����ł́A�u�[�X�^�[�ڎ�̐����������A�}�X�N���p����H�X�ւ̏o���萧���P�p�Ȃǂ�w�i��BA.2�̊������g�債�Ă��Ă���A���Ȃ��Ƃ����B18�J���Ŋ������g�債�Ă����B���Ȃ݂ɉ��B�ɂ�����V�K�����Ґ�(3/29��)�͉p����8���l(���Ґ�305�l)�A�t�����X��22���l��(��164�l)�A�h�C�c��137���l(��1�C524�l)�A�C�^���A��10���l(��177�l)�ƈ��������������ł���B
���B�����ł͊����̍Ċg��ɂ�������炸���X�ɐ����P�p���s���Ă���B���@�Ґ��Ǝ��S�����������Ă���̂Ɉ��g���Čo�ϗD��ւƑǂ��ւ����Ƃ������Ƃ��B�܂������ł��Ȃ��̂͌l��`���M�сA���{�̊����������������s���������̓P�p�𑣂��Ă���B
�p���̃W�����\���͎��@�ł̈������܂ރp�[�e�B�[���J��Ԃ����u�p�[�e�B�[�Q�[�g�v�����ł�������𑱂��邱�Ƃ��낤���Ȃ������A�R���i�}���̂��߂̊e��P�p�[�u�Ōl�̎��R���M�ԕێ�}���̎x�������߂����B
���B�e���̍s�������[�u�̉������ȒP�ɂ݂Ă��������B�|�[�����h�ł�3��28�����牮���ł̃}�X�N���p�`����P�p�����ق��APCR�����̌��ʁA�z���Ɣ��肳�ꂽ�Ƒ��̎��Ȋu���Ȃǂ̋K�������������B
�C�^���A�ł��A�����Ґ���3�����߂���قڔ{���A3��27���ŐV�K�����Ґ���6���l���z���Ă���ɂ�������炸�A���{��2�N�ȏ㑱���Ă����ً}���Ԑ錾��3�����ʼn��������B
�h�C�c�ł��A������ʋ@�ւ�E��ł̃��N�`���p�X�|�[�g�̌f���`�������������B�X�R�b�g�����h�ł͎��Ȋu����PCR�����̗v�����A�܂��C���O�����h�ł͗�����茟�����������I������Ɣ��\���Ă���B
�t�����X�ł͍���Ҏ{�݁A�����A���@�ւ��������ׂĂ̏ꏊ�ł̃}�X�N���p�`�������������B�������A���߈�T�ԓ�����ł�10���l�����芴���Ґ������߃s�[�N����928�l�Ɠ��{(��240�l�A3/23�`3/29���T)��4�{�ɂ܂ŏ㏸�����B���Ƃ̊Ԃł͎��������̔��f�~�X�ł͂Ȃ��������A�Ƃ̔ᔻ���₦�Ȃ��B
�V�K�����Ґ���3�����{�ȍ~�A����5���l�O��܂ō��܂����I�[�X�g���A�݂̂���������������������ł̌��I�X�y�[�X�̂�����}�X�N���p���Ăы`���t�����B
��ʓI�Ȏ~�ߕ��Ƃ��ẮA�I�~�N�����������̍ň����͉߂����A�ƑO�����ɂȂ��Ă���B�������Ƀf���^���̊������g�債���Ƃ��̂悤�ɓ��@���҂����������Ĉ�Õ��N�������ɂȂ������Ƃ͋N���������Ȃ��B
�������A�Ⴆ�h�C�c�ł͍���҂̃��N�`���ڎ헦���Ⴂ���߁ABA.2.�̊������X�N�͍��������B���̂��߁A�h�C�c�A�M�c������̊����h�~���������������ŁA�����̏B�ł͉����ł̃}�X�N���p�`����4�����߂܂ʼn������Ă���B
��s���ɂ��Ă͉��B�����ł�������������Ă���B��\�I�Ȍ����́u�����͂������̂ł��炭�͊����҂����~�܂肵�悤�B�������A����ʼnďꂪ�߂Â�����A�g�����Ȃ�ɂ�Đ��퉻����̂��߂��v�Ƃ����y�ϓI�Ȃ��̂��B
�Ƃ͂����A��x�������������}�~�̂��߂̋K�����ē�������͓̂���A���h���Ȍ`�ł̐l�X�̌𗬂�������ƁA�������L�����Ă����ƌ��O������Ƃ������B
����A���O�����͕̂č��ł���B���Ƃ͕č��ł͐��T�Ԃ̂����Ɋ����Ċg��Ɍ�������̂ł͂Ȃ����A�Ƌ���Ă���B�Ƃ��ɕč��ł̓��N�`���̎O��ڂ̐ڎ�A������u�[�X�^�[�ڎ킪���N��w�Ŋg����Ȃ����Ƃ��牢�B������芴���̊g��Ȃ�тɓ��@���҂̑����y�[�X�������Ă����ƌ��O����Ă���B
���{�̎�Ȉ�Ìږ�̃t�@�E�`���m�̂悤�ɂ�������Ɍ��O�����K�v�͂Ȃ��Ƃ̈ӌ��������B�������A�č��l�̎O�l�Ɉ�l�̓��N�`����2��ڎ킷��s���Ă��Ȃ��B�O��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ�Ɏ����Ă͐ڎ�ς݂̐l�͑��l����29���ɉ߂��Ȃ��B�v�����Ґ���8�C000���l���z����č��ɂ�����BA.2.�̊����g��̉\����ے肷��͓̂�������B
�킪�����V�N�x���}���A���w���A���Ў��Ől���W�܂�@������A�t�x�݂��̌�̃S�[���f���E�B�[�N�ōs�y�ɏo������@���������B���܂Ȃ��A�}�X�N���p�ƃ\�[�V�����f�B�X�^���X������Ă���Ƃ͂����A�p�S�͕K�v�ł͂Ȃ����낤���B
|
���I�~�N�����ĔR�@����Ҏ���Â̍\�z���@4/4
�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����Ґ����A�����ɓ]���n�߂��B���t���[��1���Ɍ��\�����f�[�^�ɂ��ƁA����1�T�Ԃł�44�s���{���őO�T���������B
��6�g�̂܂h�~���d�_�[�u���S�ʉ�������Ĕ������炸���B�S���̏d�ǎҐ��͌��葱���A�a���g�p�����}�����Ă��邪�A1��������̐V�K�����Ґ��́A��N�Ă̑�5�g�s�[�N��(��2��5��l)���͂邩�ɒ�������������B
�����J���Ȃ̐��Ƒg�D�̕��͂ɂ��ƁA20��̊����������A���H�X�ł̊������ڗ��Ƃ����B�����g�叉���ɂ݂���X�����B
�N�x�̐�ւ���Ԍ��Ől�o�������Ă���B�Ċg��ɂȂ��鋰�ꂪ�����B�V���Ȋ����̔g�ւ̔�����ӂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
��6�g�Ŕ����I�Ȋ������N�������I�~�N�������́A�h���^�́u�a�`�E2�v�֒u����������B�V�K�����҂ɐ�߂銄���͊���6���ɒB���A5����1�T�ɂ�9������Ƃ̗\��������B
�]���̃I�~�N�������̓f���^����3�{�߂������͂����锼�ʁA�d�lj����ɂ����B�h���^�̊����͂͂����1�E3�{�������A�d�lj����X�N�͕ς��Ȃ��Ƃ����B
����ŁA�ꕔ�̍R�̖�͌������A�u������肪�i�މp���ł͏d�ǎ҂⎀�҂������ɓ]���Ă���B
���⎩���̂́A�ψي��̊Ď������߁A������I�m�ɔc������K�v������B�����O�̏Ǘ�͂��A�h���^�̓��������ɂ߂āA�K���Ȏ��Âɐ�������悤�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
��6�g�ł́A�������@�Ɏ��a������������A�̂̋@�\���������肵�ĖS���Ȃ鍂��҂��������ł���B����҂�����Â��ǂ��\�z���邩���傫�ȉۑ肾�B
���{�V�N��w��Ȃǂ́A������������҂��u�������@�v�Ƃ��Ă��鐭�{�Ή����������A�{�l��Ƒ��̗v�]�܂��ė×{������߂�悤���Ă���B
�̒������������҂́A�뚋(������)���x���ɂ�����₷���B���o(��������)�P�A��H���w�����d�v�ɂȂ�B��b�����̒���I�Ȏ��Â����K�v�Ƃ���l�A���̕ω���ʉ���ŐS�g�Ɏx��𗈂��l�������B
�R���i�������x�����āA���������Ή���n�r�����\���ɂȂ���Ȃ���A�[���ȋ@�\�ቺ����@�̒��������������˂Ȃ��B
���Âƕ��s���āA�X�̏ɉ������×{�Ȃǂ�����d�g�݂��K�v���B�K��f�Â�g�ݍ��킹����A�̒������������ꍇ�̔����Ԑ��𐮂����肵�đΉ��ł��Ȃ����B����҂�����R���i��Â��A���܈�x�����������B |
���ߋE4�{���ŐV�K�������O�T����@���o�E���h�x���@4/4
3���A�ߋE2�{4���ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����7639�l�m�F����܂����B4�̕{���őO�̏T�̓��j��������A400�l���܂葝�����Ă��܂��B
���{�ɂ��܂���3�����\�����V�K�̊����Ґ��́A3760�l�ŁA��T�̓��j���Ɣ�ׂ�267�l�������Ă��܂��B�N���10�ォ��40�オ���S�ŁA20�オ745�l�ōő��ƂȂ��Ă��܂��B
�i�w��A�E�ȂǂŐV�����������n�܂��Ă���ق��A�Ԍ��Ȃǂ̍s�y�q�������Ă��āA�{�ł̓��o�E���h�ւ̌x�������߂Ă��܂��B
���̂ق��ɂ����s�A�ޗǁA�a�̎R�ŐV�K�̊����Ґ����O�̏T�������Ă��āA�u�I�~�N�������v�̔h���^�ł���a�`�E2�ւ̒u������肪�Ċg��ɂȂ����Ă���\��������܂��B�܂��A8�l�̕����S���Ȃ��Ă��܂��B
|
���؍��@�V�K������3���A����20���l��A �V�����ψي��u�w�d�v�o��@4/4
�؍����ł̐V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s���ɂ₩�Ȍ����X���ɓ���A�V�K�̊����҂�3���A����20���l��ƂȂ����B
3���ߑO0����̐V�K�����Ґ���23��4301�l�ŁA�ꎞ40���l�܂ő�����1�T�Ԃ�1���̕��ϊ����Ґ���20���l��(29��4105�l)�܂Ō������B�挎12��(28��4802�l)�ȗ�22���Ԃ�̂��Ƃ��B������ŐV�K���҂�306�l�ŁA5���A����1����300�`400�l��̐V�^�R���i�̎��҂����������B�V�K�����҂͊ɂ₩�Ȍ����X���������Ă��邪�A���s�̃s�[�N���ɋ}���������҂�2�A3�T�Ԃ̎�����u���ďd�ǂɈ������A4�����߂��璆�{�܂ł͏d�ǎ҂Ǝ��҂�������\��������ƕ��͂���Ă���B
4������́A�u�W�܂�̐l��������10�l�A�c�Ǝ��Ԑ����͌ߑO0���܂Łv�ɎЉ�I�����m�ۂ̑[�u�����������B���{�́A���s���m���Ɍ����X����������A18������͎����}�X�N�ł̒��p���������w�ǂ̖h�u�[�u������������j���B
�C�O����̓����҂ɑ���u���`������������A�m��(�C���`����)���ۋ�`�̖h�u�{�݂��P�����ꂽ���A�C�O�ł̓X�e���X�I�~�N�����̐V���ȕψي��u�w�d�v���������ꂽ�B3��(���n����)�A�p���̃C���f�B�y���f���g�ȂNJC�O���f�B�A�ɂ��ƁA�u�I�~�N�����v�Ɓu�X�e���X�E�I�~�N�����E�E�C���X�v�����������`�́u�w�d�v�́A�p���ɑ�����p�ł��m�F���ꂽ�B
�h�u���ǂ́A�u�p���ł̏������͂ɂ��ƁA�w�d�̓X�e���X�I�~�N�������10�������������x���������v�Ƃ��A�u�����������Ⴍ�A�������x���͂��߂Ƃ��銴���͂�d�Ǔx�Ȃǂ́A�lj��̒������͂��K�v���v�Ɛ��������B����(�R����)��w��V(�N��)�a�@�������Ȃ̃L���E�E�W�������́A�u�C�O�����҂̊u���`�����������������ɁA�����ł��w�d���߂������ɔ�������邾�낤�v�Ƃ��A�u�w�d���g�傷��A���s�����̑��x���x���Ȃ�\��������v�Əq�ׂ��B |
���ݓc���t�������甼�N �R���i �E�N���C�i�ő����������� �@4/4
�ݓc���t�̔�������4���Ŕ��N�ƂȂ�܂��B�Q�c�@�I�����ĂɍT���A�V�^�R���i�̊����g���E�N���C�i��Ȃǂɋ@���I�ɑΏ����Ă��������Ƃ��Ă��܂����A�������̂������u���邱�Ƃ��ł��邩������������邱�ƂɂȂ�܂��B
�ݓc���t�����N10��4���ɔ������Ă���4���Ŕ��N�ƂȂ�܂��B
������������V�^�R���i����ŗD��ۑ�ƈʒu�Â��Ď��g�݂�i�߁A�I�~�N�������ւ̊����������Ŋm�F����Ĉȍ~�͊O���l�̐V�K������������~����ȂǁA�������ő��ł��o���܂����B
���Ƃ��ɓ����Ă���́u�܂h�~���d�_�[�u�v���e�n�ɓK�p���đ���u���A���悻2��������̐挎�A���ׂĂ̒n��Łu�d�_�[�u�v���������܂����B
�����V�K�����Ґ����Ăё����X���ɂ��邱�Ƃ���A��Ò̐����m�ۂ���ƂƂ���3��ڂ̃��N�`���ڎ��i�߁A�Ċg��̖h�~�ƎЉ�o�ϊ����̗̉�����}�肽���l���ł��B
�O��ʂł́A���V�A�ɂ��E�N���C�i�ւ̌R���N�U�͍��ے����̍�����h�邪���[���Ȏ��Ԃ��Ƃ��āA�e���Ƌ������ă��V�A�ւ̐��ق��s���ƂƂ��ɔ��̂���Ȃ����Ɍ����̐��̐������}���ł��܂��B
����A�E�N���C�i��ɔ��������̏㏸���āA�������܂łɋً}����܂Ƃ߂�Ƃ��Ă��āA�߂����{�E�^�}���ŋc�_���{�i�����錩�ʂ��ł��B
�ĂɎQ�c�@�I�����T���A�ݓc���t�͐V�^�R���i�̊����g���E�N���C�i��Ȃǂɋ@���I�ɑΏ����Ă��������Ƃ��Ă��܂����A�������̂������u���邱�Ƃ��ł��邩������������邱�ƂɂȂ�܂��B |
���I�~�N�������uBA.2�v�n���֒u�������Ɗ����Ċg��̉\���@4/4
�����s��t���Łu�������Εa�@�v�������̒������F����3��28���A�j�b�|�������u���[�j���O���C�t�A�b�v �����̑��N���h�N�^�[�v�ɏo���B�u�܂h�~���d�_�[�u������̃R���i�v�Ƃ����e�[�}�ɂ��ĉ�������B
���I�~�N�������uBA.2�v�n���ւ̒u�������
�ѓc�_�i�A�i�E���T�[) �����搶�́A�����s�V�^�R���i�E�C���X�����ǃ��j�^�����O��c�ŕ��͂��s�����Ƃł���������Ⴂ�܂��B�u�܂h�~���d�_�[�u�v�������ƂȂ�A���炭�o���܂����B
����) �I�~�N�������̂Ȃ���BA.2�Ƃ����n��������܂�����ǂ��A����ɒu�������ƁA�����͂��������Ƃ��킩���Ă���܂��̂ŁA�������Ċg�傷��\��������܂��B����ŁA3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�i��ł��܂��̂ŁA�Ċg�債�čs���͂Ɨ}���������Ƃ����͂̃o�����X�����܂��s���A���������Ă���邱�Ƃ��F���Ă��܂��B
�������\�h�͂ł��Ă��Ȃ�����ǂ��A�d�ǎ҂͏��Ȃ��@�`2��ڂ̃��N�`���ڎ�����l�̏d�lj����͒Ⴂ
�ѓc) �I�~�N�������ł����A�ŏ��ɓ�A�t���J�ȂǂŘb��ɂȂ����̂͋��N(2021�N)�̏H���̘b�ł����B���̂��납��3��ڂ̃��N�`���ڎ�̘b������܂������A�����ƒǂ����������𑱂��ė����Ƃ����ł���ˁB
����) �����g�傪����قǑ����Ƃ͎v���Ă��܂���ł����B���ꂩ��A���N�`��2��ڎ�̌��͂�����قǃI�~�N�������ɒʗp���Ȃ��Ƃ������Ƃ��A����A�o�����Ă킩�������Ƃł��B
�ѓc) ���ۂɃI�~�N�������̊������g�債�Ă킩�����ƁB
����) �����g�傪���������Ƃ������Ƃ́A2��ڎ�̗͂�����قnj����Ȃ������Ƃ������Ƃł��B�������A�d�lj��\�h�Ɋւ��Ă͓����Ă��܂��B
�ѓc) �d�lj��\�h�ɑ��ẮB
����) 2��ڂ̃��N�`����ł��Ă���l�Ƒł��Ă��Ȃ��l�̊Ԃł́A�����̍�������܂��B�u�����\�h�͂ł��Ă��Ȃ�����ǂ��A�d�ǎ҂͏��Ȃ��v�Ƃ����̂����܂̓��{�̌���ł��B
���I�~�N�������̗��s���ʏ��Âɉe��
�ѓc) �搶�͊����̕��݂͂̂Ȃ炸�A��������ǂ��a���������čs�����Ƃ����A���̑Ώ��ɂ��Ă�����Ă�������Ⴂ�܂��B����̑�6�g�ł́A�ǂ̕ӂ肪���������ł����H
����) �����g��ɍ��킹�āA�R���i�p�̕a�����m�ۂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�����ł́A�R���i�p�a���̊m�ۃ��x�������x��1�`3�Ƃ����i�K�Ō��߂Ă��܂��B�f���^�������܂��Ă���́A�m�ۃ��x�������x��3����2�ɗ��Ƃ��A�u�ʏ��Â��ꐶ�������܂��傤�v�Ƃ����t�F�[�Y�ɂ��Ă����̂ł����A�I�~�N�������̊����X�s�[�h���������߁A�����Ƀ��x��3�֖߂��A�I�~�N�������ɍ��킹���a���m�ۂ�i�߂܂����B
�ѓc) ���x��3�ɖ߂��āB
����) �R���i�p�̕a���́A�ʏ��Â̓]�p�ł���Ƃ������Ƃ��厖�Ȃ̂ł��B�]�p���Ă��܂�����A�ʏ��Âւ̑Ή����ǂ����Ă�����̂ł��B����̃I�~�N�������̗��s�́A���̒ʏ��Â̂Ђ����������Ă��܂����Ƃ����̂������I���Ǝv���܂��B
�ѓc) �ǂ�����a���ɂł��Ȃ��Ƃ����Ƃ���ŁA�ǂ��єz���邩�ł��ˁB
����) �����ł��ˁB���Ă�͂�100���Ƃ���ƁA�u�������R���i�Ɋ����āA�������c�����v�Ƃ����єz���厖�Ȃ̂ł�����ǂ��A���̗͂�100�ȏ㑝���Ă��Ȃ��������܂��炢�Ƃ���ł��B�@ |
 |
���u�܂h�~�v���K�p����1�N�@�R���i�}�����ʂɋ^����@4/5
�V�^�R���i�E�C���X�����g��̗}����Ƃ��āA�ً}���Ԑ錾�ɏ�����u�܂h�~���d�_�[�u�v�����߂ēK�p����Ă���5����1�N�ƂȂ����B�錾���߂̑O�i�K�ł��łĂ�悤�A���������V�݁B�ݓc���Y�͐ϋɊ��p���A���s�u��6�g�v�ɑΉ������B�����A�I�~�N�����������̎����ɂ͎��炸�A���ʂ��^�⎋���鐺���o�Ă���B
��N2���̖@�����ŐV�݂��ꂽ�܂h�~�[�u�́A�s�撬���P�ʂŔ͈͂��w�肵����ŁA���H�X�ւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�A�x�Ƃ̗v���▽�߂��\�ƂȂ����B���߈ᔽ�ɂً͋}���Ԑ錾�Ɠ��l�ɍs�����̉ߗ����Ȃ��A�s���{���P�ʂ̐錾�Ɣ�ׂċ@���I�ȑΉ���_�����B |
�������s �V�^�R���i 9�l���S 6968�l�����m�F �O�T��900�l�߂��� �@4/5
�����s����5���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̉Ηj�����900�l�߂����Ȃ�6968�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ9�l�����S�����Ɣ��\���܂����B
�����s�́A5���s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v��6968�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj�����900�l�߂�����܂����B5���܂ł�7���ԕ��ς́A7482.0�l�őO�̏T��104.2���ƂȂ�܂����B100������̂�8���A���ł��B
5���m�F���ꂽ6968�l��N��ʂɌ���Ɓu20��v���ł������A�S�̂�21.9���ɂ�����1525�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�283�l�ŁA�S�̂�4.1���ł����B�����o�H���������Ă���2484�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v�ŁA�S�̂�69.4���ɂ�����1725�l�ł����B
����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A5�����_��4�����1�l������30�l�ł����B�܂��A���Z�x�̎_�f���ʂɓ��^����u�n�C�t���[�Z���s�[�v���s���Ă��銳�҂Ȃǂ��܂߂�A�I�~�N�������̓����܂�����ŏW�v�����d�NJ��҂́A5�����_��71�l�ł����B���̊�ł̏d�NJ��җp�̕a���g�p����8.8���ŁA�W�v���J�n�������Ƃ�2���ȗ��A���߂�10���������܂����B
����A�s�͊������m�F���ꂽ60�ォ��90��̒j�����킹��9�l�����S�����Ɣ��\���܂����B9�l�̂��������o�H���������Ă���̂�7�l�ŁA����Ҏ{�݂�3�l�A�a�@���Ɖƒ�������ꂼ��2�l�ł����B�܂��A9�l�̂������Ȃ��Ƃ�8�l�͊�b����������܂����B�@ |
���R���i�����ҁ@���m3128�l�@��755�l�@�O�d491�l�@4/5
���C3����5���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��͍��킹��4374�l�ł����B
���m����3128�l�ŁA���̂������É��s��1134�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A����755�l�ŁA�O�d����491�l�ł����B���A1�T�ԑO��3��29�����_�ł̊����Ґ��͈��m��2927�l(���É��s1029�l)�A��581�l�A�O�d��382�l�ł����B
|
�����ŃR���i�����g��̒���@�m���A20�`30�㑝���Ɋ�@���@4/5
���{�̋g���m���m����5���A�{����20�`30��̃R���i�����Ґ��������A�����g��̒�������Ɩ��炩�ɂ����B�I�~�N�������̔h���^�uBA�E2�v�ւ̒u������肪�i�݁A�S�̂̐V�K�����Ґ��������B�g�����́u���S�ɉ����~�܂�ɂȂ����B�㏸�p�x�������ɗ}���邩���d�v���v�Əq�ׁA��@�����������B
�{���̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���3��29���ɑ����ɓ]���A7���A���őO��1�T�Ԃ��������B20�`30��̑����������ŁA����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��̂���35�����߂��B�����g��̒�����@�m���邽�ߊ�����������20�`30��̊����Ґ����u������Ԏw�W�v�Ƃ���{�̓Ǝ���ɂ��B�����B
|
���u���钛���͂����ƌ����ĂȂ��v �q�ǂ��̊����g���~�܂�h �����g��̋�����@4/5
�܂h�~���d�_�[�u���S�ʉ�������Ă���2�T�ԁB�X�͌��̗l�q�ɖ߂����悤�ɂ��݂��܂����A�����̊����҂͎v���悤�Ɍ����Ă��܂���B
�S����5���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�̐V�K�����Ґ���4��5000�l���A���Q�ƏH�c�ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B30���{���őO�̏T��芴���Ґ����������Ă��܂��B
��ʌ��t�����s�ɂ���w����݃N���j�b�N�x�ł́A5���Ɍ������s����55�l�̂����A6��33�l���z���ł����B
����݃N���j�b�N�E���얜�K�q�@���F�u��6�g�ŗ\�p���p���ŁA�ˑR�����l������������Ȃ���Ԃ�1���㔼���炸���Ƒ�����(�܂h�~�[�u��)�������ꂽ����Ƃ����āA�����Ă��Ă��钛���͂����ƌ����ĂȂ��v
�z���ƂȂ����l�ɘb����3��ڂ͖��ڎ�Ƃ������҂��ڗ����܂��B
����݃N���j�b�N�E���얜�K�q�@���F�u��5�g���ڎ헦��70�����Ă���(�����҂�)���Ȃ��Ȃ����̂ŁA(3��ڐڎ킪)40��������Ƃ��ƁA��5�g�ɔ�ׂ�ΐڎ헦�������B2�������R�̂������Ă���C���Ȃ̂�������Ȃ�����(���N��)8��9���Ɏ����́A�����R�̂���Ă����ԁv
�C�ɂȂ�̂́A�q�ǂ��ւ̊����ł��B�S���I�ɍ��~�܂肪�����Ă��āA����A�S�̂�3����1�ȏ��10��ȉ�����߂Ă��܂��B5�`11�̎q�ǂ���1��ڂ̐ڎ���I���Ă���̂�8����B����A�V�w�����n�܂��Ċw�Z���Ŋ������L����A��������ƒ���ł̊����g��ɂȂ��鋰����w�E����Ă��܂��B
����݃N���j�b�N�E���얜�K�q�@���F�u���������q����͊Â��Ă��܂�����A���q���炩�����Ă��܂����e�䂳��͑�����������Ⴂ�܂��B��������Ƒ��݂�ȂŁB�c���ꐢ�オ�ꏏ�ɏZ��ł���ƁA�����܂ł���������Ă���̂ŁA������������ƕ|���Ƃ���ł��v
|
 |
���V�^�R���i�@�X�E���E�H�c�E�R�`�E�����̊����ҁ@4/6
�X���Ȃǂ�5���A10�Ζ�����80�Έȏ���܂ޒj��409�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�����̊����m�F�͌v3��8416�l�B�݂Ȃ��z��3�l�������V�K�����҂̓���́A�O�O�ی����Ǔ�101�l�A���ˎs91�l�A�X�s79�l�ȂǁB286�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B���ˎs���̈�Ë@�ւŃN���X�^�[���m�F���ꂽ�B
��茧�Ɛ����s��5���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��253�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͐����s50�l�A���B�s47�l�A�k��s�A��֎s�e25�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v1��9392�l�B�����s�̊w�Z�A�����ی����Ǔ�(�������s�Ȃ�7�s��)�̐E��A�v���ی����Ǔ��̍���Ҏ{�݂ŃN���X�^�[���m�F���ꂽ�B
�H�c���ƏH�c�s��5���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��389�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1��������̍ő����X�V���A�����̊����m�F�͌v1��7634�l�B�ی����ʂ̐V�K�����҂͓��s184�l�A���63�l�ȂǁB�N���X�^�[�͓��s�≡��Ǔ��̕ۈ牀�ȂǂŌv6�����������B
�R�`���ƎR�`�s��5���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��191�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͎R�`�s59�l�A�߉��s16�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v1��8407�l�B�R�`�s�̕ۈ�{�݂ŃN���X�^�[���m�F���ꂽ�B
��������5���A10�Ζ����`80��̒j��467�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͌S�R�s139�l�A���킫�s103�l�A��Îᏼ�s55�l�A�����s43�l�A�{���s31�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v3��8320�l�ƂȂ����B�S�R�s�̕��ی㎙���N���u�Ōv6�l����������Ȃ�5���̃N���X�^�[�����������B��������1�T�Ԃ̊����҂𒊏o�����{�����Q�m����͂̌��ʁA�I�~�N�������̔h���^�u�a�`�E2�v�̊�����39�E4�����߂��B
|
�������s�A�V����8652�l�̊������\�@�O�T���j����3���A�������@4/6
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�����s��6���V����8652�l�̊����\���܂����B��T���j��(3��30��)��9520�l��868�l������Ă��āA�O�̏T�̓����j���̊����Ґ��������̂�3���A���ł��B
�����s�́u���������A��t�������Ɛf�f�����v�g�݂Ȃ��z���h�̊��҂������҂Ƃ��Ĕ��\���Ă��āA24�l���g�݂Ȃ��z���h�̊��҂ł����B�V���Ȋ����҂̂����A���N�`����2��ڎ킵�Ă����l��4295�l�ŁA1����ڎ�����Ă��Ȃ��l��2235�l�ł����B�V�^�R���i�̕a���g�p����24.6���ŁA�ő�Ŋm�ۂł��錩���݂�7229���ɑ��A1777�l�����@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�̕a���g�p���́A8.3���ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł́A10�㖢����1367�l�A10�オ967�l�A20�オ1851�l�A30�オ1624�l�A40�オ1410�l�A50�オ769�l�ŁA�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂�480�l�ł����B���ݓ��@���Ă��銴���҂̂����A�����s�̊�Łu�d�ǎҁv�Ƃ����l�́A29�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��V���ɁA70��j�����܂�6�l�̎��S�����\����Ă��܂��B�@ |
���R���i�����Ҍ����A3�����Ԃ�ɏ㏸ ��B3���̏h���ғ��w�� �@4/6
��B�o�ϒ������5�����\������B7����3���́u�h���ғ��w���v�́A�O����16�E2�|�C���g�v���X��50�E0��3�����Ԃ�ɏ㏸�����B�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂̌����ɔ����A�h���{�݂̉ғ��������܂����B
47�s���{�����ׂĂőO������v���X�ƂȂ����B��B�ł́A�啪��21�E6�|�C���g�㏸��68�E4�A��������21�E0�|�C���g�㏸��58�E0�A���肪20�E6�|�C���g�㏸��58�E0�Ƒ傫�����P�B�r�W�l�X���v�̉��x��Ă���������13�E4�|�C���g�㏸��38�E7�ƂȂ����B�R����19�E5�|�C���g�㏸��61�E1�������B
4�����X���������Ă��邪�A������́u�����Ґ������~�܂肵�Ă���A�y�ς͂ł��Ȃ��v�Ƃ��Ă���B�w����100�ɋ߂��قǖ����ɋ߂����Ƃ������B
|
���R���i���N�`�����ڎ�̐l�����̗l�X�ȗ��R�����Ă킩���Ă������Ɓ@4/6
�I�~�N�������̗��s���ēK������Ă����u�܂h�~���d�_�[�u�v��������2�T�Ԃ��߂��܂����B����I�ɊO������f����Ă��������́A�u�ŋ߂́A�ݑ�Ζ��ł͂Ȃ��o�Ђ��Ă��܂��v�Ƃ�������A�u���炭�x��ł����^�����ĊJ���܂����v�Ƃ�����������������Ă��܂����B���̈���ŁA�u�R���i���|������A�܂��l�Ɖ���Ƃ�O�o�͋ɗ͍T���Ă��܂��v�Ƃ�������A�u�v���Ԃ�ɊO�o������A�w��d�Ԃɐl�������Ăт����肵���v�Ƃ�������������܂��B
�Ζ���̓��ȊO���ɔ��M���܂ޕ��Ǐ����i�Ɏ�f����銳�҂���̐��̐��ڂ���{�̐V�K�����Ґ��̃f�[�^����A���͐V�^�R���i�E�C���X(�ȉ��A�R���i)�����ǂ̑�6�g��3�����ŗ����������낤�Ɨ\�z���Ă��܂����B�������Ȃ���A2022�N4��3�����_�̐V�K�����Ґ���7,899�l�ł���A�ł���������2��9����1��8,287�l����͌������Ă�����̂́A3�����{�̊����Ґ��Ƃ��܂�ς��܂���B��6�g�̓s�[�N�A�E�g�����Ƃ͂����A�����Ґ��������Ő��ڂ��Ă���̂Ɠ��l�ɁA���Ǐ��F�߂ē��ȊO������f���������A�ꎞ�����͌��������̂́A�܂��܂���������Ⴂ�܂��B
������̂��Ƃł����B�u�h���œ����Ă���̂ŁA�������M���ċx��d�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�{���̓R���i���N�`����ł������̂ł����A�܂��ڎ�ł��Ă��Ȃ��̂ł��d�v�Ɛf�@���ɓ���Ȃ肨�������50��̏��������܂����B���M�͂��Ă��Ȃ����̂́A�P�ƍA�̒ɂ݂������O���瑱���Ă���A�u�R���i��������ǂ����悤�v�ƕs���ɂȂ��f���ꂽ���ł����B�u�R���i�ɂȂ��ċx�ނ��ƂɂȂ��Ă��d�����������A�R���i���N�`����ڎ킵�����C�����͓������玝���Ă�����̂́A���N�`����ڎ킵�������ɔM���ł���Ζ��ł����d�����������A���Ƃ����ă��N�`���ڎ�̂��߂ɋx�݂��m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��c�c�v�Ƃ������Ⴂ�܂����B PCR�����ŃR���i�z���Ɣ���������A��t�ɂ͔����͂��쐬���ی����ɒ�o����`��������܂��B�����͂ɂ̓R���i���N�`���ڎ�̗L����ڎ���A���N�`���̎�ނȂǐڎ���̗L�����ڂ��������������邽�߁A���ڎ�ł��邩�ǂ�����������܂��B�����Ŏ��́A�����̂Ȃ��͈͓��Ŗ��ڎ�̗��R���悤�ɂ��Ă��܂��B���N�`�����ڎ�ɂȂ��郏�N�`�������́A���E���ʂ̖��ł��邩��ł��B
���N�`�������ɂ������v���́A���3���邱�Ƃ��w�E����Ă��܂��B1�ڂ́u�M��(confidence)�v�ł��B���{���Âɑ���s�M�A���N�`���̗L��������S���ɑ���s�M�́A���N�`���ڎ��i�߂邤���ŏ�ǂƂȂ�\�����w�E����Ă��܂��B�O���ł��A�u���N�`���͐M���ł��Ȃ�����ł������Ȃ��v�u���Y�̃R���i���N�`���łȂ��Ɛڎ킵�܂���v�Ƃ������͏��Ȃ��炸������܂��B
2020�N10���Ƀl�C�`���[���f�B�V���Ɍf�ڂ��ꂽJV Lazarus���炪19�J����ΏۂƂ��������̌��ʁA�u���{��M�����Ă���v�Ɠ������l�́u�M�����Ă��Ȃ��v�Ɠ������l�����A���N�`���������\���������������Ƃ�������܂����BRJD Vergara����́A�R���i���N�`���Ɍ��炸�A���N�`���ڎ�̕��y�͍����̐��{�ւ̐M���Ɋ�Â��ƌ��y���Ă��܂��B
2�ڂ́u����(convenience)�v�ł��B1��ڂ̃R���i���N�`���̏W�c�ڎ킪�n�܂��������A�u����߂��̐ڎ���ł͑S���\��ꂸ�A�d�Ԃ�o�X�����p���ŗ����v�u�I�����C���\��ł����A���ɗ\�Ă�������v�Ƃ��������悭�����܂����B�ڎ�ꏊ�⎞�ԁA���i�A�ڎ�T�[�r�X�̎��A�ڎ�̗\��Ȃǂ��u�����v�ɂ������܂��B���ɁA�Ǘ���������҂�n���w�Ƃ������Љ����c���ꂪ���ȏW�c�́A�ڎ��p�������ł����Ă��A�u�I�����C���\�ł��Ȃ��v�u�ڎ���܂ōs����i���Ȃ��v�Ȃǂ̖�肪�c�邱�Ƃ��w�E����Ă��܂��B�\�ł��Ȃ��A�ڎ���܂ōs����i���Ȃ��A�Ƃ��������R�Œ��߂����͌��\����������̂�������Ȃ��ƁA�W�c�ڎ�̂���`�������Ċ����܂����B
3�ڂ����N�`���ڎ�ɑ���u���Ȗ���(complacensy)�v�ł��B���N�`�����ڎ�̗��R�����������ƁA�u���łɃR���i�ɂ�����������A���N�`���ڎ�����Ȃ����Ƃɂ����v�Ƃ����������ɂ���������Ƃ�����܂����A���N�`���ڎ�͕K�v�Ȃ��Ɣ��f���u���Ȗ����v�������ł��B�R���i���N�`���ڎ�ɔ������X�N�ƃR���i�ɂȂ郊�X�N�Ƃ��r�������u�����ɂƂ��ă��N�`���ڎ�͕K�v�ł͂Ȃ��v�Ɣ��f�������ʁA�u���Ȗ����v���A���ʓI�Ƀ��N�`�����ڎ�ɂȂ�Ƃ�����ł��B
�������Ȃ���A2�����{�A�j���[�C���O�����h�E�W���[�i���E�I�u�E���f�B�V��(N EJM)�ɃI�����C�����J���ꂽ�ŐV�̌����ɂ��ƁA�C�X���G���̖�15���l���̈�ËL�^����t�@�[�U�[���̃R���i���N�`���ڎ�O�ɃR���i��������������҂ɂ�����R���i�Ċ�������]���������ʁA�R���i���N�`���ڎ��16����64�̐l�̍Ċ�����82���A65�Έȏ�̐l�̍Ċ�����60����h�����Ƃ�������܂����B�u�R���i�늳��Ƀt�@�C�U�[���̃��N�`�������Ȃ��Ƃ�1��ڎ킷�邱�ƂŁA�Ċ����̃��X�N���L�ӂɒႭ�Ȃ������Ƃ��ŐV�̌����ŕ���܂�����v�ƏЉ�Ȃ���A�ߋ��ɃR���i�ɂȂ��Ă��܂����l�ɑ��A���̓��N�`���ڎ��E�߂�悤�ɂ��Ă��܂��B
�����ȊO�ɂ��A�R���i�̃��N�`���Ɋւ���SNS��̃j�Z����A�R���i�̃j���[�X���̂ɂ��܂�ڂ��Ă��Ȃ����ƂȂǂ��A���N�`���ڎ�����߂炤�v���ƂȂ肤��Ƃ���Ă��܂��B�u�e���r�ԑg�E���W�I�E�F�l�E�e���A���������Ă������ǁA�{���ł����H�@�ǂ��Ȃ̂ł����H�v�ƕ�����邱�Ƃ́A���܂��ɂƂ��Ă������ł��B
���̂悤�ȃ��N�`�������̗��R�����ڎ�ɂȂ�����̂��Ǝv���Ă����̂ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�`���ɂ��Љ���悤�ȁu�ڎ킵�����Ă��A�d�����x�߂��ǂ����Ă��łĂȂ��v�ƌ������R�ɉ����āA�u��l��炵������(�ڎ킵�Ȃ��Ă����Ɣ��f����)�v�u�ݑ�Ζ��ɂȂ��Ă��܂��O�o���Ȃ�����(�ڎ킵�Ȃ��Ă����ƍl����)�v�u�e���ڎ킵�Ȃ��Ă����ƌ�������v�Ƃ������R������܂����B
���N�`�������Ɋւ��钲�����ʂ́A�����������Ă��܂��B�������A�����̑������A�����s�����悤�ȃA���P�[�g����{�Ƃ��������ł��B���ۂɃ��N�`���ڎ���Ȃ������l�����Ɋւ���͂قƂ�ǂ���܂���B�O���̏�ŕ�������ł͂���܂����A���N�`�����������łȂ��A���܂��܂ȗ��R�ɂ��ڎ킵�����Ă��ڎ�ł��Ă��Ȃ��Ƃ����������Ȃ��炸���������邱�Ƃ��l������ƁA���N�`�������ƃ��N�`�����ڎ킪�K���������т��Ă��Ȃ��\��������Ǝ��͍l���Ă��܂��B
��N���{���ꂽ1�E2��ڂ̏W�c�ڎ�̍ۂɃR���i���N�`����ڎ킵�Ȃ������l�ɂ��Ă̏��(�N��A���ʁA�����Ƒ��̗L���Ȃ�)�����݁A�������ł��B���ڎ�҂̓��������炩�ɂȂ�A���ݐi�s����3��ڂ̒lj��ڎ��v�悪�n�܂��Ă���4��ڂ̐ڎ��i�߂邤���ő傢�ɖ𗧂̂ł͂Ȃ����ƁA���͍l���Ă��܂��B
|
����CDC �V�^�R���i �g�����҂�7���ȏオ�uBA.2�v�Ɛ���h �@4/6
�A�����JCDC�����a��Z���^�[�͍���2���܂ł�1�T�ԂɁA�A�����J�ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������l��7���ȏオ�I�~�N�������̂����A����Ɋ����͂������Ƃ����wBA.2�x�ɂ����̂��Ɛ��肳���Ƃ����A�ŐV�̕��͌��ʂ\���܂����B
CDC��5���A�A�����J�ōL�����Ă���A�ψق����V�^�R���i�E�C���X�̊����𐄒肵���ŐV�̕��͌��ʂ\���܂����B
����ɂ��܂��ƁA����2���܂ł�1�T�ԂɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������l�̒��ŁA�I�~�N�������̂����A����Ɋ����͂������Ƃ����wBA.2�x����߂銄����72.2���Ɛ��肳��A�O�̏T���炨�悻15�|�C���g�������܂����B
CDC�̃������X�L�[������5���̉�ŁA�����҂���@�҂̐��ɑ����̌X���͌����Ȃ��Ƃ��āA�u���N�`���̐ڎ��A�E�C���X�ւ̊����ɂ���Đl���̑�����������x����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ܂����B
�����āA�u����܂ł̃I�~�N�������Ɣ�ׂďd�lj����₷��������A�Ɖu��������₷���Ȃ����肵�Ă���Ƃ����؋��͂Ȃ����A�����͂͋����Ȃ��Ă���Ƃ݂���v�Əq�ׁA���������A�����g��̏𒍎����Ă����Ƃ��Ă��܂��B
�������X�L�[�����́A���N�`���̐ڎ킪�d�lj��⎀�S��h�������ŏd�v�Ȃ��Ƃ͕ς��Ȃ��Ƃ��āA�d�lj��̃��X�N��������b�����̂���50�Έȏ�̐l�Ȃǂɑ��A2��ڂ̒lj��ڎ���Ăт����Ă��܂��B
|
�����߂�����{�̃R���i�����A���E�Ŗ��v�̋���@4/6
19���I�̉p���̍�ƃI�X�J�[�E���C���h�́A�u���{�̑S�Ă͖ϑz�ɂ����Ȃ��v�Ƃ̌����������Ă����B
�u����ȍ��▯���͑��݂��Ȃ��v�ƃ��C���h�͋L���Ă���B���C���h�������Ƃ��Ă������Ƃ́A��ʓI�ɍl�����Ă�����{���A�قƂ�NJO���l�̑z���̎Y���ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�������A���{��2�N�Ԃɂ킽��O���l�ό��q�ɑ���������������{���A���ۓI�ȏd�v�����ቺ�����鍡�A���C���h�̌��t�͌����ɋ߂Â�����B
�C�O������{�̎p�͌����Ȃ��Ȃ�A���E�Ƃ̏d�v�ȃR�~���j�P�[�V������i�̈�ł���ό����r�₦�邱�ƂŁA���݂��Y�ꋎ���鋰�������B�ό������́A���{�W�O���̌o�ϐ���ŗB��ԈႢ�Ȃ������Ƃ�����{�����B���{��2003�N���_�ł͊O���l���s�Ґ��킸��500���l�̊ό���i�����������A19�N�ɂ��̐���3000���l�]��ɑ��������B
����ɂ���ē����������t����ό��̃T�C�N�����蒅���A���ꂪ����ɑ����̊ό��q���Ăэ��B�����ܗւ̊J�Â��ŏ��ɗ\�肳��Ă���20�N�ɂ͖�4000���l�̊O���l���s�҂������܂�Ă������̂́A�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɔ������������̂���400���l���x�ɂƂǂ܂����B�����ܗւ�21�N�ɍ����̊ϋq�����ꂸ�Ɏ��{���ꂽ�B
�x�܂��Ȃ�����{�͍ŋ߂ɂȂ��āA���w���Ⓑ���J���҂̎�����ĊJ�������A�ό��q�ɑ��Ă͈���������˂�����Ă���B���̊؍��̓��N�`���ڎ�ς݂̗��s�҂̎�����ĊJ���Ă���ق��A�u�v��(�悤����)�v�ƌĂ��j���[�W�[�����h�ł�������ĊJ�̗p�ӂ�����B�������A�ݓc���Y�͂܂��ό��q�̎���ĊJ�̉\����������������������Ă��Ȃ��B
���{�̐T�d�ȃR���i��̐������͗�����Ă���A�V�^�R���i�̃p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�J�n��2�N�Ԃł̎��Ґ��́A�č���3���P���̎��Ґ���������Ă���B
�������A���{�����≽��҂��Ă���̂��͂��͂▾�m�ł͂Ȃ��B�����̃��N�`���ڎ�͏\���ɐi��ł���A65�Έȏ��8���]�肪3��ڐڎ���Ă���B�O������̋��Ђ�h�����Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ����낤�B�����Ƃ͈قȂ�A���{�́u�[���R���i�v�����Nj����悤�Ƃ͂��Ă��炸�A���݂�1��������̐V�K�����Ґ��͖�4���l���B
���{�͂���Δn�������o��������X��(���イ����)�̌˂��ԕߑ����Ă���悤�Ȃ��̂��B�A���t�@����f���^���A�I�~�N�������͂�������A�O���l�ό��q������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�������g�債���B���{�̐��ۑ�͊��S�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�I�~�N�������ɂ��Ă͍ݓ��ČR�����{�ł̊��������Ɣ���l������B
�����������������R��1�́A���ʓI���ǂ����ɂ�����炸���ǂ����߂��B�m�g�j�̐��_�����ł́A���ۑ�������Ɗɘa���ׂ����Ƃ̉�3����1�����ɂƂǂ܂����B
�ݓc�͐��_�����ɕq���ŁA�Ă̎Q�@�I���ӎ����Ă���B�������A���������̌p���ɂ�闘�_�ɂ͋^�₪�c��B
���E���܂����N�`���ڎ�Ŋ����g��������ł���Ɗ��҂��Ă���1�N�O�ɂ́A�҂��ƂɃ����b�g���������B�������A����V�^�R���i�����S�ɖo�łł��Ȃ����Ƃ͖��炩���B���N�`���ڎ�����������O���l���s�ҁA���ɓ��{�����l��������̊����Ґ������Ȃ�������̗��s�҂́A�������g�傳���郊�X�N�͂قƂ�ǂȂ��B�ǂ��炩�Ƃ����A�����������s�҂̓}�X�N���p�̂悤�ȓ��{�̏펯�I�ȑ�������Ɏ����A�邩������Ȃ��B
���̈���ŃR�X�g�͑��債�Ă���B��Ƃ̑啔���͗Z����{�̎x���ɂ���Ĕj�]�����ɂ�����̂́A�ό��ƊE�͎����I�Ȑ����̂��߂ɊC�O����̎������K�v���B�����ܗւ̂��߂Ɍ��݂��ꂽ�C���t���͎g�p����Ȃ��܂܂��B���{�̏��q���ЁA�S����ЁA�S�ݓX�͑唼���Ԏ��ƂȂ��Ă���B
��������K�v�����傫���̂́A�C�O�Ɠ��{�̂Ȃ��肪��܂鎖�ԂɎ��~�߂������邱�Ƃ��B���{�̐����Ƃ͈ȑO����A1980�N��́u�W���p���E�o�b�V���O�v����u�W���p���E�p�b�V���O�v�ւ̈ڍs�Ɍ��y���Ă����B�����98�N�ɃN�����g���đ哝��(����)�������K��̍ۂɓ��{�ɂ͗������Ȃ��������Ƃ��č��ꂽ���t�ŁA���{�����ۓI�Ɍy������錻�ۂ̂��Ƃ��B
���̌��ۂ͍��ł͕��ʂ̂��ƂɂȂ����B�������A�؍��̃\�t�g�p���[�⒆���̌o�ϗ͂ɉ�����钆�A���{�̃R���i�����͂��̌X������i�Ɖ��������Ă���B
���{�����C���h�������Ƃ���́u�|�p�̌����ȋ�z�v�̂悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă��܂��O�ɁA���������[�u���K�v���B
�@ |
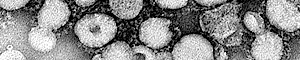 |
�������̃R���i�����ҁ@�I�~�N�����uBA.2�v7���ɋ}�g��@4/7
�����s��7���J�����V�^�R���i�E�C���X�����Ɋւ��郂�j�^�����O��c�ł̕ɂ��ƁA�s���̐V�K�����҂�7���オ�����͂������Ƃ����ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�̔h���^�uBA.2�v�ɒu��������Ă���Ƃ݂���B1�T�ԑO����15�|�C���g���g�債�Ă���A20��̊����g����ڗ��B
�s�ɂ��ψكE�C���X�̌^����肷��PCR�����ɂ��ƁA3��22�`28���ɕ��͂����I�~�N�����^�Ƃ݂��錟�̂̂���67.8%��BA.2�̋^�����������Ƃ����B52%���������O�T����15.5�|�C���g�㏸�����B
�����s��t��̒������F����́u���@���҂̌����ŃR���i�a���ɂ͗]�͂����邪�ABA.2�̑����ň�Ì���͐g�\���n�߂Ă���v�Əq�ׂ��B4�i�K�̊����A��Ò̐��Ɋւ���x���x�͂��ꂼ��A�ō����x���Əォ��2�Ԗڂɐ����u�����B
�V�K�����҂ɐ�߂�20��̊�����20.6%��3�T�A���ő������A�N��ʂōő��ƂȂ����B��w�̐V������V���Ј��ւ̒lj��ڎ�𑣐i���邽�߁A�s�͑�K�͐ڎ���ŃT�[�N����[�~�Ƃ������c�̐ڎ�̎t�����n�߁A��w�ɂ̓��N�`���o�X���h������B��c��ɃI�����C���ŋL�҉�������r�S���q�m���́u�����ǂ��Ȃ��Ă����ǂƂ͖����ł͂Ȃ��v�Əq�ׁA�ϋɓI�ȃ��N�`���ڎ���Ăт������B
|
 |
���I�~�N�����V�ψي��uXE�v�m�F�@�����͂���ɋ����c�@4/8
7���A�����Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�8753�l�ŁA�O�̏T�̓����j���ɔ�ׁA500�l�]�葝���܂����B
�s���ł́A�I�~�N�������̈��ŁA�����͂������Ƃ����uBA.2�v�ւ̒u������肪�}���ɐi��ł��܂��B�ŐV�̃f�[�^�ł́A���悻7����BA.2�̋^��������Ƃ����Ă��܂��B
���������Ȃ��A����ɐV�����ψي����m�F����܂����B�����J���ȁ@�V�^�R���i��@�A�h�o�C�U���[�{�[�h�E�e�c���������F�u�wBA.1�x�ƁwBA.2�x�̑g�ݑւ��́wXE�x�n���B���̌n���͍��A�C�M���X�ő����m�F����Ă���v
�C�M���X�ȂǂŊm�F���ꂽ�A�I�~�N�����̕ψي��uXE�v�BWHO(���E�ی��@��)�ɂ��ƁA�������L����X�s�[�h��BA.2����10���قǑ����Ƃ��Ă��܂��B
���씎�ꊯ�[�����F�u�����_�ł́A���u�⍑���ɂ����āA�wXE�x�n���̕ψي����m�F���ꂽ�Ƃ͎̕Ă��܂���v
|
���V�^�R���i �V�K�����Ґ� 32���{���őO�T��葝�� �@4/8
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł͐�T�ɑ����Ċɂ₩�ȑ����X���ŁA32�̓��{���őO�̏T��葽���Ȃ��Ă��܂��B��s���Ȃǂł͉����ƂȂ��Ă������A��B�Ȃǂő����̕�����r�I�傫���Ȃ��Ă���Ƃ��������A�n��ɂ���Ċ����ɍ����o�Ă��܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S��
�挎10���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�ɔ�ׂ�0.86�{�A�挎17����0.90�{�A�挎24����0.76�{��6�T�A���Ŋɂ₩�Ȍ����������Ă��܂����B�������A�挎31����1.17�{�Ƒ����ɓ]���A����7���܂łł�1.04�{��2�T�A���Ŋɂ₩�ȑ����X���ŁA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻4��7200�l�ƂȂ��Ă��܂��B�����Ґ���32�̓��{���őO�̏T��葝���Ă��āA��s���Ȃǂł́A�قډ����ɂȂ��Ă������A��B�Ȃǂő����̕����傫���Ȃ��Ă��܂��B
�����ꌧ
�l��������̊����Ґ����ł������̂����ꌧ�Ő挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.06�{�A�挎31����1.32�{�A����7���܂łł�1.29�{��3�T�A���ő����X���ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ���1121�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���534.73�l�ƁA�S���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
����s��(1�s3��)
�y�����s�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.78�{��6�T�A���Ŋɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��܂������A�挎31����1.19�{�A����7���܂łł�0.99�{�Ɖ����ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻7433�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���370.41�l�ƁA���ꌧ�Ɏ����őS����2�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�y�_�ސ쌧�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.72�{�A�挎31����1.01�{�A7���܂łł�1.01�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3837�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y��ʌ��z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.81�{�A�挎31����1.23�{�A����7���܂łł�0.90�{�ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ���3374�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���321.56�l�ƁA���ꌧ�A�����s�Ɏ����őS����3�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�y��t���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.74�{�A�挎31����1.17�{�A����7���܂łł�1.03�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2680�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����(2�{1��)
�y���{�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.66�{�A�挎31����1.10�{�A����7���܂łł�1.06�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3750�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���s�{�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.66�{�A�挎31����1.28�{�A����7���܂łł�1.04�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻917�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���Ɍ��z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.70�{�A�挎31����1.09�{�A����7���܂łł�0.99�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ���1829�l�ƂȂ��Ă��܂��B
������(3��)
�y���m���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.75�{�A�挎31����1.14�{�A����7���܂łł�1.00�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2506�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.80�{�A�挎31����1.24�{�A�����܂łł�1.17�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ���561�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�O�d���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.73�{�A�挎31����1.45�{�A����7���܂łł�1.19�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻585�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���ق��̒n��
�y�k�C���z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.93�{�A�挎31����1.20�{�A����7���܂łł�1.15�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1964�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�L�����z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.90�{�A�挎31����1.37�{�A����7���܂łł�1.09�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻976�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�������z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.75�{�A�挎31����1.25�{�A����7���܂łł�1.07�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2257�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����ŁA�����̕�����r�I�傫���Ȃ��Ă���n�������A�������͍���7���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.29�{�A�V������1.29�{�A�a�̎R����1.43�{�A��������1.28�{�A���茧��1.29�{�A�F�{����1.31�{�A�啪����1.27�{�A�{�茧��1.61�{�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ɓu�n�捷�͉ߋ��̊������e���̉\���v
�����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́A���݂̊����ɂ��āu�����̍Ċg�傪�����Ȏ����̂Ƃ����łȂ��Ƃ���ŔZ�W���݂��Ă��Ă���B���N�`���̒lj��ڎ헦�Ȃǂɂ͎����̂��Ƃ̍��͂��܂�Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��ẮA��������Ȃǂ̑�s�s���ł́A���łɊ��������l�������A���R�ɖƉu�����Ċ����̊g�傪�}�����Ă���̂ɑ��A����܂Ŕ�r�I�A���������Ȃ������Ƃ���ŁA���߂čL�����Ă��Ă���\��������v�Ǝw�E���Ă��܂��B
����̌��ʂ����ɂ��Ắu�I�~�N�������́A�����͂���苭���Ƃ����wBA.2�x�n���̃E�C���X�ɒu��������Ă����Ƃ݂���B���E�I�ɂ͂قƂ�ǂ̍��Œu��������Ă��āA���[���b�p�ł�9�����Ă��鍑������B���{�ł�����́A�ڐG�@������炵�Ȃ���A�\�h��������������߂ɍs�����Ƃ�A�lj��ڎ��i�߂邱�ƂȂǂ��厖���B����20��̊����҂������Ȃ��Ă���̂ŁA���̐���ւ̑đ������y���ł��邩�ǂ����̃J�M�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A�����̃I�~�N���������g�ݍ��킳�����uXE�v�ƌĂ��V���ȕψكE�C���X�ɂ��́A�u���o�������Ȃ��A�܂��͂�����������킩���Ă��Ȃ����A�����͂́wBA.2�x���́A��⋭�����낤�Ƃ������Ƃ͂킩���Ă���B��{�I�ɂ͂���܂ł̑�ŏ\���h����ƍl�����A����قǐS�z����悤�ȏɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�����A�V���ȕψكE�C���X�������Ō��o�ł���̐��́A���}�ɐ����Ă����K�v������v�Ƙb���Ă��܂��B
|
�������s�ŐV����8112 �l�����A 9�l���S�@�a���g�p��25.2�� �@4/8
�����s��8���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ�����8112�l��9�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B1���̊����Ґ��́A1�T�ԑO�̋��j���ɔ�ׂ�130�l�������B�d�ǎ҂͓s�̊��30�l�B�a���g�p����25.2%�B
�V���Ȋ����҂̂����A�����������Ɉ�t�̔��f�ŗz���Ƃ݂Ȃ��u����^���NJ��ҁv(�݂Ȃ��z����)��9�l�B 1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���8�����_��7451.9�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�97.7���B�s���̗v�̊��Ґ���131��796�l�ƂȂ����B �����҂�20�オ�ł�����1785�l�B10�Ζ���1165�l�A10��990�l�A30��1576�l�A40��1256�l�A50��725�l�ŁA65�Έȏ�̍���҂�445�l�������B �S���Ȃ����l��80�`90��̒j��9�l�B
|
������Ŋ����҂��Ăё����A�u�܂h�~�v�ēK�p��������������{ �@4/8
���{�́A���ꌧ�ȂǂŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂��Ăё������Ă��邱�ƂɁA�x�������߂Ă���B�����́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�v��������ɓ���邪�A���{�͏d�_�[�u�͌o�ςւ̈��e�����������Ȃ��Ƃ��āA�ēK�p�͉\�Ȍ������������l�����B
���슯�[������8���̋L�҉�ŁA���ꌧ����K�p�v�����������ꍇ�̑Ή������A�u�ی���Ñ̐�����������Ɖғ������邱�Ƃ���{�ɁA�������Â̏𒍎����A�K�ɑΉ�����v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂��B����܂Ŋݓc���t�͓s���{���̗v���ɑS�ĉ����Ă������A����͐T�d���B
������8���̐V�K�����Ґ���1328�l�ŁA�O�T�̓����j����17���A���ŏ������B�ʏ�f�j�[�m����7���̋L�҉�Łu�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ���Ώd�_�[�u���܂߂�����Ȃ鋭���[�u���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B
���{�́A�d�_�[�u�̓K�p���f�ŏd������a���g�p���������ł͂܂�5���ɒB���Ă��Ȃ����ƂȂǂ���A���炭���s�̊�����̌��ʂ������l�����B�����̕a���g�p����1��29����70�E6�����s�[�N�ɁA2��21���̏d�_�[�u������������X���ɂ������B�����A4���ɓ����đ����̒���������A8�����_��39�E9���ƂȂ��Ă���A���{�͊����𒍎����Ă���B
�Ċg��ɓ]�����ꍇ�ł��A���H�X�̉c�Ǝ��ԒZ�k�Ȃǂ̌������[�u�͎��Ƒ����Ȃǂō��������ɑ傫�ȉe�����o���˂Ȃ����Ƃ���A���{������Ƃ̊Ԃł��T�d�Ȑ����o�Ă���B
8���ɊJ���ꂽ���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�ł́A�Ċg�厞�̍s�������ɂ��Ď^�ۗ��_���o���B���g�Ή�͉��A�L�Ғc�Ɂu�o�ς����Ƃ������̍��ӂ͓���ꂽ���A�����ɂ��Ă͂��܂��܂Ȉӌ����o���v�ƌ�����B
|
���ʏ�m���u��7�g�ɓ˓��v�@�܂h�~�v���������@4/8
���ꌧ�̋ʏ�m����7���A�u��7�g�ɓ˓������v�Əq�ׁA�܂h�~���d�_�[�u�̗v��������ɑΉ�����l�����������B
���ꌧ�E�ʏ�m���u�S�Ă̔N��ɂ�����V�K�z���҂������X���ɂ��邱�ƂɊӂ݂�ƁA���͂��7�g�ɓ˓��������̂ƔF��������Ȃ��v
���ꌧ�ł�7���A�V����1,355�l�̊������m�F���ꂽ�B6���܂ł̐l��10���l������̐V�K�����҂̐���513.36�l�ƁA�S�����ς̂��悻2�{�ŁA�S�����[�X�g�ƂȂ��Ă���B
���ꌧ�E�ʏ�m���u���̂܂܊����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ���A�܂h�~���d�_�[�u�̗v�����܂߂�����Ȃ鋭���[�u���������Ȃ���Ȃ炸�A�c�O�Ȃ���A5���̘A�x�͊O�o�Ȃǂ����l���邱�ƂɂȂ炴��Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��v
�ʏ�m���́A�������������h�~���Ăт������B
|
��3��ڃ��N�`���A��Ґڎ���@�����Ċg��ŃR���i���ȉ�@4/8
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�(���g�Ή)��8���A�����s���ʼn���J�����B
�����Ċg��̒�������n�悪���邱�Ƃ���A��҂��܂߂����N�`��3��ڂ̑����ڎ�����߂���܂Ƃ߂��B����A�����}�g�厞�̑�����肷�邱�Ƃł���v�����B
���g���͂��̌�̋L�҉�Łu�������s�s���ō��~�܂肵�A�n���ł͏㏸���Ă���Ƃ��������A�����g�債�Ă����������Ȃ��w�i������v�Ǝw�E�B����̐��ڂɂ���ẮA�܂h�~���d�_�[�u���ēK�p����K�v���o�Ă���Ƃ̔F�����������B�@ |
 |
���V�^�R���i�@�X�E���E�H�c�E�R�`�E�����̊����ҁ@4/9
���X512�l
�X���Ȃǂ�8���A10�Ζ�����80�Έȏ���܂ޒj��512�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�����̊����m�F�͌v4��118�l�ƂȂ����B�݂Ȃ��z��34�l�������V�K�����҂̓���͍O�O�ی����Ǔ�104�l�A���ˎs95�l�A��\�O�ی���(�\�a�c�s)�Ǔ�84�l�ȂǁB���쌴�ی����Ǔ��̒��w�Z�Ȃ�4���̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
�����343�l
��茧�Ɛ����s��8���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��343�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͐����s63�l�A���B�s57�l�A�k��s21�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v2��504�l�B�����ی���(�Ԋ��s)�Ǔ��̊w�Z�ŃN���X�^�[�����������B���́A���\�ς݂̊����Ҍv7�l����I�~�N�������̔h���^�u�a�`�E2�v�����o���ꂽ�Ɣ��\�����B
���H�c365�l
�H�c���ƏH�c�s��8���A10�Ζ����`80��̒j��365�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�ی����ʂ͓��s159�l�A���63�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v1��8681�l�B���Ǔ��̕ۈ牀�ŃN���X�^�[�����������B
���R�`158�l
�R�`���ƎR�`�s��8���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��158�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͎R�`�s51�l�A�߉��s25�l�A��c�s24�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v1��8966�l�B�߉��s�̈��H�X�Ȃnjv3���̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
������642�l
��������8���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��642�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͌S�R�s213�l�A���킫�s134�l�A�����s68�l�A��Îᏼ�s50�l�ȂǁB�����̊����҂͌v4��317�l�B70��j�������S���A���҂͌v200�l�ƂȂ����B�����s�̐ڑ҂����H�X�Ōv7�l���������A���̓N���X�^�[�ƔF�肵���B����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�z���҂�210�E78�l�A�×{�҂�4888�l�ɒB���A�����g�傪�����Ă���B
|
���f�v���s��\�肵�Ă���l��1���@�u�܂�h�v���Ԓ��̏���ҐS���@4/9
��ށE�H�i���̔̔�����|����J�N���X(�����s�k��)�́A���Ђ̃��[���}�K�W���ɓo�^���Ă��郆�[�U�[��ΏۂɁA�u���N(2022�N)�̃S�[���f���E�C�[�N���s�v�ɂ��ăA���P�[�g���������{�����B�S�[���f���E�C�[�N���Ԓ�(4��29���`5��8��)�ɗ��s����\�肪���邩�������Ƃ���A�ł����������̂́u�Ȃ��v(49.6��)�������B
�����Łu�܂����߂Ă��Ȃ��v��40.1���A�\�肪�u����v��10.3���������B
3��21���܂œ����s�Ȃǂ��u�܂h�~���d�_�[�u�v�̎��{���Ԓ��������B���̊��Ԓ��ɒ��������{�������Ƃ���A���Ђ́u�悪���ʂ����\������߂���Ȃ��ł��邱�Ƃ�����������v�ƃR�����g�����B
���s����\�肪�u����v�Ɠ������l�ɁA���s�̗\��(�h����A�q�A�����^�J�[�A�V�����Ȃ�)���ς܂������ǂ�����q�˂��Ƃ���A�u�͂��v�Ɠ������l��48.0���A�u�������v��52.0���������B
���v�悷��ۂɋC����������
���s���v�悷��ۂɋC���������Ƃ����B�ł����������̂́u���l���ōs���v�u�����̌�ʋ@�ւ��g��Ȃ��v�łƂ���40.0���A�����Łu�s����͉����ł͂Ȃ��A�ߏ�ɂ���v��24.0���A�u�I�V���C�t���q����[�H�����o���ȂǁA��������T�[�r�X�̂���h�����I�ԁv��20.0���������B
�����̒����ǂ��Ȃ�Η��s���Ă݂悤�Ǝv���H
����ŁA���s�̗\�肪�u�Ȃ��v���邢�́u�܂����߂Ă��Ȃ��v�Ɠ������l�ɁA���̒����ǂ��Ȃ�Η��s���Ă݂悤�Ǝv������q�˂��B�ł����������̂́u�V�K�����Ґ����啝�Ɍ�������v��43.3���A�����Łu�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ��(������)�v��31.3���������B
���݁A�܂h�~���d�_�[�u�͉�������Ă��邽�߁A�J�N���X�́u�܂����߂Ă��Ȃ��Ɖ��Ă����l�̒��ɂ͗��s���v�悷��l���o�Ă����\��������v�ƕ��͂���B
�u�������C�ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ����AGo To�g���x���Ɋ��҂��ėl�q�����Ă���v�Ƃ��������������B���Ђ́A�u�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��őŌ��������s�ƊE����H�ƊE���������A�����ɗ��s���y���߂鍑�̎{���S�҂��ɂ��Ă���l������悤���v�ƃR�����g�����B
���L�����Z�����ɂ��Ăǂ��v���H
���s���L�����Z��������Ȃ��ɂȂ�����L�����Z�����ɂ��Ăǂ��v���������Ƃ���A�ł����������̂́u�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��L�����Z���ɂ��Ă͔z�����Ăق����v��45.9���ɏ�����B�����ŁA�u�L�����Z�������͔̂��������̂ŁA���炩���߃L�����Z�����̔������Ȃ��v������I�ԁv��29.8���Ƃ������ʂɁB�u�ǂ�ȗ��R�ł���A�x�����͓̂��R���Ǝv���v��17.8���ɂƂǂ܂����B
���R�ɂ́u���R�ɂ�炸�x�����ׂ����Ǝv�����A���ꂪ���s����ӗ~���킢�ł���ʂ�����v�Ƃ����ӌ����������B
(�������Ԃ�3��14�`17���A����242�l�B)
�@ |
 |
�������s �V�^�R���i �V����8026�l�����m�F �O�T���127�l���� �@4/10
�����s����10���̊����m�F��8026�l�ŁA1�T�ԑO�̓��j�����127�l�����܂����B
�����s��10���A�s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v�܂ł�8026�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����127�l�����܂����B�܂��A10���܂ł�7���ԕ��ς�7571.0�l�ŁA�O�̏T��99.2���ł����B10���Ɋm�F���ꂽ8026�l��N��ʂɌ���ƁA�u20��v���ł������A�S�̂�19.6���ɓ�����1576�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�422�l�őS�̂�5.3���ł����B
����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A10�����_��29�l�ŁA9���Ɠ����ł����B���S�����l�̔��\�͂���܂���ł����B
|
�������̃R���i�V�K�����҂�4��9172�l�A�V���ł͍ő��X�V�@4/10
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�10���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����4��9172�l�m�F���ꂽ�B�V������896�l��1��������̐V�K�����҂��ߋ��ő����X�V�����B�S���̎��҂�39�l�ŁA�d�ǎ҂͑O�����5�l������484�l�������B
�����s�ł́A�V����8026�l�̊����������B1�T�ԑO�̓����j���Ɣ�ׂ�127�l�����A4���A���őO�T���������B�d�ǎ҂͑O���Ɠ���29�l�ŁA���҂̔��\�͂Ȃ������B
����1�T�Ԃ̐V�K�����҂̕��ς�7571�l�ŁA1�T�ԑO�Ɣ�ׂ�0�E8�����������B
|
���S���̊����� 4��9000�l���@�d�ǎ�4���A��500�l����� �@4/10
10���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂́A4��9,172�l�������B
�����s�ł�8,026�l�̊����҂��m�F����A��T���j������127�l�����A4���A���őO�̏T�̓����j�����������B�܂��A�S���Ȃ����l�͂��Ȃ������B���҂����Ȃ������̂́A3��28���ȗ����悻2�T�ԂԂ�B�I�~�N�������̓������ӂ܂����w�W�ɂ��d�ǎ҂�63�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����7.8%�ƂȂ��Ă���B
���̂ق��A�_�ސ쌧��4,098�l�A���{��3,652�l�m�F����A�V�����ł͉ߋ��ő��ƂȂ�896�l�̊�������������ȂǁA�S���ł�4��9,172�l�̊����ƁA39�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
����A9�����_�ł̑S���̏d�ǎ҂�484�l�ŁA�O�̓�����5�l����A4���A����500�l��������Ă���B
|
���ό��q�œ��키���R�̐l�o��60�����@�u�܂h�~�v���������3�T�� �@4/10
���E���s�E���ɂł܂h�~���d�_�[�u����������Ă���܂��Ȃ�3�T�Ԃł��B4��10���̑��{�̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�3652�l�ŁA����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͂��̑O�̏T�ɔ�ׂđ������Ă��܂��B
�����͂���苭���Ƃ����I�~�N�������̈���u�a�`�D2�v�ւ̒u���������i�ޒ��A�����Ґ����Ăё����X���ɂ��邱�Ƃɂ��āA10���A���E�~�i�~�̊X�Řb���܂����B
�u(�����X����)������ƐS�z�v�u����ς�|���ł��v�u(�����Ґ���)�O�̂悤�Ɉӎ����Ă��邩�Ƃ�����ƁA���Ă��Ȃ��ł��B�����ƃ��N�`�������ł��Ă���A���ƕa����������Ȃ�Ƃ��Ȃ邩�ȂƎv���v
����A�t�̊ό��V�[�Y���^�������̋��s�E���R�B10���A�ό��q��ɘb���Ɓc�B
�u(�l�o��)�������ł��ˁB�т����肵�܂����v�u��7�g�������獢��B�₾�ȂƁv
���s�E���R���ӂł�9�����ߌ�3����̐l�o��1�����O�Ɣ�ׂ�60�����ƂȂ��Ă��āA���̂��̂ق��̎�ȉw���ӂł��l�o�͑����X���ɂȂ��Ă��܂��B
|
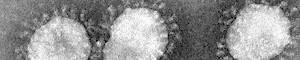 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���u�܂h�~�v�������Ă���܂�1�J���o���Ă��Ȃ��̂Ɂc�u��7�g�v�̌��O�@4/11
���{�ł͐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�ł���u�܂h�~���d�_�[�u�v(�ȉ��A�u�܂h�~�v)����������Ă���܂�1�J�����o�߂��Ă��Ȃ����A�Ċg�U�ɑ��Č��O�̐������܂��Ă���B
10���A�m�g�j�W�v�ɂ��ƁA���{�����̐V�K�����Ґ���9������Ƃ���5��2741�l�ŁA�挎22���Ɂu�܂h�~�v������������(2��227�l)�̔{�ȏ�ɑ��������Ƃ����������B�����J���Ȃɂ��ƁA5����̐V�K�����Ґ��͑O�T��1�D08�{��2�T�A���ő��������B
���{�ł͐V�^�R���i�̕ψي��E�C���X�ł���I�~�N�����̊g�U�ŁA2��5��(10��5591�l)�ɍő������҂����ꂽ�B���{���{�́u�ً}���Ԑ錾�v�����Љ�I�����m�ۂ̐������Ⴂ���A���X�g�����Ȃǂł̉c�Ǝ��Ԑ���������u�܂h�~�v�����{���Ȃ���g�U���Ǘ����A�錾����2�J����̐挎22���ɂ�������������B
���{���{�́u�܂h�~�v������A10�`20��̐N�w�Ŋ��������������ƕ��͂����B���ہA�m�g�j�������s�𒆐S�Ɋ����͂�������(9���)�ɂ��ƁA��N�w�ւ̊����g�U���ڗ����Ă����B��N12���ɂ́A�����ґS�̂�16����10��ȉ��A24����20�ゾ�����B�����A���N3������10��(33��)��20��(16��)�̊��������������Ƃɑ����A4���ɓ����Ă����10��(28��)��20��(22��)�������ґS�̂̔������߂�悤�ɂȂ������Ƃ����������B
���u��7�g�v������H�c�S�[���f���E�C�[�N�T���Č��O���܂�
�����ʐM��7��ڂ̍Ċg�U���Ӗ�����u��7�h�v�̉\�����w�E������Ƃ̐������܂��Ă���Ɠ`�����B�R�ۑ�u�Y�E�o�ύĐ��S����������8���A�u�S���I�Ɍ����Ƃ��A�V�K�����Ґ���1�T�Ԉȏ㑝�����Ă���v�Ƃ��Ċ����Ċg�U�����O�����B�I�~�N����������ԍŏ��Ɋg�U�������ꌧ�ł́u���łɑ�7�g�ɓ˓������v�Ƃ����咣���o�Ă����B�����ʐM�͌����J���Ȋ����̔��������p���A4�����{����5�����߂܂ő������{�̑�^�A�x�u�S�[���f���E�C�[�N�v�̎��ɂ͊����͂̍����I�~�N�����n�̕ʂ̃E�C���X(�a�`�D2)�̔䗦��90���ȏ�ɂȂ邾�낤�Ɛf�f�����B
����w���̃u�[�X�^�[�V���b�g�ڎ�����߂�c�����x����
���{���{�͐��Ɖ�c�Ɋ�Â��č���̊����g�傪10�`20��̎�N�w�𒆐S�ɋN���Ă���ƕ��͂����B65�Έȏ�̍���҂̃u�[�X�^�[�V���b�g(3���ڎ�)�ڎ헦��80��������Ԃ����A10�`20���20����ɗ��܂��Ă��Ċ������₷�����Ƃ����w�E���B���{�̃u�[�X�^�[�V���b�g�̐ڎ헦��44�D3�����B
�����g�U�͒n��ʂɂ��ڂɕt���n�߂Ă���B�����s��5������1�T�ԕ��ς̐V�K�����҂��O�T��1�D04�{�ɒB�������A���m���Ƒ��{��0�D97�{�������B��s�s�ł͊����g�U���}������Ă��邪�A���ΓI�ɐl���̏��Ȃ��{�錧��1�D68�{�A�啪����1�D39�{���L�^���Č����ȑ����X�����������B
���{���{�͐N�w�̃u�[�X�^�[�V���b�g�ڎ�𑝂₷���߂ɍ����x���J�[�h�����o�����B���@�ɂ��ƁA�ݓc���Y��7���̋L�҉�Łu�����̂Ƒ�w�����A�g���A�\��ɋ̂��鎩���̂̑�K�͐ڎ��ꓙ�����p���āA�w���ւ̏W�c�ڎ�𑣐i����v�Ƃ��u���̍ې�������p�������x������v�Ɩ��炩�ɂ����B�ڎ�ꏊ�܂ł̌�ʔ�����{���x�����A��w�̏W�c�ڎ�𑝂₷�Ƃ�����|���B
����A�ݓc�͊����Ċg�U�Ɋ֘A���āu�x�������邢�͊�@�����������莝���Ȃ���A�����Ǒ�ƎЉ�o�ϊ��������Ă����v�Ɛ��������B
|
���R���i�V�n���u�w�d�v���{�����̌��O...�I�~�N�����a�`�E2��荂�������́@4/11
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��̂����A�]�����������͂������Ƃ����V���Ȍn���u�w�d�v���p���ȂǂŊm�F����A���{�ւ̗��������O����Ă���B�w�d�́A���ݓ��{�ŗ��s���Ă���I�~�N��������2�n���̈�`�q���������Ă���A���㗬�s���g�債�Ă������������Ƃ����B
���E�ی��@��(�v�g�n)�ɂ��ƁA�w�d��1��19���ɉp���ŏ��߂Č��o����A3��29�����_�Ŗ�600���̏ǗႪ�m�F���ꂽ�B�����ő�6�g�������炵���I�~�N�������̎嗬�^�u�a�`�E1�v�ƁA���݊����҂������Ă���h���^�u�a�`�E2�v�̈�`�q���������Ă���B�����ɓ����Ɋ��������l�̑̓��ŁA�E�C���X�̈�`�q�̑g�݊������N���Ăł����Ƃ݂���B
�w�d�͊����͂��a�`�E2���10�������Ƃ���Ă���B���N�`���̗L�����ȂǏڂ��������͂킩���Ă��炸�A�v�g�n�́u����Ȃ�m�F���K�v�v�Ƃ��Ă���B
�����J���ȏ����@�ւō����߂�e�c�����E���������nj���������6���A�w�d�ɂ��āu�d�Ǔx�Ƃ̊֘A�͂܂��悭�킩���Ă��Ȃ��B���u�ł̃Q�m����͂𑱂��邱�Ƃ��K�v�v�Əq�ׂ��B���Y���E���s�勳��(���_�u�w)�́u�����܂������ړ��������ɂȂ�ƁA�I�~�N����������u�������\���������v�Ǝw�E����B
����A���B�ł́A��5�g�Ŗ҈Ђ�U������f���^���ƁA�I�~�N�������̂a�`�E1�̈�`�q�����������u�w�c(�f���^�N������)�v��80��ȏ㌩�����Ă���B��������ڂ��������͂킩���Ă��Ȃ��B
�w�d���f���^�N�����������{�ł̕�͂Ȃ����A���J�N��E�����_�H�勳��(�E�C���X�w)�́u�C�O���痬�����Ă��f�����������߂���悤�ɁA�Ď��̐��𐮂��Ă����ׂ����v�Ƙb���B |
��4��ڐڎ������� �`�V�^�R���i�A���Ƃ��` 4/11
�܂h�~���d�_�[�u���S���ʼn������ꂽ���A�V�^�R���i�E�C���X�E�I�~�N�������̐V�K�������I������C�z�͂Ȃ��B�f���^���̐V�K���Ґ��⎀�S�Ґ���}���Ă����A�����E�̗D�������ł��鍁�`��؍��A�����A�j���[�W�[�����h�A�V���K�|�[���Ȃǂ̍��X�ł��I�~�N�������̏o���ɂ��l���͈�ρB�����ݑ�K�͂Ȋ����g�傪�N���A���Ă̐V�K���Ґ���啝�ɏ������B���Ƃ͂��������܂��A4��ڂ̃��N�`���ڎ������ɓ����悤���Ă���B
���u�I�~�N�������A�y�ǁv�͊ԈႢ
�����ǂɏڂ������J���v�E�c����w�q������(������)�́u�I�~�N�������̊����҂́A�f���^���ɔ�ׂČy�ǂƌ����Ă���B�������A�w����͑����̐l�����N�`����ڎ킵�Ă�����ʂŁA�y�ǂɌ����邾�����x�Ƃ����ӌ����o�Ă����B�I�~�N�������͌y�ǂƂ݂�X���͊댯���v�Ƃ��A�u�D������\�̍��`�ł́A�I�~�N�����������������s���N���������A���N�`����ł��Ă��Ȃ�����҂��������S���A�s�[�N���̉��ď���������ɂ߂č������S�����L�^�����v�Ƒ�����B
�p����t�����X�A�h�C�c�Ȃǂ̉��ď����ł��ŋ߁A�����͂̋����I�~�N�����ψي�BA.2�n���̏o���ƂƂ��ɁA�ĂсA�V�K���Ґ��������X���ɓ]�����B���Ăł́A����܂ł̓���������}�X�N���p�`���Ȃǂ��~���A���X�g������p�u�̉c�Ƃ��ĊJ�����Ă��邱�Ƃ��W���Ă���ƍl������B���J�����́u����͂����܂ł��A�����I�Ȕ��f���D�悳��Ă���v�Ǝw�E����B
�����̊����g��ɔ�����
���{�ł͐V�N�x���}���Đi�w��A�E�A�E��̐l���ٓ��ȂǂŐl�̓������傫���Ȃ����B���J�����́u���̊����g���z�肵�A���̒��ň��̌x���𑱂��Ȃ��珙�X�ɃR���i�O�̓��퐶�������߂��Ă����ׂ����v�Ƙb���ƂƂ��ɁA4��ڂ̃��N�`���ڎ���������ׂ����Ƃ��Ă���B
�u����̐V�K���Ґ��������Ă���̂́A�I�~�N�������̋}�����Ɣ�ׂĂ̘b���B�f���^�����s���ɔ�ׂ�A���݂ł����{�̊��Ґ��ɂȂ��Ă���B���{�ł��A���N�`���ڎ�̌��ʂƎv���邪�A�I�~�N�������������҂��d�lj�����m���͒Ⴂ�B�������A���҂̕ꐔ���傫����Έ��̏d�NJ��҂��o�āA�Ή������Ë@�ւ��N��(�Ђ��ς�)����\��������v�ƁA ���J�����͌���͂���B
�����N�`�����ʒቺ�����O
���J�������S�z����̂́A�I�~�N�������ɑ���t�@�C�U�[��f���i�̃��N�`���̔��a�h�~���ʂ��啝�ɒቺ���Ă���_���B2��̃��N�`����ڎ킵�Ă��A4�`5�J���o�߂���ƁA���a�h�~���ʂ�10���O��ƁA�قƂ�nj��ʂ��Ȃ����x���܂ʼn�����B�u�[�X�^�[�ƌĂ��3��ڂ̐ڎ����ƈꎞ�I��70���܂ŏ㏸���邪�A2�`3�J���ŁA40�`50���ƍĂуM���M���̗L�����ɒቺ����B�����͂̋����I�~�N�������ɑ��āA���N�`���ł͏\���Ȕ��Ǘ\�h����S�ۂł��Ȃ��B�����A���N�`���́A�d�lj��h�~�ɂ�50���ȏ�̗L������ۂ��Ă���B
�u���ł����Ƃ��Ă̓��N�`����3��ڂ̐ڎ���}���Ŏ��{���ׂ��ŁA���̏�ō���̃E�C���X�̕ψقȂǂɔ�����B�ǂ̂悤�ȊԊu�ŁA�ǂ̂悤�Ȑl�ɁA4��ڂ̃��N�`���ڎ�����{���Ă������A�����I�Ȍv��𗧂Ă邱�Ƃ��K�v���낤�v�Ɛ��J�����͌����B
���D���������̃W�����}
�u���܂łɑ����̊��҂��o�������ď����ł́A����������ĖƉu���l�������l�̔䗦���l����20�`40���Ƃ��Ȃ荂���B���Ґ������Ȃ��}�����D���������ł́A����Ȃ��ƂɊ����ɂ��Ɖu�����l�̊����͒Ⴍ�A���{�ł�5���������Ȃ��v�B���J�����́u���N�`���ɂ�蓾��ꂽ�Ɖu�̌����͑����Ǝv����̂ŁA���{�ł́A4��ڂ̃��N�`���ڎ���������ׂ����낤�v�Ƙb���B
�܂��A�u4��ڐڎ�̃^�C�~���O�́A����҂�d�lj����X�N�̍������a�����l��3��ڐڎ��4�`5�J���A��ÊW�҂�6�J������߂ǂɐڎ킷��̂��]�܂����v�ƌ����B���̏�Łu��ʂ̐l�X�ł́A�u�[�X�^�[�ڎ��̃��N�`�����ʎ����̃f�[�^�����Đڎ펞�������߂�Ηǂ��B�܂��A���N�`�����[�J�[�̓I�~�N�������Ȃǂ̕ψي��ɑΉ�����V���N�`���̊J����i�߂Ă���̂ŁA�����̊J�������Ă��ׂ����v�ƕt��������B
|
����t58���A��7�g�u�n�܂����v�@4/11
�S���e�n�ŐV�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����҂��Ăё����X���ɓ]���Ă���B������������܂��Am3.com����ɑ�7�g�͎n�܂����Ǝv������q�˂��B�@(������4��4���`4��7���Ɏ��{)
��Q1.���łɑ�7�g�͎n�܂����Ǝv���܂����H
�J�ƈ��58.0%�A�Ζ����58.4������7�g�́u�n�܂����v�Ɖ����B
��Q2.��7�g�ɂ����Ă��A�܂h�~���d�_�[�u�ȂNj����K�v�ɂȂ�Ǝv���܂����H
��7�g�ɂ����Ă��܂h�~���d�_�[�u�ȂNj����K�v�ɂȂ邩�A�J�ƈ��40.6���A�Ζ����33.1�����u�K�v�ɂȂ�v�Ɠ������B����ŁA�J�ƈ��35.7���A�Ζ����41.4���́u�K�v�ɂȂ�Ȃ��v�Ɠ����Ă���A�ӌ�������錋�ʂƂȂ����B
��Q3.Q1�EQ2�̂悤�ɉ������R�������Ă��������B
�yQ1�F�n�܂��� / Q2�F�K�v�ɂȂ�z
�E�Ⴂ�l�̃��N�`���ڎ킪�i�܂Ȃ��A��������N�҂Ɉڍs���Ă���B��7�g�́A�m���ɏP���Ă��܂��B(�J�ƈ�))
�E�����Ȃ������ȏ�[���ȏɂȂ邩������Ȃ�����B(�J�ƈ�)
�E�Ăѕa�@�@�\�Ɏx�Ⴊ�o�Ă���ɂȂ�Ǝv������B(�Ζ���)
�E��6�g��芴���Ґ�����������������B(�Ζ���)
�E���łɑ������Ă��܂����A�����̐l���Ԍ��┃���������[����ɉ؊X�Ȃǂōs���Ă���A�������͂ǂ����ɐ����Ă���悤�Ɍ����܂��B���̂܂܊����Ґ������R�������邱�Ƃ͍l�����܂���B(�Ζ���)
�E�N���X�^�[�{�݁A�a�@�����Ȃ����ɐV�K�����Ґ��������̂ŁA�s�������ɂ��g�傪�l�����邩��B�l�̓������L���Ȃ�Ί����͊g�傷��̂�5���A�x�O�ɒ��ӂ��������ǂ��Ǝv���B(��t)
�yQ1�F�n�܂��� / Q2�F�K�v�ɂȂ�Ȃ��z
�E�d�ǎ҂������҂ɔ�r���ď��Ȃ����ƁB�G�ߓI�Ȋ����Lj����ł��悢�̂ł͂Ȃ����c(�J�ƈ�)
�E���t���̂Ȃ��܂h�~���d�_�[�u���l����K�v������B(�J�ƈ�)
�E�܂h�~���d�_�[�u�Ȃǂ��s���Ă��A�����}�����ʂ͂��܂���҂ł��Ȃ��B�C�M���X�Ȃǂ̃��[���b�p�A�A�����J�̊������(��7�g)�����Ă��A���̓��{�̏�Ԃ͓��l�ȌX�����݂���B(�J�ƈ�)
�E6�g�̍ۂɂ͂܂h�~�[�u�͂قƂ�Nj@�\���Ă��Ȃ������Ǝv������B(�J�ƈ�)
�E�~�}��Â̓~�̃s�[�N���z�����̂ŁA3��ڂ̃��N�`�����i��A���̓~�̃V�[�Y���܂ł͊ɘa�ł���悤�Ɏv���B���s���n�܂��Ă���Q�Ă�1�����N�`��100����L�����y�[��������̂ł͂Ȃ��A�������R���X�^���g�Ƀ��N�`�������Ă�̐��Ɉڍs�ł���A�l�A�W�c�A��Ë@�ցA�����́A���{�ɂƂ��āA��炵�₷�����ɂȂ�Ǝv���B(�Ζ���)
�E���łɎs���������n�܂��Ă���A�d�_�[�u�͂��܂�L���ȍ�ł͂Ȃ��ƍl�����邽�߁B(�Ζ���)
�E�C�M���X��A�����J�ł͐����P�p�̕����ɓ����Ă���̂ŁA�E�C���X����Ő��̂܂܂Ȃ犴���҂������Ă��܂h�~����s��Ȃ��Ƃ��A�R���i�Ɋւ���K�����ɘa����Ă����Ǝv������B(�Ζ���)
�E�܂h�~�����Ă����܂�Ӗ����Ȃ��B���̒������̂悤�ȃu���[�L�͊|���镗�����Ȃ��B(��t)
�yQ1�F�n�܂��� / Q2�F������Ȃ��z
�E�o�����Ƃ���ňȑO�̂悤�Ȍ��ʂ͖����Ǝv���邩��B(�Ζ���)
�E��w�I�ɂ͕K�v�ƍl���邪�A�C�O�̓������ÊW�҈ȊO�̍s��������Ə��炪�ł��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B(�J�ƈ�)
�E�����͂������Ă��A�d�lj������Ⴂ�̂ł���C���t���G���U�Ɠ��l�̑Ώ��ł��ǂ��Ǝv���B�E�C���X�̓����ɂ��B(�Ζ���)
�yQ1�F�n�܂��Ă��Ȃ� / Q2�F�K�v�ɂȂ�z
�E���܂����m�Ȋ����g�����������������Ȃ�����B�����g������߂�ɂ͍s���̐������K�v�B(�Ζ���)
�yQ1:�n�܂��Ă��Ȃ� / Q2�F�K�v�ɂȂ�Ȃ��z
�E���s���n�܂��Ă���̎��Z�Ȃǂ͈Ӗ����Ȃ��B�s�[�N��������O�ɋK�����Ȃ��ƁB(�Ζ���)
�E�C���t���G���U�����ł����B�Ⴂ�l�͍s�������ɖO���Ă�B(�J�ƈ�)
�yQ1�F������Ȃ� / Q2�F������Ȃ��z
�E�����͍��~�܂肵�Ă��đ�7�g���ǂ����͂킩��Ȃ��B����������͑����Ɨ\�z�����B(�Ζ���)
�E��7�g�ł͂Ȃ���6�g�̑����B���Q�u���I�̔z�B�⊴���O���͎������Ă���B����ł�6�g�������܂炸�ɑ����Ă��銴���ł��B(��t)
�yQ1�F������Ȃ� / Q2�F�K�v�ɂȂ�z
�E�S�[���f���E�B�[�N�����邽�߁A���ʂȑ[�u���Ȃ���Ί����g��ɔ��Ԃ�������Ǝv���B(���̑���Ï]����)
�yQ1�F������Ȃ� / Q2�F�K�v�ɂȂ�Ȃ��z
�E�����̔F�������ׂƂ������o�ɂ�����Ă��Ă���B(�Ζ���)
�E�����̔g�Ƃ������́A������x��퉻���Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B(��t)�@ |
���I�~�N�����h���^�uXE�v�A�������m�F�@��`���u�Ł@4/11
�����J���Ȃ�11���A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψٌ^�u�I�~�N�����^�v����h�������uXE�v�ƌĂ��E�C���X�̊����҂����{�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�Ɣ��\�����B���c��`�ւ̓����҂ŁA�����ł̊����g��͌����_�Ŋm�F����Ă��Ȃ��BXE�̓I�~�N�����^�̂����uBA.1�v�Ɣh���^�uBA.2�v�����������E�C���X�ŁA�d�lj��̂��₷���ȂǏڍׂ͕������Ă��Ȃ��B
�������m�F���ꂽ�͕̂č��ɑ؍ݗ�������30�㏗���ŁA3��26���ɐ��c��`�ɓ��������B�������̌����ŗz���ƂȂ�A���������nj���������`�q�z��̏ڍׂȉ�͂��s���Ĕ��������B�Ǐ�͂Ȃ��A�z���Ҍ����̎{�݂�9���ԗ×{���Ă��łɑޏ����Ă���Ƃ����B���N�`����2��ڎ�ς݂������B
���J�Ȃɂ��ƍq��@���̔Z���ڐG�҂�3�l�������B�����L�����܂߁u�ڍׂ��m�F�����v(����)�Ƃ����B
XE�͂���܂łɉp����č��ȂǂŊm�F����Ă���B����������XE�ɂ��āu�����҂̑������鑬�x��BA.2���12.6%�����v�Ƃ̊C�O�̕����p���A�������̍����ɒ��ڂ��Ă���B
|
 |
�������g��̉���ɐ��{�A���v���@15���܂Łu�@���I�ȑΉ��v�@4/12
���씎�ꊯ�[������12���̋L�҉�ŁA���ꌧ�ł̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ��̊g����A���t�R�c����4�l��A���v���Ƃ��Č����ɔh������Ɣ��\�����B���@��W�Ȓ��Ƃ̏�L���ړI�ŁA15���܂ł̗\��B�u�@���I�ȑΉ����\�ƂȂ�悤�ٖ��ȘA�g��}��v�Əq�ׂ��B
���{�͊����}�g�����1��7���ɂ��A���v��������ɔh�����A��9���ɂ͂܂h�~���d�_�[�u��K�p���Ă���B���쎁�͉���̌���ɂ��āA10���l������̐V�K�����Ґ����S���ő��ɂȂ��Ă���Ƃ��u�����ւ̈ڍs���Ԃ��v�Ƌ����A�������Ò̐��𒍎����đΉ�����l�����������B
|
���Ɩ��p�r�[���̔����X���@�܂h�~�����ɂƂ��Ȃ� 4/12
�Ɩ��p�r�[���̔̔����A�X���B�r�[�����e�Ђ����\�������A����u��3�̃r�[���v���܂�3���̃r�[���ނ̔̔����ʂ́A�O�̔N�̓������Ɣ�ׂāA�T���g���[��3���A�T�b�|����1���A�A�T�q�͔̔��z��15���A���ꂼ�ꑝ�������B�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ���ƂɂƂ��Ȃ��A�Ɩ��p���X���ɂȂ��Ă��邱�ƂȂǂ��v���B����A�L������2021�N�A����s�����D�����������Ƃɂ�锽���Ȃǂɂ��A�̔����ʂ�4���̌����ƂȂ��Ă���B |
���I�~�N�������h���^�uXE�v�A�����͂�d�Ǔx�́@���{�ŏ��m�F�@4/12
�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������h���^�uXE�v�̊����҂�4��11���A���{�����ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�BBA�E2��芴�����L����₷���\�����w�E����Ă��邪�A���������nj������̕��͂���ɓ����ׂĂ݂��B
���J�Ȃɂ��ƁA��������������30�㏗����2022�N3��26���ɐ��c��`�ɓ����B�č��ɑ؍ݗ�������A���Ǐ����B�������̌����Ŋ������m�F���ꂽ���ߗz���җp�̎{�݂ŏ���̊��ԗ×{���A���̌�ޏ������B�ăt�@�C�U�[�����N�`����2��ڎ�ς݂������B���������nj������������̌��̂̈�`�q�z����ڂ�����͂������ʁAXE�Ɣ��������B
���uXE�v�Ƃ�
���E�I�ȃI�~�N�����������҂̋}���A������BA.1�n������BA.2�n���ւ̒u������肪�i�s���钆�ŁA���E�e�n���炱���̑g�����̂�����Ă���AXE�͏]���^BA.1�Ɣh���^BA.2�̈�`��������Ă���B
���uXE�v�̊����͂�
XE�n���́A�C���O�����h�ł̓R�~���j�e�B�`�d���m�F����Ă���A�����҂̑������鑬�x��BA.2���12.6���������Ƃ�����Ă���B����3�T�ԂɌ����20.9%�����Ƃ̉�͌��ʂ����邪�A�܂��ڂ����������Ă��Ȃ��B�C���O�����h�ł�4��5�����_��1125��������Ă��邪�A�S�̂ɐ�߂銄����1�������ƂȂ��Ă���B���{�Ŋm�F���ꂽXE�n���̊����A�p���ŗ��s���Ă�����̂ɗR�����邩�A����Ƃ͈قȂ�ꏊ�Ő������g�����̂ł��邩�̓Q�m��������画�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����B
���uXE�v�̏d�Ǔx��
������������o���ꂽ�Ƃ̕����邪�A�d�Ǔx�Ȃǂ̕ω��Ɋւ���͂Ȃ��B�E�C���X�̊�{�I�Ȑ�����A���N�`���̌��ʂ�BA�E2�Ɠ����ƍl�����Ă���B
���uXE�v�ȊO�Ɋm�F���ꂽ���̂Ƃ�
�܂��A��`�q�z���̓I�~�N�������Ԃ̑g�����̂ƍl�����錟�̂����u�łق���2���̌��o����Ă��邪�A����܂ŕ��ނ���Ă���n���ɂ͊Y�������A�ڂ����^�C�v�����ł��Ȃ��Ƃ����B
�������́uXE�n���Ɍ��炸�A�܂��A�g�����̂Ɍ��炸�A�����g��𒍎����A�����E�`�d����Ɖu��̐����w�I�������啝�ɕω����Љ�ɑ傫�ȃC���p�N�g�������炷�ψي��̔������Ď����Ă����K�v������B���������A���O���̏�m���������W���A�Q�m���T�[�x�C�����X�ɂ��Ď����s���Ă����v�Ƃ��Ă���B
|
�������s��t��u�I�~�N������XE�Ɍx�� �Ⴂ����3��ڐڎ���v �@4/12
�V�^�R���i�E�C���X�̂����I�~�N�������̕����̃^�C�v���g�ݍ��킳�����uXE�v�ƌĂ��E�C���X�ւ̊����������̌��u�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ���Ƃɂ��āA�����s��t��̔����͉�ŁA�x�����������������ŁA�u���X�ƃE�C���X���u�������Ȃ��ŏd�v�Ȃ̂͑S�̂̊����҂����炷���Ƃ��v�Ƒi���܂����B
�����s��t��̔��莡�v���12���̒���ŃI�~�N�������̕����̃^�C�v���g�ݍ��킳�����uXE�v�ƌĂ��E�C���X�ւ̊����������̌��u�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ���Ƃɂ��āA�u����BA.2�ւ̒u������肪�i��ł��邪����XE�ɂȂ邩������Ȃ��v�ƌx�����������������ŁA�u���X�ƃE�C���X���u�������Ȃ��ŏd�v�Ȃ̂͑S�̂̊����҂����炷���Ƃ��v�Ƒi���܂����B
�܂��A�s���̊����Ґ������~�܂肵�Ă��邱�Ƃɂ��ẮuBA.2�ւ̒u������肪�i��ł��邱�Ƃ�܂h�~���d�_�[�u����������Đl�̓����������ɂȂ������߂ł͂Ȃ����B�ڎ헦���Ⴂ�Ⴂ�����3��ڂ̃��N�`���ڎ�𐄐i���邱�Ƃ���Ԍ��ʂ�����Ǝv���Ă���v�Əq�ׁA����20��A30��̎Ⴂ����ɐڎ���Ăт����܂����B
���̂����ŁA4�����{����̑�^�A�x���߂Â��Ă��邱�Ƃ܂��A�u���N�`����3��ڐڎ���I���Ă��Ȃ��l�͂��܂̎����Ƀ��N�`���ڎ�����ĖƉu������悤�ɂ��Ăق����v�Ƙb���܂����B
|
���n�C�u���b�h�̃I�~�N�����uXE�v���o��@������ɘa���ł̖h�q�@�Ƃ́@4/12
�I�~�N������BA.2�ւ̒u������肪6�����A�V�K�����҂������~�܂��Ă���B�C�O�ł�BA.1��BA.2�̈�`���̈ꕔ���g�݊�������n�C�u���b�h�̌n�������������B
�Ȃ�BA.2�̕����L����₷���̂��͂܂��킩���Ă��Ȃ��B
�I�~�N�������́A�]���̕ψي��ɔ�ׂāA�����̕ψق������Ă���B���ɁA��������ۂɍŏ��Ƀq�g�̍זE�Ɍ�������A�E�C���X�̕\�ʂɂ���ˋN��́u�X�p�C�N(S)����ς����v��mRNA�ɕψق����������Ă��邽�߁A�]���̃E�C���X�ɔ�ׂāAS����ς����̌`���ς���Ă���B
�����̑啔���̃��N�`���́A�]���^�̃E�C���X��S����ς������U������R�̂��ł���悤�ɐv���Ă���B���̂��߁AS����ς����̕ω����傫���I�~�N�������ɑ��ẮA���ʂ��ቺ���Ă���B
�pHSA�ɂ��ƁA���ǂ�h�����ʂ́A�t�@�C�U�[�����N�`����2��ڎ��25�T�Ԉȏ�o�������_�ŁA�f���^���ɑ��Ă͖�6���������̂ɑ��A�I�~�N�������ɑ��Ă�1�����x�ɒቺ���Ă����B���f���i�����A�f���^���ɑ��Ă�8�����x�ێ�����Ă������ʂ��A�I�~�N�������ɑ��Ă�1�����x�ɒቺ���Ă����B
���p���ŁuXE�v���m�F
����A���@��h�����ʂ́A�t�@�C�U�[���ƃA�X�g���[�l�J�������킹�����͂ŁA2��ڂ̐ڎ��25�T�Ԉȏ�o�������_�ŁA�I�~�N�������ɑ��Ă�44���̌��ʂ��c���Ă����B����ɁA�lj��ڎ�Ńt�@�C�U�[�А����N�`����łƁA�lj��ڎ��2�`4�T�Ԍ�܂ł͌��ʂ�90���A10�`14�T�Ԍ�ɂ���75���ɉ����B���f���i�А���lj��őł����ꍇ�A9�T�Ԍ�܂�90�`95���̌��ʂɉ����B
�����̃f�[�^�͎��BA.1�ɂ��Ă����A�pHSA��WHO�́A���N�`���̌��ʂɂ��Ă�BA.2��BA.1�ƕω����Ȃ��Ƃ��Ă���B
�I�~�N�������̓��N�`���������ɂ�������ŁA�������Ă��d�lj��͂��ɂ����B�p�C���y���A���E�J���b�W�E�����h���Ȃǂ̌����`�[����21�N11��22���`22�N1��9���Ɋ���������152���l�͂����Ƃ���A�I�~�N�������Ɋ������ďd�lj����郊�X�N�̓f���^����0.41�A���S���郊�X�N��0.31�������B
�pHSA��f���}�[�N�̍��������w�������ɂ��ƁA���������ꍇ�̏d�lj����́ABA.2��BA.1�ƍ����Ȃ��Ƃ����B
���Ăł͐V�K�����Ґ������{���������Ă��A��r�I�d�lj����X�N�̒Ⴂ�I�~�N�������̗��s���A���ۑ���܂߂���������ɘa���鍑�������Ă���B
����Ȓ��A�p���ł�BA.2��������Ɋ����̍L������������n�����������Ă���BBA.1��BA.2�̈�`���̈ꕔ���g�݊�������n�C�u���b�h�ŁA���ۓI�ɁuXE�v�ƕ��ނ���Ă���B1��19���ɏ��߂Č������Ĉȗ��A3��22���܂łɉp������637���̕��������B�����X���ɂ���A�pHSA�ɂ��ƁA3��15�����݁ABA.2����1.098�{�A�����̍L���鑬�x�������Ɛ��v�ł���Ƃ����B
���d�lj��\�h�̓��N�`��
XE�̏d�lj����X�N�͂܂��s�������A�����̃I�~�N���������x�̏ꍇ�A��芴���������₷���Ă�������̊ɘa�͑����ƍl������B
�Љ�S�̂̊����ɘa����钆�Œ��ӂ��K�v�Ȃ̂́A�d�lj����X�N�͌l�ɂ�荷���傫���Ƃ����_���B����������b��������������A���x�̔얞��������A�R����܂�Ɖu�}���܂�����ł���Ȃǂ��ĖƉu����������Ԃ������肷��l�́A�I�~�N�������ȂǏd�lj����X�N�̔�r�I�Ⴂ�E�C���X�ւ̊����ł��A�d�lj����郊�X�N�͍����B
�d�lj���h�������̍ł����ʓI�ȕ��@�̓��N�`���ڎ킾�B�pHSA�̃W�F�j�[�E�n���X������4��1���A����Ȃ銴����̊ɘa���n�܂����p���ŁA�����Ăт������B
�u���N�`���ڎ�́A�d�lj�����@��h���ŗǂ̕��@�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���v(�Ȋw�W���[�i���X�g�E�����)
|
��4��ڃ��N�`���ڎ�ɗ\�h���ʂ͊��҂ł��Ȃ��c�č��̐��Ɓ@4/12
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��Ăъg���ɓ������B���������nj�������7�����\�����u�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̒��߂̊������v(2022�N4��6������)������������Ă���B
�S���̐V�K�����Ґ�(����)�́A���߂�1�T�Ԃł�10���l�������259�l�B���T��T��1.08�Ƒ����X���ƂȂ��Ă���B
�n��ʂł͎���(0.82�{)�A����(0.95�{)�Ȃǂ̂悤�Ɍ����ɓ]���Ă���n������邪�A�{��(1.68�{)�A�啪(1.39�{)�A�a�̎R(1.33�{)���͂��߁A�����͑����������Ă���B
�������͍���ɂ��āu���Ԍ��A���}��Ȃǂ��s���鎞���ł���A���ɖ�ԑؗ��l���̑������V�K�����҂̑����v���ƂȂ肤�邱�ƁA�q�ǂ��́A�V�w�����n�܂�A�w�Z�ł̐ڐG�@���������\�������邱�Ɓv�uBA.2�n���ւ̒u������肪�i��ł���A�V�K�����҂̑����v���ƂȂ肤��B���[���b�p�ł�BA.2�n���ւ̒u������肪�i�݁A�����҂����ł͂Ȃ��d�ǎҁE���S�҂������ɓ]���Ă��鍑������v�u�I�~�N�������ɑ��銴���\�h���ʂ̓f���^���ɔ�r���Ă��Ⴍ�A�������������Ԃ��Z�����Ƃɗ��ӂ��K�v�v�ȂǂƂ��Ċ������ւ̌��O�������A���N�`���ڎ킷��悤�����Ă���B
����Ȓ��A�č��̐H�i���i��(FDA)�͐V�^�R���i�E�C���X���N�`���̒lj��ڎ�̕K�v����ψٌ^�ւ̑Ή��ɂ��č���̕��j���c�_���鎐��ψ�����J�����B���̒��Ő��E�Ŋ������L����I�~�N�����^�̔h���^BA.2�ɁA�������N�`�����\���K�����Ă��Ȃ��Ƃ̎w�E���o���Ƃ����B
����ςɂ�FDA���͂��߁A�Ď��a��Z���^�[(CDC)��č����q��������(NIH)�A���E�ی��@��(WHO)�Ȃǂ̐��Ƃ炪�Q�������B������FDA�̃��N�`���J������̕��f�B���N�^�[�́u�������N�`���͎嗬�ƂȂ�BA.2�ɏ\���K�����Ă��Ȃ��v�ƌ�����Ƃ����B
�����̐��Ƃ�4��ڃ��N�`���ڎ�̗\�h���ʂ�ے�I�Ɍ��鍪���̓t�@�C�U�[�А����N�`���̐ڎ킪�ϋɓI�ɍs����C�X���G���̌������ʁB60�Έȏ�̃C�X���G���l125���l���܂�̍��N1�`3���̌��N�L�^�̕��͂ŁA���e�͐��E�I�Ɍ��Ђ̂����w�_���G���u�j���[�C���O�����h�E�W���[�i���E�I�u�E���f�B�V���v�Ɍf�ڂ���Ă���B
����ɂ��ƁA3��ڐڎ�Q�ɔ�ׂ�4��ڐڎ�Q�͐ڎ�4�T�ڂŏd�lj����X�N��3.5����1�ɒቺ�ƂȂ������̂́A�������m�F����郊�X�N��4�T�ڂ�3�T�Q�̔����A8�T�ڂł�1.1����1�Ƃقږ߂����Ƃ����B�܂�A�����\�h���ʂ�2�J���Ԃ��������Ȃ��B
�����Ȃ�ƁA4��ڐڎ�͖Ɖu�ɖ��������l�ȂNJ�����̏d�lj����X�N�������l�ȊO�A���N�Ȑl�͍Q�ĂđłK�v�͂Ȃ��̂�������Ȃ��B���N�`����łĂ����m���Ŕ��M��ɂ݂Ȃǂ̕�����������B�ڎ�̃����b�g�ƃf�����b�g�A����ɐڎ퓖���̎��g�̑̒��B����3���悭���ɂ߂������Őڎ�̔��f�����g�ōs�����Ƃ��B�@ |
���u�[���R���i�v����̒��c�g�ߋ��ň��h�����g��̒����@�V�ψي��uXE�n���v�@4/12
�ߋ��ň��̃y�[�X�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂��������Ă��钆���ł͏�C�ł̃��b�N�_�E���������Ԃɋy�сA�[���ȐH�Ɠ�N���Ă��܂��B����A���{�����̌��u�ł�11���Ɏn�߂ĐV���ȕψي��uXE�v�n�����m�F����܂����B�S�z�����͍̂L����X�s�[�h�������Ƃ����A���̊����͂ł��B
�㓡�����J����b�F�uXE�n���̕ψي��ɂ��Ă�WHO(���E�ی��@��)�̃��|�[�g�ɂ����āABA.2�n���ɔ�ׂĎs���ł̊����҂̑������鑬�x��10���قǍ����Ƃ̕�����v
11���A���߂č����̋�`���u�Ŋm�F���ꂽ�I�~�N�������̐V���Ȍn���uXE�v�B
����A�m�F���ꂽ�̂̓A�����J�ɑ؍ݗ�������30��̏����ŁA�挎26���ɐ��c��`�ɓ��������ۂɗz���ƂȂ�A���̌�̏ڂ���������XE�ւ̊������m�F����܂����B
���Ƃɂ��܂��ƁAXE�̓I�~�N�������̕����̃^�C�v���g�ݍ��킳�������̂ŁA1�l�̐l�Ԃ��I�~�N��������BA.1��BA.2�ɓ����Ɋ����������ʁA��`�q���g�ݍ��킳���Đ��܂ꂽ���̂��Ƃ����܂��B
����XE�A���N�`���⎡�Ö�̌��ʂ�BA.2�Ɠ������ƍl�����Ă��܂����A���ڂ����̂͊����҂������鑬�x�ł��B
���������nj������ɂ��܂��ƁA�uBA.2�v����12.6�������Ƃ����܂��B
���{��ȑ�w�E�k���`�_���C�����F�u1�l�̌l�̒���BA.1��BA.2�������Ɋ������Ă�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA���Ȃ藬�s������Ȓn��ł����N����Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB�d�Ǔx��BA.2�Ƃقڕς��Ȃ��Ɨ\�z����Ă��܂��v
�����A���O�����̂̓S�[���f���E�B�[�N�Ȃǂł̍�����C�O�ł̐l�̓������Ƃ����܂��B
���{��ȑ�w�E�k���`�_���C�����F�u�l�̗���̌𗬂��N���₷���B���s�g��ɂȂ���B���s�g�傷��ƈ�ÕN��(�Ђ��ς�)�͂�����N����̂Łv
����ȂȂ��A�����I�Ɋ������g�債�Ă���̂��u�[���R���i�v�������钆���ł��B���ł�XE���m�F����Ă���Ƃ����܂��B
��ÃX�^�b�t���ߘJ�œ|��ĉ^��Ă��铮��B�����������Ă���̂́A�V�^�R���i�̊����҂ł��B��C�̏W���u���{�݂ŎB�e���ꂽ�A���̓����SNS�ł́c�B
������SNS�̐��F�u�����҂̕������C���v
�h�앞�Ŕn�ɏ��j���B�V�^�R���i�̌����L�b�g���e�n�ɉ^��ł���Ƃ����܂��B�Ԃł͂Ȃ��A�n�ɏ��ɂ͗��R������܂��B
�j���̍ȁF�u�ׂ����Ȃǂ͔n�̕����֗��ł��v
�Ȃ��ł��A�s���ɂƂ��Č������Ȃ̂���C�s�̃��b�N�_�E�����Ƃ����܂��B
���b�N�_�E���̂��߁A�����o���Ȃ��s���ւ̐H���̔z������A�e�n�Ńg���u�����N���Ă���Ƃ����̂ł��B
�s���̓{�肪������������͒�����SNS�ōL���g�U����܂������A�قƂ�ǂ��폜����܂����B
��C�x�ǂ̍����x�ǒ����������H������Ƙb���܂��c�B
��C�ł�11���A�ꕔ�̒n��ŕ�������������܂������A�����̒n���14���ԁA�����҂��o�Ȃ���������͂���܂���B
�����҂͍L���͈͂Ŋm�F����Ă��āA�S�ʉ����ɂ͐��T�Ԉȏオ�����錩�ʂ��ł��B
|
 |
�������s�A�V����8253�l�̊������\�@ �g�݂Ȃ��z���h9�l�@����5�l�@4/13
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�����s��13���V����8253�l�̊����\���܂����B��T���j����8652�l��399�l������Ă��āA�O�̏T�̓����j���̊����Ґ��������̂�2���A���ł��B
�����s�́u���������A��t�������Ɛf�f�����v�g�݂Ȃ��z���h�̊��҂������҂Ƃ��Ĕ��\���Ă��āA9�l���g�݂Ȃ��z���h�̊��҂ł����B�V���Ȋ����҂̂����A���N�`����2��ڎ킵�Ă����l��3918�l�ŁA1����ڎ�����Ă��Ȃ��l��2301�l�ł����B�V�^�R���i�̕a���g�p����26.8���ŁA�ő�Ŋm�ۂł��錩���݂�7229���ɑ��A1940�l�����@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�̕a���g�p���́A8.0���ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł́A10�㖢����1423�l�A10�オ1045�l�A20�オ1576�l�A30�オ1554�l�A40�オ1262�l�A50�オ712�l�ŁA�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂�515�l�ł����B���ݓ��@���Ă��銴���҂̂����A�����s�̊�Łu�d�ǎҁv�Ƃ����l�́A23�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��V���ɁA50��j�����܂�5�l�̎��S�����\����Ă��܂��B
|
�����E�̃R���i�����җv5���l�����c2������1���l���A�������ʂ��� �@4/13
�V�^�R���i�E�C���X�̐��E�̗v�����Ґ���12���A�ăW�����Y�E�z�v�L���X��̏W�v��5���l�����B2����{��4���l���Ă����2�����ł����1���l�������B�����̃y�[�X�͂�◎���Ă�����̂́A���E�I�Ȏ����͂܂����ʂ��Ȃ����B
�W�v�ɂ��ƁA���ʂ̗v�����Ґ��͕č�����8050���l�ƍő��ŁA�C���h��4300���l�A�u���W����3020���l�A�t�����X��2740���l�A�h�C�c��2280���l�Ƒ����Ă���B���{�͖�710���l���B���E�̗v���Ґ��͖�620���l�ƂȂ��Ă���B
���s�̊J�n����1�N�߂��o�߂�����N1���Ɋ����҂�1���l���A��N8���ɂ�2���l�ɓ��B�����B�����͂������ψي��u�I�~�N�������v���m�F���ꂽ��N11���ȍ~�A�����g��͉������A���N1����3���l��˔j�����B
|
�����E�̃R���i������5���l�ɁA2�J����1���l���@�����͓s�s�������@4/13
�V�^�R���i�E�C���X�̐��E�̊����҂��A�ăW�����Y�E�z�v�L���X��̓��{����13�����_�̏W�v�ŗv5���l�����B���N2��9����4���l���L�^������A��2�J����1���l���������ƂɂȂ�B�I�~�N�������̊����g��̃y�[�X�͗��������̂́A���E�e�n�Ŋ����҂͂Ȃ��������Ă���B
���E�̊����Ґ��͍��N1��7����3���l���L�^�B����200���`300���l�Ƃ��ĂȂ��y�[�X�Ŋ����҂��}�����A��1�J����ɂ�4���l�����B���̌�A���B�Ȃǂł͊����̃s�[�N�͉߂����Ƃ݂��Ă��邪�A���E�ł�4�����{�ł��A��100���l���銴���҂��o�Ă����B13�����_�ł̗v�����Ґ��́A�č��Ŗ�8�疜�l�A�C���h�Ŗ�4300���l�A�p����h�C�c�A�t�����X�ł��A���ꂼ��2�疜�l���Ă���B
���ĂȂǂ̓��N�`���⎡�Ö�̕��y��w�i�ɁA���N�`���ڎ�ؖ��̒�}�X�N���p�Ƃ������s���K�����ɘa����Ȃǂ��āu�E�B�Y�R���i�v�Љ��͍�����B����A�����́u�[���R���i�v��ڎw���Č������K����~���Ă��邪�A�ő�̌o�ϓs�s�ł����C�s�ŐV�^�R���i�̊������g�債�A�s�s����(���b�N�_�E��)���p�����Ă���B |
���ăR���i�����A��86�����I�~�N��������@�����ґ����̒���@4/13
�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)��12���A9���܂ł�1�T�Ԃɕč��Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�������҂̂����A�I�~�N�����ψي��̈���u�a�`�D2�v��85�D9�����߂�Ƃ������v�\�����B2���܂ł�1�T�Ԃ�75�D4���������B
�j���[�W���[�W�[�A�j���[���[�N�A�}�T�`���[�Z�b�c���܂ޖk�����ł́u�a�`�D2�v�������S�̂�90�������߂��B
9�����_�̕č����̐V�^�R���i�����҂�7���Ԃ̈ړ����ςőO�T���10������2��8339�l�B
�y���V���x�j�A�B�t�B���f���t�B�A�ł�18�����牮���}�X�N���p���ēx�`��������B���C�^�[�̏W�v�ɂ��ƁA�y���V���x�j�A�B�̐V�^�R���i�����҂�10���܂ł�1�T�Ԃ�70���߂����������B
|
���i�܂Ȃ���҂̃��N�`���ڎ�c�R���i���Nj}���̌��O���@4/13
�V�^�R���i�̐V�K�����Ґ������~�܂肷�钆�A��w�̃L�����p�X�ł�3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�s���Ă��܂��B����ŁA�R���i���ǂ̊��҂��}���A�ˑR�u�����сv�̏Ǐ�ŔY�܂����20��̏������B
��������w�@�V�����݂̂̓��w��
���{�����قōs��ꂽ������w�̓��w���B�����́u�Ƒ�1�l�Ɍ������\�v�Ƃ���Ă��܂������A�V�^�R���i�̊������l�����V�����݂̂ł̊J�ÂƂȂ�܂����B
����̐V�����@�u�e������Ȃ��������Ƃ͎c�O�Ȃ�ł����ǁA����ł��J�Âł������Ƃ͊��ӂ����Ȃ��ł��v
����̐V�����̕�e�@�u�c�O�ł����ǎq�ǂ��������Q���ł���̂ł��ꂾ���ł��ǂ������v
�R���i�ЂŌ}����3�x�ڂ̏t�B��������Ƃ�Ȃ���A�w�������������o���Ă��܂��B
����w���ɕ���3��ڐڎ�
�R�{�b�����A�i�E���T�[�@�u�V�N�x���n�܂�܂��āA������̑�w�ł͂��̂�����3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�n�܂��Ă��܂��v
����c��w�̃L�����p�X���ɐ݂���ꂽ�ڎ���ɂ́A3��ڂ̐ڎ�ɗ����w���̎p������܂����B
�R�{�b�����@�u�Ȃ���w�Ń��N�`���ڎ������ł����H�v
3��ڐڎ������w2�N(19)�@�u(�W���̃C���X�g���N�^�[��)�o�C�g�����V�l��q�ǂ������Ɛڂ���d���������̂ŁA3��ڂ��ł��Ă����Ȃ��Ɗ�Ȃ��ȂƁv
�R�{�b�����@�u3��ڂ�ł��āA�C�����I�ɂ͈��S���镔�����H�v
3��ڐڎ������w2�N(20)�@�u����͂Ȃ��ł��ˁB�������邩�킩��Ȃ����A�ł��Ă���l���������Ă���̂Łv
�R�{�b�����@�u�Ȃ��łƂ��ƁH�v
3��ڐڎ������w2�N(20)�@�u�ł���������肩����Ȃ��̂��ȂƁv
����c��w�ł͌��݁A�u�`��7����ΖʂŎ��{���Ă��܂��B�S���҂͑Ζʎ��Ƃ��ێ����邽�߂ɂ��u�w����̃��N�`���ڎ�͏d�v���v�ƌ����܂����E�E�E
����c��w�@�����ہ@���{�����ے��@�u1��ځA2��ڂ̂Ƃ��͗\����J�n�����u�Ԃɂǂ�ǂ�\��҂����܂��Ă������ł������A����͂������������Ƃ͂Ȃ���r�I�܂��Ă�����������Ƃ����ł��v
���{�̒����ɂ���3��ڂ̐ڎ���I����20��̊�����24���B30��(25.9��)���܂ߎ�҂̐ڎ킪�i��ł��Ȃ��̂�����ł��B
�R�{�b�����@�u3��ڂ�ł\��́H�v
��w2�N(19)�@�u�ł̂�����Ă���v
�R�{�b�����@�u�Ȃ������Ă��ł����H�v
��w2�N(19)�@�u2��ڂō��M���o�āA3��ڂ��܂����̔M���o��̂��Ǝv���̂ƕ|���Ƃ����̂������āv
��w2�N(19)�@�u�݂�ȏd�ǂɂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ�����Ȃ��ł����A�Ȃ��Ă����Ǐ����蕗�ג��x�ōς�ł��邱�Ƃ������̂ŁA�ł��Ȃ��Ă������̂��ȂƂ����v��������̂������ȂƂ���ł��ˁv
�����s����12���V���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�̊����҂�6922�l�B���̂���10��`20�オ���悻3�����߂Ă��܂��B11���A�����ŏ��߂ăI�~�N�������̐V�n���uXE(�G�b�N�X�C�[)�v�ƌĂ��ψكE�C���X�̊����҂��m�F����Ă��܂��B�㓡���J��b�́u(�I�~�N������)BA.2�n���ɔ�s���ł̊����҂̑������鑬�x��10���قǍ����Ƃ̕�����v�Ƙb���܂����B
���u���Ǐ����l�ł���3���Ɍ��ӊ��Ȃǂ̌��ǂ��o���v
�����͂̋����Ƃ����uXE�v�n���̏o���Łu��7�g�v�������������т钆�A���O�����̂́u���ǁv���҂̑����ł��B
�R���i���ǂŔ��̖т�������20�㏗���@�u�����Ă��鎞�����̖т������Ă��Ă���̂��킩�邭�炢�B���[���ƒn�ʂɂ����ς����̖т������Ă��銴���v
��ނɉ�����20��̏����͂܂����N�`���ڎ���Ă��Ȃ�����2021�N8���ɐV�^�R���i�Ɋ����B������̏H��������ǂƌ�����u�����сv�̏Ǐn�܂�܂����B�Ǐ��3�����قǑ����A���퐶���ɂ��x�Ⴊ�o���Ƙb���܂��B
�R���i���ǂŔ��̖т�������20�㏗���@�u�����̎d�������Ă��āA���̖т���������ٕ������ŁA��ɓ����Ă͂����Ȃ��E�ꂾ�����̂ŁA�C���g���ĉ߂����Ă����B�X��������Ă��Ă��A�w���̐l�͂��Ă�x���Ďv����̂ł͂ƕs���Ƃ������A���ȋC�����ł����v
�����E���c�J�悪�s���������ł́A�u�V�^�R���i�����Ǐ����l�ł����悻3���ɁA���ӊ��Ȃǂ̌��ǂ��o���v�ƌ����܂��B���NJO��������s���̃N���j�b�N�ł͍��A�I�~�N�������ɂ����ǂ̊��҂��}�����Ă��܂��B
���u�y�����Ă͂����Ȃ��v
�q���n�^�N���j�b�N�@��������@���@�u���N1���ɔ��ǂ��āH�v
���ǂ�i���鏗��(40��)�@�u�͂��v
��������@���@�u�ǂ�ȏǏ�ł����H�v
���ǂ�i���鏗��(40��)�@�u���ӊ��������āA�����ځ[���Ƃ��銴���ŁA�l�ɓ`���������Ƃ�l���Ă��邱�Ƃ����t�ɏo���Ȃ�������Ƃ��v
��������@���@�u����ꂽ���Ƃ��o���Ă��Ȃ��Ƃ��H�v
���ǂ�i���鏗��(40��)�@�u�͂��A����܂��v
2022�N1���ɐV�^�R���i�Ɋ�������40��̏����B�R���i���̂̏Ǐ�͌y�ǂł������A���̌�A���ӊ���]�ɂ��₪���������悤�ɂȂ�v�l�͂��ቺ����u�u���C���t�H�O�v�̏Ǐ����Ă���ƌ����܂��B
��������@���@�u10��̕���2�`3�T�ԂŐQ�������Ԃ܂Ői��ł����肷�邱�Ƃ������āA(�I�~�N�����̌��ǂ�)�����ăo�J�ɏo���Ȃ���ԁv
������t�́A��r�I�Ǐg�y���h�Ƃ����I�~�N�������ł��d�����ǂ��o�Ă���Ƃ��Čx����炵�܂��B
��������@���@�u(���ǂ�)�d���ɍs���Ȃ��A�w�Z�ɍs���Ȃ��Ƃ��A���������b�ɂȂ��Ă��܂��āA�{���ɐ�������ς������Ă���B���܂ɃI�~�N�������̓C���t���G���U�Ɠ����ł͂Ȃ����Ƃ����悤�Ȍ���������܂����A�����Ɗ����\�h�͂��Ă����Ȃ�������Ȃ����A�y�����Ă͂����Ȃ��Ǝv���v
|
���܂h�~���d�_�[�u�u�����ɕK�v�ł͂Ȃ��v�A�ݓc�����͐T�d�@4/13
�ݓc������b�͐V�^�R���i�̊����Ґ����S���I�ɑ����X���ɂ��钆�A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�ɂ��āA�u�����ɕK�v�ȏƂ͍l���Ă��Ȃ��v�Ƌ��������B
�u�����_�œs���{������܂h�~���d�_�[�u�̗v���͂Ȃ��A�����ɏd�_�[�u���K�v�ȏƂ͍l���Ă���܂���v(�ݓc����)
�ݓc�����́u�V�K�����Ґ��͑����X���ɂ���v�Ƃ�������A�u�a���g�p���A�d�Ǖa���g�p���͒Ⴂ�����ɂ���v�Ǝw�E�����B
�܂��A���{���J�n�������������Ă��郏�N�`����3��ڐڎ�Ȃǂ������ɁA�R���T�[�g�Ȃǂ̃`�P�b�g��������������鎖�Ɓu�C�x���g���N���N���v�ɂ��ẮA�u�����Ɏn�߂邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v�Ɛ��������B�@ |
 |
���܂h�~�[�u������ő��@�k�C��2768�l�����m�F�@4�l���S�@4/14
14���A�k�C���ł͐V�^�R���i�E�C���X�ɁA�V����2768�l�̊������m�F����܂����B�����Ґ��͐挎22���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v����������Ă���ő��ƂȂ��Ă��܂��B
��Ȋ����Ғn��́A�D�y1344�l�A����134�l�A����102�l�A���M70�l�B
�܂�����܂łɓ����Ŋ������m�F���ꂽ���҂̂���12�l���A�]���̃I�~�N���������������͂������Ƃ����u�a�`�D2�v�Ɋ������Ă������Ƃ��������Ă��܂��B�S���Ȃ����l��4�l�ł��B
�V���ȃN���X�^�[�̔����́A�D�y��Ë@��11�l�A���쎙���W�{��12�l�A���ٍ���Ҏ{��7�l�^�s�����̐V�l���C10�l�ƂȂ��Ă��܂��B���َs�����̐V�l���C�͐V�K�̗p�̐E���ƌ��C�S���̐E�����������܂����B���݉�Ȃǂł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B |
���uGW�𐧌��Ȃ��߂������߁A����2�T�Ԃ����O��v �R���i�g��̉��ꌧ�@4/14
���ꌧ���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�Ă��邱�Ƃ��A�ʏ�f�j�[�m����14���ߌ�A�L�҉���A�������{����n�܂��^�A�x�Ɍ�����̓O����Ăт������B�u�����Ȃ��S�[���f���E�B�[�N���߂����邩�ǂ����A���ꂩ��2�T�Ԃ����O��ɂȂ�v�Əq�ׂ��B���ɍ���҂�q�ǂ��ւ̊������L���Ȃ��悤���͂����߂��B����̊����ɂ���ẮA�܂h�~���d�_�[�u�̎w��𐭕{�ɗv�����邱�Ƃ���������Ƃ����B
�����̍Ċg���h���A����I�ȎЉ�o�ϊ������p�����邽�߁A15�`28�������Ԃƈʒu�Â���B
�m���́A����̊����g���20�オ�ˏo���đ���������6�g�Ɣ�ׁA���L������ōL�����Ă���Ǝw�E�B����19�Έȉ��⍂��҂ő����X���������ŁA�d�lj����X�N����������҂ւ̊����g�傪���@���҂̑����ɔ��Ԃ������Ă���Ƃ����B
���̂���(1)����҂ւ̊������L���Ȃ�(2)�q�ǂ�������������(3)�ړ��E��H�Ɋւ��郊�X�N���������(4)���N�`���ڎ����������\���Ƃ��Ăт������B
�d�_�[�u�́A���悲�Ƃɒ���1�T�Ԃ̐V�K�z���Ґ����O�T���2�{���̑����ƂȂ����ꍇ���A�a���g�p�����e����60���ȏ�ƂȂ����ꍇ�ɁA���{�ւ̗v������������B
|
������V�K����1426�l�@�ʏ�m���u�ł���A�܂h�~���o���Ȃ���GW���v�@4/14
���ꌧ��14���A�����ŐV����1426�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����܂����B��T�ؗj��(7��)��1355�l���71�l�����Ȃ��Ă��܂��B
13���܂ł̒���1�T�Ԃ̐l�� 10 ���l������V�K������:612.88�őS���ő�(�S������:275.54)�B
14���ߌ����J�������ꌧ�̋ʏ�m���́A����{���̕a���g�p���������܂h�~���d�_�[�u�̓K�p����������60���ɋ߂Â��Ă���Ƃ��āA15������28���܂ł��u�����g���}�����Љ�o�ϊ������p�����邽�߂̑���ԁv�Ƃ��Ĉ�w�̊�����̓O����Ăъ|���u�ł���� �܂h�~���d�_�[�u���o���Ȃ��Ă����ŏ��z���Ă����S�[���f���E�B�[�N���߂����Ă�����v�ƌ����ւ̋��͂����߂܂����B |
�������ґ����X�����܂h�~�������ɓK�p�����@4/14
�V�^�R���i�̐V�K�����҂̑����X�����������A���{�́A�a���̎g�p���Ȃǂ��Ⴂ�����ɂ���Ƃ��āA�������ɂ܂h�~���d�_�[�u�͓K�p�����A�e�����̂ƘA�������Ȃ���A�������Ò̐��𒍎�������j�ł��B
�V�^�R���i�ւ̑Ή����߂����āA�����J���Ȃ̐��Ɖ��13���ɊJ����A�S���ŐV�K�����Ґ��̑����X�����������A��s�s���ł͑����̑��x����r�I���₩�Ȃ̂ɑ��āA�ꕔ�̒n���s�s�ł͋}���Ɋg�債�Ă���Ƃ����w�E���o����܂����B
���ł��A���ꌧ�́A����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ����S���ŗB��A600�l���Ă��āA���{�͍��Ǝ����̘̂A�������ɂ�����u���G�]���`�[���v�����n�ɔh�����āA�̔c���ɓw�߂Ă��܂��B
�ݓc������b�́u�a���g�p���A�d�Ǖa���g�p���͒Ⴂ�����ɂ���A���łɏd�lj����X�N�̍�������҂�85�������N�`����3��ڐڎ���������Ă���v�Əq�ׁA�������ɂ܂h�~���d�_�[�u��K�p����ł͂Ȃ��Ƃ����F���������܂����B
���{�Ƃ��ẮA�I�~�N�������̕����̃^�C�v���g�ݍ��킳�����uXE�v�ƌĂ��E�C���X�ւ̊����������̌��u�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ���Ƃ����܂��A���������e�����̂ƘA�������Ȃ���A�������Ò̐��𒍎�������j�ł��B
����A�C�x���g�Ȃǂ̎��v���N��ɂ��āA���{���ł́A�o�ς̍Đ���i�߂邽�߂ɂ��A��^�A�x�ɍ��킹�ĊJ�n���ׂ����Ƃ����ӌ����������A�l�̈ړ������������ł���A���ʂ͎��{���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����w�E���o�Ă��āA�����Ȃǂ����ɂ߂Ȃ���T�d�Ɍ������Ă������j�ł��B
���ݓc�� �g�܂h�~ �����ɓK�p���K�v�ȏł͂Ȃ��h
�V�^�R���i����߂���A�ݓc������b��13���A�V�K�����Ґ��������X���ɂ�����̂́A�a���̎g�p�����Ⴂ�����ɂ��邱�ƂȂǂ���A�����ɂ܂h�~���d�_�[�u�̓K�p���K�v�ȏł͂Ȃ��Ƃ����F���������܂����B
13���̎Q�c�@�{��c�ł́A�o�ψ��S�ۏ�̋�����}��@�Ă̓��e�Ȃǂ��߂����Ď��^���s���A�ݓc������b���o�Ȃ��܂����B
���̒��Ŋݓc������b�́A�V�^�R���i�̊����ɂ��āu�����ŐV�K�����Ґ��͒n��ɂ��Ⴂ��������̂́A�S�̂Ƃ��Ă͑����X���ɂ���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu�a���g�p���A�d�Ǖa���g�p���͒Ⴂ�����ɂ���A���łɏd�lj����X�N�̍�������҂�85�������N�`����3��ڐڎ���������Ă���B�����_�œs���{������܂h�~���d�_�[�u�̗v���͂Ȃ��A�����ɏd�_�[�u���K�v�ȏƂ͍l���Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A�ό���C�x���g�Ȃǂ̎��v���N��̊J�n�����ɂ��āu�����_�Œ����Ɏn�߂邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v�Əq�ׁA�����Ȃǂ����ɂ߂Ȃ���T�d�Ɍ������Ă����l���������܂����B
����A13���R�c���肵���o�ψ��S�ۏ�̋�����}��@�Ăɂ��āA�ݓc������b�́u�o�ψ��S�ۏ�͑���ɂ킽��V�����ۑ�ł���A�@����̎蓖�Ă��K�v�ȋi�ق̉ۑ�ɑΉ����邽�ߐ��x�������s�����̂��v�Əq�ב��������ւ̗��������߂܂����B
�����[�����u�m������ƂƂ��A�g���ēK�ɑΉ��v
���슯�[�����́A�ߌ�̋L�҉�Łu�����_�œs���{������v���͂Ȃ��A�����ɕK�v�ȏƂ͍l���Ă��Ȃ��B�����ւ̈ڍs���ԂƂ��āA�V�^�R���i��̑S�̑��ŏ������Ă����ی���Ñ̐�����������Ɖғ������Ă������Ƃ���{�ɁA�������Â̏𒍎����A�m������ƂƂ��A�g���ēK�ɑΉ����Ă����B�V�^�R���i���N�`���̎Ⴂ�����3��ڐڎ�����i���Ă����v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A�C�x���g�Ȃǂ̎��v���N��̊J�n�����ɂ��āu��������Ƃ̈ӌ��Ȃǂ܂������I�ɔ��f����B�ʂ̓s���{���ł̎��{�͓s���{���̈ӌ��܂��邱�ƂɂȂ��Ă���v�Əq�ׂ܂����B
�����Ɖ �V�K�����Ґ��͑����X�� �n�捷��
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ��ď�������A�����J���Ȃ̐��Ɖ��13���J����A�S���̐V�K�����Ґ���10��ȉ��������ɓ]��������A50��ȏ�ł͑������݂��A�S�̂Ƃ��Ă͑����X���������Ă���Ƃ��܂����B���̂����ŁA��s�s���ł̑������x����r�I���₩�Ȉ���A�ꕔ�̒n���s�s�ł͋}���Ɋ������g�傷��ȂǁA�n�捷���o�Ă���Ǝw�E���܂����B
���Ɖ�́A���݂̊����ɂ��đS���ł͑����X���������Ă�����̂́A�n��ʂł͐V�K�����Ґ��������̒n�悪�������ŁA������u��6�g�v�̃s�[�N����\���Ɍ������Ȃ��܂܁A�㏸�ɓ]���Ă���n�������Ǝw�E���܂����B
�܂��A��s�s���ł͊����Ґ��͑������̂́A�����̑��x�͔�r�I���₩�Ȃ̂ɑ��āA�ꕔ�̒n���s�s�ł͋}���Ɋg�債�Ă���Ƃ��A���Ɋ�茧��H�c���A�������A�V�����A���쌧�A���Q���A�啪���A�{�茧�A����Ɏ��������ł͐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ς��A���łɁu��6�g�v�̃s�[�N�������Ă��Ēn���ł̊����g��ɂ����ӂ��K�v���Ƃ��܂����B
�����҂�N��ʂɂ݂�ƁA10��ȉ��͌����X���ɓ]�����̂ɑ��A50��ȏ�ő����X���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
���ɁA�挎���犴�����Ċg�債�Ă��鉫�ꌧ�ł́A����҂̑����������ɂȂ��Ă��āA����A�ق��̒n��ł�����҂̊����ɒ��ӂ��K�v���Ƃ��Ă��܂��B
��Ñ̐��ɂ��ẮA�L�����⎭�������A���ꌧ�Ȃǂŕa���g�p���̑�����������ق��A����×{�҂�×{�ꏊ���������̐l�̐��͓����s�ȂǕ����̒n��ő����������Ă���Ƃ��Ă��܂��B
�����҂���������v���Ƃ��ẮA�ڐG�@��̑�����I�~�N�������́uBA�D2�v�ւ̒u������肪�����e�����Ă���ƍl������Ƃ��āA�w�Z��ۈ牀�A��앟���{�݂Ȃǂł̑�̓O���A�E��ŐڐG�@������炷���ƂȂǂ����߂܂����B
����A�V���ɕ���Ă���I�~�N�������́uXE�v�n���ɂ��ẮA����܂ł̂Ƃ��늴���͂�d�Ǔx�Ȃǂɑ傫�ȍ�������Ƃ����͂Ȃ����̂́A���������Ď����K�v���Ƃ��܂����B
����̑�ɂ��Đ��Ɖ�́A���N�`���̒lj��ڎ������ɐi�߂邱�Ƃ�A�O�o�̍ۂɂ͍��G�����ꏊ�⊷�C�������ꏊ������A�����ł��̒���������ΊO�o���T���邱�ƁA����ɁA����A��^�A�x���߂Â����Ől�̈ړ���������Ɨ\�z����邱�Ƃ���A�s�D�z�}�X�N�̐��������p�A��A1�̖��ł�������Ƃ��������O�ꂷ�邱�ƂȂǂ����߂ČĂт����Ă��܂��B
���㓡�����J�����u�����ɒn�捷�v
�㓡�����J����b�͐��Ɖ�Łu���߂̊����͑����X���������Ă��邪�A�n��ʂɌ���ƁA�p���I�ɑ������Ă���n����������A�����̒n�������B�܂��A�s�[�N������������͒Ⴂ���x���܂Ō������Ă���n����������A�\���Ɍ������Ȃ��܂܂ɏ㏸�ɓ]���Ă���n�������A�����̐��ڂɍ��������Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu�V�N�x�ɓ���A�����̐l���W�܂�s����A�E�E�i�w�ɔ����ړ��������Ȃ��Ă���B�܂��A��^�A�x���߂Â����ŁA�l����s���{�����z����ړ��������邱�Ƃ��\�z����A�������������h�~��̓O�ꂪ�K�v���v�Əq�ׂ܂����B
���e�c���� �u�S���I�Ɍp���I�ȑ����ǖʂɁv
�����J���Ȃ̐��Ɖ�̂��ƊJ���ꂽ�L�҉�ŁA�e�c���������͊����̍Ċg��ɂ��āA�u���܌��݁A�S���I�Ɍp���I�ȑ����ǖʂɂ���Ƃ����F�������傤�̋c�_�ł������ꂽ�B�܂h�~���d�_�[�u���I������i�K�ő����ǖʂɓ������Ƃ����ӌ����������B��r�I�A�������x�����₩�ȗv���Ƃ��ẮA���R������N�`����3��ڐڎ�ŖƉu�����l�������Ă��邱�ƂƁA2�N�ԗ��s�����������ƂŊ������X�N�̍�����ʂ������s���̍s��������Ƃ����c�_���������B���݂̊����́A���N�̉Ă̗��s�̃s�[�N�������Ă��āA�l�Ɛl�Ƃ̐ڐG��������Ƌ}���Ȋ����g��Ɏ��郊�X�N������Ƃ����c�_���������v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A���N�`����3��ڂ̐ڎ�ɂ��āA�u�V�^�R���i�E�C���X�Ɍ��炸�A�����̗\�h�ڎ�ł�2��ڂ̐ڎ�܂łŊ�{�ƂȂ�Ɖu�����āA3��ڂ̐ڎ�ł���ɗǎ��ȖƉu������B�I�~�N���������嗬�ƂȂ��Ă���̃f�[�^�ł����N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ�30��ȏ�ł͏d�lj�����l��S���Ȃ�l�����Ȃ��炸���āA���N�`���̐ڎ킷�邱�Ƃŏd�lj��⎀�S�����炷���Ƃ��ł��Ă��邱�Ƃ�������Ă���B�܂��A��҂���������ƌ��ǂ̃��X�N������ق��A�����̊��������ɂƂǂ܂炸�A���͂Ɋ��������郊�X�N���o�Ă���B�@�����A�ł��邾��3��ڐڎ�܂ŎĂ������������v�Ƙb���Ă��܂����B |
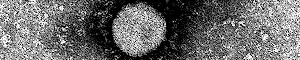 |
���i�`�k��3�����Ԏ��A1770���~�Ɋg�匩���݁c�܂h�~�ŗ��q�������� �@4/15
���{�q���15���A2022�N3�����A�����Z�̋Ɛї\�z(���ۉ�v�)�������C�����A�ŏI���v��1770���~�̐Ԏ��ɂȂ錩���݂��Ɣ��\�����B��N11�����_�ł́A1460���~�̍ŏI�Ԏ���������ł����B
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̊����g����A�e�n�Łu�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p���ꂽ���߁A�������q���v���啝�ɗ������݁A�Ɛт������������B
���q�͔��㍂�̗\�z�ɂ��Ă��A��N11�����_���840���~���Ȃ�6820���~�Ɉ����������B
|
�����S�ݓX��4����{���㑝�� �@�܂h�~�����Ȃǎ��X�ɉ� �@4/15
�܂h�~���d�_�[�u�̉����Ȃǂ��ĕS�ݓX�̔��オ���X�ɉ��Ă���B
���S�ݓX3�Ђ̔��\�ɂ��܂��ƁA14���܂ł�4���̔���́A�O�̔N�̓��������ɔ�ׂĎO�z�ɐ��O��10.6���A��������12.5���A��ۏ��≮��15�����ꂼ�ꑝ�������B
���O�W���A���[�u�����h�����i�Ȃǂ̔��グ�����������D�����������Ƃɉ����A�܂h�~���d�_�[�u�̉����Ȃǂ��ė��X�q���������Ă��邱�ƂȂǂ��v���B�����A�R���i�O��2019�N�Ɣ�ׂ��1���`2�����x�������Ă��āA�e�ЃR���i�O�̐����ɂ͖߂��Ă��Ȃ��B |
���R���i�V�K������ 1�T�ԕ��� 34�s���{���őO�T��葝 �n�捷�� �@4/15
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł͊ɂ₩�ȑ����X���������Ă��āA34�̓s���{���őO�̏T��葽���Ȃ��Ă��܂��B��s���Ȃǂ̓s�s���ł͑������ɂ₩�Ȉ���A�n���𒆐S�ɑ����̕����傫���Ȃ��Ă���Ƃ��������A�n��ɂ���Ċ����ɍ����o�Ă��܂��B
NHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S��
�挎17���܂ł�1�T�Ԃł͂��̑O�̏T����0.90�{�A�挎24����0.76�{�ŁA6�T�A���Ŋɂ₩�Ɍ������Ă��܂����B�������A�挎31����1.17�{�Ƒ����ɓ]���A����7����1.04�{�A����14���܂łł�1.06�{�ƁA3�T�A���Ŋɂ₩�ȑ����X���ƂȂ��Ă��āA���������̕��ς̐V�K�����Ґ��͂��悻4��9888�l�ƂȂ��Ă��܂��B�����Ґ����O�̏T��葝�����̂�34�̓s���{���ŁA��s������A�����̓s�s���ł͂قډ����ƂȂ��Ă������A��B�ȂǑ����̕����傫���Ȃ��Ă���n�������܂��B
�����ꌧ
�l��������̊����Ґ����ł��������ꌧ�͐挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.32�{�A����7����1.29�{�A����14���܂łł�1.17�{�ƁA4�T�A���ő����X���ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1310�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���625.09�l�ƁA�S���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
��1�s3��
�y�����s�z�@�挎24���܂ł�1�T�Ԃł͌����X���ƂȂ��Ă��܂������A�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.19�{�A����7����0.99�{�A����14���܂łł�1.01�{�Ƃقډ����Ő��ڂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻7502�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�_�ސ쌧�z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.01�{�A����7����1.01�{�A����14���܂łł�1.03�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3966�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y��ʌ��z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.23�{�A����7����0.90�{�A����14���܂łł�1.01�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3411�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y��t���z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.17�{�A����7����1.03�{�A����14���܂łł�0.96�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2577�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����
�y���{�z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.10�{�A����7����1.07�{�A����14���܂łł�1.06�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3956�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���s�{�z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.28�{�A����7����1.04�{�A����14���܂łł�1.00�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻916�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���Ɍ��z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.09�{�A����7����0.99�{�A����14���܂łł�1.06�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1931�l�ƂȂ��Ă��܂��B
������
�y���m���z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.14�{�A����7����1.00�{�A����14���܂łł�1.07�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2685�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y���z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.24�{�A����7����1.17�{�A����14���܂łł�1.10�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻618�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�O�d���z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.45�{�A����7����1.19�{�A����14���܂łł�1.04�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻609�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����̑��̒n��
�y�k�C���z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.20�{�A����7����1.15�{�A����14���܂łł�1.13�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2224�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�L�����z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.37�{�A����7����1.09�{�A����14���܂łł�1.12�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1097�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�y�������z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.25�{�A����7����1.07�{�A����14���܂łł�1.11�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻2516�l�ƂȂ��Ă��܂��B����A�����̕�����r�I�傫���n�������܂��B
�y���ꌧ�z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.66�{�A����7����1.09�{�A����14���܂łł�1.28�{�ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻446�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���384.62�l�ƁA���ꌧ�Ɏ����őS����2�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�y�{�茧�z�@�挎31���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.47�{�A����7����1.61�{�A����14���܂łł�1.29�{�ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻579�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���378.65�l�ƁA�S����3�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
���̂ق��A��茧�͍���14���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.31�{�A���쌧��1.26�{�A���䌧��1.23�{�A�ޗnj���1.31�{�A�a�̎R����1.20�{�A���R����1.32�{�A��������1.33�{�A���茧��1.29�{�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ɓu�������Ă���n���������f�ł����v
�����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́A���݂̊����ɂ��āu�n��ɂ���Ċ����ɍ����݂���̂����݂̓������B��s�s���ł́A�n���s�s�ɔ�ׂĂ��łɊ��������l�������A�Ɖu�������Ă���l�������Ȃ��Ă���ȂǖƉu�̖ʂňႢ������ƍl������B����ɉ����đ�s�s���ł͗��s�������Ƒ����Ă������߁A�E���w�Z�ȂǂŐϋɓI�A�����I�ȗ\�h����Ă��邱�Ƃ�����ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂��B
����ɂ��āA�_�c���C�����́u�܂������4�A5���l�̊����҂��o�Ă��đ������Ă���n�������̂Ŗ��f�͂ł��Ȃ��B�����A���E�I�ȌX���Ƃ��ăI�~�N�������̗��s�͌����Ɍ������Ă���̂ŁA���ӂ����Ȃ�����������䖝����Ό����Ɍ������\���͏\���ɂ���B���ꂩ���^�A�x���}���邪�A�Ⴆ�Η��s����ۂɂ̓��N�`����3��ڐڎ���A�}�X�N�̒��p���H�͏��l���ŒZ���Ԃɂ���Ȃǂ̑�𑱂��Ă��炢�����B�̒��������ꍇ�Ȃǂɂ͗��s������߂邱�Ƃ��z�肵�Ă��������������B����2�N�Ԃłǂ������s�ׂ����X�N���������������Ă��Ă���Ǝv���̂ŁA��^�A�x�ł����������𑱂��邱�Ƃ�����v�Ƙb���Ă��܂��B |
�������̐V�K����6768�l�@�V�^�R���i�@4/15
15���A�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�6768�l�ł����B��T�̋��j������1344�l����܂����B
�������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ��6768�l�ŁA��T�̋��j������1344�l����܂����B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�7310�l�ŁA�O�̏T�Ɣ�ׂ�98.1���ɂȂ��Ă��܂��B�����҂�N��ʂɌ����20�オ1364�l�ōł������A������30�オ1334�l��65�Έȏ�̍���҂�359�l�ł����B�d�ǎ҂�14������1�l������20�l�ŁA�d�ǎҗp�̕a���g�p����15���̑���l��6.8���A�S�̂̕a���g�p����27.6���ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A60�ォ��90��̒j��7�l�̎��S���m�F����܂����B
|
�������s �V�K������7�������I�~�N�����uBA.2�v �@4/15
�����s���̐V�^�R���i�E�C���X���A�����͂̋����I�~�N�������uBA.2�v�ɒu����������B
�����s�́A�s���̐V�K�����҂ɂ��āA�����͂������Ƃ����I�~�N�������uBA.2�v���Ƌ^����P�[�X���S�̂�76.7%�ɒB���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�u���s�̎�̂��wBA.2�x�n���ɒu����������ƍl������v�Ƃ̌������������B�܂��A�V�K�����҂�7���ԕ��ςƓ��@���Ґ����킸���ɑ������Ă��āA���炽�߂Ċ����\�h����Ăт����Ă���B
|
���g��̓O���3��ڃ��N�`���ڎ�h �����ҍ��~�܂��1�s3���������b�Z�[�W�@4/15
��s��1�s3���̒m����4��14���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��h�~�ƎЉ�o�ϊ����̗����Ɍ����āA��{�I�ȑ�̓O���3��ڂ̃��N�`���ڎ���Ăт����鋤�����b�Z�[�W�����܂Ƃ߂܂����B
�������t�ȂǁA1�s3���̒m���ɂ���c��14���A�I�����C���ŊJ�Â���A�e�s���̊������Ò̐�������܂����B
��������A�܂h�~���d�_�[�u�̉����ȍ~�A�a���̂Ђ����Ȃǂ͌����Ȃ����̂́A�V�K�����Ґ��̍��~�܂肪�����A�F�J�m���́u3��ڂ̃��N�`���ڎ�̓���������1�s3���ŋ��͂ɔ��M���Ă������Ƃ��d�v�v�Əq�ׂ܂����B
�����āA��c�ł́A�����g��̖h�~�ƎЉ�o�ϊ����̗����A�����2�T�Ԍ�ɍT������^�A�x�����܂��āA��{�I�ȑ�̓O���3��ڂ̃��N�`���ڎ���Ăт����鋤�����b�Z�[�W�����܂Ƃ߂܂����B
|
���k�C����2605�l�����@���͍Ċg��Ɍx���A���O����Ăт����@4/15
�k�C����15���̐V�^�R���i�E�C���X���{����c�ŁA����̊���������߂��B�����ł�3�����{�ɍ��́u�܂h�~���d�_�[�u�v���������ꂽ���A�����͂������ψي��uBA.2�v�ւ̒u������肪�i�݁A�Ăъ������g�債�Ă���B���͔N�x���E�N�x���߂̊�����������������݂����ɑ����A�u3������v��}�X�N���p�Ȃǂ̓O������߂�B
15���̐V�K�����Ґ���2605�l�ŁA3���A����2600�l���鍂�����ƂȂ����B���҂�2�l�B�N���X�^�[(�����ҏW�c)��4�����������B
���͏d�_�[�u�������3��22�����獡��17���܂ŁA�u�Ċg��h�~��v�����{���Ă����B18���ȍ~�́u�����ɂ��肢����O�̍s���v��ݒ�B�u3������v��A���H�͒Z���ԁE��b���̓}�X�N���p�A�����ɕs�����������猟�����邱�ƂȂǂ��Ăт�����B���Ǐ�҂ւ̖���������5�����܂ōs���B
�������L����₷������Ҏ{�݂�ۈ珊�A�w�Z�ɂ͉��߂đ�̓O���v���B���N�`���ڎ�ł́A64�Έȉ��ւ̐ڎ�����������邽�߁A���́u���N�`���ڎ�Z���^�[�v(�D�y�s���ʋ�)�ŁA��Ƃ��w�Ȃǂ�10�l�ȏ�̒c�̐ڎ��4��23���`5��29���ɍs���B�\���18������t����B
|
����7�g�ւ̑Ή��@�����̗͂��������@4/15
�V�^�R���i�̊����҂��e�n�ő����Ă���B�n���ł̍L���肪�ڗ����A��s�s�����ɂ₩�Ƃ͂����㏸�X���ɂ���B
��6�g�������炵���I�~�N����������A��芴���͂̋����ʌn���ւ̒u������肪�i�݁A��`���u�ł͐V���ȃ^�C�v�̃E�C���X�����������B�l�̈ړ��������ɂȂ��^�A�x���T���A�}�g�傷�邱�Ƃ��z�肵�ď�����i�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�`�d(�ł��)���₷�����d�lj����X�N�͒Ⴂ�Ƃ������̓�����A�E�N���C�i���ɂ���ĕs�������𑝂��o�Ϗ���ɂ��ŁA���{�͂���܂łɂ������ē�����f�𔗂�ꂻ�����B
�œ_�ɂȂ�̂́A��ÑԐ����[���ȏɂȂ�Ƒz�肳���ꍇ�̎{��A��̓I�ɂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ȃǂ��Ăє��o���āA�Љ�o�ϊ����̐����ɓ��ݐ邩�ۂ����B
��T�J���ꂽ���{�̕��ȉ�ł́A�u��ÕN��(�Ђ��ς�)�����P�����܂Ő������ׂ����v�Ɓu�l�X�̎����I�ȍs���ϗe��M�����A�������ׂ��ł͂Ȃ��v�̈ӌ����o�āA����(���イ���)���Ȃ������Ƃ����B
��������g�Ή�́A�K��������ɂ܂Ƃ߂��A�����̑I�����𐭕{�Ɏ������Ƃ����肤��Ƃ̍l�����������B�����Ȃ�A����܂łقڈ�v���Č�����\�����Ă������ȉ�Ƃ��Ă͑O��̂Ȃ��Ή��ƂȂ�B
�\���͂������B��6�g�ł͍���Ҏ{�݂�w�Z�A�ۈ牀�ŃN���X�^�[�������B�Ƃ��낪���{�̎��g�݂́A�ȑO�Ɠ������d�_�[�u�Ɋ�Â����H�X���S���������߁A�ꕔ�̒m���╪�ȉ���o�[����^�₪�o���B
����ŁA��Ƃ��ݑ�Ζ��𐄏�������A�l�X����l���̉�H�����l�����肷��ȂǁA�d�_�[�u�̃��b�Z�[�W���ʂ��ے�ł��Ȃ��B�n���ւ̖ڔz������߂���B�s�s���ɔ�ׂĈ�ÑԐ����Ǝ�(�������Ⴍ)�ŁA�ЂƂ��т܂������A��@�I�Ȏ��ԂɊׂ鋰�ꂪ���邩�炾�B
�����̂Ȃ���肾���炱���A���ȉ�ɂ͕��L���m�����W�߁A�l������I���������ꂼ��̃����b�g�E�f�����b�g�ƂƂ��ɒ���悤���߂�B
������������A�ǂ̓����䂭�������߂�̂������̖������B���f�Ɏ��������R�������ɒ��J�ɐ������A�w�E���ꂽ�f�����b�g��}����藧�Ă��u���A���ʂɑ���ӔC��������B�R���i���s�����̍������o�Đ������ꂽ�͂��̐��ƂƐ����Ƃ̊W���A���܈�x�m�F�������B
�ݓc�͏d�_�[�u�̔��o������ɂ��āA�n���m���́u�v���v���d�����Ă����B����̐��Ɏ����X����̂͑�����A�����̑��l�C���ł͐�����S�����i�͂Ȃ��B���Ƃ������ǖʂł������قǁA�����̃��[�_�[�̗͗ʂ��������B�@ |
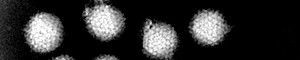 |
���V�^�R���i�@�X�E���E�H�c�E�R�`�E�����̊����ҁ@4/16
�X���Ȃǂ�16���A10�Ζ�����80�Έȏ�̒j��418�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B15���ɗz���ƌ��\����3�l����艺�����B�����̊����m�F�͌v4��3686�l�B����͔��ˎs90�l�A�O�O�ی����Ǔ�86�l�ȂǁB
��茧�Ɛ����s��16���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��357�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B���͍����1�l�̎��S�����\�B�����̊����m�F�͌v2��3308�l�A���҂͌v82�l�B�V�K�����҂̓���͖k��s92�l�A�����s54�l�ȂǁB
�H�c���ƏH�c�s��16���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��296�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�ی����ʂ͓��s137�l�A���53�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v2��1182�l�B
�R�`���ƎR�`�s��16���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��192�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͎R�`�s42�l�A�߉��s26�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v2��585�l�B
��������16���A10�Ζ�������90�Έȏ�̒j��556�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͌S�R�s176�l�A���킫�s122�l�A�����s57�l�ȂǁB14���ɗz���ƌ��\����1�l����艺���A�����̊����m�F�͌v4��5009�l�B��Ë@�ւɓ��@���Ă���90�Έȏ�̒j�������S���A�����̎��҂͌v201�l�ƂȂ����B
|
���n���Łu��7�g����v�̌������e�����́A��Ɏ�l�܂芴�\9���ōő��X�V�@4/16
�V�^�R���i�E�C���X�������n���̈ꕔ�ŋ}�g�債�Ă��邱�Ƃ��A�����̂̊Ԃł́u��7�g�̓�����ɗ������v�Ƃ̌������L�܂����B�����J���Ȃɂ��ƁA�����Ⓑ��A�{��Ȃ�9����12���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����҂��ߋ��ő����X�V�B�e�����͎̂�҂Ƀ��N�`���ڎ���Ăъ|����ȂNJ�����ɒ��͂��邪�A��l�܂芴���Y���B
�V�K�������ߋ��ő��ƂȂ����̂�3���ɉ����A���A�H�c�A�V���A���Q�A�啪�A�������̊e���B�n���ŋ}�����Ă��邱�Ƃɂ��āA���J�Ȑ��Ƒg�D�̘e�c���������́u�Ɖu�̊l���Œn�捷�����܂�Ă���v�Ƃ��A��6�g�ł���قNJ������L����Ȃ��������߂Ƃ̌����������B�����A9���̊Ԃ���́u���Ǐ�̐l���܂߂����������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����ɂ����Ȃ��̂ł́v�Ɖ��^�I�Ȑ����R���B
9���̂����A�{�茧�͖̉�r�k�m����12���̉�Łu�ߋ��ň��̊����B�ǖʂ��S���ς���Ă��Ă���v�Ɗ�@����\���B�u����������ɂЂǂ��Ȃ�A��Â��N��(�Ђ��ς�)����A��苭���s�����l�����肢������Ȃ��v�Əq�ׂ��B���쌧�̈������m����15���A�u�����x���œs���{���ʃf�[�^���悭���͂��Ă��炢�����v�Ƌ��߂��B
�������ł͍��́u�܂h�~���d�_�[�u�v���������ꂽ�挎7���ȍ~�A�����ɉƒ�����H�ł̊������O��Ȃǂ�v���B����18������͊X��������h�Ж�����ʂ����Ăъ|�����n�߂邪�A�������R���i�Ђł����������ӊ��N�̌��ʂ͔������B���̒S���҂́u�Ăъ|������߂�w���Ⴀ�A�����x�ƂȂ�B�����Ƃ��Č��ʂ͕\��ɂ������A���M�������邵���Ȃ��v�ƌ��B
����A�S���I�Ɍ��Ă������͍��~�܂肵�Ă���B�w�i�ɂ̓I�~�N�������̕ʌn���Ŋ����͂���苭���Ƃ����u�a�`�D2�v�̏o����A��҂̃��N�`���ڎ헦�̒Ⴓ������B�u�a�`�D2�͑�7�g�̑傫�Ȍ����͂ɂȂ�v(����L�����挧�m��)�A�u��7�g�ɓ������Ƃ����O��őΉ����v(�ێR�B�瓇�����m��)�Ƃ̎w�E���������B
�����s�̏��r�S���q�m����15���̉�Łu�����̘A����f������ʂ����҂ł���̂����N�`�����v�Ƌ����B���m���̑呺�G�͒m�����u�R���i�ȑO�̓�������߂����߂ɂ����N�`���ڎ���v�Ƒi�����B�@ |
���I�~�N����BA.1��BA.2�̑g�����́uXE�v�ɂ��Č����_�ŕ������Ă��邱�Ɓ@4/16
4��11���A�C�O������{�ɓ��������l����uXE�v�ƌĂ��I�~�N������BA.1��BA.2�̑g�ւ��̂����߂Č��o���ꂽ���Ƃ����\����܂����B���́uXE�v�Ƃ́A�ǂ����������������E�C���X�Ȃ̂ł��傤���B
���V�^�R���i�E�C���X�̑g�����̂Ƃ́H
�g�����̂́A2��ވȏ�̕ψي��ɓ����Ɋ������邱�ƂŁA�����҂̑̓��ł����̈�`�q�������荇���Ĕ���������̂ł��B�V�^�R���i�E�C���X�̓q�g�����łȂ������ɂ��������邱�Ƃ����邽�߁A�����̑̓��őg�݊������N���邱�Ƃ�����܂��B�����̕ψي��������ɗ��s���Ă�����ɂ�����V�^�R���i�E�C���X�̑g�����͒��������Ƃł͂Ȃ��A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s���n�܂��Ă���A�������̑g�����̂��m�F����Ă��܂��B���{�ł�2021�N10���ɃA���t�@���ƃf���^���Ƃ̑g�����̂��������Ă��܂��B�������A����܂ł͂����̑g�����̂����̕ψي����������͂������g�債���Ƃ�������͂���܂���ł����B
���I�~�N������BA.1��BA.2�̑g�ւ��́uXE�v
�I�~�N������BA.1��BA.2�̑g�����́uXE�v�́A2022�N1��19���ɃC�M���X�ŏ��߂ĕ���܂����B�I�~�N�������́A���{�ł���6�g�̎嗬�ł�����BA.1�ƁA��芴���͂������Ƃ���Ă���BA.2�A������BA.3�ɕ�����Ă��܂����B���݂͐V����BA.4�ABA.5�܂ŕ��ނ���Ă��܂��B����BA.1��BA.2�̑g�����̂��uXE�v�ƌĂ�Ă���A4��5���܂łɃC�M���X�����ō��v1098�Ⴊ�m�F����Ă��܂��B���{�ł�3��26���ɓ��������ǗႩ��XE�����o����A4��11���ɔ��\����܂����B���{�ȊO�ɂ��A���łɃA�����J�A�f���}�[�N�A�A�C�������h�A�C���h��^�C�ȂǁA�����̍��Ō������Ă��܂��B�I�~�N���������m�̑g�ւ��̂́AXE�ȊO�ɂ����E���ŕ���Ă��܂����A���̂Ƃ���p���I�Ɋ����҂������Ă���ɂ͂Ȃ��悤�ł��B
�I�~�N���������m�̑g�ւ��̂����łȂ��ABA.1�ƃf���^���Ƃ̑g�ւ���(�ʏ̃f���^�N����)���C�O�ŕ���Ă��܂��BXD�AXF�Ƃ����g�ւ��̂��A���ꂼ��t�����X�A�C�M���X�������Ă��܂����A�����_�ł͊����҂��ǂ�ǂ��Ă���Ƃ����ɂ͂���܂���B
���g�ւ��́uXE�v�ɂ��ĕ������Ă��邱��
�C�M���X�ی����S�ۏᒡ�̉�͂ł́AXE��BA.2�Ɣ�ׂ�12.6〜20.9%�����͂������Ƃ���Ă��܂��B�������A1��19���ɍŏ��̏ǗႪ����Ă���A����܂ł�1100����x�̕��ł��̂ŁA�I�~�N�����������E�ōŏ��Ɍ������Ă��琢�E���Ŕ����I�ɍL�������Ƃ��̂悤�Ȑ��܂����L������͍��̂Ƃ��낵�Ă��܂���BXE�̊����͂ɂ��Ă̕]���́A�����_�ł͂܂��m��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A����̕]�����҂���܂��B���l�ɁAXE�Ɋ��������l�̏d�Ǔx��A���N�`���ɂ��\�h���ʂɂ��Ă͏\���ȏ����܂���BBA.1��BA.2�̑g�ւ��̂ł��邱�Ƃ���A���m�N���[�i���R�̂Ƃ������Ö�̗L�����͒ቺ���Ă���ƍl�����܂����A�����f�V�r���A�����k�s���r���A�j���}�g�����r���Ƃ������R�E�C���X��̗L�����͂����炭�ς��Ȃ��Ǝv���܂��B��������XE�A�����ĐV���ɏo������ψي��̍L��������j�^�����O���Ă������Ƃ��d�v�ł��B
XE�����{�Ō��o���ꂽ�Ƃ��Ă��A��������l�ЂƂ�ɂł��銴����͕ς��܂���B���3�̖��������A�}�X�N�𒅗p����Ȃǂ̊����������܂Œʂ肵������Ƒ����邱�Ƃ��d�v�ł��B���Ƀ}�X�N���O������Ԃł̉�b���������X�N�ƂȂ�₷�����Ƃ���A��H��E��̒��H���Ȃǂِ͖H�E�}�X�N��H��S������悤�ɂ��܂��傤�B�S�[���f���E�B�[�N���T�����ꂩ��l�̈ړ��������Ȃ�܂����A��l�����W�܂��Ẳ�H�͔�����悤�ɂ��܂��傤�B�܂��A����҂��b�����̂�����ɂ����Ă͐V�^�R���i���N�`���̃u�[�X�^�[�ڎ�ŏd�lj��\�h���ʂ��Ăэ��߂邱�Ƃ��d�v�ł��B�������A���N�`�������Ŋ�����h���邱�Ƃ͍���ł���A���N�`���ڎ�������܂Œʂ�̊�����͑�����悤�ɂ��܂��傤�B
|
���ݓc�����́g���r�S���q�̗��h�x�����c�u�C�x���g���N���N���v�摗��̃��P�@4/16
�V�^�R���i��̌i�C���g��Ƃ��āA���{��5���ɂ��J�n����\�肾�����u�C�x���g���N���N���v��摗�肷������Ō������n�߂��Ƃ����B
���N���N���́u���N�v�ɂ́u���N�`���v�̈Ӗ�������B���̃l�[�~���O�Z���X���ǂ����Ǝv�����A���N�`��3��ڎ�ؖ��܂���PCR�����̉A���ؖ��ŃR���T�[�g��X�|�[�c�A����Ȃǂ̃`�P�b�g��2������(���2000�~)�ɂȂ�B�������𐭕{���⏕����d�g�݂��B
�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ���N�w�̃��N�`���ڎ�𑣐i����_�����������B
�u���N����GoTo�L�����y�[���̈�ŁA��N�x�̕�\�Z��388���~���v�サ�Ă���B��N12������͎��Ƃ̏ڍׂ��������HP���J�݂��A5���X�^�[�g�ɏƏ������킹�ď����͖��S�ł��B�R���i�Ђ̉e���Œ�����������Ǝ҂̊��҂͑傫���A�܂h�~���d�_�[�u�̉�����́w������n�܂�̂��x�Ƃ����₢���킹���}�����Ă��܂��v(�o�Y�ȊW��)
�Ƃ��낪�A�n���𒆐S�ɑ����������͍Ċg��X���ŁA��7�g�����O����Ă���B�ݓc��13���̎Q�@�{��c�Łu������(�܂h�~��)�d�_�[�u�̕K�v�͂Ȃ��ƍl���Ă���v�Ƃ̔F���������Ɠ����ɁA���N���ɂ��āu�����_�Œ����Ɏn�߂邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v�Ɛ摗������������B�ݓc���T�d�p���ɓ]�����̂́A���̂̕s�]�ɉ����A�����s�̏��r�S���q�m���̑��݂��傫���Ƃ����B
���r�m���͑����̃��N���X�^�[�g�ɔᔻ�I�ŁA��T8���̃I�����C������ł��u����܂ł����낢��ȃ^�C�~���O�Ŋ����g�傪���܂肫��Ȃ������ɉ����C���Z���e�B�u��݂��A�t�ɂ�������Ԃ�Ԃ����Ƃ��������v�ƃ`�N���B
�����s�́A�uGoTo�g���x���v�ĊJ�ɐ�삯�Ď��{����Ă���s���{���P�ʂ̊ό������x���u�������v��u�u���b�N���v�ɂ��Q�����Ă��Ȃ��B
�u2020�N�H�ɐ��������wGoTo�x��i�߂������A�N���ɂ����Ċ������g�債���B���r�m���͍���҂Ȃǂɓ��������̗��s���l��v������Ȃǂ��āA���{�̑��ᔻ���܂����B��������N�����J�n���ĉĂ̎Q�@�I�O�ɑ�7�g������������A���r�m���͓����Ɠ����悤�ɐ��{�ᔻ���J��o���A�Q�@�I�ɗ��p�����˂Ȃ��B�������Ɠ����Q�܂Ȃ��悤�A������7���̎Q�@�I��܂ŕ�������ɌX���Ă���̂ł��v(���@�W��)
�����Ƃ��A5���̊J�n�\��ɂ͎Q�@�I�O�̃o���}�L�I�ȈӖ����������B�摗�肷��A���łɊJ�n�č���ł��闷�s�E���W���[�ƊE�̎��]�⍬���������ĕ[�c�������\��������B�ݓc�ɂƂ��ẮA����܂����̒ɂ���肾�B |
 |
���V�^�R���i�@17���̓����s�̐V�K�����҂�5220�l�@�ő���30���981�l�@4/17
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA17��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�5220�l�B�d�ǎ҂͑O���ƕς�炸17�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�5220�l�B�N��ʂł�30�オ�ő���981�l�A������20���937�l�A������10�Ζ�����867�l�ƂȂ��Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�290�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�6723.1�l(�ΑO�T��88.8��)�B�s���̑���(�v)��137��3986�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����27.0��(1953�l�^7229��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T10��(8026�l)����2806�l����A6���A���őO�T�̓����j�����犴���҂��������܂����B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
������2707�l���R���i�����@5�l���S�@4/17
���{��17���A�V�^�R���i�E�C���X��2707�l���������A70�`90��̒j��5�l�����S�����Ɣ��\�����B�v�̊����҂�85��8794�l�A���҂�4868�l�ƂȂ����B1�T�Ԃ̗z������19�E5���B�a���g�p���͏d�Ǘp��12�E1���A�y�ǁE�����Ǘp33�E0���ŁA�S�̂�29�E7���������B |
���V�^�R���i�̍Ċ����A�킸��23����̎���� CDC���@4/17
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����Ґ����A���B��J�i�_�A�č��̈ꕔ�n��ōĂё����Ă���B���̒��ŁA�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊ���������A���̕a�C�ɑ��Ď����I�ȖƉu����������̂��Ƌ^��Ɏv���Ă���l�͑����B
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊ�����A�킸�����T�ԁA���邢�͐��J����ɍĊ����������Ƃ���Ă���l�͔��ɑ����B�Ƃ͂����A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊւ��Č��݂܂łɍs��ꂽ�����͏��Ȃ��A������������ł͉ʂ����ăE�C���X�����S�ɏ����Ă����̂��A�قȂ�ψي��ɂ�肻�ꂼ��ŏ��̊����ƍĊ����������N�����ꂽ�̂���f������͓̂���ꍇ������B
�Ď��a��Z���^�[(CDC)�́A�V�^�R���i�E�C���X�̃f���^���Ɋ������90���ȓ��ɃI�~�N�������ɍĊ����������Ƃ��m�F���ꂽ10�̎���ɂ��ċL�^���A���\�����B���̒����ł͑S�Q�m���V�[�P���V���O�ƌĂ���`�q��͋Z�p�ɂ��A�����҂̒��ɑ��݂��Ă����ψي������ꂼ��̊����œ��肳�ꂽ�B����́A2021�N10������2022�N1���̊Ԃ�4�̏B����W�߂�ꂽ���̂��B
�J�i�_�̃E�F�X�^���I���^���I��w�ŗՏ��Ɖu�w�E�A�����M�[�w���̃v���O�����f�B���N�^�[�߂�T�~���E�W�F�C�~�[��w�m�E���m�́u�Ċ����Ɋւ��ĐM�����Ă�������͂�����́A���ꂪ�����Ԃ̃E�C���X�r�o�ɉ߂��Ȃ��Ƃ������̂��v�Əq�ׁA�u���̂��߁A���̘_���̍ł���ۓI�ȃ��b�Z�[�W�́A�S�Q�m���V�[�P���V���O��2�̕ʁX�̊������m�F���ꂽ���Ƃɂ���v�ƕ⑫�����B
10�l�̊��҂̂���8�l��18�Έȉ��ŁA�c���2�l�͒����×{�{�݂̋��Z�҂ƈ�Ï]���҂������B�f���^���ƃI�~�N�������̊����Ԋu�ōł��Z�������̂́A12�`17�̃��N�`�����ڎ�̎q�ǂ�1�l���o�������킸��23���������B
���̎q�ǂ������߂ăf���^���Ɋ��������̂�2021�N11��23���ŁA�I�~�N��������12��16���������B���̎q�ǂ��́A�ŏ��̊������ɂ͏Ǐo�����A2��ڂ͖��Ǐ����B
����A�f���^���ƃI�~�N�������ɒZ���ԂŊ��������c���7�l�̎q�ǂ��̂����A6�l�͂ǂ���̊����ł��Ǐ���������B���������q�ǂ������͑S��5�`11�ŁA�c���1�l�̎q�ǂ��͍ŏ��̊����ŏǏ�����������A2��ڂ̊������̏Ǐ�Ɋւ���f�[�^�͓����Ȃ������B
�q�ǂ������̓f���^���̊������A�S�������N�`�����ڎ킾�����B�܂��A�I�~�N��������2��ڂ̊������o������܂łɃ��N�`����1��ڂ�ڎ킵�Ă����̂͂킸��2�l�������B
�W�F�C�~�[�́u����͌��O���������A���N�`���ڎ킪�œK�ɍs���Ă��Ȃ��\���������l�̊ԂōĊ����̑啔�����N���Ă��邱�Ƃ͈ӊO�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B�u�Ċ���������l�̃��N�`���ڎ�����ڎ킩�������ł��邱�Ƃ́A�W�c���N�`���ڎ�̎��g�݂��������������d�v�ł��邱�Ƃ���Ă���v(�W�F�C�~�[)
�č��őS�Q�m���V�[�P���V���O���鎖��͔��ɏ��Ȃ����Ƃ���A�قȂ��ނ̕ψي����m�F���A�Ċ�������肷��͓̂���B�������̑Ώێ҂�10�l�݂̂������̂͂��̂��߂��B
���_���͂܂��A�v���R�������ɗ���A����Ŏ��Ȑf�f�����Ă���l�������Ă��邱�Ƃ���A�V�[�P���V���O�̂��߂̃T���v���̓��肪�܂��܂�����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B90���ȓ��Ɏ��ۂɍĊ�������l�̐��͕s�������A����ł�CDC�̕������������ȏ�̐l�������邱�Ƃ͊m�����B
�V�^�R���i�E�C���X�̌��X�̕ψي��ł́A�����ɂ�菭�Ȃ��Ƃ�90���̓E�C���X�����ɑ���Ɖu�h�䂪������ƍl�����Ă����B90���ȓ��̌����̗z�����ʂ��؋��Ƃ��Ē�o���A�K�v�Ȍ�����N�`���ڎ�ؖ����̒�Ə�����Ă����l���������B�������A���V���ȐV�^�R���i�E�C���X�̕ψي����o�ꂵ�A�Ċ����̉\��������ɋ����Ȃ��Ă���悤���B
�f���^���́A���B��č����܂ސ��E�̑����̕����Ő����A�I�~�N��������BA.1��BA.2�ɒu��������ꂽ�B���������ψي��͔�r�I�V�����A�����̐l�Ɋ�������悤�ɂȂ����̂͂������J���Ȃ̂ŁA���������ψي��ɂ��Ċ����ɂ��Č��݁A����I�ɒm���Ă��邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��B
2���ɍ��ǑO�_���Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���K�͂ȃf���}�[�N�̒����́A20�`60���̊ԂɃI�~�N��������2������67�l����肵���B���̂���3����2�ȏ�̃P�[�X�ł́A�ŏ��ɃI�~�N��������BA.1�Ɋ�����A���x��BA.2�Ɋ������Ă����B���������l�̑唼�̓��N�`�����ڎ�̎�҂������B����́A�f���^���̌�ɃI�~�N�������Ɋ��������������������菬�K�͂�CDC�̌����Ƃ悭���Ă���B
���l�������Q�����Ă��Ȃ��������猋�_�����Ƃ͓�����̂́ACDC�̕��̒��҂�́A�Ċ����̑唼�̓��N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��q�ǂ��̊ԂŋN�������Ƃ��w�E���Ă���B
���҂�́u�Ċ����Ƃ܂��ő���h���ɂ́A���N�`���ڎ�̎��i������l���S���A�K�ȏꍇ�̓u�[�X�^�[���܂ߒx��邱�ƂȂ����N�`����ڎ킵�A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ��炳�ꂽ��Ǐo���肵����Č������s���ׂ����v�Əq�ׂ��B
|
���V���Ȍn���͂Ȃ��uX�v?�@�ψٌJ��Ԃ��V�^�R���i�̖��́@4/17
���X�ƕψق��J��Ԃ��V�^�R���i�E�C���X�B11���ɂ͍����ŏ��߂ĐV���Ȍn���uXE�v�̊����҂��m�F���ꂽ�B���E�ی��@��(WHO)�́uXE�v�n���ɂ��Ă��A��6�g�̎嗬�ƂȂ��Ă����uBA�E1�v��A���̔h���́uBA�E2�v�Ɠ��l�ɃI�~�N�������̈�ƈʒu�Â���B�ł͂Ȃ��uA�v��uB�v�ł͂Ȃ��A�����Ȃ�uX�v���t���̂��B
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�e���̓Q�m��(�S��`���)����͂��A�������قȂ�ψي����o�����Ă��Ȃ����Ď��𑱂��Ă���B�e�����Q�m�������f�[�^�x�[�X�ɓo�^����ƁA���ۓI�Ȍn�����ޖ����@�uPANGO(�p���S)�n���v�ŕ��ނ����BBA�E1��BA�E2�AXE�́A��������������B
�A���t�@����f���^���̂悤�ɃM���V����������WHO�����������ψي��ɂ��p���S�n���͗^�����Ă��āA���ꂼ��uB�E1�E1�E7�v�A�uAY�E29�v�ɕ��ނ����BA��B���悭�o�ꂷ�邪�A���͑唼�̃A���t�@�x�b�g���g�����Ƃ��ł���B���ۂ�C��M�AY��Z����n�܂�n��������B
X�ɂ͂ǂ̂悤�ȈӖ�������̂��BX����n�܂�n���͂�������A�ʁX�̌n���̃E�C���X�̈�`�q�������荇���Ăł����u�g�݊������v���BXE�́A�l�̑̓��ɓ����ɓ����Ă���BA�E1��BA�E2�̈�`�q�������荇�����B�ق��ɂ��A���t�@���ƃf���^���́uXC�v�������O�ŁA�f���^���ƃI�~�N�������́uXD�v��uXF�v���C�O�Ō������Ă���B�ǂ�ǂ����XAA�AXAB�Ƒ������[�����B
����AWHO�͕ψي����o�����A��������d�lj����X�N���������O������ꍇ�ȂǂɁA�u���O�����ψي��v��u���ڂ��ׂ��ψي��v�Ƃ��ăM���V���������g���Ė������A���s���Ď����Ă���B�����A������̑g�݊��������A�I�~�N�������̈�Ɉʒu�Â�����XE�������āA���܂̂Ƃ���M���V�������ł̖����͂Ȃ��B |
������ŐV����1315�l�����@�V�^�R���i�@4/17
���ꌧ��17���A�V����1315�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓����j��(10��)��1153�l�ɔ�ׂ�162�l�������B�v�����҂�14��3645�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����҂�16�����_��625�D54�őS���ő��B2�Ԗڂɑ��������404�D78�l�����������Ă���B�a���g�p����54�D7��(���@�Ґ�346�^�a����633)�ŁA�d�ǎҗp��13�D1��(���@11�^�a����84)�ƂȂ��Ă���B
�ČR�W�́A�V����80�l�̊��������ꂽ�B |
���uBA.2�v�ɒu������芴�����A��ÊW�ւ̎x��8���~�A3��ڐڎ��5���� �@4/17
�S���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����A3�T�A���ő����X���ɂ��邱�Ƃ��A�����J���Ȃɏ���������Ƒg�D�̉�ŕ��ꂽ�B���{�͕a���g�p�����Ⴂ���ƂȂǂ𗝗R�ɁA�����_�ł́A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�͕K�v�Ȃ��Ƃ��Ă���B
�����^�uXE�v���������m�F
�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA6�`12����1�T�Ԃ̐V�K�����҂̍��v���A34�s���{���őO�T�����������B��������1.25�{���ƍ��������̂́A���Ƌ{��A����A�a�̎R�A����A�ޗǂ�6���B13���͌��������A��������1���ȏゾ�����͎̂��ꌧ�����B
�ق��̒n���Ɣ�ׁA�֓��n���̊����͗��������Ă���B��ʂƐ�t�A���A�Q�n��4����2�`9�������B��������1�s2�����A������1�����A�_�ސ�ƓȖ�2�����Ɣ����������B
�V�K�����҂̑����v���Ƃ��āA�㓡�ΔV���J����15���A�����͂̋����I�~�N�������̈��^�uBA.2�v�ւ̒u���������������B���������nj������́A5����1�T��BA.2���S�̂�9�����ɂȂ�Ɛ��v����B
�܂��A���J�Ȃ�11���A���c�̋�`���u�ŁA�ʂ̈��^�uXE�v���������m�F�����Ɣ��\�����BXE�̊����͂͂܂��͂����肵�Ȃ��B(����䕶�F)
�����N�`��8.8����m�ۂ�2.4���~
�����Ȃ�13���̍������x���R�c��ŁA�R���i�Ђɔ�����Ë@�ւ��Ï]���҂ւ̍��̎x���z���A����܂łɏ��Ȃ��Ƃ�8���~���x�ɏ��Ɛ��������B�x���ɂ����2020�N�x�̍������a�@�̎��v�͋}���P���Ă���A�⏕���z�ɖ��ʂ��Ȃ��������ǂ����A������K�v������Ƃ��Ă���B
���N�`���ڎ�8��8200�����m�ۂ��邽�߂�2��4036���~�̗\�Z���v�コ��Ă���B����ɂ��ē��Ȃ́u�S�����̐ڎ��傫�����鐔�ʂŁA��p�Ό��ʂ��l����ׂ����v�Ǝw�E�����B
�V�K�����҂��n���ő������Ă��邱�Ƃ�����A�ݓc���Y��13���̎Q�@�{��c�ŁA�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�́A�����_�ŕs�v���Ƃ̍l�����������B�a����d�Ǖa���̎g�p�����ᐅ���ɂ���A����҂�8���ȏオ3��ڂ̃��N�`���ڎ���I���Ă���_�𗝗R�ɋ������B(�������i)
��20�E30��̐ڎ헦�ᒲ20%��
���N�`����3��ڐڎ헦�͑S�l����50����A65�Έȏ�̍���҂͖�85���ƂȂ��Ă���B����A11���Ɍ��\���ꂽ�N��ʂ̐ڎ헦�ł�20�A30�オ20����ɂƂǂ܂��Ă���B
���N�`���ڎ퐄�i�S���������˂鏼�씎�ꊯ�[�����͓��{������w����Ȃǂ�K��A�w���ւ̐ڎ푣�i�̋��͂����߂��B
���쎁�́u�Ⴂ���ł��d�lj�����P�[�X������A���ǂ̐S�z�����邱�Ƃ���ڎ�͏d�v�ƍl���Ă���v�Ƌ����B���{�Ƃ��ēs���{���̑�K�͐ڎ���Ȃǂ����p�����A��w�P�ʂł̒c�̐ڎ�̎��g�݂�i�߂�l�����������B
���J�Ȃ́A�ΐ�A���A�L��3����1�`2���̐V�^�R���i�����҂�Ώۂɂ��������̕��͌��ʂ����\�B70�A80��̏d�lj����ƒv�����͂�������A���N�`����3��ڎ킵���l�̕����A2��ȉ��̐l�����Ⴉ�����B�@ |
 |
��18���̓����s�̐V�K�����҂�3479�l�@���j����4000�l������4�T�ԂԂ�@4/18
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA18��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�3479�l�B�d�ǎ҂͑O������2�l����A15�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�3479�l(�s��6�l)�B�N��ʂł�20�オ�ő���694�l�A������30���641�l�A������40���561�l�ƂȂ��Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�183�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�6568.4�l(�ΑO�T��86.5��)�B�s���̑���(�v)��137��7465�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����26.2��(1891�l�^7229��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T11��(4562�l)����1083�l����A7���A���őO�T�̓����j�����犴���҂��������܂����B���j����4000�l����������̂�3855�l������3��21���ȗ�4�T�ԂԂ�ł��B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
���R���i�����ҁA���ŐV����2707�l�@�O�T���945�l���@4/18
���{��17�����\�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�2707�l�������B�O�T�̓������j��(10��)����945�l�������B�܂��A1��24������4��15���ɂ����āA70�`90��̒j��5�l�����S�������Ƃ��V���Ɋm�F���ꂽ�B
�{���̊����҂͉���85��8860�l�A���҂͌v4868�l�ɂȂ����B
|
���V�n���u�w�d�v�A�g��Ɍ��O�@���������́A�d�Ǔx�͕s���\�@4/18
�V�^�R���i�E�C���X���s�́u��7�g�v�̒������钆�A�I�~�N�������̐V�n���u�w�d�v�ւ̌x�������܂��Ă���B���ݎ嗬�̓���2�n����芴���͂������Ƃ���A���{�ł������҂��m�F���ꂽ�B�s�������͂̕Ȃ����A����̊g�傪���O����Ă���B
�����J���Ȃ�11���A3��26���ɕč����瓞������30�㏗���ɂ��āA�������̌����Ȃǂłw�d���������������Ɣ��\�����B�����ł̊m�F�͏��߂ĂŁA�����͓������͖��Ǐ����B
�w�d�͓����̏]���^�u�a�`�D1�v�ƁA�u������肪�i�ށu�a�`�D2�v�̈�`�q���������Ă���A�����Ɋ��������l�̑̓��őg�݊������N�����Ƃ݂���B���������nj������ɂ��ƁA�p����1�����{�ɏ��m�F����A����5�����_��1100���]��̕����邪�A������ɐ�߂銄����1���ɖ����Ȃ��Ƃ����B�č���f���}�[�N�Ȃǂł�������B
�a�`�D2�̊����͂͂a�`�D1��苭�����A�w�d�͂��̂a�`�D2�Ɣ�ׂĂ��A��莞�ԓ��̊����ґ������x��12�D6�������ƕ���Ă���B�E�C���X���זE�ɐN������ۂɎg���\�ʓˋN�u�X�p�C�N����ς����v���a�`�D2�Ɠ����Ȃ��߁A���N�`���⒆�a�R�̖�̌����ڂ͓����x�ƍl������B�d�lj����X�N�͕������Ă��Ȃ��B
���J�Ȑ��Ƒg�D��13�����\�̌����ŁA�w�d�ɂ��āA�S��`���(�Q�m��)���͂ɂ��Ď��𑱂��邱�Ƃ��K�v�Ǝw�E�B�����ǂɏڂ����c����̐��J���v�q�������́u�I�~�N�������͌y�njX�����w�E����邪�A�d�lj����邱�Ƃ������v�Ƌ���������ŁA�u�w�d�͂a�`�D2��芴���͂������Ǝv���A���Ɍx�����ׂ����݂��v�Ƙb���Ă���B
|
���S���R���i�V�K������2��4258�l�@��ʂ�2000�l�ȏ㌸���@4/18
18���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�2��4258�l�ŁA3�T�ԂԂ��3���l��������Ă��܂��B
�����s���̐V���Ȋ����҂�3479�l�ŁA��T���j��(11��)����1083�l����A7���A���őO�̏T�̓����j���̐l���������܂����B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�6568.4�l�ŁA�O�̏T��86.5���ƂȂ�A4���A����100���������܂����B����A�V����3�l�̎��S���m�F����܂����B
�S���I�Ȋ����҂�1�T�ԑO�Ɣ�ׂ�ƍ�ʂ�2000�l�ȏ㌸������1511�l�ɁA�_�ސ��1000�l�ȏ㌸������2609�l�ɂȂ�ȂǁA�k�C����H�c�Ȃ�8�������̂����A�����̓s�{���Ō������Ă��܂��BNNN�̂܂Ƃ߂ł́A18���A�S���Ŋm�F���ꂽ�����҂�2��4258�l�ŁA�挎28���ȗ�3�T�ԂԂ��3���l��������Ă��܂��B�S���Ȃ�������27�l�m�F����܂����B
����A�����J���Ȃɂ��܂��ƁA17�����_�̑S���̏d�ǎ҂́A�O�̓�����3�l�����A222�l�ł����B
|
�������Ґ��g�����~�܂�h�̊��c���́u�ԐM���v�_�������@4/18
���ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��������~�܂�̏������Ă��܂��B���V�C�Ɍb�܂ꂽ4��17��(��)�A�_�ˎs�̃����P���p�[�N�ł̓s�N�j�b�N���y���ސl�����̎p�������܂����B
�u�߂���v���Ԃ�ł��B����ς�ō��ł��v�@�u(�q�ǂ���)�Y�܂�Ă���1�ɂȂ�܂őS�R�O�ɏo�Ȃ������̂ŁA�Ђ炯�Ă��鉮�O�Ȃ�A��ė��悤���ȂƎv���āv
17���͑��E�~�i�~�ł������̐l���s�������Ă��܂����B
�u�q�ǂ������ƐH���ł��B(������)�s���͂���A������Ȃ��āv�@�u�S�[���f���E�B�[�N�����邵�A(�����҂�)�܂����������邩�Ȃ��Ďv���܂��B�[���ɂ͂Ȃ�Ȃ�����C��t���邵���Ȃ����ȂƎv���܂��v
�܂h�~���d�_�[�u����������Ă����������1�������o���܂����A���̊����Ґ��͉����~�܂�B��ヂ�f���́u�ԐM���v���_���������Ă���ł��B4��29������̓S�[���f���E�B�[�N�ł����A���N�͍ő�10���Ԃ̑�^�A�x�ƂȂ��Ă��܂��B�i�s�a�ɂ��܂��ƁA4��25���`5��5����1���ȏ�̍������s�ɍs���l�́A���N��1�D7�{�ƂȂ�1600���l�ƌ�����ł���Ƃ������Ƃł��B�@ |
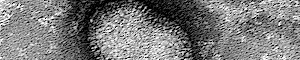 |
���V�^�R���i ������2067�l�����m�F ����ł͉ߋ��ő��Ɂ@4/19
�����ł�19���A����s�ʼnߋ��ő���256�l���܂�2067�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A1�l�̎��S�����\����܂����B�V�K�����Ґ��͑O�T�̓����j�����160�l�ȏ㑝���A���������������Ă��܂��B
�������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s�ōėz����8�l���܂�688�l�A����s�ōėz����2�l���܂މߋ��ő���256�l�A���َs��111�l�A���M�s�ōėz����1�l���܂�48�l�A�\���n����280�l�A�Ύ�n����186�l�A�I�z�[�c�N�n����117�l�A��m�n����82�l�A���H�n����62�l�A�_�U�n����49�l�A�����n����44�l�A�n���n����38�l�A���n����34�l�A��u�n���ƕO�R�n���ł��ꂼ��20�l�A�@�J�n����11�l�A�����n����8�l�A���G�n����7�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��2�l���܂�6�l�̍��킹��2067�l�ł��B�V�K�����Ґ��͑O�T�̓����j�����162�l�����A�ˑR�Ƃ��č��������������Ă��܂��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������50�l�������Ē����ǂ�1�l�A���̂ق��̐l�͌y�ǂ������͖��Ǐ�ŁA�V���Ȋ����҂̂���6���ȏ�ɂ�����1276�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������6160���ł����B�܂��A���͂���܂łɊ������m�F���ꂽ�l�̂���60��̏���1�l�̎��S�\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�13��9176�l���܂ނ̂�26��3342�l�A�S���Ȃ����l��1971�l�A���Â��I�����l��24��889�l�ƂȂ��Ă��܂��B |
�����k�̊����ҁ@4/19
�X���Ȃǂ�19���A10�Ζ�����80�Έȏ���܂ޒj��429�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�����̊����m�F�͌v4��4562�l�B����͍O�O�ی����Ǔ�120�l�A��\�O�ی���(�\�a�c�s)�Ǔ�90�l�ȂǁB���ˎs�Ȃǂ�4���̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
��茧�Ɛ����s��19���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��281�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͐����s68�l�A�k��s45�l�A���B�s24�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v2��4117�l�B�����s�ƒ����ی���(�Ԋ��s)�Ǔ��̋���ۈ�{�݂Ȃǂ�4���̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
�H�c���ƏH�c�s��19���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��363�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�ی����ʂ͓��s182�l�A���64�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v2��1973�l�B�H�c�s��\��Ǔ��̏��w�Z�Ȃnjv4���̃N���X�^�[�����������B
�R�`���ƎR�`�s��19���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��203�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����1�l�̎��S�����\����A�����̊����m�F�͌v2��1103�l�A���Ҍv85�l�ƂȂ����B�V�K�����҂̓���͒߉��s33�l�A����s23�l�ȂǁB�V���s�̕ۈ�{�݂ŃN���X�^�[���m�F���ꂽ�B
��������19���A10�Ζ�����90�Έȏ���܂ޒj��504�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͌S�R�s127�l�A���킫�s106�l�A�����s64�l�A��Îᏼ�s32�l�A�{���s30�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v4��6275�l�ƂȂ����B�N���X�^�[�͌S�R�s�̉��{�݂╟���s�̎����{�݂ȂǂŌv5�����������B
|
�������s �V�^�R���i 4�l���S 5583�l�����m�F �O�T��1300�l�]�� �@4/19
�����s����19���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̉Ηj�����1300�l�]�菭�Ȃ�5583�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��19���A�s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v��5583�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj�����1300�l�]�茸��܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�8���A���ł��B19���܂ł�7���ԕ��ς�6377.1�l�ŁA�O�̏T��84.0���ł����B
19���m�F���ꂽ5583�l��N��ʂɌ���ƁA�u10�Ζ����v�Ɓu30��v���ł������A��������S�̂�18.6���ɂ�����1041�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�340�l�őS�̂�6.1���ł����B�����o�H���������Ă���1936�l�̂����A�ł������̂́u�ƒ���v�ŁA66.5���ɂ�����1288�l�ł����B�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A19�����_��18���Ɠ���15�l�ł����B
����A�s�́A�������m�F���ꂽ40���80��A�����100�Έȏ�̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B |
�������̃R���i�V�K������4��893�l�A����52�l�c�d�ǎ҂�9�l����213�l�@4/19
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�19���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����4��893�l�m�F���ꂽ�B���҂�52�l�A�d�ǎ҂͑O�����9�l����213�l�������B
�����s�ł�5583�l�̊��������炩�ɂȂ����B�O�T�̓����j������1339�l����A8���A����1�T�ԑO����������B�s�ɂ��ƁA40�`100�Α�̒j��4�l�̎��S�����������B�d�ǎ҂͑O���Ɠ���15�l�B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�6377�l�ŁA1�T�ԑO����16���������B
|
���ϋq�ᒲ�u�S���I�n�[�h���v�@��X���`�F�A�}���\�i���[�O�@4/19
�i���[�O�̖�X���`�F�A�}����19���A�Ј������ɃI�����C���ŋL�҉���A������ł̓����������������ꂽ����A�ϋq�̖߂肪�݂�����ɂ��āu�S���I�ȃn�[�h��������ȂƂ������Ƃ͑z�肵�Ă������A���������ɏo�Ă���v�Ƃ̌������������B
�V�^�R���i�E�C���X�̂܂h�~���d�_�[�u��3�����{�ɉ����B2���l�Ƃ��������Ȃ��Ȃ������A����16�A17���ɍs��ꂽ�i1�v7�����̕��ϓ���Ґ��͖�9000�l�������B
���݂������o���Ẳ����͂ł��Ȃ��B���ւ����߂�ӌ����������A�܂��s���Ɋ�����ϋq������Ƃ��A�`�F�A�}���́u����������G���A��݂��邱�ƂŐS���I�n�[�h�����z�����邩������Ȃ��B�����Ȏ{����ɂ���Ă������Ƃ��K�v�v�Əq�ׂ��B
|
 |
����2�J���Ԃ��3000�l���@�k�C���̐V�^�R���i�V�K�����m�F�@4/20
�k�C���ł�20���A�V�^�R���i�E�C���X�ɐV����3058�l�̊������m�F����܂����B3000�l����̂́u�܂h�~���d�_�[�u�v���o�Ă���2��17���ȗ��A���悻2�����Ԃ�ł��B�S���Ȃ����l��4�l�ł��B
�����҂̓���́A�D�y�s1209�l�A����s��293�l��2���A���ʼnߋ��ő��ł��A���M�s37�l�A���َs120�l�B
|
������{���A�a���g�p��62.5%�@�N��ʂ�10�Ζ�����114�l�ő��@4/20
���ꌧ��18���A�V����10�Ζ�������90��̒j��575�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����\�����B�O�T�̓����j������2�l�����B���s��80��̒j��1�l�̎��S���m�F�����B�����̎��Ґ��̍��v��443�l�B
�{���`�v�����������Ắu�����Ґ����݉����邩�ǂ����́A���������������Ԃŗl�q�����Ȃ��ƕ�����Ȃ��v�Ɛ����B���@���̊���344�l�̂����d�ǎ҂̓[���ɂȂ������A����{���̕a���g�p����62�E5%�ƍ��������������Ă���B�{�������Ă͂܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āu�ύX�����Ώ����j�̌��ʂ����ɂ߂Ĕ��f����v�Ƃ̍l�����������B�@
�V�K�����҂̔N��ʂ�10�Ζ�����114�l���ő��B40���99�l��2�Ԗڂɑ��������B����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����҂�17�����_��636�E45�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ��������407�E35�l�����������Ă���B�V�K�N���X�^�[(�����ҏW�c)��6���B�{�Ó��s��ߔe�s�̊w�Z�A�ۈ�{�݂�6�l�`30�l���m�F���ꂽ�B������1����{����3�����{�B
�ČR��n���̐V�K�����Ґ���38�l�B
|
���ẴI�~�N�����h���^�A�ψي����s��9���ȏ�Ɂ��b�c�b�@4/20
�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)��19���A�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̔h���^�u�a�`�D2�v��16�����_�ō����R���i�ψي����s��74�D4���A���̈���u�a�`�D2�D12�D1�v��19���ƂȂ�A���킹��9���ȏ�ɂȂ����Ɣ��\�����B
�Ċ����Ґ���1���Ƀs�[�N��ł�����͋}���X���ɂ��邪�A�V�K�����Ґ����j���[���[�N�B��R�l�e�B�J�b�g�B�Ȃǖk�����B�𒆐S�ɂ������T�ԁA�Ăё����Ă���B16�����_�őS�ĐV�K������7���ړ����ς�3��4972�l�ŁA�O�T����23�D4�����������B
�R���i�����̍Ċg��͊��ɃA�W�A�≢�B�Ō����Ă���A����܂ł̃R���i�������s�̗�����l������ƁA���͕č��ŗ��s�̔g���ė�����Ƃ̌��O�����܂��Ă���B
|
���ψي���ǐՁ@�\���ꂽ�I�~�N�������̐��́@4/20
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��I�~�N�����́A�l�ގj��ōł��}���ɍL�܂����E�C���X���낤�B�ˏo���������͂Œm���閃�]�E�C���X�̏ꍇ�A1�l�̊����҂���12���Ԃ�15�l�ɍL����B�����A����~�ɔ����I�ɍL�������I�~�N�������͐l����l�ւ���ɋ}���ɂ���A1�l�̊��҂���4���Ԃ�6�l�A8���Ԃ�36�l�A12����ɂ�216�l�̊��҂���������B2�����ɂ͕č��ɂ�����V���Ȋ�����̂قڂ��ׂĂ��A���̕ψي��ɂ����̂ƂȂ����B
2020�N�H�ɍŏ��̕ψي��A���t�@�����肳�ꂽ�����A���ꂪ�������̕ψق��E�C���X�̋����ɂǂ��e�����邩�͂قƂ�ǂ킩���Ă��Ȃ������B�����A���̌��1�N�Ԃɓ���ꂽ�m���ƃf�[�^�ɂ���āA�I�~�N�������ɐ�������50�J���̕ψق̈ꕔ�ƁA�}���Ō����I�Ȋg�U�������炷�d�g�݂��֘A�Â�����悤�ɂȂ��Ă���B
�ʏ�Ȃ炱�̋�����Ƃɂ͂����ƒ������Ԃ�������Ƃ��낾���A�u����܂ŕ����̕ψي���1�N�Ԃɂ킽���Ē��ׂĂ����y�䂪�������̂ŁA�𖾂̏������ł��Ă����v�Ɖ��u���e�B�b�V���R�����r�A��w�̐����w�҃X�u���}�j�A���͂����B
�I�~�N�������̕ψق̐��͑��́u���O�����ψي��v��2�{�ɏ��A���^��BA.2�n���ł͂���ɑ����Ă���Ƃ݂���B�I�~�N�������̃X�p�C�N�^���p�N���ɐ������ψق̂���13�́A���̕ψي��ɂ͂قƂ�nj����Ȃ����̂��B�����̍\���ɐ������ω��́A���̃E�C���X�ɋ����ׂ��V���Ȕ\�͂��������t�^�����B�ȑO�̃f���^����͂����́g���l�n���N�^�h�Ƃ���A�I�~�N�������͕��ʂ����Ԃ��Ē��X�s�[�h�œ������ȁg�t���b�V���^�h���Ƃ�����B
���̋L���ł́A�I�~�N�������ŕω�����4�̓����������B����3�̕ω��͖Ɖu�n�����킵�����͂����߂�̂Ɋ�^���Ă��邪�A4�Ԗڂ͏Ǐ�r�I�y�����ނ��ƂɂȂ����Ă���B
|
���q�ǂ��̃R���i���@���A���N�`�����ڎ�Ȃ�2�{�Ɂ@�Ăb�c�b�@4/20
�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)��19���Ɍ��\�����ɂ��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������g�厞����5��11�̓��@���́A���N�`�����ڎ�҂��ڎ�҂�2�{�ɒB�����B���ڎ�̎q�ǂ��̓��@��10���l������19�D1�l�������̂ɑ��A�ڎ�҂�9�D2�l�ƂȂ����B
�I�~�N���������嗬������12��������2�����܂ł̍���14�B�œ��@����397�l�������Ƃ���A87�������N�`�����ڎ�A3����1����b�����Ȃ��A19�����W�����Î�(�h�b�t)�ł̎��ÂƂȂ����B�����͂̋����I�~�N�������ɂ��1���̕č������Ґ��͋L�^�I�����ƂȂ�A18�Έȉ��̓��@���}�����Ă����B
�ē��ǂ͍�N10���A�t�@�C�U�[�ƃr�I���e�b�N���J�������R���i���N�`����5��11�̎����ɑ���ڎ�����F�����B�b�c�b�ɂ��ƁA���̔N��̊��S�ڎ헦��28���ɂƂǂ܂��Ă���B�����ɂ��Ǝq�ǂ��̓��@�́A�s�[�N���ŃI�~�N�������嗬�̎����̂ق����f���^���̎���葽�������B
|
����芯�[�������u��^�A�x �s���������K�v�ȏɂ͂Ȃ��v �@4/20
�V�^�R���i����߂����芯�[�������́A�����_�ł͑�^�A�x�ɓs���{�����܂����ړ��Ȃǂ̍s���������K�v�ȏɂ͂Ȃ��Ƃ����F������������A�����g���h�~���邽�߁A�Ⴂ�l���܂߂����N�`����3��ڂ̐ڎ퐄�i�Ȃǂɋ��͂����߂܂����B
��芯�[�������͋L�҉�ŁA��^�A�x�̐V�^�R���i�Ή����߂���u�����_�ŁA�e�s���{������܂h�~���d�_�[�u�Ȃǂ̗v���͏o�Ă��炸�A�����ɓs���{�����܂����ړ��Ȃǂ̍s���������K�v�ȏɂ���Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
����ŁA�l�̈ړ��������ɂȂ邱�Ƃ��\�z����A�����g��h�~�Ɉ����������g�ޕK�v������Ƃ��āA�Ⴂ�l���܂߂����N�`����3��ڂ̐ڎ퐄�i��A�����L�b�g�̐ϋɓI�Ȋ��p�A����Ƀ}�X�N�̒��p�⊷�C�Ƃ�������{�I�Ȋ�����̓O��Ȃǂɋ��͂����߂܂����B�܂��A�L�Ғc����ό���C�x���g�Ȃǂ̎��v���N��̈�������ꂽ�̂ɑ��A��蕛�����́u���Ԃ̎�舵���ɂ��āA�S���Ȓ��ōŏI�I�Ȓ������s���Ă���v�Ɛ������܂����B |
�����b�N�_�E�����̏�C�ňُ펖�ԁI�H���̒D��������x�@���̖\�́@4/20
�܂h�~���d�_�[�u���e�n�ʼn��������1�J�����܂�B��7�g�̓������x���������̂́A���{�ł� �g�A�t�^�[�R���i�h �̋C�z�������n�߂��B
�����ۂ������ł́A�Ս��ȃ��b�N�_�E���������B�k���~�G�ܗֈȗ��A�O��I�Ɋ�����}������ �g�[���R���i�h ������f���Ă��钆�����{�́A�����̋}�g���������3��28�������C�̓s�s�������J�n�B�s�������������������Ȃ��A�s���̕s���͌��E���}������B
����ȏ�C�� �g�œ���h ���o����Ă���ƌ��̂́A������{�l���B
�u��C�₻�̎��ӂƂ݂���G���A�ŁA�o�ϓI�ȍ�����̒��̈����𗝗R�ɁA���g���E���݂莩�E������l���B�e�������悪�����̂悤�Ƀc�C�b�^�[�ɓ��e����Ă��܂��B�l����������Ƃ�����肩�A�n�ʂɒ@������ꂽ�l�q���f���Ă�����̂�����A�w�r������l���~���Ă���x�Ɛl�X�͋��|�ɕ�܂�Ă��܂��v
���ۂɃc�C�b�^�[�Łu��C�v�u��э~��v�Ƃ������Ӗ��̌��t�𒆍���Ō�������ƁA�ڂ��^���悤�ȓ��悪���X�ƌ���ꂽ�B�����ݏZ�̃��C�^�[�E�������O���Y�������͂���B
�u����̏�C�����ŁA�l���͍����̂������ɂ���܂��B���b�N�_�E���ɂ��ߌ������(�E�F�C�{�[)�Ȃǂ̍���SNS�ɂ�����Ɠ��ǂɑ����ɍ폜����邽�߁A������������O�Ƀc�C�b�^�[�ɓ]�ڂ��邱�ƂŁA�����i���Ă���̂ł��傤�B
����̓��e�́A���E�̂ق��A�l�����m�ŐH�i���������D�������l�q��A�����I�Ɋu�����邽�߂ɖ\�͂�U�邤�x�@���̎p�ȂǁA�����ׂ����̂�����A�b�v����Ă��܂��v
���������́u���ׂĂ����ۂɏ�C�ŋN�����Ă��邱�Ƃ��͂킩��Ȃ��v�Ƃ�����̂́A���ǂ̌��{���Ӗ��𐬂��Ȃ��قǂɁA�l���̕s���͍��܂��Ă���c�c�B�@ |
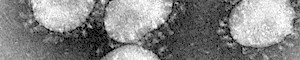 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������s�̐V�K�����҂�6713�l�@�ؗj����8000�l������14�T�ԂԂ�@4/21
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA21��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�6713�l�B�d�ǎ҂͑O���ƕς�炸�A15�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�6713�l(�s��1�l)�B�N��ʂł�30�オ�ő���1247�l�A������20���1224�l�A10�Ζ�����1203�l�Ƒ����Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�403�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�5905.1�l(�ΑO�T��78.7��)�B�s���̑���(�v)��139��6537�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����23.6��(1707�l�^7229��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T14��(8540�l)����1827�l����A10���A���őO�T�̓����j�����犴���҂��������܂����B1�T�Ԃ̒��Ŕ�r�I�����҂������ؗj����8000�l����������̂́A3124�l������1��13���ȗ�14�T�ԂԂ�ł��B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
�������R���i�����ҁAGW�����g1���l���h�̉\���@4/21
�S�[���f���E�B�[�N�����̓����s�̃R���i�����Ґ��ɂ��āA�A�x���̐l�o�Ȃǂ��N���E�N�n���݂ɂȂ��1���l����ƁA���É��H�Ƒ�w�̕��c�W�����������Z�����B
AI�Ŋ����͂��Ă��镽�c�����́A�S�[���f���E�B�[�N�O��̓s���̊����Ґ��ɂ��āA�l�o��ڐG�@��Ȃǂ��l�����Ď��Z�B�l�o�Ȃǂ����݂Ɠ������x���ƁA�����҂�6000�l�قǂʼn����ɂȂ�Ƃ����B����A��6�g�̓�����ƂȂ����N���E�N�n���݂ɂȂ�ƁA�A�x�����̗���12���ɂ�1���l����Ƃ����B
�u�S�[���f���E�B�[�N�Ƃ����͍̂��܂Ŋ������ĂȂ������R�~���j�e�B�[�Ɋ������L����\��������܂��B�]���܂��āA�v�������Ȃ��g��B�n���ȂǂōL�����������\��������ƍl���Ă��܂��v(���É��H�Ƒ�w�E���c�W������)
���̏�Łu�S�[���f���E�B�[�N�̌�ɋC�������ɂ܂܂̏������āA(�I�~�N��������)�wXE�n���x���d�Ȃ����ꍇ�ɂ͑�7�g�ɂȂ�\���͂���Ǝv���v�Əq�ׂ����c�����B6�����ɂ́A���N�`���̌��ʂ���܂�Ƃ��Ă��āA�����͂������Ƃ����I�~�N�������́uXE�n���v�̗��s�Əd�Ȃ�A�����̔g������ɑ傫���Ȃ�Ǝw�E���Ă���B
|
���u�������i�ށc�I�~�N�������gBA.2�h GW�߂Â������g��� �@4/21
�V�^�R���i�E�C���X�E�I�~�N�������́uBA.2�v�ւ̒u������肪�A���܋}���ɐi��ł��܂��B�ő�10�A�x�̃S�[���f���E�B�[�N���߂Â����A����̊����g��͋N���蓾��̂ł��傤���B
��R��̖��É��s�q���������B�����A�s���̈�Ë@�ւ���R���i�����҂̌��̂��������܂�A�E�C���X�̎�ނȂǏڂ�����͂��s���Ă��܂��B
3�����납�猟�o����銄�����}���ɑ����Ă���̂��wBA.2�x�B
���É��s�q���������̒S���ҁuBA.2���嗬�ɂȂ��Ă��܂��B����ꂪ�������Ă���̊��Ƃ��Ă�8�����炢�A���Ȃ�u������肪�i��ł���ł��v
�������܂�錟�̂�8�����I�~�N�������́uBA.2�v���Ƃ����܂��B
���É��s�q���������̒S���ҁu�ψق����Ȃ范���������肵���ꍇ�ɂ́A�����̃��N�`���̌��ʂ��ቺ���邱�Ƃ��z�肳���B�����������ψق��N���Ă��Ȃ������Ƃ��A������������`�q��͕͂K�v�v
�]���́uBA.1�v�n����芴���͂������Ƃ����uBA.2�v�B3�����납�爤�m�����Œu������肪�i��ł��܂��B
�����������ŋ߂Â��S�[���f���E�B�[�N�B���N�͊����g��㏉�߂ċً}���Ԑ錾���܂h�~�[�u���o�Ă��Ȃ��ŁA�ő�10�A�x���}���邱�ƂɂȂ�܂��B
���É��s�q���������̒S���ҁuGW�O���炢�ɂ́A�ق�BA.2�ɒu������邾�낤�ȂƎv���Ă��܂��B�ǂ����Ă�GW�͐l�������܂��̂ŁA�a���̂͐l�ɂ��ē����܂�����(�����g�傪)������ƕ|���ȂƂ͎v���܂��v
���N�̃S�[���f���E�B�[�N�ɂ��āA���m���̑呺�m���́c�B
�呺���m���m���u�����܂����ړ����ɂ��čT����悤�ɂƂ͌����܂��A��������C��t���Ă��������Ȃ���A��^�A�x�͂����v�悪������̕���������ł��傤����A�y����ł���������v
|
���i�C���f4���͏���C���A�܂h�~�����ŏ��������������o�ϕ@4/21
���{��21���ɔ��\����4���̌���o�ϕŁA�i�C���f�������������f���u�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ�錵�������ɘa����钆�ŁA���������̓������݂���v�Ƃ��A4�J���Ԃ�ɏ���C�������B�܂h�~���d�_�[�u����������A�O�H�◷�s�Ȃǂ̃T�[�r�X������P�������ƂȂǂ܂����B
���ڕʂł́A�l����̔��f���u���������ɑ����݂��݂���v����u���������̓������݂���v�Ɉ����グ���B����C����2021�N12���ȗ�4�J���Ԃ�B
�T���ł݂�������z��4���ɂ����ď��X�ɉ��P���Ă��邱�Ƃ�A�J�[�h�x�o�Ɋ�Â�������ŃT�[�r�X���3���㔼�ɂ����Ď��������Ă��邱�Ƃ܂����B��^�A�x���Ԃ̐V�����ɂ��Ă��A�\��̓R���i�ЈȑO�Ɣ�r����Ƃ܂��ア���̂́A�O�N��ł݂�Ɖ��P���Ă���Ƃ����B
�����A�����ɐg�߂ȕi�ڂ̉��i�㏸�Ȃǂ�v���Ƃ�����}�C���h�͎�܂�ł��邽�߁A�u����̏���ɗ^����e���ɂ͒��ӂ��K�v�v�Ɩ��L�����B
���������̔��f�́u�ꌘ�������ƂȂ��Ă���v�Ƃ��A�O���́u�������ɂ�����̂́A���̂Ƃ����܂�ł���v�������C�������B���f�����グ�́A2020�N7���ȗ�21�J���Ԃ�B��N���ɐ���������\�Z�̈ꕔ�������������Ƃɔ��f����Ă��邱�ƂȂǂ����R�Ƃ����B
�E�N���C�i���w�i�Ɍ����⍒���ȂǍ��ۏ��i���i�͍��������ŕs����ȓ��������Ă���A��ƕ����́u���̂Ƃ���㏸���Ă���v�Ƃ̕\���𐘂��u�����B����ҕ����́A�G�l���M�[��H���i���i�̏㏸��v���Ɂu�ɂ₩�ɏ㏸���Ă���v�Ƃ̕������ێ������B
�i�C�̐�s���ɂ��ẮA�����Ǒ�̌��ʂȂǂŌo�ρE�Љ�������퉻�Ɍ������A�C�O�o�ς̉��P��������āu���������Ă������Ƃ����҂����v�Ǝw�E�B����ŁA�E�N���C�i��Ȃǂɂ��s�����������钆�ŁA���ޗ����i�̏㏸����Z���{�s��̕ϓ��A��������ɂ�鉺�U�ꃊ�X�N�ɏ\�����ӂ���K�v������ƁA�O���̕\���P�����B
|
 |
���u�܂h�~�v����1�J���̐_�ސ�@���@�����V�K�����Ҍ��͓݂��@4/22
�V�^�R���i�E�C���X��́u�܂h�~���d�_�[�u�v����������A��\����ň�J�������B�_�ސ쌧���̓��@���Ґ��͌����X���ɂ������A�V�K�����Ґ��̌�����͓݂��B���́A�O��ڂ̃��N�`���ڎ킪�d�lj���h���ł�����̂́A�ڎ헦���Ⴂ��N�w�̊����������Ă��Ȃ��ƕ��́B�l�̈ړ��������ɂȂ��^�A�x��O�ɁA�����ڎ���Ăъ|���Ă���B(�u������)
�u�R���i�̌y�ǂ��Ă���Ȃɂ炢�B�O��ڂ̃��N�`����ł��Ă���v−�B���͏\�����A����ȃZ���t�Ŏn�܂�[������(�l�\�O�b)�擊�e�T�C�g�u���[�`���[�u�v�̌������`�����l���Ɍf�ڂ����B��N�w�̐ڎ헦�̒Ⴓ�́A�������ւ̌��O�ɉ����A�u�I�~�N�������͌y�ǁv�Ƃ̔F�����w�i�ɂ���Ƃ݂āA�u�y�ǂƂ������t�̃C���[�W�ƁA���ۂ̏Ǐ�͈قȂ�v�Ƒi����B
�d�_�[�u������A���@���Ґ��ƍ���Ҏ{�݂̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�͌����X���ŁA���ꂼ��O����\����͐玵�\��l�A�S���\�Z�����������A������\���ɂ͌ܕS��\�l�l�A���\�l���ɂȂ����B����A�V�K�����Ґ��͂Ȃ��Ȃ����炸�A�\��������悤�₭���l�䂪�����悤�ɂȂ����B
���́A���N�`���̎O��ڐڎ킪�i����҂̊����Əd�lj����}���ł��Ă�����̂́A�Ⴂ�w�ŗ��s�������Ă���ƕ��́B�\�������_�ŘZ�\�܍Έȏ��91�����O��ڐڎ���I�������A��\���33���A�O�\���37���A�l�\���48���ɂƂǂ܂�B�d�_�[�u������̗v�����Ґ��́A��\〜�l�\��őS�̘̂Z�����߂�B
�����Ɏg����a���́A�s�[�N���̓��ܕS������i�K�I�ɍ팸�B��\�������A�Z�i�K�̂���������O�Ԗڂɓ������O�S���Ƃ��A�������̐f�ÂƂ̗�����}��B����A�����}�g��Łu�ً}���I�v(������)�ɐ݂����A��t�̐f�f�����ɗ×{�ɓ���u����×{���x�v�͈ێ��B�V�K����×{�Ґ��͐V�K�����Ґ��̈ꊄ���x�Ő��ڂ��Ă���A�u���̃j�[�Y������A��߂�ł͂Ȃ��v(���S����)�Ƃ����B����×{�҂ւ̐H���z�z�̑Ώۂ��i�荞�܂܂��B
���s������w�W�u�s���z�����v�̎Z�o�p�����ۑ肾�B��Ë@�ւȂǂ̌����������m�ɔc���ł����A�����ɎZ�o���~�B����ɎO����\�������A�u�����ɕs���������Ǐ�ҁv��ΏۂƂ����u�����̂o�b�q�����v�̗z�������̗p�����B�����A�����Ƃ͎l�����܂łƂ���A��������Ȃ���ΎZ�o�ł��Ȃ��Ȃ�B
���͏d�_�[�u������A���H�X�ւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�v����C�x���g�̋q���������s�킸�A�Љ�E�o�ϊ����̍ĊJ�𑣂����A�x���Ԑ��̏o���͌����Ȃ��B����S���m���͏\����̒��L�҉�Łu�a���̕N��(�Ђ��ς�)�͉��P�X�������A�����҂����܂�ɂ�������Ƃ܂��N�������˂Ȃ��v�Əq�ׂ��B�@ |
���u��7�g�v�����ʌ��O�@�܂h�~�A�S�ʉ�������1�J���@4/22
�V�^�R���i�E�C���X�̂܂h�~���d�_�[�u�̑S�ʉ�������22����1�J���ƂȂ����B�����ȂǑ�s�s�ł͊����Ґ��̌����X�����݂��邪�A�ꕔ�̒n���ł͗��s��6�g�̃s�[�N������A�n�捷�������ɁB��7�g�ւ̌��O���@���Ȃ����A�l�̈ړ��������ɂȂ��^�A�x������B�����}���ɂ͎�N�w�̃��N�`���ڎ�������œ_�ƂȂ肻�����B
������21���Ɋm�F���ꂽ�V�K�����҂�4��7131�l�B��6�g�s�[�N����10���l�����甼���������̂́A�[�u������͕�������T����������5���l�O��Ő��ڂ��A�����~�܂��Ԃɂ���B
|
���_�ސ�2834�l�����@�[�u����1�J�������~�܂�@4/22
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�_�ސ쌧���ł�22���V����2834�l�̊������m�F����܂����B�܂h�~���d�_�[�u�̉�������1�J���A�����Ґ��͍��~�܂�̗l�q�ł��B�������m�F���ꂽ�̂́A���l�s��1017�l�A���s��690�l�A���͌��s��198�l�ȂǁA�������킹��2834�l�ł����B�O�̏T�̓����j�����1098�l�����Ă��܂����A�V�K�����Ґ���22���܂ł�1�T�ԕ��ςŁA1��������3001�l�ŁA�u�܂h�~�[�u�v�̉�������1�J���̌��݂����~�܂�̏ł��B�܂��A22���͎��S�����l�̔��\�͂Ȃ��A���̎���×{�ɂ��ẮA�V����192�l�ɏؖ��������s����Ă��܂��B
����L���X�^�[�u�S�[���f���E�C�[�N������Ă��܂��B ���̊������F����ǂ��v���Ă���̂��A�҂��s���l�ɕ����Ă݂܂����v
50���w�u(������)�C�ɂ͂��邪�A�����ɂ͊���Ă��Ă��܂������ȂƎv���v
30���Ј��u�q�ǂ�(1��)���}�X�N�ł��Ȃ��̂ŁA��l�����W���Ƃ���͂�����ƍs���Â炢�ȂƊ�����v
20���Ј��u�ڐG�͋C�ɂ��Ă��邪�A�R���i���͂�肾�������قǂ���Ȃ��̂��ȂƁv
50���w�u���̂܂�(�����Ґ���)�������Ăق������A�܂�3��ڃ��N�`�����ĂȂ��l���������邵�A�f�v���T���Ă���̂ł��ꂪ�C������v
|
���ݑ�Ζ��A�����x84���@�������i�݉ߋ��ō��\���Y���{���@4/22
���{���Y���{����22�����\�����u�����l�̈ӎ������v�ɂ��ƁA�ݑ�Ζ��̖����x��84�D4���ƂȂ�A1���̑O����77�D5���������ĉߋ��ō����X�V�����B�ݑ�Ζ��������n�߂�2020�N5����57�D0���Ɣ�ב啝�ȏ㏸�B�����͒ʐM������E�Ɩ��̐����A���ώ葱���̃f�W�^�����Ȃǂ��ۑ�ƂȂ��Ă������A���X�Ɋ��������i�ݖ����x�����サ���i�D���B
�ݑ�Ζ��Ȃǃe�����[�N�̎��{����20�D0���ŁA�ߋ��ŒႾ�����O���18�D5����������ƂȂ����B���{�͐V�^�R���i�Ή��́u�܂h�~���d�_�[�u�v��3�����{�ɑS�ʉ����������A�u��6�g���\���Ɏ������Ȃ��Œ����E���Ƃ��T�d�ȑΉ����Ƃ����v(���Y���{��)�Ƃ����B
|
���u���C�N�X���[������̏Ǐ�����̓f���^���Ɣ�ׂăI�~�N��������2�������@4/22
�V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̃��N�`��(�ȉ��A�V�^�R���i���N�`��)�ڎ��ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ���(�u���[�N�X���[����)�����l�́A���̌�ǂ̂悤�Ȍo�߂����ǂ�̂��B
����ɂ́A���������ψي��̎�ނ�u�[�X�^�[(�lj�)�ڎ�������ۂ����e������悤���B
�p�L���O�X�E�J���b�W�E�����h��(KCL)��Cristina Menni����́A�����͂̋����I�~�N�����������f���^���̕����A�u���[�N�X���[������̏Ǐ�̎������Ԃ����������Ƃ��錤�����ʂ��A�uThe Lancet�v��2022�N4��7�����\�����B
���̌��ʂ́A���B�Տ��������w�E�����NJw��c(ECCMID 2022�A4��23�`26���A�|���g�K���E���X�{��)�ł������\��ł���B
���̌����̑Ώێ҂́A�V�^�R���i�E�C���X�̌������ʂ�Ǐ�ɂ��ĕ���A�v��ZOE COVID�̎g�p�҂ŁA�V�^�R���i���N�`����2��ȏ�̐ڎ��Ɍ����ŗz�������������p����16�`99�̒j��9,980�l�B
���̂�������(4,990�l)�̓f���^���������̎嗬�ł���������(2021�N6��1��〜11��27��)�Ɋ�����(�ȉ��A�f���^��������)�A�c�锼���̓I�~�N�������������̎嗬�ł���������(2021�N12��20���`2022�N1��17��)�Ɋ������Ă���(�ȉ��A�I�~�N������������)�B
�k�o��Q�̔����p�x�́A�f���^�������҂�53���ɑ��ăI�~�N�����������҂ł�17���ł���A�k�o��Q�̃��X�N�͌�҂ő啝�ɒႢ���Ƃ����炩�ɂȂ���(�I�b�Y��0.17�AP��0.001)�B
����A�f���^�������҂Ɣ�ׂăI�~�N�����������҂ł́A�A�̒ɂ݂̃��X�N��55��(��1.55�AP��0.001)�A���̂�����(�m��)�̃��X�N��24��(��1.24�AP��0.001)���������B
�܂��A�]����COVID-19�̑�\�I��3�̏Ǐ�ł��锭�M�A�k�o��Q�A�P�̎����̂����A���Ȃ��Ƃ�1�ȏ�ǂ��郊�X�N�́A�I�~�N�����������҂̕����Ⴉ����(��0.56�AP��0.001)�B
�Ǐ�̎������Ԃ́A�f���^�������҂ŕ���8.9���Ԃ��������A�I�~�N�����������҂ŕ���6.9���Ԃ������B
�܂��A�u�[�X�^�[�ڎ���ς܂��Ă����l�ł́A�Ǐ�̎������Ԃ�����ɒZ���A2��ڎ�ς݂̏ꍇ�ł́A�f���^�������҂ŕ���9.6���ԁA�I�~�N�����������҂ŕ���8.3���Ԃ��������A�u�[�X�^�[�ڎ�ς݂̏ꍇ�ł́A�f���^�������҂ŕ���7.7���ԁA�I�~�N�����������҂ŕ���4.4���Ԃ������B
����ɁA���@�����l�̊����̓f���^�������҂�2.6���ɑ��ăI�~�N�����������҂ł�1.9���ŁA���@���X�N�̓I�~�N�����������҂̕���25���Ⴍ�A�܂��A1�T�Ԉȓ��ɉ���m����2.5�{���������B
Menni���ƌ����_���̏�Ȓ��҂ł���KCL��Tim Spector���́A�u�E�C���X�ʂɊւ��Ē��ׂ�K�v�͂��邪�A�Ǐ�̎������Ԃ��Z���Ƃ������Ƃ́A�����͂�L������Ԃ��Z���\��������B�����ł���A�E��̌��N�Ɋւ�����j����O�q����̎w�j�ɂ��e�����y�Ԃ��ƂɂȂ邾�낤�v�Ƙb���B
����̌������ʂɂ��āA�G�N�X�E�}���Z�C����w(�t�����X)��Linda Houhamdi����Pierre-Edouard Fournier���́A���������M�����t���_�]�̒��ŁA�uCOVID-19�̓����ƁA�����ƂȂ�ψٌ^�E�C���X�̊������Ԃɂ��ĉ𖾂��邱�Ƃ́A�E�C���X�̓`�d��h���A������}�����A���@���҂⎀�S���҂����炷���߂ɕs���ł���v�Əq�ׂĂ���B |
�������s�ŐV����5396�l�̊����m�F �O�T���j������1372�l���@4/22
22���A�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�5396�l�������B�O�T�̋��j��(6768�l)����1372�l����A11���A���őO�T�̓��j������������B�d�ǎ҂͑O������1�l����14�l�B
�������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�5396�l�ŁA���̒��ɂ͌��������{������t�̔��f�ɂ��Տ��f�f���ꂽ����^���NJ���6�l���܂ނƂ����B����7���Ԃ�1��������̕��ς�5709.1�l�ŁA�O�T���78.1���ƂȂ��Ă���B�N��ʂł́A20���30�オ�ł�����996�l�A������10�Ζ�����879�l�A40�オ847�l�A10�オ759�l�ȂǂŁA65�Έȏ�̍���҂�333�l�������B�V���Ȋ����҂̂���2557�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��āA1��ڎ킪45�l�A�ڎ�Ȃ���1434�l�A�s����1360�l�������B���傤���_�̐V�^�R���i���җp�a���̎g�p����23.4��(1695�l�^7229��)�B�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�a���g�p����5.3��(43�l�^804��)������(�ǂ��������͍ő�m�ی�����)�B�܂��A40�ォ��80���9�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
|
����� �V�^�R���i�u��6�g�v����Ҏ{�ݎx���ɉۑ� �̐������ց@4/22
�V�^�R���i�́u��6�g�v�Ŋ������ĖS���Ȃ����l�̐���1700�l�ȏ�ƁA�S���ōł������Ȃ������B���{�̐V�^�R���i�Ή��̐ӔC�҂��m�g�j�̃C���^�r���[�ɉ����A�u���ɑ����̃N���X�^�[��������������Ҏ{�݂ɑ��Ă����Ɉ�Îx�����s�����A�N���X�^�[�̋K�͂��傫���Ȃ����\���͔ے�ł��Ȃ��v�Əq�ׂč���Ҏ{�݂ւ̎x���ɉۑ肪�c�����Ǝw�E���������ŁA���̑傫�Ȕg�Ɍ����Ă͍���҂ɑ��đ����Ɉ�Â�ł���̐������������Ă����l���������܂����B
���N12��17���ȍ~�̐V�^�R���i�́u��6�g�v�ŁA���ł͈���Ɋm�F����銴���҂�15000�l����ȂǁA���ĂȂ��K�͂Ŋ������g�債�A�������ĖS���Ȃ����l�̐���1700�l�ȏ�ƁA�S���ōł������Ȃ�܂����B
��6�g�̂Ƃ��̑Ή��⎟�̑傫�Ȕg�ւ̔����ɂ��āA���{�̐V�^�R���i�Ή��̐ӔC�҂Ō��N��Õ��̓���r�q �������m�g�j�̃C���^�r���[�ɉ����܂����B
���̒��œ��䕔���́A��6�g�̊����ɂ��āA�u����Ɋm�F����銴���҂�1���l�������4�T�ԑ����ȂǁA�����K�͂����ɑ傫�������B�܂��A�}���Ȋ����g��������I�ŁA�O�T�䂪5�{����8�{�Ƃ��������̊g��X�s�[�h�͂���܂łɌo���������Ƃ��Ȃ����̂������v�Əq�ׁA�����͂��f���^�����������Ƃ����I�~�N�������̂܂ŁA�{�̑z���傫������������ƐU��Ԃ�܂����B
��6�g�ŖS���Ȃ���1755�l�̂����A92���]�肪70�Έȏ�ŁA����҂̊���������܂ł̔g�Ɣ�ׂčł������Ȃ�܂����B
�܂��A����Ҏ{�݂ł́A630�̎{�݂ŃN���X�^�[���������A1��865�l�̊������m�F����A����܂ł̔g�Ɣ�ׂāA�啝�ɑ����܂����B
����ɂ��āA���䕔���́A�u��Ϗd���~�߂Ă���B����҂͊��������ꍇ�̂��̌�̏Ǐd���Ȃ郊�X�N�����ɍ����A����҂������A���������̂�������傫�ȗv�����v�Ǝw�E���������ŁA�u���ɑ����̃N���X�^�[���������A�ی����̃T�|�[�g���Îx�����ǂ����Ă��A�����ɍs�����A���ʂƂ��āA�N���X�^�[�̋K�͂��傫���Ȃ����\���͔ے�ł��Ȃ��v�Əq�ׁA����Ҏ{�݂ւ̎x���ɉۑ肪�c�����ƐU��Ԃ�܂����B
����ŁA����Ҏ{�݂ő����̃N���X�^�[�������������R�ɂ��ẮA�u������̌��C��A���ӊ��N�ȂǁA����2�N�ԁA�J��Ԃ��A���g�݂�i�߂Ă����̂ŁA�Ȃ����őS���I�ȏ����ˏo�����N���X�^�[�̐������������̂��A���̌����͂킩��Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B
�܂��A���40�Ζ����̊����҂̎����z�肵�āA1000���K�̗͂×{�{�݂����܂������A�×{�����l�͍ł������Ƃ���70�l�ɂƂǂ܂�A����K�v�Ƃ��鍂��҂́A�l���ݔ����Ȃ����߁A����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
����ɂ��āA���䕔���́A�u�d�lj��̃��X�N�������Ⴂ�N��̊��҂���������Ƃ����z�肪�I�~�N�������̂܂ŁA�傫�����ς��A�~�X�}�b�`���������Ǝv���B����̊����҂ɂ��Ă��A���̎x�����Ȃ���ΑΉ�������A�j�[�Y�Ƃ̃~�X�}�b�`���������Ǝv���v�Ǝw�E���܂����B
�����āA���̊����̑傫�Ȕg�ɔ����邤���ŏd�v�ƂȂ鍂��Ҏ{�݂ւ̈�Ò̑̐��ɂ��āA���{���挎�A�{���̍���Ҏ{�݂�Ώۂɒ����������Ƃ���A�ӂ���{�݂̌��N�f�f�Ȃǂ��s���Ă��鋦�͈�Ë@�ւ���V�^�R���i�̎��Ö�̓��^�ȂǁA���Â�����Ɠ������{�݂͑S�̂�3���ɂƂǂ܂�܂����B
������ĕ{�́A�R���i���Â��s�����͈�Ë@�ւɎx��������t������A����Ҏ{�݂ւ̉��f���ł����Ë@�ւ���ʂȃ`�[���������肵�āA����Ҏ{�݂ւ̈�Îx���̑��i�߂Ă��܂��B
���䕔���́A�u�{�݂Ƌ��͈�Ë@�ւ̊W�������Ɋȏꍇ��������B�ǂ����Ă��Ή����ł��Ȃ��{�݂ɂ͉��f�`�[�����x���ł���̐��𐮂������B���{�̖ڕW��24���Ԉȓ��ɍ���Ҏ{�݂Ɉ�Îx���ɓ��邱�Ƃ��v�Əq�ׁA����҂ɑ��đ����Ɉ�Â�ł���̐������������Ă����l���������܂����B
�܂��A�R���i���җp�̕a���𑝂₷���߁A�{�́A�{���ɂ���500�]��̕a�@�̂����A����܂ŁA�R���i���҂�����Ă��Ȃ����悻300�̕a�@�ɑ��Ă����͂����߂Ă��܂��B
���䕔���́u����̊����K�͂͑��{���̂ǂ��ɂł��A�z�����҂�����Ƃ����ŁA�I�[����Ñ̐��ŗՂޕK�v������B���ɁA�R���i���҂�����Ă��Ȃ��a�@�ŃN���X�^�[���N�����ꍇ�A���̕a�@�ŃR���i���҂����Â��Ă��炤�K�v������B�I�[����Ñ̐����ł��邾�������m�����邱�Ƃ��厖���Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B�@ |
 |
���u���o�E���h�x�����ԁv���������H�X�̗��p�u8�l�v�Ɋɘa�@�����@4/23
�܂h�~���d�_�[�u���S���ʼn�������Ă���A22����1�����ƂȂ�܂��B�����������A�����s�́u���o�E���h�x�����ԁv�ɂ���4�T�ԉ����������ŁA���H�X�̗��p�l����8�l�ɂ܂Ŋɘa���邱�Ƃ����߂܂����B���҂ƕs������ނ��܂����B���������܂��������s�́u���o�E���h�x�����ԁv�ɂ��āA�X�̐l�ɕ����܂����B
�u�����Ă͂��Ă��邯�ǁA�܂�(�����҂�)���邩��A(������)�����Ƃ������܂��ˁv�u���傤���Ȃ��Ǝv���܂��A�l�����l���Ȃ̂Łv�u���S���̕��������v
�����ł�22���A�V����5396�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���܂����B�����X���ł͂���܂����A�C���ɂ߂��Ȃ����X�������܂��B���H�X�̗��p�l�����g�ɘa�h�����Ƃ����A���ꂵ������������܂��B
�u�𗬂ł���l����������̂́A�������Ƃ��Ǝv���܂��v
�����s�́A����܂ŔF�ؓX�ł̈��H�ɂ��āA�u1�O���[�v4�l�ȓ��E2���Ԉȓ��v�Ƃ���悤�ɋ��͂����߂Ă��܂����B���ꂪ25������́A�u8�l�ȓ��v�Ɋɘa����A����ɁA�S���̉A�����m�F�ł���A����ȏ�̐l���⎞�Ԃ��F�߂�Ƃ������Ƃł��B22���A���r�s�m���͎��̂悤�ɏq�ׂ܂����B
�����s�@���r�S���q�m���u�F�ؓX�͊����h�~��A�{���ɂ�������u���Ă�����킯�ł���܂��āA�i�߂�Ƃ���͐i�߁A����Ă����Ƃ���͎���Ă����Ƃ������ƂŁA�R���i�̗}���Ɉ������������͂������������v
�����`���A�ɂ��킢���݂��铌���E�V�h��̈��H�X�ł́g�l���̊ɘa�h�Ɋ��҂̐���������܂����B
�l�c�J���ꏤ�X�@�g�萳���X���u���܂�3���l�A4���l�Ƃ������\�����������ŁA���ꂩ��A�����X�l����������̂��ȂƁv
�g�܂h�~�[�u�h�������ƂȂ����挎�A��2�����Ԃ�ɉc�Ƃ��ĊJ�������̓X�́A�Ȃ̊Ԃɂ̓V�[�g���L���Ċ���������A�u1�O���[�v4�l�ȓ��E2���Ԉȓ��v�����Ȃ���c�Ƃ𑱂��Ă����Ƃ����܂��B���ꂪ�\�\
�l�c�J���ꏤ�X�@�g�萳���X���u���ꂩ��́A����(�V�[�g)���Ȃ��Ȃ��āA8���l���ł��ē��ł���B�S�[���f���E�C�[�N�́A����ق�\�������Ă��܂��B���X���g���Ă��炢�₷�����ȂƊ����Ă��܂��v
�������q�����߂鍡�A��l���ł̗��X�Ɋ��҂������Ƃ������Ƃł��B�߂�n�߂邠�̍��̓���B�����A���̈���ŁA�s���̎��̉����Ǝ҂ɂ͕s��������܂����B
�ԍ�l���@���ь���X���u�Ȃ��Ȃ��̂̂ɂ��킢�ɖ߂�Ȃ��̂��ȁv
���{����Ē��������ƕ��сA���C���͖�3000��ނƖL�x�Ȃ��������낦�����̎�X�B�g�l���̊ɘa�h�͂��肪�������̂́A�g�x�����ԁh���������ƂŁA���������g�O�ł̉�H�@��h���R���i�O�̂悤�ɉ��邩�ǂ������ʂ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�ԍ�l���@���ь���X���u��Ђł̈��ދ@������������Ă���A�Ƃ����̂����f�����Ă���̂ŁA����A�ǂ��Ȃ��Ă����̂��A�Ƃ������Ƃ�������ƕs���ޗ��B�S���������Ă�����āA���R�ɂ܂��O�ň��߂�悤�ɂȂ�������ȂƁv
���Ă̎p�ɋ߂Â�����B�R���i�ЂŌ}����3�x�ڂ̃S�[���f���E�C�[�N��O�ɁA���҂ƕs�����L�����Ă��܂��B |
�������s �R���i 4�l���S 5387�l�����m�F ��T�y�j���1400�l�� �@4/23
�����s����23���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓y�j����肨�悻1400�l���Ȃ�5387�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��23���A�s���ŐV���ɁA10�Ζ�������100�Έȏ��5387�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j����肨�悻1400�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�12���A���ł��B23���܂ł�7���ԕ��ς�5507.7�l�ŁA�O�̏T��77.3���ł����B23���m�F���ꂽ5387�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�S�̂�18.2���ɂ�����982�l�ŁA�ł������Ȃ�܂����B65�Έȏ�̍���҂�325�l�őS�̂�6���ł����B�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A23�����_��14�l�ŁA22���Ɠ����ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ60�ォ��80��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�̌i�C�g���������h������o�ϕ�ǂ݉����@4/23
�H�i�A�����K���i����n�D�i�܂ŁA�������̐g�߂Ȃ��̂̒l�グ���~�܂�܂���B���{�͌���1�x�u���{�̌i�C�̃C�}�v��\�����v�\���Ă��܂��B���̌��ʂƎ���������炷����̌���ł͓������N���Ă���̂ł��傤���H
�H�i�́u�̔����i�l�グ�̂��m�点�v���M��́u�l�グ�v�u�����h���́u���i����̂��m�点�v�c�����o�ł͓��{�̌i�C�����������ɐi��ł���悤�ȋC�����邯�ǁA���ۂǂ��Ȃ��Ă���́H����ȋ^����������Ă������{�o�ς́u�C�}�v���ꌾ�ŕ\�������v������̂͂����m�ł����H����͓��t�{���o���u����o�ϕv�ł��B���{���{������1�x�i�C�ɑ�������������������ɂȂ�܂��B
�����{�o�ς́u�C�}�v���ꌾ�ł����Ɓc
���{�͂��̕��̒���4���̌i�C�����̔��f���w���������̓������݂���x�Ə�����ɏC�����܂����B�R���i�̊������ˑR���~�܂�ł͂�����̂́A���N3�����{�ɂ܂h�~���d�_�[�u���S���őS�ʉ������ꂽ���Ƃ��v���ł��B���̂悤�Ɍ���o�ϕׂ̍��ȕ\���̕ύX������Γ��{�o�ς����ǂ̂悤�ȏȂ̂����@���邱�Ƃ��ł��܂��B����̏���C���̑傫�ȗv���́A�u�l����v��4���ɂ����ď��X�ɉ��P���Ă��邱�Ƃɂ���܂��B���ɊO�H�◷�s�Ȃǂ̃T�[�r�X��������Ă���̂ł��B���ۂ̏���̌���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B
�����s�Ƀ��C�u�c���p�q3�������c
�H�c��`�߂��̈��H�X�wHANEDA SKY BREWING�x�B�܂h�~���d�_�[�u����������Ă���A�q�������X�ɖ߂��Ă��Ă���Ƃ����܂��B��`�߂��ɂ��邽�ߗ��s�q�̗��p�������������ł͂���܂���B���͏d�_�[�u�̉����ŁA�אڂ��郉�C�u���ŕp�ɂɃ��C�u���J�Â����悤�ɂȂ������Ƃ�����A�X�̗��p�q�́A�ȑO�Ɣ�ׂĂ��悻3���������Ƃ����܂��B�������A�V���Ȗ�肪�В��̓���Y�܂��Ă��܂��B����́A���������Ȃǂ̉e���ŗ����Ɏg�����ޗ��̗A�����x�ꂽ��~�܂����肵�Ă��邱�Ƃł��B���̓X�͎��Ɛ��r�[��������ŁA���̂��܂݂Ƃ��Đ��n���̃v���V���[�g���l�C���Ƃ����܂��B�������A���̐��n���ɂ��Đ�����Ǝ҂���u�A�����x��Ă��āA�������炵�炭�����Ă��Ȃ��B�����镪�����Ƃ��g���đς��Ăق����v�ƘA�����������Ƃ����܂��B�������A�В��́u�����̂Ȃ̂ŁA��������̂߂��Ďg���Ƃ����Ă�����͖{���ɓ���v�Ƃ����܂��B�����œX�ł͐V���ɍ��Y�̏{�̖�𑽂��g�������j���[�ɕς��邱�Ƃ��������Ă���Ƃ����܂��B���������A���̖��ɉ��������̏㏸���傫�ȉe�𗎂Ƃ��Ă���̂ł��B
���T�[�����A�}�O�����c�`���V�͎����
�֓���6�X�܂���X�[�p�[�`�F�[���u�A�L�_�C�v�̎В��́u10�N�����Ēl�i���オ���Ă������i���ŋ߂͐������ŏオ�邱�Ƃ�����v�Ƃ����܂��B�Ⴆ�A�A�����̃T�[�����͉��i���オ��A�A�����̖{�}�O���͓��ׂ��炵�Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��B�����̏㏸�����i�ɓ]�ł��邱�Ƃ��ł����A�X�ł̓`���V�̐܂荞�ݍL��������ɕς��A�X���ɒu���悤�ɂ���Ȃǂ��Čo����팸���Ă��܂��B�������A���i�Ȃǂ̗A������ł��o���1�N�O�ɔ�ׂ�ƌ�30���~�ȏ�͑����Ă��āA���ʂƂ��ė��v����������ł���Ƃ̂��ƁB�В��́u���j���̒��ɓ���������Ă��邪�A���q����100�l���炢�s������B����Ȃɕ��Ԃ��Ƃ͍��܂łȂ������B���q������w�͂��Ă���̂ŁA�X���Ƃ��Ă��ł�����莩���w�͂𑱂��邵���Ȃ��v�Ƌꂵ�����̓��𖾂����܂��B�R���i�����������������A���s��O�H�������Ă��A�V���Ɍ������i�̍����╨���̏㏸�A�E�N���C�i��Ƃ�������肪�N���Ă��܂��B����͐��{����Ƃ������z�肵�Ă������[���ȏ��Ƃ����܂��B
���g���x���W����h�͕����㏸���~���H
����̓��{�o�ς͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O�̏��ѐ^��Y���́u�������㏸���ĉƌv���ꂵ���Ȃ��Ă����ꂪ�����l����̗������݂ɂȂ���킯�ł͂Ȃ��B����́w���x���W����x�����邩�炾�v�ƌ����܂��B���x���W����Ƃ̓R���i�Ђł���܂ʼn䖝���Ă��������s�����N�������Ƃł��B�����Ȃ̓��v�ɂ��ƃR���i�Ђ̎��l�ŕW���I�ȉƒ�ł͔N�Ԗ�20���~�x�o���}������Ă��܂��B����ɁA���{����̓��ʒ�z���t���̎x����������āA���v60���~�ȏ�̎������]��ƂȂ�A���̂܂ܒ��~�ɉ���Ă���Ƃ����܂��B���ю��͂����������~���O�H�◷�s�Ƃ������Ζʌ^�T�[�r�X�ɉ@������Čl����͍�����L�тĂ����Ɨ\�z���Ă��܂��B�����A���{�́u�~���A�������A�E�N���C�i��͕s�m����������B�l����͓����z�肵�Ă���������C�ɉ������ɂȂ��v�Ɨ\�����Ă��܂��B4�����܂łɊݓc�������܂Ƃ߂悤�Ƃ��Ă���o�ϑ�́A���������������i�̏㏸�╨�������ւ̑�ł��B���ʂ��������g�����߂��܂��B�@ |
 |
��GW�ɂ�郊�o�E���h���O�@�����s���u�x�����ԁv1�J������ �@4/24
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��͑����̓s���{���Ō����ɓ]�������A�ꕔ�ł͉ߋ��ő����L�^�����B�S�̓I�ɂ͑�5�g�Ɣ���������ɂ���B����������̑�^�A�x���T���A�Ȃ��x�����K�v���B
���S���ł͌����ł�3���ōő��X�V
�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂ł́A�S���̐V�K�����Ґ�(1�T�ԕ���)��22���܂�7���A���Ō��������B���J�Ȃɏ���������Ƒg�D��20���A���N�`��3��ڐڎ킪�i�ق��A�������ĖƉu���l�������l�����������Ƃ��A���P�Ɋ�^�����Ɛ��������B
�������g��X���̌�������B����1�T��(16�`22��)�ŐV�K�����Ґ��������Ǝ������A�����3���ōő����X�V�B�����19�`22���A�V�K�����Ґ���1000�l�����B
����A�����s�̐V�K�����Ґ�(1�T�ԕ���)��21���A��5905�l�ɂ܂Ō������B6000�l������1��20���ȗ��A��3�J���Ԃ�B�_�ސ�A��ʁA��t��3����1�����{�̐����ɂ܂ʼn��������B
�s���x������̂͑�^�A�x�ɂ�郊�o�E���h(�����Ċg��)���B�܂h�~���d�_�[�u������ɐݒ肵���u���o�E���h�x�����ԁv��5��20���܂�1�J����������B
���m�o�o�b�N�X�����N�`�����F
���J�Ȃ�19���A����4��ڂƂȂ�ăm�o�o�b�N�X���̃��N�`���𐳎����F�����B5�����{���玩���̂ւ̔z�����n�܂錩�ʂ��B���ɏ��F����Ă���ăt�@�C�U�[����f���i���Ƃ͎d�g�݂��قȂ�u�g�݊����^���p�N���N�`���v�ŁA�A�����M�[�Ȃǂō��܂Őڎ�ł��Ȃ������l�̑I�����ƂȂ邱�Ƃ����҂����B
3��ڐڎ���I�����l�͑S�l����49.8��(22�����\)�B20�`30��͈ˑR�Ƃ���30������Ă���B����������̑�^�A�x��O�ɁA���{�͎Ⴂ����Ɍ����Đڎ���Ăъ|���Ă���B
�����̎��Ö�J�������������悤�ƁA���J�Ȃ�22���A����`����Ƌ��a�ɍő�Ōv110���~����lj��x�����邱�Ƃ����߂��B���F�ς݂̌o����ɂ��Ă��A�\���ȍɂ��m�ۂł����Ƃ��āA�n��̋��_��ǂ̍ɏ���������グ��B(�M�܂�)
���ݕt���Ƌ��t���̐\������������
���J�Ȃ́A�R���i�Ђō��������l��ΏۂƂ������ݕt���Ƌ��t���̐\��������2�J���ԉ������A8�����܂łƂ�����j���ł߂��B�R���i�Ђ̒������ɉ����A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�ɔ��������㏸�ŁA�x���̌p�����K�v�Ɣ��f�����B���{�������ɂ܂Ƃ߂镨�������ً̋}��ɐ��荞�ށB�ً}��ł͂ق��ɁA�Ꮚ���̎q��Đ��т�ΏۂɁA�q�ǂ�1�l������5���~���x����������Ō�����i�߂Ă���B
�ό�����20���A�����A���m�A��������44���{�����s���Z���������s�����u�������v�ւ̍����x�����A4��28���h��������5��31���h�����܂ʼn�������Ɣ��\�����B��^�A�x��(4��29���`5��8��)�͎x���Ώۂ��珜�O����B���씎�ꊯ�[������20���A��^�A�x���̓s���{�����܂����ړ��̎��l�͋��߂Ȃ��l�����������B
|
���K�ߕ������S��l�|�A�u�쎀�ҁv���c�s�s����1�J���A�����E��C�@4/24
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A��2500���l���Z�ދ���s�s�A�����E��C�Ń��b�N�_�E��(�s�s����)��3��28���Ɏn�܂�A1�J���߂�������4�����{�������Ă��܂��B���E�ő�K�͂̓s�s���������ƂŁA�傫�ȍ������N���A�H���s������u�쎀�҂��o���v�Ƃ̏���ꂽ��A�啨�����Ƃ��s���ɔl�|����铮�悪�o�������A��s��łȂ������X����������ɂȂ�����ƁA����̒����ł͍l�����Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ��i�s���Ă���悤�ł��B��C�̌���ɂ��āA�m���t�B�N�V������ƂŒ����Љ����Ƃ̐����q����ɕ����܂����B
���K�ߕ����u�����錾�v�ŋC���ɂ��ʁH
Q.��C�̐V�^�R���i�̏ƁA��b���������Ă��������B
������u4��22���̐V�^�R���i�̐V�K�����Ґ��́A�Ǐ�̂���l��2736�l�A���Ǐ�̗z���҂�2��634�l�Ɣ��\����Ă��܂��B���{�̔��\����(���Ǐ�҂��܂߂��z��������)�ł����A��2��3000�l�ƂȂ�܂��B
�l��2487���l�A�ʐς��Q�n���قǂ̏�C�́A�����̒��ŕʊi�Ƃ�����s�s�ł��B�����̐����̒��S�͖k���ł����A�o�ςł͏�C�������g�b�v�ŁA����╶���̖ʂł��A�e���͂��ƂĂ��傫���s�s�ł��B�C�O�f�Ղ̐S�����ł���A���`�����̂����H�̒��S�n�ł�����A�f��Y�Ƃ����`�����C�ɒ��S���ڂ��Ă��܂��B���ώ����������S�̂�76��傫������83.66�B2021�N��GDP(����l)�͑O�N��8.1�����A���{�~�Ɋ��Z����77��5100���~�ł����B��C�ɌːЂ����Ƃ���������100���h���̉��l������Ƃ��������Ă��܂��v
Q.�����̃��b�N�_�E���́A���Ȃ茵�����ƕ����܂��B�ǂ̂悤�ȏ�ԂȂ̂ł��傤���B
������u�������O�o�֎~�A�H���s���A������PCR������R�������������Ă���悤�ł��B
����A�����̃W���[�i���X�g�Ȃǂ��I�����C���ōs�����ۃV���|�W�E���Ɏi��Ƃ��ĎQ�������̂ł����A�������̃v���f���[�T�[�͏�C�O�����w�̋����ŁA�����n�悾�����̂ł������̎Q���ł����B�ނɁw���v�ł����x�Ɛq�˂���A�w�������Ƀl�b�g�ŐH�����m�ۂ���̂����ۂł��x�Ƙb���Ă��܂����B�w���D��Ȃ̂ŁA���X�����܂����ǂˁx�Ƃ��B���̃V���|�W�E���̍Œ��ł��APCR�����̌Ăяo������������A��ɍs���Ȃ�������Ȃ���ł��ˁB10���O�Ƃ�15���O�ɓˑR�ʒm�����āA��ɒf��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B
���b�N�_�E�����̊u�������ł́A���|�S��s�����������悤�ł��B����̓I�~�N�������ɑ��鋰�|�ł͂Ȃ��A����܂Ől�����ӂ�Ă�����C�̊X������A�l�e���قڏ����Ă��܂������Ƃɑ��鋰�|�ł��B���҂̐�������Ȃ����Ƃɑ��āA�w���{�̑ǂ��t���Ă��Ȃ��̂ł́x�Ƃ����s��������Ă����܂��v
Q.�����͐��{���u�[���R���i����v��i�߂Ă���A�ꕔ�n��������Ċ����͂��Ȃ�}�����Ă����͂��ł��B�u���ۑ�v�����������A�Ȃ���C�Ŋ������g�債���̂ł��傤���B
������u�����̒����l�������^��������Ă��܂��B�l�����闝�R�Ƃ��āA1�ڂ͏�C�����ۋ��Z�Z���^�[�ł��邱�Ƃł��B�o�ρA�Y�ƁA�f�Ղ̒��S�n�ł���A����������q��@�����ې��̔����ȏオ�o�R����n�u��`�ł��邱�ƁB�C�O����u�a������₷�����������X�������ƍl�����܂��B������������ۑ�͂��Ă��܂������A����ł��h������Ȃ������Ǝv���܂��B
2�ڂ͐V�^�R���i�E�C���X�̕ψقł��B�I�~�N�������̊����̑����ɑΉ�������Ȃ������̂ł��傤�B3�ڂ́A�K�ߕ��������V�^�R���i�ւ́w�����錾�x�������ゾ�����A�Ƃ������Ƃł��B���������ۑ�͑����Ă��܂������A��ʎs���̒��ł͌x���S������Ă��Ă��āA�\�h�ӎ������Ȃ�Ⴍ�Ȃ��Ă����悤�ł��B�x���S���ɂ݁A���N�`�����ϋɓI�ɑł��Ȃ��l�������Ƃ���ŁA�ψي��������Ă��āA���s���L�������ƍl�����܂��v
���啨�����Ƃ�l�|����s��
Q.�u�쎀�҂��o���v�Ƃ̏�������܂��B����������������ŁA�����N���Ă���̂ł��傤���B
������u�쎀�҂̐^�U�͕s���ł����A�����Ȃ��Ώo���Ȃ���\�ɏo�Ă���̂��A���̏�C�̏ł��B
�Ⴆ�A�������Ƃ����A�K�ߕ����Ǝ�Ȃ̕��S����C�s�g�b�v�Ȃ̂ł����A�ނ���C�̏Z��X�����@�����Ƃ��A�Z���ɔl�|����A���̗l�q���B�e�������悪�l�b�g��ŏo���܂����B�Z��X�̂�����w�H�ו����Ȃ��B�j���W���ƃW���K�C���ƃ^�}�l�M2�������x������Ă��Ȃ��I�x�Ƌ��ׂA�ʂ̏������w�����Ă����Ȃ��B���Ȃ������͗L�߂��B�p��m��I�x�Ɣl�|�B�W���ɐ��~���ꂽ�̂ł��B
���Ă̒����ł́A����Ȃ��Ƃ͂��蓾�܂���ł����B��ʎs�����啨�����Ƃɑ��Đ����ɍR�c����Ȃǂ��蓾�܂��A���̓��悪�g�U���邱�Ƃ����蓾�܂���ł����B�������ǂ́A���{��n�����{�ɂƂ��ĕs�s���ȓ��������폜���Ă����̂ł����A�폜���Ԃɍ��킸�ɏo��������Ă��Ă��܂��B
��������w4���̐��x�Ƃ����A��C�s���̐��̐����W�߂����悪�l�b�g�ɃA�b�v����܂����B�܂��Ɏs���̐��̐��ŁA�H���s���Ȃǂ̎��Ԃ�i���Ă��܂��B�������ꂽ�I�t�B�X�r���ŏo�O���ꂽ�H�����w���ł��܂�������x�Ɣp��������ꂽ�A�����傪�z���Ŋu�����ꂽ��A��l��T���ĊX�����܂���Ă����y�b�g�̌�������E���ꂽ�A�wPCR�����̌��ʂ��܂��o�Ă��Ȃ�����x�Ǝ���̂���}���V�����X�ɓ���Ȃ��c�ȂǁA�ߎS�Ƃ��������悤���Ȃ����Ԃ��`����Ă��܂��B���̓��悪�A�폜����Ă��A���Ⴄ�Ƃ���ŃA�b�v�����B���̌�܂��폜����A�܂��N�����A�b�v����B�����Ȃ�l�b�g�x�@�ɕ߂܂�悤�Ȃ��Ƃ������ɋN���Ă����ł��ˁB����܂ł̒����ł͌����Ȃ��������ۂł��B
�������������̒��ɂ́A�f�}���������̂ł����A����҂̎��a���������Ă��a�@�Ŏ�f�ł����A�S���Ȃ鎖�Ⴊ�����Ă���͎̂����ł��B������A�L���Ȍo�ϊw�҂�98�̕�e�����S�������Ƃ�SNS�Ŗ������܂����B�̒��s�ǂ�������e�͕a�@�ɍs�������̂́A�w��f�ɕK�v�x���Ƃ��āAPCR�����̌��ʂ�4���Ԉȏ�҂�����A���̊ԂɖS���Ȃ��������ł��v
Q.�����́u�[���R���i����v�͍���������̂ł��傤���B�܂��A��C�̃��b�N�_�E���͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B
������u�[���R���i�͏K�ߕ����哱�̐���ŁA���s������H�̋��Y�}����3�I�����Ƃ����v����������Ă��܂��ł��傤�B�[���R���i�łȂ��ƁA�R���i�ɏ��������ƂɂȂ�Ȃ��ƌ��Ă���̂ŁA�����܂ő����Ă������낤�Ƃ����Ă��܂��B
�����������A�����̊����Ǒ�̑��l�҂Ƃ�������R��t���w�[���R���i����̌p���͍���x�Ƃ̎�|�̘_���\���āA�傫�Șb��ƂȂ�܂����B4��8���ɍs��ꂽ��w�@�̃I�����C���u�`�ł����̘b�����āA20���l���������A60���l���w�����ˁx�����������ł��B�������Y�}�͏ł��āA���̔�����ł������܂������A����ǂ��Ȃ邩�����ʂ��͓̂���ł��B
��C�̃��b�N�_�E�����A�����҂��o�Ă��Ȃ��ꕔ�n��ł͊O�o�����o�n�߂���A����ł܂��߂�����ƁA��s���͕s�����ł��B
����ŁA�ꕔ�̎s���̐S�ɕω����N���Ă��܂��B��C�͐�قǏq�ׂ��悤�ɁA���Z�s�s�A�o�ϓs�s�ł����A�w���������������Ă��Ă��Ӗ����Ȃ��x�Ǝv���l���o�Ă��܂����B21���I�̐�i�s�s�ŁA�w���X�����x�������Ă���̂ł��B�O���[�v�`���b�g�Łw���������Ă���̂́A�R�[�q�[�A�E�C���i�[�A�~���N�e�B�[�̃e�B�[�o�b�O�A�x�[�R���A�B���A�~�����̂͐��h�q�x�Ƃ����������ŏ������݂�����A���X����������l���������܂��B
����܂ł͏�C�l�ɂƂ��āA���@�⍂���ԁA�u�����h�o�b�O���w��ɓ��ꂽ���A���������i�x�ł����B�������V�^�R���i�ȍ~�A�L���Ȋw�Z�ɋ߂��ꏊ�ɉƂ��Ă��A�I�����C�����ƂŐ搶�ɂ��N���X���[�g�ɂ���Ȃ��B�w�Ƃ��ĉ��H�x�ƂȂ�܂��B�O�o�ł��Ȃ��̂ō����Ԃ͒u�����ςȂ��ŁA�������ԏ�ゾ�����Ă���B�����o�b�O�͔�������������B�w���������i���A�{���ɐl���ɉ��l�̂��邱�Ƃ��x�ƍl�������Ă���̂ł��B
�l�ԊW�����������������ɂ��Ȃ��Ă��܂��B���Ă̓r�W�l�X��̒��Ԃ�A���v�̂���l�Ƃ̕t���������d������Ă����̂��A����̃��b�N�_�E���ŗߏ��Ƃ̏����������Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��������Ă��܂����B��C�l�ɂƂ���180�x�̐l���ς̓]�����A�R���i�����������ɋN���Ă���悤�ł��v
|
�������s�A�V����4936�l�̊������\�@13���A���őO�T�����@4/24
�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�����s�͂��傤�V����4936�l�̊����\���܂����B��T���j����5220�l�����284�l�����Ă��āA13���A���őO�̏T�̓����j���̊����Ґ���������Ă��܂��B
�����s�́u���������A��t�������Ɛf�f�����v�g�݂Ȃ��z���h�̊��҂������҂Ƃ��Ĕ��\���Ă��āA2�l���g�݂Ȃ��z���h�̊��҂ł����B�V���Ȋ����҂̂����A���N�`����2��ڎ킵�Ă����l��2336�l�ŁA1����ڎ�����Ă��Ȃ��l��1376�l�ł����B�V�^�R���i�̕a���g�p����24.2���ŁA�ő�Ŋm�ۂł��錩���݂�7229���ɑ��A1753�l�����@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�̕a���g�p���́A5.3���ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł́A10�㖢����906�l�A10�オ757�l�A20�オ828�l�A30�オ863�l�A40�オ822�l�A50�オ386�l�ŁA�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂�276�l�ł����B���ݓ��@���Ă��銴���҂̂����A�����s�̊�Łu�d�ǎҁv�Ƃ����l�́A14�l�ƂȂ��Ă��܂��B |
�����{ �V�^�R���i �V����2733�l�̊����m�F �@4/24
���{��24���A�V����2733�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�20�l�]�葽���Ȃ�܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��87��9751�l�ƂȂ�܂����B
�܂��A24���͖S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B����܂łɕ{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��4906�l�ł��B�d�ǎ҂́A23������1�l������30�l�ł��B
|
������1311�l�R���i�����@10���l������A�ˑR�Ƃ��đS���ő��@4/24
���ꌧ��24���A�V����1311�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓��j��(17��)��1315�l�ɔ�ׂ�4�l�������B�v�����҂�15��3315�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�z���Ґ���23�����_��651.40�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ��������405.02�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����47.8��(���@�Ґ�314�^�a����657)�ŁA�d�ǎҗp��7.1��(���@6�^�a����84)�ƂȂ��Ă���B
�ČR�W�͕��Ȃ������B
|
��������3��8579�l�����@15�l���S�A�V�^�R���i�@4/24
������24���A3��8579�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����҂��m�F���ꂽ�B�s���{���ʂł͓���4936�l�A���2733�l�A�k�C��2633�l�ȂǁB���҂͐�t4�l�A�k�C���Ɖ��R�Ŋe2�l�Ȃnjv15�l�����ꂽ�B
�����J���Ȃɂ��ƁA�S���̏d�ǎ҂͑O������8�l������195�l�������B�@ |
 |
��3��ڐڎ�A�l���̔���������@�I�~�N�������ł����ʎ��� �@4/25
�V�^�R���i�E�C���X���N�`����3��ڂ�ڎ킵���l�̊������A25�����\�̐��{�W�v�Ől����50�E8���ƂȂ蔼�������B65�Έȏ��86�E9���ɏ�����A20���30�E1���A30���33�E2���ɂƂǂ܂�A��N�w�̐ڎ헦���オ�ۑ肾�B�����̓I�~�N�������ւ̌��ʂ��Ⴂ���ꂪ�w�E���ꂽ���A���̊ԂɗL�����������f�[�^���W�܂�n�߁A���Ƃ͐ڎ�����߂�B
���J�Ȃ͐ڎ�ɂ�銴���Ґ��̈Ⴂ�ׂ悤�ƁA4��4�`10���̊����҂�N��ʂɕ��́B20��ł�10���l������̊����҂����ڎ��766�l���������A2��ڎ�ς݂ł�306�l�A3��ڎ�ς݂ł�141�l�܂Ō������B
|
���O�H�Y�� �R���i�БO�̐����ɓ͂����@�u�܂h�~�v������� �@4/25
�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ���̂̊O�H�Y�Ƃ̓R���i�O�̐����ɂ͓͂����������������Ă��܂��B
���{�t�[�h�T�[�r�X������\����3���̊O�H�Y�Ƃ̔��㍂�́A�O�̔N�̓������Ɣ�ׂ�5�E9�������A�Ǝ�ʂł́A�t�@�X�g�t�[�h�́A6�E6���A��������p�u�́A4�E3���t�@�~���[���X�g�����́A4�E0���A���ꂼ�ꑝ�����܂����B
�����A����v�̑�����܂h�~���d�_�[�u�̉����ŋq�������߂蔄��グ�������グ������A�]�ƈ��s���ɂ��c�Ƌ@��̑�����~���A���ޗ���̍����ȂǂŊO�H�S�̂̉͐L�єY�݃R���i�O��2019�N�Ɣ�ׂ��86�E3���ɂƂǂ܂��Ă��܂��B
|
�������s�A�V����3141�l�̊������\�@��T���j������338�l���@4/25
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�����s�͂��傤�V����3141�l�̊����\���܂����B��T���j����3479�l����338�l����A14���A���őO�̏T�̓����j���̊����Ґ���������Ă��܂��B�����s�́u���������A��t�������Ɛf�f�����v�g�݂Ȃ��z���h�̊��҂������҂Ƃ��Ĕ��\���Ă��āA1�l���g�݂Ȃ��z���h�̊��҂ł����B�V���Ȋ����҂̂����A���N�`����2��ڎ킵�Ă����l��1464�l�ŁA1����ڎ�����Ă��Ȃ��l��877�l�ł����B�V�^�R���i�̕a���g�p����24.3���ŁA�ő�Ŋm�ۂł��錩���݂�7229���ɑ��A1757�l�����@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�̕a���g�p���́A5.1���ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł́A10�㖢����582�l�A10�オ464�l�A20�オ546�l�A30�オ565�l�A40�オ454�l�A50�オ265�l�ŁA�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂�181�l�ł����B���ݓ��@���Ă��銴���҂̂����A�����s�̊�Łu�d�ǎҁv�Ƃ����l�́A16�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�V����5�l�̎��S�����\����Ă��܂��B
|
������A�R���i��2�l���S�@�V�K������489�l�@�O�T���86�l����@4/25
���ꌧ��25���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������2�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�v���Ґ���447�l�ƂȂ����B�܂��A�V����489�l�����������Ɣ��\�����B��T�̌��j��(18��)��575�l�ɔ�ׂ�86�l�������B�v�����҂�15��3804�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�z���Ґ���24�����_��651.13�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ��������407.47�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����48.4��(���@�Ґ�318�^�a����657)�ŁA�d�ǎҗp��7.1��(���@6�^�a����84)�ƂȂ��Ă���B
�ČR�W��23����68�l�A24����50�l�A25����71�l�������B
|
����C�̃R���i������50���l�˔j�@������A����138�l�Ɂ@4/25
�����̉q�����ǂ�25���A�V�^�R���i�E�C���X��̃��b�N�_�E��(�s�s����)��������C�s��24���̐V�K������(��`���u�Ȃǂ�����)��1��9455�l�������Ɣ��\�����B�s�s�������n�܂���3��28������̗v�͖�50��3��l�ƂȂ�A����������������A�V�K�����̍��~�܂肪�����Ă���B
24���ɂ͊�����51�l�����S�B1��������̎��҂Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ŁA�����J�n��̎��҂͌v138�l�ɏ�����B��C�s�ɂ��ƁA24���̎��҂̕��ϔN���84.2�ŁA�ō����100�������B���ڂ̎����͂��������b�������Ƃ��Ă���B�@ |
 |
������3�N�Ԃ�̐����Ȃ��f�v�ցu�܂h�~������v��m�����\���@4/26
����26���A�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ��{����c���J���A29���`5��22���܂ł̊Ԃ̌��Ώ����j�����肵���B�����ł͊����̍��~�܂肪�����Ă��邪�A���͂܂h�~���d�_�[�u�̗v���͌�����A3�N�Ԃ�ɎЉ�A�o�ϊ����̖@�I�Ȑ������Ȃ����ŁA��^�A�x���}���邱�Ƃ����܂����B �@
�����A������������K�₷��ۂ�A���O����̊ό��q�ɑ���3��ڃ��N�`���ڎ�̊�����APCR�����ʼnA�����m�F����悤���߂�B
�A�x�̊��Ԓ��A���M�O�������{���Ă����Ë@�ւ̃��X�g�����z�[���y�[�W�Ō��J����Ƃ��Ă���B �@
��c��ɋL�҉�����ʏ�f�j�[�m���͑�^�A�x�Ō����̊����������ɂȂ�A�������g�傷��X��������Ƃ��āu�A�x��̊����g���}���邽�߂ɂ̓S�[���f���E�B�[�N���Ԓ��ɁA������l��l�̉߂��������d�v�ƂȂ�v�Əq�ׁA�������X�N�̍����s�����ł������������悤���߂��B
��^�A�x���Ԓ��̉߂������ɂ��āA�ʏ�m����1�Ǐ�̂���l�͊O�o���T����A�l�ɉ��Ȃ�2���l���ŐH�������Ȃ�3����҂̎����K��A�ꏏ�ɐH������l�����肷��4���X�N�̂���s�������O�ɁA�����ʼnA�����m�F����\���Ƃ��Ăъ|�����B �@
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�z���Ґ���25�����_��645.34�l�ƂȂ�A�S���ň��̏������Ă���B �@ �@
����{���ł͕a���g�p����55�E9���ƂȂ�A�����܂h�~���d�_�[�u����������ڈ���60���ɋ߂Â��Ă���B �@
�ʏ�m���́A1400�l�K�͂ŊJ�����5��15���̕��A�L�O���T�ɂ��Ắu���������Ȃ�ƁA(�Q���l����)���炷���Ƃ��l������v�Ƃ̌������������B
|
�����Ɨ�3����2.6���ɉ��P�A���I�ȗ��E�������@�L�����l�{���͏㏸�@4/26
�����Ȃ�26�����\����3���̊��S���Ɨ�(�G�ߒ����l)��2�D6���ŁA�O��(2�D7��)����0�D1�|�C���g���P�����B���X�g����|�Y�Ȃǂɂ��u���I�ȗ��E�v���������B2020�N4���ȗ��̐����ƂȂ������A���������x�Ǝ҂������A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̉e���݂͂���B���J�Ȃ����\����3���̗L�����l�{����1�D22�{�ƁA�O���ɔ�ׂ�0�D01�|�C���g�㏸�����B
���Ɨ����܂ޘJ���͒����̒������Ԃ�3��25��31���B�V�^�R���i�E�C���X��́u�܂h�~���d�_�[�u�v�͑S�ʉ�������Ă����B
���C�^�[���܂Ƃ߂����S���Ɨ��̎��O�\��(2�D7��)����������B
�j���̎��Ɨ���2�D7���ƑO������0�D3�|�C���g�ቺ�B������2�D4���őO���Ɠ������������B
�A�ƎҐ�(�G�ߒ����l)��6711���l�őO���ɔ��18���l�����B
���S���ƎҐ�(��)��179���l�ŁA�O���ɔ�ׂ�9���l���������B����ł́u�����I�ȗ��E(���ȓs��)�v��7���l�����A�u���I�ȗ��E�v��5���l�̌����B�u�V���ɋ��E�v��1���l�����������B
�x�ƎҐ�(����)��243���l�B�O������1���l���������B��N�A�N�x�ς��ɂ�����3���͋���֘A�Ȃǂŋx�Ǝ҂�������X���ɂ��邪�A����܂��Ă������͍����Ƃ����B�S���҂́u���Ǝ҂ɂȂ炸�A�x�Ǝ҂ɂƂǂ܂��Ă���Ƃ����������ł���B�ْ����̉e���Ȃǂ��l������v�Ɛ��������B
2021�N�x���ς̊��S���Ɨ���2�D8���ŁA�O�N�x�ɔ��0�D1�|�C���g���P�����B���S���ƎҐ���191���l�ƁA�O�N�x�ɔ�ׂ�8���l���������B
�L�����l�{����2020�N4���ȗ��̍����������A2019�N��1�D5��1�D6�{��Ő��ڂ��Ă������Ƃ܂���ƐV�^�R���i�̉e���͎c���Ă���A�����������������݂���B
�L�����l�{���͎d����T���Ă��鋁�E��1�l������A��Ƃ��牽���̋��l�����邩�������B���l�A���E�͂Ƃ���3�J���ԗL���ŁA�f�[�^��1�A2�A3���̏����f���ꂽ���̂ƂȂ�B
3���͐V�^�R���i�̕ψي��u�I�~�N�������v�̐V�K���������������Ă������Ƃf���A�V�K���l�����O���ɔ�ׂ�4�D4���A�V�K���E�\��������6�D7�����ꂼ�ꑝ�������B
|
��3��ڐڎ�A�l���̔������Ɂ@���{�A�I�~�N�����ւ̌��ʎ����@4/26
�V�^�R���i�E�C���X���N�`����3��ڂ�ڎ킵���l�̊������A25�����\�̐��{�W�v�Ől����50�E8���ƂȂ蔼�������B65�Έȏ��86�E9���ɏ�����A20���30�E1���A30���33�E2���ɂƂǂ܂�A��N�w�̐ڎ헦���オ�ۑ肾�B�����̓I�~�N�������ւ̌��ʂ��Ⴂ���ꂪ�w�E���ꂽ���A���̊ԂɗL�����������f�[�^���W�܂�n�߁A���Ƃ͐ڎ�����߂�B
���ꌧ����3��ڃ��N�`���ڎ헦��51�E6���őS�����ς�0�E8�|�C���g�������B�N��ʂł�70��A90��A100�Έȏ��90������ȂǍ���҂̐ڎ킪�i����A20��A30�オ30����ɂƂǂ܂�Ȃǎ�N�w�̐ڎ헦�͐L�єY��ł���B
�����J���Ȃ͐ڎ�ɂ�銴���Ґ��̈Ⴂ�ׂ悤�ƁA4��4�`10���̊����҂�N��ʂɕ��́B20��ł�10���l������̊����҂����ڎ��766�l���������A2��ڎ�ς݂ł�306�l�A3��ڎ�ς݂ł�141�l�܂Ō������B���̔N��ł��������قNJ����҂͏��Ȃ������B
���������nj������̘e�c���������́u�N��ɂ�����炸������\�h�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B(�d�lj����X�N���Ⴂ)��҂���������Ό��ǂ̃��X�N������B3��ڂ܂ŎĂق����v�Ƙb���B
16�`64��Ώۂɂ��������̌����ł́A3��ڐڎ�̃I�~�N���������s���ł̔��Ǘ\�h���ʂ�69���ŁA2��ڂ܂ł�43���ɔ�ׂč������Ƃ������B��t��a�@��_�ˑ���A3��ڐڎ�Ɉ��̗L���������邱�Ƃ������������ʂ\�����B
|
��������5048�l�����@�R���i�A3�l���S�@4/26
�����s��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����5048�l���ꂽ�Ɣ��\�����B1�T�ԑO�̉Ηj������530�l�������B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���5342�E4�l�ŁA�O�T���83�E8���B���҂̕�3�l�������B
�d�ǎ҂͑O����1�l����15�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�10�Ζ�����942�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�275�l�������B�����҂̗v��142��445�l�ƂȂ����B�@ |
���ݓc�����@GW���u���f�֕��v�c�R���i��p�����@4/26
���T������n�܂�S�[���f���E�C�[�N��O�ɁA�ݓc������b�́u���f�͋֕����v�Ƃ��āA�V�^�R���i��ւ̈��������̋��͂�i���܂����B
�ݓc������4��26���[���ɊJ������̒��Łu�����̋��͂̂�������3�N�Ԃ�ɂ܂h�~���d�_�[�u��ً}���Ԑ錾�̂Ȃ��S�[���f���E�C�[�N�ƂȂ�B���������f�͋֕����v�Əq�ׂ���ŁA���i�͎d���ȂǂŖZ�����l���A�x���Ƀ��N�`����ڎ킷��悤�A���߂ČĂт����܂����B�܂��u�A�Ȃ���l�͋A�ȑO��3��ڐڎ�A�܂��͌�������悤���肢����B�߂��̖����������_�Ō���������ق��A�A�x���͎�v�w���`���ŗՎ��̖����������_���g�[����v�Əq�ׁA�ϋɓI�Ɍ�������悤���߂܂����B
�ݓc�����̓S�[���f���E�C�[�N���u�����ւ̈ڍs���ԁv�Ƃ��A�ő���̌x�������ێ�����悤�i���܂����B
���̓��J���ꂽ�S���m����̃R���i���{���̉�c�ł��A�e�s���{���̒m�����S�[���f���E�C�[�N���Ԓ��̊�����Ȃǂ����c���܂����B�����s�����烊���[�g�ŏo�Ȃ��������s�̏��r�m���́u�O�o�E�C�x���g�E���H�Ȃǂ̋@�������B�����ŏd�v�ɂȂ�̂́A�����̘A����f���邽�߂́g����h�Ƃ��Ă�3��ڂ̃��N�`�����v�Ɣ������A�A�x���̊����g���h�����߂ɂ̓��N�`����3��ڐڎ�̑��i���d�v�ł���Ƒi���܂����B
�����������A���ɐڎ킪�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ��u�Ⴂ����v�ւ̃��N�`���ڎ�𑣐i���悤�ƁA�����s�͐V���Ȏ��g�݂��n�߂܂����B
�����s�ɂ��铌����Êw�@��w�ɓ��������̂́u���N�`���o�X�v�ł��B�����s���^�c���郏�N�`���o�X�́A�ڎ���ւ̃A�N�Z�X������Ȓn��⍂��Ҏ{�݂�����Đڎ���s���Ă��܂��B�������ŋ߂͍���҂ւ̐ڎ킪�i��ŗv�������������Ă��邱�Ƃ��A��҂ւ̐ڎ�𑣐i���邽�߁A���߂đ�w�ł̐ڎ���s���܂����B�ڎ�����w���́u�S�[���f���E�C�[�N�ɊO�o�̗\�������̂ŁA���N�`����3��ڐڎ���悤�Ǝv�����B��w�Ŏ���̂͂ƂĂ��֗��ł��肪�����v�ȂǂƘb���Ă��܂����B�܂��A������Êw�@��w�̕l�c�Nj@�w���́u�f�����Ή����Ă��炢�A��ς��肪�����v�Ƙb���܂����B
���̓���1���Ŋw����48�l���ڎ�����Ƃ������Ƃł��B���N�`���o�X�͍���A��w�Ȃǂ̗v�]�ɂ������ď���𑱂��Ă����Ƃ������Ƃł��B
|
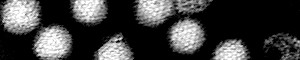 |
���A�x���A�܂h�~������@�ʏ鉫��m���u�����h�~�s�����v�@4/27
����26���A�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ��{����c���J���A29���`5��22���܂ł̊Ԃ̌��Ώ����j�����肵���B�����ł͊����̍��~�܂肪�����Ă��邪�A���͂܂h�~���d�_�[�u�̗v���͌�����A3�N�Ԃ�ɎЉ�A�o�ϓI�Ȑ������Ȃ����ŁA��^�A�x���}���邱�Ƃ����܂����B
��c��ɋL�҉�����ʏ�f�j�[�m���͑�^�A�x�Ō����̊����������ɂȂ�A�������g�傷��X��������Ƃ��āu�A�x��̊����g���}���邽�߂ɂ̓S�[���f���E�B�[�N���Ԓ��ɁA������l��l�̉߂��������d�v�ƂȂ�v�Əq�ׁA�������X�N�̍����s�����ł������������悤���߂��B
�ʏ�m����5��15���ɁA1400�l�K�͂ŊJ����鉫��ł̓��{���A�L�O���T�ɂ��Ắu���������Ȃ�ƁA(�Q���l����)���炷���Ƃ��l������v�Ƃ̌������������B
��^�A�x���Ԓ��̉߂������ɂ��āA�ʏ�m����(1)�Ǐ�̂���l�͊O�o���T����A�l�ɉ��Ȃ�(2)���l���ŐH�������Ȃ�(3)����҂̎����K��A�ꏏ�ɐH������l�����肷��(4)���X�N�̂���s�������O�ɁA�����ʼnA�����m�F����\���Ƃ��Ăъ|�����B
������������K�₷��ۂ�A���O����̊ό��q�ɑ���3��ڂ̃��N�`���ڎ�̊�����APCR�����ʼnA�����m�F����悤���߂��B�A�x�̊��Ԓ��A���M�O�������{���Ă����Ë@�ւ̃��X�g�����z�[���y�[�W�Ō��J����Ƃ��Ă���B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�z���Ґ��́A25�����_��645�E34�l�ƂȂ�A�S���ň��̏������Ă���B�{���ł͕a���g�p����55�E9%�ƂȂ�A�����܂h�~���d�_�[�u����������ڈ���60%�ɋ߂Â��Ă���B
|
�������s�̃��o�E���h�x�����ԁA5��22���܂ʼn����@4/27
�����s�́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ċg���h�����߂ɐݒ肵�Ă����u���o�E���h�x�����ԁv��5��22���܂ʼn������邱�Ƃ����肵���B����A���{�ł́A�܂h�~���d�_�[�u��̌x�����Ăт����Ă����u�N�x�ւ��̏W���x�����ԁv��24���ŏI���������A���H�X�ł�1�e�[�u��������̐l��������4�l�ȓ��̂܂܌p������ȂǁA�e�n�őΉ���������Ă���B�����ł́A�����Ƒ��̌x�����Ԃ̌���A�Ȃ�тɈ��H�X�ւ̐����ɂ��ďЉ��B
�������s�ł͈��H�X�̐l��������1�O���[�v8�l�܂łɊɘa
3��22���A�����s����{�Ȃ�18�s���{���ɓK�p����Ă����u�܂h�~���d�_�[�u�v���S�ʉ����ɁB�������A�ˑR�Ƃ��Ċ��������̖ړr�������Ȃ����Ƃ���A�e�����̂ł͊����Ċg��h�~�̍s�����Ăъ|���Ă����B
�����s�ł�3��22������4��24���܂ł��u���o�E���h�x�����ԁv�Ƃ��A��H��1�O���[�v4�l�܂ŁA�؍݂�2���Ԉȓ��Ƃ���悤���H�X�ɋ��͂�v���B���{�ł͓����Ԃ��u�N�x�ւ��̏W���x�����ԁv�Ƃ��A��H�́u����e�[�u��4�l�ȓ��v�u2���Ԓ��x�ȓ��ł̈��H�v�u�S�[���h�X�e�b�J�[�F�ؓX�܂𐄏��v�u�}�X�N��H�̓O��v��4���[�������炷��悤�Ăт����Ă����B
�܂h�~���d�_�[�u���Ԃ���x�����Ԃւ̈ڍs�ɔ����A������̒n��ł��F�ؓX�ł͎��Z�v���Ǝ�ޒ̐������I���B�܂��A�F�ؓX�ɂ����ẮA�ΏێґS���������ʼnA�����m�F�����ꍇ�͐l��������݂��Ȃ��ȂǁA�d�_�[�u���Ԃ������H�X�ւ̐������ɘa���Ă����B
���o�E���h�x�����Ԃ̏I�����߂Â��Ă���21���A�����s�͌x�����Ԃ̉���������B���Ԃ͐V����5��22���܂łƂ��A���H�X�ɑ��āA�����������p�l���̐����Ȃǂ̋��͂�v�������B�������A�l���͂���܂ł�1�O���[�v4�l�܂ł���8�l�܂łɊɘa�B�؍ݎ��Ԃ͂���܂łƓ�����2���Ԉȓ��Ƃ���悤���߂�B�܂��A�F���Ă��Ȃ��X�ɂ́A�l����4�l�܂ŁA�؍ݎ��Ԃ�2���Ԃɐ������������ŁA��ނ̒��ߌ�9���܂łƂ���B
�����{�͌x�����Ԃ��I�����A���H�X�ւ̐l�������Ȃǂ͊ɘa����
����ɑ��đ��{�ł́A�N�x�ւ��̏W���x�����Ԃ�24���ŏI���B�a���̂Ђ����x�͊ɘa����Ă���Ƃ��āA�{�̓Ǝ���u��ヂ�f���v�ɂ����Ĕ�펖�Ԃ������ԐM������A�x�����x���̉��F�M���Ɉ����������B
����ŁA���H�X�ɑ��ėv�����Ă���u����e�[�u��4�l�ȓ��v�A�u��H��2���Ԓ��x�v�Ȃǂ̐����́A5��22���܂Ōp������Ɣ��\�B���{�̋g���m���m���́A�u�S�[���f���E�B�[�N���Ԓ��́A������ƎЉ�o�ϑ�̗�����}���Ă����v�Ƃ����A�u�V���ȕψي�BA2�̏��l����ƁA����(�S�[���f���E�B�[�N)�͂�͂�x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B
|
���s�������ƈ�Êm�ۂ�4�ā@�A�x��̊����g��z��\�R���i���ȉ�@4/27
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�(���g�Ή)��27���̉�ŁA��^�A�x��ɃI�~�N�������̕ʌn���u�a�`�D2�v�̊������}�g�債���ꍇ�̑�Ƃ��āA4�Ă�����B�s�������ƈ�Ñ̐��̊m�ە��j��g�ݍ��킹�����̂ŁA���g���͉��̋L�҉�Łu�ǂꂪ�K���c�_����v�Əq�ׂ��B
��͂܂��A�܂h�~���d�_�[�u�ȂǂŎЉ�o�ϊ����𐧌�����u�l�����`�v�A�d�_�[�u�ȂǂŐ��������A�Љ�o�ϊ����ێ��ɏd�_��u���u�l�����a�v�ɕ��ނ����B
����ɁA�����҂�Z���ڐG�҂�����Ë@�ւ�h���{�݂Ɋu������ȂǓ��ʂȑΉ����ێ�����u�l����(1)�v�A���ʂȑΉ����y�����A�n��̈�Ë@�ւ�ݑ�f�Â�D�悷��u�l����(2)�v�ɕ�������ŁA�u�`(1)�v�u�`(2)�v�u�a(1)�v�u�a(2)�v��4�p�^�[�����������B
��ł͂��̂����A�Љ�o�ϊ������d������u�a(2)�v�𒆒����I�ɂ͖ڎw���ׂ����Ƃ̈ӌ������������B���g���́u5���ɂȂ�قƂ�ǂa�`�D2�ɂȂ�B���⎩���̂Ɍ��ʓI�ȑ���Ă������v�ƌ�����B
|
���u��^�A�x�͊�{�I�Ȋ�����̓O����v�R�ېV�^�R���i���� �@4/27
�R�ېV�^�R���i���S����b�͕��ȉ�̉�ŁA���̊����ɂ��āu�S���I�ɂ݂�A�V�K�����Ґ��͊ɂ₩�Ȍ����������Ă��āA�����ɂ܂h�~���d�_�[�u��K�p����ɂ͂Ȃ��ƍl���Ă��邪�A�����������������𒍎����Ă����K�v������v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu3�N�Ԃ�ɋً}���Ԑ錾��d�_�[�u�̂Ȃ���^�A�x�ƂȂ邪�A�����̍Ċg���h�~���Ȃ���Љ�o�ϊ������ێ����Ă�����悤�A���{�Ƃ��Ă̓��N�`����3��ڂ̐ڎ��ϋɓI�Ȍ����A��{�I�Ȋ�����̓O������߂Ă��肢�������v�Əq�ׂ܂����B |
���č���58�����R���i�����A�I�~�N�������҈Ђő������R�̌����@4/27
�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)��26�����\������������A�č����S�̖̂�58��������܂łɏ��Ȃ��Ƃ�1��V�^�R���i�E�C���X�������Ă������Ƃ����������B2021�N12���Ɏn�܂����I�~�N�����ψي����s�O��33�����x�������B
������21�N12����22�N2���ɍ̎悳�ꂽ���t�T���v���̍R�ׂ̂��B�Ƃ�킯�q�ǂ��̊������������ŁA11�Έȉ��̎q�ǂ��ł�75�D2���ƁA21�N12���O��3�J���ԂɊm�F���ꂽ44�D2�����瑝���B12��17��74�D2���ƁA45�D6�����瑝�������B
�b�c�b�̃������X�L�[�����ɂ��ƁA�č����̊����Ґ��͑����X���ɂ���A1��������̊����҂�4��4000�l�ƁA�O�T����22�D7�����������B
�����_�ŃI�~�N�����ψي��̈���u�a�`�D1�v���S�̂̊����ɐ�߂�䗦�͂킸��3���B����A�u�a�`�D2�D121�v�͖�30�����߁A�u�a�`�D2�v���������͂�25�������Ƃ݂���Ƃ����B |
�������s�A�V����6052�l�̊������\�@��T���j��(���j)����700�l�]���@4/27
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�����s�͂��傤�V����6052�l�̊����\���܂����B��T���j����6776�l��724�l������Ă��āA16���A���őO�̏T�̓����j���̊����Ґ���������Ă��܂��B�����s�́u���������A��t�������Ɛf�f�����v�g�݂Ȃ��z���h�̊��҂������҂Ƃ��Ĕ��\���Ă��āA3�l���g�݂Ȃ��z���h�̊��҂ł����B�V���Ȋ����҂̂����A���N�`����2��ڎ킵�Ă����l��2978�l�ŁA1����ڎ�����Ă��Ȃ�1636�l�͐l�ł����B�V�^�R���i�̕a���g�p����21.4���ŁA�ő�Ŋm�ۂł��錩���݂�7229���ɑ��A1550�l�����@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�̕a���g�p���́A4.2���ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł́A10�㖢����1075�l�A10�オ830�l�A20�オ1054�l�A30�オ1123�l�A40�オ970�l�A50�オ521�l�ŁA�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂�343�l�ł����B���ݓ��@���Ă��銴���҂̂����A�����s�̊�Łu�d�ǎҁv�Ƃ����l�́A15�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�V����6�l�̎��S�����\����Ă��܂��B
|
���h���^�uBA�E2�v�͖����܂鋰��@�a�@���A�������Â̕K�v���i���@4/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����A���~�܂肵�Ă���B���Ɏ嗬�ƂȂ��Ă���I�~�N�������̔h���^�uBA�E2�v�ɂ��āA���͈ꕔ�̎��Ö�̌��ʂ���܂鋰�ꂪ����Ƃ̌������������B70���̒����Ǖa���������s���\�O�s���a�@(���s�����)�̑q��C�@��(61)�́A���߂đ������Â̕K�v����i���Ă���B
�u��6�g�ł́A���ǂ��Ă�����@�܂ł̎��Ԃ��������A�K�v�Ȗg���Ȃ��P�[�X���o���肪�������v�B�q��@���́A�����U��Ԃ�B
�a�@�ɂ��ƁA��6�g�̎����ɑ�������2021�N12��1���`4��15���A336�l�̓��@���҂����ꂽ�B�y�ǂ⒆���LJT�̊��҂Ɏg�����̂����E�C���X�̑��B��}����R�E�C���X��́A�_�H��u�����f�V�r���v��102�l�A�Ƃ��Ɉ��ݖ�ł���u�����k�s���r���v��50�l�A�u�j���}�g�����r��/���g�i�r���v��5�l�ɓ��^�����B�E�C���X���זE�ɓ��荞�ނ̂�h�����a�R�̖�̓_�H�u�\�g���r�}�u�v��138�l�ōő��������B
�ǂ̖�����ǂ���5�`7���ȓ��Ɏg�p����K�v������B�\�O�s���a�@�ł́A��6�g��70��̒j��3�l���d�lj����A�d�ǎ҂������a�@�ɓ]�@�����B����������ǂ���7���ȏソ���ďǏ������Ă�����@���Ă���A����������𓊗^�ł��Ȃ������Ƃ����B���{���ŘA��1���l���̊����҂��m�F����A���@����������ی����̏����\�͂����������ƂȂǂ��x��ɂȂ������Ƃ݂���B
��7�g�ł́A���Ö�̑I���������܂�\��������B�]�����ŗL���������\�g���r�}�u�ɂ��āA�����J���Ȃ�BA�E2�ɂ͌��ʂ���܂鋰�ꂪ����Ƃ��Ē��ӂ��Ăт�����ƌ��߂��B����A�����f�V�r���Ȃǂ̍R�E�C���X��̌��ʂ͕ς��Ȃ��Ƃ���Ă���B�q��@���́u���̊����g��ł́A�R�E�C���X���S�ƂȂ�B�R���i�Ɛf�f���ꂽ�炷���Ɏ��Â������Ñ̐������d�v�ɂȂ�v�Ǝw�E����B�@ |
 |
��GW��Ɋ����}�g�債����c�Ή����c�_���u�H�v���āv�@4/28
�����s�ŁA27���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�6052�l�ƁA��T�̐��j�����炨�悻700�l����A16���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B
���������Ȃ��A27���ɊJ���ꂽ���{�̐V�^�R���i�����ȉ�ł́A�S�[���f���E�B�[�N��Ɋ����Ċg�傪�N�����ꍇ�̑Ή��ɂ��āA�c�_����܂����B
�_�_�̈�́A��{�I�Ȋ�����𑱂��������ŁA�u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ȃǂ̍s���̐������s���̂��ǂ����B������́A����̈�Ë@�ւł̊u���A�f�Â�����܂Œʂ葱����̂��ǂ����ł��B
2�̍l�����̑g�ݍ��킹�ŁA�@���ɂ��s����������A����@�ւł̈�Â���Ƃ�����Ԍ������p�^�[������A��Ԋɂ��A�s�������Ȃ��A����@�ւł̈�ÂȂ��̃p�^�[���܂ŁA4�ʂ�̍l������������܂������c�B
���{���ȉ�E���g�Ή�F�u���܂Ŋw����(������)���A���ꂼ�ꂪ�H�v���Ă���Ăق����Ƃ����̂��A���̈ӌ������A�����炭�����̐��Ƃ⍑�̈ӌ����Ǝv���v
���Ƃ̊Ԃňӌ��̊u���肪�傫���A�ŏI�I�ɂ́A���⎩���̂ɔ��f���ς˂����l���ł��B
|
��29���̏��a�̓�����S�[���f���E�C�[�N�c�@����@4/28
29���̏��a�̓�����S�[���f���E�C�[�N(�f�v)���X�^�[�g����B5��2���A6���̕���2���Ԃ��x�ނƍŒ�10���Ԃ̑�^�A�x���B�������A�V�^�R���i���ŁA���̐�����������Ȃ����߂Ă̘A�x���B�q��e�Ђɂ��ƁA�����H���̗\�͑O�N��20�����B�Ί_�s���̎�v�z�e���̉ғ�����90���ƌ����A�ɂ��킢�������B�ό��́A��s���̂܂h�~���d�_�[�u�̉����Ȃǂŋ���3�����玝�������̒����������Ă���A�R���i�Ђŋꂵ��ł����z�e����ό��֘A�Ǝ҂ɂƂ��āA���N�̉����T�Ԃ͍���̊ό��ւ̑傫�ȑ��|����Ƃ��Ȃ肻�����B�ό��q�̑����Ƌ��Ƀ����^�J�[���v�����܂��Ă���B�Ί_�s���̃����^�J�[�Ǝ҂ɂ��ƁA������{����f�v�̗\�E���B�R���i���ŕۗL�䐔�����炵�����Ƃ��e�����A���v�����ɑΉ��ł����A���{�ȍ~�͖₢���킹��f���Ă���Ƃ����B�S�z�͐l�̈ړ��ɔ����V�^�R���i�E�C���X�̊����Ċg��B�����ȂǓs�s���ŗ��s�����܂���邪�A�l���ړ����邱�ƂŁA�f�v�����Ɋό��n�ŐV�^�R���i�̊����g�傪�S�z����Ă���B������l����Ɨ��s�҂ɂ́A����Ŋy�������s�i���邽�߂ɂ��A�R���i���N�`����3��ڐڎ�⎖�O�̂o�b�q�����ʼnA�����m�F����ȂǁA�R���i�����ӎ������Ή������߂�ꂻ�����B
|
���f�v�@�����x���p�� �@���s�{�@4/28
�S�[���f���E�B�[�N(�f�v)���T����27���A�{�͐V�^�R���i�E�C���X���{����c���J���A�{���⎖�Ǝ҂ɂ���܂łƓ��l�̊�������Ăт����邱�Ƃ����߂��B�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ��o�Ă��Ȃ��f�v��2019�N�ȗ��ŁA�ό��n��ɉ؊X�͑����̐l�o�������܂�邪�A�{�͓��ʂȍs�������݂͐����A�����𒍎�����\�����B
�Ăт����́A���C��}�X�N���p�̓O��ȂǏ]���ƕς��Ȃ����e�ŁA���H�X�̗��p�͈��������u������4�l�܂ŁA2���ԁv��ڈ��Ƃ����B�A�Ȃ�ό��ɂ��Ă����ʂȌĂт����͂��Ȃ������B
�u�����v���u�ɘa�v�������������R�́A�����̕]����������Ƃɂ���B
�u�܂h�~���d�_�[�u�v(1��27���`3��21��)�̉�����A�{���̊����Ґ��́A500�`1000�l���x�Ő��ځB�u���Z�����̃��o�E���h�͂Ȃ������v�ƍm��I�ɑ����鐺�����邪�A�{�����́u�����܂ʼn����������͕̂s�C���B������Ƃ������������ōĊg�債���˂Ȃ��v�ƌx������B
����ŁA60�Έȏ�̃��N�`��3��ڐڎ헦(�Ώێ҂�����)�́A2�������_��5���ォ��A89�E2��(25�����_)�܂ŏ㏸�B���@���Â��K�v�ȍ���҂��������A�a���g�p����20������Ă���B���䓹��E�{��t����u�d�NJ��҂͏��Ȃ��A �N���Ђ��ς� �͂��Ă��Ȃ��v�ƌ��������B
�����͂������Ƃ����u�a�`�E2�v�ւ̒u���������s�m��v�f�̈���B�{�����o���{���Ă���Q�m����͂ł́A���łɔ������a�`�E2�ɂȂ��Ă���A���e�m���͉�c��̋L�҉�Łu�����ǖʂɓ���̂��A�l�o��a�`�E2�̗v�f�ŏ㏸����̂��A�x�����Ē�������v�Ɛ����B����̊����Ґ��Ȃǂ܂��A�V���ȑ����������l�����������B�@ |
 |
���u���헣�ꃊ�t���b�V���v�@�ɂ��킢�߂���GW�����@�V���w�@4/29
2019�N�ȗ�3�N�Ԃ�ɋً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�ȂǐV�^�R���i�E�C���X��̍s���������Ȃ��S�[���f���E�C�[�N(GW)��29���A�X�^�[�g�����B����2�N�Ƒł��ĕς��A�ɂ��킢���߂��Ă����B
JR�V���w(���s�����)�̐V�����z�[���ł́A�ߑO8���O����X�[�c�P�[�X���������Ƒ��A���c�A�[�q�炪�������������BJR���C�ɂ���29���ߑO10�������݁A�V���w�ł̐V������ԗ��͍ō��ʼn���130���A���90���ƂȂ����B�O�N�������͂��ꂼ��70���A30���������B
���s�V������̒F����(������)����(44)�͖�(9)��F�l�Ƒ��ƁA��N�Ă��牄���ɂȂ��Ă����T�}�[�X�N�[���ɎQ�����邽�ߎR���s�Ɍ������Ƃ����A�u�����Ɗy���݂ɂ��Ă����B�q������l�����킩�痣��A�������t���b�V���ɂȂ�v�ƏΊ���������B
����A���{�͐l�̈ړ��������ɂȂ�Ɨ\�z����28���`5��8���AJR�V���w�Ƒ��w�ɐV�^�R���i�E�C���X�̖�����������ݒu�B���R�����O�s�̎��ƂɋA�Ȃ�����{�ےÎs�̉�Ј��A�O��䝐�(�܂�)����(27)�́u�j���[�X�Ō�������m��A�����ɗ\���B�����͂��肪�����A�A�Ȃւ̈��S�ޗ��ɂȂ�v�ƌ�����B
|
����^�A�x���� �V�����͂ӂ邳�ƂȂǂɌ������l�����ō��G�@4/29
�V�^�R���i�ɂ��s���������Ȃ�3�N�Ԃ�̑�^�A�x�����ƂȂ���29���A��������V�����͂ӂ邳�Ƃւ̋A�Ȃ�s�y�Ɍ������l�����ō��G���Ă��܂��B
���̂����A�i�q�V���w�̃z�[���͌ߑO������A�傫�ȉו��������ĐV�����ɏ�荞�ސl�����̎p�������܂����B
�i�q�ɂ��܂��ƁA29���ߑO10�������݁A�V���w���o������V�����̎��R�Ȃ̏�ԗ��͂�������̂��݂ŁA��肪�ō���90���A���肪�ō���130���ƂȂ��Ă��܂��B
���Ƃ��́A�u�ً}���Ԑ錾�v��u�܂h�~���d�_�[�u�v�ȂǁA�V�^�R���i�ɂ��s��������3�N�Ԃ�ɂȂ��A�x�Ƃ����āA����14�����_�ł̗\��͋��N�ɔ�ׂĔ{�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
����ł��A29���ߌ�̗�Ԃ̎w��Ȃɂ͋�Ȃ�����ق��A30���ȍ~�̎w��Ȃɂ��]�T������Ƃ������Ƃł��B
�啪���ɋA�Ȃ���20��̒j���́u���Ƃ����Ђ�������ŏ��߂ċA�Ȃ��܂��B����Ȃ��d������ς������̂ł�������x�݂����ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A��e�ƂƂ��ɓ������ɏo�����鏬�w���́u���������ɉ�ɍs���܂��B�y���݂ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
|
��ANA�������AGW���Ԓ�100���l�̗��p�����ށ@�H�c��D��������^�p�@4/29
3�N�Ԃ�ɋً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���Ȃ����Ō}�����S�[���f���E�B�[�N�B�S���{��A(ANA)��4��29������5��8���܂ł̊��Ԓ��A�������S�̂őO�N���2�{�ƂȂ�100���l�ȏ�̗��p�������ށB
28�����_�̊��ԑS�̗̂\�͖�88���l�ŁA�\��57.4���B�s����͉�����ʂ����ɍD���ŁA�����ŋ�B�A�����E�l�����ʂ��l�C�ƂȂ��Ă���B���N�͒��O�\�����X���ɂ���A4��22������29���܂ł̒��O1�T�Ԃŗ\��10���l�������Ƃ����BANA�̏��R�c����q������`�x�X���́A�u22���ɃS�[���f���E�B�[�N�̗\�\�����B�S�O���Ă���������������ċ삯���݂ŗ\���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̌������������B
������29���͍������S�̂Ŗ�12���l�����p�B1��12���l�ȏオ���p����̂́A�S�[���f���E�B�[�N�ł̓R���i�БO��2019�N�ȗ�3�N�Ԃ�B�H�c��`�o���ւ̗\��95���ŁA���ɌߑO���̏o���ւ͖�99���Ƃقږ��Ȃ��Ƃ����B��`�̍��G�������܂�邱�Ƃ���A2020�N3��16���ȗ���2�N�Ԃ�ɕۈ�������D���I�[�v�����A�o��������40���O��ڈ��ɕۈ��������ʉ߂���悤�Ăт����Ă���BD������̓S�[���f���E�B�[�N���Ԓ��͊J���Ă�����̂́A���̌�̉^�p�ɂ��Ă͖��肾�Ƃ����B
|
���I�~�N�����g�V���ȕψفh�������m�F�c���҂́A�C�O�؍ݗ��Ȃ��@4/29
�s���������A�̓��őg�ݕς�������͕������Ă��܂���B
���g�V���ȕψفh�������m�F
���s�ی����E�������[�������F�u�m�F���ꂽ�̂́A�������Ƃ������ƂɂȂ�B�a�����⊴�����ɂ��ẮA���݂̂Ƃ��땪�����Ă��Ȃ��v
�V���Ɋm�F���ꂽ�̂́A�V�^�R���i�E�C���X�E�I�~�N�������́uBA.1�v�n���ƁuBA.2�v�n���̈�`�q�̈ꕔ���g�ݕς�����A�V���Ȍn���̃E�C���X�ł��B�����Ŋm�F�����̂͏��߂Ăł��B
���������nj��������A�挎���{�ɔ��ǂ������s�̊��҂̌��̂���͂��A�m�F����܂����B
���̊��҂́A���ǑO2�T�Ԉȓ��̊C�O�؍ݗ��͂Ȃ��A���łɗ×{���I���Ă��āA���̊��҂��犴�����������҂͊m�F����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�������́A���҂��s���Ŋ��������̂��A�E�C���X���̓��őg�ݕς�����̂��́A�����_�ł͕s���Ƃ��Ă��܂��B
�������g�x�����x���h��������
����A�����s��28���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�5394�l�ƁA��T�̖ؗj������1319�l�����āA17���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B
�����Ґ��̌����X�����A�s�͂��悻3�J�����Ԃ�ɁA�����̌x�����x����1�i�K�����A4�i�K���A�ォ��2�ԖڂƂ��Ă��܂��B
�����s�E���r�S���q�m���F�u���́A���o�E���h�x�����Ԃ̍Œ����Ƃ������ƁB���ꂩ��l�̓����A���ꂪ������Ƃ������ƂŁA�����̍Ċg������O�����Ƃ��������ɂȂ�v
�������E���c�w�Ɂg�����������h
���������Ȃ��A29������n�܂�S�[���f���E�B�[�N��O�ɁA��������ł́A��v�ȉw�ɐV�^�R���i�̖������������ݒu����܂����B
���̂������ł́A�ȈՃL�b�g�ɂ��R�������ŁA15������30���قǂŌ��ʂ��o��Ƃ������Ƃł��B
�팱�ҁF�u2�N�Ԃ�ɋA�Ȃ���̂ŁA�����ƌ������ĕ�e�ɉ�����v
�����������́A����8���܂ŊJ�݂���Ă��܂��B�@ |
���u�������������Ă����������Ȃ��v �ݓc�����́g���^�h������s�������Ȃ�GW�@4/29
�u�������������Ă����������Ȃ��v�R���i���S�����{�W�҂́A�S�[���f���E�B�[�N��ڑO�ɐV�^�R���i�̊����҂̔����I�ȑ����ɋ������O���������B
3�N�Ԃ�Ɍ}����ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̂Ȃ��S�[���f���E�B�[�N�́A3�N�Ԃ�̍s�������̂Ȃ��S�[���f���E�B�[�N�ƂȂ�B�s�y�n�ł͋q���̑����������܂�A�ό��E���H�ƊE�𒆐S�Ɋ��҂����܂�B
������ƌo�ω̗�����ڎw���A����u�E�B�Y�R���i�v�^�̑�^�A�x���I������ɁA�����҂͑�����̂��A����Ƃ��}������̂��B�S�[���f���E�B�[�N��̊����҂̓����́u�|�X�g�R���i�v�̂������肤�����ƂȂ�Ƌ��ɁA�ݓc�����̖��^������\��������B
���S���̊����Ґ��̍s����肤����
���݁A�R���i�̐V�K�����Ґ��͑����̒n��Ō����ɓ]���Ă��邪�A�ꕔ�̒n��Ŋ����Ґ����������Ă���B���ɉ��ꌧ�́A����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ��͑S���ōň����B���̂��ߐ��{�́A���ꌧ�Ɍ��鏑�����g�b�v�Ƃ��鍑�Ǝ����̘̂A��������S���u���G�]���`�[���v��h���B
���{�W�҂ɂ��ƁA�`�[���͉���S��ł̊����̓�����c�����A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�̕K�v�������������ق��A�i�܂Ȃ���҂̃��N�`���ڎ�ȂǂɌ����Č����Ƃ̘A�g�����������Ƃ����B
�����ꂩ��S���ւ̊����g����x��
���{���A����̊������Ƃ�킯�d������̂ɂ́A���R������B�S�[���f���E�B�[�N���ɁA�l�C�ό��n�ł��鉫��Ɋό��q���E�����A���ꂩ��S���Ɋ������g�傷�錜�O�����邩�炾�B
�R���i���S���t���̈�l�͎��͂Ɂu����܂ł͓�������n���ɃR���i���L���Ȃ��悤�ɂǂ��邩�Ƃ����b�����S���������A����͉���ȂNJό��n���瓌���Ȃǂ̓s�s���ɃR���i�������Ă��Ȃ��悤�ɂǂ��邩�Ƃ����b�ɓ]�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƃ̌����������Ă���B
����A���ӂ́u����̓��N�`���ڎ�ōR�̂��c���Ă����ԂŃS�[���f���E�B�[�N�ɓ˓����邩��A����܂łƂ͈Ⴄ�v�Ƙb���A���N�`���̌��ʂŊ����Ґ����}���ł��邱�ƂɊ��҂���B
���܂h�~�[�u�o���Ζ�}���Njy
���ɑS���I�Ȋ����������N����A���{�͂���܂łȂ�A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p������ɓ���Ă����B�������A���鐭�{�W�҂́u�܂h�~���d�_�[�u�͖{���Ɍ��ʂ�����̂��킩��Ȃ��v�u����ȊO�ɑł肪�Ȃ��č����Ă���v�ƘR�炷�B���ʂ͕�����Ȃ����A����ȊO�ɑł肪�Ȃ��B�u�܂h�~�[�u�v���݂̑�ɁA��l�܂芴���o�Ă���̂�����B
����ŁA�����ɂ͉Ă̎Q�@�I��O�ɁA�܂h�~���d�_�[�u���o�������Ȃ��v�f��������B����܂ł̂悤�Ɉꕔ�ɂ܂h�~�[�u��K�p������ɁA�܌��J���ɑΏےn�悪���T������悤�Ȏ��ԂőI���ɓ˓�����A���{�̃R���i��Ɂu���s�v����������A�^�}�ɋt���ƂȂ�댯���������B
�Q�@�I�O�ɂ́A�ߘa4�N�x�̕�\�Z��Ґ����邽�߁A�O�Q�ł̗\�Z�ψ���J�Â����B�܂h�~�[�u���o�Ă����ԂŐR�c�ɓ���A��}�������{�̃R���i���Njy����͕̂K���ŁA�����ւ̃_���[�W�ƂȂ�B
3�N�Ԃ�̍s�������̂Ȃ��S�[���f���E�B�[�N�̌�ɁA�ǂ̂悤�Ȍi�F���L����̂��B�ĂуR���i���҈Ђ��̂��B�ݓc�����̍s������傫�����E���邱�ƂɂȂ�B |
���I�~�N�������̐V���Ȕh���^�A���N�`�����蔲������Z��|��A�����ҁ@4/29
�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�����ψي��ŁA��A�t���J�̉Ȋw�҂��������������V���Ȕh���^�̓��N�`����ȑO�̊����Ŋl�������Ɖu�����蔲����\�͂������Ă���\���������B���̔h���^�Ɋւ��郊�|�[�g�\������`�q�z���̓`�[���̃g�b�v��������B
��A�̃N���Y�[���[�E�i�^�[����w�ƃX�e�����{�b�V����w�̕����̌��������琬��`�[���̃g�b�v�߂�g�D�[���I�E�f�I���x�C�������́A�V���Ȕh���^�u�a�`.4�v�Ɓu�a�`.5�v�́A��Ɍ��������u�a�`.2�v���������͂������l�q���Ɛ����B�u�a�`.2�v���]���̃I�~�N�������ɔ���������͂����B
��A�s���̂قڑS�����A���N�`����ڎ�ς݂��ߋ��Ɋ�����������B����ɂ�������炸�����Ґ������ݑ����Ă���̂́A�����̔h���^���P�ɂ�苭�������͂��������łȂ��A�Ɖu��˔j����\�͂����邽�߂��ƍl������ƁA�f�I���x�C�����͎w�E�����B
�f�I���x�C�����́u���̔h���^�ɂ͖Ɖu�̂��蔲�����\�ɂ���ψفv������Ƃ̍l����\���B�u���̔h���^�͍Ċ����������N�������ꂪ����A�ꕔ�̃��N�`����˔j����\�͂����Ƃ݂Ă���B�l����90���ȏオ���̖Ɖu�ی�Ă���ƍl�������A�ŁA�������L����̂͂���ȊO�ɐ������t���Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�����͂܂��c�C�b�^�[�ł̓��e�ŁA���݂̓�A�̐V�K�����ł͂��̔h���^����7�����߂�Ɩ��炩�ɂ��A�u�w�a�`.4�x�Ɓw�a�`.5�x�Ŋ��������͑����Ă��邪�A���@�Ґ��Ǝ��Ґ��̑�K�͂Ȕ����ɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��B���ꂪ���̔h���^�Ɋւ�������̒��S�V�i���I���v�ƌ������������B |
���S���̐V�K������ 3��6672�l�@����3893�l 18���A���őO�̏T�����@4/29
29���A�S���ł�3��6,672�l�̐V�^�R���i�E�C���X�̊������m�F����Ă���B
�����s�ŐV���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�3,893�l�ŁA��T�̋��j������1,503�l����A18���A���őO�̏T�̓����j������������B�S���Ȃ����l��5�l�������B�I�~�N�������̓������ӂ܂����w�W�ɂ��d�ǎ҂�34�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����4.2���ƂȂ��Ă���B
���̂ق��A���{��2,619�l�A��������2,298�l�A�_�ސ쌧��2,221�l�ȂǁA�S���ł͂���܂ł�3��6,672�l�̊����ƁA45�l�̎��S���m�F����Ă���B
����A�����J���Ȃɂ��ƁA28�����_�ł̐V�^�R���i�E�C���X�̑S���̏d�ǎ҂�173�l�ŁA�O�̓�����1�l�������B�S���̏d�ǎҐ��́A3���A����200�l����������B
|
 |
���uGW(�䖝�E�B�[�N)�p�����H�v ���������i�V���K�\���������@4/30
��N�A�����̐l�����s��A�ȂȂǁA�������ړ����Ƃ��Ȃ��O�o�ŋx�ɂ��y���ރS�[���f���E�B�[�N�B�������N�Ԃ̓R���i�E�C���X�����ǂ̖����ɂ��A2020�N�A2021�N�ł̓R���i�E�C���X�����ǂ̊g��ɂ��A�O�o���l�̓��������������܂����B���������Ȃ�2022�N4�����{���_�ł́A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ƃ������������������Ă��܂����A�o�����郆�[�U�[�͑����̂ł��傤���B
���y��ʏȂł́A2020�N5���Ɂu�S���̍������H�̎�ȋ�Ԃ̌�ʗʑ���(�ΑO�N��)�v�����\���Ă���A2019�N�ɔ�ׂāA2020�N�̃S�[���f���E�B�[�N���Ԃ̎�v�ȍ������H�̌�ʗʂ���70���ቺ�����Ɩ��炩�ɂ��Ă��܂��B
�Ȃ��A��s���ł́A�����g��O��2019�N�̃S�[���f���E�B�[�N���p�䐔��1��������86��7911��A�����g����2021�N�ł�78��5957�䂾�����ƌ��\�B
���������f�[�^����A�����NJg���A�������H�𗘗p����O�o���A�����Ɏ��l����Ă��邩���킩��܂��B
�����2022�N�ł́A�e�n�œK�p����Ă����u�܂h�~���d�_�[�u�v���S�ʓI�ɉ�������A���H�X�Ȃǂւ̋K��������ł͒�߂��Ă��܂��A����e�n�������̂Ȃǂ͌p�������O�o���l���Ăт����Ă��܂��B
�Ⴆ�A���@�́u�S�[���f���E�B�[�N�͊O�o���T���܂��傤�I�v�Ƃ��āA�u�A�ȁE���s���T����v�u�ߏ�̊O�o�ł����W�E���ڂ������v�u�������͏��l���E�����Ă��鎞�ԂɁv��3��B���l�ɁA���t���[�ł��u�����͂��肢���܂��v�ƊO�o���l���Ăт����Ă��܂��B
���̂悤�ȏŌ}����2022�N�S�[���f���E�B�[�N�ł����A���[�U�[�͂ǂ̂悤�ɉ߂������ƍl���Ă���̂ł��傤���B�܂��A�������H�𗘗p���悤�ƍl���Ă���l�͑����̂ł��傤���B
SNS�����Ă݂�ƁA2019�N�̃S�[���f���E�B�[�N�O�ł́u�o�����ɂ����������v�u�X�e�C�z�[������v�Ƃ������������������̂ɑ��A2022�N�́u���N�͕��ʂɏo�������肵�����v�uGW�͗��s�I�y���݁I�v�u�݂��GW���o�����Ȃ��́H�v�Ƃ������������܂��B
��N����ς�炸�O�o���l�����߂���2022�N�ł����ASNS�ł́u�������Ɂv�Ƃ������[�h���p�o���Ă���A�u���N�����́I�v�Əo������ӎv�������Ă���l�������悤�ł��B
���̈���ŁA�u���N�͍����a����������〜�v�u�����g���������ǁA�K�\�����������x���������Ȃ��c�v�uGW�͍������݂��������V�������ȁv�Ƃ����������������Ă���u�O�o���l�v�̈ӎ��Ƃ͕ʂɁu�K�\�������i�̍����v�u�x�������K�p�Ȃ��v��2�_����A�S�[���f���E�B�[�N�͍������H�̗��p������悤�ƍl���Ă���l�����������܂��B
�S�[���f���E�B�[�N���Ԃɂ�����A2022�N4��29������5��1���A5��3������5��5���A������5��7���E8���̌v8���Ԃ́ANEXCO3�Ђ���сA�{�B�������H�A�{�錧���H���Ђ̊NJ����H���ł́A�������H�̋x���������K�p����܂���B
����͍��y��ʏȂ���̗v���ɂ����̂ŁA���G�������\�z�����S�[���f���E�B�[�N�E���~�E�N���N�n���ԂɓK�p�����\��ł��B
�܂��A�K�\�������i�̍����͈ȑO���烆�[�U�[�ɂƂ��đ傫�Ȗ��Ƃ��Ē��ڂ���āA����(2022�N4��7��)�ł́A�S������1���b�g��������174.1�~�ƂȂ��Ă��܂��B
�O�q�����悤�Ɂu���N�����́I�v�Ƃ������[�U�[���������ŁA�Ȃ��ɂ́u���O��ό��n�ł̗V�т͍T���Ăق����v�uGW(�䖝�E�B�[�N)�p�����ł���I�v�Ƃ��������������A2022�N�����l���p������Ƃ����l�����Ȃ�����܂���B
|
������Ȃ�34�{���@�܂h�~�������K�v72���@4/30
�V�^�R���i�E�C���X�Ή��̂܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āA47�s���{���̂�������Ȃ�34�{��(72��)���������ׂ����ƍl���Ă��邱�Ƃ�29���A�����ʐM�̒����ŕ��������B�I�~�N�������̔h���^�ւ̒u������肪�i�ޒ��A����K�v�ƂȂ����Őq�˂�ƁA�ő��́u���H�X���S�̑�̓]���v�Ɓu����ҁE����֘A�{�݂̑��v�ł���������������B
�I�~�N�������ɂ�闬�s�u��6�g�v�ł́A�y�ǎ҂△�Ǐ�҂������ق��A����Ҏ{�݂̃N���X�^�[(�����ҏW�c)��q�ǂ��̊������ڗ��B���s���{���̃j�[�Y��I�~�N�������̓����ɍ�����������߂���Ԃ������B
������13�`26���A47�s���{���Ɏ��{�����B
�܂h�~�[�u���������ׂ����Ɠ�����34�{���́A�X�A���A���s�ȂǁB�Q�n�A���m�Ȃ�12�s���́u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�Ƃ����B�k�C���͖��������B
34�{���ɋ�̍��₤�ƁA�ߔ������_��ȑΉ����ł���d�g�݂����߂��B�������m�́u�������l�ȑ�����j���[�����A�m�����I���ł���v�A�L���́u�����ɉ����ĕK�v�ȑ��I���A�g�ݍ��킹���{�v���Ă����B
�I�~�N�������̔h���^�ɂ�銴���g�傪���O�����ꍇ�̑Ή��Łu���H�X���S�̑�̓]���v�Ɠ������͎̂R�`�Ⓑ����܂�27���B�u����ҁE����֘A�{�݂̑��v�͊A���R�Ȃ�27�{���B�u�Љ�A�o�ϓI�ȑ�������菬�����Ȃ��v(21�{��)���������B�u���̑��v�Ƃ��ďd�lj����X�N�̍����l�ւ̑��⌟���Ԑ��g�[�����������B
��6�g���̂܂h�~�[�u�Ɋւ��āA�R�����́u���ʂ��Ȃ��v�ƉB�{���_�ސ���܂�8���́u���܂�Ȃ��v�Ɠ������B
�ΐ�Ȃ�5�s�{���́u���ʂ�����v�A�Q�n�A���Ɋ܂�26�{���́u������x���ʂ�����v�Ƃ��ꂼ������B�c��7�����́u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�Ȃǂ������B
���ꌧ�́A���s�̏d�_�[�u�ɂ��āu���܂���ʂ��Ȃ��v�Ɖ����B�ƒ��E��A�w�Z�E�ۈ牀�ȂǂŊ������A������u���[�v�����v������Ƃ���Ŕ������Ă������A�d�_�[�u�͈��H�X�ւ̎��Z�v�������S�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ𗝗R�ɋ������B���̏�ŁA�d�_�[�u�̓��e�́u�������K�v�v�Ƃ��A�u���Z�v���ƃZ�b�g�ł͂Ȃ��}�����I���ł��邱�Ƃ��K�v�v�Ɖ��Ă���B�@ |
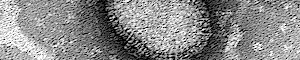 �@ �@
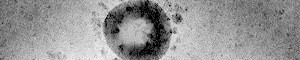 �@ �@
 |


 �@
�@ |
��3�N�Ԃ�ɍs�������Ȃ�GW�@���{�͊����g����x���@5/1
3�N�Ԃ�ɁA�V�^�R���i�E�C���X�ɑ���ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���A�S���ǂ��ɂ��o����Ă��Ȃ���^�A�x���}�����B�l�̈ړ��������Ċ������L����\��������A���{�͌x�������߂Ă���B
�������͑�5�g�s�[�N�������
�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA�S���̐V�K�����Ґ�(1�T�ԕ���)��4��28����3��9783�l�ƂȂ�A��1�J���Ԃ��4���l����������B3��22���ɂ܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ��A�V�K�����Ґ��͑����X���ɂ��������A4��22���ȍ~�́A�����ɓ]���Ă���B
�܂��A����1�T��(23�`29��)�̑S���̎��Ґ���291�l�B�O�T�Ɣ�ׂ�21�l���Ȃ��B
�����s�̐V�K�����Ґ�(1�T�ԕ���)��18���A�����Č������Ă���A4��29����4836�l�B��5�g�s�[�N(��N8��19��)��4923�l����������B
�s��4��28���A�����Ɋւ���4�i�K�̌x�����x�����ォ��2�ԖڂɈ����������B�������A�V�K�����Ґ����\���ɉ����肫��Ȃ��܂܁A�����ɓ]���Ȃ��悤�Ɉ��������x�����K�v�Ƃ����B(����䕶�F)
��60�Έȏ�Ȃ�4��ڐڎ��
�����J���Ȃ́A60�Έȏ�ƁA18�Έȏ�Ŋ�b����������l��d�lj����X�N�������ƈ�t���F�߂�l��Ώۂ�5�������烏�N�`����4��ڐڎ���n�߂���j�����߂��B3��ڂ���̐ڎ�Ԋu��5�J���ȏ�ŁA�ăt�@�C�U�[���ƕă��f���i�����g���B����ȊO�̐l�ւ̐ڎ�ɂ��āA�㓡�ΔV���J���́u����A����ɉȊw�I�m�������W���钆�Ō�����i�߂�v�Ɛ��������B
���J�Ȃ̕��ȉ�́A�ăm�o�o�b�N�X�����N�`�����A1�`3��ڐڎ�Ɏg�����Ƃ𗹏������B�����Ŏg���郏�N�`����4��ޖځB
3��ڂ̐ڎ헦�́A�S�l����50�������B�ݓc���Y��26���̃e���r�����ԑg�Łu���N�`���ڎ�͊����\�h�A�d�lj��\�h�ɑ�Ϗd�v�Ȗ������ʂ����Ă����B�Ⴂ�l��(3���)�ڎ헦���Ⴂ�̂ŁA���������ڎ���Ăъ|�������v�Ƙb�����B(�]�c�W���Y)
����v�w���`�Ŗ��������g�[
��^�A�x���̊�����Ƃ��Đ��{�́A��v�w���`�ł̖����������g�[�����B15�����x�Ō��ʂ�������R���萫�����Ȃǂ��100�J���Ŏ��{�B�A�ȋq��̗��p�𑣂��Ă���B
����̃R���i��ɂ��āA�ݓc���Y��26���̋L�҉�Łu�������������ւ̈ڍs���ԂƂ��čő���̌x�������ێ����Ȃ���A���X�ɎЉ�o�ϊ�����������v�ƌ�����B
�K�\�����Ȃǂ̔R�����i��}������⏕���̊g�[��������҂��x�����邽�߂̍����Ƃ��āA���{��28���̊t�c�ŁA�V�^�R���i���\����Ȃǂ��瑍�z1��5110���~���x�o���邱�Ƃ����߂��B
26���Ɍ��肵�����������ւ́u�����ً}��v�̈�B�x�o���[���邽�߁A���{�͍�����ɒ�o����2022�N�x��\�Z�ĂɁA�lj��̗\����Ƃ���1��5000���~���v�シ����j�B |
������̋~�}�O���A�p���N���O�c���~�܂�̃R���i�����A��f�ҋ}���@5/1
�V�^�R���i�����҂̑����ɔ�Ⴕ��4�����{����~�}�O���̎�f�҂��}�����Ă���B���M�₹���A�����ɂƑ����͌y���Ǐ�ŁA���ɂ�PCR������������]����l������Ƃ����B��Ì���͐E���̊�����Z���ڐG�Ō��Ύ҂������Ă���A�l���s���Ɋׂ��Ă���B��Ï]���҂�́u�K���őΉ����Ă��邪�A�Ђ���������Ԃ���������B��^�A�x���������������邩�v�ƁA�s���Ɠk�J��������Ȃ���Ή��ɖz�����Ă���B
���ꌧ�앗�����̓암��ÃZ���^�[�E���ǂ���ÃZ���^�[�͎�f�܂�5���ԑ҂��̏ŁA�z�[���y�[�W�ɂ��f�����Ă���B����ł��A���A��f�҂��r�₦�Ȃ��B
���ԏ�ɕ��ԎԂ̒��ł́A�|�����V�[�g�ɉ������A��f��҂�������l�̎p������B
���Z���^�[�̋~�}�O����f�҂͒ʏ�60�`70�l�قǂ����A4��������͕����͕S�l���A�y���͏]���̔{�ȏ��170�l�ɏ��B��6���������B�I�~�N�����������s������6�g�Ȍ�͑��������M�₹���Ȃǂ̌y�ǎ҂��B
���Z���^�[�͌�ʎ��̂�S�؍[�ǂȂǏd�ĂȊ��҂������3���~�}��Ë@�ւ����A�y�ǎ҂��E�����邱�ƂŁu�����Ɏ��Â��K�v�Ȑl�ւ̉�����x��鋰�ꂪ����v�ƁA�Z���^�[�̓y���m�V��t�͌��B
�{�݊O�Ŏ��Â̗D�揇�ʂf����g���A�[�W�̍�Ƃ�h���̒��E�Ȃǂ��������K�v�B�u�̊��I�Ɏ�Ԃ̓C���t���G���U�̔{�ȏ�v�ŁA�f�@�܂Ŏ��Ԃ�������B
��Ï]���҂̌��Ŏ��ӈ�Ë@�ւ̋~�}���ꕔ��������錻����A���҂��W�����Ă��������B
�u�~�}��Â͎~�߂Ȃ��v���g���Ƃ��ĕ������Ă��邪�A�y����t�́u����̔�J�������܂��Ă���v�ƘR�炷�B
���������a�@�ł����l�ɋ~�}�~���Z���^�[���Ђ������Ă��邽�߁A�Ō�t����������4��25������5��6���܂ŊO���f�Â�d�b�f�Âɐ�ւ����B
|
���V�^�R���i �����͑S�̂�4.3���� 5�s�{���̍R�ۗ̕L���� �@5/1
�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������l�́A���Ƃ�3���̎��_�őS�̂�4.3���Ƃ݂��邱�Ƃ����������nj������Ȃǂ�5�̓s�{���ōs�����R�̂ۗ̕L���ׂ����ʂ̕��͂ŕ�����܂����B�����҂̊����͓����s����{�ō��������Ƃ������Ƃł��B
���������nj������͋��N12���Ɗ����̑�6�g�̍Œ��̂��Ƃ�2������3����2��A�����s�A���{�A�{�錧�A���m���A��������5�s�{���ō��킹��1��6000�l�]���ΏۂɐV�^�R���i�ɑ���R�̂ۗ̕L���Ȃǂׂ����ʂ͂��܂����B
�������ŁA���������ꍇ�ɂ���������R�̂����l�Ɗ��������Ɛf�f���ꂽ���Ƃ�����l�̊������犴�������l�̊����𐄒肵���Ƃ���A���N12���̎��_�ł�2.5���ł������A���Ƃ�3���̎��_�ł�4.3���ɂȂ��Ă��܂����B
�n��ʂł͓����s��6.4���A���{��6.1���A���m����3.7���A��������3.3���A�{�錧��2.0���ƁA�����s�Ƒ��{�ō����A����Ƀ��N�`����1��ȏ�ڎ킵���l�ł�4���������̂ɑ��A���ڎ�̐l��10����2�{�ȏ�̍����������Ƃ������Ƃł��B
�A�����J�ł�CDC�����a��Z���^�[���l����60���߂������������Ɛ��肵�Ă��āA�����J���Ȃ̐��Ɖ�̘e�c���������́u���{�ł͂�����x�Ⴂ�����Ɋ������}����ꂽ�Ƃ�����B�����A���R�����ɂ��Ɖu������l�����Ȃ����A��̊ɘa�ʼne�����o��\��������v�Ƙb���Ă��܂��B
|
������Ҏ{�݂̊����g��ǂ��h���@�u�]�[�j���O�v����@��7�g�ɔ����铌�� �@5/1
�V�^�R���i�E�C���X�u��7�g�v�ɔ����ē����s�͍���Ҏ{�݂̑�ɗ͂�����B��6�g�ł͍���Ҏ{�ݓ��Ŋ������Ď��S����l��300�l�����B�s�̓E�C���X���������܂��O��ł����Ɋ������L���Ȃ����ɏd�_��u�����A�~�n�������s�s���Ȃ�ł͂̎������������Ă���A���ꂩ��́u�L���Ȃ��̂͌��E�v�Ƌ�Y�̐����R���B
�u�u�������܂��ł��Ă���c�v�B�s���̗{��V�l�z�[���ŕ��{�ݒ��߂�j���͌�����ɂ��܂����B2�����{��1�l�ڂ̊�����������A�����͂̋����I�~�N�������͎{�ݓ��ŋ}���ɍL����A2�T�Ԃ�39�l�̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�ƂȂ����B80��㔼�̗��p�҂̒j���͊�����ɑ咰�̎��a�������B�~�}�������Ɂu�R���i���҂͎�����Ȃ��v�ƋߗׂŒf���A30�L���ȏ㗣�ꂽ�a�@�ɉ^�ꂽ��Ɏ��S�����B
����6�g���S��3��������Ҏ{�ݓ��Łc
�{���̏W�v�ł́A1�`3���̑�6�g�Ŏ��S����994�l�̂����A����Ҏ{�ݓ��Ŋ������Ď��S�����l��312�l�őS�̖̂�3���ɏ��B�N���X�^�[�����������������ۈ牀��w�Z�ƕ���ő����A����Ҏ{�ݓ��Ŋ������L����A���҂������������Ԃ������ԁB
����Ҏ{�݂Ŋ������L���Ȃ����߂ɂ́A���҂�����G���A�Ƃ����łȂ��G���A�̋�����u�]�[�j���O�v���L���ɂȂ�B���{�ݒ��͕K�v���𗝉�������ŁA�u������̕��������Ȃ��A�h�앞��E�������镔����]���ɂ���ɂ͌��E���������v�ƐU��Ԃ�B
���H���╗�C���1�A���p���邵���Ȃ�
�E����Y�܂����̂��A�s�s���Ȃ�ł͂̎{�݂̍\�����B�H���╗�C��͒n���̂悤�Ɋe�t���A�ɑ��ꂸ�A��������1�������Ȃ��B70�l�̗��p�҂������Ŏg�킴����A���{�ݒ��́u�C���t������{�ݑS�̂ɂ܂�ׂ�Ȃ��������L�����Ă����v�Ɩ��������B
����Ҏ{�݂��^�c����s��t��̕��씎�V����́u�{�݂͏��Ȃ��l�ނŏW���I�ɃP�A�ł��鑢�肪�����A�]�[�j���O�ɂ͕s�K�B�ǂ����Ă��H��������ŗ��p�ғ��m���ڐG���Ă��܂��v�Ǝw�E����B�s��t���6�g�Ŋ����҂��o���V�l�ی��{�݂ɓ������������Ƃ��ƁA�]�[�j���O���������{�݂͑S�̂�25���ɓ�����21�{�݂ɏ�����B
�����œs��4��28���A�{�݂��ی���������Ɋ�����𑊒k�ł����p�������J�݁B���i����]�[�j���O�̕��@��h�앞�̐������̂ĕ��Ȃǂɂ��đ��k�ł���悤�ɂ����B�{�݂Ŋ����҂��o���ꍇ�͊Ō�t��ł���V�݂́u�����x���`�[���v��24���Ԉȓ��Ɏ{�݂�K��A�u����̎���ɉ����������������v�Ƃ��Ă���B1��������10�{�݂�����Ԑ���z�肵�Ă���B
����b��������G�A�]�@��m�ۂ��}��
��6�g�ł͊�����Ɋ�b�������������Ď��S����l���ڗ����A�R���i�ȊO�̌����ŖS���Ȃ����l����2�����߂�B
�s�͑�6�g�ŁA�ő�7229���̃R���i�a�����m�ۂ������̂́A�����҂̋}���ŕa�����N�����A����Ҏ{�݂̗��p�҂����@���ɂ������ԂɊׂ����B���̔��Ȃ���A��삪�K�v�ȍ���Ҍ����̕a����R���i�̎��Â��I���������҂̓]�@��𑝂₻���ƁA�M�̊m�ۂɓ����Ă���B
�����A�\�z�����銴���҂��o����6�g�̂悤�ɁA�z��ȏ�̊����҂��o��Α����x���`�[�����A�R���i�a�����Ή����ǂ��t���Ȃ��Ȃ�\��������B�s�̒S���҂́u����҂����S���ė×{�ł���������Ă��������v�Ƙb�����B
|
������ �̎O�Ѝ� �����J�� 3�N�Ԃ�ɂ݂����̒S���o�����@5/1
�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŋK�͂̏k���⒆�~�������Ă������� �̎O�ЍՂ͍���3���Ԃ̓����ŊJ�Â���A3�N�Ԃ�ɖ����݂̂����̒S���o�����s���邱�ƂɂȂ�܂����B
�O�ЍՂ́A���N5�����{�ɍs���Ă������� �䓌��̐_�Ђ̗��Ղł��B
�݂����̒S���o���Ȃǂ����Ă̕������ƂȂ��Ă��܂������A�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ł��ƂƂ��݂͂������g���b�N�ɏ悹�Ă̎��{�ƂȂ�A���N�́A���~��]�V�Ȃ�����܂����B
�����������A���Ƃ��͍���20������3���Ԃ̓����ŊJ�Â��A�ŏI���́u�{�o���v�Ɓu�{����v�ł́A3�N�Ԃ�ɐ_�Ђɕ�[����Ă���{�А_�`�����q�炪�S�����ƂɂȂ�܂����B
����A���݂̂��������ꂼ��̒�������ۂ́A�g����Ƀ^�C�������t����Ȃǂ��Ēʏ���啝�ɏ��Ȃ��l���ʼn^�ׂ�悤�v�悵�Ă���Ƃ������Ƃł��B
����Ɏ�Î҂́A�݂����̒S�����3��ڂ̃��N�`���ڎ킩�o�b�q�����ł̉A���m�F�����߂�ȂǁA�������O�ꂷ��Ƃ��Ă��܂��B
�_�Ђ́u�����Ґ��͋��N�Ɣ�ׂČ������Ă��Ȃ����A�R���i��͈ȑO�������m�ɂȂ��Ă��Ă��āA�ł���͈͂ōՂ�����{�������ƍl���Ă���v�Ƙb���Ă��܂����B�@ |
�������ŐV����2��6960�l�R���i�����c�s����1�T�ԕ��ς�23���� �@5/1
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�1���A�S�s���{���Ƌ�`���u�Ōv2��6960�l�m�F���ꂽ�B���҂�34�l�A�d�ǎ҂͑O�����6�l����165�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�3161�l�ŁA�O�T�̓����j������1775�l����A20���A����1�T�ԑO����������B�s�ɂ��ƁA70�`90�Α�̒j��6�l�̎��S�����������B�d�ǎ҂͑O������2�l����9�l�ŁA10�l�������̂�1��20��(9�l)�ȗ��B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�4238�l�őO�T����23���������B
|
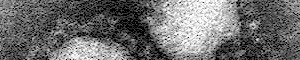 |
�����{�R���i��@���Ԃɑ������������}���@5/2
���s�́u��7�g�v�ɔ������ŁA�����̂̕s���������ꂽ���ʂƌ����悤�B
�V�^�R���i�E�C���X��ŁA47�s���{����7���ȏオ�܂h�~���d�_�[�u�݂̍�����������K�v�����w�E���Ă��邱�Ƃ������ʐM�̃A���P�[�g�ŕ��������B��6�g�ɔ����d�_�[�u�́A��̓I�ȑ�Ɗ������Ԃ̂��ꂪ�w�E����Ă����B
3�N�Ԃ�ɋً}���Ԑ錾��d�_�[�u�ɂ��s���������Ȃ����ő�^�A�x���}�������A�l�̈ړ��������邱�ƂŊ����̍Ċg�傪���O�����B���s�̒J�Ԃɂ��鍡�����A����܂ł̑�������A�����ʓI�ȓ��e�ւƌ��������}���K�v������B
���{�͏]���A�ً}���Ԑ錾�Ɋ�Â����H�X�ւ̋x�Ɨv���ƁA�d�_�[�u�ɂ���ނ̒�~��c�Ǝ��ԒZ�k�̗v�����J��Ԃ��Ă����B1���ȍ~�ɋ}�g�債����6�g�ł��A���{�͂��������O��P�B�d�_�[�u�̓K�p�n��͈ꎞ�A36�s���{���ɂ܂ōL�������B
�����A���ɂ͊������g�債�Ă��d�_�[�u�̓K�p�𐭕{�ɐ\�����Ȃ������������B���{�̎�����{�I�Ώ����j�̘g���ł́A�}�~���ʂɋ^�₪����������ɂق��Ȃ�܂��B
�d�lj����ɂ������ʁA�����͂������I�~�N�����������s�̎�̂ɂȂ������ƂŁA�����o�H�ɂ��ω����݂�ꂽ�B�N���X�^�[(�����ҏW�c)������ҁE��Q�Ҏ{�݂̂ق��A���c���{�݁A�w�Z�Ȃǂő����B���{���d�����Ă������H�X�́A�����g��̎�v�ȏ�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B
�����������Ԃ܂���A�A���P�[�g��34�{������̌����������߂��͓̂��R���낤�B�u���H�X���S�̑�̓]���v��u����ҁE����֘A�{�݂̑��v���K�v�Ƃ̉��ߔ������߂��B
���s�̓s�[�N��E�����Ƃ͂����A�S���I�ɐV�K�����҂͉����~�܂����ɂ���B�E�C���X�̓I�~�N�������́u�a�`�E1�v����u�a�`�E2�v�ւƒu������肪�i�݁A����ɕʂ̔h���^�������Ŋm�F���ꂽ�B�ω����J��Ԃ��E�C���X�̓����⊴���̍L������ɍ��킹�A�_��ȑ��߂���B
�������A���{�ɂ͑�̌��〈�����Ɍ������ϋɓI�ȓ����݂͂��Ȃ��B�ݓc�����͏d�_�[�u�̓K�p���f�ɍۂ��A�s���{���̈ӌ����d���������A������ς���Βn���C���̎p���ɂ��f��B��M�ł����Ƃ��O�ʂɏo���ʂ��ڗ������B��̐��ɖR������ۂ͐@���Ȃ��B
�����Ǒ�ŁA��Ñ̐��Ȃǒn��̎����A���Ƃ̒m�����d�v�Ȃ̂͌����܂ł��Ȃ����A��̕����������߁A�����ɐ�������ӔC�͐��{�ɂ���B
�A���P�[�g�ł͌���̏d�_�[�u�ɑ��A9�������̌��ʂ�ے�I�ɕ]�������B���{�̑�̐M�����h�炢�ł���Ƃ����Ă悢�B���〈�������Ȃ���A�s�M���͈�w�c��ނ��낤�B
��펞�ɐ��{�Ɠs���{���̑����݂������A�����̖��⌒�N���������ꂩ�˂Ȃ��B�₦����ɖ��S�������K�v������B
|
�����{��3�N�Ԃ�ɖh�u�ɘa���ꂽ�u�S�[���f���E�B�[�N�v�c�C�O���s3.7�{�}���@5/2
���{��3�N�Ԃ�ɐV�^�R���i�E�C���X������(�V�^�x��)�ɂ��s�����Ȃ��u�S�[���f���E�B�[�N�v(4��29���`5��8��)���n�܂�A��`�E�w�͗��s�q�ŏT���̊ԍ��G�����B
1���A�����V���Ȃǂɂ��ƁA�S�[���f���E�B�[�N�����̐挎29���͓����w����w�̐l�g��1�N�O�̓��������ɔ�ׂ�45�������������Ƃ����������B�D�y�w�⋞�s�w�Ȃǂɂ͐V�^�R���i�̗��s���n�܂�O��2019�N����10���قǑ����A�H�c��`�������^�[�~�i�����p�q�͍�N�ɔ�ׂ�97�D5�����������B�\�t�g�o���N�n�̈ʒu���r�b�O�f�[�^��Ɓu�`���������v���X�}�[�g�t�H���ʒu���T�[�r�X����ՂɏW�v�������ʂ��B
���N�ƍ�N�̃S�[���f���E�B�[�N�����͐V�^�R���i�̊g��ɑΉ������h�u�[�u�u�ً}���Ԑ錾�v�����{�e�n�ɔ��߂��ꂽ��Ԃ������B���{�ƒn�������̂����o���āu���s���l�v��v���������߁A���������s�����悤�Ƃ����l�͑����Ȃ������B�����A���N�ً͋}���Ԑ錾�͂������A���̉��ʑ[�u�ł���u�܂h�~���d�_�[�u�v���S��ʼn������ꂽ��Ԃ��B
�R���i���N�`���ڎ�҂ɑ���u���Ə��[�u�܂Ŏ{�s����A�C�O���s�͍������s�ɔ�ׂċ}�������B�����ʐM�ɂ��ƁA4��29���`5��8���̍q�\��͑O�N�̓��������Ɣ�r���č�������70���A���ې���370���������B
���{�̃S�[���f���E�B�[�N��4��29���u���a�̓��v����n�܂�A5��3���u���@�L�O���v�A5��4���u�݂ǂ�̓��v�A5���u���ǂ��̓��v�ɑ����A�x���B���݁A���{�̐V�^�R���i�͈��肵�Ă���B�挎30���ɂ͑S����2��5182�l�̐V�K�����҂����������B�����A�S�[���f���E�B�[�N���Ԓ��̈ړ��������ɂȂ�A�V�^�R���i���Ċg�U����̂ł͂Ȃ����Ƃ������O������B
|
���s�s����n���� �l���̉�A�̓R���i�ЂŒ蒅���邩�H�@5/2
2020�N����2�N�ԁA�R���i�Ђɂ�鎀�S���̑傫�ȏ㏸�͔�����ꂽ�B���������܂��܂ȑ��ʂŐl���͉e�����Ă���B���������͌������A���ݍT���ŏo�����͏����\����傫����������B
�l���ړ��ɂ��e�����łĂ���B�ً}���Ԑ錾�����߂���A�܂h�~���d�_�[�u���J��Ԃ����o���ꂽ���ʁA���{�l�̏o�����O���l�̗�������������āA���ېl���ړ��͑啝�ɏk�������B�����[�g���[�N�A���u���Ƃɂ���ē��X�̒ʋA�ʊw���������A�o���◷�s�����l����Č�ʗʂ����������B
�i�w�A�A�E�A�]�A�]���ɔ����s�����Ԃ̈ړ��͂ǂ����B2021�N�̓��{�l�̓s���{��������ѓs���{���Ԃ̎s�����Ԉړ��ґ�����482���l�A�O���l���܂ޑ�����525���l�������B�ߋ�5�N�A�Q�����Ă��邪�傫�ȕω��͌����Ȃ�(�}1)�B���̋K�͍͂��x�o�ϐ������n�܂�������1956�N�̐����ŁA�s�[�N��73�N(���{�l854���l)��6���ȉ��܂ŏk�����Ă���B
�l���ɑ���ړ��Ґ��̊�����7.8������3.8���ւƔ��������B�l���̗��������ቺ���Ă�����̂́A�}���ȕω��Ƃ͌����Ȃ��B
������2020�N�Ȍ�A�l���ړ��̓��e�ɕω��͂������B����͔��s�s������O��s�s���ւ̗������ڗ����Č��������Ƃł���B19�N��13���l�������O��s�s���̓]�����ߐ���20�N��8.5���l�A21�N�ɂ�6.4���l�Ɣ������Ă���B�R���i�Ђɂ���đ�s�s���̓]�����߁A���s�s������̐l�����o���k�����Ă���̂�(�}2)�B
��s�s���ւ̐l���W������܂�A�n�����ւ̐l����A���i�ނȂ�A�n���n���̖ړI�̈���B�������悤�Ɍ�����B��������Ԃ̂͑����B��1�ɂ���܂ł���s�s���ւ̓]�����߂����������������x�����������ƁA��2�ɔ��s�s������̏����̓]�o���߂��ɘa����Ă��邩�Ƃ�����肪����B
���n����A�Ȃ̂��A�i�C��ނɂ����̂Ȃ̂��H
��s�s��������s�s���ւ̐l���̉�A���N���Ă��邱�Ƃ͎����ł���B���͂��ꂪ�V�����l���̗���Ƃ��Ē蒅���邩�ǂ����ł���B
���70�N�Ԃ̓���������ƁA����܂łɂ���s�s���ւ̈ړ����傫�����������������x���������B�J�ƂȂ����̂�1976�N�A96�N�A2012�N�ł���B���ꂼ��Ζ���@�A�o�u���o�ς̕���A���[�}���E�V���b�N�Ɠ����{��k�Ђɂ���Či�C��ނ�����ꂽ�����ł���B
�O��s�s���̓]�����߁A�����Ĕ��s�s���̓]�o���߂̊g��́A�o�ϐ������Ɩ��ڂɊW����B�i�C��������ɂȂ�o�ϐ����������܂�ƁA��s�s���̘J���͎��v���c���Ől�������������A�i�C��ފ��ɂ͂��ꂪ��܂��Đl������������Ƃ����W���B����������2020�N�ȍ~�̎O��s�s���A���ɓ������ւ̓]�����߂̏k���́A����܂łƓ����悤�Ɍi�C��ނɌ�����p�^�[���ł���ɉ߂��Ȃ��̂�������Ȃ��B
�����A21�N�̏Z����{�䒠�Ɋ�Â��l���ړ�������{�o�ϐV���́A�����s�ł͎q��Đ���ł���30〜40�Α�̓]�o���߂��N�������ƁA����31�����œ�����̓]�����߂�14�N�ȍ~�A�ő��ɂȂ������Ƃ�`���āu������ɏW���Ɉٕρv�ƕĂ���(22�N2��19���u�f�[�^�œǂޒn��Đ��F31�����@�q��Đ��㗬���v)�B
�É����ł��]�o���߂̏k�������ڂ��ꂽ�B�M�҂������o�[�Ƃ��ĉ�����Ă���u�������h�ӂ��̂��Ɂh�܂��E�ЂƁE�����Ƒn��������c�v�ł́A22�N2���ɊJ�Â��ꂽ��c�̖`���Ől�������Ɋւ��������A�l�������������Ȃ��ŁA20�N�̓��{�l�̓]�o���߂��O�N�̖�7000�l�����2500�l�ւƑ啝�Ɍ����������Ƃ��`����ꂽ�B
�ڏZ�҂̑����ƂƂ��ɈڏZ���k�����̑����������Ă���Ƃ��āA�����Ɋ��҂��Ă���B20�N�̐É����ւ̈ڏZ�Җ�1400�l�̂����A���ю��8����20〜40�Α�ł��邱�Ƃ���A�u�e�����[�N�̕��y�ɂ���Ēn���ŕ�炷���Ƃւ̊S�����܂��Ă���v(�É����������h�ӂ��̂��Ɂh�܂��E�ЂƁE�����Ƒn��������c����)�Ɗ��}���Ă���B
���s�s�������s�s���ւ̓]�o���߂̏k�����A�����悤�ɐϋɓI�A�ӎ��I�ɒn�����ł̐�����I���������̂ł���A�V���������Ƃ��Ċ��}�������B��������s�s���ɂ�����J�����v�̏k����A�V�^�R���i�����ǂ̋��|���瓦��邱�Ƃ�ړI�ɂ������ɓI�ȗ��R�ł���Ȃ�A�����P�����ƍĂё�s�s���ւ̗��o���g�債�Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B
�����ڂ��ׂ������l���̒n������
��2�̖��́A�����̓������ւ̗������j���قǂɂ͐����Ă��Ȃ����Ƃ��B���{�o�ϐV���͕ʂ̋L���ŁA�����s�̐l����21�N�̓]�����߂��O�N��6����1�߂��ɏk���������A�j���͓�������̓]�o���߁A�����͑��ς�炸�]�����߂̂܂܂������Ɠ`���Ă���(�u�`���[�g�͌��F�n����A �����Ȃ��T�d�v22�N4��10��)�B�R���i�ЂŒn����A�����܂����ɂ��ւ�炸�A�������s�s�ɏW�܂�X���͒j�����������悤���B
���̗��R�Ƃ��āA�d���Ɛ��ʖ����ӎ���������B�n���ɂ͏�������]����d�����Ȃ����A���邢�͒j���Ɍ��肳��Ă��邱�ƁA�u�v�͊O�œ����A�Ȃ͉ƒ�����ׂ��v�Ƃ����Â��W�F���_�[�ς������̍s���������Ă���Ƃ����̂��B����������āA�i�w��A�E���@�ɑ�s�s���ֈڂ�Ⴊ�����Ȃ�̂ł���B
�����l���̗��o�͐É����ł��ȑO������ɂȂ��Ă����B�É����̓]�����ߐ�����s�s���Ɠ������A�o�ϐ����������������ɑ����邩�A���邢�͓]�o���߂���������B�i�C��������̎����ɂ͓������ւ̓]�o����������̂ŁA���G�ȓ����������邱�ƂɂȂ���̂́A���ʂƂ��āA�������̓]�����߂��傫���N�ɂ͐É����ł͓]�o���߂ɂȂ�Ƃ����W�����Ăł���B
1995�N�ȍ~�A�É����̏����̓]�����ߐ��̓}�C�i�X�������Ă���B�j���͎��ɓ]�����߂ɂȂ�N�����������A�����͈�т��ē]�o���߂�30�N�߂������Ă���B
���ɖ��ɂȂ�͈̂ړ��҂̔N��ł���B2021�N�̐É����̔N��K���ʓ]�����ߐ��́A5�Ζ�����35�Έȏ�ł̓v���X(�]������)�A5〜34�ł̓}�C�i�X(�]�o����)�������B�e�N��ʂł͒j���Ƃ���18��22�œ]�o���ߐ����ˏo���Ă���(�}3)�B��w�E���w�Z�ւ̐i�w�ƏA�E�ɂ�錧�O�ւ̓]�o�������ȗ��R�ł���B
�N��K���ʂł́A15〜19�̓]�o�҂͒j1332�l�ɑ��ď�1181�l�ƒj�����������A���͏������B����ɑ���20〜24�ł͒j734�l�A��1910�l�Ə�����2.5�{�ɂ��Ȃ��Ă���B
���y��ʏȂ̒���(�u��Ɠ��̓�����ɏW���Ɋւ��鍧�k����܂Ƃ߁v)�ɂ��ƁA�j���Ƃ��ɓ������ւ̈ړ��̗��R�̏�ʂ́A��]����E���ҋ�����d���̂��邱�ƁA��]����i�w��̂��邱�Ƃ���ʂ��߂Ă���B�j���̕����d���𗝗R�Ƃ���������̂��������A�o�g�n�̒n�����̌o�Ϗ����P�����ΐl�����o���~�܂�Ƃ͌����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���퐶�����ʂ̗����A�o�g�n�̎Љ�̕NJ��A�n��̕����╗�K�A��y�{�݂̏��Ȃ����ƂȂǁA�A���j�e�B�̏[�������������̂����Ȃ��Ȃ����炾�B
�������ł̐����̖��͂ɂȂ��邱���̗��R���Ƃ����̂́A�j�����������ő��������B15〜24�̏����̗��o�͎�����̏o����������������̂ŁA�u�n�����Łv�ւ̂���݂����������邱�Ƃ��Ӗ����邩��A���͐[���ł���B
���u�c�ɕ�炵�v�͑��i���ׂ��Ȃ̂�
2020�N���������̌��ʂ��āA�����Ȃ͍��N4��1����27���{����65�s�������ߑa�n��Ƃ��Ēlj������B����őS��885�Ǝs�����̉ߔ������ߑa�w��c�̂ƂȂ����B
�ߑa�c�̂͑�s�s�����ɂ����݂��邪�A�قƂ�ǂ͔��s�s���ɂ���B�o�����̌���͊ȒP�ł͂Ȃ�����A�܂��͐l�������̑�����ڎw�������̂͑����B
�u�c����A�v�u�c�ɕ�炵�v�Ɩ��ł��āA�n�������̂��s�s������̈ڏZ���i�{���ł��Ă����B�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɂ��A�܂���������߂悤�Ƃ��铮�����o�Ă���B���s�s���ł͂ǂ��ł���҂�n���ɒ蒅�����Đl���̈ێ���}�邱�Ƃɖ�N�ɂȂ��Ă���B
���̂��ߑ�w�ɂ͐l�����o�̃_���Ƃ��Ă̖��������҂���Ă���B�n����ւ̒�Z�ƎY�ƐU���̌���Ƃ��Ĉʒu�t�����Ă���B�������o�����������������ŁA�n��������w�ł͓��w��������Ȃ���w�������Ă���B�܂�����������w����҂��ꎞ�I�Ɉ������߂Ă��A���͓I�Ȑ������⓭���ꏊ���Ȃ���A��s�s���ւ̗��o���~�߂邱�Ƃ͓���B
��s�s�ŏA�E���悤�Ƃ���w�i�ɂ͒����̍���������B�ƒ���H���Ȃǐ��v��̍������l�����Ă��A�n�����ɂ͂Ȃ����͂�����ƍl�����҂͏��Ȃ��Ȃ��B��ƂɂƂ��Ă���s�s�ɗ��n���邱�Ƃ͗L���ƍl����B
�o�ϗ��_�́A�l���W�܂邱�Ƃɂ���ďW�ς̌o�ς����܂�A���Y�������コ����Ɛ�������B�l�ɂƂ��Ă��A��ƂɂƂ��Ă��A�����o�ςɂƂ��Ă��A��s�s�ւ̏W���͗L�v���Ƃ������ƂɂȂ�B�O��s�s�����邢�͓����ւ̐l���W���͓��{�o�ςɂƂ��Ĕ������Ȃ��Ƃ������A�i�߂�ׂ����ƂȂ̂��낤���B
�������]�����ɕς���Ă����l�Ԃ̋��Z
�����]�����ɂ����铌����ɏW���ƒn��������̐l�����o���̉����͊ȒP�ł͂Ȃ��B��1�ɖL�����̊T�O�̕ω�������B���{�o�ςɂƂ��Ă͓�����ɏW�����]�܂����Ƃ������������邪�A���ꂩ�狁�߂�ׂ��L�����Ƃ́A���������Y(GDP)�̂悤�Ȏs��ɂ����Ď�����ꂽ���i��T�[�r�X�̕t�����l�ő���L���������ł͂Ȃ��Ƃ̍l�����x�z�I�ɂȂ����B
���̑�\��͌o�ϋ��͊J���@�\(OECD)������Better Life Index(���ǂ���炵�w�W���K���x)�ł���B���̎w�W�́A�����E���Y�A�����E�ٗp�Ȃǂ̌o�ώw�W�̂ق��ɁA�Z��A���N��ԁA���[�N�E���C�t�E�o�����X�A����A���A���S�A�Љ�Ƃ̂Ȃ���A�s���Q���A�����Ď�ϓI�ȍK���Ƃ�����11���ڂ���Ȃ鑽�ʓI�Ȏw�W�ł���B���̂悤�ȓ��e�̖L�����̎����ɂƂ��āA�ǂ̂悤�ȋ��Z�`�Ԃ����������̂��A��������K�v������B
��2�Ɍ���Љ�A�u�\�T�G�e�B�[5.0�v(Society 5.0)�ƌĂ�镶���Љ�ւƈڍs���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B���̊T�O�͓��{�̉Ȋw�Z�p��{�v��(��5��)���������̂ŁAIoT�A�r�b�O�f�[�^�AAI�A���{�b�g�ɑ�\�����Z�p����ՂƂ���Љ�ł���B����ɉ����āA�Đ��\�G�l���M�[����ՂƂ��鎝���\�ȎЉ�ւ̈ڍs�����߂��Ă���B
����܂ł̎�E���J�E�̏W�Љ�A�_�ƎЉ�A�H�ƎЉ�A���Љ�́A���ꂼ���ՂƂȂ鎑�����قȂ��Ă���A�����A���Y�̗��n���A�l����W���̋K�͂��قȂ��Ă����B����Ȃ�\�T�G�e�B5.0�̎Љ�ł́A�ǂ̂悤�Ȃ������̐l�ԋ��Z��l���z�u�̂���悤�����߂���̂��낤���B�l�����ێ����A����܂ł̒n������̂܂܈ێ��������ł���悢�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B
�n�������͓̂s�s������̈ڏZ���i�{���ł��Ă����B�R���i�Ђ̂��ƂŁA�����[�g���[�N�≓�u���Ƃ�������O�ɂȂ�A�����Ґ���������s�s��������čx�O�ɋ��Z����X���͊m���ɂ���B���[�P�[�V�����Ƃ����悤�ȐV�������C�t�X�^�C�������܂�Ă���B����������ŁA����A�n�����ł܂��܂���������l�������Ə��q����ɑΉ����邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��낤���B
���A���{�l����50�N�Ԃ�30���������鐨���ŏk���𑱂��Ă���B�S�Ă̎����̂Ől�����ێ����邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��A���邢�͈Ӗ��̂��邱�ƂȂ̂��B��s�s���̋��͌o�ςɂǂ̂悤�ȉe���������炷�̂��B�ڏZ���i�Ɍ���ꂽ�\�Z�������̂ł͂Ȃ��A�l�����������Ă����S���Đ����ł���悤�Ȏd�g�݂̑n���ɗ͂����Ȃ���A�n��S�̂̍s���V�X�e����Љ�C���t�����������Ă��܂����ꂪ����B
�n�����ł͉\�Ȍ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ߋ��ɂ͕����Љ�̈ڍs�ɂƂ��Ȃ��āA�W���̓P�ނ�s�s�E�����̋��p�����������Ƃ������ł���B�l�̋��Z�n�I����ړ��̎��R�́A�Ƃ����Ƃ̂ł��Ȃ���{�I�l�����B����d������ŁA��ÂɍH�ƎЉ�Ƃ͈قȂ�V���ȕ����Љ�ւ̈ڍs������ɓ���Ēn��̏�������͍�����K�v������B��s�s������n�����ւ̐l���җ��̒D�������ɔ敾���Ă��܂��Ă���ł͒x���B
|
�������o�H 68.4%���ƒ���@����@�V�^�R���i�E�C���X�@5/2
����1���A�V����10�Ζ�������90��̒j��1554�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����\�����B��T�̓��j�����243�l�������B���j���Ƃ��Ă͍ő������A����4��29�����j�������x�����������߁A��T�̌������ʂ��{���ɏW���������Ƃ��e�������Ƃ��Ă���B
�N��ʂł�10�オ�ő���343�l�A����10�Ζ���278�l�A40��223�l�A30��219�l�Ƒ����B�����o�H���������Ă���692�l�̂����A��68�E4���ɓ�����474�l���ƒ���������B�ƒ�������𒆐S�Ƃ�������̊����X�����A�ˑR�Ƃ��đ���������B
����ŁA�a���g�p���͐挎��26������6���A���Ō������A35�E6���������B���̋{���`�v�����������Ăɂ��ƁA��������Ɠ��@�ɒ������₷������҂̊������}�����Ă��邱�ƂŌ��������ƍl������Ƃ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���4��30�����_��604�E13�l�őS�����[�X�g�B�ČR��n���̐V�K�����Ґ���82�l�������B
|
����^�A�x���̊���������m�A���ȏȁ@5/2
�����Ȋw�Ȃ�2022�N4��28���A��^�A�x���̐V�^�R���i�E�C���X�����g��̖h�~��ɂ��āA���t���[�V�^�R���i�E�C���X�������Ǒ����i������̎��m�˗����W�e���֔��o�����B
�u��^�A�x�ɂ����銴���g��̖h�~�ɂ��āv�́A�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�ɂ�����4��27���ɋc�_�������ʂ܂��A��^�A�x���̊����Ǒ�ɂ��Đ��{�����ӓ_�������܂Ƃ߂����́B
���݁A�V�K�����Ґ��́A�S���I�Ɋɂ₩�Ȍ����������Ă��邪�A�n��ɂ���Ċ����̐��ڂɍ�������B��s���ł͂��ׂĂ̔N��ŊT�ˌ����X�������A���ꌧ�ł͂��ׂĔN��ŐV�K�����Ґ��������B����10��ȉ��̑����������ł���A����҂̑������p�����Ă��邱�Ƃ���A����A���̒n��ł�����҂̊����𒍎����Ă����K�v������Ƃ��Ă���B
�����ꏊ�Ƃ��ẮA�w�Z���������Ƃ������A���Ŏ��Ə��A�ۈ牀�E�c�t�����B�w�Z���̊����͑����X���ɂ���B�܂��A20��ł͈��H�X�̊������������A���Ə��ł̊����������Ƃ������B�N���X�^�[����ɂ��ẮA���H�X�����A�w�Z�E����{�݁A���������{�݁A����Ҏ{�݁A�E�ꓙ���傫�Ȋ������߂Ă���B
�a���g�p���E�d�Ǖa���g�p���͒Ⴂ�����𐄈ځB����҂̃��N�`��3��ڐڎ헦��8�����Ă��邱�Ƃ���A�����_�ŁA�s���{������u�܂h�~���d�_�[�u�v�K�p�̗v���͂Ȃ��A�����ɏd�_�[�u��K�p����ɂ͂Ȃ����ƂL���Ă���B
��^�A�x���̊�����Ƃ��ẮA�u��{�I�Ȋ�����̓O��v�u�ϋɓI�Ȍ����̎�f�v�u���N�`��3��ڐڎ�̐����v��3���K�v�Ƃ��������ŁA��ʁE�ꏊ�ɉ���������K�v�ł���ƋL�ځBGW���̗��s��A�Ȃɂ��ẮA���O�Ƀ��N�`��3��ڐڎ����A�܂��͏o���O�ɍR�������L�b�g���ɂ�錟�����邱�Ƃ𐄏��B
��̓I�ɂ́A���H�X�ł͊����u�����Ă���X�܂�I�сA��{�I�Ȋ���������{���������ŗ��p����ƂƂ��ɁA��l���A�吺�A�����ԁA�O��������A���C����O�ꂷ�邱�ƁB
�C�x���g�ł́A��Îғ��͋K�͓��ɉ����āA�����h�~���S�v��ɂ����O��B�s���{���́A�ϋq�̊����g�僊�X�N��}�����邽�߁A�C�x���g���̑O��̊����ɂ������{�I�Ȋ�����̓O��̌Ăт��������s�����ƁB�Q���҂͓s���{���̌Ăт����ɏ]���A��{�I�Ȋ���������O�ꂵ�ĎQ�����邱�ƁB�K�v�ɉ����āA�ϋɓI�Ɏ��O�������邱�Ƃ����߂Ă���B
�w�Z�E�ۈ珊���́A�u�w�Z�ɂ�����V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊւ���q���Ǘ��}�j���A���v�u�ۈ珊�ɂ����銴���Ǒ�K�C�h���C���v���܂����Ή�����{�ɁA�I�~�N�������ɑΉ����Č��ݎ��{���Ă��銴����̋����̓O������炽�߂Ď��m�B���������ɂ��Ă��A���O�̑̒��m�F�⊷�C���̓O������߂��B��w�ł͋��_�ڎ�ɉ����A�����̓��Ƒ�w�����A�g�����ڎ��ꓙ�ɂ�����c�̐ڎ�ɂ��A�ڎ����]����w���ւ̃��N�`���ڎ�𑣐i����悤���߂Ă���B
�Ȃ��A�����g��ŁA�����̎{�݂ŃN���X�^�[�����������ꍇ�ɂ́A�n��̎���ɉ����A�E���̕p���A���������ɂ����銴�����X�N�̍��������̐����A�ۈ珊�ɂ�����Ǐ�̂���q���̓o�����l�v�������s�����Ƃ�t�L���Ă���B
����Ҏ{�݂ɂ��ẮA�z���҂��o���ꍇ�̑�������E�x���A���E���̉����h���A���M�����E���̋x�ɓO��A���N�`��3��ڐڎ�̑����������A�I�~�N�������̊���������̓O���������߂Ď��m�B�����āA�N���X�^�[�������́A�E���̕p���A�ʉ�̊�����̓O�ꓙ���s�����Ƃ��L���Ă���B
���̑��A�V���b�s���O���[�����A�����̐l���K��邱�Ƃ��\�z�����{�݂ɂ��A�Ǝ�ʃK�C�h���C���̏�����{�I������̎��{�����炽�߂Ď��m�O��B���ɁA����҂����W���Ȃ��悤�����E�U���⍬�G�̉����A���C�̓O�ꓙ�ɒ��ӂ���悤���߂Ă���B
���Ə��ł́A���ɐH���◾���A�E���̌���肪�z�肳���ꏊ�ł̊��C�⋤�p�����̏��œ���O�ꂷ�邱�ƁB�N���X�^�[���������Ă���ꍇ�ɂ́A�E��ł̍��e��͉����E�k�����܂߂Č�������悤���߂Ă���B�ƒ���ɂ����Ă��ړ��悩��߂�������܂߁A�̒��s�ǎ҂�����ꍇ�ɂ́A���₩�Ɉ�Ë@�ւ���f���邩�������s�����A�������O�ꂷ��悤�Ăт����Ă���B�@ |
�������s �V�^�R���i 3�l���S 2403�l�����m�F �O�T��738�l�� �@5/2
�����s����2���̊����m�F��1�T�ԑO�̌��j�����738�l���Ȃ�2403�l�ł����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��2���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2403�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j�����738�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�21���A���ł��B2���܂ł�7���ԕ��ς�4132.9�l�őO�̏T��76.3���ł����B2403�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������S�̂�19.6���ɓ�����471�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�142�l�őS�̂�5.9���ł��B�܂�����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�2�����_��10�l��5��1������1�l�����܂����B����A�s�͊������m�F���ꂽ90��̒j�����킹��3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
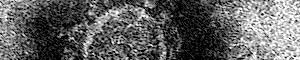 |
����t����1035�l�����A2���Ԃ��l��Ɂ@�Ό��̎��������{�݂ŃN���X�^�[�@5/3
��t������3���A1035�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������V���ɔ��������B����̊����Ґ�����l������̂�2���Ԃ�B�Ό��s���̎��������{�݂ł̓N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F���ꂽ�B�����̗v�����Ґ���42��4030�l�ɑ������B���҂̔��\�͂Ȃ������B
���������\���������̕ʂł́A����705�l�A��t�s��168�l�A�D���s��117�l�A���s��45�l�B
|
�������1761�l�����@�ߋ�3�Ԗڂ̑����@�Ηj���ł͍ő��@5/3
���ꌧ��3���A�V����1761�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�ߋ�3�ԖڂʼnΗj���Ƃ��Ă͍ő��B��T�̓����Ηj��(4��26��)��1418�l�ɔ�ׂ�343�l�������B�v�����҂�16��5061�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����҂�2�����_��639.41�l�ƂȂ�A�ˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ����k�C����335.55�l�����������Ă���B�a���g�p����35.9%(���@�Ґ�235�^�a����654)�ŁA�d�ǎҗp��16.7%(���@10�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B
�ČR�W�́A�V����40�l�̊��������ꂽ�B
|
���u��6�g����7�g�H�v26�����Ŋ��������@5/3
3�N�Ԃ�ɋً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���ǂ��̓s���{���ɂ��o�Ă��Ȃ����ő�^�A�x���}�����B�����s�Ȃǂł͊����҂͌����X���ɂ���A��6�g�͂ЂƂ܂����܂����悤�Ɍ�����B����A����܂Ŋ����Ґ������Ȃ������n���ł́A��6�g����ߋ��ő����x���̊����������Ă���A��7�g�̗l�����悵�Ă���B����A���X�̊����Ґ���ǂ������ł͌����ɂ����S���̊����Ґ����A��5�g�Ƒ�6�g�A�����đ�7�g�Ƃ̎w�E�����钼�߂�3�����ɕ����āA�W�v�����B
�d�_�[�u���������ꂽ2022�N3��22���̑O��ŕ�����ƁA�k�C���A�X�A���A�{��A�H�c�A�R�`�A�����A���A�ȖA�V���A����A�O�d�A����A�����A���R�A�L���A�R���A����A���Q�A���m�A����A����A�啪�A�{��A�������A�����26�����ŁA�d�_�[�u������Ɋ������������Ă����B�n���𒆐S��47�s���{���̔����ȏ�ň����������ƂƂȂ�B���Ƃ̊Ԃł́A����܂ł̊����Ґ������Ȃ��n��Ŋ������g�債�Ă��邱�Ƃ���A���R�Ɖu�̉e�����w�E���鐺������B
���N�`����3��ڐڎ�̐i���Ȃǂő����ł͌����ɓ]���Ă���n��͂��邪�A���܂��ɉߋ��ő����x���Ő��ڂ��Ă���n�������B�l���K�͂̑傫����s������Ō����Ă��邽�߁A�S���̊����Ґ��͑������Ă��Ȃ����A�A�Ȃ◷�s�ňړ�������������Ăѓs�s���ł��������g�傷�鋰����ے�ł��Ȃ��B���ʂ́A��{�I�Ȋ�����̓O�ꂪ���߂�ꂻ�����B
|
���I�~�N�����g�V�ψفh���̎s�������c�����Łg�ψفh���@5/3
2���A�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�2403�l�Ɛ�T�̌��j������738�l����A21���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B
����A���j���Ƃ��Ă͉ߋ�2�Ԗڂɑ���770�l�̊������m�F���ꂽ���ꌧ�ł́A�ʏ�f�j�[�m�����S�[���f���E�B�[�N���Ԓ��̊�����̓O������߂ČĂъ|���܂����B
���ꌧ�E�ʏ�f�j�[�m���F�u�������ӂ��Ă��܂��ƁA�A�x��Ɋ����҂��}������\��������B�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ��A������ۂƂȂ��āA�������������h�~�Ɏ��g��ŎQ��܂��傤�v
���������Ȃ��A������Ȏ��ȑ�w�́A����܂Ō����Ȃ������V���Ȏ�ނ̃I�~�N���������m�F�����Ɣ��\���܂����B
�V�^�R���i����116�l�̃Q�m����͂��s�������ʁA���̂�����2�l���猻�݁A�����Ŏ嗬�ƂȂ��Ă���I�~�N�������uBA.2�n���v�ɐV���ȕψق���������E�C���X�����o���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�E�C���X�̓�������A�����ŕψق����\���������A������2�l���C�O�ւ̓n�q�����Ȃ����Ƃ���A�����ł̎s�������Ƃ݂��܂��B
��������A���N�`����3��ڎ�ς݂ŏǏ�͌y���Ƃ������Ƃł����B
������Ȏ��ȑ�w�F�u�����ɂ����Ēu������肪�i�ނƁA�����Ċg��ɂȂ��鋰�ꂪ����v
|
���k�o�E���o��Q�u���v�@�I�~�N�������ǁA�������� �@5/3
���͓���A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��I�~�N�������Ɋ��������l�̌��ǒ������ʂ\�����B�f���^���ȑO�Ɣ�ׁA�k�o�E���o��Q�ƒE�т̏Ǐ��Ȃ������B�I�~�N�������͊����g�傩��܂����Ԃ���r�I�Z�����߁A���͍���A�Ǐω�����\��������Ƃ��Ē������p������B
�ꌎ�ȍ~�Ɋ��������S�O�l�̒������ʂɂ��ƁA�l�����k�o�E���o��Q�́u�Ǐ�v�ƉB�ꊄ���E�тł��u�Ǐ�v�Ɠ������B�f���^���ȑO�̕S���\���l�̒����ł́A�������k�o�E���o��Q�A�l�����E�т���Ɖ��Ă���A�I�~�N�������ł͒Ⴂ�X���ƂȂ����B��Ԃ炢�Ǐ������ł͑������ɁA����28���A����17���A����(����)��15���Ƒ������B�f���^���ȑO�ł́A�k�o��Q19���A���o��Q13���A�E��12���������B
���͌��ǂ��u������l�T�Ԉȏ㑱���Ǐ�ŁA�R���i�ȊO�̎����Ő����ł��Ȃ����́v�ƒ�`���A��N�\���猧�z�[���y�[�W�Œ������Ă���B������I�~�N�����������҂̒�����������ق��A����܂ł̉҂̂��̌�̏�Ԃ��m�F����\��B
|
�������{�y�̐V�^�R���i�V�K�s�������Ґ��͖�6��l�A3���A��1���l�ȉ��c�@5/3
�����{�y�ł́A��r�I���������ɐV�^�R���i�̕������߂ɐ������A�ȍ~�͑S���I�ɂ͈��肵���ƂȂ�A�U���I�Ȏs�������m�F�Ⴊ�x�X�o��������x���������A���N(2022�N)�ɓ����Ĉȍ~�̓I�~�N�����ψي��y�т��̈���(������u�X�e���X�I�~�N�����v��)�̗������A�ꕔ�n��Ŕ�r�I��K�͂ȍė��s���o�����Ă���B
�����̍��Ɖq�����N�ψ���(NHC)��5��2�����Ɍ����T�C�g��Ō��\�������ɂ��A����1���̒����{�y�ɂ�����V�K�s�������m�F�Ґ���368�l(�O������478�l��)�������Ƃ̂��ƁB����́A��C�s274�l�A�k���s51�l�A�����]��13�l�A�L����7�l�A�ɔJ��5�l�A�]����5�l�A������3�l�A�R����3�l�A�R����2�l�A�͓��2�l�A�������S��������1�l�A�d�c�s1�l�A�l���1�l�B���̂�����C�s��155�l�A�k���s��3�l�A�ɔJ�Ȃ�2�l�A�L���Ȃ�2�l�A�R���Ȃ�1�l�A�d�c�s��1�l�̌v164�l�����Ǐ犴���m�F�ɓ]�������āB�����{�y�Ŏs�������m�F�Ⴊ�o������̂�199���A���A3���A����3���ƂȂ����B
�s���̖��Ǐ����5647�l(�O������1248�l��)�B����́A��C�s5395�l�A�ɔJ��79�l�A���]��34�l�A�]����29�l�A�V�d�E�C�O��������26�l�A�g�я�21�l�A�]�h��13�l�A�k���s11�l�A�R����11�l�A�����]��10�l�A�͖k��5�l�A�L����5�l�A�͓��4�l�A�_���2�l�A���J��1�l�A�d�c�s1�l�B
���Ǐ���܂ސV�K�����Ґ���6015�l�ŁA3���A��1���l�ȉ��ɁB���̂�����C�s�̕���5669�l�ɏ��A�S�̂�94.2%���߂��B
5��2��24�����_�̒����{�y�Ŏ��Ò����Ă��銴���m�F�Ґ���1��6266�l(�����A������168�l)�ŁA�d�ǎ҂�615�l(�A�����̓[��)�B���Ǐ�̊���13��3610�l(�A����516�l)����w�ώ@���ɂ���Ƃ̂��ƁB
�������ǂ͈���ɂ�����g�U�h�~�Ɠ����ɁA��O����̗����Ɖ@��������h�~���邽�߂̓O�ꂵ���[�u���u����Ȃǂ��āu����(�[���R���i��)�v��ڎw���O��I�ȑΏ���i�߂Ă����B��̓I�ɂ́A�ǒn���b�N�_�E���A�S��PCR�����ɂ��X�N���[�j���O�A�����ׂ��ړ��̐����A���H�X���̓���Ǝ�ɑ���c�Ɛ������̑[�u����������B�����_�ł��[���R���i�������������l�����d�˂ċ������Ă���A���炩�̕����[�u���u�����Ă���n�悪�������݂���B
���̂Ƃ��뒆���{�y�̑����̏Ȏs��ŐV�K������̏o���������Ă��邪�A���ɐ[���Ȃ̂���C�s�B���s�ł�3�����{���玖����̃��b�N�_�E��(�s�s����)��Ԃ������A���̉������������ʂ��Ȃ��B�������A���̂Ƃ��듯�s�ɂ�����V�K�����m�F���͊ɂ₩�ȉ����X���ɂ���B����̍ė��s���n�܂��Ĉȗ��̓��s�̗v�����m�F���͖�5.4���l�A���S�Ґ���474�l�B
4��22���ȍ~�A�k���s�ł�������̏o�����������ł���A����̍ė��s�ɂ����銴���҂̗v�͖�350�l�ɁB�����܂Ŏs��14�̋�Ŋ����m�F�Ⴊ�o�����Ă���A���ɑ����̂����z��ŁA�[�R��ƒʏB�悪����Ɏ����Ƃ̂��ƁB5��3������s��12�̋�őS��PCR����(3���)�����{�����B
���`�E�}�J�I�Ɨ��Őڂ���L���Ȃł��A���N�ɓ����Ĉȍ~�A�L�B�s�A�[�Z���s�A���Ύs�A��C�s�A���R�s�ȂǂŒf���I�Ɏs�������m�F�Ⴊ�o�����Ă������A���̂Ƃ���͗��������Ă���A4��22���܂łɏȓ��S�悪��X�N�n��ɕ��A�����B�������A�ߓ��͍L�B���_���ۋ�`�̐E���y�т��̓��Z�҂𒆐S�Ƃ����V���Ȋ����Ⴊ�������o�����Ă��邪�A����܂ł̂Ƃ���u���ΏۈȊO�̈�ʎs���ɂ����銴����͕���Ă��Ȃ��Ƃ����B
�}�J�I���ʍs����ł�5��2���܂�204���A���s�������m�F��[���ƂȂ�������A���`���ʍs����ł͍�N(2021�N)12��������V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s�u��5�g�v���n�܂����B2������3�����ɂ����Ċ����m�F���̋}��������A��5�g�J�n�ȗ��A5��1���܂ł̗v�͖�119.2���l(���Ǐ�܂�)�A���S�Ґ���9105�l�A���S����0.76%�ɁB3�����{�Ƀs�[�N���߂����Ƃ���A���߂ł�2���܂�9���A��500�l�ȉ����ێ��B2���P���ł�283�l(�A����11�l�܂�)�ŁA2���A���s�[�N���ȍ~�̍ŏ����X�V�B����܂ō��`�ł͏�C�s�̂悤�ȑS�惌�x���ł̃��b�N�_�E���͎��{����Ă��炸�A����̃}���V���������ΏۂƂ����ǒn���b�N�_�E���ɂƂǂ܂�B
|
��NY�̊������X�N�u��v����u���v�Ɉ����グ�@5/3
�V�^�R���i�̐V�K��������������A�����J�E�j���[���[�N�ŁA�s�̃R���i�x���x�������グ���A�����ł̃}�X�N���p�Ȃǂ����������悤�ɂȂ�܂����B
�j���[���[�N�s��2���A�s����10���l������̐V�^�R���i�̗z���Ґ���7���ԕ��ς�200�l�����Ƃ��āA�s���̊������X�N���u�Ⴂ�v����u�����x�v�Ɉ����グ�܂����B
�s�Ƃ��Ă͉����̌����̏ꏊ�ł̓}�X�N�̒��p�𐄏�����ȂǂƂ��Ă��܂��B
�����҂͑����X���ł����A���@�Ǝ��S�̐��͌���X���ɂ���܂��B
���߂̕��͂ł́A�j���[���[�N�B���̊�����100�����I�~�N�������ɂ����̂ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�I�~�N�������̂Ȃ��ł��B���Ŋm�F���ꂽ�uBA�D2�D12�D1�v�ƌĂ��^��40�����A�L������݂��Ă��܂��B�@ |
�������s �V�^�R���i 4�l���S 3357�l���� �O�T�Ηj���1700�l�� �@5/3
�����s����3���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̉Ηj����肨�悻1700�l���Ȃ��A3357�l�ł����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��3���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���3357�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj����肨�悻1700�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�22���A���ł��B3���܂ł�7���ԕ��ς�3891.3�l�ŁA�O�̏T��72.8���ł����B3���Ɋm�F���ꂽ3357�l��N��ʂɌ���ƁA30�オ�ł������A�S�̂�18.9���ɂ�����633�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�236�l�őS�̂�7.0���ł��B�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A3�����_��11�l�ŁA2������1�l�����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70�ォ��80��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�̐V�K�����҂�3318�l�@���S13�l�m�F�@5/3
���傤3���A���{�͐V����3318�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�܂��A�V����13�l�̎��S���m�F���ꂽ�B���@���̏d�ǎ҂�24�l�ƂȂ��Ă���B
|
 |
������R���i1761�l�����@�ߋ�3�Ԗځ@�O�T��343�l���A�Ηj�ő��@5/4
���ꌧ��3���A10�Ζ�������90�Έȏ�܂ł�1761�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�ߋ�3�Ԗڂɑ����V�K�����Ґ��ƂȂ����B�O�T�̓����j���Ɣ��343�l�������A����܂ł̉Ηj���̐V�K�����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ����B���̂����{�Ó��s�ł�152�l�̐V�K�����҂��L�^���ߋ��ő��ƂȂ����B
���̋{���`�v�����������Ă͊����҂̑����̗v���ɂ��āu�S�[���f���E�C�[�N�̑O���̉e�����o�Ă���̂ł͂Ȃ����v�ƌ�����B
�V�K�����Ґ���1������O�T�Ɠ����j���������Ă���A�������g�債�Ă���B3���̊����Ґ��͍��N1��15����1826�l�A����13��1816�l�Ɏ�����3�ԖځB�{�Ó��s�̊����Ґ��͍��N1��8����132�l��20�l�������B�{�����́u�l�������������钆�A�Ǐ���ꍇ�͊O�o���T���A��l���̐H�������Ȃ��ȂǁA��{�I�Ȋ�������s���Ăق����v�ƌĂъ|�����B
|
���[���R���i����Ō��������{�@�s�������̂Ȃ�GW�ɏ��オ�v�����Ɓ@5/4
���X�̐����̂Ȃ��ł�����ƋC�ɂȂ�o������j���[�X���A������t����Â⌒�N�̖ʂ���������R�����u������Ƃ����㌩�蒟�v�B����́u���E�̃[���R���i����Ɠ��{�̌��v�ɂ��āANPO�@�l��ÃK�o�i���X�������̓��Ȉ�E�R�{���ވ�t���u�㌩�v���܂��B
�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̂Ȃ���^�A�x��3�N�Ԃ�ł��B��6�g���s�[�N�A�E�g���A�����Ґ����E��������Ō������A�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̒lj��ڎ킪�i�ޒ��A�R���i�Ƃ̋����ւƎЉ�����o���Ă���C�z�������܂��B
���ȊO���̌���ł����Ǐ��F�߂Ď�f�������͂�����������̂́A�s�[�N�̎����͂��Ȃ茸�����Ă��܂��BPCR�������s�����̂́A�z�����o��̂�1����̐����܂ʼn������Ă��Ă��܂��B���������~�̗��s������Ɨ��������Ă������Ƃ��������Ă��܂��B
�O�̃R�����ł́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ͋G�ߐ��̕ω�������̂ł͂Ȃ����ƍl�@���܂����BOur world in data�Ő��E�e���̃R���i�V�K�����Ґ��̃O���t���݂Ă���ƁA�����Ґ��̈Ⴂ�͂���ǂ��A���{�ŗ��s�����������Ă���悤�ɁA�C�M���X��h�C�c�A�t�����X��J�i�_�ł��V�K�����Ґ��͉E���������F�߂Ă��āA�A�����J�ł͂����X���ɂ�����̂́A�ᐅ�����ێ����Ă��܂��B
4��27���A�A�����J���{�̎�Ȉ�Ìږ�ł���t�@�E�`���́A�u�p���f�~�b�N�͂܂��I����Ă��Ȃ����A�p���f�~�b�N���̋}�����̒i�K��E���A�p���f�~�b�N�̐V�����t�F�[�Y�ɓ������v�Ƃ��������������܂����B�z���C�g�n�E�X�̃A�V�V���E�W���[���m�͑O����26���̋L�҉�ŁA�u�V���Ȋ��������S�Ɏ~�߂邱�Ƃ͐����ڕW�ł���Ȃ��B����ɁA�������ŏ����ɗ}���Ȃ���d�lj���h�����ƂɏW�����ׂ����v�Ƃ̍l���������Ă��܂��B
���B�A��(EU)��27���ɁA�uEU�̓p���f�~�b�N�́w�ً}�i�K�x����E�p������v�Əq�ׁA�u�H�ɐV���Ȋ����̔g������\���ɔ����āA���N�`���ڎ�A�Ď��A�����ɏd�_��u���v�ƌ����܂��B��͂莟�̗��s���������āA����l���Ă��邱�Ƃ����������m��܂��B
�����ƂɃ��N�`���ڎ헦��R���i������ɍ��͂�����̂́A�V�K�����Ґ��̑����������悤�Ȕg��`���̂́A��ϋ����[�����ۂł��B�G�ߐ��̕ω������邩�ǂ����́A����炩�̗��s�̌o�߂����Ă����K�v�����邱�Ƃ͏\�����m���Ă��܂����A�G�ߐ��̕ω�������Ƃ���A���{�ł͎��͉Ă���ɗ��s����ƍl�����܂��B�ߋ��̋L�^�ł͓~���Ă̗��s�͏������悤�ł��B3��ڂ̒lj��ڎ킪�܂��̕��́A�\�z�����Ă̗��s�ɔ�����7���܂łɐڎ���I����Ƃ����̂ł͂Ȃ����ƁA���͍l���Ă��܂��B
���āA�[���R���i������s�Ȃ��Ă��鍑�����݂������ŁA���E�ł̓R���i�K�����������Ŋɘa����Ă��܂��B�Ⴆ�A�C�M���X��t�����X�ł́A���N�`���ڎ�ؖ��������A�o���O��PCR������R�������ɂ��A���ؖ��͕K�v����܂���B����A�W�A�ł��ɘa�̓������i��ł��܂��B�J���{�W�A�ł́A���N�`���ڎ킪�ς�ł���ꍇ�A������̊u���͕s�v�A�������̍R�������������Ȃ��Ă��܂��B�^�C�ł́A2022�N5��1�����烏�N�`���ڎ���������Ă���A�o���O����ѓ������PCR�������K�v�Ȃ��Ȃ�܂����B
���{�͂Ƃ����ƁA���N��3��1���ȍ~�A�O���l�̐V�K���������̊ɘa�����{���ꂽ���̂́A�ό��ړI�̓����͋֎~�����܂܂ł��B���݁A�V�^�R���i�E�C���X���N�`���̒lj��ڎ���I���Ă���A���{�����w�肷��I�~�N�����w�荑�E�n��ȊO����̓����ł���A�������ɉA����F�߂�A�A����̊u���͖Ə�����܂��B�܂�A���{�l�ł���Ίό��ړI�̊C�O���s�ɍs���A���{�ɂ܂��߂��Ă��邱�Ƃ��ł��邯��ǁA���{�l�łȂ���A�ό��ړI�ł͈�ؓ��{�ɓ������ł��Ȃ��Ƃ����킯�ł��B
���{�e�n�̊ό��n�́A�����̊ό��q�œ�����Ă���悤�ł��B�����̐l����s�@��V�����A�S����Ԃ��g���������ړ����Ă������ŁA�C�O����̊ό��q�͍����ɓ���Ȃ��Ƃ����K���̌p���ɖ�����������͎̂������ł��傤���B���ۑ�́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ������ɗ��s���Ă��Ȃ��ꍇ�͗L���ł��B�������Ȃ���A����������đj�~���悤�Ƃ����I�~�N�������������Ƃ����ԂɑS���Ɋ������g�債�����A���͂�A���������ۑ�͈Ӗ�������܂���B
�u�R���i�͂��������������B�d�lj����Ď��Ⴄ�̂́A���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l�̎��ȐӔC�B�݂�ȁA�������ʂɐ������Ă����v�����b���A�����J�̃J���t�H���j�A�B�ݏZ�̗F�l�ɁA�r�W�l�X�◯�w�ȊO�ł͓��{�ɓ����ł��Ȃ�������ǂ��v�����������Ƃ���A�u���{�ɂ͗���Ȃ��Č�����C�����Ďc�O�B�ł��A�K�����������ꂽ���͂��������āA���{�ȊO�ɂ��s���Ă݂������͂������邩��A�ʂɓ��{�ɍs���K�v���Ȃ��ˁv�Ƃ����̂��ނ̓����ł����B
��N�̉āA�T�C�G���X���Łu�p�[�e�B�V�����̓R���i�̓`�d�������邱�Ƃ�������Ă���v�Ƃ���ɂ�������炸�A���{���p�[�e�[�V�����̎g�p�𐄏����Ă��邱�Ƃ�A�����ł��łɊ������L�����Ă���̂Ɍ��������ۑ���p�����A�C�̊ɂ݂ɂ�芴�����X�N�����܂�Ƃ����ȂǁA�Ȋw�I�E�����I�Ƃ͓���v���Ȃ���𑱂��Ă��ẮA�u���{�ɍs���K�v�͂Ȃ��v�ƌ����Ă��܂��Ă��d���Ȃ��̂�������܂���B
�Ō�ɂȂ�܂������A�����o���O�̃R���i�������A���ł���A��^�A�x�𗘗p���āA2�N�Ԃ�ɓ��{�𗣂��\��ł��B���܂łȂ�A�p�X�|�[�g�����Y��Ȃ���Ȃ�Ƃ��Ȃ������̂́A�n�q��̓��������ׁA���������悤�ɏ��ނ��������Ȃ���e�o���ł��܂���B�A�������A���{�̌������������������Ȃ��Ɠ��{�ɖ߂��Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��l����ƁA�y���݂����s���̕������{���D��C�O���s�͏��߂Ăł��B����́A��������o���܂ł̎����g�̑̌��L�����L�������Ǝv���܂��B
|
���S�[���f���E�C�[�N�㔼�@���Ɍ����̊ό��n�ɂ��키�@5/4
�S�[���f���E�C�[�N���㔼���}���Ă��āA���Ɍ����̊ό��n�́A�A���e�n�łɂ��킢���݂��Ă��܂��B
���E������Y�ō���̕P�H��B3�N�Ԃ�ɋً}���Ԑ錾���܂h�~���d�_�[�u���o�Ă��Ȃ��S�[���f���E�C�[�N�ɑ����̊ό��q���K��Ă��܂��B�W��130���[�g���ɂ��鍑�w��̎j�Ղ�1�F�{��ՁB ����̓V�C�Ɍb�܂�A�A�Ȃ�ό��ŖK�ꂽ�l���������C�Ƌ�̐�i���y����ł��܂����B�F�{�s�́A���z�ȉ��p�����ԗ�i�̃��[���Ɉᔽ�����Ƃ���5��1������2�N�Ԃӂ邳�Ɣ[�Ő��x�̑Ώۂ��珜�O����܂������A�F�{����ł́A���̂Ƃ���傫�ȍ����͂Ȃ������ł��B
����A�������H��5��4������U�^�[�����b�V�����}���Ă��܂��B
|
���R���r�j�e�ЁA���ʂ⊄����GW����@5/4
�S�[���f���E�B�[�N(GW)���܂�Ԃ��n�_�ɍ����|���������A�R���r�j�e�Ђ͊����Ԃ���}��ׂ����ʂ⊄�������{���Ă���B
���N�ً͋}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̍s���������Ȃ�GW�ƂȂ�A�R���i�Ђ�20�N���21�N��ł̓v���X���m��������钆�A�e�ЂƂ��R���i�O��19�N����x���`�}�[�N�Ɏ{���W�J���Ă���Ƃ݂���B
�l�������A�N�e�B�u��GW�ƌ���������������A�Z�u��-�C���u���E�W���p���͎芪�����ɂ���ʁB�u�Ȃ��Ȃ��l�����߂炸�A���Ɋό��n�A���邢�͊ό��n�Ɍ������Ƃ���ł́A�v���������i�̔�����������A���ɂ���ɂ��Ă͊m���Ɍ��ʂ��オ��v(�Z�u��-�C���u���E�W���p���̐R�����������s�������i�{�����������Ǘ��{������QC���Ǐ�)�Ƃ݂Ă���B
�Z�u��-�C���u���ł�8���܂ŁA�芪�����ɂ���5�A�C�e���̒��g��1.2�{�`1.5�{�ɑ��ʂ��ĉ��i�����u���Ŕ̔����Ă���B
�t�@�~���[�}�[�g�́A�t�@�~�`�L�o���Y(�^���^���\�[�X)�ƃ��W���P�[�X���̗g�����E�y���Z�b�g�Ŕ�����50�~�����Ƃ���L�����y�[����9���܂œW�J���Ă���ق��A�L�y���ق́u�u���b�N�T���_�[�v�ƃR���{�����t���[�Y���h�����N�u�t���b�y�v��O�ʂɉ����o���Ă���B
5��31������I���W�i���z�b�g�X�i�b�N�u���炠���N���v�̐ō����i��216�~����238�~�ɒl�グ����Ɣ��\�������[�\���́A9���܂Łu���炠���N���v��1���ʎ{������{�����v�����N���Ă���B
�}�[�P�e�B���O���T�[�`��Ђ̃C���e�[�W��GW�ɂ��đS����15�`79 �̒j����2600�l��4�����{���������ɂ��ƁA�u�����GW�̗\��v�̐ݖ�ł́u����ʼn߂����v��6���ƍł������ƂȂ������̂̍�N�́u����ʼn߂������v�����16�|�C���g���������B �@
�V���b�s���O�E�O�H�E�������s�Ƃ������O�o���\��̃X�R�A���傫���L�т����Ƃ��瓯�Ђł́u����܂ł�GW�Ƃ͈قȂ�O�o�◷�s�Ȃǂ����̉��݂���A�N�e�B�u��GW�ƂȂ肻���v�Ƃ݂Ă���B
|
���V�^�R���i�ɑ���ӎ��̕ω��Ɋւ��钲���@5/4
�I���䒬�헪��������4��28���A�V�^�R���i�ɑ���ӎ��̕ω��Ɋւ��钲���̌��ʂ\�����B
�V�Y�Ƃɒ��킷���Ƃɑ��Đ�����X�N�}�l�W�����g�̃T�|�[�g�ȂǁA�p�u���b�N�A�t�F�A�[�Y�̈�ő����I�ȃR���T���e�B���O���s���I���䒬�헪������������Ђ́A����2����x�A�����W�̃g�s�b�N�𒆐S�Ƃ���Web������1000�l�ɍs���Ă��܂��B
�������̔w�i
���{���V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ً}���Ԑ錾�����߂Ĕ��߂��Ă���4��7����2�N�ɂȂ�܂����B�I�~�N�������̊������g�債���u��6�g�v�̓s�[�N���z���A�܂h�~���d�_�[�u��3��21���ɉ�������܂����B�����Ґ������~�܂�̌X����������Ȃ��A�ً}���Ԑ錾�̂Ȃ���^�A�x��3�N�Ԃ�Ɏn�܂�܂��B����͐V�^�R���i�ɑ���ӎ��̕ω��ɂ���4�����{�ɒ������s���܂����B
���������ʃT�}��
• ����2�N�Ԃ̐��{�̐V�^�R���i��ɂ��āA�x�������30.3���A�x�����Ȃ���37.1���A�킩��Ȃ���32.6���B
• 3��ڂ̃��N�`���ڎ�����l�͑S�̂�41.3���B4��ڐڎ�̈ӌ������Ƃ���A�S�̂�66.8������Ɖ����B�N��ʂŌ����60��ȏ��8�����Ă���B
• �܂h�~���d�_�[�u����������Ă���A�O�H��O�o����@��������l��15.2���A�ς��Ȃ��l��79.7���A�������l��5.1���B
• ��^�A�x���ɁA1���ȏ�̗��s�̗\�肪����l��8.1���A�\�肪�Ȃ��l��83.0���B���A��Ől���W�܂�₷���ꏊ�ɂł�����\�肪����l��10.3���A�\�肪�Ȃ��l��80.1���������B
• �g�߂Ȑl�̊������������Ɗ����Ă���l��37.6���B���̂����A�q�ǂ����ʂ��c�t����ۈ牀�A�w�Z�Ȃǂ̋��猻��ő����Ă���Ɗ����Ă���l����ԑ��������B
• ���ĂȂ�106�̍���n�悩��̓������ۂ̉����A�u�C�x���g���N���N���v�̌����A�����ǖ@��̈ʒu�Â����u2�ޑ����v����u5�ޑ����v�Ɉ��������鎿��Ɋւ��ẮA�����}�x���w�͎^���������A�������͎^�h�R�����A�����^�}�ł������}�x���w�ł͔��ȂǕ]�����Ȃ��l�����������B�N��ʂɌ���ƁA70��ȏ�ŏ�L3���x������l�́A���̔N��ɔ�ז��炩�ɒႩ�����B�����ɂ��d�lj��̃��X�N���������Ƃ��\��Ă���Ƃ�����B |
���u�ψي��Ή��^�v�֕ύX�����@���N�`�����ʂɊ��ҁ\�ā@5/4
�V�^�R���i�E�C���X���N�`�����߂���A�ē��ǂ��ψي��ɑΉ��������g�ɕύX���邩���������Ă���B���̃��N�`���͕ψي��u�I�~�N�������v�ւ̗L�����������邽�߂��B�u�ψي��Ή��^�v�̊J�����i�߂A�N���ɂ���ւ����n�܂�\��������B
�č��ł̓I�~�N�������̕ʌn���u�a�`�D2�v�������̖�7�����߂�B�����͂������Ƃ���A�ĐH�i���i��(�e�c�`)�́u���̃��N�`���͂a�`�D2�ɂ��܂�K���Ă��Ȃ��v�Ǝw�E���Ă���B
�����A���s�̃��N�`�����lj��ڎ�ŕψي��ɂ��d�lj���h�����ʂ����܂邽�߁A�č��ł�50�Έȏ�ȂLjꕔ�Ώێ҂�4��ڐڎ�����{�B���Ƃ̊Ԃł́A�~�̊����Ċg����x�����A���H��4��ڂ̑Ώێ҂��L����ׂ����Ƃ̈ӌ����o�Ă���B
4��ڐڎ탏�N�`���Ƃ��ėL�͎�����Ă���̂��u�I�~�N�������Ή��^�v���B�ăt�@�C�U�[��1���A�Տ�����(����)���n�߁A���ʂ͋߂����炩�ɂȂ錩�ʂ��B�ă��f���i�����s���N�`���Ƒg�ݍ��킹���V���N�`�����J�����Ă���A�����Łu���D�ꂽ�Ɖu����������ꂽ�v�ƕ����B
�ψي��Ή��^�Ɋ��҂����܂钆�A���Ƃł���e�c�`�̎���ψ����6���A���N�`����ύX���邩�ɂ��ĐR�c���錩�ʂ��B
�ڎ�p�x�������ۑ�ɂȂ肻�����B�lj��ڎ�̊Ԋu�̓t�@�C�U�[���ȂǂōŒZ4�J���ƒZ���B���Ƃ́u�����\�łȂ��v�Ǝ咣���Ă���A�e�c�`�͐ڎ�Ԋu���L���邱�Ƃ�����ɓ����B
�R���i���s�̒������ɔ����A�����̓C���t���G���U���N�`���̂悤�ɁA���N�̗��s����\�������N�`���̒��g��ς���\��������B�����R���i�E�C���X�͕ψكp�^�[�����\�����ɂ����A�v���ȑΉ��͗e�Ղł͂Ȃ��B
|
���Ăb�c�b�u�I�~�N�������̉��ʕψي��A�j���[���[�N�Ȃ�14�B�Ŋm�F�v�@5/4
�Ď��a�Ǘ��\�h�Z���^�[(�b�c�b)���I�~�N������(�a�`�D1)�̉��ʕψي��̂a�`�D4�Ƃa�`�D5���č���14�B�Ŋm�F���ꂽ�Ɩ��炩�ɂ����B
�Ď��t�H�[�`������3���̕ɂ��ƁA�b�c�b�͂a�`�D4�̊�������̓J���t�H���j�A�B�A���[���B�A�}�T�`���[�Z�b�c�B�A�j���[�n���v�V���[�B�A�j���[���[�N�B�A�I�n�C�I�B�A�y���V���o�j�A�B�A�e�L�T�X�B�ȂǂŁA�a�`�D5�̓J���t�H���j�A�B�A�C���m�C�B�A�~�V�K���B�A�~�Y�[���B�A�m�[�X�J�����C�i�B�A�I�N���z�}�B�Ȃǂł��ꂼ�ꌻ�ꂽ�Ɩ��炩�ɂ����B�R�����h��w�̃t�B�[�r�[�E���X�g���ŋ����́u���������g�U��(2�̕ψي���)���łɕđS��ɑ��݂��Ă���\�������邱�Ƃ��Ӗ�����v�ƕ]�������B
��A�t���J�ōL�����Ă���a�`�D4�Ƃa�`�D5�͊����͂ƖƉu���͂������A��5�g�����O�����B��A�t���J�����ǑΉ��v�V�Z���^�[(�b�d�q�h)�̃g�D�[���I�E�f�E�I���x�C���ǒ��ɂ��ƁA�ŋߓ�A�t���J�Ŕ��������V�K�����҂�70�����a�`�D4�Ƃa�`�D5�̊����Ɛ��肳���B�挎���߂�1��1000�l�䂾����1�������҂͂���3���Ԃŕ���4000�l�����B�V�^�R���i�E�C���X�팱�҂̂����z���̊�����3��4�D5������ŋ߂ł�22���ɏ㏸�����B
�I���x�C���ǒ��́u�ߋ��̊����ƃ��N�`���ڎ�Ől����90�����Ɖu�͂��������Ɛ��肳����A�t���J�ła�`�D4�Ƃa�`�D5���g�U������猩��Ƃa�`�D2��芴���͂������Ƃ݂���v�Ƙb�����B�a�`�D2�͊����̃I�~�N������(�a�`�D1)��芴���͂�30���ȏ㍂�����̂Ɛ��肳���B
�u���[���o�[�O�ɂ��Ɠ�A�t���J�̃A�t���J�ی������������N�`���ڎ�����I�~�N�������Ɋ�������24�l�̌��t�T���v�����a�`�D4�Ƃa�`�D5�ɂ��炵�����ʁA���a�R�̐��Y�ʂ���8����1�Ɍ��������B���N�`���ڎ������15�l�ɓ��������������Ƃ���R�̐��Y�ʂ�3����1�Ɍ������B
|
���V�K������4��9064�l�@�ϏB�E���z��`�͗�������r�U�Ȃ������\�@5/4
�����h�u���{���ɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�4���ߑO0���܂łɐV����4��9064�l���m�F����܂����B�V���Ȋ����Ґ��͐挎21������14���A����10���l�������A�͂�����Ƃ���������ɂ���܂��B
�����ЊQ���S���{���̑S�C�`����(�`�����E�w�`����)��2�����́A4���ߑO�̉�c�ŁA�u�����ҁA�d�NJ��ҁA���Ґ�����������肵�����ێ����Ă���v�Ƌ������A�u���{�͓���̓����ɍ��킹�Ēn��o�ϊ������[�u�����{�������ŁA�����Ċg��̉\���ɂ������Ă����v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A��������ϏB(�`�F�W��)��`�ƍ]����(�J���E�H���h)�����z(��������)��`�����������O���l�ɑ��A�����\�h�K�C�_���X�̏���Ȃǂ������Ƀr�U�Ȃ�������F�߂�Ƃ������Ƃł��B
���{�͐挎�A���N�`���ڎ���I�����C�O����̓����҂ɑ���u���Ə��[�u�����{���Ă���A�����r�U�Ȃ��������F�߂���A�C�O����̗��s�҂������A�ό��s��Ɋ��C�𐁂����ނ��Ƃ��ł���Ɗ��҂���Ă��܂��B
����A����܂ŃI�~�N�������̕ψٌ^6��ނ��m�F����Ă��܂����A���{�͈�`�q���͂̋�����X�N�]���Ȃǂɂ��A�V�����ψي��̊����g��ɔ����Ă������j�ł��B�@ |
�������s �V�^�R���i 6�l���S 2999�l�����m�F �O�T��3053�l�� �@5/4
�����s����4���̊����m�F��1�T�ԑO�̐��j����肨�悻3000�l���Ȃ�2999�l�ł����B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ6�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��4���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���2999�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j�����3053�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�23���A���ł��B4���܂ł�7���ԕ��ς�3455.1�l�ŁA�O�̏T��65.9���ł����B4���m�F���ꂽ2999�l��N��ʂɌ���ƁA30�オ�ł������A�S�̂�20.7���ɂ�����620�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�217�l�ŁA�S�̂�7.2���ł��B�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A4�����_��10�l��3������1�l����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ60�ォ��90��̒j�����킹��6�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
���S���R���i������2���l6469�l ��T����2���l�߂�����@5/4
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA4���A�S���ŐV����2��6000�l���銴�������\����܂����B
�����s��4���A�V����2999�l�̊����\���܂����B��T���j������3000�l���܂茸��A23���A���őO�̏T�������܂����B����7���ԕ��ςł݂��V�K�����҂͂��悻3455�l�ŁA1�T�ԑO��65.9%�ƌ����X���������Ă��܂��B
�s���{���ʂ̊����Ґ��ł��B�����Ɏ����ő��������͖̂k�C���A�_�ސ�A�����A���A�ƂȂ��Ă��܂��B�S���ł͂��킹��2��6469�l�ŁA��T���j���Ɣ�ׂ��悻2���l���Ȃ��Ȃ�܂����B
�S���́u�d�ǎҁv��174�l�ŁA�V���Ȏ��҂�20�l���\����܂����B
|
 |
������̃R���i1201�l�@�d�Ǖa���g�p��2���@���s�����x���@5/5
���ꌧ��4���A10�Ζ�������90���1201�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�d�ǎҗp�a���̎g�p��(���)��20���ɏ㏸���A���̎w�W��3��2���ȗ�2�J���Ԃ�ƂȂ�u�������s���v���x���ɒB�����B
4���ɉ���n�����~�J���肵�A���̒S���҂͉����ʼn߂����@������邱�Ƃ��\�z�����Ƃ��u����҂̎���ɍs������A��H�����肷�邱�Ƃ͍T���Ăق����B����ʼn߂����ۂ��}�X�N�⊷�C�ȂNJ�{�I�Ȋ�����ɋC�����Ăق����v�ƁA�A�x���̍s���ɒ��ӂ��Ăъ|�����B
�V�K�����҂̔N��ʓ����10�オ238�l�ōł������A10�Ζ�����204�l�A30�A40�オ����182�l�Ƒ������B
�V�K�����҂͑O�T���j�����418�l�����������A��^�A�x���ŋx�݂̈�Ë@�ւ⌟���ꂪ����e��������A���������̔c��������Ȃ��Ă���B���̏�ԓ֊����Ǒ����ے��́u�����g��͑����Ă���Ƃ݂��ق��������v�Ǝw�E�����B
�V�K�o�b�q�����̗z������19�E2���Ə㏸�X���������Ă���B
�h���×{�{�݂ɂ�����×{�Ґ���634�l�ƂȂ�ߋ��ő����X�V�����B��Ԏ��́A�h���×{�{�݂�1230�����m�ۂ��Ă���u���̂Ƃ��댧�ŏ������Ă���{�݂Ɋ�]�҂͓���Ă���v�Ƃ����B
�ČR�W�͐V����165�l�̊��������ꂽ�B��n�ʂł͉Î�[��n���ł�����48�l�A�L�����v�E�t�H�X�^�[��47�l�Ȃǂ������B3������40�l�ɂ��Ă��A��n�ʂ̓��đ��������A�L�����v�E�t�H�X�^�[��15�l�ƍł����������B
|
���}������I�~�N�������̌��NJ��҂����@�Ǐ�"���邳"�@5/5
5��3�����_�ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ������������̗z���Ґ��͖�793���l�B���̈���ŁA�R���i���҂̑����ɂ���č���������Ă���ƍl������̂��u�R���i���ǁv���B��r�I�Ǐy���Ƃ����Ă���I�~�N�������ł��A���ǂɂȂ�ƑS�g�̂���ӊ��⓪�ɂȂǂŊw�Z��E��ɍs���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��l���吨����B����A�R���i���ǂɑ���m�����ꂽ���Ö@���Ȃ����ŁA��̌���T���Ì���̎������ނ����B
���R���i���ǂɔY�ށh�N����ꂸ�h�w�Z�Ɂw�s���������Ǎs���Ȃ��x
�����E�a�J��ɂ���R���i���ǂ̐��O���u�q���n�^�N���j�b�N�v�B���܁A���{�ōł��Z�����N���j�b�N�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
(�����@��)�u���܈�ԍ����Ă��邱�Ƃ͉�������܂����H�v
(�`����)�u�w�Z�ɍs���Ȃ��A�Q���Ⴄ�ƋN�����Ȃ�����B�ߌキ�炢����͏�������ӊ��v
���w2�N���̂`����(14)�͍��N2���ɃI�~�N�������Ɋ����B���M��̂ǂ̒ɂ݂ȂǁA�Ǐ�͌y�������Ƃ����B�������c
(�R���i���NJ��҂̂`����)�u(�×{��������)2�A3�T�Ԃ͑��v��������ł����ǁA���̌�ɂ���ӊ��Ȃǂ̏Ǐo�n�߂܂����B�������Ԃ����̂����������Ȃ��āA���ǂ��o�n�߂Ă���16���ԁ`17���ԂƂ��ɂ̂тāB(�p���܂܂Œ����ԐQ�邱�Ƃ́H)�S�R�Ȃ������ł��v
�������̏Ǐ�͌y�������Ƃ������A����ӊ��Ȃnj��ǂ̉e����1��17���Ԃ������������A�w�Z�ɒʂ��Ȃ��������Ă���B
(�����@��)�u�w�Z�ɍs���Ȃ��̂��w���x�ƊԈႦ��l�������ł���B�w���a����Ȃ��́H�x�݂����Ȃ��Ƃ��������ł����A�s���������Ǎs���Ȃ��̂����̕a�C�Ȃ�ł���ˁv
�`����̐g�̂ŋN����u�R���i���ǁv�B�����Ɋm�����ꂽ���Ö@�͂Ȃ��B
(�`����̕�e)�u��������1��o�āA��������獡�x�͖���Ȃ��Ȃ�������āv
(�����@��)�u�����̊������o�����̂͏������B������̖�͌����܂����H�v
(�`����)�u����܂�킩��Ȃ��v
�`����̂悤�Ȋ��҂͍��N�ɓ���A�I�~�N�������̊����g��ŋ}�����Ă���B���N1���ɃI�~�N�������Ɋ��������a������A�`����Ɠ����Ǐ�ɔY�܂���Ă����B
(�R���i���NJ��҂̂a����)�u�N���オ��Ȃ������ł��ˁB�ጌ���Ȃ̂��ȂƎv���ĊÂ����̂Ƃ����H�ׂĂ݂���ł����ǁA������ƈႢ�܂����B�ǂ��Ȃ�Ȃ������ł��B���E�͂���������Ɛ�ɂȂ肻���ł����H�v
�a�����2����{����d�����x�E���Ă��邪�A�R���i���ǂ͂Ȃ��Ȃ�����������ꂸ�A�E�ꂩ��͑������A����悤�Ɍ����Ă���Ƃ����B
(�a����)�u�ŏ��Ɏ�f�����Ƃ����͂����Ԋy�ɂȂ��āB���̂܂d���𑱂��Ă�����ǂ��Ȃ��Ă������낤�v
(�����@��)�u��ΐQ������ł���v
(�a����)�u����ȋC�����܂��v
(�����@��)�u�w�悭�Ȃ�������܂��������Ⴆ�x�Ɠ����Ĉ������ĂƂ����̂��J��Ԃ��āA�Q������ɂȂ��Ă���l����R����̂ŁB���̂��Ƃ��S�R�m���Ă��Ȃ��Ƃ����̂��傫�Ȗ��Ȃ�ł���ˁv
��������[��4���܂őS���̊��҂�f�@����g���ǐ��O���h
�u�q���n�^�N���j�b�N�v�ł́A��������1��100�l�߂��̃R���i���NJ��҂�f�@���Ă���B���̓��̐f�@�́A�ߑO10���`�����̌ߑO4���܂ŁB���҂̐f�@�𑱂��Ă������ߒ��H�͌ߌ�11���B����ɁA�f�@�͑����B
(�����@��)�u(�p�[��܂Őf�@����̂́H)���҂����Ă���̂ɐf��Ȃ��Ƃ����̂͐h���ł���ˁB��������邾���̂��Ƃ͂�낤�Ǝv���Ă��܂��ˁB(�f�@��)���f�肵���l��������ɖS���Ȃ��Ă��܂����Ƃ������Ƃ������ɂ������̂ŁB���Ԃ�A���E�Ȃ�ł����ǁB���3���A4���܂ł���ĐQ�܂ʼn������āA��5���ɋA���ĕ��C���������Ă܂��o�Ă���݂����ȁB�������������������Ԃ����Ƃ��Ă��܂��ˁv
�ߑO2�������B����Ȃ��X�E�a�J���l�͂܂�Ɂc�B�ҍ����ɂ������NJ��҂͂��Ȃ��Ȃ����B�������A�܂��f�@�͏I���Ȃ��B
�@�@�@�������@�����I�����C���ŃR���i���NJ��҂�f�Â��Ă���l�q
(�����@��)�u�n���̕a�@�ɍs�����Ƃ��́H�v
(���NJ���)�u�n���̕a�@�͓��ɉ������Ă���邱�Ƃ͂Ȃ��B�w���ǂł��R���i�ɂ����Ȃ�����x�݂����Ȋ����Ō����āv
�d�b�Řb���Ă����̂́A���s�{���ɏZ�ރR���i���ǂ̏�������(30��)�B�n���̕a�@�ł͐f�Ă��炦�Ȃ��S���̊��҂����ɃI�����C���f�Â��s���Ă���̂��B
(���s�{���̃R���i���NJ���)�u��ɉ���������Ă��銴���ŁA�ŏ��͂��������������ł��v
�����͍��N2���ɃI�~�N�������Ɋ����B���ǂňꎞ�A�Q������ɋ߂���ԂɂȂ��Ă����B
�@�@�@�������@�����I�����C���ŃR���i���NJ��҂�f�Â��Ă���l�q
(�����@��)�u�Q������ɋ߂���Ԃ���������ˁB�܂��ʋΗ��K�͂��Ă��Ȃ��ł����H�v
(���NJ���)�u���v�ł����A�s���͍̂s���܂����B����ǂ����Ȃ�Ȃ������̂Łv
���w�I�~�N�������͌��ǂ̒i�K�ɂȂ�Ɣ��ɂ����x
���NJ��҂ƌ��������Ă���2�N�ԁB�����@���͏Ǐ�̌��𑱂��Ă����B����܂Őf�@�����I�~�N�������̌��NJ���305�l�̂����A94��������ӊ���i���A85�����v�l�͂̒ቺ�A�P�Ȃǂ̏Ǐ��68���ɂ݂�ꂽ�B
(�����@��)�u�w�I�~�N�����͌y���x�Ƃ݂�ȂɌ������ł����ǁA���ۂɌ��ǂ̒i�K�ɂȂ��Ă��܂��ƁA���܂܂łƓ����悤�ɐh���A���ɂ����B�P�ɂ��Ă̓I�~�N�������ǂ̕��������ł��ˁv
�����������Ƌ��Ɂg���鎡�Ö@�h��7���߂��Ɍ��ʂ��������Ƃ����B
(�����@��)�u�w������C�ߗÖ@�x������܂�����Ȃ��Ƃ����̂͒E�т����Ȃ�ł��ˁB���Ƃ͑S���̏Ǐ�Ɍ����\���������ł��v
�u������C�ߗÖ@�v�Ƃ́A�@�o�̉��ɂ��������ɖ�t��t�����Ȗ_�Ȃǂ��C����ĉ��ǂ�}���鎡�Â��B����ɂ��A���ɂ�ڂ܂������P����Ƃ݂��Ă���B
(�����@��)�u�]�̈�ԋ߂��Ƃ���̉��ǂ����Ƃ������ƂȂ�ł���B��������Ȃ��Ǝ���Ȃ��ł��ˁB�ŏ������@�̉����O���O������̂Œɂ���ł����ǁA�ǂ�ǂ�y�ɂȂ��Ă����܂�����v
�����Ö@��͍��������"�R���i���NJO��"
�R���i���ǂ̐��O�����s���a�@�͊��ɂ�����B���́u�k��a�@�v�ł͌��NJO���̗\���1�N��܂Ŗ��܂��Ă���B
(���N2���ɃI�~�N�������Ɋ��������R���i���NJ���)�u������ƕ����ċA���Ă��邾���ő���݂����Ȃ̂����Ă���ǂ��Ȃ��������̂ŁB���ꂩ��܂��Ƃ���o���Ȃ��Ȃ��āv
(�ۖё���t)�u�����ƂȂ��Ă���ЂƂˁA���ꂩ�ȂƎv���̂����t�̃z�������ł��ˁB���̐��l�����ɒႢ�ł��B�w���t�s�S�x�Ƃ�����Ԃł��ˁB����ł��邢�̂��ȂƎv���܂��v
�u�k��a�@�v�̊ۖё���t���A�R���i���ǂ̎��Ö@��Ώ��@��T���Ă���1�l���B���L�̂���ӊ��͊������̎��ÂŎg��ꂽ��̉e���ŁA�u���t�s�S�v���N�����Ă���P�[�X������Ƃ݂Ă���B
(�ۖё���t)�u�w��[���Áx�Ƃ����āA�z�������̕�[���n�߂悤���ȂƎv���Ă��܂��v
�R���i���ǂ����������t�͑����͂Ȃ��B���N4���ɋ��s�Ŋw�p�u����J�Â���A�ۖш�t�̗Տ��f�[�^�̔��\�ɑ����̈�t�炪���ڂ��Ă����B
(�ۖё���t)�u�ӊO�Ƒ����͕̂��t�s�S�ł��B����ӊ��ŗ����畛�t�s�S�Ŏ�ɚk�o��Q�ɑ���_�@�X�e���C�h������������ܐ��̕��t�s�S�̕��������ł��B(�p���ǂ������Ă���l�Ƀ��N�`���ڎ�����߂�ׂ��H)���N�`���ڎ��6�����悭�Ȃ���2���������Ȃ����Ƃ����f�[�^�������āA�����߂��邩�ǂ����́A�w���������f�[�^�ł��B���X�N������܂�����ǂ��A�ǂ����܂��傤���H�x�Ƃ����`�ő��k���Č��߂Ă��܂��v
�R���i�Ђł����������������̏�͂قƂ�ǂȂ������Ƃ������A�R���i���ǂ̎��Â͏������m������悤�Ƃ��Ă���B
��1�N�ȏ㑱���u����ӊ��v�ŋx�E���̊��ҁw�E�ꂩ��̈��͂��x
����܂Ŏ�ޔǂ�1�N�ȏ�ɘj���Ă��̕a�C�̎�ނ𑱂��Ă����B���N�o������b����(40��)�́A1�N�ȏク��ӊ��������Ă��āA���܂��x�E�������Ă���B
(�R���i���NJ��҂̂b����)�u�w(�E�ꂩ��)���߂�x�݂����Ȉ��͂�����܂����A�߂��Ă��N�r�ɂȂ�낤�ȂƁB���ǂ��c�����܂܂ʼnʂ����čďA�E�ł���̂��낤���A���ɖ߂��낤���Ƃ����s�������Ȃ��ł��v
�R���i���ǂ̊��҂͂��̏Ǐ��ł͂Ȃ��A���̗͂����������Ȃ��Ƃ�����d�̋ꂵ�݂̒��ɒu����Ă���B
|
���ďB�R���i�����A�O�T��12.7�����@�k�Ă̑�����5�T�A�����o�`�g�n�@5/5
���E�ی��@��(�v�g�n)�̕ďB�����ǂł���ĕĕی��@�\(�o�`�g�n)��4���A�ďB�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ґ����O�T��12�D7�����������Ɣ��\�����B���ĂƖk�ĂŊ����҂̑����������Ă���B
�ďB�ł͐�T�A�V����61��6000�l�ȏ�̐V�K���҂����ꂽ���A���҂͓���1������4200�l�������B
�k�Ă̊����Ґ���19�D5�����ŁA5�T�A���̑����B�J�i�_�ƃ��L�V�R�Ō����������A�č���27�D1�����������B
�o�`�g�n�̃G�e�B�G���k�����ǒ��͋L�҉�ŁA�u���܂�ɂ������̍��Ŋ����Ґ�����@���Ґ����������Ă���B����������ׂ����v�ƌĂъ|�����B�@ |
 |
���ό��n�u���C���߂��_�@�Ɂv�@�K���q�����Ɋ��ҁ@5/6
���{���V�^�R���i�E�C���X�̐��ۑ���ɘa���A�O���l�ό��q�̎�����ĊJ��������ƂȂ����B�u���C�����߂����������ɂȂ�v�B�R���i�Ђɋꂵ�ފό��n�́A�C���o�E���h(�K���q)���v�̕����ɂ��o�ό��ʂɊ��҂����B
�R���i�БO�͑����̊O���l�ό��q�łɂ�����������E�B�u3���ɂ܂h�~���d�_�[�u����������A�l�ʂ肪�����������Ă������A�ȑO�ɂ͂܂������v�Ƙb���̂́A���ɑ����������ʂ�ɓX���\����P�̔��u�I�J�_���v�X���̋e�n�m�q����(77)�B�u�O���l�ό��q�����āA�ʂ�Ɋ��C���߂��Ă����v�Ɗ�����B
|
�����q�A�Ԏ�1775���~�����q�x��\22�N3�����@5/6
���{�q��6�����\����2022�N3�����A�����Z(���ۉ�v�)�́A�����v��1775���~�̐Ԏ�(�O����2866���~�̐Ԏ�)�������B���ې��ݕ����D���Ŕ��㍂�͑O����41�D9�����������̂́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�J��Ԃ���č������A���ې��͋q���̉��x�ꂽ�B�`�m�`�z�[���f�B���O�X(�g�c)�ƂƂ��ɁA�q����2�Ђ͂������2�N�A���̐Ԏ��Ɋׂ����B�@
23�N3�����́A���ЂƂ�3�N�Ԃ�̍����]���������ށB���q�͔N�Ԃ̗��q���v���R���i�БO��19�N�x�ɔ�ׂč�������90���A���ې���45�����x�ɖ߂�Ƒz��B�����v��450���~�Ɨ\�z�����B�`�m�`�g�c�������v��210���~�̌��ʂ��B���㍂�͍��ې��ݕ��̍D�����ǂ����ɁA���q���O����2�{�ɁA�`�m�`�g�c��6�����ƁA�啝�ȉ��P��������ł���B
�����A���V�A�̃E�N���C�i�N�U�Ȃǂɔ����������i�̍�����R���i�̊��������ȂǁA��s���̕s�������͐@���Ȃ��B�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�Ȃǂɂ��A���q��22�N3�����̗��q�����́A�������Ōv�����600���~���x�A���ې��ł͕S���\���~��������B
���q�̐ԍ�S��В��͋L�҉�ŁA�u��N�̂悤��(���v��)�傫�Ȕg��ł̂ł͂Ȃ��A�͋������Ă����v�Ƃ̌�������������A�������A���ې��Ƃ�25�N�x�܂łɃR���i�БO�̎��v�����ɂ͖߂�Ȃ��Ƃ��w�E�B�Ɛщ��P�Ɍ����Ĕ�q�ƂȂǂ̐�������ɗ͂�����ƂƂ��ɁA�R���i�ЂŖc��L���q���̕ԍς�i�߂�B
|
��3���̐_�˒n��S�ݓX�̔��㍂�A2�J���Ԃ�v���X�@�ߗ��i���D���@5/6
���{�S�ݓX����܂Ƃ߂�3���̐_�˒n��S�ݓX���㍂�́A�O�N������1�E3������101��6300���~�ŁA2�J���Ԃ�Ƀv���X�ɓ]�����B�V�^�R���i�E�C���X�Ђɔ����u�܂h�~���d�_�[�u�v���������{�ɉ�������A���X�q����0�E6�����B�C���̏㏸�Ȃǂ��Ĉߗ��i��13�E2�����ƐL�т��B
|
�������s��2681�l�����m�F�@�O�T���1212�l���@25���A���őO�T�����@5/6
�����s�ŁA6���A�V����2681�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă������Ƃ����������B�O�̏T�̋��j��(3893�l)���1212�l�������B1���̊����Ґ��Ƃ��Ă�25���A���őO�̏T�̓����j������������B
�S�[���f���E�B�[�N�ɓ����Ă���̊����҂̌����X���ɂ��āA���r�m���́A���傤�̋L�҉�ŁA�x���ɂ��A��Ë@�ւȂǂ��x�f�ƂȂ��Ă���e���ŁA�����҂̕����̂����Ȃ��Ȃ��Ă���\��������Ƃ̌������������B���̂��ߘA�x�����̃��o�E���h�����O����Ă���Ƃ����B
6���̊����Ґ���N��ʂɌ���ƁA10�Ζ�����259�l�A10�オ327�l�A20�オ633�l�A30�オ504�l�A40�オ485�l�A50�オ234�l�A65�Έȏオ173�l�ȂǂƂȂ��Ă���B
�܂��A�����҂̂����V����5�l�̎��S�����ꂽ�B6�����_�ŁA�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҐ���28�l�ŁA����ɑΉ������a���g�p����3.5���������B���ґS�̂ɑ���a���g�p����16.2���ƂȂ��Ă���B
|
���R���i�u�a�`�E2�v�����A�s����95�����Ɂ@5/6
�����s��6���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ɋւ�����Ƃ̕��͎��������\�����B�����̎�̂��I�~�N�������̎嗬�n���u�a�`�E1�v����A��芴���͂������Ƃ����h���n���u�a�`�E2�v�ɂقڒu�������A�S�̂�95�������B
�ψي��ɑΉ������s�Ǝ��̂o�b�q�����̌��ʁA�a�`�E2�����̋^�������4��19�`25���ɑS�̂�95�E2���ɏ�����B3����5���A4����{����ɂ�8�����Ă����B
����ŁA�����Ґ����̂��̂͌����X���������A����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ��͍���4�����_��3344�E1�l�ƁA4��27�����_��5094�E7�l��傫����������B4�����{��2�������a���g�p��������4�����_�ł�16�E8���ɉ��P�����B
3��ڂ̃��N�`���ڎ��1�����݁A�s���S�̂�53�E2���������������A�N��ʂł�20�オ3����ɂƂǂ܂��Ă���B���r�S���q�m����6���̋L�҉�ŁA�u���g�Ƒ�Ȑl�����A���S�ȎЉ�����邽�߂ɁA���Аڎ�����肢����v�Əq�ׁA�����̃��N�`���ڎ���d�˂ČĂъ|�����B
|
�����{�ŐV����1465�l�R���i�����c1�T�ԑO����1154�l���@5/6
���{��6���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1465�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j������1154�l�������B���҂�1�l�������B
|
������A�R���i��1�l���S�@�V�K������1398�l�@5/6
���ꌧ��6���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������1�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�v���Ґ���448�l�ƂȂ����B�܂��A�V����1398�l�����������Ɣ��\�����B��T�̋��j��(4��29��)��1585�l�ɔ�ׂ�187�l�������B�v�����҂�16��8987�l�ƂȂ����B�V����2��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�z���Ґ���5�����_��610.39�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ����k�C����282.21�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����40.9��(���@�Ґ�258�^�a����631)�ŁA�d�ǎҗp��25.0��(���@15�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W��157�l�������B
|
���S���̐V�K���� 2��1628�l�@�d�ǎ҂�10���A��200�l�����@5/6
6���A�S���ł�2��1,628�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�B
�����s���ł́A�V����2,681�l�̊������m�F����A��T�̋��j������1,212�l����A25���A���őO�̏T�̓����j������������B�S���Ȃ����l��5�l�������B�I�~�N�������̓������ӂ܂����w�W�ɂ��d�ǎ҂�31�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����3.9���ƂȂ��Ă���B
���̂ق��A�k�C����1,668�l�A���{��1,465�l�A���ꌧ��1,398�l�ȂǁA�S���ł�2��1,628�l�̊����ƁA37�l�̎��S���m�F����Ă���B����A5�����_�ł̑S���̏d�ǎ҂�170�l�ŁA�O�̓�����4�l�������B�S���̏d�ǎҐ��́A10���A����200�l��������Ă���B |
���R���i�V�K������ �S�s���{���Ō��� �g�A�x��̐��ڂɒ��ӂ��h �@5/6
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA��^�A�x���Ō����̐������Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����A���ׂĂ̓s���{���őO�̏T��菭�Ȃ��Ȃ�܂����B���Ƃ́u�A�x�̂��ƁA�����Ґ����ǂ̂悤�ɐ��ڂ��邩���Ӑ[�����Ă����Ȃ�������Ȃ��v�Ǝw�E���Ă��܂��B
�S���ł́A�挎7���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�ɔ�ׂ�1.04�{�A�挎14����1.06�{�Ƒ����������Ă��܂����B�������A�挎21����0.85�{�A�挎28����0.94�{�A����5���܂łł�0.67�{��3�T�A���Ō������A1��������̕��ς̐V�K�����Ґ��͂��悻2��6489�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��^�A�x���Ō����̐������Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����A�����Ґ��͑�^�A�x���O�̐�T�܂ő������Ă����k�C�����B�̈ꕔ�Ȃǂ��܂߁A47�̓s���{�����ׂĂőO�̏T��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�����Ɓu�������������A�A�x��̊����Ґ��𒍎��v
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�œ��M��w�̊ړc�ꔎ�����́A���ׂĂ̓s���{���ŐV�K�����Ґ����O�̏T��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃɂ��āu�����͏����ɉ������Ă���悤�Ɍ����邪�A��^�A�x�Ō����̐����������A�ߏ��]�����Ă���\��������B�A�x�̂��ƁA���T�ȍ~�A�����Ґ����ǂ̂悤�ɐ��ڂ��邩���Ӑ[�����Ă����Ȃ�������Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B
���̂����Łu��^�A�x�Ŋό��n�ɍs���Ēn��Ŋ������L���邱�Ƃ��N���Ă����������Ȃ������A�s�s���ɖ߂��Ă������ƁA�V���Ȋ����̉Ύ�ɂȂ�\��������B���T�ȍ~�������̑̒��̕ω�����������ώ@���ď����ł������������Ƃ�����A���ߑ��߂Ɉ�Ë@�ւ���f������A���������肷��Ȃǂ̑Ή����K�v�ɂȂ��Ă���v�Ƙb���Ă��܂��B
����ɁA����̑�̊ɘa�ɂ��Ắu��^�A�x�ő����̐l�������āA���s��A�Ȃ��y���߂�ɂ܂łȂ��Ă��Ă���B���ꂾ���l�̓��������钆�łǂ�����Ί����Ґ��𑝂��Ȃ��悤�ɂł��邩���ɂ߂������ŁA�ǂ̂悤�ȑ�̊ɘa�����Ă������l���Ă������Ƃ��厖���B���͂܂����ӂ��Ȃ���i�K�I�ɏ�������������ɘa���Ă����Ή����K�v���Ǝv���v�Ƙb���Ă��܂��B
|
�������̃[���R���i����ɓ��O����ᔻ�|�����̉\���Ⴂ�Ƃ̌������@5/6
�����͐V�^�R���i�E�C���X�̗��s��}���邽�߁A��s�k���ł̐����[�u�����X�ɋ������A��C�ł����������b�N�_�E��(�s�s����)���p�����Ă���B�����̂��������R���i��ɂ��āA�č��̊����ǐ��Ƃ͌��ʂ��Ȃ��Ɣᔻ�����B
��C��5�����ꂽ�V�K�����Ґ���4651�l�B���s�̃��b�N�_�E����1�J���]��ɋy��ł��邪�A����V�K�����Ґ���3���A���Ń[���ɂȂ�܂Ő����͊ɘa����Ȃ����낤�ƕ����̓��ǎ҂͌�����B
�k���̐V�K�����Ґ���50�l�ƁA12���A����2����ƂȂ����B�ăA�b�v���́u���o��������(�A�C�t�H�[��)�v��v�������_��i����͓�ȓA�B�s�͊����g���H���~�߂邽�߃��b�N�_�E�������{�B
�A�C�t�H�[���̎�����Y���s����p�̃t�H�b�N�X�R���E�e�N�m���W�[�E�O���[�v�́A�H��J���҂́u�N���[�Y�h���[�v�v�V�X�e�����ō�Ƃ��s���Ă���A�����_�ŋƖ��ւ̉e���͂Ȃ��Ƃ��Ă���B
�������ǂ͌o�ς���̎��ɋy�ڂ��e���ɂ�������炸�A�[���R���i������������Ă��邪�A���b�N�_�E���������I�ɐ�������\���͒Ⴂ�ƕč����A�����M�[�����nj�����(�m�h�`�h�c)�̃t�@�E�`�����͎w�E�B���{�͂��̎��Ԃ𗘗p���ă��X�N�̍�������ґw�̐ڎ헦�����}���Ă��炸�A���ǂ����{���Ă��郏�N�`���ڎ�͂���قnj��ʓI�ł͂Ȃ��Ɛ��������B
�o�C�f���đ哝�̂̎�Ȉ�Ìږ�߂�t�@�E�`���̓h�C�c�̃g�[�N�V���[�ŁA���b�N�_�E���͏Z���������̊����g���h�����������邽�߂Ɏg����ׂ��ŁA���b�N�_�E�������ő��ɉ������Ȃ��헪�͑t�����Ȃ��ƌ�����B
�������Y�}�@�֎��A�l������̌n�ł��������̌��ҏW���Ō��݂͉���҂߂�ӎ��i�����A�J��Ԃ����{����郍�b�N�_�E���ɂ�钆���o�ςƐ��E�ɂ����铯���̒n�ʂɑ���e���ɂ��Čx����炵���B
�ӎ��͎��g�̌����u���M(�E�B�[�`���b�g)�v�A�J�E���g��5���f�ڂ����_���ŁA�k���̓I�~�N�����ψي��Ƃ̓����̃��}����}������A�[���R���i�헪�̓R�X�g�ʂŊǗ��\�ȏꍇ�ɂ̂ݒNj����鉿�l������Ǝ咣�����B�����A���̌�A�_���͍폜���ꂽ�B
|
 |
���R���i�u��7�g�v�}���@�������Ԃɑ������K�v���@5/7
�V�^�R���i�E�C���X�Ђ��������Ō}������^�A�x�B�ً}���Ԑ錾�A�܂h�~���d�_�[�u���o�Ă��Ȃ��̂�3�N�Ԃ�ŁA���㉷��ȂǑS���̊ό��n���ɂ��킢�����߂����B
����A�V�K�����Ґ��͍��~�܂肵�A�l�o�������������ɂ��������̍Ċg�傪���O�����B���N�`���lj��ڎ�𐄐i����ƂƂ��ɁA�����̎��Ԃɑ��������łK�v������B
�����X�s�[�h�������Ƃ����I�~�N�������̔h���^�ւ̒u������肪�S���Ői�݁A�����u��7�g�v�̗}�����ۑ�ƂȂ��Ă���B�����a���g�p�����Ⴂ�����ɂ��邱�ƂȂǂ���A���{�͏d�_�[�u��K�p�����s�������͂��Ă��Ȃ��B
���Ƃ͌���ɂ��āA�����͂̋����Ƃ����g��v���ƁA���N�`���lj��ڎ�Ȃǂ̗}���v�����h�R(��������)���Ă���ƕ��͂���B�낤���o�����X�̏�ɂ���ƔF�����A��{���O�ꂵ�����B
���N�`���͎��Ԃ����Ɗ�����d�lj���h�����ʂ�������A�lj��ڎ킪�K�v�ƂȂ�B����1�����_�ŁA65�Έȏ�̍���҂�80������3��ڂ�ł��I�����B���������߂̊����҂̒��S�ł����N�w�͒�����A20��A30��͂������30���䂾�B
�I�~�N�������͏d�lj����ɂ����A��Ò̐����N��(�Ђ��ς�)���Ă��Ȃ��Ƃ������������Ƃ݂���B���������҂�������ƈ�Â̕��S�͑����B�����}���ɂ͎�N�w�̐ڎ헦���オ�d�v�ł���A�������Ȃǂ��܂߂Ē��J�Ȑ��������߂���B
���{�͍������ɂ�4��ڐڎ���n�߂�ƌ��߂��B�Ώۂ�60�Έȏ�ƁA���a�̂���l�Ȃǂɍi��A���L���N��w�ւ̐ڎ킩��]������B��s����C�O�̌������ʂ��Q�l�ɁA�d�lj��\�h����ȖړI�ɂ���Ƃ����B
�����J���Ȃ̃��N�`�����ȉ�ł́A�������X�N�̂����Ï]���҂炪�ΏۂɊ܂܂�Ȃ��������ƂɈ٘_�������o���B�ŐV�̒m���⓮���܂��A���������������ׂ����낤�B
����A���{�̃R���i�����ȉ�͘A�x��Ɋ������Ċg�債���ꍇ�A�d�_�[�u�Ȃǂ̐������s�킸�A�����҂͈�ʂ̐f�Ï��Őf��Ƃ������I�����荞����̑�̂���������������B�ݓc���Y���A6���ɑ��̐�i7�J��(�f7)���݂ɐ��ۑ���ɘa����ƕ\�������B�Љ�o�ϊ����̍ĊJ�Ɏ������ڂ��������������Ă���B
��6�g�ł͊w�Z�⍂��Ҏ{�݂������g��̎�v�ȏ�ɂȂ������A���{�͈��H�X�̉c�ƋK���𒌂Ƃ�����ς��Ă��Ȃ��B����̓s���{������͌��ʂ��^�⎋���鐺���������B�o�ς��~���ɉɂ͎��̗��s��}���邱�Ƃ��s���ł���A����܂ł̑�������A�K�v�ɉ����Č������ׂ����B
���N�`���ڎ킪�i���Ċe���͋K�����ɘa���Ă���B�����}���Ɋɘa����ƁA�Ő��̋����ψي��ւ̑Ή����x��鋰�ꂪ����B�R���i�Ƃ̋����ɂ͂܂��s�m��v�f�������A���{�͐T�d�ɂ�����肵�Ăق����B�@ |
���u�c�O�����Ǖ����܂����v�D��ꂽ�e���A�R���i�Ђ�`����\�莆�����@5/7
2�N�ȏ㑱���R���i�ЁB�X�̂��������Ŗڂɂ����̂��A������Ȃǂ��Ăт�����\�莆��f�����B���̌��t��ǂނƁA���]�L�̍ЉЂ��߂��������X�������яオ���Ă���B
�u�}�X�N�ŎU���ł��܂��I�I�v�@�����E����ɂ��闝�e���uHair�@Trip�v�́A2�N�قǑO����C���X�g����œ\�莆���o�������Ă���B���S���ė��X���Ă��炦��悤�ɂƁA�I�[�i�[�̉��c������(48)�̍Ȃ��������B���̓\�莆�����āu�����Ȃ���v�v�ƁA��A�ɂȂ������q���������Ƃ����B�ꏊ���A�I�t�B�X�X�ɒʋ���q�������������A�d���I���ɗ���q�͌���A�R���i�ЈȑO�̂悤�ɋq���͖߂��Ă��Ȃ��B����Ńe�����[�N�����������Ƃ�����A��ʁE�Y�a�ɂ���n��X�͂��q���������B�}�X�N���O���ăJ�b�g�����邨�q��������邪�A�C�ɂ��邨�q���������B���c����́u���̒��݂̂�Ȃ��݂�ȃ}�X�N���O���悤�ɂȂ�����\�莆�͂Ƃ����Ⴈ�����ȁv�Ƙb���B
�u�R���i�ЂɁ@���锒�߂Ɂ@�����_���v�@�ً}���Ԑ錾���ł̓����ܗւ��J�Â���Ă�����N7���A�����s�L����̑����n���ʂ菤�X�X�ɂ́A����Ȑ�����f������Ă����B���N3���ɕ�W���Ă��鏤�X�X�̑f�l������ō�N�A�ō��܂̓��I�ɑI�ꂽ��i���B��҂̉����K�I����(82)�́u����͐�����\�����́B��͂�R���i�ЂƂ��������̐��̒����r�v�Ƙb���B����������Ԃ̏W�܂�͊J�Âł����A��܂��`�����Ă��Ȃ��Ƃ����B
�����������ܗ֊J�Ò��A�����s�a�J��̑�X�،����ł́A���鏊�Ɂu�������l�v�u������߂āI�@No�@Drinking�v�ȂǂƏ����ꂽ���ӏ������f�����Ă����B�������̏��яr������(47)�́u�H����݂�������݂Ƃ����L�[���[�h���o�Ă��������ŁA�s�̗v��������A����ȏ㊴�����g�傳���Ȃ����ߐݒu�����v�ƐU��Ԃ�B�����ł͒ʏ�A���H���y���ނ͎̂��R�ŃA���R�[���̔̔������Ă���B����Ȓ��ŁA���l�����肢����������Ȃ��ɂȂ�A���o�ɑi����Ŕ̐ݒu�͖��炩�Ɍ��ʂ��������Ƃ����B�ً}���Ԑ錾�Ƃ܂h�~���d�_�[�u����������Ă�����N10�����ɓP�����n�߁A���͂�������Ȃ��Ȃ����B
�����s�V�h�旧�̐V�h���������łً͋}���Ԑ錾���o����邽�тɁA�傫�ȗV��̎���Ɉ͂�������A���p���ł��Ȃ��Ȃ����B��݂̂ǂ�����ۂ́u��̑S�Ă̌����̗V��œ��l�̑Ή��������킯�ł͂Ȃ��B����ǁA���ɐl�C�̗V��́A�ǂ����Ă�������ۂ�����ڐG��h�����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A���������Ή����Ƃ����v�ƐU��Ԃ�B
|
���g�s�������Ȃ��f�v�h�͂ǂ��߂������H�u���k�ցv�u���o�����v�l�X�Ȑ� �@5/7
�S�[���f���E�B�[�N���I�Ղł��B3�N�Ԃ�ɍs���������Ȃ����N�̑�^�A�x���ǂ��߂������̂��A5��7���A���̔ɉ؊X�Řb���܂����B
�吨�̐l�������s������7���̑��E�~�i�~�B���N�̃S�[���f���E�B�[�N��3�N�Ԃ�ɑS���̂ǂ��ɂ��ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���o����Ă��炸�A�X����́u�v���Ԃ�ɉ��o�������v�Ƃ�������������܂����B
�u���q�Ɠ��k6���܂��܂����v�u�ΐ쌧�ɍs�����B�ł⑷������A��āB�v���Ԃ�ɗV��ł����v�u����Ȃɉ��o�͂����A�Ԃł�����ƍs���銴���̂Ƃ���ցB(�p�R���i���S�z������H)�����ł��ˁA����������̂���������v
����A�ߋE�����̍������H��7���ߌ�5�������_�ŁA10�����ȏ�̏a�͔������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
|
��7���̓����s�̐V�K�����҂�3809�l�@26���Ԃ�ɑO�T���瑝���@5/7
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA7��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�3809�l�B�d�ǎ҂͑O���ƕς�炸�A8�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�3809�l�B�N��ʂł�20�オ�ő���827�l�A������30���738�l�A40���578�l�Ƒ����Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�256�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�2961.4�l(�ΑO�T��65.9��)�B�s���̑���(�v)��145��9374�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����15.6��(1128�l�^7229��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T4��30��(2979�l)����830�l�����A26���Ԃ�ɑO�T�̓����j�����瑝�����܂����B��T�y�j���͏j�������Ŋ����Ґ������Ȃ��o��X�����������Ƃ͂����A���T��5��3���ȗ�4���Ԃ��3000�l��ƂȂ�A�����҂̌����X���Ɏ��~�߂����������Ƃ͌�����܂���B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
�����{ �V�^�R���i 2�l���S 4192�l���� �O�T�y�j��3000�l�]�� �@5/7
���{��7���A�V����4192�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�3000�l�]�葝���܂����B���{��1���̊����҂�4000�l����̂͐挎14���ȗ��ł��B����ő��{���̊����҂̗v��91��87�l�ƂȂ�܂����B
�܂��A2�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��4967�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�6������ς�炸22�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�����ꌧ�̊����҉ߋ��ő��Ɂ@����2000�l�����@5/7
���ꌧ��7���A�����ŐV����2375�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����҂��m�F���A�ߋ��ő����X�V�����Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����Ґ���2000�l������̂͏��߂āB�ő��̍X�V��1800�l�����m�F���ꂽ�����g��u��6�g�v��1��15���ȗ��ƂȂ�B
����̒���1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���6�����_��597�l�ƁA�S���ōł������B7�����_�̃R���i�a���g�p����40.6%�B���͂܂h�~���d�_�[�u�̗v������������ڈ���60%�ƒ�߂Ă���B
���ꌧ�͍ő��X�V�̗v�����u�A�x���ɐl�Ɛl�Ƃ̐ڐG���������̂ɉ����A�A�x�����̕����������O���ɑ����̐l�������������߁v(�{���`�v�E������������)�Ƃ݂Ă���B����������Ґ��̐��ڂƓ��@���Ґ��̕ω��𒍈Ӑ[�������\�����B
|
 |
���A�T�q5�{�E�L����4�{�c�Ɩ��p��啝���Y����r�[�����A���ꂼ��̎{��@5/8
�r�[������5���ɕr�₽��Ȃǂ̋Ɩ��p�r�[����啝�ɑ��Y����B�A�T�q�r�[�����O�N������5�{�A�L�����r�[������4�{�Ƒ啝���Y�B2021�N5���͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŁA�ً}���Ԑ錾�����o����Ă������A3���ɂ܂h�~���d�_�[�u���S�ʉ����B���H�X�ł̎�ޒɐ������Ȃ��Ȃ������Ƃ�A��Ŗ@�����ɂ��r�[���̎�Ō��ł��A���v���g�債�Ă���B�����A19�N��ł�5�����x�̐����ɂƂǂ܂��Ă���B
�r�[�����4�Ђ�4�������Y���Ă���A�A�T�q�r�[���͓�5�����A�L�����r�[������2�{�A�T�b�|���r�[������5�����A�T���g���[�r�[������4�����B
�e�ЁA�r�[���̎��v�g����A���i�{����������Ă���B�A�T�q�͎�͂́u�X�[�p�[�h���C�v���ȗ����߂ď�������啝�Ƀ��j���[�A���B�T���g���[�͓����[���̃r�[���u�p�[�t�F�N�g�T���g���[�r�[���v�̋Ɩ��p�𓊓�����ق��A�u�}�X�^�[�Y�h���[��5���b�g���M(����)�v��W�J�B����܂ŒM���i��10���b�g����W�J���Ă������A�i���̕ێ�������������H�X�ɑ��A�e�ʂ��ɂ������i����邱�ƂŁA���v����荞�ށB�܂��A�L���������H�X�����Ƀy�b�g�{�g���Œ\�ȃT�[�o�[�u�s�`�o�o�x(�^�b�s�[)�v���g�́B21�N����̔����n�߁A�����X�܂�5000�X�ɍL�������B
21�N�́u��ޒ֎~�ȂǁA���炩�̋K�����������296���������v(����A�T�q�r�[���В�)�ƁA���������Ɗ����������B�Ɩ��p�r�[���̏o�חʂ̓A�T�q���O�N��27�����A�L��������30�����A�T�b�|������20�����A�T���g���[����25�����Ƒ啝�ɗ������B�����A22�N�͑O�N��ł͑啝�ȑ��Y�ƂȂ邪�A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��O��19�N�̐����ɂ͖߂��Ă��Ȃ��Ƃ݂���B�u22�N��19�N�̃��x���ɂ͖߂�Ȃ��A7�����x�ł́v(��)�ƌ����������������B
|
���܂�h�S�ʉ����ŗ��s�ӗ~���@5/8
���N���[�g�̂����T�[�`�Z���^�[��4��21���A�V�^�R���i�E�C���X�̗��s���n�܂��Ĉȍ~�A����҂�Ώۂɒ���I�Ɏ��{���Ă��闷�s�ӗ~�Ɋւ���A���P�[�g�����̍ŐV���ʂ��܂Ƃ߂��B�Ώۂ�20�Έȏ��1652�l�B��������3��28�A29���ŁA�܂h�~���d�_�[�u���S�ʉ�������Ă���ق�1�T�Ԍ�B�l�q�����Ă���w���܂߂����ݓI�ɍ����h�����s�Ɉӗ~�����w��64.2���ɉ����B�I�~�N�������̊����g��Ȃǂ��e�������O��(1��28�A29��)����8.5�|�C���g�㏸�����B
���ݓI�ɍ����h�����s�Ɉӗ~�����w��64.2���́A�u�\������Ă���A�C�ɂ����s���v4.8�����u�\������Ă���A�C��t���Ȃ���s���v18.6�����u���s�ɍs���������A�l�q�����Ă���v40.7���\�̍��v�B���̉́A�u���s���L�����Z���E���炭�s���Ȃ��v16.1�����u�R���i�ЂɊW�Ȃ��A���Ƃ��ƍs���Ȃ��v11.4���B
|
���S���̐V�^�R���i������3��9328�l�@���ꌧ�ʼnߋ��ő� �@5/8
7���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�3��9,328�l�ŁA�����s�ł�26���Ԃ�ɑO�̏T�̓����j�����������B�s���ŐV���Ɋm�F���ꂽ�����҂�3,809�l�ŁA��T�y�j������830�l�����A26���Ԃ�ɑO�̏T�̓����j�����������B
���̂ق��A���{��4,192�l�A���ꌧ�ʼnߋ��ő���2,375�l�ȂǑS���ł�3��9,328�l�̊�����27�l�̎��S���������Ă���B����A�S���̏d�ǎ҂�165�l�ŁA11���A����200�l����������B�@ |
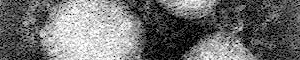 |
���f�v�����c�k�C�����̐V�K������2556�l�@3���A����2000�l������@5/9
�S�[���f���E�C�[�N��������9���A�k�C���S�̂̐V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����m�F��2556�l�ł����B���S���\��6�l(��2�l�A�D�y�s3�l�A����s1�l)�ł����B�V�K�����҂͐�T�̌��j��(2��1805�l)���751�l�����Ȃ��Ă��āA�O�T�̓��j��������̂�2���A���ł��B�܂��V�K�����҂�2000�l������̂�3���A���ł��B
�V���Ȋ����m�F2556�l�̓���́A�D�y�s��2���A����4�P�^�ɂ̂�1194�l�A����s��4���A����100�l������107�l�A���َs��3���A��150�l����151�l�A���M�s��29�l�A�k�C�����\��14�̒n���̍��v��2���A����4�P�^�ɂ̂�1075�l�ł����B
|
�������s��3011�l�����m�F �@�O�T���608�l���@3���A���őO�T����@5/9
�����s�ŁA9���A�V����3011�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ����������B��T�̌��j������608�l�������B1���̊����Ґ��Ƃ��ẮA3���A���őO�̏T�̓����j�����������B
�S�[���f���E�B�[�N���Ԓ��ɂ́A�����Ґ�������Ƃ݂��Ă������A�����s�̊W�҂́A�u�A�x��������O�ɁA�����҂������n�߂��̂͗\�z���������v�ȂǂƏq�ׁA���ꂩ��̃��o�E���h�Ɍx�������������B
9���̊����Ґ���N��ʂɌ���ƁA10�Ζ�����345�l�A10�オ372�l�A20�オ794�l�A30�オ585�l�A40�オ416�l�A50�オ256�l�A65�Έȏオ185�l�������B
�܂��R���i���҂̒��ŐV���Ȏ��S��͕��Ȃ������B9�����_�ŁA�I�~�N�������̓����܂����d�ǎ҂�31�l�A����ɑΉ�����a�ǂ̎g�p����3.9���������B���ґS�̂ɑ���a���g�p����15.7�ƂȂ��Ă���B
|
��5/3-5�̓��C3���̐l�o�c���w���ӂ͑O�N�̔{�߂�92.8%���@5/9
�S�[���f���E�B�[�N����5��3��〜5���܂ł�3���Ԃɂ��āA�l�o�̑��������X�}�[�g�t�H���̈ʒu�������ƂɏW�v�����f�[�^�����J����܂����B
���m���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v���o�Ă���2021�N�̃S�[���f���E�B�[�N�̓������ԂƔ�ׁA���É��w���ӂł͔{�߂��ɂ�����92.8�������A�h���ӂ�55.3�������Ă��܂��B
�܂��A����JR�w���ӂ�39.5�������B�O�d���̈ɐ��_�{���ӂł�11.8�������Ă��܂��B
�ɐ��_�{���ӂɌ��O����K��Ă���l����������ƁA��2.3�{�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�����{�̃R���i�����҂�1487�l�A1�T�ԑO���561�l���@5/9
���{��9���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1487�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����561�l�������B�@ |
������̐V�K������1071�l�@���j�ő��@5/9
�����ł�9���A�V����1071�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����܂����B�V���Ɋm�F���ꂽ�����҂�1071�l�ŁA2000�l�����T���̔������x�ƂȂ�܂������A���j���ɔ��\����鐔�Ƃ��Ă͉ߋ��ł������Ȃ�܂����B�V�^�R���i��p�a���̎g�p����46�D9���ł��̂������̊�ŏd�ǂ�5�l�A�����ǂ�141�l�ł��B
�����암��ÃZ���^�[�ł͓��@���҂ƊŌ�t�Ȃǂ̐E�����킹��14�l����������N���X�^�[���������Ă��܂��B���̂ق��A�I�~�N�����������s���Ă���D�w�̊����������Ă��āA���͐ϋɓI�Ƀ��N�`����ڎ킵�Ăق����ƌĂт����Ă��܂��B
|
����^�A�x���� �_�ސ� ���q�͊ό��q�łɂ��킢������@5/9
3�N�Ԃ�ɐV�^�R���i�E�C���X�ɂ��s���������Ȃ�������^�A�x���A�_�ސ쌧���q�s�͑吨�̊ό��q�łɂ��킢�������Ă��܂����B
���q�s���A�m�s�s�h�R�����g�ѓd�b�̊�n�ǂ���v���C�o�V�[��ی삵���`�ŏW�߂��r�b�O�f�[�^���g���Ē��ׂ��Ƃ���A�i�q���q�w���ӂ͍���4���̌ߌ�1���ɍ��G�̃s�[�N���}���A���N�̂��悻2�{�̐l�o������܂����B
���q�������X��̍���j��ɂ��܂��ƁA�i�q���q�w���̈��H�X��y�Y���X�����ԏ����ʂ�ł́A��^�A�x���A��������̂�����Ȃقǂ̍��G������ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
����́u�l�o�̓R���i�O��9���߂��߂����悤�Ɋ����܂��B3����4�������G�̃s�[�N�ŁA�l�ɉ�����ĕ����悤�ɂȂ邱�Ƃ�����܂����B�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�Ƃ��������낢��Ȑ��O�ꂽ���Ƃ��傫�������ƍl���Ă��܂��B�S�̓I�ɎႢ���X�����S�Ȃ͕̂ς��Ȃ��ł����A����҂�Ƒ��A��������Ă��Č��ɖ߂����̂��ȂƊ��o�I�ɂ͎v���Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
|
���I�~�N�������Ɏ��Z�v���͌��ʔ��c�h�e�͓I�Ȋ����h�~��h�^�p��v�]�@���R�@5/9
�V�K�����Ґ��̍��~�܂肪�������A���R����9���A���ɑ��e�͓I�Ȋ����h�~��̉^�p�Ȃǂ����߂��Ă��s���܂����B
���R���̈Ɍ��ؒm���ƌ��c��̐_��c���������J���Ȃ̍����p������b�ƃI�����C���Ŗʉ�A�����g��̖h�~�ƃ��N�`���ڎ�̐��i���e�[�}�ɒ�Ă��܂����B��Ăł͏d�lj����ɂ����I�~�N���������嗬�ƂȂ��Ă��钆�ł͈��H�X�ւ̎��Z�v�������̂܂h�~���d�_�[�u�͌��ʂ������Ƃ��āA�n��̎���ɉ������Ή������l�ȃ��j���[����I�ׂ�悤�������邱�ƂȂǂ����߂Ă��܂��B
���R���@�Ɍ��ؗ����m���u���N���Ă��邱�ƂƑ�ɂ��ꂪ����̂ł͂Ȃ����B(����b�����)�����������͓͂��Ă���ƁA�ǂ��Ή����邩 �撣���Ă���Ƃ��낾�Ƙb���f�����v
�܂�3��ڂ̃��N�`���ڎ�ɂ��Ă͌����̐ڎ헦��50����ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ������A���S���Ȃǂɂ��Đ����͂̂���f�[�^�������悤���߂܂����B
|
��GW���q�A��N��2�D45�{�@�V�^�R���i�O��7�D5���@JR�e�Ё@5/9
JR���q6�Ђ�9���A�S�[���f���E�C�[�N(GW)����(4��28���`5��8��)�̐V�����ƍݗ����̗��p���т\�����B
�V�������܂ޓ��}�E�}�s��Ԃ̏�q(��v46���)�́A�O�N���2�D45�{�̖�907��5000�l�ɏ�������A�V�^�R���i�E�C���X�����g��O������2018�N�Ƃ̔�r�ł͖�7�D5���ɂƂǂ܂����B
�O�N��傫���������v���́A�����g��ȍ~���߂ċً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�Ȃǂ̍s�������Ȃ��Ɍ}����GW���������Ƃ�A�ő�10�A�x�ƂȂ�j���z��̗ǂ��Ƃ݂���B�@ |
 |
���V�^�R���i�����Җk�C����2400�l�@�D�y630�l�@����251�l�@5/10
�V�^�R���i�E�C���X��10���̊����҂́A�k�C����2400�l�m�F���ꂽ���Ƃ��킩��܂����BGW���Ԓ���������T�Ηj��������700�l�������Ă��܂��B�S���Ȃ�������2�l�ł��B
�V�K�����҂̎�Ȓn��@/�@�D�y�s�@630�l�@/�@����s�@251�l�@/�@���َs�@193�l�@/�@�Ύ�Ǔ��@217�l�@/�@�_�U�Ǔ��@213�l�@/�@�\���Ǔ��@233�l�@/�@���H�Ǔ��@145�l�B
|
����������������75������a�`�D2�n���m�F�@�R���i�E�I�~�N����������u�����@5/10
�����ł�9���A�V����505�l�ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�B
�����āA�]���̃I�~�N���������������͂������Ƃ����a�`�D2�n���̊g����m�F����Ă���B
9���������m�F���ꂽ�̂́A���킫�s��104�l�A�����s�ƌS�R�s�ł��ꂼ��85�l�ȂǁA���킹��505�l�B
��T�̓����j���Ɣ�ׂ�159�l�����Ă��āA4���A���őO�̏T�̓����j���̊����Ґ�������A�����̍Ċg�傪�����Ă���B
���ɂ��ƁA3�����{����4�����{�̊ԂɌ����ŐV�^�R���i�Ɋ�������177�l�ɂ��āA�Q�m����͂��������ʁA75���ɂ�����133�l����A�I�~�N�������̂a�`�D2�n�����m�F���ꂽ�Ƃ����B
�a�`�D2�n���́A�]���̃I�~�N���������������͂������Ƃ���A�O����5�����x����u������肪�i��ł���B
|
�������s���V����4451�l�̊����m�F 4���A���őO�T���j������@5/10
10���A�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�4451�l�������B�O�T�̉Ηj���Ɣ�ׂ�1094�l�����A4���A���őO�̏T�̓����j�����������B�d�ǎ҂͑O������2�l������9�l�B
�������m�F���ꂽ�̂́A10�Ζ�������100�Έȏ��4451�l�B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�3426�l�ŁA�O�̏T�Ɣ�ׂ�88.0���ƂȂ����B10�����_�̐V�^�R���i���җp�a���̎g�p����15.2��(1098�l�^7229��)�B�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�a���g�p����4.4��(35�l�^804��)������(�ǂ��������͍ő�m�ی�����)�B�܂��A70��A90��̍��킹��2�l�̎��S���V���Ɋm�F���ꂽ�B
|
�����{�ŃR���i������4240�l�m�F�c�O�T�̓����j�����922�l�� �@5/10
���{��10���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�4240�l�m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j�����922�l�������B���҂�4�l�������B
|
�����ɂŐV����1823�l�R���i�����@1�T�ԑO����463�l�� �@5/10
���Ɍ���10���A�V����1823�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1�T�ԑO�̓����j��(3��)�Ɣ�ׂ�463�l�������B�����ǂ�70��j��1�l�̎��S�����\���ꂽ�B
�V�K�����҂̓���́A�_�ˎs��710�l���P�H�s��215�l�����s��153�l�����{�s��166�l�����Ύs��132�l�������Ǖ���447�l�B���s��1���̎�艺��������A�����̗v�����҂�39��6759�l�A�v���Ґ���2210�l�ɂȂ����B
����1�T�Ԃ�1�������蕽�ϊ����Ґ���1236�E1�l�ɂȂ�A4���A���ő����B10���ߑO0�����_�̕a���g�p����19�E9���A�����d�Ǘp�̎g�p����7�E0���������B
���쌒�N�����������Ǔ��̓��ʗ{��V�l�z�[���ŁA�����ɓ����ē����҂ƐE���v16�l�̊������������A���͐V���ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)�Ƃ��Č��\�����B
|
�������ŐV����4��2160�l�R���i�����c���m�ł͉ߋ��ő��A������ߋ�2�Ԗځ@5/10
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�10���A�S�s���{���Ƌ�`���u��4��2160�l�m�F���ꂽ�B���҂�51�l�������B�d�ǎ҂͑O������5�l����158�l�ƂȂ����B
�����s�ł́A�V����4451�l�̊������m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j������1094�l�����A4���A����1�T�ԑO���������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�3426�l�őO�T����12���������B
���m���̐V�K�����҂�366�l�ʼnߋ��ő����X�V���A���ꌧ��2265�l�ō���7���Ɏ����ʼnߋ�2�Ԗڂɑ��������B���{��4240�l�ŁA4���A����1�T�ԑO���������B |
���V�^�R���i �����Ґ� �A�x�̉e���́H�@����������H ���ʂ��́H�@5/10
3�N�Ԃ�ɍs���������Ȃ�������^�A�x�B�s���{�����܂������ړ��͊����g��O�̐����߂��܂Ŗ߂�A�e�n�̊ό��n�͑吨�̐l�o�łɂ��킢�܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��͏��X�Ɍ�������X���������Ă��܂������A�A�x�̌㔼����͉���ʼnߋ��ő��ƂȂ�A�����ł�4���A���őO�̏T�̓����j���������Ă��܂��B
�����Ґ��͑�������悤�Ɍ����܂����A�A�x�̉e�����o�Ă��Ă���̂ł��傤���H�@�����č���̌��ʂ��́c�H
��2022�N2���ȍ~ �����ނˌ����X�����������c
�S���̊����Ґ��͑�6�g�̊������s�[�N���}����2022�N2���ȍ~�����ނˌ����X���ŁA��^�A�x���O��4��27���ɂ͈����4��6000�l�]��A1�T�ԕ��ςł�4���l�]��ł����B����ɘA�x���Ɍ����X���������ƂȂ�A5��6���ɂ͈���ł��悻2��2000�l�A1�T�ԕ��ς�2��4000�l�]��ƂȂ�܂����B�Ƃ��낪5��7���ɂ͈����3��9000�l�]��A5��8���ɂ�4��2500�l�]��ɂȂ�A5��9�����݁A1�T�ԕ��ς�3���l�߂��Ƒ�������悤�Ɍ����܂��B�����s�ł��������m�F���ꂽ�l�̐���5��10���܂�4���A���őO�̏T�̓����j���������Ă��܂��B
������@��^�A�x�I�� �����Ґ��ߋ��ő���
����A3�N�Ԃ�ɍs�������̂Ȃ���^�A�x�ő����̊ό��q���K�ꂽ���ꌧ�ł͘A�x�I�Ղ�5��7����2375�l�Ɖߋ��ő��̊����Ґ��ƂȂ�A�����čŏI����5��8���ɂ�2060�l�ʼnߋ�2�ԖڂƂȂ�܂����B�l��10��������̊����Ґ���5��9�����݂�760�l�]��Ƃ���܂łōł������Ȃ��Ă��܂��B
�������Ґ��͑������Ă���̂��H ��^�A�x�Ƃ̊W�́H
���Ƃ͌��݁A�����Ґ��������Ă���悤�Ɍ�����̂͑�^�A�x�̊��Ԓ��Ɍ�����������A�m�F����銴���Ґ����ꎞ�I�Ɍ��������Ƃ̔����Ƃ������ʂ�����Ƃ����܂��B�V�^�R���i�E�C���X��ɓ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́u��^�A�x�Ŋό��n�ɍs���Ēn��Ŋ������L���邱�Ƃ��N���Ă����������Ȃ������A�s�s���ɖ߂��Ă������ƐV���Ȋ����̉Ύ�ɂȂ�\��������B�����Ґ����ǂ̂悤�ɐ��ڂ��邩���Ӑ[�����Ă����Ȃ�������Ȃ��v�Ƙb���A����̘A�x�Ől�Ɛl�Ƃ̐ڐG�����������Ƃ������̑����ɂȂ����Ă����̂��A���Ȃ��Ƃ����T�����炢�܂ł͌��ɂ߂�K�v������Ǝw�E���Ă��܂��B
���i�ރ��N�`���ڎ� �啝�ȑ����͂Ȃ��Ƃ���������
����3��ڂ̃��N�`���̐ڎ헦��5��10���̎��_��
�E�d�lj����X�N����������҂ł�90���߂�
�E�S�̂ł�55���قǂɂȂ��Ă��Ă���
���Ƃ̒��ɂ͑�^�A�x�̂��Ƃňꎞ�I�Ɋ����Ґ���������Ƃ��Ă��A���N�`���̐ڎ킪�i�݊����������ł́A�����Ґ��̑啝�ȑ����͂Ȃ����낤�Ƃ��������������Ă���l�����܂��B
���R���i�Ή��̕a�� �g�Ђ����ɂȂ���Ȃ������Ӂh
����ŃR���i�Ή��̕a���̎g�p����5��9�����݂�
�E�l��������̊����Ґ����ł��������ꌧ�ł�46.9��
�E�����s�ł�15.7���ȂǂƂȂ��Ă���
�����Ґ��̑����ɂ���ĕa���̂Ђ����ɂȂ���Ȃ������ӂ���K�v������܂��B
���V���ȕψكE�C���X�̑��݂��c
�����C�ɂȂ�̂��V���ȕψكE�C���X�ł��B���A���{�����ő������߂Ă���ψكE�C���X�̓I�~�N�������́uBA.2�v�ł����A�A�����J�ł́uBA.2�v�̒��ł��uBA.2.12.1�v�Ƃ����E�C���X�������Ă��܂��B
�@�@�@��1. �A�����J �uBA.2.12.1�v�������Ґ��̑����X���ɉe����
�A�����J��CDC�����a��Z���^�[�ɂ��܂��ƁA�uBA.2.12.1�v��4��30���܂ł�1�T�Ԃ�36.5�����߂Ă��ăA�����J�ł��̐��T�ԁA�����Ґ��������X���ɂ��邱�Ƃɉe�����Ă���Ƃ�������������܂��B
�@�@�@��2. ��A�t���J �uBA.4�v�uBA.5�v������
�܂���A�t���J�ł̓I�~�N�������̂����uBA.4�v�ƁuBA.5�v���������uBA.2�v����̒u������肪�i��ł��܂��B
�@�@�@��3. �E�C���X�̐����́c�H
�����̃E�C���X�̐����͂܂��悭�������Ă��܂��A�uBA.2�v���������g��̃X�s�[�h����⑬���\�����w�E����Ă��܂��B�C�M���X�̕ی����ǂ́uBA.4�v�ƁuBA.5�v�ɂ̓f���^���Ɍ���ꂽ�uL452R�v�̕ψق�����A���a�R�̂̓����ɉe�����o��\��������ق��uBA.4�v�ł͍R�̂̓�����������Ƃ����������ʂ̕�����Ƃ��Ă��܂��B����AWHO�����E�ی��@�ւ͂���܂ł̂Ƃ���A���@�Ɏ��郊�X�N�ɍ��͂Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
�����Ƃ́c
�C�O�̊����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́u���N�`����3��ڐڎ킪�i�C��I�Ɋ��C�����₷���Ȃ邱�Ƃ�����A�����Ґ�����6�g�̂悤�ɑ����邱�Ƃ͍l���ɂ����Ǝv���B�V���ȕψكE�C���X�ɂ��Ă͂ǂ̒��x�d��Ȃ��̂��܂��悭�������Ă��Ȃ����A������{�ɂ��wBA.4�x��wBA.5�x�������Ă���\��������Ƒz�肷��K�v������B�V���ȕψكE�C���X�̊Ď�����������s���A�����\�h�̑�𑱂��Ȃ���ǂ̂悤�Ɋɘa�ł���̂��l����K�v������v�Ƙb���Ă��܂��B
�܂����M��w�̊ړc�ꔎ�����́u��^�A�x�ő����̐l�������ė��s��A�Ȃ��y���߂�ɂ܂łȂ��Ă��Ă���B���ꂾ���l�̓��������钆�łǂ�����Ί����Ґ��𑝂��Ȃ��悤�ɂł��邩���ɂ߂������ŁA�ǂ̂悤�ȑ�̊ɘa�����Ă������l���Ă������Ƃ��厖���B���͂܂����ӂ��Ȃ���i�K�I�ɏ�������������ɘa���Ă����Ή����K�v���Ǝv���B��^�A�x�̂��Ƃ̊����g���}���邽�߂Ɏ����̑̒��̕ω�����������ώ@���āA�����ł������������Ƃ�����Α��ߑ��߂Ɉ�Ë@�ւ���f������A���������肷��Ȃǂ̑Ή����K�v�ɂȂ��Ă���v�Ƙb���Ă��܂��B
|
�����{�A�������2���l�Ɋɘa�����@6�����ɂ����{�@�V�^�R���i�@5/10
���{�͐V�^�R���i�E�C���X�̐��ۑ�Ɋւ��A�����Ґ��̏�������s��1��1���l����2���l�Ɋɘa���錟���ɓ������B���������ɂ߂���Ő������肵�A6�����ɂ����{������j���B�����̐��{�W�҂�10���A���炩�ɂ����B
���{�̓I�~�N�������̊����g����A2021�N12���ɐ��ۑ���������A�����҂̏����1��5000�l����3500�l�Ɉ����������B���N3���ȍ~�͊����̉��P�ɔ����Ēi�K�I�Ɋɘa���A4��10������͏��1���l�Ɋg��B�r�W�l�X�W�҂◯�w����̓�����F�߂Ă���B
�������A�����O�̌o�ϊW�҂炩��́u��������������������v�Ȃǂƌo�ϊ����̍ĊJ������������悤���߂鐺���������ł���B�����������A�ݓc���Y�͖K�p���̍���5���̍u���Łu6���ɂ͑��̎�v7�J��(G7)�������݂ɉ~���ȓ������\�ƂȂ�悤���ۑ������Ɋɘa���Ă����v�Əq�ׁA���������ɘa�ɑO�����Ȏp���������Ă����B
�����Ώێ҂͓��ʁA��{�I�Ɍ���ʂ�Ƃ�����������A�ό��q�ɂ��Ă����S�l�P�ʂ̌���I�ȃ��f���c�A�[������A���X�Ɋg�傷�邱�Ƃ��͍�����B�������̌����͋�`���̍��G��������邽�߁A���荑�̏o���������̊��p��N�`���ڎ�҂̌����Ə��ȂLjꕔ�ȑf������Ă����サ�Ă���B
�R�ۑ�u�Y�o�ύĐ��S������10���̋L�҉�ŁuG7�̒��ōł����������ۑ�����Ă������A���͏��X�ɊJ�������ɐi�߂�Ƃ����Ӗ��Œ��������Ă���Ƃ��낾�v�Əq�ׂ��B���{�͍���1�`2�T�ԁA��̑�^�A�x���V�K�����Ґ���a���g�p���ɗ^�����e�������ɂ߂���ŁA���������̊ɘa�����Ȃǂ��ŏI���f������j���B |
���O�H�s��͉X���Ȃ̂Ɂc�@���C�n���́g�q���h�߂炸?�@5/10
3��21���������āu�܂h�~���d�_�[�u�v����������A�ʏ�c�Ƃł���悤�ɂȂ������H�X�B
�������u�z�b�g�y�b�p�[�O�����O�H�����v�̓��v�ɂ��܂��ƁA���Ƃ�3���̊O�H�s��͎�s���ł͑O�̔N����324���~���A�����ł�34���~���ƉX���ł����A���C3���͎��Z�v���������Ă������N3���Ɣ�ׂĉ����B
�O�H�p�x�Ɏ����Ă͋��N3�������Ⴍ�Ȃ��Ă���Ƃ����̂ł��B�����ŁA�X�ōŋ߂̊O�H����ɂ��ĕ����Ă݂�ƁB
20�㏗���u�S�[���f���E�B�[�N�͍s���܂����ˁB�����̗F�B�́w�H�ׂɍs���Ȃ��Ɖi���ɍs���Ȃ��x�ƌ����ėV�Ԃ��A���C�̎q��(�R���i��)�C�ɂ��Ă���q����������w���~�ɂ��悤�x�Ƃ������ꂪ�����v
50��j���u�T��4�炢�B�ƂŎd�������Ă���̂ŋC���]�������˂āB��Ԃ��L���Ƃ���ɍs���悤�ɂ��Ă���v
20�㏗���u�ł��邾�����l���Œ������Ԃ͂��Ȃ��v
20��j���u�܂h�~�Ɋ��ꂿ����āA����܂背�X�g�����Ƃ��ɂ��s���Ă��Ȃ��v
�u�T4�����炢�s���v�Ƃ����l����u���܂�s���Ă��Ȃ��v�Ƃ����l�܂ł��܂��܁B���ہA���H�X�͂ǂ�ȏȂ̂��B9����A���É��s����̊C�N��������K�˂�ƁB
�������@�����@��ЂŎq����u���A�ߌ�10���܂ʼnc�Ƃ��Ă��邪�A���q����̖߂�͏��Ȃ��B(�������������ꂽ��q���͖߂��)�v���Ă��܂����v
�T���߂̌��j���������Ƃ͂����A���̓��̗\���1�g�����B�e�[�u���Ȃɋq�̎p�͂���܂���B
��ЂŎq����u���Ƃ���3��22������31���܂ł̊Ԃ�200�l�����āA���肪�����������A4��5���͑S�R�_���ł��B�������������v
���̓X�ł́u�܂h�~���d�_�[�u�v�����������܂ł͋x�݂̓��������A�������ꂽ����͋q�����߂�܂������A4���ɓ���ƍĂщ��̂����Ƃ����܂��B
��ЂŎq����u�w��Ђ���A�܂��_���x�Ƃ����̂�����A3�l4�l�̂��q�������B(�������Ăق����Ƃ����v����)����܂��ˁA�����ł������ˁB(������)������������A������Ȃ����ȂƎv�����A����ς�܂��A�݂�Ȍ�������Ȃ����ȁv
|
����N�x ���т̏���̋��z 4�N�Ԃ葝�����R���i�O���ᐅ���@5/10
��N�x1�N�Ԃ�2�l�ȏ�̐��т�����Ɏg�������z�́A�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŊO�o�֘A�̏���傫���������O�̔N�x��1.6������A4�N�Ԃ�ɑ������܂����B�����A�R���i�O�̐������͈ˑR�Ƃ��ĒႢ�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ȃ̉ƌv�����ɂ��܂��ƁA��N�x�A2�l�ȏ�̐��т�����Ɏg�������z�́A���̕��ς�1���т�����28��935�~�ƂȂ�܂����B
�����̕ϓ��������������ŐV�^�R���i�E�C���X�̉e���ŊO�o�֘A�̏���傫���������O�̔N�x��1.6������A4�N�Ԃ�ɑ������܂����B
����ł͊O�o�����������Ƃɂ���Ď����Ԃ�^�C���Ȃǂ̕��i���w��������p�́u��ʁv��22.9���A�z�e���◷�قȂǂ́u�h�����v��19.9���A�u�O�H�v��6.4���A���ꂼ�ꑝ�����܂����B
����A���Ƃ�3����2�l�ȏ�̐��т�����Ɏg�������z��30��7261�~�ŁA���N�̓�������2.3���������3�����Ԃ�̌����ƂȂ�܂����B
�܂h�~���d�_�[�u����������ĊO�o�̋@����������ƂŎ���Œ������ĐH�ׂ���H�֘A�̎x�o�����������ƂȂǂ��v���ł��B
�����Ȃ́u�R���i�̉e���������Ă��蕨���㏸�ɂ�锃���T�����N���Ă��邩�f����͓̂���B���܂��܂ȃf�[�^���Ƃ炵���킹�Ȃ��獡��̓����𒍎����Ă��������v�Ƃ��Ă��܂��B
|
��GW�n���C�D���A�ꕔ�֖��Ȃ��@������3�N�Ԃ�g�s�������Ȃ��h�Ŋe�Љ@5/10
�S���{��A(ANA/NH)����{�q��(JAL/JL�A9201)�A�X�J�C�}�[�N(SKY/BC)�ȂǍq��10�Ђ�5��10���A�S�[���f���E�C�[�N�̗��p���т\�����B�Ώۊ��Ԃ�4��29������5��8���܂ł�10���ԁB���ې��̓n���C���ʂ̈ꕔ�ւŖ��ȂƂȂ�ȂǁA���v�̒������݂�ꂽ�B�������͂܂h�~���d�_�[�u�Ȃǂ���������A3�N�Ԃ��3�N�Ԃ�ɍs�������Ȃ��ƂȂ������Ƃ���A�V�^�R���i�O�̐����ɂ͓͂��Ȃ��������̂̋q���̖߂肪�ڗ������B
10�Ђ̔��\�l�����v����ƁA���q���͍��ې����O�N������4.66�{��14��1156�l�A��������2�{�߂�98.2������266��6281�l�B���Ȑ��͍��ې���33.0������21��1496�ȂŁA��������39.1������397��854�Ȃ������B10�Е��ς̃��[�h�t�@�N�^�[(���ȗ��p���AL/F)�͍��ې���47.7�|�C���g�㏸��66.7���A��������20.0�|�C���g�㏸��67.1���������B
��ANA
ANA�̗��q���́A���ې����O�N������5.04�{��6��7375�l�ŁA��������88.4������95��8724�l�B���Ȑ��͍��ې���31.8������9��5877�ȂŁA��������36.0������151��9217�ȂƂȂ����BL/F�͍��ې���51.9�|�C���g�㏸��70.3���A��������17.5�|�C���g�㏸��63.1���������B
�V�^�R���i�O��2019�N�Ɣ�r����ƁA���q���͍��ې���77.3�����A��������34.8�����B���Ȑ��͍��ې���73.9���A��������17.1�����ꂼ�ꌸ�������BL/F�͍��ې���10.6�|�C���g�A��������17.2�|�C���g���ꂼ��ቺ�����B
���ې��̓A�W�A�|�k�ĊԂ̏��p�����v�������ɐ��ځB���q���E���p���Ƃ��ɉ��P�����B���p�����ł����������̂̓A�W�A�E�I�Z�A�j�A���ʂ�73.3���B�n���C�͒��Ȑ����O�N������2.59�{�A���q����4.86�{�Ƒ傫���L�т��B
���Ԓ��̃s�[�N�́A���ې��͉���(���{��)��4��29��(70.8��)�A���(���{��)��5��7��(87.2��)�B�������͉��肪4��29��(91.9��)�A����5��5��(90.9��)���ł������l�ƂȂ����B
��JAL
JAL�O���[�v�̗��q���́A���ې����O�N������4.46�{��7��3039�l�ŁA��������2.31�{��91��6376�l�B���Ȑ��́A���ې���34.1������11��4824�ȁA��������57.1������135��4064�Ȃ������BL/F�͍��ې���44.5�|�C���g�㏸��63.6���A��������21.7�|�C���g�㏸��67.7���������B
�V�^�R���i�O��2019�N�Ɣ�r����ƁA���q���͍��ې���72�����A��������19�����ƂȂ����B
���ې��͐V�^�R���i�O�̐����ɂ͒B���Ă��Ȃ����̂́A�S���ʂōD���ɐ��ځB���v�̒������o�n�߂Ă���B���Ƀn���C�����D���ŁA���Ȑ����O�N������3.79�{�A���q����9.33�{�Ƒ啝�ɑ��������B
���Ԓ��̃s�[�N�́A���ې��͉���(���{��)��5��7��(70.1��)�A���(���{��)��8��(74.6��)�B�������͉��肪4��29��(93.8��)�A����5��5��(92.4��)���ł������l�ƂȂ����B
���X�J�C�}�[�N
�X�J�C�}�[�N�̗��q���́A���������O�N������57.8������17��6960�l�A���Ȑ���4.0������27��9483�ȁBL/F��21.6�|�C���g�㏸��63.3���������B���ې��͉^�x�������Ă���B
�V�^�R���i�O��2019�N�Ɣ�r����ƁA���q����21.9�����A���Ȑ���5.1�����BL/F��21.9�|�C���g�ቺ�����B
������ʂ̍�����L/F�́A���肪4��29��(84.0��)�A����5��5��(82.6��)���ł������l�ƂȂ����B�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���V�^�R���i ����3259�l�����m�F 3200�l����2���ȗ��@5/11
11���A�����ł͐V����3259�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A1�l�̎��S�����\����܂����B�V�K�����Ґ���3200�l���鐅���ƂȂ�̂͂��Ƃ�2���ȗ��ł��B
�������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��1338�l�A����s��272�l�A�Ύ�n����227�l�A�_�U�n����208�l�A�\���n����202�l�A���َs��199�l�A�I�z�[�c�N�n����143�l�A��m�n����139�l�A���H�n����135�l�A�n���n����83�l�A���n����81�l�A���M�s��76�l�A��u�n����46�l�A�����n����34�l�A�����n����20�l�A�@�J�n����16�l�A�O�R�n����13�l�A���G�n����7�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��5�l���܂�20�l�́A���킹��3259�l�ł��B
�V�K�����Ґ��͑O�̏T�̓����j����1169�l����A4�������đO�̏T�ɔ�ׂđ������܂����B�܂��A3200�l���鐅���ƂȂ����̂�3628�l�̊������m�F���ꂽ���Ƃ�2��17���ȗ��ł��B���Ȃǂɂ��܂��ƁA��������38�l�������āA�����ǂ�1�l�A���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������ƂŁA�����ȏ�ɂ�����1876�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������8905���ł����B����A���́A����܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A80��̏���1�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B
����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�16��964�l���܂ނ̂�31��7971�l�ƂȂ�A�S���Ȃ����l��2012�l�A���Â��I�����l��29��3165�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�������s �V�^�R���i 5�l���S 4764�l�����m�F �O�T��1700�l�]�� �@5/11
�����s����11���̊����m�F��4764�l�ŁA1�T�ԑO�̐��j�����1700�l�]�葝���A5���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��11���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���4764�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j�����1700�l�]�葝���܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�5���A���ł��B11���܂ł�7���ԕ��ς�3678.1�l�ŁA�O�̏T��106.5���ł����B100��������̂͐挎14���ȗ��ł��B11���Ɋm�F���ꂽ4764�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�28.7���ɓ�����1366�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�298�l�ŁA�S�̂�6.3���ł��B�����o�H���������Ă���1547�l�̂����A�ł������̂́u�ƒ���v�ŁA71.0���ɂ�����1099�l�ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�11�����_��8�l�ŁA10�����1�l����܂����B����A�s�͊������m�F���ꂽ80�ォ��90��̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����ŐV����3679�l�̊����m�F�@������8�l�����S�@�V�^�R���i�@5/11
���{��11���A�V����3679�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̐��j���̊����Ґ��́A1545�l�ł����B���{���ł́A������8�l�̎��S���m�F����܂����B
|
���A��2000�l�R���i�����̉���@�u�����������ɗ}���邩�v���d�v�@5/11
����ŘA��2000�l����V�^�R���i�̐V�K�����҂��m�F���ꊴ�����s�������Ă��܂��B����ǂ̂悤�ȑK�v�Ȃ̂��A���̐���Q�^�߂錧�������a�@�̍��R�`�_��t�ɘb���܂����B�@�����R�́u���v�́u�͂��������v
���R�`�_��t�u��^�A�x�����������Ɋ������������Ă���B���ꌧ�͂��Ƃ��Ɛe����n��Ƃ̌𗬂������B�I�~�N�������ɂȂ��Ă���S���I�Ɏq�ǂ��ւ̊������L�����Ă���B���ɉ��ꌧ�͎q�ǂ��̊����������q�ǂ������Ɋ������L����₷���Ƃ����n�搫������v
��K�͂Ȋ������s�Ō��O�����̂���Ñ̐��̂Ђ����ł��B���ɋ~�}�f�Â͐V�^�R���i�̊����҂⌟������]����l���E�������������a�@�ł������ԑ҂��̏�ԂƂȂ��Ă��āA�����a�@�ł͈�ʊO���̐f�Â�d�b�f�Âɐ�ւ���Ȃǂ��đΉ����Ă��܂��B�Ⴂ����̓I�~�N�������Ɋ������Ă��قƂ�ǂ��y�ǂ̂܂܂ʼn��邱�Ƃ���A�~�}�̎�f�͏Ǐd���l��d�lj��̃��X�N�����鍂��҂�D�悳���Ăق����Ƃ��Ă��܂��B
���R�`�_��t�u�Ǐd�����Ɗ������鎞�͋~�}��f���}���Ŏ�f���Ă����������ق��������Ǝv���܂��B��������ŏǏy���ďǏ��ɘa������т��H�ׂ��邵�A�q�ǂ��ł���ΗV�Ԏ����ł��Ă���Ƃ������Ƃł���A�Q�ĂĎ�f�����K�v�͂Ȃ��v
�s�̖̂�p���Ǐ��܂��̂ł���Ύ���ŗ×{����悤�Ăт����Ă��܂��B���R��t���ψ��߂錧�̉u�w�E���v��͈ψ���́A���T�̐V�K�����҂̐���1��3000�l����1��9000�l�ɒB����Ɛ��v���Ă��܂��B
���R�`�_��t�u���܈ꎟ�����̔g�����Ă���Ƃ���B��^�A�x�Ŋ��������l���犴�������l�B�́w�����̔g�x���ǂꂭ�炢�̑傫���ɂȂ邩�ɂ������Ă���B���@���X�N�̍�������҂ւƊ������g�債�Ă������ꍇ�ɂ͋~�}�̃x�b�h���s�����Ă��鎖���N���������v
�����̔g��}���邽�߂ɂ͌������������g���Ȃ��悤�s�����邱�Ƃ��K�v�ł��B
���R�`�_��t�u����҂̉Ƃ�K�₵����ꏏ�ɐH����ۂ�����Ƃ����͍̂T���Ă������������B�ƒ���������܂߂č���҂ւƊg�����Ă������ꍇ�ɂ͈�ÂЂ��������炩�ɂȂ��Ă���\��������̂ŁA������h���ł����ׂɗ͂����킹�Ă������Ƃ��K�v�v
���R��t�́u�l�I�ȍl���v�ƑO�u��������ŁA�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ���܂h�~���d�_�[�u�̓K�p���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌx����炵�Ă��܂��B�����҂̑����ɂ�茧���ł͂o�b�q�����̗\���Â炢�ɂȂ��Ă��āA���̉u�w�E���v��͈ψ����50��ȉ��Ŋ�b�������Ȃ��l�͎s�̂���Ă����×p�̍R�������L�b�g�̊��p���Ăт����Ă��܂��B
|
�����ꌧ�̃R���i������2702�l�A�ߋ��ő����X�V�@5/11
���ꌧ��11���A�����ŐV����2702�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B7����2375�l���A1��������̉ߋ��ő����X�V�����B����1�T�Ԃł̐l��10���l������̊����Ґ���10�����_��787�l�ƁA�S���ōő��̐����������Ă���B
11�����_�̃R���i�a���g�p����53.1%�ƁA����1�T�Ԃ�15�|�C���g�㏸�����B���͍��Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�K�p��v�����錟���̖ڈ���60%�ƒ�߂Ă���B�d�ǎҗp�̕a���g�p����31.7%�ƁA�O�T���10�|�C���g�ȏ㍂���Ȃ����B
|
�������ŐV����4��5955�l�R���i�����c����ōő��X�V�A�����c�ց@5/11
�����̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�11���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����4��5955�l�m�F���ꂽ�B���҂�41�l�ŁA�d�ǎ҂͑O������5�l����163�l�ƂȂ����B
�����s�ł́A4764�l�̊��������������B�O�T�̓����j������1765�l�����A5���A����1�T�ԑO���������B����1�T�Ԃ̕��ς́A�O�T���6������3678�l�������B
���ꌧ�̐V�K�����҂�2702�l�ŁA�ߋ��ő����X�V�����B���͑�^�A�x���̐l�������Ȃǂ��v���Ƃ݂āA12���ɑ�����c����B�{�茧�ł��A�ߋ��ő���790�l�̊������m�F���ꂽ�B
|
���I�~�N�������̐V�n��BA.4��BA.5�Ŋ����҂��Ăы}���@��A�@5/11
�I�~�N�������̐V���Ȍn���ɂ���āA��A�t���J�ł͍ĂѐV�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����Ґ����}�����Ă���B��������́A�����̌n���͏]���̃I�~�N�������Ƃ͑傫���قȂ��Ă���A�ߋ��̊������瓾��ꂽ�Ɖu�ɂ��h����ʂ͂��قNJ��҂ł��Ȃ����Ƃ��킩���Ă����B
�uBA.4�v�uBA.5�v�ƌĂ��V���Ȍn���́A�݂��ɔ��ɂ悭���Ă���A�ǂ�������ݎ嗬�̃I�~�N������BA.2�n�������L�܂�₷���B��A�t���J�ł́A1�J�����炸�̂����ɂ����̌n����BA.2����u�������A�����Ґ���4��������3�{�ɑ������B
�u���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l�́ABA.4��BA.5�ɑ���Ɖu���قڊF���̏�Ԃł��v�ƁA�A�t���J�ی��������ƃN���Y�[���E�i�^�[����w�ɏ������鐶���w�҃A���b�N�X�E�V�K�����͌����B�u�d�lj���h�����x�̖Ɖu�͂��邩������܂��A�������甭�ǂ܂ł�h���ɂ͑���Ȃ��ł��傤�v
��A�t���J�́A�A�t���J�����̒��ł��V�^�R���i�ɂ���Q���Ƃ��ɑ傫�ȍ����B�����Ȏ��Ґ���10���l����B�������A3��10���t���ň�w���uThe Lancet�v�ɔ��\���ꂽ�����ɂ��ƁA���ۂ̐��͑啝�ɑ����Ƃ����B
����BA.4�� BA.5���������Ă��铯���ł́A���҂̐�������ɑ����邱�Ƃ��\�z�����B�����Ń��N�`���ڎ���ς܂����l�͂킸��3�l��1�l�ł���A���̊����̓A�t���J�̑����Ɣ�ׂĂ��Ⴂ�B
�č��ō��̂Ƃ���x�z�I�Ȃ̂�BA.2.12.1�ƌĂ��n�����B�Ď��a��Z���^�[(CDC)�ɂ��ƁA��T�͂��̊��ɂ���ĐV�K���@�Ґ����S����17���ȏ�A�ܑ�Βn��ƃ��V���g��D.C.���Ӓn��ł�28�����������Ă���B�������A�E�C���X���̃f�[�^�x�[�X�uGISAID�v�ł́A�V���Ȍn���͖k�āA�A�W�A�A���[���b�p��20�J���ȏ�ɍL�����Ă���A�č��ł����ł�BA.4��19��ABA.5��6�ጩ�����Ă���(�Ғ��F4��25�����_�œ��{�ł͖����o)�B
���ق��̃I�~�N�������Ɖ����Ⴄ�̂�
��A�t���J�́A�V�^�R���i�E�C���X�̈�`�q�z���͂�ϋɓI�ɍs���Ă����B���������v���ȉ�͂��A2021�N12���ABA.1�ƌĂ��]���^�I�~�N�������̔����Ƌ}���𐢊E�Ɍ����Čx�����邤���ŏd�v�Ȗ������ʂ������B����BA.4��BA.5�������̂��A���̂Ƃ��Ɠ�����̓`�[�����B
�uBA.4��BA.5�����肳�ꂽ�̂́A�ق��̑����̍��X����߂Ă��܂�����`�q�z��̉�͂��A������A�t���J�������Ă��邨�����ł��v�B���E�ی��@��(WHO)�̃e�h���X�����ǒ���5��4���A�L�҉�ł����q�ׂĂ���B�u�����̍��X�ł́A�E�C���X���ǂ̂悤�ɕψق��Ă���̂��������Ă��܂���B���ɉ����N����̂��A�����͒m��Ȃ��̂ł��v
�V�K������̃`�[�����s�������̈�`�q��͂ɂ���āABA.4��BA.5�̃X�p�C�N�^���p�N����BA.2�Ƃ悭���Ă�����̂́A6�J���ɕψق����邱�Ƃ��킩��A5��2���t���ō��ǑO�̘_���𓊍e����T�C�g�umedRxiv�v�ɔ��\���ꂽ�B�X�p�C�N�^���p�N���́A�V�^�R���i�E�C���X����������ۂɁA�זE�̎�e�̂ƌ������镔�����B
�uBA.4��BA.5�̃X�p�C�N�^���p�N���Ɍ�����ABA.2�����3�̕ψق́A�R�̉���A�E�C���X�̐����c��AACE2��e�̂ւ̌����Ɋ֘A���Ă���\���������Ǝv���܂��v�ƁA�t�����X�A�p�X�c�[���������̃E�C���X�Ɖu����𗦂���I���r�G�E�V�������c���͏q�ׂĂ���B
���̂�����2�́A�E�C���X�̊����͂����߂铭���������Ă���ƁA�p�P���u���b�W��w�̖Ɖu�w�҂ŁA�����ǂ̐��Ƃł��郉�r���h���E�O�v�^���͌����B�悢�_�Ƃ��ẮA�����̕ψق̂������ŁABA.2����̐V���Ȍn����ʏ��PCR�����ɂ���Đv���Ɏ��ʂł���_����������B
�����ЂƂ̕ψق́A�f���^���A�J�b�p���A�C�v�V�������Ƃ������A���̑��́u���O�����ψي�(VOC)�v�ɂ���������̂��B�w�p���uSignal Transduction and Targeted Therapy�v�ƁuBiological Sciences�v�ɁA���ꂼ��3��9����5��2���t���Ŕ��\���ꂽ�\���I�����ɂ��A���̕ψق͊����͂����߁A�����̍R�̂ɂ��Ɖu����߂铭�������Ƃ����B
��҂̌����ł͂���ɁABA.4��BA.5�ɂ��钿�����ψق��ABA.1�ɓ��ٓI�ȍR�̂̉���������Ă��邱�Ƃ�������Ă���B���̕ψق́A2020�N4���Ƀ~���N�_��ŃA�E�g�u���C�N�����������ہA�~���N��t�F���b�g�Ɋ��������V�^�R���i�E�C���X�̌n���Ɠ����ꏊ�ŋN�����Ă����B
�����̃X�p�C�N�^���p�N���̕ψقɉ����āABA.4��BA.5�ł́A���̃^���p�N���ɂ��ψق��������݂��邪�A���̋�̓I�ȋ@�\�ɂ��Ă͂悭�킩���Ă��Ȃ��B
��BA.4��BA.5�͂ǂ��Ői�������̂�
�V�K������̘_���ł́A���҂͂��ꂼ��2021�N12�����{��2022�N1�����{�A�܂肻�̂ق��̃I�~�N�������Ƃقړ������ɁA��A�t���J�Ŕ��������Ɛ������ꂽ�B�������A���̋N���ɂ��Ċm���Ȃ��Ƃ͂܂��킩���Ă��Ȃ��B
�uBA.4��BA.5�́ABA.1�ABA.2�ABA.3�Ƌ��ʂ̑c�悩�甭�������\��������܂����A�m���ł͂���܂���v�ƁA�N���Y�[���E�i�^�[����w�̊����Ljナ�`���[�h�E���b�Z���Y���͌����B���b�Z���Y���́A���ׂẴI�~�N�����ψي������������̈�`�q��̓`�[���ɏ������Ă���B
�l������i���o�H�̂ЂƂ́A�l�Y�~�Ȃǂ̓����̏h�傾�B���邢�͖Ɖu�V�X�e�������Ȃ�ꂽ���҂Ƃ����\��������B�O�v�^���̌����ł́A�����ɂ킽�銴���̊ԂɁA�ψق̒~�ς��N���邱�Ƃ�������Ă���B
�u���̂ق��ABA.4��BA.5��BA.2����i�������\��������܂��v�ƁA���b�Z���Y���͌����B
��BA.1�̖Ɖu���������BA.4��BA.5
�V�K������̃`�[���́A���J���O�ɏ]���̃I�~�N����BA.1���Ɋ��������o���������N�`�����ڎ�҂���ѐڎ�҂����R�̂��ABA.4��BA.5�n���𒆘a�ł��邩�ǂ����ׂ錤�����s�����B���̌��ʁA�ߋ��̊����ɂ��R�̂́A�������甭�ǂ܂ł�h�����ʂ������Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����B���ǑO�̘_����5��1���t���ŁumedRxiv�v�ɓ��e���ꂽ�B
WHO�ɂ��A���Ꮚ�����ł͐V�^�R���i���N�`����1��ł��ڎ킵�����Ƃ̂���l��6�l��1�l�ɖ����Ȃ��B�č��ł����A������23���߂��̓��N�`�����ڎ�̂܂܂��B
�uBA.4��BA.5�̃f�[�^�ɂ́A�������������Ɠ����ɋ�������܂����v�B���̖Ɖu�̋}���Ȓቺ�ɂ��āA�O�v�^���͂����q�ׂĂ���B�u�\�z���Ă��������ቺ�̓x�������傫�������̂ł��B�i������X�s�[�h�Ƃ������̃E�C���X�̐����w�I���������S�ɕς���Ă��܂����̂�������܂���v
��A�t���J�ł̌������ʂɂ́A���N�`���ڎ�ς݂̐l�����ɂƂ��Ă̘N����܂܂�Ă���B�u���Ƃ��I�~�N�������Ɋ��������Ƃ��Ă��A���N�`����ł��Ă���Α傫�Ȗh����ʂ������邱�Ƃ��킩��܂����v�ƃV�K�����͌����B
�V�K�����̌����͂܂��ABA.4��BA.5���A�Ƃ��Ƀ��N�`���ڎ�҂ɂ����āA�ȑO�̃I�~�N���������d�lj����ɂ����\�����������Ă���B��A�t���J�œ��@���銳�҂������Ă���ɂ�������炸�A�d�NJ��҂����Ȃ������闝�R�͂����ɂ���̂�������Ȃ��B���@���Ԃ̒����l���Z���Ȃ��Ă���悤���B���������̈���ŁA�V�^�R���i�����ǂɂ�鎀�Ґ��́A����̊��҂ł͈ȑO���������X�s�[�h�ő����Ă���B
�uBA4��BA.5�̃f�[�^�́A�����ǂ̉e�����₷���l�X�͂Ƃ��ɁA�u�[�X�^�[�ڎ�ɂ���čR�̃��x���������ۂK�v�����邱�Ƃ�⋭������̂ł��v�ƃO�v�^���͌����B
���f���i�Ђ́A�V���ȃu�[�X�^�[���N�`�����ł���mRNA-1273.211�ɂ��Ẵf�[�^���uResearch Square�v��4��15���t���Ō��\����(mRNA-1273.211�́A�]�����^�ƃx�[�^���^�̃X�p�C�N�^���p�N�����Y��������2�����N�`��)�B�����ǂł͂�����̂́A���̌��ʂ́A�����N�`�����I�~�N�������ɑ��Ă��Œ�6�J���ԁA�D�ꂽ�h����ʂ������Ƃ������Ă���B
�u���N�`���͏d�lj��A���@�A�l�H�ċz�푕�����������悤�v����Ă��܂��v�ƃ��b�Z���Y���͌����B�u�����āA���܂��܂ȕψي����o�ꂵ�����ł��A���̖�������ɂ悭�ʂ����Ă��܂��v
|
���������A������75���uBA�E2�v�@�V�^�R���i�A�S�ăI�~�N�����@5/11
����10���A�����ł̐V�^�R���i�E�C���X�����҂̂���177���̂𒊏o���Č��q���������ȂǂŃQ�m����͂������ʁA�S�Ă��I�~�N�������ŁA���̂���75���ɓ�����133���̂��h���^�uBA�E2�v�������Ɣ��\�����B
2�`8���̏T��3�����{����4�����{�̌��̂�ΏۂɎ��{������͂̌��ʂ����������B����4��25���`����1���̌��ʂ����\���Ă���A3�����{����4�����{�̌���148���̂����A47���ɓ�����69����BA�E2�������B���́uBA�E2�ւ̒u������肪�i��ł���v�Ƃ݂Ă���B����܂ł̉�͂Ŕ��������I�~�N�������͗v2455���ŁA���̂���BA�E2��505���ƂȂ��Ă���B
|
�������E���Ŋ���1���l���\�����@�V�^�R���i�@5/11
�����J���ȂɐV�^�R���i�E�C���X�������������Ƒg�D�̉��11���J����A���T�ɂ͓����Ƒ���1��������̐V�K�����Ґ���1��2000�l���x�ɒB����\��������Ƃ��鍑�������nj������̗\���l�����ꂽ�B�e�c����(������)�����͉�Łu����3���Ԃ͑����X�����݂���B�ڐG�@����������e���ŁA���T�ȍ~�̊���������ς݂����\��������v�Ǝw�E�����B
���Ƒg�D�͑S���̒���1�T�Ԃ̊����Ґ����O�T���0�E98�{�ƕ��́A�I�~�N�������͂a�`�E2�ɂقڒu����������Ƃ����B�e�c���͘A�x���̌������̌����Ȃǂ܂��u�����_�Ŋ����̐��m�ȕ]���͓���B1�A2�T�Ԍo�߂��݂�K�v������v�Ƌ��������B
�}�X�N���p������A�e�c���́u�������X�N���l���A��b�̗L���⊷�C�̏ȂǂŔ��f����K�v������B���͐E��̕�����1�l�ł���Ƃ��ɂ͊O���Ă���B��O�Ől�����Ȃ��Ƃ��������Ă���Ƃ��̓}�X�N�����A�V�N�ȋ�C���z���Ă��炢�����v�Əq�ׂ��B
|
�����Ɍ����̌i�C�́u���������v5�����Ԃ蔻�f�����グ�@5/11
����_�ˎx�X�͌����̌i�C�ɂ��āA����𒆐S�ɐV�^�R���i�̉e�����a�炬�A���������Ă���Ƃ��āA5�����Ԃ�Ɍi�C���f�������グ�܂����B
����_�ˎx�X��11���A�ŐV�̋��Z�o�ϊT�������\���܂����B����ɂ��܂��ƁA�u�l����v�͎�����������Ƃ��Ă��܂��B���̗��R�Ƃ��ẮA���Ƃ�3���ɂ܂h�~���d�_�[�u����������A�z�e���̉ғ������オ�������Ƃ�A�G�l���M�[���i�̏㏸���ăG�A�R���Ȃǂ̉Ɠd���ȃG�l���\�̍������i�ɔ��������铮�����o�����Ƃ������Ă��܂��B�܂��A�u�ݔ������v�͈������������ɐ��ڂ��Ă���ق��A�u�A�o�v���������Ă���Ƃ��Ă��܂��B
���̌��ʁA����͌����̌i�C�ɂ��āA�挎���画�f�������グ�A�u�V�^�R���i�̉e�����a�炮���ƂŊ�Ƃ��Ă͎��������Ă���v�Ƃ��܂����B �i�C���f�������グ����̂͋��N12���ȗ��A5�����Ԃ�ł��B
����_�ˎx�X�̎R��^�l�x�X���͋L�҉�Łu�R���i�����������A���܂��Ă������̂��g�����Ƃ�������̓��������炩�ɋ����Ȃ��Ă���B�����A�E�N���C�i��Ȃǂ̐�s���̕s�m�����͑傫���A����̏J�Ɍ��Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
|
����B�E�����Ƃ̌i�����A2�J���A���ʼn��P�@���Ԓ����@5/11
�鍑�f�[�^�o���N�����x�X���܂Ƃ߂�4���̋�B�E����̌i�C���������ŁA��Ƃ̌i�����������i�CDI�͑O����0.6�|�C���g�㏸��41.5�ƂȂ����B2�J���A���ʼn��P�����B�V�^�R���i�E�C���X��̂܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ�ق��A3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�i�W���Ă��邱�Ƃ���^�����B
�ƊE�ʂł́A�S10�ƊE�̂����u���݁v�u�s���Y�v������8�ƊE�����P�����B�K�͕ʂł͑��ƁE������ƂƂ��ɉ��P�����B
�����A��Ƃ���́u���ޗ����i��^����������Ă��邪���i�]�ł�����v(���������̉��w�i���[�J�[)�ȂǁA��s�������O���鐺�������ꂽ�B1�N��̌��ʂ�������DI�͋�B�E����S�̂�45.4�ƁA2�J���A���ň��������B�鍑�f�[�^�o���N�́u�E�N���C�i��̂ق��A��������~���̉e���Ōi�����͈�i��ނƂȂ�\���������v�Ǝw�E�����B������4��15�`30���ɃC���^�[�l�b�g�Ŏ��{���A941�Ђ�����B�@ |
 |
���V�^�R���i ����3176�l�����m�F 2���A����3000�l���@5/12
12���A�����ł͐V����3176�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A1�l�̎��S�����\����܂����B�V�K�����҂�11���ɑ�����2���A����3000�l���A���������Ő��ڂ��Ă��܂��B
�������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��1280�l�A�Ύ�n����344�l�A�_�U�n����290�l�A�\���n����212�l�A����s�ōėz����4�l���܂�206�l�A���َs��172�l�A���H�n����159�l�A�I�z�[�c�N�n����96�l�A��m�n����94�l�A���n����68�l�A�n���n����65�l�A���M�s��57�l�A��u�n����40�l�A�����n����35�l�A�����n����25�l�A�@�J�n����15�l�A�O�R�n����10�l�A���G�n����3�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��1�l���܂�5�l�́A���킹��3176�l�ł��B
�V�K�����Ґ��͑O�̏T�̓����j����1322�l�����āA5�������đO�̏T��葝�����܂����B11���ɑ�����2���A����3000�l���A���������Ő��ڂ��Ă��܂��B���Ȃǂɂ��܂��ƁA��������21�l�������ďd�ǂ�1�l�A�����ǂ�2�l�A���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������ƂŁA�����ȏ�ɂ�����1774�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������9848���ł����B
�܂�����s�́A����܂łɊ������m�F����Ă���80��̒j��1�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�16��2244�l���܂ނ̂�32��1147�l�ƂȂ�A�S���Ȃ����l��2013�l�A���Â��I�����l��29��4624�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�������s �V�^�R���i 4�l���S 4216�l�����m�F �O�T�� ��1900�l�� �@5/12
�����s����12���̊����m�F��4216�l�ŁA1�T�ԑO�̖ؗj����肨�悻1900�l�����A6���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��12���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��4216�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̖ؗj����肨�悻1900�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�6���A���ł��B12���܂ł�7���ԕ��ς�3949.0�l�ŁA�O�̏T��130.9���ł����B12���Ɋm�F���ꂽ4216�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�28.9���ɓ�����1219�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�253�l�ŁA�S�̂�6.0���ł��B�����o�H���������Ă���1417�l�̂����A�ł������̂́u�ƒ���v��74.7���ɂ�����1058�l�ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A12�����_��6�l�ŁA11�����2�l����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ80�ォ��90��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
���s�������O�T������@�V�ψي���6�Ꮙ�m�F�@5/12
�����s��12���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����͂��郂�j�^�����O��c��s���ŊJ�����B�����X���������Ă����V�K�����Ґ��������~�܂�A�S�[���f���E�C�[�N(�f�v)�㔼�ȍ~�A�O�T��Ŕ����ƂȂ����B�I�~�N�������́u�g�݊����́v6�Ⴊ�s���ŏ��߂Ċm�F���ꂽ���Ƃ��B�f�v�������A�S���������̕{���Ŋ����Ґ����������Ă���A���Ƃ͌x���̌p�����Ăъ|���Ă���B
����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ��͓s����3579�E7�l(5��11�����_)�B��4�����_��3344�E1�l����킸���Ȃ��瑝�����A7��l���Ă���4�����{����̉��~�X���͂f�v���܂����Ŏ~�܂����B
�S���I�ɂ������Ґ��͉����~�܂����A�����J���Ȃ̐��Ƒg�D�ɂ��ƁA�����̍���4�`10���̊����Ґ��͂��̑O�̏T�Ɣ��0�E98�{�Ƃقډ����ɁB���䌧��1�E55�{�A��������1�E67�{�ɂȂ�Ȃ�25�{���ł͑��������B
����A�s���ł�30��ȉ��̎�N�w���V�K�����҂�6�������߂�������Ă���B3��ڂ̃��N�`���ڎ헦��8������65�Έȏ�̍���҂Ɣ�ׁA30��ȉ��̐ڎ헦�͒Ⴍ�A���r�S���q�m���́u���g�Ƒ�Ȑl�����A���S�ȎЉ�����邽�߁A���Аڎ킵�Ă������������v�Əd�˂đ����̐ڎ���Ăъ|�����B
�ő�m�ەa��7229���̎g�p���͍���4�����_��16�E8������11�����_�ł�15�E4���ɁB�ꗈ���v�E���k��Ȗ�ȑ���C�����́u�V�K�����Ґ���a���g�p���Ȃǂ̏ɗ��ӂ��A��{�I�Ȋ����Ǒ���p�����邱�Ƃ��d�v���v�Əq�ׁA���������̌x�������߂��B
6��m�F���ꂽ�I�~�N�������̑g�݊����̂́A�嗬�n���u�a�`�E1�v�Ɣh���n���u�a�`�E2�v�̊Ԃň�`�q�̈ꕔ���g�݊�����Đ������ꂽ�E�C���X�B3�����{����4����{�ɂ����č̎悳��A�����͂Ȃǂ͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
�����҂͂�������y�ǂŁA���݂͗×{���I���Ă���Ƃ����B�ꗈ���͌����_�őg�݊����̂̊������L�����Ă���ɂ͂Ȃ��Ƃ��āA�u��ÂɂƂ炦�Ă������������v�Əq�ׂ��B
�M���ǂ̔��������O�����ď��O�ɁA������Ƃ��Ẵ}�X�N���p���p�����ׂ����ɂ��ēs�̐��Ɖ�c�ŋc�_������j�������ꂽ�B���r���́u�Ȋw�I�Ȓm���܂��A���Ƃ��Ė��m��(�w�j��)���߂�̂��ŏ��ł͂Ȃ����v�Əq�ׁA���{���܂����j�����ׂ��Ƃ̍l�����������B
|
���I�~�N������ �V���ȁu�g�����́v�s����6���m�F�@�uXE�v�Ƃ͈قȂ�n���@5/12
�����s�́A���傤�ߌ�A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋւ�����Ɖ�c���J���A�I�~�N�������̐V���ȁu�g�����́v��6���m�F���ꂽ���Ƃ𖾂炩�ɂ����B����͏]���̃I�~�N������(�uBA.1�v)�ƁA�h���^�́uBA.2�v�������荇�����u�g�����́v�ŁA�n���̕��ނ̓n�b�L�����Ă��Ȃ����̂́A�uXE�v�n���Ƃ͈قȂ�Ƃ����B�s���Łu�g�����́v���m�F���ꂽ�̂͏��߂āB
�����s�ɂ��ƁA3�����{����4����{�ɁA�����҂���̎悵��6�̌��̂ɂ��āA��`�q�������s�����Ƃ���A�V���ȁu�g�����́v�Ɣ��������Ƃ����B������̊����҂��y�ǂŁA�C�O�n�q�����Ȃ����߁A�s�������Ƃ݂��Ă���B
�����͂̋�����A�ǂꂮ�炢�d�lj����邩�Ȃǂ͕������Ă��Ȃ��B����iCDC���ƃ{�[�h�̉ꗈ�����́A��6�g�̎嗬�ƂȂ����I�~�N�������uBA.2�v�ɐG�ꂽ��ŁA�uBA.2�̂悤�Ɋ������g�傷�邩�ǂ���������Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�I�~�N�������̐V���ȁu�g�����́v�ɂ��ẮA���s�Ŋm�F����A�挎28���ɔ��\����Ă���B
|
�����ŐV����3290�l�̊����m�F�@������6�l�����S�@�V�^�R���i�@5/12
���{��12���A�V����3290�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̖ؗj���̊����Ґ��́A1243�l�ł����B���{���ł́A������6�l�̎��S���m�F����܂����B
|
������̕a���g�p��69���@������́u�܂h�~�v������@5/12
���ꌧ���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�2702�l�Ɖߋ��ő����X�V���钆�A��Ì���ł͊����Ȃǂɂ�錇�Ύ҂̑����ŕa���m�ۂ�����Ȃ��Ă���B
���͕a���m�ې���631���Ɣ��\���Ă������A�ғ��ł���a����11���ߑO11������537���ŁA�{������ł͎��ۂ̕a���g�p����69���ɂȂ�Ɩ��炩�ɂ����B��Ò̐��̕N��(�Ђ��ς�)�x�͑����Ă���A�a���g�p���͐�����ł܂h�~���d�_�[�u�̌�����ł���60�����Ă��錻�B
11���̓��@���҂�335�l�ŁA���̕a���g�p����53.1���������B����ʂł͖{��55.7���A�{��57.6���A���d�R15.9���ƂȂ��Ă���B21�d�_��Ë@�ւł͊����Ȃǂɂ��499�l�̈�Ï]���҂������Ă���A�l�J��̓������a���g�p���͌����\��荂���Ƃ݂���B
����ŁA��Ë@�ւɂ���Ă͈�ʈ�Âɐl���𓊓��������ʁA�ꎞ�I�ɐV�^�R���i��p�a���̐�������������A�m�ەa���͗����I�ȕ���������B���͕a���s���Ɋׂ�Ȃ��悤�A���@�ҋ@�X�e�[�V���������p���A��Ë@�ւƐl�J������Ă���Ƃ����B
�d�_��Ë@�ւ̑̐����N�����Ă��邽�߁A���@�ֈȊO�̕a�@�Ŋ����҂����������ꍇ�͂��̂܂��Â𑱂��Ă���A10�����_�ł͗������܂�7�a�@�Ŏl�\���l�����Â����Ă���Ƃ����B�����ł̓R���i�ȊO�̈�ʈ�Â̕a���g�p���������I�ɍ����A11���͖{���S�̂�95.2���ŁA�n��ʂł͒���99.1���A�k��97.9���A�ߔe96���ȂǂƗ]�T���Ȃ����B
���̋{���`�v�����������Ắu���암�̈�Ë@�ւł͋~�}�����̖�Ԏ���𐧌����Ă���A��ʐf�Â┭�M�O���ɂ��e�����y��ł���B��ÕN��������邽�߁A�����ɂ͎s�̖����~����Ȃǂ̑Ή����Ƃ��Ă������������v�Ƌ��͂��Ăъ|�����B
|
���s���ŐV���ȁg�I�~�N�������h�@�����҂��������@�}�X�N�Ȃ��u���蓾��v���@5/12
���I�~�N�������ɐV���ȁu�g�݊����́v
�u�I�~�N�������̒��̂܂����O�����Ă��Ȃ��n������܂��Ă��Ȃ��g�݊����̂��ƍl���Ă��������ėǂ��Ǝv���܂��B�v �����s�̐V�^�R���i�E�C���X���j�^�����O��c�́A3�����{����4����{�ɍ̎悵��6�̌��̂��I�~�N�������̂����n���̕��ނ����܂��Ă��Ȃ��B�V���ȃO���[�v�̑g�݊����̂��������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���҂͑S���y�ǂŗ×{���Ԃ��I���Ă���ق��A�C�O�Ƃ̊֘A�͂Ȃ��s�������Ƃ݂��Ă���B����iCDC���ƃ{�[�h�̉ꗈ���v�����́A���̑g�݊����̂ɂ��āu�ǂꂭ�炢�̊��������͂͂�����킩��Ȃ��v�Ƃ̌����������u������������قǍ����Ȃ��\���͂���v�Ƃ��ė�Âɑ����Ē��������A�Ƙb�����B
�������Ґ��A���Ԃ��g���Ȃ߁h��
�u�����͊g��X���ɂȂ����x�����K�v�ł���A�Ƃ��܂����v �V�K�����Ґ��� 7 ���ԕ��ς́A�O���3344�l���獡���3580�l�Ɖ������������A�����g��̃X�s�[�h������������͑O��̌����X�������]�A�����X���ł���107���ƂȂ����B�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���ۊ����ǃZ���^�[���́A���T�̐V�K�z���Ґ��́A�S�[���f���E�B�[�N���Ԓ��̋x�f�Ō������̌����������Ƃ�A�����̒x�ꓙ�̉e���������l�ƂȂ��Ă���A���̕]���ɂ͒��ӂ��K�v�ł���A�܂芴���Ґ������Ȃ߂ɏo�Ă���\���������A�Ƃ̌������������B
�������ł��}�X�N�����u���肤��v
�u�����ł��}�X�N���O���Ă����Ƃ����͓̂��R���肤��Ǝv���܂��v �ꗈ�����́A���O�ł̃}�X�N�̒��p�ɂ��Ắu�l�Ƃ̋�����������x�ۂ���Ă��钆�ŁA���Ɏq�������ɂƂ��ĔM���ǂ��Ă͔̂��ɑ傫�ȃ��X�N�ɂȂ�̂ŁA���̕����ł́A�����l�I�Ƀ}�X�N�͊O���Ă��悢�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���v�Ƙb�����B����Ɂu�����ł��}�X�N���O���Ă����Ƃ����͓̂��R���蓾��v�Ƃ̌��������߂��A��Ƃ��āu���C�����ɂ��ǂ��Ƃ���ŁA����قǑ����̉�b�����Ȃ��悤�ȏꏊ�v���������B����Łu�}�X�N���p�Ŗ�50�����炢�����̃��X�N�����炷�Ƃ����悤�ȃG�r�f���X������v�Ƃ��ĐT�d�Ɍ�������K�v������A�Ƃ��B�u�����̒m���͂��������āA�����ł͂��������āA�Ƃ��A�����͓s���{���m���̔��f�ɁA�ŋ߁A�悭�A���̌��t��������ł����A���Ƃ��Ė��m�ɂ����߂ɂȂ�̂��ŏ��v ���r�m���́A�Ȋw�I�m���Ɋ�Â��č����}�X�N���p�́g���m�ȕ��j�h�������悤���߂��B
���u�����G�l���M�[��������v
�u���Ƃ��Ɩ�����R���i�a���ɂ������̂�����ς���Č��ɖ߂��̂͑����G�l���M�[��������v ��Ò̐��ɂ��ẮA���T�V���ɓ��@�������Ґ��y�ѓ��@���Ґ��͌����X���ɂ���A�ʏ��ÂƂ̗�����ڎw���ĕa�����_��Ɋ��p����K �v������A�Ƃ̃R�����g�������ꂽ�B�����s��t��̒������F����͒ʏ�a���ƃR���i�a���̐�ւ��́g��ς��h�ƂƂ��Ɂu�ǂ̕a�@�����Ă����悤�ȕ��@���l���Ȃ�����s���Ȃ��ƌ������Ƃł�����Ƌ�J���Ă���v�Ƙb�����B
����6�g�����҂́g�ڎ�ǂ��h
�u������Ƃł����������ȂƎv������o���T������A�o�Z���T������AGW��U��Ԃ��ĕs���̂���l�͌������v ����ɏ��r�m���́u������3�����Ń��N�`���ڎ���A�Ƃ��������v�Ƃ��āu��6�g�̃s�[�N���Ɋ��������l�͍����ڎ�ǂ��v�Ɗ����������Ƃ�����l�ɂ����߂ă��N�`���ڎ����т������B GW�Ɂu�E�C�Y�R���i�v���ł����̂��ǂ����́A���T�킩��̂��낤�B |
���X�p�i�C�A4���͏����㏸�@�u�܂h�~�v�����Ől�����P�@5/12
���t�{��12�����\����4���̌i�C�E�I�b�`���[�����ŁA�i�C�̌��f�c�h��50�D4�ƁA�O����2�D6�|�C���g�㏸�����B3�����{�Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v����������A���q��l�̗��ꂪ���P���Ă������ƂȂǂŌi��������������B�i�C���f�̕\���́u�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̉e���͎c����̂́A���������̓������݂���v�Ƃ��A�O�琘���u�����B
���f�c�h�̏㏸��2�J���A���B�e����ł́A�ƌv�����֘A�c�h��2�D8�|�C���g�A��Ɠ����֘A�c�h��1�D9�|�C���g�A�ٗp�����֘A�c�h��3�D1�|�C���g���ꂼ��㏸�����B
�����Ώۂ���́A�V�^�R���i�Ƃ̋����ɑ��鐺������������A���ޗ���H���i���i�̒l�オ��ւ̃R�����g���݂�ꂽ�B�ߋE�̃X�[�p�[�́u�P�����A�b�v�������A�w���_��������A�����ȏ��i�Ɏ��v���������X���ɂ���B�����㏸�������Ƃ����l�����Z�����n�߁A�m���ɍ��z�̂Ђ����ł��Ȃ�n�߂Ă���v�Ǝw�E�����B
��s�����f�c�h�͑O������0�D2�|�C���g�㏸��50�D3�������B3�J���A���̏㏸�B���t�{�͐�s���ɂ��āu�����ǂ̓����ւ̌��O���a�炮���A���������̊��҂��������A�E�N���C�i��ɂ��e�����܂߁A�R�X�g�㏸���ɑ��錜�O���݂���v�Ƃ����B�����Ώۂ���́A���i���i�̒l�オ��ƈבւ̉~���������N�������R�����g���������B
�������Ԃ�4��25������30���B�V�^�R���i��́u�܂h�~���d�_�[�u�v��3��21���̊����������đS�ʉ�������Ă���B����A�����⌴�ޗ��̉��i�㏸���A�H�i����p�i�̒l�オ�肪�ӎ��������������B |
���R���i �I�~�N�������́uBA.4�v�ƁuBA.5�v �����̌��u�ŏ��m�F �@5/12
�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̂�����A�t���J�Œu������肪�i��ł���2��ނ̕ψكE�C���X�̊������A�����̌��u�ŏ��߂Ċm�F����܂����BWHO�����E�ی��@�ւ͓��@�Ɏ��郊�X�N�ɍ��͂Ȃ��Ƃ��Ă��Č����J���Ȃ́u�����_�ő��ς��邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��B
�������m�F���ꂽ�̂̓I�~�N�������̂����uBA.4�v�ƁuBA.5�v�ƌĂ��ψكE�C���X�ł��B
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA�挎22���ɓ�A�t���J���琬�c��`�ɓ�������50��̒j�����uBA.4�v�ɐ挎29���ɃX�y�C���ƃU���r�A���琬�c��`�ɓ��������������60��̒j��2�l���uBA.5�v�Ɋ������Ă������Ƃ��m�F����܂����B
3�l�͋�`�̌��u���Ŏ��V�^�R���i�E�C���X�̌����ŗz���ƂȂ�A�����J���Ȃ̋��߂ɉ����ďh���{�݂őҋ@�������Ǝ{�݂��o���Ƃ������Ƃł��B
��������Ǐ�͂Ȃ������Ƃ��Ă��܂��B
�����̌��u�ŁuBA.4�v�ƁuBA.5�v�̊������m�F���ꂽ�̂͏��߂Ăł��B
��A�t���J�ł́A���{�ł��嗬�ƂȂ��Ă���uBA.2�v����A�uBA.4�v�ƁuBA.5�v�ւ̒u������肪�i��ł��āA�C�M���X�̕ی����ǂ͊����g��̃X�s�[�h���uBA.2�v����⑬���\��������Ǝw�E���Ă��܂��B
WHO�́A����܂ł̂Ƃ�����@�Ɏ��郊�X�N�ɍ��͂Ȃ��Ƃ��Ă��āA�����J���Ȃ́u����̊����͒������Ă����������_�ő��ς��邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B�]���̑�𑱂��Ăق����v�Ƃ��Ă��܂��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 4�l���S4109�l�����m�F �O�T���1400�l�]�� �@5/13
�����s����13���̊����m�F��4109�l�ŁA1�T�ԑO�̋��j�����1400�l�]�葝���A7���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��13���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��4109�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j�����1400�l�]�葝���܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�7���A���ł��B13���܂ł�7���ԕ��ς�4153.0�l�ŁA�O�̏T��146.1���ł����B13���Ɋm�F���ꂽ4109�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�27.7���ɓ�����1138�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�268�l�ŁA�S�̂�6.5���ł��B�����o�H���������Ă���1433�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v�ŁA70.6���ɓ�����1011�l�ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A13�����_��4�l�ŁA12�����2�l����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70�ォ��90��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
���V�^�R���i �V�K�����Ґ� 46�s���{���őO�T��葝�� �@5/13
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA��^�A�x���Ɍ����̐������Ȃ���������������46�s���{���őO�̏T��葽���Ȃ��Ă��܂��BNHK�́A�e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S���̊�����
�S���ł́A�挎14���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�ɔ�ׂ�1.06�{�A�挎21����0.85�{�A�挎28����0.94�{�A����5����0.67�{�Ɛ�T�܂ł�3�T�A���Ō������Ă��܂������A12���܂łł�1.41�{�Ƒ������A���������̕��ς̐V�K�����Ґ��͂��悻3��7298�l�ƂȂ��Ă��܂��B��^�A�x�Ō����̐������Ȃ��Ȃ��Ă�������������A��錧������46�̓s���{���őO�̏T��葽���Ȃ��Ă��܂��B
�����ꌧ�̊�����
���ꌧ�́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.00�{�A����5����0.94�{�Ƃقډ����Ő��ڂ��Ă��܂������A12���܂łł�1.57�{�Ƒ������Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2029�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���967.71�l�ƑS���ōł������A�ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
��1�s3���̊�����
�����s�́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.86�{�A����5����0.60�{��3�T�A���Ō������Ă��܂������A12���܂łł�1.31�{�Ƒ������Ă��āA���������̐V�K�����Ґ���3949�l�ƂȂ��Ă��܂��B�_�ސ쌧�́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.86�{�A����5����0.65�{�A12���܂łł�1.04�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1839�l�ƂȂ��Ă��܂��B��ʌ��́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.87�{�A����5����0.59�{�A12���܂łł�1.24�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1590�l�ƂȂ��Ă��܂��B��t���́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.90�{�A����5����0.57�{�A12���܂łł�1.12�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1074�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����̊�����
���{�́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.91�{�A����5����0.64�{�A12���܂łł�1.67�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻3097�l�ƂȂ��Ă��܂��B���s�{�́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.05�{�A����5����0.64�{�A12���܂łł�1.54�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻842�l�ƂȂ��Ă��܂��B���Ɍ��́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.87�{�A����5����0.69�{�A12���܂łł�1.44�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1478�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����C�̊�����
���m���́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.02�{�A����5����0.58�{�A12���܂łł�1.70�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2182�l�ƂȂ��Ă��܂��B���́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.04�{�A����5����0.56�{�A12���܂łł�1.79�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻574�l�ƂȂ��Ă��܂��B�O�d���́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.87�{�A����5����0.59�{�A12���܂łł�1.59�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻423�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����̑��̒n��̊�����
�k�C���́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.08�{�A����5����0.79�{�A12���܂łł�1.24�{�ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2612�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���350�l�ƁA���ꌧ�Ɏ����őS����2�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�{�錧�́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.06�{�A����5����0.58�{�A12���܂łł�1.52�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻474�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�L�����́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.94�{�A����5����0.77�{�A12���܂łł�1.60�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ���1158�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�������́A�挎28���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.03�{�A����5����0.72�{�A12���܂łł�1.29�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2108�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�x�R����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.91�{�A�É�����1.82�{�A���R����1.77�{�A��������2.45�{�A���쌧��1.77�{��2�{�O��ɑ����Ă��܂��B
�����Ɓu����ɑ��������̂� ���ӂ��Ă݂Ă����K�v�v
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́u�S���̊����Ґ��͑�^�A�x���Ɍ������A��^�A�x�̑O����悤�ȏɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����A�ꕔ�Œ����Ă���Ƃ�������邱�Ƃɒ��ӂ��K�v���B���̒i�K�ł͔����I�ȑ����͌����Ȃ����A���ꂩ�炳��ɑ����������̂����ӂ��Ă݂Ă����K�v������v�Ǝw�E���܂����B
���̂����Łu��^�A�x�̌�A�����Ґ����܂�����قǑ����Ă��Ȃ��n��ł����T�ɂ����Ă���ɑ�������\��������B�Ǐo����A�̒������������Ǝv�����瑁�߂Ɉ�Ë@�ւ���f���Č������邱�Ƃ��d�v���v�Ƙb���Ă��܂��B
�܂��A����܂łɐV�^�R���i�Ɋ������ĖS���Ȃ����l�̐��������ł��悻3���l�ɏ�邱�Ƃɂ��āu���ĂȂǂƔ�ׂ�Ɠ��{�͎��S�����l�̐��͏��Ȃ��}�����Ă��邪�A3���l���̐l���S���Ȃ��Ă��āA�V�^�R���i���y�ڂ����e���͔��ɑ傫�������ƍl������B�S���Ȃ�l�̑����͍���҂⎝�a�̂���l�����ŁA���������l�������������邱�Ƃ��厖���B����҂ւ�4��ڂ̃��N�`���̐ڎ��K�Ȏ����ɍs���ȂǁA�S�̂Őڎ헦���グ�邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�B�܂��A��{�I�Ȋ���������炭�̊Ԃ͓O�ꂷ�邱�Ƃ��厖���v�Ƙb���Ă��܂��B |
�������Ăё����X���@���H�X����͕s���̐��@5/13
�S���I�ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂������X���ɂ���܂��B�S�[���f���E�C�[�N�ȍ~�A�������q�����߂���������H�X����͕s���̐���������܂����B���ɐ[���ȉ��ꌧ�ł́A�����g��������A���p�q���������A�A�x�O�̔����ȉ��ɗ������Ƃ������H�X������܂����B
13���ߌ�2�������A�V�^�R���i�̊����ɂ��āA�����s�̏��r�m���́u���A���o�E���h���Ԃł���܂��̂ŁA�x�����Ԃł���܂��̂ŁA�݂Ȃ���ƂƂ��Ɏ��g��ł����B�Ȃ�Ƃ��Ă��A�����Ċg���������Ă��������Ǝv���܂��v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A�}�X�N���p�ɂ��Ă����y���A�u�Ȋw�I�m�����K�v�ɂȂ��Ă���B�M���ǂŋꂵ���Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�w�q������͑�ς���ˁx���Ă����v���͋��L���Ă���B���ꂵ�āA���{�Ƃ��āA���������Ă܂Ƃ߂Ă������������v�Əq�ׂ܂����B
���̓����ł�13���A�V����4109�l�̊������m�F����܂����B6����2681�l����1428�l�����A7���A���őO�̏T�̓����j���̐l���������Ă��܂��B
�����E������ɂ�����H�X�̓X���ɂ́A�����`�ɗ��������̗��p�q�̎p�������܂����B�S�[���f���E�C�[�N�������Ė�1�T�Ԃ������܂������A�X�ɂ��ƁA�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ3������A���p�q�͖�4�����������Ƃ����܂��B
�������Ȗ{�܂����������@���㊮�X��u���̂܂܂����Ă����A����グ�������ԉ��Ă����̂��ȂƂ������҂͂��Ă���܂��v
���ɘA�x���́A�R���i�O�ɕC�G����قǂ̗��p�q�������Ƃ����܂��B���ł́A�悤�₭�R���i�O��7���قǂ܂ʼn��Ă��܂������A�����s�ł͍Ăъ����҂������X���ɂȂ��Ă��܂��B�X�傩��͕s���̐���������܂����B
���㊮�X��u���ɕs���ł���ˁB�����������Ă������������v
�S���I�ɂ������҂������X���ɂ��钆�A���ɐ[���Ȃ̂��A���ꌧ�B13���A�V����2242�l�̊������m�F����܂����B�����҂�2000�l�ȏ�ƂȂ�̂�4���A���ł��B
�ߔe�s�ɂ�����H�X�́A�v���Ԃ�ɐ����̂Ȃ��S�[���f���E�C�[�N�̘A�x���́A�قږ��Ȃłɂ�����Ă����Ƃ����܂��B
�������@���c�Đl�X���u�������炨�q��������Ă����������̂ŁA���̂܂܌��ɖ߂�̂��ȂƂ�����ۂ͂�������ł����ǁA�S�[���f���E�C�[�N�������r�[�Ɋ����Ґ�����C�ɂǂ��Ƒ������̂ŁA��C�ɂς����Ƌq�����~�܂�������������B���̂���1�g�A2�g�Ƃ��c�v
�����g��������A���p�q�͌������A�A�x�O�̔����ȉ��ɗ������Ƃ����܂��B
���c�Đl�X���u���̂܂܊����Ґ��������钆�ŁA�錾�������o�ĂȂ��̂Łw�����Ă����ʼnc�Ƃ𑱂��Ă����Ȃ��Ⴂ���Ȃ��x�Ƃ����s���̕����傫���ł��ˁv
�Ȃ��Ȃ��q�����߂炸�A�ꋫ�������Ƃ��������܂��B
�����E�a�J�ɂ��郉�[�����X�́A�R���i�O�͌ߌ�9���ȍ~�ɂȂ�ƁA�����̐l������������́g�V���̃��[�����h�ȂǂƂ��ė��p���Ă��܂������A2����A3������T���铮��������Ƃ����܂��B
�����V�_�@�ӔC�ҁE�}��ׂ���u�w�܂h�~���d�_�[�u�x�������Ȃ��Ă��Ȃ����ǁA����ł�����ϖ߂�Ȃ��ł���ˁv
�܂��A���p�q���R���i�O��5�E6�l�̒c�̂ŗ��邱�Ƃ����������Ƃ����܂����A����2�l���炢�ŗ��邱�Ƃ������Ƃ����܂��B
�}��ׂ���u(�R���i)�O�Ɛ���ɂȂ�Έ�Ԃ������ǂˁB�܂��܂��Ȃ�Ȃ��ł���v
�܂��A�g2����h�T���̉e���̓J���I�P�X�ł������܂��B�����E��c��ɂ���X�ł́A�����̎��ԑтɂ́A���p�q���R���i�O��7���قǂ܂Ŗ߂��Ă����Ƃ����܂����\�\
�J���I�P���b�N�@��J������\�u��̕��͂܂�4�����炢�����߂��Ă��ĂȂ��悤�Ȋ��o�ł��ˁB�����X�^�C�����ς���Ă��������Ȃ̂��A�킩��Ȃ��ł����A�F��������鎞�Ԃ������Ȃ��Ă��Ă��܂����̂Łv
��̗��p�q�́A�R���i�O�ɔ�ה������߂��Ă��Ȃ��Ƃ����܂��B���̂��߁A�c�Ǝ��Ԃ�Z�k���Ă���Ƃ������Ƃł��B
��J������\�u�R���i�O�͐[��3���Ƃ�4���܂ł���Ă���ł����ǁA�݂Ȃ���A����̂������Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�����Ƃ��ł��ߑO0���A�x���Ă�1���ɂ͕߂��Ⴄ�����Ɂv
�X�^�b�t�̐l����Ȃǂ̖������邽�߁A���ɕ����͉c�Ǝ��Ԃ�Z�k���đĂ���Ƃ������Ƃł��B
|
������ɘA���v���Ƃ���4�l�̐E����h���@���{�@�����Ґ��̑����X���@5/13
���ꌧ�ŐV�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��������X���ɂ��邱�Ƃ����슯�[�����͉���ɐ��{�̘A���v���Ƃ���4�l�̐E����h������Ɣ��\���܂����B
���ꌧ�́A11���̐V�K�����Ґ����ߋ��ő��ƂȂ�A�d�Ǖa���g�p���������X���ɂ���܂��B
�����������Ԃ��A���{�͉��ꌧ�ƘA�g���Ċ����g���h�����ߓ��t���[�̐E����4�l��13�����牫�ꌧ���ɔh�����邱�Ƃɂ������̂ł��B
���슯�[�����u�@���I�ȑΉ����\�Ƃ���悤�A�ٖ��ȘA�g��}���Ă܂���܂��v
�h���͐挎�ɑ������̂ŁA���鐭�{�W�҂́u���ۑ�Ȃǐ����ɘa�̌������i�ޒ��A����ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p�����悤�Ȏ��Ԃ͍ň��̃V�i���I���B���Ƃ��Ă��h�������Ƃ����_��������v�Ɛ������Ă��܂��B
|
���k����GW�h���{�݉ғ��A�R���i�O��8���܂ʼn@5/13
�S�[���f���E�C�[�N(GW)���Ԓ��A�k��3���̏h���{�݂̉ғ����V�^�R���i�E�C���X�����g��O��2019�N�̓�������8�����x�܂ʼn������Ƃ��A�x�R���ۑ�w�Ȃǂ̒��ׂŕ��������B�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���K�p���ꂸ�A�A�Ȃ�ό��ł̗��p���������B
����w�̑�J�F�j�y�����Ƌ�B�o�ϒ�������(�����s)���A������^�c����o�ϓ��v�v���b�g�t�H�[���u�f�[�^�T���_�v���g���Ē��������{�����B�h���\��T�C�g�̃r�b�O�f�[�^�����Ƃɉғ����w�����B���l�̒�����3��ڂƂȂ�B
�k��3���ł�22�N��GW�̉ғ����s�[�N�ƂȂ����̂͑S���Ɠ�����5��3���ŁA�ғ��������w����100�������B21�N�̖k��3���̃s�[�N���̎w����55.3�A�S����47.6�������B
�n��ʂł͐ΐ쌧�̉̐��������ォ�����B��J�y�����́u����s�ł͕����̎w�����Ⴍ�A�z�e���������ߑ��̏ɂ���̂ł͂Ȃ����v�ƕ��́B�z�e���̌��݂��������x�R�s���u���l�̏ɂȂ�\��������v(���y����)�Ƃ����B
|
���g���m���u�^�₪����v�@���{�̖K���q����ĊJ�����Ɂ@5/13
���{�̋g���m���m����13���A���{���ٓ��ň͂ݎ�ނɉ����A���{��6���ɂ��K���O���l�ό��q�̎�����ĊJ��������ŁA�����ɓ����Ă��邱�ƂɊւ��Č��y�����B
���݂��A�V�^�R���i��Ƃ��Đ����������Ă��邪�A�K���ɘa�ɂ��ċg���m���́u���ł͂Ȃ��v�ƑO�u��������Łu�Ȃ������I�ł͂Ȃ��A������ƕ������������Ăق����v�Ƌ��߂��B
��^�A�x��̐V�^�R���i�E�C���X�̊����Ȃǂɂ��āA�{���ł��u���T�̐��ڂ��������A�E���オ��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�����_�ł͑傫�Ȕg�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��v�Ƃ������ŁA�u�������Đl����l�ɂ�����ԂƁA����������Ԃ͐�������B���������������Ă��������v�ƌ�����x�����ɂ߂Ă��Ȃ��B
���ꂾ���ɁA�O���l�ό��q�̎���ɂ��Ắu���܂��܂ȏd������������݂̂Ȃ���ɂ��肢���Ă���v�Ƃ��u�o�ς͊��������邪�A�����͖��炩�ɍL��������ɂȂ���ό��q�̎���́A���̃E�C���X�Ƃǂ������������Ă����̂��B�S����������ς��邱�ƂȂ��i�߂邱�Ƃɂ͋^�₪����v�Ƃ���B
��6�h�ł͊����҂��}���B���H�X�ȂǂɎ��Z�v���A�{���ɂ͂܂h�~���d�_�[�u�A�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ����{�����B���ꂾ���Ɂu����̗��ꂩ�炷��ƁA���܂͉E���オ�肶��Ȃ����A�������炻���Ȃ邩������Ȃ��B�̎��ɂǂ������[�u���Ƃ�̂��v�Ƃ��A�u���̂܂܂��Ɗ�{�I�Ώ����j�ɉ����āA���H�X�݂̂Ȃ���Ɏ��Z�v�������āc�ƂȂ�B������J��Ԃ��̂��v�Ƌ^���悵���B
���̏�Ő��{�ɑ��āu�^�ۗ��_�A�o��c�_�ɂ͂Ȃ�Ǝv�����A���̕����𐳖ʂ������Ă��炢�����v�Ƒ����A�u�������L����Ȃ������炢�����A�L���邩������Ȃ��B����͕�����Ȃ��B�L���������ɑΉ�����̂͌���̒m���ł�����v�ƁA���Ƃ��Ď�����ĊJ�����ꍇ�̑Ώ����j�̖��m�������߂��B
|
���I�~�N�������̐V�n��6���A�s���Ŋm�F�c�u�a�`�E1�v�Ɓu�a�`�E2�v�������� �@5/13
�����s��12���A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̐V�n����s����6���m�F�����Ɣ��\�����B
�s�ɂ��ƁA6���́u�a�`�E1�v�Ɓu�a�`�E2�v�̈�`�q���������Ă��邪�A�u�w�d�v�Ȃǂ��łɕ��ނ���Ă���V�n���Ƃ͈قȂ�B���������nj��������s����3�`4���ɍ̎悳�ꂽ���ׂ̂Ĕ��������Ƃ����B
�����҂͂�������y�ǂ������B�����ғ��m�̐ړ_�͂Ȃ��A6���������n�����͕s���B�����ł�4���A���s�̊����҂��疢���ނ̐V�n�������߂Ċm�F���ꂽ���A���̌n���Ɠ��ꂩ�ǂ������킩��Ȃ��Ƃ����B
�s�̃��j�^�����O(�Ď�)��c�̃����o�[�E�ꗈ���v���k��Ȗ�ȑ���C�����́u(�V�n����)�������L�����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��Âɑ����Ăق����v�Ƙb�����B
|
����������3���l�����A3������1���l���c��6�g��80��ȏ�̎���73���� �@5/13
�V�^�R���i�E�C���X�����ɂ�鍑���̎��҂�13���A�v3���l�����B2���l�ɒB����2������A��3������1���l�������B�����͂̋����I�~�N���������嗬�ƂȂ�A����҂𒆐S�Ɏ��Ґ����}�����Ă���B
�����̎��҂�2020�N2��13���ɏ��߂Ċm�F����A��1�N2�������21�N4����1���l��˔j�B���̖�9������̍��N2��11����2���l�����B
�I�~�N�������̗��s�Ŋ����҂��}�����A2��22���ɂ͉ߋ��ő��ƂȂ�322�l�̎��S�������B5��13���ɂ͑S����36�l�̎��S���킩��A�N���[�Y�D�̏�D�҂����������̎��Ґ��͗v��3��10�l�ƂȂ����B
�N��ʂŌ���ƁA��5�g(��N6��30���`10��5��)�ł́A80�Α�ȏ�̎��҂�48���������̂ɑ��A��6�g(���N1��5���`3��29��)�ł�73���ɏ㏸���Ă����B���}���A���i��ȑ�̍����L�V����(�����NJw)�́A�u��6�g�ł́A����҂��������A���a������̗͒ቺ�ŖS���Ȃ�P�[�X���������B�d�lj���h�����߁A���ɍ���҂��b�����̂���l��4��ڂ̐ڎ�𑬂₩�ɎĂق����v�Ƙb���Ă���B
|
���č��ŐV�^�R���i�ė��s�A�������̏Ǘᑝ���|���Ԕc���͍���@5/13
�č��ŐV�^�R���i�E�C���X�������ĂэL�����Ă���B�ߋ��Ɋ��������l���Ċ�������P�[�X�������݂��A�ꕔ�ɂ�4�x�ڂ̊����҂�����Ƃ����B
�����A���ۂ̊�����c������̂͂���܂łɈȏ�ɓ���Ȃ��Ă���B�������v�Ɋ܂܂�邱�Ƃ����Ȃ��ƒ�ł̊ȈՌ����������A�z���Ґ��𐳊m�ɃJ�E���g����̂�������s�\�ɂȂ������炾�B�܂������̏B�⎩���̂͌��݁A�R���i�����Ɋւ���f�[�^��Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)�ɎU���I�ɂ������Ă��Ȃ��B
�I�~�N�����ψي��̐V���Ȉ���ɂ���Ċ������g�債���Ƃ݂��邪�A�Ċ�����̑����͕���Ă��炸�A���ۂ̏ɂ��Ă͂قƂ�ǔc���ł��Ă��Ȃ��Ǝw�E���钲��������B
�b�c�b��10���ɔ��\�����V�K�����Ґ���9��8000�l�]��B�����̊����Ґ������������̂͂قڊԈႢ�Ȃ��B
���b�N�t�F���[���c�̃p���f�~�b�N�\�h�������Ńg�b�v�߂�E�C���X�w�҂̃��b�N�E�u���C�g���́u�����N���Ă��邩�ɂ��āA���E�͔��Ɉ����Ȃ��Ă���v�ƌ�����B
���Ƃ�͍��㐔�J���̓W�J�͓ǂ݂ɂ����ƌ��B�d�lj���h���ɂ̓��N�`�����Ȃ��L�������A�E�C���X�͕ψق��J��Ԃ��Ă���A�����̑唼�̓p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)���I���������̂悤�ɍs�����Ă���B
�J���t�H���j�A��w���T���[���X�Z(�t�b�k�`)�̃{�u�E���t�^�[���͌��݂̏ɂ��āu�ߋ�2�N�ŏ��߂āA�ǂ�Ȃɒ��Ӑ[�����S�������Ă���l�ł��������ĕs�v�c�͂Ȃ��Ƃ�����ۂ��v�Ǝw�E�B�����҂́u�܂�����Ȃ��}�����Ă���v�ƌ�����B�@ |
 |
�������s�ŐV����3799�l�̊����m�F �O�T�y�j������10�l���@5/14
14���A�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�3799�l�������B�܂��A20��̒j���Ȃ�10�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
�����Ґ��͑O�T�̓y�j��(3809�l)����10�l����A8���Ԃ�ɑO�̏T�̓����j������������B�d�ǎ҂͑O������ς�炸4�l�B14�����_�̐V�^�R���i���җp�a���̎g�p����15.4��(1110�l�^7229��)�B�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�a���g�p����3.2��(26�l�^804��)������(�ǂ��������͍ő�m�ی�����)�B���̂ق��A20��̒j���ȂǁA�j��10�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
|
�����ŐV����3440�l�̊����m�F�@�V�^�R���i�@5/14
���{��14���A�V����3440�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̓y�j���̊����Ґ��́A4192�l�ł����B����������1��8484���ŁA�z������17.7���ł����B
����܂łɑ��{���Ŋm�F���ꂽ�����Ґ��́A�v93��2750�l�ƂȂ�܂��B���{���ł́A�����҂̎��S�͊m�F����܂���ł����B�����̏d�Ǖa���̎g�p����5.8���A�����̌y�ǁE�����Ǖa���̎g�p����20.3���ƂȂ��Ă��܂��B
|
�����M �����g��ŕs���̈���c����̃C���o�E���h���v�Ɋ��ҁ@5/14
13������u�R���i�����g��x��v���o�Ă��鉫�ꌧ�B�A��2000�l�ȏ�̊����҂��m�F����A14����2464�l�ł����B��Ì���ł́c
���ꌧ���k���a�@�@�i�c�b����t�u�Ȃ�Ƃ��ʏ�̈�Â���Ȃ���Ȃ�ł����A���Ȃ�댯�Ƃ������j�n��̂悤�ȏ��ȂƎv���܂��v
���̕a�@�ł́A35�a���̂����A���̂����_��30�l�����@�B�a���g�p����90���ɔ����Ă��܂��B����ɒǂ��ł��������Ă���̂��c
�u��ÐE�����z���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���6�g�A1���̎n�܂�̍���葝���Ă��Ă����ۂŁA�����Ŋu���A����������āA�ꎞ�����҂̎�����X�g�b�v������Ƃ����Ă���B�v
�����ł́A��Ï]���҂̌��ΐ���500�l���A�ʏ�̈�Âɂ��x����������Ă���ƌ����܂��B�l��s���͍���Ҏ{�݂ł��c
���������_�Ɉ�Îx���������s���W���p���n�[�g�ł́A�挎���ȍ~�A������N���X�^�[�����������{�݂ւ̎x���v���������Ă���ƌ����܂��B
�W���p���n�[�g�@�Ō�t�@�{�c��������u�W�c�Ő������Ă���ꏊ�ł���ˁB�����������Ƃ���ŃN���X�^�[���N����̂ł����ɑΉ��ł���X�^�b�t�������������Ȃ���ł���B�����������̗z���̕����o�ăX�^�b�t�������������Ă����ǃR���i�̑Ή��Ɋ���Ă�����X�ł͂Ȃ��̂Ō��\��ςȏɂȂ��ł���v
�a���g�p�����A�܂h�~���d�_�[�u�����ɗv������ڈ��́A60�������{�Ó��B
���ꌧ���{�Õa�@�@�ݖ{�M�O�@���u4���̒��{�ȍ~�AGW�ɓ���܂��āA��葝�����Ƃ����悤�ȏł��B �~�}��2�̕a�@�̂����A�ЂƂɂȂ����̂ŁA��X�����ɂȂ����̂ŁA�f�Ð������s���܂��Ƃ������ƂŁA5����10������ł��ˁv
��^�A�x���A�{�Ó��́A�ό��q�œ�����Ă����ƌ����܂��B�{�Îs�͂��̂��̉�Łc�@�u�Ō�t�̓R���i�����A�Z���ڐG�A���̂ق��̗��R�ŁA20�����܂�×{���ł���v��ÃX�^�b�t�s�����[�����ƌ����܂��B
���ꌧ���{�Õa�@�@�ݖ{�M�O�@���u��ʕa���𐧌����āA���炵�āA�����ǂ̕a���ɊŌ�t����𑗂��Ă���悤�ȏɂ���܂��B���炭�A���s�̗\��𗧂ĂĂ��邩���́A�������炵�Ă���������Ǝv���܂��v
10���l������̊����҂����ꌧ�Ɏ����ő����k�C���B���M�s�ɂ͑�^�A�x���A�吨�̍������s�q���l�߂����܂����B����ό��n�����҂���̂́A�C���o�E���h���v�ł��B���{�͗����ȍ~�A1���̓����Ґ���1���l����2���l�֊ɘa�̕��j�������A�O���l�c�̃c�A�[�q�̎�����������Ă��܂��B
������̃z�e���́A�O���l�ό��q��������ł��łɐV���Ȏ��g�݂��n�߂Ă��܂��B
GRAND PARK ���M�@���ԁ@�~���x�z�l�u�k�C���ɂ����Ȃ��H�ނ���悤�Ƃ��̒��ʼn��Ă̕��A�A�W�A�̕������u�ĂȂ��l�C������̂��W�r�G�����ł��̂ŁA����̓G�]�W�J�̃��[�X���g�����X�e�[�L�����v
���M�s�̊ό��U�����́c
���M�s�ό��U�����@���{�M�[ �劲�u�R���i�O�ɂ�(�ό��q��)800���l���炢���Ă��܂������A���ꂪ�ق�0�ɋ߂��ł��̂ŁA����Ƃ����̂͒n��o�ςɂƂ��đ�ς��ꂵ�����Ƃ��Ǝv���܂��v
�c�̃c�A�[�̒�ԂƂȂ��Ă���s��ł́A���G�Ȏv�����c
���M�s�ό��U�����@���{�M�[ �劲�u����ς�H���Ȃ͕��肵�܂�����A���ԂƂ���ϖ����ȂƂ������͂悬��܂��B�ǂ��̂��X�����������ǁA����ς�O���l���������Ȃ����ȂƂ�����]�ł��ˁB���҂ł��ˁB������̕����傫���ł��B�v
|
�����B�A�I�~�N�����h���^���x���@�V�^�R���i�A�������̋���@5/14
���B���a�\�h�Ǘ��Z���^�[(�d�b�c�b)��13���A�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������h���^�u�a�`�E4�v�Ɓu�a�`�E5�v�����㐔�J���̂����ɉ��B�Ŏ嗬�ɂȂ�A�����҂������������鋰�ꂪ����Ƃ��Čx�����Ăт������B
�ߋ��̊�����N�`���ڎ�œ���ꂽ�Ɖu�������������čL����Ƃ݂��A12���t�Łu���O�����ψي�(�u�n�b)�v�ƈʒu�t�����B
�]���̃I�~�N���������d�Ǔx���オ���Ă��钛��͂Ȃ����A�����҂������钆�ň�芄�������@���A�d�ǎ҂���������\��������B���{�̌����J���Ȃ�12���A���c��`�œ����q�̊������m�F�Ɣ��\�B�v�g�n�͊��ɂu�n�b�Ƃ��Ă���B�@ |
 |
�������s�A�R���i����3348�l�@1�T�ԑO���1363�l���@5/15
�����s��15���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3348�l���ꂽ�Ɣ��\�����B1�T�ԑO�̓��j���̔��\�l�����1363�l�������B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���3956.9�l�ŁA�O�T��124.3���B�I�~�N�������̓����܂����d�Ǖa���̎g�p����3.0���������B7�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
���@���҂�1145�l�A�����d�ǎ҂͑O���Ɠ�����4�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�20�オ755�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�235�l�������B�v�́A�����Ҍv149��1783�l�A���Ҍv4400�l�ƂȂ����B
|
�����ŐV����2576�l�̊����m�F�@������1�l�����S�@�V�^�R���i�@5/15
���{��15���A�V����2576�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̓��j���̊����Ґ��́A3324�l�ł����B����������1��3741���ŁA�z������17.8���ł����B����܂łɑ��{���Ŋm�F���ꂽ�����Ґ��́A�v93��5325�l�ƂȂ�܂��B���{���ł́A������1�l�̎��S���m�F����܂����B
�����̏d�Ǖa���̎g�p����5.8���A�����̌y�ǁE�����Ǖa���̎g�p����21.3���ƂȂ��Ă��܂��B
|
�������ŐV����3��5008�l�R���i�����m�F�c������1�T�ԕ��ς�24���� �@5/15
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�15���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����3��5008�l�m�F���ꂽ�B���҂�25�l�A�d�ǎ҂͑O������14�l����139�l�������B
�����s�ł�3348�l�̊����҂��m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j������1363�l����A2���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�3957�l�ŁA�O�T����24���������B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 4�l���S 2377�l�����m�F �O�T��600�l�]�� �@5/16
�����s����16���̊����m�F��1�T�ԑO�̌��j�����600�l�]�菭�Ȃ�2377�l�ł����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��16���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���2377�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j�����600�l�]�茸��܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�3���A���ł��B16���܂ł�7���ԕ��ς�3866.3�l�őO�̏T��118.2���ł����B2377�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�21.2���ɓ�����503�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�165�l�őS�̂�6.9���ł��B�����o�H���������Ă���815�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v�ŁA68.8���ɓ�����561�l�ł����B
�܂�����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�16�����_��3�l�ŁA15�����1�l����܂����B����A�s�͊������m�F���ꂽ40���60��A70���80��̍��킹��4�l�̒j�������S�������Ƃ\���܂����B
|
����^�A�x��̊����Ґ��}������ꂸ�u�������������v���� �@5/16
��^�A�x���I����Ă���1�T�ԗ]�肪�����܂������A����܂ł̂Ƃ���A�S�z���ꂽ�A�x��̐V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��̋}���͌����Ă��܂���B
���Ƃ́A�����̐l�����ӂ��Ċ�������Ƃ��Ă���Ƃ݂���Ƃ��������ŁA���ꂩ��1�T�Ԃقǂ̊ԂɏǏo�Ă��Ȃ��l�Ȃǂ���̊������L���Ȃ����߂Ɋ�{�I�ȑ�𑱂���悤�Ăт����Ă��܂��B
���Ƃ��̑�^�A�x�́A3�N�Ԃ�ɍs���������Ȃ��������Ƃ��犴���g�傪���O����Ă��܂������A15���̎��_�őS����1�T�ԕ��ς̊����Ґ��͂��悻3��9000�l�ƁA�A�x���O�̐挎28���Ƃقړ��������ŁA�}���ɂ͂Ȃ����Ă��܂���B
����ɂ��āA�V�^�R���i��ɓ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́u�����̐l�����s�ɍs���Ƃ��̈ړ���A�s������̐H���̏�ȂǂŃ}�X�N�̐��������p�⊷�C�Ȃǂ̑�ɒ��ӂ������Ƃ����̏ɂȂ����Ă���̂ł͂Ȃ����B�s�s���Ŋ����Ґ��̑傫�ȑ����������Ă��Ȃ��͔̂��ɂ�������ŁA1�T�ԁA2�T�Ԃɂ킽���đ傫�ȑ���������ꂸ�A�����X����������悤�Ȃ��Ƃ�����A��^�A�x�ő����̐l���ړ����ė��s������A�A�Ȃ����肵�����ł������Ґ��𑝂₳���ɏ��邱�Ƃ��ł����Ƃ������ƂɂȂ���̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂��B
���̂����Łu�����A�s���ɂ͂܂��E�C���X�����݂��Ă���̂ŁA���������l�����2�������A3���������N�����Ȃ��悤�ɁA���܂łǂ����{�I�Ȋ������O�ꂵ�Ĉێ����Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ�v�Əq�ׁA��𑱂���悤�Ăт����܂����B
��^�A�x�����œs���̈ꕔ�̕ی����ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂̓͂��o��������X��������A�������Ċg�債�Ȃ����x���������Ă��܂��B15���܂ł�1�T�Ԃɓ����s���Ŕ��\���ꂽ�V�K�����҂̐��͍��킹��2��7000�l�]��ŁA�O�̏T����24���������Ă��܂��B�k��ł���^�A�x�O�ɔ�ׂĊ����҂̓͂��o�͂��悻10�������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�ی����́A��^�A�x�����͌�������l���������邽�ߊ����҂̓͂��o��������X��������Ƃ��A����1�T�Ԓ��x�͊������Ċg�債�Ȃ����ǂ����x�����K�v���Ƃ��Ēʏ�̂��悻2�{�̑̐��őΉ��ɓ������Ă��܂��B
�k��ی����̑O�c�G�Y�����́u���̂Ƃ��늴�����g�債�Ă��钛��͌����Ȃ����A����A�Љ�o�ς����������邱�ƂŊ������Ċg�債�Ȃ������O�����B�����҂��}�����Ă��Ɩ����Ђ������Ȃ��悤��Ë@�ւȂǂƂ̘A�g�̐����������Ă��������v�Ƙb���Ă��܂��B |
�����{ �V�^�R���i 1�l���S �V����944�l�����m�F �@5/16
���{��16���A�V����944�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�500�l�]�茸��܂����B����ŁA�{���̊����҂̗v��93��6269�l�ƂȂ�܂����B�܂��A1�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�́A���킹��4990�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�15������1�l�����āA21�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�����V�^�R���i944�l�̊����@����`���� �J�����̃��N�`�������@�@5/16
���{��16���A�V����944�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����A1�l�̎��S���m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
���ɖ{�Ђ�u������`����͊J�����̐V�^�R���i���N�`���ɂ���12�`19�ւ̎������n�߂܂����B���̎�����12����19��350�l���ΏۂŃ��N�`����2�^������A�E�C���X�̓�����}����R�̂��ǂꂾ�������邩�𐬐l�ɓ��^�����ꍇ�Ɣ�ׂ���̂ł��B�܂��A3��ڂ̃u�[�X�^�[�ڎ�ɂ��Ă����ʂׂ܂��B
���Ƃ��ɓ���A���s�����I�~�N�������͒Ⴂ�N��w�ł̊����Ґ����������Ă��邱�Ƃ���A����`����͎q�ǂ��ɑ��Ă��ڎ�ł��郏�N�`���̑I�����𑝂₷�K�v������Ƃ��Ă��܂��B�������6���ɂ����ɏ��F��\������v��ł��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 9�l���S 3663�l�����m�F �O�T���800�l�� �@5/17
�����s��17���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���3663�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�܂��A�������m�F���ꂽ70�ォ��100�Έȏ�̒j�����킹��9�l�����S�������Ƃ\���܂����B
1�T�ԑO�̉Ηj����肨�悻800�l����܂����B�O�T���j���������̂�4���A���ł��B17���܂ł�7���ԕ��ς�3753.7�l�ŁA�O�T��109.6���ł����B3663�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�21.2���ɓ�����775�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�234�l�ŁA�S�̂�6.4���ł��B�����o�H���������Ă���1333�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v�ŁA65.4���ɂ�����872�l�ł����B����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO(�l�H�S�x���u)���g���Ă���d�ǂ̊��҂�17�����_��2�l�ŁA16�����1�l����܂����B
|
�����{�ŐV����3932�l�R���i�����c1�T�ԑO����308�l���@5/17
���{��17���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3932�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����308�l�������B
|
������ŃR���i�Ċg��@�l��10���l������̊����Ґ��A�S�����ς�5�{�@5/17
3�N�Ԃ�ɍs���������Ȃ������̐l�o����������^�A�x���I���A���ꌧ�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������Ċg�債�Ă���B�l��10���l������̊����Ґ��͑S�����ς̖�5�{�ɏ��A�Ăт܂h�~���d�_�[�u�Ȃǂ̋K��������ɓ���B����ȊO�̊����Ґ��̑����͂�����݂��邪�A���Ƃ͒Z���ԂŊ������}�g�傷��P�[�X���z�肵�āA�}�X�N���Ȃǂ̊�{�I�ȑ�̓O����Ăт����Ă���B
�A�x�����ŏ��̏T���ƂȂ���14���A�ߔe�s�̊ό��n�E���ےʂ�ł͑����̊ό��q���s���������B���s����悩�痈���j��(59)�́u�����҂͑����Ă��邪�A�ȑO����z�e����\�Ă������痈���v�Ƙb�����B���X���͂ɂ��킢���߂�X�Ɉ��g(�����)�������A�s�����B���Ȃ��B�y�Y���X�̒j���X��(43)�́u�C�w���s�����߂��Ă��邪�A�����҂������čs���������o��悤�Ȃ��Ƃ͔����Ă��炢�����v�ƒʂ�����߂��B
���ꌧ�ł́A�A�x���Ԓ�(4��29���`5��8��)�̐l�o���}�����A�\�t�g�o���N�q��Ёu�A�O�[�v�v�̃f�[�^����ɂ������͂ŁA2021�N�̓����Ԃɔ��1�E6�{�ɂȂ����B�����҂������A11���ɂ͉ߋ��ő���2702�l�̐V�K�������m�F���ꂽ�B�l��10���l�������1�T�Ԃ̊����Ґ���16�����_��1017�E76�l�ɏ��A�S������(209�E29�l)��傫���������B
�����̕a���g�p����16�����_��55�E8���ɒB���A���{�ɂ܂h�~���d�_�[�u�̓K�p��v������ڈ���60���ɋ߂Â��Ă���B����13������{���Ƌ{�Ó��Ȃǂ̋{�Ì���Ɂu�R���i�����g��x��v���o���Ē��ӂ��Ăт����Ă���B
�����g��̔w�i�Ƃ��Ďw�E�����̂́A�l�o�}���ɉ����A���N�`��3��ڐڎ헦��12�����݂őS��55�E19���ɑ��A���ꌧ��40�E73���ɂƂǂ܂��Ă���_���B�܂��A10��Ŋ������}�g�債�Ă���A�����ǂɏڂ������������a�@�̍��R�`�_��t�́u����͐l���ɐ�߂�q�ǂ��̊����������A���傤�����������B�S�[���f���E�C�[�N���Ɏq�ǂ����m�ŗV�Ԓ��Ŋ������L�܂�A�ƒ���̍���҂�Ɋ������L�����Ă���\��������v�Ǝw�E����B
���ʂɘA�x�O(4��28���܂�)�ƘA�x��(5��16���܂�)��1�T�Ԃ̊����Ґ����r����ƁA���ꂪ58�����A�R����54�����Ɗ������L�����Ă���B�{��ł�11���ɉߋ��ő���790�l�̊������m�F�����B����ŁA����A����A�����Ȃǂł͊����҂͌����Ă���A�n��ɂ���Ă�����o�Ă���̂����B
�v���đ�̍a���[�u����(�Ɖu�w)�́u�I�~�N�������͊����͂������̂ŁA����܂ŗz���҂����Ȃ������n��ł��Z���ԂɊ������L����P�[�X�͍l������B�����A�d�ǎҐ����}������ɂȂ邱�Ƃ͍��̂Ƃ���l���ɂ����A��{�I�ȑ���p�����邱�Ƃ��d�v���v�Ƙb�����B
|
���a�`�E2�̕a�����ς�炸�@����A�I�~�N��������r �@5/17
���ݗ��s����V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������h���^�u�a�`�E2�v�̕a�����́A�����I�~�N�������Ő�ɗ��s�����u�a�`�E1�v�Ɠ����x�ɒႢ�Ƃ��铮�������̌��ʂ𓌋����Ȋw�������͉̉��`�T���C����(�E�C���X�w)��̃`�[����17���A�p�Ȋw���l�C�`���[�d�q�łɔ��\�����B
���Âɂ͉���`�������̔��̏��F�����ɐ\�����̍R�E�C���X��Ȃǂ��L���Ƃ��Ă���B�ʂ̌����ła�`�E2�̕a�������a�`�E1��荂�܂����\�����w�E����Ă������A����̎����͂����ے肷�錋�ʂƂȂ����B
�`�[���͊����҂�����o�����E�C���X���n���X�^�[��}�E�X�Ɋ��������ĕ��͂����B
|
���d�_�[�u�̌������v���@�R���i��Ł\�S���m����@5/17
�S���m����̕���L���(���挧�m��)��17���A�V�^�R���i�E�C���X����߂���㓡�ΔV�����J�����ƈӌ����������B���䎁�́A�܂h�~���d�_�[�u�Ɋւ��A���H�X�𒆐S�Ƃ����Ή������߁A�w�Z�⍂��Ҏ{�݂Ȃǂł�����u������悤��������v�������B �@ |
 |
���k�C���̐V���Ȋ���2677�l�A�O�T��|582�l�c���S7�l�A�D�y1090�l�@5/18
18���A�k�C���S�̂̐V���ȐV�^�R���i�E�C���X�����m�F��2677�l�ł����B60��2�l���܂�7�l�̎��S�����\����Ă��܂��B2���Ԃ��2000�l�����������̂́A��T�̐��j��(11��3259�l)���582�l���Ȃ��Ȃ��Ă��āA�O�T�̓��j���������̂�4���A���ł��B�V���Ȋ����m�F2677�l�̓���́A�D�y�s��3���Ԃ��1000�l������1090�l�A����s��2���A��200�l������247�l�A���َs��2���A��100�l������152�l�A���M�s��2���A��50�l������67�l�A�k�C�����\��14�̒n���̍��v�A2���A��1000�l������1121�l�ł����B
�O�T�̓��j���Ɣ�r����ƁA�S�Ă̔��\�ʼn����A�D�y�s��4���A��(�|248�l)�A����s��5���A��(�|25�l)�A���َs��4���A��(�|47�l)�A���M�s��4���A��(�|9�l)�A14�̒n���̍��v��3���A��(�|253�l)�ł��B
�k�C�����\1121�l�̒n�����Ƃ̓���́A�Ύ�180�l�A��m101�l�A��u10�l�A�_�U176�l�A����33�l�A�n��41�l�A�O�R12�l�A���84�l�A���G10�l�A�@�J45�l�A�I�z�[�c�N171�l�A�\��125�l�A���H90�l�A����35�l�A���O�ݏZ�Ȃ�8�l�ł����B200�l�ȏ�̒n���͂Ȃ��Ȃ�܂���(�_�U��200�l�������̂́A9���Ԃ�)�B100�l�ȏ�́A�Ύ��52���A���A��m��7���Ԃ�A�_�U��11���A���A�I�z�[�c�N��4���Ԃ�A�\����2���Ԃ�ł��B50�l�ȏ�̒n����O�T�̓��j���Ɣ�r����ƁA���(�{3�l)�A�I�z�[�c�N(�{28�l)��������A�Ύ�(�|47�l)�A��m(�|38�l)�A�_�U(�|32�l)�A�\��(�|77�l)�A���H(�|45�l)�A���(�{6�l)�ʼn�����Ă��܂��B
���S�́A�k�C�����\��60��A80��2�l�A90��A�D�y�s���\��60��A80��2�l�ł����B
18�����\(17������)�̖k�C���S�̂̊��Ґ��͑O�����560�l������25,774�l�A���̂����d�ǂ͑O�����1�l������7�l�A�y�ǁ{�����ǂ�25,767�l�A���@���҂�17�l������415�l�ƂȂ��Ă��܂��B�a���g�p����19.3���ŁA2���Ԃ��20���������܂����B�D�y�s�����̕a���g�p����19.4���ŁA3���A����20����������Ă��܂��B
|
�������s �V�^�R���i 7�l���S 4355�l�����m�F �O�T���400�l���@5/18
�����s����18���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̐��j����肨�悻400�l���Ȃ�4355�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s�́A18���s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��4355�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j����肨�悻400�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�5���A���ł��B18���܂ł�7���ԕ��ς�3695.3�l�ŁA�O�̏T��100.5���ł����B18���Ɋm�F���ꂽ4355�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�21.3���ɓ�����926�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�276�l�ŁA�S�̂�6.3���ł��B�����o�H���������Ă���1682�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v�ŁA64.4���ɂ�����1084�l�ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A18�����_��1�l�ŁA17�����1�l����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70�ォ��90��̒j�����킹��7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����3497�l�R���i�����c1�T�ԑO����182�l���@5/18
���{��18���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3497�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����182�l�������B
|
�������g�呱������@����×{���ߋ��ő�1��4666�l�@�{�ݓ��×{�҂��ő��Ɂ@5/18
���ꌧ��18���A�V����10�Ζ�������90�Έȏ��2560�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T���j����2702�l�Ɏ����ŁA�ߋ�2�Ԗڂɑ����B���@�����ɎЉ���{�ݓ��ŗ×{���̐l��115�{��321�l�ŁA�{�ݐ��E�×{�Ґ��Ƃ��ߋ��ő��B���͎{�݂̋Ɩ��p���̂��߁A�Ō�⏕�҂��W���Ă���B
�×{���̊��҂�1��8040�l�A��������×{����1��4666�l�ŁA��������ߋ��ő��B����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ���1002�E0�l�ŁA��l�䂪�����Ă���B
����1�T�Ԃ̊����Ґ���O�T�Ɣ�r�����u�O�T��v��1�E13�{�B13���ɂ�1�E69�{�܂ŏ㏸���Ă���A���̋{���`�v�����������Ắu�����g�傪�����Ă��邪�A�����͂��݉�������v�ƕ��͂����B
���S�̂̃R���i�a���g�p����55�E3���B�����ȂǂŌ����Ă����Ï]���҂́A��ȏd�_��Ë@�ւ�598�l�ɑ������B
�{�Õی����Ǔ��ł�4������5���ɂ����A3�J���̎Љ���{�݂�6�`15�l�̐V�K�N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F���ꂽ�B�ČR��n���̐V�K�����҂�124�l�B
|
�������̐V�K�R���i����4��2161�l�c����40�l�A�d�ǎ҂�125�l �@5/18
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�18���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����4��2161�l�m�F���ꂽ�B���҂�40�l�ŁA�d�ǎ҂͑O������2�l����125�l�ƂȂ����B
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̓d�q�������ʐ^(���������nj�������)�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̓d�q�������ʐ^(���������nj�������)
�����s�̐V�K�����҂�4355�l�B�O�T�̓����j������409�l����A5���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��̕��ς́A�O�T����قډ�����3695�l�������B70�`90��̒j��7�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
|
���ăR���i�V�K�����҂��g��X���A�m�x�s�͌x�����x�������グ�@5/18
���C�^�[�̏W�v�ɂ��ƁA�č��ł͐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�1������9��7000�l�߂��ɏ��A1�T�ԑO�̖�7��3000�l���瑝�����Ă���B3�����{��3���l�܂Ō������Ĉȍ~�A�g��X���ɂ���B
�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)��17���A��T�̊����҂̖����I�~�N�����ψي��́u�a�`.2.12.1�v���n���ɂ��Ƃ̐�������\�B4�����{����L�܂��Ă���A���ɓ��C�݂̑啔���ŗD���ƂȂ��Ă���B
�o���_�[�r���g��w��ÃZ���^�[(�i�b�V���r��)�̊����ǐ���ł���E�B���A���E�V���t�i�[���m�́u����A���̃E�C���X�̉e�����ǂ̒��x�ɂȂ�����}�X�N���p���ĂъJ�n���A�Љ�I����������ɒu���K�v������̂����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�j���[���[�N(�m�x)�ł͍��܂��ɂ��̂悤�ȋc�_���s���Ă���v�Əq�ׂ��B
�m�x�s�͓����A�R���i�x�����x�����u���v�Ɉ����グ���B�s�ی����ǂ́A�S�Ă̐l�͌����̉����ŁA65�Έȏ�̐l�⍂���X�N�̐l�͍��G�������O�Ń}�X�N���p���邱�Ƃ������������Ă���B
�����������A�t�@�C�U�[�̌o���R�E�C���X��u�p�L���r�b�h�v�́A�ߋ�4�T�Ԃŗ��p��315���}�������B�ĕی����ǎ҂����炩�ɂ����B
|
�������̐V�^�R���i�V�K�s�������Ґ���1227�l�c��C��3���A��1��l�ȉ��@5/18
�����{�y�ł́A��r�I���������ɐV�^�R���i�̕������߂ɐ������A�ȍ~�͑S���I�ɂ͈��肵���ƂȂ�A�U���I�Ȏs�������m�F�Ⴊ�x�X�o��������x���������A���N(2022�N)�ɓ����Ĉȍ~�̓I�~�N�����ψي��y�т��̈���(������u�X�e���X�I�~�N�����v��)�̗������A�ꕔ�n��Ŕ�r�I��K�͂ȍė��s���o�����Ă���B
�����̍��Ɖq�����N�ψ���(NHC)��5��18�����Ɍ����T�C�g��Ō��\�������ɂ��A����17���̒����{�y�ɂ�����V�K�s�������m�F�Ґ���227�l(�O������65�l��)�������Ƃ̂��ƁB����́A��C�s96�l�A�k���s52�l�A�l���49�l�A�V�Îs16�l�A�g�я�9�l�A�͓��3�l�A�]�h��1�l�A�C��1�l�B���̂�����C�s��56�l�A�V�Îs��10�l�A�k���s��9�l�A�l��Ȃ�2�l�A�g�яȂ�1�l�A�͓�Ȃ�1�l�̌v79�l�����Ǐ犴���m�F�ɓ]�������āB�����{�y�Ŏs�������m�F�Ⴊ�o������̂�214���A���A15���A����500�l�ȉ��ƂȂ����B
�s���̖��Ǐ����1000�l(�O������113�l��)�B����́A��C�s759�l�A�l���152�l�A�V�Îs39�l�A�k���s17�l�A���J��15�l�A�͓��8�l�A�g�я�3�l�A�]�h��3�l�A�ɔJ��1�l�A���]��1�l�A�Ζk��1�l�A�L����1�l�B
���Ǐ���܂ސV�K�����Ґ���1227�l�ŁA5���A��2��l�ȉ��ɁB���̂�����C�s�̕���855�l�ɏ��A�S�̂�69.7%���߂��B��C�ł�3���A��1��l�ȉ����ێ��B
5��17��24�����_�̒����{�y�Ŏ��Ò����Ă��銴���m�F�Ґ���5205�l(�����A������178�l)�ŁA�d�ǎ҂�301�l(�A�����̓[��)�B���Ǐ�̊���4��7718�l(�A����441�l)����w�ώ@���ɂ���Ƃ̂��ƁB
�������ǂ͈���ɂ�����g�U�h�~�Ɠ����ɁA��O����̗����Ɖ@��������h�~���邽�߂̓O�ꂵ���[�u���u����Ȃǂ��āu����(�[���R���i��)�v��ڎw���O��I�ȑΏ���i�߂Ă����B��̓I�ɂ́A�ǒn���b�N�_�E���A�S��PCR�����ɂ��X�N���[�j���O�A�����ׂ��ړ��̐����A���H�X���̓���Ǝ�ɑ���c�Ɛ������̑[�u����������B�����_�ł��[���R���i�������������l�����d�˂ċ������Ă���A���炩�̕����[�u���u�����Ă���n�悪�������݂���B
���N�ɓ����Ĉȍ~�A�I�~�N�����ψي��̗����ɔ����A�����{�y�̑����̏Ȏs��ŐV�K������̏o���������Ă��邪�A���ɐ[���Ȃ̂���C�s�B���s�ł�3�����{���玖����̃��b�N�_�E��(�s�s����)��Ԃɂ���B�������A���̂Ƃ��듯�s�ɂ�����V�K�����m�F���͊ɂ₩�ȉ����X���ɂ���A�s���ǂ�5�����̎Љ�ʐ���(�u���ΏۈȊO�̈�ʎs���ɂ�����[���R���i��)������ڕW�Ƃ��Čf���Ă������A17�����_�Ŏs���S16��ł���������ł����Ƃ̌������������B����A�����G���A�̏k���A�J���������i�߁A6��1�����璆�E���{�ɂ����Đ��퉻��}��v������炩�ɂ��ꂽ�B
4��22���ȍ~�A�k���s�ł��A��2���̊����Ⴊ�����Ă���A����܂ł̗v�����Ґ���1100�l���ɏ��B�s���ł͐E��N���X�^�[�������������Ă���A�ˑR�Ƃ��ĎЉ��(�u���Ώۂł͂Ȃ���ʎs��)�ɂ�����`�d�`�F�[�����f����Ă��Ȃ��Ƃ����B�L���ł͕s�v�s�}�̋�O�ւ̈ړ��𐧌�����[�u���u������ȂǁA�s���ɂ�����h�u��̋������i��ł���B
���`�E�}�J�I�Ɨ��Őڂ���L���Ȃł��A���N�ɓ����Ĉȍ~�A�L�B�s�A�[�Z���s�A���Ύs�A��C�s�A���R�s�ȂǂŒf���I�Ɏs�������m�F�Ⴊ�o�����Ă������A���̂Ƃ���͗��������Ă���A4��22���܂łɏȓ��S�悪��X�N�n��ɕ��A�����B�������A�ߓ��͍L�B���_���ۋ�`�̐E���y�т��̓��Z�҂𒆐S�Ƃ����V���Ȋ����Ⴊ�������o���B�܂��A�ȓ암�̒X�]�s�ł�5��7������q�ɉ�Ђ[�Ƃ��������̊����҂��o���������A�ʎs���ւ̊g�U�͂Ȃ��͗l�B
�}�J�I���ʍs����ł�5��17���܂�219���A���s�������m�F��[���ƂȂ�������A���`���ʍs����ł͍�N(2021�N)12��������V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s�u��5�g�v���n�܂����B2������3�����ɂ����Ċ����m�F���̋}��������A3�����{�Ƀs�[�N���߂����Ƃ����B��5�g�J�n�ȗ��A5��17���܂ł̗v��119.6���l(���Ǐ�܂�)�A���S�Ґ���9148�l�ɁB17���P���ł�328�l(�A����39�l�܂�)�ŁA4���Ԃ�ɑ����ƂȂ������A24���A����500�l�ȉ����ێ��B���S�҂�����2���A���[���B�ڗ��������o�E���h�͔������Ă��Ȃ����̂́A����2�T�Ԃ�200�`300�l�O��ʼn����~�܂��Ă���B�\�[�V�����f�B�X�^���X�[�u�̊ɘa���āA�ߓ��̓N���X�^�[�̔����������Ă��邪�A���{��17���A�\��ʂ�19������\�[�V�����f�B�X�^���X�[�u�̑��i�K�ɘa�����{����Ɣ��\�B����܂ō��`�ł͏�C�s�̂悤�ȑS�惌�x���ł̃��b�N�_�E���͎��{����Ă��炸�A����̃}���V���������ΏۂƂ����ǒn���b�N�_�E���ɂƂǂ܂�B
|
�������Ȃ��̃S�[���f���E�C�[�N�@�����Ґ��ւ̉e���́@5/18
�l�̈ړ�������������2022�N�̃S�[���f���E�C�[�N�́A�V�^�R���i�̊����Ґ��ɂǂ̂悤�ȉe����^���Ă���̂ł��傤���B�����ǂɏڂ��������w��w�@�̐X���_�K�����ɕ����܂����B
�X���_�K�����u�z��͈͓������A�ނ��낱��Ȃ���ōς�ŗǂ������ȂƂ��������ł��v
2022�N�̃S�[���f���E�B�[�N�́A�V�^�R���i���������Ă��珉�߂Ĉړ������̖����S�[���f���E�B�[�N�ɂȂ�A�{�錧���̊ό��n�ł��ɂ��킢�������܂����B
�x�ݒ��͌����������Ȃ��������Ƃ�����܂����A�A�x�����̊����Ґ��͑O�̏T�̓����j����6���A���ŏ�������A17���܂ʼn������������Ă��܂��B
�X���_�K�����u�O�ł�������Ȑl���̉e����1�T�Ԍ�A2�T�Ԍゾ�ƌ����Ă��܂������A����(�����T�C�N����)���㎞�Ԃ͂�������2���ɂȂ��Ă��܂�����A�����ɉe���͏o��Ǝv���܂��v
�X�������́A���ɘA�x�̉e���͊����Ґ��ɕ\��Ă���Ƃ��A�l�̈ړ��͂���Ȃ��炻�ꂼ�ꂪ��������Ƃ������ƂŔ����I�ȑ����ɂ͂Ȃ���Ȃ������Ƃ̌����������܂����B
�ł́A����̊����Ґ��͂ǂ̂悤�ȕω����݂���̂ł��傤���B�X�������́A�E�C���X�̗͂���܂�ď�ɂȂ����A�I�~�N�������̌n���̈�Ŋ����͂̋����a�`�D2��w�d�ւ̒u������肪�A�ǂ̒��x�i�ނ̂����e����^����Ƃ݂Ă��܂��B
�X���_�K�����u��芴���͂̋����a�`�D1������ɂقƂ�ǂa�`�D2�ɒu��������Ă��܂�����ǂ��A�X�ɂ�������������������炢�����͂̋����w�d�Ƃ��A�X�ɂ͂a�`�D4��a�`�D5���K�������Ă��Ēu��������Ă������낤�B���̌��ʂƁA�ď�ɂȂ��ăE�C���X���̂�������ƌ��C���Ȃ��Ȃ���ʂ��v���X�}�C�i�X�[�����炢�ŁA���炭�̊Ԃ͍����炢�̐����������\���͂���̂��ȂƎv���Ă���v
|
�����{ ��H���̐l������ �F�ؓX��5��22���ʼn���������@5/18
���{�́A�V�^�R���i�̑��{����c���J���A�V�K�����҂͑����X���ɂ͂Ȃ��A�����͔�r�I���������Ă���ȂǂƂ��āA�{�̔F�����X�ɂ��ẮA����(5��)22���̊����ł����āA��H���̐l���������������邱�Ƃ����߂܂����B
���{�́A��^�A�x�̐l�o�̉e���Ȃǂɂ�銴���g��Ɍx�����K�v���Ƃ��āA����22���܂ł̊��ԁA�{���̈��H�X�ɑ��A����e�[�u��4�l�ȓ��ȂǂƂ���l��������v�����Ă��܂��B
���̊�����O�ɁA�{��18���A�V�^�R���i�̑��{�����J���A�g���m���́A�u��^�A�x�͌x�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƕ{���ɂ��肢���Ă������A�����̑傫�ȎR�͋N���Ă��Ȃ��̂����B���̊����g��ɔ����Ĉ�Ñ̐�����������ƂƂ��ɁA�Љ�o�ς����ɖ߂��A�E�C���X�Ƌ������铹��͍��������v�Əq�ׂ܂����B
�����āA��c�ł́A�{�̔F�����X�ɂ��ẮA����22���̊����ł����āA�l���������������邱�Ƃ����߂܂����B
�܂��A��H��2���Ԓ��x�Ƃ���v�������킹�ĉ������܂��B
����A�F���Ă��Ȃ��X�ɂ��ẮA���������A5�l�ȏ�̃O���[�v�̓��X�͍T����H��2���Ԓ��x�Ƃ���悤�v�����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
����ɁA��c�ł́A�����Ґ���a���̎g�p���Ȃǂ����ƂɌx�����x���������u��ヂ�f���v�ɂ��Ă��A����23���Ɍx���������u���F�v����A�x�������́u�v�Ɉ��������邱�Ƃ����߂܂����B
����ア������Ⴂ�L�����y�[���ĊJ��
���{�̑��{����c�̂��Ƃ̋L�҉�ŁA�g���m���́A�{����A�ߗׂ̕{���̗��s�҂�ΏۂɁA���s��p�̈ꕔ����������u��ア������Ⴂ�L�����y�[���v�ɂ��āA������{�܂łɍĊJ���������Ƃ����l���������܂����B
���̂����ŁA�L�����y�[���̑Ώۂ́A�V�^�R���i�̃��N�`����3��ڎ킵���l���A�����ʼnA�����m�F���ꂽ�l�Ƃ�����j�𖾂炩�ɂ��܂����B
�g���m���́A�u�ߗו{���Ƃ�������i�߁A�ł��邾���L�����p�ł���悤�ɂ������v�Əq�ׁA�ߗו{���Ƃ̒����������������A�L�����y�[�����n�߂�l���������܂����B
����A�g���m���́A���̊ό����v�̊��N��ɕύX���������ꍇ�́A���̕��j�ɉ����đΉ�����l���������܂����B
�����Ɓg�����I�ɂ��Ă��������h
�V�^�R���i�̑���߂���A���{����H���̐l�������̉��������߂����Ƃɂ��āA��������w�̏��c�g�� �����́A�u�����Ґ��̑啝�ȑ����݂͂�ꂸ�A��r�I���������Ă�����B�������������͎��{���Ԃ��������Β������قǎ��l������A���҂ł�����ʂ������Ƃ�����������B�����I�Ȃ��Ƃ�����Ă݂Ă����������ɗ��Ă���Ǝv���v�ƕ]�����܂����B
���̂����ŁA��������ꍇ�̒��ӓ_�Ƃ��āA�u�����ɂ���Ă�����x�����Ґ��������邱�Ƃ͐D�荞�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����̕ω��͈��������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���{�́A�����ɂ���Ăǂ�ȉe�����o�����͂��A����I�Ɍ��\���ĕ{���ɐ������ׂ����Ǝv���B���̂����ŁA�����Ґ��̑����ɂ���Ĉ�Ñ̐��̂Ђ������\�z�����悤�ȏɂȂ�Ăё�����߂邱�Ƃ��������ׂ����v�Ǝw�E���܂����B
�܂��A5�l�ȏ�̉�H�Ȃǂ��s���ۂ̒��ӓ_�ɂ��ẮA�u�Ƃ�ׂ������h�~��͂���܂łƕς��Ȃ����A�Ƃ�킯�d�v�Ȃ̂͊��C��������ƍs�����ƂŁA���X�������łȂ��Q������l�l���ӎ����ׂ��|�C���g���B�܂��A�̒����v�킵���Ȃ��l�ւ̔z������ŁA�Ⴆ�A�E��̏d�v�ȉ����Q�����Ȃ�������Ȃ��ȂǂƂ����������͂������Ȃ��悤���ӂ��K�v���v�ƌĂт����Ă��܂����B
�����Ɍ� �ߗׂ��l��������
���Ɍ��ł́A���Ƃ�3���ɂ܂h�~���d�_�[�u���������Ĉȍ~�A���H�X�ł̉�H��1�̃e�[�u����4�l�ȓ��Ƃ��A2���Ԓ��x�ɂƂǂ߂�悤�Ăт����Ă��܂��B����̑Ή��ɂ��Č��̒S���҂́A�u������ߗו{���̏��l�����Č������Ă��������v�Ƃ��Ă��܂��B
�����s�{ ��H��p����
���s�{�ł́A�V�^�R���i�̊����h�~��Ƃ��āA���H�X�ł̉�H��1�̃e�[�u����4�l�܂ŁA���Ԃ�2���Ԉȓ���ڈ��ɂ��ĕ{�̔F�����X�܂𗘗p����悤���߂�Ăт������p�����Ă��܂��B��H���̐l�������Ȃǂ̑���ɘa���邩�ǂ����ɂ��āA�{�́A�����Ґ������~�܂肵�Ă��邱�Ƃ���A�������炭�����̐��ڂ����ɂ߂������ŁA����A�������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�����ꌧ �l�������݂���
���ꌧ�ł́A�����ɑ��A����������ŔF�������H�X�𗘗p����悤���߂Ă��܂����A�l�������݂͐��Ă��܂���B����A��H�̍ۂ́A�}�X�N�𒅗p���邱�Ƃ�A�ł��邾�����l���ŒZ���Ԃōς܂���ȂǁA�������X�N��������H�v������悤�Ăт����Ă��܂��B
|
��2���Ԃ�}�C�i�X�����@�f�c�o�N��1�����A�ψي��ŏ���s�U�\1�`3���������@5/18
���t�{��18�����\����2022�N1�`3�����̍��������Y(�f�c�o�A�G�ߒ����ς�)����l�́A�����ϓ��̉e���������������őO����0�D2�����A���̐�����1�N�������ꍇ�̔N�����Z��1�D0�����������B�}�C�i�X������2�l�����Ԃ�B�V�^�R���i�E�C���X�ψي��̊����g��ɔ����u�܂h�~���d�_�[�u�v�̉e���ŁA�O�H�Ȃǂ̌l����U���Ȃ������B
���ޗ����i�̏㏸��V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɔ����Đ��E�o�ς̐�s���s�����������܂��Ă���A4�`6�����ȍ~�̌i�C�ɋt���ƂȂ�\��������B�R�ۑ�u�Y�o�ύ����S������18���̋L�҉�Łu�i�C�̉��U�ꃊ�X�N�ɂ�������ƑΉ����A�R���i�Ђ���̌o�ώЉ���̉��m���Ȃ��̂Ƃ���v�Ƌ����B4���Ɍ��肵�����������ւ́u�����ً}��v�𒅎��Ɏ��s����l�����������B
21�N�x�̎����f�c�o�͑O�N�x��2�D1������3�N�Ԃ�ɉ��P�����B20�N�x��4�D5�����Ɛ��ň��̗������݂��L�^���������ŁA�����ݔ������A�A�o�Ƃ�������v���ڂ������݃v���X�ƂȂ����B�������A�͈͂ˑR�Ƃ��ē݂��A22�N1�`3�����̎����f�c�o���z�͔N�����Z��537���~�ƁA�R���i�O��19�N10�`12�����̐���(541���~)�ɓ͂��Ă��Ȃ��B
1�`3�����̌l����́A�D����������N10�`12���������]���A�O����0�D03���Ə����Ȃ��猸���B�O�H��h���A���q�A���Ƃ������T�[�r�X����ᒲ�������B�Z����́A���z���ނ̍�����������1�D1�����ƕs�U�B���������́A�����{��k�Ђ���̕����Ɋ֘A������^�H�������������Ƃ�3�D6�����Ɨ������B
�ݔ������̓K�X�^�[�r���Ȃǂ̔ėp(�͂�悤)�@�B���L�т�0�D5�����������B�����S�̂ł͂f�c�o��0�D2���������グ���B
�A�o�͎����Ԃ�����������1�D1������2���A���̃v���X�B����A�A���̓��N�`����g�ѓd�b�Ȃǂ̑�����3�D4�����ƂȂ�A�O���S�̂ł�0�D4�����̂f�c�o�������v���ƂȂ����B
�����ϓ��̉e���f���A���������ɋ߂����ڂf�c�o�͑O����0�D1�����A�N�����Z��0�D4������2���A���̃v���X�������B �@ |
 |
�������R���i�����A4172�l�@��Ñ̐��x���x���������@5/19
�����s��19���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����4172�l���ꂽ�Ɣ��\�����B1�T�ԑO�̖ؗj������44�l�������B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���3689�l�ŁA�O�T���93.4���B5�l�̎��S�����ꂽ�B
�܂��A��Ò̐��Ɋւ���Ǝ��̌x�����x����1�i�K�����������B��4�J���Ԃ�ɁA4�i�K�̂���������2�Ԗڂ́u�ʏ��ÂƂ̗������\�ȏv�Ƃ����B���@���҂�1162�l�ŁA�d�ǎ҂͑O����1�l����2�l�������B�I�~�N�������̓����܂����d�Ǖa���g�p����2.2���B�V�K�����҂̔N��ʂ�20�オ860�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�262�l�B
|
�����{�̃R���i���ҁA5000�l������@4000�l������80���@5/19
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ����{�̎��҂�19���A�V����7�l���m�F����A�v��5005�l�ɂȂ����B�S���̓s���{���Ŏ��҂�5000�l�����̂͏��߂āB
���ł́A�����Ґ����S���ōł����������s(19�����_�Ŏ���4425�l)������y�[�X�Ŏ��҂������Ă���A�S���̎��Җ�3���l��6����1���߂�B���ɁA�I�~�N�������ɂ�銴�����}�g�債���u��6�g�v(�{�̒�`��2021�N12��17���ȍ~)�̎��҂�1941�l�ƑS�̂�4���߂��ƂȂ��Ă���B3��3���ɗv�̎��҂�4000�l���Ă����80���Ԃ�1000�l������n�C�y�[�X���B
�ψي��u�A���t�@���v���҈Ђ�U������u��4�g�v(21�N3��1���`6��20��)�����҂�1539�l�Ƒ����A�S�̂�3�����߂��B����҂ւ̃��N�`���ڎ킪�Ԃɍ��킸�A60��ȏ�̊����҂�11�E2�������S�����B�S�N��̎��S����2�E8���ŁA�V�^�R���i���u���m�̊����ǁv�Ƃ��ēo�ꂵ���u��1�g�v(20�N6��13���܂�)��4�E9���Ɏ����ō��������B
�A���t�@����芴���͂������u�f���^���v�ɂ���5�g(21�N6��21���`12��16��)�ł͎��҂�358�l�ɂƂǂ܂����B���N�`���ڎ킪�i���Ƃ�A�d�lj���h�����a�R�̖�̓��^�����������Ƃ��v���Ƃ݂���B60��ȏ�̎��S����3�E7���A�S�N���0�E4���ɂ܂Œቺ�����B
�������A��6�g�ł͉ߋ��ɂȂ������������N����A���҂����������B�R���i�ȊO�̎����ň�Ë@�ւɓ��@���Ă��鍂��҂ɂ��������g��B�x���ł͂Ȃ���b�����̈����ŖS���Ȃ�P�[�X���������A5��8�����_�Ŏ��҂�97�E1����60��ȏオ��߂�B����A���S����60��ȏオ2�E0���A�S�N���0�E27���Ƃ���ɉ��������B
���̎��҂������̂́A����Ҏ{�݂ŃN���X�^�[(�����ҏW�c)���������A���S���X�N�̑傫������҂̊����������������Ƃ����R�Ƃ����B��6�g�̂��Ȃ��ɂ�����2���ȍ~�ł݂�ƁA�����ł͊�����5�l�ȏ�̃N���X�^�[���N�����̂�444�{�݁A�����҂�7519�l(�������4��17�����_)�������̂ɑ��A���ł�572�{�݂�9740�l(��13�����_)��3���قǑ����B
�{�́A����Ҏ{�݂ł̃N���X�^�[������h�����߁A�{�ݐE����ɑ�3����1��̍R��������������j��ł��o�����B��Q�Ҏ{�݂��܂߂Ė�4500�{�݂��ΏۂŁA���ł�80���ȏ�̌����L�b�g��z�z���Ă���Ƃ����B�܂��A�R���i���҂�����Ă��Ȃ��a�@�ɑ��A���@�Ŕ��������R���i���҂ɂ��ē���Ȃǂ̏������Â��s���悤���߂Ă���B�g���m���m���́u����Ҏ{�݂ƈ�Ë@�ւɂ���n�C���X�N�̍���҂��ǂ���邩���d�v�ŁA��������������v�Ƙb���Ă���B
|
������@�q���̊����Ɏ��~�߂����炸�@�u�܂�h�ł͌��ʂ��Ȃ��v�@5/19
�����ł�19���ɐV����2307�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����܂����B19���ɔ��\���ꂽ�V�K�����҂͐�T�̖ؗj�����23�l���Ȃ�2307�l�ŁA3���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B�N��ʂł�10�オ424�l�ƍł�����������10�Ζ�����408�l�ƂȂ��Ă��܂��B���̊�ɊY������d�ǂ�2�l�A�����ǂ�178�l��1��5000�l�߂��̐l������ŗ×{���Ă��܂��B
�ʏ�m���͌ߌ����A������ړI�Ƃ����~�}�O���̎�f�ŋ}��v���銳�҂̑Ή��ɒx�ꂪ�o�Ă���Ƃ��Ċ����̗L�����m�F����ꍇ�͎s�̂���Ă����×p�̍R���萫�����L�b�g�����p���Ăق����ƌĂт����܂����B
�q�ǂ��̊����Ɏ��~�߂������炸�A�N���X�P�ʂŌ�������w�Z�o�b�q�����̑Ή��ɒx�ꂪ�o�Ă��邱�Ƃ���A���͍R���萫�����L�b�g�𑬂₩�ɔz�z���鏀����i�߂Ă��܂��B
�V�K�����҂����~�܂肷�钆�A�܂h�~���d�_�[�u�ɑ���l��������ꂽ�ʏ�m���͎��̂悤�ɏq�ׂ܂����B
�ʏ�f�j�[�m���u���H�X�����S�̂܂h�~���d�_�[�u�͂����Ă����ʂ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����t�G�r�f���X�̐������łĂ���B�{���ɕK�v�ȑ�͂ǂ���������������ƌ��ɂ߂Ă��������v
�ʏ�m���͎q�ǂ��𒆐S�Ƃ��������̍L�����H���~�߂�ɂ͐V�������������K�v������Ƃ��Č��s�̏d�_�[�u�̓K�p�ɐT�d�Ȏp�����d�˂Ď����܂����B
|
������m���u�K�v�ȑɂ߁v�@�d�_�[�u�\���ɐT�d�p���@5/19
���ꌧ�̋ʏ�f�j�[�m����19���̋L�҉�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ɋ֘A���āu���H�X�̉c�Ǝ��ԒZ�k��x�Ƃłǂ̂悤�Ȍ��ʂ������܂�邩���ƈӌ��������A�{���ɕK�v�ȑ�����ɂ߂����v�Əq�ׂ��B
�����͕a���g�p����60%�ɒB�����̂�ڈ��ɁA�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�\������������l���������Ă���B�ʏ鎁�́A�����ł͎q���̊����Ґ��������A���H�X�̉c�Ƃ𐧌�����d�_�[�u�ł͊�����}������ʂ������Ǝw�E�B�\���ɂ͐T�d�Ȏp�����������B
����̒���1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���1000�l���A�S���ōł������B���ɂ��ƁA19�����_�̃R���i�a���g�p����54%�ƂȂ��Ă���B
|
�������@5/19
�S���̐V�K�����Ґ�(����)�́A���߂�1�T�Ԃł�10���l�������203�l�ŁA���T��T���1.07�ƂȂ��Ă��邪�A���̐����ɂ����钼��1�T�Ԃ̈ړ����ς͌����X���ɂ���A�����X�����p�����Ă���GW�O�̐��������Ⴍ�Ȃ��Ă���BGW�ɂ�鐔�l�ւ̉e�������邽�߁A����̓����ɒ������K�v�B
�N��ʂ̐V�K�����Ґ��́A�S�Ă̔N��Ŕ������͑������Ă���A����20��Ō����ȑ�����������(5����2�T�Ƒ�1�T�̔�r)�B
�S���̐V�K�����Ґ��������ɓ]���Ă��邱�Ƃɔ����A�×{�Ґ��͑����X���B����A�d�ǎҐ��͌����������A���S�Ґ��͉����B�����Đ��Y���F�S���I�ɂ́A����(5/1)��0.97��1������鐅���ƂȂ��Ă���A��s���ł�0.94�A�����ł�0.97�ƂȂ��Ă���B
���n��̓���
�V�K�����Ґ��̐��l�́A���x�[�X�̒���1�T�ԍ��v�̑ΐl��10���l�̒l�B
���k�C��
�V�K�����Ґ��͍��T��T�䂪1.07��1������A��346(�D�y�s��402)�B20��ȉ������S�B�S�Ă̔N��ő������Ă���A����20��̑����������B�a���g�p���͖�2���B
���k�֓�
���̐V�K�����Ґ��͍��T��T�䂪1.08��1������A��134�B20��ȉ������S�B����20��̑����������B�a���g�p���͖�1���B�ȖA�Q�n�ł͍��T��T�䂪���ꂼ��0.89�A0.92��1�������A�V�K�����Ґ��͂��ꂼ���135�A128�B�a���g�p���ɂ��āA�Ȗł�1�����A�Q�n�ł͖�2���B
����s��(1�s3��)
�����̐V�K�����Ґ��͍��T��T�䂪1.0�ƂȂ�A��184�B20��ȉ������S�B�S�Ă̔N��Ŕ������͑������Ă���A����20��̑����������B�a���E�d�Ǖa���g�p���͂������1�����B��t�ł����T��T�䂪1.0�ƂȂ�A�V�K�����Ґ��͖�112�B�_�ސ�ł͍��T��T�䂪1.08��1������A�V�K�����Ґ��͖�144�B��ʂł͍��T��T�䂪0.97��1�������A�V�K�����Ґ��͖�136�B�a���g�p���ɂ��āA��ʂł͖�2���A��t�ł͖�1���A�_�ސ�ł�2����B
�������E���C
���m�̐V�K�����Ґ��͍��T��T�䂪1.13��1������A��206�B20��ȉ������S�B�S�Ă̔N��ő������Ă���A����10-20��̑����������B�a���g�p���͖�2���B�A�É��A�O�d�ł����T��T�䂪���ꂼ��1.09�A1.32�A1.08��1������A�V�K�����Ґ��͂��ꂼ���200�A190�A161�B�a���g�p���ɂ��āA�ł͖�3���A�É��ł�1�����A�O�d�ł�2����B
������
���̐V�K�����Ґ��͍��T��T�䂪1.06��1������A��236�B20��ȉ������S�B�S�Ă̔N��ő������Ă���A����20��ȉ��̑����������B�a���g�p���͖�2���B����A���s�A���ɁA�ޗǁA�a�̎R�ł����T��T�䂪���ꂼ��1.19�A1.13�A1.13�A1.22�A1.06��1������A�V�K�����Ґ��͂��ꂼ���181�A233�A194�A159�A188�B�a���g�p���ɂ��āA����A���s�A�ޗǂł�1�����A���ɂł͖�2���A�a�̎R�ł�3����B
����B
�����̐V�K�����Ґ��͍��T��T�䂪1.01��1������A��269�B20��ȉ������S�B�S�Ă̔N��Ŕ������͑������Ă���A����20��̑����������B�a���g�p���͖�2���B�F�{�A�{��ł����T��T�䂪���ꂼ��1.11�A1.13��1������A�V�K�����Ґ��͂��ꂼ���238�A325�B����A����A�啪�A�������ł͍��T��T�䂪���ꂼ��0.80�A0.94�A0.99�A0.97��1�������A�V�K�����Ґ��͂��ꂼ���230�A215�A226�A288�B�a���g�p���ɂ��āA����A����A�F�{�A�{��ł�2�����A�啪�ł͖�2���A�������ł�3�����B
������
�V�K�����Ґ��͍��T��T�䂪1.13��1������A��1014�ƑS���ōł������B30��ȉ������S�B�S�Ă̔N��ő������Ă���A����30��ȉ��̑����������B�a���g�p����5�����B�d�Ǖa���g�p����2�����B
|
���E�}�X�N�͂Ȃ��K�v�H�q���ւ̃��X�N�������@5/19
�s�V�^�R���i�E�C���X��̃}�X�N���p�ɂ��āA���ƗL�u��19���A���O�ł͉�b�����Ȃ���ΕK���������p�͕K�v�łȂ��Ƃ��錩���Ă��������B2�Έȏ�̖��A�w���̒��p�̕��Q���w�E���ꂽ�t
�}�X�N�̌��ʂƕ��Q���l���邱�Ƃ��d�v�ŁA�܂��͊����̉\�����Ⴂ���O��A�����ߒ��ɂ��関�A�w������u���ցv����͓̂��R�Ƃ�����B
�I�~�N�������������̎嗬�ƂȂ��Ă���́A���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̏�ŁA���O�ł̓}�X�N�𒅗p����K�v�͂Ȃ��ƒ��Ă͂ǂ����Ƒi���Ă����B������Â̐��Ƃ́u����ɂ߂�ƁA�������X�N�����܂�v�Ƃ̍l����������A�u�E�}�X�N�v�͂Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ������B
��ÊW�҂͂��������R���i�ЈȑO����E����}�X�N�𒅂��Ă���A���p�Ɉ�a�����o���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���ȉ���o�[�̒��ł����o�ɍ����������B�\�������ɂ����Ȃ�ȂNJ����ȊO�̃��X�N�𑽗l�Ȋϓ_���番�͂��āA�V�l����ł��o���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B
�s�}�X�N���p����ԉ����A����W�҂�����q���̔���ɉe������Ƃ̎w�E������t
����A����e���r�ԑg�����ċ������B1�T���O���X�ƃ}�X�N�����Ă���l��2�T���O���X�����̐l�B�ǂ��炪�s�R�Ǝv���������ɐq�˂��Ƃ���A�����͌�҂������B���R�́u�}�X�N�����Ă��Ȃ��l�������l�v�B��l�͂����������������A�u�q�����}�X�N���O���ɂ́A�܂���l���͂������Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƕ����t���Ă����ׂ����B
�s���E�ł͒E�}�X�N�ɂ�����鍑�����Ȃ��Ȃ����A���{�ł͋`���ł��Ȃ��̂ɑ����̐l���}�X�N���p�𑱂���t
���N�`���ڎ킪�i�݁A�R���i�����ɂ��d�lj����X�N�͒Ⴍ�Ȃ��Ă���B����ł��A���{�l�����O�ł���}�X�N�𒅂�������̂́u�݂�Ȃ��������Ă��邩��v�Ƃ����������͂����邩�炾�B�c�C�b�^�[�̓��{�l���p�҂ɂ͓����A�J�E���g�������̂́A���������҂�������Ȃ��悤�����������߂�X������������Ƃ�������B�P�Ɂu�O���Ă����ł���v�Ƃ����A�i�E���X�����ł͌��ʂ͌���I���낤�B�q���̔���ւ̉e���̂悤�ɁA�s�K�v�ȏ�ʂł̃}�X�N���p�ɂ̓��X�N������ł���B���������u�������́v�ɂ��Ă��A��藝���𑣂��ׂ����B
���{�l�͎Љ�I�ȃC���[�W���ɂ��鍑�����B�����炱�����݂��E������A������ƃ}�X�N�������肷��B�}�X�N�Ŋ�̔������B��铽�����������������蒅����A�����������{�l�̗ǂ��͎�����\��������B
�s6���ȍ~�A���ۑɘa����A�}�X�N�����Ă��Ȃ��O���l�ό��q��ڂɂ���@��������錩�ʂ����t
�u�K�v�ȏ�Ƀ}�X�N�����Ȃ��Ă�������Ȃ����v�Ƃ����ӎ��̕ω��ɂȂ��邾�낤�B�R���i�Ƌ�������u�E�B�Y�R���i�v�ɖ{�i�I�ɓ������Ǝ�������ے������E�}�X�N���B�V���Ȍ��i�́A�u�ߏ�ɃR���i������Ȃ��Ă����v�Ƃ������S�������o�I�ɗ^����͂����B(������@�\����)
�R���i�Ђŏ펯�ƂȂ����}�X�N�̒��p�B���̒��E���߂���c�_���A�M���ǃ��X�N�����܂�Ă�O�ɖ{�i�����Ă���B�������̓}�X�N�Ƃǂ����������ׂ����B���Ƃ��u�����v����B
|
�����s�@���H�X�u4�l�ȓ��A2���Ԃ܂Łv�@���傤�ƃ}�i�[�@���܂ŁH �@5/19
�V�^�R���i�E�C���X��Ƃ��Ĉ��H�X�̗��p���u1��4�l�ȓ��A2���Ԃ܂Łv�Ƃ���u���傤�ƃ}�i�[�v�̌Ăт������A���������Ă���B�l���⎞�Ԃ̐����������ẮA��^�A�x���I���Ċe�s���{���Ō������̋c�_���n�܂��Ă���A�Ăт������`�[�����Ă���Ƃ����w�E���B�{�͊����⑼�{���̓����܂��A����̂����������������j���B
�u���傤�ƃ}�i�[�v�́A�l�����H���Ԃ̖ڈ��ƂƂ��ɁA�}�X�N��H����ޓX���̏��łȂǂ��A�q��X�ɋ��߂���e�B�{���ɋً}���Ԑ錾�Ȃǂ��o�Ă��Ȃ�������N3���A�{�Ǝ��̖ڈ��Ƃ��ČĂт������n�߂��B���̌�A�����Ґ���1���ɗ��������Ă�����11���A��������Ăт������x�~���Ă������A12�����{�ɕψي��E�I�~�N���������m�F���ꂽ�̂��@�ɕ������A���݂Ɏ����Ă���B
�l���E���Ԑ����͓��[�@�Ɋ�Â��ėv�����Ă������������邪�A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�����������N3�����{�ȍ~�͂����܂Łu���肢�v�Ƃ̈ʒu�Â��ŁA�������Ȃ��B
�{�̓S�[���f���E�B�[�N(�f�v)�O�A�l�̓��������������邱�Ƃ�z�肵�A���߂ă}�i�[�̓O����Ăт������B�������A����܂ł̕{���̊����͂f�v�O�Ɠ������Ő��ڂ��A�a���g�p����2������Ă���B���e�m����17���A�w�̎�ނɁA�u�e���͗��T���炢�ɕ������Ă���v�Ƙb���A�������炭�𒍎�����l�����������B
��
���H�X���p�ւ̌Ăт����́A�e�s���{���Ńo���c�L������B���Ɍ��⎠�ꌧ�͌���A4�l�ȉ��ł̗��p���Ăт����Ă������A���{��18���̑��{����c�ŁA�����Ċg��̌X���͂Ȃ��Ɣ��f�B�u�Љ�o�ς�߂��Ă������Ƃ��d�v�v(�g���m���m��)�Ƃ��āA�F�ؓX�Ɍ����Đl���⎞�Ԃ̐�����P�p����B�����s��4�l�̐������ɘa���A�~���{�b�N�X�Ȃł̗��p��z�肵�A�����8�l�Ƃ��Ă���B
���ہA���傤�ƃ}�i�[�͎���Ă���̂��B
���s�s���̔ɉ؊X�ł́A5�l�ȏ�ň��H����O���[�v�̎p���ڗ��B��������ŋ��������o�c����50�Α�j���́A�u���Z�c�ƂƂ��킹�Đl���������I������Ǝv���Ă����v�Ƃ��������ŁA�u4�l��5�l���ꏏ�B���������ӎ����Ă��炸�A���ʂ͋^��v�Ƙb�����B���ӂɂ̓J�E���^�[�Ȃ���~�������X������A�Ή��͂܂��܂��Ƃ����B
�{�����́u�Ăт������`�[�����Ă���ʂ͔ۂ߂Ȃ��v�Ƃ̔F���������A�u�G�r�f���X(����)���������ɌĂт����𑱂���A����Ă��炦�Ȃ��Ȃ�v�ƌx�����������ɂ����B
|
���k���N �V�^�R���i���\����1�T�� ���M�҂̗v�͐l���̖�8���� 5/19
�k���N���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂����߂Ċm�F�����Ɩ��炩�ɂ��Ă���19����1�T�Ԃł��B�k���N�w�����́A�O�ꂵ���s�s������l�C��p�Ŋ����̕������߂�ڎw���Ă��܂����A���M�҂̗v��200���l�߂��ƁA�l���̂��悻8���ɒB���Ă��āA���N�`���̒����ޒ��ŁA����Ȃ銴���g�傪���O����Ă��܂��B
�k���N�͍���12���A�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������������ɗ������āA���߂Ă̊����҂��m�F���ꂽ�Ɩ��炩�ɂ��܂����B
���ꂩ��1�T�ԂƂȂ���19���̔��\�ɂ��܂��ƁA18���ߌ�6���܂ł̈���ŐV����26��2000�l�]��ɔ��M�̏Ǐm�F����A1�l�����S�����Ƃ������Ƃł��B
1��������̔��M�҂́A17���܂�2���A���Ō����X���ł������A�Ăё����ɓ]�����`�ł��B
�܂��A�挎���{�ȍ~�̔��M�҂̗v��197��8000�l�]��ƁA�l���̂��悻8���ɒB���Ă��܂��B
�����������A�L���E�W�����E��(������)�����L�́u�����ȗ��̑哮���ƌ�����v�Ƃ��āA������@���������A������O�ꂵ�ė}�����ށu�[���R���i�v�����i�߂钆���ɂȂ���āA���ׂĂ̎s��S�Ȃǂ����Ă��܂��B
����ɁA3000�l�߂��̌R��炪��s�s��������(����)�̐��S�����̖�ǂɔh������A24���ԑԐ��ň��i����������ƂƂ��ɁA��t���ȑ�w�̊w����140���l�ȏオ�����⎡�Âɓ��������ȂǁA�l�C��p�Ŋ����̕������߂�ڎw���Ă��܂��B
�������A�k���N�͈�Ñ̐��������ゾ�ƌ����A19���t���̒��N�J���}�@�֎����u�����ɂ͐�i�I�Ȉ�Î{�݂��s�����A�ی����삪�\���ɔ��W���Ă��Ȃ��v�ƔF�߂Ă��܂��B
�����āA�k���N�w���������O����̃��N�`���̒�����ł��钆�ŁA�؍��̏��@�ւ́A�����̃s�[�N�����������痈�����߂ɂȂ�Ƃ��������������Ă��āA����Ȃ銴���g�傪���O����Ă��܂��B
�k���N�ւ̎x�����s���Ă���؍��̕����̖��Ԓc�̂�19���A�\�E���ŋL�҉���A�����L�b�g����i�A����Ɉ�Ï]���҂̖h�앞�ȂǁA���z��1000���h���A���{�~�ł��悻12��9000���~�K�͂̎x�����s��������i�߂Ă���Ɩ��炩�ɂ��܂����B
�k���N�ւ̎x�����߂����ẮA�؍����{�������ҋ��c�̒�Ă荞�ʒm���𑗂邱�Ƃ�k���N���ɑŐf���܂������A�k���N�͂���܂ł̂Ƃ���A�ʒm������邩�ǂ����̈ӎv�𖾂炩�ɂ��Ă��܂���B
�L�҉�����c�̂̑�\��1�l�́u��k���ꏏ�ɂȂ��āA���̍�������z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�k�͌ł�����������J���ׂ����v�Əq�ׁA���₩�Ɏx���������悤�Ăт����܂����B�@ |
 |
�������s�ŐV����3573�l�����A7�l���S �@5/20
�����s��20���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ�����3573�l��7�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�O�T�̋��j������536�l�������B�d�ǎ҂͓s�̊��3�l�B�a���g�p����15.7%�B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���20�����_��3612.4�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�87.0%�B�s���̗v�̊��Ґ���150��9923�l�ƂȂ����B
�N��ʂōł����������̂�20���769�l�B���̂ق�10�Ζ���565�l�A10��440�l�A30��688�l�A40��537�l�A50��310�l�A60��96�l�A70��82�l�A80��59�l�A90��23�l�A100�Έȏ�4�l�A65�Έȏ�̍���҂�210�l�������B���S�����̂�70�`90��̒j��7�l�B
|
�����ŐV����2991�l�̊����m�F�@������8�l�����S�@�V�^�R���i�@5/20
���{��20���A�V����2991�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̋��j���̊����Ґ��́A3210�l�ł����B���{���ł́A������8�l�̎��S���m�F����܂����B
|
���R���i�V�K�����Ґ� 1�T�ԕ��� �S���قډ��� �ꕔ�ő����X�� �@5/20
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł͂قډ����ƂȂ��Ă�����̂́A���ꌧ��k���n���ȂLjꕔ�̒n��ł͑����X���������Ă��āA�n��ɂ�芴���ɍ����݂��܂��B
�挎21���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�ɔ�ׂ�0.85�{�A�挎28����0.94�{�A����5����0.67�{��3�T�A���Ō����X���ƂȂ��Ă��܂������A���̌�A����12����1.41�{�Ƒ������A����19���܂łł�0.97�{�Ƃقډ����ƂȂ��Ă��āA���������̕��ς̐V�K�����Ґ��͂��悻3��6275�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V�K�����Ґ��́A��s���Ȃǐl���̑����n��𒆐S��26�̓s���{���Ō����X���ƂȂ�܂������A���ꌧ��k���n���Ȃǂł͑����X���������Ă��āA�n��ɂ���Ċ����ɍ����o�Ă��܂��B
�����ꌧ
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.94�{�Ƃقډ����ł������A����12����1.57�{�A����19���܂łł�1.05�{��2�T�A���ő����X���ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2123�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���1012.48�l�ƑS���ōł������A���ꌧ�Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
�������s
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.60�{�ŁA����12����1.31�{�ɑ������܂������A����19���܂łł�0.93�{�ƍĂь������Ă��āA���������̐V�K�����Ґ���3689�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���_�ސ쌧
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.65�{�A����12����1.04�{�A����19���܂łł�1.02�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1875�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����ʌ�
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.59�{�A����12����1.24�{�A����19���܂łł�0.88�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1393�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����t��
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.57�{�A����12����1.12�{�A����19���܂łł�0.93�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻995�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����{
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.64�{�A����12����1.67�{�A����19���܂łł�0.96�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2965�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����s�{
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.64�{�A����12����1.54�{�A����19���܂łł�1.02�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻855�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ɍ�
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.69�{�A����12����1.44�{�A����19���܂łł�1.03�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1523�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����m��
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.58�{�A����12����1.70�{�A����19���܂łł�1.02�{�ƂȂ��Ă��āA���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2222�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���k�C��
����5���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.79�{�A����12����1.24�{�A����19���܂łł�0.97�{�ƂȂ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻2529�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���338.90�l�ƁA���ꌧ�Ɏ����őS����2�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
|
�����ۑ���ɘa�A�����Ґ���1��2���l�Ɉ����グ�ցc�@5/20
���슯�[������20���ߌ�̋L�҉�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̐��ۑ��6��1������ɘa���A1��������̓����Ґ��̏�������݂�1���l����2���l�Ɉ����グ��Ɣ��\�����B�����ґS���Ɏ��{���Ă����������̌����ɂ��ẮA�V�^�R���i���������郊�X�N�̒Ⴂ���E�n�悩��̓����҂ɑ��Ă͖Ə�����B
���쎁�́u�����҃x�[�X��8�����x�̍��E�n��́A�����������Ƒҋ@�����߂Ȃ����E�n��ƂȂ錩���݂��v�Əq�ׂ��B��̓I�ȍ��E�n��͗��T�A���\����B
|
�����{�̃R���i�Ή����@���g���u�ӎv���肪�s�����v�@5/20
�V�^�R���i�ł̐��{�̑Ή��Ȃǂ�������L���҉�c�Ő��{���ȉ�̔��g��́A�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̌��ߕ����s�����������Ǝw�E���܂����B
���{���ȉ�E���g��F�u�ӎv����݂̍���Ƃ������̂��s�����������B�ً}���Ԑ錾�Ȃnj��肷�鎞�͓��R�ӎv���肪�d�v�ł���v
���g��́A�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ����߂�ۂ̐��{�Ɛ��Ƃ̖������S�������܂��������Ǝw�E���܂����B
�܂��A�A�h�o�C�U���[�{�[�h�Ȃǐ��Ə����g�D�ւ̐��{�̃T�|�[�g���s�\���������Ƃ��i���܂����B
���̂����ŁA�����̋}�g��ɑΉ��ł���Ȋw�I�ȏ����V�X�e���̍\�z�⍑�ƒn�������̂̈ӎv����̎d�g�݁A�������S�m�ɂ��邱�ƂȂǂ����߂܂����B
|
�����q�s�A�s��3�C������3�N�Ԃ�J�݂ց@7��1������8�����܂Ł@5/20
���q�s��20���A�ޖ؍��A�R��K�l�A���z�̎s��3�J���̊C����������āA�J�݂���Ɣ��\�����B�V�^�R���i�E�C���X�����NJg��̉e���ŁA��N�ƈ��N�͋x�ꂵ�Ă���A3�N�Ԃ�ƂȂ�B
���Ԃ�7��1������8��31���܂ł̌ߑO9������ߌ�5���܂ŁB�s�ɂ��ƌ���A��������r�I���������Ă��邱�Ƃ�A�����g��̍ۂɂ͋x�ꂷ�邱�ƂȂǂƂ��A�n��Z���Ƃ̍��ӂ�����ꂽ���Ƃ����R�Ƃ����B
�C�̉Ƃ͊����\�h���O��B�܂h�~���d�_�[�u��ً}���Ԑ錾�����o���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̗v�����e�����悤�w�߂�ق��A�x��v�����������ꍇ�ɂ͑��₩�ɉ����邱�Ƃ��m�F����Ă���B
�s�́u�n��Z���̐������Ƃ̒��a��}��Ȃ���A�N�������K�Ɉ��S�E���S�ɗ��p�ł���C��������m�ۂ��邽�߂̎��g�݂����{���Ă��������v�Ƃ��Ă���B
|
�������̐V�^�R���i�V�K�s�������Ґ���1115�l�c��C��5���A��1��l�ȉ��@5/20
�����{�y�ł́A��r�I���������ɐV�^�R���i�̕������߂ɐ������A�ȍ~�͑S���I�ɂ͈��肵���ƂȂ�A�U���I�Ȏs�������m�F�Ⴊ�x�X�o��������x���������A���N(2022�N)�ɓ����Ĉȍ~�̓I�~�N�����ψي��y�т��̈���(������u�X�e���X�I�~�N�����v��)�̗������A�ꕔ�n��Ŕ�r�I��K�͂ȍė��s���o�����Ă���B
�����̍��Ɖq�����N�ψ���(NHC)��5��20�����Ɍ����T�C�g��Ō��\�������ɂ��A����19���̒����{�y�ɂ�����V�K�s�������m�F�Ґ���176�l(�O������15�l��)�������Ƃ̂��ƁB����́A��C�s88�l�A�k���s50�l�A�l���20�l�A�V�Îs8�l�A�͓��4�l�A�L����3�l�A�g�я�2�l�A�ɔJ��1�l�B���̂�����C�s��71�l�A�k���s��6�l�A�V�Îs��4�l�A�ɔJ�Ȃ�1�l�̌v82�l�����Ǐ犴���m�F�ɓ]�������āB�����{�y�Ŏs�������m�F�Ⴊ�o������̂�216���A���A17���A����500�l�ȉ��ƂȂ����B
�s���̖��Ǐ����939�l(�O������114�l��)�B����́A��C�s770�l�A�l���102�l�A�͓��24�l�A�k���s12�l�A�V�Îs11�l�A�g�я�9�l�A���J��6�l�A�ɔJ��2�l�A���]��1�l�A�]����1�l�A�Ζk��1�l�B
���Ǐ���܂ސV�K�����Ґ���1115�l�ŁA7���A��2��l�ȉ��ɁB���̂�����C�s�̕���858�l�ɏ��A�S�̂�77.0%���߂��B��C�ł�5���A��1��l�ȉ����ێ��B
5��19��24�����_�̒����{�y�Ŏ��Ò����Ă��銴���m�F�Ґ���4906�l(�����A������192�l)�ŁA�d�ǎ҂�280�l(�A����1�l)�B���Ǐ�̊���4��3766�l(�A����419�l)����w�ώ@���ɂ���Ƃ̂��ƁB
�������ǂ͈���ɂ�����g�U�h�~�Ɠ����ɁA��O����̗����Ɖ@��������h�~���邽�߂̓O�ꂵ���[�u���u����Ȃǂ��āu����(�[���R���i��)�v��ڎw���O��I�ȑΏ���i�߂Ă����B��̓I�ɂ́A�ǒn���b�N�_�E���A�S��PCR�����ɂ��X�N���[�j���O�A�����ׂ��ړ��̐����A���H�X���̓���Ǝ�ɑ���c�Ɛ������̑[�u����������B�����_�ł��[���R���i�������������l�����d�˂ċ������Ă���A���炩�̕����[�u���u�����Ă���n�悪�������݂���B
���N�ɓ����Ĉȍ~�A�I�~�N�����ψي��̗����ɔ����A�����{�y�̑����̏Ȏs��ŐV�K������̏o���������Ă��邪�A���ɐ[���Ȃ̂���C�s�B���s�ł�3�����{���玖����̃��b�N�_�E��(�s�s����)��Ԃɂ���B�������A���̂Ƃ��듯�s�ɂ�����V�K�����m�F���͊ɂ₩�ȉ����X���ɂ���A5��17���܂łɑS�s�ŎЉ�ʐ���(�u���ΏۈȊO�̈�ʎs���ɂ�����[���R���i��)�����������Ƃ����B������āA����A�����G���A�̏k���A�J���������i�߁A6��1�����璆�E���{�ɂ����Đ��퉻��}��v�悪�����ꂽ�B19���A�s���ǂ͐V����22���������ׂ���ʂɂ��Ēi�K�I�ɍĊJ���邱�Ƃ����炩�ɂ����B
4��22���ȍ~�A�k���s�ł��A��2���̊����Ⴊ�����Ă���B�ˑR�Ƃ��ĎЉ��(�u���Ώۂł͂Ȃ���ʎs��)�ɂ�����`�d�`�F�[�����f����Ă��炸�A���̂Ƃ���̓N���X�^�[�̔������������B�s���ǂł́A�ډ��̂Ƃ���h�u��ɂ����ĕ��G���[���ȏɂ��邪�A�Љ�ʂɂ�����_�C�i�~�b�N�[���R���i�����̖ڕW���������A�I�m�ȑΉ��œ`�d�`�F�[���̎Ւf��ڎw���Ƃ��Ă���B
���`�E�}�J�I�Ɨ��Őڂ���L���Ȃł��A���N�ɓ����Ĉȍ~�A�L�B�s�A�[�Z���s�A���Ύs�A��C�s�A���R�s�ȂǂŒf���I�Ɏs�������m�F�Ⴊ�o�����Ă������A���̂Ƃ���͗��������Ă���A4��22���܂łɏȓ��S�悪��X�N�n��ɕ��A�����B�������A�ߓ��͍L�B���_���ۋ�`�̐E���y�т��̓��Z�҂𒆐S�Ƃ����V���Ȋ����Ⴊ�������o���B�܂��A�ȓ암�̒X�]�s�ł�5��7������q�ɉ�Ђ[�Ƃ��������̊����҂��o���������A��ʎs���ւ̊g�U�͂Ȃ��͗l�B19���̏ȓ��̊����m�F��͂��ׂĒX�]�s������ꂽ���́B
�}�J�I���ʍs����ł�5��19���܂�221���A���s�������m�F��[���ƂȂ�������A���`���ʍs����ł͍�N(2021�N)12��������V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s�u��5�g�v���n�܂����B2������3�����ɂ����Ċ����m�F���̋}��������A3�����{�Ƀs�[�N���߂����Ƃ����B��5�g�J�n�ȗ��A5��19���܂ł̗v��119.7���l(���Ǐ�܂�)�A���S�Ґ���9153�l�B19���P���ł�291�l(�A����38�l�܂�)�ŁA3���Ԃ�Ɍ����ƂȂ�A25���A����500�l�ȉ����ێ������B�����܂Ŗڗ��������o�E���h�͔������Ă��Ȃ����̂́A����2�T�Ԃ�200�`300�l�O��ʼn����~�܂��Ă���B�\�[�V�����f�B�X�^���X�[�u�̊ɘa���āA�ߓ��̓N���X�^�[�̔����������Ă��邪�A19������\�[�V�����f�B�X�^���X�[�u�̑��i�K�ɘa�����{����A����̃��o�E���h�̗L���ɒ��ڂ����B����܂ō��`�ł͏�C�s�̂悤�ȑS�惌�x���ł̃��b�N�_�E���͎��{����Ă��炸�A����̃}���V���������ΏۂƂ����ǒn���b�N�_�E���ɂƂǂ܂�B
|
�����{ �}�X�N���p�̍l�������\ ���O�ʼn�b�Ȃ��Ȃ璅�p�K�v�Ȃ� �@5/20
�V�^�R���i��ł̃}�X�N�̒��p�ɂ��Đ��{�̍l���������\����܂����B���O�ł́A����̐l�Ƃ̋������m�ۂł��Ȃ��Ă��A��b���قƂ�ǂ��Ȃ��ꍇ�ɂ͒��p�̕K�v�͂Ȃ��ȂǂƂ��Ă��܂��B
�㓡�����J����b�͌ߌ�6����������A���{�̍l������������܂����B
����ɂ��܂��ƁA��{�I�Ȋ�����Ƃ��Ă̒��p�̈ʒu�Â��͕ύX���Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B���̂����ŁA2���[�g���ȏ��ڈ��ɁA����̐l�Ƃ̋������m�ۂł����ʂł́A�����ʼn�b������ꍇ�������āu���p�̕K�v�͂Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��B�����ʼn�b������ꍇ�ł��A�\���Ȋ��C�Ȃǂ̑���Ƃ��Ă���u�O�����Ƃ��ł���v�Ƃ��Ă��܂��B
����A�������m�ۂł��Ȃ���ʂł́A���O�ʼn�b���قƂ�ǂ��Ȃ��ꍇ�Ɂu���p�̕K�v�͂Ȃ��v���Ƃm�ɂ��A����ȊO�̃P�[�X�́u���p�𐄏�����v�Ƃ��Ă��܂��B
�܂��A2�����璅�p�𐄏����Ă������w�Z���w�O��2�Έȏ�̎q�ǂ��ɂ��ẮA�I�~�N�������s��������O�̈����ɖ߂��āA����̐l�Ƃ̋����ɂ�����炸�u�ꗥ�ɂ͋��߂Ȃ��v�Ƃ��A2�Ζ����̎q�ǂ��́A���������������Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
���̂ق��A�ď�͔M���ǂ�h���ϓ_����A���O�ʼn�b���قƂ�ǂ��Ȃ��ꍇ�Ȃǂ́A�O�����Ƃ𐄏�����ƂƂ��ɁA����҂Ɖ�Ƃ���a�@�ɍs���Ƃ��Ȃǂ͒��p���邱�Ƃ����荞��ł��܂��B
���{�́A���������l�����J�Ɏ��m�������Ƃ��Ă��܂��B
�㓡�����J����b�͋L�Ғc�Ɂu�}�X�N�̒��p�ɂ��ẮA���������ǂ�������ʂŊO���Ă悢�̂��Ƃ�������A�}�X�N���p�����������钆�ŕ\������ɂ����Ȃ邱�ƂŁA�q�ǂ��ɑ���e�������O���鐺���������B���ꂩ��C���⎼�x�������Ȃ蒅���Ă���ƁA�M���ǂ̃��X�N�����܂邱�Ƃ����O�����v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu����̌o�ϊ�����Љ���𐳏퉻���Ă������ƂƁA��{�I�Ȋ�����Ƃ��Ẵ}�X�N�̒��p�͗���������B����Ƃ������Ȃǂ̕ύX�ɂ���ă}�X�N�̒��p�₻�̑��̑�ɂ��Ă��A�G�r�f���X�x�[�X�őΉ����Ă����v�Əq�ׂ܂����B
|
���V�^�R���i�̂悤�ȁg���Ёh�ɁH ���E�Ŋ����g�債�Ă���u�T�����v�Ƃ́@5/20
�S���E�ŃE�C���X���̊����ǁu�T�����v�̊��҂��������ŕ���Ă���B
�J�i�_�̃����g���I�[���ی����ǂ̔��\�ł́A������17�l�����̋^��������Ƃ����B���̒n��ł́A�A�����J��1�l�A�C�M���X9�l�A�|���g�K��14�l�A�X�y�C��7�l�̊������m�F����Ă���(AP�ʐM)�B
���́u�T�����v�Ƃ́A�V�R���E�C���X�Ɏ����u�T�����E�C���X�v�����ɂ��}�����]�������ŁA�l�Y�~��X�ȂNJ��������Ɋ��܂ꂽ��A���҂̔E�̉t���Ƃ̐ڐG�Ŋ�������\��������B
�Ǐ�Ƃ��ẮA���̂ɓ����I�Ȕ��]���o��ق��A���M��̂ǂ̒ɂ݂Ȃǂ��������Ă��āA�v�����͒Ⴂ�a�C���B
���̊����ǂɂ��āA�j���[�X�ԑg�wABEMA�q���Y�x�ɏo�������o�C�����K����t�̃j�R���X�E���j�b�N���ɘb�����B
�\�\�T�����Ƃ��������ǂ̗R���͉����H
�u�T�����́A1958�N�ɃT���Ō������������ǂȂ̂ŁA�����������O�ɂȂ��Ă���B�قƂ�ǂ́A�l�Y�~�������Ă��邱�Ƃ��������A�l�Y�~�Ɋ��܂ꂽ�T�����������A�T���̒��ŗ��s���m�F���ꂽ�a�C���v
�\�\�V�^�R���i�E�C���X�̂悤�ɐl�ނɋ��ЂɂȂ�\���͂��邩�H
�u�����_�ł̃f�[�^������ƁA�傫�ȋ��ЂɂȂ��ۂ͂Ȃ��B�Ȃ����Ƃ����ƁA�܂��A����������ɂ����a�C�B1970�N����A�t���J�ł����Ίm�F����Ă��邪�A���������g�傷��݂̂ŁA������1�l�����ɉ��l�Ɋ��������邩�������uR���l�v��1�l�ȉ��ɂȂ��Ă���B����́A��������������d�Ԃ̒��A�w�Z�̒��Ŋ������L����悤�ȕa�C�ł͂Ȃ��B���A�����̂قƂ�ǂ́A�����ɂ����́v
�\�\�ȏ�̘b����A�T�����͊����͂������Ȃ��v�������Ⴂ�H
�u�����}�j�A�b�N�Șb�����A�T������2��ނɕ��ނ���Ă��āA���A�t���J�ƃR���S�B�R���S�́A�v�������������A�������g�債�Ă���̂́A���A�t���J�̕��Ȃ̂Œv�����������͂Ȃ��A1%�����ɂȂ��Ă���v
�@ |
 �@ �@
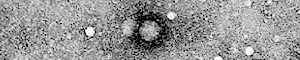 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i 7�l���S 3464�l�����m�F �O�T��300�l�]�� �@5/21
�����s����21���̊����m�F��3464�l�ŁA1�T�ԑO�̓y�j�����335�l����܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��21���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�̍��킹��3464�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j�����335�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�8���A���ł��B21���܂ł�7���ԕ��ς�3564.6�l�ŁA�O�̏T��85.9���ł����B21���Ɋm�F���ꂽ3464�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�19.4���ɂ�����672�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�260�l�ŁA�S�̂�7.5���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A20���ƕς�炸3�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70�ォ��90��܂ł̒j�����킹��7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����3030�l���R���i�����c1�T�ԑO����409�l���@5/21
���{��21���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3030�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����409�l�������B���҂�6�l�������B
|
���V�^�R���i ���̊�����(21���ߌ�6��)�@5/21
��2�{4���ŁA21���ɔ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂͂��킹��6323�l�ł����B�O�̏T�̓y�j���Ɣ�ׂ�700�l�߂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�{���ʂł́A��オ3030�l�A���ɂ�1392�l�A���s��871�l�A���ꂪ482�l�A�ޗǂ�284�l�A�a�̎R��264�l�ł����B����ŁA��2�{4���̊����҂̗v��178��1475�l�ƂȂ�܂����B�܂��A����6�l�A���s��2�l�̎��S�����\����܂����B
��2�{4���ŁA����܂łɖS���Ȃ����l��8672�l�ƂȂ��Ă��܂��B�ŐV�̏d�ǎ҂́A��オ19�l�A���ɂ�3�l�A���s��2�l�ł����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 2�l���S �V����2215�l�����m�F �@5/21
���ꌧ��21���A�V����2215�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B��T�̓y�j���Ɣ�ׂ�249�l���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�͍̂��킹��20��1080�l�ɂȂ�܂����B
�܂��A����90��̏�����50��̒j�������S�����Ɣ��\���A�����ŖS���Ȃ����l��457�l�ɂȂ�܂����B
|
�������̃R���i�����ҁA3��5922�l�m�F�c�s����1�T�ԕ��ς�14���� �@5/21
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�21���A�S�s���{���Ƌ�`���u��3��5922�l�m�F���ꂽ�B���҂�31�l�ŁA�d�ǎ҂͑O������5�l����101�l�������B
�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̓d�q�������ʐ^(���������nj�������)�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̓d�q�������ʐ^(���������nj�������)
�����s�ł�3464�l�̊������m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j������335�l����A8���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ�1��������̕��ϐV�K�����҂�3565�l�ŁA�O�T����14���������B70�`90�Α�̒j��7�l�̎��S�����������B
|
���R���i�����Ґ��AGW��������@���Ɓu�����X���͗\�z�قǑ傫���Ȃ��v�@5/21
��^�A�x�̉e�������O���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ��āA�����J���Ȃɑ������������Ƒg�D�́A�A�x�㔼�ɂ����Ċ����g��̒�����ꂽ���̂́A���̌�͉�����Ԃ������Ă���Ǝw�E�����B���Ƃ́u�A�x�̉e���͂���قǑ傫���Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̌����������B
19���ɊJ���ꂽ��̎����ɂ��ƁA18���܂�1�T�Ԃ̑S���̐V�K�����Ґ��͑O�T�Ɣ��1�E07�{�B�A�x������9���ȍ~�A�����҂��}�����鎖�ԂƂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B��B7���͋{��(1�E13�{)�A�F�{(1�E11�{)�A����(1�E01�{)��3���������ŁA�啪(0�E99�{)�A������(0�E97�{)�A����(0�E94�{)�A����(0�E8�{)�����������B
�A�x���͐l�̓���������ɂȂ邱�Ƃɉ����A�����͂̋����I�~�N�������̔h���^�uBA�E2�v�ւ̒u������肪�i�݁A�����g�傪���O���ꂽ�B�����A������̓O���N�`��3��ڐڎ�̕��y�A1�`2���̎��R�����Ŋl�������Ɖu���ʂȂǂ̗v���ŁA�}�����ꂽ�\��������Ƃ����B
�e�c���������͉�Łu�A�x���Ɉ�ߐ��̏㏸�������邪�A�����X���͗\�z�قǑ傫���Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��B�����A�A�x���͐f�Â⌟���̐�������A���Ԕc���Ɏ��Ԃ������邽�߁A���Ƒg�D�́u���m�ȕ]���͓���v�Ƃ��Ă���B�@ |
 |
������2065�l�����m�F 5���A����2000�l���@5/22
22���A�����ł͐V����2065�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�ق��A1�l�̎��S�����\����܂����B�V�K�����Ґ��͑O�̏T�̓����j����400�l�]�艺��������̂́A5��������2000�l���A�ˑR�Ƃ��č��������Ő��ڂ��Ă��܂��B
�������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��958�l�A�Ύ�n����166�l�A�_�U�n����146�l�A����s�ōėz����2�l���܂�145�l�A�\���n����125�l�A���َs��97�l�A���H�n����82�l�A�I�z�[�c�N�n����79�l�A��m�n����56�l�A�n���n����43�l�A���M�s��41�l�A���n����40�l�A�����n����36�l�A��u�n����19�l�A�����n����11�l�A�@�J�n����9�l�A�O�R�n����5�l�A���G�n����2�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�����A���O��1�l���܂�5�l�̂��킹��2065�l�ł��B
�V�K�����Ґ��͑O�̏T�̓����j����423�l�����܂������A5��������2000�l���A�ˑR�Ƃ��č��������Ő��ڂ��Ă��܂��B
���Ȃǂɂ��܂��ƒ�������40�l�������āA�����ǂ�4�l�A���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������ƂőS�̂�4���ȏ�ɂ�����864�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������4675���ł����B�܂��A���́A����܂łɊ������m�F���ꂽ�l�̂����A90��̒j��1�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�17��2024�l���܂ނ̂�34��5711�l�A�S���Ȃ����l��2046�l�A���Â��I�����l�͂̂�31��9721�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�S���ł͕a���g�p����20.8���A�d�ǎ҂̕a���g�p����4.3���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���319.3�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���471.1�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�������s �V�^�R���i 6�l���S 3317�l�����m�F �O�T��31�l�� �@5/22
�����s����22���̊����m�F��3317�l�ŁA1�T�ԑO�̓��j�����31�l����܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ6�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��22���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�̍��킹��3317�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����31�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�9���A���ł��B22���܂ł�7���ԕ��ς�3560.1�l�ŁA�O�̏T��90.0���ł����B22���Ɋm�F���ꂽ3317�l��N��ʂɌ���ƁA10�Ζ������ł������A�S�̂�18.8���ɂ�����622�l�ŁA�����đ���20��͑S�̂�18.4���ɂ�����609�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�206�l�ŁA�S�̂�6.2���ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A21���ƕς�炸3�l�ł����B����A�s�͊������m�F���ꂽ70�ォ��90��܂ł̒j�����킹��6�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
������R���i1750�l�A�a���g�p48���@�����{�݂̊������ő��@5/22
���ꌧ��22���A10�Ζ�������90�Έȏ�܂ł�1750�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�Љ���{�݂ɂ����銴���Ґ���394�l�A�����҂��o���{�ݐ���127�J���ƂȂ肢������ߋ��ő��ƂȂ����B����́A����Ҏ{�݂�103�J����340�l�A�Ⴊ���Ҏ{�݂�24�J����54�l�������B
�V�K�����҂�N��ʂŌ���ƍő���10�Ζ�����346�l�ɑ����A10��289�l�A30��281�l�A40��278�l�Ƒ����B���S�̂̕a���g�p����48�E8���ŁA����ʂł͖{����52�E5���A�{��42�E4���A���d�R��13�E6���������B�d�ǎҗp�a���g�p����23�E3���ƂȂ����B
��ȏd�_��Ë@�ւ̈�Ï]���҂Ŋ����Ȃǂɂ�錇�Ύ҂�581�l�B���̂ق��̕a�@�̌��Ύ҂��܂߂�ƌ��S�̂Ōv1030�l�ƂȂ����B��ԓ֊����Ǒ����ے��́u�����g��̐����͎�܂��Ă��Ă��邪�A�V�K�����Ґ���2000�l�߂��o�Ă��āA���@���҂�300�l���Ă���B��Ì���͌������������Ă���A���������x�����K�v���v�ƌ�����B���j���̂��߁A�ČR�W�҂͂̕Ȃ������B�@ |
 |
�������s�̐V�K�����҂�2025�l�@5���ɓ����Ă���ŏ��@5/23
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA23��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�2025�l�B�d�ǎ҂͑O������1�l�����A4�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������90��܂ł�2025�l(�s��3�l)�B�N��ʂł�20�オ�ő���367�l�A������30���359�l�A10�Ζ�����345�l�Ƒ����Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�137�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�3509.9�l(�ΑO�T��90.8��)�B�s���̑���(�v)��151��8729�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����17.3��(1248�l�^7216��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T16��(2377�l)����352�l����A10���A���őO�T�̓����j�����猸���B5����2320�l�������A5���ɓ����Ă���ŏ��ƂȂ�܂����B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
�����{�A�ό��U������ĊJ�@6��1������@6/23
���{��23���A����̏Z���̗��s���⏕����ό��U����u�u���b�N���v��6��1���Ɏn�߂�Ɣ��\�����B�ޗnj���������2�{3���̏Z�������{���𗷍s�����ꍇ���ΏۂŁA5��30������\����t����B1�l������1���ő�5000�~�̏h�������������A2�A���܂ŗ��p�ł���B���H�X��ό��{�݂Ŏg����N�[�|�������ő�2000�~���z�z����B
���p�ɂ�3��̐V�^�R���i�E�C���X���N�`���̐ڎ�����APCR�����Ȃǂɂ��A���ؖ��̒��K�v�B���{�͕{�����{���𗷍s�����ۂ̗��s���⏕����L�����y�[���u�{�����v�Ȃǂ̊ό��U��������{���Ă������A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�K�p�ɔ����Ď��Ƃ𒆒f���Ă����B
�u���b�N���͓s���{�������{���A������p�S����d�g�݁B���݂̊�����6��30���܂ŁB
|
������R���i662�l�����A2�l���S�@3�T�ԂԂ�1000�l��@5/23
����23���A10�Ζ�������90�Έȏ��662�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�������2�l�����S�������Ƃ����炩�ɂ����B�V�K�����҂͐�T���j�����428�l�������A��l�������̂�5��2���ȗ��ƂȂ�B����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��̑O�T���0�E92�{�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A���̋{���`�v�����������Ắu�����g��̐����͎�܂����v�Əq�ׂ��B
����ŎЉ���{�݂̊����͍��~�܂肪�����B23����132�J���Ōv394�l���{�ݓ��×{�𑱂��Ă���B����͍���Ҏ{��108�J��339�l�A�Ⴊ���Ҏ{��24�J��55�l�B���ɂ��Ɖ�쌻��̕N��(�Ђ��ς�)�������Ă��邽�߁A�����Ɋ�����̌p�����Ăъ|���Ă���B
23���̐V�K�����҂̔N��ʂł�10�Ζ�����129�l�ōő��������B���@���҂�307�l�B�d�_��Ë@�ւŊ����Ȃǂɂ�茇���Ă����Ï]���҂�557�l�������B
�S���Ȃ����͓̂ߔe�s��90�Ώ���2�l�ŁA��������ʂ̎����œ��@��������4���Ɋ������������A�S���Ȃ����B�ČR�W��46�l�������B
|
�������ŐV����1��8510�l�R���i�����c�s���̒���1�T�ԕ��ς�9���� �@5/23
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�23���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��8510�l�m�F���ꂽ�B���҂�31�l�������B�d�ǎ҂͑O������4�l����96�l�ƂȂ����B
�����s�ł́A2025�l�̊����҂��m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j������352�l����A10���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�3510�l�ŁA�O�T����9�����������B�d�ǎ҂͑O������1�l����4�l�B60�`80�Α�̒j��6�l�̎��S�����������B
|
���S���̐V�K������ 1��8510�l�@����2025�l 10���A���O�T���j������� �@5/23
�S���ł�23���A�V����1��8,510�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��킩�����B
�����s��23���A�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�2,025�l�ŁA��T�̌��j������352�l����A10���A���őO�̏T�̓����j������������B�S���Ȃ����l��6�l�������B�I�~�N�������̓������ӂ܂����w�W�ɂ��d�ǎ҂�18�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����2.2%�ƂȂ��Ă���B
���̂ق��A�k�C����1,468�l�A�_�ސ쌧��1,378�l�A��������1,240�l�ȂǁA�S���ł�1��8,510�l�̊�����31�l�̎��S���m�F���ꂽ�B����A�����J���Ȃɂ��ƁA22�����_�ł̑S���̏d�ǎ҂�96�l�ŁA�O�̓�����4�l���������A2���A����100�l����������B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 5�l���S �V����3271�l�����m�F �@5/24
�����s����24���̊����m�F��1�T�ԑO�̉Ηj�����A���悻400�l���Ȃ�3271�l�ŁA11���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��24���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3271�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj�����A���悻400�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�11���A���ł��B24���܂ł�7���ԕ��ς�3453.9�l�ŁA�O�̏T��92.0���ł����B24���Ɋm�F���ꂽ3271�l��N��ʂɌ���ƁA30�オ�ł������A�S�̂�18.7���ɂ�����613�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�240�l�ŁA�S�̂�7.3���ł��B�����o�H���������Ă���1245�l�̂����A�ł������̂́u�ƒ���v��67.2���ɂ�����837�l�ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A23���Ɠ�����4�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ80�ォ��90��̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
���V�^�R���i���� �S���ő� ���ʼn����H �������͂����c �@5/24
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̑�6�g�B���ł̎��Ґ��͑S���ő���1934�l�ƂȂ��Ă���B(2021�N12��17���`2022�N5��18���܂ł̔��\�����W�v)����܂ł̌o�����炳�܂��܂ȑ���Ƃ��Ă����͂��̑��B�Ȃ�����قǑ����̐l���S���Ȃ����̂��B
��1000���̎���{�ݐ������A���ۂ́c
5�����A���s���̓W����ɐ������ꂽ�A�V�^�R���i���҂̎���{�݂��Ђ�����ƕ�����邱�ƂɂȂ����B�u�z����銴���������N���A�a�@��h���×{�{�݂ɓ���Ȃ��Ȃ�悤�Ȏ��̎{�݂Ƃ��Ďg���v���{�̋g���m���������b���A���M���݂��Ă����{�݁B���N�H�A�ЊQ���̊����g��ɔ�����K�v������Ƃ��āA�{�����悻78���~�̗\�Z��1000���K�͂������B���@��h���×{�̑ΏۊO�ƂȂ���40�Ζ����̌y�NJ��҂̎����z�肵�A��t��Ō�t���풓���āA���S���ė×{�ł�����𐮂����B�Ƃ��낪�A��6�g�ŁA���̎{�݂��g���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B�^�p�J�n����̂��悻3�����Ԃɗ��p�����l�͂킸����303�l�B�ߋ��̌o�����炳�܂��܂Ȏ��V���ɑł��Ă�������ŁA��6�g�ŖS���Ȃ����l�̐��͑S���ōł������Ȃ������B���������A�����N���Ă����̂��H�w�i�ɂ́A�{�̑z��Ƒ傫���قȂ鎖�ԂƂȂ�A���O�ɂƂ�����Ƌ��߂���Ή��Ƃ̊Ԃɂ��ꂪ���������Ƃ��������B
���z����͂邩�ɏ��銴���g��
���N11���A�{�́A��6�g�ɂ�����1���̍ő�̊����Ґ����u3833�l�v�Ƃ���z������\�B�V���ȕψكE�C���X�����s���Ă��A���N�`���̐ڎ킪�i�ނ��Ƃŋ}���Ȋ����g��͂�����x�A�}������ƌ�����ł����B�Ƃ��낪�A��6�g��1���̐V�K�����Ґ��͍ł��������ŁA���{�̎��O�̑z��̖�4�{�A1��5000�l�����B�z������I�~�N�������̊����͂��͂邩�ɋ����������Ƃɉ����āA�����̐l�����N�`����2��ڎ킵�Ă�����������A���ʂ�������������ƂȂǂ��v���ƍl�����Ă���B���ł��[���������͍̂���Ҏ{�݂ł̃N���X�^�[���W�c�������}���������Ƃ��B���̐��́A��5�g�̂��悻14�{�ƂȂ�716�����ɂ̂ڂ����B(2021�N12��17���`2022�N5��15��)
���[���ȏɊׂ�������Ҏ{�� �ی����ɂ��Ȃ��炸�c
�����̑�6�g�ŃN���X�^�[���N�����L���V�l�z�[����1���A�����������Ɏ�ނɉ������B���E����s�ɂ���5�K���Ă̌����B�e�t���A�ɍL��14�������[�g������17�������[�g���قǂ̌������сA���X�^�b�t���e����������āA�H��������̉�Ȃǂ̉��T�[�r�X����Ă���B�}�X�N�̒��p��O�ꂵ�A�H���ɃA�N������ݒu����Ȃǂ̊�������Ƃ��Ă������Ƃ�����A��5�g�܂ł͎{�ݓ��ł̃N���X�^�[�͋N���Ă��Ȃ������B�N���X�^�[�̎n�܂�́A1��28���B80��̓����҂̒j�������M�����̂����������������B�{�ݓ��ł̑Ή��͏o��������܂������B�����͍���Ҏ{�݂Ŋ����҂��o���ꍇ�A�ی����ɘA�����ē��@������̂������ƂȂ��Ă����B�{�ݒ��̒j�����ی����ɘA�����Ƃ낤�Ɖ��x���d�b�������A�R�[�����������őS���Ȃ���Ȃ������Ƃ����B�������L���Ȃ����߂ɂ́A�����҂ǂ����̐ڐG�̋@������炷�K�v������Ǝ{�ݒ��̒j�����������Ă������A�F�m�ǂ̐l�������A�J��Ԃ����ӂ��Ă��A���̓����҂̕�����K��Ă��܂��l�����₽�Ȃ������B���̎��_�Ŏ{�݂ɓ������Ă����̂�63����99�܂ł�41�l�B�{�ݒ��̒j���������Ă��ꂽ�����҂̃��X�g�́u��b�����v�̗��͂��܂��܂ȕa�C�̖��O�Ŗ��܂��Ă����B�x����A�]��ᇁA���A�a�A���S�ǁA�F�m�ǁA����ɔ]�[�ǁB�قڑS���ɂȂ�炩�̎��a���������B
�{�ݒ��̒j���u�������Ă����Ǐ�ł���Ȃ�Ƃ��Ή��ł��܂����A�������L�����Ă����d�ǂɂȂ�l���o�Ă��������͌���邱�Ƃ����ł��܂���B�ی����ɓd�b���Ȃ���Ȃ��̂łǂ��ɑ��k���Ă��������킩�炸�A�ǂ����邱�Ƃ��ł��܂���ł����v
����t�������ɂ͗���ꂸ �Ǘ��[�܂�
���ǁA�ی����ɓd�b���Ȃ������̂́A�j���̗z�����������Ă���A1������������1��31���̂��Ƃ������B�������A��t�͂����ɂ͗����Ȃ��Ƃ����B�L���V�l�z�[���ɂ́u���t���v��u�Z��^�v�Ȃǂ������̃^�C�v������A�H��������̉�ȂǁA���T�[�r�X���s�����m���������A��t���풓���Ă���Ƃ���͋ɂ߂ď��Ȃ��̂�����B���̘V�l�z�[���ɂ���t�͂��炸�A�����҂��̒���������Ƃ��Ȃǂɂ́u���͈�Ë@�ցv�ƌĂ���g��̐f�Ï��̈�t�ɉ��f�ɗ��Ă�����Ă����B������A�{�ݒ��̒j���͂��̐f�Ï��ɏ��������߂����A�����A�f�Ï��ɂ͐V�^�R���i�̎��ÖȂ��A���I�Ȏ��Â͓�������Ƃ����B���̓�(31��)�A�V���ɔ��M�Ȃǂ̏Ǐ�̂�����������4�l���z���Ɣ����B�O������̎x�����Ȃ��܂܁A�{�ݓ��Ŋ����͍L�����Ă������B
���u�����Ɏ��Âł��Ă���c�v
���{�̗v�����A����s�̘V�l�z�[���ɉ��f�̈�t���K�ꂽ�̂́A1�l�ڂ̔��M����5����̂��Ƃ������B���f�ɖK�ꂽ����ȑ�w������ÃZ���^�[�̒��X����t���g���Ă����̂́u�\�g���r�}�u�v�Ƃ����_�H�̖B�d�lj���}������ʂ����҂ł��鎡�Ö�̓��^���悤�₭�s��ꂽ�B�u���q�͂ǂ��H���C�o���Ă�v�����A�{�݂̐E�����B�e��������ɂ͒��X��t�������҂ЂƂ�ЂƂ�̕������܂��A�_�H�𓊗^���Ȃ��琺�������ė�܂��l�q��������Ă���B�{�݂ł̊����͍ŏI�I�ɓ����҂�8���ɂ̂ڂ�33�l�ɂ܂Ŋg��B���ɂ͊����ɂ���đ̗͂������A���Ƃ��Ƃ̕a�C����������l���o�Ă��Ă����B�Ǐ��ɐ[��������2�l�ɂ��Ē��X��t�͓��@���K�v���Ɛf�f�������A�����ł����̂�1�l�����������B�����͊����҂̋}���ƂƂ��Ɉ�Ò̐����[���ȉe�����A�{���̌y�ǁE�����ǂ̕a���^�p����80�����A���@����������ɂȂ��Ă����B����A�{���W����ɐ��������×{�{�݂ō���҂�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B����K�v�Ƃ��鍂��҂�����邾���̐l���ݔ����Ȃ��������߂��B���X��t�͂��̌���{�݂ɒʂ��A���@�ł����A�{�݂Ɏc���ꂽ80��̒j����̎��Â𑱂����B
����ȑ�w������ÃZ���^�[ ���X����t�u�j���͑����Ɏ��Â����Ȃ��������Ƃœ��@���K�v�ɂȂ�قǏ�Ԃ������Ȃ��Ă��܂��Ă��܂����B���������{�݂ł̑Ή��́A�\�g���r�}�u�Ȃǂ̖��1���ł��������^���ďd�lj���h�����Ƃ��ł��邩���d�v�ł��B���̒j���̂悤�Ɏ��Â��x��A�d�lj����Ă��܂��Ύ{�݂őΉ�����͕̂s�\�ŁA�ʏ�Ȃ珕���閽��������Ȃ��Ȃ肩�˂܂���v
�c���ꂽ80��̒j���́A�Ǐ��P���Ȃ��܂{�ݓ��ŖS���Ȃ����B��6�g�Ŏ{�ݓ��ŖS���Ȃ��������҂�90�l�Ɖߋ��ő��B(2021�N12��17���`2022�N5��18��)���Ґ����S���ő���1934�l�ɂ̂ڂ�A����9����70��ȏ�̍���҂���߂��B
�{�ݒ��̒j���u�S���Ȃ���80��̒j���͓����҂̊Ԃł��l�C�҂ŁA��������̐l���ނ̕�����K��Ă��܂����B�����Ƒ������Â���ꂽ��Ǝv���Ǝc�O�ȋC�����ł����ς��ł��v
���u�g���ƂɈقȂ�� ��Ƀ~�X�}�b�`���v
����Ҏ{�݂�_����������`�ƂȂ�����6�g�B���Ԃ��d���������{�́A����Ҏ{�݂Ȃǂ̈�Ñ̐��������B���̌��ʁA���悻3600�{�݂̂����A�R���i�̎��ÂɑΉ��ł����Ë@�ւ��m�ۂł��Ă���Ɠ������̂́A��6�g�̂��Ȃ���3���̎��_�ŁA���悻3���ɂƂǂ܂����B����͑S�����ς̔����ɂ������Ȃ������������B���̏��đ��{�́A����Ҏ{�݂ւ̈�Îx���̎d�g�݂̍č\�z�ɓ����o�����B�{�݂̂��������ɂ�����u���͈�Ë@�ցv���Ή��ł��Ȃ��ꍇ�A�{��ی�������˗����ĉ��f�̈�t��h������d�g�݂��B���f�ɋ��͂����Ë@�ւ�5��13�����_��119�܂ő��������B���{�́A���g�݂�����ɐi�߁A����҂ւ̎��Â��x��鎖�Ԃ���������Ƃ��Ă���B
���{���N��Õ� ����r�q�����u��6�g�ō���҂𒆐S�ɑ����̕����S���Ȃ������Ƃ͑�Ϗd���~�߂Ă��܂��B�����Ƒ����A����������ݍ��߂Ηǂ�������������Ȃ��Ƃ����v���͂���܂��B����܂�6�̔g���o�����Ă��āA���̓s�x�A�z������鎖�Ԃ��o�����Ă��܂����B���̂Ȃ��ŁA��Ƀ~�X�}�b�`�������镔��������܂����B�͔g���Ƃɑ傫���قȂ�̂ŁA�ł��邾�������҂ɂƂ��Đg�߂ȂƂ���ő������Â�����Ƃ����傫�ȕ��j�������Ȃ���A�N�������ۑ�ɂł��邾���f�����O���C�������āA�����A����ł��A���i�߂邱�Ƃ�ςݏd�˂邵���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��v
��������N���肤��u�z��O�v�ɂǂ�������
�ψق��J��Ԃ��A���E��|�M��������V�^�R���i�E�C���X�B�����̂́A�����̔g���N���邽�тɁA�ۑ��o���A���ɔ����đ��i�߂Ă����B�����āA�����̑�6�g�ŁA���ł́u���O�̑z��v���炱�ڂꂽ����Ҏ{�݂ɏ\���Ȉ�Â��͂����Ȃ����Ԃ��N�����B�u�z��O�v��������N���肩�˂Ȃ����A���߂��Ă���̂͂ǂ�Ȕg�����Ă��K�v�Ȑl�ɕK�v�ȂƂ��ɓK�Ȉ�Â��͂�����Ή��͂��B���܁A�����͂�����x�����������݂��A�ǂ�ȏȂ�}�X�N���O���Ă������̂��Ƃ������o���헪�̋c�_���n�܂��Ă���B�������A����Ȃ��܂����炱���A����܂ŁA�V���������̔g���N���邽�тɂ��͂��̂悤�ɐςݏd�˂Ă�����{�I�Ɍ������A�z��O�̊������L�������Ƃ��ł��A�Ή��ł��鐧�x��̐��𐮂���K�v������̂ł͂Ȃ����B�V�^�R���i�̎��Ґ����S���ő��̑�ォ��˂�����ꂽ�₢���B
|
���V�^�R���i�u�I�~�N�������v2�n���@�s���ŏ��m�F�@�s�������̉\���@5/24
�s���ŁA���߂āA�V�^�R���i�̃I�~�N�������̔h���^�ł���uBA.5�v�n���ƁuBA.2.12.1�v�n�����m�F���ꂽ���Ƃ����������B�����s���A����A���\�����B�s���ŕ�������������2�l�̃Q�m����͂��s�����Ƃ���A2�̌n���ł��邱�Ƃ����������Ƃ����B
������̊����҂��A�ŋ߁A�C�O�ɓn�q�������Ƃ͂Ȃ��A�s�������̉\��������Ƃ����B�uBA.5�v�ւ̊��������������̂�70��j���ō�����{�ɁA�uBA.2.12.1�v�ւ̊��������������̂�50��j���Ő挎���{�ɁA���ꂼ�ꔭ�ǁB2�l�Ƃ��y�ǂ��Ƃ����B
�I�~�N�������uBA.5�v�́A�挎29���ɐ��c��`�ɓ��������A�X�y�C���ƃU���r�A�ɑ؍ݗ�������60��̒j�����猟�o����Ă���B
�����s�ɂ��ƁA�uBA.2.12.1�v�́A���݁A�����Ŏ嗬�ƂȂ��Ă���uBA.2�v����ψق������́B�A�����J�ł́A�uBA.2�v�����uBA.2.12.1�v�̕��������Ă���Ƃ̂��ƁB����܂łɁA���{�̋�`���u�ŁA�uBA.5�v��3���A�uBA.2.12.1�v��71���m�F����Ă���Ƃ����B
�uBA.5�v�uBA.2.12.1�v�Ƃ��ɁA�uBA.2�v���������͂������\��������Ƃ����B�d�lj��̃��X�N�ɂ��Ă͕������Ă��Ȃ��B
|
���s���ŃI�~�N��������2�V�n�����m�F�c�����̃R���i�V�K����3��2383�l �@5/24
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�24���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����3��2383�l�m�F���ꂽ�B���҂�42�l�B�d�ǎ҂͑O�����4�l����100�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�3271�l�������B�O�T�̓����j������392�l����A11���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�3454�l�ŁA�O�T����8���������B
�s���ł͂܂��A�ψي��u�I�~�N�������v�̓�̐V�n����1�Ⴘ�m�F���ꂽ�B�d�lj����X�N�Ȃǂ͕s���Ƃ����B
|
���S���̐V�K������3��2383�l�@������3271�l 11���A���őO�T����� �@5/24
24���A�S���ł�3��2,383�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�B
�����s�ł�24���A�V����3,271�l�̊������m�F����A��T�̉Ηj������392�l����A11���A���őO�̏T�̓����j������������B�S���Ȃ����l��5�l�������B�I�~�N�������̓������ӂ܂����w�W�ɂ��d�ǎ҂�19�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����2.4%�ƂȂ��Ă���B
���̂ق��A���{��3,561�l�A���m����2,470�l�A�_�ސ쌧��1,919�l�ȂǁA�S���ł�3��2,383�l�̊�����41�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
�����J���Ȃɂ��ƁA23�����_�ł̐V�^�R���i�E�C���X�̑S���̏d�ǎ҂�100�l�ŁA�O�̓�����4�l�������B�S���̏d�ǎҐ���100�l��ƂȂ�̂�3���Ԃ�B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 8�l���S 3929�l�����m�F �O�T����400�l�� 5/25
�����s����25���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̐��j����肨�悻400�l���Ȃ�3929�l�ŁA�O�̏T�̓����j����12���A���ʼn����܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ8�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��25���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3929�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j����肨�悻400�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�12���A���ł��B25���܂ł�7���ԕ��ς�3393�l�ŁA�O�̏T��91.8���ł����B25���Ɋm�F���ꂽ3929�l��N��ʂɌ����30�オ�ł������A�S�̂�18.6���ɓ�����729�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�248�l�őS�̂�6.3���ł��B�����o�H���������Ă���1436�l�̂����A�ł������̂́u�ƒ���v��71.3���ɓ�����1024�l�ł����B
�܂�����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A24���Ɠ�����4�l�ł����B����A�s�͊������m�F���ꂽ60�ォ��90��̒j�����킹��8�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�̐V�K�R���i�����҂�2927�l�A�O�T���570�l�� 5/25
���{��25���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2927�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����570�l�������B���҂�5�l�������B
|
���u�f�v�㔼�ȍ~�̊����ґ����͌p�������A�����ɓ]�����v�c���J�ȏ����@�� 5/25
�V�^�R���i�E�C���X�̊�����]����������J���Ȃ̏����@�ւ�25���A�S���̐V�K�����Ґ��ɂ��āA�u��^�A�x�㔼�ȍ~�̑����X���͌p�������A�����ɓ]�����v�Ƃ̌������܂Ƃ߂��B�N��ʂɂ݂�ƁA10�Ζ����̂ݑ������Ă���A�w�Z��ۈ珊�E�c�t���ł̊��������~�܂肵�Ă���Ǝw�E�����B
���J�Ȃ̂܂Ƃ߂ł́A�S���̐V�K�����Ґ��́A24���܂ł�1�T�ԕ��ςŁA1���������3��4000�l�ŁA�O�T��0�E91�{�ƂȂ����B13�����_�ł�4���l���A6�����_����قڔ{���������A���̌�͌����X�����݂���B
�n��ʂɂ݂�ƁA24�����_�ŁA�����A��オ�O�T��0�E92�{�A���m�A��������0�E95�{�ƁA41�s���{���Ō������Ă���B����܂ő����������Ă�������������ɓ]�������A�u�S���ōł������������Ă���v�Ƃ����B
�����s���Ŋ����Ⴊ�m�F���ꂽ�I�~�N�������̐V�n���u�a�`�E2�E12�E1�v�Ɓu�a�`�E5�v�ɂ��ẮA�u�ꕔ�̍��Œu������肪�i��ł���A�Ď��𑱂��Ă����K�v������v�Ƃ����B
����A����Ҏ{�݂̑�Ɋւ��āA�㓡���J�����S���̖�5��6000�{�݂̂���94���ʼn��f������̐��𐮂����ƕ����B����1�����ԂŖ�30�|�C���g�㏸�����B
|
���R���i�����͑S���I�Ɍ����X���A���ӂ��K�v�Ȓn��� 5/25
�V�^�R���i�E�C���X��������J���Ȃɏ���������Ƒg�D(�A�h�o�C�U���[�{�[�h)��25���A�����ɂ��āu��^�A�x�㔼�ȍ~�̑����X���͌p�������A�S���I�ɂ͈ꕔ�̒n����̂����Č����X���������Ă���v�ƕ��͂����B����1�T�Ԃ̑S���̐V�K�����҂͑O�T��0�E91�{�B�O�T��葽�������̂͋{��A����A����A�����A���Q�A�F�{��6���ɂƂǂ܂�A��������1�E09�{���ő�B10�Ζ������̂����S�Ă̔N��Ō��������B
�������ꌧ�̂悤�ɁA����7���Ԃ̕��ς���N������̃s�[�N������n�������A�u�����������ӂ��K�v�v�Ƃ��Ă���B
|
���V�^�R���i���N�`����4��ڐڎ킪�X�^�[�g�@���ʂƕ�����������@5/25
���{�ł����傤����V�^�R���i���N�`����4��ڐڎ킪�X�^�[�g���܂����B�Ώۂ́u60�Έȏ���b��������18�Έȏ�̐l�̂݁v�ł��B�ڎ킷��l�����肷�闝�R�͏d�lj��\�h�̂��߂ł��B4��ڐڎ�̌��ʂƕ�������������܂��B
�����N�`���ڎ�4��ڃX�^�[�g�@�Ώۂƌ��ʂ�?
�z������H�L���X�^�[:�@���N�`����4��ڐڎ킪5��25������n�܂�܂����B��������3��ڂ̐ڎ�́A2021�N12���̔N������n�܂����Ƃ������ƂŁA�������N�قnjo���Ă���̂ł����A3��ڂ��܂��ł��ĂȂ��̂ɂ���4��ڂ��Ƃ����ӂ��Ɏv���������������邩������܂���B
3��ڂ�4��ځA�ǂ�ȈӖ�����������̂��A4��ڐڎ�͑Ώۂ����܂��Ă��܂��B���̑Ώۂ��������O�Ɏg���̂͂ǂ�ȃ��N�`���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ����Ă����܂��傤�B
1��ڂ���3��ڂɐڎ킵�����N�`���̎�ނɊւ�炸�A�t�@�C�U�[���̂��̂܂��̓��f���i�А��̂��̂ɂȂ�܂��B���N�`���ɂ͗l�X�ȍ\���̂��̂�����̂ł����A�ǂ����mRNA���N�`���Ƃ������̂��g���܂��B���J�ȂƂ��Ă��A�C�O�̌�����4��ڐڎ�ɂ��I�~�N�������Ȃǂւ̗L�������m�F���Ă��܂��̂ŁA����ł����܂��Ƃ������Ƃł��B�����āA�Ώۂ́A����͏d�lj����X�N��������Ɍ��肵�Đڎ���s���܂��B
3��ڂ̐ڎ킩��5�������o�߂��Ă��āA60�Έȏ�ł��邱�ƁA���邢�͊�b����������18�Έȏ�ł��邱�ƁA�������������X���ΏۂƂȂ�̂ł����A�����̂ɂ���ẮA�ΏۂɂȂ�Ƃ������Ƃ���������\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��P�[�X������܂��̂ŁA���Z�܂��̎����̂̃z�[���y�[�W�Ȃǂ��m�F���Ă݂Ă��������B�܂��A�ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ��̂ɐڎ팔���z���Ă����Ƃ������́A�ڎ팔���������Ƃ��Ă��ΏۂłȂ���ΐڎ킷�邱�Ƃ͂ł��܂���̂ŁA�����ӂ��������B
��4��ڐڎ�́g�d�lj��\�h�h�ɗL��
�z�����L���X�^�[:�@�Ȃ����肳��Ă���̂��Ƃ����_�ɂ��ČJ��Ԃ��ɂȂ�܂����A�g�d�lj��\�h�h�̂��߂Ƃ������Ƃ���͂肠��悤�ł��B�ł́A�d�lj��\�h�ɂ��ăf�[�^(���J�ȐR�c���)�����Ă����܂��傤�B
�C�X���G���̃f�[�^�ł��B�C�X���G���̓��N�`���ڎ�Ɋւ��āA��ɐ擪�𑖂��Ă����킯�ł����A4��ڐڎ�ɂ��I�~�N�������ւ̌��ʂɂ��āA�f�[�^���W�܂��Ă��܂����B�܂��͂��̏d�lj��\�h�̌��ʂ��ǂꂭ�炢����̂������Ă����܂��傤�B4��ڂ�ڎ킵����̊��ԂŌ��Ă݂܂��B4��ڐڎ��A22-28���o�߂������́A3��ڎ�҂Ɣ�r����3.5�{�̏d�lj��\�h���ʂ��������B�����āA36-42���o�߂������́A4.3�{�̏d�lj��\�h���ʂ��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�d�lj��\�h���ʂɉ����āA�����\�h���ʂ����҂ł���ƌ����Ă������N�`���ł����A������̕��́A�f�[�^�����Ă݂܂��Ƃ����܂łł��Ȃ��̂�������Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B4��ڐڎ��A22-28���o�߂������́A3��ڐڎ�҂Ɣ�r����2.0�{�A�����āA50-56���o�߂������́A1.1�{�Ɖ������Ă����܂��̂ŁA���̃f�[�^�����Ă݂܂��Ă��A��͂�d�lj����X�N��������Ɍ��肵�Đڎ킵�Ă������Ƃ��L�����낤�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
4��ڐڎ킪�C�O�łǂ̂悤�ɍs���Ă���̂��Ƃ����̂����Ă����܂��ƁA
4��ڐڎ� �C�O�̎��{��(���J��HP)
�E�A�����J�@�@50�Έȏ�̐l�@�Ɖu�s�S�̐l�Ȃ�
�E�C�M���X�@�@75�Έȏ�Ȃǁ@�d�lj����X�N�̍����l
�E�J�i�_�@�@�@70�Έȏ�̐l�@����Ҏ{�݂ɓ�������l
�E�t�����X�@�@60�Έȏ�̐l�@�Ɖu�s�S�̐l
�E�h�C�c�@�@�@70�Έȏ�̐l�@���{�݂ɓ�������l�Ȃ�
�E�C�X���G���@60�Έȏ�̐l�@18�Έȏ�̏d�lj����X�N�̍����l�Ȃ�
��͂肠����̔N��ȏ�̕��A���ꂩ��d�lj����X�N�̍������Ƃ����悤�ɑΏۂ����肵��4��ڐڎ���s���Ă��鍑�������悤�ł��B
���M���L���X�^�[:�@����̃I�~�N�������Ƃ����̂́A�d�lj����Ƃ����̂��N����b����������Ȃ��ő����J��������̂ŁA�܂��̓��X�N�̍���������������Ǝ���Ă������Ƃ����l�����ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��傤���B
���ۈ�Õ�����w �����NJw�u�� ���{�N�Ǝ�C����:�@���E�I�ɍ��A��{�I�ɂ̓I�~�N�������̗��s�����S�ł��̂ŁA�Ⴂ���͂��܂�d�lj����ɂ����B����҂͂���ς�d�lj����₷���̂ŁA��{�I�ɂ̓��N�`����4��ڐڎ����{�I�ɍ���҂ƖƉu�s�S�Ƃ���b�����������Ă�l�ŏd�lj��̃��X�N�������l�B���̐l����������Ƃ��Ă���Ă����ƁB���ケ�̂܂܂����Ƃ������ǂ����킩��܂��ǂ��A�܂��͂��������l�������ΏۂɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
���L���X�^�[:�@����̃��N�`���Ɋւ��ẮA�������ǂ��������߂Ɋ����\�h���ʂƂ����Ƃ��낪�����Ɍ����܂������ǁA���𐳂��ƃ��N�`���͏d�lj��\�h�Ƃ����l�����Ȃ̂ł���ˁB
���ۈ�Õ�����w ���{��C����:�@���N�`���̎�ނɂ����܂�����ǁA����̂悤�ȋC���n�̃E�C���X�̃��N�`���Ƃ����̂͂���ȂɊȒP�ɑS�����ǂ���\�h�ł���Ƃ����͍̂��܂ł��܂肠��܂���ł����B������l����Ƒ����͂���ς�Ǐo���肵�Ă��܂��܂�����ǁA��ԑ厖�Ȃ̂͂�͂�d�lj��\�h�Ƃ����ӂ��ɂ����������Ă��Ă�Ǝv���܂��B
��4��ڐڎ�̋C�ɂȂ镛������? 5��ڂ̐ڎ��?
�z�����L���X�^�[:�@���N�`���ڎ�Ƃ����C�ɂȂ�̂��������ł��B4��ڂ̕������ɂ��Ă�������C�O�̃f�[�^�Ō��Ă����܂��ƁA��قǂ̃C�X���G���̌����f�[�^�ł��B1��ځA2��ڂ�����3��ڃt�@�C�U�[�̂��̂�ł��܂����B�������́A��Ȃ��̂ŁA���M(37.5�x�ȏ�)39.8���A�ڎ핔�̒ɂ�91.6���A����ӊ�69.1���A����55.0���Ȃǂ������Ă݂��̂ł����A3��ڂ̂Ƃ��͂���������Ȃ�̊����ŁA�����ꂩ�̎҂��邢�͕����̂��̂�����������������悤�ł��B
4��ڂ����Ă����܂��傤�B
���f���i�ƃt�@�C�U�[�̂��̂ŏ������͂���̂ł�����ǂ��A�Ⴆ�Δ��M�A���ꂩ�瓪�ɂȂǂŌ��Ă����܂���4��ڃt�@�C�U�[�ŁA���M(37.5�x�ȏ�)10.7���A����28���A4��ڃ��f���i�ŁA���M(37.5�x�ȏ�)6.9���A����23.3����4��ڂ͂�����x�y������Ă���Ƃ����Ƃ��낪������Ǝv���܂��B
�����ڎ핔�̒ɂ݂Ȃǂ́A4��ڃt�@�C�U�[�ŁA�ڎ핔�̒ɂ�88���A4��ڃ��f���i�ŁA�ڎ핔�̒ɂ�83.6���A����������������Ŋ�������������悤�ł��B
�����č����4��ڂ͒N�ɐڎ킷�邩�͌��肳��Ă��܂����A5��ڂ̐ڎ킻�ꂩ��܂��ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ�4��ڂ̐ڎ�Ȃǂɂ��āA���B���i���Ɖ��B���a��Z���^�[��4��6���ɐ����\���Ă��܂��B
4��ڈȍ~�̐ڎ�ɂ��āA����͍���ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ������܂߂ĂȂ̂ł����A�~�ɗ��s���₷�����Ƃ���A�lj��̐ڎ����������K�v�����邻���ł��B�����A�����_�ł́A�V�^�R���i�E�C���X�ɂ�鈫�e����h���ł��L���ȕ��@�́A2��̐ڎ��3��ڂ̒lj��ڎ�Ƃ������ƂŁA��͂�3��ڎ킵�Ă��邱�Ƃ������_�ł͏d�v�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
���@�̃z�[���y�[�W��5��24�����_�̓��{�S�̂�3��ڂ̐ڎ헦�́A57.9���ł��̂ŁA�������オ���Ă������Ƃ����z�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����ˁB
���L���X�^�[:�@�悭�Ⴂ����̐ڎ킪�i�ނƂ����Ƃ����������Ȃ���܂����A�Ⴂ���̓��X�N���������蔻�f���đł��Ȃ��Ƃ����I�����Ƃ�Ƃ����̂��ƂĂ��[���͂ł��܂����A�������̐ӔC��N������Ă����̂��Ƃ������Ƃ�����܂����A���N�`���ɂ��Ă͂̕ǂ������ɂȂ��Ă��܂���?
�H�׃`���N �H�����ޑ�\:�@��͂茋�ǁA�d�lj����Ȃ��Ⴂ���Ɋւ��Ă͂����ȑI����������܂����A�l�l�Ŕ��f���Ă�����������ȂƂ����͎̂v���Ă��܂��B���A70��̕ꂪ����̂ł�����ǂ��A����ς�3��ڂ̐ڎ킪�n�܂���12���A1���ɔ�ׂ�ƍ����Č��\�A�s���ʂ������Ă���̂Ő����S�z�ȕ����͂������̂ŁA���������I�������ł���Ƃ����̂͂��������肪�����ȂƎv������ŁA�p��������Ԃ��Ăǂꂭ�炢�Ȃ̂��ȂƂ����̂�������ƂЂƂ^��Ɏv���܂����B�d�lj���h���m�����A4�{���炢�ɂȂ��Ă�Ƃ������Ƃł�������ǂ��A�ǂꂭ�炢����������̂Ȃ̂��Ȃ��Ă����̂͂�����ƋC�ɂȂ��Ă��āA���\�A�ǂꂭ�炢�������ɂ���Ă��A���f�ɂ��e�������邩�Ȃ��Ă����͎̂v�����̂ł����A���{�搶�ɂ����Ђ��f���ł�����E�E�E�B
���ۈ�Õ�����w ���{��C����:�@����4��ڂ̐ڎ�����ł����Ƃ�����A�d�lj��\�h�̌��ʂƂ����̂�3�A4�������炢�͔�r�I�ۂ���܂����ǁA�������z�肳��Ă���悤�ȓ~�̗��s�܂ł͑��������Ȃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B�Ȃ̂ŁA���������Ӗ��ł͑��߂ɑł��Ƃ͂��ꂼ��̔��f�ł����ǂ��A�����4��ڂ������Ō�̐ڎ�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��\���͂���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���L���X�^�[:�@5�����Ԋu���炢��5��ځA6��ڂƂ������Ƃ�����ɂƂ������Ƃł���?
���ۈ�Õ�����w ���{��C����:�@5��ڂ܂ł͍��N����ς�~�̎������}���āA���邩������܂��B6��ڈȍ~�́A�ł����1�N��1�炢�ɂ��Ăق����ȂƂ����ӂ��Ɋ��҂��Ă��܂��B
|
��4���̊O�H���㍂�A13�E5�����@�܂h�~�����ŋq�������@5/25
���{�t�[�h�T�[�r�X���25�����\����4���̊O�H���㍂(�S�X�x�[�X)�͑O�N������13�E5���������B������5�J���A���B�V�^�R���i��̂܂h�~���d�_�[�u��3�����{�ɑS�ʉ�������A�T���𒆐S�ɋq���������������B����2019�N4����ł�8�E1�����ŁA�R���i�БO�̐����ɂ͓͂��Ȃ������B
�t�@�X�g�t�[�h�́A�R���i�ЂŒ蒅���������A���z�B���v�Ɏx�����A�O�N������8�E4���������B�t�@�~���[���X�g�����A�p�u�E�������͂��ꂼ��17�E5�����A81�E9�����Ƒ啝�ɐL�т��B
19�N4���Ƃ̔�r�ł́A�t�@�X�g�t�[�h��7�E7�����A�t�@�~���[���X�g�����ƃp�u�E�������͌��������B�@ |
 |
�������̃R���i�����ҁA13���A���őO�T�����@5/26
�����s��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�V����3391�l�m�F�����Ɣ��\�����B1�T�ԑO(19��)����781�l����A13���A���őO�T�̓����j������������B26���܂ł�1�T�ԕ��ς̊���������ƁA1��������̊����Ґ���3281�E4�l�ŁA�O�T(3689�E0�l)��89�E0%�������B60�`90��̒j��10�l�̎��S�����\���ꂽ�B
26���̐V�K�����҂�N��ʂɂ݂�ƁA�ő���20���737�l�ŁA30���595�l�A10�Ζ�����518�l�A40���510�l�A10���405�l�A50���299�l�Ƒ������B65�Έȏ�̍���҂�234�l�������B
�a���g�p����15�E7%�B�܂��A�s��30�`40%�ŋً}���Ԑ錾�̗v���f����w�W�Ƃ��Ă���d�ǎҗp�a���g�p����1�E9%�������B�u�l�H�ċz�킩�̊O�����^�l�H�x(ECMO(�G�N��))���g�p�v�Ƃ���s��̏d�ǎҐ��͑O�����1�l������3�l�ƂȂ��Ă���B
|
�������s �R���i 10�l���S 3391�l�����m�F ��T�ؗj���800�l�� �@5/26
�����s����26���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̖ؗj����肨�悻800�l���Ȃ�3391�l�ŁA�O�̏T�̓����j����13���A���ʼn����܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ10�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��26���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3391�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̖ؗj����肨�悻800�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�13���A���ł��B26���܂ł�7���ԕ��ς�3281.4�l�ŁA�O�̏T��89.0���ł����B26���Ɋm�F���ꂽ3391�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�21.7���ɂ�����737�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�234�l�ŁA�S�̂�6.9���ł��B�����o�H���������Ă���1236�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v�ŁA69.9���ɂ�����864�l�ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�3�l�ŁA25�����1�l����܂����B����A�s�͊������m�F���ꂽ60���80��A�����90��̒j�����킹��10�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�������������Ċg�匜�O�A�x�����x���ێ��@�s���j�^�����O��c�@5/26
�����s��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����͂��郂�j�^�����O��c��s���ŊJ�����B�V�K�����Ґ��͌����X���ɂ�����̂́A�I�~�N�������̐V���Ȕh���^���s���ł��m�F�����ȂNJ����Ċg�傪���O�����������A�����̌x���x��4�i�K�̂����ォ��2�Ԗڂ̃��x���ɐ����u�����B
����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���25�����_��3304�l�B18�����_��3587�E6�l���猸���������A12���̑O���c�ȍ~�A�I�~�N�������h���^�́u�a�`�E5�v�Ɓu�a�`�E2�E12�E1�v�̊����҂��s���ŏ��m�F����A���Ƃ́u(�ψي���)�Ď��̐����������Ă���v�ƕ����B
�u���o�E���h�x�����ԁv������22���̊����ŏI�����Ĉȍ~�A��v�ɉ؊X�̖�Ԃ̐l�o���������Ă���A���Ƃ���u�������X�N�̍����s�����Ƃ�l���啝�ɑ�����ƁA�������Ăш�������\�����\���ɂ���v�Ƃ̌��O�������ꂽ�B
���r�S���q�m���́u��{�I�Ȋ����h�~���O�ꂷ�邱�Ƃ�������}�����Ԃ̃x�[�X�ɂȂ�v�Əq�ׁA��̌p�����d�˂ČĂъ|�����B
|
�����V�^�R���i2524�l�̊����m�F�@2�l���S�@5/26
���{��26���A�V����2524�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����A2�l�̎��S���m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
|
���}�X�N�O���Ȃ��̂́u�Z���ڐG�҂△�Ǐ�E�y�ǎ҂Ɉꗥ�̎���ҋ@���E�E�E�v�@5/26
�����{�m���ŕٌ�m�̋����O����26���A���g�̃c�C�b�^�[���X�V�B�V�^�R���i�E�C���X�����\�h�̂��߂̃}�X�N���p�̌���ɂ��āA�������q�ׂ��B
���̓��A���{��23���ɐV�^�R���i�E�C���X��̎w�j�u��{�I�Ώ����j�v������B�}�X�N���O�����̓I�ȗ����A���O�ł͂�قǐl�����W���Ă��Ȃ�����A�قڃ}�X�N�͕s�v�ł���悤�Ɏv������e�ƂȂ������Ƃ���L����\��t�����������B
�u�d�lj������Ⴂ���A���N�`����ł��Ă���Ȃ�����R���i���̂�S��|����l�͏��Ȃ��Ȃ��Ă���v�ƂÂ�ƁA�u�O���ɂ����͔̂Z���ڐG�҂△�Ǐ�E�y�ǎ҂Ɉꗥ�̎���ҋ@���Ԃ����܂��ɐ݂��Ă��邩�炾�v�Ƒ����Ă����B
|
�����ꌧ�A�R���i�x���6��9���܂Ōp���@���{���j�܂����O�}�X�N�ɘa�@5/26
���ꌧ�̋ʏ�f�j�[�m����25���A�����ŋL�҉���A�V�^�R���i�E�C���X�ւ̑Ή��ŁA���O�Ől�Ƌ�����ۂĂ�ꍇ���b���Ȃ���ʂ̓}�X�N���p�͕K�v�Ȃ��Ƃ̕��j���������B���{�̑Ή����j�܂����B����ŁA����{���Ƌ{�Òn��ւ̃R���i�����g��x���6��9���܂Ōp������Ɣ��\�����B25���̐V�K�����҂�10�Ζ�������90�Έȏ�̒j��2081�l�ŁA�ߋ�2�Ԗڂɑ���������T18����2560�l����479�l���������B(�Љ�E������N�A���o���E���g�r�[)
���͉ď�̔M���Ǘ\�h�̊ϓ_����A���O�Ń}�X�N���O���悤�������Ă���B�����O���킸2�Ζ����̃}�X�N���p�͐��������A2�Έȏ�̖��A�w�������͂̑�l���̒��ɒ��ӂ�����Œ��p�����邩�f����悤���߂Ă���B
�w�Z�ł͋������m�ۂł���ꍇ��̈�̎��ƁA�������Œ��p�͕K�v�Ȃ��Ƃ��Ă���B������ψ���͏����w�Z�����ǂ���s�����ɂ����������e��ʒm�����B
�����Ŋ����Ґ������~�܂肷�钆�A�}�X�N���E�̔��f�Ɍ˘f�����\�z�����B�ʏ�m���́u�Ή��������ɔ��f���Ă��炤�͔̂��ɓ�����A�������������Č��N���L�[�v���Ăق����v�ƌĂт������B�������ی���Õ����́u(���O�̔p��)������̊ɘa�Ƃ������M���ǂ�����邽�߁v���Ƌ��������B
���͈�Ñ̐���������I�ȎЉ�o�ϊ������ێ��������ԂƂ��āA6��23���܂Ō��S��ŗ\�h�̓O������߂��B
�e����̐V�K�����Ґ����O�T��2�{�����ꍇ��a���g�p����60���ȏ�ƂȂ����ꍇ�́A�܂h�~���d�_�[�u�ɏ������Ή��̐��{�ւ̗v������������B
�V�K������2081�l��10�Ζ�����418�l���ő��ŁA10�オ352�l�B24�����_��10���l������̊����Ґ���920�E26�l�őS�����[�X�g�B�ČR�W��78�l�������B
26�l�̊������m�F����Ă������������a�@�ł̃N���X�^�[(�����ҏW�c)2���́A�����҂�8�l�����Čv34�l�ƂȂ����B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 8�l���S 2630�l�����m�F ��T����900�l�� �@5/27
�����s����27���̊����m�F��1�T�ԑO�̋��j����肨�悻900�l���Ȃ�2630�l�ŁA�O�̏T�̓����j����14���A���ʼn����܂����B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ8�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��27���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2630�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j����肨�悻900�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�14���A���ł��B27���܂ł�7���ԕ��ς�3146.7�l�ŁA�O�̏T��87.1���ł����B27���Ɋm�F���ꂽ2630�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�19.6���ɂ�����516�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�209�l�ŁA�S�̂�7.9���ł��B�����o�H���������Ă���1002�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v�ŁA73.7���ɂ�����738�l�ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�2�l�ŁA26�����1�l����܂����B����A�s�͊������m�F���ꂽ70�ォ��90��̒j�����킹��8�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����2210�l�R���i�����c1�T�ԑO����781�l���@5/27
���{��27���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2210�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j��(2991�l)���781�l�������B���҂�3�l�������B
|
���O�T�̓����j����茸���A2�T�ԑ����@�����̃R���i�����ҁ@5/27
�����s��27���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�V����2630�l�m�F�����Ɣ��\�����B1�T�ԑO(20��)����943�l����A14���A���őO�T�̓����j������������B27���܂ł�1�T�ԕ��ς̊���������ƁA1��������̊����Ґ���3146�E7�l�ŁA�O�T(3612�E4�l)��87�E1%�������B70�`90��̒j��8�l�̎��S�����\���ꂽ�B
27���̐V�K�����҂�N��ʂɂ݂�ƁA�ő���20���516�l�ŁA30���486�l�A40���431�l�A10�Ζ�����361�l�A10���333�l�A50���236�l�Ƒ������B65�Έȏ�̍���҂�209�l�������B
�a���g�p����15�E4%�B�܂��A�s��30�`40%�ŋً}���Ԑ錾�̗v���f����w�W�Ƃ��Ă���d�ǎҗp�a���g�p����1�E9%�������B�u�l�H�ċz�킩�̊O�����^�l�H�x(ECMO(�G�N��))���g�p�v�Ƃ���s��̏d�ǎҐ��͑O�����1�l������2�l�ƂȂ��Ă���B
|
���V�^�R���i 1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ� 46�s���{���Ō��� �@5/27
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł͊ɂ₩�Ȍ����X���ŁA46�̓s���{���őO�̏T��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S�� / 4��28���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�ɔ�ׂ�0.94�{�A5��5����0.67�{��3�T�A���Ō������Ă��܂������A��^�A�x��������12����1.41�{�Ƒ����ɓ]���܂����B���̌�͍���19����0.97�{�A26���܂łł�0.87�{�Ɗɂ₩�Ȍ����X���ƂȂ��Ă��āA1��������̕��ς̐V�K�����Ґ��͂��悻3��1607�l�ƂȂ��Ă��܂��B�V�K�����Ґ��͎R�����������āA46�̓s���{���őO�̏T��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�����ꌧ / ����1�T�� �l��10��������S���ő� / ���ꌧ�͍���12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.57�{�A����19����1.05�{��2�T�A���ő������Ă��܂������A26���܂łł�0.84�{�ƌ������Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1783�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���850.71�l�ƁA�S���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
�������s / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.31�{�Ƒ������Ă��܂������A����19����0.93�{�A26���܂łł�0.89�{��2�T�A���Ō������Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻3281�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���_�ސ쌧 / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.04�{�A����19����1.02�{�A���̂��܂łł�0.91�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1707�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����ʌ� / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.24�{�A����19����0.88�{�A26���܂łł�0.80�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1120�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����t�� / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.12�{�A����19����0.93�{�A26���܂łł�0.90�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻899�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����{ / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.67�{�A����19����0.96�{�A26���܂łł�0.88�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻2595�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����s�{ / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.54�{�A����19����1.02�{�A26���܂łł�0.93�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻796�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ɍ� / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.44�{�A����19����1.03�{�A26���܂łł�0.87�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1330�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����m�� / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.70�{�A����19����1.02�{�A26���܂łł�0.90�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻2000�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���k�C�� / ����12���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.24�{�A����19����0.97�{�A26���܂łł�0.78�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1963�l�ƂȂ��Ă��܂��B |
�������̃R���i�V�K����2��7551�l�c������1�T�ԕ��ς�13���� 5/27
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�27���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����2��7551�l�m�F���ꂽ�B���҂�38�l�B�d�ǎ҂͑O������5�l����90�l�������B
�����s�ł́A�V����2630�l�̊������m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j������943�l����A14���A����1�T�ԑO����������B�s�ɂ��ƁA����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�3147�l�ŁA�O�T����13���������B70�`90�Α�̒j��8�l�̎��S�����������B
���{�ł́A�V����2210�l�̊����������B�O�T�̓����j������781�l�������B70�`90�Α�̒j��3�l�����S�����B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 7�l���S 2549�l�����m�F �O�T����900�l�� �@5/28
�����s����28���̊����m�F��1�T�ԑO�̓y�j����肨�悻900�l���Ȃ�2549�l�ŁA�O�̏T�̓����j����15���A���ʼn����܂����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��28���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2549�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j����肨�悻900�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�15���A���ł��B28���܂ł�7���ԕ��ς�3016.0�l�ŁA�O�̏T��84.6���ł����B28���Ɋm�F���ꂽ2549�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�19.1���ɂ�����488�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�188�l�ŁA�S�̂�7.4���ł��B
�܂�����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�3�l�ŁA27�����1�l�����܂����B����A�s�͊������m�F���ꂽ20��̒j��1�l��70�ォ��90��܂Œj��6�l�̍��킹��7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����V�^�R���i2243�l�̊����m�F�@2�l���S�@5/28
���{��28���A�V����2243�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����A������2�l�̎��S���m�F����܂����B
|
������R���i1509�l�����@�O�T���706�l���@8���A���ʼn����@5/28
���ꌧ��28���A�V����1509�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓y�j��(21��)��2215�l�ɔ�ׂ�706�l����A8���A���őO�T�̓����j������������B�v�����҂�21��2141�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�z���Ґ��͑O�����_��792.33�l�ň��������S���ő��B2�Ԗڂɑ����{�茧��260.48�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����46.5��(���@�Ґ�299/�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��16.7��(���@10/�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����57�l�̕��������B�@ |
 |
�������s�A�V����2194�l�̊������\ 16���A���őO�T�����@ �d�ǎ�3�l�@5/29
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�����s��29���V����2194�l�̊����\���܂����B��T���j����3317�l����1123�l�����Ă��āA16���A���őO�̏T�̓����j���̊����Ґ���������Ă��܂��B�����s�́u���������A��t�������Ɛf�f�����v�g�݂Ȃ��z���h�̊��҂������҂Ƃ��Ĕ��\���Ă��āA1�l���g�݂Ȃ��z���h�̊��҂ł����B�V���Ȋ����҂̂����A���N�`����2��ڎ킵�Ă����l��1081�l�ŁA1����ڎ�����Ă��Ȃ��l��536�l�ł����B�V�^�R���i�̕a���g�p����15.2���ŁA�ő�Ŋm�ۂł��錩���݂�7216���ɑ��A1096�l�����@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�̕a���g�p���́A2.1���ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł́A10�㖢����389�l�A10�オ268�l�A20�オ354�l�A30�オ421�l�A40�オ359�l�A50�オ191�l�ŁA�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂�158�l�ł����B
���ݓ��@���Ă��銴���҂̂����A�����s�̊�Łu�d�ǎҁv�Ƃ����l�́A3�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��V���ɁA4�l�̎��S�����\����Ă��܂��B |
�������ŐV����2��828�l���R���i�����c������1�T�ԕ��ς�20���� �@5/29
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�29���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����2��828�l�m�F���ꂽ�B���҂�19�l�A�d�ǎ҂͑O������7�l����88�l�������B
�����s�ł́A�V����2194�l�̊����҂��m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j������1123�l����A16���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�2856�l�őO�T����20���������B���҂�80�`90�Α�̏���4�l�������B
���{�́A1502�l�̐V�K�����҂��m�F���ꂽ�Ɣ��\�B�O�T�̓����j��(2252�l)���750�l�������B���҂�4�l�������B
|
������ŐV����1173�l�����@�V�^�R���i�@5/29
���ꌧ��29���A�V����1173�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓����j��(22��)��1750�l�ɔ�ׂ�577�l�������B�v�����҂�21��3314�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����҂�28�����_��744.79�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ����{�茧��247.97�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����49.9��(���@�Ґ�321/�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��18.3��(���@�Ґ�11/�a����60)�ƂȂ��Ă���B
�ČR�W�́A�V����10�l�̊��������ꂽ�B
|
���R���i�Ђ̓s���Ő��������p�[�e�B�[�ĊJ�@�����A�s���t�@�A���r�m�����@5/29
�Q�@�I���߂Â��A�V�^�R���i�E�C���X�ЂŊJ�Â��������Ă������������p�[�e�B�[���ĊJ���铮�����A�L�����Ă���B�����ł͎����}��n�搭�}�u�s���t�@�[�X�g�̉�v��5���ɓ����čĊJ�����̂ɑ����A������𗦐悵�ČĂъ|���Ă������r�S���q�s�m�����J�Âɂ���������B�I�����d������v�f�������钆�A�ˑR�A�T�d�_������B(���������A�y��N�Y)
�u���Ԃ������Ă��܂��v�u����V�������h�Ȃ́v
���r�m����25�����A�s���̃z�e���ŕ���Ƒ肵�����2���~�̐��������p�[�e�B�[��2019�N11���ȗ��A2�N���Ԃ�ɊJ�����B�w�ɔ���J���������A�o�Ȏ҂ɂ��ƁA�p�[�e�B�[�I�ՂɎ��炪���ʌږ�߂�s���t�@�[�X�g�̉��A�Q�@�I�ɏo�n���鏗�����҂�d��ɌĂ�Ŏ��g�́u��p�v�ƏЉ�A�I�����[�h�����o�B�p�[�e�B�[�ɂ͓s��t��̊������700�l���o�ȁB���r�m���͏o�Ȏ�1�l���ɖ��h����n���A���J�ɋA������������B
���爬��̎�������o������A�̂������ċL�O�B�e�����肷��l�q����́A���r�m���̃R���i�Ƃ̌����������ɕω������ꂽ���Ƃ���ۂÂ����B
�s���t�@�[�X�g�̉��15���A���������p�[�e�B�[���J�����B�R���i�ЈȑO�̂悤�ȗ��H�`���ł͂Ȃ��A1���[�g���Ԋu�ŕ��ׂ��֎q�ɍ����ču�����̂݁B����s�c�́u�H���Ȃ��ł̓p�[�e�B�[���������Ă��炦�Ȃ��v�Ƃڂ₢�����A���2���~��400�l���Q�������B���̓��͓s����߂Ă����u���o�E���h�x�����ԁv�̍Œ����������A�s���t�@�����́u�������O�ꂵ�Ă���̂ł��Ȃ��I�����͂Ȃ������v�Ƙb�����B
�����}��10���A�u���i�̂ǂ��v�Ə̂������������p�[�e�B�[��2�N���Ԃ�ɊJ�ÁB�}�̊ݓc���Y���ق��p�������钆�A�Q�@�I�ɏo�n�������2�l�����ӕ\�������B���W������Ȃ��悤�ɂ��邽��2�����ɂ��ĉ���2000�l�߂����Q���B�}�W�҂́u�{���͗��H�ł�肽�����ǔᔻ�����̂Łc�v�ƘR�炵���B
���̂Ƃ���ق��ɓ����͌����Ȃ����A�Q�@�I�ɏo�n�\��̓��{�ېV�̉�̌��҂͎�ނɁu�ĊJ�̓����͗ǂ����Ƃ��B�������������Ōo�ς�����Ă����͍̂D�܂����v�B
�����s���ł�29�����_�ŁA����1�T�Ԃς���1��������̐V�K�����҂�2800�l����B�Q�@�I�ɗ����\��̗�������}�̌��҂̓p�[�e�B�[�ĊJ�ɂ��āA�u�����Ŗ��ȏ�����̂͂����B���̊��o���S��������Ȃ��v�Ǝw�E�B��������Ăъ|���闧��̏��r�m�����J�Â��邱�Ƃɂ́u������Ƃǂ����Ǝv���v�Ɣᔻ�����B
���V�^�R���i�Ђ̐��������p�[�e�B�[�@
�V�^�R���i�E�C���X�Ђ��g�債��2020�N�A����c����̐��������p�[�e�B�[�̊J�Â͌����B�����ȕ��̓��N�̐����������x���ɂ��ƁA�����c�̂̃p�[�e�B�[�����͑O�N��28������63��8�疜�~�������B�V�^�R���i��ً̋}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�͍��N3��21���܂łɊ��S�ɉ�������A����ȍ~�̓p�[�e�B�[�J�Â��ڗ��B
�ŋ߂͊ݓc���Y���p�ɂɓ}���e�h���Ȃǂ̃p�[�e�B�[�ɏo�ȁB�דc���V�O�@�c�����ᔻ�𗁂т��u��100���~�����̎���̋c���𑽏����₵�����Ĕ��͓�����Ȃ��v�Ƃ̔������������̂��A����10���̎����}�����c���̃p�[�e�B�[�������B �@ |
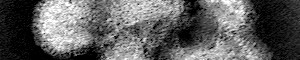 |
�������s���̐V�K�R���i�����ҁA�O�T��681�l���Ȃ�1344�l�Ɂ@5/30
�����s��30���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�V����1344�l�m�F�����Ɣ��\�����B�O�T�̌��j��(23��)����681�l�������B30���܂ł�1�T�ԕ��ς̊����Ґ���2758�E3�l�ƑO�T(3509�E9�l)��78�E6%�ƌ��������B70�`80��̒j��3�l�̎��S�����\���ꂽ�B
30���̐V�K�����҂�N��ʂɂ݂�ƁA�ő���30���264�l�ŁA20���248�l�A40���207�l�A10�Ζ�����189�l�Ƒ������B65�Έȏ�̍���҂�109�l�������B
�a���g�p����14�E8%�B�܂��A�s��30�`40%�ŋً}���Ԑ錾�̗v���f����w�W�Ƃ��Ă���d�ǎҗp�a���g�p����2�E0%�������B�u�l�H�ċz�킩�̊O�����^�l�H�x(ECMO�q�G�N���r)���g�p�v�Ƃ���s��̏d�ǎҐ��͑O�����1�l������4�l�ƂȂ��Ă���B
|
������ �R���i 3�l���S 1344�l�����m�F �O�T���j����700�l�� �@5/30
�����s����30���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̌��j����肨�悻700�l���Ȃ�1344�l�ŁA�O�̏T�̓����j����17���A���ʼn����܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��30���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1344�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j����肨�悻700�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�17���A���ł��B����̊����m�F��2000�l�������̂͂��Ƃ�1��11���ȗ��ł��B30���܂ł�7���ԕ��ς�2758.3�l�ŁA�O�̏T��78.6���ł����B30���Ɋm�F���ꂽ1344�l��N��ʂɌ���ƁA30�オ�ł������A�S�̂�19.6���ɂ�����264�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�109�l�ŁA�S�̂�8.1���ł��B�����o�H���������Ă���467�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v�ŁA71.9���ɂ�����336�l�ł����B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�4�l�ŁA29�����1�l�����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70���80��̒j�����킹��3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����548�l���R���i���� �O�T���j�����336�l���@5/30
���{��30���A�{���ŐV����548�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\�����B�O�T�̓������j��(23��)���336�l���Ȃ������B1��������̊����҂�600�l�������̂́A499�l������1��10���ȗ��B
�܂��A5��29����70��̏���1�l�����S���Ă������Ƃ��V���Ɋm�F���ꂽ�B�{���̊����҂͉���97��1573�l�A���҂͌v5041�l�ƂȂ����B�@ |
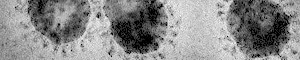 |
�������s���̃R���i�����ҁA�T���ς͑O�T��24%���@�V�K��2362�l�@5/31
�����s��31���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�V����2362�l�m�F�����Ɣ��\�����B�O�T�̉Ηj��(24��)����909�l�������B31���܂ł�1�T�ԕ��ς̊����Ґ���2628�E4�l�ƑO�T(3453�E9�l)��76�E1%�������B80�`90��̒j��6�l�̎��S�����\���ꂽ�B
31���̐V�K�����҂�N��ʂɂ݂�ƁA�ő���30���441�l�ŁA20���431�l�A10�Ζ�����413�l�A40���368�l�Ƒ������B65�Έȏ�̍���҂�175�l�������B
�a���g�p����13�E9%�B�܂��A�s��30�`40%�ŋً}���Ԑ錾�̗v���f����w�W�Ƃ��Ă���d�ǎҗp�a���g�p���͑O���ƕς�炸2�E0%�������B�u�l�H�ċz�킩�̊O�����^�l�H�x(ECMO�q�G�N���r)���g�p�v�Ƃ���s��̏d�ǎҐ��͑O�����1�l������3�l�ƂȂ��Ă���B |
�����{�ŐV����2314�l���R���i�����A1�T�ԑO�̓����j�����1246�l���@5/31
���{��31���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2314�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����1246�l�������B���҂�5�l�������B�@ |
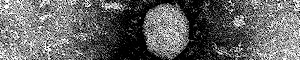 �@ �@
 �@ �@
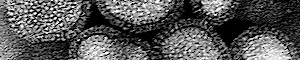 |


 �@
�@ |
�����ꌧ���R���i����1469�l�@11���A���őO�T�䌸�@6/1
���ꌧ��5��31���A10�Ζ�������90�Έȏ��1469�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�N���X�^�[(�����ҏW�c)��2�����������B��T�Ηj������449�l���������B11���A���őO�T�̓����j����茸�����A���̋{���`�v�����������Ắu�s�[�N�A�E�g�����v�ƕ����B
�Љ���{�ݓ��×{�҂�119�J���Ōv337�l�B����͍���Ҏ{��97�J����261�l�A�Ⴊ���Ҏ{��22�J����76�l�ƂȂ��Ă���B30���ɔ�ׂ�10�l���������B
�V�K�����҂�10�Ζ�����285�l�ōő��B10�オ241�l�A40�オ232�l�A30�オ225�l�Ƒ������B���芴���o�H�͉ƒ�����ő���479�l�B�F�l�E�m�l��123�l�ƂȂ����B�a���g�p���͌��S�̂�44�E9���B����ʂł́A�{����51�E0���A�{�Â�12�E1���A���d�R��20�E5���ƂȂ��Ă���B�d�ǎҗp�a���g�p����18�E3���������B
�N���X�^�[��2��������A�ǂ�����{�Ó��s���Ŕ��������B17������27���ɂ����ĎЉ���{�݂�15�l�A��Î{�݂�10�l�����������B
�ČR�W�҂̐V�K�����Ґ���56�l�ŁA��n�ʂ̓���͕s���B
|
�������ҁA1������2���l�@���{�A�u�T�����v�x���@���ۊɘa�@6/1
���{��1���A�V�^�R���i�E�C���X�̊������P�܂��A���ۑ���ɘa�����B
�����Ґ��̏����1��2���l�ɔ{���B�E�C���X�̗������X�N�ɉ����č��E�n���3���ނ��A���X�N�̍ł��Ⴂ98�J���E�n�悩�痈������ꍇ�͓����������Ƒҋ@��Ə�����B�����A���E�ł͓V�R���ɏǏ�̎����u�T�����v�̊������L����A���{�͓������x�����Ă���B
���{�͍�N12���A�ψي��I�~�N�������̊����g����A�����Ґ���1��3500�l�܂ŏk���B���N3���ȍ~�A�����ɍ��킹�Ēi�K�I�Ɋɘa���Ă����B�����g�̊g���4��10����1���l�Ɉ����グ�Ĉȗ��ƂȂ�B
���{�͍���A�E�C���X�������X�N���Ⴂ���Ɋe���E�n����u�v�u���v�u�ԁv�ɕ��ށB���������Ă����S������������߁A�̍��E�n�悩��̏ꍇ�͓�����������3���Ԃ̑ҋ@��Ə�����B���̓��N�`��3��ڐڎ�������ɐƓ��������Ƃ��A�Ԃɂ͌����Ƒҋ@�����߂�B������̋敪���؍ݍ��o���O�̌����͈��������K�v���B
31�����_�ŁA�͕č��A�����A���V�A�Ȃ�98�A���̓C���h�A�E�N���C�i�A�k���N�Ȃ�99�A�Ԃ̓p�L�X�^���A�t�B�W�[�Ȃ�4�̍��E�n��B���ނ͊����Ȃǂɉ����ď_��Ɍ������B�@ |
�������s�ŐV����2415�l�����A5�l���S�@19���A���őO�T����� �@6/1
�����s��1���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ�����2415�l��5�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B1�T�ԑO�̐��j���ɔ��1514�l���Ȃ��B�O�T�̓����j���������̂�19���A���B�d�ǎ҂͓s�̊��3�l�B�a���g�p����18.3%�B�V���Ȋ����҂̂����A�����������Ɉ�t�̔��f�ŗz���Ƃ݂Ȃ��u����^���NJ��ҁv(�݂Ȃ��z����)��5�l�B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���1�����_��2412.1�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�71.1%�B�s���̗v�̊��Ґ���154��2723�l�ƂȂ����B
�N��ʂōł����������̂�20���478�l�B���̂ق�10�Ζ���391�l�A10��272�l�A30��434�l�A40��387�l�A50��214�l�A60��115�l�A70��60�l�A80��41�l�A90��22�l�A100�Έȏ�1�l�B65�Έȏ�̍���҂�174�l�������B���S�����̂�70�`90��̒j��5�l�B |
�������s �V�^�R���i 5�l���S 2415�l���� �O�T�ɔ�ז�1500�l�� �@6/1
�����s����6��1���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̐��j����肨�悻1500�l���Ȃ�2415�l�ŁA�O�̏T�̓����j����19���A���ʼn����܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��6��1���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2415�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j����肨�悻1500�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�19���A���ł��B6��1���܂ł�7���ԕ��ς�2412.1�l�ŁA�O�̏T��71.1���ł����B6��1���Ɋm�F���ꂽ2415�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�19.8���ɂ�����478�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�174�l�ŁA�S�̂�7.2���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A5��31���Ɠ���3�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70�ォ��90��̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�������ŃI�~�N�������h���^6���m�F�A����5�l�͊C�O�n�q���Ȃ��@6/1
�����s��1���A�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������h���^�́uBA�E5�v�̊����҂�1�l�A�uBA�E2�E12�E1�v�̊����҂�5�l�A�s���Ŋm�F���ꂽ�Ɣ��\�����B��������y�ǁB����5�l�͊C�O�n�q�����Ȃ��A�s�������Ƃ݂���B
�I�~�N�������́uBA�E1�v�ƁuBA�E2�v�̈�`����������u�g�݊����́v���V����2���m�F���ꂽ�B
|
���{�̃R���i�͋��A240�X�܂����Z�v����炸�Ɍv3���~�c�@6/1
�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�ɔ����A�x�Ƃ�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���ɉ��������H�X�ȂǂɎx������鋦�͋��ɂ��āA���{��31���A��240�X�܂��v������炸�ɍ�N1�`10�����Ƃ��Čv��3���~�����Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���̂�����6000���~�͉���ł��Ă��Ȃ��Ƃ����B
�{�́u���Z������Ă��Ȃ��X������v�Ƃ̒ʕ�Ȃǂ���Ɍ��n�������A�ᔽ�X�܂ɂ͋��͋���Ԃ��悤�v�����Ă���B�Ԋ҂ɉ����Ȃ��X�܂ɂ́A�@�I�[�u������������j�B
�@ |
������1472�l�R���i�����@��T���j�����609�l���@6/1
���ꌧ��1���A�V����1472�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̐��j��(5��25��)��2081�l�ɔ�ׂ�609�l����A12���A���őO�̏T����������B�v�����҂�21��6721�l�ƂȂ����B�܂��A�V����1��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���5��31�����_��662.51�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ����{�茧��210.99�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����45.4��(���@�Ґ�292/�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��20.0��(���@12/�a����60)�ƂȂ��Ă���B
�ČR�W�͐V����50�l�̕��������B
|
���u�I�~�N�������v�V�n���̊����ғs����8�l�m�F�c�����̐V�K������2��2768�l�@6/1
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�1���A�S�s���{���Ƌ�`�E�C�`���u�ŐV����2��2768�l�m�F���ꂽ�B���҂�36�l�A�d�ǎ҂͑O�����2�l����95�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�2415�l�������B�O�T�̓����j������1514�l����A19���A����1�T�ԑO����������B�s�ɂ��ƁA����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�2412�l�őO�T����29���������B�s���ł͂܂��A�ψي��u�I�~�N�������v�̐V�n���̊����҂��v8�l�m�F���ꂽ�B |
���g�R���i�����Ґ� �����X�������O����h ���J�Ȑ��Ɖ �@6/1
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ��ď�����������J���Ȃ̐��Ɖ���J����A�S���̊����Ґ��͌����X���������Ă������A���܂��ɋ��N�Ẵs�[�N���������Ґ��������������Ă���Ƃ��܂����B�w�Z�⍂��ҕ����{�݂Ŋ������銄�������~�܂�ɂȂ��Ă���Ƃ��Ĉ���������{�I�Ȋ�����Ȃǂ�O�ꂷ��悤�Ăт����Ă��܂��B
���Ɖ�͌��݂̊����ɂ��ĂقƂ�ǂ̒n��Ō����X���������A��s������{�A���m���Ȃǂŋ��N�Ă̑�5�g�̃s�[�N��������Ă���ق��A�����Ґ����S���ōł��������ꌧ�ł�����2�T�Ԃ͌����X���������Ă���Ƃ��Ă��܂��B
�N��ʂɌ���ƑS���ł͂��ׂĂ̔N��Ŋ����Ґ��������X���ƂȂ��Ă�����̂́A�ꕔ�̒n��ł�80��ȏ�̍���҂ő����X����������ق��A�����ꏊ�̂����w�Z�⎖�Ə��A����ҕ����{�݂̐�߂銄�������~�܂肵�Ă���ƕ��͂��Ă��܂��B
�܂���Ԃ̔ɉ؊X�̐l�o�ɂ��Ă͑S���̔����ȏ�̒n��ő����X���������A���ɂ͋��N�̔N���̃s�[�N���ɔ���قǑ�������n�������A���������͓���20�ォ��60��ň��H�X�Ŋ������銄���������X���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
����ň�Ñ̐��ɂ��Ă͑S���ł͔����ȏ�̒n��ŕa���g�p���̌����X������������̂́A���ꌧ�ł͓��@�Ґ���a���g�p���͂قډ������Ƃ��Ă��܂��B
�����������Ƃ�����Ɖ�́A���ɑ�s�s���ł͒Z���I�ȗ\���Ō����X�����������Ƃ������܂����̂̑S���I�ɂ͂��܂��ɋ��N�Ẵs�[�N���������Ґ��������������Ă���Ƃ��āA���N�`����3��ڂ̐ڎ������ɐi�߂�ƂƂ��ɏ����ł��̒���������ΊO�o���T���邱�ƁA�s�D�z�}�X�N�̐��������p�A��A1�̖��ł�������Ƃ�������{�I�Ȋ������O�ꂷ�邱�ƂȂǂ��Ăт����܂����B
����ɍ���҂̏d�lj���\�h���邽�߂ɁA��앟���{�݂ł͓����҂ւ�4��ڂ̃��N�`���ڎ��i�߂�悤���߂܂����B
���e�c�����u�����X���������Ɨ\�����Ă��邪�c�v
�����J���Ȃ̐��Ɖ�̂��ƂɊJ���ꂽ�L�҉�Ře�c���������͌��݂̊����ɂ��āu���A�����Ґ����������Ă���v���̓��N�`���̐ڎ�⊴���������Ƃɂ��Ɖu�̊l���Ȃǂ��傫���Ǝv���B�������N�`����3��ڐڎ킩�玞�Ԃ����Ɣ��Ǘ\�h���ʂ͉�����B4��ڂ̐ڎ�͍���҂𒆐S�ɏd�lj��̗\�h����ȖړI�Ȃ̂ŁA���s��h�����ʂ͌���I���ƍl������B��N6���͐l��������قǑ������ł͂Ȃ��̂ł��炭�����X���������Ɨ\�����Ă��邪�A�~�J�����ȍ~�A���N�`���̌��ʂ�������A�ċx�݂Ől����������Ɗ����Ґ����ď㏸����\��������Ƃ����c�_���������v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂����ۑɘa���ꂽ���Ƃɂ��āu�z���҂����蔲���邱�Ƃ͑�����Ƃ݂��邪�A���ݑS����2���l���銴���Ґ��̋K�͂ɉe������̂����j�^�����O����K�v������B�܂��V���ȕψكE�C���X���C�O���痬�����Ă��Ȃ����ǂ����Q�m����͂��s���Ē������Ă����K�v������v�Ƙb���Ă��܂����B
���q�ǂ��ɉߏ�Ȋ����\�h��������邱�Ƃ��Ȃ��悤��
�I�~�N�������Ŏq�ǂ��̊����������钆�A���Ƃ̗L�u�͎q�ǂ��ɉߏ�Ȋ����\�h��������邱�Ƃ��Ȃ��悤�����_�ł̎q�ǂ��ւ̑��ۑ���܂Ƃ߂����������\���܂����B
���̕����͌����J���Ȃ̐��Ɖ�ŁA���Ɖ�̃����o�[�𒆐S�ɏ�����Â̐��ƂȂ�15�l�������܂����B
���̒��ł͔���r��ɂ���q�ǂ��ɉߏ�Ȍx���������邱�ƂȂ��A�V�т�w�т̋@���D��Ȃ��悤���͂̑�l���w�͂��ׂ����Ǝw�E���܂����B�����Č��ݑE�߂��邱�ƂƂ��āA�}�X�N���O�����ʂł͈ꗥ�ɒ��p�����߂Ȃ����Ƃ�A�^����⑲�Ǝ��Ȃǂ̍s���͊�������H�v���������Ŏ��{��������Ō������邱�ƂȂǂ������܂����B
�܂��Ǐ�̌y���q�ǂ��Ɋw�Z��ۈ珊�A�ی�҂̐E��Ȃǂ����������߂�P�[�X�������Ă���Ƃ��āA�s�p�ӂɌ��������߂�Ə�����Â̂Ђ����ȂǂɂȂ��邨���ꂪ����Ǝw�E���A��w�I�ɂ��q�ǂ��̑S�g��ԂƂ��Č��C�ł���Έꗥ�Ɍ������Ȃ��Ă��悢�Ƃ��܂����B
���̂ق������ł͋}���]�ǂȂǂ܂�ɏd�lj�����q�ǂ��ɐv���ɑΉ��ł��鏬���~�}��Ñ̐��̐����̕K�v���Ȃǂ��w�E���܂����B
�L�u��1�l�Ő��s���N���S�������̉����M�F�����́u�q�ǂ��̊����͍Ăё�����\�������荡�̍l�����⒆�����I�ȑ���܂Ƃ߂��B��������������Ɏq�ǂ��̑�ɂ��ڂ������Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B
��1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��̑O�T�� �S���ł͌����X������
�����J���Ȃ̐��Ɖ�Ŏ����ꂽ�����ɂ��܂��ƁA5��31���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑S���ł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�0.73�{�ƌ����X���������Ă��܂��B
��s����1�s3���ł͓����s�A�_�ސ쌧�A�����Đ�t����0.76�{�A��ʌ���0.81�{�A���ł͑��{��0.74�{�A���Ɍ���0.76�{�A���s�{��0.72�{�A���C�ł͈��m����0.75�{�A����0.83�{�A�O�d����0.74�{�Ɗe�n�Ō������Ă��܂��B
�܂��k�C����0.67�{�A�{�錧��0.75�{�A�L������0.69�{�A��������0.74�{�A�l��������̊����Ґ����ł��������ꌧ��0.72�{�ȂǂƂ�����������ƂȂ��Ă��܂��B
46�s���{���Ō������Ă��đO�̏T���V�K�����Ґ��������Ȃ����̂�1.13�{�������R�����݂̂ƂȂ��Ă��܂��B
�l��10��������̒���1�T�Ԃ̊����Ґ��́A�����X���������Ă�����̂̉��ꌧ��670.47�l�ƑS���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
�����ŋ{�茧��214.48�l�A����������205.95�l�A�ΐ쌧��204.32�l�A�k�C����195.63�l�A�L������191.66�l�A��������191.09�l�A�����đ��{��161.44�l�A�����s��130.98�l�ȂǂƂȂ��Ă��āA�S���ł�137.80�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���㓡���J���u�\�Ȃ�������퐶�����߂���u����v
���Ɖ�Ō㓡�����J����b�́u�S���̐V�K�����Ґ���1�T�Ԃ̕��ςŐ�T��0.73�ƂȂ��Ă��āA�قƂ�ǂ̒n��Ō����X���������Ă���B���ꌧ�͑S���ōł������������Ă�����̂́A���߂�2�T�Ԃقǂ͌������قڌp�����Ă���v�Ǝw�E���܂����B
���̂����Łu���ꌧ�ȊO�̒n����܂߁A����̊��������������������Ă����K�v������B�ő���̌x�������A���S���S���m�ۂ��Ȃ���\�Ȃ��������̐��������߂����߂ɕK�v�ȑ���u���Ă����v�Əq�ׂ܂����B
|
���іF���O�����R���i�����@�O���l�����Ґ������グ�@���ۑ�ɘa�ւ̕s���@6/1
6��1���A�O���Ȃ́A�іF���O����b���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�����甭�M������������PCR�������A�z�����m�F���ꂽ�B�ŒZ�ł�6��11���܂ŁA����×{�𑱂�����j���Ƃ����B
�u�ъO���́A5���ɂ̓\�E���Ŋ؍��̛����x(�����E�\���j����)�V�哝�̂Ɖ�k���A����Ƀh�C�c�ł�G7�O���̉�ɏo�Ȃ���ȂǁA�O�����щ���Ă��܂����B
���肵�����{�́A6��1������1��������̊O���l�����Ґ��̏����2���l�ɔ{��������A�V�^�R���i�E�C���X���ۑ�̊ɘa�ɓ��ݐ��Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ������^�C�~���O�ƂȂ��Ă��܂��܂����v(�������L��)
�іF���O���̃R���i�������o�ɁASNS�ł͐S�z���鐺�������������Ă���B
�s�ё�b�A�����Ɠ������炢�O���ɂ����A�����̗v�l�����Ƃ����Ă�������A�ǂ����ŃR���i�Ɋ��������Ƃ��Ă����������Ȃ��t
�s����������щ���Ă�����ˁA�O���B�����ă}�X�N�����ň��肵�Č��t�����킵�āB
����ς�}�X�N�͕K�v�Ȃ�Ȃ���?���Ďv����t
�s���ۑ��[�u�ɘa���n�܂�^�C�~���O�ŁB���Ƃ������R�ł��傤���t
�s����?�@�������郊�X�N�������Ă�������A���낢��Ɛ����������Ă��Ȃ������̂���?�t
6��10������́A�O���l�ό��q�̎�����A2���l�̘g���ōĊJ���邱�Ƃ𐭕{�͌��肵�Ă���B���̓_��s�������鐺��SNS�ł͌���ꂽ�B
�s�����̂͗ǂ����ǗႦ�}�X�N�Ƃ����{�l�ƊO���l�ōl�����S�R�Ⴄ�̂��ǂ��������Ȃt
�s�C�O����̗��s�҂͊X���������ʋ@�ւŃ}�X�N���������R��舕�����p�������q�������́A�����B�ɏƂ炵���킹�Ăǂ��v���̂��낤�t
�ݓc���Y�́A�O���l����ĊJ�ɐ旧���A���݂����Ȃ��Ă��銴���h�~��Ȃǂ������邽�߂́u���؎��Ɓv�̌��ʂ܂��A6��7���ɃK�C�h���C�������\����\�肾�B���̒��O�ɁA�O����S�����{�̐ӔC�҂��V�^�R���i�Ɋ�������Ƃ����̂́A�Ȃ�Ƃ�����Șb���B
|
���ъO�����R���i�����A�����L�����Z��������×{�c�t���ł�3�l�� �@6/1
�O���Ȃ�1���A�ъO�����V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�ȓ��ɔZ���ڐG�҂͂��Ȃ��Ƃ����B���ʂ̊ԁA����ŗ×{����B
���Ȃɂ��ƁA�ю��͓����ߑO�ɓo����A�̂ǂ̒ɂ݂�i���o�b�q�����������ʁA�z�����m�F���ꂽ�B�����\�肵�Ă����č��c��c����Ƃ̖ʉ�Ȃǂ̌�����S�ăL�����Z�����A�O�@�\�Z�ψ�������Ȃ����B
���슯�[������1���̋L�҉�ŁA�ю��̌����ɂ��āu�㗝�o�Ȏ҂����A�x�Ⴊ�Ȃ��悤�Ή����Ă����v�Əq�ׂ��B����c���Ŋ������m�F���ꂽ�̂�65�l�ڂŁA�t���ł͖�c���q�����A�Ð�@���ɑ���3�l�ځB
|
���R���i�����Ґ� ���E���Ō����X�� �v���� �g���������h�w�E�� �@6/1
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��͐��E���Ō����X���������Ă��āA���Ƃ͐�i���𒆐S�Ƀ��N�`���ڎ킪�i���Ƃ�A�n��ɂ���Ă͑����̐l���������Ɖu�����l�������Ȃ��Ă��邱�ƂȂǂ����R���Ǝw�E���Ă��܂��B���̈���ŁA�����̑̐����k�����Ă��鍑�����邱�Ƃ���AWHO�����E�ی��@�ւ́u�������������ĕ���銴���Ґ����������Ă���B�����X���͐T�d�ɂ݂�ׂ����v�Ƃ��Ă��܂��B
�V�^�R���i�̊����͂��ƂƂ����E���ɍL��������A�����͂������ψكE�C���X���o�����邽�тɊ������g�債�A���̒��ł��I�~�N���������L���������N11���ȍ~�ɂ͂���܂łƂ͌��Ⴂ�̊����Ґ�������܂����B
�A�����J�̃W�����Y�E�z�v�L���X��w�̂܂Ƃ߂ɂ��܂��ƁA�I�~�N�������ȑO�ł́A�ł������������N4���⋎�N8������ł��A���E�S�̂ł̈��������̊����Ґ���70���l����90���l�قǂł������A���Ƃ�1�����{�ɂ�400���l���܂����B
�������A���̌�A�����Ґ��͂����ނˌ����X���������A�挎�ȍ~�͑������ł�70���l��ŁA���Ȃ����ɂ͂��悻27���l�ƃs�[�N����15����1�قǂɂƂǂ܂邱�Ƃ�����܂��B
�����̗v���Ƃ��ē�����ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́A��i���𒆐S�Ƀ��N�`���̐ڎ헦���オ�������Ƃ�A�l���̑������������Ɖu�����l�������Ȃ��Ă��邱�ƁA����ɋG�ߓI�ȗv��������ȂǂƂ��Ă��܂��B
�C�M���X �I�b�N�X�t�H�[�h��w�̌����҂Ȃǂ��^�c����E�F�u�T�C�g�uOur World in Data�v�ɂ��܂��ƁA���N�`���̒lj��ڎ�����l�̊����͐挎31���̎��_�ŁA�h�C�c��65.1���A�C�M���X��58.2���A�t�����X��56.9���AEU�S�̂�52.7���Ȃǂƍ����Ȃ��Ă��܂��B
�Ꮚ�����ł́A1��ł����N�`�������l��20���ɖ����Ȃ��ق��A�A�����J�ł��lj��ڎ�����l�̊�����31.1���ɂƂǂ܂��Ă��܂����ACDC�����a��Z���^�[�͂��Ƃ�4���A�S�Ă̌��t�����Ō��o���ꂽ�V�^�R���i�̍R�̂̕��͂���A����܂łɐl����60���߂������������Ɛ��肳���ƕ��Ă��܂��B
�_�c���C�����́u�����������ł̓��N�`���ڎ헦�͒Ⴂ�������̐l�����ۂɊ������ĖƉu�������A�����̌����ɂȂ����Ă���\��������v�Ǝw�E���Ă��܂��B
����WHO�����E�ی��@�ւ́A�挎22���ɏo�����T��ŁA�����Ґ��̌����X���݂͂���Ƃ��Ȃ���u�����̐헪��ύX������������A�������������ĕ���銴���Ґ����������Ă��邽�߁A�T�d�ɂ݂�ׂ����v�Ǝw�E���܂����B
�_�c���C�������u���N�`���⊴���ɂ��Ɖu�̌��ʁA�G�ߓI�ȗv���ȂǂŌ��݁A���E�I�Ɋ����Ґ��������Ă���Ƃ����̂͌X���Ƃ��Ă͌�����B�����A�e���Ō����헪����������钆�A���͂⊴���҂̐�ΐ���c�����悤�Ƃ��Ă��Ȃ���������B���ʂŊ����Ґ����r���邱�Ƃ̈Ӗ��͖����Ȃ����A�e���̊����Ґ��͑����⌸���Ȃǂ̃g�����h�������Ƃɔc������Ƃ����Ӗ��Ō���ׂ����v�Ƙb���Ă��܂��B�@ |
 |
�������s�ŐV����2335�l�����A5�l���S�@20���A���őO�T����� �@6/2
�����s��2���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ�����2335�l��5�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B1�T�ԑO�̖ؗj���ɔ��1056�l���Ȃ��B�O�T�̓����j���������̂�20���A���B�d�ǎ҂͓s�̊��1�l�B�a���g�p����18.3%�B�V���Ȋ����҂̂����A�����������Ɉ�t�̔��f�ŗz���Ƃ݂Ȃ��u����^���NJ��ҁv(�݂Ȃ��z����)��1�l�B
1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���2�����_��2261.3�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�68.9%�B�s���̗v�̊��Ґ���154��5058�l�ƂȂ����B�N��ʂōł����������̂�20���489�l�B���̂ق�10�Ζ���348�l�A10��246�l�A30��465�l�A40��367�l�A50��209�l�A60��95�l�A70��66�l�A80��35�l�A90��15�l�B65�Έȏ�̍���҂�146�l�������B���S�����̂�40�`90��̒j��5�l�B |
�������s �V�^�R���i 5�l���S 2335�l�����m�F �O�T��1000�l�]�� �@6/2
�����s����2���̊����m�F��1�T�ԑO�̖ؗj�����1000�l�]�菭�Ȃ�2335�l�ŁA�O�̏T�̓����j����20���A���ʼn����܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��2���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł�2335�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̖ؗj�����1000�l�]�茸��܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�20���A���ł��B2���܂ł�7���ԕ��ς�2261.3�l�ŁA�O�̏T��68.9���ł����B2���Ɋm�F���ꂽ2335�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�20.9���ɓ�����489�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�146�l�ŁA�S�̂�6.3���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�1�l�ŁA1�����2�l����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ40���70�ォ��90��̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ\���܂����B |
�����{ �V�^�R���i 5�l���S �V����1531�l�����m�F �@6/2
���{��2���A�V����1531�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA���悻990�l����܂����B����ŁA�{���̊����҂̗v��97��7328�l�ƂȂ�܂����B�܂��A5�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5057�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�6��1������2�l�����āA18�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
������R���i1373�l�����A�O�T��230�l���@13���A���ʼn����@6/2
���ꌧ��2���A�V����1373�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̖ؗj��(5��26��)��1603�l�ɔ�ׂ�230�l����A13���A���őO�̏T����������B�v�����҂�21��8094�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���1�����_��621.50�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ�������������197.03�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����45.3��(���@�Ґ�291�^�a����:643)�ŁA�d�ǎҗp��20.0��(���@12�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����67�l�̕��������B
|
�������ŐV����2��680�l�R���i�����c������1�T�ԕ��ς͑O�T����31�����@6/2
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�2���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����2��680�l�m�F���ꂽ�B���҂�24�l�������B�d�ǎ҂͑O������3�l����92�l�ƂȂ����B
�����s�̐V�K�����҂�2335�l�ŁA�O�T�̓����j������1056�l����A20���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�2261�l�őO�T����31���������B���҂�40�`90�Α�̒j��5�l�������B
���{�̐V�K�����҂�1531�l�ŁA�O�T�̓����j������993�l�������B60�`90�Α�̒j��5�l�����S�����B
|
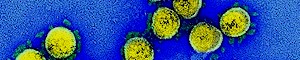 |
���g���m���̂���̃R���i�×{�{�݁u�����܂����ՌÒ��v�����Ă����c�@6/3
�ېV�̉�̋��Ŕu�g�����v�v�����ڂ��B���{�̋g���m���̂���̗Վ���Î{�݁u���R���i��K�͈�ÁE�×{�Z���^�[�v���قڎg���Ȃ��܂܁A�挎���ɕ������B
�����p��0.3���A����78���~���p�[�̂��e���Ԃ�
�u���a�@������v�Ƃ����g���m���̊|�����ō�N9�����ɐݒu����A10�����ɂ�1000���̐��Ɋg�[�B���N1�����ɉғ��������A�v���p�Ґ��͂�����303�l�B�����\�Z78���~�̓h�u�Ɏ̂Ă�ꂽ�����R���B
���ł͐V�^�R���i�̑�4�g�Ƒ�5�g�œ��@�ł����A����×{���Ɏ��S���鎖�Ⴊ���o�����B�Ҕᔻ�ɂ��炳�ꂽ�g���m���͍�N8���ɗՎ��{�݃I�[�v�����u�`�グ�A���s�Z�V�]��̍��ۓW����u�C���e�b�N�X���v�ɐݒu�B���@�����g���m���̓x�b�h�ɐ��荞�݁A�u���K�ɉ߂�����B����ŕs���ɉ߂��������S��������v�Ƃ����x���������A�h����A�s�[�����ނȂ����A�����܂����ՌÒ������Ă����B
����Ë@�ւ̃��X�g�����R���i�̋]���҂�c��܂���
�J�݊��Ԃ͐挎10���܂ł�99���B1���̍ő�����҂�70�l(3��10��)�������B���p��0.3���A������1�l������̃R�X�g�͖�2574���~�B�k������Ȃ�A���X�Ɏ肶�܂������͂Ȃ������̂��B���{�ɕ������B
�u�f���^�����嗬��������5�g�ł͎Ⴂ���ł��e�̂��}�ς��A����ł���ǂ��Ȃ�P�[�X�������������āA��K�͎{�݂������ė×{���Ă��������O��Őݒu�Ɏ���܂����B��6�g�̃I�~�N�������͊����Ґ��͑�������ǁA�y�ǂ̕��������̂��傫�ȈႢ�B���ʓI�ɃZ���^�[�̗��p�͏��Ȃ������ł����A�d�lj�����������o������ǂ��Ȃ�́A�Ƃ������Ƃ�����A�ғ��͌v��ʂ�Ɍp�����܂����v(��@�Ǘ����ЊQ���)
���s�̏���s������\�߂���ېV�̉�̓z�[���y�[�W�Łu���v���яW�v���f���A�q�s�����v�v�����ɂ��팸���ʗv�z378��8300���~(2012�N�x����2014�N�x)�r�ƌւ��Ă��邪�A��Ë@�ւ̓O�ꃊ�X�g�����R���i�̋]���҂�c��܂����̂͋^���悤���Ȃ��B�l��100���l������̐V�^�R���i�E�C���X���S�҂́A��オ���܂Ȃ��S���f�g�c�B�S������242.7�l�ɑ��A2�{����571.0�l���B
�ېV�́u�����疯�ցv�̃X���[�K���̂��ƁA�Ԏ��{�݂�ׂ��A�����{�݂͖��ԈڊǁB�Z�g�s���a�@��{�����N�Ȋw�Z���^�[�͔p�~����A�{�����O�q���������Ǝs�����Ȋw�������͓����k���B�{���a�@�̗\�Z���啝�ɍ��A�痢�~���~�}�Z���^�[����ԏ\���a�@�ւ̕⏕���͔p�~���ꂽ�B
07�N��8785�l�����������̈�t�E�Ō�t�Ȃǂ̕a�@�E������19�N�ɂ�4360�l�ɔ����B�ی����Ȃǂ̉q���s���E�������̊ԁA1��2232�l����9278�l��25���팸���ꂽ�B����ŁA�u����S�͂Ȃ��v(����)�ƍ��ꂵ�Ă����J�W�m�U�v�ɁA�y�����Ƃ���790���~�������ތ�o���c�c�B
�ېV�͎Q�@�I�őS�����}�����������ł��邪�A����ȘA���ɕ�炵��a���Ă����킯�Ȃ��B |
���R���i�� �L���҉�c �g�܂h�~�h�������O���ɐ����� �@6/3
�V�^�R���i��������鐭�{�̗L���҉�c�́A����܂ł̋c�_�܂����_�_�����̈Ă��܂Ƃ߂܂����B�܂h�~���d�_�[�u�ɂ��Ĉ��H�X�ւ̎��Z�v���𒌂Ƃ��鍡�̑[�u�̌��������O���ɁA�K�p�̍l���������ׂ����Ƃ��Ă��܂��B
����ɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�̊������g�債���ۂɁA�s���{�����a���Ȃǂ��m�ۂ���v��𗧂Ă����̂́A�n��ɂ���ẮA��Ðl�ނ̊m�ۂ�����\���ȑ̐����Ƃ�Ȃ������ق��A�h�앞�̕s����A�ی����Ɩ��̂Ђ����Ȃǂ����Ë@�ւł̌��������������ɁA�\���Ή��ł��Ȃ������ȂǂƎw�E���Ă��܂��B
�܂��A���N�`���⎡�Ö�𑬂₩�ɊJ���ł����ƂȂǂ��琬������g�݂��s�\���������Ƃ��Ă���ق��A���Ƒg�D�̃����o�[�̔��������{�̕��j�Ƃ��������邩�̂悤�ɍ����ɎƂ߂����ʂ��������X�N�R�~���j�P�[�V�����̂�����Ƃ��Ė�肪�������Ƃ��Ă��܂��B
����ɁA�܂h�~���d�_�[�u�ɂ��đS���m����Ȃǂ���A���H�X�ւ̎��Z�v���𒌂Ƃ��鍡�̑[�u���������悤���߂��Ă��邱�ƂȂǂ܂��āA�V���Ȋ����ǂ̋}���Ȋg��ɔ����A�[�u��K�p����ꍇ�̍l���������ׂ����Ƃ��Ă��܂��B
�܂��A������b���i�ߓ��ƂȂ��Ĉꌳ�I�Ɋ����Ǒ���s���̐���A���{�̐��Ƒg�D���������邱�Ƃ����߂Ă��܂��B
�L���҉�c�́A�_�_�����̈Ă����Ƃɋc�_���d�ˁA�������{�ɂ����{�ɒ��s�����Ƃɂ��Ă��܂��B�@ |
�������s �V�^�R���i 4�l���S 2111�l�����m�F �O�T����500�l�]�� �@6/3
�����s����3���̊����m�F��1�T�ԑO�̋��j�����500�l�]�菭�Ȃ�2111�l�ŁA�O�̏T�̓����j����21���A���ʼn����܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s�́A3���s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł�2111�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j�����500�l�]�茸��܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�21���A���ł��B3���܂ł�7���ԕ��ς�2187.1�l�ŁA�O�̏T��69.5���ł����B3���Ɋm�F���ꂽ2111�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�21.6���ɓ�����456�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�184�l�ŁA�S�̂�8.7���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�2�l�ŁA2�����1�l�����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70���90��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����ŐV����1530�l�̊����m�F�@������5�l�����S�@�V�^�R���i�@6/3
���{��3���A�V����1530�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̋��j���̊����Ґ��́A2210�l�ł����B���{���ł́A������5�l�̎��S���m�F����܂����B
|
������A�V�^�R���i��2�l���S�@�V�K������1326�l�@�O�T����212�l����@6/3
���ꌧ��3���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������2�l���V���Ɏ��S�����Ɣ��\�����B�v�̎��Ґ���462�l�ƂȂ����B�܂��A1326�l�̐V�K�������m�F�����B��T�̋��j��(27��)��1538�l�ɔ�ׂ�212�l�������B�v�����҂�21��9420�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�z���Ґ���2�����_��606.01�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ�����������190.23�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����43.2%(���@�Ґ�:278/�a����:643)�ŁA�d�ǎҗp��16.7%(���@�Ґ�:10/�a����:60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����60�l�̕��������B
|
���R���i�����Ҍ��@�u���Ԕ��f�������̗]�n�v�u������������v�@���Ǝw�E�@6/3
1���̊����Ґ��������Ă��Ă��邱�Ƃɂ��Đ��Ƃ́A�܂������������������Ɣ��f���邱�Ƃ͂ł����A����������{�I�ȑ�̓O����ƌĂт����Ă��܂��B
���k��Ȗ�ȑ�w�@�����j�Y�a�@�����u�Ȃ��Ȃ�����Ƃ��낾���A�l���������Ă���̂ŕ\�ʓI�ɂ͗��������Ă��Ă���Ǝv���B�Ɖu�����������������Ă��Ă���Ƃ͎v���Ă���B����ňȑO�̂悤�ɏǏ�̂�������K�������S�����������Ă���ł͂Ȃ��ƍl������̂ŁA�{���ɐV�K�̗z���Ґ������Ԃf���Ă��邩�A���������̗]�n������v
�����������A���ۑ�̊ɘa�Ō����ł��O���l�ό��q��������\��������܂��B
�����j�Y�a�@�����u�O���̕������{�����ɓ����ė��邱�Ƃ��C�R�[���Ŋ����҂�������Ƃ͂Ȃ�Ȃ����A��Ԍ��O�����̂͊O���̕��������ė��邱�ƂŁA�����ł͔������Ȃ�������������Ȃ��ψي����������܂�郊�X�N�������͍����Ȃ�B�ψي��ł������̊��ł���{�I�ɂ͊�����͕ς��Ȃ��̂ŁA���܂Œʂ�̊�������s���Ă������Ƃ��K�v�v |
���܂h�~�u�K�p�̍l���� �������ׂ��v�@�L���҉�c ���Z���������O��...�@6/3
���{�̐V�^�R���i�E�C���X���������L���҉�c�́A�܂h�~���d�_�[�u��K�p����ꍇ�̍l���������ׂ����Ǝw�E��������Œ����ɓ����Ă���B
�Îs��������u����2�N�Ԃ��āA�Ⴆ�Έ��H�X���Ƃ���҂ł���Ƃ��A�����҂���̐��̕������͏\���������̂��A�q�A�����O�̏d�v���ɂ��Ă��w�E���܂����v
�܂h�~�[�u���߂����ẮA���H�X�ւ̎��Z�v���̗L�����Ȃǂ��c�_����钆�A�S���m����Ȃǂ������������߂Ă���B
�L���҉�c�ł́A���Z�v���𒌂Ƃ��鍡�̑[�u�̌��������O���ɁA�K�p�̍l���������ׂ����Ƃ���_�_���ł��o����錩�ʂ��B�܂��A��Ò̐��ł́A�a���̋�Ȃǂ̏����f�W�^���Ǘ����āu�����鉻�v��i�߁A���i�ߓ��ƂȂ��Ĉꌳ�I�ɑ���s���̐��������߂�����B�@ |
 |
�����͂⊴���Ґ��Ȃǃj���[�X�ɂ��Ȃ�Ȃ��A�u�R���i�͂��łɉߋ��v�̉��B�@6/4
�M�҂͉p���ɏZ��ł��邪�A������Ŏ������Ă���NHK�ȂǓ��{�̃j���[�X�ԑg���A�s���{���ʂ̃R���i�����Ґ�������A�u��6�g�͎����X���v�Ƃ��������҂̔������Љ���肷�邽�тɁA�u1�N�O�̔ԑg��!?�v�Ƃ��������ŁA�v�킸�e���r��ʂ��Î������肵�Ă���B
�p���̃��f�B�A�ɂ����ẮA�R���i�͂��͂�ߋ��̘b�ŁA�j���[�X�ɂ���Ȃ�Ȃ�(���̓p�[�e�B�Q�[�g�ɂ��W�����\���ւ̎��C���͂ƃE�N���C�i���̕�����)�B
���p���ւ̓����ɂ̓��N�`���ڎ�ؖ�����s�v
���B�̂قƂ�ǂ̍��́A���N�`���̐ڎ�ؖ���������A�����ł���悤�ɂȂ����B�p���ɂ������ẮA���N�`���̐ڎ�ؖ�����K�v�Ȃ��A�����葱���̓R���i�ЈȑO�Ƃ܂������ς��Ȃ��B�I�~�N�������������ɑ��݂��Ă���̂ŁA���̗������킴�킴�`�F�b�N����Ӗ����Ȃ����Ƃ͘_���I�ɖ��炩���낤�B
���N3���ɃR���i�֘A�K�����[���ɂ��A�������������ɂ����p���ł́A�R���i���ė��s���邱�Ƃ��Ȃ��A�����Ґ������Ґ������葱���Ă���B1���̊����Ґ��͍��N1��5���̃s�[�N���ɖ�28���l�A1���̎��Ґ��͍�N1��20����1387�l���������A���͂��ꂼ��5000�l���100�l�����ɂ܂Ō������B������ʋ@�ւ⏤�X�E�{�ݓ��ł̃}�X�N���p�`�����Ȃ��Ȃ�A�}�X�N�����Ă���͍̂���҂�p�S�[���l(�M�҂�����1�l)�����ŁA�S�̂�1�����x�ɂȂ����B
���{�ł�6����������K�����ɘa���ꂽ���A����ł��܂��O���l�̓����Ґ��̏���A�o��72���Ԉȓ��̃R���i�A���ؖ����̒A���J�Ȃ̒ǐՃA�v���̃C���X�g�[���Ƃ������ʓ|�Ȏ葱���������A�����吨�̃X�^�b�t�����ă`�F�b�N���Ă���B
�M�҂̓R���i�ЈȑO�͔N��2����x�ꎞ�A�����Ă������A�ώG�ȓ����葱�������ŁA����2�N���܂�A���Ă��Ȃ��B�������A������e�̉��̂��߂Ɉꎞ�A����]�V�Ȃ������m�l�͑���(�Ж��ɂ�钓�݈����܂߁A��134���l�̓��{�l���C�O�ɂ���̂œ��R�ł���)�A���c��`�œ����ł���܂�5���Ԃ��������Ƃ����悤�Șb���悭�������B�挎�̏I���ɂ��^�����g�̐猴�����������u�ē����ɂ������Ă߂��Ⴍ����`�F�b�N�čŌ��pcr�̌��ʑ҂�1���ԁv�ƃC���X�^�O�����ŕs�����q�ׂĂ����B
�����{�́u�R���i�����v�ŁA2019�N��4��8113���~�ɏ�����K���O���l����̂قƂ�ǂ������Ă���B�܂��ʓ|�ȓ����葱��������ƁA���{�l�̊C�O���s�ɂ��u���[�L��������̂ŁA�q���Ђ̋Ɛщ��x���B
���@���Ń}�X�N���p�����ۂ�����ᔻ�������{�ACA����}�X�N���Ă��Ȃ��p��
�M�҂�5��28���ɁA2�N�Ԃ�̊C�O���s�ʼnp������C�^���A�̃V�`���A���Ƀu���e�B�b�V���E�G�A�E�F�C�Y�̔�s�@�ōs�������A�o���n�̃����h���E�q�[�X���[��`�́A2�N�߂��������R���i�K���̂����Ղ�𐰂炷���̂悤�ɁA���s�҂ł��ӂ�Ă���(�`���̎ʐ^���Q��)�B
��s�@�ɏ��ƁA���������Ƃɋq���斱���͒N���}�X�N�����Ă��炸�A��q���������x�������p���Ă��Ȃ�����(�l�I�ɂ͕s���葽���̐l�������������Ԃł́A�}�X�N�𒅗p�����ق��������Ǝv��)�B���{�ł͋@���Ń}�X�N�𒅗p���Ȃ������j�����Y���ٔ��ɂ�����ꂽ��A��s�@����~�낳�ꂽ�s�c��c�������Q�����Ȃǂ����߂Ė����i�ׂ��N�������肵�Ă��邪�A���͂�p���ł͂����������Ƃ��N����]�n�͂Ȃ��B���悵���ւ͖��ȂŁA�R���i�֘A�K���̓P�p�ʼn��Ă̍q���Ђ̋Ɛт��}���Ă��邱�Ƃ����������B
�C�^���A�����ɕK�v�ȃ��N�`���̐ڎ�ؖ����́A�o���O�ɉp����NHS(���c��ÃT�[�r�X)�̃T�C�g���玩���̐ڎ�L�^���_�E�����[�h���A������u���e�B�b�V���E�G�A�E�F�C�Y�̗\��T�C�g�ɃA�b�v���[�h����B�A�b�v���[�h����ƁA�@�B�ŏؖ����̗L�����肵�u���Ȃ��̏ؖ����͎�̂���܂���(���邢�͂��̋t)�v�Ƃ������b�Z�[�W��1���ȓ��ɕԂ��Ă���B���������Ă����A��`�ŏؖ����̗L����L�������`�F�b�N���ꂽ�肷�邱�Ƃ��Ȃ��A��s�@�ւ̓���葱���̓R���i�ЈȑO�Ɠ����ɂȂ�B
�p���Ŋ��S����̂́A���N�`���̐ڎ�\��ɂ���A�q���Ђւ̐ڎ�ؖ����ɂ���A�V���ȃ��[�����ł���Ƃ����ɃR���s���[�^�[�E�V�X�e��������A���ׂăI�����C���Ŏ葱���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��B�e�ЁA�e�@�ւƂ��A�����Ȑ��̗D�G��IT�X�^�b�t��i���Ă���A����͂��͂��̕������ƌ����邾�낤�B
���C�^���A�ł͌�����ʋ@�ւō��@�\�}�X�N���p���`���t�����Ă�����x
�ł́A�C�^���A�́u�R���i��v�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B
����҂̃��N�`���ڎ�ؖ����̊m�F���q���Ђ��s���Ă���̂ŁA�C�^���A�̓����R���ł͉������`�F�b�N����邱�Ƃ��Ȃ��A�R���i�ЈȑO�Ƃ܂����������ł���B���Ȃ���X�g�����Ń}�X�N�𒅂��Ă���l�͊F���ƌ����Ă����B
�������A�o�X��d�ԂƂ�����������ʋ@�ւł�FFP2�Ƃ�����ÂȂǂɗp�����鍂���\�}�X�N�̒��p���`���t�����Ă���B���ʂ̃}�X�N�������肵�Ă���ƁA�ԏ��Ɂu���̃}�X�N�ł͑ʖڂł��B���ւ��ĉ������v�ƒ��ӂ����B�u�]��Ȃ���A�~�Ԃ��A���ǂɓ˂��o��(submit to competent authority)�v�ƃC�^���A��Ɖp��Ŏԓ��A�i�E���X������Ă���B�p���ł́A������ʋ@�֓��̃}�X�N���p�`���͓P�p����A�C�^���A���߂������ɂ����Ȃ�\��������B
�Ȃ��C�^���A(�����Ă����炭���B�S��)�ł́A�R���i�������̓��{�A�������͂��߂Ƃ���A�W�A�n�̊ό��q�͂قڃ[���ŁA�M�҂͏��X��X�g�����Ȃǂł���������ڂ����A�n���̐l�������琺���������Ă���B
�����łɃI�~�N�������������Ȃ̂ɐ��ۑ�Ӗ�����̂�
�u���{��G7�ł����Ƃ����������ۑ������Ă���v�Ƃ����̂����{�̃L���b�`�R�s�[�����A�I�~�N�������������Ŗ������Ă���̂ɁA���ۑ�����Ƃ����̂͗����ɍ���Ȃ��B����ŁA���_�����ŁA���������ۑ���x�����鍑����4�����x����Ƃ��������ʂ��o�Ă���̂ŁA���{�̐���͉Ă̎Q�c�@�I���낤�B
���{�ł͎��^�}�ɗL���ȃ^�C�~���O�����v����ċc������U���A���I�������Ƃ���(�M�҂Ɍ��킹��Εs�т�)���s������̂ŁA��Ɏ��̑I���������Ă��āA�قƂ�ǂ̐���͐l�C���̎��_���猈�肳���(���t���̂�T���ȂǓ��ɂ�����)�B�c���������イ�C���r���ʼn��U������i���͓��{���炢�Ȃ��̂ŁA�R���i��ɂ����ꂪ�e�����Ă���B
�܂����{�ł́u�g���C�A���E�A���h�E�G���[�v�̕������Ȃ��A��������Ŏ��s����ƒ@�����̂ŁA���{����l���Ϗk���āA�������Ǝv���Ă���_�Ȑ�����Ƃ�Ȃ��B���̓_�A�p���Ȃǂ́A�u�ʖڂ��������蒼�������v�Ǝv���Ă���B
�R���i���N�`�����m�ۂ��邽�߂ɁA�܂����������ʂ��Ȃ��J���i�K���琻���Ђ̃v���W�F�N�g�ɋ����o���Ƃ����x���`���[�L���s�^���I�Ȏ�@�ɑł��ďo����A�f�l��O��P������1���l�̒��ˑł��̃{�����e�B�A��{�������肵���̂��A�������������������Ă����ł���B
���������ł��A���f�Ǝ��s�̑����́A���������Ă������ƁA���̊C�֑����o���Ă��������Ƃ̈Ⴂ��������Ȃ��B���ẴR���i�֘A�K���̉����Ƃ��̌��ʂ́A���{���{�ɂƂ��Ă���̈��S�ޗ�(�Ȃ����͐���̐����ޗ�)�ɂȂ�Ǝv���̂ŁA�Q�@�I��ɂ́A�u�g���C�A���E�A���h�E�G���[�ł���Ă݂܂��v�Ɛ錾���Ă����\�Ȃ̂ŁA���ĕ��݂̓����葱���ɂ��ׂ������ɂ��Ă���ƕM�҂͍l����B
(�NjL�F�{�e���M����ɃC�^���A���{�͓����ɍۂ��Ẵ��N�`���ڎ�ؖ��͕̒s�v�Ƃ��܂����B������ʋ@�ւł̍��@�\�}�X�N���p�`����6��15���܂ʼn�������錩�ʂ��ł�)�@ |
�������s �V�^�R���i 5�l���S 2071�l�����m�F ��T����500�l�� �@6/4
�����s����4���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓y�j����肨�悻500�l���Ȃ�2071�l�ŁA�O�̏T�̓����j����22���A���ʼn����܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��4���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł�2071�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j����肨�悻500�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�22���A���ł��B4���܂ł�7���ԕ��ς�2118.9�l�ŁA�O�̏T��70.3���ł����B4���m�F���ꂽ2071�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�19.2���ɂ�����398�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�142�l�ŁA�S�̂�6.9���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A3���Ɠ���2�l�ł����B����A�s�͊������m�F���ꂽ80���90��̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����ŐV����1493�l�̊����m�F�@������8�l�����S�@�V�^�R���i�@6/4
���{��4���A�V����1493�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̓y�j���̊����Ґ��́A2243�l�ł����B
����������1��4010���ŁA�z������10.4���ł����B����܂łɑ��{���Ŋm�F���ꂽ�����Ґ��́A�v98��351�l�ƂȂ�܂��B���{���ł́A60�`90��̊�����8�l�̎��S���m�F����܂����B�����̏d�Ǖa���̎g�p����6.4���A�����̌y�ǁE�����Ǖa���̎g�p����16.7���ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i������ 1��8252�l�@����2071�l 22���A���őO�T����� �@6/4
4���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂́A1��8,252�l�������B
�����s�ł�2,071�l�̊������m�F����A��T�y�j��(5��28��)����478�l�����āA22���A���őO�̏T�̓����j������������B
���̂ق��A���{��1,493�l�A���ꌧ��1,341�l�A���m����1,165�l�ȂǁA�S���ł�1��8,252�l�̊����ƁA23�l�̎��S���m�F����Ă���B�@ |
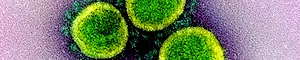 |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 1584�l�����m�F ��T���600�l�]�� �@6/5
�����s����5���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓��j�����600�l�]�菭�Ȃ�1584�l�ŁA�O�̏T�̓����j����23���A���ʼn����܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��5���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł�1584�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����600�l�]�茸��܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�23���A���ł��B5���܂ł�7���ԕ��ς�2031.7�l�ŁA�O�̏T��71.1���ł����B5���Ɋm�F���ꂽ1584�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�18.4���ɂ�����292�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�134�l�ŁA�S�̂�8.5���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A4���Ɠ���2�l�ł����B����A�s�͊������m�F���ꂽ80���90��̏������킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����1153�l�R���i�����A1�T�ԑO����349�l�� �@6/5
���{��5���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1153�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����349�l�������B���҂�4�l�������B
|
�������ŐV����1��5109�l�R���i�����c������1�T�ԕ��ς�29���� �@6/5
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�5���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��5109�l�m�F���ꂽ�B���҂�16�l�A�d�ǎ҂͑O������7�l����77�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�1584�l�������B�O�T�̓����j������610�l����A23���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�2032�l�ŁA�O�T����29���������B���҂͏���2�l�������B
|
���V����1�l���S�E137�l�̊����@�����Ҍ����X�����Ċg��ɒ��Ӂ@�������@6/5
��������5���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������1�l�̎��S��137�l�̊������m�F���ꂽ�Ɣ��\���ꂽ�B
�������m�F���ꂽ�̂͌S�R�s��35�l�A���킫�s��23�l�A�����s�Ɖ�Îᏼ�s�ł��ꂼ��15�l�Ȃ�21�̎s�����ƌ��O�ō��킹��137�l�B����̊����҂Ƃ��Ă�22���A���őO�̏T�̓����j����������Ă���B�܂�4���܂łɌ����̈�Ë@�ւɓ��@���Ă���70��̒j�����S���Ȃ����B�����̊����҂͌����X���������Ă��邪�A�������͍Ċg��h�~�֊�����̌p�����Ăт����Ă���B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1013�l�����m�F ��T���j�����300�l�]�� �@6/6
�����s����6���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̌��j�����300�l�]�菭�Ȃ�1013�l�ŁA�O�̏T�̓����j����24���A���ʼn����܂����B
�����s�́A6���s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł�1013�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j�����300�l�]�茸��܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�24���A���ł��B6���܂ł�7���ԕ��ς�1984.4�l�ŁA�O�̏T��71.9���ł����B6���Ɋm�F���ꂽ1013�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�18.1���ɂ�����183�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�81�l�ŁA�S�̂�8.0���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A5���Ɠ���2�l�ł����B���S�̔��\�͂���܂���ł����B |
�������V�K�����A1���l�����@1��11���ȗ��@�V�^�R���i�@6/6
6���Ɋm�F���ꂽ�����̐V���ȐV�^�R���i�E�C���X�����҂́A9106�l�������B1���̐V�K�����҂�1���l�������̂�1��11���ȗ��B�d�ǎ҂͑O����2�l����75�l�A���҂�24�l�������B
���������҂́A�ψي��u�I�~�N�������v�̗��s�ɔ������N�ɓ���}���B2����{�ɂ�1��10���l���A�s�[�N���}�����B���̌�A�����y�[�X�͓݉����A5���܂ł̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂�13��294�l�ƁA�O�T�Ɣ��6���l���������Ă����B
�����s�ł�1013�l�̊������m�F�B�V�K�����҂͑O�T���j���Ɣ��331�l����A24���A���őO�T�̓����j������������B�V���Ȏ��҂�5��9���ȗ��A��1�J���Ԃ�Ɋm�F����Ȃ������B�s�ɂ��ƁA�V�K�����҂̒���1�T�ԕ��ς�1984�D4�l�ŁA�O�T��71�D9���B�s��ɂ��d�ǎ҂͑O���Ɠ���2�l�������B |
��1��3���f�c�o�M���b�v��-3.7���A��21���~�̎��v�s�������t�{�@6/6
���t�{��6���A2022�N1��3�������������Y(�f�c�o)��1������l�f�����f�c�o�M���b�v���}�C�i�X3�D7���������Ɣ��\�����B���悻21���~���x�̎��v�s���B2021�N10�\12����������v�s���͊g�債�A10�l�����A���̃}�C�i�X�ƂȂ����B
���N1�\3�����̂f�c�o�͔N�����Z��1�D0���������A2�l�����Ԃ�̃}�C�i�X�����������B�u�I�~�N�������v�̊����g����āu�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p���ꂽ���߁A���s��O�H�Ȃǂւ̏����܂������ƂȂǂ��w�i�B
�f�c�o�M���b�v�͓��{�o�ς̎��v�Ƌ����̃o�����X�����������̂ŁA ���v�������������}�C�i�X�ƂȂ�B���t�{�́A�O��ƂȂ�f�[�^�␄�v���@�ɂ���Č��ʂ��傫���قȂ邽�߁A�����̕��������Ă݂�K�v������Ƃ��Ă���B�@ |
 |
�������s�̃R���i�����ҁA�V����1800�l�m�F�c25���A����1�T�ԑO�������@6/7
�����s��7���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�s���ŐV����1800�l�m�F�����Ɣ��\�����B�O�T�̓����j������562�l����A25���A����1�T�ԑO����������B
|
�����{�ŐV����1925�l�R���i�����A1�T�ԑO���389�l�����@6/7
���{��7���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1925�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����389�l�������B���҂�6�l�������B�@ |
 |
�����ꌧ���R���i����1467�l�@�������݉��A���~�܂茜�O�@6/8
���ꌧ��7���A10�Ζ�������90�Έȏ��1467�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�O�T�Ɠ����j���Ɣ�r����ƁA5��29�������1�T�Ԃ͌�������100�l�ȏ�ƂȂ��Ă������A6��5���͑����ɓ]���A7���͂킸��2�l�̌����ɂƂǂ܂����B���̋{���`�v�����������Ắu��������������X�s�[�h�������Ă��Ă���\��������v�Ɗ����Ґ��̍��~�܂�����O�����B
�N��ʂł�10�オ269�l�ƍő��ŁA10�Ζ�����268�l�Ǝq�ǂ�����Ɋ������L����B�a���g�p����39�E2���Ō���ʂł͖{��46�E5���A�{��3�E0���A���d�R4�E5���������B�{�������Ăɂ��ƁA�d�_��Ë@�ւł͓��@������������Ԃ͉������A���@�ҋ@�X�e�[�V�����̗��p��1��4�A5�l���x�Ƃ����B�����҂�����Љ���{�݂�71�J���ŁA����͍���Ҏ{�݂�57�J��189�l�A�Ⴊ���Ҏ{�݂�14�J��27�l�������B�d�_��Ë@�ւ̏]�ƈ��Ȃǂ������ȂǂŌ����Ă�����363�l�ŁA�����y�[�X�͓݉�������B���͓����A4�`5���ɓߔe�s���̈�Î{�݂�Љ���{�݂ŋN�����N���X�^�[(�����ҏW�c)4�������B�ČR�W��49�l�������B�@ |
���V�^�R���i�@8���̓����s�̐V�K�����҂�1935�l�@�d�ǎ҂�1�l������3�l�@6/8
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA8��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�1935�l�B�d�ǎ҂͑O������1�l�����A3�l�ƂȂ��Ă��܂��B(���l�͑���l)
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�1935�l(�s��1�l)�B�N��ʂł�20�オ�ő���347�l�A������30���335�l�A40���334�l�Ƒ����Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�138�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�1835.6�l(�ΑO�T��76.1��)�B�s���̑���(�v)��155��5572�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����16.2��(816�l�^5047��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T1��(2415�l)����480�l����A26���A���őO�T�̓����j�����猸���B�V�K�����҂�4���A����1000�l��ɗ}�����Ă��܂��B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 1935�l�����m�F �O�T��480�l�� �@6/8
�����s����8���̊����m�F��1�T�ԑO�̐��j�����480�l���Ȃ�1935�l�ŁA�O�̏T�̓����j����26���A���ʼn����܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��8���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1935�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j�����480�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�26���A���ł��B8���܂ł�7���ԕ��ς�1835.6�l�ŁA�O�̏T��76.1���ł����B1935�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�17.9���ɓ�����347�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�138�l�őS�̂�7.1���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�3�l�ŁA7�����1�l�����܂����B����A�s�͊������m�F���ꂽ70���80��̒j��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B |
�����{�ŐV����1644�l�R���i�����A1�T�ԑO����333�l���@6/8
���{��8���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1644�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����333�l�������B���҂�3�l�������B
|
�������ŐV����1��8416�l�R���i�����c������1�T�ԕ��ς�24�����@6/8
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�8���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��8416�l�m�F���ꂽ�B���҂�21�l�A�d�ǎ҂͑O������3�l����79�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�1935�l�B�O�T�̓����j������480�l����A26���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�1836�l�ŁA�O�T����24�����B70�A80�Α�̒j��2�l�̎��S�����������B |
���V�^�R���i���Ɖ �g������ �����X�����Ă���ɑ������O�h �@6/8
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ��ď�����������J���Ȃ̐��Ɖ���J����A�S���̊����Ґ��͌����X���������Ă������ŁA���Ԃ����ƃ��N�`���ڎ�Ȃǂœ���ꂽ�Ɖu�̌��ʂ��������Ă������ƂȂǂ���A�Ă���ɂ͊����Ґ��̑��������O�����Ǝw�E���܂����B
���Ɖ�́A���݂̊����ɂ��đS���Ō����X���������A��s������{�A���m���ȂǑ�s�s���̂ق��A�ꕔ�̒n���s�s�ł����N�Ă̑�5�g�̃s�[�N��������Ă���ق��A�l��������̊����Ґ����S���ōł��������ꌧ�ł�����3�T�ԁA�����X���������Ă���Ƃ��Ă��܂��B
�N��ʂł����ׂĂ̔N��Ŋ����Ґ��͌������A����܂ʼn����������S���Ȃ�l�̐��������ɓ]�����Ƃ��܂����B
����̊����ɂ��āA�Z���I�ɂ͑�s�s���Ō����X�����������Ƃ������܂�����ŁA3��ڂ̃��N�`���ڎ�₱��܂ł̊����ɂ���ē���ꂽ�Ɖu�̌��ʂ����X�ɉ������Ă������ƁA�����ȍ~�͉ċx�݂̉e���������Đl�Ƃ̐ڐG�@������邱�ƁA�I�~�N�������̐V�����n���ɒu��������Ă����\�������邱�Ƃ���u�Ă���Ɋ����Ґ��̑��������O�����v�Ƃ��āA��Ñ̐��ւ̉e���Ȃǂ𒍎�����K�v������Ǝw�E���܂����B
�܂��A�ɘa���i�ސ��ۑ�ɂ��ẮA�C�O����K���l�ɑ��ē��{�Ɍ����ďo������O�̌������p�����ċ��߂A���{�ɓ�������ۂ̌����ŗz���ƂȂ����l�ɂ��ẮA�ψكE�C���X�̏��Ď����邽�߃E�C���X�̈�`�q��͂𑱂��邱�Ƃ��K�v���Ƃ��܂����B
���Ɖ�́A�n���s�s�𒆐S�ɑS���̔����ȏ�̒n��ł��܂��ɋ��N�Ẵs�[�N���������Ґ��������������Ă���Ƃ��āA���N�`����3��ڂ̐ڎ������ɐi�߂�ƂƂ��ɁA�����ł��̒���������ΊO�o���T���邱�ƁA�s�D�z�}�X�N�̐��������p�A��A1�̖��ł�������Ƃ�������{�I�Ȋ������O�ꂷ�邱�ƂȂǂ��Ăт����܂����B
����ɁA����҂̏d�lj���\�h���邽�߂ɁA��앟���{�݂ł͓����҂ւ�4��ڂ̃��N�`���ڎ��i�߂�悤���߂܂����B
���㓡���J���u�S���I�Ɍ����X���������Ă���v
���Ɖ�Ō㓡�����J����b�́u�S���̐V�K�����Ґ���1�T�Ԃ̕��ςŐ�T��0.70�ƂȂ��Ă��āA�S���I�ɂ����ނ˂��ׂĂ̒n��Ō����X���������Ă���B�n��ʂɌ����1�T�Ԃ̕��ςŎ�s���A���{�Ȃǂ̑�s�s���ɉ����A�ꕔ�̒n���s�s�ł͍�N�Ẵs�[�N���������ɂ���v�Ǝw�E���܂����B���̂����Łu���ꌧ�ł͑S���ōł������������Ă�����̂́A���߂̂��悻3�T�Ԃ͌������قڌp�����Ă���B������������̊����𒍎����Ă����v�Əq�ׂ܂����B
��1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ� 46�s���{���Ō���
�����J���Ȃ̐��Ɖ�Ŏ����ꂽ�����ɂ��܂��ƁA7���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑S���ł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�0.70�{�ƌ����X���������Ă��܂��B
��s����1�s3���ł́A�����s��0.72�{�A�_�ސ쌧��0.68�{�A��t����0.67�{�A��ʌ���0.63�{�A���ł͑��{��0.71�{�A���Ɍ���0.68�{�A���s�{��0.58�{�A���C�ł͈��m����0.72�{�A����0.80�{�A�O�d����0.69�{�Ɗe�n�Ō������Ă��܂��B
�܂��A�k�C����0.65�{�A�{�錧��0.71�{�A�L������0.64�{�A��������0.65�{�A�l��������̊����Ґ����ł��������ꌧ��0.88�{�Ȃǂƌ������Ă��܂��B
46�s���{���Ō������Ă��āA�O�̏T���V�K�����Ґ��������Ȃ����̂�1.01�{�������������݂̂ƂȂ��Ă��܂��B
�l��10��������̒���1�T�Ԃ̊����Ґ��́A�����X���������Ă�����̂́A���ꌧ��590.20�l�ƑS���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
�����Ŏ���������170.94�l�A�{�茧��152.58�l�A���茧��152.40�l�A�F�{����140.48�l�A���䌧��132.88�l�A�����đ��{��113.94�l�A�����s��94.88�l�ȂǂƂȂ��Ă��āA�S���ł�96.76�l��100�l�������܂����B
����Â��쌻��̑� ��
��Â���̌���ł̐V�^�R���i�E�C���X��ɂ��āA�����J���Ȃ̐��Ɖ�̃����o�[�炪���܂Ƃ߂܂����B
�ł́A���ʓI�ŕ��S�̏��Ȃ��ł���ɂȂ����Ƃ��āA�W���I�ȗ\�h����Ƃ邱�Ƃ�O��ɂ�����ŁA�����҂ւ̑Ή��ő̂����������A�r�����ȂǂɐG���\�����Ⴂ�ꍇ�ɂ̓G�v������K�E���̒��p�͕K�v���Ȃ��A��Ë@�ւŊ����҂������ꍇ�ł��a���S�̂��R���i��p�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�a���P�ʂŊ��҂������ꏊ��݂���Ƃ������Ή����\���ȂǂƂ��Ă��܂��B
�܂��A����Ҏ{�݂ł̖ʉ�͉\�ŁA��Ë@�ւł̖ʉ�ɂ��ẮA�q�ǂ��̓��@���҂�o�Y�̗�����A���҂݂̂Ƃ�ȂǕK�v����������ʂ������Ă����ׂ����Ƃ��Ă��܂��B
����ɁA���C�͏d�v���Ƃ��Ȃ���A�ڐG�ɂ�銴���̍L����͓����l�����Ă�����菭�Ȃ��Ƃ��������Ƃ��āA���x���ݔ��̏��ł�����Ȃǂ̉ߏ�ȑΉ��͌��炷�ׂ��Ƃ��܂����B
���Ɖ�̊ړc�ꔎ�ψ��́u�{�݂ɂ���Ă͊ɘa�ɐT�d�ɂȂ炴������Ȃ��Ƃ��������B�����������������Ƃɂł������l���Ăق����v�Ƃ��Ă��܂��B�@ |
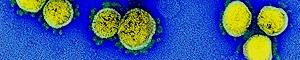 |
�������s�A�R���i����1876�l�@�O�T��78.3���A4�l���S�@6/9
�����s��9���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1876�l���ꂽ�Ɣ��\�����B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���1770�l�ŁA�O�T���78.3���B���҂̕�4�l�������B
���@���҂�784�l�ŁA�a���g�p����15.5���B�d�ǎ҂͑O����1�l����2�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�30�オ380�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�130�l�������B�v�͊����҂�155��7448�l�A���҂�4530�l�ƂȂ����B
|
��27���A���őO�T�����j�������@�����s�̃R���i�����ҁ@6/9
�����s��9���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�V����1876�l�m�F�����Ɣ��\�����B1�T�ԑO(6��2��)����459�l����A27���A���őO�T�̓����j������������B9���܂ł�1�T�ԕ��ς̊���������ƁA1��������̊����Ґ���1770�E0�l�ŁA�O�T(2261�E3�l)��78�E3%�������B�܂��A70���80��̒j��4�l�̎��S�����\���ꂽ�B
�a���g�p����15�E5%�B�܂��A�s��30�`40%�ŋً}���Ԑ錾�̗v���f����w�W�Ƃ��Ă���d�ǎҗp�a���g�p����3�E3%�������B�u�l�H�ċz�킩�̊O�����^�l�H�x(ECMO(�G�N��))���g�p�v�Ƃ���s��̏d�ǎҐ���1�l������2�l�ƂȂ��Ă���B
|
�����{�ŐV����1419�l�R���i�����c1�T�ԑO���112�l���@6/9
���{��9���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1419�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����112�l�������B���҂�2�l�������B
|
������1353�l�R���i�����@�V����4��̃N���X�^�[�m�F�@6/9
���ꌧ��9���A�V����1353�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̖ؗj��(2��)��1373�l�ɔ�ׂ�20�l�������B�v�����҂�22��6820�l�ƂȂ����B�܂��A�V����4��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���8�����_��588.91�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ�������������163.34�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����38.6��(���@�Ґ�248/�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��23.3��(���@14/�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����40�l�̕��������B
|
������{���A�{�Â̊����x������@�R���i1353�l�@�a���g�p38���@6/9
���ꌧ��9���A�{���Ƌ{�Ì���ɏo���Ă����V�^�R���i�E�C���X�̊����g��x������������B�x���5��13���ɔ��߂��Ă����B�����҂���������5�����{���a���g�p�������P����A���@����������ɂȂ�Ȃ������ɂȂ������Ƃ��l�������B�����̐V�K�����Ґ���1353�l�A�a���g�p���͌��S�̂�38�E6���������B
�ʏ�f�j�[�m����9���A�����ŋL�҉���A�����Z�����̈�����������Z���̐���Ŋ����������X���ɂ��邱�Ƃ��w�E�����B�����v���̓���͍���Ƃ��u���̘A(�����w�Z�����̈���)�����ꂩ��{�i������B
�q�ǂ������Ɍ��炸�A�ی�҂��C�x���g�ɎQ������ۂ͑��l���ŏW�܂炸�A�C�x���g��ꂩ�璼�s���A���Ăق����v�Əq�ׁA�����\�h��̓O����Ăъ|�����B
9���̐V�K�����Ґ��͑O�T���20�l���������B���T�͑O�T�������������A�����~�܂芴���݂���B����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���588�E91�őS��1�ʁB�S������93�E02�̖�6�E3�{�ƂȂ��Ă���B����ʂ̕a���g�p���͖{��45�E2���A�{��7�E6���A���d�R4�E5���������B
����5���ɔ��������N���X�^�[4�������\�����B�Ί_�s���̎Љ���{�݂�53�l�����������B����s�̎Љ���{��(2��)�A�k���ی����Ǔ��̎Љ���{��(1��)�ł��N���X�^�[���������B�ČR�̐V�K�����҂�40�l�������B
|
���s���R���i������ ���Ɓu�ψكE�C���X������������K�v�v �@6/9
�����s���̐V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ��āA�s�̐��Ƃ́u�V�K�z���Ґ��͌p�����Č������Ă���v�ƕ��͂�������A�C�O����̊ό��q�̎��ꂪ�ĊJ�����Ȃǐ��ۑɘa����邱�Ƃ���A�u����̕ψكE�C���X�̓����𒍎�����K�v������v�Ǝw�E���܂����B
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̃��j�^�����O��c��9���J����A�s���̊�����4�i�K�̂����ォ��2�Ԗڂ̌x�����x�����ێ�����܂����B
�V�K�z���҂�7���ԕ��ς́A8�����_�őO�̏T�̂��悻76����1784�l�ƂȂ��Ă���Ƃ��āA���Ƃ́u�V�K�z���Ґ��͌p�����Č������Ă���v�ƕ��͂��܂����B
����A�s���ł��A�Q�m����͂̌��ʁA����܂łɃI�~�N�������́uBA.2.12.1�v��12���A�uBA.5�v��5���A���ꂼ��m�F����Ă��邱�Ƃ�����܂����B
���Ƃ́u�C�O����̊ό��q�̎��ꂪ�ĊJ�����ȂǁA���ۑɘa����Ă���B����̕ψكE�C���X�̓����𒍎�����K�v������v�Ǝw�E���܂����B�܂��A��Ò̐��ɂ��āA���Ƃ͓��@���҂̐����������Ă���ȂǂƂ��ĉ�����2�Ԗڂ̌x�����x�����ێ����܂����B |
 |
���u����ȗv���͑O�㖢���v�����r�W�l�X�Ɉٕϑ��o�A���{�̒�����Ƃ����f�@6/10
�����̑ΊO�f�Ղ̑����Ƃ������C�Œf�s���ꂽ���b�N�_�E���́A�ꕔ�̓��{�̌o�c�҂̐S���ɂ������ȉe�𗎂Ƃ����B�V�^�R���i�E�C���X�����g�傩���2�N�����o�߂������A�����E���Ƃ̑Β��r�W�l�X�ɂ͔����ȕω����\��A�����Ƃ̋�������i�ƍL�����Ă���B
���u�C�O����̗A���i�͗v���Ӂv ��r�I���R�������f�Ղ��g�I���h�̒���
���N3���������C�ŋ��s���ꂽ���b�N�_�E���ɂ���āA���E�̕����Ԃ��卬���������Ƃ͕̂Ƃ��肾�B��C��2021�N��4.3����(��85���~)��GDP���������o���������ő�̌o�ϓs�s�����A���s�ɂ����镨���̂܂Ђ͑����̓��{��ƂɑŌ���^�����B
�v�w�Ŗf�Ջ�(�{�ЁE�����s)���c�ޗѓc�a�v����(����)���A��C�̃��b�N�_�E���Œʊւ�҂����ꂽ��l���B���������ɓ��{���̐����G�݂�A�o���Ă���ѓc����́A�u�ݕ���3�����{�ɏ�C�ɓ������܂������A�ʊւ����̂�6��1���B2�J�������~�߂��Ă��܂����v�Ƒł�������B
�ѓc����̑Β��f�Ղ͂���܂Ńg���u�����Ȃ������������B�Ƃ��낪����́A��C�̐Ŋւ���u���i�Ɋ܂܂�鐬���ɂ��āA�lj��������o����v�Ɨv������A�A���R���̐����ɂ��Ă̓��e����̊w�p����܂ŋ��߂�ꂽ�Ƃ����B
��20�N�ɂ킽��Β��f�ՂɌg����Ă����ѓc�����u����ȗv���͑O�㖢���ł��B�R���i�Ђ�2�N���ŁA�Β��f�Ղ��ƂĂ����ɂ����Ȃ�܂����v�ƒQ���B�A�o���i�͖������������A������茟��(�����_���Ɉꕔ������Č���)���p�x�𑝂����B
����A2020�N�ɕ����̃��b�N�_�E������������A�u�����̓R���i�̊����g���}�����v�Ɛ錾���Ĉȍ~�A�����ł́u�������[�g�͊C�O����A�������ݕ��ɂ���v�Ƃ������߂��蒅�����B
���̌���������ŋǏ��I�Ɋ����҂��o�邪�A�������{�͂��̌������u�C�O��������炳�ꂽ���̂��v�Ǝ咣���A���t�̏�C�s�ɂ�����I�~�N�������̊g��ɂ��Ă��A���l�̐������s�����B�K�ߕ��w�����́u�C�O����̗A���i�͗v���ӂ��v�ƌx�����č����̖h�u�̐��������������A�g�C�O�h���ߏ�Ɉӎ������A�i�E���X�́u�ʂ̖ړI������̂ł͂Ȃ����v�Ƌ^����������B
�R���i�В��O�܂ŁA�ѓc����̃r�W�l�X�́A�����ł̓��{���i�u�[����ǂ����ɏ㏸�C���ɏ���Ă������A����2�N���ő傫�������Ă��܂����B�ѓc����́g���v�̐j�̋t�߂茻�ہh��q���Ɋ������A�u�������ΊO�f�Ղ̃n�[�h�������߂Ă���͖̂��炩�B��r�I���R�ɂȂ����Β��f�Ղ��A����2�N���ł��������ނ��Ă��܂��܂����v�ƌ��B
�������ɓۂݍ��܂��O�ɁA �������ƂɎ������V�t�g
�T�T�L���쏊(�{�ЁE��ʌ��A���X�؋v�Y��\�����)�́A�����ԁE�Ɠd���i�𒆐S�Ƃ����v���X�`�b�N�ޗ��̋��^�삷�钆����Ƃ��B
50�N�߂����j�������A10�N�قǑO���璆���ɉ��H���_��݂��A�d�����V�t�g�����Ă����B���{�Ŏ������^�𒆍��Ő��삵�A�ŏI���H����{�ōs���Ƃ������f�����\�z���邽�߂ɁA���X�؎В����炪�����ɉ��x���K��A���n��ƂɋZ�p�w�����s���Ă����B
���]�f���^�n�т𒆐S�ɓ��Ђ��z���Ă��������̉��H���_�́A��10�N�̍Ό��ƂƂ��ɐ��n�����}���A��C�̃��b�N�_�E���ł����N�|�����M���W���͂������B��������̉ݕ��̒x��ɋC�����ނ��Ƃ����������A�u�����l�p�[�g�i�[���z�����Ă���āA4��23���ɏ�C�`���o��D�ɋ��^��ς�ł��ꂽ�v(���X�؎В�)�ƁA�����Ȃł��낷��ʂ��������B
�����ɂ͎����^�]��EV�ȂNj��^�̎d�����R�̂悤�ɂ���\�\�ƌ�鍲�X�؎В������A�����ɂ̂߂荞�ނ���͂Ȃ��B�u��X�̂悤�ȋ��^�ƊE�͂�����ꋫ�Ɋׂ�v�Ɗy�ς������Ȃ����R�����̂悤�ɐ�������B
�u�����̋��^�ƊE�͎����͂�����A�ݔ����������B���ӂ��̂Â���̎嗬�͒����ɂȂ�A��X�͂����ꒆ��������^�̎d�������炤�悤�ɂȂ�ł��傤�B�����Ă����g���������h�ɂȂ肩�˂Ȃ��B���̂��߂ɂ����ƍ\���̓]�����}���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł��v
���A���Ђ��S���𒍂��̂́A���{�̍����H��ł̐V�K���Ƃ��B�R���i�Ђ̍����Ƃ͂����A�����ł��̂́A�������萫�������߂���{�̓S���C���t���Ɋւ��ʐM�@��̐����������B
�u�s�ސT��������Ȃ��ł����A���Ђ̓R���i�ɏ�����ꂽ�ʂ�����܂��B��s���璲�B�ł��Ȃ��������������̎x�����x�ōH�ʂł����������ŁA���͓��{������3�H�ꂪ�t���ғ����Ă��܂��v(��)
���ƍ\���̓]����i�߂钆�A���Ђ̒������Ƃ����C������T�u�ɑ��݉��l��ς�����B
��������ƂƃI�[�v���ȉ�b�͕s�\ �g�܂邲�ƒ������Y�h��������
2020�N�㔼���A���{�̓R���i�����g��ɂ��A��×p�i��q���p�i���i���ƂȂ����B
�����A�u�l���ɂ�������ÁE�q���p�i�̒����ˑ��͌������ׂ����v�Ƃ������_�����܂����B
�����������ł��A�����ɋ��_��u���q���p�i���[�J�[��A�Ђ́A��C����}�X�N�B�������Ă����B����̏�C���b�N�_�E�����o�Ă��A���N�̃p�[�g�i�[�ł����C��Ƃ�B�ЂƂ͈���I�Ȏ���������Ă���Ƃ����B
�ډ��A�g�T�v���C�`�F�[���̒E�����h����荹������Ă��邪�AA�Ђ́u���i���������ł��钆���̐��Y���_��ʂ̍��ɃV�t�g������l���͂Ȃ��v�Ƃ����B
���̈���AA�ЊǗ��E�̍�ꌒ��(����)�́A��C�̃p�[�g�i�[�ł���B�ЂƂ̂��Ƃ�ɔ����ȕω��������Ă��邱�Ƃ���������Ă����B
�u����̏�C���b�N�_�E���������ł������AB�Ђ̎���̈����������Ă��܂��B���b�N�_�E�������w���v�ł����x�̈ꌾ�����|�����܂���ł����B�����ɂ������Ƃ��z���ł��邩��ł��B���̒����̏��v���A���ЂƂ��Ă����[����`���b�g�ɗ]�v�ȗ������c���Ȃ��悤�p�S���Ȃ���Ȃ�܂���B�R���i��2�N����B�Ђւ̜u�x(����)���肪�����A����܂ł̂悤�ȃI�[�v���ȉ�b�́A�قƂ�ǂł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����v(��ꎁ)
���N�̋��͐�ł���Ȃ�����A���{��A�Ђ���C�p�[�g�i�[B�Ђɑ� �g�Ղ̔��h�܂Ȃ��悤�_�o���g���l�q������������B�K���AA�Ђ�B�Ђ���A�����鐻�i�́A���N�̃��s�[�g�������x�[�X���B���s�[�g�����ł���A�V���Ȗ������������]�n�͂قƂ�ǂȂ��B
�������A����A�Ђ�B�ЂƂ̊ԂŐV���Ȏ��Ƃ��ꂩ�痧���グ��ƂȂ�Ƙb�͕ʂ��B�����̒n�����{�̉����B�Ђْ̋������܂钆�ŁA��������͂��܂��܂Ȑ�����邱�Ƃ��ڂɌ����Ă��邩�炾�B��ꎁ�́A����̕������������������Ă���B
�u�V�K���Ƃɂ��ẮA���ޗ��̂ݒ������璲�B���āA���{�����Ő�������v��ł��B���ꂪ�ł���A�בփ��X�N�����点�܂��B�m���ɒ����́g���肵���p�[�g�i�[�h�ł͂���̂ł����A�V���Ȑ��i����悵����������i�Ƃ��Đ��Y����ꏊ�ł͂Ȃ��Ȃ�܂����v
���Ȃ݂ɁA�C�O���n�@�l�������{��Ƃ�ΏۂɁA���ۋ��͋�s(JBIC)���s�����u�킪�������Ɗ�Ƃ̊C�O���ƓW�J�Ɋւ��钲����(2021�N�x�C�O���ړ����A���P�[�g�������ʁE��33��)�v������ƁA2020�`2021�N�x�ɂ����āu�C�O���Ƃ͌���ێ��v�u�������Ƃ͋����E�g��v����X�������܂��Ă��邱�Ƃ��킩��B
��̑O�A�u�����𐧂���҂����E�𐧂��v�Ƃ��������t�����s�������̂����A�ŋ߂́u���������Ăɂ��Ă�����A�H���͂����v�Ƃ��������̎~�ߕ������ɂ���悤�ɂȂ����B �g�R���i��2�N���h���o�ē]���_���}����������Ƃ̒����r�W�l�X�́A����܂��܂�������A��i�߂�C�z���B
�@ |
�������s �V�^�R���i 3�l���S 1600�l���� �O�T���j�����511�l�� �@6/10
�����s����10���̊����m�F��1�T�ԑO�̋��j�����511�l���Ȃ�1600�l�ŁA�O�̏T�̓����j����28���A���ʼn����܂����B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��10���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���1600�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j�����511�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�28���A���ł��B10���܂ł�7���ԕ��ς́A1697.0�l�ŁA�O�̏T��77.6���ł����B10���m�F���ꂽ1600�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�21.6���ɂ�����346�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�107�l�ŁA�S�̂�6.7���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�4�l�ŁA9�����2�l�����܂����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70�ォ��90��̏������킹��3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����1192�l�R���i�����A1�T�ԑO���300�l�ȏ�̌��@6/10
���{��10���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1192�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����300�l�ȏ㌸�����B���҂�1�l�������B
|
���V�^�R���i �V�K�����Ґ� 1�T�ԕ��� 46�s���{���őO�T�䌸 �@6/10
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł͊ɂ₩�Ȍ����X���ŁA46�̓s���{���őO�̏T��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S���@/�@��^�A�x�����挎12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T�ɔ�ׂ�1.41�{�Ƒ������܂������A���̌�A�挎19����0.97�{�A�挎26����0.87�{�A����2����0.68�{�A����9���܂łł�0.75�{�ƁA4�T�A���őO�̏T��������Ă��܂��B���������̕��ς̐V�K�����Ґ��͂��悻1��6270�l�ƂȂ��Ă��܂��B�V�K�����Ґ��͓�����������46�̓s���{���őO�̏T��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�������s�@/�@�挎26���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.89�{�A����2����0.69�{�A����9���܂łł�0.78�{��4�T�A���Ō����B���������̐V�K�����Ґ���1770�l�B
���_�ސ쌧�@/�@�挎26���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.91�{�A����2����0.70�{�A����9���܂łł�0.72�{�A���������̐V�K�����Ґ��͂��悻857�l�B
����ʌ��@/�@�挎26���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.80�{�A����2����0.76�{�A����9���܂łł�0.70�{�A���������̐V�K�����Ґ��͂��悻598�l�B
����t���@/�@�挎26���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.90�{�A����2����0.70�{�A����9���܂łł�0.70�{�A���������̐V�K�����Ґ��͂��悻436�l�B
�����{�@/�@�挎26���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.88�{�A����2����0.68�{�A����9���܂łł�0.78�{�A���������̐V�K�����Ґ���1375�l�B
�����ꌧ�@/�@�挎26���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��0.84�{�A����2����0.72�{�A����9���܂łł�0.97�{�ƁA3�T�A���őO�̏T��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���������̐V�K�����Ґ��͂��悻1247�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10��������̊����Ґ���594.62�l�ƁA�S���ōł�������Ԃ������Ă��܂��B
|
���u�҂��ɑ҂����v�K���q����ĊJ�u����苓���Ă͊�ׂ��v�̐����@6/10
�V�^�R���i�E�C���X�̐��ۑ�Ŗ�2�N�Ԏ~�܂��Ă����K���O���l�ό��q�̎��ꂪ10���A�ĊJ���ꂽ�B���ۂ̓����͑����Ă����T�ȍ~�ɂȂ錩�ʂ������A�ό��Ǝ҂�́u����Ɩ{�i�I�ɏ������ł���v�Ɗ��҂���B����A������̓���ɔY�ދƎ҂������B
�u�҂��ɑ҂��Ă����v�B�����s�̗��s��Ёu�h���[���C���^�[�t�F�C�X�v�̗k��(���)�В�(50)�͐���e�܂���B���Ђ̓R���i���L����O�A�A�W�A�𒆐S�ɔN�Ԗ�5���l�̊ό��q�Ȃǂ�����Ă������A�����~�ő�Ō��B�������A���������������Ă������t�ɂȂ��đ�p�Ȃǂ̗��s��Ђ���c�A�[�Ís�̖₢���킹������悤�ɂȂ�A�ݓc���Y�����ۑ�̊ɘa���j�������ƈ�C�ɑ������B
�����A������ɂ͋C�����ށB�u�z�e���̐H�����o�C�L���O�̏ꍇ�A���{�l�̓}�X�N�Ǝ�܂𒅂��ė�������邪�A�O���l�͑S�����S���A�����ł��邩�B�������������̂��q����Ɩ��C���N���Ȃ���������v
��B�ł�5�����{�A����ĊJ�Ɍ��������{�̎��؎����Ń^�C���痈�����A�����A�啪�Ȃǂ����V���Ă��������̗��s��Ј�1�l�̃R���i�����������B��̓������������ɂȂ����B�h���[���C���^�[�t�F�C�X�̍L��S���҂́u(�����o����)�K�C�h���C���ɏ]���āA�n�������̂̕��j�ɉ����ĔZ���ڐG�҂𑬂₩�ɓ��肷��ȂǁA��������Ή��������v�Ƙb���B
�����s������̊ό��n�E�Ől�͎Ԃ��^�c����u���㉮�v(�䓌��)�͐l�ފm�ۂɓ���Y�܂���B�R���i�Ђ����������e���ŁA35�l�����l�͎Ԃ������X�^�b�t�͌���18�l�B�̗p�������ĊJ���Ă��邪�A���̎��v�͈��H�X�ȂǑ��ƊE�ł����܂��Ă���Ƃ����A�l������200�L�����ɂȂ�l�͎Ԃ�������l�ނ͂Ȃ��Ȃ����Ȃ��B�����p����\(66)�́u�Ȃ�ׂ������R���i�O�Ɠ������̐l����m�ۂ������v�ƑΉ����}���B
�啪���ʕ{�s�̊ό������u���̒r�n���v�̉^�c��Ђ̍H�������ꖱ(55)�́u�~���ŊC�O����̊ό��q�������߂�B�n��o�ς̊������ɂȂ���v�Ɗ��҂���B����Łu���{�ƊC�O�Ŋ�����ւ̔F���̈Ⴂ������A�Ăъ������L����Ȃ����S�z���v�Ƃ����A�V���Ƀ}�X�N���p���w���ł𑣂��p��\�L�̈ē���ݒu�������Ƃ𖾂������B
�ό����u���[�f�B���O�Y�Ɓv�ƈʒu�Â��鉫�ꌧ�ł����҂ƕs������������B�R���i�̊g��O�A�ό��q��1000���l���A����3�����K���q�������B�������A�l����őS���ő��̐V�K�����҂��o�钆�A�W�҂́u����𗷍s��ɑI�Ԑl�͏��Ȃ��̂ł́v�Ɗ뜜����B�ߔe�s�œy�Y���X���o�c����j���́u�C�O�ł̓}�X�N�����Ȃ��n�������ƕ����B�ψي����������Ȃ������S�z���v�B�C�w���s�⍑�����s�ɉ̒��������邾���ɁA�܂��ً}���Ԑ錾���o�鎖�ԂɂȂ�Ȃ����A�s���͏����Ȃ��B�u����ĊJ�������������Ă͊�ׂȂ��v
�����̋ʏ�f�j�[�m�����u�����g��̖h�~�ƎЉ�o�ϊ����̃o�����X�����̂���O��B�K�������}���鑤���A��������Ƃ�����������p�����邱�Ƃ��d�v���v�Ƙb���B |
�������s�ŁuBA.2.12.1�v�uBA.5�v���������ɘa �g�ψكE�C���X�������h�@6/10
�����������̊ɘa �g�s�����h�̍ĊJ��
���{��6��1������1��������̓����Ґ��̏����2���l�Ɉ����グ�A10������͊O���l�ό��q�̎�����ĊJ���܂����B����A����̑ΏۂɂȂ�̂́A�A�����J��؍��A�C�M���X�ȂǁA���X�N���Ⴂ�Ɣ��f���ꂽ���킹��98�̍��ƒn�悩��̓Y����t���̃c�A�[�q�Ɍ��肳��܂��B�����̊ό��q�̓��N�`���ڎ���Ă��Ȃ��Ă��������̌�����ҋ@�[�u�͖Ə�����܂��B�܂��A�����s�́A�s�����s���ŗ��s����ۂ̔�p����������@������g�s�����h�A�u������Tokyo�v��7 �����܂Ŏ����I�ɍĊJ���܂����B
���s���ŁuBA.2.12.1�v�uBA.5�v���� �g�����������h
�s���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��́A9���̒i�K�ŁA�O�̏T�̓����j����27���A���ʼn����܂����B�܂��A�V�K�z���҂�7���ԕ��ς́A8�����_�őO�̏T�̂��悻76����1784�l�ƂȂ��Ă��āA�s�̃��j�^�����O��c�Ő��Ƃ́u�V�K�z���Ґ��͌p�����Č������Ă���v�ƕ��͂��܂����B���̈���ʼn�c�ł́A�s���ł��Q�m����͂̌��ʁA����܂łɃI�~�N�������́uBA.2.12.1�v��12���A�I�~�N�������̌n���̂ЂƂŁuBA.5�v�ƌĂ��V���ȕψكE�C���X��5���A���ꂼ��m�F����Ă��邱�Ƃ�����܂����B
���Ɓu�C�O����̊ό��q�̎��ꂪ�ĊJ�����ȂǁA���ۑɘa����Ă���B����̕ψكE�C���X�̓����𒍎�����K�v������v
���S���E�֓��n���̐V�K�����Ґ��̏�
�����J���Ȃ̐��Ɖ�Ŏ����ꂽ�����ɂ��܂��ƁA7���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑S���ł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�0.70�{�ƌ����X���������Ă��܂��B�֓��n���́A�����s��0.72�{�A�Ȗ،���0.71�{�A�_�ސ쌧��0.68�{�A��t����0.67�{�A��錧��0.66�{�A�Q�n����0.65�{�A��ʌ���0.63�{�ƂȂ��Ă��܂��B���Ɖ�́A���݂̊����ɂ��āA�S���Ō����X���������A��s���ȂǑ�s�s���̂ق��A�ꕔ�̒n���s�s�ł����N�Ă̑�5�g�̃s�[�N��������Ă���Ƃ��܂����B�N��ʂł����ׂĂ̔N��Ŋ����Ґ��͌������A����܂ʼn����������S���Ȃ�l�̐��������ɓ]�����Ƃ��܂����B
���Z���I�ɂ͑�s�s�Ō����X�� �Ă��둝���̌��O
����̊����ɂ��Đ��Ɖ�́A�Z���I�ɂ͑�s�s���Ō����X�����������Ƃ������܂��Ƃ��܂����B���̈���ŁA3��ڂ̃��N�`���ڎ�₱��܂ł̊����ɂ���ē���ꂽ�Ɖu�̌��ʂ����X�ɉ������Ă������ƁA7���ȍ~�͉ċx�݂̉e���������Đl�Ƃ̐ڐG�@������邱�ƁA�I�~�N�������̐V�����n���ɒu��������Ă����\��������Ƃ��Ă��܂��B�����������Ƃ���u�Ă���Ɋ����Ґ��̑��������O�����v�Ƃ��Ĉ�Ñ̐��ւ̉e���Ȃǂ𒍎�����K�v������Ǝw�E���܂����B�܂��A�ɘa���i�ސ��ۑ�ɂ��ẮA�C�O����K���l�ɑ��ē��{�Ɍ����ďo������O�̌������p�����ċ��߂A���{�ɓ�������ۂ̌����ŗz���ƂȂ����l�ɂ��Ă͕ψكE�C���X�̏��Ď����邽�߁A�E�C���X�̈�`�q��͂𑱂��邱�Ƃ��K�v���Ƃ��܂����B�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
��������1526�l�����@�R���i�A2�l���S�@6/11
�����s��11���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1526�l���ꂽ�Ɣ��\�����B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���1619�E1�l�ŁA�O�T���76�E4���B2�l�̎��S�����ꂽ�B���@���҂�704�l�ŕa���g�p����13�E9���B�d�ǎ҂͑O���Ɠ�����4�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�30�オ287�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�97�l�������B�����҂̗v��156��574�l�A���҂�4535�l�ƂȂ����B
|
�����{ �V�^�R���i 2�l���S �V����1255�l�����m�F �@6/11
���{��11���A�V����1255�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�200�l�]�茸��܂����B�{���̊����҂̗v��98��9398�l�ƂȂ�܂����B�܂��A2�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5093�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�10������1�l������12�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
��1�s3���ł͊����Ґ�4000�l���ꑱ�� �@6/11
�V�^�R���i�E�C���X�̐��ۑ�ɘa�̈�ŁA�K���O���l�ό��q�̓����葱�����ĊJ���ꂽ�B�w�Z�ł̔M���Ǒ�ŁA���{�́A�̈�̎��Ƃ�^�����������A�o���Z���Ƀ}�X�N���O���w��������悤���߂�ʒm���A�S���̋���ψ���ɏo�����B
���S���̐V�K�����҂͑O�T��3����
�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA����1�T��(4�`10��)�A�S���̐V�K�����Ґ���2���l�����̓����������B���J�Ȃɏ���������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�ɂ��ƁA�S���̐V�K�����Ґ��͑O�T��Ŗ�3�������Ă���A10���l������ł�100�l����������B500�l�ȏゾ������6�g�̃s�[�N��(2�����{)�Ɣ�ׂ�ƁA5����1�ȉ��̐����B
�����Ɛ_�ސ�A��ʁA��t��1�s3����10���̐V�K�����Ґ��͌v3418�l�B5���ȍ~�A4000�l�����̓��������Ă���B��6�g�s�[�N(2��5���A4��2272�l)��10����1�ȉ��B1��8000�l�������Ă���2�J���O�Ɣ�ׂĂ���5����1�Ɍ������B
��s���̂ق��A���{�∤�m���A�������Ȃǂ͍��Ă̑�5�g�s�[�N��������Ă���B����A�k�C���≫�ꌧ�ȂLjˑR�Ƃ��đ�5�g�s�[�N������n��������B
���m�o�o�b�N�X�ڎ�J�n�A3��ڐڎ��6����
�p�A�X�g���[�l�J�Ђ̓��{�@�l��9���A�J�������V�^�R���i�̍R�̖�Ɋւ��A�����̔��̏��F�������J���Ȃɐ\�������B�R����v���ɐi�߂���Ᏻ�F�̓K�p����]���Ă���B���ÂȂǂŖƉu�@�\���ቺ���A���N�`���̌��ʂ��o�ɂ����l��ΏۂɁA�����O�ɓ��^����B�y�ǂ��璆���ǂ̊��҂ւ̎��Â��z�肷��B�㓡�ΔV���J����10���̋L�҉�Łu(�R�̖��)�m�ۂ��������Ă����v�Əq�ׂ��B
������4�Ԗڂɏ��F���ꂽ�ăm�o�o�b�N�X�Ђ̃��N�`���ڎ킪�n�܂����B���А���蕛���������Ȃ��Ƃ���A�A�����M�[�ȂǂŃ��N�`���ڎ킪�ł��Ȃ������l�̗��p�������܂��B
3��ڐڎ���I�����l�͑S�l����6�������B65�Έȏ�̐ڎ헦��9�����x�Ȃ̂ɑ��A20�`30���4����ɂƂǂ܂�B60�Έȏ�̐l�炪�Ώۂ�4��ڐڎ�́A��2��2000�l���I�����B
��2�N�Ԃ�ɖK���q�������
���{��10���A�K���O���l�ό��q�̎���葱�����2�N�Ԃ�ɉ��ւ����B�č��A�����Ȃ�98�̍��E�n�悪�ΏہB�Y��������s����p�b�P�[�W�c�A�[�Ɍ��肵���B
���y��ʏȂ�7���Ɍ��\�����w�j�́A���s�Ǝ҂͎Q���҂ɑ��ă}�X�N�̒��p��A��Ô�J�o�[�����C�O���s�ی��ւ̉����Ȃǂ����߂�ƋK�肵���B
�o�ϋ��͊J���@�\(OECD)��8���A��������2022�N�̃C���t�������O�N��8.5%�ƁA��N�\�\����4.2%����㏸����Ƃ̌��ʂ������\�B�E�N���C�i��@�̉e���ŃG�l���M�[��H���̉��i�������������ƂȂǂf�����B
���E�o�ς̓R���i�Ђ���̉������܂�Ă������A�����݉����������Ȃ����ʂ��ƂȂ�A���{�̃C���t��������N12���\����0.8%����1.9%�ɏ�U�ꂷ��Ƃ̌������������B�@ |
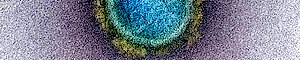 |
���u�����Ґ��̌����X���������~�܂��Ă���v�@����̐V�^�R���i�@6/12
���ꌧ��11���A�V����10�Ζ�������100�Έȏ��1368�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�O�T�y�j�����27�l���B5������11���܂ł̒���1�T�ԍ��v�͑O�T���1�E03�{�������B�����Ґ��̌����������Ă������A2���A���Œ���1�T�Ԃ̑O�T�䂪1���Ă���A��ԓ֊����Ǒ����ے��͂��炽�߂āu�����Ґ��̌����X���������~�܂��Ă���v�Ƃ̔F�����������B
�V�K�����҂̔N��ʓ���́A10�Ζ������ő���269�l�A10��242�l�A40��197�l�A30��183�l�Ƒ����B����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���10�����_��595�E24�l�ƂȂ�S�����[�X�g�������Ă���B�R���i�a���g�p����38�E3���B����ʂł͖{��45�E0���@�{��6�E1���@���d�R4�E5���B�W�����Î�(�h�b�t)�⍂�x���Î�(�g�b�t)�ɓ����Ă��鍑��̏d�NJ��҂͑O������2�l����18�E3���������B�ČR��n���̐V�K�����Ґ���68�l�B�@ |
�������s �V�^�R���i 1546�l�����m�F �O�T�̓��j�����38�l�� �@6/12
�����s����12���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓��j�����38�l���Ȃ�1546�l�ŁA�O�̏T�̓����j����30���A���ʼn����܂����B
�����s��12���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���1546�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����38�l����܂����B�O�̏T�̓����j���������̂�30���A���ł��B12���܂ł�7���ԕ��ς�1613.7�l�ŁA�O�̏T��79.4���ł����B12���Ɋm�F���ꂽ1546�l��N��ʂɌ���ƁA10�Ζ������ł������A�S�̂�18���ɓ�����278�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�90�l�ŁA�S�̂�5.8���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�11���Ɠ���4�l�ł����B���S�����l�̔��\�͂���܂���ł����B
|
�����{ �V�^�R���i 3�l���S �V����1151�l�����m�F �@6/12
���{��12���A�V����1151�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA�قړ����l���ł����B�{���̊����҂̗v��99��549�l�ƂȂ�܂����B�܂�3�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5096�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�11���Ɠ���12�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����1126�l�����m�F �@6/12
���ꌧ��12���A�V����1126�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�l�̗v��23���l���A23��754�l�ƂȂ�܂����B |
�������ŐV����1��3394�l�R���i�����c�s��1546�l�A1�T�ԑO����38�l���@6/12
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�12���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��3394�l�m�F���ꂽ�B���҂�9�l�A�d�ǎ҂͑O������3�l����66�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�1546�l�B�O�T�̓����j������38�l����A30���A����1�T�ԑO����������B
�@ |
 |
�������s�̐V�K�����҂�960�l�@1000�l�����ƂȂ����͖̂�5�����Ԃ�@6/13
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA13��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�960�l�B�d�ǎ҂͑O���ƕς�炸�A4�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�960�l(�s��1�l)�B�N��ʂł�10�Ζ������ő���184�l�A������40���174�l�A30���158�l�Ƒ����Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�61�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�1606.1�l(�ΑO�T��80.9��)�B�s���̑���(�v)��156��3080�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����13.3��(670�l�^5047��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T6��(1013�l)����53�l����A31���A���őO�T�̓����j�����猸���B�V�K�����҂�1000�l�����ƂȂ����̂�959�l������1��11���ȗ����悻5�����Ԃ�ł��B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
������ �R���i 2�l���S 960�l�����m�F ��5�����Ԃ�1000�l����� �@6/13
�����s����13���̊����m�F��960�l�ł��Ƃ�1��11���ȗ��A���悻5�����Ԃ��1000�l�������܂����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��13���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��960�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B����ɔ��\����銴���Ґ���1000�l�������̂͂��Ƃ�1��11���ȗ��A���悻5�����Ԃ�ł��B�܂�1�T�ԑO�̌��j�����53�l����A31���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B13���܂ł�7���ԕ��ς�1606.1�l�őO�̏T��80.9���ł����B960�l��N��ʂɌ���ƁA10�Ζ������ł������S�̂�19.2���ɓ�����184�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�61�l�őS�̂�6.4���ł��B
����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�12���Ɠ���4�l�ł����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ80��̒j����90��̏����̍��킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B |
�����ꌧ���̃R���i493�l3�l���S�@�����Ґ��͉����~�܂�@6/13
���ꌧ��13���A�V����10�Ζ�������90�Έȏ��493�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B3�l�̎��S��8���ɔ��\���ꂽ�N���X�^�[(�����ҏW�c)�̒lj����������ꂽ�B12�����\�̊����҂�1126�l�������B
13���͑O�T�̓����j������58�l�������A�����Ґ��͉����~�܂�̏B���́u�a���g�p�����Ⴍ�A��ÕN��(�Ђ��ς�)�ɂȂ���ł͂Ȃ��v�ƌ������q�ׂ��B�����~�܂肪�ꎞ�I�Ȃ��̂��ǂ������A���������Ȃ��画�f����Ƃ����B
���S�����̂͂���s��60��j���A�ߔe�s��80�㏗���A�ߔe�s��90��j����3�l�B5��13������24���̊Ԃɗz�����������ē��@���A�������܂łɖS���Ȃ����B�v�̎��Ґ���473�l�ƂȂ����B
8���ɔ��\���ꂽ�����암��ÃZ���^�[�E���ǂ���ÃZ���^�[�̃N���X�^�[�ŐV����7�l�̊��������\���ꂽ�B�����o�H�Ȃǂ͒������B10��̐V�K�����Ґ���94�l�ƍő��B�����o�H�͉ƒ����150�l�ōő��������B�ČR�̐V�K�����҂�44�l�������B
|
�������ŐV����7956�l�R���i�����A����21�l�ŏd�ǎ҂�61�l �@6/13
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�13���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����7956�l�m�F���ꂽ�B���҂�21�l�A�d�ǎ҂͑O������5�l����61�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�960�l�ŁA1���̊����Ґ���1000�l����������̂�1��11��(959�l)�ȗ��A��5�����Ԃ�B�O�T�̓����j������53�l����A31���A����1�T�ԑO����������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�1606�l�ŁA�O�T����19���������B
���{�ł́A�V����424�l�̊��������������B�O�T�̓����j�����37�l�������B |
���k�C���@�u�܂h�~�v���Ԓ��̎��Z���߈ᔽ �V����82���H�X�ɉߗ��@6/13
���N�̂܂h�~���d�_�[�u�̊��Ԓ��ɖ@���Ɋ�Â����c�Ǝ��Ԃ̒Z�k���߂Ɉᔽ�����Ƃ��āA�ٔ����͐V���ɓ����̈��H�X82�X�܂ɑ��ߗ����Ȃ����Ƃ����߂܂����B
���́A�܂h�~���d�_�[�u�̊��Ԓ��A�@���Ɋ�Â����c�Ǝ��Ԃ̒Z�k���߂Ɉᔽ�����Ƃ��āA���N�A�̂�120�X�܂ɑ�20���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ��悤�ٔ����ɋ��߂܂����B���ɂ��܂��ƁA������āA�NJ�����ٔ����́A�����ߗ������߂����H�X�̂����V����82�X�܂ɂ���13���܂łɉߗ����Ȃ����Ƃ����߂��Ƃ������Ƃł��B�܂��A1�X�܂ɂ��Ă͉ߗ����Ȃ��Ȃ����Ƃ����߂܂����B�X�̖��O���̓I�ȉߗ��̋��z�͌��\����Ă��܂���B
����ł܂h�~���d�_�[�u�Ɋ֘A���ĉߗ����Ȃ�����������H�X�́A�����ٔ����ɋ��߂��̂�120�X�܂̂������킹�Ă̂�117�X�܂ɂȂ�܂����B
����A�ߗ����Ȃ��Ȃ�����������H�X�͍��킹��2�X�܂ɂȂ��Ă��܂��B�c��1�X�܂ɂ��Ă͊NJ�����ٔ����ň��������ߗ��Ɋւ���葱�����i�߂��Ă��܂��B
|
���R���i����������@�����}�A�i�ߓ��@�\���@6/13
�����}��13���A�V�^�R���i�E�C���X�Ή��̒������I�ȉۑ�Ɋւ�����܂Ƃ߂��B�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̔��ߎ��Ɏ��Z�E�x�Ƃ̗v���▽�߂ɉ����Ȃ����Ǝ҂������Ƃ��āA�x����O��ɔ��������グ���K�v�ȂǂƂ����B���{���߂����߂钆�����I�ȑ�ւ̔��f�����߂�B
���̂ق��A�i�ߓ��@�\�̋������Ò̐��̊m�ہA�ی����⌟���Ȃǂ̑̐������A�f�[�^��f�W�^���Z�p�����p������Ñ̐��̊Ǘ��Ȃǂ����荞�B
�ł́A����Ăыً}���ԑ[�u�����ہA�������m�ۂ��K�v���Ǝw�E�B���Ǝ҂�l�ւ̑Ή�����������K�v������Ƃ����B |
 |
���R���i�����h�~���ʂ͂�������2���Ȃ̂Ɂc�Ȃ����{�l�̓}�X�N���O���Ȃ��@6/14
�Ȃ��A���{�l�̓}�X�N���O���Ȃ��̂��B�u���l�̖ڂ��C�ɂȂ�v�Ȃǂ̖��������w�E���鐺�����邪�A���R�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B�}�X�N�̌��ʂɂ��āA���m�ȏ�����ɓ`�����Ă��Ȃ����Ƃ��傫���B
���́A�}�X�N���R���i������\�h������ʂ͒Ⴍ�A�����ʂ�����Ƃ�����w�I�ȃR���Z���T�X�͂Ȃ��B���N2���A�؍��̃T���X�����f�B�J���Z���^�[�̈�t�������R���i�ɑ���}�X�N�̌��ʂ����������^��͂��u��ÃE�C���X�w�v���Ŕ��\�����B�{�e�ł��Љ�悤�B
���^��͂Ƃ́A�����̗Տ��������܂Ƃ߂ĉ�͂��邱�Ƃ��B
�Տ������́A����̏W�c�ɉ�����邽�߁A����Ώۂ�ς���A���ʂ��Č������Ƃ͌���Ȃ��B�قȂ���Ŏ��{���ꂽ�����̗Տ��������܂Ƃ߂ĉ�͂��Ă͂��߂āA���̌��ʂ���ʉ��ł���B�Տ���w�̐��E�ł́A���^��͂̌��ʂ́u�ō����x���̃G�r�f���X�v�ƕ]�������B
�ł́A�؍��̌����͂ǂ�Ȍ��ʂ������낤���B�ނ�͐V�^�R���i�ɉ����A�����R���i���̏d�Nj}���ċz��nj�Q(SARS)�A�����ċz��nj�Q(MERS)�E�C���X�ɑ���}�X�N�̗\�h���ʂ��Č������B���̍ہA��Ï]���҂����p����N95�Ƃ�������ȃ}�X�N�ƁA��ʐl�����p����T�[�W�J���}�X�N�ɂ��āA�ʌɉ�͂����B
�܂��͈�Ï]���҂�N95�}�X�N�𒅗p�����ꍇ�̌��ʂ��B����Ă���14�̗Տ��������܂Ƃ߂�ƁA�������X�N��71�������炵�Ă����B�ɂ߂ėL�����B�����AN95�}�X�N�͒��p����Α����ꂵ���Ȃ�A��ʐl������I�ɒ��p����͓̂���B
�T�[�W�J���}�X�N�͂ǂ����B��Ï]���҂�ΏۂƂ���12�̗Տ��������܂Ƃ߂��31���A��ʐl��ΏۂƂ���2�̗Տ��������܂Ƃ߂��22�������̃��X�N�����炵�Ă����B�������Ȃ���A�����Ƃ��A���̍��͓��v�I�ɗL�ӂł͂Ȃ������B����́A�����Ŏ����ꂽ�L�����͒P�Ȃ���R�ł��������\�ŁA��w�I�ɂ͌��ʂ͏ؖ�����Ă��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B
���Ȃ݂ɁA���̌��ʂ̓C���t���G���U�ɑ���}�X�N�̗L���������������^��͂̌��ʂƂ��������B��s�����Ƃ���v���A����̌������ʂ͐M���ł��������B�ȏ�̎����́A��ʐl���}�X�N�������ꍇ�̗L�����͈�w�I�ɏؖ�����Ă��炸�A�����������Ƃ��Ă�2�����x�Ƃ������ƂɂȂ�B
������A�}�X�N�͒�����ׂ��łȂ��ƁA���͎咣�������͂Ȃ��B�����A���݂̈�w�I�G�r�f���X�Ɋ�Â��A������l�ɑ�������������K�v�͂Ȃ����A���������}�X�N�̌��ʂɂ͌��E������B����Ȃ��Ƃ����A�������Ă��Ȃ��l�����͂ɂ��Ă��A�����܂ŋC�ɂ���K�v�͂Ȃ��̂�������Ȃ��B�����l���邾���ŁA���퐶���̃X�g���X�͊ɘa�����͂����B�}�X�N�̒��p�ɂ��ẮA�Ȋw�I�ȋc�_���K�v�ł���B�@ |
�������s���ŐV����1528�l�R���i�����c32���A����1�T�ԑO�������@6/14
�����s��14���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�s���ŐV����1528�l�m�F�����Ɣ��\�����B�O�T�̓����j������272�l����A32���A����1�T�ԑO����������B
|
��14���̓����s�̐V�K�����҂�1528�l�@�d�ǎ҂͑O������4�l����0�l�@6/14
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA14��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�1528�l�B�d�ǎ҂͑O������4�l����A0�l�ƂȂ��Ă��܂��B(���l�͑���l)
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������90��܂ł�1528�l�B�N��ʂł�20�オ�ő���264�l�A������10�Ζ�����257�l�A30���255�l�Ƒ����Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�84�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�1567.3�l(�ΑO�T��82.3��)�B�s���̑���(�v)��156��4608�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����12.1��(610�l�^5047��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T7��(1800�l)����272�l����A32���A���őO�T�̓����j�����猸�����܂����B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
�������s �V�^�R���i 6�l���S1528�l�����m�F 32���A���O�T����� �@6/14
�����s����14���̊����m�F��1�T�ԑO�̉Ηj�����272�l���Ȃ�1528�l�ŁA�O�̏T�̓����j����32���A���ʼn����܂����B�܂��A�d�ǂ̊��҂́A�s���W�v���n�߂����ƂƂ�4���ȗ��A���߂�0�l�ƂȂ�܂����B
�����s��14���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���1528�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj�����272�l����A32���A���őO�̏T�̓����j���������܂����B14���܂ł�7���ԕ��ς́A1567.3�l�őO�̏T��82.3���ł����B14���Ɋm�F���ꂽ1528�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������S�̂�17.3���ɂ�����264�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�84�l�őS�̂�5.5���ł��B�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A13������4�l�����āA14���̎��_��0�l�ł����B���̊�̏d�ǂ̊��҂����Ȃ��Ȃ�̂́A�s���W�v���n�߂����ƂƂ�4��27���ȍ~�ŏ��߂Ăł��B
����A�I�~�N�������̓����܂��A���Z�x�̎_�f���ʂɓ��^����u�n�C�t���[�Z���s�[�v���s���Ă��銳�҂Ȃǂ��܂߂��ʂ̊�ŏW�v�����d�NJ��҂́A14���̎��_��10�l���܂��B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ40��̒j���ƁA80�ォ��90��̒j���̍��킹��6�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����E�g���m���@�Z���ڐG�Ŗ��Ǐ�Ȃ�u���p�~�@���ɗv�]�ց@6/14
���{�̋g���m���m����14���A�V�^�R���i�E�C���X�̔Z���ڐG�҂������Ԋu�������[�u������A���Ǐ�҂ɂ��Ă͔p�~����悤���ɗv�]����l���𖾂炩�ɂ����B���̓��J���ꂽ�{�̐V�^�R���i���Ɖ�c�ň�Â̐��Ƃ�����^��������ꂽ���߁A�{�Ƃ��Ă̈ӌ����܂Ƃ߂�B
�Z���ڐG�҂̊u�����Ԃɂ��āA���͌���7���ԂƂ��Ă���B�u�����Ԓ���4�A5���ڂɌ����ʼnA�����m�F�ł����5���ڂ���̊u���������\�Ƃ��Ă���B�g������4���A�������閺�̊������������A�Z���ڐG�҂ƂȂ����B����ҋ@�ƂȂ������ߍݑ�Ō��������Ȃ��A��1�T�ԓo���ł��Ȃ������o��������A�Z���ڐG�҂̊u������߂�ׂ����Ƒi���Ă���B
���Ɖ�c�͊����ǂ����̈�t��ō\������邪�A���̓��̉�c�ɂ͌o�ϊw�҂���������B��c�ł͌o�ϊw�҂���u�I�~�N�������ł͊������Ă���ʂ̐l�Ɋ���������܂ł̊��Ԃ��Z���B�Z���ڐG�҂̓����s�����������邱�Ǝ��̂ɂ��܂���ʂ͂Ȃ��Ɗ����Ă���v�Ƃ̈ӌ����������ق��A�����ǂ̐��Ƃ�����u����҂Ȃǃ��X�N�̍����l�ƐڐG����ꍇ�͌���̑[�u�𑱂���ׂ������A����ȊO�̓}�X�N������ȂNJ������O�ꂷ��Ίu�����Ȃ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������[�u�̊ɘa���x������ӌ������������B
����A�ʂ̊����ǂ̐��Ƃ��u�I�~�N�������ł���Ίɘa�����邪�A���̃E�C���X���ǂ��Ȃ邩������Ȃ��v�Əq�ׂ�ȂǁA�V���ȕψي����I�~�N�������������ʼn����邱�Ƃ��z�肵�A���}�Ȋɘa�ɐT�d�Ȉӌ����������B
|
������1342�l�R���i�����@��T�Ηj�����125�l���@�V����2��̃N���X�^�[�m�F�@6/14
���ꌧ��14���A�V����1342�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̉Ηj��(7��)��1467�l�ɔ�ׂ�125�l�������B�v�����҂�23��2589�l�ƂȂ����B�܂��A�V����2��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���13�����_��592.81�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ�������������157.90�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����37.8��(���@�Ґ�243/�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��15.0��(���@9/�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����49�l�̕��������B |
 |
���I�~�N�����V�h���^�BA.4��BA.5����g��A�Ċ����҂̖�20���Ɂ@6/15
�Ď��a��Z���^�[(CDC)��14���A�č��̐V�^�R���i�E�C���X�����ɃI�~�N�����ψي���2�̔h���^�uBA.4�v�ƁuBA.5�v����߂銄����11�����_�ł��ꂼ��8.3����13.3���ɒB�����Ƃ̐��v���������B
�����͂������Ƃ���闼�h���^��3���ɐ��E�ی��@��(WHO)�̊Ď����X�g�ɒlj����ꂽ�ق��A���B�ł����O�����ψٌ^�Ɏw�肳��Ă���B
���B���a�\�h�Ǘ��Z���^�[(ECDC)��13���A���h���^�̊��������̃R���i�ψي����������y�[�X�ōL�����Ă���A�嗬�ɂȂ�Γ��@�⎀�S�Ⴊ������v���ɂȂ�Ɣ��\�����B
�~�l�\�^�B���`�F�X�^�[�̃}���E�N���j�b�N�Ń��N�`�������O���[�v�𗦂���O���S���[�E�|�[�����h���́A��A�t���J�̃f�[�^�ŗ��h���^�͉ߋ��̊�����N�`���Ŋl�����ꂽ�Ɖu���������\�͂��オ���Ă���Ƃ��A�u���Ɍ��O���Ă���v�Əq�ׂ��B
�܂��A�ߋ��̊����ƃ��N�`���ڎ�͎��S��d�lj��ɑ���\�h���ʂ����\����������̂́A�V�w���J�n��2��ڂ̒lj��ڎ�(�u�[�X�^�[�ڎ�)�̌��ʌ���ŁA�ċG�ɗ��h���^�̊������L���鋰�������Ǝw�E�����B |
������@�}�_�s�킸�@���_�̕{�̑̂��炭�ے��@6/15
�^��}�̓}�_���s��Ȃ��܂܁A�ʏ퍑��͂��傤�A��������}�����B
���{�Љ�́A�V�^�R���i�E�C���X������Əo���헪�A���V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɔ����o�ςւ̈��e���ȂǍ���������傫�����E����ۑ�ɒ��ʂ��Ă���B
�Q�@�I���T���A�}�_�͐������O��}�̎{���i���錩����ɂȂ�͂������A�e�}�͊i�D�̋@��ƌ�����������������ɓ������B���_�̕{�̑̂��炭���ے����鎖�Ԃ��B
�������1��17���A�R���i�̕ψي��u�I�~�N�������v���}�g�傷�钆�ŏ��W���ꂽ�B
�I�~�N�������͊����͂������A�V�K�����Ґ����I�ɑ�������������A�d�lj����X�N�͔�r�I�������B
���̓����܂��A�R���i��̘_�_�͊����h�䂩��Љ�o�ϊ����̐��퉻�Ɏ������ڂ�A������͊ݓc���Y�̂�����肪���A���^�C���Ŗ��ꂽ�B
�ݓc�����͉�����A�����Ґ��̊g��Ƌ�`���u�̈ꕔ�Ə��A���O�ł̃}�X�N���p�̊ɘa�Ȃǂ�ł��o�����B�o�ϊ�����T�d�ɉ��Ƃɕ��S�������A����܂ł̃R���i�Ƃ̓�������������U��Ԃ邱�ƂȂ��A�����]��������̂͏ꓖ����I�ł͂Ȃ����B
��Âƌ����̐��̕N��(�Ђ��ς�)�A���������┱�����ً}���Ԑ錾�Ƃ܂h�~���d�_�[�u�̐���Ȃǘ_�_�͑���ɂ킽�邪�A���{���Ƒ�O�҂̕��͂����܂��Ȃ���Ă��Ȃ��B
�ݓc�͐挎�A���{�Ή��̌���L���҉�c�Ɏ��₵�����A�����͂킸��1�J���ゾ�B���炩�ɐّ��ŁA�Q�@�I���ӎ������A���o�C���̂悤�ȋ����ȓ������B
���������̓R���i�Ή��ɋ����A���{�W�O�A���`�̗����C�����Ő��������o�����Ԃ��J��Ԃ����B
���̌���p�����ݓc�������R���i����̌��ɋy�э��Ȃ͈̂��{�A��������ᔻ���邱�ƂɂȂ�Ɯu�x(����)�����Ƃ��������Ȃ��B�����̕��������Ă��Ȃ����ӔC�Ȏp�����B
�����}�͒Njy�s�����B��N�H�̏O�@�I��ɏA�C������������}�̐���\�́A�ݓc���Ɠ}�_�őΛ�(������)���Ă��Ȃ��B
�}�_�͉p���c����Q�l��2000�N�ɓ������ꂽ���A18�N�ɓ����̗�����\�̎}��K�j���ƈ��{�����ݍ���Ȃ��c�_�̖��A�u(���_��)���j�I�g�����I�����v�Ƌ��ɒf�����B���̍ۂ��������Q���J��Ԃ��ꂽ���A�}�̊炪�ւ���Ă����x�����_�܂Ȃ��ُ͈̂킾�B
��}�̓R���i�Ɋւ��鐭�{�Ή��݂̂Ȃ炸�A����̐�����O�҂������Č����A���_�̍ޗ��ɂ��ׂ��������B
�����͈ꎞ���A�����̗}�����݂Ǝx����O�ꂷ��u�[���R���i�헪�v��ł��o�����B�u��}�͔ᔻ���邾���v�̃C���[�W�@(�ӂ����傭)�������̂Ȃ�A�����Ƃ̑Η����ɐ�������v����̕ϑJ�������ɂ��āA���ꂼ������ӔC���ʂ����ׂ��ł���B |
�������s �V�^�R���i 3�l���S 2015�l�����m�F �O�T�䁪��5���ȗ��@6/15
�����s����15���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̐��j�����80�l����2015�l�ł����B�����m�F���O�̏T�̓����j��������̂͐挎13���ȗ��ł��B
�����s��15���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���2015�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j�����80�l�����܂����B�����m�F���O�̏T�̓����j��������̂͐挎13���ȗ��ł��B15���܂ł�7���ԕ��ς́A1578.7�l�őO�̏T��86���ł����B15���Ɋm�F���ꂽ2015�l��N��ʂɌ����30�オ�ł������A�S�̂�17.9���ɓ�����360�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�147�l�őS�̂�7.3���ł��B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A14������1�l������1�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ70���90��̏���3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����1320�l�R���i�����A1�T�ԑO����324�l���@6/15
���{��15���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1320�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����324�l�������B���҂�1�l�������B
|
������A�R���i��3�l���S�@�V�K������1414�l�@�V����3��̃N���X�^�[�m�F�@6/15
���ꌧ��15���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������3�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�v���Ґ���476�l�ƂȂ����B�܂��A�V����1414�l�����������Ɣ��\�����B��T�̐��j��(8��)��1557�l�ɔ�ׂ�143�l�������B�v�����҂�23��3968�l�ƂȂ����B�܂��A�V����3��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���14�����_��584.40�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ�������������159.50�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����38.1��(���@�Ґ�245�^�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��11.7��(���@7�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����47�l�̕��������B |
�������ŐV����1��6592�l�R���i�����A����23�l�c�����̏d�ǎ҂�1�l�@6/15
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�15���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��6592�l�m�F���ꂽ�B���҂�23�l�B�d�ǎ҂͑O������8�l������53�l�ƂȂ����B
�����s�̐V�K�����҂�2015�l�ŁA�O�T�̓����j�����80�l���������B�O�T������̂�5��13���ȗ��A��1�����Ԃ�B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�1579�l�ŁA�O�T����14���������B�d�ǎ҂�1�l�A���҂�70�`90�Α�̏���3�l�B
���{�́A�O�T�̓����j������324�l������1320�l�������B
|
���a���m�ہA�[�u�Ȃ��N���@�R���i�Ή����؉�c�����@6/15
�V�^�R���i�E�C���X�Ή��̌����s�����{�̗L���҉�c��15���A�ߋ��̑Ή��܂����������I�ȉۑ�ɂ��ĕ����܂Ƃ߂��B�a���m�ۂ̎�������S�ۂ���[�u���Ȃ��������߁A�����g�厞�Ɉ�Â̕N�����������Ǝw�E�����B�f�W�^�����⍑�Y���N�`���J���̒x��Ȃǂ��ۑ�ɋ������B���{�͕����A����̊����Ǒ�ł̉��P���}���B
���ł͉ߋ��ɗ��s�����V�^�C���t���G���U�̑Ή��o�����\���ɐ��������u�����E�a���m�ۂȂǂ̕ی��E��Ò̐��̗����グ�ɑ����̍���������v�ƐU��Ԃ����B�R���i�̊����g�厞�ɂ͎w���Ë@�ւ����Ŋ��҂����ꂫ�ꂸ�A���ÂȂǂ�S����ʂ̕a�@�̒ʏ��Â𐧌����ĕa�����m�ۂ���K�v���������B
���@���҂������e��Ë@�ւ̖������S�����m�ɂ���Ă��炸�u��Ë@�ւ̋��͂�S�ۂ��邽�߂̑[�u���Ȃ������v���߂Ɉ�Â̕N�����N�����ƌ��y�����B���@�����A�~�}�����A�@���Ŋ������X�N������ꏊ�ƈ��S�ȏꏊ����u�]�[�j���O�v�Ƃ������P�������{���Ă��炸�A�̐��\�z�܂łɎ��Ԃ����������B
�����������P�܂��A�����g�厞�Ɉ�Ë@�ւ�l�ނ��I�m�ɖ�����S����悤�@�I�ȑΉ����܂߂��d�g�݂Â��肪�K�v���Ƌ��������B
�ی���Õ���̃f�W�^�����̒x�ꂪ���N�`���ڎ�⎡�ÂƂ����������ǑΉ��̐���v���ɂȂ����Ƃ��L�ڂ����B
�Ⴆ�Ί����ҏ��̎��W�Ɍ����ē��������ꌳ�Ǘ��V�X�e���uHER-SYS(�n�[�V�X)�v�̉^�p�ł́A�W�v��S���ی�������͂����Ë@�ւ̕��S�����������ߊ����g�厞�Ƀf�[�^���͂��x��鍬�����������B�d�q�J���e�Ԃ̋K�i�����ꂳ��Ă��Ȃ����ߊ��ҏ��̋��L����������_�Ȃǂ������B
���Y�̃��N�`���⎡�Ö�̐v���ȊJ�����x�ꂽ�����ɂ��G�ꂽ�B�V���Ȋ����ǂ̔������Ƀ��N�`���⎡�Ö���J���ł����Ƃ��琬���邽�߂̕�������̎��g�݂��u�s�\���������v�ƋL�����B
�V���Ȋ����ǂ����������ꍇ�ً̋}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�Ƃ������V�^�C���t���G���U�����ʑ[�u�@�Ɋ�Â��[�u�̉^�p�ɂ��Ă��ۑ���������B�R���i�Ђł͂����������������ɂȂ���[�u������������Ȃǂ��^�⎋����w�E���o�Ă����B
���ł́A����K�p����ꍇ�Ɂu���e����ԂȂǂ�K�v�ŏ����ɂ���ƂƂ��ɏ̕ω��ɉ����ď_��Ɍ��������Ƃ��d�v�ł���v�Ɩ��L�����B
|
���I�~�N�����V�h���^�BA.4��BA.5����g��A�Ċ����҂̖�20���Ɂ@6/15
�Ď��a��Z���^�[(CDC)��6��14���A�č��̐V�^�R���i�E�C���X�����ɃI�~�N�����ψي���2�̔h���^�uBA.4�v�ƁuBA.5�v����߂銄����11�����_�ł��ꂼ��8.3����13.3���ɒB�����Ƃ̐��v���������B�ʐ^�̓j���[���[�N�̃^�C���Y�X�N�G�A�̌����{�݁A2021�N12���B�e(2022�N�@���C�^�[/Andrew Kelly)
�Ď��a��Z���^�[(CDC)��14���A�č��̐V�^�R���i�E�C���X�����ɃI�~�N�����ψي���2�̔h���^�uBA.4�v�ƁuBA.5�v����߂銄����11�����_�ł��ꂼ��8.3����13.3���ɒB�����Ƃ̐��v���������B
�����͂������Ƃ���闼�h���^��3���ɐ��E�ی��@��(WHO)�̊Ď����X�g�ɒlj����ꂽ�ق��A���B�ł����O�����ψٌ^�Ɏw�肳��Ă���B
���B���a�\�h�Ǘ��Z���^�[(ECDC)��13���A���h���^�̊��������̃R���i�ψي����������y�[�X�ōL�����Ă���A�嗬�ɂȂ�Γ��@�⎀�S�Ⴊ������v���ɂȂ�Ɣ��\�����B
�~�l�\�^�B���`�F�X�^�[�̃}���E�N���j�b�N�Ń��N�`�������O���[�v�𗦂���O���S���[�E�|�[�����h���́A��A�t���J�̃f�[�^�ŗ��h���^�͉ߋ��̊�����N�`���Ŋl�����ꂽ�Ɖu���������\�͂��オ���Ă���Ƃ��A�u���Ɍ��O���Ă���v�Əq�ׂ��B
�܂��A�ߋ��̊����ƃ��N�`���ڎ�͎��S��d�lj��ɑ���\�h���ʂ����\����������̂́A�V�w���J�n��2��ڂ̒lj��ڎ�(�u�[�X�^�[�ڎ�)�̌��ʌ���ŁA�ċG�ɗ��h���^�̊������L���鋰�������Ǝw�E�����B�@ |
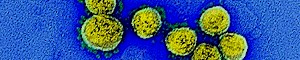 |
�������s�ŐV����1819�l�̊����m�F �O�T���j������57�l���@6/16
16���A�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�1819�l�������B�O�T�̖ؗj��(1876�l)����57�l�������B
�������m�F���ꂽ�̂́A10�Ζ�������90��܂ł�1819�l�B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�1571�l�őO�̏T��88.7���������B��T�ؗj�����_�ł̕��ς�78.3���ŁA�s�̒S���҂́u�����������������Ă��܂��Ă�����v�Ƃ̔F���������A���ς̐��ڂ𒍎����Ă����K�v������Ƙb���Ă���B�s�̊�ɂ��d�ǎ҂͑O����1�l����1�l����A0�l�������B�d�ǎ҂͂��ƂƂ�(14��)�A���ƂƂ�4��27���ɓs�����v�����n�߂Ă��珉�߂�0�l�ɂȂ��Ă��āA���傤�Ă�0�l�ɂȂ����B
���傤���_�̐V�^�R���i���җp�a���̎g�p����11.4��(574�l�^5047��)�ŁA�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�a���g�p����2.1��(9�l�^420��)������(�ǂ��������͍ő�m�ی�����)�B�܂��A90��̏���3�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
|
�����{ �V�^�R���i 1213�l�����m�F ��T�ؗj�����200�l�� �@6/16
���{��16���A�V����1213�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
��T�̖ؗj���Ɣ�ׂĂ��悻200�l����܂����B����ŁA�{���̊����҂̗v��99��5095�l�ƂȂ�܂����B�܂��A16���͖S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�15������1�l����A7�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
������1404�l�R���i�����@��T�ؗj�����51�l���@�V����2��̃N���X�^�[�m�F�@6/16
���ꌧ��16���A�V����1404�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̖ؗj��(9��)��1353�l�ɔ�ׂ�51�l�������B�v�����҂�23��5372�l�ƂȂ����B�܂��A�V����2��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ��́A15�����_��574.77�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ�������������154.06�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����38.7��(���@�Ґ�249/�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��11.7��(���@7/�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����80�l�̕��������B�@ |
 |
�������s�ŐV����1596�l�̊����m�F �O�T���j������4�l�� ���S4�l�@6/17
17���A�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�1596�l�������B�O�T�̋��j��(1600�l)����4�l����A2���A���őO�T�̓��j������������B�d�ǎ҂͑O�����瑝����0�l�B
�������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�1596�l�ŁA���̒��Ɍ��������{������t�̔��f�ɂ��Տ��f�f���ꂽ����^���NJ��҂͂��Ȃ������B����7���Ԃ�1��������̕��ς�1570.0�l�ŁA�O�T���92.5���ƂȂ��Ă���B�N��ʂł́A30�オ�ł�����318�l�A������20�オ305�l�A40�オ263�l�A10�Ζ�����225�l�ȂǂŁA65�Έȏ�̍���҂�113�l�������B�V���Ȋ����҂̂���852�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��āA1��ڎ킪19�l�A�ڎ�Ȃ���376�l�A�s����349�l�������B
���傤���_�̐V�^�R���i���җp�a���̎g�p����10.8��(545�l�^5047��)�B�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�a���g�p����1.9��(8�l�^420��)�������B�܂��A70��A80��A90��̍��킹��4�l�̎��S���m�F���ꂽ�B |
�������s�ŐV����1596�l�����A4�l���S �@6/17
�����s��17���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ�����1596�l�Ǝ���4�l���m�F�����Ɣ��\�����B�d�ǎ҂͓s�̊��0�l�B�a���g�p����10.8%�B
1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���17�����_��1570�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�92.50%�B�s���̗v�̊��Ґ���157��0038�l�ƂȂ����B�N��ʂł�10�Ζ���225�l�A10��179�l�A20��305�l�A30��318�l�A40��263�l�A50��148�l�A60��79�l�A70��43�l�A80��29�l�A90��6�l�A100�Έȏ�1�l�B65�Έȏ�̍���҂�113�l�������B���S�����̂́A70��`90��̒j��4�l�B
|
�����{�̃R���i�V�K������1125�l�A1�T�ԑO����67�l���@6/17
���{��17���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1125�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����67�l�������B���҂�2�l�������B
|
���V�^�R���i�V�K������ �S���Ō����X���� 7���͑O�T��葝�� �@6/17
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł�1�����ȏ�ɂ₩�Ȍ����X���������Ă��܂����A���k���B�̈ꕔ�Ȃ�7�̌��ł͑O�̏T��葽���Ȃ��Ă��܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S��
��^�A�x�̂��Ƃ܂ł͑������Ă��܂������A5��19���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T�ɔ�ׂ�0.97�{�A5��26����0.87�{�A6��2����0.68�{�A6��9����0.75�{�A6��16���܂łł�0.87�{�ƁA5�T�A���őO�̏T��������Ă��܂��B
1��������̕��ς̐V�K�����Ґ��́A���悻1��4234�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V�K�����Ґ��́A�����s����{�Ȃǐl���̑����n����܂߁A40�s���{���ʼn������猸���ɂȂ��Ă������ŁA��B�Ⓦ�k�̈ꕔ�ȂǁA7�̌��ł͑O�̏T��葽���Ȃ��Ă��܂��B
�������s�@/�@6��2���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.69�{�A6��9����0.78�{�A6��16���܂łł�0.89�{�ƁA5�T�A���Ō������Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻1571�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���_�ސ쌧�@/�@6��2���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.70�{�A6��9����0.72�{�A6��16���܂łł�0.84�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻717�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����ʌ��@/�@6��2���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.76�{�A6��9����0.70�{�A6��16���܂łł�0.95�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻567�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����t���@/�@6��2���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.70�{�A6��9����0.70�{�A6��16���܂łł�0.97�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ���424�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����{�@/�@6��2���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.68�{�A6��9����0.78�{�A6��16���܂łł�0.85�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻1163�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����ꌧ�@/�@6��2���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.72�{�A6��9����0.97�{�A6��16���܂łł�0.98�{�ƁA4�T�A���őO�̏T��菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1227�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ���585.15�l�ƁA�S���ōł�������Ԃ������Ă��܂��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 4�l���S 1681�l�����m�F �O�T���155�l���� �@6/18
�����s����18���̊����m�F��1�T�ԑO�̓y�j�����155�l������1681�l�ŁA�O�̏T�̓����j��������܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��18���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1681�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j�����155�l�����܂����B18���܂ł�7���ԕ��ς�1592.1�l�ŁA�O�̏T��98.3���ł����B18���Ɋm�F���ꂽ1681�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�20.1���ɂ�����338�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�97�l�ŁA�S�̂�5.8���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�17���Ɠ���0�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ80���90��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����1255�l�R���i�����c1�T�ԑO�Ɠ����@6/18
���{��18���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1255�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j���Ɠ����������B���҂�1�l�������B
|
������R���i1268�l�����@�O�T��100�l���@6/18
���ꌧ��18���A�V����1268�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓y�j��(11��)��1368�l�ɔ��100�l�������B�v�����҂�23��7857�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ��͑O�����_��563.19�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ�������������155.55�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����38.6��(���@�Ґ�248�^�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��8.3��(���@5�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B�N���X�^�[�͐V����3�Ⴊ�m�F���ꂽ�B�ČR�W�͐V����15�l�̕��������B
|
�������ŐV����1��4837�l�R���i�����c�s����1�T�ԕ��ς͑O�T����2�����@6/18
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�18���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��4837�l�m�F���ꂽ�B���҂�20�l�A�d�ǎ҂͑O������1�l����39�l�ƂȂ����B
�����s�̐V�K�����҂́A1681�l�B�O�T�̓����j������155�l�����A3���Ԃ��1�T�ԑO���������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�1592�l�őO�T����2���������B80�`90�Α�̒j��4�l�̎��S�����������B
|
����̔ɉ؊X������l�́A�R���i�O����4�������Ă���@6/18
���R���i�O�̏ɂ͖߂��Ă��Ȃ�
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̗��s�ƁA���ڂɊW���Ă���̂��A�ɉ؊X�̐l���݂ł��B�ɉ؊X�ŁA��Ԃ̑ؗ��l����������ƁA2�`3�T�Ԍ�ɐV�K�z���҂�������Ƃ����X��������̂ł��B���̂��߁A�����̔ɉ؊X�́A�V�^�R���i�E�C���X�̗��s���ɁA�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k���ނ̒֎~�Ȃǂ̋K�����J��Ԃ��܂����B���̌��ʁA�ŏ��ً̋}���Ԑ錾������2020�N4���ȗ��A��Ԃ̑ؗ��l���́A�R���i�O��2019�N��������Ԃ������Ă��܂��B2022�N6���ł��A2019�N�̓��������ɔ�ׂ�ƁA4�����}�C�i�X�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂾ���A��̔ɉ؊X�ɏo������l�������Ă��܂����̂ł��B
���K��������́A�����������Ă���
�������A�Z���I�Ɍ���ƁA��Ԃ̑ؗ��l���͑����Ă��܂��B�Ŋ��̋K�����������ꂽ2022�N3�����{�ƁA6�����{���ׂ�ƁA�ǂ̎��ԑт��l�������܂����B���ɁA���H�̎��ԑтł���u18������24���v�Ō���ƁA6�����{��3���������Ă��܂��B�R���i�O��菭�Ȃ��Ƃ͂����A�u�ً}���Ԑ錾�v��u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ȃǂ̋K���������������ɔ�ׂ�ΐl���߂��Ă��Ă��邱�Ƃ�������܂��B
���܂����s�͏I����Ă��Ȃ�
�j���[�X�Ŏ��グ���ɂ����Ȃ����Ƃ͂����A�܂��V�^�E�C���X�����ǂ̗��s���I������킯�ł͂���܂���B���݂��A�����ł́A�V�^�E�C���X�����ǂ̗z���҂Ǝ��҂��A�����������Ă��܂��B���̂Ƃ���A�V�K�z���҂́A�O�̏T��7�`8���Ɍ����Ă��܂����A�܂����f�͂ł��܂���B�ł��邾���A�l���݂�A�Ζʂł̈��H������A���Ӑ[�������𑗂��Ă��������B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 4�l���S1622�l�����m�F �O�T���j���76�l�� �@6/19
�����s����19���̊����m�F��1�T�ԑO�̓��j�����76�l������1622�l�ŁA�O�̏T�̓����j��������܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s�́A19���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1622�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����76�l�����܂����B19���܂ł�7���ԕ��ς́A1603.0�l�ŁA�O�̏T��99.3���ł����B19���A�m�F���ꂽ1622�l��N��ʂɌ���ƁA30�オ�ł������A�S�̂�17.1���ɂ�����277�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�110�l�ŁA�S�̂�6.8���ł��B
�܂��A����܂ł̓s�̊�ŏW�v�����l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�18���Ɠ���0�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ60���70��A�����90��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 1�l���S �V����883�l�����m�F �@6/19
���{��19���A�V����883�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����ŕ{���̊����҂̗v��99��8358�l�ƂȂ�܂����B�܂�1�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l��5103�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�18������ς�炸8�l�ł��B
|
������R���i1268�l�����@�a���g�p38���@��ÎҌ������~�܂�@6/19
���ꌧ��18���A10�Ζ�������100�Έȏ��1268�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�܂��A5���ɓߔe�s���̎Љ���{�݂Ōv45�l����������Ȃǂ̃N���X�^�[(�����ҏW�c)3�������B18���̊����҂̂����A�N��ʂł͍ő���10���263�l�ŁA������10�Ζ�����204�l�A30�オ203�l�ȂǁB���@���҂�248�l�ŁA���S�̂̕a���g�p����38�E6���B����ʂ͖{��45�E6���A�{��3�E0���A���d�R6�E8���ƂȂ��Ă���B�{�ݓ������ɂ�茧���{�����x���ɓ����Ă���Љ���{�݂͌v67�J���ŁA�{�ݓ��×{�҂Ȃǂ͍���Ҏ{��61�J����250�l�A�Ⴊ���Ҏ{�݂�6�J����3�l�ƂȂ��Ă���B����Ҏ{�݂ł�7�l���_�f���^���Ă���Ƃ����B
�d�_��Ë@�ւŊ����Ȃǂɂ�錇�Ύ҂�388�l�B6���͐V�K�����҂̍��~�܂�ɘA�����āA��Î҂̌���350�l�ȏオ�����Ă���B�ČR�W�̊�����15�l�������B
|
���S���̐V�K�����ҁA1��3160�l�m�F�@�O�T����200�l���@6/19
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�19���A�S���ŐV����1��3160�l�m�F���ꂽ�B�O�T�̓��j�������200�l�������B���҂�10�l�B�d�ǎ҂͑O�����2�l����41�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�1622�l�ŁA�O�T�̓����j����2���A���ŏ������B�ȖƎR���̗����ʼnߋ��ɔ��\���ꂽ�����҂���艺����ꂽ�B�@ |
 |
�������s�ŐV����1076�l���� �@6/20
�����s��20���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ�����1076�l���m�F�����Ɣ��\�����B�d�ǎ҂͓s�̊��0�l�B�a���g�p����11.2%�B
�V���Ȋ����҂̂����A�����������Ɉ�t�̔��f�ŗz���Ƃ݂Ȃ��u����^���NJ��ҁv(�݂Ȃ��z����)��1 �l�B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���20�����_��1619.6�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�100.8%�B�s���̗v�̊��Ґ���157��4417�l�ƂȂ����B�N��ʂł�10�Ζ���142�l�A10��170�l�A20��187�l�A30��191�l�A40��184�l�A50��102�l�A60��52�l�A70��25�l�A80��15�l�A90��7�l�A100�Έȏ�1�l�B65�Έȏ�̍���҂�69�l�������B
|
�������s �V�^�R���i 1076�l�����m�F 3���A���őO�T���� �@6/20
�����s����20���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̌��j�����116�l����1076�l�ŁA3���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
�����s��20���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1076�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j�����116�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�3���A���ł��B20���܂ł�7���ԕ��ς�1619.6�l�ŁA�O�̏T��100.8���ł����B7���ԕ��ς��O�̏T������̂́A���悻1�����O�̐挎18���ȗ��ł��B20���Ɋm�F���ꂽ1076�l��N��ʂɌ���ƁA30�オ�ł������A�S�̂�17.8���ɓ�����191�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�69�l�ŁA�S�̂�6.4���ł��B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�19���ɑ����A���܂���ł����B���S���m�F���ꂽ�l�̔��\�͂���܂���ł����B
|
�����{ �V�^�R���i �V����394�l�����m�F �@6/20
���{��20���A�V����394�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����ŕ{���̊����҂̗v��99��8752�l�ƂȂ�܂����B�܂��A20���͖S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�19������1�l������7�l�ƂȂ�܂����B
|
������̐V�^�R���i�@�l����̐V�K�����ҁ@�S���ő������@6/20
���ꌧ��19���A�V����10�Ζ�������90��̒j��1012�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�O�̏T�̓��j����1126�l����114�l�������B�v�����҂�23��8869�l�ƂȂ����B
�V�K�����҂̔N��ʓ���́A��������10�Ζ���204�l�A10��172�l�A40��150�l�A30��149�l�B����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ��͖�549�l�őS���ő��������B�O�����_�̑S�����ς͖�78�l�������B���@����251�l�ŁA��������̏d�ǂ�2�l�B�h���{�ݗ×{����575�l�A����×{����8752�l�B�a���g�p���͖{��45�E6���A�{��4�E5���A���d�R4�E5���ŁA���S�̂ł�39�E0���ƂȂ��Ă���B
����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���O�T�Ɣ�r�����u�O�T��v��0�E93�{�ŁA1�{��������Ă���B�V�KPCR�����̗z������14�E5���B�ČR��n���̐V�K�����Ґ��ɂ��Ă͏����Ȃ������B
|
�������ŐV����7800�l�R���i�����c�d�ǎ҂͑O���ƕς�炸41�l�@6/20
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�20���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����7800�l�m�F���ꂽ�B���҂�13�l�A�d�ǎ҂͑O���Ɠ���41�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�1076�l�B�O�T�̓����j������116�l�����A3���A����1�T�ԑO���������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�1620�l�łقړ��������������B�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i �V����1963�l�����m�F 4���A���őO�T���� �@6/21
�����s����21���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̉Ηj�����435�l����1963�l�ŁA4���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
�����s��21���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1963�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj�����435�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�4���A���ł��B21���܂ł�7���ԕ��ς́A1681.7�l�ŁA�O�̏T��107.3���ł����B21���Ɋm�F���ꂽ1963�l��N��ʂɌ���ƁA30�オ�ł������A�S�̂�18.0���ɂ�����354�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�160�l�őS�̂�8.2���ł��B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�20���ɑ����A���܂���ł����B���S���m�F���ꂽ�l�̔��\�͂���܂���ł����B |
�����{�ŐV����1511�l�̐V�^�R���i�����ҁc�v100���l����@6/21
���{��21���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1511�l�m�F����A�v��100���l�����Ɣ��\�����B���҂�3�l�������B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����1421�l�����m�F �@6/21
���ꌧ��21���A�V����1421�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A���킹��24��712�l�ɂȂ�܂����B
|
�������ŐV����1��5384�l�R���i�����A����17�l�c�d�ǎ҂�7�l����34�l �@6/21
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�21���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��5384�l�m�F���ꂽ�B���҂�17�l�A�d�ǎ҂͑O������7�l����34�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�1963�l�ŁA�O�T�̓����j������435�l�������B1�T�ԑO������̂́A4���A���B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�1682�l�ŁA�O�T����7�����ƂȂ����B
���{�ł�1511�l�̊������������A�{���̊����҂͗v��100���l�����B |
�����Ɂ@�u�܂h�~�v��������3�J���A�����҂�3���Ɍ����@�y�[�X�͓݉��@6/21
�V�^�R���i�E�C���X��̂܂h�~���d�_�[�u����������Ă���A22����3�J���B���Ɍ��ł͐V�K�����Ґ��̌������x���݂����B����1�T�Ԃς���1��������̊����Ґ��́A��������3�����x�ƂȂ��550�l�܂Ō��������A�����ɗ���3���A���Ŕ����B�_�ˎs�ł̓I�~�N�������̐V���Ȕh���^���������Ŋm�F����Ă���A���s�Ȃǂ��x�������߂Ă���B
�����ł�1��27���ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����A1�T�ԕ��ϊ����Ґ���2��10���A�s�[�N�̖�5600�l�ƂȂ����B���@���҂͐�l�A����×{�҂�5���l�����ꂼ�꒴�����B
���̌�A�����҂̌����������A3��22���ɓ��[�u���������ꂽ�B�S�[���f���E�C�[�N��ɂ�������������A�Ăь����B����1���A��l����������B
����A3�����{�ȍ~�̓I�~�N�������̔h���^�u�a�`�E2�v���嗬���������A�ŋ߂͂�����������͂������u�a�`�E5�v�Ɓu�a�`�E2�E12�E1�v���A�_�ˎs���ő������Ŋm�F����Ă���B
�ŋ߂̌����݉��ɂ��āA���s���N�ǂ̒S���҂́u�����͂킩��Ȃ����A��ɐV���Ȕh���^���m�F���ꂽ�����ő����̒���������A����̌X���𒍎�����B�u������肪�i�߂Ċg������O�����̂ŁA��{�I�Ȋ�����͑����Ă��炢�����v�Ƃ��Ă���B |
���R���i�Ή��u�S�Ă͌��ł����v�@���{��c��������@6/21
�V�^�R���i�E�C���X�Ή��������Ă������{�̗L���҉�c�̉i��ǎO����(������ȑ�w�w⻑)��21���A�s���ŋL�҉���J�����B15���ɂƂ�܂Ƃ߂����ɐ旧�c�_�ŁA���{�̎i�ߓ��@�\�̂�����𒆐S�ɋc�_�����Ɩ��炩�ɂ����B�������킸��1�J���قǂŏI��������ɂ��āu�S���̌��͂ł��Ȃ��Ǝv���Ă����v�Əq�ׂ��B
����c��5���̏�����܂߂Čv5��J�Â��A6��15���ɕ����Ƃ�܂Ƃ߂��B���͕a���m�ۍs�\���ŁA�����g�厞�Ɉ�Â̕N�����������_�Ȃǂ��莋�����B�i�䎁�́u�S��������ɂ͉��N��������A����������ȑg�D���K�v���v�Ƒi���A�����̉ۑ萮�����ړI�������Ƃ̍l�����������B
�����������ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�Ƃ��������{�̑Ή��ɂ��Ă��c�_�͐s������Ȃ������Ƃ̌������q�ׂ��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1�l���S 2329�l�����m�F 5���A���O�T���� �@6/22
�����s����22���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̐��j�����314�l����2329�l�ŁA5���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��22���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2329�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j�����314�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�5���A���ł��B22���܂ł�7���ԕ��ς�1726.6�l�ŁA�O�̏T��109.4���ł����B22���m�F���ꂽ2329�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�20.6���ɂ�����480�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�187�l�őS�̂�8.0���ł��B
�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�21���ɑ����A���܂���ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ60��̏���1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
��5���A���őO�T�����j��������@�����̃R���i�����ҁ@6/22
�����s��22���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�V����2329�l�m�F�����Ɣ��\�����B1�T�ԑO�̓����j��(15��)����314�l�������B�O�T������̂�5���A���B22���܂ł�1�T�ԕ��ς̊������݂�ƁA1��������̊����Ґ���1726�E6�l�ŁA�O�T(1578�E7�l)��109�E4%�������B60�㏗���̎��S�����\���ꂽ�B
�a���g�p����12�E1%�B�s��30�`40%�ŋً}���Ԑ錾�̗v���f����w�W�Ƃ��Ă���d�ǎҗp�a���g�p����2�E4%�������B�u�l�H�ċz�킩�̊O�����^�l�H�x(ECMO�q�G�N���r)���g�p�v�Ƃ���s��̏d�ǎҐ���7���A���Ń[���������B
|
�����{ �V�^�R���i �V����1414�l�����m�F�@6/22
���{��22���A�V����1414�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����A���{�́A���Ƃ�2��1����2���A�����3���ɔ��\����3�l�ɂ��āA�d�����������Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��100��1673�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�21���ƕς�炸7�l�ł��B
|
���V�^�R���i ���̊����@6/22
��2�{4���ŁA22���ɔ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂́A���킹��2898�l�ł����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�90�l�قǑ����Ă��܂��B
�{���ʂł́A��オ1414�l�A���ɂ�676�l�A���s��346�l�A���ꂪ201�l�A�ޗǂ�159�l�A�a�̎R��102�l�ł����B��2�{4���̊����҂̗v�́A188��1793�l�ƂȂ�܂����B
�܂��A���ɂ�3�l�A���s��1�l�̎��S�����\����A��2�{4���ł���܂łɖS���Ȃ����l�́A8822�l�ƂȂ��Ă��܂��B�ŐV�̏d�ǎ҂́A��オ7�l�A���ɂ�4�l�A�ޗǂ�2�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
������1580�l�R���i�����@��T���j�����166�l���@6/22
���ꌧ��22���A�V����1580�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̐��j��(15��)��1414�l�ɔ�ׂ�166�l�������B�v�����҂�24��2292�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���21�����_��549.32�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ����F�{����161.32�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����40.6��(���@�Ґ�261�^�a����643)�ŁA�d�ǎҗp��11.7��(���@7�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����15�l�̕��������B
|
�������̃R���i�V�K����1��7285�l�c�����s��1�T�ԕ��ς�9�����@6/22
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�22���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��7285�l�m�F���ꂽ�B���҂�15�l�ŁA�d�ǎ҂�36�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�2329�l�B�O�T�̓����j������314�l�����A1�T�ԑO��5���A���ŏ������B�s�ɂ��ƁA����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�1727�l�ŁA�O�T����9���������B
���{�ł͐V����1414�l�̊������������A�O�T�̓����j������94�l�������B���҂͂��Ȃ������B |
 |
�������A�R���i�����Ґ������~�܂�@�C���t���G���U���s���x�� �@6/23
�����s��23���A�V�^�R���i�E�C���X�̃��j�^�����O��c���J�����B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ�(22�����_)���O�T���110����5�T�ԂԂ�ɑ����������Ƃɂ��āA�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���ۊ����ǃZ���^�[���́u���o�E���h�̒���Ƃ������A�����~�܂����ƕ��͂���B����̓����ɒ��ӂ��K�v���v�Ǝw�E�����B
��c�ł́A�s���̌������w�Z��21�A22���ɃC���t���G���U�ɂ��w�N�����������ق��A�I�[�X�g�����A�ł�3�N�Ԃ�ɗ��s���Ă�������ꂽ�B���r�S���q�m���́u���ւ̗v�]�ƂƂ��ɁA�s�Ƃ��Ă���̓I�ȑ�𑁋}�Ɏ��܂Ƃ߂����v�Əq�ׂ��B
|
�������s �V�^�R���i 1�l���S 2413�l�����m�F 6���A���O�T���� �@6/23
�����s����23���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̖ؗj����肨�悻600�l����2413�l�ŁA6���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��23���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2413�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̖ؗj����肨�悻600�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�6���A���ł��B23���܂ł�7���ԕ��ς́A1811.4�l�ŁA�O�̏T��115.3���ł����B23���Ɋm�F���ꂽ2413�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�21.4���ɂ�����516�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�180�l�őS�̂�7.5���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A22���͂��܂���ł������A23����1�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ80��̒j��1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�������s�E�R���i�����Ґ��̕��ς�5�T�ԂԂ�ɑ����@�u�Ԃ�Ԃ�����v�@6/23
�����s�́A���傤�ߌ�A�V�^�R���i�E�C���X��Ɋւ�����Ɖ�c���J���A�V�K�����Ґ���7���ԕ��ς��A5�T�ԂԂ�ɑ����ɓ]�������Ƃ𖾂炩�ɂ����B
�����s�ɂ��ƁA����15�����_�̐V�K�����Ґ���7���ԕ��ς�1542�l�������̂ɑ��āA���̂����_�ł�1698�l�ɂ̂ڂ����Ƃ����B����1�T�ԂŁA���悻1�����������ƂɂȂ�B��ނɑ��āA�����s�̊W�҂́u�����g�傪�A�Ԃ�Ԃ�����v�Ƃ̌����������Ă���B
�����҂ɐ�߂銄����N��ʂɌ���ƁA20�オ18.3���ƍł������A������30�オ18.2���������B30��ȉ����A�S�̂�64.8�����߂Ă���Ƃ����B�ߋ��̊����g�厞�́A�܂���N�w�Ɋ������L����A���̌�A�����N�w�ɔg�y�����Ƃ���A�����s�́A���������A�x�����Ăт������B
�܂���c�ł́A���݁A�嗬�ƂȂ��Ă���I�~�N�������uBA.2�v���������͂������\��������uBA.5�v���A�S�̂�13�����߂��Ƃ̃f�[�^���o���ꂽ�B���Ƃ���́u�ψي����܂߁A����̓����ɒ��ӂ���K�v������v�Ƃ̌x������������܂����B
�s���ł́A�������w�Z�ŁA���V�[�Y�����߂ẴC���t���G���U�ɂ��w�N���̕��������B���̎��Ԃ��ē����s�́A�C���t���G���U�ƃR���i�́h���������h�ƂȂ�Ȃ��悤�A�\�h�Ƒ�����߂ēO�ꂷ��悤�A���ӊ��N�����Ă���B |
�����ŐV����1248�l�̊����m�F�@������3�l�����S�@�V�^�R���i�@6/23
���{��23���A�V����1248�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B��T�̖ؗj���̊����Ґ��́A1213�l�ł����B����������1��3877���ŁA�z������8.8���ł����B���{���ł́A������3�l�̎��S���m�F����܂����B
|
������A���傤�̐V�K������1542�l�@�O�T����138�l������@6/23
���ꌧ��23���A�V����1542�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B��T�̖ؗj��(16��)��1404�l�ɔ�ׂ�138�l�������B�v�����҂�24��3834�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�z���Ґ���22�����_��560.49�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ����F�{��160.75�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����42.6%(���@�Ґ�:269/�a����:631)�ŁA�d�ǎҗp��11.7%(���@�Ґ�:7/�a����:60)�ƂȂ��Ă���B�ČR��n���̐V�K�����Ґ���46�l�������B
|
�����̊����ǂɂ��x���K�v�@6/23
���ꌧ�͈�ÂƉ��̘A�g�ň�Õ����h���ł����B�����g��̑�7�g�̃R���i�a���g�p���́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�\���̖ڈ��ƒ�߂�60%�ȉ���ۂ����B�����N���X�^�[(�����ҏW�c)�����̍���Ҏ{�݂ȂǂɈ�ÃX�^�b�t��h�����A���n�ň�Â���Ă�����ʂ��傫���B
�����A�ˑR�Ƃ��ăR���i���҂������d�_��Ë@�ւ̕��S�͑傫���B1��������V�K�����Ґ������~�܂肵�A6���ȍ~����������Ȃ���t��Ō�t����300�l��㔼�̍��������Ő��ڂ��Ă��邽�߂��B
�k���n���t��a�@(����s)�ċz��E�����ljȂ̓c������t�́u�[���R���i���O��̈�Âƌo�ς̃M���b�v���傫���B�E���w�Z�ŔZ���ڐG�҂�ǐՂ��Ȃ��̂Ɠ��l�A�a�@�̑Ή��ɘa���Љ�I�ȃR���Z���T�X������K�v������v�Ɛ����B
�o�ύĊJ�ɍ��킹�A���̊����ǂւ̔������������Ȃ��B�I�[�X�g�����A�ł̓C���t���G���U���҂��}�����A�R���i�Ɠ������s���Ă���B������Q�^�̍��R�`�_��t�́u���̓R���i�ƃC���t���̓������s�ɍ���������Ă����ׂ����v�Ƃ̔F���������B�@ |
���S���ŐV����1��6676�l���R���i�����@3���A���őO�T����@6/23
�V�^�R���i�E�C���X�̍��������Ґ���23���A�ߌ�7�������݂ŐV����1��6676�l���m�F���ꂽ�B�O�̏T�̓����j��(16��)���1165�l�����A3���A���őO�T���������B���҂�15�l�������B
�s���{���̐V�K�����Ґ����ő������������s��2413�l���m�F����A�O�T�̓����j�����594�l�����A6���A���őO�T���������B
�s���{���̐V�K�����Ґ��́A�����Ɏ����ʼn��ꌧ(1542�l)�A���{(1248�l)�A���m��(914�l)�̏��ő��������B
|
���u�����̒���������n����v�@�V�^�R���i�A���J�Ȑ��Ƒg�D�����́@6/23
�V�^�R���i�E�C���X��������J���Ȃɏ���������Ƒg�D(�A�h�o�C�U���[�{�[�h)��23���A�V�K�����Ґ��̌������S���I�ɓ݉����Ă���ƕ��͂����B��^�A�x������5�����{����S���I�Ɍ����X���������Ă������A����1�T�Ԃ̐V�K�������͎�s�����B�Ȃ�20�s�{���őO�T��葝�������B
�����̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂�22�����_�ŁA�O�T��0�E98�{�Ɖ����~�܂�̌X�������܂����B���Ƒg�D�́A��s�s�ŒZ���I�ɋ}���ȑ����͌����܂�Ă��Ȃ����̂́A���N�`���ڎ�Ɗ����ɂ��Ɖu�����X�ɒቺ���Ă������Ƃ�I�~�N���������V���Ȍn���ɒu�������\�������邱�Ƃ���A�u����͊����Ґ��̑��������O�����v�Ƃ̌������������B
�s���{���ʂł́A�������őO�T��2�E85�{�Ɗ����҂��}�������B�O�T�䂪1�E1�{�����̂́A��������2�E85�{�A���挧��1�E34�{�A�X���ƕ�������1�E16�{�̂ق��A�x�R���A�F�{���A�_�ސ쌧�B�����s��1�E09�{�������B46�s���{���őO�T�䂪��������2�T�ԑO�̉���_�����]���āA�����X���������s���{�����������B
���Ƒg�D�����̘e�c�����E���������nj��������́A�ꕔ�s�{���̊��������ɂ��āA�Ɖu�̒ቺ��s���̊������ɂ��ڐG�@��̑������e�����Ă��邱�Ƃ���ȗv���ɂ������B
����ŁA�I�~�N�������́uBA.5�v�n���������Łu������x���o����Ă���v�Ǝw�E�B�C�O�̊�������A�d�Ǔx�̏㏸�݂͂��Ȃ����̂́A�u������肪�i�ނ��Ƃɂ���Ċ����Ґ�����@�Ґ��������グ��\���Ɍx�������������B
����ɘe�c�����́A�u���܂��������x���͍����������A�ꕔ�̒n��ʼn����A�����̒�����������n�悪����v�Ƃ��āA���N�`���ڎ�⊴���h�~��̌p�������߂��B
|
���R���i���Ɖ�g�����Ґ� ���������݉� ����͑��������O�h�@6/23
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ��ď�����������J���Ȃ̐��Ɖ���J����A�S���̊����Ґ��͌��������݉�������Ƃ��������ŁA���N�`���ڎ�Ȃǂœ���ꂽ�Ɖu�̌��ʂ��������Ă������ƂȂǂ���A����͊����Ґ��̑��������O�����Ǝw�E���܂����B
���Ɖ�́A���݂̊����ɂ��đS���ł͌����X���������Ă�����̂̌��������݉�������A��������̒�����������n�������Ƃ��Ă��܂��B
�܂��A�l��������̊����Ґ����S���ōł��������ꌧ�ł����������A�������Ă���Ƃ��č���̊����̓����ɒ��ӂ��K�v���Ƃ��Ă��܂��B
��s�s���ɂ��Ă̒Z���I�ȗ\���ł͋}���ȑ����͌����܂�Ă��Ȃ����̂́A3��̃��N�`���ڎ�₱��܂ł̊����ɂ���ē���ꂽ�Ɖu�̌��ʂ����X�ɉ������Ă������Ƃ�A�����ȍ~�͉ċx�݂̉e���������Đl�Ƃ̐ڐG�@������邱�ƁA����ɃI�~�N�������́uBA.4�v��uBA.5�v�Ȃǂ������ł����o�����ȂǁA�V���Ȍn���ɒu��������Ă����\�������邱�Ƃ��獡��A�����Ґ��̑��������O�����Ƃ��Ĉ�Ñ̐��ւ̉e���Ȃǂ𒍎�����K�v������Ǝw�E���܂����B
���̂����ŁA���Ɖ�̓��N�`����3��ڂ̐ڎ������ɐi�߂�ƂƂ��ɁA�����ł��̒���������ΊO�o���T���邱�ƁA�s�D�z�}�X�N�̐��������p�A��A1�̖��ł�������Ƃ�������{�I�Ȋ������O�ꂷ�邱�ƂȂǂ��Ăт����܂����B
�܂��A��Â���̌���ł́A�{�݂̎���ɍ��킹�Ė����̂Ȃ���������l���邱�Ƃ��d�v�ŁA��앟���{�݂ł͍���҂̏d�lj���\�h���邽�߂ɁA�����҂ւ�4��ڂ̃��N�`���ڎ��i�߂�悤���߂܂����B
��1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ� �S���ł͌����X�����牡���ɓ]����
�����J���Ȃ̐��Ɖ�Ŏ����ꂽ�����ɂ��܂��ƁA22���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑S���ł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�0.98�{�ƁA����܂ł̌����X�����牡���ɓ]���Ă��܂��B
��s����1�s3���ł́������s�ƍ�ʌ���1.09�{�A���_�ސ쌧��1.12�{�A����t����1.08�{�Ƒ����ɓ]���܂����B
���ł́����{��0.93�{�A�����Ɍ���0.94�{�A�����s�{��1.00�{�Ƃقډ����̌X���A���C�ł́����m����0.95�{�A������0.69�{�A���O�d����1.04�{�ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A���k�C����0.82�{�A���{�錧��0.86�{�A���L������0.82�{�A����������0.99�{�A���l��������̊����Ґ����ł��������ꌧ��0.98�{�ȂǂƉ�������ɂ₩�Ȍ����ƂȂ��Ă��܂��B
����A����������2.85�{�A�����挧��1.34�{�A���X���ƕ�������1.16�{�ȂǂƁA19�̓s���őO�̏T��葝�����Ă��܂��B
����A�l��10��������̒���1�T�Ԃ̊����Ґ��́A�����ꌧ��567.23�l�ƑS���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
�����Ł��F�{����162.63�l�A������������149.47�l�A�����ꌧ��131.12�l�A���X����119.31�l�A�����ā����{��88.20�l�A�������s��86.04�l�A�ȂǂƂȂ��Ă��āA���S���ł�78.15�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���e�c���� �g�C���t���G���U ����̓����𒍎�����K�v����h
�����J���Ȃ̐��Ɖ�̂��Ƃ̋L�҉�Ře�c���� �����́A�����s���̏��w�Z�ŃC���t���G���U�ɂ��w�N���ƂȂ�A���ƂƂ�3���ȗ��ƂȂ�Վ��x�Ƃ��s��ꂽ���Ƃɂ��āu�씼���̃I�[�X�g�����A�ŃC���t���G���U�������Ă���Ƃ���������B2�N�ԁA�V�^�R���i�̗��s�ɂ���ăC���t���G���U�̗��s���قڂȂ��ŁA�C���t���G���U�ɑ���Ɖu���R���i�ȑO�Ɣ�ׂ�Ɨ����Ă��邱�Ƃ͏\���ɍl�����邽�߁A�������s����ƍL����\�������邩������Ȃ��B�����ł͒ʏ�~�ɂ����ė��s���A�܂����̎����ł͂Ȃ����A����̓����𒍎�����K�v������v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A���{�����������nj������ƍ������ۈ�Ì����Z���^�[�����A�A�����J��CDC�����a��Z���^�[�̓��{�ł�n�݂��邱�Ƃ����߂����Ƃɂ��āu���������g�D�𗧂��グ�邱�ƂȂǂ�ʂ��āA����̊����Ǒ��i�ނ��Ƃ����҂ł��邪�A���e�Ɋւ��Ă͍���c�_����Ă������̂��ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
|
�����ōĂуR���i�����̔g�A�I�~�N�����h���^���g�偁���ǎҁ@6/23
�t�����X�̃��N�`���ڎ�헪�����܂Ƃ߂�Ɖu�w�҂̃A�����E�t�B�V�F����22���A�O���̐V�^�R���i�E�C���X�����҂���2�J���Ԃ��9��5000�l���ɒB���钆�A�V���ȕψي��g����Ăъ����̔g�ɒ��ʂ��Ă���Əq�ׂ��B
�t�����X2�e���r�ŁA�����Ŋ������Ăъg�債�Ă��邱�Ƃ͋^���Ȃ��Ǝw�E�B�l�I�ɂ͌����A���@�ւł̃}�X�N���p�`�����Ăє�������̂��D�܂����ƍl����Ƃ��A�u���͂��̔g���ǂ̒��x���͂����v�Əq�ׂ��B
���B�ł̓|���g�K���𒆐S�ɑ����ł��I�~�N�����ψي���2�̔h���^�u�a�`�D4�v�Ɓu�a�`�D5�v�ɂ�銴���g�傪�����Ă���B���B���a�\�h�Ǘ��Z���^�[(�d�b�c�b)�ɂ��ƁA����2�͓��n��Ŏ嗬�ɂȂ���Z���傫���Ƃ݂��Ă���B
�t�����X�ł́A5�����ȍ~�V�K�����҂������B7���Ԃ̈ړ����ς�5��27����1��7705�l����6��21����5��0402�l�ɖ�3�{�����Ă���B�����A�N���ɋL�^����36��6179�l�͑傫��������Ă���B
|
�����B�ŐV�^�R���i�̐V���Ȕg�A�����͋����ψٌn�����嗬�Ɂ@6/23
���B�ŐV�^�R���i�E�C���X�̏Ǘᐔ���}�����Ă���B�����͂̋����I�~�N�������̕ψٌn���̊����g�傪�����Ƃ���A�R�̒l�̒ቺ��Ă̗��s�V�[�Y�������ɔ����A���E�I�����̐V���Ȕg�ɑ���x���������܂��Ă���B
���B���a�\�h�Ǘ��Z���^�[(�d�b�c�b)�͐�T�A�I�~�N�������̕ψٌn���u�a�`�D4�v�Ɓu�a�`�D5�v�����B�A��(�d�t)�����Ŏ嗬���ɂȂ�A�Ǘᐔ���}������Ƃ̌��ʂ��������Ă����B
�ăI�b�N�X�t�H�[�h��w�̂n�v�h�c�v���W�F�N�g�ɂ��ƁA�����Ґ��̓|���g�K���A�h�C�c�A�t�����X�A�M���V���A�I�[�X�g���A�A�C�^���A�A�X�C�X�A�X�y�C���Ȃǂ̊e���ő����Ă���B
�I�~�N�������̉��ʌn���a�`�D4�Ƃa�`�D5�́A����܂ł̌n�����������͂������A�Ɖu�����킷�\�͂��������Ƃ������Ŏ�����Ă���B�܂�A�ߋ��̊��������N�`���ڎ���A���������n���̊�����h�����ɂ͗����ɂ����B
�����A�a�`�D4�Ƃa�`�D5�͏d�lj��ɂ͌��т��ɂ����Ǝv����B����ł��Ǘᐔ��������Γ��@���҂⎀�҂�������\��������B
�|���g�K���ł͂a�`�D5�̉e���ŐV�^�R���i�̊����҂��}���B21���̎��_�ʼnߋ�7���Ԃ̐V�K�Ǘᐔ��1���̕��ς�100���l������1332��ɒB���A���E��5�Ԗڂɑ��������B�h�C�c��760��A�t�����X��747��ƂȂ��Ă���B
�|���g�K���̓��@�Ґ���1896�l�ƂȂ�A���N1���ɃI�~�N�������̊������g�債�����̏�Ԃɋ߂Â����B
�t�����X�ł�100���l������̐V�K�Ǘᐔ���������߈ȗ��A3�{�߂��ɑ����A���@�Ґ���4�����{�ȗ��A���߂đ����ɓ]���Ă���B
�p���ł��Ǘᐔ����@�Ґ����}���B17���ɍ��Ɠ��v�ǂ����\�����ŐV���v�ɂ��ƁA�����Ґ��͑O�̏T�ɔ�ׂ�43�����������B
|
���u�V�ψي��͊����͎���Ŋg��̉\���v ���� �u���㉺���~�܂���v�@6/23
�V�^�R���i�̐V�K�����Ґ��͍���͂ǂ��Ȃ�̂��AAI���l�H�m�\�ɂ�镪�͂Ő��Ƃɗ\�����Ă��炢�܂����B
���É��H�Ƒ�w�̕��c�W�������́A�u�l���v��u�C��v�A�uSNS��̃L�[���[�h�v�Ȃǂ̃f�[�^��AI�ŕ��͂��A�V�^�R���i�̊����Ґ���\�����Ă��܂��B
���݁A�����Ґ��͗��������Ă���悤�ɂ݂��܂����c�B
���c�����u(�����Ґ���)����܂ŏ����ɉ������Ă�����ł����A���ꂩ�牺���~�܂肷��\��������܂��v
���c�����ɂ�铌���s�̐V�K�����Ґ���AI�\���B���ݎ嗬�̃I�~�N������BA.2�n���������Ƃ����ꍇ�̂��̂ŁA�����~�܂�̗v���ƂȂ�̂��u�~�J�v���ƌ����܂��B
���c�����u���C���~�J���G�ɂȂ��ď��X�����Ȃ��Ă���B�������������Ƃ���A���X�ɉ�����ɂ����Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��v
�܂��A���~�Ȃljċx�݊��Ԓ��ɐl�̈ړ��������ɂȂ邱�ƂŁA8�����{�ȍ~�͑����ɓ]����\��������Ƃ��Ă��܂��B
�l���̑����ȏ�ɕ��c�������x����炷�̂��u�V�����ψي��v�ł��B
���c�����uBA.4�ABA.5�ƌ����Ă��܂����A�V�����ψي��������Ă��āA���̊����͂������ꍇ�ɂ́A���Ȃ�g�傷��\��������܂��v
�I�~�N�������́uBA.4�v�uBA.5�v�n���B��A�t���J�ł́uBA.2�v�n������̒u���ς�肪�i��ł��āA�����g��̃X�s�[�h�������\�����w�E����Ă��܂��B
�����ł͍��N4���A�uBA.4�v�n���ƁuBA.5�v�n���Ɋ��������l�����߂ċ�`�̌��u�Ŋm�F����܂����B
���c������AI�\���ł́A�uBA.2�v�n����1.2�{�̊����͂Ɖ��肵�āuBA.4�v�n�����L�܂����ꍇ�A�����ł�7���ɓ����čĂы}���ɑ������A�����ɂ�1���l��˔j�B���̌��8����{�܂ő��������A���̂܂�9�����܂ō��~�܂肷��Ƃ��Ă��܂��B
Q.�ψي��ւ̒u�������́A�����Ґ��ɑ傫���e�����y�ڂ��̂��H
���c�����u�����͂����ł͂Ȃ��āA���̓Ő���������x�����ƌ����Ă��܂��B�V�����ψي��͂ǂ�Ȃ��̂��o�Ă��邩������܂���̂ŁA�������炭�x�����Ă������ق����A�O�ɂ͔O�����ĂƂ��������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��v�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 2181�l�����m�F 7���A���O�T���� �@6/24
�����s����24���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̋��j�����580�l�]�葽��2181�l�ŁA7���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��24���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł�2181�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j�����585�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�7���A���ł��B24���܂ł�7���ԕ��ς́A1895.0�l�ŁA�O�̏T��120.7���ł����B24���m�F���ꂽ2181�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�22.0���ɂ�����480�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�149�l�őS�̂�6.8���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A23�����1�l������24����2�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ80��̏���2�l�����S�������Ƃ\���܂����B |
�����{ �V�^�R���i �V����1365�l�����m�F�@9/24
���{��24���A�V����1365�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA240�l�����܂����B����A���{�́A����܂łɔ��\����5�l�ɂ��āA�d�����������Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��100��4281�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�23������1�l������7�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
������A�R���i��2�l���S�@�V�K������1175�l�@�V����2��̃N���X�^�[�m�F�@6/24
���ꌧ��24���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������2�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�v���Ґ���484�l�ƂȂ����B�܂��A�V����1175�l�����������Ɣ��\�����B��T�̋��j��(17��)��1217�l�ɔ�ׂ�42�l�������B�v�����҂�24��5009�l�ƂȂ����B�܂��A�V����2��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���23�����_��569.79�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ����F�{����161.37�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����43.1��(���@�Ґ�272/�a����631)�ŁA�d�ǎҗp��13.3��(���@8/�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�́A�V����42�l�̊��������ꂽ�B
|
���S���ŐV����1��5815�l���R���i�����@4���A���őO�T����@6/24
�V�^�R���i�E�C���X�̍��������Ґ���24���A�ߌ�7�������݂ŐV����1��5815�l���m�F���ꂽ�B�O�̏T�̓����j��(17��)���A1110�l�����A4���A���őO�T���������B���҂�15�l�������B
�ł��V�K�����҂��������������s�́A2181�l���m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j������585�l�������B�O�T������̂�7���A���B24���܂ł�1�T�ԕ��ς̊������݂�ƁA1��������̊����Ґ���1895�E0�l�ŁA�O�T(1570�E0�l)��120�E7%�������B2�Ԗڂɑ����������{��1365�l�B�O�T�̓����j�����240�l���������B3�Ԗڂɑ��������͉̂��ꌧ��1175�l�B |
���S���̐V�K�����Ґ��u�������͓݉�������v�@6/24
�����J���Ȃ����\������88��V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�̊����̕��́E�]���ł́A�S���̐V�K�����Ґ��ɂ��āA�u�����������Ă��邪�A���̌������͓݉�������v�Ǝw�E���Ă���B
�V�K�����Ґ���n��ʂŌ���ƁA�u�����𑱂��Ă���n�������A�������͑����̒�����������n�������ȂǁA�����̐��ڂɍ��������Ă���v�Ɛ����B���ɁA�ꕔ�̐l���K�͂̏������n��ł́A�u�N���X�^�[�̔����ɂ��V�K�����Ґ��̋}����������v�Ǝw�E���Ă���B
�V�K�����҂̊����ꏊ�ɂ��Ắu�w�Z���ɂ����銄���������X���ɂ�����̂́A�ˑR�Ƃ��č��������Ő��ڂ��Ă���v�ƋL�ځB����̊����ɂ��ẮA���N�`����3��ڐڎ�Ɗ����ɂ��l�����ꂽ�Ɖu�����X�Ɍ������Ă������Ƃ�A7���ȍ~�͔~�J�����A3�A�x��ċx�݂̉e��������A�ڐG�̑����Ȃǂ��\�z����邱�Ƃ������A�u����͊����Ґ��̑��������O�����v�Ƃ��Ă���B |
���V�^�R���i�V�K������ �S���ʼn�����23�s���ł͑O�T��葝�� �@6/24
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�S���ł͉����ŁA�l���̑�����s�����܂�23�̓s���ł́A�O�̏T��葽���Ȃ��Ă��ĉ����~�܂�̌X���������Ă��܂��BNHK�́A�e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��āA�O�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S���@/�@��^�A�x�����ȍ~�A5��26���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T�ɔ�ׂ�0.87�{�A6��2����0.68�{�A6��9����0.75�{�A6��16����0.87�{�ƁA5�T�A���Ō����X���ƂȂ��Ă��܂����B������23���܂łł�1.00�{�ƁA�����ɂȂ��Ă��āA1��������̕��ς̐V�K�����Ґ��́A���悻1��4248�l�ƂȂ��Ă��܂��B�V�K�����Ґ��́A�����s��_�ސ쌧�ȂǁA��s���Ⓦ�k��R�A�A��B�Ȃ�23�̓s���őO�̏T��葽���Ȃ��Ă��܂��B
�������s�@/�@6��9���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.78�{�A6��16����0.89�{�ƁA5�T�A���Ō����X���ƂȂ��Ă��܂������A6��23���܂łł�1.15�{�Ƒ������Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻1811�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���_�ސ쌧�@/�@6��9���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.72�{�A6��16����0.84�{�A6��23���܂łł�1.16�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻834�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����ʌ��@/�@6��9���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.70�{�A6��16����0.95�{�A6��23���܂łł�1.09�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻614�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����t���@/�@6��9���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.70�{�A6��16����0.97�{�A6��23���܂łł�1.06�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ���451�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����{�@/�@6��9���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.78�{�A6��16����0.85�{�A6��23���܂łł�0.96�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻1119�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����m���@/�@6��9���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.74�{�A6��16����0.79�{�A6��23���܂łł�0.99�{�ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻798�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����ꌧ�@/�@6��9���܂ł�1�T�Ԃ́A�O�̏T��0.97�{�A6��16����0.98�{�A6��23���܂łł�0.99�{�ƁA3�T�A���łقډ����ƂȂ��Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻1209�l�ŁA����1�T�Ԃ́A�l��10��������̊����Ґ���576.63�l�ƁA�S���ōł�������Ԃ������Ă��܂��B
�@ |
 |
��2022�Q�@�I�@�R���i��@�]���̔��ȓ_���炩�Ɂ@6/25
�V�^�R���i�E�C���X�̗��s�������Ŏn�܂��Ė�2�N���ɂȂ�B���̊ԁA��Ò̐��̕N��(�Ђ��ς�)�Ȃǂ��J��Ԃ���A���{�Ή��́u���v�Ɣᔻ�𗁂тĂ����B
�Q�@�I�Ŋe�}�A���҂͏]���̐V�^�R���i��̖��_����������_���Ăق����B���̏�ō��゠��ׂ��ی��E��Ñ̐���A�R���i��ƎЉ�o�ϊ����𗼗����������������ׂ����B
���{�ŏ��̊����҂��m�F���ꂽ�̂�2020�N1���B���{�͓����A�C�x���g���l�⏬�����Z�̈�ċx�Z�Ȃǂ�v���B���̌�A�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���o���Ή����Ă����B
���H�X�̉c�Ɛ����ȂǂŔɉ؊X�̐l�o�͌����B���s�Ȃǐl�̈ړ��͑啝�ɐ��ꂽ�B���ɍ��Ă̗��s�u��5�g�v�ł͈�Ì��ꂪ���҂������ꂸ�A����×{���ɗe�̂��}�ς��ĖS���Ȃ�Ⴊ���������B
���݂́A3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�i���ʂȂǂ������Ċ����͗��������������A�Љ�o�ϊ����Ƃ̗����Ɍ������������i��ł���B����������A�V���ȕψي��������Ȃǂ��āA�܂������g��̋ǖʂ��}���錜�O������B����ȏꍇ�ɂ���ÕN���������Ȃ��̐��Â��肪�ő�̉ۑ�Ƃ�����B
�ݓc���Y�́A���{�����{���Ă����R���i��̌��܂��A�V���Ȏi�ߓ��g�D�ł���u���t�����NJ�@�Ǘ����v��A�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)�����f���Ƃ���u���{�łb�c�b�v�n�݂̕��j��ł��o�����B�܂��A�a����l�ނƂ�������Î�����v���Ɋm�ۂ��邽�߁A�����ǖ@���������č���s���{���̌�������������Ƃ����B
�����̕��j�̍����ƂȂ����L���҉�c�̌��؍�Ƃ͍��N5�����{����킸��1�J���Ԃ������B�Q�@�I�ɊԂɍ��킹�邽�߂́u�ˊэH���v�̊��͐@���Ȃ��B�L���҉�c�̍������A�����\���łȂ����������邱�Ƃ�F�߂Ă���B
�����g�哖���̈�ċx�Z�⊴���g�傪���܂�Ȃ����ł̊ό��x�����Ɓu�f���@�s���@�g���x���v�̊J�n�ȂǁA�^�ۂ������ꂽ����̑Ó����ɂ͓��ݍ��܂Ȃ������B���Ƒg�D�̒�����ɂǂ��������ꂽ���Ƃ����_���܂߁A���{�̈ӎv����ߒ��̕s�������͎c���ꂽ�܂܂ƌ��킴��Ȃ��B
�Ⴄ����u���Ă���Ί����Ґ������炵�A�o�ϊ������ێ��ł�����������Ȃ��B���܂������Ȃ���������������������茟���A���P���ׂ��_�͉��P���邱�Ƃ����P�������ƂɂȂ�͂����B
�R���i�������A��������}�͏d�lj����X�N�������l���m���Ɉ�Â�����u�V�^�R���i���������v���x�n�݁A���{�ېV�̉�͊����ǖ@��̃R���i�̎�舵�����G�ߐ��C���t���G���U�Ɠ���5�ނɕύX���邱�ƂȂǂ�����Ɍf����B�^��}�͌����i����Ɠ����ɁA�_���ʂ��Ă���܂ł̑�̔��ȓ_�𖾂炩�ɂ��A����ɐ��������������Ăق����B |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 2160�l�����m�F 8���A���O�T���� �@6/25
�����s����25���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓y�j�����470�l�]�葽��2160�l�ŁA8���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��25���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł�2160�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j�����479�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�8���A���ł��B25���܂ł�7���ԕ��ς́A1963.4�l�ŁA�O�̏T��123.3���ł����B25���Ɋm�F���ꂽ2160�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�23.3���ɂ�����504�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�150�l�őS�̂�6.9���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A24�����1�l�����āA25����3�l�ł����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ50���70��̒j��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
��������2160�l�����@�V�^�R���i�A2�l���S�@6/25
�����s��25���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2160�l���ꂽ�Ɣ��\�����B8���A����1�T�ԑO�̓����j�����������B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���1963.4�l�ŁA�O�T���123.3���B2�l�̎��S�����ꂽ�B
���@���҂�737�l�ŁA�a���g�p����14.5���B�d�ǎ҂͑O����1�l����3�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�20�オ504�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�150�l�������B�v�͊����҂�158��5463�l�A���҂�4567�l�ƂȂ����B
|
�����{ �V�^�R���i 2�l���S 1472�l�����m�F �O�T���200�l�� �@6/25
���{��25���A�V����1472�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA���悻200�l�����܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��100��5753�l�ƂȂ�܂����B�܂��A2�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5111�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�24���Ɠ���7�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
������1499�l�R���i�����@��T�y�j�����231�l���@6/25
���ꌧ��25���A�V����1499�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓y�j��(18��)��1268�l�ɔ�ׂ�231�l�������B�v�����҂�24��6508�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���24�����_��566.96�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ����F�{����167.97�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����39.1��(���@�Ґ�247/�a����631)�ŁA�d�ǎҗp��15.0��(���@9/�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����58�l�̕��������B
|
������@�V�K�����҂��O�T��1.05�{�Ɂ@�l����A�S�����[�X�g�����@6/25
����25���A�V����10�Ζ�������90�Έȏ��1499�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����231�l�����B�v�����҂�24��6508�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���O�T�Ɣ�r�����u�O�T��v��1�E05�{�ƁA2���A����1�{���������B��T�̓y�j����0�E93�{�������B���̋{���`�v�����������Ắu�����̐������キ�A�����X���ɂ���Ƃ͌����Ȃ��v�Ƃ̌������������B
�V�K�����҂̔N��ʓ���́A10�オ�ő���297�l�A10�Ζ���272�l�A30��236�l�A40��221�l�Ƒ����B�a���g�p���͌��S�̂�39�E1���B����ʂł͖{��46�E6���A�{��1�E5���A���d�R6�E8���ƁA�{���ł͈ˑR�Ƃ��č��������ƂȂ��Ă���B
���\���ꂽ1499�l�̂����A���O���Z�҂�9�l�B����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ�(24�����_)��566�E96�l�őS�����[�X�g�B�ČR�W�̐V�K�����Ґ���58�l�������B
|
���S���ŐV����1��6593�l�̃R���i�����m�F�@5���A���őO�T����@6/25
�V�^�R���i�E�C���X�̍����̊����Ґ���25���A�ߌ�7�������݂ŐV����1��6593�l���m�F���ꂽ�B�O�̏T�̓����j��(18��)���1759�l�����A5���A���őO�T���������B���҂�9�l�������B
�s���{���ʂōł������Ґ������������͓̂����s�ŁA2160�l�̊������m�F�B1�T�ԑO�̓����j������479�l�����A�O�T������̂�8���A���ƂȂ����B25���܂ł�1�T�ԕ��ς̊������r����ƁA1��������̊����Ґ���1963�E4�l�ŁA�O�T(1592�E1�l)��123�E3%�������B
���{�ł��V����1472�l�̊������m�F����A�O�T���217�l���������B80��̏���2�l�̎��S���V���Ɋm�F���ꂽ�B
|
���u�R���i��Ɨ��q���A����������{����v�@���������̊ό��n�@6/25
�V�^�R���i�E�C���X��̍s����������������A���Ɍ����̊ό��n�A�W�q�{�݂Ȃǂł��C�x���g���ĊJ���铮�����L�����Ă���B�R���i�Ђ����������Ō��͍��[���A�W�҂���́u���������̂��傫������v�u���ɖ߂�̂��v�Ɛ؎��Ȑ����オ��B�����A��킪�n�܂����Q�@�I�Ŋό��x���Ȃǂ����グ����҂͌���I�B�L���҂͊�����Ɗό����i�A�C���o�E���h(�K���q)�g��𗼗�������{��ɒ��ڂ��Ă���B
�����ł�3�����{�A�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ�B����1���ɂ͈��H�X�ɋ��߂��Ă������l���A�Z���ԗ��p�̐������Ȃ��Ȃ�A10���ɂ͊O���l�ό��q�̎��ꂪ��2�N�Ԃ�ɍĊJ���ꂽ�B
�_�ˁE�����̓싞���ł͍�����{�A�[�ߐ߂̃C�x���g�Ŋ�d���̐l�_��O�Ɏ��q������I���ꂽ�B2���̏t�ߍՂł́A�Â��̋K�͂��k���������ߏo���ł��Ȃ������B
�u����2�N�͋ꂵ�������B���ɂ܂Ō����u�Ԃ��}�����Ă��ꂵ���v�B�싞�����X�X�U���g���̑��p��������(65)�͖ڂ��ׂ߂�B��N������l�o�͖߂�n�߂����u���Ăɔ�ׂč��̑Ή����T�d�ŁA�o�ς̕������x��Ă���B�ό��Ƃ��x�����Ċ��C������{�ɂ��Ăق����v�Ƌ��߂�B
���E������Y�E����P�H��ɂ́A�R���i�БO��2019�N�x�A��155���l���K�ꂽ�B�O���l�q������҂�4����1���x���߂Ă����B�������A20�A21�N�x�ً͋}���Ԑ錾�ɔ����x�Ƃ�����A���ꂼ��40���l�O��ɗ������B
22�N�x��4�A5���Ɍv��16��7��l�����K���A19�N�x�̓�����Ŗ�4���܂Ŗ߂����B����Ǘ��������̉����d������(51)�́u���̂܂ܒ��É����Ăق����B������𑱂��āA���O����W�q�𑝂₵�����v�Ɗ��҂���B
��킪�������z�e���ƊE�ł��A���p�̒�����������B
�_�˃����P���p�[�N�I���G���^���z�e��(�_�ˎs������)�́A2�N�O�ɋً}���Ԑ錾���o���ꂽ����A�����q�⍑���c�̋q���قڃ[���ƂȂ�A��K�͔�I���̉��������������B�������A�����ɂ��ď������l�q�͎��������A3�N�Ԃ�ɉčP��̃r�A�K�[�f�����ĊJ�����B����͋����ɂ����͂���B
3�N��ɂ͑��E���������T���A��p�ȂǃA�W�A�̒c�̋q�̉������ށB���������x�z�l�́u���A���ɑS�̂̊ό��̖��͂��グ���邱�Ƃ��d�v�B�Ƃ��Ɋ������Ă����z�e���⌧�A�_�ˎs�ƘA�g���A�������_�Ŋό��������������v�Ɨ͂����߂�B
���{��̎��ǂ����܋����A�C���o�E���h���v�̉�S�҂��ɂ��Ă���B�����u�����v�̑����E�_�ˎ�S��(���s�����)�͂���2�N�A�����X��X�g�����̋q�������������B
�R���i�БO�͊O���l�q���蒅���Ă��������ɁA�v�ۓc���M���В��́u�ɂ͎��Ԃ�������B���S�A���S�����{�ό��̊ŔB���E���������߂��A���⎩���̂̓C���o�E���h�����S���ē��{��K��ł�����Â���ɒm�b���i���Ăق����v�Ƙb���Ă���B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1�l���S 2004�l�����m�F 9���A���O�T���� �@6/26
�����s����26���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓��j�����382�l����2004�l�ŁA9���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s�́A26���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2004�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����382�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�9���A���ł��B26���܂ł�7���ԕ��ς́A2018.0�l�ŁA�O�̏T��125.9���ł����B26���m�F���ꂽ2004�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�18.9���ɂ�����379�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�165�l�ŁA�S�̂�8.2���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A25���Ɠ���3�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ40��̒j��1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 3�l���S 1134�l�����m�F �O�T���250�l�� �@6/26
���{��26���A�V����1134�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA���悻250�l�����܂����B����A���{�͂���܂łɔ��\����5�l�ɂ��āA�d�����������Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��100��6882�l�ƂȂ�܂����B�܂��A3�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5114�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�25���Ɠ���7�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
������ŐV����1268�l�����@�V�^�R���i�@�l����őS�����[�X�g�����@6/26
���ꌧ��26���A�V����1268�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓����j��(19��)��1012�l�ɔ�ׂ�256�l�������B�v�����҂�24��7776�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���25�����_��582.51�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ����F�{����172.97�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����40.4%(���@�Ґ�255�^�a����631)�ŁA�d�ǎҗp��18.3%(���@�Ґ�11�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�́A�V����9�l�̊��������ꂽ�B
|
�������V����1��4238�l�����@6���A���O�T����@�V�^�R���i�@6/27
�����ł�26���A�V����1��4238�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�B
�V�K�����҂͑O�T���j���Ɣ�ׁA��1070�l�������B�O�T�̓����j��������̂�6���A���B�S���̏d�ǎ҂͑O������4�l������40�l�ŁA���҂�12�l�m�F���ꂽ�B
�����s�ł�2004�l�̊������m�F�B�V�K�����҂͑O�T���j���Ɣ��382�l�����A9���A���őO�T�̓����j�����������B���҂�1�l�������B�s�ɂ��ƁA�V�K�����҂̒���1�T�ԕ��ς�2018�D0�l�ŁA�O�T��125�D9���B�s��ɂ��d�ǎ҂͑O���Ɠ���3�l�������B�@�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1517�l�����m�F ��T���j�����441�l�� �@6/27
�����s����27���̊����m�F��1�T�ԑO�̌��j�����441�l����1517�l�ŁA10���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
�����s��27���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���1517�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j�����441�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�10���A���ł��B27���܂ł�7���ԕ��ς�2081.0�l�ŁA�O�̏T��128.5���ł����B1517�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�20.7���ɓ�����314�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�111�l�őS�̂�7.3���ł��B����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�26������1�l������4�l�ł����B���S���m�F���ꂽ�l�̔��\�͂���܂���ł����B
|
�������s�̐V�K�����҂�1517�l�@10���A���őO�T�̓����j�����瑝���@6/27
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA27��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�1517�l�B�d�ǎ҂͑O������1�l�����A4�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������90��܂ł�1517�l�B�N��ʂł�20�オ�ő���314�l�A������30���260�l�A40���249�l�Ƒ����Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�111�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�2081.0�l(�ΑO�T��128.5��)�B�s���̑���(�v)��158��8984�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����15.7��(792�l�^5047��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T20��(1076�l)����441�l�����A10���A���őO�T�̓����j�����瑝�����܂����B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
�����{ �V�^�R���i 586�l�����m�F ��T���j������190�l�� �@6/27
���{��27���A�V����586�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA���悻190�l�����܂����B����ő��{���̊����҂̗v��100��7468�l�ƂȂ�܂����B����A�S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�26������1�l�����āA6�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���h���^�A���ꌧ���ŏ��m�F�@�����͋����@�O�T��181�l����603�l�����@6/27
���ꌧ��27���A�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̔h���^�u�a�`�E2�E12�E1(�r�[�G�[�c�[�E�����c�[�E����)�v�̊�����1�l�������ŏ��m�F�����Ɣ��\�����B���̌n���͎嗬�̂a�`�E2��芴���͂������Ƃ̕�����B27���̐V�K�����Ґ���603�l�ŁA��T���j�����181�l�����A3���A���őO�T�̓����j�����������B
�a�`�E2�E12�E1�̊����҂͓암�ی����Ǔ���70�㏗���B���n���͓�������Ȃnj��O��10�s�{���Ŋm�F����Ă���B�a�����̋�����N�`���̌��ʂ͂͂����肵�Ă��Ȃ��B�ʂ̔h���^�a�`�E5��9�l�̊����҂�������A�v13�l�ɑ������B
�ǂ���̌n�����A���q�������������������{���牺�{�ɍ̎悵��288���̂��猩�������B�V���Ȋ����҂ɏd�ǎ҂͂��Ȃ��B
����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����҂͖�612�l�ɑ������B600�l��͍���2���ȗ��B
���@���̐l��261�l�B�R���i�a���g�p����41�E4���ƂȂ��Ă���B
���̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA2022�N�x��1�`11�T(22�N3��28���`6��12��)�ɃR���i�֘A�̋~�}������30���ȏ�ҋ@�����̂�217���B�Œ���147���������B
|
�������ŐV����9572�l�����A����13�l�c�d�ǎ҂�5�l����45�l �@6/27
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�27���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����9572�l�m�F���ꂽ�B���҂�13�l�A�d�ǎ҂͑O������5�l����45�l�������B
�����s�ł�1517�l�̊��������������B�O�T�̓����j������441�l�����A10���A����1�T�ԑO���������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�2081�l�ŁA�O�T����28�����������B
���{�̐V�K�����҂�586�l�ŁA�O�T�̓����j������192�l�����A6���A����1�T�ԑO���������B
|
 |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 2514�l���� �O�T�Ηj�����551�l�� �@6/28
�����s����28���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̉Ηj�����550�l�]�葽��2514�l�ŁA11���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
�����s��28���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���2514�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj�����551�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�11���A���ł��B28���܂ł�7���ԕ��ς́A2159.7�l�ŁA�O�̏T��128.4���ł����B28���m�F���ꂽ2514�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�20.0���ɂ�����502�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�182�l�ŁA�S�̂�7.2���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A27�����1�l������5�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ40��̒j���ƁA80��̒j���̍��킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����2302�l�R���i�����c1�T�ԑO����791�l���@6/28
���{��28���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2302�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j������791�l�����A7���A����1�T�ԑO���������B
|
���u�S���I�ɑ����ɓ]���Ă���v�Ɖ��ꌧ�@1�l�������l�����u1�v����@6/28
�V�^�R���i�E�C���X�Ɋւ��鉫�ꌧ�u�w���v�E��͈ψ����28���A������1�l�����l�ɂ����������������Đ��Y������T�͉���{����1�E06�A�ߔe�s��1�E15�A�{�Â�1�E13�A���d�R��1�E44�ƂȂ�u�S���I�Ɋ����Ґ��������ɓ]���Ă���v�ƕ��͂����B
����҂̒j���ő����������Ƃ��w�E���u�{�ݓ���ƒ���̊�������������H���U������A���̐���̊��������������Ă���\��������v�Ɛ����B����҂ȂǏd�lj��̃��X�N������l�̃��N�`���ڎ���Ăт������B
�����͂������Ƃ����I�~�N�������̔h���^�u�a�`�E5�v�̒u������肪�i��ł���Ƃ��A�u�����ȍ~�̗��s�̎�͂ɂȂ�ƍl������v�Ƃ����B
�R���i�a���͐�L����92�E5���̖k���������n���50����������Ă�����̂́A�R���i�ȊO�̕a����L���͉���{����90���ȏ�ƂȂ�u��ʈ�Ë@�ցA����Ҏ{�݂Ƃ̖������S��i�߂Ȃ���ΏZ���̌��N�𑍍��I�Ɏ�邱�Ƃ�����v�Ƃ��A�����ɑ��Ĉ�Â̓K�����p�����߂��B�@ |
���Q�@�I�������́@�R���i��c�o�ςƂ̗������@�� �@6/28
�u���H�X�ɂ��c�Ǝ��ԒZ�k��x�Ƃ͂ǂ��܂Ō��ʂ��������̂��B�����[���������Ȃ��v
�����s�V�h��̋������u�a�n��@ �� �@���V�h�v�̓X���A��q�a�K����(42)�́A�V�^�R���i�E�C���X�Ђ� �|�M�ق�낤 ���ꂽ��2�N�Ԃ��A�����U��Ԃ����B
���X�́A�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�ɔ����x�Ƃ⎞�Z�c�Ƃ̗v���ɑS�ď]�����B��ɉ�������������Ă��邱�Ƃ������u��O�ҔF�v���擾���Ă���B
�����A1������̑�6�g�ł��d���A��̈��q���������B50�Ȃ̓X���ɐ��g�������Ȃ���������A�]�����N�����̂Ă邱�Ƃ����������Ƃ����B�s���狦�͋����o�����̂́A�������S���~�̐Ԏ����������B�u��7�g�v�������C�ɂ������q����́A�u��������H�X��v���Ώۂɂ���Ȃ�A����܂ł̌��ʂ������Ăق����v�ƒ����������B
��6�g�ł�1�`3���ɍő�36�s���{���ŏd�_�[�u���K�p���ꂽ�B�V�^�C���t���G���U�����ʑ[�u�@�Ɋ�Â��A�s���{�������H�X�̎��Z���K�̓C�x���g�̐l��������v���B���ۑ���������ꂽ�B�o�ςւ̑Ō����[���ŁA���N1�`3�����̎������������Y(�f�c�o)��2�l�����Ԃ�ɑO����}�C�i�X�ƂȂ����B
����A��6�g�Ŏ嗬�́u�I�~�N�������v�͏]�������d�lj����X�N���Ⴂ�Ƃ���A�����g��̏�͈��H�X���獂��Ҏ{�݁A�w�Z�Ɉڂ��Ă����B���̂��߁A���Ƃ�ꕔ�����̂Ȃǂ���d�_�[�u�̕K�v���ɋ^�₪�悳�ꂽ�B�o�ϓI�����̐����ƂȂ���H�X�̎��Z�v���Ȃǂ͍ŏ����ɗ}����ׂ��ŁA���ʂ������Ȃ�������ׂ����Ƃ����킯���B
������ƌo�ρE�Љ���̗����������ۑ�ƂȂ�A�Q�@�I�ł͊e�}�Ƃ��A�����ނˌo�ϊ����Ɗ����h�~�̗������f���Ă���B
����Ŏ����}�́u�Љ�E�o�ϊ�������w�i�߂Ă����v�Ƃ��A���N�`���ڎ�̑��i�⌟���Ԑ��̊g�[�A��ʋ@�ւ̊����h�~��A���ۑ�ɖ��S�������Ƃ��Ă���B
��������}���u�o�ϊ����Ƃ̗�����}��v�Ƃ��A���ۑ�̓O���A�N�ł��o�b�q����������̐��̊g�[���������B
�ق��̊e�}���o�ϊ����p���̏d�v����A���t�ɂ�鍑�������E�o�ς̎x���A�����ǖ@��̕��ނ����݂�2�ޑ�������G�ߐ��C���t���G���U�Ɠ���5�ނֈ��������邱�ƂȂǂ��f����B
�����A��̓I�ȑ��A�o�ρE�Љ���̂��߂ɂǂ��܂ōs����������߂邩�Ƃ��������f�́A���㌻���ψي��̊����͂�d�lj����X�N�ɉ����Č��߂���Ȃ��̂�����B���̂��߁A�e�}�Ƃ�����ł͑傫�ȕ������������ɂƂǂ܂��Ă���B�e�}���R���i�Ђɂǂ��������������Ƃ��Ă���̂��A�_���ʂ��Č��ɂ߂�K�v������B
|
�����E�̃R���i�����ҁA�����X���Ɂ@�����H���͕ς�炸�@6/28
���E�̐V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��������n�߂��B�����͂������Ƃ����uBA.4�v�ȂǃI�~�N�����^�̔h���^�̗��s���w�i�ɂ���B�����A�����_�ł͎��҂�d�ǎ҂̐��ɑ傫�ȕω��݂͂�ꂸ�A�e���̓R���i�Ƃ̋������߂������j�͕ς��Ă��Ȃ��B
�ăW�����Y�E�z�v�L���X��w�ɂ��ƁA���E�̐V�K�����Ґ�(7���ړ�����)��26�����_�Ŗ�66��2��l�ƂȂ�A��2�J���Ԃ�̐����ɑ��������B�I�~�N�����^�̗��s��1�����s�[�N�ōŋ߂͊����Ґ������������Ă������A�e���Ŕh���^�́uBA.4�v�uBA.5�v�Ȃǂ��L�����Ă���B���ɑ������ڗ��͉̂��B�⒆��Ă��B
�p���ł�6���ɓ����đ����X���������B�p�ی����S�ǂɂ��ƁA�uBA.4�v�uBA.5�v�������҂̉ߔ����߂�B�z���ɂȂ��Ă�����`�����Ȃ����߁A���ۂ̊����Ґ��͂���ɑ����\��������B���ǂ̎�Ȉ�ÃA�h�o�C�U�[�̃X�[�U���E�z�v�L���X�����́u75�Έȏ��17.5%���ߋ�6�J���ȓ��Ƀ��N�`����ڎ킵�Ă��炸�A�d�lj��̃��X�N������v�Ƃ��Ēlj��ڎ���Ăт����Ă���B
�t�����X�ł������҂͑����Ă���B�u���M�j�����ی�����27���A�u�`���ł͂Ȃ����A��ʋ@�ւł̓}�X�N�����Ăق����v�Əq�ׁA�x�������ɂ��܂����B
����Ăł́A���L�V�R��u���W���Ŋ����Ґ����Ăё����X���ɂ���B�ăW�����Y�E�z�v�L���X��ɂ��ƁA���L�V�R�ł͐V�K�����Ґ�(7���ړ�����)��25�����_�Ŗ�1��4000�l��1�J���O�̖�14�{�ɑ������B�u���W���ł�25�����_�Ŗ�4��1000�l��1�J���O�����6�������Ă���B�I�~�N�����^�̔h���^�𒆐S�Ɋ������L�����Ă���B
�h���^�͊����͂������Ƃ���邪�A�d�lj����ɂ͑傫�ȕω��͂Ȃ��������B�p���{�̃f�[�^�ɂ��ƁA�l�H�ċz�킪�K�v�ȏd�NJ��҂̐��ɑ傫�ȕω��͌����Ȃ��B�ނ���I�~�N���������s���Ă���͊ɂ₩�Ȍ����X���ɂ���B�����h�����S���ł̓}�X�N�����Ă���l�͂قƂ�ǂ��炸�A�傫�Ȗ��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
���C���O�����h����C�㖱���̃W���i�T���E�o���^������BBC�ɁA�u�v�����ł̓C���t���G���U�ɋ߂��B�C���t���G���U�ł������ԑ̒�������Đ����Ɏx��𗈂����Ƃ����邵�A��X�͐V�^�R���i�ɂ��Ă����̂悤�ȊT�O�łƂ炦�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B
���N�`���ڎ킪�i�݁A�d�lj����}�����Ă���ʂ�����B���L�V�R�ł�12�Έȏ��86%�A18�Έȏ��91%�����N�`�������Ȃ��Ƃ�1��ڎ킵�Ă���B18�Έȏ�Ń��N�`�������S�ɐڎ킵���l�̂���66%�͒lj��ڎ�(�u�[�X�^�[�ڎ�)���I���Ă���B
�I�~�N�����^�����s���Ă���d�lj����͉�����A�e���͎�T��Ȃ�����ʏ�̕�炵�ɖ߂����Ƃ��Ă���B�č���12������A�����O�̉A���ؖ��̒�s�v�Ƃ����B�j���[���[�N�s�̌���X�u���[�h�E�F�[��7������ϋq�̃}�X�N���p�`������������B
���Ăł͂��łɑ����̐l���������o�����Ă��邽�߁A�V�^�R���i�ւ̌x����������Ă���B�����A����̔����I�ȑ����̌��O�͎̂Ă���Ȃ��ق��A���N�`���̌��ʂ͎��ԂƂƂ��ɒቺ����Ƃ����B���{����Ƃ͔h���^�̏d�lj��������ɂ߂邽�߁A���҂�d�ǎ҂̃f�[�^�𒍈Ӑ[��������Ă���B�@ |
 |
�������s�A3803�l���R���i�����@��1�J���Ԃ�3��l��A3�l���S�@6/29
�����s��29���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3803�l���ꂽ�Ɣ��\�����B3��l�����̂�5��26���ȗ��B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���2370.3�l�ŁA�O�T���137.3���B3�l�̎��S�����ꂽ�B���@���҂�857�l�ŁA�a���g�p����16.9���B�d�ǎ҂͑O���ƕς�炸5�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�20�オ840�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�230�l�������B�v�͊����҂�159��5301�l�A���҂�4573�l�ƂȂ����B
|
�������s �R���i3�l���S 3803�l���� �O�T���j���1400�l�]�����@6/29
�����s����29���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̐��j�����1400�l���܂葽��3803�l�ŁA12���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
�����s�́A29���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3803�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j�����1474�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�12���A���ł��B�܂��A1���ɔ��\����銴���Ґ���3500�l�����̂�5��25���ȗ��ł��B�s�̒S���҂́A�u�{���̊����Ґ��͐�T�̓����j�����A�啝�ɏ㏸���Ă��邪�A���̑������������ȍ~�ǂ����ڂ��Ă����̂��������Ă����K�v������B�܂��A���@���҂̐��Əd�ǎ҂̐������ɏd�v�Ȏw�W�Ȃ̂ŁA�������������Ă��������v�Ƙb���Ă��܂����B29���܂ł�7���ԕ��ς́A2370.3�l�ŁA�O�̏T��137.3���ł����B29���A�m�F���ꂽ3803�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�22.1���ɂ�����840�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�230�l�ŁA�S�̂�6���ł��B�����o�H���������Ă���1298�l�̂����ł������̂́u�ƒ���v��68���ɂ�����883�l�ł����B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A28���Ɠ���5�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ50���80��̒j�����킹��3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����2222�l�R���i�����A8���A����1�T�ԑO������@6/29
���{��29���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2222�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j������809�l�����A8���A����1�T�ԑO���������B
|
������ő���������R���i�����A2���A����1700�l��@5���A���őO�T������@6/29
���ꌧ��29���A�V����10�Ζ�������90���1709�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B2���A����1700�l��ŁA6���ł͑O����1744�l�Ɏ�����2�Ԗڂɑ����B��T���j�����129�l�����A5���A���őO�̏T�̓����j�����������B
�V�K�����҂̔N��ʂ̓����10���356�l���ő��B10�Ζ���308�l�A40��263�l�A30��233�l�Ƒ����B�����o�H���������Ă���̂�906�l�ŁA�ƒ��������598�l�Ƒ唼���߂�B���H��32�l�Ɩڗ��B����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���O�̏T�Ɣ�r�����u�O�T��v��1�E15�{�B����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ�����642�l�Ɗɂ₩�ɑ����Ă���B�O�����_�̑S�����ς�86�l�B���@����263�l�ŁA��������̏d�ǂ�3�l�B�R���i�a���g�p����41�E7���ƂȂ��Ă���B�R���i�ȊO�̕a���g�p�����e�n���90�����ƕN��(�Ђ��ς�)���Ă���B�V�KPCR�����̗z������16�E8���ƍ��������B���@�����{�ݓ��ŗ×{���Ă���̂�207�l�B����͍���Ҏ{��199�l�A�Ⴊ���Ҏ{��8�l�B�ČR��n���̐V�K�����Ґ���50�l�������B
|
���������i�܂Ȃ��g�{���́g�V�^�R���i�E�C���X�ɂ�鎀�S�Ґ��@6/29
�h�V���Y��6��28���A���g���p�[�\�i���e�B�߂�j�b�|�������w�h�V���Y �Y�[�� �����܂Ō������I�x�ɏo���B���X���\�����V�^�R���i�E�C���X�̎��S�Ґ��ɂ��āu��������a����������v�Ƌ^���悵���B
�ŋ߁A��ÊW�҂Ƙb������@��������Ƃ����h�V�B�V�^�R���i�E�C���X�̕ψٌ^�I�~�N�������̗��s���嗬�ɂȂ��Ĉȍ~�u�R���i���������ďd�lj�������A�S���Ȃ����肷��l���܂��������ƂȂ��ł��ˁv�ƕ������Ƃ����B���X���\����铝�v��́A������芄���̐l���V�^�R���i�E�C���X�ŖS���Ȃ��Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���B
���́g��a���h�ɂ��Đh�V�́A2�N�O�Ɍ����J���Ȃ��o�����ʒB�ɐG��A���������̂��Ƃɉ��������ăR���i���ƃJ�E���g���邩�̔��f����o���o���ł��������߁A�ǂ̂悤�ȕa�C�ŖS���Ȃ��������킸PCR�����Łu�V�^�R���i�z���v�ł���ΑS���R���i���Ƃ��ē��v��͕��ނ���Ă���Ɖ���B���̂����ŁA�������\�����V�^�R���i�E�C���X�ɂ�鎀�S�Ґ��̂����A�ǂ�قǂ̊����̐l�������ɐV�^�R���i�E�C���X�Ƃ����a�C�����̈����A�����ŖS���Ȃ����̂��̐������i��ł��Ȃ��Ɣᔻ�B�N���������������킩��Ȃ��܂܁A���肪�i��ł���Ǝw�E�����B
�܂��h�V�́A�A���̏����ɂ��V�^�R���i�E�C���X�ɜ������M���ǂɂȂ郊�X�N�̕����͂邩�ɍ����Ƃ��āA���܂��ɉ��O�Ń}�X�N���O�����X�s���l���قƂƂ��āA�u�Ӓn�ɂȂ��ă}�X�N�O���Ȃ��̂͂�߂܂��傤��v�Ƒi�����B
|
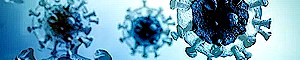 |
���R���i�Ђ̑I����@�����ґ��A�I�������̂�����N���X�^�[�̐S�z�Ȃǁ@6/30
��28���A�����s�͐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2514�l���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�Ηj�������550�l���������B11���A���őO�̏T�̓����j���������Ă���B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���2159�E7�l�őO�T���128�E4���B�a���g�p����16�E5���B�܂��N��ʂł݂��20�オ502�l�ōő��B�S�̂�20�E0���B65�Έȏ�̍���҂�182�l�őS�̂�7�E2���B�l�H�ċz�킩ECMO(�l�H�S�x���u)���g���Ă���d�ǎ҂͑O����1�l��5�l�B���҂�2�l���m�F���ꂽ�B
���~�J�������A�I�����A�܂��Ȃ��ċx�݂ɓ��鍡�A�d�ǎ҂������Ȃ����̂́A�����҂͊m���ɑ����n�߂Ă���B28���A���ꌧ�ł͐V���Ȋ����҂�1744�l�B����ȊO�ɂ��ČR�W����V����19�l�̊����҂̕��������B������27���A�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̔h���^�uBA�E2�E12�E1(�r�[�G�[�c�[�E�����c�[�E����)�v�̊�����1�l�������ŏ��m�F�����Ɣ��\�����B���̊��͎嗬��BA�E2��芴���͂������Ƃ����Ă���B�܂����m���E�ʏ�f�j�[�͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��m�F����A28���������������߂Ă���B
��28���A���{�ł��V����2302�l�̐V�K�����҂\���Ă��邪�A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA���悻790�l�����Ă���B�_�ސ쌧�ł������A1091�l�̐V���Ȋ��������\���ꂽ���O�̏T�̓����j���Ɣ��276�l�����A�C�㎩�q���̉��{�ꏊ�������ł̃N���X�^�[���������Ă���B�R���i�̊����͓��X�h��ւ����Ă������A�����̈ӎ��̒��ł́A���ɉߋ��̂��̂ɂȂ����B���̃f�[�^���ǂ��������B�I����ƃR���i��ʕ��ɂ��Ă���S���̑I����������w�c�́A�I�������̂�����N���X�^�[�̐S�z�ȂǁA���_�����ׂ����B |
���ďB�R���i�����Ґ�14�����A��ĂŊ����L���遁�o�`�g�n�@6/30
���E�ی��@��(�v�g�n)�̕ďB�����ǂł���ĕĕی��@�\(�o�`�g�n)��29���A�ďB�̑O�T�̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ����O�̏T����14��������130���l�ɂȂ����Ɣ��\�����B���Ґ���4158�l�������B
��Ăł̊������L�����Ă���A�V�^�R���i�����ǂɂ�鎀�S���͑O�̏T����32�D8���㏸�B��T�̐V�K�����Ґ��͖�50���l�ƑO�̏T����24�D6�����������B
�k�Ă̐V�K�����Ґ��͑O�̏T����7�D7�������B�J�i�_�Ō����������̂́A�č��ƃ��L�V�R�ő����X���������Ă���Ƃ����B
|
�������A3621�l���R���i�����@�O�T��1200�l���@6/30
�����s��30���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3621�l���ꂽ�Ɣ��\�����B1�T�ԑO�̖ؗj�������1200�l�������B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���2542.9�l�ŁA�O�T���140.4���B2�l�̎��S�����ꂽ�B
���@���҂�907�l�A�a���g�p����17.9���B�d�ǎ҂͑O������2�l����3�l�������B�V�K�����҂̔N��ʂ�20�オ880�l�ōő��B65�Έȏ�̍���҂�194�l�������B�s�́A5���ɔ��\���������҂ɂ��āA�Č����ʼnA������������Ȃǂ���91�l����艺�����B�v�͊����҂�159��8831�l�A���҂�4575�l�ƂȂ����B
|
�������s�A�V�^�R���i�x���x�グ�@�����҂������X���@6/30
�����s��30���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����͂��郂�j�^�����O��c���J���A4�i�K�Ŕ��f����x���x��1�i�K�������ďォ��2�Ԗڂɂ����B�V�K�����҂��Ăё����X���ɂ��邽�߁B������ċx�݂ȂǂŊ����g��̉\��������Ƃ݂āA�����⎩��×{�x���̑̐�����������ق��A��N�w�⍂��҂Ƀ��N�`���ڎ�𑣂��B
�s����7���ԕ��ς̐V�K������(30�����_)�͖�2542�l�őO�T��40%�������B���@���҂������X���ɂ��邪�u����̓������x������K�v������v�Ƃ��A��Ò̐��̌x���x�͏ォ��3�ԖڂŐ����u�����B�s�͌��݁A�R���i�a�����5000���m�ۂ��Ă���B�a���g�p����40%�ɒB�����i�K�ŁA�M���ǑΉ��ȂǂƂ̃o�����X���l�����Ȃ���a���̏�ς݂f����B
��c��ɃI�����C���ŋL�Ғc�̎�ނɉ��������r�S���q�m���́u���܂߂Ȑ����⋋�Ȃǂ����ĔM���ǂɗ��ӂ��Ȃ���A���C�ȂNJ����h�~������߂ēO�ꂵ�Ăق����v�Əq�ׂ��B |
�����{ �V�^�R���i 4�l���S �V����2193�l�����m�F�@6/30
���{��6��30���A�V����2193�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA940�l�]�葝���܂����B
�܂��A���{�́A28���ɔ��\����1�l�ɂ��āA�����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��101��4180�l�ƂȂ�܂����B�܂��A4�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͂��킹��5210�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�29������1�l������5�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
������R���i1727�l�A6���A���őO�T�䑝�@�{�ݓ��×{259�l�@6/30
���ꌧ��30���A10�Ζ�������90��ȏ��1727�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�O�T�̓����j���Ɣ�ׂ��185�l�̑����ƂȂ�A6���A���őO�T���������B�{�ݓ��×{��87�J���Ōv259�l�Ƒ����X���ɂ���B
�{�ݓ��×{�̓���͍���Ҏ{�݂�74�J���Ōv251�l�A�Ⴊ���Ҏ{�݂�13�J���Ōv8�l�������B���̏�ԓ֊����Ǒ����ے��́u�{�ݓ��×{�̊����Ґ��͑����Ă��邪�A����҂̊������g�債�Ă���Ƃ����ł͂Ȃ��v�Ɛ��������B�a���g�p����41�E8���Ō���ʂɌ���ƁA�{����48�E6���A�{�Â�3�E0���A���d�R��20�E5���ƂȂ��Ă���B�N��ʂł�10�オ282�l�ƍő��B40�オ276�l�A10�Ζ�����267�l�Ƒ������B���芴���o�H�̍ő��͉ƒ����579�l�B�����ėF�l�E�m�l��123�l�A�E�����67�l�������B�ČR�W�̐V�K�����Ґ���8�l�������B
|
���u�S���I�ɏ㏸�X���ɓ]�����B�����g��ǖʂɁv �����Ґ����e�n�ő����@6/30
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ��āA�����J���Ȃɑ��ď���������Ɖ�c���A���傤�ߌ�A�J���ꂽ�B��c��A�L�҉�ɗՂe�c�����́A�u�V�K�����Ґ����A�S���I�ɁA�㏸�X���ɓ]�����B�����̒n��ő����ɓ]���Ă���B�����g��ǖʂɓ����Ă����v�Ƃ̕��͌��ʂ𖾂炩�ɂ����B
���͌��ʂɂ��ƁA�S���ŁA��T�����A�����Ґ������������̂�29�s�{���ŁA��s�s�ł́A�����ނˏ㏸�X���ɂȂ����Ƃ����B���ɉ��ꌧ�ɂ��ẮA���̒n������A�������x���������Ƃ̂��ƁB����ł́A���łɕa���g�p������������A�����ɓ]�����Ƃ����B
�����Ґ��������X���ɓ]�����v���ɂ��ẮA�h��̊X�h�̐l�o�����������Ƃ�A���N�`���ڎ�̌��ʂ�����A�������̂���l�́u�Ɖu�v���ቺ���Ă��邱�Ƃ�������ꂽ�B���̑��ɁA�]���̃I�~�N���������������͂������uBA.5�v�������Ă��邱�Ƃ��A�v����1�Ƃ���Ă���B
�����s�ł́A�����Ώۂ�4�l��1�l���A�uBA.5�v�̊����҂������Ƃ����B���ꂩ��uBA.5�v�ɒu������肪�i�߂A�u�����g�傪��������v���������Ƃ̂��ƁB
����̌��ʂ��ɂ��Ęe�c�����́A�u�~�J�������āA3�A�x������A�ċx�݂��}���邽�߁A�ڐG�@������A�V�K�����Ґ��̑������\�z�����B�����҂̑������ł��邾���}�����邽�߁A��{�I�Ȋ������O�ꂵ�ė~�����v�ȂǂƌĂт������B
�܂��A�������������������A�u��[��D�悷�邽�߁A���C������ɂ����ꍇ������v�ȂǂƎw�E���A�u���C�Ȃǂ̓O����p������K�v������v�Ƌ��������B
|
���R���i������1.17�{�ɁA29���܂ł�1�T�ԁ@���Ɖ�c�@6/30
�����J���ȂɐV�^�R���i�E�C���X�������������Ɖ�c��30���A29���܂ł̒���1�T�ԂɊm�F�����S���̊����Ґ����O�̏T��1.17�{�ɑ������Ƃ̕��͂����\�����B29�s�{���őO�T��芴���Ґ��͑��������B
�㓡�ΔV���J���͓���c�Łu���N�`����3��ڐڎ�⊴���Ŋl�������Ɖu�̌����A�I�~�N�����^�̐V���Ȍn���ւ̒u�������̉\�����獡��͊����Ґ��̑��������O�����v�Ƃ̌������������B
���N�`����4��ڐڎ�Ɋւ��Ắu���コ��ɉȊw�I�m���Ȃǂ����W���A60�Ζ����ւ̐ڎ�ɂ��Č�����i�߂�v�Əq�ׂ��B
�㓡���͔M���ǂ�h�����߉��O�Ől�Ɖ�b���Ȃ��ꍇ�ȂǂɁA�}�X�N���O���悤���߂ČĂт������B�u�C���⎼�x�������Ȃ��Ă��Ă���B�M���Ǒ�̊ϓ_���牮�O�ł͋ߋ����ł̉�b������ꍇ�������ă}�X�N���O���Ăق����v�Ƒi�����B
|
���u��7�g�v�ɂȂ���\���́H�@�R���i������ �S���ő����X���@6/30
�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����Ґ���6�����{�����肩���s���ȂNJe�n�ő����ɓ]�����悤�Ɍ����܂��B�S���̊����Ґ����O�̏T�Ɣ�ׂđ������Ă��܂��B����܂łɂ������g��͌J��Ԃ���Ă��܂������u��7�g�v�ɂȂ���̂ł��傤���H
���Ƃ́u�傫�ȗ��s�ɂȂ��邩�͂܂��킩��Ȃ����A�V���ȕψكE�C���X�ւ̒u�������Ȃǂɒ��ӂ��ׂ��ŁA�ꎞ�I�Ɋ�����ւ̈ӎ������߂Ă��炤�K�v������v�Ƃ��Ă��܂��B
���V�K������ �O�T��ő����X�� �����ł͉ߋ��ő���
�S���̐V�K�����Ґ��͑�^�A�x�����Ɉꎞ�����������ƁA5�����{�ȍ~�A�����X���������Ă��܂������A�O�̏T�Ɣ�ׂ�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͐�T���瑝���X���ŁA6��29���܂łł͑O�̏T��1.17�{�ƂȂ��Ă��܂��B�����s�ł�6��30���܂ł̐V�K�����Ґ����O�̏T�Ɣ�ׂ�1.40�{�ɂȂ�ȂǁA�l���̑�����s���Ⓦ�C�A���A�����ċ�B�Ȃǂő����X���ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�������ł͏o�_�s�̎��Ə��ő�K�͂ȃN���X�^�[����������ȂǁA6��28���ɂ͈��������ʼnߋ��ő��ƂȂ�305�l�̊������m�F����܂����B
�������̕]���u�����v���v�̋L�q������
�����J���Ȃ̐��Ɖ�́A�����̑����ɂȂ���v���Ɨ}���ɂȂ���v��������A���̃o�����X�������ɉe������Ƃ��Ă��܂����B��̌�ɖ���o����銴���̕]���̕����ł́A���̂Ƃ��둝���ɂȂ���v���ɂ��Ă̋L�q�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B��̓I�ȗv���Ƃ��Đ��Ɖ�������Ă���̂��A���N�`���ڎ�⊴���ɂ���ē���ꂽ�Ɖu�����Ԃ̌o�߂Ŏ�܂��Ă��Ă��邱�ƁA��Ԃ̔ɉ؊X�̐l�o���������A�����s�ł�2022�N3���ɂ܂h�~���d�_�[�u����������钼�O�ɔ��35���ȏ�̑�����������ȂǁA2021�N���̃s�[�N�Ɠ�����������悤�Ȓn������邱�ƁA����ɋC���̏㏸��J�̓��������Ȃ邱�Ƃɂ���ĉ����ł̊����������Ȃ邱�Ƃł��B
�����N�`������ ���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɒቺ
���݁A�����̎�̂ƂȂ��Ă���I�~�N�������ɑ��ẮA���N�`���̌��ʂ����Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɉ����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�C�M���X�̕ی����ǂ̃f�[�^�ł́A���Ƃ��t�@�C�U�[�̃��N�`����2��ڎ킵3��ڂɃt�@�C�U�[�����f���i�̃��N�`����ڎ킵���ꍇ�A�V�^�R���i�E�C���X�̔��ǂ�h�����ʂ�3��ڂ̐ڎ킩��2�T�Ԍォ��4�T�Ԍ�ł�70�����x����܂����A3�����قnj�ɂ�50�����x�A4�����قnj�ɂ�30�����x�ɉ�����Ƃ������Ƃł��B����A�������ďǏ��������@�Ɏ���̂�h�����ʂ́A3��ڂ̐ڎ킩�甼�N�ȏソ���Ă�70������Ƃ���Ă��܂��B���Ɖ�́A������h�����ʂ͂�葁���ڎ�����l���獡�㉺�����Ă����ق��A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ċl�������Ɖu�ɂ��Ă�������ʂ����X�ɉ������Ă����Ɨ\�z�����Ƃ��Ă��܂��B
���uBA.5�v�ւ̒u������� �Ď��K�v��
����܂ł͂�芴���͂̋����ψكE�C���X�ɒu������邱�ƂŊ������g�債�Ă��܂������A�����ł͂���܂łƕς�炸�I�~�N�������́uBA.2�v���قڂ��ׂĂ��߂Ă��܂����B�����A�A�����J�ȂǂŎ嗬�ƂȂ��Ă��Ă��Ă��L����₷���Ǝw�E�����uBA.5�v���s�������Ō��o�����悤�ɂȂ��Ă��Ă��āA����u������肪�i�ނƂ݂��邱�Ƃ�����Ɖ�͓����̊Ď��𑱂��邱�Ƃ��K�v���Ƃ��Ă��܂��B�����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́u�wBA.5�x�͌��o�����̂͂܂���������̂́A�N���X�^�[���������������ȂNJe�n�ő����n�߂Ă���B�A�����J�⒆���ł��wBA.5�x�ւ̒u������肪���Ȃ�i��ł��āA���ۑɘa����钆�ł͍�����{�ł����ӂ��K�v���v�Ǝw�E���܂����B
����r�I���K�͂ł̑��� �J��Ԃ�
�u��6�g�v�ł́A�I�~�N�������̍L����ł��ĂȂ��K�͂ł̊����g�傪�N�������ƁA2022�N 2�����{�ȍ~�͌����X���������Ă��܂����B�������̊Ԃ��A3�����{����̂��悻20���ԁA5�����{��1�T�ԗ]��͑������Ă��āA��r�I���K�͂ł̑����͌J��Ԃ���Ă��܂��B�܂��A�C�ɂȂ�̂������������ȎႢ����̊����ł��B6�����{�ȍ~�A�����s�Ȃǂł͊����҂ɐ�߂�20��̊�����20�����������Ă��Ă��܂��B����܂ł̊����g��ł́A�Ⴂ����ň��H�̏�Ȃǂ���čL���������ƁA����҂Ȃǂق��̐���Ɋg�傷��`�Ŋ����̋K�͂��傫���Ȃ�X���������܂����B
���u�w��7�g�x�ɂȂ��邩�܂��킩��Ȃ�������v
����A�����X�����n�܂��Ă��炨�悻1�T�Ԃ������Ă��܂����A�_�c���C�����͍���������̂��A���ꂩ�琔�T�Ԃ̐��ڂ𒍈Ӑ[������K�v������Ǝw�E���܂��B�_�c���C�����́u����̑������ꎞ�I�Ȃ��̂��A�w��7�g�x�ɂȂ��邩�͂܂��킩��Ȃ��B���N�`�����ʂ����ԂƂƂ��ɉ����邱�Ƃ��̊ɘa�ɉ����āA���̂Ƃ���̋}���ȋC���㏸�Ŋ��C���s��ꂸ�A�����ł̊����������Ȃ��Ă��邱�Ƃ������v���ɂȂ蓾��B�ꎞ�I�ȑ����ɂƂǂ߂邽�߂ɂ�������ւ̈ӎ���Z���ԋ��߂Ă��炢�A�ҏ��̒��ł��M���ǂ�����Ȃ���\�Ȃ����芷�C�����A�̒��������ꍇ�͐ڐG���T����ȂNJ�{�I�ȑ�����Ăق����B�܂��A���ɍ���҂͏d�lj���h�����߂ɂ�4��ڂ̐ڎ�����ЎĂق����v�Ƙb���Ă��܂��B�@ |
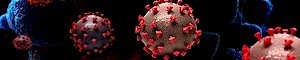 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 3546�l�����m�F �O�T��1365�l�� �@7/1
�����s����7��1���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̋��j�����1300�l�]�葽��3546�l�ŁA14���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
�����s��1���A�s���ŐV����10�Ζ�������90���3546�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j�����1365�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�14���A���ł��B1���܂ł�7���ԕ��ς�2737.9�l�ŁA�O�̏T��144.5���ł����B1���Ɋm�F���ꂽ3546�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�23.5���ɂ�����832�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�236�l�ŁA�S�̂�6.7���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A�O�����1�l������4�l�ł����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ80��̒j��1�l�ƁA70��̏���1�l�̍��킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i �V����2135�l�����m�F �@7/1
���{��1���A�V����2135�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�770�l�����܂����B����ő��{���̊����҂̗v��101��6315�l�ƂȂ�܂����B����A�S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�6��30������2�l������3�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����1543�l�����m�F �@7/1
���ꌧ��1���A�V����1543�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B��T���j���Ɣ�ׂ�368�l�����A7���A���őO�̏T�̓����j���Ɣ�ׂđ������܂����B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�͍̂��킹��25��5102�l�ƂȂ�܂����B
|
���V����2��3156�l�R���i�����c�}���̓����A�����҂�77�����u�a�`�E5�v �@7/1
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�1���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����2��3156�l�m�F���ꂽ�B���҂�21�l�B�d�ǎ҂͑O���Ɠ���52�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�3546�l�������B�O�T�̓����j������1365�l�����A14���A����1�T�ԑO���������B�s�ɂ��ƁA����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�2738�l�ŁA�O�T����44�����B�d�ǎ҂͑O������1�l����4�l�ŁA70�`80�Α�̒j��2�l�̎��S�����������B
�����҂��}�����Ă��铇�����ł́A355�l�̊������m�F�B����6��22�`27���̊����҂��璊�o�������̂��Q�m����͂����Ƃ���A77�����I�~�N�������̐V�n���Ŋ����͂���苭���Ƃ����u�a�`�E5�v�Ɋ������Ă����B
|
���V�^�R���i�����ҁg�����̗v���h�@�u�����Ŋ��C�s�\���v���Ƃ��w�E�@7/1
1���A�����s�ŐV����3546�l�̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��m�F����܂����B6��24������1365�l�����A14���A���őO�̏T�̓����j���̐l��������܂����B�����g��̈���ɂ��āA���Ƃ́g��[�̂�������������ߐ�A���C���s�\���ɂȂ邱�Ɓh���w�E���܂������A�M���Ǒ���s���Ȃ���A�ǂ̂悤�Ɋ��C����������̂ł��傤���H
1���A�X�̐l���S�z���Ă����̂́A�S���̐V�^�R���i�����Ґ��������X���ɂ��邱�Ƃł��B
�u�R���i����N�w�ɂ��L�܂��āA���킢�v�u(�����Ґ���)���\����������āA�ً̂̋}���Ԃ��炢�܂ő����邩���ȂƁv�Ȃǂƕs���̐���������܂����B
�����s��1���A�V����3546�l�̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��m�F����܂����B6��24������1365�l�����A14���A���őO�̏T�̓����j���̐l��������܂����B
�����E�k��ɂ���u���Ƃ����q�_�J���ȊO�ȃN���j�b�N�v�̔��M�O���ł́A20�ォ��30��̊��҂��������Ă��܂��B
�@���u���̂��̒�����A�̂ǂ��ɂ������H�v
28�@�j���u�ŏ��͋ł��ꂽ���ȂƁB�ΏƂ��Ă���ȂƂ��������������āA�鑪������38�x�ȏ゠���āA�ŏ��A�M���ǂ��ȂƎv�����v
�����̌��ʂ́A�V�^�R���i�E�C���X�z���ł����B
���Ƃ����q�_�J���ȊO�ȃN���j�b�N�@�ɓ������@���u���̈�T�Ԃ́A�����Ȃ��1.5�{�߂������҂̗z�����̏㏸�������܂����v
1���ߌ�2������A�����s�̏��r�S���q�m���́u�ҏ��̒��ŃR���i���܂��Ԃ�Ԃ��A�킢�������Ă���Ɓv�Əq�ׂ܂����B
�����͂���s�̉�c�ŁA�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v�Z���^�[���́u��[�̂������������A�ߐ��������ɂ����肷��B���C�������̂ŁA�������X�N���オ��Ɓv�ƁA�g�g��̈���h���w�E���܂����B
�ҏ��������o�̍��N�̉ẮA��[�ŕ�����ߐ�A���C���s�\���ɂȂ邱�ƂŁA�������X�N�����܂�Ƃ����̂ł��B�X�̐l���u�R���i�Ƃ������́A��������D�悵�Ă��āA���C�Ƃ��͂��Ă��Ȃ��ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�M���Ǒ�����A�ǂ����C����������̂ł��傤���B
���Ƃ����q�_�J���ȊO�ȃN���j�b�N�@�ɓ������@���u��@�����܂��g���āA���߂̑��̌��Ԃ���Η�������āA�O�ɓ������Ƃ��v
�܂��͊��C����A�G�A�R���͂����܂܁A�����킸���ɊJ���܂��B�����āA���Ɍ����Đ�@��u�����ƂŁA�O�̋�C����荞�ނ��Ƃ��ł��A�����I�ɕ����S�̂̊��C���ł���Ƃ������Ƃł��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1�l���S 3616�l�����m�F �O�T��1400�l�]�� �@7/2
�����s����2���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓y�j�����1400�l���܂葽��3616�l�ŁA15���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�����s��2���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3616�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B
1�T�ԑO�̓y�j�����1456�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�15���A���ł��B2���܂ł�7���ԕ��ς́A2945.9�l�ŁA�O�̏T��150.0���ł����B2���m�F���ꂽ3616�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�22.1���ɂ�����798�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�284�l�ŁA�S�̂�7.9���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A1�����1�l������5�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ80��̒j��1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
���V�^�R���i �k�C������626�l���� 1�������Ԃ�ɑO�T�䑝�@7/2
�����ł�2���A�V����626�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A�O�T�̓����j������41�l�����Ȃ�܂����B�O�T�̓����j���Ƃ̔�r�ő����ɂȂ����̂͂��悻1�������Ԃ�ł��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��282�l�A�Ύ�n����84�l�A�_�U�n����41�l�A����s��35�l�A���َs��33�l�A�\���n����31�l�A�I�z�[�c�N�n����28�l�A���n����20�l�A�����n����16�l�A��m�n���Ə@�J�n���ł��ꂼ��12�l�A�n���n����9�l�A���H�n����8�l�A���M�s��4�l�A��u�n���ƍ����n���ł��ꂼ��3�l�A���G�n����2�l�A�O�R�n����1�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\����2�l�̍��킹��626�l�ł��B
�V�K�����Ґ��͑O�T�̓����j���Ɣ�ׂ�41�l�����܂����B
1���܂�48���A���őO�T�̓����j����������Ă��܂������A���Ƃ�5��14���ȗ��A���悻1�������Ԃ�ɑ����ɓ]���܂����B
����A2���͓����ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���Ď��S�����l�̔��\�͂���܂���ł����B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������5�l�������A��������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
�܂��A�S�̂̂��悻�����ɂ�����301�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
��������3157���ł����B
����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�18��7680�l���܂ނ̂�38��3027�l�A�S���Ȃ����l��2096�l�A���Â��I�����l��37��5708�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i ���{�ŐV����2545�l�̊����m�F 1�l�����S�@7/2
���{��2���A�V����2545�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�1000�l���܂葝���܂����B�܂��A���Ƃ�2���ɔ��\����3�l�ɂ��Ă͏d�����Ă����Ƃ��āA�����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��101��8857�l�ƂȂ�܂����B�܂��A1�l�̎��S�����\����A���{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͂��킹��5211�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂́A30���ƕς�炸3�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�������1695�l�R���i�����@�O�T��196�l���@7/2
���ꌧ��2���A�V����1695�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓y�j��(6��25��)��1499�l�ɔ�ׂ�196�l�����A8���A���őO�T�̓����j�����������B�v�����҂�25��6797�l�ƂȂ����B�N���X�^�[�͐V����2�Ⴊ�m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ��͑O�����_��679.61�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ�����������265.01�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����44.5��(���@�Ґ�281�^�a����631)�ŁA�d�ǎҗp��13.3��(���@8�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����39�l�̕��������B
|
���V�^�R���i �S����2��4000�l�������@���� 4���A��3000�l���� �@7/2
2���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂́A2��4,904�l�������B�����s�ł�3,616�l�̊������m�F����A��T�y�j��(6��25��)����1,456�l�����A4���A����3,000�l���������B�S���Ŋm�F���ꂽ�����҂�2��4,904�l�A���҂�11�l�������B
|
���R���i���Ċg��̂������@32�s�{���Ŋ��������A�L����uBA.5�v�@7/2
�V�^�R���i�E�C���X�̊������A�S���e�n�ōĂё�������B�V�K�����Ґ���5�����{���猸���X���������Ă������A1�T�ԕ��ς�����ƁA32�s�{���őO�T��葝��(6��30�����_)�B��Ë@�ւł͖ҏ��ɂ��M���NJ��҂Ƃ��킹�đΉ��ɒǂ��Ă���B���������L����₷���Ƃ����I�~�N�������̂ЂƂuBA.5(�r�[�G�[�t�@�C�u)�v�ւ̒u������肪�i��ł���A���Ƃ́u���l���[�h�����ޒ��A�������Ɋ����҂������鋰�ꂪ����v�ƌx������B
�����̒���1�T�Ԃ�����̐V�K�����Ґ��́A6��21���ɖ�1�J���Ԃ�ɏ㏸�ɓ]�����B���������_�ŁA�R�A�A��B�A�l���A�ߋE��8�����O�T��1�E5�{�ȏ�A�����s�Ƒ��{��1�E4�{��Ə㏸�X���������B
�v���̂ЂƂ��uBA.5�v�̍L���肾�B�����s���N���S�����Z���^�[��PCR�����ł́A6��20���܂ł�1�T�Ԃ�BA.5�̋^�����25�E1%���߁A�O�T��13�E6%����{���B�嗬������BA.2�ɑ��萨�͂�L������BBA.5�ɂ��āA���������nj������̗�؊�E�����lju�w�Z���^�[���́A���o�����Ȃ��s�m�����������Ƃ����A�u(�S���I��)���o������7���㔼�ɂ͔�������v�Ɨ\�z����B
���B���a�\�h�Ǘ��Z���^�[(ECDC)��BA.5���ABA.2����12�`13%�����҂������₷���ƕB�����A�d�Ǔx�����܂钛��͂Ȃ������Ƃ����B���{�Ǝ����̃|���g�K���ł́A5����BA.2����BA.5�ւ̒u������肪�i�ނƓ����ɁA1���l�O�ゾ����1��������̊����Ґ����ꎞ2��7��l�܂ő������Ă���B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1�l���S 3788�l�����m�F �O�T��1784�l���� �@7/3
�����s����3���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̓��j�����1700�l�]�葽��3788�l�ŁA16���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
�����s��3���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3788�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����1784�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�16���A���ł��B3���܂ł�7���ԕ��ς́A3200.7�l�ŁA�O�̏T��158.6���ł����B�m�F���ꂽ3788�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�21.1���ɂ�����801�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�259�l�ŁA�S�̂�6.8���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A2���Ɠ���5�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ90��̒j��1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i �V����2010�l�����m�F �@7/3
���{��3���A�V����2010�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�876�l�����܂����B����ő��{���̊����҂̗v��102��0867�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�2���ƕς�炸3�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����1196�l�����m�F �@7/3
���ꌧ��3���A�V����1196�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�����Ŋ������m�F���ꂽ�͍̂��킹��25��7993�l�ɂȂ�܂����B
|
���R���i���������Ċg��c�u�a�`�E5�v�u�������Ń��N�`�����ʎ�܂� �@7/3
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂��A�S���ōĂё�������B�ψي��u�I�~�N�������v�̂����A�����͂���苭���Ƃ����u�a�`�E5�v�ւ̒u������肪�����̈���B�a�`�E5�́A���N�`���ڎ�ɂ�銴���\�h���ʂ��キ�Ȃ�ق��A�Ċ������X�N�����܂�Ƃ�������������A���Ƃ͌x�������߂Ă���B
�S���̐V�K�����Ґ��́A2���܂ł�1�T�ԂőO�T��1�E34�{�ɑ������B������2�E81�{�A������1�E5�{�ȂǁA33�s�{���őO�T���������B�����s�ł́A�����҂ɐ�߂�a�`�E5�^���̊������A6��20�����_��25�E1���ɋ}�����Ă���B
���N�`����ڎ킷��Ɗ�����h���̓��́u���a�R�́v�ʂ��㏸����B�����A�ăn�[�o�[�h��Ȃǂ̌����ł́A�a�`�E5��A����ɕψق����Ă���u�a�`�E4�v�ɑ���R�̗ʂ́A�����̃I�~�N�������u�a�`�E1�v��3����1���x�ɂ��������Ȃ����Ƃ��킩�����B
�����̌����`�[�����A�a�`�E5�Ȃǂ��a�`�E1�ւ̊����œ���ꂽ�Ɖu��������₷���Ƃ̉�͌��ʂ��A�Ȋw���l�C�`���[�Ŕ��\�����B�a�`�E1�͍����ł�2�����s�[�N�ƂȂ����u��6�g�v�������N�����Ă���A����Ċ������X�N�����܂鋰�ꂪ����B
������Ȃǂ́A�a�`�E5�Ȃǂ̊����͍͂����Ŏ嗬�́u�a�`�E2�v����1�E2�{�����A�a����(�d�lj����X�N)�������\��������Ɣ��\���Ă���B�`�[���̍������E�����勳��(�E�C���X�w)�́A�u�V�^�R���i�E�C���X�́A������ψّ̂̓o��Ɗ����Ґ��̑������J��Ԃ����ꂪ����v�Ƙb���Ă���B
|
 |
�������s �V�^�R���i 1�l���S 2772�l�����m�F �O�T��1255�l�� �@7/4
�����s����4���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̌��j�����1200�l�]�葽��2772�l�ŁA17���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
�����s�́A4���s���ŐV����10�Ζ�������90���2772�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j�����1255�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�17���A���ł��B4���܂ł�7���ԕ��ς́A3380.0�l�ŁA�O�̏T��162.4���ł����B4���Ɋm�F���ꂽ2772�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�19.8���ɓ�����549�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�192�l�ŁA�S�̂�6.9���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A3�����1�l������6�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ80��̒j��1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 1150�l�����m�F �O�T���j����2�{�߂��ɑ��� �@7/4
���{��4���A�V����1150�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA2�{�߂��ɑ����܂����B����A���{��3���ɔ��\����1�l�ɂ��āA�d�����Ă����Ƃ��Ď�艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��102��2016�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�3���ƕς�炸3�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����{�uBA.4�v�{���ŏ��߂Ċm�F�Ɣ��\
���{�͐V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̌n���̂ЂƂŁuBA.4�v�ƌĂ��V���ȕψكE�C���X���{���ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B���{�ɂ��܂��ƁA�{���̈�Ë@�ւ���f���挎���{�ɐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�A�C�O�ւ̓n�q���̂Ȃ�1�l�ɂ��āA���̌�̃Q�m����͂Ŋ��������̂��uBA.4�v�ƌĂ��ψكE�C���X���������Ƃ��m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�{�͔N���ʂ𖾂炩�ɂ��Ă��炸�A�Ǐ�͌y���Ƃ������Ƃł��B
�uBA.4�v�͏]���̃I�~�N�������ɔ�ׂďd�Ǔx�Ȃǂɑ傫�ȍ���������Ƃ����Ȋw�I�ȏ؋��͌����_�ł͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B�uBA.4�v�́A����܂łɉ��R���╺�Ɍ��ȂǂŊm�F����A���{���Ŋm�F�����̂͋�`�ł̌��u���̂����č����߂Ăł��B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 4�l���S �V����668�l�����m�F �@7/4
���ꌧ��4���A�V����668�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�͍̂��킹��25��8661�l�ɂȂ�܂����B�܂�����70�ォ��90��܂ł�4�l�̎��S�\���A�����ŖS���Ȃ����l�͍��킹��491�l�ɂȂ�܂����B
|
��������1��6808�l���R���i�����A�s����1�T�ԑO����قڔ{���@7/4
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�4���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��6808�l�m�F���ꂽ�B���҂�14�l�B�d�ǎ҂�62�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�2772�l�B�O�T�̓����j������1255�l�����A17���A����1�T�ԑO���������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�3380�l�őO�T����62���������B�d�ǎ҂�6�l�ŁA80�Α�̒j��1�l�̎��S�����������B
���{�ł́A1150�l�̐V�K�����҂��m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j�����炨�悻2�{�ƂȂ�A13���A����1�T�ԑO���������B�@ |
 |
�������s�ŐV����5302�l�̊����m�F ��T�Ηj�̔{�ȏ�Ɂ@7/5
5���A�����s���m�F�����V�^�R���i�̐V�K�����Ґ���5302�l�������B��T�̉Ηj��(2514�l)�Ɣ�ׂĔ{�ȏ���L�^���A4��28���ȗ����悻2�J���Ԃ��5000�l���������B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A10�Ζ�������100�Έȏ��5302�l�B��T�̉Ηj������2788�l�����A18���A���őO�̏T�̓����j�����������B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�3778�l�őO�̏T��174.9%�ƂȂ����B
5�����_�̐V�^�R���i���җp�a���̎g�p����22.6��(1143�l�^5047��)�A�I�~�N�������̓����܂����d�ǎҗp�a���g�p����3.6��(15�l�^420��)������(�ǂ��������͌����_�̍ő�m�ی�����)�B�d�ǎ҂͑O������1�l����7�l�B�܂��A80���90��̒j��3�l�̎��S���m�F���ꂽ�B�s�̒S���҂́u���߂��߂���C�������A�G�A�R���Ȃǂ��g���M���ǂɒ��ӂ��Ȃ�������܂߂Ȋ��C�����Ăق����v�Ɗ����h�~����Ăт����Ă���B
|
�����{�ŐV����4523�l�̊����m�F�@��T�Ηj�����2222�l�����@7/5
7��5���A���{�ŐV����4523�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B�܂��A4�l�̎��S�҂��m�F����܂����B1�T�ԑO��6��28��(��)��2301�l�̊����҂��m�F����Ă��āA�O�T����2222�l�������Ă��܂��B1���̐V�K�����Ґ���4000�l����͍̂��N5��10���Ɋm�F���ꂽ4240�l�ȗ��A��2�����Ԃ�ł��B�O�T�̓����j���ŐV�K�����Ґ�������̂́A14���A���ł��B
|
�����m���u�����Ċg��̌X���v�@��7�g�̉\�����@7/5
���{�̋g���m���m����5���A�{���̐V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ��āA�u�����Ċg��̌X���ɂ���v�Ƃ̌������������B�{���ŋL�Ғc�̎�ނɓ������B
�{���ł́A6��25����20�`30��̐V�K�����Ґ������ƂɊ����Ċg��̒���������u������Ԏw�W�v�̌x�������ɓ��B�B���߂̐V�K�����Ґ���7���ԕ��ς�2396�E71�l�ŁA1�T�ԑO(6��28�����_)��1359�E43�l����1�E76�{�ɑ��������B
����4���ɂ̓I�~�N�������h���^�́u�a�`�E4�v�̊����҂����m�F����Ă���A�g�����́u(�h���^��)�u��������Ă������Ŋg�傪�N���Ă���\�������ɍ����v�ƕ��́B�u�����7�g�ɂȂ�\���͏\���ɂ���v�ƌx�������߂��B
|
���k�C������561�l�����m�F 4���A���őO�T�䑝�@7/5
5���A�����ł͐V����561�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B4���A���őO�̏T�̓����j��������A�����X���������Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s��162�l�A�Ύ�n����74�l�A����s��66�l�A�I�z�[�c�N�n����33�l�A���َs��31�l�A���n����30�l�A���M�s��27�l�A�\���n����24�l�A���H�n����22�l�A��m�n����21�l�A�_�U�n����20�l�A�����n����16�l�A�n���n����14�l�A�����n����8�l�A���G�n����4�l�A��u�n���Ə@�J�n���ł��ꂼ��2�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��2�l���܂߂�5�l�́A���킹��561�l�ł��B
�V�K�̊����Ґ��͐�T�̉Ηj�����140�l�����A4���A���őO�̏T�̓����j���������Ă��āA�����X���������Ă��܂��B
����A5���A�����ł͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���Ď��S�����l�̔��\�͂���܂���ł����B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������24�l�������A�����ǂ�3�l�ŁA���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�܂��A�S�̂�4������258�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������2928���ł����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�18��8424�l���܂ނ̂�38��4612�l�A�S���Ȃ����l��2096�l�A���Â��I�����l��37��7451�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
������2266�l�R���i�����@��T�Ηj�����522�l���@7/5
���ꌧ��5���A�V����2266�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̉Ηj��(6��28��)��1744�l�ɔ�ׂ�522�l�������B�v�����҂�26��927�l�ƂȂ����B1���̐V�K�����҂�2000�l����̂�5��25���ȗ��B�܂��A�V����1��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���4�����_��692.34�l�ňˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ�����������363.84�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����48.2��(���@�Ґ�304/�a����631)�ŁA�d�ǎҗp��16.7��(���@10/�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�͐V����21�l�̕��������B
|
���V�^�R���i�����ҁA5���ȗ���3���l���@�����A���Q�A�F�{�͉ߋ��ő��@7/5
�V�^�R���i�E�C���X�̍��������҂�5���ߌ�7�������݁A�V����3��6189�l���m�F���ꂽ�B3���l����̂�5��26���ȗ��A��1�J���Ԃ�B�O�T�̓����Ηj��(6��28��)�̖�1�E9�{�ɂ�����A1��6808�l���������B�����͂������Ƃ����I�~�N�������̂ЂƂuBA.5(�r�[�G�[�t�@�C�u)�v���L�����Ă���Ƃ݂���B
�V�K�����Ґ����O�T������̂�15���A���B�����A���Q�A�F�{��3���͉ߋ��ő��������B���҂͐V����20�l���m�F���ꂽ�B
�V�K�����҂̓s���{���ʂł͓����s��5302�l���ő��������B�s����5��l������̂�4��28���ȗ��Ŗ�2�J���Ԃ�B�O�T�̉Ηj���̖�2�E1�{�ŁA18���A���őO�T���������B
���{�ł��O�T�Ηj������قڔ{����4523�l�̊������m�F�B���m�����A15���A���őO�T��ő����ƂȂ�2481�l���m�F�����B�呺�G�͒m���́u���炩�ɑ�7�g�ɓ������ƌ����Ă����v�Ƃ̔F�����������B
��������755�l�A���Q���ł�582�l�A�F�{����1589�l�̊������m�F�B���ꂼ��̌��ʼnߋ��ő��������B
|
���S�������Ґ���5��20���ȗ���3��6000�l���� ���Q�E�����E�F�{�ʼnߋ��ő��@7/5
�V�^�R���i�E�C���X�̊������Ċg�債�Ă���B
ANN�̏W�v�ɂ��ƁA�S���ł��傤�V�^�R���i�E�C���X�ւ̐V���Ȋ����҂��A5��20���ȗ��A3��6000�l�����B
�����ł��傤�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�5302�l�ŁA�O�̏T�̉Ηj���ɔ�ׂ��2�{�ȏ�ƂȂ�A�ق��ɂ�����4523�l�A���m��2481�l�ƂȂ����B���Q�͉ߋ��ő���582�l�A�����ʼnߋ��ő���755�l�A����ɁA�F�{�ł��ߋ��ő���1589�l�̊������m�F����Ă���B
ANN�̂܂Ƃ߂őS���̊����҂͌ߌ�7���̎��_��3��6176�l�ƂȂ�A�S����3��6000�l����̂́A5��20���ȗ��ƂȂ�B
|
���V�^�R���i�����ґ��� ���Ɓg1�A2�����͏㏸�X���������h�@7/5
�����s����5���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̉Ηj����2�{�]��ƂȂ�5302�l�ŁA18���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B
���݂̊����ɂ��č��ۈ�Õ�����w�̏��{�N�Ǝ�C�����́u�����Ȑ�������������đ����̐l�̓����������ɂȂ�A�ڐG�̕p�x�����܂��Ċ������₷�����N�����Ă���B�܂��A�w�a�`�D5�x�Ƃ��������͂������V���ȕψي����o�Ă��Ă���e�����Ă���Ǝv���v�ƕ��͂��܂����B
���̂����Łu����A���s����H�Ȃǂ̓����͏ꍇ�ɂ���ẮA����Ɋ����ɂȂ�\��������̂ŁA�����Ґ��͂��̂܂܂��炭1�A2�����͏㏸���Ă����\��������v�Əq�ׂ܂����B
����A���{��C�����͈�Ò̐��ɂ��āu���N�`���̌��ʂ������x�F�߂��邵���łɊ��������l������̂Ŋ��������Ƃ��Ă��d�lj����銄����������킯�ł͂Ȃ��B����A��Â̂Ђ����͂���قǑ傫�Ȃ��Ƃ͋N����Ȃ��ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu���ɉĂ͔M���ǂ̊��҂������A�M���ǂȂ̂��R���i�̊����Ȃ̂��������蕪���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA��Ì���͂��Ȃ荬������\���������B�R���i�̊������̂��̂ɂ���Â̂Ђ����͋N����Ȃ��Ă��A�M���ǂ��Ƃ��ɂ���ċ~�}�̑Ή��Ȃǂ��������ɒǂ����܂��\���͂���Ǝv���v�Ǝw�E���܂����B
�܂��A���{��C�����͔M���Ǒ��߂���Ȃ��ł̃}�X�N�̎g�����ɂ��āu�ǂ̃^�C�~���O�ł��}�X�N���O����킯�ł͂Ȃ����A���Ȃ��Ƃ������ł͊������X�N�͂Ȃ����낤�Ƃ����Ƃ���ł͂ނ���t�ɂ��̏��������́A�ϋɓI�ɊO�����Ƃ��厖���B���V���Ń}�X�N�����Ă���ƔM�������邵�A���������ɂ����Ȃ�̂ŁA�����n���������}�X�N�̎g�����ɕς��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
����ɕ����̊��C�ɂ��āu��[���g���A���C���T���Ă���Ƃ���������Ǝv�����A�����̐l�������W�܂��ĉ�b��������悤�ȏꏊ�͊��C�����Ȃ��ƃ��X�N�͍����Ȃ��Ă���v�Əq�ׁA��[�̎g�p���ɂ����C���K�v���Ƃ����F���������܂����B
|
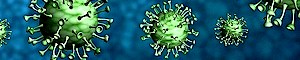 |
�������̊����ҁA1�T�ԑO����{��5302�l�c�����E���Q�E�F�{�ʼnߋ��ő��� �@7/6
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�5���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ȂǂŐV����3��6189�l�m�F���ꂽ�B�����A���Q�A�F�{��3���ʼnߋ��ő����X�V�����B�S���̎��҂�20�l�A�d�ǎ҂�60�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�5302�l�B�O�T�̓����j������{�����A18���A����1�T�ԑO���������B�V�K�����҂�5000�l����̂�4��28��(5392�l)�ȗ��B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�3778�l�ŁA�O�T����75���������B80�`90�Α�̒j��3�l�̎��S�����������B
���{�̐V�K�����҂�4523�l�ŁA�O�T�̓����j������2222�l�������B
��������755�l�A���Q����582�l�A�F�{����1589�l�̊������������A���ꂼ��1��������̊����Ґ����ߋ��ő��ƂȂ����B
|
���R���i������ �S��3���l���A�s���{���@�S�����s�x����7���O���ɔ��f �@7/6
������5���̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂��A�O�̏T���{���������Ƃ��A���r�m����6�����A�x�������������B�����s��5���̐V�K�����҂́A5,302�l�ŁA�O�̏T���2�{�ȏ㑝���Ă���B
���r�m���u�z���ɂȂ�����ł��ˁA���Ȃ葬���X�s�[�h�ōL�����Ă��Ă���܂��v
���r�m���́A2��ڂ̃��N�`���ڎ�ɂ��\�h���ʂ��������Ă��邱�Ƃ���ǂ̃��X�N���w�E���A�Ⴂ�l�����̐ڎ���Ăт������B
����A���{���A�����̉��P�������ɁA7���O��������{����Ƃ��Ă����u�S�����s�x���v�̊J�n�����ɂ��ẮA�T�d�Ɍ������i�߂��Ă���B���{�W�҂́A�u7���O���ɔ��f����v�Ƙb���Ă��āA10���̎Q�c�@�I����̔��f�ƂȂ錩���݁B�܂��A�ʂ̐��{�W�҂́u�������S�����s�x��������āA�����g��̌��O�𑝂₷���Ƃ��Ȃ����낤�B�J�n��������������Ȃ�A�Ă��H�̂ǂ��炩���낤�v�Əq�ׂĂ���B |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 8341�l�����m�F �O�T��2.2�{�� �@7/6
�����s����6���̊����m�F��1�T�ԑO�̐��j����2.2�{�ƂȂ�8341�l�ł����B�O�̏T�̓����j��������̂�19���A���A2�{���鑝����5���ɑ�����2���A���Ŋ������Ċg�債�Ă��܂��B
�����s��6���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��8341�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j����2.2�{��4538�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�19���A���ŁA2�{���鑝����5���ɑ�����2���A���ł��B�܂������8000�l����̂͂��Ƃ�4��14���ȗ��ł��B6���܂ł�7���ԕ��ς�4426.6�l�ŁA�O�̏T��186.8���ƂȂ芴�����Ċg�債�Ă��܂��B8341�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������S�̂�22.9���ɓ�����1912�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�553�l�őS�̂�6.6���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�5�����1�l������8�l�ł����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ70��̏�����80��̒j���̍��킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����r�m���u�����ő�v
�����s�̏��r�m���͋L�Ғc�ɑ��u�����Ґ��̐L�ї���1.5���Ă���A�����ǂ̍L����̑����������Ă���v�Əq�ׂ܂����B
����A�s���̍��̕a���g�p���͑�6�g�ɔ�ׂ�ƒႢ�����ƂȂ��Ă��āA���r�m���́u��Â⌟���̐��Ȃǂ͐����Ă���B�����ő���s���ĖS���Ȃ�l�������ɂ�}���邩���|�C���g�ł���A�d�ǂɂȂ�l��}���邽�߁A�z���ƂȂ����l�����̃T�|�[�g�����Ă����v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŏ��r�m���́u3��ڂ̃��N�`����ł��Ă��Ȃ��l�́A2��ڂ̃��N�`���̌��ʂ������Ă���̂Œlj��ڎ�����肢�������v�ƌĂт����܂����B
|
�����{�̐V�^�R���i�A6���̐V�K����4621�l�@1�l���S�@7/6
���{��6���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�4621�l�m�F�����Ɣ��\�����B�����Ґ��͑O�T���j��(2222�l)�Ɣ�ׁA2399�l�������B�V����80��̒j��1�l�̎��S���������A�{���̗v���Ґ���5216�l�ɂȂ����B
6�����_�̏d�ǎ҂͑O������1�l����4�l�ŁA�d�����a�Ȃǂ������y�ǁE�����NJ��҂���܂ߏd�Ǖa��(605��)�̎����̎g�p����4.3%�ƂȂ����B�y�ǁE�����Ǖa���ɂ�658�l�����@���Ă���A�y�ǁE�����Ǖa��(3709��)�̎g�p����17.7%�ƂȂ����B�a���ɂ́A�m�ې����Ď��ۂɉ^�p���Ă�����̂��܂�ł���B
�V�K�����҂̂����A�����҂Ɠ������ďǏ���APCR���������Ɉ�t�̐f�f�ŗz���Ɣ��f���ꂽ�Z���ڐG�҂�56�l�������B����×{�҂�1��8063�l�B����ɂ��PCR�����Ȃǂ�1��7576�����{�����B
|
������A�R���i2241�l�����@2���A����2000�l�����@7/6
���ꌧ��6���A�V����2241�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̐��j��(6��29��)��1709�l�ɔ�ׂ�532�l�������B�v�����҂�26��3168�l�ƂȂ����B�܂��A�V����3��̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����҂�5�����_��727.48�l�ƂȂ�A�ˑR�Ƃ��đS���ő��B2�Ԗڂɑ�����������430.73�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����48.2%(���@�Ґ�304�^�a����631)�ŁA�d�ǎҗp��15.0%(���@9�^�a����60)�ƂȂ��Ă���B�ČR�W�́A�V����22�l�̊��������ꂽ�B
|
���k�C������821�l�����m�F 5���A���őO�T�䑝�@7/6
�����ł�6���A�V����821�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A1�l�̎��S�����\����܂����B�V�K�����Ґ���5���A���őO�T�̓����j��������A�����X���������Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s�œ��O��2�l���܂�353�l�A�Ύ�n����103�l�A�_�U�n����48�l�A�I�z�[�c�N�n����43�l�A���َs�œ��O��1�l���܂�42�l�A����s��38�l�A�\���n����32�l�A���n���Ƌ��H�n����29�l�A��m�n����20�l�A���M�s��18�l�A�n���n����17�l�A�����n����11�l�A�����n����10�l�A��u�n����9�l�A���G�n����4�l�A�@�J�n����2�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��11�l���܂߂�13�l�̍��킹��821�l�ł��B�V�K�����Ґ��͐�T�̐��j�����109�l�����A5���A���őO�T�̓����j���������Ă��āA�����X���������Ă��܂��B�܂��A����80��̏���1�l�����S�����Ɣ��\���܂����B���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������7�l�����������ǂ�3�l�ŁA���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�S�̂̔�������445�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������6359���ł����B
����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�18��8777�l���܂ނ̂�38��5433�l�A�S���Ȃ����l��2097�l�A���Â��I�����l��37��7993�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���R���i������4��5��l���A�O�T���j������قڔ{���@7/6
������6���A�V���ɕ��ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�����҂�4��5��l�����B4���l������̂�5��18���ȗ��B�O�T�̓����j������قڔ{�����A�S�s���{���ő��������B
|
���ǂ��Ȃ�H���N�́g�ċx�݁h�@�g��7�g�h���c�@�����Ґ��g3���l�h�����@7/6
�V�^�R���i�E�B���X�̊������Ċg�債�Ă��܂��B5�����\�̑S���̊����Ґ���5�����ȗ���3���l���܂����B�g��7�g�h�ւ̌��O�����܂钆�A�܂��Ȃ�����Ă���ċx�݂�O�ɁA�������ɋ��߂��Ă���s���Ƃ́[�B
�Ė{�Ԃ�O�ɏ������������Ȃ钆�A�V�^�R���i�E�C���X�̊������������𑝂��Ă��܂��B5���A���ŐV���Ɋm�F���ꂽ�����Ґ���4523�l�B��T�̉Ηj��(6��28��)�̖�2�{�ł��B
�X�̐l�u���`�I�{��ˁv�u�ԉΑ��ɂ͍s�������Ǝv���Ă����ł����ǁA�����Ґ��l���Ă��Ċ����ł����ˁv
���{�̊����Ґ���4500�l�����̂�4��12���ȗ��A��3�����Ԃ�ł��B�����҂̋}���ɐ��Ƃ́[�B
����w��w�@(��������w)�̍��ߌ��u�����u�a�@�E���̊����҂������Ă��Ă���̂ŁA�s���ł��������L�����Ă��Ă���ȂƊ�����B��ۂƂ��Ă͑S�Ă̐���ő����Ă���v
�N��ʂŌ��Ă݂�ƁA�ł������̂�10��ȉ���1534�l�B���̂ق��A���ׂĂ̐���ő����Ă���̂��킩��܂��B�����҂̋}���ɂƂ��Ȃ����O�����͈̂�Â̂Ђ����ł��B���݁A�a���g�p����15�D4���ƒႢ�������Ă��܂����A���E�L���s�̕ی����ł́[�B
�L���s�ی����̏������Y�����u�N��w�Ō�����20��A30��ƎႢ�l�������������A����1�T�Ԃ��炢�ɂȂ��Ă���ƍ���҂ɃV�t�g���Ă���B���炩�ɏ㏸�X��������܂��v
�Ȃ������҂������Ă���̂ł��傤���B�w�E����Ă���̂́A�V���ȕψكE�C���X�u�a�`�D5�v�ւ̒u�������ł��B
���ߋ����u���܂ł�(�I�~�N������)�a�`�D2�����L����₷���ƍl�����Ă���̂ŁA�����̃I�~�N�������Ɋ��������l�ł��a�`�D5�Ƃ��ɂ͊���������Ƃ����Ă���B���������Ӗ��ł́A��芴���҂������₷�����ɓ����v���̈�ɂȂ�v
�܂��Ȃ��n�܂�s���������Ȃ��ċx�݁B�������͂ǂ̂悤�ȑ���Ƃ�Ηǂ��̂ł��傤���B
���ߋ����u���Ƃ��A�H�����Ƃ鎞�̐l�����ŏ����ɂ��Ă��炤�Ƃ��A(��H��)���Ԃ�Z�����Ă��炤�Ƃ��B����A�a�`�D5���L�����āA��7�g�����鎞�ɂ͊��������肵������ƍs���Ă��������Ƃ������Ƃ́A������x�A���s�ɂ��킹�đΉ����Ă����K�v������܂��v
|
�����{ �V�^�R���i�����ґ� ����Ҏ{�݂Ȃ� �x�������v���ց@7/6
���{�́A�V�^�R���i�̊����҂��Ăё����Ă���Ƃ��āA�d�lj����X�N�̍�������҂���������{�݂Ȃǂɑ��A�E����Ώۂɂ������������܂߂ɍs���Ȃǂ��āA�x������苭�߂�悤�����ŗv�����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���{���ł́A���������A�V�K�z���Ґ����O�̏T�̓����j����2�{�قǂƂȂ�y�[�X�ő����Ă��܂��B
���{�́A�I�~�N�������̂����A��芴�����L����₷���Ǝw�E�����u�a�`�D5�v�Ȃǂւ̒u������肪������1�Ƃ݂Ă��āA�{�̃X�N���[�j���O�����ł́A�����̕ψي��ւ̊������^��ꂽ�l�́A�挎27�����獡��3���܂ł�1�T�Ԃ�26.9���ƁA���̑O��1�T�ԂƔ�ׂ�3�{�قǂ̊����ɑ������Ƃ������Ƃł��B
�����������āA���{�́A�d�lj����X�N�̍�������҂ւ̊�����}����K�v������Ƃ��āA����Ҏ{�݂���@���҂�������Ë@�ւɑ��A�x�������߂�悤�����ŗv��������j�����߂܂����B
��̓I�ɂ́A�E���Ȃǂ�Ώۂɂ������������܂߂ɍs���āA�E�C���X���������܂��Ȃ��悤�ɂ���ƂƂ��ɁA�������m�F���ꂽ�ꍇ�͑����Ɏ��Â��邱�ƂȂǂ����߂�Ƃ��Ă��܂��B
���{�̋g���m���͋L�҉�ŁA�u���_���[�W�̑傫������҂���x�̍����l�ɃE�C���X������Ȃ��悤�ɂ������B���ׂĂ̔N��ő����Ă��Ă���A��{�I�Ȋ�����̓O������肢�������v�Əq�ׂ܂����B
|
���V�^�R���i �gBA.5�e���� �����ґ����������Ȃ��h���Ɖ�� �@7/6
6���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��̔��\�́A�S����4��5000�l���܂����B1�T�ԑO�̂��悻2�{�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����s��6���A�s���ŐV����8341�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\�B1�T�ԑO�̐��j����2.2�{�ɑ����܂����B��Ë@�ւł́A���ґ����ɉ����A�����������̉e�����Ȃ���̑Ή��𔗂���P�[�X���łĂ��Ă��܂��B�M���ǂ��������Ă��邱�̎����̋�̓I�Ȋ������I�~�N��������1�uBA.5�v�̉e���A�����̍���̌��ʂ��ɂ��āA���Ƃɕ����܂����B
���s���N���j�b�N ���M�O����f�̊��ґ��� �R���i�z����������
�V�^�R���i�E�C���X�̊����������X���ɓ]����Ȃ��A�s���̃N���j�b�N�ł́A���M�O������f���銳�҂̐����������Ă��܂��B�����ڍ���ɂ���N���j�b�N�̔��M�O���ł́A���T�ɓ����Ď�f�ƌ�������]����l���������A1���̎�f�҂�1�����O��2�{�ƂȂ�20�l�]��ƂȂ��Ă��܂��B�������ʂ���t���ɂ܂Ƃ߂��ꗗ�\���݂�ƁA�挎��{�ɂ͌����������҂̂����z���ƂȂ�l��1���O��ł������A���������7���قǂ܂ő����Ă��܂��B6����38�x�̔��M�̏Ǐ�̂���30��̏�������f���A��t�����f������ӊ��╠�ɂ����邱�Ƃ������������PCR�������Ă��܂����B�܂��A�����甭�M�O���̎�f�����߂�d�b���������A�ߑO���Ɉ���̗\��g�����ׂĂ����ς��ɂȂ�܂������A���̌���d�b�����܂��A��t�̃X�^�b�t���Ή��ɒǂ��Ă��܂����B
���u�M���ǁv�Ŏ�f���V�^�R���i���������̃P�[�X��
�N���j�b�N�ɂ��܂��Ɗ����̑�6�g�ł͂̂ǂ̌������ɂ݂�i���銳�҂����������̂ɑ��A�ŋߎ�f���銳�҂́A���M��38�x�ȏ�ƍ����A����ӊ���i����l�������X���ɂ���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�ҏ�������������T�́A�u�M���ǂɂȂ����v�Ƃ��Ď�f�������҂��A���ۂ͐V�^�R���i�Ɋ������Ă����P�[�X��5�����������Ƃ������Ƃł��B���̂��߃N���j�b�N�ł͖�f�ŏ��ڂ�����������������ŁA�����̗������ꏊ�Ɉړ��������Ƃ��̒�������������M���オ�����肵���ꍇ�́A�M���ǂł͂Ȃ��V�^�R���i�₻��ȊO�̕a�C�̋^��������ƐT�d�Ɍ������Ă���Ƃ������Ƃł��B�u���R�N���j�b�N���ڍ��v�̉Ñ��m�u��t�́A�u���T�ɓ����Ă�����ɁA�}���ɔ��M�O���̎�f�������Ă���B���N�`���̕��y�ōēx�������g�債�Ȃ����Ƃ����҂��Ă������A�܂���ςȎ����������B���̎����̔��M�͔M���ǂ�ۊ����ɂ��x���Ȃǂق��̕a�C�̉\��������̂Ŗ�f�Ō��ɂ߂����ă~�X�Ȃ��Ή����Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă���v�Ƙb���Ă��܂��B
������������ ����Ń��N�`���ڎ�̎��g�݂�
�V�^�R���i�E�C���X�̊����������X���ɓ]���Ă��邱�Ƃ��A�s���ł͒n��̈�t������҂̎����K�₵��4��ڂ̃��N�`���ڎ���s�����g�݂��n�߂Ă��܂��B4��ڂ̃��N�`���ڎ�͑O��̐ڎ킩��5������������60�Έȏ�̐l�Ȃǂ�Ώۂɐi�߂��Ă��܂����A�ڎ���I�����l��6�����\���܂łőS���ł��悻130���l�ƂȂ��Ă��܂��B���ɍ���҂̒��ɂ͑̂��s���R�������茵�����������������肵�Đڎ���ɏo�������Ƃ�����l�����Ȃ�����܂���B���̂��ߓ��� �a�J��̍ݑ��Â̐��N���j�b�N�ł͐�T�����t�����ځA����҂̎����K�₵��4��ڂ̃��N�`���ڎ���s�����g�݂��n�߂Ă��܂��B���̂����S���ȂǂɎ��a������90��̒j���̎���ł͈�t���̒����m�F���������Ń��N�`����ڎ킵�A15���Ԃ̌��N�ώ@���s���Ă��܂����B�j���̍Ȃ́u���������ĂȂ��Ȃ��O�ɏo��ꂸ����Őڎ�����ĂƂĂ�������܂��v�Ƙb���Ă��܂����B���̃N���j�b�N�ł̓R���i�̎���×{�҂̉��f���s���Ă��܂����A�挎���{�ȍ~�A���҂��Ǐ�����������ĉ��f���˗�����P�[�X�������n�߂Ă���Ƃ������Ƃł��B�����̑�6�g�ł͂̂ǂ̒ɂ݂�i���銳�҂����������̂ɑ��A�ŋ߂͋�������ӊ��₨���f�A�����Ȃǂ̏Ǐ��i����P�[�X�������Ƃ������Ƃł��B�uGreen Forest�㊯�R�N���j�b�N�v�̊֒J�G�S�@���́u�����Ґ��������Ă��Ă��邱�Ƃ����f�̌���ł������Ă���B����������ȏ�g�債�Ă��܂��O�̍��̂����ɍ���҂��b����������l�ȂǏd�lj����X�N�������l�ւ̐ڎ���}�������v�Ƙb���Ă��܂����B
���e�n�Ŋ����ґ����֑Ή����铮��
�������� �Ɩ��Ђ����̕ی����ɐE��50�l��lj��������@���������̈���̊����Ґ����ߋ��ő���755�l�ƂȂ���5���A���͑��{����c���J���A���̂Ȃ��Ŋ����Ґ������ɑ������Ă���o�_�ی����Ŋ����҂ƘA�����Ƃ�Ɩ��Ȃǂ����Ă��邱�Ƃ�����܂����B���́A�o�_�ی����̋Ɩ����Ђ������Ă���Ƃ��āA5�����玖���E�̐E��50�l��lj��ʼn����ɏo�����Ƃ����߂�ƂƂ��ɁA������i�߂č��コ���50�l��lj����A�ی����̑̐����������邱�Ƃ��m�F���܂����B
�������� �Ǝ��̃R���i�x�����@�������ł�6�����\���ꂽ�V�K�����҂�2000�l���A�a���̎g�p����4���̎��_��15�����܂����B���̂��ߕ������́A6���A���Ǝ��̃R���i�x������܂����B�R���i�x��̔����́A�挎1���ɉ�������Ĉȗ��ł��B������ĕ����m���͋L�҉���A3���̉���⊷�C�ȂNJ�{�I�Ȋ�����̓O��ƂƂ��Ƀ��N�`���̐ڎ�△���̌����̊��p�Ȃǂ��Ăт����܂����B
����A�������͌����_�ł͈��H�X�ւ̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�Ȃǂ͗v�����Ȃ����j�ł��B
�����Ɓu�wBA.5�x�e���� �����Ґ������������Ȃ��v
���݂̊����ɂ��ĊC�O�̊����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́u�\�h�ɘa����Ă��邱�Ƃ�A�I�~�N��������1�Ŋ����͂���⋭���wBA.5�x�������Ă��邱�Ƃ��e�����Ă���̂ł͂Ȃ����B������x�A�����Ґ��������邱�Ƃ͔������Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B�uBA.5�v�ɂ����_�c���C�����́u���܂܂ŗ��s���Ă����^�C�v�̃I�~�N�������ɔ�ׂĊ����͂���⋭���A�Ɖu�������Ă���l���������Ă��܂����Ƃ�����B�wBA.2�x����u������邾���łȂ��A������x�A�����Ґ��������邱�Ƃ͔������Ȃ��B�e������̕ł͊��������ꍇ�̏d�Ǔx�͍��̂Ƃ��날�܂�ς�炸�A�]���̃I�~�N�������Ɠ����x���Ƃ���Ă���B�����A�����Ґ����ǂ�ǂ���A�d�ǂɂȂ�l���ł�̂ŁA���ӂ��Ă����K�v������v�Ǝw�E���܂����B���̂����ō���̌��ʂ��ɂ��āu���N�`���������ɂ����\��������ƌ����Ă����Ȃ�̐l���Ă��邽�߁A���Ƃ�1����2���ɃI�~�N�������̊������g�債�������̂悤�ɁA�����Ґ����}������\���͍����Ȃ��ƍl���Ă���B�a���g�p����d�NJ��Ҍ����̕a���̎g�p���𒍈ӂ��Ȃ���A������𑱂��邱�Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ܂����B
���u���߂Ƀ��N�`���ڎ�� �̂ǂ̒ɂ� ��������Έ�Ë@�֎�f�v
��̓I�ȑ�ɂ����_�c���C�����́u���Ȃ��Ƃ����N�`����2���Ă��Ȃ��l�͂��Ȃ肩����₷���Ǝv���������悭�A3��ڂ̐ڎ�𑁂߂ɎĂق����B����҂͎�����������4��ڂ̐ڎ�𑁂߂ɎĂق����B�܂��A�R���i�Ɋ��������Ƃ����M���ǂɂȂ����Ƃ������M�������邪�A�R���i�̏ꍇ�͂̂ǂ̒ɂ݂₹��������̂ŁA�����������Ǐ���Ί������^���Ĉ�Ë@�ւ���f���Ăق����B�܂��A�q�ǂ��̏ꍇ�A�Ă������Ђ����Ƃ�����A�M���o�����Ƃ�����Ώ����Ȃ̎�f��A��ǂŌ����L�b�g����肵�Č������邱�Ƃ��l���Ăق����v�ƌĂт����܂����B����Ɂu���Ƃ��͓씼���ŏH����~�ɋG�߂��ڂ鎞���ɁA�C���t���G���U�����s���Ă��āA���{�ł������������痬�s����\��������ƍl���āA�����Ă����K�v������v�Ǝw�E���܂����B
�����J�� �����̂Ɉ�Ò̐������ȂNj��߂�ʒm
�����J���Ȃ́A�V�K�����҂��S���I�ɑ����X���ɓ]���Ă���Ƃ��āA5����A�����̂ɑ��A��Ò̐��̐����Ȃǂ�i�߂�悤�ʒm���܂����B��̓I�ɂ́����M���҂Ȃǂ��m���Ɍ���������悤�Ή��ł����Ë@�ւ��g�[���A�������L�b�g�����O�ɔz�z���鏀���Ȃǂ��i�߂�悤���߂Ă��܂��B�܂��A������̊��҂������邱�Ƃ��z�肵�ĕa���̊m�ۂ�Վ��̈�Î{�݂��J�݂��鏀���Ȃǂ�i�߂�ƂƂ��Ɂ�����Ҏ{�݂���v��������Έ�t��Ō�t�Ȃǂ�h���ł���̐����m�ۂ���悤���߂Ă��܂��B����Ɂ�����×{�҂��}�������ꍇ�ɔ����A�n��̈�Ë@�ւƘA�g���āA���f�̂ق��A�I�����C���ɂ��f�Â⌒�N�ώ@�Ȃǂ��s���d�g�݂����Ăق����Ƃ��Ă��܂��B�����̂ق��M���ǂ̊��҂������Ă��邱�Ƃ���A�~�}����������ȏɊׂ�Ȃ��悤�V�^�R���i�ƒʏ�̈�ÂȂǂ𗼗����邱�Ƃ��Ăт����Ă��܂��B�����J���Ȃ́u����A�I�~�N�������̂�����芴�����L����₷���Ƃ����wBA.5�x�ɒu������肪�i�މ\��������B���N�`����3��ڐڎ�̌��ʂ����X�Ɍ������Ă��邤���A�ċx�݂ȂǂŐڐG�̋@������邱�Ƃ��\�z����A�����g��ɑΉ��ł���悤�����̂͑̐����������Ăق����v�Ƃ��Ă��܂��B�@ |
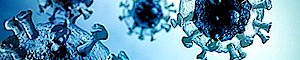 |
�������s �V�^�R���i �V����8529�l�����m�F �O�T2�{���̑������� �@7/7
�����s����7���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̖ؗj����2.4�{�ƂȂ�8529�l�ł����B5������́A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{���鑝���������Ă��āA�������}���Ɋg�債�Ă��܂��B
�����s��7���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��8529�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̖ؗj����2.4�{��4900�l�]�葝���܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�20���A���ł��B�܂��A5������́A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{���鑝���������Ă��āA�������}���Ɋg�債�Ă��܂��B7���܂ł�7���ԕ��ς�5127.7�l�ŁA�O�̏T��201.6���ł����B5000�l����̂́A���Ƃ�4��28���ȗ��ł��B7���Ɋm�F���ꂽ8529�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�24.1���ɂ�����2056�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�543�l�ŁA�S�̂�6.3���ł��B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A6�����2�l������6�l�ł����B���S���m�F���ꂽ�l�̔��\�͂���܂���ł����B
|
�����{ �V�^�R���i �V����4615�l�����m�F �O�T��2�{�ȏ� �@7/7
���{��7���A�V����4615�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{�ȏ�ɑ����Ă��āA4000�l������̂�3���A���ł��B����A���{�͂���܂łɔ��\����6�l�ɂ��āA�d�����������Ƃ��āA�����Ґ������艺���܂����B����ő��{���̊����҂̗v��103��5768�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�6������1�l�����āA5�l�ł��B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 2�l���S 2389�l�����m�F 3���A��2000�l�� �@7/7
���ꌧ��7���A�V����2389�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���A3���A����2000�l���܂����B
�܂��A��T�̖ؗj���Ɣ�ׂ�662�l�����Ȃ��Ă��āA4���A���őO�̏T�̓����j���������Ă��܂��B����ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�26��5557�l�ɂȂ�܂����B�܂��A���́A2�l�̎��S���m�F���ꂽ�Ɣ��\���A�����ŖS���Ȃ����l��493�l�ɂȂ�܂����B
|
���V�^�R���i �k�C������901�l�����m�F 2�l���S�@7/7
�����ł�7���A�V����901�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A2�l�̎��S�����\����܂����B�V�K�����Ґ���6���A���őO�T�̓����j��������A�����X���������Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s�œ��O��5�l���܂�417�l�A�Ύ�n����83�l�A����s��58�l�A�_�U�n����57�l�A���َs�œ��O��3�l���܂�43�l�A�\���n����37�l�A�I�z�[�c�N�n����34�l�A��m�n����31�l�A�����n����27�l�A�n���n����22�l�A���M�s��20�l�A�����n���Ə��n����17�l�A���H�n����16�l�A�@�J�n����9�l�A��u�n����5�l�A���G�n����4�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��1�l���܂߂�4�l�̍��킹��901�l�ł��B
�V�K�̊����Ґ��͐�T�̖ؗj�����256�l�����A6���A���őO�T�̓����j���������Ă��āA�����X���������Ă��܂��B�܂��A���͐��ʁE�N�����\��1�l��6���Ɏ��S�����Ɣ��\���A�D�y�s��80��̏���1�l������1���Ɏ��S�����Ɣ��\���܂����B���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������7�l�����������ǂ�1�l�ŁA���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�܂��A�S�̂̔�������488�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������5130���ł����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�18��9194�l���܂ނ̂�38��6334�l�A�S���Ȃ����l��2099�l�A���Â��I�����l��37��8483�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���g�R���i�����ҁh������2���A��2000�l���@���ꌧ�͉ߋ��ő��@7/7
�������ł�7���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2774�l�m�F����܂����B�܂����ꌧ�́A�ߋ��ő����X�V���Ă��܂��B�V�K�����҂̕ی����NJ��ʂ̓���́A�����s��1114�l�A�k��B�s��317�l�A�v���Ďs��134�l�A���̂ق��̒n���1209�l�ł��B�S���Ȃ����l�͂��܂���B�V�K������2774�l�́A1�T�ԑO�̖ؗj���Ɣ�ׂāA1400�l���܂葝���āA2000�l������̂�2���A���ł��B�a���g�p����17�D7���ŁA�O���ɔ��1�D4�|�C���g�オ���Ă��܂��B�d�Ǖa���g�p���́A6���ƕς�炸0�D5���ł��B
�܂��A���ꌧ�ł�7���A694�l�̊������m�F����A���Ƃ�4��19����680�l���āA�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
|
�����E�̃R���i�����ҁA1�T�Ԃ�460���l�c�v�g�n�u���E�E���E�n��Ŏ��g�ݕK�v�v�@7/7
���E�ی��@��(�v�g�n)�ɂ��ƁA���E�̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���3���܂ł�1�T�ԂŖ�460���l�ɏ��A4�T�A���ő��������B���ɂ���2�T�Ԃ�30���߂��������Ă���A�v�g�n�͊e���ɒ��ӂ𑣂��Ă���B
�����̔w�i�Ƃ��āA�I�~�N�������̐V�n���u�a�`�E4�v�Ɓu�a�`�E5�v�ւ̒u���������w�E���Ă���B�Ȃ��ł��a�`�E5�̊����͂������T�Ԃŋ}���ɑ����Ă���A�V�K�����Ґ��S�̂�52�����߂Ă���B�v�g�n�͗��n�����A�x���x���ł������u���O�����ψي�(�u�n�b)�v�Ƃ��ĊĎ��𑱂��Ă���B
�e�h���X�E�A�_�m�������ǒ���6���̋L�҉�ŁA���E�S�̂Ō��������������A�E�C���X�ψق◬�s�Ȃǂ̎��Ԃ������ɂ����Ȃ��Ă���Ǝw�E���A�u���E�A���A�n�惌�x���ł̎��g�݂��K�v���v�Ƒi�����B
|
 |
���V�^�R���i�����ҋ}���A�ҏ����e�����@��[�Ŋ��C�T���A�N���X�^�[���������@7/8
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����Ґ����㏸�ɓ]���Ă���B7���܂�3���A����500�l�ȏオ�m�F���ꂽ�B���͊����͂������I�~�N�������̔h���^�ւ̒u������肪�i���Ƃ���ȗv���Ƃ݂�B��[���������邽�߂Ɋ��C���T���A�N���X�^�[(�����ҏW�c)�����������Ȃǖҏ��̉e�����o�Ă���B�l�̉�����������ċx�݂��߂Â����A����Ȃ�g��Ɍx�������߂�B
���ɂ��ƁA6��1�`22���Ɍ��\���ꂽ�����̊����҂̂����A30�l�̌��̂���`�q��͂������ʁA�h���^�́u�a�`�E5�v�Ɓu�a�`�E2-12-1�v�Ɍv8�l���������Ă������Ƃ����������B���̂���3�l�͊C�O�n�q�҂Ƃ̐ڐG���Ȃ��A�������̎s�������Ɣ��f�����B�����͂̋����͍����Ŏ嗬�ƂȂ��Ă����u�a�`�E2�v��1�E2�`1�E3�{�Ƃ����B
�����̐V�K�����Ґ���6��20����43�l�܂Ō������B���͓�28����4�i�K����]�����u�X�e�[�W2(�Q��)�v�Ɉ��������A��H���̐l������(1�e�[�u��4�l�ȉ�)�����������B�����A���̌��200�l��ō��~�܂肵�A���T�ɓ����Ĉ�C�ɋ}�������B
�啪���w���̕����a�j����(59)�������NJw���͍s�������̊ɘa�ȂǂŁA�C�x���g���H�Ƃ������s���葽���̐l�Ƃ̐ڐG�@����������Ƃ��v���ƕ��́B�u�I�~�N�������͌y�ǂōςނƂ����������L�����Ă��邪�A�����҂�������A���̂��ƏǏ����Ȃ�l��������v�ƌx����炷�B
�ҏ������������ٗ�̓V����Ђ������B�G�A�R���g�p�̂��߂Ɏ�����ߐ��Ċ��C���s�\���ɂȂ�A���Ə���{�݂ȂǂŃG�A���]��(���V�����q)��������P�[�X���ڗ��Ƃ����B���͏펞2�J���ȏ�̑����J���A��@�ȂǂŎ����ɕ��̗�������邱�Ƃ����߂�B
���������́u����҂��b�����Ȃǂ̃��X�N���q������l�͊����������s�����K�v�B�d�lj���}���邽�߂ɂ�3�A4��ڂ̃��N�`���ڎ�����Ăق����v�Ƙb�����B
|
���R���i�u��7�g�ɓ������v�c�a�`�E5�����T�Ԃŋ}���A�V�K�����ґS�̂�52�� �@7/8
�����̐V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�A47�s���{�����ׂĂőO�T��ő����ɓ]�����B7���̑S���̐V�K�����҂́A1�T�ԑO��2�{��4��7977�l�ɒB�����B�e�n�̒m������u��7�g�ɓ������v�Ȃǂ̔������������A���{�͎����̂ɑ��A�a���̊m�ۂ��}���悤�v�����Ă���B
7���̓����s�̊����҂�8529�l��1�T�ԑO��2�E4�{�A���{��4615�l�œ�2�E1�{�B����A�����2���ʼnߋ��ő����X�V���A����1�T�Ԃł͓����A���Q�A�F�{���܂�5���ʼnߋ��ő��ƂȂ����B���t���[�ɂ��ƁA6�����_��1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ��͑S�s���{���őO�T���������B
�����s�̏��r�S���q�m����7���A�u��7�g�ɓ������Ƃ��l������v�Ɣ����B��t��Q�n�̒m�������7�g�Ɍ��y�����B
�����̗v���́A���N�`���ڎ�Ȃǂœ����Ɖu�̓����̒ቺ�ƁA�I�~�N�������̐V�n���u�a�`�E5�v�̊g��Ƃ����B
���N�`����2��ڐڎ�͑S�����8�����邪�A3��ڂ�62���ɂƂǂ܂�A�N��ʂł�12�`19��31���A20�Α�46���A30�Α�50���A40�Α�59���ŕ��ς������B���������Ⴂ����Ŋ������ڗ����Ă���B�d�lj��\�h���ړI��60�Έȏ�̐l�Ȃǂ��Ώۂ�4��ڐڎ��23���ƂȂ��Ă���B
�a�`�E5�́A�������ł�6�����{�̊����҂�8���ɒB���A�����s��3���Ɋg��B���������nj������́A7���㔼�ɑS���Ŕ����ȏオ�u�������Ɛ��v����B
�s�̏��r�m���́A�m�ەa�������݂̖�5000������ő��7000���ɑ��₷���߂̏�����i�߂�悤��Ë@�ւɗv�������B
7���̑S���̏d�ǎҐ���67�l�ŁA��6�g�s�[�N��4���ɂƂǂ܂邪�A����A����������҂Ɋg�傷��Α������邱�Ƃ����O�����B
����A���E�ی��@��(�v�g�n)�ɂ��ƁA���E�̃R���i�����Ґ���3���܂ł�1�T�ԂŖ�460���l�ɏ��A4�T�A���ő��������B���ɂ���2�T�Ԃ�30���߂����������B
�w�i�Ƃ��āA�a�`�E4�Ƃa�`�E5�ւ̒u���������w�E���Ă���B�Ȃ��ł��a�`�E5�̊����͂������T�Ԃŋ}���ɑ����Ă���A�V�K�����Ґ��S�̂�52�����߂Ă���B�@ |
�������s�̐V�K�����҂�8777�l�@3���A����8000�l��@7/8
�����s�����ی��ǂ̃E�F�u�T�C�g�ɂ��ƁA8��16��45���̎��_�Ō��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂�8777�l�B�d�ǎ҂͑O������1�l�����A7�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł�8777�l(�s��1�l)�B�N��ʂł�20�オ�ő���2091�l�A������30���1594�l�A40���1422�l�Ƒ����Ă��܂��B�d�lj����₷���Ƃ����65�Έȏ�̍���҂�622�l�ł����B����7���Ԃ̈ړ����ς�5875.0�l(�ΑO�T��214.6��)�B�s���̑���(�v)��164��3502�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s���̕a���g�p����31.2��(1577�l�^5047��)�ƂȂ��Ă��܂��B
�j���ʂ̐��ڂł݂�ƁA��T1��(3546�l)����5231�l�����A21���A���őO�T�̓����j�����瑝���B�܂��A3���A���ŐV�K�����Ґ���8000�l���܂����B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
�������s �V�^�R���i 1�l���S 8777�l�����m�F �O�T���j�̖�2.5�{ �@7/8
�����s����8���̊����m�F�́A1�T�ԑO�̋��j���̂��悻2.5�{�ƂȂ�8777�l�ł����B3���O��5������A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{���鑝���������Ă��āA�������}���Ɋg�債�Ă��܂��B
�����s��8���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��8777�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j���̂��悻2.5�{�ŁA5200�l�]�葝���܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�21���A���ł��B�s���ł�5������A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{���鑝���������Ă��āA�������}���Ɋg�債�Ă��܂��B8���܂ł�7���ԕ��ς�5875.0�l�ŁA�O�̏T��214.6���ł����B8���Ɋm�F���ꂽ8777�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�23.8���ɓ�����2091�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�622�l�ŁA�S�̂�7.1���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A7�����1�l������7�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ90��̏���1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i3�l���S �O�T��2�{�ȏ��4805�l�����@7/8
���{��8���A�V����4805�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{�ȏ�ɑ����Ă��āA4000�l������̂�4���A���ł��B����A���{�͂���܂łɔ��\����2�l�ɂ��āA�����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��104��571�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�V����3�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�́A���킹��5219�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�7������3�l�����āA8�l�ł��B
|
����������3068�l�����@�V�^�R���i�A4�l���S�@7/8
��������8���A�V����3068�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����ƁA4�l�̎��S���m�F���ꂽ�B���ǎ����̕ʂł͕����s1101�l�A�k��B�s324�l�A�v���Ďs159�l�A��1484�l�B
|
���V�^�R���i�V����2417�l�����@���j���ł͉ߋ��ő��@����@7/8
���ꌧ��7��8���A�V��2417�l�̐V�^�R���i�������m�F�����Ɣ��\���܂����B���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B�܂�4���A����2000�l���Ă��܂��B
7���܂ł̒���1�T�Ԃ�����̐V�K�����Ґ���807.88�l�őS���ő��ƂȂ��Ă��܂��B�܂��a���g�p����51.8����50��������ȂǁA�����̈�Ñ̐��ɂ��e�����o�n�߂Ă��܂��B
|
���V�^�R���i �k�C������887�l�����m�F 7���A���őO�T�䑝�@7/8
8���A�����ł͐V����887�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A1�l�̎��S�����\����܂����B�V�K�����Ґ���7���A���őO�̏T�̓����j��������A�����X���������Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s�œ��O��3�l���܂�417�l�A�Ύ�n����97�l�A���َs��68�l�A�I�z�[�c�N�n����44�l�A����s��37�l�A�_�U�n����36�l�A�\���n����32�l�A���H�n����27�l�A���n����22�l�A�n���n����21�l�A�����n����19�l�A��m�n����17�l�A���M�s��16�l�A�����n����11�l�A�@�J�n����10�l�A��u�n����5�l�A���G�n����2�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��4�l���܂߂�6�l�́A���킹��887�l�ł��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������18�l�������A�d�ǂ�1�l�A�����ǂ�1�l�ŁA���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�܂��A�S�̂̔�������475�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������́A4494���ł����B
�V�K�̊����Ґ��́A��T�̋��j��(1��)���246�l�����A7���A���őO�̏T�̓����j���������Ă��āA�����X���������Ă��܂��B
�܂��A�D�y�s�͂���܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A90��̒j��1�l���A7���A�S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B
����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�18��9611�l���܂ނ̂�38��7221�l�A�S���Ȃ����l��2100�l�A���Â��I�����l��37��9160�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�������R���i������5���l���@4��14���ȗ��@7/8
������8���A�V����5��107�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����҂����ꂽ�B5���l����̂�4��14���ȗ��ŁA1�T�ԑO�̓����j������2�{�ȏ㑝�����B����ƈ��Q�A�啪�A�F�{�ʼnߋ��ő��ƂȂ�ȂǁA�����̒n��ő����X���������ƂȂ��Ă���B
�s���{���ʂł͓���8777�l�A���4805�l�A�_�ސ�3677�l�ȂǁB�����J���Ȃɂ��ƁA�d�ǎ҂͑O������4�l������71�l�������B���҂͕���4�l�A��t�����3�l�Ȃnjv29�l�������B
|
���V�^�R���i�V�K�����ҁ@�S����5���l������ 3�J���Ԃ� �@7/8
8���A�S���ł͐V����5��107�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�����҂�5���l����̂́A���悻3�J���Ԃ�B
�����s�Ŋm�F���ꂽ�����҂�8,777�l�ŁA��T�̋��j������5,231�l�����A3���A����8,000�l�����B���҂�1�l�������B
���̂ق��A�F�{����1,672�l�A���Q����605�l�A�啪����585�l�A���挧��243�l�ƁA4�̌��ʼnߋ��ő�������A�S���ł�5��107�l�̊������m�F���ꂽ�B
�����҂�5���l����̂�4��14���ȗ��A���悻3�J���Ԃ�B���҂�29�l�������B�܂��A7�����_�ł̑S���̏d�ǎ҂�71�l�ŁA�O�̓�����4�l�������B�@ |
 |
���V�^�R���i�@�����s��1�T�Ԃ̐V�K�����҂�4��7225�l�@�O�T�̖�2.3�{�@7/9
�����s�����ی��ǃE�F�u�T�C�g���\�̑���l��Ǝ��W�v�������ʂɂ��ƁA���j�������1�T��(3���`9��)�Ŋm�F���ꂽ�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂͌v4��7225�l�B�v2��621�l�������O�T(6��26���`7��2��)�Ƃ̔�r�ł͖�2.3�{�ƂȂ�A2��6604�l�������Ă��܂��B
���T�A�ł������҂̊m�F�������������͓̂y�j����9716�l�B�����ŋ��j����8777�l�A�ؗj����8529�l�Ƒ����܂����B1�����ς�6746.4�l�B9�����_�ŏd�ǎ҂�10�l�ł��B�܂��A�O�T(�v2��621�l�^����2945.9�l)�Ƃ̔�r�ł͖�229.0���B�a���g�p����9�����_��33.9��(1713�l�^5047��)�ƂȂ��Ă��܂��B
���T�̍��v�����Ґ��͑O�T�Ƃ̔�r��2��6604�l�̑����B�j���ʂ̐��ڂŌ���ƁA7���Ԃ��ׂĂőO�T������܂����B�܂��A���j���ȍ~��4���A���ŐV�K�����҂�8000�l������A�y�j���ɂ�101���Ԃ��9000�l����L�^���܂����B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
|
�����̃R���i�����ҁA4���ȗ���5��l���@�O�T����3��l���@7/9
���{��9���A�{���ŐV����5567�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\�����B�O�T�̓����y�j��(2��)���3022�l�����A1��������̊����Ґ���5��l����̂�4��13��(5121�l)�ȗ��B80��̒j��1�l�����S�������Ƃ��V���Ɋm�F���ꂽ�B�{���̊����҂͉���104��6204�l�A���҂͌v5220�l�ƂȂ����B
|
���������ŐV����3256�l�m�F�@�V�K�����ҁA2���A��3000�l���@7/9
��������9���A�V����3256�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�B�V�K�����҂�2���A����3��l�����B8���ɗz���ƌ��\����1�l����艺�����B�V�K�����҂̏��ǎ����̕ʂł͕����s1394�l�A�k��B�s357�l�A�v���Ďs218�l�A��1287�l�B
|
���R���i�y�j�ő�2518�l �����Ґ��A�ߋ�3�Ԗڂ̑����@7/9
���ꌧ��9���A10�Ζ�������90�Έȏ��2518�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����҂Ƃ��Ă͉ߋ�3�Ԗڂɑ����A�y�j���Ƃ��Ă��ߋ��ő��ƂȂ����B���ɂ��ƁA�S���I�Ȋ����g��Ɠ�������ɂ���B
����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��̑O�T���1�E33�{�ƂȂ��Ă���B���S�̂̃R���i��p�̕a���g�p����51�E2���ŁA����ʂł͖{����55�E5���A�{�Â�10�E6���A���d�R��59�E1���������B�d�ǎҗp�̕a���g�p����21�E7���ƂȂ��Ă���B�N��ʂł�10�Ζ�����509�l�A10�オ447�l�A40�オ396�l�A30�オ351�l�ȂǂƂȂ��Ă���B���̋{���`�v�����������ẮA�����Ŋ����Ґ��������Ă��邱�Ƃ܂��u�����n��ł͐�Ƀ��N�`���ڎ킪�i���A3��ڂ���5�J���o�߂����l�������Ă���ƁA�����҂������Ă���B�d�ǎҗ\�h�ł́A���N�`���ڎ���Ăт����Ă��������v�Ƙb�����B�ČR�W�҂̐V�K�z���҂́A51�l�������B
|
�������ŐV����5��5019�l�R���i�����c�����s�ł�3��30���ȗ���9��l���Ɂ@7/9
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�9���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����5��5019�l�m�F���ꂽ�B���҂�12�l�B�d�ǎ҂͑O������3�l����74�l�ƂȂ����B����A�����A���Q�A�啪��4����1��������̐V�K�����҂��ߋ��ő��������B
�����s�̐V�K�����҂�9716�l�B9000�l�����̂́A3��30��(9518�l)�ȗ��������B�O�T�̓����j����2�E7�{�ŁA22���A���őO�T���������B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂́A�O�T��2�{��6746�l�������B�d�ǎ҂͑O������3�l������10�l�ƂȂ����B
���{�ł�5567�l���V���Ɋ��������B5000�l����̂�4��13��(5121�l)�ȗ��B�O�T�̓����j������2�{�ȏ�ɑ������B
|
���S���̐V�^�R���i�����ҁ@2���A����5���l������@7/9
9���ɑS���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�5��5035�l�ŁA2���A����5���l���܂����B
9���̑S���̐V�K�����҂�5��5035�l�ŁA5��5000�l����̂�4��14���ȗ��A���悻3�J���Ԃ�ł��B��T�̓y�j����2��4900�l�������̂ŁA2�{�ȏ�ɂȂ��Ă��܂��B
9���͒���A�����A���Q�A�啪�ʼnߋ��ő����X�V���܂����B�܂��A������9716�l�ŁA9000�l��ɂȂ����̂�3��30���ȗ��ł��B��T�̓y�j����2.7�{�߂��ɂȂ��Ă��āA�����̑����̃y�[�X�����܂��Ă��܂��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1�l���S 9482�l�����m�F ��T���j�̖�2.5�{ �@7/10
�����s����10���̊����m�F��9482�l�ŁA1�T�ԑO�̓��j���̂��悻2.5�{�ƂȂ�܂����B5���O����O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{���鑝���������Ă��āA�������}���Ɋg�債�Ă��܂��B
�����s��10���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��9482�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j���̂��悻2.5�{�ŁA5600�l�]�葝���܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�23���A���ł��B�s���ł�5���O����O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{���鑝���������Ă��āA�������}���Ɋg�債�Ă��܂��B10���܂ł�7���ԕ��ς�7559.9�l�ŁA�O�̏T��236.2���ł����B10���Ɋm�F���ꂽ9482�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�20.6���ɓ�����1956�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�741�l�ŁA�S�̂�7.8���ł��B
����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A9���ƕς�炸10�l�ł����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ60��̒j��1�l�����S�������Ƃ\���܂����B |
�����{�ŐV����5081�l�R���i�����A1�T�ԑO����3072�l���@7/10
���{��10���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����5081�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j������3072�l�������B���҂�1�l�������B
|
���������ŐV����2757�l�����@�V�^�R���i�@7/10
��������10���A�V����2757�l�̐V�^�R���i�E�C���X������80��j��1�l�̎��S���m�F���ꂽ�B�V�K�����҂�3��l�������̂�3���Ԃ�B6���ɗz���ƌ��\����1�l����艺�����B���ǎ����̕ʂł͕����s803�l�A�k��B�s317�l�A�v���Ďs220�l�A��1417�l�B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����2458�l�����m�F �@7/10
���ꌧ��10���A�V����2458�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B��T�̓��j���Ɣ�ׂ�1262�l�����Ȃ��Ă��āA�O�̏T�̓����j��������̂�7���A���ƂȂ��Ă��܂��B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�27��2950�l�ɂȂ�܂����B
|
���V�^�R���i 859�l�����m�F 9���A���őO�T���j��������@7/10
10���A�����ł͐V����859�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�V�K�����Ґ��́A9���A���őO�̏T�̓����j�������葝���X���������Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s��442�l�A�Ύ�n����84�l�A�_�U�n����65�l�A���َs��46�l�A�\���n����45�l�A�I�z�[�c�N�n����33�l�A����s��30�l�A�n���n����19�l�A�����n����18�l�A���H�n���Ƌ�m�n���ł��ꂼ��12�l�A�����n����10�l�A���M�s�A��u�n���A����ɏ@�J�n���ł��ꂼ��8�l�A���n���Ɨ��G�n���ł��ꂼ��2�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��10�l���܂߂�15�l�̂��킹��859�l�ł��B
���Ȃǂɂ��܂��ƏǏ�͒�������3�l�������A��������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
�܂��S�̂̔�������438�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������2514���ł����B�V�K�̊����Ґ��́A��T�̓��j�����242�l�����Ȃ��Ă��܂��B�O�̏T�̓����j�����������̂�9���A���ŁA�����X���������Ă��܂��B����A10�������ł͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���Ď��S�����l�̔��\�͂���܂���ł����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�19��434�l���܂ނ̂�38��8991�l�A�S���Ȃ����l��2101�l�A���Â��I�����l��38��327�l�ƂȂ��Ă��܂��B�@ |
 �@ �@
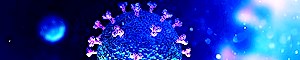 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i 6231�l�����m�F ��T���j����2.2�{�@7/11
�����s����11���̊����m�F��6231�l�ŁA1�T�ԑO�̌��j����2.2�{�ł����B2�{���鑝����7���A���ƂȂ�}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B
�����s��11���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��6231�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j����2.2�{��3459�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�24���A���ł��B�܂�2�{���鑝����7���A���ƂȂ�A�}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B11���܂ł�7���ԕ��ς�8054.0�l�ŁA�O�̏T��238.3���ł����B6231�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������S�̂�20.5���ɓ�����1277�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�465�l�őS�̂�7.5���ł��B����A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�10�����1�l������9�l�ł����B���S���m�F���ꂽ�l�̔��\�͂���܂���ł����B
|
�����{�ŐV����2515�l�R���i�����c1�T�ԑO��2�{���Ɂ@7/11
���{��11���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2515�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j�����1365�l�������B
|
����������2354�l�������@�V�^�R���i�@7/11
��������11���A�V����2354�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B21���A���őO�T�̓����j�����������B���ǎ����̕ʂ̓���͕����s707�l�A�k��B�s228�l�A�v���Ďs91�l�A��1328�l�B
|
������A�����~�܂�ʐ����A�R���i�u�g��x��v�@�a���g�p6������@7/11
11���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�943�l�ƂȂ����B�ʏ�͌������錎�j�������A5���̑�^�A�x��ɋ}��������l���ɔ��鐨���ƂȂ��Ă���B����1�T�Ԃ̐V�K�����҂̑O�T����}������1.48�{�ƂȂ����B�����A�{������Ɣ��d�R����Ɂu�R���i�����g��x��v���o�����ʏ�f�j�[�m���́A�I�~�N�������h���^�uBA5�v�̒u������肪�i�ނ��ƂŁu�����Ґ��͔{�̔{�̔{�Ƃ����L�т������邩������Ȃ��v�Ƌ����x�����������ƂƂ��ɁA�����Ɋ�����̓O����Ăъ|�����B
�V�^�R���i�̓��@���҂�361�l�Ō��S�̂̕a���g�p����56.1���ƂȂ�A�����s����������������w�W��6���ɔ����Ă���B�R���i�ȊO�̈�ʕa���g�p�������S�̂�95.8���ƍ��~�܂肪�������A�d�_��Ë@�ւł͊����ȂǂŌ������Î҂��������~�܂炸�A512�l�ƂȂ����B500�l����̂�5��27���ȗ����B
��Ò̐����������𑝂�������A�ʏ�m����11���̉�ŁA�����̔��M�O�����p��~�}�Ԃ̓K�����p�ƂƂ��ɁA�u�}�Ȏq�ǂ��̕a�C�őΉ��ɖ����ꍇ�͏����~�}�d�b���k�w��8000�x�ɑ��k���Ăق����v�ƌĂъ|�����B�܂��A���g�����������o���܂��āu����Ɉ��ݖ��������Ă������Ƃ����߂����v�Əq�ׂ��B
�Љ���{�݂ł����s�͑����Ă���A�������_�Ō����x���ɓ����Ă���Љ���{�݂�111�J���������B�{�ݓ��×{�҂͌v355�l�ŁA����͍���Ҏ{��334�l�A�Ⴊ���Ҏ{��21�l�B�_�f���^���Ă��銳�҂�7�l�őS�č���Ҏ{�݂������B
�ČR�W�̊�����23�l�������B
|
���k�C�� �V�^�R���i 1�l���S �V����602�l�����m�F �@7/11
11���A�k�C�����ł́A�V����602�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�܂��A���́A����܂Ŋ������m�F����Ă����l�̂����A10����80��̏���1�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����ŁA�����̊����҂͎D�y�s�̉���19��797�l���܂މ���38��9593�l�A�S���Ȃ����l��2102�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i�S����3��7143�l�@����7���ԘA���Ŋ����Ҕ{���@7/11
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�S���ł͐V����3��7143�l�̊��������\����܂����B�S���I�ɑ����X���������Ă��܂��B
�����s�͂��̂��A�V����6231�l�̊����\���܂����B��T�̌��j�������3400�l�ȏ㑝���Ă��āA1�T�ԘA���őO�̏T�Ɣ�����Ґ����{�����Ă��܂��B����7���ԕ��ς̐V�K�����҂͂��悻8050�l�ŁA1�T�ԑO��238.3�p�[�Z���g�ł����B
�S���ł͐V����3��7143�l�̊��������\����܂����B
���ׂĂ̓s���{���őO�̏T�̌��j��������A5���ԘA���őO�̏T�Ɣ�����Ґ����{�����Ă��܂��B
�S���œ��@���Ă��銴���҂̂����u�d�ǎҁv�Ƃ����l��75�l�ŁA�V���Ȏ��҂�15�l���\����Ă��܂��B
|
����ヂ�f���Ăсu���F�M���v�Ɂ@���H�X�ւ̗v���͌�����@7/11
���{��11������Ăщ��F�M�����_���ł��B���{�́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��Ăы}�����Ă��邱�Ƃ��A���{����c���J���܂����B��c�ł́A11������Ǝ���́u��ヂ�f���v�Ōx����\���u���F�M���v�����Ƃ����߂܂����B�܂�����Ҏ{�݂ł�12�����瓖�ʁA�ʉ���������l�B��Ë@�ւɂ́A���@���҂����������ꍇ�A���̂܂܃R���i�̎��Â�����悤�v�����܂��B����ŁA���H�X�ւ̎��Z�v���Ȃǂ͍���͌������܂����B
���{�E�g���m���u���܂ł̂悤�Ȉ��H�X�ȂǓ���̎��Ǝ҂ɕ��S�����肢����̂́A�ʂ����Ăǂ��܂Ō��ʂ�����̂��B��l��l�̊���������肢����v�B
����A���s�{���V�K�����Ґ������߂�1�T�ԕ��ς�908�l�ɏ��A�O�T�ɔ�ׂ�2�D33�{�Ƒ����X���ƂȂ��Ă��܂��B
���s�{�E���e�m���u���̊��o�Ƃ��Ă͑�7�g�̓�����ɗ����Ă���\���������Ǝv���v�B
���e�m���́A���܂߂Ȋ��C���b�̍ۂ̃}�X�N���p�Ȃǂ��Ăт����Ă��āA���T���ɂ͑��{����c���J���A�Ή������c����Ƃ��Ă��܂��B
|
�����g�Ή�A�R���i�����ґ��Łu��7�g�v�ƔF���@7/11
���{�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��11���A�ŋ߂̊����ґ����ɂ��āu�V�����g�ɓ������̂͊ԈႢ�Ȃ��v�Əq�ׁA���s�u��7�g�v�Ƃ̔F�����������B�܂h�~���d�_�[�u�Ȃǂ̍s�������ɂ��Ắu���̒i�K�ł͕K�v�Ȃ��v�Ƃ����B�ݓc���Y�Ɗ��@�Ŗʉ��A�L�Ғc�̎�ނɉ������B
������11���ɕ��ꂽ�����҂�3��7143�l�ƂȂ����B1�T�ԑO�̓����j���ɔ��2�E2�{�B�O�T�Ɣ�ׂ��S���̊����҂̔䗦��6��21���ɑ����ɓ]������A���X�ɑ����y�[�X�𑬂߁A���߂�5���A����2�{���ɂȂ��Ă���B11���̎��҂͈��A���ɁA����Ŋe2�l�Ȃnjv15�l�����ꂽ�B
���g���͒��߂̑����ɂ��āA�������L����₷���Ƃ����I�~�N�������̔h���^�uBA�E5�v�ւ̒u������肪�i��ł��邱�ƂȂǂ������ƍl������Ǝw�E�B���N�`���ڎ�Ŋl�������Ɖu�����X�ɒቺ���Ă��邱�Ƃ��v�����Ƃ����B
���̏�Łu�������X�N��������ʂ͂���܂łƕς��Ȃ��B�݂�Ȃ��ł��邱�Ƃ����A�s�������͍��̒i�K�ł͕K�v�Ȃ���(��)�\���グ���v�ƌ�����B
�V�K�����҂̓���͓���6231�l�A�_�ސ�4230�l�A���2515�l�A���2429�l�A����2354�l�ȂǁB��������O�T����2�{���ɑ������B���{�͊����҂��}�g�債�Ă���Ƃ��āA�Ǝ���Ɋ�Â��x�������̈����グ�����߂��B
�����J���Ȃɂ��Əd�ǎ҂�75�l�ŁA�O�����5�l�������B
|
���Ђ�䂫���u����Ȃɑ����Ȃ��Ă������̂ł́v�V�^�R���i�g��7�g�h�Ɏ��_�@7/11
8���A�����s�Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���8777�l���L�^�B��9����9716�l�̊������m�F����A3��30���ȗ���9000�l���ƂȂ����B���j�^�����O��c�ɏo�Ȃ������r�s�m���́u������@�Ǘ��Ƃ��đ�7�g�ɓ���A���̂��߂ɕK�v�ȋ����x���Ɛ���̑�ɂ�������Ǝ��g��ł����v�Ƒi���Ă���B
�V�^�R���i�̊��������{�Ŋm�F����Ă��炨�悻2�N���B�Ȃ����������Ċg�債�Ă���̂��B�v���̈�Ƃ��Ďw�E����Ă���̂��A�V���ȕψي��̏o�����B
�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v��t�́uBA.2��芴�����������Ƃ����BA.5�ւ̒u������肪�i��ł���v�ƃR�����g�B��Ȏ��ɂ��ƁA���̂܂܂̃y�[�X�Ŋ������g�債���ꍇ�A�P���v�Z�����8��3���ɂ͓����ň���������5��5000�l�̊����҂��o��Ƃ����B
�ψق���BA.5�́A�ǂ�قǂ̋��ЂȂ̂��B�j���[�X�ԑg�uABEMA Prime�v�ł́A�����J���ȃN���X�^�[���ǂŌ�WHO�R���T���^���g�̌Ð��S�C���Ƃǂ̂悤�ȑL�p�Ȃ̂��l�����B
�s���Ŋ����҂��}���ɑ����Ă���ɂ��āA�Ð����́u�s�m������w��7�g�ɓ������̂ł͂Ȃ����x�Ƃ������������������A���̊����҂̐���������ƁA���łɑ�5�g�̃s�[�N���z���Ă���B����́w�������x�ƌ����Ă��܂��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă���v�Əq�ׂ�B
�܂��A�Ð����̓I�~�N�������̕ψٌ^�̋��Ђɂ��āu�܂��܂����E���ŏo�Ă�������ŕ�����Ȃ��Ƃ���������v�Ƃ�����Łu�S�z���Ă���͖̂Ɖu�̐��������܂ł̂��̂ƈ���Ă��āA���N�`����ł��Ă��Ă��A���܂ł̊��ɂ����������Ƃ��������Ƃ��Ă��A���̖Ɖu�����܂芴����h���̂Ɍ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B���ꂪ���R�ŁA���{�����ł͂Ȃ��A���E���ő傫�Ȕg�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���v�ƃR�����g�B
����ŁA�l�b�g�f���w2�����˂�x�n�ݎ҂̂Ђ�䂫���́u�t�����X�ł͑�7�g�����Ă��āA�������ƈ���̊����Ґ���16���l���Ă���B�����15���l�Ŋ��S�ɑ�7�g�����A�O�͕��ʂɊy�����ό��q������B�����͂����ʂ�Ȋ������v�Ƙb���B
�t�����X�̈�Ñ̐��ɂ��ĂЂ�䂫���́u���҂�1��100�l�����Ȃ����炢���B�d�lj��x�b�h�̗��p�����t�����X�S�̂�2���A�p�����ӂł�3�����炢�Ȃ̂ŁA�܂��܂��S�R�]�T�B�S���Ȃ��Ă���l�����邪�A����Ȃɑ������Ƃ��Ȃ��Ƃ�����C���ł͂���v�Ɛ����B�u�����s�ł��d�lj������l����10�l�ȉ��Ȃ̂ŁA8000�l�͂��������A�̂̃C���t���G���U��7�l�`8�l���d�lj�����a�C�������B����Ȃɑ����Ȃ��Ă������̂ł͂Ȃ����v�Ɠ������B
���{�̏ꍇ�A���N�`����3��ł��Ă��炠�܂莞�����o���Ă��Ȃ��l������B��Â��Ђ������A�ǂ��̕a�@������Ȃ��Ƃ����͋N���肤��̂��낤���B
�Ð����́u�m���Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A���̊��o�Ƃ��ẮA���ꂩ�烏�N�`���̃u�[�X�^�[�ڎ킪�i�܂Ȃ��āA�O���Ɗ����҂��������Ƃ��A�F����̍s�����ς��Ȃ��Ȃ�A��͂�܂��a�����Ђ�������悤�ȏ͂��蓾��Ǝv���B�����A�u�[�X�^�[�ڎ킪���ꂩ�瑝���āA�w������Ɗ����Ґ��������Ă����ȁB�����l�Ɖ�@������炻�����ȁx�Ǝv���l���o�Ă���ƁA���܂������\�����܂��\���ɂ���Ǝv���v�Ƃ����B
�����ŁA�Ђ�䂫�����Ð����Ɂu�~���Ɗ��ƕߐ邩�玺���Ŋ������₷�����A�Ă͊��Ƒ����J���邩�犴������������Ƃ����b�����������A���ꂪ�����Ă������͂͋����܂܂Ȃ̂��v�Ǝ���B�Ð����́u�����͂�����BA.5�������킯�ł͂ǂ����Ȃ��������v�Ƃ�����ŁuBA.2���쒀����悤�ɍL�����Ă��邪�A���̗��R�͖Ɖu�̐������Ⴄ����B�L����͎��̂͂���Ȃɕς��Ȃ��������B�R���i�E�C���X�̈�ʂ̐����Ƃ��āA�Ă͓~�ɔ�ׂčL����ɂ����Ƃ����̂͊m���ɂ���Ǝv���v�Ɠ������B
BA.5�ł́A���Ǐ�̊����҂͑����̂��낤���B�Ð����́u�t�����X���獸�ǑO�̃f�[�^���o�Ă���v�ƏЉ�B
�u�d�lj����͕ς��Ȃ��������A���Ǐ�̊����������Ă��āA�Ǐo�Ă���l�������Ă��������Ƃ������Ƃ��������Ă���B�̂ǂ��ɂ��Ȃ�l�A�����������Ⴄ�l���ABA.1�Ƃ�BA.2�̐̂̃I�~�N�����^�C�v�ɔ�ׂāA���̃I�~�N�������Ɣ{���炢���肻�����ƕ���Ă���v
�����҂����ȏ�ɑ����Ă����ꍇ�A�ċx�݂ɃC�x���g�◷�s���l���Ă���l�����͂ǂ�����ׂ��Ȃ̂��낤���B
�Ð����́u�ċx�݂��ǂ̒��x�e�������邩�͕�����Ȃ��v�Ƃ�����Łu�q�ǂ������̃��N�`���ڎ헦���܂��܂��Ⴍ�āA�������܂��N���X�^�[�̉����ɂȂ肻�����ȂƂ������O�͂���v�ƃR�����g�B
�u�����l����ƁA�q�ǂ��������m�̐ڐG�͋t�ɉċx�݂͌���悤�ȋC�����Ă��āA��T�Ɂw�ċx�݂͐l���������犴���g�傷��x�Ƃ͌����ɂ����Ǝv���B���̑�7�g�Ō��������邩�ǂ����A�|�C���g�͂�������Ǝv�����A���ǁA�q�ǂ����ǂꂾ�����N�`����ł��ǂ���������B�����āA3��ڂ̃��N�`�����ǂꂾ���̐l���ł��Ă���邩�B�ŏI�I�Ȉ�ÂЂ����͂܂��Ȃ����A��Õ������ȂƂ��ɊF���s����ς����邩�ǂ����B�����ɂ���āA�d�_�[�u�A���邢�͌��I�ȋ@�ւ��烁�b�Z�[�W���o���Đ��������邱�ƂɂȂ邩�ǂ����A�������̂ł͂Ȃ����ȂƎv���v�@ |
 |
�������s�̃R���i�����ҁA4�J���Ԃ��1���l�� 7/12
�����s��12���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�1��1511�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B1���l�����̂�3��16���ȗ��B�s���̐V�K�����Ґ��́A��6�g�����É�����6��13���ɂ�960�l�ɂ܂Ō����Ă������A����������Ăы}���B���r�S���q�m�����u��7�g�ɓ������\��������v�Ƃ��������������Ă����B
|
���V�^�R���i ���{�̐V���Ȋ�����9000�l�����ʂ�3���ȗ� 7/12
���{�ɂ��܂��ƁA�{���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�12����9000�l���錩�ʂ����Ƃ������Ƃł��B���{���̐V�K�����҂�9000�l������̂͂��Ƃ���3��2���ȗ��ł��B
|
�������� �V�^�R���i 4�l���S 4295�l�����m�F �O�T�Ηj��2�{�ȏ� �@7/12
��������12���A�����ŐV����4295�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B4000�l����̂͂��Ƃ�2��17���ȗ��ł��B
1�T�ԑO�̉Ηj����2�{�ȏ�ɑ����A22���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B����́A�����s��2208�l�A�k��B�s��584�l�A�v���Ďs��466�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A10���Ɋ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ1�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����47��6478�l�ɂȂ�܂����B�܂��A80���90��ȏ�̍��킹��4�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1288�l�ƂȂ�܂����B
|
���k�C������803�l�����m�F 11���A���O�T�䑝�@7/12
�����ł�12���A�V����803�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�V�K�����Ґ���11���A���őO�T�̓����j��������A�����X���������Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��285�l�A�Ύ�n����85�l�A���َs��80�l�A����s��74�l�A��m�n����46�l�A�I�z�[�c�N�n����39�l�A�n���n����38�l�A�_�U�n����36�l�A���n����19�l�A���M�s�Ə\���n���A�����n���ł��ꂼ��17�l�A���H�n����14�l�A�����n����10�l�A�@�J�n����7�l�A��u�n����5�l�A���G�n����2�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��5�l���܂߂�12�l�̍��킹��803�l�ł��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�܂��A�S�̂̔�������430�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������3476���ł����B�܂��A�����ł�12���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���Ď��S�����l�̔��\�͂���܂���ł����B�V�K�̊����Ґ��͐�T�̉Ηj�����242�l�����Ȃ��Ă��܂��B�O�T�̓����j�����������̂�11���A���ŁA�����X���������Ă��܂��B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�19��1082�l���܂ނ̂�39��396�l�A�S���Ȃ����l��2102�l�A���Â��I�����l��38��1531�l�ƂȂ��Ă��܂��B |
�����ꌧ �V�^�R���i 4�l���S 3436�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/12
���ꌧ��12���A�V����3436�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����Ɍ��\�����V�K�����҂̐��́A����܂łōł������������Ƃ�5��11����2702�l�������ĉߋ��ő��ƂȂ�A�����Ŋ������m�F���ꂽ�l��27��7329�l�ɂȂ�܂����B�܂��A���͐V����4�l�̎��S���m�F���ꂽ�Ɣ��\���A�����ŖS���Ȃ����l��497�l�ɂȂ�܂����B |
���S���R���i������7��6012�l�@12���ʼnߋ��ő��@������4�����Ԃ�1���l���@7/12
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�S���ł͂��傤�V����7��6012�l�̊��������\����܂����B
�����s�́A���傤�V����1��1511�l�̊����\���܂����B��T�Ηj�����6209�l�����A���悻4�����Ԃ��1���l���܂����B����7���ԕ��ςł݂��V�K�����҂͂��悻8940�l�ŁA1�T�ԑO�̂��悻2.4�{�ɑ������Ă��܂��B
�S���ł́A�V����7��6012�l�̊��������\����Ă��܂��B���ׂĂ̓s���{���Ő�T�̓����j��������A�X�A����A�����Ȃ�12�̌��ʼnߋ��ő����X�V���܂����B�S���œ��@���Ă��銴���҂̂����u�d�ǎҁv�Ƃ����l��83�l�ŁA�V���Ȏ��҂�23�l���\����Ă��܂��B
|
���V�^�R���i �g��7�g�ɓ������h �ߋ��ő��̊����� �e�n�ő����� �@7/12
�g�����g��̑�7�g�ɓ������h���{���ȉ�̔��g�Ή��11���A���������F���������܂����B������12���͊e�n�ʼnߋ��ő��ƂȂ銴���m�F���������A�S���̊����҂̔��\��7���l���܂����B���Ƃ�3��3���ȗ��ɂȂ�܂��B�܂������s�ł����Ƃ�3���ȗ��ƂȂ�1���l���̊����҂����\����܂����B
���g�ߋ��ő��h �S���e�n�Łc
12���͂���܂łɑS����7��6011�l�̊��������\����Ă��܂�(18:45����)�B���̂����X�A�a�̎R�A���Q�A�����A����A�R���A�啪�A����A�F�{�A����A�������A�����12�̌��ł́A����Ƃ��Ă͉ߋ��ő��̊����Ґ������\����܂����B
������ �V����1���l���̊����m�F
�����s��12���A�s���ŐV����1��1511�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���̊����m�F�������1���l����̂́A���悻4�����O�̂��Ƃ�3��16���ȗ��ł��B
�����r�m���u���N�`���ڎ킵�Ă������������v
���r�m���͋L�Ғc�ɑ��u���@����l�������a���g�p�����㏸�𑱂��Ă��邽�ߊm�ۂ���R���i��p�a�������₷�ق��A����×{�҂̃T�|�[�g���s���Ă���B����܂ł̂��܂��܂Ȓm�������đΉ����Ă���B3��ځA4��ڂ̃��N�`���ڎ�̉���p�ӂ��Ă���̂Őڎ킵�Ă������������v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�M���ǂɋC�����Ȃ����[���g���Ăق����B���̍ہA�ߓd���C�ɂȂ�Ǝv�����A�����ɋC�����邱�Ƃ��厖�Ȃ̂Ō����������Ǝv���l�����邩������Ȃ�������I�Ɋ��C���s���Ăق����v�Əq�ׂ܂����B
���Ȃ������Ċg��H
�Ȃ������͍Ċg�債���̂��H���Ƃ͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��B
���uBA.5�̍L����v�u���N�`���̖Ɖu���ʂ��ቺ�v
���{���ȉ�̔��g�Ή����Ƃ�11���A������b���@��K��ݓc������b�Ɖ�k���܂����B
���g��ɂ��܂��ƁA��k�ł͐��Ƃ�
�E���݂̊����ҋ}���̔w�i�ɃI�~�N�������̂��������͂���苭���Ƃ����uBA.5�v�̍L�����
�E���N�`���ڎ킩�玞�Ԃ������ĖƉu�̌��ʂ��������Ă��Ă��邱�Ƃ����邱�ƂȂǂ���������Ƃ������Ƃł��B
���g�����g��̑�7�g�ɓ������h
��k�̂��Ɣ��g��́u�V���Ȋ����̔g�������Ƃ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��v�Əq�ׁA�����g��̑�7�g�ɓ������Ƃ����F���������܂����B���̂����Łu�����͂̋����wBA.5�x���嗬�ɂȂ��Ă����X�N�̍�����ʂȂǂ͂���܂łƕς�炸�A����ꂪ��邱�Ƃ�3����吺���o����ʂ�����邱�ƁA����Ɋ��C�ȂǂŁA�]������Ă������Ƃ�O�ꂵ�Ăق����v�ƌĂт����܂����B
���g�����_�ōs�������͕K�v�Ȃ��h
����ɔ��g��́u�����s�������͑����̐l�͏o�������Ȃ��ƍl���Ă���Ǝv���B���������[�u���Ƃ炸�Ƃ�������N�`���̐ڎ�A��{�I�ȑ�ŏ��z���邱�Ƃ͉\�ŁA���⎩���̊܂߂đΉ���O�ꂷ��ׂ����v�Əq�ׁA�����_�ł͂܂h�~���d�_�[�u�̂悤�ȍs�������͕K�v�Ȃ��Ƃ����F���������܂����B
���㓡���J���u���� �s�����������鎖�ԂƎv���Ă��Ȃ��v
�㓡�����J����b�͋L�҉�ŁA�������Ċg�債�Ă���v���ɂ��āu3��ڂ̃��N�`���ڎ�Ȃǂɂ��Ɖu�����X�Ɍ������Ă��邱�Ƃ�A�I�~�N�������̐V���Ȍn���ւ̒u������肪�i�ނ��ƂȂǂ��l������v�Əq�ׂ܂����B�܂����g�����7�g�ɓ������Ƃ����F�������������Ƃɂ��Ắu����Ȃ銴���Ґ��̑��������O�����Ƃ���ŁA��Ò̐��ւ̉e�����܂߂Ē������Ă����K�v������v�Əq�x�����������܂����B���̂����Ō㓡��b�́u����Ƃ��Ă͍s�������������鎖�ԂƂ͎v���Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ�����A����A�ċx�݂ɓ����Đl�Ɛl�Ƃ̐ڐG�@������邱�ƂȂǂ��\�z�����Ƃ��āA�}�X�N�̒��p���ȂNJ�{�I�Ȋ����h�~��̓O����Ăт����܂����B
�����Ɓu�ӔC������{�I��𑱂��邱�Ƃ��d�v�v
���ۈ�Õ�����w�̏��{�N�� ��C�����͌��݂̊����ɂ��āu�����g��̃X�s�[�h�������قǑ����A�O���ł������̗z������50���ȏ�̓��������Ă���B�v��������悤�Ȋ������X�N���Ȃ��Ƃ����l���z���ɂȂ�p�^�[���������Ȃ��Ă��āA���퐶���̒��łǂ����Ŋ������Ă���l�������Ă����ۂ��v�ƕ��͂��܂����B�܂��u������肪�i��ł���Ƃ����ψي��uBA.5�v�ɂ��Ắu����܂ł̕ψي��Ƃǂ̒��x�ǏႤ�̂��͓�����������邪�S�̂̌X���Ƃ��ĔM�����߂ɏo�₷���l�������A�̂ǂ̏Ǐ��߂ɏo����A�������o���肷��Ȃǂ�⍡�܂łƂ͈Ⴄ�Ǐo�Ă���Ɗ�����B�����͂����������łȂ��Ɖu�������\�͂������̂Ń��N�`����ڎ킵���l�ł��������₷���ʂ�����B����A�d�lj����₷�����͂܂��킩��Ȃ����A���݂̓��N�`���̌��ʂ�����d�lj����͒Ⴍ�}�����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E���Ă��܂����B����ŏ��{�����͌���̃y�[�X�Ŋ����g�傪�i�ނƗ�����{�ɂ͓����s�̈���̐V�K�����҂�5���l������\��������Ƃ������Z���o�Ă��邱�ƂɐG�ꂽ�����Łu���͂����܂ň�Â��Ђ������Ă��Ȃ��Ƃ������w����x��w���NJ��x�݁A���̂܂ܓ˂������Ă����ƋC�t�������ɑ����̐l���S���Ȃ�Ƃ������Ԃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��B�����͍��̂����ɏ������A���N�`���ɂ��늴����ɂ���A�����ȒP�ɂ͊ɂ߂Ă͂����Ȃ����Ǝv���B�w3���x�̏�ł̓}�X�N��������K�x�Ɋ��C�������肷��ȂǁA�ӔC�������Ċ�{�I�Ȋ�����𑱂��Ă������Ƃ��d�v���v�ƌĂт����܂����B
���ߋ��ő��̊����m�F
�ߋ��ő��ƂȂ�V�^�R���i�ւ̊����m�F�����\���ꂽ���͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
���X 699�l�����m�F / �X���ł�12���A�V����699�l�̊����m�F�����\����܂����B���������̔��\�Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ��Ă��܂��B
���a�̎R 609�l�����m�F / �a�̎R����12���A�V����609�l�̊����m�F�\���܂����B����ɔ��\���ꂽ�����Ґ��Ƃ��ẮA���Ƃ�2��2����597�l�������Ă���܂łōł������Ȃ�܂����B
�����Q 1014�l�����m�F / ���Q����12���A�����̈���̊����Ґ������߂�1000�l���A�ߋ��ő���1014�l�̊����m�F�\���܂����B
������ 1271�l�����m�F / ��������12���A�V���ɉߋ��ő��ƂȂ�1271�l�̊����m�F�\���܂����B����̊����Ґ���1000�l����̂͏��߂ĂŁA�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B
������ 429�l�����m�F / ���挧��12���A�V����429�l�̊����m�F�\���܂����B����̊����m�F�̐��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B
���R�� 527�l�����m�F / �R�����Ɖ��֎s��12���A�V����527�l�̊����m�F�\���܂����B����ɔ��\���ꂽ�����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B
���啪 1113�l�����m�F / �啪����12���A�V����1113�l�̊����m�F�\���܂����B����̊����Ґ��Ƃ��Ă͂���܂łōł������A1000�l��ƂȂ����̂͏��߂Ăł��B
������ 1205�l�����m�F / ���ꌧ��12���A�����ŐV����1205�l�̊����m�F�\���܂����B���������̐V�K�����Ґ��͍���7����691�l��啝�ɏ���A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
���F�{ 2333�l�����m�F / �F�{���ł�12���A�V����2333�l�̊����m�F�̔��\������܂����B����̐V�K�����҂�2000�l����̂͏��߂ĂŁA�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
������ 849�l�����m�F / ���茧�Ȃǂ�12���A���킹��849�l�̊����m�F�\���܂����B����ɔ��\���ꂽ�V�K�����Ґ��Ƃ��Ă͂��Ƃ�1��29����717�l������A����܂łōł������Ȃ�܂����B
�������� 1517�l�����m�F / �����������ł�12���A�V����1517�l�̊����m�F�����\����܂����B����܂Ō����ň��������̐V�K�����҂��ł����������̂͂��Ƃ�4��26����974�l�ŁA�����啝�ɏ��肱��܂łōł������Ȃ�܂����B
������ 3436�l�����m�F / ���ꌧ��12���A�V����3436�l�̊����m�F�\���܂����B����Ɍ��\�����V�K�����҂̐��͂���܂łōł������������Ƃ�5��11����2702�l�������ĉߋ��ő��ƂȂ�܂����B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 1��6878�l���� 2���A����1���l�� �@7/13
�����s����13���̊����m�F��1��6878�l�ŁA2���A����1���l���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2�{���鑝����13����9���A���ƂȂ�A�}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B
�����s��13���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1��6878�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���Ŋ����m�F��1���l����̂�2���A���ł��B�܂��A1�T�ԑO�̐��j����2.02�{�ƂȂ�A8537�l�����܂����B2�{���鑝����13����9���A���ƂȂ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B13���܂ł�7���ԕ��ς�1��160.6�l�ŁA�O�̏T��229.5���ł����B7���ԕ��ς�1���l����̂�4�����]��O�̂��Ƃ�3��7���ȗ��ł��B13���Ɋm�F���ꂽ1��6878�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�21.3���ɓ�����3589�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�1000�l����1167�l�ƂȂ�A�S�̂�6.9���ł����B
�܂��l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A12�����1�l������13�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ80��̏�����90��̒j���̍��킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
���V�^�R���i �������傤1��6878�l�����@���҂��}���u�X�s�[�h������...�v�@7/13
��s�E�����́A�����̑�7�g�ցB�����Ԃ���A���r�m���́u�җ�Ȑ����v�ƕ\�������B
�����s�E���r�S���q�m���u�����҂͖җ�Ȑ����ő����Ă���B�ψي��ւ̒u�������̓����ȂǁA���낢�땪�͂��Ă�����Ă���v
�����s�ł�13���A�V���ɁA1��6,878�l�̊������m�F�B2���A����1���l�����B��T�̐��j��(6��)����2�{�ȏ�ɑ����A26���A���őO�̏T�̓����j�����������B
13�����߂���̓����E�a�J�B�\��s�v�̌����Z���^�[�ł́A��������]����l���r��Ȃ������Ă����B�J�̒��APCR�����Z���^�[�ɂ́A�����瑽���̐l���K��s�ł��Ă����B
PCR�������ɗ����l�u(�����҂�)�����Ă��Ă���̂ŐS�z�ɂȂ��āB�C�ɍs���\���F�����Ɨ��ĂĂ��āA�L�����Z���Ƃ��ɂȂ����肷��̂��ȂƎv���v�A�u�Ζ����Ă���Ƃ��낪�A�D�w�������肷��̂ŁA������������Ǝv���āv
13���̑S���̊����҂́A9���l�����B
��Ì���ł́A���łɑ�7�g�Ƃ̓������n�܂��Ă����B��ʁE�z�J�s�̃N���j�b�N�u���C�N�^�E�������̂����@��A�ȁv�B���݂̃v���n�u�f�Î��ɂ́A��ƂŐf�ÂɖK���Ƒ��A�ꂪ13�����������ł����B��t�́A���S�ɑ�7�g�ɓ������Ƃ݂Ă���B
���C�N�^�E�������̂����@��A�ȁE�|���h�B�������u2�T�ԑO����h�[���Ƒ����āA(���Ґ���)�����ɏオ��悤�Ȋ����ł���ˁB�Ƃɂ����X�s�[�h�������ł��ˁA�������́B�������S�Ɂg��7�g�h�ɓ����Ă܂��v
13���̔����Ō�������39�l�̂����A22�l���z���B�z�����͂��悻56���ŁA��6�g�̃s�[�N����60����ɔ����Ă���Ƃ����B
�|���������u(�Ǐ��)��ԑ����̂́A�̂ǒɂł��B����͂����A�N��w���W�Ȃ��A�S�̂ő����Ă銴��������܂��ˁBBA.5�ɒu��������Ă�Ƃ���ƁA�����̗͂������̂ŁA�L���肪�������ƂɂȂ�v
�����s��13���A�V���Ɋm�F���ꂽ�����҂�1��6,878�l�B1��6,000�l����̂́A2��18���ȗ����悻5�J���Ԃ�B�����s�́A�a���m�ې����6�g�̍ő厞�Ɠ����K�͂̂��悻7,000���ɂ܂ň����グ���B����ɂ��A13�����_�ł̕a���g�p���́A12����41.1������31.7���ɉ��������B
�����͑S���K�͂Ŋg��B�啪���ł́A�V����1,124�l�̊������m�F����A2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ����B����ɁA�É����⍂�m���A�ΐ쌧�ȂǁA���킹��11�̌��ʼnߋ��ő��̊����҂��o�Ă���B13���̑S���̊����҂́A����܂ł�9���l�����B
���{��t��E���{��u���T�������3�A�x��A���̂��Ɖċx�݂Ȃǂ����邱�Ƃ���A���������A��{�I�Ȋ����h�~��̓O������肢�������v
�����������A���ɁE�_�ˎs�͐V���Ȋ�����ɂ��Ĕ��\�����B�s���ɏZ��40��̏������A�I�~�N�������̐V���ȕψي��uBA.2.75�v�Ɋ������Ă����Ƃ����B���{�����ŁuBA.2.75�v�������m�F�����̂́A���߂āB
WHO(���E�ی��@��)�ɂ��ƁA�uBA.2.75�v�́A6���ɃC���h�ŏ��߂Ċm�F����A���E�ł̏Ǘ�́A����14�J����200�����x�B���킵�������͂�d�lj����X�N�Ȃǂ͂킩���Ă��炸�AWHO�͌��O�����ψي��Ɉʒu�Â��Ă���B
����A��7�g�Ɍ�������Ñ̐��ɂ��āA���{�W�҂́u�܂��a���𑝂₹��]�T�͂��邪�A���ꂪ�N��(�Ђ��ς�)������A���{���ǂ��ɂ�����Ƃ�Ȃ���ƂȂ邾�낤�v�Ƃ̌��ʂ��������Ă���B�����̐��{�W�҂ɂ��ƁA���{�́A���~�Ȃǐl�̈ړ��������鎞���Ɏ�v�ȉw���`�Ŗ����������s���l���B���̕��j�ɂ��āA�ݓc�́A14���ɊJ���\��̉�ŕ\�����錩�ʂ��B�܂��A���݂�60�Έȏオ�Ώۂ�4��ڂ̃��N�`���ڎ���A��Ï]���҂╟���{�݂œ����l�ȂǂɍL����Ă��������Ă���B
|
�����{ �V�^�R���i 1��452�l�����m�F 1���l����2��26���ȗ� �@7/13
���{��13���A�V����1��452�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B1���l������̂͂��Ƃ���2��26���ȗ��ŁA�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA2.26�{�ɑ����܂����B
����A���{�͂���܂łɔ��\����6�l�ɂ��āA�d�����Ă����Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��107��4139�l�ƂȂ�܂����B�܂��A3�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͂��킹��5226�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�12���ƕς�炸7�l�ł��B
|
�����������Ŋ�����5000�l���@��B�e���ł��}���@�R���i�Ċg��Ɋ�@���@7/13
���{���ȉ�̔��g��́A�u��7�g�ɓ������v�Ƃ̔F�����������B�V���ȁu�����������ԁv�ɓ������ƌ�����̂ł͂Ȃ����B
7��12���̋�B�ƎR���̐V�K�����҂́A�����Ƌ{�������7�̌��ʼnߋ��ő��B����A�啪�A�������͏���1��l�����A�F�{�͏���2��l�����B����͏���3��l�����ŁA����ɕa���g�p����60���ɔ���A��Ñ̐��̂Ђ��������O����Ă���B
�����Ɋւ��Ă��A�O�̏T�̓����j������2�D3�{�ɋ}�g�債��4295�l�B�܂��A��������13���̐V�K�����҂�5180�l�ŁA�a���g�p��28�D3���A�d�Ǖa���g�p����0���B����܂ł̉ߋ��ő���2��5����5599�l�����A���̎��̕a���g�p����80�����A�d�Ǖa���̎g�p����10�����x�������B�����Ґ��͉ߋ��ō����x�������A��Ñ̐��ɗ]�T�����邩�ǂ����Ō���ƁA����܂ł̑�5�g�A��6�g�Ƃ͈Ⴄ�l�q�B
�����Ċg��̗v���Ƃ��Ďw�E����Ă���̂��A���N�`����3��ڐڎ킩�甼�N�قnjo���A���̌��ʂ������n�߂Ă��邱�ƁB���͕������A3��ڂ̃��N�`���ڎ헦�͑S�����[�X�g5�ŁA58�D86���B���ʂ������n�߂�Ƃ����ȑO�ɁA���������A3��ڐڎ�����Ă���l�̊��������Ȃ��B����ɂ��āA���Ƃ́c
|
������R���i3518�l�����@�×{2���l���@�ő��X�V�@�a���g�p��61%�@7/13
����13���A�V����10�Ζ�������90�Έȏ��3518�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B2���A����3��l���A�ő����X�V�����B�×{���̊��҂�2��598�l�ŏ��߂�2���l��ɒB�����B�R���i�a���g�p���́A���@�����ɍ�������鐅���Ƃ����60������61�E3���ƂȂ����B
2��7���ȗ��́u�N��(�Ђ��ς�)�v�ŁA���ɔ��d�R�ł͕a���g�p����84�E1���ƂȂ����B�f�Ð����̂ق��A�ی����������Ɩ����~�߂ăR���i�Ή��ɏW�����Ă���B�Ί_�s�ł͐l��10���l������̊����҂���2861�l�������B
����11���ɉ���{���Ɣ��d�R����(�Ί_�s�A�|�x���A�^�ߍ���)�ɃR���i�����g��x����o��������B������̋������Ăт����Ă��邪�A�s�������Ȃǂ̑[�u�ɂ͎����Ă��炸�A�����g�傪���܂�C�z�͌����Ȃ��B
�C�̓����܂ލ��T�������3�A�x��ċx�݂�O�ɁA���̋{���`�v�����������Ă͊�@�����点�邪�u�R���i�����g��x��̗l�q������v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂��B���d�R�ɂ͈�Ï]���҂�̔h�����������Ă���Ƃ����B
��芴���͂������Ƃ����I�~�N�������h���^�u�a�`�E5�v�Ȃǂւ̒u������肪�i��ł���B����6��27���`7��6���A244���̂͂����Ƃ���A��3�����h���^�̂a�`�E4�A�a�`�E5�������B
13���̍���̏d�ǎҗp�a���g�p���͑O�����8�E4�|�C���g������31�E7���Ɉ����B�����k���a�@�ł�12���܂łɃN���X�^�[(�����ҏW�c)���������A�v7�l�����������B�ČR�W�̐V�K�����҂�53�l�������B
��n���ݖ����l����g�[�N�L�����o���ʼn��l�s��K��Ă���ʏ�f�j�[�m���́u���ʓI�ȃu���[�L�̓��ݕ��Ƃ������Ƃ��A�G�r�f���X����ɂ����ȕ��������l���Ă���v�Ƌ����B�܂h�~���d�_�[�u�Ɋւ��鍑�̍l�����Ȃǂ�c�����邽�߂ɂ��u������������W���A���Ƃ̈ӌ������𖧂ɂ������v�Əq�ׂ��B
|
���k�C���@�V�^�R���i�V�K������1349�l �挎8���ȗ���1000�l���@7/13
�����ł�13���A�V����1349�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�����̐V�K�����Ґ���1000�l����̂͐挎8���ȗ��ŁA�����̍Ċg�傪�����Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��586�l�A�\���n����152�l�A�Ύ�n����125�l�A�_�U�n����77�l�A���َs��61�l�A����s��59�l�A��m�n���Ɠn���n���ł��ꂼ��42�l�A�����n����38�l�A�I�z�[�c�N�n����37�l�A���H�n����29�l�A���M�s��24�l�A�����n����23�l�A��u�n����16�l�A���n����14�l�A�@�J�n����10�l�A���G�n����6�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��6�l���܂߂�8�l�̍��킹��1349�l�ł��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA��������8�l�������ďǏ�͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
�S�̂̔�������790�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
��������6502���ł����B
�܂��A���ƎD�y�s�͂���܂Ŋ������m�F����Ă����l�̂����A90��̏���1�l�Ɛ��ʁE�N�����\��2�l�̍��킹��3�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B
�V�K�����Ґ��͐�T�̐��j�����528�l�����A����̐V�K�����Ґ���1000�l����̂͐挎8���ȗ��ł��B
�܂��A�O�T�̓����j�����������̂�12���A���ł��B
�����ł�5�����{�ȍ~�A�V�K�����Ґ��̌����X���������Ă��܂������A����5���ɐl��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ����S���Łu1�v������A�����X���ɓ]���܂����B
����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�19��1668�l���܂ނ̂�39��1745�l�A�S���Ȃ����l��2105�l�A���Â��I�����l��38��2184�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���a�`�D5�u����100���Ɂv���S���̊����Ґ��u�}���Ɋg��v�\���J�ȏ����g�D�@7/13
�V�^�R���i�E�C���X���������������J���Ȃ̐��Ƒg�D�̉��13���J����A�I�~�N�������̕ʌn���u�a�`�D5�v�̊�����8����{�ɂ�100���ƂȂ�A�u������肪��������Ƃ̗\���������ꂽ�B�a�`�D5�͏]���̃I�~�N���������������͂������Ƃ���A�u��7�g�v�Ƃ��Ă�銴���Ċg��̗v���Ǝw�E����Ă���B
���Ƒg�D�́A�S���̊����ɂ��āu�}���Ɋg�債�Ă���v�Ƃ̌������܂Ƃ߂��B�S�s���{���Ŋ����Ґ����������Ă���A�u��Ò̐��ւ̉e�����܂ߒ�������K�v������v�ƌx�������������B
�����̘e�c�����E���������nj��������͉��̋L�҉�ŁA�u�s���������K�v�Ƃ����ӌ��͂Ȃ������v�Əq�ׂ�����A�u�Z���I�ɂ͋}���ȑ����������v�Ƃ��Ċ�{�I�Ȋ�����̓O������߂��B
���Ԍ����@�ւŒ��ׂ����̂ɐ�߂�a�`�D5�̊�������ɁA������������̒u�������̗\�����������B�ŏI�I�ɑS�Ă��a�`�D5�ƂȂ邱�Ƃ�O��ɐ��肷��ƁA�������{�ɂ�75�����A8���ɂ�100���ɒB����Ƃ����B
|
���S���̃R���i�����Ґ��@5�J���Ԃ�9���l������@7/13
13���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�9��4492�l�ł����B9���l����̂�5�J���Ԃ�ł��B�܂��A31�l�̎��S�̔��\������܂����B
13���̐V�K�����҂�9��4492�l�ŁA��T�̐��j���Ɣ�ׂ��2�{�ȏ�ɑ������܂����B
�X�A�ΐ�A�É��A�a�̎R�A���m�A�F�{�A����Ȃ�13�̌��ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
����1��452�l��5�J���Ԃ��1���l���܂����B
������1��6878�l��2���A����1���l���܂����B�����s�͈�Ë@�ւ̃R���i���җp�̊m�ەa�������悻5000������7000���Ɉ����グ��ȂǑ�6�g�̃s�[�N���Ɠ��������Ɋg�[����������j�ł��B
|
���V�^�R���i�V�K������ �S���ł͑O�T��2.14�{ �S�s���{���ő��� �@7/13
�����J���Ȃ̐��Ɖ�Ŏ����ꂽ�����ɂ��܂��ƁA12���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑S���ł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�2.14�{�ƁA���ׂĂ̓s���{���ő������A3�{����n����o�Ă��Ă��܂��B
��s����1�s3���ł́A�����s��2.37�{�A�_�ސ쌧��2.41�{�A��t����2.33�{�A��ʌ���2.19�{��2�{���Ă��܂��B
�܂����ł́A���{��2.22�{�A���Ɍ���2.13�{�A���s�{��2.27�{�A���C�ł����m����2.26�{�A����2.18�{�A�O�d����2.07�{�ƁA�������2�{���Ă��܂��B
���T�ɓ����āA���������ʼnߋ��ő��̊����҂��m�F���ꂽ�n��ł��A��������1.80�{�A���挧��2.18�{�ȂǂƑ����������Ă��܂��B
���̂ق��ɂ��A�H�c����3.57�{�A�ޗnj���3.01�{�A��茧��2.77�{�A�Q�n����2.70�{�A�É�����2.65�{�A�܂��A�l��������̊����Ґ����ł��������ꌧ��1.52�{�ȂǁA���ׂĂ̓s���{���ő������Ă��܂��B
�l��10��������̒���1�T�Ԃ̊����Ґ��́A���ꌧ��1117.70�l��1000�l��傫�������đS���ōł������A�����œ�������776.46�l�A�F�{����639.99�l�A���ꌧ��626.42�l�A�����s��445.54�l�A���{��420.52�l�ȂǂƂȂ��Ă��āA�S���ł�290.14�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��������1�T�ɂ� �قڑS�̂��uBA.5�v�ɒu�������Ɛ���
13���ɊJ���ꂽ�����J���Ȃ̐��Ɖ�ł́A���������nj������̗�؊���lju�w�Z���^�[�����I�~�N��������1�ŁA��芴���͂������Ƃ����uBA.5�v�ɂ��āA����̍����ł̍L����𐄒肵���f�[�^�������܂����B
����ɂ��܂��Ɩ��Ԃ̌�����ЂŌ��o���ꂽ�uBA.5�v�̊��������Ƃɐ��肷��ƑS���́uBA.5�v�ɂ�銴���̊����́A������1�T�̎��_�őS�̂̂��悻36���Ƃ݂���Ƃ������Ƃł��B�n��I�ɂ͓���������1�T���_�ŁA��s����1�s3���ł͂��悻57���A����2�{1���ł��悻29���Ɛ��肳��Ă��܂��B
�����́uBA.5�v�́A����������𑱂���Ƃ݂��A������1�T�ɂ́A�S���I�ɂقڑS�̂��uBA.5�v�ɒu�������Ɛ��肳���Ƃ������Ƃł��B
�����Ɓu�����͊����͋����wBA.5�x�̊g�傪�傫���v
�V�^�R���i�E�C���X�̊������S���I�Ɋg�債�Ă��邱�Ƃɂ��āA�C�O�̊����ǂɏڂ���������ȑ�w���_�c�ĘY���C�����́A�u�����Ƃ��ẮA�I�~�N��������1�ŁA�����͂������Ƃ����wBA.5�x�̊g�傪�傫���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
�uBA.5�v�̊����͂ɂ����_�c���C�����́u����܂ł̃I�~�N�������ɔ�ׂĊ������L����X�s�[�h�����Ȃ葬���ق��A���N�`����ڎ킵���芴�����o�������肵���l�̏ꍇ�ł��wBA.5�x�͖Ɖu���瓦���Ă��܂����Ƃ�������B�����������Ƃ������I�Ɋ����͂������Ƃ������ƂɂȂ����Ă���v�Əq�ׂ܂����B
����A���������ꍇ�̏d�Ǔx�ɂ��ẮA�u�d�lj��������N���������͂���܂ł́wBA.1�x��wBA.2�x�Ƃ��܂�ω����Ȃ��Ƃ���Ă��邪�A���������l�q�����Ă����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B���̒i�K�ŁA�d�ǎ҂⎀�S�҂������Ă��鍑�͂��܂葽���Ȃ����A����̕ω������ɂ߂�K�v������v�Əq�ׂ܂����B
����̊����̌��ʂ��ɂ����_�c���C�����́A�u�wBA.5�x�̓��N�`���������ɂ����ƌ����Ă��邪�A����ł����{�����ł͑����̕������N�`����3��ڂ̐ڎ���Ă��邱�Ƃ�A���������ł͂Ȃ����ƂȂǂ܂���ƁA���Ƃ�1���ɃI�~�N�����������s���n�߂�����قǂɂ͊����Ґ��͑����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl������B�����A�t�����X��C�^���A�A�h�C�c�Ȃǐ����[���b�p�ŁA����1�A2�T�Ԃ̊ԂɊ����Ґ������Ȃ葝���Ă���B�����������X�Ŋ����Ґ���d�ǎҐ����ǂ̂悤�ɑ����邩�A����̓��{�̏�\�����邤���Ŕ��ɏd�v���v�Ǝw�E���܂����B
�܂��A���㋁�߂����ɂ����_�c���C�����́A�u�����A�������ȑO�o���������g�傷�邱�Ƃ��z�肵�ď�������ׂ����B3��ڂ̃��N�`���ڎ���܂��Ă��Ȃ����́A���߂ɎĂ��������������A����҂̕���4��ڂ̐ڎ���邱�Ƃ�������厖���B�����Ґ������ɑ����Ă���Ƃ��́A��l�ЂƂ�̗\�h���������x���߂ɍs�����Ƃ���ŁA�������^���Ǐ���A���߂Ɍ����������Ë@�ւ���f�����肵�Ăق����B�����̒n��ł͕a���͂܂��Ђ������Ă��Ȃ����s���@�ւ͑O�����ď������A��Ï]���҂���{�݂̐E���Ȃǂւ�4��ڂ̐ڎ���������Ă��炢�����v�Ǝw�E���܂����B
�����[�����u�����g��h�~�ƌo�ώЉ���̗����}��v
���슯�[�����͌ߌ�̋L�҉�ŁA�u�����g��̖h�~�ƌo�ώЉ���̗�����}��d�lj��h�~��O���ɕی���Ñ̐��̈ێ��E�����A���N�`���ڎ�Ȃǂ̎��g�݂𒅎��ɐi�߂�l�����v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A�V�^�R���i�̊����ǖ@��̈������G�ߐ��̃C���t���G���U�Ɠ����x�Ɍ��������ǂ����ɂ��āA�u�I�~�N�������ł����Ă��v������d�lj������C���t���G���U���������A����Ȃ�ψق̉\��������Ɛ��Ƃ���w�E����Ă���A�ő���̌x���ǖʂ̌����_�Łw�ܗށx�ɕύX���邱�Ƃ͌����I�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
����ɃI�~�N�������̂����A�����͂���荂���Ƃ����uBA.5�v�ɂ��āA�u�����_�ł͍����ɂ����銴���̎嗬�ł͂Ȃ����A��������̃I�~�N����������̒u������肪�i�݁A�����Ґ��̑����v���ƂȂ�\�����w�E����Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁA�u�wBA.2�x�n���Ɣ�r���āA�����Ґ��̑����X�s�[�h�������\������������Ă��邪�A�����_�ł͏d�Ǔx��Ǐ�̈Ⴂ�ɂ��ĉȊw�I�m���͓����Ă��Ȃ��B�����������Ƃ̈ӌ��������Ȃ���A�m���Ȃǂ̎��W�A�Ď��𑱂��Ă����v�Əq�ׂ܂����B
�����{��t���C�����u4��ڐڎ�Ώۊg�嗈�T���X���炢�Ɍ����v
���{��t��̊��ˏ�C�����͋L�҉�ŁA�����̍Ċg��ɂ��āu�wBA.5�x�ւ̒u��������ڐG�@��̊g������邪�A��{�I�ɂ͂���܂Ŋl���ł��Ă����Ɖu�̌����ɂ�銴���g�傪�傫���Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A4��ڂ̃��N�`���ڎ�̑Ώ۔͈͂̊g��ɂ��ẮA�u����Ȃ�ׂ����������ɍ��ӌ`�����K�ɑΉ��������B����ꂽ�G�r�f���X�������J���Ȃ����Ă���邾�낤�B���T���X���炢�Ɍ��������Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
����ŁA���ˎ��͌����_�ł͍s�������͕K�v�Ȃ��Ƃ��Ȃ�����A�u����͎���×{�̑I�����K�v�Ȋ����҂̑����������܂��̂ŁA����×{�ւ̃t�H���[���ł���悤�ɒn��Ŋm�F���K�v���B�t�H���[�A�b�v�̑̐����s�\���Ȏ����̂͊g�[�̕K�v������v�Əq�ׂ܂����B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 1��6662�l�����m�F �O�T��1.95�{ �@7/14
�����s����14���̊����m�F��1��6662�l�ŁA3���A����1���l���܂����B�O�̏T�̓����j����1.9�{�]��ƈ����������������ő������Ă��ċ}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B
�����s�́A14���ɓs���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1��6662�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���Ŋ����m�F��1���l����̂�3���A���ł��B1�T�ԑO�̖ؗj����1.95�{�ŁA8133�l�����܂����B�s���ł�13���܂ł�9���A���ŁA�O�̏T�̓����j����2�{���鑝���ł������A14���͂킸����2�{�������܂����B�����A�����������������ő������Ă��āA�}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B14���܂ł�7���ԕ��ς�1��1322.4�l�ŁA�O�̏T��220.8���ł����B�m�F���ꂽ1��6662�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�22.8���ɂ�����3802�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�1166�l�ƂȂ�A�S�̂�7.0���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A13�����2�l������15�l�ł����B����s�́A�������m�F���ꂽ70���80��̒j���̍��킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 4�l���S �V����9957�l�����m�F �@7/14
���{��14���A�V����9957�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA2�{�ȏ�ɑ����܂����B����ő��{���̊����҂̗v��108��4096�l�ƂȂ�܂����B�܂��A4�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5230�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂́A13������1�l������6�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 3�l���S �V����5718�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/14
��������14���A�����ŐV����5718�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
���Ƃ�2��5����5599�l������A�ߋ��ő����X�V���܂����B2���A����5000�l���A24���A���őO�̏T�̓����j���������Ă��܂��B����́A�����s��2451�l�A�k��B�s��759�l�A�v���Ďs��400�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����48��7375�l�ɂȂ�܂����B�܂��A70���90��ȏ�̍��킹��3�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1292�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����3565�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/14
���ꌧ��14���A�V����3565�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
3���A����3000�l���A����܂łōł���������13����3518�l��47�l�����ĉߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A��T�̖ؗj���ɔ�ׂ�1176�l�����Ȃ��Ă��āA�O�̏T�̓����j��������̂�11���A���ł��B����ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�28��4412�l�ɂȂ�܂����B
|
���V�^�R���i�����m�F1713�l ��1�������Ԃ�1500�l���@7/14
14���A�����ł͐V����1713�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�����̐V�K�����Ґ���1500�l������̂͂��Ƃ�5��28���ȗ��A���悻1�������Ԃ�ł��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s��809�l�A�Ύ�n����192�l�A�\���n����152�l�A���َs��84�l�A�_�U�n����75�l�A����s��72�l�A��m�n����53�l�A�I�z�[�c�N�n����47�l�A���H�n����45�l�A�n���n����40�l�A���M�s��33�l�A��u�n����21�l�A�����n����20�l�A���n����16�l�A�����n����15�l�A�@�J�n����10�l�A�O�R�n���Ɨ��G�n���ł��ꂼ��4�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��13�l���܂�21�l�̍��킹��1713�l�ł��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA��������15�l�������Ē����ǂ�2�l�ł��̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
�܂��S�̂̔�������1107�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������5777���ł����B14���͓����ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���Ď��S�����l�̔��\�͂���܂���ł����B
�V�K�����Ґ��͐�T�̖ؗj�����812�l�����A1���̐V�K�����Ґ���1500�l������̂͂��Ƃ�5��28���ȗ��A���悻1�������Ԃ�ł��B
�܂��A�O�̏T�̓����j�����������̂�13���A���ł��B
����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�19��2477�l���܂ނ̂�39��3458�l�ƂȂ�A�S���Ȃ����l��2105�l�A���Â��I�����l��38��2750�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i�̑�7�g���}�g��A�V�K�����҂͉ߋ��ő�10���l���鐨���@7/14
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��S���I�ɋ}�����A�����g��̑�7�g�������ɂȂ��Ă���B�����J���Ȃɂ��ƁA13���ɂ͍����̐V�K�����҂�9��4000�l�ȏ�𐔂����B�ߋ��ő��̖�10��4000�l�ɔ���A����ɒ����鐨�����B�����J���ꂽ�����J���Ȃɑ������������Ƒg�D�̘e�c���������́A�I�~�N�������h���^�uBA.5�v�̊����͂́uBA.2�v�̖�1.3�{�����ABA.5�̍L���肪��7�g�̋}�g��̗v���ɂȂ��Ă���Ƃ̌������������B���g�D�́u��Ò̐��ւ̉e�����܂߂Ē�������K�v������v�ƌx�����Ă���B
���Ƒg�D��ɒ�o���ꂽ���J�Ȏ����ɂ��ƁA12���܂ł�1�T�ԂɊm�F���ꂽ�S���̐V�K�����Ґ��͑O�T���2.14�{�Ƌ}���B�V�K�����Ґ��͑S�s���{���A�S�Ă̔N��ő������A7���ɓ����Ă��璛�����o�Ă�����7�g�������ŁA����Ɋg��X���ɂ���B��s���ł͓����s���O�T��2.37�{�A�_�ސ쌧����2.41�{�B���̂ق��ł͐É�������2.65�{�A���쌧����2.58�{�ȂǤ�����҂̑����͑S���I�X�����B
�a���g�p���͂܂���r�I�Ⴂ���������A���ꌧ��5�����ōł������A�����ŌF�{����5����A�a�̎R���Ǝ��ꌧ��4�����Ƒ����B�����̓s���{���ō����Ȃ�X���ŁA��Ñ̐��ւ̕N��(�Ђ��ς�)�����O�����B
�����s�ɂ��Ǝ��̏W�v�ł́A13���̐V�K�����҂�1��6878�l�𐔂���O�����5367�l�������B��6�g�̃s�[�N��2��8���ŁA�V�K�����҂�1��8012�l�B�������͎̂��Ԃ̖��Ƃ݂���B�s�̐V�^�R���i�E�C���X�̃��j�^�����O��c��7���̉��8����{�ɂ͐V�K�����҂�5���l����\��������Ƃ̎��Z�����\���Ă���B
���������nj������͐��Ƒg�D�̉�ŁABA.5�̊����҂���߂銄���͌����_��8���߂��ɏ��Ƃ̐��v�������A8����1�T�ɂ͑S��BA.5�ɒu�������Ƃ݂Ă���B�ŋ߂̊����ɂ��Đ��Ƒg�D�́u�����̒n��Ŋ����҂̑��������傫���Ȃ��Ă���A�}���Ɋ����g�債�Ă���B������������������Ƃ������܂��v�ƌ��_�t�����B
���ɋL�҉�����e�c�����͍����ɓ����Ă���̊����}�g��̗v���Ƃ��āA���N�`����3��ڐڎ����ۂ̊����Ŋl�����ꂽ�Ɖu�����X�Ɍ������Ă��邱�Ƃ�A�}���ɍL�����Ă���BA.5�͊����͂������Ƃ��ꂽBA.2��肳��ɖ�1.3�{�����A�Ɖu���������\�͂����邱�ƂȂǂ��������B
�㓡�ΔV���J���͂��̉�Łu����͑����̒n��ŐV�K�����Ґ��̑����������ƌ����܂��B�}�X�N�̒��p�Ȃǂ̊�{�I�Ȋ����h�~���O�ꂷ�邱�Ƃ�S�����Ăق����v�Əq�ׂĂ���B���J�ȊW�҂ɂ��ƁA�d�ǎ҂⎀�S�҂̐����܂��ᐅ���Ő��ڂ��Ă��邱�Ƃ��瓖�ʐ��{�Ƃ��čs�������͋��߂Ȃ����j�Ƃ����B
�����̐��Ƃ́A�S�̂̊����҂�������������Ώd�ǎ҂̐���������Ǝw�E�B3��ڃ��N�`���ڎ헦��50���O���20��A30���3��ڐڎ�ƁA����҂⎝�a������l��4��ڐڎ���}���K�v������A�Ƌ������Ă���B
|
 |
�������̃R���i�����ҁA�v��1000���l���Ɂc��6�E7�g������800���l �@7/15
�����̐V�^�R���i�E�C���X�̗v�����҂�14���A�ǔ��V���̏W�v��1001��5724�l�ƂȂ�A2020�N1���ɏ��߂Ċm�F����Ă���2�N����1000���l�����B�����͂̋����I�~�N�������̉e���ő����X�s�[�h�͋}���ɏオ���Ă���A���N1���ȍ~�̑�6�g�Ƒ�7�g������800���l���Ă���B
�v�����҂͍��N1��20����200���l���A2��28���ɂ�500���l��˔j�B���̌�A�������x�͈ꎞ�݉��������A7���ɓ���A�����͂̋��������̐V�n���u�a�`�E5�v�̊g��ōĉ������Ă���B�s���{���ʂł́A�����s����171���l�A���{����108���l�A�_�ސ쌧����83���l�ȂǁB
14���̑S���̐V�K�����҂�9��7788�l�m�F���ꂽ�B�����s��1��6662�l�ŁA�O�����216�l���Ȃ����A�O�T�̓����j������2�{�ɑ����A27���A����1�T�ԑO���������B�X�A�É��A�O�d�A�R���A����A�����A����A�F�{�A�����9���ł͉ߋ��ő����X�V�����B
�s��14���̃��j�^�����O(�Ď�)��c�ŁA�Ǝ���4�i�K�ŕ]�����銴���̌x�����x����1�i�K�����グ�A�ł��[���ȃ��x���Ƃ����B��Ò̐���2�Ԗڂɐ[���ȃ��x���Ɉ����グ���B
��c�ł́A���݂̑����X�s�[�h�������A1��������̐V�K������(�T����)��1�T�Ԍ�ɂ�2��3000�l���Ɖߋ��ő����X�V���A2�T�Ԍ�ɂ�5��3000�l���ɒB����Ƃ̎��Z�������ꂽ�B�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���ۊ����ǃZ���^�[���́u����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������I�Ȋ����ɂȂ�v�Əq�ׂ��B
����A�S���̏d�ǎҐ���100�l�őO�����10�l���������A��6�g�̃s�[�N(1507�l)��7���ɂƂǂ܂��Ă���B
���t���[�̏W�v�ɂ��ƁA13�����_�̕a���g�p���͉��ꌧ��61���ƑS���ōł������A�a�̎R����54���A�F�{����50���A�����s��31���������B |
�������s �V�^�R���i 2�l���S 1��9059�l�����m�F �O�T��2.17�{ �@7/15
�����s����15���̊����m�F��1��9059�l�ŁA�O�̏T�̋��j������1���l�]�葝���A�}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s�́A15���s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1��9059�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j����2.17�{�ŁA1��282�l�����܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂĂ킸����2�{���������14���������ẮA����5������2�{���鑝���ƂȂ��Ă��āA�}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B15���܂ł�7���ԕ��ς�1��2791.3�l�ŁA�O�̏T��217.7���ł����B15���Ɋm�F���ꂽ1��9059�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�22.4���ɂ�����4273�l�ł����B20��̊����́A����܂łōł������Ȃ��Ă��āA�s�̒S���҂́u20��͊����������Ȃ����A3��ڂ̃��N�`���̐ڎ헦���Ⴂ���Ƃ��w�i�ɂ���ƌ�����B�ϋɓI�ɐڎ킵�Ă��炢�����v�Ƙb���Ă��܂����B
65�Έȏ�̍���҂�1449�l�ƂȂ�A�S�̂�7.6���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A14�����1�l������16�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ50���70��̒j���̍��킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 1�l���S 9745�l�����m�F �O�T���j��2�{�ȏ� �@7/15
���{��15���A�V����9745�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂāA2�{�ȏ�ɑ����܂����B����A�{�͍���12������14���܂łɔ��\�����A���킹��4�l�ɂ��āA�d�����������Ƃ��Ď�艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��109��3837�l�ƂȂ�܂����B�܂��A1�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5231�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂́A14������3�l������9�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i �V����6356�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/17
��������15���A�����ŐV����6356�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
6000�l����̂͏��߂ĂŁA�ߋ��ő����X�V���܂����B25���A���őO�̏T�̓����j���������Ă��܂��B����́A�����s��2400�l�A�k��B�s��816�l�A�v���Ďs��435�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
����A14���Ɋ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ1�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����49��3730�l�ɂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����3462�l�����m�F 4���A��3000�l�� �@7/15
���ꌧ��15���A�V����3462�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�V�K�����҂�4���A����3000�l���܂����B��T�̋��j���ɔ�ׂ�1045�l�����Ȃ��Ă��āA�O�̏T�̓����j��������̂�12���A���ł��B�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�28��7874�l�ɂȂ�܂����B
|
���V�^�R���i ������1734�l�����m�F 2���A��1500�l���@7/15
15���A�����ł͐V����1734�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�����̐V�K�����Ґ���2���A����1500�l������A�������g�債�Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s��865�l�A�Ύ�n����157�l�A���َs��124�l�A�\���n����118�l�A�_�U�n����78�l�A����s��63�l�A��m�n����55�l�A���H�n����49�l�A�n���n����42�l�A�I�z�[�c�N�n����39�l�A���M�s�ƍ����n���ł��ꂼ��32�l�A���n����31�l�A��u�n����16�l�A�����n����11�l�A���G�n����8�l�A�@�J�n����2�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��7�l���܂�12�l�̍��킹��1734�l�ł��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA��������3�l�������Ē����ǂ�2�l�ł��̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�܂��S�̂̔�������1013�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������5771���ł����B15���́A�����ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���Ď��S�����l�̔��\�͂���܂���ł����B�V�K�����Ґ��͐�T�̋��j�����847�l�����A1���̐V�K�����Ґ���2���A����1500�l������܂����B�܂��A�O�̏T�̓����j�����������̂�14���A���ł��B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�19��3342�l���܂ނ̂�39��5192�l�ƂȂ�A�S���Ȃ����l��2105�l�ƂȂ��Ă��܂��B���Â��I�����l��38��3404�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i ����̊������\ �S����10���l�� ���Ƃ�2���ȗ� �@7/15
15���́A����܂łɑS����10��3311�l�̊��������\����Ă��܂��B����̊����Ґ��̔��\��10���l����̂͂��Ƃ�2���ȗ��ɂȂ�܂��B
�܂��A��t����3�l�A�啪����3�l�A���Ɍ���2�l�A�{�錧��2�l�A���m����2�l�A�����s��2�l�A�F�{����2�l�A��錧��2�l�A����������2�l�A���s�{��1�l�A���ꌧ��1�l�A��ʌ���1�l�A���{��1�l�A��茧��1�l�A��������1�l�A���Q����1�l�A�Ȗ،���1�l�A���ꌧ��1�l�A���䌧��1�l�A�X����1�l�̍��킹��31�l�̎��S�̔��\������܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͋�`�̌��u�Ȃǂ��܂�1011��8297�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��1011��9009�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�S���Ȃ����l�͍����Ŋ������m�F���ꂽ�l��3��1565�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��3��1578�l�ł��B
|
���S���ŐV�K������10���l�����@�ߋ�2�Ԗڂ̑����@7/15
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āAJNN�̂܂Ƃ߂ł́A���傤�S���ʼnߋ�2�Ԗڂ̑����ƂȂ�10��3311�l�̐V�K�����҂��m�F����܂����B�S����1��������̐V�K�����Ґ���10���l�����̂́A�ߋ��ő��ƂȂ������N2��5����10��4169�l�ȗ��ŁA��5�����Ԃ�A2��ڂł��B
�����s�ł�1��9059�l�A���{�ł�9745�l�A�_�ސ쌧��7603�l���m�F�����ȂǁA�S���I�Ȋ����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��ł��B
����܂łɑS���ł́A�X��(920�l)�A�a�̎R��(632�l)�A������(6356�l)�A�F�{��(2643�l)�A��������(1599�l)�̍��v5���ʼnߋ��ő��̐V�K�����҂��m�F����Ă��܂��B
�S���œ��@���Ă��銴���҂̂����d�ǎ҂Ƃ����l�́A107�l�ł����B7��1�����_�ł̏d�ǎ҂�52�l�������̂ŁA�����Ŕ{���������ƂɂȂ�܂��B�V���Ȏ��҂�30�l�Ɣ��\����Ă��܂��B
|
���S���̊����Ґ�10���l������@���悻5�J���Ԃ�@��6�g�s�[�N�ɔ���@7/15
���傤�A����܂łɁA�S���ŁA�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������l���A���킹��10��1993�l�ɂ̂ڂ������Ƃ��AFNN�̂܂Ƃ߂ŕ��������B1���̑S���̊����Ґ����ł����������̂́A�����g��h��6�g�h��2��5����10��4155�l�B�u10���l�����v�́A����ȗ��A���悻5�J���Ԃ�ƂȂ�B
���݁A�S���e�n�ŁA���Ȃ葬���X�s�[�h�Ŋ������Ċg�債�Ă��āA���Ƃ���́A�h��7�g�h�ɓ������Ƃ̌�����������Ă���B�����s�ł́A���傤�V����1��9059�l�̊������g�傳�ꂽ�B1���̊����Ґ��Ƃ��ẮA4���A����1���l���������B
���傤�A����܂łɁA��������5718�l�A�F�{����2643�l�A����������1599�l�A�X����920�l�A�a�̎R����630�l�̊���������A��������ߋ��ő����X�V���Ă���B
|
���V�^�R���i�̊����� 10���l�� �g�f�@��ꂸ�h�a���Ђ����� �@7/15
�V�^�R���i�̊����҂̔��\��15���A���Ƃ�2���ȗ��A�S����10���l���܂����B�������}���ɍL���钆�A�V�^�R���i�̊������^���Ă��A�����ɐf�@�����Ȃ�������A�~�}�̎���v�����}�����A�a�����Ђ��������ԂɂȂ��Ă��܂��B����̏ƁA���{�̑Ή��A�����đS���̊������܂Ƃ߂܂����B
���e�n����S�z�⌜�O�̐�
2�N�Ԃ�Ɏ�ނ���Ă���r�A�K�[�f���ł́A����̊����҂̓��������O���鐺���������Ă��܂��B�����E�`��̃z�e�����^�c����r�A�K�[�f���́A������Ƃ��ė��X���̌������w�̏��ł�O�ꂵ�Ă���ق��A600�Ȃ�����Ȃ�320�Ȃ܂Ō��炵�ăe�[�u���ǂ����̊Ԋu��ʏ��2�{���x�ɍL���Ă��܂��B
7��1���̃I�[�v���ȍ~�A�T���𒆐S�ɑ����̋q�łɂ�����Ă���Ƃ������ƂŁA�r�A�K�[�f���ł͉Ė{�ԂɌ����Ă���Ȃ�W�q�Ɋ��҂������ŁA�����s�ł͐V�^�R���i�̐V�K�����Ґ���4���A����1���l���Ă��荡��̊��������O������Ȃ��Ƃ����܂��B�r�A�K�[�f�����^�c���铌���v�����X�z�e����������̊C�V�������x�z�l�́u�y���݂ɂ��Ă������������������������̂ŁA�������O�ꂵ�Ăł������c�Ƃ𑱂������v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A���L���̊ό��n�Ƃ��Ēm����a�̎R�����l���ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ʼnĂ̊ό��V�[�Y���ւ̉e����S�z���鐺���オ���Ă܂��B�����̘V�܂̉��قł́A�����_�ł�7����8���̏h���\��͂�������O�̔N�������Ă���Ƃ������ƂŁA�ʏ�̊����\�h�ɉ����ďh���҂����M�����ꍇ�ɔ����āA�u���ł��镔�����m�ۂ���Ȃǂ̑���Ƃ��Ă��܂��B�������A���̂܂܊����g�傪�����Η\��̃L�����Z�����������˂Ȃ��ƌ��O���Ă��܂��B���ق̂����݁A���c�O������́u�ً}���Ԑ錾���o���Ƃ��̂悤�ɑ傫�ȉe���͏o�Ă��܂��A�������L�����Z���̘A���͓����Ă��Ă��܂��B��7�g�͐S�z�ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
���ݓc�u�s���������� �Љ�o�ω��v
�S���I�ȐV�^�R���i�̊����Ċg����āA���傤���{�̑��{�����J����A�ݓc������b�́A�����_�ł͐V���ȍs�������͍s�킸�A�ő���̌x���𑱂��Ȃ���Љ�o�ϊ����̉Ɍ��������g�݂�i�߂Ă������j�������܂����B���{���ł́A�S���I�Ȋ����̍Ċg����āA�ċx�݂̋A�Ȃō���҂ɉ�ꍇ�Ȃǂ̎��O�̌�����A�����ꂽ��Ԃ̌��ʓI�Ȋ��C�̎��{�����߂邱�ƂȂǂ荞��{�I�Ώ����j�̕ύX�����肵�܂����B�ݓc������b�́u��Ñ̐����ێ��E�������Ȃ�����������ő���̌x����ۂ��A�Љ�o�ϊ����̉Ɍ��������g�݂�i�K�I�ɐi�߂Ă����B�܂��͋������ꂽ�Ή��͂�S�ʓI�ɓW�J���A�V���ȍs�������͌����_�ł͍l���Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
���㓡���J�� �u�Ώۂ��g�� 4��ڐڎ�i�߂�v
�܂��A���{�͌��݁A60�Έȏ�̐l�Ȃǂɍs���Ă���V�^�R���i���N�`����4��ڐڎ�̑Ώ۔͈͂��A��Ï]���҂ƍ���Ҏ{�݂̃X�^�b�t�Ȃǂɂ��g�傷����j�ł��B����ɂ��āA�㓡�����J����b�́A�t�c�̂��Ƃ̋L�҉�Łu���T22���ɊJ�×\��̌����Ȋw�R�c��ŋc�_���A���������A���₩�ɕK�v�Ȏ葱�����s���A�V���ȑΏێ҂ɑ���4��ڐڎ��i�߂����v�Əq�ׂ܂����B
���Ȃ��Ȃ��f�@���Ȃ��c�u�����āv�u�ق����v
�����s����15���̊����m�F�́A�O�̏T���1���l�ȏ㑝���A1��9059�l�ƂȂ�A�}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B�s���ɏZ��50��̏����͊������^��ꂽ���Ƃ���Ë@�ւ�\��ł����A�V�^�R���i�̗z���Ɛf�f�����܂łɔ��M����3�����������Ƃ����܂��B�����́A���w���̑��q�̗z�����m�F���ꂽ������7��9���A���g�����M�������ߎs�̖̂������ŐQ�����̂́A�������ɋꂵ���Ȃ��Ėڊo�߂��39�x6���܂ŔM���オ���Ă����Ƃ����܂��B����҂��āA�s�̔��M���k�Z���^�[�ɓd�b���Đ��̋@�ւɕa�@���Љ�Ă���������̂̓d�b���Ȃ���Ȃ��������A�Ƒ����a�@��T���Ă���܂������Z�����Đf���Ȃ��ƒf���A����ɔM��40�x���ߌ�ɂ͈ӎ��������낤�Ƃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B������11�����A���M�O���Ȃǂɓd�b�������܂������\�����ς��Őf�Ă��炦���A�M���o�Ă���3�����7��12���ɁA�q�ǂ��̂��������̏Љ�ł悤�₭�f�@�����z���Ɛf�f����܂����B�����͎��g�̏Ǐ�ɂ��āu�M���������ăC���t���G���U�̈�Ԃ炢�Ƃ�����C�ɗ����悤�Ȋ����ŁA�S�g���ɂ��g�C���ɂ��s���Ȃ��悤�ȏŁA�������v���Ă����R���i�̃C���[�W�ƈႢ�܂����B���N�`�����ł��Ă���̂ɂ���ȂɏǏo��ƕs���ȋC�����ɂȂ�܂����v�Ƙb���Ă��܂����B�Ȃ��Ȃ��f�@�����Ȃ��������Ƃɂ��āu�w�����āx�w�~�����x�Ɩ{���ɂ��ꂾ���ł����B���̓��{�ł͑��k�Z���^�[���������肷���ɕa�@���Љ�Ă��炦�Ĉ��S�����̂ɁA���̐�̕a�@�ɂ܂������Ȃ���Ȃ��̂Ŝ��R�Ƃ��܂����B�����łȂ�Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂����v�Ƙb���Ă��܂����B
���g��f���銳�ҁh �g���N�`���ڎ�̊�]�h �}��
�Ή��ɒǂ����Ì���B�V�^�R���i�̊����̋}�g����Đ�t�s��ы�̃N���j�b�N�ł́A6���͐V�^�R���i�̊����m�F��1����2�l����3�l���x�ł�����7���ɓ����Ă���}�����Ă��܂��B15���͌ߑO���A���M�O����K�ꂽ50�l�̂����A4������22�l�̊������m�F����܂����B�N���j�b�N�ɂ��܂��Ɣ�r�I�Ǐy�����҂�����������6�g�Ɣ�ׂāA���M�⋭������ӊ���i���銳�҂������Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
�܂��A4��ڂ̃��N�`���̐ڎ����]����l���}�����A�������ɂ�1��100�l���̗\��g��݂��Ă��܂����A���ł�7��24���܂Ŗ��܂��Ă��āA�V���ȗ\����ɂ����Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B�u��уT�e�B�N���j�b�N�v�͓̉����Y��t�́u�����o���������炢�̖Z�����ɂȂ��Ă���B�s���������Ȃ��Ȃ̂ŁA�}�X�N���Ȃlj��߂Ċ������O�ꂵ�Ăق����v�Ƙb���Ă��܂����B
���R���i��p�a��8�����܂� �Ђ����������
�����s���̕a�@�ł͋~�}�̎���v�����ʏ�̂��悻2�{�ɑ����A�R���i��p�a����8�������܂�ȂǁA�Ђ���������ԂƂȂ��Ă��܂��B���� �k��̓����k��ÃZ���^�[�͐V�^�R���i�̐�p�a����41���m�ۂ��āA�����ǂ𒆐S�Ɋ��҂�ϋɓI�Ɏ���Ă��܂��B6�����{�̎��_�Ŗ��܂��Ă����a���́A�^���ǂ̊��҂��܂߂�10�����x�ł������A��T����}�����A14�����_�ł́A���ł�34�������܂�a���̎g�p����8�����Ă��܂��B
���@���҂͍���҂�q�ǂ��A�D�w�������A�M�₹���A�̂ǂ̒ɂ݂Ȃǂ�i����l�������Ƃ������Ƃł��B�����A�_�f�z�����K�v�ɂȂ�ȂǏd�lj�����P�[�X�́A���̂Ƃ��둽���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�܂��A�~�}�̎���v�������40������50�����x�ƁA���T�ɓ����Ă���ʏ�̂��悻2�{�ɋ}�����Ă��āA���̂����������x���R���i�̋^���̂��銳�҂⎩��×{�҂��Ƃ������Ƃł��B�s�S���⑽���n��Ȃlj�������̗v��������܂����A�a�������܂���邽�߁A�������͔̂������x�ɂƂǂ܂��Ă���Ƃ������Ƃł��B�a�@�͍���A�M���ǂ̊��҂���������ƃR���i�Ƃ̌�������������߁A�A�����m�F�����܂ł́A��p�a���ɓ����Ă��炤���ƂɂȂ邽�ߕa���̍X�Ȃ�Ђ��������O���Ă��܂��B
�����k��ÃZ���^�[�̋{�荑�v��t�́u��T������@�������āA�s������̈˗���~�}�̃R���i���҂̈˗���f�炴������Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��B7���A8���͂��Ƃ��ƔM���ǂȂǂō���҂��̒��s�ǂ��N�����A���@���邱�Ƃ������A�x�b�h�����܂鎞���ł�����A����ɕa�����Ђ�������̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ł��v�Ƙb���Ă��܂��B
���l���̑�����s������Ȃ� �O�T��2�{��
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA���ׂĂ̓s���{���ő����A�l���̑�����s������Ȃ�32�̓s�{���őO�̏T��2�{���Ă��܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1��8919�l�̊����m�F 5���A����1���l�� �@7/16
�����s����16���̊����m�F��1��8919�l�ŁA�O�̏T�̓y�j������9000�l�]�葝���A�}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��16���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1��8919�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j����1.95�{�ŁA9203�l�����܂����B�s���Ŋ����m�F��1���l����̂�5���A���ŁA�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B16���܂ł�7���ԕ��ς�1��4106.0�l�ŁA�O�̏T��209.1���ł����B16���Ɋm�F���ꂽ1��8919�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�21.0���ɂ�����3975�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�1493�l�ƂȂ�A�S�̂�7.9���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A15�����2�l������14�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ80��̒j����70��̏����̂��킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 1�l���S 1��2351�l�����m�F �O�T��2.2�{�] �@7/16
���{�́A16���A�V����1��2351�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B1���l����͍̂���13���ȗ��ŁA�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2.2�{�]��ɑ����܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��110��6188�l�ƂȂ�܂����B�܂��A50��̏���1�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5232�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�15������2�l������11�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 1�l���S 6588�l�����m�F 3���A���ʼnߋ��ő� �@7/16
��������16���A�����ŐV����6588�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B3���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B26���A���őO�̏T�̓����j���������Ă��܂��B����͕����s��2957�l�A�k��B�s��829�l�A�v���Ďs��435�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A15���Ɋ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ1�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l��50���l���A����50��317�l�ɂȂ�܂����B�܂�80���1�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1293�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 3904�l�����m�F �ߋ��ő� 5���A��3000�l�� �@7/16
���ꌧ��16���A�V����3904�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B5���A����3000�l���A����܂łōł���������14����3565�l��339�l�����ĉߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�29��1778�l�ɂȂ�܂����B |
���k�C������1928�l�����m�F 1�l���S�@7/16
�����ł�16���A�V����1928�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A1�l�̎��S�����\����܂����B�V�K�����Ґ���3���A����1500�l������A�������g�債�Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��893�l�A�Ύ�n����216�l�A���َs��151�l�A�\���n����143�l�A�_�U�n����86�l�A�n���n����67�l�A�I�z�[�c�N�n����52�l�A����s��50�l�A��m�n����49�l�A���H�n����47�l�A���M�s��40�l�A�����n����34�l�A���n����25�l�A��u�n����23�l�A�����n����14�l�A�@�J�n����10�l�A�O�R�n����4�l�A���G�n����2�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��15�l���܂�22�l�̍��킹��1928�l�ł��B
�V�K�����Ґ��͐�T�̓y�j�����1000�l�ȏ�������A3���A����1500�l������܂����B�܂��A�O�T�̓����j�����������̂�15���A���ł��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA��������7�l�������Ē����ǂ�2�l�ŁA���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�܂��A�S�̂̔�������1105�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������7119���ł����B�܂��A����s�͂���܂łɊ������m�F����Ă����l�̂���80��̏���1�l��15���ɖS���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�19��4235�l���܂ނ̂�39��7120�l�A�S���Ȃ����l��2106�l�ƂȂ��Ă��܂��B���Â��I�����l��38��4153�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���R���i�ߋ��ő�11���l�������@��7�g�{�i���ABA�E5������@7/16
�����ŐV���ɕ��ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�����҂�16���A11��676�l�ƂȂ�A1��������̉ߋ��ő����X�V�����B10���l������̂�2���A���B�X��{��A�R���Ȃ�14���ōő����X�V�����B�����ɓ����Ă���e�n�Ŋ����҂��}���ɑ������A���s�u��7�g�v���{�i�����Ă���B�s�[�N�͌��ʂ����A���㎀�S�҂�d�ǎ҂̑��������O�����B
����܂ł̍ő��́A��6�g�s�[�N�̍��N2��3���̖�10��4��l�������B�����҂͂��̌㌸�����Ă������A6�����{���瑝���X���ɓ]�����B�������L����₷���Ƃ����I�~�N�������̐V���Ȕh���^�uBA�E5�v�ɒu������肪�i��ł��邱�Ƃ�����Ƃ݂���B
|
�������̐V�K�R���i�����A����11���l�����c����̕a���g�p����6������ �@7/16
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�16���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����11��676�l�m�F���ꂽ�B1��������̐V�K�����҂Ƃ��ẮA2��5����10��4202�l������ߋ��ő����X�V�����B1����11���l����̂͏��߂āB�n���𒆐S�Ɋ����Ґ����ߋ��ɂȂ������ƂȂ��Ă���n�������A�e�����̂͌x�������߂Ă���B
16���̑S���̐V�K�����Ґ��́A�O�T�̓����j���̖�2�{�ŁA�����∤�m�Ȃ�14���ʼnߋ��ő����X�V�����B�d�ǎ҂͑O������7�l������114�l�A���҂�20�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�1��8919�l�������B�O������140�l���������̂́A�O�T�̓����j����1�E9�{�ŁA29���A����1�T�ԑO���������B�N��ʂł́A10�Α�̊����҂�2520�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ����B
���{�ł�1��2351�l�̊������m�F���ꂽ�B�O�T�̓����j��(5567�l)����2�E2�{�ɂȂ����B
14�����_�̕a���g�p���͓����A���A���m�A�����Ƃ������s�s���ł́A�����ނ�20�`30����ƂȂ��Ă���B
�ǔ��V���̏W�v��7���ɓ����Ă��犴���Ґ����ߋ��ő����L�^���������̂�23���ɏ��A���ɒn���Łu��6�g�v�܂ł̃s�[�N��啝�ɒ����鎩���̂��ڗ��B
�������ł�7��12����1271�l�̊����҂��m�F�B��6�g�ōő�������4��22��(219�l)�̖�6�{�ɏ��A���̌��1000�l�O��ō��~�܂肵�Ă���B
���]�A�o�_���s�ł͂���܂łɊ����҂��m�F�����Ȃǂ����s�������w�Z�Ȃnjv11�Z�ɂ��āA���20���ɗ\�肵�Ă����I�Ǝ���15���ɑO�|�������B
�N���X�^�[(�����W�c)�̔�����}����̂��_���ŁA���]�s�̏�菺�m�s���́u�e�Z�̏����Ȃ���_��ɔ��f���Ă����v�Ƃ��Ă���B
�F�{���ł�16���A�V����2752�l�̊������m�F����A5���A���ōő����X�V�B15�����_�̕a���g�p����48�E9���ƁA1�T�ԑO�ɔ�ׂ�14�E9�|�C���g�㏸���Ă���B
�������A�����҂̂������@����l�̊�����2���O��ŁA���ł́A�s������������i�K�ɂ͂Ȃ��Ƃ��u��{�I�Ȋ�������Ƃ�A��ÂȑΉ������肢�������v�ƌĂт����Ă���B
����A���ꌧ�́A�a���g�p����60�E7���ɒB���A��苭���������ɓ���n�߂��B16���̐V�K�����҂�3904�l�Ɖߋ��ő��ŁA5���A����3000�l�����B�r�c �|�B�������� ���m����14���̋L�҉�Łu3000�l����������A�s���������s�킴��Ȃ��Ȃ��Ă���v�Ƃ̍l���������Ă����B
|
�����{���ȉ� ���Ɓu���T�ɂ�20���l�����Ă����������Ȃ��v�@7/16
�S���ň���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�̊����Ґ������߂�11���l���A�ߋ��ő����X�V�������Ƃɂ��Đ��{�̕��ȉ�̃����o�[�œ��M��w�̊ړc�ꔎ�����́u�w�i�ɂ�7���ɓ����Đl�̓����������ɂȂ��ĐڐG�@������Ă��邱�ƂƁA�����͂������I�~�N�������́wBA.5�x���S���ōL�����Ă��邱�ƁA�����3��ڂ̃��N�`���ڎ킩�玞�Ԃ������āA���ʂ��������Ă���l�������Ă��Ă��邱�ƁA�����������Ƃ��d�Ȃ��āA���܂̋}���ȑ����ɂȂ����Ă���Ǝv����v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A����̌��ʂ��Ȃǂɂ��āu�d�ǎ҂͂܂��}���ȑ����͌����Ă��Ȃ����A�����Ґ��͑S���őO�̏T��2�{���鑝���������Ă��āA���T�ɂ�20���l���銴���҂��o�Ă����������Ȃ����B���܂܂ł̏�����Ƃ��炭�͊����҂��������邱�Ƃ��l���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B��萔�̐l�͏d�lj�����̂ŁA�d�ǎ҂������邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ������ɂ����������Ă���Ǝv����v�Ǝw�E���܂����B
���̏�ŁA���܋��߂����ɂ��āu3�A�x�ŗ��s�̌v��𗧂ĂĂ���l�������Ǝv�����A���ł��邱�Ƃ͋�������A�w�Ă������ȁx�Ǝv���l�̓R���i�̉\��������̂ŁA���������Ȃ��ŊO�o���T���Ă��炤���ƁA�ϋɓI�Ɍ������邱�Ƃ��B�܂��A���ɏd�lj����郊�X�N�̍�������҂Ƃ̐ڐG�ɂ͒��ӂ��āA�̒������l�͐ڐG���T����Ή����K�v�ɂȂ��Ă���v�ƌĂт����܂����B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 1�l���S 1��7790�l���� 6���A����1���l�� �@7/17
�����s����17���̊����m�F��1��7790�l�ŁA�O�̏T�̓��j������8308�l�����A�}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B
�܂��s�́A�������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��17���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1��7790�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j����1.88�{�ŁA8308�l�����܂����B�s���Ŋ����m�F��1���l����̂�6���A���ŁA�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B17���܂ł�7���ԕ��ς�1��5292.9�l�ŁA�O�̏T��202.3���ł����B17���Ɋm�F���ꂽ1��7790�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�19.4���ɂ�����3456�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�1569�l�őS�̂�8.8���ł����B
�܂��l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A16�����1�l����A13�l�ł����B����A�s�͊������m�F���ꂽ80��̒j��1�l�����S�������Ƃ\���܂����B |
�����{ �V�^�R���i 1�l���S 1��804�l���� 2���A����1���l�� �@7/17
���{��17���A�V����1��804�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
2���A����1���l���A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2.1�{�ɑ����܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��111��6992�l�ƂȂ�܂����B�܂��A80��̏���1�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�́A���킹��5233�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂́A16������1�l������12�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 1�l���S �V����5859�l�����m�F �@7/17
��������17���A�����ŐV����5859�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B27���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B����͕����s��2290�l�A�k��B�s��1011�l�A�v���Ďs��523�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A15����16���Ɋ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���킹��2�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����50��6174�l�ɂȂ�܂����B�܂��A80���1�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1294�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 4165�l�����m�F �ߋ��ő� ����4000�l�� �@7/17
���ꌧ��17���A�V����4165�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����܂łōł���������16����3904�l������A����Ɋ������m�F���ꂽ�l���Ƃ��Ă͉ߋ��ő����X�V���܂����B4000�l����̂����ꂪ���߂Ăł��B�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�29��5943�l�ɂȂ�܂����B
|
���k�C�� �V�^�R���i �V����1833�l�����m�F �@7/17
�k�C�����ł�17���A�V����1833�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s��973�l�A�\���n����140�l�A�Ύ�n����127�l�A���َs��122�l�A�I�z�[�c�N�n����73�l�A��m�n����59�l�A�_�U�n����58�l�A���H�n����56�l�A����s��53�l�A�n���n����50�l�A���M�s�ƍ����n���ł��ꂼ��23�l�A���n����22�l�A��u�n����16�l�A�����n���Ə@�J�n���ł��ꂼ��10�l�A���G�n����2�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��10�l���܂�16�l�́A���킹��1833�l�ł��B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̉���19��5208�l���܂މ���39��8953�l�A�S���Ȃ����l��2106�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i17�l���S 10��5584�l�����@7/17
17���͂���܂łɑS����10��5584�l�̊��������\����Ă��܂��B
�܂��A���茧��3�l�A��������2�l�A���s�{��1�l�A��t����1�l�A���{��1�l�A�{�錧��1�l�A�{�茧��1�l�A�R������1�l�A�R������1�l�A�����s��1�l�A�F�{����1�l�A�_�ސ쌧��1�l�A��������1�l�A�Q�n����1�l�̍��킹��17�l�̎��S�̔��\������܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͋�`�̌��u�Ȃǂ��܂�1033��4531�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��1033��5243�l�ƂȂ��Ă��܂��B�S���Ȃ����l�͍����Ŋ������m�F���ꂽ�l��3��1602�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��3��1615�l�ł��B
|
���V�^�R���i�����ҁu8����40���l�߂����v�@�c���O���J�������������@7/17
�c���O�����J�����́A17�����̃t�W�e���r�u���j�� THE PRIME�v�ɏo�����A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂ɂ��āA8����{�ɂ́A�S����1���Ɂu40���l�߂��Ƃ������Ƃ����肦��v�Ƃ����������������B
�����}�V�^�R���i���{�������E�c���O���J���u(1�������l�܂ōs���Ƃ݂Ă��邩?)���A8��1�T�ڂƂ����b�����������A40���l�߂��ň��B�������Ăق����Ȃ��ł����A���ꂮ�炢�̂��Ƃ����蓾��v
�����}�̑��{���̍��������߂�c�����́A16���ɏ��߂�11���l���������V�K�����Ґ��ɂ��āA�u�ψقɒu�������ߒ����������L�т�v�Ƃ��āA���T�ɂ́A1��20���l�ɒB����\�����w�E�����B
���̂����ŁA��Ò̐��̈ێ��̂��߁A�_�f�z���Ȃǂ��s����u�Վ��̈�Î{�݂��K�v���v�Əq�ׂ��B
|
���R���i��7�g�A�×{�挈�܂�Ȃ��u�������v��1�T�Ԃ�2�E2�{�c�@7/17
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g����A�S���̎���×{�҂��}�����Ă���B�����J���Ȃɂ��ƁA13�����_��32��9538�l�ɒB���A1�T�ԑO(6�����_)��15��9780�l����{�������B�����͂������I�~�N�������̐V�n���u�a�`�E5�v�̗��s�Ŋ����g�傪�����Ă���A����ɑ������邱�Ƃ������܂��B
����×{�Ґ���2�����{�ɖ�58���l�ɒB���Ĉȍ~�A�����X�����������A�Ăё������Ă���B
�s���{���ʂł́A�����s��5��3015�l�ōł������A���{3��3374�l�A�_�ސ쌧3��146�l�A������1��7862�l�A���m��1��7839�l�Ƒ����Ă���B�×{�悪���܂�Ȃ��u�×{�撲�����v��7��6701�l�ɏ��A1�T�ԑO����2�E2�{�ɑ������B
���J�Ȃ́A��6�g�ŕی����ɂ�銴���҂̌��N�ώ@���x�ꂽ��A���@�ł����Ɏ���ŖS���Ȃ�l�������肵�����Ƃ���A7����{�A�S���̎����̂Ɍ��N�ώ@�̑̐���_���E��������悤���߂��B
����A���@���Ґ���1��1679�l�A�h���×{�Ґ���2��2682�l�B�m�ەa���̎g�p�����㏸�X���ŁA���ꌧ��57���ōł������A�����ŌF�{����53���A�a�̎R����48���ƂȂ��Ă���B�@ |
 |
�������s��1��2696�l�����A7���A����1���l���� �@7/18
�����s��18���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ�����1��2696�l��1�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�O�̏T�̌��j���ɔ��6465�l�������B1���̊����Ґ���1���l������̂�7���A���B
�d�ǎ҂͓s�̊��15�l�B�a���g�p����38.5%�B�V���Ȋ����҂̂����A�����������Ɉ�t�̔��f�ŗz���Ƃ݂Ȃ��u����^���NJ��ҁv(�݂Ȃ��z����)��132 �l�B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���18�����_��16216.4�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�201.3%�B�s���̗v�̊��Ґ���178��2446�l�ƂȂ����B�N��ʂł�10�Ζ���1643�l�A10��2006�l�A20��2377�l�A30��1955�l�A40��1949�l�A50��1351�l�A60��640�l�A70��416�l�A80��252�l�A90��98�l�A100�Έȏ�8�l�B65�Έȏ�̍���҂�1015�l�������B�S���Ȃ����̂�80��̏����B |
�����{ �V�^�R���i �V����4859�l�����m�F �O�T��2300�l�]���� �@7/18
���{��18���A�V����4859�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�2300�l�]�葝���Ă��܂��B����ő��{���̊����҂̗v��112��1851�l�ƂȂ�܂����B�܂��S���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�17���ƕς�炸12�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 2�l���S �V����4187�l�����m�F �@7/18
��������18���A�����ŐV����4187�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B28���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B����͕����s��1122�l�A�k��B�s��483�l�A�v���Ďs��228�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A17���Ɋ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ1�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�͉���51��360�l�ɂȂ�܂����B�܂�60���80��̍��킹��2�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1296�l�ƂȂ�܂����B
|
���ˏo���đ�������̃R���i�����ҁ@�C�x���g���ց@���j�ő���1990�l�@7/18
���ꌧ��18���A10�Ζ�������90�Έȏ��1990�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B���j���̐V�K�����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��B�W�҂ɂ��ƁA���͂��̓��ً}�ŊJ��������J�̊�����c�ŁA��ÕN��(�Ђ��ς�)�ƍ���̊����Ґ����̌��O����A�C�x���g�̊������ȂǐV���ȑ�̕��j���m�F�����B
���́A�����͂������Ƃ����I�~�N�������̔h���^�uBA�E5�v�ւ̒u������肪�i�݁A�C�x���g�Ȃǂ̊J�ÂŐڐG�������Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���Ƃ݂Ă���B���҂̏�����͂��锭���͂�6�������犴���o�H�L�ڂ��C�ӂɂȂ�A�����o�H����肵��Ă��Ȃ��B
���@�����{�݂ŗ×{����l�͍���Ҏ{�݂ƏႪ���Ҏ{�݂Ōv655�l�B21�d�_��Ë@�ւŋx�Ƃ����t��Ō�t���732�l�ŁA��������ߋ��ő��ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��͑S�����[�X�g��1548�E23�l(17�����_)�B�S�����ς�493�E39�l�A���[�X�g2�ʂ̓�����(961�E63�l)�Ɣ�ׂĂ��ˏo���đ����B
�����悪���܂�Ȃ����҂��ꎞ�I�Ɏ������@�ҋ@�X�e�[�V�����ŗ×{���Ă���̂�19�l�B100���K�͂����A��Ï]���҂��s�����A����l���𐧌�������Ȃ��ɂ���B
���͂܂��A�����҂̑������āA�p���X�I�L�V���[�^�[�ݗ^�̑Ώێ҂�����×{���̊�]�ґS������A�u50�Έȏ�v�u��b����������l�v�u7�Έȉ��̖��A�w���v�Ɍ���Ƃ�����j�𖾂炩�ɂ����B
|
���k�C�� �V�^�R���i �V����1515�l�����m�F �@7/18
18���A�k�C�����ł͐V����1515�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s��783�l�A�Ύ�n����150�l�A���َs��129�l�A�\���n����101�l�A�_�U�n����74�l�A���H�n����59�l�A��m�n����46�l�A�n���n����30�l�A�I�z�[�c�N�n����26�l�A�����n����24�l�A����s��23�l�A��u�n����17�l�A�O�R�n����10�l�A���n����9�l�A���G�n����7�l�A�@�J�n����5�l�A���M�s��4�l�A�����n����2�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��8�l���܂�16�l�̍��킹��1515�l�ł��B
�܂�18���A�����ł͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���ĖS���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̉���19��5991�l���܂މ���40��468�l�A�S���Ȃ����l��2106�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���S����3���A��10���l�����@�V�^�R���i�����g��@7/18
�S���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����A3���A����10���l���܂����B
�Ė{�Ԃ�m�点�鉹�F�B�_���Ղ̍ő�̌�����u�R�g���s�v�́A�V�^�R���i�̉e����3�N�Ԃ�B�҂��ɑ҂����J�Âɉ����͂��̂ɂ��킢�ł��B
�ϋq�u�J�Â��ꂽ�����ł��ꂵ���B�ق�܁A�悩�����ł��v�B
����ŁE�E�E�B
�a�̎R���E��K�F�q�����ی����Z�āu�{��(15��)�́A(������)�V����632���ł������܂��āA�ߋ��ő��X�V�v�B
���m���E����֕����N��ۉے��u�{��(16��)�́A(�V�K������)427�����m�F����āA�ߋ��ō��v�B
�~�܂�Ȃ��u�ߋ��ő��v�̍X�V�B17���A�����Ŋm�F���ꂽ�V�K�����Ґ���10��5580�l�ł����B3���A����10���l�����ƂȂ�A�O�T�ɔ�ׂ�Ƃقڔ{���ł��B
�R���i�Ђłނ�����3�x�ڂ̉āB�������7�g�ɁA���~�߂͂�������̂ł��傤���B
���{�E�g���m���m���u�h�g��������ɍ������邩�B��l��l�̊���������肢����v�B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i �V����1��1018�l�����m�F 8���A����1���l�� �@7/19
�����s����19���̊����m�F��1��1018�l�ŁA�O�̏T�̉Ηj������493�l����܂����B�s���Ŋ����m�F��1���l����̂�8���A���ł��B
�����s��19���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��1��1018�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj�����493�l����܂����B�s���Ŋ����m�F��1���l����̂�8���A���ł��B19���܂ł�7���ԕ��ς�1��6146.0�l�ŁA�O�̏T��180.6���ł����B19���Ɋm�F���ꂽ1��1018�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�19���ɓ�����2092�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�909�l�őS�̂�8.3���ł����B
�܂��l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�18�����4�l�����A19�l�ł����B���S���m�F���ꂽ�l�̔��\�͂���܂���ł����B
���s���̕a���g�p�� 40��������
�����g��ɔ����ē����s���ł́A�V�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p�����㏸���Ă��āA19���̑���l��40�����A40.5���ɂȂ�܂����B����1�����_�ł�18.9���������a���g�p���́A�㏸�������܂����B
���̌�A�a����2000�����₵�Ă��悻7000���Ɋg�[�������ƂŁA��������͉�����܂������A�����̋}�g��ōĂя㏸�����`�ł��B
�s���̕a���g�p���́A��6�g�ōł�������������60���߂��܂ŏ㏸���܂����B
����A�I�~�N�������̓����܂����d�NJ��җp�̕a���g�p���́A�s�[�N���ɂ�36.3���������̂ɑ��āA19�����_�̑���l��11.2���ł��B
|
�����{ �V�^�R���i 3�l���S �V����5019�l�����m�F �@7/19
���{��19���A�V����5019�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����ő��{���̊����҂̗v��112��6870�l�ƂȂ�܂����B�܂��A3�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5236�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�18������7�l������19�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 2�l���S �V����3969�l�����m�F �@7/19
��������19���A�����ŐV����3969�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����́A�����s��1200�l�A�k��B�s��529�l�A�v���Ďs��373�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A����15������18���܂łɊ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���킹��5�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����51��4324�l�ɂȂ�܂����B�܂��A80���2�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1298�l�ƂȂ�܂����B
|
������R���i�@2055�l�����@�a���g�p����73.7%�Ɉ����@7/19
���ꌧ��19���A�V����2055�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̉Ηj��(12��)��3436�l�ɔ�ׂ�1381�l�������B�v�����҂�29��9988�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ��͑O�����_��1618.73�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ����F�{��950.56�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����73.7��(���@�Ґ�:477/�a����:647)�ŁA�d�ǎҗp��28.3��(���@�Ґ�:17/�a����:60)�ƂȂ��Ă���B�ČR��n���̐V�K�����Ґ���64�l�������B
|
���V�^�R���i�V����2055�l�����@���ꂠ���ɂ�30���l�z���@7/19
���ꌧ����19���A�V����2055�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ���Ƃ�������܂����B
���ꌧ���̊����҂͗v��29��9988�l�ƂȂ���(���l����6��1�����_��146��7800�l)�B���ꌧ�̔��\�ł́A����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���1618.73�l�őS���ő�(�S�����ς�524.21�l)�B���S�̂̕a���g�p����73.7���A�d�ǎҗp�a���g�p����28.3���ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i �����ŐV����1185�l�̊����m�F �g��X�������@7/19
�����ł�19���A�V����1185�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B����̐V�K�����Ґ��͑O�T�̓����j���Ɣ�ׂ�1.47�{�ƂȂ��Ă��āA�����̊g��X���������Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��546�l�A���َs��140�l�A�Ύ�n����105�l�A���H�n����57�l�A�_�U�n����53�l�A�\���n����51�l�A����s��45�l�A��m�n����40�l�A�I�z�[�c�N�n����33�l�A�����n����28�l�A�n���n����23�l�A���M�s��21�l�A���n���Ə@�J�n���ł��ꂼ��9�l�A�����n����7�l�A��u�n���Ɨ��G�n���ł��ꂼ��5�l�A�O�R�n����1�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��4�l���܂�7�l�̍��킹��1185�l�ł��B
����̐V�K�����Ґ���O�T�̓����j���Ɣ�ׂ�ƁA380�l�]�葝��1.47�{�ƂȂ��Ă���ق��A�O�T�̓����j�����������̂�18���A���ƂȂ�A�����̊g��X���������Ă��܂��B���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������1�l�������ďd�ǂ�1�l�A�����ǂ�5�l�ŁA���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
�܂��A�S�̂̔����߂��ƂȂ�572�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������2951���ł����B�܂��A���͂���܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A80��̒j��������16���ɖS���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�19��6537�l���܂ނ̂�40��1653�l�A�S���Ȃ����l��2107�l�ƂȂ��Ă��܂��B���Â��I�����l��38��6749�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i�S����6��6745�l�����@������8���A����1���l�����@7/19
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�S���ł��傤�V����6��6745�l�̊��������\����܂����B������8���A���Ŋ����҂�1���l���Ă��܂��B
�����s�͂��傤�V����1��1018�l�̊����\���܂����B��T�Ηj�����493�l�������A���悻1�����Ԃ�ɑO�̏T�̓����j���������܂������A8���A����1���l���鍂�������������Ă��܂��B
�S���ł͂���܂�6��6745�l�̊��������\����Ă��āA����ʼnߋ��ő����X�V���Ă��܂��B
���@���Ă��銴���҂̂����u�d�ǎҁv�Ƃ����l��155�l�ł����B��T�̉Ηj�����65�l�������Ă���A�d�ǎ҂������X���ł��B�V���Ȏ��҂ɂ��ẮA28�l���\����Ă��܂��B
|
�������Ґ��g��ň�ÂЂ��� �~�}�������ꍢ��� �@7/19
�����̃s�[�N�����܂������Ȃ��V�^�R���i�B19���͑S����6��6745�l�̊��������\����Ă��܂��B�����s�́A�s���ŐV����1��1018�l���������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���Ŋ����m�F��1���l����̂�8���A���ł��B���䌧�͉ߋ��ő��ƂȂ�܂����B���̂悤�Ȓ��A���S�������Ă���̂���Ë@�ւł��B
��2�T�ԑO�́g1.7�{�h �S���ʼn��f�̗v��������
�V�^�R���i�E�C���X�̊������Ăы}�g�傷��Ȃ��A��Ԃ�x���ɉ��f���s����t�O���[�v�ւ̈˗���2�T�ԑO��1.7�{�܂ő����A�����ŗz���Ɣ��f����銳�҂̊������������A��t�O���[�v�́A��{�I�Ȋ������O�ꂷ��悤�Ăт����Ă��܂��B
��Ԃ�x���ɓo�^������t���������f���s���u�R�[���h�N�^�[�v�ɂ��܂��Ɛ挎���{���甭�M�Ȃǂ�i���銳�҂���̉��f�˗����}�����A17���܂ł�1�T�Ԃł́A2�T�ԑO��1.7�{�܂ő����܂����B
�����ŗz���Ɣ��f����銳�҂̊����������u�z�����v��2�T�ԑO���18�|�C���g����51���ƂȂ�A�������Ă��܂��B
�܂��A�z���Ɣ��f���ꂽ���҂̂����A10�Ζ������S�̂�3�����߁A�ł������Ƃ������Ƃł��B
��t�O���[�v�́A18���܂ł�3�A�x�����Ή��ɒǂ��A���̂�������16���ɉƑ�����̈˗������f�����s���ɏZ��3�̒j�̎q��38�x�̔��M�₹���̏Ǐ݂��A�����������ʁA�z���ł����B
�܂��A10�ォ��30��܂ł̎Ⴂ����ł́A3��ڂ̃��N�`���ڎ���Ă��Ȃ��l�̊������ڗ��Ƃ��Ă��܂��B
����16���ɂ����Ȃǂ̏Ǐo�ĉ��f���˗����A�����ŗz�����m�F���ꂽ�s���ɏZ��30��̒j�����A3��ڂ̃��N�`����ڎ킵�Ă��܂���ł����B
���f��S�������ێR�_�i��t�́A�u�Ⴂ����𒆐S�Ɋ������L�����Ă��邪�A���҂ɑΉ������t������������A�Z���ڐG�҂ƂȂ��ċΖ��ł��Ȃ��Ȃ����肷����o�Ă��Ă���̂ŁA��{�I�Ȋ���������߂ēO�ꂵ�Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
�����s���ɏZ��30��̒j���́A����16���A38�x�̔��M�₹���̏Ǐ݂�ꂽ���߁A�R�[���h�N�^�[�ɉ��f���˗����܂����B
��t���f�@�ɖK�ꂽ���A��M�܂��g���M��36�x��܂ʼn������Ă��܂������A����ӊ�������A���������Ƃ���A�z�����m�F����܂����B
����A�j���̌��t���̎_�f�̒l�ɖ��͂Ȃ��A�x���̋^�����Ȃ����ƂȂǂ���A��t�͌y�ǂ͈̔͂��Ɣ��f���A����×{���w�����܂����B
���̒j���́A3��ڂ̃��N�`���ڎ�͎Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�����s���ɏZ��3�̒j�̎q�́A����16���A38�x�̔��M�₹���̏Ǐ݂�ꂽ���߁A�Ƒ����R�[���h�N�^�[�ɉ��f���˗����܂����B
�K�ꂽ��t���f�@�����Ƃ���A�M��37�x��ɉ������Ă��āA�x���̋^���͂���܂���ł�������̃����p�߂����Ă��܂����B
�j�̎q��PCR�������A�����Ɍ��ʂ��o��܂ŁA��M�܂₹���~�߂̖����������Ď���ŗl�q�����邱�ƂɂȂ�܂������A�����A�z�����m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
���~�}�������ꍢ��̈�Ë@�ւ�
�V�^�R���i�E�C���X�́u��7�g�v�̊������}�g�債�ē����s���̋~�}�a�@�ł̓R���i�^���̊��҂��E�����A�v���������҂̔������x����������Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ�����o�Ă��Ă��܂��B�����������ŔM���ǂ̊��҂�������ƌ����܂�A����̈�t�̓R���i�����łȂ���ʂ̋~�}���҂̎�����������Ȃ��Ă���Ɗ�@�����点�Ă��܂��B
���� �����q�s�ɂ���2���~�}�̎w��a�@�A�u�쑽���a�@�v�͐V�^�R���i�̐�p�a����23���m�ۂ��A�����ǂ܂ł̊��҂ɑΉ����Ă��܂����B
�R���i�a���́A�������߂̒i�K�ł͂قƂ�ǎg�p����Ă��܂���ł������A��T����R���i�^���ŋ~�}��������銳�҂��}�����A��T���̎��_�łقږ��܂�܂����B
����ɂ���3�A�x�̊ԁA���҂��E���������߁A�ʂ̕a���̈ꕔ������Ă����̎��_��31���ɑ��₵�܂������A�����ɖ��܂�A����ȏ�R���i���҂������̂͌������Ƃ������Ƃł��B
�܂��A�M���ǂ̋^���Ŕ�������銳�҂��������ł��āA���M�₯��ӊ��ȂǁA�Ǐ����������̂�������߁A�������O�ꂵ�đΉ��ɓ������Ă��܂����A�u���ł���X�y�[�X�����Ȃ��A��x�ɑΉ��ł��銳�҂͌����Ă���Ƃ������Ƃł��B
�a�@�ł́A�ӂ���͗v�������~�}���҂�9���ȏ������Ă��܂������A���܂͕a��������Ȃ����߁A��ʂ̋~�}���܂߂Ĕ������x�̎����f�炴��Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
�~�}����̐ӔC�҂߂�֗T���@���́u�ď�͔M���ǂ̂ق��A�Ⴂ�l�̂�����������X���ɂ������ŁA�����̃s�[�N�͂܂��Ȃ̂ŁA�~�}�̎���͂���Ɍ������Ȃ�Ɨ\�z�����B���̊����ŐE�����Ƒ��Ȃǂ��犴�����Ă��܂��A������l�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ċ�@�I�ȏ��}���Ă���v�Ƌ�����@���������Ă��܂��B
���s���̕a���g�p�� �㏸����40������
�����s���ł͐V�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p�����㏸���Ă��āA19������l��40�����A40.5���ɂȂ�܂����B
����1�����_�ł�18.9���������a���g�p���͏㏸�������܂����B
���̌�a����2000�����₵�Ă��悻7000���Ɋg�[�������ƂŁA��������͉�����܂������A�����̋}�g��ōĂя㏸�����`�ł��B
�s���̕a���g�p���́A��6�g�ōł�������������60���߂��܂ŏ㏸���܂����B
����A�I�~�N�������̓����܂����d�NJ��җp�̕a���g�p���́A�s�[�N���ɂ�36.3���������̂ɑ��āA19�����_�̑���l��11.2���ƂȂ��Ă��܂��B�@ |
 |
�������s �R���i 4�l���S 2��401�l�����m�F 2���l����2��5���ȗ� �@7/20
�����s����20���̊����m�F��2��401�l�ł����B2���l�����̂͂��Ƃ�2���ȗ��ł��B�܂��s�͊������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��20���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2��401�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���̊����m�F��2���l����̂́A���悻5�������O�̂��Ƃ�2��5���ȗ��ł��B1�T�ԑO�̐��j�����3523�l�����܂����B20���܂ł�7���ԕ��ς�1��6649.3�l�ŁA�O�̏T��163.9���ł����B2��401�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�18���ɓ�����3666�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�1849�l�őS�̂�9.1���ł����B
�܂��l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�19�����1�l����18�l�ł����B����A�s��70���90��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ\���܂����B
���r�m���͓s���ŋL�Ғc�ɑ��A�u���M�̑��k���������̂Ƃ���傫�Ȑ��ɂȂ��Ă���B��������Ɠd�b������悤�Ԑ����������Ă����B�×{���Ă��炤�z�e���Ȃǂɂ��Ă��A�����ǂ�Ǐ�ɉ������`�œ����Ă��炦��悤�Ԑ��𐮂��Ă���Ƃ��낾�v�Əq�ׂ܂����B�܂��A���r�m���̓��N�`���ڎ�ɂ��āA�u��]����l�������Ă��Ă���B�Ⴂ�l��3��ڂ��Ăق����B4��ڂɂ��Ă��ΏۂƂȂ�l�����͂��Аڎ���������Ăق����v�ƌĂт����܂����B
|
�����{�ŐV�K�����Ґ� �ߋ��ő��@7/20
20���A���{���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂́A2��1976�l�ƂȂ�A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
����܂ŁA����̐V�K�����҂��ł����������̂́A���Ƃ�2��11����1��5291�l�ŁA���{����2���l�����̂͏��߂Ăł��B���Ƃ́A����(8��)�ɂ����Ċ����҂̐��͂���ɑ������邨���ꂪ����Ǝw�E���Ă��܂��B
�����m���g�g�呱�� ���O����h
���{���̐V�^�R���i�̐V�K�����҂��ߋ��ő��ƂȂ�Ȃ��A�g���m���́A����������g��̌X���͑����Ƃ��āA�}�X�N�̒��p��\���Ȋ��C�ȂNJ�{�I�ȑ�̓O������߂ČĂт����܂����B
���{�̋g���m����20���̋L�҉�ŁA�{���̐V�K�����Ґ������߂�2���l���ĉߋ��ő��ƂȂ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
���̂����ŁA�I�~�N�������̈��ł�芴�����L����₷���Ƃ����u�a�`�D5�v�Ȃǂւ̒u������肪�i�݂���Ƃ��āA�u�g��X���͍���������Ƒz�肵�Ă���B����Ҏ{�݂Ȃǂł̃N���X�^�[�������Ă��Ă���A�d�lj����郊�X�N�̍�������҂�����ɗ͂���ꂽ���v�Əq�ׂ܂����B
����ɁA�g���m���́A�����҂�Ώۂɂ����A���P�[�g�����ł̓}�X�N�����Ă��Ȃ���ʂ⊷�C���s�\���ȏꏊ�Ŋ��������S�����肪����Ƃ������������Ă���Ƃ��āA�u�}�X�N�̒��p�⊷�C�̓O��Ȃǂ����ɏd�v���B��{�I�Ȋ�����̓O������肢�������v�Ɖ��߂ċ����Ăт����܂����B
�������}�g��Ŗ��������̗��p������
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g��ɔ����A�����Ō�����������s���̖�ǂɂ͊����ɕs����������l�Ȃǂ��������ŖK��Ă��܂��B
���E����̖�ǂł́A���{����p�S���閳���̂o�b�q������R�������ɑΉ����A�ǏȂ��ꍇ�ł������Ō��������܂��B
20�����ߑO�����犴���ɕs����������l�◷�s�Ȃǂňړ���\�肵�Ă���l���������Ō����ɖK��Ă��܂����B
���̖�ǂł́A�挎(6��)�����납�猟���̗\�����n�߁A���݂́A�T��30���قǂƁA���Ƃ�5���ɔ�ׂĂ��悻3�{�ɑ������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�E�G���V�A���V���X�̖�t�̒J���O����́u�����Ґ��������Ă��Ă��邱�Ƃɔ����āA�����̗��p�҂������Ă��āA�A���A�\��͂قږ��܂��Ă�����B�������L���钆�A�s�����������邽�߂ɂ����p���Ă��炦����Ǝv���v�Ƙb���Ă��܂����B
�����́A���̂ق��̕{���ł��}�g�債�Ă��܂��B��2�{4����20���ɔ��\���ꂽ�V���Ȋ����҂͂��킹��3��3963�l�Ɖߋ��ő��ƂȂ�܂����B
���̂������ɂł��A���Ƃ�2���̑�6�g�̃s�[�N������A�ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
|
�������� �V�^�R���i 2�l���S �ߋ��ő���9136�l�����m�F �@7/20
�������́A20���A�����ŐV����9136�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�V�K�����҂�9000�l����̂͏��߂ĂŁA��T16����6500�l�]���傫������A�ߋ��ő����X�V���܂����B����́A�����s��5511�l�A�k��B�s��1128�l�A�v���Ďs��776�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A����17���Ɋ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ1�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����52��3459�l�ɂȂ�܂����B�܂��A80���90��ȏ�̍��킹��2�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1300�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 5160�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/20
���ꌧ��20���A�V����5160�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����Ɍ��\�����V�K�����҂̐��Ƃ��ẮA����܂łōł�������������17����4165�l�����悻1000�l����ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�30���l����30��5148�l�ɂȂ�A�l�����悻146���l�̌����̂��悻5�l��1�l�����łɊ��������v�Z�ɂȂ�܂��B
|
�������V�^�R���i�����m�F2060�l ��2�����Ԃ�2000�l���@7/20
20���A�����ł͐V����2060�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B1���̐V�K�����Ґ���2000�l������̂͂��Ƃ�5��25���ȗ����悻2�����Ԃ�Ŋ����̊g�傪�����Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s��652�l�A���َs��213�l�A����s��190�l�A�Ύ�n����157�l�A���H�n����140�l�A��m�n����131�l�A�I�z�[�c�N�n����118�l�A�\���n����95�l�A���n����74�l�A�_�U�n����65�l�A�n���n����63�l�A���M�s��37�l�A�����n����31�l�A�����n����22�l�A�@�J�n����20�l�A���G�n����14�l�A�O�R�n����10�l�A��u�n����9�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��10�l���܂�19�l�̂��킹��2060�l�ł��B
�܂����͂���܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A80��̒j��2�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B20���́A1���̐V�K�����Ґ������Ƃ�5��25���ȗ����悻2�����Ԃ��2000�l���������ق��A�O�̏T�̓����j����19���A���ŏ���ȂNJ����̊g�傪�����Ă��܂��B���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������30�l�������ďd�ǂ�1�l�A�����ǂ�2�l�ł��̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
�܂��A�S�̂̔�������1165�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������4554���ł����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�19��7189�l���܂ނ̂�40��3713�l�A�S���Ȃ����l��2109�l�ƂȂ��Ă��܂��B���Â��I�����l��38��7714�l�ƂȂ��Ă��܂��B |
���S���̐V�K�����҂�����15���l�����@30�{���ʼnߋ��ő��@51�l���S�@7/20
����܂łɑS���Ŋm�F���ꂽ�����҂�15��2495�l�ŁA1���̐l���Ƃ��Ă͏��߂�15���l������A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B����16����11��662�l����4���l�ȏ�̑啝�ȑ����ƂȂ�܂����B
���傤�͓����s��5�������Ԃ��2���l����2��401�l�̊������m�F�B��������9136�l�A���{��2��1976�l�A���m����1��3628�l�A�É�����3724�l�A���ꌧ��5160�l�ȂǁA���킹��30�̕{���ʼnߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B���҂�51�l�B
|
���S���̃R���i������15���l�����@��7�g�N���A��Ñ̐��ɉe�����@7/20
�V�^�R���i�E�C���X�̍��������҂�20���A�ߌ�8�����݂ŐV����15��2536�l���m�F���ꂽ�B1��������̑S���̐V�K�����Ґ��͍���16����11��660�l(�C���l)���ő����������A�����͂������I�~�N�������̕ψٌn���uBA.5�v�ւ̒u������肪�i�݁A�u��7�g�v�̊����g�傪�S���őN���ɂȂ��Ă���B
�V�K�����Ґ����ߋ��ő����X�V�����̂�30�{���B���{�ł͐V����2��1976�l�̊������m�F���A���߂�2���l�����B�g���m���m���́A�u�x�ݖ����̗��X���ɐ��������Ȃ�X��������v�Ƃ��A�u���������������Ă�BA.5�̊����g��͂������B�g��X���͂܂������Ƒz�肵�Ă���v�ƌx�����Ăт������B
���m���Ɛ_�ސ쌧�ŏ��߂�1��������̊����҂�1���l���A�X�A�{��A�R���A����A�R���A����̊e���ł͏��߂�1��l�����B�{��A�H�c�A�R���A����A�A���m�A���Q��7���ł́A����܂ł̍ő�����قڔ{�������B�����s�͑�6�g��2���ȗ��A��5�J���Ԃ��2���l����2��401�l�ŁA�ߋ�4�Ԗڂɑ��������B
�u��7�g�v�ɂ�銴���g�傪�������A�R���i�a�����}���ɖ��܂�A��Ò̐��ւ̉e�����o�n�߂Ă���B���ꌧ�ł�2�T�ԑO�ɂ�5����������Ă����m�ەa���g�p�����A19����74%�ɒB�����B�F�{����2�T�ԑO��33%����65%�ɁB�a�̎R����16%����59%�A���ꌧ��17%����57%�A��������32%����53%��5����5�����A�a���̕N��(�Ђ��ς�)���i�݂���B
��Ì���ł́A��t��Ō�t������������A�Z���ڐG�҂ɂȂ����肵�ďo�ł��Ȃ��P�[�X�����o�B�~�}�Ԃ̎����A��ʂ̐f�Â��ꎞ�I�ɂ�߂���Ȃ��a�@���o�n�߂��B
�㓡�ΔV�E�����J������19���A�����҂�����ɑ����A�a�����N�������ꍇ�A�u�s���������܂ށA�������̍������͂Ȋ����g��h�~�[�u���u���邱�ƂƂȂ�v�Əq�ׂ��B�����A�s�������Ȃǂ̔��f��ɂ��Ắu��̓I�ɖڈ���ڕW���l���Ă���킯�ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ė�����������B�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
������ �R���i 5�l���S 3��1878�l�����m�F ����3���l�� �ߋ��ő� �@7/21
�����s����21���̊����m�F�͏��߂�3���l����3��1878�l�ł����B21���܂ł�7���ԕ��ς��ߋ��ő��ƂȂ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��s�͊������m�F���ꂽ5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��21���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3��1878�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B��6�g�̃s�[�N���������Ƃ�2��2����2��1562�l��1���l�]�����A���߂�3���l���ĉߋ��ő��ƂȂ�܂����B1�T�ԑO�̖ؗj����1.9�{��1��5216�l�����Ă��܂��B21���܂ł�7���ԕ��ς͑O�̏T��166.2���ƂȂ�1��8823.0�l�ł����B20�����_���炨�悻2200�l�����ĉߋ��ő��ƂȂ�܂����B3��1878�l�̂������Ǐ�̐l��2860�l�ɏ��A������ߋ��ő��ł��B
�܂��N��ʂɌ���ƁA100�Έȏ������10�Ζ�������90��ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B20�オ�ł������S�̂�19���ɓ�����6057�l�A������40�オ5350�l�A30�オ5341�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂��ߋ��ő���2452�l�ƂȂ�A�S�̂�7.7���ł����B�����̋}�g��Ŏ���ŗ×{����l�������Ă��܂��B�s�ɂ��܂��ƁA21�����_�ŏ��߂�10���l����10��1548�l�ɂȂ�܂����B����1����1��7000�l���炨�悻6�{�ɋ}�����Ă��܂��B�܂��l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂�20�����3�l������15�l�ł����B����A�s��80�ォ��100�Έȏ�̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
���r�m���́u��{�I�Ȋ�����̓O������肢�������B���ꂾ�����������ɂȂ�ƁA�F����̋߂��ŗz���ɂȂ����Ƃ��Z���ڐG�҂ɂȂ����ȂǁA�g�߂Șb�ɂȂ��Ă����B�s������菜�����߂̃T�|�[�g�̐���~���Ă��邵�A���k����R�[���Z���^�[�����Ă���B�헪�I�Ɉ�Î�����L���Ɋ��p�������v�Əq�ׂ܂����B
|
�����{ �R���i 5�l���S2��2047�l�����m�F 2���A���ߋ��ő��X�V �@7/21
���{�́A21���A�V����2��2047�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�{����1���̊����҂����߂�2���l��������20���������悻70�l�����A�ߋ��ő����X�V���܂����B�܂��A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�ƁA���悻2.2�{�ɑ����Ă��܂��B
����A���{��20���A���\����1�l�ɂ��ďd�����������Ƃ��Ď�艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��117��0891�l�ƂȂ�܂����B�܂��A5�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5248�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�20������1�l������24�l�ł��B |
�������@�R���i������1��752�l�@����1���l���ʼnߋ��ő��@7/21
�������́A���傤�����ŐV����1��752�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�V�K�����҂�1���l����̂͏��߂ĂŁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B����́A�����s��5122�l�A�k��B�s��1480�l�A�v���Ďs��740�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A����15�����炫�̂��܂łɊ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ7�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A�̂�53��4204�l�ɂȂ�܂����B�܂��A70���80��̂��킹��2�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1302�l�ƂȂ�܂����B�������͂���܂łōł�����1��8766���ŁA�z������56.6���ł����B�V���ɕ����s�̈�Ë@�ւ�ђˎs�̍���Ҏ{�݂ȂǂŃN���X�^�[���m�F����܂����B
���̂��̎��_�ŁA�����m�ۂ����Ƃ��Ă���1681�̕a���ɓ��@���Ă���l��851�l�ɑ����A�a���̎g�p����50.6���ƂȂ�܂����B50��������̂͂��Ƃ�3��7���ȗ��ł��B���̂����A�l�H�ċz��̑����Ȃǂ��K�v�ȏd�ǂ̊��҂�3�l�ɑ����A�d�ǎ҂̂��߂̕a��217���̎g�p����1.3���ƂȂ��Ă��܂��B���̂ق��A�h���×{���Ă���l��1135�l�A����×{���Ă���l��4��4760�l�ƂȂ��Ă��܂��B |
�����ꌧ ��ÂЂ����ŕs�v�s�}�̊O�o���l�Ȃ� �s�������v���� �@7/21
�V�^�R���i�̊����}�g��܂����ꌧ��21���A���{����c���J���A�s�v�s�}�̊O�o���l���H���̐l���A���Ԃ̐����ȂǁA�����ɍs��������v�����邱�Ƃ����߂܂����B
���ꌧ���ł�20���A����̐V�K�����҂����߂�5000�l���A21����5250�l�Ɖߋ��ő����X�V���A��Ò̐����Ђ������Ă��܂��B
���́A21���ߌ�A���{����c���J���A�����ɑ���V���ȍs�������̗v�����e�����肵�܂����B
��̓I�ɂ́A�s�v�s�}�̊O�o���l��A��H��4�l�܂ŁA2���Ԉȓ��Ƃ��邱�ƁA����҂ȂǏd�lj����X�N�̂���l�́A�������Ă���Ƒ��ȊO�̐l�Ɖ�̂��T���邱�ƁA����ɁA1000�l�ȏオ�Q������C�x���g���J�Â���ۂ́A������̌v������O�Ɍ��ɒ�o���邱�Ƃ�A�A���R�[���̒��ꍇ�́A�����̕ύX���������邱�ƂȂǂ����߂�Ƃ��Ă��܂��B
���Ԃ́A7��22������8��14���܂łƂ��Ă��܂��B
����ɁA��Ò̐����Ђ������Ă��邱�Ƃ���A���́A21���Ɂu��Ô�펖�Ԑ錾�v���o���A�y�ǂ⌟���ړI�ł̋~�}�O���̎�f�͍T����悤���߂Ă��܂��B
���ʏ�m�� �g�ő�̊�@ ���z���邽�ߋ��͂��h
���ꌧ�̑��{����c�̂��Ƃ̋L�҉�ŁA�ʏ�m���́u���傤�V�K�����Ґ��͉ߋ��ő��ƂȂ����B�����̐����͐����Ă��炸�A����A�ď�̃C�x���g�J�Â��\�肳��Ă��邱�Ƃ�A�ċx�݂ɂ�肳��Ȃ銴���g�傪��������ттĂ���B���ЂƂ�������̂ƂȂ��āA���́A���̍ő�̊�@�����z���Ă������߁A�����͂����肢�������v�Əq�ׁA������̓O����Ăт����܂����B
����A����̗v�����߂����āA�����ǂ̐��Ƃ���́u�s�\�����v�Ƃ��āA��苭��������߂�ӌ����������ł��܂������A���e��傫���ς��Ȃ��������Ƃɂ��āA�ʏ�m���́u�Љ�o�ϊ��������A�i��ł��邱�ƂƁA�t�ɁA��Â͋ɂ߂Ċ�@�I�ȏɂ���Ƃ������Ƃ���A�ǂꂾ���v�������Ă����̂����������B�����ǂ̐��Ɖ�c�ƌo�ϒc�̂̉�c�A�S�̂����Ă��đΉ������Ă����������v�Əq�ׁA�����g��̖h�~�ƎЉ�o�ϊ����̗������d���������Ƃ��������܂����B
|
��������3965�l�����m�F 1�T�ԑO��2.3�{�Ɂ@7/21
�����ł�21���A�V����3965�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B����̐V�K�����Ґ���3000�l������̂͂��Ƃ�5��13���ȗ��ŁA�������Ăы}���Ɋg�債�Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��1594�l�A�Ύ�n����325�l�A���َs��323�l�A��m�n����259�l�A�_�U�n����196�l�A�\���n����194�l�A����s��189�l�A�I�z�[�c�N�n����172�l�A���H�n����147�l�A�n���n����146�l�A���n����103�l�A���M�s��80�l�A��u�n����70�l�A�����n����49�l�A�����n����27�l�A�@�J�n����24�l�A���G�n����23�l�A�O�R�n����9�l�A�����u���̑��v�Ɣ��\�������O��19�l���܂�35�l�̍��킹��3965�l�ł��B
�����ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���ĖS���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B
����̐V�K�����Ґ���3000�l������̂͂��Ƃ�5��13���ȗ��ŁA�O�T�̓����j���Ɣ�ׂ��2.31�{�ƂȂ�ȂǁA�������Ăы}���Ɋg�債�Ă��܂��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�͒�������42�l�����������ǂ�8�l�ŁA���̂ق��͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�܂��A�S�̂̔�������2266�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������9462���ł����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�19��8783�l���܂ނ̂�40��7678�l�A�S���Ȃ����l��2109�l�A���Â��I�����l��38��8773�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���S���̃R���i�����m�F �ߋ��ő�18��6246�l 35�s�{���ōő� �@7/21
21���́A����܂łɑS����18��6246�l�̊��������\����Ă��܂��B����܂łōł���������20����15���l�]�������A2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�܂��A�_�ސ쌧��7�l�A���{��5�l�A�����s��5�l�A�L������4�l�A���Ɍ���3�l�A�R������3�l�A��t����2�l�A�啪����2�l�A�ޗnj���2�l�A��������2�l�A�O�d����1�l�A���s�{��1�l�A���ꌧ��1�l�A����1�l�A���R����1�l�A��������1�l�A���m����1�l�A�Ȗ،���1�l�A�Q�n����1�l�A��錧��1�l�A�É�����1�l�A���쌧��1�l�A���挧��1�l�̍��킹��48�l�̎��S�̔��\������܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͋�`�̌��u�Ȃǂ��܂�1081��6128�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��1081��6840�l�ƂȂ��Ă��܂��B�S���Ȃ����l�͍����Ŋ������m�F���ꂽ�l��3��1750�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��3��1763�l�ł��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 7�l���S 3��4995�l�����m�F 2���A���ōő� �@7/22
�����s����22���̊����m�F��3��4995�l�ŁA���߂�3���l����21���ɑ����A2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B22���܂ł�7���ԕ��ς����߂�2���l���Ċ����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��22���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3��4995�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B���߂�3���l����21�����A�����3000�l�]�葝���A2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B1�T�ԑO�̋��j���Ɣ�ׂ�Ƃ��悻1.8�{��1��5936�l�����A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B22���܂ł�7���ԕ��ς͑O�̏T��165���ŁA���߂�2���l���āA2��1099.6�l�ƂȂ�A��������ߋ��ő��ƂȂ�܂����B22���Ɋm�F���ꂽ3��4995�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�20.7���ɂ�����7235�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�2736�l�ŁA�S�̂�7.8���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A21���Ɠ���15�l�ł����B����A�s�́A20���60�ォ��90��̒j�����킹��7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����r�m���u�K�v�ȑ� ������]
�����s���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����m�F���}������Ȃ��A���r�m���͋L�҉�ŁA�s�������̕K�v������ꂽ�̂ɑ��A�u�����Ȃǂ����j�^�����O���A�K�v�ȑ������ōs���Ă��������v�Əq�ׁA�𒍎�����l���������܂����B
�����s���ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l���A21���A���߂�3���l�����̂ɑ����A22���͂���ɑ�����3��4995�l�ƂȂ�A2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B
���r�m���͋L�҉�ŁA�L�Ғc����u�s�������͍s��Ȃ��̂��v�Ǝ��₳�ꂽ�̂ɑ��A�u�s�Ƃ��Ă͖�����邱�Ƃ��ŗD��̍��ڂɋ����A���̂��߂ɉ������Ă����̂��A���Ԃɏd�_�����čs���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu������a���g�p���Ȃǂ����j�^�����O���A������Ƃ̈ӌ��Ȃǂ����܂��ĕK�v�ȑ������ōs���Ă��������v�Əq�ׁA�𒍎�����l���������܂����B
�����āu�E�C���X�˕Ԃ��w���N�`���x�A�ǂ��o���w���C�x�A�߂Â��Ȃ��w�}�X�N�x��3�����肢�������B�F�l�̖�����邽�߂Ɉ�Ò̐����������Ă����v�Əq�ׂ܂����B
���Վ��̃��N�`���ڎ����1������ŊJ��
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�钆�A�����s�͎Ⴂ����ւ�3��ڂ̃��N�`���ڎ��i�߂悤�ƁA���O�̗\�Ȃ��Ă��ڎ������Վ��̉���1������œ��� ������s�ɐ݂��܂����B
���̗Վ��̐ڎ���́A�Ⴂ����ւ�3��ڂ̃��N�`���ڎ��i�߂悤�ƁA�����s��������s�Ƌ��͂���1������Ŏs���̏��H��ق̉�c���ɐ݂��܂����B
�s�������ł͂Ȃ��s���ɒʋE�ʊw���Ă���l���ΏۂŁA�ڎ팔�Ɩ{�l�m�F���ł��鏑�ނ�����A���O�̗\�Ȃ��Ă��ڎ���邱�Ƃ��ł��܂��B
22���͎t�����n�܂�O����Ⴂ����𒆐S�ɂ��悻20�l���������A��t�̖�f�̂��Ɛڎ���Ă��܂����B
�s�ɂ��܂��ƁA20���܂łɁA�s���S�̂�3��ڂ̐ڎ���I�����̂�60.9���ŁA�N��ʂɂ݂��65�Έȏオ88.6���ɂȂ��Ă���̂ɑ��A30���53.1���A20���45.9���ƎႢ����̐ڎ헦���Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B
�s�͗��T28����29���ɂ��AJR�V���w�O��SL�L��ɗ\��Ȃ��Őڎ������Վ��̉���݂���\��ŁA���ԑт͌ߌ�5��������ߌ�8�����܂łƂȂ��Ă��܂�
�B |
�����{ �V�^�R���i 5�l���S �V����1��9952�l�����m�F�@7/22
���{��22���A�V����1��9952�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�ƁA���悻2�{�ɑ����Ă��܂��B����A���{��20���ɔ��\����2�l�ɂ��ďd�����������Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��119��841�l�ƂȂ�܂����B�܂��A5�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͂��킹��5253�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�21������1�l������23�l�ł��B
|
�������@�R���i������1��2155�l�@�ߋ��ő����X�V�@4�l���S�@7/22
�������́A���傤�����ŐV����1��2155�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�V�K�����҂�1��2000�l����̂͏��߂ĂŁA3���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B����́A�����s��5159�l�A�k��B�s��1753�l�A�v���Ďs��752�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A����18���Ƃ��̂������҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���킹��4�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A�̂�54��6355�l�ɂȂ�܂����B�܂��A10�Ζ�����50�ォ��90��ȏ�̂��킹��4�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1306�l�ƂȂ�܂����B���ɂ��܂��ƁA���S�����͕̂��������ɏZ��10�Ζ����̒j�̎q�œ����͌y�ǂœ��@�͂��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B���������ŐV�^�R���i�Ɋ�������10�Ζ����̎q�ǂ������S�����̂͏��߂Ăł��B�������͂���܂łōł�����2��246���ŁA�z������59.7���ł����B�V���ɕ����s�̍���Ҏ{�݂�ђˎs�̈�Ë@�ւȂǂŃN���X�^�[���m�F����܂����B
���̂��̎��_�ŁA�����m�ۂ����Ƃ��Ă���1681�̕a���ɓ��@���Ă���l��947�l�ɑ����A�a���̎g�p����56.3���ɂȂ�܂����B���̂����A�l�H�ċz��̑����Ȃǂ��K�v�ȏd�ǂ̊��҂�6�l�ɑ����A�d�ǎ҂̂��߂̕a��217���̎g�p����2.7���ƂȂ��Ă��܂��B���̂ق��A�h���×{���Ă���l��1101�l�A����×{���Ă���l��4��9886�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 3�l���S �V����4654�l�����m�F �@7/22
���ꌧ��22���A�V����4654�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�31��5022�l�ɂȂ�܂����B�܂�����60�ォ��90��܂ł�3�l�����S�����Ɣ��\���A�����ŖS���Ȃ����l��500�l�ɂȂ�܂����B
|
���k�C�� �V�^�R���i 1�l���S �ߋ��ő���4464�l�����m�F �@7/22
�k�C�����ł�22���A�V����4464�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A����̊����m�F�Ƃ��ẮA����܂łōł������Ȃ�܂����B�܂��A���َs�́A����܂łɊ������m�F����Ă����N��Ɛ��ʂ�����\��1�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̉���20��860�l���܂ށA����41��2142�l�A�S���Ȃ����l��2110�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i �S���̊�����19���l���ʼnߋ��ő� �@7/22
7��22���A����܂łɑS���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂�19��5160�l�ƂȂ�A3���A���ʼnߋ��ő��̊����ƂȂ����B19���l������̂����߂āB
�����s�ł�2���A���̉ߋ��ő��ƂȂ�3��4995�l�̊������m�F���ꂽ�B
FNN�̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA�ߌ�9���̎��_�ŁA�����s�̑��ɁA�k�C����4464�l�A�X����1620�l�A��茧976�l�A�{�錧��2508�l�A��錧��2753�l�A�Ȗ،���2184�l�A�Q�n����1974�l�A��ʌ���1��1598�l�A��t����9463�l�A�V������1968�l�A���䌧��841�l�A�É�����5890�l�A���s�{��3951�l�A���Ɍ���9256�l�A�ޗnj���2067�l�A���ꌧ��1760�l�A���R����1866�l�A�L������2548�l�A��������1��2155�l�A���茧��1706�l�A����������2816�l�ƂȂ��Ă��āA���킹��22�s���{���ʼnߋ��ő����X�V�����B�܂��A�S����55�l�̎��S���m�F����Ă���B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 7�l���S 3��2698�l���� 3���l����3���A�� �@7/23
�����s����23���̊����m�F��3��2698�l�ŁA3���A����3���l���܂����B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��23���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3��2698�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���ň����3���l����̂�3���A���ł��B23���̊����m�F�́A22���Ɋm�F���ꂽ�ߋ��ő���3��4995�l�Ɏ����ŁA2�Ԗڂɑ����Ȃ�܂����B1�T�ԑO�̓y�j���̂��悻1.7�{��1��3779�l�����܂����B22���ɏ��߂�2���l����7���ԕ��ς͂���ɑ����āA23�����_�ʼnߋ��ő���2��3068�l�ƂȂ�A�����̊g�傪�����Ă��܂��B23���Ɋm�F���ꂽ3��2698�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�21.2���ɂ�����6923�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�2673�l�őS�̂�8.2���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A22�����1�l������14�l�ł����B����A�s��50��̒j��1�l�ƁA70�ォ��90��̒j��6�l�̍��킹��7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 9�l���S 2��2501�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/23
���{��23���A�V����2��2501�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
21����400�l�ȏ����A����܂łōł������Ȃ�܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�ƁA���悻1.8�{�ɑ����Ă��܂��B����A���{��21���A���\����1�l�ɂ��ďd�����������Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��121��3341�l�ƂȂ�܂����B�܂��A9�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5262�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�22������5�l������28�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 2�l���S �V����1��2619�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/23
��������23���A�����ŐV����1��2619�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B4���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B����́A�����s��5778�l�A�k��B�s��1930�l�A�v���Ďs��758�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A����19������22���܂łɊ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���킹��6�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����55��8968�l�ɂȂ�܂����B�܂��A70���80��̍��킹��2�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1308�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 3�l���S �V����5297�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/23
���ꌧ��23���V����5297�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����Ɍ��\�����V�K�����҂̐��Ƃ��ẮA����܂łōł���������21����5250�l������A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B��T�̓y�j���Ɣ�ׂāA1393�l�����Ă��܂��B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�32��319�l�ɂȂ�܂����B�܂�80�ォ��90��܂ł̒j��3�l�����S���A�����ŖS���Ȃ����l��503�l�ɂȂ�܂����B
|
���k�C�� �V�^�R���i 3�l���S �V����4636�l�����m�F �ߋ��ő� �@7/23
23���A�k�C�����ł͐V����4636�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A����̊����m�F�Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��2188�l�A�Ύ�n����409�l�A�\���n����334�l�A���َs��282�l�A�_�U�n����231�l�A����s��212�l�A���H�n����154�l�A��m�n����150�l�A�I�z�[�c�N�n����146�l�A�n���n����94�l�A���M�s��86�l�A���n����72�l�A�����n����65�l�A��u�n����61�l�A�����n���Ə@�J�n���ł��ꂼ��30�l�A�O�R�n����29�l�A���G�n����25�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�����A���O��27�l���܂�38�l�̍��킹��4636�l�ł��B
�܂��A���Ɣ��َs�͂���܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A70��̒j��2�l�ƔN��Ɛ��ʂ�����\��1�l�̍��킹��3�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̉���20��3048�l���܂މ���41��6778�l�A�S���Ȃ����l��2113�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���S���̃R���i�����ҁA����20���l���@4���A���ōő��X�V�@7/23
�S����23���A�V����20��975�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�B4���A���ʼnߋ��ő����X�V���A���߂�20���l���������B������3��2698�l�̊���������A����_�ސ�A���m�Ȃ�17���{�����ő��������B�����͂������I�~�N�����^�̔h���^�uBA.5�v�̊g�傪�����A�����̊g�傪�����Ă���B
�S���̊����҂͗��s�u��6�g�v�̃s�[�N������2���̖�2�{�̐����ɒB�����B������3���A����3���l���A��オ2��2501�l�A���m��1��4348�l�A�_�ސ삪1��3716�l�A������1��2619�l�A��ʂ�1��2424�l�������B
�����J���Ȃɂ��ƁA�S���̏d�ǎ҂�22�����_��203�l�ƑO������12�l�����Ă���B�����҂̋}���ŁA���t���[���܂Ƃ߂�a���g�p��(21�����_)�͉��ꌧ��77%��M����8����50%�������Ă���B�d�Ǖa���g�p��(��)�͓����s(49%)�A���{�A���ꌧ(�������28%)��2�����Ă���B
|
���V�^�R���i �S���̊����҂�����20���l���ʼnߋ��ő� �@7/23
���傤�A�ߌ�6��30���܂łɁA�S���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂�20��975�l�ƂȂ�A4���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B20���l����̂����߂āB
�����s�ł͂��傤�A3��2698�l�̐V�K�����҂��m�F����A3���A����3���l�����B�ߋ��ő��ƂȂ����A���̂���3��4995�l�͉�������B
FNN�̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA����܂łɁA���{��2��2501�l�A���m����1��4348�l�A��ʌ���1��2424�l�A�_�ސ쌧��1��3716�l�̊����������ȂǁA17�̓��{���ʼnߋ��ő����X�V���Ă���B�@ |
 |
�������s �R���i 2�l���S 2��8112�l�����m�F �O�T���j����1.58�{ �@7/24
�����s����24���̊����m�F��2��8112�l�ŁA1�T�ԑO�̓��j������10322�l�����܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s�́A24���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2��8112�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j����1.58�{�ŁA10322�l�����܂����B24���܂ł�7���ԕ��ς�2��4542.6�l�őO�̏T��160.5���ł����B24���A�m�F���ꂽ2��8112�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�20.3���ɂ�����5702�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�2511�l�őS�̂�8.9���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A23���Ɠ���14�l�ł����B����A�s�́A60���90��̒j�����킹��2�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{��1��7445�l�̊����m�F 2�l�����S�@7/24
���{��24���A�V����1��7445�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�ƁA���悻1.6�{�ɑ����Ă��܂��B����A���{�́A7��16���ɔ��\����1�l��22���ɔ��\����3�l�ɂ��āA�d�����������Ƃ��āA�����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��123��782�l�ƂȂ�܂����B�܂��A2�l�̎��S�����\����A���{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͂��킹��5264�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂́A23���ƕς�炸�A28�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 3�l���S 1��758�l�����m�F ���j���ōő� �@7/24
�������́A24�������ŐV����1��758�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B1���l����̂�4���A���ŁA���j���Ƃ��Ă͍ł������Ȃ�܂����B����́A�����s��3292�l�A�k��B�s��1871�l�A�v���Ďs��600�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����56��9726�l�ɂȂ�܂����B�܂��A70���80��̍��킹��3�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1311�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����4625�l�����m�F �O�T��460�l�� �@7/24
���ꌧ��24���V����4625�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B��T�̓��j���Ɣ�ׂ�460�l�����Ă��܂��B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�32��4944�l�ɂȂ�܂����B
|
���k�C�� �V�^�R���i 2�l���S �V����4072�l�����m�F �@7/24
24���A�k�C�����ł͐V����4072�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A2�l�̎��S�����\����܂����B�܂��A���͂���܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A60��̒j��1�l��80��̏���1�l�̍��킹��2�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̉���20��5174�l���܂މ���42��850�l�A�S���Ȃ����l��2115�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���S���̐V�K������17��6555�l�@���j�Ƃ��ĉߋ��ő��@7/24
�V�^�R���i�E�C���X��24���̑S���̊����҂�17��6555�l�B��T���j��1.7�{�߂��œ��j�Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B
�����̐V�K�����҂�2��8112�l�B��T���j������1.6�{�߂��ɑ����Ă��āA�����ł̓��j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B�s���ŐV���ɖS���Ȃ�������2�l�B�]���̓s�̊�ɂ��d�ǎ҂͑O���ƕς�炸14�l�ł����B
NNN�̏W�v�ɂ��24���ߌ�5��50�����݂̑S���̐V�K�����҂�17��6555�l�ŁA��T���j��1.7�{�߂��ɑ����܂����B�S���ł����j���̊����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B�S���Ȃ�������25�l�B�܂��A23�����_�̑S���̏d�ǎ҂͑O�̓�����30�l������233�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i 25�l���S 17��6554�l�����m�F�@7/24
24���͂���܂łɑS����17��6554�l�̊��������\����Ă��܂��B
�܂��A���m����3�l�A��������3�l�A�k�C����2�l�A���{��2�l�A�����s��2�l�A�F�{����2�l�A���䌧��2�l�A�O�d����1�l�A���ꌧ��1�l�A�ޗnj���1�l�A�R������1�l�A����1�l�A��茧��1�l�A��錧��1�l�A�É�����1�l�A���m����1�l�̍��킹��25�l�̎��S�̔��\������܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͋�`�̌��u�Ȃǂ��܂�1138��8680�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��1138��9392�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�S���Ȃ����l�͍����Ŋ������m�F���ꂽ�l��3��1902�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��3��1915�l�ł��B
�e�����̂Ȃǂɂ��܂��ƁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͗v�Ŏ��̂Ƃ���ł��B( )����24���̐V���Ȋ����Ґ��ł��B
�����s��194��1548�l(28112)�A�_�ސ쌧��92��7588�l(12100)�A��ʌ���68��2310�l(12185)�A��t����55��5284�l(8436)�A��錧��18��7507�l(2757)�A�Q�n����11��8379�l(1847)�A�Ȗ،���11��2040�l(1914)�A�k�C����42��850�l(4072)�A���m����70��4167�l(11514)�A���{��123��782�l(17445)�A��������56��9726�l(10758)�A���ꌧ��32��4944�l(4625)�E�E�E
�����J���Ȃɂ��܂��ƐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�l�ŁA�l�H�ċz���W�����Î��ȂǂŎ��Â���Ȃǂ��Ă���d�ǎ҂́A24�����_��233�l(�{30)�ƂȂ��Ă��܂��B����A�Ǐ��P���đމ@�����l�Ȃǂ́A24�����_�ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�l��995��7109�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����659�l�̍��킹��995��7768�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A����21���ɍs��ꂽ���匟��������PCR�����Ȃǂ̐��͑���l��10��7250���ł����B
|
���R���i�����}�g�� ���M�O���͓��j�������G �f�Ï��O�ő҂l�� �@7/24
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�钆�A���j���͋x�f�ƂȂ��Ë@�ւ��������Ƃ���f�Â��s���s���̃N���j�b�N�ɂ͏Ǐ��i����l�Ȃǂ����X�ɖK��A�Ή��ɒǂ��Ă��܂����B
�y�j���Ɠ��j�������M�O���ł̐f�@���s���Ă��铌�� �`��̃N���j�b�N�ɂ́A�����̋}�g��ɂƂ��Ȃ��ēy���ɖK���l���}�����Ă��܂��B
24�����ߑO10���̐f�ÊJ�n�O����Ǐ��i����l�Ȃǂ����X�ƖK��A�f�ÊJ�n����15���قǂőҍ��������܂�A�O�ő̒���������Ȃ��l�q�Őf�@��҂l�����܂����B
�M���o�����ߕ�e�ƂƂ��ɖK�ꂽ�j�̎q�͌����̌��ʁA�������m�F����A���M�̂ق��A�̂ǂ̒ɂ݂⓪�ɂȂǂ̏Ǐ��i���Ă��܂����B
��e�́A��t�ɑ��A�u�q�ǂ�����Ɂw���ꂳ���x�ƌ������̂ł͂�������39�x4���̔M������܂����B�����������Ă��܂�����q�ǂ��̐��b������Ȃ�̂ŐS�z�ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�Ճm�咆���N���j�b�N�̒����N�G�@���́u�y���ɐf�Â��Ă���Ƃ��낪���Ȃ����Ƃ������āA�y���͑����̐l�����Ă��܂��B�_�ސ���ʂȂǂ��痈��l������قǂł��B���Ȃ���E�ɗ�����A�X�^�b�t�̎肪�{���ɑ���Ȃ���Ԃł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�����}�g��̒��A�y�j������j���͋x�f�ƂȂ��Ë@�ւ��������Ƃ���A�ݓc������b��22���A���{��t��ɋx�����f�Â��t���锭�M�O���𑝂₷���ƂȂǂ̋��͂����߂��ق��A�����s��23���̐f�Õ�����x���̐f�Î��тɉ����Ĉ�Ë@�ւɋ��͋����x������ȂǑΉ��̋�����}���Ă��܂��B�@ |
 |
������ �V�^�R���i 3�l���S 2��2387�l���� ���j��2���l���͏� �@7/25
�����s����25���̊����m�F��2��2387�l�ŁA1�T�ԑO�̌��j�����炨�悻9700�l�����A�����̊g�傪�����Ă��܂��B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��25���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2��2387�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̌��j���̂��悻1.8�{�ŁA9691�l�����܂����B���j����2���l����̂͏��߂Ăł��B25���܂ł�7���ԕ��ς�2��5927.0�l�őO�̏T��159.9���ł����B25���Ɋm�F���ꂽ2��2387�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�21.1���ɂ�����4730�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�1736�l�őS�̂�7.8���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A24�����1�l������15�l�ł����B����A�s�́A80��̒j��2�l��90��̏���1�l�̍��킹��3�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�ŐV����7785�l�̊����m�F�@�V�^�R���i�@7/25
���{��25���A�V����7785�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B�܂��V���Ɋ�����1�l�̎��S���m�F����܂����B��T���j���̊����Ґ��́A4859�l�ł����B���{�ł�23���ɉߋ��ő��ƂȂ�2��2498 �l�̐V���Ȋ����҂��m�F���Ă��܂��B�܂��a���g�p���́A48.1���ő��{�̓Ǝ���u��ヂ�f���v�̔�펖�Ԃł���u�ԐM���v���_������50���ɔ����Ă��܂��B���{�̋g���m����25���̉�ŁA�a���g�p����50%�̊�ɒB�����i�K�ő��{����c���J���Ή�����l����Ƙb���܂����B�d�Ǖa���g�p����5.2%�ł����B
|
�������� �V�^�R���i 6�l���S 8665�l�����m�F ���j�ł͉ߋ��ő� �@7/25
��������25���A�����ŐV����8665�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�O�̏T�̓����j����2�{�ȏ�ŁA���j���Ƃ��Ă͍ł������Ȃ�܂����B����́A�����s��2353�l�A�k��B�s��1080�l�A�v���Ďs��308�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A23����24���A�����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���킹��5�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����57��8386�l�ɂȂ�܂����B�܂��A60�ォ��90��ȏ�̍��킹��6�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1317�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i �V����2562�l�����m�F ���j���ł͉ߋ��ő� �@7/25
���ꌧ��25���A�V����2562�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B��T�̌��j���Ɣ�ׂ�572�l�����āA���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��̊����Ґ��ŁA����ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�32��7506�l�ɂȂ�܂����B
|
���k�C�� �V�^�R���i 3�l���S �V����3361�l�����m�F �@7/25
25���A�k�C�����ł͐V����3361�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A3�l�̎��S�����\����܂����B�܂��A����܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A����80��̏���1�l�A���َs���N��Ɛ��ʂ�����\��2�l�̍��킹��3�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̉���20��6811�l���܂މ���42��4211�l�A�S���Ȃ����l��2118�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i 48�l���S 12��6575�l�����@7/25
25���́A����܂łɑS����12��6575�l�̊��������\����Ă��܂��B
�܂��A��������6�l�A�_�ސ쌧��5�l�A���Ɍ���4�l�A�X����4�l�A�k�C����3�l�A�����s��3�l�A�F�{����3�l�A�{�茧��2�l�A���m����2�l�A�Q�n����2�l�A��錧��2�l�A���s�{��1�l�A��t����1�l�A���{��1�l�A�x�R����1�l�A�R�`����1�l�A�R������1�l�A���R����1�l�A�L������1�l�A���Q����1�l�A���쌧��1�l�A�É�����1�l�A���挧��1�l�̍��킹��48�l�̎��S�̔��\������܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A��`�̌��u�Ȃǂ��܂�1151��5182�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��1151��5894�l�ƂȂ��Ă��܂��B�S���Ȃ����l�́A�����Ŋ������m�F���ꂽ�l��3��1950�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��3��1963�l�ł��B |
��JR��B ���}���120�{�^�x�� �R���i�����g�� �斱���m�ۓ�� �@7/25
JR��B�́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��̉e���ŁA��Ԃ̉^�s�ɕK�v�ȉ^�]�m�ȂǏ斱���̊m�ۂ�����ƂȂ������߁A7��27������8��5���ɂ����āA���}��ԍ��킹��120�{���^�x����Ɣ��\���܂����B
JR��B�ɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�Ɋ���������Z���ڐG�҂ƂȂ����肵�āA7��25���̎��_�ŁA�^�]�m�Ǝԏ����킹��38�l���A����ҋ@�ȂǂŋƖ����ł��Ȃ���ԂɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
���̂��߁A�����Ԃ̉^�s�ɕK�v�ȏ斱���̊m�ۂ�����Ƃ��āA7��27������8��5���܂ł̊��ԁA�ꕔ�̓��}��Ԃ��^�x�Ƃ��邱�Ƃ����߂܂����B
�^�x�ƂȂ�̂́A�����Ƒ啪�����ԓ��}�u�\�j�b�N�v�̏㉺�����킹��100�{�A�����ƒ�������ԓ��}�u�����߁v�̏㉺�����킹��20�{�ł��B
JR��B�ł́A�^�x�ɂ���ė��s�Ȃǂ�����߂�l�ɑ��ẮA�萔�����Ƃ��ĕ����߂��ɉ�����Ƃ��Ă��܂��B
JR��B�́A����̊����ɂ���Ă͉^�x�̊��Ԃ���������\��������Ƃ��āA�z�[���y�[�W�ȂǂōŐV�̏����m�F���Ăق����Ƃ��Ă��܂��B
JR��B�́u���q���܂ɂ͂��s�ւ����������邱�Ƃ�S��肨��ѐ\���グ�܂��v�Ƃ��Ă��܂��B
�����p�҂���͋�����s���̐�
JR�����w�ł͗��p�҂̊Ԃ��������s���̐���������܂����B
���}���悭���p����Ƃ���40��̏����́u�т�����ł��B���}�ɏ���ďo�����邱�Ƃ������̂ŁA����܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
20��̏��q��w���́u�ʊw�ʼnw�𗘗p����̂ŁA�����܂Ŋ������L�����Ă���Ǝv���ƕ|���ł��B�����R���i�����܂��Ăق����v�Ƙb���Ă��܂����B
���s�A���70��̏����́u���s�ɍs�����q����͑����Ă���悤�Ɍ����邪�A�����������Ƃ�����ƍ���͗��s�ɂ��s���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��ƍl���Ă��܂��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B |
 |
��BA.5 �̓f���^�̖�5.85�{�g�ŋ��h�̊����́@�ڎ킩��̎��Ԍo�߂��W���@7/26
�����ł͑�7�g�ɓ���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����L�^���X�V�������Ă���B��Ȍ����Ƃ݂���̂��I�~�N�������̐V�n��BA.5���B
7��22���A�����s�̐V�K�����҂���3��5��l�ɂȂ�ȂǁA�S����22�s���{���ʼnߋ��ő��̐V�K�����Ґ����L�^���A�S���̐V�K�����Ґ��͏��߂�19���l���Ė�19��5��l�ɂ̂ڂ����B
�����J���Ȃ̐��Ɖ�c�̍����A�e�c����(������)�E���������nj���������21���̉�ŁA�����ҋ}���̌����̂ЂƂƂ��āA�����̐V�^�R���i�E�C���X���I�~�N��������BA.5�n���ɒu��������Ă���_���������B�������̐��v�ł́A���̓����_��96���̃E�C���X��BA.5�ɂȂ����Ƃ݂���Ƃ����B
���J�Ȃ̐��Ɖ�c�́A�����Ґ����O�T���1�{�ȏ㑝���Ă���Ƃ��낪�������Ƃ���A�u�����̒n��ŐV�K�����Ґ��̑������������Ƃ������܂�A�S���I�ɂ�����A�ߋ��ō����X�V���Ă������Ƃ��\�������v�ƌx�������B
BA.5�́A�I�~�N�������̒��Ԃ��B�ŏ��̃I�~�N�������͍�N11���ɓ�A�t���J���a���Ȃǂŕ��ꂽ�B���Ă̑�5�g�̌����ƂȂ����f���^���ɔ�ׁA50�J���ȏ���ψق������Ă����B�������L���鑬�x�����E����`�d��(������)��3�{�߂������Ƃ݂�ꂽ�B
�����A���s���Ă����I�~�N�������́A���ۓI�ȃE�C���X���ޖ@�ŁuBA.1�v�ƌĂ�Ă����n���̒��Ԃ������B���ꂪ�����ő�6�g�������N�������B
2022�N�ɓ���ABA.1�ɂ���ɕψق�����A�`�d�͂���1.5�{�����Ȃ����uBA.2�v�����E�I�ɍL�������B�����ł�5���ɂ͐V�^�R���i�E�C���X�̂ق�100����BA.2�ɒu����������B���̂��߁A��6�g�͊��S�ɂ͐V�K�����Ґ����������Ȃ��܂ܐ��ڂ����B
��BA.2��1.3�{
BA.5�͍��N2���ɓ�A���珉�߂ĕ��ꂽ�BBA.2��肳���1.3�{���x�A�`�d�͂������Ƃ݂��Ă���B
�����ł�5���ɋ�`�̌��u�ŏ��߂Č��������B�����s���N���S�����Z���^�[����͂����V�^�R���i�E�C���X�̒�����BA.5�����߂Č��o���ꂽ�̂�5��24�`30���̏T���B6�T�ԂŁA���Z���^�[����͂���E�C���X��74.5����BA.5����߂�悤�ɂȂ����B
���E�I�ɂ�BA.5�ւ̒u������肪�i�ށB���E�ی��@��(WHO)��7��20���Ɍ��\�����u�w�T��ɂ��ƁA���E100�J������BA.5�����o����Ă���A6��27���`7��3���̏T���瓯4�`10���̏T�ɂ����A���ۓI�ȃf�[�^�x�[�X�ɓo�^���ꂽ�I�~�N�������̂����ABA.5����߂�䗦��51.84������53.59���ɑ������B
WHO�́ABA.5�̑������u�e�n�̊����҂���@�A�W�����Î��ł̎��Â̐��������グ�Ă���v�Ǝw�E�����B�������AWHO�͓����ɁA����܂ł̂Ƃ���BA.5��BA.2�ȂǑ��̃I�~�N�������̌n�����d�lj����₷���Ƃ����؋��͂Ȃ��Ƃ��Ă���B�I�~�N��������BA.2��BA.1�́A�f���^���ɔ�ׂ�Əd�lj����͒Ⴂ�B
���ڎ킩�玞�Ԃ��o��
���N�`����BA.5�ɑ�����ʂ������E�łǂ̒��x�Ȃ̂��͂܂��f�[�^���\���ɂ�����Ă��Ȃ����̂́A�p�����N���S�ۏᒡ�ɂ��ƁA�\���I�ȃf�[�^�ł́A�d�lj���h�����ʂ́ABA.2�ɑ�����ʂƑ傫�ȍ��͂Ȃ��Ƃ����B
�`�d�������������łȂ��A�����ł͍Ō�̃��N�`���ڎ킩�玞�Ԃ��o���A���ʂ̌������Ă��Ă���l�������Ă��邽�߁A�Z���Ԃɂ���܂łɂȂ��K�͂Ŋ����҂��}�����Ă���B���Ƃ��Əd�lj����ɂ����l�ł��A���̕p�x�ŏd�lj�����B���̂��߁A�����҂̎�����������A���X�N�̒Ⴂ�l�̊Ԃ�����d�lj������莀�S�����肷��l�������鋰�ꂪ����B
�����āA�Z���ԂɊ����҂��W������ƁA��Ë@�ւ��p���N���鋰�ꂪ����B���łɔ��M�O����A�~�}�O���Ȃǂł́A���M�ȂǂŐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊����̉\���̂��銳�҂��}�����A�Ή�������Ȃ��Ă��Ă���n�悪����B
�w�i�ɂ́A��f�҂̋}�������łȂ��A�X�^�b�t�̌��̑���������B��Ë@�ւ̐E���{�l������������A���邢�͉Ƒ����������ĔZ���ڐG�҂ɂȂ����肵�āA�o�ł��Ȃ��Ȃ�l�������Ă���̂��B |
�������s �V�^�R���i 5�l���S 3��1593�l���� �O�T�Ηj�̖�2.9�{ �@7/26
�����s����26���̊����m�F��3��1593�l�ƁA�Ă�3���l���āA�����̊g�傪�����Ă��܂��B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��26���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3��1593�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���ł́A25����24����2���l��ł������A�Ă�3���l���Ċ����̊g�傪�����Ă��܂��B�ꕔ�̈�Ë@�ւ��x�f���Č����������Ȃ�3�A�x�����������A1�T�ԑO�̉Ηj���ɔ�ׂ�ƁA���悻2.9�{��2���l�]�葝���܂����B26���܂ł�7���ԕ��ς�2��8866.3�l�ŁA�O�̏T��178.8���ł����B26���Ɋm�F���ꂽ3��1593�l��N��ʂɌ���ƁA20�オ�ł������A�S�̂�18.6���ɂ�����5869�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�2873�l�őS�̂�9.1���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A25�����6�l������21�l�ł����B����A�s�́A60���70��A�����90��̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 12�l���S �ߋ��ő���2��5762�l�����m�F �@7/26
���{��26���A�V����2��5762�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����23����2��2498�l�������āA����܂łōł������Ȃ�܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��126��4320�l�ƂȂ�܂����B�܂��A12�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5277�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�25������8�l������39�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 9�l���S �V����1��1956�l�����m�F �@7/26
��������26���A�����ŐV����1��1956�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�Ηj���Ƃ��Ă͍ł������Ȃ�܂����B����́A�����s��5696�l�A�k��B�s��1678�l�A�v���Ďs��749�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A����21������25���܂łɊ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���킹��8�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����59��334�l�ɂȂ�܂����B�܂��A30��ƁA70�ォ��90��ȏ�̍��킹��9�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1326�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 4�l���S �ߋ��ő���5622�l�����m�F �@7/26
���ꌧ��26���A�V����5622�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����Ɍ��\�����V�K�����҂̐��Ƃ��ẮA����܂łōł�������������23����5297�l������A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B��T�̉Ηj���Ɣ�ׂĂ��A3567�l�����Ă��܂��B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�33��3128�l�ɂȂ�܂����B�܂��A����80���90��̍��킹��4�l�����S�����Ɣ��\���A�����ŖS���Ȃ����l��507�l�ƂȂ�܂����B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 5622�l���� �ߋ��ő� ��Ñ̐��[���@7/26
���́A26���A�ߋ��ő���5622�l���V�^�R���i�Ɋ��������̂��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�R���i��p�̕a���g�p���͉���{����93.7���ƂȂ��Ă��āA��Ò̐��̂Ђ����x�������[���ȏɂȂ��Ă��܂��B26���̐V�K�����Ґ���5622�l�ŁA1���Ɍ��\�����V�K�����҂̐��Ƃ��ẮA����܂łōł�������������23����5297�l������A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�N��ʂł͑������ɁA10�Ζ�����971�l�A10�オ856�l�A30�オ793�l�A40�オ791�l�A20�オ621�l�A50�オ591�l�A60�オ444�l�A70�オ229�l�A80�オ195�l�A90�Έȏオ115�l�A�s����16�l�ƂȂ��Ă��܂��B�n��ʂł͑������ɁA�ߔe�s��1054�l�A����s��537�l�A�Y�Y�s��536�l�A����s��362�l�A�X��p�s��358�l�A�{�Ó��s��278�l�A�Ί_�s��266�l�A�L����s��248�l�A�����s��230�l�A����s��223�l�A���s��164�l�ł��B���̂ق��̒����́A�ی����̊NJ��ʂɁA�����ی����Ǔ���604�l�A�암�ی����Ǔ���513�l�A�k���ی����Ǔ���143�l�A���d�R�ی����Ǔ���36�l�A���O��64�l�A�m�F����6�l�ƂȂ��Ă��܂��B��T�̉Ηj���Ɣ�ׂāA3567�l�����܂����B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�33��3128�l�ɂȂ�܂����B
�܂����͓ߔe�s�ɏZ��80��̏���3�l��90��̒j��1�l�����S�������Ƃ\���܂����B���̂����A90��̒j���́A����9���ɓ������Ă�������Ҏ{�݂Ŋ������m�F����A���̂܂ܗ×{���Ă����Ƃ���e�̂��������A����18���ɓ��@�����̂��߂ɓ��@�ҋ@�X�e�[�V�����ɓ������A���̓��̂����ɖS���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
�l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A25���܂ł�1�T�Ԃ�1993.31�l�ƈ��������S�����[�X�g�ŁA�S�����ς�2.3�{�ƂȂ��Ă��܂��B26�����ݓ��@���Ă���̂́A25�����21�l����596�l�ŁA���̊�ł̏d�ǎ҂�25�l�A�����ǂ̐l��311�l�ł��B�V�^�R���i���җp�̕a���g�p���́A���S�̂ł�85.3���ŁA���̂�������{���ɂ��Ă�93.7���ƂȂ�A�[���ȏ�ԂƂȂ��Ă��܂��B�V�^�R���i�ɑΉ����Ă���21�̈�Ë@�ւł́A����������Z���ڐG�҂ɂȂ����肷��Ȃǂ��ċΖ��ł��Ȃ���Ï]���҂�1187�l�ł��B����A�����҂��������Ă��̂܂ܗ×{���Ă���{�݂�����Ҏ{�݂�150�{�݁A��Q�Ҏ{�݂�37�{�݂���A�×{�҂�1336�l�Ɖߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B���̂ق��A�����J�R���猧�ɑ��A�V����105�l�̊������m�F���ꂽ�ƘA�����������Ƃ������Ƃł��B
|
���k�C�� �V�^�R���i 6���A����3��l�� �����̋}�g�呱���@7/26
26���A�k�C�����ł͐V����3268�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A5�l�̎��S�����\����܂����B1���̐V�K�����Ґ��͑O�̏T�̓����j���ɔ�ׂ�2�{�ȏ�ɑ����A6��������3000�l���Ă��āA�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��952�l�A����s��349�l�A�\���n����244�l�A���َs��221�l�A�Ύ�n����217�l�A�_�U�n����214�l�A��m�n����188�l�A�I�z�[�c�N�n����152�l�A���M�s��138�l�A���H�n����127�l�A�n���n����119�l�A���n����89�l�A�@�J�n����53�l�A�����n����45�l�A�O�R�n���Ɨ��G�n����39�l�A�����n����35�l�A��u�n����19�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�����A���O��18�l���܂�28�l�̂��킹��3268�l�ł��B1���̐V�K�����Ґ��͑O�̏T�̓����j���ɔ�ׂ�2�{�ȏ�ɑ����A6��������3000�l���Ă��āA�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��A���́A����܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A80��̒j��1�l�ƁA90��̏���2�l�A�N��Ɛ��ʂ�����\��2�l�̂��킹��5�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�20��7763�l���܂ނ̂�42��7479�l�A�S���Ȃ����l��2123�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����ł�26���A�V����8�̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�Ɣ��\����܂����B���̂����A�D�y�s�ł́A�O���[�v�z�[���œ�����9�l�ƐE��2�l�̂��킹��11�l�A�ʂ̃O���[�v�z�[���œ�����6�l�ƐE��1�l�̂��킹��7�l�A�T�[�r�X�t������Ҍ����Z��œ�����4�l�ƐE��1�l�̂��킹��5�l�̊������m�F����܂����B�܂��A�Ύ�n���̈�Ë@�ւŊ���7�l�ƐE��10�l�̂��킹��17�l�A��m�n���̈�Ë@�ւŊ���12�l�ƐE��8�l�Ƃ̂��킹��20�l�A�_�U�n���̈�Ë@�ւŊ���6�l�ƐE��2�l�̂��킹��8�l�A�\���n���̈�Ë@�ւŊ���4�l�ƐE��5�l�̂��킹��9�l�A�\���n���̗L���V�l�z�[���œ�����7�l�ƐE��3�l�̂��킹��10�l�̊������m�F����܂����B
|
�������҂�19���l������@�ߋ�2�Ԗڂ̑����@���E���m�E����Ȃǂʼnߋ��ő��@7/26
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āAJNN�̂܂Ƃ߂�26���ߌ�5��20�����݁A�S���ł͂��傤�V���ɁA19���l���銴���҂��m�F����܂����B
���ł�2��5762�l�A���m�ł�1��5315�l�A����ł�5622�l�ƁA���ꂼ��ߋ��ő��̊����҂��m�F����Ă��܂��B
���̂ق��A�H�c(1284�l)�A�Ȗ�(2297�l)�A�Q�n(2424�l)�A����(1821�l)�A��(3449�l)�A����(587�l)�A����(1288�l)�A���m(963�l)�A����(2029�l)�A�啪(2142�l)�A������(3149�l)�ȂǁA�S��14�{���ʼnߋ��ő����X�V���Ă��܂��B
�����ł�7���A����2���l����A3��1593�l�̊��������\����܂����B
|
���ߋ�2�Ԗ� �S��19��6500�l�@���҂��}�� 4�J���Ԃ�100�l�� �@7/26
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�26���A�S����19��6,500�l�m�F����A�ߋ�2�Ԗڂ̑����ɂȂ����B�܂��A���Ґ������悻4�J���Ԃ��100�l����ȂǁA�}�����Ă���B
�����s��26���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�̐V�K�����҂́A3��1,593�l�������B�O�̏T�Ɣ�ׂ�3�{�߂������A�Ηj���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��B
���̂ق��A���{��2��5,762�l�A���m����1��5,315�l�Ȃ�14�̕{���ʼnߋ��ő��ƂȂ����B
�S���ł�19��6,500�l�̊������m�F����A�ߋ�2�Ԗڂ̑����B�܂��A�S���Ŕ��\���ꂽ���҂�115�l�ŁA���悻4�J���Ԃ��100�l���A�}�����Ă���B
|
���R���i�����g�� ���{ �ڎ헦�Ⴂ�Ⴂ���㒆�S�ɌĂт����@7/26
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g�傪��������A���Ȃǂ̊��e�n�ł́A�Ⴂ����𒆐S��3��ڂ̃��N�`���̐ڎ헦���L�єY��ł��܂��B���{�̒S���҂́u�����̊g���h�����߂Ƀ��N�`���ڎ���������Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
���{�����\�������v�ɂ��܂��ƁA25�����_�̊�2�{4����3��ڂ̃��N�`���̐ڎ헦�́A�Ⴂ����𒆐S�ɐL�єY�݁A�����̕{���őS�����ς�������Ă��܂��B����A�����͋}�g�債�Ă��āA2�{4����25�����\���ꂽ�V���Ȋ����Ґ��́A2���l���܂����B�����������A���E������̑��{���V�ʊقɐݒu���ꂽ��K�͐ڎ���ł́A�ڎ���ɖK���l���������Ă��܂��B�{�ɂ��܂��ƁA���̉��Ő�T1�T�Ԃɐڎ�����l�́A������1�T�Ɣ�ׂĂ��悻2�{�ɑ����Ă���Ƃ������Ƃł��B26����3��ڂ̐ڎ�ɖK�ꂽ���E��؎s��26�̏����́A�u�����A���ƂɋA�Ȃ���̂Ŋ�����h�����߂ɐڎ킵�悤�Ǝv�����B�����҂��Ăё����Ă���̂ŁA������Ȃ��悤�ɂ������v�Ƙb���Ă��܂����B���{�́A�r�m�r�ł̏�M��ʂ��ĎႢ����ւ̃��N�`���ڎ�̌Ăт������������Ă��܂��B���{���N�`���ڎ퐄�i�ۂ̐i���R�V �Q���́u�����̊�����h�������łȂ��A����̐l�̗\�h�ɂ��Ȃ���̂ŁA�����̐ڎ���������Ăق����v�Ƙb���Ă��܂����B
�����N�`���ڎ헦 ��㒆�S�ɐL�єY��
��2�{4����3��ڂ̃��N�`���̐ڎ헦��60��ȏ��80�����Ă������A�Ⴂ����𒆐S�ɑS�����ς������A�L�єY��ł��܂��B���{�����\���Ă���25�����_�̓s���{���ʂ̐ڎ헦�ɂ��܂��ƁA���̂������{�̊e�N��̐ڎ헦�́A20���37���A30���41���A40���50���ƂȂ��Ă��܂��B��������S����2�ԖڂɒႭ�A�S�����ς�10�|�C���g���x������Ă��܂��B����ɁA10���19���ƑS���ōł��Ⴍ�A�S�����ς�14�|�C���g������Ă��܂��B�܂��A���{�Ɏ����ŋ��s�{�ƕ��Ɍ����ڎ헦���Ⴂ�X���ɂ���A10�ォ��40��̊e�N��ŁA�S�����ς�4�|�C���g����10�|�C���g���x������Ă��܂��B
���Ⴂ�����
�Ⴂ����𒆐S�ɐV�^�R���i�E�C���X��3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�i��ł��Ȃ����Ƃɂ��āA��҂������s���������E�~�i�~�ŕ����܂����B�ڎ��1����Ă��Ȃ��Ƃ������E�����29�̏����́A�u���N�`����ڎ킵�Ă��������Ă���l������̂ŁA���ʂ��^��Ɏv���B������ڎ킷��\��͂Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂����B2��ڎ킵�����ƁA3��ڂ��Ă��Ȃ��Ƃ����_�ˎs��30�̏����́A�u���������ڎ킵���̂��A�Q���������C�x���g�Őڎ킪�Ăт������Ă�������ŁA�]��Ŏ��킯�ł͂Ȃ��B�K�v�������܂芴���Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂����B����A3��̐ڎ���ς܂������E��s��29�̏����́A�u�ڋq�̎d�������Ă���̂ŁA������Ƃ��ĐE��ڎ�Ŏ��B�Ă��Ȃ��l�����܂����A�ڎ킷��Ί�������d�lj���}���Čo�ς������ɉ��Ǝv���̂ŁA�Ăق����Ǝv���v�Ƙb���Ă��܂����B3��ڎ킵�����ƁA2�T�ԑO�ɐV�^�R���i�Ɋ��������Ƃ����A���E��s��28�̒j���́A�u�������Ă��܂����̂ŁA���ʂ��^��Ɏv���Ƃ�������邪�A3��ڎ킵������d�lj������ɍς̂��ȂƂ�������B�����������Ăق��������X�N�������邽�߂ɂ��ڎ킪�i�߂����v�Ƙb���Ă��܂����B |
 |
���V�^�R���i�����}�g�� ���{ ��ÂЂ����h���s����������� �@7/27
�V�^�R���i�̊����}�g�傪�������A���{�͔��M�O������f���Â炭�Ȃ��Ă��錻��܂��A�������������̂Ƌٖ��ɘA�g���Ȃ����Â̂Ђ�����h�����ƂŁA�s���������s�����Ԃ͉���������l���ł��B
�V�^�R���i��26���̐V�K�����Ґ���19��6000�l�]��ŁA14�̕{�ƌ��ʼnߋ��ő��ƂȂ�ȂǑS���Ŋ����̋}�g�傪�����Ă��܂��B
���{�͔��M�O������f���Â炭�Ȃ��Ă��錻��܂��A��Ò̐����ێ��E�������Ă������߂̑�ɏd�_��u�����j�ł��B
�ݓc������b�́u�����Ґ��͑����Ă��邪�A���̂Ƃ���d�ǎҐ��⎀�S�Ґ��͒ᐅ�����B4��ڂ̃��N�`���ڎ�̊g��ȂǁA�����n���̌���������s���Ȃ���Љ�o�ϊ������ێ�����悤�w�߂Ă����v�Ƌ������܂����B
�܂��A�㓡�����J����b�͑S���m����Ƃ̃I�����C����Ŋ��Ҍ����̕a���𑬂₩��5�����ɂ܂ő��₷�ق��A�����R�������L�b�g���グ�Ď����̂�ʂ��Ĕ��M�O�����ǂȂǂŖ����Ŕz����j����������͂����߂܂����B
���{�́A�������������̂Ƌٖ��ɘA�g���Ȃ����Â̂Ђ�����h�����ƂŁA�s���������s�����Ԃ͉���������l���ł��B |
�������s �V�^�R���i 6�l���S 2��9036�l�����m�F �O�T��1.4�{�] �@7/27
�����s����27���̊����m�F��2��9036�l�ŁA8���A���őO�̏T�̓����j�����������ق��A7���ԕ��ς͏��߂�3���l�������̊g�傪�����Ă��܂��B����A�s�͊������m�F���ꂽ6�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��27���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��2��9036�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̐��j���ɔ�ׂ��1.4�{�]��ŁA8635�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�8���A���ł��B27���܂ł�7���ԕ��ς́A���߂�3���l����3��99.9�l�ƂȂ�A�O�̏T��180.8���Ɗ����̊g�傪�����Ă��܂��B�܂��A�s���Ŋ������m�F���ꂽ�l�̗v�́A27���܂ł�200���l���A202��4564�l�ƂȂ�܂����B27���Ɋm�F���ꂽ2��9036�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�19.1���ɓ�����5532�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�2636�l�őS�̂�9.1���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A26�����3�l������24�l�ł����B����A�s��70�ォ��90��܂ł̒j�����킹��6�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{ �V�^�R���i 14�l���S �V����2��1860�l�����m�F �@7/27
���{��27���A�V����2��1860�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
���{�ɂ��܂��ƁA���ҏ����W��V�X�e���uHER-SYS�v��26���Ɉꕔ�œ��͂ł��Ȃ���ԂƂȂ����e���ŁA�{���ł������҂̏�ꕔ�A���͂ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B���̂��߁A26���ɓ��͂ł��Ȃ����������҂ɂ��ẮA27���̔��\���ɂ͌v�ス���A28���̔��\�Ōv�シ��Ƃ��Ă��܂��B����A���{��26���ɔ��\����13�l�ɂ��āA�d�����Ă����Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B����ő��{���̊����҂̗v��128��6167�l�ƂȂ�܂����B�܂��A14�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5291�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�26������2�l������41�l�ł��B
|
�������� �V�^�R���i 8�l���S 1��1188�l�����m�F �@7/27
��������27���A�����ŐV����1��1188�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B2���A����1���l���A���j���Ƃ��Ă͍ł������Ȃ�܂����B
����͕����s��5258�l�A�k��B�s��1744�l�A�v���Ďs��906�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A26���Ɋ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ1�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l��60���l���A����60��1521�l�ɂȂ�܂����B�܂�80���90��ȏ�̍��킹��8�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1334�l�ƂȂ�܂����B
|
������R���i4816�l�����@�O�T��344�l���@7/27
���ꌧ��27���A�V����4816�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̐��j��(20��)��5160�l�ɔ�ׂ�344�l�������B�v�����҂�33��7944�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ��͑O�����_��2233.49�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ������{��1555.15�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����87.8��(���@�Ґ�614/�a����699)�ŁA�d�ǎҗp��43.5��(���@27/�a����62)�ƂȂ��Ă���B�ČR��n���̐V�K�����Ґ���57�l�������B
|
���k�C�� �V�^�R���i 5�l���S �V����5522�l�����m�F �@7/27
�k�C�����ł�27���A�V����5522�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A5�l�̎��S�����\����܂����B�܂��A����܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A����80���90��̏���2�l�ƁA70��̒j��1�l�A�D�y�s��70��̒j��2�l�́A���킹��5�l�̎��S�\���܂����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̉���21��121�l���܂މ���43��3001�l�A�S���Ȃ����l��2128�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i ��ヂ�f���u�ԐF�v�Ɉ����グ ��Ô�펖�Ԑ錾�� �@7/27
�V�^�R���i�̊����g����āA���{��27�����{����c���J���A�����Ȃǂ�`����Ǝ��̊�u��ヂ�f���v���펖�Ԃ������u�ԐF�v�Ɉ����グ��ƂƂ��ɁA��Ò̐����Ђ������Ă���Ƃ��āu��Ô�펖�Ԑ錾�v���o���܂����B
���{�ł́A26���ɔ��\���ꂽ�V�K�����҂��ߋ��ő��ɂȂ�ȂNJ������g�債�A�a���̎g�p���������Ȃ��Ă��܂��B
�����������āA���{�͑��{����c���J���A�g���m���́u�����͂���Ɋg�傷��\��������A���M�O����~�}�O�����܂߂Ĉ�ÑS�̂��Ђ������Ă���B�܂��A���@���҂̑�����70��ȏ�̍���҂ŁA���������_�܂����v���������߂����v�Əq�ׂ܂����B
������ĉ�c�ł́u��ヂ�f���v���펖�Ԃ������u�ԐF�v�Ɉ����グ��ƂƂ��ɁA��Ò̐����Ђ������Ă���Ƃ��āu��Ô�펖�Ԑ錾�v���o���܂����B
���킹�ĕ{���ɑ��A���܂߂Ȋ��C�ȂNJ�{�I�Ȋ�����̓O��⑁���̃��N�`���ڎ���Ăт�����ق��A�d�lj��̃��X�N����������҂��b�����̂���l�ɂ͕s�v�s�}�̊O�o���T����悤�ɁA��������Ƒ��ȂǓ���I�ɍ���҂Ɛڂ���l�ɂ͊������X�N�̍����s�����T����悤�ɁA�Ăт����邱�Ƃ����߂܂����B
���H�X�Ȃǂɑ��ẮA�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�͗v�����܂��A�}�X�N��H�̓O��Ȃǂ����߂�Ƃ��Ă��܂��B
���������v����28�����痈��27���܂ōs���Ƃ��Ă��܂��B
���̂ق���c�ł́A�����Ґ��̋}���Ȃǂ܂��A�I�����C���ł̐f�Â������̑̐����������邱�Ƃ��m�F���܂����B
���{����c�̂��Ƃɔ��\���ꂽ27�����_�̑��{���̕a���g�p����52.0���ƂȂ�A��펖�Ԃ̖ڈ���50�����܂����B
�����z�̓����Ԃ�
�u��ヂ�f���v����펖�Ԃ������u�ԐF�v�Ɉ����グ��ꂽ���Ƃ��āA��� ���c�s�̖����L�O�����ɂ��鑾�z�̓����Ԃ����C�g�A�b�v����܂����B
���z�̓����Ԃ����C�g�A�b�v�����̂́A27�����痈��2���ɂ����ẮA���v����ߌ�11���܂łł��B
�u��ヂ�f���v�Łu�ԐF�v���_������̂͂��Ƃ���4��24���ȗ��ł��B
���،����[�������u�ٖ��ɘA�g���Ή��v
�،����[�������́A�ߌ�̋L�҉�ŁA���{���d�lj��̃��X�N����������҂��b�����̂���l�ɕs�v�s�}�̊O�o���T����悤�Ăт����邱�Ƃɂ��āu�e�s���{���ł̊�����͒n��̊����₻�ꂼ��̈�Ò̐��ɉ����ĕK�v�Ȏ��g�݂����{���Ă�����̂Ə��m���Ă���B���{�Ƃ��Ă͑��{�Ƌٖ��ɘA�g���K�ɑΉ��������v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu�S���I�ɂ������Ґ��͑������Ă���B�d�lj����X�N�̂��鍂��҂���邱�Ƃɏd�_��u���A���N�`���ڎ�̂���Ȃ鑣�i�⌟���̊��p�E���i�A���ʓI�Ȋ��C�̓O��Ȃǃ����n���̂��銴����Ɏ��g��ł��������v�Əq�ׂ܂����B
|
���S���̃R���i�����ҁA20��9000�l�@�ߋ��ő����X�V�@7/27
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�27���A�S���ł��悻20��9000�l���m�F���ꂽ�B23����20��937�l(�����J���ȏW�v)������A1��������ʼnߋ��ő����X�V�����B�k�C�����ʁA�_�ސ�A���ɂȂ�25���{���ōő��ƂȂ����B
�����͂������Ƃ����I�~�N�����^�̔h���^�uBA.5�v�ւ̒u������肪�i�݁A�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��������Ă���B������2��9036�l���A����2��1860�l�̊��������ꂽ�B
�㓡�ΔV���J���́A�S���̏T���Ƃ̐V�K�����Ґ����O�T���1.89�{�ɂȂ������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���Ȃ�27���J�����R���i�������������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�̖`���ŏq�ׂ��B�a���g�p���������ď㏸�X���ɂ���Ƃ��u�d�ǎҐ��A���Ґ��͒Ⴂ���������S���I�ɑ����X���ɂ���v�Ǝw�E�����B
|
���V�^�R���i�V�K���� �S��20��9694�l�ʼnߋ��ő� 25���{���ōő� �@7/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����m�F�̔��\��27���A����܂łɑS����20��9694�l�ƂȂ�܂����B����܂łōł�������������23����20���l�]�������A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂��A�S��25�̓��{���ōő��ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A���킹��129�l�̎��S�̔��\������܂����B�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͋�`�̌��u�Ȃǂ��܂�1192��1222�l�ƂȂ��Ă��܂��B�S���Ȃ����l�͍����Ŋ������m�F���ꂽ�l��3��2194�l�ł��B
|
���X�� �S��154�����ő����Ɩ��x�~ �]�ƈ��̃R���i�����Ȃǂ� �@7/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��̉e���ŁA�S���̗X�ǂł́A�]�ƈ�������������A�Z���ڐG�҂ɂȂ����肵�āA�����Ɩ����x�~����Ƃ��낪�����Ă��܂��B
���{�X�ւɂ��܂��ƁA27�����_�ŁA�]�ƈ����V�^�R���i�Ɋ���������A�Z���ڐG�҂ɂȂ����肵�āA�����Ɩ����x�~���Ă���X�ǂ͑S����154�����ɂ̂ڂ�Ƃ������Ƃł��B
�]�ƈ������l�̏��K�͂ȗX�ǂ����S�ŁA�����̂ق�ATM�����������a�������@���x�~���Ă���Ƃ��낪�����A��������c�ƍĊJ�̎����͖��肾�Ƃ��Ă��܂��B
��Ђɂ��܂��ƁA�]�ƈ��Ɋ����҂��o��Ȃǂ����ꍇ�A�ߗׂ̗X�ǂ��牞���̗v����h������Ȃǂ̑Ή����Ƃ��Ă��܂����A�ꏊ�ɂ���Ă͐l�J�肪���������Ɩ����ł��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
����A���{�X�ւł͗X�֕���䂤�p�b�N�Ȃǂ̔z�B�Ɩ��ɉe���͏o�Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
��Ђł͗��p�҂ɑ��A�͂莆��z�[���y�[�W�Ȃǂŋߗׂ̗X�ǂ𗘗p����悤�Ăт����Ă��āA�����g��̉e�����Љ�̃C���t����S���X�ւ̃T�[�r�X�ɂ��y��ł��܂��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i �ߋ��ő�4��406�l���� ����4���l�� �@7/28
�����s��28���A�s���ʼnߋ��ő��ƂȂ�4��406�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ�V���Ɋm�F�����Ɣ��\���܂����B
�s���ň����4���l����̂͏��߂Ăł��B����A�s�́A�������m�F���ꂽ7�l�����S�������Ƃ\���܂����B�����s��28���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��4��406�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���ň����4���l����̂͏��߂Ăł��B1�T�ԑO�̖ؗj���ɔ�ׂ�Ƃ��悻1.3�{�ŁA8500�l�]�葝���܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�9���A���ł��B
�܂��A�l�H�ċz�킩�AECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A27�����3�l������27�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ50��̏���1�l�ƁA80�ォ��100�Έȏ�̒j��6�l�̍��킹��7�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����Ɓu�����I�Ȋ��������Љ�@�\�̈ێ��ɉe�����v
�����s�̓��j�^�����O��c���J���A�s���̊����ƈ�Ò̐��̌x�����x������������ł��[���ȃ��x���ňێ����܂����B
�����ɂ��āA���Ƃ́u�V�K�z���҂�7���ԕ��ς͉ߋ��ő��ƂȂ�A�����I�Ȋ����������Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu�����̊g��ɂƂ��Ȃ��A�A�Ɛ�������l�������������A��Â��͂��߂Ƃ����Љ�@�\�̈ێ��ɉe�����y�ڂ��Ă���v�Əq�ׁA������@���������܂����B
����A��Ò̐��ɂ��āA���Ƃ́u���@���Ґ���6�T�ԘA���ő����������Ă���A��Ë@�ււ̕��ׂ����債�Ă���v�Əq�ׂ܂����B
|
�����{�V�^�R���i 21�l���S �V����2��4296�l�����m�F�@7/28
���{��28��)�A�V����2��4296�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�ߋ��ő��ƂȂ������ƂƂ��Ɏ�����2�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B���{�ɂ��܂��ƁA���ҏ����W��V�X�e���u�g�d�q−�r�x�r�v���A26���A�ꕔ�œ��͂ł��Ȃ���ԂƂȂ����e���ŁA27���A�����Ґ��ɔ��f�ł��Ȃ��������̂��������Ƃ������ƂŁA28���̊����Ґ��Ƃ��č��킹�āA���\���Ă���Ƃ������Ƃł��B����A���{�͂���܂łɔ��\����7�l�ɂ��āA�d�����Ă����Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B����ŁA���{���̊����҂̗v��131��456�l�ƂȂ�܂����B�܂��A21�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͂��킹��5312�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�27������5�l������46�l�ł��B |
���������@�R���i�V�K������1��2714�l�@�ߋ��ő��@9�l���S�@7/28
�������́A���傤�����ŐV����1��2714�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
��T23����1��2600�l�]��������ĉߋ��ő����X�V���܂����B����́A�����s��4961�l�A�k��B�s��2385�l�A�v���Ďs��570�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A���ƂƂ������҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ1�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A�̂�61��4234�l�ɂȂ�܂����B�܂��A70�ォ��90��ȏ�̂��킹��9�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1343�l�ƂȂ�܂����B��������2��710���ŁA�z������60.4���ł����B�V���ɕ����s�̍���Ҏ{�݂�喴�c�s�̈�Ë@�ւŃN���X�^�[���m�F����܂����B
���̂��̎��_�ŁA�����m�ۂ����Ƃ��Ă���1725�̕a���ɓ��@���Ă���l��1216�l�ɑ����A�a���̎g�p����70������70.4���ɂȂ�܂����B���̂����A�l�H�ċz��̑����Ȃǂ��K�v�ȏd�ǂ̊��҂�12�l�ɑ����A�d�ǎ҂̂��߂̕a��217���̎g�p����5.5���ƂȂ��Ă��܂��B���̂ق��A�h���×{���Ă���l��1120�l�ɑ����A����×{���Ă���l�͉ߋ��ő���7��9653�l�ƂȂ��Ă��܂��B�������͌��Ǝ��̃R���i���ʌx����o���āA��{�I�Ȋ�����̓O����Ăт����Ă��܂��B
|
������R���i����5442�l�@�a���g�p85���@�ʏ�m���A��ÕN���Ɋ�@���@7/28
���ꌧ��28���A�V����10�Ζ�������90�Έȏ��5442�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B���S�̂̕a���g�p����85�E5���ɏ㏸�����B�ʏ�f�j�[�m���͓����A�����ŋL�҉���u�S������₯���Ȃǂŕa�@�ɉ^��Ă��A�����ɂ͓��@���ł��Ȃ����ƁA�\�肵�Ă����������p����������邱�ƂȂǂ��z�肳���قǁA��ÕN��(�Ђ��ς�)���i��ł���v�Ɗ�@�������������B
����ʂ̕a���g�p���͖{��92�E9���A�{��33�E3���A���d�R63�E3���B���@����������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A���͍��Ȃǂ���Ō�t�̔h�����A���@�ҋ@�X�e�[�V�������g�[����B8��1������1���ő�30�l�̔h�����A�a�����������31������75���ɑ��₷�B
�����{�ݓ��ł̊����҂��������Ă���A����҂�Ⴊ���҂̎{�ݓ��ŗ×{���̊��҂͉ߋ��ő���1505�l�ɂȂ����B�����x���ɓ���{�ݐ����ߋ��ő���211�{�݂ƂȂ����B������Z���ڐG�ȂǂŌ����Ă���d�_��Ë@�ւ̈�Ï]���҂�28�����_��1199�l�������B8���A����l���Ă���B
���a�@���Ƌǂ͌����k���a�@�Ɛ��a�a�@�̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���g�債�Ă��邱�Ƃ����\�����B�k���a�@�͕a�����Ⴄ2���̃N���X�^�[������A���̂���1���͐V����17�l�̊����������B�����҂͌v29�l�Ɋg�債�A����1�l�����S�����B
|
���V�^�R���i ������5676�l�̊����m�F 2���A���ōő��X�V�@7/28
28���A�����ł͐V����5676�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A2�l�̎��S�����\����܂����B1���̐V�K�����Ґ��́A27����5522�l������A2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��2490�l�A�Ύ�n����546�l�A����s��335�l�A�\���n����309�l�A�I�z�[�c�N�n����277�l�A���َs��265�l�A��m�n����229�l�A�_�U�n����194�l�A���n����183�l�A���M�s��175�l�A���H�n����166�l�A�n���n����152�l�A��u�n����86�l�A�@�J�n����76�l�A�����n����45�l�A�����n����39�l�A���G�n����37�l�A�O�R�n����21�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��43�l���܂�51�l�̂��킹��5676�l�ł��B
1���̐V�K�����Ґ��͑O�̏T�̓����j���ɔ�ׂĂ��悻1.5�{�����A27����5522�l������A2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�܂�����܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����D�y�s��80��̒j��2�l�̎��S�\���܂����B
����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�21��2611�l���܂ށA�̂�43��8677�l�A�S���Ȃ����l��2130�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�K������ 23��3100�l�� 2���A���ʼnߋ��ő��X�V 19�s���{���ōő��l���@7/28
�V�^�R���i�ɂ��āA���傤�����s�ł́A�����҂����߂�4���l���A�S���ł͉ߋ��ő��ƂȂ�23��3100�l�̊��������\����܂����B
�����s�͂��傤�V���ɁA4��406�l�̊����\���܂����B��T�ؗj������8528�l�����A���߂�4���l���A�ߋ��ő����X�V���܂����B����7���ԕ��ςł݂��V�K�����҂͂��悻3��1300�l�ŁA1�T�ԑO�̂��悻1.7�{�ł��B
�S���ł́A���킹��23��3100�l�̊��������\����Ă��܂��B��T�ؗj�����炨�悻4��7000�l�����āA�ߋ��ő����X�V���Ă��܂��B40�̓s���{���őO�̏T�̓����j��������A���A���m�A��ʂȂ�19�̓s���{���ʼnߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
�S���œ��@���Ă��銴���҂̂����u�d�ǎҁv�̐���346�l�ŁA�V���Ȏ��҂�114�l���\����Ă��܂��B
|
���S���m����c �g�R���i �����ǖ@�㈵���������܂ߑ��]�����h �@7/28
�S���m����c���A28������ޗǎs�ŁA3�N�Ԃ�ɑΖʌ`���Ŏn�܂�܂����B�V�^�R���i�̊������}�g�傷�钆�A�Љ�o�ϊ������ێ����邽�߁A�V�^�R���i�̊����ǖ@��̈������G�ߐ��̃C���t���G���U�Ɠ��������Ɍ��������Ƃ��܂߁A����܂ł̑��]�����ׂ����Ƃ����ӌ����������܂����B
��c�ł́A�V�^�R���i�̊����ǖ@��̈����ɂ��Ĉӌ����������A�_�ސ쌧�̍���m���́u���܂ł��w2�ޑ����x�ł͎��Ԃƍ��킸�A�Љ�o�ϊ������~�܂��Ă��܂��v�ƁA�G�ߐ��̃C���t���G���U�Ɠ����u5�ށv�Ɍ������ׂ����Ƒi���܂����B
�܂��A�k�C���̗�ؒm�����u�I�~�N��������99�����y�ǂł��邱�Ƃ܂��A�c�_��i�߂Ă��������d�v���v�Ǝw�E�����ق��A��t���̌F�J�m�����u�����҂́w�S���c���x�͌������̕K�v������B���S���y�����邽�߁w��_�c���x�Ɉڍs���ׂ����v�Əq�ׂ܂����B
����A�����s�̏��r�m���́u���@�Ґ����������钆�A4��ڂ̃��N�`���ڎ�̑Ώۊg��⍑�Y�̈��ݖ�̌㉟�������肢�������v�Əq�ׂ܂����B
�����āA�S���m����Ƃ��āA���N�`����3��ڂ�4��ڐڎ�̑��i��}�邱�Ƃ�A�����L�b�g�̈���I�ȋ����A����ɐV�^�R���i�̊����ǖ@��̎�舵���ɂ��Č������邱�ƂȂǂ����ɋ��߂�ً}���܂Ƃ߂܂����B
����t��ƒm���� �g�����L�b�g�z�z�h�n��̎����
���{��t��ƑS���m����́A�V�^�R���i�Ή����߂����ăI�����C���ňӌ������킵�܂����B
���̒��ŁA���{��t��̏��{��́A��Â̂Ђ�����h�����߂̍R�������L�b�g�̔z�z�ɂ��āu�s���{���̈�t��ƍs�������c���A�n��̎���ɍ������d�g�݂𑁋}�ɒz�����Ƃ����ɏd�v���v�Ǝw�E���A���M�O���Ɍ��炸�A�X��������{�݂Ŕz�邱�Ƃւ̋��͂����߂܂����B
�܂��A���ˏ�C�����́u���Â̗D�揇�ʂ�����g���A�[�W�@�\�����d�g�݂�n��ɍ\�z���Ăق����B�e�n�ɃR�[���Z���^�[�Ȃǂ�݂��Ă��邪�A�Ȃ���ɂ����Ƃ�����肪����A����Ɋg�[���Ăق����v�Ƌ��߂܂����B
����ɑ��A�S���m����̉�߂钹�挧�̕���m���́u���ꂼ��̒n��̓����ɍ��킹������Ƃ肽���v�Ɖ����A���͂��Ď��g�݂�i�߂Ă������Ƃň�v���܂����B
����A�S���m�������A�V�^�R���i�̊����ǖ@��̈������G�ߐ��̃C���t���G���U�Ɠ����Ɍ������ׂ����Ƃ����ӌ����o���̂ɑ��A���{��́u�����ȍ~�A���{�R�c��̋c�_���n�܂邪�A���������c�_�ł��A�g���Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
|
���S���̊�����23���l���@�ߋ��ő��@�m������{�ցu���j���������c�v�@7/28
�S���̐V�^�R���i�̐V�K�����҂�23���l���A27���ɑ����ߋ��ő����X�V���܂����B�����s�ŏ��߂�4���l����ȂǁA�u��7�g�v���S���Ɋg�債�Ă��܂��B�s���������s�����A����Ƃ��s��Ȃ����B�����̂ɂ���͊���Ă��܂��B
���{���������u��Ô�펖�Ԑ錾�v�B
����27���܂ŏd�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂ɁA�s�v�s�}�̊O�o���l�����߂Ă��܂��B
91�Βj���u������ˁA�قƂ�ǃO�����h�S���t�ȊO�͊O�ɏo�Ȃ��悤�ɂ��Ă���B�|������v
83�Ώ����u�ǂ������Ă� �w�����Ă��x���H�ׂ��������B��_�́B�H�ׂ��鎞�ɐH�ׂƂ��Ȃ��Ƃˁv�u(Q.���̂��g���m�����c)������˂�B�w�������Ƃ����ȁx�Ǝv�������ǁB���̂������߈��������邯�ǁA�ǂ����Ă��H�ׂ���������N��������A�҂���ւ�̂�v
�l�X�Ȑ����オ��Ȃ��A�u�V���E�v�̋߂��ł̓J���I�P�̉̐����ʂ�ɋ����Ă��܂����B
65�Βj���u����ς肨�ƂȂ������ĂȂ�����̂��ȂƎv���˂ǁA�ǂ��Ȃ��낤�v
���{�E�g���m���m���u����҂̕��A���A�����g�傪�L����Ȃ��ŁA���g�̐g�����s�����Ƃ��Ē��������v
65�Βj���u(Q.�g���m���̍���҂ւ̊O�o���l�v���͓��ӂ���H)������ȁc�v
79�Βj���u����ς�N����S�z���Ă���Č����Ă邩��A����ς肻��͎��Ȃ�����Ǝv���v
47�s���{������o�Ȃ����S���m����B28���̎��͋}�g�傷��u��7�g�v�ւ̑Ή��ł��B
���挧�E����L���m���u���̂���20��9694�l���z���ł���Ɗm�F������܂����B�ߋ��ő��ł���܂��B��������Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
��c�ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̈ʒu�t���������ǖ@��̕��ނł��錋�j��SARS���݂́u2�ޑ����v����������������߂�Ă��o�܂����B
����ł��c�_�ɂȂ��Ă���G�ߐ��C���t���G���U���݂́u5�ށv�ւ̌������́u��Ô�̕��S��������v�A�u�O�o�v�����ł��Ȃ��Ȃ�v�Ȃǂ̈ӌ�������A�T�d�_�������ł��B
�����s�E���r�S���q�m���u(Q.���ł͍���҂̍s��������v���������A�����́H)�����h�~���O�ꂷ��Ƃ������Ƃ����肢���Ă��܂��v�u(Q.��̓I�ȍs�������ɂ��ẮH)����ɂ��ẮA���ꂼ��̕���ł����Đ������ׂ��Ƃ���A�����ƌ����܂��傤���A�����h�~��O�ꂵ�Ē����Ȃ���Ȃ�܂���B�������������b�Z�[�W���o���Ă���܂����A����ɏɂ���ďd�ǎ҂��o���Ȃ��A���҂𑝂₳�Ȃ��A���̓_�ɂȂ��邱�Ƃ�����ĎQ��܂��v
28���A�V���Ɋm�F���ꂽ�����҂��ߋ��ő���4���l���铌���B
���r�m����4��ڂ̃��N�`���ڎ�̐��i�������g���h���A�d�ǎ҂�}������ʓI�ȕ��@���Ƃ��A����ɑS���m����Ƃ��ĐV�^�R���i�Ή��́u�V���ȕ��j�v�������K�v�������ɋ��߂�l���Ȃǂ������܂����B
�V�K�����҂��A�����������ɂ����t���ł́A�ߋ��ɗႪ�Ȃ��قNj~�}�����̒ʕ����������Ă���Ƃ����܂��B
��t�s���h�njx�h���~�}�ہE�L���G�i�ے��u�d�b�����Ă��A�Ȃ��Ȃ�����悪������Ȃ����Ⴊ�U�����Ă��܂��̂ŁA��Ë@�֑������Ɍ������낤�Ƃ����F���͂��Ă��܂��B��͂�ʕ��t�s(�ӂ�����)(�W��)���邱�ƂŁA�~�}�Ԃ��ꎞ�I�ɑ���Ȃ��Ȃ�Ƃ����͌����Ƃ��Ă���܂��v
�ʏ�A��t�s�̏��ǃG���A�ŋ~�}��26�䂪�Ή����Ă��邻���ł����A28���̎�ޒ��A�ꎞ23�䂪�ғ����A�قڗ]�͂Ȃ����Z���ɂ߂Ă��܂����B
�܂��A�E������������Ɛl��s���Ɋׂ邽�߁A��ɂ͏\���ɒ��ӂ��Ċ����ɂ������Ă��܂��B
�S���ł�28�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�20���l�ɒB���A�s���{���ʂł͐�t���∤�m���Ȃǂōő����X�V���Ă��܂��B
|
���ݓc�����̎����ő�7�g�̎��Ґ��ň��̋���c�u�R���i�̉āv���ޗ��@7/28
27���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��͑S����21���l�ɔ���A�ߋ��ő����X�V�����B���Ґ���129�l��2���A��100�l�������A����ɖc��オ�鋰�ꂪ����B
��9���܂ő������ґ�
��6�g�ł͐V�K�z���҂��ő�������2��5��(10��4169�l)����17����Ɏ��Ґ����s�[�N(322�l)�ɒB���A���̌�A�����ɓ]�����B
�u���Ă̗��s�́A8�����{�܂Ŋ����g�傪�����Ƃ݂��A��7�g�̎��Ґ��́A9����{�܂ő���������\��������܂��B�����Ґ��̕ꐔ���P�^�Ⴂ�ɑ����A1��2000�l�����S���Ȃ�����6�g�������Ă�������������܂���v(�����w����w�Z�p���w�Z�����Z�Z���̒����p�b��=�����NJw)
�������
�������ڋl�܂肪�N���Ă���B�Z���ڐG�҂̑ҋ@���ԒZ�k�ɂ��A���v���}�����Ă���R�������L�b�g�͕i���B�L�b�g���Ȃ���Ύ��匟���������Ă��ł��Ȃ��B
����������PCR�������ɂ����Ȃ��Ă���BPCR�����̐f�Õ�V�͍�N12��30���܂�1��1��8000�~���������A���݂͓�7000�~(���N7��1���`)�Ƒ啝�Ɍ��z�BPCR�����̎��{�������炷�N���j�b�N�����Ȃ��Ȃ��̂��B
���ƒ������
�s���̏h���×{�{�݂͉ғ������̖�7�������܂�A�����҂��������Ă���B�ƒ���������������Ύ��a�����̍���҂Ȃǂ̎��S���X�N�͍��܂�B
���~�}�����N��
�����ȏ��h���ɂ��ƁA�~�}���҂̔����悪�������܂�Ȃ��u�~�}��������āv�́A24���܂ł�1�T�Ԃ�6035���ɏ��A�ߋ�2�Ԗڂɑ��������B�����R���i�^���̌�����2676���ʼnߋ��ő��B����×{���ɋ}�ς��Ă��A�����ɓ��@�ł��Ȃ��P�[�X�����������˂Ȃ��B
�u���ޗ�����ł����A�ݓc�����������N�������ʂ��傫���B������1.8���̍ɂ����錟���L�b�g�́A�����ƑO�ɔz��悩�����BPCR�����̐f�Õ�V�����z����A�N���j�b�N�̌������k������͓̂��R�ł��B�����g���z�肵�āA�����邱�Ƃ͂ł����͂��ł��v(�����p�b��)
���P���^�E���X
�I�~�N�������̈���A�ʏ́u�P���^�E���X�v(BA.2.75)���C�����肾�B��������̂ق��A27���͈��m�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�B��7�g�̎嗬�ɂȂ��Ă���BA.5�͑�6�g�ŗ��s����BA.2���1.35�{�̊����͂�����Ƃ���邪�A�P���^�E���X��BA.5��3.24�{�Ƃ̌������ʂ��o�Ă���B��7�g�����ɂȂ�^�C�~���O��BA.5����P���^�E���X�ɒu������錜�O������B��́A�ǂ�ȁu�R���i�̉āv�ɂȂ�̂��B
����T�̐V�K�����Ґ� ���{�����E�ő�
��T�̐V�^�R���i�V�K�����Ґ������E�ő��������̂́A�Ȃ�Ɠ��{�������B���E�ی��@��(WHO)��27���A�V�^�R���i�̐��E�̊����Ɋւ���ŐV���|�[�g�����\�B����ɂ��ƁA���A�W�A�Ŋ����g�傪�����Ă�����{�̐V�K�����҂͐�T1�T�Ԃł͐��E�ő���96��9068�l�������B
���{�ł̓I�~�N�������̐V�n��BA.5�̉e���Ŋ����҂��}�����Ă���B����A��������BA.5�̊������g�債�����B�ł͐V�K�����Ґ��͂��łɌ����X���ƂȂ��Ă���B
|
��WHO �g1�T�ԓ�����̐V�K������ ��97���l�œ��{�����E�ő��h�@7/28
WHO�����E�ی��@�ւ�7��27���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��̕��\���܂����B7��24���܂ł�1�T�ԓ�����̐V�K�����Ґ��͓��{���A���悻97���l�Ɛ��E�ōł������Ȃ��Ă��܂��B
WHO�́A�V�^�R���i�E�C���X�̐��E�S�̂̐V�K�����Ґ��̏����܂Ƃ߂Ă��āA7��27���A�V���ȕ��\���܂����B
����ɂ��܂��ƁA7��24���܂ł�1�T�ԓ�����̐V�K�����Ґ��́A���E�S�̂�660��7653�l�ƑO�̏T���3���������܂����B
�V�K�����Ґ��́A���E�S�̂ł킸���Ɍ������Ă��܂����A���A�W�A�ł͑����X���������A�O�̏T�ɔ�ׂāA�����S���͂��悻7�{�A�؍���80�������Ă��܂��B
�܂��A���{��73�������Ă��āA�V�K�����Ґ���96��9068�l�Ɛ��E�ōł������Ȃ��Ă��܂��B
����A�A�����J��3��������86��97�l�A�h�C�c��16��������56��5518�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
WHO�́A�e�����������ɂ͍�������Ƃ��Ă��āA���ۂ̊����Ґ��́A����ɑ����\��������Ƃ��Ă��܂��B
WHO�́A�ˑR�Ƃ��ăI�~�N�������́uBA.4�v�ƁuBA.5�v���A���E�I�Ɏ嗬���Ƃ��Ă��Ċ������O�ꂷ��悤�Ăт����Ă��܂��B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 3��6814�l�����m�F �O�T���j���1819�l�� �@7/29
�����s����29���̊����m�F��3��6814�l�ŁA�O�̏T�̋��j������1819�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�10���A���ł��B����A�s�́A�������m�F���ꂽ5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��29���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3��6814�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̋��j���ɔ�ׂ��1819�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�10���A���ł��B29���܂ł�7���ԕ��ς�3��1578�l�ƂȂ�A�O�̏T��149.7���ł����B29���A�m�F���ꂽ3��6814�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�20.1���ɓ�����7390�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�3362�l�őS�̂�9.1���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A28�����1�l������26�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ50���70��̒j�����ꂼ��1�l�ƁA80��̒j��3�l�̍��킹��5�l�����S�������Ƃ\���܂����B
|
�����{�A�R���i�̐V�K����2��1387�l�@18�l���S�@7/29
���{��29���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�2��1387�l�m�F�����Ɣ��\�����B�����Ґ��͑O�T���j��(1��9948�l)�Ɣ��1439�l�������B�V����60�`90��̒j��18�l�̎��S���������A�{���̗v���Ґ���5330�l�ɂȂ����B
29�����_�̏d�ǎ҂͑O������3�l����49�l�ŁA�d�Ǖa��(596��)�̓����̎����g�p��(�d�����a�Ȃǂ������y�ǁE�����NJ��҂���܂�)��22.1%�ɂȂ����B�y�ǁE�����Ǖa���ɂ�2505�l�����@���Ă���A�y�ǁE�����Ǖa��(4198��)�̎g�p����59.7%�ƂȂ����B�a���ɂ́A�m�ې����Ď��ۂɉ^�p���Ă�����̂��܂�ł���B
�V�K�����҂̂����A�����҂Ɠ������ďǏ���APCR���������Ɉ�t�̐f�f�ŗz���Ɣ��f���ꂽ�Z���ڐG�҂�759�l�������B����×{�҂�13��3010�l�B����ɂ��PCR�����Ȃǂ�4��836�����{�����B
|
���������@�R���i�@1��4060�l�����m�F�@�ߋ��ő��@7�l���S�@7/29
�������́A���傤�����ŐV����1��4060�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B1��4000�l����̂͏��߂ĂŁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
����́A�����s��4532�l�A�k��B�s��2482�l�A�v���Ďs��814�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A���ƂƂ��Ƃ��̂������҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���킹��7�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A�̂�62��8287�l�ɂȂ�܂����B�܂��A70�ォ��90��ȏ�̂��킹��7�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂́A1350�l�ƂȂ�܂����B�������͂���܂łōł�����2��1584���ŁA�z������64.2���ł����B�V���ɒ����s�̈�Ë@�ւ⎅���s�̍���Ҏ{�݂ȂǂŃN���X�^�[���m�F����܂����B
���̂��̎��_�ŁA�����m�ۂ����Ƃ��Ă���1725�̕a���ɓ��@���Ă���l��1271�l�ɑ����A�a���̎g�p����73.6���ɂȂ�܂����B���̂����A�l�H�ċz��̑����Ȃǂ��K�v�ȏd�ǂ̊��҂�11�l�ŁA�d�ǎ҂̂��߂̕a��217���̎g�p����5���ƂȂ��Ă��܂��B���̂ق��A�h���×{���Ă���l��1113�l�A����×{���Ă���l��8���l���ĉߋ��ő���8��5026�l�ƂȂ��Ă��܂��B�������͌��Ǝ��̃R���i���ʌx����o���āA��{�I�Ȋ�����̓O����Ăт����Ă��܂��B
|
������R���i�@5253�l�����@�a���g�p����88%�Ɂ@7/29�@
���ꌧ��29���A�V����5253�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̋��j��(22��)��4654�l�ɔ�ׂ�599�l�������B�v�����҂�34��8639�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ��͑O�����_��2223.26�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ���������1583.63�l�����������Ă���B�a���g�p����88.7��(���@�Ґ�678/�a����764)�ŁA�d�ǎҗp��40.3��(���@�Ґ�25/�a����62)�ƂȂ��Ă���B�ČR��n���̐V�K�����Ґ���65�l�������B
|
�����ꌧ �V�^�R���i 5253�l���� ���j���Ƃ��ĉߋ��ő��@7/29
���ꌧ��29���A�V����5253�l���V�^�R���i�Ɋ����������Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���A���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ɂȂ�܂����B
29�����\���ꂽ�V�K�����҂�5253�l�ŁA��T�̋��j���Ɣ�ׂ�599�l�����A�ߋ�4�Ԗڂɑ����Ȃ�A���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ɂȂ�܂����B
�N��ʂł͑�������40�オ858�l�A30�オ778�l�A10�Ζ�����759�l�A10�オ684�l�A20�オ599�l�A50�オ587�l�A60�オ466�l�A70�オ257�l�A80�オ182�l�A90�Έȏオ77�l�ŁA�s����6�l�ł��B
�n��ʂł͑������ɓߔe�s��1069�l�A����s��550�l�A����s��522�l�A�Y�Y�s��446�l�A�X��p�s��360�l�A����s��257�l�A�����s��235�l�A�L����s��227�l�A���s��154�l�A�Ί_�s��131�l�A�{�Ó��s��101�l�ł��B
���̂ق��̒����͕ی����̊NJ��ʂɁA�����ی����Ǔ���524�l�A�암�ی����Ǔ���508�l�A�k���ی����Ǔ���101�l�A���d�R�ی����Ǔ���13�l�ŁA���O��53�l�A�m�F����2�l�ł��B
����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�34��8639�l�ɂȂ�܂����B
���́A�~�}�a�@�̋@�\�����d�_��Ë@�ւȂǂ̕��S���y�����邽�߁A�V���ɋx���ɔ��M�O���̐f�Â��s���n��̈�Ë@�ւɑ����͋����x�����邱�Ƃɂ��Ă��܂����A����ɉ����āA31���͌�����9�̈�Ë@�ւŐf�Â��s����Ƃ������Ƃł��B
�l��10���l������̐V�K�����҂�28���܂ł�1�T�Ԃ�2223.26�l�ƈ��������S�����[�X�g�ŁA�S�����ς̂��悻2.1�{�ł��B
29�����ݓ��@���Ă���̂�28�����25�l����678�l�ŁA���̊�ł̏d�ǎ҂�25�l�A�����ǂ̐l��354�l�A�V�^�R���i���җp�̕a���g�p���͌��S�̂�88.7���ł��B���̂����A����{����96.9���ƁA�[���ȏ�Ԃ������Ă��܂��B
�V�^�R���i�ɑΉ����Ă����Ȉ�Ë@�ւŊ���������Z���ڐG�҂ɂȂ����肷��Ȃǂ��ċΖ��ł��Ȃ���Ï]���҂�1234�l�ŁA28������35�l�����܂����B
�܂��A�����҂��������Ă��̂܂ܗ×{���Ă���{�݂�����Ҏ{�݂�178�A��Q�Ҏ{�݂�48����A�×{�҂�1609�l�Ɖߋ��ő��ɂȂ��Ă��܂��B
���̂ق��A�����J�R���猧�ɑ��A�V����65�l�̊������m�F���ꂽ�ƘA�����������Ƃ������Ƃł��B
|
���V�^�R���i ����6594�l 3���A���ōő��X�V�@7/29
29���A�����ł͐V����6594�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A4�l�̎��S�����\����܂����B1���̐V�K�����Ґ���6000�l����̂͏��߂Ă�3���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��3359�l�A�Ύ�n����462�l�A�_�U�n����349�l�A����s��343�l�A�\���n����322�l�A���َs��282�l�A�I�z�[�c�N�n����268�l�A��m�n����240�l�A���H�n����201�l�A���M�s��158�l�A�n���n����125�l�A���n����119�l�A��u�n����110�l�A�@�J�n����62�l�A�����n����49�l�A�����n����44�l�A���G�n����23�l�A�O�R�n����22�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�����A���O��42�l���܂�56�l�̂��킹��6594�l�ł��B
1���̐V�K�����Ґ���6000�l����̂͏��߂ĂőO�̏T�̓����j�����1.5�{�߂������Ă��܂��B
�܂��A28����5676�l��啝�ɏ���A3���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�Ǐ�́A��������47�l�������A�����ǂ�8�l�ŁA���̂ق��́A��������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�S�̂̔����ȏ�ɂ�����3552�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
��������1��1915���ł����B�܂��A����܂łɊ������m�F����Ă����l�̂�������80��̒j��1�l�A�D�y�s��70��̏���1�l��90��̒j��1�l�A���َs���N��Ɛ��ʂ�����\��1�l�̂��킹��4�l�̎��S�\���܂����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�21��5970���܂ނ̂�44��5271�l�A�S���Ȃ����l��2134�l�A���Â��I�����l�͂̂�40��3358�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���R���i�����ҋ}�� �e�n�ň�Ë@�ցE���{�݂Ȃǂɉe�� �@7/29
���{�͓s���{�����Ǝ��Ɂu���錾�v���o���A�����̃��N�`���ڎ�ȂNJ�����������Ăт�����d�g�݂̓��������߂܂����B
�����s���̍���Ҏ{�݂ł́A�{���͈�Ë@�ւɓ��@���]�܂����d�ǂ̍���҂��{�ݓ��Ŏ��Â�����Ȃ��P�[�X���������Ă��܂��B
�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂ɂ��܂��ƑS���̍���Ҏ{�݂Ŋm�F���ꂽ�N���X�^�[�Ȃǂ�7��24���܂ł�6���ԂőO�̏T���41������337���ɂ̂ڂ�A���Ɖ�͍���A����҂𒆐S�ɏd�ǎ҂�S���Ȃ�l�������邱�Ƃ����O�����Ƃ��Ă��܂��B
�����̑�6�g�ł͕a���̂Ђ����œ��@�ł����{�ݓ��ŗ×{������Ȃ��P�[�X�������������Ƃ���A�e�n�Ŏ{�݂Ɉ�t��h�����č���҂����Â�����g�݂��i�߂��Ă��܂��B
���� ����̃N���j�b�N�̗�ؗz���t�́A����ɂ��鍂��Ҏ{�݂ɓ�������V�^�R���i�̊��҂�K�₵�Đf�@���Ă��܂��B
���̂�������26���ɖK�₵������Ҏ{�݂ł͎_�f�z������g�p���Ă���90��̏����̎��Âɂ�����A�x�b�h�ɉ�������������ɐ��������Ȃ���_�f�̏�Ԃ��m�F���čR�������𒍎˂��Ă��܂����B
��t�ɂ��܂��Ə����͍������{�ɔ��ǂ��A�Ǐo�����Ɍ��t���̎_�f�̒l��79���ɂȂ��Ċ댯�ȏ�ԂƔ��f����~�}�Ԃ�v�������Ƃ����܂��B
�Ƃ��낪�A4���Ԉȏソ���Ă������悪������Ȃ��������ߎ_�f�z��������A�{�ݓ��Ŏ��Â𑱂�����Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
��؈�t�����f��S�����Ă���3�̍���Ҏ{�݂ł́A�p���I�Ɉ�t�̐f�@���K�v�ȃR���i���҂����킹��15�l�قǂ��āA���̏������܂�2�l���ċz��h�{��Ԃ������A���@���]�܂�����Ԃł������A�a���̂Ђ����ɂ���ē��@�ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
��������O�f�Ï��̗�؈�t�́u�{���͓��@�����ق����悢����҂����͂ǂ��ɂ�����Ȃ��̂Ŏ{�݂łł��鎡�Â������ԂɂȂ��Ă���B��5�g�A��6�g�Ŏ{�݂̃X�^�b�t����Î҂��o����ς��ƂőΉ��͂͏オ���Ă��č��͎����������Ă��邪�A����Ɋ������g�傷��Ας�����Ȃ��Ȃ��ʂ��o�Ă��邩������Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B
������×{�҂̋}�����f�˗��E��
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��⎩��×{�҂̋}�����āA���f���s����t�̂��Ƃɂ͈˗����E�����Ă��܂��B
��t�̃O���[�v�ł́A�d�ǃ��X�N�̂��銳�҂��������Ȃ����߁A�Ǐ�J�ɕ�������đΉ��ɂ������Ă��܂��B
��Ԃ�x���ɋ~�}���҂̉��f���s����t�O���[�v�A�u�t�@�X�g�h�N�^�[�v�ɂ͊����̊g��ɔ����ĉ��f�̈˗����E�����Ă��āA�������ɂ�200���ȏ�A�f�炴�邦�Ȃ����Ƃ�����Ƃ������Ƃł��B
�d�lj��̃��X�N�������l�Ɉ�Â��ł���悤�R�[���Z���^�[�ł́A���҂̏Ǐ��ً}�������邩�ǂ����A�����ŕa�@�ɍs�����Ƃ�������ǂ������ڂ��������Ƃ��Ă��܂����B
����ɁA��t�O���[�v�ł́A�����̂��璼�ڐf�@�̕K�v������Ɣ��f���ꂽ����×{�҂̉��f���s���Ă��܂����A���̈˗����}�����Ă��邽�߁A��ʂ̎t���𐧌�����������Ȃ����Ƃ�����Ƃ����܂��B
��ނŖK�ꂽ�ߌ�7�������ɂ��ꎞ�I�ɗ\����~���Ă��܂����B
�܂��A����×{�҂̒��ɂ́A���@�̕K�v�������Ă������ɂ͎����̈�Ë@�ւ����܂�Ȃ��P�[�X�������Ă��Ă���Ƃ����܂��B
���̂����A�s���Ŏ���×{����90��̒j���́A1�T�Ԉȏ㔭�M�������A���@����]���Ă������̂̒��������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃʼn��f������t�́A�ی����ɓd�b�Ŋ��҂̏Ǐ�������ŁA���@���K�v�ȏ�Ԃ��Ɠ`���Ă��܂����B
�u�t�@�X�g�h�N�^�[�v�̑�\�A�e�r����t�́u�����҂��}�����Ă��āA���ׂĂ��~�߂�̂�����̂�����ł��B�d�lj����X�N�������l�Ɉ�Â�ł���悤�g�g���A�[�W�h�������������v�Ƙb���Ă��܂��B
���s�� ����×{�ҋ}�� 7��1����10�{����
�����I�Ȋ����g��ŁA�����s���ł͎���ŗ×{����l���}�����Ă���28�����_�ł��悻17��9000�l�ɂȂ�܂����B
7��1���͂��悻1��7000�l�������̂ŁA7��������10.6�{�ɂȂ��Ă��܂��B
7��21���ɂ�10���l���đ�6�g�̃s�[�N���A���̌�����т��эő����X�V���Ă��܂��B
�܂��A���@���邩�����h���×{�����邩�������̐l��28�����_��7���l�]��ŁA7��1�����_��11.5�{�ɂȂ�܂����B
28���J���ꂽ���j�^�����O��c�œs�̈�Ò̐��͂��Ă��铌���s��t��̒������F����́A�u�×{�Ґ����傫���������āA���݁A�s���̂��悻60�l��1�l�������z���҂Ƃ��ē��@�E�h���E����̂����ꂩ�ŗ×{���Ă���B�S�Ă̗×{�҂ɐ�߂銄���͎���×{�҂Ɠ��@�E�×{�Ȃǂ̒������̐l�����悻96���Ƒ������߂Ă���v�Ǝw�E���Ă��܂��B
�e�n�ł������}�g��ɂ��Ή��ɒǂ��Ă��܂��B
����� ����ŗz������ł���d�g�݉^�p
��ʌ��͈�Ë@�ւ̕��S�����炷���߁A���M�Ȃǂ̏Ǐ����Ĉ�Ë@�ւł̌�����f�Â̗\���Ȃ��Ȃǂ̏ꍇ�A����ɍR�������L�b�g��X���������ƃI�����C���ň�t�̐f�f���A�z���̔��肪�ł���d�g�݂��^�p���Ă��܂��B
�Ώۂ́A�d�lj����X�N����r�I�Ⴂ�Ƃ����A��b�����̂Ȃ�50�Ζ����̐l�ł��B
���M�Ȃǂ̏Ǐ����Ĉ�Ë@�ւł̌�����f�Â̗\���Ȃ��Ȃǂ̏ꍇ�A�E�F�u�T�C�g�Ő\������ƍR�������L�b�g��2���O��Ŏ���ɓ͂����悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�����L�b�g�ŗz���ƂȂ����ꍇ�A���̃E�F�u�T�C�g��ʂ��ăI�����C���ň�t�̐f�f������Ƃ������Ƃł��B
���ɂ��܂��ƁA���̎d�g�݂�7��20������^�p���Ă��Ĕz�z�ł������͈��2000�ł����A�����A����ɒB���Ă���Ƃ������Ƃł��B
���̂��ߍ�ʌ��͍�����z�z�����\��̌����L�b�g�Ȃǂ��܂ߏ�����𑝂₷�����Ō������Ă��܂��B
���Q�n �����L�b�g�̖����z�z��
�Q�n����60�Ζ����ŁA��b�����������d�lj����X�N�̒Ⴂ�l�̒��Ŕ��M�Ȃǂ̏Ǐ���l�ɂ͌����L�b�g��X�����A�݂����猟�����Ă��炤�d�g�݂�8����{����^�p������j�ł��B
����ɗp�ӂ��錟���L�b�g�̐��⌟����̋�̓I�Ȏ菇�Ȃǂ͌��݁A�Q�n����t��Ȃǂƌ������s���Ă���Ƃ������Ƃł��B
�Q�n���́A���̎��g�݂ɂ���Č����̂��߂Ɉ�Ë@�ւ�K���l�����炵�A���S�y����}�肽���l���ł��B
���{�� ��K�͐ڎ���̗\��}��
�{�錧�Ȃǂ��݂��Ă��郏�N�`���̑�K�͐ڎ���ł�31���̏I����O�ɗ\�}�����Ă��āA�����̐l���ڎ�ɖK��Ă��܂��B
�{�錧�Ɠ��k��w�Ȃǂ����w�����̃r���ɐ݂��Ă��郏�N�`���̑�K�͐ڎ���́A����ɂ��悻2000�l�̐ڎ���t���Ă��܂�����31���ŏI���ƂȂ�܂��B
���ɂ��܂��ƁA�����ŐV�^�R���i�̊������}�g�債�Ă��邱�Ƃ��Ï]���҂⍂��Ҏ{�݂̃X�^�b�t�Ȃǂɂ�4��ڂ̐ڎ�Ώۂ��g�債�����ƂȂǂ��獡��22���ȍ~�͎��O�\�}�����Ă��āA29���ߌ�3���̎��_�ŁA�ŏI����31���܂ŗ\���܂��Ă���Ƃ������Ƃł��B
���ɂ͑����̐l���K��Ă��āA���X�Ƀ��N�`���̐ڎ���Ă��܂����B
4��ڂ̐ڎ����70��̒j���́u�����ȊO�̉Ƒ��͉Ƃ̋߂��̃N���j�b�N�Őڎ킵�܂��������Ԃ��Ȃ��l�ɂ͓���ł��B�����͑҂����Ԃ����Ȃ��Ă����ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
3��ڂ̐ڎ����30��̒j���́u���������Ȃǂ��Ȃ��̂ŁA���̉��ł����Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ǝ����ŕa�@��T���̂���ς��Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
����8���ȍ~�A�e�s�����̏W�c�ڎ�����Ë@�ւł̐ڎ���Ăт����Ă��܂����A����A�ڎ�Ώۂ�����Ɋg�傳���ȂǑΉ����K�v�ɂȂ����ꍇ�͑�K�͐ڎ���̍ĊJ����������Ƃ��Ă��܂��B
���É� ��ǂōR�������L�b�g�̍Ɍ���
�É��s�̖�ǂł́A�V�^�R���i�E�C���X�̌����L�b�g�����߂�l�������Ă��܂����A���Ǝ҂���[�i����������Ă��āA���~��O�ɍɂ��Ȃ��Ȃ�Ȃ�����@�����点�Ă��܂��B
�É��s����ɂ����ǂł́A���T����R�������L�b�g�����߂�l�������n�߁A�挎��1�����ɐ��������̂��A���T�����ł��ł�13���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
���̓X�Ŏ�舵���Ă���2�̃��[�J�[�̌����L�b�g�̍ɂ�10���x�Ɍ����Ă��܂��B
���ꂩ�炨�~�̎������}���A�A�Ȃ◷�s�̂��߂ɂ���ɔ������߂�l��������Ɨ\�z���Ă��܂����A28���A���i�̉��Ǝ҂ɒlj��̔����������Ƃ���A��1�̃��[�J�[�̂��̂́A5�܂łɐ�������A���ʂ̃��[�J�[�̂��̂́A�[�i�܂�2�T�Ԓ��x������Ƃ���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�u��܂�����ǁv�̗�؊���t�́A�u����قǂ̌����L�b�g�̎��v�́A����܂Ō����Ȃ��������ۂł��B���[�J�[�̐������Ԃɍ����̂��S�z�ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�����Ɓu��7�g�̂܂������� ���z��f����K�v�v
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����͌��݂̊����ɂ��āu�����I�Ȋ����Ґ��̑������S���Ō����A�܂��ɑ�7�g�̂܂��������ɂ�����B�Ђ��������Ë@�ւ���{�݂���ߖ��������A�Љ�@�\����Q���o�n�߂Ă���B���Ƃ����̈��z��f����˂Ȃ�Ȃ��v�Ɗ�@���������܂����B
���̂����Łu���̃y�[�X�Ŋ����g�傪�����A���������̊����҂��S����30���l����40���l�A����������5���l����6���l�ɑ����Ă��܂��ƁA��Õ����傫�ȎЉ�@�\�̏�Q���N���Ă��܂��ƍl���Ă���B����1�A2�T�Ԃ̂����Ɍ����X���ɓ]���Ȃ���A�����s���������o������Ȃ��ɂȂ�v�Ǝw�E���܂����B
�����āu1�l1�l���������O�ꂷ�邱�ƂŁA�����s���������o�����ɂ��̑�7�g������邩��������Ă���B���ꂩ�炨�~�̋A�ȂȂǗ��s�̎������}���邪�A�l�̓����������邱�ƂŊ����g��̃��X�N�����܂�̂ŁA���s�̑O�Ɍ���������A���N�`���̐ڎ���ς܂����肷�邱�Ƃ��厖���B�܂��A�}�X�N�����ʓI�Ɏg�����ƁA3��������邱�ƁA���C��p�ɂɍs�����ƂȂǂ�O�ꂵ�A�����ł��̒������������Ƃ����Ƃ��͗��s��O�H�͍T���Ăق����v�ƌĂт����܂����B
���V�K�����Ґ�1�T�ԕ��� 37�̓s���{���ʼnߋ��ő�
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA37�̓s���{���ʼnߋ��ő��ɂȂ��Ă��āA���̂���6�̓��{���ł͑O�̏T��2�{�ȏ�ɂȂ�ȂǁA�}���ȑ����������Ă��܂��B
NHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S��
6��30���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�ɔ�ׂ�1.23�{�A7��7����1.78�{�A7��14����2.13�{�Ƒ����̃y�[�X�͏オ�葱���Ă��܂����B7��21����1.72�{�A28���܂łł�1.67�{�ƁA�y�[�X�͂�≺���������̂̋}���ȑ����͑����Ă��܂��B���������̕��ς̐V�K�����Ґ��͂��悻19��1177�l�ƁA�O�̏T�ɑ����ߋ��ő����X�V���܂����B28���̎��_��1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ���37�̓s���{���ʼnߋ��ő��ɂȂ��Ă��āA���̂����A6�̓��{���őO�̏T��2�{�ȏ�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ꌧ / 7��14���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��1.57�{�A7��21����1.38�{�A28���܂łł�1.27�{�Ƒ����������Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻4717�l�ŁA�ߋ��ő��ƂȂ��Ă���ق��A����1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ���2249.98�l�ƑS���ōł������Ȃ��Ă��܂��B
�������s / 7��14���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��2.21�{�A7��21����1.66�{�A28���܂łł�1.66�{�ƈ��������}���ȑ����������Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻3��1318�l�ŁA�ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
���_�ސ쌧 / 7��14���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��2.24�{�A7��21����1.85�{�A28���܂łł�1.48�{�ŁA1��������̐V�K�����Ґ��͉ߋ��ő��̂��悻1��3138�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����ʌ� / 7��14���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��2.32�{�A7��21����1.85�{�A28���܂łł�1.82�{�ŁA1��������̐V�K�����Ґ��͉ߋ��ő��̂��悻1��1203�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����t�� / 7��14���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��2.26�{�A7��21����1.79�{�A28���܂łł�1.81�{�ŁA1��������̐V�K�����Ґ��͉ߋ��ő��̂��悻9061�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����{ / 7��14���܂ł�1�T�Ԃ͑O�̏T��2.24�{�A7��21����1.80�{�A28���܂łł�1.61�{�ŁA1��������̐V�K�����Ґ��͉ߋ��ő��̂��悻1��9939�l�ƂȂ��Ă��܂��B |
���V�^�R���i ����×{�҂�109���l���ʼnߋ��ő���(27�����_) 7/29
�V�^�R���i�E�C���X�̊������g�傷�钆�A����ŗ×{���Ă��銴���҂�27�����_�ʼnߋ��ő���109��8671�l�ɏ�������Ƃ������J���Ȃ̂܂Ƃ߂ŕ�����܂����B
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ď���ŗ×{���Ă���l��27���̎��_�őS���ō��킹��109��8671�l�ł����B
�O�̏T����48��6648�l�����A2�T�A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�s���{���ʂł͓����s���ł�����15��7576�l�A�����ő��{��11��5909�l�A���m����7��5160�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A���@���K�v�Ɣ��f���ꂽ�l�̂����A���������������l��2069�l�őO�̏T����1104�l�����܂����B
�u��6�g�v�ł͎���×{�҂ւ̕ی����ɂ�錒�N�ώ@���x�ꂽ��A���@�ł����ɗ×{���Ɏ���Ŏ��S�����肷��l���������Ƃ���A�����J���Ȃ͑S���̎����̂Ɉ�Ò̑̐��Ȃǂ���������悤���߂Ă��܂��B
|
������×{�ҏ���100���l���A1�T�ԑO��2�{�߂��c����������22��1443�l�@7/29
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�29���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����22��1443�l�m�F���ꂽ�B���҂�122�l�A�d�ǎ҂͑O������30�l����376�l�������B�����J���Ȃ��W�v�����S���̎���×{�Ґ�(7��27�����_)��110��6122�l�ŁA���߂�100���l��˔j�B1�T�ԑO����2�{�߂��ɑ������B
�����s�ł�3��6814�l�̊������m�F�B�O�T�̓����j������1819�l�����A10���A����2���l�����B�s�ɂ��ƁA����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂�3��1578�l�ŁA�O�T����50���������B50�`80�Α�̒j��5�l�̎��S�����������B
�k�C�����ʁA�����Ȃ�11�����́A�V�K�����Ґ����ߋ��ő����X�V�����B
|
���㓡���J�� �g�V�^�R���i �����ǖ@��̈����������ׂ��łȂ��h �@7/29
�V�^�R���i�̊����ǖ@��̈������������悤���߂鐺���o�Ă��邱�Ƃɂ��Č㓡�����J����b�́A�@���Ɋ�Â����͂ȑ[�u������悤�ɂ��Ă����K�v������Ƃ��āA�����_�ł́A�������ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����l���������܂����B
28���̑S���m����c�ł́A�V�^�R���i�̊����ǖ@��̈������A�G�ߐ��C���t���G���U�Ɠ��������Ɍ��������Ƃ��܂߁A����܂ł̑��]�����ׂ����Ƃ����ӌ����������܂����B
����ɂ��Č㓡�����J����b�́A�L�҉�Łu�����_�ŁA�V�^�R���i�̒v�����̓C���t���G���U��荂���A���ɍ���҂͂��̍����������B�����͂��ɂ߂ċ������߁A�����̋K�͂����ɑ傫���Ȃ�\��������B�����Ȃ�Έ�Â��Ђ������A�K�v�Ȑl�Ɉ�Â��ł��Ȃ������ꂪ�o�Ă���v�Ǝw�E���܂����B
���̂����Łu�����͂������wBA.5�x�̏Ȃǂ��l����A�`�Ƃ̕Ƃ������ׂ��A���ʑ[�u�@��̋��͂ȑ[�u�̉\�����c���Ă����ׂ����v�Əq�ׁA�����_�ł́A���̈������������ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����l���������܂����B
����A�㓡��b�́u����̊�����E�C���X�̐���ȂǁA���V�����A�ڂ�����q�ϓI�ɐςݏオ���Ă���A���Ƃ̈ӌ����f���Ȃ���_��ɋc�_�𑱂��Ă��������v�Əq�ׂ܂����B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 12�l���S 3��3466�l�����m�F �y�j���ōő� �@7/30
�����s����30���̊����m�F��3��3466�l�ŁA�O�̏T�̓y�j������768�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�11���A���ŁA�y�j���̊����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B����A�s�́A�������m�F���ꂽ12�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��30���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3��3466�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j���ɔ�ׂ��768�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�11���A���œy�j���̊����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B30���܂ł�7���ԕ��ς�3��1687.7�l�ŁA�O�̏T��137.4���ł����B30���Ɋm�F���ꂽ3��3466�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�19.7���ɂ�����6600�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�3198�l�őS�̂�9.6���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A29�����2�l������24�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ80�ォ��100�Έȏ�̒j�����킹��12�l�����S�������Ƃ\���܂����B |
�����{ �V�^�R���i 12�l���S 2��2833�l�����m�F �@7/30
���{��30���A�V����2��2833�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����܂ł�3�Ԗڂɑ����A�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂ�300�l�]�葝���܂����B����A���{��29���ɔ��\����1�l�ɂ��āA�d�����Ă����Ƃ��Ċ����Ґ������艺���܂����B���{���̊����҂̗v��135��4667�l�ƂȂ�܂����B�܂��A12�l�̎��S�����\����A�{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͍��킹��5342�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂�29�����2�l������51�l�ł��B |
�������� �V�^�R���i 8�l���S 1��3954�l�����m�F �@7/30
��������30���A�����ŐV����1��3954�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�y�j���Ƃ��Ă͍ł������Ȃ�܂����B����́A�����s��4986�l�A�k��B�s��2399�l�A�v���Ďs��713�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A����12���A�����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ1�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A����64��2240�l�ɂȂ�܂����B�܂��A50�ォ��90��ȏ�̍��킹��8�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1358�l�ƂȂ�܂����B |
�����ꌧ 5762�l�����m�F �ߋ��ő� ��Ñ̐��Ђ����@7/30
30���A�V���ɐV�^�R���i�Ɋ������m�F���ꂽ�͉̂ߋ��ő��ƂȂ�5762�l�B �Ζ��ł��Ȃ���Ï]���҂��ߋ��ő��ƂȂ��Ă��āA��Ò̐������������Ђ������Ă��܂��B
30���A���\���ꂽ�V�K�����҂�5762�l�ŁA1���Ɍ��\�����V�K�����҂̐��Ƃ��ẮA����܂łōł�������������26����5622�l������A�ߋ��ő��ƂȂ�܂��� ��T�̓y�j���Ɣ�ׂ��465�l�����Ă��܂��B
�N��ʂł͑������ɁA40�オ947�l�A10�Ζ�����859�l�A30�オ784�l�A10�オ777�l�A20�オ634�l�A50�オ606�l�A60�オ496�l�A70�オ296�l�A80�オ237�l�A90�Έȏオ117�l�ŁA�s����9�l�ł��B
�n��ʂł͑������ɁA�ߔe�s��1143�l�A����s��558�l�A����s��479�l�A�Y�Y�s��473�l�A�X��p�s��396�l�A�����s��301�l�A�{�Ó��s��251�l�A�L����s��239�l�A����s��221�l�A���s��202�l�A�Ί_�s��158�l�ł��B
���̂ق��̒����͕ی����̊NJ��ʂɁA�����ی����Ǔ���592�l�A�암�ی����Ǔ���557�l�A�k���ی����Ǔ���118�l�A���d�R�ی����Ǔ���19�l�ŁA�{�Õی����Ǔ���1�l�A���O��48�l�A�m�F����6�l�ł��B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�̂�35���l���āA35��4401�l�ɂȂ�܂����B30�����ݓ��@���Ă���̂�29�����12�l������666�l�ŁA���̊�ł̏d�ǎ҂�26�l�A�����ǂ̐l��347�l�A�V�^�R���i���җp�̕a���g�p���͌��S�̂�87.2���ł��B����×{��h���×{���܂߂āA���݁A�×{���Ă���l��4���l����4��826�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V�^�R���i�ɑΉ����Ă����Ȉ�Ë@�ւŊ���������A�Z���ڐG�҂ɂȂ����肷��Ȃǂ��ċΖ��ł��Ȃ���Ï]���҂�1277�l�ŁA�ߋ��ő��ƂȂ��Ă��āA��Ò̐������������Ђ������Ă��܂��B����{�����̐V�^�R���i���җp�̕a���g�p����96.4���ƂЂ������Ă��܂��B���̂ق��A����Ҏ{�݂Ə�Q�Ҏ{�݂ŗ×{���Ă���l���ߋ��ő���1671�l�ƂȂ��Ă��āA���̂���75�l���{�ݓ��Ŏ_�f���^���Ă��܂��B
|
���k�C�� �V�^�R���i 2�l���S 6286�l�����m�F �@7/30
30���A�k�C�����ł͐V����6286�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A2�l�̎��S�����\����܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s��2984�l�A�Ύ�n����573�l�A�\���n����342�l�A����s�ōėz����1�l���܂�338�l�A�I�z�[�c�N�n����309�l�A�_�U�n����275�l�A���َs��253�l�A��m�n����227�l�A���H�n����194�l�A���M�s��171�l�A�n���n����153�l�A���n����142�l�A��u�n����85�l�A�����n����49�l�A�@�J�n����45�l�A���G�n����33�l�A�����n����25�l�A�O�R�n����12�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�����A���O��59�l���܂�76�l�̍��킹��6286�l�ł��B
�܂��A����܂łɊ������m�F����Ă����l�̂�������80��̒j��1�l�A�D�y�s��80��̒j��1�l�̍��킹��2�l�̎��S�\���܂����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̉���21��8954�l���܂މ���45��1557�l�A�S���Ȃ����l��2136�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���S���̃R���i����22��2000�l�@4���A��20���l�����@7/30
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�30���A�S���Ŗ�22��2000�l�m�F���ꂽ�B�ߋ��ő�������28����23���l��������������̂́A4���A����20���l�����B�����s�ł�3��3466�l�̊��������ꂽ�ق��A���R���≫�ꌧ�Ȃǂʼnߋ��ő����X�V�����B
�����J���Ȃɂ��ƁA�S���̏d�ǎ҂�29�����_��403�l�ƑO������27�l�������B�����s��30���̐V�K�����҂�N��ʂɂ݂�ƁA20�Αオ6600�l�ƍł������A��N�w�𒆐S�Ɋ����g�傪�����Ă���B����7���ԕ��ς̐V�K�����҂͖�3��1687�l�őO�T��37%�������B |
���V�^�R���i �S���̊�����22���l�� 6���ʼnߋ��ő� �@7/30
30���ߌ�6��20�����݁A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂͑S����22��2308�l�ƂȂ�A4���A����20���l�����B�܂��A�S����101�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
�����s�ł́A�V����3��3466�l�̊������m�F����A11���A���őO�̏T�̓����j��������A�y�j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ����B
�܂��A���{��2��2833�l�A�_�ސ쌧��1��5031�l�̊��������������ق��A���ꌧ�A�L�����Ȃ�6�̌��ʼnߋ��ő����X�V�����B
����A�����J���Ȃɂ��ƁA29�����_�ł̑S���̏d�ǎ҂�403�l�������B400�l����̂́A4��12���ȗ��A109���Ԃ�B�@ |
 |
�������s �V�^�R���i 8�l���S 3��1541�l�����m�F ���j�ʼnߋ��ő� �@7/31
�����s����31���̊����m�F��3��1541�l�ŁA1�T�ԑO�̓��j�����3429�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�12���A���ŁA���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B����A�s�́A�������m�F���ꂽ10�Ζ����̎q�ǂ�1�l���܂ލ��킹��8�l�����S�������Ƃ\���܂����B
�����s��31���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ��3��1541�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����3429�l�����܂����B�O�̏T�̓����j��������̂�12���A���ŁA���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B31���܂ł�7���ԕ��ς�3��2177.6�l�ŁA�O�̏T��131.1���ł����B31���m�F���ꂽ3��1541�l��N��ʂɌ����20�オ�ł������A�S�̂�18.6���ɓ�����5863�l�ł����B65�Έȏ�̍���҂�3189�l�őS�̂�10.1���ł����B
�܂��A�l�H�ċz�킩ECMO���l�H�S�x���u���g���Ă���d�ǂ̊��҂́A30�����1�l������23�l�ł����B����A�s�́A�������m�F���ꂽ10�Ζ����̏��̎q1�l�ƁA70�ォ��90��̒j��7�l�̍��킹��8�l�����S�������Ƃ\���܂����B����A�s�́A6���������m�F�����Ɣ��\�����l�̂����A�Č����ʼnA�����m�F�����Ȃǂ���58�l��V�K�z���҂���폜���A�l����������܂����B |
�����{��1��6473�l�̊����m�F 6�l�����S�@7/31
���{��31���A�V����1��6473�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����A���{�́A30���ɔ��\����1�l�ɂ��āA�����Ґ������艺���܂����B���{���̊����҂̗v��137��1139�l�ƂȂ�܂����B�܂��A6�l�̎��S�����\����A���{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l�͂��킹��5348�l�ɂȂ�܂����B�d�ǎ҂́A30�����2�l�����āA49�l�ł��B |
�������� �V�^�R���i 2�l���S �V����1��1043�l�����m�F �@7/31
��������31���A�����ŐV����1��1043�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
12���A���őO�̏T�̓����j��������A���j���Ƃ��Ă͍ł������Ȃ�܂����B����́A�����s��2940�l�A�k��B�s��1985�l�A�v���Ďs��630�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����A����27����29����30���Ɋ����҂Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���킹��7�l����艺�����܂����B���������Ŋ������m�F���ꂽ�l�͉���65��3276�l�ɂȂ�܂����B�܂��A90��ȏ�̍��킹��2�l�����S�������Ƃ��m�F����A���������Ŏ��S���������҂�1360�l�ƂȂ�܂����B
|
������R���i4406�l�����@�O�T����219�l����@�a���g�p����84.7%�@7/31
���ꌧ��31���A�V����4406�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B��T�̓��j��(24��)��4625�l�ɔ�ׂ�219�l�������B�v�����҂�35��8807�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���30�����_��2294.90�l�őS���ő��B2�Ԗڂɑ�����������1625.53�l��傫�����������Ă���B�a���g�p����84.7��(���@�Ґ�647/�a����764)�ŁA�d�ǎҗp��41.9��(���@�Ґ�26/�a����62)�ƂȂ��Ă���B�ČR��n���̐V�K�����Ґ���30����66�l�A31����50�l�������B
|
���k�C�� �V�^�R���i 3�l���S �V����6065�l�����m�F �@7/31
�k�C�����ł�31���A�V����6065�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�܂��A����܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A����80��̏���1�l�ƔN��Ɛ��ʂ�����\��1�l�A���َs���N��Ɛ��ʂ�����\��1�l�̍��킹��3�l�̎��S�\���܂����B����œ����̊����҂́A�D�y�s�̉���22��2183�l���܂މ���45��7622�l�A�S���Ȃ����l��2139�l�ƂȂ��Ă��܂��B
|
���V�^�R���i �S���̊�����19���l���@���j�g�ߋ��ő��h���� �@7/31
�S���ł�31���A19���l����V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��m�F����A���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ����B
�����s�ł́A3��1,541�l�̊������m�F����A���j���Ƃ��Ă͏��߂�3���l�����B�܂��A��b�����̂���10�Ζ����̏������܂�8�l���S���Ȃ����B
���̂ق��A���{��1��6,473�l�A�_�ސ쌧��1��5,088�l�Ȃǂ̊������������A��ʌ����錧�ȂǁA4�̌��ʼnߋ��ő��ƂȂ����B
�S���ł́A���j���Ƃ��Ă͍ł�����19��7,792�l�̊��������������ق��A83�l�̎��S���m�F���ꂽ�B����A�S���̏d�ǎ҂�427�l�ŁA2���A����400�l�������Ă���B |
 �@ �@
 �@ �@
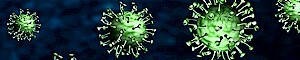 |
�����E�ő��̊����Ґ��E���{ �V�^�R���i�u���A5�ނɈ��������Ă����́H�v�@8/1
���E�ی��@��(WHO)��27���A���{�̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�7��18���`24����1�T�ԂŖ�96��9000�l�ɏ��A���E�ő��������Ɣ��\�����B �I�~�N�������̔h���^�uBA.5�v�̔����I�Ȋ����g�傪�[�������Ă���B
�܂��V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������A����ŗ×{���Ă��銳�҂̐���109��8671�l�ƂȂ�A���߂�100���l����(7��27���ߑO0�����_�E�W�v���������J���Ȃ�29���ɔ��\)�B�����I�Ȋ����g��u��7�g�v�ɂ���āA�ی����Ȃǂ̌��N�ώ@����@�������ǂ��t���Ȃ��Ȃ��Ă���B�Z���ڐG�҂��܂߁A����ɑ����̐l������őҋ@���Ă���A�Љ�@�\�̈ێ��ɂ��e�����o�Ă���B
�����������A���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�A�u��7�g�v�̎�����R���i�E�C���X�̊����ǖ@�ł̈ʒu�t���̌�������}�낤�Ƃ��Ă���B��Ì���̂Ђ�����������A�Љ�o�ϊ����̈ێ��ɂȂ���_�������邽�߂��B �S�����҂̏����W��h�S���c���h����߂̐�����₤�Ƃ����B
�����ǖ@��ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̊댯�x�ɂ��āA���j��SARS(�d�Nj}���ċz��nj�Q)�Ƃ������u2�ށv�����Ljȏ�̌��i�ȑ[�u���w2�ޑ����x������Ă��邪�A������G�ߐ��C���t���G���U���݂́w5�ށx�����Ɋɘa���ׂ����Ƃ��������オ���Ă���B
�������A�w2�ޑ����x����w5�ށx�Ɉ����������ꍇ�A�ی������Ë@�ւ̕��S�͌y������邪�A��Ô�̌���S����@�����Ȃǂ̑Ώۂ���͊O���B
���u5�ށ`�G�ߐ��C���t���G���U���݂ɁA�Ƃ͌������̂́c�v
�_�ˎs���̈��H�Ƃ̒j��(50��)�́A���̒i�K�Łw5�ށx�Ƃ��邱�Ƃɋ^��𓊂��������B
�u�m���ɍ��̃I�~�N�������́A�y�ǂŖ��Ǐ�̃P�[�X�������̂ŁA5�ނɈڍs����悤���߂�ӌ������܂�̂͂킩��܂��B�������A5�ނɂ���Ƃ������Ƃ́A2�ޑ����قǂ̍s������̎�����T�|�[�g���Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�d�lj����Ȃ��Ƃ����m���Ȃ��B����܂ŋً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�����x���o���Ă����Ȃ���A��7�g�̂܂������Ȃ̂Ɂw�s���������Ȃ��Ȃ�āA�����������v�Ȃ낤���x�Ƌ^��Ɏv���l�������Ǝv���܂����A�}��5�ނɂ��āA�V���ɑΉ��ς�邱�ƂŐ��Ԉ�ʂɌ˘f���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�S�z�A����S�ł͂Ȃ��Ȃ�̂Ȃ�A(��Ë@�ււ�)��f�����邵�A�����҂����~�܂肷�邩������܂���v�Ɗ뜜����B
���݁A�V�^�R���i�͊����ǖ@��A�댯�x���ォ��2�Ԗڂɍ����w2�ޑ����x�����̈����ƂȂ��Ă���B��f�ł���̂��w���Ë@�ւȂǂɌ����A�ی�����w���Ë@�ւɂ͑傫�ȕ��S��������B��f�҂��E�����Ă���h���M�O���h�̂Ђ��������̏ے��I�Ȍ��ۂ��B���ꂪ�w5�ށx�Ɉ�����������ƁA�G�ߐ��C���t���G���U�̂悤�Ɉ�ʂ̈�Ë@�ւł��Ή����\�ɂȂ�B
���̒j���́u�G�ߐ��C���t���G���U���݂ɁA�Ƃ͌������̂́A�uBA.5�v�̋}���Ȋ����͂Ɗ����Ґ��̑啝�ȑ������݂�A��ʂ̈�Ë@�ւ��C���t���G���U�Ɠ����悤�ɑΉ��ł���̂����O������܂��B������ɂ��Ă���Ë@�ւ̓t����]�ɂȂ炴��Ȃ��Ǝv���܂��B�}�X�N���p�̃��[����A����҂ւ̑Ή��ȂNJ�����̈ӎ����\���ɕς���Ă���A�{���Ɂhwith�R���i�h�̔F�����Z�������^�C�~���O�Łw5�ށx�Ɋi��������̂��A�������������ɍςނ̂ł́v�Ƙb�����B
���s���{���Ǝ��́uBA�E5���錾�v�A�����܂ł����͗v��
���{��29���A�V�^�R���i�̃I�~�N�������̔h���^BA�E5�ɂ�銴���}�g����A�s���{�����Ǝ��ɔ��M�ł���uBA�E5���錾�v��V�݂���Ɣ��\�����B�a���g�p����50������ȂLj�Ò̐����Ђ��������ꍇ�A���ł͂Ȃ��s���{�����n��̎���ɉ����Đ錾���o�����́B
�����҂̋}���ɂƂ��Ȃ��A��t�E�Ō�t���͂��߂Ƃ�����Ï]���҂̊����҂�Z���ڐG�҂��}�����A�ꕔ�̓S���E�o�X�Ȃnj�����ʋ@�ւł́A�^�s�ɕK�v�ȏ斱�����m�ۂł��Ȃ��Ȃ�Ȃ��A�����C���t���̕���ɂȂ��肩�˂Ȃ��B
���u����҂ɂ��ڂ��čs�������A�Ƃ����̂��c�v
���{��؎s�̉�Ј��̏���(30��)�́A�E�C���X�̎�ʼn���d�lj����̒Ⴓ�͂킩�邪�A�u���ꂾ���w��7�g�����x��w�����ҋ}���x�ȂǂƘA������Ă��A����O�o���l���邱�Ƃ��Ȃ��A�ߐe�҂Ɋ����҂��o�Ă�����ҋ@���邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���܂��B
����A�s���������Ȃ����ƂŊO�o�̍ۂ̌��߂����͂���܂��A���H�X�Ȃǂ̎��Z�c�Ƃ��Ȃ��͕̂֗��ł����A�{���ɂ���ŗǂ������̂��Ǝv���܂��B�U��Ԃ�A5���̑�^�A�x����A�ڗ����Ċ����҂������Ȃ��������ƂŁA���͋}�ȑ��łK�v���������Ă��Ȃ������̂��Ǝv���܂��B�o�ς��z�����邱�Ƃ��厖�ł����A���͈ꗥ�̑[�u�����Ȃ��ƁA��7�g�����������Ƃ��Ă��A���ɐV���ȕψي����o���������ɓ������Ƃ̌J��Ԃ��ɂȂ��Ȃ��ł��傤���B���ʓI�Ɍ��ɉ�����悤�ȋC�����܂��B
�܂h�~���d�_�[�u��ً}���Ԑ錾���̂悤�ȁA�l�̓������Ȃ��Ȃ��Ԃ܂ł͋��߂܂��A���A�������ɓ`����Ă���̂́A�w����҂̊�����ɗ��ӂ��Ăق����x�ƌ��������ŁA�d�ǎ҂⎀�S�҂�(���̂Ƃ���)���Ȃ����牽�����ł��o���Ȃ��̂͋^��ł��v�ƕs�������B���Ȃ��B�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 �@�@ �@�@
 �@ �@
 �@ �@
 �@�@ �@�@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 |
�S��
�R���i������
�R���i������
�I�~�N����������
�܂h�~���d�_�[�u
�@ |
�I�~�N�����ɂ��ẲȊw�I�E�Љ�I���
���{�S���̏��
���{�̒n�悲�Ƃւ̉e�� (�E�E�����E���E�E)
�֘A�j���[�X
���{���{�̑Ή�
���E�̒n�悲�Ƃւ̉e�� |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
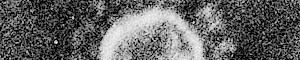 �@
�@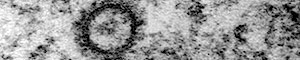 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
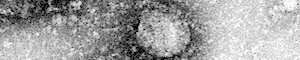




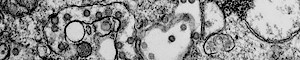 �@
�@ �@
�@

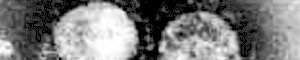

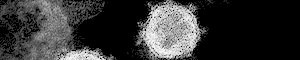
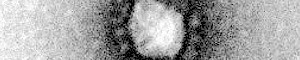




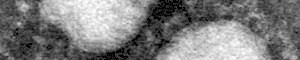
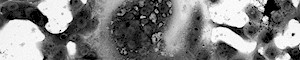 �@
�@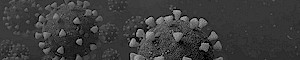

 �@
�@ �@
�@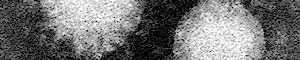
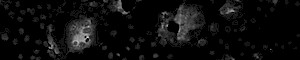
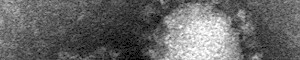
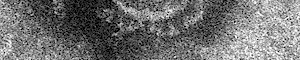


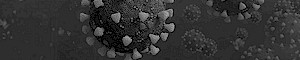
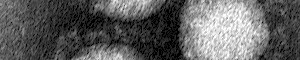


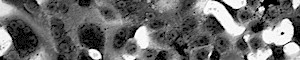 1/31
1/31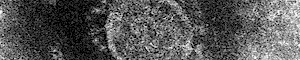 �@
�@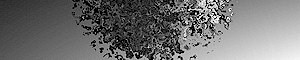 �@
�@
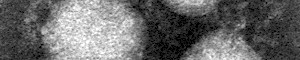

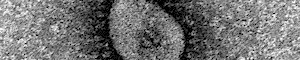
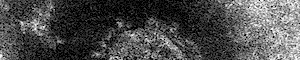

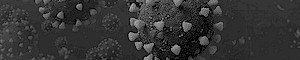
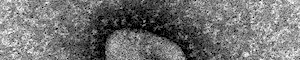

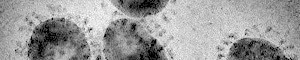
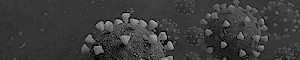 �@
�@ �@
�@


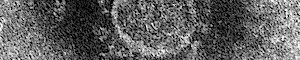

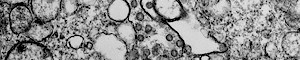

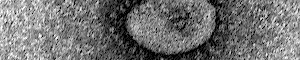


 �@
�@ �@
�@
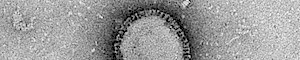

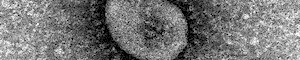
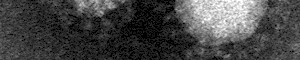
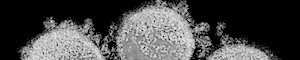


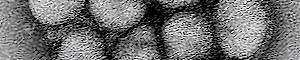 �@
�@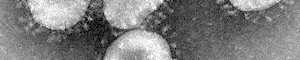






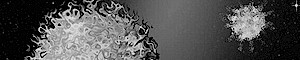


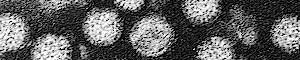
 �@
�@ �@
�@





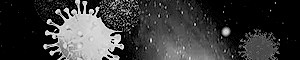
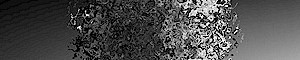

 �@
�@ �@
�@

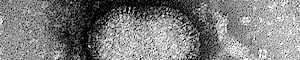








 �@
�@


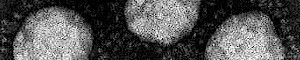


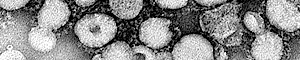



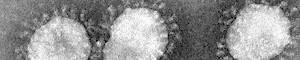
 �@
�@



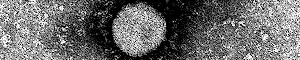
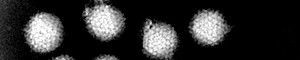


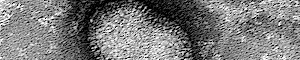

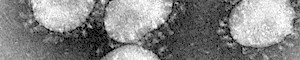 �@
�@ �@
�@





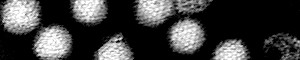



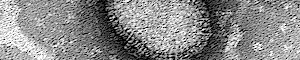 �@
�@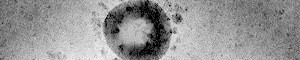 �@
�@
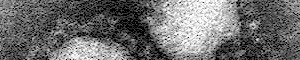
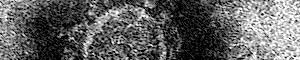





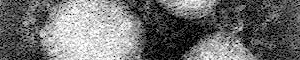

 �@
�@ �@
�@









 �@
�@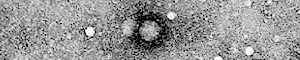 �@
�@








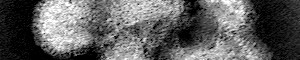
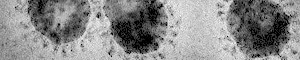
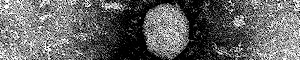 �@
�@ �@
�@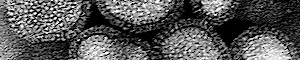

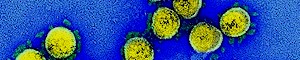

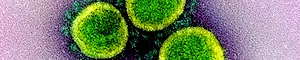



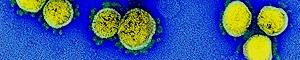

 �@
�@ �@
�@
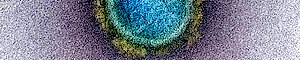



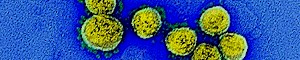




 �@
�@ �@
�@








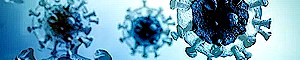
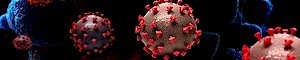 �@
�@ �@
�@




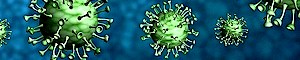
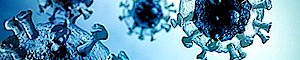



 �@
�@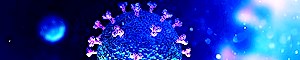 �@
�@









 �@
�@ �@
�@










 �@
�@ �@
�@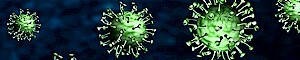
 �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
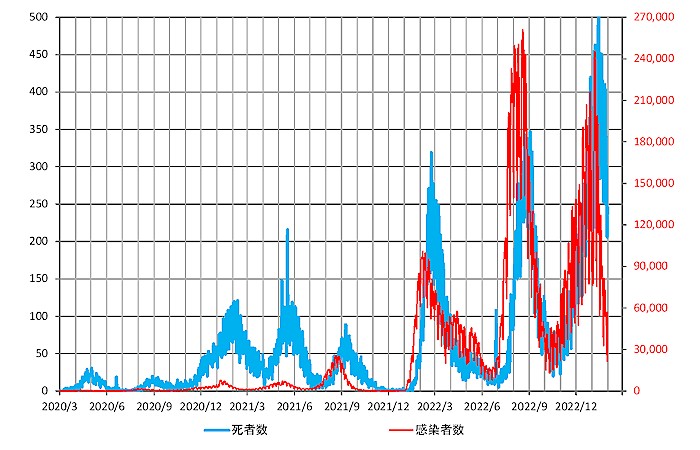
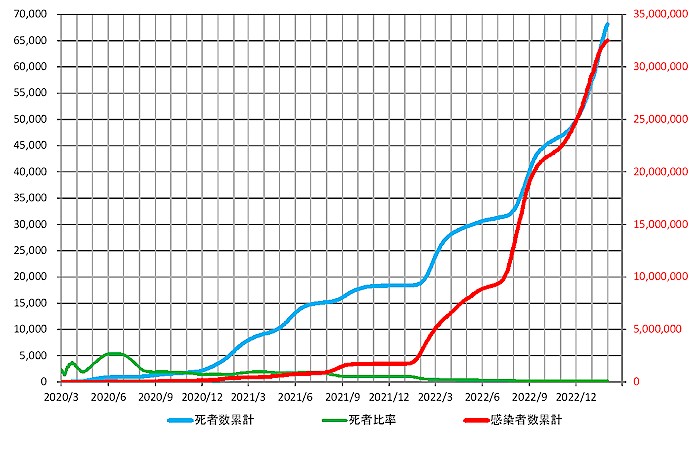

 �@
�@





 �@
�@ �@
�@