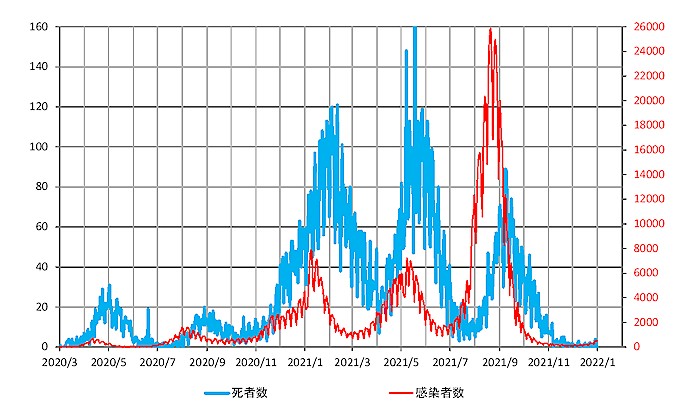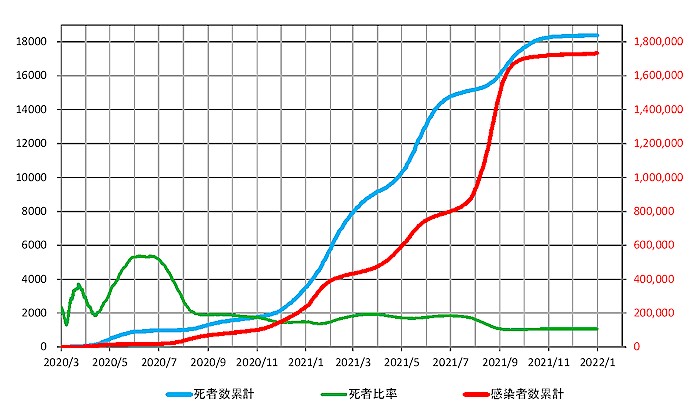�����ꌧ�̐��Ɓu�܂h�~�Ɉڍs���ׂ��v�@�ً}����11���̏I���O�ɒ@7/6
���ꌧ�̐V�^�R���i�E�C���X���Ɖ�c��5���A�����ŊJ����A�ً}���Ԑ錾��\��ʂ�11���ŏI�����A�����n��ʂɐ������e�f�ł���u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ɉڍs����ׂ��Ƃ̈ӌ��ň�v�����B�����ɁA�����Ґ���1�T�Ԃ�1��������̕��ς�80�l����ً}���Ԑ錾�߂���ׂ��Ƃ̍l�����܂Ƃ߂��B
���Ɖ�c�̒�Ă��A�ʏ�f�j�[�m�����o�ϊE�Ȃǂ���ӌ����������Ő錾�̏I���Əd�_�[�u�̓K�p�����ɗv�����邩�f����B
���c���Y����(������w��w�@����)�͉�c��̉�Łu�����ł͊���������A�����̂ɂ���ă��N�`���ڎ�ɍ�������v�Əq�ׁA�n��̏ɍ��킹���K�����e�����߂���d�_�[�u�̕K�v������������B
��c�ł͌��O����̐��ۑd�v�Ƃ̈ӌ������������Ɛ����B���c�����͐��Ɖ�c�̈ӌ��Ƃ��Ēm���ɑ�(1)�錾��d�_�[�u���o�Ă���n�悩��̕s�v�s�}�̗����������(2)��������ꍇ�ɂ͎��O�o�b�q��������(3)���N�`����ڎ킵�Ă���ꍇ�͂�����x�̍s�������Ă悢�|��3�_�����b�Z�[�W�Ƃ��Ĕ��M����悤���߂��B
5���̐V�K�����҂�28�l�B����1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ��͑S���ő��������Ă������A28�E10�l�őS����2�ԖڂƂȂ����B�ő��͓����s��29�E16�l�ŁA�S�����ς�8�E77�l�B
�s�����ʂł͓ߔe�s��16�l�ōő��������B�����o�H�͉ƒ����6�l�ōł������E����A�F�l�E�m�l�A���̑������ꂼ��1�l�������B
�ČR�W�̊�����4���̔��\��4�l�A5���̔��\��2�l�Ōv6�l�B���v1461�l�ƂȂ����B
�����Z����4�X�ɓs���ߗ�25���~�@�ٔ�������͑S�����@7/6
�����s��6���A�ً}���Ԑ錾���ŁA�������ʑ[�u�@45���Ɋ�Â��c�Ǝ��ԒZ�k���߂ɉ����Ȃ��������H�X4�X�܂ɑ��āA�ٔ��������ꂼ��ɉߗ�25���~�����肵���Ɣ��\�����B�s�͌��肪�m�F�ł����̂͑S�����Ƃ��Ă���B
4�X�܂�1�`3���ً̋}���Ԑ錾���ߒ��Ɍߌ�8���܂ł̎��Z���߂����ہB�s��3��29���A�ߗ����Ȃ����߂̎葱�����ٔ����ɒʒm�����B����͔���J�̂��߁A�ٔ����ɕ�����t��\�����m�F�����Ƃ����B
�ٔ����̌��藝�R�ɂ́u�ԗl����x�A���߈ᔽ�ɂ��e���Ȃǂ̎���𑍍��I�ɔ��f�v�Ƃ̋L�ڂ��������B�s�́A�X�܂̓���ɂȂ���Ƃ��ĊNJ��̍ٔ����𖾂炩�ɂ��Ă��Ȃ��B
������O���^�A5��20.7%���@�O�N�ً̋}���Ԑ錾�̔����@7/6
�����J���Ȃ�6�����\���������ΘJ���v����(����A�]�ƈ�5�l�ȏ�)�ɂ��ƁA5����1�l������̌������^���z�͑O�N������1.9%����27��3777�~�������B�O�N����������̂�3�J���A���B���̂����c�Ƒ�ȂǏ���O���^��1��7486�~�Ɠ�20.7%���������B�������͔�r�\��2013�N1���ȍ~�ōő傾�����B
20�N5���͐V�^�R���i�E�C���X�̏��ً̋}���Ԑ錾�����߂���Ă��鎞���ŁA���̔������傫���o���B����O���^�̑��������Y�ƕʂɂ݂�Ɓu�����֘A�T�[�r�X�ƁA��y�Ɓv��51.9%�ōő傾�����B�u����A�w�K�x���Ɓv(39.0%)�A�u�����Ɓv(37.8%)�A�u�s���Y�E���i���Ɓv(37.3%)�Ƒ������B
��{����������������^��24��5086�~��0.8%���A�{�[�i�X�ȂǓ��ʂɎx����ꂽ���^��1��1205�~��1.0%���������B�J�����Ԃ̉����^�̎��������ɂȂ����Ă���B
�����V�^�R���i�O��19�N5���Ɣ�r����ƌ������^���z�Ȃǂ̓}�C�i�X�ŁA���J�Ȃ͊����g��O�̒��������ɂ͖߂肫���Ă��Ȃ��Ƃ݂Ă���B�@�E�E�E
���ً}���Ԑ錾���̉���Ɍܗ֎��O���h�ŏ��̊C�O�I��c �@7/6
�����I�����s�b�N�Ɍ����ĉ���s�Ŏ��O���h���s���t�����X�̃o���[�{�[���̑�\�`�[�������ꌧ�ɓ���܂����B�S���ŗB��ً}���Ԑ錾���o�Ă��鉫�ꌧ�ɁA���O���h�̂��߂ɊC�O����I��c���K���̂͏��߂Ăł��B
�t�����X�̃o���[�{�[���j�q�̑�\�`�[��21�l�́A6���ߑO11������ߔe��`�ɓ������܂����B�I��Ȃǂ͓����̍ہA�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��Č������āA�S���A�A�����m�F����Ă��܂��B�I��Ȃǂ͊����h�~��ŁA�ق��̏�q�ƕ�����ē������r�[�Ɏp�������܂����B���̂��ƑI��Ȃǂ͏\���ȊԊu�����Ȃ���A���O���h���s������s���̏h���{�݂ɓ���܂����B
�S���ŗB��ً}���Ԑ錾���o�Ă��鉫�ꌧ�ɁA���O���h�̂��߂ɊC�O����I��Ȃǂ��K���͍̂����߂Ăł��B�`�[���͍���19���܂ō��h���s���A�I�肽���͌����A�������������߂���ق��A�h���{�݂Ɨ��K���̍s�����̂ق��͊O�o���F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
����A�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŁA����s�́A�����\�肵�Ă����q�ǂ������Ƃ̌𗬃C�x���g�����ׂăI�����C���ɐ�ւ��Ď��{���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B���ɂ��܂��ƁA�����ł͓����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̎��O���h��5�̎s�����ōs���A5��������100�l�ȏオ�K���\��ɂȂ��Ă��܂��B
�h����̃z�e���͊������O�ꂵ�Ă��܂��B���Ȃǂ���߂��K�C�h���C���Ɋ�Â��A�I��Ȃǂ́A��ʋq�ƐڐG���Ȃ��悤��������o���肵�A�Ɩ��p�̃G���x�[�^�[���g�p���܂��B�q����1�̃t���A���\�`�[���̐�p�ɂ��A�H�������݂���ɂ��܂��B�I��Ȃǂ̓z�e�����ŁA�����̕����̂���t���A�ƐH����ꂵ���s�����ł��Ȃ��ȂǍs������������������Ă��܂��B
�H���̒ȂǑI��Ȃǂƒ��ڐڐG����X�^�b�t40�l�͖����A�ԐړI�ɐڐG����X�^�b�t��3����1��A�������A�A���ł��邱�Ƃ��m�F���܂��B
�z�e���͊����h�~���O�ꂷ�����ŁA�H�����ɑ싅���e�[�u���Q�[����p�ӂ���ȂǁA�O�o���ł��Ȃ��I��Ȃǂ������ł����K�ɑ؍݂ł���悤�H�v���Â炵�Ă��܂��B
�t�����X�̑I��Ȃǂ������I�L�i���O�������[�����]�[�g�̗ѕS�� ���x�z�l��s�́u�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŏC�w���s���L�����Z���ɂȂ�ȂǁA����グ���傫����������ł��܂��B�������������Ă���̂ŁA�t�����X�̑�\�`�[�����؍݂��Ă����̂͑�ς��肪�����ł��B�����A�t�����X�̊F����͊O�ɏo���Ȃ��̂ŁA�����ł�����Ŏv���o������Ă��炦��悤�A�y�������͋C�ł��}���ł�����Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
���Z�ʂ̗����Ȃ��u�V�t�g���v�@�R���i�Ђŕ��ƒT���ɋ�J �@7/6
��������R���r�j�̓X���ȂNjΖ�����(�V�t�g)�������Ԃ��Ƃɕϓ�����u�V�t�g���J���ҁv���A���ƒT���ŋ�킵�Ă���B�R���i�Ђŋx�Ƃ����o����Ȃǂ��ăV�t�g�̒��������G���A�J���҂ɓ`�����鎞�����x��A�V���Ȏd���̃X�P�W���[���ƍ��킹�ɂ������߂��B�x�ƕ⏞���o����������Ɋׂ�V�t�g���́u���v�͎Љ��艻�������A�����ێ��̂��߂̕��Ƃ�������Ƃ����ۑ�������яオ���Ă���B(�R�c�W�j)
�u�V�t�g�̗Z�ʂ������A���o�C�g�͂��܂�Ȃ��A�T���̂���ρv
�����f�B�Y�j�[���]�[�g�̃V���[�ɏo������_��Ј��̏����́A�d���������������A���ƒT���̓����Ɋ����Ă���B�{�Ƃ̃V�t�g��1�T�ԕ��������݂Ɍ��܂�A������̂͑�����2�T�ԑO�B���������ƒT���ő�����ɁA�{�Ƃ̃V�t�g����̃X�P�W���[����`����Ɓu�����Ƒ������߂Ă��炦�Ȃ��ƁA������̃V�t�g���g�߂Ȃ��v�ƒf���邱�Ƃ������B
���̎d���͏T5���̋Ζ������R���i�ЂŏT2�`3���Ɍ������B��Ђ���̋x�ƕ⏞�ł͎�������₦���A�V�t�g���o����ł��T����1������̔h���̎d���ŐH���Ȃ��B�u��������Ɏd��������Ƃ͌��炸�s����v�ƌ�����B
�]�ƈ��̈ꕔ����������J���g���Ȃ̂͂ȃ��j�I���͍��t���ŁA���Ƃ��₷���������̂��߃V�t�g�̉^�p���P��v���B�^�c��Ђ̃I���G���^�������h(��t���Y���s)�͎�ނɁu�����₷�����̐�����i�߂Ă���A�]�ƈ��̗v�]�܂��č�������P���Ă����v(�L��)�Ɠ������B
�V�t�g���J���҂��������H�ƊE�́A�x�Ƃ⎞�Z�����o���ăV�t�g���������G���������ƂȂǂ��猈�肪�x��邱�Ƃ������A�J�g�ɂ̓V�t�g�`�B�𑁂߂�v�]���������B�c�̌����Ă�����H�X���j�I���̔��ѓN��́u�c���Ȃ�Ή�Ђ̉^�p��ς�����v�Ƙb���B
�����J���Ȃɂ��ƁA�ݐE���Ȃ���ʂ̃A���o�C�g�Ȃǂ�T�������͑S���ł݂��A�S���҂́u�V�t�g����x�ƒ������Ŏ���������A���̕�U�̂��߁v�Ɛ����B�S���J���g�����A���̒���q�K�Z���^�[�����ǒ����u�o�C�g��̑��D�킪�N���Ă���v�Ƙb���B���ɍ���҂͕��Ƃ�������Ȃ����Ԃ��N���Ă���B
�V�t�g���J���ɏڂ�������q��ٌ�m�́u�K�̃V�t�g���J���҂͂��Ƃ��Ƃ̎����������A���Ƃɒǂ����܂��\�}�B���Ƃ����ɍςޕ⏞�̏[�����K�v�v�Ǝw�E����B
���R���i�Ђ���̉Łu�댯�Ș����v�������h�l�e�ꖱ�����@7/6
���ےʉ݊��(�h�l�e)�̃Q�I���M�G�o�ꖱ������5���A�V�^�R���i�E�C���X�̃p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)����̉ߒ��ŁA�x�T���Ɣ��W�r�㍑�Ƃ̊ԂɁu�댯�Ș����v�������Ă���ƌx�������B
�p�����a�t�H�[�����ŁA�č��ȂǕx�T���̗͋��������́u�ǂ��j���[�X�v�����A�r�㍑�ł͒ᐅ���̃��N�`���ڎ헦���j�Q�v���ɂȂ��Ă���Ǝw�E�B�u����͐����̓��ꐫ�ɉ����A���E�̈��萫����ш��S���Ɋ�@�������炵�Ă���v�Əq�ׂ��B
���t�H�[�����ɎQ���������E�f�Ջ@��(�v�s�n)�̃I�R���W���C�E�F�A�������ǒ������l�̌��O��\���B���e���A�����J�A�����A�A�t���J�Ȃǃ��N�`���ڎ헦���Ⴂ�n��ł͐��������ɒᒲ�ɂȂ�u�j���^�̉v�ɂ��Čx����炵���B
���R���i�ЂŐl�C�̃n���o�[�K�[�X�ɂ��Ă̈ӎ������@7/6
�R���i�Ђł��D���ȃn���o�[�K�[�X�ɂ��Ă̈ӎ�����(�L����1,000��)��2021�N6��16���`6��21���Ɏ��{���܂����B
�R���i�Ђł����n���o�[�K�[�`�F�[���͍D���A�V�K�n���o�[�K�[�ƑԂ̏o�X���������ł��܂��B���̂悤�ȏ��̂��ƁA����҂̓n���o�[�K�[�X�i�ǂ̂悤�ɂ��g���ɂȂ��Ă���̂��A�ӎ����������{���܂����B���̌��ʁA�����̂��璆���H�܂ŁA������t�@�[�X�g�t�[�h�̒���70���̕����n���o�[�K�[�X���u�ł����p����v�Ɖ��Ă��܂��B���̗��R�Ƃ��āA�u�����Ĕ��������v�A�u��y������v�A�u�����ł�����₷������v�Ɨ����̍����őI�ԕ��������A�R���i�ȑO�Ɣ�ׂăn���o�[�K�[�X�̗��p����27���������Ă��܂��B�R���i�O�̓C�[�g�C�����嗬�ł������R���i�Ђł̓e�C�N�A�E�g���p�������A��Ɉ�l�ł̗��p��41���A�Ƒ��Ƃ̗��p��54���Ƃ������ʂƂȂ�܂����B���p���Ԃ�74%�ƃ����`�т��������̂́A�[�H���n���o�[�K�[�ł���R�Ȃ�70%�ƁA���p���Ԃ̕����L�����Ă��܂��B���łɍ����H�ƂȂ����n���o�[�K�[�ł����A���̐����͂܂��܂����������ł��B
��������
��1�F�ł��悭���p����t�@�[�X�g�t�[�h�͈��|�I�Ƀn���o�[�K�[��1�ʂ�70��
��2�F�R���i�ЂŃn���o�[�K�[�X�̗��p��������27%
�n���o�[�K�[�X��20���Ј�����ł��x���Ă��܂����B20��̊w���ɂȂ�Ƙ����̗̂��p�����㏸���܂��B�e�C�N�A�E�g���p�ƉƑ����p�̑������炩�A�R���i�O��̔�r�ł͊����҂̕����R���i�Ђŗ��p���������Ɖ��Ă��܂��B���ׂĂ̐ݖ�ŔN��A���ʁA�E�ƁA�����E�����ŏW�v���Ă��܂��B���A��������������A���ׂĂ̒������ʂ������肢�����܂��B
��3�F�[�H�̃n���o�[�K�[�ɒ�R�Ȃ�70%
�S�̂�70%�͗[�тɃn���o�[�K�[����R�Ȃ��A�ǂ��炩�Ƃ����ƒ�R�Ȃ��Ƒ����Ă��܂����A�����҂ł��q�l������������ƒ�ł́u�h�{�̃o�����X���C�ɂȂ�v�Ƃ��������R����T���������������Ⴂ�܂����B�����������҂ł�66���̕��͒�R�Ȃ��Ɖ��Ă��܂��B
��4�F�R���i�O�̓C�[�g�C�����嗬���A�R���i��̓e�C�N�A�E�g���p������74%
��5�F���o�C���I�[�_�[(���O����)�ɐZ���̒����A30��40��ɍL����
����̒������ʂł́A�R���i�O�ƃR���i�ЂŔ�r����ƁA�n���o�[�K�[�X�̗��p���Ԃ��傫���ω��������Ƃ��킩��܂����B�e�C�N�A�E�g���p�̓R���i�O��44���ł������R���i�Ђł�74���Ƒ傫���������A�f���o���[�̗��p�͔����ɂƂǂ܂�܂������A���O���ς��S�̂�9%���̕��ɗ��p�o��������A����30���40��ōL���肪�����܂��B�{�����ł͂���ȊO�ɁA��l������̍w�����z�⋖�e�ł�����ԁA�D���ȃp�e�B�̎�ނ�o���Y�̎�ށA�D���ȃT�C�h���j���[��ꏏ�ɒ�����������ȂǑS33��ʼnāA�N��ʁA���ʁA�E�ƕʁA�����E�����ʂɏW�v���Ă��܂��B
���R���i�Ђ����E�̊ό��Ƃɗ^���鑹���u2�N�Ԃ�4���h���v�@7/6
�V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̃p���f�~�b�N�ɔ����A�C�O���s�ƊE���������Ƃɂ�鐢�E�o�ςւ̑��Q�́A2020�N��2021�N�����킹���4���h���ɏ��\�������邱�Ƃ��A���A�̐V�������Ŗ��炩�ɂȂ����B
����قǂ̑����z�����肳�ꂽ�̂́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��ό��ƊE�ɒ��ڂ����炵���e���ɉ����A�ό��ƊE�Ɩ��ڂȂȂ���������̕���ւ̔g�y���ʂ����݂��邩�炾�B�����܂������ό��q���}���������ƂŁA2020�N��2��4000���h���̑������������B2021�N�����K�͂̑������o��\��������A�ƍ��A���͌x�����Ă���B�̓x�����́A���E�S�̂Ń��N�`���ڎ킪�ǂ̂��炢�i�ނ��ɂ���đ傫�����E�����Ƃ����B
���̎w�E�ɂ��ƁA���݂͐�i���̑唼�Ŋό��ƊE�̑������������Ă������ŁA�����̔��W�r�㍑�ŏ��������Ă���B���̌����̓��N�`���i�����B�t�����X��h�C�c�A�X�C�X�A�p���A�č��ȂǁA���N�`���ڎ헦���������X�ł́A�ό��ƊE����r�I��������ƌ����܂�Ă���B�������A�C�O���s���p���f�~�b�N�O�̐����ɖ߂�̂́A�����Ă�2023�N�Ƃ����̂����Ƃ̌������B
���ɂ��2021�N�̐��葹���z�́A�ό��q�̂��܂��܂Ȍ����p�^�[���ƁA���N�`���ڎ헦��O���ɒu����3�̃V�i���I���x�[�X�ɒe���o���ꂽ�B2021�N�̊ό��q��75%���Ƒz�肵���ł��������V�i���I�ł́A���E�̑����z��2��4000���h���ɂȂ�B���̃V�i���I�������ƂȂ����ꍇ�ɉ�œI�ȑŌ������˂Ȃ��̂��A�ό��ƂɈˑ����鑽���̍��X���B���Ƃ��g���R�́A�ό��Ƃ�GDP(���������Y)��5%���߂Ă���B
���̗\���ɂ��A�ň��̃V�i���I�������ƂȂ����ꍇ�A�g���R�̊ό��Ƃ́A���v��330���h���������ތv�Z���B���H�ƁA�����ƁA�ʐM�ƁA�^�A�ƂƂ������֘A����̑����������AGDP�����z��930���h���ƁA����3�{�ɂȂ�B�ό��q�̌����ŁA����GDP�͂��悻9%���ƂȂ邪�A���ۂɂ͌o�ώh����ɂ���āA���̈ꕔ�͑��E�����ƕ��͏q�ׂĂ���B
�ό��ƂɈˑ����鑼���ɖڂ������Ă݂�ƁA�G�N�A�h�����A�ň��̃V�i���I�����������ꍇ�ɍł��傫�ȑŌ����錩���݂ŁAGDP��9%��������B�܂��A��A�t���J��GDP����8%���ɂȂ�ƌ����Ă���B
���ł��y�ϓI�ȃV�i���I�ł�7������1���̊�������1000�l����@7/6
2021�N6��30���ɊJ�Â��ꂽ��41��V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�ł́A�����s�̊����ƍ���̌��ʂ����c�_�̒��S�ł����B
�}1�́A���s��w��w�@�����̐��Y���搶��̌����f�[�^�ł��B�����s�̕��ʊ����Ґ��̐��ڂɊ�Â��Z���\��(���T��T��1.1�A1.2�A1.3 ���p�������ꍇ)�����������̂ł����A1.1�{�̏ꍇ�ł�7�����ɂ�1���̊����Ґ���1000�l�ɒB���Ă��܂��B������1.2�{�قǂŐ��ڂ��Ă��܂����A���̏ꍇ�ł�7������1��1500�l��������\�z����Ă��܂��B�ň���1.3�{�̏ꍇ�́A��������������悤��7�����ɂ�1��2000�l��D�ɒ����銴���Ґ����o�邱�Ƃ������܂�Ă��܂��B
�܂��A���Y�搶��͓����s�̕a�����A���^�C���v���W�F�N�V�����̌��ʂ��o���Ă��܂��B����́A���s�̎��Ԕ��W�ɂ��āA���Ɋm�ەa���E�d�Ǖa���Ɨ��s�̊W�̌����݂ɂ��ă��A���^�C���Ŕc�����邱�Ƃ�ړI�Ɍ������ꂽ���̂ł��B�����ł̓��A���^�C���v���W�F�N�V�����̌��ʂ������܂����A�ȉ���4�_�ɂȂ�܂��B
1�D���s�̊g�呬�x�͐ڐG���̑���Ɉˑ�����
2�D������0�`39���������A���@��40�`59���ő��ɂȂ�
3�D�d�NJ��Ґ��Ō��Ă�4�N��Q�̒���40�`59�Αオ�ő��ƂȂ錩����
4�D���݂̑��x�Ŋg�傪�����ƁA7���㔼�܂łɏd�NJ��ҕa�������m�ەa���̕�����ɂЂ�������\��������
�u1�v�́A�l���̑����Ɗ����Ґ��̑����̊W���猩���Ă�����̂ł��B�����s�͌��݁A�ɉ؊X�ł̐l���������𑱂��Ă���A���ɖ�̎��ԑт������ł��邱�Ƃ��l����ƍ���A�����Ґ��̑����X�s�[�h���������郊�X�N������܂��B
�u2�v�͔N��ʂɌ�������̌��ʂ��ŁA�����Ґ���40�Ζ����̎Ⴂ�l�ɑ�������A���@��40�Αォ��59���ő��ɂȂ�Ɨ\�z����Ă��܂��B�u3�v���֘A���Ă��܂����A�d�ǎ҂����̔N�オ�ő��ƌ����܂�Ă��܂��B�����s�k��ی����̑O�c�G�Y�搶����o���ꂽ�����ł��铌���s�̔N��ʂɌ��������Ґ��̐��ڂ�����ƁA���߂ł�10�Α�̊����������Ă��Ă��܂�(�}2)�B���w�Z�⍂�Z�ł̃N���X�^�[���������Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���܂����A10�Α�ɑ�������}����܂��B
�u4�v�͈�Î҂ɂƂ��Ă͂ƂĂ����O�����\���ƂȂ�܂��B�u�d�NJ��ҕa�������m�ەa���̕�����ɂЂ�������v�Ƃ́A�y�ǂ⒆���ǂ̊��҂��}�����āA���̎���{�݂̗e�ʂ��Ă��܂��댯������Ƃ������Ƃł��B�s���̊m�ەa������6000���Ƃ������Ă��܂����A���ۂ�3000������ƌ��ꂪ�Ђ�������ƌ����Ă��܂��B����3000�����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�l���̑�����}���Ă������Ƃ��}���ƌ����܂��B
�C���h�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�ψكE�C���X�ł���f���^���̉e�������O����Ă��܂��B�}3�́A���������nj������̗�؊�搶����o���ꂽ�����ł����A L452R�ψكE�C���X�ɂ�銴���E�`�d���̑��������������̂ł��B�����̂悤�ɁA�����̂��₷���́A�A���t�@���̎����Đ��Y��1�Ƃ���Ɗ֓���56.1���������Ă��܂��B����38.2���̑����ł��B
�f���^���̍ő�̋��Ђ́A���̊����E�`�����̑����ɂ���܂��B�p���ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�A���t�@���̎��������E�`�����̑��������Ђł������A�f���^���͂���������Ă��邱�Ƃɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
�������s��593�l���V�^�R���i�����@7��6�����\�A�T����600�l��ɏ㏸�@7/6
�����s��7��6���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�593�l���ꂽ�Ɣ��\�����B1�T�ԑO�Ɣ�ׂ��117�l�������Ă���A�O�̏T�̓����j��������̂�17���A���B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���600�l��ɏ㏸����602�E3�l�ŁA�O�T���121�E7���B70��j��1�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
�s��6��30���ȍ~�A���{�̑����ȉ�����X�e�[�W4(�����I�����g��)�̐����������Ă���B�s�̒S���҂́u�}���܂ł͂����Ȃ����A�����͊m���ɍL�܂��Ă���B�s�������̃��X�N�͍��܂��Ă���v�Ƃ̔F�����������B
�V�K�����҂̂����A65�Έȏ�̍���҂�24�l�B�����o�H���s���Ȃ̂�388�l�������B���@���҂͑O������3�l����1677�l�A�����d�ǎ҂�6�l������63�l�B�v�͎��҂�2241�l�A�����҂�17��7436�l�B
���䌧��7��8���܂œƎ��́u���䌧�ً}���Ԑ錾�v�߁B���ً̋}���Ԑ錾�Ώےn��Ƃ܂h�~���d�_�[�u�Ώےn��Ƃ̉����͍T����悤���߁A���̑��̒n��͐T�d�ɔ��f����悤�Ăъ|���Ă���B�S���ً̋}���Ԑ錾�A�܂h�~�[�u�̑Ώےn��͈ȉ��̒ʂ�B
�y�ً}���Ԑ錾�z���ꌧ(7��11���܂�)
�y�܂h�~���d�_�[�u�z�k�C���A��ʌ��A�����s�A��t���A�_�ސ쌧�A���m���A���s�{�A���{�A���Ɍ��A������(7��11���܂�)
���܂h�~�A��������l���̍�ʌ��m���@�a���g�p�����㏸�@7/6
��ʌ���5���A�V�^�R���i�E�C���X�̐��Ɖ�c���J���A�������܁A������s��[�u���Ƃ��A11���Ɋ������}����܂h�~���d�_�[�u�ɂ��ċ��c�����B��쌳�T�m���́u����ʼn����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����R���Z���T�X(����)���v�Ƃ��A�f���^���̑����Ⓦ���R���̊����g��܂��A12���ȍ~���[�u���p������K�v������Ƃ̍l�����������B
�����ł�6��13������19����1�T�Ԃ̐V�K�����҂̍��v��484�l(1��������69�E1�l)���������A6��20������26���̏T��641�l(��91�E6�l)�A6��27������7��3���̏T��721�l(��103�l)�ƑQ���X���ɂ���B�܂��A7��4�����_�̊m�ەa���g�p����19�E6��(326�l�^1666��)�A�����d�ǂ�12�E8��(21�l�^164��)�B���̎w�W�ł܂h�~���d�_�[�u���o���ڈ��̃X�e�[�W3(�����}��)������������Ă��邪�A6�����{�ȍ~�A�V�K�����҂̑����ɔ����ĕa���g�p���͏㏸�ɓ]���Ă���B
�m���͌����̊��������ɂ��āA���암�̗z���҂̑����̊������������R���ŁA�ƒ�������Ɠ����܂ő����Ă���Ǝw�E�B�܂��A�f���^��(�C���h��)�Ȃǖ��m�̗v�f�̌��O�ɂ��Ă��G��u�[�u���̌p�����A�L���邩�͂��Ɛ����ԁA�����܂��傤�Ƃ����ӌ����������v�Ƃ��A�߂����Ɖ�c���ēx�J���A�͂������Ƃ����B
��c�ɏo�Ȃ������䒉�j��́u�����ɐڂ��Ă���킪���́A����Ƃ��܂h�~���d�_�[�u���p������K�v��������B�����s���ǂ������[�u�����̂�������͔̂��ɏd�v�v�Əq�ׂ��B�@
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�����ꌧ �ً}���Ԑ錾����u�d�_�[�u�v�ւ̈ڍs�𐭕{�ɗv�� �@7/7
���ꌧ�́A����11���Ɋ������}����ً}���Ԑ錾�ɂ��āA�n��ɂ���Ċ������قȂ��Ă��Ă���Ƃ��āA
�S���ŗB��A���ꌧ�ɏo����Ă���ً}���Ԑ錾�́A4����̍���11���Ɋ������}���܂��B
���ꌧ��7���ߌ�A���{����c���J���A�V�K�����Ґ��ɍ��~�܂�̌X�����݂�����̂̒n��ɂ���Ċ������قȂ��Ă��Ă���Ƃ��āA���{�ɑ��āA�n����i���ďd�_�I�ɑ���s���u�܂h�~���d�_�[�u�v�ւ̈ڍs��v�����邱�Ƃ����߁A�v�����܂����B
�d�_�[�u�ւ̈ڍs�ɂ������ẮA�V�K�����Ґ���N�`���̐ڎ헦�܂��đΏےn����w�肵�������ŁA�O�o���l�̗v������H�X�ɑ���c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���͌p����������ł��B
����A���̒ɂ��ẮA����25���܂Ŏ��l���p�����������ŁA26���ȍ~�͔F�����X�܂̂ݖ�7���܂ł̒�F�߂�ĂƁA4�A�x���܂ލ���21�������5���ԂɊ��Ԃ��i���Ē̎��l�����߂�Ă���������Ă��܂��B
�ʏ�m���́A�L�Ғc�ɑ��u����܂Ŋ撣���Ă���ꂽ�����̊F�l�̐S����l������ƁA�����X���������Ă��邱�̎����ɂ�������ً}���Ԑ錾���������A�d�_�[�u�Ɉڍs�������B�����߂̑Ώ����j���p�����ׂ��ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���u�ً}���Ԑ錾�v������ő��@�V�^�R���i�E�C���X�@�k�C��67�l�����@7/7
�k�C�����ł�7���A�V����67�l�̊������m�F����܂����B50�l����ً̂͋}���Ԑ錾�����㏉�߂Ăł��B�D�y�s�͐挎26���ȗ���30�l��ł��B�����o�H�s����21�l�ł��B���Z�v�����o�Ă��鈮��s5�l�A�Ύ�Ǔ�4�l�ł��B���̂ق��A���َs��I�z�[�c�N�Ǔ���9�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V���ȃN���X�^�[���m�F����Ă��܂��B����s�̉�Ђ�6�l�A���َs�̊w������13�l�B
����1�T�Ԃ�10���l������̊����Ґ��́A�D�y��7�D8�l�A�S����5�D0�l�A�������������̎w�W�́u�X�e�[�W3�v��15�l��傫��������Ă��܂��B
�a���g�p����6�����_�ŎD�y��17�D2���Ɓu�X�e�[�W3�v��20���������܂����B�S���ł�15�D9���ƂȂ��Ă��܂��B
������7���̊����Ґ���67�l�ŋً}���Ԑ錾�ŏI����6��20���ȗ���50�l�����ƂȂ�܂����B
���ً}���Ԑ錾�������g����ʌx��ɐ�ւ��@����@7/7
���{�m����7���A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊւ���Վ��̋L�҉���J���A�����̐V�K�����҂��������Ă��邱�ƂȂǂ���A���Ǝ��ً̋}���Ԑ錾��9�������i�K���̊����g����ʌx��ɐ�ւ���Ɣ��\�����B���ʌx��̊��Ԃ�7��22���܂ł�2�T�ԁB
�m���͉�Œ���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͌��������̂́A�a���̐�L���͈ˑR�Ƃ��ē��ʌx�x���Ō������ɂ���Ƃ��āA����������b���H�̍ۂ̓}�X�N���p��O�ꂷ�邱�Ƃ�E����ł̊���������߂ēO�ꂷ��悤�Ăъ|�����B
�܂�6��21�����瑱������s�����n��̊��������ʒn��̎w����������A����͓��n��̈��H�X�Ȃǂ̎��Ǝ҂��x������N�[�|�����s����ȂǁA�o�ωɌ��������ƂɎ��g�ޕ��j���������B�K�v�ȍ����ɂ��Ă͌���6����\�Z�Ăɐ��荞�ނƂ��Ă���B
���g���m���@�R���i�Ђ̏����x�������݂���@7/7
�g���m�����{�m����7���A�{���Œ���ɂ̂��݁A�R���i�Ђ̏����x���̂��߂ɁA���O�\��s�v�̑��k������݂��邱�Ƃ𖾂������B14������X�^�[�g����Ƃ��Ă���B
�g���m���̓R���i�Ђɂ����āA�u�����͌ٗp�E�����̖ʂŒj����茸���Ă���v�Ƃ��A�u�������������A�Ȃ��Ȃ����v�Ƃ���������31���A�j����25���Ƃ̒������ʂ��������B
�g���m���͑��{���j�������Q��E���N�Z���^�[(�h�[���Z���^�[)�ɑ��k������݂��邱�Ƃ��q�ׁA�u���O�\��͕s�v�ł��B1�l�ŔY�܂��ɁA�ӂ���Ƃ��C�y�ɗ�������Ăق����B�J�E���Z���[���풓���Ă���B1�l�ŔY�܂��ǂ�ǂk�ɗ��Ăق����B�R���i�Ђ̑��k�ǂ�Ȃ��Ƃł��t����B�Y��ł���̂͂�1�l�����ł͂Ȃ��B�����Y�݂�����Ă�����Ƃ��𗬂ł���v�ȂǂƏq�ׂ��B�r�m�r�ł��t���Ă����Ƃ����B
�������s�ɋً}���Ԑ錾�A�܂��o��̂��@�ǂ��Ȃ�t����c�@7/7
10�s���{����11���܂ł̊����ŏo����Ă���V�^�R���i�Ή��́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̈����ɂ��āA���{��7���ߌ�ɊW�t����c���J���Đ��{�Ă��ł߂�B��s��4�s���̏d�_�[�u����������Ă����ɒ������Ă��邪�A�������������铌���s�ւً̋}���Ԑ錾�����߂鐺������B�����̃R���i�Ή���7��23���ɊJ������ܗւ̂�����ɂ��傫���e�����邽�߁A���ڂ��W�܂��Ă���B
���`�̎�6���ɂ��W�t���ƑΉ������c�������A���j���ł܂炸7���̍ċ��c�ƂȂ����B���{�W�҂́u�⊯�[�����͏d�_�[�u�h�����A���ƂƂ̒����ɂ����鐼���N���o�ύĐ������A�錾�Ɍ��y���Ă���v�Ƙb���B
�t����c�̑O�ɂ́A�����J���Ȃ̐��Ƒg�D(�A�h�o�C�U���[�{�[�h)�̉���J�����B���Ƃ��������ǂ����͂��A�ǂ̂悤�ȃ��b�Z�[�W����̂��܂��A�t����͐��{�Ă��ł߂���j���B
���̐��Ƒg�D�̈���ŁA���{�Ă����₳���u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή��7���ߑO�̏O�@���J�ψ���ł���������B�u�I���p���̊��Ԃ��܂߂�7���̏��߂���9���ɂ����Ă�2�A3�J���́A����܂ł̓��{�̃R���i��̎��g�݂̒��ł��ł��d�v�Ȏ����̈���v
���{���ł́A�����̊����ɂ��āA���Ƃ��������F���������̂ł͂Ȃ����Ƃ̗\�����L����B���̂Ƃ��됭�{�W�҂̊Ԃł́A�����Ȃǎ�s��4�s���ɂ��āu�d�_�[�u��1�J���ȏ㉄������Ă��L�́v�Ƃ���Ă��邪�A���Ƃ��ً}���Ԑ錾��O���ɒu��������������A���{���j�ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��B
���c��j�Y���A�����ɋً}���Ԑ錾�̉\���𖾂����c�@7/7
7�������̂s�a�r�n�u�Ђ邨�сI�v(���`���j�E�ߑO10��25��)�ł́A11����1�s3���ł܂h�~���d�_�[�u�̉����������}���邱�Ƃ���B
�����W���[�i���X�g�̓c��j�Y���́A����̐V�^�R���i�̑�Ƃ��āu�����ɋً}���Ԑ錾�̉\�����o�Ă����v�ƃp�l���ɒB
���R���u���{�Ƃ��ẮA�܂��܂h�~���d�_�[�u�ł��������Ƃ������ƍl�����Ȃ�ł��ˁB���������g�搶�𒆐S�ɐ��Ƃ̕����A�����ً͋}���Ԑ錾�ɂ�������������Ȃ����Ƃ����b���o�Ă��āv�Ɛ��{���ȉ��̈ӌ�������Ɛ����B
�����A�����ɐ錾�����߂��ꂽ�ꍇ�ł��u3���̕��͂܂����������Ă��āA���������������͓̂����Ȃ̂ŁA�����ɋً}���Ԑ錾��3���ɂ͂܂h�~���d�_�[�u�Ƃ����l���v��3���ł͌��݂̑p�������\���������Ƃ����B
�܂��ً}���Ԑ錾���o���ꂽ�ꍇ�̊��Ԃɂ��Ắu1�������x�v�Ƃ��A���̏�Łu�I�����s�b�N�̊Ԃ�S�ăJ�o�[���邭�炢�B�܂h�~���d�_�[�u���̌ܗւȂ̂��A���邢�ً͋}���Ԑ錾���̌ܗւȂ̂��Ƃ������Ƃł��B(�܂h�~���d�_�[�u���Ƃ��Ă�)1�����͂ǂ����݂�������ŁA�ǂ��炩�ƂȂ��ė����v�Ƃ����B
����܂ł̐��{�̕��j���u(�܂h�~���d�_�[�u�łƂ���)�������������������ł��ˁA���ہv�Ɩ������A�u(���g���)�����������l�����Ƃ������Ƃ��A���{�ɂ͓`������Ƃ������ƁB(����)�ǂ��������̂��Ǝv���Ă��āA������5��b��ŁA�͂����Ĕ��g�搶�̂�������������̂��ǂ����Ƃ������Ƃ𒆐S�ɘb��������Ǝv���v�Ƙb�����B
�������s�ŐV����920�l�̃R���i�������m�F�@7/7
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����܂h�~���d�_�[�u�����������s���ŁA7���A�V����920�l�̊������m�F����܂����B
6��30��(��)�Ɣ��206�l�������܂����B1���̊����҂�900�l������̂�5��13����1010�l�ȗ��ł��B
�s���̊����҂́A18���A���ŁA�O�̏T�̓����j���̐l��������A���o�E���h�X���������ƂȂ��Ă��܂��B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�631�D7�l�ŁA�O�̏T��124�D3���ƂȂ�܂����B
����A�V����3�l�̎��S���m�F���ꂽ�ق��A�d�ǎ҂�1�l������62�l�ł����B
�������V����920�l�����Ɂu��l�����œ����ܗ֊J����}���鎖�ԂɂȂ肻���v�@7/7
�O�����s�m���ō��ې����w�҂̑C�Y�v�ꎁ(72)�����g�̃c�C�b�^�[�ɐV�K���e�B�����s��7���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����920�l���ꂽ�Ɣ��\�������ƂɁA�R�����g�����B
900�l����5��13����1010�l�ȗ��ƂȂ����B�C�Y���́u�����Ă��܂����A�{���̓����s�̃R���i�����҂�920�l�A��T�̐��j�����206�l�����v�Ɠ`���A�u�����Ґ�l�����œ����ܗ֊J����}���鎖�ԂɂȂ肻���ł���v�ƌ��O�����B
�܂��u�f���^���̊������g�債�Ă���v�Ǝw�E�B�s����11���܂ł܂h�~���d�_�[�u�̑Ώۊ��ԂƂȂ��Ă��邪�A�V�K�����Ґ��̑����X���������Ă���B�u�����h�~���d�_�[�u�̉����ǂ��납�A�ً}���Ԑ錾�Ĕ��߂��K�v�ȏ�ԂɂȂ����v�ƂÂ����B
���u�܂h�~�v�����Ȃ��ޒ�~���@�����s�A���{�ɗv�]�@7/7
�����s��7���A�V�^�R���i�E�C���X��́u�܂h�~���d�_�[�u�v����������ꍇ�A���H�X�̎�ޒ�������~����ȂNJ�����̋����𐭕{�ɗv�]�����B�����ł�6���܂ł̐V�K�����Ґ���17���A���őO�̏T�̓����j��������ȂǁA�Ăъ����g�債�Ă���B��ޒ̐��������߂�K�v������Ɣ��f�����B
���{��11���������Ƃ��āA�����Ȃ�10�s���{���ɏd�_�[�u�A���ꌧ�ɋً}���Ԑ錾��K�p�����B�d�_�[�u�̑Ώۋ��̈��H�X�͈��̏��������Όߌ�7���܂Ŏ�ނ�ł���B�s�͌��݁A���{��茵�����Ǝ����݂��A1�g2�l�ȓ��A�؍ݎ��Ԃ�90���ȓ��Ƃ��Ď�ޒ�F�߂Ă���B
�s�͂��̂ق��A�d�ǎ҂������Ă���50��Ȃǒ����N�w�ւ̃��N�`���ڎ푣�i��A���H�X�ւ̋��͋��x���ɏ[�Ă�����[�u�̌p���Ȃǂ��v�]�����B�@
���ٗp�̉A�n��Ŗ��Á@�ً}���Ԑ錾���e�����@7/7
�ٗp�̎w�W�Ƃ��Č����J���Ȃ��������\����u�L�����l�{���v���߂���A�V�^�R���i��ً̋}���Ԑ錾���J��Ԃ����n��Ƃ���ȊO�̒n��ŁA��ɍ����o�n�߂Ă���B�c�Ǝ��l�v���Ȃǂ��n��o�ς̑������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��f�[�^�����t���Ă���`���B
���l�{���́A���E��1�l�ɑ��A���l���������邩�������B�L�����l�{��(�G�ߒ����l)�̑S�����ς�2019�N12���ɂ�1�E57�{�������B���ꂪ20�N4�`5���ɑS�����ΏۂɂȂ���1��ڂً̋}���Ԑ錾���o�āA��10���ɂ�1�E04�{�܂Œቺ�B�s���{���ʂ̔{���������݉�����A20�N���͂قډ����Ő��ڂ����B
21�N�̓s���{���ʂ̗L�����l�{��(�A�ƒn��)�́A������2�ɉ����Ă���B
1���ȍ~�A�錾��u�܂h�~���d�_�[�u�v���f���I�ɏo�Ă��铌���s�Ƒ��{�B5������N10���Ɣ�ׂ�ƁA������0�E05�|�C���g�A����0�E03�|�C���g���ꂼ�ꈫ�����A�܂��ꂪ�����Ȃ��B���l�ɐ錾��d�_�[�u�̑ΏۂɂȂ������m�A�����A����Ȃǂ̒n�����0�E1�|�C���g�����Ə������B
����A���N�ɓ����Ă���͐錾�̑ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ��n��ł́A���l���傫�������Ƃ��낪����B�Ⴆ�A���䌧�͍�N10������0�E25�|�C���g�A�H�c����0�E28�|�C���g���P���A�R���i�БO�̐��������߂��������B
5���̔{����1�E81�{�őS���g�b�v���������䌧�͍��N�A�x�����Ăт����錧�Ǝ��́u�ً}���Ԑ錾�v��2��o�������A���H�X�Ɏ�ނ̒��l�Ȃǂ͋��߂Ă��Ȃ��B���ɂ��ƁA�����̐����Ƃ����l�ӗ~�����߂��Ă���Ƃ����B
��Ƃ̗̍p�ӗ~��\���V�K���l���ɐ錾��d�_�[�u���^����e�������J�Ȃ��������Ă���B�c������E�ƈ���ǒ���6��29���̋L�҉�ŁA�u�R���i�������o�ϊ����ɗ^���Ă���e����ʂ��A�J�����v�ɂ��e����^���Ă���\�����l������v�ƌ�����B
���J�Ȃ́A�x�Ǝ蓖���Čٗp���ێ�������Ƃ��x������ٗp�����������̊g�[�Ȃǂ𑱂��Ă����B�����R���i�Ђ��������ɂ�A�����s����S�z���鐺���オ��n�߂Ă���B
��ꐶ���o�ό������̐V�Ƌ`�M�E��ȃG�R�m�~�X�g�͓s���{���ɂ�鍷���o�Ă���ɂ��āu�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ��n��̌ٗp�ɉe����^���Ă���͖̂��炩���v�Ǝw�E����B�R���i�Ђ��������n��قNjꂵ�����Ə��������Ă���Ƃ��āA�u���N�`���ڎ��i�߁A�����̑������������邱�Ƃ��K�v���v�Ƒi����B
���R���i�Ђ̎Г��R�~���j�P�[�V�����@�ۑ肾�Ǝv������́H��L���x���@7/7
�l�ޏЉ�Ƃ�W�J����G�C�g�V�[�N�G���X��7��6���A�u�R���i�Ђ̎Г��R�~���j�P�[�V�����ۑ�Ɋւ��钲���v�̌��ʂ\�����B�ۑ肾�Ɗ�������̂�1�ʂ́u�Г��ł̏�L���x���v�A�ۑ肾�Ɗ����鑊���1�ʂ́u��i�v�������B
�ۑ肾�Ɗ�������̂�1�ʂ́u�Г��ł̏�L���x���v(31.7��)�A2�ʂɁu����ԁE���Ə��Ԃ̘A�g�����܂������Ȃ��v(24.8��)�A3�ʂɁu�E��(�Ɩ��ȊO)�̂��Ƃ��C�y�ɑ��k�ł��Ȃ��v(21.5��)���������B���Ђ́u�R���i�Ђɂ�郊���[�g���[�N�̊g���A�H�������Ȃ����b�������ʂ����������Ƃɂ��A�Ɩ��O�̃R�~���j�P�[�V�����@������ۑ��������̂ł͂Ȃ����v�ƕ��͂��Ă���B
�ۑ肾�Ɗ����鑊��ōł����������̂́u��i�v(32.8��)�ŁA�u�����v(24.2��)�A�u�В��v(19.5��)���������B���N��ʂł݂�ƁA20�㏗���̖�(49.2��)���u��i�v�Ɠ����Ă���A�ق��̐��N������ۑ�������Ă��邱�Ƃ����������B
�Г��E�ЊO��킸�A���k�ł��鑊�肪�~�����Ɗ����邩�����Ƃ���A�S�̂�51.0�����u������v�Ɖ����B���N��ʂł݂�Ɓu������v�Ɖ����������ł����������̂�20�㏗����60.7���������B
�s�����Ă��炦��E���k�ł��鑊��Ƃ��čł������́u�����v(34.7��)�ŁA�����Łu�F�l�v(24.8��)�A�u��i�v(24.0��)�̏��ɂȂ��Ă���B���N��ʂł݂�ƁA20�`30�㏗���́u�Ƒ��v�Ƃ��������������Ȃ��Ă���A50��j����4���ȏ�A30��j����3���ȏ�́u���k�ł��鑊�肪���Ȃ��v�Ƃ����������B
�ǂ̂悤�ȑ��k���肪�~�����Ǝv���������Ƃ���A1�ʂ́u�l�Ƃ��đ��h�ł���v(49.0��)�A2�ʂ́u�I�m�ȃA�h�o�C�X�������v(46.3��)�A3�ʂ́u�������ł���v(32.2��)�������B�u���k���肪�~�����Ƃ͎v��Ȃ��v�Ɠ������l�́A50�㏗����7.7���A30�㏗����13.6���ƑS�̕���(22.0��)���Ⴂ�B
�A���P�[�g��5��7�`10���ɁA�]�ƈ��K��5�`300�l�̊�Ƃœ����S����20�`50��j��600�l��ΏۂɁAWeb�A���P�[�g�����Ŏ��{���ꂽ�B
���R���i��1�N�̉ƌv����̕ω��|�E�B�Y�R���i�ƃ|�X�g�R���i�̍l�@�@7/7
��1�@�R���i�Ђ̌l����̐���
�R���i�Ђ��n�܂�1�N�]�肪�o�߂����B���炽�߂Čl�����U��Ԃ�ƁA�����ŋً}���Ԑ錾�����߂Ĕ��o���ꂽ2020�N4�E5���̗������݂́A���[�}���V���b�N�Ⓦ���{��k�Ќ��啝�ɏ�����̂ł������m�}�\1�n�B
�@�@�@�m�}�\1�n����ғ����w��(CTI�}�N��)
���̌�͌o�ϊ����̍ĊJ���đ啝�ɉ��P�������A�����Ċg��ōĂщ������ɁA���P����Ώ�����ɂȂ邱�Ƃ��J��Ԃ��Ă���A�����ł͖����R���i�O�̐����ɂ͖߂��Ă��Ȃ��B�Ȃ��A�����Ґ��͊i�i�ɑ����Ă���ɂ��ւ�炸�A�����g����g�Ɣ�ׂđ��g���O�g�ɂ�����̗������݂͐B����ً͋}���Ԑ錾���o����X�{�݂̉c�Ǝ��l�v��������I�ł��邱�Ƃɉ����āA�����h�~��̏K������C�̊ɂ݂Ȃǂ��琶���҂̊����s������܂�A�l��������ɂ����Ȃ��Ă��邽�߂��B
��2�@�ƌv����̓���̕ω�
�R���i�ЂŊO�o�����l����A��ڐG�u�������܂邱�ƂŁA���s��O�H�Ȃǂ̊O�o�^�����ڐG���Ζʌ^�T�[�r�X�̏���啝�Ɍ������A�o�O��e�����[�N�֘A���i�ȂǑ������������������Ă���B�R���i�Ђő傫���ω���������̈�ɂ��Č��Ă����B
�@�@�@�m�}�\2�n�V�^�R���i�ő傫�ȕω����������Ȏx�o�i��(��l�ȏ㐢�сA�ΑO�N����������������)
��1/�H�`�O�H���v�̒��H�E���H�V�t�g
�����ȁu�ƌv�����v�ɂ��Ɠ�l�ȏ㐢�тł́A�O�H������������A�p�X�^�⑦�ȖˁA�Ⓚ�H�i�Ȃǂ̗����̍����H�i�̑��A���N���A�`�[�Y�A�����E�������A�e���ށA�o�O�Ȃǂ̎x�o�z�͑������Ă���m�}�\2a�n�B�܂�A�Ƃł̐H�������������ƂŁA��y�ɐH�ׂ�����v�ƂƂ��ɁA�H���̎������߂������v�̗��ʂ������Ă���悤���B�Ȃ��A�o�O��e�C�N�A�E�g�Ȃǂ̒��H�s��́A�R���i�O���痘���d���u���̍����P�g���т⋤�������т������钆�Ŋg��X���ɂ��������A�R���i�ЂőΉ�������H�X�����������ƂŁA����҂ɂƂ��ăT�[�r�X�Ƃ��Ă̖��͂����܂�A��w���v�������Ă���悤���B���N�`���ɂ��W�c�Ɖu���l������A�s���������ɘa���ꂽ�|�X�g�R���i�ł́A�O�H���v�͎����Ɖ���������낤�B�������A�e�����[�N�̐Z���Ől�̗��ꂪ�ς�������߁A�I�t�B�X�X�̒��H����݉���v�Ȃǂ̓R���i�O�̐����ɂ͖߂�ɂ����B���Ɉꕔ�̊O�H�`�F�[���ł͉w�O����x�O�֏o�X�헪��ς��铮�������邪�A����̓R���r�j�G���X�X�g�A�ȂǑ��ƑԂ̓X�ܗ��n���ς��\��������B
��2/���s�E���W���[�`���ʑ��GoTo
���s��W���[�̓R���i�Ђő傫�ȑŌ����Ă���B����ŁA���{�́uGoTo�g���x���L�����y�[���v�̌��ʂŁA��N�̉Ă���H�ɂ����āA�h������p�b�N���s��͑啝�ɉ��A2020�N10���̏h�����͑O�N������{��3�����������m�}�\2b�n�B�Ȃ��A��ʔ���܂ރp�b�N���s��Ɣ�ׂďh�����P�̂̉�������̂̓R���i�Ђɂ����Ă͎��Ɨp�ԂȂǂ̃Z���t��i�𗘗p���ċߏ�֗��s���A�h���{�݂����𗘗p����u�}�C�N���c�[���Y���v�u�����������߂��B���W���[�ł́A2020�N6�����͋x�Ɨv���������Ɋɘa���ꂽ���p�ق┎���قȂǂ̕����{�݂��A������������������B���̌�A�Ăɂ����āA�f��ق�V���n�̉c�Ƃ��ĊJ����A�ǐ����铮���������Ă���B�|�X�g�R���i�ł͗��s��W���[�̎��v�͎����Ɩ߂�n�߂邾�낤�B�܂��A���ݒ�~����Ă���GoTo�g���x�����ĊJ�����̂Ȃ�A�L�����y�[�����Ԃł͌��I�ȉ����҂ł���B����ŃR���i�O����A���s��W���[�Ȃǂ̏]���Y�Ƃł́A�f�W�^�����̐i�W�Ō�y�̑��l�����i�݁A���l�ς��ω����钆�ŁA�u��҂̗��s����v���w�E����Ă����悤�ɁA�Ⴂ����̑��ΓI�ȋ����S�̒ቺ���ۑ�ł������B����āA�������I�Ɏ��v���l�����Ă������߂ɂ͈��������n�ӍH�v���K�v���B
��3/�f�W�^���֘A
(1) �e�����[�N���v�̍��܂�
�ݑ�Ζ��ɂ��e�����[�N�̐Z���ɂ��A�p�\�R����Ƌ�̎x�o�z�͑O�N���������錎�������m�}�\2c�n�B�č��̃s�[�N�́A�u���ʒ�z���t���v��Ă̏ܗ^���㉟�������̂ƌ�����B�Ȃ��A10���̃s�[�N�͑O�N�����ɏ���ŗ������グ�ɂ�锽���������������߂ɁA2020�N10���̓v���X�ɐU��₷���e���ł���A��r�I�l�̒���i�ڂœ��l�̓������m�F����Ă���B�p�\�R����Ƌ�Ȃǂ͑ϋv������ł���A�w����̐��N�͎��v�ɗ��������������邾�낤�B�������A�|�X�g�R���i�ł͓��������ς�邱�ƂŁA��������̃T�C�N���ł̎��v�������҂ł���B�܂��A���݂̂Ƃ���A�S���I�ɂ͕K�������傫�Ȓ����ł͂Ȃ����A�x�O���Z��t�H�[���Ȃǂ̏Z�ݑւ����v�ɔ����ĉƋ��Ɠd�A�����ԂȂǂ̎��v�������܂��\��������B ����A�I�t�B�X�ւ̏o�����邱�ƂŁA�w�L���͂����ނˑO�N�����������B��N4���̗������݂́�79.9%�Ƒ傫�����A����͓��w���Ȃǂ̊e�펮�T�������ݒ��~�E�����ƂȂ����e�������邾�낤�B�|�X�g�R���i�ł̓I�t�B�X���̎��v�͎ア��������\���͂��邪�A�ˑR�Ƃ��Č������������ƌ�����B�e�����[�N�̉e���ɉ����āA�R���i�O����A�N�[���r�X�ȂǃI�t�B�X���̃J�W���A�����Ƃ���������������B���݁A�A�p�������[�J�[�ł̓����b�N�X���̂���e�����[�N�d�l�̃I�t�B�X���̃��C���i�b�v�𑝂₵����A�G�݂�H�i�̔̔����n�߂�Ȃǎ��v��͍����铮���AEC�T�C�g��SNS�ł̏�M�ɐϋɓI�ȓ���������B����Ƃ��A�p�����s��ł͐��i���C���i�b�v�̍H�v��A���X�܂̃l�b�g���Ƃ���������͋��܂邾�낤�B
(2) ��������Ńf�W�^����y���v��
�������萶���Ŋy���݂₷���Q�[����d�q���ЂȂǂ̃f�W�^����y�ł͎x�o�z�̑������ڗ���(�}�\��)�B���ɃQ�[���@�͎q�ǂ��̐����ƘA�����Ă���A�S����ċx�Z���v�����ꂽ2020�N3���⊴���Ċg��ŋA�Ȏ��l���Ăт�����ꂽ8��(�ċx��)�Ȃǂɓ��ɑ����Ă���B�܂��A�d�q���Ђ�f���E���y�\�t�g�A�A�v���Ȃǂ̎x�o�z�͂�������O�N����������B�x�o�z�͊����ƕK�������A�����Ȃ����A����́A�f�W�^�����̐i�W�ŃR���i�O����f�W�^����y�̎��v�͑����Ă�����ɁA�R���i�Ђɂ����v��������������߂��낤�B�R���i�Ђ͓����������łȂ��A����s���̃f�W�^���������������Ă���B�|�X�g�R���i�ł��f�W�^����y�̎��v�ɂ͐L���̗]�n������B����̓V�j�A�ɂ��X�}�[�g�t�H���̗��p���g�傷�邱�Ƃŕ��L���w�̎��v�����҂ł���B
��4/���̑�
���̑��A�R���i�Ђ̓����I�ȓ����Ƃ��āA�}�X�N���p��O�o���l�̉e���Ńt�@���f�[�V��������g�Ȃǂ̃��C�N�A�b�v�p�i�̎x�o�z���������Ă���B�������A�����̓}�X�N���p���s�v�ƂȂ�Β����ɉ���������낤�B�܂��A�Ƃʼn߂������Ԃ����������߂��A�y�b�g�֘A�̎x�o�z�������Ă���B�Ȃ��A��ʎВc�@�l�y�b�g�t�[�h����̒����ɂ��ƁA2020�N�̌���L�̐V�K����҂̎��瓪���͑O�N��葝�����A���������ȑO���傫���B�|�X�g�R���i�ł͍x�O���Z�ɔ����ăy�b�g���v�������\��������B
��3�@����̏���̓��N�`���ڎ킪��
2020�N�̌l����́A�H��e�����[�N�֘A���i�Ȃǂ̑����������Ɏx����ꂽ�B�܂��A��Ƃł̓I�����C���Ή����͂��߂Ƃ����V�̈�ւ̓W�J�A�Ƒԓ]���̍H�v�ȂǗl�X�ȑn�ӍH�v������ꂽ�B����ŃI�����C���ɂ��T�[�r�X�͒P����������X��������A�R���i�Ђł͑Ζʂ�g�ݍ��킹���t�����l�̍����T�[�r�X�̒ɂ�����������B�܂��A�l�X�ȍH�v�������Ă��A��͂�]������x�o�z�̑傫�ȗ��s�Ȃǂ̊O�o�^����̑啝�Ȍ������l����S�̂֗^����e���͑傫���B���łɃC�X���G����č��Ȃǃ��N�`���ڎ�̐i�ޑ����ł́A�O�o�^�̏���R���i�O�̐����ɔ��鐨���ʼnX���������Ă���B���{�ɂ����Ă����N�`���ڎ킪�����ɑ����ɐi�ނ����A����̌l����̌����B
���q�ǂ��ɏΊ���@�R���i�ЁA�ٓ��z�z�̃{�����e�B�A�c�̂֊�t�����@7/7
���m���I�]���Ŏq�ǂ��H�����^�c����{�����e�B�A�c�́uONiGiRi(���ɂ���)�v�́A�R���i�Ђɂ����Ă��A�q�ǂ��̂���ƒ��ΏۂɁA�H�������z�z��A�ٓ�������Ĕz�B����ȂNJ������x�~�����邱�ƂȂ��x���𑱂��Ă����B�u�����������ł��邱�ƂŁA�N���̏����ɂȂꂽ��v�ƒn���Ɋ�������p�ɁA�n���̐l�炩���t������Ȃǎ^���̗ւ��L�����Ă���B
2018�N�ɔ����������ɂ���́A�q��Ē��̕�e�炪�Q�����q�ǂ��H�����Вn�x����W�J�B�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɂ��w�Z���x�Z�ɂȂ�ƁA���H�t���Ŏq�ǂ�������a��������A�t�[�h�o���N������ꂽ�H�����z�z�����肵�Ă����B
�u�R���i�ЂŎ������������ƒ낪��������A�e����Ï]���҂ň�l�ŗ���Ԃ�����q�ǂ��������肷��B���͂��H�ׂ����q�ǂ���A�H���̒�����Ə�����e�͑����v�ƁA��\�̉����T�q����(41)�͌����B���H����́A�������ȂǂŊ�]����ƒ�̎q�ǂ������ɕٓ������A�T2��قǖ����Ŕz�B���Ă���B30�H����Ƃ��Ă��邪�A�\�����݂���������60�`70�H�قǒ��Ă���Ƃ����B
�K�v�ȐH�ނȂǂ͊�t�ł܂��Ȃ����肵�Ă��邪�A�n���̐l�炩��̊�t�̐\���o�������Ă���B7��2���ɂ́A�����̃E�F�u����ƁA�O�H�����Y����(41)���u�K�v�ȕ��Ɏg���Ăق����v�ƁA1��50������̃}�X�N1500��������B�̔��p�ɊC�O����d���ꂽ���̂����A�]�蕪�̒u����ɍ����Ă����Ƃ���A�m�荇���œ����̏Z��t�H�[����Ј��A�˒J�Y������(59)�����t���Ă��ꂽ�Ƃ����B�˒J�����SNS�Ȃǂł��ɂ���̊�����m��A�u�撣���Ă�����p�����āA�������͂ł�����Ǝv���Ă����v�Ƙb���B�}�X�N�͐H���ƈꏏ�ɔz�z����Ȃǂ��Ċ��p���Ă����Ƃ����B
��������́u�����̂��x���Ɋ��ӂ��A�����������������C�������Ȃ����Ă������炤�ꂵ���B��l�ł������̎q�ǂ��������Ί�ɂȂ��悤�A���������Ί�Ŋ����𑱂��Ă��������v�Ƙb���B�c�͔̂N���ɖ@�l����ڎw���Ƃ��Ă���B
�������ɋً}���Ԑ錾���߁@���{�����@7/7
���{���V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â�����(�܂�)�h�~���d�_�[�u��K�p���Ă��铌���s�ɑ��A�ً}���Ԑ錾�߂�������Œ����ɓ��������Ƃ�7���A���������B�����̐��{�W�҂����炩�ɂ����B23���ɊJ����s���铌���ܗւ́A�������ϋq�ōs������Z���傫���Ȃ����B�����s�ɐ錾�����߂����A�����4��ڂƂȂ�B
���{�͌��݁A10�s���{���ɑ�11���������Ƃ��ďd�_�[�u��K�p���Ă���B��t�A�_�ސ�A��ʂ̎�s��3���ɂ��Ă͏d�_�[�u�̊������������A�c���6���{���ɂ��Ă͉�����������Ō������Ă���B�ً}���Ԑ錾�����߂���Ă��鉫�ꌧ�ɂ��ẮA�d�_�[�u�Ɉڍs��������Œ������Ă���B
���`�̎�7���[�A�W�t���Ƌ��c������ŁA�ŏI�I�ȕ��j���ł߂�B
�����r�m���u�ً}���Ԑ錾�A�K�v�Ȓi�K�v������...�ܗւ́u���S�ɁE�E�E�v �@7/7
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŁA7���ɔ��\���ꂽ�����s���̐V�K�����Ґ���8�T�ԂԂ��900�l�������Ƃ��A���r�S���q�m���͓����A�s���ŁA�ً}���Ԑ錾�ɂ��āu�K�v�Ȓi�K�Ȃ̂��ȁv�Əq�ׂ��B����A�����ܗւɂ��Ắu�R���i���i�߂Ȃ���A���S�ɊJ�����悤�ɐi�߂Ă��������v�Ƃ��A�ً}���Ԑ錾�Əd�Ȃ錩���݂����܂钆�ł��J�Âւ̈ӗ~���ɂ��܂����B�L�Ғc�̎�ނɓ������B
7���̓s���̐V�K�����Ґ���920�l�ŁA�O�T�̐��j�����206�l�������A18���A���őO�T�̓����j�����������B
���r�m���́u�͂ƂĂ��������ł��B����ŁA�d�ǎҐ��A�d�ǂ̐���Ȃǂ͂���܂łƂ�����Ɨl�����Ⴄ�B50��⒆���N�ɓI�Ă��悤�ȑK�v�ɂȂ��Ă���v�Ƃ̔F����\���B���{��8���ɓ����ً}���Ԑ錾���o���葱����i�߂邱�ƂɐG��A�u�����̂Ƃ���㏸�������Ă���܂��̂ŁA�����̑[�u���K�v�Ȓi�K�Ȃ̂��ȁv�Əq�ׂ��B
�����g����āA�ܗւ̊J�Ò��~�����߂鐺�����邪�A���r�m���́u�ƂĂ��������ł͂������܂�����ǂ��A����܂ł�2020���̏������A�����Ă܂��R���i��A���܂��ܐi�߂Ă܂���܂����B�R���i���i�߂Ȃ���A���S�ɊJ�����悤�ɐi�߂Ă��������Ǝv���܂��v�ƌ�����B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������ɋً}���Ԑ錾�߂ցA8��22���܂Ł@�����ܗցA���ϋq�Œ����@ 7/8
���{��8���[�A�����s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾��12�����甭�߂���ƌ��肷��B11���������Ƃ��Ă������ꌧ�̐錾�͉�������B��ʁA�_�ސ�A��t�A����4�{���̂܂h�~���d�_�[�u����������B�������8��22���܂ŁB���Ƃ�ɂ��ߑO�̊�{�I�Ώ����j���ȉ�ɐ����N���o�ύĐ��S���������j������A���������߂�B
�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���̏d�_�[�u��11���ʼn������錩�ʂ��B���ȉ�̗�����������A�ߌ�ɊJ�����O�Q���@�̋c�@�^�c�ψ���ɐ����������A���`�̎��[���̐V�^�R���i�����Ǒ��{���ŕ\������B���̌�A�͋L�҉�ɗՂ݁A���f�̗��R�Ȃǂ��������B
�����̐錾���߂ɔ����A23���ɊJ����}���铌���ܗւ̓s�����͖��ϋq�Ƃ�������Œ�������B���{�A�s�A���g�D�ψ���A���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�Ȃǂɂ��5�ҋ��c��8���ɂ��J�Â��A�ŏI���肷��B
�錾�Ώےn��ł́A��ނ������H�X�ɑ����������x�Ƃ�v������B
��������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ց@�������u�ł���Ō�ɂ������v 7/8
���{��8���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����ē����s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�߂��A�_�ސ�A��ʁA��t�e���ւ̂܂h�~���d�_�[�u�̊�������������Ȃǂ̎葱�����n�߂��B����ł̂�����A��̗l�q�𐏎��A����B
��14:45�@�錾�u�K���Ō�Ɂv�������傪����
���N��(��������})�́A���������ً}���Ԑ錾�ɂ��āu�ł���Ō�ɂ������v�Ɠ��ق������ƂɐG��A�u���̋ǖʂŁw�ł���x�Ȃ�Ă������t���g���Ăق����Ȃ��B�K���Ō�ɂ���Ƃ����������ӂʼn߂����Ăق����v�ƒ��������B�������́u�w�ł���x�Ɛ\���グ���̂́A�C�M���X�A�C�X���G���ł��Ⴂ���X�𒆐S�Ɋ������L��������A���@�Ґ����������肵�Ă���̂Łv�ƊC�O�ł̕ψي��̊����g�傪�O���ɂ��������Ƃ�����B���N�`���̌��ʂɊւ���f�[�^���͂�i�߂�Ƃ��A�u�K�����ʂ͂���܂��v�Ƃ����������B
��14:35�@���Y�A�ܗ֒��~���ׂ��ɐ������uIOC�����f�ƕ����v
����S�玁(���Y�})�́u�ܗւ͒��~�̌��f�����ׂ��ł͂Ȃ����v�Ɩ₢���������B �������́u�J�Ì�����IOC�����f�����ƕ����Ă���v�Əq�ׁA�u���E�I�ɂ݂�Γ��{�̊����͒Ⴍ�}�����Ă邪�A�����̈�Ò̐�������I�Ȃ��̊m�ۂ��Ă������߂ɁA����ΐ��A���ŋً}���Ԑ錾�𓌋��s�ɔ��o���邱�Ƃɂ����v�Ɛ��������B
��14:30�@�����u�ܗցA���ϋq�������v
�����p����(�����})�́u���ϋq������ɓ���Č������ׂ��v�Ɣ������B �������́A���5000�l�A���e��50���ȓ��̕��j�܂��đg�D�ςȂǂ�5�ҋ��c�őΉ������Ƃ����F������������Łu�Ⴆ�A��Ԃ̖��ϋq�Ȃǂ��܂߂āA���܂��܂Ȍ����������Ə��m���Ă���v�Əq�ׂ��B
��14:15�@�����u����̎��s�v
���z��Y��(��������})�́A�����ܗ֖ڑO�ŁA�����ɋً}���Ԑ錾�߂���ɂȂ������Ƃ��u����̎��s�v�Ɣᔻ���A������ӔC�̏��݂�q�˂��B�����S�����́u�n���}�[�A���h�_���X�Ƃ������t�����邪�A�����������Ă��������ł����}����B���܂��Ă���Α����������B�@���I�ɑΉ�����Ɛ\���グ�Ă����v�Ƃ��킵���B
��14:15�@�������A�ً}���Ԑ錾�u�ł���Ō�Ɂv
���c�B�v��(�����})���獡��̌��ʂ������A�������͐��ƂɈӌ������߂Ă���Ƃ�����Łu����A�Ō�ɂ������Ǝv���Ă��邪�A������ɁA�ł���Ō�ɂ������Ƃ����v���ŋً}���Ԑ錾�̔��o�����₳���Ă����������v
��14:00�@�����S�����@�x�Ɨv�������Ȃ��X�Ɏ����~��v��
�����N���S�������O�@�c��^�c�ψ���ŁA���{�̕��j�Ă���������B�����s�ɂ��ẮA�����Ґ��̑����X����C���h�R���̕ψي��u�f���^���v�ւ̒u������肪�i��ł��邱�ƂɐG��A�u�����ň�Ò̐����m�ۂ���K�v������v�Əq�ׂ��B���l�v�������������邱�Ƃ�A���͋���v���Ɏx�����邱�Ƃւ̗v�]�܂��A�u���H�X�ւ̋��͋��̐�n�����\�ƂȂ�d�g�݂̓����Ȃǂ����A�����Ɏ�ޒ̒�~��O�ꂷ�邽�߁A��ޔ̔����Ǝ҂ɑ��A��ޒ�~���x�Ɨv�����ɉ����Ȃ����H�X�Ƃ̎�ނ̎�����s��Ȃ��悤�v������v�Əq�ׂ��B����ɓ��[�@�Ɋ�Â����߁A�����������ɓK�p����Ȃǎ��g�݂̂���Ȃ鋭�����s���Ƃ����B
���ߑO�@���{���j����Ƃ炪����
�����s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾��12�����甭�߂��A���ꌧ�̐錾��A��ʁA�_�ސ�A��t�A����4�{���̂܂h�~���d�_�[�u���������鐭�{���j���A���Ƃ�ɂ���{�I�Ώ����j���ȉ���������B�����͂������8��22���܂ŁB�ً}���Ԑ錾�̑ΏۂƂȂ铌���A����ł́A��ނ������H�X�̋x�Ƃ�v���B�܂h�~�[�u������4�{���ł́A����͗e�F���Ă����ނ̒�������~�ɂ��A�����Ȃǂ܂��Ēm���̔��f�Ōߌ�7���܂ł̒�F�߂�ɘa���ł���Ƃ����B
���ً}���Ԑ錾�A�u�܂����v�@���_�ƒ��߁A�q������]�傫���@������E���H�@7/8
���{���V�^�R���i�E�C���X�̊����Ċg�傪���������s��4��ڂً̋}���Ԑ錾�߂�����j���ł߂�7����A�c�Ǝ��ԒZ�k�Ȃǂ��������錩�ʂ��̕S�ݓX����H�X�̊Ԃł́A�u�܂����v�Ɨ��_�ƒ��߂̐����L�������B
�l�̈ړ�����������錩���݂ŁA�ċx�ݎ��v�č���ł����q����́u�V���b�N���v�Ǝ��]���B����Ȃ��l�q���B
�s�ł�6�����{�ɐ錾���܂h�~���d�_�[�u�ɐ�ւ����A���Ԃ�l���̐����t���Ȃ���悤�₭��ނ̒��F�߂��Ă܂�2�T�ԗ]��B�ēx�̒֎~�̉\���ɁA���������́u�q�ϓI�ȍ����������Ăق����v�Ɣߒɂȋ��т��グ���B
�s���̕S�ݓX�ł́u�ً}���ԂƂ܂h�~�[�u�̈Ⴂ��������Ȃ��v�u�v���̓��e�������炸�s�����v�ƁA��̓I�ȑΉ����j�������Ȃ����Ƃւ̌x�������܂�B
�q��ƊE�́A�����ܗցE�p�������s�b�N�J�Âɔ���7��22�������4�A�x��A�ċx�݂ɐl�C�̉���H���ŗ��p������������ł������A��s�����Ó]�B��芲���́u�܂��ꂵ��(���p)�ɂȂ邩������Ȃ��v�Ƃ��ߑ��������B�@
�������O���@4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�Ɂu�l�͂��������ς蕪����Ȃ��v �@7/8
�����{�m���ŕٌ�m�̋����O��(51)��8���A�t�W�e���r�̏��ԑg�u�߂��܂�8(�G�C�g)�v(���`���j�O8�E00)�ɏo���B���{�������s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾�߂�����j���ł߂����ƂɌ��y�����B
���{��8���[�ɓ����s�ً̋}���Ԑ錾��12�����甭�߂���ƌ��肷��B11���������Ƃ��Ă������ꌧ�̐錾�͉�������B��ʁA�_�ސ�A��t�A����4�{���̂܂h�~���d�_�[�u����������B�������8��22���܂ŁB�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���̏d�_�[�u��11���ʼn������錩�ʂ��B�����̐錾���߂ɔ����A23���ɊJ����}���铌���ܗւ̓s�����͖��ϋq�Ƃ�������Œ�������B
�������́u�l�͂��������ς蕪����Ȃ��Ƃ�������ł��v�ƌ����A�u�p���͍��A1��������2��7000�l�A2��8000�l�̊����Ґ��ł��B����ł��Љ�o�ϊ����͊��S�ɍĊJ���Ă������Ƃ������z�Ȃ�ł��A�W�����\�������������ӂ��ɑǂ��܂����B����͎��Ґ��Ƃ��d�ǎҐ����������}�����Ă����ł���A���N�`���̌��ʂɂ���āB������A�l�́A���{�ł��ˁA���������c�_����Ƃɂ��Ă��炢�����ȂƎv���āv�Ƙb�����B���̏�Łu�͂����茾���Ă��̂�����̏������Ȃ���ł���B���A���{�̏d�ǎҐ��⎀�Ґ��̐L�т��ǂ��Ȃ̂��B���Ɋ����Ґ��̂�������҂�65�Έȏ�̊�����1�����Ă���Ƃ����������Ă܂�����A�d�ǎ҉����X�N�������������A����ȂɐL�тȂ�������A����Ӗ��A�����Ґ����Ă��̂͗e�F���Ă����Ȃ��Ɓv�Ƃ����B
�����āu�Ⴆ�C���t���G���U�Ȃł��ˁA���R���i�ŃC���t���G���U�̐����}�����Ă��܂����ǁA���ʂ͖��N���N�A1000���l�̊����Ґ����C���t���G���U�ŏo�Ă����ł���ˁB�ł��呛�����Ȃ��͎̂��҂��d�ǎ҂����N�`���Ƃ���ŗ}�����Ă��邩��Ȃ�ł��v�Ƃ��A�u�����炻�̂�����̋c�_����Ƃł���Ă��炢�����Ǝv����ł��B�����Ґ�������ɒ��ڂ���͈̂Ⴄ��Ȃ����Ǝv����ł����ǂˁv�Ǝ��g�̌������q�ׂ��B
�������s�ւ�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�A���ȉ���� �@7/8
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�Ɋւ����{�I�Ώ����j���ȉ��8���A�u�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p���Ă��铌���s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�߂���Ă�Ó��Ɣ��f�����B���{�͓����[�ɑ��{�����J���A�������肷��B
���ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�ƍ�ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���̏d�_�[�u�͌p������B���Ԃ͂������12������8��22���܂ŁB
�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���ɓK�p���Ă���d�_�[�u�́A������11���ʼn�������B���{��8���[�ɑ��{�����J���A�������肷��B
�����o�ύĐ����͕��ȉ�œ����s�ւ̐錾���߂ɂ��āu�����ň�Ò̐����m�ۂ���K�v������v�Əq�ׂ��B
�������ɋً}���Ԑ錾�ցA�ܗ��8��22���܂Ł|���ȉ�����@7/8
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��������铌���s�ŁA���{��4��ڂً̋}���Ԑ錾�߂���B12������8��22���܂ŁB�����ܗւً͋}���Ԑ錾���ŊJ�Â��邱�ƂɂȂ�B
���Ƃɂ���{�I�Ώ����j���ȉ�ŗ������ꂽ�Ɛ����N���o�ύĐ��S���������炩�ɂ����B�[���̑��{���Ō��肵�A���`�̎��ߌ�7������̋L�҉�Ő��{�̑Ή����������B
���N�`���ڎ킪��s���鑼���̌o�ϊ������̒����������钆�A���{�ł͎�s�̃R���i�����҂��}�����A�ً}���Ԑ錾���Ĕ��߂���鎖�ԂƂȂ����B�����ܗցE�p�������s�b�N�ւ̉e���ɉ����A����ւ̉��������͂ƂȂ邱�Ƃ͔�����ꂸ�A�O�@���U�̎����⎩���}���ّI�̍s�������E���������B�����ł�6��20���ɋً}���Ԑ錾���������A�܂h�~���d�_�[�u�Ɉڍs���Ă����B
11���������̂܂h�~���d�_�[�u�͍�ʁA��t�A�_�ސ�A���ʼn������A�k�C���A���m�A���s�A���ɁA�����͉�������B���ꌧ���ً}���Ԑ錾����������B�@
�錾�̑Ώےn��ł́A���H�X�Ɏ�ނ̒�~��v���B���͋��̐�n�����\�ƂȂ�d�g�݂���������B�̔��Ǝ҂ɂ��v���ɉ����Ȃ��X�Ƃ͎�����Ȃ��悤���߂�B
�q���ЂƗ��s��Ђɂ́A���p�҂Ɏ��O�̂o�b�q���������߂�悤���͂��˗�����B�ċx�݊��Ԓ��̊����g���}���邽�߁A�H�c��`����E�ɒO��`�Ȃǂ���k�C���Ɖ���Ɍ�������q�́A��]����Ζ����Ō���������悤�ɂ���B
���`�̎�7����A�u���S�̑̐�������Ċ�����}���Ă��������v�Ƙb�����B�ܗցE�p�������s�b�N�̊ϋq���̏���ɂ��ẮA���{�̑Ή��܂�����ő��g�D�ψ���ȂǂƂ�5�ҋ��c�Ō��߂�Əq�ׂ��B
�����ܗւ�23������8��8���܂ŊJ�Â���A�ً}���Ԑ錾��܂h�~�[�u�������ԂƏd�Ȃ����ꍇ�ɂ́A���ϋq���܂߂Č������邱�ƂɂȂ��Ă���B��������܂ŁA�ً}���Ԑ錾���ߎ��́u���ϋq�����蓾��v�Ƃ̔F���������Ă����B
�s����7���̊����Ґ���920�l(�O��593�l)�ƁA5��13��(1010�l)�ȗ��̐����������B
�ً}���Ԑ錾�����߂����ƕ�ꂽ���Ƃ��A���q���v���������ƌ��O���ꂽ��^�◤�^���������A������������͑��������B�s�n�o�h�w�͌ߑO9��5�����_�őO����3.03�|�C���g(0.2��)����1934.65�B
�ɓ��������̕��c�~�`�[�t�G�R�m�~�X�g�́A�ܗւ̖��ϋq�J�Â�\�z������ŁA�ϋq�̏����R���i���������҂�����y���v�ւ̈��e�����w�E�B����A���N�`���ڎ킪�i�ނɂ�ď���͉���Ƃ݂Ă���A7�|9�����̎������������Y(�f�c�o)�ւ̉e���́u���Ȃ����I�ɂȂ�v�Ƃ̌������������B
��������4��ڂ́u�ً}���Ԑ錾�v���ȉ���� ���{���Ō���� �@7/8
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̍Ċg�傪���������s�ɂ��āA���Ƃł��镪�ȉ�́A7��12������8��22���܂ŁA4��ڂً̋}���Ԑ錾���o�����Ƃ𗹏����܂����B���{�́A�[���̑��{���Ō��肷�邱�Ƃɂ��Ă��āA��������b������L�҉���āA�錾���o�����R�Ȃǂ�������A�����ɋ��͂��Ăт����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���ꌧ��Ώۂɂ����ً}���Ԑ錾�ƁA��������Ȃ�10�̓s���{���ɓK�p����Ă���܂h�~���d�_�[�u�̊�����3����ɍT���A8���ߑO�A�����ǂȂǂ̐��Ƃł��鐭�{�́u��{�I�Ώ����j���ȉ�v���J����܂����B
�����o�ύĐ��S����b�́A�����s�ɂ��ẮA�����̍Ċg��Ɏ��~�߂�������Ȃ����Ƃ���A7��12������8��22���܂ŁA4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o���ƂƂ��ɁA���ꌧ�ɏo����Ă���錾��8��22���܂ʼn���������j������܂����B
7��23���ɊJ�����铌���I�����s�b�N�́A�J�Ê��Ԃ��ׂĂ��錾�̎����Ɋ܂܂�܂��B
������b�́A�����ɐ錾���o�����R�ɂ��āu���̂��̐V�K�z���Ґ���920�l�ƂȂ�Ȃnjp���I�ɑ������A�ŋ�1�T�Ԃ�10���l������̐l����30�l���w�X�e�[�W4�x�����ɂȂ��Ă���B�d�ǎ҂���@�������̐l�̐����������A�����ň�Ò̐����m�ۂ���K�v������v�Ɛ������܂����B���̏�ŁA���H�X�ɑ��A��ނ̒��~���A�c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łɒZ�k����悤�v������Ƃ��āu���͋��̐�n�����\�ƂȂ�d�g�݂����A�x���̐v�����Ɍ����āA�K�v�Ȏ��g�݂�i�߂����v�Əq�ׂ܂����B�܂��A��ނ�̔����鎖�Ǝ҂ɑ��A��~�ɉ����Ȃ����H�X�Ƃ̎��������s��Ȃ��悤�v������l���������܂����B����ɁA�錾���o����Ă���n��̃C�x���g�̊J�Ð����ɂ��ẮA���̎��e�����50���܂ł��A5000�l�̂����ꂩ���Ȃ���������Ƃ��A���Ԃ͌����ߌ�9���܂łƂ������ێ�������j�������܂����B����A�܂h�~���d�_�[�u�͍�ʁA��t�A�_�ސ�Ƒ���4�{���ł́A8��22���܂ʼn������A�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{����7��11���̊����������ĉ���������j�������܂����B�����āA�d�_�[�u�̓K�p�n��ł��A�����A��ނ̒�~��v��������j�������܂����B������b�́u�f���^���ɂ�銴���g��ƃ��N�`���ڎ�̃X�s�[�h�����Ƃ����̒��Ń��N�`���ڎ�𒅎��ɐi�߂�B���N�`�����s���n��܂ŁA���⌒�N����邱�Ƃ��1�ɁA�����ŋ@���I�ɑ���u�������g���}���Ă��������v�Əq�ׂ܂����B���ȉ�ł́A�����������{�̕��j�ɂ��ċc�_���s���A��������܂����B
�u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή�́A��̂��ƕw�̎�ނɉ����A�����ɋً}���Ԑ錾���o���ȂǂƂ������{�����������j�𗹏������Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�����s�ɐ錾���o�����Ƃɐ��Ƃ����ӂ����̂́A1���̊����Ґ���900�l��������Ƃ������A�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�w�f���^���x���L�����Ă��Ă��邱�Ƃ�A40��50��𒆐S�ɏd�lj�����l����@����l�������Ƃ������A����܂łƂ͖��炩�ɈႤ�X���������Ă��Ă��邽�߂��B���̂܂܊������g�傷��A���̌X���͂���ɉ������A���ӁA�܂����Ă���Â̂Ђ������N���Ă��܂��B���ꂩ��ċx�݂�4�A�x�A���~�x�݁A����ɂ̓I�����s�b�N������ƁA�l�̗��ꂪ�W�����Ă��܂��B�I�����s�b�N�̂��߂ɐ錾���s���킯�ł͂Ȃ����A���̑����������炵������Ƒ���s���A��Â̂Ђ�����h���˂Ȃ�Ȃ��v�Ƌ������܂����B����ɔ��g��́u���H�X���͂��߁A�����̐l���������ɂȂ�A����J������������Ƃ������Ƃ��s�������Ƃ��\���������đ���s���K�v������B�����̏[����N�`���ڎ�A���H�X�̔F�ؐ��x�ȂǁA�����i�߂�ׂ����Ƃ��\���ȃX�s�[�h�ōs���Ă��Ȃ��B���肢����ȏ�A����Ɍ��������A����ȏ�ɂ�������Ƒ��i�߂�p�������⎩���̂������Ȃ��ƁA�����̐l�̋��͓͂����Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B
�����o�ύĐ��S����b�́A���ȉ�̂��ƋL�Ғc�ɑ��A��ނ̒�~�̗v���Ȃǂɉ����Ȃ����H�X�ւ̑Ή��ɂ��āu���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��āA�v���▽�߁A�ߗ������i�ɑΉ����Ă����B���łɉߗ����Ȃ���Ă���X�܂����邪�A�v���ɉ����Ȃ���A���x�ł��葱�����Ƃ邱�Ƃ��܂߁A�����̂ƘA�g���āA�������Ή����Ă����v�Əq�ׂ܂����B�����āA���ȉ�ł́A����̎�舵�����߂����āA�ł������̎��Ԃ������ꂽ�Ƃ��āu�ʏ�m��������w�܂h�~���d�_�[�u�Ɂx�Ɨv�]���������������A�����Ґ����Â̏��w�X�e�[�W4�x�ł���A�錾���p�����錋�_�ƂȂ����B���P����w�i�߂A������҂������������肤��Ƃ������Ƃ����ȉ�Ƃ��Ċm�F���ꂽ�v�Ɛ������܂����B���̂����Łu����́A�Ă͊ό��q�������ɂ��키�����ŁA�{���ɑ�Ȏ������������[�u�ő����邱�ƂɂȂ�A�����̊F����̐S����悭������B���Ƃ������g���}���A�����ɉ��P���Ă�����悤���͂����肢���������A���Ƃ��Ă������������v�Əq�ׂ܂����B�����āA������b�́u�ً}���Ԑ錾�̂��тɁA�����g�́w�����Ō�ɂ������x�Ǝv���Ă��邪�A���ɍ���́A�ł���Ō�ɂ������Ƃ����C���������������Ă���B���N�`���ڎ��i�߂Ȃ��犴���g���}���A��Ò̐�������I�Ȃ��̂ɂ��Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
������āA���{�́A�O�Q���@�̋c�@�^�c�ψ���ɕ��A���^���s������ŁA�ߌ�5������J�������{���Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�����āA8���ߌ�7�����߂ǂɐ�������b���L�҉���A�����ɐ錾���o�����R�Ȃǂ�������A�����ɗ����Ƌ��͂��Ăт����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���{��t��̊��ˏ�C�����́A���ȉ�̂��ƋL�Ғc�ɑ��A�ً}���Ԑ錾�ɂ��āu���ɒ����ɂ킽�邪�A�ċx�݂̌������z�����ړ��̋@��̑傫����������������J�o�[����Ƃ����Ӗ��ł͕K�v���Ǝv���B�e�����ɂ߂đ傫���̂ŁA�����P���ĉ����̕����ɂ����Ă�����̂ł���A��������Ɣ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B����A�錾�̊��Ԓ��ɓ����I�����s�b�N���J�Â���邱�Ƃɂ��āu���̂悤�ȏŁA�����ɑ��郁�b�Z�[�W���������������̂ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA��������Ǝ蓖�Ă��K�v���Ƃ����c�_�ɂȂ����v�Əq�ׂ܂����B
�o�ς̐��ƂƂ��ĕ��ȉ�̈ψ��߂�A�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O�̒|�X�������́u��a�̌��f�Ƃ������A�����ő����Ă��銴�������{�S���ɍL�܂�̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӎ�����o���[�u�������B�����̋��͂��ǂ���������A�������l�������Ă���w���܂ł��x�Ƃ����t���X�g���[�V�����ɁA�ǂ��Ή����Ă��������d�v�ȋc�_�������v�Əq�ׂ܂����B�܂��A�����I�����s�b�N�̊ϋq�̈������߂���u�������Ŗ��ϋq�ɂ���I�����͂��邩������Ȃ����A���ʂ̖싅��T�b�J�[�̎�����5000�l�����Ă���̂ɁA�Ȃ��I�����s�b�N�����Ȃ��ɂ��Ȃ�������Ȃ��̂��A�b���������Ȃ��B���ϋq�œ˂����݂����̂Ȃ�A�ق��̃X�|�[�c�̎��������ϋq�ɂ�������v�Əq�ׂ܂����B
����} �ܗ֊J���O�ɗՎ�����W��v�� �ً}���Ԑ錾���ʂ��� �@7/8
�ً}���Ԑ錾�̔��o���ɁA�����I�����s�b�N���J�Â���錩�ʂ��ƂȂ������Ƃ���A��}���́A�����҂̋}���ȂǁA�s���̎��Ԃɔ�����K�v������Ƃ��āA����23���̃I�����s�b�N�J���O�ɗՎ���������W����悤�^�}���ɋ��߂܂����B
���{�́A�����s�ɁA����12�����痈��22���܂ŁA4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o�����j�ŁA����23���ɊJ�����铌���I�����s�b�N�͐錾�̊��Ԓ��ɊJ�Â���錩�ʂ��ł��B
������āA��������}�A���Y�}�A��������}�̍����ψ����炪��k���A����Ƃ��Ă������҂̋}���ȂǕs���̎��Ԃɔ�����K�v������Ƃ��āA�J���O�ɁA�Վ���������W���ׂ����Ƃ����F���ň�v���܂����B
�����āA��������}�̈��Z�����ψ������A�����}�̐X�R�����ψ����Ɖ�k���ėՎ�����W�����߂��̂ɑ��A�X�R���͎����A���Č�������l���������܂����B
�܂����Z���́A8���ߌ�J�����O�Q���@�̋c�@�^�c�ψ���ɐ�������b���o�Ȃ��Ď��^���s���悤���߂��̂ɑ��A�X�R���́A�ے�I�ȍl����`���܂����B
�����}�̐X�R�����ψ����́A�L�Ғc�ɑ��u���̂�����R�����s���A���傤���c�@�^�c�ψ�����J���̂ŁA��ł�����Ƃ��ăX�s�[�f�B�[�ɑΉ��ł���B�Վ�����̏��W�͋ɂ߂ĐT�d�ɂƎv���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
��������}�̈��Z�����ψ����́A�L�Ғc�ɑ��u���Ƃ̕����Ɋւ��悤�Ȏ��Ԃ��B�����Ɏ��l�����߂Ă����Ȃ��瓌���I�����s�b�N�͂��܂��Ƃ����A����Ȃ˂��ꂽ���Ƃ����Ȃ��獑��ŋc�_���Ȃ����Ƃ͐����s�M�ɂȂ���v�Əq�ׁA�^�}�������ۂ���A���@�̋K��Ɋ�Â��āA�Վ�����̏��W�����߂Ă����l���������܂����B�܂��AIOC�̃o�b�n��̗����Ɋ֘A���u�ꍇ�ɂ���Ă͍���ɗ��Ă��炤�K�v���o�Ă���B�Ȃ��I�����s�b�N���J���̂������������A�����P�ɓ��̊ۂ̊���U���Č}����悤�Ȋ��ł͑S���Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
���u���������v����ً̋}���Ԑ錾�p�����j�ɒm�� �@7/8
���ꌧ�̋ʏ�f�j�[�m����8���A�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾��8��22���܂Ōp�����������ƂȂ������Ƃɂ��āA�w�ɑ��A�u����������ƒ����ȂƎv���v�Əq�ׂ��B����8���ߌ�̑��{����c�ŁA�������Ԃ̑Ή������c������j�B
�ʏ�m����7���A�����o�ύĐ����ɑ��A�錾��������11���ʼn������A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ɉڍs����悤�v�����Ă����B������Ȃ��������Ƃ�w�ɖ���A�u�ċx�݁A�I�����s�b�N������A�����������ĉ��P���s���Ă����Ȃ��ƁA�����̊����Ċg�傪����ɂ��e�����Ă��܂��ƍl�����̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂��B
���͌��݁A�����̈��H�X�ɑ��A��ނ̒��l�ƌߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v�����Ă���B
����A�d�_�[�u����������錩�ʂ��̕������̕��������Y�m����8���A������ɂ��āA���H�X�ւ̎��Z�v������艺����ӌ������߂Ď������B�w�̎�ނɑ��A�u�����̐����������[�u�͕K�v�Ȃ��Ǝv���v�ƌ�����B
������ �ً}���Ԑ錾�����𗹏� ���{���J�� �Ώ����j����}�� �@7/8
���ꌧ�ɏo���Ă���ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ��A8��22���܂ʼn������鐭�{�̕��j���A���Ƃł��镪�ȉ�������܂����B���ꌧ��8���ߌ�A���{����c���J���A���݂̑���p����������ŁA�Ώ����j�̍�����}�����Ƃɂ��Ă��܂��B
���ꌧ�ɏo���Ă���ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ��A8��22���܂ʼn������鐭�{�̕��j����Ƃł��镪�ȉ�������܂����B
���ȉ�̖`���Ő����o�ύĐ��S����b�́A�V�K�����Ґ��̌����̃X�s�[�h�������Ă��邱�ƁA�d�ǎҗp�̕a���g�p����50�����āA�������ł��邱�ƁA�ẴV�[�Y�����}���A�l�X�̊�����ړ��������ɂȂ邱�ƂȂǂ��ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ��������闝�R�ɂ����܂����B
���ꌧ�́A�n��ɂ���Ċ������قȂ��Ă��Ă���Ƃ��āA���{�ɑ��Ēn����i���ďd�_�I�ɑ���s���u�܂h�~���d�_�[�u�v�ւ̈ڍs��7���v�����܂������A������Ȃ������`�ł��B
���ɏo����Ă���ً}���Ԑ錾�́A���Ƃ�5��23���Ɏn�܂��āA6��21������3�T�ԁA��������A����̉����Ő錾�̊��Ԃ�3�����ɋy�Ԃ��ƂɂȂ�܂��B
����8���ߌ���{����c���J���A�Ώ����j�̍�����}�����Ƃɂ��Ă��܂��B
���u�ً}���Ԑ錾�v��K�͏��Ǝ{�݂ɂ͋x�Ɨv���o���Ȃ������Œ��� �@7/8
4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o����錩�ʂ��ƂȂ��������s�ł́A��ޒɂ��Ă͒��~��v���������A�f��ق�S�ݓX�ȂǑ�K�͏��Ǝ{�݂ɂ��ẮA����̂܂܂Ƃ�������Œ������i�߂��Ă��邱�Ƃ��킩�����B
�����s�ł́A�܂h�~���d�_�[�u��7��11���Ɋ������}���邪�A�����Ȃǂ���A8��22���܂ŋً}���Ԑ錾���o����錩�ʂ��ƂȂ����B
�W�҂ɂ��ƁA���Ɠs�̋��c�̌��ʁA���Ԓ��A���H�X�ɂ͌����Ƃ��Ď�ނ̒̒��~��v�����A�ł��Ȃ��ꍇ�͋x�Ƃ�v������悤�������Ă���Ƃ����B
���̈���ŁA�f��ق�S�ݓX�ȂǑ�K�͏��Ǝ{�݂ɂ��ẮA�x�Ɨv���͏o�����A���݂̑[�u���p����������Œ������Ă��邱�Ƃ��킩�����B
�������s �f�p�[�g�Ȃǂւ̋x�Ɨv�����Ȃ����� 4��ڂ̐錾�� �@7/8
�����s�́A����E4��ڂً̋}���Ԑ錾�̂��Ƃł́A�O��̐錾�ōs�����f�p�[�g�ȂǑ�K�͎{�݂ւ̋x�Ɨv���͎��{���Ȃ������Œ������Ă��܂��B
�s���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����̍Ċg��Ɏ��~�߂�������Ȃ����A���{��4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o�����j�ł��B
�s�́A�V���Ȑ錾�̊��Ԓ��ɍu����[�u�̓��e���������Ă��āA����̓f�p�[�g��f��قȂǑ�K�͎{�݂ւ̋x�Ɨv���͎��{���Ȃ������Œ������Ă��܂��B
��K�͎{�݂ɑ��ẮA���Ƃ�4��25�������3��ڂً̋}���Ԑ錾�őS�ʓI�ȋx�Ƃ�v�����A�ĉ������ꂽ�挎1������20���܂ł͓y���݂̂̋x�Ɨv���⎞�Z�̗v���ɐ�ւ��܂����B
���݂́A�܂h�~���d�_�[�u�̂��Ƃʼnc�Ǝ��Ԃ�Z�k����悤�v�����Ă��āA4��ڂ̐錾�̂��Ƃł͋x�Ɨv���͍s��Ȃ����̂̎��Z�v�����p����������ł��B
����A�������H�̏�Ŋ������X�N��}���邽�߁A�O��̐錾�̂Ƃ��Ɠ��l�Ɉ��H�X�ɑ��Ă͎�����Ȃ��悤�v��������j�ŁA���{�̕��j�܂��ċ�̓I�ȑ[�u�̍�����}���ł��܂��B
�����s�̏��r�m���́A4��ڂً̋}���Ԑ錾�̂��Ƃň��H�X�ɑ��Ď��̒̒�~�����߂���j�ɂ��āu�������}���ƍl���Ă��邩�v�ƋL�Ғc������ꂽ�̂ɑ��āu�������}��������B�����Ɏ��������グ�邩�Ƃ������Ƃ��d�v���B�����I�ɍl���Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
������ �ً}���Ԑ錾�Łg��Ȃ��h�ėv���� �������̊m�ۉۑ� �@7/8
4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����錩�ʂ��ƂȂ��������s�́A�O��̐錾�̂Ƃ��Ɠ��l�Ɉ��H�X�Ɏ�����Ȃ��悤�v����������Œ������Ă��܂��B�����A���яd�Ȃ鎞�Z��x�Ƃ̗v���ɉ����Ȃ��X�������Ă��āA�������̊m�ۂ��ۑ�ƂȂ�܂��B
�����s���ł́A7���A�����m�F��900�l����ȂǍĊg��Ɏ��~�߂������炸�A���{�́A4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o�����j�ŁA8���̑��{���Ő����Ɍ��肵�܂��B
�s�́A�V���Ȑ錾�̊��Ԓ��ɍu�����Ƃ��āA6��20���܂ł�3��ڂ̐錾�̂Ƃ��Ɠ��l�Ɉ��H�X�Ɏ�����Ȃ��悤�v����������Œ������Ă��܂��B�܂��A���Ȃ��X�ɂ͌ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ����߂���j�ł��B�����A����܂ł̂��яd�Ȃ鎞�Z��x�Ƃ̗v���ň��H�X�̌o�c�͂���Ɍ������Ȃ��Ă��āA�����Ȃ��X�������Ă��邱�Ƃ�����������m�ۂł��邩���ۑ�ƂȂ�܂��B
�܂��A�J����2�T�Ԍ�ɔ����������I�����s�b�N�́A�ً}���Ԑ錾���o�����Ȃ��ł̊J�ÂƂȂ錩�ʂ��ł��B���ϋq�Ƃ���Ă���������Ă�����̂́A�s���⎖�Ǝ҂ɐ�������߂�Ȃ��ŊJ�Â̕��j���ێ����邱�Ƃɑ����̎x���������邩�͕s�����ł��B
���Îs�������@4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�u�o��������A�ܗւ͂�߂�v�@7/8
�Љ�w�҂̌Îs������(36)��8���A�t�W�e���r�̏��ԑg�u�߂��܂�8(�G�C�g)�v(���`���j�O8�E00)�ɏo���B���{�������s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾��12�����甭�߂�����j���ł߂����ƂɌ��y�����B
���{�́A�܂h�~���d�_�[�u���������铖�����j����]�������B23���ɊJ����}���铌���ܗւ̓s���̉��ϋq�Ƃ�������Œ�������B���ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�͉�������B��ʁA�_�ސ�A��t�A���̊e�{���̂܂h�~���d�_�[�u�͉������錩�ʂ��B�������8��22���������B�����t���Ōߌ�7���܂ŗe�F���Ă����d�_�[�u�̒n��ł̎�ޒ͌�����~�Ƃ���B
�Îs���́u�ً}���Ԑ錾�͏d���錾���Ǝv���܂���B����ς���H�X�̕����͂��ߌl�̎��R�𐧌�����킯����Ȃ��ł����B�����`�A���R��`�̂��̓��{�ɂ����āA����𐧌�������Ă������d�����ƁB�d�����Ƃ�����ɂ�������炸�ܗւ�������ă`�O�n�O���Ǝv���v�Ǝw�E�B�����āu�{���ɍ����ً}���Ԃ��Ǝv���Ă���Ȃ�A�����s�����̂��̏�Ԃ��ً}���Ԃ��Ǝv���Ă���Ȃ�Όܗւ͂�߂�ׂ��ł�����Ă����c�ً}���Ԓ��ɂ�������炸�ܗւ�������Ă����̂́A�l�l�Ƃ��Ĕ[���ł��Ȃ����v�ƌ����A�u�l�͌ܗւł���Ǝv����ł��B�ł���Ǝv����ł����ǁA�ً}���Ԑ錾���o��������A���Ⴀ�ܗւ͂�߂���Ďv�����Ⴂ�܂��ˁv�Ǝ��g�̍l�����q�ׂ��B�@
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
��������@������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�@7/8
�����ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�͉���
�i��F��������萛���t������b�̋L�҉���s���܂��B���߂ɐ��������甭�����������܂��B����ł͑����A��낵�����肢�������܂��B
���F����3���A�É����M�C�s�Ŕ��������y�Η��́A����܂ł�9���̕��̎��S���m�F�����Ȃǐr��Ȕ�Q�����������Ă���܂��B�܂��A�����e�n�ł���Q���������Ă��܂��B�S���Ȃ�ꂽ���X�̂����������F�������ƂƂ��ɁA��Q�ɑ���ꂽ�S�Ă̊F���܂ɐS��肨��������\���グ�܂��B�M�C�s�ł͌��݂�20��������X�̈��ۂ��m�F�ł��Ă��Ȃ��Ƃ̕��Ă���A�x�@�A���h�A�C��ۈ����A���q����2000������Ԑ��Ō����ɋ~�������ɓ������Ă���܂��B�����������₩�ȋ~���Ɣ�Ў҂̎x���ɑS�͂������Ă܂���܂��B
��قǐV�^�R���i���{�����J�Â��A�����s�ɋً}���Ԑ錾�o���邱�ƁA���ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�͉������邱�ƂƂ��A���Ԃ����ꂼ��8��22���܂łƂ��邱�ƁA�܂h�~���d�_�[�u�ɂ��Ă͍�ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{�ɂ���8��22���܂ʼn������A�k�C���A���m���A���s�{�A���Ɍ��A�������ɂ���7��11���������ďI�����邱�Ƃ����肢�����܂����B
�������Ґ��͖��炩�ȑ����ɓ]���Ă���
4���̏��{���[�u�𑱂��Ă܂���܂������A���̊ԁA���N�`���̐ڎ킪�啝�ɐi�W�����A�S���̑����̒n��ɂ����ĐV�K�����҂̌����������Ă���܂��B�d�ǎҐ����啝�Ɍ������A��Â̌��ꂩ��͕��S���y������Ă����Ƃ��������������Ă��܂��B���q������ш�Ï]���҂̊F����ɐS��芴�ӂ�\���グ�܂��B
�����������ł��A�c�O�Ȃ����s���ɂ����Ă͊����҂̐��͖��炩�ȑ����ɓ]���Ă��܂��B���̗v����1���l���̍��~�܂�ɉ����āA�V���ȕψي��ł���f���^���̉e���ł���A�A���t�@����1.5�{�̊����͂�����Ƃ��w�E����Ă��܂��B�f���^�����}���Ɋg�傷�邱�Ƃ����O������܂��B
����Ŋ����ɂ́A�]���Ƃ͈قȂ閾�炩�ȕω��������Ă��܂��B�����ł͏d�lj����X�N�������Ƃ���鍂��҂̃��N�`���ڎ킪70���ɒB���钆�A�ꎞ��20�����Ă��������҂ɐ�߂鍂��҂̊�����5�����x�܂łɒቺ���Ă��܂��B����ɔ����d�ǎҗp�̕a�����p����30����Ő��ڂ���ȂǁA�V�K�����҂��������钆�ɂ����Ă��d�ǎ҂̐���a���̗��p���͒Ⴂ�����ɂƂǂ܂��Ă���܂��B
�������Ȃ��瓌���̊����g��͑S���ɍL���肤����̂ł���܂��B�ċx�݂₨�~�̒��ő����̐l���n���ֈړ����邱�Ƃ��\�z����܂��B���N�`���ڎ킪�傫���i�݁A�V�^�R���i�Ƃ̓����ɂ���肪�����Ă������ŁA�����ōēx�A�������N�_�Ƃ��銴���g����N�������Ƃ͐�ɔ����Ȃ���Ȃ�܂���B���������v���ŁA�����ŗ\�h�I�[�u���u���邱�ƂƂ��A�����s�ɋً}���Ԑ錾�����ЂƂ��є��o���锻�f���������܂����B�[�u�̊��Ԃ͂��~������8��22���܂łƂ������܂����A���N�`���̌��ʂ�����ɖ��炩�ƂȂ�A�a���̏Ȃǂɉ��P��������ꍇ�ɂ͑O�|���ʼn��������邱�Ƃ����f���������܂��B
�O��̐錾���������Ă���3�T�ԂōĂѐ錾�Ɏ���A�����̊F���܂ɂ��܂��܂Ȃ����S�����|�����邱�Ƃ͑�ϐ\����Ȃ��v���ł���܂��B�������Ȃ��炱�̊��Ԃ����z���āA�K�����S�̓�������߂��Ƃ̌��ӂŎ��g��ł܂���܂��B
��̓I�ɂ͓����E����ł́A���H�ɂ�銴�����X�N�����炽�߂ĕ������߂邽�߂ɁA���H�X�ɂ������ނ̒��ꗥ�ɒ�~�������܂��B�܂h�~�[�u�̑ΏۂƂȂ�n��ł���ނ̒͌�����~�Ƃ��A�n��̏ɉ����Ĕ��f���������܂��B���H�X�ɑ��鋦�͋��̎x���̒x�������A�c�Ƃ⎞�Ԃ̒Z�k���ނ̒̃��[���ɂ����͂��������Ȃ��X�܂������Ă���Ƃ̂��w�E������܂��B
�����H�X�ւ̋��͋����O�x�������\��
�܂��A�����̈��H�X�ɂƂ��Ă����̒��c�Ƃ𑱂����ł̎������ƂȂ��Ă���Ƃ����������ɂ��܂��B�x���̒x�ꂪ�o�c���ɒ������邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA����܂ł̋��͋����ȈՂȐR���ő��₩�Ɏx������ƂƂ��ɁA����̑[�u�ɂ����͂�����������H�X�ɑ��Ă͋��͋������O�Ɏx�������Ƃ��\�Ƃ��܂��B
�����ɁA����A�e�s�{���ɂ����Ĉ��H�X�ւ̌������g�債�A��̎����������߂Ă܂���܂��B���������H�͂ǂ����Ă��}�X�N���O�����Ԃ������Ȃ�A�傫�Ȑ��ł̉�b���������܂���B���H�X�̊F����ɂ͓x�d�Ȃ邨�肢�ɑ�ϐ\����Ȃ��v���܂����A���܈�x�A���Ƃ������͂����肢�\���グ�܂��B
�܂��A�����ł�20�ォ��50��̊����҂��}�����A40��E50��ł͏d�ǎ҂������Ă��܂��B�E���ƒ���̊����������ɂȂ��Ă��܂��B�}�X�N�A��A3���̉���Ƃ�����{�I�Ȋ������O�ꂵ�A�Ƃ�킯��b�̍ۂɂ̓}�X�N�𒅗p����悤���肢���������܂��B
�S���̒ÁX�Y�X�Ń��N�`���ڎ�̉������i��ł��܂��B���q�����ÂȂǂ̊W�҂̂��s�͂ɂ��A���␢�E�ł��ł��X�s�[�h�Őڎ킪�s���Ă���Ƃ����Ă��܂��B1�T�Ԃ̐ڎ��900������Ă��܂��B�{�i�I�Ȑڎ킪�n�܂��Ă���2�J���]��ŗv�̉�5400������A���łɍ���҂�72���A�S������27����1��̐ڎ���I���Ă��܂��B
��s���ă��N�`���ڎ킪�i�߂�ꂽ���X�ł̓��N�`����1��ڎ킵�����̊������l����4���ɒB�����ӂ肩��A�����҂̌����X�������m�ɂȂ����Ƃ̎w�E������܂��B���̃y�[�X�Ői�߂������ɂ͊�]���鍂��҂�2��̐ڎ�͊������A��x�ł��ڎ킵���l�̐��͑S������4���ɒB���錩�ʂ��ł���܂��B
���ڎ킪�~���ɐi�ނ悤�w�߂�
����A�\�z������y�[�X�Őڎ킪�i�ޒ��ŁA�ꕔ�̎����̂Ȃǂ��烏�N�`��������Ȃ��Ƃ̐���������܂��B�S�̂Ƃ��đS���̎����̂ɂ͐挎�܂ł�9000����̃t�@�C�U�[�Ђ̃��N�`�����l���ɉ����Ĕz������Ă���܂��B���̂���4000�����g�p���ꂸ�ɍɂƂȂ��Ă���ƌ����܂�܂��B���̏��7������9���ɂ͖���2500�����z������܂��B���̂��ߍɂ����킹�Ċ��p���Ă���������A1��120������x�̃y�[�X�Őڎ�𑱂��Ă������Ƃ��\�ł��B���N�`���̔z�����@�ɂ��Ă���������A�ڎ�̐i�ގs�����ɑ����z���ł���悤���������s�����ƂƂ��A�܂��A�z���ʂ��ł��邾�������ɂ��������邱�Ƃɂ���āA�ڎ킪�~���ɐi�ނ悤�ɓw�߂Ă܂���܂��B
�����āA���f���i�Ђ̃��N�`��������܂ł�1400���m�ۂ���A9���܂ł�3600�����lj�����܂��B��������p������Ƃ��w�Ȃǂ̐ڎ�ɂ��Ă��A��T�܂ł�200����̐ڎ킪�s���܂����B�t�����\���̐����𑬂₩�ɍs���A�m���ɑΉ����Ă܂���܂��B�����̊F���܂ɑ�ςȂ��S�z�����|�����܂������A���̂悤��9���܂łɊ�]�����S�Ă̍����ɐڎ킪�\�ƂȂ�2��2000���̏\���ȗʂ��m�ۂ���Ă���܂��B���₩�ɐڎ�ɖ��S��s�����Ă܂���܂��B
�I�����s�b�N�̊J���܂ł���2�T�Ԃł��B�ً}���Ԑ錾�̉��ňٗ�̊J�ÂƂȂ�܂����B�C�O����I��c�A���W�҂������A�������Ă��܂��B�����O��2��A�������̌����ɉ����A��������I��͖����A�������s���Ă���A�E�C���X�̍����ւ̗�����O�ꂵ�Ėh���ł܂���܂��B�I�����W�҂̑����̓��N�`���ڎ���ς܂��Ă���A�s���͎w�肳�ꂽ�z�e���Ǝ��O�ɒ�o���ꂽ�O�o��Ɍ��������A��ʂ̍����̊F����ƐڐG���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɊǗ�����܂��B
�������ɂ��āA���͂���܂ŁA�ً}���Ԑ錾�ƂȂ�Ζ��ϋq�������Ȃ��A���̂悤�ɐ\���グ�Ă��܂����B�����������ŁA���̂��Ƃ̑g�D�ψ���A�����s�AIOC�ȂǂƂ�5�ҋ��c�ɂ����Ċϋq�̎�舵�������߂���\��ł��B���E��40���l���e���r��ʂ��Ď�������Ƃ�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ́A���E���̐l�X�̐S��1�ɂ���͂�����܂��B�V�^�R���i�Ƃ����傫�ȍ���ɒ��ʂ��鍡�����炱���A���E��1�ɂȂ�邱�Ƃ��A�����đS�l�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���ē�ǂ����z���Ă����邱�Ƃ��A�������甭�M���������Ǝv���܂��B
�܂��A�����͎j�㏉�߂ăp�������s�b�N���x�A�J�Â���s�s�ƂȂ�܂��B��Q�̂�������Ȃ������A���N������҂��A�݂�Ȃ����������ċ��ɐ�����Ƃ��������Љ�̎����Ɍ������S�̃o���A�t���[�̐��_����������`�������Ǝv���܂��B
�����j�Ɏc���������������
����̑��͑����̐�����A����܂ł̑��ƈقȂ�܂����A�����炱�����S�E���S�ȑ��𐬌������A��������q�������ɖ��Ɗ�]��^����A���j�I�ȁA���j�Ɏc����������������Ǝv���܂��B
��N���A��i��ނ̊��������A�����̊F���܂ɂ͂��̓x�ɂ����f�����|�����Ă܂���܂����B���m�̓G�Ƃ̓����͎��ɂƂ��Ă��S���x�܂�Ƃ��͂���܂���B�������A���N�`���ɂ���āA�ψي��ł����Ă����ǂ�d�lj���傫���h�����Ƃ��ł��܂��B���Ö�̊J�����i��ł��܂��B���A�K�v�Ȃ��Ƃ́A������}���Ȃ���1�l�ł������̕��Ƀ��N�`����ڎ킵�Ă����������Ƃł��B����ɂ���ĐV�^�R���i�Ƃ̓����ɏI�~����ł��āA���S�ł�������K�����߂����Ƃ��ł���ƐM���Ă��܂��B�F���ܕ��̂������Ƃ����͂�S���炨�肢�\���グ�܂��B
|
���L�Ҏ���
�i��F����ł́A���ꂩ��F���܂�育��������������܂��B���g��ɂ�����܂��Ă͏���̈ʒu�ɂ��i�݂��������B������̓��e�ɂ��܂��āA���g��ɂ����������������܂��B�w�������܂������͂��߂��̃X�^���h�}�C�N�ɂ��i�݂��������܂��āA�����Ƃ����O�𖾂炩�ɂ��Ă�����������ŁA1�₸����������肢�������܂��B�܂��A�����Ђ��炲��������������܂��B�k�C���V���A��������A�ǂ����B
����̓^�C�~���O���x���A���e���s�\���������̂ł�
�k�C���V���F�k�C���V���̍����ł��B�����ɂ��f�����܂��B������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ł��B�����ł́A�܂h�~�[�u��ً}���Ԃ���������Ȃ�������3�J�������Ă��܂��B�����͖���A������}�����ނƑi���Ă��܂����A�͉ʂ����ꂸ�A���܂ł���Ȑ��������炾�瑱���̂��ƁA�����̔�J��s�M���̓s�[�N�ɒB���Ă��܂��B���{�̂��̊Ԃ̑�́A�����g��̌��ʂ��̊Â�����1��1�̃^�C�~���O���x���A���e���s�\���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����̐ӔC�ƕ����ĔF�����f���܂��B
�܂��A�x�d�Ȃ�錾�ł��̌��ʂ�����Ă���Ǝv���܂����A����̑�Ŏ������͏\���Ȃ̂��A���Ō�̐錾�ƌ������̂��A���������������B����ɁA���ɂȂ���������͕��ʂ̐����ɖ߂��̂��A���̌��ʂ��𑍗��̌��t�ō����Ɍ���Ă��������B��낵�����肢���܂��B
���F�܂��A���N�ɓ����ē�x�ً̋}���Ԑ錾�����肢�����Ă���܂����A����A�����Ґ���a���̏A�����ɂ��Ĕ��f���s���A���H�𒆐S�ɂł������I���i���đ����Ɋ������s�[�N�A�E�g������A���̂��߂Ɏ��g��ł��܂����B���̒��ō����̊F����⎖�Ǝ҂̕��X�ɂ͑�ς����f�����|�����A�܂��A�����͂������Ă���܂����ƂɊ��ӂ�\���グ�܂��B
����������i��ނ̏���E���āA������̌��ߎ�ƂȂ�̂����N�`�����Ǝv���Ă��܂��B7�����܂łɂ͊�]����65�Έȏ�̍���҂̊F�����2��ڎ�A�S���ŏI������A���̗\��ł���܂��B�܂��A����A���E�����Ă݂܂��Ă��A���E�͓��{�����͂邩�Ɍ��������b�N�_�E�����s���A�����ĊO�o�֎~�A�����A���������������ɂ����Ă��A����ƂȂ��������Ƃ��J��Ԃ��Ă��Ă���Ƃ������Ƃ���������Ȃ��ł��傤���B�܂��ɂ��������Ӗ��ŁA���N�`����ڎ킷�邱�Ƃɂ���āA���Ă̓�������߂����Ƃ��ł���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�ł�����A�����̐V�K�����ҁA���A���������Ă��܂��B����҂̊�����d�ǎ҂����Ȃ��A�����������Ƃ͖��炩�ɍ���҂̊F����ɐڎ���n�߂Ă��܂�����A�����͑傫���ς���Ă��邱�Ƃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�܂��A��������S���ɔ�щ����邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA��ρA�S�ꂵ�����f�ł���܂�������ǂ��A����A�ً}���Ԑ錾�o�������Ă��������܂����B�������ă��N�`���ڎ킪�i�݁A���ʂ������܂ŁA�S���I�Ȋ���������h�����߂̑[�u�Ƃ��Ă��������������������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
��1��������4���ɓ��B���邱�Ƃ��厖
���O���̗�����Ă��A�S�l���̖�4����1��ڎ킪�B�����ӂ肩��A�܂��ɂ��̊����҂Ƃ����̂͌����X���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ����m�ɂȂ��Ă��܂��B����������������߂����߂ɂ́A1������������4���ɓ��B���邱�Ƃ��厖���Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B7�����ɂ͂��Ђ�����ڎw���Ă��������A���������ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�k�C���V���F�Ō�̐錾�ƌ������̂��ǂ������₵�Ă��ł�����ǂ��B
�i��F�lj��̂�����͂��T�����������B
���F��Ɏ����g�́A���܂ł��̊�������s���Ă��܂������ǁA���N�`���Ƃ����͍̂��߂Ăł��B���E�͂��̃��N�`���ɂ���āA���Ă̓�������߂��Ă��鍑���o�n�߂Ă��܂��B�ł����烏�N�`���ڎ���ŗD��ōs���Ă���Ƃ���ł���܂��B���̂��Ƃɂ���đ傫���ς�邾�낤�ƁA�����͋����M�O�������č�����Ă��܂��B
�搶����낵���ł����B
������1�`2�J���͍ł��d�v�ȎR���1��
���g�F���������ł��̂ŁA���A��������̂��w��������܂����̂ŁB���͍���A���������ɑ��ċً}���Ԑ錾�o����Ƃ���������A�����̐��Ƃ̂ق��ɏo���ꂽ�킯�ł����ǁA�������͂���Ɏ^���������܂����B���̗��R�͑傫�������āA���́A�w�i�Ƃ����܂����A4�������Ǝv���܂��B
1�ڂ́A���ꂩ��̂���7���A8���A����1�`2�J���Ƃ����̂́A���́A���܂�1�N���ȏ�ɂ킽���čs���������̃R���i��A���g�݂̒��ŁA�ł��d�v�ȎR���1���Ǝv���܂��B���ꂪ1�ł��ˁB���ꂩ��A����������������������悤�ɁA���A�������̋����Ǝv����f���^���̒u������肪���������ɐi��ł���Ƃ������Ƃ�����܂��B
���ꂩ�烏�N�`�����������Ɍ��ʂ��A����҂𒆐S�ɏo�Ă��Ă���܂�����ǂ��A1�����A�����̌��O�A���Ȃ��ً}���Ԑ錾�o����̂��������Ǝv����1�̑傫�ȗ��R�́A���͍���҂̏d�lj��Ƃ����͔̂�r�I�A���A���N�`���̂������ŏ����}�����Ă��܂����A���͂���A�����炭�f���^���̉e�����Ǝv���܂����A40��A50��̔�r�I�Ⴂ�N��w�̏d�lj��A���ꂩ����@����A���ۂɐl�H�ċz����g���悤�Ȑl���A���܂ł̑�3�g�A��4�g�ɂ͌����Ȃ��������Ƃ�����܂��B
�]���č���́A����������������悤�ɁA���Ԃ́A������Ō�̂Ƃ������ƂɊ��҂��܂��B���ꂩ�牽�����邩������܂��ǁA���N�`��������i��ł��܂��̂ŁA���̑O�ɁA����1�`2�J���̊ԂɁA���Ƃ��Ă�����40��A50��́A���ꂪ���Ȃ�X�s�[�h�������ӂ��ɁA���@���Ґ��A�d�ǎҐ��������Ă��܂��̂ŁA���̊��ԂɂȂ�Ƃ����āA���ꂪ�A����������Ɋg�債�Ĉ�Â̕N���A���̂܂ܕ����Ă����Ƃ����Ȃ�W�R�������Ȃ荂���Ƃ����͔��f���Ă��܂��B���������Ӗ��ō���A���̂ق��������������f�����Ă������������Ƃɑ��āA����������ɂ��Ă͑S����v�ō��ӂ����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�i��F����ł͑����܂��āA�Y�o�V���A���{����A�ǂ����B
�����ϋq�ł��ܗւ̈Ӌ`�͂���̂�
�Y�o�V���F�Y�o�V���̐��{�ł��B��낵�����肢�������܂��B�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��Ă��f���������܂��B�����͂���܂ŁA�ً}���Ԑ錾�����߂����Ζ��ϋq�������Ȃ��Ƃ������l����������Ă��܂����B��قǁA�����A�`�������ŃI�����s�b�N�̈Ӌ`�ɂ��āA���E��1�ɂȂ�邱�ƁA�l�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���āA�R���i�����z�����邱�ƂM����Ƃ����ӂ��ɂ�����������Ǝv����ł�����ǂ��A���ϋq�ł������Ƃ��Ă����������Ӌ`�Ƃ����̂͂���Ƃ����ӂ��ɂ��l���ł��傤���B
�����܂��āA7�J����ɂȂ�܂�����ǂ��A���N2���ɂ͒����̖k���œ~�̃I�����s�b�N���J�Â���܂��B�����炭�������{�́A�����̐����V�X�e�����R���i�ɏ��������ł���Ƃ����ӂ��Ȑ�`�������Ƃ��ăI�����s�b�N�𗘗p����Ƃ������Ƃ��l������Ǝv���܂�����ǂ��A���̑O�Ɏ��R��`���Ƃł�����{���I�����s�b�N���J�Â���Ƃ������Ƃ��ǂ̂悤�ȃ��b�Z�[�W�����Ƃ����ӂ��ɑ����͂��l���ɂȂ�܂��ł��傤���B��낵�����肢���܂��B
���F�܂��������̈Ӌ`�ɂ���2�\���グ�����Ǝv���܂��B��͂�1�ڂ͐V�^�R���i�̒��ł̈��S�E���S�ȑ��̎����A�܂��ɐl�ނ�����ɒ��ʂ��钆�ɂ����āA�������炱�����E��1�ɂȂ��A�͂����킹�Ă��̓�ǂ����z���Ă���A�����������Ƃ���͂萢�E�ɔ��M���邢���@��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
�����2�ڂ͂�͂�p�������s�b�N�ł��B64�N�̓����I�����s�b�N�̍ۂɁA���߂ăp�������s�b�N���Z�A�p�������s�b�N�Ƃ������̂����̂Ƃ��납��g��ꂽ�B���������Ӗ��ŗ��j�I�ȑ��ł���܂����B�����ď�Q�҂̊F����͂��̑��̒��ŎЉ�i�o�Ƃ������̂����悤�Ƃ����A1�̑傫�Ȍ_�@�ɂȂ����ƁA����A�����Ă��Ă��܂��B
�����E�ɔ��M�ł���ō��̋@��
�����������ŁA���̃R���i�̌��������ŁA��Q�̂���l���Ȃ��l���A�܂��A���N�����Ⴂ�l���A���́A���ɏ��������Ƃ��������Љ�A���̎����Ɍ����āA�܂��ɐS�̃o���A�t���[�A�����������̂���͂萢�E�ɔ��M����Ƃ������Ƃ͋ɂ߂đ厖���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
����ƁA���x�̑��Ƃ����̂́A���ꂩ��ǂ����邩�Ƃ������Ƃ�5�҉�c�Ō��߂�킯�ł�����ǂ��A���E��40���l�̐l���e���r�ł��̃I�����s�b�N�E�p�������s�b�N����������A���������Ă���܂��B���������Ӗ������ɂ����āA���̑��Ƃ����̂͐��E�ɔ��M�ł���ō��̋@��ɂȂ�A���̂悤�ɂ��v���Ă���܂��B
G7�̐�ʂ̃T�~�b�g�ɂ����āA���̐錾�ɂ����L����Ă��܂�����ǂ��A���{�����炱�����������Ƃ��ɃI�����s�b�N�E�p�������s�b�N�A������J�Âł���A�������F����F��Ƃ����A����������|���錾�̒��ɏ������܂�Ă���܂��B���������Ӗ��ɂ����ẮA�e���̊��҂ɂ��������艞������A�����������ɂ������ƁA���������ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�i��F����ł́A�����芲���ЈȊO�̕����炲����������Ǝv���܂��B���������]�������͋�������肢�������܂��B������Ŏw���������Ă��������܂��̂ŁA�}�C�N�ɂ��i�݂��������B�Ȃ�ׂ������̕��ɂ����₢���������߂ɂ��A�����1�₸�Ȍ��ɂ��肢�������Ǝv���܂��B�����͂����肢�������܂��B����ł́A���{�e���r�̎R�肳��A�ǂ����B
�������҂����������ꍇ�̐ӔC���ǂ��l����H
���{�e���r�F���{�e���r�̎R��ł��B��قǁA�����͓����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��Ĉٗ�̑��ɂȂ�Ƃ������Ⴂ�܂����B�ً}���Ԑ錾���̊J�ÂɂȂ�܂�����ǂ��A�����͑O��̉�ŁA�������ɂ��āA�����̈��S�E���S�����̂͑����Ƃ��Ă̎��̎d���ł�����A�����ӔC�������čs���Ɩ������܂����B���������ً}���Ԑ錾���̊J�ÂƂȂ�킯�ł����A�����҂����������ꍇ�̐ӔC�ɂ��āA�����͂ǂ̂悤�ɍl���Ă��܂����B
���F�܂��A�ً}���Ԑ錾�̒��ł��ꂩ������}����킯�ł���܂��B�����������ɁA����A�ً}���Ԑ錾�̒��ɑ傫�Ȑ��ʂ��グ�Ă��Ă����̂��A��͂��ނ̒�~�ł��B���H�X�̎�ނ̒�~�A�����͑傫�Ȑ��ʂ��A���̊����g��h�~�ɂ��Ă͏グ�Ă��Ă���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�����������ŁA�܂��A���ً̋}���Ԑ錾�̒��ł���܂�����A�����������Ƃ͓��R�A��ނ͒�~�ɂȂ�܂��B�܂��A�܂h�~�[�u�̂��ꂼ��̎����̂ɂ��Ă��A���̎�s�A3���ł����A�����ȊO�́A���������Ƃ���ɂ����ꂪ�K�p�����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�����������Ƃ̒��ŁA��͂���S�E���S�Ƃ������Ƃɂ��āA�R���i�̊����g��[�u�Ƃ������̂��܂߂āA�����������낢��ȑΉ��A���邢�͂���A�l���������Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ă��܂�����ǂ��A����͌�ʋK�����邢�̓e�����[�N�A����͂����ԑO����O�ꂵ�čs���Ă��Ă��邱�Ƃł�����ǂ��A�����������Ƃɂ���āA���S�E���S�̑��������ł���ƁA���������ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�i��F�����܂��āA����ł͉��̗�A�V������̉��R����A�ǂ����B
���n���ō������N���Ă��邱�Ƃւ̎~�߂�
�V������F�V������̉��R�Ɛ\���܂��B��낵�����肢���܂��B�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���̋����ɂ��Ă��f�����܂��B������̃t�@�C�U�[���̃��N�`�������̌��ʂ��������Ȃ����Ƃ���A�V�������ł����N�`���ڎ�̗\����ꎞ��~�����艄�������肷��s�������o�Ă��܂��B����́A����͑卬���ɂȂ��Ă���A���̌����݈Ⴂ���ƌ����������オ���Ă��܂��B�܂��A�����̊Ԃɂ����łĂ�̂��ƕs�����L�����Ă��܂��B�����̓��N�`���̐ڎ���قǂ������ς葁���i�߂����Ƃ���������Ă����܂�����ǂ��A�����������ŁA�n���ł��ꂾ���������N���Ă���Ƃ������Ƃɂ��āA�����ɂǂ̂悤�Ɏ~�߂Ă�����̂������������������B
�܂��A��قǃ��N�`���̔z���ʂ𑁊��Ɏ����Ƃ������Ⴂ�܂������A������ꍏ�����������Ăق����Ƒ����̎����̂��v���Ă���Ǝv���܂��B��̓I�ɂ����남�����ɂȂ�\��ł��傤���B��낵�����肢�������܂��B
���F�܂��A��]���鍑���̊F����ɂł�����葁�����N�`���ڎ���s���ׂ��A�S���Ń��N�`���ڎ킪�������Ă��܂��B��قǐ\���グ�܂�������ǂ��A��i���̒��ł��ł������X�s�[�h���Ƃ����Ă��܂��B
����A�\�z������y�[�X�Őڎ킪�i�ޒ��ŁA�ꕔ�̎����̂��烏�N�`��������Ȃ��ƕs���̐���������Ă���܂��B��قǐ\���グ�܂�������ǂ��A�S���ɂ���6�����܂ł�9000����̃t�@�C�U�[�̃��N�`���ɂ��ẮA���ꂼ��̐l�����Ŕz�点�Ă��������Ă��܂��B������6�������ς��̒��Őڎ킪5000�����Ă��܂�����ǂ��A����ȊO�̖�4000���ɂ��Ă͎����̂ɂ���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�����A����2��ł�����A2��̃��N�`��������Ȃ��Ɛڎ킵�Ȃ��Ƃ��A�����Ȃ���A������낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B�����������Ƃɑ��āA7���ɁA���ɉ��s���Ƃ������Ƃ��A����m�ɂ��܂��āA������8������������i��ł���Ƃ���ɂ͌X�Δz������Ƃ��A�����������Ƃ������āA�����̂Ȃ��悤�ɂ������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�����A���������܂Ŗ���130�`140����ő����Ă���A���������̒��ŊF����ɂ����́A�ڎ�����Ă��������Ă��邱�Ƃɂ͊��Ӑ\���グ�����Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
�i��F����ł̓h�����S�̎�������A�ǂ����B
���Ȃ��ܗւ����͋������̂�
�h�����S�F�A������ꂳ�܂ł��B��낵�����肢���܂��B�����܂���A�悤�₭���I�ʼn�ɎQ���ł��܂��āA���₪��Ⓑ���Ȃ�܂����A���������������B
���y�t�@���A�A�[�e�B�X�g���S�҂��ɂ��Ă���܂����uROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021�v����ނȂ����~�ƂȂ�܂����B4��ڂً̋}���Ԑ錾�ŁA�C�x���g�╶���ՁA�C�w���s�ȂǁA�w�Z�̍s���̒��~�������Ȃ�Ǝv���܂��B���ꂼ���Î҂�Q���҂��������X�N���ŏ����ɂ��邽�߂̓w�͂�i�߂Ă������ŁA�Ȃ��ܗւ����͋������̂��A�������������ȋ^���{��ɑ��đ����͂ǂ��������ɂȂ�̂ł��傤���B
�܂���N�A���ʒ�z���t��1�l10���~�̎x�������{���܂������A���͌o�ϓI�ɂ����_�I�ɂ��͂邩�Ɍ������A�����̍����͉䖝���Ă����Ǝv���܂��B�O��A���s�Ɋ|���������z�͖�13���~�Ƃ����Ă���܂����A��N�x�A�����s�̗\�Z30���~���c���Ă���܂��B�����ւ̍ēx�̎x���ɂ��āA���l�������������܂��B��낵�����肢���܂��B
���F�܂��A���w�E�̃C�x���g�ł�����ǂ��A��O���y�t�F�X�Ƃ��Ă͂܂��ɍő勉�ł����āA�Ⴂ���𒆐S�ɑ�ϊy���݂ɂ���Ă���A���������ӂ��ɏ��m���Ă��܂��B���~�ɂȂ������Ƃ͑�ώc�O�Ɏv���܂��B�����A���̃C�x���g�̊J�Ð����ɂ��ẮA�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�������͓��l�̎�舵���ł���܂��B�ً}���Ԑ錾�̉��ł͌ߌ�9���ȍ~�͖��ϋq�ł̊J�Â����肢����A���������A9���ȍ~�͂Ȃ��Ă��܂��̂ŁA���������_�ɂ��Ă͂��������������������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
����������߂���悤�ɑS�͂�������
�ł�����A���ꂩ��ǂ̂悤�ȑ̐��œ����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�����J�Â��邩�Ƃ����̂́A5�҂̕��ł��ꂩ�猈�߂���\��ł���܂��B�����A�����g���A���ً̋}���Ԑ錾���������ۂɂ́A����͖��ϋq�������Ȃ��Ƃ������Ƃ�\���グ�Ă��܂��B�����������ŁA5�҂̒��łǂ̂悤�ȑ��ɂ��邩�Ƃ������Ƃ͌��܂��Ă������낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B������ɂ���A�����̗}���ƃ��N�`���ڎ�A�S�͂Ŏ��g��ŁA1���������A���Ă̓�������߂����Ƃ��ł���悤�ɑS�͂�������̂����̎d�����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�܂��A����10���~�̌��ł���܂����ǂ��A�R���i�̒��ő�ςȉe�����Ă�����A�����������ɂ͂��܂��܂Ȏx����A�l����⎑���J��Ȃǂ̂��̎x�����Ƃ��A���邢�͌ٗp�����̏��������Ƃ��A�����ȑ�̒��A�����ł����������R���i�Ђ̒��ŁA�������̕��ɂ͂���`�������Ƃ��đΉ�����Ƃ����̂́A����͓��R�̂��Ƃł���܂��̂ŁA���������`�ōs���Ă���܂��B
�R���i�ɂ���Ă����ȕ����e�����Ă���Ǝv���܂����ǂ��A�����������ƂŎx���������Ă������������A���������Ă���Ƃ����̂����̎���ł���܂��B
�i��F����ł͓��{�o�ϐV���A�d�c����A�ǂ����B
���o�ϑ�̕Ґ����w������l����
���{�o�ϐV���F���{�o�ϐV���̏d�c�ł��B��낵�����肢���܂��B�o�ϑ�ɂ��Ă��f���������Ǝv���܂��B����A6�T�ԂƂ����錾�́A�����̔��߂ƂȂ�܂��āA�o�ςւ̖ڔz��A���ꂪ�s���ɂȂ邩�Ǝv���܂��B�^�}���Ȃ�ł�����ǂ��A���̉Ăɂł��o�ϑ�̍��i���܂Ƃ߂�ׂ����Ƃ̐�������܂��B�����͌����ɂ����̕Ґ����w������邨�l���͂���܂��ł��傤���B�����ɃR���i�őŌ������ƌv���Ƃɂǂ��������K�v�ł���̂��B�܂��A�z�肷��K�͊��Ȃǂ������ċ����Ă������������Ǝv���܂��B
���F�܂��͐V�^�R���i�̉e�����Ă�������������������肨�x������Ƃ����̂́A���ꂪ�ŗD�悾�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�����J��̎x�����Ƃ��ْ����ɂ��l����̎x���A���H�X�ւ̋��͋��A�����������Ƃ͑��}�ɂ���Ă��������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B
���{�o�ςł���\���グ��A��N�x�̐Ŏ��A����A���\����܂�������ǂ��A�ł����������ɂȂ��Ă��܂��B����ɍ��N�x�̌o�ϐ�������3.7���ɂȂ�A�����������Z��������Ă���A���N�x����GDP�ŃR���i�O�̐��������錩�ʂ��ɂȂ邾�낤�Ƃ������ʂ�������܂��B����Ƀ��N�`���ڎ����������邱�Ƃɂ���āA�o�ςɂ��傫�ȗǂ��e�����o��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�����������ŐV�^�R���i�������̊F����̓���̐����ɉe�����邱�Ƃɏ\���A�ڔz������Ȃ���A���R�A�����o�ςƂ������̂��A���ЂƂ�����A�傫�ȖڕW�Ɍf���Ă��܂�����A�������������o�ς�����A�����ł���悤�Ȃ��̍��ɂ������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B������ɂ���A�o�ς̏����Ȃ���Ջ@���ςɁA�����͂�������Ή�����Ƃ����A�����������ŁA��ɂ��̌o�ϑ�Ƃ����͓̂��̒��ɓ���Ȃ�����g��ł���܂��B
�i��F�����܂��āA����ł́A���ႠNHK�A��������A�ǂ����B
�����̏O�@�I�܂łɓ��t�������s���l����
NHK�FNHK�̒����Ɛ\���܂��B��낵�����肢���܂��B��̓����s�c��c���I�����āA�����}������͂��܂��܂Ȉӌ����o�Ă���킯�ł����ǂ��A�����A���̏O�c�@�I���܂łɓ��t�������s�����l���͂���܂��ł��傤���B
���F�}���ɂ����Ȑ�������Ƃ������Ƃ͎����g�����m�����Ă��܂��B�����������Ŏ��A��ɍŗD��Ƃ������Ƃ�\���グ�Ă��܂��̂́A�R���i�A�R���i����ŗD��Ɏ����g�͎��g��ł��������ƁA���������ӂ��Ɏv���Ă��܂��B����Ɠ����Ɏ����g�̔C���A���قƂ��Ă̔C���A����ɂ܂������ƂƂ��Ă̏O�c�@�̔C���A�����������Ƃ����R�A�ԋ߂ɗ���킯�ł���܂�����A���������S�̂��l���Ȃ��琭��Ƃ��Ă��܂��܂Ȃ��Ƃ����点�Ȃ�����g��ł��������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă���܂��B
�i��F����ł͍Ăщ��̗�A���ႠTribunnews�̃X�V������A�ǂ����B
��VIP�W�҂ɂ��K�p�����̂�
Tribunnews�F��낵�����肢���܂��B�C���h�l�V�A��Tribunnews�̃X�V���Ɛ\���܂��B����6������V�������ۑ�ɌW��V���ȑ[�u�����肳��܂����B�Ⴆ�C���h�l�V�A�̏ꍇ��10���ԁA���u�̕K�v������܂��B���̖@���͌ܗւ̊W�Ҋ܂߂āAVIP�W�҂��K�p����܂��ł��傤���B���ꂩ��A���ɂ́AVIP�W�҂͊C�O���炾���������J������\��ł��傤���B��낵�����肢���܂��B
���F�܂��A�C�O������{�ɗ���I�����W�҂ɂ��ẮA�����O��2��A�������Ɍ������s���A������3���Ԃ͖����A���������{�A�I��͂��̌�������A���������{���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B����Ƀf���^���Ȃǂ̗��s���āA�C���h�l�V�A�Ȃǂ���̈�ʂ̓����҂ɑ��ẮA�������܂����悤�ɁA���ۑ�������Ă��܂��B�����������Ƃ܂��āA�����̍�����̑I��Ȃ�тɊW�҂́A�����O7���Ԃ���ѓ�����3���Ԃ͖����A�������s���A�`�[���ȊO�̕��ƐڐG���s��Ȃ��Ƃ������[�����V���ɓ�������܂����B���������������[�u���̂��Ă��邱�Ƃ�O��ɁA�ܗ֊W�҂̕��ɂ͈�ʂ̓����҂Ƃ͕ʂ̃��[����K�p���Ă���܂��B�����������S�E���S�̑��������ł���悤�A���ۑ�������������Ă��������A���̂悤�Ɏv���܂��B
�i��F����ł̓W���p���^�C���Y�A���R����B
�����哝�̂Ɠ��؎�]��k���s���l����
�W���p���^�C���Y�F�W���p���^�C���Y�̐��R�ł��B�����ɂ��f�����܂��B�؍��̕��ݓБ哝�̂��ܗւɍ��킹�K������ӌ����ƈꕔ�ŕ���Ă��܂����A�����Ƃ��ĕ��哝�̂Ɠ��؎�]��k���s�������Ƃ������l���ł��傤���B�܂��A�s���̂ł���Ȃ�炩�̑O����������߂�̂ł��傤���B
���F�܂��J��ւ̊؍�����̏o�Ȏ҂ɂ��Ă͂܂����肵�Ă��Ȃ��ƁA���������ӂ��ɏ��m���Ă��܂��B���̏�Ő\���グ��A���݂̓��؊W���Ă����̂͂܂��ɋ����N�����o�g�̘J���Җ��A���邢�͈Ԉ��w���Ȃǂɂ���Ĕ��Ɍ������ɂ���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B���ؗ����̂����������Ă��������邽�߂ɂ́A��͂�؍����ӔC�������đΉ����Ă����A���̂��Ƃ��d�v���Ǝv���܂��B���������؍����ɓK�ȑΉ����������߂Ă����Ƃ�������ɕς��͂���܂���B�����A���̏�ŖK�������ꍇ�́A�O����A���J�ɑΉ�����Ƃ������Ƃ́A�����͓��R�̂��Ƃ��Ƃ����ӂ��ɔF�������Ă��܂��B
�i��F����ł͋����ʐM�A�g�Y����A�ǂ����B
���ǂ��Ȃ�Έ��S�E���S�ȑ��ƌ�����̂�
�����ʐM�F�����ʐM�̋g�Y�ł��B��낵�����肢���܂��B�����ܗցA�p�������s�b�N�ɂ��ďd�˂Ă��������܂��B��قǑ����͈��S�E���S�ȑ��𐬌������Ƃ̌��ӂ�\������܂����B���̓������A�ǂ̂悤�ȏ���������A���̈��S�E���S�ȑ����ł����ƌ�����̂ł��傤���B���̋�̓I�Ȕ��f��ɂ��đ����̔F�������������܂��B
���F�܂��A���S�E���S�ȑ��̎����Ɍ����āA�I�����W�҂̓O�ꂵ��������s���Ǘ��A�����������Ƃ��s�����Ƃɂ���āA�E�C���X�̍����ւ̗������A�܂��͖h�������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă܂��B����ɂ���đI�肪���S���đ��ɎQ���ł���悤�ɁA��������I�����W�҂ɂ���āA�����̊����ɉe�����y�ԁA�����������Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�����͂������肵�����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
����ɍ���̑��l���������N���������g��ɂȂ���A�����������Ƃ͐�Δ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����悤�Ɏv���Ă��܂��B��قǐ\���グ�܂������ǁA����A1�N�ȏ�O����A�Ⴆ�Ύ�s���̗�����1000�~�グ�邾�Ƃ��A���̌�ʂ̋K���A���邢�͂���A�D�������ł����ǂ��A�I�����s�b�N���Ԓ��̒��݁A�ڊ݂ł����A�����������Ƃɑ��Ă̑Ή��Ƃ��A�����ăe�����[�N�ɂ��Ă��I�����s�b�N�Ƃ����A���ꂾ����邤���́A����͏������Đi�߂Ă܂�����A���������ڂŃe�����[�N�A��ʗʂ̋K���A���̂Ƃ��̐l���Ƃ����̂͌��݂����ɂ߂ė}�����Ă���A�����������ʂ��̒��ōs�����ƂɂȂ��Ă���܂��B�ł�����A�����������ł����������X�N���N������Ȃ������ƁA�����g���j�~�������A�����������ʂƂ����̂͑厖���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�i��F����ł́A�ł́A���W�I���{�̈ɓ�����A�������ł��傤���B
��������65�Έȉ��̐ڎ��]�҂ɐڎ킷��l����
���W�I���{�F���W�I���{�̈ɓ��ł��B�����ɂ��q�˂��܂��B��قǂ������������������Ă�������܂��悤�ɁA���N�`���̉��������A�����ł�����҂̊����҂����Ȃ��Ƃ������Ƃ̓��N�`���̌��ʂ��Ǝv���܂��B�����ł��q�˂�������ł�����ǂ��A�Ⴆ���A����͓����ւً̋}���Ԃł��̂ŁA����65�Έȉ���50��A40��A30��̕��X�ɑ��āA�����̊e�����̂ɕ��U����Ă���A���邢�͊m�ۂ���Ă��郏�N�`�����A�Ⴆ�Ή͖샏�N�`���S����b�ɃR���g���[�����Ă��������āA�Ⴆ���N�`���͂��邯�ǐڎ��]�҂����Ȃ������̂�����킯�ł��ˁB�����������̂�Ⴆ�A�����̂�������65�Έȉ��̐ڎ����]������ɐڎ킷��悤�Ȃ��l���͂������܂����B���肢���܂��B
���F�܂��A���N�`���ڎ�̊�{�ł����ǂ��A��͂��{�I�ɂ͑S���ꗥ�ōł��d�lj�����Ƃ�����65�Έȏ�ɂ�蒆�S�ɂ��ׂ��B����͉�̔��g�搶����A�����������Ƃ���̂��w�E�̒��ŁA65�Έȏ�̕���2���D�������悤�ɂƂ����A����͑S���̊e�s���{���ɂ��肢�������Ă��������Ă��܂��B�����āA���������܂�1��ڂ�65�Έȏ�̕��Őڎ킵������71���܂ō��A�Ȃ��Ă܂��B2��ł�������40���ł��B
��������������ɂ�āA�S����1741�s���������ł����ǂ��A�����������ō���҂̊F�����7�������ς��őł��Ă���������B���������\��ō��A�����ɐi��ł܂��B�܂�����҂��ŗD��B���̒��Œn���̂��̂�s��ɂƁA����A�s��̎����̂̎������Ă�����������āA�V�����ŕ���Ă܂����ǂ��A�܂��͂����͑S���ꗥ��65�Έȏ�̕��͂��肢�����āA���ƁA��͂�ǂ����Ă������Ƃ���s�s�����犴�����X�N���n���͑����ł�����A�����������ŐE��ڎ�A�܂��͑�w�ł̐ڎ�A�����������Ƃ����ǂ��l���āA���A�ڎ킳���Ă��������Ă���Ƃ������Ƃł���܂��B
���A�����̒��ł��A�������ł�64�Έȉ��̐l�ɐڎ팔�����Ă�Ƃ��������܂���ŁA���������Ƃ���ɂ��ẮA���q���̐ڎ���ł��t�������Ă܂���ŁA���������Ƃ���ŗ��Ă��������āA�i�߂Ă���������Ƃ����ӂ��ɁA�ڎ킵�Ă���������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�i��F����ł̓e���r�����A������A�ǂ����B
���A�X�g���[�l�J����I�����ɓ����l����
�e���r�����F�e���r�����A���ł��B��قǂ����b����܂������A�����̂Ń��N�`���̗\��̃L�����Z���Ȃǂ��������ł���܂��B�����������ԂɑΏ����邽�߂ɁA���݁A�����ł͔F����Ă�����̂̐ڎ킪�n�܂��Ă��Ȃ��A�X�g���[�l�J���̃��N�`���������Őڎ킷�邱�Ƃɂ��āA�����I�����ɓ����l���͂���܂��ł��傤���B
���F�A�X�g���[�l�J�Ђ̃��N�`����Վ��ڎ�Ŏg�p���邱�Ƃɂ��āA���J�Ȃ̐R�c��ɂ����āA���O���ɂ�����Ȃǂ܂��Ȃ���A�킪���ɂ����Ă̗��p�A���̏ɂ��Č�������Ă���Ƃ���ł����āA�܂����_�͏o�ĂȂ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�����������Ƃɂ��c�_�̓����𒍎����Ȃ���A�܂���9���܂łɑS�����̃��N�`�����t�@�C�U�[�ƃ��f���i�A�����ɂ��Ă�2��2000���p�ӂ��Ă܂��̂ŁA�����ō��A�i�߂Ă��Ă��܂��̂ŁA�����ł܂��A�����͎g�����Ă��������A���̂悤�Ɏv���Ă���܂��B
���ƁA������ɂ��낻���������ŁA�A�X�g���[�l�J�ɂ��ẮA���J�Ȃ̐R�c��Ƃ�����ł����B�����������ł̌��_���钆�ōl���Ă��������Ǝv���܂��B�C�O�ɂ���Ă�60�Έȏ�Ƃ����낢��ȏ�����悤�ł�����A�����������Ƃ����J�Ȃ̒��ł���������A�C�O�̏����W�߂钆�ō��A���ꂩ��R�c���邱�Ƃ��낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�i��F����ł͑�ϋ��k�ł����A����2��Ƃ����Ă��������܂��B����ł́A�����V���̏��R����A�ǂ����B
�������̉��ɂ��Ă͂ǂ��l���Ă���̂�
�����V���F�����V���̏��R�ł��B��낵�����肢���܂��B�ܗւ̊ϋq���ɂ��Ďf���܂��B��قǗ��������Ă��܂��ƁA�����s�ɂ��Ă͖��ϋq�Ƃ��������̂��l�����Ǝv���܂�����ǂ��A�����̉��ɂ��Ă͂ǂ����l���ł��傤���B�������A���̂��Ƃ�5�ҋ��c�Ō��܂�Ƃ������Ƃ͕������Ă����ł����A�����������̈��S�E���S�ɐӔC�����ƌ����Ă���ȏ�A�����̂��l�����������m�肽���Ǝv���Ă���Ǝv���܂��B�����Ƃ��Ă̕��j�������ł��������邱�Ƃ͂ł��܂���ł��傤���B
���F�܂��A����܂Ŏ��A�\���グ�Ă��܂������ǂ��A�ً}���Ԑ錾�ɂȂ�A���ϋq������͎����Ȃ��A�����������Ƃ�\���グ�Ă܂��B�����������Ŋϋq�̈����ɂ��ẮA���A5�ҋ��c�A���ꂩ��ł����B�s���āA���������o�����Ƃ����悤�Ɏv���܂��B�����A�ً}���Ԑ錾�A�܂h�~�̂Ƃ��̃��[��������܂��B�����̃��[���ɍ������`�̒��Ō��߂��Ă����낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�ً}���Ԑ錾�ł�5000�l�Ƃ��A�����������[������Ă܂�����A�����������Ō��߂Ă������낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�i��F����ł͍Ō�ɍ��ۃ��f�B�A����A�A���u�j���[�X�̃A�Y�n������A�ǂ����B
�����y���Չ���Ɏ��g��ł���
�A���u�j���[�X�E�W���p���F(�p��)�B��T�̔M�C�ł̓y���ЊQ�̂悤�ɁA�C��ϓ���������A�܂��A�l�I�v�����厩�R�ЊQ�ɂȂ���܂����B�������͂���܂ł��n��̊������ƃC���t���������d�������Ă����܂������A����A�ǂ̂悤�ȃ_�C�V�R�E�n�A�I�l�K�C�A�I�J���A�����܂���A�s�������ł��傤���B���肪�Ƃ��B
���F�ߔN�͍ЊQ���p�������A���r�����钆�ŁA���{�Ƃ��Ă͍��y���Չ��A�����ɂ���������g��ł���܂��B�����������ŁA�����͐삾�Ƃ��V���r�̐������Ƃ��A�܂��C���t���̘V�����A�����������Ƃ��A�h�ЁE���Ђɑ��Đ��{�������č��y���Չ���ɂ���������g��ł���Ƃ���ł���܂��B�����Ēn���̊������Ƃ������ŁA�����g�͂�͂�ό��A�_�ƁA�����������̂𒆐S�ɒn���̏����������グ�Ă��������A���������Ƃ���Ɏ��g��ł���Ƃ���ł���܂��B�����������Ă��������Ǝv���܂��B
�i��F����ł́A���������肳��Ă��������Ă���܂��F���܂ɂ�����܂��Ă͑�ϋ��k�ł������܂�����ǂ��A���̂���1������[���ł����肢�����������Ǝv���܂��B����A�𑍗���菑�ʂɂĂ��Ԃ������Ă��������ƂƂ��ɁA�z�[���y�[�W�Ō��J�������Ă��������܂��B�ǂ����������Ƃ����͂���낵�����肢�������܂��B����ł́A�ȏ�������܂��Ė{���̋L�҉���I�������Ă��������܂��B�����͂��肪�Ƃ��������܂����B�@ |
����� �錾�͗\�h�I�[�u�̂��� �ܗցE�p���J�Â̈Ӌ`���� �@7/8
�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o���ƌ��肵�����Ƃ��āA��������b�͋L�҉���A��������S���ւ̊����g���h�����߂ɐ����ŗ\�h�I�[�u���u���邽�߂��Ɛ������A���������߂܂����B�܂������I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��āA�u�l�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���ē�ǂ����z���Ă����邱�Ƃ𓌋����甭�M�������v�ƊJ�Â̈Ӌ`���������܂����B
���̒��Ő�������b�́A�����s��4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o���ƌ��肵�����Ƃɂ��āA�u�����̊����g��͑S���ɍL���肤����̂��B�����ōēx�A�������N�_�Ƃ��銴���g����N�������Ƃ́A��ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B
���̂����ŁA�u�����ŗ\�h�I�[�u���u���A�����s�ɋً}���Ԑ錾�����ЂƂ��є��o���锻�f�������B���N�`���̌��ʂ�����ɖ��炩�ɂȂ�A�a���̏Ȃǂɉ��P��������ꍇ�ɂ́A�O�|���ʼn������邱�Ƃ����f����v�Əq�ׂ܂����B
�����āA�u�O��̐錾���������Ă���3�T�ԂōĂѐ錾�Ɏ���A�����̊F�l�ɁA���܂��܂ȕ��S�������邱�Ƃ͑�ϐ\����Ȃ��v�����B���̊��Ԃ����z���āA���S�̓����K�����߂��Ƃ������ӂŎ��g��ł����v�Əq�ׁA���������߂܂����B
�܂����N�`���ڎ�ɂ��āA��s���Đڎ킪�i�߂�ꂽ���X�ł́A1��ڎ킵���l�̊������l����4���ɒB���������肩�犴���҂̌����X�������m�ɂȂ����Ƃ����w�E������Ƃ��������ŁA�u���̃y�[�X�Ői�߂������ɂ͊�]���鍂��҂�2��̐ڎ�͊������A1�x�ł��ڎ킵���l�̐��͑S������4���ɒB���錩�ʂ����v�Əq�ׂ܂����B
�����āA�S���̎����̂ɂ́A�挎�܂ł�9000���̃t�@�C�U�[�̃��N�`�����z������A���̂���4000���ɂƂȂ��Ă��邱�Ƃ������܂��Ƃ��āA�ɂ����킹�Ċ��p����A���120������x�̃y�[�X�Őڎ�𑱂��邱�Ƃ��\���Ɛ������܂����B
���̂����ŁA�ڎ킪�i�ގs�����ɑ����z���ł���悤�������A�z���ʂ𑁊��Ɏ����ق��A��Ƃ��w�Ȃǂ̐ڎ���\���̐����𑬂₩�ɍs���A�Ή����Ă����l���������܂����B
����A�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��Đ�������b�́A�ً}���Ԑ錾�̂��Ƃł̈ٗ�̊J�ÂƂȂ�Ǝw�E���A�u����܂ŁA�ً}���Ԑ錾�ƂȂ�Ζ��ϋq�������Ȃ��Ɛ\���グ�Ă����v�Əq�ׂ������ŁA���̂��ƊJ�����g�D�ψ���A�����s�AIOC�����ۃI�����s�b�N�ψ���ȂǂƂ�5�҉�k�ɂ����āA�ϋq�̎�舵�������߂���Ɛ������܂����B
�����āu�V�^�R���i�Ƃ����傫�ȍ���ɒ��ʂ��鍡�����炱���A���E����ɂȂ�邱�ƁA�����Đl�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���ē�ǂ����z���Ă����邱�Ƃ𓌋����甭�M�������B���S�E���S�ȑ��𐬌������A��������q�ǂ������ɖ��Ɗ�]��^����A���j�Ɏc����������������v�Əq�ׂāA�J�Â̈Ӌ`���������܂����B
����A�u�ǂ̂悤�ȏ���������A���S�E���S�ȓ������J�Âł����ƌ�����̂��v�Ǝ��₳�ꂽ�̂ɑ��u�������l���������N�����A�����g��ɂȂ��邱�Ƃ́A��Δ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E�C���X�ɐN�����ꂸ�A�����g���j�~�����Ƃ������ʂ͑厖���v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A�؍��̃����E�W�F�C��(���ݓ�)�哝�̂��������ɍ��킹�ē��{��K�ꂽ�ꍇ�A��]��k���s���l���͂��邩�Ɩ��ꂽ�̂ɑ��āA�J��ւ̊؍�����̏o�Ȏ҂͂܂����肵�Ă��Ȃ��Ƃ��������Łu�哝�̂����{��K���ꍇ�́A�O����A���J�ɑΉ����邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃ��ƔF�����Ă���v�Əq�ׂ܂����B
��4��ڂً̋}���Ԑ錾 �����s�̑[�u���e �{�ݕʁ@7/8
4��ڂً̋}���Ԑ錾�̊��Ԓ��ɓ����s���s���u�ً}���ԑ[�u�v�ɂ��Ă܂Ƃ߂܂����B
����J���I�P�ݔ������u�V���{�݁v�ɂ́A�@���Ɋ�Â��ċx�Ɨv�����s���܂��B���Ȃ��ꍇ�͊�����h������s���悤�v������ƂƂ��ɁA�ߌ�8���܂ʼnc�Ǝ��Ԃ�Z�k����悤�v�����܂��B�ΏۂɂȂ�̂̓L���o���[�A�i�C�g�N���u�A�_���X�z�[���A�X�i�b�N�A�o�[�A�p�u�Ȃǂł��B
�܂��A����J���I�P�ݔ������u���H�X�v�ɂ��A��z��e�C�N�A�E�g�̃T�[�r�X�͏����āA�@���Ɋ�Â��ċx�Ɨv�����s���܂��B���Ȃ��ꍇ�͊�����h������s���悤�v������ƂƂ��ɁA��z��e�C�N�A�E�g�̃T�[�r�X�͏����āA�ߌ�8���܂ʼnc�Ǝ��Ԃ�Z�k����悤�v�����܂��B�ΏۂɂȂ�̂͋��������܂ވ��H�X�A�i���X�Ȃǂł��B
����J���I�P�ݔ������u��������v�ɂ́A�@���Ɋ�Â��ċx�Ƃ�v�����܂��B���Ȃ��ꍇ�͉c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łɒZ�k����悤�v�����܂��B�J�Î��Ԃɂ��Ă͍ő��1���Ԕ��Ƃ��A���e�l���ɂ��Ă�50�l�܂��͒����50���̏������ق��ɂ���悤�A�s�Ǝ��ɋ��͂��˗����܂��B
�u����v��u�����فv�A�u�^���{�݁v�Ȃǂ́A�@���Ɋ�Â��āA�l���̏����5000�l�ŁA�����50���ȓ��Ƃ���悤�v�����܂��B�C�x���g���J�Â���ꍇ�͉c�Ǝ��Ԃ��ߌ�9���܂łɂ���悤�v�����܂��B
�C�x���g�J�ÈȊO�̏ꍇ�́A���ʐς̍��v��1000�������[�g������{�݂͌ߌ�8���܂łɂ���悤�@���Ɋ�Â��ėv�����A1000�������[�g���ȉ��̎{�݂ɂ͓s�Ǝ��Ɍߌ�8���܂ł̎��Z�ւ̋��͂��˗����܂��B�܂��A������h������s���悤�v������ق��A���ƃJ���I�P�ݔ��̒̎��l��A���p�҂ɂ����̎������݂�F�߂Ȃ����Ƃ��v�����܂��B
�ΏۂɂȂ�̂͌���A�ϗ���A�f��فA�v���l�^���E���A���|��A�W���A����A�W����A�݉�c���A������فA���ړI�z�[���A�z�e���̏W��p�̕����A���ق̏W��p�̕����A�̈�فA�X�P�[�g��A���j��A�����e�j�X��A�_������A�{�E�����O��A�싅��A�S���t��A���㋣�Z��A���O�e�j�X��A�S���t���K��A�o�b�e�B���O���K��A�X�|�[�c�N���u�A�z�b�g���K�A���K�X�^�W�I�A�e�[�}�p�[�N�A�V���n�A�����فA���p�فA�Ȋw�فA�L�O�فA�����فA�������A�A�����Ȃǂł��B
�u���Ǝ{�݁v��u�V���{�݁v�Ȃǂł́A���ʐς̍��v��1000�������[�g������{�݂ɁA�����K���i�̔̔���T�[�r�X�������āA�@���Ɋ�Â��Čߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k��v�����܂��B1000�������[�g���ȉ��̎{�݂ɂ́A�s�Ǝ��Ɍߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�̋��͂��˗����܂��B�܂��A������h������s���悤�v������ق��A���ƃJ���I�P�ݔ��̒̎��l�◘�p�҂ɂ����̎������݂�F�߂Ȃ����Ƃ��v�����܂��B
�v���⋦�͈˗��̑ΏۂɂȂ�̂͑�K�͏����X�A�V���b�s���O�Z���^�[�A�S�ݓX�A�}�[�W�����X�A�p�`���R���A�Q�[���Z���^�[�A���r�f�I�X�A���t����ƂɌW����O����A�˓I��A���n���[���������A��O�Ԍ�����A�X�[�p�[�K���A�l�C���T�����A�G�X�e�e�B�b�N�ƁA�����N�[�[�V�����ƂȂǂł��B
�c�t���⏬�w�Z�A���w�Z�A���Z�A��w�A����ɕۈ珊����V�l�ی��{�݂Ȃǂɂ́A�������X�N�̍��������𐧌����邱�Ƃ�A���u���Ƃ̊��p�Ȃnj��ʓI�Ȏ��Ƃ����{���邱�Ƃɋ��͂��˗����܂��B
���Տ�ɂ́A���̒�J���I�P�ݔ��̎g�p�����l����悤���͂��˗����܂��B���ɂ��Ă͎{�݂ւ̎������݂�F�߂Ȃ����Ƃ����߂܂��B
�}���ق͓���̐������s���悤���͂��˗����܂��B
�u�V���{�݁v�̂����l�b�g�J�t�F�A�}���K�i���ȂǁA�u���Ǝ{�݁v�̂����K���A���e�X�A���e�X�A�����A�݈ߑ����A�N���[�j���O�X�Ȃǂɂ͓���̐����ւ̋��͂��˗�����ƂƂ��ɁA���̒ƃJ���I�P�ݔ��̎g�p�����l����悤���͂��˗����܂��B���ɂ��Ă͎{�݂ւ̎������݂�F�߂Ȃ����Ƃ����߂܂��B
�����ԋ��K����w�K�m�Ȃǂɂ̓I�����C���̊��p�ւ̋��͂��˗����܂��B
���̂ق��C�x���g�̊J�Âɂ��ẮA��Î҂ɑ��āA�l���̏����5000�l�Œ����50���ȓ��Ƃ��邱�ƁA�J�Î��Ԃ��ߌ�9���܂łɒZ�k���邱�ƁA����ɋƎ킲�Ƃ̃K�C�h���C�������炵�A�Q���҂ɒ��s�E���A�̌Ăт�����O�ꂷ��悤�v�����܂��B
�E��ւ̏o�ɂ��ẮA�e�����[�N�̊��p��x�ɂ��擾���邱�ƂȂǂɂ���ďo�Ύ҂�7���팸��ڎw���悤�v�����܂��B�܂��A���Ƃ̌p���ɕK�v�ȏꍇ�������āA�]�ƈ��͌ߌ�8���܂łɎd�����I���ċA�����悤�v�����܂��B
�s���ɑ��ẮA�������܂߂Ĉ�Ë@�ււ̒ʉ@����K���i�̔����o���A�K�v�ȐE��ւ̏o�A���O�ł̎U���ȂǁA�����⌒�N�̈ێ��ɕK�v�ȏꍇ�������āA�����Ƃ��ĊO�o���Ȃ��悤�A�@���Ɋ�Â��ėv�����܂��B���̂����ŁA�ߌ�8���ȍ~�̕s�v�s�}�̊O�o���l�A���G���Ă���ꏊ�⎞�Ԃ�����čs�����邱�ƁA�s�v�s�}�̋A�Ȃ◷�s�ȂǓs���{�����܂����ړ����ɗ͍T���邱�ƁA�H�������ȂǂŏW�c�Ŏ������ނ��ƂȂǁA�������X�N�������s���̎��l��O�ꂷ��悤�v�����܂��B
�����s�̏��r�m����8����A�Վ��̋L�҉���J���܂����B���̂Ȃ��ŁA���r�m���́u����ً̋}���Ԑ錾�͍��̋�����@���̂��ƂŔ��o�������̂ł���A�s�Ƃ��Ă����Ɗ�@�ӎ������L����B�l�̗���̗}�����{�I�Ȋ����h�~��̓O��Ɍ����āA�������̂����w���͂ȑ[�u���u���Ă����v�Əq�ׂ܂����B�܂��A���r�m���́u�s�̃��j�^�����O��c�ł́A�������Ċg�債�A��N�w�⒆�N�w�̓��@���҂��������A�d�NJ��҂������Ă��āA����50�オ�������Ƃ������͂������������B��Ԃ̔ɉ؊X�̑ؗ��l���������X���ɂ���A�ߌ�8�����߂����n�C���X�N�̎��ԑт��܂߂ĈˑR�Ƃ��č��������ł̐��ڂƂȂ��Ă���B����Ɋ����͂������ƌ�����f���^�����������Ă��āA���s�̎�̂ɒu������邱�Ƃ��z�肳��Ă���B���̉e���ŐV�K�z���Ґ��̂���Ȃ鑝�����뜜�����B���Ԃ͂��ؔ����Ă���A���Ƃ��Ăł�����ȏ�̊����g����~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B���̂����ŁA���r�m���́u�s���̖��⌒�N����邽�߂�3�̒��́A���Ɉ��H�X�̑���������邱�ƁB���ɏd�ǎ҂������Ă���50��ɓI�Ă��A����w50����x�ւ̏d�_�I�ȑΉ��B��O�Ƀ��N�`���ڎ�̐��i���B����3�̒��̑��O��I�ɂ�蔲���Ă����v�Ƌ������܂����B
��������4��ڂً̋}���Ԑ錾�@�u���ŗ\�h�I�[�u�v�@7/8
���{��8���[�A�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ��{��(�{�����E���`�̎�)�̉���J���A�����s��4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̔��߂����߂��B���ꌧ�ւ̐錾�Ǝ�s��3���A���{�ւ́u�܂h�~���d�_�[�u�v�͉�������B���Ԃ͂������12������8��22���܂ŁB�錾���ōs���铌���ܗ�(7��23���`8��8��)�͎�s��1�s3���őS���̖��ϋq�J�Â����܂����B
�����͊����Ċg�傪�~�܂炸�A���~�x�݂��܂߂������K�v�Ɣ��f�����B��8����A���@�ŋL�҉���A�����ւ̐錾���߂ɂ��āu�ēx�����g����N�������Ƃ͐�ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŗ\�h�I�[�u���u����v�Ɛ����B�u�����ɂ��܂��܂ȕ��S�������邱�Ƃ́A��ϐ\����Ȃ��v�����v�Əq�ׂ����A���N�`���̌��ʂȂǂ����ɂ߂���Ő錾���u�O�|���ʼn������邱�Ƃ����f����v�ƌ�����B
�����ܗւɊւ��u�S�l�ނ̓w�͂Ɖp�m�œ�ǂ����z���Ă����邱�Ƃ𓌋����甭�M�������v�Ƌ����B�u���S���S�ȑ��𐬌������A���j�Ɏc����������������v�ƕ\�������B
�錾���ł́A�v���싅�Ȃǂ̑�K�̓C�x���g�́A�l�����5000�l�����e��50���̐���������A�ߌ�9���܂ł̎��ԒZ�k�����߂���B����܂��A���{����g�D�ψ���A�����s�A���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�Ȃǂɂ��5�ҋ��c��W�����̂Ƃ̋��c�8����ɊJ����A�����s�ƍ�ʁA��t�A�_�ސ�3���ł̑S���̖��ϋq�J�Âō��ӂ����B
�錾�Ώۂ̓����Ɖ���ł́A���H�X�ɑ��Ď�ޒ�~�ƌߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v������B�d�_�[�u�̋��ł���ޒ�������~�Ƃ��A�m���̔��f�Ŋɘa�ł���悤�ɂ���B�́u(�v���ɉ�����)���H�X�ɑ��Ă͋��͋������O�Ɏx�������Ƃ��\�Ƃ���v�ƌ�����B
����A�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���ɓK�p���̏d�_�[�u��7��11���������ĉ�������B
���������A������4�x�ڂ́u�ً}���Ԑ錾�v���o��\�� ����22���܂Ł@7/8
��������8���A���{���{����c�œ����s�ɑ��u�ً}���Ԑ錾�v�o����l�����������B4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ͍���12�����痈��22���܂ł�6�T�ԂɂȂ���j�B
�܂��A���ꌧ�ő����Ă���u�ً}���Ԑ錾�v���ʁE��t�E�_�ސ�E���ɓK�p����Ă���u�܂h�~���d�_�[�u�v�͗���22���܂ʼn������A�k�C���E���m�E���s�E���ɁE�����ɂ��Ă͍���11���ʼn���������j�������Ă���B
��Ő������́u���N�`���̐ڎ��5400��������v�ƕB����҂̂��悻7���A�S������3����1��̐ڎ���I�����Ɩ��������B
���{����������{�I�Ώ����j�ł́A�錾�̑Ώےn�悾���łȂ��A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�n��ł����H�X�Ɍ����Ƃ��Ď�ނ̒��s��Ȃ��悤���߂Ă���B���̏�ŁA���{��4��ڂً̋}���Ԑ錾�̔��o�ɓ������āA��ނ̒�~�Ȃǂɉ��������H�X�ɋ��͋��̐�n����}��Ɣ��\�B����A�v���ɉ����Ȃ����H�X�ɑ��āA������b�͖��߂┱�������i�ɓK�p����l���������ƂƂ��ɁA���̔̔����Ǝ҂ɑ��A����̒�~�����߂���j�������Ă���B
��������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�@�ܗւ�1�s3���Ŗ��ϋq�Ɂ@7/8
���{���{��8���A�V�^�R���i�E�C���X�̊�����̂��߁A�����s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o���ƌ��ߔ��\�����B���Ԃ�12������8��22���܂ŁB������A����23���J���̓����I�����s�b�N�́A�s���Ƌߗ�3���ł͖��ϋq�ŊJ�Â��邱�Ƃ��A�W5�҂����c�Ō��肵���B
���ꌧ�ɏo����Ă���ً}���Ԑ錾������22���܂ʼn�������B�����I�����s�b�N�́A���ׂĂ̋��Z�Ǝ��T���ً}���Ԑ錾���ōs���邱�ƂɂȂ�B
8����ɋL�҉�������`�̎́A�u���N�`���̐ڎ킪�啝�ɐi�W���A�S���̑����̒n��ŐV�K�����҂̌����������Ă���v�A�u�c�O�Ȃ����s���ł͊����Ґ��͖��炩�ȑ����ɓ]���Ă���B�v���͐l���̍��~�܂�ɉ����A�V���ȕψي��̃f���^���̉e�����v�Ɛ����B
�u�����̊����g��͑S���ɍL���蓾��B(����)�ċx�݂₨�~�ŁA�����̐l���n���Ɉړ����邱�Ƃ��\�z�����B�V�^�R���i�Ƃ̓����ɋ�肪�����Ă������ŁA�������N�_�Ƃ��銴���g��͐�ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŗ\�h�I�[�u���u���邱�ƂƂ��A�����s�ɋً}���Ԑ錾�����ЂƂ��є��o���锻�f�������v�Əq�ׂ��B
�܂��A���N�`���ڎ�̌��ʂ�����ɖ��炩�ɂȂ�A�a���̏ɉ��P��������A�O�|���ʼn�������Ƃ����B
���݁A�܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă����ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���́A����22���܂œK�p����������B����A�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���́A����11���ŏd�_�[�u����������B
���͉�ŁA�ً}���Ԑ錾���o����铌���s�Ɖ��ꌧ�ł́A���H�X�ł̎�ނ̒��ꗥ�ɒ�~����Ƃ����B�܂��A�d�_�[�u���o�Ă���n��ł��A��ނ̒͌�����~�Ƃ��A�n��̏ɉ����Ĕ��f����Əq�ׂ��B
���ܗւɂ��Ă�
�����I�����s�b�N��2�T�Ԍ�ɔ��钆�A�����s�ł͐V�^�E�C���X�̊����҂����߂đ����Ă���B8����896�l�A�O����7����920�l�������B8���܂�19���A���ŁA�O�̏T�̓����j���������Ă���B����������Ɋg�傷�邱�Ƃ����O���A�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̉����⒆�~�����߂鐺�́A���L���w����o�Ă���B���͓������̊J�Âɂ��āA�u�ً}���Ԑ錾�̒��ňٗ�̊J�ÂƂȂ�v�ƔF�߂������ŁA�u�E�C���X�̍���������O�ꂵ�Ėh���ł����v�ƌ��ӂ��q�ׂ��B�ϋq�ɂ��ẮA�u�ً}���Ԑ錾�ƂȂ�Ζ��ϋq�������Ȃ��ƌ����Ă����B���̂��Ƃ�5�ҋ��c�Ŋϋq�̎�舵�������܂�\�肾�v�Əq�ׂ��B�܂��A�u���E��40���l���e���r��ʂ��Ď�������Ƃ�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ́A���E���̐l�X�̐S��1�ɂ���͂�����B�V�^�R���i�Ƃ����傫�ȍ���ɒ��ʂ��鍡�����炱���A���E��1�ɂȂ�邱�Ƃ��A�����Đl�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���ē�ǂ����z���Ă����邱�Ƃ��A�������甭�M���Ă��������v�Ǝv����������B�����āA�u����̑��͑����̐����肱��܂łƈقȂ邪�A�����炱�����S���S�ȑ��𐬌������A��������q�������ɖ��Ɗ�]��^������j�I�ȑ��������������v�Ƙb�����B
���ϋq�͂ǂ��Ȃ�
8���ɂ́A���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃g�[�}�X�E�o�b�n������������B������A���g�D�ψ���A���{�A�����s�A���ۃp�������s�b�N�ψ���(IPC)�̑�\�̑��W5�҂ɂ�鋦�c�ɃI�����C���ŗՂB���c�ł́A���Ɋϋq������̂��ǂ������b������ꂽ�B�I����A�ې���ܗ֑��́A�����A��ʁA��t�A�_�ސ��1�s3���ŊJ�Â���鋣�Z�ɂ��āA���ϋq�ŊJ�Â��邱�Ƃ����܂����Ɣ��\�����B�܂��A�{��A�����A�É���3���ōs���鋣�Z�́A���̎��e�l����50����1���l�̂����ꂩ���Ȃ����܂ŁA�ϋq�����Ď��{����Əq�ׂ��B���g�D�ς̋��{���q��́A�u�ɂ߂Č��肳�ꂽ�`��]�V�Ȃ������̂͑�ώc�O�B�`�P�b�g�w���ҁA�n��̊F����ɑ�ϐ\����Ȃ��v�ƁA�Ӎ߂����B�����I�����s�b�N��7��23���`8��8���A�p�������s�b�N��8��24���`9��5���̓����ŊJ�Â��\�肳��Ă���B
�����{�̊�����
���{�ł�4���ɁA�����̑�4�g���������A�����҂����������B�����A�V�^�E�C���X�̗��s���n�܂��Ă���̊����Ґ��͔�r�I���Ȃ��A���҂�1��4900�l�قǂƂȂ��Ă���B7���̐V�K�����Ґ���2180�l�������B����920�l�͓����s�Ŋm�F����A�O�̏T�̓����j����714�l����傫���������B1010�l���L�^����5��13���ȗ��̑����ƂȂ����B���{�̃��N�`���ڎ펖�Ƃ͓W�J���x���A����܂łɐڎ�����������l�͍����̖�15���ɂƂǂ܂��Ă���B�f���^�ψي��̋��Ђ����܂��Ă���B�����s�Ƒ��{�ł͓��Ɋ����҂������Ă���B���{��7�����܂łɁA65�Έȏ�̍���҂̃��N�`���ڎ���������������ӌ����B����8���̉�ŁA�u�S���̒ÁX�Y�X�Őڎ킪�i��ł���B���␢�E�ōł��X�s�[�h�̂���ڎ킪�s���Ă���ƌ����Ă���v�Ƃ̌������������B���̂����ŁA�u�ꕔ�̎����̂Ȃǂ���̓��N�`��������Ȃ��Ƃ̐����o�Ă���v�A�u���N�`���̔z�����@���������A�z���ʂ𑁊��Ɏ������ƂŁA�ڎ킪�~���ɐi�ނ悤�ɓw�߂Ă����v�Ƃ����B����ɁA�u9���܂łɊ�]���邷�ׂĂ̍����ɐڎ�\�ƂȂ�2��2000�����m�ۂł��Ă���v�Ɛ��������B���{�͌��݁A�C�M���X���܂�159�J������̊O���l�̓������֎~���Ă���B
�������̓I�����s�b�N��]��ł���̂�
�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɔ��̐l�͑����B�挎���{�̒����V���̐��_�����ł́A�J�Ấu���~�v���u�Ăщ����v���悢�Ɠ������l�͌v60���ɏ�����B�����V����5���ɎА��ŁA���~���ׂ����Ƒi�����B�\�肳��Ă����p�u���b�N�r���[�C���O�͒��~����A��Ƃ͐��_�̔������O���āA�I�����s�b�N�֘A�̍L�����o���̂����߂���Ă���B
�������s��4��ڂً̋}���Ԑ錾�A�R���i�����g��ōĂю�ޒ�~�v�� �@7/8
�����s��8���A�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɔ���4��ڂً̋}���Ԑ錾��12�����甭�߂����̂��A�����ȍ~�A�Ăш��H�X�Ɏ�ޒ̑S�ʒ�~�Ȃǂ�v�����銴���h�~��\�����B�Ώۂ͓s���S���8��22���܂ŁB
�s�̑�́A��ނ�J���I�P�ݔ��������H�X�Ȃǂɂ͋x�Ƃ�v�����A����߂�ꍇ�ɂ͌ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k�����߂���e�B���s�̂܂h�~���d�_�[�u�ł́A2�l�ȉ��̋q�Ɍ����Čߌ�7���܂ł̎�ޒ�F�߂Ă���B��ޒ̑S�ʒ�~�v���́A6��20���܂Ŕ��߂���Ă����O��ً̋}�錾�ȗ��ƂȂ�B
���̂ق��͌���̂܂h�~���d�_�[�u�̗v�����e�Ƃقړ����ŁA�S�ݓX�Ȃǂ̑�K�͏��Ǝ{�݂Ȃǂɂ́A�ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ�v���B�C�x���g�J�Â̐l�������5000�l�Ƃ���B
�錾���Ԓ��A�s�̗v���ɑS�ʋ��͂������Ǝ҂ɂ͎��ƋK�͂ɉ��������͋��Ƃ��āA���H�X��1�X�܂�����168���`840���~�Ȃǂ��A��K�͎{�݂�1000�������[�g��������1���ő�20���~�Ȃǂ��x��������j�B�s��7��8���A���͋��x���̂���5118���~�̕�\�Z��ꌈ���������B
���r�S���q�m���͓�����̑��{����c�Łu���H�X�ւ̑��N�`���ڎ�̐��i�Ȃǂ̑�ŁA����ȏ�̊����g������Ƃ��Ă��H���~�߂Ă����v�Ƌ��������B
���u�ً}���Ԑ錾�v�Ɓu�܂h�~���d�_�[�u�v�ǂ��Ⴄ�H�@�@7/8
�܂h�~���d�_�[�u�̑ΏۂƂȂ��Ă��铌���s�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�A���{��8���A���{���̉�ŁA������12������A4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�߂��邱�Ƃ����߂��B���ꌧ�ً̋}���Ԑ錾��A�_�ސ�A��ʁA��t�A����4�{���̂܂h�~�[�u�͉�������B�u�ً}���Ԑ錾�v�Ɓu�܂h�~�[�u�v�B�������������ǂ��Ⴄ�̂��B�ړI��Ώےn��A�����̓��e�A�ł��邱�ƁE�ł��Ȃ����Ƃ̐������ȂǁA�C�ɂȂ�_�������B
����s���̏�
�����s�c7��11���܂ł܂h�~�[�u�A12������8��22���܂ŋً}���Ԑ錾
�_�ސ쌧�A��ʌ��A��t���c8��22���܂Łu�܂h�~�[�u�v����
����@�ً}���ԂȂ�x�Ƃ��A�܂h�~�͎��Z�̂�
����̐��{���j�ł́A�܂h�~�̑Ώےn��ŁA�����t���ŔF�߂Ă�����ޒ�������~�Ƃ��A�m�����������ɘa����Ɣ��f�����ꍇ�̂ݏ����t���Ōߌ�7���܂Œł���d�g�݂ɕς����B�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ł́A��ނ������H�X�ɂ͋x�Ɨv�����o�����B���{�́A��ނ̔̔����Ǝ҂ɑ��Ă��A�x�Ɨv�����ɉ����Ȃ����H�X�Ƃ̎�������Ȃ��悤���߂�B�ً}���Ԑ錾�ł́A���H�X�Ȃǂɑ��A�x�Ƃ�c�Ǝ��ԒZ�k�̖��߂�v�����ł���B����A�܂h�~�[�u�ł͋x�Ƃ̖��߂�v���͂ł����A�c�Ǝ��ԒZ�k�݂̂ƂȂ�B��̓I�Ȗ��߁A�v���̓��e�́A���{�����܂Ƃ߂�u��{�I�Ώ����j�v�̓��e����{�Ƃ�����ŁA�e�s���{���̒m�����n��̏܂��đ�̏�悹������B��{�I�Ώ����j�̓��e�͕ύX���d�˂Ă���B
���Ώےn��@�ً}���Ԃ͓s���{���S��A�܂h�~�͈ꕔ�n��
�ً}���Ԑ錾�͊e�s���{���S�悪�ΏۂɂȂ�̂ɑ��A�܂h�~�[�u�͓���̒n����Ŋ�����}�����ނ��Ƃ�ړI�Ƃ��A�m�����w�肵���n��݂̂��ΏۂɂȂ�B�Ⴆ�A�����s�͞w�����Ɖ��������A�����啔�͂܂h�~�[�u�̑ΏۊO�����A�ً}���Ԑ錾�ɂȂ�A�S�悪�Ώےn��ƂȂ�B
����K�̓C�x���g�ϋq����
�v���X�|�[�c�Ȃǂ̑�K�̓C�x���g�̊ϋq�́A�ً}���Ԑ錾�ł��܂h�~�[�u�ł������ŁA�u5000�l�v���u�����e�l����50���v�̏��Ȃ���������ƂȂ�B�ǂ����������1�J�����x�̌o�ߑ[�u�ł́u1���l�v���u�����e�l����50���v�̏��Ȃ������K�p�����B�܂h�~�[�u������ɏ��1���l�Ƃ���o�ߑ[�u�́A6��16���ɊJ���ꂽ���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�ŐV���ɗ������ꂽ�B���̏��1���l�𓌋��ܗցE�p�������s�b�N���ɓK�p���邩�ǂ����́A�c�_�����������A�����ɋً}���Ԑ錾�����߂���邱�Ƃ��A�s���ϋq�Ƃ���Ȃǂ̒������s���Ă���B
�����߈ᔽ�̔����́H
�m���͎��Z�c�Ƃ�x�Ƃ̗v���������H�X�Ȃǂɖ��߂��o�����Ƃ��ł��A���߂ɉ����Ȃ��ꍇ�͍s�������Ȃ����B���̏d���ɂ͍�������A�ً}���Ԑ錾��30���~�ȉ��̉ߗ��A�܂h�~�[�u��20���~�ȉ��̉ߗ����B
�����߁A�K�p�̃^�C�~���O�́H
��Ò̐��̕N�����V�K�����Ґ��������w�W�����Ƃ�4�i�K�ŋ敪����銴�������߁A�K�p�̖ڈ��ɂȂ��Ă���A�ً}���Ԑ錾�͍ł��[���ȁu�X�e�[�W4(�����I�����g��)�v�A�܂h�~�[�u�́u�X�e�[�W3(�����}��)�v�ŏo�����B�����A�@�B�I�ɔ��߁A�K�p�����킯�ł͂Ȃ��A���{�����Ƃ̈ӌ��܂��čŏI���f���Ă���B6��15�����_�̎w�W�ł́A���{�͓��@���Ɛl��10���l������̗×{�Ґ����X�e�[�W4�������������A20���܂łłً̋}���Ԑ錾���������܂����B
���ً}���Ԑ錾�A�܂h�~�[�u������ۑ�
�x�Ƃ�c�Ǝ��ԒZ�k�̖��߁A�v���������ẮA���������B���ɂȂ�A���e�ɔ[���ł��Ȃ��ƊE�c�̂��s���ɍR�c����P�[�X������B�����s�ɑ���ً}���Ԑ錾���������ꂽ5���ɂ́A����≉�|��̉c�Ƃ������t���ŔF�߂�ꂽ����A�f��ق͋x�Ɨv���̂܂܂ƂȂ�A�f��ق̊W�҂��s���O�Ŗ����̍R�c�f�����s�����B���������������ɂ́A�s����������u����������v�Ƃ��������R��Ă����B�܂h�~�[�u�̑Ώےn��̍i�荞�݂ł��A���������ۑ�ɂȂ����B�s�������Ƃ̎w�肪�\�ŁA�n��̊����ɍ��킹�����ߍׂ��ȑΉ����ł��邪�A�������̌��ʁA�����w���ӂ̔ɉ؊X�őΏۂɂȂ���ƁA�Ȃ�Ȃ���悪���݂��鎖�Ԃ��N�����B�����s��4��12������܂h�~�[�u���K�p���ꂽ�ۂɂ́AJR�O��w�k���̕�����s���ΏۂƂȂ����A�쑤�̎O��s�͑Ώۂ���O��A���Z�c�Ɨv���͕�����s���̓X�Ȃ�ߌ�8���A�O��s���Ȃ�ߌ�9���Ǝ��������܂ꂽ�B�K�p�����ɂ́u���O��s���ɗ��Ă��܂��v�Ɩ������q�������B���Z�c�ƂȂǂ̗v���̎������ɂ��ۑ肪����B�������́A���߂Ɉᔽ�����ꍇ�̔����ƁA�v���ɉ��������Ǝ҂ւ̋��͋��̎x�����ɂ���ĒS�ۂ���Ă��邪�A5���ɂ͈��H�X�o�c�҂���u���Z�v���ɋ��͂��������A�ł��Ȃ��v�Ƃ������������ꂽ�B�����s�ȂǂŎ��Z���͋��̎x�����x��Ă������炾�B5�����{���_�ł́A3��8�`31�����̖��x�����������s��45�D8���A�_�ސ쌧��51�D0���������B
�����ʂ́H
�Љ�o�ϊ�����������������ً}���Ԑ錾�̕����A�l�̗����}��������ʂ������\���������f�[�^�͂�����̂́A�錾���Ԃ����������ꍇ�ɗ}�����ʂ�����Ă����X�����݂���B�����J���Ȃɏ���������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�ŁA�����s��w�����������̐��c�~�u�E�Љ�N��w�����Z���^�[������o������Ȕɉ؊X�̑ؗ��l���̕��͌��ʂɂ��ƁA�����s�ł�4��12���̂܂h�~�[�u�̓K�p������A����25���ً̋}���Ԑ錾���ߒ���̕����啝�Ɍ��������B���̕��͂́A�q�����p���ʃV�X�e��(�f�o�r)�����p���A�ɉ؊X�Ƀ��W���[�ړI�őؗ������Ƃ݂���l���𐄒肵�Ă���B�����s�ł́A4���ً̋}���Ԑ錾���O��90���l���Ă����ߌ�2�`4���̑ؗ��l�����A�錾��ɂ͈ꎞ�I��50���l��ɂ܂ʼn��������B�����A6��13���܂ł̕��͂ł́u5�T�A���Ŕɉ؊X�ؗ��l���������B��ԁE���ԂƂ��ɐ錾�O�̐����ɂ܂Ŗ߂����A�錾������͂���ɑ�������\���v�Ǝw�E���ꂽ�B �@
���o�b�n��A�ً}���Ԑ錾�m��Ȃ������H�u�ǂ��������Ƃ��A�������������v �@7/8
���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�̃o�b�n���8����A�����ܗւ̊ϋq��������߂�5�҉�c�̖`���ŁA�u�ً}���Ԑ錾�͂ǂ��������ƂȂ̂��B���ꂪ�ܗցE�p�������s�b�N�ɂǂ̂悤�ȃC���p�N�g�������炷�̂��A���b���������������v�Ɣ��������B�o�b�n����4���̋L�҉�ŁA������3�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o����邱�Ƃɂ��āu�����ܗւƂ͊W���Ȃ��v�Ɣ������Đ��_�̔����������Ă����B
5�҉�c�ɂ́A�ې���ܗ֑��A�����s�̏��r�S���q�m���A���g�D�ψ���̋��{���q��炪�o�ȁB�o�b�n���̔����͌��J���ꂽ��c�`���Ŕ�яo�����B
5�ҋ��c�Ȃǂ̌��ʁA�s���ƍ�ʁA��t�A�_�ސ��3���ōs���鋣�Z�͖��ϋq�Ƃ������A�{��A�����A�É��̋��Z�͎��e�l��50���A���邢��1���l�ȓ��̏��������Ŏ��{���邱�Ƃ����܂����B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
������E���䑏������4�x�ڋً}���Ԑ錾�Ő����{���J�X�ᔻ�@7/9
���{��8���A�V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��A�����s��4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̔��߂�����B���łɏo����Ă�������ւ̐錾�ƍ�ʁA��t�A�_�ސ�A���ɓK�p���̂܂h�~���d�_�[�u�̉��������߂��B���Ԃ�12�����痈��22���܂ŁB���˂Đ錾�ɔ���������p�������O���Ă������s��w��w�@�̓��䑏����(52)�͐��{�̕��j���������ƁA�u�����}�W�ł��čs���܂���v�Ǝ��g�̃c�C�b�^�[�ɓ��e�B���̐^�ӂ𖾂������\�\�B
�����s�͂��̓��A896�l���V���ɐV�^�R���i�Ɋ��������Ɣ��\�B19���A���őO�̏T�̓����j�����������B���{�͍���A��Ò̐��̂Ђ������������˂Ȃ��Ɣ��f���A4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̔��߂����肵���B���H�X�ł̎�ޒ͌����֎~�Ƃ���B
���`�͉̎�ŁA�f���^���ɂ�銴���g��Ɍ��O�������u�������N�_�Ƃ��銴���g��͐�ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŗ\�h�[�u���u���邱�Ƃɂ����v�Ɛ��������B
����̐��{�̕��j������ƁA���䎁�͎��g�̃c�C�b�^�[�Łu�����}�W�ł��čs���܂���v�Ɠ��e�B�����āu�����n���ȗ��R�v�Ƃ��āA1��������ܗփ�����2������������ƕ⏞�V��3����܂ł̐錾��ƑS�R�Ⴄ4���N�`�����̂��߂ɑł��Ă����\�\��4�_�������A�u�R���i�Ђ̌����̓R���i����Ȃ����������̂ł��v�Ǝa��̂Ă��B
��ނɉ��������䎁�́A�ő�̖��_�Ƃ��āu�ً}���Ԑ錾�Ƃ������̂́A�v�����������ꂽ�ꍇ�ɏo����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B����͗v��������܂łƑS���Ⴄ�i�K�ŏo���Ă���A�����Ƃ̐����I�ȖړI�̂��߂ɍs����c�߂��`�ɂȂ��Ă���B���̗F�l�������Ă������A����͖\���Ńt�@�V�Y���I����ł���v�Ɣᔻ�B�u���f�B�A��@���Ƃ͓O��ᔻ���ׂ����ł��v�Ǝw�E�����B
���̂����ŁA�錾�̔��߂ɂ�鍑������ɂ��Ă������y�����B
�u�܂���������I�Ɉ�ԕ������̂́A�錾���o���Ȃ�I�����s�b�N����߂����Ă��Ƃł���B���ۑ�ǂ��납�Y���Y���ɊO���l�����Ă�̂ɁA�����ȃC�x���g���ً}���ԂƂ������ƂŒ��~�ɂ����Ă�B�ǂꂾ���_�u���X�^���_�[�h��A���Ęb�ł���B���O�@���������ō���Ă���悤�Ȃ��̂ŁA��������Ƃ��Ă͑傫�ȃ|�C���g�ł���ˁv
���䎁�͂��˂āA�R���i�������Ґ����������g�����x���ł���̂̓f�[�^�㖾�炩�ŁA�[���R���i�Љ�����߂邠�܂�A�o�ς��]���ɂ���͓̂��{�S�̂��łт�Ǝ咣���Ă���B
�R���i�����������łȂ��A�|�Y�⎸�ƂƂ������o�ϓI��Q�ɂ��A���a�⎩�E�҂̑��������ׂČ������������ŁA��Q���ł��������Ȃ�悤�ȃx�X�g�E�F�C��͍����ׂ����Ƃ��āA�ً}���Ԑ錾�̔��߂ɂ͔ے�I�ȗ��������Ă����B
���ꂾ���Ɂu����ł����܂�������p�����邩��⏞��O�ꂷ�ׂ��Ȃ̂ɁA�����⏞�����߂Ȃ��܂ܔ��o���������߂��B�����g�ɂ���Ȃ��Ă��Ȃ��̂ɗ\�������Ő錾���o���āA�X���Ԃ�āA���E����l��������Ȃ�ăo�J�Șb�͂Ȃ��B�����I�ȍ����̐����ƍ��Y�ɑ����@�Ƃ����_�ŋɂ߂Đ[�����v�Ɠ{����ɂ��܂����B
����ɁA���䎁�̓��N�`���ڎ�ɂ��Ă����y�����B
�u���ɂ͊��X�Ƃ��đł��Ă���l�����邾�낤���A���N�`���݂͂�Ȍ��X�ł��Ă���킯�ł��B����p�������ĕ|�����A�M���o��l������B�����h�����đł̂́A�ܗւ��͂��߂Ƃ����Љ�����Ɠ������߁A�ً}���Ԑ錾������������߁B��Õ����N�����Ȃ���ً}���Ԑ錾�Ȃ�Ă��Ȃ��Ă������A���ꂾ�ƃ��N�`����ł��Ă���Ӗ����Ȃ��v
�ً}���ԂȂ̂ɓ����ܗւ͊J�ÂƂ�����������������Ȃ���A�s����6�T�Ԃ̉䖝���������邱�ƂɂȂ�B
���ً}���Ԑ錾���̌ܗցA�L���Ȋ�����́u���~�v�ł́@7/9
���{�������s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�߂���B�錾���Ԃ͓����ܗւ̊J�Ê��ԂƊۂ��Ԃ�ŁA�����g��h�~�̂��߂̍ŏI��i�Ƃ������A�����Ȃ�ł��ܗւ��J�Â��邽�߂̐錾�Ȃ̂͌����������B���ꂪ���{�W�O�O�A���`�̌����ĎO�J��Ԃ��Ă����u�l�ނ��R���i�ɑł����������Ƃ��Ă̌ܗցv�ƌ�����̂��B���A�ł����ʓI�Ȋ����h�~��́u�ܗ֒��~�錾�v�ł͂Ȃ��̂��B
���u�����o�����v�͈��{�O��
�ܗւ��u�R���i�ɑł����������v�ƌ����n�߂��̂́A���{�W�O�O�������B��N3��16���̐�i7�J��(�f7)��]�Ƃ̃e���r�d�b��c�ŁA�����āu���S�Ȍ`�Ŏ��{�������v�Əq�ׁA�e���̎x�����Ƃ����B���{���͓���23���̎Q�@�\�Z�ψ���ł��u�S�Ă̎Q���������S�ȏ�ԂŎQ���ł��邱�Ƃ��d�v���v�u(�R���i��)�����������Ƃ��Čܗւ��J�Â������v�Əq�ׂ��B�ܗւ�1�N���������܂����̂́A���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�̃o�b�n��Ɠd�b��k������24���B�����̉�ł��u�ł����������Ƃ��āv�Ɣ��������B
����p������������N10���A����ł̏��M�\���Łu�l�ނ��E�C���X�ɑł����������Ƃ���(�ܗւ�)�J�Â��錈�ӂ��v�ƌ�����B���N3��21���̎����}���ł������t���[�Y���J��Ԃ����B4���̓��Ď�]��k�ł͎g�킸�A�u���E�̒c���̏ے��v�ɕ\����ς������A�A����A���̂��Ƃ��O�@�{��c�Ŗ�}�c���ɒNjy�����Ɓu�ł����������Ƃ��Čܗւ���������Ƃ̌��ӂɉ���ς��Ȃ��v�Ɠ������B
���{���������o������N3���́A������1��������̐V�K�����Ґ���2���Ő��ڂ��Ă��������B�U��Ԃ�ƁA�܂��y�Ϙ_���������B���唭�̈�Ãx���`���[�u�A���W�F�X�v�������A���Y���N�`���̊J������\�B�������N���Ɏ��p������A���Ăɐڎ킪�s���n��ϑ����o�Ă����B�V�^�C���t���G���U���Ö�u�A�r�K���v���V�^�R���i�x���̓�����ɂȂ�Ƃ̊��҂��������B
���������Ȃ����������h�~�u�y�σv�����v
����A���{�͓�������A�o�b�q������}���Z���ڐG�҂����ǂ�N���X�^�[��ɏd�_���B�e���Ŕ����I�Ɋ��҂������钆�A���Ґ����r�I�}���������ł��������B���{���͍�N5���A�ŏ��ً̋}���Ԑ錾���������߂��ۂ̋L�҉�Łu�킸��1�J�����ŗ��s���قڎ��������邱�Ƃ��ł����B�w���{���f���x�̗͂��������v�Ƌ������B
�������A�y�σv�����͌����ɂȂ�Ȃ������B�A���W�F�X�̃��N�`�����p���͗��N�ȍ~�ɂȂ錩�ʂ������܂��Ă���B���{�͕ăt�@�C�U�[�ЂȂNJC�O�����А����N�`���̊m�ۂ���Ԏ��A�ڎ�y�[�X�͐�i���̒��ł��x�ꂪ�ڗ��B�ڎ�ɓ�����n�������̂���͋����s���ɍ��ݐ߂��オ��B
���H����N�����ɂ����Ă͊��Ґ���1000�l������ԉ������B���{�������Ȃ�1�s3����2�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o�����̂́A���N1��7���B���ꂩ�甼�N�ŁA�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�Ɛ錾�Ĕ��߂�2�x�J��Ԃ����ԂɊׂ��Ă���B
�ً}���Ԑ錾���̌ܗւ́A�ނ���u�R���i�ɑł����ĂȂ��������v�ł͂Ȃ��̂��B��s���̕����̈�Ë@�ւōݑ��Â𒆐S�Ɏ肪����ؑ��m��t�́u����ŃR���i�ɑł��������ƌ�����v�f�͂Ȃ��B�����́A�ܗւ��J�Â��Ă������I�Ɋ��҂������Ȃ���A�������ƌ�������Ȃ̂��낤���B�ً}���Ԑ錾���o���قNJ����҂������Ă���̂ɁA���X�N�𑝂₷�ܗւ��J�Â���͈̂Ӗ���������Ȃ��v�ƕ���B
���ً}���Ԑ錾�Łu�ٗ�̌ܗցv�Ɛ��� �u���S���S�v�Ɩ������炯�@7/9
���{�������s�ւ�4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾���߂����肵�A23���J���̓����ܗւ͐錾���ŊJ�Â���邱�Ƃ����܂����B���J��Ԃ��Ă����u���S���S�̌ܗցv���A�錾���Ŏ��{�ł���̂��B��}����́u�������v�Ƃ̔ᔻ�����o����B���~��A�Ȃ̎������T���A�錾���Ɋ����Ċg����������O���ʂ����Ȃ��B
���u�����͂Ȃ��v
��8���̋L�҉�ŁA�錾���̌ܗւ��u�ٗ�̊J�Áv�ƔF�߂u�R���i�Ƃ�������ɒ��ʂ��鍡�����炱���A���E����ɂȂ�邱�ƂM����ǂ��@��v�ƈӋ`�����������B
����A8���̏O�@�c�@�^�c�ψ���ł́A��������}�̐��z��Y�����u�R���i�ɑł������Ă����Ȃ��B�w���S���S�Ȍܗցx�������͂��Ȃ��v�Ɣᔻ�B���Y�}�̎u�ʘa�v�ψ����͋L�҉�Łu�����o���ȁA�O�o����ȁA�^����A�čՂ�A�ԉΑ����S�����~����(������)���߂Ȃ���A�ܗւ������Ƃ����͖̂��������ԓx���v�Ǝw�E�����B
���������ً}���Ԑ錾�́A�R���i�̊���������������o�ςɐr��ȉe�����y�ڂ����ꂪ�����@�I�ȏ����Ɣ��f���A���߂���B��6���̓}�_�ŌܗւɊւ��u�����̖��ƈ��S�����͎̂��̐Ӗ�������A�����łȂ���ł��Ȃ��v�Ɣ����������A�������������Ă��J�Â��肫�̎p���͌����B���@�����͐�̐�i7�J����]��c(�f7�T�~�b�g)�̌��ʂ��u�e���̎x�������ی���v�ƕʂ̊J�×��R��������B
���^�`����
����܂Ő��{�́A�����g��h�~�ւ̋������ӂ������Ȃ���A�Ċg���}�����Ȃ����̗�����J��Ԃ��Ă����B
6���̐錾�����̍ہA�́u�����x�����ׂ��͑傫�ȃ��o�E���h���v�Ƌ��������B�����A�s�s���𒆐S�ɐl�̗��ꂪ�����B���u��D�v�ƈʒu�t���郏�N�`���ڎ���A�����̂��Ƃʼn������n�߂��^�C�~���O�ŋ������ǂ����Ȃ��Ȃ�A���{����u���[�L��������`�ɂȂ����B
�����N���o�ύĐ��S������8���̎Q�@�c�^�ςŁu�l�o������(��ޒ̎��l)�v���ɉ����Ȃ��X���o�Ă��钆�Ŋ������g�債�Ă���v�Ɛ����������A�����̋g�썹�D���́u�錾�����̔��f���K�������̂��^�`������v�Ǝw�E�����B
���O���C���]�V�Ȃ�
�ܗւ̊ϋq���ł́A���_�̓������̔��f�ɉe����^�����\���������B
�͊ϋq����ɂ�������Ă������A4�����J�[�̓����s�c�I�ł́A���~�△�ϋq�J�Â�i�������͂��ߔ������l���B�����}�̎R���ߒÒj��\���u���ϋq���x�[�X�ɂ��������悢�v�Ɩ������A���g�D�ψ���̐X��N�O����u���ϋq�����Ă����v�ƌ��ȂǁA�O�x�͖��܂��Ă������B���{�����́u�����̑��ӂ݂����Ȃ��̂����痬��ɂ����������Ƃ��厖���v�ƋO���C����F�߂�B
�����A���ϋq�J�Âł������g��̌��O�͏����Ȃ��B�ܗ�ɂ͂��~��A�Ȏ������}���A�����Ɋ����͂������ψي��̃f���^��(�C���h��)�ւ̒u������肪�i�ނƂ݂��Ă���B���{�̊�{�I�Ώ����j���ȉ���o�[�̊ړc�ꔎ�E���M�勳����8���A�L�Ғc�Ɂu�C�̊ɂ݂⊵��Ȃǂ̏d�Ȃ���l����ƁA���Ȃ茵�����ɂȂ��Ă����v�ƌx����炵���B
���L�����Z���A���ւ��x���@�ً}���Ԑ錾�A�ċx�ݒ����\�ό��E�^�A�ƊE�@7/9
���{��8���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ċg����ē����s��4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̔��߂����߁A�ό��E�^�A�ƊE�ɏՌ����L�������B�錾���Ԃ�12������8��22���܂łƁu�������ꎞ�v�ł���ċx�݂��B����ɍ��킹�����ܗւ��s���̉��͑S�Ė��ϋq�ŊJ�Â���邱�Ƃ����܂����B�e�Ђ͗��s�̃L�����Z���A�q�ւƂ������������ǂ��܂ōL���邩�x�������߂Ă���B
�u���s�̐\�����݂͏��X�ɉ��Ă������A�ً}���Ԑ錾�ŊԈႢ�Ȃ��傫�ȉe������v�B���{���s�Ƌ���ō������s��S�����鍂���L�s���(�i�s�a�)��8���̋L�҉�ł����b���A�K�v������L�����Z���������̕⏞�Ȃǂ̎x����𐭕{�ɋ��߂Ă����l���𖾂炩�ɂ����B
���s���̊����́u�錾���Ԓ��͓���������c�A�[�͒��~�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�\���������͐��{�̌ٗp�����������Ȃǂ����p���ď��邵���Ȃ��v�ƑΉ��ɋꗶ�B�ʂ̓��Ƒ��W�҂́A����ł̐錾�����ɂ��āu����͉Ă̍������s�̒�Ԓ��̒�Ԃ��B���Ɏ�ɂ��v�ƌ��𗎂Ƃ����B�s���̑��z�e���̎Ј��́u�ܗւ�����\�肾�������q���܂��\����L�����Z������̂ł͂Ȃ����v�ƐS�z���ɘb���B
���{�q���8���A�������̉^�q�ɂ��Ď��ƌv����7���㔼�ɖ�700�ցA8���O���ɂ�3300�ւ����炷�Ɣ��\�������A�����≫��ً̋}���Ԃ̉e���͔��f���Ă��Ȃ��B����Ȃ錸�ւ𔗂�����Z���傫���A�W�҂́u�ꂵ���Ƃ��낾�v�Ƒł�������B�S���{��A�͋߂��A�錾�̉e���܂����^�q�v��\����\�肾�B
�i�q�����{�͍����㔼�ɐV�����ƍݗ������}�ŗՎ���Ԃ̉^�s�����߂Ă���B4�A�x��ܗ֊��Ԃ̈ړ������邱�ƂŁA�W�҂́u���Ȃ��炸(���p������ւ�)�e���͏o�Ă��邾�낤�v�Ƙb�����B�i�q���C��21�`31���ɓ��C���V�����̗Վ���Ԃ��^�]����\�肾���A����Ōv��̌������𔗂�ꂻ�����B
�������ŋً}���Ԑ錾�A��ޒ��ꗥ��~�@7/9
��1 �K�������̓��e�́H
���`�̎�7��8���A�ً}���Ԑ錾�̔��߂\����ƂƂ��Ɂu(�錾�߂���)�����A����ł́A�������X�N�����߂邽�߂Ɉ��H�X�ɂ������ނ̒��ꗥ�ɒ�~����v�ƕ\�������B�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑ΏۂƂȂ�_�ސ����Ȃ�4�{���ł��A��ނ̒͌�����~����(�m���̔��f�Ōߌ�7���܂ł͒ł���)�B����܂œ����s�̂܂h�~�[�u�̒n��ł́A1�g2�l�܂ł�ΏۂƂ�����ނ̒�F�߁A�I�[�_�[�͌ߑO11���`�ߌ�7���̊Ԃ܂łƂ��A�؍ݎ��Ԃ�90���ȓ��ɂ���悤�v�����Ă����B�X�܂̉c�Ǝ��Ԃɂ��ẮA����܂łƓ������ߌ�8���܂łƂȂ��Ă���B�����N���o�ύ����E�Đ����͓����A���H�X�ł̎�ޒ�����������@��B��ނ̒��~�����A�x�Ɨv���ɂ������Ȃ��X�Ƃ̎���͂�߂�悤�A��ނ̔̔��Ǝ҂ɑ����Ƃ����B�x�Ɨv���ɉ����Ȃ����H�X�̏������Z�@�ւɋ�������j�����������A�s���߂��Ă���ȂǂƎw�E���A7��9���ɓP�邱�ƂƂȂ����B
��2 ��ނ̒������������闝�R�́H
������b��7��8���A���Z�c�Ƃ̗v���Ȃǂ���܂ł̎��g�݂ɑ��āu���͂��Ă�����H�X�����(���Z�c�ƂȂǂ��s���Ă��Ȃ����H�X�ɋq���W�܂�ɂ�����Ă��邱�Ƃ�)�s������������Ă��鐺����������v�Ǝw�E�����B���͂��Ă���X�܂͑����Ɏx�����Ă�������ŁA���͂��Ȃ��X�ɂ͉����V�^�C���t���G���U�������ʑ[�u�@�Œ�߂����߂┱�������{���邱�Ƃɉ����A��L�̂悤�Ɏ���Ǝ҂ɂ����������u�����n�������Č����ɑΉ����Ă����v�Ƃ����B
��3 �X�ł������o���Ȃ����Ƃ��A�����}���ɗL���ȗ��R�́H
����7��8���A�u���������H�́A�ǂ����Ă��}�X�N���O�����Ԃ������Ȃ�v�Ȃǂƃ��X�N��i�����B���{�͂���܂ł������̉e���ŋC�������g���A���ӗ͂��ቺ������A�吺�ɂȂ�₷�����ƂȂǂ𗝗R�Ƃ��āA���H�����W�܂肪�������X�N�����߂�Ɛ������Ă����B�����A��Ȃ��ǂꂾ�������g��ɉe�����Ă����̂��A�����ɂ����Ƃ̎w�E������B����ɑ��Č����J���Ȃ̐��Ƒg�D�ł���A�h�o�C�U���[�{�[�h��7��7���A���̏o���H�ɕ�����Q�������l�͐V�^�R���i�Ɋ������₷���Ȃ�Ƃ̕��͌��ʂ����\�B�ߋ�2�T�Ԃ̂����ɁA���̏o��3�l�ȏ�̉�H��2��ȏ�Q�������l�́A����ȉ��̉̐l�ɔ�ׂĖ�5�{�������₷�������Ƃ����B
��4 ���͂��Ȃ����H�X�ւ̔����́H
�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ł́A���[�@�Ɋ�Â��ċx�Ƃ�v���E���߂ł���B���߂ɏ]��Ȃ��X�ɂ�30���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ����Ƃ��\�B�܂��A�܂h�~�[�u�̑Ώےn��ł͖��߂ɏ]��Ȃ����20���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ����\��������B �����͏]���ƕς��Ȃ��B
��5 ��x����������A���������͎Ȃ��H
�����s�ł͂���܂ʼnߗ����Ȃ���ꂽ�P�[�X��4������B������b��7��8���̉�Łu�ߗ����Ȃ���Ă����������v���ɏ]���Ă��炦�Ȃ��ꍇ�͂���ɖ��߂��s���A�ߗ��̎葱�����s���Ƃ����悤�ɁA�J��Ԃ��Ή����Ă����v�Əq�ׂ��B
��6 ���͂��Ă�����H�X�ւ̎x���́H
���݁A�x�Ƃ⎞�Z�̗v���ɏ]�������H�X�ɂ́A�����g��h�~���͋����x������Ă���B����ً̋}���Ԑ錾�̔��߂��āA�����s�ł�7��12���`8��22���܂ł̊ԁA�O�N�܂��͑O�X�N��1��������̔��㍂�ɉ����āA�������Ǝ҂�Ώۂ�1�X�܂ɂ�1��������4���`10���~�A���Ƃ͔��㍂�̌����z�ɉ����āA�����20���~���x������悤�ύX����\�肾�B���O����Ă���͎̂x�����̎����B���͋��ً͋}���Ԑ錾�̊��ԊO�ł��A���z��ύX���Ȃ���x������Ă������A�x�����ɂ��Ȃ�̓�����v���Ă���B�����s�̎x�����藦�́A2021�N4��1���`11���̊��Ԃ�78���A4��12���`5��11���ł�36���ɂƂǂ܂��Ă���(7��8�����_�A�X�ܐ��x�[�X)�B5��12���ȍ~�̋��͋��ɂ��ẮA�t�����܂��n�܂��Ă��Ȃ����B�x�����̒x���̓R���i�БO�̉c�Ǝ��Ԃ̏ؖ���A�\�����ނɕs�����������ۂ̍����߂��������ɂȂ��Ă����B�����ŁA7��8���̉�Ő�����b�́A����̋��͋�������A�ߋ��̎x�����Ă�����H�X�ɂ��ẮA��ނ̒����l����|�̐����o���邱�Ƃ������ɁA1��������4���~���ꗥ�Ő�s���Ďx������l���𖾂炩�ɂ����B
��7 ��ޔ̔��Ǝ҂ւ̎x����?
���Ⓦ���s�́A�ً}���Ԑ錾��܂h�~�[�u�ɔ������H�X�x�ƂȂǂ̉e��������ޔ̔��Ǝ҂��܂ޒ�����ƁE�l���Ǝ҂ɁA����グ�̌����z�ɉ������x����ł��o���Ă����B�����A�s�́A��ޒ𑱂������H�X�Ƃ̎����~�v��������V���Ȏx���ɂ��āu�܂��������̓I�Ȏw�j�����Ă��Ȃ��̂ŁA�����_�Ō��܂��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ��Ă���B
��8 ��ޔ̔��Ǝ҂Ȃǂ̔����́H
�s���̎�ޔ̔��Ǝ҂Ȃǂł��铌��������̑g���̋g�c���F�������́u����܂ł������ɂ킽���đ傫�ȑŌ����Ă���A(��ޒ��ꗥ��~�ƂȂ邱�Ƃ�)�Ԏ���Ԃɒǂ��ł���������v�Ƙb���B�g���ɉ������Ă����X����́u���̒𑱂��Ă�����H�X����w����̗v���ɉ����Ď���𒆎~����̂ł������̊W���������x�ƌ���ꂽ�v�Ƃ������A�����������Ƃ����A�e�����R���i������ɂ��y�ԉ\�������O�B���{�ɑ��āA�v���̌������Ǝx���̏[�������߂��B���r�[����Ђ���́u�Ɩ��p�̔���グ��(�V�^�R���i�̗��s���n�܂���)��N���{���{�����������A���N�͂��������ɉ����ɂ���B����̐錾���߂ň�w�������Ȃ�v�u�S���ɐ錾���g�傷�邱�Ƃ��Ȃ���������v�Ɛ�s�������O���鐺�������ꂽ�B����̈ꗥ��~���āA���H�X�ւ̉e����s�������郁�[�J�[�̈ӌ��͑����B�L�����r�[���̕z�{�F�V�В���7��9���̋L�҉�ŁA�l�I�Ȉӌ��Ƃ��������Łu�O�H�̋ꂵ�݂͓��R�������Ă���B�m���Ɉ��H�X�͊������[�g��1���Ǝv�����A�ƒ��E��ɂ�����(�������[�g��)���͂�������Ȃ����ŁA���H�X�͍s���K���������Ȃ��Ă���B�s���̗v���ɏ]���C�����͂����Ă��A���ꂾ�����������ƌo�c�������s���Ȃ��B�F�A�����J��ɖz�����Ă���B�S�z���Ă���̂͊O�H�Y�ƂɌg���]�ƈ���400���l�ȏア�邱�Ƃ��B�ǂ�ǂE����X�����o�Ă��āA�ٗp�ƐH�����̈ێ�������Ȃ��Ă���B�V�^�R���i�̊����g���h�����ߋK���͕K�v�����A����Ɍ������⏕�Ƃ̃o�����X�����܂�������肵�Ă��炢�����v�Əq�ׂ��B
��9 �R���r�j�G���X�X�g�A�ȂǁA�l�ɑ����ނ̔̔��ւ̉e���́H
�����s�̒S���҂́u�����_�ŃR���r�j�Ȃǂł̎�ނ̔̔����l�v���͌������Ă��Ȃ��v�Ƙb���B����ŁA���H�X�����Z�c�Ƃ����钆�ŎU�������H����݂Ɋւ��Ắu���l�̃|�X�^�[���R���r�j�Ɍf�����Ă��炦��悤���肢����Ȃǂ̑�͈��������s���Ă����v�Ƃ��Ă���B
��10 �@�I�ɂ͍���̎�ޒւ̋K�������̗v���ɖ��͂Ȃ��H
���@�����̌c���`�m��w��w�@�@�������Ȃ̉��哹�������́u���[�@45��2���Œ�߂��Ă���s���{���m�����g�p�����Ȃǂ�v�����邱�Ƃ��ł���{�݂́A�w�Z��Љ���{�݁A���s��̂ق��A���������p����{�݂Ƃ���Ă���v�Ǝw�E�B���̂����Łu������{�݂��v���̑ΏۂƂ���Ă��钆�ŁA�ǂ����Ĉ��H�X�Ɏ�ނ�̔�����Ǝ҂ւ̗v�����\�Ȃ̂��B����̂悤�Ȃ����͂��������z�肳��Ă��Ȃ��B���߂ɂ���č���̗v���[�u��lj�����Ƃ�����A�ϔC�̌��x����@�ł͂Ȃ����v�Ƌ^���悷�B�����āA�u����̗v���́A�@���̍����̂Ȃ��v���Ƃ������ƂɂȂ邪�A��ނ̔̔��ƖƋ����o�����Œ��ȂǂƂ̊W�ŁA������͋����̂悤�ɋ@�\����\���������v�Ǝw�E�B�u���H�X�Ŏ�ނ���邱�Ƃ������̊g��Ɋ�^���Ă���Ƃ����̂ł���A�������Ə؋��������������Ōʂ̖@���������ċK�����邱�Ƃ��ł͂Ȃ����v�Ƌ������Ă���B
�������s��4��ڂً̋}���Ԑ錾 ��炵�͂ǂ��Ȃ�@7/9
���{�́A�����s��4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o�����Ƃ����߂܂����B�����I�����s�b�N�́A�J�Ê��Ԃ��ׂĂ��錾�̎����Ɋ܂܂�邱�ƂɂȂ�A�V���Ȋ����g��ɂȂ���Ȃ��悤��ɖ��S���������Ƃɂ��Ă��܂��B�������̕�炵�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B�V�^�R���i�E�C���X��ŁA���{�́A�����s�ɑ��A7��12������8��22���܂ŁA4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o���ƂƂ��ɁA���ꌧ�ɏo����Ă���錾��8��22���܂ʼn������邱�Ƃ����肵�܂����B�܂��A�܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āA��ʁA��t�A�_�ސ�Ƒ���4�{���ł́A8��22���܂ʼn����������A�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���́A11���̊����������ĉ������邱�Ƃ����߂܂����B���{�́A���H�X�ł̊�������������邽�߁A���̒�~��v������ƂƂ��ɉc�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���ɉ��������Ǝ҂ւ̋��͋����n���ł���d�g�݂����A�x����v��������ȂǁA�����������߂����Ƃ��Ă��܂��B
�������s ��̈��H�X�ɋx�Ɨv��
�����s�́A8����A�V�^�R���i�E�C���X�̑��{����c���J���A7��12������8��22���܂ł�4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̂��ƂŎ��{����[�u�����肵�܂����B����ɂ��܂��ƁA����J���I�P�ݔ��������H�X�Ȃǂɑ��Ă͋x�Ƃ�v�����܂��B���Ȃ��ꍇ�͌ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ�v�����܂��B�s�́A6��21������A���p��1�O���[�v2�l�܂ŁA�؍ݎ��Ԃ�90���܂łȂǂ̐�����݂��Ď��̒�F�߂Ă��܂������A3�T�ԂŁA�Ăђ̒�~�����߂邱�ƂɂȂ�܂��B����A���ʐς̍��v��1000�������[�g�������K�͎{�݂ɑ��Ă͋x�Ɨv���͍s�킸�A�����������Z�c�Ƃ�v�����܂��B���Ԃ́A�f�p�[�g��Q�[���Z���^�[�ȂǁA�q�����R�ɏo����ł���{�݂͌ߌ�8���܂ŁA�����W����Ȃǂ̎{�݂��C�x���g���J�Â���ꍇ��A�f��ق͌ߌ�9���܂łł��B���̂ق��A�C�x���g�ɂ��ẮA�J�Î��Ԃ��ߌ�9���܂łƂ��������ŁA�l���̏����5000�l�ŁA�����50���ȓ��Ƃ���悤�v�����܂��B����ɁA�s���ɑ��ẮA�������܂߂��s�v�s�}�̊O�o�ƈړ������l���A���ɋA�Ȃ◷�s�Ȃǂ̓s���{�����܂����ړ��͋ɗ́A�T����悤���߂܂��B
���f�p�[�g�e��
�����s�ɋً}���Ԑ錾���o����邱�Ƃ����f�p�[�g�e�Ђ̑Ή��ł��B�O�z�ɐ��O�A�����A���}�S�ݓX�́A�s���̓X�܂ɂ��Ă͌��݁A�ߌ�8���܂łƂ��Ă���c�Ǝ��Ԃɂ��Ă͕ύX�����A�錾���o�����T����12���E���j�����烌�X�g�����Ȃǂł̎��̒͒��~����Ƃ������Ƃł��B�������A�������E�����A�����S�ݓX�A�����S�ݓX�A���c�}�S�ݓX�͋�̓I�ȑΉ��͌������Ƃ��Ă��܂����A���̒̒��~���܂߂ē����s�̗v���ɉ����đΉ�������j���Ƃ��Ă��܂��B
���O�H�`�F�[��
�����s�ɋً}���Ԑ錾���o���ꂽ���Ƃ̊O�H�`�F�[���e�Ђ̑Ή����܂Ƃ߂܂����B�Ή��́A��������s���̓X�܂ɂ��Ăł��B
���t�@�~���X
�܂��A�t�@�~���[���X�g�����ł��B�ő��́u��������[���z�[���f�B���O�X�v�́A�W�J���Ă���u�K�X�g�v��u�o�[�~�����v�̉c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łƂ��A�A���R�[���̒͏I���A�x�~���܂��B�u�f�j�[�Y�v�����l�ŁA�ߌ�8���ɕX���A�A���R�[���̒��I���A�Ƃ��߂܂��B�u�T�C�[�����v�̂ق��A�u���C�����z�X�g�v��u�Ă��v��W�J����u���C�����z�[���f�B���O�X�v�́A���{�Ⓦ���s�̗v���ɉ����đΉ���������Ō������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�������`�F�[��
�����āA�����`�F�[���ł��B�u�����Ɓv�A�u�g��Ɓv�A����Ɂu�����v�́A�X���ł̈��H�͌ߑO5������ߌ�8���܂ŁA����ȊO�̎��ԑт͎����A��ł̉c�Ƃ��s���Ƃ��Ă��܂��B�A���R�[���̒͂�������I���A�x�~���܂��B
����苏�����`�F�[���e��
�����s�ɋً}���Ԑ錾���o����邱�Ƃ�����苏�����`�F�[���e�Ђ̑Ή��ł��B�O�H�`�F�[���̃R�����C�h�́A���Ⓦ���s�̗v���ɏ]���Ƃ��Ă��āA�s���̏Ă����X��X�g�����ł͉c�Ǝ��Ԃ�Z�k����Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�u�Ñ��Y�v�ȂǓs���ɂ��鋏�����̓X�܂́A�x�Ƃ����������Ƃ��Ă��āA�ڍׂɂ��Ē�����i�߂Ă��܂��B���^�~���v���ɏ]���A�s���ɂ���u�~���C�U�J�v��u�O��ڒ������v�ȂǁA70�X�܂̋��������x�Ƃ��܂��B���̂ق��A�u����v�Ȃǂ�W�J����可�O���[�v��A�u���J�c�c���v�͑Ή������������Ƃ��Ă��܂��B�@
���u�����͏Ă��쌴���v�E�[�o�[�z�B�����ً}���Ԑ錾���Ɍ������́@7/9
�V�^�R���i�E�C���X�ЂŎ����̓[���A��������300�~���܂�B�ǂ��l�߂�ꂽ28�̒j�����I�̂́A�����ւ́u�o�҂��v�������B���߂ċً}���Ԑ錾���o���ꂽ1�J���ԁA������z�T�[�r�X�u�E�[�o�[�C�[�c�v�̔z�B���Ƃ��Ď��]�Ԃ������������j���́u2020�N�̓����͏Ă��쌴���v�Ɗ������Ƃ����B�������鎩�]�Ԃ��猩�����i�F�͂ǂ�Ȃ��̂������̂��낤���B
�j���́A����B��w�ʼnf����w���ƁA�n���̎R�����ʼnf������̎d����^�]��s�̃A���o�C�g�����Ȃ���f������@������������Ă����B�������A�V�^�R���i�̊����g��Ŏd�����Ȃ��Ȃ�A�������[���ɁB�n���ɂ͂ق��Ɏd�����Ȃ��A�o�҂������ӂ����B�u����肨�����Ȃ��A�҂��Ȃ��Ƃ����܂���ł����B�������l�����Ȃ��Ȃ��������ɂ�����������܂����B���R�ɓ����鎩�]�Ԕz�B���̎��_����L�^����A���������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���A�B�e���n�߂܂����v
�ً}���Ԑ錾����20�N4�`5���̓����B�X�}�[�g�t�H���⏬�^�J�������g���Ď��g��g�߂ȕ��i�̎B�e�𑱂����B������܂Ƃ߂��h�L�������^���[�f��u�������]�Ԑ߁v���A���N7��10���Ɍ��J�����B���������ӂ��z�B���̎��_�ƁA������̓Ɣ��𒆐S�ɕ`����Ă���B
�E�[�o�[�C�[�c�́A�z�B�����l���Ǝ�Ƃ��Č_�闿���z�B�T�[�r�X�B�z�B���͊�ƃ��S�̓������o�b�O���w�����A����Ɏ��]�ԂȂǂ̑����i�͑S�Ď��O�ŗp�ӂ���K�v������B���{�ł�16�N9���ɃT�[�r�X���J�n�������A�V�^�R���i�ɂ��O�o���l�̉e���Ŏ��v���}�g�債�A�z�B�����n�߂�l���������B�z�B���͋C�y�ɂȂ�čD���Ȏ��Ԃɓ��������ŁA�l���Ǝ�̂��ߏA�ƒ��Ɏ��̂ɑ����Ă��J�Еی����K�p����Ȃ����Ƃ�A������p�̕��S���d�����Ƃ����_�Ƃ��Ďw�E����Ă���B
������͂����U��Ԃ�B�u���͍ŏ��́A�z�B���ɓ������������ł��B�l�̗��ꂪ�r�₦�������Ől�Ɛl���Ȃ��悤�ȁA�s�s�Ɍ���ʂ킷�C���[�W���������B�ł��A���ۂ́w�u���z�x�Ƃ����z�B���鏤�i�����֑O�ɒu���P�[�X���قƂ�ǂŁA���q����Ɗ�����킷���Ƃ�����܂���ł����B�N�̖��ɗ������̂�����킩��Ȃ��B�����̓V�X�e���̈ꕔ�ɂȂ��Ă��邾���ȂƋC�t���܂����v
������̈�a���͎���ɃE�[�o�[�́u�V�X�e���v�Ɍ������Ă����B�@�E�E�E
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�A�s���Q���@���ߌ����A���̓y�j�@7/10
�����s��Ώۂ�4�x�ڂƂȂ�V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾���ߌ����A���߂Ă̓y�j�����}����10���A�s���̊ό��n��ɉ؊X�ł́A�I���̌����Ȃ����l�����Ɂu�X�g���X�����܂�v�ƒQ������A�錾�̌��ʂɉ��^�I�Ȑ��������ꂽ�B�錾���ŊJ����铌���ܗւɂ͕��G�ȐS�����̂��������B
��N�Ȃ�A������ό��q�łɂ��키�����E�B�y�Y���X�u�I�J�_���v�̓X���e�n�m�q����(76)�́u�錾�͎d���Ȃ����A�ό��q������Ǝv���̂ŒɎ�B��A�q�ʼn��Ƃ������������Ă��邪�A�܂��܂�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƙb�����B
�錾�̊�����23���ɊJ����}���铌���ܗ֊��Ԃ��܂߂�����22���܂ŁB
��4�x�ڋً}���Ԑ錾�Ɂu����Ă���l�Ƃ₯�����̐l���c�v�@7/10
�^�����g�̃r�[�g������(74)��10���ATBS�u�V�E���7days�j���[�X�L���X�^�[�v(�y�j��10�E00)�ɐ��o���B���{�������s��4�x�ڂ̔��߂����肵���V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾�ɂ��Č��y�����B
���{��12������8��22���܂łً̋}���Ԑ錾�Ĕ��߂�����BTBS������ԍ�܂ňړ����Ă����������́u�₯�����ɂȂ��Ă����B�ԍ�̊X��ʂ��Ă�����}�X�N���Ȃ��ŃK�u�K�u����ł���l�����āB�����_�����Ȃ��B�����Ƃ��Ă���l�ƁA�₯�����ɂȂ��Ă���l���X���c�v�ƃR�����g�B
�������́u���T����(����㉺�ɍL����)����ȂɂȂ����Ⴄ��Ȃ��H����܂Œʂ�A�����Ǝ���Ă���l�ƁA����Ȃ��Ƃǂ��ł��������Č����l�ƁB�l�ɂ���čl�������S�R����Ă�������ĕ|����v�ƃR���i�Ђł̊�����Ɋւ���l�X�̈ӎ��̍���Q���Ă����B
���ً}���Ԑ錾���O�̏T�� �����E�a�J�͑����̎�҂┃�����q�@7/10
12���A�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����钼�O�̏T�����}���܂������A�����E�a�J�ł͎�҂┃�����q�̎p�������݂��܂����B
�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����钼�O�̏T���ƂȂ���10���A�i�q�a�J�w�O�ł́A�ߑO�����瑽���̎�҂┃�����q�����Ǝ{�݂���H�X�ȂǂɌ������p�������܂����B
�s���ɏZ��20�̑�w3�N���̏����́u�{�錧�ōs����I�����s�b�N�̏��q�T�b�J�[�̎����̃`�P�b�g��������܂������A�ً}���Ԑ錾���o��̂Ŋϐ�ɂ͍s�����ɕ����߂����邱�Ƃɂ��܂����B�c�O�ł����A��K�͂ȃ��b�N�t�F�X�e�B�o�������~�ƂȂ��Ă���̂ŁA�������Ȃ��Ǝv���܂��B���ꂩ��A�E�����ł����A������ً}���Ԑ錾���J��Ԃ����Ɖe�����o�Ȃ����S�z�ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A35�̉�Ј��̒j���́u�ً}���Ԑ錾�͂���4��ڂȂ̂ŁA�����͕ς��Ȃ��Ǝv���܂��B�ċx�݂͓��ɗ\��͓���Ă��Ȃ��̂ŁA����܂łǂ��芴��������Ȃ���߂����܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
���Z1�N���̒j�q���k�́u�����̎��������~�ɂȂ��Ă��܂��c�O�ł��B�ċx�ً݂͋}���Ԑ錾���ɂȂ�܂����A�V�т����Ƃ����̂������ȋC�����ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
��4�x�ڂً̋}���ԂŊɁH�s���̐l�o�A�ꕔ�ő����@7/10
9����̓s���̔ɉ؊X�̐l�o�́A4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�̔��o�����܂����ɂ�������炸�A1�T�ԑO�Ɣ�ׂđ傫���͌������Ă��Ȃ����Ƃ�������܂����B
�g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^�ɂ��܂��ƁA�ߌ�8����̊e�n�̐l�o��1�T�ԑO�ɔ�ׂďa�J�Z���^�[�X��2.3���A�V�h�E�̕��꒬��13.5���A�ԍ��10.3��������������A�V����8.5���A�Z�{��8.7���A�����3.2���������܂����B
12������ً̋}���Ԑ錾�ɔ����āA�����s�͈��H�X�ɑ��Ď�ނ̒����Ȃ��悤�ɋ��߂邱�ƂɂȂ�܂����A�O��̐錾���ԂŖ�̐l�o���������Ă��Ȃ����Ƃ���A�K���̎�����������Ă��܂��B
�������̐l�o �����̒n�_�őO�T��葝�� �u�܂h�~�v�n��ł� �@7/10
4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����邱�Ƃ����܂���������A�܂h�~���d�_�[�u�����������n��ł́A9���̐l�o�������̒n�_��1�T�ԑO��葝�����܂����B
NHK�́AIT�֘A��Ƃ́uAgoop�v�����p�҂̋��Čl�����肳��Ȃ��`�ŏW�߂��g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^���g���āA�����≫��Ȃǂ̎�Ȓn�_�̐l�̐��͂��܂����B
���͂������Ԃ́A�������ߑO6������ߌ�6���܂ŁA��Ԃ��ߌ�6�����痂���̌ߑO0���܂łł��B
����ɂ��܂��ƁA9���A�����̐l�o��1�T�ԑO�Ɣ�ׂđ����̒n�_�ő������Ă��܂��B
�e�n�_�̑������́A�a�J�X�N�����u�������_�t�߂œ�����37���E��Ԃ�13���A�����w�t�߂œ�����3���E��Ԃ�2���ł����B
����A�ً}���Ԑ錾�̉��������܂�������ł́A�ߔe�s�̌����O�w�t�߂œ�����9���A��Ԃ�34���������܂����B
�܂h�~���d�_�[�u������������ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ł́A�������s�̑�{�w�t�߂œ�����10���E��Ԃ�7���A���l�w�t�߂œ�����5���E��Ԃ�21���A���~�c�w�t�߂œ�����3���E��Ԃ�7���A���ꂼ�ꑝ�����܂����B
����A��t�w�t�߂ł͓�����13���A��Ԃ�2���������܂����B�@
���k�C������]�A�ܗ֖��ϋq�ŊJ�Á@�Ĕ��߂̓����Ƃ̉������O�@7/10
�����ܗցE�p�������s�b�N�g�D�ψ����9����A�D�y�h�[���ōs����ܗւ̃T�b�J�[�j��1�����[�O��S�Ė��ϋq�ŊJ�Â���Ɣ��\�����B
�����ߌ�ɁA�����Ɏn�܂�Z�b�V����(���ԑ�)�͎��e�l����50���ȓ��ōő�1���l�̊ϋq�����Ď��{����Ɣ��\�������A�}���匈������B����ɂ��A�V�^�R���i�E�C���X�Ђ̓����ܗւ͑S42���̖�8�����W�܂��s��1�s3���̂ق��A�k�C�������ϋq�J�ÂƂȂ����B
�k�C���̗�ؒ����m���́A�ً}���Ԑ錾�Ĕ��߂����܂��������s�ȂǁA��s���Ƃ̉�����h���̂�����ł���̂����R�Ƃ����B�����A��ʁA��t�A�_�ސ�̊ϋq���k�C����K��Ȃ��悤�g�D�ςɑ�����߂����A�������̒S�ۂ��������Ɣ��f�B�u�����̈��S���S���ŗD�悵�����f�Ɨ������Ăق����v�ƌ�����B
�D�y�s�ł̃}���\���A�����͉����ł̊ϐ펩�l��v������B
�g�D�ς�10���A�ܗւ̊ϋq��������ɔ����`�P�b�g�̍Ē��I���ʂ����\�����B�Ē��I�̑Ώۂ́A�k�C���̃T�b�J�[���O��A�{�錧�̃T�b�J�[�ƕ������ł̃\�t�g�{�[���Ɩ싅�̂����A�`�P�b�g�w���҂��ϋq������Ă���v4�Z�b�V����(���ԑ�)�����ƂȂ����B
�����T�C�g�̃}�C�`�P�b�g�Łu�L���v�ƕ\�������A���̂܂܊ϐ�ł���B���I�ɘR�ꂽ�ꍇ�́u�����v�Ǝ������B�L���̃`�P�b�g�ł�20���ߑO�܂ł͕����߂����t����B���ϋq�ƂȂ������⒊�I�ɊO�ꂽ�ꍇ�͎����I�ɕ����߂��ƂȂ�B
���ً}���Ԑ錾�ɖ��ϋq�ܗցA���Z�́u���V�i���I�v�@7/10
7��4���ɓ��[���s��ꂽ�s�c��I���́A�����̐��Ƃ̗\���Ƃ͈قȂ�A�����}�ƌ����}�͍��v���Ă��ߔ����ɂ͓͂��Ȃ������B�t�ɓs���t�@�[�X�g������Ԃ��A�c�Ȃ͌��炵�����̂́A�����}�Ɲh�R�����2�}�̒n�ʂ��m�ۂ����B�l���c�Ȑ��́A�s��31(−14)�A����33(�{8)�A����23(�}0)�A���Y19(�{1)�A����15(�{7)�A�ېV1(�}0)�A�����҃l�b�g���[�N1(�}0)�A������4(−1)�ł���B
���c�ȑ��ł��u�s�k���v�̎����A�c�Ȍ��ł��u�����v�Ƃ����s���t�@
�����}�̐L�єY�݂́A�R���i�s�Ɠ����ܗ֊J�Ë��s�̐ӔC�𐛐������w�������ƂɂȂ������Ƃɂ���B�Ƃ��ɑI�����Ԓ��ɁA�����̂�E��ɓ͂���ׂ����N�`�����s�����A�ڎ�\�����������������Ȃ��Ȃ�悤�Ȏ��Ԃ����������Ƃ��傫�ȑŌ��ɂȂ����B�R���i�����̎S��͓����̘b�Ȃ̂����A���r�s�m���͎���̓��@�Řb������点�A���̐ӔC����肭���ꂽ���A�܂��A�����ܗւɂ��ẮA��Î҂ɂ�������炸�ڗ����Ȃ��悤�ɂ��āA�ᔻ�̖���ŗ��Ȃ��悤�ɒm�b�����Ă���B���[����42.39���ƁA�ߋ�2�Ԗڂ̒Ⴓ�ł��������A����ɏ�����ꂽ�̂������}�ŁA��������̌�₪�M���M���Ŋ��荞�݁A�R����\�������悤�Ɂu��ՓI�Ɂv�S�����I���ʂ������̂ł���B��������}�Ƌ��Y�}�͋c�Ȃ���ς݂������A����͗��}�Ԃ̑I�����͂�����t�������ʂł���B�������A������ׂ��O�c�@�I���ő���i�𐋂���قǂ̐L�т͌����Ă��Ȃ��B
���u���I���ŏ����v�ւ̐헪���h�炬�n�߂�������
�I���̋A�������߂��͖̂��}�h�w�ł���A�s���t�@�[�X�g�̉�ő�̎M�ɂȂ�A�����}�ɂ͂��܂藬��Ă��Ȃ��B����ł͕������𗧂Ă������}�����|��ɂȂ�͓̂��R�ł���B�����}�̎�̉���������������Ȃ��B�������ɂȂ��āA��v�I���ɂ����鎩���}�̐���͖F�����Ȃ��B1��24���̎R�`���m���I�A3��21���̐�t���m���I�A4��25���̍����I(�O�@�k�C��2��A�Q�@����A�Q�@�L��)�A6��20���̐É����m���I�Ǝ����}�͑S�s���Ă���B�R���i���������������A�����ܗւ𐬌������āA�l�S��ς��A�x�������グ�ďO�c�@�I������������Ƃ������̐헪�����{����h�炬�n�߂Ă���B
�����҂Ɨ����A�����銴����
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��ẮA�����s�ł́A���̊��҂Ƃ͋t�Ɋ������}�g�債�Ă���A7��7���̃R���i�����҂�920�l�Ɛ�T�̐��j�����206�l�������āA�l�X���V�������B900�l����̂�5��13���ȗ��ł���B�������A�����͑S���ɂ��g�y���Ă���A�S���ł�2191�l�ƁA6��10���ȗ���2000�l���Ƃ����������o�Ă��܂����B���{��151�l�A�k�C����67�l�A���ꌧ��58�l�Ɗe�n�ō��������ɂȂ��Ă���B7��8���������s�̊����҂�896�l�ƍ��������ɂ���A���������g�債�Ă���B�S���ł�2246�l�Ƒ����A�S���Ɋg�債�Ă��邱�Ƃ����O�����B����1�̌����́A�ψكE�C���X�̃f���^��(�C���h�^)�̎s���������L�܂��Ă��邱�Ƃɂ���ƍl������B���E�ł��A����f���^�����嗬�ɂȂ��Ă��邪�A�����͂̋������Ƃ����F�ł���A���̊������x�ƃ��N�`���ڎ�X�s�[�h�Ƃ̋������J��L�����Ă���B�c�O�Ȃ���A��q�����悤�ɁA���{�ł͋����s������ڎ�Ƀu���[�L���������Ă���A�[���Ȏ��ԂɊׂ�댯��������B�����҂�1000�l�����Ԃœ����ܗ֊J����}���鎖�ԂɂȂ肻���ł���A�����Ԓ���2000�l���Ɨ\��������Ƃ�����B�����s�Ȃǂ̂܂h�~���d�_�[�u�̊����ł���7��11����O�ɁA���{�͂��̌�̑Ή����������Ă������A�����̋����ׂ��}�g����āA7��8���A�����s��8��22���܂ŋً}���Ԑ錾�߂��邱�Ƃ����߂��B���ꌧ�ɂ��Ă��ً}���Ԑ錾���p�����邱�Ƃɂ����B�܂��A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{�͂܂h�~���d�_�[�u����������B�k�C���A���m���A���s���A���Ɍ��A�������́A�[�u��11���ʼn�������B
��900���~�����`�P�b�g�����͂قڃ[���ɁA�����͍����̐ŋ�����
���̂悤�ȋٔ������̒��A8���ߌ�AIOC�̃o�b�n������������B�ň��̃^�C�~���O�ł���B�����ւ�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���߂����܂�A���Ƃ͑�5�g�̓������뜜���Ă���B�������A�K���ɋ����Ă���L���͑�J�ɒ�������A�R�z�V�������^�x�����ȂǑ傫�Ȕ�Q���o�Ă���B�M�C�̓y�Η��ЊQ����ł̋~�o�������������Ă���A�����̐l�����ɂƂ��āA�ܗւǂ���ł͂Ȃ��ł���B�o�b�n��ɂ́A���{�̌���𐳂����F�����Ă��炢�����Ǝv���B������A��ɂ̓o�b�n��̓I�����C����5�ҋ��c�ɗՂ��A���c�̌��ʁA��s���̑S���Ŗ��ϋq�Ƃ��邱�Ƃ����܂����B�����܂ł��̂Ȃ�A�É����A�������A�{�錧���A�܂�S���Ŗ��ϋq�ɂ��ׂ��ł���B��s���̃R���i�z���҂��s�O�̋��Z���ɍs�����Ƃɂ���Ċ������L����\�������܂邩��ł���B���O�ł̈ړ��̂Ƃ��������ł���B���Ǐ�̗z���҂�����Ƃ����E�C���X�������l�����ׂ��ł��낤�B�`�P�b�g������900���~��������ł������A����͂قڃ[���ƂȂ��Ă��܂��B�J�Ós�s�Ƃ̌_��ł́AIOC�͐ӔC������A�����������肵�Ȃ��Ƃ����u�s�������v�ƂȂ��Ă���̂ŁA���̑����͓��{�����̐ŋ��ŃJ�o�[���邱�ƂɂȂ�B�܂��ɓ���R������ł���B
���₩���̂Ȃ��ܗւ�
�C�O���猩��ƁA�ً}���Ԑ錾���ł̌ܗ֊J�ẤA��O���킵�����̂ł���B���E�ł́A���̎�̐錾����������ƁA�s�s����(���b�N�_�E��)���s����Ƃ������Ƃł���A�x�@�����X�p�ɗ����ċ������O�o����҂������܂邱�ƂɂȂ�B�����K���i�������X�ȊO�͉c�ƒ�~�ƂȂ�A�����̐l���W�܂��^�C�x���g�͒��~�ɂȂ�B����ً̋}���Ԑ錾���߂́A�s�c�I�ł̎�����́u�s�k�v�̌��ʂɐ_�o���ɂȂ��������}�������A�����}�g��Ƃ������Ԃɉߏ�ɔ����������̂ł���B�����g����~�߂邱�Ƃ��ł����ɁA�ň��̏ꍇ�A�ܗ֒��~�ɒǂ����܂��Ƃ������Ԃ�����Ȃ���A��q�������헪�����A�ɋA���Ă��܂�����ł���B���{�̃R���i��̎��s������������邱�ƂɂȂ�A���ӂ͗������A�x�����͉������Ă��܂��B�u���`�̂ł͑I���͐킦�Ȃ��v�Ƃ������[�h�������}���ɍL�܂�ƁA�����ސw������ɓ����Ă���B�����ŁA�ɂ߂Ĉُ�ȏł́A�ُ�ȌܗւƂȂ�A�����ɂ͉₩���̌��Ђ��Ȃ����ƂɂȂ�B���E�ł̓f���^�^�̕ψي��̊����g��Ɋ�@�������܂��Ă���BWHO�ɂ��ƁA6�����_�ŁA104�̍���n��Ɋ������g�債�Ă���B���Ƃ��C���h�l�V�A�ł̓f���^���̉e����������7���̃R���i�����҂�3��4379�l�ɂ̂ڂ�A���҂�1000�l���A���n�ݏZ�̓��{�l������܂ł�12�l�����S���Ă���B
�t�����X�ł́A3�̒n��ŁA�f���^���̔䗦��50�����A��@�����点�Ă���t�����X���{�́A�K�������ɏ��o�����j�ł���B�t�����X�l���y���݂ɂ��Ă���Ẵo�J���X�����䖳���ɂȂ�ƌ����Ă���B�}�N�����哝�̂́A�����J�Òn���p���Ȃ̂ŗ�������\��ł��邪�A�x�������ቺ���A��̒n���I���ł���s����ȂNjꂵ�������^�c�������Ă���B�ܗւ̂��߂ɗ������邱�Ƃ́A�哝�̂ɂƂ��Ă͉��̗��_���Ȃ��悤�ł���B���{�ł��f���^�����}���ɍL�����Ă���A�S����304�l�̊������m�F����Ă���B�ő��������s��61�l�A�����Ő�t����48�l�A�_�ސ쌧��41�l�A���{��31�l�A���m����27�l�ȂǂƂȂ��Ă���B���̕ψكE�C���X�̊����g��𒍈ӂ��Č���K�v������B�t�@�C�U�[��f���i�Ȃǂ̃��N�`���́A�ψي��ɑ��Ă��L���ł���A�ڎ�̉����������߂���B�Ƃ���ŁA8��22���܂ŋً}���Ԑ錾�ƂȂ�ƁA�����̈��H�ƊE�Ȃǂ͉�œI�Ȕ�Q���邱�ƂɂȂ�B��ނ̒��ł��Ȃ��Ȃ�A�X��߂�������Ȃ��Ƃ����o�c�҂̐����������ł���B�x�Ƌ��͋����s�\���ł���A���������̎x�������x��Ă���ƂȂ�A�w�ɕ��͑ウ���Ȃ��Ƃ��ċK���j��̓X�����������ł���B
�����ܗւɂ́A3���~���̌o��������Ă���B������l����A���̗ܒ��x�̕⏞�ł悢�͂��͂Ȃ��B33���~�Ƃ����ܗւ̌o�ό��ʁA�C���o�E���h�̍��܂肪�����Ɍ��`����Ă������߁A�ϋɓI�ɐݔ��������s������Ƃ������B�������A�p���f�~�b�N�ł��ׂĂ����ڂɏo�Ă��܂����B����͒N�̐ӔC�ł��Ȃ��A�䕗��n�k�Ȃǂ̎��R�ЊQ�Ɠ����ŁA���{���~���̎�������L�ׂ邵���Ȃ��B�������A�c�O�Ȃ���A���{���\�S�ɋ@�\���Ă���Ƃ͎v���Ȃ��̂��A���{�̌���ł���B���[���b�p�͍��A�T�b�J�[���B�I�茠�Ő���オ���Ă���B11���Ɍ����킪�s���邪�A�J�Òn�̃C�M���X�ł͊ϋq���Ȃǂ̐�����啝�ɉ������Ă���B�W�����\����19���ɃR���i�K����S�ʉ�������B�f���^���̊����g��͂�����̂́A���N�`���ڎ킪�����ɐi��ł��邱�Ƃ�O���ɁA�u���܂ł��K���͑������Ȃ��B�V�^�R���i�E�C���X�Ƃ̋�����}��v�Ɩ������Ă���B�������A���̃T�b�J�[�I�茠�Ŋ����g�傪�N����悤�Ȃ��Ƃ�����A��K�̓X�|�[�c�C�x���g�J�Âɑ��ċt�����������ƂɂȂ�B�����āA�����ł̊���������Ɋg�傷��A���~�Ƃ����I���������サ�Ă��邩������Ȃ��B������ɂ��Ă��A���j�Ɏc��ُ�ȑ��ƂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
���X�Ǝ҂������̊�@�� ���� 4��ڂً̋}���Ԑ錾�� �@7/10
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��œ����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����邱�Ƃ��āA���H�X�ȂǂɕX��̔����鎖�Ǝ҂͌������ɒǂ����܂�Ă��܂��B
�����E������ɂ���n��73�N�̕X�̉������Ђ́A���X���[�J�[����d���ꂽ�X���p�̋@�B���g���Đ蕪���A���H�X��z�e���A�C�x���g�Ǝ҂Ȃǂ��悻700�X�܂ɔ̔����Ă��܂��B
���H�X�Ȃǂɑ��鎞�Z�c�Ƃ�x�Ɨv���̉e���ŋ��N�t���甄��グ�͔������������A���������1���قǂ��p�Ƃ����Ƃ������Ƃł��B
���悻20�l����]�ƈ��̈ꕔ���x�܂�����A���̏����������p�����肵�Čٗp���ێ����Ă��܂������A12�����瓌���s�ɍĂыً}���Ԑ錾���o����邱�ƂŁA�o�c�͂���Ɍ������Ȃ�Ƃ݂Ă��܂��B
�X�̎��v���}������ď�͔N�Ԕ���グ�̔����߂����߂�g�������ꎞ�h�ł����A�ً}���Ԑ錾�̂��Ǝ��������H�X�ȂǂɍĂыx�Ɨv�����o����邤���A��^�C�x���g�̒��~���������A��s�������ʂ��Ȃ��Ƃ����܂��B
�u�����Ⓚ�Y�Ɓv�̈ɓ��O���В�(46)�́u�����܂���ً}���Ԑ錾�͒v�����Ȃ����������邪�A�o�c�I�ɂ͑傫�ȒɎ�ŐS���܂��B���̉Ă����z�����邩�A��Ђ̑�������Ԃ܂����v�Ƙb���Ă��܂����B
���ً}���Ԑ錾�ւ̑Ή��܂Ƃ� ������ �O�H�`�F�[�� �f�p�[�g �@7/10
�����s�ɋً}���Ԑ錾���o����邱�Ƃ����A��苏�����`�F�[���e�ЁA�O�H�`�F�[���e�ЁA�f�p�[�g�e�Ђ̑Ή����܂Ƃ߂܂����B
�O�H�`�F�[���̃R�����C�h�́A���Ⓦ���s�̗v���ɏ]���Ƃ��Ă��āA�s���̏Ă����X��X�g�����ł͉c�Ǝ��Ԃ�Z�k����Ƃ��Ă��܂��B�u�Ñ��Y�v�ȂǓs���ɂ��鋏�����̓X�܂́A�x�Ƃ����������Ƃ��Ă��āA�ڍׂɂ��Ē�����i�߂Ă��܂��B���^�~�͗v���ɏ]���A�s���ɂ���u�~���C�U�J�v��u�O��ڒ������v�Ȃ�70�X�܂̋��������x�Ƃ���ق��A�u���؉��v�ȂǓW�J���郂���e���[�U���A�s���ɂ���200�X�ܗ]����x�Ƃ��܂��B�u����v�Ȃǂ�W�J����可�O���[�v��u���J�c�c���v�͑Ή������������Ƃ��Ă��܂��B
�ő��́u��������[���z�[���f�B���O�X�v���W�J���Ă���u�K�X�g�v��u�o�[�~�����v�̉c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łƂ��A�A���R�[���̒͏I���x�~���܂��B�u�f�j�[�Y�v�����l�ŁA�ߌ�8���ɕX���A�A���R�[���̒��I���Ƃ��߂܂��B�u���C�����z�X�g�v��u�Ă��v��W�J����u���C�����z�[���f�B���O�X�v�����X�g�����͌ߌ�8���ɕX���A�A���R�[���̒͋x�~����Ƃ��Ă��܂��B�u�T�C�[�����v�́A���{�Ⓦ���s�̗v���ɉ������Ή����������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�u�����Ɓv�u�g��Ɓv�u�����v�́A�X���ł̈��H�͌ߑO5������ߌ�8���܂ŁA����ȊO�̎��ԑт͎����A��ł̉c�Ƃ��s���Ƃ��Ă��܂��B�A���R�[���̒͂�������I���x�~���܂��B
�O�z�ɐ��O�A�����A���}�S�ݓX�A�����S�ݓX�́A�s���̓X�܂ɂ��Ă͌��ߌ�8���܂łƂ��Ă���c�Ǝ��Ԃɂ��Ă͕ύX�����A�錾���o����鍡��12�����j�����烌�X�g�����Ȃǂł̎��̒͒��~����Ƃ������Ƃł��B�������A�������E�����A�����S�ݓX�A���c�}�S�ݓX�͋�̓I�ȑΉ��͌������Ƃ��Ă��܂����A���̒̒��~���܂߂ē����s�̗v���ɉ����đΉ�������j���Ƃ��Ă��܂��B
���u�I�����s�b�N�ނ�I�v�ƒ��莆�̗��쑊�ݕa�@���@7/10
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�����A�u�I�����s�b�N�ނ�I�v�Ƒ��K���X�ɒ��莆���f�����Ă��闧�쑊�ݕa�@(�����s����s)�̍�����Ɖ@��(58)��9���A�{���̎�ނɁu���ϋq�Ń��X�N�������͌���Ǝv�����A�R���i�Ђɖҏ����d�Ȃ鎞���B�J�Ô��̈ӎv�͕ς��Ȃ��v�ƌ�����B
�u��Â͌��E�@�ܗւ�߂āI�@�����J���x���@�I�����s�b�N�ނ�I�v�Ƃ̎��肾�����̂�4��30���B�@�������Ă��A�@����c�ŗ������ꂽ�B�u�����͌ܗ։��������߂���N3����舫���̂ɁA�ĉ����⒆�~�ɂȂ�Ȃ��܂܊J�Â��߂Â��A���������ƍl�����v�Ƙb���B
���莆�͉�����𗬃T�C�g(�r�m�r)�Ŕᔻ�����������A�n������͍D�ӓI�Ɏ��ꂽ�Ƃ����B�ܗ֊J���ւ̓������i�ޏɁu�l�̗����}����ً}���Ԑ錾�ƁA(�I�����W�҂�)�C�O���琔���l������ܗւ͍��{�I�ɖ�������v�Ɣᔻ����B
�a�@�ł͍�N4���̃R���i���Ҏ����A���r�̗p�ł����Ō�t�͗�N��3����1��5�l�B�V�^�R���i�̓��@���҂�6������2�l�܂Ō��������A�Ăё�����12�l�ƁA�����_�ʼnғ��ł���16���ɔ���B�u�J�Â��ꂽ��A�ЊQ���N�����Ǝv���đΉ�����B�ܗ֊W�҂���������Ă��A��ʂƓ����悤�Ɏ����v�ƌ��ӂ���B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
����s���E���E����Ŏ��~�@���������ۑ�@����12������ً}���Ԑ錾�@7/11
���{��12���A�V�^�R���i�E�C���X�́u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����Ă��铌���s��4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�߂���B
�錾���������鉫�ꌧ�ƂƂ��ɁA���H�X�Ɏ�̈ꗥ��~�����߂�B�d�_�[�u���p�������ʁA��t�A�_�ސ�A���4�{�������H�X�̎��������~�Ƃ���B
�����A����̐錾�A4�{���̏d�_�[�u�̊����͂������8��22���B�����ܗ�(7��23���`8��8��)�₨�~�x�݂̊��Ԃ��܂܂�A�l�̈ړ��ɂ�銴���Ċg�傪���O����邱�Ƃ���A���Ǝ҂⍑���ɑ�̓O������߂ČĂъ|����B
���{���d������̂����H�X�Ȃǂł̊����B���݂̏d�_�[�u���̎�s��4�s���Ȃǂł͏����t���Ōߌ�7���܂ł̎�ޒ��F�߂��Ă������A�����s�͎�ނ�J���I�P�������H�X�ɋx�Ɨv������B
�d�_�[�u���̎�͏T�����ȍ~�A������~�ƂȂ�A�m���̔��f�Ŋɘa�ł���悤�ɂ����B�����o���Ȃ��ꍇ�ł��A�ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k�������������߂�B
���̒�~�v�����߂����ẮA�]��Ȃ����H�X�����Ȃ��Ȃ��B�����ɋ��͂邩���ۑ�ƂȂ�B
���{�͈��H�X�Ɏx�����鋦�͋��ɂ��āA����o�������ɐ敥���ł���悤�ɂ���B���͋���\�����Ă��x���܂Ŏ��Ԃ�������A�v�������ޓX�܂����������߂��B�܂��A���̔̔��Ǝ҂ɂ́A�v���ɉ����Ȃ��X�Ƃ̎�����s��Ȃ��悤���߂�B�s�{���̖��߂ɏ]��Ȃ����Ǝ҂ɂ͉ߗ����Ȃ��B
�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���ɓK�p���̏d�_�[�u�ɂ��ẮA7��11���̊����ʼn�������B�@
�����r�m���́u50����v��@�����Łu�Ō�ً̋}���Ԑ錾�v��? �@7/11
4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�̔��߂����܂��������s�B�V�^�R���i�E�C���X�̊������Ċg�傷�钆�A���r�S���q�m�������1�Ƃ��đł��o�����̂��u50����v�B�����Ґ����S���ōő��̓����ł́A���@���҂��d�NJ��҂�����ʂ�50�オ�ł������Ȃ��Ă��邽�߂��B�����ܗւ̊J����23���ɔ��钆�A�u���Ƃ��Ă��Ō�ً̋}���Ԑ錾�Ɂv�Ƙb�������r�m���B50����̑�Ŋ����җ}�~���ł���̂��B
��50��@���@�A�d�NJ��҂��ő�
�u����҂̃��N�`���ڎ�̌��ʂ�����悤�Ɏv�����A�z���Ґ������@���Ґ�������ґw����50��Ɉڂ��Ă��Ă���B�t�F�[�Y���ς����50�オ�ł������ɂ���킯�ŁA�܂��Ɂw50����x�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��v
�����ɋً}���Ԑ錾�����߂���邱�Ƃ����܂���8����A���r�m���͗Վ���ŁA�u�s���̖��E���N�����3�̒��v�Ƃ��āA1���H�X��̋���250����ւ̏d�_�I�ȑΉ�3���N�`���ڎ�̐��i�[��ł��o�����B
���̑��1�Ƃ��āA50������グ���̂́A50��̓��@���Ґ��A�d�NJ��Ґ��������Ă��邽�߂��B
�N��ʂ̓��@���Ґ�1673�l(7�����_)�̂����A50���355�l�őS�̂�21���B60��(188�l)�A70��(155�l)��傫���������B�N��ʂ̏d�NJ��Ґ�62�l(7�����_)�ł��A60�オ12�l�A70�オ17�l�������̂ɑ��A50�オ�S�̂�37�����߂čő��������B
����b��������
���r���́u50��̏d�ǎ҂́A�j���̕��������B�S�����A���A�a�A�̋@�\��Q�Ȃǂ̊�b�������������̕��A�������A���R���X�e���[���A���^�{�̕��������B����ɋi�����̂�������d�lj��̃��X�N�������ƁA���̂悤�Ȏw�E������B���ɒ��ӂ��K�v�ɂȂ�v�Ǝw�E�����B
����Ɋ����o�H�ɂ��āu�E��܂����H�X�Ŋ�������(�ƒ��)��������ł���Ƃ����\���������v�B50��͊�b���������l�������A��������ʼn�H�Ȃǂ�����@����������Ƃ�����@�A�d�ǎ҂������Ă���Ƃ̔F�����������B���̏�ŁA�e�����[�N�̓O���A���k�A�ł����킹�Ȃǂł̃I�����C���̐��i�A���H�₨��������ۂ́A���l���A�����A�Z���Ԃ̓O����Ăъ|�����B
��9���̒���ł��A���r����50����̑�̏d�v�����J��Ԃ��u����҂̃��N�`���ڎ�́A7�����ɂ͊�]����S�Ă̕��X�̐ڎ�͊�������Ƃ����\�肾�B50�Α�ɑ��Ẵ��N�`���̐ڎ���W���I�ɐi�߂Ă����v�Ƃ��A���ɕK�v�ȃ��N�`���̋����m�ۂ����߂��B
����Ɂu���N�`�����F����ɍs���n��܂ł̊ԂƂ����̂́A����܂Œʂ�̊�{�I�Ȋ����h�~��̓O��A���ꂩ��l���̗}���Ƃ������Ƃ��厖�ɂȂ��Ă����B����Ń��N�`���̐ڎ�̃X�s�[�h��(������)�グ�Ă������ƁA���̗����ł��������Ȃ��v�Ƃ��A�u���Ƃ��Ăł��Ō�ً̋}���Ԑ錾�ɂ��Ă����B���̂��߂ɂ��A�F�����l�ЂƂ�̍s���A���ꂪ���ɂȂ��Ă����Ė���������Ă����v�ƌĂъ|�����B
���u���S�A���S�Ȍܗi�߂�v
23������͓����s�A�_�ސ�A��t�A��ʂ�1�s3���ϋq�ɂ��Ă̈ٗ�̌`�œ����ܗւ��n�܂�B���ϋq�Ƃ͂����A�ܗւ̊J�Â͊����҂̑����ɂȂ���Ȃ��̂��B
9���̋L�҉�ł́A�L�҂���u�������Ò̐�������Ɉ��������Ƃ��Ă��A����̑��~�̔��f�Ƃ������Ƃ́A���蓾�Ȃ��̂��v�Ǝ��₪�o���B
���r���́u�R���i�ЂŐ��E�������ނ��Ă����A���̒��ŃX�|�[�c�̗͂������āA���E��40���l�̕��������ɂȂ�v�Ƃ�����ŁA�u���������Ӗ��ň��S�E���S�ȑ���i�߂Ă������Ƃɂ��ẮA�h�n�b���A�܂����̌�̃p�������s�b�N�̂h�o�b���A���A�g�D�ψ���A�����ē��R���ǂ��������v���ł������܂��v�Ɠ����ܗւ̈Ӌ`�����������B
�����������A�����ً̋}���Ԑ錾�Ɂu���@�ᔽ���Ǝv���܂��v�c�@7/11
���O�@�c���Ń^�����g�̐���������11���A�s�a�r�n�u�T���f�[�E�W���|���v(���j�E�ߑO9��54��)�ɃR�����e�[�^�[�Ƃ��ă����[�g�o�������B
�ԑg�ł́A�����s�̂܂h�~���d�_�[�u��11���Ɋ������}���A12������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����o����邱�Ƃ���B
�l�b�́u���Ζ��v���c������u(����܂łً̋}���Ԑ錾��)�Ⴂ�l����������č���҂ɂ����̂�h�����߂ɐl�����~�߂�Ƃ����̂����������ǁA���N�`�������y���钆�ō��܂łƓ����ً}���Ԑ錾���o���Ӗ����A���������[���������ė~�����v�Ɛ��`�̑����ɏڂ������������߂锭�����A�u�������̉���������ǁA�����̐������S���Ȃ��ł���v�����B�u(7����)920�l�̊����҂��o�������A60�Έȏ�̊����҂͂킸��60�����ł���B���N�`���̌��ʂ��o�Ă���B7���ɓ����Ă���A�S���Ȃ��Ă�����͂����ƈ�P�^�ł���v�ƔM�����A�u���̏�Ԃŋً}���Ԑ錾���o�����āA�l�͌��@�ᔽ���Ǝv���܂���v�Ǝ咣�����B
��������4�x�ڂ́u�ً}���Ԑ錾�v8��22���܂Ł@7/11
���`�̑�����8���A������4��ڂ́u�ً}���Ԑ錾�v�o�A��s���̐�t�A��ʁA�_�ސ�Ƒ���4�{���ɑ��Ắu�܂h�~���d�_�[�u�v�������B���ꌧ�ɂ��Ă��u�ً}���Ԑ錾�v����������Ɣ��\�����B�������8��22���܂ŁB�����́u�ً}���Ԑ錾�v��7��12������X�^�[�g����B
�������́u�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ͑S���I�ɂ͌������Ă��邪�A�����𒆐S�Ƃ����s����6�����ȍ~�A�����Ґ��̑����������Ă���v�Ƃ��A�u�ψي��̉e�����l������v�Ƃ��u�ĂёS���ւ̊����g���g�y�����Ȃ����߂ɂ������������K�v������v�Ƃ����B
����ɂ��A�ܗ֊J�Â����s����ɂ͓����E��t�E��ʁE�_�ސ��4�s���ł̌ܗ��Z�́u���Ȃ��Ƃ����S���ϋq�łȂ�������̗�����̂͒������ɂȂ�v�Ƃ̌��������܂��Ă���B
�l�b�g��ł́u�ً}���ԂȂ�����A�܂��I�����s�b�N�Ȃ�ďo���Ȃ��B���ʂɍl������t�F�X�����~�Ȃ�I�����s�b�N�����ē��������A�ً}���Ԑ錾�o���Ȃ�I�����s�b�N�����ďo���Ȃ��B�Ȃ��I�����s�b�N�������s���悤�Ƃ���̂��S�������ł��Ȃ��B�ŋ��͍����̂��߂ɐ������g���Ăق����v�u�e�n�Ő������[��I�����s�b�N�Ȃ�Ă���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��Ǝv���v�B
�u���̐����Ƃ�ނ�ƍ��ӂɂ��Ă�������Ƃ�ܗ֑I��ׂ̈ɍ����⍑����Ƃ��䖝���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�ܗւɂ͉����ǂ��납�����݂����Ȃ��v�u�w�Z�ł͈ꐶ�Ɉ�x�̑̈�Ղ╶���Ղ��ł��Ȃ��B�ł��ܗւ͂��B�{���ɗ��s�s�����A���ꂶ�Ⴀ�����Ґ�������Ȃ��v�ȂǂȂNJJ�Â��̂��̂Ɍ����������������ł���B5�ҋ��c�ł̊ϐ�̎�舵�������������B
���g�錾�h���o�铌����g�܂h�~�h��4�{�� ��Ԃ̐l�o���� �@7/11
4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����邱�Ƃ����܂���������A�܂h�~���d�_�[�u������������ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ł́A10���̐l�o����Ԓ��S��1�T�ԑO��葝�����܂����B
NHK�́AIT�֘A��Ƃ́uAgoop�v�����p�҂̋��āA�l�����肳��Ȃ��`�ŏW�߂��g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^���g���āA�����≫��Ȃǂ̎�Ȓn�_�̐l�̐��͂��܂����B
���͂������Ԃ́A�������ߑO6������ߌ�6���܂ŁA��Ԃ��ߌ�6�����痂���̌ߑO0���܂łł��B
����ɂ��܂��ƁA10���̓����̐l�o��1�T�ԑO�Ɣ�ׂāA�a�J�X�N�����u�������_�t�߂œ�����27���A��Ԃ�48���A�����w�t�߂ł͓�����1���A��Ԃ�10�����ꂼ�ꑝ�����܂����B
�܂��ً}���Ԑ錾�̉��������܂�������ł��A�ߔe�s�̌����O�w�t�߂œ�����11���A��Ԃ�80���������܂����B
���̂ق��A�u�܂h�~���d�_�[�u�v������������ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ł́A�������s�̑�{�w�t�߂œ�����3���A��Ԃ�15���A���l�w�t�߂œ�����1���A��Ԃ�28���A���~�c�w�t�߂œ�����4���A��Ԃ�9�������܂����B�܂���t�w�t�߂ł͓�����1�����������̂́A��Ԃ�12���������܂����B
��4��ڂ́u�ً}���ԁv�c�}������f���^���̋��Ё@7/11
(����)�����ɏo�����4��ڂً̋}���Ԑ錾�Ŋ����g���}������̂��A�����ǂ������̐���F����ɂ��b���f���܂��B
�����̂��傤�̊����҂�950�l�Ƃ������ƂŁA1000�l�ɔ���悤�Ȑ����ł��B���삳��A����ɔ����ďd�ǎ҂������Ă���A�������C�ɂȂ�܂��ˁB�������ł��傤���H
(���삳��)�����s�̏d�ǎҐ��ł����ǂ��A�����N�`��������҂̕��ɂ��Ȃ�i��ł��܂��B�ł��̂ŏd�ǎ҂̒��ł�����܂ł�60��70��̕������ɑ��������Ƃ��낪���̍���҂̊����������Ă��Ă�Ƃ����Ƃ���͘N�Ǝv���܂��B�������̈���ŁA40��50��̕��̏d�ǎ҂̊����������Ă��鏊�A���������O�����Ƃ���ł��āA���ɍŋ߂̃f���^���͎�N�҂ł��d�lj�����\��������Ƃ����Ă܂��̂ŁA���̕ӂ����O����邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
(�q)����̎�ȑ���܂Ƃ߂܂����B�܂����H�X�ɂ��Ăł����A����͑O�l�A��ނ̒̒�~�����߂܂��B����ɉ����Ȃ��ꍇ�͂����������Ă���Ǝ҂ɑ��Ď��������Ȃ��悤���߂�Ƃ������ƂȂ�ł��B�܂��S�ݓX�Ȃǂɂ��ẮA�ߌ�8���܂ł̎��Z��v������Ƃ��Ă��܂��āA�C�x���g�ɂ��Ă͊ϋq��5000�l�܂łƂ���ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
(����)���삳��A����̑��S�̓I�ɂ����ɂȂ��Ă������ł����H
(���삳��)����܂ł̑�Ƃ���قǕς���ĂȂ��悤�Ȉ�ۂ͂���܂��B�����A�����̏I���Ɍ}���铌���I�����s�b�N������܂��̂ŁA���̂���������������Ƃ���Ȃ̂��ȂƎv���܂��B���Ƃ́A���̎��ۂɐf�Â��Ă��錻��̈�ۂȂ�ł����ǂ��A�����N�`���ڎ킪���ɐi��ł܂��̂ŁA�����炭�ی����ł́A���̃��N�`���ڎ�̋Ɩ��ł��Ȃ�N�����Ă�Ƃ��낪�e�����Ă邩�炩�ȂƎv����ł�����ǂ��A����܂łƓ����悤�ȐϋɓI�ȉu�w�����������ɂ��Ȃ��Ă�悤�Ȉ�ۂ������Ă��܂��B���ɂ���܂ł͕ی������璼�ڔZ���ڐG�҂̈˗������Ȃ�Ă���ł����ǂ��A�ŋ߂ł͕ی�������Ƃ�����肩�́A�e�E��Ƃ��A���邢�͂��ƒ납�猟�������Ăق����Ƃ����˗������ɑ����Ă܂��̂ł��̕ӂ�̑����̔����A���ꂩ�瑁���̌����A���߂̑�B���̕ӂ��]�܂�邩�ȂƂ͍l���Ă܂��B
(����)���x���J��Ԃ����ً}���Ԑ錾�ł����A1��ڂ̂Ƃ��́A1�T�ԕ��ς̊����҂���7�l�ʼn�������܂����B���ꂪ2��ڂɂȂ�܂���301�l�ʼn����B������3��ڂ�388�l�ʼn����Ƃ������ƂŁA�����肫��O�ɉ������ꂽ����ł��傤���A���̐錾�ɓ���Ԋu���Z���Ȃ��Ă��Ă��܂��B�Ս���A�킸��3�T�ԂōĂыً}���Ԑ錾�Ƃ������ƂɂȂ�܂������ǁA�ǂ̂悤�ɂ����Ȃ��Ă܂����H
(�uZaim�v��\�@�Ս���)�����ł͑O��ً̋}���Ԑ錾����̊��Ԃ����܂�ɂ��Z���āA�܂��A���N�`���̐ڎ�̐i�������܂��āA�l�����\���ɉ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɋ뜜���Ă��܂��B
(����)�{���ł���ˁB���������ł��ˁA��͂�u�I�����s�b�N��L�ϋq�ł�肽���B�������琮�������Ƃ��Ă��̕ӂ�ł��������Ȃ���v�ƁA�����l�����̂��ȂƂ����ӂ��ɂ������Ă��܂��܂��ˁB
(�Ս���)�����ł��ˁB�ƌv��͂���ƁA���N�`���ڎ킪��s���Ă���65�Έȏ�̕������̌o�ϊ��������ɐL�тĂ���悤�ȏƂ����̂������Ă��Ă��܂��B�Ⴆ�A���N��5������6������1�T�ԂŔ�ׂ�ƁA65�Ζ����̕��̗��s��p�Ƃ����͔̂������炢�Ȃ�ł����A65�Έȏ�ɂȂ�܂��Ɩ�4�{�ȏ�ɑ����Ă���悤�ȏƂ����̂����Ď��Ă��܂��B
(����)�܂��������N�`���̈��S���Ȃ̂��ȂƂ������������܂����A���삳��A65�Έȏ�̕��́A���ԂN�`����2��ł��ꂽ�����Ǝv����ł�����ǂ��A���X�ň��H�������Ƃ����̂����낢�둝���Ă���ƁA���̕ӂ肢�����ł����B
(���삳��)���̊����ǂƂ����̂́A�}�X�N�Ȃ��ʼn�b������@��Ŋ������N����܂��̂ŁA���̕ӂ肵�����������Ă��������Ƃ������Ƃ��厖�ł��B���ꂩ��A���N�`����1���ł��ƂȂ��Ȃ��ψي��ɑ��Ă͌��ʂ��\���ł͂���܂���̂ŁA���������2��ł��Ē����āA����ɂ��ꂩ��2�A3�T�Ԃ��Ă��炵������ƖƉu�����Ƃ������Ƃ�F�����Ă����K�v������v���܂��B
(����)�����ĐS�z�Ȃ̂��f���^���ł��B�����ł�����A�f���^���̊����҂��ߋ��ő��ƂȂ�ȂǑ����Ă��Ă��܂��B����܂łƓ����悤�ȑ�ŁA�����g��Ɏ��~�߂������邱�Ƃł����ł��傤���B
(���삳��)������Ƃ��ẮA��قǐ\���グ�܂������ǂ��A�ł���ˁB�}�X�N�Ȃ��ł̉�b�̋@������炷���Ƃɂ͕ς��܂���B�����ŋ߁A���̂Ƃ���ł����̃f���^���̊��҂�������l���q�����Ă��ł����ǂ��A����܂ł͑�l���Œ����Ԃň��H�̋@��������ꂽ������������̂��ڗ����Ă���ł����ǂ��A�����������f���^���̕��́A���l���ŒZ���Ԃł����H�̋@��������B����ł��z���ɂȂ��Ă�Ƃ��������ڗ����Ă���܂��̂ŁA���̂�����͂�������Ƃ����������K�v�����邩�ȂƂ������ɍl���Ă��܂��B
(����)����ً̋}���Ԑ錾���ɊJ�Â���邱�ƂƂȂ�܂��������I�����s�b�N�ł��B�����Ȃ�1�s3���Ɩk�C���ł͖��ϋq�ł̊J�Â����܂��Ă��܂������A���傤���������ϋq�ɂ���Ɣ��\������܂����B���삳�̊������X�N�Ƃ����_�ł́u���ϋq�v�ɂ��Ă������ł��傤���B
(���삳��)�l�l�������銴���ǂł��̂ŁA�l���W�܂�@�������X�N�͌���Ǝv���܂��B�������̈���ŁA����͂��q�����̖�肶��Ȃ��ĊW�҂̕��ł��ˁB���̊W�҂̕��ł��قڐ����l������Ƃ������Ɏf���Ă܂��̂ŁA��������������ւ̑����������ƕK�v���ȂƂ����͍̂l���Ă܂��B
�������ݑ��Ő��키�u��������Ĉ��߂�̍Ō�v12������ً}���Ԑ錾�@7/11
�����s��12������8��22���܂ŁA4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾���Ԃɓ���B�����Ċg��܂��A���~��ċx�݂̐l����}���������l�������A�u�錾����v�����O����A���ʂ͕s�������B11���A�ό��q�łɂ��키�����̉����E�͒����琌�q�łɂ�������B�ʏ́u�z�b�s�[�ʂ�v���ƌ����{�ʂ�ɂ͐��z�b�s�[��r�[�����S�N�S�N�ƍ����ɂ����钋���ݑ����勓���ĉ����������B
�u��������Ĉ��߂�̂�11�����Ōゾ����ˁv�u�����ܗւ͎���Ńe���r�����v�u12������ً}���Ԃ�4�x�ځA���܂Ȃ��Ƃ���Ă��Ȃ��v�ƃ��P�C���Ŋ��t���J��Ԃ��B���ɂ́u�����ł����̈��߂�X�����Ă���ł���B���������Ƃ����T����v�ƁA�������߂鐺���オ�������A�z�b�s�[�ʂ�̋������u�Ȃ́v�Ė�䑾�Y�X��(49)�́u12������8��22���̊����܂ŋx�݂܂��B�Ƃɂ����R���i���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̓X�傳����Y�݂ɔY��œX��߂�Ɓc����������ǂ���ł��v�ƐO�����݂��߂�B
�������ʂ�̓y�Y���X�ł́u��������1�N�A�ǂ����Ă����̂�������Ȃ����A�X���J���Ă����B12��������J�������܂���v�Ƃ��ߑ��܂���B����ł��u���{�����ɏZ�ފO���l���w���̐e�ʂ�F�l�ɑ���x�Ƃ܂Ƃߔ������Ă���邱�Ƃ������āA���肪�����ˁv�ƁA�킸���̃C���o�E���h�̌��ʂɂ����ӂ���A�[������̓S���S���Ɨ����Ƃǂ낫�A�������J�Ɍ�����ꂽ�B��K�ꂽ�l�X�́A�����ɋA�H���}���ł����B
���H�苒�ő䓌�悩�痧���ނ����w�����ꂽ�`�@�@�̏��X�X���ً}���Ԑ錾�ɗ\������킳�ꂽ�B���X�X�����̏��������������Łu�j���[�X�����Ă��ꂽ�l���킴�킴�k�C���Ƃ���B����K�˂ɂ��Ă����B���肪�����v�Ɛ`�@�@���h��̐��эG�͉(59)�͘b���B���ł�1���l�ȏ�̏������W�܂�A�������12���ɂ���ɒ�o����͂����������A�ً}���Ԕ��߂ł�������͏�����o�����������B�u��Ƃ��������͂Ȃ��B���̏��������������ɘa���ł���_���݂������v�Ɛ��щ�͘b�����B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������A4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�X�^�[�g�c�ܗ֏I�ՂɊ�����1500�l�̊�@ �@7/12
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A�����s��12������8��22���܂�4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�ɓ������B�錾���ɂ́A�����ܗւ̊J�Ê���(7��23���[8��8��)�����ׂĊ܂܂��B���{�Ⓦ���s�́A���H�X�̎�ޒ��Ăђ�~���A�l���̗}�����Ăъ|���Ċ����̗}����}�邪�A��Ԃ̐l��͌����Ă��炸�A�C���h�R���̃f���^���̉e���Ōܗ֊��Ԃ̏I�Ղɂ�1��������̊����҂�1500�l�ɒB����̂ł͂Ƃ̌��O���o�Ă���B(�f�W�^���ҏW��)
���ɉ؊X�ɐ[��܂Ől��
�u����A��x�����Ԃ܂ŋL�҉���s�킹�Ă��������āA���̌�A�����s�����o������ɉ؊X�Ȃǂ����ĉ�����B�J�����ڍ~��ɂ��ւ�炸�A���Ȃ葽���̕��X���o�Ă����B�H��Ńo�[���J���Ă�悤�ȕ��Ȃǂ��������v�@�����s�̏��r�S���q�m����9���̒��L�҉�ŁA�ً}���Ԑ錾�̔��߂����܂���8����ɓs���̔ɉ؊X������A�l���̑����Ɋ�@�����������Ɩ��������B���r�����l���̑������w�E�����̂́A���㓌���̊����҂��}���ɑ�����ƌ��O����邽�߂��B8���ɓs�̃��j�^�����O��c�ōs��ꂽ���Ƃ̕ɂ��ƁA7���ԕ��ς̐V�K�z���҂́A7�����_�Ŗ�625�l�ƂȂ�A��503�l������1�T�ԑO��6��30���Ɣ�ׂ�1.24�{�ɁB�u�������Ċg�債�Ă���v�Ǝw�E���ꂽ�B����ɂ��̂܂܂̑����������A�ܗ֊J����ƂȂ�3�T�Ԍ��7��28���ɂ͍���1.91�{��1���������1192�l�ɁB�ܗւ��I�Ղɍ�����������4�T�Ԍ��8��4���ɂ͍���2.36�{�̂��悻1478�l�ɂȂ�A�u��3�g�ɂ�����N�n�Ƃقړ����x���̐V�K�z���Ґ��ɂȂ�v�Ƃ����B
���Z���Ԃɋ}���Ɋ����ґ��̋���
�s���ł͊����͂������C���h�R���̕ψي��u�k452�q�v�̊��������������n�߂Ă���u����Ȃ�l���̑�����k452�q�̉e���ɂ���đ����䂪����ɏ㏸����Ɨ\���l�͂���ɑ������A��3�g����}���Ȋ����g��̊댯�������Ȃ�v�Ƃ����B�܂����Ƃ���́A�s���̐[��т̑ؗ��l���͑�4�g�ɓ˓�����3�������Ɠ������������ɂ���A�u��4�g���������y�[�X�Ŋ�������������\��������v�Ƃ̌����������ꂽ�B�܂肱��܂ňȏ�ɒZ���Ԃɋ}���Ɋ������L���邱�Ƃ����O����Ă���B�����������A���r���́u���܂ňȏ�ɁA�s�v�s�}�̊O�o�A�ً}���Ԑ錾�ւƂ܂����x�����オ��̂ŁA�l����}�����邱�ƁA���ɖ�Ԃ̐l����}���Ă����K�v������v�Ƒi�����B
���u���S�E���S�Ȍܗցv�͉\�Ȃ̂��c
�������������Ăъ|���́A�ǂ��܂Ō��ʂ�����̂��B���ɋً}���Ԑ錾��4��ڂƂȂ��āu�錾����v���w�E�����ق��A����͉ċx�݂Əd�Ȃ��Ă��ė��s�ȂǂŐl���̑��������O�����B�����Ď�s���ł͓����ƁA��ʁA�_�ސ�A��t��1�s3���͖��ϋq�Ƃ͂������̂̌ܗւ��J�Â����B���{�l�I�肪����C�������g�����l��������ɔɉ؊X�ɌJ��o������A�u�ܗւ��J�����̂���������O�o���䖝����K�v�͂Ȃ��v�ƍl�����肷��l���o�Ă���\��������B�ܗւɂ��ď��r���́u���S�E���S�ȑ����J�Â�����Ƃ������Ƃ͋ɂ߂ďd�v�v�Ƃ�����ŁA�u���E�̗l���̓R���i�ɂ���đ傫���ς�����B�����������ŃI�����s�b�N�Ƃ��������A���ۓI�ȑ����s���Ă����Ƃ������Ƃ́A�F�X�O��̖������Ƃ���ɂȂ낤���Ǝv���v�Əq�ׁA���ϋq�J�Âɂ��Ă���������B�u(�O��̓����ܗւ�)�����g�A���w�Z���������A�e���r�ŃA�x�x�I�肪���蔲����V�[�������܂��Ɋo���Ă���B���̕����Z�p�Ȃǂɂ���āA�F�X�Ȍ������A�y���ݕ����A����������ł����Ƃ����Z�p���H�v���Ȃ�����B���E�ɓ����ɔz�M���A�e���r��ʂ��Čq�����Ă������Ƃ��A���E�̘A�ъ��A��̊��������o���A�����̈Ӗ��ŏ��߂Ă̑��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v ���ϋq�Ōܗւ��J�Â������ŁA�l����}���A1��1000�l�������O����铌���̊�����}�~���邱�Ƃ��ł���̂��B�����ɂƂ��đ��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�̊��Ԃ��n�܂����B
���ʋ��b�V���ɕω��Ȃ��u�d�Ԃ͖����v�c������4��ځu�ً}���ԁv �@7/12
�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɔ���4��ڂً̋}���Ԑ錾��12���A�����s�ɔ��߂��ꂽ�B���{��s�͏o�Ύ҂̍팸��ڎw���Ă��邪�A�s���̎�v�w�ł͏����̒��A�錾�O�Ƃقڕς��Ȃ��l�o���݂�ꂽ�B
���̓��͉��ꌧ�ɑ���ً}���Ԑ錾�ƁA�_�ސ�A��ʁA��t�A����4�{���ւ́u�܂h�~���d�_�[�u�v���������ꂽ�B���Ԃ͂������8��22���܂ŁB
4��ڂً̋}���Ԑ錾�����A�E��ȂǂɌ������l����(12���ߑO8��41���A�����s�������)4��ڂً̋}���Ԑ錾�����A�E��ȂǂɌ������l����(12���ߑO8��41���A�����s�������)
�����s������̓s�c�n���S��]�ː��̏��ǂ��w�ł�12�����A�}�X�N�p�̒ʋq�炪�r��邱�ƂȂ����D����E��ւƌ������Ă����B�n�c��̏�����Ј�(22)�́u�d�Ԃ͖����ŁA���i��荬��ł���悤�ȋC�������v�Ƙb�����B���s�̒j����Ј�(63)�́u�錾���}���l�������Ă��Č��ʂ�����̂��v�Ǝ�����������B
�ǔ��V�����m�s�s�h�R���́u���o�C����ԓ��v�v�̃f�[�^�𗘗p���A12���ߑO8����̓s���̎�v�w���ӂ̐l�o���A�d�_�[�u���Ԓ���1�T�ԑO�̌��j��(7��5��)�Ɣ�r�����Ƃ���A�����w��0�E5�����A�V�h�w2�E2�����A�i��w3�E5�����ŁA�قډ����������B3��ڂ̐錾�㏉�߂Ă̌��j��(4��26��)�Ɣ�r���Ă��A�����w4�E3�����A�V�h�w1�E3�����A�i��w0�E6�����ŁA�l�o�̑傫�ȕω��݂͂��Ȃ������B
����̐錾�ɔ����A�s���ł�12�������ނ������H�X�ɋx�Ƃ��v�������B��ނ���Ȃ��X�ɂ͈��������A�ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k�����߂���B
��4��ڂ̐錾�����@�ς��ʒʋΕ��i�u�܂����A�Ƃ��������v�@7/12
�V�^�R���i�E�C���X�����҂̑������A�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o���ꂽ12���̒��A�����w�O�̓}�X�N�p�̒ʋΎ҂��s�������A�錾�O�ƕς��Ȃ����i������ꂽ�B
�L����Ђɋ߂鐁���炳��(40)�́A���J���O����d�Ԓʋ���߁A����̂��铌���s�n�c�悩�玩�]�Ԃʼn�Ђɒʂ��Ă���B�u�ً}���Ԑ錾�Ɋ��ꂫ���Ă��܂��ĎГ��ł��b��ɏオ��Ȃ��B�܂����A�Ƃ��������v�Ɗ��z��R�炵���B�錾�̊��Ԃ������I�����s�b�N�Əd�Ȃ邱�Ƃɂ��āu�ܗւ����l���[�h�ŁA�{���ɂ��̂��Ƌ^�킵���Ȃ邭�炢����オ��Ɍ�����v�Ǝ���Ђ˂����B
�i��悩��ʂ������E��60�㏗���̉�Ђł́A����܂ł��e�����[�N�𐄏����Ă������A�錾���o�����Ƃʼn��߂ēO�ꂷ��悤�Г��Ɏ��m�����Ƃ����B�����́u�m�l�ƑΖʂʼn�Ȃ����Ԃ��������Ƃɍ����Ă���B(�錾�����ł�)�����g���h���̂ɉ�������Ȃ��̂��悭������Ȃ��B�Ȋw�I�����������Ăق����v�ƒQ�����B
����A��t���s��s����ߐ�Ɍ������Ă����j��(60)�́u(�������g�債�Ă��钆�ł�)�錾����炴��Ȃ��B�ܗւ���邱�Ƃɕς��Ȃ��̂�����A(�����Ă�)�ǂ����悤���Ȃ��v�ƌ�������ꂽ�B
���{�͐錾���������鉫�ꌧ�ƂƂ��ɁA�u�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p���Ă��������s��4��ڂ̐錾�߂��A��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���͂܂h�~�[�u�����������B�������������8��22���܂ŁB
�������A4�x�ڂً̋}���Ԑ錾 ���������ۑ�Ɂ@7/12
�����́A12������A4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�ɓ���܂����B���H�X�ɑ��ẮA�ĂсA���̒�~���v������Ă��܂��B
�u����4�x�ڂł���ˁB���܂�(���ʂ�)���҂ł��Ȃ��ł���ˁB��͂�A�ܗւ����Ȃ�e�����Ă�Ǝv���B�J�Â��邽�߂ɂ́v(60���Ј�)
�u���ސl�͂ǂ��ł����ނ��A����Ă邨�X�͐錾�W�Ȃ�����Ă�Ƃ���͂���Ă邵�v(50���Ј�)
12�����痈��22���܂łƂȂ鍡��ً̋}���Ԑ錾�ŁA�����s�́A���H�X�ɑ��A�������ꍇ�͋x�Ƃ�v�����A���Ȃ��ꍇ�͌ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ�v�����܂��B
����ŁA�O��A4���ɏo�����ً}���Ԑ錾�̍ۂɂ́A�f�p�[�g��f��فA�����قȂǂɋx�Ɨv�����s���܂������A����́A���Z�v���ɂƂǂ܂��Ă��܂��B�܂��A�O��́u���ϋq�v��v�����ꂽ�C�x���g�⌀��ɂ��Ă��A�ϋq��5000�l�ȉ��A������̔����ȉ��Ƃ��������ŊJ�Â��F�߂��܂��B
�����A�����s�̐V���Ȋ����Ґ��́A���߂�7���ԕ��ςŁA���������733�D9�l�ƁA�O��̐錾���o���ꂽ����������`�ő������Ă��܂��B�O��̑�4�g�������炵���C�M���X�^�̕ψكE�C���X����1�D5�{�قNJ����͂̍����Ƃ����C���h�^�̃f���^���������钆�A�錾�̎��������ۑ�ł��B
�u4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����ƂȂ������傤�A��������͂���܂łǂ���I�[�v�����܂����v(�L��)
�s���̕S�ݓX���Ή��ɒǂ��Ă��܂��B��������ł͉c�Ǝ��Ԃ͂���܂łƕς��Ȃ����̂̎�ނ̒�~�v���ɂƂ��Ȃ��A�r�A�K�[�f���ł̃A���R�[���̒𒆎~���邱�Ƃɂ��܂����B���̃r�A�K�[�f���͐挎���Ɏn�߂�����ŁA����21������̓X�^�[�g���Ԃ�O�|�����ă����`�c�Ƃ��n�߂܂��B
�u�A���R�[�����o���Ȃ����Ƃ͎c�O�ł͂������܂�����ǂ��A���S���S�Ȋ����p������Ƃ������Ƃ���ɁA�����܂őO�����ɑ��������v(������� ���ؗY��H�i�S������)
�������s ���傤����Ăыً}���Ԑ錾 �ܗ֍T���}�����݉ۑ� �@7/12
�����s��12������4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ���A���������H�X�ɑ��ċx�Ƃ�v�����܂��B�I�����s�b�N�̊J�������T�ɔ��钆�A�錾�̂��Ƃł̋�����ɗ����Ƌ��͂Ȃ�����̐��ۂɂ��ւ�銴���̗}�����݂��ł��邩���ۑ�ƂȂ�܂��B
�����s��12������4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ���A�O��E3��ڂ̐錾����������Ă���1�����������Ȃ������ɍĂѐ錾���o����邱�ƂɂȂ�܂��B
����̐錾�ŁA�s�͎���J���I�P�ݔ��������H�X�ɑ��Ă͋x�Ƃ��A���Ȃ��ꍇ�͌ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ�v�����܂��B
�s�͂��̂ق��s���ɑ��ē������܂߂��s�v�s�}�̊O�o�ƈړ������l���A���ɋA�Ȃ◷�s�Ȃǂ̓s���{�����܂����ړ��͋ɗ͍T����悤���߂܂��B
�I�����s�b�N�̊J���͗��T�̋��j���E23���ɔ����Ă��āA�錾�̂��Ƃł̋�����ɗ����Ƌ��͂Ȃ�����̐��ۂɂ��ւ�銴���̗}�����݂��ł��邩���ۑ�ƂȂ�܂��B
��12������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�@���� 614�l���� 22���A���ŏ��� �@7/12
�V�^�R���i�E�C���X�̊������Ăъg�債�Ă��铌���s�ł́A12������A4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ���B
�s���ł�11���A�V����614�l�̊������m�F����A�N��ʂł́A20�オ208�l�ƍł������A30���119�l�Ƃ��킹��Ɗ����ґS�̂̔����ȏ���߂Ă���B
1���̊����Ґ��Ƃ��ẮA22���A���őO�̏T�̓����j���������Ă���B�܂��A���̂ق��ɐ_�ސ쌧��389�l�A��t����183�l�A���{��167�l�A��ʌ���163�l�ȂǂƂȂ��Ă���B
�����g�傪�~�܂�Ȃ������s�ł́A7��12������8��22���܂ł�6�T�ԁA4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ���B���̊ԁA��ނ�J���I�P�������H�X�Ȃǂɋx�Ƃ�v�����A��ނ���Ȃ����H�X�ɂ́A�ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�����߂�B�S�ݓX�Ȃǂ̑�K�͏��Ǝ{�݂ɂ͋x�Ƃ����߂��A�ߌ�8���܂ł̎��Z�v�����p������B
�������ɋً}���Ԑ錾 ���~�v�� �������ǂ����߂邩�@7/12
�����s�́A12������4��ڂً̋}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ���܂����B���{�́A���H�X�ł̊�������������邽�߁A�錾�������������ꌧ�Ƃ��킹�Ď��̒�~��v�����邱�Ƃɂ��Ă��āA���������ǂ����߂邩���ۑ�ƂȂ�܂��B
�����s�́A12������4��ڂً̋}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ���A���ꌧ�ł��錾����������A��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ł́A�܂h�~���d�_�[�u������������Ԃ́A�����������22���܂łƂȂ�܂��B
���T23�����痈��8���܂œ����I�����s�b�N���J����A���̌�͂��~�x�݂��T���Ă��邽�߁A���{�́A�l�̈ړ��������Ȃ邱�Ƃɂ�銴���g���A�ψكE�C���X�̍L���肪���O�����Ƃ��āA��̓O����Ăт����Ă��܂��B
�Ƃ�킯�A���H�X�ł̊�������������邽�߁A�錾�̑Ώۂ̓����Ɖ���ł́A���̒�~��v�����A�d�_�[�u����������4�{���ł����̒�������~���A�m���̔��f�Ŋɘa�ł���悤�ɂ��܂��B
�������[�����́A11���A�m�g�j�̔ԑg�u���j���_�v�Łu���H�X�ł͎�����Ȃ��ƌo�c�ɖ{���ɉe��������B���͋��̐�n�����܂߁A���͂��Ē��������邱�Ƃɓw�͂������v�Əq�ׂĂ��āA��̎��������ǂ����߂邩���ۑ�ƂȂ�܂��B
����ŁA���{�́A���N�`���̐ڎ헦�����߂邱�Ƃŏd�lj����X�N��ጸ�����A������}�����݂����l���ŁA�a���̏Ȃǂɉ��P��������ꍇ�ɂ́A�����O�̐錾�̉���������������j�ł��B
������4�x�ځg�ً}���Ԑ錾�h�Ɂu�Ӗ������v�@�ܗ֒�1000�l�� �����\���� �@7/12
�V�^�R���i�E�C���X�̊������Ċg�傷�铌���s�ŁA4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾��12���ɔ��߂���A��t�E�_�ސ�E��ʁE����4�{���́A�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ�B���Ԃ́A8��22���܂łƂȂ�B
12�����̕i��w�ł́A�ʋ���l�Ȃǂ���A�O��̐錾��������A���悻3�T�Ԃł̍Ĕ��߂Ɍ��ʂ��^�⎋���鐺�Ȃǂ������ꂽ�B
��Ј�(40��)�u(�錾��)�Ӗ��������Ȃ��Ă���B�������ꂿ����ĂāA�ً}���Ԃ��Ă����C�݂͂�Ȃ��Ă��Ȃ��v
�����E(20��)�u(�܂h�~���d�_�[�u�̎��Ƃ̈Ⴂ��?)�d�Ԃ��܂��܂�����ł��邵�A�S�R�ς��Ȃ��C������B���̊Ԃ�(�錾��)���������Ӗ��������̂��ȁv
��Ј�(50��)�u(4�x�ڂ̐錾���߂ƂȂ邪?)����͂������ɂȂ��Ǝv���Ă����̂ŃV���b�N�v
��T�̓����s�̐��Ɖ�c�ł́A���̃y�[�X�ŐV�K�����Ґ���������A�I�����s�b�N���Ԓ���1,000�l����Ƃ̕��͂�������Ă���B�ً}���Ԑ錾�̊��Ԓ��A�����s�͈��H�X�Ɍߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ����߁A��ނ̒��l�����߂�ق��A���ꂪ�ł��Ȃ��X�܂ɂ��Ă͋x�Ƃ�v������B
���u���������ォ��ڐ��ł��肢���܂����ፑ�����䖝����܂���v�@7/12
12�������̓��{�e���r�n�u��C�u�@�~���l���v(���`���j�E�ߌ�1��55��)�ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���22���A���őO�T������A8��22���܂łً̋}���Ԑ錾���o�ƂȂ��������s�̗l�q��`�����B
�R�����e�[�^�[�Ń����[�g�o���̔o�D�E�~��x���j�́u�����A�Ԃ�(�ǂ܂�)���܂������ǁA�Ԃ������ł����A�l����������o�Ă܂����ˁv�ƃR�����g�B
���̏�Łu����͂�͂�A����(�����Ґ���a���g�p����)���̂��炢�܂ŗ�����������܂���ƌ����Ă����A�����Ȃ�����������܂�����䖝���ĉ������ƌ����Ă�����Ȃ炢�����ǁA���������A���肢���܂��ƁB�ォ��ڐ��ŁB���ꂶ�Ⴀ�A�������䖝����܂���B���ɂ��̂��Ƃ����肢���Ă��������Ǝv���܂��v�ƌ����������ői���Ă����B
����̋ƊE�u���Ԓm�炸���v�A���{�ɔ����@�K�����������z�̋���@7/12
�V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â������s��4��ڂً̋}���Ԑ錾��12�����߂��ꂽ���A�K�����������ꂽ���H�X���ޔ̔��ƊE�Ȃǂ̔��������܂��Ă���B���琭�{�����̉����Ǝ҂ɁA��ޒ𑱂�����H�X�Ƃ̎�������l����悤�v���������߂��B�����A���H�ƊE���������_�������������s�M���┽������A��ނ����X�͑����Ă���Ƃ̎w�E������A�K�����������z�Ɋׂ��Ă��鋰�������B
�u�M���W�Ő��藧���Ă���̂�(�X�������)���܂�Ēf��Ȃ�Ăł��Ȃ��B�l�����l�Ԃ͂���ۂǐ��Ԓm�炸���v�B�����s�V�h��̋Ɩ��p��̓X�u���X�؎�X�v�̍��X�؎��В�(66)�͂�������B
���t���[�ƍ��Œ���8���A���X�܂Ƃ̎�����~�߂�悤�A�����Ǝ҂ɕ����ŗv�������B���X�؎��ɂ��ƁA���H�X�͔[�i�ɖK��鉵���Ǝ҂ɓX�̌���a����قǁA���i���狭���M���W������B�����琭�{�̗v���ł��A�����͂̂Ȃ�����̑[�u�Ɂu�]���Ǝ҂͂��Ȃ����낤�ˁv�Ƙb���B
�S��������̑g���������9���ɐ��{���̍R�c���\�B�����~�ɑ���⏞���Ȃ��A������f��Όڋq���������ꂪ���邩�炾�B�������l�����ǒ����u�����̈˗��ɉ����Ăق����Ƃ͂����Ȃ��v�ƁA����ɑ��ē��i�̓��������͂��Ȃ����j���B
�ƊE�̊��K���������{�̑Ή����^�⎋���鐺�͋��Z�ƊE������o�Ă���B�����N���o�ύĐ��S������8���ɖ��X�܂̏���������Z�@�ւɗ����A������|���Ă��炤���j��\���������ᔻ�����o�A�����ɓP���B�����s�W�҂́u���H�X�ڐ������܂�ɂ��ア�v�Ƃ������B
����Ő��{�̈ӌ��ɔ����A�c�Ƃ�����H�X�͑����Ă���Ƃ݂���B���H�X�̖@�����ɏڂ��������~�M�ٌ�m�́u�����o���������X�̔������炢�͉c�Ƃ𑱂��Ă����ۂ��v�ƌ��B�ߗ����Ăł��c�Ƃ��������L���Ȃ��Ƃ������A�ׂ̓X������Ă��邩��Ɖc�ƍĊJ�ɓ��ݐ�P�[�X���ڗ��Ƃ����B�������́u�������������ĕ⏞���[��������ȂǁA�����҂��������Ȃ��d�g�݂Â��肪�K�v���v�Ƙb���Ă���B
���u�A�Ȃ◷�s�T���āv�ً}���Ԑ錾�E�u�܂h�~�v�̑Ώۋ��@�X���@7/12
�����s�ً̋}���Ԑ錾�Ȃǂ��ĎO���m���͑Ώۋ��̐l�����ɉċx�݂₨�~�̎����̌����ւ̋A�Ȃ◷�s���T����悤�Ăт����܂����B
���͓����E����Ώۂً̋}���Ԑ錾��4�{���Ώۂ̂܂h�~���d�_�[�u���Ċ�@���{����c���J���܂����B
��c�ł͎O���m�����錾��[�u�̊��Ԓ��A�Ώۋ��Ƃ̕s�v�s�}�̉������T����悤�����Ȃǂɉ��߂ČĂт����܂����B
�u(�Ώۋ��̐l��)�ċx�݂₨�~�ɂ�����X���ւ̋A�Ȃ◷�s�Ȃǂ��T���Ă����������Ƃ����肢������Ȃ��v
��c�ł͌����S�Ă̈�Ì���ŕa���g�p�����X�e�[�W3�̊��20����������Ă��邱�Ƃ�����܂����B����A���͕ψكE�C���X�̊��������܂��Ă���ق������o�H�s���̐V���������҂������Ă���Ƃ��Ċ�����̌p�����Ăт����܂����B
���ʏ�m���A���N�`���m�ۑi���@����ً̋}���Ԑ錾�A�ĉ������Ԃɓ���@7/12
���ꌧ��12������8��22���܂ŁA�V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾�̍ĉ������Ԃɓ������B5��23���̔��߈ȗ��A����ɐ錾���o�������Ԃ�3�J���ɋy�Ԃ��ƂɂȂ�B�����̉��P��N�`���ڎ�̉������ȂǂŁA����7�����̑O�|��������ڎw���p����ł��o���Ă���B�錾���Ԓ��̎�ޒX�܂ւ̋x�Ɨv����A���H�X�ւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�v���͌p������B
�ʏ�f�j�[�m����11���A�S���m����V�^�R���i�E�C���X�ً}���{����c�ɃI�����C���ŎQ�������B�ʏ�m���͊�����̐�D�ƂȂ郏�N�`���ڎ�̉������Ɍ����A3�J���ڂƂȂ�L��ڎ�Z���^�[�̐ݒu�Ɍ����u�����̃��N�`���̕K�v�ʂ̊m�ۂ����ɋ��������|���Ăق����v�Ƒi�����B
�����ł͓ߔe�s�̌��������قƋX��p�s�̉���R���x���V�����Z���^�[��2�J���ɍL��ڎ�Z���^�[���J�݁A�ڎ팔������18�Έȏ�̑S�������ڎ������B���͓ߔe�s�̓ߔe�N���[�Y�^�[�~�i���ɂ��L��ڎ�Z���^�[��ݒu���A15������J������\�肾�������A���N�`���̋����s���Œx���\�����o�Ă���B
�ĉ��������܂����ً}���Ԑ錾�ɂ��āu�����ɂ킽�邱�ƂŌ����A�ƊE�ɂ͕��S���|���Ă���v�Əq�ׁA���߂đ��������Ɍ����Ċ����h�~��ɓO�ꂵ�Ď��g�ލl�����������B
���u�Ƃɂ����䖝���Ă���A�i��ɍi���Ă���ƌ����Ă��ς����Ȃ��v�@7/12
12�������̓��{�e���r�n�u��C�u�@�~���l���v(���`���j�E�ߌ�1��55��)�ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���22���A���őO�T������A8��22���܂łً̋}���Ԑ錾���o�ƂȂ��������s�̗l�q��`�����B
�{�����i�L���X�^�[�́u�P�ɓ��ɂ��������߂�����ċً}���Ԑ錾�Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ��A�ς����Ȃ��Ǝv���v�Ƙb���ƁA�u�Ⴆ�A�����Ґ������ꂭ�炢��������A������������������Ƃ��A�a�������ꂭ�炢����A�������������������Ƃ��A���[�h�}�b�v���Ȃ��ƁA�Ƃɂ���22���܂ŊF����䖝���Ă���A�i��ɍi���Ă���ƌ����Ă����܂�Ȃ��ł���ˁv�ƌ������\��ő����Ă����B
���g���������h�ɓ{��S���̈��H�X�����N�I�@�u�����ȊO�ɓ��[�v�|�X�^�[�@7/12
12�����瓌���s�ł�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���������A���H�X�ɂ͉c�Ǝ��ԒZ�k�y�ыx�Ƃ��ޒ̌�����~�����߂���B���{�̖���Ƃ������ׂ��ɓ{��S���̈��H�X�ɁA���N�����߂�Ăт������L�����Ă���B
�l�b�g��Ŋg�U����Ă���|�X�^�[������B
�u���X�͂������芴���h�~������Ă��܂��B�s�����ȁw�ً}���Ԑ錾�x�ɂ͒f�Ŕ����܂��B�H�̑��I���ł́A�����}�ƌ����}�ȊO�ɓ��[���܂��B���q�l�������͂��������v�B�^������X�̓v�����g�A�E�g���A�X��Ɍf������悤���肢����Ă���B
���������͌����{�}�C�N���\�t�g�В��E���������̂r�m�r�ł̓��e���B
�u(���{��)���͂�O�_�O�_�Ȃ̂�����A�H�̑��I���͓s�c�I�ȏ�̔g�����N���邾�낤�B���}������������\��Ŏ����}�͑���ꂷ��̂ł͂Ȃ��낤���B����ɏ悶�ē����̈��H�X�͓���|�X�^�[��p�ӂ���ׂ����v�u���H�X�͎������������{���Ă��邱�Ƃ����ʓI�ɕ\�����Ȃ��ƃ_���v�Ȃǂ�8���ɌĂт������B
����Ƀz���G�������Ɩx�]�M����(48)���^���B�x�]�����O���u�t�߂�u�x�]���o�m�v�m���ŁA��N�̓s�m���I�ɂ��o�n���Ă����ē�����Y��(40)���ĉ����A���m����̓I�ɓ����Ă���B
����ɐ����N���o�ύĐ��S����(58)�����{�̗v���ɉ����Ȃ����H�X�ɑ��A�u���Z�@�ւ��瓭���������s���Ă��������v�Ɣ��������̂����H�X�̓{��ɔ��Ԃ������Ă���B�@
���g�����H�X�o�c�҂������ē����́u�o�ς̏z���~�߂Ă܂ŁA���H�X��߂�K�v�����邩�ɂ��Ă͐r���^��B�����̈��H�X�����ɋꂵ��ł���p�����Ă����B(�����ւ̓��[�m�n��)���{�ւ̔ᔻ�ł͂Ȃ��B�����}�����߂��邪�䂦�ɗ��\�Ȑ��ʂ��Ă��܂��B������b�̔��������̖��f���炫�Ă���B�^�}�̎x���҂��|�X�^�[�f�����Ă��ꂽ�����{�ӂł�����B���А��{�^�}�ɂْ͋����������Ăق����v�Ƙb�����B
�^���̐��͒����ɍL�����Ă���A�ڕW�͓s��5���X�ւ̌f���B���{�A�����}�ɓ{��̃��b�Z�[�W�Ƃ��āA�͂��̂��B
���s���o�X��� �ً}���Ԑ錾�ƌܗ֖��ϋq�œ�d��@7/12
�����̘V�܃o�X��Ёu�͂ƃo�X�v�́A�����s��12������4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����A�I�����s�b�N�����ϋq�ƂȂ������ƂŁA���҂��Ă����ό����v�������߂���d��Ɋׂ��Ă��܂��B
�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̑����Ԓ��A���ւ̊W�҂̗A����S���v�������܂����A�Ј��̈ꕔ�͋x�Ƃ�����Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
�����E��c��ɖ{�Ђ�����V�܃o�X��Ђ́u�͂ƃo�X�v�́A�����s��12������4��ڂً̋}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ���̂��āA�s��������قڂ��ׂẴc�A�[���^�x���邱�ƂɂȂ�A�L�����Z���Ȃǂ̑Ή��ɒǂ��Ă��܂��B
��Ђł́A�ً}���Ԑ錾���o����邽�тɂ��ׂẴc�A�[���^�x���Ă��܂������A����́A��������{���������̂Ȃ��I�[�v���^�̃o�X�ŁA�r�����Ԃ����ɓs���̊ό��n������1�R�[�X�����́A�^�s���p������Ƃ������Ƃł��B
�܂��A�I�����s�b�N��1�s3���̉�ꂪ���ϋq�ƂȂ������ƂŁA�����Ԓ��Ɋ��҂��Ă����ό����v�������߂Ȃ��Ȃ�܂����B
��Ђɂ��܂��ƁA�ً}���Ԑ錾���f���I�ɏo����Ă��邽�߁A���Ƃ��ɓ����Ă���110��̃o�X�̑������c�A�[�̂��߂ɉғ��ł��Ȃ���Ԃ������Ă��܂��B
���N�`���̑�K�͐ڎ���ւ̑��}�o�X���^�s���Ă���ق��A�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̑����Ԓ��ɉ��ւ̊W�҂̗A����S���v�������܂����A�Ј��̈ꕔ�͋x�Ƃ�����Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
�͂ƃo�X�L�̖{�c���ނ���́u���N�`���ڎ킪�n�܂�A�ċx�݂ɗ��s���v�����邩�Ǝv���Ă����Ƃ���ōĂыً}���Ԑ錾���o���̂ŁA���ɔ߂����ł��B�����܂���������Ȃ��Ƃ͎v���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
�������@�̕�������I���N�`�����݂̎��s�A�ܗ֊ϋq�Ŗ����A�錾�̘A���@7/12
���N�`�����݂̎��s�A�ܗ֊ϋq�̗L���Ŗ����A�ً}���Ԑ錾�̘A���ȂǁA���̋��S�͂͂��Ȃ�ቺ���Ă��Ă���悤���B����ɉ����āA���F�B�l���A�n���̎s���I�Ɏ鏑���l���ƁA�}���������Ă��Ȃ��g���u�����U�������B���łɐ����@�̕�����n�܂��Ă���悤���B
�u�����ɗ��ċ�C���ς��������������B�����ǂ��܂Ŏ��̂��A�S�z�ɂȂ��Ă����v
�����b���̂́A�����}�̂���t���o���҂��B�ǂ��������ƂȂ̂��H�@
�u�������ł����N�`�����݂ŗ����̂͊Ԉ���Ă��炸�A�����ɗ���������������Ƃ����w2��ڐڎ�40���x�ɂł��邾���������B�������Ƃ����_�����������킯�ł����A���������Ă��܂����B�ܗւɊϋq�����邩�ۂ��́A���{�g�D�ω���L�ϋq�ɂ�����肷���ĊJ��2�T�ԑO�ł���ƌ����Ƃ����h�^�o�^�ŁA�g�Ō�ɂ������h�Ɛ��������ً}���Ԑ錾�͘A���������Č��ʂ͂��������͖]�߂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�����̓W�]���`���Ȃ���ۂ�����܂��ˁv
���{���̗���Ō����Ȃ�A�X��N����˔@�ޏꂵ�ĉΒ��̌I���E���悤�ɏA�C�����|�X�g�łȂ��Ȃ������ꂪ���Ȃ����A�v7��ɂ���Ԍܗ֏o���������Ƃ��đI��ڐ��Ŏ咣�ł���̂��u�L�ϋq�v�������Ƃ������Ƃ��낤�B
����͂Ƃ������A�����Ɍ����Č����A���N�A�ً}���Ԑ錾�Ɓu�܂h�~���d�_�[�u�v���o�Ă��Ȃ������������������قǂ��B
���̈���ŁA�R���i��ܗ֊֘A�قǖڗ����Ȃ��ɂ��Ă��A���̋��S�͂������悤�ȏo�������������N�����Ă���B�Ⴆ�A�s�c�I����ɎR���ז��I�Έψ��������ށE�s�o�n��\���������Ƃɂ��āA�L�҂������������B
�u�R������͉�̐ȏ�A70�ň���ƌ����Ă��܂������A���N�A���������ł�����������ނ͂قڊ���H���ł����B������ƎR������͓��I�����ŝ፧�̊ԕ��B�R�����n�Ղ����邱�ƂɂȂ鎟�j�𐛎������Ŏ���Ĕ鏑�Ƃ��Čo����ς܂���Ȃǂ����Ă��܂����B�R������͑I�g�b�v�̃|�X�g�����U���I���܂ő�����ƌ����܂����A�����������̂��F�B�l���̈����Ƃ���B�����Ă��ӔC�����K�v�̂Ȃ��l���d��I���ɂ̓k������C�����ꂪ���ŁA����������ꂩ�˂܂���v
����c�����鏑���A�g������͖{�C�őI���ɏ��C�ł���̂��h�ƌ����l�͏��Ȃ��Ȃ��Ƃ����B�����ʂ萛�̋��S�͉͂��������̂悤�����A���l�s���I�Ɍ��E��4�I��_���ďo�n�̌����݂��Ƃ����j���[�X���܂��A�u������A���v�Ȃ́H�v�̐��������Ă���B
�u���l�s�ƌ����������A������̂��G���B���E�ɑ��Ĉ�U��������̂͐�����{�l�ŁA������̖��F�E�����؈�Y�����t�������C���ďo�n���邱�ƂŎ��߂悤�Ƃ����̂ɁA����g���ْ�h�Ɍ��E�����R�Ɣ�����|�����Ƃ����킯�ł��B���Ɍ��E���o�n���ނɒǂ����܂ꂽ��A�o�n���ď����؎������������肵�Ă��A�n������}�����Ȃ��l�����Ƃ̏������ǂ��S���Ă����̂��Ƃ����ᔻ�͂����Ƃ��܂Ƃ�������ł��傤�v(��)
�����āA�����̎鏑���l�����߂����Ă��������������B6���̊t�c�ŁA�鏑���̏����7�l����8�l�ɑ��₷���Ƃ����߂���ŁA��N���܂Ŕ鏑���߂Ă����V�c�͕������ĂыN�p����l���\���Ă���B
�������f�X�N�ɂ��ƁA�u�V�c����2006�N���琛����̔鏑�߁A���N9���̐�������������鏑���ɋN�p����܂������A�����Ȃ̎����������ƌ�シ��`�ō��N1��1���t�Ŏ��E���Ă��܂����B�������͐V�c���Ƌ��ɐ�����̊��[��������ɔ鏑���߂��l���ŁA�����̍��������ƌ����Ă��܂����A������Ƃ��Ă͕s���������B�V�c���͎��ɒɂ����Ƃ���������^�C�v�ŁA�gto do���|�[�g�h�����N�A�ɒ�o�����̂��a���Č�コ����ꂽ�ƌ����Ă������ŁA����Ăі߂���邱�ƂɂȂ����̂͂��Ȃ�ٗ�̂��Ƃł��v
����8���̉�ŁA�����s�ً̋}���Ԑ錾���Ԓ��ɊJ�Â��铌���ܗւɂ��āu���S���S�v���A�s�[���������A�J�Âɔ����ĐV�^�R���i�̐V�K�����҂������郊�X�N�⎩�g�̐ӔC�ɂ��Ă͌��y���Ȃ������B
�������ɖk���N�̋����������L�Ƃ̃g�b�v��k�����o�����A�c���ό��O���ȐR�c���̓c�C�b�^�[�ŁA�ƌ������ᔻ���Ă���B���ɂ��A�c�����ɂ��ʗ_�J�Ȃ͂��܂Ƃ����A����̋�������I�m�ɂƂ炦�����b�Z�[�W�ł͂Ȃ��������B
��قǂ̃f�X�N�ɐ������̍�������Ă��炤�ƁA�u�I���ɖ��ނ̋������ւ������{�������ł́A���N�Ɋ������Ă��Ȃ��Ă����Ă��悤�Ȍ�₪����A�w����3�x�Ȃǂƌ�����c�����������̈��ł��B���鑍�I���Ŕނ炪�����c��Ȃ����Ƃ������Ă��A���͂Ȗ�}�����Ȃ����肻��Ȃ�̐����͗��͂��ŁA�̂܂܍��N�����邱�Ƃ͉\�ł��傤�v
�����āA�u�����c�c�v�Ƃ��āA����������B
�u�N�������ĐV�^�R���i�����g��𐧌�ł��Ă��Ȃ�������A�t���̃X�L�����_������荹�����ꂽ�肷��A7���̎Q�@�I�O�Ɂg������ł͐킦�Ȃ��h�Ƃ�����C���o�Ă��āA�I���O�ɑސw���A�I���̊�Ƃ��Ċ��҂����l�����������ق̍��ɏA���Ƃ����V�i���I���\���ɂ���܂��B������͊��[��������ɂ́A�ǂ������Ή��Ή��A���������ΐl���o�J�ɂ����Ƃ��������Ȃ��Ή����J��Ԃ��A����ł���ǂ������Ă����̂ł����A�ɂȂ��Ă������g�[���ŁA�g���J�ɐ������Ȃ��h���������������E���Ă��܂��ˁB�ߘa��������Ƃ��H�c�̂������_�Ƃ���k��ŏ㋞���āc�c�Ƃ������G�s�\�[�h�Ŋl�����Ă����D���x�͂��łɔ����ꗎ���Ă��܂��܂����v
�����@�̕���͂��łɎn�܂����ƌ����邩������Ȃ��B�@
���ً}���Ԑ錾�u���ʂȂ��v56���A���{�̑Ή��u�]���v��28���c �@7/12
�����s�ɔ��߂��ꂽ4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ɂ��āA�ǔ��V���Ђ�9�`11���Ɏ��{�����S�����_�����ł́A���ʂ��^�⎋���鐺�����������B�錾�������g��h�~�Ɍ��ʂ�����Ɓu�v���v��38���ŁA�u�v��Ȃ��v��56������������B
�V�^�R���i�����邱��܂ł̐��{�̑Ή����u�]������v��28��(�O��6��4�`6������27��)�ŁA�����������������Ă���B���N�`���ڎ�����鐭�{�Ή��ɂ��Ă��u�]������v��36���ƒႭ�A�u�]�����Ȃ��v��59���ɏ�����B
��������4��ڋً}���Ԑ錾�@�}���Ȋ����g���a���Ђ����̌��O �@7/12
�����s��3��ڂً̋}���Ԑ錾����������Ă���킸��3�T�Ԃ�4��ڂ̐錾���o���ꂽ�w�i�ɂ́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����\���Ɍ���Ȃ��܂܁A1�T�ԓ�����̊����Ґ����O�̏T��1.2�{�O��ɂȂ��Ԃ�2�T�Ԉȏ㑱���A�}���Ȋg�傪���O�����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�A���T�ԂŁA���@�Ґ����m�ۂ��Ă���a�������Ĉ�Â��Ђ�������悤�Ȏ��Ԃ��z�肳��Ă��邱�Ƃ�����܂��B����܂ł̊����g��ł́A���⎩���̂�������߂锻�f���x�ꂽ�Ǝw�E����Ă��邱�Ƃ���A���{�̕��ȉ�͂��Ƃ�4���A�����g��̒����𑁊��ɑ����ċ�������u���邽�߂̎w�W�������܂����B�w�W�ł́A2�T�Ԃ���4�T�Ԃœs���{�����ő���m�ۂ���a���������ɒB���邱�Ƃ��z�肳���ꍇ�ɂ͋�������s���ׂ����Ƃ��Ă��āA��Ԃ̐l�o���������A�����҂̒���1�T�Ԃ̐����O�̏T��傫�����鎖�Ԃ�2�T�Ԉȏ㑱���ꍇ�A���ɑ����̑K�v���Ƃ��Ă��܂��B
����Ԃ̐l�o ���������Ő���
����ɏƂ炵�ē����s�̏�����ƁA�ɉ؊X�Ȃǂł̖�Ԃ̐l�o�́A�O��A4��25����3��ڂً̋}���Ԑ錾���o���ꂽ����͌���܂������A��^�A�x��������5�T�A���ŏ��X�ɑ������A6��21���̉�������ɂ�1�T�Ԃ�1.2�{�ƂȂ�A�����������������Ő��ڂ��Ă��܂��B
���O�T�Ƃ̊����Ґ��̔�r ����������
1�T�ԓ�����̊����Ґ���O�̏T�Ɣ�r����ƁA�����s�ł́A6�����ȍ~�͑O�̏T��1.2�{�O��ɂȂ��Ԃ�2�T�Ԉȏ㑱���A12���̎��_�ł�1.29�{�ƂȂ�ȂǑ����������ƂȂ��Ă��܂��B1���̊����Ґ��́A��3�g�̂��Ƃł�3����{��1�T�Ԃ̕��ς�250�l�܂ʼn�����܂������A��4�g�̂��Ƃł�6��15���ɁA1�T�Ԃ̕��ς�375�l�܂ł���������Ȃ���Ԃ��瑝���ɓ]���Ă���A�N�_�������A���̕��A�����g��̔g���傫���Ȃ邱�Ƃ����O����Ă��܂��B
���a����3�T�ԗ]��łЂ����̂�����
����ɁA�ً}���Ԑ錾�ȂNj����ł���Ȃ������ꍇ�A�a���͍�����3�T�ԗ]��łЂ������邨���ꂪ����Ƃ��鎎�Z���o����Ă��܂��B����7���Ɍ����J���Ȃ̐��Ɖ�ŋ��s��w�̌Ð��S�C����y�������������V�~�����[�V�����ł́A�����ł���Ȃ������ꍇ�A�����s�ł͍������{�ɂ�1���̊����Ґ���2000�l���A�������{�ɂ́A���@�Ґ����s���m�ۂ��Ă��邨�悻6000�̕a������Ƃ��Ă��܂��B���{�̕��ȉ�̔��g�Ή�́A4��ڂً̋}���Ԑ錾���o�����Ƃ����܂�������8���̉�ŁA�����͂̋����C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�u�f���^���v����s����3���ȏ���߂�Ɛ��肳��A�}���ɒu������肪�i��ł��邱�ƁA�����s�ł̓��N�`���ڎ킪�i�ލ���҂ŏd�ǎҐ��̑������}�����Ă������ŁA���N�`���ڎ킪�i��ł��Ȃ�40��A50��̏d�ǎҐ������Ƃ��t�̊����g��́u��4�g�v�̃s�[�N���������đ������Ă��邱�ƁA�����āA���ꂩ��4�A�x��ċx�݁A�����I�����s�b�N�Ȃǒn����z����l�̈ړ����}������^�C�~���O���W�����Ă��邱�ƂȂǁA���O�ޗ��������܂����B���̂����Łu���N�`���ڎ�̌��ʂ��������̂͂܂���ŁA���̂܂܊������L����A��Â��Ђ�������W�R���������v�Əq�ׂĊ�@���������܂����B
����4�g �l�H�ċz�푫��Ȃ��Ȃ����a�@
�V�^�R���i�̒����ǂ̊��҂�����Ă�����{���̕a�@��NHK�̎�ނɉ����A�����̑�4�g�̍ہA�ꎞ�A���@���҂�3����1�ɂ����邨�悻20�l�̏Ǐ������Đl�H�ċz��Ȃǂ�����Ȃ��Ȃ�A�g�p����Ώۂ����Ǐ�̏d�����҂ɍi�荞�܂�������Ȃ��ɒǂ����܂ꂽ�Ɩ��炩�ɂ��܂����B���E�����s�ɂ���s��������ÃZ���^�[�́A�V�^�R���i�E�C���X�̒����ǂ̊��҂𒆐S�ɂ���܂�700�l�ȏ�A����Ă��܂����B�a�@�ɂ��܂��Ƒ�4�g�ł͌ċz��Ԃ������������҂����X�Ɖ^�э��܂�A�ꎞ�A60������R���i�a����3����1�ɂ����鐔�̊��҂��l�H�ċz�킪�K�v�ȏ�ԂɂȂ����Ƃ������Ƃł��B�������A�d�NJ��҂ɑΉ�����ICU���W�����Î���4�������Ȃ��A�ق��̕a�@�ɓ]�@�����邱�Ƃ�����ŁA�a�@�͑Ώۂ̊��҂��i�荞�܂�������Ȃ��Ƃ��Đl�H�ċz����g����������グ�đΉ����܂����B��̓I�ɂ́A�_�f�}�X�N�ŏ]���̔{�̗ʂ̎_�f�����Ă������̎_�f�̒l��93���ȉ��̏ꍇ�ŁA���ċz�̏�Ԃ��������҂ɐl�H�ċz����g�����Ƃɂ��܂����B���̏�ŁA�a�@�̈�t�炪�c�_���Ă�莡�Ì��ʂ����҂ł���l���ΏۂƂȂ�悤�A75�Ζ����̐l��x�̋@�\�ɑ傫�Ȗ�肪�Ȃ����ȂǁA5�̎w�W��݂����Ƃ������Ƃł��B���������w�W��ڈ��ɁA���҂�Ƒ��Ƙb�������������ŁA�l�H�ċz������邩�ǂ������f�����Ƃ������Ƃł��B���ł͑�4�g�̍ہA�d�Ǖa���̉^�p����100������ȂLj�Â��j�]�̊�@�ɒ��ʂ��܂����B�����������ŁA����ꂽ�l�H�ċz��Ȃǂ��ǂ̊��҂ɗD�悵�Ďg���̂��A���ꂼ��̈�Ë@�ւɈς˂��Ă���̂�����ł��B
�s��������ÃZ���^�[�̒҈䐳�F�@���͏d�lj����Ă��l�H�ċz�����]���Ȃ����҂����Č��ʓI�ɁA��������]�����̂ɂł��Ȃ��������҂͂��Ȃ������Ƃ��������Łu���ґ�����]�����Ƃ͂����A�ӂ���ł���ΐl�H�ċz��������Ԃ̐l�����Ȃ��܂ܖS���Ȃ��Ă����ɁA�g������X�^�b�t�͔��ɂ炢�v���������B����Ɋ��҂������Ă���ΗD�悷�ׂ��l�ɂ�����ꂸ���S����P�[�X���o�Ă�����������Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B
���a�@�̑Ή� �ڍ�
���E�����s�̎s��������ÃZ���^�[�͒����ǂ̊��҂𒆐S�Ɏ���Ă��܂����A�����̑�4�g�ł́A���łɌċz��Ԃ������������҂����X�Ɖ^�э��܂�Ă��܂����B�a�@�ł́A�]���́A�_�f��5���b�g�����^���Ă������̎_�f�̒l��93���ȉ��̏ꍇ�ɐl�H�ċz�������Ή����Ƃ��Ă��܂����B�������A��4�g�ł͉^�э��܂ꂽ���_�Ŏ_�f�̓��^�ʂ�5���b�g�����Ă��銳�҂������A�]���̊�ʼn^�p����ƁA���@���҂�3����1�ɂ����邨�悻20�l�ɐl�H�ċz�킪�K�v�ƂȂ�܂��B�l�H�ċz����������҂́A��̓��^���Ԃ̊ώ@�Ȃ�24���ԑ̐��̍��x�ȊǗ������������AICU���W�����Î��ł̎��Â��K�v�ł����A�����ǂ̊��҂�����Ă������̕a�@�ł́A�R���i�̏d�NJ��җp�Ɋm�ۂł���ICU��4���ŁA����ɁA�@�ނ�X�^�b�t�����肸�ɑΉ��ł��Ȃ��ɒ��ʂ��܂����B���{���̂ق��̕a�@�ł��A�d�Ǖa�����s�����A�]�@�����邱�Ƃ�������A�a�@�͐l�H�ċz����g�����҂��i�荞�܂�������Ȃ��Ƃ��āA�]���̊�̔{�́A10���b�g���̎_�f�𓊗^���Ă������̎_�f�̒l��93���ȉ��̊��҂�ΏۂƂ���悤�A��������グ�܂����B����ɕa�@�́A��莡�Ì��ʂ����҂ł���l���ΏۂƂȂ�悤�A75�Ζ����̐l��A�x�̋@�\�ɑ傫�Ȗ�肪�Ȃ����A����ɓ��퐶���̓���Ɏx�Ⴊ�Ȃ����A�Ȃǐl�H�ċz������邩�ǂ����̔��f��5�̎w�W��݂��܂����B�a�@�̂���܂ł̎��Â̌o���ł͂��̎w�W�ɓ��Ă͂܂銳�҂͐l�H�ċz������Ă��A���ǂ��ł����ɐQ������ɂȂ�ȂǁA���Ì�̌o�߂��ǂ��Ȃ��\���������Ƃ������Ƃł��B�a�@�ł́A���҂�Ƒ��ɐ������Ċ�]�����A�\���ɘb�������������ŁA�l�H�ċz������邩�ǂ������f�����Ƃ������Ƃł��B�a�@�ɂ��܂��ƁA�l�H�ċz��̑�������]���Ȃ��������҂ɂ́A����ɁA���҂̕@�ɑ������đ�ʂ̎_�f�𑗂�u�l�[�U���n�C�t���[�v�ƌĂ�����ȑ��u���g�������Â��s�����Ƃ������Ƃł��B�l�H�ċz������~�����͉�����܂����A�C�Ǒ}�ǂ����Ȃ����ߑ������Ă��Ă���b���ł���ق��AICU�ł͂Ȃ��ʏ�̕a���Ŏ��Â�����Ƃ������Ƃł��B
�����B�ł� �g�N��D����h
�V�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�A�d�NJ��҂����X�ɕa�@�ɔ��������ɂȂ����ꍇ�A���@�������D��x���ǂ̂悤�Ɍ��߂�ׂ����A�e���ł͔Y�݂�����Ȃ��������߂��^�p���s���Ă��܂��B���ɂ́A���Â�����t����\�����������҂�Ⴂ���҂Ɉ�Î�����D��I�ɔz������ׂ����Ƃ����l�����������Ă���Ƃ��������܂��B����1���X�E�F�[�f���ŁA�����J���ȏo�g��2013�N�܂ŃX�E�F�[�f����g�߂��n糖F������ɂ��܂��ƁA��s�X�g�b�N�z�����ōő�̕a�@�u�J�������X�J��w�a�@�v�ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊������L���钆�ŁAICU���W�����Î��Ŏ���銳�҂�80�Ζ����������ŁA70��ł͋@�\�s�S�̑��킪1�ȉ��A60��ł�2�ȉ��̊��҂Ɍ����A������Ȃ��ꍇ�͐ϋɓI�Ȏ��Â͍s�킸�A�ɂ݂�ꂵ�������P�A���s���Ă����Ƃ������Ƃł��B�܂��A�C�M���X�ł͋��N�A�e���Ŋ����g�傪�N���������ANICE�������ی���Ì��������K�C�h���C�������肵�A���a�̗L�����̕K�v�x�Ȃǂɉ����Ċ��҂̏�Ԃ�9�i�K�ŕ]������w�W���g���āA�W�����Â���D�揇�ʂ����߂邱�Ƃ𐄏����܂����B���̒��ł́A�s���ւ̎x���₳��ɉ���K�v�Ȋ��҂ł́A�~���~�}��Â��s�������b�g�����邩�͕s�m�����Ƃ��܂����B�������A���@�̗D��x�Ȃǂ̊�ɏڂ������É���w��w���̊��J�땶�����͂��̎w�W�́A���҂��~���ł���\���Ƃ͊W�����A���̎w�W�݂̂��g�������f�ɂ͐T�d�ɂȂ�ׂ��Ƃ����ᔻ���������Ƃ������Ƃł��B���݂̃K�C�h���C���ł͂����������e����菜����Ă��܂��B
�����Ɓu�N��ɂ���ėD�揇�� ���v
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ň�Â��Ђ����������̓��@�⎡�Â̍ۂ̗D��x�ɂ��ē��{�����ł������̊w��l�����������Ă��܂����A�N��ŕ�����l�����͍̗p���Ă��܂���B���{�~�}��w��Ȃǂ�6���l�����������A�}���ɏd�lj�����ً}���̍������҂������������@�ł���悤���҂̏�Ԃ��ً}���ɉ�����4�ɕ����Č��t�������w�I�Ȑf�f�̌��ʂ����Ƃɔ��肷��Ƃ��Ă��܂��B�܂��A���{�V�N��w����N8���Ɏ������ł͍���҂��l���̍ŏI�i�K�܂Ŗ]�ވ�Â�����悤�ɂ��ׂ��ŁA�N�������ɐl�H�ċz��̑����Ȃǎ��Â��s�����ǂ������߂邱�Ƃ͔�����ׂ����Ƃ��Ă��܂��B���̒��Ƃ�܂Ƃ߂����É���w��w���̘V�N���Ȃ̊��J�땶�����́u�w��Ƃ��Ă͔N��ɂ���ėD�揇�ʂ����߂邱�Ƃɂ͖��m�ɔ��̗��ꂾ�v�Ƙb���Ă��܂��B�̒��ł́A��w�I�Ɏ��Â̌��ʂ������܂�Ȃ��ꍇ�́A�l�H�ċz��̎��Î��̂��傫�ȕ��S�ɂȂ邱�Ƃ����邽�߁A�s��Ȃ����Ƃ�����Ƃ��Ă��܂����A����ȊO�̏ꍇ�́A�{�l����]���Ȃ�����A�l�H�ċz��̑����Ȃǂ̎��Â��J�n���Č��ʂ����邩�ǂ����m�F���A���ʂ������܂�Ȃ��ꍇ�Ɍ����Ď��Â������T���邱�Ƃ��������Ƃ��Ă��܂��B�����A���{�̈�Ì���ł͂�������n�߂����Â𒆒f���邱�Ƃ͓�����߁A���J�����͌ċz��̑������K�v�ɂȂ�ۂ⎡�Â̌��ʂ������߂Ȃ��ꍇ�ɂǂ̂悤�Ȉ�Â�P�A��]�ނ����O�ɉƑ����t�Ƙb�������Ă����u�A�h�o���X�E�P�A�E�v�����j���O�v���s���ׂ����Ǝw�E���Ă��܂��B���J�����́u�V�^�R���i�ł͉Ƒ�������u������ċ}���ɏǏ������A�����Ƃ����ԂɈӎv�a�ʂł��Ȃ��Ȃ�ꍇ������B40���50��̔�r�I�Ⴂ����ł��ň��̏ꍇ�͎��Ɏ��銴���ǂ��Ƃ����F���������Ęb�������Ă����ƁA���Õ��j����@�̔��f������ۂɃX���[�Y�Ȉӎv����ɂȂ���B���ЉƑ��₩�������Ƙb�������Ă��炢�����v�Ƙb���Ă��܂��B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���ɉ؊X�̐l�o �����X���@4�x�ځg�ً}���Ԑ錾�h12����̓��� �@7/13
4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o���ꂽ�����s����12����̔ɉ؊X�̐l�o�́A1�T�ԑO�Ɣ�ׂāA�����̒n�_�Ō������Ă����B
�\�t�g�o���N�̎q��ЁuAgoop�v�̃f�[�^�ɂ��ƁA12���ߌ�8�����_�̓s���̐l�o�́A1�T�ԑO�Ɣ�ׂāA�a�J�Z���^�[�X��11.9%�������Ă����B
�܂��A�V�h�E�̕��꒬�ł�5.2%�����Ă����ق��A�����18.0%�A�V����2.2%�A�ԍ��5.9%�A���ꂼ�ꌸ�����Ă����B
����A�Z�{��16.8%�������Ă������A�s���̖�̔ɉ؊X�̐l�o�́A1�T�ԑO�Ɣ�ׂāA�����̒n�_�Ō����X���������B
��4��ڂ̐錾�������҂́u2�T�Ԑ�ȍ~�̌����͌����Ȃ��\�����v�@7/13
�e���r�����̋ʐ�O����13���A�R�����e�[�^�[�߂铯�njn�u�H���T�ꃂ�[�j���O�V���[�v(���`���j�E�ߑO8��)�ɃX�^�W�I���o�������B
�ԑg�ł́A12�����瓌���s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����o���ꂽ���Ƃ���W�����B�X�^�W�I�ł́A2��ڂ�3��ڂً̋}���Ԑ錾���o����̐l�o�̕ω����Љ�B�a�J�Z���^�[�X�A�V�h�w��2��ځA3��ڂ͌����������A����́A�a�J��0�E6�p�[�Z���g�A�V�h��0�E4�p�[�Z���g���������Ƃ����������B
�����������ʂɋʐ쎁�́u�����ė~�����ȂƎv������ł����v�Ƃ�����Łu�ς��Ȃ����Ă��ƂɂȂ�ƁA2�T�Ԑ�ȍ~�̌����͌����Ȃ��\��������܂���ˁA�����҂́v�ƈĂ��Ă����B
���u��ՓI�ɓd�Ԃ���l���������v�B�����s�̉p��c�C�[�g�ɔᔻ�������폜�@7/13
�����s�̌���Twitter�ɔᔻ���������ł���B�ً}���Ԑ錾�ŁA�����d�Ԃ���u��ՓI�ɐl���������v�Ƃ������e�𓊍e�����Ƃ���u�R���v�ȂǂƎw�E����Ă���̂��B
���̃c�C�[�g�́A�����s�̉p��A�J�E���g�uTokyo Gov�v��7��13���ɓ��e�������́B�s���^�c�����M�T�C�g�uTOKYO UPDATES�v��5��14���Ɍf�ڂ����L�����Љ����̂ŁA�p��Łu�����̃��b�V���E�A���[�͐��E�I�ɗL���ł����ACOVID-19�ɂ��ً}���Ԑ錾���Ŋ�ՓI�Ɏp���������v�ƙꂩ��Ă����B�����l�߂̖����d�ԂƁA2020�N4���ɎB�e���ꂽ�Ƃ���K�����Ƃ����d�ԓ��̎ʐ^�����ׂ���A�X���C�h�V���[�`���̓�����Y�t����Ă����B
���̃c�C�[�g�����e�����ƁA�ᔻ�����������B�����s���ŎB�����Ƃ݂���w��d�ԓ��̎ʐ^�ƂƂ��ɁA�p��Łu�R���v�Ǝw�E������̂�A�u�������ˁA�������ˁv�Ɣ����R�����g���������B
���{��ł��A�u�ʋΎ��ԑт͓d�ԍ���ł��܂��v�u���ʂɖ������v�Ƃ������w�E����ꂽ�B
�ᔻ�����Ă���c�C�[�g�����A�����N��̋L���͈Ⴄ���e�ƂȂ��Ă���B�`���́A�u�����������b�V��������ڂ̓�����ɂ��āA�����l�͋������v�ȂǂƋً}���Ԑ錾�ŒʋΎ��ԑт̌��i���l�ς�肵���Ƃ��Ă��邪�A��i�Łu�����̐l���͖߂�n�߂Ă���B�ً}���Ԑ錾�̔��߉��ł��A�ʋΓd�Ԃ͍Ăэ��݂����Ă���v�Ǝw�E����B
�����āA�V�^�R���i�����������ɁA�ʋ�d���̂�������ς��\���ƁA�R���i�O�ɖ߂�P�[�X�������A�u�O�i�ƌ�ނ��镪��_�A������͂ǂ��ɂ���̂��\�\�B�c�O�Ȃ���A���̓�����M�҂͎������킹�Ă��Ȃ��v�Ȃǂƒ��߂�������e���B
�uTokyo Gov�v�̃c�C�[�g�́A���̋L������u���b�V�����������v�Ƃ���O�������݂̂����o���ďЉ�����߁A�u�R�����Ă���v�Ƒ�����ꂽ�\��������B
���̃c�C�[�g��13���[���܂łɍ폜���ꂽ�B�����s���������ۂ̒S���҂́u2020�N4���̎ʐ^���Ɩ��L���Ă������A���A�R����������܂ŋĂ���Ƃ�����ۂ�^�����˂Ȃ����e�������v�Ƙb���Ă���B�폜�̌o�܂ɂ��Ă�Twitter�Ő�������Ƃ����B
���Ȃ݂ɁA�s���̓d�Ԃ̍��G���́A���ۂǂ̒��x�ω����Ă���̂��낤���B ���y��ʏȓS���ǂ��u�s�s�S���̍��G���������ʁv�����\���Ă���B
�����Ō��\����Ă��鍬�G���Ƃ́A�e�ԗ��̒���ɑ��A�ǂꂭ�炢��q�����邩���w���B100%�Łu�����ԁv�ƂȂ�A���Ȃɂ����A�݊v�ɂ��܂邩�A�h�A�t�߂̒��ɂ��܂邱�Ƃ��ł����Ԃ��B
����ɂ��Ɨߘa2�N�x(2020�N4���`2021�N3����)�̎��т́A�����Ƃ����ݍ���1���Ԃ̕��ςŁA��������107%�B���̑O�N�x��163%������m���ɍ��G�x�͌����Ă���B
�܂��A�e�����[�N�⎞���o���Ăт�������O�̍��G�x��100�Ƃ����ꍇ�A�L���ŏЉ��Ă���2020�N4���A�܂菉�߂Ăً̋}���Ԑ錾���o���ꂽ����́A��s���ł�30��܂ő啝�ɉ������Ă���B
�ł͒��߂͂ǂ����B�ً}���Ԑ錾���ɂ�����2021�N6���̎��тł́A2019�N6����1�T�̍����100�Ƃ����ꍇ�A�����w(JR�����{)��49�A���{���w(�������g��)��55�A��蒬�w(�����s��ʋ�)��58�ƂȂ��Ă���B�R���i�O�̔�������⑽���Ƃ�����������B
���y���u�q���v�X�����c�@�����g�ً}���Ԑ錾�h�ŃL�����Z�������@7/13
�����҂��}�����Ă��铌���s�ɂ́A12���A4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o����܂����B�q�����߂�������y���̃z�e���ł́A���łɗ\��̃L�����Z�����o�Ă��āA����̉e�������O���Ă��܂��B
�������瑽���̊ό��q���K���y���B���l�̔����⍂��҂𒆐S�Ƀ��N�`���ڎ킪�i���Ƃ�����A�q���͉X���ł����B
�������A�Ăѓ����s�Ŋ����҂������B12�����痈��22���܂ŋً}���Ԑ錾���o�܂����B
��������u�����ł����Ɓw���l�����x�������̂ŁA�����������t���b�V�����悤�Ɓv�u(�錾���ɗ��s)������Ɛ\����Ȃ����������邩�ȁc�v
������̃z�e�����Ă̊ό��V�[�Y���̗\��͍D���ŁA�R���i�����g��O�̂��ƂƂ��̐����܂Ŗ߂��Ă��܂����B�������A�錾���o�����Ƃ�70���߂��L�����Z���ƂȂ�܂����B
���y���z�e�����H�m�X�E��؎В��u��Ԃ̔ɖZ�����}����Ƃ��ɋً}���Ԑ錾���o�Ă��܂������ƁB�Ȃ�ƂȂ��\���͂��Ă��������Ɏc�O�v
�y��ّg���͉ẴV�[�Y���Ɉ��S���ċq�ɗ��Ă��炨���ƁA�挎����]�ƈ���ΏۂɃ��N�`���̐E��ڎ��i�߂Ă��������ɗ��_�͑傫���悤�ł��B
��؎В��u(���S���ċq��)�}������Ԑ���i�߂��ɂ��ւ�炸�A���q�������Ă��܂��Ǝc�O�Ȏv���B���������Ґ��������āA����ł������ً}���Ԑ錾���O��邱�Ƃ��F���Ă���v
���ً}���Ԑ錾�C������J�݂𒆎~ ��[���@��t���@7/13
��[���s��12���A���Ă̊C������̊J�݂𒆎~���邱�Ƃ\�����B�����s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����߂����ȂǁA�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��g�債�Ă��钆�A�C������ɂ͌����O���瑽���̗��K�҂��\�z����A���S�E���S�ȉ^�c������Ɣ��f�����B
��N���s�ł́A�s��10�����ɊC��������J�݁B���ẮA�x�Y�n��̑��c�ǖk�l�A�L��������8�����ŊJ�݂���\�肾�����B
�J�݂ɔ����A�����h�~��K�C�h���C�������肵�A�C������̕����݂��Ă���A���̂����́u�����s���t���ɋً}���Ԑ錾�����߂����ꍇ�v�ɓ��Ă͂܂������߁A�����������ʁA�J�ݒ��~�����߂��B
�C�����ꂪ�s�J�݂ƂȂ������߁A�C�݂ł͖��S�ȊĎ��̐�����ꂸ�A���S���m�ۂł��Ȃ��Ƃ��āA�S���̓��s�ό��v�����[�V�����ۂł́u�V�j�͍T���Ă��������v�ƌĂъ|���Ă���B
�Έ�T�s���́u���N�����̊F���܂Ɋy����ł��������Ă���C�����̂��߁A��a�̌��f�ƂȂ�܂����A���Ƃ����������������܂��悤�A���肢���܂��v�ƃR�����g���Ă���B
��������4��ڂ́u�ً}���Ԑ錾�v�@���H�X�̎�ޒA6�s�{���̃��[���@7/13
1�s3���𒆐S�ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����Ăъg�債�Ă���B���{��7��12���A������4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�o�B�錾���ɂ��铌���Ɖ���̈��H�X�ɂ��ẮA���Z�c�Ƃɉ����A�ꗥ�Ŏ�ޒ̒�~���v������Ă���B�܂h�~���d�_�[�u(�ȉ��A�u�܂h�~�[�u�v)�ɂ��ẮA��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����8��22���܂ʼn����B�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���́A11���ʼn����ƂȂ����B
�������͂܂h�~�[�u���������]�A�ً}���Ԑ錾���߂�
11���������ƂȂ��Ă��������̂܂h�~�[�u�́A�����A��s���̊����g�哙��w�i�ɉ�������ƌ����Ă������A�ً}���Ԑ錾�̔��߂ւƕ��j��ς����B�s���ł�1���̐V�K�����Ґ���900�l��������o�Ă��Ă���A���~�x�݂̈ړ��Ȃǂɂ��S���I�Ȋg������O���āA�܂h�~�[�u����ً}���Ԑ錾�Ɉڍs���邱�ƂɂȂ����B�����Ґ��������X���ɂ����s����3���Ƒ��ɂ��Ă��A���������܂h�~�[�u���K�p�����B����́A���{�ɂ܂h�~�[�u�ւ̈ڍs��v�����Ă������̂́A��Ò̐����̏���ً}���Ԑ錾����������`�ƂȂ����B�����͂������8��22���܂łƂȂ��Ă���A�����ܗ֊J�Ê��Ԃ₨�~�Ȃǂ��܂ށB���N�`���̌��ʂ�a���̏ɂ���ẮA�O�|������������Ƃ��Ă��邪�A���H�X�ɂ͈����������Z�c�Ƃ��ޒ̐������v������Ă���A���̉e���͌v��m��Ȃ��B����A�ȑO����x���̒x�ꂪ�w�E����Ă�����H�X�ւ̋��͋��Ɋւ��āA���{��7��12������̎�ޒ�~�v���ɋ��͂�����H�X�Ɍ���A7���ȍ~���̋��͋��̎��O�x���������{����Ɣ��\�B�u�ߋ��ɋ��͋����������Ǝ҂́A���̒�o�݂̂Łw��n���x���s���v�Ƃ��Ă��邪�A�\����t�����Ȃǂ͌����_�Ŗ��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
���ً}���Ԑ錾�E�܂h�~�[�u���̎�ޒ��[���́H
���{�́A�ً}���Ԑ錾��܂h�~�[�u���K�p�����n��̈��H�X�ɑ��A20���܂ł̎��Z�c�Ƃ�v�����Ă���B��ޒɂ��ẮA�����A����͈ꗥ��~�B�܂h�~�[�u�̑Ώےn��ɂ��Ă������A��ޒ͒�~�����A�m���̔��f�ɂ����v���������ꍇ�́A19���܂Œ\�ƂȂ�B�ً}���Ԑ錾�y�т܂h�~�[�u���K�p����Ă���n��̎�ޒ��j�́A���L�̒ʂ肾�B
�������s
�E�E�E7��11���܂ł̂܂h�~�[�u���Ԓ��́A���������̏������������H�X�Ɍ���A2�l�ȓ��E90���ȓ��ł���Ύ�ނ̒��\�������B�������A�ً}���Ԑ錾���Ԓ��̌��݂́A��ޒ��ꗥ�Œ�~����悤�v������Ă���B�E�E�E�Ώےn��F�s���S��@/�@��ޒF��~
�����ꌧ
�E�E�E�ً}���Ԑ錾����������鉫�ꌧ�ł́A����������ޒ���~�ƂȂ�B�E�E�E�Ώےn��F�����S��@/�@��ޒF��~
����ʌ�
�E�E�E12���ȍ~����ޒ̗v���ɕύX�͂Ȃ��A�����������̔F���Ă���X�܂ɂ̂��������j���B�E�E�E�܂h�~�[�u�Ώےn��F�������s�E����s�@/�@��ޒF�u�ʂ̍��w�V���������l���x���S�錾���H�X�{(�v���X)�v�F�؍ς݂̓X�܂́A11���`19���܂Ŏ�ނ̒��\�B1�l�A�܂��͓����Ƒ��݂̂̃O���[�v�Ɍ���B
����t��
�E�E�E�܂h�~�[�u�̉����O��Ŏ�ނ̒v���ɕω��͂Ȃ����A12���ȍ~�A�܂h�~�[�u�̓K�p�n�悪�ς��B�E�E�E�܂h�~�[�u�Ώےn��F��t�s�E�s��s�E�D���s�E���ˎs�E���c�s�E�K�u��s�E���s�E�s���s�E�Y���s�@/�@��ޒF11���`19���܂ŁB1�O���[�v2�l�E�؍ݎ���90���ȓ��Ɍ���B
���_�ސ쌧
�E�E�E12���ȍ~�A�܂h�~�[�u�̑Ώےn�悪�k�������ƂƂ��ɁA��ޒ̏����Ƃ��āu�}�X�N���H���{�X�v�̔F�������B�E�E�E�܂h�~�[�u�Ώےn��F���l�s�E���s�E���͌��s�E���؎s�@/�@ ��ޒF�u�}�X�N���H���{�X�v�̔F���Ă���X�܂Ɍ���A11���`19���܂Œ\�B�؍ݎ���90���ȓ��E1�O���[�v4�l�ȓ��A�܂��͓����Ƒ��ł��邱�Ƃ������B
�����{
�E�E�E�܂h�~�[�u���K�p�������ɕύX�͂Ȃ����A��ނ̒������u2�l�ȓ��v����u4�l�ȓ��v�ւƊɘa�����B�E�E�E�܂h�~�[�u�Ώےn��F���s�E��s�E�ݘa�c�s�Ȃ�33�s�@/�@��ޒF�������l�����A�S�[���h�X�e�b�J�[�X�e�b�J�[�F�ؓX�ł́A11���`19���܂Œ\�B����O���[�v����4�l�ȓ�(�����Ƒ��͏���)�Ɍ���B
�����ꌧ�������فE���p�ق��ĊJ�@�ً}���Ԑ錾���������O��@7/13
�ً}���Ԑ錾�ɔ����x�ق��Ă������������ٔ��p�ق����̐V���ȑΏ����j�܂�13������ĊJ�����B
�ߔe�s�̌��������فE���p��5���ɋً}���Ԑ錾���o����Ĉȍ~�A�x�ق������Ă��܂�����12������錾���ĉ������ꂽ�̂ɔ������肳�ꂽ���̑Ώ����j�Ɋ�Â�13������ĊJ���ꂽ�B
�ĊJ�ɍ��킹���W���n�܂�x�g�i���푈�̏]�R��ނŒm����ΐ앶�m����̎ʐ^�W�͍�����ꂽ�x�g�i���̏Z���������f���l�q�Ȃǐ푈�Ɋ������܂��c������`���Ă���B
���������فE���p�قł͊�������u���Ȃ����i�ɐG���@���݂��Ă��������Ƃ��Ă���B
���錾�Ȃǁg�w�W�̌��������h�@�V�K�����Ґ��͏d�����ׂ��łȂ��@�����s�@7/13
���������Ŋ����̃��o�E���h�̒�������Ȃ��A�����s�̍����s���́A�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ߂���ꍇ�̎w�W�ɂ��Č������K�v������Ǝ咣���܂����B
�����s���u����܂ł̂悤�ȐV�K�z���҂̐��ł͂Ȃ��A�a���̉ғ�����d�Ǖa���̉ғ����Ƃ�����Õ���ɂȂ��肩�˂Ȃ������̂j�o�h(�w�W)���d�����Ă����v
�����s����13���̒���ŁA�ً}���Ԑ錾�Ȃǎ����̐������v��������ۂ̎w�W�ɂ��āA1��������̐V�K�����Ґ��͏d�����ׂ��ł͂Ȃ��Əq�ׂ܂����B
���̗��R�Ƃ��āA�s���̍���҂̔����ɂ������18���l��2��ڂ̃��N�`���ڎ���I����ȂǍ���҂ւ̃��N�`���ڎ킪�i���ƂŁA�����҂������Ă������ɂ͕a���g�p���̑����ȂǂɂȂ���Ȃ��Ƃ̍l�����q�ׂ܂����B
������1��������̊����҂�12���܂�5���A���őO�̏T�������Ă��܂����A���ɂ��܂��ƁA7���̊����҂̂���60��ȏオ��߂銄���͈ȑO�ɔ�����X���ɂ���Ƃ������Ƃł��B
���u���{�v���ɏ]���̂́A���������Ȃ����v�@��̓X������ �@7/13
�l�x�ڂƂȂ�V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾���s���ɔ��߂��ꂽ�\����A�����n��̈��H�X�X�ł͎�ޒ̒�~�⎞�Z�c�Ƃ̗v���ɉ����Ȃ��X���ڗ����n�߂��B������\����܂ł̐錾�ʼnċx�ݒ��̏W�q�������߂Ȃ��Ȃ����ό��n����́A���N�`���ڎ킪�i��Ŋό��q���߂邱�Ƃ��F�鐺���R�ꂽ�B
�u���{�̗v���ɏ]���̂͂������������Ȃ����v
�i�q�g�ˎ��w�߂��́u�n���j�J�����v(������s)�ŕ����̋��������o�c����j���́A����͑唼�̓X�Œʏ�c�Ƃ𑱂��邱�Ƃɂ����B�O��̐錾���Ŏ��̒𑱂����X�ɋq������Ă���u�v���ɉ����Ă��Ă͂���n�ɂȂ�v�Ɣ��f�����B�u�g�ˎ��ŎO�A�l���̓X�͗v�������ۂ���̂ł́v�Ƃ݂�B
����A���s�̋g�ˎ��ʂ艈���Łu�H���Ƃ����J���V�}�v���o�c���鍲���F�ꂳ��(68)�́A��ޒ��~�ƌߌ㔪���܂ł̎��Z�c�Ƃɉ�����B����グ�̓R���i�O�̖������u���͋����܂߂�Ή��Ƃ����ꂻ���v�Ƙb�����B�����Ɂu�������͏]���Ȃ��Ƃ������H�X�������B���肬��̏�ԂȂ�ł��v�Ƒi����B
����s�̋������u�L�q�̂��݁@����{�X�v���v���ɏ]�����A�X���̑吼�L�I����(32)�́u����グ�͑S�R�v�Ɩ������B�v���ɉ����Ȃ��X�ɂ��u���ꂼ�ꎖ�����B�d�����Ȃ��v�Ɨ����������B��œP�����A�v�������������Z�@�ւ��瓭���|���Ă��炤�Ƃ��������N���o�ύĐ��S�����̔����ɂ́u�����߂ł���ˁv�ƕ������B
�����q�s�̍����R�ł́A�o�R���y���ސl�̎p�͂܂�ŁA�ՎU�Ƃ��Ă����B�s���ōł��W���̍����r�A�K�[�f���u�����R�r�A�}�E���g�v�́A�\��������ޒ��~�B�R���߂��Łu��܂т������v���o�c���鏼�����Y����(71)�́u���N�`�����s���n���ď\�ꌎ����ɂ͉��Ƃ��l�o���߂��Ă��ꂽ��v�Ƙb�����B
�~�s��x�R�̕�����Ԑ_�Ћ߂��ŐH���Ɠy�Y���̔��́u����X�v���c�ޔn��ӍƂ���(67)�́u�ċx�݂͈�Ԃ̏������ꎞ�Ȃ̂Ŏc�O���v�ƌ��𗎂Ƃ����B���������x�R���X�g���́u�X�̗d���v�ƌĂ�郌���Q�V���E�}�̉Ԃ������ƂȂ鎵��〜�㌎�ɗ\�肵�Ă����e��C�x���g��錾���Ԓ����ׂĒ��~�����B�@
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���ً}���Ԑ錾2���ځ@13���̓s���̐l�o�͌����@7/14
4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ɓ����Ă���2���ڂ�13����A�����E�Z�{�ł͑O�̏T�ɔ�ׂ�3���قǐl�o�������Ă��܂����B
�g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^�ɂ��܂��ƁA�ߌ�9����̓����s���̐l�o�ً͋}���Ԑ錾���o�����O��1�T�ԑO�Ɣ�ׂďa�J�Z���^�[�X��10���A�Z�{��27���A�V����25���A�̕��꒬��7�������Ă��܂����B
�ԍ�ł�5�������Ă��āA����ł͂قډ����ł����B
�ߌ�3����̐l�o��1�T�ԑO�ɔ�ׂĘZ�{��18���A�V����14���A�̕��꒬��17�������Ă��܂����B
�a�J�Z���^�[�X��ԍ�A����ł͂قډ����ł����B
�����{������̎����~��̈˗��P��B�g�����h�Ŏ������M���A�錾�̎������@7/14
������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����o����钆�A���t���[���R���i��Ƃ��ďo����2�̢�˗���ɔᔻ���������A������������œP��ɒǂ����܂ꂽ�B��5�g�̓������x����������A����l��⢗v������Ăт����鐭�{�ւ̐M������w�h�炮���ԂɊׂ��Ă���B������̢�˗�����ً}���Ԑ錾�E�܂h�~���d�_�[�u�̉��ŁA��ނ̒𑱂�����H�X���߂�����̂������B�\���ȍ����x����Ȃ��v���ł���A�W�c�̂͢�����ł��Ȃ���ƍR�c�B�^�}��������ᔻ�����o�����B��}����͖@�I�����ɋ���Ȃ�����������ͣ�ɓ�����̂ł͂Ƃ̎w�E���o�Ă���B
����@�I�����Ȃ���w�E�A���t���[��2�̢�˗���Ƃ́c�c
��1�@����Z�@�ւ�����H�X�֏���̓��������𣁨1���œP��
2�̈˗��̓��e�ɂ��āA�܂��͌o�܂��������Ă������B
1�ڂ�7��8���t���ŁA���o���͐����S���������ǂ�����t���[�̐V�^�R���i�����Ǒ����i��(�R���i��)�B
��ނ̒𑱂�����H�X�ɑ��A���H�X�ɗZ����������Z�@�ւ����ޒ̒�~�v�������炷��悤���������Ă��炢�����Ɗe�{�Ȓ�������Z�@�ւɈ˗�����悤���t���[�R���i�����߂���e�������B
���̕��j�́A�����S������8���̋L�҉�ŕ\������������Z�@�ւɂ��D�z�I�n�ʂ̗��p�ɂȂ�̂łͣ�ȂǁA�^��}����ᔻ�����o�����B
9���ߑO�A���`�̎͐����S�����̕��j�\���ɂ��Ģ�ǂ��������������ꂽ�����m���Ă��Ȃ���Əq�ׂĂ������A�ߌ�ɂȂ��ĉ������M���[����������j�P���\�������B
���������o�܂��碐��{���ł́g�l�߁h���Ȃ���Ȃ��܂܁A�����S�������ƒf�ŕ\���������̂łͣ�Ƃ����������L���������A��������}�̎R���u�����O�@�c����12���A���t���[�̈˗����������\�B���t���[�̃R���i�����ł͂Ȃ����Z���A�����ȁA�o�ώY�ƏȂƂ����O�⒲���⌟�������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B
��������}�̋ʖؗY��Y�}��͢�{���������Ƃ�������ׂ����{�n���Z�@�ւ��g���āA�����̋����ƒ��ߕt����v�����悤�Ƃ��Ă����킯���B�������@�I�����͂Ȃ���Ɣᔻ���Ă���B
�u�Ռ��I�Ȃ̂́A���Z���ēǂ����łȂ��A�����Ȃ̐�����Z�ۂ�o�Y�Ȃ̒�����ƒ����Z�ۂ��˗��̖����l�Ƃ��ē����Ă��邱�ƁB�܂�A�{���������Ƃ�������ׂ����{�n���Z�@�ւ��g���āA�����̋����ƒ��ߕt����v�����悤�Ƃ��Ă����킯���B�������@�I�����͂Ȃ��̂ɁB�ǂ������Ă���B�v— �ʖؗY��Y(��������}��\)
��2�@���̋Ǝ҂͎������H�X�Ǝ����~�𣁨6���œP��
2�ڂ͓�����7��8���t���̈˗������A���o���ɂ͓��t���[�R���i�ɉ����č��Œ���ʼnۂ�����A�˂Ă���B
�˗���͢��ޒ����c�̋��c��e�g����B�܂�A���H�X�ȂǂɎ�ނ�̔����鎖�Ǝ҂̋ƊE�c�̂Ɍ��������́B
���e�́A��̋Ǝ҂ɑ��A��ނ̒�~�ɏ]��Ȃ����H�X�ɂ͢��ނ̎�����~����悤���肢���܂���ƌĂт�������̂��B����������S������8���̐V�^�R���i�����ȉ��L�҉�Ŗ��炩�ɂ��Ă����B
������Ă��R�����͢�@�I�����͂���܂���Ǝw�E�B���������A���̈˗����e�͎��{��`�E���R�s��o�ς̑�O��ł���_��̎��R��A���@���ۏ���c�Ƃ̎��R�������������ꂪ����A�ጛ�̉\������荹������Ă���B
�V�^�R���i���[�@5���ł́A�R���i��ɂ��Ģ�����̎��R�ƌ����ɐ�������������Ƃ���ł����Ă�����{���邽�ߕK�v�ŏ����̂��̂łȂ���Ȃ�Ȃ���ƒ�߂Ă���B
���{��13���ߑO�̎��_�ŁA���ނ̎����~��̈˗�����艺������j�͂Ȃ������悤���B�������Y�������͂��̓��̉�Ţ����͂����ς�����B�����������Ăǂ����甃�������Ă����B��߂܂��ƌ���ꂽ�瑼�̏��ɕς�����������̂��ƣ�Ɣ����B�����͂�Ȃ��v���Ƃ��āA�P�Ȃ����j�������Ă����B
�����A�^�}������͢����̎�����悭��������Ă��Ȃ��������ȂƋ����v���܂����(�����}�E�X�R�T���Έψ���)�Ȃǔᔻ���o���B
���������������āA���{��13���ߌ㢎�ނ̎����~��̈˗��𐳎��ɓP���B
�����āA��ނ̎����~�̔��o���̈���������Œ���13���A�E��7�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����BNHK�j���[�X�ɂ��ƁA7�l�͂�����������s�̂܂h�~���d�_�[�u���Ԓ���3�l�ȏオ�Q��������݉�ɎQ�����Ă����Ƃ����B
����̋Ǝ҂̒c�̢�����ł��Ȃ��������K�̏펯���猾���Ă�����
���{����̗v���ɓ{�肪�ɂ��ލR�c�������̂��A���H�X�Ƃ̔��݂ƂȂ����A���H�X�Ɏ�ނ�������̋Ǝ҂��B
�S����5�����̎�ޏ����Ǝ҂���������ƊE�c�̂̈�¢�S��������̑g��������9���t���Ŏ�ނ̎����~�ւ̍R�c�����\�����B
��̋Ǝ҂��܂��A�R���i�ЂŋƐт��������Ă���B�����������ł̢�˗���ɁA������͍R�c�����Ţ���S�E ���S�ȍ������������߂����Ƃɋ��͂��邱�Ƃ͓��R��Ƃ��Ȃ�����A���Ӑ悩��̒��������ۂ��邱�Ƃ͒��N�|���Ă������q�l�Ƃ̐M���W����������������ƂȂ蓾�飂Ǝw�E�B
���̏�Ţ�����I�x��������S�ۂ���Ȃ��܂܁A�P���g�����Ɉ���I�ɋ��͂����߂邱�Ƃ͏����ł��Ȃ����w��ނ̎����~�x�ɑ���⏞���Ȃ����ŋB�R�Ƃ����Ή����Ƃ邱�Ƃ́A�����K�̏펯���猾���Ă����ƁA���{�ɑ��đ��}�Ȍ����������߂Ă����B
�������S������t����Ŏ�������������Ɩ�����
�����S������13���̉�ŁA���Z�@�ւ�����H�X�֎��~�ɂ��Ă͢���Ƃ�������}�������A�ł��邾�������̕��ɂ����͂������������Ƃ��������v������ł͂��������A��|���\���ɓ`�����ꂸ���Ȃ��Ă��飂Əq�ׁA�Z���𐧌������|�ł͂Ȃ������Ǝߖ��B���C�͔ے肵���B
����Ő����S�����͋��Z�@�ւȂǂւ̈˗����ގ����~�ɂ��āA�����o�Ȃ������@�ł̊W�t���Ԃ̉(5��b�)�Ŋt���Ԃ̋c�_�ɓ���O�Ɏ��������犴���ȂǂƂƂ��ɐ������Ȃ��ꂽ�Ɩ��������B�t���Ԃł͈˗��ɂ��Ă̋c�_�͂Ȃ������Əq�ׂ��B
�����A�����Ȃ��9�����ɐ����q�ׂ�����������m���Ă��Ȃ���Ƃ����������ꗂ�����̂ł͂Ƃ����^�₪������B
�������M���[������13���ߑO�̉�Ţ�w�������̂��̂����m���ĂȂ��x�Ƃ������Ƃ�����ꂽ�ƔF�����Ă��飂Ǝߖ������B�����S������13���̉�œ��l�̓��e���q�ׂĂ���B�t���Œ����������e���낤�B
���N���~�߂��Ȃ������̂��H
�P�ꂽ�Ƃ͂����A���H�X��_���������邩�̂悤�Ȑ��{���j���������ŏo���ꂽ���Ƃ͈��H�X���̐S��܂肩�˂Ȃ��B
����܂ŗv��������Ă����X�ł��A���N�ɓ����ċً}���Ԑ錾�������������Ƃ�A���͋��̐U�荞�݂��x�ꂽ���ƂŒǂ��l�߂��āg����̉c�Ɓh������X������B��������{������ŁA�����l�l��ł���Ύ������X���o�Ă��Ă���B
�����ւ��āA����ᔻ�������������{���j���߂��鍬�����B
��5�g�̓������x������钆�A�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̉��Ţ���l���v������Ăт����鐭�{�ւ̐M������w�����鎖�Ԃ����������Ƃ́A��Ō�̐�D��ł���͂��ً̋}���Ԑ錾�̃��b�Z�[�W���������������ɑ��Ȃ������������B
��ጛ��̉\�����l������Ǝw�E�̏o��悤�ȕ��j�ɁA���������ŏ�����X�g�b�v�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂��B
��������}�A���{���Y�}�A��������}�̖�}3�}��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ɔ������Ǝ҂ւ̐V���ȕ⏞���c�_���邽�߂ɂ��A�Վ�����̏��W�����߂Ă���B
����ł�14���A15���ɓ��t�ψ���ŕ�R�����J�����B��}�͐����S������Njy������j���B
�������A4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���߂�]���@7/14
���{��t��̒���r�j���14���̋L�҉�ŁA���{�������s��4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�߂������Ƃɂ��āu�p�f���B(�錾��)�o���ׂ����Ǝ��͎v���Ă����v�ƕ]�������B
����ŁA�x�d�Ȃ锭�߂Ŋ��ꂪ�����A����܂ł̂悤�Ȑl���}�����ʂ������Ȃ��\��������Ƃ��āA���{�ɑ��u�����ȃ��b�Z�[�W���M�����Ă������������v�Ƌ��߂��B
����^����͒��~�ł��ܗւ�OK��`�O�n�O�ȋً}���Ԑ錾�����{��ׂ��@7/14
����������������{�o�ς́u���j�̌��v
���{�͓����s�ɒʎZ4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�߁A12�����K�p�����B���Ԃ�8��22���܂ł�42���ԂƂȂ�B4��25������6��20���܂ł̖�2�J���Ԃ��o�āA3�T�ԂԂ�ً̋}���Ԑ錾�ł���B�Ȃ��A1��8������3��7�����ً}���Ԑ錾���Ԃ������B
�����ł͂Ȃ����Ԃ��܂h�~���d�_�[�u���Ԃ��~����Ă����̂ŁA�v�����2021�N�̓��{�o�ς͏�ɑ��g��t�������݂��������Ă���B�Ђ�A�C�O�ɖڂ����Ɖp���ł̓T�b�J�[���B�I�茠(EURO2020)�̌�����7��11����6���l�ȏ�����e�����X�^�W�A���ŊJ�Â���A�E�B���u���h���I�茠�������̊ϋq�����Ď��{����Ă���B
�������f�����������قƂ�ǃ}�X�N�͂��Ă��Ȃ��B�č��̃��W���[���[�O�̎����ł������悤�Ȍ��i���B���N�`���ڎ헦�ɍ�������Ƃ͂����A�����Ґ��₻��ɔ����d�ǎҁE���Ґ������Ⴂ�ɑ������ĂƂ̊i���ɜ��R�Ƃ������ł���B�����܂ł���Ɓu�i�����傫���v�Ƃ��������u�Z�ސ��E���Ⴄ�v�Ƃ����`�e�̕����������肭��B
�N���ً̋}���Ԑ錾���ߎ��A�M�҂́u�w����ꂽ40�N�ɂȂ肩�˂Ȃ��x2�x�ڂً̋}���Ԑ錾���c���Ѝ� �w���~�����`�x�œ��{�o�ς�����t���v�Ƒ肵�A���~�E����(IS)�o�����X��p���č���̐�s�����Ă����B
��̓I�ɂ́u���j�̌��v�̂悤�ɊJ�����u���ԕ���̒��E���~�ߏ�Ɛ��{����̒��E���~�s���v�Ƃ����\�}����ԉ����A�u���~�����`�v�Ƃ����ϔO�����܂钆�A�����͂��납���������������i�v�I�ɏオ��Ȃ��o�ς����悢��Œ艻����̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜�����B
�}�\1��2021�N1-3�����܂ł̓��{��IS�o�����X�����A�u���j�̌��v�͉ƌv����̒��~�ߏ������Ƃ��Ă���ɊJ���Ă��܂����B
���G�r�f���X�̂Ȃ��R���i��Ǝ��]���̉e��
�N���̎��_�ł́A�܂�������������Ƃ͎v�������Ȃ��������A�����ɖڂ����Α����̎{�ł���Ă���̂͊m���ł���B
7��12������8��22���܂ł�42���ԂƂ������Ԃ͓����ݒ�Ƃ��Ă�4�x�ڂɂ��čŒ��ł���A���ς�炸�ꕔ�Ǝ�(�Ƃ�킯���H��)�Ɋ��������A�ӂ����悤�Ƃ��鍪���s���̑W�J����Ă���B
�������ɏd�Ȃ��������ܗւ͊�{�I�ɖ��ϋq�J�Â����肵�Ă��邪�A�T�b�J�[��싅�Ȃǂ̃v���X�|�[�c�͗L�ϋq�ŊJ�Â���Ă��邱�Ƃ��v���A�����̓������ł���B�܂��A�����P�����ꂽ���̂́A�ꕔ�t��������Z�@�ւ������������H�X���ߏグ����������A���̔g��͂܂����܂��Ă��Ȃ��悤�ɂ�������B
�ǂ��݂Ă����N�O�Ɣ�r���ĎЉ�S�̂��ȋ^�S���[�����Ă���A�[�I�Ɍ����Ε��͋C�͈����Ȃ��Ă���B�Ȃ��A��D�������͂��̃��N�`���ڎ�͏����ɐi��ł������̂́A�u���͍ɂ��Ȃ��v�Ƃ����������I�悵�A�����ł����]���������Ă���B
���ȋ^�S���u���ԕ���̒��~�ߏ�v�������Ă���
��������A�ƌv�E��ƂƂ��������ԕ���̏���E�����ӗ~�͍Ăї������ނ��Ƃ͂����Ă�����オ�邱�Ƃ͍l���ɂ����B
�����犴���h�~�ɋ��͂��Ă��A���̑Ή����u�����҂��������̂Ŏ��l����v�Ƃ������J��Ԃ���Ă���A�u������������邩������Ȃ��v�Ƃ����ȋ^�S�𐭍����ǂɕ��������͑����̂ł͂Ȃ����B
��ʓI�ɗ\���\�����Ⴂ���ɏ���Ⓤ��������オ�邱�Ƃ͂Ȃ��BIS�o�����X�ɂ�����u���ԕ���̒��~�ߏ�v�͖c��オ�����ȋ^�S�̌��ʂł͂Ȃ����낤���B
�Ⴆ�A4�����ً̋}���Ԑ錾�́u�Z���W���v�Ɩ��ł��ꂽ�����R�Ɩ�2�J�����������B�錾���Ԃ̉����͏�ԉ����Ă���A�u�ǂ��������8��22���ŏI���͂����Ȃ��v�Ƃ����v�f�͂����Ԃ�B
�א��҂̌��t���M�p�ł��Ȃ��Ɣ��f�����ꍇ�A����E�������T���Ē��~��ςݏグ��Ƃ����h�q�I�ȍs���ɏo��̂������I�ł���B�p���̗�����Ă�������悤�ɁA���N�`���ڎ킪�i��ł��d�ǎ҂⎀�S�҂͌��邪�A�����҂̍���͂ł��Ȃ��B
�l��1400���l��i�����s�����̈�Ñ̐���60�l���x�̏d�ǎ҂ŕ���(�炵��)�����ŊJ���Ȃ���A���{�������i�v�I�Ɍo�ϊ����̗}���𑱂�����Ȃ��Ȃ�B��Î����̍œK�z���Ƃ����b�͂ǂ��Ȃ����̂��낤���B
�����S�Ɂg�A�e�h���͂��ꂽ���{�̌y���ȍs���K��
���{�͉��ĂƔ�ׂĊ������y�����������Ƃ�����A�ɂ��s���K���������I�Ɍp�����Ă����B����̓O�[�O���Ђ̌��\����uCOVID-19 Community Mobility Reports�v������Ɨǂ�������B
�p���f�~�b�N�ȑO�����������s����������Ă��������ɖڂ����ƁA���̊��Ԃ�[�x�̂�������Ƃ��Ă����Ăقǂł͂Ȃ��A���{�ł͑����āu���킪�����Ă����v�悤�Ɍ�����(�}�\2)�B
�ɂ�������炸�A�`�������悤�ɁA�}�N���o�ϑS�̂Ō���A�u���ԕ���̒��~�ߏ�v���ςݏオ��A���{���傪�K���ł���������߂��A�u���j�̌��v���g�債�Ă���B�y���ȍs���K���͌i�C�ɔz����������ł��������͂������A���S�ɃA�e���O�ꂽ�i�D�ł���B
���������Ɋւ��āu�y���ȍs���K��������������W���K�����p���Ē��������v�Ƃ����ᔻ���悭�������邪�A�M�҂��D�ɗ����Ȃ��B
���Ă͓�������߂������ł���ً}���Ԑ錾���̓��{��芴�������Ⴂ�Ɉ����B�Ⴆ�ΐl��10���l������̊����Ґ�(7��10�����_)�͕č���1��225�l�A�p����7524�l�ł���̂ɑ��A���{��648�l�ł���B
�y���ȍs���K���̂����œ��{�̊����������ߎS�Ȃ�A���r���[�Ȑ�������x�������Ă���Ƃ����ᔻ�����Ă͂܂邵�A����Łu���ԕ���̒��~�ߏ�v���ςݏオ��Ƃ����̂�������B�����A�����͈قȂ�B
���Ȃ݂ɁA�č����u���ԕ���̒��~�ߏ�v�����܂������Ă͂��邪�A�s�[�N�͂����܂�2020�N4�`6�����ł���A�N�Ԃ�ʂ��Ĉ���I�ɒ��~���ςݏオ�葱����Ƃ����ɂ͂Ȃ��B
���u���~�͐��`�v�Ƃ������{�l�̖h�q�{�\
���ǁA�u�y���ȍs���K��������������W���K�����p���Ē��������v���Ƃ����Ȃ̂ł͂Ȃ��A���̓s�x���蓖�Ă���y���ȍs���K���Ɉ�ѐ����Ȃ����Ƃ����Ȃ̂ł͂Ȃ����B�Ⴆ�u�w�Z�̉^����͑ʖڂ����A�ܗւ͉\�v�u�����d�Ԃ�OK�����A���H�X�̐Ȃ͊Ԉ����v�Ƃ������������I�ɐ����ł���҂͂��Ȃ����낤�B
�������������s���̎�j������������O�ɂȂ��Ă��܂��ƁA�ƌv���Ƃ̂悤�Ȍo�ώ�͉̂�����ɏ���E�����v����\�z���ׂ���������Ȃ��Ȃ�B
�uCOVID-19 Community Mobility Reports�v�������ړ��X���͂���قǃR���i�ȑO�ƕς���Ă��Ȃ��̂ɁAIS�o�����X�ɂ�����u���ԕ���̒��~�ߏ�v���g��̈�r�ɂ���̂́A�ȋ^�S���c����ʁA�u���~�����`�v�Ƃ����h�q�{�\���������ꂽ����ł͂Ȃ����B
���p���f�~�b�N�I����ɂ��e���͎c�邩
���E�I�Ɍ���A���N�`���ڎ헦�����߁A�d�ǎҁE���S�҂̐�����}�����A�s����������������Ƃ����A�v���[�`������ɂ�����B�ꖳ��̏o���헪�ƌ�����B
�ً}���Ԑ錾�𗐔����A���̓s�x�A�ׂ��ȍs���K����������Ζ��ԕ�����ȋ^�S�͑����A���~�Ɉˑ�������{�o�ς̑̎��͕s�ς̂܂܂��낤�B���Ȃ��Ƃ��ߋ�1�N�͂����������悤�Ɍ�����B
���́A�p���f�~�b�N�����S�I�����Ă��A���ԕ��傪�����א��҂ւ��ȋ^�S�������ꂽ�܂܂ɂȂ�A����E�����ӗ~�͂����ĉ����Ɍi�C���g���܂܂Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ɏ��邱�Ƃł���B���{�o�ς͌��X�u���ԕ���̒��~�ߏ�v����ԉ����Ă��鍑�����ɁA���̓x��������i�Ƌ��܂邱�Ƃ͑����Ɍ��O�����B
�O��̃R�����ŕM�҂́u2020�N�ɏo�������ɒ[�Ȏp(�����~�ߏ�)�͌o�ϊ��������Ƃ�������Ȑ���̌��ʂł���A�i���������҂�����̂ł͂Ȃ��v�Əq�ׂ����A�c�O�Ȃ���A�͕ς��Ȃ��ǂ��납�������Ă���B
�u���ԕ���̒��~�ߏ�v��90�N��㔼����p��������{�́u����ꂽ20�N�v���ے����錻�ۂł���B�p���f�~�b�N�Ή����o�Ė��ԕ���ɐA���t����ꂽ�ȋ^�S���u���ԕ���̒��~�ߏ�v����i�Ƃ������A�u����ꂽ30�N�v�Ȃ����u����ꂽ40�N�v�ւ̉����ƂȂ�Ȃ����Ƃ��F�����ł���B
��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�Ŗ��������������@�g�S�̂�炬�h�������ߌ��@7/14
�l�͏�ɍ����I�ȍs�����Ƃ�Ƃ͌��炸�A���ɐ����̂��Ȃ��s���ɏo����́B����ȁg����̂܂܂̐l�ԁh���������o�ς���Z�̎��Ԃ�ǂ݉����̂��u�s���o�ϊw�v���B���N���Ă���{�ȃj���[�X�����A���̔w�i��l�X�̐S�����A�s���o�ϊw�̑��l�҂ł���@����w��w�@�����E�^�Ǐ��v�����������V���[�Y�u�s���o�ϊw�œǂ݉������Z�s��̍��v�B��26��́A�g�����h�������������̃R���i�Ή��ɂ��ĕ��͂���B
��
�O��ً̋}���Ԑ錾���������Ă���킸��3�T�ԁA�����s�ł�4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�����߂��ꂽ�B�J�����_�[�����Ԃ��ƁA���N�ɓ����Ă���u�ً}���Ԑ錾(1��8���`3��21��)�v���u�܂h�~���d�_�[�u(4��12���`24��)�v���u�ً}���Ԑ錾(4��25���`6��20��)�v���u�܂h�~���d�_�[�u(6��21���`7��11��)�v�A�����Ă܂�����ً}���Ԑ錾�Ɓg�������Ă͍Ăѐ錾���߁h�Ƃ����u�����v���J��Ԃ��Ă����B
��N���瑱���R���i�ЂŐl�X�̎��l�������E�ɒB����Ȃ��A��D�̂͂��̃��N�`���ڎ�������ɗ��ċ����s�����w�E�����ȂǁA�����̕s���E�s�������܂�̂����R�Ƃ������ɂ���B�e���l�b�g�̏������݂Ȃǂ�����ƁA�u�����ɗ��Ă܂������_���A�C�x���g�����~�B������y���݂�D��ꑱ���Ă���̂ɁA�����ܗւ����͂��Ȃ�āv�A�u�{���ʂ��z���ĕ����v�A�u������ꂽ�A���čs���Ȃ��v�Ƃ��������t���ڗ��B
�����Ɓg�G���h����Ă������H�X������A�u�����_���Ƃ����G�r�f���X���Ȃ��̂ɁA�g�Ƃɂ����������ȁh�ł͐����n�����v�Ƃ�������������A���������M���M���܂ł�������������ܗւ́u�L�ϋq�v�����ǒf�O���A�u���Ŋϐ�ł��Ȃ���ɊC�O����̊ό��q���v�������Ȃ��āA���Ӗ�����́H�v�Ƃ��������ň��Ă���B
����A���{�W�O�O���ォ�牽�x���J��Ԃ���Ă����u���S�E���S�ȑ��v�A�u�R���i�ɑł����������v�Ƃ͑S����������Ă���A��̂ǂꂾ���u�����v���J��Ԃ������̂��B
���������Ă��A���`�̎��ً}���Ԑ錾�\��������(7��9��)�̓��o���ϊ����͈ꎞ600�~�����}�����A2��8000�~�����荞�B�T�����Ɋ����͎����������Ƃ͂����A���̃^�C�~���O�ł̐錾���o�͐��E�̓����Ƃ���������ۂ������ꂽ�i�D�ł���B
��̂Ȃ�����ȑΉ�����J��Ԃ��Ă���̂��B�������̐S���I�w�i��ǂ݉����ƁA���ꂱ���u�S���̂�炬�v�Ƃ��������悤���Ȃ��B�א��҂Ƃ��ẮA�R���i�ЂŌi�C�������Ȃ邱�Ƃɂǂ��ɂ��ς����Ȃ��u�����ϔO�v�ɋ�������ŁA�R���i�Ђł��D���Ȋ�Ƃ���̑傫�Ȑ��͕������Ă��Ȃ��B����Ƃ܂��܂��u�i�C�̈��������Ƃ����ė~�����v�Ƃ��������肪�傫���������Ă��āA���̐��ɑ�����u�����ϔO�g��̖@���v�Ɋׂ��Ă��܂��B���̂��߁A�����}���������ł����킯�ł��Ȃ��̂ɁA�����錾�������Ă��܂��̂��B
�g��e�h���ǂ��Ă��Ȃ�����
7��4���̓s�c�I�ł́A�����}�͉ߋ�2�Ԗڂɏ��Ȃ��c�Ȑ��ƂȂ�A�ڑO�ɓ����ܗւ��T����Ȃ��H�ɂ͑��I�����\�肳��A�����Ƃ��Ắu����ȏ�̎���͋�����Ȃ��v�Ƃ����g���|�h�ɋ����B�����āA�g�ً}���Ԑ錾���������ĉ��Ƃ��Ă��i�C���}�������h�Ƃ������f�ɌX���A�܂����Ă������g��Ƃ������Ԃ������Ă��܂��̂ł���B
����A�S�̒��ł͏�Ɂu�o�ρv�Ɓu��(�R���i��)�v�̓V������炢�ł����ԂŁA�u�o�ρv�̓V�����d���������ʁA�錾���������A�����g��������Ă���i�D�ł͂Ȃ����낤���B
����ɁA���N�`���ڎ킪�n�܂�A�ꎞ�͐ڎ헦���オ���Ċ����������X��������ꂽ���Ƃ���A�א��҂̐S�ɂ́g����ŃR���g���[���ł���h�Ǝv�����ށu�R���g���[���C�����[�W�����v���������B�������A����͂�͂�g���z�h�ŁA���ۂɂ̓��N�`���̋����s���Ȃǁu�ڋl�܂�v���N�����Ă܂��L���s���n���Ă͂��Ȃ��B
���̌��ʁA�܂��܂��u�o�ρv�Ɓu���v�̓V������炬�A�ǂ�����d������Ηǂ��̂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���{�����R���i�ɐU����Ȃ��A�{���A��ԐU���Ă͂����Ȃ��͂��̍��̃��[�_�[���������Ă���\�\�s���o�ϊw�I�Ȋϓ_�Ō��Ă����ƁA����ȁu�S�̂�炬�v�������Ă���̂��B
����7��8���̉�ŁA�u���A���ŗ\�h�I�[�u���u����v�Ɣ����������A�����܂ł̑Ή�������ƁA�ނ���u�����v�Ƃ��������悤���Ȃ��B���Ȃ��Ƃ����Ԃ���ɗ�ÂɌ��ēI�m�Ȕ��f�������Ă����A�Ƃ͕]���ł��Ȃ����낤�B
�p�����h������A�������m�l�ɂ��ƁA�u���{�ً̋}���Ԑ錾�͊Â�����v�Ƃ����B���b�N�_�E��(�s�s����)���s�Ȃ�ꂽ�����h���ł́A�X�p�̏��X���痑�⏬�����Ƃ������K���i�܂ŏ������B���b�N�_�E���ɂ���Ĕ��鑤�┃���l�����łȂ��A�ꎞ�͏��i�̗��ʂ܂Ŏ~�܂������߂ɁA�X����������Ă��܂����������B����ł������h���ł͍Ăъ������g�債�Ă���Ƃ�������A��ؓ�ł͂����Ȃ��悤�ł���B
���Ă⒆���Ȃǂ̎�������Ă����炩�Ȃ悤�ɁA����́u��e�v��ǂ��Ă���肭�@�\���Ȃ��B�Ƃ��낪�A�킪���̑�����Ă���ƁA�u�o�ρv�Ɓu���v�𗼓V���ɂ����āA���ǂ͂ǂ��������ň�e���ǂ��Ă��Ȃ��B���ꂱ���ڐ�̑������Ƃ肠��������������Ƃ����u�ߎ���I��������v�ł���A�c�O�Ȃ��璷���I�Ȏ��_�͌����Ă��Ȃ��B
�Z���I�Ȓɂ݂����A�����D�悵�ēO��I�ɑ������ŁA�����ЂƂ̉ۑ���������Ă����Ȃ���A�ǂ�������{�I�ȉ����ɂ͎���Ȃ����낤�B����ł́u���v���ŗD��Ȃ̂͌����܂ł��Ȃ����A���̔��f�ł�炢�ł�����{�͖{���Ɂg�ߌ��h�Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�����m���@�����u�X�e�[�W4�v�ŋً}���ԗv�����@7/15
���{�̋g���m���m����15���A���̕��ȉ�����V�^�R���i�E�C���X�̊����̎w�W���ł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̐����ɂȂ�A���{�ɋً}���Ԑ錾��v������\���Ɍ��y�����B�g�����͕{�����ŋL�Ғc�̎�ނɑ��A�錾�v���ɂ��āu�X�e�[�W4������ɓ���Γ��R�l������v�Əq�ׂ��B���{�ɂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����Ă���B
���{��15���̐V�K�����҂�324�l�ŁA�����̊g��X�����N���ɂȂ��Ă���B�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���15�����_�Łu�X�e�[�W3�v(15�l�ȏ�)��17.14�l�ƂȂ����B�u�X�e�[�W4�v(25�l�ȏ�)�̊��1�����ς̐V�K�����Ґ��ł݂��315�l�ƂȂ�B�g�����́u1�̐������X�e�[�W4�ɒB�������炷��(�錾�v��)�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��q�ׂ��B
���̂ق��̍��̕��ȉ�̎w�W�ł́A15�����_�̊m�ەa���ɑ���a���g�p����17.6%�A�d�Ǖa���g�p����11.7%�ŁA�u�X�e�[�W4�v(50%�ȏ�)�̐�����傫��������Ă���B�{�̃X�N���[�j���O�����ł�15�����_��157�l���ψكE�C���X�̃C���h�^(�f���^�^)�̊����^�������邱�Ƃ��������Ă���A�{�͌x�������߂Ă���B
����� �V�^�R���i328�l���� �ً}���Ԑ錾������ő��@7/15
��ʌ����ł́A�V����328�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă������Ƃ��m�F����܂����B
��ʌ�����1���Ɋ��������\�����l�̐���300�l����̂͂��Ƃ�1��30���ȗ��ŁA��ʌ����ɏo����Ă���2��ڂً̋}���Ԑ錾�����Ƃ�3���ɉ�������Ă���A�ł������Ȃ�܂����B
����́A��ʌ��̔��\��215�l�A�������s��49�l�A����s��37�l�A�z�J�s��15�l�A��z�s��12�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�������s��13���A�����\�����l�̂����A1�l�ɂ��Ď�艺����Ɣ��\���܂����B
����ō�ʌ����Ŋ��������\���ꂽ�̂́A���킹��4��8784�l�ƂȂ�܂����B
�܂��A�������s�͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������A�����̈�Ë@�ւɓ��@���Ă���80��̏��������S�����Ɣ��\���A����ō�ʌ����Ŋ������m�F����A���S�����̂�841�l�ƂȂ�܂����B
�����q�A8���ɒlj����ց@�S������A�ً}���Ԑ錾�Ł@7/15
���{�q���15���A8���̍������̉^�q�ɂ��āA�V���ɖ�4000���炷�Ɣ��\�����B�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɔ����A�����s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����߂��ꂽ���ƂȂǂ��A�\��̐L�т��݉����Ă��邽�߁B�S���{��A��8��1�`22���ɂ����āA�������Ōv��5800�̌��ւ����߂��B
��Ȍ��֑Ώۂ͉H�c�\�����≫�ꔭ���H���ȂǁB���q�͍��N�x�̎��ƌv��ɔ�ׂ�8���̉^�q����73���B�S����̓R���i�БO�ɍ��肵����N�x�̎��ƌv��Ɣ�ׁA8��1�`22����65���ƂȂ�B
���u���̏������Ƌً}���Ԑ錾�̑O�|�������������Ȃ�v�@���ꌧ�@7/15
���ꌧ��15���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�60�l�ŁA2���A���őO�̏T�̓����j����25�l����܂����B�����Ċg��̌��O�����܂��Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�60�l�ŁA�O�̏T�̓����j�����25�l�����Ȃ��Ă��܂��B
14�����O�̏T�Ɣ�ׂ�25�l�����Ă��āA���̎w�W�ŃX�e�[�W3�ɉ������Ă���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͍ĂуX�e�[�W4�Ɉ������܂����B
���ی���Õ��E������ËZ�āw�ً}���Ԑ錾�̑��������Ɍ����č����g��ł���Ƃ��낾���A���̏������Ɣ��Ɍ������Ȃ�ƔF�����Ă���x
���͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������80�ォ��90��̒j��4�l���S���Ȃ��Ă������Ƃ\���A�����̎��҂̗v��215�l�ƂȂ�܂����B
�������m�ꎁ���ً}���Ԑ錾���o�̔w�i������@�u���r�����܂������v�@7/15
�o�ϊw�҂̍����m��(65)��14���A���g�̌������[�`���[�u�`�����l���u�����m��`�����l���v���X�V��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�̕��䗠�ɂ��Ď��_���q�ׂ��B
�u���ŋً}���Ԑ錾���o�����H�v�Ƃ̎���ɍ������́u�s�v�c����ˁB�ً}���Ԑ錾�Ƃ����͖̂{���̎�|���������Õ������Ⴂ���Ȃ�����B�d�ǎ҂������������Ă�Ƃ����҂������Ă鎞�ɂ͎d�����Ȃ��B����ȊO�̎��ɂ����������̂�����v�Ǝw�E�����B
�����āu�v����Ɋ����Ґ��͑����Ă邯�ǁA�قƂ�ǂ͎�҂�����B��҂͌�ʎ��̂Ɣ�ׂ�Ǝ��S�̃��X�N�Ƃ����̂͌�ʎ��̂��͂邩�ɒႢ�B��ʎ��̂��Ⴂ�̂Ɋ����҂������Ă邩��ƌ����ċً}���Ԑ錾����̂͌�ʎ��̂�����Č�ʂ��X�g�b�v����̂Ɠ����悤�Ȃ���ł���v�Ɣ���������Č�����B
�u���X�N���Ȃ��̂Ɋ����҂���������������������Ƃ����̂���ԈႢ�B(���N�`����)60�Έȏ�ɂȂ�Ɗ����ҁA���ҁA�d�ǎ҂������Ă�B���N�`�������܂������Ă邱�Ƃ𗝗R�ɂ���Ί����҂͑����Ă邯�ǁA�����ً͋}���Ԑ錾������K�v�͂Ȃ����Ă͂����茾�������x���v�ƒf�������B
����ł��ً}���Ԑ錾���߂��ꂽ�̂́u�܂����r�����܂������v�Ə��r�s�m���̑��݂��w�E�B�u���r�����܂����ƒK�Q���肵�ēs�c�I������������ł���B�s�c�I���������Ƃ�����K����ƎR����������}��(����)�[���Ƒ����āw�I���̘b���x���Č����Ă���Njً}���Ԑ錾(�ܗ�)���ϋq���Č����Ă��B(�Ȃ�ŋً}���Ԑ錾���o�������H)�s���t�@�[�X�g�̌���ŋً}���ϋq���Ă����ƌ����Ă�(����)�B������ً}���Ԑ錾��������Ɩ��ϋq�ɂ����Ȃ邩�炻���_�����킯�v�Ƙb�����B
�����āu�����炻�̌シ�����g����̏����s���Ă�B����͑f�����B���{�̕��͓s�c�I�ŕ����ăI�^�I�^���Ă��錄�ɃT�[�b�Ɖ��������Ă����ō����I�����������B�}�]�����A���r����ɂ���ċً}���Ԑ錾���ϋq���Ęb�ɂȂ���������B�����̂ق��́w���[�x���čQ�Ăď\���Ȍ����Ȃ��ł������������Đ��E�v�Ə��r�s�m���ɂ��Ă��ꂽ�Ɛ��@�����B
�������́u�����I�Ȕ��f���ł��Ȃ��Ȃ��Ă�l�����ď��r����͂����̏��ɓ��������Ď����̐����I�v���X�e�[�W�A�������ɏグ���Ƃ����Ƃ��낶��Ȃ��ł����v�Ƙb�����B
���u�ً}���Ԑ錾�̃}���l�����v�Ɋׂ��������c���������������܂ʼnc�Ɓ@7/15
�V�^�R���i�̊g��œ�����4�x�ڂً̋}���Ԃ������ꂽ�����ł���13���ߑO8��30���A�V���w�L��͏o���b�V���ō��ݍ������B����Ȃ��ĐE���������Ј��̎p����V�^�R���i�̊g��h�~�Ɍ������ً}���Ԃ����ߒ��Ƃ������͋C�͌�������Ȃ������B����j����Ј��́u�����ǂ����Łw�ً}���Ԑ錾�̃}���l�����x�Ƃ����\�����g���قNjً}���ԂɊ��ꂷ�����v�Ƙb�����B
�����ً̋}���Ԃ͗���22���܂ł��B���̓�����ɓ����s���͍��N��86�����ً}���ԂƏ��ً}���Ԃł���u�܂h�~���d�_�[�u�v�̏ő��邱�ƂɂȂ����B���ʑ[�u��������Ȃ�������24���ɉ߂��Ȃ��B�m�s�s�h�R���̌g�ѓd�b�ʒu��͂ɂ��ƁA�ً}���ԏ����ł���12���A�����w�E�V�h�w�E�a�J�w�E�V���w�E����w�Ȃǎ�ȓs�S�̐l�g��2�T�ԑO�ɔ�ׂ�2�������ɂƂǂ܂����B1�x�ڂ�2�x�ڂً̋}���Ԃɂ͂��̒n��̐l�g�͂��ꂼ��29���A20�����������B
���{���{�̎�ޒ��~�v���𐳖ʂ��狑�ۂ�����H�X���������Ă���B��Ј�����H�ꏊ�Ƃ��čD�ސV�����y�X�ɂ͉c�Ɛ������Ԃł���ߌ�8���ȍ~�ɂ�����X�����Ȃ��Ȃ������B�u11���܂ʼnc�Ɓv�u������5���܂Ŏ���܂��v�Ɠ��X�Ə����ē\�����X���������B���H�X��l�͂���ȏ㎝�����������Ȃ��ƌ������낦���B���{���{���x�Ɨv���ɏ]���X�ɕ⏕�����x�����邪�A���z�����Ȃ��x���������x������Ƃ������Ƃ��B
����ɐ旧����3��ً̋}���Ԃ̎��͐��{���j�𒉎��ɏ]���������̘V�܋������u���͎𑠁v������͓X���I�[�v�������B���c�X���̓e���r�����Ƃ̃C���^�r���[�Łu�c�Ƃ����Ȃ���Ώ]�ƈ���30�������ق��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi�����B
���Ƃ͂��łɓ����ŐV�^�R���i�̑�5�����s���n�܂����ƌ��Ă���B13���A�����ł�830�l�̐V�K�����҂����������B24���A���Ŋ����҂�1�T�ԑO�Ɠ����j����葝�����B�܂��V�^�R���i���N�`����ڎ�ł��Ȃ�40�`50��𒆐S�ɏd�NJ��҂��}������X�����B
�B����S�ł���̂͑傫���オ�������N�`���ڎ헦���B14���A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�̓��v�T�C�g�u�A���[�E���[���h�E�C���E�f�[�^�v�ɂ��ƁA�؍��Ɠ��{�̐V�^�R���i���N�`����1��ڂ̐ڎ헦(12���)�͂��ꂼ��30�D46����30�D45���łقړ����������B���{�̃��N�`���ڎ헦���؍��Ɠ��������ɂȂ����̂͏��߂Ă��B2��ڂ̐ڎ헦�͓��{��18�D6���Ŋ؍������[�h���Ă���B�S�������ł��N�`�����m�ۂ������{�́A6���ɓ����ĘA������ڎ��100����������Ă���B�m�g�j�ɂ��ƁA12�����1��ڂ̐ڎ��3851���B���{�l3�l��1�l�͏��Ȃ��Ƃ����N�`����1��ł����Ƃ������Ƃ��B2��ڂ̐ڎ�܂ō��킹���v�ڎ��6199���B
�������́u���̂������炸�A���ׂ��K�͎��̂�������Ȃ��Ȃ��Ă�v�@7/15
�H��܍�Ƃ̕���[��Y����15���A���g�̃c�C�b�^�[���X�V�B�ً}���Ԑ錾���̓����s�̌����Q�����B
���̓��A�u���{�̃R���i�������ɂ߁A�ܗւ̂��߂ɗ�O�����܂����Ă�̂ŁA�}���{�E�Ȃ̂��A�ً}���Ԑ錾�Ȃ̂��A�v����ɍ��͉������ėǂ��āA�������Ă͂����Ȃ��̂��A���̂������炸�A���ׂ��K�͎��̂�������Ȃ��Ȃ��Ă�v�ƌ������M�v�łÂ������쎁�B
23���ɔ����������ܗ֊J����O�Ɏ�s�̍����Ԃ��J���Ă����B
���D�y�s�E�H���s���@���T�̊�������Łu�܂h�~�[�u�v�̍ēK�p�@7/15
�D�y�s�̏H���s���́A�u�ً}���Ԑ錾�v�����ɓ���ē��Ƌ��c���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Əq�ׂ܂����B
�u����������������w�܂h�~�[�u�x�̍ēK�p��v������Ƃ��A����ɂ�����Ă����悤�ȋً}���ԂȂǂ����ɓ���Ȃ���k�C���Ƃ����c��i�߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v(�D�y�s�E�H�����L�s��)
�H���s���͋L�҉�ł��̂悤�ɏq�ׁA���T�̊�������ł́u�ً}���Ԑ錾�v�̗v���Ƌ��c����l���������܂����B
�D�y�s���̈��H�X�́A���T����ߌ�9���܂ł̎��Z�c�Ƃ��v������Ă��܂����A�u���Z�c�Ƃ͊ɘa����ɂ͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
���l���̗}�����i�܂Ȃ����Ƃ����O�A����-�ً}���Ԑ錾���߂́u�p�f�v�@7/15
���{��t��̒���r�j���14���̋L�҉�ŁA�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̐V�K�z���Ґ���13�����_��830�l�ƂȂ�A�u24���A���őO�̏T�������Ă���v���ƂȂǂ������āA�����Ċg��̒����邱�Ƃւ̌��O���������B
�����s�ւ�4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���߂ɂ��ẮA�u�p�f���Ǝv���B�o���ׂ����Ǝv���Ă����̂ŕ]���������v�Ƃ����A�J��Ԃ����ً}���Ԑ錾�Ɋ���Ă��܂������߁A�l���̗}�����i�܂Ȃ����Ƃ�S�z���Ă���A�����ȃ��b�Z�[�W�M���Ăق����ȂǂƘb�����B
���̓��̉�ł͏��{�g�Y��C��������A��t�̘J�����ԒZ�k�ւ̎��g�݂Ȃǂ�]������u��Ë@�Ζ����]���Z���^�[�v�̐ݒu�����ɂ��āA�����J���Ȃ�2021�N�x�̈ϑ����Ƃ���������Ɣ��\���������B22�N4���̃Z���^�[�ݒu�Ɍ������������ƂƂ��āA�T�[�x�C���[�̑I�o��u�K��̎��{�A���i�t�^�ȂǂɌ����ċ�̓I�Ȑ�����i�߂�B
���{��C�����@�܂��A�u��t�̓��������v�̐��i�Ɋւ��錟����v�ł̋c�_�ɂ��ď��{��C�����́A��t�̎��ԊO�E�x���J�����N960���Ԃ����Ë@�ւ́A23�N�x���܂ł̘J�����ԒZ�k�v��̍쐬����ю��g�ݎ��{���A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɑΉ������Ë@�ւ����钆�A�z�����ׂ��Ƃ̈ӌ��܂��āA�w�͋`���ɂȂ������Ƃ��u���˂Ă���w�E���Ă������_�������̂ŕ]������v�Ƃ����B
���s�ً̋}���Ԑ錾�A�����Đ��Y��20���ȏ�̌����K�v�@7/15
�����s�ł�4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾��7��12�����甭�o���ꂽ���A�����Đ��Y���̑��ΓI������10�����ɂƂǂ܂�A������V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̏d�ǎҐ��͑��������A9�����߂ɂ�250�l����\�\�B
���s��w��w�@�����̐��Y������ɂ��v���W�F�N�V������7��14���̌����J���Ȃ̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h(�����F�e�c�����E���������nj���������)�ɒ�o���ꂽ�B�V�K�z���Ґ�����@���Ґ����܂߂Č����ɓ]�������邽�߂ɂ́A20���ȏ�̎����Đ��Y���̌������K�v�Ƃ������v�B�d�lj�������������҂̃��N�`���ڎ킪�i�݁A�y�Ϙ_�����钆�A�����Đ��Y�������炳�Ȃ���Η\�f�������Ȃ����������������Ƃ������f�[�^��(�����́A���J�Ȃ̃z�[���y�[�W)�B
���Y����́A�����s�ł̓f���^������߂銄����7��17���ɂ�50�����A7��23���̓����ܗ֊J����_�ł�61.5�����߂�Ƃ̐��v���B���Y���́u�����Đ��Y���͏��Ȃ��Ƃ��ꎞ�I�ɑ������邱�Ƃ������܂��B�f���^���ւ̒u�������ɔ��������Đ��Y���̑�����������Ăł��A20�����͏��Ȃ��Ƃ��m�ۂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��������́A���\���������ʂ��v�Ɗ�@�����点��B�u�����Đ��Y��������Ȃ����Ƃ��A�\���ɑz�肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�B
��40�A50��̏d�ǎґ��̉e����
���Y����́A�錾�O�̓����s�̎����Đ��Y�����A1.2(�ŐV���芴�����t6��28�����_)�Ƒz��B�ً}���Ԑ錾�Ŏ����Đ��Y����10���A20���A30�����ꂼ�ꑊ�ΓI�Ɍ��������Ɖ��肵�āA�V�K�z���Ґ��A���@���Ґ��A�d�ǎҐ��ɂ��āA9��5���܂ł̃v���W�F�N�V�������s�����B�f���^���ւ̒u�������A�N��Q����N��Q�Ԃ̓`�d�A���N�`���ڎ�ɂ����ʂȂǁA���܂��܂ȗv�����������Ă���B�f���^���̎����Đ��Y���́A�]������1.9�{�Ɛ���B
�����Đ��Y����20�����̏ꍇ�A�d�ǎҐ��́A8����{�ɂ�130�l���œ��ł��ɂȂ���̂́A130�l������9���ɓ����Ă���������Ɛ��v�B30�����ł����7������100�l������̂́A���̌�͌����ɓ]���A9����{�ɂ�70�l������錩���݂��B�N��ʂɌ���ƁA40�A50��̏d�ǎҐ����������A60��ȏ�ł������Đ��Y����10�����ɂƂǂ܂�A�V�K�����Ґ���������A����ɔ����d�ǎ҂�������B
����Î҂ւ̃��N�`���ڎ�ŃN���X�^�[������}��
���Y�����7��14���̃A�h�o�C�U���[�{�[�h�ɁA2020�N11������2021�N6���܂ł̈�Ï]���҂̃��N�`���ڎ�ƃN���X�^�[�����̊֘A�͂����b�茋�ʂ����\�����BVRS��A��Ï]���҂̐ڎ헦��6���ɂ�100�����邪�A6���ȍ~��100���Ɖ���B����҂ւ̐ڎ�͎n�܂�������̎����ł��邽�߁A���̉e���͉������Ă��Ȃ��B
���̌��ʁA��Î{�݂ɂ��Ă�164���A����Ҏ{�݂ł�155���A��Ï]���҂ւ̃��N�`����s�ڎ�ɂ�肻�ꂼ��}�����ꂽ�Ɛ��肳�ꂽ�B
���Y���́A�u����A���肳�ꂽ���l�́A��Ï]���҂̐ڎ�ɂ���āA�{�l�ȊO�̒N���̖h����ʂ�������Ƃ����A������ԐړI���ʂƌĂ����́B���ꂪ�N���X�^�[�����ɂ܂Ŕh�����Ă��邱�Ƃ��������ʂ��B��Ë@�ւ⍂��Ҏ{�݂ŃN���X�^�[������̂́A��s�ڎ�̎����ƌ�����v�ƌ���B
�u����A����Ҏ��g�̐ڎ�ɂ�钼�ړI���ʂƐl�����x���̐ڎ�ɂ��A�K�ɗ��s�����䂳��Ă������́A�����̃N���X�^�[�͂܂��܂�������̂Ɗ��҂����v�Əq�ׁA����A���̓_�ɂ��Ă̊ώ@�Ɛ����i�߂Ă����\�肾�Ƃ����B
���R���i�Ή��g���{�̔s�k�h�@4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�@7/15
�����ܗւ̊J�(23��)������Ȃ��A�����s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾�����߂���A�����ܗւ́A��s��1�s3���ƁA�k�C���A�������ł́u���ϋq�v�J�ÂƂȂ����B���Ăɔ�ׂāA�V�^�R���i�̐V�K�����Ґ������Ⴂ�ɏ��Ȃ�����ł̔��f�ɁA�ܗ֎Q����������A�X���[�g��A������ᔻ����C�O���f�B�A������B�]�_�Ƃ̔����a�Y�����A�����ܗւ����������A�킪���́u�R���i�Ή��v�ɂ��čl�@�����B
�����u���_�v8�����ŁA�u�����E�C���X�Ƃ̐킢�@���{�͔s�k�����̂��v�Ƃ����Βk���A�����J�Ȉ�n�Z���ň�t�̖ؑ�������(�����Ɖu�w)�ƍs�����B
���́u��N�ƍ��N��2�N�Ԃł̌o�ς̗������݂́A�����̋K�͂����Ⴂ�ȉ��ĕ��݂�����w���{�̔s�k�x�v�Ɛ\���グ���B
�u�ܗ֒��~�v��A�u���ϋq�v�J�Â��咣���Ă�����t��Ȃǂ́A���{��ǂ�����œ��Ӗ��ʂ��낤�B�����s��t��̔��莡�v���A���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��̊炪�����ԁB
���Ăɔ�ׂ��炳���g�̂悤�ȏł��A�u��Õ����˂Ȃ��v�Ƃ��ċً}���Ԑ錾�����߂��ꂽ�B���������̘_�����������āA�����̕�炵���ꂵ�߁A�ܗւ��u���ϋq�v�ɂ����̂��A���������ł��邱�Ƃ����p����ׂ����B
���{�̓��@��Ñ̐��́A�y�ǂƂ��I�����̊��҂����@�����Ėׂ���悤�ɂȂ��Ă���A�ȑO����u��@�Ή��Ɍ����Ȃ��v�Ɗ뜜����Ă����B
�����A�����ƂȂ�����A��ÊE�͂���܂ł̘g�g�݂����Ή�������Ǝv���Ă����̂ɁA���S�Ɋ��ҊO�ꂾ�����B�d�ǎҗp�x�b�h�����قƂ�Ǒ��₳���A�x�݂͂����̂悤�Ɏ��̂ŁA��Â��N��(�Ђ��ς�)�����������B
���H�ƁA���Ɏ����o���̂������̍����Ƃ����������ȁu��w�I�Ȍ��n�v����A���{�̕��j����̎哱��������A�������キ�A�b�܂�Ȃ������甇���オ���Ă����l���������̋ƊE�����߂𑱂����B�u�K���������Ȃ�ƖO������v�u�������l���ĕ��S���L�����������S���ׂ��v�u�x�ƕ⏞�����ł͐l�ނ͒����m�ۂł��Ȃ��v�Ƃ������w�E�ɂ�����݂��Ȃ������B
���́A�ł��c�Ək�����ׂ��Ǝ�͈�ÊE���Ǝv���B�R���i�ЂŐ��E�I�ɒʏ��Â͏k������Ă���B�����h�~�̂��߂ɂ��A��Ë@�֒ʂ��͌��炷�ׂ����B�C�O�ł͈�Î����m�ۂ̂��߂ɁA�R���i�ƊW�Ȃ�����͐f�Î��Ԃ����炵�A���N�`���ڎ���܂߂��R���i�Ή��ɉĂ����B
�Ƃ��낪�A���{�ł̓��N�`���ڎ�Ő��{���u��t�Ɛ�͈͂̍Č����v���`��������܂œ����Ȃ������B
�������A��Ï]���҂�́A���E�ŗޗ�����Ȃ��u�ŗD��ł̃��N�`���ڎ�v�����萷��ł����B���J�Ȑ��v�Ŗ�300���l�������̂ɁA�e��Ë@�ւɔ��f��������2�{�߂���500���l�ȏ�ɂȂ����̂́A���܂��܂ȈӖ��Łu�s�K�Ȑl�X�v���܂܂�Ă��邱�Ƃ��������鐔�����B
���N�`���ڎ�̒x��̗��R�͂��낢�날�邪�A���N�`���ւ́u���قȕs�M���v�����z����Ă���ʂ�����B��w�E�ł���������l���������āA�嗬�h�̐l�X���܂Ƃ��ɐ��Ȃ��̂ŁA�q�{�N�`���̐ڎ킪�i�܂��A�N��3000�l�̎��҂Ǝq�{������������ςݏグ�Ă���B
�R���i�E���N�`���̏��F���}�����߂ɁA��N11���ɖ@���������s�����̂����A��������}�⋤�Y�}�̗v���ɂ��t�ь��c�Ŕ����������ꂽ�B���ꂪ�x��̍ő�̌����ł��邱�Ƃ��}�X�R�~���Ȃ��̂��c�O���B�@
��4��ڂ́u�ً}���Ԑ錾�v�c���Ȃ��͉����v���܂������H�@7/15
���f���E�^�����g�Ƃ��Ċ��郆�[�W�ƁA�t���[�A�i�E���T�[�̋g�c�������p�[�\�i���e�B���Ƃ߂�TOKYO FM�̔ԑg�uONE MORNING�v�B7��12��(��)�̕����ł́A���b�Z�[�W�e�[�}�u4��ڂً̋}���Ԑ錾�c�c���Ȃ��͉����v���܂������H�v�Ɋ�ꂽ���b�Z�[�W�̈ꕔ���Љ�܂��B�V�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�Ă��铌���s�ł́A7��12��(��)��4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�����߂���܂����B���Ԃ�8��22��(��)�܂ł�6�T�ԁB�܂��A���łɉ��ꌧ�ɔ��߂���Ă����ً}���Ԑ錾���A8��22��(��)�܂ł̍ĉ���������B���͊��Ԓ��A��ނ�J���I�P�����X�܂ւ̋x�Ɨv�����p�����A��^���Ǝ{�݂ւ̎��Z�v�����p�����Ă��܂��B�����ō���́A���X�i�[�����ꂽ�u�ً}���Ԑ錾�v�ɂ��Ă̈ӌ����Љ�܂����B
�������A�u�����c�c�܂����v�Ƃ����������ŁA�܂����������Ȃ��Ȃ�܂����B�ً}���Ԑ錾���o���Ă͉������A�܂��錾���o���Ƃ������������[�v�B�����ł����䖝�����Ă���̂ɁA���H�X�������^�[�Q�b�g�ɂ���Ă���̂��[���������Ȃ��ł��B���̂܂܂��ƁA�R���i��{���ɏI��������C���Ȃ��̂ł́H �Ǝv���Ă��܂��܂��B�ł��O�����ɑ����Đ������Ă��������Ȃ������ł��ˁc�c�B
�����ꌧ�k���̊ό��n�G���A�ɏZ��ł��܂��B���ꌧ�́A�����Ƌً}���Ԑ錾�����ߒ��ł����A���݉����J���Ă��Ȃ��ŁA���H�X�̓e�C�N�A�E�g����B����ȂȂ��ł��~�J�����ɍ��킹�āA���O����̊ό��q�������Ă���C�����܂��B�����ɂ̓����^�J�[�������Ă��܂����A���암����k���Ƀ}�����X�|�[�c���y���݂ɗ��������A�}�X�N�����Ă��Ȃ��݉��ČR�̕ĕ�����A���̂��Ƒ����������܂��B����͓s��ɔ�ׂĐl�����x���Ⴂ���ƂɊԈႢ����܂��A�t�ɗ�������ꏊ�������Ă���̂Ől���W�����Ă��܂��B
����w���ł��B�����A�u������ꂽ�c�c�v�Ƃ����̂��{���ł��B���N���獡�܂ő�w�Ŏ����Ƃ�1���Ȃ��A���K�����~�B�T�[�N���̈��ތ������A�O��ً̋}���Ԑ錾��1�����O�ɒ��~�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�F�B�Ƃ���킸�A�Ƃ�1�l�Ŏ��Ƃ��āA�O�o�̓o�C�g�����ł��B�o�C�g�ő����̂��q����Ɛڂ��邽�тɁA�ǂ����Ă��ꂪ������āA�����̑�w�����͉䖝����Ȃ낤�c�c�Ǝv���Ă��܂��܂��B
�����H�X����ɕ��S�����������I ���������A�ً}���Ԑ錾�Ɋ���Ă��܂��Ď��Ȃ��l�������Ă���Ȃ��ŁA�錾���o���Ӗ����Ă���́H
�����W�̎d�������Ă��܂��B�ً}���Ԑ錾���낤���A�܂h�~���d�_�[�u���낤���A�����ς�炸�Ɏd�������Ă��܂��B�����ً}���ԂŁA�������ʂȂ̂��A�����킩��܂���B���W�Ȃ̂ɁA�R���i���N�`���̗\��ꂽ�̂��ŋ߂ł��B
����T���A�p���������ēs���ɏo���̂ł����A�H����݂����Ă���O���[�v�𐔑g�������܂����B�����������Ă��邹���������Ă��A�������ĕ����Ă��鎄�ɂ��������邭�炢�̑吺�Ń}�X�N�������ɂ���ׂ��Ă��āA����ʂ�߂���̂��|�������ł��B�ً}���Ԑ錾���Ăѓ����ɔ��߂���A���X�ł���������Ȃ��Ȃ��Ă��A���̂悤�ȘH����݂��Ȃ��Ȃ�Ȃ�����́A�����g����~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��ȂƊ����܂����B�錾���o���̂ł���A��������������������݂���K�v������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���ً}���Ԑ錾�B���͂���ʂ͋^��ł����A���߂����ΐ����ɏ]�킴��Ȃ��Ƃ��������̂Łc�c�B���̂����Ŏq�ǂ������̋M�d�Ȍo����A���܂��܂ȋƎ�̐l�X�̕�炵������ꂽ��A���т₩����Ă���ƍl����ƁA�ƂĂ��ς����܂���B���{����낤�Ƃ��Ă���g��炵�h�Ƃ́A��̒N�̂��̂Ȃ̂ł��傤���c�c�H
��4�x�ڂ̔��߂��u����ς�ˁv�݂����Ȋ��o�ł����A�o�ϓI�ɂ����Ȃ茵�����Ƃ��������̂ŁA��������������炸�ɊO�H�E��y���y���߂�����̂ł́H
�������s�Ŋ������g�債�Ă��邩��錾���o�����̂ɁA�u�錾����v�Ƃ��u���l���v�Ƃ�������ƁA�����A�s�O�̐l�Ԃ��䖝�����Ċ����҂����炵�Ă��Ӗ����Ȃ��̂��ȁc�c�Ǝv���Ă��܂��܂��B
����ޒX�Ƃ̎�����~����悤�ɁA�̔����Ǝ҂֗v���������ǁc�c�v�́u�����ƒ��ǂ������炨�O�̂��Ƃ��C�W���邩��ȁv���Ă������Ƃł���H ����A�����������ˁc�c�B
���ً}���Ԑ錾�c�c���\�Ȍ������ł����A�錾���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�ǎ��̂Ȃ���l�����̍s���ɑ��Ă��Ǝv���܂��B�q�ǂ������͈��݂ɂ�������A�H��ʼn��������킯�ł�����܂���B�q�ǂ������̃X�|�[�c�̑��≉�t��A���\��Ȃǂ��ł����A�w�Z�����ʼn䖝���������A��Q���Ă���͎̂q�ǂ������ł��B���H�X�̖����肪���グ���Ă��܂����A�܂��͎q�ǂ������̂��Ƃ��l���A��l�����̍s�������炽�߂邱�Ƃ��d�v���Ǝv���܂��B���̔��f�ɂ������������Ƃ͂���܂����A�������ɂ��ӔC������Ǝv���܂��B
�����Ŏq�ǂ��ɃX�|�[�c�������Ă��܂��B�s�̌����{�݂�w�Z�̑̈�قł����Ȃ��Ă���̂ŁA�ً}���Ԑ錾���͂����Ƃ��x�݂ł����B�q�ǂ������̃��`�x�[�V�������������Ă��܂��A��߂Ă����q�������܂����B������̎������[���ɂȂ�܂��B�������������̂ŊO�o�����܂���B�ً}���Ԑ錾�Ő����������ς��Ȃ��l�������Ǝv���܂����A����ŁA�������܂������Ȃ��Ȃ�l������̂ł��B
�����͎q�ǂ����ɋΖ����Ă���̂ŁA�s�S�ɂ����̂Ƃ���ɖ���A��ďo������͍̂T���Ă��܂��B��������������������A�Ζ���͋x�����邱�ƂɁB200�l�ȏ�̍݉����̂��Ƒ��A�E���ɖ��f�������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B�ł��A�����Ɖ䖝���Ă����̂ɔ��Ă��܂����B���̉Ắu�s�S�̕�̂Ƃ���Ɉ��S���čs����͂��v�Ɗ撣���Ă����̂ŁA4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ƂȂ藎�_���Ă��܂��B��l�ЂƂ�A�����������͂��v������čs�����Ă݂܂��H
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���_�ސ쌧�A�ً}���Ԑ錾�v���������@�����ҋ}���A���Ǝ��̔��߂�����@7/16
�_�ސ쌧���̐V�^�R���i�E�C���X�����ҋ}�����A�����u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ώۋ��̑S���g���{�ւ́u�ً}���Ԑ錾�v���ߗv�����������Ă��邱�Ƃ�15���A�����̊W�҂ւ̎�ނŕ��������B
�߂����{����c���J���A�Ή������c����B
15���̌����̐V�K�����Ґ���403�l�ŁA1��28���ȗ��A�N�Ԃ��400�l���������B�ŋ߂�300�l������������A����������6�w�W�̈�̐V�K�����Ґ��͍���14���A�ً}���Ԑ錾���߂̖ڈ��ƂȂ�X�e�[�W4(�����I�����g��)�Ɉ��������B
���͏d�_�[�u���ĉ������ꂽ12���ȍ~�A�Ώۋ������l�A���A���͌��A����4�s�ɏk�������B�������A�L�͈͂Ŋ����҂��}�����Ă��邱�Ƃ���Ώۋ��̑S���g���ً}���Ԑ錾�̔��ߗv�����������A���Ȃǂƒ�����i�߂Ă���B
�ɂ���Ă͌��Ǝ��ً̋}���Ԑ錾���߂�����ɓ���Ă���Ƃ����B
���_�ސ삪�ً}���Ԑ錾�v�������@15����403�l�����@�ܗ֍T���l�����l���@7/16
�_�ސ쌧���V�^�R���i�E�C���X�����g����A���{�ɋً}���Ԑ錾�̔��߂�v����������Ō����ɓ������B���W�҂�16���A���炩�ɂ����B�߂����{����c���J���A�Ή������c����B�����I�����s�b�N(�ܗ�)�̊J�Â��T���A�l���̑������l�������Ƃ݂���B
�����ł�15���A403�l�̊������V���Ɋm�F���ꂽ�B1��������̊����Ҕ��\����400�l����̂́A1��28���ȗ��ŖN�Ԃ肾�����B7���ɓ�����300�l������������A����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��̓X�e�[�W4(�����I�����g��)�ƂȂ����B
���͂܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ12���ȍ~�A�Ώۋ������l�A���A���͌��A����4�s�ɏk�����Ă����B
�����Α�̊ϗ����l���Ăт����@�ً}���Ԑ錾���@7/16
�I�����s�b�N�J�Ê��Ԓ��A�����̗ՊC���ɐ����Ƃ�����܂��B�g�D�ψ���͂��̐��Α���ӂł̊ϗ����l���Ăъ|���܂����B�I�����s�b�N�̐��͊J���ɗՊC���ɂ��閲�̑勴�ɐݒu����鐹�Α�Ɉڂ���A�Ƃ�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�ՊC���ɂ̓X�|�[�c�N���C�~���O�Ȃǂ̋��Z��ꂪ�W�܂��Ă��Đ��Α���ӂł͑����Ԓ��A�����̃C�x���g���J�����ق��A���H�Ȃǂ������v��ł����B�������A�����s�ɋً}���Ԑ錾�����߂��ꂽ���Ƃ��A�g�D�ψ���͐��Α�̊ϗ����l���Ăъ|���邱�Ƃ����߂܂����B
�l���W�܂�Ȃ��悤�ɐ��Α���͂��悤�ɍݒu����A���Ԓ��͌x������z�u���ĕ��U����悤�ɐ��|�����s���Ƃ������Ƃł��B
����ʓ암�A�u�����R���v�̊��������c�ً}���Ԑ錾�̍Ĕ��ߗv���� �@7/16
��ʌ������V�^�R���i�E�C���X�����́u��5�g�v�ɓ������Ƃ݂��钆�A�����A���݂͂������܁A�����2�s�Ƃ��Ă���u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�����A�g�傷������Ō������Ă���B���ɓ����s�ɋߐڂ��錧�암�Łu�����R���v�Ƃ݂��銴���҂��������Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���B���͍���̊�������ł́A�����ł������Ɠ��l�A�ً}���Ԑ錾�̍Ĕ��ߗv���������Ȃ��l�����B
�����ł�15���A328�l�̐V�K�����҂��m�F����A���N�O��1��22����358�l�Ɏ��������ƂȂ����B
���m����15����A�������Ɗ����ɂ��ċ��c�����B�I����A�o�Ȏ҂̈�l�́u�����g��̃X�s�[�h�������B�ڂɌ�����`�ŋ����[�u���u����K�v������v�ƌ�����B
�����ł����O���Ă���̂��A�����҂�2���A����1000�l���������ւ̒ʋE�ʊw�ȂǂɋN�����銴���̑������B�u�����R���v��6�����{�ȍ~�A�������Ƃ��čő��́u�ƒ���v�ɕC�G���鐅���ɋ߂Â��Ă���B6��17�`23����1�T�Ԃ�114�l�����������҂́A��24�`30���ɂ�147�l(�O�T��29����)�A7��1�`7���ɂ�184�l(��25����)�Ƌ}�����Ă���B
���ہA�����ɋߐڂ��A�x�b�h�^�E���Ƃ��ēs���Ƃ̐l�̉������������암(�˓c�A�����A�u�A�a���A�V���A�ӂ��ݖ�s�Ȃ�)�̊����҂̑������������B1��������̕��ϊ����Ґ��́A�a���s��5��1���`6��20����2�E06�l����A6��21���`7��6���ɂ�2�E94�l�ƁA42�����������B�ӂ��ݖ�s�ł�1�E90�l����2�E63�l�ƁA38�����ƂȂ����B
���͓����Ƃ̉������T����悤�����ɋ��߂邪�A�s�������ԉ����ӂ��ݖ�s�ł�����������Œr�܂܂ŕГ���30���ōs�����ł��A�������ł��u�����E�o�ό����d�Ȃ��Ă���A�����Ȃ��肢���v�Ƃ̐����オ���Ă���B�����Ŋ������Ď����A���Ă���P�[�X�������Ƃ݂��A�������́u�������犴�������ݏo���Ă���v�Ɗ�@���������B
���͏d�_�[�u���̊g������Ɋ����Ȃǂ𒍎�����\�������A���������ł̑�ł͌��E�����邱�Ƃ��I�悵����B��s����̂ł̑s���Ƃ��āA�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ���A���{�ɑ���ً}���Ԑ錾�̍Ĕ��ߗv���ɓ��ݐ�\�����B
����16���A���Ƃ̈ӌ����l�������A�[�u�����ƂȂ�Ό�����̕��S�͂���ɏd���̂������邱�ƂɂȂ�A������Ƃ̊Ԃœ�����f�𔗂�ꂻ�����B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���_�ސ쌧�A22���ɓƎ��́u�錾�v�c���{�Ƃ̐��ʉ��̒����܂荇�킸 �@7/17
�_�ސ쌧��16���A�V�^�R���i�E�C���X��́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑Ώےn����A���݂̉��l�A���A���͌��A����4�s����A���쑺�����������S��(32�s��)�Ɋg�債�A���H�X�ł̎�S�ʒ�~�����߂�Ǝ��́u�_�ސ�ŋً}���Ԑ錾�v�߂��邱�Ƃ����߂��B22������K�p����B���Ԃ́A�d�_�[�u�Ɠ���8��22���܂ł̗\��B
�����ܗ֊J����O�ɁA�l�̗����}�����邽�߂ɋ����K�v�Ɣ��f�����B�����A���{�ɋً}���Ԑ錾�̔��߂�v�����邱�Ƃ��������Ă������A�W�҂ɂ��ƁA���{���Ƃ̐��ʉ��̒����Ő܂荇�킸�A���������Ƃ����B�����A���̓������ŊJ���ꂽ���{����c�ł́A��������������Ή��߂ėv������������Ƃ����B
�����̐V�K�����҂�16����446�l���m�F����A2���A����400�l�����B
���ً}���Ԑ錾���߁I�@�E��̐l�ԊW���C�ɂ���̂͋��̍����ł���@7/17
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ɏ��~�߂�������܂���B�����ɂ�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����߂���܂����B���̂悤�Ȓ��A�������̐������܂����������̂ł͂Ȃ����ƕs�������鐺��������Ă��܂��B���A�E��̐l�ԊW�ŋC��t����ׂ����Ƃ͉��ł��傤���B
����́A���_�Ȉ�Ńx�X�g�Z���[��Ƃ̊�������ɁA�ǎ��ȁu�E��̐l�ԊW�v��z�����߂̃q���g�ɂ��Ďf���܂��B�ߒ��Ɂu�����������Ɗy�����Ȃ�s���œK����S�v(KADOKAWA)������܂��B
�E��̐l�ԊW�ŔY��ł���l�͔��ɑ����A�r�W�l�X�p�[�\���̃X�g���X��9���͐l�ԊW�Ƃ������Ă��܂��B�t�ɂ����A�E��̐l�ԊW�������܂������A���X�A�y�����d�����ł���悤�ɂȂ�܂��B����͎��̂悤�ɉ�����܂��B
�u�l�ԊW�������ƃV���v���ɍl���Ă݂܂��傤�B���͐E��̐l�ԊW�͏d�v�ł͂Ȃ��̂ł��B�E��ɂ��Ȃ����U��������A�����点�������肷��w�U�����l�x����l�ł�����ƁA���̂������J�T(�䂤����)�ȋC���ɂȂ�ł��傤�B�E��̐l�ԊW�͋ɂ߂ďd�v���ƍl����l�������̂ł����A���́A���Ȃ��̐l���ɂ����Ă��قǏd�v�ł͂Ȃ��̂ł��v(����)
�u���ہA���̌�F�W���݂�ƁA�E��Œm�荇���Ă��猻�݂܂�10�N�ȏ��F������l�͈�l�����܂���B�E��̐l�ԊW�Ƃ́w��x�Ɋ֘A�t����ꂽ�A�ꎞ�I�ň�ߐ��̐l�ԊW�ł��B���ɂ��Ȃ�����Ђ����߂��ꍇ�A�X�g�[�J�[�̂悤�ɒǂ������Ă��邱�Ƃ͂���܂���B�U�����l�͉�Ђ������o��A�A�J�̑��l�ł��v
�������A�Ώ����@�͊ȒP�ł͂���܂���B�E��ł̕s���ȏo�����͊m���ɏĂ��t�����ċꂵ�ސl�����Ȃ��Ȃ�����ł��B����́u���͂��Ȃ��U�����l�̂��Ƃňӎ���D���Ă���Ƃ����Ȃ�A���Ȃ����g�ŏ�������Ă���̂Ɠ������v�ƌ����܂��B
�u�S���w�́w�ΐl�W�Ö@�x�ł́A�ł��d�v�Ȑl�ԊW�͉Ƒ�����l�A�p�[�g�i�[�ł��B���ɏd�v�Ȃ̂͗F�l�B�d�v�x���Ⴂ�̂��E��̐l�Ɖ��߂���Ă��܂��B�����䗦�ŕ\���Ɓw5��3��2�x�ƂȂ�܂��B�܂�A�Ƒ���F�l�Ƃ̐l�ԊW�����肵�Ă���A�l�ԊW��8���͈��肵�Ă���Ƃ������Ƃł��v
�u�����l����A�E��̐l�ԊW�������K�^�K�^���Ă��A��Ђ����߂�K�v�ȂǑS���Ȃ��̂ł��B�E��̐l�ԊW�ɒ��ӂ�D����ɂ�����̂Ȃ�A�Ƒ���F�l�������Ƒ�ɂ��܂��傤�B�����āA�Ƒ���F�l�ƌ𗬂��鎞�Ԃ𑝂₵�A�����������₵�̎��Ԃ�ʂ��āA�X�g���X�U����������ł��v
���̂悤�ȁA���_�����̋���������܂��B�u10�l�̐l������Ƃ�����A���̂�����1�l�͂ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ���ᔻ����B���Ȃ��������Ă��邵�A����������̐l�̂��Ƃ��D���ɂȂ�Ȃ��B�����āA10�l�̂�����2�l�݂͌��ɑS�Ă����ꍇ����e�F�ɂȂ��B�c���7�l�͂ǂ���ł��Ȃ��l�X���v�Ƃ������̂ł��B
�u�����4000�N�O����`��郆�_���l�̒m�b�ł����A���͂��̋�����m��O����A�����̌o���Ɋ�Â��ē������Ƃ��Z�~�i�[�Řb���Ă��܂����B10�l������A���Ȃ��������l��1�l�A���Ȃ����D���Ȑl��2�l�A�ǂ���ł��Ȃ��l���c���7�l�ł��B���Ȃ��̉�Ђ⏊�����Ă���O���[�v�����Ă��A�قڂ��̊����ł͂Ȃ��ł��傤���v
�u�d�v�Ȃ̂́A�ǂ��̐E��A�`�[���A�R�~���j�e�B�[�Ɉړ����Ă��w�����������l�x�w�\���̍���Ȃ��l�x�͕K������Ƃ������Ƃł��B�܂��A�悭�ώ@����ƁA����2�{�ȏ�̖����A�����̉����҂�����̂ł��B��������́w�D�ӂ�1��2��7�̖@���x�ƌĂ�ł��܂��B10�l�S�Ă��猙���邱�Ƃ��Ȃ���A10�l�S�Ă���D����邱�Ƃ�����܂���v
�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�����̐l�́u�݂�Ȃƒ��ǂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝv������ł��܂��B���ۂ́A�݂�Ȃƒ��ǂ�����K�v�ȂǂȂ����Ƃ��悭������܂��B
�u��Ђ́w�d��������ꏊ�x�ł����āA�w���ǂ��O���[�v�x�������ł͂���܂���B�Œ���̎d���ɍ����x���̂Ȃ��R�~���j�P�[�V����������Ώ\���B�d����̃h���C�ȊW�ł����̂ł��B�������A���l���̋C�̍����l�ƒ��ǂ�����̂͂悢�Ǝv���܂��B�������A�����ɑS���ƒ��ǂ�����K�v�ȂǑS���Ȃ��̂ł��v
�u���͎����������l�������ꍇ�A�w�����A10�l��1�l�������ɂ����̂��x�Ǝv�������ŁA�X���[���܂��B��������̐l�Ɖ�Ή�قǁA���̊m���ŏo������U�����l�B���Ȃ��̐��_�G�l���M�[�Ƒ�Ȏ��Ԃ́A���Ȃ��������l�̂��߂ł͂Ȃ��A���Ȃ��ɂƂ��đ�Ȑl�̂��߂Ɏg���ׂ��Ȃ̂ł��v
�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŁA�������̓���͑傫���ω����܂����B���āA�E��̐l�ԊW�ŋC��t����ׂ����Ƃ͉��ł��傤���B���ȑ���ɂ́u���肪�Ƃ��I�v�Ɛ��������A���ʂ݂̏ŃX�|�C�����܂��傤�B���̋@��ɁA�K�v�ȍs�����w��ł݂܂��B
���g�ً}���ԁh�����j�̐l�o�@��̔ɉ؊X�͌����@7/17
������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o����čŏ��̋��j����̔ɉ؊X�̐l�o�́A1�T�ԑO�����������܂����B
�g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^�ɂ��܂��ƁA16���ߌ�8����̓s���̔ɉ؊X�̐l�o��1�T�ԑO�ɔ�ׂďa�J�Z���^�[�X��5.9���A�V�h�E�̕��꒬��13.5���A�V����21.5���A�Z�{��20���������܂����B
����A�ߌ�3����̐l�o�͉H�c��`�������^�[�~�i����7.6���A�����w��1.2���������܂����B
�����ł�3���A���ŐV�^�R���i�̐V�K�����Ґ���1000�l���Ă��āA���ȉ�̔��g��͉ċx�ݒ��̌������z����ړ����T����悤�Ăт����Ă��܂��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
��2�x�ڂً̋}���ԑO���l�o��30�����@�����A�C�|����ȑ�5�g�@7/18
�������ւ̂܂h�~���d�_�[�u����������ď��̏T���ƂȂ���17���A�����s�̔ɉ؊X�͔�������W���[���y���ސl�łɂ��킢���������B�u����v���߂���邱�Ƃ����}���鐺���オ�����A�����Ґ��̃��o�E���h�ւ̌��O���@�����A�s���̐��������ꂽ�B
�����s�E�V�_�̌�����3�J���Ԃ�ɑ��ƖK�ꂽ���s�̒|���Y����(75)�́A�d�_�[�u�̉����܂ł͂Ȃ�ׂ��O�o���T�����B��(5)�������ŗV�Ԏp�����āu�����X�g���X�����܂��Ă����͂��B�O�V�т��ł��Ă��ꂵ���v�ƂقُB
JR�����w�O�ŗF�l�ƒ��H���ς܂����k��B�s���q�k��̒j����Ј�(36)�́A���H�X�X�Ɋ��C���߂��Ă������Ƃ����}���Ȃ�����u�e�[�u���Ɏd����Ȃ��X��������ہB�����g��̑�5�g�����Ȃ����A�C�|���肾�v�Ƙb�����B
NTT�h�R���̃f�[�^��͂ɂ��ƁA�V�_���ӂ�17���ߌ�3�����݂̐l�o�́A�����g��O�Ɣ��11�E2��������������A2�x�ڂً̋}���Ԑ錾���������ɏo�����O�̍��N1��7���Ɣ�ׂ��30�E8�����������B
���ܗ�A2400�l�������u���ꂭ�炢�Ȃ���v�v�@�J�Ò��~�̑I�����Ȃ��@ 7/18
�V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾���ł̓����ܗ֊J���܂�1�T�Ԃ�����B�����s�ł�17���܂�4���A���ŐV�K�����҂�1000�l����ȂǁA�����͖��炩�Ɉ����X���ɂ���A���̒��~�����߂鐢�_�͍������B�������{�ɂ́A����Œ��~����������l���͊��ɂȂ��A���̂܂܊J�����}������j���B
���`�̎�16���A���{�̓����ܗցE�p�������s�b�N���Z���i�{���̉�Łu���S���S�̑��̎����Ɍ����čŌ�܂ō����ْ����������Ď��g��łق����v�Ƙb�����B17���̓ǔ��e���r�ԑg�ł́u���Ƃ����ϋq�ł��A�����𐢊E�ɓ͂���B��ǂ����z������Ɣ��M���邱�ƂɈӋ`������v�Ƌ��������B
15���ɊJ���ꂽ�s�̃��j�^�����O��c�ł́A�V�K�����҂̑��������̃y�[�X�ő����A�ܗ֕������8��11���ɂ͒���1�T�ԕ��ςŖ�2400�l�ɒB����Ƃ̎��Z�������ꂽ�B�������{�����́u���ꂭ�炢�Ȃ���v�B���~�͂Ȃ��v�ƈӂɉ�Ȃ������B
�ܗ֊J�Âɂ��ẮA������3�x�ڂً̋}���Ԑ錾���ɂ�����6��2���̎��_�ŁA���{�̐V�^�R���i�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή���u���̏ł��̂́A���ʂ͂Ȃ��v�Ǝw�E���Ă����B���u�����̖��ƈ��S�����͎̂��̐Ӗ��B���Ȃ��Ȃ�������Ȃ��͓̂��R�v�ƁA���~�̉\����ے肵�Ȃ������B
�����A����ȍ~�A�͋L�҉�ȂǂŁA�ǂ̂悤�Ȋ����ɂȂ�Β��~����������̂��Ƃ��������m�Ȕ��f����������Ƃ͂Ȃ������B
�����٘A��̉F�s�{�����ٌ�m��15���A�C���^�[�l�b�g�ŏW�߂����~�����߂�45�����̏������父�Ăɒ�o�����B
���̏������A�������M���[������16���̉�Łu���S���S�ȑ��v������������j�����߂ċ��������B��������i�ƈ��������ꍇ�A�����Ԓ��ł����~�����蓾�邩�Ƃ̖₢�ɂ́u�厖�Ȃ��Ƃ͑����̊����ɑ��Ă�������ƑΉ����A���N�`���ڎ��i�߂邱�Ƃ��v�Ƙb���ɂƂǂ߂��B
���^�ً̋}���Ԑ錾���K�v�@���喼�_�����E���n�L�s�@7/18
�V�^�R���i�Ђ̓��X�A���҂������đ����ƂȂ�Ɓu�ً}���Ԑ錾�v���߁B���炭���Ă���̉����A�܂����߁A�܂������c�Ƃ������Ƃ̌J��Ԃ��B�l�X�͂���Ɋ���Ă��āu�ً}���Ԑ錾�v���o�Ă��A���A�����A�Ƃ��������x�̊����B�Ȃ�Ƃ��^�����Ɍ����Ă���B�������̎��Ԃ��A�Ⴆ�A����ɂ����{�ւ̍U���ł���Ƃ���ƁA���s�́u�ً}���Ԑ錾�v�ȂǂƂ����_(���)�Șb�ł��ނł��낤���B�����������ƗL���̂Ƃ��́A���{�������A��ʍ��Ƃł́A�܂��͉����߁A�����ČR�̓����ƂȂ�̂����ʂł���B�������A���{�ł͂��ꂪ�ł��Ȃ��B
�Ȃ����B�����͎��́A�݂Ȃ��悭�m���Ă���B���Ȃ킿�A��̑��ɔs��A�����҂̃A�����J���̌R�ɂ���Č����@�����������A�R�������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A���R�A�����߂����ł�����ꂽ�B���Č���B���{���ӂ̏������{�́A���Ȃ̐����ێ��ɕK���ł���B�Ⴆ�Β����B�K�ߕ����Ǝ�Ȃ͎��ȗi��ɑS�͂�s�����Ă���B�S�������̊���������A�f���ɂ��̒n�ʂ𑼎҂ɏ���ςނ��̂��A�������i���g���ďK�����̈ێ���}���Ă���B
�ނ�̎�@�͓���B�Ⴆ�ΐ������ꂵ���Ȃ�A���{�ᔻ�̐������܂��Ă���ƁA���ӂ̊O���ɂ��̌���������ƌ������āA�����ւ̕s�����O���ᔻ�ɋ�(��)�������A���̂��ׂĂ̌����������֏W�������Ă䂭�B���̓T�^�Ƃ��ā���t��������{�͕s�@��̂��Ă��遄�ƖҐ�`���邱�Ƃł��낤�B���������͍s�g�����Ă���B���̂Ƃ��A���{���{�͂ǂ�����̂��B�܂Ƃ��ȕ���͂���̂��B�����炭�u�b�������𑱂��悤�v�Ƃ����_�Șb���ւ̎R�B����ł͛�(��)�̓˂�����ɂ��Ȃ�Ȃ��B����͂킪���̗̓y�ɏ㗤���Ă���\��������B
�Ƃ���A�R���i�Ђ̍��Ȃ�������{�́u�ً}���Ԑ錾�v�̎��������s���ׂ��ł���B���Ȃ킿�܂������߂Ɋւ���@�������s�����Ƃł���B�吳12(1923)�N�A�֓���k�Ђ̂Ƃ��A�����{(����)�A�����āA�_�ސ�E��t�E��ʂ�3���ɑ��āA���{�ً͋}���߂Ɋ�Â��A������u�s�������v��鍐�����B���Ȃ킿�A�����̍s�����E�i�@���̈ꕔ���~���A������R�̎i�ߊ��Ɉ�(�䂾)�˂��̂ł���B���R�A�����q���𐳎��ɌR�Ƃ��Ė@���ŋK�肷�ׂ��ł���B
���đ��݂������{�R�������߂��A���҂ƂȂ�����̌R�ɂ���Ĕp�~���ꂽ���A���{���܂Ƃ��ȍ��ƂƂ��ė��Ē����ɂ́A�R�Ɖ����߂��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���A�R���i�Ђ̒��ɂ�������A��v���͂��ĕK�v�Ƃ���@�����ׂ��ł͂Ȃ��̂��B���s�́u�ً}���Ԑ錾�v�ɂ͐^�̋����͂��Ȃ��A�o������������߂��肳��Ă���p�́A���S(�ނ���)�B���{�l�͒c�������ӁB���̓����̉��A�@���������ׂ����B
�w���q�x��n�ɞH(����)���A���̏M�������āk����l��(�킽)��ɓ�(����)��A���ɋ�(��)�ӂ�A���̑�(��)�Ћ~(����)���邱�ƍ��E�̎�̂��Ƃ��A�ƁB�@
���ً}���Ԑ錾�Łg�e�����[�N���h�̌X�� �u�ǓƊ��v�u�a�O���v������l���@7/18
�ً}���Ԑ錾�Ő��{���o�ΎҐ���7���팸�����߂�Ȃ��A�g�e�����[�N���h�̌X���������Ŗ��炩�ɂȂ����B
����1100�l��Ώۂɍs���������ɂ��ƁA�T��3��ȏ�e�����[�N�������l�̊�����42.4���ŁA���N5���ɒ������n�߂Ă���ł��Ⴂ�����ɂȂ����B�e�����[�N�Łu�������オ�����v�u���オ�����v�Ɠ������l�̊����́A���N5���ȍ~�����X�������������߂Č����B�܂��u�e�����[�N�̉ۑ�v�Ƃ��āu�ǓƊ��v��u�a�O���v���������l��2���ɂ̂ڂ�A1���䂾�������N���瑝�������B
�������������{���Y���{���́A�����l�Ɂu�e�����[�N���v���L�����Ă��āA����V�^�R���i�̊������g�債�Ă��e�����[�N���傫���i�މ\���͒Ⴂ�Ƃ݂Ă���B
��4�x�ځu�ً}���Ԑ錾�v���̏T�� �����̐l�o�́E�E�E�@7/18
������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o�ď��߂Ă̓y�j���ƂȂ���17���A�����̊X�̐l�o�͂����ނˌ������܂����B
17���ߌ�3���̐l�o��O�̏T�̓y�j���Ɣ�ׂ��Ƃ���A�a�J�Z���^�[�X�Ń}�C�i�X28�D4�p�[�Z���g�A�����Ń}�C�i�X19�D5�p�[�Z���g�A�Ń}�C�i�X15�D7�p�[�Z���g�A�V���w�Ń}�C�i�X15�D1�p�[�Z���g�ȂǂƁA�����ނˌ������Ă��܂��B
����A��X�،������v���X44�D2�p�[�Z���g�Ƒ啝�ɑ����B�܂��A�H�t���w�Ńv���X5�D5�p�[�Z���g�A���h�w�Ńv���X3�D6�p�[�Z���g�ȂǂƁA�킸���ɑ����Ă���n�_������܂����B
��4�x�ڋً}�錾�㏉�̓y�j�A�����̐l�o�͌����ݑ����@7/18
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��h�~���߂���12������4��ڂً̋}���Ԑ錾�����߂��ꂽ�����s���ŁA���ߌ㏉�̓y�j���ƂȂ���17���̐l�o���A���N1����2��ځA4����3��ڂً̋}���Ԑ錾����̏T���Ɣ�ׂČ����ݑ����������Ƃ��A�V�X�e����Ёu�A�O�[�v�v�����\�����X�}�[�g�t�H���̈ʒu������ɂ����l�o�f�[�^�̕��͂ŕ��������B
�A�O�[�v�̃f�[�^���͂ɂ��ƁA�i�q�V�h�w���ӂł́A����17���ߌ�0����̐l�o�̕��ς��A2��ڂً̋}���Ԑ錾�����߂���ď��̓y�j��������1��9���̓����ԑтɔ�ׂ�1.3�{�������B�����ł�1.7�{�A�������g������w���ӂ�1.2�{�ƂȂ��Ă����B
4��25����3��ڂً̋}���Ԑ錾�����߂���ď��̓y�j���ƂȂ���5��1���̓����ԑт��݂Ă��A�V�h�w���ӂł�1.5�{�B�����ł�2.3�{�Ɠ��ɒ������A����w���ӂ�1.6�{�ƂȂ����B
�s���ł͊����Ґ��̑����Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B����23���ɊJ����s���铌���ܗւ�O�ɁA���łɐl���}��������Ȃ��Ă���������ԁB
�������t�̎x����35���͉ߋ��Œ�@7���߂����u�ً}���Ԑ錾�Ɍ��ʂȂ��v�@7/18
�����ʐM�Ђ�17�A18�����Ɏ��{�����S���d�b���_�����ɂ��ƁA�����t�̎x������35�D9���őO��6����������8�D1�|�C���g�������A��N9���̓��t�����ȍ~�Œ�ƂȂ����B�s�x������49�D8���Ő����t�Ƃ��čł������A�x������13�D9�|�C���g�������B�����ܗցE�p�������s�b�N�ɂ��V�^�R���i�E�C���X�������g�傷��s�������Ƃ���A�u������x�v���܂߁u�s���������Ă���v�Ƃ̉��v87�D0���ɏ�����B
���{�������s�ɔ��߂���4�x�ڂ̐V�^�R���i�ً}���Ԑ錾�ɂ��āu���ʂ�����Ǝv���v��29�D4���A�u���ʂ�����Ǝv��Ȃ��v��67�D9���������B��ނ������H�X�Ƃ̎����~�v�������鍬���Ɋւ��u�ɐӔC������Ǝv���v��72�D3���B�����N���o�ύĐ��S�����ɂ��āu���C����ׂ����v��26�D1���������B
���ό��ƊE�A�������Ă̓����@4�x�ڋً}���ԂɌܗ֖��ϋq�c�u�⏞���v�@7/18
�����s�ɔ��߂��ꂽ4�x�ڂƂȂ�V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾(8��22���܂�)���A�敾�����ό��ƊE�ɒǂ��ł��������Ă���B4�x�ڂ̐錾�́A�������ꎞ�̉ċx�݃V�[�Y����23���`8��8���̓����ܗւ��B�ܗւ͑啔���̋��Z���Ŗ��ϋq�J�ÂƂȂ邱�Ƃ������A�s���̃z�e���ł͊ϋq��̃L�����Z�������������B�����ƂȂ�����N�ɑ����A���N���������u�Ă̓����v�B�ς����˂��W�҂�͍��ɋ����⏞�����߂Ă���B
�u���N�����I�����s�b�N���Ɛщ̂��������ɂȂ�Ǝv�����̂Ɂc�v
�ܗւ̋��Z����{�݂��W�����铌���E�L�����ӂɂ���z�e���̒S���҂́A�����R�炵���B
��N��7�A8���͑S��300�����������������A�R���i�Ђɓ˓�������N�͔����ȉ��̋q���ɁB�����Ċ��҂����ėՂ��āB���ϋq�J�Â�����8���Ɍ��肷��ƁA9�A10�̗����ɂ��ꂼ�ꐔ�S�����̗\��L�����Z���̓d�b���������Ă����Ƃ����B
�s���ŏ\���X�܂�W�J����z�e���`�F�[����\�̒j�����u�ǂ��̓X�܂ł��L�����Z�������o���Ă���v�Ƃ��ߑ������B�K���q(�C���o�E���h)�̗��p�������������Ƃ���A��N2���ȍ~�͋q���ғ�����3�������̏B�ܗ֓��������҂��Ă��������ɁA�c�O�ȋC�����͑傫���B
�j���ɂ��ƁA�ό��n�ƈ���ēs���̃z�e���̓C���o�E���h��n���̋q�����S�̂��߁A�Ƃ�킯�_���[�W���傫���Ƃ����B�u�⏞���Ȃ���Όo�c�ێ��͂����ł��Ȃ��v�ƌ�����B
�{���͌ܗւ��牶�b����͂��������u�I�t�B�V�����p�[�g�i�[�v����O�ł͂Ȃ��B�ϐ�`�P�b�g�t���̌����c�A�[��̔����Ă����j�m�s�\�b�s�z�[���f�B���O�X�A�i�s�a�A�����g�b�v�c�A�[�Y�̗��s���3�Ђ͖��ϋq�J�Ì����A�c�A�[�̒��~�ƕԋ��\�����B���O�̒��~�̂��߁A�h����̃z�e���̃L�����Z�����S���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ꂪ����Ƃ����B
8���ɍs��ꂽ���{���s�Ƌ���(�i�`�s�`)�̋L�҉�ł��A�⏞�����߂鐺�����������B�����L�s���(�i�s�a�)�͗��s��Б��Ɋϐ�c�A�[�̃L�����Z�������S�����������ꍇ�A�u���ɕ⏞�����߂Ă������Ƃ��l�������v�Ƃ����B
�e�ԏ��ᕛ�(���[���h�q��T�[�r�X�)�́u�ό��ƊE�ɂ͕⏞���S���Ȃ��v�ƌ�C�����߂��B����ɍ��Ăƈ���č��N�͐��{�̊ό��x����u�f���@�s���@�g���x���v�����S�ɒ�~����Ă��邽�߁A��茵�����ƂȂ邱�Ƃ��\�z�����B�u�⏞�ƃZ�b�g�łȂ���A����ȏ�͑ς����Ȃ��v
����A���͌ٗp�����������ȂNJ����̎x����̊��p���J��Ԃ����߂Ă���B�ό��������́u�z�e���ɂ͉c�Ǝ��l�⎞�ԒZ�k�����߂Ă��炸�A���H�X���l�ɕ⏞����͓̂���v�Ɛ����B����Ɂu�Ō����Ă���ƊE�͑��ɂ�����A�ό��ƊE��F�߂��������F�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���������̂͏d�X���m���Ă��邪�A����H�������Ăق����v�ƌ�����B�@
��������Ɍ���A�R���i�БO�ɖ߂�������A���܂܂̏���@7/18
�l����́A2020�N4������5���ɂ����ċ}���Ɍ��������B�V�^�R���i�E�C���X�̊�����1�g�g��ɑΉ����Đl�X�O�o�����l�����ق��A1��ڂً̋}���Ԑ錾���߂ɂ��L�͂ȋƎ�Ŋ�Ɗ������������ꂽ���߂��B������w�������Ă��A2020�N5���̌l����̓R���i�БO�̕��ϓI�Ȑ�������C��15%���x������Ă���B
�ً}���Ԑ錾���������ꂽ��A�l����͋}�������A2021�N�ɓ���L�єY��ł���B�N���͊�����3�g��2��ڂً̋}���Ԑ錾�̉e���A�t���͊�����4�g��3��ڂً̋}���Ԑ錾�̉e�����\�ꂽ���߂��B���N�̌l����́A�R���i�БO��5%���x����鐅���Œ�����Ă���B
������ς���A��N�̌l����ً͋}���Ԑ錾�̔��߁E�����ő傫���U�ꂽ���A���N�̌l����͐錾���߂ł����قǗ������܂��A�t�ɐ錾�����ł����قlj����A��i��ނŒ�����Ă���B���̔w�i�Ƃ��ẮA�ƌv���Ƃ������Ċg������O���Ĉ��̊������l�𑱂��Ă���e�������낤�B�܂��A���v�E�����̍\�����ω����A������j���[�m�[�}��(�V���)���}���Ă���\�����l������B
�l����̌����c�������ł́A���̓���̓���������K�v������B�ȉ��A�ƌv������p����2�l�ȏ㐢�тɂ��������x�o�z�̍��ڕʁA�i�ڕʂ̕ω����m�F���Ă݂悤�B
��r����̂�5���̏���x�o�z���B���N5���̏���x�o�z�́A1��ڂً̋}���Ԑ錾�ŋ}���ɗ�������N5����2��9046�~�A���ɂ���11.5%�������B�����A�R���i�БO��2019�N5����1��9838�~�A���ɂ���6.6%��������܂܂��B
�Ȃ��A2019�N5����10�A�x���ʂŗ�N��������x�o�z����U�ꂽ�_�ɒ��ӂ���K�v������B�����ŁA�ȉ��ł̓R���i�БO��5���f�[�^�Ƃ���2017�N����2019�N��3�J�N���ς�p����B����ƁA���N5���̏���x�o�z��3�J�N���ς�7358�~�A���ɂ���2.6%��������܂܂��B
���ߔ����̏���ڂŃR���i�БO�����������E�E�E
���������ƁA�R���i�БO���������̂��S59���ڂ̂���32���ڂŁA�ߔ������߂����̂́A�ꕔ�̍��ڂ�������A�S�̂̏���x�o�z�������������B
�ȉ��A(1)���N5���̏���x�o�z���R���i�БO��3�J�N���ς�傫�����������ځA(2)��N5���Ɉ�U��������A�R���i�БO�̐������݂֖߂������ځA(3)�R���i�БO��傫����������܂܂̍��ځA��3��ނɐ������Ă݂悤�B
(1)�R���i�БO��傫������������
���N5���̏���x�o�z���R���i�БO��3�J�N���ς�傫����������ȍ��ڂƂ��ẮA�u���̏��G��v�u�d������v�u�����ԓ��w���v�u�����H�i�v�u���ށv�u�ƒ�p�ϋv���v�u���{��y�p�ϋv���v����������B
���̂����A�u���̏��G��v�͍���W����N5���ɂ��Ȃ苭���A�R���i�В���ɉ������ꂽ�������s���ꂽ�\��������B�����A�ƌv�����͒����Ώې��ѐ������Ȃ����߁A�T���v���ɕ�(�o�C�A�X)�������Ă���\��������B
�܂��A�u�����ԓ��w���v�̓R���i�В���ɊO�o���l�⌸�Y�E�c�Ƌx�~�̉e���Ő摗�肳�ꂽ�����w���Ɏ������\�������邪�A�V�Ԕ̔��䐔�Ɣ䂵�Ă��Ȃ苭���A�T���v���o�C�A�X�̉e�����傫���Ƃ݂���B
���f���Ɋ�ׂȂ��u�d������v�̑���
�ȏ�̂悤�ɁA���N5���̏���x�o�͕����̃T���v���o�C�A�X���d�Ȃ��U�ꂽ���ʂ�����B�������A�����Ƃ��ċ������ڂ�����B�u�d������v��2�N�A���̑������B�i�ڕʂɌ���ƍ����V�w�d������������B�w���̃A���o�C�g�@��k���Ȃǂ�w�i�ɐe����̎x�������������Ƃ݂��A������Ŋ�ׂ�킯�ł͂Ȃ����̂́A�w���̏���k����}���Ă��悤�B
�u�����H�i�v��2�N�A���̑������B�O�o���l��O�H�X�c�Ək���̉e�����\��Ă���Ƃ݂���B�i�ڕʂł́A��N�̃R���i�В���͕ٓ��̐L�т��ڗ��������A���N�͑��ؓ��̑������ڗ��B
�u���ށv�͍�N�ɑ傫���������A���N�͌����������̂̏����ɂƂǂ܂����B�i�ڕʂɌ��Ă��S�ʂɓ��l�̌X�����B���i�ω����e�������\��������B
�u�ƒ�p�ϋv���v�y�сu���{��y�p�ϋv���v�͂Ƃ���2�N�A���ő��������B�i�ڕʂł̓p�\�R���A�e���r�A�d�C����@�A���̗�g�[�p���D���ŁA�S�ʂɃe�����[�N�ȂǍݑ�@��̑������e�������Ƃ݂���B
�e���r�ɂ��ẮA�n�f�W��ւ������10�N���o�߂��A�X�V���v���o�n�߂Ă���\��������B���̗�g�[�p���ɂ��Ă͋�C����@�ȂNJ��C���v�̑����f���Ă���\��������B�Ȃ��A��N���Ȃ苭�������G�A�R���́A�������ꕞ�����͗l�ŁA���N��������ł���B
(2)��U��������A���̐������݂֖߂�������
��N5���Ɉ�U��������A�R���i�БO�̌��̐������݂֖߂�����ȍ��ڂƂ��ẮA�u�ی���ÃT�[�r�X�v�u�ݔ��C�U�E�ێ��v�u�����ԓ��ێ��v�u���ӗށv�u���Ɨ����v����������B
�u�ی���ÃT�[�r�X�v�́A�o�Y���@���������S�i�ڂō�N���A���N���ƂȂ����B���Ɏ��Ȑf�Ñオ�������B��N�̃R���i�В���͊����ւ̕s������s�}�̎��Â�������铮�����o�����̂́A�����ǂ̑�◝�����i���N�͒ʉ@�@����Ă���Ǝv����B�Ȃ��A��Ȑf�Ñ�͎x�o�̖߂肪�݂��B
���X�|�[�c�≹�y�Ȃǂ̏K�����͖߂炸
�u�ݔ��C�U�E�ێ��v���S�ʂɍ�N���A���N���ƂȂ����B��N�͕s�}�̍H����������铮�����o�����̂́A���N�͉����B�Ȃ��A�ЁE�n�k�ی�����2�N�A���̑����ŁA�ЊQ���ɂ��ی��������㏸�����e�����傫���Ƃ݂���B
�u�����ԓ��ێ��v���S�ʂɍ�N���A���N���ƂȂ����B�K�\�����オ�����ŁA���v�ϓ������낤���A�K�\�������i�ϓ��̉e�����傫�����낤�B
�u���ӗށv�͑S�i�ڂɂ����č�N���A���N���ƂȂ����B��N�͏K�������T���铮�������������̂́A���N�͉����B�������A�x�����ɂ͔Z�W������A�����ԋ��K�����̓R���i�БO��������̂́A�X�|�[�c���ӂ≹�y���ӓ��͉�������܂܂��B
(3)�R���i�БO��傫����������܂܂̍���
�R���i�БO��傫����������܂܂̎�ȍ��ڂƂ��ẮA�u�O�H�v�u�p�b�N���s��v�u���۔�v�u��ʁv�u���Â���(�g�r�s��)�v�u���̋��{��y�T�[�r�X�v�u�m���v�u�h�����v����������B
�u�O�H�v�͑S�ʂɍ�N���A���N���ƂȂ������A�߂肪�ア�܂܂��B�O�o���l��c�Ɛ����ɂ��ꎞ�I�Ɏ��v���k�����Ă���ق��A�e�����[�N���y�ɂ��\���I�Ɏ��v��������Ă���ƍl������B�ł��x�o�z�����������̎�H�I�O�H�̓���͕s�������A��H�Ȃǂ̎��v��������Ă���̂ł͂Ȃ����B
������2�N�A���̌����ŁA�ω����ł݂�R���i�БO�Δ�Ŗ�9�����ƍł��������B�����Ǒ�ɂ��O�o���l��c�Ǝ��ԏk���A��ޒ������e�������Ƃ݂���ق��A�\���I�Ȏ��v�k�������낤�B�e�����[�N���y���@�ɁA��Њ֘A�̉���k�����Ă����ɁA�v���C�x�[�g�ł�������ݓI�Ȉ��݉�����Ă���B�Ȃ��A�w�Z���H�͍�N�啝�Ɍ���������A���N���Ă���A�x�Z�[�u�̉������e�������Ƃ݂���B
��2�N�A���Ō������Ă���u���Â����v
�u�p�b�N���s�v�y�сu�h�����v����N���A���N���ƂȂ������A�߂肪�ア�܂܂��B���s���l�̉e�����\��Ă��悤�B�u�p�b�N���s�v�̓���͍������s�ƊC�O���s�����邪�A�C�O���s�̎x�o�z��2�N�A���Ń[���~���L�^�����B
�u���̋��{��y�T�[�r�X�v����N���A���N���ƂȂ������A�߂肪�ア�܂܂��B�i�ڕʂɂ݂�ƁA�C���^�[�l�b�g�ڑ����������������̂́A����E�ϗ��E�Q�[���オ�S�ʂɗ�������ł���A�O�o�@��k���ɔ������v�V�t�g���ے��I�ɔ��f���Ă���B
�u���۔�v����N���A���N���ƂȂ������A�߂肪�݂��܂܂��B���^����������Ă���A�e�ʂ�F�l�m�l���Ɛڂ���@��̌����f���Ă���B
�u���Â���(�g�r�s��)�v��2�N�A���̌������B�����I�Ȃ̂́A��N�������N�̌����������傫���_���B���ю傱�Â�������������ł���A�O�o�@��k���ɉ����A��N���⍡�N�Ă̏ܗ^���������e�����Ă���̂��낤�B
�u�m���v����N���A���N���ƂȂ������A�߂肪�݂��܂܂��B�i�ڕʂł́A�w�L����2�N�A���Ō������Ă���A�e�����[�N���y�̉e�����\��Ă��悤�B
�u��ʁv����N���A���N���ƂȂ������A��͂�߂肪�݂��܂܂��B�i�ڕʂł́A�S���^����L�����H���A�q��^������������ł���A�������܂����������ړ��̋@��k���f���Ă���B�܂��A�ʋΗp�̒���オ��������ł���A�e�����[�N���y�̉e���Ƃ݂���B
�������I���ł��R���i�O�ɖ߂肫��Ȃ��i�ڂ�
������Ă��鍀�ځE�i�ڂ͊T���ĊO�o���l��c�Ɛ����̉e�����F�Z���Ƃ݂���B���N�`�����y���ɂ�芴������������A�l����͊�{�I�ɂ͉��邾�낤�B�������A�O�H�A�m���A��ʂȂLjꕔ�i�ڂ̒���́A�e�����[�N���y�ȂǍ\���I�ȑ��ʂ�����Ƃ݂���B�������������Ă��A�V��Ԃ̒蒅�Ŗ߂��Ȃ��i�ڂ����낤�B�@
�@ |
 |


 �@
�@ |
���C�̉Ƃ���͕s���̐��c�_�ސ쌧�œƎ��ً̋}���Ԑ錾���߂Ă̏T���@7/19
�_�ސ쌧�œƎ��ً̋}���Ԑ錾���o����ď��߂Ă̏T���A�C�̉Ƃł͎�ނ̒�~���ӂ����ы��߂��邱�Ƃɑ��s���̐��������Ă���B
�_�ސ쌧�͐V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g�����16���Ɍ��Ǝ��ً̋}���Ԑ錾���o���Ă���B22�����痈��22���܂ł͌����̂قڑS��Ŏ�ނ̒�~�����߂��B
���N�A�C�����ꂪ�J�݂���Ȃ���������2�N�Ԃ�̉c�ƂƂȂ����]�̓��߂��ɂ���C�̉Ƃ���́u�}�C�i�X�X�^�[�g�Ō}���Ă��܂��̂ŁA�A���R�[�����o���Ȃ��Ȃ�ƃ}�C�i�X�����d���̂�������̂��ȂƎv���܂��v(AJITO���˓N��I�[�i�[)�ƕs���̐����オ���Ă���B
�I�[�v���O����@�ނ̃����e�i���X�ȂǂŔ�p�������ނȂ��A1�J���ɓn���Ď�ނ�ł��Ȃ��̂́A�e�����傫���Ƃ����B
��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�A��Î҂ł��]���������@7/19
���{���A�����s�ɍ���12�����痈��22���܂�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾��(���ꌧ�ɏo����Ă���ً}���Ԑ錾�ɂ��Ă�����)�������Ƃɂ��āAm3.com����ɐq�˂��Ƃ���A�錾�̎����E�Ώےn��Ƃ��ɉ����U���A�]����������錋�ʂƂȂ����B�܂��A�u���������ً}���Ԑ錾���o���K�v�͂Ȃ��v�����̉����W�܂����B�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����g��ɑ��A�ǂ̂悤�ȑ���Ƃ�ׂ����A��t�̊Ԃł��ӌ���������Ă������������ƂȂ����B
Q �ً}���Ԑ錾���o�������� ���āA�ǂ��v���܂����B
��t�E��t�ȊO��33.3%�`41.9%���u�x������v�Ɖ������ŁA33.3%�`34.7%���u�Ó��v�Ɖ����B�܂��A16.5%�`19.7%���u���������ً}���Ԑ錾���o���K�v�͂Ȃ��v�Ɖ����B
Q �ً}���Ԑ錾���o���n��ɂ��āA�ǂ��v���܂����B
��t�E��t�ȊO�Ƃ��ɁA�ł��������u�Ó��v��36.2%�`41.2%�A�����ŋ͍��Łu�����E����ȊO�ɍL����ׂ��v��28.5�`34.3%�ƂȂ����B�܂��A14.1%�`17.9%���u���������ً}���Ԑ錾���o���ׂ��ł͂Ȃ��v�Ɖ����B
Q �V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊւ���ً}���Ԑ錾�ɂ��āA���l���������������B
�E�挎�A�����s�̊����������Ă����̂ɋً}���Ԑ錾�������������Ƃ����ł��B[�Ζ���]
�E�M���W�ɗ������f�Âɂ͌��E�������镔��������B[�Ζ���]
�E�c�O�ł����A���������{��M�����Ă��Ȃ��A���ʁA������h�~�ł��Ȃ��B�����ȃI�����s�b�N�J�Â͋����܂��B[�Ζ���]
�E�����Ǝ��Â̌��ꂩ����̔��M�����������ǂ��Ǝv���B�����Ƃ���ʂ̐l�����ꂪ������Ȃ����낤����B[�Ζ���]
�E�݂�Ȋ���Ă��Ă���B�Ⴄ�������l���������ǂ��B[�Ζ���]
�E��{�I�ɐ��Ԉ���Ă���B�I�����s�b�N�����Ȃ�A���N�`���ڎ�𑁋}�ɂ��ׂ��������B�V�l�����s�N��D�悷��ׂ��������B�����s���͂������Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���l�ł͂Ȃ��A�����ōs���ׂ��ł͂Ȃ����B[�Ζ���]
�E���Ղɉ�����ً}���Ԑ錾���o�������Ă��܂������߁A���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
����́A��Ñ̐��𐮂��鏀�������Ă��Ȃ����������̂ƁA���|���������肷���Ă������f�B�A�̐ӔC���Ǝv���B[�Ζ���]
�E�[���ł��闝�_�I�E���ؓI��������������A�o�ς���ނ�������Ɏ�҂̐S��g�̂̌��N��I�ނ����B[�J�ƈ�]
�E�ψي��������Ȃ��āA�]������芴�������a�����������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��������Ă���̂ɁA�Ή����j���ς���Ă��Ȃ����Ƃ������ł��Ȃ��B[�J�ƈ�]
�E��������3���̒i�K�ł������Ɠ����E���̃��b�N�_�E�������Ă���Ηǂ������Ǝv���B[��t]
�E�e���r��V����ǂ܂��A�����̂���SNS�Ȃǂ��������A�̂���C���t���G���T�[�̏�����Ȃ��B����Ȑl�X�ɍł��o�������ً}���Ԑ錾���A�܂��`���Ȃ��B[���̑���Ï]����]
���m���u�ܗւ͉Ƒ��ȊO�Ƃ̑�l���E�����Ԋϐ�T�d�Ɂv�V�^�R���i �O�d�@7/19
�O�d���ł�19���A�V����7�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����܂����B1��������̊����҂�10�l�������̂́A7��12���ȗ�7���Ԃ�ł��B
�������킩�����̂́A�Îs��鎭�s�ȂǂɏZ��20�ォ��50��܂ł̒j��7�l�ł��B
�ɉ�s��20��j���́A7��16���ɍA�Ɉ�a�����o�������߁A17���A�������ėz�����������܂����B�j����17���܂Ō����̉�Ђɏo���Ă������Ƃ���A���͐E��̓�����8�l�ƕʋ��e�����܂߂��Ƒ��Ȃ�9�l�̌�����i�߂Ă��܂��B
�O�d����19�����_�ł̕a���g�p����17.7���ŁA�v�̊����҂�5451�l�ł��B
7��16����17���̊����Ґ����A������߂銴���g��̗\���̊�u17�l�ȏオ2���A���v�����������Ƃ��āA��ؒm���͗Վ�����J���A�����I�����s�b�N�ɂ��ĉƑ��ȊO�ł̑�l���E�����Ԃł̊ϐ�͐T�d�Ɍ�������Ȃlj��߂Ă̊�����������ɋ��߂܂����B
�܂��A����1�T�Ԃł̊����̌X����30��ȉ��̎Ⴂ����ƊO���ЂƂ݂���l���������Ă���ƕ��͂��������ŁA�a�����Ђ��������ɂȂ����ƂȂǂ𗝗R�Ɂu�����ɋ����[�u���u����ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��B
����s���̈��H�X���p�q �O��̐錾���Ԃ̕��ς��3���� �@7/19
������4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă���18���܂ł�1�T�ԂɎ�s����1�s3���ň��H�X�𗘗p�����l�́A���Ƃ�4�����{�����3��ڂ̐錾���o�Ă������Ԃ̕��ςƔ�ׂ�30�������Ȃ����Ƃ������Ԃ̒������܂Ƃ܂�܂����B
���H�X�ɗ\���ڋq�Ǘ��̃V�X�e������铌����IT��Ɓu�g���^�v�́A��s����1�s3���ɂ��邨�悻3000�X�̗��X�q���ȂǂׂĂ��܂��B
����ɂ��܂��ƁA18���܂ł�1�T�Ԃ̗��X�q���͓�����3��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă������Ԃ̕��ςƔ�ׂ�30.2�������Ȃ�܂����B
���ԑѕʂɌ���ƁA���p���ł������u�ߌ�5������ߌ�8���v���v���X35.2���A���H�̎��Ԃ��܂ށu�ߑO11������ߌ�3���v���v���X12���ł����B
����A�O�̏T�Ƃ̔�r�ł́A11.5������܂����B
���ԑѕʂɌ���ƁA�u�ߌ�5������ߌ�8���v���}�C�i�X14.4���A���H�̎��Ԃ��܂ށu�ߑO11������ߌ�3���v���}�C�i�X5.9���ŁA������4��ڂً̋}���Ԑ錾���o���ꂽ���ƂɂƂ��Ȃ��ė��X�q���͌����Ă��܂��B
�������s �����}�g�� 7���ԕ���1000�l���� ��3�g��1���ȗ��̐��� �@7/19
�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă���19����1�T�ԂƂȂ�܂��B�s���ł͊����̋}�g�傪�����Ă��āA18���܂ł�7���ԕ��ς�1000�l���āA��3�g�̂��Ƃ�1���ȗ��̐����ƂȂ��Ă��܂��B
�s����7���ԕ��ς�377.7�l������6��19���ȍ~�A18���܂ŁA29���A���ŏ㏸���Ă��܂��B
1�T�ԑO�̍���12����4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ĉȍ~�������̋}�g�傪�����Ă��āA12�����_��756.7�l�������̂��A17����1000�l����1012.0�l�A18����1068.3�l�ɂȂ�܂����B
1000�l����̂́A��3�g�̂��Ƃ�1���ȗ��ł��B
�܂��A7���ԕ��ς̑O�̏T����̑���������ƁA17����140.5���A18����145.6���ł����B
140���ȏ�ƂȂ�̂���3�g�̂��Ƃ�1���ȗ��ŁA�����̃y�[�X���������Ă��܂��B
��3�g�ł́A�s�[�N����7���ԕ��ς�1861.1�l�A�O�̏T����̑�����207.1���ƂȂ�ȂNj}���Ɋ������g�債�A���@���҂��}�����Ĉ�Ò̐����Ђ������܂����B
�������[�����͌ߑO�̋L�҉�Łu�����J���Ȃ̐��Ɖ�ł́A��s���̊����ɂ��āA��ԁA���ԂƂ��ؗ��l�����������Ă���A�����𒆐S�ɏ��Ȃ��Ƃ����ʂ͊����̊g�傪���O�����Ȃǂ̕]���A���͂��Ȃ���Ă���B���������A�������Â̂Ђ������������蒍�����Ȃ���A�ْ����������āA�e�s���{���Ƃ��悭�A�g���Ƃ�Ȃ��犴����ɑΉ����Ă����K�v������v�Əq�ׂ܂����B
�����Ɓu�������̗v�������Ȃ� �[���ȏ�Ԃ��ƔF�����v�@7/19
�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă���19����1�T�Ԃ������܂����B���������Ȃ��ł��������g�債�����Ă��錻��ɂ��āA���ۈ�Õ�����w�̏��{�N�Ƌ����́u���ꂩ��ċx�݁A�I�����s�b�N�Ɗ�����������v�������Ȃ��A���Ȃ�[���ȏ�Ԃ��ƁA����1�x�A�F�����Ăق����v�Ƒi���܂����B
�y�s���̊��� 1��3000�l�߂��̉\�����z
�܂����{�����͓s���ŁA���̂Ƃ���1000�l�����銴���Ґ��ƂȂ���������A18���܂ł�7���ԕ��ς�1000�l���Ă��邱�Ƃɂ��āu�ً}���Ԑ錾���ł���Ȃ��犴���Ґ��������x�I�ɑ����Ă���B�����̐l�������ً}���ԂɊ���Ă��܂��A��������Ăт����Ă��s���ɗ}�����������Ă��Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B���̂����Łu���ꂩ��ċx�݁A����ɃI�����s�b�N�ƍl����ƁA�����Ґ���������v�������Ȃ��A����v�����Ȃ��B����ԑ傫�Ȕg�ɂȂ�A1��3000�l�߂��܂ő�����\�����o�債�āA���Ȃ�[���ȏ�Ԃ��Ƃ���1�x�A�F�����Ăق����v�Ɗ�@���������܂����B
�y�u�f���^���v�e�� �E���w�Z�ł̃N���X�^�[���O�z
�܂��A�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�u�f���^���v�̉e���ŁA�E���w�Z�Ȃǂł̃N���X�^�[�������Ă���Ǝw�E���܂��B���{�����́u����̊����g��ł͐E���A����܂ŏ��Ȃ������w�Z�Ȃǂł̃N���X�^�[�������Ă���B�����͂������Ƃ����̂́A���̐l�����E�C���X�̗ʂ����������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��ƍl���Ă��悭�A�ŋ߂�3���ł͂Ȃ��A2����1���ł��������₷���Ȃ��Ă���B�������̊O���ł��v�������邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����������Ȃ肢�邵�A�Ⴂ�l�̏d�Ǘ�������Ă���v�Ƙb���Ă��܂����B
�y�ܗփe���r�ϐ�ɂ����ӂ��z
���̂����ŁA�J�����T���������I�����s�b�N�̊��Ԓ��������h�~��̓O�ꂪ�K�v���Ƒi���܂��B���{�����́u���ϋq�ł��W�c�ň��H���Ȃ���e���r�ŃI�����s�b�N������Ƃ������ƂɂȂ�A���ǁA�������N����₷���ɕς��͂Ȃ��B�Ȃ�ׂ����l���ŏW�܂�Ȃ����ƁA�吺���グ�ċ߂������Řb������@������Ȃ����Ƃ��厖���B�����̐l���W�܂邱�Ƃ͔����A�ƂŃI�����s�b�N����������悤�O�ꂵ�Ăق����v�Ƙb���Ă��܂����B
���ً}���Ԑ錾�͈Ӗ����Ȃ��Ȃ������A1�T�ԑO�ɔ�ׂĊ����Ґ�45�������@7/19
�����ܗւ�4����ɍT�����ŊJ�Òn�����̐V�^�R���i�E�C���X�����g��̐����������Ȃ��B
NHK�ɂ���19���A�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ���727�l�ƏW�v���ꂽ�B1�T�ԑO�̓����j���ɔ�ׂ�225�l(44.8%)�������������B�����s�ł�30���A����1�������芴���Ґ����O�T�̓������̊����Ґ��������Ă�����B�ŋ߂�1�T�Ԃœ����s�ɂ����銴���Ґ���45.4%���������B
�����ł�14������18���܂ł�5���Ԃ�1�������芴���Ґ���1000�l�����B1�T�Ԃ̕��ϊ����Ґ���19����1100�l���A�O�T���45.4%�������B4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�o��������12���A�����s�ɂ�����1�T�Ԃ̕��ϊ����Ґ���756�l���������A17���ɂ�1000�l�����B19���ɂ�1068�l�ƂȂ�A��3�g���s���̍��N1���ȍ~�ő��ƂȂ����B
�����̃E�C���X�����`�d�͂������f���^�ψي��������g��ɐ��������Ă���Ƃ������͂��B�V�^�R���i�E�C���X�d�NJ��҂̂قƂ�ǂ́A���N�`���ڎ헦���Ⴂ50��ȉ��̎�N�w���قƂ�ǂ��B�挎���{�܂ł͍������Z��̋߂��̕a�@�̕a���g�p����30%���x���������A���@���҂����������Ƃ�19���ߑO�ɂ�70%�ɒB���A��Õ����O����Ă���B
�܂��A���{���{�ɂ��h�u���ʂ������炵�Ă��Ȃ��Ƃ����_�����Ƃ��Ďw�E����Ă���B��N���獡�܂�4��ɂ킽���ċً}���Ԑ錾�o���������ŁA�����̔�J�x�������Ă���Ƃ����������B���ۈ�Õ�����w�̏��{�N�Ƌ����́u�����̐l���ً}���Ԑ錾�Ɋ���āA�������i���Ă�(������u��)�s���ɂȂ���Ȃ������v�ƕ]�������B
�ċx�݂Ⓦ���ܗ֊J���ȂNJ���������������c����Ă��Ȃ��Ƃ����J�����o�Ă���B���{�N�Ƌ����́u�V�K�����Ґ���1��3000�l�ɑ�����\�����o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��u���Ȃ�[���ȏł��邱�Ƃ�������x�F�����Ăق����v�Ɩh�u�[�u�����炷�邱�Ƃ𑣂����B
�����r�m���́u�ϋq����͐��{�̕��j�ɉ����āv�����@���{�ɔ��f�ۓ����@7/19
������4��ڂً̋}���Ԑ錾�����߂����Ȃ��A�����ܗւ́u���ϋq�v�ŋ��s�J�Â����B�����Ƃ͍����ɍ����Ȃ��y�Ϙ_��U��܂��ĊJ�Âցg���U�h���Ă������B
�������댯�ɒǂ��������ƂƌܗM���́A�u�Ղ��n�܂�A����ȓ{��ȂǖY��邳�v�ƃ^�J���������Ă���B�����炱���A���̖S���̔�����������ƋL�^���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��N3��24���A�����̈��{�W�O�E�̓g�[�}�X�E�o�b�nIOC(���ۃI�����s�b�N�ψ���)��Ƃ̉�k�Ōܗւ�1�N�������j�����߁A�u�l�ނ��V�^�R���i�ɑł��������Ƃ��āA���S�Ȍ`�ŊJ�Â���v�ƌ�����B
���r�S���q�E�����s�m���������̖��ӔC���ł͕����Ă��Ȃ��B��N3���ɂ͈��{���́u���S�Ȍ`�v�������u�����͈��{�����̍l�����Ƌ��ʂ��Ă���v�Ǝx�����Ă������A�����g��Ŋ��F�������Ȃ�Ǝ��X�ɐӔC�]�Ŕ������J��o�����B
������3��ڂً̋}���Ԑ錾���ɂ��������N5���ɕč����{�����{�ւ̓n�q���~�������o���ƁA�u�A�����J�̈ψ���w�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��Ă͖��Ȃ��x�Ƃ������b�Z�[�W���o���Ă���ƕ����Ă���v�ƕč��ܗֈψ���́g���n�t���h�𗝗R�ɊJ�Â͉\�Ƃ̌������������B
����ɁA6���ɐ��{�̐V�^�R���i�����ȉ�̔��g�E�����ƗL�u���u���ϋq�J�Â��]�܂����v�ƒ���ƁA���{�ɔ��f���ۓ�������悤�Ȏ��̔����������B
�u�ϋq�̏���͐��{�̕��j�ɉ����Č��߂�v
���̏��r���̌㌩�l�I���݂̓�K�r���E�����}���������ܗւ������������B���N���߂ɂ́A
�u�X�|�[�c�U����}�邱�Ƃ͍����̌��N�ɂ��Ȃ���B�w(�ܗւ�)�J�Â��Ȃ��x�Ƃ����l�����Ă݂������炢���v
�u�I��͊ϋq�������ق����ǂ��Ɍ��܂��Ă���v
�ƌ����Ă������Ǝv���ƁA4���̐��̖K�Ē��O�Ɂu�w����ȏ�A�ƂĂ��������x�Ƃ������Ƃł���A���ς��Ƃ�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƒ��~�_���Ԃ��グ�A���̌�����ł̎��̒֎~�△�ϋq�J�ÂɌ��y���Ă����B
�ꌩ�A���ӂɕq���Ȃ悤�Ɍ����邪�A�u�ܗւɎ��s�����琛�����ɐӔC�킹�邽�߂̗\�h���B�ܗւ𐭋ǂɗ��p���Ă���v(�����}�x�e�����c��)�Ƃ̌������L�͂��B
���s�������}�g�� 7���ԕ��ς�1000�l�� ��3�g�ȗ��̐����@7/19
�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă���19����1�T�ԂƂȂ�܂��B�s���ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g�傪�����Ă��āA18���܂ł�7���ԕ��ς�1000�l���āA��3�g�̂��Ƃ�1���ȗ��̐����ƂȂ��Ă��܂��B
�s����7���ԕ��ς́A377.7�l�������挎19���ȍ~�A����18���܂�29���A���ŏ㏸���Ă��܂��B
1�T�ԑO�̍���12����4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ĉȍ~�������̋}�g�傪�����Ă��āA12�����_��756.7�l�������̂��A17��1000�l����1012.0�l�A18����1068.3�l�ɂȂ�܂����B
1000�l����̂́A��3�g�̂��Ƃ�1���ȗ��ł��B
�܂��A7���ԕ��ς̑O�̏T����̑���������ƁA17����140.5���A18����145.6���ł����B
140���ȏ�ƂȂ�̂��A��3�g�̂��Ƃ�1���ȗ��ŁA�����̃y�[�X���������Ă��܂��B
��3�g�ł́A�s�[�N����7���ԕ��ς�1861.1�l�A�O�̏T����̑�����207.1���ƂȂ�ȂǁA�}���Ɋ������g�債�A���@���҂��}�����Ĉ�Ò̐����Ђ������܂����B
���ܗ�5���O�ɑI�葺�̑I��2�l�����߂Ċ����m�F�c�@7/19
23���̓����ܗ֊J����5����ɍT���A�I�葺�ł����2�l�̑I�肪�V�^�R���i�E�C���X������������B�I�葺�ŏo��I��̊������m�F���ꂽ�̂͏��߂āB�����𒆐S�ɓ��{�����̊����҂�4��l�ɔ���ȂǐV�^�R���i�̊g�U�������Ă���B
�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���g�D�ψ����18���A�u�I�葺�ɑ؍݂���I��2�l���V�^�R���i�̌����ŗz����������v�Ɣ��\�����B�I�葺�ɑ؍݂��Ă���I��̒��ł́A���߂ăR���i�����������������Ⴞ�B����ɐ旧��16���A�C�O������������ܗ֊W�҂��V�^�R���i�����̔�����A�I�葺���ŏ��̊����҂��������Ă���2����̂��Ƃ��B
���{���ǂƑ��g�D�ψ���͓O�ꂵ���V�^�R���i�h�u�𐾂��Ă��邪�A�ܗ֊J��(23��)�𐔓���ɍT���A�������Ŋ����҂��������A�I�葺���̖h�u�Ɍ����J�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������O�����܂��Ă���B
�g�D�ψ���́A�l���𗝗R�ɍ���z����������l�̍��Ђ�ʁA�N��Ȃǂ͖��炩�ɂ��Ȃ������B�g�D�ψ���̊W�҂́u3�l�Ƃ��������̏o�g�ŁA������ڂɎQ�����Ă���v�Ƃ��u�ނ�̕����Ɋu������Ă���A�H�����z�B�����v�Əq�ׂ���AFP�ʐM���`�����B�I�葺�͏o��I��ƊW�҂Ȃ�6700�l�����e�ł���B
�g�D�ψ���͂��̓��A�I��2�l���܂ߌܗ֊W�҂̂���10�l���V���ɗz����������Ɩ��炩�ɂ����B�c���8�l�́A���W��5�l�A�}�X�R�~�W��2�l�A�g�D�ς̈ϑ��Ɩ��E��1�l�B�g�D�ψ�����炩�ɂ����ܗ֊֘A�̊����҂͌v55�l�ɑ������B
�܂��A�E�K���_�̏d�ʋ����I��̃W�����A�X�E�Z�`�g���R�I��(20)������16���A���̃L�����v�𗣒E���A���{�̖h�u���ǂ̌��O��ł���B�E�K���_��\�`�[���͓��{���������A2�l���R���i�����̔���������炾�B�ނ͏h�ɂɁu�E�K���_�ł̐��������������ߓ��{�œ��������v�Ƃ������e�̃������c�����Ƃ����B
���{�����̐V�^�R���i�������g�U�X���������Ă���BNHK�̏W�v�ɂ��ƁA17���ߌ�6��30�����݂̐V�K�����҂�3886�l�ŁA�����ȂǑS��10�̍L��n��ŋً}���Ԃ���������Ă���5��27��(4134�l)�ȍ~�A�ł������B�V�K�����҂�3��l���������̂��A14���ȍ~4�������Ă���B
�����s�̏ꍇ�A���̓��̐V�K�����҂͑O�����139�l������1410�l�B�O�T�̓����j���ɔ�אV�K�����҂�28���A���ő������A1��21��(1471�l)�����6�J���ōő��ƂȂ����B����12������4��ڂً̋}���Ԑ錾���������������̂ق��A�_�ސ쌧(539�l)�A��ʌ�(318�l)�A��t��(244�l)�̎�s��3�����A���Z�l���ɑ��ĐV�K�����Ґ����ً}���Ԑ錾�̃��x�����A�ً}���Ԃɏ����鋭�����ꂽ�h�u������{���Ă���B���̓��܂ł̓��{�̗ݐϊ����҂�83��9109�l�A�����S�Ґ���1��559�l�ƂȂ����B
��18���̐l�o ��������ł�3��ڐ錾���Ԃ�葝���@7/19
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g�傪�������A18�����j���̓�������̐l�o�́A4������6���ɂ����ďo���ꂽ3��ڂ̐錾�̊��Ԃ̓y���A�j�����ς�傫������܂����B
�m�g�j�́A�h�s�֘A��Ƃ́u�`���������v�����p�҂̋��āA�l�����肳��Ȃ��`�ŏW�߂��g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^���g���āA�e�n�̎�Ȓn�_�̐l�̐��͂��܂����B
���͂������Ԃ́A�������ߑO6������ߌ�6���܂ŁA��Ԃ��ߌ�6�����痂���̌ߑO0���܂łł��B
18���̐l�o��3��ڂ̐錾���o�Ă������Ԃ̓y���A�j���̕��ςƔ�ׂ��Ƃ���A�����ł͏a�J�X�N�����u�������_�t�߂œ�����47���A��Ԃ�50���������܂����B
�����w�t�߂ł͓�����6������܂������A��Ԃ�7�������B
���~�c�w�t�߂ł͓�����130�������Ƃ��悻2.3�{�ɁA��Ԃ�136�������Ƃ��悻2.4�{�ƂȂ�܂����B
����A�O��4�T�Ԃ̓y���̕��ςƔ�ׂ��Ƃ���A5������ً}���Ԑ錾�������Ă��鉫��ł͓ߔe�s�̌����O�w�t�߂œ�����26�������A��Ԃ�72���������܂����B
���̂ق��܂h�~���d�_�[�u����������Ă����ʁA��t�A�_�ސ�ł́A��{�w�t�߂œ�����13���A��Ԃ�35�����ꂼ�ꌸ���A��t�w�t�߂�������6���A��Ԃ�28�����ꂼ�ꌸ���A���l�w�t�߂�������3���A��Ԃ�6���A���ꂼ�ꌸ�����܂����B
��1000�l�K�͂̂��̂��c�I�����Ƃ����́u�삯���݃p�[�e�B�v����@7/19
4��ڂً̋}���Ԑ錾�����߂����4���O��7��8���B�����E�Ō���(�`��)�ɂ��铌���v�����X�z�e���̑�L�ԂɁA�����̐l���W�܂��Ă����B���̓��J�Â��ꂽ�̂́A�w�G�r��ƌ���x�B�����}�E�ݓc���Y�O������̔h���̐��������p�[�e�B�ł���B
�u���͈�l2���~�B������ɃT�[���Z���T�[���ݒu����Ă�����A���ŏ��ʼnt�̎g�p�����x����(���Ȃ�)�����ȂǁA�������Ɋ����h�~��͍s���Ă��܂����B�������A��n�܂钼�O�̗[��5�����߂��ɂ́A�z�e���̃G���g�����X�͍��R�̐l������ƂȂ��Ă����B�����炭1000�l�߂��͏o�Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���v(�o�Ȏ�)
����7��8���ɂ́A�Δj�Ύ��̔h���w������x���s���̃z�e���Ő��������p�[�e�B���J�Â��Ă����B12���ً̋}���Ԑ錾�̔��ߑO�ɁA�e�h�����삯���݂ŃJ�l�W�߂̂��߂̃p�[�e�B���J�Â����̂��B
���̑O����7���ɋً}���Ԑ錾���߂̕��j�����A�S���ň��H�X���n�߂Ƃ��鑽���̐l���ߖ������Ă����B
7��14���A�ݓc�h�c���̔鏑4�l���V�^�R���i�z���ɂȂ����ƕ�ꂽ�B����4�l�́A���ꂼ��ݓc����n�ꐬ�u�Q�@�c���ȂǕʁX�̋c���̔鏑�ŁA�ނ炪�ꓰ�ɉ���A���̃p�[�e�B�ł̃N���X�^�[�̉\���������B�����̋ꂵ�݂����A���������̎�Ŋ������L���Ă���̂��B
�����̐��Ȃǂ܂�ŕ����C���Ȃ��̂́A�����Ǒ�̃g�b�v�������ł���B�����E�i�c��(���c��)�́u�����L�O�فv�B7��5���A�����̍u���ŁA�w���R��Y���o�Z�~�i�[�x�Ȃ鐭�������p�[�e�B���Ђ�����ƊJ����Ă����B�����Ɍ��ꂽ�̂́A�c�����v���J�����B�o�Ȏ҂��b���B
�u����͏O�@�c���̔��R��Y���̐��������p�[�e�B�ŁA100���قǂ��o�Ȃ��Ă����Ǝv���܂��B���̉�̃Q�X�g�X�s�[�J�[�Ƃ��ēc�����������ꂽ�̂ł����A�u���e�[�}�́w�V�^�R���i��ɂ��āx�ł����B�����̐l���ꎺ�ɏW�߂āA�R���i��ɂ��Ęb���Ƃ����A�܂�Ńu���b�N�W���[�N�̂悤�ȍÂ��ł����v
�c�������A�o������܂����ƍl�����̂��낤�B�r�o�Ɉ͂܂�Ȃ���A���̐��ʌ��ւł͂Ȃ��A�������炱������o���肵�Ă����B
�c�����̎������ɘb���ƁA�u�u�����Ő��{�̐����������邱�Ƃ͍����x���Ȃ��|�����[�����Ɋm�F���A�����āA�u�������v�Ɠ������B�����W���[�i���X�g�̊p�J�_�ꎁ�����B
�u�u���̈˗��������Ă��A�����g���h���w���w�����Ƃ�͂��̌��J���ł���ȏ�A�m�b��s�����ׂ��ł��傤�B�����[�g�ōu��������A�r�f�I���b�Z�[�W�ɂ���ȂǁA������ł������͂������͂��ł��B�h���̃p�[�e�B�ɂ��Ă��A�H�ɏO�@�I���T���A�����W�߂����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�w�ɕ��͑ウ���Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B�������A���H�X���n�߂Ƃ��鍑���̂ق����敾�A�������Ă��܂��B���������̓s���͉����ʂ��A�����ɂ͋]����������B���܂�ɐg����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���v
���������̓s���ŁA�p�[�e�B���ܗւ����s����B���̃c�P���x���킳���̂́A��ɍ����Ȃ̂��B
�����t�x����39.0���ɉ����@���N�`���ڎ폇���łȂ�70.5���@FNN�E�Y�o�������_�����@7/19
����1 �����t���x�����邩�A�x�����Ȃ���?
1.�x������@39.0�� 2.�x�����Ȃ��@55.5�� 3.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@5.5��
����2 �ǂ̐��}���x�����邩?
1.�����}�@36.3��
2.��������}�@8.0��
3.�����}�@2.4��
4.���Y�}�@3.7��
5.���{�ېV�̉�@2.2��
6.��������}�@0.7��
7.���}�@0.7��
8.�ꂢ��V�I�g�@0.3��
9.���̓}�@0.0��
10.���̑��̐��}�@0.4��
11.�x�����}�͂Ȃ��@41.0��
12.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@4.2��
����3 ���{�̐V�^�R���i�E�C���X���]�����邩�A���Ȃ���?
1.�]������@30.4�� 2.�]�����Ȃ��@63.8�� 3.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@5.8��
����4 ���{�́A������4��ڂً̋}���Ԑ錾�߂��A��ʁE��t�E�_�ސ�E���̂܂h�~���d�_�[�u�ƁA����ً̋}���Ԑ錾���A8��22���܂ʼn��������B���̌�����ǂ��l���邩?
1.�Ó����Ǝv���@38.8��
2.�����ƌ���������ׂ����Ǝv���@44.8��
3.�����Ɗɘa����ׂ����Ǝv���@12.7��
4.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@3.7��
����5 ���{�́A��ނ̒𑱂�����H�X��Ƃ��āA���Z�@�ււ̓��������̗v����A��ނ̔̔��Ǝ҂ւ̎����~�̗v�����s�������A�P���B�����̗v�����ǂ��v����?
1.�Ó��������Ǝv���@22.9�� 2.�Ó��������Ǝv��Ȃ��@74.2�� 3.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@2.9��
����6 �����I�����s�b�N�́A�J���قƂ�ǂ̋��Z�ϋq�ŊJ�Â��邱�ƂɂȂ������A�ǂ��v����?
1.�Ó����Ǝv���@39.4��
2.�ϋq�𐧌����ē����ׂ����Ǝv���@24.4��
3.���~���ׂ����Ǝv���@35.4��
4.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@0.8��
����7�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ŁA�C�O���痈��I���W�҂Ɋւ��銴���g��h�~����ǂ��v����?
1.�ƂĂ����ʂ�����Ǝv���@2.6��
2.������x���ʂ�����Ǝv���@40.6��
3.���܂���ʂ͂Ȃ��Ǝv���@40.5��
4.�܂��������ʂ͂Ȃ��Ǝv���@14.3��
5.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@2.1��
����8 23���ɊJ�����铌���I�����s�b�N���y���݂ɂ��Ă��邩?
1.�y���݂ɂ��Ă���@47.2�� 2.�y���݂ɂ��Ă��Ȃ��@49.2�� 3.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@3.6��
����9 ���{�ɂ��V�^�R���i�E�C���X���N�`���ڎ�̐i�����ǂ��v����?
1.�����ɐi��ł���@26.5�� 2.�����ɐi��ł��Ȃ��@70.5�� 3.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@3.0��
����10 ���N�`���ڎ�ɂ��āA�ǂ��l���邩?
1.�ڎ������肾�@31.3��
2.���łɐڎ�����@48.8��
3.�l�q�����Đڎ���邩���f����@15.6��
4.�ڎ�͎Ȃ��@4.2��
5.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@0.1��
����11 �����ł́u���N�`���p�X�|�[�g�v�A�ڎ�ؖ����̗��p�ɂ��āA�ǂ��l���邩�B
1.���Ǝ{�݂���H�X�E���s�ȂǁA�����ŕ��L�����p�ł���悤�ɂ��ׂ����@50.3��
2.�����ł̗��p�͌���I�ɂ��ׂ����@30.4��
3.�����ŗ��p�ł���悤�ɂ��ׂ��łȂ��@14.1��
4.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@5.3��
����12 �H�܂łɍs����O�c�@�I���̔���\�ŁA�ǂ̐��}�ɓ��[���悤�Ǝv����?
1.�����}�@32.3��
2.��������}�@10.8��
3.�����}�@3.1��
4.���Y�}�@4.6��
5.���{�ېV�̉�@2.8��
6.��������}�@1.0��
7.���}�@0.9��
8.�ꂢ��V�I�g�@0.4��
9.���̓}�@0.0��
10.���̑��̐��}�@2.3��
11.���[�ɂ͍s���Ȃ��@6.3��
12.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@35.6��
����13 ���̎ɂ͒N���ӂ��킵���Ǝv�����B
1.���{�W�O�@8.7��
2.�Δj�@16.0��
3.�}��K�j�@5.5��
4.�������M�@0.4��
5.�ݓc���Y�@3.2��
6.�͖쑾�Y�@18.1��
7.����i���Y�@8.5��
8.���������@0.1��
9.���`�́@9.1��
10.�����N���@0.2��
11.��c���q�@0.8��
12.�Ζؕq�[�@1.0��
13.���̒��ɂ͂��Ȃ��@20.7��
14.�킩��Ȃ��E�����Ȃ��@7.7��
��
FNN�E�Y�o�������_�����@/�@�S����18�Έȏ��1179�l�@/�@����:2021�N7��17�`18��
�@ |
 |


 �@
�@ |
���f���B�v�l ���ϋq�ܗցu���{�������ւ��҂荘�v�ƌ����@7/20
�^�����g�̃f���B�v�l(81)��16���A�����s���ŃZ���u�p�[�e�B�[���J���Ă������Ƃ����������B4��ڂً̋}���Ԑ錾���Ńp�[�e�B�[�����͓����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�3���A����1000�l���A�����g�傪�N���Ȓ��ł̊J�Â������B�f���B�v�l�͊J��(23��)�ڑO�̓����ܗւ����ϋq�ŊJ�Â���邱�ƂɁu�Œ�v�ƕ��S�c�C�[�g������������B�r�Ԃ�M�w�l�̋����́\�\�B
�����̒m�l�ɂ��ƁA�f���B�v�l��16���A�s���̌������ꌓ���X�g�����X�u�s�v�ŁA�Z���u�p�[�e�B�[���J�Â����B
�u�f���B�����5�`7���Ƀ`�����e�B�[�p�[�e�B�[����Â��Ă��܂��B��N�͓s���̃z�e���ł����A���N�͂s�B����2�����ł����v(�m�l)
���͒��̕�2��2000�~�A��̕�2��7000�~�B������12������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���ŁA16���͐V�^�R���i�̊����҂�1271�l�����3���A����1000�l�����ƂȂ������ł̊J�Â������B
�f���B�v�l�͍�N��݂������獡�N�����ɂ����āA�s����90�l�K�͂̃J�E���g�_�E���p�[�e�B�[���J�ÁB�r�m�r��Ŕg����Ă�ł��������ɁA����͊�����ɂ��z�������悤���B
�u300�l���e�̍L�ԂŁA�o�Ȏ҂�100�l���������悤�ł��v(�O�o�̒m�l)
�p�[�e�B�[�̖͗l���B�����ʐ^������B�~��Ƀp�[�e�B�V�����͂Ȃ��B�H�����͂������Ƀm�[�}�X�N�������B
�u�s���̈��H�X�͌ߌ�8���܂ł̎��Z�����߂��Ă��邱�Ƃ������āA��̕��͌ߌ�4���J�n�E�ߌ�8���I���ɑO�|�������悤�ł��v(��)
�f���B�v�l��19���A��ނɑ��A����̃p�[�e�B�[�J�Âɂ��āu4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����{�̕��j�Ƃ��Č��܂����͍̂ŋ߂ŁA�������̏��ҏ�͂����ԑO�ɑ��t���Ă���A�C�x���g���L�����Z�������艄��������͂ł��܂���v�ƌo�܂�����B�u�������̐����͈͓����犴���҂͈�l���o�Ă��炸�A��N�A5��̃C�x���g���J���܂������A�����҂͈�l���o�Ă���܂���v�Ǝ咣�����B
�m�łƂ����M�O�������Ă̊J�Â��������Ƃ́A�p�[�e�B�[2�����18���̓����ܗւɊւ���c�C�[�g����ǂݎ���B�v�l�́u�I�����s�b�N�ϋq�ł���Ȃ�čŒ�v�u���E�̍ՓT�X�ƊJ�Â��ׂ��B�h�n�b�o�b�n��Ɏ���Ȏ�������͓̂��{�l�̒p�B�R���i�ɕ������A���⍑�Ƃƍ�������v�c�����ăI�����s�b�N�𐬌��������{�����ɂ���Ɛ��E�ɔ��M���ׂ��v�Ƃ��Ă����B
�����œ����ܗւ̊J�Ð���ɂ��Ă����߂Č��������߂��Ƃ���A�u�傢�Ɏ^���ł��B�܂��A�L�ϋq�ɂ���ׂ����Ǝv���Ă���܂��v�ƉB�u�I�����s�b�N���Z��̓I�[�v���E�G�A�ł��B�o�b�q�����A�����A���ŁA�}�X�N�A���Ȃ͈�l�u���ō���A���̖����N���Ȃ��͂��v�Ƃ����B���̏�Łu���E�̃X�|�[�c���ł��L�ϋq��������O�̒��A���{�������A�ւ��҂荘�B��シ���܂��v�Ƒi�����B
�m���ɑ�J�̊���ŕ����č��̃��W���[���[�O��A�e�j�X�̑S�p�I�[�v���A�T�b�J�[�̉��B�I�茠�͗L�ϋq�J�ÂŐ���オ�����B�����{�������͂Ƃ������A�ꕔ�̎�v���Ől���̋K���ɘa���n�܂��Ă���͎̂������B
�f���B�v�l�ƈӌ���X�^���X�̈Ⴂ�͂��邪�A�ܗւ̗L�ϋq�h�����Ȃ��Ȃ��B�T�b�J�[�t�\24���{��\�叫�̂c�e�g�c����(32���T���v�h���A)�A�ܗ֑I�葺�����̐앣�O�Y��(�����{�T�b�J�[����)�A�����Ăh�n�b��ł���o�b�n���������グ�Ă���B�e�E�̒����l�ł͔]�Ȋw�҂̖Ζ،���Y���A���������Ō��p�\�i��̒|���������A���O�@�c���Ń^�����g�̐��������炪����B
�ً}���Ԑ錾���̃p�[�e�B�[�J�ÂƌܗւɊւ��锭���͍Ăєg����������낤���A�f���B�v�l�ɂЂ�ޗl�q�͂Ȃ��B�u���{�l�̈ӋC��������Ƃ��ł��v�ƍŌ�����C�Ɍ��B
�����{�ŐV�^�R���i�}���c1�T�ԑO���55�������@7/20
�����ܗ֊J����4����ɍT����19���A���{�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂��}�����Ă���B
�m�g�j�ɂ��Ƃ��̓��ߌ�6��30����œ��{�̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ���2329�l�ƏW�v���ꂽ�B1�T�ԑO�̓����j���Ɣ�r�����54�D9���������������B
����ɂ����{�����̗ݐϊ����Ґ���84��4539�l�A���S�҂�12�l������1��5075�l�ɂȂ����B
�ܗ֊J�Ós�s�̓����ł��V�^�R���i�E�C���X�̊����g��X���͑��ς�炸���B���̓������ł�727�l�̐V�K�����҂����ꂽ�B�����1�T�ԑO���44�D8�������������l���B
1�T�ԑO�̓����j���Ɣ�r���������̐V�K�����҂͐挎20�����炱�̓��܂�30���A���ő����X�����������B
���{���{���V�^�R���i�E�C���X�̊����g���}�����邽�ߋً}���Ԑ錾�߂��������ʂ͌���Ă��Ȃ��B
�����ʐM��17�`18���ɓ��{�̗L���҂�ΏۂɎ��{�������_�����ŁA�҂�67�D9���͓�����4��ڂ̔��߂ƂȂ����ً}���Ԑ錾�������g���h�~������ʂ��Ȃ��Ɠ������B
�܂��A�҂�87�D0���͓����ܗցE�p�������s�b�N���J�Â����ꍇ�A�V�^�R���i�E�C���X�̊������Ċg�傷��Ƃ����s���������Ă���Ɩ��炩�ɂ����B
���R���A���{�A�ې�A�X�A�o�b�n�c�u�S���ܗցv�ɗU�����W�҂̖ό��W�@7/20
������4��ڂً̋}���Ԑ錾�����߂����Ȃ��A�����ܗւ́u���ϋq�v�ŋ��s�J�Â����B�����Ƃ�ܗM�������́A�����ɍ����Ȃ��y�Ϙ_��U��܂��ĊJ�Âցg���U�h���Ă������B����Ȕނ�́g�S���̔����h��������ƋL�^���Ă����K�v�����邾�낤�B
�ܗւɌ����Ē����Ɍ����ȃA�X���[�g�����������́u�ېg�̏|�v�Ɏg���Ă���̂�JOC(���{�I�����s�b�N�ψ���)��g�D�ψ���̎�]�������B
�R���חT�EJOC��͉(6��28��)�Łu�ꕔ�̑I��ɐS�Ȃ����b�Z�[�W���͂��Ă���v�Ƃ��������ŁA�����ɂ����Ăт������B
�u�@��������JOC�Ƃ��̉�̎���@���āv
�ܗ֊J�Âɑ���s���ƕs���̖��悪���̐ӔC���Ȃ��I��Ɍ������Ă��邱�Ƃ�ᔻ���A�I�������Ă�����肩������Ȃ��B
�����AJOC��g�D�ψ�������̕s���ɐ��ʂ�����������A��������w�͂����Ă��Ȃ��������ʁA�����̈ꕔ�͂ǂ����悤���Ȃ��{���I��ɑi����Ƃ����Ԉ���������Ɍ������B�����������Ԃ��������ӔC��I�ɏグ�āu�@���Ȃ�JOC�Ǝ��v�Ƃ͔ߌ��̃q�[���[�C���ł����Ȃ��B
�u�I����|�v�ɊJ�Â𐳓������锭�z�͑g�D�ψ���̐X��N���̎��̔���������킩��B
�u���ϋq�����Ă�������Ȃ��B���q����̂��߂Ɍܗւ�����킯����Ȃ��v
�g�D�ϕ���߂鉓�������E���ܗ֑��̐��������p�[�e�B�[(7��6��)�ł������A�u����ς�ꐶ�����w�͂��Ă����A�X���[�g(�̂��߂ɂ���)�v�Ƒ������B
�I�肽���̓I�����s�Y�����킩���Ă��Ȃ��l���g�D�ς̉������Ă����̂��ƈ��W�Ƃ����C�����ɂȂ����͂����B
�ܗւ́A�u�����E���ЂȂǂ��܂��܂ȍ��ق��A�F��A�A�ъ��A�t�F�A�v���[�̐��_�������ė������������ƂŁA���a�ł��悢���E�̎����ɍv������v(JOC��HP���)���Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
������g�A�X���[�g�̂��߂Ɍܗւ��J���Ă��h�ƌ�������̐X���̔����́A�J�Â̕s������w�I��Ɍ�����ꂩ�˂Ȃ��B
���j�̒r�]���Ԏq�I����SNS�Ȃǂŏo�ꎫ�ނ𔗂鏑�����݂��s�Ȃ�ꂽ���ƂɁA�u�A�X���[�g���ӂ߂���ׂ�����Ȃ��v�ƌ������{���q�E���g�D�ψ����́A�������b�����B
�u�I�肪�g���Ђ�肽���h�Ƃ��猾���Ȃ��ɂ���v
�A�X���[�g���ܗ֊J�Ð������ɗ��p���锭�z���g���h�ƕ炤�X���Ɠ����ł���B
�����́u���a�̍ՓT�v�ɑ�����҂����ڂ܂��������͑����B
�ې���E�ܗ֑��́A���N3���ɂ́u�����������𑱂��Ă��鍑���̊F���܂̗�����v�ƌ�������A4���ɂȂ�ƁuIOC(���ۃI�����s�b�N�ψ���)�̃R�[�c�����ψ����́w�K���J�Â���x�Ƃ������t�͔��ɐS�����v���Ă���v�ƌ��AIOC�ɐӔC�]�ł��Ă݂����B
����ɁA���{�̐V�^�R���i�����ȉ�̔��g�E�������Łu�p���f�~�b�N�̒��ł̌ܗ֊J�Â͕��ʂł͂Ȃ��v�Ə،�����Ƃ����ᔻ���Ă̂����B
�u�S���ʂ̒n�����猩�Ă������t�����̂܂܌����Ă��Ȃ��Ȃ��ʂ��Â炢�v
�����ɂ͔��g�،��̂ق��������ɋ߂��B�ې쎁�͎������g�����Ƃ͑S���ʂ̒n���h�ɗ����ĊJ�Â𐄐i���Ă��邱�Ƃ����甒���ɓ������B
IOC�����������J�Í��̍����̋C�������t�Ȃł��锭�����c���Ă����B�g�[�}�X�E�o�b�n��͓����ŋً}���Ԑ錾�����o���ꂽ�ꍇ�̊J�Âɂ��Ă�������Ă����B
�u(�ً}���Ԑ錾��)�ܗւƂ͊W�Ȃ��v
�W�����E�R�[�c����͂����Ƃ͂�����A�u�ً}���Ԑ錾���ł̊J�ÁH�@�����̓C�G�X���v�Ɣ����BIOC�̌ÎQ�ψ��ŃI�����s�b�N�����@�\��߂�f�B�b�N�E�p�E���h���́u�A���}�Q�h�����N���Ȃ�������͊J�Â����v�ƌ��������B
�������������ō����̐S�͌ܗւ��痣��A���ϋq�J�Ì���œ����͌ܗւ́g���P�n�h�ƂȂ����B
�u�e���r�ł��\�������ł���v
�����N���E�o�ύĐ�����NHK�̔ԑg�ł�����������A�����S���e���r�Ō���Ȃ瓌���ŊJ�Â���Ӗ��͂Ȃ��B
�����Ƃ�ܗM�������̖��ӔC�Ȍ��t�ɂ���āA�����͋t�Ɍܗ֕s�M�Ɗ����ւ̕s�����点�Ă���B���̍��̐����Ƃ��ܗ��s�œ��{�́u�R���i�s��v���B�����Ƃ��Ă���Ƃ��������Ȃ��̂��B
���ً}���Ԑ錾���e�����c���~���Ԓ��̐V�����E�w��ȗ\���96%�Ɣ����@7/20
JR���C�͂��~���Ԓ��̓��C���V�����̎w��Ȃ̗\��ɂ��āA�����łً̋}���Ԑ錾�̉e���ȂǂŁA���N���20���ȏ㉺����Ă���Ɩ��炩�ɂ��܂����B
JR���C�ɂ��܂��ƁA8��6������17���܂ł̂��~���Ԓ��A���C���V�����̎w��Ȃ͂��悻29���Ȃ̗\�����Ă��܂��B
����͋��N�̓�������菭�Ȃ�96�p�[�Z���g�ɂ�����A�V�^�R���i�E�C���X�̉e������O��2019�N�Ɣ�ׂ��8���قnj������Ă���Ƃ������Ƃł��B
���N���\�������Ă��邱�Ƃɂ��āAJR���C�́u�����ŋً}���Ԑ錾���o����Ă��邱�Ƃ����̉e����^�����Ƃ݂���v�Ƃ��Ă��܂��B
����A�ݗ������}�̗\���2���ȂŁA�O�N��112�p�[�Z���g�Ƒ����Ă��܂��B
������Łu�S�ł̐n�v4�A�x�ɂ܂���f�@�ً}���Ԑ錾�ł������ł͔����@7/20
�u����Łw�S�ł̐n�x������ԕҁv���A�܂��X�N���[���ɖ߂��Ă���B2021�N7��22���`29���̊��Ԍ���ŁA�S��383�̉f��قŏ�f�����B
2020�N10��16���Ɍ��J����Ĉȍ~�A���N�ȏ�ɋy�Ԓ������O�����Ō���ł͏�f����Ă����B���̌�A�قƂ�ǂ̌���Ō��J�I�����A�u�[�������������Ă������Ǝv������A�ď�f�̗\�n�܂�Ƃ����܂������̐l�C�Ԃ肾�B
����i�͏�f���Ԃ������������Ƃ�����A���łɉ��x������ɑ����^��Ŋӏ܂����l�������B21�N5��24���ɂ́A�����j�㏉�ƂȂ鋻�s����400���~��˔j�����B�č��ł�2021�N4��23���ɉf�悪���J�ɁB4��30������5��2���̏T���ɂ����āA�S�ĂŃg�b�v�ɂȂ�قǁA�C�O�ł������]������Ă���B
��l�C��i���Ăщf��قŌ����邱�Ƃ�����A�`�P�b�g�͂��łɑ��D��ƂȂ��Ă���Ƃ�����B�uTOHO�V�l�}�Y�v�ł́A��f2���O����ӏ܃`�P�b�g�̗\�ł���B���J����21�N7��22�����́A7��20����0������\�t���J�n�ɂȂ����B�L�҂�TOHO�V�l�}�Y�̌����T�C�g���m�F����ƁA21�N7��20��13�����_�ŁA�Z�{�A�ю����A�a�J�A�V�h�A�r�܂ȂǓs���̉f��قł͂��łɁu�����v�̕\�����o�Ă���B
�c�C�b�^�[�ɂ́A�����Ƀ`�P�b�g�����Ĉ��g����l��A���������������Ă��ĉ�������l�̏������݂��������B��������A�����ɑ����l�C�Ԃ�ɋ����l�������B�܂��A����Łu�S�ł̐n�v�́A�n��g�ł̕��������܂��Ă���B21�N9��25����21������A�t�W�e���r�n�̓y�j�v���~�A���ŁA�S�҃m�[�J�b�g�ŕ����\�肾�B���Ə����҂Ăe���r�Ō�����̂ɁA�ƂԂ₭�l���B
���Ԃł͌��J����7��22�����炿�傤��4�A�x���X�^�[�g����B�ċx�݂ɓ������w���������A�f��ق͍��G���������B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���R���i���l�͎�҂ɂƂ��āu�C�x���g�v�������H�u�錾�v�J��Ԃ������ɊS�Ȃ��@7/21
4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���������������A�l���}���̌��ʂ͊��҂ł��Ȃ��������BAERA 2021�N7��26�����ŁA�錾�̎��l���ʂ́u1�x���������Ȃ��v�Ɛ��Ƃ͎w�E����B
57���ɋy��3�x�ڂً̋}���Ԑ錾����������Ă���A�킸��22����̍Ĕ��o�������B7��12���A�����s��4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���Ԃɓ˓��B8��22���܂ŁA�v42���Ԃ̒����ꂾ�B�ܗ֊J�������7����4�A�x���A���~�x�݂��A�q�ǂ������̉ċx�݂̑唼���ً}���Ԑ錾���ɒu����邱�ƂƂȂ�B�����A�����g��h�~�́u�́v�Ƃ����l���}���ɁA�錾�͂��͂���ɗ����Ȃ���������Ȃ��B
�����̗��s���v�́A�ً}���Ԑ錾���o�����܂��Ă��Ȃ��������B�S����łً͋}���Ԑ錾���o�����܂�O�̒i�K�ŁA7��22�`25����4�A�x�ɑO�N������2�{�̍��������p�҂������݁A�A�x�����ƍŏI���A����ɂ��~�x�݂̃s�[�N���ɂ͑S����1��10���l�����p���錩�ʂ��������Ă����B�ً}���Ԑ錾�̉e���́u�������v�Ƃ��Ă��邪�A�錾���o�����܂���8�`11����4���Ԃł��~�V�[�Y���̍������\�͖�2���l�������Ƃ����B
�X�̐����Ă��A�u�錾�s���v�������ɕ\��Ă���B�錾�����A7��12���̐V�h�E�̕��꒬�̖�́A����܂łƕς��ʖ��邳�������B�s�ł͎�ނ�J���I�P�ݔ��������H�X�ɂ͋x�Ƃ�v���B����߂�ꍇ�ɂ͌ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ����߂Ă��邪�A��11��������Ă������̓X�̃l�I�����P���Ă���B�q�����̏����ɂ��Ɓu��T�Ƃ��܂�ς���Ă��Ȃ��v�B
���łɂ��Ȃ��݂̌��i�ƂȂ����u�H����݁v������O���[�v�����������ɂ���B�̕��꒬��ԊX�ɖʂ����V�l�V�e�B�L��(���R�}����O�L��)�ł́A�v120�l�قǂ����ނ낵�Ă����B�Ȃ��ɂ͊�������Ȃ���ʃ`���[�n�C����C���݂�����A�������̂悤�Ɍ���������o�����肵�đ�����Ă���10�l�قǂ̃O���[�v������B
20��̒j��4�l�ɘb���ƁA3�l�ً͋}���Ԑ錾���o�Ă��邱�Ƃ���m��Ȃ������B�B��u�m���Ă���v�Ɠ�������w���̏����������b���B
�u�w�܂����x�Ƃ����v��Ȃ��B���N�̏��߂���܂ł͎��l���ăX�g���X�����߂Ă�������ǁA�����C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂����B�錾���o������Ƃ����ĉ����s����ς��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��ˁv
�c���`�m��w��w�@�̏����яy����(�s���t�@�C�i���X)�́A�ً}���Ԑ錾�ɂ��͂�l����}��������ʂ͂Ȃ��Ƃ��āA�����w�E����B
�u��N4���A�ŏ��̐錾�̂Ƃ��͖��m�̃E�C���X�ɑ���w���|�x����F���s�������l���܂����B����ǁA���|�ōs�����x�z����̂́w�W���[�J�[�x��1�x�����g���Ȃ��B2�x�ڂ���́w�����x�������Ȃ��Ȃ��Ď��l���ʂ��Ȃ��Ȃ�܂����v
����ɁA�ŏ��̐錾���ɂ͎�҂����l���u�C�x���g�v�Ƃ��ď�������ʂ�����Ƃ����B
�u�w�R���i���l�x������ΖڐV�����g�����h�ŁA��҂��C�x���g�Ƃ��ĐϋɓI�ɎQ�������B�����A2�x�A3�x�ƌJ��Ԃ������ɊS�������Ȃ��Ȃ�܂����v(�����y����)
�������s�ŐV����1832�l�̃R���i�����m�F�@7/21
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ���4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă��铌���s���ŁA21���A�V����1832�l�̊������m�F����܂����B�s���̊����҂́A2���A����1000�l���܂����B
1���̊����҂�1800�l����̂́A��3�g�Ɍ�����ꂽ1��16���ȗ��A���悻���N�Ԃ�ł��B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�1277�D6�l�ŁA�O�̏T��155�D2���ƂȂ�܂����B����A�V����4�l�̎��S���m�F���ꂽ�ق��A�d�ǎ҂�4�l������64�l�ł����B
�������s��1832�l�̐V�^�R���i�����m�F�A���Ƃ͊����}�g������O�@7/21
�����s��21���A�V����1832�l(�O��1387�l)�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B1800�l����̂�1��16��(1839�l)�ȗ��B
���\�ɂ��ƁA�����҂̒���7���Ԉړ����ς�1277.6�l(��1180.0�l)�őO�T��155.2��(��149.3��)�ƂȂ����B�d�ǎ҂�64�l(��60�l)�B
�N��ʂ̊����Ґ���20�オ577�l�ōł������A30�オ410�l�A40�オ294�l�ő������B20�|30�オ�S�̂�54�����߂�����A���N�`���ڎ킪�i��ł���60��ȏ�̊�����6���ɂƂǂ܂��Ă���B
���{�̐V�^�R���i�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��20���A���{�e���r�̔ԑg�ŁA8����1�T�ɂ͓�����1��������̊����Ґ���3000�l�߂��܂ő�������Ƃ̌��ʂ����������B���̏�Łu��Â̂Ђ������N���Ă���\�����ɂ߂č����v�Ǝw�E�����B
21���̓s�̃��j�^�����O��c�ł͐��Ƃ��A���݂̃y�[�X�Ŋ����g�傪�������ꍇ�A1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���2�T�Ԍ��8��3����1���������2598�l�ɂȂ�Ɨ\���B�ψي��ւ̒u������肪�i�݁A�����䂪����ɏ㏸����u2�T�Ԃ�҂����ɑ�3�g���͂邩�ɒ������@�I�Ȋ����ɂȂ�v�ƕ��͂����B��3�g�̃s�[�N����1���������1816�l�B
���u�ً}���ԁv����4�A�x�A����֊ό��q�߂钛���@7/21
�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɔ����ً}���Ԑ錾����4�A�x���T���钆�A�ό��q�����߂钛��������B�q��W�҂ɂ��ƁA�A�x�̗\��͑O�N�������8������قډ����B�錾�����ŃL�����Z���͏o�Ă�����̂́A�uGo�@To�@�g���x���v���n�܂�����N�̓������Ɣ�ׂ�ƌ������͑傫���Ȃ��B�����^�J�[�����l���ł̗\�����萔����B����A���{�����{���鉫��ւ̓���҂ւ̖���PCR�������n�܂������A�\�͍��������c�����Ă��Ȃ��B�ό��ƊE����͎������̂��鐅�ۑ�����߂鐺���オ��B
�q��W�҂ɂ��ƁA22�������4�A�x�̗\��́A�O�N�������Ɣ�r����8�����x�Ƃ����B�u��v�}�[�P�b�g�̓����ɋً}���Ԑ錾���o���ꂽ�e�����傫���A��N�����L�єY��ł���v(�W��)�B�ʂ̊W�҂́u�\��̐L�т͓݉����Ă��邪�A�\��͑O�N���݂���������x�v�Ƃ����B
�����A��N�̓������́A�����܂����ړ����l���S�ʉ�������A�ό��q����ɂ������܂���ƁA�ً}���Ԑ錾���̍��N�͍�N��ōq��ւ̗\�ɑ傫�Ȍ������͌����Ȃ��B
�����^�J�[�ƊE�̊W�҂ɂ��ƁA�錾�����Ńt�@�~���[�Ȃǒc�̋q�����̃��S���Ԃ̃L�����Z���͏o�Ă��邪�A��҂̗��p���������^�Ԃ͗\��r�I�����Ă���Ƃ����B
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���������154�l�ɋ}������20���A�ʏ�f�j�[�m���́u��5�g�ɓ˓������v�Ƃ̋�����@�����������B�����A�ό����Ǝ҂́u(�h���Ȃ�)�\���S�Ƀ[���ɂȂ����킯�łȂ��A�錾���ł����̉����͂��邾�낤�v�Ƃ݂�B
����Ɍ������q��@�̓���҂̂����A��]�҂�Ώۂɏo���n�ł̖���PCR�����������n�܂������A�\�͍��������c�����Ă��Ȃ��Ƃ����A�ǂꂾ�����������S�ۂł��邩�͕s�������B
����q��ƊE�W�҂́u�����̋��͂��Ăъ|���邱�Ƃ͂ł��邪�A���ۂɏo���n�ŎĂ������ǂ������m�F���邱�Ƃ͖��Ԃ����ł͂ł��Ȃ��B�s�����`�F�b�N����̐��𐮂��Ăق����v�Ƙb���B
����ό��R���x���V�����r���[���[�̉��n�F�Y��́u�f�[�^�Ȃǂ������ɁA�����g��̗v���m�ɂ�����ő���u���Ăق����v�Ɨv�]����B���̏�ŁA�o���n�ł̖���PCR�����̎��m�O���A�ߔe��`�ł̍R�������̐��̑����\�z�����߂��B
���u��3�g�͂邩�ɒ������@�I���v�����s���j�^�����O��c �@7/21
�����s�̃��j�^�����O��c�ŁA���Ƃ͑�3�g������y�[�X�Ŋ������}�g�債�Ă���Ǝw�E���������Łu�����䂪����ɏ㏸�����2�T�Ԃ�҂����ɑ�3�g���͂邩�ɒ������@�I�Ȋ����ɂȂ�v�Əq�ׁA�������O�������܂����B
�T��1�x�A�J����Ă���s�̃��j�^�����O��c��21����55��ڂŁA�����I�����s�b�N�̊J���O�A�Ō�̉�c�ł��B
���̂Ȃ��ŁA���Ƃ́A�s���̊����ƈ�Ò̐����������4�i�K�̂����ł������x�����x���ňێ����܂����B
�V�K�z���҂�7���ԕ��ς́A20�����_�ł��悻1170�l�ł���1�T�Ԃ�1.5�{�ɂȂ�A���Ƃ́A�u��3�g������y�[�X�Ŋ������}�g�債�Ă��āA�g��̑��x���オ�葱���Ă���v�Ɛ������܂����B
�����āA���̑����䂪�p�������ꍇ�A7���ԕ��ς́A7��27���ɂ͂��悻1743�l�A8��3���ɂ͂��悻2598�l�ƂȂ�A��3�g�ł̃s�[�N�ł���܂łōł�����1���̂��悻1816�l��傫������Ƃ��Ă��܂��B
���Ƃ́A�u�ψكE�C���X�ւ̒u������肪�i�݁A�����䂪����ɏ㏸����Ɗ����g�傪�}���ɐi�݁A2�T�Ԃ�҂����ɑ�3�g���͂邩�ɒ������@�I�Ȋ����ɂȂ�v�Əq�ׁA�������O�������܂����B
����A���Ƃ�20�����_�ŁA���@���҂�2388�l�Ƃ��悻1�����Ŕ{�������ق��A�d�ǂ̊��҂�60�l�ƍ����l�Ő��ڂ��Ă���Ɛ������܂����B
�����āA�u�V�K�z���҂�������������A��Ò̐����Ђ����̊�@�ɒ��ʂ���B���@��ÁA�h������ю���×{�̊�@�Ǘ��̐��̏������}�����v�Ǝw�E���܂����B
�����Ɓu��Ñ��͋��|���v
���j�^�����O��c�̂��Ɠ����s��t��̒������F����͈�Ò̐��ɂ��āA�u��3�g����悤�Ȋ����ɂȂ��Ă���ƁA���@���Ґ�����3�g���ȒP�ɒ�����B���̂Ƃ��ɂ́A�d�NJ��҂����Ƃ���x��đ����Ă���v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�����ǂ̊��҂��݂Ă����t�Əd�NJ��҂��݂Ă����t�͏d�Ȃ��Ă��邽�߁A�d�NJ��҂�������Ɣ��Ɍ������Ȃ�B��Ñ��́A��3�g�̑O�̋��N12�������C���[�W���邭�炢�̋��|���������Ă���v�Əq�ׁA��Â̂Ђ����ɋ�����@���������܂����B
�����r�m���u���Ԃ͂��ؔ� ������@�������L�v
���j�^�����O��c�̂��ƁA���r�m���͋L�Ғc�ɑ��A�u���傤���瑽���̊w�Z�ʼnċx�݂��}���A���������4�A�x�ŁA�I�����s�b�N���n�܂�B��N���Ɨ��s��A�Ȃ̃V�[�Y�������A�����͂̋����ψي��ɒu����������Ƃ����ǖʂŁA���Ԃ����ؔ����钆�ŁA����܂ňȏ�ɋ�����@�����F����Ƌ��L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�w��@���A��@���x�ƕ����O������������Ȃ����A�ɂ߂ďd�v�ȏɂ���B�F���ǂ������s�����Ƃ�A�l�̗��ꂪ�ǂ��Ȃ�̂����d�v�ŁA���̉Ă��Ō�̃X�e�C�z�[���ɂ��Ă��������v�ƌĂт����܂����B�܂��A21���̃��j�^�����O��c�ł́A4��ڂً̋}���Ԑ錾�ɓ����Ă���A�s���̔ɉ؊X�̑ؗ��l�����������Ă���Ƃ������Ƃ̕��͂�������܂����B����ɂ��ď��r�m���́u���͋C�I�ɂ́w�������͂��Ȃ��x�Ƃ����C���[�W������Ă���悤�Ɏ��͎~�߂Ă��邪�A���ۂ͊F����ɋ��͂��������Ă���v�Əq�ׂ܂����B�����āA�u�f���^���̉e���Ȃǂ��l������ƁA���Ȃ��Ƃ��O��ً̋}���Ԑ錾���Ɠ����悤�ɖ�ԑؗ��l��������������K�v������B���ɂ��Ă����H�X�ɋ��͂��������A���p�q�ɂ����낢��Ǝ��l���������Ă���A�������������Ƃ����ꂩ��̐����ɂ�����Ă���Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B�܂����r�m���́A���f���i�̃��N�`���ɂ���20���A�c�������J����b���A������Η��N�͂��߂���A�lj���5000���̋�������_������Ɩ��炩�ɂ������Ƃɂ��āA�u���N�̂��������������̂��͂ق����Ƃ����̂������ȂƂ��낾�v�Əq�ׁA�����̂ɑ��đ��₩�ɏ\���ȗʂ̃��N�`������������悤�����������ɗv�]���Ă����l���������܂����B
���C���h�Ŋm�F�uL452R�v�ψكE�C���X�z�����g���
�C���h�Ŋm�F���ꂽ�uL452R�v�̕ψق�����E�C���X���ǂ����ׂ�X�N���[�j���O�����̌��ʁA����11���܂ł�1�T�Ԃœs���̗z�����͑O�̏T���9�|�C���g�㏸����30.5���ƂȂ�܂����B4�T�A���ŏ㏸���Ă��܂��B�܂��A����18���܂ł�1�T�Ԃł͑���l�Ȃ���z������39�����Ă��āA����Ɋg�債�Ă��܂��B���Ƃ́A�C�M���X�Ō��������uN501Y�v�̕ψق�����E�C���X�̗z�����̐��ڂƔ�r����ƁA�uL452R�v�̕ψق�����E�C���X�́A3�T�ԂقǑ����y�[�X��30�������Ǝw�E���܂����B���̂����Łu�z�����̏㏸�y�[�X���猩�Ă�L452R�̕ψق�����E�C���X���s���ɍL�������B���̃E�C���X�ւ̒u������肪�}���ɐi��ł���̂��߈��������\���x������K�v������v�Ǝw�E���܂����B
���s���̃R���i�a�� 5967����
�s���ŐV�^�R���i�E�C���X�̓��@���Ґ����������钆�A�����s�͒����ǂ̊��Ҍ����̕a����85���V���Ɋm�ۂ��A�s���S�̂̐V�^�R���i�̕a����5967���ɂȂ����Ɩ��炩�ɂ��܂����B����Œ����nj����̕a����5575���ɑ����A�d�NJ��Ҍ����͕ς�炸392���ƂȂ��Ă��܂��B21���̃��j�^�����O��c�Ŏ����ꂽ�s���̊����ƈ�Ò̐��ɂ��Ă̕��͌��ʂł��B
�����Ƃ̕��� ������
�V���Ȋ����̊m�F�́A20�����_��7���ԕ��ς�1170.0�l�ƂȂ�A�O��E����14�����_��817.1�l��肨�悻352�l�������܂����B���Ƃ́A�u�挎21����387�l����A�킸��1������1000�l�̑����Ă��đ�3�g������y�[�X�Ŋ������}�g�債�Ă���v�Ǝw�E���Ă��܂��B������͑O�̏T�̂��悻149���ŁA�O�����18�|�C���g�㏸���܂����B����19���܂ł�1�T�ԂɊ������m�F���ꂽ�l�̔N��ʂ̊����́A20�オ31.9���ŁA3�T�A����30�����A�ł������Ȃ�܂����B������30�オ20.8���A40�オ17.0���A50�オ11.7���A10�オ7.6���A10�Ζ�����4.5���A60�オ3.8���A70�オ1.5���A80�オ1.0���A90��ȏオ0.2���ł����B�挎�ȍ~�A50��ȉ��őS�̂̂��悻90�����߂Ă��܂��B����A65�Έȏ�̍���҂́A���T��286�l�őO�̏T���73�l�����܂������A������0.4�|�C���g������3.7���ł����B
�����o�H���킩���Ă���l�ł́A��������l����̊�����54.1���ƍł������A�����ŐE�ꂪ18.7���A�ۈ牀��w�Z�A����ɍ���Ҏ{�݂�a�@�Ƃ������{�݂ł̊�����7.8���A��H��6.2���ł����B
���T�́A�{�݂ł̊������O�̏T����1.6�|�C���g�����A���ɁA�ۈ牀�⏬�w�Z�A�m�Ȃǂł̊�������������A�N��ʂł�10�Ζ������O�̏T����4.7�|�C���g������27.4���A10��ł�6.4�|�C���g������19.7���ł����B
�܂��A��H�ł̊����͍��T��60��ȉ��̂��ꂼ��̐���Ŕ������Ă��āA���Ƃ́u�F�l�⓯���Ƃ̉�H�ɂ�銴���͐E���ƒ���ł̊����̂��������ƂȂ邱�Ƃ�����B�A�x��ċx�݁A����ɃI�����s�b�N�ϐ�Ȃǂł̈��݉�́A�I�����C�������p����Ȃǂ̍H�v�����߂���B���ɁA�ӂ������Ă��Ȃ��l�Ƃ̉�H�͔�����K�v������v�Ǝw�E���Ă��܂��B
�u�����̍L����f����w�W�v�Ƃ����A�����o�H���킩��Ȃ��l��7���ԕ��ς�20�����_��720.7�l�ŁA�O�̏T���炨�悻218�l�����A6�T�A�����đ������Ă��܂��B
�܂��A������́A20�����_��149.7���ƑO��18.9�|�C���g�㏸��7�T�A�����đ������܂����B
���Ƃ́u��3�g�̃s�[�N���O�̂���Ɠ������x�Ŋ������g�債�Ă���B����Ȃ�g���h�����߂ɂ͂���܂ňȏ�ɓO��I�ɐl�̗���̑�����}�����A�����h�~������s����K�v������v�ƌx�����Ăт����܂����B
�����o�H���킩��Ȃ��l�̊����͂��悻62���őO�̏T�Ɣ�ׂĉ����ł����B
�N��ʂł́A20�ォ��60���50�����Ă��āA���ɁA�s����������20���30��ł�60����㔼�ƍ����A���Ƃ́A�u�ی����̐ϋɓI�u�w�����ł��A�ǂ��Ŋ��������̂�������Ȃ��Ƃ���z���҂��������Ă���B���₩�ɔZ���ڐG�҂̌������s���̐��̋������K�v�ł���v�Ǝw�E���Ă��܂��B
�����@���� ��1�����Ŕ{��
�����̗z������7���ԕ��ς́A20�����_��10.2���ƂȂ�A�O�̏T�̍���14�����_����3�|�C���g�㏸���܂����B10������̂́A���N�O��1��20���ȗ��ł��B���@���҂́A20�����_��2388�l�ƍ���14���̎��_���365�l�������܂����B���Ƃ́A�u���悻1�����Ŕ{�������v�Ǝw�E���������ŁA�u����A����Ȃ�l���̑�����ψي��̉e���ȂǂŐV�K�z���҂�������������A��Ò̐����Ђ����̊�@�ɒ��ʂ���v�Ǝw�E���Ă��܂��B
���@���҂�N��ʂɂ݂�ƁA60��ȉ����S�̂̂��悻86�����߂Ă��āA���Ƃ́A�u�挎��{��65���O�ォ��㏸�X�����v�ƕ��͂��Ă��܂��B�N��ʂɂ݂�ƁA40���50�オ���ꂼ��S�̂̂��悻21���A30��ȉ����S�̂̂��悻34�����߂Ă��܂��B
���Ƃ́u�挎�ȍ~�A��N�A���N�w�𒆐S�Ƃ����V�K�z���Ґ��̋}���ȑ����ɔ����A���@���҂��}�����Ă���B���̏������Ύ�N�E���N�w�̒����NJ��҂��������A�x��ďd�NJ��҂���������\��������v�Ǝw�E���܂����B���̂����ŁA�u�l�Ƃ̐ڐG�̋@������炵�A��{�I�ȑ��O�ꂵ�A���N�`���ڎ�͗\�h���ʂ����҂���邱�Ƃ��[������K�v������v�Ƃ��Ă��܂��B
�s�̊�ŏW�v����20�����_�̏d�NJ��҂́A����14�����_���6�l������60�l�ŁA���Ƃ́u�����l�Ő��ڂ��Ă���v�Ǝw�E���܂����B�j���ʂł́A�j��48�l�A����12�l�ł��B�܂��A�N��ʂł́A60�オ17�l�ƍł������A�����ŁA50�オ16�l�A70�オ14�l�A40�オ10�l�A30�オ2�l�A80�オ1�l�ł����B���Ƃ́u�d�NJ��҂�75����60��ȉ����B���T��10�Ζ�����30��ł��V���ȏd�ǗႪ�������Ă���B�얞��i����������l�͎�N�ł����Ă��d�lj����X�N�������v�Ǝw�E���܂����B
���̂ق��A�l�H�ċz�킩ECMO�̎��Â��܂��Ȃ��K�v�ɂȂ�\����������Ԃ̐l��20�����_��203�l�ŁA����14�����_���20�l�����܂����B�܂��A����19���܂ł�1�T�Ԃł́A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������14�l���S���Ȃ�܂����B���̂���10�l��70��ȏ�ł����B
���u����×{���҂����ɑ����Ă���v������@��
���j�^�����O��c�ł́A20�����_�ŗz���ƂȂ����l�̗×{������܂����B����14�����_�Ɣ�ׂ�ƁA����ŗ×{���Ă���l��1816�l������3657�l�ƁA�{�߂��ɑ����Ă��܂��B�܂��A�s���m�ۂ����z�e���Ȃǂŗ×{���Ă���l��73�l������1769�l�A��Ë@�ւɓ��@���邩�A�z�e���⎩��ŗ×{���邩�������̐l��367�l������1671�l�ł����B���@���Ґ����܂߂��×{������4���ׂĂ̍��ڂ��������Ă��āA���������킹���u�×{���K�v�Ȑl�v�S�̂̐���9485�l�ŁA����14�����_��6864�l�̂��悻1.4�{�ɂȂ�܂����B���j�^�����O��c�ɏo�Ȃ��������s��t��̒������F����́u���@�����łȂ��A�z�e�����Ȃ��Ȃ��������ɂȂ��Ă��Ă���ق��A����ŗ×{���銳�҂����ɑ����Ă��Ă���B�h���×{�A����×{��S���A��ÂƂ��Č��Ă����Ȃ�������Ȃ����v�Əq�ׁA������@���������܂����B
���u�����x�����ŋٖ��ɘA�g���Ή��v���[����
�������[�����͌ߌ�̋L�҉�Łu�����s�̃��j�^�����O��c�ł́A���Ƃ���A�V�K�z���Ґ��̑����䂪�p������Ƒ�3�g�̃s�[�N����傫������Ƃ̋@�B�I�Ȏ��Z���Љ�ꂽ�Ə��m���Ă���B�����s�Ƃ́A�������Ò̐��̂ق��A���łɎ��{���Ă����̌��ʂȂǂ��܂߁A�F���̋��L����}���Ă���A���������A�����x�����������āA�����Ȃǂ𒍎����A���Ƃ̈ӌ������܂��A�ٖ��ɘA�g���đΉ����Ă����v�Əq�ׂ܂����B
�������g��̓����u2�T�ԑ҂�����@�I�v�@7/21
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪���������s�́A���͉�c���J���A���Ƃ́A�ψي��̉e���ȂǂŁA�u2�T�Ԃ�҂����ɑ�3�g���͂邩�ɒ������@�I�Ȋ����ɂȂ�v�ƌx����炵�܂����B
�������ۈ�Ì����Z���^�[�E��ȋM�v��t�u�ψي��ւ̒u������肪�i�݁A�����䂪����ɏ㏸����Ɗ����g�傪�}���ɐi�݁A2�T�Ԃ�҂����ɁA��3�g���͂邩�ɒ������@�I�Ȋ����̏ɂȂ�܂��v
�s���̊����҂́A�O��̂��悻817�l����A1170�l�ɋ}�����A�������149���ɏ㏸���܂����B���Ƃ́A�����I�Ȋ����g�傪�N�����u��3�g������y�[�X�Ŋ������}�g�債�Ă���v�Ƃ��āA���̃y�[�X�������A2�T�Ԍ�ɂ�1�������肨�悻2598�l�ƂȂ�A��3�g�̃s�[�N��傫������Ǝw�E���܂����B
���@���҂�6�����{����{������2388�l�ƂȂ�A�����g�傪�����A�u��Ñ̐����Ђ����̊�@�ɒ��ʂ���v�Ɗ�@���������܂����B
�܂��A�����͂̋����f���^���ւ̒u���������}���ɐi�݁A�z������30�D5���ƂȂ�܂����B�����̈������A���r�m���́A�u22�������4�A�x��A�ċx�݂̗��s��W���[�͍T���ė~�����v�ƌĂт����܂����B
����A�����I�����s�b�N�W�҂̊����ɂ��ẮA��`���u��0�D06���A�X�N���[�j���O������0�D02���ƁA�����҂̊����́A�u�Ⴍ�}�����Ă���v�ƕ���܂����B
���V�^�R���i�����g��� 2�T�Ԍ�2598�l�Ɂ@�����s�̐��Ɖ�c �@7/21
���̃y�[�X�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�����ƁA�����s���̊����Ґ����A2�T�Ԍ�ɂ́A�ߋ��ő���2,598�l�ɒB����Ƃ̕��͂������ꂽ�B
21���ߌ�ɊJ���ꂽ�����s�̐��Ɖ�c�ł́A�V�K�����Ґ���7���ԕ��ς�1,170�l�ŁA�O��̂��悻1.5�{�ɂ̂ڂ��Ă���Ƃ̕��͌��ʂ������ꂽ�B
���̂����ŁA���̂܂܂ł�2�T�Ԍ��8��3���ɂ́A1���̊����Ґ���2,598�l�ɒB���A�ߋ��ő���2,520�l������Ƃ����B
���S���̐V�K������ �O�T��1.53�{ �����̃f���^�� ��60���Ɛ��� �@7/21
�����I�����s�b�N�̊J����4�A�x��O�ɁA�V�^�R���i�E�C���X��ɂ��ď�����������J���Ȃ̐��Ɖ���J����A�������}�g�傷�铌���s�Ȃǎ�s����Ċg��ɓ]�������ꌧ�ȂǁA�e�n�̊������Ñ̐��̏ɂ��ĕ��͂��s���܂����B
��Ŏ����ꂽ�����ɂ��܂��ƁA�V�K�����Ґ���20���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�Ɣ�ׂāA�S���ł�1.53�{�Ƒ傫���������Ă��āA�ً}���Ԑ錾���o����Ă���B�����s�ł�1.49�{�A��T�܂Ō����������Ă������ꌧ�ł�1.67�{�ƍĊg��ɓ]���܂����B�܂��A�܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă���n��ł��A���{��1.89�{�A��ʌ���1.87�{�A��t����1.39�{�A�_�ސ쌧��1.38�{�Ƌ}���X���ƂȂ��Ă��܂��B
���̂ق��A�k�C����1.54�{�A���Ɍ���1.94�{�A���s�{��1.74�{�A��������1.53�{�ȂǂƊe�n�Ŋ������}�g�債�Ă��܂��B
���݂̊������A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��Ō���ƁA�����s��59.33�l�A���ꌧ��38.47�l�A�_�ސ쌧��33.20�l�A��ʌ���26.93�l�A��t����26.67�l�Ɗ������ł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ���25�l���Ă��āA���{��23.91�l�A���挧��18.35�l�A�ΐ쌧��17.49�l�A����ɑS���ł�18.25�l�ƁA�u�X�e�[�W3�v�̖ڈ���15�l���Ă��܂��B
�܂������͂̋����C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�u�f���^���v�́A�����s�ł͂��łɊ����S�̂̂��悻60�����߂�Ɏ������Ɛ��肳��Ă��āA��ł͋}���Ɋg�傷��u�f���^���v�̍L�����O��Ƃ������A�A�x��I�����s�b�N�J�ÂȂǂŐl�̈ړ���������Ȃǂ��āA�������g�傷�郊�X�N���ǂ��}���邩�Ȃǂɂ��ċc�_���s���܂����B
�c�������J����b�́A���Ɖ�̖`���u�V�K�����҂̐����L�тĂ��āA���̑�������s�����B���ł������͖�Ԃ̑ؗ��l�����ً}���ԑ[�u�ɓ���O�����������Ă��āA���낻����ʂ��o�Ă��鎞�ɂ�������炸�A�������L�тĂ���v�Ǝw�E���܂����B���̂����Łu�������S�Ɋ����̊g�傪�݂��A�����҂��{�X�ő����Ă����ƁA�ǂꂾ���a�����m�ۂ��A���N�`����ł��Ă��Ă��A�a���̂Ђ������\�z�����B���X�N�̍����s�����ǂ��h���ł������l���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
���{��t��̒����́A�L�҉�Łu���łɁw��5�g�x���i�s���Ă���ƍl���Ă���A�����������Ґ����ł����������w��3�g�x���錜�O������B�����͂������ψي��ɂ��}�g��̊댯�������鍡�A���߂āA��{�I�Ȋ�����̓O������肢�������v�Əq�ׂ܂����B
���u�����O������������Ȃ����c�v�@���������g��A���r�m������@���@7/21
�����s��21���A�s���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����1832�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�����҂�1800�l����̂�1��16��(1839�l)�ȗ��ŁA���j�Ƃ��Ă͉ߋ��ő��B����7���Ԃ̕��ς�1277�E6�l�ŁA�O�T��155�E2���Ƒ����y�[�X������ɏオ���Ă���A�����I�����s�b�N�̊J����O�Ɋ����g��Ɏ��~�߂��|����Ȃ��Ȃ��Ă���B
21���ɊJ���ꂽ�s���j�^�����O��c�ł́A���݂̃y�[�X�Ŋ������L����A�s���̐V�K�����҂�7���ԕ��ς��ܗ֊��Ԓ���8��3���ɂ͖�2598�l�ɂȂ�Ƃ������v�l�����\���ꂽ�B�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v�E���ۊ����ǃZ���^�[���́u�����䂪����ɏ㏸����ƁA2�T�Ԃ�҂����ɑ�3�g���͂邩�ɒ������@�I�Ȋ����ɂȂ�v�Ƌ����x�������������B
�s���̐V�^�R���i���@���҂�20�����_��2388�l�B�O�T�����18���������A50��ȉ���7�������߂Ă���B�s�̊�ŏW�v����21�����_�̏d�ǎ҂�64�l�ŁA�d�ǎҐ��͐V�K�����҂̑����ɒx��đ����邱�Ƃ����Ò̐��̕N��(�Ђ��ς�)�����O����Ă���B�s�������̍L��������������z������19�����_��10�E2���ɂȂ�A���N�Ԃ��10�������B
���r�S���q�m���́u�ċx�݂��n�܂�A22������4�A�x�������Ċ�������w�g�傷�鋰�ꂪ����B������@���A��@���ƕ����O������������Ȃ����A���܋ɂ߂ďd�v�ȏɂ���v�ƌĂъ|�����B
���a�̎R�����R���i��5�g�@�m���A4�A�x�ɒ��ӑ����@7/21
�m��g�L�m����21���A�a�̎R�����̐V�^�R���i�E�C���X�����ɂ��āA11�������5�g�ɓ����Ă���Ƃ����F�����������B�����͂������Ƃ����C���h�R���̕ψي��u�f���^���v�ɂ�銴���g��̋��ꂪ����Ƃ����A22�������4�A�x��O�ɒ��ӂ��Ăъ|���Ă���B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A�����s�ł�6�����{����}�����A19�����݁u���������i�K�v(�X�e�[�W4)�̊25�l��傫������55�E3�l�ƂȂ����B���{��22�E9�l�A�S���ł�17�E2�l�Ɓu�����}���i�K�v(�X�e�[�W3)�̊15�l���Ă���B
�����̊����Ґ���7��10����1�E2�l���������A11�����瑝���X���ɂȂ�A19����3�E9�l�ƂȂ��Ă���B�Ƃ�킯�a�̎R�s��7�E6�l�܂ŏ㏸���Ă���B
�����ی����̖�K�F�q�Z�ẮA����̊����g��̓x�����ɂ��āA�����̍s����N�`���̐ڎ�A�ی���Ís���̑�ɂ��Ƃ�������A�ߋ��̏܂���Ɓu���̏㏸��͑傫�Ȕg�ɂȂ���\��������B���ł��X�e�[�W4�ɋ߂������ɂȂ��Ă���B���Ȃ��@���������đΉ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƃ̌������������B
�u�f���^���v�ɂ��ẮA�����ł͂��ł�3�l�̊��������̋@�ւŊm�肵�Ă���B����ɁA�܂��m��ł͂Ȃ����A����a�̎R�s�̌����ŁA6�l�̋^���Ⴊ����B����9�l��4�Ƒ��ɂ܂������Ă��邱�Ƃ���A����u�f���^���v�̊g�傪���������Ƃ����B
����A����7��1���ȍ~�ɕ�����������������68�l�̐��芴���o�H�͂����B���O���炪�ł�����22�l�A�Ƒ����炪16�l�A�E��E�w�Z���炪13�l�A�s��11�l�ȂǂƂȂ����B���O����̂������R����19�l�łقƂ�ǂ��߂��B
���肳��銴���@��ɂ��Ă͐E��Ȃǂł̉�b��20�l�A�Ƒ��ȂNj��������ɂ����̂�14�l�A���H��13�l�ȂǂƂȂ����B
�m��m���́u�I�����s�b�N����ʂȂǂŌ��邽�߂Ɉ��H�X�ɏW�܂��āA���Ȃǂ�����Ő���オ��P�[�X���悭���邪�A�������X�N�������̂ł�߂Ăق����B���H�X�ɂ����肢�������v�Ƌ����B�����ւ̋A�Ȃɂ��ẮA���܂��܂Ȏ�����l�����A�����ւ̈ړ��̑S�ʎ��l�͋��߂Ȃ����u�T�d�ȍs��������Ăق����v�Ɖ��߂ċ��߂��B
���́A��5�g�ɓ�����11���ȍ~�̌���������44�l�̂����A���N�`����2��ڎ킵���l�͂��Ȃ��������Ƃ����炩�ɂ����B
1��ڎ킵���l�����l�����ق��́A�قƂ�ǂ����ڎ킾�����Ƃ����B�D��I�ɐڎ킳�ꂽ��Ï]���҂̊����҂͂��炸�A60���2�l�A70��ȏ�1�l�����������B20�����݂̌����̓��@�҂�41�l�ŁA�d�ǎ҂͂��Ȃ��B
�m��m���́u���炩�Ƀ��N�`���������Ă���B�d�lj����₷�����N��肩��ڎ킹��ƌ��������{�͐����������B�Ⴂ�l���f���^���͊�Ȃ��B�\����Ȃ��Ă��邪�A�@��͎c���Ă���B�ڎ킵���������S�ŁA�l�ɖ��f���|���Ȃ��v�Ƙb�����B
���u3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�͊����g���}�������v�V�^�R���i�̃f�[�^���́@7/21
���{�͓����ܗ֊J�Ò����܂�8��22��(��)�܂ŁA�����s�Ɖ��ꌧ��Ώۂɋً}���Ԑ錾�o�����B���W�w�V�^�R���i�ƃf�[�^����〜4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�͉��������炷�̂��H�x��3��ڂł́A��������̃r�b�O�f�[�^����2�x��(1��13��〜2��28��)��3�x��(4��25��〜6��20��)�ً̋}���Ԑ錾�̌��ʁA����ь��݂ƍ���̊����g��̉\�����l�@����B
���݁A���{�͓����s�Ɖ��ꌧ��ΏۂɁA�����ܗւ̊J�Ò����܂�8��22���܂�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�o���ł���B�ȑO���瓌���ܗւ�ً}���Ԑ錾�ɂ́u�����ܗւ��J�Â���ɂ�������炸�A�����g��h�~�̂��߂ɍ����ɂ͊O�o���l���Ăт�����̂��v�u�܂����H�X��_����������̂��v�Ȃǂ̔ᔻ���������B
�����ł́A�����ܗւ̒��~�����߂�I�����C����̏�����45�����A���{�́u����H�X�ւ̎����~���v�ɔᔻ���W�܂�A�P��ɂ�����Ȃǖ�肪�I�悵�Ă���(��1�A2)�B���̂悤�ȏɑ���s���͓����ܗւ̊J�Â�ڑO�ɂ��Ă��ĂȂ��قǍ��܂��Ă���悤�Ɍ�����(��3)�B���ہA�����s���́u�O�o���l���v�͒ቺ�X���ɂ���Ƃ���������(��4)�B
����ŁA���߂�3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�͂ǂ��������̂��B�������JX�ʐM�� �������CXO �ז�Y�I����6��29��(��)��Ledge.ai�ҏW���̃C���^�r���[��ނɉ����A2�x�ڂ�3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�͎��I�ɈقȂ�ƕ��͂��A3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ɂ��āu�f�[�^���������A���m�Ɋ���������}�������ƌ����܂��v�Ƙb�����B
2�x�ڂً̋}���Ԑ錾�͐V�K�����Ґ����s�[�N���ɔ��o�����B���ɋً}���Ԑ錾�o���Ȃ������Ƃ��Ă��A�����X���ɓ]���Ă����\���������B�ً}���Ԑ錾�o���Ă���1�T�ԂŌ����X���ɓ]���Ă������A�ً}���Ԑ錾�̉e�������ł͂����ɂ��̂悤�ȉe�����N���邱�Ƃ͖{�����蓾�Ȃ��Ǝw�E���A�ً}���Ԑ錾�Ō����X���ɓ]�����Ƃ͌����Â炢�ƌ��B
3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�͐V�K�����Ґ��������X���ɂ���r���Ŕ��o�����B���ۂɔ��o���Ă����1�T�Ԍ�̃S�[���f���E�B�[�N(GW)���Ɋ����g��̃s�[�N���K��A�����Ɍ����X���ɓ]���Ă������B���{��GW�Ƃ����l���������ɂȂ�Ǝv���鎞�����������A�ً}���Ԑ錾�o�����ƍl������B
�ז쎁��3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ɂ��āu�����炭�A�����1�T�ԑO�ɔ��o���Ă����ق������ʂ͂������Ǝv���܂��v�Ƃ����A�u�l�̌𗬂̋@���p�x������A47�s���{���ŐV�K�����Ґ�������ƌ���܂����B�ً}���Ԑ錾�͐l�̐S���ɊW�Ȃ����ʂ��������Ǝv���܂��v�Ƙb�����B
���{�Ⓦ���s�Ȃǂ́A3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ł́u�l���}���v���d�����Ă���(��5)�B���H�X�͌ߌ�8���܂ł̎��Z�v���A��ޒ�J���I�P�ݔ��������H�X�͋x�Ɨv���A�S�ݓX��V���b�s���O�Z���^�[�A�ʔ̓X�A�f��قȂ�1000�������[�g�������^�{�݂͋x�Ɨv����������ꂽ�B
�ז쎁�͐��{�ɂ����H�X�ւ̑Ή��ɂ��āu(���{�ɂ��Ή���)�������͉��Ō��܂�̂��B���ɓ�����v�Ƃ����A�f�[�^���͂̊ϓ_����u���Ђ����Ă���f�[�^�ł͈��H�X�ƃI�t�B�X��2���傫�Ȋ������ɂȂ��Ă��܂����B�����Ґ������炷�Ƃ����Ӗ��ł͑Ó��Ɍ����܂��v�ƌ��(��7)�B
�ז쎁�́u3�x�ڂً̋}���Ԑ錾���͑����̈��H�X�����Z�c�Ƃ�x�Ƃ�]�V�Ȃ�����܂����B���߂ł́A�Ƒ�������H�X�ȊO�̎��Ə��A�I�t�B�X�Ȃǂ̊������Ⴊ���C���ɂȂ��Ă��܂����v�Ƙb���Ă���B
�f��ق���p�قȂǂւ̑Ή��ɂ��Ắu�\�ʓI�Ɍ���ƁA�Ȃ������܂ł���K�v������̂��Ƃ����b������Ǝv���܂��B�������A(�f��ق���p�قȂǂ�)�ړI�n�ɍs�����łɊ�蓹����P�[�X������܂��B�l���}���̊ϓ_�Ō����ƁA�s���̖ړI���̂��̂��Ȃ��������ʂ����ꂽ�ƍl����ق������R�ł��傤�v�Əq�ׂ��B
�ז쎁���w�E����Ƃ���A�ً}���Ԑ錾�ɂ����鐭�{�̑Ή����ǂ��]������̂��́u���ɓ�����v���B���Ƃ��A���H�X�Ȃǂ͂����ł������X�q����������ƌ�����ŁA�x�Ƃ⎞�Z�c�Ƃ�]�V�Ȃ������ƁA�ň��̃P�[�X�Ƃ��Ă͔p�Ƃ�|�Y��������Ȃ��P�[�X���l������(��8)�B
���ہA������Г������H���T�[�`�ɂ��ƁA7��2����16�����_�ŐV�^�R���i�E�C���X�֘A�̌o�c�j����͑S���ŗv1650��(�|�Y1558���A�ٌ�m��C�E������92��)�B���H�Ƃ͍ő���296���ɂ����(��9)�B�����ł́u�����܂Ńf�[�^���͓I�ɂ͐������v�Ƃ����\���ɗ��߂����B
�܂��A���҂Ƃ��Ă͖`���ŐG�ꂽ�悤�Ȗ�����������������܂���ƁA�����4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���ߋ��Ɠ����悤�Ȋ����g��h�~�̌��ʂ�]�߂邩�͋^��ƌ��킴��Ȃ��A�ƕ⑫���Ă��������B
���l�������Ȃ��s���{���u�Ύ�͂ǂ��ɂ��邩�킩��Ȃ��v
����̎�ނł́A�n��ʂɂ�����V�^�R���i�E�C���X��������̃r�b�O�f�[�^�����ƂɁA���݂ƍ���̊����g��̉\���ɂ��Ă��b�����B�܂��͐l�������������s�Ƒ��{���猩�Ă������B
�����s�͐��c��𒆐S�ɓs�S���ł܂�ׂ�Ȃ��������オ���Ă���B
���{�̓I�t�B�X�X����H�X�Ȃǂ����W����ɉ؊X�ŃL�^(�k��)�ƃ~�i�~(������)�Ɋ������Ⴊ�W�����Ă���B�Ȃ��A�����̐}�̊�������ɂ͉Ƃ�}���V�����ȂǁA�N���[�Y�h�ȃR�~���j�e�B�͊܂܂�Ă��Ȃ��B
��Ɋ����g�傷��̂̓I�t�B�X����H�X�ȂǃI�[�v���ȃR�~���j�e�B�Ƃ����B�������Ⴊ�����ꏊ�͒P�ɐl�������W���Ă��邾���ł͂Ȃ��A�I�t�B�X����H�X�Ȃǐl�Ɛl����ړI�n�����邩�ǂ������傫���e�����Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƍז쎁�͕��͂���B
�u�ƒ���̊��������Ȃ�A�Z���ԂŊ����g��͎�������ł��傤�B�������A���ۂ͂����ł͂���܂���B�I�[�v���ȃR�~���j�e�B�������ɗ}�����Ă����̂��������}�~�ɂ͏d�v�ł��B�����炱���A�w�l���}���x�Ƃ������l���������܂�Ă����̂ł͂Ȃ����v
����ŁA�����s����{�ȊO�̒n��ł͂ǂ̂悤�ȓ���������̂��B�l���������s���{���قǑ��������茸��������Ƃ������}���ȕω��͋N����Â炢�̂ɑ��A�l�������Ȃ��s���{���͍��ׂȂ��������ŋ}������X��������Ƃ����B
���Ƃ��A���ꌧ�ł͋��N7���ً̋}���Ԑ錾���ɂ����āA�킸����1�T�ԂŐl��10���l������100�l�̗z���҂����������B���݂��ˑR�ƍ��������ɗ��܂��Ă���B
�ז쎁�́u���݂�3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�������Ă���A�S���I�ɂ͌����X���Ȃ����͉����X���ł��B����ŁA6��15�����ɂ͎R�����A6��29�����ɂ͏H�c���ȂǁA����̒n�悪�����X���ɂ���Ƃ����ӏ����������o�Ă��Ă��܂��B(�l�������Ȃ��s���{���ɂ����ẮA�����g�傪�N���肤��)�Ύ�͂ǂ��ɂ��邩�킩��Ȃ��ł��v�ƌ�����B�@
�������s �x�Ɩ��߈ᔽ�̈��H�X60�X�܂ɑ� �ٔ����ɉߗ����߂� �@7/21
6���܂ł�3��ڂً̋}���Ԑ錾���ɁA�@���Ɋ�Â����x�Ƃ̖��߂Ɉᔽ�����Ƃ��āA�����s�͍ٔ����ɑ��ēs����60�̈��H�X�ɉߗ����Ȃ��悤���߂܂����B
�����s�́A���Ƃ�4������6��20���܂ł�3��ڂً̋}���Ԑ錾�̂��ƂŁA���������H�X�ɋx�Ƃ�v�����A�����Ȃ������X�ɑ��ĐV�^�R���i�E�C���X��̓��ʑ[�u�@�Ɋ�Â��ċx�Ƃ̖��߂��o���܂����B
�������A�s�ɂ��܂��ƁA���߂ɉ������̂�2�X�܂����ŁA�����Ȃ�����60�̓X�͋x�Ƃ����Ɏ��̒𑱂��Ă������Ƃ��m�F�����Ƃ������Ƃł��B
���̂��ߓs�́A�s���̒������l����Ɗʼn߂ł��Ȃ��Ɣ��f���A21���ɍs�����Ƃ���30���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ��悤�A�ٔ����ɋ��߂�ʒm���o���܂����B
�s�́u���[�@�̎葱����K�Ɏ��s�����B���H�X�̕��͋ꂵ���Ƃ��낪����Ǝv�����A�命���̓X�͉����Ă��������Ă���̂ŁA�Ȃ�Ƃ��������Ƃ����͂����肢�������v�Ƃ��Ă��܂��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���H�c��`�A4�A�x�����̒��͑����̐l�œ��키 ��������E�o���铮�����@7/22
�����I�����s�b�N�̊J��ɔ����āA�ꕔ�̏j�����ړ��������Ƃɂ��4�A�x�ɓ˓������B4�A�x�����ƂȂ�7��22���̒�6���߂��̉H�c��`�́A4�A�x���g���ė��s�ɏo������l�̎p�œ�����Ă����B�ً}���Ԑ錾���ł́A���܂ōł�������`���p�҂ɂȂ��Ă���B
���ً}���Ԑ錾�����ߌ���V�K�\�L�����Z��������
���܂łً͋}���Ԑ錾�����߂���邱�ƂŁA���������p�҂͐V�K�\��������L�����Z��������A�\���������Ă����B����������́A����܂łً̋}���Ԑ錾���ł͏��߂āA7��12���ً̋}���Ԑ錾���߈ȍ~�A�e�q���Ђł̓L�����Z�������V�K�\��̕�������ٗ�̏�ԂƂȂ��Ă���B�i��w����H�c��`���������l�}�s�ł�����Ȃ��l���o�Ă���A�d�Ԃ��������邽�тɉ��D���ł͑����̐l���~��Ă�����i�������AJAL��X�J�C�}�[�N���o�������1�^�[�~�i���AANA���o�������2�^�[�~�i���Ƃ��ɒ�6���̒i�K�ō��G���Ă����B
���ߑO���̕ւ͖��Ȃ������͖��Ȃɋ߂��\�����Ă���B���H���X�g�������s��
���ۂɉH�c��`�̔����ē��ł����Ă��A�ߑO���𒆐S�ɑ����̕ւ����Ȃ������͖��Ȃɋ߂��\�����Ă���\��������Ă����B�܂��ɋً}���Ԑ錾���ł͈ٗ�̏ł���B��6����ɂ�������炸�A�H�c��`���̒��H���H�ׂ��郌�X�g�����ɂ͍s�ł��Ă����B
�����L������̗��p�҂̎p�B����҂̎p���ȑO�ɔ�ׂđ������BANA�ł͍�N�Ɣ�ׂĖ�1.3�{�A2�N�O�ɔ�ׂ��5�`6�����x
�S�̂̌X���Ƃ��ẮA����܂ł͉Ƒ��A���Ⴂ�l�Ȃǂ����������Ă������A�H�c��`�Ŏ�ނ����Ă��钆�Ŋ��������ƂƂ��ẮA����҂̎p���ȑO�ɔ�ׂ�Ƒ��������A�N����킸�H�c��`����o�����闷�s�҂�A�ȋq�̎p������ꂽ�BANA�ɂ���7��19�����_�ō����4�A�x(7��22���`25��)�̗\��̓s�[�N���ōő�1��8��5000�l�̗��p�҂ɂȂ錩���݂ŁA��N��4�A�x�Ɣ�ׂĖ�1.3�{�A�R���i�O��2�N�O�Ɣ�ׂ�Ɩ�5�`6�����x�̗��p�҂ƂȂ��Ă���B
�������ȓ�������4�A�x�������ł��E�o���������s�҂�����
����4�A�x�ɍ������s������l�Ɏ�ނ������Ȃ��ŁA���������ꂽ�̂������ȓ�������E�o���������Ƃ������������B�����s��7��12������Ăыً}���Ԑ錾���Ĕ��߂��ꂽ���Ƃň��H�X�̂����̒��l�A�����ܗ֊J�Âɔ�����s������1000�~�A�b�v(��p�Ԃ����S)���ʋK���ɂ��a�̊g��A�X��1��������̓����s���̐V�K�����Ґ���1000�l����ȂǁA�啝�ɑ��������Ƃœs����4�A�x���߂������́A�R���i���������ŁA�l�Ƃ̐ڐG�͍ŏ����ɂ��Ȃ��痷�s�ɏo�ĉH����L�������Ƃ��������������B
���I�����s�b�N���ϋq�Ŋϐ�`�P�b�g�̕ԋ�������ŗ��s�ɍs���l��
����A�����I�����s�b�N�̊ϐ�`�P�b�g�������Ă����l���A���ϋq�J�ÂɂȂ������ƂŁA�ϐ킷�邱�Ƃ��ł����A�����ɂ���K�v���Ȃ��Ȃ������ƁA�X�Ɍ���ԋ������\��Ŋϐ�`�P�b�g�̑�����ԋ�����邱�Ƃ�������ŁA���ϋq�J�Â����܂���7��8���ȍ~�ɍ������s��\���l���m�F�ł����B�ϐ�`�P�b�g�̕ԋ��z�������~�̐l������A�Ȃ��ɂ͊J����܂߂�100���~�ȏオ�ԋ��ΏۂɂȂ����l������B�C�O���s�Ɏ��R�ɏo�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����ŁA�s���ł��ܗփ��[�h�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�V�^�R���i�E�C���X�̊ϐ�҂��g�債�Ă��铌���ɂ�������A�d����4���ԋx�݂ɂȂ邱�ƂŁA�����𗣂�Ă������߂��������Ƃ������Ƃ���ً}���Ԑ錾�����߂���Ă��痷�s���v�悷��l���o���B����A�ً}���Ԑ錾���ߌ�ɃL�����Z���������V�K�\���������悤���B�����I�����s�b�N�̊J����ڑO�ŁA�ܗ֊W�҂�v�l�̌����ׂ����ړ������Ă���p�����f�B�A�ŕ���Ă��邱�Ƃ��A���{�⎩���̂����l���Ăт����Ă������͂��Ȃ��Ƃ������������ꂽ�B
�����s�ɏo������l�̈ӎ����ω��B�����Ŏ���PCR��������l�C
�������s�ɏo������l�̈ӎ����ς���Ă���B�����O����s����2000�~�O���PCR�������ł���Z���^�[�ɂ͒����s�ł��A�\������Ȃ������o�Ă���Ȃǃ��N�`���ڎ���I���Ă��Ȃ�������A���s��A�A�Ȑ�ɖ��f�������Ȃ��ׂɐϋɓI�Ɍ�������l���������ق��A����҂𒆐S�Ƀ��N�`����2��ڎ���I����2�T�Ԉȏオ�o�߂������ƂŁA�ً}���Ԑ錾���ł͂��邪�A�\��ʂ�ɏo�����錈�f�������l�������Ă���B���s�Ҏ��g�������\�h�̑��������ŏo�����Ă���l������ǂ����Ƃɑ������Ă���B
��������ʂ͑䕗�̉e���ŗ��s����߂̐l��
���݁A�䕗�����ꌧ�ɐڋ߂��Ă���e���ŁA�H�c����ߔe�A�{�Ó��A�Ί_���A�v�ē��A���n���ւ̒��s�ւ�22���͑S���q�A23�����ߔe�s���͌ߑO���ɓߔe��`��������ւ̂قƂ�ǂ����q����ق��A�����ւ̕ւ�23�����S���q�̘H�����o�錩���݂��B�\��̒i�K�ł�22���o���̂قڑS�ւ����Ȃ̏ɂȂ��Ă������Ƃ���A�ߑO�������ł�����l�P�ʂŗ��p�҂����������ƂŁA�ۈ�������O�̑卬�G�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A����ł��H�c��`���͑傫�ȉו������������s�q�̎p����������ꂽ�B����̕��ʂƂ������́A�S���ʂō��G���Ă���B
7��23���̓����I�����s�b�N�̊J��̃e���r�ϐ���A����ł͂Ȃ������A�Ȑ�Ŋς�l�������Ȃ肻�����B
������21���̐l�o ����Ƃ�3��ڂ̐錾���Ԓ����ς�葝���@7/22
������21���A���j���̐l�o�́A���Ƃ�4�����{�����3��ڂً̋}���Ԑ錾���o�Ă������Ԃ̕��ςƔ�ׂē����A��ԂƂ������ƂȂ�܂����B
�m�g�j�͂h�s�֘A��Ƃ́u�`���������v�����p�҂̋��Čl�����肳��Ȃ��`�ŏW�߂��g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^���g���A��Ȓn�_�̐l�o�ׂ܂����B
�܂��A21���A���j���̓����̐l�o���A3��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă������Ƃ�4��25������6��20���܂ł̕����̕��ςƔ�r���܂��B
����ɂ��܂��ƁA�a�J�X�N�����u�������_�t�߂�������21���A��Ԃ�43���A�����w�t�߂œ�����3���A��Ԃ�38���Ƃ�����������ƂȂ�܂����B
�����đO��4�T�Ԃ̕����̕��ςƔ�r���܂��B
�����ł́A�a�J�X�N�����u�������_�t�߂͓�����4���A��Ԃ�16���A�����w�t�߂œ����̓}�C�i�X10���A��Ԃ�20���ł����B
����A�ً}���Ԑ錾���������ꂽ����̐l�o�́A�ߔe�s�̌����O�w�t�߂œ����̓}�C�i�X30���A��Ԃ̓}�C�i�X43���Ƒ啝�Ɍ������܂����B
�܂��A�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����21���̐l�o�́A�������s�̑�{�w�t�߂ł͓����̓}�C�i�X1���A��Ԃ�36���A��t�w�t�߂œ�����30���A��Ԃ�62���A���l�w�t�߂œ����̓}�C�i�X9���A��Ԃ�6���A���E�~�c�w�t�߂͓�����7���A��Ԃ�21���ł����B
���ً}���Ԑ錾����4�A�x�����@��A�S���̐l�o�� �@7/22
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�����A��s���ɋً}���Ԑ錾��A�܂h�~���d�_�[�u���o����Ă��钆�A�I�����s�b�N�J����23���ɍT���A4�A�x�̏������}�����B
�������H�͌������a�ƂȂ����ق��A�����w�ł͗��s�Ɍ������l�q������ꂽ�B
22���ߑO9���������JR�����w�̓��C���V�����̃z�[���B�R���i�БO���l�o�͏��Ȃ����̂́A�����h�~�����������ŗ��s�Ɍ������Ƃ������Ƒ��A��Ȃǂ�����ꂽ�B���c���Ɍ������Ƒ��A��u�z�e�����ʼn߂�����Ƃ���ŁA�A�x���߂��������Ǝv���āv
�H�c��`�̍������́A2020�N�̓���������藘�p�҂������A�A�Ȃ���Ƒ��A��Ȃǂ̎p������ꂽ�B�F�{�ɋA�Ȃ���Ƒ��A��u���Ƃ̕��ƕ�����N�`���ڎ킪�ς�ł��āA����Ɓv
�܂��A�����E�����q�s�̍����R�ł́A�����瑽���̐l���K��A�o�R���y����ł����B���i���A�l�o�͑����Ƃ����B
����A�C�̓���22���A�_�ސ�E����s�̊C������ł́A�R���i�БO���͏��Ȃ����̂́A�C�������y���ސl�̎p������ꂽ�B�K�ꂽ�l�u(�����X��)1�N�Ԃ肭�炢�ɐH�ׂ��̂ŁA�������������������܂��v
�������H�́A�e�n�Œ����猃�����a�ƂȂ��Ă��āA�ߑO11�����_�̒��������肪�A�����g���l���t�߂�擪��40km�̏a�ƂȂ��Ă���B
�������̊���1��3��l�Ɍ������@�郏�N�`�������݂̍j�@7/22
�����s���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�����Ȃ��A1��������̊����Ґ���3��l����Ƃ̌��ʂ������܂��Ă���B���������́A���{�̑����ȉ�̔��g�Ή�ɂ�锭���B���ۂɊ����Ґ��́u�u�w�I�Ɉُ�v�ƌ���ꂽ�N���N�n�Ɏ����㏸�y�[�X�������Ă���A3��l������ŃI�����s�b�N���J�Â���鎖�Ԃ���������ттĂ����B
�u3��l���Ă������͂Ȃ��v
����s������21���A���T�ȍ~�̊����ɂ��ĒW�X�ƌ�����B�����Ɋm�F���ꂽ�����Ґ���1832�l�ɏ��A1��16���ȗ���1800�l�����B�O��20����1387�l����}�����Ă������A���̊����́u21����2��l���Ă����������Ȃ��Ǝv���Ă����v�Ɩ������B
7��14���ɖ�2�J���Ԃ��1��l���Ĉȍ~�A�㏸�y�[�X�𑁂߂�s���̊����Ґ��B�S���҂́u�����x�I�Ɋ����Ґ����㏸���Ă������N�����̏Ɏ��Ă���v�Ƃ݂�B�N�����́A1��5����1315�l�̊������m�F�����ƁA6����1640�l�ɒ��ˏオ��A7���ɂ͉ߋ��ő���2520�l�ɒB���Ă����B
���̒S���҂�21����A�L�Ғc�Ɂu�����A�������2��l�ɓ��B����̂��v�Ɩ����ƁA�u����Ȃɑ������̃��x���ɒB����Ƃ͎v��Ȃ������B�\���͂��邩������Ȃ��v�Əq�ׁA�\�z�O�̏㏸�y�[�X�ɋ������B���Ȃ������B
�����A�����͂̋����ψي�(�f���^��)���L����s���̊����Ґ��́A2��l�����ł͂Ƃǂ܂�Ȃ��Ƃ̌��������܂��Ă���B���g����20���A���{�e���r�̕ԑg�ŁA8����1�T�ɂ͉ߋ��ő���3��l�߂��܂ő�������Ƃ̌��ʂ������������߂��B
���ۂɁA12���ɏo���ꂽ�ً}���Ԑ錾�ɂ�錸�����ʂ͂��܂��������A22������4�A�x���}����s���ł́A�����Ґ������炷�v�f�͂قƂ�nj�������Ȃ��B
4�A�x�̑O���ƂȂ���21���̓s�S�ł́A�s�̗v������炸�Ɏ�ނ���鋏�����ɋq���E���B�s�̒S���҂́u�䖝�ł����ɊO�o���Ă����҂������̂ł́v�Ƃ݂�B
���������Ɍ����Ȃ������g��̎����B�ŊJ��������Ȃ��Ȃ��A���݂̍j�͐ڎ킪���Ă��郏�N�`�����B
���r�S���q�m����21���A�L�Ғc�Ɂu���N�`����{���ɔ����őł������v�ƌ������ł����ڂ₢���B
�u��s��������������i�߂悤�Ƃ��Ă����̂����܁A�L�����Z��������Ȃ��Ȃ��Ă���B�����Ƃ��ďW���I�ɑł��Ă������Ƃ����܁A�����Ґ��̊g��ɏ����ł����~�߂����������Ȃ����v�@
��21���̓����̐l�o 3��ځg�錾�h���Ԃ̕��ϔ�Œ���Ƃ����� �@7/22
������21���̐l�o�́A���Ƃ�4�����{�����3��ڂً̋}���Ԑ錾���o�Ă������Ԃ̕��ςƔ�ׂē����A��ԂƂ������ƂȂ�܂����B
NHK�́AIT�֘A��Ƃ́uAgoop�v�����p�҂̋��Čl�����肳��Ȃ��`�ŏW�߂��g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^���g���A��Ȓn�_�̐l�o�ׂ܂����B
�܂�21�����j���̓����̐l�o���A3��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă������Ƃ�4��25������6��20���܂ł̕����̕��ςƔ�r���܂��B
����ɂ��܂��ƁA�a�J�X�N�����u�������_�t�߂�������21���A��Ԃ�43���A�����w�t�߂œ�����3���A��Ԃ�38���Ƃ�����������ƂȂ�܂����B
�����đO��4�T�Ԃ̕����̕��ςƔ�r���܂��B
�����ł́A�a�J�X�N�����u�������_�t�߂͓�����4���A��Ԃ�16���A�����w�t�߂œ����̓}�C�i�X10���A��Ԃ�20���ł����B
����A�ً}���Ԑ錾���������ꂽ����̐l�o�́A�ߔe�s�̌����O�w�t�߂œ����̓}�C�i�X30���A��Ԃ̓}�C�i�X43���Ƒ啝�Ɍ������܂����B
�܂��A�܂h�~���d�_�[�u���������ꂽ��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����21���̐l�o�́A�������s�̑�{�w�t�߂ł͓����̓}�C�i�X1���A��Ԃ�36���A��t�w�t�߂œ�����30���A��Ԃ�62���A���l�w�t�߂œ����̓}�C�i�X9���A��Ԃ�6���A���E�~�c�w�t�߂͓�����7���A��Ԃ�21���ł����B
������ �V�^�R���i 1979�l���� �O�T�ؗj���671�l���@7/22
�����s���ł�22���A�V����1979�l�̊������m�F����A1�T�ԑO�̖ؗj�����671�l�����܂����B�����̋}�g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B���@���҂́A���Ƃ�2���ȗ��A2500�l���A�s�͈�Ò̐��̂Ђ������뜜�����Ƃ��Ă��܂��B
�����s��22���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��1979�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�s���ł�21���A��3�g�̂��Ƃ�1���ȗ��A1800�l���܂������A22����21����肳���147�l�����Ȃ�܂����B�܂��A1�T�ԑO�̖ؗj�����671�l�����Ă��܂��B22���܂ł�7���ԕ��ς�1373.4�l�ŁA�O�̏T��155.7���ƂȂ�A�����̋}�g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
�s�̒S���҂́u�ً}���Ԑ錾�̌��ʂ����T�ȍ~�A�ǂ��o�Ă��邩�������Ă���B����ɑ啝�ɑ������邩�͂킩��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��傫�����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�ƔF�����Ă���v�Ƃ��Ă��܂��B
22����1979�l�̔N��ʂ�10�Ζ�����95�l�A10�オ159�l�A20�オ658�l�A30�オ399�l�A40�オ314�l�A50�オ246�l�A60�オ56�l�A70�オ38�l�A80�オ11�l�A90�オ2�l�A100�Έȏオ1�l�ł��B�����o�H���킩���Ă���729�l�̓���́A�u�ƒ���v���ł�����406�l�A�u�E����v��109�l�A�u�{�ݓ��v��70�l�A�u��H�v��40�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�����I�����s�b�N�֘A�ł́A�I�葺�ɑ؍݂���O���Ђ̋��Z�W��3�l�ƑI��2�l�A�I�葺�ȊO�ňϑ��Ǝ҂̓��{�l1�l�̂��킹��6�l�̊������m�F����܂����B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂�19��5041�l�ɂȂ�܂����B
����A22�����_�œ��@���Ă���l��21�����78�l������2544�l�ŁA���Ƃ�2��11���ȗ��A2500�l���܂����B�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��42.6���ł��B�s�̊�ŏW�v����22�����_�̏d�ǂ̊��҂�21�����1�l������65�l�ŁA�d�NJ��җp�̕a����16.6�����g�p���Ă��܂��B
�s�̒S���҂́u���@���҂͐V�K�z���҂̊m�F���班���x��đ����Ă���X��������B���܂̋}�g��̂��Ƃł͂���ɑ�������Ǝv���A����̈�Ò̐��̂Ђ������뜜���Ă���B�d�ǂ̊��҂́A���N�`���̌��ʂō���҂̊����҂������Ă��邽�ߗ}�����Ă��镔���͂��邪�A����A���������O����A���S�ł���ł͂Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂����B22���A���S���m�F���ꂽ�l�͂��܂���ł����B
��22���̐l�o�A5����ő����@�������A�ċx�݂��e�����@7/22
NTT�h�R�����܂Ƃ߂�22���ߌ�3�����_�̐l�o�́A�S���̎�v�w��ɉ؊X�v95�n�_�̂���5�����44�n�_�őO�̋x����18�����瑝�����B�V�^�R���i�E�C���X�����g���12������ً}���Ԑ錾���Ĕ��߂��ꂽ�����s�́A�l�o���������n�_���ڗ������B�ċx�݂��{�i���������Ƃ��e�������Ƃ݂���B
�����s��12�n�_�̂���8�n�_��18���Ɣ�ׂđ������B����͐V�^�R���i�����g��O(��N1��18���`2��14��)�̋x�����ςƔ�ׂ��4.0�������������A����18����9.7��������5.7�|�C���g�オ�����B�a�J�Z���^�[�X��5.3�|�C���g���������B
���f���^��3���A�������150%�B�V�^�R���i�A�����s��4�A�x���O�f�[�^�@7/22
7��21���A�����s�ł͐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�z���҂��A�V����1832�l�m�F����܂����B1800�l����̂�1���ȗ��ł��B
4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����߂���Ă���10�����߂��Ă��܂����A�c�O�Ȃ��炻�̌��ʂ͂��܂��Ɍ����Ă��܂���B
7��21���̒i�K�ł́A�����s���A�����\���Ă���V�K�z���Ґ��͑����𑱂��Ă��܂��B�����s�̓s�S���ɂ�����l�o�̌�������A�����E��ԂƂ��ɂ���܂ł̐錾����Ɣ�ׂē݂��Ȃ��Ă��܂��B
���������ւ̗v�ƂȂ郏�N�`���̐ڎ킪�i��ł����Ƃ͂����A7��21���̒i�K��1�x�ȏハ�N�`����ڎ킵���l�̊����͑S���Ŗ�35%�B�����s�Ɍ���Ζ�33%�ł��B�W�c�Ɖu�ɂ͂܂�����܂���B
�����͂������Ƃ���Ă���f���^���̉e���Ȃǂ���������ƁA����̂܂܂ł͎��R�Ɗ����Ґ��������Ă������Ƃ͂��Ȃ����Ƃ�����ł��傤�B
���X�N�Ƃ�1���[�����͂����肵�Ă�����̂ł͂Ȃ��A�������ςݏオ���Ă������̂ł��B����1���X�N����镪�A���炽�߂ă��X�N�������邽�߂̑�������������Ă݂܂��H
�u�O���v�́A�ł������������Ă��܂����H
�l�ɉ���ɂ́A�}�X�N���������蒅�p�ł��Ă��܂����H
������ɋC�����Ă��܂����H
������̊�{��U��Ԃ�ƂƂ��ɁA�����̌����9�̃f�[�^�ŗ�ÂɌ��ɂ߂Ă����܂��傤�B
�����̎�v�ɉ؊X�̑ؗ��l���͎�����Ă͂��܂����A�ߋ�3��ً̋}���Ԑ錾�Ɣ�r����ƁA��������݂��Ȃ��Ă��܂��B
�����s�̐V�K�z���҂�7���ԕ��ς́A7��20���i�K��1170�l�B�������149%�ŁA���̃y�[�X�Ŋ������L�����4�T�Ԍ�ɂ͖�5�{��5000�l�K�͂ɂȂ�v�Z�ł��B
�����z�����͏㏸�𑱂��Ă���A7��20���ɂ�10%���Ă��܂��B
�����҂�6����30��ȉ��B40��ȏ�͊������������Č����܂����A4���㔼����ً̋}���Ԑ錾�ȍ~�A�z���Ґ����ŏ��ƂȂ���6����{�ɔ�ׂāA�ꐔ�ƂȂ�z���Ґ��͔{�߂��ɁB
�����X�N�Ƃ����65�Έȏ�̍���҂̐V�K�z���҂́u�����v�͌��葱���Ă��܂��B�������A�����͏��Ȃ��Ă��u���v�͂����X���ɂ���܂��B
�V�K�z���҂̂����A���Ǐ�҂̊�����14%���x�B�܂�A86%���L�Ǐ�ł��B�u��҂͊������Ă����Ǐ��y�ǂ������v�ƌ����܂����A������x�̐l�ɂ͈��̏Ǐ���Ă���ƌ����܂��B
�d�ǎ҂̐�������ƁA40��A50�オ�����Ă��܂��B�܂��A4���ȍ~�͂���܂łقڌ����Ȃ�����20���30��̏d�ǎ҂��������m�F����Ă��܂��B�����҂��g�傷��A�����Ɏ�҂��d�lj����ɂ����Ƃ͂����A���̊����Œ����Ljȏ�̊��҂������\���͍����ƍl�����܂��B
����̊����ґ��̎w�W�Ƃ��Ȃ�u���M�����k�����v�̓s�[�N���܂��������A�����𑱂��Ă��܂��B����������Ґ��̑������\�z����܂��B
�f���^���̊����́A7��5���`11���̒i�K��30%���܂����B�A���t�@������̒u������肪�i��ł��܂��B
���g�錾�h�̓����A�g�܂h�~�h��ォ��c4�A�x�����̋���Ɋό��q�勓�@7/22
�����Ɖ���ɋً}���Ԑ錾�A���Ȃǂɂ܂h�~���o���ꂽ��22������4�A�x���X�^�[�g���܂����B�ΐ쌧���ɂ͑����̊ό��q���K��Ă��܂��B
���|�[�g�u4�A�x�����̍����A����w�͂��ꂾ���̊ό��q�Ŗ��ߐs������Ă��܂��v
22������X�^�[�g����4�A�x�B�i�q����w�͑傫�ȉו����������ό��q�ł��ӂ�Ă��܂����B
��������̊ό��q�u��������ʼnA���������̂ő��v���ȂƎv���āv�u�����^�J�[�Ől�ƐG�ꍇ��Ȃ��悤�ȃR�[�X���l�������v�u�v�������l�����������̂ŕ|���ł��ˁv�u�Ȃ�ׂ��l���݂ɂ����Ȃ��悤�ɂ������Ǝv���܂��v
�l�C�̊ό��n�A�ߍ]���s��ł́c�B
���|�[�g�u�ߌ�1���̋ߍ]���s��ł��B�ʘH�͐l�ł����ς��Ől�C�̈��H�X�ɂ͍s�ł��Ă��܂��v
�����̋ߍ]���s��͂ǂ̓X�ɂ���E��E��B�C�N��ړ��Ăɂ���Ă����ό��q�œ��킢�܂����B
��������̊ό��q�u(�ً}���Ԑ錾�O��)�\��������̂Ŗ�������ł����Ǘ��܂����v�u����������肵�Ċy���݂����ȁv
��ォ��̊ό��q�u(�܂h�~��)����܂�C�ɂ��Ă��Ȃ��v�u�����l��������������Ȃ��v
��4�A�x�A�ɂ��키�s�y�n�u����Ɨ��s�v�@�����E�o�̓����@7/22
�����ܗւ̊J��ɂ��킹�Ď�������4�A�x��22���n�܂����B�{���Ȃ�ܗփ��[�h�ɃV�t�g����͂����A�R���i�ЂŊO�o���l���Ăт������A���Z���������ϋq�ɁB�s�������܂����ړ����l���Ăт������钆�A�ܗւƊW�Ȃ��A�x���y�������Ƃ����l�X�ōs�y�n�͂ɂ��킢�A��������u�E�o�v���悤�Ƃ����������݂�ꂽ�B
�����E�H�c��`�̍������^�[�~�i���́A������傫�ȃo�b�O���g�����Ƒ��A��Ȃǂ̎p���ڗ������B
�u�����҂������A�C�O�̐l�����������Ă���B�ł���A�s������������v�B��w���̒j��(19)�͌ܗ֑O�ɋA�Ȃ��悤�ƍl���Ă����Ƃ����B�����E���C�̑I�葺�߂��Ɏ������Ƃ�����Ј�����(34)�́u���������s�����痣�ꂽ���Ǝv���Ă����v�Ƙb�����B
�k�C���ɋA�Ȃ���s���̉�Ј��j��(38)�̓e���r�ŊJ�������\�肾�B�u���ϋq�Ȃ痷��Ō��Ă��ς��Ȃ��ł���ˁv�B���̓��͉H�c���̕ւ����G���A�\�͓��{�q��80%�قǂƂ݂��A�S����͌ߑO�������Ŗ�95%�ɂ̂ڂ����B
�������H���s�O�Ɍ������ԂȂǂŁA������𒆐S�ɍ��G�����B���{���H��ʏ��Z���^�[�ɂ��ƁA�������͓���PA(�_�ސ쌧)��擪�ɖ�46�L���̏a�������B�։z���̓����RIC(��ʌ�)�����41�L���A���������̈ɐ���JCT(�_�ސ쌧)�����38�L���̏a���N�����B
�����A��ʁA��t�A�_�ސ�̎�s��4�s���̒m���́A�s�������z����ړ����ɗ͍T����悤�Ăт����鋤�����b�Z�[�W��21���Ɍ��\�����B�����A���ۂɂ͐l�̓����������ɂȂ�A�e�n�̍s�y�n���ɂ�������B
��ʌ������s�ɂ��铌�������������̉ċG����̃v�[���ɂ͐e�q�A��Ȃǂ��W�܂����B�Ƒ�4�l�ŖK�ꂽ�Ƃ���30�㏗���́u�q�ǂ����V�т������ĖO���Ă��Ă���B�����̂ŋߏ�ŗV�ׂ���Ǝv���ė����B�����ɂ͋C�����Ȃ���y���݂����v�Ƙb�����B
��s��������āA�e�n�ɑ����^�ԓ������݂�ꂽ�B
JR�V���w�B�_�ސ쌧����F�l�ɉ�ɂ����Ƃ�����w�@���̏���(25)�́u�����͌ܗւŐl����������W�܂肻���Ȃ̂ŁA���ɗ��悤�Ǝv���āv�B�F�l�Ƒ��s�����ό����邪�A�}�X�N�͒��p���A�����Ȃ��Ȃlj\�Ȍ���̊������������肾�Ƃ����B
�C�����q�łɂ�������a�̎R�����l���B�����ɂ��锒�Ǒ��O�����h�z�e���ɂ��ƁA4�A�x���͊�����̊ό��q�𒆐S�ɖ����ɁB�����R�s�̕�������������̏h���q���K��A�n���ό�����̏��ѐ��a�E�O��ɂ���22�`24���͂ǂ��̗��ق������ŁA���p�҂���́u1�N�ԗ��s�������A����Ɨ���ꂽ�v�Ƃ������������ꂽ�Ƃ����B
��B�̌����EJR�����w(�����s)�����̓��͐l�g���₦�Ȃ������B���s�̉�Ј��j��(66)�͋�B�𗷍s����Ƃ����A�u�A�x�ŁA�ܗւ����̂Ɂw�O�o���T����x�Ƃ����̂͂����͂����v�Ƙb�����B
�L���s�̊Ō�t�̏���(36)�͖k��B�s�̎��ƂɋA�Ȃ��邽�ߕ������ցB�����w�ɒ����āu����Ȃɐl�������Ǝv��Ȃ������v�Ƌ������Ƃ����B�u�܂��������������������Ȓ��Łw�{���Ɍܗւ�����́H�x�Ƃ��܂��Ɏv���B�ϋq�������ɂȂ��Ă���J�Â��������I��ɂƂ��Ă��ǂ������̂ł́v
���s����JTB�̂܂Ƃ߂ł́A�ċx��(7��20���`8��31��)�̍������s�Ґ���4�疜�l�ŁA��N��5�E3%���ƂȂ錩�ʂ����B�����A�R���i�БO��19�N�Ɣ�ׂ��44�E8%�̌����ŁA�u�傫���ɓ]���Ă���킯�ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ă���B
����苏�����A�R���i�ЂŐ�X���@���݉�Ȃ��������o�c�@7/22
�������̓X�ܐ����������Ă���B�������H���T�[�`�ɂ��ƁA��苏�����`�F�[����W�J��������14�Ђ̓X�ܐ��͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g��O�Ɣ�ׂĖ��X�������B���݉���v�̌������������������Ƃ���ȗv�����B���Ăً͋}���Ԑ錾�ɂ���ނ̒�~��A�����ܗւ̖��ϋq�J�Â��e���������ŁA�o�c���͋ɂ߂Č������B
�������H���T�[�`��14�Ђ̓X�ܐ��������Ƃ���A�R���i�O��2019�N12�����͌v7200�X���������A���N3�����ɂ�6152�X�ƂȂ����B��������14�����B�����̋��J�c�c���z�[���f�B���O�X������13�Ђ��s�s���𒆐S�ɓX�܂����炵���B
��4�A�x�����@�R���i�Ё��ܗ֊J�Âłǂ��߂����H�@7/22
���N�͓����I�����s�b�N�̊W�ŏj�����ړ��ɂȂ�A7��22�����u�C�̓��v�A�����ĊJ����s����23�����u�X�|�[�c�̓��v�ƂȂ�܂����B�y���܂Ŋ܂�4�A�x�Ƃ������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�I�����s�b�N�A�����āA�R���i�Ђł̘A�x���ǂ��߂��������������܂����B
�����������w�ł͌ߑO������A���s�����X�[�c�P�[�X���������l�����̎p�������݂��܂����B
���݂₰�̎��܂��ʐ^�Ɏ��߂Ă����������2�l�B�_�ސ삩��K�ꂽ�Ƃ����܂��B
(�_�ސ삩��)�u���v���哇�ɍs���B���傤�v
(�_�ސ삩��)�u�R���i�O�ɁA�C�O�Ƃ��s���Ă����Ǎs���Ȃ��Ȃ���������̂ŁA��������s���ĂȂ������ł��B�y�����ł��I�v
�܂��A������̒j���͕��ɂ���̂ЂƂ藷���Ƃ����܂��B
(���ɂ���)�u����߂���ŗ�����ł��B��B�������Ƃ܂���Ă����B����������A�����܂ŁB�v
�V���قł́A�����������̂����X�A�u���F�v�̐��X�ɗł��Ă��܂����B����A�������s���̌������A�����瑽���̐e�q�A��łɂ�����Ă��܂����B�R���i�ЂŁA���O�ɂ͏o�Ȃ����f������l�������悤�ł��B
(30��E�j��)�u�q����2�l�Ƃ��������̂ŁA���X�N�����邩�ȂƎv���čT���Ă��܂��B�Ȃ̂ŋߏ�ŁA�Ȃ�ׂ��O�ŗV�ԂƂ����Ƃ���ł����ˁv
(30��E����)�u1�N�ȏ㎩�l�������Ƃ����A�O�ɍs���v�l�͂Ȃ��Ȃ�܂��ˁB�������Ŋy���߂邱�Ƃ����悤���ȂƁB����ŃI�����s�b�N�ł����悤���ȂƎv���Ă��܂��v
����A��������`�́A��������Ȃǎ�s�����瓞������ւł́A���s�q�̎p�͌���ꂽ���̂́A���ɍ��G�͂���܂���ł����B
(��������)�u����������̂ƁA�w�h�ō����C�ɓ��낤���Ɓv�u���W�_�Ђɍs���v
(��������)�u�����\�h���Ă��܂����v
���������ł́A�ċx�݊��Ԓ��̐V�^�R���i�̊����g���h�����߁A22������H�c��`�ƈɒO��`�ōs���Ă���A���Ԃ̂o�b�q�����̔�p�̈ꕔ���S���͂��߂܂����B�H�c�Ǝ������A�����A�ɒO�Ǝ������ȂǁA5�̍q��H���̗��p�q���A��p�T�C�g�ŗ\�Ăo�b�q���������ꍇ�A7900�~�̔�p�̂���5900�~���������S���܂��B�o�b�q�����̔�p���S�́A8��31���܂łł��B
���S���O���[�v���u�J���[�v�@�R���i�Ђ́g�H���ύX�h�@7/22
����グ������N���܂ƂȂ�̂ł��傤���B�S���̃O���[�v��Ђ��d�|�����̂́A�܂��ɃX�p�C�V�[�ȁu�J���[���v�ł��B
�������������t���s��s�B�R���i�Ђ̍��A�t�@�~���[�w�ɐl�C���Ƃ����J���[�X���A�w�߂��̃V���b�s���O���[���ɂ���܂��B
�t�[�h�R�[�g�̈�p�ɋ��N8���ɃI�[�v�������A���̖����u100���ԃJ���[�v�B
�S���W�J����`�F�[���X�ŁA�����̃J���[�͂��̖��̒ʂ�A100���Ԉȏォ���č�����A�[�݂̂���Z���ȃ��[�������ł��B���āA�J���[�̌����A�����E�_�c�ŃO�����v���ɋP�������Ƃ��B
�Ƒ��A��⏗���q���^�[�Q�b�g�ɂ����Ƃ��������J���[�B
�����q�F�u�V�`���[�̂悤�Ȑ[�݂̂���J���[�B�������������������B���̃J���[�H�ׂ����ǁA�����ڂ����������ꂢ������A���͖��H�ׂ悤���ȂƁv
�ŋ߁A���̃J���[�`�F�[���X�ɈًƎ킪���X�ƎQ�����Ă���Ƃ����܂��B
�u100���ԃJ���[�v���c�A�[�N�X�E�f�J���ꖱ�F�u1�J���ȓ��ɏo�X���b�V���ŁA5�X�܂قǒlj��ŏo�X�����܂��Ă���v
���́A��قǂ̃V���b�s���O���[���̓X�܂��^�c���Ă���̂́A�����d�S��100���o������q��Ђł��B����1�N�ŁA��t������3�X�܂��I�[�v���B�Ȃ��A�S���ƊE���u���Ⴂ�v�Ƃ�������A�J���[���X���n�߂��̂ł��傤���B
�u100���ԃJ���[�v�^�c�A�C�E�H�������E�������z�В��F�u�����������O���[�v�́A�S���A�o�X���܂߂āA���c��`�ֈړ����邨�q�l�̗A����S���Ă���_������A��`�̗��q��100���߂������Ă���B��Q�͂��Ȃ�傫���v
�R���i�Ђŗ��p�҂������������c��`�Ɠ��������ԋ������́A��~�l����3���߂��������B����ɁA�q��Ђ���`���≈���ɓW�J���Ă��郌�X�g�����Ȃǂł��A����グ���啝�Ƀ_�E���B
�����ŁA�t�@�~���[�w�ɂ��x������Ă���J���[�X�Ɋ��H�����o�����Ƃ����܂��B
�u100���ԃJ���[�v�^�c�A�C�E�H�������E�������z�В��F�u�A�t�^�[�R���i���������Ă̏o�X�B�m���Ɏ��v�������߂āA�Ȃ����C�O�̂��q�l�����Ȃ��ƍ���Ƃ����ł͂Ȃ��A�����̎s��Ɍ������X�𑝂₵�Ă������ƂŁA�ł��邾������I�Ȍo�c���ł���悤�ɂ��Ă��������Ɓv
���傫�ȑŌ��Ɂc�v���k�������R�A�L�����y�[���@�R���i�g��ŐV�K��t��~�@7/22
���T���j������ꕔ�������V�K�̎�t���~����Ɣ��\���ꂽ�R�A����̗U�q�������v���k�������R�A�L�����y�[���B���b���傫�����������ɑ傫�ȑŌ��ƂȂ��Ă���B����s�̃S���t��A����J���g���[�N���u�B�A�x�����̂��傤�������瑽���̃S���t�@�[�����𗬂��Ă����B���̃S���t��͂v���k�������R�A�L�����y�[���̑Ώێ{�݂ŁA�L�����y�[�����g����3000�~�����������B
�S���t�@�[�F�T�Ɉ�炢�͗��Ă���B�v���k�������͑傫���B���z������ˁB
�����ł͍��N3������6���̃S���t�q�����N�̓�����������3�����������B
�x�z�l�F��9�����v���k�������𗘗p���Ă��܂��B
�h���ōő�5��~�����ȂǃR���i�Ђł��R�A�̐l����ŗ������݂ɒn��̗U�q��}��v���k�������R�A�L�����y�[���B�����g��������������̐l�������ŗ��p����ꍇ���̂���26������V�K�\����~���鎖�ԂƂȂ����B
�x�z�l�F�S���t��Ƃ��Ă͔��ɒɂ��B�e��������B
���T���j���̎�t��~�܂łɋ삯���ݎ��v�����҂��邪���傤�ߑO���ɂ͗\��̓d�b��1�{�����Ȃ������B
�x�z�l�F8���ɂ͘g�ɋ�����B����3�A4���̊Ԃɐ\������łق����B
���b�̑傫�������L�����y�[���A��t��~�͘A�x�̊ό��n�ɑ傫�ȒɎ�ƂȂ��Ă���B
�����傤����4�A�x���c�R���i�����g��Ŋό��q�͂܂�@����s�@�Ďq�s�@7/22
���傤����͂��܂���4�A�x�B�����ŐV�^�R���i�̊����}�g�傪�������A�����̊ό��n�̐l�o�͗l�X�B
�ό��q�F�������������Ǝv�����B
���傤�����̒��捻�u�B�A�x�����ɂ��Ă͊ό��q�͂܂�B
���捻�u�r�W�^�[�Z���^�[�O�c���u�ْ��F��N�̑�^�A�x�Ɣ�ׂ��3�����x�B���ԏ�ɂ����ڗ����܂����B
�R���i�БO�̓��������ɂ�1��1���l���x���K��Ă����Ƃ������捻�u�B�A�x�����̐l�o�͂���3�����x�B�ό��q�̖�6�����߂錧�O�q�������̍Ċg������������������Ƃ������Ƃ݂��Ă���B
�Ďq�s�̊F���C�݁u�F������C�V�r�[�`�v�B�C�̓��̂��傤�I�[�v�������̂��C��A�X���`�b�N�B�����}�g��Əd�Ȃ钆�A��Î҂̑z���������킢�ƂȂ����B
�q�ǂ��F�߂��Ⴍ����y�����ł��B�����Ƃ��y���������B
��������l�́B
��l�F�l�ƂȂ�ׂ������悤�ɁB���O�ɂ͏o���Ȃ��̂Œn��̊C�ɗV�тɗ����Ƃ��������B
�A�X���`�b�N�͎��O��t���Ől�������ȂǂŊ�����B�߂������ɒ��ӂ��͂炢�Ȃ���̘A�x�X�^�[�g�ƂȂ����B
�������s��1979�l�̐V�^�R���i�����m�F�A1�s3���̊����g�呱���@7/22
�����s��22���A�V����1979�l(�O��1832�l)�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B1���̊����Ґ��Ƃ��Ă�1��15��(2044�l)�ȗ��̑����B
���\�ɂ��ƁA�����҂̒���7���Ԉړ����ς�1373.4�l(��1277.6�l)�őO�T��155.7��(��155.2��)�ƂȂ����B�d�ǎ҂�65�l(��64�l)�B
��s���ł͊����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��B�m�g�j�́A�_�ސ쌧��631�l�̐V�K�������m�F���ꂽ�ƕ��B�O����522�l����啝�ɑ����A1���ȗ��̍������B�����ʐM�ɂ��ƁA��ʌ��ł�510�l(�O����381�l)�������B���̃f�[�^�ɂ���500�l����̂�1���ȗ��B��t���̊����Ґ��͋����ɂ���343�l�ŁA2���A����300�l�����B
�����m�������g�� 2���A��100�� �u�ܗւ̓e���r�Łv�@7/22
���C3���ł�22���A�v187�l�̐V�^�R���i�E�C���X���������\���ꂽ�B3���Ƃ��O�T�̓����j���Ɣ�ׂđ傫���������Ă���B
���m����146�l�ŁA2���A����100�l�����B140�l�����̂́A���m���ɂ��ً}���Ԑ錾���o�Ă���6��11���ȗ��ƂȂ�B�܂��A�����1�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
���ɂ��ƁA21�����_�̊���820�l�̂����A228�l�����@���A134�l���h���×{�{�݂ɓ����B347�l������ŗ×{���Ă���Ƃ����B
����23���ɊJ�����铌���ܗւɂ��āA�u���H�X�Ȃǂő����̐l���W�܂��ċ��Z���ϐ킷��A�������X�N�̊g��ɂȂ���v�ȂǂƂ��āA����̃e���r�ŏ��l���ʼn�������悤�Ăт����Ă���B
���ł�14�l�̊��������\���ꂽ�B���ɂ��ƁA�����͂̋����ψي�(�f���^��)�̋^��������ψكE�C���X���V����2�l���猩�������B�O�d���̊����҂�27�l�������B
���_�ސ쌧��635�l�A��ʌ���510�l�̐V�K������ ��s���Ŋ����g��@7/22
��s���ŐV�^�R���i�̊������}�g�債�Ă���B
�_�ސ쌧�ł��傤����܂ł�635�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��m�F���ꂽ�B�_�ސ쌧��1���̐V�K�����҂�600�l�����̂�1��22���ȗ��A���N�Ԃ�ƂȂ�B
��ʌ��ł�510�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊����҂��m�F���ꂽ�B1���̊����҂�500�l����̂́A�ߋ��ő��ƂȂ���582�l�̊����҂��m�F���ꂽ1��16���ȗ��B
�܂��A��t���ł́A���傤�V����343�l�̊������m�F����Ă���B�@
���R���i�����Ċg����x���@�A�x��ċx�݂Ł@�L���@7/22
�A�x��ċx�݂ł̐V�^�R���i�����Ċg��Ɍx���������܂��Ă��܂��B
�����E��L�ҁu���R�w�O�ɐݒu���ꂽPCR�Վ��X�|�b�g�ɂ̓X�[�c�P�[�X�p�̐l���ڗ����܂��v
JR���R�w�O�ɐݒu���ꂽ�̂�PCR�����L�b�g���Ŕz�z������ł��B�A�x��ċx�݂ɓ��葽���̐l���ړ����邽�ߊ����g����x�����݂����܂����B
��ォ��A�ȁu�����ĂĂ����������Ⴄ���Ƃ������ł����Ƃ����Ȃ��悤�Ɂv
�L�������N�����ǁ@���������卸�u(PCR������)���N�`���̐ڎ�Ɨ\�h��g�ݍ��킹�Ă��炢�Ȃ��犴���h�~�ɓw�߂Ă��炢�����v
����A�L���w�O�̃f�p�[�g�ł́E�E�E
����ޔ��L�ҁu������ł̓f�p�[�g�̔������̂��łɃ��N�`����ł��Ƃ��ł��܂��v
�����L���w�O�X�ɐݒu���ꂽ�V�^�R���i���N�`���̏W�c�ڎ���B�w������߂������^�т₷�����ߍL���s�͕��L���N��ɖK��Ăق����ƌĂт����Ă��܂��B
�ڎ킵���l�u���������łɐڎ�ł��邵���������ꏊ�������Ă������̂ł́v
�ڎ킵���l�ɂ͊ٓ��̓X�܂Ŏg����N�[�|�������z�z����Ă��܂����B�L���s�ł�24������ꕔ���Ɍ���64�Έȉ��̈�ʐڎ�\����X�^�[�g���܂��B
���V�^�R���i�E�C���X�@�R�A�����Ŋ����g��c�����ŐV����31�l�����@7/22
�V�^�R���i�̊����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��B�R�A�����ł�21���̌����ŐV����31�l�̊������m�F���ꂽ�B
���̂����������ł́A�_��s��8�l�A���]�s��6�l�A�����s��5�l�A�o�_�s��1�l�ƌv20�l�̊������m�F���ꂽ�B�v�̊����Ґ���645�l�ƂȂ����B
���̂����A5�l�̊������m�F���ꂽ�����s�łً͋}�̋L�҉���J�����B�����s�c�����v�s���F�u5�l�̒���1�l�͈����s���a�@�̐E���ł��邱�Ƃ��������܂����v�����s���a�@�̕a���ɋΖ�����E����l�̊����\�����B���������E���͓�������Ƒ����ʂ��A�w�Z���邢�͐E��Ŋ����҂��o�����Ƃ��獡��18�����玩��ҋ@�����Ă��āA20���ɕa�@���ło�b�q�������z�������������B
�E���͂��ł�2��A�V�^�R���i���N�`���̐ڎ���Ă����Ƃ����B�����s���a�@�ł́A�K�����K��n�r���́A26��(���j��)�܂Œ�~���邪�A�O���E���@���҂̎���͌p�����邱�Ƃɂ��Ă���B����A���挧���ł͕Ďq�ی����Ǔ���10�l�A����ɑq�g�s��1�l�̊������V���Ɋm�F���ꂽ�B�v�̊����Ґ���626�l�ƂȂ����B
�Ďq�ی����Ǔ��ł�9�l������܂ł̗z���҂̔Z���ڐG�҂��A�ڐG�҂Ƃ��Ăo�b�q�������z�������������B�܂��A���̂�����4�l�͂o�b�q�����ň�x�͉A���Ɛf�f���ꂽ���A���̌�ǏłāA�Č������z�������������Ƃ����B���挧�ł�7���ɓ����Ă���̊����Ґ��������146�l�ƂȂ�A�Ђƌ��̊����Ґ��Ƃ��ĉߋ��ő����X�V�������Ă���B�܂��A���ݓ��@����1�l�̊��҂��d�ǂ��Ƃ����B
���g���^�̍����H��A�ꕔ���Y��~�@�x�g�i�������g��ŕ��i������@7/22
�g���^�����Ԃ�22���A�x�g�i���ł̐V�^�R���i�E�C���X�����g��ŁA�C�O����̕��i��������A�q��Ђ̃g���^�ԑ̕x�m���H��(���m�����J�s)�̈ꕔ���Y�����v5���Ԓ�~����Ɣ��\�����B�e���䐔�͖�3���B
�~�j�o���́u�A���t�@�[�h�v��u���F���t�@�C�A�v�u�m�A�v�u���H�N�V�[�v�u�G�X�N�@�C�A�v�Y�����2���C�����ΏہB7��29�A30���A8��2�`4���ɉғ����~�߂�B
�x�g�i���ł͐V�^�R���i�̊����g�傪�����Ă���A�s���̍s������������Ă���B�x�g�i���ȊO�̓���A�W�A�e���ł������Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B
���R���i����������v�g�n�Ē����v���ɒ��������@7/22
�����͐V�^�R���i�E�C���X���Ζk�ȕ����̃E�C���X���������痬�o�����Ƃ�����ɂ͏؋����Ȃ��Ƃ��āA�����������鐢�E�ی��@��(�v�g�n)�̍Ē����v���ɔ��������B
�o�C�f���đ哝�̂̓��N�`���ڎ���Ă��Ȃ��Z���̊ԂŊ������}�����Ă���Ƃ��āA��葽���̍����ɐڎ�������v�������B�e�L�T�X�B�̃f�[�^�ł́A�V�^�R���i���҂̑啔���̓��N�`�����ڎ�҂ł��邱�Ƃ������ꂽ�B
�V���K�|�[���̓N���X�^�[�̔������m�F���ꂽ�}���[�i�x�C�E�T���Y�̃J�W�m��2�T�ԕ�����B
�x�g�i���̃n�m�C�s���ǂ́A�O�o�֎~�߂��o�Ă���z�[�`�~���ȂǓ암�n�悩�瓞�����闷�s�҂ɂ��āA22������u���{�݂ւ̎��e�𖽂����B�u�����Ԃ͕s���B
�^�C�̐V�K�����Ґ���22����1��3655�l�ƁA�V�^�R���i�̃p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)���������Ĉȗ��ōő����L�^�����B
�؍��̐V�K�����Ґ��͉ߋ��ő���1842�l�B�ی����ǂ͒����ŊC����ɓ������Ă����C�R�̋쒀�͂ł�270�l�̊������������B��g����20���ɋA�������B���̑D�ł̊����҂Ɠ����҂̊����Ǘ�������������̐V�K�����҂�1533�l�ŁA�O����1726�l���猸�������B
�I�[�X�g�����A�̃N�C�[���Y�����h�B�͊����g�僊�X�N��}�����邽�߁A�j���[�T�E�X�E�F�[���Y�B�Ƃ̋��E��23���ߑO1���ɕ�����ƏB���c�C�b�^�[�Ŗ��炩�ɂ����B�j���[�T�E�X�E�F�[���Y�B�̃V�h�j�[�ł́A1��������̊����Ґ���22����124�l�ɏ��A6�����Ɏn�܂������݂̗��s���ł͍ő����L�^�B�����������Ɨ\�z����Ă���B
�C���h�̃R���i�������Ґ��͎��ۂɂ�130������500���l�̃����W�ł���\��������B�ł��T���߂ȗ\�z�ł��A����܂Ő��E�ő��̕č��̎��Ґ���2�{���B�����̐��l�͌������f����n�����ǂ̃f�[�^���瓱���o���ꂽ���̂ŁA�����̌����W�v��3�{����10�{�̃����W�B
�ăW�����Y�E�z�v�L���Y��w�ƃu���[���o�[�O�̏W�v�f�[�^�ɂ��ƁA���E�̐V�^�R���i�����Ґ���1��9200���l�A���Ґ���412���l�����ꂼ�꒴�����B�u���[���o�[�O�̃��N�`���g���b�J�[�ɂ��A���E�̃��N�`���ڎ�͌v37��1000������������B
�@ |
 |


 �@
�@ |
��1�s3���̊����ҁA2���A��3000�l���@�����g��Ōܗ֊J�� �@7/23
�����ܗւ͐V�^�R���i�E�C���X�����g��̒��ŊJ�����}����B�����s��_�ސ�A��ʁA��t��1�s3���̐V�K�����Ґ��̍��v��2���A����3000�l�����B1���́u��3�g�v�̃s�[�N�ɔ��鐨�����B���Ƃ́u����ŖS���Ȃ�l���o�鎖�Ԃ͔��������v�ƈ�Ñ̐��̕N�������O�B���߂ĕs�v�s�}�̊O�o���T����悤�ɌĂъ|����B(����䕶�F�A�������A�_�J�~��)
���C���h���̉e���Ŕ��N�Ԃ萅��
22����1�s3���̐V�K�����҂̍��v��3463�l�B3000�l���͖N�Ԃ�̐������B�����͂̋����f���^��(�C���h��)�̉e���ŁA�ߋ��ő���4327�l(1��9��)���\�����o�Ă����B�����������w�W�̂����ŏ��ɐ��l���オ��̂��u�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��v���B������6��30���ɁA�ł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ�(25�l)��˔j�B�ً}���Ԑ錾���o������12���ɂ́A��37�E94�l�ɑ������B�_�ސ��14���ɃX�e�[�W4�ɒB�����B���͂܂h�~���d�_�[�u�͈̔͂��g�傷��Ȃǂ̑������������P�����A22���ɂ�37�E35�l�Ɉ����B��ʁA��t������19���ɃX�e�[�W4�ɂȂ����B������20�����_�ŁA�d�ǎҗp�a���̎g�p�����X�e�[�W4�ɂȂ����B
����Ԑl������
�����J���Ȃɏ���������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�ɂ��ƁA�ً}���Ԑ錾�����ߒ��̓����ł͖�Ԃ̑ؗ��l���������Ă�����̂́A�O��̐錾���Ɣ�ׂ�ƌ�����͊ɂ₩���B�_�ސ�A��t�͉����B��ʂł͑����������Ă���B�����̃����o�[����A3���ɂ��ً}���Ԑ錾���K�v���Ƃ̐����o�Ă���B��ނ������H�X�ɋx�Ɨv�����o�Ă��铌������3���ɉz�����Ă���\�����w�E�����B�O�c�G�Y�E�����s�k��ی������́u�����ɗאڂ��Ă���Ƃ���͓����悤�ɂ��Ă����Ȃ��ƁA�l��������Ȃ��v�Ƙb���B
���i�܂�40�A50��̃��N�`���ڎ�
20�����_�ŁA�S���̍���Җ�62����2��̃��N�`���ڎ���I�����B���̌��ʂ��猻�݂́u��5�g�v�ł́A����܂ł�荂��҂̏d�ǎ҂����Ȃ��B���̂��ߊy�ώ�����s�������邪�A���Ƃ͌x����炷�B�u40��A50��̏d�ǎҐ��͑�3�g�����B����قǎ��҂��o�Ȃ�����܂��ٔ������Ȃ����A���܂łōő�̊������v�ƑO�c���B���N�`���ڎ�̐i�܂Ȃ�������40�`50��̏d�ǎ҂́A7���ɓ���20�l�O��Ő��ڂ��Ă���B20�`30��̓��@���҂������Ă���B���������܂�Ȃ���A���@�ł����Ɏ���×{�ɂȂ銳�҂��o��B���ۈ�Õ�����̘a�c�k�������́u40�`50�オ��Âɂ����ꂸ�ɖS���Ȃ�͔̂��������v�ƌ��B�V�K�����҂�}����ɂ͐l�Ƃ̐ڐG�@������点�邩���J�M�ɂȂ�B�a�c���́u�s���͂������������Ă���Ȃ��ƌ����l�����邪�A���X�N��`���Ă����̂��l�����̎d�����v�Ƙb���B
���������ŐV����10�l�̊������m�F�@�����̊����g�呱���@7/23
�V�^�R���i�A���������ŐV����10�l�̊������m�F���ꂽ�B�����s��5�l�A���]�s��2�l�A�_��s��2�l�A�o�_�s��1�l�B���������ł�4���A���̓��m�F�Ŋ����҂̗v��655�l�ƂȂ����B�������ł̊����m�F�������Ă���2�P�^�̊m�F��4���A���B
�����Y�����̒����t1�l���V�^�R���i�����A�u������×{�[�u�@7/23
�i�q�`��22���A���Y�g���Z�������̒����t1�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ\�����B���Y�����t�͌��݁A�u�����ꂽ�����ŗ×{�[�u�ƂȂ��Ă���B�i�q�`���́u����͏����ی����ȂǂƘA�g���A�����g��̖h�~�Ɏ��g��ł܂���܂��v�Ƃ��A24���ȍ~�̒������n�ɂ��Ắu�������������g��h�~�̑[�u��O�ꂵ�J�Â������܂��v�ƃR�����g�����B
���e�����[�N�u�����オ�����v �V�^�R���i�����g��� ���̌����� 7/23
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ȍ~�A�������i�ރe�����[�N�ɂ��āA�d���̌������オ�����Ɗ����Ă���l�̊��������߂Č����ɓ]�����Ƃ��閯�Ԃ̒������܂Ƃ܂�܂����B
���̒����́A���{���Y���{���������g���̓�������ӎ��̕ω��ׂ邽�߂ɋ��N5������s���Ă��āA�����6��ڂƂȂ�܂��B
������{�ɃC���^�[�l�b�g��ʂ��čs���A1100�l����������̒����ł́A����Ńe�����[�N�����Ă���l�Ɂu�d���̌������オ�������v�q�˂��Ƃ���A�u�オ�����v�u���オ�����v�Ɠ������l�̊��������킹��50���ŁA�O��E���Ƃ�4���̒�������9�|�C���g�����ď��߂Č����ɓ]���܂����B
�܂��A�u����ł̋Ζ��ɖ������Ă��邩�v�̖₢�ɂ́A�u�����v�u�ǂ��炩�ƌ����Ɩ����v��70���ŁA�O���75�����猸�����Ă��܂��B
����ɂ��āA�����������{���Y���{���̊`������Ȍ������́A�����g�傩��1�N�ȏオ�߂��A�����l�̊ԂŌǓƂ�������Ȃǂ̂�����g�e�����[�N���h���N���Ă���̂łȂ����Ǝw�E���������Łu��ƌo�c�҂͓����l�̐S�̌��N�ɔz�����邱�Ƃ��K�v���v�Ƙb���Ă��܂��B
���V�^�R���i �����͊����g����� �u�錾�v�e�n�������}�g��@7/23
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�����s�łً͋}���Ԑ錾���o����Ă��钆�ł��A�I�����s�b�N�̊J����O�ɁA�����g��̃y�[�X���オ�葱���Ă��āA��s����3������{�A���ꌧ�Ȃǂł��������}�g�債�Ă��܂��B�m�g�j�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S��
�S���ł́A�挎24���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�0.94�{�ƁA6�T�A���ŐV�K�����Ґ����������Ă��܂������A����1����1.04�{�A����8����1.16�{�A����15����1.41�{�A22���܂łł�1.56�{�ƁA4�T�A���ő������A�������g�傷��y�[�X���オ���Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻3823�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���ً}���Ԑ錾�̒n��
4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă��铌���s�́A�挎���{�܂ł�5�T�A���Ō������Ă��܂������A�挎���{���瑝���ɓ]���܂����B����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.27�{�A����15����1.33�{�A22���܂łł�1.56�{��5�T�A���ő������A�������g�傷��y�[�X���オ�葱���Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1373�l�ƁA��T��肨�悻490�l�����A�l��������̊����Ґ��͑S���ōł����������ƂȂ��Ă��܂��B�ً}���Ԑ錾���p�����Ă��鉫�ꌧ�ł́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��0.78�{�������̂�����15����1.09�{�ƍĂё����ɓ]���A22���܂łł�1.92�{�Ɗ������}�g�債�Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻105�l�ŁA�l��������̊����Ґ��͓����s�Ɏ����ō��������ƂȂ��Ă��܂��B
���d�_�[�u�K�p�̒n��
�u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����Ă����s����3���Ƒ��{�ł��������}�g�債�Ă��܂��B�_�ސ쌧�́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.15�{�A����15����1.45�{�A22���܂łł�1.43�{�Ɗ������g�傷��y�[�X��������Ԃ������A1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻492�l�ƂȂ��Ă��܂��B��ʌ��́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.32�{�A����15����1.48�{�A22���܂łł�1.74�{�Ɗ����g��̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻328�l�ƂȂ��Ă��܂��B��t���́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.22�{�A����15����1.28�{�A22���܂łł�1.40�{�Ɗ����g��̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻265�l�ƂȂ��Ă��܂��B���{�́A�挎���{���獡����{�͐V�K�����Ґ��͉����̏ł������A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.28�{�Ƒ����ɓ]���܂����B���̌�A����15����1.78�{�A22���܂łł�1.58�{�Ƌ}���Ȋ����g��ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻341�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���d�_�[�u�����̎�����
����11���������ɏd�_�[�u���������ꂽ�n��ł��A�V�K�����Ґ��̑����̃y�[�X���オ���Ă���Ƃ��낪����܂��B�k�C���́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.22�{�A����15����1.52�{�A22���܂łł�1.65�{�Ƒ����̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻103�l�ƂȂ��Ă��܂��B���s�{�́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.13�{�A����15����1.68�{�A22���܂łł�1.80�{�Ƒ����̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻51�l�ƂȂ��Ă��܂��B���Ɍ��́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.36�{�A����15����1.77�{�A22���܂łł�1.89�{�Ƒ����̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻102�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́A���݂̊����ɂ��āu�S���Ŋ����g��̑�5�g�ɓ����Ă��Ă��邱�Ƃ������Ă��Ă���B�����Ґ���������ƁA���̊����ŏd�ǗႪ�o�āA50��ȉ��ł��S���Ȃ�l�������Ă��邱�Ƃ��l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��5�g�ł́A�����͂������ψكE�C���X�w�f���^���x�̉e��������A��4�g�̊��Ō���ꂽ�悤�ȋ}���Ȃ܂A��Ì���̂Ђ������A������x�S���ŋN���Ă����������Ȃ��ɂȂ����B�傫�Ȋ����̔g�͍��Ȃ��Ƃ������ӂ������āA1�l1�l��������h���s�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B�����ăI�����s�b�N���J�Â���铌���̏ɂ��Ắu�����łً͋}���Ԑ錾���o����Ă���܂��Ȃ�2�T�ԂɂȂ邪�A�܂��錾�̌��ʂ͌���ꂸ�A�������~�܂�Ȃ��S�z�ȏɂȂ��Ă���B�ً}���Ԑ錾�ł����������܂�Ȃ����Ƃ������Ă����ꍇ�ɂ́A����ɋ���������イ����Ȃ����o�傪�K�v�ɂȂ��Ă��邾�낤�v�Ƙb���Ă��܂��B���̏�ŃI�����s�b�N�ɂ��āu�{���ɏd�����f�Ƃ��āA���ϋq�ł̊J�Â����߂��̂ŁA���Z��̎���ɏW�܂��đ����ł��܂��ƁA���ʂ�����Ă��܂��B���Z��̎���ł̈��H�A�������ނ悤�ȋ@�����ƁA�������L���郊�X�N�����߂邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA�Ƃł�������l�ƁA�e���r��ʂ��ĉ������Ăق����v�Ƒi���܂����B
���u�ܗւ��̂ɁA���͈���?�v�@�J���ꂩ��2km�̉̕��꒬�ł́@7/23
�����I�����s�b�N�̊J����J���ꂽ23���A�������Z�ꂩ���2�L����������Ă��Ȃ��S�����w�̔ɉ؊X�A�V�h�E�̕��꒬������ƃV���b�^�[�����낳��u�Վ��x�Ɓv�Ȃǂ̒��莆������X���ڂɕt�����B�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o�Ă��邽�߁A��ɂȂ��Ă�������̂��Ȃ����H�X�r�����ڗ������B
�u�ܗւ̕��͋C�Ȃ�đS�R�����܂����v�B�̕��꒬�őn��58�N�ڂ̂���Ԃ���ԁE�����Ă��X�u�ĐV�v���c�ދ��{�O����(58)�́A�J����n�܂����ߌ�8������A�̂���Â��ɓX���ɂ��܂����B�V�^�R���i�E�C���X�̖�肪�N����O�͐[��܂ʼnc�Ƃ��Ă������A���̓������Z�v���ɉ����đ��X�ɓX��߂��B
�X�͋q�����ȑO�̖�10����1�Ɍ������Ƃ����B���N�`���ڎ킪�i��ŋq�����߂邱�Ƃ����҂������̂́u����Ŏ������ސl�������A�X�ɋq������̂ł͂Ȃ����B����ȏ̒��ŋ��Z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��I�肪��ԉ����������A���������䖝�𑱂��邵���Ȃ��v�Ƃ��ߑ��������B
�����A�ߌ�9���߂��ɂȂ��Ă��A�܂�ł͂�����̂̊X��K���l�̗���͓r��Ȃ��B�u�A���R�[��OK�v�u24���܂ʼnc�ƒ��v�ȂǂƋq���Ăэ��ޓX������B�H��ɍ��荞�݁A�ʃ`���[�n�C��Ў�ɘb�����ޒj���̎p���������B
���H�X�œ����j��(21)�́u�ܗւ�����Ă���̂Ɏ������ȂƂ����͈̂�a��������B���łȂǂ̑�����Ă���B�������҂ɂ��Ȃ��łق����v�Ƙb�����B
���u�S���ő�5�g�ɓ����Ă��Ă���v�V�^�R���i �����}�g�� �@7/23
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�����s�łً͋}���Ԑ錾���o����Ă��钆�ł��A�I�����s�b�N�̊J����O�Ɋ����g��̃y�[�X���オ�葱���Ă��āA��s����3������{�A���ꌧ�Ȃǂł��������}�g�債�Ă��܂��B
NHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
�S���ł́A�挎24���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�0.94�{�ƁA6�T�A���ŐV�K�����Ґ����������Ă��܂������A����1����1.04�{�A����8����1.16�{�A����15����1.41�{�A22���܂łł�1.56�{�ƁA4�T�A���ő������A�������g�傷��y�[�X���オ���Ă��܂��B
1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻3823�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���ً}���Ԑ錾���̓����E����Ŋ����}�g��
4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă��铌���s�́A�挎���{�܂ł�5�T�A���Ō������Ă��܂������A�挎���{���瑝���ɓ]���܂����B����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.27�{�A����15����1.33�{�A22���܂łł�1.56�{��5�T�A���ő������A�������g�傷��y�[�X���オ�葱���Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1373�l�ƁA��T��肨�悻490�l�����A�l��������̊����Ґ��͑S���ōł����������ƂȂ��Ă��܂��B�ً}���Ԑ錾���p�����Ă��鉫�ꌧ�ł́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��0.78�{�������̂��A����15����1.09�{�ƍĂё����ɓ]���A22���܂łł�1.92�{�Ɗ������}�g�債�Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻105�l�Ől��������̊����Ґ��͓����s�Ɏ����ō��������ƂȂ��Ă��܂��B
���d�_�[�u�K�p�̎�s��3���Ƒ��{�ł������g��y�[�X�オ��
�u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����Ă����s����3���Ƒ��{�ł��������}�g�債�Ă��܂��B�_�ސ쌧�͍���8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.15�{�A����15����1.45�{�A22���܂łł�1.43�{�Ɗ������g�傷��y�[�X��������Ԃ������A1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻492�l�ƂȂ��Ă��܂��B��ʌ��͍���8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.32�{�A����15����1.48�{�A22���܂łł�1.74�{�Ɗ����g��̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻328�l�ƂȂ��Ă��܂��B��t���͍���8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.22�{�A����15����1.28�{�A22���܂łł�1.40�{�Ɗ����g��̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻265�l�ƂȂ��Ă��܂��B���{�͐挎���{���獡����{�͐V�K�����Ґ��͉����̏ł������A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.28�{�Ƒ����ɓ]���܂����B���̌�A����15����1.78�{�A22���܂łł�1.58�{�Ƌ}���Ȋ����g��ƂȂ��Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻341�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���d�_�[�u�������ꂽ�����̂ł������ґ���
����11���������ɏd�_�[�u���������ꂽ�n��ł��A�V�K�����Ґ��̑����̃y�[�X���オ���Ă���Ƃ��낪����܂��B�k�C���͍���8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.22�{�A����15����1.52�{�A22���܂łł�1.65�{�Ƒ����̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻103�l�ƂȂ��Ă��܂��B���s�{�͍���8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.13�{�A����15����1.68�{�A22���܂łł�1.80�{�Ƒ����̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻51�l�ƂȂ��Ă��܂��B���Ɍ��́A����8���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.36�{�A����15����1.77�{�A22���܂łł�1.89�{�Ƒ����̃y�[�X���オ���Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻102�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ɓu��5�g�ɓ����Ă��Ă���v
�V�^�R���i�E�C���X��ɓ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́A���݂̊����ɂ��āu�S���Ŋ����g��̑�5�g�ɓ����Ă��Ă��邱�Ƃ������Ă��Ă���B�����Ґ���������ƁA���̊����ŏd�ǗႪ�o�āA50��ȉ��ł��S���Ȃ�l�������Ă��邱�Ƃ��l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��5�g�ł́A�����͂������ψكE�C���X�w�f���^���x�̉e��������A��4�g�̊��Ō���ꂽ�悤�ȋ}���Ȃ܂A��Ì���̂Ђ�����������x�S���ŋN���Ă����������Ȃ��ɂȂ����B�傫�Ȋ����̔g�͍��Ȃ��Ƃ������ӂ������Ĉ�l��l��������h���s�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B�����āA�I�����s�b�N���J�Â���铌���̏ɂ��Ắu�����łً͋}���Ԑ錾���o����Ă���܂��Ȃ�2�T�ԂɂȂ邪�A�܂��錾�̌��ʂ͌���ꂸ�A�������~�܂�Ȃ��S�z�ȏɂȂ��Ă���B�ً}���Ԑ錾�ł����������܂�Ȃ����Ƃ������Ă����ꍇ�ɂ́A����ɋ���������イ����Ȃ����o�傪�K�v�ɂȂ��Ă��邾�낤�v�Ƙb���Ă��܂��B���̂����ŁA�I�����s�b�N�ɂ��āu�{���ɏd�����f�Ƃ��āA���ϋq�ł̊J�Â����߂��̂ŋ��Z��̎���ɏW�܂��đ����ł��܂��ƁA���ʂ�����Ă��܂��B���Z��̎���ł̈��H�A�������ނ悤�ȋ@�����ƁA�������L���郊�X�N�����߂邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA�Ƃł�������l�ƃe���r��ʂ��ĉ������Ăق����v�Ƒi���܂����B
�������g��h�~ �ܗւ͎���ʼn��� �A�x���̈ړ��T���ā@7/23
�����I�����s�b�N�̊J����s���鍑�����Z��̎��ӂ�e�n�̍s�y�n�ł́A�����̐l�łɂ��키�l�q�������܂����A���Ƃ́A��s���𒆐S�ɍL����V�^�R���i�E�C���X�̊������A�S���e�n�Ɋg�傷�邱�Ƃ�h�����߁A�I�����s�b�N�͎���Ŋy���ނƂƂ��ɁA�������z�����ړ����ł��邾���T����悤���߂Ă��܂��B
�����s�Ȃǂ𒆐S�Ɋe�n�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�����A22���A�S���̊����҂͂��Ƃ�5���ȗ��A2�����Ԃ��5000�l���܂������A23���́A�����I�����s�b�N�̊J����s���鍑�����Z��̎��ӂ�e�n�̍s�y�n�ł��l�o�������Ȃ��Ă��āA����Ȃ銴���g�傪���O����Ă��܂��B
���{�̕��ȉ�̔��g�Ή�́A����16���A�����ȂǂŊg�傷�銴�����e�n�ɍL����̂�h�����߁A4�A�x��ċx�݁A���~�A�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ȂǁA�l�o��������@��W�����邱�ꂩ���2�����Ԃ��u������ɂ�����R�ꂾ�v�Ƃ��āA��̓O������߂�k�b���o���Ă��܂��B
�k�b�ł́A�����I�����s�b�N�ɂ��āA�����͎���ōs���A�L���H��A���H�X�Ȃǂł̑�l���̉������T���邱�Ƃ�A�ӂ�����Ȃ��l�Ƃ̉�H��A��l���Ⓑ���Ԃɋy�ԉ�H���T����悤�i���Ă��܂��B
�܂��A�������z����ړ����ł��邾���T���A�A�Ȑ�̍���҂����ł�2��̃��N�`���ڎ���ς܂��Ă���ꍇ�ł��A�A�Ȃ�2�T�ԑO���犴���\�h����\���ɍs������ʼn�悤���߂Ă��܂��B
���{���ȉ�̃����o�[�œ��M��w�̊ړc�ꔎ�����́u�I�����s�b�N���n�܂�A�X�^�W�A���̎���ł�������̐l���W�܂��Ă���l�q������ƁA�A�x�ł����邵�A�O�ɏo�Ă�������Ȃ����Ƃ������b�Z�[�W���`����Ă��܂��B���Ɍ����������Ɍq�����Ă��܂��\�������܂��Ă���B��Ì���ł̂Ђ����̓x���������܂��Ă��邱�Ƃ��l���āA�������炭�䖝���ė~�����B�I�����s�b�N�͉Ƃł�������l�Ɖ������A�������z����ړ����Ȃ�ׂ��T���ė~�����v�Ƒi���܂����B
���I�葺�Łg�����L�b�g�s���h���o�c�����g��~�܂炸�@7/23
�����s�ł�23���A�V����1359�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B��������������A�x���Ƃ͂����A34���A���ŁA�O�̏T�̓����j��������܂����B�d�ǎ҂�22�����3�l�����āA68�l�B�N��ʂł́A65�Έȏ�̍���҂�37�l�A����A20�オ�ő��ŁA492�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��Ì���́A�ˑR�A���������甲���o���Ă��܂���B���a��w�a�@�ł́A�V�^�R���i�̓��@����25�l�̂����A21�l��50��ȉ��ł��B
���a��w�a�@�E���ǔ��T�a�@���u��ԑ����̂́A��N�҂̊�������̉ƒ�������B�Ⴂ�l�������A�ǂ��Ŋ������Ă��Ă��邩�́A�悭�킩��Ȃ��B��͂�l�o�A�l�����Ǝv���B�����Ƒ����Ă��邾�낤�ȂƁB��X�̎{�݂����������A�x�b�h�������Ɨp�ӂ��Ă����Ȃ��ƁA���������ɂȂ��Ă���ƕs���������Ă���B���҂̐��������Ă���v�f�͌������B�ċx�݁A�I�����s�b�N���J�n�������Ƃ܂��āA���҂̐��͂܂��オ���Ă���Ǝv���v
���a��w�a�@�́A�����I�����s�b�N�Ɉ�t�ƊŌ�t��h�����Ă��܂��B���؈�t�́A���̂����̈�l�ŁA�g���C�A�X�����̉��ŁA��ÐӔC�҂߂܂��B
���a��w�a�@�E���ؐ�����t�u��w�I�Ȃ��Ƃ����l����A�����܂ő�K�͂ȑ��́A�������͖��炩�ɂ��肦�Ȃ��b�B�����ςȌ`�ł��A�I�����s�b�N�������Ƃ����̂��킩��B�ܒ��ĂƂ��Ė��ϋq�̏�Ԃ����邪�A���̕����ł��A������x�ł���Ȃ�A���̂͂��傤���Ȃ����ȂƁv
���g�D�ψ���ɂ��܂��ƁA�V����19�l�̊������m�F����܂����B���̂���3�l�́A�C�O�̑I��ł��B����ŁA�I����܂ށA���W�҂Ȃǂ̗z���҂́A���킹��110�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�I�葺�ōs���Ă��錟���ł����A�����L�b�g���s�����A�ꕔ�̑I��ŁA�����A�������s���Ȃ��������Ƃ��킩��܂����B���g�D�ψ���́A���Ԃ��H�v���čs�����ƂŁA�v���[�u�b�N�ɒ�߂�ꂽ�̌������s�����Ƃ������Ƃł��B24���Ɍ����L�b�g����ʂɓ͂��̂ŁA�K�v�Ȗ{�����A���܂Ȃ��z�z����Ƃ��Ă��܂��B
���a��w�a�@�E���ؐ�����t�u2�T�Ԍ�A1�J���オ���ɕ|���B���̎��ɂǂ��Ȃ��Ă���̂��Ƃ����s���͂���B�������[���͓����������Ȃ����A�N���������Ȃ��ő����I�������v
����w�ŃN���X�^�[�������A���ƈȊO�Ŋ����g�傩�@����̐V�^�R���i�@7/23
���ꌧ��23���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Č����̈�Ë@�ւɓ��@���Ă���70��j�������S���A�V����10�Ζ����`60��̒j��14�l�����������Ɣ��\�����B�����ł̊����m�F�͌v5764�l�A���҂͌v92�l�ƂȂ����B20�����\�̐V�K�����҂̂����A��Îs�̏���1�l���lj��̌����ʼnA���Ɣ��f���ꂽ�ȂǂƂ��Ď�艺�����B
�V�K�����҂͋��Z�n�ʂɑ�Îs6�l�A���Îs3�l�ȂǁB4�l�͑�Îs�̂т킱�����X�|�[�c��̊w���ŁA19���ȍ~�Ɋ������m�F���ꂽ�w���͌��O���܂ߌv12�l�ƂȂ�A���̓N���X�^�[(�����ҏW�c)�ƔF�肵���B���ɂ��ƁA���ƈȊO�̊����Ŋ������L�������Ƃ݂��A����܂ł�29�l���������A17�l�͉A���Ɣ��������B����w�́A�Z���ڐG���^����w���E���E��������ҋ@�Ƃ��Ă���Ȃǂ̑Ή����z�[���y�[�W�Ŕ��\�����B
���Îs��23���A�s�����ǂ����̉���1�l�̊������m�F����A������24������26���܂ŋx������Ɣ��\�����B
�������������A���邩�@�A�x�Ɠ����ܗւ��d�Ȃ��s���̏����̎��@7/23
�ً}���Ԑ錾���Ɏn�܂���4�A�x�Ɠ����ܗցB���݁A��s���͐V�K�����Ґ��̊g�傪�~�܂�Ȃ����A���ꂩ��ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��H�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�\�����ŁA����2020���ɂ�����V�^�R���i�E�C���X��̂��߂̐��ƃ��E���h�e�[�u�������Ȃǂ����߂��A���s���N���S�����������̉����M�F����ɕ����܂����B
�\�\������7��20�����_�ŐV�K�����Ґ��̕�1387�l�A1�T�ԑO���557�l�����Ă��܂�(���̌�A22�����݂�1979�l)�B��͂�}�����Ă��܂����A������ǂ����Ă��܂����H
������Ƃ������Ǝ��̂͑z����Ƃ����Αz����ł��B�V���b�N�������̂́A���(20��)�A��ʌ��̉�c�ɃI�����C���ŏo���̂ł����A��ʂ̊����Ґ��͋}�㏸���Ă���Ƃ������܂����B�{�����x(�����҂̐����{�ɂȂ�X�s�[�h)�����̂����������Ȃ��Ă��܂��B�_�ސ���t�������悤�ȏł��B�S���I�Ɍ���Ƃ����ł��Ȃ��̂ł����A���݁A�V�^�R���i�̗��s�͎�s���𒆐S�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B2009�N�̐V�^�C���t���G���U�̗��s�̎����v���܂������A�����ǂ͂�͂�l�����W���Ă����s�s���ł��傫�Ȗ��ɂȂ�̂ł��ˁB
�\�\7��12���ɓ����ɏo���ꂽ�ً}���Ԑ錾�̌��ʂ��o��̂͂��������ゾ�Ƃ������Ƃł��傤���H
�����ł��ˁB���̊����́A�ً}���Ԑ錾�����낤���Ȃ��낤���A�I�����s�b�N�����낤���Ȃ��낤���W�Ȃ������Ă���킯�ł��B�ً}���Ԑ錾�ɂ�鉽�炩�̌��ʂ����邩�Ȃ�����1�`2�T�Ԃ����Ă���Ȃ̂ŁA���T�����痈�T���炢�̏�����K�v������ł��傤�B
�\�\�錾���o�Ă���̐l�̗���͂ǂ��ł��傤�H
����(7��21��)�̌��J�Ȃ̃A�h�o�C�U���[�{�[�h�ɏo���ꂽ�����s��w�����������Љ�N��w�����Z���^�[�̐��c�~�u�搶�̎���������ƁA�ً}���Ԑ錾���o���ꂽ�����肩��A�����̔ɉ؊X�̐l�̗���͗����Ă��܂��B�ً}���Ԑ錾�̃A�i�E���X���ʂȂ̂��A�u�V�K�����҂�1000�l�����v�ƂȂ��āu��ς��v�Ǝv�����̂��B�����p�ƍl�������̂ł���......�B�J�○�̂��������邩������܂��A�����̕�����苭�������Ă���͉̂ċx�݂ɂȂ����e�������邩������܂���B����A�����̎����Đ��Y��(1�l������̓����Ґ��B1����Ɗ����҂͑����ɓ]����)�͏オ���Ă��܂��B��Ԃ̔ɉ؊X�̐l���͉������Ă��邱�Ƃ́A�����ǂ����闧�ꂩ��͂��肪�������Ƃł��B���͊����҂̕Ґ��͑����Ă��܂����A����ɔ����āA�����Đ��Y����V�K�����҂��������Ă��邩�ǂ����B1�A2�T�Ԍ�ɂ��̌��ʂ������Ă��邩�ǂ����𒍖ڂ��Ă��܂��B
�\�\�ł͖��邢�����������Ă���Ƃ������Ƃł����B
���邢�Ƃ܂ł͂܂������Ȃ�����ǁA���Ҋ�������ł͂���A�Ƃ������Ƃł��B�Ƃ��낪�A�ً}���Ԑ錾���������ꂽ����̔ɉ؊X�̐l�̗���͑����Ă��܂��B
�\�\���ꂪ�����Ă���̂́A��͂�ċx�݂̗��s�҂̉e���ł��傤���H
����ً͋}���Ԑ錾��A�V�K�����ҕ͂����ƌ����Ă����̂ł��B�Ƃ��낪�A��Ԃ̐l�̗��ꂪ�����Ă����̂�ǂ�������悤�ɁA�����ҕ��㏸�ɓ]���Ă��܂��B�����Ď����Đ��Y����1���āA�����Ă��Ă��܂��B�����̂��������͌��O����̗��K�҂̂悤�ł����A���̌�̑����͉��ꌧ���ł̍L����ƕ��͂���Ă��܂��B�_�ސ�́A��Ԃ̐l����������Ƒ����Ă��邵�A�V�K�����҂�����Đ��Y���������Ă��܂��B�_�ސ�ŋً}���Ԑ錾���o���ƒm�����\�����Ă���l�̗���͏������������Ă���̂ł����A����قlj������Ă͂��܂���B�u�l�̗���͊����҂̑����ƒ��ڊW�Ȃ��v�Ƃ����l�����܂����A�m���ɐl�̗���Ɗ����Ґ��͂قڈ�v���Ă��܂��B��t�͏����������Ă��܂��B��ʂ͓����̐l�̗���͌����Ă��܂����A��͏オ���Ă��܂��B�����Ď��s�Đ��Y�����V�K�����ҕ����}�����Ă��܂��B���(20��)��ʂ̉�c�ɏo���Ƃ���A�����o�H�Ƃ��Ĉ��H�X�E��H���Ăт�����Ƒ����Ă���Ƃ̏�������܂����B�����Ŋ��������l������̂����ʂŊ������L���Ă���Ƃ����p�^�[���ł��B�f�[�^�����Ă݂�ƁA���l���k���Ⓦ��������ȂǓ����ƂȂ��鉈�������Ō����ɑ����Ă��܂��B
�\�\�e�����̂Ŕ����ɌX�����Ⴂ�܂��ˁB
�����ł��B�Ⴆ�A�k�C���̐V�K�����҂͈�x�傫������������ɁA�ŋ߂܂������Ă��܂��B���m���͂��ߊW�҂̓s���s�����Ă���Ǝv���܂��B�����āA�l�̗�������~�܂�ŁA�������Ă���Ƃ͂ƂĂ������Ȃ��ł��B22������4�A�x������܂����A�����k�C���͂���܂ŕK���A�x�Ȃǂ̌�ɐV�K�����Ґ����オ���Ă��܂��B�ό��q�̉e���͂���ƌ�����ł��傤�B�ό��n�Ƃ��Ă͂��C�̓łł����A���O�̐l�ɗ��Ă��炢��������ǁA���Ă��炢�����Ȃ��A�Ƃ����W�����}������Ă���Ǝv���܂��B
�\�\�����͊��҂����Ă邩������Ȃ��Ƃ������Ƃł������A��Â͂�����������ł��傤���H
���̏t�̑����A�݂�Ȃ��u����͂܂����v�Ǝv���������班���x��Ĉ�Â��N�����܂����B�����͍��A���̌x�����Ƌْ��������鎞���ł��B
�\�\�����̈�t������SNS�ł̂Ԃ₫���Ă���ƁA���X�Ɉ�Â��N�����Ă����Ƃ������������Ă��܂��B
�����œ�������̈�t�̊��o�͈�ԏd�v�ł��B�u�N���v�Ɓu�Z�����v�͈Ⴄ�̂ł��ˁB�u�N���v�Ƃ̓R���i�̊��҂�f�Ă���Ƃ��낾�����Z�����̂ł͂���܂���B�a�@�S�̂Ƃ��ĕ��ʂ̊��҂����������Ȃ��A���邢�͕a�@�O�Œn��̓��@�̒������s���Ă���S���҂��A���������ɓ��@���₢���킹�Ă�����悪�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���Ƃ����ł��B���Ƃ��Εa����10���Ă��鎞�ɁA2������5���Ԃɂ킽���ē��@������Ă���Ȃ���͂Ȃ��̂ł����A������5�l�}�ɓ���ƁA���Ƃ����������Ƃ��Ă��l��ɂ�����ɕ��S��������A�ْ��͍��܂�A�N�������o�Ă���Ǝv���܂��B�܂��A�a����3���Ă����Ƃ��Ă��A�l�H�ċz����Ǘ��ł���X�^�b�t��7���ɂ����肫��A�ȂǂƂ������N�����ɂȂ���܂��B��ʂ̐l�́u�N���v�Ƃ����ƕa���p���p���Ɋ��҂����邱�Ƃ��v���`���ł��傤����ǁA�����ł͂Ȃ����A���������ł̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł��B�K���ɒv�����͈ȑO�����P���Ă��Ă��܂��B�Ώ��@�⎡�Ö@���i��ł��āA����҂̊��Ґ������Ȃ��Ȃ��Ă��邩��ł��B����҂̃��N�`���ڎ킪�i��ŁA����̊��҂������Ă��Ă��邱�ƁA����Ҏ{�݂ł̃N���X�^�[���������Ă��邱�ƂȂǂ����R���ƍl�����܂��B�����Ȃ�ƁA���҂���̖����댯�ɂȂ邱�Ƃ͌����Ă��Ă��܂��B����͂ƂĂ��ǂ����Ƃł��B�������A���x�͕ʂ̕��S�������Ă��܂��B����m�荇���̈�t�������O�̉�c�̍Œ��Ɂu���ꂩ��ECMO(�̊O�����^�l�H�x)��2�l�̊��҂ʼnȂ��Ƃ����Ȃ��̂Łv�Ɠr���ʼn�c�𗣂���܂������A20���50��̊��҂���ł����B���ꎩ�̂���������ςȂ��ƂȂ̂ł����A�����20���50�ゾ�ƁA��Ì�����u��ɏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����v���b�V���[�������Ȃ�܂��B�N��ɂ���Ď���Ƃ����킯�ł͂���܂��A70��A80������Â��鎞�Ƃ͈ӎ�������Ă���Ǝv���܂��B���̂悤�ɐl�������ł͑���Ȃ����S�̏d��������܂��B�u������v�Ƃ������Ǝ��̂͗ǂ����ƂȂ̂ł����A���Ȃ�̎�������ĉ��Ƃ����������Ȑl��10���̕a����10�l��������A��Î҂̓��̓I�S���I���S�͏d���Ȃ�܂��B�����āA�����҂��傫�������Ă���ƁA����҂ɔ�ׂĊ��������Ȃ��Ƃ��Ă��A�d�ǁA�����ǎ҂̐�ΐ��������܂��B
�\�\�a��������Ȃ��Ȃ�Ƃ����f�[�^�͌����Ă��Ȃ��ł����H
�����_�ł̎�s���ł͐����Ƃ��Ă͂܂��Ȃ�Ƃ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B
�\�\�N��w����Ԃ������Ƃɂ�镉�S���̋��܂肪����Ƃ������Ƃł��ˁB
40��A50��𒆐S�ɏd�ǎ҂̒��ŎႢ�l�̑����������Ă���킯�ŁA��l�ɂ����鎡�Â̌�����������͈���Ă���B���N���͑����������Č����邱�Ƃ���t�̎d���̂����ɂȂ�܂��B�l�͏����ȂŒ����������f�Â�����Ă��܂������A�q�ǂ��̊��҂���߂�Ƃ������Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł����B���҂���Ԃ��Ă��鍡�̐V�^�R���i�̈�ẤA���܂ňȏ�Ɂu�~�����Áv�A���u�ł������̎��s������Áv�ɂȂ�ł��傤�B
�\�\����ȏ̒��ŁA�����Ől�̗��ꂪ�����Ă���̂́A�S�z����Ă����Ō�̐�D�u�ً}���Ԑ錾�v�̌��ʂ�����Ă���Ƃ������Ƃł��傤���H
�V�C�̂�����������Ȃ��A�ċx�݂̂�����������܂���B�����������̐l�́u���̂܂܂ł͂������......�v�Ƃ����C���������f����Ă���̂ł����Ăق����Ǝv���܂��B���܁A�������X�N�������Ƃ���Ă���Ⴂ����́A�d�ǂɂȂ�ǂ̂悤�Ȍ��i�ɂȂ邩�Ƃ������Ƃ́A�e���r�̃j���[�X�Ō��邮�炢�ŁA���������Ȃ��Ǝv���܂��B�|���͂��邯��ǁA�����Ɏ����ɋN���蓾�邱�ƂƂ͍l�����Ȃ��Ǝv���܂��B�������A���A�����Ґ��������Ȃ��Ă���Ƃ͂����A�C���t���G���U�̂悤�ɂ������ɂ���l�����X�Ƃ�����悤�ȏł͂Ȃ��̂ŁA�u�����������邩������Ȃ��v�Ƃ�����@�ӎ��͏��Ȃ��ł��傤�B�ł��A�u�����̐V�K�����Ґ���1000�l����2000�l�ɓ͂��������v�Ƃ�������������A�u����͂��̂܂܂ł͂܂����v�Ǝv�����Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�j���[�X�ԑg�Ŕɉ؊X�ɗV�тɂ��Ă���l�̃C���^�r���[�����Ă���ƁA�u�݂�ȗV�тɂ��Ă��邩�炢���Ǝv���܂����v�Ȃǂƌ����Ă��܂����A�S�̒��ł͂ǂ��������܂������ȂƎv���Ă��镔��������悤�Ɍ����܂��B���ꂪ�����I�ɐ������オ���Ă���ƁA�u����͂������ɂ܂����v�Ƃ����ӎ������߂�l�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������ɔ�������l������ł��傤����ǁB
�\�\�A�h�o�C�U���[�{�[�h�̐��Y���搶�A�Ð��S�C�搶�̗\���͂��Ȃ�ߊϓI�ł������A�Ō�̐�D�̍팸���ʂ͏o�Ă���ƍl���Ă�낵���ł����H
�l�͊��҂������B�s���ɂȂ邱�Ƃ��A�s�M�������K�v���Ȃ�����ǁA�������Ȑl����邽�߂Ɍx�����͎����Ă��炢�����킯�ł��B�l�͂܂��l�̎��R�ȑP�ӂ�ǎ������҂������B
�\�\�������A����(21��)���瓌���ܗւ̗\�I���Z���n�܂�A����(22��)����4�A�x���n�܂�A23���ɂ͓����ܗւ̊J����������܂��B�e���r���V�����ܗփ��[�h�ɂȂ��Ă��܂����B���̋�C��������ɗ^����e�����ǂ����Ă��܂����H
�e���r�͗l�ς�肵�Ă��܂��ˁB�V������������ܗ֎��ʂɂȂ��Ă��܂��B
�\�\4�A�x������ł��傤����ǂ��A�����̖邩�痷�s�ɏo������l�Ŗ��Ȃ̍q��ւ������ł��B���ʂ��o�n�߂邩�A�Ƃ����Ƃ���ŁA�ܗ֊J�ÁA�A�x�A�ċx�݂Ɛl�̓����𑣂��C�x���g���ڔ������ł��B
����͏�X�����Ă���悤�ɁA�������Ǝ��͎̂~�߂��Ȃ��ł����A�Ă��鏊�ɋĂ��鎞�Ԃɍs���Ăق����̂ł��B2020�N�̂��Ԍ��̎����Ɍ��������Ƃƈꏏ�ł��ˁB�Ƒ������Ől�̏��Ȃ��Ƃ���ɍs���Ȃ�A�����̃��X�N�͉�������B�u���Ԍ��v�͊y���߂�B����Q����Â��ɂł���B�v�́A�݂�ȂŏW�܂��Ă�܂Ȃ��ł���ƌ��������̂ł��ˁB����1�N���A�݂�Ȃ��̊����ǂɂ��Ă悭�w��ł��܂�������A���S�Ɋy���ޕ��@�͂킩���Ă��Ă���͂��ł��B���ꂪ��N�Ƒ傫���Ⴄ�Ƃ���ł��B
�\�\�����ܗւɂ��ĉ��߂ĕ����܂��B�c�O�Ȃ��犴���҂����Ȃ葝���āA��Â��N�����鎖�ԂɂȂ�����A�n�܂��Ă����~���ׂ��Ƃ����l���ɕς��͂Ȃ��ł����H
����͑I�����̒��ɓ����ׂ����Ǝv���܂��B���̑I�����͑S���Ȃ��Ƃ��ׂ��ł͂Ȃ��B�{���ɒ��~���邩�ǂ����́A���^�c��̖��ȂǐF�X�Ȗ�肪����Ǝv���܂����A���f�ɂ͐F�X�ȗv�f�����ނƎv���܂��B�ł���ÂɌg���҂��炷��A���̑I���͏�ɂ���ׂ��ł��B
�\�\�n�܂�������ƌ����āA�������������Ă���̂ɂȂ������ɏI���܂ő�����Ƃ������Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
�ł�����͋t�����蓾��̂ł��B���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃g�[�}�X�E�o�b�n����u���������P������ϋq�����Ă���v�ƌ����܂����ˁB������A�u�������悭�Ȃ�A�����ł���Ƃ����ł��ˁv�Ɠ����Ă������B��������`�P�b�g�����肵�Ȃ�������Ȃ��ł��傤����A�^�c��͗L�ϋq�ɐ�ւ���͓̂����������܂���ˁB�����A����͓����ɑ����߂����璆�~���l���Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�o�b�n����ǂ������j���A���X�Ō��������A�p���ł̃X�s�[�`�����Ă��Ȃ��̂ł킩��܂���B�uI hope(�`���]�܂���)�v�ƌ������̂��A�uIt should be(�`���ׂ���)�v�ƌ������̂��ł����Ȃ�Ⴄ�Ǝv���܂��B�����ǂƃ}�X�M���U�����O(�吨���W�܂邱��)�̊W�ɒ�����������Ă����҂Ƃ��āA�u�����ǂ������ő嗬�s���[���ȃ_���[�W��������(����������)�ł́A�}�X�M���U�����O�̒��~�����O�ɔO���ɒu���Ă����ׂ����v�Ƃ����l���͕ς��܂���B
�\�\�Ƃ͌����A�ً}���Ԑ錾���ɊJ�Â���킯�ł��ˁB
�d�ǎ҂̔������}�����A��Â�������x������Ȃ��Ȃ�悤�ȏ�Ԃł́A���~�Ƃ����I������炴��Ȃ��Ǝv���܂��B�@�E�E�E�@
���x�g�i���A��v3�s�s�ŊO�o�����@�R���i�����g��A�A��5000�l�K�́@7/23
�x�g�i�����{�́A4�����{�ɍĔR�����V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A�n�m�C�A�z�[�`�~���A�_�i���̎�v3�s�s�ɁA�s���̊O�o�����[�u�������B��N����̊����҂͗v7���l���A���҂͖�370�l�B���{�͌��i�Ȑ����[�u�ŗ��s��}�����݂����l�������A1��������̐V�K�����҂͘A��5000�l�O��ɒB���A�����̒����͌����Ă��Ȃ��B
�z�[�`�~���ł͍���9���A�s�v�s�}�̊O�o���֎~���A�ᔽ�҂ɔ������Ȃ��Ȃnj������K�����n�܂����B19���ɂ̓z�[�`�~�����܂߂��암�̂قڑS��ɓK�p�͈͂��g�傳�ꂽ�B
�H��̑��Ƃ́A�~�n���ɐQ���܂肷��X�y�[�X��p�ӂ��ĘJ���҂����h�����邩�A�ߗׂɊm�ۂ����z�e���ɘJ���҂��h�������A��p�ԗ��ōH��Ƃ̊Ԃ�A�����邱�Ƃ������Ƃ����B�Ή��ł��Ȃ��H��́A���Ƌx�~�ƂȂ����B
�k���Ɉʒu�����s�n�m�C�ł�19���A�s�v�s�}�̊O�o������A����ɂƂǂ܂�悤�s���ɗv���B�������ɒʋ���l�́A�S�]�ƈ��̔����ɗ}���邱�ƂɂȂ����B�����̃_�i���ł�22���A�s���ɔ�������E��ւ̏o�Ȃǂ������ĊO�o���l�����߁A�^�N�V�[�������ʋ@�ւ��^�x�ƂȂ����B
��r�I�����i�K����V�^�R���i�����߂Ă����x�g�i�������A�����ی����͍���̗��s�ɂ��āA�u����܂ł�蒷���ɂ킽��A��i�Ɛ[���ȉe�����y�ڂ��v�ƌ��O�B�����͂̋����C���h�R���̃f���^���̍L����ɋ�����@���������Ă���A���i�Ȑ����[�u�ƂƂ��Ƀ��N�`���ڎ���}���l�����������Ă���B
���V�^�R���i�����g��̓암����o�҂��J���҂������E�o�@7/23
�o�҂��J���҂��S���ōő��̏��s�z�[�`�~���s�����A4��������L�������V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̍�����4�g�̉e���ɂ��A�o�ϊ������[���ȃ_���[�W���Čٗp���������Ă���B
�H��̑��ƒ�~��e��c�Ǝ{�݂̕��ɂ�莸�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�����̐l�X���A������ʋ@�ւ̉^�s��~���܂ތ��������b�N�_�E��(�s�s����)���n�܂������Ƃ����������ɁA���̒n��E�o���Č̋��Ɍ��������i���e�n�Ō�����B
���ɂ́A�n�������߃o�C�N���Ȃ��A�k���⎩�]�ԂŋA�Ȃ����݂�l�X�̎p������B�ŋ߁A�����Ƃ����]��2��ɏ���āA�o�҂���̓��암�n���h���i�C�Ȃ���A��1300km�����ꂽ�k�����n���Q�A���ȂɌ������Ă���l�q���Љ��A�������瓯��̐����������Ă����B
�{�[�E�^�C���E�r������(�j���E28��)�́A��e(51��)�A�o(30��)�A��(12��)�̈��4�l��5�N�O�Ƀh���i�C�ȃ`�����{���S�Ɉڂ�Z�݁A�H��J���҂Ƃ��Đ��v�𗧂ĂĂ����B�������A�V�^�R���i�̉e���ō��N4������S�������ƁB
7��9���Ƀh���i�C�Ȃ����b�N�_�E������邱�Ƃ����܂�A��Ƃ͂��̖�A�Ȃ����ӂ����B�莝���̂����͋͂��ŁA�o�C�N���Ȃ����A�u��������E�o���Ȃ��ƁA���������Ă����Ȃ��v�Ɗ������r������͎��]�Ԃł̋A�Ȃ��J�n�B�r��������A�o���Â��q�����ꂼ�ꎩ�]�Ԃ̌��ɏ悹�Ėk�֖k�ւƐi�B
��Ƃ͏o������10����̒��A�h���i�C�Ȃ����300km���ꂽ�쒆�����ݒn���j���g�D�A���ȃj���t�I�b�N�S�t�I�b�N�U�����̌��⏊�ŌĂю~�߂�ꂽ�B����������⏊�̃X�^�b�t�͈�l�ɓ���A�������o�������Ĉ�Ƃ̂��߂ɐH�i��������w���B����ɁA�C���^�[�l�b�g�ň�Ƃ̎x�����Ăъ|�����B
����ƁA���e��ǂl�X���瑽���̊�t�����W�܂����B�����ߌ�ɂ͒n���Z���ɓ��ȃt�@�������s�^�b�v�`�����w�܂ő����Ă��炢�A��ԂŌ̋��Ɍ����ďo����21���ɓ��������B���̂܂��]�ԂŖk�i�𑱂��Ă�����A����40���͂�����Ƃ����啝�Ɏ��ԒZ�k�ł������ƂɂȂ�B
�r������́A�u1����30km���i��ł����B���̓r���ő����̐l�X����H�ו����������������Ă�������B���⏊�ł͒S���҂ɔz�����Ă��炢�A�ʍs��F�߂Ă�������B�������ɂ͎��]�Ԃ����������A�����b�N�T�b�N��w�����Ē�����������ċA�Ȃ���l�X�������B�������Ƒ��͌b�܂�Ă���v�ƁA���ӂ̋C�������q�ׂ��B
�܂�11���ɂ́A�J����47�l���쒆�����ݒn���J�C���z�A�Ȃ��o�����A�k���Ŗ�400km���ꂽ���n���N�A���K�C�ȂɌ��������B��s�͏o���n�����50km�i�j���z�A���ŕی삳��A�ʕ�����J�C���z�A�ȌR���w�������ԗ������āA��s���̋��܂ő���͂����B
���؍� �����g�厕�~�߂����炸 �\�E���Ȃǂ̋K���[�u���� �@7/23
�؍��ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ɏ��~�߂������炸�A�؍����{��25���܂łƂ��Ă����\�E���Ȃǎ�s���łƂ��Ă���ł����������x���̋K���[�u���A2�T�ԉ�������Ɣ��\���܂����B
�؍��ł̓C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�̃f���^�����L����������Ă��āA�\�E���Ȃǂ̎�s���ŁA��H�Ȃǂ̎��I�ȉ���ߌ�6���ȍ~�A2�l�܂łɐ�������ȂǁA�ł����������x���̋K���[�u���Ƃ��Ă��܂��B
�������A22���̊����҂͑S����1630�l�ƁA����܂ł�3�Ԗڂɑ����Ȃ�A�����g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
�n��ʂŌ���ƁA��s�\�E����520�l�A�אڂ���L�����M(���E)����415�l�ȂǁA�S�̂�63������s���ɏW�����Ă��܂��B
���̂��ߊ؍����{��23���ɊJ���ꂽ���c�ŁA25���܂łƂ��Ă�����s���̋K���[�u�������2�T�ԉ������邱�Ƃ����߂܂����B
���{�͉����̊��ԓ��Ŋ����g��̃X�s�[�h��}�������Ƃ��Ă��܂����A������L���葱����ꍇ�A�K���̂���Ȃ鋭������������Ƃ��Ă��܂��B
�`�����E�w�`�����s�����S���́u�����g��̐�����}���邽�߂ɂ͎��I�ȉ��ړ������炷�ق��Ȃ��B�Ă̋x�Ɏ����Ŋ����̊g�傪�傫�����O�����v�Əq�ׂāA�������[�u�̓O����Ăт����܂����B
���V�^�R���i�����Ċg��A���[�����i�C�̃��X�N���d�b�a���ف@7/23
���B������s(�d�b�a)�̃��K���h���ق�22���A�V�^�R���i�E�C���X�����Ċg�傪���[�����̌i�C�ɑ��郊�X�N�ɂȂ鋰�ꂪ����ƌ��O���������B
�d�b�a�͂��̓��ɊJ����������ŁA��������̐����u�������肷��Ɠ����ɁA��i�ƒ����I�Ȏx���̉\�������������B
���K���h���ق͗������̋L�҉�ŁA�d�b�a�͌o�ςɑ��郊�X�N�́u�����ނˋύt���Ă���v�Ƃ̌�����ς��Ă��Ȃ��Ƃ��Ȃ�����A���ʂ��͈��������A�����̂ق��A���N�`���ڎ�̐i�W�Ɉˑ����Ă���Ǝw�E�B�u�o�ς̑傫�ȕ����̊������ĊJ���ꂽ���ƂŁA�T�[�r�X����̗͋������x������Ă���B�����A�V�^�R���i�̃f���^�ψي��̊����g��ŁA�ό��ƂƐڋq�Ƃ𒆐S�ɃT�[�r�X����̉��݉����鋰�ꂪ����v�ƌ��O���������B
���̏�ŁA�d�b�a��6���Ɍ��\�����X�^�b�t�\�z�́A�����g��}���[�u�̈ꕔ����3�A��4�E�l�����܂Ōp�������Ƃ̌��ʂ��Ɋ�Â��Ă����Əq�ׂ��B
���B�ł������͂������f���^�ψي����嗬�ɂȂ����A���N�`���ڎ헦����r�I�������ł��������Ċg�債�Ă���B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���k�C�� 118�l���� 7��6��ڂ�3�P�^�c�u�ً}���ԁv������2�Ԗڂɕ��� �@7/24
�k�C������7��24���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂�118�l�m�F����܂����B100�l����̂�2���Ԃ�ŁA21���A���őO�T�̓����j��������܂����B7��2�Ԗڂɕ��Ԑ��ƂȂ�܂����B
���҂�3���Ԃ�Ɋm�F����Ă��܂���B�����҂͎D�y�s88�l�A�k�C�����\��26�l�A����s4�l�ł��B
�k�C���S�̂�1�T�ԑO�̓y�j��111�l����7�l(�{��6��)�������܂����B�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̉�������13���ځB21�������đO�T������A7���ɓ�����100�l����̂�6��ځB�����X���������ɂȂ��Ă��܂��B
�k�C���S�̂̎g�p�a������7��23����327���ƑO������25�������A�k�C���Ǝ��̌x���X�e�[�W4�̖ڈ��u350���v�ɋ߂Â��Ă��Ă��܂��B
�����͂������Ƃ����C���h�^�̕ψكE�C���X�E�f���^���^���́A�k�C�����\����1�l�A�D�y�s���\����5�l�m�F����A�v6�l�ƂȂ�܂����B
����Ŗk�C�����ł́u�����v�Ɓu�^���v�v312�l�ƂȂ�܂����B
���{�́u�ً}���Ԑ錾�v�𓌋��s��4�x�ڂ̔��߁A���ꌧ���������A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{�́u�܂h�~���d�_�[�u�v�������B�k�C���A���m���A���s�{�A���Ɍ��A��������12���ɉ������܂����B
�k�C����12������8��22���܂ł��u�Ă̍Ċg��h�~���ʑ�v���ԂƂ��A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p��20���ɗv���B�D�y�s�́u�s�v�s�}�̊O�o���l�v�A�D�y�s�Ƃ́u�������l�v�A���H�X�ɂ͌ߌ�9���܂ł̎��Z�v�������A��ނ͈̒��̗v���������ꍇ�Ɍߌ�8���܂łƂ���v�������Ă��܂��B
�k�C�����̊����҂́A�v42912�l�ƂȂ�܂����B
�������̊����Ґ��A�ߋ��ő��ɋ߂Â��@��3�g�ƈقȂ鎖��@7/24
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g�傪���������s�ŁA�ߋ��ő��������~�̑�3�g���Ԃ��Ȃ�������\�����o�Ă��Ă���B�����Ґ��͓����ɋ߂Â����邪�A�������Ò̐��ł͑傫���قȂ�_�����Ȃ��Ȃ��B1��������̐V�K�����Ґ����N�Ԃ��2��l�ɔ�����7��22���ƁA�ߋ��ő���2520�l�̊������m�F���ꂽ1��7���̏��ׂĂ݂��B
�u�܂��ɁA�͊�@�I�ł����ċɂ߂Đ[���v
1��7����̗Վ���B���r�S���q�m���́A�R���i�Ђɂ����錻��������\�������B���{�͂��̓��A��s��1�s3����2�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�o�B�O����6���ɓs���Ŋm�F���ꂽ�����Ґ���1640�l�ŁA����܂ł̉ߋ��ő���287�l�������B���ꂾ���ł����ٓI�������̂ɁA��7���ɂ͈�C��2520�l�܂Œ��ˏオ�����B
�����A�����Ґ��̒��ˏオ����ȏ�Ɋ�@�I�ȏɒ��ʂ��Ă����B
1��7���̊�����2520�l�̂����A65�Έȏ�̍���҂�264�l(����l)�B1979�l�̊������m�F���ꂽ7��22����66�l��傫������B�����A�d�lj����₷������҂̃��N�`���ڎ�͂܂��n�܂��Ă��炸�A����҂ւ̊������L����L����قǁA��Ò̐��̕N��(�Ђ��ς�)�����܂�댯�����������B
���ۂ�1��7�����_�ł̏d�NJ��Ґ���121�l�ƁA7��22�����_��65�l�̂ق�2�{���B���@���Ґ���1��7����3154�l�ɏ��A7��22����2544�l��傫������B����ŁA�m�ۂ��Ă����R���i���җp�̕a���͓���4�珰�ŁA���݂�5976����傫��������Ă���A�R���i�Ѝő�̈�Ê�@�������Ă����B
�ق��ɂ����O�ޗ��͂������B����×{�҂��B1��7�����_��5319�l�ɒB���A1�J���O��4�E7�{�ɋ}���B���@������Ă���ԂɖS���Ȃ����l���������A�����J���Ȃɂ��ƁA��N12������̖�2�J���ԂŁA�s���Ōv8�l������×{���ɖS���Ȃ��Ă����B
����×{�҂͑�5�g�̍����1��7�����݂ɍ��܂����B7��22�����_��4512�l�ɏ��A1�T�ԑO����2375�l�����B���@�Ɏ���Ȃ���҂�̊������������Ƃ��w�i�ɂ��邪�A����×{�҂̑̒��Ǘ����傫�ȉۑ�ɂȂ��Ă���B
�s��t��̒������F����́u�×{�҂̃t�H���[�A�b�v�̐�������ɋ������A�ł�����莩��×{���̏d�lj���h���K�v������v�Ǝw�E������ŁA�a���̕N���ɂ��Ă��������O����B
�u�����҂���3�g����悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă���ƁA���@���Ґ��͑�3�g���ȒP�ɒ����Ă��邾�낤�v
���V�^�R���i�A�S����4215�l�̊������m�F�@7/24
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�S���ł��̂��V����4215�l�̊������m�F����܂����B
�����̊g�傪���������s�ł́A���̂��V����1359�l�̊��������\����܂����B1���̊������\��1000�l����̂�4���A���ŁA34���A���őO�̏T�̓����j��������܂����B�N��ʂł�20�オ492�l�ƍł������A20���30��Ŕ����ȏ���߂Ă��܂��B
�܂��A�_�ސ쌧��652�l�A��ʌ���401�l�A���{��379�l�̊��������\����Ă��܂��B
�S���̏d�ǎ҂͑O�̓�����39�l������431�l�ł����B�܂��A8�l�̎��S�����\����Ă��܂��B
�����铌���̈�Õ���c�s�̍ݑ�҂�1�J����6233�l���I�@7/24
�����s��23���̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ���1359�l�B4���A����1000�l�����B�����}�g��ɔ����A����(���@�A�h���×{�A����×{�A���@�E�×{��������)���}�����Ă���B6��23����3552�l���������A23����1��1957�l�B1�J����3�{���A8405�l�������Ă���B���̂����A���@����2558�l�ɉ߂����A�ݑ�҂�7641�l(����×{5172�l�A������2469�l)�ƁA1�J����6233�l�������Ă���B
�ݑ�҂�������̂́A���@���Â炭�Ȃ��Ă��邩�炾�B���{�̐V�^�R���i�����ȉ�̔��g�Ή��21���A�u���@�����ō����Ă���l�A�����(�×{����)����l�������Ă���v�Ɣ����B���c�J��L������̂��A�q�a�@��z�e���̊m�ۂ����͂⍢��ɂȂ��Ă���r�ƃc�C�b�^�[�ŋ斯�ɒ��ӊ��N�����B
���̂܂܂ł͉ߋ��ň��̈�Õ�����������˂Ȃ��B
��3�g�ɏP��ꂽ1���A�V�K�����Ґ��͉ߋ��ő���2520�l���L�^�B���Ґ���2���l�ɔ���A�ݑ�Ґ���1��5000�l�ɏ�����B���̂��߁A�K�v�Ȉ�Â����Ȃ����ԂɊׂ��Ă��܂����B�x�@���ɂ��ƁA1���̗z���҂̎���͓s����14�l�őS���ő��������B����œ|��A����17���ɕa�@�Ŏ��S�����s����40��j���́A���S�㌟���ŗz���������B
�����ł�1��1000�l�y�[�X�Ŋ��҂������Ă���B�A�b�Ƃ����Ԃɑ�3�g�������B�s�͑�3�g���Ɣ�ׂĕa�����2400�����₵�A���݂�6406�����m�ۂ��Ă���B23�����_�̕a���g�p����39.9��(2558�l�^6406��)�ƃX�e�[�W3(�����}��)�ɂƂǂ܂��Ă��邪�A�X�e�[�W4(�����I�����g��)�܂�10�|�C���g�قǂ����]�T�͂Ȃ��B�����w����w�Z�p���w�Z�����Z�Z���̒����p�b��(�����NJw)�͌����B
�u��3�g�ł́A1���㔼�ȍ~�͐l�������ɂȂ���C�x���g�����Ȃ����Ƃ������āA�����Ґ��͌������A��Ò̐��̕N������������܂����B����́A�ċx�݂�ܗւ��d�Ȃ�A�l�̓����͊����ɂȂ�B�����͂������C���h��(�f���^��)�����s�̎嗬�����Ă���B��3�g�ȏ�̐[���Ȏ��Ԃ��l�����܂��v
���́u�����̖��ƌ��N�����Ȃ���A(�����ܗւ�)���Ȃ��͓̂��R���v�Ɩ������Ă������A��Õ��N������A�u�ܗ֒��~�v��{���Ɍ��f����o�傪����̂��B
���s�� �V�^�R���i 1128�l���� 1000�l����5���A���@7/24
�����s�ł́A24���A�s���ŐV����1128�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B1�T�ԑO�̓y�j������282�l���������̂́A1����1000�l����̂͂����5���A���ł��B�d�NJ��҂�74�l�ŁA70�l����̂͐挎2���ȗ��ƂȂ��Ă��܂��B
�����s�́A24���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł̒j�����킹��1128�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓y�j�����282�l���������̂́A1����1000�l����̂͂����5���A���ƂȂ�܂��B24���܂ł�7���ԕ��ς́A1345.7�l�ŁA�O�̏T��133���ƂȂ�A�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B24����1128�l�̔N��ʂ�10�Ζ�����60�l�A10�オ96�l�A20�オ380�l�A30�オ251�l�A40�オ167�l�A50�オ115�l�A60�オ34�l�A70�オ16�l�A80�オ7�l�A90�オ2�l�ł��B����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂�19��7528�l�ɂȂ�܂����B
����A�s�̊�ŏW�v�������傤���_�̏d�ǂ̊��҂�23�����6�l������74�l�ł����B�d�NJ��҂͍��T�ɓ����đ����X���������Ă��āA70�l����̂͐挎2���ȗ��ł��B24���͎��S�����l�̔��\�͂Ȃ��A�s���Ŋ������Ď��S�����l��2277�l�̂܂܂ł��B
���S�����Z�싅�_�ސ��� ���C�告�͑I��R���i���� �o�ꎫ�ށ@7/24
���Ƃ��̃Z���o�c���Z�싅�ŗD���������͌��s�̓��C�告�͍��Z���A���ݍs���Ă���Ă̑S�����Z�싅�_�ސ���̓o�^�����o�[�ɁA�V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�l���o���Ƃ��āA���X�����܂Ői��ł��������ւ̏o������ނ������Ƃ�������܂����B
�����24���A�_�ސ쌧�����w�Z�싅�A�������炩�ɂ��܂����B����ɂ��܂��ƁA���C�告�͍��Z����A�o�^�����o�[�̂����A17�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ���߁A�싅���̊������֎~�ɂȂ����Ƃ��āA�o������ނ���\���o���������Ƃ������Ƃł��B����ɂ��A24���ɗ\�肳��Ă����S�����Z�싅�_�ސ���X�����ŁA���C�告�͍��Z�Ƒΐ킷��\�肾���������ėˍ��Z�͕s�폟�ƂȂ�܂����B���C�告�͍��Z�́A���͌��s�ɂ��鎄�����Z�ŁA���a38�N�̊J�Z�Ɠ����ɖ싅�����n������A�Ă̍b�q���ł�2��̗D�����ʂ����Ă���ق��A�Z���o�c���ł�����12�N�ƕ���23�N�ɑ����A���Ƃ��̏t���D�����Ă��āA�t�ĘA�e�ւ̊��҂��������Ă��܂����B
���C�告�͍��Z�ɂ��܂��ƁA21���A�싅���̗��Ő������Ă�������1�l���̒��s�ǂ�i���A22���ɂo�b�q���������Ƃ���A�V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�������23���A�����𒆐S��40�l�]��ɂ��Č��������Ƃ���A�V���ɕ���20�l�Ƌ���1�l�̂��킹��21�l�̊������m�F����A���̂���17�l�́A�Ă̑S�����Z�싅�_�ސ���̓o�^�����o�[�ł����B�����o�H�͂܂��킩���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł����A�w�Z�ł͍���A�����ȊO�̕����ɂ��Ă�������i�߂Ă������Ƃɂ��Ă��܂��B
���Ƃ��̏t���܂߁A����܂ł�4�x�̍b�q���D�����ʂ����A���̉Ăł̑ޔC��\�����Ă����n�h���ḗu�������ނ��邱�ƂɂȂ�A�W�҂̊F�l�ɐ[������ѐ\���グ�܂��B�ی����ƘA�������Ȃ���A���k�ւ̑Ή����ŗD��ɁA�����g���h�����ƂɑS�͂𒍂��ł��܂��v�ƃR�����g���Ă��܂��B
���C�告�͍��Z�싅���ƂȂ��݂̐[���n���̎��i�X����́A�ˑR�̑��ނ�߂��ސ���������܂����B�w�Z�̋߂��ɂ�����i�X�u�Z�����v�͖싅�����ɂ͒ʏ��3�{�̗ʂ̊C�N������ʂȉ��i�Œ���ȂǁA���N�A�����������Ă��܂����B���̉ĂőޔC�����n�h���ē����Z���̂��납���A��1�l���Ƃ������ƂŁA�X��̍g�яH�j����́A�������A�X70�L���������Ċw�Z�ɍ�������ɂ������Ƃ������Ƃł��B�������A�I�肪�N�����炸�A���������Ǝv���Ă����Ƃ���A�o��̎��ނ�m�����Ƃ������Ƃł��B�g�т���́u�V���b�N�œ����^�����ɂȂ�A�ē�I��̂��Ƃ��v���ƁA���킢�����ł炢�B�����ɕ������̂ł͂Ȃ��A�R���i�ɕ����Ă��܂����̂ŁA����ȏI�����͂Ȃ��B�R���i�͖{���ɐl�����ނ��Ⴍ����ɂ�����Â����낵�����̂��v�ƐS��ɂ߂Ă��܂����B�@
�����͋��A�{���Ɂu�敥���v�H�@�����͂��Ή��A���H�X����\�����@7/24
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ċg��ɂ��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o�Ă��铌���s���ł́A�錾�����߂��ꂽ7��12���ȍ~�A�c�Ǝ��ԒZ�k�v���Ȃǂɉ�������H�X�ɑ��A���͋��𑬂₩�Ɏx������u�敥���v���x���������ꂽ�B�Ƃ��낪�A���̎x�����}�����܂�A5�A6�����̐\���t������ɂȂ鎖�Ԃ������Ă���B���H�X����́u�q�����܂����v�Ɠ{��̐����オ���Ă���B
�敥�����x�́A�������x�Ƃ⎞�Z�v���ŋꋫ���������H�X�ւ̋��͋��x�����x���Ƃ̔ᔻ���A����ً̋}���Ԑ錾���߂ɐ旧�����{������������B���̒�o�������ɁA�敥�����Ƃ��ē��z4���~���ꗥ�x�����A����Ȃ��ꍇ�͐R�����o�Ēlj��x������B���₩�Ȏx���ɂ��A�v�������ވ��H�X���Ȃ����Ă����̂��_�����B
������A�s�͐錾�����߂��ꂽ7��12���`8��8�����̋��͋��ɂ��āA�\�����Ԃ�����܂ł��2�J�����x�O�|�����A7��19������t�����J�n�����B�������A���̍�Ƃ�D�悷�邽�߁A5��12���`6��20�����̐\���J�n���͓����\�肵�Ă���7��15�����瓯26���ɉ����B6��21���`7��11�����ɂ��ẮA������\�����t���邩���猈�܂��Ă��炸�A�敥�����x�ɂ���ċt�]���ۂ��������i�D���B
�s�͂���܂ŁA�\���V�X�e���̉��P��l�����ɂ��A�\�����̎�A���ϖ�5����ɂ͎x���ł���Ԑ����\�z�B�����u�����̋��͋��̐\�����Ԃ��d�Ȃ�ƁA���Ǝґ����������A���ʓI�Ɏx���̒x��ɂȂ���v�Ǝߖ�����B
����ɑ��A�s�̋x�Ɨv���ɉ����Ă��钆���̋������o�c�҂́u����܂ł̋��͋����o�Ă��Ȃ��̂ɁA�܂�Ŏq�����܂��ł͂Ȃ����v�Ɣᔻ�B�u������Ă���̂ɋ��͋�������Ă���X������B�����𐳂��Ăق����v�ƕ������B
���s�E�����s�v�s�}�̊O�o���l�Ăт��� ��҂���́c�@7/24
�����I�����s�b�N���J�����A�l�o�̑��������O�����Ȃ��A�s�̐E�����s�v�s�}�̊O�o�����l����悤�Ăт������s���܂����B��҂���́u�l�o������Ȃ��̂͋C���ɂ�ł��邩��ł͂Ȃ����v�Ƃ��A�u�I�����s�b�N�͂��̂ɊO�o���T���Ăق����Ƃ����̂͋��Ⴄ�Ǝv���v�Ƃ���������������܂����B
�J�Ós�s�̓����s�ɋً}���Ԑ錾���o�����Ȃ��I�����s�b�N�͊J�����܂������A�s���ł͊����g�傪�����Ă��܂��B
�I�����s�b�N�͓s���̉��ł͖��ϋq�ł����A23����̊J��ł͍������Z��̎��ӂɑ吨�̐l���K�ꂽ��A24�������Z������l�������ɑ����W�܂����肷��ȂǁA�l�o�̑��������O����Ă��܂��B
���������Ȃ��A�s�̐E���Ȃǂ�24���ߌ�A�����E�\�Q���ŕs�v�s�}�̊O�o�����l����悤���s����҂ȂǂɌĂт����܂����B
�E�������́u�ψكE�C���X�����s���Ă���B���o�ُ̈��E�тȂǂ̌��ǂɋꂵ��ł���l����������v�Ƒi���Ă��܂����B
�������̋A�肾�Ƃ������q���Z���́A�u�Ȃ��Ȃ��l�o������Ȃ��ً̂͋}���Ԑ錾���o�Ă��Ă��C���ɂ�ł��邩��ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂����B
�܂��A������̂��߂��炭��H���T���Ă���Ƃ���25�̉�Ј��̒j���́u�����ړI�ŏo�Ă����������A��B�I�����s�b�N�͂��̂Ɉ�ʂ̐l�͊O�o���T���Ăق����Ƃ����̂͋��Ⴄ�B������Ƃ��Ղ葛���ɂȂ�C���ɂނ̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂����B
�������s��1�T�Ԃ̐V�K�����҂�1���l�ڑO�@1�����ς�1345�l�Ɂ@7/24
�����s�����ی��ǃE�F�u�T�C�g���\�̑���l��Ǝ��W�v�������ʂɂ��ƁA���j�������1�T��(7��18���`24��)�Ŋm�F���ꂽ�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂͌v9420�l�ł����B�v7084�l�������O�T(7��11�`17��)�Ƃ̔�r�ł�133���ƂȂ�܂����B
���T�A�ł������҂̊m�F�������������͖̂ؗj��1979�l�B�����Ő��j��1832�l�A�Ηj��1387�l�Ƒ����܂����B1�����ς�1345.7�l�ŁA�O�T(�v7084�l/����1012�l)�Ƃ̔�r�ł�133����4�T�A���ő������܂����B
�����s��12������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����ߒ��B�܂�23���A����2020�I�����s�b�N���J�����܂����B�����g�傪�����Ă��܂��B���������A�������O�ꂵ�܂��傤�B
���S�R�̎�ޒ��H�X�ɉc�Ǝ��ԒZ�k�v���@7��26�����畟�����@7/24
�������S�R�s�ł̐V�^�R���i�E�C���X�����g��Ɏ��~�߂��|����Ȃ����A���������͓��s�ɂ����ނȂǂ������H�X�ɑ��A26������8��16���܂ŁA�V�^�R���i�Ή��̉������ʑ[�u�@�Ɋ�Â��c�Ǝ��Ԃ̒Z�k��v������B24���A�����Ō��V�^�R���i���{������c���J���A�S�R�s�ł̏W��������肵���B���s�͂i�q���k�V�����Ⓦ�k�����ԓ��������ʂ̗v�ՂŁA���͊����҂������X���ɂ����s������̉e������\���������Ɣ��f���A��苭����ɏ��o���B
���Z�v���̑Ώۂ̓X�i�b�N�Ȃǂ̐ڑ҂����H�X�A�������Ȃǂ̎�ނ������H�X�ŃJ���I�P�X�Ȃǂ��܂ށB���͖�1450�X�܂��ΏۂƂ݂Ă���B�v���ɉ������X�܂ɋ��͋����x������B�O�N�x���O�X�N�x��1��������̔��㍂����Z�肵�A1�������蒆����Ƃ�2��5000�~����7��5000�~�܂ŁA���Ƃ͍ő�20���~���x������B���̒n���n���Վ���t���������Ƃ�������Œ�������B���ԑO�ł��c�Ǝ��Ԃ�Z�k�����ꍇ�͌�t���A�x�Ƃ���ꍇ���ΏۂƂ���B
�S�R�s���ɂ�26������8��15���܂ŁA�s�v�s�}�̊O�o���l�����߂�B���s�ȊO�̌����ɂ͈��������A��{�I�Ȋ�����̓O��A�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̑ΏۂȂNJ����g��n��Ƃ̕s�v�s�}�̉������l�Ȃǂ��Ăъ|����B
�S�R�s�ł�7���ɓ���A�V�^�R���i�̃N���X�^�[(�����ҏW�c)��4�������B�l��10���l������̒���1�T��(17���`23��)�̐V�K�����Ґ���18�E38�l�ŁA���{�̕��ȉ�����X�e�[�W3(�����}��)�̎w�W�u15�l�v�������Ă���B�i���ݗ��s����24���A���x��Y�m���ɑ��v�������B
���x�m���͑��{������c�I����̋L�҉�ŁA��s������̊����g��̉e���ɉ����A�����͂̋����ψي��u�f���^���v�̉\���������u�k452�q�v�̊m�F�������ő������ł���_�܂��u�����g��𑁂����É������A�����h�~�ƒn��o�ς̈ێ��E�Đ��𗼗����������v�Ƒ�ւ̋��͂����߂��B
�����ł͌S�R�s�̑��A�쑊�n�s�ɂ����ނȂǂ������H�X�ɑ������c�Ǝ��Ԃ̒Z�k��8��1���܂ŗv�����Ă���B
���u���ƌ|�v�_���͋��E��Ŕ��i�c�R���i�ɐU��ꂽ�u����v�I�肽���@7/24
�����I�����s�b�N��24���ɓ��{�́u���ƌ|�v�_�����n�܂�A�j�q60�L�����̍������������A���q48�L�����̓n���앗�삪��ƁA2�̃��_�����l�������B
�_��������S���{�_���A��(�S�_�A)�́A�I�����s�b�N��1�N�����Ƃ������Ԃɒ��ʂ��A����I��̈����ɍł��ꗶ�������Z�c�̂̈���B
�V�^�R���i�E�C���X�����g�傪�[�������钼�O��2020�N2��27���A14�K���̂������肵�Ă���13�K���̑I��̂���I�ڋL�҉���s�����B�c��j�q66�L������4���̑S���{�I���̏d�ʑI�茠(����)�Ɉ������O�ƊێR��u�Y���o�ꂵ�A���ׂĂ̑I�肪���܂�͂��������B����3�����{�A�I�����s�b�N��1�N�����ɂȂ����B
�̏d�ʑI�茠�������ƂȂ�A����I����ǂ��������Ƃ����c�_���n�߂�����4���ɂ́A�S�_�A���ŐE�������X�ɃR���i�������Ď����ǂ��@�\�s�S�ƂȂ�A66�L�����̌���Ƒ�\����҂̈����͒��ɕ������`�ƂȂ����B
�����ψ���ł́u����ێ��v�h�Ɓu���蔒���v�h�Ƃ̋c�_���o�āA���_�͏o�Ȃ������B���Ԃ��������`�[�����[�N�̏�����A�X���[�g�̌o���l���d������邱�Ƃ����鋣�Z�Ƃ͐��i���قȂ�̂��A�l�̊i���Z���B���̎��_�ň�ԋ����I����\�ɁA�Ƃ����l���͐��_�ł��������B
���蔒���̉\�����r������Ȃ��ƒm�炳�ꂽ�I�肩��́A���痧���̐����o���B�j�q60�L�����œ��肵�Ă������������͓����A���g�̃c�C�b�^�[�ł����Ԃ₢�Ă����B
�u��\�I�l��蒼���Ƃ��Ȃ����痬�ɖ����B�P���Ɉ�x���܂����I��ƌ��߂��Ȃ������I�肪��������̂̓����^���ʂŃA���t�F�A�����B��ɓ����������̂��s���ɂȂ�̂͂��������v
����̃}���\���␅�j�ȂǑ��̎�v���Z�ł́A���������ɓ���I��̈ێ���ł��o�������A�_�������蔒������ނȂ��ƍl�����w�i�ɂ́A���̋��Z��������Ȏ���������B
�j�q�����߂Ēj�q�̐�����ڂƂȂ���1964�N�������ȗ��A�Q���������ׂẴI�����s�b�N�ċG���ŋ����_����ςݏグ�Ă������j������B�u���ƌ|�v�Ƃ̖��������܂Ƃ��A���ȊO�̓��_���ł͂Ȃ��ƌ��R�ƌ����镗�y������B
�S�_�A�́u�����V�X�e���Ɋւ�����K�v�ł́A���̍ŏ��́u�ړI�v�̍��ł���������Ă���B
�u�I�����s�b�N�Ɛ��E�I�茠�ŋ����_�����l�����邱�Ɓv�u�S�K���Ń��_���A���̓������̋����_�����l�����邱�Ɓv�u���{���\�������_�����l���ł���\���̂���I���I�l����v�Ƃɂ����u�����_���v�Ƃ������t�����ԁB
�ܗ֑�\�I��̑I�l��Ƃ��Ē���2�N�Ԃ̑��̐��т���e���|�C���g������A�I�l�����ƂȂ�B2020�N�ĂƂ����O���ꂽ���A����̈����̔��f�͓�������B
���ǁA�S�_�A��2020�N5���A�R���i�Ђő��J���Ȃ��Ȃǂ��������āA���łɌ��܂��Ă���13�K���̑I���ύX���Ȃ����Ƃ�����B�j�q66�L�����͓��N12���̌����ň������ێR��j���Č��������B
�u�����̎コ���Ō�ɏo���v�Ɨ܂��n����B�u�݂�ȂɎx���Ă���������ʂł��B�J�Â��Ă����������������ł��v�Ƌ����_���̍����B
�������Ԃ�҂��������I�肽���̃I�����s�b�N�������J�����B
���������A5���ԂŌv71�l�����@24����7�l�A�V�^�R���i�@7/24
��������24���A�V����7�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B���Z�n�͏o�_�A�_�염�s�e3�l�A�v�c�s1�l�B����5���Ԃ̊������\�͌v71�l�ƂȂ��Ă���B
�������Ǒɂ��ƁA�o�_�s��1�l�������A6�l�͂����������܂ł̊����҂ƐڐG������A�֘A�̌����Ŕ��������Ƃ����B�_��s��2�l�A�o�_�A�v�c���s�̊e1�l��1��ڂ̌����ʼnA�����������A���M�Ȃǂ̏Ǐo������2��ڂ̌����ŗz�����m�F���ꂽ�B
�����҂Ƃ̐ڐG���m�F����Ă��Ȃ��o�_�s��1�l�́A7���ȍ~�Ɋ����g��n��̌��O�ֈړ����Ă����Ƃ����B21����38�x��̔��M������A23���Ɉ�Ë@�ւ���f���ėz�������������B�S�����y�ǂŁA�s���葽���Ƃ̐ڐG�͂Ȃ��Ƃ����B
�����ł̊����m�F��12���A���ŁA7���̊������\�͌v109�l�ƂȂ����B24���ߑO10�����_�œ��@�҂�98�l�ŁA�m�ەa��(324��)�̎g�p����30�E2���ƂȂ��Ă���B�d�ǎ҂͂��Ȃ��B���͊����ɂ��āA�u�����ōL��I�ɔ������Ă��邪�A�ڐG�҂L���������Ċ����g������߂Ă���i�K�v�Ƃ��A��������������i�߂Ă����Ƃ��Ă���B
���ĂŃR���i�����g��Ăс@�ꕔ�B�Ń��N�`���ڎ�����@7/24
�č��ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������Ăъg�債�Ă���B�V�K�����ɐ�߂�C���h�^(�f���^�^)�̊�����8�����A17���A���Ŋ����҂��������B���N�`���ڎ킪�x���ꕔ�̏B�ł͊����g��Ɋ�@�������܂�A�ڎ�y�[�X���㏸���Ă���B
�ăW�����Y�E�z�v�L���X��̏W�v�ɂ��ƁA22���̐V�K�����Ґ��͖�5��5000�l�B�u���W����C���h�l�V�A�A�p�������萢�E�ő��������B7���ړ����ςł͖�4��4000�l�ƂȂ�17���A���ő��������B
�w�i�ɂ̓f���^�^�̋}���ȍL����ƁA���N�`���ڎ튄�����Ⴂ�n��ł̊����g�傪����B�Ď��a��Z���^�[(CDC)�̃������X�L�[�����̓f���^�^���u�M�����Ȃ��قǂ̑����ōL�����Ă���v�Ǝw�E����B�f���^�^��9������n�������Ƃ����B
�p�I�b�N�X�t�H�[�h��̌����҂炪����u�A���[�E���[���h�E�C���E�f�[�^�v�Ȃǂɂ��ƁA���Ȃ��Ƃ�1��ڎ�����l�̊����͑S�Ă�56%�B�ł��������Ⴂ�암�~�V�V�b�s�B(38%)���܂߁A�암�⒆�����Ȃǖ�30�B���S�ĕ��ς������B
�����g��͐ڎ킪�x���n��Ŗڗ��B�~�V�V�b�s�B��22���A�V�K�����Ґ�����1200�l��1�T�ԑO�ɔ��2�{�ɑ������B���e�L�T�X�B(50%)�⓯�A�[�J���\�[�B(45%)��2�{�A���A���o�}�B(42%)��6�����ƂȂ����B
�u���N�`�����ڎ�҂̊ԂŃp���f�~�b�N���N���Ă���v(�������X�L�[��)�Ƃ���������A�ꕔ�̏B�ł͐ڎ�y�[�X���㏸���Ă���B1���̐ڎ��(�l��100�l������)���݂�ƁA����܂ő��ΓI�ɒx��Ă����A�[�J���\�[�B��t�����_�B�A�~�Y�[���B�A�l�o�_�B�A�e�L�T�X�B�Ȃǂ��S�ĕ��ς�����n�߂��B
�S�Ăł݂�ƁA1��������̃��N�`���ڎ�ɉ����~�܂�̒������o�Ă���B22����7���ړ����ςŖ�53�������B7�����{����1��50�����̃y�[�X�������Ă���B
���N�`���ڎ�ɏ��ɓI�Ȓn��̑����͋��a�}�̒n�Ղɏd�Ȃ�B�����Ґ��̋}�����~�߂悤�ƁA���a�}�̎�c������ڎ���Ăт����Ă���B
�u���N�`���͖����~���Ă���v�B�t�����_�B�̃f�T���e�B�X�m����21���A���N�`���̌��ʂ�i�����B�B����95%�ȏ�̓��@���҂́u���S�ɐڎ���I���Ă��Ȃ����A���ڎ킾�v�Ƃ�������B������5���A�B���̊�Ƃ��ڋq�Ƀ��N�`���ؖ������߂邱�Ƃ��ւ���@�Ăɏ������Ă����B
�A�[�J���\�[�B�̃n�b�`���\���m�������N�`���̌��O�@���邽�߁A�B��������Đ�������J���B���a�}�̃}�R�l����@�@��������20���A�u�ł��邾�������ڎ�����Ăق����B�����łȂ���ΏH�ɂ͂܂���N�Ɍo�������悤�ȏ�Ԃɖ߂��Ă��܂��v�Ƒi�����B
���A�����J �Ăу}�X�N���p�`�����̓����u�f���^���v���}�g�� �@7/24
�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψق����V�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�Ă���A�����J�ł́A�e�n�ōĂсA�}�X�N�̒��p���`���������萄�������肷�铮�����o�Ă��܂��B
�A�����JCDC�����a��Z���^�[�ɂ��܂��ƁA�A�����J�ł́A�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�́u�f���^���v���}���Ɋg�債�A������̂��悻83�����߂�Ɛ��肳��Ă��܂��B
22���ɔ��\���ꂽ1���ɕ���銴���҂̐���7���ԕ��ς́A3��7674�l�ƁA�O�̏T�ɔ��52.5�������A���@�����l��3521�l��32.2���̑����ƂȂ��Ă��܂��B
�A�����J���{�̓��N�`���̐ڎ킪�ł��d�v�ȑƂ��Đڎ���Ăт����Ă��܂����A1��������̐ڎ�̓s�[�N���̂��悻8����1�ɂ܂Ō������A�ڎ헦�͐L�єY��ł��܂��B
�����������A�����J���t�H���j�A�B�̃��T���[���X�Ń��N�`����ڎ킵���l���܂߂������ł̃}�X�N���p���`���Â�����ȂǁA�lj��̊�����Ƃ��āA�ĂсA�}�X�N�̒��p���`����������A���������肷�铮�����������ł��܂��B
CDC�̃K�C�h���C���̓��N�`���̐ڎ���I�����l�͌����Ƃ��ă}�X�N�̒��p�͕K�v�Ȃ��Ƃ��Ă��܂����A�A�����J�̕����̃��f�B�A�̓o�C�f���������}�X�N���p�̐����ɂ��Č������n�߂��Ɠ`���Ă��܂��B
CDC�̃������X�L�[������22���̉�ŁA�����_�ŃK�C�h���C���̕ύX�͕K�v�Ȃ��Ƃ����l���������܂������A�ψكE�C���X���g�傷�钆�A�}�X�N�̒��p���߂���c�_�������ɂȂ��Ă��܂��B
�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψق����E�C���X�̃f���^���ւ̊������g�傷�钆�A�}�X�N�̒��p���Ăы`���Â��铮�����o�Ă��Ă��邱�Ƃɂ��āA���T���[���X����j���[���[�N��K��Ă���j���́u���������A���S��D�悵���ق��������Ǝv���̂ŁA���N�`����ڎ킵���l�ɂ��}�X�N�̒��p�����߂邱�Ƃɂ͎^���ł��v�Ɨ����������܂����B
�܂��A�A�C�I���B����ŋ߁A�j���[���[�N�Ɉڂ�Z�Ƃ����j���́u�f���^���̂��Ƃ͐S�z�ł��B���N�`���̐ڎ�͏I���܂������A�����ł͂��܂ł��}�X�N������悤�ɂ��Ă��܂��v�ƔO����ꂽ������Ă���Ƙb���Ă��܂����B
���؍��A�R���i�V�K������1629�l�c���s���ɂ��g��@7/24
�؍��̒����h�u���{����24��0������Ɉ���̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ���1629�l�A�v�����Ґ���18��7362�l�Ɩ��炩�ɂ����B
�O���̐V�K�����Ґ�(1630�l)�Ƃقړ����ŁA2���A����1600�l��ƂȂ����B����̐V�K�����Ґ���7��(1212�l)����18���A����1000�l���4�����B�V�K�����҂̊����o�H�͍���������1573�l�A�C�O����̓�����56�l�������B
��s���̊����g�傪�������A�ŋ߂͔��s���ł������҂������A�S���I�ȑ嗬�s�Ɍ������\�������܂��Ă���B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���ܗx���̋@�������A�����҂͌v6�l�Ɂc���p�̐��ʏ��E�g�C���Ŋ����� �@7/25
�x������25���A�����ܗցE�p�������s�b�N�̌x���Ŕh�����ꂽ���Ɍ��x�@������20�`30�Α�̒j������2�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B24���ɂ�4�l�̊������������Ă���A�����̊����҂͌v6�l�ƂȂ����B�ʂ̓�������3�l���ȈՌ����ŗz�����m�F����Ă���A����A��Ë@�ւŌ�������B
���\�ɂ��ƁA6�l�͂�����������s�{���s���̌x�@�{�݂̓����t���A�̌��ɏh�����A19����22���ɓs���̋��Z���Ōx���ɂ������Ă����B���p�̐��ʏ���g�C���Ŋ������L�������\��������Ƃ����B
�����W�҂ŐV����10�l�z���A�I���2�l�c�v132�l�� �@7/25
�����ܗցE�p�������s�b�N���g�D�ψ����25���A�{�[�g�̃I�����_�I��Ǝ��]�Ԃ̃h�C�c�I���2�l���܂߁A�V����10�l���V�^�R���i�E�C���X�����ŗz���Ɣ��肳�ꂽ�Ɣ��\�����B�g�D�ς�24���Ɍ��\�����A�X���[�g�̓G�N�A�h���̑I��ŁA�������Ɍ��\���Ă����Ƃ��ē����̗z������҂�16�l�ɏC�������B
�g�D�ς�7��1���ȍ~�Ɍ��\�������W�҂̗z���҂́A�v132�l�ƂȂ����B
���D�y�s 80�l���� 3���A��80�l�ȏ�@�N���X�^�[�g��@7/25
�D�y�s��7��25���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊�����80(�ق��ėz��2�l)�l���m�F�����Ɣ��\���܂����B
�����҂͔���\�܂�10�ォ��60���80�l(�ق��ėz��2�l)�B82�l�������O�T�̓��j������2�l�����ł����A3���A����80�l�ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B
�����͂������Ƃ����C���h�^�ψكE�C���X�E�f���^���́u�����^���v���V����14�l�m�F����܂����B
����ŎD�y�s���ł̃f���^���^���́A�v245�l(����8�l�m��)�ƂȂ�܂����B
1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A�u26.85�l�v�Ɓu�ً}���Ԑ錾�v�̖ڈ��ƂȂ�u25�l�v��5���A���ŏ���A�������Ă��܂��B
�g�p�a������7��24�����_�ł����ɑΉ��ł���543����151���Ŗ�28���Ɖ����ŁA�a�@�ȊO�̏h���×{�{�݂⎩��ҋ@�҂�24�����_�Ōv587�l�ƑO������33�l�����Ă��܂��B
�X�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�A������"��̊X"�֘A�͐V����1�X��3�l���m�F����A304�X��1148�l�ƂȂ�܂����B
80�l���A��������46�l�̊����o�H���s���ŁA�d�ǎ҂͑O���ƕς�炸3�l�ł��B
���{�́u�ً}���Ԑ錾�v�𓌋��s��4�x�ڂ̔��߁A���ꌧ���������A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{�́u�܂h�~���d�_�[�u�v�������B�k�C���A���m���A���s�{�A���Ɍ��A��������12���ɉ������܂����B
�k�C����12������8��22���܂ł��u�Ă̍Ċg��h�~���ʑ�v���ԂƂ���ƂƂ���20���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�����ɗv�����܂����B
�K�p��O��22������u�������X�N������ł��Ȃ��ꍇ�v�Ƃ����������O���A�D�y�s�́u�O�o���l�v��u�D�y�s�Ƃ̉������l�v�A�D�y�s�̈��H�X�ł́u���Z�v���v�p���A�����{�݂̌����x�قȂǓƎ��̑�Ɏ��g��ł��܂��B
������{�錧�m�����T�b�J�[�L�ϋq�ᔻ�ɖҔ��_�@7/25
����Í_�{�錧�m����25���A�t�W�e���r�n�u���j�@�s�g�d�@�o�q�h�l�d�v�ɐ��o���B�����ܗւ̖��ϋq�������釀�_�u���X�^���_�[�h�����������ᔻ�����B
�����ܗւ̊ϋq���ɂ��Ă͐V�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�Ă���Ƃ��āA�����̏��r�s�m����J�Òn�e���̒m�������O�ɖ��ϋq�ł̎��{�����肵���B����m���͂��̗���ɋ��������B�u�����ŗD�悷��͓̂��R�ł����A��Ԗ��Ȃ̂͑��̋��Z�Ɛ蕪���Ă��邱�Ɓv�Ɖs�����_��W�J�����B
����m�����w�E�����̂͗L�ϋq�ł̎����J�Â������v���싅�Ƃ̈Ⴂ���B�����ܗ֓��{��\�ł��鎘�W���p���ƍ������c�̋����������A�L�ϋq�ōs��ꑱ���Ă���B
���m���́u�{�錧��(�v���싅��)�I�[���X�^�[�Q�[��������܂���(7��17�����y�V����)�B���̒��S����1��5000�l�̐l���W�܂��āA���������������߂���ł���ˁB���������W���p���̋������������̒��S��(�y�V����)�ŁA���w����2�L���̋����ł���Ă���킯�ł��B������A���������߂�킯�ł���B1��5000�l�W�߂āv�Ɛ����B�����āu����͂�������ǂ��A(�ܗւ̃T�b�J�[���Z��)��䂩�痣�ꂽ���{�Ƃ����ꏊ�ōs����B5���l�̃X�^�W�A����3000�l�Ƃ�5000�l��������Ȃ��B�����͈��܂Ȃ��B(����ł�)�w����͂��߂��x�Ƃ����咣�������ƁA���͂ƂĂ��[���ł��Ȃ��v�Ƃ����ς茾�������B
���̏�Łu�I�����s�b�N���y���݂ɂ��Ă�������A�싅���y���݂ɂ��Ă�����������Ή��������ׂ��B���͐����^��������Ă���悤�Ɍ������A�R�A�œ����Ă�����������v�Ǝ�Î҂̓����s��g�D�ρA���{���ÂɎw���ċ���������������B
�{�錧�ł͓����E���{���̋{��X�^�W�A���œ����ܗւ̃T�b�J�[���Z���L�ϋq�ŊJ�����Ă���B���m����e��t��͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g��������Ƃ��Ė��ϋq��v�]�������A����m���̓u�����ɗL�ϋq�ł̎��{�f�B�^�ۗ��_�������N�����Ă����B
���u�������v�J�n���ʂ����@�������A�R���i�����Ċg��ʼn����@7/25
���x��Y�m����24���̗Վ��L�҉�ŁA�����������̗��ق�z�e���ɏh������ۂ̔�p��⏕����u�������v���X�v�ɂ��āA�J�n���������ʂ��Ȃ��Ƃ̔F�����������B
���͓����A����14���ɃX�^�[�g������j���������A�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ċg��ɔ����ĉ��������߂��B�쑊�n�s�ɉ�����24���ɂ͌S�R�s�ł̏W����̎��{�����߂��ق��A�f���^���������Ŋg�債����A���x�m���́u�������������v���͂��邪�w���A������x�Ƃ͌����Â炢���v�Əq�ׂ��B
�����C�告��17�l�R���i�����ŏo�ꎫ�ށc�b�q���t�ĘA�e�������@7/25
��103��S�����Z�싅�I�茠(8��9������17���ԁA�b�q��)�̒n������24���A27����86�������s��ꂽ�B���t�̃Z���o�c�ŗD���������C�告�͂͏o��o�^�����o�[17�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��A�_�ސ���ւ̏o������ނ����B���̓��\�肳��Ă��������ė˂Ƃ̏��X�����͕s��s�ƂȂ�A���Č���őޔC�����n�h���ē�(51)�͎v��ʌ`�Ń��j�z�[����E�����ƂɂȂ����B25����25����65�������s����B
�v��ʌ`�ŁA�j��8�Z�ڂ̍b�q���t�ĘA�e�̖����j�ꂽ�B�o��o�^�����o�[20�l���A17�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����B���O�̏o�ꎫ�ނƂȂ�����n�ḗu���̂��т͖{�Z�싅���ŐV�^�R���i�E�C���X�����ɂ�鑽���̗z���҂������Ă��܂��܂������Ƃ�[������ѐ\���グ�܂��v�ƎӍ߂����B
�w�Z�ɂ��ƁA21���Ƀx���`���肷�闾��1�l�����M�ɂ��̒��s�ǂ�i���A�a�@�ł́u�M���ǂ̋^���v�Ɛf�f���ꂽ�B����ɖ߂�����APCR��������f�B���䓡��Ƃ�5���ɏ�����22���̗[���Ɋ������m�F���ꂽ�B23���ɗ���36�l��PCR�������A�������21�l�̗z�����m�F���ꂽ�B�w����1�l���܂ށA�v22�l�̏W�c�������A���̓��\�肳��Ă��������ė˂Ƃ̏��X���������ށB��N���犴�����O�ꂵ�Ă��Ă��A����鎖�Ԃ͋N���Ă��܂����B
�Z���o�c�ł́A���H�h���t�g���ɋ�����G�[�X���r�̐Γc���s(3�N)�𒆐S��10�N�Ԃ�̗D�����������B���Ă̐_�ސ���ł�8�����肵�A19�N�t���瑱�������A���L�^��45�ɐL���Ă����B�t�č��킹��4�x�̓��{��ɓ����A���Č���ł̑ޔC��\�����Ă�����n�ē͌����Ȃ��G�Ɂu�Ō�̉āv��ˑR�D��ꂽ�`���B
�����ł�����݂���Ȃ�����B��n�ḗu�NJ��̑��͌��s�ی����ƘA�������Ȃ���A�ŗD��Ő��k�ւ̑Ή����s���Ă���܂��B���N��Ԃ�c�����Ȃ���������A����Ȃ銴���g���h�����ƂɑS�͂𒍂��ł���܂��v�Ƙb�����B�R���i�����ɂ�鎫�ނ��������ł���A���{����A�����c�p�����̕����ŁA�s���{������A�Ɋ����h�~��̓O���v�������B
��RS�E�C���X�����ǁ@�X�����ŗ��s�^7����{�̜늳�ҁA�ߋ��ő��@7/25
���c���ɔx�����N�������Ƃ�����RS�E�C���X�����ǂ��X���ł����s���Ă���B7����{�̜늳(�肩��)�҂͌������v�����n�߂�2004�N�ȗ��A���̎����Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ����B��ÊW�҂͔w�i�Ƃ��āA�V�^�R���i�E�C���X�����h�~�̂��ߎ�w���łȂǂ̑O�ꂳ�ꂽ���߁ARS�E�C���X�̊����҂�����A�Ɖu�������Ă��Ȃ��q�ǂ����������B�ۈ珊�ȂǂɃE�C���X������Ɗ������g�傷��|�ƕ��͂��Ă���B
RS�E�C���X��2����܂łɂقƂ�ǂ̐l����������B�����͂����┭�M�ȂǕ��ׂ̂悤�ȏǏo��B���U�ɂ킽���Ċ������J��Ԃ����A���X�ɖƉu�����A�������ɂ����Ȃ�B���N�͑S���I�ɗ��s���Ă���B
���N�Ă���H�ɂ����đ����n�߂邪�A���̎����ɂ��ƍ��N��3�A4�����납�瑝���B������42�J�������_��Ë@�ւ������銴���Ґ��͒��߂̑�27�T(7��5�`11��)�ŁA1��Ë@�֓����蕽��1.05�l�ƂȂ�A20�N��0.0�l�A19�N��0.14�l�A18�N��0.62�l��傫������ߋ��ő��ƂȂ����B���̑O�T(6��28���`7��4��)��1��Ë@�֓�����2.10�l�Ɖߋ��ő��������B
�O�O�s�́u���炢���ǂ��N���j�b�N�v�ł�4�������납�犴���҂��ڗ����n�߁A5���A�x�ォ��͋}���ɑ������B5�A6���ɓ��N���b�N�̕a���ۈ�ŗa�������q�ǂ�100�`120�l�̂����A��8����RS�E�C���X�������B7���ɂȂ��Ă�◎�������Ă����Ƃ����B
�r��G���@���́A���N�̗��s�̌����Ƃ��āA�V�^�R���i�����g��̉e�����w�E����B�s���������w���ŁA�}�X�N���p�Ȃǂ̊�����ɂ���āA��N�͂قƂ��RS�E�C���X�Ɋ�������q�ǂ������Ȃ������B�W�c�Ɖu���ቺ�������߁A���N�ɂȂ��Ĕ����I�ɗ��s�����|�Ɛ����B�u�Ԃ����������ƌċz��Q���N����ȂNJ댯�Ȃ��Ƃ�����B�Ƒ��ɕ��Ǐ�̐l������A���߂ɂ�����������f���Ăق����v�Ƙb�����B
RS�E�C���X�́A��ɔ�(�Ђ܂�)��ڐG�ɂ���Ċ������A���Ƃ��ďd�lj�����Ɠ��c���̓ˑR���̗U���ƂȂ邱�Ƃ�����B�\�h�ɂ͎�₤�����A�u�����G�`�P�b�g�v�̓O��A�l���݂ւ̊O�o������邱�Ƃ��厖�Ƃ����B
���������o���̂����ĂȂ��Ń��N�`���O�|���v�����t�@�C�U�[�̓X���[�@7/25
���`�͓̎����I�����s�b�N�̊J�(7��23��)�ɂ��킹�ė�������10���鍑��@�ցA��Ƃ̃g�b�v��Ɖ�k���A3���Ԃ̃}���\���O�����I�����B
���ł������E���ԍ�̌}�o�قɏ����Ƃ������o���̂����ĂȂ��Ō}�����̂́A�V�^�R���i�E�C���X���N�`���𐢊E�ɋ�������Đ�����t�@�C�U�[�̃u�[��CEO���B
�u�[������IOC(���ۃI�����s�b�N�ψ���)�Ƀ��N�`�����������ƂȂǂ���A�J��ɏo�ȁB����23���ߑO�A�͖쑾�Y���N�`���S���������Ȃ�����ŁA10���ȍ~�ɗ\�肵�Ă��鋟�����̑O�|����v�������Ƃ����B���̉�k�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��B���{�W�҂������������B
�u���@�ł͂Ȃ��}�o�قŐH�������Ȃ���̂����ĂȂ���k�ŁA���o���̈����ł����B���@����k�O���琷��Ƀ��f�B�A�ɉ�k�ɂ��Đ������Ă����̂Łw���N�`���O�|��������v���x�̃j���[�X����Ăɕ��܂������A�����́w�I��c�ɑ���4���l���̃��N�`�������x���x�ɑ������̌��Ɨ�̕s�тȁw���S���S�ȑ��ւ̌��Ӂx���q�ׂ����Ƃ��A���C���ł����B���{�̃R���i�����Ȃǂ̃��N���u�[�����ɂ��Ă��܂����v
�ł́A�̐S�́u���N�`�������O�|���v�̌��ʂ͂ǂ��Ȃ����̂��H
�u�����猾�y�͂������̂́A�w�������������S���ғ��m�Łx�ƌy���������ꂽ�ƕ����Ă��܂��B���A�͖��b��2�l������Ńu�[�����ƌ����A��������Ă���̂��A�Ǝ��]�̐������@����o�Ă��܂��B�t�@�C�U�[�ɑ������݂��Ă���Ƃ������Ƃł��傤�v(���O)
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪���܂炸�A���N�`���������ꕔ�̎����O�ő钆�A���{�⎩���}���ł́u����������}�̂������v�Ƃ��������������ł���B
�����������ɔ���������������}�́A����Twitter�Łu���N�`���x�ꂽ�͖̂�}�̂����H�v�Ƃ���QA���̃c�C�[�g��7��16���ɘA�����A�u�Ⴂ�܂��B���{�̐ӔC�ł��v�ȂǂƎ��_��W�J�����B
�����A��}�͂���܂ō���ʼn������Ă����̂��ɂ��Ă͉��߂Č����Ă݂�K�v������B
AERAdot.�Łu���͐�ƂɊԈႢ�Ȃ����A�����A���Y�}���|���R�c�߂������N�`������v(6��17���t)�ƕ��Ƃ���A�����⋤�Y�}�����N�`���̍��������ɂ������A���Ċe���ōs���Ă������N�`���ً̋}�g�p�ɖҔ��������Ƃ��ڎ�̒x��ɂȂ����Ă��邱�Ƃ͊��ɒm���Ă���Ƃ��낾�B
�u���N�`�����͔���\�Ȃ̂ł���܂ŕ��Ă��܂��A���͗�������}�����c���̌y���ȍ���ł̌������t�@�C�U�[�̓{����A���N�`�������̒x��Ɉ�����Ƃ����d������������̂ł��v(���@���ӎ�)
���ƂȂ����̂́A��������}�E�M�ؓ��`�O�@�c�������N2��12���̏O�c�@�\�Z�ψ���ł̈ȉ��̔������Ƃ����B
�u���N�`���m�ۂ������ɉ���Ă��Ă��Ȃ����Ǝw�E�����钆�ŁA���͂��ЁA3�ЈȊO�Ń��V�A�����N�`���A���������N�`�����܂߂Ċm�ۂɓw�߂�ׂ��v
�����A���{�̓t�@�C�U�[�Ƌ����ʂ⎞��������M���M���̌���삯�������s���Ă����Ƃ����B
�u���̍������m�����t�@�C�U�[�����͌��{�B�w��X�̃��N�`���͐��E�����߂Ă�����̂��B���{�ȊO�ɋ��߂Ă���Ƃ���͂�����ł�����x�w����Ƃ��������̏�ŁA������V�A���狟������ȂǂƂ����c�_���Ȃ���Ă���̂ł���A���{�̑ԓx�͗��������x�Ƃ��đԓx���d�����Ă��܂����̂ł��B���������w�������A�����̒x��Ɍq�������Ƃ����o�܂�����܂��v(���O)
���ɂ��M�؏O�@�c������Ă����Ƃ���ɒ�������V�A�����N�`�����m�ۂł����Ƃ��āA���ʂ͏o�����́A�r�����������낤�B���������N�`���̓f���^���ɂ͗L�������ቺ����Ƃ���A�܂����V�A�����N�`����EU�ł��܂����F����Ă��Ȃ���Ԃ��B���Ɋm�ۂ��Ă����{�����ł͂قƂ�NJ��p�ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B���ǁA��}�̍����Ă����N�`���m�ۂ̑���傢�Ɉ������邱�ƂƂȂ����Ƃ����̂��B
����ɗ�������}�������s�̐�����j�O�@�c����21���A���g�̃c�C�b�^�[�Ɂu�É����J��Łw���̒��~�x��錾����邵���A�ő��~�߂�藧�Ă͖����v�Ɠ��e�B�u�V�c�̐������p�v�Ƃ����ᔻ���������A���e�͂��̌�A�폜���ꂽ�B
�u���{�����{�����A�����̍���c���̌������y������v(��}�̏O�@�c��)
�u��Ɓv�͂��������A�N�Ȃ̂��A��Âɓǂ݉������Ƃ��K�v���낤�B�@�@
�ܗ֊J�Ì���A���A�I�葺�Ȃǂ��犴���҂��o�Ă���A�����s���̊����҂�1000�l�����������Ă���B
���g�D�ψ���Ŋ����Ǒ�ɂ�������Ƃ̉~���c�ō����߂鉪���M�F�E���s���N���S���������́A�����V���̎�ނɑ��A�u�V�^�R���i�E�C���X�������g�債�A�w��4�g�x�Ɍ�����ꂽ�ۂ̑��{�̂悤�ɁA�����s�œ��@���ׂ��l�����@�ł��Ȃ��悤�ȏɂȂ�������̒��~���l����ׂ����v�ȂǂƑi���Ă���B
�����̂����Ń��N�`���Ƃ����u�Q�[���`�F���W���[�v�̊m�ۂ����r���[�Ȃ܂܁A����ȏ�A�������|�M����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�F����肾�B
�������̐l�o �ܗ֑O��œ����͌�������Ԃ͑����@7/25
4�A�x3���ڂ�24���A�����E�a�J�Ȃǂ̐l�o�̓I�����s�b�N�J��O��1�T�ԑO�Ɣ�ׂē����͌�����������ŁA��Ԃ͑������܂����B
�m�g�j�͂h�s�֘A��Ƃ́u�`���������v�����p�҂̋��Čl�����肳��Ȃ��`�ŏW�߂��g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^���g���A��Ȓn�_�̐l�̐��ׂ܂����B
�����������Ԃ͓������ߑO6������ߌ�6���܂ŁA��Ԃ��ߌ�6�����痂���̌ߑO0���܂łł��B
�܂��A4��ڂً̋}���Ԑ錾���o�Ă��铌����24���̐l�o���A3��ڂ̐錾�̊��Ԃ�����4��25������挎20���܂ł̓y���A�j���̕��ςƔ�r���Ă݂�ƁA�a�J�X�N�����u�������_�t�߂ł͓�����48���A��Ԃ�62�����ꂼ�ꑝ�����܂����B
�����w�t�߂ł͓�����7�������A��Ԃ�18���������܂����B
�܂��A�I�����s�b�N���n�܂�O��1�T�ԑO�Ƃ̔�r�ł́A�a�J�X�N�����u�������_�t�߂ł͓�����1���̌����A��Ԃ�11���̑����A�����w�t�߂ł͓�����13���̌����A��Ԃ�7���̑����ƂȂ�A���������Ԃ��������܂����B
�܂h�~���d�_�[�u����������Ă����ʁA��t�A�_�ސ�A���ł�1�T�ԑO�Ɣ�ׂđ�{�w�t�߂œ�����5���A��Ԃ�11�����ꂼ�ꑝ����������A��t�w�t�߂œ�����25���A��Ԃ�6�����ꂼ�ꌸ�������ق��A���l�w�t�߂œ�����25���A��Ԃ�18�����ꂼ�ꌸ���A���~�c�w�t�߂œ�����7���A��Ԃ�2�����ꂼ�ꌸ�����܂����B
�ً}���Ԑ錾����������Ă��鉫��ł�1�T�ԑO�Ɣ�ׂēߔe�s�̌����O�w�t�߂œ�����31���̑����A��Ԃ�26���̑����ł����B
�������s�� �V�^�R���i1763�l���� �s���ɑ����̊����҂���@7/25
�����s���ł�25���A�V����1763�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A1�T�ԑO�̓��j�����755�l�����A���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B�s�̒S���҂́u���ˏオ���Ă��āA4�A�x�̍ŏI���ɂ��ꂾ���̐������ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�s���ɂ��Ȃ葽���̊����҂�������v�Ƌ�����@���������A�s�v�s�}�̊O�o��s�⌧���܂����ړ������l����ȂǁA�l�Ɛl�Ƃ̐ڐG������ė~�����Ɖ��߂ČĂт����Ă��܂��B
�����s��25���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��1763�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B
1�T�ԑO�̓��j�����755�l�����A���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B1���̊����m�F��1000�l����̂͂����6���A���ł��B�܂�25���܂ł�7���ԕ��ς�1453.6�l�ŁA�O�̏T��136.1���ƂȂ�A�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B
�s�̒S���҂́u�ʏ�A�A�x�̂Ƃ��͋x�f���Ă����Ë@�ւ��������߁A�����҂������Ă������A���傤�͒��ˏオ���Ă���B�����͂������f���^���ւ̒u������肪�e�����Ă���v�ƕ��͂��Ă��܂��B���̂����Łu4�A�x�̍ŏI���ɂ��ꂾ���̐������ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�s���ɂ��Ȃ葽���̊����҂�������v�Ƌ�����@���������A�����ً}���Ԑ錾�������Ă���Ƃ��āA�s�v�s�}�̊O�o��s�⌧���܂����ړ������l����ȂǁA�l�Ɛl�Ƃ̐ڐG������ė~�����Ɖ��߂ČĂт����Ă��܂��B
25����1763�l�̔N��ʂ�10�Ζ�����82�l�A10�オ166�l�A20�オ574�l�A30�オ368�l�A40�オ305�l�A50�オ183�l�A60�オ49�l�A70�オ20�l�A80�オ12�l�A90�オ3�l�A100�Έȏオ1�l�ł��B�����o�H���킩���Ă���664�l�̓���́u�ƒ���v���ł�����387�l�A�u�E����v��93�l�A�u�{�ݓ��v��66�l�u��H�v��25�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�����I�����s�b�N�֘A�ł͊O���l�̋��Z�W��3�l�A�O���l�̑I��2�l�A���{�l�̋��Z�W��1�l�A���{�l�̈ϑ��Ǝ�1�l�̂��킹��7�l�̊������m�F����܂����B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂�19��9291�l�ɂȂ�܂����B
����A25�����_�œ��@���Ă���l��24�����6�l������2632�l�Łu���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��44.1���ł��B�s�̊�ŏW�v����25�����_�̏d�ǂ̊��҂�24�����2�l������72�l�ŁA�d�NJ��җp�̕a����18.4�����g�p���Ă��܂��B�܂�25���A���S���m�F���ꂽ�l�͂��܂���ł����B
��4�A�x�ŏI���A�����s�S�ɐl�o�@���������g��A�s���ɕs�����@7/25
4�A�x�̍ŏI���ƂȂ���25���A�����̔ɉ؊X��ό��n�͐V�^�R���i�ً̋}���Ԑ錾���ɂ�������炸�A�����̐l�łɂ�������B�����ܗւ̈���A�s���R�Ȑ�������������s������͕s���̐����B�����g��������A�s���̐V���Ȋ����҂͓��j���ʼnߋ��ő���1763�l�B�S���ł�5��l�����B���r�S���q�m���́u����ʼnƑ��ƁA���l���ŔM��������I��ɑ����Ăق����v�ƁA�l�o�̗}���ɋ��͂��Ăъ|�����B
�ܗւ̃��C���X�^�W�A���ƂȂ鍑�����Z����ӂ��Ƒ�4�l�ŎU��������̎��c�Ƃ̒j��(31)�́u���͂ƌܗւ̘b��ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ����A�����܂Ő���オ���Ă��镵�͋C�͂Ȃ��ˁv�Ƌ���B
���k�C��111�l���� �V�^�R���i�����Ċg�呱�� 22���A���u�O�T�v����@7/25
�k�C�����ł�7��25���A111�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��m�F����܂����B�ˑR�A�����g��X���������Ă��܂��B
�k�C������7��25���A�������m�F���ꂽ�͎̂D�y�s��80�l�A����s��9�l�ȂǍ��킹��111�l�ł��B
�����͂������Ƃ����C���h�^�ψكE�C���X�A�f���^���Ɋ��������^�������銳�҂͎D�y�s��14�l�A����s��7�l�m�F����Ă��āA�����g��̈���ƂȂ��Ă��܂��B
�k�C�����ł�7��4���ȍ~�A22���A���őO�̏T�̓����j��������V�K�����҂��m�F����Ă��āA�k�C���ł͉ċx�݂₨�~���Ԃ�8��22���܂ŁA�D�y�s�ŕs�v�s�}�̊O�o���l��v������ȂǁA�����g��h�~�ɋ��͂����߂Ă��܂��B
�����r�s�m���Ɛ��� �g�����h���Љ�� ��������������h �@7/25
�����s�̏��r�m���͐�������b�Ɖ�k���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g���h���Ȃ���Љ�������߂���悤�A���������̍������i�߂Ă������Ƃ��m�F���܂����B
���r�m����25���ߌ�A������b���@��K��āA���悻1���ԁA��������b�Ɖ�k���A�V�^�R���i�E�C���X��Ȃǂɂ��Ĉӌ������킵�܂����B
��k�̂��ƁA���r�m���͓s���ŋL�Ғc�ɑ��u���������̍�����̓W�J���K�v�Ȃ̂ŁA�����̊g���h���Ȃ���Љ�������߂��������ŁA���܂��܍H�v���Ȃ���i�߂Ă������Ə������ƈӌ������������v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁA���r�m���́A���N�`���ڎ킪�i�ݍ���҂̏d�lj��⎀�S�Ⴊ�����Ă���Ƃ��āu���̊����҂͎Ⴂ���オ���|�I�ɑ����B��Î������������邱�ƂȂ��A�����������X�̌��N�����i�߂Ă����v�Əq�ׁA�Ⴂ����ւ̑���[��������l���𐛑�����b�ɓ`�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
����A25���̉�k�ł͓����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��Ă��b��ɏ�����Ƃ������ƂŁA���r�m���́u�I�����s�b�N�̊J�Â����ɃX���[�Y�ɂ����Ă���A�p�������s�b�N�Ɍ����Ă��~���ȉ^�c�ɂȂ�悤�ɂ��Ă������Ƌ��ʂ̔F�����m�F�����v�Əq�ׂ܂����B
���j�̏��q400���[�g���l���h���[�ő勴�I�ˑI�肪�A�X�P�[�g�{�[�h�̒j�q�X�g���[�g�Ŗx�ėY�l�I�肪�A���ꂼ������_�����l���������Ƃɂ��āA�����s�̏��r�m���͋L�Ғc�ɑ��u��ς��ꂵ���v���B���ꂩ����F����ɂ͎���ʼnƑ��Ə��l���ŁA���ДM��������I��ɑ����Ă������������v�Əq�ׂ܂����B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�����Z�v���Ȃǂ̋��͋� �x�����Ԃ��t�]�� �g��n���h�œ����s �@7/26
�����s�͍��ً̋}���Ԑ錾�ɔ������Z�v���Ȃǂ̋��͋����ꕔ���T�����n���������A�ȑO�̗v�����̒��ɂ͐\���t�����n�܂��Ă��Ȃ����̂�����A�x���̏��Ԃ��t�]���邱�ƂɂȂ�܂��B
�����s�́A����12������ً̋}���Ԑ錾�̂��ƂŎ��Z�c�ƂȂǂ��s�������H�X�ւ̋��͋����A�ꕔ���T�����n�����܂��B
�s�̗v���ɑS�ʓI�ɉ����邱�Ƃ��ꍇ�A�v���̊��Ԓ��ɐ�Ɏx������d�g�݂ł��B���瓱������A��T�t�����n�܂�܂����B
����ŁA�挎21�����獡��11���܂ł̂܂h�~���d�_�[�u�ɔ����v�����ɂ��Ă͎t���J�n�������܂����܂��Ă��܂���B
�܂��A������O�̂��Ƃ�5��12������6��20���܂ł�3��ڂ̐錾�ɔ����v�����̐\����26���ߌォ��t�����n�܂�܂��B���̌��ʁA�v���̎����Ǝx���̏��Ԃ��t�]���邱�ƂɂȂ�܂��B
�s�́u������n���𑬂₩�ɍs���悤���߂Ă��邽�߁A���̎葱����D�悵�Ă���B�Ԑ�������ɋ������A����܂ł̗v�������Ȃ�ׂ������x���ł���悤��Ƃ��}���ƂƂ��ɁA���Ǝ҂��������Ȃ��悤���J�ɐ����������v�Ƃ��Ă��܂��B
���s���挩���Ȃ��V�^�R���i�g�o���헪�h ���Ƃ���@���@7/26
���Ɏn�܂��������ܗցE�p�������s�b�N�B�����𒆐S��10���l�߂��I��A���W�ҁA���f�B�A�W�҂Ȃǂ��W�����钆�A�ˑR�Ƃ��ē����s�̐V�K�����҂�1��1000�l�������Ă���B
Twitter�A�J�E���g�u���~�}��Taka�v�Ƃ��Ă��m����A�V�^�R���i���N�`���������^�X�N�t�H�[�X(CoV-Navi)����\�ň�t�E�؉����O���́u�ً}���Ԑ錾�̎����������̂����������Ă���v�Ɗ�@���������B
�u�ً}���Ԑ錾���ł��A�l���������Ă��Ȃ��B���A�����s��1���̐V�K�����Ґ���1000�l���Ă��邪�A���̐����ɐ��_�����܂蔽�����Ă��Ȃ����B��N12��31���ɁA���߂ē����̊����Ґ���1000�l�����B�����ł悤�₭�w������ƃ��o���x�Ƃ�����C�����o�āA2�T�Ԍギ�炢�Ɋ������������Ă������B������l����Ƃ����V�K�����҂�1000�l�Ƃ������x���ł́A���o����Ⴢ��Ă��āA3000�l�����Ƃ���Łw���o���x�Ƃ�����C���o�n�߂�̂ł͂Ȃ����B�������犴���Ґ���������n�߂闬����l����ƁA�{����1��5000�l�����A6000�l�����܂ł����Ǝv���v
�C�M���X�ł́A�V���ȕψكE�C���X�ɑΉ�����ׂ��A9�����獂��҂��Ï]���҂Ȃǂ�Ώۂ�3��ڂ̃��N�`���ڎ���n�܂�\�肾�B����A���{�ł�3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�K�v�ɂȂ��Ă���̂��낤���B�؉����́u�ŏ�1�N���炢�́w3��ڂ͗v��Ȃ��x�Ǝv���Ă����v�Əq�ׂ�B
�u�l���v��Ȃ��Ǝv���Ă����̂́A�������������B(���N�`����)�R�̉��̐��ڂ����Ă���ƌ����͂��Ă������A���N�ł����Ȃ荂�����l��ۂ��Ă��āA1�N���炢�͂��������h��͂��c��Ƃ������ʂ��o�Ă����B�������A���Ȃ苭���`���͂����f���^�^���o�Ă����B�������A�Ɖu�����ƌ����āA���N�`���������ɂ����Ȃ��Ă������Ƃ��킩�����B�C�M���X�ł́A�f���^�^�ɑ��Ă�90���߂��L������������Ă��邪�A�C�X���G���ł́A64���������v
�u���̍��͉����Ƃ����ƁA�C�X���G���͑������烏�N�`����ł��n�߂Ă���̂ŁA�R�̉����������Ă��Ă���B�������Ԃ��o���Ă���ƃf���^�^�ɑ���L�����͂��ꂮ�炢�ɂȂ��Ă��܂��B��������ƁA������3��ڂ̃��N�`���ڎ킪�K�v�ɂȂ�\�����o�Ă���v
�����Ńl�b�g�f���w2�����˂�x�n�ݎ҂̂Ђ�䂫���́u3��ڂ̃u�[�X�^�[(���N�`��)�̓f���^�^�p�ɂȂ�̂��H�v�Ǝ���B�؉����́u����͐����ǂ߂Ȃ��v�Ƃ����A�u���������x�[�^�^�p�̃��N�`������낤�ƁA�����܂ł���Ă����B�������A���x�[�^�^�͗��s���Ă��Ȃ��B�J�����Ă����ɑł̂ł���A�f���^�^�p�̃��N�`�������Ƃ����b�ɂȂ��Ă���v�Ɩ��������B
����ɁA�؉����̉����Ђ�䂫���́u�H�Ƀf���^�^�p�̃��N�`�����ł��Ă��A���łɕʂ̕ψٌ^�����s���Ă���\��������Ƃ������Ƃ��H�v�Ɗm�F�B�؉����́u���̉\��������v�Ƃ�����ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊���������R��(ADE)�Ɍ��y����B
�u���A�f���^�^��p�̃��N�`�����o�������铮�������邪�A����͐T�d�ɂȂ�ׂ����Ǝv���B����܂łƏ����Ⴄ���N�`���Ȃ̂ŁA�Ⴆ�AADE�Ƃ����āA�R�̈ˑ���(����)�����̌��ۂ��ے�ł��Ȃ��B����̓��N�`����ł��ƂŒ��a�R�̂Ƃ����A�o���̈����R�̂��ł��Ă��܂��āA�]�v�ɃR���i���d�lj������Ă��܂��B�f���O�M�ŋN�����悤�ȕ��������o�Ă���\���̓[���ł͂Ȃ��v
�u�ł��Ď����𒆓r���[�ɂ��ăS�[�T�C�����o���Ă��܂��ƁA��ɂ������ؕԂ���H�炤�B���̂�����̃o�����X�͂��Ȃ����B��͂���̎�������������Ƃɏo�����ق��������B��������Ǝ��Ԃ�������A���̊Ԃɂ܂��Ⴄ�ψٌ^���o�Ă��邱�Ƃ��N���蓾����v
�C�O�ɖڂ�������ƁA�C�M���X�ł̓}�X�N���p�`������H�X�̐l�������ȂǁA�����̋K�������łɓP�p����Ă���B���{�ł��A26�����烏�N�`���p�X�|�[�g�̐\����t���J�n���ꂽ���A��Ƃ��ǂ̂悤�Ɏg�����A���j�͌��܂��Ă��Ȃ��B
�؉����́u���{�ł̓��N�`�����Δh������B���Ƃ��Ă͎w�����ɂ������낤�B�����͌����Ă��o�ς��ĊJ���Ȃ��ƃ��o���̂ŁA�X�̊�Ƃ�c�́A���H�X�A�C�x���g�J�Î҂Ȃǂ���w���N�`����ڎ킵���ؖ���������������Ă�����x�ƁA���Ԃ�����I�ɓƎ����[�����o���\������ԍ����Ǝv���v�ƃR�����g�B
�؉����̌��������Ђ�䂫���́u���N�`���ڎ���������ǂ������Ԃ��m�F�����i�́A���{����Ȃ��ƍ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƌ^����ׂ�B
�u�t�����X�̏ꍇ�A���N�`���p�X�|�[�g�͍��������A�v���ŁA�w���QR�R�[�h���X�}�[�g�t�H���œǂݍ��߂��l���w���N�`����ł����l�x�������́w48���Ԉȓ��ɉA���ؖ�����������l�x���B���ꂪ�A���X�g�����ȂǂŁw�H�������Ă�������x�Ƃ����ؖ��ɂȂ�B�����哱���Ȃ�����A�����������`�̃`�F�b�N�͂ł��Ȃ��Ǝv���v
���N�`���ڎ킪�i�ޒ��A�c�_����n�߂��V�^�R���i�̏o���헪�B�����̍Ċg���}���o�ς������邽�߂ɂ��A�������m�����L�߁A�����ɕ��j�������K�v�����肻�����B
�������g��̌X���u5���A�x��̃p�^�[���ƈꏏ�v�@�����209�l�@7/26
���ꌧ��25���A�V����10�Ζ����`90��̒j��209�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B6��5���ȗ��A��1�J�����Ԃ�Ɋ����҂�200�l�����B��T�̓��j���Ɣ�ׂ��139�l�����A��3�{�ƂȂ����B�V�K�����҂��O�T�̓����j��������̂�13���A���B�V����3�l�̎��S���m�F����A�v���S�҂�231�l�ɂȂ����B
�V�K������209�l��N��ʂɌ���ƁA20��46�l�A30��43�l�A10��35�l�Ɠ��ɎႢ����𒆐S�Ɋ������L�����Ă���B�����g��̌X���ɂ��āA���̎�������ËZ�Ắu5���̑�^�A�x�����ɁA�Ⴂ����Ŋ������L�������p�^�[���ƈꏏ�v�Ɨގ��_���w�E�B����̌��ʂ��ɂ��Ắu(������)�R�̍����͑z��ł��Ȃ��B�R���������Ȃ��悤�A���������������݂����v�Ƃ����B
�܂�������ËZ�ẮA�����Ŋ����҂��}�����Ă���܂��u�z���ƂȂ����ۂ̗×{��͈�t�̎w���Ō��肵�Ă���A�K��������]����a�@�ɓ���Ȃ��ꍇ������v�Ƌ����B�u�w�Ƃ���߂��a�@���x�w���̕a�@�͌����x�ȂǁA��]��S�������͍̂���v�Ɨ��������߂��B
���S����3�l�́A����s��80�㏗���Ɠߔe�s��90��j���B�c��1�l�̋��Z�n��N�㐫�ʂ͉Ƒ��̈ӌ��Ŕ���\�������B
�����o�H���ǂ����̂�93�l�ʼnƑ�����52�l�ƍő��B����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����҂�53�E47�l�őS��2�Ԗڂɍ����B���j�ŕČR�W�͂̕Ȃ������B
���g���^�A�R���i�Ђœ���A�W�A�ł̐��Y�e���g��|�����H��ɂ��g�y�@7/26
�g���^�����Ԃ̍����O�̍H��ғ��ɓ���A�W�A�ł̐V�^�R���i�E�C���X�����g��̉e�����L�����Ă����B
�g���^�L��S���̋��{�j�D���ɂ��ƁA�V�^�R���i�����g��̉e���Ŏd�����̍H�ꂪ�ғ���~�ɂȂ������Ƃŕ��i�Ɍ��i���������A�^�C��3�H���20�|21������ғ���~���Ă���B�j�����܂߂�28���܂Œ�~���錩�ʂ��ƂȂ��Ă���A����ȍ~�̉ғ��͏����Ĕ��f���Ă����Ƃ����B
�g���^�́A����A�W�A�ł̓R���i�����g������s�s����(���b�N�_�E��)�̑[�u�����ꂽ�}���[�V�A��6��1�����琶�Y�Ɣ̔����~���Ă���B���{���ɂ��ƁA�H��̉ғ��͌��݂��~�܂��Ă���B�^�C�ƃ}���[�V�A�̍H���~�ɂ�鐶�Y�ւ̉e���䐔�͖��炩�ɂ��Ă��Ȃ��B
�܂��A�R���i�����g��Ńx�g�i���̎d�����̍H�ꂪ��~�������Ƃŕ��i�������s�����邽�߁A�q��Ђ̃g���^�ԑ̂̕x�m���H��(���m�����J�s)�̑�2���C����29������8��4���̂���5���Ԓ�~����B��3000��̐��Y�ɉe�����o��Ƃ����B
���݊O�M�l�̎x���͏d�v�Ȍo�ϐ헪�`�R���i�����̋}�g�傷��A�W�A�����@7/26
�����E�ł���݊O�M�l�̈��S�̊m�ۂƎx����
ASEAN�����́A���{�̖f�Ց���Ƃ��ẮA�A�����J�A�����Ɏ����f�Պz�����d�v�ȃp�[�g�i�[�ł���B�䂪���̍���̌o�ρA�����̐헪�I�ɂ��A�d�v�Ȓn��A���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������ASEAN�����Ƃ̖f�Ղ�o�ρA�����̌q������x���Ă���̂́A��X�̓��E�ł���݊O�M�l�̐l�����ł���B�u�C�O�ɏZ�ނ͎̂��ȐӔC���v�Ǝx�����s�v���Ɣᔻ����ӌ������邪�A����͔��Ɉ�ʓI�ȑ������ł���A����̉䂪���̍��ۓI�Ȓn�ʂ�����I�Ɉێ����邽�߂ɂ��A�܂����E�ł���݊O�M�l�̈��S�̊m�ۂƎx�����d�v�ł���B
���^�C8���l�A�}���[�V�A3���l�A�C���h�l�V�A1��8��l�E�E�E
�O���Ȃ̎����ɂ��A2017�N10���̒i�K�ŁA�݊O�M�l�̓^�C�ɖ�8���l�A�}���[�V�A��3���l�A�x�g�i����2��3��l�A�C���h�l�V�A��1��8��l�A�t�B���s����1��7��l���ݗ����Ă���B��Ƌ��_���́A�^�C��5��9�S�A�}���[�V�A��1��2�S�A�x�g�i��2��S�A�C���h�l�V�A��2��A�t�B���s����1��4�S�ƂȂ��Ă���B�C���h�l�V�A�ł̐V�^�R���i�̊����g��ƈ�Õ���́A�����ł�����A�S���W�߂Ă���B�������A�^�C�A�~�����}�[�A�}���[�V�A�ȂǑ���ASEAN�����ł������g�傪�~�܂炸�A�����Ґ����}�����A���n�̈�Ñ̐����Ђ��������ƂȂ����B���łɓ��{�l�̎��S������Ă���B���̑傫�ȉe�����Ă���̂��A�����̍��ɒ��݁A�؍݂��Ă�����{�l�Ƃ��̉Ƒ����B
���ً}�A���p�̗Վ��ւ��K�v��
�C���h�l�V�A�ł́A�݊O�M�l�ً̋}���p��7��21����25���ɓ��{�ւ̗Վ��ւ��^�q���ꂽ���A�\�E�����A����ɍq���15���~����20���~���x�ɉ����đҋ@�{�݂⌟���̔�p�����ȕ��S�ł��������߂ɁA�A����p��40���~����50���~�ƍ��z�ɂȂ����B���̂��߁A�����̔ᔻ����ꂽ���߁A���{���{��26����28���ɂ��Վ��ւ��^�q���A���̍ۂɂ͎葱���̊ȗ����Ƒҋ@�{�݂⌟���̔�p�𐭕{���S�Ƃ���Ɣ��\�����B�������A1�֓�����̏�q�����200���قǂŁA4�֍��킹�Ă�1�疼���ɉ߂��Ȃ��B�^�C����̋A���ւɊւ��ẮA���{�q��A�S����A�^�C���ۍq��Ȃǂ��^�q���Ă��邪�A����������ł�8�����܂ŗ\�����ς��̏��B����Ƃ�{�n�@�ւ̒��ɂ́A���݈��₻�̉Ƒ��̈ꎞ�A�������߂Ă���Ƃ�����o�Ă��Ă���B����A�^�C�ɐ��Y���_����������ƌo�c�҂̂悤�ɁA�u���ƂƈقȂ�A�������Ȃ��A���Y��������{�l�X�^�b�t�����Ȃ��Ɠ����Ȃ��B�A���������̂͂�܂�܂����A����v�Ƃ����̂����B�܂��A���Ƃ̏]�ƈ��ł��u�Ƒ��̋A���w�����{�Ђ���o�����A���݈��͂��̂܂܂��v�ƌ����B�Վ��ւ̉^�q�ɂ��āA�^�C�̍q���ЊW�҂́A�u����A�A������]������{�l���������邱�Ƃ��\�z����邪�A���̏ꍇ�A�^�C������{�ւ̏�q�͂��邪�A���{����^�C�͂قڃJ���̏�ԁB���ւƂ����Ă��A�q���ЂɂƂ��Ă̕��S�͑傫���B���Ԋ�ƂƂ��Ă͌��E������v�ƌ����B�V�^�R���i�̊����g��́A�C���h�l�V�A�����ł͂Ȃ��A���̃^�C�A�}���[�V�A�A�~�����}�[�Ȃǂł��[�������Ă���A�݊O�M�l�ً̋}�A����N�`���ڎ�̗v�]�͑傫���Ȃ��Ă���B����A�C���h�l�V�A�����ł͂Ȃ��A���Ӎ��̏���������A�M�l�~�o�̂��߂ɁA���{���x�����Ă̗Վ��ւ̉^�q���K�v�ƂȂ�B�������A���ꂾ���̍q��@�̉^�q��A������`�ł̎���Ԑ��𐮂��邱�Ƃ͌����I�ł͂Ȃ��B
�����n�ł̃��N�`���ڎ�̉\��
�݊O�M�l�̊Ԃ���́A���{��g�ق���{�l�w�Z�Ȃǂł̃��N�`���ڎ�̎��{�����߂鐺���o�Ă���B�c�C�b�^�[��ł́A�u#�݊O�M�l�̌��n���{��g�قł̃��N�`���ڎ����]���܂��v�Ƃ����^�O�ŁA�����̓��e�����Ă���B���{���{�́A�݊O�M�l�̋A�����N�`���ڎ�̃C���^�[�l�b�g�\���7��19���ɊJ�n�����B���{�Ɉꎞ�A�����ă��N�`���ڎ���s�����Ƃ���]����l�����ɑ��āA���c��`�ƉH�c��`�ɓ��݉���݂���Ƃ������̂��B���̋A�����N�`���ڎ�̑Ώێ҂́A�݊O�M�l�ŏZ���[�������Ȃ��ڎ펞�ɖ�12�Έȏ�̎҂ƂȂ��Ă���A�݊O�M�l�ł����{�ɏZ���[������҂�A�A�����ɓ]���͂��o�����ꍇ�͑ΏۊO�ƂȂ�B�������A�A���̔�p�͑傫���A�l�A��Ƃւ̕��S���傫���B����ɃC���h�l�V�A��^�C�ɂ́A���{��Ƃ̐������_�Ȃǂ����������݂��A���݈����A���ł��Ȃ��P�[�X�������B�����I�ȉ������@�Ƃ��āA�݊O��g�ق���{�l�w�Z�Ȃǂ����Ƃ��āA�݊O�M�l�ւ̃��N�`���ڎ킪�ł��Ȃ����Ƃ�����Ă��A�A�u#�݊O�M�l�̌��n���{��g�قł̃��N�`���ڎ����]���܂��v�ł���B���ہA�x�g�i���ł̓t�����X��g�ق�18�Έȏ�̃t�����X�����Ɣz��҂Ȃǂ�ΏۂɃ��N�`���ڎ���n�߂Ă���ق��A�^�C�ł̓I�[�X�g�����A��g�ق�t�B���s����g�قł����ꂼ��̎������ɑ��郏�N�`���ڎ���J�n���Ă���B
���݊O�M�l�̎q�������̋���@��̕ۏ��
�^�C�E�o���R�N�̓��{�l�w�Z�ɂ͏��w�Z�A���w�Z�����킹�Ė�1��l�̎����A���k��2019�N�ɂ͍ݐЂ��Ă����B�C���h�l�V�A�E�W���J���^�̓��{�l�w�Z�ɂ��A��1��l���ݐЂ��Ă����B���̂ق��ɂ��AASEAN�����ł́A�����̏����w�������n�Ŋw��ł��邪�A�e���̐V�^�R���i�E�C���X�����g��ɂ���āA���̑������I�����C�����Ƃ����ɂȂ�A����ɏ̈����ɂ���āA�A����]�V�Ȃ�����Ă���B����A�e������̉Ƒ��̋A�������������ƂȂǂ��������A���������q�����������{�ɋA�����鎖�Ԃ��N������̂Ǝv����B���������q�������̋���@��̕ۏ���d�v�Ȃ��ƂƂȂ�B�����̏����w�Z�ւ̃X���[�Y�Ȏ���Ȃǂ��A���{�A�����̂Ȃǂ̎x�����K�v���B����ɁA�C�O�̓��{�l�w�Z�ւ̎x�����d�v�ƂȂ�B���Ԃ����É����A�ĂщƑ��ѓ��ł̊C�O���݂��\�ɂȂ������̂��߂ɂ��A���{�l�w�Z�̌p���́A�M�l�̋������{��Ƃ̊C�O�i�o�̂��߂ɏd�v�ł���B
���݊O�M�l�̎x���́A�䂪���̌o�ϐ헪�̈��
���{�̖f�Պz�ł݂�ƁA�A�����J�A�����AASEAN�������ق�20�����Ƃ��������ɂȂ��Ă���B���̌o�ϊ����́A���Ƃ̒��݈������ł͂Ȃ��A������Ƃ̒��݈��A�l���Ǝ�ȂǑ����̐l�����ɂ���Ďx�����Ă���B�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���J�Â���A�I�肽���̊���ɒ��ڂ��W�܂�A�K���O���l�I��c��W�҂ւ̑Ή��Ȃǂ��b��ɂȂ�B�������A������d�v�ł���B�������A��@�I�ɒ��ʂ��Ă���䂪�����E�ł���݊O�M�l�ɑ���x�����v���ȑΉ����K�v�ȏd�v�ۑ�ł���B�ߔN�A�C�O�]���D�܂Ȃ��Ⴂ���オ�������Ă���B���Ƃɂ����Ă��A�C�O���Ƃ�S���l�ނ̊m�ۂɋꗶ���Ă���B���ɁA����A�݊O�M�l�ւ̎x�����蔖�ł���A����A����ɊC�O�]��]�܂Ȃ��l����������\��������B�o�ϊE�̂Ƃ��Ă��A�傫�Ȗ��ł���B����ɍ�����o�ϔ��W�����҂ł���ASEAN�����ł̉䂪���̌o�ϊ������ێ����邽�߂ɂ��A���{�ɂ��ϋɓI�ȍ݊O�M�l�ւ̎x�����K�v�ɂȂ��Ă���B����́A�䂪���̌o�ϐ헪�̈�ƌ�����B�ً}�A���ւ̎x���ƍ݊O��g�قȂǂł̃��N�`���ڎ�̎��{�ȂǁA�V�^�R���i�E�C���X�����g�傪��@�I�ȏɂ��鏔���̍݊O�M�l�ւ̑��}�Ȃ�x�������߂���B
�������ܗւ��J�� ��t�s�ł́g��Ԑ��h�Ɓg�����g������O���鐺�h�@7/26
23���ɊJ����������2020�I�����s�b�N�B���Z���̂��開�����b�Z�߂��̊C�l�����w�ł́A�J������Ԑ��������ꂽ����A�V�^�R���i�̊����g������O���鐺��������܂����B
�X�̐l�u�R���i�ЂŁA�����Ǝ��l�ō���������ł�Ǝv���B���������l��TV�ȂljƂ̒��Ō��C�Â��āA���{�Ɋ��C�����߂���悤�ȑ��ɂȂ��Ăق����v
�X�̐l�u(Q.�����ܗ֊J���ɂ���)�y���݂ɂ��Ă���A�������v�u(Q.�V�^�R���i�ɂ��Ă�)��Ίg�債�Ă��܂��̂ŁA����͎c�O�B�{���݂͂�ȂŐ���オ���Ă����������A�R���i��}����K�v������A���ǂ������v
�X�̐l�u(Q.���ڂ̋��Z��)�������b�Z�ŊJ�Â���Ă��鋣�Z�ɂ��ẮA���ɊS�������āA���ڂ��Ă��������v�u(Q.�ǂ�ȑ��ɂȂ��)�I�肪���ꂩ��1�����ɂ킽���Ċ��钆�ŁA���낢��Ȋ�������{�S���A���E�l�X�ɂ������Ă����Ǝv���̂ŁA�����������Ƃ�������҂��A��������Ɖ��������Ă���������ȂƎv���v
�����ł́A��t�s�̖������b�Z�ŁA���X�����O�E�t�F���V���O�E�e�R���h�[��3���Z���A�����Ĉ�{���̒ރ���C�݂ł́A�ܗ֏��ƂȃT�[�t�B�����J�Â���܂��B
����N�x�\�Z�̌J�z���A30���~���̌��ʂ��c�R���i�Ή���ʼnߋ��ő�� �@7/26
����2020�N�x�\�Z�̂����A21�N�x�ւ̌J�z�����ߋ��ő��30���~���ɒB���錩�ʂ��ƂȂ����B�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɑΉ����邽�߁A���z�̕�\�Z��3�x�g���A���z��5����1�O�オ���s���ꂸ�Ɏ����z���ꂽ�B
��N��5���~�ȉ��Ɏ��܂邱�Ƃ������A����܂łōő傾���������{��k�В����12�N�x��7�E6���~��傫������B20�N�x�̈�ʉ�v�̍Ώo���z�́A3�x�̕�\�Z�ɂ���ăR���i�БO�ɕҐ����������\�Z(102�E7���~)�ɔ�ׂ�1�E7�{��175�E7���~�ɖc���ł����B
���̗\�Z�́A�N�x���Ɏg����u�P�N�x��`�v�������ŁA�����@�́A���R�ЊQ�Ȃǂ�ނȂ����R�Ɍ����ė��N�x�ɌJ��z�����Ƃ�F�߂Ă���B�H�̏O�@�I���T���A�^�}����͌J�z���̊��p������ɓ��ꂽ��^�o�ϑ�����߂鐺����i�Ƌ��܂���Z���傫���B
2020�N�x�\�Z�̌J�z�z���ߋ��ő��30���~���ɒB����B�V�^�R���i�E�C���X�̎��������ʂ��Ȃ����A�^�}�͍Ώo���ւ̈��͂����߂�Ƃ݂��A�����Č��Ɍ������u�\�Z���퉻�v�Ƃǂ����������邩�������B
�����Ȋ����́A�u�R���i�Ђ͉����N����̂��\�z�ł��Ȃ����Ƃ̘A���B�����Ɉ��S���Ă��炤���߁A�\���ȗ\�Z���蓖�Ă���K�v���������v�Ɛ�������B
�J�z�����ł����������̂́A���������q�E���S�ۗZ�����s���������Z�@�ւ̎����J��x���̗\�Z�ŁA��6�E4���~�ɂȂ錩�ʂ����B�R���i�ŋƐт�����������Ƃɑ��鐭�{�n���Z�@�ւ̗Z�����z��قǐL�тȂ������B�n���n���Վ���t�����A5���~���x���J��z���\�肾�B�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���ɉ��������H�X���x�����鋦�͋��̌�������ȗp�r�ƂȂ邪�A�s���{�����S�����t��Ƃ��ǂ��t���Ȃ������B
���̂ق��A��Ë@�ւ��R���i���҂������a���̊m�ۂɕK�v�Ȕ�p�Ȃǂɏ[�Ă�u�ً}��x����t���v(1�E5���~)�A�����g��ɔ����Ď��Ƃ𒆎~���Ă���u�f���@�s���@�g���x���v(1�E3���~)�Ȃǂ��J�z�z�����������B
���{���ł́A���z�̌J�z���́u�ꎞ�I�Ȃ��́v�Ƃ̌������������̂́A���Ƃ́u���N�̂悤�ɑ����A�����g�����̃`�F�b�N���Â��Ȃ�v�ƌ��O����B
���łɁA�x�d�Ȃ��\�Z�̕Ґ��ȂǂŁA���̍�����Ԃ͈�i�ƈ������Ă���B���ƒn���̒������c����21�N�x���ɁA��v���ōň��̐����ƂȂ�1209���~�܂Ŗc��ތ��ʂ����B
�i�C�Ɍ�������^�̌o�ϑ�Ƃ��āA�^�}���ł́u30���~�K�́v�Ȃǂւ̊��҂���ь����A���̑��������O��������Ȃ͌x�������߂Ă���B�c����̓y����N�����́u�J�z����L�����p���A�Ώo�̊g��ɂȂ����\�Z�͂ł��邾���}������ׂ����v�Ǝw�E���Ă���B
���������H�i�l�グ�ŏ���}�C���h�ɗ�␅ �����̓R���i�Ђ���̌o�ω@7/26
�H�p���⏬�����Ƃ������H�i�̒l�グ���������ł���B�����ł̎��v�����Ȃǂ��Č������ƂȂ��Ă���A��Ɠw�͂ŃR�X�g���z������͍̂���ȏ��B�A�������̉��i���㏸���Ă���A�ƌv����������A����}�C���h�̉̑������ɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ̌��O���L�����Ă���B
���H�p���A�����A�����A�A������......
�ƒ�p�H�p�����̓����I�C���I�O���[�v�AJ�|�I�C���~���Y�A���a�Y�Ƃ�3�Ђ�8���A�ƒ�p�H�p����1�L���O����������50�~�ȏ�l�グ����B5�������_�ő哤���O�N������8�����A�؎킪9�����ƍ��ۑ��ꂪ�������Ă��邽�߂��B
�R���i�Ђ��炢�������o�ς����������Ŏ��v���g�債�Ă���̂����ڂ̗v���ŁA�����I�ɂ����E�I�Ȑl�������ɂ����v���ŁA���i�͍������Ő��ڂ���\��������B
�e�H�p�����[�J�[�͋Ɩ��p�ł��l�グ�B�L���[�s�[�Ɩ��̑f�́A���������Ɏg���}���l�[�Y���A7���o�ו�����ő�10���l�グ���Ă���B
�ƒ�p���������A���������O���[�v�̓����t�[�Y�A�j�b�v��(�����{����)�A���a�Y�Ƃ�7������A1.5�`4�����x�l�グ�B3�Ђ͉ƒ�p�p�X�^��2�`8���l�グ��\�����Ă���(���{�����͎Ђɂ��قȂ�)�B
��������̖�9�����߂�A�������́A���{�������グ����Ŗ��Ԋ�Ƃɔ���n���Ă���A4���̐��{�ɂ�鉿�i�����グ�����ԍ��Ŕ��f�������̂��B�哤�̉��i�����ɂ���`�ŏ����̍��ۓI�ȑ�����オ���Ă���ق��A�������̎����p�ŐϋɓI�Ȕ�����������ꂽ���ƂȂǂ��e�����Ă���B
�����ő���DM�O�䐻���z�[���f�B���O�X�̎P��2�Ђ�7��15������A�����̏o���i��1�L���O����������6�~(��3��)�����グ�Ă���B1���ɑ������N2��ځB�V��s����R���i�Ђɂ��A���Ԃ̍����ŁA��v�Y�n�̃^�C��C���h����̋���������Ƃ̎v�f�Ȃǂ���A�j���[���[�N�s��̐敨�����4�N�Ԃ�̍��l��t���Ă���A��������������w�i�ɁA�������l�オ��B
���̂��߁A���{�̃��[�J�[�����i���i�ɓ]�ł�]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ����B���[�J�[����d����鉵�Ǝ҂���A�������[�J�[��ى�Ђɉ��i�㏸�̉e��������A�ǂ��܂ōL�����Ă������A�W�҂͒������Ă���B
�č��Y�������オ���Ă���B�Ⓚ����̉������i��4�`5���ɂ͑O�N������1.7�{���x�ɍ��������B��鯂Ɍ�����ꂽ���B�Y�̋��������������Ƃŕč��Y�Ɏ��v���W�������Ƃ���ɁA�R���i�Ђ���o�ς����Ă����č��⒆���Ŏ��v���L�т����߂��B
�X�[�p�[�Ȃǂ̓X���ł͍��B�Y���p�������A�č��Y���W�����A�l�オ�肵�Ă���B�O�H�Ȃǂ̓R���i�Ђʼnc�Ǝ��l�Ȃǂƃ_�u���p���`�����A�R���i�̉e�����傫�����A�������i�㏸�����̉e���́A�t�Ɍ����ɂ����Ȃ��Ă���B
�������͌o�ς̋}�A�J���l�����ɕ����A�V���
�l�オ������ۓI�ȓ��v�Ŋm�F���Ă����ƁA���A���܂Ƃ߂�H�����i�w��(2014�`16�N=100)��21�N5���A127.8�ƁA12�����A���㏸���L�^�B1�N�O�����4���㏸�������ƂɂȂ�A2011�N9���ȗ��A��10�N�Ԃ�̍������ƂȂ����B
���̎w���͍�����H���A�����i�Ȃǂ̍��ێ�����i����Z�o����A���E�̐H���S�̂̒l�����������B6����3.2�|�C���g�_�E����124.6�ƁA1�N�Ԃ�̒ቺ�ɂȂ������A�Ȃ����������B
�����������i�㏸�̗��R�́A�X�̕i�ڂɂ��Ĉꕔ�����������A��������ƁA�R���i�Ђ���o�ω����钆�����͂��ߕč��Ȃǂ̎��v���ő�̗v�����B����ɁA�R���i�Ђɂ��ړ������Ŕ_��Ƃ̒S����ł���O���l�J���҂��ꕔ�̍��ŕs�����A���Y�Ɏx�Ⴊ�o����A���l�ɕ����Ԃ��������ă��m������Ȃ�������A������㏸���Ă���\�\�Ȃǂ��e�����Ă���B���B�̋����ȂǓV��̉e�������i�ڂ�����B
�����A�H�p�����ł͐����ł��Ȃ��v�����w�E�����B���Ƃ��A����Ńf�B�[�[���R���ɑ哤��؎�̐A���������p����P�[�X�������Ă��邵�A�g�E�����R�V��T�g�E�L�r������o�C�I�G�^�m�[�����A�K�\�����ƍ����ăG�R�R���Ƃ��Ďg����B���̂��߁A�i�C�ϓ���V��̉e���Ƃ�������ߐ��̗v���Ƃ͕ʂɁu�\���I�Ɏ������N��(�Ђ��ς�)����\��������v(���H�p�����[�J�[)�Ƃ̎w�E������B
�R���i�Ђ̂��߂ł���A���̗v���ł���A�H�i�̒l�オ��́A���E�ł͓r�㍑���A�����ł��Ꮚ���w�����邾���ɁA���̓�������ڂ������Ȃ��B
��2021�Ẵ{�[�i�X�@7/26
�����ă{�[�i�X�ɃR���i�Ђ̉e��
���{�̘J������S�Ắh�����h�Ƃ������l�ς��ω������A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ƃ����p���f�~�b�N���A2020�N9���Ɍ����J���Ȃ̒����ɂ���āA���Ԋ�Ƃɂ��Ẵ{�[�i�X�x���z��2�N�A���Ō������Ă���Ƃ����f�[�^�����\����܂����B�V�^�R���i�̊����g��ɂ��A�{�[�i�X�̎x���p�~�⌸�z�̌X�������钆�A���̓xJob���������{�����u2021 �Ẵ{�[�i�X���Ԓ����v�ł́A���̎x���z��A��N�Ɣ�r�����ۂ̕��ώx���z�A�܂����̑����Ȃǂɂ��āA�R���i�Ђɂ��{�[�i�X�x���̕ω������܂����B
���O�N��{�[�i�X�z������
�S�̂�65.6%�����ă{�[�i�X�u�x������v�Ɖ��A���̒��ł����[�J�[�Ζ�34.4%�AIT�֘A���15.0%���ƁA���ƊE���u�x������v�̉��ڗ����ʂɂȂ�܂����B�܂��A���Ăƍ��Ẵ{�[�i�X�z�ɂ��ċ�̓I���z�̉W�v�̌��ʁA����87.2���~�A����81.3���~�ƂȂ���ă{�[�i�X�x���z���6���~�����������ʂƂȂ�܂����B
���R���i�ЂŖ�7�������Ă���{�[�i�X�p�~
���Ẵ{�[�i�X�x���ƃR���i�Ђ̉e���ɂ��ẮA�傫���e������27.5%�A�����e������26.6%�Ɣ����ȏオ��Ȃ菬�Ȃ�R���i�Ђ̉e�����Ă���Ɖ��܂����B�܂��A���ă{�[�i�X�̎x�����Ȃ��������̒��ŁA���ă{�[�i�X�̎x��������������65.8%�ŁA���N�ɂȂ��ăR���i�Ђ̉e�����Ďx���p�~�ɂȂ��Ă�����ʂɂȂ�܂����B
�����ă{�[�i�X�ɉߔ������[��
�S�̂�ʂ��č��ă{�[�i�X�x���ɂ��Ă̔[���x�́A�[���ł���28.2%�A���[��25.8%�őS�̂̉ߔ���������54.0%���[�������Ɖ��A�[���ł��Ȃ�19.6%�A���܂�[���ł��Ȃ�26.4%�ō��Z����46%���[���ł��Ȃ������Ɖ��܂����B�u�R���i�Ђ��e���������Ƃ���A�{�[�i�X�x���̔p�~�⌸�z�ɂ��[�������v�ȂǁA�R���i�Ђ̉e���ɑ���R�����g�����������w�i����A�{�[�i�X�x���̗L���Ɋւ�炸�[���x���ߔ������������Ƃ݂��܂��B
���Ҏ��R�L�q�R�����g�܂Ƃ�
�E��Ђ̎��Ǝ��̂��R���i�Ђ̉e�����Č��������ł̃{�[�i�X�x���͂��肪�����������ǂ��̐悪�s���B
�E�R���i�ЂŃ��X�g���͂��������A�O���n�̂��߂��̕��c�����X�^�b�t�ɋ����A�ܗ^�͎�����Ȃ����B
�E�R���i�ʼne�����Ă���̂ʼnă{�[�i�X�̎x���p�~�͎d�����Ȃ��B
�E�{�[�i�X�����́A�Ɛт��������ł��܂��܂��ێ����ꂽ���A�R���i�ЂŎc�ƋK�����������N���͌���
���܂Ƃ�
������{�����u2021�Ẵ{�[�i�X���Ԓ����v�ł́A�S�̓I�ɃR���i�̉e�����������Ƃ������ڗ����A���ă{�[�i�X�x���z�Ɣ�r����ƁA��7�����{�[�i�X�x���p�~�Ɖ��A���ώx���z��6���~�����Ƃ������ʂɂȂ�܂������A6�����[���Ɖ��錋�ʂɂȂ�܂����B
�܂��A��L�ȊO�̎��R�L�q�ł������̃R�����g������A�{�[�i�X��N���ɃR���i���e�����Ă��邱�Ƃ��킩��R�����g���ڗ����A����̃R���i�Ђɂ��Љ��̕ω��₻��ɑ���g�̐U����ւ̌��O�ȂǁA���g�̃L�����A�ɂ��ĕs��������R�����g���������܂����B�@
������ �R���i�����}�g�呱�� 4�A�x�͌ܗւŐl�o�������c�@7/26
4��ڂً̋}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ���2�T�ԂƂȂ��������s�B26���͐V����1429�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����A1�T�ԑO�̌��j����2�{�߂��ɑ�����ƂƂ��ɁA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B
25���܂ł�4�A�x�A�����I�����s�b�N�̊J����s��ꂽ�������Z��̎��ӂ⋣�Z��ꂪ����p�݃G���A�ȂǂŐl�o�����������Ƃ�������A���Ƃ́u���Z������邱�Ƃ����ł���w�����ĂȂ��x�ŁA����ʼn������Ă��炢�����v�Ƙb���Ă��܂��B
�����j�ő��̊����m�F
�����s���ł�26���A�j�����킹��1429�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����܂����B727�l������1�T�ԑO�̌��j���Ɣ�ׂ�ƁA2�{�߂��̑����ƂȂ�܂����B����Ɍ��j���͔�r�I�A�����m�F�����Ȃ��X���ɂ���܂����A�ő�������1��11����1252�l�����肱��܂łōł������Ȃ�܂����B1���̊����m�F��1000�l����̂�7���A���ł��B����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂�20���l���āA20��720�l�ƂȂ�܂����B
���g�C���h�^�h�ψكE�C���X�̊����m�F���ő�
�܂��A�s���ł̓C���h�Ŋm�F���ꂽ�uL452R�v�̕ψق�����E�C���X�ɐV����940�l�̊������m�F����A1���ɔ��\�����l���Ƃ��Ă͍ő�����������21����681�l���250�l�ȏ㑝���A��������ł������Ȃ�܂����B
��4�A�x �l�͂ǂ��ɏW�܂����H
���̂��E25���܂ł�4�A�x�A�s���ł͂ǂ��ɐl���W�܂����̂��B�r�b�O�f�[�^�͂������ʁA�����I�����s�b�N�̊J����s��ꂽ�������Z��̎��ӂ⋣�Z��ꂪ����p�݃G���A�ȂǂŐl�o�����������Ƃ�������܂����BNHK�́ANTT�h�R�����g�ѓd�b�̊�n�ǂ���v���C�o�V�[��ی삵���`�ŏW�߂��r�b�O�f�[�^���g���āA����4�A�x�̌ߌ�3����̓s���̐l�̓����͂��A�O�̏T�̓y���Ƃ���������ϒl�Ŕ�r���܂����B�f�[�^�͓������獑���Ōg�ѓd�b�𗘗p���Ă��郆�[�U�[�Ɍ����Ă��āA�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̂��߂ɗ������Ă���I���W�҂͊܂܂�Ă��܂���B���͓͂����s����500���[�g���l���ɋ敪�����čs���Ă��āA�l�o��5���ȏ㑝�����n�_�̓I�����W�F�ɁA5���ȏ㌸�����n�_�͐��F�ɂ��Ă��܂��B���̌��ʁA�J����s��ꂽ�V�h��ɂ��鍑�����Z��̎��ӂ�A���j��̑��̋��Z���Ȃǂ�����p�݃G���A�A����ɉH�c��`�̎��ӂł͑����̒n�_�Ől�o�������Ă��܂����BNHK�̎�ނł��A�����I�����s�b�N�̊J��O��ɍ������Z��̎��ӂɑ����̐l���K��Ă���l�q���m�F����Ă��āA�l�̖��W�����O���鐺��������Ă��܂����B����AJR�a�J�w���ӂł�9����������Ȃ�23����̑����̒n�_�Ől�o�͑����Ă��܂���ł����B
�����Ɓu���ϋq�̈Ӗ����Ȃ� ����ʼn������v
25���܂ł�4�A�x�A�J����s��ꂽ�������Z��⋣�Z�����ӂŐl�o�̑���������ꂽ���Ƃɂ��āA���{�̕��ȉ���o�[�Ő��s���N���S�������̉����M�F�����́u���ϋq�Ƃ����̂͑I���W�҂̊Ԃł̃N���X�^�[��H���~�߂邱�Ƃ������ړI�ł͂Ȃ��A�ϋq���W�܂��Ă݂�ȂŐ���オ���ĉ������邱�ƂŁA���̌�A�����Ɋ������L�����Ă��܂��̂�h�����߂��B���Z�����ӂɏW�܂��Ă��܂��Ă͖��ϋq�ɂ����Ӗ����Ȃ��A�����I�Ȋ����g��̓p�������s�b�N�̊J�Âɂ��e����^�����˂Ȃ��B�J�Í��͑I�肽���ɋ���������̂���ڂł���A���Z������邱�Ƃ����A�������ɂł���w�����ĂȂ��x���B���̐��̔M�C�ɐG���y���݂͂Ȃ��Ȃ邯��ǁA�����ꏏ�ɂ���l�����Ǝ���ʼn������Ă��炢�����v�Ƙb���Ă��܂����B
�����N�`�� �S�l���̖�36����1��ڎ�
����A���N�`���̐ڎ�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B���{��26���Ɍ��\�����ŐV�̏ɂ��܂��ƁA�����ŏ��Ȃ��Ƃ�1��A�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`����ڎ킵���l�͍��킹��4625��210�l�ŁA�S�l����36.38���ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A2��ڂ̐ڎ���I�����l��3147��6719�l�ŁA�S�l����24.76���ƂȂ�܂��B�S�l���ɂ̓��N�`���ڎ�̑Ώ۔N��ɖ����Ȃ��q�ǂ����܂݂܂��B�����̃f�[�^�͊e�n�悩��V�X�e���ɓ��͂��ꂽ�l���Ɋ�Â����̂ŁA�E��ڎ�Ȃǂɂ���Ď��ۂ͂���ȏ�ɐڎ킪�i��ł���\��������A����A�������邱�Ƃ�����܂��B
���ܗ֊J��4�A�x �����s����e�n�ւ̈ړ� �O�T��20���ȏ㑝�@7/26
25���܂ł�4�A�x�ɋً}���Ԑ錾���̓����s����S���e�n�ɂǂꂾ���l���ړ������̂��r�b�O�f�[�^�͂������ʁA�O�̏T�̓y���Ɣ�ׂ�20���ȏ㑝���A10�̌��ł͓�������ړ����Ă����l��2�{�ȏ�ɂȂ������Ƃ��킩��܂����B�m�g�j�́A�m�s�s�h�R�����g�ѓd�b�̊�n�ǂ���v���C�o�V�[��ی삵���`�ŏW�߂��r�b�O�f�[�^���g���āA����4�A�x�ɂ��ċً}���Ԑ錾���̓����s�Ƒ��̓��{���Ƃ̈ړ��͂��܂����B
�y���o��20�����z�@���̌��ʁA��������ق��̓��{���Ɉړ������l�͑O�̏T�̓y���Ɣ�ׂ�1�����ς�20���������܂����B
�y�����̒n���ő啝�����z�@�ł́A��������ǂ��Ɍ��������̂��B�ړ���͂���ƁA���ꌧ���������ׂĂ̓��{���ő������Ă��āA���̂���10�̌��ł�2�{�ȏ�A���ɂ���100���ȏ�̑����ƂȂ�܂����B�ł����������̂͘a�̎R����121���A�����ŕ��䌧��115���A�ΐ쌧�ƕx�R����113���A���挧��112���A��������110���A���ꌧ��106���A�V������104���A���쌧�Ɠ�������102���ł����B4�A�x�ł��邱�Ƃɉ����ăI�����s�b�N���n�܂��������́A�s���ł͖��ϋq�ƂȂ������ƁA���N�`���̐ڎ킪�i�ݗ��A��������l���������ƂȂǂ��w�i�Ƃ��čl�����܂��B
�y�ߍx�A�s�s���͑����������z�@�܂��A�������������������̂́A�_�ސ쌧��3���A��t���ƍ�ʌ���5���A��錧��25���A�{�錧��26���A���m����31���ȂǂŁA�ӂ��瓌���Ƃ̍s�����������ߍx�̒n���s�s���������Ȃ�܂����B����A�����s�Ɠ������ً}���Ԑ錾�������Ă��鉫�ꌧ�͗B��A36���̌����ƂȂ�A�䕗�̉e�����������Ƃ݂��܂��B
�y�s�ւ̗����͌����z�@�܂��A�ق��̓��{�����瓌���Ɉړ������l��2���������܂����B
���ً}�錾�̐l�o�}�����ʔ��܂�@�����w��10�����ǂ܂�@7/26
�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾�́A����d�˂邲�Ƃɐl�o��}��������ʂ����܂��Ă���B�����s��4��ڂ̐錾�J�n����2�T�Ԃ�O�ɂ���25���̐l�o�́A1��ڂ̐錾�J�n�O�̍�N3��(���j������)�ɔ�ׁAJR�����w��10�����ɂƂǂ܂����B�\�t�g�o���N�q��ЁuAgoop(�A�O�[�v)�v�̃f�[�^����ߌ�9����̐l�o�𒊏o�����B
��N3���̓��j�����ς̐l�o�ƁA1�`4��ڂ̐錾�J�n�����2�T�Ԍ�̓��j���̐l�o�𓌋��w�Ŕ�r�B�錾1��ڂ̍�N4���͍�N3���ɔ��65�����B��������2��ڂ̍��N1����42�����A3��ڂ�5����33�����A4��ڂ̍���25���ɂ�10�����ƂȂ����B
����_���ݎq�u���͂�ً}���Ԃ����� �w�����x�͂Ȃ��C�����E�E�E�v�@7/26
�������V���L�҂ŃA�t���w�A�|���g���[�h�}�[�N�̈�_���ݎq���uAERA�v�ŘA�ڂ���u�A�t�����v�����͂����܂��B50���߂��A�v�����đ����ސE�B�V���Ȑ����ւƔ�яo�������X�ɋN����o��������A�l�Ƃ̂ӂꂠ���A�v���o�Ȃǂ��Â�܂��B
��
�����ɍĂыً}���Ԑ錾�B�O��̉�������3�T�ԁB���͂�ً}���Ԃ�����B���ꖵ���B��̂ǂ����������Ȃ̂��낤�B�ܗւ͂��Ƃ������ƂȂ̂ŁA�Ȃ�Γ��킩�Ǝv���ً}���Ԃ��Ƃ��������B�ŁA�ܗֈȊO�̂��Ƃ͎��l���Ă˂ƁB�]��Ȃ���Δ���^���܂��ƁB���͂Ⓦ����SF�I�p���������[���h�A���邢�͒����̈Í�����̂悤���B
��(����)��ɂ��Ă��A�ŏ��ɐ錾���o�����̂悤�ȁA�F���͂����킹�Ď��l������̐�Ɍ���������̂��Ƃ����t�B�N�V�����͋C�Â������ǂ��ɂ���������Ȃ��B���ɂ��Ďv���A���͂���������Î_���ς��v���o�̂悤���B�Ȃ����̂悤�ȃt�B�N�V�������F���M�����̂��s�v�c�ł��炠��B����������ƍŏ����炻��ȃt�B�N�V�����͑��݂����A�����F�����̂悤�ɐM���������������Ȃ̂�������Ȃ��B�m���ɓ����̎́u2�T�ԂŃs�[�N�A�E�g�\�v�Ƃ�������������A�ނƂĈ�l�̐l�ԁB�ӂ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ꂩ��1�N�ȏ�o�����������͉������ꂸ���������ʂ܂܁B�����Ă������Ă������R�B
�ł����肵�Ă������Č����͉����ς��Ȃ��B�����͂����A�����͐��U�ً}���Ԃ̒�����̂����Ɗo�債���ق��������悤�Ɏv���Ă����B���̏�ʼn����Ȃ��ׂ������l����B������l�̈ꐶ�͈�x����B���������O��Ǝv��˂Ȃ�ʁB
��������߂��̂́A�����u�R���i��������������v�Ƃ����͂�߂悤�Ƃ������Ƃ��B����͎U�X�g��ꂽ�Z���t�����A���͂�u����1���~����������v�݂����ȋȎЌ����߂Ɏv����B����ȋ��J��o���ɂ���������A���̂��邱�Ƃ��l�������B
����̒��ł��m�b���g���S���g���A���ׂ����Ƃ���肽�����Ƃ��摗�肹�����w�͂��������B�����A�͂Ȃ��B����͍̂��̂݁B����܂ł̌o�������A�C������ׂ����Ƃ͂�������C������Εs�\�͂Ȃ��Ƃ����̂��A���̓x�̌ܗւɗՂސ��{�̎p���ł��낤�B��������w�ׂ邱�Ƃ͊w�ю�肽���Ǝv���B
���V�^�R���i 4�A�x ��t���f��4000�����̑��k�E�� �@7/26
�V�^�R���i�E�C���X�̊������g�傷�钆�A��Ԃ�x���Ɉ�t�̉��f���s���Ă��閯�Ԃ̉�Ђɂ́A����4�A�x�����M�������҂Ȃǂ���̈˗����E�����A4000���ȏ�̑��k����ꂽ���Ƃ��킩��܂����B
��s���𒆐S�ɕ����̈�Ë@�ւƘA�g���Ė�Ԃ�x���Ɉ�t�̉��f���s���Ă����Ђł͓d�b�Ȃǂň˗�����Ɠo�^���Ă����t�����҂̎����K��Đf�@���̏������s���A�V�^�R���i�ւ̊������^����ꍇ�́APCR���������{���܂��B
��Ђɂ��܂��ƁA����22������25���܂ł�4�A�x�����M�������҂Ȃǂ����ꂽ���f�̑��k�́A�S����4000���ȏ�A��s����1�s3�������ł����悻2500���ɏ��Ƃ������Ƃł��B
1��������̌����́A��3�g�̔N���N�n���4�g��5���̑�^�A�x�������Ă��āA�d�b�ɂ���f�ʼn��f���K�v�Ɣ��f�������҂Ɉ�t���蕪�����Đf�@�ɂ��������Ƃ������Ƃł��B
�܂��APCR�������s������s���̊��҂̃E�C���X�ׂ��Ƃ���A�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�u�f���^���v�̊����́A�挎27���܂ł�1�T�Ԃ�19���ł������A����4���܂ł�24���A����11���܂ł�33���A����18���܂ł�1�T�Ԃł�55���Ɣ������A�}���ɒu������肪�i��ł���Ƃ������Ƃł��B
���̉�Ђ𗧂��グ�A���g�ʼn��f���s���Ă����t�̋e�r������́A�ŋ߂̊����҂̌X���ɂ���40�ォ��50��̊��҂��d�lj�����P�[�X���ڗ����Ă���ق��A��H�Ȃǂ̖��炩�ȃ��X�N�s�����Ƃ��Ă��Ȃ��̂Ɋ�������P�[�X�������m�F����f���^���̊����͂̋����������Ă���Ƙb���܂����B
�e�r��t�́A���f�̑��k���E���������Ƃɂ��āu�����҂��������Ă���̂ɉ����������������ɑ���s����������M�̏Ǐ�ł����k����P�[�X�������Ă���̂ł͂Ȃ����v�ƕ��͂��������Łu�I�����s�b�N���n�܂��ċC�̊ɂ݂₷�������ł����A�����҂̑����X���͍���������Ă����Ƃ݂��܂��B����������߂ēO�ꂷ��悤���肢�������v�Ƙb���Ă��܂����B
���̉�Ђł́A�����s�̈ϑ����ĐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ�����������×{�҂̐f�Â��s���Ă��܂��B�����I�����s�b�N�̊J����J���ꂽ23���̖�ɂ́A����×{�𑱂��Ă���s����50��̕v�w�̎����K��܂����B����5���O�ɕv�����ǂ��A�����A�Ȃ����ǂ��Ċ������m�F���ꂽ�Ƃ������ƂŁA��t�͓�������Ɩh�앞�ɒ��ւ��Ă��畔���ɓ���܂����B�����āA���t���̎_�f�̏�Ԃ��݂�u�p���X�I�L�V���[�^�[�v�̒l��x�̏�Ԃ�f�����ʁA���M�͑����Ă������̂́A�x���̉\���͒Ⴂ�Ɣ��f���A�o�ߊώ@�Ƃ����Ƃ������Ƃł��B
���V�^�R���i�@���ŐV����86�l�A�X�e�[�W3�u�����g���ԁv�Ɂ@7/26
��錧�Ɛ��ˎs��26���A�V�^�R���i�E�C���X�����҂������ŐV���Ɍv86�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�����̊����҂͗v1��1611�l�ƂȂ����B
���Ǝs�ɂ��ƁA86�l�̂����z���҂Ƃ̔Z���ڐG�ɂ�銴���Ƃ݂���l��46�l�A�����o�H��������Ȃ��l��40�l�B
���Ǝ��̃R���i�����f�w�W�̂����A26���̎��_��1��������̗z���Ґ�(����1�T�ԕ���)��66.7�l�A�����o�H�s���̗z���Ґ�(��)��28.7�l�ƂȂ�A�Ƃ���2�Ԗڂɐ[���ȃX�e�[�W3(�����g����)�ɏオ�����B�X�e�[�W3�ɂȂ�̂́A���ꂼ��5��20���A4��28���ȗ��B
�s�����ʂ̊����Ґ��́A���Ύs23�l�A�푍�s9�l�A��J�s8�l�A�}���s7�l�A���݂炢�s4�l�A���ˎs3�l�A�É͎s3�l�A���Ȏs3�l�A�g�c�s3�l�A���P��s3�l�A����s2�l�A���C��2�l�A���O2�l�A������2�l�A�_���s2�l�A�s���s2�l�A�����s2�l�A�헤��{�s1�l�A���s1�l�A����s1�l�A����1�l�A�Ⓦ�s1�l�A�y�Y�s1�l�B
���������҂��������Ă��邱�Ƃɂ��āA�������Ǒ�ۂ́u����E�����n��𒆐S�ɑ����A1�̌ł܂�łȂ����낢��ȏꏊ�Ŋ����҂��o�Ă���v�Ɛ������Ă���B
�V���Ɍv43�l���މ@�A�ޏ��A����×{�I���Ȃlj��A�҂͗v1��718�l�ƂȂ����B
���V�^�R���i �����ǂł��}���Ɉ��� �d�ǂɓ]����P�[�X������ �@7/26
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ɏ��~�߂������炸�A��s���̊��҂̎��Âɂ������w�a�@�ł́A�����ǂœ��@�������҂�������A�d�ǂɓ]����P�[�X���������ł��܂��B��t�́u�d�ǂ͂���܂łƔ�ׂď��Ȃ��ƌ����邪�A���͏d�ǂƂ����X�R�̉��ɒ����ǂ��吨���āA���������邩�����炸�A�x�����ɂ߂��Ȃ��v�Ƒi���Ă��܂��B
��z�s�ɂ���A��ʈ�ȑ�w������ÃZ���^�[�́A�d�ǂƒ����ǂ̊��҂̎��Âɂ������Ă��āA��T�ȍ~�A�ق��̕a�@�ŏǏ����������҂��A���^��Ă��Ă��܂��B
24�����_�ŁA13�l�����@���Ă��āA30�ォ��50��̎Ⴂ�����10�l���߁A�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�u�f���^���v�Ɋ������Ă������҂�11�l�ɂ̂ڂ��Ă��܂��B
�Ǐd�����Ɂu�d�ǁv�u�����ǁv�u�y�ǁv�ƂȂ�܂����A��Ì���ł́A�u�����ǁv�́A�_�f�̋z�����K�v�ȂقǏǏ��������u������2�v�ƁA����ȊO�́u������1�v�ɕ��ނ���܂��B
���̕a�@�ł͂���܂ł̂Ƃ���A�u�d�ǁv��2�l�A�u������2�v��7�l�ł����A�d�ǂ�2�l�͓��@���͒����ǂ��������̂��d�lj������Ƃ������Ƃł��B
50��̒j�����҂́A���@��A�u������2�v�̃��x���܂ŏǏ������܂������A���Â̌��ʁA�����������Ƃ��ł����Ƃ������Ƃł��B
�j���́u�M�����̂����������Ȃ�A�炩�����B�R���i�ɂ͓�x�Ƃ����肽���Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂����B
�����ljȂ̉��G�������́u������2�́A�悭�������邪�A�C�O�ł͏d�ǂɕ��ނ���Ƃ��������A�_�f���z��Ȃ��Ƃ����Ȃ��A�l�H�ċz��̈����O�̏�ԂƂȂ�B���͏d�ǂ����Ȃ��ƌ����邪�A���͏d�ǂƂ����X�R�̉��ɁA������2���\���R�̂悤�ɑ吨����Ƃ����̂���5�g�̓������B������2�œ��@�������҂��A�킸�������ň������A�����ێ����u���K�v�ɂȂ�P�[�X������A�x�����ɂ߂��Ȃ��v�Ƒi���Ă��܂��B
���d�Ǔx��4�i�K�ɕ���
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�̑Ή��ɂ������Ì���ł́A�d�Ǔx�ɂ��āA�u�d�ǁv�u������2�v�u������1�v�u�y�ǁv��4�i�K�ɕ��ނ��Ă��܂��B
���̂����A�u������2�v�́A���t���̎_�f�̐��l��93���ȉ��ɂȂ�A�ċz�s�S�������Ă����ԂŁA�l�H�ċz��̑�������������i�K���Ƃ��Ă��܂��B
����́A�l�H�ċz���l�H�S�x���u��ECMO�������u�d�ǁv�Ɏ����ŏd���Ǐ�ɕ��ނ���Ă��܂��B
���u������2�v�ɂ܂ňꎞ���������j����
������{�A��ʈ�ȑ�w������ÃZ���^�[�ɓ��@����50��̒j���́A�����͂������A�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�u�f���^���v�ւ̊������m�F����܂����B
�j���̓��N�`���͐ڎ킵�Ă��炸�A�ŏ��͌y�ǂƐf�f����܂������A��b���������������߁A���@���邱�ƂɂȂ�܂����B
���̌�A���X�ɔx�����L����A���t���̎_�f�̐��l���������A���@���炨�悻1�T�Ԍ�A�_�f�}�X�N������������Ȃ��Ȃ�A�u������2�v�̏�Ԃɂ܂ň������܂����B
���̌�A�W���I�Ɏ��Â��s�������ʁA�Ȃ�Ƃ����������A��t�����₷��`���Ŏ�ނɉ����Ă���܂����B
�j���́u�d�����ɋ}�Ɋ��C�����ċx�e���œ|�ꍞ��ł��܂����B39�x�ȏ�̔M���o�āA�Ƃɂ����炩�����B���@���͕s���ł��܂炸�A�R���i�ɂ͓�x�Ƃ����肽���Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂����B
�j���́A��t����X���ɂ���ƍ�������ƁA�ق��Ƃ����\����ׂĂ��܂����B
���Â�S�����������ljȂ̉��G�������́u���̊��҂͓��@����7���ڂɌċz��Ԃ��������Ē�����2�ɂȂ����B�y�ǂœ��@�����l���A1�T�Ԍ�ɂ͒�����2�ɂȂ�����A�d�ǂɂȂ邩������Ȃ��B���傤�̏d�ǎ҂̐l�������đ��v���Ɣ��f�����ƁA����Ƃ��Ă͌����ɂȂ��Ă��܂��ƌ��킴������Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i 2�l���S �V����2848�l�̊����m�F �ߋ��ő��@7/27
�����s��27���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��2848�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̉Ηj���̔{�ȏ�ƂȂ�A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B1����2000�l����̂́A��3�g�̂��Ƃ�1��15���ȗ��ł��B27���܂ł�7���ԕ��ς�1762.6�l�őO�̏T��149.4���ƂȂ�A�����̋}�g��Ɏ��~�߂�������܂���B����ŁA�s���Ŋ������m�F���ꂽ�̂�20��3568�l�ƂȂ�܂����B����A�s�̊�ŏW�v����27�����_�̏d�ǂ̊��҂�26�����4�l������82�l�ł����B�d�ǎ҂�80�l����̂́A���Ƃ�5��18���ȗ��ł��B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ60��̏�����50��̒j�������S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B����ŁA�s���Ŋ������Ď��S�����l��2279�l�ɂȂ�܂����B
���c�����J���u�v������� ����邱�Ƃɋ��͂��v
�c�������J����b�͋L�Ғc�ɑ��u���E���Łw�f���^���x�ɂ�芴�����}�g�債�A�������w�f���^���x�ɒu����������Ȃ̂ŁA�����Ґ��������x�����邱�Ƃ̓E�C���X�̐����゠�蓾�邱�Ƃ��Ǝv���v�Ǝw�E���܂����B���̂����Łu�ً}���ԑ[�u�߂��Ă���ɂ�������炸�A�v���ɉ������A���R�[�����o���Ă���X���U������邪�A�����o���X�͊J���Ȃ��Ƃ������Ƃ�����Ă������������B�I�����s�b�N�̃A�X���[�g������̒��Ŏ����ɏo�Ċ撣���Ă���B�v������ɂ��Ċ������Ȃ�Ƃ��}���A������邱�Ƃɋ��͂������������v�Əq�ׂ܂����B
���ߋ��ő� �s���̊X�̐l��
27���A�s���ŁA�ߋ��ő��ƂȂ�2848�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ���Ƃ��āA�a�J�w�O�Řb���܂����B���̂����A���N�`���ڎ�̋A�蓹���Ƃ���50��̏����́u�����A�т�����ŋ����Ă��܂��B�l�������炻���Ƃ��Ă��܂������ʂ�����Ă��Ȃ��Ɗ����܂����A���߂āA���}�X�N�̒��p�ȂǁA���͂̐l�ɂ����ӂ���悤�Ɍ����Ă��������ł��v�Ƙb���Ă��܂����B�܂��A�d���A���70��̒j���́u�ً}���Ԑ錾���Ȃ̂ɂ��ꂾ���l���o�Ă���Ƃ����Ɗ����҂������Ă����������Ȃ��Ɗ����܂��B�O�o�𐧌�����Ȃǂ�苭��������Ƃ�Ȃ��ƁA�����͎~�܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B����A20��̒j���́u���������Ⴂ����͍s�����ł��Ȃ��Ȃ��ĉ䖝���Ă��钆�ŁA�I�����s�b�N������Ă���Ȃ�O�o���Ă������̂ł͂Ǝv���l������̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
�����Ɓu�l�̓�����}�������v
�����s����27���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l���ߋ��ő��ƂȂ������Ƃɂ��āA�V�^�R���i�E�C���X��ɂ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�œ��M��w�̊ړc�ꔎ�����́u�ً}���Ԑ錾���o�����2�T�Ԃ������A����܂łł���Ί����Ґ��������Ă��鎞���ɉߋ��ő��̊����Ґ��ƂȂ������Ƃً͋}���Ԑ錾�̌��ʂ��o�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���܂̊����Ґ���2�T�ԑO�Ɋ��������l�ł���A�l�̗��ꂪ�����Ă��Ȃ����Ƃ��l����ƁA�����Ґ��͂���ɑ�����\��������v�Ǝw�E���܂����B�������}���Ɋg�債�Ă���v���Ƃ��ẮA�u4�A�x�Ⓦ���I�����s�b�N�̊J���A����ɉċx�݂ȂǂŔZ���ڐG�̋@������Ă���ق��A�����͂̍����f���^���ւ̒u���������}���ɐi��ł��邱�Ƃ��w�i�ɂ���ƍl������B�s���ł͂��ł�2000�l�ȏオ���@�悪���܂��Ă��炸�A���̂܂܊����Ґ���������Ƃ���Ñ̐����Ђ������Ă����������Ȃ����v�Ƃ��Ă��܂��B�����āA����A�K�v�ȑ�ɂ��ẮA�u�����̊����Ґ��̑����͍���A�S���Ɋg�傷�鋰�ꂪ����B�����_�̃��N�`���ڎ킪�\���ɐi��ł��Ȃ��ł͂�苭���K�v�ŁA���H�X�����ł͂Ȃ��ق��̋Ǝ�̓X�܂̉c�Ƃ̎��l����������ȂǁA�l�̓��������}�����𑁂߂ɑł��Ƃ��d�v���v�Ƙb���Ă��܂����B
�����J�� �����u�����҂̑��� �z���葁���v
�����J���Ȃ̊�����1�l�́u�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�́w�f���^���x�̊������L�����Ă���̂ŁA�����҂����ꂭ�炢�܂ő����邱�Ƃ͑z������������A�\�z���Ă�����葁�������B�ً}���Ԑ錾���o��2�T�ԂɂȂ�̂ŁA�{���Ȃ���ʂ��o�Ă��鎞�������A�ȑO�̂悤�ɂ͌����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�I�����s�b�N�̐���オ����l���̑����ɂȂ����Ă����ۂŁA�����҂͂���ɑ�����̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂��B�܂��A�ʂ̊����́u�����͏d���~�߂Ă���B�ċx�݂��}���A���s�ȂǂŐl���������鎞���Ȃ̂ŁA��w�̒��ӂ��K�v���B�d�ǎ҂������Ĉ�Âւ̕��ׂ����܂��Ă���̂ŁA������̊�{������Ă��炦��悤�A�ǂ��ɂ����č����̋��͂Ċ�����}������ł��������Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B�ʂ̊����́u���Ƃ��Ƃ����Ȃ邱�Ƃ�z�肵�āA�s�v�s�}�̊O�o���T����悤�����ɂ��肢���Ă������A��̐ςݏグ�����܂������Ȃ������B���{�ւ̐M�����Ȃ��A�ǂ�ȃ��b�Z�[�W���o���Ă�������̂�����Ȃ��Ă���v�Ƙb���Ă��܂��B
������ ���R�������u�Ռ��I ���~���ׂ����ő��v
��������}�̕��R�������́A�L�҉�Łu�ً}���Ԑ錾���o����A�{���Ȃ�Ί����Ґ������~���Ă����ׂ����ɍő��ɂȂ�Ƃ����̂͏Ռ��I���B���4�A�x�̉e���ɉ����A�I�����s�b�N�ł�������̐l�o������A����ǂ̂悤�Ȍ`�Ŋ������L�����Ă����̂��ɂ߂ĐS�z���B���{�͐��Ɖ���J���ƂƂ��ɁA���̍l���������ɐ�������K�v������A����������߂����v�Əq�ׂ܂����B
���V�^�R���i�A�����s��2848�l�@�ߋ��ő��@7/27
�����s��27���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2848�l���ꂽ�Ɣ��\�����B����܂ōő����������N1��7����2520�l��傫���������B�d�ǎ҂�82�l�������B
�������s�́g���M���k�h �����I�Ɋ����g�債����3�g���ő��� �@7/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋^��������l�Ɉ�Ë@�ւ��Љ�铌���s�́u���M���k�Z���^�[�v�ւ̑��k���A����܂łōł�����������3�g������܂����B���k��������Ɗ����m�F��������X�������邱�Ƃ���A�s�͌x�������߂Ă��܂��B
�����s�́A��������オ���Ȃ��l�Ŕ��M�ȂǐV�^�R���i�E�C���X�̊����̋^��������l�ɑ��u���M���k�Z���^�[�v��ʂ��Ď�f�ł����Ë@�ւ��Љ�Ă��܂��B
���k������7���ԕ��ς͂��悻1000��������6�����{���瑝���������Ă��āA25�����_�ł�2724���ƂȂ�܂����B
�����������I�Ɋg�債����3�g�Ńs�[�N���������Ƃ�1��4����2676���������Ă��āA����܂łōł����������ł��B
1�����Ƃ̌���������ƂƁA���ƂƂ��܂ł�4�A�x�́A22����3589���A23����3386���A24����3192���A25����3323���Ƃ������3000�����܂����B
����܂ł�3000�������̂͂��Ƃ�1��3����3239�������ŁA����4�A�x���ɑ��k���}�����Ă��āA�s�͌x�������߂Ă��܂��B
�s�̒S���҂́u�A�x���ɑ��k�ł����Ë@�ւ����Ȃ��������Ƃɉ����Ċ������g�債�Ă��邱�Ƃ����k�̑����ɂȂ������ƌ��Ă���B���M���k��������Ɗ����m�F��������X��������B�s���ł܂��Ă���Ȃ̂ŁA��{�I�ȑ��O�ꂵ�ĊO�o�͍T���Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
�������A2�J���A���l�����o�@7/27
�����Ȃ�27�����\����6���̐l���ړ���(�O���l���܂�)�ɂ��ƁA�����s����̓]�o�҂͓]���҂�583�l����A2�J���A���Ől�����o�������u�]�o���߁v�ƂȂ����B�����s�ɂ�6��20���܂ŐV�^�R���i�E�C���X�����g��ɔ����ً}���Ԑ錾�����߂���Ă���A�]�o���ɉe�������\��������B
�����s�ւ̓]���҂�2��9224�l�ŁA��N6����0.6�����B�]�o�҂�2��9807�l��8.9�����������B
��ʁA��t�A�_�ސ��3�����܂ށu�������v�ł݂�ƁA�]���҂��]�o�҂�3106�l�������B3���Ƃ��]���҂̕��������A���ߐ��͍��1362�l�A��t1062�l�A�_�ސ�1265�l�������B
�������}�g��œs���R���i�a���m�ۂ�v�� �ʏ�f�Ð������@7/27
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����A��1000�l���A�������}�g�債�Ă��邱�Ƃ��A�����s���s���̈�Ë@�ւɑ��A�ʏ�f�Â̐���������ɃR���i�a�����m�ۂ���悤�v���������Ƃ��킩��܂����B
�����s�ł́A7���ԕ��ς̐V�K�����Ґ������̂����_��1500�l���A���@���Ґ����A����1�����Ŕ{������Ȃǂ��Ă��āA���Ƃ́u����A��Ò̐�����@�ɒ��ʂ���v�Ǝw�E���Ă��܂��B
�����s�����̂��t���œs���̈�Ë@�ւɑ������ʒm�́A�R���i���җp�̕a��������Ɋm�ۂ���悤�v��������̂ŁA�~�}��Â̏k�����~�A�\���p�̉����A�f�Ë@�\�̏k���Ȃǒʏ�f�Â̐�������������悤���߂Ă��܂��B�����s�����݁A�m�ۂ��Ă���R���i�a����5967���ł����A����𗈌�6���܂łɌv��̍ő吔�ɂ�����6406���܂ő��₵�����l���ŁA�����ɂ��A��Ë@�����ɐ�������J�Â�����j�ł��B
�����r�m���u������Əd�ǎ҂������Ă��� �Ⴂ�l�Ƀ��N�`�����v�@7/27
�����̋}�g�傪�����V�^�R���i�E�C���X�ւ̑Ή��ɂ��āA�����s�̏��r�m���͋L�Ғc�ɑ��u�a���̊m�ۂ�i�߂Ă���B������Əd�ǎ҂������Ă���̂��C�ɂȂ�B�����A26���������҂̂���65�Έȏ�̐�߂銄����2���ŁA�v�͎Ⴂ�l�ɑ������N�`����ł��Ă��炤���Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁA�I�����s�b�N�̑I���W�҂̊����m�F���������ł��邱�Ƃɂ��āu�g�D�ψ�����\���鐔���̂������������͓��{�̊W�҂Ƃ������ƂŁA����𑫂��グ�Ė����A����̂͂ǂ������Ӗ�������̂��Ǝv���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
����t���،���H�c��`�W�҂̊�����������̔ߖ@7/27
���{�l�I�肪���X�Ƌ��⓺�̃��_�����l�����A2�x�ڂ̓����ܗւ̗��j������ł���B���̈���A�����s�̐V�K�����Ґ����A��1000�l��D�ɒ����钆�A��Ì��ꂪ�N�����Ă��Ă���B�s���̓��@���҂�7����{��1500�l�䂩��킸��4�T�ԑ��炸��2700�l��ɋ}���B�ی����œ��@������߂��ꂸ�A�s�ɓ��@�������������܂��1�������茏����1�J���O��50������184���ւ�3.7�{���������B�����s�̌����̗z������10�����A���������̃X�e�[�W4�������Ă���B��@�������܂钆�A�ܗ֊W�҂̊����g������ɂȂ��Ă���B�����ܗցE�p�������s�b�N���Z���g�D�ψ���ɂ��ƁA7��1���ȍ~�̗v�����Ґ���148�l�ɂ̂ڂ鎖�ԂƂȂ��Ă���(7��26�����_)�B�����������A���x�͊C�O������W�҂��}������錺���A��`�]�ƈ��̊����҂̑��������O����n�߂��B�H�c��`�߂��̕a�@�ɋΖ����邠���t�́u�H�c��`�]�ƈ��̐V�^�R���i�������҂������Ă���v�Ə،�����B�H�c��`�́A���c��`�ƕ��сA�����ܗւ̑I��c����W�҂��吨�}������Ă���B
����`�̑����Ŋ�������l������
���̈�t�͉H�c��`�̂��铌���s��c����̑����a�@�Ń��N�`���O���┭�M�O����S�����Ă���B��t�ɂ��A7���㒆�{����A�H�c��`���̃��X�g�����]�ƈ���A�A���҂��ē�����O�����h�X�^�b�t�ȂNj�`�̑����Ŋ�������l�X�̊ԂŐV�^�R���i�������҂������Ă���Ƃ����B��t��26���A�M�҂̎�ނɑ��A�����b�����B�u�������M�O���ɓ�����7�����{�A3�l�̕���PCR����������2�l���z���ł����B����1�l���H�c��`�œ����Ă�����ł����B���̑O�̏T���疾�炩�ɗz���Ґ��������Ă��āA����1�l��PCR�����ŗz�����������Ă��܂����B�H�c��`�W�҂̊����������Ƃ����̂͊Ō�t����������Ă��܂��v���̋�`�߂��̑����a�@�ŁA��`�W�҂̃R���i���҂������n�߂��̂́A���傤�NJC�O���烁�f�B�A��I��c�A���W�҂炪�H�c��`�Ɋ��ɖ{�i�I�ɓ������Ă��������Əd�Ȃ�B����7��26���ɔ������ꂽ�������wHanada�x�̃C���^�r���[�̒��ŁA�����ܗ֊J�Âɂ���ĐV�^�R���i�̊������g�傷��Ƃ̔ᔻ�ɂ��āA�u���N�`���ڎ�Ґ����ɂ߂ď����ɑ����Ă��邽�߁A���̌��O�͂�����Ȃ��Ǝv���v�Əq�ׂ��B����ɑ��A���̈�t�́u�����I�ɓ����ܗւɔ����l�������ŁA�H�c��`�W�҂̊����������Ă���ƍl�����܂��v�Ǝw�E����B�M�҂��H�c��`�̂����c�抴���Ǒ�ۂɓd�b��ނ����Ƃ���A11��������̐V�K�����҂�7��1�����_�ł�23�l���������A7��20�����_�ł�3�{�߂���68�l�ɑ����Ă���B�Ȃ��A�M�҂́A�H�c��`�߂��ɂ��镡���̑��̕a�@�ɂ��d�b��ނ����݂����A�d�b���ʂ��Ȃ�������A�d�b���ʂ��Ă����҂̎��`���𗝗R�ɒf��ꂽ�肵���B
���H�c��`�́u�o�u�������v�͂���Ȃɂ��ɂ�
�����������{�Ⓦ���ܗցE�p�������s�b�N���Z���g�D�ψ���́A�V�^�R���i�̊����g��h�~��ł���u�o�u�������v�̐Ǝコ���A�����w�E����Ă����B�u�o�u�������v�́A�C�O����̑I�����W�҂���ʎs���ƐڐG�����Ȃ��Ƃ������́B�����u�I��A�W�҂͈�ʍ����ƌ����Ȃ��v�Ƌ������Ă����B�������A���̃o�u���͑I��c�������̉H�c��`�Ŏ�����A���Ă���B�M�҂͊C�O�I��c�̗������s�[�N���}���Ă���16���A�ނ炪��������H�c��`��3�^�[�~�i�����ې��������r�[����ނ��Ă���B�������r�[��K���ƁA�����ꏊ�Ől���������Ԃ��Ă����B������Ȃ��قǂ̑吨�̉p���ƃA�����J�̑I��c���M�҂̖ڂ̑O���������ƕ����Ēʂ�߂��čs�����B�I��c�̓X�^���V����(�d��_)�łȂ��ꂽ���x���g2�{�̊Ԃ�i��ł������B���ꂪ�I��c�ɂƂ��Ă̓���(�ʘH)�ɂȂ��Ă����B�������A�������ׂ̗ɂ́A�X�[�c�P�[�X�������ĕ�����ʋq�̎p��������������ꂽ�B�M�҂��z�����Ă����u�o�u�������v�Ƃ͐������Ȃ肩������Ă����B�x���g���z���ĈႤ���[��������Ă͂��߂�A�Ƃ������P�Ȃ�X��̋敪���x�̕������������B
�܂��A�X�^���V�����Ŏd��ꂽ�x���g�̓����́A���o�Ⴊ���җp�̗U���u���b�N��ʂ����߁A�Ƃ���ǂ���q�����Ă��炸�A�r��Ă���B���̂��߁A�I��c���ʂ����シ���Ɉ�ʋq�������ꏊ��ʂ�Ƃ����u���������v�������Ă����B�����Q�[�g�O�ɂ����ʈē����̎�t�̏����Ƃ��炭�G�k�����B�\���ɑł������Ă���u����Ŗ{���Ƀo�u���ƌ�����̂ł��傤���v�Ɩ₤�ƁA�u�R��{�̎d��ł�����ˁB����Ȃɋ߂��œ�����C���z���Ă��܂����v�ƐS�z�����ȕ\��Řb�����B���̏����̓��f���i�̃��N�`�����܂�1���ڎ킵�Ă��Ȃ��Ƃ����B�u����ȋ߂��œ����Ă���̂ɁA���N�`�����܂����Ƃ͌ٗp�ҐӔC������܂��ˁv�Ɩ₤�ƁA�����́u�����v�Ƌ������肾�B���̎�t�������S�z���闝�R�͂悭�����ł��邾�낤�B�V�^�R���i�̓G�A���]��(��C���ɕ��V����ő̂�t�̗̂��q�̂���)�ɂ���Ċ������邱�Ƃ��������Ă��邩�炾�B�����ǂ̐��Ƃ̓E�C���X���܂ރG�A���]�����z�����݂₷���Ȃ�3��(���A���W�A����)�ɒ��ӂ���悤�Ăъ|���Ă���B�{���́A�����قɂ���悤�Ȑ����ň͂܂��悤�ȑI��c��p�̒ʘH������悢�̂����A����͉H�c��`�ł͕����I�ɖ������B�C�O�̃X�|�[�c�C�x���g�ł��o�u�������͍̗p����Ă��邪�A������͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B���N1���ɃG�W�v�g�ōs��ꂽ�n���h�{�[���j�q�̐��E�I�茠���Q�l�ɂȂ�B�����V����2��9���̋L���ɂ��ƁA�n���h�{�[���̓��{��\�c���u��H�ŃJ�C�����肷��ƁA�����H�ɂ͂��łɃo�X���҂��Ă����B�����ŏ�荞�ނƁA�z�e���܂ʼn^�ꂽ�v�Ƃ����B�u��`�ɒ����Ă���A�o�u���ȊO�̏ꏊ�́A�قړ���ł��Ȃ��ł��ˁv�B�n���h�{�[�����{��\�̎叫�A�y�䃌�~�C�Ǘ��͂����������Ă���B���{�́u�o�u�������v�̓G�W�v�g�Ɣ�ׂāA���܂�ɂ��ɂ��B�c�O�Ȃ���A�H�c��`�W�҂Ɋ����҂������Ă���Ƃ̏،��ɂ��[����������B
����c��ɂ͕ی�����1�J�������Ȃ�
�ċx�݂�ܗւ��}���A�H�c��`�ȊO�ł��l�̈ړ���ڐG�������Ă���B���~�̋A�ȃV�[�Y���ɂȂ�ΐl���͉������邾�낤�B�u�l��70���l�]���������c��ɂ́A�ی�����1�����Ȃ��BPCR�����������o�H�̒ǐՂ��S�R�ǂ��t���Ă��Ȃ��B�ҏ��ɂ��M���Ǒ����ς��B�����A�I�����s�b�N�ǂ���ł͂Ȃ��B�ߘJ�ȂǂŃ����^��������Ă����Ï]���҂������v�B�O�q�̈�t�͂��������i�����B��Ò̐����N�����钆�A���������������A�ܗւ����s��������̂́A���d�Ƃ����ق��Ȃ��B���̍s�ׂ̃c�P���̂́A����̈�Ï]���҂ł���A��ʂ̍������B�u�������ł��ܗ֊J�Áv�ł͂Ȃ��A�l�X�̖��ƈ��S�ƌ��N���������ŗD��Ƃ������Ƃ��A���{���{�ƍ��ۃI�����s�b�N�ψ���͖{���ɗ����ł��Ă���̂��낤���B
���R���i�g��@�[���ȓ����@�J�Ò��̌ܗւ͒��~���@���r���L�ǒ��@7/27
���{���Y�}�̏��r�W���L�ǒ���26���A������ŋL�҉���A�����s���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���25���ɓ��j���ł͉ߋ��ő��1763�l���L�^�������Ԃւ̔F�������A�a���g�p����44���ɒB����ȂLj�ÂЂ������N���Ă���Ƃ��āA�u���̂܂܂ł͓������͂��ߎ�s���ň�Õ���Ƃ������ԂɂȂ肩�˂Ȃ��[���ȏɂ���v�Əq�ׁA���߂ĊJ�Ò��̌ܗւ̒��~�����߂܂����B
���r���́A�����s�̏d�ǎ҂̕a���g�p����18���Ƃ���Ă��邪�A�u�d�ǎҁv�ɂ��ēs�̊�ł͐l�H�ċz���d�b�l�n(�̊O�����^�l�H�x)���g�p���Ă���ꍇ�Ɍ��肵�Ă��邪�A���̊�ł͂h�b�t(�W�����Î�)��g�b�t(���x���Î�)�Ŏ��Â��Ă��銳�҂��܂߂Ă���Ǝw�E�B�u25���̓����s�́w�d�ǎҁx72�l�́A���̊�ɓ��Ă͂߂��678�l�ɂȂ�B�d�Ǖa���g�p�������łɃX�e�[�W4�������������v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A��Ë@�ւ�����u�x�b�h�����t�ɋ߂��v�u���@�������Ȃ��v�Ȃǂ̐������A����×{�҂��}�����Ă���Ƃ��āA�u�����ł͈�ÂЂ��������łɋN���Ă���v�Ƃ̔F�����d�˂Ď����܂����B
���r���́A���{���Y�}�̎u�ʘa�v�ψ�����22���Ɂu������邱�Ƃ��ŗD��ɂ��闧���h�邪���т��A�J��r���ł����~�����f���邱�Ƃ����ߑ�����v�Ƃ̐����\�������ƂɌ��y�B�u���܂̊������l����A�������\���_��������ɐ[���ɂȂ��Ă���v�Ƌ������܂����B
�܂��A�u���{�̒�������w�����s�œ��@���ׂ��l�����@�ł��Ȃ��悤�ȏɂȂ�������̒��~���l����ׂ����x�Ƃ̔������o�Ă��邪�A�d�ǎ҂����@�ł��Ȃ��Ȃ鎖�ԂɂȂ�����A��x�ꂾ�v�Ǝw�E�B�ܗ֑I��ȂNJW�҂�153�l���̊����҂��o�Ă��邱�Ƃ������A�u(����������)�w�o�u���x�̕���͖��炩���v�Ƃ��āA�u���̐[���Ȏ��Ԃ̂��ƂŁA�����ŗD��ɂ��A�R���i��ɑS�͂��W�����ׂ����Ƃ������ꂩ��A�ܗւ̒��~���A�����ēO�ꂵ��������A���N�`���̈��S�Őv���Ȑڎ�A��K�͂Ȃo�b�q�����A�\���ȕ⏞�A��Ë@�ւɑ���S�ʓI�ŋ��͂Ȏx�����������߂Ă��������v�ƕ\�����܂����B
����t���Ŋ����m�F�ő� �}�g��̏́@7/27
��t���ł�26���A�ߋ��ő��ƂȂ�509�l�̊������m�F���ꂽ�Ɣ��\����܂����B1�T�ԑO��19�����j�����275�l�����A26���܂ł�1�T�Ԃ̕��ς͑O�̏T��1.37�{�ƁA�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B����23�����_�ł̂o�b�q�����̗z�����́A10.65����1�T�ԑO���3�|�C���g�ȏ�A1�����O���6�|�C���g�ȏ㍂���Ȃ��Ă��܂��B
26�����_�œ��@���̐l�͏d�ǎ�21�l���܂�590�l�ŁA��p�a���̎g�p����46.3���ƂȂ��Ă��܂��B����×{���̐l��1461�l�A���@��z�e���×{�̒������̐l��247�l�ŁA�����1�T�ԑO�Ɣ�r����ƁA���@���Ă���l��1.1�{�A����×{���̐l��1.8�{�A�������̐l��1.5�{�ɑ����Ă��܂��B�܂�1�����O�Ɣ�r����ƁA���@���̐l��1.6�{�A����×{���̐l��5.5�{�A�������̐l��2.1�{�ɑ����Ă��܂��B
��t���̂܂Ƃ߂ɂ��܂��ƁA�l��10���l�������26���܂ł̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂̐��́A���S�̂ł�36.22�l�ł����A���ɓ����s�ɗאڂ��錧�k�����ł́A�����X�����ڗ����Ă��܂��B
�D���s��54.87�l�A�s��s��52.32�l�A���s��43.32�l�ȂǂƂȂ��Ă��āA���{�̕��ȉ�ł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ��Ƃ��Ă���25�l��傫�������Ă��܂��B�����1�T�ԑO�Ɣ�r�����10�l�ȏ�A1�����O�Ƃ̔�r�ł�30�l����40�l���x���ꂼ�ꑝ���Ă���ł��B
���k�����̕a���g�p���͌����ōł��������ŁA��T21�����_�ł��ł�50�����Ă��āA���̌�A����ɂЂ���������Ԃ��i��ł��邨���ꂪ����܂��B
�����{�I��c�W�ҁg���̗z���h�c�ܗ֒������g�呱���@7/27
�I�����s�b�N�̈���ŁA�����g�傪�����Ă��܂��B
���g���j�ő��h����1492�l����
�����s�E���r�S���q�m���F�u�������ŃI�����s�b�N����������Ƃ������Ƃ����ǁA�l����}���Ă����ȂǁA�F��Ȍ��ʂɂȂ��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��v26���A�����s�ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�1429�l�ŁA��T���j�����A702�l�����܂����B���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�A�����7���A����1000�l�����ł��B�d�ǂ̊��҂́A�O�̓�����6�l�����āA78�l�B���@���҂́A�O�̓����85�l�����A2717�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����{�I��c�W�ҁg���̗z���h
���W�҂̊������������ł��܂��B�g�D�ψ���́A�V���ɊC�O�̑I��3�l���܂ށA16�l�̊����\���܂����B�܂��A���{�I��c�̊W��1�l���A�V�^�R���i�̌����ŁA�z���ƂȂ������Ƃ�������܂����B�����Ԓ��ɁA���{�I��c�̊W�҂̊��������������̂́A���߂Ăł��B
����t���E���g�[���H�h��2�l����
���������ł͂���܂���B��t����26���A���������̊����҂Ƃ��ẮA�ߋ��ő��ƂȂ�509�l�̊������m�F����܂����B���̐�t���ł́A���̐E����6�l���A16���̌ߌ�8��������17���̌ߑO0������܂ŁA�s��s���̃J���I�P�X�ň�������H�����Ă������Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B�܂��A���̂���2�l�́A�V�^�R���i�ւ̊������m�F����܂����B����4�l�ɂ��ẮA26���̎��_�ŁA�̒��s�ǂ͑i���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B6�l����H���������܂߁A�s��s�̈��H�X�Ȃǂɂ́A������c�Ǝ��ԒZ�k�̗v�����o����Ă��܂��B
�������g��̍��6�s���A�x�����ɒlj��@�ً}���Ԑ錾�̗v���������@7/27
��쌳�T�m����26���A�Վ��̋L�҉���J���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��X���ɂ���є\�A���R�A���ԁA����A�K��e�s�Ƌ{�㒬��5�s1����V���Ɍ��Ǝ��́u�x�����v�Ɏw�肵���Ɣ��\�����B�x������20���Ɏw�肳�ꂽ��ˁA�g�염�s�ƍ��킹�A�v7�s1���ƂȂ����B�m�ەa���g�p����6������20������Ă������A�V�K�����҂̑����ƂƂ��ɏ㏸�𑱂��A25�����_��47�E4��(789�l�^1666��)�B�����ً}���Ԑ錾���o���ڈ��Ƃ���w�W�u�X�e�[�W4(��������)��50���ȏ�v�ɔ����Ă���B
�m���́u�}���̏͘A�x���ς��Ȃ��B�S�̂������グ��v���Ƃ��āA�������痈�����̂��A���x�͌����ʼn��ɍL�������B���݁A�ً}���Ԑ錾�̗v�����܂߂Ē����Ō������Ă���v�Əq�ׁA�߂��A���Ɖ�c���J���A���݂̊���������Ή��Ȃǂɂ��Ĉӌ����Ƃ����B
�����Ǝ��Ɏw�肷��u�x�����v�́A�n��I�ȗz���҂̏W���h�~�Ǝs�������h�~�A�N���X�^�[(�����ҏW�c)��̂��ߐ݂���ꂽ�[�u�B�s������1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�z���Ґ���1���ł�15�l�ȏ�ƂȂ����ꍇ�Ȃǂ̏����������ꍇ�Ɏw�肵�A���Ɖ�c�ɂ܂h�~���d�_�[�u�̑[�u���w��̉ۂȂǂ����₷��B
�����ł�7��20������8��22���܂ŁA�������܁A����A��z�A����A�t�����A�����A�z�J�A�n�A�˓c�A�����A�u�A�a���A�V���A�����A�x�m���A�O���A�߃P���A�ӂ��ݖ�e�s�ƈɓށA�O�F�����̌v20�s�����A�܂h�~���d�_�[�u���Ɏw��B�����20�������ˁA�g�염�s���x�����Ɏw�肵�A���[�u���ƂȂ�Ȃ��悤���ӂ��Ăъ|���Ă����B
20�`26����1�T�Ԃ̌����V�K�z���҂͌v2849�l(1������407�l)�B22���ɂ�1���ȗ��A���N�Ԃ��500�l���A�ߋ�3�Ԗڂɑ���510�l�ƂȂ����B
�������350�l���R���i�����@�ߋ��ő����X�V�@���o�E���h�}�g��@7/27
���ꌧ����27���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�����l��350�l���錩�ʂ��ł��邱�Ƃ����������B�����̊W�҂����炩�ɂ����B������1��������̉ߋ��ő�(5��29����335�l)�����鐔�ƂȂ�B
�O�T�̓����j��(7��20��)�̐V�K�����҂�154�l�ŁA2�{�ȏ�̋}���B�ʏ�f�j�[�m����26���̋L�҉�Łu���������o�E���h(�Ċg��)���A�}�g��ɓ]���Ă���v�Ƃ��A�x�����Ăъ|���Ă����B�@
����t���ŐV����405�l�����@28���ɂ��ً}���Ԑ錾�𐭕{�ɗv���� �@7/27
��t�����ł�27���A�V����405�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�B�F�J�r�l�m���́A�����҂̑������A28���ɂ����{�ɋً}���Ԑ錾��v������l�����������B
�܂����́A������������ݏZ��80��j�����҂�70�㏗�����҂����S�����Ɣ��\�����B�j�����ʂ̎����̂��ߓ��@���Ă����a�@�ŃN���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă����Ƃ����B
���ɂ��ƁA�V���Ȋ����҂̂����A1�l���d�ǁA11�l�������ǁB
�Y���s�ł͓����܂łɁA�ۈ牀�u�|�s���Y�i�[�T���[�X�N�[���Y���v�ʼn�����5�l�A�u�{�[���o���G�X�^�W�I�v�Ő��k�̏����w����6�l�̊�����������A���̓N���X�^�[�����������Ɣ��f�����B�܂���t�s��t��ł́A�N���X�^�[���m�F����Ă����c�t���ŐV���ɉ���20�l�̊����������B�����̊����҂͌v67�l�ƂȂ����B
�������s�̃R���i�V�K�����ő��@���{�̑��l�܂�@7/27
�����s��27���̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ����ߋ��ő���2848�l�ƂȂ����B���{�������s��12������ً}���Ԑ錾�߂���2�T�Ԉȏオ�o�߂������A�����͂������C���h�^�ψي�(�f���^��)�̖���(�܂�)������A���ʂ��\��钛���͂Ȃ��B��͎�l�܂�Ɋׂ��Ă���A���N�`�����ʂƁA��@����w�i�ɂ��������̍s���ϗe�Ɋ��҂��邵���Ȃ����B
�u�����̊F����ɂ�����ẮA�s�v�s�}�̊O�o�͔����A�ܗւ̓e���r�ȂǂŊϐ킵�Ăق����v
���`�̎�27���A�L�Ғc�ɂ������A�O�o���l���d�˂ČĂт������B�u���������܂Ől���͌������Ă���v�Ƃ��q�ׂ����A�������Ƃ������ʂɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��B
��̒��ł�����H�X�̎�ސ������s���l�܂肪���Ă��B�c�����v�����J������27���A�L�Ғc�Ɂu�v���ɉ������A���R�[�����o���Ă���X���U�������v�Ƃ��ĉ��߂ċ��͂����߂����A���Z�@�ւ��̎��Ǝ҂�ʂ����u���������v���j���Ҕ����œP��ɒǂ����܂ꂽ�ꌏ������A���͓͂����ɂ����Ȃ��Ă���B���{�W�҂���́u�����ł肪�Ȃ��v�Ƃ̐����R���B
�錾�ɏ����������h�~���d�_�[�u��K�p���̎�s��3���ł������g�傪�����Ă���A�a���g�p���̎w�W�͍ł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�ɔ���B���{�͐錾�ւ̈ڍs���܂ߑΉ��𔗂��Ă��邪�A�u�d�ǎ҂͌����Ă���v(��������)�Ɣے�I�Ȍ������Ȃ������B
�������̐V�K�����Ґ���2848�l�c�u�ً}���Ԑ錾���ĉ��v�̐� 7/27
7��27���A�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ���2848�l�ɂȂ����ƕ�ꂽ�B�l�b�g�Ŕg����Ă�ł���B
�����s��26���ɐV���Ȋ����Ґ���1429�l�ƕ�ꂽ����B����͑O�T���j���̂��悻2�{���̐��ł���A���������B������������27���A�w�����ʐM�x�ɂ��Ɠ����s�̐V�K�����Ґ���2848�l�ɁB����܂ł̍ő���1��7����2�C520�l���������߁A300�l�ȏ�����邱�ƂƂȂ����Ƃ����B
����12���A�����s�ɋً}���Ԑ錾�����߂��ꂽ�B�����4�x�ڂƂȂ邪�A����ȂȂ��V�K�����Ґ��͉ߋ��ő��Ɂ\�\�B���̂��߃l�b�g�ł́u�ً}���Ԑ錾���ĉ��H�v�Ƌ^�⎋���鐺���オ���Ă���B
�s�����Ă����ً}���Ԑ錾�o�Ă��ˁH�t�s�����ً}���Ԑ錾�Ƃ��Ӗ��Ȃ������t�s�����ً}���Ԑ錾�����Ȃ��Ⴂ���Ȃ��ˁI�c�����H�����o�Ă�́H�H�H�H�t�s�ً}���Ԑ錾���ĉ��Ȃ낤�c�t
���r�S���q�s�m��(69)�͍�N12���A�����ܗւɂ��āu�l�ނ���ۂƂȂ��āA���̃R���i�ɑł��������Ƃ���(����)�F�l�Ɓw�v���X�����x�̓��X��ςݏd�ˁA���𐬌��ɓ����Ă��������v�Ɣ����B����ɍ���15���ɂ́wBloomberg�x�̎�ނɑ��āu�����ܗւ́A���E���V�^�R���i�����ǂ������N���������ɗ������������ƒc�����钆�A��]�̌��ƂȂ�ɂ߂ďd�v�ȃC�x���g���v�ƌ���Ă���B
�������ł����������A��]�̌����A�܂��܂������Ƃ���ɂ���悤���B
����������A�Ȃ���30�㏗���z���@������18�l�����A�����͌o�H�s���@7/27
���Ɗs��27���A����8�s���ȂǂŌv18�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B�V�K�����҂�10�l������̂�2���A���B�����Ґ��͗v9482�l�ƂȂ����B
�V�K������18�l�̂����A9�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B
�����s��30�㏗���͌����̎��ƂɋA�Ȓ��ɑ̒��������Ȃ�A�����̌��ʁA�z�������������B���́A�A�Ȃɂ��ĐT�d�ɔ��f���A���ɋً}���Ԑ錾�̑Ώےn����܂ފ����g��n�悩��̋A�Ȃ͎��l����悤���߂Ă���B
26�����_�̓��@���҂�71�l�ŁA�a���g�p���͑O����0�E9�|�C���g����9�E1���B
�V���Ɋm�F�����N���X�^�[(�����ҏW�c)��g�債���N���X�^�[�͂Ȃ������B
�s�̐E��֘A������10�l�̃N���X�^�[�́A�V���Ȋ����҂��m�F���ꂸ�I�������B
�V�K�����҂̋��Z�n�ʂł́A�s7�l�A��_�s�A�H���s�A���s���e2�l�A�������s�A�e�����s�A����s�A�H���S�}�����A�����s���e1�l�B�N��ʂ�10�Ζ�����10�オ�e1�l�A20��9�l�A30���40�オ�e2�l�A50��A60��A70�オ�e1�l�B�@
�@ |
 |


 �@
�@ |
�����[�����g��s��3�� �錾�̗v���o�����Α��₩�Ɍ����h�@7/28
�V�^�R���i�E�C���X����߂���������[�����́A�ߑO�̋L�҉�ŁA��s����3���ł͐V�K�����Ґ����������Ă��邱�Ƃ���A�����Ȃǂ̔F�������L���Ă���Ƃ��āA�ً}���Ԑ錾�o����悤�v�����o�����A���₩�Ɍ�������l���������܂����B
���̒��ŁA�������[�����́A�ً}���Ԑ錾���o����Ă��铌���ɉ����āA��s���̍�ʁA��t�A�_�ސ��3���ł́A�V�K�����Ґ��̑����������Ă��邱�Ƃ���A27���A�W�t���ŁA�����x���������L�����Ɛ������܂����B
���̂����ŁA��t���̌F�J�m�����A�ً}���Ԑ錾�̔��o�𐭕{�ɗv������l���������Ă��邱�Ƃɂ��āu��t�����܂�3���Ƃ̊ԂŁA�������Ò̐��̏̂ق��A��̌��ʂȂǂ��܂߁A�F���̋��L����}���Ă���B���ɗv�����o�����A���₩�Ɍ������s���A��{�I�Ώ����j�ɂ̂��Ƃ��Ĕ��f���Ă������ƂɂȂ�v�Əq�ׂ܂����B
�����āA���������A��l���A�����Ԃ̉���T����ق��A�����I�����s�b�N�͎���Ŋϐ킷��ȂǁA�s�v�s�}�̊O�o�����l����悤�A���߂ċ��͂��Ăт����܂����B
�܂��A�L�Ғc����I�����s�b�N�ւ̉e�������₳�ꂽ�̂ɑ��u�����s�̖�Ԃ̑ؗ��l��������ƁA�O��ً̋}���ԑ[�u�̍ۂƔ�ׂāA�ɂ₩�Ȍ����ƂȂ��Ă�����̂́A�����������Ă���B�C�O���痈�������I�����W�҂ɏd�ǎ҂��������Ƃ����ɂ��ڂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��v�Əq�ׁA���������A��ɖ��S�������l���������܂����B
������ �ً}���Ԑ錾�̎�������ܗ֊J�Âł̊�����ȂǂŘ_�� �@7/28
�����s���̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��ߋ��ő��ƂȂ�Ȃ��A����ł�28���A��R�����s���A�ً}���Ԑ錾�̎����������߂邽�߂̕����A�I�����s�b�N�̊J�Âɔ���������Ȃǂɂ��Ę_�킪���킳��錩�ʂ��ł��B
����ł�28���A�O�c�@���t�ψ���ŕ�R�����J�Â���A�͖�K�����v�S����b����o�ύĐ��S����b�炪�o�Ȃ��A�V�^�R���i�E�C���X��Ȃǂɂ��ė^��}�̎��^���s���܂��B
���̒��ŁA�^�}���ً͋}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̎����������߂邽�߂̕���ɂ��Đ��{�̌��������������Ƃɂ��Ă���ق��A���E�I�Ȋ����g�傪�����Ȃ��ŁA�I�����s�b�N���J�Â���Ӌ`����ɔ�������������߂Đ�������悤���߂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
����A��}���͈��H�X�ւ̋��͋��̎x���̒x�ꂪ�A���Z�Ȃǂ̎��l�v���̌��ʂ̒ቺ�������Ă���Ƃ��ĉ��P�����߂�ق��A�I�����s�b�N�W�҂̊O�o���[�����\���Ɏ���Ă��Ȃ��ȂǁA������͖�肪�����ƒNjy������j�ŁA�_�킪���킳��錩�ʂ��ł��B
����s��3���A�錾�v���֒����@�R���i�����}�g��� �@7/28
��ʁA��t�A�_�ސ�̎�s��3����28���A�V�^�R���i�E�C���X�����̋}�g����A�ً}���Ԑ錾�̔��߂𐭕{�ɗv�����钲���ɓ������B�_�ސ쌧�̍���S���m���́u���A�ǂ�Ȍ`�ō��ɗv�]����̂��������Ă���v�ƕw�ɏq�ׂ��B�u3���ł͂Ȃ��A���Ƃ̒������B�����ǂ����f���邩�̒������s���Ă���v�Ƃ��āA���{�̑Ή����悾�Ƃ̔F�����������B
�������M���[�����͋L�҉�Łu�v�����o��A���₩�Ɍ������Ĕ��f����v�Əq�ׂ��B
��ʌ��̑�쌳�T�m�����u���{���t�A�_�ސ염���Ƌ��c���Ă���B�ۂ��܂߂Ē����̍ŏI�i�K���v�ƌ�����B
���u�R���i����v�u���l���v�����炩�ɁA��Ƃ̏o�Η��͏㏸�X���@7/28
���ً}���Ԑ錾���J��Ԃ����قǏo�Η����㏸���Ă����X��
�ً}���Ԑ錾�����o����Ă��A�o�Η����������Ă��Ȃ����Ƃ��AIoT�����p������Ƃ̓��ޏo�f�[�^�̏W�v�Ŗ��炩�ɂȂ����B
������Ѓt�H�g�V���X(Photosynth)���A�S���̗v5000�Јȏ�̊�Ƃɓ������Ă���uAkerun���ގ��Ǘ��V�X�e���v��IoT�f�[�^���W�v�����Ƃ���A2020�N3��2����100�Ƃ����ꍇ�A�e�T��1��������̏o�ΎҐ��̊����́A�����s�ł́A1���(2020�N4��7���`5��25��)�ً̋}���Ԑ錾���ɂ�30.4���Ƒ啝�Ɍ����������̂́A2���(2021�N1��8���`3��21��)�ً̋}���Ԑ錾���ɂ�48.5���Ƒ����B3���(2021�N4��25���`6��20��)�ɂ�54.4���Ƃ���ɑ����������Ƃ��킩�����B
�܂��A2��ڂ�3��ڂ̐錾���o���̏o�Η��́A�ً}���Ԑ錾����������Ă�����ԂƔ�r���Ď�������邪�A����قǑ傫�ȍ����Ȃ����Ƃ���������ɂȂ����B
�����āA���̏́A4��ڂً̋}���Ԑ錾�����o����Ă��錻�݂��ς��Ȃ��B�ŐV�̏W�v�ƂȂ�7��18�������1�T�Ԃɂ�����o�Η���58.5%�ƁA�ނ���㏸�X���ɂ���B
���Ԃł́A�u�錾����v�u�R���i����v�u���l���v�ȂǂƂ��������t���g���Ă��邪�A�ً}���Ԑ錾�����o����Ă��A�o�Η����������Ȃ��Ƃ��������܂�Ă��邱�Ƃ��A���̃f�[�^��������炩�ɂȂ��Ă���B
���l�̌��ʂ́A�����s�ȊO�ł������Ă���B
������������s�ً̋}���Ԑ錾���o�̃^�C�~���O�ł̏W�v�����A���{�̏o�Η��́A1��ڂɂ�34.9%���������̂��A2��ڂ�57.2���A3��ڂ�50.9���Ƒ����B�����s�Ƒ��{�������A45���{���ł̏o�ΎҐ��́A1��ڂ�49.1���ƁA���Ƃ��ƍ��������������Ă������A2��ڂɂ͂���ɑ�����62.3���ƂȂ�A3��ڂɂ�67.8���ƁA��������A�R���i�O�̖�3����2�̐����ō��~�܂肵�Ă���B
���o�ΎҐ���7���팸�̗v�������Ԃ͉���
�����s�ł́A4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���A7��12���`8��22���܂ł����ԂŁA���o���Ă���Œ������A���̑O��̊��Ԃ̃f�[�^���A���������ڂ������Ă݂悤�B
����ɂ��ƁA�����ł́A�ً}���Ԑ錾���o�O��6��27���̏T�ɂ�59.6%�A7��4���̏T�ɂ�59.7%�ƂȂ��Ă������A�ً}���Ԑ錾�����o���ꂽ7��11���̏T�ɂ�57.7%�Ǝ�����B�����A7��18���̏T��58.5%�ƂȂ��Ă���A�ŐV�T�ł́A�ً}���Ԑ錾���o�O�̐����ɖ߂��Ă���B
�܂��A���ł́A���ꂼ��59.1%�A57.4%�A57.0%�A59.2%�ƁA��������ˑR�Ƃ��č��������Ő��ڂ��Ă���B
����ɁA�����A���ȊO�̑S���ł́A6��27���̏T��72.4%�ƁA�o�Η��͍��������ƂȂ��Ă���A���̌��72.4%�A72.5%�A74.1%�ƁA�T��ǂ����Ƃɔ������Ă���B
���{�ł́A�ݑ�Ζ�(�e�����[�N)�̊��p�Ȃǂɂ��o�ΎҐ���7���팸���o�c�A�Ȃǂ�ʂ��ėv���A�����s�ł��T3���A�Ј���7���ȏ�̃e�����[�N�����{����������Ƃɏ�������x������Ȃǂ̎{����u���Ă���B�������A���������ڕW�ɑ��Ď��Ԃ͑傫�Ș�����������B
������ �ߋ��ő�2848�l���� �S����2�J���Ԃ�7000�l�� �@7/28
�����s�ł�27���A�ߋ��ő��ƂȂ�2,848�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�B�܂��A�S���̊����Ґ��́A2�J���Ԃ��7,000�l�����B
27���A�����s�ł́A�V����2,848�l�̊������m�F����A����܂ōő�������1��7����2,520�l��300�l�ȏ����A�ߋ��ő��ƂȂ����B�s�̒S���҂́A�u���ꂾ���������L�����Ă���ƁA�܂�������v�Ƃ��Ă���B����A�s�̊����́A�I�����s�b�N�J����̐l�o�͌����Ă���Ƃ��āA�u�I�����s�b�N�������e�������Ă���Ƃ͎v��Ȃ��v�Ƃ̍l�����������B
���̂ق��A���ꌧ��354�l�A��ʌ���593�l�̊������m�F����A�Ƃ��ɂ���܂łōő��ƂȂ����B
�S���ł́A7,626�l�̊����ƁA13�l�̎��S���m�F����Ă���B
����A405�l�̊������m�F���ꂽ��t���̌F�J�m���́A27���[���A�����̊������������Ă��邱�Ƃ���A�ً}���Ԑ錾��v������l�����������B�_�ސ쌧�A��ʌ��ƈӌ��������A���ʔF���������������ŁA�v���̎葱���ɓ��肽���Ƃ��Ă���B
�������g��A�ܗւɕ��������ŋ������u�ʏ�c�Ɓv�ĊJ�c�u��v���o�@7/28
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ���4��ڂً̋}���Ԑ錾�ŁA��ނ������H�X�ɋx�Ɨv�����o���ꂽ�����B�����A�����ܗւ̊J�����g�@�h�ɒʏ�c�Ƃ��ĊJ���A�����o���Ă���X������B�Ȃ��v�������ꂸ�A�X���J�����̂��B�X���Ɏv�������B
��
�����E�]�ː��̋������B�ߌ�8���߂��ɓX���̂����ƁA�����̋q�łɂ�����Ă����B������̓\�莆�ɂ́A����������Ă����B
�u�ĊJ���܂����v
���̓X�́A���N1����2��ڂً̋}���Ԑ錾�̎����炸���ƓX��߂Ă������A7�����{�ɒʏ�c�Ƃ��ĊJ�����B
�j���X���́u���ł���邨�q����≵���Ǝ҂��������܂����A�ᔻ����邱�Ƃ��o�債�Ă��܂��v�Ƃ��������ŁA�ĊJ�̗��R�������b�����B
�u�ƒ���l����Ȃǂ����킹��Ƌ��͋��ł͂��肸�A������������������Ȃ���ς��Ă��܂����B�����A�����Ƌx�Ƃ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���ĊJ�����f���邩�Y��ł��܂����B�ܗւ��߂Â����ŁA������ᔻ����Ă��J�ÂɌ���������s�̎p�������āA�]�ƈ��Ƃ��b�������ĊJ���邱�Ƃɂ��܂����B���H�X�͈��҈�������̂ɁA�ܗւ��Ɖ����ǂ��ᔻ����Ă��w���S�A���S�́`�x�Ƃ�������Ȃ���ł�����A�����ꂵ���v�������ėv���ɏ]���؍����͂Ȃ��Ƃ����̂��{���ł��B���������Ŋ�������撣��Ȃ���c�Ƃ𑱂������ł��v
���u���N�`���ł��I��������v
�]����̋����H�n�ɂ��鋏�������A7��20������Ȃ��݂̋q�Ɍ��肷��`�Œʏ�c�Ƃ��ĊJ�����B60��̏����X��́A
�u�ً}���Ԃł��ꂾ���l���W�܂�I�����s�b�N������ėǂ��āA��A�������̂��X���_���Ȃ�ăo�J�Șb�͂Ȃ��Ǝv���āA�c�Ǝ��l����߂܂����B��������̂��q��������N�`���ł��I����Ă邵�ˁB�������͋����\�����܂���B���q�����Ă̏����ŁA���܂ł��߂Ă��炨�q�����ꂿ�Ⴄ����ˁv
��A���Ƃ����j���q(61)�́A�u�o�b�n����(IOC�̃o�b�n�)�̐ڑ҂͓��X�Ƃ������A�����N���������ƕ����Ȃ���v�Ə��B
�䓌��ŁA�x�Ɨv�������ꂸ�c�Ƃ𑱂��Ă����������o�c�҂̒j���̂��ƂɁA7����{�A�ߏ��̈��H�X�傪�K�˂ė����B
�u�������ĊJ���邱�Ƃɂ����B���낢�눫�������v
���̓X��͍��N2������A�X�̃C���[�W�������Ȃ邽�߁u�c�Ƃ���߂��ق��������v�ƒ������Ă������Ƃ��������Ƃ����B
�������o�c�҂͌����B
�u(�Ӎ߂�)�����̖ʂŌ��E�����Ă��Ƃł����B���N�`���ڎ킪�L�܂�̂�҂��肾�������ǂ��܂�ɒx���̂ŁA�ܗւ���邱�Ƃ����X���J���܂��ƁB���ǁA���͋������������Ă����Ȃ��X�́A�c�ƍĊJ���������x�����̈Ⴂ�������Ǝv����ł���B���̈�т��A��������ŊJ����X���ǂ�ǂ��Ă��Ă��܂��B�X�Ə]�ƈ������Ȃ�A�������f���Ȃ��Ƃ����Ȃ���������̂ŁA�������͈����ł��������Ȃ������Ōܗւ���������Ƃ́A���H�X�ɂ͂������������Ȃ�ł��v
��������������̂��c
27���ɂ͊����҂��ߋ��ő��ƂȂ�2848�l�ƂȂ��������B�����g��Ɏ��~�߂�������ʏ̒��ŁA�����o���X�Ɍ�����������������l�����Ȃ��Ȃ��B�����A�ܗ֊J�Âɂ���āA�c�Ǝ��l�v���̌��͂�����ɔ��܂����͎̂����̂悤���B
�������o�c�҂́A�����{����R�炷�B�u�j���[�X������ƃ}�X�N�����Ă��Ȃ��I���A�ɉ؊X�Ɉ��݂ɍs�����W�҂�����݂����ł����A��������Ȃ��݂����ł��ˁB���r(�s�m��)������A���������ܗւ̖��ɂ͉�������Ȃ���ł���ˁc�c�B���������H�Ƃ́A����ł��������������ł��傤���v
�����g��u��ÂЂ������łɋN���n�߂Ă�v�O�@���t�ψ����R���@7/28
�O�@���t�ψ����28���ߌ�A��R�����J�����B�����s�ŐV�K�����҂��ߋ��ő����X�V����ȂǁA���~�߂�������Ȃ��V�^�R���i�E�C���X�̑�Ⓦ���ܗւ̑Ή��A���N�`���ڎ�Ȃǂɂ��Ď��^���ꂽ�B�͖쑾�Y�s�����v�S�����A�����N���o�ύĐ��S�����炪�o�Ȃ����B
��13:00�@���t�ψ���n�܂�
�ߌ�1���A���t�ψ���n�܂�A�ŏ��Ɏ����}�̒��R�W�G��������ɗ������B���N�`���ڎ�̏��Đq�˂�ƁA�͖쎁��9�����܂łɃt�@�C�U�[�ƃ��f���i�����킹�āA�u2��2000�������ɍs�����������\�肾�B10������11���ɂ����Ċ�]���鍑���̊F�l�ւ̃��N�`���ڎ�������������v�Əq�ׂ��B
��13:25�@�����̊����ҁu������������v������
��������̌��t����Y��������ɂ������B�����s�Ŋ����Ґ����ߋ��ő����X�V����ȂǁA�ً}���Ԑ錾�̌��ʂ�����Ă��Ă��邱�Ƃɂ��āA�������́u�A�x���A�����������T������C�ɍs���Ă��鎖�������Ǝv�����A�����������A���Ȃ葝����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̌��ʂ����������B�_�ސ�A��t�A��ʂ�3���ɂ��Ă��u�A�x���ɂ��܂��Ă���(������)���������A����(���ʂƂ���)�o�Ă���̂ł͂Ƃ������Ƃ�����v�Ɛ��������B7���ɓ����Đl�o�����ɑ����Ă��邱�Ƃ��e�����Ă���Ƃ����A�u���ɖ�Ԃ̐l���������A���H�̋@����������Ƃ��w�i�ɂ���Ǝv���v�Əq�ׂ��B���`�̎�27���Ɍܗ֒��~�͂Ȃ��Ƃ������R�Ɂu�l���������Ă���v���Ƃ��������_������ƁA�������́u�����͎�̌����X�����v�Ƃ������ŁA���N�t�ً̋}���Ԑ錾�ɔ�ׂ�Ɓu�������͊ɂ₩���v�Ƃ����B
��14:00�@���g���u�����ň�ÂЂ������łɋN���n�߂Ă���v
��������̗M�ؓ��`��������ɂ����A�����s�̐V�K�����҂��ߋ��ő����X�V�������Ƃɂ��Ď��₵���B���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή�́u�ڐG�̋@��ً}���Ԑ錾�ŏ��X�Ɍ����Ă���B�������A���҂���郌�x���ɂ͎c�O�Ȃ��玊���Ă��Ȃ��v�Ǝw�E�����B�����s���ł͓��@���҂����łȂ��A�h���⎩��×{����l�������Ă��邽�߁A�u��Â̂Ђ����Ƃ������̂����łɋN���n�߂Ă���Ƃ����̂���X�̔F���B���{�̎Љ��@�������L���邱�Ƃ����ɏd�v���v�Əq�ׂ��B
��14�F30�@���������u�����_�ł����Ȃ�(��Â�)�Ђ������Ă���v
���Y�̉���S�玁������ŏd�˂āA�����s�̈�Õ���ɂ��āA���{�̔F�������������B�������́u�����ǂ���d�lj�����40��A50��̓��@�҂����������Ƃ܂����Ή��𓌋��s���s���Ă���v�Ǝw�E������Łu�����_�ł����Ȃ�Ђ������Ă��邪�A�R���i�Ή��ƈ�ʂ̈�Â������ł���悤�A�����g���}���邱�ƂɑS�͂������Ă��������v�Əq�ׂ��B���쎁�́u�����閽���������Ȃ���������Ȃ������Ɍܗւ��J����Ă���B�ܗւ͍����̐l���𑣐i���Ċ������g�傷��\��������v�Ǝw�E�B�u�l���}���Ƃ����č����Ɏ��l�����߂Ȃ���A���E�ő�̍ՓT���s���̂͑傫�Ȗ����ŁA�����̋��͂��Ȃ��̂ł́v�Ǝ��₵���B�������́A���ϋq���Z��A�����W�҂̍팸�A�����o���s�����̒l�グ�Ȃǂ���������Łu����܂łً̋}���Ԑ錾���ɔ�ׂ�ƁA(�����҂�)�������͏��Ȃ������̌������݂Ă���B�����݂̂Ȃ���ɋ��͂��Ă�����ĉ��Ƃ�������}���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Əq�ׂ��B
���u�ܗւȂ̂ɉ䖝�����v�@�����ҍő��X�V�œ����̊X�́@7/28
�ܗւ̃��_�����b�V���ɂ킭�����s��27���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����ߋ��ő���2848�l�ƂȂ����B4�x�ڂً̋}���Ԑ錾����2�T�ԁB���܂�Ȃ������g����A�X�̐l�X�͂ǂ��~�߂�̂��B
�a�J�w�O�ɂ���r���ǖʂ̓d���f���B�u�ߋ��ő��v�̃j���[�X���\�����ꂽ����A���_���l���̃j���[�X�ɐ�ւ���Ă����B
�u���o���B���܂ł�葝�������������v�B��t�s����ʋ��鏗����Ј�(20)�́A���������Ă����B����ǂ����Ƃɍݑ�Ζ����`�[�����A�d�Ԃ����G����悤�ɂȂ����Ɗ�����B�u�ܗւł��Ղ胀�[�h�Ȃ̂Ɂw�����h�~�̂��߉䖝���x�Ƃ����͖̂�������������Ȃ����v�ƌ����B
�a�J��ɏZ�ޒj����Ј�(33)���u���������Ȃ�Ǝv���Ă����B�w�撣���Ă������Ґ��͌���Ȃ��x�ƁA�݂�Ȓ��߂Ă����Ȃ����v�Ƙb�����B
���Z�c�ƂƂȂ��Ă���A�����̈��H�X�͌ߌ�7���`8���̎��ԑсA�[�H�ɂ�������Ƃ���T�����[�}���Ŗ��Ȃ��Ƃ����B�u�錾��4��ځB�݂�Ȋ���Ă��Ă���B����ȏ�̉䖝�͂ł��Ȃ��Ǝv���v�B��N�w�Ƀ��N�`���ڎ킪�Z������̂͂܂���ƍl���Ă���B�u��҂ɗD��I�ɐڎ킳����Ƃ����b�����������ǁA���͌ܗֈ�F�ł���ˁc�c�v
���u�ܗւ������ʈ����v�̐���
�ߋ��ő��̂��̓��̊����҂̔����ȏ�́A20�`30��B���c�J��ɏZ�މ�Ј��̏���(22)�́u�܂���҂����҂ɂ����̂��ȁv�Ƃ��ߑ������B�ܗւɂ��l�̓�����O���ɁA�u�������͗��s��A�Ȃ�1�N�ȏ�䖝���Ă���̂ɁA�ܗւ������ʈ����͔[���ł��Ȃ��v�ƕs�������ɂ����B
�u�܂�������Ȃɑ�����Ȃ�āv�ƃV���b�N���Ă����̂́A�߂��ɏZ�ގ��c�ƁA���{���q����(62)�B�Ⴂ����ւ̐ڎ킪�v���悤�ɐi��ł��Ȃ����Ƃ��C�����肾�B�u�����ƂȂ�A����҂͉Ƃɂ����邱�Ƃ��ł���B�d���ȂǂŊO�ɏo��������Ȃ��Ⴂ�l�ɗD�悵�Đڎ킷��ׂ��������̂ł́v�Ƙb�����B
JR�V���w(�`��)�O�́A�T�����[�}����q�ǂ��A���ō��G���A�}�X�N�������ɘb�����ސl�̎p������ꂽ�B���ɂ́u�Ƃʼn䖝����������v�Ƃ����l���B
��Ј��̍����Y�i����(37)�͐E��ڎ�Ń��N�`����2��ڎ킵�A���͂ɂ����������l�͂��Ȃ��B�u���܂Œʂ�̑�����Ă����犴�����Ȃ����ȁv�Ƃ�������ŁA����ɂ��āu�R���i�̕|���͂킩���Ă��邯�ǁA�s����ς���͓̂���̂����v�Ƙb���B
�]����ɏZ�ގ��c�Ƃ̏���(69)�́A�n���Ōܗւ̊֘A�{�݂������Ă����l�q��������Ă����B�ܗւ��n�܂�ƁA�u�X�e�C�z�[���͏I������v�Ɗ����A����܂ł����O�o����@��������Ƃ����B�u�ܗւ������������v���ƁA���������g�傪�������Ăق����Ƃ����v��������v�ƌ�����B
�R���i�Ђ̒��ŁA�x�d�Ȃ�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k���ޒ̎��l�����߂��Ă������H�X�B�X���́A���̎��Ԃɉ����v���̂��B
�����H�X�u�悪�����Ȃ��v
�u�ŋ߂̊�������g��͗\�z���Ă������A�܂�������Ȃɋ}�ɑ�����Ƃ́B�悪�����܂���v
1��~�Ő�����u����ׂ�v�̊X�Ƃ��ėL���ȐԉH��ԊX���X�X(�k��)�ɂ��鋏�����̒j���X��(33)�͂����Q���B
�����g������������邽�߁A��N4����1��ڂ̐錾�ȍ~�A�s�̗v���ɂ͑S�ĉ����Ă����B�����A�R���i�БO�ɔ�ׂ�Δ���グ�͔����قǂɗ������݁A���݂͋x�ƒ����B�u�v���ɉ����Ȃ��X�ւ̑Ή���ܗւł̊����\�h���������̂ł͂Ȃ����B��������������撣���Ă��A�Ӗ����Ȃ��͖̂{���Ɏc�O���v
���ܗ֊֘A�̗z��79�l�@�g�D�ϊ����u�t���܂��܂��v
�����s����1��������ߋ��ő���2848�l�̊����҂��m�F���ꂽ���Ƃ��A�����I�����s�b�N(�ܗ�)���g�D�ψ���̊����́u�ܗւɑ���t���͂܂��܂��������Ȃ邾�낤�B�C���������߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Əq�ׂ��B
���Z�J�n����1�T�Ԃ��o�߂��������ܗցB�g�D�ς�27���̋L�҉�ŁA26�����_�Ŗ�3��8��l���������A�����V�^�R���i�̗z���҂�79�l�Ɛ����B�u���̑��̃R�~���j�e�B�[�Ɣ�ׁA�����d��Ȕ�Q�������炳��Ă�����̂ł͂Ȃ��v�Ƃ̔F�����������B
�I���I��ɋ߂��W�҂́A������������悤���߂��Ă���A���ۃI�����s�b�N�ψ���̍L��S���҂͉�̒��Ō���������24�����ɂ̂ڂ�A�u��o�ς݂̌��̂̕��͂͂ق�100%�I���Ă���v�Ƌ��������B����A�ܗ֊W�҂̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�Ȃǂ͊m�F����Ă��Ȃ����A�ʂ̑g�D�ϊ����́u�ܗւ��ǂ�ȉe����^���Ă��邩�A��X��������Ȃ��B�����Ґ���2�T�ԑO�̓��e�ƌ����Ă���A���̐������ܗ֊J���O�̂��̂��ƐM�������v�Ƙb���B
���u�R���i�����������A�X���[�g�̂����ɂ����v ��t�����{�����e�@7/28
�ٔ��̓x�����𑝂��Ă����B�����ܗւœ��{���̃��_�����b�V�����������A27���͓����s�ŐV����2848�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�B�ߋ��ő����X�V���A�ً}���Ԑ錾���ɂ�������炸�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����B�ܗ֊W�҂���O�ł͂Ȃ��A���g�D�ψ���͌����őI��2�l���܂�7�l���z�����������Ƃ\�B�����ǂɏڂ���������t�͍���u1��5000�l�v�K�͂̊����҂�z�肵�A�R���i�Ђƌܗւ����т����邱�Ƃ��뜜���Ă���B
�Ռ��I�Ȑ����������B�����s�����\�����V�K������2848�l��1�T�ԑO�̓����j���̔{�ȏ�ŁA1��7����2520�l������ߋ��ő����X�V�B�ً}���Ԑ錾���ɂ�������炸�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��������Ă���B
�����A23���ɊJ����}�����ܗւ͂��̓����_����\�t�g�{�[���A�d�ʋ����A�V���Z�̃T�[�t�B���œ��{�������_�����l���B�قƂ�ǂ̉��Ŗ��ϋq�J�ÂƂȂ������A�͑傢�ɐ���オ���Ă���A�����̍������I��̊���ɒ��ڂ��Ă���B�����A�R���i�Ђ͌ܗ֊W�҂���O�ł͂Ȃ��B�g�D�ς͐V���ɑI��2�l���܂�7�l�������ŗz���ɂȂ������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���̂����I�葺�����1���ő�4�l�̊������������A�g�D�ς�1���ȍ~�ɔ��\�����z���҂͌v160�l�ƂȂ����B
�ܗ֊��Ԓ��̊����ҋ}���ő��ւ̉e�������O����钆�A��ÃK�o�i���X���������������œ��Ȉ�̏㏹�L��(52)�͌�����u�\�z�ʂ�ł���ˁB�ď�̒���I�ȗ��s�̎����Ƀf���^�������Ԃ��Ă���̂ŁA�ܗւ��J�Â��Ă��Ă��A�����łȂ��Ă�(�����҂�)�����Ă���Ǝv���܂���v�ƕ��͂���B
�㎁�ɂ��A�����Ґ������Ⴄ���̂̇��㏸�J�[�u���͍��ĂƓ����X���ɂ���Ƃ����B
��N��6��������8����{�܂ő������������B�����������Ƃ܂��u�f���^���̊����͂ɂ���Ă̓s�[�N������Ɍ��ɂ��ꍞ�݁A�����҂�����������Ԃ������Ȃ邩������܂���(��)��N�ƑS���ꏏ�B������(��N�̃f�[�^�����Ƃ�)���z�����Ă݂��7��������8����{�ɂ����Ċ����҂͔{�߂��ɂȂ�ł��傤�ˁv�ƁA���̃y�[�X��������1��5000�l�K�͂̊����҂��m�F����Ă����������Ȃ��Ƃ����̂��B
�������A�㎁�͂����܂ŋG�ߓI�ȗ��s�ł���A�ܗ֊J�Â��v���Ƃ͍l���ɂ����Ƌ�������B�u��̂���Ɋ����҂������Ă�����A�����ƌܗւ̂����ɂ�����ł���B�w����ς�A�ܗւ���������爫���x�ƁB����ł̓A�X���[�g�����킢�����ł���B�ܗւ̉e���Ȃ�Ĕ��X������́B���̓s�s�������悤�ɑ����Ă���̂������ł��B�ܗւ̂����Ȃ�ć��G��߇��̉\���������v
���˂�9�A10���̏H�J�Â���Ă����㎁�́u���ܗւ���������爫�����ł͂Ȃ��āA���̎����ɂ��̂����߂��l������������ł���B���ꂪ��Ԃ̖��ŁA���Ƃ�{�����̂��Ƃ������т��Ɂw�������C���ɂ߂��x�Ƃ������Ă���͖̂{���]�|�B���Ȃ����������������Ă���̂��Ƃ������Ɓv�ƒɗ�ɔᔻ�����B
���`�̎͂��̓��A�u�����x�����������Ċ����h�~�ɓ������Ă����v�Ƙb������ŁA�����ܗ֒��~�̉\���͔ے肵�����c�B����Ȃ銴���̊g�傪�I�肽���̊���ɐ��������Ȃ����Ƃ��F����肾�B
���R���i�����g��ƃI�����s�b�N�̊֘A�� �g�D�� ���������� �@7/28
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��}�g�傷�钆�A�����g��Ɠ����I�����s�b�N�̊֘A���ɂ��āA���g�D�ψ���̍L��ӔC�҂�28���̉�Łu���Ƃ��I�[�v���ȂƂ���ŋc�_���Ă���v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߁A����������܂����B
�����I�����s�b�N���J�Â���钆�A�s���ł�27���A�ߋ��ő��ƂȂ�2848�l�̊������m�F����A�}�g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
�����������A�g�D�ψ���̍��J���N�X�|�[�N�X�p�[�\����28���̉�ŁA�����g��Ɠ����I�����s�b�N�̊֘A���ɂ��Ė����Ɓu�����҂̑����͐S���ɂނ��A���Ƃ��I�[�v���ȂƂ���ŕ��L���c�_���Ă�����̂Ɨ������Ă���v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߁A����������܂����B
���̂����Łu�������J��Ԃ��s���Ă���ق��A�W�҂̍s�����������Ă���A���W�̊����Ґ��͗}�����Ă���B���̑I����s���A�����̊F���܂ɂƂ��Ă��A���S�ň��S�ȑ��ɂȂ�悤�R�~�b�g���Ă����v�Əq�ׁA����������̓O��Ɏ��g�ލl�����������܂����B
����AIOC�����ۃI�����s�b�N�ψ���̃}�[�N�E�A�_���X�L��ӔC�҂́u���̊W�҂ƍ����̓o�u�������Ŋu���ł��Ă���B�W�҂�2��̃��N�`���ڎ���Ă��邵�A�z�������Ⴂ�v�Əq�ׁA���̊W�҂��N���Ƃ��������g��̉\���ɂ��Ă͔ے�I�ȍl���������܂����B
�������̐V�K����3177�l�@�S�����ő��A9000�l���Ɂ@7/28
�����s��28���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3177�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B2���A���ʼnߋ��ő����X�V���A�S���̐V�K�����҂����߂�9000�l�����B��s���̊����g�傪�ڗ����A��ʁA��t�A�_�ސ��3���͂��ꂼ��870�l�A577�l�A1051�l�ŁA��������ő��B�����͂������C���h�^(�f���^�^)�ƌĂ��ψكE�C���X�̊g�傪�w�i�ɂ���B
��s����4�s�����v��5675�l�B�����g��́u��3�g�v�Ńs�[�N������1��9����4327�l�ɔ��3�������B
3����28���A���ɋً}���Ԑ錾��v����������Œ������p���B�����N���o�ύ����E�Đ����͓����̏O�@���t�ψ���Łu(3������)�����ȗv��������Α��₩�Ɍ������A�@���I�ɑΉ��������v�Əq�ׁA29���ɂ�3���m���Ɖ�k����\��𖾂炩�ɂ����B
�s���̊����҂͗v20��6745�l�ƂȂ����B����1�T�ԕ��ς̐V�K�����҂͖�1954�l�ŁA�O�T(��1277�l)��153.0%�������B�d�ǎ҂͑O�����2�l����80�l�������B�V����6�l�����S���A�v�̎��Ґ���2285�l�ƂȂ����B
�s���̐V�K�����҂�N��ʂɂ݂�ƁA20�オ1078�l�ƍł������A30�オ680�l�A40�オ485�l�ő������B�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂�95�l�������B
�������A�A���ő��X�V��3177�l�@��Ò̐��A�ܗւɌ��O�@7/28
�����s��28���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3177�l���ꂽ�Ɣ��\�����B27����2848�l������A2���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B6�l�̎��S���m�F���ꂽ�B����12������ً̋}���Ԑ錾���Ԃ�2�T�Ԃ��o�ߌ�����N�`�����ڎ�̐���𒆐S�Ɋg�傪�����ăs�[�N�������Ȃ��B��Ò̐��Ⓦ���ܗււ̉e���Ɍ��O�����܂肻���B
����7���Ԃς���1��������̊����Ґ���1954.7�l�ɒB���A1��11����1861.1�l�������ĉߋ��ő��ƂȂ����B21���ɊJ���ꂽ�s�̃��j�^�����O��c�ł͐��Ƃ��ܗ֊��Ԓ���8��3�����_��7���ԕ��ς��2600�l�Ǝ��Z���Ă���B
�������o�����A3���ւً̋}���Ԑ錾�u�v������ΑΉ��v�@7/28
�����N���o�ύ����E�Đ�����28���̏O�@���t�ψ���ŁA��ʁA��t�A�_�ސ��3���ւ̐V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾�ɂ��āu�����ȗv��������Α��₩�Ɍ������A�@���I�ɑΉ��������v�Əq�ׂ��B29���ɂ�3���̒m���Ɖ�A�錾���߂̗v������\�肾�Ɩ��������B
�������͑S���I�Ȋ����g��ɐG��u�ɂ߂ċ�����@����L���Ă���v�Ƙb�����B���҂̏Ɋւ��u����҂̏d�lj��̓��N�`���ł��Ȃ�}�����Ă������A�_�f�z�����K�v��40�`50��̓��@�������Ă���v�Ɛ��������B
�����}���̂��߁A���H�X�ւ̋x�Ɨv���ɔ������͋��̑������t�Ɏ��g��ł���Ƌ��������B�u������������ɂ��x�����J�n�ł���v�Ƙb�����B
�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή�́A�����s�̊����g��Łu��Â̕N�������łɋN���n�߂Ă���v�Ƌ��������B
���@�Ґ��ɉ������@�҂��⎩��×{�̐l�������Ă���Ǝw�E�����B������h���ɂ́A�����������u�s���ɏ\���ɗ������Ă��炢��@�������L���邱�Ƃ��d�v���v�ƌ�����B
�����}�̒��R�W�G���A��������}�̌��t����Y���A�M�ؓ��`���̎���ɓ������B
���A�W�t���Ƌ��c�@�S���̃R���i�����ߋ��ő��Ł@7/28
���`�̎�28���[�A�V�^�R���i�E�C���X�̑S���̊����Ґ����ߋ��ő����X�V�����̂��A���@�œc�����v�����J������W�t���Ƌ��c���A�����͂����B�����s�ł�28���̊����Ґ���3177�l�ƁA2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ����B
���{��8��22���܂œs�ɋً}���Ԑ錾�߂��Ă���B�錾�ɏ�����u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑ΏۂƂȂ��Ă����ʁA��t�A�_�ސ�3���̒m���͐錾���߂𐭕{�ɗv�����錟�������Ă���B
����Ɋ֘A���A�����N���o�ύ����E�Đ�����7��28���̏O�@���t�ψ���ŁA3������v�����������ꍇ�́u���₩�Ɍ������A�K�v�Ȃ�@���I�ɑΉ��������v�Əq�ׂ��B
�����{�A28���̐V�K����798�l�@2���A����700�l��@7/28
���{��28���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�798�l�m�F�����Ɣ��\�����B2���A����700�l�����B�N��ʂł́A20�`30��̊����҂�396�l�łقڔ������߂��B60��ȏ�̊����҂͑S�̂�5%�ɂ�����40�l�������B�V���Ȏ��҂͊m�F����Ȃ������B
28�����_�̏d�ǎ҂͑O������5�l����67�l�B�m�ەa��(587��)�ɑ���g�p����11.4%�ƂȂ����B�����Ɏg����u���^�p�a���v(312��)�ɑ���g�p����21.5%�BPCR�����Ȃǂ��v1��2143�����{���A�z������6.6%�������B
10�Ζ�������60��̒j��8�l���C���h�^(�f���^�^)�Ɋ������Ă������Ƃ����������B�{�ɂ��ƁA8�l�ɊC�O�ւ̓n�q���͂Ȃ��B���������nj������Ȃǂ̊m�茟���Ńf���^�^�̊��������������͕̂{���Ōv78�l�ƂȂ����B
�������g��m���@���Z�v��������@�Ȗ،��@7/28
�Ȗ،����̐V�^�R���i�E�C���X�����̊g��X�����A���c�x��m���͓�\�����̒��L�҉�Łu�ċx�݊��Ԃł����Ă��A�����ւ̊O�o���l���ނ������H�X�̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k��v�����邱�Ƃ����肦��v�Ɗ�@�����������B
���ɂ��ƁA���߈�T��(��\�Z���܂�)�̐V�K�����҂͑O�T�̈�E�Z�{�B���̂܂ܐ��ڂ���ƁA������{�ɂً͋}���Ԑ錾�̐����ɒB����Ƃ����B���̃X�N���[�j���O�����ł͕ψي�(�k452�q)�͎l��(�\��〜��\�ܓ�)���A�����͂������Ƃ����ψي��ւ̒u������肪�g��v���̈�Ƃ݂���B
���ڂ̃��N�`���ڎ��\�l���ȏ�o�߂����l�ŁA���Ȃ��Ƃ����l�̊������m�F���ꂽ���Ƃ����炩�ɂ��A�ڎ��������h�~��O�ꂷ��悤���ӂ��Ăъ|�����B
������×{�̃R���i������ ������1�����O��5.7�{�ɑ����@7/28
�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ���������ŗ×{���Ă���l�͍���21�����_�őS����1���l���A�����s�ł�4000�l�]��ƑO�̏T��2�{�A1�����O��5�{�]��ɑ��������Ƃ��A�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂ŕ�����܂����B
�����J���Ȃ͓s���{�����Ƃ̕a���̎g�p���⊳�҂̗×{��ɂ��čŐV�̏��܂Ƃ߂܂����B
����ɂ��܂��ƁA����21�����_�Ŏ���ŗ×{���Ă���l�͑S����1��717�l�ŁA�O�̏T��肨�悻4900�l�����Ă��܂��B
�����s�ł�4068�l�őO�̏T�̂��悻2�{�A1�����߂��O��6��23�����_�Ɣ�ׂ��5.7�{�ɑ������Ă��܂��B�_�ސ쌧�ł�2241�l�őO�̏T��1.5�{�A1�����O��3�{�ɁA��t���ł�792�l�ŁA�O�̏T��1.7�{�A1�����O��3�{�]��ɁA��ʌ��ł�1104�l�ŁA�O�̏T��2.7�{�A1�����O�Ɣ�ׂ��10�{�ȏ�ɋ}�����Ă��܂��B
�܂��A�z�e���Ȃǂ̏h���{�݂ŗ×{���Ă���l�͑S����6364�l�őO�̏T���1600�l�]�葝���A1�����O��2�{�ɂȂ��Ă��܂��B
���@���K�v�Ɣ��f���ꂽ���̂̎��������̐l���挎�����瑝���X���ƂȂ��Ă��đS����201�l�ƁA�O�̏T���35�l�����܂����B
�����J���Ȃ́u20�ォ��40��̎Ⴂ����̐V�K�����҂��������Ƃ�����×{�Ґ��������Ă���v���ƍl������B���̂܂܊����҂������Ă����Ɠ��@��×{��̒������x��Ă���\��������A��Âւ̕��S�����O�����v�Ƃ��Ă��܂��B
����×{�҂̉��f�ɂ������t�́A�Ǐ�̏d�����҂��ݑ�̂܂��Â���������Ȃ��Ȃ鎖�ԂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗ�@�������߂Ă��܂��B
�����s�͎���×{�҂̉��f��I�����C���f�Â��s���̐�����i�߂Ă��āA����1�����݁A�s��54�̒n���t��̂���21�̈�t��Ɩ��Ԃ̎��ԊO�~�}�Z���^�[���Q�����Ă��܂��B
���̂����A���c�J��̋ʐ��t��ł͒n���3�̈�Ë@�ւ��֔ԂŎ���×{�҂���̑��k��f�Âɂ������Ă��܂��B
����܂ł͓d�b���k1���݂̂ł������A4�A�x������26���A���߂ĉ��f�̈˗����������Ƃ������Ƃł��B
�Ή������w�ӂ��낤�N���j�b�N���X�́x�̎R�����@���ɂ��܂��ƁA��Ă��܂����̂ŏ������Ăق����Ƃ������҂ł������A�K�˂Ă݂��1�T�ԔM������Ȃ��Ƙb���A�x���̏Ǐ�����������ߒ����ǂƐf�f���ē��@���邱�ƂɂȂ����Ƃ������Ƃł��B
�R���@���́u�����Ґ����l����ƍ���A����×{�҂���̑��k�̌����������邱�Ƃ�A��4�g�̂Ƃ��̑��̂悤�ɓ��@�ł��Ȃ��l���ݑ�Ŏ��Â���������Ȃ��Ȃ鎖�ԂɂȂ邱�Ƃ����Ɍ��O�����B�ݑ�ł��_�f���^��_�H�͂ł��邪�A�a�@�ł̎��ÂƔ�ׂĈ��|�I�Ɏ�Ԃ���������E������B�n��̂��������͐V�^�R���i�̐f�f���������Ƃ͂����Ă����Â̌o���͂قƂ�ǂȂ��A�\���ɑΉ��ł��邩�S�z���Ă���v�Ƙb���Ă��܂��B
�����s�ɂ��܂��ƁA����×{�҂̉��f��I�����C���f�ÂȂǑΉ������͐挎�܂ł�1������5���قǂł������A����7���܂ł�1�T�Ԃ�1��10���قǂƂȂ��Ă���A���̌�͂���ɑ����X�����Ƃ������Ƃł��B
�����̊g��Ŏ���×{�҂�������Ƃ݂��邱�Ƃ���A�ق��̒n���t��ɂ����͂��Ăт����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�����{ 40��E50��̃��N�`���ڎ�ϋɓI�i�ߊ����g��h�~�� �@7/28
�����s�ł�27���A�ߋ��ő��̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��m�F����܂����B���{��40���50��ȂNJ����������Ă��鐢��ւ̃��N�`���ڎ��ϋɓI�ɐi�߂�ƂƂ��ɁA��ɏ��F���ꂽ���Ö�����p����Ȃǂ��āA��Â̂Ђ����₳��Ȃ銴���g���h�������l���ł��B
�V�^�R���i�E�C���X��ŋً}���Ԑ錾���o����Ă��铌���s�ł�27���A�ߋ��ő��ƂȂ�2848�l�̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂��m�F����܂����B
�����������A��������b�͑�����b���@�ŊW�t���Ƃ��悻1���Ԕ��A�Ή������c�������ƁA�L�Ғc�ɑ��u�f���^���̊������}���ɑ������Ă���A�܂���4�A�x�̐l�̗�����܂߂ĕ��͂����Ă����B�e�����̂ƘA�g���Ȃ���A�����x�����������āA�����h�~�ɂ������Ă����v�Əq�ׂ܂����B
���{�́A���@���҂������Ă���40���50��ȂNJ����������Ă��鐢��ւ̃��N�`���ڎ��ϋɓI�ɐi�߂�ƂƂ��ɁA��ɏ��F���ꂽ���Ö�����p���ďd�lj���h���A��Ò̐��ւ̕��ׂ��y���������Ƃ��Ă��܂��B
�����āA�����͂̋����ψكE�C���X���}���ɍL�����Ă��邱�Ƃ܂��A�����I�����s�b�N�͎���Ńe���r�Ŋϐ킷��悤���߂�ȂǁA�s�v�s�}�̊O�o�̎��l�����߂ČĂт����Đl�̗����}������ق��A�����̂ƘA�g���Ĉ��H�X�̌������s���ȂǁA��̓O���}�邱�ƂŁA����Ȃ銴���g���h�������l���ł��B
�������̊����}�g��u��҂��A�ԐM���݂�Ȃœn��c�ɂȂ��Ă���v�@7/28
������͂��̖�쌓��28���A�t�W�e���r�u�o�C�L���O�l�n�q�d�v�ɏo���B�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ɂ��āu�ԐM���A�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ���ԂɂȂ��Ă���v�Ƙb�����B
�i��߂�o�D�̍��E���ċx�ݒ��̂��߁A���̓��͖�삪�i���S�������B
28���̓����s�͐V�K�����Ґ���2848�l�ƑO�T����{���B��Â��Ђ������Ă���B4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o����2�T�Ԃ��������A���̌��ʂ͌����Ȃ��B
���`�̎�28���A�L�Ғc�Ɂu�Ԃ̐����ł���Ƃ��A�e�����[�N�Ƃ��A�F����̂��������܂ɂ��܂��āA�l���͌������Ă���B(�ܗ֒��~��)�S�z�͂Ȃ��Ǝv���Ă���v�����B����Łu�e���r�ȂǂŊϐ킵�Ăق����v�ƌĂт������B
���`�j�a�̍����݂Ȃ݂́u���̘b���Ă�ƁA���t������Ȃ��Ȃ��Ďv�����Ⴄ�B���ꂾ�������Ґ��������Ă��钆�ŁA���v������Č����Ă��A�������v�Ȃ̂��Ďv�����Ⴄ���A�����ƕs�v�s�}�̊O�o�͍T���ĉ������Ƃ��e�����[�N���Ƃ��A�����Ă��邱�Ƃ��ς��Ȃ��̂ŁA�����������ǂ���������̂����Ă���������͋������t�Ŏ����Ăق����v�Ƌ��߂��B
���́u�����̃J���X�}���o�ė��Ȃ��Ɠ����ˁv�ƃ��[�_�[�V�b�v�������ł��Ă��Ȃ��̂ӂ����Ȃ���\���B���̌��ʂƂ��āu��҂Ƃ����Ă���ƁA�w�ԐM���A�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��x��ԂɂȂ��Ă����ˁB�݂�Ȉ��ݎn�߂Ă邩�������������Ă����ˁv�ƌ�����B
���R���i�g��͐V��I4�A�x�u���M���k�v�A��3000�����Ŋ��������̗\���@7/28
�������胏�[�X�g�L�^��˔j���B27���̓����̐V�K�����҂�2848�l�B1��7����2520�l��啝�ɏ���A�ߋ��ő����X�V�����B�O�T�̓��j����2�{���y�������A�����g��͐V��̐����B���̐������v���͌�������Ȃ��B�����ܗւ̃��_�����b�V���ɂ������Ă���ꍇ����Ȃ��B
�܂h�~���d�_�[�u����4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ɐ�ւ����2�T�ԗ]�B�ߋ��ő��̊����́A�錾�O��́g�삯���݉���h�Ȃǂ̐l�����������f�����Ƃ݂���B����ɐ錾����A4�A�x�Ɍܗ֊J���ƌ��O�ޗ����ڔ������B�����g��Ɏ��~�߂������肻���ɂȂ��B
�C�ɂȂ�̂́A�s�́u���M���k�Z���^�[�v�ւ̑��k�������B
22������25���܂ł�4�A�x�͂������1��3000�������B����܂�3000�����́A������1���B���N1��3����3239���݂̂������B
4���A��3000�����͑O��̂Ȃ��ٗ�̐����B���k�����͍���̊����̑��������ʂ���s�w�W�Ƃ���A�ߋ��ɂȂ������唚���̑O���ƍl�������������B
���u8���O��4000�l�v�̍ň����Z���n�C�y�[�X
1��������V�K������4000�l�̑�����������ттĂ����B����E�C���X�E�Đ���Ȋw�������̌Ð��S�C����y����������7���̌��J�ȃA�h�o�C�U���[�{�[�h�̉�ŕ������Z�ɂ��A�u������v���Ȃ���A7�����{��2000�l�A8�����߂�3000�l�A10������ɂ�4000�l�ɒB����Ƃ��Ă���B27���̒i�K��3000�l�ɔ���y�[�X�́A���́g�ň����Z�h���͂邩�ɗ��킵�Ă���̂��B
�u������v�Ƃ́A�A�i�E���X���ʂɂ��A�����Đ��Y����20���ቺ�A��̎��{�ɂ�肳���20���ቺ�����郌�x���̑���w���B�������A�錾���߂���2�T�Ԍo���A�V�K�����҂͘A���A�O�T���j����2�{�O��̐����ő����Ă���B�����w����w�Z�p���w�Z�����Z�Z���̒����p�b��(�����NJw)�������B
�u4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�́w������x�ɂ͒������A�Ă��ɐ��ɂ����Ȃ�Ȃ������B�錾�̃A�i�E���X���ʂ́A���Ƃ��Ɣ���Ă�����ɁA�ܗ֊J�ÂƂ��������������b�Z�[�W�ɂ���āA���S�ɑ��E����Ă��܂��B���ܗւ���B���̂܂܌ܗւs���A�n�C�y�[�X�̊����g�傪�����A�a���͈�C�ɖ��܂�A�K�v�Ȉ�Â��ł��Ȃ����ԂɂȂ肩�˂܂���v
�����̓��@���͖�20���B�R���i���҂�10�l��2�l���������Ȏ��Â����Ȃ����B���̐�A�V�K�����҂�4000�l�A5000�l�Ƒ����Ă����A�ԈႢ�Ȃ������閽��������Ȃ��Ȃ�B
27���̂Ԃ牺�����ŁA���͓����ܗւ𒆎~����I�����ɂ��āu�l���͌����Ă��܂����A����͂���܂���v�ƒf�������B�����]���ɂ��Ăł��ܗւ𑱂������̂悤���B
���R���i�̋^���O�T��1.6�{
1��������̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����ߋ��ő��ƂȂ钆�A�~�}���҂̎���悪�����Ɍ��܂�Ȃ��P�[�X�������Ă���B
�����ȏ��h����27���A�u�~�}��������āv���A19�`25����1�T�ԂɑS��52�̏��h��2202���������Ɣ��\�����B�O�T���43�������A3�T�A���̑����B�����A37�x�ȏ�̔��M��ċz����Ȃǂ̏Ǐ���A�V�^�R���i�E�C���X�������^���鎖�Ă�698���ŁA�O�T��1.6�{�Ƒ啝�ɑ������B
1�T�Ԃ̌�����2000������͍̂��N5��3�`9���ȗ��B�n��ʂł́A�������h����1121���ƍő��ŁA�O�T����34�����������B
�������I�����s�b�N�̊�@�F���ϋq�ł����������@7/28
�����Ȃ�u�L�^�X�V�v�ƂȂ�܂����B7��27���A������1�������芴���Ґ�2846�l�A�ߋ��ō��ł�����2021�N1��7���A�^�~�̃s�[�N2520�l��300�l�ȏ���������ώc�O�ȁu1�ʍX�V�v�ƂȂ��Ă��܂��܂����B�������A���̃��R�[�h�͒��������Ȃ��ł��傤�B�Ƃ����̂����܃s�[�N�Ɍ������ċ}����삯����Ă���Œ�������ŁA������A���̋L���������[�X�����7��28���A�L�^���X�V�����\��������ƍl�����܂��B
���͖{�e�̗\��e�͈ȉ��̂悤�ȏ����o���ŏ������Ă��܂����B
7��25���A�����s�͓��j���̐V�^�R���i�E�C���X�����Ґ��Ƃ��āu�ߋ��ő��v��1763�l���L�^���܂����B�ܗ֊��Ԓ��̃��R�[�h�A�I�����s�b�N�L�^�ł��E�E�E�B
����ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
�O�̏T�̓��A���A�Ηj�����e�X1008�l�A727�l�A1180�l�A�����́u��v�œ`�d���܂��B
�P���ɓ��j���̑�������1.7���|���Ă��Ό��j��1271�l�A�Ηj��2063�l�ƁA�T�O���̊����ґ��������ڂ������悻���������܂��B
�{���Ȃ犴�������₩�Ȃ��̎�����2000�l����u�V�L�^�v���o��\���A�����w���ł��\�����ł��鐔���ł����B
�ʂ����āA�W���J���Ă݂�ƌ��j���̊����҂́E�E�E1429�l�B
�����w�������̒P���Ȕ�(���`�O�})�ōl����1271�l����͂邩�ɑ���1.96�{�̊����Ґ����L�^���܂����B
�����ĉΗj���̊����҂��E�E�E2848�l�A��������ƋL�^���X�V�A�قƂ��3000�l�Ɏ�̓͂������ł��B
�{�X�Q�[���Ƃ������A�����w�Z�ŏK���w�������ɋ߂����Ƃ�������܂��B�����Łu�ܗ֑�5�g�v�ƌĂԂׂ��}���ȃs�[�N���`���������B
�������{�S���̃f�[�^�ł݂�ƁA����ɏ�Ԃ��������ł��B
����̌ܗ֑�5�g�A�����_�܂ł̃s�[�N�́u�J��v���O��7��22����5395�l���L�^���Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A7��25���͓��j�����Ƃ����̂�5020�l�A�O�̓��j��7��18����3103�l�ł�����A���{�S�̂ł�1.6�{�Ƃ����}���Ȋ��������̐^���Œ��ɂ���B
7��19���̑S�������Ґ���2328�l�ł�����A��͂蓙��I�ɍl�����3766�l���x�̊������\������܂������A�W���J���Ă݂��4692�l�B
�O�̏T��2�{�����A���������{�S���̕����A����ꂽ�X�|�b�g��r�ł����A�����ґ�����ɉ������|�����Ă��܂����B
�W���J���Ă݂�ƁA�Ηj���̑S�������Ґ�7401�l�B��͂�1�T�ԑO��3755�l��1.97�{�B���̃I�[�_�[�ɏ��̂����Ԃ̖��Ǝv���܂��B
�{���Ȃ�A�ƂĂ��ł͂Ȃ��ł����ܗ։��̂Ƃ�����ł͂���܂���B���Ă������A���̊����͂ǂ��܂ŁA�ǂꂭ�炢�L�т�̂ł��傤�H
������l���邤���ł́u���N�`���ڎ헦�v����������̂���Ԃ̑����ł��B
��x�ł����N�`����ł��Ă���A�V�^�R���i�ւ̜늳���͒����������邱�Ƃ��ł���B���̊ϓ_����A����������яオ���Ă����̂��u�I�����s�b�N�E�A�X���[�g�̃��N�`�����ڎ�v���ł��B
�����N�`�����ڎ�̌ܗ֑I����
����̐V�^�R���i�E�C���X�����ǃ��N�`���A���ɐ������Ă���mRNA���N�`���ɂ��ẮA�d�Ăȕ���p�͔��ɏ�����������Ă��܂���B
�ڎ풼��Ɏ��S������́A7��7�����݂�453�P�[�X�B���̒��Łu���炩�Ƀ��N�`���ڎ�ƈ��ʐ�������v�ƔF�߂�ꂽ�̂�1�������B
451���́u�W������Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ȃ��v�B�v����ɂ킯��������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
����͂����ł��傤�B�u���N�`���ڎ킪�����v�ƔF�肳���A�\�h�ڎ�@�Ɋ�Â��č����������˂Ȃ�܂���B
���疜�~�ɏ�锅�����ł��B��������Ƃ͔F�ł��Ȃ��Ƃ��������I�Ȏ����������Ȃ��킯�ł͂���܂���B
�������A�t�Ɍ����ƁA����܂őS�����N�ł҂�҂Ă����l���A���ɕa�C�ł��Ȃ��̂Ɂu�\�h�̂��߁v�Ƀ��N�`����ł�����A���̓��ɖS���Ȃ����E�E�E�B
��҂́u���R���v���Ƃ����B���v�I�ɂ����Ɏ��S���͏オ���Ă݂��Ȃ��ȂǂƐ��������Č�����B���̎��A�ۏ؋��ȂLj�؎x�����Ȃ��E�E�E���������ɂ���킯�ł��B
���̏́u�Ō�̂ЂƘm�v���Ƃ��č��ۓI�ɂ��_�����Ă���A�e�����߂Ď��グ��\��ł��B
��b�̗̗͂����Ă��鍂��҂Ȃǂ́A���N�`���ڎ킪�������������āu���R���v���Ă��܂��A���̕ۏ�����Ȃ����x�ɂ��邱�Ƃ́A���ӂ��Ă����Ă悢�_�ł��B
�u����Ȃ��Ƃ���܂����A���N�`���͏\�����S�ł��B����͑łĂA�ŏ��̓C���t���G���U�ɜ�����悤�ȏɂȂ�܂��B���˂������Ƃ���͎��܂����A�e�̉�����ꂽ��r���グ�ɂ��������炭�������肷�邯��ǁA���̒��x�E�E�E�v
�m���Ɂu���̒��x�v�Ƒ����̐l�͎v���ł��傤�B�������u���肪�オ��Ȃ��Ȃ�����������v�Ƃ�������O�ꂵ�Ċ����������Ǝv���l�����̒��ɂ͑��݂��Ă���B
�I�����s�b�N�E�A�X���[�g�́A���̏����̗�O�ɑ������܂��B
���Z�ɂ���Đ獷���ʂł����A100����1�b�Ƃ������^�C���̍��������āA�S���E�Łu���̐��v�̑I�肽�������̂�������Ă���B
�����������ŁA�ܗ֑I��̍��������Ă���Œ��̃A�X���[�g�A���邢�́A�I�����s�b�N�o����ˎ~�߁A�{�ԂɌ����Ă�����̒����x�X�g�ɐ����悤�Ƃ��Ă���I�肽�����A�킴�킴�u�܂������ĕK���A�����C���t���G���U���l�̏Ǐo�A�����͕Ў肪�グ���Ȃ��Ȃ�v���N�`���ڎ�����Ă��邩�E�E�E�H�@
���ہA���N�`����ł������Ȃ��Ƃ����A�X���[�g�̐��͕��Ă���A������u�����ɐ�������v�e���ܗֈψ���Ƃ����A������̍\�}�������яオ���Ă��܂��B
�����ڎ�҂��ׂĂ��u�����̐L�т���v
�č��̃I���p���ψ���̈�ÐӔC�҂�7��23���A�č���\�I��613�l�̂����A��100�l�����N�`�����ڎ�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
IOC�͓����I�����s�b�N�ɎQ�����Ă���A�X���[�g�́u��85�������N�`���ڎ�ρv�Ɓu����v���Ă��܂����A���W�ҁA���̑����܂߂���W�c�ŁA���������ǂ̂悤�Ȑ����ɂȂ�̂��́A�����Ɍ����đS��������܂���B
�u�w�قځx�S������x�͐ڎ킵�Ă���w�Ɗm�M���Ă���x�v�ȂǁA���悻����̂����b�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
�I�葍����1��1000�l���A�����W�Ґ�5.3���l��O���ɒu����85���̊��ڎ�ł�15���͖��ڎ�B
�܂�A�I�肾���ł�1700�l�A�W�҂��܂߂�Ζ�8000�l�́u���ڎ�ҁv���A�킴�킴�A�����g��̂�ڏɂ���u�ĕ��׃s�[�N���v�̓��������ē��{�ɏI�����Ă��Ă���B
���J�n�킸��3���ł��ł�132�l�̊����҂�1.7���قǁB���łɏ㏸���Ă���u�o�u�����v�̊��������l���A���ڎ�҂̐���O���ɂ����A�}�����Ă����̕s�v�c���Ȃ��B
�������Ƃ����{�l�S�̂ɂ������܂��B
���{��7��19�����݂́A���N�`���ڎ�ςȂ�тɖ��ڎ�̐l���������A�N��ƒn��ɂ킯�Ĕ��\���܂����B
�{���I�ɏd�v�ȕ������������o����
�����{�S���ɖ��ڎ�̐l�́u8600���l���v���݂���
�����̂����A65�Ζ����́u�ᒆ�N�w�Ɍ��肷���7900���l���v
�܂�A�����ܗւŖ�8000�l�̖��ڎ�W�҂�����̂ɑ��āA���{�S���ł�8000���l�A1���{�̋K�͂Łu�����I�����s�b�N�v�̋L�^���o����悤�Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�B
���܂���@�ҁA�d�ǎ҂�6�`7���́u20�`30��v�Ɓu40�`50��v����߂�悤�ɂȂ�A���N�`���ڎ헦�̏オ����65�Έȏ�͉����̏�Ԃ͌����Ă��܂��������Ċ��Ґ��͑����Ă��Ȃ��B
����ɑ��āA���m�ȓ��v�͒m��悤������܂��A�ܗ֊W�҂͈�ʓI�Ɂu����ҁv�ł͂Ȃ��u��N�w�v�u���N�w�v�܂�A���܂̃f���^�n�ψي��������Ґ���L���Ă���Œ��́u�V���w�v�Əd�Ȃ��Ă���\���������B
�v����ɁA�ܗ֊W�҂��A���{�l�S�̂��A���ꂩ��2�T�Ԃقǂ̊ԁA�����K�͂̊����g�傪�����Ō��O����邱�ƂɂȂ�܂��B
���Ȃ݂ɁA2020�N����21�N�ɂ����Ă̓~�́u��3�g�v�A�t����A�x�ɂ����Ắu��4�g�v�ł͊e�X30���l�K�͂̊��Ґ��g���6000�l�K�͂̎��҂��o�܂����B
�������̍D���ȁu�t�F���~�Z�v�ŁA1��2000���l���邢��8000���l�̖��ڎ�҂ɑ���30���l�̊�����6000�l�̎��҂��قǂ́u�����w�������v�܂�u���`�v�ōl����A�ꐔ��0.25���Ƃ�0.375�����������A���̂���2�����x�̒v�����ƂȂ�̂ŁA�����b�A2���l��1�l���S���Ȃ�v�Z�ł��B
�����l����ƁA����Ȍv�Z�ɂȂ�܂����u�����I�����s�b�N�ŗ������A�ܗւŊ����������ƂŖ��𗎂Ƃ��l�v��2.5�l���x���Ă��A����ȍr���ۂ��v�Z�ł���s�v�c�łȂ����Ƃ�������܂��B
���������u���`�O�}�v�́A���́u�����]���v�Ȃǂɗp����̂ɕ֗��ł��B��قǂ��u�ŒႱ�ꂭ�炢�̊������v�ƌ�����ł�����A��قǂ����葽�������B
�u�����I�����s�b�N�̂��߂ɗ������āA�R���i�Ɋ������A����Ŗ��𗎂Ƃ��l�v�́u�����v��2�`3�l���x����E�E�E�Ƃ������܂�l�������Ȃ��b�ł����A�q���ł�������v�Z�Ń��X�N��]�����Ă݂܂����B
�͂�����ƈ�i�M�A���グ���\�h��ɃV�t�g���Ȃ��ƁA�O��܂łƌ��̈Ⴄ��Q��H���~�߂�͍̂���ł��傤�B�L�����ɍ������������{�K�{�ł��B
���R���i�����g��̒��̓����ܗցA��̓o�[�`�����ōs���ׂ��@7/28
���J�Âɂ͎^�ۗ��_������������̑����A��Ő����͂̂��郁�b�Z�[�W�M�ł���Ε]���͉��P���邩����
�A�����J�ł͍���̊����g����u��4�g�v�Ƃ����������ŌĂ�ł��܂��B�j���[���[�N�E�^�C���Y�̂܂Ƃ߂ɂ��A7��26���̐V�K�z���҂�5��6000�l���Ă���A14���O�Ɣ�r�����44���̑����ƂȂ��Ă��܂��B
���̏Z�ރj���[�W���[�W�[�B�ł��A�ꎞ��1��������̐V�K�z���҂�100�l�ȉ��܂ʼn��������̂ł����A7��27���̔��\�ł�792�l�Ƒ����Ă��܂��B���́u��4�g�v�̓����ł����A�S�̂��g��X���Ȃ̂̓f���^���̊����͂������Ƃ����v��������܂��B�܂��A���N�`���ڎ헦�̒Ⴂ�B�ł̊������[���ł���A����ȊO�̒n��ł��d�ǎ҂̑����̓��N�`�����ڎ�̐l�����ł��B
�o�C�f���哝�̂Ƃ��ẮA7��4���̓Ɨ��L�O���܂łɁA�Œ�1��ł����N�`����ڎ킵���l�̗���70���̐����ɂ܂Ŏ����Ă����āu�E�B���X����̓Ɨ��v��錾����͂��ł����B�܂��A�����O��Ƀ}�X�N�`�������~�߂Čo�ς��t���ғ������������킯�ł��B�ł����A�ڎ헦���}�~�����钆�Łu��4�g�v���g�債�A���̖ژ_���͊O�ꂽ�`�ł��B
�����_�ł́A���Ȃ��Ƃ����{�ƃA�����J�Ɋւ��Č����A���N�`���ڎ킪�v���悤�ɐi�܂Ȃ��Ƃ�����A�f���^���Ɂu�����܂ꂽ�v�`�ŁA����Ɏ����Ă���ƌ����܂��B
����Ȓ��ŁA�����ł͉ċG�ܗւ��i�s���ł��B���̑��ł����A�������́u���~�̑I�����͂Ȃ��v�ȂǂƁA�f��I�Ȍ����������Ă��܂��B�ł����A���̐扼�ɁA
�u�����̈�Â��N�����āA�ܗ֊J�Â̓s�s�Ԍ_��Ŗ��ꂽ��ÃT�[�r�X���s�\�v�ƂȂ����ꍇ��A�u�I�葺�𒆐S�Ɍ����ȃN���X�^�[���������A�J�Ós�s�����̈�Ò̐���N��������v�Ƃ����ɂȂ����ꍇ�́A���Ԓ��ɂ����钆�~�Ƃ����\���͔r���ł��Ȃ��Ǝv���܂��B
���̈���ŁA���ɂ����܂Ő[���ȏɎ��炸�ɁA�ꂵ�݂Ȃ�������݂Ƃǂ܂�\��������Ǝv���܂��B���̏ꍇ�ł��A�����āu�l�ނ��R���i�ɑł��������v�Ƃ����悤�Ȏv���オ�������b�Z�[�W�͏o���܂���B
�����g��u���łɈ�ÂЂ����v���������}�� ����ł́c �@7/28
�ߋ��ő���3177�l�ƂȂ���28���̓����s�̐V�K�����Ґ��B�����g��Ɏ��~�߂������炸�A��Ñ̐��̂Ђ����ւ̊�@�����L�����Ă��܂��B�����s�̈�Ñ̐��̌�����܂Ƃ߂܂����B
�����g��u��Â̂Ђ��������łɋN���n�߂Ă���v
28���A���{�̕��ȉ�̔��g��́A�O�c�@���t�ψ���Łu��Ԃ̑ؗ��l���́A�ɉ؊X�Ȃǂł͏����������Ă��Ă��邪�A���҂���郌�x���ɂ͎c�O�Ȃ��玊���Ă��Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B���̂����ŁA���g��́A���@���҂⍂�Z�x�̎_�f�z����K�v�Ƃ���l�A����Ɏ����h���{�݂ŗ×{���Ă���l�Ȃǂ������Ă���Ǝw�E���u��Â̂Ђ��������łɋN���n�߂Ă���Ƃ����̂��A�����̔F�����v�Əq�ׂ܂����B�����āu���������}���ɁA�l����ڐG�̋@���������K�v������B���@�̂Ђ����Ɋւ���w�W���s���ɏ\���������Ă��������A���{�̎Љ�݂�Ȃ���@�������L���邱�Ƃ��A���A���ɏd�v���v�Əq�ׂ܂����B
�������NJ��� ����̕a�@�u�L���p�I�[�o�[�v
�����ǂ̊��҂�����Ă���s���̕a�@�ł́A�p�ӂ����a�������銳�҂����@����ȂǁA�Ή��ɒǂ��Ă��܂��B���� ������ɂ���u�͖k�����a�@�v�́A�V�^�R���i�E�C���X�̊��҂ɑΉ������a�@��1�ŁA�{�@�Ƌ߂��ɂ��镪�@�Œ����ǂ܂ł̊��҂�����Ă��܂��B�a�@�ł͐V�^�R���i�̊��҂̂��߂�43�����m�ۂ��Ă��܂����A1�T�ԂقǑO������@���҂������A28���̎��_�ł�46�l�����@���Ă��܂��B�ƒ���Ŋ�������P�[�X���������߁A�Ƒ��͓����a���ɓ��@���Ă��炤�Ȃǂ��đΉ����Ă���Ƃ������Ƃł��B�N��ʂł́A30��܂ł̎Ⴂ���オ�S�̂�3����2���߂Ă���ق��A40���50��̊��҂��d�lj����ĕʂ̕a�@�ɓ]�@����P�[�X������Ƃ������Ƃł��B�܂��A1�Ζ����̐Ԃ�����6�l���@���A������h���K�E���𒅂��Ō�t�����������ă~���N��^����Ȃǂ��Ă��āA���@���҂̑����ŁA�Ɩ��̕��S�������Ă���Ƃ������Ƃł��B���̕a�@�̔��M�O���ɂ͘A��20�l�ȏオ�K��Ă��āA���������l�̂��悻4�����z���Ɗm�F���ꂽ��������܂����B
�͖k�����a�@�̐����m��@���́u7���̏��߂��炢�܂ł�35�l����40�l���������A����2�T�Ԃقǂ�43���������ɂȂ�A1�T�Ԃ��炢�O����͓��肫��Ȃ��Ȃ����B�����͂������A�������Ԃ������ψي��̊��҂������Ă��āA40��A50�オ�d�lj����Đl�H�ċz���t����P�[�X�������Ă���B�L���p�I�[�o�[�̏͂��炭�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���v�Ƙb���܂����B����Ɂu���܈�Ԓ��ӂ��Ă���͉̂@���������N�����Ȃ����ƁB���̏ʼn@���������N����ƈ�Õ���ɒ�������̂ŁA���ꂩ�玡�Â⌟���œ��@�����܂��Ă���l�́A�ɗ͊�������悤�ȏꏊ�ɂ͍s���Ȃ��łق����B������A�l����}����w�͂����āA�Ⴂ�l�ɂ͍��܂ł������������Ƀ��X�N�������Ă��邱�Ƃ�m���Ă��炢�����v�Ƙb���Ă��܂����B
���s�u�ʏ��Â̐������������v ��Ë@�ցu�s���ɐ������v
�s���̓��@���Ґ��́A27�����_��2864�l��1�����O�̔{�߂��ɂȂ����ق��A�a���̎g�p�����㏸���A48���ɂȂ�܂����B�����������A�����s�͐V�^�R���i�E�C���X�̊��҂�����Ă����Ë@�ւ�Ώۂɐ�������J���A�ʏ��Â̐������������Ă���ɕa�����m�ۂ���悤�v�����܂����B��Ë@�ւ���́u�ʏ��Â𐧌�����Ȃ�s���s���ɑ��Ă�������������Ăق����v�ȂǂƂ������O�̐����o���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�s�́u���݁A�m�ۂ��Ă���a���v��5967�����A����6�����߂ǂɁu�ő�Ŋm�ۂł���v�Ƃ��Ă���6406���܂ő��₵�����Ƃ��Ă��܂��B
����w�a�@�u��ʐf�Âɉe�����o���˂Ȃ��v
�s�̗v�����A���� ������̓�����Ȏ��ȑ�w�����a�@�ł́A�a���̊m�ۂɂ��Ăǂ��Ή����邩�A28�����A�a�@�̊����Ȃǂ��W�߂ăI�����C����c���J����܂����B��c�ł́A28���̎��_�ŁA�����ǂ̊��҂�21�l�A�d�ǂ̊��҂�4�l�A���ꂼ����@���Ă��āA�����ǂ̕a����������ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂����B�����������Ƃ���A����܂ł͕ψكE�C���X�̊��҂̕a���ɂ��āA�C�M���X�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�u�A���t�@���v�ƁA�����͂������C���h�ōL�������u�f���^���v�̊��҂Ȃǂŕ����Ă��܂������A�������}�g�債�Ă��鍡�A�a������̂����������߁A�����ɂ��邱�ƂŁA�a�����Ċ��҂���葽�������̐�����邱�Ƃ����߂܂����B
�a�@���B�e�����f���ł́A�f���^�����Ӗ�����uL452R�v�Ƃ����\�莆�����ꂽ�a���ɁA�Ō�t�炪�Q���������o���肵�đΉ��ɓ������Ă��܂����B���̕a�@�ł́A�d�NJ��҂͂܂����������̂́A����Ɋ����̋}�g�傪�����A�d�NJ��҂������Ă����A��ʐf�Âɉe�����o���˂Ȃ��Ɗ�@�������߂Ă��܂��B������Ȏ��ȑ�w�����a�@�̏��r���i���a�@���́u���҂͔����I�ɑ����Ă���B�ψي��̌^�ŕa������Ƃ����K�v�x�����A���҂����e����Ƃ������Ƃ�D�悹��������Ȃ��̂ł������������������v�Ƙb���Ă��܂��B
���~�}��������ȃP�[�X�}��
�~�}���҂�������Ë@�ւ������Ɍ��܂�Ȃ��u��������v�ȃP�[�X���A7���ɓ���}�����Ă��܂��B�����ȏ��h���̂܂Ƃ߂ɂ��܂��ƁA����25���܂ł�1�T�Ԃł�2202����3�T�A���ő������A�O�̏T(18���܂�)��1�T�Ԃ�1545���Ɣ�ׂ��1.4�{�ɂȂ��Ă��܂��B���̂����A�V�^�R���i�E�C���X�̊������^����P�[�X��698���ŁA�O�̏T�܂ł�1�T�ԂƔ�ׂ�1.6�{�ɋ}�����Ă��܂��B�����ȏ��h���́u�n��ɂ���邪�A��Ë@�ւ̑I��⊳�҂̔����Ɏ��Ԃ�����������łɔ������A�f�[�^����͕a�����Ђ������钛���������Ă���B��肢�������V�^�R���i�E�C���X�̊�������Ƃ��Ăق����v�Ƃ��Ă��܂��B
�������s�̎���×{�� 1�����O��5�{�ȏ��
����ŁA����×{���Ă���l�̐l����1�����O�Ɣ�}�����Ă��܂��B����21�����_�őS����1���l���A�����s�ł�4000�l�]��ƁA1�����O��5�{�]��ɑ��������Ƃ������J���Ȃ̂܂Ƃ߂ŕ�����܂����B
�����J���Ȃ̂܂Ƃ�(����21�����_)
�S�� 1��717�l�@�O�̏T(5809�l)��肨�悻4900�l�����Ă��܂��B
�����s 4068�l�@�O�̏T(1839�l)�̂��悻2�{�A1�����߂��O��6��23�����_(711�l)�Ɣ�ׂ��5.7�{�ɑ������Ă��܂��B
�_�ސ쌧 2241�l�@�O�̏T(1468�l)��1.5�{�A1�����O(746�l)��3�{��
��t�� 792�l�@�O�̏T(470�l)��1.7�{�A1�����O(251�l)��3�{�]���
��ʌ� 1104�l�@�O�̏T(410�l)��2.7�{�A1�����O(108�l)�Ɣ�ׂ��10�{�ȏ�ɋ}�����Ă��܂��B
�����f�̈�t�u�ݑ�ł͏\���Ɏ��Âł��邩�S�z�v
����×{�҂̉��f�ɂ������t����@�������߂Ă��܂��B���c�J��ɂ���w�ӂ��낤�N���j�b�N���X�́x�̎R�����@���ɂ��܂��ƁA26���ɉ��f��������×{�̊��҂��u1�T�ԔM��������Ȃ��v�Ƙb���A�x���̏Ǐ�����������ߒ����ǂƐf�f���ē��@���邱�ƂɂȂ����Ƃ������Ƃł��B�R���@���́u�ݑ�ł��_�f���^��_�H�͂ł��邪�A�a�@�ł̎��ÂƔ�ׂĈ��|�I�Ɏ�Ԃ���������E������B�n��̂��������͐V�^�R���i�̐f�f���������Ƃ͂����Ă����Â̌o���͂قƂ�ǂȂ��A�\���ɑΉ��ł��邩�S�z���Ă���v�Ƙb���Ă��܂��B�����̊g��Ŏ���×{�҂�������ƌ����邱�Ƃ���A�ق��̒n���t��ɂ����͂��Ăт����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���z��������g��Ɋ�@���@�u�ܗւŊɂ݁v�w�E���\�����s�@7/28
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�28���A2���A���ʼnߋ��ő����X�V���A3177�l���L�^�����B����܂Ńs�[�N������1���́u��3�g�v��莀�҂�d�ǎ҂����Ȃ����Ƃ���A���r�S���q�m����s�����́u���g���Ⴄ�v�ȂǂƓs����̕s�������ɖ�N���B�������A�ً}���Ԑ錾���߂���2�T�Ԃ����Ă������g�傪��������Ɋ�@������点�Ă���A�u�����ܗւ��C�̊ɂ݂ɂȂ����Ă�v�Ƃ̎w�E���o�Ă���B
�u��������ɕs����������Ȃ��łق����v�B�s�����ی��ǂ̋g�����F�ǒ��́A�V�K�����҂�2848�l�ƂȂ���27���A�e�ЂɈٗ�̌Ăъ|�����s�����B���N�`���ڎ�ɂ�鍂��̏d�ǎ҂̌�����a���g�[�������A�u��3�g�Ƃ͖{���I�ɈقȂ�v�ƌ�����B����Łu���T�傫�Ȑ������o��Ɗo�債�Ă������A2500�l����Ƃ͑z���ł��Ȃ������v�ƌ������\����������B
��28���A�ǒ��̔����ɂ��ċL�Ғc������ꂽ���r���́u���͗z���Ґ������̖��ł͂Ȃ��B���N�`�������邩�Ȃ����̈Ⴂ�͂�������`���Ăق����Ƃ�����|���Ǝv���v�Əq�ׂ��B���������͂������C���h�R���̕ψي����g�傷�钆�A����̐ڎ�̐i�W�͕s�������B�s���ł́A��~�����߂��Ă����ޒ𑱂�����H�X��A�H����݂�����������B
�M�킪�����ܗւ̉e�������O���鐺������B���銲���́A�l�o���傫������Ȃ�����Ɂu�ܗւ�����Ă��邱�Ƃ��A�O�o���l�Ƃ͋t�̃��b�Z�[�W�Ɏ���Ă���v�Ǝw�E�B�u���A���ɑ���������Ă��������������v�Ɠ��������B
��l�܂芴���Y�����A���r����26������3���A���Ŋ����Ґ��̔��\�O�ɑޒ��B28���́u���Еs�v�s�}�̊O�o���T���Ă��������v�ƋL�Ғc�Ɍ����c���A�s������ɂ����B
�����Ɓu�o���Ȃ��g��v�w�E�@��s����75%���ψي����@7/28
�V�^�R���i�E�C���X��������J���Ȃɏ���������Ƒg�D(�A�h�o�C�U���[�{�[�h)��28���A����J���A�����s�𒆐S�Ƃ����s�������łȂ��A�S���̑����̒n��Ŋ����҂������X���ɂ���A�u����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��ƂȂ��Ă���v�Ǝw�E�����B
�����s�ɑ���4��ڂً̋}���Ԑ錾����2�T�Ԃ��o�������A�l�o�̌������͑O���菬�����A���ʂ͔����B�����͂������ψي�(�f���^��)���A����Ŏ�s���̐V�K������75%���߂�悤�ɂȂ�A����������g�傪�����ƌ��O����Ă���B
27���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����҂͐l��10���l������ŁA������88�E63�l�B�O�T���1�E49�{�ɑ������B�e�n�ő������͍����A�k�C��1�E35�{�A��ʌ�1�E58�{�A��t��1�E48�{�A�_�ސ쌧1�E37�{�A���m��1�E46�{�A���{1�E52�{�A������2�E20�{�A���ꌧ2�E15�{�ƂȂ��Ă���B�S�����ςł�1�E54�{�������B
�����s��w�����������́A3��ڂ�4��ڂً̋}���Ԑ錾�ŁA�ɉ؊X�̑ؗ��l�����r�B�錾��2�T�ԂŁA3��ڂ͒���(���߁`�ߌ�6��)��36�E0%�A���(�ߌ�6���`�ߑO0��)��48�E2%�����Ă����B����������́A���Ԃ�13�E7%���A��Ԃ�18�E9%����2����1�ȉ��̌��蕝�ɂƂǂ܂��Ă���B
�f���^���̋^��������uL452R�v�̕ψق�����E�C���X�Ɋ��������l��26���܂łɁA�S����PCR�X�N���[�j���O������7153�l���m�F�����B8������s���������B�O�T��4349�l����}�����Ă���B
���Ƒg�D�̘e�c���������͉��̋L�҉�ŁA�ً}���Ԑ錾�ɂ��āA�u���ʂ��o�Ă���Ƃ͌����������v�Ǝw�E�B��Âւ̕��ׂ����܂��Ă���Ƃ��A�u���̂܂܂̏������A�ʏ�ł���Ώ����閽��������Ȃ��ɂȂ邱�Ƃ��������O�����B����������@�����s���Ǝs�������L�ł��Ă��Ȃ����Ƃ����݂̍ő�̖��v�Əq�ׂ��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������s �����}�g��ŎႢ����Ƀ��N�`���ڎ푣���ȂǑ��@7/29
�����s���ł�28���A�����m�F�����߂�3000�l���A�}�g�傪�~�܂�܂���B�s�́A���Ԃ�ŊJ����J�M�͎Ⴂ����̊�����H���~�߂邱�Ƃ��Ƃ��āA���N�`���ڎ�𑣂��ȂǐV���ȑ�������������l���ł��B
�s���ł́A28���A����܂łōł�����3177�l�̊������m�F����A2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B3000�l����̂͏��߂Ăł��B�ً}���Ԑ錾���o����Ă���2�T�Ԃ������܂����A���ʂ͂܂��݂�ꂸ�A�}�g�傪�~�܂�܂���B
28����3177�l�̂������N�`���̐ڎ킪�i��ł��鍂��҂̊����͂��悻3���Ȃ̂ɑ��āA20���30������킹���55�����܂���߂Ă��āA�Ⴂ����Ŋ������g�債�Ă��܂��B�s�́A���Ԃ�ŊJ����J�M�͎Ⴂ����̊�����H���~�߂邱�Ƃ��Ƃ��āA�O�o���l�Ȃǂ̌Ăт����𑱂���ق��A���N�`���ڎ�𑣂��ȂǐV���ȑ�������������l���ł��B
�����A�ً}���Ԑ錾�͍����4��ڂŁA���������l�v���ɗ����������ɂ����Ȃ��Ă���ق��A�Ⴂ����͐ڎ�ɑ����R�����������Ƃ��w�E����Ă��āA�������}�g�傷�錵�����ǖʂŌ��ʓI�ȑ��ł��o���邩���ۑ�ł��B
���R���i�}�g��@�����蒼���˂� �@7/29
�����s�𒆐S�Ƃ����s���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�Ă���B�ً}���Ԑ錾�����~�߂ɂȂ��Ă��Ȃ��B�����g��h�~�ɉ�������Ȃ��̂��A���{�͑��}�ɑ����蒼���ׂ����B
�����s�̈���̐V�K�����Ґ����N�n�́u��O�g�v������A�_�ސ�A��t�A��ʎO���ł��}�����Ă���B��\�����ɊJ���ꂽ�����J���Ȃ̐��Ɖ�c�́A�}���Ȋ����ґ����u����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��v�Ǝw�E�����B
�s�s���̊����g��͒n���ɂ��g�y����B���ꌧ��k�C���͂��łɑ����ɓ]�����B�l�̗��ꂪ�����邨�~�̎�����O�ɁA�������������u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���`�̎́A�����g��ɔ��������ܗցE�p�������s�b�N�𒆎~����\���ɂ��āu�l���������Ă���v�Ɣے肵���B
�l�x�ڂ̐錾���ߌ�A�l�o�͊m���Ɍ����Ă��邪�A�ȑO�̔��ߎ��ɔ�ׂ�Ό�����͓݂��B���Ɖ�c�ɂ��ƁA�����̖�Ԃ̐l�o�̌���͑O�ߌ��T�ԂƔ�ׂ�ƍ���͓̈�ȉ��ɂƂǂ܂�B�l�o�͌����Ă��Ȃ��Ƃ����̂������̎������낤�B
�l�X�̊ԂŁu�R���i���v���L����A���{�̑�ɕs��������Ă���̂ɁA�̐����͊�@���������A�ܗ֗D��̎p�����瓧���Č�����B���܂�ɂ��s�������B
���Ɖ�c���ł����O����͈̂�Â̕N��(�Ђ��ς�)���B
����҂ւ̃��N�`���ڎ킪�i�ݏd�ǎ҂⎀�S�҂͌����Ă��邪�A�����S�̂̓��ڎ헦�͎O�����x�ɂƂǂ܂�B�����}�����݂̌��ʂ͂܂����҂ł���ł͂Ȃ��B
�����҂��}�����铌���ł́A����×{����@�҂��Ȃǂ����l�����B���𐢑�ł����@�ł����ɏd�lj��⎀�S����P�[�X�������Ȃ����S�z���B
�d�lj����₷���Ƃ�����C���h�^�̃f���^���ւ̒u���������i�ށB�a���ƈ�Ðl�ނ̊m�ۂ�����ɐi�߂�K�v������B
���H�X�ł̊����g���h���ɂ͈��H�X���̋��͂��s�������A���{�͋��Z�@�ւ��މ��Ǝ҂�ʂ��Ĉ��͂������悤�Ƃ��Č������������������B�ǂ���������H�X�̋��͂�������̂��A�ߋ��̐U�镑����ҏȂ��A�����������������������ׂ����B
�_�ސ�A��t�A��ʎO���ً͋}���Ԑ錾���߂�v��������j���B���{�́A���Z���ɋ߂������̂Ƃ���@�������L���ׂ��ł���B
���R���i�����}�g��@�y�ώ̂đ�ɖ{�����@7/29
�S���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���28���A9500�l���ĉߋ��ő��ƂȂ����B�����s�ł͘A���̉ߋ��ő��X�V��3��l��ɒB�����B�������銴���g��ɑ��A���{�͊y�ώp�������߁A����ȏ�̊g���H���~�߂邽�߂ɐϋɓI�ȑ���u���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�����Ɠ��l�ɉߋ��ő��̊����Ґ��ƂȂ�����ʁA��t�A�_�ސ�̎�s��3���͋߂��ً}���Ԑ錾�𐭕{�ɗv���A���߂����������B4�s���őS���̊����Ґ��̖�6�����߂Ă��錻�猩����̓����͒x�߂���B
�k�C���A���{�A���ꌧ�ȂNJe�n�Ŋ����҂̑������������B���͂��s�������̊����g��ł͂Ȃ��B�n���̊�@�����d���~�߁A���{�͕K�v�Ȏx������i�߂�K�v������B
���Ƃ��挎���Ɏ����������ܗ֊��Ԓ��̊����g��V�~�����[�V����������B�����͂̋����C���h�R���̃f���^���g��̉e���ȂǂŁA�s���̐V�K�����҂�8����3��l����\�����w�E����Ă����B
���̃V�i���I���O�|���Ō��������Ă���̂͐[���B�����s�ɔ��߂��ꂽ4��ڂً̋}���Ԑ錾�̌��ʂ��������Ƃ͖������B
�N��ʂɌ�����N�`���ڎ킪�i��65�Έȏ�̐V�K�����҂͏��Ȃ��A���ڎ��50��ȉ��������X��������B�s�̒S���҂͎Ⴂ����̏d�lj����X�N�̒Ⴓ���������āA��ÕN��(�Ђ��ς�)�̏͐����Ă��Ȃ��Ƃ����B
����̏O�@���t�ψ���ł͐��{�̐V�^�R���i�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή���u��Â̕N�������ɋN���n�߂Ă���Ƃ����̂������̔F�����v�Ƌ�����@�����������B�����Ґ��̑�������Ì���ɋy�ڂ��e�����������͂��͂Ȃ����낤�B
���`�̎͋C�ɂȂ锭�������Ă���B���Ö�̊m�ۂ�N�`���ڎ�̌��ʂ���������ƂƂ��ɏq�ׂ��u�l�̗���͌����Ă���B�S�z�͂Ȃ��v�Ƃ����ɂ߂Ċy�ϓI�Ȍ������B
����Ɋ����g��ւ̊�@���̊�������Ƃ���Ζ�肾�B���{��胏�N�`���ڎ헦���������X�ł������̍Ċg�傪�N���Ă���B�����̋C�̊ɂ݂�U�����˂Ȃ����b�Z�[�W�͌��ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���Ə��r�S���q�s�m�����������낦�ē����ܗւ̃e���r�ϐ���Ăъ|���Ă���B����ȑi�������Ől�o���}�������Ƃ͓���v���Ȃ��B
�s���̔ɉ؊X�̐l�o�͐錾��ɂ�⌸�����Ă���Ƃ͂������̂́A�ߋ��̐錾���Ɣ�ׂČ�����͏������Ƃ����B�ċx�݂��n�܂�A���ϋq�Ƃ͂����ܗ��Z�̔M�킪�J��L������s���ł́A���g�����C���̍L����������Đl�o�̗}���͂܂��܂�����Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����B
�����̃s�[�N�����ʂ��Ȃ��܂܁A���~�̋A�Ȃ�ċx�݂̉Ƒ����s�V�[�Y�����}����B���{�����m�ȃ��b�Z�[�W��ł��o���ƂƂ��ɁA�e�����̂ƘA�g���ċ��͂ȑ�����Ȃ�����A���̊����}�g��͎~�߂��Ȃ��B
�������ܗ� �u�����������ɂ͓P�ނ������Ă������C���������K�v������v�@7/29
�����{�m���ŕٌ�m�̋����O��(52)��29���A�t�W�e���r�̏��ԑg�u�߂��܂�8(�G�C�g)�v(���`���j�O8�E00)�ɏo���B�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɂ�铌���ܗււ̉e���ɂ��Č��y�����B
�����s�ł�28���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3177�l���ꂽ�B27����2848�l������A����3000�l��ƂȂ���2���A���ʼnߋ��ő����X�V�B6�l�̎��S���m�F���ꂽ�B����12������ً̋}���Ԑ錾���Ԃ�2�T�Ԃ��o�ߌ�����N�`�����ڎ킪��������𒆐S�ɂȂ��g�傪�����ăs�[�N���������A��Ò̐���J�Ò��̓����ܗււ̉e���Ɍ��O�����܂��Ă���B
�������́u�l�́A�ܗւƊ����Ґ��̓_�C���N�g�ɂȂ����Ă��Ȃ��Ƃ����悤�ȗ���Ȃ�ł����ǁv�Ƃ�����ŁA�u����ł�����ς�P�ރ��C���c�A�l�͌ܗւ𒆎~�ɂ��Ăق����Ȃ���ł����ǁA�����������ɂ͓P�ނ������Ă������C���������K�v������Ǝv����ł���B��Ì���Ŗ{���ɑ�ςȏɂȂ��Čܗւǂ���ł͂Ȃ��Ƃ����Ƃ��낪����Ǝv����łˁB�����������C�����������ɂƂɂ����ܗւɓ˂��i�ނ��Ă����͉̂ߋ��ɐ푈�œP�ރ��C�������߂��ɂǂ�ǂ�˂��i��ł����Ĕs�킵�����ʂƂ��A�����������Ƃ��w��ł��Ȃ��̂��B�����{��k�Ђ̎��ɂ��z��O���Ă������̂�u���Ă͂����Ȃ����Ă��Ƃ�l��U�X�w�̂ɁB�P�ރ��C������������u���āA�������Ȃ��悤�ɍ��Ɖ^�c���Ă����̂������̖������Ǝv���v�Ǝ��g�̌������q�ׂ��B
�����āA��̓I�P�ރ��C���ɂ��Ắu��Õ���̂Ƃ��낾�Ǝv���B�V�K�����Ґ������ł͂Ȃ��āA��Ì��ꂪ�ƂĂ�����Ȃ����Ǎ��ܗւ���悤�ȏ���Ȃ����Ă������C�����z����Όܗւ͂��ׂ�����Ȃ��Ǝv���B�����l�͂����Ȃ�Ȃ��悤�ɍ��Ɖ^�c�����Ă����ƁB���̓P�ރ��C���������Ă��Ȃ�����A�݂�ȐV�K�����Ґ������ŕs���ɂ����Ă��܂��B��Õ���̂Ƃ��낪�P�ރ��C�����Ǝv���v�Ƙb�����B����Ɂu�l�͌ܗւ͂��̂܂ܑI����������ĂȂ�Ƃ����܂Ō}���Ă��炢�����Ǝv����ł����A������������ɔz�����邱�ƂȂ��������˂�����ƍ��㍑���͐��{�̌������Ƃ��Ȃ��Ȃ�Ǝv���v�Ǝw�E���A�u���H�X�ɂ������č����S�̂��B�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ����̃��C�����z������ܗւ͂ł��Ȃ��B���̃��C�����z���Ȃ��悤�Ɉꐶ��������ƁB�����͈�Õ��Ǝv���v�Əq�ׂ��B
�����Ɓu���ꂪ���������c���͒f��E�C���v�@7/29
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂́A28���A�����s��3177�l�m�F����A�����g�傪�~�܂�܂���B�����ǂ̐��Ƃ́u���ꂪ�I�[�o�[�V���[�g�v�Ɗ�@�����点�A�����g����~�߂邽�߂ɂ́A���݉��l���W�܂�@��ɂ́u���͂�߂悤�ƒf��E�C���v�ƌĂт����Ă��܂��B�����J���Ȃ̐��Ɖ�c(�A�h�o�C�U���[�{�[�h)�̃����o�[�Ō��O�q�������́A���ۈ�Õ�����w�̘a�c�k�������̓c�C�b�^�[�ŁA�u���ꂪ�����N����Ƌ���Ă����I�[�o�[�V���[�g(��������)�ł��B�������s�[�N�����킩��܂���v�Ɗ�@�����点�A�u����1�N���œs���Ŋ�������\���͍�����ԍ����v�ƒ��ӂ��Ăт����܂����B28���ߑO�A����ƍ���̌��ʂ��A���������Ƃ�ׂ��s���ɂ��ĕ����܂����B
����������ǂ��݂Ă��܂����H���̋ǖʂŎ������͂ǂ��s������悢�̂ł��傤���H
�����Ґ�������Ȃ��č����Ă��܂��B�����������ǖʂł��B���̒��ł́u�F�Ŋ����g����~�߂悤�v�Ǝv���Ă��������̂��厖���Ǝv���܂��B1�̃S�[���Ƃ��āA�����҂����炷�Ƃ����悤�ȕ����ł��܂��傤�Ƃ����l���ł��B�I�����s�b�N�̃e���r�ϐ���A�Ƒ��ȊO�Ƃ̐ڐG�����炵�āA�Ƃł̎��Ԃ��߂������Ƃ́A�����g����~�߂��ŗL�����Ǝv���܂��B�I�����s�b�N�J�Âɂ͔����Ă���l�����܂�����ǁA(������}������)�ړI�͐l���ꂼ��ł����Ǝv����ł��B���A�I�����s�b�N�����邵�A����A���~�����邵�B���~�́A�A�Ȃ�����A�Ⴆ�Ώ��~�ł���Q�肵�����Ƃ��A�����ɉ߂��������Ǝv�����͑����ł��傤�B�l�ɂ���āA�����}����ڎw���̂͌ܗւ��ɍs�����߂ɂƂ��A�����Ƃ�����̐l���������Ȃ����߂ɁA�Ƃ��A���~���ɉ߂��������Ƃ��A���������̑�ɂ��邱�ƁA�ړI��I�т₷���A�悢�^�C�~���O���Ǝv���܂��B���ꂼ�ꂪ���炩�̖ړI�Ŋ���������̂����邽�߂ɂ́A���Ȃ��Ƃ�����1�T�ԂȂ�10���ԁA�l�Ƃ̐ڐG�̋@������炵�Ă��炤�A���i���Ȃ��l�Ƃ͉��Ȃ��A�ꏏ�ɏZ��ł���Ƒ��Ƃ̐ڐG�ɂƂǂ߂�Ƃ������Ƃ𑱂��Ăق����B�����̂��߂����邯�ǁA�N���A�Ƃ������̂��߂ɁA���ƁA�ӊO�ɍs����ς�����A��������߂���ł�����̂Ȃ�ł��B�_�C�G�b�g��։��������ł���ˁB
�������ƂƂ��āA���ɑłׂ���͍l���Ă���̂ł��傤���H
��{�͐ڐG�����炵�Ă��������Ƃ������Ƃł��B�ȑO��8���̐ڐG���Ƃ������Ƃ�����܂����B�C�O�ł悭�s���Ă�����g�݂ŁA���{�ł܂����{����Ă��Ȃ��̂��A�Ƒ��ȊO�̐l���W�܂�ۂ̐l�������ł��傤���B�u���l�ȏ�ŏW�܂�͍̂T���āv�Ƌ�̓I�Ȑ��Ŏ����̂��ǂ����B�����A�I�����s�b�N�͂���Ă���̂ɂƌ����Ă��܂���������Ȃ��B���ۂ̊����́A���K�͂œ���̏�ŋN���Ă���̂ł����A���̈Ⴂ��������Ɛ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�傫�ȉe����������̂͂������A�������ł��B�C�O�ł����{�������ɂ߂������ނȂ������Ă��܂����A���������������i�K�ɂ���܂��B
�����s���̔ɉ؊X�A�l���͈����x�����Ă���B���̒��ł��A�ꕔ�A���݉�ŏW�܂�l���������Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H
�����ł��ˁA���݉���łȂ��A����̏��K�͂ȐڐG���N���Ă���A�ɉ؊X�����łȂ��A���܂��܂ȏꏊ�œ���̏�ʂŊ������N���Ă���킯�ł��B������N�������S�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ƁB���́A�ڐG�@������炵�Ă��炤�A�Ƃɂ��Ă��������^�C�~���O�B�ܗւ̂��߁A���~�̂��߁A�Ƒ��̂��߁A�����́u�����̂��߁v�����߂āA�Ƃɂ��Ăق����ȂƎv���܂��B
�������݉����Ă���A�Ƃ����l������Ǝv���܂��B
�����ł��ˁB���݉�𖾓��\�肵�Ă���A�c�ɂɋA�낤�Ɨ\�肵�Ă���l�́A���͂�߂�A�Ƃ������Ƃ��厖�Ȃ�ł��ˁB�����ɍs�����ƂŁA�ق��̐l�Ɋ���������Ƃ�����c�c���́A���Ȃ�����������\���A�N��������������\�����A�V�^�R���i�E�C���X���������Ă���̂���1�N���̒��ň�ԍ����ł��B
�������������Ǐ�ł��A���͋C�����Ȃ������ɃE�C���X�������Ă��āA����𖾓��A��l�ɂ����\������Ԃ��鎞���ȂƎ��o����Ƃ������Ƃł��ˁB
�����ł��B���ɓ����͂����ł��B
�������́A���̉䖝�͂��܂ł��ׂ��Ȃ̂��H�l���������Ă��犴���҂�����܂łɈȑO��2�T�Ԃقǂł������A�O��̗��s���̑����݂Ă��A5�T�Ԃ��炢������܂����B
�����Ȃ�ł��B��͂�(�f���^����)�����₷�����犴���҂��Ȃ��Ȃ�����Ȃ��B�l���̌����������Ȃ���ł��B���̑O�A6�����{�ȍ~����l���������Ă����ςݏオ�肪����B���́A������i���炳�Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���݉���Ђ̏W�܂�Ŋ��������������܂��B�����������̂ɎQ�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�f��E�C�Ƃ������B���͂�߂悤�ƌ�����E�C�Ƃ����̂́A�������A���A�厖���Ǝv���܂��B�u����߂܂��傤�v�Ƃ����̂́A�����������I�Ȕ��f���Ǝv���B�܂�����������J�Â�������ƍl���Ă��������āB
�������܂Ŋ����g��͑����̂��B1�`2�T�Ԃ��H
����͖ł��Ȃ����A�I�����s�b�N���8��8���܂łɂ́A����菭�Ȃ�(�V�K�����҂�)�l�����݂����Ǝv���Ă����ł��B�����܂łł��߂Ȃ�A���~�́A�S���Ō��������łK�v���o�Ă��܂��B
�������A�O�o���l��Ȃ��ƁA���܂ł������҂͌���Ȃ��ƁB
�͂��B���������ǖʂȂ�ł��B�ƂĂ�������B
�����Ⴂ�l�����f�ł��Ȃ��B
�f���^�����ƎႢ�N��������������Ă��܂��B���f�ł��Ȃ��B�f���^���ɒu��������Ă��Ă��邩��A�ǂ̔N������ӂ��Ă��������K�v������܂��B�e�����܂��͖������s�������Ă��������B
���ܗ֑��������̖�����̂��@7/29
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����A�����s�ŏ��߂�3��l���ĉߋ��ō����X�V����ȂLjُ�ȃy�[�X�ŋ}�����Ă��܂��B�s�͓s���̈�Ë@�ւɑ��A�ʏ��Â𐧌����ăR���i�a���̊m�ۂ����߂�ʒm���o���Ă��܂��B�s���ł͈�Õ��N�������ƌ����܂��B����������@�I�ȏɂ�������炸�A���`�͓̎����ܗ֒��~�̑I�����́u�Ȃ��v�ƒf�����܂����B�����̖��ƈ��S�����Ȃ��Ȃ�Όܗւ͂��Ȃ��Əq�ׂĂ�������̍���ł̓��قɂ���������̂ł��B�ɂ͂��̎��Ԃɂǂ��Ώ�����̂������ƍ���ɐ�������ӔC������܂��B
�s�̒ʒm(26���t)�́A�����Ȃǂ́E�]������s���j�^�����O��c���u(�V�^�R���i)���@���Ґ���6�����{�����1�����Ŕ{�����Ă���A����A�V�K�����Ґ����}���ɑ�������A��Ò̐����N��(�Ђ��ς�)�̊�@�ɒ��ʂ���v�Ǝw�E���Ă��邱�Ƃ��Љ�A�R���i�a���̊m�ۂ�v�����܂����B
���̂��߂Ɂu�ʏ��Â̐����v������ɓ��ꂽ�u�a���̓]�p�v�����߁A��̗�Ƃ��ċ~�}��Â̏k���E��~�A�\���p�̉����A�ꕔ�f�ÉȂ̒�~�A�f�Ë@�\�̏k���\�������܂����B�����̈�Â����ĂȂ��@�\�s�S�Ɋׂ���邱�Ƃ������Ă��܂��B
�����ł�4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾��12���Ɏn�܂��Ă���2�T�Ԃ��߂��A�{���ł���Ό��ʂ��o�Ă��鎞���Ƃ���Ă���̂ɁA�Ȃ��������}�g�債�Ă���̂��B�����͂̋����f���^���̍L����ɉ����A�u���{�ւ̐M�����Ȃ��A�ǂ�ȃ��b�Z�[�W���o���Ă�������̂�����Ȃ��Ă���v(�����J���Ȋ���)�Ƃ̐������Ă��܂�(27���̂m�g�j�j���[�X)�B
�M���������������Ȃ��̂́A���������ܗւ𑱂��Ȃ���A�����ɂ͊O�o���T����悤�ɌĂъ|���閵���������b�Z�[�W���o���Ă��邩��ɑ��Ȃ�܂���B�����̈����́A��s���S�̂���S���ɔg�y������܂��B
���́A27���ɓ����ł���܂ł̍ő��ƂȂ�2848�l�̐V�K�����҂��o�����ƂɊւ��u(�ܗ�)���~�̑I�����͂Ȃ��̂��v�ƋL�҂������A�u�l���������Ă��邵�A�����͂Ȃ��v�Ɩ������܂����B
�������A���{�̐V�^�R���i�����ȉ�̊ړc�ꔎ���M��w�����́u���̊����Ґ���2�T�ԑO�Ɋ��������l�ł���A�l�̗��ꂪ�����Ă��Ȃ����Ƃ��l����Ɗ����Ґ��͂���ɑ�����\��������v(���O)�Ǝw�E���܂��B�͐l�������̗��R�Ƃ��āu�Ԃ̐����v�Ɓu�e�����[�N�v�������܂������A�{���ɂ���Ō����Ă���̂��B���m�ȍ����������Ȃ��͖̂��ӔC�ł��B
����6��9���̍���ł̓}�_�ŁA���{���Y�}�̎u�ʘa�v�ψ����̎���ɑ��u�����̖��ƈ��S�����͎̂��̐Ӗ����B���Ȃ��Ȃ�����(�ܗւ�)���Ȃ��͓̂��R�v�Əq�ׂĂ��܂��B���͂܂��Ɂu�����̖��ƈ��S�����Ȃ��Ȃ��Ă���v���Ԃł͂Ȃ��̂��B�����ł���Ύ͍���ł̌����ʂ�ܗ֒��~�����f���ׂ��ł��B
���Y�A�����A�����A�Ж��̖�}�͌��@�Ɋ�Â��A�����ŗՎ�����̊J�Â𐛐����ɋ��߂Ă��܂��B�ꍏ������������J���A�R���i�ƌܗւ̖���O��I�ɐR�c���A�������̕s����^��ɉ����Đ�������K�v������܂��B
���ܗ��Z���p���[��c�Ƃ̈��H�X�� �s200�l�Ԑ��Ō����� �@7/29
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�钆�A�����̔ɉ؊X�ł́A�s�̗v���ɉ�����������A�[��܂ʼnc�Ƃ��Ă�����H�X������܂��B���̒��ɂ̓I�����s�b�N�̒��p�𗬂��đ����̋q�Ŗ���ԂɂȂ��Ă���X������A�����s�͈��H�X�̌������s���A������Ȃ����ƂȂǂ����߂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�����s�́A7��12������ً̋}���Ԑ錾���A���H�X�ɑ����̒������A��8���܂ł̎��Z�c�Ƃ�v�����Ă��܂��B
�܂��I�����s�b�N�ɂ��āA����s�͕s�v�s�}�̊O�o�����l���Ď���Ńe���r�ϐ킷��悤�Ăт����Ă��܂��B
�����������E�a�J�̔ɉ؊X�ł́A�X�̑O�Ɂu�I�����s�b�N���f���v�Ƃ����\�莆������Ȃǂ��Ď�����Ȃ���c�Ƃ𑱂��Ă���X������A�����̋q���K��Ă��܂��B
���̂����[��12���܂ʼnc�Ƃ��Ă�����H�X�ł́A28����̓I�����s�b�N�A�T�b�J�[�j�q�̓��{�̎��������j�^�[�ŗ����A�����̋q���������݂Ȃ���X�̊O�܂ŕ�������قǑ傫�Ȋ������������Ă��܂����B
���̓X�̓X���́u�s����o����鋦�͋��͏\���ł͂Ȃ��A�����łǂ��ɂ����邵���Ȃ��B�X��߂ē|�Y����̂ł͂Ȃ��A�J���Đ����c�����I�B����������Ɋg�債�Ă��A�c�Ƃ𑱂��邵���Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂����B
����A�a�J�ɂ���X�|�[�c�o�[�uFields�v�ł́A�s�̗v���ɏ]���Ď�������A�����ߌ�8���ɓX��߂Ă��܂��B
28���̓T�b�J�[�̎�����X�Ō������Ƃ����d�b�������Ă��܂������A�X���̓c���炳���X��f���Ă��܂����B
�c������́u�s���ɏ]��Ȃ��X�����邪�A�o�c�҂����ꂼ�ꌈ�f�����Ɨ������Ă���B�����̓X�����[���ɏ]���Ă��钆�ŁA�������g�債�A�ނȂ���������v�Ƙb���Ă��܂����B
�s�ً͋}���Ԑ錾��A�ő��1��200�l�����H�X�̌������s���Ԑ����Ƃ��Ă��āA�������}�g�傷�钆�A������Ȃ����Ƃ⎞�Z�c�Ƃ����߂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�������ҁg�ߋ��ő��h�Ɂu�ŕs��������Ȃ��Łv �ǒ����ٗ�̐����@7/29
�����s��28���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3177�l�m�F���ꂽ�B���߂�3000�l���A���̂���2848�l�ɑ����A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
���̊����Ґ��̑�����s�͂ǂ̂悤�ɂ݂Ă���̂��B�e���r�����Љ�̖��c�����L�҂́u�܂�4�A�x�����ł��邱�ƁA�����ĕψي����L�����Ă��邱�Ƃ���A�s���̊����́w�o��͂��Ă����x�Ƙb���Ă����B�s�����Ƃ��ẮA�l�����������Ă���Ƃ����f�[�^������B��ԐS�z����͈̂�Ò̐��̕����A�R���i���җp�̕a�������m�ۂł��Ă��邱�ƁA�����҂���N�����Ă��č���҂������Ă��邱�Ƃ���A�����́w������Â�����������̂ł͂Ȃ��x�Ƃ��Ă��āA�ߋ��ő��Ƃ��������͏o�Ă��邪�A���C�Ȕ����͖ڗ����Ă���v�Ɛ�������B
2848�l�̊������m�F���ꂽ27���́A�L�Ҍ����ɍs����s�̒S���҂̊����̃��N�̑O�ɁA�ǒ�����ނɉ������Ƃ����B�u����͔��ɒ��������ƁB���̈͂ݎ�ނŋǒ����ǂ�Șb���������Ƃ����ƁA��X�ɑ��āw��������ɕs����������Ȃ��łق����x�ƁB1���Ƃ͈Ⴄ���Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��b���Ă����B�w�������ɂǂ��Ȃ���̂ł͂Ȃ��̂ŁA�ŕs����������Ȃ��ł���x�Ƃ����b�������v�B
�Ƃ͂����A�����g��̃X�s�[�h�͑����A�ʂ̊�������́u�ȑO�A���̈�Â�����Ƃ����悤�ȏɂȂ������A�����Ȃ�Ȃ��悤�ɍőP��s�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�u���̃^�C�~���O�Ŋ����҂������Ă����̂́A�I�����s�b�N�̂������ƂȂ肩�˂Ȃ���Ȃ����v�Ƃ����S�z�̐����������Ă���Ƃ����B
���N1���ɂ��s�̊����Ґ���2000�l�������A�s�͌��݂̓��N�`���ڎ킪�i��ł���ȂǁA�����Ƃ͈قȂ���Ɛ�������B�܂��A�����Ґ���2�T�ԑO�̏f����Ƃ���Ă��邪�A������2�T�ԑO�͂܂��I�����s�b�N���n�܂��Ă��炸�A�ǒ����u���̐����̓I�����s�b�N�����ډe�����Ă��鐔���ł͂Ȃ��v�ƌ������q�ׂ��Ƃ����B
����̌��ʂ��ɂ��ẮA�u�������s�[�N���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��v�Ƃ����̂��s�̍l�����B����ŁA����ׂ��w�W�͊����Ґ������ł͂Ȃ��Ƃ����A���c�L�҂́u�����҂͈�Ԃ킩��₷���w�W�ŁA�����ɂт����肵�Ď��l���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��Ƃ��A�����̊�������l����Ƃ����Ӗ��ł͑厖���Ǝv���B�����A���@�Ґ���d�ǎҐ��Ȃǂ����Ȏw�W�����đ����I�ɔ��f���Ă���̂ŁA���낢��ȕ𒍎������ق��������Ǝv���v�Ƃ����B
�������҂̋}���@�Љ�Ŋ�@���̋��L���@7/29
�V�^�R���i�̊����҂��S���ŋ}�g�債�Ă���B�����s�ł�2���A���ʼnߋ��ő����X�V���A����3��l�����B����3���ł����{�ɋً}���Ԑ錾�̔��o�����߂铮��������B
����҂̊����͂����ނ˗}�����Ă�����̂́A���@���K�v�Ȋ��҂�d�ǎ҂̒��S����������̐���Ɉڂ�A�x�b�h�͊m���ɖ��܂����B���E�e�n�Ő��͂��L����f���^���ւ̒u������肪�A�����ł��i�ށB
�l�̓����������ɂȂ�ċx�݊��ԂƏd�Ȃ�A�����ǂ̐��Ƃ��Ì��ꂩ��͂���܂ňȏ�̊�@����������Ă���B
�Ƃ��낪���̊�@�����A���A�����́A�����č����̊Ԃŋ��L����Ă���Ƃ͌�����B
���Ƃ��ΐ��ł���B�s�v�s�}�̊O�o�������悤�Ăт��������ŁA���ƂƂ������ܗււ̉e��������Ɓu�l���͌������Ă���B�S�z�Ȃ��v�Ɠ������B�������������͉ߋ��̐錾���ɔ�ׂď������A�ꏊ�ɂ���Ă͂ނ��둝�����Ă���B
�s���̂�����������������������͕s�M��[�߂邾�����B����܂ł��y�Ϙ_��U��܂��Ă͗}�����݂Ɏ��s���Ă��������Ɋʼn߂ł��Ȃ��B
�����s�̕����ی��ǒ��́A��Ò̐��ɖ��͂Ȃ��Ƃ̔F���������A�u��������ɕs����������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă������������Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�����s��26���t�ŁA�R���i�a���m�ۂ̂��߁A�~�}��Â̏k�����p�̉����Ȃǂ̌�������Ë@�ւɗv�����Ă���B�Ȃ����𔒂ƌ�������߂�悤�Șb������̂��B�l�X�������s���A��Ï]���҂̐ؔ����Ƃ̂���͖��炩���B���r�S���q�s�m�����ǒ��Ɠ��������Ȃ̂��B
���{�E�s�͊O�o���l��ړ��̗}�������߂Ȃ���A�ܗւƂ�������C�x���g�����s���A�j�ՋC���������o���Ă����B���̖��������܂��܂ȏ�ʂŕ��o�B�J��Ԃ����錾�ւ̊����A��ނ̒�~���߂��鎸���ւ̔������d�Ȃ��āA�s���̗v���ɋ��͂��悤�Ƃ����ӎ��͋ɂ߂ĊɂȂ��Ă���B
���������̐U�镑���ɂ���āA���������̌��t���s���ɓ͂��Ȃ��B�܂����̎��o�������A����܂ł̔��f�~�X�Ȃ��������ŁA�̉��P�ɓ�����˂Ȃ�Ȃ��B�ܗւɂ��Ă��A������ŕ\�������u�����̖��ƌ��N������Ă����̂��J�Â̑O������v�Ƃ����ɂ�����ʑΉ����Ƃ�K�v������B
����҂̗l�q�����Ă��A���N�`�����s���n��Έ��̌��ʂ����҂ł���B����܂Ŏ��҂�d�ǎ҂��ŏ����ɂƂǂ߁A�ʏ��ÂɎx������������ƂȂ����̓�ǂ�����B���̂��߂ɉ���苁�߂���̂́A�Љ�S�̂ŔF���̋��L��}�邱�Ƃ��B
����ʌ��A�ً}�錾��v���ց@���@�����ȂNj���������@7/29
��ʌ���28���A�V�^�R���i�E�C���X�̐��Ɖ�c���J���A�����҂̑����y�[�X�����܂��Ă��邱�Ƃ���A���{�ɑ��A�ً}���Ԑ錾��v�����邱�Ƃɂ��Ĉӌ������߂��B�߂����̑��{����c���J�����肵�A�����ɗv������B��쌳�T�m���͉�c�Łu�a���m�ۂ�ی����A���@�����̐��̋�����}���Ă��邪�A����ȏ㊴�����g�傷��ꍇ�͏d��Ȏx�Ⴊ������\��������v�Əq�ׁA��w�̑����K�v���Ƃ����B������28���̐V�K�����҂�870�l�ƂȂ�A27����593�l��啝�ɏ���A2���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
��c�ł͐��Ƃɑ��A���݂̌����̊��������ƕK�v�ȑΉ�������B������28���̐V�K�����҂�870�l�ŁA�O�T21����381�l����1�T�ԂŔ{�ȏ�ɑ����B1���ȗ��A���N�Ԃ�ɉߋ��ő����X�V����27����593�l��啝�ɏ���A2���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B�����ł�20������8��22���܂ŁA20�s����[�u���Ɏw�肵�A�܂h�~���d�_�[�u�ɂ�銴���h�~�s���Ă��邪�A�����ƂɐV�K�����҂͋}�����A�y�[�X�����܂��Ă���B
22�`28����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͌v3617�l(1������516�E7�l)�ŁA2�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o���ꂽ�����1�����{�������Đ��ځB�V�K�����҂̑����ƂƂ��Ɍ����m�ەa���g�p�����㏸�𑱂��A27�����_��51�E4��(857�l�^1668��)�A�����d�Ǖa���g�p����23�E6��(39�l�^165��)�ƂȂ��Ă���B
�����͂������Ƃ����C���h�R���̃f���^���̗z���������19�`25����1�T�Ԃ�47�E4���B�O�T(12�`18��)��36�E6������啝�ɏ㏸���A�����߂����f���^���ɒu��������Ă���B
�����{�u���b�N�_�E���v�̌������@�V�^�R���i�}�g��Ɂu�ł�Ȃ��v�@7/29
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����}�g�債�Ă���B2021�N7��28���ɂ͓����ł���3177�l�Ə���3000�l��˔j�����B4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����߂���Ă���ɂ�������炸�A�����Ґ��͑����������B
�S���̊����҂�9583�l�ƂȂ�ߋ��ő�B�ܗւƓ����i�s�ŁA�R���i�����Ґ����V�L�^�����������i�D���B����܂ł̑�𑱂��邾���ŁA���܂�َ������x���ɂȂ���銴�������ɑΉ��ł���̂��낤���B
����ʎՒf�A�X�̉c�ƒ�~�A�Z���͊O�o�֎~
���O�����R���i�Ɂu���b�N�_�E���v(�s�s����)�őΉ����Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B����ɑ��A���{�́u�ً}���Ԑ錾�v�ɂƂǂ܂��Ă���B�u���b�N�_�E���v�ɂȂ�ƁA�ʏ�A����̓s�s�E�n��ւ̐l�̏o���肪�K��(�֎~)�����B�J�~���̖���w�y�X�g�x���L�����B�A���W�F���A�̏����ȍ`���I�����B������A�l�Y�~�̑�ʎ���������B�y�X�g���Ƃ킩���Ē��͕����B��ʋ@�ւ̓X�g�b�v���A�d�b��X�ւ��K�������B�O���̐��E����u�₳�ꂽ�Z�������͂��炾���ƌǗ�����[�߂�B��Ñ̐��͍������A�����K���i�͍����A�����Ė����̂悤�ɑ����Ă������ҥ���B����͕��w��i�����A�R���i�Ђł͌����ɂȂ����B�R���i�̔����n�A�����E�����s�͂����������b�N�_�E���B���s�s�Ƃ̉������Ւf����A�H���i�͑�z�ɁB���̌�����B�e�n�ŗގ��̑��ꂽ�āB���b�N�_�E���́A��`�I�ɂ́A���s�s�Ƃ̌�ʁE�𗬂̐������w�����Ƃ������B�Z���̍s�����K������ꍇ�́A�����Ɂu�O�o�֎~�߁v�����߂����B����ɊO�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�p����t�����X�ł͈ꎞ�A�����K���i�̔����o���Ȃǂ������ĊO�o���ւ����A�ᔽ�҂ɂ͔������Ȃ���ꂽ�B���̂悤�Ɍ�ʎՒf�����łȂ��A�X�܂̉c�ƒ�~��A�Z���̊O�o�֎~�Ȃǂ��܂߂āu���b�N�_�E���v�Ə̂���邱�Ƃ������B
���K���̑唼�́u�v���v�ǂ܂�
��펞�ɁA�����͂���ʎs���̎�����@���Ő�������Ƃ����Ӗ��ł́A�ً}���Ԑ錾�A���b�N�_�E���A�O�o�֎~�߂͎��Ă���B�Ⴂ�͋����́B���{�ً̋}���Ԑ錾�́A���O���̃��b�N�_�E����O�o�֎~�߂ɔ�ׂ�ƁA�K�����ɂ��B�l�X�ȋK���̑唼�́A�u�v���v�ɂƂǂ܂�A�u�����K��v���Ȃ��B�����V���ɂ��ƁA���{�ً̋}���Ԑ錾�́A�����V�^�C���t�����ʑ[�u�@(�V�^�R���i���[�@)�Ɋ�Â��A���Ώۋ��Ɗ��Ԃ��߂Ĕ��߂���B������ēs���{���m�����A�Z���ɊO�o���l��A�C�x���g�̊J�Ð����Ȃǂ�v���A�w�����邱�Ƃ��ł���B�u�v���v�͑���ɑ��Ă̂��肢�B�u�w���v�ɂ͖@�I�ȗ��s�`���������邪�A�����͂Ȃ��B�Վ��̈�Î{�݂��J���ړI�ŁA�y�n�E�����ӂȂ��Ɏg�p������A���{�ւ̈��i����n���ɉ����Ȃ������肵���ꍇ�ɂ͔��������邪�A�����͂�����[�u�͌�����B�u�C�O�̂悤�ȋ��������͂ł̗}�~�͖@����͓���v�̂����{�̌��Ƃ����B�@�K���̈Ⴂ�́A���ꂼ��̍��̗��j�⌛�@�A�����ӎ��Ƃ��֘A����B�Y�o�V���ɂ��ƁA�u���{����O�̑���{�鍑���@�ɂ͍��Ƌً}���̋K�肪���������A���s���@�ɂ͑��݂��Ȃ��B�푈�̔��Ȃ��獑�Ƃ̖\����h���ӎ����������Ƃ����B���̂��ߓ��{�ł͐��A��ЊQ�ȂǗL���̍ۂ͌ʂ̖@����V�݁A�������đΉ����Ă����o�܂�����v�B
���u���J�[�h�́A�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���v
�����ł�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�Ƃ������Ƃ�����A�ْ���������A����̐l�o�͂��܂茸���Ă��Ȃ��B����܂ł̐錾�ƈ���āA�錾��Ɋ����҂��}�����Ă���̂�����̑傫�ȓ������B�_�ސ�A��t�A��ʂł���C�Ɋ����҂������Ă����B�����͂̋����f���^����75�����߂�悤�ɂȂ��Ă���Ƃ����B�S���̊����҂̑����͎Ⴂ����Ɉڂ��Ă���B�������A64�Έȉ��̃��N�`��2��ڎ헦��26�����݁A�܂�2����B�����̍������A���h���̂܂ܖ҈Ђ�U�邤�f���^���ɂ��炳��Ă���B���ʁA�S���̊����Ґ��͋}�����Ă������Ƃ��m���ȏ���B�����ʐM�ɂ��ƁA���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��28���A�u��Â̕N�������ɋN���n�߂Ă���Ƃ����̂������̔F�����v�ƌ��A���{�ɋ��߂���Ή��ɂ��āA�u�l�X�ɂ�������Ɗ�@�������L���Ă��炦�郁�b�Z�[�W�̏o�����ƁA�����ɂӂ��킵�����ʓI�ȑ��łƂ������Ƃ��v�ƌ�����Ƃ����B�u���ʓI�ȑ�v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��z�肳���̂��B����܂ł��������͂��������̂ɂȂ�̂��B�e����news��28���A�����s�̏��r�S���q�m���͌J��Ԃ��X�e�[�z�[�����Ăъ|���Ă��邪�A��l�܂芴�͔ۂ߂Ȃ��Ƃ��A�u���J�[�h�́A�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���v�Ƃ������{�����̐���`���Ă���B
���@�����Ȃ��Ă��ł���
�����ǐ���̒��ɂ́A�@���͂Ȃ��Ă������I�ȃ��b�N�_�E���͂ł���Ǝ咣����l������B�_�ˑ�w�a�@�����Ǔ��Ȃ̊�c�����Y������28���A���~�ɃI�����C���ŁA�����w�l���uPCR�v������`�ɔ����闝�R�x(�W�p�ЃC���^�[�i�V���i���A2020�N12����)�̈ꕔ���E�ĕҏW���A�T�ˈȉ��̂悤�ɐ������Ă���B�u���{�ɂ͊O�o���K������@�����Ȃ��B�����烍�b�N�_�E���͂ł��Ȃ��v�B����Ȃ��Ƃ������l�����܂��B����������͊ԈႢ�ł��B�@����A�u�O�o������ȁv�Ƃ��u�X�͕߂�v�Ƃ��������Ƃ������ł��Ȃ��͎̂����ł����A����͏d���̋������c�_�ŁA�{���I�Ȗ��ł͂���܂���B���{�ł����b�N�_�E���͂ł��܂��B�u���̒n��ɓ���Ȃ��ł��������v�u���̒n�悩��o�Ȃ��ł��������v�u���̒n��ɏZ��ł���l�͊O�o���Ȃ��ł��������v�u�����͂Ȃ�����ǁA���͂��Ă��������v�B������������������̂����b�N�_�E���ł��B�������I��������Ƃ����ړI�ɂ����āA���b�N�_�E���͍ł��p���t���ȑ�ł��B���̌��ʂɂ͐��Ȃ��̂�����܂��B�Z���Ԃ̂����Ɋ�����}�����ނ��߂ɂ́A�ł��邩���芮�S�ɋ߂��`�Ől�̓������~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u���������Z���v�����b�N�_�E���𐬌�������v���ł��B
��c����̎咣�ƁA���g��̔����͂Ȃ�ƂȂ��d�Ȃ�Ƃ��낪����B�܂��u�ł�͂���v�Ƃ������̂��B����𐭕{�ɋ��߂Ă���B�������A�����ł͌ܗւ��J�Ò��B���̂��Ƃ����ԂG�ɂ��A��苭���R���i���ł��o���Â炭���Ă���B
���t�[�u�݂�Ȃ̈ӌ��v�́A�u�ܗ֊��Ԓ��Ɋ������g��A���{�̑�Ɍ��ʂ͂���Ǝv���H�v�Ƃ����A���P�[�g�����{�������A28�����݁A96���̐l���u���ʂ͂Ȃ��v�Ɠ����Ă���B
���S���ő�9500�l���c�u�d�ǂ͕m���ł��v��Ì���ƈ�ʂ̃M���b�v�@7/29
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂����߂�3000�l����ȂǁA1�s3���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B����3���ɂ��ً}���Ԑ錾���g�傳�������ɁB����A����̈�t�́A��Ì���ƈ�ʂ̐l�����Ƃ̔F���Ɂu�M���b�v�v������Ǝw�E���܂��B
�������ŏ��̊�����3000�l�����u�s���Ɨ��Ȃ��c�v
���߂�3000�l���������̊����ҁB
�z�e����(20��)�u���܂����������傫�����ăs���Ɨ��Ȃ����Ă̂͊����Ă܂��v
��Ј�(20��)�u����w3���x���Ă������t������ɂȂ��Ă�Ȃ����Ȃ��炢�v
��Ј�(20��)�u�����g�A�x�݂̓T�E�i�s���̂ŁA�S�̓I�Ɉӎ��́A�ŏ��ɋً}���Ԑ錾�o���ꂽ�Ƃ���舳�|�I��(�ӎ���)�Ⴂ�v
����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�1954�D7�l�ŁA�O�̏T��153���ɁB�V���ɁA50�ォ��90��܂�6�l�̎��S���m�F����܂����B
28���A�S����9500�l�ȏ�̊����҂��m�F����܂����B�����̋}�g�傪�~�܂�Ȃ��ɁA���̓��̖�A���J�ȃA�h�o�C�U���[�{�[�h�̘e�c�����̈́���
�e�c�����u(�S���I��)����܂łɌo���������Ƃ��Ȃ������g��Ƃ����]���B�A�x�ɂ��e��������܂��̂ŁA���コ��ɕҐ�����ς݂����\��������v
�����錾�̌��ʂɂ���
�e�c�����u�錾���o���Ă���2�T�Ԍo�߂��Ă��邪�A���̌��ʂ��o�Ă���Ƃ͌����������B�l���������Ă���̂͊m���ɂ��邪�A�O��ً̋}���Ԑ錾�̌����Ɣ�ׂ�ƁA�܂����ꂻ���ɂ͋y�Ȃ��v
�l�o�̌����X�s�[�h���x�����߁A����������Ґ����Ȃ��Ȃ�����Ȃ���@�I�ȏɂ���Ǝw�E�B�܂���c�ł́A�����������܂̃y�[�X�Ŋ����Ґ��̑����������ƁA���悻1������ɂ͓s���̈���̐V�K�����Ґ���1���l����Ƃ̐V���ȃV�~�����[�V������������܂����B
�L�ҁu�����A�����s��3000�l�A�S����8000�l���銴���҂��m�F����܂����B�ǂ��Ή����܂����H�v
�L�ҁu�����Ƀ��b�Z�[�W���o���K�v�͂������ɂȂ�܂��H�v
�������͖����̂܂܊��@����ɂ��܂����B����A�����̏��r�m���́B
���������Ґ�3000�l�Ƃ���������܂����H
���r�m���u�F�l���ɂ͂��Еs�v�s�}�̊O�o���T���Ă��������B(�������H��c����)�e�����[�N�̓O������肢���܂����B���̂悤�ɊF����̂��͂ė}������ł��������Ǝv���܂��v
����Ȃ�₢�����ɂ͓����܂���ł����B
�u��5�g�v�͓����̎��ӂł��B�_�ސ쌧�ł�1051�l�Ə��߂�4���ƂȂ����ق��A��ʌ��ł�870�l�A��t���ł�577�l�Ƃ�������ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
���g����������ԁh3�����ً}���Ԑ錾��v����
�_�ސ�E����m���u���̂�700�l���Ă����ł���������ł����A��C��1000�l(���)�B����������Ԃɓ����Ă��邱�Ƃ����߂Ċm�F�ł��Ă��܂����킯�ł��āA��ϑ傫�ȏՌ����Ă���܂��v
��t�E�F�J�m���u��t���̊����͔��ɋ}���ȑ����X���������Ă���܂��B�����₻�̎��ӂ̒n������Ă��A���悢���@�I�����ɒB������ƍl���Ă���܂��̂Łv
29���A�_�ސ�E��t�E��ʂ�3���ł�����č��ɑ��ċً}���Ԑ錾��v��������j�ɁB���{�́A30���ɂ��錾�̔��o�����肷������Ō������Ă��܂��B
�܂��A���킹�đ��ɋً}���Ԑ錾�o���邱�Ƃ�A�k�C���ɂ܂h�~���d�_�[�u��K�p���邱�Ƃ��������Ă��āA�����Ȃǂ����Ȃ���T�d�ɔ��f������j�ł��B
����Ì���ƈ�ʂ̐l�����̔F���Ɂu�M���b�v�v
28���ߌ�A���{���ȉ�̔��g�Ή���i�����̂́A��Ñ̐��ɑ�����Ƃ̊�@���ł��B
���g��u���͈�Â̂Ђ����Ƃ������̂����łɋN����n�߂Ă���Ƃ����̂���X�̔F���ł���܂��v
���@���҂�d�ǎ҂̐��������Ă��邱�ƈȊO�ɂ�����
���g��u���@����������l�������Ă���B�h���×{�����Ă���l�������Ă���B����ŗ×{���Ă���l���}�����Ă����ł��ˁB��ʂ̐l�X�ɂ܂��\���ɂ��̊�@�����`����ĂȂ��v
��ʌ����́w��ʈ�ȑ�w������ÃZ���^�[�x�ł́A28���A�W�����Î��Ől�H�ċz����������҂̎��Â��s���Ă��܂����B
�u�����炪�����@���Ă��銳�҂���ŁA42�A56�A46�A�قƂ�ǂ�40�`60��̊��҂���ł��v
���Âɂ������t�̉��G�������̈́���
���G�������u�ꕔ�y�Ϙ_�Ƃ��ẮA�d�ǎ҂����Ȃ��A����҂����N�`���ڎ���I���Ă��邩����v�Ƃ����ӌ�������܂����A����̊��o�͂����ł͂���܂���v
��Ì���ƈ�ʂ̐l�����Ƃ̔F���Ɂu�M���b�v�v������Ǝw�E���܂��B
���G�������u�d�ǂ͕m��(�Ђ�)�A�C�O�ł����ƃN���e�B�J���B��ʂ̕��͏d���x��������̂��d�ǂ��Ǝv���Ă���B�������i�K����i�K����Ă���v
�������ɂ��ƁA�u�d���x���v�Ǝv��ꂪ���ȏd�ǂƂ́A���ۂɂ́A���͂ł̌ċz���ł����l�H�ċz�킪�K�v�ȏ�ԂŁA���̎�O�́u�����ǁv�ɂ��Ă��A���M��ċz�s�S�Ȃǂ̏d���Ǐ���A����ł͑傫�ȕ��S�ɁB���̂��߁A�d�ǎ҂̐����������Ĕ��f���邱�Ƃ́A��Ì���̂Ђ����������\��������Ƃ����܂��B
���G�������u�����NJ����Ă�����ȂŎg���钆���ǁE�d�ǂ̕a������23�ł��B���̕a�����{���̒i�K��20���A���܂��Ă��܂��B��3�g�̂Ƃ���(�ً}����)�錾�������Ă��Ċ��҂������Ă������B���ꂩ�瑝���Ă����ł���ˁA�����ɐ����A��]��������v
�����̃s�[�N�������Ȃ�����ɁA���{���ȉ�̃����o�[�̈́���
���{���ȉ�E�ړc�ꔎ�����u���H�₨����}���邱�ƂɏW�����Ă��邪�A��������L���͈͂ŁA���Ǝ{�݂��܂߂ĉc�Ƃ̎��l���X���l���Ă����Ȃ�A��苭�����b�Z�[�W���Ă����K�v���l���Ă����Ȃ�������Ȃ��v
�����[�����A�R���i�����g��u��Ñ̐����m�ہv�@7/29
�������M���[������29���̋L�҉�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̑S���I�Ȋ����g��Ɋւ��u��Ñ̐����m�ۂ��A�ی����̋@�\�̊g�[��}���Ă����B�����I�ȑΉ����K�v���v�Ƃ̔F�����������B
�����Ɂu�����h�~���O�ꂵ�A���N�`���ڎ�ɑS�͂Ŏ��g�ށv�Ƌ����B���N�`���ڎ�̐i�W�ɔ����A�����ɖ��炩�ȕω���������Ƃ��āu�ڎ킪�\���ɐi��̓K�Ȋ����h�~��݂̍���ɂ��Ă��������Ă����v�ƌ�����B
��120�l�R���i�����A�g��~�܂炸�@28���̐É������@�����Ŕ����@7/29
�É�������28���A�V����120�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����҂��m�F���ꂽ�B�ߋ�3�Ԗڂ̑����ŁA120�l�̊����m�F��5��15���ȗ��B�����n�悪�قڔ�����58�l���߁A���ɏ��Îs��O���s�Ȃǂ̏x���c���n��A���c�s�Ȃǂ̉�Βn��Ŋ����g�傪�~�܂�Ȃ��B���͗��n��̏Z���Ɂu����̎d���┃�����ȊO�ł͊O�o���T���Ăق����v�ƌĂъ|�����B
���ɂ��ƁA���S�̂̒���1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���14�E8�l�B7�����{�ȍ~�A�E���オ��ŁA�������������̃X�e�[�W3(�����}��)�̊(15�l�ȏ�)�ɔ���B
�����28�����_�̏d�ǎ҂�2�l�ŁA�O��120�l����������7�l�ɔ���Ȃ��B���́u�d�lj����₷������҂̊ԂŃ��N�`���ڎ킪�i���ʁv�Ƃ݂Ă���B����҂̊���������5�����{��10���䒆�Ղ���1���܂Ō��������B�Ⴂ����̊����}�����ǂ��}�邩������̌��ƂȂ�B
����85�l�̐V�K�����҂\�����B���ɃN���X�^�[(�����ҏW�c)�ɔF�肳�ꂽ�֓c�s�̊w�Z��3�l�A���c�s�̃o�[�uCOCO�@�������v�Ɛڑ҂����H�X�u�i�C�g�p�u�EONE�ETWO�ETHREE�v�Ŋe1�l�B���s�̊g�匟���ł�25�A26����651���̂��̎悵�A11���̗z�����m�F�����B
�l���s��16�l�̊����\�����B�����s���̊w�Z�̕������֘A�N���X�^�[��2�l�A�֓c�s�̊w�Z�N���X�^�[�̊W�҂�1�l�B�É��s��19�l�̐V�K�����\�B������̐����Ƃ̎��Ə��֘A�N���X�^�[�́A�s�O�̏]�ƈ�5�l�̗z�����������A�v13�l�ɂȂ����B
�����̗v�����Ґ���1��488�l(�ėz���҂��܂�1��489�l)�ƂȂ����B
�����g��u������v�f���܂�Ȃ��v�c�@��s���̊����}�g�� �@7/29
29���ɊJ���ꂽ�Q�@���t�ψ���̕�R���ŁA���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή�́A��s���Ȃǂł̐V���ȐV�^�R���i�����҂̋}���ɑ��u��ςȊ�@���������Ă��܂��B���̊�����������v�f�����܂肠��܂���v�Ƌ��������B
�����g���i�߂�v���Ƃ��āA�u�R���i���v�⊴���͂̋����ψي��u�f���^���v�ւ̒u�������ƂƂ��Ɂu�ċx�݁A���~�A����ɃI�����s�b�N�v�Ɨ��A�����ܗւ̊J�Â��l�o�̑����ɉe�����Ă��錜�O���w�E�B�u�ő�̊�@�́A�Љ��ʂ̒��Ŋ�@�������L����Ă��Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��v�Ƃ��q�ׂ��B�i�܂Ȃ��ꍇ�A�u���ӁA��ÕN��������������ɐ[���ɂȂ�v�Ƒi���A����×{���ɏd�lj����銳�҂��o�Ă��鋰���z�肵�đ�K�v���ɂ����y�����B
�ܗ֒��~��p�������s�b�N�̗L�ϋq�J�Â̐���ɂ��Ė����ƁA����̔��f�̕\���͔����A�u(�����̐V�K�����Ґ���3000�l����)���̎������Ȃ��ŁA���m�ȋ������b�Z�[�W���o���Ă���������Ǝv���܂��v�Ɛ��{�ɒ��������B
���������������}�̐����G�Ǝ��̎���ɓ������B
���{����̃��b�Z�[�W�������ẮA���`�̎�28���A�����̋}�g�������ޑΉ������ۂ����B���@���́u�{���͂�����������e���Ȃ��v(�鏑��)�Ɛ��������B
���V�^�R���i�@���ł������}�g��@�e�{�����x�����߂�@7/29
����2�{4���ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�Ă��܂��B���{�̋g���m���́A���̕��j�𒍎����A�{�Ƃ��āA�y�ǁE�����ǂ̕a�����A�d�Ǖa���̂����ꂩ�̎g�p����50���ɏ�������_�ŁA�ً}���Ԑ錾�̔��o��v������l���̂ق��A���Ɍ��́A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�����߂�ȂǁA�e�{���ł͌x�������߂Ă��܂��B
����2�{4����28���ɔ��\���ꂽ�V�^�R���i�̐V���Ȋ����҂́A���킹��1354�l�ŁA���̂����A���̊����҂�798�l�ƁA2���A����700�l�����ق����s��175�l�ƁA����܂łōł������Ȃ�܂����B
���������ɂ��āA���{�̋g���m���́u�����̑��x�͎�s���Ƃقړ����ŁA�����ŋN���Ă��邱�Ƃ́A���ł����Ԃ������ċN���Ă���v�Ƌ�����@���������܂����B
�����āA���̕��j�𒍎����A�{�Ƃ��āA�y�ǁE�����ǂ̕a�����A�d�Ǖa���̂����ꂩ�̎g�p����50���ɏ�������_�ŁA�ً}���Ԑ錾�̔��o��v������l���������܂����B
�܂��A���Ɍ��́A�W���I�ȑ���u����K�v������Ƃ��āA28���A���ɑ��A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��Ɏw�肷��悤�v�����܂����B
����ɁA�����̎����̂ł���u���L��A���v��29���ɐV�^�R���i�̑��{����c���J���đΉ������c����ȂǁA�e�{���ł́A����Ȃ銴���g��ւ̌x�������߂Ă��āA�{�����ɏd�˂đ�̓O��������Ăт����Ă��܂��B
���V�^�R���i�@������80�l�A�����g��@7/29
��������28���A10�Ζ����`80��̒j��80�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�����҂̓���͕����A�S�R�A���킫��3�s���e23�l�ŁA�N���X�^�[(�����ҏW�c)�𒆐S�ɋ}�g�債�Ă���B�����̊����҂͌v5499�l�B
������1��������̌��\���Ƃ��Ă�5��12����95�l�Ɏ����ʼnߋ�2�Ԗڂɑ����B�m�ەa���̎g�p����48�E6���ŁA�X�e�[�W4(�����I�����g��)�̖ڈ���50���ɔ���B
�����s���̋�������25�`27���ɗ��p�q�Ə]�ƈ��v8�l�A���킫�s�̎����{�݂�25�`27���ɗ��p�҂ƐE���v7�l�̗z�����m�F����A���͂��ꂼ��N���X�^�[�ƔF��B���ʂ̃N���X�^�[������19���ŁA4���ƕ���ōő��ƂȂ����B�������H�X�W��15�����߂�B
����28���A�����A���킫���s�̎�ނ������H�X�Ȃǂ�31������8��22���܂ŁA�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k��v������ƌ��߂��B�ߌ�8���`�ߑO5���̉c�Ǝ��l�����߁A��ޒ͌ߑO11���`�ߌ�7���Ɍ���B�Ώۂ͌v��2800�X�܂ŁA���㍂�ɉ������͋����x������B
���Ɏ��Z�c�Ƃ�v�����Ă���쑊�n�A�S�R���s�̂����A�쑊�n�͊����҂������������Ƃ���\��ʂ荡��31���ŏI������B
���ܗ։��̎����̊W�҂�@�����g��Ɋ�@���u�L�ϋq���e���v�@�É� �@7/29
�����ܗւ����{�l�I��̃��_���l���Ő���オ�����ŁA�S���̐V�^�R���i�E�C���X�����҂��A����Ƃ��ĉߋ��ő����X�V�����B���]�ԋ��Z���L�ϋq�ōs���Ă���É��������ł���\�����A�V���Ȋ����m�F���������A�����̊W�҂�͊�@�������߂Ă���B�@(�˒C���A�n�ӗz���Y)
�u�L�ϋq�ɓ��ݐ����e���͓��R����v�B���[�h���[�X�̃R�[�X�̌�a��s�Ńr�W�l�X�z�e�����o�c����j���͘b���B�J�Ó��̍�����\�l�A��\�ܓ��͉����ɑ����̊ϋq���W�܂�A�z�e���ɂ���s���̋q�����������Ƃ����B�u�R���i�ЂŌ}����|���͂��������A�o�c�͋ꂵ��������f�������v
�}�E���e���o�C�N�ƃg���b�N�̊J�Òn�A�ɓ��s�B�s�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���i�ۂ̐X���N�j�ے��́u����Ɋ����g�傷��Ζ��ϋq�ɂȂ鋰�ꂪ����B���ꂾ���͔��������v�Ƙb���B
���Z�J�Ó��A�s�͉��ւ̃V���g���o�X����������ɓ������S���C�P���w�Ɂu�����ĂȂ��G���A�v��݉c���ϋq�ɋL�O�i�₤�����n���Ă���B���ɏI�������}�E���e���o�C�N�ł͑����̋q�����Ŏ��A�n��̂o�q�Ɏ艞���������Ă����Ƃ��낾�����B
�X���ے��́u���{�l�̃��_�������҂���闈�����{�̃g���b�N��s���̎����E���k���ϐ�\��̃p���ւ̉e�����S�z�v�Ƙb�����B
���Îs�͍����A���ɕ����̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�������A����̊����҂��o������p�ɂɂ���B�i�q���Éw�O�ł̓{�����e�B�A���ܗւ̊ϋq���ē����Ă���A���d�G��s���͉�Łu����鑤�͊����h�~�̃K�C�h���C�������炷��B������������Z�����̂̏o���Ă���K�C�h���C�������炵�Ăق����v�Ƒi�����B
��������\�u���̈����v�@��s���̃R���i�����g��@7/29
�����}�̎R���ߒÒj��\��29���̓}��ŁA��ʁA��t�A�_�ސ�̎�s��3�����V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾�̔��ߗv���Ɍ�����������i�߂Ă��邱�Ƃ��߂���A���{�ɑ��}�ȑΉ������߂��B�u�����̂���v��������A���Ƃ̈ӌ��܂��A���₩�Ɏ��̈��A�������̂�����𐭕{�Ƃ��Č��߂Ăق����v�Əq�ׂ��B
�����g�傪�������{�̌���ɂ��G��u��オ�ǂ��Ȃ邩���C�ɂȂ�Ƃ��낾�v�Ǝw�E�B���N�`���ڎ�ɂ��Ắu�����̌��ʂ��������Ă����B����Ɛ��{�A�s���{�������ɘA�g���A�����ɐi��ł����悤�Ɍ㉟���������v�ƌ�����B
�k����Y����������͋L�҉�ŁA��s��3���ւً̋}���Ԑ錾�Ɋւ��u���o�͂�ނȂ��̂ł͂Ȃ����v�Ƙb�����B
������ �����ւ̃��b�Z�[�W �u���傤�m�F���Đ����v�����g��� �@7/29
�V�^�R���i�E�C���X�Ή��ŁA��������b�́A29�����A������b���@�ɓ���ہA�L�Ғc����A�����g�傪�������A�����ւ̃��b�Z�[�W�͂Ȃ����Ɩ���u���傤�m�F���Ă����������v�Əq�ׂ܂����B
�ً}���Ԑ錾���o����Ă��铌���s�ł́A28���A2���A���ʼnߋ��ő��̐V�K�����҂��m�F����A�܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă���A��ʁA��t�A�_�ސ��3���ł��V�K�����҂�����܂łōł������Ȃ�܂����B
��������b�́A29�����A������b���@�ɓ���ہA�L�Ғc����u�S���Ŋ����g�傪�����Ă��邪�A�����Ƀ��b�Z�[�W�͂Ȃ����v�Ɛ����������u���傤�m�F���Ă����������v�Əq�ׂ܂����B
���{�́A��ʁA��t�A�_�ސ��3���ł͊������}�g�債�Ă���Ƃ��āA���߂̊����Ȃǂ����ɂ߁A�ً}���Ԑ錾���o�����Ƃ��������Ă��āA���j���ł܂�A30���ɂ��A�����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�������Ƃ̉������l���@�R���i�����g�哥�܂����v���@7/29
���ꌧ��28���A10�Ζ����`90�Έȏ�̒j��19�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B
�����҂̑����X����A���̊����o�H�̕��͂܂��Č��́A�������ւ̕s�v�s�}�̉����Ɖ�H�����l����悤�����ɋ��߂��B�����ł̍s�����Ȃǂ�����l���A��������P�[�X�������Ă��邽�߂��Ƃ����B����܂Ŏ����Ă�����s����1�s3���ւ̉����Ɖ�H�̎��l�������������߂�B
�b�㒼���E�����N����������ɂ��ƁA����1�`27���̊����Ҍv100�l�̂����A����܂ł̊����҂ƊW���Ȃ��l��36�l�B���̂������ǑO�ɕ������ł̍s����������l��A�s����������l�Ƃ̐ڐG������P�[�X���v24�l�ɂ̂ڂ����Ƃ����B���������\�̊����Ґ��͋}�����Ă���28����405�l�ƂȂ��Ă���B
�b�㕔���́u(�������ɊW����)�����������������N�_�ɂ��ĉƒ����E��ł̊����ɂȂ����Ă��������v�Ǝw�E�����B
����܂ł͕������Ƃ̉������H�ɂ��Ắu���Ɍx������v�悤���߂Ă��Ă���A���l�܂ł͓��ݍ���ł��Ȃ������B
���u��5�g�v�����g��@�V�^�R���i�E�C���X�@�D�y�s150�l�䌩���݁@7/29
�W�҂ɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�E�C���X��29���̊����m�F�́A�D�y�s��150�l��ƂȂ錩���݂ł��邱�Ƃ��킩��܂����B�����ő����X�V���錩�ʂ��Łu��5�g�v�̊����g�傪�����Ă��܂��B
�������A�ܗ��4532�l�̋���u�o���̂Ȃ������I�Ȋ����Ɍ������Ă���v�@7/29
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̃��j�^�����O��c��29������A����̃y�[�X�Ŋ����g�傪�������ꍇ�A����1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ��́A�����ܗ֏I�����8��11���ɂ�1���������4532�l�ɒB����Ƃ̎��Z�����ꂽ�B�s���̊����҂�2���A���ōő����X�V���A3000�l���˔j���Ă��邪�A����Ɉ������錜�O������B��ȋM�v�E���ۊ����ǃZ���^�[���́A�u����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������I�Ȋ����g��Ɍ������Ă���B���݂̐V�K�z���҂̑����䂪�p�����邱�Ƃ͑��}�ɉ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi�����B
�ɂ��ƁA�V�K�����Ґ�(1�T�ԓ�����)��7��20�����_�̖�1170�l����A28�����_�ł͖�1936�l�Ƒ啝�ɑ����B���̂܂܂̑����䂪�p������ƁA1�T�Ԍ�̌ܗ֏I�Ղ�8��4���ɂ�1��������2962�l�Ɓu�ʏ�̈�Â��܂߂���Ñ̐����Ђ���������3�g�̃s�[�N����傫������v�Ƃ��A8��11���ɂ͓�4532�l�ƂȂ�u��Ò̐�����@�ɕm����̂ő��}�ɉ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƒi�����B
�����s��t��̒������F����́A�����_�̓s���̈�Ò̐��ɂ��āA��1�J���O������@���Ґ����{���������ƂɐG��u�N���͎n�܂��Ă��܂��B�^���������ƌ����Ă������悤�ȏv�ƕ����B�ܗ֊J��O���22�`24����4�A�x�Ɋւ��ẮA�u���ɘA�x���̓��@�����͋ɂ߂Č������A�����ȍ~�̒����ɌJ��z���A����ҋ@��]�V�Ȃ�����鎖�Ⴊ���������܂����v�ƌ��y�B���@����������͘A�x��������Ă���A���コ��ɓ�q���邱�Ƃ��\�z�����Ƃ����B
PCR�����Ȃǂ̗z������16�D9���ŁA1�T�ԑO��10�D2������啝�ɏ㏸�B�������́A�������Ă��炸�A�s�����c���ł��Ă��Ȃ������҂������Ă��鋰����w�E���u���M�₹���A����A���ӊ��Ȃǂ̏Ǐ���ꍇ�́A���������ɓd�b���k����ȂǁA������PCR��������K�v������v�Ƃ����B �@
�����H�X��41���������I�����s�b�N�J�ÂɁu�^���v���A�����g��ɕs�����@7/29
�������T�v
�����ΏہF���H�X(���H�X�o�c�ҁE�^�c��)
���F495��
�������ԁF2021/6/29�`6/30
�������@�F�C���^�[�l�b�g����
���҂ɂ���
�{�����ɂ����͂����������҂̂���70.7����1�X�܂݂̂��^�c���Ă���܂��B�܂��A�҂̂��������ɂ�����H�X�̊�����54.3��(��s���̈��H�X�̊�����72.4��)�ƂȂ��Ă���A���������w�i�����ʂɉe�����Ă���Ɛ�������܂��B
���������ʂɂ���
88.9���̈��H�X�����͋����u�\���ς݁v���A4�����ȍ~�����܂��ł��Ȃ��X�܂�����
�V�^�R���i�E�C���X�̐��E�I�ȗ��s�����܂�Ȃ����A7��23����蓌���I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���J�Â���Ă܂��B�������A�J�Òn�ƂȂ铌���ł͈���̐V�K�����Ґ���1,000�l����ȂǁA7�����݂��[���Ȋ����g�傪�����Ă���ł��B����́A���������ٗ�̏��ŊJ�Â���邱�Ƃւ̗l�X�Ȉӌ��⌜�O�ɂ��Ē������邽�߁A�A���P�[�g�����{�������܂����B�Ȃ��A�{�A���P�[�g�̎��{��(6/29�`6/30)�́A�����s�A���{�A�k�C���A���m���A���s�{�A���Ɍ��A��������7�s���{���ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă������Ԃł���A�����t���Ŏ�ޒ̒�~����������Ă��܂����B�܂������A�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���ɂ�����ϋq�̓����Ɋւ��Ă͖���ł���A����(7�����{)�̏Ƃ͈قȂ邱�Ƃ����l�����������B
�ŏ��ɁA2021/5�̌o�c�ɂ��āA�R���i�ɂ��e������O��2019�N�����Ɣ�r���Ă�������Ƃ���A�u2019�N5�����70���ȏ㌸�����v�Ƃ̉��ł������A37.8���B�����ŁA�u50��������(10.5��)�v�A�u60��������(10.3��)�v�Ƒ����܂����B���̌��ʂ���A���H�X��58.6�����u2019�N�������50���ȏ㌸�����v�Ɖ������Ƃ��킩��܂��B
4���̔���ɂ��ē��l�̒������s�����ۂ́A�u2019�N�������50���ȏ㌸�����v�Ƃ̉�52.1�����������Ƃ���A���H�X�ւ̒��������Z�c�Ƃ��ޒ̒�~�v���Ȃǂ��A�[���Ȕ���̒���������炵�Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
���ɁA����܂ʼnc�Ǝ��ԒZ�k�v���ɔ��������g��h�~���͋��̐\�����������Ƃ����邩�����Ă݂�ƁA9���߂����u�\���������Ƃ�����(88.9��)�v�Ɖ��܂����B
����Ɂu�\���������Ƃ�����v�Ɖ����l�ɑ��A�����_�ł̋��͋��̎x���ɂ��Đq�˂��Ƃ���A�S���̍ő��́u2021�N3���܂ł̗v�����ԕ����U�荞�܂�Ă���v�ŁA36.8���B�����́A�u4���܂ł̗v�����ԕ�(33.2��)�v�A�u2���܂ł̗v�����ԕ�(12.3��)�v�ƂȂ�܂����B
����A�s���{���ʂɌ���ƁA��ʌ��ł́u5���܂ł̗v�����ԕ�(38.1��)�v�Ƃ̉��ł������A�x���X�s�[�h�̑������\��錋�ʂɁB�����̂̑����͗v�����ԏI�����炨�悻1�����ȏォ�����Đ\����t���J�n����P�[�X���������A��ʌ��ł͏�ɗv�����ԏI���̗��������t���X�^�[�g���Ă���A���������v���ȑΉ�������t���Ă�����̂Ƃ݂��܂��B
�����������A�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���J�Â���邱�Ƃɂ��āA�ǂ������Ă��邩�q�˂��Ƃ���A�u���~����ׂ��v�Ƃ̉�29.3���ƍő��ɁB�������A�����u�^��(22.8��)�v�A�u���ϋq�ł̊J�ÂȂ�^��(18.4��)�v�����킹��ƁA41.2���͊T�ˎ^���̈ӎv�������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�{�A���P�[�g���{���_�ɂ����āA�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���ɂ�����ϋq�̓����Ɋւ��Ă͖���ł���
�܂��A�J�Ê��Ԓ��̉c�ƈӌ����ŕ������Ƃ���A�ł����������̂́u�ʏ�ʂ�c�Ƃ���(77.4��)�v�Ƃ̉B�����Łu����I�Ɏ��Z�c�Ƃ��s��(13.7��)�v�A�u�e�C�N�A�E�g�̔��A�f���o���[���������ĉc�Ƃ���(7.1��)�v�Ƒ����܂����B�܂��A�ʏ�ʂ�c�Ƃ���Ƃ��Ȃ�����A�u�A���R�[���͎̒��l����v�Ƃ̉�����A�e�X�܂ŗl�X�ȉc�Ƃ̃X�^�C������������Ă����l�q�������Ă��܂��B�{�A���P�[�g���{���7��12������A�ꕔ�n��ɋً}���Ԑ錾�����߂���܂���(8��22���܂�)�B����ɂ��7�����{���݂́A�e�n�̈��H�X�Ɏ�ޒ̒�~�Ȃǂ��v������Ă��܂�
�����āA�{�A���P�[�g�ɋ��͂����������Җ{�l�ɁA�V�^�R���i�E�C���X��1��ڂ̃��N�`����ڎ킵���������ƁA�u�܂��ڎ킵�Ă��Ȃ����A����ڎ킷��ӌ�(61��)�v�Ƃ̉��ł��������錋�ʂɁB�����́A�u�ڎ킷�邩������(16.4��)�v�A�u�ڎ킷��ӌ��͂Ȃ�(13.5��)�v�ƂȂ�A���N�`���̐ڎ�Ɉ��̌��O������Ă���l�����Ȃ��炸���邱�Ƃ������ƂȂ�܂����B
���ɁA�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̊J�Âɂ�����A�X�܂̉c�Ƃ��s�������ōł����O�����̂͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��q�˂��Ƃ���A�����̍Ċg��ɂ��l�X�ȉe����s�������鐺�𒆐S�ɁA�ȉ��̂悤�ȉ����܂����B
������
�@�@�@���l�������A�����ґ����ɂ��ً}���Ԑ錾�̍Ĕ��߂ƁA��ނ̒�~�v��
�E�����g�傷��Ǝv����̂ŁA�ً}���Ԑ錾���܂����߂���邾�낤�B�܂������̒��o���Ȃ��Ȃ�̂ł�(�_�ސ쌧�^�������E�_�C�j���O�o�[�^1�X��)
�E�����̈����ɂ��A�ً}���Ԑ錾�̍Ĕ��߁B�Ƃɂ����A�A���R�[���̔���~�����͊��ق��Ă�����������(�����s�^�t�����X�����^2�X��)
���{�A���P�[�g���{���7��12������A�ꕔ�n��ɋً}���Ԑ錾�����߂���܂���(8��22���܂�)�B����ɂ��7�����{���݁A�e�n�̈��H�X�Ɏ�ޒ̒�~�Ȃǂ��v������Ă��܂�
�@�@�@���q���������邱�Ƃɂ�锄��̌���
�E�����g��ɂ��ċً}���Ԑ錾��A�܂h�~�̎��Z�c�Ɨv���Œʏ�c�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�A���㌸�������O�����(��ʌ��^�t�����X�����^1�X��)
�ETV�ϐ�ɂ��ݑ�Ԃ̑����Ŏ��v���������A���オ�ቺ���邱��(�_�ސ쌧�^�a�H�^3�`5�X��)
�@�@�@���ߓx�����Ȃ��q�������邱��
�E�P�Ɏ�����Ő��������đ������������̐l�X���X�Ɉ��āA���[�������œ��X���Ă��邩������Ȃ��Ƃ������O(�����s�^�������E�_�C�j���O�o�[�^1�X��)
�E���Ղ葛���ŁA�ςɂ͂��Ⴎ�l�����Ɋ������܂�Ȃ��悤�ɂ�����(�����s�^�J�t�F�^1�X��)
�@�@�@���O���l�q�̑����ɂ�鏔���
�E�C�O����̂��q�l���A�����h�~���[���𗝉��ł����Ɏ��Ȃ�����(�����s�^���^1�X��)
�E�C�O����̗��K�҂ɂ��V���ȕψي��̔���(��t���^�J�t�F�^1�X��)
�@�@�@�������I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ���
���~�܂��͉�������ׂ�
�E���H�X�ɂ͎��Z�c�Ƃ�A���R�[�������l����悤�ɗv�������̂ɁA�I���p���Ȃ�Έ��S���S�őI�葺��{�݂ɂ̓A���R�[��OK�Ȃǂ�������������ł��B�������I���p���͒��~�ɂ��ׂ�(��ʌ��^�t�����X�����^1�X��)
�����܂ł��Ă�闝�R�m�Ɏ����Ăق���
�E�J�Â���ɂ������Ĕ[���̂������R(�l���⍑���̓��퐶�����]���ɂ��Ăł��J�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R)��������Ăق���(�����s�^�J�t�F�^1�X��)
�����̈��S����ɍl���Ăق���
�E�����̌��N�ƃI�����s�b�N�J�Â̈Ӌ`���A����x��ÂɓV���ɂ����Ă�����������(�����s�^�������E�_�C�j���O�o�[�^1�X��)
�u�J�Î��͎̂d���Ȃ��v�Ƃ̌�������\�\
���S�̊����h�~����u���Ăق���
�E�I�����s�b�N�ŗ��������l�B����������u�����A�O�o�̋K����O�ꂵ�Ăق���(�_�ސ쌧�^�J�t�F�^1�X��)
�J�É��͖��ϋq�̏�Ԃɂ���ׂ�
�E�J�Â���̂ł���A���̏��炵�Ė��ϋq�ł��ׂ�(�����s�^�t�����X�����^1�X��)
(�{�A���P�[�g���{���_6/29�`6/30�ɂ����āA�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���ɂ�����ϋq�̓����Ɋւ��Ă͖���ł���)
����A�J�Âɂ������Ĉ��̗������������̂ق��A���߂̊�����������Ȃǂ������܂����B
�E�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�����܂������́A�܂����N������ȏɂȂ�Ƃ͎v���ĂȂ������Ǝv���܂��B���ł��鎖��S�����āA�����ɊJ�Â��Ē�������Ǝv���܂�(�_�ސ쌧�^���[�����^2�X��)
�E�����n���A���ʂ��n���B�����Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ��Ǝv���܂�(�����s�^�o�[�^1�X��)
�������s�ŐV����3865�l�̊����m�F �ߋ��ő� 2���A����3000�l���@7/29
�����s��29���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3865�l�m�F���ꂽ�B28����3177�l������A3���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
�������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ��3865�l�ŁA����7���Ԃ�1��������̕��ς�2224.1�l�ƁA�O�T(1373.4�l)�ɑ���161.9���ƂȂ����B�N��ʂŌ����20�オ�ł�����1417�l�A������30�オ782�l�ŁA�d�lj����X�N������65�Έȏ�̍���҂�105�l�������B
�d�ǂ̊��҂͑O������1�l������81�l�ƂȂ����B�܂��A3�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
�������s �V�^�R���i �V����3865�l�����m�F 3���A���ߋ��ő��X�V �@7/29
�����s�́A29���A�s���ʼnߋ��ő��ƂȂ�3865�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ�V���Ɋm�F�����Ɣ��\���܂����B�s���ł́A28���A�͂��߂�3000�l���A3177�l�̊������m�F����܂������A29���͂����688�l�����Ȃ�܂����B����ŁA3���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�܂��A29����3865�l�́A1�T�ԑO�̖ؗj���̔{�߂��ɑ����Ă��āA����܂łɂȂ��X�s�[�h�Ŋ������g�債�Ă��܂��B����A�s�̊�ŏW�v����29�����_�̏d�ǂ̊��҂�28�����1�l������81�l�ł����B
�������� ���̑S��1���l�� �g�o���Ȃ��}���Ȋ����g��h ���Ɓ@7/29
�����E3865�l�A�_�ސ�E1169�l�A����E392�l�B29�����V�^�R���i�E�C���X�̊����m�F�̔��\���ߋ��ő��ƂȂ����Ƃ��낪�������A�����҂͑S���ŏ��߂�1���l���܂����B�g����܂łɌo���̂Ȃ��}���Ȋ����g��ɂȂ��Ă���h���݂̊������������͂���钆�A���Ƃ́u��@���̋��L�v���w�E���Ă��܂��B
���S���̊������\ ����1���l��
�V�^�R���i�E�C���X�͊e�n�ł���܂łɂȂ��X�s�[�h�Ŋ������g�債�Ă��āA29���̔��\�͑S���ŏ��߂�1���l���܂����B����̊������\���ߋ��ő����X�V����̂�2���A���ł��B�܂��A�S����14�l�̎��S�����\���ꂽ�ق��A�d�ǎ҂�539�l��28������17�l�������Ă��܂��B
����s��. �����E�_�ސ�͂��傤���ő�
�����s�@/�@�ߋ��ő��ƂȂ�3865�l�̊����m�F�����\����A���߂�3000�l����28����肳���688�l�����܂����B�����3���A���ʼnߋ��ő����X�V��1�T�ԑO�̖ؗj���̔{�߂��ɑ����܂����B
�_�ސ쌧�@/�@1164�l�̊����m�F�����\����A����̊����Ґ���2���A����1000�l���ߋ��ő����X�V���܂����B
��ʌ��@/�@864�l�̊����m�F�����\����A2���A����800�l������܂ł�2�Ԗڂɑ����Ȃ�܂����B
��t���@/�@576�l�̊����m�F�����\����A�ߋ��ő�������28����577�l�Ƃقړ���������2���A����500�l���܂����B�܂��A1�T�ԑO�̖ؗj������233�l�����܂����B
����. ����5��11���ȗ���900�l��
���{�@/�@932�l�̊����m�F�����\����܂����B����̊����Ґ���900�l����̂�5��11���ȗ��ŁA��T�̖ؗj���̔{�ȏ�ɏ���Ă��܂��B
���Ɍ��@/�@280�l�̊����m�F�����\����܂����B
���s�{�@/�@164�l�̊����m�F�����\����܂����B
�����Ɓg��@�����L���h
�u����܂łɌo���̂Ȃ��}���Ȋ����g��ɂȂ��Ă���v28����̌����J���Ȃ̐��Ɖ�͌��݂̊����ɂ��Ă������͂��܂����B�����ċً}���Ԑ錾�Ȃǂɂ��l�o�̌���������I�ŁA�����͂������ψكE�C���X�u�f���^���v�ւ̒u���������i�݁A�����ł͂��łɈ�ʈ�Âւ̉e�����N���Ă���Ƃ��āu���̂܂܂̏������Βʏ�ł���Ώ����閽��������Ȃ��ɂȂ邱�Ƃ��������O�����v�Ɗ�@���������܂����B����Ɂu����������@�����s���Ǝs�������L�ł��Ă��Ȃ����Ƃ��ő�̉ۑ肾�v�Ǝw�E���܂����B
���e�c�����u��@�I�� �s���ɋ��L����Ă��Ȃ����Ƃ����v
�����J���Ȃ̐��Ɖ�̂��Ɖ�����e�c���������́u�����s�ً͋}���Ԑ錾���o����Ă���2�T�Ԍo�߂��Ă��邪�A���̌��ʂ��o�Ă���Ƃ͌�����B�l���͌������Ă��邪�O��̐錾���Ɣ�ׂ�Ɗɂ₩�Ō��������������A���傤�̉�ł͂��̂܂܂ł͂Ȃ��Ȃ������Ґ������炷�܂łɂ͎���Ȃ��̂ł͂Ƃ����c�_���������B���̏͒P���Ɋ����Ґ��������Ă��邾���ł͂Ȃ��A���łɈ�ʈ�Âւ̉e�����n�܂��Ă��Ċ�@�I�ȏ��Ƃ������Ƃ��\���Ɏs���ɋ��L����Ă��Ȃ����Ƃ�������̖�肾�B�s���ɋ��͂��Ă��炦��悤�ȃ��b�Z�[�W�M���邱�Ƃ��d�v���v�Ƙb���Ă��܂����B
�����g��u�ő�̊�@�͎Љ�Ŋ�@�������L����Ȃ����Ɓv
���{�̕��ȉ�̔��g��͎Q�c�@���t�ψ���ŁA����ł͊���������������v�f���قƂ�ǂȂ��Ƃ��āA�Љ�S�̂Ŋ�@�������L����Ȃ���Α��ӁA��Â̂Ђ������[���ɂȂ�Ƌ�����@���������܂����B���̒��Ŕ��g��͊����ɂ��āu���A���̊�����������v�f�����܂�Ȃ����グ��v�f�͂�������B��ʂ̎s�����w�R���i����x���Ă��邱�ƁA�f���^���̊����͂������Ȃ��Ă��邱�ƁA�ċx�݂₨�~�A����ɃI�����s�b�N���v�Ǝw�E���܂����B���̂����Łu�ő�̊�@�͎Љ�Ŋ�@�������L����ĂȂ����Ƃ��B���̂܂܋��L����Ȃ���A�����͂���Ɋg�債���ӁA��Â̂Ђ���������ɐ[���ɂȂ�v�Ƌ�����@���������܂����B�����āu����1�N���ōł��������ɂ���B�����̊����Ґ���3000�l�������̎������Ȃ��ŁA���܂ňȏ�ɋ������b�Z�[�W���o���Ăق����v�Ɛ��{�ɋ��߂܂����B
���g��@�����L�h ���{�ɋ��߂��邱�Ƃ́H
�u��@�������L����Ă��Ȃ��v�Ɛ��Ƃ��w�E���Ă��邱�Ƃɂ��Đ��{�ɂ͉������߂��邩�A�������E���w�L�҂̉���ł��B���g����w�E�����悤�Ɋ��������Ԃɋy�сA�������錾���ꂵ�Ă��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�ɉ؊X�ł̐l�o�����{�����҂���قnj����Ă��Ȃ����Ƃ͂��̕\��̈�ƌ����܂����A���鐭�{�W�҂��u�����A�����V��������u����͓̂���v�ƘR�炵�Ă��܂����B�����������ŁA�ً}���Ԑ錾�̌��ʂ������Ă������߂ɂ́A�������[����������̓O��Ȃǂɋ��͂��悤�Ǝv���郁�b�Z�[�W���o�����Ƃ��������܂���B����̐錾�͂���܂łƂ͉����ǂ��قȂ�̂��A�ǂ�ȑ���Ƃ��Ă�����܂łɉ���ڎw���̂��Ƃ��������Ƃ���薾�m�ɐ������邱�Ƃ����߂���Ǝv���܂��B
���g�錾�h ��� ��t �_�ސ� ����lj�
�����āA���{�́A�����s�Ɖ��ꌧ�ɏo����Ă���ً}���Ԑ錾�ɂ��č�ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����lj�������j���ł߂܂����B���Ԃ͗���2������31���܂łƂ��A�����Ɖ���̐錾�̊���������ɂ��킹�ĉ���������j�ł��B��������b�͌ߌ�5�����납��A������b���@�Ő����o�ύĐ��S����b��c�������J����b��Ɖ�k���܂����B���̌��ʁA�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɍ�ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����lj�������j���ł߁A�^�}���ɓ`���܂����B
���g�܂h�~�[�u�h �k�C�� �ΐ� ���s ���� �����ɓK�p
�܂��A�k�C���A�ΐ�A���s�A���ɁA������5���{���ɐV���ɂ܂h�~���d�_�[�u��K�p������j�ł��B���Ԃ́A�����������2������31���܂łƂ��A����22���܂łƂȂ��Ă��铌���Ɖ���̐錾�̊���������ɂ��킹�ĉ���������j�ł��B���{�́A�����������j��30���A�����ǂȂǂ̐��Ƃł���u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�Ɏ����������ő��{���Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�����{���ȉ� 4�{���g�錾�h�lj� 5���{���g�܂h�~�h�K�p���� �@7/30
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A���Ƃł��镪�ȉ�́u�ً}���Ԑ錾�v�̑Ώےn��ɍ�ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����lj�����ق��A�k�C���A�ΐ�A���ɁA���s�A������5���{���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p���A���Ԃ͂����������2������31���܂łƂ���ƂƂ��ɁA�����Ɖ���̐錾�̊���������ɂ��킹�ĉ������鐭�{�̕��j�𗹏����܂����B
�V�^�R���i�E�C���X����߂���30���ߑO�A�����ǂȂǂ̐��Ƃł��鐭�{�́u��{�I�Ώ����j���ȉ�v���J����܂����B
���̒��ŁA�����o�ύĐ��S����b�́u�S���̐V�K�z���Ґ��͂��̂�1���l�������s��3865�l�Ƃ�������ߋ��ő��ƂȂ�A���ɍ��������̕������Ă���B��s����3������ً͋}���ԑ[�u��v�����ꂽ�B�����Ƃ��킹�Ď�s���ŖʓI�Ɉ�̓I�ɋ������g�݂����{���邱�ƂŊ��������Ƃ��Ă��}���Ă����B���ł���Ë@�ւ̕��ׂ����債�Ă��Ă��āA��苭���[�u���u���Ă����v�Əq�ׂ܂����B
���̂����œ����s�Ɖ��ꌧ�ɏo����Ă���u�ً}���Ԑ錾�v�̑Ώےn��ɍ�ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����lj����A�k�C���A�ΐ�A���ɁA���s�A������5���{���ɂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p������j������܂����B�܂��A�d�_�[�u�̓K�p�n��ł͌����A���H�X�Ɏ��̒�~��v��������j�������܂����B
�����Ċ��Ԃ͂����������2������31���܂łƂ���ƂƂ��ɁA����22���܂łƂȂ��Ă��铌���Ɖ���̐錾�̊���������ɂ��킹�ĉ���������j��������܂����B
������b�́u���̉Ă͓s���{�����z�����ړ��ɂ͂ł��邾���T�d�������Ă��������A�ǂ����Ă��ړ�����ꍇ�͏��K�͕��U�^�Ō������Ă����������Ƃ����肢�������B�����I�����s�b�N�͉Ƒ��₢�����钇�ԂƏ��l���ŁA����ʼn�����ϐ�����Ă��������A�H���L��ł̑�l���ł̉�������H�͍T���Ă����������Ƃ����肢�������v�ƌĂт����܂����B
���ȉ�ł́A�����������{�̕��j�ɂ��ċc�_���s��ꗹ������܂����B
������Đ��{�͏O�Q���@�̋c�@�^�c�ψ���ɕ��A���^���s���������Ōߌ�5������J�������{���Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�����Đ�������b��30���ߌ�7�����߂ǂɋL�҉���u�ً}���Ԑ錾�v�̑Ώےn���lj����邱�ƂȂǂ�������A�����ɗ����Ƌ��͂��Ăт����錩�ʂ��ł��B
�����g��u����̊�@�������L����Ă��Ȃ��v
�u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή�́A��̂��ƕw�̎�ނɉ����A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɁA��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����lj�����ȂǂƂ������{�����������j�𗹏������Əq�ׂ܂����B���̂����Łu����̊�@�����Љ�ɋ��L����Ă��Ȃ��B���܉����N���Ă���̂��A�ǂ����Ĉ�Â��Ђ������Ă���̂��Ƃ������Ƃ��܂߂āA���{�Ǝ����́A���Ƃ������{�C�X�ŋ������b�Z�[�W���o�����Ƃ��d�v���B���ɂ��܂͊�@�I�ȏɂ���B����܂ő�����肢���Ă������Ƃ��K�������\���ɂł��Ă��Ȃ��������獡�̏ɂ���B���ׂ����Ƃ���������ƓO�ꂵ�čs�����Ƃ��K�v���v�Ƌ������܂����B�����āA���ׂ���Ƃ���3�̒�������Ƃ��āu�ӂ���A���܂���Ȃ��Ƒ��ȊO�̐l�ƁA���H�̏����H�ȊO�̋@��ł���l���ŐڐG����@������A�������g�債�Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�I�����s�b�N������Ō��邱�Ƃ��܂߁A�ڐG�@����Ȃ�ׂ������邱�Ƃ�O�ꂵ�Ă��炢�����B�܂��A�����ł���������Ǝv������PCR������R�������Ȃǂ��ł��C�y�Ɍ������Ă��炦��̐����\�z���邱�Ƃ��K�v���B����Ɉ�Â̂Ђ����ɑΉ����邽�ߖK��Ō��ݑ��ÁA�J�Ƃ��Ă���N���j�b�N�Ȃǒn��̕������ɁA���܂ňȏ�ɃR���i�Ή��Ɋ֗^���Ă��炤���Ƃ��K�v���v�Əq�ׂ܂����B
��������b�u��ÂЂ����ŋɂ߂ċ�����@�������L�v
�����o�ύĐ��S����b�͕��ȉ�̂��ƋL�Ғc�ɑ��u�����̊������Ò̐��̏ɋɂ߂ċ�����@���������ꂽ�B���Ɉ�Âɂ��Ă�40���50��œ��@����l���������Ă���B���̂܂ܖ������ꂾ���̊����҂̐��������Έ�Â��Ђ������A�~���閽���~���Ȃ��Ȃ�Ƃ����ɂ߂ċ�����@���������̐搶�����玦����A���̂��Ƃ����L�����v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu���N�`���ڎ킪�i�߂ǂ����������Ƃ��\�ɂȂ�̂���A������o���̎w�W�݂̍���ɂ��Ă��������Ă����ׂ����Ƃ����c�_���o���B�����A�����ł��ꂾ���̊����҂��o�Ă���̂ŁA�܂��͊������Â̏ɂ��č����ɐ��m�ȏ�����������Ɠ`���A���{�⎩���̂ő��O�ꂵ���������グ�Ă������Ƃ̏d�v���ɂ��Ďw�E�𑽐������������v�Əq�ׂ܂����B
���S���m���� �ѐ��u���b�N�_�E�� �@�����������v
���ȉ�̂��ƑS���m����̔ѐ��͋L�Ғc�ɑ��u�Ύ��ŗႦ��A�R�������Ă���B������ǂ��H���~�߂邩�A�������i���g���Ă����ׂ����B���{�ł̓��b�N�_�E�����ł��Ȃ����A������l����ׂ����Ƃ����b�����ȉ�ł͂������B�C�O�ł���Ă���悤�ȁA����G���A�Ől����{���Ɏ~�߂邽�߂̖@��������������i�K�ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
�����ȉ�ψ� �|�X�������u������h�����ƂɑS�́v
�o�ς̐��ƂƂ��ĕ��ȉ�̈ψ��߂�A�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O�̒|�X�������͋L�Ғc�ɑ��u���N�`���ڎ킪�i��ł���ƌ������A���N�`���Ɗ����͈Ⴄ�B�����A��@�I�ȏɂȂ�\�������邱�Ƃ��l���A�܂��͊�����h�����ƂɑS�͂𒍂��ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ����F���ł܂Ƃ܂����v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�����̎��Ԃ��}���Ɉ����Ȃ�A�V���ɂƂ�鐭��Ƃ��ĉ������邩���l�ߐ�Ă��Ȃ��B���H�̏�Ȃǂɑ��L�͂Ȏ��~�߂��������Ă��炸�A�V�����@�I�ȑ[�u�Ȃǂ�݂��邱�Ƃ��K�v���ǂ����A����̃f�[�^�����Ȃ��画�f���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�v�Əq�ׂ܂����B
���������[�����u�錾�����Ɍ��������؎��������v
�������[�����͊t�c�̂��Ƃ̋L�҉�Łu�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ������ɋy�сA���H�X��W���ƎҁA�����̊F����ɑ�ςȂ����S�����������Ă���B�����������ŁA����������ʓI�A�����I�Ȃ��̂ɂ��Ă������߂ɂ́A��̕K�v�������ł͂Ȃ��A����̌��ʂ����\�Ȃ����莦���A�����͂����肢���Ă������Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu���N�`���ڎ킪�i�ޒ��ŁA�����ɂ����炩�ȕω��������Ă���B����҂̓��@��d�lj����}�����Ă���A����A40��A50��ȉ��̐ڎ킪�i�߂A���l�̉��P���ʂ����҂����B�ڎ킪�i�W���钆�ŁA�������Ò̐��̏��ǂ̂悤�ɓK�ɕ]�����Ă����̂��A���Ƃ̂��ӌ����f���Ȃ���A���́A������i�߁A�ً}���Ԑ錾�̉����Ɍ��������������Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
���c�����J���u���N�`���ڎ������i�i�ނ܂ł͋��͂��v
�c�������J����b�͊t�c�̂��Ƃ̋L�҉�Łu�ً}���ԑ[�u���o�����ɂ�������炸�������}���ɐL�тĂ���̂͑�ϊ�@�I�ȏ��B���܂ł����͂����肢��������͖̂������Ƃ����̂͏d�X�������Ă͂��邪�A���N�`���ڎ킪������i�i�ނ܂ł́A�ǂ����������A�����͂��������������v�Əq�ׂ܂����B�܂��u40���50�オ�d�ǎ҂̃{�����[���]�[���ɂȂ��Ă��邪�A���̐���̃��N�`���ڎ�͍���҂Ɠ����悤�ɐi��ł���킯�ł͂Ȃ��A�܂�1�������炢�͂�����B8�������ς��͉��Ƃ��������X�N�̍����s���͍T���Ă������������v�Əq�ׂ܂����B
���ې�ܗ֑��u�錾���� ���Ƃ͑S���ʁv
�ې�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�S����b�͊t�c�̂��Ƃ̋L�҉�ŁA�L�Ғc���獡��̑��^�c�Ȃǂւ̉e���ɂ��Ė��ꂽ�̂ɑ��u�ً}���Ԑ錾�̉����Ȃǂɂ��ẮA���Ƃ͑S���ʂɎЉ�S�̂̊����܂��čs������̂Ə��m���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
������ ���Z���Έψ����u����ő��}�ɋc�_���ׂ��v
��������}�̈��Z�����ψ����͋L�Ғc�ɑ��u�����������܂ōL�������{�̐����ӔC�͏d���A�����t�S�̂ŐӔC���Ƃ��Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�����͂��łɓ�������n���ɍL����n�߂Ă��āA���̂܂܌��߂����ΑS���ň�Õ��N�����˂Ȃ��B�܂��A�p�������s�b�N�ւ̑Ή����ǂ�����̂��Ȃǂ����荑����J���đ��}�ɋc�_���ׂ����v�Əq�ׂ܂����B
�����{�A�V�^�R���i�V�K������1���l�����c�ً}���Ԑ錾�g��@7/30
�����I�����s�b�N(�ܗ�)�̍Œ��A���{�ŐV�^�R���i�E�C���X������(�V�^�x��)���}���Ɋg�債�A�ً}���Ԑ錾���ߒn�悪�啝�Ɋg�傳���B
30���A�����ʐM��m�g�j�ɂ��ƁA���{���{�͂��̓��[���A�V�^�R���i���{����c���J���A�_�ސ�E��ʁE��t�̎�s��3���Ɗ��n��̒��S�n�E���{�ɋً}���Ԕ��߂����肷��B
���ߊ��Ԃ͗���2������31���܂ŁB���{�ً̋}���Ԑ錾�́A�O�o���l����H�X�̉c�Ǝ��Ԃ̐����A�ݑ�Ζ��̊g��Ȃǂ����q�Ƃ���B
���łɋً}���Ԑ錾�����߂���Ă��铌���s�Ɖ��ꌧ�̔��ߊ��Ԃ́A����22���܂ł��瓯��31���܂łɉ��������B
����ɂ��A����24���ɊJ�����铌���p�������s�b�N���ً}���Ԕ��ߊ��ԂɊJ�Â���邱�ƂɂȂ����B
�m�g�j�ɂ��ƁA�O���A���{�S���ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�����҂�1��699�l�ŁA�V�K�����҂����߂�1���l�����B
23���̌ܗ֊J����A���{�ł͐V�^�R���i���}���ɍL�����Ă���B
�V�^�R���i�̐V�K�����҂͊J������4225�l����O��1��699�l�ɁA153���}�������B
���Z�������s���铌���s�ł́A3865�l���������A3���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
�����ܗւɂ�200�J���ȏ�̑I���W�҂���8���l�W�܂��Ă��邽�߁u�����I�����v�ւ̕s�������܂��Ă���B
�ܗ֏o��I����͂��߂Ƃ�����W�ҁA�W���[�i���X�g�A�ϑ��Ɩ��X�^�b�t�Ȃǂ��犴���҂��������Ă���B�����ܗ֊֘A�̊����҂͍��v193�l�ƂȂ����B
�������A�͖쑾�Y���N�`���S�����́A�`�o�ʐM�Ƃ̃C���^�r���[�Ōܗ֎Q���҂����ʎs���ɐV�^�R���i�����������Ƃ����؋��͂Ȃ��Əq�ׂ��B
���u��A���ŁA�}�X�N�ƁA�ł��邱�Ƃ𑱂��邵���Ȃ��v�g�傷��V�K�����@7/30
�ߋ��ő���A���X�V�����V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��B���{�͐_�ސ�A��ʁA��t�̎�s��3���Ƒ��{�ɑ��ً}���Ԑ錾�̔��o���A�����A����̊��ԉ����̕��j���ł߂��B
����Ŋ��҂̑Ή��ɂ������Ă������m��ȑ�w�a�@�z����ȏ����̌㓡��i��t�́u�����s��1���̐V�K�����Ґ����A�����炭5000�l���x�͍s���̂ł͂Ȃ����Ɨ\������Ă���Ǝv���B����҂̃��N�`���ڎ킪�i��ł���̂ŏd�lj����̂Ƃ���ł͂܂��`�����X�����邩������Ȃ����A�g��T�d�Ɍ��Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����A��͂�g���̕a�C�h�ł���ȏ�A�����X���ł͂Ȃ��v�Ƙb���B
�����s�̕����ی��ǂ�27���A�u(���f�B�A��)��������ɕs�������Ȃ��悤�ɂ��Ă���������B�d�lj����͋ɂ߂ĒႢ�B��Âɑ��鈳���́A������Ƃ͎�Ⴄ���ȂƂ�����ۂ������Ă���v�Ƃ��āA�O��̃s�[�N���Ƃ͏��ω����Ă��邱�Ƃ��w�E�B����A�s��t��̒������F�����29���̃��j�^�����O��c�̐ȏ�A�u���@���Ґ���d�NJ��Ґ��ɗ]�͂�����悤�Ɍ����邪�A����͌����Ă����������Ƃł͂Ȃ��v�ƌx����炵�Ă���B
�㓡��t�́u���N�`���ڎ킪�i�݁A�d�ǎҐ������Ȃ��Ȃ��Ă���Όo�ϊ������ĊJ���ł���悤�ɂȂ�̂ŁA�d�lj����̕������������Ƃ����ӌ�������Ǝv�����A�Q�Ăăf�[�^�̉��߂����āA���ՂɌ��t�ɏo��������͖̂�肾�B���ڎ�̕��X�̊ԂŊ������g�傷��Εa���͕N�����Ă��܂����A���@�悪�u���a���łȂ���A���̐l�ւ��������L���Ă��܂��\��������B����ɋU�z���ł��u������邱�Ƃ�����̂ŁA�������X�N�̍����Ƃ����2�T�ԋ߂��x�b�h�߂�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�B���ɒv������1�����Ƃ���ƁA�����҂�1�l�ł���Ύ��ʉ\���͋ɂ߂ĒႢ���A�����҂�100�l�o���1�l�͖S���Ȃ�킯�����A�����҂�100���l�A1000���l�c�ɂƂȂ�A����ɘA��Ď��S�Ґ��������Ă����킯���B�d�lj��̎w�W������̂��������厖�����A��͂�V�K�����Ґ����厖���v�Ǝw�E�B
�܂��A�u�g�m�ەa���̎g�p���h�Ƃ����������悭�o�Ă��邪�A�d�ǂ̐l��f�邽�߂̔��͊m�ۂ���Ă��Ă��A�X�^�b�t�S�����l�H�ċz���������킯�ł͂Ȃ��ȂǁA�}���p���[��n�[�h�ɂ���āA���ԂƂ��Ă̕a�����͏��Ȃ��Ȃ�B�����������Ŏg�p�������Ă��A��Ë@�ւɂ͉_�D�̍�������Ƃ������Ƃ��B���ɓ����͏d�ǂ̐l��f�邽�߂̔��̐��͂����������B����ł���w�a�@�Ȃ�ICU�����������Ă���悤�ȂƂ���̐搶�����g�ꂵ���h�g�������h�ƌ����Ă���Ƃ������Ƃ́A�m���ɂ��������ɂ���Ƃ������Ƃ��Ǝv���B�ď�ɂ͏d�x�̔M���ǂ̕��X������Ă��邵�A��Â����߂̗]�T�A�����Ċ����Ґ��������Ă���1�T�ԁA2�T�Ԍ�Ƃ����^�C�����O�����܂�����ŁAICU�̐�L�������Ă����Ȃ��ƁA���ꂩ���ɏd�lj��������X�ɂƂ��Ă͔ߌ��ɂȂ��Ă��܂��v�ƌ��O���������B
����ɔɉ؊X�Ȃǂ̐l�o�ɂ��Đ�������27���A�u�Ԃ̐������Ƃ��e�����[�N�A�����Ă܂��ɊF����̂��������܂ɂ���Đl���͌������Ă���v�ƃR�����g�B�������[�������u����1�A2�T�ԁA��̑ؗ��l�������邩����́A�����Ă��Ă���Ƃ����͖̂��炩�ł͂Ȃ����낤���v�Ƙb���Ă��邪�A���Ԃ𐳂������f���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ̐��͌�������Ȃ��B
�㓡��t�́u20��⓭�������30��̊����������͍̂��܂ł��ς��Ȃ����A�s���ϗe�����b�Z�[�W�Ƃ��ē͂��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����Ǝv���B�g�ً}���h�Ƃ����̂���̉���o���A�g�������R���h�ƌ������A��̉���R�������Ă���̂��A�Ƃ������Ƃ��낤�B����ł��L�a���������Ȃ̂Ŏc��̐l�����ɂ͂킩��Ȃ����A������l�����́g����ς肱�̕a�C��ς������B���Ȃ���悩�����h�ƌ����Ă���B��͂芴�����Ȃ��ɉz�������Ƃ͂Ȃ����A���H�X����ً̈c�������A���Z�E�x�Ɨv���ɂ͉����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��Ă���̂ŁA�����͌X�l�������̍s�����������B���ǁA�l���x���ł͂������������A���ł����A�����Ƃ���ł̓}�X�N��t����Ƃ������Ƃ��A�Q�Ă��������J��Ԃ��Ȃ����Ƃ������Ƃ��v�Ƙb���Ă����B
�������s�́u�s������Ȃ��Łv�Ɂu�����Ă�͓̂s�m���v�̑升���@7/30
�u��������ɕs���������邱�Ƃ͂��Ă������������Ȃ��v
�����s�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ���2848�l���L�^����7��27���B�����̉ߋ��ő��ƂȂ�V�K�����Ґ����������A�w�����ʐM�x�ɂ��Ɠs�̋g�����F�����ی��ǒ��͖`���̂悤�ɃR�����g�����Ƃ����B�������A�l�b�g�ł́u�����Ă�͓̂s�m������v�Ƃ̐����������ł���B
�s�u�s������Ȃ��Łv���ēs�m������ԕs�������Ă��t�s��������ɕs�����������Ă������{�l�����r�s�m���t�s���r�s�m���̂ق����Ǝv���܂���B�������������A�A���[�g���邨�d���������ĂȂ��ł���ˁt
�ł́A���r�S���q�s�m��(69)�̌�����U��Ԃ��Ă݂悤�B�V�^�R���i�E�C���X���҈Ђ��n�߂���N3��25���A���r�s�m���́u���C�u�n�E�X�Ȃǂ̗��p�����l����悤�Ɂv�Ɣ����B�������A�u�⏞���ɂ��ẮA�ŋ��𓊓����邱�Ƃ��{���ɐ������̂��c�_������Ƃ��낾�Ǝv���v�Ƒ������B���́u���l��v�����Ă��⏞�͂Ȃ��v�Ƃ̎p���ɁA���H�ƂȂǂ��܂��܂ȋƎ킪�s�����o���鎖�ԂƂȂ����B
����2��������ƂȂ�6��2���A���r�s�m���́w�����A���[�g�x���B�����������g��ɑ����̍�\���Ȃ��������߁A�u�s�����ԐF�ɕς���������v�Ƃ̐������ɓ��ɑ����Ă������ƂɁB�܂�7��2���ɂ͉�Łu�g��̊X�h�v���Ӂv�Ƃ̃{�[�h���f�������A�s�t���b�v�|�t�Ƃ̝������B����Ɂu��̊X�̃X�e�B�O�}(���ʂ�Ό��ɔ������̃C���[�W)����������̂ł́v�Ɗ뜜���鐺���オ���Ă����B
�����đ���Ȃ��Ȃ��A����15���ɂً͋}�L�҉���J���u�V�^�R���i�E�C���X�̌x�����x����4�i�K�̂����ł������g�������g�債�Ă���h�Ɉ����グ��v�Ɣ��\�����̂��B
���s�\���B�����Č����̕s��v
���N12��17���ɏ��r�s�m���́A�w�N���N�n�R���i���ʌx��x�o�B��������Ë@�ւɂ͕a���̊m�ۂ��A���H�X�ɂ͎��Z�c�Ƃ��A�����ēs���ɂ͉�H���T����悤�g���肢�h�B�܂����Ă���̓I�ȑ�̔��\���Ȃ��������߁A�s�u����� �����v�ƌ��������t�s���̂��������������A���[�g�ƕς��Ȃ���ہt�Ƃ����������オ���Ă����B
�����č��N�ɓ����Ă��A���r�s�m���́g�s������h���~�߂Ă��Ȃ��B4��23���ɂ́u�X���̏Ɩ����Ŕ�l�I���A�C���~�l�[�V�����Ȃǂ�20���ȍ~�͒�~����悤�v������v�Ɖ�Řb�������߁A�s�d�C��������W�܂�Ȃ����낤���āc�s���͉�ł����H�t�ƌ��ʂ��^�⎋���鐺���B�s�X�̖����肪����A�ƍ߂�������̂ł́B�����̋A��ȂǓ��ɐS�z�ł��t�Ɗ뜜���鐺���������B
�܂������A���r�s�m���́u�O�ꂵ���l���̗}���⊴�����X�N�������{�݂ւ̓K�ȑΉ��Ȃǂ��K�v�v�Ƃ��āA�����ȂƊe�S�����Ǝ҂Ɂg�Ԉ����^�]�h��v���B���������ւ������A��v�w�͒ʋ�ʊw�ł����������G���邱�ƂɁB�������āg3���h�����o�����B�����ۂ��ŁA���āg�����d�ԃ[���h�Ƃ̌�����f���Ă������߁u����������������Ă��Ȃ��v�Ƃ̍Ĕᔻ���Ȃ��ꂽ�B
�����č���18���ɂ͓����ܗւɂ��Ȃ�ŁAIOC�̃g�[�}�X�E�o�b�n�(67)�̊��}����J�ÁB�����ɂ͐X��N��(84)��ې���ܗ֑�(50)��40�l�قǂ��Q�����Ă����ƕ��Ă���B���r�s�m���͂���܂Łu��l���ŏW�܂�Ȃ��悤�Ɂv�Ɖ��x���Ăт����Ă������߁A�����̕s��v�ɃE���U�����鐺���������B
���uCOVID19�Ƃ̐킢�ŋ����_������肽���v
�܂��s�́u�s�������Ȃ��Łv�Ƃ������A���Ƃ�����������������w�E���鐺���オ���Ă���B
�wNHK NEWS WEB�x�ɂ��ƍ���21���ɊJ���ꂽ�����s�̃��j�^�����O��c�Ő��Ƃ́u�V�K�z���҂�������������A��Ò̐����Ђ����̊�@�ɒ��ʂ���v�u��Ñ��́A��3�g�̑O�̋��N12�������C���[�W���邭�炢�̋��|���������Ă���v�Ƌ�����@�����������Ƃ����B
�����Ė`���̉�����A�s���̕s���͂���ɐ����邱�ƂɁB�R���i�Ђŏ��r������������㉉���Ă������r�s�m�������A�w�����ʐM�x�ɂ��Ɗ����Ґ������\���ꂽ�[�����_�Ŋ��ɑޒ��B�u��ޑΉ��͂Ȃ������v�Ɠ`����ꂽ�̂��B���̂��߃l�b�g�ł́A����Ȑ����オ���Ă���B
�s�����ӔC���ʂ������ޒ��I�������A�s���ɔ��܂肱��łł��s���̖�����邱�ƂɎ��ɂ��̂��邢�őΉ����ׂ��t�s���������A����Ȃɂ��Ⴕ���o�Ă������r�S���q�͂ǂ��ʼn����Ă�́H�o�Ă���͍̂�����Ȃ��́H�����ӂ̃t���b�v�Ƃ��W��Ƃ��J���^�Ƃ��U�肩�����Ċ����h�~�ɓw�߂��Ȃ��́H�ǂ��������𗧂������������ǁt�s���r�S���q�A�������̑����ƋC�z�̏�������z���Ă�t
7��24���A�����ܗւɍۂ��āu���Г�������COVID19�Ƃ̐킢�ŋ����_������肽���Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă����s�m���B�������A�\����͂܂������̂�������Ȃ��B
�����r�s�m���@��҂Ƀ��N�`���ڎ�v�����u���������\��ł��Ȃ��v�Ɣᔻ���o�@7/30
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�����g�傪�Ƃ܂�Ȃ��B7��28���ɂ�3177�l�̐V�K�����҂����\����A���߂�3000�l�������L�^�B������29����3865�l�̊������m�F����A27������3���A���ōő����X�V�����B
�ً}���Ԑ錾���ł���ɂ��ւ�炸�����̂߂ǂ������Ȃ��Ȃ��A�s�̐V�^�R���i���w���w�����Ă��鏬�r�S���q�s�m��(69)�ɂ��g���������Ă��Ȃ��h�v���ɔᔻ���E�����Ă���B
NHK�ɂ��ƁA28���ɏ��r�s�m���͓s���ŕw�̎�ނɉ����A�u���N�`����������̐l�����̊����͂����Ɖ������Ă��āA�t�Ƀ��N�`�����Ă��炸�d�ǂ⒆���ǂɂȂ�Ⴂ���オ�����Ă���v�ƌ��݂̏�����B
����Ɂu�s�v�s�}�̊O�o���l��O�ꂵ��{�I�Ȋ����������Ăق����B���N�`�����Ⴂ�l�ɂ��ł��Ăق����B�Ⴂ�l�����̍s�����J�M�������Ă���̂ŁA���ЁA�����͂������������v�ƌĂт������Ƃ����B
��N�w�ւ̃��N�`���ڎ��v���������r�s�m�������A�����s�ł̓��N�`����ł������Ă��łĂȂ�������B
�Ⴆ�ΗD��ڎ�҂ł͂Ȃ�16����39�̑ΏێҁA�z��9��5��l���Z��ł���L����̃z�[���y�[�W�ɂ́A�s8��1��(���j)�ɐV�K�\����ĊJ���܂��B���݁A������S���̎����̂ɋ�������郏�N�`���̋������啝�Ɍ������A�{��ւ̔z���ʂ��z��ȏ�ɍ팸���ꂽ���Ƃ���A7��9��(��)����7�����܂ł̊ԁA���N�`���ڎ�(�ʐڎ�A�W�c�ڎ�A����ڎ�)�̐V�K�\����ꎞ�I�ɒ�~�������܂��t�ƋL���ꂨ��A������̋��������������Ƃɂ��A�܂��\�n�܂��Ă��炢�Ȃ��B
����ɁuTBS NEWS�v�ɂ��ƁA���q�����^�c���铌���s�̑�K�͐ڎ�Z���^�[��29���ɕ�W���ꂽ3���l���̐V�K�\��g��1����2���Œ���ɒB���Ă���A�e�Ղɗ\��ł���ł͂Ȃ��B
���̂悤�Ȏ��ԂƘ����������r�s�m���̗v�]�ɁASNS��ł́u�łĂ�̐����o���Ă��Ȃ��v�Ƃ̔ᔻ�����������B
�s�ł������Ă��łĂȂ��Ƃ����m��Ȃ��낤�ˁt�s����B�J�M�������Ă�̂͏��r�����X�K����Ȃ̂�B�Ⴂ�l�����܂Ń��N�`����͂��Ȃ�����B�ł������Ă��łĂȂ��B�Ȃ�ł���҂̂����ɂ���Ȃ�t�s�ǂ������ƌ����Ƒ����ł����ė~�������ǁt�s���������ł������Ă��\��ł��Ȃ���Ȃ��t
�������ً̋}���Ԑ錾��8�����ɉ����A4�{���lj��ց|���ȉ�����@7/30
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A���{�͓����s�Ɖ��ꌧ�ɔ��߂��Ă���ً}���Ԑ錾��8�����܂ʼn�������B�����̊����͓���22���܂ł̗\�肾�����B
�Ώےn��ɂ͐_�ސ�A��t�A��ʂ̎�s��3���Ƒ��{��lj�����B���Ƃɂ���{�I�Ώ����j���ȉ�ŗ������ꂽ�Ɛ����N���o�ύĐ��S���������炩�ɂ����B�[���̑��{���Ō��肵�A���`�̎͌ߌ�7������L�҉����B
�������́A���N�`���ɂ��āu8�����{�ɂ͐ڎ�����݂̉��ĕ��݂ɂȂ邱�Ƃ������܂��v�Ƃ��āA�ڎ킪���L���s���͂��܂ł͌������[�u�𑱂���ӌ����������B�ċx�݊��Ԃ̊����g���h�����߁A�H�c��`�Ȃǎ�v��`����k�C���E����Ɍ������l�ɉ����A�����ւ̓���҂ɂ��������������{����Ƃ����B
�ܗ֊J�Ò��̓�����12������錾���ɂ���A�s�͎�ނ̒�~��v�����Ă���B�����A29���̊����Ґ���3865�l(�O��3177�l)��3���A���ʼnߋ��ő����X�V�B���Ӓn��ł��������L�����Ă���A�_�ސ쌧�ł�2���A����1000�l�����B
����29����A���@�ŋL�Ғc�Ɂu������@���������đΉ����Ă���v�Əq�ׂ��B�����ܗւƊ����g��̈��ʊW�ɂ��Ė��ꂽ�ۂ́A�u���ۑ�������������Ă���v�Ɣے肵���B�@
�ɓ��������̕��c�~�`�[�t�G�R�m�~�X�g�́A�ً}���Ԑ錾�̉e���͔͂���Ă��Ă���A�Ώےn����g�債�Ă��u���قnj��ʂ͏o�Ȃ��v�Ǝw�E�B�o�ϊ������傫���}������Ȃ����Ƃ���u���{�o�ςւ̉e���͌���I�ŁA�傫���}�C�i�X�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ̌������������B
���ً}���Ԑ錾�A�v6�s�{���Ɋg��c���J���u�V���ȋ��낵���ǖʁv�Ɗ�@�� �@7/30
���{��30���ߑO�A�V�^�R���i�E�C���X��̐��Ƃ�ɂ���{�I�Ώ����j���ȉ���J���A��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ɐV���ɋً}���Ԑ錾�߂�����j�������A�������ꂽ�B�����[�̐��{���{���Ő������肷��B���Ԃ�8��2������31���܂ŁB�錾�̑Ώۂ́A���łɔ��ߒ��̓����s�Ɖ��ꌧ�����킹�A6�s�{���Ɋg�傷��B
�c�������J�����͕��ȉ�ŁA�V�K�����Ґ����}�����Ă��邱�Ƃɂ��āu���܂łƂ͈�����V���ȋ��낵���ǖʂɓ����Ă��Ă���v�Ɗ�@�����������B
���{�͌��݁A��s��3���Ƒ��{�ɑ��A�錾�ɏ������\�ƂȂ�u�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p���Ă���B��������V�K�����Ґ����錾�̖ڈ��ƂȂ�u�X�e�[�W4�v�ɒB���A��Ë@�ւ̕��S�����債�Ă��邱�Ƃ��l�������B�����Ɖ�����A8��22���܂ł̊�����31���܂ʼn�������B�錾�̑Ώےn��ł͈��������A��ނ������H�X�ɋx�Ƃ�v������B
����A�������}�����Ă���k�C���A���s�A���ɁA�ΐ�A������5���{���ɂ͏d�_�[�u��V���ɓK�p����B���Ԃ�8��2������31���܂ŁB�d�_�[�u�̒n��ł́A�����Ƃ��Ď�ނ̒�~�����߂�B���݂͈��̊�������Ƃ����X�ł́A�m���̔��f�Ŏ�ނ̒��O�I�ɔF�߂Ă��邪�A����̊�{�I�Ώ����j����Ăł́u���������~�X���ɂ���ꍇ�v�ɂ����F�߂��A��������茵���������B
�����ɂ��āA���{���ɂ͓����A8��22���܂łƂ���Ă��������B�����o�ύĐ����͕��ȉ�ŁA�u���𐢑�ɂ����N�`���ڎ킪�i�ނ��Ƃɂ����ʂ����ɂ߂邽�߁A31���܂łƂ������v�Ɛ��������B
���{�́A8�����ɑS�l���̂������N�`����2��ł����l�̊�����4�`5���ɒB����ƌ�����ł���B���݁A40�A50�Α�̏d�lj��������Ă���A8�����ɂ��̐���̃��N�`���ڎ킪�i�߂A�����̉��P�����҂ł���Ƃ����킯���B
���{��30���[�̐��{���{���Ő������肷��B������ɐ����L�҉���J���A�����ɗ��������߂�B
��4�{���ɋً}���Ԑ錾�A5���{���ɏd�_�[�u�ց@7/30
���{��7��30���A��{�I�Ώ����j���ȉ�(��F���g�E�n���Ë@�\���i�@�\�kJCHO�l������)���J���Č��ݓ����s�Ɖ��ꌧ�ɏo���Ă���ً}���Ԑ錾����ʁA��t�A�_�ސ�e���Ƒ��{�Ɋg��A�܂h�~���d�_�[�u��k�C���A���s�{�Ɛΐ�A���ɁA�����e���ɏo�����Ƃ�����A�������B�����ߌ�ɏO�Q���@�̋c�@�^�c�ψ���ł̐������o�Đ��{���{���Ő����Ɍ��肷��B���Ԃ�8��31���܂łŁA����22���܂ł����������s�A���ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�����킹��8��31���܂ʼn�������B
���ꌧ��5��23������A�����s��7��12������ً}���Ԑ錾���p�����B��ʁA��t�A�_�ސ�e����4��20������A���{��6��21������܂h�~���d�_�[�u���p�������������A�����g��Ɏ��~�߂������炸�A��苭���[�u�Ɉڍs���邱�ƂɂȂ�B�����N���o�ύĐ��S�����͕��ȉ�`���A�u���ɍ��������ł̊����������Ă���B�����ł�6���ȍ~�l���������������Ȋ������s���Ă������ʂƍl���Ă���B�f���^���ւ̒u������肪�i�ޒ��A�ɂ߂ċ�����@���������Ă���v�Əq�ׂ��B�����s�̊����͐V�K�z���Ґ��A���@�Ґ��Ƃ����̊�ŃX�e�[�WIV�������A��ʁA��t�A�_�ސ�e�������l�̏ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���u�ʓI�ɁA��̓I�ɋ������g�݂����{���邱�ƂŊ�����}���Ă��������v�Əq�ׂ��B
���ɂ��Ă��A���{�ŐV�K�z���Ґ��Ɠ��@�Ґ����X�e�[�WIV�ň�Âւ̕��ׂ������Ă���A���s�{�A���Ɍ����V�K�z���Ґ����������Ă��邽�߁u���ƍ��킹�Ċ�����̂ƂȂ������g�݂��������v�Əq�ׂ��B���ꌧ��6���㔼����7���ɂ����Ă�������V�K�z���Ґ��������������A���̌�܂��}�����A�k�C���Ɛΐ�A���������������X���ɂ���Ɛ��������B
���Ԃ�8��31���܂łƒ�����������Ƃɂ��ẮA����҂ւ̃��N�`���ڎ킪�i���ߏd�NJ��҂������Ă��Ă��邱�Ƃ܂��A�u���𐢑�ւ̃��N�`���ڎ킪�i�ނ��Ƃ̌��ʂ����ɂ߂邽�߂�1�J���ԂƂ������v�Ɛ����B���𐢑�ւ̐ڎ킪�i�ނ��Ƃň��̉��P���ʂ����҂ł���Ƃ��āA�u�n��ɂ����銴�����Ò̐���K�ɕ]�����邽�߂ɁA40��A50��̐ڎ�ƍ��킹�Ĉ�Ò̐��̕��ׂɒ��ڂ������́A������i�߂Ă��������v�Əq�ׂ��B
�c�����v�����J����b�́A�u�뜜���Ă���̂́A�ً}���Ԑ錾����2�T�Ԉȏ�o���Ă̋}���ȐV�K�����҂̐L�т��B�l�����̂͊m���ɈȑO�قlj������Ă��Ȃ����A�����Ă���킯�ł��Ȃ��A�����������ŐL�тĂ���B����܂łƂ͈Ⴄ���낵���ǖʂɓ����Ă���v�Ɗ�@���������ɂ����B
���ȉ�I����Ɏ�ނɉ������@���M��w�������E�����NJw�����̊ړc�ꔎ���́A�u(�����s�ւ�)�ً}���Ԑ錾�̔��o��A2�T�Ԃ��߂��Ă����ꂾ�������Ґ����������Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�l���Ɋւ��Ă͏������������Ă��邱�Ƃ��m�F����Ă�����̂́A���̌��ʂ͂�͂�c�O�Ȃ������I�ł������ƍl������Ȃ��v�Əq�ׁA�u�����_�Ŋ���1�T�ԁA2�T�Ԑ�̂��Ƃ����܂��Ă���̂ŁA���̂悤�ȑ��������炭�͑����ƍl���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƌ������������ƌ��ʂ����B
�����s�ɂ��ẮA�u�����I�Ȋ����Ґ��̑��傪�����Ă���v�Ɗ�@���������A���S�Ґ��ɂ��Ă͂܂������Ă��Ȃ����̂́A�d�Ǘ�₻�̗\���R���m���ɑ������Ă���A���N�`���ڎ킪�\���ɍs���n���Ă��Ȃ�40�A50��̏d�Ǘ�̑��������O�����B
���������F���̉��A�ړc���́A7��30���ɉ��肳����{�I�Ώ����j�ł́A��ނ���H�X���^�[�Q�b�g�ɂ�����������邪�A���͂������Ȃ��Ȃ��Ă���܂��A�u����������Ґ��̑����������̂ł���A�f�p�[�g���܂߂����Ǝ{�ݓ��̉c�Ǝ��l���܂߂Ă��肢���Ȃ�������Ȃ��ƌl�I�ɂ͎v���v�Ƃ�苭����̕K�v����i�����B����ɁA�u����A�ً}���ԑ[�u�̓��e�̌��������s���\�����A(���{��)�l�����Ă���Ɨ������Ă���v�Əq�ׂ��B
��c�ł́A�Ώےn��̊g��Ɗ�{�I�Ώ����j�̉�����e�ɂ��ẮA���Ɉӌ����o�Ȃ������Ƃ����B�����A�S���I�Ȋ����̍L���肪�����Ă��邱�Ƃ���A��������Ɖ�͂𑱂��Ȃ���A�K�v�ɉ����đS���ɓW�J����悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă����ׂ��Ȃǂ̕����̈ӌ����o���B�ܗւɂ��ẮA���̊�������ɒ��ڂ̓����N���Ă͂��Ȃ����A�ԐړI�ɖ����������b�Z�[�W�ɂȂ��āA���ꂪ�l�̓����̑����ɂȂ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ����������Ƃ����B
���R���i�����҉ߋ��ő��^��@�����L�����O����@7/30
�V�^�R���i�E�C���X�����́u��5�g�v�̊g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��B���̂��͑S����1���Ƃ��Ă͏��߂�1���l���V�K�����҂��m�F���ꂽ�B�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���̎�s��1�s3���Ŋ����҂̖�6�����߂����Ƃ́A�����������͂���E�ɗ��Ă��邱�Ƃ������Ă���B���̂܂܂ł́A�����������n���ɍL���鋰�ꂪ��������ттĂ���B
�����ҋ}���̗v���́A�����͂̋����C���h�R���̃f���^�����A���N�`�����ڎ�҂�����20�`50������Ă��邱�Ƃɂ���B�l�̗���̌��������A�O��ً̋}���Ԑ錾����菬�������Ƃ��傫���B
���́A���������ɂ�������炸�A���{�A�����́A�����̊ԂŊ�@�������L�ł��Ă��Ȃ����Ƃ��B
���{�̊����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή�͂��̂��̎Q�@���t�ψ���̕�R���ŁA��@�������L����Ȃ��������Ί���������Ɋg�債�A�u�������Ñ̐����[��������v�ƌx�������B
���g���͐��{�ɋ������b�Z�[�W�M���邱�Ƃ����߂����A���`�̎̍ŋ߂̔�������͋�����@���͓`����Ă��Ȃ��B���r�S���q�s�m�������l���B
�s���ł́A1���̑�3�g��������҂̊����̊����������Ă���B�d�ǎ҂����Ȃ��B�����Ґ����������グ�邱�Ƃ��^�⎋���鐺���������ŁA�����҂�������Β����ǂ�d�ǂ̊��҂��������郊�X�N�͍��܂�B��p�̉����ȂǃR���i�ȊO�̎��Âɂ��e����^���Ă���A��Ì���͍ĂѕN��(�Ђ��ς�)������B�����Ċy�ςł��Ȃ��B
���O�����̂́A��s���̊����������n���ɋy�Ԃ��Ƃ��B���k�ł������A�{����͂��ߊ����҂������X���ɂ���B�w�Z�͉ċx�݂ɓ����Ă���A���~�ɂ͌������܂����ړ��̑������\�z�����B�e���͋A�Ȃ◷�s���T����悤�����Ăъ|����ׂ����B
�����̊Ԃɂ́A���l���⑊�����錾�ւ̊��ꂪ����B���{��s���s�v�s�}�̊O�o���l��ړ��̗}�������߂����ŁA�����ܗւ̊J�Âɓ��ݐ������Ƃ������������b�Z�[�W�Ǝ���A�v���ɋ��͂��悤�Ƃ����ӎ��̒ቺ�ɂȂ����Ă���ʂ͔ۂ߂Ȃ��B
����������̐�D�Ƃ��郏�N�`���ڎ���݉����Ă���B�o�ϊ����̐���������ȏ�L���邱�Ƃ��A�o�ς̔敾�Ԃ���l����Ɠ�����̂�����B���g�����u���̊�����������v�f�͂��܂�Ȃ��v�ƌ����悤�ɁA�����ӂ�����ȏɂ���B
������Ƃ����āA������܂˂��Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��B�s�v�s�}�̊O�o������A�l�Ƃ̐ڐG���ɗ͌��炵�A�}�X�N�̒��p�����s����B������̊�{��O�ꂵ�A���N�`���ڎ킪�s���n��̂�҂B����̐g�����ɂ́A����ł͂��ꂪ�őP�̍�ł��邱�Ƃ��ĔF�����A���H���邵���Ȃ��B
���f���^����������������ĐV�K������1���l�˔j�@7/30
�V�^�R���i�E�C���X�̒��ł������͂������C���h�R���̃f���^�^�ψي�(�f���^��)����s���Ŕ����I�ɍL����A�S���I�ɂ��������}�g�債�Ď��܂�C�z���Ȃ��B29���̓����s�̐V�K�����҂͏��߂�3000�l����28����������ɑ����ĉߋ��ő����X�V�B�S���ł�1���l�����߂Ē����A�v�ł�90���l��˔j���Ă��܂����B�����̒��S��20�`40��̊����I�Ȑl�⓭������B���Ƃ͑������Łu����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��v�u��ÕN��(�Ђ��ς�)���[��������v�Ǝw�E����ȂǁA������@����\�����A������ĐV���ȋ�����̕K�v�������߂Ă���B
�����J���ȂⓌ���s�ɂ��ƁA�����s��29���̐V�K�����҂�3865�l�ŁA�O����3177�l��葝����4000�l�ɔ����Ă���B��s���𒆐S�Ɋ����҂͑S���I�ɑ����A29���[��܂ł�1��693�l�𐔂����B�����҂�8���Ɍ�������ɑ����鐨�����B���{��7��12���ɓ����s��4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�߂������A�������߂ɂ�2000�l�ȉ���������Ă��������̐V�K�����Ґ��͒��{��3000�l���A22����5000�l�����B��s���̋}�g��Ɉ���������`��28���ɂ�9000�l���Ă����B
���J�Ȑ��Ƒg�D��28���̉�Ŏ����ꂽ�����ɂ��ƁA27���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����҂͐l��10���l�����蓌����88.63�l�B59.33�l�������O�T���1.49�{�ɑ����Ă����B���̂ق��A��������2.20�{�A���ꌧ��2.15�{�A���{��1.52�{�B��s�������łȂ��S���I�Ȋ����}�g�傪�����Ă����B�����đS���̐V�K�����҂��܂��m�肵�Ȃ�29���̗[���̒i�K�Ŋ���1���l��˔j�����B�����������Ԃ��d���������{�͓�����A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɍ�ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{����lj�������j�����߂��B30�����ɐ����Ɍ��߂�B
���J�Ȃ̂ق��A�����̐��Ƃ͊����҂̋}�g��̔w�i�ɂ͊����͂������f���^���̂܂�����Ƃ݂Ă���B���������nj������͎�s���ł̐V�K�����҂�70���ȏ���f���^������߂�Ɛ��v���A���̊����͍��コ��ɑ������A�S���ɂ܂���̂͊m���Ƃ݂Ă���B
�����҂��ł����������s�̏ɂ��āA���J�Ȃ̐��Ƒg�D��28���̉�Łu20�`40��𒆐S�ɋ}���Ȋ����g�傪�����Ă���v�ƕ��́B����A���N�`���ڎ킪�i��ł���65�Έȏ�̐V�K�����҂͂킸����3���ɂ܂Œቺ���Ă���B�����̂��Ƃ���A�����s�����łȂ��S���I�Ƀ��N�`���ڎ킪�I��炸�������������A����Γ�������̎Ⴂ�l��s�N�w�������͂������f���^���E�C���X���P���Ă���Ƃ݂Ă���B
���g�D�͂܂��A�d�ǎ҂�40�`50��𒆐S�ɑ������Ă���Ƃ��A�u����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��v�u�M���ǂȂǂŋ~�}������������ȂLj�ʈ�Â̕��ׂ��������钆�ł��̂܂܂̏������A�ʏ�ł͏����閽��������Ȃ��ɂȂ邱�Ƃ��������O�����v�ȂǂƋ�����@�����������B
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή�́A28���̏O�@���t�ψ���̕�R���Łu��Â̕N��(�Ђ��ς�)�����ɋN���n�߂Ă���Ƃ����̂������̔F�����v�Əq�ׂ��B�Q�@���t�ψ���̕�R���ł�29���A�u���̍ő�̊�@�͎Љ��ʂ̒��Ŋ�@�������L����Ă��Ȃ����Ƃ��B���L����Ȃ���������ÕN���͐[��������v�u���̊�����������v�f�����܂�Ȃ��v�ȂǂƔ������u���܂ňȏ�ɖ��m�ȋ������b�Z�[�W���o���Ăق����v�ȂǂƑi�����B
�܂��A���{�����NJw������ŁA���J�Ȑ��Ƒg�D�����o�[�ł�����ړc�ꔎ�E���M��w�����͓��g�D��ɐ旧����28���ߌ�A���{�L�҃N���u�ŋL�҉�����B���̒��Ō��ݓ����s�ɔ��߂���Ă���ً}���Ԑ錾�ɂ��āu���ʂ͌���I�v�ȂǂƎw�E���A(�����g���H���~�߂邽�߂ɂ�)����܂ł̐錾���e�Ƃ͈قȂ鉽�炩�̋����K�v�Ƃ̔F�����������B
�ړc�����͂܂��A���N�`���ڎ헦��60�����x�œ��ł��ɂȂ�C�X���G����č��̃f�[�^�������A���{�����l�̌X���ɂȂ�\�����w�E���Đڎ헦���オ�ۑ�ł���A�ȂǂƏq�ׂ��B���̂ق��A���N�`���ڎ��̓f���^���ɑ��Ă������͌��ʂ�����������̂̊m���ɒ��a�R�̂��ł���f�[�^�������Đڎ�̏d�v�����������Ă���B
���u���̂܂܂����ΏT��1000�l���v�����ҋ}���̐V�����@7/30
�V�������ł��������}�g�債�Ă���V�^�R���i�E�C���X�B���߂̊������ӂ܂��A�������ی����̏��{�����������V�����̏ɂ���29������܂����B
�����̊����ɂ��ẮA���O����̐l���ȂǂŊg�債�A��̐l�o�͌��Ǝ��́u�x��v���ߑO�ƕω����Ȃ��Ƃ����܂��B�T���Ƃ̊����҂̑��������݂�ƒ���2�T�ԂŁA1�D5�{���x�ɑ����Ă��邱�Ƃ���A�������̂܂ܑ����Ă����Ɖ��肷��ƁA8���ŏI�T�ɂ�1�T�Ԃ̊����Ґ���1000�l���x�ɂȂ�̂ł͂Ɛ��v�����Ƃ������Ƃł��B
�����̕a�����p���́A�u�x��v���ߎ���2�{���x�ɂȂ��Ă��āA�����ǂ�3����1�ȉ��Ƃ����܂��B7��28�����_�̕a�����p���́A22�D3��(���@����124���^555��)�A�d�ǎ҂�2�l�ł��B
����҂̃��N�`���ڎ킪�i��ł��Ă�����̂́A���̂܂ܑ����Ă����ƒ����ǂ������Ă���Ɨ\�z����邽�߁A8�����{�ɂ͕a�����Ђ������Ă���\��������A���̂܂܂̃y�[�X��1���������Ă���Ƃ�����A��Ë@�ւ͊�@�I���Ƃ����܂��B
�����҂̔N��ʂł�60��A70��̍���҂����Ȃ��Ȃ��Ă������ŁA20�オ�����Ȃ��Ă��܂��B
�n��ʂ̊����Ґ��́A�V���s�ɑ������Ă��Ē��߂̊����Ґ��̂��悻�������V���s�ł��B30��ȉ��̔����ȏ�͊����̔��[�����O�R���ł��B
���ɂ��ƃ��N�`���ڎ�̎��т�1��ڂ�ڎ킵��12�Έȏ�̐l�͌����̖�4���ɂȂ������߁A�ڎ�������ł���悤���g��ł���Ƃ������Ƃł��B
���Ƀ��N�`���ڎ�����ė~�����͔̂얞�̐l�A�D��ڎ�̑Ώۂɂ��Ȃ��Ă���a�l�h30�ȏ�̐l�A���A�a�A�a�l�h�̐��l���傫���l�͐ڎ����т����Ă���B�얞�̐l���d�lj����₷���X���͌����ł��݂��Ă��āA�̒��̎��b�̍זE�������Ă���Ɣx����������₷���Ȃ�ȂǂƁA�x�����i�ނƃ��X�N�����܂�Ƃ����܂��B
���݉�����ĔM������ꍇ�́A������f�����Ăق����Ƃ�т����Ă��܂��B
�ψكE�C���X�́A18�Έȉ��ł��M���o�邽�߁A���ׂ��Ǝv���Ă�����V�^�R���i�������Ƃ����Ⴊ�悭����Ƃ����܂��B
�q�ǂ������l�֊�������P�[�X�������Ă���̂ŁA�q�ǂ������M������A��f�����Ăق����B�܂������͂̋����f���^���́A�ڂ��Ă������Ԃ��Z���Ă��������郊�X�N���������߁A�x�����Ăق����Ƃ����܂��B
����30���ߌ�A���{����c���J���܂��B
���_�ސ�A��ʁA��t�A���ւ̐錾���ߌ���@�����A����������� �@7/30
���{��30���[�A�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷���ʁA��t�A�_�ސ�A���4�{���ւً̋}���Ԑ錾���߂����肷��B�������8��2������ŁA�����͓�31���B�����s�Ɖ��ꌧ�̊�������31���܂ʼn�������B���`�̎�30���ߌ�7������L�҉���J���B�����ܗւ̊J�Ò��ɐ錾�̑Ώےn�����Ԃ��g�傷��ٗ�̎��ԁB���߂ւ̎葱���␛�̉�Ȃǂ�B
��17:15�@4�{���ւً̋}���Ԑ錾������
�����V�^�R���i�E�C���X���{���ŁA8��2������_�ސ�A��ʁA��t��3���Ƒ��{�ւً̋}���Ԑ錾���߂�\�������B�����s�Ɖ��ꌧ�ɏo�Ă���錾�͉�������B�������8��31���܂ŁB
��16:45�@�s���̊����Ґ�3300�l
�����s�͂��̓��̐V�K�����Ґ���3300�l�������Ɣ��\�����B3���A����3000�l��ƂȂ�A�����g��Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B
��15:00�@���r�m���@��M�u��������Ή��v
���Ƃ���ܗւ��l�������������ɂȂ��Ă���Ƃ̌��O���o�Ă��邱�Ƃɂ��āA�����s�̏��r�S���q�m���͌ܗւ̃e���r�̎�������20�����Ă���Ƃ��āu�I�����s�b�N�͂��������Ӗ��ŃX�e�C�z�[���Ɉ���Ă��邵�A�܂����ꂪ�I��ւ̐����ɂ��Ȃ����Ă���Ǝv���v�Ƌ��������B�܂������̐V�K�����Ґ���3���A���ʼnߋ��ő����X�V���钆�A���r�S���q�m���������Ґ��̔��\�O�ɓs������ޒ����Ă��邱�Ƃɂ��āA�L�҂��u�������b�Z�[�W�M����K�v���Ȃ������̂��v�Ǝ���B���r�m���́u���͓K�X�K�ɁA���̃^�C�~���O�ŁA���傤����������Ă��`�������Ă���B��������ƑΉ����Ă���v�Ɠ������B
��14:50�@��}�c���u�c�C�b�^�[�̔��M���ܗւ����v�Ɣᔻ
�Q�@�c�@�^�c�ψ���ł́A���Y�}�̎R�Y���A�̊�@�ӎ��̌��@������A�̍ŋ߂̃c�C�b�^�[�ɂ��Č��y�B�u23�����獡���܂�30��̃c�C�[�g�̂���20�ܗ֊W�A�������قƂ�ǂ����_���l���̂��j���A����������_���������B�����g��ɂ��ĂԂ₫�����Ȃ��̂͗�������v�Ɣᔻ�����B�������̓c�C�b�^�[�ɂ��Ă͒��ڐG�ꂸ�A�u�L�҉�ŁA���������g�����g�̌��t�ō����ɂ�������Ăъ|���Ă��炢�����v�Əd�˂ċ��߂��B
��14:35�@���r�m���A�����̈��S���S�u�m�ۂɓw�߂Ă���v
���r�S���q�m���͋L�҉�ŁA�V�K�����Ґ��̉ߋ��ő��X�V�����������̏ɂ��āA�u���S���S�͊m�ۂł��Ă���Ƃ��������ꂩ�v�Ɩ���A�u���̊m�ۂɓw�߂Ă���Ƃ���ł���܂��v�Ɠ������B�����A�L�҂Ɂu�����͈��S���S�ȏƌ�����̂��v�Ɩ��ꂽ�ۂɂ́A�u������v�Ƃ��u�����Ȃ��v�Ƃ��������A�V�^�R���i�p�̕a����h���×{�{�݂̊g�[�A����×{���x����̐��̋����̓s�̓w�͂ɐG�ꂽ��ŕψي��u�f���^���v�̊����͂̋����������B�u�s���݂̂Ȃ��܂̋��͂����������A�����s�Ƃ��Ă̈��S���S������Ă����v�Ɠ������B�L�҂��m���̔F�����m�F�������ƁA�u�w�߂Ă���Ƃ���v�Əq�ׂ��B
��14:30�@�����S�����u�����Ȃ�̕\���Ŋ�@�����L�v
�O�@�ɑ����J���ꂽ�Q�@�c���^�c�ψ���ł́A��������}�̋g�썹�D�����u�̊�@���v�����������B�����N���S�����Ɂu�S���ŐV�K�����҂�1���l�����@�I�ɂȂ��Ă������͍���ɏo�Ȃ��Ȃ��B�Љ�Ɋ�@�������L����Ă��Ȃ��v���̂ЂƂƂ��āA�������g�������ɑ��ă��b�Z�[�W�𐳖ʂ���`���Ă��Ȃ����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����v�ƒNjy�����B�������́u������a������@�I�ł��邱�Ƃ����������Ȍ`�œ`���A���L���Ă���v�Ɛ����B�u�����Ȃ�̕\�����@�ł͂��邪�A��@�������L���\�����Ă���Ǝv���v�Ɣ��_���A�u�{���̋L�҉�ł��A�����̌��t�ō��̏���������ƍ����݂̂Ȃ���ɂ�т����Ă��炢�����v�Əq�ׂ��B
��13:00�@�����S�����u�ܗւō��g���O�o�v�Ɋ�@��
�O�@�c�@�^�c�ψ���n�܂����B�����N���S�����͓����ܗւ̉e���ɂ��āu�I�����s�b�N������Ŋϐ킵�Ă��������āA20���ȍ~�A�l���͌����Ă��Ă���v�Ƃ�����ŁA�u���{�l�I��̊����A�I�����s�b�N�Ȃ�ł͂̊����A�������v���͎����Ă��܂����A���̂܂܂̍��g�������o�ŊO�o���Ă��܂��ƁA�����͂̋����f���^���͂�����Ƃ������Ŋ������L���Ă��܂��v�Əq�ׁA�����h�~�ɂ�����ܗւ̈��e���ւ̊�@�����������B��������}�̌����ꔎ���Ɂu�ܗւ̓P�ސ헪�A�P�ރ��C���͂��������B�����̖��ƕ�炵��q���Ɏg��Ȃ��łق����v�Ɩ���āA���ق����B
���u�~���Ȃ��Ȃ�v�u��J�s�[�N�v��Ì���͕��O�@����R���i�}�g��@7/30
�V�^�R���i�E�C���X�̋}���Ȋ����g���29���̐V�K�����҂͉ߋ��ő����X�V���A���@���҂�434�l�ɏ��B�J��Ԃ�����Ñ̐��̊�@�ɁA���Âɓ����鉫�ꌧ����Ë@�ւ́u���҂��~�������Ă��~���Ȃ��ɂȂ�B���ق��Ăق����v�ƁA����܂łɂȂ���@�����点��B
�R���i�̌y�ǁE�����NJ��҂̎��Âɓ�����k���鑺�̒������F��a�@�B�����g��ŁA�~�}�Ԃʼn^��Ă��銳�҂��ʊ��҂��A�M������ꍇ�͂��ׂĊ������^��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƂȂ����B�ȑO�̐f�Â���Ԃ⎞�Ԃ��������A��ɋْ������Y���B
�d�NJ��҂̏ꍇ�́A�Ή��ł����Ë@�ւɑ����Ă��邪�A�S���҂́u����]�@�悪�����ɂȂ�ƁA�����őΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��\��������B�l�H�ċz���l�H�S�x���uECMO(�G�N��)�͂����Ă��A�o����ςl�łȂ���ΑΉ��͓���v�Ƙb�����B
���Âɓ��������A�����Ґ��̋}���ł���Ȃ�a���m�ۂ�N�`���ڎ�ȂǑ����̈˗����������ށB�u����ɂǂ�ǂS�������A���_�I�E���̓I�ɂ���J�̓s�[�N�ł͂Ȃ����B�悪�����Ȃ��B�肪��炸���҂��~���Ȃ��Ȃ�����Ɏn�܂��Ă���B������l��l���^���ɍl���Ă��炢�����v�Ɛ؎��ɑi�����B
�ߔe�s���a�@��5�����{�����ʐf�Â��ꕔ�������A�R���i���҂̎���a�����g�債���B��������݂̕a�������p��������j���B�\���p�̉����◈�@���T���Ă��炤���������A�S���҂́u��ʂ̎��Â�S�����Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B��ʐf�Â̐������������Ă���A�T�d�ɑΉ�����K�v������B���ʂ͊m�ۂ��Ă���a���Ő��ڂ�����v�ƌ�����B
��7�s�̈��H�X�Ɏ��Z�v���@�Ȗ،��A�V�^�R���i�����ҋ}���@7/30
�V�^�R���i�E�C���X�����҂̋}�����A����29���A���{����c���J���A�x���x���x�����u�X�e�[�W3(�܂h�~���d�_�[�u)�v�ֈ����グ�A�����g�傪�[���ȉF�s�{�A�����A�ȖA����A�����A���R�A�^����7�s�̈��H�X�ɑ��A�ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k��v�����邱�Ƃ����߂��B���Ԃ�8��2���`22���ŁA�v���ɉ�������H�X�ɂ͋��͋����x������B�����ɑ��Ă͕s�v�s�}�̊O�o��s���{�����܂����ړ��̎��l�Ȃǂ����߂�B
29���̌����̐V�K�����Ґ���142�l�ƂȂ�A3���A����100�l�����B�v�����Ґ���8034�l�ŁA7��l����6��30�������1�J���Ő�l�ȏ㑝���������ƂɂȂ�B�����g��́u��5�g�v�Ɏ��~�߂������炸�A���c�x��(�ӂ����Ƃ݂���)�m���͉�c��̉�Łu�N���N�n�̑�3�g�ȏ�̏v�Ɗ�@���������A����̗v���ɂ��āu(�����͂̋���)�f���^���ւ̒u������肪�}���ɐi�݁A��Ë@�ււ̕��ׂ����܂��Ă��邱�Ƃ܂��Č��f�����v�Ɨ��������߂��B
���Z�v���ł͉c�Ǝ��Ԃ͌ߑO5���`�ߌ�8���A��ނ̒͌ߑO11���`�ߌ�7���Ƃ���悤���߂�B7�s�͒��߂̐l��10���l�������1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���15�l�ȏ�ł��邱�ƂȂǂ���ΏۂƂȂ����B
���͋��̎x���z�́A������Ƃ�1��������̔���グ�ɉ�����52��5��~�`157��5��~�A���Ƃ�420���~�ȓ��B�\���̎�t���Ԃ�12������9��30���B
���c�m���́A����̑�Ŋ����҂�}�����Ȃ��ꍇ�A���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p��v������Ƃ�����Łu�����Ȃ����ȏ�̐�����v��������Ȃ��Ȃ�B�����̑�����j�~���邽�߂ɁA�����͂����肢����v�Ƒi�����B
�����C3���V�^�R���i30�������Ґ��@���m229�l�@��34�l�@�O�d33�l�@7/30
���C3����30���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��́A���킹��296�l�ł����B�@�@
���m����229�l�ŁA���̂������É��s��95�l�A����s��6�l�A��{�s��9�l�A�L�c�s��11�l�A�L���s��10�l�ŁA���̂ق���98�l�ł����B���m����3���A���A200�l���Ă��܂��B
����34�l�ŁA2���Ԃ��30�l���܂����B
�O�d����33�l�ŁA3���A��30�l���Ă��܂��B
�������s �V�^�R���i 2�l���S 3300�l�����m�F 3���A����3000�l�� �@7/30
�����s��30���A�s���ŐV����3300�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B3���A����3000�l�����ق��A7���ԕ��ς̑������29�����㏸����180�����A����܂łɂȂ��X�s�[�h�Ŋ������g�債�Ă��܂��B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ2�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s��30���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł̒j�����킹��3300�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B29����3865�l�Ɏ����ʼnߋ�2�Ԗڂɑ����A1���̊����m�F��3000�l����̂�3���A���ł��B�܂��A1�T�ԑO�̋��j�����1941�l�����܂����B30���܂ł�7���ԕ��ς́A2500�l����2501.4�l�ŁA�O�̏T����̑������29����肳��ɏ㏸���A180.5���ƂȂ�A����܂łɂȂ��X�s�[�h�Ŋ������g�債�Ă��܂��B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A21���l���āA21��3910�l�ƂȂ�܂����B����A�s�̊�ŏW�v����30�����_�̏d�ǂ̊��҂́A29�����7�l������88�l�ł����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ80��̒j��2�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2290�l�ɂȂ�܂����B
�����s�̏��r�m���͋L�҉�ŁA�s���̊����m�F���A���A�ߋ��ő����X�V���Ă��邱�Ƃɂ��āu�ɂ߂Đؔ�������Ԃ��v�Ƃ����F���������������ŁA�אڂ���3���ɋً}���Ԑ錾���o����邱�Ƃ܂��u�s�⌧�̋����z����ړ���A�g���ĐT�ނ��ƂŌ��ʂ��o���Ă��������v�Əq�ׂ܂����B���̒��ŏ��r�m���́A�s���̊����m�F���A���A�ߋ��ő����X�V���Ă��邱�Ƃɂ��āu�ɂ߂Đؔ�������Ԃ��v�Əq�ׂ܂����B�����āu�傫�ȗv���̂ЂƂ��f���^�����B���Ƃɂ��Ί����͂͂���܂ł��2�{�߂������v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu���Ƃ���͔ɉ؊X�̑ؗ��l��������������K�v������Ƃ����w�E���������B��Ò̐��͑�ό��������A��3�g�Ƒ�4�g�ł͎����Ⴄ�Ƃ����w�E������A���̕ω��ɐv���ɑΉ����Ă������Ƃ��K�v���v�Əq�ׂ܂����B
����ɏ��r�m���́A�אڂ���3���ɋً}���Ԑ錾���o����邱�Ƃ܂��u�s�⌧�̋����z����ړ���A�g���ĐT�ނ��ƂŌ��ʂ��o���Ă��������B��{�I�ɂ̓X�e�C�z�[���ł��肢�������v�Əq�ׁA1�s3���ő����݂����낦�ċ��͂��Ăт����Ċ�����}�����݂����Ƃ����l���������܂����B
�����r�m�� �u���͂�������Ή��v �R���i�����A3���A���ő������\�O�ɑޒ� �@7/30
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���3���A���ʼnߋ��ő����X�V���钆�A���r�S���q�m���͊����Ґ��̔��\�O�ɓs������ޒ����Ă���B30���̋L�҉�ł́A�L�҂��u�������b�Z�[�W�M����K�v���Ȃ������̂��v�Ǝ���B���r�m���́u���͓K�X�K�ɁA���̃^�C�~���O�ŁA���傤����������Ă��`�������Ă���B��������ƑΉ����Ă���v�Ɠ������B
���r�m���͓s���ւ̓�������ޒ����ɕw�̎�ނɑΉ����Ă���B�����A1���ȗ��̉ߋ��ő��ƂȂ�V�K�����Ґ�2848�l�����\���ꂽ����27���́A���\��1����40���قǑO�ɕw�Ɂu���炵�܂��v�Ƃ��������|���đޒ��B��28���̑ޒ����́A���߂Ă�3000�l�����ƂȂ�3177�l�̔��\15���O�ɕw�̑O�Ɍ���A�u�����1�₾���v�ƒʍ��B�u�s�v�s�}�̊O�o���T���āv�ȂǂƏq�ׂ�ɂƂǂ܂�A��30�b�Ŏ�ޑΉ���ł������B
29���̑ޒ����͖�1��20�b�A�u�Ⴂ������v�Ǝv��Ȃ��悤�ɂ��āv�ȂǂƌĂъ|�������A��ނɉ������^�C�~���O�́A3���A���̍ő��X�V�ƂȂ�V�K�����Ґ���3865�l�����\������30���O�������B�����A���̓��́A�s�̃��j�^�����O��c�I����ɂ���37���ԁA��ނɉ����Ă����B
���V�K�����҂�9%�A���N�`���ڎ��Ɋ����@�����E�`�撲�ׁ@7/30
�����s�`��݂̂Ȃƕی�����6��16������7��21���ɓ͂��o�̂������V�^�R���i�E�C���X������1478�l�̂����A9%�ɂ�����131�l�����N�`���ڎ��̊����������Ƃ̒������ʂ��܂Ƃ߂��B���̂����A8����1��ڂ̐ڎ��Ɋ������Ă����B��́u�\���Ȋ����\�h���ʂ�ɂ�2��ڂ̐ڎ킩��2�T�Ԓ��x������B�}�X�N���p���w���ł�ӂ�Ȃ��łق����v�Ƃ��Ă���B
131�l�̐ڎ��̊����҂̂����A111�l(8%)��1��ڂ̐ڎ��A20�l(1%)��2��ڂ̐ڎ��̊����������B�N��ʂł�30�オ31�l�ƍł������A40���27�l�A20���24�l���������B�����o�H�����������P�[�X�ł́u1��ڂ̐E��ڎ��ɉ�H������Ј���Ƒ����������ڗ������v(�݂Ȃƕی����̏��{���㏊��)�B
1��̐ڎ킾���ň��S���Ă��܂��l������Ƃ݂āA�ی����͐ڎ��������\�h���K�v�Ȃ��Ƃ𒍈ӊ��N���郊�[�t���b�g���쐬���A�z�[���y�[�W�ɂ��f�ڂ����B���{�����́u���R�Ƀ_�E�����[�h���Đڎ��ɔz�z����ȂNJ��p���Ă��炦��v�Ƙb���Ă���B
������8��������2��5��l���̏Ռ����Z ����ł����͐S�����ɂ��炸�@7/30
�u�����I�v�Ƃ������t���s�b�^�����B29���A�s���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�����҂�3865�l�ƁA3���A���ʼnߋ��ő�����������X�V�B�S���ł�1��697�l���m�F���ꂽ�B1��1���l�����͏��߂āB���̊����}�g��ł��A���̃g�b�v�̓R���i�ȊO�œ��������ς��̂悤�Łc�c�B
���߂ēs�������҂�3000�l����28���A���@�ŋL�Ғc�Ɂu�ǂ��Ή����邩�v�Ɩ��ꂽ���͖����̂܂܃X���[�B��ދ��ۂ̗��R�����@���́u�{���͂�����������e���Ȃ��v�Ɛ��������Ƃ����B�u�������e�v���Ȃ���Ή����������Ȃ��̂��낤���B
�܂�Ő��͊��������ɂ����l�������A�ܗ��s�Łu�y�σo�C�A�X�v���L����A�����҂͍��コ��ɑ����Ă����Ƒ����̐��Ƃ��\�����Ă���B
�s���̐V�K�����҂̒���7���ԕ��ς́A29�����_�őO�T��1.61�{�ɋ}���B28���̌��J�ȁu�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�ɋ���̐��Y����������o���������ɂ��ƁA�O�T��1.7�{�ő����Ă������ꍇ�A8��26���ɂ͓s���̊����Ґ���2��5000�l����B1.4�{�ɗ}�����Ă�1���l�ȏ�ɒB����Ƃ����B
�����g��y�[�X�́g8����������h�̍ň��V�i���I�ɔ����Ă���̂ɁA���͏�̋�B���̒��͍��A�R���i����ܗւƒn���̑I���ł����ς����Ƃ����Ă���B
���n���E���l�s���I�̂��߂Ȃ���
����29���A���l�s���̐V���܂荞�ݍL���ƈꏏ�ɔz��ꂽ�^�E�����ɓo��B���l�s���I(8��8�������E22�����J�[)�ɏo�n���鏬���ؑO���ƌ����ψ����Ƃ̑Βk�ŁA�u��������̊o���S�ʓI�Ɏx�����܂��v�Ə��߂Ďx����N���ɂ����B�����ɘb�����Ƃ͂Ȃ��Ă��A�I���̂��߂Ȃ���ɂȂ�̂��B
�����؉ƂƐ��̔鏑�߂Ă������Ƃ̉��͐[���B�������A�����؎��̓J�W�m�U�v�����f���ďo�n�B���i�h�̐��́A�J�W�m�U�v��i�߂錻�E�̗юs�����x������Ƃ̉������������B
�u�x���������̏ł肪����̂ł��傤�B���G���̎s���I�ŕ��������C�ɋ��S�͂������A�}���Łg���~�낵�h���u�������˂Ȃ��B�юs��������������̕������Ă錩���݂�����Ɣ��f���A�S�ʎx����\�������悤�ł��B���S�̘a��⍲�����g���āA�n���[�l�R���ɏ����؎x���̈˗������Ă���B�����A�w������J�W�m���̏����͂��Ȃ��x�ƁA�юx���𑱂���\����������[�l�R������������B���Ă͐������̈ӌ��͒n���Ő�ł������A���̐_�ʗ͂ɉA�肪�����n�߂Ă��܂��v(�_�ސ쌧���W��)
�����߂��g���ăV���J���L
���߂Ő_�ސ�I�o�̍��w���[�������ɂ��A���̖���Ƃ��Ēn������点�Ă���悤�����A�������͖{���A���@�ƍ���̃p�C�v���B
�u�����g��ő�ςȎ��ɒn���I���ɂ��܂��Ă���ꍇ���I�v�ƁA�n��������}��������X�J�����B
�u���E�������A�n���I�œ���̌��ɂ����܂Ō����ꂷ��͈̂ٗ�ł��B�^�E�����ɂ��o�ꂵ�A������������ǂ��������Ȃ̂��B�������Ƃ��Ă��A�J�W�m�͂ǂ�����̂��A�����ӔC������܂��B�������������}�s�c�c�͎��哊�[�ƂȂ�A�����؈�{���ł܂Ƃ߂���Ȃ������_�ɂ��A���̗͂̐�����������B�R���i�����g��Ő_�ސ쌧�ɂ��ً}���Ԑ錾���o�����Ƃ����܂�A�錾���̑I���ɂȂ邱�Ƃ��t���ł��傤�v(�����W���[�i���X�g�E�p�J�_�ꎁ)
�u�n����Γ݂���v��n�ōs���W�J�ƂȂ肻�����B
���I�����s�b�N �I��3�l�܂�27�l���R���i���� 2���A���ő��X�V �@7/30
�����I�����s�b�N�ɏo�ꂷ�邽�ߊC�O���痈�������I��3�l���܂ށA���킹��27�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ�������܂����B���g�D�ψ��PCR�����ŗz��������������30�����\�������̂ŁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�g�D�ψ����30���A�C�O���痈�������I��3�l���V�^�R���i�E�C���X�̌����ŗz���������������Ɣ��\���܂����B���̂����A�A�����J�̗���I����܂�2�l�͑I�葺�ɑ؍݂��Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�I�葺�ɑ؍݂���C�O����̑��W��1�l�̂ق��A�I�葺�ȊO�̏ꏊ�ő؍݂��Ă�����W��3�l��A���{�ݏZ�̃{�����e�B�A4�l�̊������m�F����A�����ƊC�O���킹��27�l�̊��������炩�ɂȂ�܂����B�g�D�ψ�����\���n�߂�7��1���ȍ~�ł������Ȃ�A2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�����I�����s�b�N�̑��g�D�ψ���́A�V�^�R���i�E�C���X��PCR�����ŗz���������������̊W�҂��A7��1�����甭�\���Ă��܂����A���8���ڂ�30���܂łɊ������m�F���ꂽ�̂́A�����ƊC�O���킹��220�l�ɏ���Ă��܂��B���̂����A�C�O���痈�������I���23�l�ŁA�o������ނ���l���������ł��܂��B�܂��A���{�ݏZ�̑I��̊�����30���܂łɊm�F����Ă��܂���B
���̂ق��A�g�D�ψ���̈ϑ��Ǝ҂�110�l�A���W�҂�65�l�A���f�B�A�W�҂�12�l�A�{�����e�B�A��6�l�A�g�D�ψ���̐E����4�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�@
���ܗ֑��֘A�̐V�^�R���i������2��������1��������ő��X�V�@7/30
�����ܗցE�p�������s�b�N�g�D�ψ����30���A���֘A�̊W�҂ŊC�O����̑I��3�l���܂߁A�V����27�l���V�^�R���i�E�C���X�����ŗz���ƂȂ������Ƃ\�����B����͑I��3�l�A���W��4�l�A�Ɩ��ϑ��X�^�b�t15�l�A���f�B�A�W��1�l�A�{�����e�B�A�W��4�l�B�I��2�l�Ƒ��W��1�l��3�l�������E���C�̑I�葺�ɑ؍݂��Ă����B
�g�D�ς����\���n�߂�7��1������̗z���҂́A�v225�l��200�l�ȏ���L�^�����B29����1���Ƃ��Ă͍ő���24�l�̊����҂��m�F���Ă������A2�������čő����X�V�����B28�����_�ő��֘A�̊C�O����̓����҂�3��9853�l�ɏ�����B
���R���i�z���̌ܗ֊W�҂����f�O�o�c�u�R���i����T���ɍs���Ă�v�@7/30
�����ܗւ̃{�[�g���Z�̐R���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������h���×{�{�݂ɑ؍݂��Ă���2�l�����f�O�o���Ă������Ƃ�30���A�e���r�����ɂ���ĕ��A�g�䂪�L�����Ă���B
29���ɂ́A�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���3865�l�ŁA�ߋ��ő����X�V�B�l�X�̕s�������܂�Ȃ��A�l�b�g��ł́u�z���̌ܗR����2�l�v�u���f�O�o�v���c�C�b�^�[�g�����h���肵���c�������Ă���B
�l�b�g��ł́u�o�u���ǂ��낶��Ȃ��ˁB�ܗ֊W�̗z���҂܂ŕ\������Ă��v�u�z���̌ܗR����2�l�����f�O�o�Ƃ��K�o�K�o�������v�u�R��������ȃ��[�������Ȃ��łǂ�����́v�u�J���������ӂ�����Ȃ��v�u�z���Ŗ��f�O�o�Ƃ��@�R���i����T���ɍs���Ă�݂����Ȃ�����v�Ȃǂ̐����オ���Ă���B
��9�l���S �ߋ��ő�1��744�l�����m�F�@7/30
30���́A����܂łɑS����1��744�l�̊��������\����Ă��āA1���̔��\�Ƃ��ẮA����܂łōł������Ȃ�܂����B�܂��A��t����2�l�A�����s��2�l�A�Ȗ،���1�l�A���ꌧ��1�l�A�ΐ쌧��1�l�A�_�ސ쌧��1�l�A�É�����1�l�̍��킹��9�l�̎��S�̔��\������܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A��`�̌��u�Ȃǂ��܂�91��4065�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��91��4777�l�ƂȂ��Ă��܂��B�S���Ȃ����l�́A�����Ŋ������m�F���ꂽ�l��1��5184�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��1��5197�l�ł��B
��`�Ȃǂ̌��u�ł̊����m�F��3482�l(16)�A��������̃`���[�^�[�@�ŋA�������l�ƁA���̐E���⌟�u���Ȃǂ̊����͍��킹��173�l�ł��B
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�l�ŁA�l�H�ċz���W�����Î��ȂǂŎ��Â���Ȃǂ��Ă���d�ǎ҂́A30�����_��626�l(87)�ƂȂ��Ă��܂��B
����A�Ǐ��P���đމ@�����l�Ȃǂ́A30�����_�ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�l��83��1087�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����659�l�́A���킹��83��1746�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A28���ɂ͑���l�ŁA1����4��9892����PCR�����Ȃǂ��s���܂����B
[()����30���̐V���Ȋ����Ґ��ł��B]
�����Ắg�M���h�͂Ȃ��Ă��`���ϋq�̃I�����s�b�N���������l �@7/30
���O�Ɍ��܂������ϋq�J�ÁB�J��S���҂̑������X�L�����_���B1�N�̉������o�ē����I�����s�b�N�͈É_�Y�����Ŗ����J�����B���̌����_�𐁂�����悤�ȃA�X���[�g�����̖��i�ɂ���āA�I�����s�b�N�ւ̌����������͔��炢���悤�Ɍ�����B�������A�R���i�ЂŊJ�Â���Ă��鏉�߂ẴI�����s�b�N�́A���Ă̑��Ō������ƂȂ����i�̘A�����B�������Ċ�����]�V�Ȃ������I��A�����������{�ɗ��邱�Ƃ��炩�Ȃ�Ȃ��I�肽���B�����āA�����̂Ȃ����B�J������1�T�ԁA57�N�Ԃ�̃I�����s�b�N�Ŗڂɂ������̂́B
������ꂽ�劽��
�����̐��n ���{�����فB�ϋq�p�̎�t���ו��m�F���Ƃ��Đݒu���ꂽ�e���g�����l�̂܂ܕ���ł���B���O�ɖ��ϋq�����܂������ߓP�����鎞�Ԃ��Ȃ������Ƃ����B������ɓ��P�������������̎p���������B
�_������K�ꂽ�����u�_�����ǂ����Ă��������Ǝv���ă`�P�b�g��\������ł�����ł����ǁA������Ȃ�������ł��B���ǖ��ϋq�ɂȂ�܂��������߂ċ߂��ɗ��Ă݂悤�Ǝv���āv
�����͎₵�����ɏ������ƁA���Ɍ������āu�����[�v�Ə������Ԃ₢���B
�V�^�R���i�E�C���X�̊������g�傷�钆�A���ϋq�ł̊J�Â͂�ނ����Ȃ����f�������B�����A��邹�Ȃ��v����������l����������̂��낤�B�J����s��ꂽ�������Z��̎��ӂɂ́u���͋C�����������v�Ƒ����̐l���K�ꂽ�B
�������g���čs��ꂽ���]�ԋ��Z�ł����l�̌��i������ꂽ�B
����K��Ă����A1984�N���T���[���X�I�����s�b�N�̃��X�����O�����_���X�g�A�x�R�p������͊ϋq�̑��������Ă��ꂽ�B�u�����͖����̉��ŁA���̏�ɂ���l�ƈꏏ�Ɋ�т�����������L�ł������Ƃ���Ԃ̍��Y�ɂȂ����B������������オ��ɂ͌����邵�A�I��ɂƂ��Ă��c�O�Ȃ��Ƃ��v
���g�_���ȏꏊ��2�l�����h
���ϋq�̃I�����s�b�N�ŁA��ۓI�������V�[��������B
24���ɓ��{�I��̑�1���ƂȂ�����_�����l�������A�_���̍��������I��B7�����錈���̌������I����ƁA��т������ɂ���O�ɂ܂�����ɕ��݊��A����̎���f���Č��������������B
�����I��u���ϋq�̒��ŁA����̑��̉�����������A���̊��������т�܂����ˁB���_����������Ƃ����������Ȃ��A����Ƃ��Ă��āA���R�Ƃ��݂����������������Ƃ��ł��܂����B�_���ȏꏊ��2�l�����Ő킦���Ƃ������Ƃ��ւ�Ɏv���܂��v
�ϋq�̂��Ȃ��I�����s�b�N�����炱���A���炽�߂Ċ������X�|�[�c�}���V�b�v�B�ق��̋��Z�̉��ł��A�I���W�҂����X�Ɍ��ɂ����̂́u���J�Â��ꂽ���Ƃւ̊��ӂ̌��t�v���B�R���i�ɕ���ꂽ�Љ�ł́A�X�|�[�c���ł��邱�Ƃ́A���͂ⓖ����O�ł͂Ȃ��B
���g�b�v�I�� �s�݂̒���
�R���i�̉e���͑I�肪�����⌇���]�V�Ȃ������ȂNj��Z���̂��̂ւ��L�����Ă���B
26���܂ōs��ꂽ�ˌ��̏��q�X�L�[�g�B���E�����L���O1�ʁA�C�M���X�̃A���o�[�E�q���I��͓��{�Ɍ��������O�̍���20���ɐV�^�R���i�Ɋ����B������]�V�Ȃ����ꂽ�B
23�̃q���I��͎��g��SNS�Łu5�N�Ԃ̃g���[�j���O�Ə����̌�A���z�����������A���̐S�͕��X�ɂȂ����v�ƔߒɂȎv�����Â����B
�������A���������I�肪���Z�ɏo�ꂷ��A����Ȃ銴���g����������ꂪ���邽�߁A�^�c���̔��f�͊Ԉ���Ă��Ȃ��B�����A���ꂪ�R���i�Ђ̃I�����s�b�N�̌������B
�X�|�[�c���̋L�ҁu�ޏ��̌���͑傫�Ȗ��Ńi���o�[1�������A�ق��̑I��ɂ͊ȒP�ȏɂȂ����v
�������A����Ŏ�ނ��Ă����t�B�������h�̃e���r�ǂ̋L�҂͂������������B�u�ޏ��̌���͔߂������A���N���ĂΒN�����ꂵ�����Ƃ������Ƃ��N�����_������������̕����L���Ɏc�邾�낤�v
�V�^�R���i�ɂ�錇��͂ق��̋��Z�ɂ��L�����Ă���B
�S���t�j�q�ł͐��E�����L���O1�ʂł��Ƃ��̑S�ăI�[�v���𐧂����X�y�C���̃W�����E���[���I��Ȃǃg�b�v�I�肪�������Ō���B�e�j�X���q�ł��V���Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ�A�����J��17�A�R�[���E�K�E�t�I�肪���ꂵ���B
�I�肽���͓��{�ł̑؍ݒ��A�����������`���Â����A�z���������������ꍇ�A�I�肪���Z�ɕ��A�ł���悤�ɂȂ�ɂ͍ŒZ��7��������Ƒ��g�D�ψ���͐������Ă���B
�����������������ƂɑI�肪���Z�ɕ��A�����P�[�X������B22���̓��{�Ƃ̏�������ꂵ���T�b�J�[�j�q�̓�A�t���J�̑I��2�l��25���̃t�����X��ŕ��A�����B
�������A�������^�C�g�Ȍl���Z�ł́A��������Α���́u1���A�E�g�v���Ӗ�����̂����B
��������g�����s�\�h�̐���
���Ɍ������Ȃ��Ƃ���Ă����u���S���S�v�ɂ��^�O�����܂�Ă���B�W�҂����Ń}�X�N���O���Ă�����A�O�o���ĕ����ŐH�������Ă�����ƃ��[���ᔽ���A���A�m�F����Ă���̂��B
�_���̉��ł́A�A���A�C�O�I���R�[�`�����������l�q�Ń}�X�N���O���A�吺�ŋ��Ԏp���ڌ�����A����̃X�^�b�t���uWear a Mask�v�Ə��������������A���ӂ��ĉ���Ă���B
����ł��}�X�N���O���l�����͈���Ɍ���Ȃ��B
�ʂ̉������Z�̉��œ��������X�^�b�t�ɂ��ƁA���ӂ��J��Ԃ��Ă��f���ɕ����Ă����l����ł͂Ȃ��A����ꂽ�l���ł��ׂĂ̐l�̈ᔽ�������܂�͎̂����A�s�\���Ƃ����B����ɑI��ƊC�O���f�B�A�Ȃǂ̊W�҂��ڐG���邱�Ƃ���������A�g�o�u���h���������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B
���̏����X�^�b�t�u���ꂾ���̋K�͂̑��ŕ�����K���̈Ⴄ�l�����̍s�������S�ɔ�����邱�Ƃ͓���B�N���X�^�[���N����Ȃ��悤�A�S�͂�s��������ǁA���̏ő����n�߂Ă��܂����ȏ�A�������L�����Ă��܂��\���͂���Ǝv���܂��v
�������g�� ���Ɓu��@���̋��L���v
�V�^�R���i�̓s���̊����Ґ��͏��߂�1��3000�l���A�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��B���Z���ł̊�����ɏڂ������Ƃ́A�u���͂�I�肪�������Ă����@�ł��Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��v�ƌx����炷�B
�l���a�@���u����őI����܂߂����W��1�l1�l�����O�ꂷ��ق��Ȃ��B�����͊�@�I�ɂ��钆�ŃI�����s�b�N������Ă���Ƃ������Ƃ�I��ɗ������Ă��炢�A���[���̏�������߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v
���g�Ӌ`�̂������N�h
���ĂȂ����ŊJ�Â���Ă���I�����s�b�N�ŁA�V���ȈӋ`�������������Ƃ���������A����N�ɂ����ڂ��W�܂��Ă���B
�̑����q�̗\�I�ɓo�ꂵ���h�C�c�`�[���̓��I�^�[�h�ł͂Ȃ��A�S�g���{�f�B�X�[�c�𒅗p�����B�����A�X���[�g�̓��B��Q��A���I�ȖړI�ʼn摜���g�U����邱�Ƃ֍R�c�����`���B
�h�C�c�̑̑������SNS�Łu�̑��̐��I�Ȗ��ɂ��ď��q�A�X���[�g���s���ɂȂ邱�ƂȂ����������������߁v�Ɣ��M�B�u���̓��ɉ��𒅂������Ō��߂�v�Ƃ����I��ɑI���������邱�Ƃ���������Ƃ����l���ŁA�����A�X���[�g�̃��j�t�H�[���̂�������l���邫�������ƂȂ����B
������IOC�����ۃI�����s�b�N�ψ���́A�I�����s�b�N���͂̋K����ꕔ�ɘa���A���Z�̑O��ɑI�肪�l�퍷�ʂȂǂւ̍R�c�̈ӎv���������Ƃ�F�߂��B
�I�����s�b�N�ł́A����܂ł��������R�c�͂��������F�߂��Ă��Ȃ��������A���N�A���E���ő傫���L�������u�u���b�N�E���C�u�Y�E�}�^�[�v�^�����@�ɏ����t���ł͂��邪�A���߂ă��[�����ύX���ꂽ�B
�T�b�J�[���q�ł͂��������A�I�肽�����������Ńs�b�`�ɕЂЂ������čR�c�B�C�M���X�`�[���̊ḗu�Ђ������s�ׂ́A�Љ�̕s���`�A�s�����ɑ��镽�a�I�ȍR�c�̏ے����v�Ƙb�����B
�����āA8��2���ɂ̓E�G�C�g���t�e�B���O���q��87�L������N���X�Ƀj���[�W�[�����h��43�ŁA�g�����X�W�F���_�[�̃��[�����E�n�o�[�h�I�肪�o�ꂷ��BIOC�͏������N���A����Ώ����ɐ��ʂ�ύX�����I��̏o���F�߂Ă��邪�A���ۂɂ��̏������N���A���āA�g�����X�W�F���_�[�̑I�肪�I�����s�b�N�ɏo�ꂷ��̂͏��߂Ă��B
�������A�u�����w�I�ȗD�ʐ��͕ς��Ȃ��v�Ƃ������������ᔻ�����܂Ƃ��B�I��̐����F�̖��́A�Љ�S�̂ł̋c�_���s���ŁA���ꂩ��̃X�|�[�c�E�������Ă͒ʂ�Ȃ����ł�����B
���̓�����̍ŏ��̈�����A���̓����I�����s�b�N�ɂȂ�B
���ٗႸ���߂̑����炱��
�܂��Ȃ��܂�Ԃ����}���铌���I�����s�b�N�B�ϋq�̕s�݁A�L�͑I��̊����A������̂ق���сB�����̊����g��Ɏ��~�߂͂����炸���������𑝂����ŁA�Ō�܂ő��蔲�����Ƃ��ł���̂��A�\�f�������Ȃ��B
���̒��ł��A�S�͂�s�����A�X���[�g���������P����A���ӂ̋C�����A�����đ������������p���́A�������ɑ�Ȃ��̂��v���o�����Ă��ꂽ�B
�ٗႸ���߂̑����炱���A���ĂȂ������������Ă���̂ł͂Ȃ����B�����������u�I�����s�b�N�̉��l�v��T�����������B
�@
���R���i�Ђɂ��������ꂩ�猩����u���̍��̖����v�@7/30
�R���i�ЂɌ}����2�x�ڂ̉āB����ɂ́A�����̉Ă̓��킢�͂Ȃ��B����s�����ނ𑱂���m���t�B�N�V�������C�^�[����������ɂ́A���̍��̂��ꂩ�炪�Ïk����Ă����[�B
7��29���A�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ��́A������3865�l�A�����392�l�Ɖߋ��ő����L�^�����B�l����Ŋ��Z����ƁA����́u392�l�v�͓����ł́u3750�l�v�ɓ������B���ꌧ�̏͋ɂ߂Đ[�����B����́A���{�̖���ɂ���āA�g�傷��R���i�Ђ̔�Q�ɑ��������Ă����B
��5�����炸���Ƌx�Ƃ��Ă���
������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����o���ꂽ7��12���A����ł�5��23���ȗ��ً̋}���Ԑ錾������ɉ������ꂽ�B�ܗ֊J�����ɉ���́u�ً}���ԁv�͊�2�����o�߂��Ă����̂��B2�����Ԃ����Ɓu�ً}���Ԑ錾���v�ɂ����Čo�ϊ������~�߂��Ă������ꌧ���B�u����Ȃ̂Ɂv�����͍Ċg�債���B�ό�����ȎY�Ƃł��鉫��ɂƂ��āA���̉ċx�݊��Ԃ̃_���[�W�͌v��m��Ȃ��B
�ߔe�s���ŋ��������o�c����j���́A�s������̋��͗v�����A�ٗp�����������Ȃǂ����p���ď]�ƈ��ɋ������Ȃ���A5�����炸���ƗՎ��x�Ƃ𑱂��Ă���B
�u���炩�ɃI�����s�b�N�ɍ��킹���ً}���Ԑ錾�����ł���ˁB����̈�Ì������邽�߂ɂ͎d�����Ȃ����Ƃ��ȁA�Ǝv���܂����ǁA���������X���J�����Ȃ��̂́A��͂�ꂵ���ł��B�ł��ˁA�E�`�Ȃ܂��悢�ق��ł��B�����̎�������ȂA�Ȃ�̕⏞���Ȃ��撣���Ă܂��B���������Ƃ���ɂ��蓖�Ă��K�v����Ȃ��ł��傤���v
�Ƃ��낪���{�́A�ꂵ��ł���l�����ɑ��āA�^�t�̂��Ƃ����B�����N���R���i���S����b�́A��ނ����҂ɂ��Ĉ��H�X���u�����v���悤�Ƃ��������́A���H�ƊE�ɂƂ��Ă͖Y����Ȃ��u�\���v���낤�B���ꌧ�����́A���c�Ƃ̈��H�X���o�c����j���͂��������B
�u����̏ꍇ�A��ԕK�v�Ȃ̂́A���O���痈���邨�q����́A�o���n�̋�`�ł�PCR����(�n�q�O����)�̂͂��ł��B�ł����ꂪ����1�N�������ԁA�S�R�ł��Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�דc(���V)�����[�����̔����ȂA�Ђǂ������ł���ˁB�ʏ�f�j�[�m�����㋞���āA�n�q�O�����ɐ��{�̎x�����ق����Ɛ��{�E�^�}�̊W�҂ɒ��i�����Ƃ��A�܂�Ńo�J�ɂ����ԓ������܂����B����́A���ꌧ���S�̂ɑ��錾�t���Ɗ����܂����v
5��19���u���ɗ���Ȃ�āA����炵���Ȃ��v�דc���V�����[�����́A���������������B����ł̊����g����u�o�J����Ȃ����v�Ƃ܂Ō������̂��B
���{�́A�悤�₭�`����́u�x����v���n�߂��B���ۑ�̊�{�u�o���n�����v(����y�іk�C���ւ̓n�q�O��PCR�܂��͍R������)���A8��31���܂ł̉ċx�݊��Ԍ���ŁA��]�҂������Ŏ���悤�ɂ����̂��B������������A�H�c�A���c�A�ɒO�A��A������5��`�̂݁B����ւ̒��s�ւ́A���ɂ������ȋ�`������ł���B��͏\���Ƃ͌�����B���e���ȁu���ۑ�v�ł���������ꂽ�̂ł́A�����ł������{�̗��s�s�Ȑ���ɋꂵ�߂��Ă������ꌧ���͂��܂������̂ł͂Ȃ��B
���ČR��n�̊�������������鉫��
����ɁA�דc�����̒��Ŋʼn߂ł��Ȃ�����������B�����̏I�Ղɏo�Ă���u(�V�^�R���i�E�C���X��)���s�҂������ė���Ɍ��܂��Ă����B�ČR�������ė���킯�ł��Ȃ����낤���v�Ƃ����u�����v���B��������Ƃ��A�����̉��ꌧ�����{����o�������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
����̊����Ō��߂����Ă͂Ȃ�Ȃ����ȑ��݂��A�܂��ɕČR��n�Ȃ̂��B�݉���ČR�W�҂Ɋ������}�����Ă��邱�Ƃ͂��˂Ă��w�E����Ă���B(�u�ČR�Ńf���^�����s���v���ꌧ������ – �����V��f�W�^��)
������������̉Î�[��R��n�Ⓦ���̉��c��n�Ȃǂɂ́A��ɑ����̕ČR�W�҂��~�藧���A���{�̌��u�ƊW�Ȃ��A��n�̃t�F���X�̊O�Ɏ��R�ɏo�Ă����B���̂��Ƃ́A���{�����@������ʂɈʒu����Ɣ��������Ēn�ʋ���ŋ�����Ă���B�܂�A�ČR�W�̊����҂��t�F���X�̊O�ɏo���Ƃ��Ă��A�ǂ�ȍs�����Ƃ����̂��A���ꌧ���Ƃǂ��ŐڐG�����̂��Ƃ������_���܂߁A����u���b�N�{�b�N�X�Ȃ̂��B
����̐V�K�����҂�354�l�ɂȂ���27���ɂ́A���̐����Ƃ́u�ʂɁv�ČR�W�̐V�K�����҂�19�l�����������Ƃ����\����Ă���B����ɒ�������ĕ��E�R���y�щƑ��̐��m�Ȑl���͔��\����Ă��Ȃ��B���A���悻5�`6���l�Ɛ��肳���B����6���l�Ƃ��Đl���䊷�Z������ƁA�݉��ČR�W�́u19�l�v�́A�����́u4420�l�v�ɓ������A���낵�������Ґ��ł���B
��N7���̓Ɨ��L�O���A���ꒆ���ŕČR�W�҂����Ղ葛�������ăN���X�^�[�����������B������A�R�W�҂��t�F���X�O�łǂ�ȍs�����������܂������s���ȏ��������Ǝv���ƁA�����̊����s���͕����肾�B
���{���{���A���̉���̏�m��ʂ͂��͂Ȃ��B���̂����ŁA��яo�����דc�����[�����̖\���́u���ꍷ�ʁv�u���ꂢ���߁v�Ƃ����v���Ȃ��B
�u���̐��̒n�����W�߂��v�ƌ`�e�����n���̉����B���̒��ォ��27�N�ԑ������l�����W���̂��̂̕ČR��������B�����ĕ��A����A�L��ȓy�n��ČR����L�������A���O�@���̗��s�s�ȏ�Ԃɒu���ꑱ���Ă���B
�q�ǂ��̕n�����ЂƂ��Ƃ��Ă��A�����E�ČR�������ォ��n�����̉���Ȃ�ł̖͂�肪����B�܂�A�S���ꗥ�̎�@�ł͂Ȃ��A����ɑ��ẮA�Ǝ��̒��J�Ȏ蓖�̂�������͍������ׂ��Ȃ̂ɁA���݂̐��{�E�^�}�W�҂ɂ́A����̗��j�ƌ�����������Ŗ{�C�Ŗ�������}�낤�Ƃ���^�����������Ă���B
�ČR��n�̑��݂���Ɂu���Ёv�ł��葱���Ă��鉫��́A���݂̊�Y�Ƃ́u�ό��v���B���H�Ƃ݂̂Ȃ炸�A�_�C�r���O�V���b�v�Ȃǂ̃}�����T�[�r�X�A�z�e���A�^�N�V�[���ό��Y�Ƃł́A3�������ً̋}���Ԑ錾���Ŗ����ȕ⏞���Ȃ��b���ł���B
����k���̃^�N�V�[�^�]�m�͂����Q���B
�u��Ђɂ́A�s�����瑽���̎x��������݂����ł����ǁA�^�]��͏o�Γ������炳��Ă邾���ł��B�킽���Ȃo���Ȃ��Ǝ����̓[���̌_��ł�����A���̎d����T�����Ƃ��l���Ă܂���v
�ߔe�s���̈��H�X�o�c�҂́A�����b���Ă����B
�u�����ł͎��Z���͋����Ȃ��Ȃ��x�����Ȃ��ċꂵ���Ƃ����b�������܂����A����ł͍s���̐l�����͊撣���Ă�Ǝv���܂��B�E�`������łȂ�Ƃ��H���Ȃ��ł��܂��B�������A�_�C�r���O�T�[�r�X�̌o�c�҂Ȃ܂������⏞���Ȃ��̂ɁA���q�������Ă���킯�ł��B���������l�ւ̎蓖�Ă𐭕{���Ȃ�Ƃ����Ă���A�ƌ��������ł��v
���푈�ƕ��a�ɂ��Ċw�ԏ����@��
����ɂ́A�푈�ƕ��a�ɂ��Ă̊w�т̏�Ƃ��ċM�d�Ȏ����ق���p�ق����������邪�A�ǂ������n�ɗ�������Ă���B�����s�́u�Ђ߂�蕽�a�F�O�����فv��A�ߔe�s�́u�s���فv�ł́A�`�����e�B�[���C�u�����Ċ�t����������A�N���E�h�t�@���f�B���O�Ŏx������A�Ƌꋫ�����z���Ă����B�ۖ؈ʗ��E�r�v�Ȃ́u�����̐}�v�V���[�Y�Ȃǂ������W�����Ă��邱�ƂŒm����X��p�s�́u���������p�فv�W�҂́A���������������Ă���B
�u�R���i�ЂŁA�C�w���s�̃L�����Z�����������܂����B���ꗿ�������������A�傫�ȃ_���[�W���Ă܂��B�ق�ƂɃM���M���̂Ƃ���܂ŗ��Ă��܂��B���낻��E�`���N���t�@�����l���Ȃ��Ƃ����Ȃ���������܂���v
�R���i�Ђŋꂵ���̂́A������ꂾ���ł͂Ȃ��B���A�ČR��n�̖�7�����u�����������Ă���v���̒n�̕s���́A�����Ƃ͈قȂ��Ă���B�Ǝ��̊�����A�o�ϑK�v���낤�B���������{�́A�R���i�Ђɏ悶�ĕӖ�ÐV��n���݃S�������H��������������C���X���B
��N4���A����{���암�n��́u�����]���҂̈⍜�܂���̓y���v��Ӗ�Ö��ߗ��ėp�Ɏg���v�悪���炩�ɂȂ����B�����⍜���W�{�����e�B�A�u�K�}�t���[�v��\�E��u����������炪���S�ɂȂ��āA�v�撆�~��i���Ă���B���N3����6���ɂ̓n���K�[�X�g���C�L������ȂǁA�K���̑i�������Ă���̂��B
�u�⍜�̖���y�n���@��N�����āA���̓y����ČR��n�邽�߂ɊC�ɓ��������Ȃ�āA��v�҂��x�E���悤�Ȃ��̂ł��B���ɂ�鎀�҂ւ̖`��(�ڂ��Ƃ�)���ɋ����킯�ɂ͂����܂���v(��u������)
3���ɂ͓����E�i�c���̎��@�O�ł��A����o�g�҂��P�ƂŃn���X�g�����s�����B���荞�݂�4���܂ő������B�������f�B�A�͑傫�����A�����ւ̋����͌����̊ԂɍL�����Ă���B���A�S�����f�B�A�͂̕��܂葽���Ȃ��B��u�������́A8��15���̐�v�ҒǓ����ɍ��킹�A���ɂȂ铌���E���{�����ًߗׂł̃n���X�g���l���Ă���Ƃ����B
�����{�́A����̐��_���˂���������
���`�̎��g��������F�ƈ�ۑ���ɂ���āA�R���i�×{�҂̂��߂̏h���{�݂�p�ӂł��Ă��Ȃ��͉̂��ꌧ�̎���̂������ƌ��`���悤�Ƃ������Ƃ�����B
���邢�́A�����^�}�c���������͂��̐ԗ䏸���c��c�����APCR�����̊g�[���ł��Ȃ��܂܊����g��Ɏ������̂͋ʏ�f�j�[�m���̎���̂������ƌ��`���悤�Ƃ������Ƃ�����B
���́A�V��n���ݐ��i����Ɏ�����������̐��_���Ȃ�Ƃ����Ă˂����������B���̂��߂́u����̖��ӕ��f�H��v���A���[�������ォ��₦���������Ă����B�́E�����Y�u�O�m���Ƃ̉�k�ŁA���V�Ԋ�n���o�������j�I�o�܂Ȃǂ�������ꂽ�Ƃ��A�u���͐�㐶�܂�Ȃ̂ŁA���j�̘b������Ă�����܂��v�ƕԂ����B
���`�̂Ƃ����l�́A���j�Ɋw�Ԃ��Ƃ����Ȃ��B����ƌ��������ۂɍŒ���K�v�Ȑ^�������������Ă���B���{�̓R���i�Ђɏ悶�āu���ꂢ���߁v�����������Ă���A���̓x�����͂܂��܂������Ȃ��Ă���̂��B
���ꂩ��́A���̍��̋������p����������ƌ�����B���̋ꋫ�́A�����ꉫ�ꂾ���łȂ��S���ɍL�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B�������ꂩ�猩����{�̖����́A�������Ė��邢���̂ł͂Ȃ��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���R���i�����g��ƌܗւ͖{���ɖ��W���H�@��������A�����炯�o�u���@7/31
������4000�l��A�S���ł�1���l���Ɗ����Ґ����ߋ��ő����X�V�����R���i�ЁB�����A�����}���Ɠ����ܗւƂ̈��ʊW�ɂ��ẮA���`�̎́u�l���͌����Ă���v�A���r�S���q�s�m���́u�e���r�ϐ�ɂ��X�e�C�z�[�����i�v�ȂǂƔے�B���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�̍L���Ɏ����Ắu�ܗւ̓p���������[���h(���s���E)�v�Əq�ׁA�����g��ɐӔC�͂Ȃ��Ƌ��������B�{���ɌܗւƊ������ɊW�͂Ȃ��̂��B
��30���܂łɌܗ֊W��225�l�̊���������
�������璼�ړI�e���Ƃ��Č��O����Ă����̂́A�ܗ֊W�җ����ɂ�銴���g�傾�B
�I��E�W�҂͍��N1������A��`������̊u���Ȃǐ��{�̐��ۑ�ɔ���ꂸ�ɓ���Ƃ��ē������Ă���B���̓�������҂̐���1������6���܂ł�3551�l�ɏ��B���t���[�ɂ��ƁA���̒�����2����1�l�����6�����܂łɌv6�l�̊������������Ă���B7��1���ȍ~��3��9000�l������������B���g�D�ψ���ɂ��ƁA30���܂ł�225�l�̊������������Ă���B
�Ƃ��낪�A�����҂̍��Ђ⊴�������E�C���X�̎�ނȂǂ̏ڍׂ́A���g�D�ψ���v���C�o�V�[�����Ɍ��\���Ă��Ȃ��B�Z���ڐG�҂̗L�����悭�����炸�A�ڍׂȏ�o�Ă���̂́A�e���̃I�����s�b�N�ψ����ꍑ�̃��f�B�A�����ꍇ�������B
�I�葺���I�[�v�������̂�7��13���B���t���[�́A�h�n�b��g�D�ς���߂��K���W(�v���[�u�b�N)���u�I���W�҂��A���炷�邱�Ƃ�O��ɂ��Ă���v(�S����)�̂�����������Ƃ��āA�����g��ɂȂ����Ă��Ȃ��Ɛ�������B
������ʃv���[�u�b�N
�Ƃ��낪�A�v���[�u�b�N���m���Ɏ���Ă��邩�Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B�ܗ֊J��O����A�I�葺��z�e���Ƃ����o�u���̒��ʼn߂����͂��̑I��E�W�҂��A�X�̒��ʼn߂����p�͉��x���ڌ�����Ă���B�J��ł́A�}�X�N���������ꂷ��p���e���r�ʼnf����A�l�b�g�ł͓s���ό�������I��̎p�̕�����B�����A�h�n�b�Ȃǂ̏����͕������Ă��Ȃ��B����ŁA��`�ł̓����葱���͑I���̗��������ɍ��킹�āA�ɂ߂�ꂽ�B�I���́A��`�̌��u�ʼnA�����m�F����Ă�������̎葱�����s���Ă����B�Ƃ��낪�A�����̃s�[�N�ɔ����č���7������͍��G�ɘa�̂��߂Ɍ������ʂ��o��O�ɓ����葱�����I���A��`���̑ҋ@�{�݂ő҂��ƂɂȂ����B
�������炯�̌ܗփo�u��
���������o�u���ɂ��ė�������}�̈����R���i���{�����́u�����炯���v�ƌ������ᔻ����B�����́A6��28���ɐ��`�̎��H�c��`�̐��ۑ�����@������A���n���m�F�����B����Ɓu�ו������^�[���e�[�u���͑I�����ʋq���ꏏ�������v�B�I��炪���u��������R���A�ŊւƐi�ޏꏊ���e�[�v�Ŏd���Ă��邾���ŁA�u�������������Ă���킯�ł͂Ȃ��v�B�I�葺�Ŗ����s����R�����������Ԃ͕s�����B���⎁�́u������x�ꂩ������Ȃ��v�Ɗ�@�����点�Ă���B�����������Ԃ��炷��A�ܗւƊ����g��̒��ړI�W���S���Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�������J���Ȉ�n�Z���ň�t�̖ؑ���������́u�l�������ē����A�������g�傷��͓̂�����O�̂��ƁB�t�ɁA�l�̓������~�܂�A�Љ�ƌo�ς��~�܂�v�Ǝw�E����B�ł́A�����҂̑������~�܂�Ȃ�����łł��邱�Ƃ͂Ȃ��̂��B�ؑ�����́u�����Ȃ����ȏ�A�����҂̎���Ԑ��ȂǁA��ẪL���p�V�e�B�[(�\��)���グ�邵���Ȃ��v�Ƒi����B
���u�₩�ȏj�Ձv���l�̐S���J���I��
�ܗւ����������������Ǝv�킹�闝�R�͑��ɂ�����B�����̐S���ɋy�ڂ��e�����B�������q��̍L���O�����_����(�ЊQ�E���X�N�S���w)�́u�ܗւ͉₩�ȏj�ՂƂ������ʂ�����A�J�Òn�̐l�����̐S���J���I�ɂ�����B���炭�O�o���T���Ă����l�������䖝���ɂ߁A�o�|���Ă��܂����Ƃ��������͂��v�Ƃ݂�B�u�J����͊e���Z�̕�����������A�R���i�֘A�̃j���[�X�͌������B���_�����b�V���ł��̌X������苭�܂����B���ʓI�ɐl�тƂ��R���i���ӎ�����@��ȑO��茸��A���l�̈ӎ�����܂邱�ƂɂȂ����B�S���ʂŁw�y�σo�C�A�X�x�����������v
�����u�l�����v�A���r�m���u�ݑ���v�c�����̐S�ɂ܂���
����Ȓ������炱���A��@�������߂郁�b�Z�[�W���o���ׂ��Ȃ̂ɁA����27���Ɂu�l���͌����Ă���v�Ɗy�Ϙ_��U��܂��A���r�m����29���Ɂu(�ܗւ̎���ϐ킪���������Ƃ�)�X�e�C�z�[��(�ݑ�)�����オ���Ă���v�Ɣ����B�h�n�b�̃}�[�N�E�A�_���X�L���́u(�ܗւ�)�p���������[���h�݂����Ȃ��́B����ꂪ�����Ŋ������L���Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B�L�����́u�ܗ֊J�Âō����̐S���ɂޒ��A����ɔ��Ԃ��|����悤�Ȕ������������ł���B�S�������ł��Ȃ��v�Ɛ�̂Ă�B
���ً}���Ԑ錾�̂��ѐl���}�����ʔ���c
����������A�̊y�Ϙ_�͂��݂̂ɂł��Ȃ��B�������R�����悤�ɂ���v����B�g�ѓd�b�̈ʒu���؍ݐl���͂���\�t�g�o���N�̎q��Ёu�A�O�[�v�v�̃f�[�^�ɂ��A�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o�Ă���2�T�Ԃقǂ�����25���A�i�q�����w�̐l�o�͍ŏ��̐錾�O�̍�N3���ɔ�ׂ�10�����ɂƂǂ܂����B1��ڂ̐錾�̍�N4����65�����A2��ڂ̍��N1����42�����A3��ڂ̓�5����33�����Ȃ̂ŁA�錾���o�����тɐl���}���̌��ʂ��傫������Ă��邱�Ƃ��悭�\��Ă���B
���u���[�C���p���X�A���[�h���[�X�ϏO�Łu���v
���ꂾ���ł��u�l���͌����Ă���v�Ɗy�ςł��Ȃ��͖̂��炩�����A�ܗ֊J�Âɂ���āu���v�ɂȂ�قǂ̐l�o�������Ă���B�Ⴆ�ΊJ���������23���ɂ́A�ܗւ̋�C�𖡂킨���Ƃ���l�������������Z����ӂɎE�������ق��A���̃u���[�C���p���X�̎ʐ^���B�錩���l�̖��W��Ԃ��ł����B��24���ɂ��A���]�Ԃ̃��[�h���[�X�̑I�肽�����삯�������O��s���ł́A�X�}�[�g�t�H����������ϏO�����������قǏW�܂����B�u�ݑ�������v�Ƃ������r���̔������������B�����́u�e���r�̎��������@���Ɏ����Ă���v�Əq�ׂĂ���A�u�����������������ݑ�v�ƌ��������悤�����A�r�f�I���T�[�`�Ђ����\����֓��n��̐��ю�����������ƁA�J�����56�E4�����������A����20������L�^�����������10����B�u�N������������Ōܗ֒��p�ɂ��Ԃ���v�Ƃ͒������B
���������郁�b�Z�[�W��߁A�����̋^��ɓ�����
���{�E�s�Ȃǂ��u�ܗւ��肫�A�ܗւ������ʈ����v�Ƃ����p���������Ă����e�����������Ȃ��B�������J�������Ő_�ˊw�@��̒���뎊����(�s���w)�́u���H�X�ɑ�����ߕt����R�����x���ȂǂŐ��{��s�ɕs�M������Ă���̂ɁA����ɖ������v�킹�郁�b�Z�[�W���o���ΐM������������B�����ɉ������͂����肢���悤�ɂ�����݂��Ă��炦�Ȃ��Ȃ�v�Ƙb���B�암�`�T�E���c����u�t(�����w)�́u���ǂ̂Ƃ���A�����⏬�r�����y�Ϙ_��G����͎̂������g�ɑ��v�ƌ���������������������Ȃ��̂��v�Ƃ݂�B�K�v�Ȃ̂́A����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�u���͂ǂ�ȏ��A�����͂ǂ�ȕs��������Ă��邩�A������ƒ������ׂ����B���̏�Ŗ����A�L�Ғc�̂Ԃ牺�����ނ��ɉ����A�����̋^��ɓ����Ȃ��獑���ւ̂��肢��`���Ă����B���������^���Ȏp�����Ȃ�����A�����̋��͓͂����Ȃ����A�����g��͎~�߂��Ȃ��v
����5�g�N���Ɂ@�S��1��2��l�������A4���A���ő��@7/31
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�31���A�S����1��2342�l�ƂȂ�A4���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B�����s�ł�4058�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ����ق��A���{�ł�1040�l���m�F�����ȂǁA�����̋}�g��Ɏ��~�߂������炸�A�V�^�R���i�Ђ́u��5�g�v���N���ƂȂ��Ă���B����A��Ò̐��̕N��(�Ђ��ς�)�����O�����B
�����s�ł͍ő�������7��29����3865�l������A���߂�4��l�����B6��20����3�x�ڂً̋}���Ԑ錾���S�ʉ������ꂽ���납�犴���҂̑����X���������A���������͋}���Ɋ������g��B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���2920�l�ƂȂ�A�O�T��2�{�ȏ�ɂȂ����B
7��12�������4�x�ڂ̐錾��8��31���܂ł̉��������܂������A����̐錾�͂���܂Ŋ����Ґ��̗}���ɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��B�ɉ؊X�̐l�o�͂�⌸�����Ă�����̂́A�����͂̋����C���h�R���̃f���^���̉e�����w�E����Ă���B
��N�w�ł̊����g����������B����4��l��ƂȂ��������̊����҂̔N��ʓ���́A20�オ1484�l�ƍł������A30�オ887�l�Ƒ����B30��܂ł̊����҂�2878�l�ƂȂ�A�S�̂�7�������B
���@���҂�3200�l������A����×{�҂����߂�1���l�����B
����A2������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����߂������{�ł́A7��31����1040�l�̐V�K�����҂����\���ꂽ�B��l����̂�5��8���ȗ����B������2������錾�����߂����_�ސ쌧���ʌ��ł�7��31���ɐ�l���A�ߋ��ő��ƂȂ����B���̂ق����ꌧ�⋞�s�{�Ȃnjv10�s�{���ʼnߋ��ő����X�V�����B
�S���̎��҂͓�����3�l�A�k�C���A�X�A���ȂǂŊe1�l�̌v9�l�����ꂽ�B�����J���Ȃɂ��ƁA�d�ǎ҂�41�l������667�l�ƂȂ����B
��1���̊����Ґ���1���l�˔j�������A��11���ɂ�����̈��H�X�͑���킢�@7/31
���ʂ�ɓ���Ɩ��邢�l�I���̉��Ŏ�����ɑ呛�����Ă���O���[�v���ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�B��2���[�g���قǂ̓�������ő�^�̈��H�X�⋏�������������c�Ƃ��Ă����B�X���Ƃɒu���ꂽ���\�̃e�[�u���ɋ͂Ȃ������B��ɂȂ��Ă�28�x�������Ȃ��M�і�ɂ�������炸�A�G�A�R���̕����Ƃǂ��Ȃ��H��̃e�[�u�����قږ��Ȃ������B29����11�����A��������̐V�������ˉ��߂��̗��ʂ�̕��i���B
����12���ɋً}���Ԑ錾�����߂��ꂽ�����s�ł͈��H�X�̉c�Ǝ��Ԃ���8���܂łɐ�������Ă���B��ނ̔̔���������֎~���ꂽ�B�R���i�̊����g���h�����߂��B
�Ƃ��낪���̓��A�����s�S�̊e�n�ł͂�������ĉc�Ƃ𑱂���X�A����ɂ����̓X�ɏW�܂�q�����̎p���ȒP�ɖڂɂ��邱�Ƃ��ł����B�c�Ƃ𑱂��邢�����̓X�ɋq���W�����邽�ߋp���Ė��ɂȂ����悤���B�L�y���w���ӂŎ�ɋ�����邠����H�X�ł��]�ƈ����������A�K���q�������ē����邽�ߖZ������������Ă����B�]�ƈ��Ɂu�c�Ǝ��Ԃ̐����͂Ȃ��̂��v�Ǝ��₵���Ƃ���A�u������5���܂ʼnc�Ƃ��Ă���v�Ɛ��������B�������24���ԉc�Ƃ������B
���̓��͓��{�S���ŃR���i�̊����҂��͂��߂�1���l(1��692�l)��˔j�����B�����s������3865�l���B�����قŏ_���̎�ނ��I���Ă���s����������Ƃ���A���̗��R���킩��悤�ȋC�������B
��ʂ�͂ǂ����Â��������A���������ɓ���Ɗ��S�Ɉ�������E�ɂȂ��Ă����B��v�Ȕɉ؊X�͂ǂ����悭�����������B�T�����[�}�����悭�K���V���w���ӂł͒ʏ�Ɠ������q�����������ʍs�l�ɐ����|���Ă����B���ӂɎ~�܂����^�N�V�[����͗l�X�ȍ����痈���O���l�������~��ăo�[�⋏�����Ɍ��������B��̒n���S�ɂ̓r�[���̋ʂ␌���ׂ�Ė���l���ڂɂ����B
�u���͂�ً}���Ԑ錾�ɂ͌��ʂ��Ȃ��Ȃ����v�ƈ�ÊW�҂�s���͌������낦��B������u�I�����s�b�N�̉e���v�Ǝw�E���鐺������B�����V���́u�I�����s�b�N�J�Â������h�~�̕����ꓹ�v�Ƃ����\�����g�����B���{��Ö@�l����̑��c�\�m����́u�I�����s�b�N���J�Â��邱�ƂƊ����g��h�~�͖����������b�Z�[�W�ɂȂ��Ă���v�Ǝw�E����B�����ł��������I�Ȋ�����ւ̔�J�����L�܂��Ă���ŁA�I�����s�b�N�̂��ߊ���������ʂ��o�Ȃ��Ƃ����̂��B
�I�����s�b�N�̑I���W�҂��u�������v�Ƃ��ĕs�������鐺�����܂��Ă���B���ۂɑ��g�D�ψ���u������̃��[��������Ăق����v�Ɨv��������������B�v���X�Z���^�[�Ɍ������ہAAD�J�[�h�Ɍ��������͂���̎��������X�Ɍ������Ȃ��Ă���悤�Ɋ�����B�I�����s�b�N�����̂悤�ɖ��҂ɂȂ�Ƃ͒N���z�������ł��Ȃ��������낤�B
���V�^�R���i�E�C���X�̊����g��~�܂炸�c���m��4���A����200�l���@7/31
31���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂ł��B���m����31���A�V����286�l�̊������m�F����܂����B�������É��s��134�l�ŁA���m��4���A����200�l�����ł��B����18�l�A�O�d����44�l�ł��B
���u��ÂЂ����̌����`�������v���m��Ï]���҂��ܗ֒��~��i���X���f���@7/31
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A���m�̈�Ï]���҂炪31���A�����I�����s�b�N�̒��~��i���ăf�����s���܂����B
�u��Õ���s���𒆐S�ɍL�����Ă��钆�ŃI�����s�b�N�𑱂��Ă���ꍇ�Ȃ�ł��傤���v(���m����J�A)
�f�����s�����̂́A��Ï]���҂炩��Ȃ鈤�m����J�A�ł��B
���É��s�̋��R�����w�ł̃f���͍���7��ڂł��B
�V�^�R���i���҂̑����ň�Ñ̐����Ђ������錻��܂��A�����I�����s�b�N����������ɗ͂�����ׂ����Ƃ��āA���̒��~��i���܂����B
�u�������Ōܗւ���߂邱�Ƃł݂�Ȃɂǂꂾ���R���i��ς��̌���̌�������`���邱�Ƃ��ł���Ǝv���v(���m����É�앟���J���g���A����@���^���q����)
���̓��̃f���ł́A�R���i�Ђő̌��������Ƃ��莆�ɏ����Ă��炤�悤�ʍs�l�ɋ��߂܂����B��Õ���̊�@��i���邽�߁A8���ɁA�W�܂����莆�̓��e�\����Ƃ������Ƃł��B
�����ł�31���A�V�K�����҂����߂�4000�l���A���m�ł�287�l�̊������m�F����Ă��܂��B
���u���������ɂ͂����Ȃ��v ���̑��������ܗւɐS���J�����{�l�@7/31
�R���i�ЂŊJ�Â���Ă��铌���ܗցB�����g�傪�������A���~�����Ԑ��͂�ދC�z���Ȃ����A�����炱����ʼn������������������Ă���B�t�@���́A�K��������������ŃA�X���[�g���܂��A���O�b�Y�����߂Ă���B���̂��������Ă��A���{�͑��O���ɃS�[���h���b�V���̉��i�����������B���8����(7��30��)�I�����_�ŁA���{��17�̋����_���ɋP���Ă���B
�V�^�R���i�E�C���X�̊�����̂��߁A�قڂ��ׂẴC�x���g�����ϋq�ƂȂ�A�����ł̋��Z�ɂ͋߂Â��Ȃ��悤�v������Ă���B����ł��A�ܗւ���ڌ��悤�ƁA�t�@����͑��̌���ɏo�����Ă���B
�u�����Ă���I�������ƁA�w�����x���Ă����ӂ��Ɏv���Ă��܂��܂��v�Ƙb�����̂́AIT�W�̐��E�ɏA���Ă���40��̃t�@���B������яo���A�J�̒��ŏ��q�̃g���C�A�X�������ϐ킵���B
�u�J��܂ŁA�^��Ɏv���Ă����Ƃ���͂���܂����v�Ɩ����������̃t�@���́A�u���Z���n�܂�Ɓw����Ă悩�������ȁx�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B�p�������s�b�N�܂ň��S�ɊJ�Âł���Ƃ����ȂƎv���܂��v�Ƙb���Ă���B
�����ܗւ͐��E�����琔���̃A�X���[�g�A�����ƃ��f�B�A�W�҂��ꓰ�ɏW�߁A23���ɊJ�������B�������A�V�^�R���i�E�C���X�����g��̂��߁A�ܗւً͋}���ԉ��̓����Ői�s���A�t�@���͉�ꂩ��ߏo����A�������銴���Ґ��ɍ����̕s���͕���Ă���B
����ł��J������A���̍������Z����ӂɂ͐���̐l�X���Q����A���̕��͋C�ɐZ��ƂƂ��ɑł��グ��ꂽ�ԉɌ������Ă����B���̐��͌ܗ֔��̃f���Q���҂��͂邩�ɏ����Ă����B
���u�����I�ɖZ�����v
�J��e���r�����p�̓����ł̕��ϐ��ю�������50�p�[�Z���g���Ă����B�̔��X����g�D�ψ���̊W�҂ɂ��ƁA�������̊֘A�O�b�Y�̎��v���}�㏸���Ă���Ƃ����B
�g�D�ς̔я��Ђ���}�[�P�e�B���O�ǎ厖�́A�J����_�@�ɃO�b�Y�X�܂́u�����I�ɖZ�����Ȃ��Ă����v�Ɩ������A�����ܗ֊֘A���i�邽�߂̓��ݓX�܂́A�q�s���ł�������͕��������̂́A���݂͍ĊJ���Ă���Əq�ׂ��B
����グ�����̌X���́u�s���œ��Ɍ����v���Ƃ��Ă���A���㍂�͖������Ȃ��������̂́AT�V���c��}�O�J�b�v�A�^�I���Ȃǂ��l�C�Ƃ����B
�l�X�̋C�����̕ω��́A�����̑I�肽���̑劈��Ɩ��W�ł͂Ȃ����낤�B���{���j���q���ƂȂ�2����B�������勴�I�˂��͂��߁A13�̏��q�X�P�[�g�{�[�_�[�̐���A�_���̈������ƈ������O���傤�����A�싅��ڂŒ����̓Ɛ�ɏI�~����ł������J���ƈɓ������A���q�\�t�g�{�[���`�[���ȂǁA�����̓��{���������_�����l�������B
�ޗǏ��q��w�̃X�|�[�c�Љ�w�����ҁA��F�i�y�����ɂ��ƁA���{�l�I�肪������̃R�����g�Łu��т̔������A������l���A���̏���������Ă��ꂽ�l�X�ւ̊��ӂ�`���Ă���v���Ƃ��A�}���̌���������オ��ƂȂ�A���ɑ��锽����a�炰��ꏕ�ɂȂ��Ă���\��������Ǝw�E�����B
���u�����Ă��ꂵ���v
���ׂĂ̐l�����ɋC�����̕ω����������킯�ł͂Ȃ��B���ł������̐l�X���E�C���X�̃��X�N��S�z���Ă���B�����s�̃R���i�V�K�����҂̐��́A29���̎��_��3���A���ߋ��ō����X�V���Ă����B
���{�o�ϐV����26���Ɍf�ڂ��ꂽ���_�����ɂ��ƁA���ł�31�p�[�Z���g�̐l�X�����͉��������~�����ׂ��������ƍl���Ă���B����ł���70�p�[�Z���g�߂��́A���炩�̌`�ł̊J�Â��x�����Ă���B
�C���h�o�g�ŁA���݂����ɏZ��ł���`���^���E�}�N���i����́A�ߏ��ōs���鋣�Z�����ɏW�܂����l�̌Q��ɕs���������A�u�l�̓R���i������ƖY��Ă���B������ɏZ��ł���l�ɂƂ��ẮA�ȑO���ƂĂ��|���ł��v�ƌ�����B
�ՊC���̂����ɂ�27���A���ǂ̋K���ɂ�������炸���S�l���W�܂�A�J�̒��ŏ��q�g���C�A�X�����̑I����������Ă����B
�قƂ�ǂ��}�X�N�𒅂��A�����͔��肾���ɂƂǂ߂Ă���A���ꂽ�ꏊ���琺�����グ��l�������B
�ߏ��ɏZ��60��̃t�@���́A���Z�ɗՂޑI��Ɂu������ā[�A������ā[�v�Ɛ����|���A�u�ɂ킩�t�@���ł����ǁA�����Ă��ꂵ���ł��B�q�ǂ��Ɏ������܂��v�Ə����B
�u�����Ȃ��Ƃ������āA�����Ȃ��Ƃ�����ꂽ����ǁA�����ɍ��킹�Ă����I�肽�����������Ă��������Ǝv���܂��v
��CNN�L�҂������������u�ܗ֖��W�͍l����v�@7/31
�A�����JCNN�̓����x�ǒ���ANN�̎�ނɉ����A�I�����s�b�N�J����Ɋ������}�g�債�Ă��邱�Ƃɂ��āu���̉e�����Ȃ��ƍl����͓̂���v�ƌ��܂����B
2019�N������h���߂�u���C�N�E�G�V�b�O����B30���ɂ͓s���ŃI�����s�b�N�֘A�̃s���o�b�W��̔����Ă���j������ނ��܂����B
CNN�����x�ǁA�u���C�N�E�G�V�b�O�L�ҁF�u�R���i�̊����g��͔���グ�ɉe�����Ă��܂����H�v
�ܗփs���o�b�W���W�ƁE����c�@�t��������F�u���ʂ̏Ȃ�s�ł��Ă���Ǝv���܂��B�R���i�ŊC�O�̊ό��q�����Ȃ���Βn���̐l���o�Ă��Ȃ��v
�G�V�b�O�L�҂́A���{�ɏZ�ސl���I�����s�b�N���ǂ����Ă���̂����e�[�}�Ɏ�ނ�i�߂Ă��āA�R���i�Ђł̑��ɂ��āu�ϋq���M�����Ȃ��A�l�X�Ȗʂŕs�\�����v�Ƙb���܂����B
�܂��A�J����̊����}���̌������f���^�������f����ɂ͎��������Ƃ��Ȃ�����A�u���̉e�����Ȃ��ƍl����͓̂���v�Ƃ̌����������܂����B
CNN�����x�ǁA�u���C�N�E�G�V�b�O�L�ҁF�u(��ނ�����Ï]���҂�ɂ���)�ܗւ��J�Â������Ƃō����ɂ��̊�@�͂���قǂł��Ȃ��Ƃ������G��^�����B���̌��ʁA�l�o�͑����A�d���ɍs������A���X�g�����ň������Ċ���������(�܂�)���Ă���̂����ł��v
�܂��A�G�V�b�O�L�҂͑��{�����e�B�A�̍s���͈͂�N�`���ڎ헦�̒Ⴓ���莋���Ă��܂��B
CNN�����x�ǁA�u���C�N�E�G�V�b�O�L�ҁF�u(�o�u����)�s��������l�����ă��N�`���ڎ헦���Ⴂ�Ȃ��A��������l���Ύ�ɂȂ肩�˂Ȃ��Ȃ̂ł��B���ꂪ�ő�̌��O�ł��v
�������ܗւ̊J�Âɑ���~�߂ɕω��̒����@7/31
�����ŐV�^�R���i�E�C���X�����҂̑����Ɏ��~�߂�������Ȃ���������ܗւ̊J�Âɑ���~�߂ɕω��̒������o�Ă���B�w�i�ɂ���̂ͤ�A���̓��{�I��̃��_�����b�V�����B
���{��30���܂łɌܗ��Z�ŋ����_����15�l����������Ɏ���2�ʂɂ��Ă���B�V��ڂ̃X�P�[�g�{�[�h(�X�g���[�g)�͒j���Ƃ��D�������褏_���͈����Z���̉������܂ߋ����_��8�¤�̑��̒j�q�l�����ł͋��{��P�I�肪���߂Ă̌ܗւŋ�����ɂ����B
�����s�̊����Ґ��ͤ29����3865�l�ƂȂ�3���A���ʼnߋ��ō����X�V����ȂǤ�g��y�[�X�͈ˑR�Ƃ��Đ[�����B������\�[�V�������f�B�A�̓��e�͂���Ƥ�ܗււ̔ے�I�Ȑ��ɔ�ׂĤ�e���r��X�}�z�̉�ʉz���ɉ���������{�I��ւ̍m��I�ȃR�����g�������Ă��Ă���̂��킩��B
�J���ȍ~��c�C�b�^�[��ł͢�ܗ֒��~������Ԑ��ȊO�ɤ�I��̃��_���l������ԃc�C�[�g��J������ɓ����̋���ʂ����q�q���̃A�N���o�b�g��s�`�[����u���[�C���p���X��ɂ��p�t�H�[�}���X������ĊJ������̉ԉȂǂ̓��e���ڗ��B
���{�e���r��JX�ʐM�Ђ̕��͂ɂ��Ƥ�c�C�b�^�[��ł͊����g������O���ăl�K�e�B�u�ȃR�����g���ˑR�Ƃ��đ唼���߂邪��J��O����22����3�������������|�W�e�B�u�ȃR�����g�ͤ27���܂ł�4�������B
�܂�������ʐM�ɂ��Ƥ���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�Ȃǂ����{����܂�9�J����œW�J��������T�C�g��A�v����ʂ����f�[�^�ʐM�ʂͤ2016�N�̃��I�f�W���l�C���ܗւ�2�{�ɒB���Ă���B���ł����{��č���C���h����̃A�N�Z�X�������Ƃ����B
�J����̏T����26���ߌ㤂����ɂ�����S��������T�V���c�Ȃǂ̌ܗ����O�b�Y��̔�����X�܂͕����ɂ�������炸�ɂ��킢�������Ă����B
�e�ʂ�Ƒ��ւ̂��y�Y�ɃL�[�z���_�[�Ȃǂ��w�������Ƃ����s���ݏZ�̕������v����(44)�ͤ��ǂ��炩�Ƃ����ƌܗS�z�h����������n�܂��Ă݂���t�ɂ��ꂪ�Ȃ�������₵��������������Ȃ���ƐS���̕ω������ɂ����B
��������̓X�P�[�g�{�[�h��̑��Ȃǂ��e���r�ϐ킵���Ƃ����B3�ɂȂ閺���傫���Ȃ������ɤ�L�[�z���_�[�������Ȃ��瓌�����̎v���o��`�������Ƙb�����B
��̍l��
�I��������������C�����Ɗ����g��ւ̌��O���������Ă���Ƃ̌���������B�J�ÑO�ɑ�X�،����ł̃p�u���b�N�r���[�C���O�T�C�g���ݒ��~���l�b�g�ői�������{�ݏZ�̌o�c�R���T���^���g����b�V�F����J�b�v���͢��̍l���͖������Ȃ���Ɠd�b��ނŏq�ׂ��B
�ޗǏ��q��w�̐�F�i�y����(�X�|�[�c�Љ�w)�ͤ��������͊J���O�Ƒ傫���ς���Ă��Ȃ��Ǝw�E����B�R���i�Ђł̌ܗ֊J�Âɔے�I�������l�͢���܂��ɊJ�Â���ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��邵�������ł��Ԃɍ����̂ł���Β��~����ׂ����Ǝv���Ă��飂Ƃ����B
������ܗւɍm��I�Ȉӌ����������₷���Ȃ������Ƃ͑傫�ȕω����Ƃ����B����܂łͤ�R���i�Ђł̌ܗւ��|�W�e�B�u�ɍl�����Ȃ������������ߤ�I��������������Ƃ����C������\�ɏo���Â炢���͋C�������B��������ߏ�ɂ͂��Ⴎ���ƂȂ��W�X�Ɗ���I�肽���̎p�������̐l�̐S�𑨂��Ă���Ɛ��������B
�����V�^�R���i1040�l�̊����m�F�@�f���^�������g��͂̓��K�g�����@7/31
���{��31���A�V����1040�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����A�S���Ȃ����l��0�l�Ɣ��\���܂����B1���̐V�K�����҂�1000�l����̂́A5��8���ȗ��ł��B�܂������I�����s�b�N�J�Ò��̓����s�ł́A�ߋ��ő���4058�l�̊������m�F����܂����B
���{�V�K�����Ґ��̐���(���Ґ�)�@7��30��(��)882�l(0�l)/ 7��29��(��)932�l(2�l)/ 7��28��(��)798�l(0�l)/ 7��27��(��)741�l(0�l)/ 7��26��(��)374�l(1�l)/ 7��25��(��)471�l(1�l)/ 7��24��(�y)283�l(1�l)
8��2������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���K�p�������{�ł́A��ނ����{���̈��H�X�Ȃǂɑ��Ă͋x�Ƃ�v������ƂƂ��ɁA���Ȃ��ꍇ�͉c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂ł̒Z�k�A�܂��S�ݓX�Ȃǂ̑�K�͏��Ǝ{�݂ɂ͌ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ�v�����܂��B
�g���m���̓c�C�b�^�[�Ɂu���Ɉ��H�X�̊F�l�ɂ͕��S�����Ő\����܂���B���߂ăS�[���h�X�e�b�J�[�X�܂͂Ƃ��v���܂����A�@����ł��܂���v�Ɠ��e���A2������ً̋}���Ԑ錾�̓K�p�ɗ����Ƌ��͂��Ăъ|����ƂƂ��ɁA�u�f���^���̊����g��͕͂ʊi�ł��B���̋����̓��K�g�����ł��v�ƋL���A������̓O����Ăт����Ă��܂��B
���x���x�����グ�@�Ȗ،���7�s�Ŏ��Z�v���@�X���u���G�Ȏv���v�@7/31
�V�^�R���i�E�C���X�̋}���Ȋ����g�����30������Ȗ،��̌x���x���x�������̂܂h�~���d�_�[�u�ɑ�������X�e�[�W3�Ɉ����グ���܂����B
7�s�̈��H�X�ɂ�8��2������c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v�����o����A�҂����Əd�Ȃ鎞���̍Ăт̎��Ԃɋꂵ�������i���鐺���������܂����B
����30�����瑍���I�Ȍx���x���x�������̂܂h�~���d�_�[�u�ɑ������錧�ŃX�e�[�W3�Ɉ����グ�܂����B
�x���x�̈����グ�ɔ������߈�T�Ԃ̐V�K�����Ґ������ɑ����F�s�{�s�Ȃnj���7�s�̈��H�X��8��2������c�Ǝ��Ԃ��ߑO5������ߌ�8���܂łɒZ�k�A��ނ̒͌ߑO11������ߌ�7���܂łƂ���悤�v�����܂��B
�Ώےn���1�Ō����L���̊ό��n�E�����s�ɂ�����H�X�@�x(������)�ł��B
���E��Y�̓�Јꎛ�֑������C�����[�h�����ɂ��蓒�t�Ȃǒn���̖������g�����������l�C�ŐV�^�R���i�E�C���X�������g�傷��O�͍����O���瑽���̊ό��q���K��܂����B
�ȍ~�́A�e�C�N�A�E�g��SNS�ł̔��M�ɗ͂����n���̐l������D�]�Ă��܂����B
���̏T���ɂ͎s���̃C�x���g�p�ɑ���̒���������܂������A�}����C�x���g�����~�ɂȂ�L�����Z���ɂȂ�܂����B
����A�F�s�{�s�̒��S�X�ɂ���F�s�{���䉡���ł́A�ߌ�4�����납�炨�悻20����X�̓X����W�߂ĉ^�c��Ђ����Z�v���̓��e�Ȃǂ�`���܂����B
�F�s�{���䉡���ł͗v���ɋ��͂�����Ŋ�]����X�͒ʏ��葁�����Ԃ���c�Ƃ��邱�Ƃ����߂܂����B
�S�Ă��₩�炠��������̓X�ł́A���T����͂���܂ł��2���ԑ����ߌ�4���ɉc�Ƃ��n�߂邱�Ƃɂ��܂����B
�ŋ߂͂悤�₭�R���i�Ђ̑O��6�A7���قǂ܂ŋq�̐����߂��Ă������A�Ăт̎��Z�v���ɗ����������Ȃ�����v���͕��G�ł��B
�������b���@��ؑq�@�X��F�u�܂����A�Ƃ��������B�d���Ȃ����A��x���Ԃ�Z�k���ċq������Ă��܂�����߂�̂ɂ͎��Ԃ�������B�v
�������A�f���^�������@���N�`�����y�ł��u�����E�u���v�@7/31
�V�^�R���i�Ђ�}������ł��������{�y�ŁA�O��������荞�Ƃ݂���f���^���̊����������ƍL�����Ă���B�������{�́A����܂Ō��ʂ��グ�Ă�����K�͂�PCR�����Ɗu���̑̐��Ō}�������A�ċx�݂̗��s�V�[�Y���̎����������đΉ��ɋꗶ���Ă���A7��31���ߑO�܂ł�10�ȁE�����s�E�������20�s�s�ȏ�ō��킹��260�l���銴�����m�F����Ă���B
�������g�債�Ă���f���^���́A7��20���ɍ]�h�ȓ싞�s�̍��ۋ�`���ӂŔ��o���������҂��珉�߂Č��o���ꂽ�B�s�q�����ǂ́A�������̌��u�œ���҂̊������������Ă��郍�V�A����̍��ەւ̋@�����|�̒S���҂�ʂ��čL�������Ƃ݂Ă���B���s�̊����҂�30���܂ł�200�l�߂��ɂȂ�A���ǂ͋�`��3���l�ȏオ�Z�ގ��ӂ̊X���B��920���l�̑S�Z����PCR������3�������Ă���B
�����{�y�ł̎s��������1�N�ȏ�ɂ킽���āA�U���I�Ȕ������������������╕���A�Z���ڐG�҂�̓O��I�Ȋu���̑g�ݍ��킹�ŗ}�����ޏ�Ԃ������Ă���A�g��͈̔͂����̒n��ɂƂǂ܂�P�[�X�������B
�����A����͊����͂������Ƃ����f���^�����A�w�Z���ċx�݂ɓ����đ����̗��s�҂łɂ��키��`��ʂ��čL�������B�o�R�ւœ싞��`�ɐ����Ԃ����؍݂����l�����������������A���̌�̗��悩�炳��ɕʂ̏ꏊ�ւƊg�U�B�Γ�Ȃł͐��E��Y�̂���ό��n�E���ƊE�s�̌����퓿�s�̊ό��D�Ȃǂł̏W�c�������킩��A蟐��Ȑ����s�ł͊����҂��K�ꂽ���n��(�ւ��悤)�̔����ق��Վ������ꂽ�B�L���Ȃ�Γ�ȁA�l��ȂȂǂŒn��̕�����S�Z����PCR���������X�Ɏ��{����Ă���B
��9�l���S 1��2341�l�����m�F�@7/31
31���͂���܂łɑS����1��2341�l�̊��������\����Ă��܂��B�܂��A�����s��3�l�A�k�C����1�l�A�X����1�l�A��錧��1�l�A��ʌ���1�l�A�_�ސ쌧��1�l�A�É�����1�l�̍��킹��9�l�̎��S�̔��\������܂����B
�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͋�`�̌��u�Ȃǂ��܂�92��6405�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��92��7117�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�S���Ȃ����l�͍����Ŋ������m�F���ꂽ�l��1��5193�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��1��5206�l�ł��B
�����J���Ȃɂ��܂��ƐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�l�ŁA�l�H�ċz���W�����Î��ȂǂŎ��Â���Ȃǂ��Ă���d�ǎ҂́A31�����_��667�l(�{41)�ƂȂ��Ă��܂��B
����A�Ǐ��P���đމ@�����l�Ȃǂ́A31�����_�ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�l��83��4967�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����659�l�̍��킹��83��5626�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A29���ɂ͑���l��1����6��4322����PCR�����Ȃǂ��s���܂����B
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�l�ŁA�l�H�ċz���W�����Î��ȂǂŎ��Â���Ȃǂ��Ă���d�ǎ҂́A31�����_��667�l�ƂȂ�܂����B30������41�l�������Ă��܂��B����A�Ǐ��P���đމ@�����l�Ȃǂ́A�����Ŋ��������l��83��4967�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����659�l�̍��킹��83��5626�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A29���ɂ͑���l��1����6��4322����PCR�����Ȃǂ��s���܂����B
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA31���܂łɃt�B���s����C���h�l�V�A�Ȃǂ��琬�c��`�Ȃǂɓ��������j��14�l���A��`�̌��u���ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă������Ƃ��V���Ɋm�F����܂����B��`�ƍ`�̌��u�Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A���킹��3496�l�ƂȂ�܂����B
���ً}���Ԑ錾2������ �T���̑��́@7/31
�V�^�R���i�E�C���X��ŁA8��2��������ɋً}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����܂��B�i�q���ꕔ�̘H���ōŏI�d�Ԃ𑁂߂�ȂǁA�l�o�̗}���Ɍ������[�u���e�n�ōs���܂��B
8��2������A���ɋً}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����邱�ƂɂȂ�A3�{���́A�ΏۂƂȂ���H�X�Ȃǂւ̎�ނ̒�~�̗v���Ȃǂ����肵�܂����B
�l�o�̗}���Ɍ������[�u�Ƃ��āA�i�q�����{�́A�錾�̊��Ԓ��A������ōŏI�d�Ԃ��J��グ�āA���w�ƓV�����w���o������ŏI�d�Ԃ��ő��16�����߂邱�Ƃ����߂܂����B
���{�ɋً}���Ԑ錾���o�����O�̍Ō�̏T���ƂȂ���31���A���E�~�c�ł͔������q�Ȃǂ̎p�������܂����B
�]�ƈ����������ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă������Ƃ��m�F���ꂽ��_�~�c�{�X�́A31����8��1����2���ԁA�Վ��x�Ƃ��邱�ƂɂȂ�܂����B
����܂łɊ������m�F���ꂽ�]�ƈ���67�l�ƂȂ��Ă���Ƃ������ƂŁA�X�̓�����ɂ͋x�Ƃ�m�点�鎆������o����Ă��܂����B
�q�ǂ���A�ꂽ30��̕v�w�́A�u��Ìn�̎d�������Ă���̂Ŋ����������Ă���Ɠ��X�����Ă��邪�A�ً}���Ԑ錾�ɂ�����Ă��܂��Ă���ʂ�����Ǝv���v�Ƙb���Ă��܂����B
��Ј���70��̒j���́A�u�݂�Ȋɂ�ł��邩�炱���ł�����x�������߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�����Ɋ���Ă��܂��Ă���̂ł��������錾���o�邱�Ƃň������߂邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂����B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���_�ސ��2������ً}���Ԑ錾�@����m���u��Õ��O�̌����v�@8/1
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g����A������2���A���{�ɂ��ً}���Ԑ錾�����߂����B1���̐V�K�����Ґ���1258�l�ƁA5���A���Ő�l�����B����S���m���́u�錾�͉��Ƃ��Ă��������������V�i���I�����A��Õ��O�̏�Ԃɒ��ʂ��Ă��錻�������Ăق����v�ƌĂъ|���Ă���B
�����ł͐��쑺�������S32�s����Ώۋ��Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����Ă��邪�A2������ً}���Ԑ錾�����߁B�錾���Ԃ�31���܂łŁA��ނ܂��̓J���I�P�ݔ��������H�X�Ȃǂɂ͋x�Ƃ�v������B�����A����܂ł̗v���ɉ����Ē��~���Ă���唼�̓X�܂ɂ͈����������Z�c�Ƃ����߂�B
�m����1���A�L�Ғc�̎�ނɁu�~�}�Ԃ��Ă�ł����Ȃ��A�����Ƃ��Ă��^�ԏ����Ȃ��Ƃ������Ԃ��ڂ̑O�ɔ����Ă���B���̊�@�ӎ������L���Ăق����v�Əq�ׁA��N�w�𒆐S�ɐl���}���ւ̋��͂����߂��B
���u�Ă̎��v�����S�ɂȂ��Ȃ����v�@�ً}���Ԑ錾�g��@�h���A�^�A�ƊE�ɒQ���@8/1
2��������{�Ȃ�4�{���ւً̋}���Ԑ錾���߂�5���{���Ɂu����(�܂�)�h�~���d�_�[�u�v���K�p����邱�ƂŁA�Ă̏������ꎞ���}�����ό��A�^�A�ƊE�ɑŌ��ƂȂ肻�����B�S���m����s���{�����܂��������s���������~����悤�Ăъ|����ȂǁA�t�������܂�B�������s�͑����̒����������������ɁA�o�Ȃ��������ꂽ�i�D���B
�u����ŁA�ċx�݂̗��s�V�[�Y���̎��v�����S�ɂȂ��Ȃ����v
�������s���𒆐S�Ƀz�e���`�F�[����W�J�����}��_�z�e���Y(���s)�͌��𗎂Ƃ��B���V��}�z�e���ȂǑ��s���Ⓦ���s���̒��c5�z�e���������A31���܂ŋx�Ƃ��邱�Ƃ����߂��B�ً}���Ԑ錾�����x�Ƃ͂��ł�4�x�ځB�u�w�܂��x�Ƃ��x�Ƃ����C�������v�ƒQ���B
�ό�����7��30�����\���������h���{�݂̋q���ғ���(6���A����l)�́A28�E7���B���N�ɓ����Ă���20�`30����ƒ���s�𑱂��Ă���B
�����A�ً}���Ԑ錾�̊g��O�ɂ́A���Ă̍������s�l���͑O�N��5�E3������4�疜�l�Ƃ̐��v(�i�s�a)������Ȃlj��P�X���������n�߂Ă����B���ꂾ���ɗ�␅�𗁂т���ꂽ�ɂȂ��Ă���B
�N���u�c�[���Y���́A�錾�����߂����4�{����8��2���ȍ~�ɔ�������Y����t���c�A�[�̌������~�����߂��B����ґ��ł��A�\�肵�Ă������s���������������\�z�����B
�^�A�ƊE�̑Ō����傫���B�i�q�����{��7��30���A�����̘A���Ɛї\�z�������C�����A2���A���̍ŏI�Ԏ��ɂȂ�Ƃ����B�؍��p���햱���s�����́u(���~�Ȃǂ�)�w�������ꎞ�x�ɋً}���Ԑ錾�����߂����Ƃ����̂͒ɂ��v�B
��͂̎R�z�V�����̗��p�́A�R���i�БO�Ɣ�ׁA3�����x�̐����ɂƂǂ܂�B�����A8���ɂ͉ɓ]����Ɨ\�z���Ă������A��Y�����錩���݂��B�؍����ً͋}���Ԑ錾�̉e���ɂ��āu�܂��D�荞�ݐ�Ă��Ȃ�����������v�Ƃ��A�Ɛт�����ɉ��U�ꂷ��\�������������B
�������܂������s���~���߂� �ً}���Ԑ錾�g��S���m����@8/1
�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ̒n�����Ԃ̊g����āA�S���m����́A�����̋}�g��ւ̑Ή��Ȃǂ����c���A�������܂������s��A�Ȃ̌������~�����߂邱�Ƃ����߂��B
�S���m�����E�ѐ�Ö哿�����m���u(�����҂�)3���A����1���l�����B��5�g�Ƃ������A���������Ƃ����Ă��ߌ��łȂ��B���O����}���Ă���v
���挧�E����L���m���u�����͂̋����َ͈����B�O�ᓥ�P�̑�ł́A��ɏ���Ȃ��v
���Q���E�������L�m���u��ϐS�ꂵ�����A�Ă̋A�Ȃ͂�����x�l���Ă������������v
���c�ł́A�ċx�݂₨�~�ȂǁA�l�̈ړ��������鎞���̊����}�g��ւ̊�@�����������ŕ\������A�s���{�����܂������s��A�Ȃ̌������~��A���l�����߁A��ނȂ��ꍇ�́A���O��PCR��������悤�Ăт����邱�Ƃň�v�����B
�������A�ً}���Ԑ錾�̑S���ւ̊g��ɂ��ẮA�^�ۂ������ꂽ�B
���N�`���ڎ���߂����ẮA�s����ȋ����ւ̕s�������o�����ق��A�ڎ헦�Ȃǂ𐧌������̖ڈ��Ƃ���u�o���헪�v�ɂ��Ă��A�����E���M����悤���{�ɋ��߂Ă���B
�����{�m���u�S����Ăɋً}���Ԑ錾�߂��ׂ��v�E�E�E�S���m����Œ�ā@8/1
�V�^�R���i�����g��h�~�̑�ɂ��āA���{�m����1���ɊJ���ꂽ�S���m����ŁA�S����Ăً̋}���Ԑ錾�𐭕{���Ăє��߂���悤��Ă����B
�S��44�s���{���̒m�����I�����C���ňӌ������킵���B���ً̋}���Ԑ錾��2������31���܂Ŏ�s���Ƒ��A�����6�s�{���Ɋg�債�Ĕ��߂���邪�A���{�m���͓s���{���P�ʂ̑��Ŋ�����}���邱�Ƃ͋ɂ߂ē���ƌ��y�B���N4���Ɠ��l�A�S����ΏۂƂ����ً}���Ԑ錾�̔��߂̌����𐭕{�ɋ��߂�ׂ��Ƃ����B
���̂ق��A�ړ��̎��l���b�̍ۂ̃}�X�N���p�����Ƃ��ċ������߂邱�Ƃ���Ă����B�����̈ӌ��͑S���m����Ƃ��ċ߂����{�ɒ���B
���ً}���Ԑ錾�ŕ� ���傤�ōŌ�̊C������ɂ��키 ��t �@8/1
�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɐ�t�����lj�����邱�Ƃ��āA��t�����ł͊J�݂���Ă������ׂĂ̊C�����ꂪ2���A������܂��B�����A���Ƃ��Ō�̊J�݂ƂȂ�َR�s�̊C������́A8��1���������̋q�łɂ�����Ă��܂����B
��t�����ł͂��Ƃ��A���킹��11�̊C�����ꂪ�J�݂���Ă��܂����A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ւ̒lj����A8��2�����������܂��B
���̂����َR�s�ł́A7��22������4�����ŊJ�݂���Ă��܂������A���ׂĕ�����邱�ƂɂȂ�A���Ƃ��̊C������̊J�݂�8��1���ōŌ�ƂȂ�܂��B
���̂����َR�w����߂��k���C������́A�ߑO9�������ɂ́A�ꕔ�̒��ԏꂪ���ԂɂȂ�A�����̉Ƒ��A��Ȃǂłɂ�����Ă��܂����B
�C�����ɖK�ꂽ60��̏����́u�C�����ꂪ�܂�̂͒m��܂���ł������A�������g�債�Ă���̂ł��������Ȃ��Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
��t�����ŕ������C������ł́A���C�t�Z�[�o�[�ɂ��p�g���[���Ȃǂ̈��S��𑱂��邱�Ƃ��������Ă��܂����A�����̂⌧�́u�Ď��̂Ȃ��C�͔��Ɋ댯�Ȃ̂ʼnj���Ȃ��łق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
���ً}���Ԑ錾�̊g��u1�T�Ԓx���v ����̈�t���ߒɁ@8/1
1���A�����ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ���3058�l�ŁA��T���j���̐挎25���ɔ�ׂĖ�1.7�{�ɑ����Ă��܂��B31����4058�l�͉���������̂́A�����5���A����3000�l���z���܂����B�d�ǎ҂�31������6�l������101�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����1���̊����Ґ���N��ʂɌ��Ă݂�ƁA20���30�オ���|�I�ɑ����A����2�̐���Ŕ����ȏ��߂Ă��܂��B
�����āA�C�ɂȂ�̂̓��N�`���̐ڎ�ł��B�挎30���̔��\��65�Έȏ�̖�73����2��ڂ��I���Ă�����̂́A�l���S�̂Ō���Ɩ�28���ɂƂǂ܂��Ă��܂��B�\���ɂ����Ƃ����������Ă��܂��B
���������Ȃ��A�s���̎���×{�Ґ��͖�1�J���O����10�{�ȏ�ɋ}�����A31���ɏ��߂�1���l���܂����B����2������ً͋}���Ԑ錾�̑Ώےn�悪6�s�{���Ɋg�傳��܂��B
�����Ŋ���1000�l���@2������ً}���Ԑ錾�@8/1
31���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂́A����1000�l���A��2�{4���ō��킹��1706�l�ƂȂ�܂����B
�����̋}�g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����ŁA2��������ɋً}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����邱�ƂɂȂ�A�e�{���͊�����̓O��������Ăт����Ă��܂��B
31���ɔ��\���ꂽ�V�^�R���i�̐V���Ȋ����҂́A��オ1040�l�A���ɂ�329�l�A���s��199�l�A�ޗǂ�59�l���ꂪ45�l�A�a�̎R��34�l�ŁA��2�{4���ō��킹��1706�l�ƂȂ�܂����B
����1��������̐V���Ȋ����҂�1000�l����̂́A3��ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă���5��8���ȗ��ł��B
���̂ق��A���ɂ�5���A����250�l���������ق��A���s�ł͉ߋ��ő��ƂȂ�199�l�ƂȂ�ȂǁA�e�n�Ŋ����̋}�g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
����A�������ĖS���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B
�����������A2�����獡�����܂ŁA���ɋً}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����܂��B
�e�{���́A�ΏۂƂȂ���H�X�ւ̎�ނ̒�~�Ȃǂ�ʂ��āA���H�̏�ł̊������X�N��l�o�̗}���ɂȂ��Ċ����g���H���~�߂����l���ŁA�[�u�ւ̋��͂ƁA������̓O��������Ăт����Ă��܂��B
���ً}���Ԑ錾�O���̑��@���J�c�X�u���o���������v�@8/1
���{��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����߂����O���ƂȂ���1���ߌ�A���E�~�i�~�ɂ�����J�c�`�F�[���u��������ܓ��ږx�X�v�ɂ́A�J�b�v����Ƒ��A��炪���X�ƖK�ꂽ�B2������͎�ނ����X�ɂ͋x�Ƃ��v������A���X�ł͎�ނ̒�����߂�\�肾�B�q��͖��c�ɂ������ɁA�����̋��J�c�ƃr�[�����y���B
�ߌ�1���߂��A�X���͑吨�̋q�łɂ�����Ă����B�o���Ɗό������˂ē����s���������K�ꂽ�Ƃ�������(38)�́u�O�ł��������ނ̂͋v���Ԃ�Ȃ̂ł��������v�ƏΊ���݂����A�u������Ă��Ă��ǂ��Ŋ������邩������Ȃ����A�ŏ���(�錾���o��)�����Ɣ�ׂ�ƃR���i����݂����Ȃ��̂͂���v�Ƙb�����B
�u�����Ґ��������Ă����̂�(�錾��)�o�邩�Ǝv���Ă͂������A������������ł��Ȃ��Ȃ�̂͂����v�B���X�̒��������X��(38)�͌��𗎂Ƃ��B�����ŋ߂̔���グ�́A���H�X�Ɏ�ނ̒�~���v�����ꂽ3�x�ڂ̐錾��(4��25���`6��20��)�Ɣ�ׂ�ƁA��1�E5�{�ɉ��Ă����Ƃ����B
�ċx�݂₨�~���}���邱�̎����͊ό��q�������A��N�Ȃ�Ή҂����B����Ȃ锄��グ�������҂��ꂽ���A�����ł��Ȃ���q���͉��̂��B�u�悪�����Ȃ��B�������������Ȃǂ��g���Ă���Ă��Ă��邪�A�̗͂̂Ȃ��X�͂����ԋꂵ���͂��v
���X�́A���{�������������Ă���X��F����u�S�[���h�X�e�b�J�[�v���擾���A�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k���ނ̒��l�Ȃǂ̗v���ɉ����Ă������A�v���ɏ]�킸�A�[��܂Ŏ�ނ̒𑱂�����H�X������B�����X���́u�s���͈��H�X���ЂƂ�����ɂ����A�X�e�b�J�[���擾���ċ��͂��Ă���X�ɂ͎��Ԃ����肵�Ď��̒�F�߂�ȂǁA���ʉ����K�v�ł͂Ȃ����v�Ƒi�����B
���ً}���Ԑ錾�O�� �x�ƌ��߂����H�X����͌˘f���̐��@8/1
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ŁA2������ً}���Ԑ錾���K�p�������ł́A��ނ������H�X�Ȃǂɂ͋x�Ƃ��v������܂��B�x�Ƃ����߂����H�X����́A�˘f���̐���������܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g����āA2������A���ɂً͋}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����A���{�́A�������{���̈��H�X�Ȃǂɋx�Ƃ�v������ƂƂ��ɁA���Ȃ��ꍇ���c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łɒZ�k����悤�v�����܂��B
���E�~�i�~�ɂ���Ă����X�́A�����̐l���ċx�݂ɓ��邨�~�܂łɋq����������ƌ�����Ŏd������ς܂��Ă��܂������A�v���ɉ����A2������̋x�Ƃ����߂܂����B
�x�Ɨv���̊��Ԃ͍������܂łŁA1���̂����ɋq�ɒł��Ȃ��������Ȃǂ́A�p��������Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B
�Ă����X�̓X��A����������́A�u�U����̂��A�������ق��Ăق����Ƃ����̂��{�S�ł��B�Ă����X�Ȃ̂ŁA�w���Ƃ��͂o��������x�Ƃ�����������܂����A���Ɏ��͕t�����Ŏ����o���Ȃ��̂͒ɂ��̂ŋx�Ƃ�����܂���B�������ʂ̌`�ʼnc�Ƃł���悤���������܂��Ăق����ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
���D�y�s162�l���� �O�T����{�� �c�����ȏ��"�o�H�s��" �@8/1
�D�y�s��8��1���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂�162�l(���ėz��1�l)�m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B���҂̔��\�͂���܂���B
�����҂͔���\�܂�10�ォ��80���162�l(���ėz��1�l)�B5���A����100�l������A80�l�������O�̏T�̓��j�������2�{�ɑ����B�ً}���Ԑ錾�������2�Ԗڂ̐��ƂȂ�܂����B
�����͂������Ƃ����C���h�^�ψكE�C���X�E�f���^���́u�����^���v��35�l�m�F����܂����B
�D�y�s���ł̃f���^���^���́A�v585�l(����8�l�m��)�ł��B
1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A�u50.3�l�v�Ɓu�ً}���Ԑ錾�v�̖ڈ��ƂȂ�u25�l�v��12���A���ŏ���A�������Ă��܂��B
�g�p�a������7��31�����_�ł����ɑΉ��ł���543����209���Ŗ�38���A�a�@�ȊO�̏h���×{�{�݂⎩��ҋ@�҂�31�����_�Ōv915�l�ƑO������157�l�����A900�l���܂����B
�V���ȃN���X�^�[�͊m�F���ꂸ�A�����N���X�^�[���g�債�Ă��܂��B
�X�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�A������"��̊X"�֘A��6�l�m�F����A311�X��1182�l�ƂȂ�܂����B
162�l���A��������88�l�̊����o�H���s���ŁA�d�ǎ҂͑O������1�l����4�l�ƂȂ�܂����B
���{�́u�ً}���Ԑ錾�v�𓌋��s�A���ꌧ���������������ŁA��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{��lj��A�k�C���A�ΐ쌧�A���s�{�A���Ɍ��A�������Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p���邱�Ƃ����߂܂����B���Ԃ�8��2������31���܂łł��B
�k�C����2������D�y�s���܂h�~�[�u�̋��Ƃ��A���H�X�ł́u��ނ̒��I�����l�v�v�������A���Z�v����1���ԌJ��グ�ߌ�8���܂łƂ��܂��B�O�o���l�A�������l�v���ɉ����A�����{�݂̌����x�ق��p�����܂��B
�D�y�s�͎s�c�n���S�Ǝs�d�̏I�d���20������30���J��グ����5������J�n�B�����w�Z�Ȃǂł̏C�w���s��9���ȍ~�ւ̉�����v���B�����{�݂͎s���̌��N�ێ���q�ǂ��̌��S�Ȑ������i�̊ϓ_������ɕK�v�Ȏ{�݂������A�����x�قƂ��܂��B
���o�b�n����!?�����ܗցu����Ă悩�����v��77�����I�@8/1
����Ɏ��܂�Ȃ��V�^�R���i�E�C���X�̉e���ɉ����A�J��̃h�^�o�^�������ĊJ�ÑO�͔ے�I�Ȑ������|�I�ɑ������������ܗցB�������A�����J�����Ă݂�Γ��{�I��c���ߋ��ő��̋����_�������l������劈��ƂȂ�A���ϋq�ł��傢�ɐ���オ���Ă���B
�J���O��6���ɂƂ����{���̃A���P�[�g�ł́A�u�����ܗւ͊y���݂ł����H�v�Ƃ�������ɑ��A�����ȏ�̐l���u�������Ȃ��v�u�Ō�܂Ŋy���߂Ȃ��v�Ɖ��Ă����B
�������ܗւ͊y���݂ł����H�@(6��23���`25������)
�y���݁F16��
���͊y���݂ł͂Ȃ����A�n�܂�Ίy���߂����F31��
�Ō�܂Ŋy���߂Ȃ��Ǝv���F30��
�������Ȃ��F23��
�������A�J����̂��܁u�����ܗւ͊J�Â��ėǂ������Ǝv���܂����H�v�ƃA���P�[�g�������Ƃ���A����77���̐l���J�Â��Ă悩�����ƉB���_�͂�������t�]���Ă��܂������Ƃ��킩��B
�������ܗւ͊J�Â��ėǂ������Ǝv���܂����H�@(7��27���`7��30������)
�͂��F77��
�������F23��
�J�Â��Ă悩�����Ǝv�����R�Ƃ��ẮA�u�ŏ��͔��ł���������ς茩�Ă��܂��B�I��̊撣��ɂ͊������܂��B���{�̐�����ψ���̐l�I�͑I��ɊW�Ȃ�����v�u�R���i�ЂŖ��邢�j���[�X���Ȃ��������A�I��̑f���炵������̂��A�ʼnƑ��݂�ȂŐ���オ�ꂽ���߁v�Ƃ�����������ꂽ�B
�����ܗ֊J�Ì�A�V�^�R���i�E�C���X�͂��ĂȂ��قNJ����g�債�Ă��邪�A�ܗ֊J�Âւ̔ے�I�Ȑ��͂��قǍ��܂��Ă��Ȃ��B���ʓI�ɂ́A�g�[�}�X�E�o�b�nIOC����������u���{�̕��͑��n�܂�Ί��}���Ă����Ǝv���v�̂Ƃ���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��c�c�B
�������O�A���I��̌Z�������_���A����I��̍ŔN�������_���A���J���E�ɓ������y�A�̑싅�ߊ�̏������_���A�\�t�g�{�[����13�N�Ԃ�����_���Ȃǁc�c���ꂾ���N�����A���_���ς��̂������͂Ȃ����낤�B
�ܗւ̐���オ��ƃR���i�Ђ̎����A�ǂ��炩��I�ԂȂ�Ăł��Ȃ�!?
�@ |
 |


 �@
�@ |
��2������֓���3���ɋً}���Ԑ錾�@8/2
�֓��n���ł�2������A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɐ_�ސ�E��ʁE��t��3���������A�����ɕs�v�s�}�̊O�o�����l����ƂƂ��ɁA���H�X�Ȃǂɑ��Ď�ނ̒��I�����l����悤�v�����Ă��܂��B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂̔��\�́A1���A�����s��3058�l��5���A����3000�l�����ق��A�_�ސ쌧�ʼnߋ�3�Ԗڂɑ���1258�l�A��ʌ���899�l�A��t����767�l�A��錧��202�l�ƁA��ʁE��t�E���͂�������ߋ�2�Ԗڂɑ����Ȃ�܂����B
�����̋}�g��ŁA�֓��n���ł�2������ً}���Ԑ錾�̑Ώےn�悪�L����A�����ɐ_�ސ�A��ʁA��t��3���������܂����B
�����͂����������31���܂łŁA�����ɕs�v�s�}�̊O�o�����l����ƂƂ��ɁA�����S��̈��H�X�ȂǂɎ�ނ̒��I�����l���A�c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łƂ���悤�v�����Ă��܂��B
�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɉ���邱�Ƃɂ��āA�_�ސ쌧�̍���m����1���A�u�܂h�~���d�_�[�u�������Ă������Ŋ����҂������Ă���̂́A�O�o�̗}���Ȃǂ��\���Ɏ���Ă��炦�Ă��Ȃ����Ƃ�����Ǝv���B�����͈�Õ��O�̏ŁA�~�}�Ԃ��Ă�ł����Ȃ��A���Ă������Ȃ��A�^�ԂƂ��낪�Ȃ��A�����������Ԃ��ڂ̑O�ɔ����Ă���v�Ƒi���܂����B
�܂��A��ʌ��̑��m�����u��Ë@�ւ��������A�ق��̈�Âɂ�������o���˂Ȃ���@�I�ȏ��B�ی����ւ̉����ȂǑԐ��������������v�Əq�ׂ܂����B
����ʁE��t�E�_�ސ�E���ɋً}���Ԑ錾�A31���܂Łc�S��Ŏ��~�@8/2
���{��2���A�V�^�R���i�E�C���X��Ƃ��āA��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ɋً}���Ԑ錾�߂����B�Ώےn��́A���ߒ��̓����s�A���ꌧ�ƍ��킹�A�v6�s�{���Ɋg�債���B�k�C���A�ΐ�A���s�A���ɁA������5���{���ɂ́A�V���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p�����B���Ԃ͂������31���܂ŁB
����1���A���@�Ō����J���Ȋ����炩��ŐV�̊����ɂ��ĕ����B
�V���ɋً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ƂȂ�����t�A��ʁA����3�{���ł́A�S���ΏۂɁA���������H�X�ɋx�Ƃ�v�����A����ȊO�̈��H�X�ɂ��ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v������B�J���I�P�X�̋x�Ƃ��v������B
����܂œƎ��̑��i�߂Ă����_�ސ쌧�ł́A���H�X�ւ̎��Z�c�ƂƎ�ޒ�~�̗v�������S��Ɋg�傷��B
�d�_�[�u�̑Ώےn��ł́A�ߌ�8���܂ł̎��Z�v���ɉ����A�����Ƃ��Ď��̒�~�����߂�B�u�����������X���ɂ���ꍇ�v�Ɋ�����ȂLj��̗v�������X�Ɍ���A�m���̔��f�Ōߌ�7���܂Ŏ��̒�F�߂�B
���Ȃǂ́A�����̗̂v���ɉ����Ȃ��X�܂����邽�߁A���H�X�ւ̌�������������ق��A�H�������ł̏W�c�ɂ��������l�̌Ăт�������������B
���{�́A�s�v�s�}�̊O�o���l��e�����[�N�ւ̋��͂��Ăт�����ق��A�����ܗւ͎���ł̊ϐ���Ăт�����B���N�`���ڎ�ł́A�������{�ɂ͑S������4����2��ڂ̐ڎ���I���邱�Ƃ�ڎw���B�V�K�����҂̑������߂��N�w�ւ̓������������߂�l�����B
�����r�m���u�s�������Ȃ��Łv�@�ً}���Ԑ錾�A2������1�s3���Ɋg�� �@8/2
�����s�̏��r�S���q�m����1���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����āA2�����瓌���ɉ����A��ʁA��t�A�_�ސ�̎�s��3�����ً}���Ԑ錾�̊��Ԃɓ��邱�Ƃɂ��āu�s�������z���Ȃ��悤�ɁA�e�����[�N�̓O������Ă������������v�ƌĂъ|�����B�s���őS���m����ɏo�Ȃ�����A�w�̎�ނɉ������B
�����s�̊����Ґ��͂��̓��A3058�l�ƂȂ�A5���A����3000�l�����B�����Ґ��̔��\15���O�ɕw�̑O�Ɏp�����������r����1�s3���ɋً}���Ԑ錾���g�傷�邱�Ƃɂ��āu����Ő錾�ł��낢�܂����B����300���l���A��{�I�ɏo�ƒʊw�ŁA�����Ă��܂��B�ʊw�̕������A�ċx�݂��Ȃ��Ƃ��Ă��A�o�̕����̓e�����[�N��O�ꂵ�Ă��������v�Ƃ��ēs�������z���Ȃ��悤�ɋ��߂��B
����ŁA���r���́A����ɐ旧�s���̎��@��ł̎�ނŁA�����ܗւ̊J�Ìp���̈ӎv�������u�z���ƂȂ���W�҂̔����͍����B�C�O�Ƃ������͍����̊��������������Ƃ��邱�Ƃɐs����v�Əq�ׂ��B
���ً}���Ԑ錾 ���傤����6�s�{���Ɋg�� 5���{���ɏd�_�[�u �@8/2
�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn���2������A��s����3���Ƒ�オ�����6�s�{���Ɋg�傳��܂����B���{�́A�����͂̋����ψكE�C���X�u�f���^���v�̍L����ŁA����܂łƂ͋ǖʂ��قȂ�Ƃ��āA�����Ɗ�@�ӎ������L���A�����̗}�����݂ɂȂ������l���ł��B
�V�^�R���i�E�C���X��ŁA�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn���2������A�����Ɖ���ɁA��ʁA��t�A�_�ސ�̎�s����3���Ƒ�オ�����A6�s�{���Ɋg�傳��܂����B
�܂��A�k�C���A�ΐ�A���ɁA���s�A������5���{���ɂ́A�܂h�~���d�_�[�u���K�p����A���Ԃ́A�����Ɖ���̐錾�̊�������������A�������8��31���܂łł��B
�����s�ł́A1���ɁA���j���Ƃ��Ă͏��߂�3000�l����ȂǁA�V���Ȋ����҂͑S����4��������1���l���܂����B
�����}�g��̗}�����݂ɂ͈ꍏ�̗P�\��������Ȃ��Ƃ��đS���m����́A1���A���~�̋A�Ȃ��܂߉ċx�ݒ��̓s���{�����܂������s��ړ��͌������~�E��������悤�����Ăт����邱�ƂȂǂ����ɋ��߂邱�Ƃ����߂܂����B���{�́A�����͂̋����ψكE�C���X�u�f���^���v�̍L����ŁA����܂łƂ͋ǖʂ��قȂ�Ƃ��Ă��āA�c�������J����b�����X�N�̍����s�����T����悤�A�����Ƌ��͂��Ăт����܂����B
�錾�̑Ώےn��ł́A���H�X�Ɏ��̒�~��v������ƂƂ��ɁA�d�_�[�u�̓K�p�n��ł��A�����A���̒�~��v�����A�ł������������������ȂNJ������O�ꂷ�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�܂��A�H�c��ɒO�Ȃǂ̋�`����k�C���≫��A�����Ɍ������ւ𗘗p����l�ɖ�����PCR���������{����ȂǍ����Ɗ�@�ӎ������L���A�����̗}�����݂ɂȂ������l���ł��B
���ً}���Ԑ錾�A��s���E���ɔ��߁@6�s�{���Ɋg��A�����܂Ł@8/2
���{��2���A�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾����ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ɔ��߂����B�錾�ɏ������u�܂h�~���d�_�[�u�v�����ւ�����B�����͍������܂ŁB�錾�Ώۂ͔��ߒ��̓����s�A���ꌧ�ƍ��킹6�s�{���Ɋg�債���B
�k�C���A�ΐ�A���s�A���ɁA������5���{���ɂ͐V���ɏd�_�[�u��K�p�B�����͓������������܂ŁB�錾�A�d�_�[�u�̒n��ł́A���H�X�Ɍߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v������B��ޒ́A�錾���ł͈ꗥ��~�B�d�_�[�u�̋��ł͌�����~�Ƃ��A�u���������~�X���v�̏ꍇ�Ɍ���A���̊�������u���邱�ƂȂǂ������Ɍߌ�7���܂ŔF�߂�B
�����̗̂v���ɉ����Ȃ��X�܂��ڗ����߁A�������������A����������Ɏ��g�ށB�H�������ł̈����̎��l�������������߂�B
�ċx�݂��}���钆�A���{�͐l�̗���̑����������g��ɂȂ��邱�Ƃ��x���B�s�v�s�}�̊O�o���l��e�����[�N�ւ̋��͂��Ăъ|����B�����ܗւ͎���Ńe���r�ȂǂŊϐ킷��悤���߂�B�Ⴂ����ւ̃��N�`���ڎ�ɗ͂����A�������܂łɑS������4����2��ڎ���I���邱�Ƃ�ڎw���B
��2��������Ɂu�ً}���ԁv���� ���s�Ɂu�܂h�~�[�u�v�@8/2
�V�^�R���i�E�C���X���2������A���ɋً}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɁA�܂h�~���d�_�[�u���K�p����܂����B3�{���ł́A����31���܂ł̊��Ԓ��A�W���I�ȑ���u���邱�ƂŁA����ȏ�̊����g���H���~�߂����l���ŁA�{�����ւ̌Ăт��������߂Ă������j�ł��B
����2�{4����1�����\���ꂽ�V�^�R���i�̐V���Ȋ����҂́A��オ890�l�A���ɂ�317�l�A���s��166�l�A�ޗǂ�77�l�A���ꂪ44�l�A�a�̎R��33�l�̂��킹��1527�l�ŁA6���A����1000�l���܂����B
�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����A2��������ɋً}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɁA�܂h�~���d�_�[�u���K�p����3�{���́A�ΏۂƂȂ���H�X�Ȃǂւ́A��ނ̒�~�v���Ȃǂ̑[�u�ɓ��ݐ�܂����B
����Ɋ֘A���āA���{�̋g���m���́A�u�������O�ꂵ�āA��5�g���ł��邾���Ⴂ�R�ɂ��Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�w�܂����x�w���x���������Ƃł͂Ȃ����x�Ǝv���邩���m��Ȃ����A�������ɏd�v�Ȏ����Ȃ̂ŁA���Ћ��͂����肢�������v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A1���A�C�������Ɍ��̍֓��m���́A�S���m����̃I�����C����c�ŁA�u���~�ɋA�Ȃ���l���������A�������A�F�B�ƏW�܂��Ĉ��݂ɍs���̂͂��܂A�ƂʼnƑ��Ɖ߂����܂��傤�Ƃ������b�Z�[�W����̓I�ɓ`���Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
3�{���ł́A����31���܂ł̊��Ԓ��A�W���I�ȑ���u���邱�ƂŁA����ȏ�̊����g���H���~�߂����l���ŁA�{�����ւ̌Ăт����������������߂Ă������j�ł��B
���ً}���ԁA���Ȃ�6�s�{���Ɋg��@�ς��ʒʋΕ��i�@8/2
�V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾��2���A��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ɓK�p���ꂽ�B���łɓK�p����Ă��������s�Ɖ��ꌧ�ƍ��킹�A�Ώۂ�6�s�{���ɍL�������B���Ԃ�31���܂ŁB�����͈̂��H�X�ɉc�Ǝ��Ԃ̒Z�k���ޒ̒�~��v������Ȃǂ��Ċ����g���}����B
�錾�ɏ�����[�u���Ƃ��u�܂h�~���d�_�[�u�v��2������31���܂ŁA�k�C���A�ΐ�A���s�A���ɁA������5���{���ɓK�p�����B5���{���͊��������P����܂őΏےn��Ŏ�ޒ̒�~�����߂�B�k�C���͎D�y�s�A�ΐ쌧�͋���s�A���s�{�͋��s�s�A���Ɍ��͐_�ˎs�Ȃ�15�s���A�������͕����s�Ȃ�22�s������Ώےn��Ɏw�肵���B
���{�S�̂̐V�K�����҂�1���܂�4���A����1���l���A�������}�g�債�Ă���B�錾��d�_�[�u�̓K�p�����͎̂��Z�c�ƂȂǂ̗v����ʂ��Đl����}����_�����B�����A2�����̎�v�w�Ȃǂ̒ʋΕ��i�ɑ傫�ȕω��͌����Ȃ��B
�h�R���E�C���T�C�g�}�[�P�e�B���O(�����E�L��)�̈ʒu���f�[�^�ɂ��ƂÂ��A�ߑO8����̐l�o��O�T���j����7��26���Ɣ�r�����B�������s�̑�{�w�������ӂ�3%���A��t�w���ӂ�7%���A���s�̔~�c���ӂ�5%���������B���l�w���ӂ�15%�������B�����s�̊ۂ̓����ӂ�1%�������B
�S���m�����1���A���{�ɑ���V�^�R���i��ً̋}�ƂƂ��ɁA���������̃��b�Z�[�W���܂Ƃ߂��B�ċx�݃V�[�Y���͓s���{�������܂������s�E�A�Ȃ������Ƃ��Ē��~�E��������悤�i�����B
���V�^�R���i�V�K������5���A����200�l���āc�@���m�@8/2
�S���ŐV�^�R���i�̊����g�傪�������A���m���̑呺�m���́A�ċx�ݒ��̌����܂������s��A�Ȃɂ��āA���߂Ď��l����悤���߂܂����B
�u�ċx�݊��Ԓ��A�s���{�����܂����ړ��A�ȗ��s�͂�߂Ă������������B�I�����s�b�N�̃p�u���b�N�r���[�C���O�̂悤�Ȃ��̂��A��߂Ă������������v(���m���@�呺�G�͒m��)
�S���ł�2������u�ً}���Ԑ錾�v�̑Ώےn��ɁA��s����3���Ƒ�オ�lj�����A6�s�{���Ɋg��B
�܂��A�k�C���╟���Ȃ�5���{���ɂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����܂����B
���m���́A�V�K�����Ґ���5���A����200�l���Ă��āA�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�\�������邩�ǂ����ɂ��āA�呺�m���́u���T�͓��ɓ��@���Ґ��ɒ������A�q�ϓI���l�Ɋ�Â��đΉ����Ă��������v�Ƙb���܂����B
���������\��́u�f�� �s���v���݁@�錾�Ώۊg������s���v�˂苭���@8/2
2������V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾�̓K�p�Ώۂ��]���̓����s�A���ꌧ�ɁA�_�ސ�A��t�A��ʂ�3���Ƒ��{��������6�s�{���Ɋg�債�A���s�֘A�ƊE�ł́u�܂����v�ƁA���v���ւ̌��O���������ł���B�������S���ł݂�Η\��L�����Z���̓����͍T���߂ŁA��̕ւł̓s�[�N���̍������\������{�̊ό��x����u�f���@�s���@�g���x���v�Ŏ��v������オ���������Ɠ��K�͂��ێ��B�S�苭�����s�֘A���v�ɂ��Đ��Ƃ́u���N�`���ڎ�̊g��Ȃǂňړ����邱�Ƃւ̒�R�����������v�ƕ��͂��Ă���B
�u�ċx�݂̗��s�v������̎����ɍl����l�������B���ꂾ����(�K�p�g���)�\��̉������o�Ă��邩���c�v�B���s�����{���s�̒S���҂ً͋}���Ԑ錾�̈��e�������O����B���~���Ԃ̗\��͌��݁A�O�N��98���ƉX���ɂ��邾���ɕs���͑傫���B
���N�`���ڎ�҂ɑ���Ǝ��̊����T�[�r�X�����{���Ă��闷�s��Ѓr�b�O�z���f�[�̒S���҂��A�u���Ƃ��Ɠ����Ă��鏭�Ȃ��\��܂ŃL�����Z���ɂȂ��Ă��܂��̂ł́v�ƌ��O����B
���ۂɋً}���Ԑ錾�̑ΏۂƂȂ����_�ސ쌧�������̔����n�C�����h�z�e���ł́A50�������x�̃L�����Z�����o���Ƃ����B�\��q�ɑ��A���O�Ɏ�ޒ̒�~��`�����Ƃ���A����߂�ꂽ�P�[�X�����������B�\��S���҂́u8���̗\��͂�����߂Ă���v�ƌ��𗎂Ƃ��B
�����A���s�q��A�ȋq����悹��q��ւ�S���̑S���I�ȗ\����݂�A�����g��͌��O�ޗ��ł͂�����̂́A�����_�ł̉e���͌���I�Ȃ悤���B
�`�m�`�z�[���f�B���O�X�ɂ��ƁA6�`15���̂��~���Ԃ̍������\���́A�O�N�������3���ȏ�L�тĂ���B���Ƀs�[�N����1��9�����ȏ�Ƃ��������́u�f���@�s���@�g���x���v���Ԓ���������N11���̘A�x���Ɠ��K�͂Ƃ����B
���Ђ̕��V��Y�ꖱ��7��30���̗ߘa3�N4�`6�������Z��Łu(������)�o�b�q�����Ȃǂ�ϋɓI�ɎȂ��獑���ړ����Ă���̂��ȂƎv���B�\���͒ቺ���邱�ƂȂ��i��ł���v�Ɛ��������B
�S���ł��A�i�q�����{�����\�����V�����̗\��Ȑ�����N�Ɣ�r����ƁA�k�C����28�����A���k48�����A��z33�����Ȃnj����݉��Ă���A�L��S���҂́u�[���ȏł͂Ȃ��v�Ƃ����B
�q��E���s�A�i���X�g�̒��C�����N���́A���݂̊����g��ɂ��āu�\�f�������Ȃ��v�Ƃ������A�u�����ɂ��Ă��������X�N�͂���B����Ȃ���N�`���ڎ�̊g��Ȃǂ�����A�����������n�������ė��s������Ƃ̔��f�ɂȂ��Ă���̂��낤�v�Ƙb���B
���������E�����u�ً}���Ԑ錾�Ŋ�����}����v�Ƃ����d�g�݁`�@8/2
�j�b�|�������u�ѓc�_�i��OK! Cozy up!�v(8��2������)�ɃW���[�i���X�g�̐{�c�T��Y���o���B�����Ɖ���ɉ����A�V���ɍ�ʁA��t�A�_�ސ�A��オ�Ώےn��ƂȂ�ً}���Ԑ錾�A�܂��A�k�C���A�ΐ�A���s�A���ɁA������5���{���ɓK�p�����܂h�~���d�_�[�u�ɂ��ĉ�������B
�V�^�R���i�E�C���X��œ����Ɖ���ɔ��߂���Ă���ً}���Ԑ錾�́A8��2�������ʁA��t�A�_�ސ�̎�s��3���Ƒ����Ώےn��ƂȂ�B�܂��A�k�C���A�ΐ�A���s�A���ɁA������5���{���ɂ́A�܂h�~���d�_�[�u��K�p�B����������Ԃ�8��31���܂łƂȂ�B
�ѓc)�Ώےn�悪�g��A�܂h�~���d�_�[�u��5���{���ɓK�p�Ƃ������Ƃł��B
�{�c)�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ̑[�u�ɂ���Đl����}���A������}����Ƃ����d�g�݂��A�������E���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ɂ��ẮA���ȉ�̔��g����F�߂Ă���Ƃ���ł��B�ً}���Ԑ錾�o���邱�ƂŁA�ǂꂭ�炢�}������̂��Ƃ����ڏ������Ă��Ȃ��ł͂Ȃ��ł����B���������Ȃ��ŁA�������邱�Ƃ̈Ӗ�������̂��낤���B
�ѓc)�����ł��ˁB
�{�c)���N�`���ڎ�ɂ͈��ȏ�̌��ʂ��F�߂��Ă��āA�{���ł���A�S�z����Ă�������҂̊������h�����Ƃ��ł������A�d�lj���}���邱�Ƃ��ł����B���ܒ��S�ƂȂ��Ă���͎̂Ⴂ�l�����Ƃ������ƂɂȂ�̂�����ǂ��A�Ⴂ�l�����ւ̃��N�`���ڎ킪���ɂȂ�̂��A���̃X�P�W���[���̖ڏ��ɂ��Ă��A������Ə����o���ׂ��ł����A���̕ӂ�Ƃ̐��������Ȃ��Ȃ��o�ė��܂���B
�ѓc)�}���邽�߂ً̋}���Ԑ錾�͏o�Ă��A�u���N�`�����i�߂v�Ƃ����Ƃ��낪�����ė��܂����ˁB
�{�c)���H�X�ɑ���x�Ɨv���́A�����܂ł��v���ł�����A����ɏ]�����]��Ȃ����Ƃ�����肪����B���邢�́A�A���R�[���ނ̒��l�ɂ��Ă��A�ǒ��ʒB�̂悤�Ȃ��̂����o�Ă��Ȃ��āA�@���ɂȂ��Ă��Ȃ��B�ǂ��܂ŋ����͂����Ă�̂��B�����ł́A����ɏ]��Ȃ��X���ǂ�ǂ�o�Ă��āA�l�������������A������オ���Ă���B�����Ȃ�ƁA�v���ɏ]���Ă���X�Ə]���Ă��Ȃ��X�ɍ����o�āA�s�����������܂�Ă���B����ɑ��āA�ǂ��Ή�����̂��Ƃ�����̍����Ȃ��B�s���{���ɂ��Ȃ���A���ɂ��Ȃ��Ƃ����ŁA�u�o�����̂����珟��ɂ��v�ƁA�ǂ����˂��������悤�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂���ˁB
�ѓc)��������ƁA�u��������ɂ�邼�v�Ƃ����l�����������Ă��܂��܂���ˁB
�{�c)���������Ƃ���Ɋ�@�����o�����̂ł��傤�B�����ɗ��đS���m����́u���b�N�_�E���v�̂悤�ȋ����[�u�̌����荞�ً}���܂Ƃ߂܂������A�u���b�N�_�E���v�Ƃ����Ȃ茾���Ă��ƁB
�ѓc)�s�s�����Ƃ������܂����B
�{�c)�����͂��Ă��̂ł���A���܂̖@�̘g�g�݂̂Ȃ��ł͂ł��܂���B��̓I�Ɍ����A�������낤�Ƃ����ꍇ�A���@�ᔽ�ɂȂ��Ă��܂��B���Ɍ��@22���́A�`���I�ɂ͐E�ƑI���̎��R�Ȃ̂�����ǂ��A�����I�ɂ͌o�ϊ����̎��R�ł�����A�����ɒ�G���Ă��܂��̂ł��B�����̐��������l���Ȃ��ŁA�m����́u���b�N�_�E�����v�ƌ����B���̕ӂ���ǂ��l���Ă���̂ł��傤���B
�ѓc)�����ł���ˁB���܂̖@�̌n�̂Ȃ��ŁA�������������ċ�̓I�ɕs���v�������ƂȂ�ƁA��i�ł��邱�ƂɂȂ�܂�����ˁB���̂Ƃ��̈���͂ǂ��Ȃ̂��Ƃ������ƂŁA�s���{���m�������̑���ɂȂ�̂��A���̊o�傪����̂��ƁB
�{�c)����Ő����O�ɁA�A�����J�̃j���[���[�N�̃}���n�b�^���Ń��X�g�������o�c���Ă���l�Ə����b�������̂ł��B��͂�c�Ǝ��l��v������āA�u�ǂ����悤���v�Ɩ����Ă�����A�����Ȃ�100���h�����U�荞�܂�ė����Ƃ����̂ł��B
�ѓc)�����Ȃ̂ł����B
�{�c)�����āA�]������Ԃ��Ă��������ƁB
�ѓc)�O�n�������ł����B
�{�c)�O�n�������ŁA�\���߂���قǂ̊z�ł��B��������ƁA�u�\���ȕ⏞��������A��߂Ă������v�ƂȂ�B�⏞���s�\���ŋ��z�I�ɂ��킸���ł���A�����ɐU�荞�܂�Ă��Ȃ��Ƃ����̂����{�̏ł��B7�����͑O�|��������ǂ��A����܂ł̕��͂ǂ������炢���̂��ƁB
�ѓc)�c�Ƃ̎��R�͓��R�A���O�����@�ɂ����邵�A�����̕����͓O�ꂵ�Ă��܂��ˁB
�{�c)���̕ӂ�A���{���{�͉�������Ă��u�тɒZ���F�ɒ����v�̂悤�ȏɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ً}�錾���߂�4�{���A�ʋq�̑傫�Ȍ�������ꂸ�c �@8/2
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A���{��2���A��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ŋً}���Ԑ錾�߂����B���łɔ��ߒ��̓����s�A���ꌧ�ƍ��킹�A�Ώےn���6�s�{���Ɋg�債���B�k�C���A�ΐ�A���s�A���ɁA������5���{���ɂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p�����B���Ԃ͂������31���܂ŁB���{�͐l���}���̂��߃e�����[�N�𐄐i���Ă��邪�A2������4�{���̎�v�w�Œʋq�̑傫�Ȍ����͌����Ȃ������B
�ً}���Ԑ錾���̓s�{���́A���܂��̓J���I�P�ݔ��������H�X�ɋx�Ɨv�����s���A����ȊO�̈��H�X�ɂ͉c�Ǝ��ԒZ�k(�ߌ�8���܂�)��v������B
�ǔ��V�����m�s�s�h�R���́u���o�C����ԓ��v�v�̃f�[�^�𗘗p���A2���ߑO7����̐l�o��1�T�ԑO�̌��j��(7��26��)�Ɣ�r�����Ƃ���A�~�c�w(���s)��4�E3�����A��t�w(��t�s)��3�E8�����ƂȂ������A���l�w(���l�s)��0�E9�����A��{�w(�������s)�������������B
�ً}���Ԑ錾���g�傳�ꂽ�����A�����̒ʋq���s���������l�w(2���ߑO8��3���A���l�s�����)����Ό��o�B�e�ً}���Ԑ錾���g�傳�ꂽ�����A�����̒ʋq���s���������l�w(2���ߑO8��3���A���l�s�����)����Ό��o�B�e
���l�w�ł�2�����A�E��Ɍ������}�X�N�p�̉�Ј��炪�r��邱�ƂȂ����D���o���肵�Ă����B
�w�߂��ɋΖ��悪���铌���s�`��̉�Ј�(23)�́A�u�錾���o�Ă��l�͑S�R�����Ă��Ȃ��B���ʂ����܂��Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ǝ�����������B���s�̉�Ј�(53)�́u����܂ł̔��߂͒��r���[�B��x���߂����Ȃ�A�������啝�Ɍ���܂Ōp�����Ăق����B���Ö�̊J���ɂ��͂����Ăق����v�Ƙb���Ă����B
���w���A�ʋq�ō��G���Ă����B���{�L���s�̉�Ј��j��(69)�́u�����o�ŌߑO10���߂��ɓd�Ԃɏ�������A�ʋq��Ŗ����������v�Ƙb���A���s�Q����̊Ō�t����(40)�́u���������̐l�ɊO�o�����l����C�������Ȃ��Ȃ��Ă���Ɗ�����B��Ì���͑�ςŁA���ʂ����������Ăق����v�Ƒi�����B
��{�w�O�̃z�e���ɂ�2�����A�e�����[�N�v�����̗��p�q���K�ꂽ�B�����g��ɔ����āA�q�����ő�11���ԗ��p�ł���v�����̗\�����A7����120���قǗ��p���������B2���͌ߑO10���܂łɗ\��5������A�S���҂́u�錾���܂����߂���ė��p�q�������邩������Ȃ��B�������O�ꂵ�ĕ�����������v�Ƙb�����B
��t�w�߂��ɂ�����H�X�́A�錾���Ԓ��͖�̉c�Ƃ���߁A�����`�̎��ԑт����X���J���邱�Ƃɂ����B�o�c��(43)�́u�R���p�N�g�ȉc�ƂŐl�����}���Ȃ������Ă��������Ȃ��v�ƌ�����B2�������̋x�Ƃ��������Ă����t�s�̈��H�X��́u�q���������Ă����̂ŁA�錾���o�Ė�̋x�Ƃɓ���肪�����v�Ƃ��ߑ��������B
���ً}���Ԑ錾 6�s�{���Ɋg��@�C��������� �u���ꂿ���������������v�@8/2
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŁA2������ً}���Ԑ錾�̑ΏۂɁA�_�ސ�E��t�E��ʁE��オ�lj�����A�����E����Ƃ��킹�A6�s�{���Ɋg�債���B
�ً}���Ԑ錾�����߂��ꂽ�_�ސ�E���l�s��JR���ؒ��w�O�ł�2�����A�����ƕς��Ȃ��o�Ε��i������ꂽ�B
�X�䂭�l�́u�l�̑����͕��i�ƕς��Ȃ��̂��Ȃ��āB�錾���̂ɈӖ��͂���̂��ȂƋ^��������܂����ǁv�A�u���ꂿ���������������̂ŁA�p���̂Ȃ��Ƃ��͉Ƃɂ��悤���ȂƎv���v�ȂǂƘb�����B
��t���łً͋}���Ԑ錾�ɂƂ��Ȃ��A�����̊C�����ꂪ�����ꂽ�B
��t�s�̂��Ȃ��̕l�C������́A�g�ł��ۂ̐��V�тȂǂ͉\�����A�V�j�͋֎~���ꂽ�B
�K�ꂽ�l�́u�j������Ő����Ƃ��S�������Ă����̂ɁA�j���Ȃ��Ďc�O�v�A�u�C�ł����ς��j�����������v�ȂǂƘb�����B
�ً}���Ԑ錾�̑Ώۂ́A2������6�s�{���Ɋg�債�A�k�C���E�ΐ�E���s�E���ɁE�����ɂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����A���Ԃ͂������8��31���܂łƂȂ��Ă���B
���V�^�R���i�����g��Ō�O��s�̊C�����ꂪ���@�É����@8/2
�V�^�R���i�E�C���X�̊����������ł��g�傷�钆�A��O��s�̊C�����ꂪ8��2������ꎞ������܂����B
�L�ҁu��O��̊C������ł��B�����������m����f�����s���Ă��܂��v
��O��s�́u�}�����p�[�N��O��C������v��7��17���A2�N�Ԃ�ɃI�[�v���������̂́A8��2������ꎞ������܂����B�s�Ȃǂ���߂��V�^�R���i�����h�~��̃K�C�h���C���ɉ����āA���̌x�����x�����u5�v�Ɉ����グ��ꂽ���Ƃ���Ή����܂����B�Ė{�Ԃ̏������ꎞ�ɕ��ƂȂ������ƂɊό�����̒S���҂����_�̐F���B���܂���B
��O��s�ό�����u2�N�Ԃ�̊J��Ƃ������ƂŌ�O��̊C��������y����ł���������Ɗ��҂��Ă��܂������A�����ɂ��ĕ�Ƃ������Ƃő�ώc�O�Ɏv���Ă��܂��v
�����̊C������͍X�ߎ���V�����[���Ȃǂ����p�ł��Ȃ��Ȃ�ق��A����ɗ������y����߂܂��B����ŁA���C�t�K�[�h�͒u���A����̂�h����ɂ�����܂��B�C������̍ĊJ�͌��̌x�����x�����u4�v�Ɉ���������ꂽ���_��\�肵�Ă��܂��B
�������s �V�^�R���i 2195�l�����m�F ���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő� �@8/2
�����s�́A2���A�s���ŐV����2195�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B
�����s�́A2���s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł̒j�����킹��2195�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO���766�l�����āA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B2���܂ł�7���ԕ��ς�3214.4�l�ŁA�O�̏T��206.9���ƂȂ�A����܂łɂȂ��X�s�[�h�Ŋ����̋}���Ȋg�傪�i��ł��܂��B����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A22��3221�l�ƂȂ�܂����B
����A�s�̊�ŏW�v����2�����_�̏d�ǂ̊��҂�1�����13�l�����āA114�l�ł����B110�l����̂͂��Ƃ�2��7���ȗ��ł��B�܂��A2���s���Ŏ��S���m�F���ꂽ�l�͂��܂���ł����B
�����s�̊�ŏW�v����2�����_�̏d�ǂ̊��҂�1�����13�l������114�l���������Ƃɂ��āA���r�m���͓s���ŋL�Ғc�ɑ��A�u�d�ǎ҂́A�����҂̑�������x��ďo�Ă���ƌ����Ă���B40���50�オ�d�ǎ҂̑������߂Ă��āA���ʂ��Ă���̂��A���A�a�⍂�����A������얞�Ƃ������Ǐ�����Ƃ��ƕ����Ă��邱�Ƃ��B�܂��A�قƂ�ǂ����N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l���v�q�ׂ܂����B���̂����ŁA�u40���50��ŁA�܂��ڎ���Ă��Ȃ����X�ɂ́A���N�`���ڎ���ł��邾���������肢�������v�ƌĂт����܂����B�܂��A2������A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɐ_�ސ�E��ʁE��t��3��������������Ƃɂ��āA���r�m���́A�u1�s3���ŋً}���Ԑ錾�Ƃ����`�Ńx�[�X�����ʂɂȂ����B���Гs�⌧�̋����z����悤�Ȉړ�������Ă��������A�܂��A��{�I�ɂƂĂ������E�C���X�ł���Ƃ����F���̂��ƂŊ�{�I�Ȋ����h�~����Ƒ�������ču���Ă������������v�Əq�ׂ܂����B����ɁA���Ǝ҂ɑ��ẮA�u�e�����[�N�̓O��ɉ����āA�d����ł̃}�X�N�̒��p�Ȃǂ��O�ꂵ�Ă��肢�\���グ��v�ƌĂт����܂����B
���z����19%�A�u�ُ�v���铌���@�����u�\�z�����v�@8/2
�����s���ł̐V�^�R���i�E�C���X�̊����������w�W�������݁A�ُ�Ƃ������鐔���ɒ��ˏオ���Ă���B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���3��l���A�s���ł̊����̍L����������z������19�E5%�ɒB�����B��������u�u�w�I�Ɉُ�v�ƌ���ꂽ�N�����̐������͂邩�ɏ���B�s�́A����Ƃ���ɃE�C���X���L�����Ă����ԂƂ݂Ē��ӂ��Ăт�����B
�u�x�݂̓��ɂ��ꂾ���̐l���B�s���ɂ��Ȃ芴�����L�����Ă���낤�ȂƂ��������͂���B�������������ɂȂ�������܂�̂��\�������Ȃ��v
�s�̒S���҂͓��j��������1���A�s���̊����ɂ��Ă����Q�����B���̓��̐V�K�����҂�3058�l�ɏ��A5���A����3��l�����B����܂łœ��j���̍ő�������1763�l(7��25��)��啝�ɏ������B
7����{���瓞�����w�E����Ă����s���ł́u��5�g�v�B����܂ł̕ψي����������͂������ψي�(�f���^��)�̗��s������̔g�̗v���Ƃ݂��邪�A���̔g�͂���܂łƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قNj��剻���A����܂ł̌o���ɂȂ��َ����̔g�̗l����悵����B
�����g��̒��x��\��1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���3105�l(1�����_)�ƁA7��1��(523�l)�̖�6�{�ɒB����B�����Ґ��̑����y�[�X�������V�K�����Ґ��̑O�T���214%�ɏ��A�u�u�w�I�Ɉُ�v�Ǝw�E���ꂽ�N�����̃s�[�N������207%(1��10��)�����B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���ܗ֑I��̐V�^�R���i�����͗}���A�����s�̊����ҋ}���ł��@8/3
�����s���ŐV�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��������͂̋����f���^���̉e���ŋ}�����Ă��邪�A�����ܗ֊W�҂̊����͂���܂ł̂Ƃ����r�I�}������Ă���B
�����ܗցE�p�������s�b�N�g�D�ψ��2�����\���������ɂ��ƁA�V�^�R���i�Ɋ����������W�҂�276�l�������B���̂���1��1000�l�ȏオ�Q�����Ă���I��̊����҂�24�l�ɂƂǂ܂�B���W�҂�40����ȏ���{���ꂽ�o�b�q�����̗z�����͂킸��0.02�����B
���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�L��S���̃}�[�N�E�A�_���X����2���A�u�I��Ƒ��W�ҁA��ʂ̐l�X�̊Ԃɂ͊u���肪����v�ƋL�Ғc�Ɍ�����B�������ł͊O���Ƃ̐ڐG���Ւf����u�o�u�������v���̗p���Ă���A �u���X�N���[���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�\�Ȍ��肻�̃��X�N�����炷���Ƃ��ł���v�Ƃ̌������������B
�������m�F���ꂽ���W�҂̂����A�ł������̂͑��Ɩ����ϑ����鎖�Ǝ҂��144�l�A�����łh�n�b�W�҂��83�l���B�g�D�ψ���́A���ڍׂȊ����ɂ��Ă͌��\���Ă��Ȃ��B
���W�҂̊��������́A7��31���ɉߋ��ő��4058�l�̊����҂��L�^���������s���ł̋}���Ƃ͑ΏƓI���B��s�s���𒆐S�Ɋ����̋}�g�傪�����钆�A���{�͓����s�Ɖ��ꌧ�ɔ��ߒ��ً̋}���Ԑ錾��8�����܂ʼn�������ƂƂ��ɁA�_�ސ�A��t�A��ʂ̎�s��3���Ƒ��{��Ώےn��ɒlj������B
�����s�̗z������7���ԕ��ς�19.5��(7��30�����_)�ƁA7�����ɂق�4�{�ɏ㏸�����B����҂ւ̃��N�`���ڎ���s���钆�A20�|30��̎�N�w���S�Ɋ������}�g��B7���̓��@�Ґ��͌����܂łɔ{������3000�l���A�a���g�p����50���ɔ����Ă���B
�������s�̌��N�ώ@�u���E�ɋ߂��v�A����×{1��2000�l���@8/3
�V�^�R���i�E�C���X�����҂̋}���ɔ����A�����s�ł͎���×{�҂����̖�1�J����12�{�ɑ����A2�����_�ʼnߋ��ő���4���A���ōX�V��12161�l�ƂȂ����B��r�I�Ǐ�̌y���Ⴂ���オ���S�����A�e�̋}�ς̋��ꂪ����A�~�}���������×{�҂�����B�ی����͌��N�ώ@�ɒǂ��A�Ɩ��N���̗v���ɂȂ��Ă���B(���{��)
�s���̐V�^�R���i���҂͖�1�J���O��7��1���A���@��1557�l�A�s�����������z�e���ł̏h���×{��1176�l�A����×{��1006�l�������B
�����A�����̋}�g��ƂƂ��Ɏ���×{���}���B30���ɑ�O�g�̃s�[�N������9442�l(1��18��)����9793�l�ƂȂ�A31���ɂ�10000�l��˔j�B2�����_�œ��@����2�{��3231�l�A�h���×{��1769�l�Ŗ�1�E5�{�ƂȂ������A����×{�̐L�т��ۗ����Ă���B
�s�ɂ��ƁA����҂̃��N�`���ڎ킪�i�݁A�����̒��S���Ⴂ����Ɉڍs�B�ȑO��肷���ɓ��@�ƂȂ�l�̊����͏��Ȃ����A�q��Ă���Ȃǂʼnƒ�𗣂��ꂸ�A����×{����]����l�������Ȃ����Ƃ����B
�����y�ǂ̎Ⴂ����ł��×{���ɗe�̂��}�ς��郊�X�N�͂���B7����{�ɉ��l�s��40��j�����A5���ɂ͋��s�s��20��j�����A�Ƃ��Ɏ���×{���ɗe�̂̋}�ςŎ��S�B�s���ł�1���Ɏ���×{��50�㏗�����S���Ȃ����B
���̂��߁A�ی����͖{�l�ɒ���I�ɓd�b�Ȃǂő̒����m�F���A�s��1���ȍ~�A����×{�҂̃t�H���[�A�b�v�Z���^�[���g�[�B�����̎_�f�O�a�x�𑪂�p���X�I�L�V���[�^�[��ݗ^���A65�Ζ����̎���×{�҂̌��N�ώ@���������B
�������A�×{�҂̋}���œs�̃Z���^�[�ɗ]�͂��Ȃ��Ȃ�A7��28���ȍ~�͊ώ@�Ώۂ�30�Ζ����Ɉ����������B�ی����ɕ��S���W�����邪�A�s�̒S���҂́u�Ή�����Ō�t�̊m�ۂ̓��N�`���ڎ�ȂǂŎ��v�������A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��B�s�����E�ɋ߂��v�Ɛ�������B
�s���̈�t����A�n��̈�t�����f�Ȃǂ̑̐����\�z���邪�A���̑����y�[�X�������ƁA�Ή�������Ȃ��Ȃ�\�������܂��Ă���B�s���j�^�����O��c�̐��ƃ����o�[�ŁA�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v��t�́u���S���S�Ȏ���×{�̂��߂ɂ́A�R���i��f�Ă��Ȃ������J�ƈ�Ȃǂ̋��͂��s�����v�Ƙb�����A��ʐf�ÂƂ̃o�����X�Ȃǂ�����A�̐��Â���͗e�ՂłȂ��Ƃ����B
�s�̒S���҂́u�×{�҂����������������A�Ή��͈�w����Ȃ�B�Ƃɂ��������҂����炳�Ȃ��Ɓv�Ɗ�@�����点��B
�������s�ŐV����3709�l�̊����m�F �O�T�Ηj������861�l���@8/3
���傤�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�3709�l�������B�������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������100�Έȏ��3709�l�B����7���Ԃ�1��������̕��ς�3337�l�ŁA�O�̏T�Ɣ�ׂ�189�D3���B�N��ʂł�20�オ�ł�����1208�l�A������30�オ852�l�ŁA�d�lj����X�N������65�Έȏ�̍���҂�115�l�B�d�ǂ̊��҂͑O�̓�����2�l����112�l�ƂȂ����B�܂��A50�ォ��80��̒j��7�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
��������3709�l�c�g��X���~�܂�ʐV�^�R���i ���C3���ŐV�K������378�l�@8/3
���C3���ł�3���A�V����378�l�ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F����܂����B���m����257�l�A���̂������É��s��81�l�ł��B����54�l�A�O�d����67�l�ł��B�����s��3709�l�ł����B
�������A���[�g�A������3�T�ԁc�u��������v�̃C���t�����������炵�����̑��ʁ@8/3
2���A�����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�2195�l�������B��T�̓��j������766�l�����A���j���Ƃ��Ă͏��߂�2000�l�����B�d�ǂ̊��҂͑O������13�l������114�l�ɂȂ����B
���N�`�����ڎ퐢��ɂ����銴���Ґ��̑����ɁABuzzFeed Japan News���ҏW���Łw���|���c�@�����x�̒��ҁE�_�뗺��́u�����̊�@�������炢�ł���v�Ǝw�E����B
�u�������傪�C���t�������Ă���B��N���琭�{���w�������O�ꂾ�x�w���ˍۂ��x�w������3�T�Ԃ��x�ƌ������������ʁA�g�I�I�J�~���N�h��ԂɂȂ��āA�����̊��o����Ⴢ��Ă��܂����B�ԈႢ�Ȃ������ő�̊�@�Ȃ̂ɁA��@�������炢���܂܁A�����܂Ŋ����҂������Ă��܂����v(�_�뗺��E�ȉ���)
���̏�Ő_�뎁�́A��N6���ɓ����s���s�����u�����A���[�g�v�Ɍ��y�B�V�^�R���i�����ւ̒��ӂ��Ăт����邽�߂ɁA�����̃��C���{�[�u���b�W��Ԃ����C�g�A�b�v�������{�B
�u�����̓s���̐V�K�����Ґ���30�l�قǂ������B���݂Ɣ�r����Ƃ��Ȃ菭�Ȃ��B��ċx�Z��f��ق̋x�ƂȂǁA�R���i�����̒i�K�Ő�Ȃ��Ă����J�[�h����������������ʁA��Ԃ̃s���`�Ɋ�@�����`���ɂ����Ȃ��Ă��܂����v
����Ȓ��A���s�̏����Y�s����7��30���A���{�ȂǂɐV�^�R���i�Ή��ً̋}���Ԑ錾���o����Ă��u8���ɗ\�肳��Ă���s�����w�Z4�Z�̏C�w���s�͎��{����v�Ɣ��\�B�u�I�����s�b�N������Ă���B�ꐶ�̎v���o�Ɏc��s���͎��{�������v�Əq�ׁA���ڂ��W�܂��Ă���B���ۂɐ��k�͑S���o���O��PCR�������s���A�A���̐��k�������Q������Ƃ����B����s���̒ɂ��āA�_�뎁�́u������Ƃ��Ă͗ǂ��Ȃ��v�Ƃ�����Łu�͒ʂ��Ă���v�Ƙb���B
�u�w�I�����s�b�N������Ă��邩��A�C�w���s�����܂��x�Ƃ�������s���̕��j�͊�����Ƃ��Ă̓_�������A���Ȃ��Ƃ��_���I�ɂ͎����т��Ă���A���ʂ��Ă���B�w�I�����s�b�N�͂�邯�ǁA���H�◷�s�͉䖝���Ăˁx�Ƃ����͖̂����������b�Z�[�W�ŁA�����Ɋ�@�����`���Ȃ��B���{���̐l���w�I�����s�b�N������Ă邵�A�ʂɂ��������x�ƈ�ĂɊɘa�����ɓ��������ƂŁA�����g��ɔ��Ԃ����������ʂ͔ۂ߂Ȃ��̂ł́v
�u�������A���ׂĂ����{�̂����A�I�����s�b�N�̂����ł͂Ȃ��B�P�Ɉӎ����Ⴍ�ĘH����݂����Ă���l���������邾�낤�B��Ì���̂Ђ�������������ƁA�V�^�R���i���҂̑Ή������ł͂Ȃ��A��ʎ��̂�M���ǂȂLj�ʂ̊��҂ɂ��肪���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����g���h�����߁A���͕����l�ł̉�H������Ăق����B����ŁA���N�`���̌��ʂ͊m���ɏo�Ă���B���{�⎩���̂́A����҈ȊO�̒��N�w�A��N�w�ւ̐ڎ������ɉ���������K�v������v
�����V�^�R���i1079�l�̊����m�F�@�}���I�y�ǁE�����NJ��ҁ@��Â̌���́c�@8/3
���{��3���A�V����1079�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����A�S���Ȃ����l�� 0�l�Ɣ��\���܂����B�܂������I�����s�b�N�J�Ò��̓����s�ł�3709�l�̊������m�F����܂����B
���{�V�K�����Ґ��̐���(���Ґ�)
8�� 2��(��)448�l(1�l)
8�� 1��(��)890�l(0�l)
7��31��(�y)1040�l(0�l)
7��30��(��)882�l(0�l)
7��29��(��)932�l(2�l)
7��28��(��)798�l(0�l)
7��27��(��)741�l(0�l)
���{�������̋}�g����}���A�y�ǁE�����ǂ̊��҂������Ă���Ȃ��A��Â̌���́c���E���ԋ�ɂ�����Ŗ��ٕa�@�B3���ɎB�e���ꂽ�R���i���҂̐�p�t���A�ł��B�h�앞�p�̊Ō�t���f���Ă��܂����A���������Ă���l�q�ł��B�b���Ɓc�B
���Ŗ��ٕa�@�@�������_�������u����͑�4�g�Ɣ�ׂ�Ɓc���|�I�ɏǏy���l�������B�v
���Ŗ��ٕa�@�́A�y�ǁE�����ǂ̊��҂�����Ă���a�@�ł��B���S�͏d���Ȃ��Ƃ����A����9������a����8�l�����@���Ă��܂��B���{�̌y�ǁE�����NJ��Ґ��͂���1������3�{�ȏ�ɑ����A2�����_��1140�l�ɏ���Ă��܂��B�{�̗v�����A�Ŗ��ٕa�@�͗��T�ɂ͎���a����17���܂ő��₷�\��ł��B
�����u17���ƂȂ�Ƃ܂��}���������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��\�������邪�A�ł��邾�������Ȃ�Ȃ��悤�ɍєz�������v
�������A���݂̑�5�g�ɂ͌��O�������܂��B
�����u(�����҂�)�ꐔ��������ƁA�d�lj�����l�������ő����邱�Ƃ����O����܂��v
�����{���j��ő����_�����c�c�����ܗւ����H�X��ǂ��l�߂�4�̗��R�@8/3
��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾��������
2021�N7��30���ɐ��`�̎��A�����s�≫�ꌧ�ɔ��o����Ă����ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ�8��22������8��31���ɉ�������Ɣ��\���܂����B���킹�č�ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{�ɑ��āA8��2������31���܂ŋً}���Ԑ錾�o����Ƃ��Ă��܂��B
�����s�Ɋւ��Ă����A2021�N1��8����2�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�A4��12������܂h�~���d�_�[�u�A4��25������3�x�ڂً̋}���Ԑ錾�A6��21������܂h�~���d�_�[�u�A7��12������4��ڂً̋}���Ԑ錾�ƂȂ�܂����B
�����̊��Ԓ��A���⎩���̂��s�������Ǒ�́A���H�ƊE�ɑ���{���S�ƂȂ��Ă���A���H�X�ɑ��鎞�Z�c�ƁA����сA��ޒ̐�����֎~����B�����s�̈��H�X��2020�N11��28������̎��Z�c�Ɨv�����炸���Ɣ�펖�Ԃ̂��Ƃɒu����Ă��܂����B�����s�̈��H�X�͎���8�����ȏ���̒����ԁA�c�Ƃ𐧌�����Ă����̂ł��B
�������ܗւ��J��
�����s�ɋً}���Ԑ錾�����o����A���H�X�̌o�c������w�N�����Ă������ŁA�傫�ȓ��킢���݂��Ă���̂������ܗցB�����ܗւ̊J���7��23���ɊJ�Â���܂����B���Z�͂�������O��7��21������J�n����Ă���A��̓���8��8���܂ő����܂��B
�����ܗւ͍�N�̊J�Â�1�N�����ƂȂ�܂������A�V�^�R���i�E�C���X���҈Ђ��ӂ邤���ŁA�{���ɊJ�Âł���̂��Ɗ�Ԃ܂�Ă��܂����B�J�Òn�̓����s��2020�N�����炸���Ɣ�펖�ԂƂȂ��Ă����͂��ł����A�C���t���Ă݂�A�Ȋw�I�ȍ�����[���̂����������Ȃ��܂܁A�����ܗւ��J�n����Ă��܂��B
���{���j��ő��̃��_�����l�����Ă���͔̂��Ɋ�������Ƃł��B�����A���H�ƊE�̊W�҂ɂƂ��Ă͕��G�Ȏv��������܂��B�Ȃ��Ȃ�A���⎩���͈̂��H�X�ɗ��s�s�Ȃقnj������[�u���Ƃ��Ă��܂����A�����ܗւɂ͕���邭�炢���e�ŁA�[�������Ȃ��Ɗ����Ă��邩��ł��B
���L���ł͓����ܗւ����H�X�ɋy�ڂ��Ă���D�܂����Ȃ��e���ɂ��ďq�ׂĂ����܂��B
�Ȃ��A�A�X���[�g����邱�Ƃ͖ړI�ɂ��Ă��܂���B���̓A�X���[�g�����X�y�N�g���Ă���A�A�X���[�g���^���ɑł����ގp�Ɋ�����E�C�����炢�A�S��ł���邱�Ƃ����X���邱�Ƃ��q�ׂĂ����܂��B
���X�e�C�z�[���̌Ăт���
�����ܗ֒��̐l�����������Ă��邩�A�������Ă��邩�ɂ��ẮA�l�X�ȃf�[�^�〈��������̂ŁA�܂����R�Ƃ��܂���B�����A���⏬�r�S���q�s�m�����X�e�C�z�[����O�o���l���Ăт����A����ł̓����ܗ֊ϐ���������߂Ă���͕̂�����Ȃ������ł��B
�����ł������H�X�́A��ޒ̐�����f�B�i�[�̎��Z�c�Ƃɂ���Ĕ��オ�������Ă��܂��B�����ł���ɊO�o���l������Ă͂��܂�܂���B�O�H���T���悤�Ƃ��镵�͋C����������Ă��܂��A���H�X�ɖK���q���܂��܂�����\�������邩��ł��B
���͋��́A��ޒ̐����⎞�Z�c�Ƃ�⏞������̂Ƃ��Ē���Ă��܂��B�����ɉ����ĊO�o���Ȃ��悤�ɂ��A�i�E���X����̂ł���A���͋��̋��z�z���Ȃ���Β��낪����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���W�҂̍s����������{��
�����ܗ֊W�҂̃}�i�[���悭�Ȃ��̂ŁA���H�X�ɂ������e�����y�ڂ��̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜���Ă��܂��B�I�����s�b�N�ψ���J��Ń}�X�N�����Ȃ������l�X���莋���Ȃ�������A�W�҂��I�葺�ŘH����݂����Čx�@�����ɂȂ�����ƁA�v���C�u�b�N�ɂ��ᔽ����s�ׂ����R�ƍs���Ă��܂��B
�����ܗւƂ����傫�ȕ���ŁA�}�X�N���p��̂�ɂ�����A�H����݂��߂��Ȃ������肷��A���H�X�ɔh�~�����߂���A��ޒ𐧌������肷�鐳�����������Ă��܂��ł��傤�B���H�X�ł͐�������Ă���{�A�����ܗւł͖��Ȃ��Ƃ����̂ł���A�Ȋw�I�Ȉ�ѐ��������܂��B
���Ǝ����̂́A�I�����s�b�N�ψ���Ɠ����ł͂���܂���B�������A�����ܗւ��s���Ă���͓̂��{�ł���A�����s�ł��B���H�X�ɋ��߂��Ă��邱�Ƃ��A�����ܗւł������悤�ɋ��߂��Ȃ��̂ł���A���{�Ⓦ���s�̎{��͎��Ȗ������͂�ނ��ƂɂȂ�܂��B
�����Ղ胀�[�h�̕��Q
�����ܗւ��J�n����Ă���A�e���r��C���^�[�l�b�g�ł͓����ܗւ̘b��ň�F�ƂȂ��Ă��܂��B���ɕ������Ԃ����܂��Ă���e���r�ł͂��̌X�����������A���ԑg��C�h�V���[�A����ɂ͌����ԑg�ł����A���{�l�A�X���[�g�̋��Z���ʂ����ł͖O�����炸�A�����ܗւŋN���������Ȃ��Ƃ܂ł�ʔ������������グ�A���C�ɑ����ł��܂��B
���Ƃł͂Ȃ��R�����e�[�^�[����ƌ��������Ƃ̐���͂��Ă����āA�e���r�̏o���҂������҂ɑ��āA���⎩���̂��s���V�^�R���i�E�C���X�̑�ɂ��Ė������N���邱�Ƃ́A��肪�Y�ꋎ��Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ŕ��ɏd�v�ł��B�������A���݂ł͂��ꂳ�����@�\���Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�����ܗւ̊J�n�O�ł���A�e���r�ł͍��⎩���̂̎{���������A�����ܗւ̈��S�����������肵�Ă��܂����B�����������ܗւ��n�܂������ł́A�A�X���[�g�̃C���^�r���[�▧����ނɎ��Ԃ������Ă���A�V�^�R���i�E�C���X�̎{��ɂ��ċc�_���鎞�Ԃ������Ԍ��������悤�Ɏv���܂��B
�{���ł�����⎩���̂̓������Ď�����̂��A���f�B�A�̐Ӗ��B���������ꂪ�A�����ܗւɂ�邨�Ղ胀�[�h�ɂ���ĂȂ�����ɂȂ�Ƃ���A�����ܗւ͊����������Q�������炷���ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����āA���̕��Q�̎�ȑΏۂƂȂ�͎̂{��̃^�[�Q�b�g�ɂ���Ă�����H�ƊE�ɑ��Ȃ�܂���B
2016�N�ɂ�����S���̈��H�X���͖�45���X�A���H�X�̏]���Ґ��͖�319���l�ɂ����(������Ƃ������ȓ��v�ǂ���)�A2019�N�ɂ�����O�H�Y�Ƃ̎s��K�͂�26���~(���{�t�[�h�T�[�r�X�����)���ւ�܂��B
���{�̍����Y�Ƃ̂ЂƂł�����H�ƊE�����⎩���̂̎{��ɂ���ĕN�������ɒu����Ă��邱�Ƃ��ӂ݂�A���f�B�A�́A���ɕ����̂��郁�f�B�A�ł���A���H�X�ɑ���{��̌��ʂɂ��đ����̎��Ԃ������ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������ܗ�̃c�P
�ł��J�����Ă��邱�Ƃ͓����ܗւ̃c�P�����H�X���x���킳��邱�Ƃł��B�����s�ɂ�����4�x�ڂً̋}���Ԑ錾��7��12�����甭�o����Ă���̂ŁA���ʂ������̂�2�T�Ԍ�ł���7��26�����炢����B�������A7��26������͂ނ���A�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�Ă��܂��B
�܂�A���H�X�ɑ��鎞�Z�c�Ƃ��ޒ̐����͌��ʂ��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���A���⎩���̂ɂ��{��̖��Ӗ�������Ă���̂ł��B
���߂�8��2���ɂ�����V�K�����Ґ�2195�l�̂����A�����o�H���������Ă���795�l�̓���́A�ƒ�����ł�������468�l�A�E�����136�l�A�{�ݓ���48�l�A��H��43�l�B�����Ĉ��H�X�ɂ������H�������킯�ł͂���܂���B
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��͑����̈�r��H���Ă���A�������݂Ƃ��郏�N�`���ڎ���s�m��v�f�ɖ�������Ă��܂��B
���������āA8��31���ŏI�����}����ً}���Ԑ錾������ɉ������ꂽ��A�܂h�~���d�_�[�u�ɃX�E�B�b�`�����肷��\���͍����ł��傤�B�����Ȃ�A�����������H�X�ɑ��鎞�Z�c�Ƃ��ޒ̐����������ƍl�����܂��B
�鍑�f�[�^�o���N�ɂ��A�V�^�R���i�E�C���X�֘A�ɂ��|�Y�ŁA�Ǝ�ʂ̍ő��͈��H�X�B
���H�X�͉�ȏɂ��炳��Ă��邾���ɁA�����ܗւ̃c�P�܂ŕ��킳���̂ł���A���⎩���̂͂���������͋���⏞��ł��o���ׂ��ł��B
�����⎩���̂ւ̕s�M��
���⎩�͓̂����ܗւ̊J�ÂɌ����ăA�N�Z�����v���蓥�݂��߂Ȃ���A�����ɂ͎��l���Ăт�����Ƃ����u���[�L���ɓ���ł��܂��B����ł͍����͂ǂ�����悢�̂��킩��܂���B�ԓx��b�Z�[�W�ɐ����͂��ѐ����Ȃ��̂ŁA�����͍��⎩���̂ɑ��ĐM�p��M�������Ă�͂����Ȃ��ł��傤�B
���͈��S�ň��S�̓����ܗւ��J�Â���Əq�ׂ܂����B�������A����������������A���H�X�ɑ���K�������߂��肷�邱�Ƃ��A���S�ň��S�Ȃ̂ł��傤���B
�S�͂�s�����A������^���Ă���Ă���A�X���[�g�ɂ͉��̍߂�����܂���B���ꂾ���ɁA�����ܗւɂ܂�鍑�⎩���̂̎{���ԓx�ɂ͕��肷��o����Ƃ���ł��B
���u�ܗւ��X�e�C�z�[���Ɍ��ʂ���v���r�m����������l�o�������̖����@8/3
���r�S���q�s�m��(69)��7��30���A�u�ܗւ͎�����20��������A�X�e�C�z�[���ɖ𗧂��Ă���v�Ɖ�ō��ꂵ���B�l�b�g�ł͕���Ԃ鐺���オ���Ă���B
�����̂ڂ邱�Ɠ���29���B���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή(72)�͍���ŁA�����ܗւ��l�o�̑����ɉe������̂ł͂ƌ��O���Ă����B�����30���A���r�s�m���͒���ł����b�����B
�u���̂Ƃ���A��������20�����҂���R���e���c���Ă����̂́A�Ȃ��Ȃ������Ƃ����̂��e���r�ƊE�̕��ł������āA�l���Ă����邱�ƁB(����)�X�e�C�z�[���Ɍq�����Ă���Ƃ������Ƃ��l������v
����Ɂu�ł�����A�I�����s�b�N�͂��������Ӗ��ŃX�e�C�z�[���Ɉ�������Ă��邵�A�܂����ꂪ�I��ւ̐����ɂ��q�����Ă���Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��v�Ƒ������B
�������������o���A�g�ܗ��ʁh���]�������r�s�m���B�����������ܗւ̊J�����5����ƂȂ�挎28���A�����s�̐V�K�����Ґ���3177�l���L�^�B�ȍ~5���Ԃ͖���3000�l��˔j���Ă���A31���ɂ�4058�l���̐V�K�����҂��m�F����Ă���B
����ɁwNHK NEWS�x�ɂ��Ɠ���30���A�����s�̐l�o�́u�I�����s�b�N�̊J���O��3��ڂ̐錾���o�Ă������Ԃ̕����̕��ςƔ�ׁA�����A��ԂƂ������v���Ă����Ƃ����B�u�����ܗւ̓X�e�C�z�[���Ɉ�������Ă���v�Ƃ́A���������ɂ͂Ȃ����B
����ł�8��1���A���r�s�m���Ɂg���R�g���o�ꂵ���B�����ܗցE�p�������s�b�N�g�D�ψ���̕����q�Y�����������B
�w���X�|web�x�ɂ��ƕ������������͓����ܗւƐV�^�R���i�̊����g��Ɍ��y���u�������͈��ʊW�͂Ȃ��Ɣے肵�Ă���B�����s�̏��r�m�����ܗւ̐l��������ے肵�Ă���B���������オ���āA�ނ���X�e�C�z�[�������オ���Ă���v�ƃR�����g�B�����āu���낢��Ȉӌ������邪�A�������A���r�m���Ɠ�������ōl���Ă���v�Ɖ�Řb�����Ƃ����B
�������A�l�b�g�ł͔��X�̗l�q�B�u�ܗւ͎���������������X�e�C�z�[���ɖ𗧂��Ă�����v�ɑ��āu�����[���v�Ƃ̈٘_�����o���Ă���B
�s���A���������Ȋw�I�����Ȃ�H�}�W���悱��Ȃ��Ă�m���₩��A�����������Ƒ��������Ă�Ⴄ��H�t
�s���̎������́u���ю������v�ŁA�u���ѓ��̊e�l�v���X�e�C�z�[�����Ă��邱�Ƃ͕ۏ���Ă��Ȃ��t
�s���������オ��ƍݑ���オ��Ɠ��`���鍪���͉����t
�s���ǃI�����s�b�N�̐������ۂ��͎������Ō��߂���悤�ł���t
20���̎������𒍎����鏬�r�s�m���ƕ������������B�������A�c���80���͎���ɓ����Ă��邾�낤���H
���f���^�������g��u�@���}�X�N����o�Ă܂���v���ӂɃs���b�Ƃ���@8/3
��ƁE�k���݂̂肳��̘A�ځu����Ȃ̘b�͂��肪�����v�B����́A�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�鍡�̏ɂ��āB
��
�V�^�R���i�E�C���X�E�f���^���̊����g��ŁA�s���ɕ�炷�҂Ƃ��ẮA���܂łƈႤ��ނْ̋����������Ă���B�g�߂Ȑl�����������A�S���Ȃ����Ƃ��������悤�ɂȂ��Ă����B����́A���N�`����2��ڎ킵����Ƀf���^���Ɋ��������Ƃ������̘b�����B���N�`���̌��ʂŏd�lj����Ȃ��ƌ����Ă͂��邯��ǁA���N�`����ł����̂Ɋ����Ȃ�āc�c�Ɩ{�l�̗��_�͂ƂĂ��ƂĂ��傫���B
�z���҂Ƃ��ꂿ�����������ł��A�G�A���]�����z�����߂Ί������邱�Ƃ�����f���^���B�������������s�[�N�Ƃ͎v���Ȃ������ŁA�z���҂������Ă���Ȃ��ŁA����̌i�F���������ς���Ă����̂�������B
����A�}�X�N�Ȃ��Ń����j���O���Ă���l�ɁA�u�}�X�N����I�v�Ɠ{���Ă���l�������B���̋��������ɁA�u�͂��H�v�Ɖ����A�����i�[�������~�܂�B�{���Ă���l�̌�������A�}�X�N�Ȃ������i�[�̌�������A�G�A���]�����u���[���������[�ƍL����R���N���[�g����̔M�����Y���̂�������悤�ȋC�����ɂȂ�B����̐l�͌��Ă܂���A�������Ă��Ȃ��Ƃ����ӂ��ɑ�����2�l���狗����u�������A��������B��������1�l�B�s���s��������C����͂ł��邾���������������B�Ƃ͂��������ŋ߁A�@�}�X�N�̃X�^�b�t�ɂ́u�@���o�Ă܂���v�ƌ����悤�ɂȂ����B���ӂ���ق��������ق����A��u�s���b�Ƃ���B
�����s�̎���×{�҂͐�T1���l�����B���Ǐ�҂����ł͂Ȃ��A���@�̒��������Ȃ����߂Ɂu�҂��Ă���v�l������B���N1������5���܂ŁA�z�����m�肵�Ă����̂Ɉ�Âɂ����ꂸ����ŖS���Ȃ����l��120�l�������Ƃ����\����Ă���B���āA����Ɏ���ł̎��҂������Ă��܂����Ƃ́A���̌�������͖Ƃ�Ȃ����낤�B���Ă̂悤�ɁA�g���b�N�ɂ���̑܂��ς܂��f�������Ȃ��Ă��A�\���Ɉ�Â͕N�����A�������̈��S�E���S�͊��ɑ傫���D���Ă���B
6��1��������{�����̐ؐ�����t��Ɓu���������~�߂邵���Ȃ������I���p���v�Ƃ����I�����C���ł̍R�c�����[���A�T1�ōs���Ă���B���܂�50�l�ȏ�̏����������o�����A�I���p���ɔ����闝�R������Ă����B�O��͌ܗւ��X�^�[�g���ď��߂Ẳ�ŁA�W���[�i���X�g�̐����J�������o�����A�I�葺�̏�A���������C�O�̋L�҂Ƃ̂��Ƃ�ɂ��Ęb���Ă��ꂽ�B
��������́A�u3��l���x�̊����Ґ�(��T�̓����̏�)�́A���[���b�p����݂��炤���܂������炢���Ȃ��݂���v�Ƙb�����B���[���b�p�ł���Έ�������l�̊��������ʂ����炾�B�ł�����͂������A�N�ł��ǂ��ł�24���Ԗ����ōs�������ł��邩�炱���o�Ă������A���Ȋ����Ґ����B���{��PCR������24���ԒN�ł��ǂ��ł������Ŏ��Ȃ��������u��i���v�ł��邱�Ƃ��C�O�̋L�҂ɓ`����ƒN���������ƁA��������͘b���Ă��ꂽ�B������ǂ���́u���E�v�̘b�B�����ɂ͊W�Ȃ����ƂƁA�ܗւ̓����̐l�����͓��X�̍s�����l�X�Ɛi�s���Ă���B
�߁X�����̊����Ґ���1���l���Ƃ����l�����邪�A�����ق�1���l���炢�����������Ă��Ȃ������ŁA1���l�̗z���҂������Ƃ��ďo�邱�Ƃ́A���̂Ƃ���l���ɂ����B�{���̐������S�������Ȃ��̂����̓��{�̕|���Ȃ̂�������Ȃ��B
����A�����������B�ܗ֊W�҂̎Ԃ�n�����痈���p�g�J�[��A�s���Ō������Ƃ̂Ȃ��n���̊ό��o�X�������B�R���i�ȑO�͒����l�x�T�w�łɂ�����Ă���GINZA SIX�̑O�ɓ����ܗ֊W�҂̃V�[���������o�����~�܂��Ă����B�ǂ�Ȑl���߂��Ă���̂��ȂƂ��炭���Ă������A10���ȏ�o���Ă��N���߂��Ă��Ȃ������B�����������Ă���̂�������Ȃ����A�l���݂̋���ɂ����ʂɗV�тɂ�����ܗ֊W�҂ł���A�o�u���Ȃ�Ė{���ɈӖ����Ȃ���˂Ǝ�������B
�����ܗ֊J�Âƃf���^���̊����}�����������Ɏn�܂����B�u�s���̐l�o�͌ܗւ̂������Ō����Ă���v�Ƒ������s�m���������Ă��邪�A�l�o�������Ă����̓I�ȍ������������o�Ă��Ȃ��B����A��~�l�グ�����������H�����߂Ďg�������A����Ⴛ���ł���A�Ƃ������炢�ɋĂ����B������݂āu�l�o���������v�Ƒ����͎v���Ă���̂��낤���B���̓��������݂��Ă���̂��������Ȃ��̂��낤���B
����ȏɂȂ��āA�_�C�������h�E�v�����Z�X���̂��Ƃ��A�ŋ߂悭�l����B�C�ɕ�������ȑD�ŁA�K�Ȉ�Â��s��ꂸ�S���Ȃ������������B3711�l�S����PCR�����������ɍs��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A���ɑ��ꂵ����i���Ă���75�̒j���͌��������Ă��炦���ɁA���M���o�Ă��u���t�v�Ɛf�Â�f���A1�T�Ԍ�ɉ��D���ē��@�������ꌎ��ɖS���Ȃ����b�́A���x�����Ă������ɂ��B
���̎�����PCR�����𑬂₩�ɁI�Ƃ̐��͋������������A���{���W�߂����Ƃ����́uPCR���������߂�l�X���a�@�ɑ勓���Ĉ�Õ���ɂȂ�v�Ƃ��u�l�X���p�j�b�N�ɂȂ��Ă��܂��v�Ȃǂƌ����A�M���o�Ă�4���Ԃ͎���őҋ@�ƒʉ@�𐧂��A�R���i��Ƃ������u�p�j�b�N�����v�ɗ͂����Ă���悤�Ɍ������B
����Ȃ��Ƃ������Ƒ����Ă���1�N���������B�_�C�������h�E�v�����Z�X���ŕv��S�����ꂽ���̔߂����i�����A���̍��ɃR���i��̍ŏ��̈���������悤�Ɏ��͋L������B�����Ă��̎�����A�͈���������肾�B�����҂͑D�ɕ����߂ďo���Ȃ�������A�l�X���p�j�b�N�ɂȂ�Ȃ��悤�ɏ��̓R���g���[����������B�ܗւŐ���オ��Εs�������܂邾�낤�B���{�ɕ�炷�������́A�ꕔ�́u�G���C�l�v���̂����Ă݂�ȃ_�C�������h�E�v�����Z�X���ɏ悹���Ă���̂�������Ȃ��B
�����D������āA���R�ȋ�C���z���āA�}�X�N�Ȃ��Ŏv�������ŐH�ׂĂ�����ׂ肵�đ��肽���B����Ȏ��Ɍܗւɂ����Ɛl�Ǝ��Ԃ��g�����f�����������Ƃ��ǂ����D�́A����ς�댯���B
���d�LjȊO�͌����g����×{�h�@���{�̕��j�]���ɔg��@8/3
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂̂����u�d�ǎ҂�d�lj����X�N�̍������҈ȊO�͎���×{����{�Ƃ���v�Ƃ������{�̐V���ȕ��j���g����L���Ă��܂��B�s���ł�1��2000�l���鎩��×{�ҁA���́u�����������v����ނ��܂����B
2�x�ڂ̉Ă��}���A������͐V���ȋǖʂ��}���Ă��܂��B
�c�������J����b�u�ݑ���܂߂đΉ�������Ȃ��B����́w�����҂̐��x�Ɓw�a���x���l����ƁA���ꂭ�炢�t�F�[�Y���ς���Ă��Ă���v
���{�͒����Ljȏ�́u�������@�v�Ƃ��Ă������j���������A�d�ǎ҂�d�lj����X�N�̍������҈ȊO�́u����×{�v����{�Ƃ��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�c�������J����b�u�d�lj����ꂽ���X���Ƃł����āA�����Ɉ�Ë@�ւɍs����Ƃ������ƁA�a������Ɋm�ۂ��Ă������Ƃ��d�v�Łv
�}�����銴���҂ɑ��A�a���m�ۂ�ړI�Ƃ����A���̕��j�]���B��������3���ߌ�A��ÊW�҂�Ɩʉ�܂����B
��������b�u�g�߂ŗ��鑶�݂ł���n��̐f�Ï��ɂ�����ẮA���f��I�����C���f�Âɂ���Ă����������҂̏�c�����Ē����A�K�Ȉ�Â���Ē����܂��悤�ɂ��肢��v���܂��v
���{�͎���×{�҂̕a��J�Ɋm�F����悤�A���f�̐f�Õ�V���g�[��������j�ŁA��ÊW�҂�ɋ��͂����߂܂����B
���{��t��E����r�j��u��t�����f���āA����͓��@���K�v���Ƃ������ƂɂȂ�A���������@�ł����Ɗm�F�����̂ŁA����͑S���̊F����A�S�z���Ă���Ǝv�����A���v�Ȃ̂ň��S���Ē��������v
�����s�̕a���g�p����50�����A����×{�҂�1�J���O��12�{�ɋ}�����A1���l���܂����B
�����s�E���r�S���q�m���u���̂��̐��{�̐V�������j�ɔ����āA����Ȃǂł̗×{�������ɂ���ɉ��P����u����Ƃ������ƂŁA���̂�������S���ǂ̕��ɕK�v�ȑΉ�������悤�Ɏw�������Ă��܂��v
��}����͋����ᔻ�̐����オ���Ă��܂��B
��������}�E�}���\�u����×{�Ƃ����̂͌��t�����ŁA�g��������h�Ƃ��������悤���Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ������܂�Ă��܂��v
�g�߂ɔ���A����×{�B�ʂ����āA����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B
����×{���鏗��(31)�u��i�̕����w���͑̒��������x�݂����Ȋ����Ō����Ă��āA�M�𑪂�������37.5�x���o�Ă��̂ŁA2�l�ł�����ƃ��o����������Ȃ��Ǝv���āv
�V�h��ɏZ�ޔ��e���Ζ��̏���(31)�B���M������A�������e�t�̏�i�ƂƂ��ɐ挎28���ɗz���Ɣ��肳��܂����B
���݁A����×{6���ڂł��B�z���������������ɁA�ی������玩��×{����悤�w��������܂����B
����×{���鏗���u�w10���ԂƂ肠��������ŋx��łĉ������x�݂����Ȋ����̓��e�B���[�����͂��āB����ǂ��ł����ǁA�������g���ċz���ł��邵�A�z�e���̕��Ɉړ��������Ƃ��A���������C�����͂Ȃ������ł��ˁv
�����͐H���̂����킦������A���R����������×{�ł����͂Ȃ��Ɗ����Ă��܂����B�����A�M���}�ɏオ��ȂǑ̒��͈��肹���A�s���������Ă��܂��B
����×{���鏗���u����×{���̐l�Ɍ����Ă̑����Ƃ����̂������ł����ǁA�S�R�Ȃ���Ȃ���ł���ˁA�d�b���Ă��B�������}�ɂЂǂ��Ȃ�����Ƃ��ċz���ꂵ���Ȃ鎞�����܂ɂ����āA���|�E�s���͂���܂��v
�����r�s�m���u����×{�@���P����u�������v�@���{���j�ɑΉ��@8/3
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂̋}�g�傪�����s���̈�Ñ̐����}���ɕN��(�Ђ��ς�)�����Ă��܂��B�����s��8��3���ɐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�3709�l�ŁA����܂ł�3�Ԗڂɑ��������Ґ��Ƃ������������������Ă��܂��B
�����̊g��ɔ����Č��O�����̂�����×{�҂̋}���ł��B�����s���̎���×{�҂�3�����_��1��4019�l�Ɖߋ��ő����X�V���Ă��܂��B�����������A���{�����@�̊�ɂ��āA�Ώۂ��u�d�ǎ҂Əd�lj����X�N�������l�Ɍ���v�Ƃ����V���ȕ��j�������܂����B����܂Ō������@�ƂȂ��Ă�������ҁE��b�����̂���l�E�����ǂ̊��҂́A�����Ƃ��āu����×{�v�ɂȂ�܂��B�c�����J���͂��̐V�������j�ɂ��āu�t�F�[�Y���ς��A�ݑ�ł̑Ή����l������Ȃ��B�K�v�Ȏ��ɓ��@�ł���a�����m�ۂ��邱�Ƃ��d�v�B�a���̗]�͂����Ή������Ă����v�Ɛ������Ă��܂��B
�����s�̏��r�m���́A�V�^�R���i�̊����҂̂����u�d�ǎ҈ȊO�͎���×{����{�v�Ƃ������{�̕��j�ɑ��A����×{�҂ւ̉��P����u�������Ƙb���܂����B����ł������������B
�����[�@�����u�c�_���ׂ������v�@�V�^�R���i�����}�g��Ł\���r�s�m���@8/3
�����s�̏��r�S���q�m����3���A�V�^�R���i�E�C���X��̓��ʑ[�u�@���߂���A�u�ۑ肪��������ɂȂ��Ă���B���܂��܂Ȗ@�����Ȃǂ̕K�v�����܂߂ċc�_���ׂ������ɗ��Ă���̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��B��ʁA��t�A�_�ސ�e���Ƃ̃e���r��c�Ō�����B
���r���́A���s�̓��[�@�Ɋ�Â������g��h�~��ɂ��āu�ً}���Ԑ錾�������x���o���������A��ɂ��肢�x�[�X�ɂȂ��Ă���v�Ǝw�E�B�s���Ŋ������}�g�傷�钆�A�u����܂ňȏ�ɐl�̗���̗}�����K�v�ɂȂ�v�Əq�ׁA��̎����������߂�K�v������Ƃ̔F�����������B
�S���m�����1���ɂ܂Ƃ߂����ւ̒ŁA�����͂��u���b�N�_�E��(�s�s����)�̂悤�Ȏ�@�݂̍���v�̌����Ɍ��y�����B
���g�錾�h�Œ��؊X�͊ՌÒ��u�l�o8�����v�@8/3
�����ł�3���A3709�l�̊����҂��m�F����A�V�^�R���i�E�C���X�̋}�g��͎����̒����������܂���B���{�͒����ǂł��d�lj����X�N�����Ȃ����҂͌����A����×{�Ƃ��邱�Ƃ����߂܂����B
���l���؊X�B��N�A�ċx�݂͑����̉Ƒ��A��Ȃǂłɂ��키�Ƃ����܂����B
���l���؊X�ݘҍs��ʂ�X�̔����E���������u(���؊X�̐l�o��)����������8���قnj����Ă��܂��v
�y�Y���X�ɂƂ���1�N�̒��ł��������ꎞ���Ƃ������̎����B�������A6�s�{���Ɋg�傳�ꂽ�u�ً}���Ԑ錾�v�̉e���Ől�o������B
���������u����グ�I�ɂ������ȂƂ���A���Ȃ�̃_���[�W���o�Ă���܂��B(��N�Ɣ�ׂ�)�������炢�͉������Ă��܂��v
�錾������2���A�ߋ��ő��ƂȂ����_�ސ쌧�̊����Ґ��B3����1298�l�̊������m�F����A�����7���A����1000�l�����ɁB
�_�ސ쌧���u�}����2�{3�{�ɒ��ˏオ�����̂ŁA����ς肿����ƕ|���ȂƁv
���ĂȂ������̋}�g��B3���A��ʂł�1053�l�A����ł�467�l�Ɖߋ��ő��̊������m�F����܂����B�����ē����s�ł́A�V����3709�l�̊������������A�Ηj���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
����Ɋ����҂��}�����Ă����錧�ł́A����m�������ɋً}���Ԑ錾��v�������Ƃ������Ƃł��B
�I���f�B�A�ȂǑ��W�҂̊������A���A���炩�ɂȂ钆�B���W�җp�̃p�X���Ԃ牺�����j���A���́B
�m�s�s�����{�֓��a�@�E���X�]����Y��t�u�I�����s�b�N��(�C�O��)�ǂ̕��́A��Â̎{�݂ɍs�����Ă��������܂��v
�s���̕a�@�ɋΖ����鍲�X�]��t�B�ʏ�̐f�Âɉ����A�T���́A�I�����s�b�N�ŗ��������C�O���f�B�A�̂��߁A�v���X�Z���^�[���̈㖱���œ����Ă���Ƃ����܂��B�����������ł��B
���X�]����Y��t�u����Ȏ����ł͂���܂���ˁB(���҂��R���i�^���̏ꍇ)�K�v�����������ς�h�앞�����܂����v
�����g��̗]�g�B����ɐ��{��2���A���ĂȂ������̋}�g����A�����ǂł��d�lj����X�N�̒Ⴂ���҂́A�����A���@��������×{�Ƃ�����j�ɓ]�����܂������A���̕��j�ɂ���3���ߌ�A��������b�́A���{��t��Ȃǂɋ��͂�v�����܂����B
���R���i�����ҋ}���A��錧�����ɋً}���Ԑ錾�v���@8/3
�V�^�R���i�E�C���X�����}�g����A��錧�̑���a�F�m����3���A�Վ�����A���Ǝ��ً̋}���Ԑ錾��6�����猧���S��ɔ��߂���Ɣ��\�����B���Ԃ�19���܂ŁB���Ǝ��̐錾���߂�1���ȗ�2�x�ځB�����āA���ً̋}���Ԑ錾�̓K�p��v���������Ƃ����炩�ɂ����B
���Ǝ��̔��f�w�W��3�����݁A4���ڒ�3���ڂ��ł��[���ȃX�e�[�W4�ƂȂ�A���͑S�̂̑�X�e�[�W���A���߂�4�Ɉ����グ���B���ʁA���Ǝ��̐錾�Ɋ�Â��[�u�Ŋ����}�~�Ɏ��g�݂Ȃ���A���̐錾�K�p���Ă���Ȃ����}�肽���l���B
����m���́A�O�i�̂܂h�~���d�_�[�u���щz���ċً}���Ԑ錾��v���������Ƃɂ��āA�u�����̃X�s�[�h�������A���}�ɋ��͂ȃu���[�L�ނׂ��B���Ԃɂ�����炸�A�ً}���Ԑ錾�߂��ׂ��ƍl�����v�Ɛ����B���̐錾�̌��ʂƂ��āA��ނȂǂ������H�X�̋x�Ɨv���Ȃǂ������A�u���Ǝ��̐錾��啝�ɏ���[�u������v�Ɗ��҂����B
�O��̌��Ǝ��ً̋}���Ԑ錾�͑�3�g����1��18���`2��23���ɔ��߂��ꂽ�B����̓Ǝ��錾�ł́A7��30������u�����g��s�����v�Ɏw�肷�錧��A�����Ȃǂ�16�s����ΏۂƂ���s�v�s�}�̊O�o���l�v����A���H�X�̌ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k�v���A���s���{���Ƃ̉������l�v���A�������̐����Ȃǂ̑[�u��S���Ɋg�傷��B
�����āA�A�N�A���[���h����������ق₢�炫�t�����[�p�[�N�A�ܓc�̑���e��Ȃǂ̌��L�{�݂������x�قƂ���B�����̔��p�ق�}���ق͊�������������ŊJ�ق��p������B�܂��A�J�ݒ��̊C������(�����P�Y�A����A���T���r�[�`)�̕����Ђ����Ȃ��s�Ƒ�����ɗv�������B
����m���́u���̂܂܊����g�傪�����Ɗm�ۂ��Ă����Ñ̐��̕������ɂȂ�v�Ƒi���A�����ɑ�ւ̋��͂����߂��B����Ō��O�Z���ɑ��Ă��u���N�̉ċx�݂͈��ɗV�тɗ��Ȃ��ŁB�A�Ȃ��T���Ăق����v�ƌĂъ|�����B
�����ł̓f���^�����܂ޕψي�����̂̑�5�g�}�g��ɔ����A�Ǝ��̔��f�w�W�̂����V�K�z���Ґ��ƌo�H�s���Ґ��ɉ����A�a���ғ�����3���A289���ɑ����X�e�[�W4�ƂȂ����B
�Ǝ��Ɋ����g��s�����Ƃ��Ă����A�l��1���l������̐V�K�z���Ґ�(����1�T��)��1.5�l�ȏ�̎����̂́A���k�������܂߂�37�s�����Ɋg�債���B
���u�d�NJ��҈ȊO�͎���×{�v�c���{�� �g��Õ���h ���R�̔��\�@8/3
���{��t��̒���r�j���8��3���A���Ƃ̖ʉ�Łu�S���I�ȋً}���Ԑ錾�̔��߂ɂ��A��O�Ȃ��������z���Ȃ��Ȃǂ̋��͂Ȋ����h�~�K�v���v�Ɨv�������B�����ʐM���Ă���B
�u�ܗ֊J�Òn�̒��S�ł��铌���͌��݁A�����Ґ�������܂łɂȂ��قǖc��オ���Ă��܂��B7��31���̓����s�̐V�K�����Ґ���4058�l�Ɖߋ��ő����L�^�B
���Â�N�`���ڎ킾���łȂ��A�ܗւ̈�Ã`�[���ɐE����h������a�@�����邱�Ƃ���A����͂��łɌ��E�B�g��Õ���h ��h�����߂ɁA��t��͋����v���ɓ��ݐ����̂ł��傤�v(��ÃW���[�i���X�g)
���{�̗\�z��傫�����邱�ƂƂȂ����A�ܗւ̗��� �g��5�g�h�B�c�����v�����J������8��3���̋L�҉�ŁA����҂��b����������l������×{�ƂȂ�\��������Ƃ̌������������B����܂ł͌������@���������u��r�I�Ǐy���A���X�N������قǍ����Ȃ��l�͍ݑ���܂߂đΉ�������Ȃ��v�Ƃ����B
���{�̋g���m���m���͂��̔��\�������A�����J���ꂽ��Łu��Îx���̐��̐����ƃZ�b�g�ł���ׂ����B�������������܂܂̌�������×{�͔��Ƀ��X�N�������v�Ǝw�E�����B
�u����҂��b�����������Ă���l�ł��A�Ǐy����A����A����×{�ɂȂ�\��������Ƃ̔F���������Ă��܂��B�������A���S�Ȏx���̐��̂Ȃ�����×{�́A�悯���ɏd�lj����銳�҂𑝂₵�Ă��܂����X�N������܂��v(�O�o�E��ÃW���[�i���X�g)
����ɂ��āA�l�b�g�ł́u�ܗւ�����Ă���ꍇ����Ȃ��v�Ƃ����ӌ����E�����Ă���B
�s�ܗւőI�肽�����犴����������Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�ł��A�l�����D�悳��Ȃ��̂ł�����܂����ɂł���߂�ׂ��t�s�ȂA�ܗւ����������Ŋ������������̂����܂������Ƃ��Ă��銴��������t
�u���S�E���S�̌ܗցv�c�c���̌��t���A���͂��܂ǂ��~�߂Ă���̂��낤���B
������×{�����̓����A���̈�Õ���u�Č��v���O�@8/3
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��}����������5�g���}���Ă��铌���s�ŁA�t�̑�4�g�ň�Õ�������������{�́u�Č��v���뜜����Ă���B���Ƃ͔�r�ޗ��̈�Ɏ���×{�҂̑����������A����̐��ڂɒ��ӂ��Ăт�����B���{�͎���×{����{�Ƃ�����j��ł��o�������A����҂ɉ����ċz�����x���̏Ǐ���l������×{�ƂȂ�\��������e�̋}�ςւ̑Ή����œ_�ƂȂ�B�s�͕a�@��h���×{�ȂǁA�S�̂̎M�ň�Õ����h���l�����B
�u����×{�҂�������ƕK�v�ȃP�A�����Ȃ��l���o�Ă��邵�A�Ǘ��ɐl�肪��������@�����Ȃǎ����̂̑��̋Ɩ����������鋰�������B��Õ���̒����Ƃ݂Ă���A���̂܂܂��Ƒ��̓�̕����ɂȂ肩�˂Ȃ��v�B�����w����w�Z�p���w�Z�����Z�Z���̒����p�b���͂����w�E����B
����ɁA�u���E����ƍ��]���藎����悤�ɖc��オ��A���z�Ɋׂ��Ă��܂��v�ƍ���̓����ɂ��x����炵���B
�s���̎���×{�҂�1��2��l���Ă���B���łɑ�3�g�̃s�[�N��傫������A�A���ߋ��ő����X�V�����B���@��h���×{�̑ҋ@�Ȃǂ��܂߂��2���l�߂��\��������B�s���̕ی������́u�̒��m�F�̋Ɩ����������A���@�����Ȃǂɉe�����o�n�߂��v�Ɩ������B
���{��3���ȍ~�̑�4�g�ň�Õ���ɒ��ʂ����B4��13���ɐV�K�����҂�1��l�����K�͂���3�T�Ԍp���B�d�ǎ҂�5��4���ɍő�449�l�܂ő����A�d�Ǖa�������ł͎��e������Ȃ��Ȃ����B
�����A����×{�҂͍ő�1��5��l���A�a�������Â����Ȃ��܂�19�l�����S�B�ی����̋Ɩ��N��(�Ђ��ς�)������ŁA�����҂ƘA�������O�ɖS���Ȃ鎖����������Ƃ����B����×{�҂̐���������A�s���̐����͂���ɋ߂Â����邩�A���łɏ����Ă���B
�����A�����ƈقȂ�̂̓��N�`���̑��݂��B65�Έȏ�̍���҂̖�4����3�ɂ͍s���n�����B�s�̒S���҂́u���̎���×{�҂͎�E���N�w�����S�ŁA�d�ǂɂȂ�������҂�����Ńo�^�o�^�ƖS���Ȃ鎖�Ԃ͍l���ɂ����v�ƌ��B���{���d�ǎ҈ȊO�͌�������×{�Ƃ����f�ȂǂőΉ�����V���j���܂Ƃ߂��̂����������w�i������B
�s�́u����݂̍���Ƃ��ė����͂ł���v(�S����)�Ƃ����A�����_�ł͎�����h���×{�{�݂�D�悷��B�Ō�t���풓���A�a���������ۂɈ�t���삯�t����V�X�e���������Ă��邩�炾�B
���݁A�s���ɏh���×{�{�݂�3��l�����邪�A�Ō�t�s���̂��ߔ������x�����ғ����Ă��Ȃ��B�s�͍���A�Ō�t�̊m�ۂ�i�߂�ȂǏh���×{�{�݂̉ғ��������߁A�K�v�Ȏ���×{�҂̎M�ɂ���ƂƂ��ɁA�d�ǎ҂�ւ̑Ή��ɐ�O�ł���悤��Ë@�ւ̕��S���y�����Ă������j���B
�@ |
 |


 �@
�@ |
������ �V�^�R���i�V����3709�l�����m�F �ߋ�3�Ԗڂ̑����@8/4
�����s���ł�3���A����܂ł�3�Ԗڂɑ���3709�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�܂��A����ŗ×{���Ă���l��2������C��2000�l�߂�������1��4000�l�]��ɂȂ�܂����B����1������13�{�߂��ɋ}�����Ă��āA�s�́u���ꂾ�������Ȃ�ƃt�H���[����̂����Ȃ茵�����B�E���̑�����i�߂Ă���v�Ƃ��Ă��܂��B
�����s��3���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��3709�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B����Ɋm�F���ꂽ�l���Ƃ��Ă͂���܂ł�3�Ԗڂɑ����Ȃ�܂����B�܂��A1�T�ԑO���861�l�����āA�Ηj���Ƃ��Ă͏��߂�3000�l���āA����܂łōł������Ȃ�܂����B3���܂ł�7���ԕ��ς�3337.4�l�ŁA�O�̏T��189.3���ƂȂ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��A�z������2�����_��20������20.1���ɂȂ�܂����B
3����3709�l�̔N��ʂ́A10�Ζ�����157�l�A10�オ321�l�A20�オ1208�l�A30�オ852�l�A40�オ590�l�A50�オ404�l�A60�オ102�l�A70�オ44�l�A80�オ22�l�A90�オ8�l�A100�Έȏオ1�l�ł��B�����o�H���킩���Ă���1337�l�̓���́A�u�ƒ���v���ł�����768�l�A�����ŁA�u�E����v��258�l�A�u��H�v��66�l�A�u�{�ݓ��v��59�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�s�̒S���҂́u�����g�傪�����Ă��āA�ƒ�A�E��Ƃ�������̏�ʂł̊����������B�E��̐Ȃ��߂�������A��c�ňꏏ��������A�܂��͈ꏏ�ɎԂňړ����Ċ��������P�[�X������B�s���Ǝ��Ǝ҂ɂ́A��c�̓I�����C���ōs���A�ړ�����Ԃł��}�X�N�����ĉ�b�͍T����ȂǑ�����肢�������v�Ƙb���Ă��܂����B
�����I�����s�b�N�֘A�ł́A�O���l�����Z�W��4�l�A�I�肪1�l�A���f�B�A1�l�A���{�l���ϑ��Ǝ�2�l�A���Z�W�҂�1�l�A�{�����e�B�A1�l�̍��킹��10�l�̊������m�F����܂����B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A22��6930�l�ƂȂ�܂����B
����A3�����_�œ��@���Ă���l��2�����120�l������3351�l�ŁA�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��56.2���ł��B����܂łōł�����������3�g��1��12����3427�l�ɔ����Ă��܂��B�s�̊�ŏW�v����3�����_�̏d�ǂ̊��҂�2�����2�l������112�l�ł��B�d�NJ��җp�̕a����28.6�����g�p���Ă��܂��B�����āA����ŗ×{���Ă���l�́A3�����_��2�����1858�l������1��4019�l�ɂȂ�܂����B1�����O��13�{�߂��ɋ}�����Ă��܂��B
�s�̒S���҂́u���ꂾ�������Ȃ�ƈ�Ñ��k�⌒�N�ώ@�ɂ�����s�̃t�H���[�A�b�v�Z���^�[���Ή������Ȃ茵�����B�E���̑�����i�߂Ă���v�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ50�ォ��80��܂ł̒j�����킹��7�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B����ŁA�s���Ŏ��S�����l��2300�l�ɂȂ�܂����B
��1�s3���������b�Z�[�W ���s��A�Ȃ͒��~ ���N�`���ڎ���@8/4
��s���Ŋ����̋}�g�傪�����Ȃ��A1�s3���͋������b�Z�[�W���܂Ƃ߁A���s�A�A�Ȃ̌������~��ϋɓI�ȃ��N�`���ڎ�ւ̋��͂��Ăт����܂����B
�����A��ʁA��t�A�_�ސ��1�s3���̒m���́A3����A�I�����C���ʼn�c���J���A�V�^�R���i�E�C���X������c���܂����B���̒��ŁA1�s3���Ŋm�F���ꂽ�V�K�z���҂͐挎31���܂ł�1�T�Ԃɍ��킹��3��6484�l�ɏ��A2�T�O��3�{�߂��ɑ����������Ƃ�������܂����B�����āA�ψكE�C���X�̉e���ł���܂łɂȂ��}���ȃX�s�[�h�Ŋ������L�����Ă���Ƃ��āA��̓O����Ăт����鋤�����b�Z�[�W���܂Ƃ߂܂����B���̒��ł́A���ׂĂ̓s���E�����ɑ��A���s��A�Ȃ͌������~���������邱�Ƃ�A�s�ƌ��̋����z����ړ��͋ɗ͍T���邱�ƁA����ɐϋɓI�ȃ��N�`���ڎ���Ăт����Ă��܂��B�܂��A20���30��ɑ��ẮA�����҂̂��悻�������߁A��H��ʂ�������������������Ƃ��āA������H����݂��l���ł̈��H�Ȃǂ͂�߂�悤�Ăт����Ă��܂��B����ɁA40���50��ɑ��ẮA�d�lj����X�N�������A���@����l�����ɑ����Ă���Ƃ��āA���O�ꂷ��ƂƂ��ɁA�����ł��Ǐ�������ɑ��k����悤���߂Ă��܂��B
�����s�̏��r�m���͉�c�̒��ŁA�V�^�R���i�E�C���X��̓��ʑ[�u�@�ɂ��āu�R���i�Ƃ̂��������ɂ����āA�ً}���Ԑ錾�����x���o�����Ă������A�s���E�����̍s�����A�ǂ̂悤�ɂ��ė������Ă��炢�Ȃ��琧�����Ă����̂��͂����w���肢�x�[�X�x�ɂȂ��Ă���v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�����낢�듮���Ă��钆�ŁA���s�̓��[�@�̉ۑ�����߂ĕ�������ɂȂ��Ă���ƒɐɊ����Ă���B�@�����ȂǁA�K�v�����܂߂ċc�_���ׂ������ɂ��Ă���Ɗ����Ă���v�Əq�ׂ܂����B�������������ɂ��āA��c�̂��ƁA���r�m���͋L�Ғc�ɑ��u�F����́w���肢���肾�x�Ƃ����b�ŁA���ꂾ���������ƁA�Ȃ��Ȃ����ʂ������Ȃ��������Ă���v�Əq�ׂ܂����B�܂��A�L�Ғc���u�ꕔ�Łw���b�N�_�E���x���s�s�����̓����̋c�_���o�Ă��邪�A�ǂ��l���Ă��邩�v�Ǝ��₵���̂ɑ��A���r�m���́u�O���猾���Ă��邱�ƂŁA�����Ȃ�Ƃ������Ƃ̂Ƃ���ɂ��ǂ蒅���B���L���ۑ�͂���A�{���̘b�����ׂ����Ƃ������Ƃ͂��˂Ă���\���グ�Ă���v�Əq�ׂ܂����B
��s����1�s3���̒m���ɂ��I�����C���̉�c�̌�A�_�ސ쌧�̍���m���́u���܊������L�����Ă���f���^���͂���܂ł̂��̂Ƃ͍��{�I�ɈႢ�A�����͂����ɋ����B�Â����Ȃ��ł��炢�����v�Əq�ׂ܂����B�܂��A�u�O�o���l��l���̗}���ɂ����͂����������Ȃ��Ɗ����҂�����ɑ�������B�����Ƃ����Ƃ��ɋ~�}��Â���ꂸ�A�݂Ȃ���̖��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ肩�˂Ȃ��B�����̊F����ɂ́A8�����܂ōŌ�̉䖝�����肢�������v�Ƙb���Ă��܂����B
��s����1�s3���̒m���ɂ��e���r��c�ŁA��t���̌F�J�m���͌����Œ���1�T�Ԃ̐V�K�����҂̈��������̕��ς�700�l�]��ƂȂ�A�O�̏T�̂��悻2�{�̃y�[�X�ő����Ă��邱�Ƃ�������������Łu��Ԓ������Ă���͎̂_�f���^���K�v�ȏǏ�̏d�������NJ��҂̏ŁA���ɓ��ɑ������Ă���B�܂��A���悢��d�ǎ҂������Ă���ǖʂɓ������B�a���m�ۂ̌v����ő�̃��x���ɕύX���A�~�}���҂̓��@�̎���𐧌����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɗ�@���������܂����B���̂����Łu1�s3���ȊO�̒n��Ɉ�Ò̐��̃_���[�W��^���Ȃ����߂ɂ��A�s�����܂������s��A�Ȃ͌������~�A�܂��͉������Ăق����B���N�`���̐ڎ헦�������ɑO�i���Ă���̂ŁA�m���ɃX�e�[�W���ς���Ă������Ƃ�ڂɌ�����`�Ŕ��M���Ă��������v�Əq�ׂāA�����ɋ��͂����߂邽�߂ɍ���̌��ʂ��ɂ��ď\���Ȑ������K�v���Ƃ����l���������܂����B��c�̂��ƌF�J�m���͋L�Ғc�̎�ނɑ��u����ɕa�����Ђ������A�R���i���܂߂čőP�̈�Â����Ȃ����҂��o�Ă��邱�Ƃ��z�肳���̂ŁA����1�l1�l�������h�~������āA�����������҂�����Ȃ����Ƃ��d�v���B���g�̍s�����N���̖��ɒ������Ă��邱�Ƃ��~�߂Ă��������ė\��̌��������s���A�s���ɂ��אS�̒��ӂ��Ăق����v�ƌĂт����܂����B
��s����1�s3���̒m���ɂ��e���r��c�ŁA��ʌ��̑��m���́u����1�T�Ԃ̐V�K�z���҂����߂�6000�l����Ȃǂ���߂Đ[���ȏ��B����Ɋ����҂̑����̃y�[�X�����܂�ɑ������߁A��Ë@�ւ̐l�̂�肭�肪���Ă��Ă��炸�A��������낤�Ƃ���ƃR���i�ȊO�̈�Â�����\�����o�Ă��Ă���B��Â���@�ɒ��ʂ����Ȃ����߂ɂ͒��N�w���d�lj������Ȃ����Ƃ��}�����B��s���S�̂Ōx�����x�������߂Ă��������v�Əq�ׂĂ��܂����B
�������R���i����1���l�����중S���łً̋}���Ԑ錾�c�_��-���g���@8/4
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��4���A�����s�̐V�K�����҂�1��������1���l�ɒB���邱�Ƃ����蓾��Ƃ̔F�����������B�O�@�����J���ψ���Ŕ��������B
���g���́A�����̊����}�g�傪�u��ʂ̐l�̐S���ɂǂ��e�����邩�A�Ȃ��Ȃ��ǂ߂Ȃ��v�Əq�ׂ���ŁA�f���^���̏��}�ɕς�邱�Ƃ��Ȃ��A���낢��ȕ������钆�Łu1���l�ɂȂ�Ƃ������Ƃ�����v�ƌ�����B
�����s�ł�3���A3709�l�̃R���i�������m�F�B�挎31���ɂ�4058�l�Ɖߋ��ő����X�V�����B
�ً}���Ԑ錾��S���ɍL����ׂ����Ƃ�������ɑ��Ĕ��g���́A�u���R�c�_�̑Ώۂɂ��ׂ����́v�Ǝw�E�B����Ɂu�錾���o���ĉ�����邩�Ƃ����c�_�����s���Đi�߂�ׂ����v�ƌ�����B
���{�͓����Ɖ��ꌧ�ɑ���錾��31���܂ʼn�������ƂƂ��ɁA�Ώےn��ɐ_�ސ�A��t�A��ʂ̎�s��3���Ƒ��{��lj������B
�����@�����ɖ�}���u�l�Ёv�Ɣᔻ�A�a���m�ۂƍݑ�̐��g�[�Ɛ��{�����@8/4
�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������d�ǎ҈ȊO����������×{�Ƃ�����j�ɂ��āA�^��}����ᔻ�⌜�O�̐����������ł���B�c�����v�����J������4���A�ň��̎��Ԃ�z�肵���d�ǎҕa���̊m�ۂƍݑ�ł̈�Ñ̐��g�[�̂��߂��Ɨ��������߂��B
�O�@�����J���ψ���ŗ�������}�̒��ȏ�����\�́A�K�v�Ȑl�����@�ł��Ȃ��ɂȂ��Ă���̂͐��{�ɂ��u�l�Ђ��v�Ɣ��A�Ӎ߂����߂��B
�c�����͊������}�g�傷�錻����u�ً}���Ԃɓ������v�Ƃ�����ŁA�����҂̋}���ŏh���{�݂̊m�ۂ��ǂ��t���Ȃ��ꍇ�ɔ����A�u�ݑ�ň����������ɂ����ƑΉ��ł���̐���g�ށv���Ƃ��K�v���Ƌ����B���@�̐����́u�����v�̑Ή��ł͂Ȃ��A�������K�v�łȂ��ƂȂ�u���j�����ɖ߂��v�ƌ�����B
�܂��A�����}�̍��ؔ��q�㎁�́u�_�f�z�����K�v�Ȓ����ǂ̊��҂�����Őf��Ȃ�Ă��Ƃ͂��蓾�Ȃ��v�Ǝw�E������ŁA�u�P����܂߂Č����������Ăق����v�Əq�ׂ��B�c�����́u�����ǂ������ȕ��X������B�ċz�Ǘ�����Ă���������@���Ȃ����Ƃ͂��蓾�Ȃ��v�Ɗ��҂̏��l������l�����������B
���`�̎�2���̊t����c�ŁA�d�ǎ҂Əd�lj����X�N�̍����l�͊m���ɓ��@���������A����ȊO�͎���ł̗×{����{�Ƃ���V���ȕ��j���������B����×{�̏ꍇ���n��̐f�Ï������f��I�����C���f�Âŏ�c�����A�Ǐ��������ꍇ�ɂ͓��@����̐��𐮂���l���ŁA3���ɂ͓��{��t��Ȃǂɋ��͂�v�������B
�s���ł͊������}�g�債�Ă���A3����3709�l(�O��2195�l)�̊����҂��m�F�B�N��ʂł�20�オ1208�l�ōł������A20�|30��őS�̂�55�����߂��B�����65�Έȏ�̍���҂�3���ɂƂǂ܂��Ă���B
�s���m�ۂ��Ă���R���i�p�̕a����5967���ŁA���@�Ґ���3351�l�Ŏg�p����5���ɒB���Ă���B�d�ǎҗp��392���ɂ́A112�l�����@���Ă���B
�������g��̌����@�@�����c�_����Ñ̐��̋����g����Ȃ�����Ȃ� 8/4
�����ܗւ��J�Â���Ă��邪�A�����s���͂��ߊe�n�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂������Ă���B�u�ܗւ̊J�ÂŋC���ɂv�u�ܗ֊W�҂̓����Ő��ۑÂ������v�Ȃǂ̎w�E�����邪�A����̊����g��ƌܗւ͊W������̂��B
�u�C���ɂv�Ƃ����̂́A�q�ϓI�Ɍv�����悤���Ȃ��̂Ō��ؕs�\�����A�u�ܗ֊W�҂̓����̂��߁v�Ƃ����̂́A�ܗ֊W�҂ɖ��m�ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă��炸�A�W�͂Ȃ��Ƃ����邾�낤�B
���݂̊����g��͓��{�����łȂ��A���E�ł��N���Ă���̂ŁA�����͂̋����ψي��ɂ����̂ƍl������B���Ȃ݂ɁA��N1�����炱��܂Ől��������V�K�����Ґ��ɂ��āA���{�Ɛ�i7�J��(�f7)�̑��W��(1���ő�)���Ƃ�ƁA0�E35�`0�E68�ƂȂ��Ă���A���{�̐V�K�����Ґ��͐��E�Ƃ��Ȃ�̒��x�A�����Ă���B
�ܗ֊��ԂƂ����Ă��A�����X���͏]���ʂ�ł���A���Ɍܗւ̉e���Ƃ͎v���Ȃ��B�Ȃ��A�f7�ł́A���{�̓J�i�_�A�h�C�c�ƂƂ��ɐl��������V�K�����Ґ��A���S�Ґ��͒�ʂł���B
���E�ŐV�K�����Ґ��𑝂₵�Ă���̂̓f���^���ł���B���ہA�����̐V�K�����҂��唼�̓f���^���ƂȂ��Ă���B�����͂��]���̂��̂ɔ�ׂč����͎̂����ł��邪�A�����ǃE�C���X�̌o�����ɂ��A�����͂̍������̂͒v���͔͂���Ⴗ��悤�ɂ���قǍ����Ȃ��B
�f���^���̒v�����͂܂��f�[�^�ł͂�����ƌ�����Ă��Ȃ����A�]���̃��N�`���͂قƂ�Ǔ��l�Ɍ��ʂ����邱�ƂȂǂ���b�m���Ƃ��ė������Ă������ق����������낤�B
�����������A���{��8��2������31���܂ŁA��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���ɐV���ɋً}���Ԑ錾�߂����B�Ώۂ͂��łɔ��ߒ��̓����s�Ɖ��ꌧ�����킹6�s�{���Ɋg�傳�ꂽ�B����ɁA�k�C���A���s�A���ɁA�ΐ�A������5���{���͖���(�܂�)�h�~���d�_�[�u��V���ɓK�p�����B
������8��31���Ƃ����̂́A�������܂łɑS�l���̂������N�`����2��ł����l�̊�����4�`5���ɒB����ƌ����܂�Ă��邽�߂ŁA���𐢑�̃��N�`���ڎ�����ɂ߂����Ƃ��Ă���B
7��30���̐��{���ȉ�ɂ����āA���Ẵ��b�N�_�E��(�s�s����)�̂悤�ȋ����[�u�����{���邽�߂̖@�������K�v�Ƃ̈ӌ����o���Ƃ����B����̌����ۑ肾�Ƃ������A���������ӌ���1�N�ȏ�O�Ɍ����ׂ��������B
���Ȃ݂ɁA���������c�_�́A�ߋ��̃C���t���G���U�����ʑ[�u�@�̐��莞�ɂ��c�_���ꂽ�B�����͌��@��F�߂��Ă���̂ŁA����𐧌�����ɂ͌��@�ɋً}���Ԑ錾�̍����K�肪�Ȃ��Ƃł��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B���������ߋ��̌o�܂��������āA�Ăыc�_�������Ȃ̂��낤���B
����ȋc�_���A��Ë@�ւ��R���i���҂������a���̊m�ۂɕK�v�Ȕ�p�Ȃǂɏ[�Ă�u�ً}��x����t���v��1��5000���~�̗\�Z�[�u�̖������Ȃǂ��c�_���ׂ��ł͂Ȃ����B���ȉ�́A��Ñ̐��̋����g��ɂ��ĉ������킸�ɁA�Љ�o�ϊ�����}�����邱�Ƃ�������Ȃ��̂��B
�������u�����I�g��Łc�v�g�S���K�́h�錾��v���@8/4
3���A�����s�ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂́A3709�l�ł����B
�ߋ�3�Ԗڂ̑����ŁA�Ηj���Ƃ��Ă͍ő��ł��B�܂��A����×{�����Ă���l��1��4019�l�ŁA1�J���Ŗ�13�{�ɋ}�����Ă��܂��B
���`�̑�����b�́A��t���a�@�W�҂Ɩʉ�A�d�ǎ҂�d�lj����X�N�̍����l�ȊO������×{�Ƃ���Ȃǂ̐V���Ȑ��{���j�Ɋւ��A�x�������̋��͂�v�����܂����B
����A���{��t��̒����́A�������ɑ��A�u��苭�͂Ȋ����h�~�S���K�͂ŕK�v���v�Ɨv�����܂����B
���{��t����u��5�g�������I�Ɋg�債�A��Ò̐��́A�}���ɕN��(�Ђ��ς�)������B�S���ւً̋}���Ԑ錾�̔��o���������Ē��������v
���V�^�R���i �S��1��2072�l���� 8���ʼnߋ��ő��X�V�@8/4
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA3���͐V���ɑS����1��2072�l�̊��������\����܂����B
�����s��3���A�V����3709�l�̊����\���܂����B1���̊����҂̔��\�ʼnΗj���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B����7���ԕ��ςł݂��V�K�����Ґ��͂��悻3330�l�ŁA��T�Ɣ�ׂ�ƁA���悻1�D9�{�ɑ����Ă��܂��B
�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ł́A��ʌ���1053�l�A���ꌧ��467�l�ŁA�Ƃ��ɉߋ��ő����X�V���܂����B���̂ق��������A�V�����ȂǁA���킹��8���ʼnߋ��ő����X�V���Ă��āA�S���Ŋ������g�債�Ă��܂��B
�i�m�m�̂܂Ƃ߂ł́A3�����\���ꂽ�����҂͑S����1��2072�l�B���҂�10�l�B�S���œ��@���Ă���d�ǎ҂͑O�̓�����50�l������754�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���S���̐V�^�R���i������ 1��2000�l���@�����u�ً}���Ԑ錾�v�v���ց@8/4
3���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�1��2,013�l�ɂ̂ڂ�A�ߋ�2�Ԗڂ̑����ƂȂ����B
�����s�ł́A�V����3,709�l�̊��������炩�ɂȂ����B�Ηj����3,000�l����̂͏��߂ĂŁA�z������20.1���Ƒ�3�g�����鍂���B�����͂̋����C���h�^�ψكE�C���X�u�f���^���v�́A�V����1,049�l�m�F����Ă���B
����A197�l�̊��������\���ꂽ��錧�́A�����g����Č��Ǝ��ً̋}���Ԑ錾��8��6�����甭�߂��A�����āA���{�ɋً}���Ԑ錾�̓K�p��v�������B�܂��A��ʌ���1,053�l�A���ꌧ��467�l�A�Q�n����148�l�ȂǁA7�̌��ŐV�K�����҂��ߋ��ő��ƂȂ����B
3���A�S���ł͉ߋ�2�Ԗڂɑ���1��2,013�l�̊������m�F���ꂽ�B
���V�^�R���i�@�����g�呱�����@8/4
3���A���Ŕ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂́A���킹��1898�l�ƂȂ�܂����B�����g��Ɏ��~�߂������炸�A�e�{���ł́A�������O�ꂷ��悤�Ăт����Ă��܂��B
����2�{4���ŁA3���ɔ��\���ꂽ�V�^�R���i�̐V���Ȋ����҂́A��オ1079�l�A���ɂ�441�l�A���s��190�l�A���ꂪ����܂łōł�����79�l�A�ޗǂ�76�l�A�a�̎R��33�l�ŁA���킹��1898�l�ł����B
������̕{���ł������҂̐����O�̏T�̓����j���������Ԃ�1�T�Ԉȏ㑱���A�����̊g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
����A�������ĖS���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B
�܂��A��}��_�S�ݓX�Ȃǂ��P���Ɏ��u�G�C�`�E�c�[�E�I�[ ���e�C�����O�v�͐V�^�R���i�̏W�c�������N���X�^�[���������Ă�����E�k��ɂ���u��_�~�c�{�X�v�ŁA�V����18�l�̏]�ƈ��̊������m�F���ꂽ���Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�������m�F���ꂽ�]�ƈ��͂��킹��115�l�ɏ��A�����҂�9���߂����H�i�����̂���1�K�ƒn��1�K�ɏW�����Ă���Ƃ������ƂŁA��Ђ͔̔��̐�������Ȃ��Ƃ��āA4�����H�i�����̋x�Ƃ𑱂��邱�ƂɌ��߂܂����B
�������g�債�Ă��邱�Ƃ���e�{���ł́A�s�v�s�}�̊O�o���T����ȂNJ������O�ꂷ��悤�Ăт����Ă��܂��B
�������܂����ړ��Ŋ����g�傩�@���킫�ŋ}���A�s���ƒm�������y�@8/4
���������킫�s�̐V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�~�܂�Ȃ��B�n���I������A�֓����Ƃ̌o�ϓI�Ȍ��ѕt���������A��Ɗ�����ό��ȂǂŐl�Ɛl�Ƃ̐ڐG�̑����������̍L����ɔ��Ԃ��|���Ă���B�����҂���������1�s3������k�֓��A�k�֓����瓌�k�ւƊ����̔g�������Ă���Ƃ݂���B
�u�������܂����ړ��������g��������Ă���v�B�����q�j���킫�s����2���̗Վ��L�҉�ŕ\�������点�A�u(�֓����Ȃ�)�����g��n��Ƃ̉����͍T���Ăق����v�Ƒi�����B
�s�̒����ɂ��ƁA7���̊����҂Ŋ����o�H���s���Ȑl�̂�����4�������O���܂ގs�O�̐l�Ƃ̐ڐG���������B���O����d���ŖK�ꂽ��A�ό��⍇�h�Ȃǂő؍݂���l�̊����m�F���ڗ������Ƃ����B
���x��Y�m����2���̋L�҉�Łu�����͖k�֓��ƕ����ʂ�n�����ŁA���ڂ̉e�����₷���v�Ǝw�E�����B�����͂̋����f���^���̖҈Ђƍ��킹�A���킫�s�ŋ}���Ɋ������L�܂����v���̈�Ɂu�֓��Ƃ̋����I�ȋ߂��v���������B
���킫�s�ƌ������܂����ŗאڂ����錧��3���A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ւ̒lj��𐭕{�ɗv���B�Ȗ،����������Ɠ���2���ɂ܂h�~�[�u�̓K�p�����߂��B3���Ƃ�7�����{�Ɋ������}�g�債�A���~�߂�������Ȃ��Ȃ����B
2�����_�ł��킫�s�̒���1�T�Ԃ�10���l������V�K�z���Ґ���74�E18�l�B�����{���́u����ȏ�̊�����H���~�߂邽�߂ɂ��s�v�s�}�̊O�o�͔����A��{�I�Ȋ������O�ꂵ�Ăق����v�Ɖ��߂Ďs���ɌĂъ|����B
���g�i�[�X�݂�Ȃ����E�h �����g��ŊŌ�t�Ȃǂ��瓊�e������ �@8/4
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A�l�b�g��ɂ́A�Ō�t�Ȃǂ����Ì���̌�������i���铊�e���������ł��܂��B���e�҂�1�l�����e�ɍ��߂��v��������Ă���܂����B
�u�����A�R�ł�����H���Ă��炢���M������N�w�����������ė��Ă��܂��c�v�u�Ō��1�l������āA�����ʂ薞���ł��v�u�ی����̕�����a��������2�A3�����₵�ė~�����ƑŐf�����܂����B�����Ƃǂ̕a�@�������Ă�v
����1�T�ԂقǁA���l�̓��e���������ł��܂��B
�u�����Ԃ̖h�앞��N95�}�X�N���������ăL�c�C�B�����q�킶��Ȃ��B�����ƖZ�����ő̗͂����E�������v
���̃c�C�[�g�𓊍e�������Ō�t�̏�������ނɉ����Ă���܂����B
�����͊����g�傪��������ɂ��āu�f���^���̊����З͂������A���|�������Ă��܂��B���N�ƈႢ�A�Ⴂ���̊������Ƃɂ����ڗ����Ă��܂��B�R���i�͐g�߂ɂ���܂��B�w�����͊������Ȃ����낤�x�ƈ��Ղɍl���Ȃ��łق����B���N�`����R���i�ɂ��Ă̐��������Ɋ�Â��čs������悤�ɂ��Ăق����v�Ƃ��Ă��܂��B
���̂����Łu�Ƒ��ɂ��Ȃ��Ȃ�����A�ސE���Ă����Ō�t�������ł��B�Z�������Ĕ�J���ς��Œ��Ԃǂ����Ő����|���������Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�c�C�[�g�ɑ��Ă̕ԐM������A���̂��ƂŊ��҂���Ɍ��������撣�邱�Ƃ��ł��Ă��܂��B���A���鏊�ɐl���W�܂�l�q���������܂����A�w�~����͂��̖����~���Ȃ��x�悤�Ȃ��Ƃ��N���Ȃ��悤�ɂ��Ăق����ł��v�Ƒi���Ă��܂����B
�������ܗ����_�����ʁA���{���ɋg�Əo�邩�|�R���i�����}�g�傪�d���@8/4
�����ܗւ͐��J���ɂ킽��A�����W������������{�̊�������ɉe�𗎂Ƃ��Ă����B�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g�傪���O��������A�ܗւł̃��_���l�����R���i�Ђ������Ő��_�I�Ȏx���ɂȂ�Ɗ��҂���l������B
�p�������s�b�N�O�̑��I���܂Ŏc��1�T�Ԃ�钆�A�ܗ֎��̂͐����ƌ��Ȃ����\�������܂��Ă���B���{��\�I�肪�l�����������_�����͊��ɉߋ��ő����X�V�A�R���i���݂̍����͍ŏ����ɗ}�����Ă���B
�����A��������̌��ʂ��͂܂��܂����B���_���l������������Βʏ퉟���グ������{�������N�`���ڎ�i�W�ɔ����Č��������J���ɏ㏸����̂��A�A�i���X�g�̈ӌ��͕�����Ă���B�V�^�R���i�̊����ҋ}���Ƃ��̑Ή��ւ̍����̎��]�������s���ɂȂ���A���{���̃A���_�[�p�t�H�[�}���X����������Ƃ̌���������B
��N�Ȃ�A�����_�����b�V���͎s��Ƀv���X�ɓ����͂����B�O��Z�F�c�r�A�Z�b�g�}�l�W�����g�̑�X���g�`�[�t�G�R�m�~�X�g�̓��|�[�g�ŁA1968�N�̃��L�V�R���ȍ~�A���{�̋����_���l������2���ɒB�����S�Ă̑��ŁA���o���ϊ����͑����Ԓ��ɏ㏸�����Ǝw�E�����B
�������A����̑��͑O��̂Ȃ��R���i�����g��̐^���������ŊJ�Â���A���ʂ��܂��܂������ً}���Ԑ錾�ɍ����̊Ԃł͎��l��ꂪ�L�����Ă���B�H�̑��I���ɐ旧�����}���ّI��9���ɍT�������`�̎́A�R���i�Ђɂ�����u���S�E���S�ȓ������v�̊J�Âɓq���Ă����B
����،��̌E�c����Y�V�j�A�}�[�P�b�g�A�i���X�g�́u���ܗւ��J�Â��Ă��āA���̊ԂɊ������g�債�Ă���B�����Ȃ�Ɛ������������̃R���g���[���Ɏ��s�����Ƃ̃C���[�W���t���Ă��܂��v�Əq�ׂ��B
���������C���[�W���H�̑��ꔽ����z�肵���V�i���I�ɂ����炷�Ӗ������ɂ��āA�ꕔ�����Ƃ͌x����炵�Ă���B���o���ς̔N�����㏸����1�������ƁA�u���[���o�[�O���c�������i���s��̊����w�W�ōň��̕��ނ̃p�t�H�[�}���X���B
�s���c�A�Z�b�g�}�l�W�����g�̘Q���G�`�[�t�E�X�g���e�W�X�g�́u�ň��̃P�[�X�ł́A�G�R�m�~�X�g�͏H�̌o�ωV�i���I������������\���������Ȃ�B�����ڐ��ł͌ܗւɏ��ɓI�Ȓ��ŊJ�Â��A�������̎x�����͂�艺����\��������A���{���ɂ͏d���v�ƂȂ蓾��Ɨ\�z�����B
�����A��1400���l�̐l��������铌���̃R���i�֘A���Ґ���7��29���܂ł�1�T�ԂŌv5�l�ɂƂǂ܂�A���������E�̑��̎�s���l�ɃR���i�Ƌ������Ă����悤�ɂȂ�Ƃ̌���������B
�Z�]�����M�^�p���̐����N�Y�^�p�����́A�u���C�h�V���[�Ƃ��͕ʂ����A�d�ǎ҂⎀�S�҂̐��̕����ڐ��Ƃ��ċ����Ǝv���B���N�Ɣ�ׂ�ΑS�R�Ⴄ�v�Əq�ׂ��B
���N�`���ڎ�̍L����ŁA65�Έȏ�̍�����75����2��̐ڎ�������B���_�����͂Ȃ��������i�W�ɕs���������Ă��邱�Ƃ������Ă�����̂́A���݂̔�펖�Ԑ錾��8�����ɏI������܂łɁA�S�l����40������2��̐ڎ���I����Ɛ��{�͗\�z���Ă���B
�r�l�a�b�����،��̚����k�`�[�t�����X�g���e�W�X�g�ƈ��c�������X�g���e�W�X�g�̓��|�[�g�ŁA�u�����ɂ����Ă�9�������王�E������n�߂�v�Ƒz��B�������9���܂łɃ��N�`����2��ڎ킵���l���̊�����50����˔j����Ƃ̗\���ɉ����A�I���O�Ɏh�����������\���������A�u9������10�|12�����ɂ����ē���������V�i���I��`���悤�v�Ƃ̌������������B
���u�a���N�����Ȃ��v���玩��×{�g��}�]���@���ʂ��Â����{�@8/4
�V�^�R���i�E�C���X�����̋}�g����āA���{�͓��@�Ώۂ��d�ǎ҂⒆���ǂ̂����d�lj����X�N�̍������҂�Ɍ��肵�A����×{����{�Ƃ���V���ȕ��j��ł��o�����B���N�`���ڎ�̐i�W�𗝗R�Ɂu�V�K�����҂������Ă��a���͕N���Ђ��ς����Ȃ��v�Ƃ��Ă����Â��z��͕���A��}�́u��Â̕������v�Ɣᔻ�����߂�B
����t�������炢�Ă��ǂ����Ȃ��c
���`�̎�3���A���@�œ��{��t��̒���r�j����ÊW�c�̂̑�\�Ɩʉ�u�}���Ȋ����g��ł���ÒԐ����m�ۂ��A�N�����Ǐ�ɉ����ĕK�v�Ȉ�Â��s�����Ƃ��ł���悤���j�]�������v�Ɛ����B����×{�҂̏��A���f��I�����C���f�ÂŔc�����ēK�Ȉ�Â����悤���͂����߂��B���쎁�͖ʉ��A�L�Ғc�Ɂu�����������I�ɑ����Ă����ƁA(��t��)�����炢�Ă��ǂ����Ȃ����Ƃ͌����ɂȂ�B�撣��邾���撣��ƌ��������Ȃ��v�Ɣߑs����Y�킹���B
�����{�E�^�}�Ɋy�Ϙ_���܂�
���{�̓��˂ȕ��j�]���́A���̎����̕a���N���ɔ����Ă��Ȃ��������Ƃ̕\�ꂾ�B����҂ւ̃��N�`���ڎ�̐i�W�ɂ���āA�d�ǎ҂͌���Ƃ݂Ă����B�����͂������f���^���ւ̒u�������ɂ��A7���ɓ����ĐV�K�����҂����������Ă��A���{�E�^�}���ł́u���ꂩ��͊����Ґ��łȂ��d�ǎ҂⎀�S�Ґ�������ׂ����v(�����}����)�Ȃǂ̊y�Ϙ_���x�z�I�������B���L�҉�ŁA�����̏Ɋւ��u�l�H�ċz�킪�K�v�ȏd�ǎҐ���1���Ɣ�r���Ĕ����B�a���g�p����2�����x�ɗ}�����Ă���v�Ɛ������Ă����B�������A7�����{��4�A�x��A����Ɋ����Ґ��͋}���B29���ɂ͏��߂đS���̐V�K�����Ґ���1���l�����B���{�̃R���i�����ȉ�̔��g�Ή��28���̒i�K�Łu��Â̕N�������ɋN���n�߂Ă���v�Ɩ����B�f���^���͎Ⴂ�l�ł��d�lj����X�N������A�����҂�������Ώd�ǎ҂�������̂́u�K�R�I�v(���쎁)�������̂��B
������ł��u�a���͑���Ă���v
���j�]���ɒǂ����܂�Ă��A���{���ɂ͂Ȃ��y�Ϙ_���Y���B���������̈�l�͕N���̗��R���u�y�ǎ҂△�Ǐ�҂��ǂ�ǂ���@�����Ă��邩�炾�v�Ǝw�E�B�ʂ̊����́u�Ǐ�ɉ����ĉ�]������Εa���͑���Ă���v�ƌ��B�����A�V���j�͉^�p�����Γ��@�̒x���a��̈����������A���҂̖��̊댯�����߂��˂Ȃ��B��N�t�Ɍ����J���Ȃ��R���i�̎�f�̖ڈ����u37�D5�x�ȏ�̔M��4���ȏ�v�Ǝ������ۂ́A��ɖ����Ȃ��l�����������Ȃ��Ⴊ���o���A�y�ǎ҂��d�lj������莀�Ɏ������肷�邱�Ƃ��������B�������M���[������3���̋L�҉�Łu�����������O�����܂��đΉ����Ă����K�v������v�Ƌ����B�ʂ̐��{�����́u����×{�҂̌��N�ώ@�́A�ی��������ł͌��E������v�ƈ�Ë@�ւƂ̘A�g�������ۑ�ɋ�����B���{�̑Ή��ɁA��������}�̎}��K�j��\��3���̓}��Łu�w����×{�x�Ƃ����̂͌��t�����Łw��������x�ƌ��킴��Ȃ��B�Ƃ�ł��Ȃ������܂�Ă���v�ƈ�Â̕������Ɣᔻ�B���Y�}�̎u�ʘa�v�ψ����̓c�C�b�^�[�Łu���g���w��Õ���x��������F�߂��v�Ǝw�E�����B
���u���͉����������Ă��Ȃ��v�@�d�LjȊO�́u����×{�v�͖����Ɂc�@8/4
�R���i�Ђ̊g�傪�~�܂炸�A�a�����N�����Ă������A���{��2���A�d�ǎ҂�d�lj��̋���̂���l�ȊO�́A��������×{�Ƃ�����j�����߂��B����܂ł��Ȃ��Ȃ����@�ł����A����ɂ���ԂɖS���Ȃ�P�[�X�����X�������̂ɁA����ɓ��@���Â���������Ƃ����킯���B�u�����v�̌��t����D���Ȑ��`�̎炵�������ւ̎d�ł������A��������������ڂ����炻���ƁA���[���̕���s���悭�ς��Ă����̂��B
������×{�ŕ��e���c
�u���{�͉�������Ă���̂��Ǝv���B����×{���Ɉ�C�ɏd�lj�����A�����ɂȂ�̂Ɂc�v�B�R���i�����ŕ��e��S�����������s����50��j���͕���B���e���S���Ȃ����͍̂ŏ��ً̋}���Ԑ錾���̍�N�t�B�����ƔM���o��悤�ɂȂ�A�n���̕a�@����f�B���������M�܂ł�������M�͉����������A1�A2���ŏǏԂ�Ԃ����B�~�}�������ꂽ�a�@�ło�b�q�������ėz�����肪�o���B�����@���Ǝv��ꂽ���A��������ɋA���ꂽ��A�ی������͎���×{���w���B�Ƒ��͉��x���u���������ɓ��@�����Ăق����v�ƕK���ɗ������܂�A�S���҂́u�Ǐd���l������@�����Ă���v�ƌ��������������Ƃ����B�������A3���قǂŕ��̗e�̂͋}�ς����B�ʂ̕a�@�ɋ~�}�������ꂽ�Ƃ��ɂ͂��łɁA�l�H�ċz�킪�K�v�ȂقǏd�lj����Ă���A����1�T�Ԍ�ɑ�������������B�z�����肪�o�Ă��炠�����Ȃ����������B�j���́u�������������Ȃ��瓖�����@��f��ꂽ���ƁA�t���Y�����Ƒ����ǂ�Ȃɕs�����������B�ی����͓d�b�̂��Ƃ�ŁA���e�̏Ǐ���ǂ����f���Ă����̂����܂��ɕ�����Ȃ��B���u���ꂽ�悤�Ȃ��́B�~�}�������ꂽ�Ƃ��ɓ��@�ł��Ă�����A����������Ȃ����Ǝv���Ă���v�ƐU��Ԃ�B
�����{���j�ő����̋���
���������P�[�X�𑱔������鋰�ꂪ����̂��A�V���Ȑ��{�̓��@���j���B����܂ł́A�ċz��ɏǏȂ��y�ǂł���b����������ꍇ��A�x����ċz������钆���Ljȏオ���@�̑Ώۂ������B����͒����ǂł��A�d�lj����X�N���Ⴂ�Ɣ��肳�ꂽ�l�́A��������×{�ƂȂ�B�ƒ�������̋���⎩��×{������Ȏ������Ɣ��f���ꂽ�ꍇ�ɂ͏h���×{�ɂȂ�B������������}�g�咆�̒n�悪�ΏۂƂȂ�B���̕��j�]���̔w�i�ɂ���͕̂a���̕s�����B�f���^���̍L����ŐV�K�����҂�1��1���l�ɒB������������B�����J���Ȍ��j�����ljۂ̒S���҂́u�K�ɕa�����m�ۂ��邽�߁v�Ɛ����B�����߂��S�s���{���ɒʒm���A�e�����̂��n��̎���ɉ����Ĕ��f���邱�ƂɂȂ�B���͎���×{�ɔ��������_�f�Z�x�𑪂�u�p���X�I�L�V���[�^�[�v�̔z����i�߂�B�d�lj��̋�������݂₷������Ƃ����B
���d�lj��u���ɂߊȒP�ł͂Ȃ��v
�����A���������x�����N�����ċz���ꂵ���悤�ȏǏ�̊��҂��A��Â����Ȃ�����ŗ×{������̂͊댯�ł͂Ȃ��̂��B���ۈ�Õ�����̍����a�Y����(�����NJw)�́u���͏ꓖ����I�ʼn����������Ă��Ȃ��v�Ƃ������B�u�_�f���^���K�v���ǂ����ɂ���Ē����ǂ�1��2�̃��x���ɕ�����邪�A1����2�܂ł͐i�s�X�s�[�h�������B2�܂ŏd�lj�����Α}�ǎ�p���K�v�ɂȂ�A�蓖�Ă��x�ꂽ�疽�͊댯�ɂȂ�B�d�lj��̌��ɂ߂͊ȒP�ł͂Ȃ��B����͊�b�����̗L����Ǐ�̕ω��ȂǍ��܂ňȏ�ɒ��J�ɂ݂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƌ�����B
�����������킫�̎����{�݃N���X�^�[50�l�Ɋg��@�V�^�R���i�A2�l�����@8/4
����3���A���킫�s�̎����{�݂Ŕ������A48�l�̊������m�F���ꂽ����106���ڂ̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�͒����̌��ʁA7��31���ƍ���1���ɗz��������2�l���܂܂�邱�Ƃ�������A50�l�Ɋg�債���Ɣ��\�����B
���Ƃ��킫�s�ɂ��ƁA����������s�̕ʂ̎����{�݂Ŕ�������96���ڂ�9�l�A���H�X�ł̉���Ŕ�������102���ڂ�11�l�A�C�x���g�{�݂�104���ڂ�7�l�A�ڑ҂����H�X��94���ڂ�20�l�Ɋg�債���B�܂��A�����w�@���n���h�{�[�����Ȃǂ̍������K�ɔ���99���ڂ�13�l�ɍL�������B
����_�~�c�{�X�̃N���X�^�[128�l�Ɂ@��}���߂��{�X�ł�34�l�̊����m�F�@8/4
�N���X�^�[�������������~�c�̍�_�S�ݓX�ŐV����13�l�̐V�^�R���i�E�C���X�̊������������A�����҂͌v128�l�ƂȂ�܂����B�܂��A��}�S�ݓX�ł�����܂ł�34�l�̊������m�F����Ă��܂��B
���s�k��ɂ����_�~�c�{�X�ł́A�̔����̊ԂŃN���X�^�[�������������Ƃ���A7��31������2���ԑS�ٗՎ��x�Ƃ��A8��2������͒n��1�K��1�K�̐H�i�����������ĉc�Ƃ��ĊJ���Ă��܂��B
�^�c����G�C�`�E�c�[�E�I�[���e�C�����O�ɂ��ƁA�V���ɏ]�ƈ�13�l�̊������������A�����҂͌v128�l�ƂȂ�܂����B
3���܂łɁu�������S�z�v��u�����ɂ��ċ����Ăق����v�Ƃ������q����̖₢���킹��1000���ȏ㑊�����ł���Ƃ������Ƃł��B
5���ȍ~�̉c�Ƃɂ��ẮA�]�ƈ���2000�l�Ɏ��{����PCR�����̌��ʂ��l�����A���肷��Ƃ��Ă��܂��B
�܂���}�S�ݓX�ł��A����܂ł�34�l�̊������m�F����Ă��܂����A�����o�H�͕s���Ō��݁A�N���X�^�[�ɂ͔F�肳��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��}�S�ݓX�ł͏��ł�O�ꂵ�������A�ʏ�ʂ�c�Ƃ��Ă��܂��B
���V�^�R���i�̉e�� 1860�Ђ��|�Y ���H�X�Ȃǒ��S�ɂ���ɑ����� �@8/4
�V�^�R���i�E�C���X�̉e���œ|�Y������Ƃ̐��́A3���܂ł�1860�ЂƂȂ�܂����B���Ƃ��ɓ����đ����X���������Ă��āA������Ђً͋}���Ԑ錾�̉�����g��̉e���ŁA���H�X�Ȃǂ𒆐S�ɂ���ɓ|�Y���������邨���ꂪ����Ǝw�E���Ă��܂��B
�M�p������Ђ́u�鍑�f�[�^�o���N�v�̂܂Ƃ߂ɂ��܂��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�̉e���Ŕj�Y�Ȃǂ̎葱��������ē|�Y������Ƃ⎖�Ƃ��~���Ė@�I�����̏����ɓ�������Ƃ͌l���Ǝ���܂߂ċ��N2������3���܂ł̗v��1860�ЂɂȂ�܂����B
�Ǝ�ʂł́u���H�X�v��311�Ђƍł������A�u���݁E�H���Ɓv��185�ЁA�u�z�e���E���فv��101�ЁA�u�H�i���v��97�ЂȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�|�Y���������������Ƃł́A���Ƃ�3����177�Ђƍł������A�����ł��Ƃ�4����168�ЂȂǂƂ��Ƃ��ɓ����đ����X���������Ă��܂��B
�鍑�f�[�^�o���N�́u���H�X�Ȃǂ̓|�Y�ɔ����A�X�̏C�U�⌚�݂𐿂��������Ǝ҂Ȃǂ��A���I�ɓ|�Y����P�[�X�������Ă���B�Ẵ��W���[�V�[�Y���ɋً}���Ԑ錾�������E�g�傳�ꂽ���ƂŁA���コ��Ȃ�|�Y�̑����ɂȂ��邨���ꂪ����v�Ƙb���Ă��܂��B
��1���̊�����600�l�ɋ߂Â��\�����@�����467�l�����@1�l���S�@8/4
���ꌧ��3���A�V�^�R���i�E�C���X��10�Ζ�������80��܂ł�467�l���������A1�l�����S�����Ɣ��\�����B1���̊����Ґ��ł͉ߋ��ő��ŁA��T�Ηj����354�l����1�E32�{�ɑ������Ă���B�×{��3106�l�Ⓖ��1�T�Ԃ̐V�K������2603�l���ߋ��ő��ƂȂ����B���{��3���A�����NJ��҂̂����A�d�lj����X�N�̒Ⴂ�l�͎���×{�Ƃ�����j�����߂����A���͌����_�ō��̕��j�ɕύX����\��͂Ȃ��A������̒ʒm���đΉ�����������Ƃ����B�@
�V�K�z���҂̂����A20�オ117�l��30�オ76�l�A10�オ75�l�A40�オ63�l�A10�Ζ�����54�l�ƎႢ�N��Ŋ������ڗ����Ă���B���芴���o�H���m�肵���̂�171�l�ŁA�Ƒ�����99�l�ōł������A�F�l�m�l25�l�A�E��Ǝ{�ݓ����e15�l�A���H11�l�������B����1�T�ԕ��ς̊����o�H���s���ȏǗ��58�E4���ƂȂ��Ă���A�����}�g��ɔ�Ⴕ�Ċ������������Ă���Ƃ����B����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����҂�170�E68�őS���ő����p�����Ă���B
��������ËZ�Ắu��T1�T�Ԃ̊����҂�2400�l���x���������Ƃ���ɂ���ƁA���T��1���̊����҂�600�l�ɋ߂Â����Ƃ��z�肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƙb���A�����X�����~�܂�Ȃ����Ƃ����O�����B
���@���҂�531�l�ŁA�d��7�l�A������335�l�B������Ë@�ւ̕a�����́A3�����_�ŗ��s��4�g������716���m�ۂ��Ă���B���݂͌y�ǎ҂�����Ă��邪�A���҂����������邱�Ƃ�z�肵�A�Ǐ��P�������҂��h���×{�z�e���Ɉړ���������A����ɖ߂����肷�邱�ƂŁA�a�����m�ۂ��Ă����Ƃ����B
���S���̐V�^�R���i������ 1��2000�l���@�����u�ً}���Ԑ錾�v�v���ց@8/4
3���A�S���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�1��2,013�l�ɂ̂ڂ�A�ߋ�2�Ԗڂ̑����ƂȂ����B
�����s�ł́A�V����3,709�l�̊��������炩�ɂȂ����B�Ηj����3,000�l����̂͏��߂ĂŁA�z������20.1���Ƒ�3�g�����鍂���B�����͂̋����C���h�^�ψكE�C���X�u�f���^���v�́A�V����1,049�l�m�F����Ă���B
����A197�l�̊��������\���ꂽ��錧�́A�����g����Č��Ǝ��ً̋}���Ԑ錾��8��6�����甭�߂��A�����āA���{�ɋً}���Ԑ錾�̓K�p��v�������B
�܂��A��ʌ���1,053�l�A���ꌧ��467�l�A�Q�n����148�l�ȂǁA7�̌��ŐV�K�����҂��ߋ��ő��ƂȂ����B
3���A�S���ł͉ߋ�2�Ԗڂɑ���1��2,013�l�̊������m�F���ꂽ�B
���Ă̋A�ȁu���l�v�ɔ����@�������ɋ^����\�V�^�R���i�@8/4
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�剺��2�x�ڂƂȂ�ċx�݃V�[�Y���B�S���m����͓s���{�������܂����A�Ȃ̒��~�E������v��������܂Ƃ߂����A�C���^�[�l�b�g�𗬃T�C�g(�r�m�r)��ł͔������������A�����Ǒ�̐��Ƃ����������^�⎋����B
�m�����1���A���ւ̒Łu�l������������ċx�ݖ{�Ԃ��T���A�}�����݂Ɉꍏ�̗P�\�������Ȃ��ɂ���v�Ǝw�E�B�A�Ȃ̗}���ɉ����A���b�N�_�E��(�s�s����)�̂悤�ȋ����[�u�̌��������߂��B
���ꂪ����ƁA�c�C�b�^�[��ł́u���̂��߂̍���҂ւ̃��N�`���ڎ킩�v�u�Ȃ��������z�����A�Ȃ͒��~�ŁA�������z�����ܗւ͂��̂��v�Ɣᔻ�����������B
���l�s�̏�����Ј�(45)�́A�s���ɏZ��70��̗��e���ڎ���I���A������߂�2�x�ڂ��邽�߁A�u2�N�Ԃ�Ɋ�����킹�����v�ƌ����̋A�Ȃ��y���݂ɂ���B�O�o���l�����߂���ً}���Ԑ錾�̑Ώےn�悾���A�u�ܗւ͊J�Â��Ă���̂ɁA���������̐��������������͔̂[���������Ȃ��v�ƕs�����B���Ȃ��B
���a��̓�ؖF�l�q������(�����NJw)�́u���N�`���͏d�lj���\�h���邪�A�ڎ킵�Ă��������X�N�͎c��v�Ɛ����B�ړ��}���̕K�v����F�߂A�錾���ł������҂͑����Ă��邽�߁A�u(�m�����)�ɂ��v�]�ł͌��ʂ��Ȃ��̂ł́v�Ƌ^��𓊂��|�����B
�@
�������s �V�^�R���i 4166�l�����m�F �ߋ��ő� ��T���989�l�� �@8/4
�����s��4���A�s���ŐV����4166�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1���̔��\�Ƃ��Ă͐挎31����4058�l������A����܂łōł������Ȃ�܂����B1�T�ԑO�����989�l�����Ă��āA�����̋}���Ȋg�傪�~�܂�܂���B
����A�s�̊�ŏW�v����4�����_�̏d�ǂ̊��҂�3�����3�l������115�l�ł����B
�������NJԊ��҂̋}�ς�d�lj��ɑΉ��ł��邩�@���{�V���j�@8/4
���{�́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̒����NJ��҂�����×{��������j�ɓ]�������̂ɍ��킹�A����ł̋}�ςɔ������{���ł��o�����B�����A�ۑ�͑����B�}�ϑ�̒��́A�ی�����n��̈�t��ɂ��ݑ�҂̌��N�Ǘ��������B�����A�����s���̕ی����͊��Ɏ���×{�҂̎x������@�����ɖZ�E����Ă���B�R���i��������J���Ȃɏ���������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�̈���ŁA�����s�k��ی������̑O�c�G�Y���́u���{���j�͐Q���ɐ��B�ی����ɂƂ��Ă͍���ȓ��e���v�Ɩ{���̎�ނɌ�����B
�f���^���͖��Ǐ��y�ǎ҂��Z���ԂɈ�������P�[�X������B�O�c���́u�x�����K�v�ȗz���҂��������ꍇ�A�Ή��͓���B�ˑR�d�lj����A�S���Ȃ�����������錜�O���傫���v�Ƙb���B���@��������̕K�v���������鐭�{�ɂ��u���̓��@���҂͏Ǐd���A����×{������l�B�w�y�ǂ����ǔO�̂��ߓ��@�����Ă������x�Ƃ����Ή��͂��Ă��Ȃ��v�Ƌ^����������B���{�͍ݑ�R���i���҂̉��f�Ȃǂ̐f�Õ�V�̏�悹�����߂��B��t��̈ӗ~�����߁A���҂��ݑ��Â��₷������_�����B�������A���f�̒S���肪�}�ɑ�����ۏ͂Ȃ��B�Ǐ�̈������c���ł����Ƃ��Ă��A���J�Ȃ̏W�v�ɂ��ƁA7��28�����_�œ��@�̕K�v������̂ɁA����悪����̓s���̊��҂͊���202�l�B�v���ȓ��@���m�ۂ���Ă���Ƃ͌����Ȃ��B
�d�lj���h�����߁A�ݑ�҂ɂ��R�̃J�N�e���Ö@��ϋɓI�Ɏ��{���邱�Ƃ��f�����B�����A�m�ۗʂ��\�����A�v���ɔz���ł��邩�s�����c��B�Ō�̎�i�ƂȂ�~�}�����ɂ��e�����o�Ă���B�����ȏ��h���̏W�v�ł́A7��26���`8��1���A���҂̔����悪�����Ɍ��܂�Ȃ��~�}��������Ă��S����2376������A�O�T���8�����������B
���u��Õ���𐭕{�������I�ɔF�߂��`�v �V�^�R���i���@�Ώێ҂̕��j�]���@8/4
���{��2���ɐV�^�R���i�E�C���X�̓��@�Ώێ҂ɂ��Č����d�ǎ҂ɍi�荞�ނƕ��j�]�������A�^�}����e�����́A��Ì��ꂩ�甽���̐����オ���Ă���B
���{�̕��j�ł͒����ǂ̒��ł��d�ǎ҃��X�N���������҂ɑ��Ă͈����������@�ΏۂƂ��邪�A�����g�傪�����Ȃ��A����×{�҂���������̂͊m�����B�����s�̎���×{�Ґ���3�����_�ʼnߋ��ő���1��4019�l��1�����O�̖�13�{�ƂȂ��Ă���B
4���́u�H���T�ꃂ�[�j���O�V���[�v(�e���r�����n)�ɏo���������ǂ̃R�����e�[�^�[�E�ʐ�O���́u��Õ���𐭕{�������I�ɔF�߂��`�B���{�͑��ӁA�d�ǎ҂ł����@�ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����ɓ���Ă���Ǝv���v�Ƃ��������ŁA���`�̎��i�߂�Ƃ��Ă���V���Ö�u�R�̃J�N�e���v�̋����ʂɂ��āu���{�͍��̒i�K����č��ƌ����A���ȏ�ɗA���ł���悤�ɑ��}�ɂ���Ăق����v�Ƒi�����B
��}�������������A��������}�̎}��K�j��\��3���A�u����×{�Ƃ����̂͌��t�����ŁA��������Ƃ��������悤���Ȃ��v�ƖҔᔻ���Ă���B
�������ǂ͎���×{�Ƃ������j�ŁA��Õ���͖h����̂�?�@8/4
�����x�̔x���ǂ��Ď_�f�z�����K�v�Ȋ��҂�����×{������Ƃ����Ă𐛓��t����Ă��Ă��܂��B�ړI�͂���1�A�f���^���𒆐S�Ƃ����V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪���������ꍇ�ɁA�R���i�a�������ӂ�ď����閽�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�܂葭�Ɍ�����Õ����h�~���邽�߂ł��B
�ł����A���ɒ����ǂ���Ǐ���(����)�����ꍇ�ɓ��@���x�ꂽ��A�ݑ�̂��߂ɕK�v�Ȗ�ܓ��^���ł��Ȃ����Ⴊ�������āA�~���ł���͂��̊��҂����S����悤�ł́A��Õ���̖h�~�ɂ͂Ȃ�܂���B
���{������Ȃ��Ƃ͕������Ă���̂��Ǝv���܂����A���{�̐��_�ɂ͏d��Ȍ��O���L�����Ă��܂��B�����́A���X�N�R�~���j�P�[�V�����̑傫�ȕ���_���Ǝv���܂��B�ȉ��A3�_�ɂ��Ē��J�Ȑ������s���K�v������Ǝv���܂��B
���A�����J�͈�w��������
1�ڂ́A�a���m�ۂ̖��ł��B2020�N��1���A�����̌Ζk�ȕ����ł͓ˊэH���ŃR���i��p�a�@�����݂��Ă��܂����B������v���A����͊��������ɂ�钆���ǎ��Â̂��߂̂��̂ō����I�Ȕ��f�ł��������Ƃ�������܂��B2020�N��3������4���ɂ́A�A�����J�̃j���[���[�N�ł́A�����Ƀe���g������A�R�̕a�@�D����q��������A�R�̍H���������ˊэH���Ō��{�s����a���ɉ��������肵�Ă��܂����B������R���i�a���m�ۂ̂��߂ł����B
���������Վ��̑����{���{�͑I�����܂���ł����B�����炭�A�a�@�̌��݊�����i�ł���ȂǁA�@����x�̖��Ƃ��ĕs�\�������̂��Ǝv���܂��B���ɂ����ł���A�������K�����ꎩ�̂��l������邽�߂ł��邱�Ƃ�������A�����ɗ��������߂�ׂ����Ǝv���܂��B
2�ڂ́A��Ï]���҂̊m�ۂ̖��ł��B�A�����J�̏ꍇ�́A�����g�傪�������ɂȂ�ƁA��������̈�t�����łȂ��A��ȑ�w�@�̊w���A�O���̈�t�Ƌ��ۗL�҂܂Ō���ɓ������܂����B�܂��A�]�T�̂���B����Վ��ɗv����Z�ʂ��邱�Ƃ����܂����B����8���ɓ��������_�ł��A�ň��̏�ԂɊׂ������C�W�A�i�B�ɂ́A�A�M���{����ЊQ��̘g�g�݂ň�t33�����}�h����Ă��܂��B
����×{�̏ꍇ�ɂ��A��Ï]���҂��ǂ��P�A���Ă䂭�̂��A�v���̖��͂��ĉ��܂��B�Ⴆ�A�l�H�ċz��̐ݒ�ƊǗ��͂ǂ�����̂��A�����_�f�Z�x���ُ�l�ƂȂ����玩���I�Ɏ��Â������͓��@���ł���̐��͎���̂��A����ȑO�ɋ}���ɗe�̂��������钛����������Ȃ����߂ɁA��t��Ō�t���ǂ�������̂��Ƃ��������͏d�v�ł��B
��t��Ō�t�ɂ��ẮA���N�`���ڎ�̗v���m�ۂ����ƂȂ��Ă��܂��B�ł����A�����炭�������\�z�����ݑ�×{�҂̃��j�^�[�A����f�ÂƂ������f�Ís�ׂ́A�ȒP�Ȍ��C�ŗL���i�҂��g��ł���悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B�ǂ��v�����[������̂��A��̓I�Ȍv��̐������K�v�ł��B
�������܂ł��ʏ�f�Â͎��̂�
3�ڂ́A�ʏ�f�Âւ̉e���ł��B�A�����J�̏ꍇ�́A�����������N���ăR���i�a�������ӂꂽ�ꍇ�́A�ʏ�f�Â̂��߂�ICU��߂ăR���i���҂ɉĂ��܂����B�����炭�A����ɂ���ăR���i�ȊO�̊��҂ŋ~�����ł��Ȃ������P�[�X������Ǝv���܂��B�ł����A���Â��x���ƁA�y�ǂ����C�ɗe�̂��������Đ������Ɏ��S����\���̂���R���i���҂́A�����܂ŗD�悷��Ƃ����̂��Љ�I�Ȕ��f�ƂȂ��Ă��܂��B
���{�͂��̍l����������Ă��܂���B����̎���×{�ɂ��x�b�h���m�ۂ���Ƃ������j�́A�R���i�̏d�ǎ҂Ɍ����ăx�b�h���邽�߂Ɛ�������Ă��܂��B�ł����A�����ɂ����܂Œʏ�f�Â����A���Ԃ̕a�@�őΉ��s�\�ȂƂ���ɂ̓R���i���҂��Ȃ��Ƃ����u����v���ێ�����Ƃ������f���܂܂�Ă��܂��B
����͌��J�Ȃ��t����R�ƕϊv�������Ă���A�����Ƃ͂���ɗ�����Ă���Ƃ��������ōς܂��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B�@����x�̖��Ƃ��āA�ς����Ȃ����͕̂ς����Ȃ��Ƃ������Ƃł���A����ł��ς���Ƃ������ƂȂ�A���_�Ɛ������^���ȑΘb�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
�����ǂ̎���×{�ɂ��ẮA����Ŕᔻ���ꂽ���Ƃ���A�c�����J���́u�������v�Ƃ��ĕ��j�P�����킹�Ă��܂��B���ɖ{���Ɍ����������āA�����������������Ă������NJ��҂�100�����@������̂ł���A���x�����ʏ�f�Â̌���ێ�����߂邱�ƂɂȂ�܂��B����Ȃ�A���������^���ȋc�_���K�v�ł��B
������×{�A�e�̋}�ςɌ��O�@�u�����ǁv�ł����X�N�����\��Õ������֓]���@8/4
�V�^�R���i�E�C���X�����҂̋}�����A���{��3���A���@���d�NJ��҂�d�lj����X�N�̍������҂Ɍ�����j����{��t��Ȃǂɓ`�����B�ߋ��ɂȂ����������ɒ��ʂ��A�a�����m�ۂ��邽�ߕ��j�]����������ꂽ�B�����A����×{�҂̗e�̂��}�ς��鎖����������ł���A�����҂̕a������ߍׂ����Ǘ��ł��邩���ۑ�ƂȂ�B
�u�}���Ȋ����g��ł���Ò̐����m�ۂ��A�Ǐ�ɉ����ĕK�v�Ȉ�Â��ł���悤���j��]�������v�B���`�̎�3���A����̒���r�j���Ǝ��@�ʼn�A�y�ǎ҂����łȂ��d�lj����X�N���Ⴂ�����NJ��҂���{�I�Ɏ���×{�Ƃ��鐭�{���j������B���@�ł��Ȃ����҂̃P�A�Ɋe�n�̐f�Ï��̋��͂��Ăъ|�����B
���{�����@�i�荞�݂ɓ��ݐ����̂́A�V�^�R���i�u��5�g�v���O��̂Ȃ��L����������Ă��邽�߂��B2�����_�̓��t���[�����ɂ��ƁA�����s�̗z������19�D8���B���̑��̒n��ł�10�����̎w�W���ڗ����A�����ǐ��Ƃ��u�ُ�Ȑ��l�B�s���������܂��Ă����ԁv�Ǝw�E����قǁB�S���̏d�ǎҐ���7�����{�ȍ~�͑����X���ɂ���B�����N���o�ύĐ��S������3���̋L�҉�ŁA�u���̏������ΓK�Ȉ�Â���ꂸ�A�~���閽���~���Ȃ��ɂȂ肩�˂Ȃ��v�Ɗ�@���������ɂ����B
���݁A�����҂̑������߂�30��ȉ��ł́A���Ǐ��y�ǂ��قƂ�ǂƂ����B�����A����×{���Ɍċz����������ǂւƈ�������P�[�X������B�V�^�R���i�Ɋ��������o��������ÊW�҂́A�u���ޏ�͒����ǂƂ��ꂽ���A���ۂ͑�������̂�����Ƃ������B����Ŏ���×{��������ǂ��Ȃ��Ă������v�ƐU��Ԃ�B
�����I�ȑ�5�g�Ɏ���×{�őΉ�����ɂ́A�Ǐ�̒��J�Ȋώ@���������Ȃ��B���{�͉��f��I�����C���f�ÂȂǂ�ʂ��A����×{�҂̏c���ɓw�߂�l���B�f�Õ�V���g�[���A��t�ւ̕��L�����͂����߂�B�����u�J�ƈ�ł��V�^�R���i�f�Âɒ�R������������������v(���{�W��)�B�e�n�̕ی������V�K�����҂̋}���ŕ��S����������A���҂̗e�̂̕ω��ɑΉ��ł��Ȃ���A���ʓI�Ɉ�Õ���̏�ԂɊׂ肩�˂Ȃ��B
�����ɂ��Đ��{������×{��O�ʂɑł��o���K�v�ɔ���ꂽ�̂́A�V�^�R���i���Ҍ����̕a���̏�ς݂��i��ł��Ȃ����Ƃ̗��Ԃ��ł�����B�^�}��������{���j�Ɍ˘f�����o�Ă���B�����}�̎R���ߒÒj��\��3���A�ƒ��H�����ɂ����ہA�u���������Ή��ł���a���𑝂₷�Ƃ��A�}���p���[�𑝂₷�Ƃ��A�����ǂɒ��J�ȑΉ������肢�������v�ƒ�����t�����B
���d�ǎ҂������Ă��c�����ҋ}���ň�Õ���̊�@�@��t���u�����̗��v�@8/4
�I�����s�b�N�J�Ò��̓����𒆐S�ɑS���Ŋ����g�傪�~�܂�Ȃ��B���莡�v�E�����s��t���́u�d�NJ��҂������Ȃ��Ă������}���ň�Õ���v�ƌx������B
�\�\�����s�̐V�K�����Ґ����ߋ��ő����X�V�������Ă���B7��29���܂ł�1�T�ԕ��ς�2224.1�l�ŁA���̑O�T�̕��ς�1.6�{�ȏ�ɂȂ����B����܂łɂȂ��X�s�[�h�̑��������B
4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o�Ă���ɂ�������炸�������}�g�債�Ă���̂́A�E�C���X����芴���͂̋����ψي��ɒu����������̂ɁA�l�̗��ꂪ�\���Ɍ����Ă��Ȃ�����ł��B�ψي��u�f���^���v�̊����͂́A�]���̃E�C���X�����2�{�߂��A��4�g�ŗ��s�����u�A���t�@���v���1.5�{���x�����Ƃ���Ă��܂��B�s���ł͏��Ȃ��Ƃ��E�C���X�̔������f���^���ɒu��������Ă��܂��B����ɑ��A�l���͍���ً̋}���Ԑ錾�̑O�ɔ��2�����x���������Ă��܂���B�f���^���̊����͂��l�����5���ȏ㌸��Ȃ��Ɗ����g��͖h���܂���B�l�����\���Ɍ���Ȃ������̓I�����s�b�N�J�ÂƁA�����Ƃ̔����ł��B����܂ł̓w�͂����������Ă���A�X���[�g�̕��������݂�A�J�Âɂ��ǂ��ʂ͂������Ǝv���܂��B�������A�V�^�R���i�E�C���X��ɂƂ��Ă͕��̑��ʂ���ł��B�s�����͂��ߍ����́A���������̖~�x���C�x���g�����~�ɂȂ��Ă���̂ɃI�����s�b�N�͊J�Â���Ă��錻����݂āA�u�I�����s�b�N���J����Ȃ�o�����Ă��������낤�v�Ƃ����S���ɂȂ��Ă���������Ȃ��炸����Ɛ����ł��܂��B�������A���`�̎⏬�r�S���q�s�m���́A�u�l���͌������Ă���B�S�z�͂Ȃ��v�u����҂̃��N�`���ڎ킪�i��ł���A(�s������Õ��O�ɂȂ���)��3�g�̎��Ƃ͏��قȂ�v�ȂǂƔ������Ă��܂��B������A�������܂��܂��u�Ȃ�Ύ��l���Ȃ��Ă����v�Ǝv���Ă��d���Ȃ��ł��傤�B�m���ɍ���҂̃��N�`���ڎ�͐i��ł��܂��B�������A40���50����d�lj����܂��B�s�̃��j�^�����O��c��{�̕��ȉ�̐��Ƃ͊F�A��Ñ̐��̕N���̊댯����i���Ă��܂��B���{��s�̐ӔC�҂͐��Ƃ̐��ɂ�����Ǝ����X����ׂ��ł��B
�\�\�g�����F�E�s�����ی��ǒ���27���A�u��Ò̐����ɂ������������������Ȃ��Ȃ錻��͂Ȃ��v�ƋL�Ғc�ɐ��������B
�����O�O�Ɍ��Ăق����Ǝv���܂��B������������A�V�^�R���i�E�C���X���҂̎���x�b�h��5967������̂ɑ�29���̓��@���҂�3039�l�A�����d�NJ��Ҏ���x�b�h��392���A���@��81�l�ł�����A�]�T������悤�ɂ݂��܂��B�������A���ĂȂ������Ŋ����҂��}�����Ă��邽�߂ɓ��@�̎��ꂪ�Ԃɍ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����җp�x�b�h��30�������Ă���15���Ă���a�@���A����1���ŐV�K��15�l������邩�Ƃ����A����͓���B��t��Ō�t���Ï]���҂�����Ȃ�����ł��B���{��s�́A�d�ǎ҂������Ă��Ă��邩���Ò̐��͕N�����Ȃ��ƌ����܂����A����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�ŋ߁A�����ǂ̊��҂������Ă��Ă��܂��B�����ǂł��_�f���^�̕K�v�Ȑl�����āA�e�̂���������ΐl�H�ċz��ȂǂőΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����߂Ɉ�Ï]���҂͖ڂ𗣂����A�����ǂƂ͌����A��Ë@�ււ̕��ׂ͏���������܂���B�s���ł͓��@�悪������Ȃ������҂������Ă��܂��B���@���A�h���×{�{�݂ł̗×{�����̂��߁A����őҋ@���Ă���l��29�����݁A5575�l�ɒB���Ă��܂��B
�\�\�s�͈�Ë@�ւɑ��A�~�}��Â��ʐf�Â��k���������p�����������肷��Ȃǒʏ��Â𐧌����邱�Ƃ�����ɓ���āA�V�^�R���i�����NJ��҂̎��ꂪ�\�ɂȂ�悤�Ȉ�Ò̊m�ۂ�v�������B
�s�͏����O�܂œs��t��ƈꏏ�ɁA�s���̈�Ñ̐������A�V�^�R���i�E�C���X�ɂ����̈�Âɂ��Ή����悤�Ƃ��Ă����̂ɁA�s�͍ŋ߁A�����]�������悤�ɂ݂��܂��B��Â͐V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̎��Â����̂��߂ɕK�v�Ȃ̂ł͂���܂���B���̋G�߁A����҂𒆐S�ɔM���ǂŋ�̈����Ȃ�l�������Ă��܂��B�����K�ɑΏ����Ȃ���Ζ��ɂ������܂����A�ʏ��Â𐧌�����A�M���NJ��҂̎��ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ����܂��B�s���ł͎��ۂɁA�~�}�������K�v�Ȋ��҂���ɂ��āA�~�}����5�J���̈�Ë@�ւɎ����v������Ȃǂ��Ă������悪���܂�Ȃ��������}�����Ă��܂��B20���ɂ͉ߋ�7���Ԃ̕��ς�62.0���������̂��A28���ɂ͓�93.3����1.5�{�ɂȂ�܂����B�܂��A���Ȃ�i�s������Ԃł������銳�҂���������Ă��Ă��܂��B��N���A���f����̂��T���Ă����l�����Ȃ��Ȃ�����ł��B�������������������A�������Â����Ȃ���Ύ�x��ɂȂ�܂��B���A�a�⍂�����Ƃ����������K���a�Ȃǂ͂ӂ��炫����ƃR���g���[�����Ă����Ȃ��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������ɏd�lj����₷���Ȃ�܂��B��Ð���͖ڐ�̂��Ƃ������݂ĂƂ�̂ł͂Ȃ��A���L�������I�ɖڔz�肵�A�Ȋw�I�ɔ��f������Ō��߂�ׂ��ł��B
�\�\���t�{�ɂ���65�Έȏ�̍���҂̃��N�`���ڎ헦��30�����݁A2��I����73.1���A1��ڎ��85.7���ɒB�����B
��҂��܂߂��ڎ�ΏێґS�̂ł݂��2��I�������l��3���A1���4�����x�ɂ����܂���B�������L�����N�`���ڎ���I�����̂ł��Ȃ���S�ł���A�Ƃ����b���ł���̂͑����Ă�10����11���ł��傤�B���͂���Șb���ł���ł͂���܂���B����Ȃ̂ɁA����҂̃��N�`���ڎ킪�i�����3�g�Ƃ͈Ⴄ�A�Ƃ�������������b�Z�[�W�𐭎��Ƃ�͏o���Ă���B
���͈��S�ł���ǂ��납�A�S���Ɋ����̗��������r���̂�h���邩�ǂ����̐��ˍۂł��B
���}�b�N�A�X�^�o�̃R���i���J���ŃO���t�쐬�@���@��5�g�̂����������@8/4
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ������I�@�ւ��疈�����\����钆�A�}�N�h�i���h�ƃX�^�[�o�b�N�X�̓X�܂ɂ����銴�������Ƃɂ����O���t�����ڂ���Ă��܂��B�R���r�j���͐}�Ȃǃf�[�^�����������b���SNS�ɔ��\���Ă���c�C�b�^�[���[�U�[�̂ɂ����(@ShinagawaJP)���쐬�������̂ŁA�f���^���̗��s��v���Ƃ����5�g�̂����܂����������܂��B�t�@�X�g�t�[�h��R�[�q�[�̃`�F�[���X����݂�R���i�ЂƂ������_�Ɂu�킩��₷���v�u�s�X�n�ł̊����x�����𑪂��ŋ����[���v�u�}�b�N�͐��̒����q�ώ�����̂ɕ֗��ȑ��݁v�Ȃǂ�SNS���[�U�[���������Ă��܂��B
�S���̓X�ܐ��̓}�b�N��2928(2021�N6��)�A�X�^�o��1655(2021�N6��)�BHP�ŏ]�ƈ��̊����₻��ɔ����X�܂̈ꎞ�x�Ƃ̏������J���Ă���A���̃f�[�^�ɒ��ڂ��܂����B���N1��1������7�����܂ł̊����������W�v���A�}�b�N�ł͈ꎞ�x�X���ƒ��Ԑl�����x�̊W��T��܂����B
�O���t���`����̂́A��3�A��4�𗽉킷���5�g�̂����܂����B����7�����{����̃O���t�̒��ˏオ�肩�甚���I����(�I�[�o�[�V���[�g)�����������A�u�����̎��Ԃ����߂�v�u�����O�ꂵ�Ă���`�F�[���X(�ł��̐���)�����炱���A�����͂����܂������Ƃ�������v�ƃl�b�g��ł͋����������Ď~�߂��Ă��܂��B����X�܂ł̏d�������O����ƁA����܂łɃ}�b�N��764�X��(26%)�A�X�^�o��361�X��(22%)�ŏ]�ƈ��̗z�����o�Ă��邻���ł��B
�l�����x���������Ƀ}�b�N�X�܂�100�X���O���[�v�����A1�x�ł������x�X�����X�܂̊������W�v����ƁA�l�����W�n�قNjx�X���������A��s�s�̔ɉ؊X�ł�50%�ɔ���܂����B���Ƃ��Ɛl��������̗z���Ґ��͒��Ԑl�����x�ɔ�Ⴕ�Ă���A�}�b�N�������X���ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�ɂ������ɕ����܂����B
�\�}�b�N�ƃX�^�o��I�̂́A�����J��X�ܐ��̖ʂ���ł��傤��
�u�]�ƈ��̊����h�~���A�����Ҕ������̕X�E���ŁE�ĊJ�̃I�y���[�V��������^������Ă���A���̓��e��Web�T�C�g�ŊJ������Ă��܂��B�X�ܐ��̑����ɉ����A�����Ǒ�̎�����e���S���ψ�ł���Ǝv���邽�߁A�����g��𑪂�w�W�ɂӂ��킵���ƍl���܂����B���ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂́A���̃O���t�̌����ł��B���`�F�[���̋x�X���͑S���̐V�K�����Ґ��̐��ڂƘA�����Ă��āA���̂Ƃ������ȓ����͂��Ă��܂���B���H�X���s���Ɋ������L���Ă���Ƃ��A�}�b�N��X�^�o���댯�ł���A�Ɖ��߂���̂͑��v�ł��v
�\�O���t���牽���ǂݎ��܂���
�u����3�T�ԂقǁA�S���̐V�K�����Ґ��͑O�T��1.4�{(�{40%)�قǂŐ��ڂ��Ă���A�}�b�N��X�^�o�̋x�X���������悤�ȌX���������Ă��܂����B���ꂪ7��27�����납��}�����A���ł̓}�b�N�A�X�^�o�Ɍ��炸�A�����̈��H�E�����`�F�[���ŗՎ��x�Ƃ��������ł��܂��B�f���^���̋��������͂����т��ѕ��Ă��܂����A�X�܂̗Վ��x�Ɛ������Ă����炩�ŁA�܂��ɍ��A�����g��̐^�������ɂ��邱�Ƃ������������܂��B���Ԃ̐l�����x�������G���A�قNjx�X�����������Ƃ���������ɂȂ��Ă��܂��B�����̐l���W�܂�s�X�n�قǁA�s�������̃��X�N�������̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��v
�\8���ɓ����Ă����
�u�O���t���쐬����7��30���ȍ~�A���`�F�[���̐V�K�x�X���͓��ł��ɂȂ��Ă��܂��B����̗\���͓��v�E�����ǂ̐��ƂɈς˂����Ƃ���ł����A�s�X�n�̐l�o��7�����{���猸���ɓ]���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA��5�g�ɂ��Ă͂��낻��R���z���Ăق����Ƃ����v���ł��v
�\�}�b�N�A�X�^�o�Ɍ��炸�A�ڋq�Ƃ̐l�͕s���Ɣw�����킹�œ����Ă��܂�
�u��5�g�ɂ����Ă��A�u��������H�v�̊댯������������ASNS�ł́u�����͎��Ǝ����v�u��H���Ȃ���Ί������Ȃ��v�Ƃ����������ڂɂ��܂��B�ڋq�Ƃɂ����銴���g��ƑS���̊����g��Ƃ̑������������ƂŁA�f���^���̊������X�N�̍����������������Ƃ����v���ň�A�̃O���t���쐬���܂����v
�\��Ƃ̊�@�Ǘ��͌��J���ǂݎ��܂���
�u���S���ĐH�����y����ł��炦��悤���H�`�F�[���͊����Ǒ�ɗ͂����Ă���A�}�b�N�A�X�^�o��Web�T�C�g�Ɋ����g��h�~�̎��g�݂��f�ڂ��Ă��܂��B��A�A���R�[�����łƂ������ʂ��Ղ̓��e�ɂƂǂ܂炸�A�x�X�E�ĊJ�̂��m�点�A�]�ƈ��̉q���Ǘ��A�w�����̐ڐG���y���ł���T�[�r�X�Ȃǂ����ɂ킩��₷���Љ��Ă��܂��B���H�X�Ƃ��Ă̎g���ƈ��S�E���S�𗼗�������Ƃ����ӋC���݂��`����Ă��܂��v
�\�ɂ������̎��͂ł����H�X��
�u���������ł����H�`�F�[����X�[�p�[�A�w�r���̃e�i���g�ŗz���҂��������A1�`2���قNjx�Ƃ���Ƃ������Ă�ڂɂ���悤�ɂȂ�܂����B����܂ňȏ�ɁA�ڂɌ����Ȃ������ǂ����������ɔ����Ă���Ƃ������Ƃ��������Ă��܂��v
�@ |
 |


 �@
�@ |
���O�d�ʼnߋ��ő���74�l���V�^�R���i�Ɂ@���w�Z�̉^�����ł͐V���ȃN���X�^�[�@8/5
�O�d����4���A�����ʼnߋ��ő��ƂȂ関�A�w������80��܂ł̒j��74�l���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\���܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�Îs��19�l�A�l���s�s��18�l�A����s��12�l�A�鎭�s��7�l�ȂǍ��킹��74�l�ł��B
4���ɔ��\���ꂽ1���̊����Ґ�72�l��2�l����A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
���̂����A����܂ł�6�l�̊����҂��m�F����Ă����l���s�s���̒��w�Z�̉^�����ł́A�������鐶�k1�l�̊������V���Ɋm�F����Ă��܂��B���̉^�����ł̊����҂͂����7�l�ƂȂ�A�O�d���Ǝl���s�s�Ŋ����҂̐ڐG��֘A���ׂ����ʁA����89��ڂ̃N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B
�܂��N���X�^�[���������Ă���Îs���̒ʏ��̕����{�݂ł́A�V���ɐE��2�l�̊������m�F����A���̎{�݂ł̊����҂�8�l�ƂȂ�܂����B
�Ȃ��A4�����_�̕a���g�p����37.2���ŁA�d�ǎҗp�a���̎g�p����8���ƂȂ��Ă��܂��B
���N�`���ڎ�ɂ��ẮA3�����_��1��ڂ̐ڎ���I�����l�̐ڎ헦��36.6���A2��ڂ��I�����l�̐ڎ헦��27.7���ƂȂ��Ă��܂��B
�������s �V�^�R���i�����m�F ����5000�l�� �ő��̌��ʂ��@8/5
�����s����5���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l�͏��߂�5000�l���A�ߋ��ő��ƂȂ錩�ʂ��ł��邱�Ƃ��W�҂ւ̎�ނł킩��܂����B
4166�l���m�F���ꂽ�O���ɑ����ĉߋ��ő����X�V����ق��A1�T�ԑO�̖ؗj�������C��1000�l�ȏ�̑����ƂȂ�܂��B
�s�̐��Ƃ́u����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������I�Ȋ����g�傪�i��ł���B���̏͗L�����̂��̂ŁA�w�����̂��́x�Ƃ��Ă݂�Ȃŋ��L����K�v������v�Əq�ׁA������@���������Ă��܂��B
���g�����I�����g�� 2�T�Ԍ�ɂ�1���l�����h �s���j�^�����O��c �@8/5
�����s�̃��j�^�����O��c�ŁA���Ƃ́u�o���������Ƃ̂Ȃ������I�Ȋ����g�傪�i�s���Ă���v�Ƃ��������ŁA���̑����y�[�X��������2�T�Ԍ�ɂ͐V�K�z���҂�7���ԕ��ς�1���l���邨���ꂪ����Ƃ����\���������܂����B�܂��u���@���҂⎩��×{�҂��}�����Ă��Ĉ�Ò̐����Ђ������Ă���v�Ƃ��āA�ً}���̑̐��ֈڍs����K�v������Ǝw�E���܂����B
��c�̒��Ő��Ƃ́A�s���̊����ƈ�Ò̐����������4�i�K�̂����ł������x�����x���ňێ����܂����B
�����āA�V�K�z���҂�7���ԕ��ς�4�����_�ł��悻3443�l�ƁA1�����]���7�{�߂��ɋ}�����Ă���Ɛ������A���Ƃ́u����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������I�Ȋ����g�傪�i�s���Ă���v�Ǝw�E���܂����B
�܂��A���̑����䂪�p�������ꍇ�A7���ԕ��ς�1�T�Ԍ�̍���11���ɂ�1.78�{��6129�l�A2�T�Ԍ�̍���18���ɂ�3.17�{��1��909�l�ɏ��Ɨ\�����u��@���������̂��̂Ƃ��ċ��L����K�v������v�Ƌ������܂����B
����A4�����_�œ��@���҂�3399�l�A�d�NJ��҂�115�l�Ƃ�������傫���������A���Ƃ́u�~�}��Â�\���p�Ȃǂ̒ʏ��Â̐������܂߂Ĉ�Ò̐����Ђ��������ɂ���v�Ǝw�E���܂����B
����ɁA�l�H�ċz��Ȃǂɂ�鎡�Â��܂��Ȃ��K�v�ɂȂ銳�҂������l�Ő��ڂ��Ă��邱�Ƃ�������u�}���ȏd�NJ��҂̑����͈�Ò̐��̊�@�������v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A���@���҂����łȂ�����×{�҂Ɠ��@���×{���Ȃǂ����̐l���}�����Ă��邱�Ƃ���u�̒��̈����𑁊��ɔc�������₩�Ɏ�f�ł���d�g�݂Ȃǂ̃t�H���[�A�b�v�̐�������ɋ������A����×{���̏d�lj���\�h����K�v������v�Ƃ��Ă��܂��B
�����āu���@��ÁA�h���×{����ю���×{�̑̐����ً}���̑̐��ֈڍs����K�v������v�Ǝw�E���܂����B
�����r�m���u����ꂽ��Î������ő�����p�v
���j�^�����O��c�̂��Ə��r�m���͋L�Ғc�ɑ��A�s���̈�Ò̐��ɂ��āu�ً}�Ή��Ƃ��ē��@�d�_��Ë@�ւ��d�ǁE�����ǂƌy�ǁE�����ǂɖ����m������B�z�e���ł̏h���×{�{�݂��d�_�����A��ϑ����Ă��鎩��×{�҂̃t�H���[�A�b�v�̐�����������g�[���Ă����v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu���ꂩ�����Ë@�ւⓌ���s��t��A�ی����ȂNJ֘A���邷�ׂĂ̕��X�Ƌ��łȘA�g��}��B��Î����͌����Ă���̂ŁA������ő�����p���Ĉ�Ò̐��̏[����}���Ă����B�^�Ɉ�ÃP�A���K�v�ȕ��X�ɓ��@���Ă���������悤�ȑ̐����Ƃ��Ă����v�Əq�ׂ܂����B
�����Ɓu���̏͗L�����̂��́v
���j�^�����O��c�̂��ƍ������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���ۊ����ǃZ���^�[���͋L�Ғc�ɑ��u�V�K�z���Ґ��͖{���ɑ������}���ŁA���������o���Ƃ������炢�̐������Ă���B�L���莩�̂��{���ɔ����I�Ȋ����g��̏��v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu���̏͌��N��@�ƌ������L�����̂��̂ŁA�����̂��̂Ƃ��Ă݂�Ȃŋ��L����K�v������B���̕a�C�́A�������ċꂵ���ڂɂ���Ȃ��Ƃ炳���Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ����{���ɑ�ς��B�����̐g�̉��Ɂw��������������x�Ƃ������X�N�����Ă���A�����ɂ����炸�ɍςނ̂����̕��@�����܈�x�m�F���Đg������Ă������������v�Əq�ׂ܂����B
���s��t���u�×{�Ґ�����������Ύ����Ȃ��Ȃ�v
���j�^�����O��c�̂��Ɠ����s��t��̒������F����͋L�Ғc�ɑ��A�s���̈�Ò̐��ɂ��āu�����̈�Ë@�ւ̂��낢��ȓ��������Ȃ��玩��×{�������Ɉ��S�Ɍ��Ă�������A�h���×{�Ƃ��܂��A�g���Ȃ��瓌���Ȃ�ł͂̑̐����Ƃ��Ă������ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B����Łu���̑̐����×{�Ґ�����������������ꎝ���Ȃ��Ȃ�Ǝv���B���̎��ɂ���ꂪ�Ή��ł��邩�Ƃ����̂͐r���s��������A���АV�K�z���Ґ������炷���Ƃ����肢�������v�Əq�ׂ܂����B
���l�H�ċz��Ȃǂ̎��ÕK�v�̉\�������l���ő���
�s���ł́A���@���҂̂����A�l�H�ċz��Ȃǂɂ�鎡�Â��܂��Ȃ��K�v�ɂȂ�\����������Ԃ̐l���A����܂łōł�����318�l�ɏ���Ă��܂��B�s�̐��Ƃ́A���T�A�s���郂�j�^�����O��c�ŁA��Ë@�ւŏW���I�ȊǗ����s���Ă���u�d�NJ��҂ɏ����銳�ҁv�̐l�������\���Ă��܂��B���̂����A�l�H�ċz��܂���ECMO�ɂ�鎡�Â��܂��Ȃ��K�v�ɂȂ�\����������Ԃ̊��҂́A4�����_��318�l�ƂȂ�܂����B1�T�ԑO�̐挎28������58�l�������A����܂łōł������Ȃ�܂����B318�l�̂����A���悻������154�l�͕@���獂�Z�x�̎_�f���ʂɑ��荞�ށu�l�[�U���n�C�t���[�v�Ƃ������u���g�������Â��s���Ă���Ƃ������Ƃł��B���Ƃ́A�����������҂����������Ő��ڂ��Ă��邱�Ƃ���A�d�NJ��҂�����ɑ������邨���ꂪ����Ƃ��Ă��܂��B���Ƃ́u�l�H�ċz��̗��E�܂ł͒����Ԃ�v���邽�߁AICU�Ȃǂ̕a���̕s�����뜜�����v�Əq�ׁA��@���������܂����B
���s�������ƈ�Ò̐� ���Ƃ̕��͌���
5���̃��j�^�����O��c�Ŏ����ꂽ�s���̊����ƈ�Ò̐��ɂ��Ă̕��͌��ʂł��B
��������
�V���Ȋ����̊m�F�́A4�����_��7���ԕ��ς�3443.3�l�ƂȂ�A�O��E�挎28�����_��1936.4�l��肨�悻1500�l�������܂����B���Ƃ́u�傫���������A�\��������l���B6��30���̂��悻503�l����A�킸��5�T�Ԃ�7�{�߂��ɋ}�������v�Ǝw�E���܂����B������͑O�̏T�̂��悻178���ŁA���悻153���������O�����25�|�C���g�㏸���܂����B���Ƃ́u�����g�傪����ɐ����𑝂��Ă���B2�T�Ԍ�̍���18���̗\���l��1��909�l���B���̊�@�����w�����̂��́x�Ƃ��Ă݂�Ȃŋ��L����K�v������v�Əq�ׂ܂����B����2���܂ł�1�T�ԂɊ������m�F���ꂽ�l�̔N��ʂ̊����́A20�オ35.9���ƍł������A5�T�A����30�����܂����B
6�����{�ȍ~�A50��ȉ��őS�̂�90���ȏ���߂Ă��āA���Ƃ́u��N�w���܂߂������鐢�オ�������X�N������Ƃ����ӎ�������w�������悤�[������K�v������v�Ǝw�E���Ă��܂��B����A��r�I�}�����Ă�������҂̊����Ґ����Ăё������n�߂Ă��邱�Ƃ�����܂����B��̓I�ɂ́A65�Έȏ�̍���҂͍��T��596�l�ŁA309�l�������O�̏T��2�{�߂��ɑ����Ă��܂��B
�����o�H���������Ă���l�ł́A��������l����̊�����61���ƍł������A�����ŐE�ꂪ13.7���A�ۈ牀��w�Z�A����ɍ���Ҏ{�݂�a�@�Ƃ������{�݂ł̊�����5.6���A��H��5.2���ł����B
���Ƃ́u�����ɋC�t�����ɃE�C���X���������܂�A�E��A�{�݁A�ƒ���ȂǑ���ɂ킽���ʂŊ������m�F����Ă���v�Əq�ׂ܂����B�܂��A�u�V�h�̕����̑�K�͏��Ǝ{�݂Ő��\�l�K�͂̃N���X�^�[���������Ă��āA�����̐l���W�܂�{�݂ł̊����h�~������܂ňȏ�ɓO�ꂷ��K�v������B�I�����s�b�N�̋��Z��̎��ӂ≈���ɑ吨�̐l���W�܂�A��������p�������Ă���B���O�ł����Ă����W�A���ڂ��đ吺�ʼn������邱�Ƃ͊������X�N���������Ƃ��[������K�v������v�Əq�ׂ܂����B
�u�����̍L����f����w�W�v�Ƃ����A�����o�H��������Ȃ��l��7���ԕ��ς�4�����_��2240�l�ŁA�O�̏T���炨�悻1000�l�����A8�T�A�����đ������Ă��܂��B
�܂��A������́A4�����_��179.8���ƑO��22.4�|�C���g�㏸��9�T�A���ő������܂����B
���Ƃ́u����Ȃ�g���h�����߂ɂ͐l�����\���Ɍ��������A����܂ňȏ�ɓO��I�Ɋ����h�~������s����K�v������v�ƌx�����Ăт����܂����B
�����o�H��������Ȃ��l�̊����͂��悻66���őO�̏T���3�|�C���g�㏸���܂����B
�����o�H��������Ȃ��l�̊�����40��ł�60�����Ă��āA����ɁA�s����������20���30��ł�70�����Ă��܂��B
���Ƃ́u�����o�H���ǂ��Ȃ����ݓI�Ȋ����g�傪�����Ă���B��{�I�Ȋ����h�~���O�ꂵ�čs�����Ƃ��K�v���v�Ǝw�E���Ă��܂��B
�������s�̊����u2�T�Ԍ�ɏT����1���l�Ɂv�@���Ǝ��Z�@8/5
�����s��5���A�V�^�R���i�E�C���X�Ή��̃��j�^�����O��c���J���A�u�d�NJ��҂��܂ޓ��@���ҁA�×{�҂��}�����A��Ò̐����N��(�Ђ��ς�)�����ɂ���v�Ƃ��āA�u���@��ÁA�h���E����×{���ً}���̑̐��ֈڍs����K�v������v�Ƃ̐��Ƃ̃R�����g�����\�����B
1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���3��l�ȏ�ɏ��s���̊����̌���ɂ��ẮA�����͂̋����ψي�(�f���^��)�ւ̒u������肪�}���ɐi�݁A�u�o���������Ƃ̂Ȃ������I�Ȋ����g�傪�i�s���Ă���v�ƕ��͂����B
��c�Ŏ����ꂽ1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���3443�l�ŁA�O�T��1936�l����1�E78�{�ɋ}���B�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���́A���̑�������������11���ɂ͏T���ς̐V�K�����Ґ���6129�l�A2�T�Ԍ��18���ɂ�1��909�l�ɑ�����Ƃ̎��Z�������A�u�s����1��l��1�l��������������v�Z�ɂȂ�B���̊�@���������̂��̂Ƃ��ċ��L����K�v������v�Ƒi�����B
�s���̓��@���Ґ���3399�l(4�����_)�ƁA�O�T����404�l�����B�ߋ��ő�������3427�l(1��12��)�ɔ������B�d�NJ��Ґ���115�l�ɏ��A�O�T��80�l����啝�ɑ������B
�ی����œ��@������߂��ꂸ�A�s�ɓ��@�������������܂�錏��(1��������)��450���ƁA�O�T��270������啝�ɑ������B�s��t��̒������F����ɂ��ƁA�����ȍ~�ɒ������J��z�����ق��A����ł̑ҋ@��]�V�Ȃ�����Ă��鎖�Ⴊ���������Ă���Ƃ����B
�����Ґ��̋}���ɔ����A�S�̗̂×{�Ґ���2��9703�l�ɏ��A�O�T��1��6344�l����}�������B���Ɏ���×{�Ґ���1��4783�l�ƑO�T����{���B�������͉�c�Łu����ł̑̒������𑁊��ɔc�����A���₩�Ɏ�f�ł���d�g�݂̃t�H���[�A�b�v�̐�������ɋ������A����×{���̏d�lj���\�h����K�v������v�Ǝw�E�����B
�������͂��̓��̉�c�ŁA���@��ÁA�h���E����×{�ً̋}���̑̐��ɂ��āA���҂̏Ǐ�ɉ��������@�A�]�@��i�߂邽�߁A�R���i���Ҍ����̓��@��Ë@�ւ̖������d�ǁE�����ǎҌ����ƁA�����ǁE�y�ǎҌ����Ƃɖ��m�����������ŁA�h���×{�{�݂Ɏ_�f�z���ł����Ë@���z������Ȃǂ��āA�h���×{�{�݂ɂ���Ë@�\���������邱�Ƃ�z�肵�Ă���Ɛ��������B
��c�ł́A�����͂̋����ψي�(�f���^��)�ɂ��āA�s�̌����ɐ�߂銄����7��25���܂ł�1�T�Ԃ�64�E6%�ɏ��A�O�T��46�E2%����u������肪����ɐi���Ƃ����ꂽ�B
�s���̎�v�ɉ؊X�ł̐l�o�����������Ă��Ȃ��B��c�Ŏ����ꂽ�s��w�����������̒������ʂɂ��ƁA7��12����4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o��3�T�Ԍ�̃��W���[�ړI�̑ؗ��l���́A�錾���O��1�T�ԑO�Ɣ�ׂāA��Ԃ�22�E5%�A�������X�N�̍����[���(�ߌ�10���`�ߑO0��)��20�E8%���������B�����A����1�T�Ԃł͖�Ԃ͑O�T��3�E6%�Ɣ����ɂƂǂ܂�A���Ԃ͉����Ő��ڂ��Ă���Ƃ����B
���������̐��c�~�u�Z���^�[���́u�ɉ؊X�̑ؗ��l��������������ƂƂ��ɁA�l�Ɛl�Ƃ̐ڐG���ɗ͌��炷���߃X�e�C�z�[������O�ꂵ�č��߂Ă������Ƃ��K�v�v�Ǝw�E�����B
���r�S���q�m���͉�c�Łu���~���T���Ă��邪�A�����A���s�E�A�Ȃ͒��~�܂��͉������ăX�e�C�z�[����O�ꂵ�Ăق����v�ƌĂт������B
���ψي��A���Ă��}���@�V�^�R���i����2���l�� 8/5
�ăW�����Y�E�z�v�L���Y��̏W�v�ɂ��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�̗v�̊����҂�4��(���{����5��)�A���E�S�̂�2���l�����B1��26����1���l�ɓ��B���Ă��甼�N�]��Ŕ{�������B�����͂̋����C���h�R���̕ψي�(�f���^��)���҈Ђ�U����Ă���A���N�`���ڎ킪�i��ł��鉢�ĂȂǂł������҂��}�����Ă���B
1��������̐V�K�����Ґ�(7���ԕ���)��6�����{���瑝���ɓ]���A���E�͍Ăъ����g��̋ǖʂɓ����Ă���B���҂͐��E�S�̂�425���l���Ă���B
���ʂ̗v�����Ґ���̏W�v�ł݂�ƁA�č�(3533���l)���ł������A�C���h(3176���l)�A�u���W��(2002���l)�A���V�A�ƃt�����X(627���l)�Ƒ����B
�č��ł͐��l��60�E7�������N�`���ڎ�������������A�f���^���͐ڎ튮���҂̊Ԃł��������L���邱�Ƃ������B�V�K�����Ґ��͍Ăё����Ă���A���ɐ[���ȓ암�t�����_�B�ł�1��������̐V�K�����Ґ�(7���ԕ���)��2�����_��2��2��l�����B�b�m�m�e���r�ɂ��Ɠ��@���Ґ���1��1��l���ĉߋ��ő��ƂȂ�A�W�����Î�(�h�b�t)�̕a���g�p����86�E5���ɒB���Ă���B
���E�ی��@��(�v�g�n)�����\������T1�T��(7��26���`8��1��)�̐��E�S�̂̐V�K�����Ґ��͑O�T���400���l���������A���̂�����āE�k�ĂƉ��B���v222���l�Ɣ����ȏ���߂��B�O�T��37���������������E�k�A�t���J���NJ����铌�n���C�n�掖���NJǓ��Ɠ�33�������������{���܂ސ������m�n�掖���NJǓ��̊g�傪�ڗ��B
�f���^����135�J���E�n��Ɋg��B182�J���E�n��Ŋm�F���ꂽ�p���R���̃A���t�@���Ɏ���đ��鐨���ōL�����Ă���B
���u�o���������Ƃ��Ȃ��悤�Ȍ��Ⴂ�ȑ����v8���ɂ܂h�~�A���ȉ���� �@8/5
���{��5���A�V�^�R���i�E�C���X�̊������L�����Ă��镟���A���A�ȖA�Q�n�A�É��A���m�A����A�F�{��8���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p���邱�Ƃ����߂�B�܂��A�����g��n��ł̗×{���j������A�c�������J�����͓����A�u�����NJ��҂͌������@�v�Ƃ̌������������B
���{��5���ߑO�A���Ƃł����{�I�Ώ����j���ȉ���J�����B8���ɏd�_�[�u��K�p����Ă���A�������ꂽ�B�����ߌ�ɐ��{���{��(�{�����E����)���J���A�������肷��B8���ւ̏d�_�[�u�̓K�p���Ԃ�8�����獡��31���܂ŁB
�d�_�[�u�̓K�p�n��ł́A���H�X�Ɍߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k�v���ɉ����A�����Ƃ��Ď��̒�~�����߂�B�u�����������X���ɂ���ꍇ�v�Ɋ�����ȂLj��̗v�������ꍇ�Ɍ���A�m���̔��f�Ōߌ�7���܂Ŏ��̒�F�߂�B
��{�I�Ώ����j���ȉ�ł��������鐼���o�ύĐ���(5���ߑO�A�����s���c���)�����������B�e��{�I�Ώ����j���ȉ�ł��������鐼���o�ύĐ���(5���ߑO�A�����s���c���)�����������B�e
�����o�ύĐ����͕��ȉ�ŁA�u�V�K�z���Ґ����A�o���������Ƃ��Ȃ��悤�ȁA�ɂ߂đ����A���Ⴂ�ȑ��������Ă���v�Əq�ׂ��B
8���ł́A�V�K�����Ґ����É��A���m������6���ŁA���̎w�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�ɑ�������B
��
�c�����J����5���ߑO�̎Q�@�����J���ψ���̕�R���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��n��ɓK�p����V���ȗ×{���j�ł́A�����NJ��҂͌������@�Ƃ̊�����������B
�c�����́u�����ǂ͌������@�v�Ɩ������������ŁA�u��t����r�I�d�lj����X�N���Ⴂ�Ɣ��f�������͎���őΉ����������v�Ɛ��������B
�V�×{���j�������ẮA���{�̐����s������u�����ǂł����@�ł��Ȃ��v�Ƃ̌������ꎞ�L����A�^�}��������u���j���������ׂ����v�Ȃǂ̔������o�Ă����B���̂��߁A�c�����͓��@�Ɋւ����m�����邱�ƂŁA�O���C����}�����Ƃ݂���B
���d�_�[�u8���lj�������@���{�A���ȉ�Ɂu�����Ⴂ�ȑ����v�@8/5
���{��5���ߑO�A�V�^�R���i�E�C���X�̊�{�I�Ώ����j���ȉ���J���A�R���i���[�@�Ɋ�Â��u����(�܂�)�h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�Ώۂɕ����A���A�ȖA�Q�n�A�É��A���m�A����A�F�{��8����lj�������j����ƂɎ������B���Ԃ�8������31���܂ŁB������������ΏO�Q���@�ւ̕��o�āA�[���̐��{���{���Ō��肷��B
���ȉ�Ő����N���o�ύĐ��S�����́A�����Ґ��ɂ��āu�S�������̒n��ł���܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��悤�ȁA�ɂ߂đ��������Ⴂ�ȋ}���ȑ��������Ă���v�Ɗ�@����\�������B
�����͂̋����C���h�R���̃f���^���̖�����A�N���X�^�[(�����ҏW�c)���S�ݓX�◝���e�A�w�K�m�ȂǏ]���݂��Ȃ������ꏊ�ł��������Ă���Ɍ��y���A�u����܂ňȏ�ɐl�Ɛl�̋������Ƃ�Ȃ�������Ȃ��v�Ƌ��������B�O�o�͏��l���Ƃ��A�������͍��G���鎞�ԑт�����邱�Ƃ�A�A�Ȃ◷�s���ɗ͍T���A��ނȂ��ꍇ�����O�Ɍ������邱�ƂȂǂ��Ăъ|�����B
�d�_�[�u�łً͋}���Ԑ錾�ɏ������[�u����邱�Ƃ��ł���B�K�p�n��ł͌����Ƃ��Ĉ��H�X�Ɏ�ޒ̒�~��v�����A�m���̔��f�ŁA���̏����������ꍇ�Ɍ���ߌ�7���܂ł̒��\�Ƃ���B
�d�_�[�u�̓K�p�Ώۂ͌��݂̖k�C���A���s�A�����Ȃ�5���{������13���{���Ɋg�傷��B�ً}���Ԑ錾�͍�ʁA��t�A�����A�_�ސ�A���A�����6�s�{���ɔ��߂���Ă���B
���X�ł��f���^���̋^���A�}���@8/5
�X����4���A7���̗z��������27�l�A8���̗z��������1�l����A�f���^���Ƃ݂���uL452R�v�̕ψكE�C���X�����o�����Ɣ��\�����BL452R�̊����҂̊����́A���̐��v���܂߂�ƁA7���ŏ��Ȃ��Ƃ�32%�A8���ŏ��Ȃ��Ƃ�44%���߂�B
�������Ǒ�R�[�f�B�l�[�^�[�̑吼����t�͌����̊����ɂ��āA��7�����{���犴���҂����������O�R���⊴���o�H�s���̊����҂��S��ő�������N�҂̊������ڗ����f���^���̊������}�����Ă���\�\�ȂǂƎw�E�B�u�]�����ł͍l�����Ȃ��������ŁA������8�����ɂ̓f���^���Ɋ��S�ɒu������邾�낤�B�w�Z���n�܂�Ƌ}���ɑ�������\��������v�Ɗ�@�����������B
�܂��C�O�̎��Ⴉ��f���^���ɑ��郏�N�`���̌��ʂ��ቺ���Ă���Ƃ��āA�u�d�lj��\�h�͔F�߂���悤�Ȃ̂Ń��N�`���͕K�v�����A�ł��Ă������������Ăق����B�l�̖h��͂������A�C�x���g���܂߂��l���W�܂�@������炷���Ƃ��K�v�v�Ƙb�����B
����4���A16�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɩ��炩�ɂ����B���ˎs��40��j���͎s���̉^���{�݂Ŋ��������Ƃ݂��A����܂łɗz�����������Ă���4�l�ƍ��킹�A���̓N���X�^�[�����������Ɣ��f�B�s���̏��w�Z�Ŕ��������N���X�^�[�Ƃ��֘A������Ƃ����B
���܂h�~�A�F�{�s��Ώۋ��Ɂ@8/5
�F�{���̊�����v�m����5���A���{���V�^�R���i�E�C���X�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�����߂����Ƃ��A�����ґ������������F�{�s��Ώۋ��Ƃ���ӌ��𖾂炩�ɂ����B����������̓O����m�F�����u�F�ؓX�v���܂ގs���S�Ă̈��H�X�ɑ��A��ޒ̏I�����l��ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v������B���Ԃ�8������31���܂ŁB
�����Ƒg�D�u�o���������ƂȂ������g��v�@��B�A�S�����鑝�����@8/5
�V�^�R���i�E�C���X��������J���Ȃɏ���������Ƒg�D��4���A����J���A�S���ŐV�K�����Ґ��̉ߋ��ő����������������u�o���������Ƃ̂Ȃ������g�傪�����Ă���B�d�ǎҐ����}���ɑ��債�A���S��������ɓ]����\��������v�ƕ��͂����B�ً}���Ԑ錾��6�s�{���ɏo����Ă��邪�A�����͂̋����C���h�R���f���^���̖҈Ђ͎��܂炸�A����Ȃ銴���g��ɋ�����@�����������B
��Ŏ����ꂽ�����ɂ��ƁA3���܂ł̒���1�T�Ԃ̊����Ґ��́A�O�T�ɔ�ׂđS����2�E09�{�ɑ������B���ɋ�B�̑����y�[�X���������Ă���A�啪3�E60�{������3�E56�{���F�{3�E01�{������2�E79�{������2�E77�{���{��2�E50�{��������1�E98�{�|�ƁA6���őS���̑��������������B������1�E89�{�ŁA�����}�g�傪�n���ɍL�����Ă�����Ԃ�����������B
��ł́A�S���̐V�K�����Ґ������ꂽ�B3���܂ł̒���1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A���ꂪ��179�l�A��������167�l�A�_�ސ삪��102�l�ƁA3�s����100�l�����B��B�ł��A��������59�l�A�F�{�͖�28�l�ŁA�X�e�[�W4(�����I�����g��)������25�l�ȏ���������B
��s���≫�ꌧ�ł͈�Ò̐����N��(�Ђ��ς�)���Ă���B�����s�ł�20�`50��𒆐S�ɓ��@�҂������A����40�`50��Ől�H�ċz���l�H�S�x���u���g���d�ǎ҂������B�a���g�p����50�E4��(2�����_)�A�d�ǎҗp�a���̎g�p����69�E6��(��)�ɒB����B�M���ǂȂǂŋ~�}�����������钆�A��ʈ�Â̐������������Ă���B���ꌧ�ł��a���g�p����74�E9��(��)�A�d�ǎҗp�a���̎g�p����74�E7��(��)�ƌ������ɂ���B
����A��B�ł͕a���g�p������������25�E3��(1�����_)�A�F�{���ł�29�E3��(2�����_)�B�Ƃ��ɃX�e�[�W3(�����}��)�̖ڈ�20���ȏ�����邪�A��s���≫�ꌧ�ɔ�ׂ�ƁA�܂��]�T������B���������n��ɒx��āA��B�ł��a�����s�����邱�Ƃ����O����Ă���B
�w�i�ɂ́A�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�Ȃǂ̑Ώےn��ł́A�l�o�������X���ɂ�����̂́A�����}���ɂȂ����Ă��Ȃ��������B���̌����Ƃ݂���f���^���͋�B�ł��u������肪�i�݁A�������̐V�K�z���҂ɐ�߂銄����85��(2�����_)�ɏ��ƍ��������nj������͐��v���Ă���B
��ł͊����҂̓��@�𐧌����鐭�{�̐V���ȕ��j���c�_���ꂽ�B�L�҉���������̘e�c�������������nj��������́u�d�ǎ҂⒆���ǂł��d�lj����X�N�̍����l���m���ɓ��@�ł���̐����m�ۂ��A�K��Ō����[�g�f�ÂȂǂ̈�Î������ő���Ɋ��p���A�d�lj��ɐv���ɑΉ��ł���̐��̐������K�v���v�ƌ�����B
�������s�ŘA�������Ґ��ő��c�g�ܗփh���`���������h �Ɂu���{�̖���v�ᔻ�@8/5
8��5���A�����s���ŐV���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l��5000�l���A�ߋ��ő��ƂȂ錩�ʂ����Ƃ����BNHK���Ă���B
�����s����4����4166�l�̐V�K�����҂��m�F����A�ߋ��ő����X�V��������B�������A5000�l����Ƃ��Ȃ�ƁA��1000�l���̍X�V�ƂȂ�B
�ܗւ��n�܂��Ă���A�����҂͑����̈�r�����ǂ�B���r�S���q�s�m�����͂��߁A���{�̓��N�`���̐ڎ���s���Ă��邪�A���`�̎��f�����u���S�E���S�̌ܗցv�ɂ͒��������B
�u���ً݂͋}���Ԑ錾���ŁA���H�X�̉c�Ǝ��Ԃ���������Ă��܂��B�������A�ܗ֒��p�Ȃǂ�[��܂ŕ���������H�X���c�c�B�T�b�J�[�̏������E���{�X�y�C���������Ȃ�ꂽ8��3���́A�a�J���吨�̎�҂œ�����Ă����Ƃ����܂��v(�X�|�[�c���L��)
�l�b�g�ł́A�ً}���Ԑ錾���ł��ܗւɐ���オ���҂�ᔻ���A���{�� �g����h �Ԃ�Ɍ������������Ă���B
�s����ች����ً}���Ԑ錾�o���Ă��炱���Ȃ��B�݂�Ȃ̋C���ɂ��ɌܗւȂ�Ă�����t
�s���l���ĂȂ����Ƃ͔ᔻ�����ׂ��B�����A����ȏ�ɂ��܂�ɂ����{��������B���[���h�J�b�v�Ŗ��x�̂悤�ɏa�J�Ńh���`�����������N���邱�Ƃ͐����Ƃ��m���Ă���͂��B�����h���l�����Ȃ������̂��ȁH�t
�s�ܗ�������҂͒��ˏオ�����ł��傤�ˁB���Ɖ���ً}���Ԑ錾�����߂���邱�Ƃ��t
�g���Ղ葛���h �Ɋւ���Ă��Ȃ��l�ł��A�������Ă���l�͂�������B���{�ɂ͐v���������ȑΉ������߂���肾�B
���܂h�~���d�_�[�u 8����lj� ����8���`31�� ���{������ �@8/5
�V�^�R���i�E�C���X��ŁA���{�͂܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�n��ɕ����A���A�ȖA�Q�n�A�É��A���m�A����A�F�{��8����lj����A���Ԃ͍���8������31���܂łƂ��邱�Ƃ����߂܂����B
���{��5���[���A������b���@�ŐV�^�R���i�E�C���X���{�����J���A��������b�̂ق������o�ύĐ��S����b��c�������J����b�炪�o�Ȃ��܂����B
�����Ċ����̈������āu�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�n��ɕ����A���A�ȖA�Q�n�A�É��A���m�A����A�F�{��8����lj����A���Ԃ͍���8������31���܂łƂ��邱�Ƃ����߂܂����B
����ɂ���ďd�_�[�u�̓K�p�n��͖k�C���A�ΐ�A���ɁA���s�A������5���{������A13���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B
���{�́A�d�_�[�u�̓K�p�n��ł͈��H�X�ł̎��̒������A��~����Ȃǂ̑��O�ꂷ��ƂƂ��ɁA��Ò̐��̊m�ۂɎ��g�ނ��Ƃɂ��Ă��܂��B
�����āA�ψكE�C���X�̍L����Ɋ�@���������đΉ�����K�v������Ƃ��āA�����ɑ���{�I�Ȋ�����̓O��̂ق��s�v�s�}�̊O�o�̎��l��A���~�̎����̋A�Ȃ◷�s�͋ɗ͍T���邱�ƂȂǂ�S�苭���Ăт����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�����u�o���������Ƃ̂Ȃ������g��v
��������b�͐��{�̑��{���Łu��s�����͂��ߑ����̒n��ł���܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g�傪�i��ł���B�����͂̋����w�f���^���x�ւ̒u������肪�}���ɐi�݁A�����ł�9���ɒB���A�����̒n���7�A8���ɒB���Ă���ƌ����Ă���B�����Ґ��̋}���ȑ����ɔ����A����܂ŒႭ�}�����Ă����d�ǎҐ�������������v�Ǝw�E���܂����B���̂����ŁA�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�n��ł͈��H�X�ł̎��̒�������~���A�e�����[�N�̎��{��s�v�s�}�̊O�o���l��O�ꂷ��l�����������܂����B�����Đ�������b�́u�w�f���^���x�͏]���Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ������͂����ƌ����Ă���A�����̊F�l�ɂ͊������X�N�ɓ��ɒ��ӂ��čs�����A�ċx�݊��Ԃ��s�v�s�}�̊O�o��A�ȁA���s�͋ɗ͍T���Ă��������悤���肢����v�Əq�ׂ܂����B
���O�T�Ƃ̔�r�ŕ�����}�g��
�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂́A5���ɑS����1��5000�l����1���̔��\�Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�ȂǁA�A���A�ߋ��ő����X�V���Ă��܂��B4���܂ł�1�T�Ԃ̑S���̐V�K�����Ґ��́A�O�̏T�Ɣ�ׂ�1.96�{�ƁA�}���ɑ������Ă��܂��B����A�V���ɂ܂h�~�d�_�[�u�̑Ώےn��ɒlj������8���ł��A��������2.28�{�A��錧��2.28�{�A�Ȗ،���2.16�{�A�Q�n����3.40�{�A�É�����1.72�{�A���m����1.97�{�A���ꌧ��2.53�{�A�F�{����2.65�{��1�T�ԑO��2�{�O��A�Ȃ��ɂ�3�{���Ă���Ƃ��������A�������}�g�債�Ă��邱�Ƃ�������܂��B
���l��10���l������̊����Ґ���
�܂��A���݂̊�����l��10���l������̒���1�T�Ԃ̊����Ґ��ł݂Ă݂�ƁA��������33.42�l�A��錧��49.69�l�A�Ȗ،���45.86�l�A�Q�n����43.31�l�A�É�����25.41�l�A���m����23.56�l�A���ꌧ��29.56�l�A�F�{����32.15�l�ƂȂ��Ă��āA�������ł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ���25�l���邩�A����ɔ��鐔���ƂȂ��Ă��āA�������������Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B
�������o�ύĐ��� �g�S���Ōo���Ȃ����Ⴂ�̊����g��h
�����o�ύĐ��S����b��5���ߑO�ɊJ���ꂽ�u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̂��ƋL�Ғc�ɑ��u�S���ɋً}���Ԑ錾���o�����炢���Ɍ������ɂ���Ƃ������ӌ��������������B����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ����Ⴂ�̊����g��ł���A���O�ꂵ�Ă����K�v������Ƃ���������@�������L�����v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�܂h�~���d�_�[�u�ɂȂ�n��ł́A�n����������Ăł͂��邪��ނ�J���I�P�̒�~�ȂNjً}���Ԑ錾�Ɠ����̌������[�u�����肢���邱�ƂɂȂ�B�V�K�z���҂̐���}���Ȃ��ƈ�Ò̐��̕��ׂ����܂��Ă����̂ŁA�s���{���ƘA�g���đ��O�ꂵ�Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
�����g��u�S���ɋً}���Ԑ錾�̈ӌ����v
�u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή�͉�̂��ƕw�̎�ނɉ����A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�n���8����lj�����Ƃ������{�̕��j�𗹏������Əq�ׂ܂����B���̂����Łu��{�I�Ɏ^���͂������ꕔ�̈ψ�����͊��������ɂȂ�Ȃ����̊�@�I�ȏŁA�����̎s���Ɋ�@�ӎ������L���Ă��炤���߂ɂ��S����Ώۂɂ����ً}���Ԑ錾���o���ׂ��Ƃ����ӌ����������B�����A�錾���o�Ă���n��ł����K�������ڐG�̋@���������l�o���������Ă����肷��킯�ł��Ȃ��\���Ȍ��ʂ��o�Ă��Ȃ��B��������ƃ��b�Z�[�W���o���A������Ȃ���ΒP�ɐ錾�̑Ώےn����g�債�Ă����������Ȃ��Ƃ����l�����������v�Ɛ������܂����B�܂��A���g��͎��ׂ���ɂ��āu���N�`���ڎ��i�߂邱�Ƃɂ͋c�_�̗]�n���Ȃ��B�܂��A�����ł���������Ȃ����牓�������Ɍ������ł���̐������邽�߁A�����̃L���p�V�e�B�[��O��I�ɋ������邱�Ƃ��d�v���B����Ɉ�ÊW�҂ɂ�������̓w�͂����Ă��炢�A�K��f�Â̋����Ȃǂ�i�߂Ă��炤�K�v������B�����������i�ߐ��{�ɂ͂킩��₷���[�����̂��郁�b�Z�[�W���o���Ă����Ȃ�������Ȃ��B�������ǂ�ǂ�g�債�Ă���Ɏ��~�߂������Ȃ��ƁA���b�N�_�E���̂悤�ȑ���\�ɂ���@���������c�_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��v�Əq�ׁA������@���������܂����B
������ �R����\ �g��Ñ̐��ێ��Ȃǐ��{�������Ή����h
�����}�̎R����\�͓}�̒���������Łu�f���^�����҈Ђ��ӂ邢����Ȃ̂ŁA��Ñ̐�����������ێ������N�`���ڎ�������ɐi�߂Ă�����悤���{�������đΉ��ɂ������Ă��炢�����B���{�E�^�}�Ƃ��č����̕s�����������A���҂ɉ�������悤�S�͂������Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
�����Y���E���勳���@�V�^�R���i���������ƈ�ÕN���̊�@�@8/5
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�������Ă��܂��B�V�K�����҂�1�T�ԂŔ{�����闬�s�͂ǂ��܂ōL����̂��A��Ñ̐��͈ێ��ł���̂��A�V���Ȍ��O�_�͂ǂ��ɂ���̂��B�����E���v���f�����g���������ǐ����u�w�����̐��Y���E���s��w�����ɕ����܂����B
�\�\�S���̐V�K�����Ґ���1��1���l������������Ă��܂��B����A�����Ґ��͂ǂ����ڂ��Ă����̂ł��傤���B
���Y�@���łɗ��s���n�܂��Ă���ً̂͋}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�ƂȂ��Ă����s����ߋE���A�������A�k�C���Ƃ�������s�s���ł��B�����s����{�Ȃǂł�1�T�ԂŊ����҂�2�{�ɑ�����Ƃ������A����܂łɂ݂����Ƃ̂Ȃ��悤�ȃX�s�[�h�ŗ��s���g�債�Ă��܂��B���m���͂܂��ΏۊO�ł����A�����҂��}�����Ă���A���s���n�܂�̂͊m���Ƃ݂��܂��B��s�s���ȊO�ł����s���n�܂钛�����݂��Ă��܂��B�����Ƃ̐l�̍s������������錧��Q�n���ł͂��łɊ����҂����Ȃ葝�����Ă��܂����A�ΐ쌧�A�V�����Ȃǂ̖k���n���A�L�����≪�R���Ƃ����������n���ł������ǖʂɓ����Ă��Ă��܂��B
�\�\��4�g�͑�ォ��S���ɍL����܂����B����͓�������S���ɍL�����Ă����Ă���Ƃ݂��܂����B
���Y�@�����ł��ˁB�܂��s���ŁA�E�C���X���A����܂ł�芴�����̍����Ȃ����u�f���^���v�ւ̒u������肪�i�݂܂����B�������͊������₷���̂��Ƃł��B�s���ő������f���^�����e�n�ɔg�y���A�n���ŋN�����N���X�^�[�́A�ق�100���f���^���ɂ����̂ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
�\�\�����̊����Ґ��̍���̕ω��ɂ��āA7��28���̌����J���Ȃ̐��Ɖ�c�ł�3��ނ̃V�~�����[�V��������Ă����܂����B�ǂ̃V�i���I�ő����Ă��������ł����B
���Y�@�����ł�1�T�ԂŊ����Ґ���2�{�ɂȂ��Ă��܂��B�c�O�Ȃ���A1�l�̊����҂����l�Ɋ��������邩�Ƃ����u�����Đ��Y���v���ق�2�ɋ߂��Ȃ��Ă��܂��B���̂܂܂̃X�s�[�h�Ŋ������g�傷��A8�����ɂ��s����1���̐V�K�����Ґ���1���l����悤�ȁA�����Đ��Y��1.7�̃V�i���I��肳��ɋ}���ɗ��s���g�傷�鋰�ꂪ����܂��B
�\�\�Ȃ����̂悤�ȃX�s�[�h�Ŋ������g�債�Ă���̂ł��傤���B
���Y�@�l�̗��ꂪ�v�����悤�Ɍ���Ȃ��Ƃ����v�f������܂����A��ɂ̓f���^�����������ƍl���Ă��܂��B�f���^���͊����̃E�C���X�ɔ�ׁA�����ԓ��̊����҂̑������x�������グ�܂��B�����̃E�C���X���f���^���ɒu�������ƁA�ǂ��̍��ł��}�s(���イ�����)�Ɋ����Ґ��������Ă��܂��B�܂��u�������̓r�����ƍl�����܂��̂ŁA���̂܂܂̑�ł́A���炭�p���I�Ɋ����҂������Ă����Ǝv���܂��B
�\�\��4�g�ł́A���ň�Õ��N���܂����B��Õ���̉e���̎����A�����҂̔N��ɂ���ĈقȂ邻���ł��ˁB
���Y�@4���ȍ~5����{�ɂ����A���{���ł͊����҂������I�ɑ����A��Õ��܂����B��4�g�ŖS���Ȃ����������Ŗ�1200�l���܂������A���̂�����2����̊����҂͎���ŖS���Ȃ�A900�l�͓��@���ɐl�H�ċz���̊O�����^�l�H�x(ECMO)�������ɖS���Ȃ�܂����B�x�b�h�������ς��œ��@�ł��Ȃ����A���邢�́A���@�͂ł������̂́A�l�H�ċz��Ȃǂ��Ï]���҂��s�����Ă����肵�ĐϋɓI���Â��ł����ɖS���Ȃ��������҂����Ȃ肢���Ƃ������Ƃł��B�Ƃ���ŁA���̊��Ԃ̔N��ʂ̏d�ǎҐ��Əd�lj������݂�ƁA�d�NJ��҂̎����͑S�N��ő����Ă���̂ɁA�d�lj����́A40���50��ł͏オ���Ă���̂ɑ��A60��ȍ~�͋t�ɉ������Ă��܂��B������ǂ����߂��邩�B�d�lj��̍ő僊�X�N�͔N��ł�����A���R��60��ȍ~�̏d�lj��������������Ƃ͍l�����܂���B���̏ꍇ�A���͂ł͏\���Ɍċz�ł����A�l�H�ċz��Ȃǂ����邽�߂ɋC�ǂɑ}�ǂ����l��A�W�����Î�(ICU)�ł̎��Â����l���u�d�ǁv�Ƃ��Đ����Ă��܂��B�ł�����A60��ȍ~�A�Ƃ��ɏd�lj����̒ቺ�����̑傫��80��ȍ~�́A�ϋɓI�Ȏ��Â��邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܊Ŏ�(�݂�)�炴��Ȃ����������҂����������A�܂�u���̑I���v���N���Ă����\��������Ɖ��߂���̂������Ƃ����R�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�\�\�����Ȃǎ�s���ł��̂܂܊����҂�����������ƁA��4�g�̍ۂɑ��ŋN�����悤�Ȉ�Õ��N����̂ł��傤���B
���Y�@��4�g�̑��Ƃ͂����ԈقȂ����ɂȂ�Ǝv���܂��B���܁A�d�lj����X�N�̂����Ƃ���������҂�8���߂���2��̃��N�`���ڎ���I���܂����B���̂��A�ŁA��4�g�̑��قǂ͏d�NJ��҂��}�����Ă��܂���B����ŁA�����ǂ�y�ǂ̊��҂���̂��߂Ɋm�ۂ��Ă����ʕa��(�R���i��ʕa��)���N�����Ă���A�Ȃ��Ȃ����@�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����ƒ����ǂ�y�ǂ̊����҂̑������Â��ł��Ȃ��Ȃ�A�d�lj���h���̂�����Ȃ�܂��B���N�`���̌��ʂƂ͕ʂɁA��N�ɔ�ׂďd�lj�����l�������Ă���w�i�ɂ͎��Â̐i�W�����邩��ł��B�����ǂ̏ꍇ�A�u�����f�V�r���v(�R�E�C���X��)��u�f�L�T���^�]���v(�X�e���C�h��)���g�����Ƃł��Ȃ�d�lj���h�����Ƃ��ł��܂��B�܂��A�y�NJ��҂ɂ��g����o�ꂵ�܂����B���`�̎���Łu(�y�ǎ҂⒆���ǎ҂�)�d�lj����X�N��7�����炷����I�Ȏ��Ö�v�ƏЉ���A�u�J�V���r�}�u�v�Ɓu�C���f�r�}�u�v�Ƃ���2��ނ̒��a�R�̂�g�ݍ��킹���u�R�̃J�N�e���Ö@�v�ŁA�挎19���ɓ��Ᏻ�F����܂����B��������������_�H�Ȃǂœ��^���邽�߁A���@���Ă��Ȃ��Ƃقڎg���܂���B��Â��N�����đ������@���ł��Ȃ��Ȃ�ƁA���N�`���ڎ헦������҂��Ⴍ�A����҂Ɏ����ŏd�lj����X�N�̍���40�`50��̒��ŁA�d�lj�����l�������Ă��鋰�ꂪ����܂��B
�\�\�ҏ������������A�Ƃ��ɍ���҂��d�lj����₷���M���ǂ������Ă��Ă��܂��B��Â̕N���ɂ��V�^�R���i�E�C���X�ȊO�̕a�C�̎��Âւ̉e�����S�z����Ă��܂��B
���Y�@�R���i��ʕa���́A���X�̋~�}��Â�S���Ă��鑍���a�@�̋~�}�Ɋm�ۂ���Ă��邱�Ƃ������̂ŁA�����̕a�����N������ƁA�R���i�ȊO�̂�����~�}�f�Â��N�����Ă��鋰�ꂪ����܂��B�G�ߕ������A�M���NJ��҂���̒��ł��A����҂ŏǏ�̏d�����́A���M���ȂǐV�^�R���i�E�C���X�Ƃ̌�������������Ƃ����Ȃ�����܂���B�������A����̕��͂��Ȃ�d���Ȃ�܂Ŏ��o�Ǐ�̂Ȃ��ꍇ�����Ȃ��Ȃ��A���}�Ɏ蓖�Ă����Ȃ��Ɩ��ɂ�����邱�Ƃ�����܂��B����ŁA���c���ɑ����ARS�E�C���X�����ǂ��A6�����{�ȍ~�A3�T�A���ʼnߋ��ő��̊����Ґ����X�V�������Ă��܂��B����������M��P(����)�Ƃ������Ǐo�邽�ߐV�^�R���i�E�C���X�Ƃ̊ӕʂ�����ł��B�������A���߂Ċ����������c���͏Ǐd���Ȃ�₷���A�x����C�ǎx�����N�������Ƃ����Ȃ����܂���B�Ƃ���1�Ζ����̓����̔x���̖���RS�E�C���X�����ǂ��������Ƃ݂��Ă��܂��B�����������A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂƂ̌�������������҂������Ă��钆�ŁA�~�}��Â��N������ƁA�����ɕ\���ȏ�̉e�����o�鋰�ꂪ����܂��B�~�}�����������T���ۂɁA�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̋^��������Ƃ��������Ŕ�����f����\���������Ȃ�A�Ȃ��Ȃ��������������ꂸ�ɁA�ӂ���������Ɏ��Ԃ�������A���̌��ʂƂ��Ď��ɋ~�}�������K�v�Ȑl�̂Ƃ���ɍs�����Ԃ��x���A�Ƃ������Ԃ������܂��B�R���i��ʕa���ɗ]�T������A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂƂ̊ӕʂ�������҂��������Ă��炦�܂����A�R���i��ʕa�����N������Ƃ��ꂪ����Ȃ邽�߂ɁA�����Ƒ����a�@�ɔ�������A�K�Ȑf�f���āA���Â��Ă���Ώ��������M���ǂ̕���RS�E�C���X�����ǂ̎q�ǂ��ւ̎��Â���x��ɂȂ�Ƃ����Ɋׂ肩�˂܂���B
���u�ǂ��Ŋ������Ă����������Ȃ��v�@������5000�l���Ɋ�@���@�����@8/5
�����s�����\�����V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ������߂�5000�l����5���A�s���ł͊����g��̑����Ɂu�|���v�u�ǂ��Ŋ������Ă����������Ȃ��v�ƌ��O���鐺�������ꂽ�B
�����E�����K��Ă����`��̎��c�Ə��䖾������(63)�́u�|�����Ƃ��B�����~�܂�Ȃ��Ǝv���v�Ɗ�@���������ɁB�d�lj����X�N�̒Ⴂ���҂͎���×{����{�Ƃ��鐭�{�̐V���j�ɂ��Ă��u���Ȃ�Ђǂ��b�B���{������������Ă��Ȃ��`���\��Ă���v�ƕ������B
��t�����R�s�̃X�^�C���X�g�̏���(64)�́u�y�[�X�������������B�g�߂ɔ����Ă��āA�ǂ��Ŋ������Ă����������Ȃ��v�ƕs�������ɂ����B
��҂�Ƒ��A��łɂ��키JR���h�w���ӁB���c�J��̑�w����c��Ԃ���(21)�͊����Ґ���5000�l�������ƂɁu�{���ł����v�Ƌ������B���Ȃ��B2��ڂ̃��N�`����ł��I������牓�o���悤�ƍl���Ă����Ƃ������A�u�������ɕ|���̂ōs�����ǂ����l���܂��v�Ƙb�����B����A�F�l�Ɣ������ɗ����a�J��̉�Ј��̏���(24)�́u�����꒴����Ǝv���Ă����B���ɋ����͂Ȃ��v�ƒW�X�ƌ�����B�@
�������s �V�^�R���i �ߋ��ő���5042�l�����m�F 5000�l���͏� �@8/5
�����s���ł�5���A����̔��\�Ƃ��Ă͂���܂łōł�����5042�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B5000�l����̂͏��߂ĂŁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s��5���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��5042�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B����̔��\�Ƃ��ẮA����܂łōł���������4����4166�l������A���߂�5000�l���܂����B�ߋ��ő����X�V����̂�2���A���ł��B5����5042�l�́A1�T�ԑO�̖ؗj������1177�l�����Ă��܂��B5���܂ł�7���ԕ��ς�3646.9�l�ŁA�O�̏T��164.0���ƂȂ�܂����B
�s�̐��Ƃ́u����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������I�Ȋ����g�傾�v�Ƃ��āA������@���������Ă��܂��B
�s�̒S���҂́u���ς�炸�Ⴂ����̊����҂��������A�w�����͊������Ă��Ǐy��������v�x�Ȃǂƍl���Ă����҂������Ƃ�����ۂ�����B��҂ł��d�lj�����\��������A�ň��̏ꍇ�A�������������āA���������肪�S���Ȃ�\�������邱�Ƃ܂ōl���āA��{�I�ȑ�̓O���S�����Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
5����5042�l�̂��������o�H���킩���Ă���1799�l�̓���́A�u�ƒ���v���ł�����1125�l�A�u�E����v��284�l�A�u�{�ݓ��v��116�l�A�u��H�v��72�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�����I�����s�b�N�֘A�ł́A�O���l���ϑ��Ǝ�1�l�A���Z�W��1�l�A���f�B�A1�l�A���{�l���ϑ��Ǝ�2�l�A���Z�W��1�l�́A���킹��6�l�̊������m�F����܂����B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂�23��6138�l�ƂȂ�܂����B
����A5�����_�œ��@���Ă���l��4�����16�l������3383�l�ŁA�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��56.7���ł��B�s�̊�ŏW�v����5�����_�̏d�ǂ̊��҂�4�����20�l������135�l�ŁA�d�NJ��җp�̕a����34.4�����g�p���Ă��܂��B�d�ǂ̊��҂�130�l����̂͂��Ƃ�2��1���ȗ��ł��B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ60��̒j��1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B����œs���Ŏ��S�����l��2302�l�ɂȂ�܂����B
������̊����Ґ�5000�l���Ƃ�
�����s�ŐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�l��5���A����̔��\�Ƃ��Ă͏��߂�5000�l���܂����B�V�^�R���i�E�C���X�̊������n�܂��Ă���1�N���ȏオ�����ŁA����ɔ��\�����V�K�����Ґ���5000�l�����̂͑S���ł�5�����܂߂�47���Ԃ����Ȃ��A�����s�Ƃ���1�̎����̂�����5000�l���鎖�ԂɂȂ����̂͏��߂ĂŁA���݂̊����g�傪����܂łɂȂ��K�͂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B�S���ň���ɔ��\�����V�K�����Ґ������߂�5000�l�����̂͊����̑�3�g�̂��Ƃ�1��6���ŁA��3�g�ł�1��22���܂ł�5000�l�����̂�14���Ԃł����B�܂��A�����̑�4�g�ł�4��21������5��21���܂ł̊Ԃ�21���ԁA�����̑�5�g�ł͐挎22���ȍ~�A5�����܂߂�12���ԂƂȂ��Ă��܂��B�����s�ł͌��݁A���������l�̂����z���Ɣ��肳���z������20�����A����܂łɂȂ������g��������ɂȂ��Ă��܂����A��T�㔼����͖�Ԃ̐l�o�������ɓ]���Ă��Č����J���Ȃ̐��Ɖ�͓��ʂ͊����g��̌p�����������Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
���uL452R�v�ψكE�C���X �ߋ��ő�2444�l�m�F
�����s��5���A�s����1���̔��\�Ƃ��Ă͂���܂łōł�����2444�l���C���h�Ŋm�F���ꂽ�uL452R�v�̕ψق�����E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�܂��A�z���Ɗm�F���ꂽ�����͏��߂�80������82.4���ƂȂ�A����܂łōł������Ȃ�܂����B5����2444�l�̂��������o�H���킩���Ă���̂�487�l�ŁA�ƒ����284�l�A�E�����70�l�A��H��32�l�A�{�ݓ���7�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B����ł��̕ψكE�C���X�ւ̊������s���Ŋm�F���ꂽ�̂́A1��2768�l�ɂȂ�܂����B
�����r�m���u�f���^���͔��Ɍ������v
5���A�s���ʼnߋ��ő���5042�l�̊������m�F���ꂽ���Ƃɂ��āA�����s�̏��r�m���́A�s���ŋL�Ғc�ɑ��u�����͂��Ă������A�f���^���͔��Ɍ������B��ʂ̕��X�̉�b�̒��ł��w�m�荇�������������x�Ƃ��������Ƃ����킳���悤�ɂȂ��Ă���A�������Ƃ��đ����Ă��������ȊO�ɂȂ��B���߂Ē��ӊ��N���������肵�Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
�������J���Ȋ����u�z�����銴���́v
�����J���Ȃ̊�����1�l�́u����܂ł̓��N�`���ڎ킳���i�߂ǂ��ɂ��Ȃ�Ƃ����C���[�W���������A�f���^���̊����͂������̑z���������Ă���2�T�Ԃ������ɓs����1���̐V�K�����҂�1���l���Ă��邱�Ƃ��\���ɍl������B�����̍s�����傫���ς��Ȃ�������A���Ă̈ꕔ�̂悤�ɐڎ��������`�������邩�A���b�N�_�E���̂悤�ȋ��������邱�Ƃ��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂����B�ق��̊����́u�V�K�����҂̐����{�A���̔{�Ƃ����悤�ȑ����������Ă��ċ��|���o����X�s�[�h���B���Ƃ������ǂ̃f�[�^�����Ă������҂�����v�f���Ȃ��A���܂ł��܂�ŗ��K�������悤�Ɏv����قǑS�������̈Ⴄ�i�K�ɓ����Ă����Ǝ~�߂Ă���B�����͉Ƒ��Ȃǐg�߂Ȑl�ɂ������Ȃ��ȂǁA��l��l�ɑ���������Ă��炤�ȊO�ł肪�Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B�܂��A�ʂ̊����́u���̏��d���~�߂Ă���B�m�ۂł���a���ɂ͌��E������̂Ŋ������g�傷�錳��₽�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A�����ɑ��ĉ�������̂����߂��Ɠ`���Ă������͓����Ȃ��̂ŁA�������X�N�����ɍ����s���ɍi���Ď��l�����߂�Ȃǃ����n�������ČĂт����Ă��������Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂����B
���s���̏d�Ǖa���g�����g�呱���������ɖ����h���Y�����玎�Z�@8/5
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̍���̊����ɂ��āA���s��w�̐��Y�������̃O���[�v���V�~�����[�V�������s���A���̂܂܊����g�傪�����A�������ɂ͓s���̏d�Ǖa���������ς��ɂȂ邨���ꂪ����Ƃ��錋�ʂ����\���܂����B
����́A���Y������4���A�����J���Ȃ̐��Ɖ�Ŏ��������̂ł��B�O���[�v�́A�����g�傪�������ꍇ�A�����s��1���̐V�K�����Ґ����ǂ��Ȃ邩�ɂ��āA�O�̏T�̓����j���Ɣ�ׂĉ��{�ɂȂ��Ă��邩�̃f�[�^���g���č���2�����_�Ŏ��Z���s���܂����B���̌��ʁA�����̃y�[�X���ŋ߂̃f�[�^�ɍ��킹�āu1.7�{�v�Ƃ����ꍇ�A����12���ɂ�1���̊����҂�1���l���A����26���ɂ�3���l����Ƃ����v�Z�ƂȂ�܂����B�܂��A�����荂���y�[�X��������T�́u2.2�{�v���������ꍇ�͍���17����3���l�ɒB����Ƃ����v�Z�ɂȂ����ق��A�t�Ƀy�[�X�������āu1.2�{�v�ƂȂ����ꍇ�ł�����4���ɂ�1���l����Ƃ������ʂɂȂ�܂����B
�a���̂Ђ����ɂ��Ă����Z���s���Ă��܂��B���Z�ł�1�l�����l�Ɋ��������邩�����������Đ��Y�����A�����͂̋����f���^���̉e�����l�����Ă��܂�荂���u1.7�v�Ƒz�肵�A�����s�̍���̏d�ǎҐ��̐��ڂ��v�Z���܂����B���̌��ʁA�����Đ��Y���̌�����10���ɂƂǂ܂�Ɖ��肵���ꍇ�A�d�NJ��҂̐���8��20���ɂ��悻399�l�ƂȂ�A�s���m�ۂ��Ă���392������v�Z�ƂȂ�܂����B�܂��A���Ƃ�4������ً̋}���Ԑ錾�Ɠ����̌��ʂƂ��Ď����Đ��Y����30�������ƂȂ����ꍇ�ł��d�NJ��҂̐��͑��������A8�����{�ɂ͓s���m�ۂ��Ă���d�Ǖa����50���ɒB���A9��6���ɂ�400�l���錋�ʂƂȂ�܂����B����A�����Đ��Y����50�����������邱�Ƃ��ł����ꍇ�́A�d�NJ��҂̐���150�l���邱�Ƃ͂���܂���ł����B���Y�����́u�I�����s�b�N���J�Â���钆�A�s���̎��l�����߂�͖̂���������A���b�Z�[�W���͂��ɂ����l�����\���Ɍ����Ă��Ȃ��B�l�Ɛl�Ƃ̐ڐG�����炵�āA�����Ґ�����C�Ɍ��炳�Ȃ��Ƃ����Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂��B
���u1000�l��1�l�����������v�����ŐV�K����5000�l���@8/5
�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��̊g�傪���肳��܂����B�lj����ꂽ�͕̂����E���E�ȖE�Q�n�E�É��E���m�E����E�F�{�ŁA���Ԃ͍���8������31���܂łł��B��ނ̒�~�ȂǁA�ً}���Ԑ錾�Ɠ��l�̌������[�u���v������܂��B�V�^�R���i�����g��̃s�[�N�͂��܂��݂��܂���B�V�K�����Ґ���5���A��s���̂ق��A�F�{�E����ʼnߋ��ő����X�V�B�S���ł�1��5000�l���A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
��������ł́A��K�͏��Ǝ{�݂Ő��\�l�K�͂̊������������Ă��܂��B�ɐ��O�V�h�X�ł́A�挎29�����獡��4���܂ł�81�l�B��҂������K��郋�~�l�G�X�g�V�h�ł́A�挎22�����獡��4���܂ł�72�l�̊��������o���܂����B���̍�_�~�c�{�X�ł́A�挎26�����獡��4���܂ł�138�l�̊��������炩�ɂȂ��Ă��܂��B�ɐ��O�V�h�X�ƍ�_�~�c�{�X�ł́A�H�i�����̏]�ƈ��̊������ڗ����܂����B���Ƃ͒n���X�̊댯�����w�E���܂��B��������w�E���c�g�������F�u�l�����x�E�l���E���C�A����3�ł��B�f�p�[�g�ɔ��������ɗ���l�����A�^�[�~�i�����ړ�����Ȃ��ŁA������Ɨ�������ė[�H���l�����A�ʂ肷����l�����A�l�X�ȑ������������l���ׂĂ��ʂ�̂��n���X�B���̌��ʂƂ��Đ����鍂�����x�������v
�����s�Ŋm�F���ꂽ�V�K�����҂�5042�l�ŁA2���A���ʼnߋ��ő���啝�ɍX�V���Ă��܂��B�s�̃��j�^�����O��c�̎��Z�ɂ��܂��ƁA���̃y�[�X�Ŋ������g�傷��ƁA2�T�Ԍ�ɂ́A�����҂�7���ԕ��ς�1��909�l�ɏ��Ƃ������Ƃł��B�������ۈ�Ì����Z���^�[�E��ȋM�v��t�F�u���悻�ł����A�s����1000�l��1�l��������������v�Z�B���̊�@���������̂��̂Ƃ��āA�F�ŋ��L����K�v������v���{�����T�ł��o�����g���@�����h�Ƃ��w�E�������j�]�����A�����s���A�މ@�̊��ύX���Ă������Ƃ�������܂����B�W�҂ɂ��܂��ƁA�s��4���A���@���҂ɂ��āA��t�̔��f�Ŏ���×{��h���×{�Ɉڂ��悤�A�a�@�ɓ`�����Ƃ������Ƃł��B�����A����×{�҂�������A�̒����}�ς��Ă��K�Ȉ�Â����Ȃ����O�����܂�܂��B��������}�E���ʍG�Q�@�c���F�u�~���閽���~���Ȃ��Ȃ�ł���A����×{�ŁB���̂��Ƃ��F����S�z���Ă����Ȃ��ł����v�c�����v�����J����b�F�u���������Ĉ�ÂɌg�����X�̃}���p���[�͌��E������B���s���ɐ��܂�Ă��Ȃ���ł��B���s���͂��蓾�܂���B���A�������X���K���ɂȂ��ĐF�X�Ȃ��Ƃ����������Ē����Ă���v
�@ |
 �@ �@
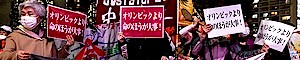 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���u�����ܗւ͊����g��̌����ł͂Ȃ��v�Ȃ����͖����ł���̂��@8/6
�����g�Ή�u�ł����܂ł̒��ŏd�v�Ȋ�@�ɒ��ʁv
8��2���A��ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���Ɂu�ً}���Ԑ錾�v�����߂���A�����s�Ɖ��ꌧ�ɔ��ߒ��̓��錾���������ꂽ�B�k�C���Ȃ�5���{���ɑ��Ắu�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p���ꂽ�B���Ԃ͂������2������31���܂łł���B�����́A7��30���ɐ��{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ��{����c�Ō��܂����B��c��A���`�̎͋L�҉�ŁA�u��s��������̑����̒n��ł���܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ��X�s�[�h�Ŋ������g�債�Ă���B�a�����N�����鋰�ꂪ����v�Ƙb���A�����I�����s�b�N(7��23���`8��8��)�̊J�Âɂ��Ắu�����g��̌����ɂȂ��Ă��Ȃ��v�Ƌ������Ȃ�����A�u����̃e���r�Ő����𑗂��Ă������������v�ƍ����ɋ��߂��B����A�L�҉�ɓ��Ȃ����V�^�R���i���ȉ�̔��g�Ή�́u���ɋ}���Ȋ����g��ɓ��{�Љ�ǂ̂悤�ɑΉ�����̂��B�ł����܂ł̒��ŏd�v�Ȋ�@�ɒ��ʂ��Ă���v�ƌ�����B���͓����ܗւƊ����g��́u���W�v�Ɩ��������B�������A�{���ɊW�Ȃ��̂��낤���B
���s���ł́u���������߂܂��v�Ɠ\��o�����H�X���ڗ���
�s���ł̓I�����s�b�N�J�ÑO����7��22����1979�l�̊����҂��L�^������A27��(2848�l)�A28��(3177�l)�A29��(3865�l)�A30��(3300�l)�A31��(4058�l)�Ƃ��Ȃ����Ɋ����҂��������B�S���ł������҂͑����A29����10698�l��1���l��˔j���A30��(10743�l)�A31��(12340�l)��1���l�䂪�������B���̊����҂̋}���́A�I�����s�b�N�̊J�Âō����̋C�������g���ĐV�^�R���i�ɑ����@�������ꂽ���ʂ��ƁA��������͍l���Ă���B�ċx�݂��d�Ȃ�A�l�X�́u���E�����牽���l���̑I���W�҂��W�܂��ăI�����s�b�N����邮�炢��������͂Ȃ����낤�v�Ɣ��f���ꂽ�̂��낤�B�����A�ܗ։��̃I�����s�b�N�X�^�W�A��(�������Z��A�V�h��)�̎��ӂł͋L�O�B�e�ɋ�����l�����̎p��������B�l���X���ɌJ��o���̂ɍ��킹�āA�s���ł͎��l�����߂��Ă���A���R�[�����o�����H�X���ڗ��B
���f���^���̊����͂̍����Łu�ǖʂ��ς�����v
�ܗ։��ɑ����^�Ȃ��Ƃ��A����̃e���r�ϐ�œ��{�̑I���`�[���������_�����l������V�[����ڂɂ���ƁA���ꐰ�ꂵ���Ȃ邵�A�ނ炪�u�x���Ă��ꂽ�݂�Ȃ̂������ł��v�Ɨܐ��Ō��ƁA�e���r�����Ă��邱������v�킸�܂����ݏグ�Ă���B���̈Ӗ��ŃI�����s�b�N�͐V�^�R���i�Ђŗ������������̐S�ɏ�����^���A���₵�Ă����B�����C���]���ɂȂ�B�������A���E�ő�̍ՓT�ł���ܗւ͎��������ɂ����邠�܂�A��@����r��������B���ړI�ɂ́u���ϋq�v�u�o�u���J�Áv�Ŋ������������Ă��A�ԐړI�ɂ͊ԈႢ�Ȃ������̊g��ɂȂ���B�ܗ֊J�Â������g��ɖ��W�Ƃ͌����Ȃ��͂����B��Ȃ̂́A�I�����s�b�N�ɖ����ɂȂ��Ď����������@����ۂo�����X���o���낤�B�����ɂ͕K���A�ǂ��ʂƈ����ʂ�����B�ܗւ������ł���B�������̔w�i�ɂ́A�C���h�R���̕ψكE�C���X�u�f���^���v(L452R)�̊����͂̍���������B�A�����J��CDC(���a��Z���^�[)�ɂ��ƁA�f���^���̊����͂�1�l��5�l�`9.5�l�Ɋ���������\��������A�]���̐V�^�R���i�ɔ�ׂ��Ȃ荂���B��C��������u���ڂ������v�̃E�C���X�Ɠ������炢�̊����͂ɕC�G����Ƃ����B�����CDC�́A�d�lj�������A���S�����肷�郊�X�N�������Ȃ�X���ɂ���A���N�`����ڎ킵���l�ł��ڎ�����Ă��Ȃ��l�Ɠ����悤�Ɋ������L����\�����w�E�B�u�����̋ǖʂ��ς�����v�ƒ��ӂ��Ăт����Ă���B
���u�s���ϗe�ɂȂ��郁�b�Z�[�W��ł��o���v�ƒ����А�
7��31���t�̒����V���̎А��́u���⏬�r�S���q�s�m���͍������A���Ƃ��Ì���̋�����@���𐳖ʂ���~�߁A�����̍s���ϗe�ɂȂ��郁�b�Z�[�W��ł��o���˂Ȃ�Ȃ��v�Ɩ`���Ŏ咣���A�Ō�ɂ����i����B�u�����Ȃ��y�ς�r���A���t��s�����Č����������č����ɋ��͂����߂�ׂ������B�ɂ��̐擪�ɗ��o�傪����̂����A����Ă���v���o�����u�錾�n��g��@�����Ȃ��y�ςƌ��ʂ��v�ł���B�ً}���Ԑ錾���o�������̂Ȃ��ŁA�I�����s�b�N���J�Â���B�u�y�ρv�Ƃ��������ُ�ł���B���ɂ͌����������������̖ڂŘ��Ղ��Ăق����B�����А��͎w�E����B�u���{�͓����A�V���ȑ[�u�ɐT�d�������B�����҂������Ă��A���N�`���ڎ�̂������ŁA�d�lj����₷������҂͑啝�Ɍ���A�d�ǎ҂͗}�����Ă���Ƃ����킯���B�������A���������̊����҂̋}���ɉ�����A���f����]�������B���̂��Ǝ��́A����F���〈�ʂ��̊Â���@���Ɏ����Ă���v���̒����А��̎w�E�͐������Ǝv���B�������̌���F���ƌ��ʂ��͊É߂���B�Â�����ً}���Ԑ錾�̒n��̉�����g��ȂǏ����̑����Ȃ��̂ł���B�ǂ��l���Ă������ً͋}���Ԑ錾�Ɋ���A�ْ����ɂ͌��ѕt���Ȃ��B�����������̊g��ɂȂ���I�����s�b�N�܂ŊJ�Â��Ă��܂����B
�����͌ܗ֊J�Í��̋`���ƐӔC�����o���Ă���̂�
����8��1���t�̒����А��́u�ܗ܂�Ԃ��@���S�E���S���������āv�Ƃ̌��o�����f���A�u���́A���Ă�͂𑶕��ɔ����ł�������A��Â��鑤�����S���ʂŗp�ӂ��Ă��邩���v�Ǝw�E���A�u�p���f�~�b�N���ŋ��s���ꂽ���ƂŒ����s���̑I�肪�����A�L�^�͑����Ēᒲ���B�����Ď��͂Ɋ����҂��o�āA�{�Ԓ��O�̗��K�̎��l��]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ����P�[�X���o�Ă���v�Ə����B�p���f�~�b�N�Ƃ�����펖�Ԃ̂Ȃ��ŊJ�Â���Ă��铌���ܗւ́A�ۉ��Ȃ��ɍ���̃I�����s�b�N�j�Ɏc�邾�낤�B�����̔��Έӌ����������ĊJ�Â����ȏ�A�������͊o������ׂ����B�u���Ă�͂𑶕��ɔ����ł�����v��p�ӂ��邱�Ƃ́A�J�Í����{�̋`���ł���A�ӔC�ł���B�����А��͎w�E����B�u�E�C���X�����O���玝�����܂��̂��A���{���獑�O�ɍL����̂��h���B���̖͂ǂ��܂ʼnʂ�����Ă��邩�B���h�ȍs���K�͂������Ă�����Ȃ���ΈӖ����Ȃ��B�ᔽ�s�ׂɑ��锱�����܂߁A���J�Â̏����Ƃ��ꂽ���̂�����ނ�ɂȂ��Ă͂��Ȃ����v�����ܗւ̊J�Âɋ��������A�u���~�̌��f���ɋ��߂�v(���o��)��5��26���t�Ōf�ڂ��������А��炵���w�E�ł���B�����А��́u���ɂ��I��E�W�҂��悹���p�o�X�̉^�s�g���u����ٓ��̑�ʔp���ȂǁA���v���̃A�s�[���|�C���g�������^�c�\�͂���̗��O���̂��̂ɋ^�╄�������Ƃ��A�J�����������v�Ƃ��w�E���A�Ō�ɂ����咣����B�u�ՓT���J�Â��鑤�̎p���ƐӔC�́A�Ō�܂Ŗ��ꑱ����v�J��Ԃ����A���ɂ͋`���ƐӔC�����o���Ă��炢�����Ǝv���B
���u�V�������_������Ԃɉ�������@�ɐ�ւ���v�Ɠǔ��А�
7��29���t�̓ǔ��V���̎А��͏����o���Łu�����s�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����ߋ��ő����L�^����ȂǁA�R���i�Ђ͏d��ȋǖʂ��}�����B����ȏ�̊��������ɂȂ���ʂ悤�����w��������K�v������v�Ǝ咣���A�����Ăт�����B�u�����A����܂łƈقȂ�������\��Ă���B��Âɏ����ɂ߁A�V�������_������Ԃɉ�������@�ɐ�ւ��鎞�@�ł͂Ȃ����vWHO(���E�ی��@��)���p���f�~�b�N��錾�����̂��A��N��3��11���B���ꂩ��1�N���߂��������A�����͕̏ω����Ă���B�V���ȋǖʂɉ����đ���ւ���͓̂��R�ł���B�ǔ��А��͂���܂łƈقȂ銴���̓�����������B�u�����҂̒��S�͎�N�w�ŁA�s���ł�30�Α�ȉ����S�̂�7�����߂�v�u���N�`���̐ڎ킪�i��65�Έȏ�́A�����҂̊������S�̂�3�����x�ŁA�R���i�Ђ��n�܂��Ĉȗ��̒ᐅ���ɂ���B�S�̂̏d�ǎҐ�����3�g�̔������x���B���Ґ����[���̓��������Ă���v�u40�`50�Α�̏d�ǎ҂������A�a���̕N�����S�z����Ă���v��Ғ��S�̊������ŁA����҂̊��������Ȃ��A�d�ǎҐ����}�����Ă���Ƃ͌����A�y�ς͂ł��Ȃ��B����͐l�ނ����߂đ��������V�^�E�C���X�ł���B�����҂̐���������A����ɉ����ďd�ǎ҂⎀�҂̐l���������Ă���B���̏d�ǎ҂Ǝ��҂̑����́A�����Ґ��̑�������x��Č���邽�ߒ��ӂ��������Ȃ��B
���d�v�Ȃ̂́A�e����F�߂A����������邱�Ƃ�
�u�ً}���Ԋg��@�ɂ݂͌ܗւ̂����ł͂Ȃ��v�ƌ��o���𗧂Ă�7��31���t�̓ǔ��А��ɂ͋������ꂽ�B�����I�����s�b�N�ł̓��{���̉��i������̓I�ɋ�������A�u�C������Ȃ̂́A�V�^�R���i�̊������v�Ə����A�u�ꕔ�ɂ́A�������������g��ƌܗ֊J�Â����т���ӌ������邪�A�؈Ⴂ���낤�v�Ǝw�E����B�ǔ��А��͖��W�̍����Ƃ��āu�����́A�����h�~���ŗD��ɁA�唼�����ϋq�ŊJ�Â���Ă���B����܂ŁA���Z����I�葺�ő傫�ȏW�c�����͋N���Ă��Ȃ��B���ϋq�Ƃ�����a�̑I�����t�����Ă���ƌ����悤�v�Ə������A�u���ϋq�v�͕��ȉ�̔��g�����Ƃ̋��߂ł���A�����A���͗L�ϋq�ɌŎ������ϋq�ɔ����Ă����B���Z����I�葺�ł̏W�c�����ɂ��Ă��{���ɔ������Ă��Ȃ��̂��A�^��ł���B����ɓǔ��А��́A���E�ő�̍ՓT���l�X�̋C�������g�����A��@����r��������댯���ɂ��Ă͈ꌾ���G��Ă��Ȃ��B�ܗւ�4�N�Ɉ�x�̐��E�K�͂̃C�x���g���B���ꂪ�s���Ă���A�y�͂��݂ȍs���������Ă��܂��Ƃ����͎̂d���Ȃ��B�d�v�Ȃ̂́A�e����F�߂A����������邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B
���f���^���g1�̋N�_����S���g�傩�h ���������nj����������� �@8/6
�����ł��嗬�ɂȂ��Ă���V�^�R���i�E�C���X�́u�f���^���v�ɂ��āA���������nj���������`�q�̃f�[�^�����Ƃɂǂ��L�����������͂����Ƃ���A�C�O�����s���ɗ�������1�̋N�_����S���ɍL�������Ƃ݂��邱�Ƃ��킩��܂����B
���������nj������́A�����͂̋����ψكE�C���X�f���^���ɂ��āA���������l����̎悵���E�C���X�̈�`�q����͂��Ăǂ��L�����������͂������ʂ�4���A�����J���Ȃ̐��Ɖ�Ɏ����܂����B
����ɂ��܂��ƌ��݁A�S���e�n�ɍL�����Ă���f���^���̌n���ōł������̂��̂́A���Ƃ�5��18���Ɏ�s���ŊC�O�n�q�����Ȃ��l���猟�o���ꂽ�E�C���X�������ƕ�����A����ɒ��ׂ�ƁA����Ƃ悭�����E�C���X��4��16���ɋ�`�̌��u�Ō������Ă����Ƃ������Ƃł��B
���������nj������͊C�O���痬������1�̋N�_�����s���𒆐S�Ɋg�債�A���̌�A�S���K�͂Ŋg�U�����Ɛ��肳���Ƃ��Ă��܂��B
����ŁA���Ƃ�5������֓�����A�����A��B�ȂǂŊm�F����Ă����A�C�O���痬�������Ƃ݂���f���^���̃N���X�^�[�̑����͑傫�Ȋ����g��ɂȂ��炸�A7�����{����܂łɂ͂قڎ��܂����Ƃ݂���Ƃ������Ƃł��B
���������nj������̘e�c���������́A�u����܂ł̍����̗��s�ł��A��͂�1�̋N�_����S���Ɋg�債�Ă��āA������������Ƃ��N���Ă���\��������v�Ƙb���Ă��܂��B
���f���^�� ��s���ł͊����S�̂̂ق�90����
�����͂������ψق����V�^�R���i�E�C���X�u�f���^���v�́A��s���ł͂��łɊ����S�̂̂ق�90���A���ł�60���]����߂�ȂǁA�}���ɒu������肪�i��ł���Ƃ��鐄��̌��ʂ��A���������nj��������܂Ƃ߂܂����B
���������nj����������Ԃ̌������7�Ђ́u�ψي��X�N���[�j���O�����v�̃f�[�^����ɁA�f���^���ł݂���uL452R�v�̕ψق��܂܂ꂽ�E�C���X���A�ǂꂭ�炢�̊������߂Ă��邩���肵�����ʂ�4���A�����J���Ȃ̐��Ɖ�Ŏ����܂����B
����ɂ��܂��ƁA�����s�ł̓f���^���Ȃǂ����ł�90���A�_�ސ쌧�A��ʌ��A��t�����܂߂���s����1�s3���ł�89�����߁A�������{�ɂ͂قڂ��ׂĒu�������Ƃ��Ă��܂��B
�܂����{�A���s�{�A���Ɍ��̊���2�{1���ł́A�挎��{�܂ł͏��Ȃ���Ԃł������A�}���ɍL������63���ƂȂ��Ă��āA�������{�ɂ�80������Ƃ��Ă��܂��B
����ɉ��ꌧ��89���A��������85���ȂǂƁA�e�n�Œu������肪�i��ł��āA���@���҂��}�����A��Â̂Ђ����ɂȂ����Ă���Ǝw�E����Ă��܂��B
���Ɖ�̘e�c���������́u�f���^���͊����͂��]���̃E�C���X��2�{���x�ŁA�]���Ɠ���������x�̋����ōu���Ă����䂪����B�������}�g�債�Ă���n��ł͐l����}���邾���łȂ��A�l�Ɛl�Ƃ̐ڐG�@��̍팸���s�������Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B
���u�܂h�~�[�u�v8����lj��@�����Ȃǂւ́u�錾�v�Ƃ̑�̈Ⴂ�́H�@8/6
�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�Ƃ��Ď����o����u�ً}���Ԑ錾�v�B��N4���A�����č��N1���A4���ɑ����A7��12�������4��ڂƂȂ�錾�����o����Ă��܂��B�����s�A���ꌧ�ɉ����A8��2������͎�s��3���Ƒ��{���lj��B�����8��5���ɂ͖k�C���⋞�s�Ȃ�5���{���œK�p���́u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ɉ��m�A�É��A�F�{�Ȃ�8����lj����邱�Ƃ����܂�܂����B�j���[�X�ł悭���ɂ���ً}���Ԑ錾�Ƃ܂h�~���d�_�[�u�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂łǂ�Ȋ����h�~���荞�܂�Ă���̂ł��傤���B
Q�F�����������{�́u�ً}���Ԑ錾�v���āH
�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�Ƃ��Ď����o����u�ً}���Ԑ錾�v�B��N4���A�����č��N1���A4���ɑ����A7��12�������4��ڂƂȂ�錾�����o����Ă��܂��B�����s�A���ꌧ�ɉ����A8��2������͎�s��3���Ƒ��{���lj��B�����8��5���ɂ͖k�C���⋞�s�Ȃ�5���{���œK�p���́u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ɉ��m�A�É��A�F�{�Ȃ�8����lj����邱�Ƃ����܂�܂����B�j���[�X�ł悭���ɂ���ً}���Ԑ錾�Ƃ܂h�~���d�_�[�u�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂łǂ�Ȋ����h�~���荞�܂�Ă���̂ł��傤���B
Q�F�Ώےn��͂ǂ��H�@�ǂ����܂�́H
���{�͐錾���o���ۂ�(1)����(2)���(3)�ً}���Ԃ̊T�v�A�����ꂼ�ꎦ���K�v������܂��B�錾�̓��e���̓I�ȑ�́u��{�I�Ώ����j�v�ɋL����A�e�s���{���͂���܂��đ�����{���܂��B�錾���o��������e��ύX�����肷��ꍇ�́A���Ƃ�ō\�����鐭�{�́u��{�I�Ώ����j���ȉ�v(��F���g�Ύ�)�Ɏ����Ĉӌ����葱�����K�v�ł��B
3��ڂ̐錾�́A4��25���ɓ����A���A���ɁA���s��4�s�{����Ώۂɔ��o���ꂽ��A�Ώےn��̒lj��≄�����Ȃ���A6��20���ɂ͉��ꌧ�������ē����A���Ȃ�9�s���{���ʼn�������܂����B
�������A�����ł͐V�K�����҂��Ăё����ɓ]���A�C���h�R���́u�f���^���v�ւ̒u������肪�i��ł������ƂȂǂ���A��������3�T�Ԍ��7��12���ɍĔ��o����܂����B���ꌧ�ƂƂ���8��22���܂ł������ł������A������7���㔼�ɘA��3000�l����L�^����ȂNj}���Ȋ����g�傪���������ߐ錾��8��31���܂ʼn������A�Ώۋ�����ʁA��t�A�_�ސ�̎�s��3���Ƒ��{�܂Ŋg�傷�邱�ƂɂȂ�܂����B���݁A�v6�s�{���Ő錾�����o����Ă��܂��B
Q�F����̐錾�ł͂ǂ�ȑ����́H
����ً̋}���Ԑ錾�́A���Ԓ��ɓ����ܗ�(7��23���`8��8��)���͂��߁A4�A�x��ċx�݁A���~���T���A�l�тƂ̈ړ��⊈���������ɂȂ邱�Ƃ��\�z����邽�߁A�u�����ŗ\�h�I�[�u���u����v(���`�̎�)���Ƃ�ړI�ɔ��o�����܂�܂����B
�����h�~��Ƃ��ẮA3��ڂ̐錾�Ɠ��l�Ɉ��H�X�ɂ������ނ̒��~���邱�Ƃ��傫�Ȓ��ł��B��̓I�ɂ́A
��ނ�J���I�P�������H�X�ɑ��ċx�Ɨv��(����ȊO�̈��H�X�͌ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v��)
���ʐς��v1000�������[�g�������^���Ǝ{�݂ɑ��Čߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v��
��K�̓C�x���g�͏��5000�l�����e��50���ȉ��ŊJ�×v��
�Ȃǂ̑��荞�܂�Ă��܂��B
��^���Ǝ{�݂ւ̑���߂����ẮA�Ⴆ�Ή��ꌧ�ł͓y�����S�̋x�Ɨv�����s���ȂǁA�m���̔��f�ő����悹���邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă��܂��B
�܂��A�������܂ޕs�v�s�}�̊O�o���l��A�s�v�s�}�̋A�ȁE���s�ȂǓs���{���Ԃ̈ړ����ɗ͍T���邱�Ƃ����߂Ă��܂��B��ނ��O�o����ꍇ���A�Ƒ��╁�i�s�����Ƃ��ɂ��Ă��钇�ԂƏ��l���ŏo�����邱�Ƃ���A���G���Ă���ꏊ�⎞�Ԃ��ɗ͔����邱�Ƃ���������Ă��܂��B
Q�F�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑Ώےn��́H
�܂h�~���d�_�[�u�Ƃ́A�ً}���Ԑ錾���o���Ɏ���Ȃ��悤�A�}���Ȋ����g�傪������n��ɍi���ďW���I�ȑ���s���[�u�ŁA�ΏۂƂȂ����s���{���́A���̓s���{�����ŃG���A���w�肵�A���H�X�ւ̎��Z�c�Ɨv���Ȃǂ��s�����Ƃ��ł��܂��B�ً}���Ԑ錾�����������n��ł̓K�p���z�肵�Ă��܂��B
�����ȊO�̍�ʁA��t�A�_�ސ�̎�s��3���Ƒ��{�ɂ�8��22���܂ŏd�_�[�u���K�p����邱�ƂɂȂ��Ă��܂������A����4�{����8��2������ً}���Ԑ錾�Ɉڍs���܂����B�����ɏd�_�[�u�͖k�C���A�ΐ�A���s�A���ɁA������5���{�����ΏۂɂȂ�A�����8��8������͕����A���A�ȖA�Q�n�A�É��A���m�A����A�F�{��8�����lj��B�d�_�[�u�̑Ώۋ��͌v13���{���ƂȂ�܂��B���Ԃ͂������8��31���܂łł��B
Q�F�d�_�[�u�̒n��ł͂ǂ�ȑ����́H
�d�_�[�u�̑ΏۂƂȂ������{�����̎w��G���A�ł́A���H�X�ɑ��Čߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ�v�����܂��B����Ɏ�ޒ͌�����~�ƂȂ�܂��B�������u���������~�X���v�̏Łu���̗v���v�������X�ɂ��ẮA�m���̔��f�Ōߌ�7���܂Ŏ�ޒ��\�ɂ���Ȃǂ̑�̊ɘa���s����Ƃ��Ă��܂��B
���̂ق��A�������܂߂��s�v�s�}�̊O�o�̎��l��A�ً}���Ԑ錾�̒n��Ƃ̉����ȂǓs���{���Ԃ̈ړ����ɗ͍T����悤���߂Ă��܂��B
���R���i������ 1��5000�l���@�ً}���Ԑ錾 �S���֊g��u�l���Ă��Ȃ��v �@8/6
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂����߂�1��5,000�l���钆�A���́A�S���ɋً}���Ԑ錾���o���l�����Ȃ����Ƃ��������B
5���A�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�5,042�l�B��T�ؗj�����炨�悻1,100�l�������A���߂�5,000�l�����B
�܂��A�d�ǎ҂�135�l�B�V���Ɏ��S���m�F���ꂽ�̂�1�l�������B
�����Ɨאڂ���4���Ȃǂł��A�V�K�����҂��ߋ��ő��ɁB
�S���ł�1��5,259�l�̊������m�F����A���߂�1��5,000�l�����B
�����������A���{��5���A5�̓��{���ɓK�p����Ă���A�܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āA�V���ɕ����A���A�ȖA�Q�n�A�É��A���m�A����A�F�{��8����lj����邱�Ƃ�����B
����A���łɁA�܂h�~�[�u���K�p����Ă��镟�����ł́A�����҂�2���A����700�l���A���͐��{�ɑ��A�ً}���Ԑ錾�̓K�p��v�������B
�������E�����m���u���̗z���҂̐L�т́A���܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ��A�����̔����I�Ȋg��������Ă���v
�S���Ŋ������}�g�傷�钆�A5���ɍs��ꂽ���{�̕��ȉ�ł́A�ꕔ�̐��Ƃ���u�S���ɋً}���Ԑ錾���o�������������v�Ƃ����ӌ����オ�����Ƃ����B
���u�S���I��(�錾���o��)�Ƃ������Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v
����A���{�����\�������N�`���̐ڎ��5���A9,800������A���Ȃ��Ƃ�1��ڂ̐ڎ���I�����l�͑S�̂�45.2%�B
2��ڂ̐ڎ�����������l��32.1%�ƂȂ��Ă���B
�������@�R���i������5000�l�����@�����I�Ȋ����g�呱���@8/6
�����s��5���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����5042�l���ꂽ�Ɣ��\�����B4����4166�l����2���A���ʼnߋ��ő����X�V���A����5��l��ɏ���Ĕ����I�Ȋ����g��̌X���������Ă���B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���3646�E9�l�ɏ㏸���ĉߋ��ő��B�O�T���164���ƂȂ����B���@���҂⎩��×{�҂��}�����A��Ò̐��̕N��(�Ђ��ς�)���n�܂��Ă���B���@���҂̂����d�ǎ҂�20�l����135�l�B
�����ł͐V����1��5263�l�̊����҂��m�F����A�ߋ��ő����X�V�B���߂�1��5��l�����B�����ȊO�ɐ_�ސ�1846�l�A���1235�l�A��t942�l�A�R��67�l�A�F�{127�l�A����648�l�ƁA6�����ߋ��ő����X�V�����B
���������A�V�^�R���i106�l�����@���킫�A�����̃N���X�^�[�g��@8/6
����5���A�����ŐV����106�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B4���ɗz���Ɣ������A�����m�F�͉���6222�l�ƂȂ����B
���킫�s��4���ɔ��\�����s���̎����{�݂̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�ŐV���Ɏ���1�l�̊������m�F����A�N���X�^�[�͌v7�l�Ɋg�債���B�����s�̗V�Z��ł��V���ɗ��p��2�l�̗z�����������A�v8�l�ƂȂ����B
106�l�̓���́A���킫�s56�l�A�S�R�s15�l�A�ɒB�s8�l�A�����s�ƎO�t���e5�l�A�{���s4�l�A�쑊�n�s3�l�A�쑽���s�Ɠ�{���s�e2�l�A�c���s�A�������A���쒬�A�L�쒬�A�x�����A��ʌ��e1�l�B36�l�̊����o�H���s���B
4�����݂̓��@�Ґ��͏d��11�l���܂�388�l�B162�l���h���×{���ŁA����×{�҂͉ߋ��ő����X�V����183�l�B102�l���×{�撲�����B�����܂ł�29�l���މ@���A9�l���h���×{�{�݂���k�ޏ������B
����Ñ̐��̕N���u���Ԃ̖��v�@�������A�f���^�������g��ɏł�@8/6
�V�^�R���i�E�C���X�������}�g�債�Ă��镟�����B5���ɂ�2���A����700�l���銴���҂��m�F����A���͐��{��4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̔��߂�v�������B���̐��v�ł͏T�����ɂ͊m�ەa���g�p����5�����錩�ʂ��ŁA��Ò̐��N��(�Ђ��ς�)�̌��O�����܂��Ă���B
�u���܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ��悤�Ȋ����̋}�g�傪�݂��w�f���^���x�̊����͂ɂ��A�a�������܂鑁���������x�I�ɂȂ鋰�ꂪ����v�B�������̕��������Y�m����5���̗Վ��L�҉�ŋ�����@�����������B
4�����_�̊m�ەa���g�p����33�E6�������A�m���́u���̏�������8��9���ɂ�50���ȏ�́w�X�e�[�W4�x(��������)�̒i�K�Ɏ��邱�Ƃ������܂��v�Ɛ����B���Ǝ��́u�����R���i�x��v���u�x��v����u���ʌx��v�Ɉ����グ�A���p�ق�}���قȂǂ̌��L�{�݂�6���ȍ~�A����������Ɣ��\�����B�ً}���Ԑ錾�����߂����A�����S��Ŏ�ނ������H�X�ɋx�Ƃ�v�����A����ȊO�̈��H�X�ɂ��ߌ�8���܂łɉc�Ǝ��Ԃ�Z�k����悤���߂���j���B
�u���̂܂܂ł͑��ӁA�I�[�o�[����v�Ɗ�@���������ɂ���̂́A������w�a�@(�����s����)�̐Αq�G���EECMO(�G�N��)�Z���^�[���B�Z���^�[�ł͐l�H�S�x���u�uECMO�v�ŏd�NJ��҂����Â��邪�A�d�Ǘp�x�b�h��4���̂���1���A�����Ǘp�x�b�h��8���̂���6�������܂�B�����Ǘp�̂����j���p�͖������B�Z���^�[�͋}�����ʕa�������炵�A�R���i�a���ɓ]�����邱�Ƃɂ����B
7���ȍ~�́u��5�g�v�ł͊��҂̎�N�����ڗ��Ƃ����A�����ǂ�6�l��40��ȉ���4�l�B�u�f���^���v�̊g�傪�v���Ƃ݂��A�Αq�Z���^�[���́u�A�x�ɐl�̓�����������Ί�����������B�~�}��Âւ̉e�����������Ȃ��v�Ɗ뜜����B
�[���Ȋ����g��ň�Â��N�����鉫�ꌧ��6��14�`20���A�x���ɓ��������Z���^�[�̐���k��(������)��t�́u����������̂悤�ɂȂ�͎̂��Ԃ̖�肾�v�Ƙb���B�a�����s�����鉫��{���ł͓��@�ł���悤�ɂȂ�܂Ŏ_�f���^���Ȃ���ҋ@���Ă��炤�u���@�ҋ@�X�e�[�V�����v�������{�݂ɐݒu����A�����ł͊��҂�{���Ƀw���R�v�^�[�Ŕ���������Ȃ��P�[�X���������Ƃ����B
�������ł͊��҂̏Ǐ�ɍ��킹���g���A�[�W(�D�揇�ʕt��)���i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���B����́A�ی����������҂���Ǐ������ē��@��h���×{�A����×{�̂ǂꂪ�K�������f���邪�A���������œ��@�������u�V�^�R���i�E�C���X�����ǒ����{���v�̖{�����A��쓹�Y��t�́u�����Ґ��������钆�A�g���A�[�W���ی����ɑ傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă���v�Ǝw�E�B�u���ɒ����ǂ̊��҂��ǂ��������邩���f����͓̂���A����×{�ƂȂ��Ă����̌�ɗe�̂��}�ς��ĕa�@�ɔ����������ꂾ������ɕ��S�������B��������オ�g���A�[�W�Ɋւ���悤�Șg�g�݂̍\�z���}�����v�Ƌ�������B
���É����u�܂h�~�v���̓K�p�@�������ƐÉ��E�l����Ώی����@8/6
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊g��ɔ����u�܂h�~���d�_�[�u�v�̐É��������K�p���A����5���A�������L�����Ă��錧�����Ɛ��ߎs(�É��s�E�l���s)��Ώےn��ɂ��錟���ɓ������B�����{��(�{�����E�쏟�����m��)��6���A�{������c���J���ĕ��j�����߂�B
�����̐V�K�����Ґ���4���A202�l�ŏ��߂�200�l���A�ߋ��ō����X�V�����B���̂����l���s��54�l�ŁA�s�̉ߋ��ō��ɂȂ�A�s�Ǝ��̊����g��x���錾�߂����B
�܂h�~�[�u�̌����ւ̓K�p�ɂ��āA�쏟�m����4���A�u���̍l�����Ƃ���v����B���A�s���ƒ����̂���6�����ɂ͖{������c���J�Â��A���j�����肷��v�ƃR�����g�\�����B
���̐��Ɖ�c(�����A�q��؎q�E�É�����Z���^�[�����Ǔ��ȕ���)�́A���̎w�W�ɂ��x���敪���X�e�[�W3(�����}��)����ł��[����4(��������)�ֈ����グ�邱�Ƃň�v�B���Ƃ̈ӌ��܂��A���͂܂h�~�[�u���ً}���Ԑ錾�����ɗv������\�肾�����B
���ɂ��ƁA3���ߌ�5�����݂Ŏ���×{�҂�549�l�A���@�Ȃǂ̒������Ŏ���ҋ@���Ă���l��156�l�B4�����ߌ��݂ŁA�����̏h���×{�{��(6�{�݁A�×{�җp�q��735��)��292�l���������Ă���B
�a����L��(4�����ߌ���)�͌��S�̂�38�E4���B�n��ʂœ���53�E8���A����37�E1���A����27�E3���ɒB���Ă���B�܂��A�V�^�R���i���N�`���̐ڎ��2��Ƃ��I�����l��3�����݂�24�E96���ɂƂǂ܂�B
����7��29������A�S�s���{���ւ̕s�v�s�}�̉������l�������ɋ��߂Ă���B��b���Ȃ���̐H���͊������X�N�����߁A�����̉Ƒ��ȊO�̐l�ƐH��������ہA�u�H���͖ق��āv�u��b�͕K���}�X�N���p���v�Ɨv���B�S���I�ɒ��w�Z�⍂�Z�̕������ł̊����Ⴊ����ƒ��ӊ��N���Ă���B�Ј����⋤�������̏�Ŋ������g�債�Ă��邱�Ƃ���A�]�ƈ��������ŗ��p����ꏊ�ł̊����h�~��̓O����Ăт����Ă���B
���������s�̊����ҁA�����I�ɑ����c�O�T��3�{���@�@8/6
��ʌ��������s�̐����E�l�s����5���̒���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����������I�ɑ������Ă���Ƃ��āA�u����܂łɂȂ����ɋ�����@���������Ă���B���@���҂̑����������ƁA��ʈ�Âւ̉e����������Ƌ������O���Ă���B�A�Ȃ◷�s�Ȃnj������܂����ړ����ɗ͍T���A�Ƒ��ȊO�̐l�Ƃ̉�H������Ăق����v�ƌĂъ|�����B
�s�ی����ɂ��ƁA�s�����Z�҂̊����҂�3�����݁A�v1��1260�l�B��T1�T�Ԃ̐V�K�����҂�1145�l�ŁA���߂Đ�l���A�O�̏T��3�{�����B�����s���͊����܂��A�ی����̑̐�������\���B�Ō�t�̎��i�����E��2�l���܂�12�l�̐E����V���ɔz�u���āA��100�l�̐��ɂȂ�Ƃ����B
�����ܗւ̊J�Â������g��ɉe���������ɂ��āA�����s���́u�l���̑����͊J���O����n�܂�A���ϋq�J�Â̂��ߑ傫�ȉe���͂Ȃ��v�Ƃ����B�ԐړI�ȉe���̗L�������A�u�Ȃ����Ă��鑤�ʂ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�ƒ�Ō��Ă���l������̂ŁA�v���X�ʂƃ}�C�i�X�ʂƗ���������v�Ƃ��q�ׂ��B�@
�@ |
 |


 �@
�@ |
���ߋ��ő��A�S����1��5753�l�������@6���ōő��X�V�@8/7
�����̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�7���ߌ�8�����݂ŐV����1��5753�l���m�F����A�ߋ��ő����X�V�����B1��5��l����̂�3���A���B�d�ǎ҂�6�����_��1068�l�ƑO�����48�l���������B���~�x�݂̎������}�������A�����g��̌X���͎��܂��Ă��Ȃ��B
���̓��ő��̓����s�͉ߋ�2�Ԗڂ�4566�l�B����×{�Ґ���1��8444�l�ŁA�O������408�l�������B���@���Ґ���3485�l�ƂȂ�ߋ��ő��ɁB
���̂ق��ً}���Ԑ錾���o����Ă���n���A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��ƂȂ��Ă���Ƃ���𒆐S�Ɋ������g��B��ʌ�(1449�l)�A��t��(1075�l)�A�R����(79�l)�A�É���(236�l)�A���ꌧ(117�l)�A�F�{��(151�l)�ʼnߋ��ő����X�V�����B
�����������A8������8���ŏd�_�[�u���V���ɓK�p�����B�����̒n��̎�v�w�̐l�o��1�T�ԑO�Ɣ�r����ƁA�����ނˌ����X��������ꂽ�B
NTT�h�R���̌g�ѓd�b�̈ʒu��琄�v�����f�[�^�ɂ��ƁA���m���̖��É��w���ӂ̌ߌ�1����̐l�o��1�T�ԑO�ɔ�ׂ�3%���������ȊO�́A�������̂��킫�w���ӂ�13%���A�F�{���̌F�{�w���ӂ�11%���A�Q�n���̍���w���ӂ�8%���A���ꌧ�̑�Éw���ӂ�6%���A�É����̐É��w���ӂƈ�錧�̐��ˉw���ӂ͂������5%�������B�Ȗ،��̉F�s�{�w���ӂ͂قڕω����Ȃ������B
����A�����w��7���ߑO10����̐l�o�͑O�T��Ŗ�15%���B�����s�Ɠ��l�ɐ錾���o�Ă�����{�̐V���w���ӂ�3%���������B
�������s�@7���̐V�K������4566�l�@8/7
7���A�V���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�̊����҂́A4566�l�ƂȂ�A6���ɑ�����4500�l���Ă��܂��܂����B�܂��A�d�ǎ҂�150�l�ɑ����Ă��܂��B
���̂Ƃ���̊����҂͉ߋ��ő��ƂȂ���5����5042�l���܂߁A4���A����4000�l�ȏ�ƁA�����I�Ɋ������g�債�Ă���ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł͍ł�����20�オ1467�l�A������30���982�l�A40���675�l�ƂȂ�܂����B�d�ǎ҂�6������9�l������150�l�ƂȂ�A�����҂̑����ɔ����A�d�ǎ҂������Ă��܂��B
�����������ҁ@���T�ɂ͈��1���l�����@���Z�@8/7
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��̑����Ɏ��~�߂�������Ȃ����A����̐V�K�����Ґ������T�ɂ́A1���l����Ƃ��鋞�s��w�̐��Y��������̃V�~�����[�V���������\����܂����B
����4���̌����J���Ȃ̐��Ɖ�c�Ɏ����ꂽ���Y������̃V�~�����[�V�����ł́A�V�K�����҂��A���̃y�[�X�Ƃقړ����ŁA�O�̏T��1�D7�{�ő�����ƁA����12���ɂ͈���̊����Ґ���1��1000�l����Ƃ������Ƃł��B
����ɁA����24���ɂ́A2��3000�l���A����26���ɂ�3���l���A�ً}���Ԑ錾�̊�����31���ɂ́A4���l������Ɨ\�����Ă��܂��B
�܂��A�����荂���O�̏T��2�D2�{�̃y�[�X���������ꍇ�́A����17���ɂ�3���l�ɒB����\���ƂȂ��Ă��܂��B
����ŁA��̌��ʂ��o�Đl��������Ȃǂ��A�����̃y�[�X���O�̏T��1�D2�{�ɗ}����ꂽ�ꍇ�ł��A8��21���ɂ�7000�l����Ɨ\������܂��B
�V�~�����[�V�������s�������Y�����́A�u���̂܂ܗ��s���g�傷��Ǝ���ŋꂵ�ޕ��▽�𗎂Ƃ��l�������Ă��܂��܂��v�Ɗ�@�����点�Ă��܂��B
�u��A�}�X�N�A�f�B�X�^���X(�l�Ƃ̋���)��3�ŁA�啝�Ƀ��X�N��������܂��B�܂��A���炭�͂������Ȃ��l�ɉ��Ȃ��A�W�c�ʼn����ŏW�܂������Ȃ��A�����Ȃ����Ƃ����邱�ƂŁA���X�N�������邱�Ƃ��ł��܂��v�Ƙb���Ă��܂��B
�����āA�u�F�ŋ��͂����āA��U�蔲������ŗ\�h�ڎ��i�߁A�����ɂ��Ęb���Ă�������̂Ǝv���܂��B�����͂����肢���܂��v�Ɖ��߂ČĂт����܂����B
���C�Y�v�ꎁ�u�Ή��͌���肾�v�@�����V�K������4566�l�Ɏ����@8/7
�O�����s�m���ō��ې����w�҂̑C�Y�v�ꎁ(72)��7���A�c�C�b�^�[�ɐV�K���e�B�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ��������Ă���v���͂�����ŁA�u���{��s�̑Ή��͌���肾�v�Ɣᔻ�����B
�V�K�����҂́A�����͂̋����C���h�R���̃f���^���̉e��������A�����y�[�X���������Ă���B�C�Y���́u�{���̓����s�̃R���i������4566�l�A�d�ǎ�150�l�Ƌ}�g��v�Ɠ`���A�u�ً}���Ԑ錾���A���l�������邪�A�f���^���̊����͂̋������傫�ȗv�����v�ƋL�����B
�����āu�����ł͎Ⴂ����ւ̃��N�`���ڎ킪�i��ł��Ȃ��B�������A���̃E�C���X��3��ڂ̐ڎ킪�K�v�Ȃ��炢�ɖ��ȕψق𐋂��Ă���v�ƌ��O�������A�u���{��s�̑Ή��͌���肾�v�Ǝw�E�����B
�t�H�����[�炩��́A��ăy���[�R���Ƃ����u�����_���v�������Ŋm�F���ꂽ���Ƃ�S�z���鐺��A�u�ᔻ�����ˁI�����Ȃ�č����ł��������Ƃ��I���̌�����ǂ�������ǂ��Ȃ邩�O�����ȍl�����o����̂��́I�v�u�ł́A�ǂ�����ׂ����ƁH�v�ȂǁA��̍�����߂�R�����g�����Ă���B
���A�Ȗ{�i���A�n���ւ̔g�y���O�@�R���i�����A��ÕN�����@8/7
�V�^�R���i�E�C���X�̊������S���I�Ɋg�傷�钆�A�ċx�݂̖{�i�I�ȋA�ȃV�[�Y����7���n�܂����B���Ƃ͓s���{�����܂����ړ��̎��l�����߂邪�A��ʋ@�ւ̗\��͍�N��葝���B��ÕN�������O����n���ł͊����̔g�y�Ɋ�@�������܂��Ă���B���{��8���A�V���ɂ܂h�~���d�_�[�u��8���ɓK�p�B�����Ȃ�6�s�{���ւً̋}���Ԑ錾�Ɠ���31���������ƂȂ�B�l�̗��ꂪ�}�����߂Ȃ��ŁA�m���ɉ����ł���̂��͌��ʂ��Ȃ��B
�����s��7���Ɋm�F���ꂽ�V�K�����Ґ��͉ߋ�2�Ԗڂɑ���4566�l�B���@���҂̂����d�ǎ҂�6���ɔ�ׂ�9�l����150�l�ƂȂ����B
���������������R���i�����}���Ŕ��g��u�ܗւ̉e������v�����ɔ��_�@8/7
���`�̎�8��6���A�L���s���ŋL�҉���A�����ܗւƐV�^�R���i�E�C���X�����}�g��̊֘A���ɂ��āu����܂ł̂Ƃ���ܗւ������g��ɂȂ����Ă���Ƃ̍l�����͂��Ă��Ȃ��v�Ƙb���A�g����Ă�ł���B
�������s�m���ō�Ƃ̒�����������4���A���g�̃c�C�b�^�[���X�V�B���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή���s���𒆐S�Ɋ����҂��}�����Ă��邱�Ƃɂ��āA�u�I�����s�b�N���l�X�̈ӎ�(�C�̊ɂ�)�ɗ^�����e���͂���v�Ɣ����������Ƃ��������ᔻ���Ă����B
��������4���̏O�@�����J���ψ���Ŕ��g�������������L����\��t���A�u�ȉ��̔��g�����A�G�r�f���X�̂Ȃ��A�Ȋw�I�����Ƃ͖����̔����ł��ˁv�ƃc�C�[�g�����B�L���ɂ��ƁA���g���͊����g��̗��R�̈�Ƀf���^���̉e������������ŁA�u�����Ԃ̎��l�Ől�X���R���i���ꂵ�āA�ً}���Ԑ錾�̃C���p�N�g���Ȃ��v�Ǝw�E�B�u�����̃��[�_�[�̃��b�Z�[�W���A�K��������̊��̂��鋭�����m�ȃ��b�Z�[�W�ł͂Ȃ������v�Əq�ׂ��Ƃ��Ă���B
SNS�A�l�b�g��ł́A�u���̕��͏ɑ��镪�͗͂��{���ɑ���Ȃ��l�ł��ˁB�G�r�f���X�͂����Ԃ��ɂ������ł��Ȃ����A���̎��ɂ͒x���Ɏ����Ă���B�𐳂����������A���f����̂��K�v�ł��B�I�����s�b�N�������ڍL���Ă��鎖�͔��f�ł��Ȃ��Ƃ͎v�����A����Ă��鎖�ւ̕s��������C�̂��݂͑傢�ɂ��邱�Ƃ̓G�r�f���X���Ȃ��Ă����f�ł���v�Ƃ����ӌ����������ŁA�u���g��̌����Ă��邱�Ƃ͐������Ǝv�����ǁA�m���ɃG�r�f���X�͖������Ƃ����A���ƂƂ��Đ��{�Ɉ�w�I�A�Ȋw�I�ȃA�h�o�C�X���闧��Ȃ̂��l����ƌl�I�ȉ����ł���s�K�Ȕ������Ǝv���B�܂������Ă��邱�Ƃ͐������Ǝv���܂����ˁv�ƒ������̈ӌ��ɗ����������ӌ�������ꂽ�B
�u��������͎����������s�m���̎��ɓ����ܗւ�U�v�������Ƃ������̔w�i�ɂ���Ǝv���܂��B�����A���{�⎩���̂��ً}���Ԑ錾�ŕs�v�s�}�̊O�o���T����悤�ɌĂт����Ă���ɂ��ւ�炸�A�����ܗւ��J�Â���Ă���̂Őؔ������Ȃ��͎̂����ł��B�������s�M���Ŏ����X���Ȃ��Ȃ��Ă���B���ꂩ�犴���������N���Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��v(�s���E��)
������������6���Ɏ��g�̃c�C�b�^�[���X�V�����ۂ��A�g����ĂB�u�����ܗ֊J�Ô��������l�����́A�ܗւ��n�܂�Ɠ��{�I��̊��C�ɂȂ��Ďd���Ȃ��A�ƋC�������ω��������ƂɋC�Â����낤�B�ł�����͂����ӂ��̌��S�Ȋ���ŏ��������߂������̂ł͂Ȃ��v�Ǝ��_��W�J������ŁA�u�l�����������̂́A�����̈ӎ��̐[�w�ɑz���v�����ƂȂ��A�y���Ɉӌ��炵�����̂��q�ׂ�����������v�ƒԂ����B�����ܗւ̊J�Âɔ�����l�������u�����v�ƕ\���������ƂɁA�ᔻ�̐����E�����鎖�ԂƂȂ����B
�R�����g���ɂ́A�����s�̕��m���߂Ă���2012�N7���Ɂu�������l������̂Ō����B2020�����ܗւ͐_�{�̍������Z������z���邪�قƂ��40�N�O�̌ܗ֎{�݂����̂܂g���̂Ő��E��J�l�̂�����Ȃ��ܗւȂ̂ł��v(���݂͍폜����ĉ{���ł��Ȃ�)�ƃc�C�[�g�������Ƃ����グ���A�u���E����̂�����Ȃ��ܗւƂ������Ă������m�������tweet�������悤�ł����A���̂��Ƃɂ��Ă����g�̈ӎ��̐[�w�ɂȂɂ��z�����Ƃ͂Ȃ��̂ł����H�v�Ȃǒ������̌��s�s��v���w�E���鑽���̏������݂�����ꂽ�B
�����ܗւ�8���ɕ���}����B���ʊW�͏ؖ�����Ă��Ȃ����A�R���i�������}�����Ă��邱�Ƃ͊m�����B���ꂩ�犴�������̋��ꂪ���鎖���ɖڂ������Ȃ�������Ȃ��B
����������99�l�����@��7�����\���@�ߋ��ň��̃y�[�X�ő����@8/7
�������͌�����99�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ��7���A���\�����B99�l�̗z����6���ɔ��������B����1�T��(7��31���`8��6��)�̐V�K�����Ґ���644�l�ʼnߋ��ő����X�V�B�����͂̋����ψي��u�f���^���v�̉e���������ƂȂ���7�����{�ȍ~�A1�T�ԒP�ʂ̐V�K�����Ґ��͉E���オ��ő��������Ă���A���ʂōő�������5��������y�[�X�Ŋg�債�Ă���B
�����}�g��ɔ�����Ò̐��ւ̕��ׂ��[�������钆�A8�����炢�킫�s�ւ̂܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�A���s�ȊO��58�s�����ł̌��Ǝ��̏W���J�n�B31���܂Ō����������Ċ����h�~�Ɏ��g�ށB�������́u��@�I�Ȋ����}�g���}�����ސ��O��v�ƈʒu�t����B
1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���3�T�O(7��10���`16��)��97�l�ŁA2�T�O(7��17���`23��)�͑O�T��122����118�l�A1�T�O(7��24���`30��)�ɂ͓�396����467�l�Ƌ}�g�債���B����1�T��(7��31���`8��6��)����138����644�l�𐔂��A�L�т����ɂ₩�ɂȂ������̂̈ˑR�Ƃ��đ��������A���~�܂�̏�Ԃɂ���B
����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���1�����ς�92�l�B1�J���Ɋ��Z�����2852�l�ɏ��A���ʂʼnߋ��ő�������5��(1179�l)��2�{����ߋ��ň��̃y�[�X�ƂȂ��Ă���B
6����������99�l��1��������̔��\���ʼnߋ�3�Ԗڂɑ����B6�����݂̕a���g�p���͑O������ς�炸73�D6���B�S�×{�Ґ�(858�l)�A����×{�Ґ�(274�l)�����ꂼ��ő����X�V�����B���͓��@���Â������Ƃ��Ă������A�a���N��(�Ђ��ς�)�ɔ�������×{�ɐU�������P�[�X���������ł���B
���킫�s�ւ̂܂h�~���d�_�[�u�ł́A�����s���̈��H�X�ɏI���̎�ޒ��l��v���B58�s������ΏۂƂ����W����ł́A��ނ������H�X�ւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�����߂Ă���B�S�����ɕs�v�s�}�̊O�o���l���Ăъ|���Ă���B
�����̊����҂͗v6400�l�B6����������99�l�̂���34�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��B
�������g�傷�钆�ł̂��~�Ɂc�V�^�R���i ���C3���ŐV�K������609�l�@8/7
���C3���ł�7���A�V����609�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��܂����B���m����459�l�A����67�l�A�O�d����83�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���m���Ɗ��ł��ꂼ��1�l�̎��S���m�F����Ă��܂��B
�����܂����s�v�s�}�̈ړ����l���Ăъ|����ꂽ���ł̂��~�x�݃X�^�[�g�B���C���V�����͎��R�Ȃ̏�ԗ����ō��ł�100�p�[�Z���g�ƁA�ڗ��������G�݂͂��܂���ł����B
JR���C�ɂ��܂��ƁA���~�x�݊��Ԓ��̎w��Ȃ̗\��́A�R���i�O��2019�N����8�����ŁA���N�Ƃقړ������ƂƂ������Ƃł��B
�V�����̗��p�҂́u�v���P�g���C�Ȃ̂ʼn�ɍs���v�u�o���ł�����ɗ��Ă����̂ŋA��B�R���i������̂œ����ł̏�芷�����|���v�ȂǂƘb���܂����B
�܂��A���C3���̍������H�ɂ͌ߌ�5�������݁A�ڗ������a�͂���܂���B
����A�������ۋ�`�����̍������\��Ґ��́A���N�̂��~�Ɣ�ׁA���{�q���悻1���������̂ɑ��A�S����͖�1�������Ă���Ƃ������Ƃł��B
���R���i�����}�g��̂��~ �ό��n �� ���R�ł͕s���̐��� �@8/7
�V�^�R���i�E�C���X�̊������S���I�ɋ}�g�傷�钆�A���~�x�݂̊��Ԃ��}�������R�s���S���̊ό��n�ł͕s���̐���������܂����B
�]�ˎ���̕���c������R�s�̒��S���̌Â������݂ł́A7���ߑO���A�}�X�N�p�̊ό��q�������Ă���l�q���܂�ɂ݂��܂����B
����ׂ��X��40��̒j���́u�F����ً}���Ԑ錾�ȂǂɊ���Ă��Ă��銴���������āA�����͐l�������Ɨ\�z���Ă��܂��B�}���鑤�͊����̂��킳������܂����A�����Ƃ��Ă͗��Ă����Ȃ��ƍ��镔�����������ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�l�͎Ԃ��^�c����50��̒j���́u�����������Ă��Ă���̂ł��킢����������܂����A��������グ���オ��������ȂƎv���Ă܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
��t������ό��ŖK�ꂽ�Ƃ���20��̒j����Ј��́u���ꂼ��̂��X�ł̓A���R�[�����ł⌟���Ȃǂ��������Ă���̂ŁA�n���̐l�ɂ͖��f�������Ȃ��悤�ɍs�����܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
���R�s���S���̗��ق�z�e���ł���g���ɂ��܂��ƁA���N�ɔ�ׂďh���̗\��͉��P���Ă�����̂́A�V�^�R���i�̊������S���I�ɋ}�g�債�Ă���e���ŁA�ꕔ�ŃL�����Z�����o�Ă���Ƃ������Ƃł��B
���^����Ŋ����g�傩�c�w�Z�ŃN���X�^�[������8�l�����@�x�R �@8/7
�V�^�R���i�E�C���X�A������8��7���V����46�l�̊������m�F����܂����B�܂��A�x�R�s���̊w�Z�ŁA�V���ȃN���X�^�[���m�F����܂����B�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�x�R�s�A�����s�Ȃnj���8�̎s�ƒ��A����ɓ����s�ȂǂɏZ��46�l�ł��B�܂��A���ƕx�R�s�͕x�R�s���̊w�Z�ŐV���ɃN���X�^�[���m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B���̊w�Z�ł�8��7���܂łɊW��8�l�̊������m�F����Ă��܂��B8�l��10�ォ��20��̏������Ƃ������Ƃł��B���ƕx�R�s�́A�挎30���ɂ��̊w�Z�̑̈�قŊJ���ꂽ�^����Ŋ������L�������Ƃ݂ĊW�҂��킹��205�l�̌������}���ł��܂��B�܂��A8��6���N���X�^�[�����\���ꂽ�x�R�s�̉�ЂŐV����5�l�̊������m�F����܂����B���̉�Ђ̊����҂�12�l�ɏ���Ă��܂��B�����̗v�̊����҂�2534�l�A���@�܂��͒�������196�l�d�ǎ҂�4�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����s271�l�����A���s�s���S�ɓ암�Ŋg��@�V�^�R���i�A7���锭�\�@8/7
���s�{�Ƌ��s�s��6���A�j��271�l���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�{���̊����Ґ��͌v1��9917�l�ƂȂ����B
�{���\����77�l�B���Z�n�ʂł͉F���s25�l�A�����s6�l�A��z�s�A�������s�A���c�ӎs�e5�l�A���s�s�A�T���s�A�ؒÐ�s�A���ؒ��e4�l�A���ߎs�A��蒬�e3�l�A�����s�A���O��s�e2�l�A�{�Îs�A��O�s�A�F���c�����A�^�Ӗ쒬�A�k�C���e1�l�B
���s�s���\����194�l�B
���L������117�l�����A1�l���S�@7���V�^�R���i�@8/7
�L��������7���A�V����117�l�̐V�^�R���i�E�C���X���������\���ꂽ�B100�l������2���A���B���s��1�l�̎��S�����\���A�����̎��҂̗v��180�l�ƂȂ����B
�V�K�����҂̋��Z�n�ʂ́A�L���s70�l�A���R�s22�l�A�O���s12�l�A�����s3�l�A�|���s�A�{�����e2�l�A���s�A�����s�s�A�{���s�A���L���s�A�F�쒬�A���s�{�e1�l�B�Ǐ�ʂ͌y�ǂ�105�l�A���Ǐ�12�l�������B
�L���s�ł́A�V�K�����҂�5��29���ȗ�70���Ԃ��70�l�ȏ�ƂȂ����B70�l�̔N��ʂ́A10�Ζ���4�l�A10��12�l�A20��17�l�A30��13�l�A40��10�l�A50��11�l�A60��3�l�B70��ȏ�̓[���������B
���R�s��22�l�̓���́A10��3�l�A20��5�l�A30��3�l�A40��1�l�A50��3�l�A60��6�l�A70��1�l�B�y��20�l�ŁA���Ǐ�2�l�B�s�́A�s���̎��Ə���5�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ��ăN���X�^�[�ƔF�肵���B
���s��1�l��20��ŁA���Ǐ�B3���ɃN���X�^�[�ƔF�肵���C��ۈ���w�Z�̌��C���ŁA���Z�̊����҂͗v12�l�B�܂��A���\�ς݂̊����҂̂����A���@���Ă���1�l�����S�����Ɣ��\�����B�s���ł̎��҂͌v13�l�ƂȂ����B
���̂ق���6�s1���Ƌ��s�{�̌v24�l�͍L���������\�����B�N��ʂ́A10�Ζ���3�l�A10��7�l�A20��4�l�A30��3�l�A40��2�l�A50��3�l�A60��2�l�B70��ȏ�̓[���������B
���́A���L���s���̎��Ə��ŐV���ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)��F�肵���B����܂łɓ��s�ݏZ��3�l�ƌ��O�ɏZ�ޏo����5�l�̐E���v8�l���z���ƂȂ����B
���u���̗��݂̍j�v���N�`���ڎ헦���オ��قNJ����g�傷���5�g�@8/7
�����ܗւ̂��Ȃ��A��1�g�`4�g��傫������K�͂̐V�^�R���i��5�g�̊��������ɏP���Ă���B�f���^���̉e���Ȃǂ������̗v�����������Ă��邪�A���v�f�[�^���͉Ƃ̖{��T���́u���N�`���ڎ헦�̍������قǍĂъ����g�債�Ă��܂��B�ڎ킵�����ƂŐl�X�̋C���ɂ݁A���S������s���}���������Ȃ��Ȃ��Ă���v�ƌx����炷�\�\�B
���ߋ��̑�1�`4�g�����5�g�̊�������
�����I�����s�b�N�J�Ò��̂��Ȃ��A�ŋ߂ɂȂ��āA�ߋ��̑�1�g�`4�g��傫������K�͂̐V�^�R���i��5�g�̊��������ɏP���Ă���B��Õ���ւ̑�Ƃ��Đ��{���ł��o�����u�����NJ��҂̓��@�������j�v�ɑ��č�����^��}����͌������ᔻ�����Ă���B
����������5�g�̊��������̔w�i�Ƃ��Ă͈ȉ��̂悤��6�������������Ă���B
1] �����͂̍����f���^���̉e���@/�@�����͂�1.5�{�Ƃ�������f���^���ւ̒u������肪��5�g�̊��������̎�ƂƂ�������x�z�I�ł���B
2] �R���i���ɂ���@���̌��ށ@/�@���{�����o����ً}���Ԑ錾���u�܂����v�ƍ����ɂ͐^���Ɏ~�߂�ꂸ�A�����@�ւ⏤�Ǝ{�݂ւ̌������x�Ɨv�����Ȃ����Ƃ������Ċ����}�����ʂ�����I�ł���B
3] ���N�`���ڎ�ɂ��C�̂��݁@/�@����҂ւ̃��N�`���ڎ킪�i�݈��S������s���}���������Ȃ��Ȃ��Ă���B���N�`���ڎ킪��������65�Ζ����w���N�w���������������Ă�����̕���܂Ŋ������މ\���͒Ⴍ�Ȃ�A���ȐӔC����������ƋC���ɂ�ł���B
4] �u���[�N�X���[�����@/�@���N�`���ڎ킵���l�ɂ��������Ă��܂����Ⴊ��������Ă���B
5] �I�����s�b�N�J�Ẩe���@/�@�I�����s�b�N�J�ÂŐS���I�ȗ}�����������A�s����������������C�x���g���̐������������ɂ����Ȃ��Ă���B
6] ���Ԍ����̋}���ɂ�銴���������̏㏸�@/�@����̖��Ԍ��������y���Ă��Ċ������������銄�����㏸���Ă���B
����́A���O�̃f�[�^���ώ@�����2�R���i���ɂ���@���̌��ށA3���N�`���ڎ�ɂ��C�̂��݁A����3�̗v�����傫���Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ������Ǝv���B
�����N�`���ڎ�Ŏ��S�Ґ����x�����ߋ��Œ�x���Ő��ڂ��Ă���
�V�^�R���i�֘A�̃f�[�^�̊�{�́A�V�K�����Ґ��Ɗ������S�Ґ�(�z���҂̂������S����Ɏ������҂̐�)�ł���B
���{�̗��f�[�^�̐��ڂ����Ă݂��(�}�\1�Q��)�A���炩��5�g�ɋy�Ԋ����g�傪�F�߂���B��5�g�̓����͉��Ƃ����Ă������Ґ��̑����ł���B��3�g�Ƒ�4�g�̃s�[�N�ł͈��������̐V�K�����Ґ���6000�l�̃��x���ł������̂ɑ��āA��5�g�ł͂��ł�1���l��傫�������Ă���A�܂��A�s�[�N�����ʂ��Ȃ��ł���B
��5�g�̂����ЂƂ̑傫�ȓ����́A����܂ł̔g�ƈقȂ��Ď��S�Ґ��̊g�傪�����Ă��Ȃ��_�ł���B���S�Ґ��̊g��͊����Ґ��̊g�傩�炩�Ȃ�x���̂��ʗ�ł���̂ŁA���ꂩ��㏸�ɓ]����Ƃ������ꂪ�Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����A�g�`���画�f����ƌ���I�ȍ��������Ă���ƌ�����Ȃ��B�ȉ��łӂ�鉢�Ă̐��ڂ��l�����킹�Ă��A���S�Ґ��̒ጸ�͂܂��ԈႢ���Ȃ����낤�B
����́A�l����̃��N�`�����S�ڎ헦(�����ڎ�ł͂Ȃ��K�v�ł��I���������)�̃J�[�u������A���N�`���ڎ킪�i��ł���e���ł��邱�Ƃ͊m���ł��낤�B�킪���ł͍���҂�D�悵�Đڎ��i�߁A�d�lj��⎀�S�ɂȂ���₷������҂Ɍ����Ă�2��̊��S�ڎ헦�͖�8���ɒB���Ă���B���ꂪ���S�Ґ��̒ቺ�������炵�Ă���̂ł���B
�e���r��V���ł͊����Ґ��̃O���t�͂₽��Ɠo�ꂷ��̂Ɏ��S�Ґ��̃O���t�͂قƂ�nj����Ȃ��B�������A�����l��g�߂Ȑl�̎��S���Ⴊ�ڂɂ��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��獑���͂��̓_���������n�߂Ă���A���ꂪ�C�̂��݂ɂȂ����Ă���_�͔ے�ł��Ȃ��̂ł���B
����A���S�Ґ��̒ጸ�͐��{�⎩���̂������͂��Ă���A�����̍s���}���ɂȂ��鋭�d�ȃR���i�ł��o����Ȃ��w�i�ƂȂ��Ă���ƍl������B
�����l�v���ɉ��������������̊�@���͌��ނ��A��5�g�̊�������
���ɁA���{�̏���肵�Ă���Ǝv���鉢�Ă̏����Ă݂悤�B
�}�\1�ɂ́A���B�ƕč��̊����Ґ��Ǝ��S�Ґ��̐��ڂ���{�Ɠ����`���Ōf�����B���B�̍ŐV�g�͑�4�g�A�č��̍ŐV�g�͓��{�Ɠ�����5�g�ł��邪�A�Ƃ��ɁA�����Ґ��͊g�債�Ă����S�Ґ��͂قƂ�ljߋ��Œ�x�����ێ����Ă���_�������ƂȂ��Ă���B
���{�Ɣ�ׂ�Ƒ�1�g�ɂ����鎀�S�Ґ��̃��x�������Ăł͔��ɑ傫�������Ƃ����_���������Ȃ��B���ꂪ�A���ď����ł̓��b�N�_�E���Ƃ��������I�ȍs���}���̐�����Ƃ点���傫�ȗ��R�ł������_�͊m�F���Ă����K�v������B
����ɑ��āA���{�́A������i�Ƃ�����莩�l�v���Ƃ����������ŃR���i���ł��Ă����̂��A��1�`2�g�ɂ����鎀�S�Ґ����x���̒Ⴓ�ɂ���Ă��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��낤�B�������A���ꂪ�������āA���X�ɍ����̊�@���̌��ނɂȂ���A��3�g�ȍ~�̊����Ґ��⎀�S�Ґ�����1�`2�g���傫���Ȃ�������A����ɑ�5�g�̊��������ɂ܂Ŕ��������Ă���Ƃ�������̂ł���B
�Ȃ��A���Ăł��A���{�قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���N�`���ڎ킪�i�ނɂ�Ċ����Ґ��͍Ăё傫���������Ă���_�ɂ͒��ӂ��K�v�ł���B���N�`���ڎ�́A�����\�h���ʂ�d�lj��\�h���ʂ����邪�A�C�̂����ʂ������\�h���ʂ������Ċ����g��ɂނ��т��Ă���_�ɓ��{�����Ă��ꏏ�Ȃ̂ł���B
�ŋ߂̊����g��́A�Ȃ��A�č��ł̓s�[�N�ɒB�������ǂ����肩�ł͂Ȃ����A���B�ł͂ǂ����s�[�N���ނ����Ă���悤�ł���B���[���b�p�Ŋ����Ґ��̑��������ł��ƂȂ������R�Ƃ��ẮA�ċx�݂ɓ��������߂Ƃ��W�c�Ɖu���l������Ă�������Ƃ��_�c����Ă���悤���B
�����N�`���ڎ헦�̍������قǁA�����g��Ɍ������Ă���
���Ċe���ł́A6���ȍ~�A���N�`���ڎ�̐i�W�Ƃ��ꂪ����t�����ƌ����鎀�S���̒�x���ێ����āA�R���i��̍s���K���̊ɘa�ɑ������ŏ��o���Ă���B���S�����㏸���Ȃ��̂ɁA���{�Ƃ��ẮA���{�Ɣ�r���Ă����Ȃ�̃X�g���X�������ɗ^���Ă�������܂ł̍s���}����͈ێ����������Ȃ��Ă����̂����R���낤�B
����A���Ԃł̋C�̂��݂��ے��I�Ɏ������f���Ƃ��ẮA7����{�ɂ̓T�b�J�[���B�I�茠�ŃC���O�����h��\�̎��������邽�тɁA�}�X�N�Ȃ��̃T�|�[�^�[�炪�����h���̈ꕔ�̊X���ߐs���������{�ł����ꂽ�B
�����Ґ����}�����钆�A���Ґ��͔�r�I�Ⴍ���ڂ��Ă��邽�߁A���N�`���ڎ�̐i�W�����ʂ������Ă���Ɣ��f�����p���{��7��19���ɃC���O�����h�Ŏc���Ă����s���K�����قڂ��ׂēP�p�����B���̉p���{�̔��f�ɑ��A���E�e���̐��Ƃ��A���ʼnp��w���w�����Z�b�g�x�Ɂu�댯�Ŕ�ϗ��I�Ȏ����ɏ��o���Ă���v�Ɣᔻ���鏑�Ȃ��A�čl�𑣂����Ƃ���(�����V��2021.7.31)�B
�����ӎ����l���������{�̐���ɑ��Đ��Ƃ��ꌾ��悷��Ƃ����\�}�͂킪���ł�������ڂɂ��Ă�����̂��B
��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA����܂ł��Ȃ茵�����s���}���������ɋ����Ă�������́A���N�`���ڎ�̐i�W�Ǝ��S�Ґ��̒ጸ���Ĉێ����������Ȃ��Ă���̂�����ł��낤�B
���������_���͂����莦���f�[�^�Ƃ��āA�}�\2�ɂ́A�e���ɂ����郏�N�`���ڎ헦�Ɗ����Ґ��̍Ċg��̒��x�Ƃ̑��ւ��������}���f�����B
�}�\2����́A���N�`���ڎ킪�i��ł��鍑�قǑ傫�Ȋ����Ċg��Ɍ������Ă��邱�Ƃ����Ď���B���N�`���ڎ킪2���ȉ��Ƃ��܂�i��ł��Ȃ����V�A��E�N���C�i�̊����g���2�`4�{�̃��x���ɂƂǂ܂��Ă���̂ɑ��āA5���ȏ�̐ڎ헦�̃I�����_�A�p���ł�14�`18�{�̑傫�Ȋ����g�傪�N�����Ă���̂ł���B
���f���^�����u���������̐^�Ɛl�v�Ɏd���ďグ���̂͒N��
���̑��}�ɂ�������{�̈ʒu�Ƃ��ẮA�����ނˁA�E�オ��̋Ȑ��Ƃ����X������ɂ���A�{����5�{�Ƃ���قǑ傫���Ȃ����̂́A���́A�����������傫�����܂��Ă��Ȃ���Ԃ���̍Ċg��ł��邽�߁A�����������ߋ��̔g�����ԂɎ����Ă���Ɨ����ł���̂ł���B
���Ă���{�̍ŋ߂̊����g��ɂ��ẮA�����͂̍����f���^���̐Z���ɂ��ƌ��Ȃ��̂��e���ł��ʗ�ƂȂ��Ă���悤�ł��邪�A���N�`���ڎ킪�i��ł���قNJ������傫���g�債�Ă���Ƃ�����������������m��ƁA�ނ���A�s���}���̉����ɂȂ��郏�N�`���ڎ킻�̂��̂��^�Ɛl���ƍl������Ȃ��B
�f���^�������������̐^�Ɛl�Ƃ���Ă���̂́A��ň����ɖ����ɂ��₷���_�̂ق��A�������s���}�����������ł��Ă��Ȃ��Ƃ����R���i��̕s�������ꂽ���Ȃ����߁A�����̐S���I�ȗv�������������Ȃ����{�̈ӌ����e�����Ă���ƌ���������Ȃ��B
����5�g�́A�S���̓s���{���ň�ĂɊ������}�g�債�Ă����
�Ō�ɁA������ς��āA�s���{���ʂ̊������ڂ̏���A�^����T���Ă݂悤�B
�}�\3�ł́A��ȓs���{���̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��̐��ڂ�ǂ����B
�}�\3�́A����܂ł�5�g�ɂ킽�銴���g�傪�e�s���{���łǂ̂悤�ɋN���������������Ă���Ă���B��5�g�̓����Ƃ��āA����܂ł̔g�ƈقȂ�_�́A��ĂɊ������g�債�Ă���_�ł���B
��3�g�ł͖k�C�����オ��s�������Ȃǎ�s���∤�m�Ȃǂ��ǂ��������B��4�g�ł͉�����オ��s���A�k�C���≫��(��)���ǂ������A�����Ȃǎ�s���͂���قǂ̊����g��ł͂Ȃ������B
��5�g�̓����́A��Ⓦ������s�������̂́A�قƂ�ǑS����ĂɊ����������N���Ă���_�ɂ���B
���R�Ƃ��čl������̂́A�ߋ��ƈقȂ��Ēn��I�Ȏ���ł͂Ȃ��S���I�Ȏ�������Ă��邩��ƌ���̂��Ó����낤�B�������Ƃ���ƑS������I�ɒn�悲�Ƃɑ傫�Ȓx���Ȃ��i�߂��Ă��郏�N�`���ڎ�ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��B
���J�Ȃ̐��Ɖ(2021.8.4)�ł͍��������nj������̐��v�ł͐V�K�����҂̂����f���^���Ɋ��������l����߂銄���́A8�����{�̎��_�ŁA�֓��Ŗ�90���A���Ŗ�60���ɒB�������Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B���̒n�捷�̓C���h������̗����������������ǂ����ɂ���Ă���Ƃ����(�����V��2021.8.5)�B
�������A�f���^���̂��������n�捷�͊����g��̎����I�ȓ������Ƃ͖�������B�֓��Ŋ����K�͂��������Ƃ͊m���Ȃ���A�f���^�����5�g���̂̎�ƂƂ��錩���͑ނ����悤�B
�����߂Ŏq���̒a���������������т̊������͒a�����̂Ȃ����т�1.6�{
���N�`���ڎ�ɂ��C�̂��݂��5�g�̐^�Ɛl�Ƃ��邱���ł̎咣�́A���܂�ɐS���I�v���ɏd����u�������������Ƃ̔ᔻ�����낤�B�������A�����ǂ̊g��ɂƂ��ĐS���I�ȉe���͔��ɑ傫���̂ł���B
2020�N1���`11���ɂ����Ă̕č�300�����т̃f�[�^�͂��������ɂ��ƁA����2�T�Ԃɒa�������}�����l�����鐢�тł́A�����łȂ����т��R���i�������X�N��1.3�{���������B�܂��A�q�ǂ����a�����̏ꍇ�͂���Ɋ������X�N��1.6�{�ɂȂ��Ă����Ƃ����B�a�����p�[�e�B���J�����ƁA���Ɏq�ǂ�������ꍇ�͂������Ƃ������Ƃ������������ʂɂȂ������ƌ�����B
���N�`���ڎ�̐i�W���������X�N��}����ȏ�ɁA�S���I�Ȍ��ʂŊ������X�N�𑝂����Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��̂ł���B
�������f���^�������g��͗}�����߂邩�H�@8/7
�����ł̓f���^���ɂ�銴�����싞��`����n�܂�192�����ɍL�����ċً}�Ή��ɒǂ��Ă���B�W�s�s�Z���̑S����PCR���������A���Ǐ�҂��u�����@�����Ă��邪�A�ʂ����ė}�����߂邩�A������l�@����B
�������œ˔@�f���^�������g��
7��10���A�]�h�ȓ싞�s�ɂ���싞�\����`�ɒ����������X�N������CA910�ւɃR���i����7�l������Ă������Ƃ��A��������̋�`�ł�PCR�����Ŕ��������B��q�݂͂ȔZ���ڐG�҂Ƃ݂Ȃ���Ċu������Ċu���{�݂ɑ��荞�܂ꂽ���A7��20���̒���I�ȋ�`�]�ƈ��S����PCR�������s�����Ƃ���A�@�����|��17�l���z���ł��邱�Ƃ��킩�����BCA910�֓��̐��|�́A�����̂悤�ɖh�앞�𒅂����|���������s�����̂��������A�ǂ����h�앞��E���Ƃ��ɒ��ӂ��s���͂��Ȃ������炵���BCA910�̏�q�̒��̊����҂������Ă����E�C���X���C���h�R���̃f���^���̋��͂Ȃ��̂ł��������Ƃ���`���A���|���Ɉڂ��Ă��܂����悤���B�����̐��|�������͍��ەւ̐��|�����łȂ������ւ̐��|�ɂ��g����Ă��鐴�|��Ђ̏]�ƈ������ŁA���܂��ɐ��|���̑����͓싞�s�ɏZ��ł��邽�߁A10���Ԃɂ킽���ĉƑ���m�l�E�F�l�ɂ��ڂ��Ă���A�f���^���̃R���i��������C�ɍL�����Ă������B
�������҂̓����ǐ�
7��20������8��1��24���܂ł̊������[�g���u�l������v�̓d�q�łł���u�l���ԁv�̃A�v�����ȉ��̂悤�ɕ`���Č��\���Ă���B���܂�ɒ����̂ł��̃y�[�W�Ɏ��܂��Ȃ����߁A4�������Ă��邱�Ƃ��������肢�����B
�@�@�@�}1�F�u�l���ԁv�̃A�v���Ɍ���싞�\����`���甭�������f���^�������҂̓���
����������������ƁA���̎��_�œ싞�s���ł�215�l�̊������m�F���ꂽ���A��`�𗘗p���������邢�͐ڐG�����҂��]�h�ȗg�B�ɂ��閃��������ɗV�тɍs���āA�����ŃN���X�^�[�����߂Ă���B���̓��̈�l(64�̏���)�͓싞�s����g�B�ɍs���Ă��邪�A���̍ہu�����v�Ȃǂ������Ă���QR�R�[�h���������g�̂ł͂Ȃ��F�l�̌��N�R�[�h����Ď��Q���Ă������߁A�R���i���������Ă��邱�Ƃ���������Ȃ������Ƃ����B�g�B�ɂ����郏�N�`���ڎ헦��18����59�܂ł�70���ȏ�ŁA60�Έȏ��40�������Ƃ����t�]���ۂ��N���Ă���B�����͊O���Ŋ����ɓ�������҂̕��������}�̂ƂȂ�\�����������Ƃ���A��҂����ɐڎ���n�߂�Ƃ������j���̗p���Ă��邩�炾�B����64�̏����͎��̓��N�`����ڎ킵�Ă��炸�A������҂͖����V�тȂǂʼnɂԂ�������҂������̂ŁA4�����ȏ゠��g�B�s�̖������͑S�Ĉꎞ�I���𖽂���ꂽ�B�싞�\����`����ɔJ�ȑ�A�ɔ�҂�����A�����������l�����ƊE��l��Ȑ��s�ȂǁA�����玟�ւƃf���^�����^��ōs���P�[�X������B
�������S�y17�̏Ȏs�Ɋg�債�A�S��PCR�������A���Ǐ�҂��u�����@
�������Č����_�ł�17�̏Ȏs�n��ɂ킽���Ċ������L����A�������{�͂����̒n��̑S�Ă̏Z���ɑ���PCR������O�ꂳ���A�z���Ɣ��肷��ΑS�����u�����@�����Ă���B���Ƃ��Γ싞�s�̏ꍇ�́A7��21���ɓ싞�s�s��930���l�S����PCR�������w�����Ď��s���A�B��Ă���z�����҂��i��o���Ă���B7��29���ɂ�3��ڂ�PCR�����ɓ������B���Q������������͓̉�ȓA�B�s�ł��S����PCR�������s���Ă���A���ƊE�����l���B8��6��15���ɂ�����R���i�����n�C���X�N�E�����X�N����192�����ɂȂ��Ă���B�����Z�t������Ȃ��n��Ɋւ��ẮA�S�������ÊW�҂�h�����A��C�Ɍ������I���悤�ȃV�X�e���œ����Ă���B�z���Ɣ��肳���Ζ��Ǐ�҂ł��u�����@�����A�Z���ڐG�҂͓���{�݂Ɋu������Ċm���ɉA�����m�F�����܂Ŋώ@�𑱂���B���̃��[���́A2020�N2���ɒ����H���@�̉@�m�œ`���a�̐��Ƃł���ߓ�R�́u���Ǐ�҂��A���ˑR�d�lj����邩������Ȃ��̂ŁA�K����t������u���a���ɓ��@�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ȃǂ̐i���Ɋ�Â��ċK�肳��A���̌���P���d�˂Ȃ������Ă���B
�������̃R���i���{���[��
�����̃R���i��́A�����_�ł͊�{�I��2021�N5��14���ɉ������ꂽ�w�V�^����a�Ŕx���h�T����(�R���i�E�C���X�x���h�����) �攪�Łx�Ɋ�Â��ĉ^�c����Ă���B�����������@�����⑷�t�����������n�ߍ��Ɖq�����N�ψ�����S�ƂȂ�A���ׂĂ̒����s���Ȓ��̑�\����\�������u�����@�R���i�E�C���X�x���u������h�u�@�\�����g�v�������I���Ɋ�Â��Ē���I�ɏ������������z���Ă����B
�����͈ȉ��̓�B
���S����PCR������O�ꂳ���邱�ƁB
�����Ǐ�҂�y�ǎ҂����łȂ��A�Z���ڐG�҂��܂߂āA�S�Ċu�����Ĉ�Ë@�ւɈڑ����ώ@��O�ꂳ���邱�ƁB
���{�̂悤��PCR�������ł��邾�������A�����ґS������Ë@�ւɊu�����@����������×{���d������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͐�ɂ��Ȃ��B���{�̂����́A�Ђ�����R���i�����g��Ɋ�^���邾���ŁA�����̃R���i�����猩��Ɓu���{�̊����g��͐�Ɏ��܂�Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ邩������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��R���i�����ȉ��(���g)����m�炳��Ă��Ȃ������悤�ȃR���i���A�����̑ł����킹�ɂ���Ē�����ߓI�ɁA�s�������������ŏo�����悤�ȃV�X�e���Ƃ͈Ⴄ�B�Z���ڐG�҂����ׂďE���グ�Ċu���ώ@����Ƃ����O��Ԃ肾�B������14���l���̐l��������Ȃ���A�U���I�ɋN���邢�����̒n��ɂ����銴�������ȊO�́A���ϓI�ɂ͐V�K�����Ґ��͈ꌅ�����x�ɗ}���邱�Ƃ��ł��Ă����B
���Ȃ��싞�������̂��\�\�k����`�ɂ͒��������Ȃ����[��
��N3��19�����璆���ł͊C�O���璼�ږk����`�ɒ������邱�Ƃ��֎~���Ă���A3��20���́u���X�N���]�k���v�̃t���C�gCA910�͖k���ł͂Ȃ��V�Ë�`�ɒ�������悤�ɕύX����Ă����B7��4���ɂȂ�ƓV�ÈȊO�ɐΉƏ��A�c�z�A���B�A�A�B�A�싞�E�E�E�Ȃǂ��������n�Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�B���ʂ����X�N�����k�����̂͂��̃t���C�gCA910�́A�V�Â�ΉƏ��A�c�z�ȂǁA�k���ɋ߂���`�ɒ����̑Őf���������A�ǂ������ꂸ���ۂ��ꂽ�̂ŁA�ŏI�I�ɗB�ꏳ�����Ă��ꂽ�싞�\����`�ɒ������邱�ƂɂȂ����킯���B
�������S�y�̐V�K�����Ґ���
8��6�����݂̒����S�y�ɂ�����V�K�����Ґ������Ɖq�����N�ψ���̃f�[�^����E���グ�ȉ��̂悤�ɃO���t�����Ă݂��B�����Ŕ������ꂽ�V�K�����Ґ��̒��ɂ́A�C�O��������ꂽ�t���C�g�̏�q�̒��ɂ���(��`���u�Ŕ������ꂽ)�z���Ґ��ƁA���������ɂ�����PCR�����Ŕ������ꂽ�z���Ґ��̗��������邪�A���L�Ɏ������l�́A��q�z���Ґ����������f�[�^�ł���B
�@�@�@�}2�F�����{�y�����ɂ�����V�K�����Ґ��̐���
6���ɏ��������Ă͂�����̂́A�܂��������ł��邱�Ƃ��킩��B�g�U���ǂ��܂ōs���̂��Ɋւ��ẮA���炭�ώ@���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ȉ��̂悤�Ȏ���͎Q�l�ɂȂ邾�낤�B
���L�B�̏ꍇ
6��2���̃R�����������L�B�Ŕ��������R���i�V�K�����҂ւ̑Ώ��Ɍ��钆���̎p�����ɏ������悤�ɁA5��21���Ƀf���^�������҂��������ꂽ��(24���Ƀf���^���Ɗm��)�A���̊����͍L�B�s�̋ߗׂŎ��܂�A6��18���ɍŌ�̊����҂��������ꂽ��A170�l�̊����ŗ}�����ނ��Ƃ��ł����B6��26���Ɉ��S�錾���o����A7��8���ɂ͍Ō�̊��҂��މ@�����B���̎��Ⴉ�猩����悤�ɁA���Ƃ��f���^���ł��A���n��Ɋg�U���Ă��Ȃ���Η}�����ނ��Ƃ��ł���Ƃ������͕������Ă���B
����p�̎���
��p�ō��N4�����ɒ��؍q��̃p�C���b�g���������Ă������Ƃ���n�܂��āA�u����Ƃ��Ďg���Ă����z�e���]�ƈ��Ɋ������A�s�������������Ƃ��������B���̂Ƃ���k�s�̞h���N�s�����A�ߓ�R����Ă������a�@���́u���y(�ق�����)�a�@�v�Ƃ����u�Վ���Î{�݁v�݉c���w�������B����ɂ���p�̃R���i�g����g�́A�ꂩ���Ԃقǂň�C�Ɏ������Ă���B�h���N�͂��Ƃ��Ƒ�p��w�̈�w�҂Ȃ̂ŁAPCR�������O�ꂳ���A���ɉȊw�I���B���g�ł̓f���^�������������Ă����̂ŁA�����������������i�Ƃ��Ă悢����ƂȂ邾�낤�B
���ʂ����Ď�������̂��H
8��5���ɊJ���ꂽ�L�҉�ŁA���Ɖq�����N�ψ���́A�싞�\����`���̃f���^�������g��Ɋւ��āu2�`3�̐������ԂŊ�{�I�Ɏ��������邱�Ƃ��ł���v�Ɣ������Ă���B�������Ԃ��ő�2�T�Ԃƌ��ς������ꍇ�A�T��4�`6�T�Ԍ�ɂ͎������Ă��邾�낤�Ɛ����������ƂɂȂ�B�ʂ����č���ǂ��Ȃ邩�\�\�B��p���嗤�{�y���A�uPCR�����̓O��v�Ɓu���Ǐ��҂��܂߂����ׂẴR���i�����҂̊u�����@�v����{�����Ƃ��Ċg�U��}�����Ă����B���̊�{�������Ɏ��Ȃ����{�̃R���i��́A�ʂ����Đ�������̂��ۂ��B���{���{���A���{�����̖����ŗD�悷�鐭��ɓ]�����邽�߂ɁA�������p�̎��Ⴊ�𗧂��Ƃ��肢�A�l�@�����݂��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�����������A�V����1��4472�l�@6���A����1���l���@�V�^�R���i�@8/8
�����ł�8���A�V����1��4472�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�B
1��������̊����Ґ���1���l������̂�6���A���ŁA�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ���Ԃ������Ă���B
�S���ŐV���Ɋm�F���ꂽ���҂�9�l�B�d�ǎ҂�1138�l�ŁA�O������70�l�������B
�����s�̐V�K�����҂�4066�l�ŁA�O�T�̓��j���Ɣ��1008�l���������B1��������̊����Ґ���5���A����4000�l�����B�s��ɂ��d�ǎ҂�151�l�őO������1�l�������B
���(299�l)�A���s(333�l)�A������(104�l)�̊e�{���ʼnߋ��ő����X�V�B���{�ł�1164�l�̗z�����������A6���A����1000�l�����B
�Q�n����8���A3�`5���Ɍ��\�����V�K�z���҂̂����v63�l�����ۂ͉A���������ƒ��������BPCR�������s�������Ԍ�����Ђ��A�A�����������̂�z���ƌ���Ĕ��肵�Ă����Ƃ����B�@
��������1��4472�l�����A6���A��1���l���c�����̒���1�T�ԕ���4000�l��@8/8
�����̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�8���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��4472�l�m�F���ꂽ�B1���l�ȏ��6���A���ŁA�����g�傪�����Ă���B���҂�9�l�A�d�ǎ҂͑O�����70�l������1138�l�ƂȂ����B
�����s�ł́A4066�l�̊������m�F�����B1��������̊����҂�4000�l����̂�5���A���B1�T�ԑO����1008�l�����A���j���Ƃ��ĉߋ��ő��ƂȂ����B����1�T�Ԃ̕��ϐV�K�����҂͑O�T(3105�l)����30������4037�l�ŁA���߂�4000�l��ƂȂ����B���@���҂�3517�l�ƂȂ�A2���A���ōő����X�V�����B�d�ǎ҂�1�l����151�l�������B
���A���s�A��������3�{���ŐV�K�����҂�����܂łōł����������B
�������ܗց@�R���i�g��̒��ŕ�c�����I��ƌ��g�ގp���Ȃ��@8/8
��32��ċG�I�����s�b�N��������8���A�����s�V�h��̍������Z��ŕ���s���A17���Ԃ̓������I�����B1964�N�ȗ�2�x�ڂ̓������͐V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ��j�㏉�߂�1�N��������A���̂���9�s�����̂���6�s�����Ŗ��ϋq�J�ÂƂȂ����B���Ԓ������̓��O�Ŋ����͎~�܂炸�A�����z���ɂ�������]�V�Ȃ������I��������B�J�Òn�̍����I���S�⍓���ő������������ύX���܂߁A�ܗւ̕��̑��ʂ��������ꂽ���ƂȂ����B
���������̎c��ߌ�8���ɕ�̓X�^�[�g�B����ɉԉ��ł��オ�������A�ϋq�͓����Ă��炸�A���W�҂�w�̔��肾�����܂�ɋ������B
205�̍��E�n�悲�Ƃɓ��ꂵ���J��ƈقȂ�A�S�I��c�̊��Ɗ��肪��Ăɓo��B���̌�A�I�肽���͎��R�ȏ��Ԃœ��ꂵ���B������܂��œ��ꂷ������́A1964�N�̑O�����̕�Œ蒅���A���a�̏ے��Ƃ��Ĉȍ~�̌ܗւɈ����p���ꂽ�B
��������́A�V�^�R���i��Ŏ��͂Ƃ́u�Љ�I�����v�����悤�ɌĂъ|�����Ă��邹�����A�����I��ƌ���g��ŕ����Ȃǂ̏�ʂ͏��Ȃ��A�����̑I�肽���ŋL�O�B�e������Ȃǂ��Ċy����ł����B
���Z�I����2����ɂ͑I�葺�𗣂�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����[��������A��̎Q���I��͖�4500�l�ŁA�ߋ������͏��Ȃ������Ƃ݂���B
����ł�����s�i��A���y��_���X���s��ꂽ�X�e�[�W�̎���őI�肪�u���v�ɁB������悤�ȏ����Ń}�X�N���O���I������Ȃ��Ȃ������B�}�X�N�̋`�����ȂǑI��̍s���K�́u�v���[�u�b�N�v����������̂̓O��͂ł����A�����ɂ��ꂵ�߂�ꂽ�����ے�����悤�Ȍ��i�������B
�R���i�ЂȂ�ł͂̎��g�݂��B�ܗ֊��͏��r�S���q�����s�m�����獑�ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�̃o�b�n��ɕԂ���A���̊J�Òn�p���̃C�_���S�s���Ɏ�n���ꂽ�B�ʏ�A��ł͎���J�Òn���Љ��X�e�[�W�����邪�A����̓p���̃G�b�t�F������m�[�g���_���吹���ƒ��p���Ȃ��ōs��ꂽ�B
��̂������ő��g�D�ψ���̋��{���q��̓{�����e�B�A���Ï]���҂Ɋ��ӂ�`������A�u�A�X���[�g�ƃX�|�[�c�̗͂ɂ���Ė����ւ̔����J���ꂽ�B�X�|�[�c�ɂ͐��E�Ɩ�����ς���͂�����B���̗͂��p�����ɂȂ���Ă����ƐM���Ă���v�Əq�ׂ��B
�o�b�n��́u�p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)���n�܂��Ă���S���E����ɂȂ����v�Ƒ������掩�^�����B
�����J�Âւ̘_���������܂����ٗ�̌ܗցB�Ō�ɑ��z�����`�[�t�ɂ������Α䂪�Ԃт�̂悤�ɊJ������Ԃ��猳�̋��̂ɖ߂�A���͏����Ă������B
���R���i�Ђ̓����I�����s�b�N�J�� �s���̎~�߂� �@8/8
�����E�ՊC���ɐ݂���ꂽ�����I�����s�b�N�̐��Α�̎��ӂł́A�V�^�R���i�E�C���X�̊������g�傷�钆�ŊJ���ꂽ���ɂ��āA���܂��܂Ȑ���������܂����B
���� �]����ɂ���u���̑勴�v�ɐ݂���ꂽ���Α�̐��́A8���̕�̓r���ŏ�����邱�ƂɂȂ��Ă��āA���n�ł̊ϗ��͊����g���h�����ߎ��l���Ăт������Ă��܂����B
�߂��ɏZ��30��̏����́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������ŊJ�Â��ꂽ���ɂ��āA�u�Ƃ�ꂽ�ƕ����Ă���̂ŁA���Ŋ������g�債���Ƃ͎v���܂���B�J�ÑO�͂�����₵�����̂�����܂������A�V�^�R���i�Œ���ł��钆�ŁA�e���r�ŃI�����s�b�N���ϐ�ł����̂͌��C�̍ޗ��ɂȂ����Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
����A20��̒j���́u���Ղ�ŕ����オ���Ă��܂��A�R���i�̊����҂������Ă��܂����Ƃ���͂���̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���A���l�X�̍s���ɉe�������Ɗ����Ă��܂����B
�܂�70��̏����́u�I��̊撣�������ƊJ�Âł��Ă悩�����Ǝv���܂��B����ŃI�����s�b�N�ɂ͐ŋ����g���Ă��āA����A���R���̕��S���������Ă���킯�ł�����A�����Ɍ����ƐS�z�ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�������I�����s�b�N��n�܂�@���_�A�ٗႸ���߂̑��ɖ��@8/8
��32��I�����s�b�N���Z�������(�����ܗ�)��8���A����������Z��(�����s�V�h��)�Ŗ��ϋq�Ŏn�܂����B�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ŏj�㏉��1�N�����ƂȂ�A�����s�ɋً}���Ԑ錾���o�đ唼�̉�ꂪ���ϋq�ƂȂ�ȂǁA�ٗႸ���߂̑������B
�I�肽�������Ђ�l��Ȃǂ̈Ⴂ���ċ��������A�F�ߍ����X�|�[�c�}���V�b�v����{���̊���ŁA�J�ÑO�̐��_�̋t���͂�����x�a�炢���B����A���Ԓ��ɐV�K�����҂��}�����A�ܗւƂ̊W���w�E�����ȂǁA���_������܂܂������B
���͕s�Q���̖k���N������205�̍��E�n��(���V�A�͌l���i�ł̎Q��)�Ɠ�I��c���킹�đI���1��1��l���Q���B���{�͎j��ő��̋����_��27���l�����A��14�A��17�����킹�������_����58���j��ő��������B�唼�̉��͖��ϋq�������B
���g�D�ψ���ɂ��ƁA7��1���ȍ~�̑I�����W�҂̐V�^�R���i�����̗z���҂�430�l�������B���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃g�[�}�X�E�o�b�n��␛�`�̎�͌ܗւƍ����̃R���i�����g��̊W��ے�B�o�b�n��͂��̓���IOC����Łu�ܗւ͓K�Ȏ����ɊJ�Â����Ǝ��M�������Č�����B�I�����������ӂ��Ă���v�Əq�ׂ��B��Â̐��Ƃ炩��́u�����̈ӎ��ɊԐړI�ȉe����^�����v�Ƃ̎w�E���o�Ă���B
�����p�������s�b�N��24���ɊJ������B�ϋq�̈����͐��{�A�����s�A�g�D�ρA���ۃp�������s�b�N�ψ���(IPC)�AIOC��5�ҋ��c�Ō��߂�B�W�҂̊Ԃɂ́A�L�ϋq�͓���Ƃ̌������L�����Ă���B
���N���22�N2���ɂ͖k���œ~�G�ܗւ��J�Â����B����̉ċG�ܗւ�24�N�Ƀp���A���X���28�N�Ƀ��T���[���X(�č�)�ŊJ�Â����B
���I�����s�b�N �V�^�R���i ���f�B�A�W�҂ȂǐV����26�l���� �@8/8
�����I�����s�b�N�̂��ߊC�O���痈���������f�B�A�W�҂ȂǍ��킹��26�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ�������܂����B���17���ڂ�8���A���g�D�ψ���͍��킹��26�l���V�^�R���i�E�C���X�̌����ŗz���������������Ɣ��\���A�������m�F����܂����B���̂����A�C�O���痈�������l�̓��f�B�A�W�҂�5�l�A���W�҂�1�l�A�ϑ��Ǝ҂�1�l�̍��킹��7�l�ł����B�C�O�̃��f�B�A�W��5�l�͂������������14���Ԃ̊u�����Ԃ��o�����ƂŁA����܂ł̗v�ł͍��킹��25�l�ɂȂ�܂����B�܂��A���{�ݏZ�̐l�́A�g�D�ψ���̐E����1�l�A�{�����e�B�A��3�l�A�ϑ��Ǝ҂�15�l�̍��킹��19�l�ł����B�I���I�葺�̒��ł̊����҂͂��܂���ł����B����ŃI�����s�b�N�Ɋ֘A���������҂̗v�͍����ƊC�O���킹��430�l�ƂȂ�܂����B
���ܗփR���i�����g��ɉe�����c�o�b�n��u�����I�ȗ��t���Ȃ��v��R �@8/8
�����ܗւ́A���Ԓ��Ɋ����҂��}�������V�^�R���i�E�C���X��A�������l���������Z�����̋}�ȕύX�ȂǁA�Ō�܂őΉ��ɒǂ�ꂽ�B���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�Ƒ��g�D�ψ���͈�l�ɐ������������邪�A�^���s���͎c�����B
�u�V�^�R���i��͌��ʓI�ŁA���܂��������v�B����2����ɍT����6���A�ꑫ��ɑ�������L�҉�ɗՂh�n�b�̃o�b�n��͋������B�g�D�ςɂ��ƁA7��1���`8��7���Ɍܗ֊W�҂Ŋm�F���ꂽ�����҂͌v404�l�B�I���f�B�A�Ȃǂ�ΏۂɎ��{���Ă���o�b�q�����̗z������0�E02���ɂƂǂ܂�B�����p���E���J�Ó�����7���̋L�҉�Łu�z�����̒Ⴓ�́A���S�ȋ�Ԃ��m�ۂ��ꂽ1�̃G�r�f���X���v�ƕ]���B�u�j��ł�����ȑ��v�ƐU��Ԃ�u�X�P�W���[���ʂ�ɍs�����Ƃ��ł����̂́A�^�c�����������؍����Ǝv���v�Əq�ׂ��B
����A���J�Âɂ��S���̊����g��ւ̊ԐړI�ȉe���͕s�������A�����̐��Ƃ���́A�����h�~�̌Ăъ|���ƌܗւ̂��Ղ胀�[�h���u�����������b�Z�[�W�ƂȂ�A�l�X�Ɋ�@�����`���Ȃ��v���ɂȂ��Ă���v�Ƃ̎w�E������B�h�n�b��g�D�ς͂����������ɔے�I���B�o�b�n���́u�ܗւ��ԐړI�Ɋ����g��ɉe�������Ƃ����咣�ɂ́A�����I�ȗ��t�����Ȃ��v�ƈ�R�B�h�n�b�ɃR���i�����������Ɨ����ƃp�l���̃u���C�A���E�}�N���X�L�[���m���ܗւŐl�X�̋C�������ɂƂ����u�Ȋw�I�ȍ����͂Ȃ��v�Ƌ��������B
�����h�~�̂��߁A�C�O����̑��W�҂͍s�����������������ꂽ���A���������ڗ������B�g�D�ς�7�����_�ŁA8�l�̎Q�����i��剝�D�����ق��A�ꎞ���͒�~��8�l�A���d���ӂ�16�l�ɏ��ƌ��\�����B剝�D�̂���2�l�́A�ό��ړI�őI�葺���o���W���[�W�A�̑I��B�����A6�������ɂ��I�[�X�g�����A�̑I�肪�r�[�����ɏo�|�������A�h�n�b�́u�I�[�X�g�����A�I�����s�b�N�ψ���v���ɑΉ������v�Ƃ���̂݁B���ہA�s���̔ɉ؊X�ł͑��W�҂̎p�������ڌ�����Ă���A���[���^�p�ɕs���������c��B
�R���i�Ђ̑O�́u�ő�̃��X�N�ۑ�v������������́A���O���ȑO����o�Ă����ɂ�������炸�A�y�d��ł̕ύX�����������B7�������̃}���\�����q������1���ԌJ��グ�����܂����̂͑O����B6���̏��q�T�b�J�[�����͓��������ɕύX����A���̉e���œ��{�����L�V�R�Ƒΐ킵���j�q�T�b�J�[3�ʌ������O�|���ɂȂ����B�̒�������I��ւ̕��S�͑傫���A���O�̕ύX�́u�������肦�Ȃ��v(�T�b�J�[�̋v�ی��p�I��)�Ƃ̋ꌾ���R�ꂽ�B����ɑ��A�������́u�Ō�̍Ō�܂Ńt���L�V�u���ɑΉ����Ă����v�Ƌ������锼�ʁA�����Ƒ������߂��Ȃ������̂��Ƃ������ɂ́u�I��̗���ł��������������߂��Ȃ������̂��A�Ƃ����̂͂���B�^���ɍ���̑��^�c�ōl���Ă����Ȃ���v�Ɣ��Ȃ̕ق����ɂ����B
���R���i�����}���A�����ɑŌ��@���A��@���`�����ꂸ�@�ܗ֕��@8/8
8�����̓����ܗցB
�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾���ŁA���`�̎͋��Z�̂قڑS�Ăϋq�Ƃ���Ȃǁu���S�E���S�̑��v������ڎw�������A�����͔����I�Ȋ����}�����~�܂�Ȃ��B�����Ɋ�@����`������Ȃ��܂܁A��Õ���Ȃǂ̎��Ԃ������A�����ւ̑Ō��͔������Ȃ��B
�u����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g�傪�i��ł���v�B��5���A���{�̐V�^�R���i���{���ł����i�����B���̈���ŁA�͂��̓����܂߂ĘA���̂悤�ɁA���{�I��̋����_���l�����c�C�b�^�[�ŏj���B�����}������́u�͂��Ⴂ�ł���悤�Ɍ�����v(����)�Ƃ̕s�����R���B
�R���i�Ђ̌ܗ֊J�ÂɁA�����̎����͌������B��6���̋L�҉�Łu�ܗւ������g��ɂȂ����Ă���Ƃ����l�����͂��Ă��Ȃ��v�Ɖe����ے肵�����A���{�ɂ��A�Ȃ̎��l�A���H�X�̎��~�Ȃǂ̌Ăъ|�����A�������ɂ����Ȃ��Ă���͖̂��炩���B���{���ȉ�̔��g�Ή���u�ܗւ����Ƃ������Ƃ��l�X�̈ӎ��ɗ^�����e���͂���̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E�����B
���A�����͂̋����f���^���̖҈Ђ͑S���ɔg�y���A�z���҂͗v��100���l��˔j�B�ً͋}���Ԑ錾�̊g��E�����ɒǂ����܂ꂽ�B���{�W�҂́u�����͊�Ȃ����B���̂܂܍s���Ώd�ǎ҂⎀�҂�������v�ƌx����炵�A�ꕔ�̐��Ƃ͑S���ւ̐錾���߂����߂�B
�ܗւ̏j�Ճ��[�h�𐭌����g�ɂȂ��A�O�@�I�⎩���}���ّI������\�B����Ȏ̖ڎZ�͊����g��ŋ������B�����t�̎x�����͉ߋ��Œᐅ���ɗ������݁A�D�]���钛���͌����Ȃ��B
���̊ԁA�d�ǎ҂�ȊO�͎���×{����{�Ƃ��鐭�{�̐V���j�́A�^�}�̔������āu�����ǂ��������@�v�Ɛ����̏C���ɒǂ����܂ꂽ�B����D�ƈʒu�t���郏�N�`���ڎ���A�s�s���Ȃǂł͗\���Â炢�������B
�������Ōܗ֊J�Â̕]���͒�܂�Ȃ��B�u���E���̃A�X���[�g���撣���Ă���̂����āA���Ă悩�����v(�͖쑾�Y�K�����v�S����)�Ƃ̐����������A�����}�����́u�ܗւ�����オ��قǁA�w�Ȃ����N�`���ڎ킪�i�܂Ȃ��̂��x�Ƃ����ᔻ�ɂȂ�v�ƌ��O���B���Ȃ��B
��}�́u�ܗւ𐭎����p���悤�Ƃ����l�����������v(��������}����)�ƑΌ��p�������߂�B
24���ɂ͓����p�������s�b�N���n�܂�B���@�����́u�W�X�Ƃ�邾�����v�ƒ��~�_��ے�B���{�͋߂��A���g�D�ψ���Ⓦ���s�ȂǂƂ�5�ҋ��c���J���A�ϋq�̈��������߂邪�A31���������ً̋}���Ԑ錾�͍ĉ����̉\������荹������Ă���A�ܗ֓��l�ɖ��ϋq�ƂȂ���Z���傫���B�@
���D�y�s ������195�l �f���^���^��67�l ���@"�ȊO"�̊��� 1500�l�����@8/8
�D�y�s��8��8���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂�195�l(�����ėz��1�l)�m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
�����҂͔���\�܂�10�ォ��80���195�l(�����ėz��1�l)�B200�l�������܂������A�O�̏T�̓��j�������1.2�{�ɑ������܂����B
�����͂������Ƃ����C���h�^�ψكE�C���X�E�f���^���́u�����^���v��67�l�m�F����܂����B
�D�y�s���ł̃f���^���^���́A�v1164�l(����18�l�m��)�ł��B
1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A�u69.75�l�v�Ɓu�ً}���Ԑ錾�v�̖ڈ��ƂȂ�u25�l�v��19���A���ŏ���A�������Ă��܂��B
�g�p�a������8��7�����_�ł����ɑΉ��ł���557����234���Ŗ�42���A�a�@�ȊO�̏h���×{�{�݂⎩��ҋ@�҂�6�����_�Ōv1520�l��1500�l���A7���A����1000�l���܂����B
����܂ł̃N���X�^�[���g�債�Ă��܂��B�X�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�A������"��̊X"�֘A�͐V����1�X�܂�8�l�m�F����A319�X��1226�l�ƂȂ�܂����B
195�l���A����91�l�̊����o�H���s���ŁA�d�ǎ҂͑O���ƕς�炸8�l�ł��B
���{�́u�ً}���Ԑ錾�v�𓌋��s�A���ꌧ���������������ŁA��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{��lj��A�k�C���A�ΐ쌧�A���s�{�A���Ɍ��A�������Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v��2������K�p���܂����B���Ԃ�31���܂łł��B����Ɉ��∤�m���Ȃ�8����lj����邱�Ƃ����߂܂����B
�k�C����2������D�y�s���܂h�~�[�u�̋��Ƃ��A���H�X�ł́u��ނ̒��I�����l�v�v�������A���Z�v����1���ԌJ��グ�ߌ�8���܂łƂ��܂��B
�O�o���l�A�������l�v���ɉ����A�����{�݂̌����x�ق��p�����܂��B
�D�y�s�͎s�c�n���S�Ǝs�d�̏I�d���20������30���J��グ����5������J�n�B�����w�Z�Ȃǂł̏C�w���s��9���ȍ~�ւ̉�����v���B�����{�݂͎s���̌��N�ێ���q�ǂ��̌��S�Ȑ������i�̊ϓ_������ɕK�v�Ȏ{�݂������A�����x�قƂ��܂��B
���V�^�R���i�V����28�l����m�F�@6���A����20�l�����@�N���X�^�[�g����@�R�`�@8/8
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�R�`����8���V����28�l�̊����\�B�����҂�20�l���锭�\��6���A���B
�R�`����8���ߑO11���ɔ��\�������e�ɂ��ƁA�V���Ȋ����m�F�͎R�`�s��15�l�A���͍]�s��4�l�A���R�s��3�l�A�V���s��2�l�A�����s�A���ԑ�s�A�R�Ӓ��A�߉��s��1�l�̒j�����킹��28�l�B28�l�̂���26�l��50��ȉ��B
�R�`�s��15�l�̂���30�ォ��40��̒j��4�l�́A�N���X�^�[�����������R�`�s�́u�\�j�[�����ی�������ЎR�`�x�Ёv�̊֘A�B
20�l���銴�����\��6���A���ŁA�v�̊����҂�2359�l�B���@����69�l�A�����d�ǂ�2�l�B�V���ɔ��\���ꂽ���҂͂��Ȃ��B�h���×{��48�l�A�ݑ�×{��73�l�B���@�Ȃǂ̒�������51�l�B
�a����L���͐V���s�̌����V���a�@���ł�����66�A7���A�����Ō��������a�@��40�A4���A���S�̂ł�29�D1���ƂȂ��Ă���B
����A�R�`�s�͊����͂������u�f���^�^�v�̋^���̂���u�k452�q�v�ψق̂��錟�̂��V����1���m�F���ꂽ�Ɣ��\�B���̌��͎̂R�`�s�ō�����{�ɔ��ǂ��������҂̂��́B�R�`�����Łu�k452�q�v�ψق��m�F���ꂽ�̂͂�����܂�79���ŁA���̂���14�����u�f���^���v�Ɗm�F����Ă���B
���V�^�R���i �����s4���A��4��l�� ����×{��1�l���S�@8/8
�����s���ł́A7���A����܂ł�2�Ԗڂɑ���4566�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����A4���A����4000�l���܂����B�܂��A50��̏���������×{���ɗe�̂��}�ς��āA�������ꂽ�a�@�ŖS���Ȃ�܂����B����̑�5�g�Ŏ���×{���Ɏ��S�����l��s���c�������̂͏��߂Ăł��B
�����s�́A7���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�̒j�����킹��4566�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B
����܂ł�2�Ԗڂɑ����A����̊����m�F��4000�l����̂�4���A���ł��B
1�T�ԑO�̓y�j�����508�l�����܂����B
7���܂ł�7���ԕ��ς�3893.0�l�ŁA�O�̏T��133.3���ƂȂ芴���̋}�g�傪�����Ă��܂��B
7����4566�l�̔N��ʂ́A10�Ζ�����208�l�A10�オ418�l�A20�オ1467�l�A30�オ982�l�A40�オ675�l�A50�オ543�l�A60�オ161�l�A70�オ63�l�A80�オ39�l�A90�オ9�l�A100�Έȏオ1�l�ł��B
�����o�H���킩���Ă���1673�l�̓���́A�u�ƒ���v���ł�����1065�l�A�u�E����v��244�l�A�u�{�ݓ��v��81�l�A�u��H�v��56�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�����I�����s�b�N�֘A�ł�7�l�̊������m�F����܂����B����́A�O���l�����Z�W��1�l�A���f�B�A�W��1�l�ŁA���{�l���g�D�ψ����2�l�A�ϑ��Ǝ�2�l�A�{�����e�B�A1�l�ł��B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A24��5219�l�ƂȂ�܂����B
����A7�����_�œ��@���Ă���l��3485�l�ɂȂ�܂����B
6�����102�l�����A���Ƃ�1��12����3427�l���ĉߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��58.4���ł��B
�܂��A�s�̊�ŏW�v����7�����_�̏d�ǂ̊��҂�6�����9�l�����āA150�l�ł����B
150�l�ȏ�ƂȂ�̂͂��Ƃ�1��28���ȗ��ŁA�d�NJ��җp�̕a����38.3�����g�p���Ă��܂��B
�s���̏d�NJ��҂͑����X���������Ă��āA����1����100�l�������ƁA1�T�Ԃ������Ȃ�������50�l�߂������܂����B
�ł������������Ƃ�1��20����160�l�ɔ����Ă��܂��B
�s�̒S���҂́u�����҂���3�g�̃s�[�N�̔{�߂��ɂȂ��Ă��āA����ɔ����ē��@���҂Əd�NJ��҂������Ă���B�����҂̑�������A�����x��đ�����̂ŁA����A����ɑ�����\���������v�Ƙb���Ă��܂��B
���̂����ŁA�u�w��Ñ̐��̂Ђ������n�܂��Ă���x�Ɛ��Ƃ��w�E���Ă���B�����҂������ł����炷���Ƃ����@���҂Əd�NJ��҂����炷���ƂɂȂ���B�A�x�₨�~�x�݂��X�e�C�z�[�����Ă��������A��H�ȂNJ������X�N������s�����T���Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B
���̂ق��A���̂Ƃ��둝�������Ă��鎩��ŗ×{���Ă���l�́A6����肳���408�l������1��8444�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����X�V���܂����B
�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ50��̏���2�l��60��̏���1�l�A�����70��̒j��1�l�̂��킹��4�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
���̂���50��̏���1�l�́A����2���ɗz�����킩��A����×{�����Ă����Ƃ������Ƃł��B
����×{���n�߂�4���ڂ̍���5���ɂȂ��ėe�̂��}�ς��āA�������ꂽ�a�@�ŖS���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
����̑�5�g�Ŏ���×{���Ɏ��S�����l��s���c�������̂͏��߂ĂŁA�s�̒S���҂́u���ꂾ������×{�҂�������Ƒ̒����}�ς���l�̃t�H���[�A�b�v���d�v�ɂȂ�B�t�H���[�A�b�v�̐��̊g�[���͂���K�v������v�Ƙb���Ă��܂��B
����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2310�l�ɂȂ�܂����B
��8���̐��s�@410�l�����A�N���X�^�[�g�告�����@8/8
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�����A���s��8���A10�Ζ����`90��̒j��410�l�̊������V���Ɋm�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�d��1�l�A������5�l�A�y��380�l�A���Ǐ�24�l�B260�l�̊����o�H���s���Ƃ����B�s���\�̊����҂́A�v2��2240�l�ƂȂ����B
�N��ʂł�20�オ109�l�ōő��B30���40�オ�e77�l�A50��61�l�A10��34�l�A10�Ζ���27�l�A60��15�l�A90��4�l�A70���80�オ�e3�l�������B
���Z�n�ʂł͐��悪110�l�A�{�O�悪50�l�A�����悪42�l�A�����悪40�l�A���Ë悪37�l�A�K�悪27�l�A�����悪23�l�A���l�s��48�l�A�s����15�l�A����s��7�l�A���P��s��3�l�A���͌��s�E���{��s�E���ˎs�E���q�s�E���؎s�E��a�s�E�ɐ����s�E���������e1�l�B
���s�ɂ��ƁA�N���X�^�[(�����ҏW�c)�֘A�ł́A�E���Ɨ��p�҂̌v10�l���������Ă����K��̃f�C�T�[�r�X�{�݂ŁA�V���ɐE��1�l���z���ƂȂ����B������̗L���V�l�z�[���ł����p��2�l�ƐE��1�l�̗z�����������A�����Ґ��͌v9�l�ƂȂ����B
�����o�H���������Ă���150�l�̂����ƒ��������99�l�A�z���҂̐ڐG�҂�51�l�������B
���v236�l�����@7���̐É������A2���A���ōő��X�V�@�A�x���̊g�匜�O�@8/8
�É�������7���A�V����236�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�B200�l����̂�2���A���ŁA6����224�l������ߋ��ő��ƂȂ����B����7�����{��4�A�x���Ɋ������L�܂����Ƃ݂āA7�������3�A�x�ɂ�銴���g������O�B�u��l��l�̍s�����܂h�~���d�_�[�u�̉����ɂȂ���\��������B�s�v�s�}�̊O�o�͍T���Ăق����v�Ɖ��߂đ�̓O������߂��B
���Îs�ł�7���܂łɁA�V���ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)�����������B�N���X�^�[�͎��Ə��ŁA�]�ƈ��v6�l�̗z�������������B���Z�n�ʂ̊����Ґ��͏��Îs29�l�A�ĒÎs16�l�A�֓c�s13�l�ȂǁB
�É��s�͐V����43�l�̊������m�F�����B����2�l�͎s�L��ۂ̏����E���B���s�̒���1�T�Ԃ̐l��10���l�����芴���Ґ���27�E78�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����������N1��14����26�E91�l���������B
�l���s��56�l�̐V�K�����҂����\�B1���̊����Ґ��Ƃ��čő��ƂȂ����B���̂���8�l�́A�s���̊w�K�m�N���X�^�[�֘A�������B
�����̗v�����Ґ���1��2051�l(�ėz���҂��܂�1��2052�l)�ƂȂ����B
�����������s��Ŕ����̃N���X�^�[�g��c�V�^�R���i �ΐ쌧�@8/8
�ΐ쌧�ł͐V����55�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������܂����B
�ΐ쌧��8���ߑO10���܂ł�422���̌������s���A���̂���55�l�̊������m�F���܂����B����͊����o�H��������Ȃ��l��23�l�A�Z���ڐG�҂Ȃǂ�26�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�N���X�^�[�֘A�͋���s���������s��W��2�l�A�q�ǂ����ʂ������{�݊W��4�l�ł��B�����҂͗v��5732�l�ƂȂ�܂����B
���܂h�~���d�_�[�u ���傤����g�� �s�v�s�}�̊O�o���l�� �@8/8
�V�^�R���i�E�C���X��ŁA�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�n�悪�A8������g�傳��܂����B���{�́A�S���K�͂̊����g���}���邽�߁A���_�ƂȂ�n��ł̑����������ƂƂ��ɁA���������A�s�v�s�}�̊O�o���l�Ȃǂ�S�苭���Ăт�������j�ł��B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A8������A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�n��ɁA�����A���A�ȖA�Q�n�A�É��A���m�A����A�F�{��8�����lj�����A�d�_�[�u�̓K�p�n���13�̓��{���Ɋg�傳��܂����B
�܂��A��s����1�s3���Ƒ��{�A���ꌧ�ɂً͋}���Ԑ錾���o����Ă��āA���Ԃ́A�錾�Əd�_�[�u�̂����������31���܂łƂȂ��Ă��܂��B
�����������A�����ł́A7���A����܂ł�2�Ԗڂɑ���4500�l���܂�̊������m�F�����ȂǁA�V���Ȋ����҂́A�S����1��5000�l���A1���̔��\�Ƃ��Ă�4���A���ōł������Ȃ�܂����B
���{�́A�S���K�͂̊����g���}���邽�߁A�錾��d�_�[�u�ɂ��A���_�ƂȂ�n��ł̑���������邱�Ƃɂ��Ă���A���H�X�̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k��A���̒�~�Ȃǂ�O�ꂷ��ƂƂ��ɁA��Ò̐��̊m�ۂ�i�߂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
����ɁA�l�̗�����\�Ȃ�����}������K�v������Ƃ��āA���������A�s�v�s�}�̊O�o���l��A���~�̎����̋A�Ȃ◷�s���ɗ͍T���邱�ƂȂǂ�S�苭���Ăт�������j�ł��B
���y�Ϙ_��]�A����Ɂ@�f���^���҈Ђ��l�o���炸�@8/8
�����s���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�5����5000�l��˔j���A��ÕN��(�Ђ��ς�)�͐[�����𑝂��Ă���B
�s�͏Ǐ�̌y���l�̑މ@�𑣂��a���m�ۍ�����������A���̑Ή��������B�f���^���̊g��ɉ����A�l�o���\���}����Ă��炸�A���Ƃ͐V�K�����҂�18����1���l���ɂȂ�Ɨ\���B�u���N�`�����ʁv�ɂ��y�Ϙ_�����]�A�����������˂��t�����Ă���B
�u���@���ׂ��l���ł��Ȃ���ԂɊׂ����v�B�s���̊����ǎw���Ë@�ւ̈�t�́A�a�������܂鋇���i�����B���@���҂�7������3485�l�Ŋm�ەa���̔������A���w�W�̃X�e�[�W4�ɁB�s��̏d�ǎ҂�7�����{��60�l�O��Ő��ڂ��Ă������A�킸��������150�l�ɑ����A�ߋ��ő���160�l(1��20��)�ɋ߂Â��B���̈�t�́u�f���^���̋��Ђ������s���Â����Ă����v�ƕ���B
�d�ǎ҂�6�����{��30�l��܂łɌ���A�s�����Ɠ��l�A����҂ւ̃��N�`���ڎ�̐��ʂƎ��M��[�߂��B���傤�ǂ��̎����A���r�S���q�m�����ߘJ�œ��@�B�u�m�����s������l�K�e�B�u�ȏ��͔������A�y�Ϙ_���L�������v(�s����)�B
���r����7��1���̕��A��A����҂ɑ���d�ǎ҂̒��S�ƂȂ���50��Ɂu�ϋɓI�ȃ��N�`���ڎ킪�K�v�v�Ƒi����悤�ɂȂ����B�s�����́u���ꎩ�̂͐��������A��҂��R���i��l���ƂƑ����Ă��܂����v�Ƙb���B���݂�30��ȉ��������҂�7�����߁A�d�lj�����o�Ă���B
�s���ɂ͓�12������ً}���Ԑ錾���o�Ă��邪�A��K�͏��Ǝ{�݂ւ̋x�Ɨv���ɂ͓��ݍ���ł��Ȃ��B�ƊE�̔����ɉ����A���͋��̍��̕⏕�����啝�ɉ����������߂��B�ɂ��[�u�ƃf���^���̑䓪�A�����������Ō}���������ܗցB���Ղ胀�[�h�Ƒ��܂��āA�錾�̌��ʂ͌���I�ƂȂ����B
�ܗ֕���͂��~���T����B���r���͍���6���̋L�҉�Łu���~�x�݂͐l�Ɛl�Ƃ̐ڐG�����I�Ɍ��炷�v�Ƌ������A�O�o��A�ȁA���s�̎��l�����߂ċ��߂��B�s�����́u���R�������Ă��炢�����v�Ƃ��Ȃ�����u��������ɂ�C�͂����ȒP�ɂ͖߂�Ȃ��v�ƌ������������������B�@
���A�ȃV�[�Y���Â��ȃX�^�[�g�@���ȂNJ����g��h�~�Ăъ|���@8/8
�V�^�R���i�E�C���X�̊����u��5�g�v���S���ɍL���钆�A���~�x�݂̋A�ȃV�[�Y�����}�����B�������z�����l�̗��ꂪ���������A����Ȃ銴���g�傪���O����邪�A3�A�x������7���A�V�������̓S���⍂�����͖ڗ��������G�͂Ȃ������B���Ȃǂ͂i�q�V���w�ȂǂŋA�ȋq�Ɍ����Ċ����h�~��̓O����Ăъ|�����B
�����͂̋����f���^�����҈Ђ��ӂ邤���Ȃ��̋A�ȃV�[�Y������B�����ł������҂����ɑ����V���s�ł́A���Ǝ��̓��ʌx���ߒ����B
�i�q�V���w�ł́A��N���l�ɐV�����̋�Ȃ��ڗ������B�i�q�����{�ɂ��ƁA7���ߌ�4�����݂̏�z�V���������Ԃ̎��R�ȏ�ԗ��͍ő�60���������B
�V�����z�[���ł́A�}�X�N�p�̉Ƒ��A��炪�傫�ȉו�������A�~�藧�����B1�N�Ԃ�ɋA�Ȃ��������s���s�A��Ј��j��(43)�́u���e��2��ڂ̃��N�`���ڎ���I�����̂ŁA�A�Ȃ���ƌ��߂��v�Ƙb���B�V���s�H�t��̎��ƂɌ����������s����A��w������(19)�͎��O�ɂo�b�q�������ċA���B�u�F�B�ɂ͋A��Ɠ`���Ă��Ȃ��B��������������Ȃ����ȂƎv���āv�Ǝ��Ƃł������߂����Ƃ����B
�V���w�ł͉��D���o�Ă����A�ȋq��Ɍ����Č��ƐV���s�̐E�����u�ӂ邳�ƐV���ɂ��z���̊F�l�ցv�ƋL�����{�[�h���f���A�u�s�v�s�}�̊O�o���T���Ă��������v�Ɗ����g��h�~�ւ̋��͂��Ăъ|�����B
�����s�̊։z���z�����T�[�r�X�G���A�ł��A���l�ɂ̂ڂ��p�l����ݒu�����B��������ԂʼnƑ����s�ɖK�ꂽ�^���ƒj��(35)�́u���������N���Z���ɂȂ�̂ŁA�Ƒ��̎v���o���͍��N���Ō�B�s�������邯�ǁA�\�h���Ȃ���y���݂����v�ƌ�����B
�����茧���ŃR���i������55�l�@�N���X�^�[�g��@8/8
7���A���茧���ł͐V����55�l�̐V�^�R���i�z���҂����\����܂����B����͒���s��16�l�A�����ێs��18�l�A���^����7�l�A���Ò���4�l�A�|���s�A�呺�s�A�����s�Ŋe2�l�A�_��s�A���C�s�A���ދn���A��I���Ŋe1�l�ł��B
����s�ł�6����5�l�̃N���X�^�[�����\���ꂽ���Y���Z��蕔�ŐV����13�l�̕����̊������������A�N���X�^�[��18�l�Ɋg�債�܂����B����s���㒬��JR��B�z�e�������7���A��������]�ƈ��Ńt�����g�X�^�b�t1�l�̊��������������Ɣ��\���܂����B�t�����g�X�^�b�t��5���̋Ζ��ォ��A�Ɉ�a���������A�x�݂�����6���̒��Ɍ��ӊ��A�[��37�D7���̔��M������A7����PCR�����ŗz�����������܂����B�t�����g�f�X�N�ɂ̓A�N������ݒu���A�}�X�N�𒅗p���ċƖ��ɓ������Ă������߁A�ی�������q��]�ƈ��ɔZ���ڐG�҂͂��Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B���������������t�����g�X�^�b�t���Ɩ��ɓ�����t�����g����⎖�����A���b�J�[�Ȃǂ͏��ł��ς܂��A�c�Ƃ��p�����Ă��܂��B
���ށE���^���̌�����w�V�[�{���g�Z�́A3������5���ɂ����Ċw��7�l�̊��������������Ɣ��\���܂����B�����҂͑S���A�ߋ�2�T�Ԃ̌��O�ړ��͂���܂���B
�������\�������^����7�l�̂���3�l�́A10��̒j�q�w����10���20��̏��q�w���ł��B
�����ێs�́A�ی��������ɋΖ�����40��̒j���E��2�l�̊����\���܂����B�E���́A4���̋Ζ��ォ�猑�ӊ��┭�M�̏Ǐ����A5���͎���ʼn߂����A6���Ɍ������z���������B����1�l�̒j���E���́A�����̐E���̔Z���ڐG�҂ŁA6���̋Ζ���A���M�̏Ǐ���A���̓��̌����ŗz�����������܂����B2�l�Ƃ��ߋ�2�T�Ԃ̌��O�ړ��͂���܂���B�����ێs�́A6���ɒ��ɂ̏��ł��ς܂����Ƃ������Ƃł��B
�܂��A�������Y���Ԓn��6���Ɋ������m�F���ꂽ20��̑����̓����ŔZ���ڐG�҂�����10���20��̒j������3�l�̊������V���ɔ������܂����B
6���ɔ��\���������ێs�̎��Ə��ł̃N���X�^�[�ŐV����50��̒j��1�l�̊������������A�N���X�^�[�͌v6�l�ɂȂ�܂����B
�_��s�Ŋ������m�F���ꂽ10��̒j�q�w���́A5���ɕ���������s���̎��ƂɋA�ȁB���̓��̖�ɔ��M���������z�����m�F����܂����B
����A6���ɒ��茧�������X�e�[�W��4�Ɉ����グ���~�O��ً̋}�v�����o�������Ƃ��āA����s�͎s�̊ό��{�݂�10������x�ق��܂��B�c�㒷��s���F�u���̎����ɐڐG���o���邾�����炷���Ƃ�����̊����̍L�����h���ő�̃|�C���g�ŁA�����ɂ킽�銴���̊g���h�����ƂɂȂ�v�B����s�́A8��7������23���܂ŁA�s�v�s�}�̌��O�Ƃ̉������l��O�o���l�A�Ƒ��ȊO�Ƃ̉�H�����l�����펖�ԍs���̓O����Ăт����܂����B�O���o�[����o���A�y���M�������قȂǁA���O����̗��p�҂������s�̊ό��{�݂Ȃ�35�{�݂�8��10������23���܂ŋx�ق��܂��B8��7������31���܂Ŏs��ẪC�x���g�͌����A���~�≄���A���ϋq����[�g�ł̊J�ÂƂ��܂��B
8��9���ɊJ����镽�a�F�O���T�ɂ��ẮA�\��ʂ���{���A������Ƃ��āA���҂����g�Ȃǂɂ́A�s���Ƃ̐ڐG������邽�ߐE�����A�e���h���A�z�e���ŐH�����Ƃ�悤�����g��h�~�̋��͂��ŋ��߂Ă��邢�����Ƃł��B�܂��A6���܂łɎs�����܂މ^�c�X�^�b�t��550�l�̍R���������I���A�S���u�A���v�������Ƃ������Ƃł��B
8��15���̐��여���ɂ��ẮA�ɗ͍T���Ăق����Ƃ�����ŁA�u�����v�⏬���߂̑D�𗬂��ȂǗ����肪�ڐG����@������炵�Ăق����ƌĂъ|���܂����B
���u���ĕ��݂̑嗬�s���v�R���i�����g�呱������ ��t�������������@8/8
6���A�����̗v�����Ґ���100���l�����B��s���ł�7���A�����̐V�K�����҂�4���A����4000�l���A����ɍ�ʂł�1449�l�A��t��1075�l�̊������m�F�A���̂ق����A���s�A�É��A�O�d�A�x�R�A�����A�������ł������҂���������ȂǑS���I�Ɋ������g�債�Ă���B
���ł��[���Ȃ̂����ꂾ�B1���A���ꌧ�̋ʏ�m���́u���ꌧ���Ŋm�F����銴���Ґ��̐l����͑S���Ń��[�X�g�B�C�O�����ł̓��b�N�_�E�������̃��x�����v�Əq�ׁA��@�����ɂ��܂��Ă����B�ʏ�m���̗J�����I�����邩�̂悤�ɁA����ł�8��4������4���A���ŐV�K������500�l�����B
5�����{�ɋً}���Ԑ錾�ɓ������܂܁A�܂h�~�[�u�ւ̈ڍs���Ȃ��A�����Ƌً}���Ԑ錾�������Ă��鉫��B�j���[�X�ԑg�wABEMA Prime�x�ɏo���������ꌧ�������a�@�����Ǔ��ȁE�n��P�A�ȕ������̍��R�`�_���́u����ł͉��ĕ��݂̑嗬�s�̏��v�Ƙb���B
�u�����̂Ƃ���A1��������̐V�K�z���Ґ���600�l�O��Ő��ڂ��Ă���B����͓����Ō����ƁA6000�l�ɊY������B�������A�܂����s�̐����ɐ����������Ȃ��B���s��}�����ގ{������Ă��Ȃ��B�܂��܂������邾�낤�v(���R���E�ȉ���)
�������͂��ߎ�s���ł́A40��A50��̏d�lj������[���ɂȂ��Ă��邪�A����ł͂ǂ̂悤�ȏȂ̂��낤���B
�u�������͂�40��A50��̃��N�`�����ڎ�҂̏d�lj��������Ǝv���B���̐���̗͑͂�����̂ŁA�����ɖS���Ȃ��Ă��܂����Ƃ͂Ȃ����A�d�lj����ċꂵ��ł��銳�҂������B���̐V�^�R���i�̃C���p�N�g�́A���S���ő���̂ł͂Ȃ��A�d�ǎ҂̐��Ō��Ă����K�v������Ǝv���B���̏�ŁA����́A���������[���ŃR���i���嗬�s���Ă���Ǝv���Ăق����v
2�J���ȏ���ً}���Ԑ錾�𑱂��Ă���̂ɁA�Ȃ������҂�����Ȃ��̂��낤���B���R���́u�ً}���Ԑ錾�́A�����悤�Ȍ��ʂ�������҂ł���킯�ł͂Ȃ��v�Ɠ�����B
�u�ً}���Ԑ錾���o��������͂�����x�����B�������A�o�����ςȂ��ɂ��Ă����A�ɂ�ł���͓̂��R���B�d���̂Ȃ����������邪�A�錾�ɂ�銴���҂̌����͊��҂ł��Ȃ��B�����܂Ŏ��l�ɋ��͂ł��郀�[�h���ǂ̂悤�ɍ���Ă����̂��B���{�̃R���i��̓��[�h�ł���Ă����B�����āA�����܂����[�h�ʼn��Ƃ����悤�Ƃ��Ă���B���ꎩ�̂���肾�B������l�ɋ��͂��������Ă���������邪�A�w�������͂ł��Ȃ���x�ƍl���Ă����҂����Ƀ��[�h�łȂ�Ƃ����悤�Ƃ��Ă��������v
���R���i�����҂����o���Ɂu���������p�[�e�B�[�v���J�����u���鎖��v�@8/8
�z�e���j���[�I�[�^�j�����E�߂̊ԁB�ő�2500�l���e�̉���ꂾ���A7��21�����߁A�����ɏW�܂����l�͂܂炾�����B
�u���R���m���܂���v�B���R���͎����}�ݓc�h�����̑�c�m���B�܂肱��͐��������p�[�e�B�[�ł���B
�u�ݓc�h�ł́A�����c���̔鏑6�����h���̃p�[�e�B�[��Ɏ��X�ƐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ������A�N���X�^�[���N�����Ă��܂����B����Ȏ��ɂǂ����āH�@�ƊJ�Â�s�������鐺���}���ł��オ��܂����v(�����}�W��)
���͎�ނ��f��B�����Ŗ{�����p�[�e�B�[�I����Ɏ�ނ�\�����ނƐ��R���̕v�l���������B
�u3���A6���Ɖ�����ɂȂ��Ă���A�{�����������������܂������A9���ɉ��������ꍇ�A�V�^�R���i�E�C���X�̊���������Ɋg�傷�郊�X�N������ƍl�����A�J�Âɓ��ݐ�܂����B�Q���l���͉��ł�35�l�A�����[�g�ł�170�l�ł��B�S�ʃ����[�g�ł̊J�Â��l�����̂ł����A�����̔M�S�Ȏx���҂̗v�]�ł��̌`���ŊJ�ÂƂȂ�܂����v
���I�����߂��A�������~�܂�Ȃ��̂Łu�������Ȃ��v�Ƃ�������̂悤���B�h���Ŋ��������������A�s���͂Ȃ������̂��B
�u��̊J�Âɓ�����A�ݓc�搶����́w�Ƃɂ����n���ɁA�s�̃C�x���g�J�Ê�Ɉᔽ���Ȃ��悤�Ɂx�Ƃ̌��t�����������܂����v(���R���v�l)
�v�l�́A�[�����琷�R�c���ƃ��N�`���ڎ�̗\�肪����ƌ����c�������Ă������B���N�`���ڎ��Ƀp�[�e�B�[���J�����ق����ǂ�������������Ȃ��B
���u�Ō�̂Ƃ�Łv�~�}��Â̌�����a���Ђ��� �����}�g��� �@8/8
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g��́A�~�}��Â̌���ɂ��e�����y�ڂ��Ă��܂��B�d�NJ��҂�����Ă���s���̕a�@�ł́A�V�^�R���i�ȊO�̊��҂ł��f�炴������Ȃ��P�[�X���o�Ă��āA��t�́u�R���i�͂������ȊO�̕a�C�₯�����v���Ɉ�Â����Ȃ��ɂȂ����B�ЂƎ��ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ăق����v�Ƒi���Ă��܂��B
���� ������̓��{��ȑ�w�t���a�@�́A�ً}���̍����d�NJ��҂ɑΉ�����3���~�}�̎w��a�@�ŁA�u�Ō�̂Ƃ�Łv�̖�����S���A�V�^�R���i�̊��҂�����Ă��܂����A�����̋}�g��ŕa���͂Ђ������Ă��܂��B
8�����߂�9���������R���i���җp�̏d�Ǖa����13���ɑ��₵�đΉ��ɓ������Ă��܂����A�����̏�Ԃ������Ă���Ƃ������Ƃł��B
6���́A�ߑO���ɏd�lj�����30��̃R���i���҂�ʂ̕a�@�������Ė����ƂȂ�܂������A���x�~���~�}�Z���^�[�̃z�b�g���C���ɂ́A���h����R���i���҂̎���v�������X�ɓ���A�~�}�オ����͓���Ɠ`���Ă��܂����B
����A��ʂ̏d�Ǖa�����R���i���҂ւ̑Ή��Ŕ����ȉ���21���Ɍ��炵�Ă��邽�߁A�R���i�ȊO�̊��҂̎����f�炴������Ȃ��P�[�X���o�Ă��āA���̓��͐S�؍[�ǂ̊��҂͎��ꂽ���̂́A���������N���������҂͎���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B
�Z���^�[�ɂ́A1���łӂ����6�{�ɓ�����31���̗v��������܂������A�����ꂽ�̂�8���ɂƂǂ܂����Ƃ������Ƃł��B
���{��ȑ�w�t���a�@���x�~���~�}�Z���^�[�̉��x���i�Z���^�[���́u����v��������قǗ���̂́A���܂łɂȂ����ƂŁA�s�[�N�������Ȃ�����X���X�Ƃ��Ă��܂��B��Ò̐�������ɐ����悤�Ƃ��Ă��܂����A�l�I�����ɂ������肪����܂��B�R���i�͂������ȊO�̕a�C�₯�����v���Ɉ�Â����Ȃ��ɂȂ����A�ЂƎ��ł͂Ȃ����Ƃ��F����ɒm���Ăق����B�����Ґ������炷���Ƃł������͉̏��P���܂���B�����̃��X�N�����炷���߂̍s�����Ƃ��Ăق����v�Ƒi���܂����B
���u�����_�����B���v�ă��f�B�A���c��������17����̔����ɋ^�╬�o�@8/8
�����s�ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��A4���A����4000�l����ȂNJ������}�g�債�Ă���B�C���h�R���̃f���^�����L�܂���邱�Ƃ���A���{��8��8���ɕ����A���A�ȖȂ�8�����u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑ΏۂƂ��Ēlj������B
����ȂȂ��A��āE�y���[��R���Ƃ���郉���_���̍����������m�F���ꂽ�̂��B�e���ɂ��ƁA�y���[�ɑ؍ݗ��̂���30�㏗����7��20���ɉH�c��`�ɓ������A���u�ŗz���������B���̌�A���������nj������̒����ɂ�胉���_���Ɗm�F���ꂽ�Ƃ����B
�u�����_���͍�N8���Ƀy���[�ŏ��߂Ċm�F����܂����BWHO�͕ψي����w���ڂ��ׂ��ψي��x(VOI)�Ɓw���O�����ψي��x(VOC)�ɕ��ނ��Ă��܂��B���N6���AWHO�̓����_�����w���ڂ��ׂ��ψي��x(VOI)�Ɏw��B�����ۂ����������nj�������7���ɔ��\�����ł́A�����Ń����_���̕��Ȃ��������Ƃ���VOI�AVOC�̂ǂ���ɂ��ʒu�t���܂���ł����v(�S�����L��)
�O���Ȃɂ��ΐ��ۑ�Ƃ��āA�y���[����̓����҂́u���u���̏h���{�݂ł�3���ԑҋ@(�ޏ���A������14���ڂ܂Ŏ���ҋ@)�v�Ǝw�肵�Ă���(8��2�����_)�B
�����͂̋�����N�`���̌����ڂȂǏڍׂ��킩���Ă��Ȃ������_�������A�������̊����m�F�������J���Ȃ����������̂�8��6���������Ƃ����̂��B���Ȃ������ɔ��\�������̂ł͂Ȃ��A�@�ւ̎�ނɂ���Ĕ����B�܂����������nj������ł̒������A�ǂꂭ�炢�̓�����v����������������Ă��Ȃ��B
�����ۂ��č��j���[�X�T�C�g�u�f�C���[�E�r�[�X�g�v��8��6���t�ŁA�s�����̓I�����s�b�N���O�ɖ��Ɋւ��V����COVID�̕ψي����B���t�Ƒ肵���L����z�M�B�����ɂ́A�s���������nj������̌����҂̓f�C���[�E�r�[�X�g�ɁA�����_���͋�`�̃`�F�b�N�Ŕ������ꂽ�ƌ�����t�ƕĂ���B
����Ɋ����ǐ���̍��ߌ��u����8��1���ɁuYahoo!�v�֊�e�����A�s�V�^�R���i ��ĂŊg�債�Ă��郉���_�^�ψكE�C���X �����_�ŕ������Ă��邱�Ƃ́H�t�Ƒ肵���L���ɂ͎��̂悤�ɂ��Ԃ��Ă���B
�s���{�����ł�2021�N7��31�����݁A�܂������_�^�ψكE�C���X�͂̕���܂���(���{�L���𓊍e��A���������nj��������GISAID�ɖ{�M1��ڂ̃����_�^�ψكE�C���X�������Ⴊ����܂���)�t
7��23���ɊJ�����A8��8���ɕ���}���������ܗցB�����_�����m�F���ꂽ30�㏗���̓������ܗ֑O���������Ƃ���A�l�b�g��ł́u�����B���Ă����̂ł́H�v���b���ސ����L�����Ă���B
�s7��20���H�@��H�@�Ȃ����̃^�C�~���O�Ō��\�H�H�@�Ȃ�ł���Ȃɒx���Ȃ����̂��ȁH�H�t
�s�I�����s�b�N���O�A���\�����A�B���H�t
�s���u�ň����������Đ��ۂŎ~�߂Ă邩����v��Ǝv�����ǁA���̎����ɂȂ��Č��\�����͉̂����I�����s�b�N�֘A�̈Ӑ}�I�ȕ���������t
���f���^�������ŕς�銴���o�H�@8/8
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����A�C���h�R���̃f���^���ւ̒u������肪�i�݁A�������{�̒i�K�ŗz����ɐ�߂銄���́A�֓��Ŗ�90���A���Ŗ�60���Ɛ��肳��Ă���B�]�����₻�̌�ɒu����������p���R���̃A���t�@���Ɣ�ׁA�f���^���̊����͂̋����͍ۗ����Ă���A�N���X�^�[(�����ҏW�c)�̔����⊴���o�H���ϗe�B��͈�w�̋����𔗂��Ă���B
�u����܂ŃN���X�^�[���قƂ�ǂȂ������S�ݓX�◝���e�A�w�K�m�Ȃǂł��������Ă���B�S�ݓX�ł́A�l�������n����1�K�ő����̗z���҂��o�Ă���v
�����N���o�ύĐ��S�����́A���{�̊�{�I�Ώ����j���ȉ�ł����q�ׂ��B
�R���i�̊����g�哖���A�N���X�^�[�����������͈̂��H�X��C�u�n�E�X�A�X�|�[�c�W���ȂǁA������3��(���E���W�E����)�̏����S�������B���̌�A����Ҏ{�݂Ȃǂő����A���N�`���̐ڎ킪�i�ނɂ�A�������Ă����B���������ɂ��f���^�����e����^������B
��_�S�ݓX�~�c�{�X(���s)�ł͏]�ƈ��̏W�c�����������A�����Ґ��͌v130�l�����B�����͗��p�q�炪��������Ȃ��X�܂̃o�b�N���[�h�Ŋ������L�������Ƃ݂��Ă������A���s�̏����Y�s���͕ی����̒������ʂ܂��A�u�q����̊����̉\���������v�Ƃ̌������������B
�s�͖��Ǐ�̋q���A�}�X�N�𐳂����������ɑ吺�ʼn�b������A�E�C���X���t������ʼn�����G�����肵�����ƂŊ������L�������\�����w�E�B���{�̋g���m���m���́u�f���^���̊����g��͂̋�������Ă���B���܂ł̐ڐG�̒��x�ł���Ί������Ȃ��������̂���������Ƃ������Ƃ��Ǝv���v�ƌ�����B
���������nj������Ȃǂɂ��ƁA�f���^���̊����͂͏]�����Ɣ��2�{�A�]������荂���Ƃ����A���t�@���Ɣ�ׁA1�E5�{�����\�����w�E����Ă���B������1�l���炤��l���������u�Đ��Y���v��5�`9�E5�ŁA�G�ߐ��C���t���G���U��荂���A���ڂ�����(8�E5)�ɕC�G�B�u�ł������͂̋����E�C���X�̈�v�Ƃ̌���������B
�܂��A�������������J���Ȃɑ������������Ƒg�D�ɒ�o���������ł́A�����҂̃E�C���X�ʂ��A�f���^���͏]�����ɔ��1200�{�ŁA���B���x���������������Ɋ������������\��������Ƃ��钆���̃O���[�v�̌����������ꂽ�B
�����A�f���^���Ǝ��̑���킯�ł͂Ȃ��B
���Ƒg�D�́A�}�X�N���w�q���A�l�Ƃ̋����̊m�ہA���C�Ƃ�������{�I�����h�~��̋����𑣂��A�u�}�X�N�ɂ��ẮA��(�Ђ܂�)�h�~���ʂ̍����s�D�z(�ӂ��傭��)�}�X�N�Ȃǂ̊��p�𐄏�����v�ƌĂт������B�����������Ő��Ƒg�D�̘e�c����(������)�����͏��Ǝ{�݂𗘗p����ۂ̑�ɂ��āA�u�Ȃ�ׂ����l���Ŏ��Ԃ�Z�����āA���G������ʂ�����邱�Ƃ��d�v���v�Ɖ��߂đi���Ă���B�@
��40��50��̃R���i�d�ǎ҂������c�e��Ì������芪����5�g�̌����@8/8
�V�^�R���i�̊����Ċg���40��A50��̏d�lj����[���ɂȂ��Ă���B�����s�̏��r�m����6���̉�Łu40��50��̏d�ǂ̕��X�̔䗦�������v�ƃR�����g�B�����A�m�F���ꂽ�d�ǎ�135�l�̂����A��6����40��A50�ゾ�����B
���̔����I�Ȋ����g��̌����̓f���^���̗��s���B�j���[�X�ԑg�wABEMA Prime�x�ł́A�őO���Ŏ��Âɂ������t6�l�������[�g�o���B����܂ł̊����Ƃ̌���I�ȈႢ�A�܂���ÂЂ����̎���ȂǁA���ꂼ�ꂪ���ʂ��Ă��錻�������B
���݂̊���������̈�t�����͂ǂ̂悤�Ɍ��Ă���̂��B����w��w���E��������w�����̍��ߌ��u���́u����҂��L�����N�`����ڎ킵�����ƂŁA����҂̊����E�d�lj��͌����Ă���v�ƌ��B
�u������������w�̕a�@�ł́A���N�`����ł��Ă���40�`50��ŏd�lj������l�́A�܂����Ȃ��B�������A40�`50��ŁA���N�`����ł��Ă��Ȃ����X�́A�f���^���̉e���ł��d�lj����₷���Ȃ��Ă���B����̎����ł́A�d�lj����Ă���l�͂قƂ�ǃ��N�`����ł��Ă��Ȃ����A�^�������N�`���̌��ʂ��o�Ă��Ȃ��Ԃɏd�lj����Ă��܂��������肾�B�����҂��}���ɑ��������ʁA�x��č��ɂȂ��ďd�ǎҐ��������Ă��Ă���悤�Ɋ�����v(���ߎ�)
�`���a�@���@��A�Ȉ㒷�̖ؑ��S���������u�܂�40��A50��ɂ̓��N�`�����s���n���Ă��Ȃ��v�Ƃ����A�u���N�`����ł��Ă��ďd�lj����Ă���l�͏��Ȃ���ہB��͂胏�N�`����ł��Ă��Ȃ��l���d�lj����Ă���Ǝv���v�Ƙb���B40��A50��̃R���i���҂������钆�A����̑�5�g�͂���܂łƉ����Ⴄ�̂��낤���B
�u�����ڂ̏d�ǎҐ��́A�O�̑�3�g�̗��s���Ƃ��܂�ς��Ȃ��悤�Ɍ����邩������Ȃ����A(�d�ǎ҂�)����҂̏ꍇ�A������x�A�ŏI�I�ɂ͍����ǂ���������A�Q������ł�������A�ɘa���Â̌`�ŁA��Î�������������邱�ƂȂ��S���Ȃ�l�����Ȃ葽�������A�������A40��A50��͐l�H�ċz���G�N��(�̊O�����^�l�H�x)�ȂLj�Î��������ׂē������Ă���B����āA��Î����������Ǝg�������邱�ƂɂȂ�B���A���������a�@�͂�������100���ȏオ���@���Ă��邪�A���̒��ŏd�lj����銳�҂����ɑ����Ă��Ă���B�Ⴍ�Ă��A����悠���Ƃ����ԂɎ_�f���^���K�v�ɂȂ��āA���X�s���[�^�[(�l�H�ċz��)���K�v�ɂȂ銳�҂���������B���낻��A���ǂ��̕a�@�ł͎���𐧌�������Ȃ��悤�ȏɗ��Ă���v(�ؑ���)
�u���ʂ̕a�@�ɂ�100�l���̐l�H�ċz��͓��R�Ȃ��B���ǂ��̕a�@�ł���10�䂾�B�ǂ̕a�@�ł�100�����邩��Ƃ����āA100���Ől�H�ċz����g���邩�Ƃ����ƁA�S������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���͌����Ă��邵�A�l�H�ċz����ێ�����ɂ́A�]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��X�^�b�t�����ɑ����B������A���̌���͔��ɂ܂������v(�ؑ���)
�l�H�ċz������҂Ɏg���ꍇ�A2�T�Ԃ���1�J�����x�͑��������܂܂ɂȂ�B�܂�A10�䂵���Ȃ��l�H�ċz��ŁA1�J���Ԃŏ�������͍̂ő��20�l�A�ŏ��Ŗ�10�l���B
���N�A��K�͂ȃN���X�^�[���������������i�������a�@�͌��݂ǂ̂悤�ȏȂ̂��낤���B���a�@�̂���f�Îx���E�ɘa�P�A�Z���^�[���̜A���Ҏ��́u�����́A�܂���1�g�ő��肪�킩��Ȃ��������BPCR�������ł����A���Â��킩�炸�A�ǂ�ǂ҂���̋�������Ȃ��āA��X�����������|�������Ă����v�Ɖߋ���U��Ԃ�B
�u���ǂ��̕a�@�͓����̂ǐ^�A���̒��S�ɂ���B��5�g�̊������L���钆�A���ʂɔɉ؊X�ɍ���(7��6��)���l�������ς������B�w���v���ȁH�x�Ƃ��Ȃ苰�|�������Ȃ���������B(�V�^�R���i�ȊO�̕a�C��)��ʎ��Âœ��@����Ă��銳�҂���������B�~�}�̊��҂�����A�ʏ�̎�p�̊��҂�����A�S��PCR�������s���Ă��邪�A�܂������\�z���Ă��Ȃ��Ƃ���Łw����PCR�ŗz���������x�Ƃ������P�[�X���������B�����ǂɊ���Ă���a�@�Ȃ�Ƃ������A���ǂ��̂悤�Ȉ�ʂ̕a�@�́A���ɕ|���v�������Ȃ���A�ʏ�f�Â��s���Ă���v(�A����)
�܂��A�ݑ��Â̌���ɂ��āA��s���ōő�K�͂̍ݑ��Â���Ă����Ö@�l�Вc�I�ĉ�̗������E�f�Õ����̍��X�؏~���́u�ݑ��́A���i�͊�b������������A�ʉ@������ȗv���̐l���������I�ɐf�@����B����͐V�^�R���i�ɂ������ĕ��i�͐f�Ȃ��Ⴂ���҂������w����Őf�Ă���x�Ɠ����s���t���Ȃǂ���v������āA���܂��ɂ��̎��g�݂��n�߂��Ƃ��낾�v�Ƙb���B
���N�����獡�N���߂ɂ����āA�����s��1���̐V�K�����Ґ���2000�l�������A���X�؎����f�@�ɍs���Ă�����{�݂�ݑ��Â̌���ŃN���X�^�[���������������B�������A���́u��̂悤�ȉ��₩�ȏ�ԂŁA�܂������N���X�^�[�������N���Ă��Ȃ��v�Ƃ����B�Ȃ��Ȃ̂��낤���B
�u�ݑ��Âŕ��i�f�Ă��鍂��҂̉��{�݁A�������Ƃ����������̕a�C���������l�����̐��E�͍��A�N���X�^�[�����͖{���ɂȂ��B�Ȃ����Ƃ����ƁA��������É��]���҂݂͂�ȃ��N�`����ł��Ă��邵�A��X�̊��҂����́A95�����炢�����N�`���ڎ���������Ă���B����Ҏ{�݂ł̓X�N���[�j���OPCR�Ƃ����A�������Ă��Ȃ����ǂ�������I�ɑS����PCR���������B���܂�1�l�A�z���̐l���������Ă��A�S���L�����Ă��Ȃ��B�ȑO��1�l�����牽�l���z���������̂��A���͂��̐l�����B����ȏŃN���X�^�[�����͋N���Ȃ��B�����玄�����̐��E�͈��S�ȃo�u���̓����Ƃ����������v
�V�^�R���i�}�����݂̃J�M�ƂȂ郏�N�`���B�O�q�̍��ߎ��́u����̑�5�g�����N�`���ڎ킪�i��ŁA�����܂ł̗��s�ɂȂ�Ȃ���A��ԗǂ������v�Əq�ׂ�B���̏�Łu��5�g�����ꂩ�痎�������Ƃ��āA���̌�A�܂����̑傫�Ȋ����̔g�������Ƃ��ɁA��������d�ǎ҂����Ȃ��}���邽�߂ɂ́A��͂胏�N�`���ڎ���ǂ�ǂ�i�߂�K�v������v�ƃ��N�`���ڎ�̏d�v���Ɍ��y�B
�u���{�̏ꍇ�A���O����菭���x��ă��N�`���ڎ킪�J�n���ꂽ�̂ŁA�����I�ȍR�̉��̐��ڂ͂Ȃ��B�������A�R�̉��Ō���Ɖ������Ă���Ǝv���B�����A���N�`���̌��ʂ͕K�������R�̂̐��l�ƈ�v���Ȃ��Ƃ��낪����B�R�͉̂������Ă��邪�Ɖu�S�̂ł͕ۂ���Ă���\��������B�lj��ڎ킪�K�v�Ȃ̂��A�܂��c�_(�̗]�n)������B�C�O�̎�����Q�l�ɂ��Ȃ���A�lj��ڎ�̌��������ׂ����Ǝv���v(���ߎ�)
����ŁA�����̂ɂ���Ă̓��N�`���ڎ�̗\�ł����A10���A11���ɂȂ�Ƃ������P�[�X���������Ă���B���N�`���ڎ��S������͖쑾�Y��b�̃u���O�ɂ́A9�����ɂ͊�]�ґS���Ƀ��N�`������邾���̐����m�ۂ��Ă���ƂÂ��Ă��邪�A�Ȃ������̂ɂ���Ă��̂悤�Ȗ�肪�o�Ă���̂��낤���B�ǂ����ɗ]�胏�N�`��������̂��낤���B
�u���̂�����͎����\���ɔc���ł��Ă��Ȃ��B���N�`���̐��͕ۂ���Ă��Ă��A�{���ɕK�v�Ƃ���Ă���Ƃ���ɂ����Ɣz������Ă��炸�A�ǂ����Ń��N�`�����]���Ă���̂��Ǝv���B���N�`�����A�ǂ��ɂǂꂭ�炢���邩�A������x�c���ł��āA�Z�ʂ������d�g�݂����ׂ����v(���ߎ�)�@
���u���݂��Ȃ炱������Łv���Ə��r�s�m���̌ܗ��J�͎��^�ɋ^��̐��@8/8
���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�g�[�}�X�E�o�b�n���8���A���`�̎Ɠ����s�̏��r�S���q�m���ɑ��A�ܗ։^�����W�Ɋ�^�������Ƃ���������u�ܗփI�[�_�[�v(���J��)�ōō��̋��͂����Ŏ��^����Ɣ��\�������Ƃ��A�u�ܗ��J�́v�u���Ə��r�s�m���v���c�C�b�^�[�Ńg�����h���肵���B
�V�^�R���i�E�C���X�����g�傪���������A�����⒆�~��]�ސ��������������ł̊J�Â��������Ƃ������Ă��A�Ə��r���̎�͂ɋ^�⎋���鐺�����������B�u(2�l��)���������H�v�u�����̐������ċ��s�������Ƃ����_�ɂȂ�̂��v�u�{�����e�B�A���Ï]���҂݂̂Ȃ���ɂ����Ă��������v�Ƃ��������e���������B
����Ɂu�͑��s���I�@���݂��Ȃ炱������Łv�ƁA���É��s�̉͑��������s���̋����_���������ɗ��߂铊�e���������B
���o�b�n������Ə��r�s�m���Ɂu�ō��M�́v�@��������t�Ȃŕ\���@8/8
���{�̍�������������Ӗ��s���́g���M�h���B���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃o�b�n���8���AIOC����Ōܗ։^���̔��W�Ɋ�^�������Ƃ���������u�ܗփI�[�_�[�v(���J��)�ōō��̋��͂��A����Ő��`�̎Ɠ����s�̏��r�S���q�m���Ɏ��^����Ɩ��炩�ɂ����B
����ɑ��A�l�b�g��ł͋�����{��̐������o���Ă���B�uIOC���炵������J�҂�������܂����{�������炵���炱��2�l�͐�Ƃł��v�u��������IOC�ɍv�������Ƃ������J�����ȁH�v�u���{���߂���߂���ɂ����ŏ́v�Ȃǐh��Ȑ������сA�j������l�͂قڊF���B����ɂ́u���łɓ�l�������ċA���Ă���B�ǂ��������Ă���������v�ȂǁA�ܗ֕�Ɠ����ɐ��Ə��r�s�m���̑ޔC���肤�����������B
IOC�ɂƂ��āA�R���i�Ђł̋��s�J�Â𐄂��i�߂����A�����ĊJ�ÂɃX�g�b�v�������Ȃ��������r�m���ɑ��A���ӂ͐s���Ȃ����낤�B�������A�ܗ֊J�Ò��ɃR���i�����҂͋}���B2�l�̌M�͂ƈ��������ɍ��������������͂ƂĂ��Ȃ��傫���B
���u���J���́vIOC�o�b�n����������r�m���Ɂw�ō����J�܁x���^�@8/8
���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃o�b�n���8����IOC����ŁA���`�̎Ɠ����s�̏��r�S���q�m���ɓ���Łu�ܗ��J�́v�̍ō��͂����^���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ������Ƃ��A�l�b�g��ł́u���J���́v�u�f���C������v�Ȃǂƕ���̐������o�����B
2�l�Ɏ��^�����̂́A�ܗ։^���̔��W�Ɋ�^�������Ƃ���������u�ܗփI�[�_�[�v(���J��)�ōō��̋��́B�������A�J�Ô���ĉ��������߂�ӌ�����8�����߂钆�ōs��ꂽ�����ܗւ̊��Ԓ��A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��͔��������B���ڂ̊֘A���͕s�������A���������������l�������B
�������������ȏɂ�������炸�A�o�b�n����g���J���h�𐛎Ə��r�m���ɗ^����ӌ������������Ƃɑ��A�u�{���ɓ������l�����͂��̃j���[�X���Ăǂ��v���̂��Ȃ��v�u�����Ɋ�^�����̂͐F�X�Ɖ䖝���������v�Ȃǂ̎w�E�����o�B�u����͊���ł��r�߂Ă��悢�ȁB�͑��搶�A���肢���܂��v�u���������݂ɍs�����炢���̂Ɂv�Ɩ��É��s�̉͑��������s���́g�o�ԁh�����߂�R�����g���݂�ꂽ�B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���ܗ֊��Ԓ� �R���i�����}�g�� �p���T�������̗}�����݉ۑ�@8/9
8���������I�����s�b�N�̊��Ԓ��A�J�Ós�s�̓����s�ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�A������Ƀp�������s�b�N�̊J�����T����Ȃ�������}�����߂邩���ۑ�ł��B
�挎23���ɊJ�����A8���A�����������I�����s�b�N�́A�����g��ŋً}���Ԑ錾���o�����Ȃ��A�����Ȃ�1�s3���̉��͖��ϋq�ɂȂ�ȂǁA�ٗ�̑��ƂȂ�܂����B
�����Ԓ��A�J�Ós�s�̓����s�ł́A����܂łɂȂ��X�s�[�h�Ŋ������}�g�債�A1���̊����m�F�́A8���܂ł�5���A����4000�l���܂����B
�܂��A7���ԕ��ς́A������8�����_�ŊJ�������挎23����2.9�{�ɂȂ�܂����B
����ɁA���@���҂́A7���A8���ƁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V�����ق��A����×{�҂��}�����Ă��āA�s�̐��Ƃ́A��Ò̐����Ђ������Ă���Ǝw�E���Ă��܂��B
���̊J�Â��l�o��U�������Ƃ����������������A���r�m���́A�u�e���r�Ŋϐ킵���l�������A�X�e�C�z�[���ɂȂ������v�Əq�ׁA�J�Î��̂��l�o�̑����⊴���̊g��ɂȂ����Ă͂��Ȃ��Ƃ����F���������Ă��܂��B
��̌��ʂ������ɂ͂��悻2�T�Ԃ�����Ƃ������Ă��āA������̍���24���ɂ̓p�������s�b�N�̊J�����T����Ȃ��A������}�����߂邩���ۑ�ł��B
���ꌾ�Ō����ƎႢ���オ�����A����҂��ꈬ��@�R���i�u��5�g�v�@8/9
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ċg��̌X�������Ɍ��P�H�s���Ō����ƂȂ��Ă���B7�����{�Ɂu��5�g�v�̗��s���N���ƂȂ�A8����1��������̐V�K�����Ґ���7���ɉߋ��ő���49�l�ɏ��ȂǍ��������Ő��ڂ���B�ċx�݂₨�~�̋A�Ȏ������}���A�l���̑��������O�����B��5�g�̓����⋁�߂����ɂ��āA�P�H�s�ی������ň�t�ł�����ї��D�F����ɕ������B
�\�\��5�g�̌X����
�ꌾ�Ō����ƎႢ����̊����҂������A����҂��ꈬ��ɂȂ����B���̂��߁A�d�ǎ҂͏��Ȃ��B�����A�����Ґ��̑����ɔ����A�s���̏h���×{�{�݂͂قڋ��Ȃ��Ȃ����B���M��H�~�̌��ނŐ��サ���l�����@����P�[�X������A�a���͖��܂��Ă��Ă���B
�\�\�����g��̓f���^���̉e����
�f���^���͊����͂������Ƃ���邪�A�����ŋ߂͎s����1�l�̊��҂����l���ɍL���������Ⴊ�Ȃ��A�N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F����Ă��Ȃ��B��������A�Ⴂ����̐��������X�ɃR���i�БO�ɖ߂�A�s���͈͂��L�����Ă���e�����傫���B�F�l�Ƃ̐H���Ȃǃ}�X�N���O���Đl�Ɛڂ����ʂ�������ƁA�������X�N�͍��܂�B
�\�\���{�������������҂̓��@�������j��������
�P�H�s�ł͈ȑO����y�ǁA���Ǐ�̊��҂͌����A�����h���{�݂ł̗×{�Ƃ��Ă����B�����_�f�Z�x���ቺ���Ă���u������1�v�̏ꍇ�́A��b����������ȂǏd�lj��̃��X�N���������҂̓��@��D�悵�A�ċz�s�S�̂���u������2�v��d�ǎ҂͑S�������@�ƂȂ�B65�Έȏ�͏Ǐ�ɊW�Ȃ����@�Ƃ��Ă��邪�A�����҂̑����ɂ��a�����N��(�Ђ��ς�)���Ă���ƁA���̊�œ��@�̉ۂf����B
�\�\����×{�҂ւ̑Ή���
���@���K�v���ǂ�����Ζʂ��Č��ɂ߂邽�߁A�ی��t��̃`�[�����߂�35�Έȏ�̍ݑ�҂ւ̖K����n�߂�B34�Έȉ��ł��K�v�Ɣ��f����Α����^�ԁB����ɁA��Ԃɋ}�ς������҂̔�����Ƃ��āA�s���̕a�@�ňꎞ������\�Ƃ���a���̊m�ۂ��������Ă���B�~�}�̔�������Ẳ����ɂ��Ȃ������B
�\�\���~�̎����ɓ���B���ӓ_��
�}�X�N�̒��p���A�������̓O��͊�{�B�A�Ȑ�ł͎��g�⑊�肪���N�`���ڎ���I���Ă��Ă��A�}�X�N�͒����Ă����B�����l�ł̐H���̏�ł͈��������đ������A�H�I������}�X�N�𒅗p����B�q�ǂ��͂����ƉƂʼn߂����͓̂�����낤�B�M���ǂɋC��t���A���ɂȂ�Ȃ����O�ł̋C���]�����y����ł��炢�����B
���d�lj��h�~�ֈ�t���f�A8�����{�ɂ��^����×{�ґ���
�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�����������×{�҂̏d�lj���h�����߁A�P�H�s��t��͎s�ی����ƘA�g���A8�����{�ɂ����҂̉��f���n�߂�B�s���̎���×{�҂͊����Ċg��ƂƂ��ɑ������Ă���A���f���Ǐ��̑��������ɂȂ���_�����B
�s�ɂ��ƁA�s���̎���×{�Ґ��͊�����4�g��5����{�ɍő���332�l���L�^�B6�����{�Ɉꎞ�[���ƂȂ������A7�����{����ĂщE���オ��ƂȂ�A8��6�����_��164�l�ɏ��B
���f�Ɏ��g�ނ̂͊J�ƈ���30�l�B�s�ی�������˗��������ґ��K�₵�A�Ǐ�̊m�F���̏����Ȃǂ��s���B�s��t��̒S���҂́u�Ǐd���Ȃ钛��ɑ����C�t���A�K�v�ɉ����ē��@������ی����ɓ����|�������v�Ƃ����B
�s�ی����̖ї��D�F�����͂���܂Ŏ��牝�f��S���Ă����Ƃ����u��t��̋��͂͂ƂĂ��S�����v�Ƙb�����B
���ً}���Ԑ錾�E�܂h�~�[�u����1�T�ԁ@�����g�呱���@8/9
8���A��2�{4���Ŕ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂͂��킹��2149�l�ƂȂ�A5���A����2000�l������܂����B
���ɋً}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɂ܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă���9����1�T�ԂƂȂ�܂����A�����̊g��͑����Ă��Ċe�{���͑�̓O������߂ČĂт����Ă��܂��B
��2�{4����8���A���\���ꂽ�V���Ȋ����҂́A��オ1164�l�A���ɂ�450�l�A���s��333�l�A���ꂪ89�l�A�ޗǂ�88�l�A�a�̎R��25�l�̂��킹��2149�l�ŁA5���A����2000�l������܂����B
�܂��A����2�l�̎��S�����\����܂����B
8��2���ɑ��ɂً͋}���Ԑ錾���A���ɂƋ��s�ɂ͂܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă���1�T�ԂƂȂ�܂��B
�������A���s�ł͏��߂�300�l���ߋ��ő����X�V�����ق��A���ł�6���A����1000�l���銴���҂ƂȂ�ȂNJ��e�n�Ŋ����̋}�g�傪�����Ă��܂��B
�e�{���͂��̘A�x�₨�~�̊��Ԓ��A�s�v�s�}�̊O�o�����l���A�s���{�����܂����ړ��͋ɗ́A�T����ȂǁA���O�ꂷ��悤���߂ČĂт����Ă��܂��B
���A�A�Ȏ��l�Ăт����@�u�ɂ߂đ厖�Ȏ����v�@8/9
���`�̎�9���A����s���ł̋L�҉�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊�����ɂ��āu���T���炨�~�̎������}����B�����͂̋����ψي��ɂ��A���ĂȂ������g�傪�i��ł��钆�ŋɂ߂đ厖�Ȏ������v�Ƌ��������B���̏�Łu�A�ȁA���s���ɗ͔����Ă��������A��ނȂ��Ƃ��͌��������Ȃ���g�߂Ȑl�Ə��l���ōs���ȂǎႢ�l�����ɂ����͂��Ă���������v�ƌ�����B
�͐V�K�����҂ɐ�߂�30�Έȉ��̊�����7�����Ă���Ƃ��āu�Ⴂ�l�̑ɂ߂đ厖���v�Ǝw�E���A�c�C�b�^�[�⓮�擊�e�T�C�g�u���[�`���[�u�v�Ń��N�`���ڎ���Ăт����Ă���Ƃ����B�܂��A�u��҂���ƒ�ւ̊������L�����Ă���Ƃ����w�E������B��҂ł��d�lj��̃��X�N�����܂��Ă��邵�A���ǂ���������o�Ă��Ă���B�Ⴂ����e�����Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��F���������������v�Əq�ׂ��B
�͂܂��A���ڎ��1��������Ƃ��A65�Έȏ�̍���҂�8���ȏオ2��ڎ���I���Ă��邱�Ɛ��������B����Ɂu1��������2��ڎ��i�߂Ă������Ƃ������g��A�d�lj��h�~�ɑ傢�Ɍ��ʂ�����B���������ڕW�𗧂ĂȂ���S�͂Ŏ��g��ł���v�ƌ�����B
����A�����s�ŐV�^�R���i���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��ً}���Ԑ錾�����߂���Ă��钆�Œ���s��K�₵�����R�����A�u����ƍL���ŋN�����S�Ђɂ���Ă����炳�ꂽ�ꂵ�݂��x�ƋN�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��ċ����v���̉��œ����͐錾�������K�₵�A(���茴���]���҈ԗ약�a�F�O)���T�ɎQ�������v�Əq�ׂ��B
���u�ܗ֏I���R���i��F�v�y�Ϙ_�Ɍ����������A���������ɏł�@8/9
�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾���Ŗ����J���A8���ɖ������낵�������ܗցB�����I�ɂ͈��{�W�O�O�������̋��S�͂ɁA��p�̐��`�̎������O�@�I�ւ̒e�݂ɂƁA���ꂼ��ʒu�t�����������B���{���̃��_�����b�V���ɍ����������̂ƕ��s���āA�R���i�u��5�g�v�̔����I�����������B�y�σV�i���I�Ōܗւɓ˂��i�������̎x���������钛���́A�܂������Ȃ��B�@(�v�m�M)
���ɐ旧���A�͍������Z����ō��ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃o�b�n�����A�ܗ։^���̔��W�Ɋ�^�������Ƃ���������u�ܗփI�[�_�[�v(���J��)�ōō��̋��͂����^���ꂽ�B�ߌ�8������̓}�X�N�p�ŏH�{���܂ƕ���ŕ�ɗՂ݁A����s�i����e���̑I�����W�҂������A�������˂�������B
�u���S���S�̑��v(��)�̗��ŁA�����ł�1���̐V�K�����Ґ���1��5��l����ȂǁA���Čo���������Ƃ̂Ȃ����������������B6���̋L�҉�ŁA�́u�ܗւ������g��ɂȂ����Ă���Ƃ����l�����͂��Ă��Ȃ��v�Ƌ����������̂́A���������Ɍ����킹�邽�߂ɐ��{���Ăъ|���鎩�l�ƍs���ϗe���A�����̐S�ɋ����Ă��Ȃ��͖̂��炩���B���{�̊����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή�́u�ܗւ��l�X�̈ӎ��ɗ^�����e���͂���̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E����B
�������O�A�͒��~��ĉ�����i�����鑤�߂̐��Ɏ���݂����Ƃ͂Ȃ������B�u��߂邱�Ƃ͈�ԊȒP�B���킷��̂����{�̖������v�B�J�����O�̕Ď��E�H�[���X�g���[�g�E�W���[�i���̃C���^�r���[�ɂ́A���������ɐS���𖾂����Ă���B
���C�̌���́A���N�`���ڎ�̉����������B�����͂������f���^���ւ̌��O�����܂��Ă��钆�ł��A���ĂȂǂ̐�s�������Ɂu7�����ɂ͊������D�]����v�Ƃ̊y�Ϙ_�Ɍ������B�Ƃ��낪�|�B
���ʂ́A���O�Ɂu�\�h�I�v�ɓ����ɔ��o�����ً}���Ԑ錾�ł���5�g�̐����͐H���~�߂�ꂸ�A�����Ԓ��A�Ȃ�ӂ�\�킸�錾�̑Ώےn����g�傹����Ȃ����ԂɁB�d�ǎ҂��}�����A��Õ���̊�@����������тт�B�ŋ߂܂Łu�d�lj����₷������҂̐ڎ킪�i�݁A�V�K�����Ґ��Ɉ���J����K�v�͂Ȃ��v�Ƃ��Ă������@�W�҂��A�����s�[�N������Ɍ����Ȃ�����ɏł���B���Ȃ��B
�u�l�ނ��E�C���X�ɑł����������v�Ƃ��Čܗւ̈��̐������A�s�[�����A�j�Ճ��[�h�̒ǂ������ďO�@���U�E���I���A�����}���ّI�ɂȂ��ꍞ�ށ|�B�̊�{�헪�́A���{�I�ȗ��蒼���𔗂�ꂻ�����B�ܗւ�1�N���������܂�O����̖�1�N���̊ԁA�����x�����̓E�C���X�̏ɒ������ď㉺���Ă����B�u�������R���g���[���s�\�Ɋׂ�A�o���������Ȃ��Ȃ��Ă���v(���{�W��)����ŁA���U�����܂ގ̐����I���S�͂͑��������Ă���B
���{�����́u�ܗւ��J���Ă悩�����B�w����Ȏ�������E�C�Â���ꂽ�x�Ƃ������������v�Ƌ���B�����A���J�Â̑O������Ƃ����u�����̖��ƌ��N�����v���Ƃ�����Ȃ��Ă��鍡�A�u�ܗւ��I���R���i��F�ɂȂ�B���̂܂܂ł͑I���ɑ啉������v(�����W��)�Ƃ̐����R��n�߂��B
���ܗ֕� ���u�J�Í��̐ӔC�ʂ������v�����Ɋ��ӂ̈ӎ��� �@8/9
�����I�����s�b�N�̕����A��������b�́A������b���@�̃c�C�b�^�[�Ƀr�f�I���b�Z�[�W�𓊍e���A�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ł��܂��܂Ȑ����钆�A�J�Í��̐ӔC���ʂ����A�p�����Ƀo�g�����Ȃ����Ƃ��ł����Ƃ��āA���ӂ̈ӂ������܂����B
���̒��ŁA��������b�́u�V�^�R���i�̒��ŊJ�Â�1�N��������A���ĂȂ����܂��܂Ȑ���̂��Ƃł̑��ƂȂ������A�J�Í��Ƃ��Ă̐ӔC���ʂ����A�p�����ւƃo�g�����Ȃ����Ƃ��ł����B�����̊F�l�̂������Ƃ����͂̂��܂��̂ł���A�S��芴�Ӑ\���グ��v�ƍ����Ɋ��ӂ̈ӂ������܂����B
���̂����Łu�I��̊F����̊���ɂ��A���炵�����ɂȂ����B�����𐬂��������I��A���ƈ���͂��������܂𗬂����I��A���ׂĂ̑I��ɑ傫�Ȕ���𑗂肽���B�����āA�����]�A�������A�q�ǂ����ҁA���E�̐l�X�ɓ͂��Ă��ꂽ���Ƃ́A�����ɂ����������������ւ̍��Y�ɂȂ����v�ƑI��̊�����������܂����B
�����āu������ɂ��āA�C�O����́w����������x�Ƃ̐������������w���{������ł����x�ƕ]�����鐺�������ꂽ�B���W�ҁA��ÊW�ҁA�{�����e�B�A�̕��X�A�����͂������������ׂĂ̊F����ɐS���犴�ӂ�\���グ��B���肪�Ƃ��������܂����v�Əq�ׂ܂����B
���V�^�R���i ���u�s�v�s�}�̊O�o�A�A�ȁA���s �ɗ͔����āv �@8/9
�V�^�R���i�E�C���X����߂���A��������b�́A����s�ŋL�҉���A�Ⴂ����ŏd�lj��̃��X�N�����܂��Ă���Ƃ��āA�s�v�s�}�̊O�o��A�A�ȁA���s���ɗ͔�����ȂǁA�����g��h�~�ւ̋��͂��Ăт����܂����B
���̒��ŁA��������b�́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ��āu��҂���ƒ�ւ̊������L�����Ă���Ƃ����w�E������B��҂ł��d�lj��̃��X�N�����܂��Ă���ق��A���ǂ�����l���o�Ă��Ă���v�Əq�ׁA�V�K�����҂������Ă���Ⴂ����ւ̊����h�~���i�߂邱�Ƃ��d�v���Ƃ����F���������܂����B
���̂����Łu���T���炨�~�̎������}���邪�A�����͂̋����ψي��ɂ��A���ĂȂ������g�傪�����Ă��āA�ɂ߂đ厖�Ȏ������B�Ⴂ����e�����Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ƔF�����A�s�v�s�}�̊O�o���T���Ăق����B�A�ȁA���s���ɗ͔����A��ނȂ��Ƃ��́A���������Ȃ���A�g�߂Ȑl�Ə��l���ōs���ȂǁA�Ⴂ�l�����������g��̖h�~�ɂ��Ћ��͂��Ē��������v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A���N�`���ڎ�ɂ��āu���ڎ��1������Ă���B1���������A2��̐ڎ�𑽂��̍����ɐi�߂Ă������Ƃ��A�����g���d�lj��̖h�~�ɑ傢�Ɍ��ʂ�����v�Əq�ׂ܂����B
���V�^�R���i�@�Ђ����Ȃ��E�Y�����N���X�^�[�g��A�}���̎��Ə����@���@8/9
��錧�Ɛ��ˎs��9���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ҍv217�l�̂����A1�l�͂Ђ����Ȃ��s�̐��ˌY�����̔���e�҂ŁA���ɂ��ƁA�����o�H�͕s���B���Y�������̊����҂͔���e�Ҍv9�l�Ɋg�債���B
�}���s���̎��Ə��ł��]�ƈ�1�l�̊������������A�����Ə����̊����҂͏]�ƈ��v11�l�ɍL�������B
���ˎs�̊����҂�1�l�͎s�����w�Z�ɋΖ����鋳�E���̏����B���w�Z��7��21������ċG�x�ƂƂȂ��Ă���A������Ƃ̐ڐG�͂Ȃ������B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������s��2612�l�����@�d�ǎ҂��ߋ��ő���176�l�� �@8/10
�����s��10���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�2612�l�A����3�l���m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�s���̗v���Ґ���25��4781�l�ɂȂ����B���̂������ݓ��@���Ă���d�NJ��҂�176�l�ƁA1��20����160�l������ߋ��ő����L�^�����B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���3978�D7�l�ŁA10�����_�őO�̏T�ɔ��119�D2���ƂȂ����B
�N��ʂł́A20�オ844�l�A30�オ560�l�A40�オ420�l�A50�オ296�l�ȂǂƂȂ��Ă���B65�Έȏ�̍���҂�103�l�������B���S�����̂�70���80��̒j���A90��̏����B
������3992�l�ւ̃X�N���[�j���O�����ł́A�ψي��u�f���^���v�ɂ݂���ψفu�k452�q�v��3364�l�Ŋm�F����A�����͖�84�D3���������B
�������s�ŐV����2612�l�̊����m�F�@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�̐[���Ȋ����g�傪���������s����10���A�V����2612�l�̊������m�F����܂����B��T�Ηj����3709�l����͌������܂������A15���A����2000�l���Ă��܂��B
����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�3978�D7�l�ŁA�O�̏T�Ƃ̑������119�D2�p�[�Z���g�ƂȂ�A�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B����A�V����3�l�̎��S���m�F����܂����B
�܂��d�ǎ҂�19�l������176�l�ƂȂ�A1���̑�3�g�̂Ƃ��̃s�[�N�������ĉߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
������×{�ŏd�lj� �s���̊��� �g120�̈�Ë@�� ���ꂸ�h �@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�钆�A�s���̎���ŗ×{���Ă���50��̊��҂��d�lj����ċ~�}�������ꂽ�ہA���悻120�̈�Ë@�ւɎ����f���Ă������Ƃ��킩��܂����B
�V�^�R���i�Ɋ������Ď���ŗ×{���Ă���l�́A9�����_�œs����1��7356�l�ɏ��A1�����O��11.4�{�Ƌ}�����Ă��܂��B
�s���ɏZ��50��̒j���́A8����{�ɔ��M�̏Ǐo�ėz���Ɣ����������Ǝ���ŗ×{���Ă��܂����B
������2����ɂ́A�ċz�̏�Ԃ������Ȃ�ȂǏd�lj����A�~�}��������܂������A���悻120�̈�Ë@�ւɎ����f��ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�����Ĕ����J�n����5���ԗ]�肽���ē����E������̓��{��ȑ�w�t���a�@�Ŏ��ꂪ���܂�A���@���܂����B
���̕a�@�ً͋}���̍����d�NJ��҂ɑΉ�����3���~�}�̎w��a�@�ł��������̏�Ԃ������Ă��āA���h��ق��̕a�@���玟�X�Ɨv���������Ă��f�炴��Ȃ��P�[�X���������ł���Ƃ������Ƃł��B
���{��ȑ�w�t���a�@���x�~���~�}�Z���^�[�̉��x���i�Z���^�[���́A�u�����ɏd�Ǖa�������܂��Ă��܂��ŁA����ȂɎ��e�̈˗�����������Ƃ����͍̂��܂łɌo�����Ȃ��B�����閽��������Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ����\�����l���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�����Ґ������炳�Ȃ����肱�̏͑����v�Ƙb���Ă��܂����B
������ 40��〜50��̏d�NJ��� ��3�g�s�[�N����4�{�߂��Ɂ@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������ďd�ǂɂȂ������҂̐��́A�����s���ł͂���܂łōł����������N������N�����̊����g��́u��3�g�v�̃s�[�N���A�ߋ��ő���176�l�ƂȂ�܂����B
��3�g�ł�60��ȏ�̐��オ�d�NJ��҂�80���ȏ���߂܂������A����̊����g��ł�50��ȉ������悻70�����ߓ���40�ォ��50��̏d�NJ��҂͑�3�g�̃s�[�N����4�{�߂��ɂȂ��Ă��܂��B
�����s�ɂ��܂��ƁA�s�̊�ŏW�v�����d�NJ��҂̐��́A��3�g�̂��Ƃ�1��20����160�l�ƍł������Ȃ������ƁA3�����{�ɂ�37�l�܂Ō���A4�����{�܂ł�1�����Ԃ�30�l�䂩��40�l�䂪�����܂����B
���̌�A��4�g�ɂ���ďd�NJ��҂��������A5��12���ɂ�86�l�ƂȂ�܂������A��Ñ̐�����@�I�ȏƂȂ������{�╺�Ɍ��Ȃǂɔ�ׂ�Əd�NJ��Ґ��͏��Ȃ��A6�����{�ɂ�37�l�ɂ܂Ō���܂����B
�Ƃ��낪�A�挎�ȍ~�͊����g��̑�5�g�ŏd�ǎҐ��������X���ƂȂ�A���ɐ挎���{�ɂ�60�l�䂾�����̂��A����3�T�Ԃقǂ�176�l��3�{�߂��ɋ}�����Ă��܂��B
�N��ʂɌ���ƁA��3�g�ł�60��ȏ�̐��オ�d�NJ��҂�80���ȏ���߂܂������A���݂̊����g��ł�50��ȉ������悻70�����߂Ă��܂��B
���ɑ����Ă���̂��A40�ォ��50��̏d�NJ��҂ŁA1��20���̎��_�ł�24�l�ƑS�̂�15���ł������A9���̎��_�ł�94�l�Ƒ�3�g�̃s�[�N����3.9�{�ƂȂ�A�S�N��̂�����60�����߂Ă��܂��B
�܂��A30��ȉ��̏d�NJ��҂́A1��20���ɂ͂��܂���ł��������̂��̎��_�ł́A10�オ1�l�A20�オ4�l�A30�オ10�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����60��ȏ�̏d�NJ��҂�1��20���ɂ�136�l�������̂��A���N�`���ڎ킪�i��ł��邱�Ƃ�����A9���̎��_�ł�48�l�ł����B
�����r�m���A�ܗ֊֘A�̐V�^�R���i�́u�S�đz��̒��v�@8/10
�����s�̏��r�S���q�m����10���A�����ܗւ����S���S�ȑ��Ƃ��Ď��s�ł���������A�u���Ɋւ��ẴR���i�́A�S�đz��̒��Ɏ��܂��Ă���v�Əq�ׂ��B�s���ŕw�̎�ނɓ������B
�����ܗցE�p�������s�b�N�g�D�ψ���̔��\�ɂ��ƁA���֘A�̐V�^�R���i�����̗z���Ґ���7��1���ȍ~�̗v��460�l���A���̂���300�l���������ݏZ�҂���߂��B
���r�m���́u�C�O���痈��������A�ނ���(�ܗ֊W�̋Ɩ����ϑ�����)��������̋Ǝ҂̕��X���ǂ�����̂����낤�Ǝv���܂��B��������x�����������������B�Ԉ�����C���[�W��^���Ă��܂��v�ƌ�����B
�܂��A�����Ԓ��ɓs���̊������}�g�債�����Ƃ́A�ܗւƊ֘A�t�����Ɂu�f���^���̖҈ЂƂ������Ƃɐs����v�Ɣ����B���@�悪�����炸�Ɏ���ɂ��銴���҂�̑����ɐG��A�u�G�r�f���X�x�[�X�ł�������ƑΉ����Ă��������v�Əq�ׂ��B
���s�̊X���o�b�q�A�\�����߂��@�R���i�u��5�g�v�@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��̗\�������ނ��߁A�����s�����{���郂�j�^�����O�����Łu��5�g�v�̔����I�Ȋ����g���ߑ��ł��Ȃ��������Ƃ����炩�ɂȂ�A�����݂̍��������Ă���B6�A7����1�T�Ԃ��Ƃ̌������͖�2��4��`6�猏�ŁA�z���҂̊m�F���ő�20�l���x�ɂƂǂ܂�B���Ƃ́u�����̐l���K�͂��l����ƌ����������Ȃ��A�\���̔c���Ƃ����ړI�͌����I�ł͂Ȃ��v�Ǝw�E���A������Ƃ��Ă̗L�����ɋ^��𓊂�������B
�s��4���ȍ~�A�L�Ǐ�҂�̊������m�F����s�������Ƃ͕ʂɁA���ƘA�g���Ĕɉ؊X�ȂǂŖ��Ǐ�҂̂o�b�q�����𑱂��Ă���B�s�̌��\�f�[�^�ɂ��ƁA�T���Ƃ̌��������Ɨz���Ґ�����Z�o�����z�����́A7����1�T��0�E05���ŁA���̌�0�E10���A0�E14���A0�E27���Ə㏸�B�����A�s�������̐V�K�����Ґ���z���������l�ɑ������A�s�̒S���҂́u���j�^�����O�����ɁA�����ȌX���͊m�F�ł��Ȃ������v�ƕ��͂���B
4�����{����5����{�ɂ����āA1���������1��l���̐V�K�����҂��m�F���ꂽ��4�g�ł��A�z�����ɂ�����������B�s���Ŗ��Ǐ�z���҂̊����������钛��������A���̑���u���邱�Ƃ�����ɓ��邪�A�u���ʓI�Ȋ��p�͓���v(�s�S����)�B
�ۑ�ƂȂ��Ă���̂��A���������̏��Ȃ����B���j�^�����O�����ōő��������̂�6����4�T�̏T��2��4�猏�ŁA7���͏T��6��`9�猏�ɂƂǂ܂����B�z���Ґ���6����5�T��7����4�T��20�l���ő��ŁA3�l�Ƃ������Ƃ��������B
���M�Ȃǂ̏Ǐ�̂Ȃ��l�Ɍ����ɋ��͂��Ă��炤�K�v�����邪�A�����̗L�����m�F���邽�߂����ɕs���葽���̐l���W�܂�A�����n�_���Ƃ̌X���̐��m�����h�炬���˂Ȃ��B���̂��߁A�s�͎��{�ꏊ���u�ɉ؊X�A���H�X�A���Ə���w�O�A��`�Ȃǁv�Ƃ��āA��̓I�Ɏ����Ă��Ȃ��B
�����͎��{�ꏊ�̊m�ۂŌ������������錩���݂ŁA�s�͌������ʂƑ�5�g�̐��ڂ͂���l�����B
�s���̋��͂������Ȃ��́A���̃��j�^�����O�����ł���������ɂȂ��Ă���B���͉ċx�ݒ��̊����h�~��Ƃ��āA�H�c�Ȃǎ�v��`����k�C���Ɖ���Ɍ������q��ւ̓���҂ɁA�����̂o�b�q������R�����������{���Ă��邪�A����1���܂ł�2�T�Ԃ̓���Җ�28���l�̂����A���������͖̂�1���l(�z��17�l)�������B
�c�����v�����J������5���̎Q�@���J�ψ���Łu�����̔����Ő����ɉe�����o�邱�Ƃ�����A�����Ă��炤�̂�����B���������t�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B
���ۈ�Õ�����̘a�c�k������(���O�q���w)�́u���Ǐ�҂̌����́w���������A���l�ɂ����Ȃ��x�Ƃ����ړI�ł���Η��ɂ��Ȃ����A�n��̗��s�̒�������ނ��߂ƂȂ�ƃR�X�g�܂���Ό����I�ł͂Ȃ��v�Ǝw�E�B�q��֗��p�҂̌������u�z�����̃L�����Z�����̕⏞�Ȃǂ��Ȃ���Α����Ă����Ȃ����낤�v�Ƃ̌������������B
���}�����鎩��×{�� �����A�����������Ȃ��Ă��܂�����c �@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�̋}���Ȋ����g��œ����s�ł�10���A�V����2000�l���銴�����m�F����A�d�ǎ҂͉ߋ��ő��ƂȂ�܂����B����×{�̊��҂��������Ă��āA�s���ł͏d�lj����ċ~�}�������ꂽ���̂�100�����Ë@�ւɎ����f����P�[�X���N���Ă��܂��B�����A����×{��]�V�Ȃ����ꂽ��c�B�Ƒ��ւ̊����h�~���Ǐ��̒���ɋC�t���|�C���g���A���Ƃɕ����܂����B
������ �d�ǎ҂��ߋ��ő�
�����s���ł�10���A�V����2612�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����A1�T�ԑO�̉Ηj�����1097�l����܂����B����A�s�̊�ŏW�v����10�����_�̏d�ǂ̊��҂�176�l�ł����B��3�g�̂��Ƃ�1��20����160�l������A����܂łōł������Ȃ�܂����B���̂ق��A�ً}���Ԑ錾���o�Ă���n��ł́A�_�ސ쌧��1572�l�A��ʌ���1166�l�A��t����860�l�A���{��697�l�A���ꌧ��332�l�̊������V���Ɋm�F����܂����B
����120�̈�Ë@�ւɎ���f����P�[�X��
�s���ł͏Ǐ������Ă����@�悪�����Ɍ�����Ȃ��P�[�X���N���Ă��܂��B����ŗ×{���Ă���50��̊��҂��d�lj����ċ~�}�������ꂽ�ہA���悻120�̈�Ë@�ւɎ����f���Ă������Ƃ��킩��܂����B�s���ɏZ��50��̒j���́A������{�ɔ��M�̏Ǐo�ėz���Ɣ����������Ǝ���ŗ×{���Ă��܂����B������2����ɂ͌ċz�̏�Ԃ������Ȃ�ȂǏd�lj����~�}��������܂������A���悻120�̈�Ë@�ւɎ����f��ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
���u�����Ґ����炳�Ȃ������肸���Ƒ����v
�����Ĕ����J�n����5���ԗ]�肽���ē��{��ȑ�w�t���a�@�Ŏ��ꂪ���܂�A���@���܂����B���̕a�@�ً͋}���̍����d�NJ��҂ɑΉ�����3���~�}�̎w��a�@�ł����A�����̏�Ԃ������Ă��āA���h�Ȃǂ���v���������Ă��f�炴������Ȃ��P�[�X���������ł���Ƃ������Ƃł��B���{��ȑ�w�t���a�@���x�~���~�}�Z���^�[ ���x���i�Z���^�[���́u����Ȃɂ����e�̈˗�����������Ƃ����͍̂��܂łɌo�����Ȃ��������ƁB�����閽��������Ȃ��Ȃ��Ă���\���͏\���ɍl���Ȃ�������Ȃ��B�����Ґ������炳�Ȃ������肸���Ƃ���͑����v�Ƙb���Ă��܂��B
������×{���}�� �ٔ�����ی���
�s���ł͎���ŗ×{����l��9���̎��_��1��7356�l�ɏ��A1�����O��11.4�{�ɂȂ�܂����B�ی����ł͗e�̂ɕω����Ȃ����m�F�ɒǂ��Ă��܂��B���� �]�ː��̕ی����ł͂ق��̕������牞�����W�߁A�ʏ��3�{��80�l�Ԑ��ŁA�̒��̕ω����Ȃ�����Z���ڐG�҂����Ȃ����m�F���Ă��܂��B
�E������l��l�ɓd�b�������A�̉���Ǐ�̕ω��ƂƂ��ɋ悪�݂��o�����u�p���X�I�L�V���[�^�[�v���g���đ̓��Ɏ_�f���ǂ̒��x�A��荞�߂Ă��邩���肵�Ă��炢���l������Ă��܂����B����ł��e�̂���������l���������A���悻1�T�ԁA����×{�𑱂��Ă���60��̒j�������t���̎_�f�̐��l���}���Ɉ������Ă��邱�Ƃ�������A�ی��t����t�Ƒ��k���Ȃ�������̕a�@��T����ʂ��݂��܂����B�s�ɓ��@�������˗��������ʁA�j���͓��@�ł����Ƃ������Ƃł��B
�]�ː��ł́A����Ɋ������g�傷������������N�ώ@������Ȃ�A�e�̂��}���Ɉ��������l���@�m�ł��邩��@�������߂Ă��܂��B�]�ː�挒�N���̓V���_�����́u(�×{�҂�)�Ȃ��Ȃ��A�������Ȃ��P�[�X������A�e�̂����������̂ł͂Ȃ����A�����œ|��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɣ��ɋْ������ɂȂ��Ă���B�}�ɗe�̂��������邱�Ƃ������Ă͂����Ȃ��̂Ŗ������N��Ԃ��m�F���Ă���B�d�lj����Ă�����@�ƂȂ�Ɣ��Ƀ��X�N�������A����ȏ�A�����������Ă��܂�������@�悪�Ȃ��Ƃ������ԂɂȂ肩�˂Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂����B
������×{ 8�̃|�C���g
�����A����ł̗×{��]�V�Ȃ����ꂽ���A�l�ʼn����ł���̂��B�Ƒ��ւ̊�����h�����߂̑��Ǐ�̈����ɋC�t���̂ɕK�v�Ȃ��Ƃɂ��āA�����Ǒ�ɏڂ������ۈ�Õ�����w�̏��{�N�Ƌ����ɕ����܂����B���{�����́A�����s���쐬��������×{�Ҍ����̃n���h�u�b�N�ŏЉ��Ă����{�I��8�̃|�C���g���Œ���A����Ăق����Ǝw�E���܂����B
�������邱�Ɓ@/�@���������l�̐��b������l�͂ł��邾������ꂽ�l�ɂ��邱�Ɓ@/�@���������l�␢�b������l�͂��݂��Ƀ}�X�N�����邱�Ɓ@/�@���܂߂Ɏ����Ɓ@/�@�����͂ł��邾�����C�����邱�Ɓ@/�@��̂悭�G��鋤�p������|���E���ł��邱�Ɓ@/�@���ꂽ���l���E�ߗނ���邷�邱�Ɓ@/�@�S�~�͖����Ď̂Ă邱�Ƃł��B
���ׂčs�����Ƃ�����ꍇ�A�Ⴆ�u�������邱�Ɓv������ꍇ�́A���������ł��d���u������߂����G���A���ċ������Ƃ����肷��ȂǁA�ł��邾���H�v�����Ăق����Ƃ��Ă��܂��B
���Ǐ��̒���ɋC�t���ɂ�
����×{���ɏǏ������A���Â��Ԃɍ��킸�ɖS���Ȃ�P�[�X���������ł��܂��B���������ň��̎��Ԃ�h�����߂ɂǂ����������ƂɋC����������̂��B���{�����́u�x���̈����ɔ����Čċz��Ԃ������Ȃ钛����������Ȃ����Ƃ��厖���v�Ǝw�E���܂��B�����ǂݎ�邽�߂ɂł��邱�ƂƂ��āu�p���X�I�L�V���[�^�[�v�Ō��t���̎_�f�O�a�x�����܂߂ɂ͂���A�}���ɉ���������90��������肵���ꍇ�A�����ɕی����ɑ��k���邱�Ƃ������Ă��܂��B�u�p���X�I�L�V���[�^�[�v���Ȃ��ꍇ�ł��A���ő������Ă������F�������O�����߂Ă����肷��ꍇ�ɂ͌ċz��Ԃ��������Ă���\��������Ƃ��āA����������Ԃ��Ƒ��ɋC�t���Ă��炤���ƂȂǂ��厖���Ƃ��Ă��܂��B
��1�l��炵�̗×{�ł�
1�l��炵�Ŏ���ł̗×{��]�V�Ȃ����ꂽ�ꍇ�A�ǂ���������̂ł��傤���B���{�����́u��������Ă���Ƒ��ł��F�l�ł������̂ŁA���܂߂ɘA�������A�A�����Ȃ���Έ��������Ƒ��߂ɋC�t���Ă��炦���Ԃ�z���Ă����K�v������Ǝv���B���ڕی����ɓd�b���Ă��Ȃ��炸�䖝���Ă���l�����邩������Ȃ����A����Ɉ�������Ƌ~�}�Ԃ��ĂׂȂ���ԂɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA�����Ă��炦��l��������x���߂Ď��O�ɘA�����Ă������Ƃ��厖���v�Ǝw�E���Ă��܂��B����ɏ��{�����́u����������×{���邱�Ƃ�z�肵�ĉ�M���ɖ��������A�H���i�Ȃǂ�~���Ă����Ăق����v�ƁA�ӂ���̔���������Ƃ��������ŁA�������Ȃ��ꍇ�ɂ͉Ƒ���F�l�Ɍ��ւ̊O�܂ŐH���i��͂��Ă��炤���ƂȂǂ����߂Ă��܂��B
�����N�`�� 50��ȉ��ւ̐ڎ�������߂� �m����
�������������g���h����D�Ƃ����̂����N�`���ڎ�B�͖�K�����v�S����b�͑S���m����Ƃ̃I�����C���̉�c�ŁA�����͂̋����u�f���^���v�̉e���Ŋ������g�債�Ă���Ƃ��āA�ڎ�̐��i�ɘA�g���Ď��g�ލl�����������܂����B���̒��ŁA�͖�K�����v�S����b�́u�挎���ɍ���҂ւ�2��̃��N�`���ڎ�������ނˊ������邱�Ƃ��ł����B����҂��d�lj����Ă���P�[�X���ڂɌ����Č����Ă���̂́A�F�l�̂������Őڎ킪���Ȃ葬�₩�ɍs��ꂽ���炾�v�Əq�ׂ܂����B�����āu�w�f���^���x�̊����͂������������g�債�Ă��邪�A��������ƃ��N�`����ł��ĉ��Ƃ��d�lj���}���Ă��������v�Əq�ׁA����ɐڎ��i�߂邽�ߒm����ƘA�g���Ď��g�ލl�����������܂����B����ɑ��đS���m����̔ѐ��́u�o���������Ƃ̂Ȃ��w���������x�ƌ����Ă悭�A�܂��ɐ��O����}���Ă���B�Ȃ�ׂ�������]���鍑���ւ̃��N�`���ڎ킪�i�ނ悤�A�����܂��Ă��܂��܂ȍH�v���Â炵�Ăق����v�Əq�ׁA50��ȉ��ւ̐ڎ�̉����������߂܂����B
��1��ڐڎ�͑S�l����46���]
���{��10���Ɍ��\�����ŐV�̏ɂ��܂��ƁA�����ŏ��Ȃ��Ƃ�1��A�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`����ڎ킵���l�͍��킹��5962��9433�l�őS�l����46.9���ƂȂ��Ă��܂��B2��ڂ̐ڎ���I�����l��4328��3582�l�ŁA�S�l����34.0���ƂȂ�܂����B�܂��A����҂ŏ��Ȃ��Ƃ�1�N�`����ڎ킵���l��3109��6194�l�ō���ґS�̂�87.6���ƂȂ�܂����B2��ڂ̐ڎ���I��������҂�2895��6774�l��81.6���ƁA8�����Ă��܂��B�S�l���ɂ̓��N�`���ڎ�̑Ώ۔N��ɖ����Ȃ��q�ǂ����܂݂܂��B�܂��A���ۂ͂���ȏ�ɐڎ킪�i��ł���\��������A����A�������邱�Ƃ�����܂��B
�������s�̊����A1��1���l�̉\���@8/10
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ�������l�ɏ��A�n���ł��������g�債�Ă���B�w�i�ɂ́A�����͂����ɍ����f���^���̓o�ꂪ����Ƃ����B���̂��߁A����́u���B�ŋN�����悤�ȁA�����҂��Z���Ԃɋ}������w���������x�����{�ŋN���Ă���B���{�I�ȑ��}�ɕK�v���v�Ƒi���Ă���B
�����҂ł��ʐl���}��
�u�����s�Ɖ��ꌧ��4��ڂً̋}���Ԑ錾�����z����Ă��玞�Ԃ������Ă��A���҂���Ă����l���̗}���͌���I�ŁA�����Ґ��̑����������Ă���B�s�̖����̊����m�F�҂�5��l���������̂ŁA�������ɍ���́A�V���b�N���čs������������l�͏o�Ă��邾�낤�B����ł��A�����ܗւɉ����ĉċx�݂₨�~�Ƃ����l���𑝂₷�v�f�����邱�Ƃ��l����A���݂̂܂܂ő啝�Ȑl���}���͊��҂��ɂ����v���M��w��w�������Ő��{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̈ψ��ł�����ړc�ꔎ��(������)�́A������y�ςł���v�f�͂Ȃ��ƕ��͂��A�u�s�̐V�K�����m�F�҂�1��8��l����1���l�ɒB���鎖�Ԃ����蓾��B�����͂������A�ŏ��Ɋm�F���ꂽ�C���h�ő嗬�s���N�������ψي��́w�f���^���x���嗬�ɂȂ����B���Ґ��͗ݐς���̂ŁA���Â�K�v�Ƃ��銳�҂͑啝�ɑ��傷��B���݂ł��A�p���N�������Ă����Ì���̕N��(�Ђ��ς�)�x�����͐[�����v�Ǝw�E����B
��40�`50��̏d�NJ��҂�����
���O�̈�́A���N�`���ڎ�̐��i�ō���҂̏d�NJ��҂�����A���ΓI��40�`50��̏d�NJ��҂����Ɣ䗦�̗��ʂő��債�Ă��邱�Ƃ��B�ړc�����́u���̐���́A������x�̗͂�����A�Љ�A�̃j�[�Y�������B�Տ�����ł́A�ł������̎��Â����߂��邵�A��Ñ����Ō�܂ŃT�[�r�X�����v�Ƙb���B���̂悤�ȏł́A����1�l���K�v�Ƃ���@�ނ�l���Ȃǂ̈�Î����͂���܂ł��������A���̕��A��Ì���̕��S���傫���Ȃ�B��4�g�̑��{�ȂǂŋN���������A�K�v�Ȋ��҂ɕK�v�Ȉ�Â��ł��Ȃ��Ȃ�u��Õ���v���N����댯�������܂��Ă���A�Ɗړc�����͊뜜����B
���s�s�����u�\�t�g�Łv��
��Ƃ��āA�W�q�͂�������K�͏��Ǝ{�݂�W���[�{�݂̈����Ԃ̋x�ƁA��K�̓C�x���g�̒��~�ȂǁA��蓥�ݍ��l���}�����K�v���A�Ɗړc�����͍l���Ă���B�u����܂ł̌o�܂���A���H�ƂɁA����ȏ�̕��S�����߂�̂͌����I�ł͂Ȃ��B�ł���Γ��퐶���ɕs���ȓX�܈ȊO�͋x��ł��炢�A�����S�̂ɉ\�Ȍ���̊O�o���l�����߂�A���Ẵ��b�N�_�E��(�s�s����)�́w�\�t�g�Łx�͂ǂ����낤���B���Ԃ�2�T�ԑO��Ɍ���A�����g��̐����͎~�߂��邾�낤���A�����ɂ�����Ă��炦��̂ł͂Ȃ����낤���v�ƌ����B�u�����I�ɂ͂o�b�q�Ȃǂɂ�銴���̗L���̌����ƁA���N�`���ڎ�����m�F�ł��郏�N�`���p�X�|�[�g��g�ݍ��킹�āA�s���͈͂��g�債�Ă������Ƃ��K�v���낤�B�܂��A�ً}���Ԑ錾�̑Ώۂ���C�ɑS���Ɋg�傷�邱�Ƃ��I�����ɂȂ�v�Ƃ݂�B
����Î҂̔Y��
���R�A�����̑[�u�����{����ɂ͎Љ�̗������s�����B���̓_�ɂ��Ċړc�����́u���{����s�����l�Ȃǂ̊�������Ăъ|���鋭�����b�Z�[�W�M����K�v�����邪�A�\���ɂł��Ȃ������B�ܗւȂǂŃ��b�Z�[�W�E���铮�����o�����߂ɁA���ʂ͂ƂĂ��\���ł͂Ȃ��v�ƌ����]������D���̏�Łu�ܗւ�p�������s�b�N�̊J�Ẩۂ��c�_���闧��ł͂Ȃ����A���Ƀp�������s�b�N�̑I��ɂ͋��Z�����Ă��炢�����C�����͂���B�������A���Î҂Ƃ��ẮA���ϋq�J�Â��Љ�ɗ^����C���p�N�g�ƃ��b�Z�[�W�́A������ɗL���ɂȂ邱�Ƃ��ے肵��v�Ƌꂵ�����̓��𖾂������B
���u���~�����߃p�����~���v�����}�g��ŕa�@�̑Ή��]�͌��E�Ɂ@8/10
��s���ł̐V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ŁA�R���i���҂������a�@�̑Ή��]�͂����E�ɋ߂Â�����B�����āA�����NJ��҂���Ԃɂ����@���A����E�h���×{�ɐU�蕪���鐭�{�̕��j�]�����A����̑Ή�������ɓ�����鋰�������B�@(�n�����A�]���ߑY�q)
�����s����̓��{��w���a�@�́A4���ɃR���i�Ή��a��������܂ł�4�{�ȏ�ɑ��₵���B���������݂̊����g���7���ȏオ���܂�A������@���́u�a���͕N�����Ă���ƌ����Ă����v�Ɗ뜜����B���a�@�̃R���i�a���͏d�ǎҗp�̏W�����Î�(�h�b�t)6���ƁA�����ǁ`�d�ǂ̊��҂�f��50���̌v56��������B6�����_�Ŏl�\�������g�p���ŁA�u����1�A2�T�Ԃłǂ�ǂ��Ă����v�Ƃ����B�Ή��X�^�b�t�͑S�f�ÉȂ���W�߂Ă��邪�A�u����ȏ�R���i���҂�������ƁA�Ō�t������Ȃ��Ȃ�A��ʕa���̎���ɉe�����o�邩������Ȃ��v�B
�����NJ��҂Ɋւ��鍑�̕��j�ύX�́u�R���Z�v�g�͂����v�ƑO�����ɑ����Ȃ�����A�d�lj����X�N�̌��ɂ߂̓���𗝗R�Ɂu���ۂɋ@�\���邩�͓���v�Ƃ��B����ł́A�ċz�킪���O�̈�t�����@�̕K�v���f���Ȃ�������Ȃ��P�[�X������Ƃ����B�����@���́u���S�������ē��@���������܂łƕς��Ȃ��Ȃ邵�A����őҋ@�����Ė�����̂��Ƃ��������ꍇ�ɒN���ӔC�����̂��Ƃ����c�_�ɂȂ�v�Ǝw�E�����B
�u���T����R���i�Ή��̂��ߑ��̎�p�͂قƂ�ǒ��~�ɂȂ����B�l�����l����Ȃ�A�p�������s�b�N�͈ꍏ���������~���ׂ����v�B�R���i���҂������s���̕a�@�Ζ��̏�����t(50��)�́A�~���閽���~���Ȃ��Ȃ��Ă��錻��Ɍx����炷�B���̕a�@�ł́A��3�g�̃s�[�N���}����1���A�s�̗v�]���R���i�a����240���Ɋg��B�������A�ܗ֊J�ÑO����̊����}���őΉ��ł���Ō�t���s�����A8���ɓ�����150���܂Ŏ��ꂽ��́A�V���Ȏ�����~�߂���Ȃ��Ȃ����B������t�́u�a���������Ă��A�Ή��ł���Ō�t�̐������|�I�ɑ���Ȃ��B�s�����\�������a�����́A�����I�Ɏ���\�Ȑ��ƕK�������C�R�[���ɂȂ��Ă��Ȃ��v�Ƙb���B����ɍ��T����́A���݂����ꕔ�p�����Ă����p�ȊO�́A�o�Y�������đS�Ē��~�ƂȂ�u�����m���ɋ~���Ȃ��Ȃ��Ă���v�Ɗ�@�������B
�����NJ��҂̓��@���f�ɂ��Ắu����A��t�łȂ��ی����E�����d�b�ŕ������f���邪�A���1�̌����_�f�O�a�x�͎��X�̏ł����Ƃ����Ԃɕω�����B�y�ǂ⒆���ǂł���C�ɏd�lj����鋰�ꂪ����A�������Ɏ���ҋ@�����߂�̂͂��܂�Ɋ댯���v�ƍ��̑Ή���ᔻ�����B
�������a���u�����Ə��Ȃ��v�@�������ʑ҂��ł����@�@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}���ɍL���钆�A�����s���m�ەa�����̊g����}���ł���B�ő�Ō�����6406�����m�ۂł���A��Ò̐��ɗ]�T�����܂��Ƃ���Ă��邪�A�����҂Ƃ��Ă͈����Ȃ��������ʑ҂��́u�^�����ҁv���m�ەa���ɓ���P�[�X�������A���łɁu�����v�������Ă���Ƃ̎w�E������B��ÊW�҂́u�����҂��Ɏ������a���́w���x��肸���Ə��Ȃ��v�ƌx����炷�B
�s��10�����_�ŐV�^�R���i�̊����Ҍ����Ɋm�ۂ��Ă���a����5967���B7���ȍ~�̊����}�g��ŁA6�����{�ɂ�1500�l�O�ゾ�������@���҂́A����10���ɂ�3594�l�ɏ��A�a���g�p����6������B
�s�͕a�����̊g��Ɍ����A7��26���ɓs���̈�Ë@�ւɑ��A�~�}��Â̏k����\�肷���p�̉����Ȃǂɂ��R���i�a���̊m�ۂ�v���B���łɊm�ۂ��Ă��镪�ƍ��킹�A�ő��6406���܂Ŋg��ł���A�a���g�p����56�����x�ɗ��������v�Z�ƂȂ�B
�����A��Ì���ł͂��̐����ȏ�ɕa���̎g�p���i��ł���B�o�b�q�����Ȃǂ̔��肪�m�肷��O�̊��҂ł��A�z���̋^��������Ζ��S�̊����h�~�u����ꂽ�m�ەa���ɓ��@������P�[�X�����邽�߂��B���̏ꍇ�A�u�V�^�R���i�̓��@���ҁv�Ƃ͈���ꂸ�A�s�����\������@���Ґ��ɂ��J�E���g����Ȃ��B
����5���̓s�̃��j�^�����O��c�ł́A�s���S���1��������178�l�́u�^�����ҁv���m�ەa���Ɏ���Ă��邱�Ƃ����ꂽ�B���a��w�a�@(�i���)�̑��ǔ��T�@���́u�����Ō�����ȏ�ɁA����́w�����x�ɋ߂Â��Ă���v�Ƒi����B
���@�ł�38�̃R���i�a���̂���30���]��Ɋ��҂�����Ă���B�����ɂȂ�͎̂��Ԃ̖��ŁA�����̏�����i�߂Ă���Ƃ����B
�a�@���������ÃX�^�b�t���Ɍ��肪���邱�Ƃ��A�u�N��(�Ђ��ς�)���v�ɔ��Ԃ������Ă���B�l�H�S�x���u(�d�b�l�n)�Ȃǂ��g�p����d�NJ��҂ɂ͈�t��Ō�t�A�Տ��H�w�Z�m��10�l���x�̃X�^�b�t���A�g���Ȃ���Ή�����K�v������A���@���҂�������������Ă�������Ȃ��P�[�X���o�Ă���B
���{��w���a�@(����)��56�����m�ۂ��Ă��邪�A�a�����Ă��Ă�1���ɑΉ��ł��銳�Ґ�������A�����v����f�鎖�Ԃ������Ă���Ƃ����B���R���P�a�@���⍲�́u�a�@���Œ������Ȃ����ÃX�^�b�t���m�ۂ��Ă���A���肬��̏�Ԃł���Ă���v�Ɛ�������B
�s�̒S���҂́u��Ë@�ւ�1���Ɏ�����銳�Ґ��ɂ͌��x������v�Ƃ̔F���������A�u�m�ەa�����ƁA���ۂɕa�����Ă��邩�ǂ����͕ʂ̋c�_���v�Ƙb�����B
���ǎ��́u�����Ɏ������a���́A�s���S�̂ł����ɏ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E���A���ۂɑ����\�ȕa���̊m�ۂ�i���Ă���B
���V�^�R���i�̊������͒n���X��n���S�H �������Ȋw�I�Ȓ������@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ʼnߋ��ň��ƌ����Ă��������Ԃ��������Ă���B
��s����ߋE���A���邢�͎D�y�A�����Ȃǂ̑�s�s���Ŗ����A����l�K�͂̊����҂�a�l�����o���Ă���Ƃ����������B
�����͂������������邾�낤�B�����A�ő�̖��_�́A����܂Ő��{����Ɖ�c�A�����s�Ȃǂ��S�͂��X�����ăR���i��Ɏ��g��ł����ɂ�������炸�A�Ȃ��A���݂̂悤�Ȋ��S�����̌����ݏo�����̂��Ƃ������Ƃ��B
���āA�����s���Q�ǂɊW�������Ƃ̈�l�́A���̂悤�Ɍ���Ă����B
�u��w�W�̐��Ƃɑ���g�ۓ����h�������Ƃ����������̌�肾�����B����܂Ő��{�Ⓦ���s�͂��ׂĂ̐ӔC�����ƈ��H�X�ɂ��Ԃ��Ă������A�����̌����͑S�̂̂ق�̐��p�[�Z���g�ɉ߂��Ȃ��B����A����l�K�͂̊����҂����������������ƂŁA���������H�X��������ł͂Ȃ����Ƃ��͂����肵���B�����炭���������̂ЂƂ́A�n���S��n���X�ōL����E�C���X�ɉ������ꂽ��C�ł͂Ȃ����v
��s�s���̒n���X��n���S�ł́A1���ɐ��\���A���邢�͐��S���l�K�͂ŕ��s�҂��q���������A�����œf���o�����ċC�̒��ɂ́A���ʂ̃E�C���X���܂܂�Ă���Ƃ݂���B���̃E�C���X����ԂȂǂɏ������ؐρB�₪�ĖO�a��ԂɒB���A�����Ɋ����͂���������1.5�{�Ƃ����f���^���Ȃǂ��o�����邱�Ƃɂ���āA�ꋓ�Ɋ��������̒i�K�ɓ˓������̂ł͂Ȃ����\�\�Ƃ����������B
�m���ɑ�K�͂Ȋ����g��̒��݂���ꏊ�̒��ɂ́A�n���S��n���X�ɊW�����Ƃ݂��闧�n�����Ȃ��Ȃ��B���̔~�c�A�����̐V�h��r�܂Ȃǂ��B�n���S��]�ː��̊W�҂ɂ��N���X�^�[(�����ҏW�c)�������������Ƃ��������B
�������g�債�Ă���s���͑f�ʂ肵�������B�H�������Ȃ������ɂ�������炸�A�������m�F���ꂽ�Ƃ����A����n���ݏZ�҂́u�n���S�����x����芷�����v�ƌ���Ă����Ƃ����A�����҂��m�F���ꂽ�S�ݓX�̏]�ƈ��́u�n���X�̐H�i�����ɋΖ�����W�҂��犴���҂����l���������Ă���v�ȂǂƘb���Ă����B
�n���S��n���X��Y����C�Ƃ����Ɋ܂܂����ʂȃE�C���X�\�\�B���܂��ɏڂ����������J�j�Y����������Ȃ��V�^�R���i�E�C���X�̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��邽�߁A�������A���炽�߂ĉȊw�I�ȕ��͂��K�v�Ȏ��ł͂Ȃ����낤���B
���m���g�D�y�ȊO�ł������X�� ���߂Ċ������O����h�@8/10
��ؒm���͓��̑��{����c�ŁA�u�����g��Ɏ��~�߂������炸�A�D�y�s�ȊO�̒n��ł��V�K�����Ґ��������X���������Ă���v�Ɗ�@���������A���~�̋A�Ȃ��T����ȂǓ����ɉ��߂Ċ�����̓O����Ăт����܂����B
���̒��ŁA��ؒm���͓����̊����ɂ��āA�u�S���̐V�K�����Ґ���300�l������������Ă���A�D�y�s�ł�200�l������������A�����g��Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��ɂ���B�D�y�s���S����7�����߁A�S�̂������グ�Ă��邪�A���̑��̒n��ɂ����Ă������X���������Ă���v�Ƃ����F���������܂����B
���̏�ŁA��ؒm���́A�u���T���炨�~�̎����ɓ���A�A�ȂȂǂ��T����悤�ɂ��肢���Ă��邪�A�ʏ�ł���Έړ��������Ȏ����ƂȂ�B�������X�N���ł����܂邽�߁A�ő���̌x�������Ăق����B���g�͂��Ƃ��A�Ƒ��A�F�l�̖��ƌ��N�����s����O�ꂵ�Ăق����B��̓I�ɂ́A�s���{�����܂����������T���邱�Ƃ�A�Ƒ��ȂǕ��i��l�Ɖ߂������Ƃ�O�ꂵ�Ăق����v�Ƃ��āA�����Ɋ�����̓O������߂ČĂт����܂����B
���V�^�R���i1166�l�@�d�ǎҐ��g��ŕa�������v���@��ʌ��@8/10
�����ł�10���A�V����1166�l�̐V�^�R���i�E�C���X�̊�����2�l�̎��S���m�F����Ă��܂��B
���������Ȃ��A�d�ǎ҂̐����}���ɑ������Ă��邱�Ƃ��āA���͏d�ǎҗp�̕a�����𑝂₷�悤�A�����̊e��Ë@�ւɗv�����܂����B
���ی���Õ��ɂ��܂��ƁA10���V���Ɋm�F���ꂽ�����҂͒j��1166�l�ŁA1��������̊����Ґ���8���A����1000�l���A�Ηj���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�m�F���ꂽ�����҂̂����A10��̒j��10�l�͊w�Z�œ����������ɏ������Ă��āA���ł͈��������w�Z�̔Z���ڐG�҂̒�����i�߂�Ƃ��Ă��܂��B
�܂��A�S���Ȃ����̂�40���50��̒j��2�l�ŁA��b������������40��̒j���́A����×{���ɗe�̂��}�ς������߁A�~�}����������@���Ă����Ƃ������Ƃł��B
����A�����}�g��ɔ����A�����̏d�ǎҐ���9���̎��_��91�l�ƁA�ߋ��ő���92�l�ɔ��鍂�������ɒB���Ă��܂��B
����Ð����ۂł͍���̏d�ǎҐ��𐄌v�������ʁA9����̍���19���ɂ͌������Ŋm�ۂ��Ă���d�ǎҌ�����165��������Ɨ\�����܂����B
������A����104�̈�Ë@�ւƒ������A����19���܂ł�ڈ��ɏd�ǎҗp�̕a������46�����₵�A211���Ƃ���̐��ɐ�ւ���悤�A��قNJe��Ë@�ւɗv�������Ƃ������Ƃł��B
���_�ސ�̊����ҁA�v10���l���@�u���������v�Ɋ�@���@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�����A�_�ސ쌧����10���A1572�l�̊������m�F����A�����҂̗v��10���l�ɒB�����B�s���{����10���l�����͓̂����A���Ɏ�����3�ԖځB�C���h�R���̃f���^���̊g��Ŋ����҂��}���ɑ������Ă���A������@�������߂Ă���B
�����ŏ��߂Ċ������m�F���ꂽ�͍̂�N1��16���B���N4��15���ɗv5���l�ɒB����܂Ŗ�1�N3�J�����������̂ɑ��A���̌�10���l�܂ł͖�4�J���Ƒ����y�[�X���}�������Ă���B
���O�d���@�V�^�R���i�����g��ň��H�X�ւ̎��Z�v���������� �@8/10
�O�d���̗�؉p�h�m���́A�A���̊����g����A���H�X�ւ̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v������������l���������܂����B
�O�d���ł́A�����g�����8��6���Ɍ��Ǝ��ً̋}�x���錾���o���A�����ɑ��āA���O�ւ̕s�v�s�}�̈ړ����T����悤���߂Ă��܂��B
�܂��A10���͐V����55�l�̊������m�F����A�a���g�p����50���������Ƃ���A�m����10���̉�ŁA���H�X�ւ̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v������������l���������܂����B
�߂��c����J���A��t�炩��ӌ�������j�ł��B
�܂��A�܂h�~���d�_�[�u�ɂ��Ă��A���ɗv�����邱�Ƃ������10�����琭�{�Ə��������n�߂��Ƃ������Ƃł��B
��ؒm���́u�����ɗv������킯�ł͂Ȃ����A�@���I�ɑΉ����Ă����v�Ƃ��Ă��܂��B
�����u�V�䌩���Ȃ��v�������A�����Ɠ������܂Ŋg��u�z��̕K�v����v �@8/10
�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾�����{�Ǝ�s��3���Ɋg�傳��A1�T�Ԃ��o�߂����B�S���ʼnߋ��ɂȂ������g��ƂȂ�A���{�ł�1��������V�K�����҂��t�́u��4�g�v�̃s�[�N���X�V�����B���@���҂͋}���ɑ������A��� �N���Ђ��ς� �̋���������Ă���B
9���̕{���̐V�K�����҂�995�l�B9���܂ł̒���1�T�Ԃ̗v��7980�l�ŁA�l��10���l������ł�90�l�Ɓu��4�g�v�̃s�[�N�ƕ��B�O�T����̑������1�E4�{�ŁA�u�ǂ��܂ő����邩�A�V�䂪�����Ȃ��v(�{����)���B�����s�ł�5����1���̐V�K�����҂����߂�5000�l��˔j�B9�����_�̒���1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ���207�l�Ƒ��̔{�ȏゾ�B�����͂̋����ψكE�C���X�u�f���^���v�́A��s���Ő�s���Ēu������肪�i�݁A����9�����x���߂�B���͂܂�6�����x�Ƃ���A����A����������ɑ�����\���������A�{���N��Õ��́u�����Ɠ������܂Ŋ������g�傷��Ƒz�肷��K�v������v�ƌx������B
���@���҂͂���1�T�Ԃ�1�E4�{�ɑ����A���N�`���̕��y�ŗ]�T���������a�����������Ȃ��Ă����B9�����݁A�d�ǎ҂�112�l�A�y�ǁE�����ǎ҂�1677�l�B�ő�m�ەa���ɑ���a���g�p���͏d��(587��)��19�E1���ɑ��A�y�ǁE������(2531��)��66�E3���ŁA1�T�ԂŖ�20�|�C���g�㏸�����B����×{�҂�6134�l�B��4�g�̃s�[�N(��1��5000�l)�ɔ�ׂ�Ɣ����ȉ������A�h���×{�҂�2399�l�ő�4�g���Ă���B�×{�p�z�e��(4076��)�̎g�p����58�E9���ŁA�{�͋߂�6000���܂ő���������̂́A���e�͂��s������A����×{�҂��}�����鋰�������B
�錾�ɂ��l�o�̗}�����ʂ͎v�킵���Ȃ��B�\�t�g�o���N�n��̂h�s��Ɓu�A�O�[�v�v�̃f�[�^�ɂ��ƁA�i�q���w�̐l�o�́A�錾���ߌ�A�O�T��1�����x�����������Ă��Ȃ��B��4�g�Łu�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����Ă���4�����{�Ɠ��������ŁA�����͊����Ɏ��~�߂�������Ȃ������B���{�̋g���m���m����9���A�����o�ύĐ�����Ƃ̃e���r��c��A�u�錾���ł������҂����������Ă���v�ƌ��O�������A��苭����̕K�v���Ɍ��y�����B
���c�g���E�������勳��(�n�q��w)�̘b �u���̂܂܂ł͑�4�g�̂悤�Ȉ�Â��N�����鎖�Ԃ��z�肳���B�l�o�����炷���߁A��^���Ǝ{�݂ւ̋x�Ɨv�����������ׂ����v
���V�^�R���i�����ґ����X���Ɂ@�����⎖�Ə��ŃN���X�^�[�@�F�{�@8/10
���H�X�ɉc�Ǝ��Ԃ̒Z�k��A��ނ̒�~��v����������߂�Ȃ��A10���������\�����V�K�����҂�90�l�ƁA8�����瑝���X���ƂȂ��Ă��܂��B
�x���͐f�Â��x�ވ�Ë@�ւ������A�x�ݖ����͊m�F�������Ȃ��Ȃ�X�����炷��ƁA�����g��̐������~�܂��Ă��Ȃ����Ƃ�������܂��B
�����Ґ��������グ��v���̂ЂƂƂȂ�N���X�^�[���A3���N���Ă��܂��B
�F�{�s�ł́A���C��w�F�{�L�����p�X�ŃS���t���̊w���j��9�l���B
���Ə��ł́A20�ォ��40��̏]�ƈ��j��10�l�̊������m�F����Ă��܂��B
�܂���Ò��ł́A�w���ۈ�{�݂ŐE���Ǝ������킹�j��8�l���������Ă��܂��B
���a���g�p��50�����@5���ȗ��u�x���4�v4���ڂɊg��@�������@8/10
�����������V�^�R���i�E�C���X�����Ҍ����Ɋm�ۂ���a���̎g�p����9�����_��50�D8���ɂȂ�A�ł��[���ȁu�X�e�[�W4(�����Ҕ����I�g��)�v�̖ڈ�50����2�J�����Ԃ�ɒ������B����Ōx����̎�v7���ڂ̂���4���ڂ��u4�v�̐����ɒB�����B�X�e�[�W3(�����ҋ}��)����4�ւ̈����グ�ɂ��āA���́u���ڐ������ł͌��߂Ȃ��B���H�X�ւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�v���̌��ʂ����ɂߔ��f����v�Ƃ��Ă���B
�a���g�p����50�������̂�5��10�`26���ȗ�2�x�ځB�m�ەa�����͌���425���ŁA����(378�`397��)��葝�������A�����ҋ}���ň�Ò̐��̕N��(�Ђ��ς�)��͐i��ł���B
����6���A�x������X�e�[�W3�Ɉ����グ���B����ɔ����A�������s�Ǝ�q���̈��H�X�ɁA9�`22���̎��Z�c�Ƃ�v�����Ă���B
�X�e�[�W4�ɂȂ�ƁA���H�X���K�͎{�݂ɑ���x�Ɨv����Ǝ��ً̋}���Ԑ錾�A�s�v�s�}�̊O�o���l�v���Ȃǂ��z�肳���B
�x����̏グ�����́A��v7���ڂ̂ق��A��t����Ƃ̈ӌ����l�����A�����ł�����{����c�������I�ɔ��f����B
����ŁA���́u�X�e�[�W3�����v���ڈ��Ƃ����u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�v��������ɐ��{�Ƌ��c��i�߂Ă���B
�����ꌧ���̃R���i�����g��ŕی����̑����Ɩ����ꎞ�x�~�Ɂ@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�Ă��邱�Ƃ��āA�����ی����Ɠ암�ی����͊����o�H�Ȃǂׂ�̐����������邽�߁A10�����獡��13���܂ňꕔ�̑����Ɩ����x�~���܂��B
�����ł�9���A���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ł�����332�l�̊������m�F�����ȂǁA1��������̐V�K�����҂̐����O�̏T�̓����j��������������Ă��܂��B
���������Ȃ��A�����ی����Ɠ암�ی����͊����o�H��Z���ڐG�҂���肷��u�u�w�����v�̑̐����������邽�߁A���H�X�̉c�Ƌ��Ȃǂ����������q����H�i�q���̕���ȂǁA4�̑����Ɩ���10������ꎞ�x�~����Ɣ��\���܂����B
�����̈ꎞ�x�~�͍���13���܂ł̗\��ł����A�V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ���Ă͉�������ꍇ������Ƃ��Ă��܂��B
�����������u�ܗւ͊����g��̒��ړI�����ł͂Ȃ��v�@8/10
�����I�����s�b�N�̊J�Ê��Ԓ��ɁA�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂����������Ƃɂ��āA�������[�����́u�I�����s�b�N�͒��ڂ̌����ł͂Ȃ��v�ƈ��ʊW��ے肵�܂����B
�u���{�Ƃ��ẮA�I�����s�b�N�����݂̊����g��̒��ڂ̌����ƂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��ƍl���Ă���܂��v(�������M ���[����)
�������[�����́A�I�����W�҂ɂ��Ē���I�Ȍ����⌵�i�ȍs���Ǘ������ꂽ�Əq�ׁA�C�O����̓����҂��悻4��3000�l�̒��ɁA�V�^�R���i�̏d�ǎ҂�1�l�����Ȃ����Ƃ��������܂����B
�I�����s�b�N�J�Âɂ�鍑���̋C�̊ɂ݂��w�E���鐺�ɑ��ẮA�u�l�X�Ȍ���������Ǝv���v�Ƃ��������ŁA�u�J�Ê��Ԓ��̓����̖�̐l�o�����炩�Ɍ����������Ƃ͎����v�Əq�ׁA���̎w�E�ɔ��_���܂����B
���u�ܗ֊J�� �����g��̌����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��v�ې�ܗ֑� �@8/10
8�������������I�����s�b�N�ɂ��āA�ې�S����b�͋L�҉�ŁA���ł͐V�^�R���i�E�C���X��̓O���}�����Ƃ��āA�����g��ɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��Ƃ����F���������܂����B
���̒��ŁA�ې�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�S����b�́A8�������������I�����s�b�N�ɂ��āu���W�ҁA�{�����e�B�A�A��Ï]���҂̋��͂�s�͂ɂ���Ė����ɑ����I�������ƂɐS���犴�Ӑ\���グ�����v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁA�I�����s�b�N�ł̐V�^�R���i�E�C���X��ɂ��āu�I�����W�҂ւ̒���I�Ȍ����⌵�i�ȍs���Ǘ��A���N�Ǘ��Ȃǂ̖h�u��̑[�u���A�g�D�ψ���Ƃ��A�g���Ȃ���O���}�����B���̂����_�ŁA�C�O����̓����҂��悻4��3000�l�̂����A�z���҂͗v151�l�ŁA�d�ǎ҂͏o�Ă��炸�A�I�����s�b�N�̊J�Â͊����g��̌����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����̂ƍl���Ă���v�Ǝw�E���܂����B
�܂��A�p�������s�b�N�̊ϋq�̈����ɂ��ẮA8��24���̊J���܂łɁA�g�D�ψ���Ⓦ���s�AIPC�����ۃp�������s�b�N�ψ���Ƌ��c���Ĕ��f����l�����d�˂Ď����܂����B
���g�ې씭���h�� �u��������Ȏ�������������Ă�ꍇ�ł͂���܂���v ��t�@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�������҂̑Ή��ɂ�����Ȃ���TBS�uN�X�^�v(���`���j��3�E49)�ȂǑ����̃e���r�ԑg�Ƀ����[�g�o���𑱂��Č���̔ߒɂȐ���i�������Ă���u�C���^�[�p�[�N�q���ċz����ȁv(�Ȗ،��F�s�{�s)�̑q���m�@����10���A���g�̃c�C�b�^�[���X�V�B�ې���ܗ֒S����(50)�̔��������������B
�ې��b��10���ɍs��ꂽ�t�c��̋L�҉�ŁA�����ܗ֊��Ԓ�(7��23���`8��8��)�ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��������������Ƃɂ��āu�ܗւ̊J�Â͊����g��̌����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����̂ƍl���Ă���v�Ɣ����B��������͔ᔻ�̐����������ł��邪�A�q���@���͂��̂��Ƃ��j���[�X��\��t������Łu��������Ȏ�������������Ă�ꍇ�ł͂���܂���v�ƃo�b�T���B�u����͂̂��ɉȊw�I�ȕ��@�Ŗ��炩�ɂȂ�܂��B�n�E�X�I�Ƃ͌����܂���̂ŁA�A�A�A�v�Ƒ����ĐÂ��ɓ{����ɂ��܂����B
�ې��b�͍��ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃g�[�}�X�E�o�b�n�(67)�������ܗ֕�������9���[���ɓ����E������U�����ɂ��Ă��u�܂�14���Ԃ�������Ɩh�u�[�u�̒��ʼn߂����Ă��������Ă��邩�Ƃ������Ƃ͏d�v�ȃ|�C���g���Ǝv���܂��B�����ĕs�v�s�}�ł��邩�Ƃ������Ƃ́A������������育�{�l�����f���ׂ����̂ł���܂��v�ƌ��A�ɖ��𒍂����B
���V�^�R���i�����g��u���~���Ԓ��̋A�� �ɗ͍T���āv�@8/10
�V�^�R���i�̊����g����A�ً}���Ԑ錾���ߒ���6�s�{���ƒS����b�ɂ���c��9���A�J�Â���܂����B
�����N���o�ύĐ��S����b�́A9���̃I�����C����c�Łu�����҂̑����́A����܂Ōo���������Ƃ��Ȃ����������B�K�Ȉ�Â����Ȃ��Ȃ肩�˂Ȃ��������v�Ɗ�@���������܂����B
���̂����ŁA6�s�{���̒m���ɑ��A�s�v�s�}�̊O�o���l���Ăт�����悤�v�����A���ɂ��~���Ԃɂ��āu�A�Ȃɂ��n���ւ̈ړ����ɗ͍T����悤�Ăт����Ăق����v�Ƌ��͂����߂܂����B
����A�m��������͂��ꂼ��̊�����Ǝ��̎��g�݂�����܂����B
��c�I����A�L�Ғc�̎�ނɉ������F�J��t���m���ɂ��܂��ƁA�m����͍��ɑ��A1�s3���ɂ����K�͏W�q�{�݂ւ̋x�Ɨv������������悤���߂܂������A������b�͊e���̕a���̏ŁA���ꂼ��̒m�������f���ׂ��Ƃ̔F���������Ƃ������Ƃł��B
��t���ł�7���A����̐V�K�����҂��ߋ��ő����X�V���A�d�ǎҗp�̕a����5������Ȃnj������������Ă��܂��B��t�� �F�J�r�l�m���u�����z�肵�Ă����ň��̕����ɐi��ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�ł�����肱��ȏ�̊����g���h���ł����Ȃ���A��Ò̐��������Ȃ��ɂȂ�B�����̊g���}������悤�ɁA�����ւ̌Ăт����ƈ�Ò̐��̍X�Ȃ鐮���Ɏ��g��ł��������v
������͊w�Z�W�҂̂݁A���t�͉\�Ɂ@�Ă̍b�q���R���i��@8/10
���Ɍ����{�s�̍�_�b�q�������10���A�J��������103��S�����Z�싅�I�茠�ł́A���t�̑�93��I�����Z�싅���ɑ����āA�V�^�R���i�E�C���X�̊g���h�����߁A���܂��܂ȑ{����Ă���B
���t�̃Z���o�c�ł�1�����̊ϋq�̏����1���l�������B�V�^�R���i�̊����g�����2�N�Ԃ�̉Ă̍b�q���ł͓���҂͊w�Z�W�҂݂̂ŁA����Ȃ�1�Z������2000�l���x��F�߂Ă���B
����A�u���X�o���h�̉��t�́A���t�̃Z���o�c�ł͋֎~����^�������������g�p�������A������50�l�ȓ��Ȃ�A���v�X�Ȃł̉��t���\�ɂȂ����B
��\49�Z�͑��O�Ə��폟����A���X����������̍ő�3��PCR���������{����B�R���i�����҂����������ꍇ�ً͋}���{����ݒu���A�ʎ��ĂƔ��f�����A�`�[���̏���܂ł͑I������ւ��邱�Ƃ��ł���B
���ی����ɖ����@�����яオ��u��5�g�v�̊����g��o�H�@8/10
�V�^�R���i�E�C���X���Ăі҈Ђ��ӂ邢�A�����҂ւ̑Ή��ɂ�����ی����͑��Z���ɂ߂Ă��܂��B���̋Ɩ��ɖ�������ƁA��5�g�̊������ǂ̂悤�ɍL�����Ă���̂��A���炩�ɂȂ��Ă��܂����B�Ђ�����Ȃ��ɖ葱����d�b�B�v���Ďs�ی����̐V�^�R���i��`�[���ł��B
�ی��t�u�������炢�H���߂ĔM���o�����A38�����炢�ł��ˁB�v�����҂₻�̐ڐG�҂ƘA��������āA�ǂ̂悤�ȍs�������������ׂ���A��Ë@�ւƂ̒����Ȃǂ̋Ɩ��ɒǂ��Ă��܂��B
�v���Ďs�ی����E�c���_�V�ے��u�����炪�ی��t�̓��A��Ò����B��Ë@�ւ���̔����͂����ƂɁA���̐l�̏������ǂ����邩�h�N�^�[�Ƙb���Č��߂Ă���B�v�v���Ďs��7�����{�ɂ͊����҂��[���̓�������܂������A8����1�T��1�T�Ԃ�180�l�Ƌ}���B�R���i��`�[����ʏ��2�{�̖�40�l�ɑ��₵�܂������A�Ɩ��͘A���[��܂ŋy��ł��܂��B
�v���Ďs�ی����E�c���_�V�ے��u7���̉��{����5�g�̓�����Ŋ����g��A�v���Ăł������g��A�Ȃ�Ƃ���肭�肵�Ă���v�����Ō����Ă��������o�H�̈���u�E��v�ł��B
�ی��t�u�ꏏ�ɓ�����������ڐG���x�ɉ����Č����ɂȂ��邪�A�悢���v�d�b�̑���͂�����H�X�̒S���ҁB�������������܂����B������38���̔��M������܂������A���������Ǐo��2���O������͂Ɋ��������邨���ꂪ���邽�߁A�Ζ����d�Ȃ��Ă����l��A�E��̊�������m�F���܂��B
�ی��t�u�o�ΑO�̑̉�����͂��Ă��܂����A�}�X�N�̒��p�͂��Ă��܂����B�{�l�ƈꏏ�ɓ����Ă����l��4�l�ő��v�ł����ˁB�v������������e����t�Ƌ��L���A�Z���ڐG�҂Ȃǂ���肵�Ă����܂��B
�ی��t�u�C���J���Ƃ����W�ƃp�\�R���A���p���������ď��ł��O�ꂳ��Ă��Ȃ��B�v
��t�u�Z���ڐG�҂̓[���ŁA�ڐG��4�l�ŁB�v���p���Ďg����������܂������A�}�X�N�ȂNJ�{�I�Ȋ�����͂ł��Ă������Ƃ���A�E��̓���4�l�́u�Z���ڐG�ҁv�ł͂Ȃ��A�u�ڐG�ҁv�ƂȂ�܂����B�u�Z���ڐG�ҁv�͊����҂ƍŌ�ɐڐG����������2�T�Ԃ̎���ҋ@�A�u�ڐG�ҁv�͂o�b�q�����̉A�����m�F�����܂ŁA����ҋ@�����߂��܂��B�ی������u�ڐG�ҁv��1�l�ɘA�������ƁB
�ی��t�u���͈Ⴄ���ɂ��Ă���Ȃ��ł����ˁA����̂́A�z����������A�܂���������ڐG�ҁA�����̐l�������̑ΏۂɂȂ�\��������̂ŁB�v�A�Ȃ��邽�߁A�o�b�q�����̌��ʂ��o��O�ɔ��e���Ŕ���肽���Ƃ����܂��B
�ی��t�u���肢��������ǁA��ɍs���@�I���͂Ȃ��̂ŁA�ڐG�҃��x���ōs�������ł��Ȃ��B�K�v����������āA���Ƃ͂��肢�ɂȂ�B�v�O�o���l���Ăт����܂����A������͓̂���Ƃ����܂��B�����ɂ��Ċ����͂̋����f���^�����L����A�s�������̑������S�z����Ă��܂��B
�v���Ďs�ی����E�c���_�V�ے��u����̓����Ƃ��Ă͊����o�H�s���̊��������\����B�ǂ��Ŋ����������A������Ȃ��P�[�X�����\�o�Ă���B�v�s�������̑����ɂƂ��Ȃ��A�E�C���X���ƒ���Ɏ������܂�邨��������܂��Ă��܂��B
�ی��t�u�̒��͂ǂ�Ȃł����A���j��ɔM���ł��ˁB�v�d�b�̑���́A���̓��������m�F���ꂽ���A�w�̒j�̎q�̕�e�ł��B�ŏ��ɕ��e���������A��������ق���4�l��Z���ڐG�҂Ƃ��Č��������Ƃ���A�j�̎q�̊������m�F����܂����B���e�̓z�e���×{����]���܂������A�����̋}�g��ŁA�����ɒ��������܂���ł����B�����ԁA����Ŋu�����������A���̌�A�悤�₭�z�e���Ɉڂꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�ی��t�u�����Ƒ��͔Z���ڐG�҂ɂȂ邪�A�������ǂ�����ƔO���ɒu���ĉƒ���ł��u���A�ƒ���ł��}�X�N������A���C������A��{�I�ȂƂ����O�ꂵ�Ă��炤�悤�`���Ă���B�v���N�`���ڎ���{���ڎw���v���Ďs�ł́A���łɐl���̂��悻������1��ڂ̐ڎ���I���Ă��܂��B�����҂�6����20�ォ��30��ŁA���܂̂Ƃ���d�ǎ҂͂��܂���B��t�ł�����ی����̐E���́A�u���N�`���̌��ʂ��o�Ă���v�Ƃ��Ȃ�����A���f�����Ȃ��悤�Ăт����Ă��܂��B
��t�u���N�`����100���h�����̂ł͂Ȃ��̂ŁA�����2��ł��Ċ��������l������̂Ŗ��f�͂ł��Ȃ��A�]���ʂ�̊�����͕K�v���Ǝv���B�v�ߋ��ɗ�̂Ȃ������҂̑������������Ă���u��5�g�v�B�E���ƒ�ł̊����g�傪�����Ă��āA�g�̉��ł̑��܂܂ňȏ�ɕK�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�����܂郍�b�N�_�E���_�@�����h�~��l�܂�\�u�Ō�̎�i�v���͐T�d�@8/10
�V�^�R���i�E�C���X�V�K�����҂̋}�����A���b�N�_�E��(�s�s����)���\�ɂ���@���x����{�ł��������ׂ����Ƃ̐������Ƃ⎩���̂̊Ԃŋ��܂��Ă����B���݂̘g�g�݂ł͌���I�ȋ����[�u������ꂸ�A�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��Ƃ̏ł肩�炾�B���`�̎͐T�d�����A�����}����������������߂�ӌ����o�Ă���B
�u���b�N�_�E�����������Ăق����v�B�܂h�~���d�_�[�u�̒n��g�傪���܂���5���A���{�̊�{�I�Ώ����j���ȉ�Ő��Ƃ��炱��Ȑ����オ�����B���ȉ�̔��g�Ή�͋L�Ғc�ɁA������}�����߂Ȃ���u���b�N�_�E���̖@���������c�_���Ȃ�������Ȃ��Ȃ�v�ƌ�����B
�S���m������u���b�N�_�E���̂悤�Ȏ�@�݂̍���̌����v�Ȃǂ荞�ً}���܂Ƃ߂Ă���A�����s�̏��r�S���q�m����3���̃e���r��c�Łu�@�����Ȃǂ̕K�v�����܂߂ċc�_���ׂ������ɗ��Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ƌ��������B
���b�N�_�E���͉��Ă𒆐S�Ɏ���Ă�����@�����A�c�Ƌ֎~���ʋ@�֒�~�ȂǁA���ɂ���ē��e�⋭���͂̋����͈قȂ�B���Ƃ��u�����Ȓ�`�͂Ȃ��v�ƌ��B
�V�^�R���i��̓��ʑ[�u�@�́A�������Ȃ���Ώۂ����Ǝ҂ɋx�Ƃ�c�Ǝ��ԒZ�k�𖽂���ꍇ�Ɍ��肵�Ă���B���Ƃ�m����́A���b�N�_�E���̋�̑��m�ɂ��Ă��Ȃ����A�l�ɑ��锱���t���̊O�o���l���߂Ȃǂ��O���ɂ���悤���B
�����A���{�͂��܂̂Ƃ��냍�b�N�_�E���ɂ͐T�d���B�͐挎30���̋L�҉�Łu���{�Ƀ��b�N�_�E���Ƃ�����@�͂Ȃ��܂Ȃ��v�Ɩ����B�u���B�ł̓��b�N�_�E�����Ă��A�Ȃ��Ȃ��o���͌����Ȃ������B���ʓI�ɂ̓��N�`���������v�Əq�ׁA�u��D�v�ƈʒu�t���郏�N�`���ڎ�̐��i�ɑS�͂�������l�����B
�w�i�ɂ́A�u���b�N�_�E���͌o�ςւ̑Ō��ɂȂ�v(���{�W��)�Ƃ̌��O������Ƃ݂���B�����𐧌�������e�̂��߁A���{�����́u�����͂̋����@�Ă𐬗�������̂͑�ς��v�Ǝw�E����B���̂��߁A�ƌ����}�̎R���ߒÒj��\��3���̉�k�ŁA�@�����ɐT�d�ȗ���ň�v�����B
�Ƃ͂����A�ً}���Ԑ錾�̌��ʂ͔������A�����}����������b�N�_�E�������͔������Ȃ��Ƃ̐����o�n�߂Ă���B���������������4���̃e���r�ԑg�Łu�Ȃ��܂Ȃ�����c�_���Ȃ��ł����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׁA���ɓI�ȎɈ٘_���������B�u�V���ȕψي��Ń��N�`���������Ȃ��Ȃ����Ƃ��ɂǂ�����̂��v�Ƃ��āA�u���N�`����{���v�̎p���ɂ��^��𓊂��|�����B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
���ې�ܗ֑��A�������[�������u�ܗ֊J�Â͊����g��̌����ł͂Ȃ��v�@8/11
�ې���ܗ֑���10���ɍs��ꂽ�t�c��̉�ŁA�ܗ֊��Ԓ��ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�����Ƃɂ��āA�u�I�����s�b�N�̊J�Â͊����g��̌����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����̂ƍl���Ă���v�ƈ��ʊW��ے�B�܂��A���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃g�[�}�X�E�o�b�n�(67)���A�����O�ɓ����E������U�����Ƃɂ��Ắu14���Ԃ�������Ɩh�u�[�u�̒��ʼn߂�����Ă��邱�Ƃ��d�v�ȃ|�C���g�v�u�s�v�s�}�ł��邩�ǂ����́A���{�l�����f���ׂ����̂ł���܂��v�ƌ�����B���������������傫�Ȕg����Ă�ł���B�@
�ɂ��ƁA�ܗւƊ����g��̈��ʊW�ɂ��āA�ې�ܗ֑��͊C�O������������I�����W�Җ�4��3000�l�̂����A9�����_�ŗz���҂��v151�l���������ƂȂǂ��A�u���ʊW���Ȃ��v�����Ƃ��ċ������B�������M���[�����������ɍs�����L�҉�ŁA�u���{�Ƃ��ẮA(�ܗւ�)���݂�(�R���i)�����g��̒��ڂ̌����ɂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��v�Ɛ����B�u�����̖�ԑؗ��l���͌��������B�����̕����A���A���{�l�I���̊��������Ŋϐ킵�A�����������Ƃ̕\�ꂾ�v�Ɨ͐������B
�u���͓����ܗւ����{��������p���������I���K�V�[(��Y)�ɂ������B�������̌��тɂ��邽�߂ɂ��A�R���i�̊����g��ƌܗ֊J�Â̈��ʊW��F�߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B�ې�ܗ֑��A�������[�����͐��Ɂw�E�����E�x�Ȃ̂ŁA�w���ʊW�͂Ȃ��x�ʼn����ʂ������Ȃ��̂ł��傤�v(�e���r�̐������L��)
�v���`���Ă����V�i���I�͕��ꂽ�B�����}�W�҂́u�����ܗ֊J�Âɔ��̐��͑����������A�����n�܂�A���{�l�I�肪���č����̊ԂŁw�ܗւ�����Ă悩�����x�Ƃ�����C�ɂȂ邾�낤�v�Ƒ��O�ɘb���Ă����B�����A���{�l�I�肪���_�����b�V���Ő���オ��̂ƁA�R���i�̊����Ґ������������钆�Ő��������ӔC���ʂ����Ȃ��܂܁A�ܗ֊J�Âɓ��ݐ����͕̂ʖ�肾�B�����͗�ÂɌ��Ă���B
SNS�A�l�b�g��ł́u�ܗ֊J�ẪA�i�E���X���ʂ͑傫�������Ǝv����B�݂�Ȃ��݂�Ȑ��{�̌������Ƃ��Ȃ����B�ܗ֊��Ԓ��ɓs�s����ό��n�̐l���͉�����ǂ��납�オ�鏊�����������B����ɔ�Ⴕ�ăR���i�����҂������I�ɑ����Ă܂��܂��V�䂪�����Ȃ��v�A�u���ʊW���ؖ�����͓̂���ł��傤�ˁB�ł��A�����g��̈ꏕ�ɂ͂Ȃ��Ă���Ǝv���܂���B���ǐl����}������Ƃ����Ă��ܗւ��J�Â��Ă���A���Ōܗւ͈ړ����Ă������Ă��ƂɂȂ�܂���B�������{�̂������������͏��Ȃ��ł��傤�v�ȂǗ��₩�Ȑ��������B
�O�o�̎����}�W�҂́u�ܗ֊J�Ò��͓��{�l�I��̊������ᔻ�́w���悯�x�ɂȂ��Ă������A��������������C�ł͂Ȃ��B�����̍����������ɕs�M���������A�{�肪���܂��Ă���B�R���i�̊����҂�����ɑ������琛�����͎������������邩�B�����I�ȏ��}���Ă���Ǝv���v�Ɗ�@�������ɂ���B
����9���ɊJ�Â��ꂽ����̕��a�F�O���T�ɏo�ȁB�ɂ��ƁA�u�J�Â�1�N��������A�l�X�Ȑ���̂��Ƃł̑��ƂȂ������A�J�Í��Ƃ��Ă̐ӔC���ʂ����Ė����ɏI���邱�Ƃ��ł����B�I��̊F����A�劈�����B�f���炵�����ɂȂ����v�Ɠ����ܗւ̈Ӌ`�����������Ƃ����B
�R���i�͊����g��̈�r�����ǂ��Ă���B�����ܗւ̋��Z���Ől���݂��ł��Ă�����i������ƁA�ً}���Ԑ錾���}�~�͂ɂȂ��Ă���Ƃ͌�����B�����̕s���͖c��ނ��肾�B
���������A�f���^�����o77���@57�l�����m�F�A�a���g�p��8�����@8/11
����10���A������57�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B9���ɗz���Ɣ��������B�����̊����m�F�͉���6619�l�B���ɂ��ƁA�C���h�R���̕ψي��u�f���^���v�̉\���������uL452R�v�ψق̌��o����77�D0���ɏ���Ă���A�u������肪�}���ɐi��ł���B
���ɂ��ƁA2�`8���ɗz���Ɣ�������655����486�������������Ƃ���A374����L452R�ψقŁA�O�T(7��26���`����1��)�ɔ�ׂ�7�D9�|�C���g���������B���̂���227���������������킫�s�ی����Ǔ��ł̌����ł�218�����߂Ă���A���o����96�D0���B�Q�m����͂̌��ʁA�V����35�����f���^���Ɗm�F����A�v44���ƂȂ����B
9�����݂̐V�^�R���i�E�C���X�̓��@�Ґ��͏d��10�l���܂�416�l�ŁA�a���g�p����83�D9����5��16���ȗ��A��3�J���Ԃ��8�������B94�l���h���×{�A334�l������×{���Ă���B�×{�撲������37�l���܂߂��×{�Ґ���881�l�ʼnߋ��ő����X�V�A�l��10���l������̗×{�Ґ���47�D72�l�ƂȂ�A�a���g�p���A����1�T��(3�`9��)�̐V�K�z���Ґ�(32�D39�l)�ƂƂ��ɃX�e�[�W4(�����I�����g��)�̐���������Ԃ������Ă���B
57�l�̓���́A���킫�s28�l�A�����s8�l�A�S�R�s7�l�A��Îᏼ�s�A�{���s�A�쑽���s���e2�l�A���n�s�A��{���s�A�{�{�s�A���Β��A�ΐ쒬�A�L�쒬���e1�l�B���O��2�l�B
57�l�̒��ɂ́A�����s��9���ɔ��\�����������ō��̉^�����ł̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�ɂ�銴����5�l���܂܂��B�܂��A���킫�s�̎����{��(106����)�ŐV���ɗ��p��1�l���z���Ɣ������A�N���X�^�[�͌v64�l�Ɋg�債���B����A14�l�̊����o�H���s���B
���ɂ��ƁA9���܂ł�18�l���މ@�A21�l���h���×{�{�݂�ޏ����A9�l�̎���×{�����������B
���ߋ��ő��@85�l�V�^�R���i�����@�����S��x���������@���Q�@8/11
���Q����10���̌����̑���l�Ƃ��āA�V����85�l���V�^�R���i�Ɋ��������Ɣ��\�����B������1���̊����Ґ��Ƃ��Ă�3����59�l��啝�ɏ���ߋ��ő��B
�S���I�Ɋ������}�g�傷�钆�A�����ł�1���̊����҂�30�l������������A�����͗\�f�������Ȃ��B
������3�A�x��������10���̌������ʂ̑���l�ł́A�V����85�l�̊������m�F���ꂽ�B������1���̊����Ґ��Ƃ��Ă�3��25�����\��59�l��啝�ɏ���ߋ��ő��B
���́u�����S��Ōx�������߂Ăق����B���ɏ��R�s�̐l�́A�l�Ƃ̐ڐG���T���A��H��A�Ȃ̗\��̒��~�〈����̌������������肢�������v�ȂǂƊ�������s���̓O����Ăт����Ă���B
�����m���́A11���ߌ�A�Վ��L�҉�ŁA���Ǝ��̊����x�����x���̈����グ�Ȃǂɂ��Č��y������̂Ƃ݂���B
���ߋ��ő�85�l�����m�F�@���R�s���ˏo�̈���őS���ɂ��g��@���Q�@8/11
�ߋ��ő��̊����Ґ��m�F�ƂȂ������Q�����̏��ڂ������Ă����܂��B
3�A�x�����̌������ʂƂ������ƂŊ����Ґ��̑������S�z����Ă��܂������A�ߋ��ő���85�l�B
����܂łōł���������3�����{��59�l��傫������܂����B
3����59�l�͑�4�g�̔��[�ƂȂ������R�s�ɉ؊X�̑�K�̓N���X�^�[�ɂ����̂ł����B
��4�g�ł́A���R�s�̔ɉ؊X�N���X�^�[���犴��������E�n����Ĉ��Q�����S��Ɋg�債�܂����B
3�����{����5���O���ƒ����Ԃɂ킽��A�����Ґ���2���̏�Ԃ������ȂǁA��4�g�����z����܂łɖ�2�J���ƒ������Ԃ�����܂����B
7�����߂���܂ł͈��Q�����̊����҂͗�����������Ԃł������A7�����{���珙�X�Ɋg�債�A8���ɓ����Ă���}�]�A�����҂�20�l��㔼����50�l��ƂȂ�A11���ɉߋ��ō���85�l�ƂȂ�܂����B
����85�l�̊����҂̓��������ƁA���R�s��36�l�Ɠˏo���Ă��܂��B
���̂����V�K��12�l�ŁA���R�s���ł��l�X�ȏꏊ�Ŋ������m�F����Ă��܂��B
�����m���u��4�g�̔ɉ؊X�N���X�^�[�̂悤�Ȉꕔ�̋Ǐ��I�ȏ�ʂŏW���I�Ȋ������m�F���ꂽ���̂ł͂���܂���B�����e�n�A�S�̂ł͂���܂���A���ɏ��R�s�ł͗l�X�ȏꏊ�Ŋ����o�H���s���ȑ����̎��Ⴊ�������āA���ꂼ�ꂪ�������L���Ă���ɂ������܂��v
�����āA�m�����x���������߂Ă����̂��V���l�s�ł��B
11���Ɋm�F���ꂽ15�l�̂���9�l���V�K�̗z���m�F�ł����B
�V�K�̊����҂�������Ƃ������Ƃ́A���ʉ��ł̊����̍L���肪���O����܂��B
���̂ق��A��F�s��S�k���ȂǓ�\�n��ɂ��U���I�Ɍ����A�f���^�����S�̌��݂̊����͑S���Œ��ӂ��K�v�ł��B
�����ĔN��ʂł́A85�l�̊����҂̂����A20�`50�オ7�����߁A��������̐���̊����������m�F����Ă��܂��B
�N���X�^�[�́A���݁A6���Ⴊ�������ŁA�����s�̎��Ə��ł͐V����5�l�A���R�s�̃z�X�g�N���u�̃N���X�^�[��2�l�A���̑���1�l�������Ă��܂��B
���Q�����̈�Ñ̐������Ă݂�ƁA��Ë@�ւɓ��@���Ă���l��82�l�A�d�NJ��҂�1�l������5�l�A�����āA����×{�҂͍���A���@�������̕����܂߂Ĉ�C��73�l������193�l�ƂȂ�A��Ì���̕��S�͌����Ă��܂���B
�����m���͂����������݂̊������4�g�Ƃ͈قȂ�ƌx�����Ă��܂��B
�����m���u�����̊����́A����܂łƂ͊��S�ɕʂ̋ǖʂɓ˓������A�ƁB��4�g������ɂȂ��Ă��Ă���ƌ��킴��܂���B���R�s���������o���ƃX�e�[�W4�ɓ����Ă���B�{������w��������x�Ɉ����グ�����Ă��������܂��v
�����E���̏o�Ύ�5���팸�c�����g����ʌx��o�����x�R���@8/11
�V�^�R���i�E�C�X�́u�����g����ʌx��v���o�������́A11������E���̏o�Ύ҂�5���팸������g�݂��n�߂܂����B
����́A����10���ɏo���������g����ʌx��ɂ��킹�A���ɓ���ʋΎ��̌�ʋ@�ւȂǂ̖�������邽�߂ɍs������̂ł��B
�ΏۂƂȂ�̂͒m�����ǂ̐E�����悻3600�l�̂����A�R���i����@�Ǘ��̒S���҂Ȃǂ��������悻2000�l�ł��B
���Ԃ�11�����瓖�ʂ̊ԂƂ��Ă��āA�ݑ�Ζ��⎞���o�A�x�ɂ̎擾�ɂ�蒡�ɓ��̐E����ʏ��5�����x�ɗ}����Ƃ������Ƃł��B
���l���ہ@�R�{�����q�ے��u�e��ƁA���ԋƎ҂�(�o�Ύҍ팸��)���g�݂��i��ł��邱�ƂƎv�����A����̌x�o����A���������g�݂��n�߂����Ō����ɂ��L�����Ă����Ǝv���v
�����o�Ύ҂̍팸������̂́A���N�̑S���ً̋}���Ԑ錾�ȗ�2�x�ڂł��B
���x�R���������g����ʌx��@�܂h�~�̗v�������@8/11
�x�R����10���A�����ŐV�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂���@�҂̑����������Ă���Ƃ��āA�Ǝ��́u�����g����ʌx��v���o�����B�Ǝ��̌x�����x�������݂̃X�e�[�W2����X�e�[�W3�Ɉ����グ�邱�Ƃ�A�ً}���Ԑ錾�ɏ������u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�v�������}�Ɍ�������B�V�c���N�m���́u����܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��ǖʂɓ����Ă����v�Ɗ�@���������A�����h�~��̓O����������߂��B
���͓����A35�l�̊������m�F�����Ɣ��\���A�����̊����m�F�͌v2649�l�ƂȂ����B����1�T�ԕ��ς̓��@�Ґ���9�����_��151�E0�l�B�x�����x���̔��f�w�W�̊�ƂȂ�140�l�������������B
���̓X�e�[�W3���ڑO�ɔ����Ă���Ɣ��f�B��Ò̐����N��(�Ђ��ς�)���A�����ɋ������l�v�����s�����Ԃ�����邽�߁A���N5���ȗ��ƂȂ���ʌx����o�����B
�����ɂ͌��O����̋A�Ȃ��܂߁A�S�s���{���Ƃ̉��������l����ƂƂ��ɁA�����O���킸���i����Ă��Ȃ��e�ʂ�F�l��Ƃ̉�H���T����悤���炽�߂ČĂъ|�����B�Z���Ԃł���b�̍ۂ̓}�X�N�𒅗p���邱�Ƃ����߂Ă���B
�����ł�11�����猧�E���̏o�ΎҐ���5���팸���A���c�{�݂̊����h�~����ēO�ꂷ��B
�V�c�m���͌����ň�Â�o�ρA����֘A�̗L���҂���ӌ�������ŁA�R���i���{����c���J���A���ʌx����o�����Ƃ����߂��B�����Č���t��̔n���叕��Ɖ���A�X�e�[�W3�ɂȂ�A�s�v�s�}�̊O�o���l�����߂�ق��A�x�Ƃ�c�Ǝ��ԒZ�k�̗v������������Ƃ��u�s���������}���ɍL�����Ă���B�����ْ����������Ăق����v�Ƙb�����B
�n����́u�X�e�[�W3�Ɉڍs����Έ�Ì��ꂪ�ꂵ���Ȃ�A��ʂ̐f�Â��ł��Ȃ��Ȃ�B��������F�����Ă��炢�����v�ƌ�����B
���R���i���������@��@�����L�����O����@����@8/11
����ŐV�^�R���i�E�C���X�����������I�Ɋg�債�Ă���B4����602�l���m�F����Ĉȍ~�A8���܂�1��������̊����҂͘A��500�l���A���~�܂肪�����B4�������1�T�ԂŊ����Ґ���3601�l�ɏ��B10���l������̐l����̊����Ґ����ĂёS�����[�X�g���B�����͂̋����ψي��A�f���^���ɒu������肪�i�ށB
���̑�5�g�̓R���i�Ђ��n�܂��Ĉȗ��A�ň��̏��B�O�o���l�Ȃnj����ɂ�鎩�������ł͓���}�����Ȃ��B��@�������L���A���ۂł̐l�������Ȃǔ��{�I�ȕ������߂��K�v���B
6���ɊJ�Â��ꂽ���̊����Ǒ����Ɖ�c�ł́A�R���i�a���̋��ꎞ�I��2���ɂ܂łȂ������Ƃ����ꂽ�B������̒����̂��ߋ~�}�����̌���؍ݎ��Ԃ͉��тĂ���B�����암��ÃZ���^�[�E���ǂ���ÃZ���^�[�͗\����@�����~�����B
��5�g�̓����́A���X�̊����Ґ��̂���20�`30��̊����Ґ������������������Ȃǎ�N�w�������Ă��邱�Ƃ��B
����(0�`15��)�̓��@��4����2�l����A7����28�l�A8����6�����_��9�l�Ƌ}�������B��b�����̂���������d�lj����鎖�Ⴊ����A�D�w�̊������g�債�Ă���B������D�w�ւ̊����o�H�͉ƒ���������قƂ�ǂŁA���ꂼ��̈�Ñ̐����N��(�Ђ��ς�)���Ă���B
���u�w���v�E��͈ψ���ɂ��ƁA���N�`���ڎ헦�������قNJ����Ґ������Ȃ��Ȃ鑊�ւ�����Ƃ����A���Ƃ̓��N�`���ڎ킪�����Ґ������炷�L���Ȏ�i�ƌ��Ă���B����A20�`30��̎Ⴂ����̐ڎ�͎s�����ʂŐi��ł��Ȃ��B������w�̐E��ڎ�ł��A6�����_�ŗ\���3���قǂ����w�����W�܂��Ă��Ȃ��B
�����}�g��̗v���Ƃ��āA���Ɖ�c�̓��c���Y����(������w��w�@����)�͊ό��q������ɓ����ė��Ă��邱�Ƃ������A���ۑ�̏d�v�����w�E�����B
7�����炨�~�x�݂̎����ɓ������B���O�̓S����q��ւ̗\���2019�N�ɂ͋y�Ȃ����A�R���i�Ђ�20�N��������B���~�x�݂𗘗p���ĉ����K��A����Ȃ�l���̑������\�z�����B20������͋��~���n�܂�B
�ʏ�f�j�[�m���͌����̈�ÊE�ƌo�ϊE�A�s�����̑�\�҂Ƌ��ɋً}�������b�Z�[�W�\���A2�T�Ԃ̊O�o���l�Ȃǂ��Ăъ|�����B�����������ɋ��߂邾���ł͊g���}�����Ȃ��̂����B
��`�Ȃlj���̌����𗘗p����l�ɑ��A�o�b�q�������`��������Ȃǔ��{�I�ȑK�v���B�����������玩�l�Ɏ��g��ł����O����̐l���ɑΏ����Ȃ���Ζh���悤���Ȃ��B
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή�́u�l�X�̈ӎ��ɗ^�����e���͂���v�ƁA�ܗւɂ��C�̊ɂ݂Ɗ����g��̊֘A�Ɍ��y�����B���{�͑��₩�ɐl���ɔ��{�I�ɑΏ����A�����g������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
������]����������Ȃ��I�e�����̇������������R���i����^�����g���،��@8/11
�_�u���X�^���_�[�h���I�@�e���r�����̓����ܗ֔ԑg�X�^�b�t10�l���ł��グ�̈��݉���J���I�P�X�ŊJ�������Ƃ�10���A���炩�ɂȂ����B�e���r�e�ǂ��ً}���Ԑ錾���̈��݉�͍T����悤���钆�A���������������l�j�臁�������Ƃ��o�����i�D���B���蓾�Ȃ����ԂɁA�L�������^�����g�����ǂ̇����������R���i��\�I����ȂǁA�o�b�V���O�̗��������r��Ă���B
�u�r���̑�����l���������������ǁv�ڌ��҂�110�Ԓʕ��̂́A9���ߑO4�����낾�����B
�e�����̔��\��x�����A�����̊W�҂̘b�𑍍�����ƁA�e�����̓����ܗ֔ԑg�X�^�b�t10�l�͕��������8����`9���������܂ŁA�����E�a�J�̃J���I�P�X�őł��グ���J�ÁB����1�l��20�㏗���Lj������ɐ����A���X2�K�̑�����]�������Ƃ����B
�u�ܗւ��I��������g������C�����n�W���A���瑋���燀�_�C�u�������Ƃ̋V��������܂����A�ڍׂ͕s���ł��v(�e���r�NJW��)
�����Lj��͍��������܂���Ȃǂ̏d���B�s���̕a�@�ɋ~�}��������A���@���Ă���B10�l�́A���Y�Lj����܂ރX�|�[�c�NjLj�6�l�ƋNJO�X�^�b�t4�l�B
�e�����́u���Ђł͏]�O���A�V�^�R���i�E�C���X�����g��h�~�̊ϓ_���牃�ȓ����ւ���Г����[����݂��A���̏����O�ꂵ�Ă܂���܂����B���������̓x�A�s�v�s�}�̊O�o���̎��l���Ăт����闧��ɂ���Ȃ��璘�������o�������s�������������Ƃ͑�ψ⊶�ł���A�[�����Ȃ��Ă��܂��v�Ƃ̐����\���ĎӍ߁B�r�m�r��ł͈Ă̒�A�u�_�u���X�^���_�[�h�I�v�Ȃǂƌ������ᔻ����Ă���B
�����Ƃ��A�e�����̂����������p���͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B�Ⴆ�A���̏��ԑg�u�H���T�ꃂ�[�j���O�V���[�v�͌ܗ֊J���O����R�����e�[�^�[�̓��NjLj��E�ʐ�O�����͂��ߌܗւɔے�I���������A�J�����߂Â�����͎�̂Ђ�Ԃ��ōD�ӓI�Ɏ��グ�A�r�m�r��ŋ^�⎋���ꂽ�B
�_�u���X�^���_�[�h�͂ق��ɂ�����B����L�������^�����g�͂����������B
�u�ԑg�ɏo�����Ă��������Ďv�����Ƃ͂���܂��B�J����������Ă��鎞�̓A�N�����ƃA�N�����̊Ԃɗ��悤�X�^�b�t����Ɍ����܂����A����Ă��Ȃ����͏o���҂̕���X�^�b�t�����̓t�c�[�Ƀ��[���[�Ƃ���ׂ��Ă���ȂƁv
�O�ꂳ�ꂸ�A���������Ȃ悤���B
�u���ǁA�����҂ɑ���u�x�ł����Ȃ��B��͂���Ă��A�ƁB�����҂���N���[�������Ȃ��悤�ɂ��Ă��邾���ł��v
����̑������e�����������̂��|�C���g���B
5���z�M�̃f�C���[�V���ɂ��A�����ܗւł́A�m�g�j�����������e�ǂ��������̒��p�����߂����Ă��炩���߃N�W�����āA���������ǂ��قړƐ��������̐��ɂȂ����B���̉��b�ɂ����������̂��e�����������B
�����_�����l�������_���⋣�j�Ȃǂ𒆌p���A���ю�����20������A��(�֓��n��A�r�f�I���T�[�`����)�B�ܗ֊��Ԓ��̖����̎����������Ńg�b�v��Ƒ������B
�u�ܗւɔᔻ�I�Ȕԑg�����������e���������에�����������ł��B����Ōܗ֔ԑg�X�^�b�t10�l�͒��q�ɏ��A�J���I�P�X�ɌJ��o�����Ƃ����Ă��܂��B��͂��Ƃ������v(�O�o�W��)
�e�����Lj��ɂ��ƁA�u�Ǐ�w��������Ă���̂́A10�l�̒�����V�^�R���i�̊����҂��o�邱�Ɓv���Ƃ����B
���s�a�r�A�i�E���T�[�Ńt���[�̋g�����q�A�i�͂��̓��A���{�e���r�n�u��C�u�@�~���l���v�ŁA��A�̑����ɂ��āu�������Ⴂ���Ȃ����ǁA�o�J�ł��˂Ƃ��������悤���Ȃ��v�Ǝa��̂Ă��B
���u���������g�_�E���v��Ԃł����������߂�J�I�X�@���^�}�[������̋���@8/11
�S����1���̐V�K�����Ґ���1��4��l���Ĉ�Â��N��(�Ђ��ς�)���钆�A�������͒����NJ��҂̈ꕔ������×{�Ƃ����B�^��}������̐�����Ăɏオ���Ă���BAERA 2021�N8��16���|8��23���������ł́A���ׂƂ��鐭�{�̌������ނ����B
�u�����܂Ő��������ˏオ��ƁA�����������~�߂�L���Ȏ�i�͂Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�������̒N�����������Ă��܂���B�����炱�̊ԁA���Ƃ̈ӌ�����͂����Ȃ��B�܂Ƃ��ɕ����Ă�����I�����s�b�N�����Ȃ���A�R���i�̊����g���h���Ȃ�Ĕ�Ȋw�I�Ȍ|���͐�ɂł��܂���v
��ނɉ����������J���Ȃ̊����́A���̏�Ԃ́u�����g�_�E�����������Ɠ����ŁA�g��������~�߂�L���Ȏ�i���Ȃ��v�ƌ��𗎂Ƃ����B
4���A�S����1���̐V�K�����҂�1��4��l��˔j�B�O�㖢���̃I�[�o�[�V���[�g(��������)�͎~�܂�C�z���Ȃ��B�������������U���I����O�ɁA�u�I�����s�b�N���J�Â�������A�����x�����͉���v�Ƃ������`�̎̊�]�I�y�Ϙ_���v�����Ƃ������Ƃ́A�W�҂̒N�����M���ċ^��Ȃ��B
2���O�A���{�͐V�^�R���i�E�C���X�̓��@�Ώێ҂��d�ǎ҂Ɍ��肷��Ƃ������j�\�B�����ǂł��ꕔ�̊��҂͎���×{�ƂȂ�A���I��Â̑ΏۊO�ɒu�����B��}�����̈�l�́A�u�M�����Ȃ��B�����������ɖ��̑I����˂�����̂��v�ƕ���B���̌���ɖʐH������̂́A��}�����ł͂Ȃ��B�^�}�����}�E�����}���甽���̐�����C�ɕ����o�����B
�u����ł͎����}�x���҂������B�R���i�ɑł����������ǂ��납������̔s�k�錾���v(�����}�c��)
�u����������Ƒ��I���ł͔��^�}�[�������ł�������Ȃ��v(�����}�x�e�����c��)
�����̂́A���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή���A���̐��{�̕��j�]���ɂ��Ď��O�ɉ��̑��k���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ��B4���̏O�@���J�ψ���ł̗�������}�E����c�[�G�c���̎���Ŗ��炩�ɂȂ����B
���g��͓��قŁA�u���̌��Ɋւ��ẮA(���O��)�Ƃ��ɑ��k�A�c�_���������Ƃ͂Ȃ��v�ƒf���B������A���̌���̐ӔC�҂ł���c�����v�E���J���́A�u�a���̃I�y���[�V�����̖��ł���܂��̂ŁA����͐��{�����߂�b�ł������܂��v�ƊJ���������B�������A���{�̃g�b�v�ł��鐛�́A���̎�����c�����Ă��Ȃ������Ɣ����B�c����b�̌����u���{�v�Ƃ͂��������N�̂��Ƃ��B�O�o�̌��J�Ȃ̊����́u�m�M�Ɓv���Ə،�����B
�u���O�ɔ��g��ɑ��k���Ă���A���R�������B�����������Đ��{�����߂��ƂȂ�A����͂���ő���ƂȂ荡��A�w���Ɓx�Ƃ����s���̂������n�t�����ʗp���Ȃ��Ȃ�v�Ƃ�����ŁA�u�I�[�o�[�V���[�g����Έ�Ñ̐���������ɂ߂邱�Ƃ́A���J�Ȃ��琭�{�ɉ��x���������Ă����B����ǂ��A���@�̓I�[�o�[�V���[�g���Ȃ��Ƃ����A�������ȂȎp�����т����B������A��ÕN��(�Ђ��ς�)����i���������ɁA��Ñ̐��̊g�[�ɗ\�Z�𓊉����A�a���̊m�ۂ��}���Ƃ������z�������i�K�Ŕے肳�ꂽ�̂ł��v
�����}���ّI�A�����ĉ��U���I����O�ɁA�����̈ӗ~��R�₷���́A�����s�Ŋ����Ґ��u1���l�v���Ă��A�u�z��͈̔͂��v�ƊJ�����邾�낤�B�z��O�ƔF�߂�u�R���i�ɕ������v�Ɣ�����g���邱�ƂƓ��������炾�B���̓r�[�A��������u���~�낵�v�̍U�����n�܂�B
�i�c���ł͊����g��𗝗R�ɁA24������n�܂�p�������s�b�N�𒆎~���A�����ɐ����̊�@�Ǘ��\�͂ƌ��f�͂�m�炵�߁A���̒���ɉ��U�Ƃ����\�������B
�^��}����̔ᔻ�ɂ��炳�ꂽ�����������A���@��4���A�L�Ғc�Ɂu����̑[�u�͕K�v�Ȉ�Â�����悤�ɂ��邽�߂ŁA�������Ă��炢�����v�Əq�ׁA�u�����ǂ̈ꕔ�̊��҂�����×{�v�Ƃ������j�͓P�Ȃ��Ƒ��X�ɐ錾�����B�������A�����́u�P�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A������A�ł��Ȃ��v�̂ł͂Ȃ����B�������ł������̖������Ƃ����p���Ɗo�傪�������Ȃ��B���ꂪ���̌����u�����v�̐��̂Ȃ̂��낤���B
���錾�u�o���v���ʂ����@��K�͋x�ƕK�v�_���\�f���^���Ɏ�l�܂芴�E���{�@8/11
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A�������������Ƃ���ً}���Ԑ錾�̉��������ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă����B�u�o���헪�v��`�����Ƃ������{�̎v�f�͕������A�W�����̂���́A��K�͏��Ǝ{�݂ւ̋x�Ɨv���Ȃǐl�o�̗}���ɂȂ��鋭�͂ȑ�����߂鐺�����������B�f���^���̖҈ЂɊ������s�[�N�A�E�g���钛���͌������A���{���ɂ͎�l�܂芴���Y���B
�����N���o�ύĐ��S������10���̋L�҉�Łu����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ����Ⴂ�̊������p�����Ă���v�Ɗ�@����\���B40�`50�Α���N�w�̏d�ǎ҂��������Ă���̂�O���Ɂu�~���閽���~���Ȃ��ɂȂ肩�˂Ȃ��v�Ƌ��������B
�錾���ߒ���6�s�{���͊������}�g�債�Ă���B1��������̓����s�̐V�K�����҂�8�����ɂ�1���l����Ƃ̗\�����s���j�^�����O��c�Ŏ�����A���{�W�҂́u�錾�����͖�����������Ȃ��v�Ƃ̌������������B���t���[�����ɂ��ƁA�S���̏d�ǎ҂�1230�l(9�����_)�ŁA7�����{�̖�3�{�ɒ��ˏオ�����B
���`�̎͂��˂āu������4�������N�`���ڎ��1��I����Ɗ����҂���������v�Ƃ̌��������͂Ɏ����Ă����B�����A4�����ƂȂ������݂ł������g�傪���܂�C�z�͌����Ȃ��B�����̑������R�̂��������s����������u�W�c�Ɖu�v�̒B�����u���ʂ͍���v�Ƃ̌��������{���ł͋��܂��Ă���B
���{�̓��N�`���ڎ�̐i�W�ɍ��킹�A�錾���߁E�����̔��f�ɓ�����A�d�ǎҐ���a���g�p���Ƃ������V�K�����Ґ��ȊO�̎w�W�Ɏ������ڂ������ӌ��������B�����ǖ@��̈ʒu�t�����A�G�ߐ��C���t���G���U�ȂǂƓ���5�ނɕύX���ׂ����Ƃ̈ӌ����o�Ă������A�z�����ψي��̖҈Ђ܂��A�����ǐ��Ƃ́u�܂��͌��݂̑�5�g�Ɛ^���Ɍ����������ׂ����v�Ɗy�ϓI�Ȍ��ʂ������߂�B
����A�錾�Ώۓs�{���̒m������́A���H�X�ւ̗v���𒆐S�Ƃ��銴����̌��E���w�E���鐺���オ��B���{�̋g���m���m����9���A�������Ƃ̃e���r��c�Łu���܂Œʂ�̂����ł����̂��v�Ƌ^���悵�A�_�ސ쌧�̍���S���m���͗��q�@��d�Ԃ̏�q���������āB��t���̌F�J�r�l�m���͉�c��A�L�Ғc�Ɏ�s���S�̂ő�K�͎{�݂̋x�Ɨv�����������ׂ����Ƃ̍l�����������B
��������10���̉�Ŋ������Ɋւ��A�u(�����̊Ԃ�)�l���ɍ�������B���Ƃ��Ă悭�������A�Ή����Ă��������v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂��B �@
���V�^�R���i��5�ފ����ǂɂ���ƈ�Ì���͂ǂ��Ȃ邩�H�@8/11
���u5�ފ����ǁv�_
���݁A�V�^�R���i���G�ߐ��C���t���G���U���݂�5�ފ����ǂɃ_�E���O���[�h���邱�Ƃ���������Ă��܂��B����́A�ی����E�s������@�a���̕��S���琶�܂ꂽ�c�_�ł����āA�����ĐV�^�R���i���G�ߐ��C���t���G���U���݂Ɍy�ǂ��Ƃ����킯�ł͂���܂���B���̃e�[�}�A���Ƃ̊Ԃł����Ȃ�ӌ���������Ă��܂��B�������ɂł�5�ފ����ǂւƂ����ӌ��́u�E�B�Y�R���i�v�A�܂����v���Ƃ����ӌ��́u�����̗}���E�����v��z�肵�Ă��邽�߂ł��B�u�����ǖ@�v�ł́A�Ǐ�̏d�Ǔx��a���������̊����͂Ȃǂ���A�����ǂ��u1�ށ`5�ފ����ǁv��5�i�K�Ɓu�V�^�C���t���G���U�������ǁv�u�V�����ǁv�u�w�芴���ǁv��3��ނ̍��v8�敪�ɕ��ނ��Ă��܂�(�\)�B
�V�^�R���i�́A�ǏȂ��z���҂��܂߂����@������A�Ɛ����A�Z���ڐG�҂⊴���҂̒ǐՂȂǂ̑Ή����K�v�ȁA�w�芴���ǂ�1�`2�ޑ����Ƃ��Ĉ����Ă��܂����B2021�N2������u�V�^�C���t���G���U��������(��)�v�Ƃ����g�g�݂ɕύX����A����͊����ǖ@�ɂ�����u����g�v�ł��B�@�����Ɏ��Ԃ�v���邽�߁A�_��ɉ^�p�ł���悤�A�V�������ǂɂ��Ă͓���g���݂����Ă��܂��B
�������_�Łu�V�^�C���t���G���U�������ǁv�Ƃ́A�V�^�C���t���G���U�����ǁA�ċ��^�C���t���G���U�����ǁA�V�^�R���i�E�C���X�����ǁA�ċ��^�R���i�E�C���X�����ǂ̂��Ƃ��w���܂��B
5�ފ����ǂւ̃_�E���O���[�h�ɂ��Ă͎^�ۗ��_���邩�Ǝv���܂����A���{�S�̂ŕs�K���ɂȂ銴���҂������Ȃ��悤�^�p���₷���g�g�݂ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B�݂Ȃ������Ă��関���͂����Ɠ��������Ȃ̂ŁA���J�ȋc�_���d�˂Ă������������Ƃ���ł��B
�l�I�Ȉӌ��������ƁA���N�`���ڎ킪�����݁A�����̗�����������悤�ł���A�ǂ����̃^�C�~���O�Řg�g�݂�ς��邱�Ƃ͂��肾�Ǝv���܂��B�����A�u��������C��5�ފ����ǂɂ��܂��傤�v�ł͂Ȃ��A�����c���ĉ���ς��邩��b�������A�����I�ȕύX���������ׂ��ƍl���܂��B
���āA����������5�ފ����ǂɃ_�E���O���[�h����ƁA��Ì���͂ǂ̂悤�ɂȂ�ł��傤���B
���ی����E�s���̕��S���y��
5�ފ����ǂɂ���ƁA���@�����⊴���҂̒ǐՂ��s�v�ɂȂ�܂��B���݁A�����̕ی����ł����Ȃ��Ă���×{�҂ւ̓d�b����@�����Ȃǂ̋Ɩ����y�����A�ی����E�s���̕��S���ɘa�����ł��傤�B����������ŁA�����Ɍ����Ď��l�̗v�����o���Ȃ��Ȃ�܂��B���[�@���K�p�ł��܂���B
�������Ґ��̑���
5�ފ����ǂɂ���ƁA��q�����悤�ɁA�ی����ɂ����@�����⊴���҂̒ǐՂ͂Ȃ��Ȃ�܂����A����ҋ@�v���E���@�v�����ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���A�Đ��Y���������ψكE�C���X������ł͎c�O�Ȃ���S�̂̊����Ґ��͑�����ƍl�����܂�(���N�`���̐ڎ킪�����߂��̌���ł͂���܂���)�B
���ʉ��Ŋ����Ґ���������ƁA�c�O�Ȃ��璆���ǎҁE�d�ǎ҂�������ł��傤�B����܂ł̉��Ă̊����Ґ��E���Ґ����݂�ƁA���{��5�ފ����ǘ_�ɐT�d�ɂȂ�̂͒v�����Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B
���́A�ǂ̂��炢������̂��Ȃ��Ȃ��\��������Ƃ����_�ł��B
����Ï]���҂̕��S�́H
�����Ґ���������A���C���ɐe�a���������a���������ł��邱�Ƃ���A���x�̔x�����N�������҂���̐�ΐ�����Ⴕ�đ����܂��B��ÕN���x�́A�P���Ɋ����Ґ��Ɠ��@��v����m���̐ςŌ��܂�܂��̂ŁA�����g��ɂ���Ă͑S����ICU�ɐl�H�ċz������ꂽ�V�^�R���i���҂����������������Ƃ������Ԃ��N���邩������܂���BICU�x�b�h���N������ƁA�O�Ȏ�p��~�}��Âɍ�����肪�łĂ��܂��B
5�ފ����ǂɕ��ނ�ς����Ƃ��Ă��A1�N���ȏ���Λ����Ă���V�^�R���i�ɑ���x�����͂����ς��܂��A�v�������G�ߐ��C���t���G���U���͂邩�ɍ������Ƃ���(1)�A����^�p�Ƃ��Ă͌l�h���̑�����]�[�j���O�͌p�������ł��傤(�G�ߐ��C���t���G���U�Ɠ����ł悢�ƒʒB���o�Ă������_�ł͌���͊ԈႢ�Ȃ������܂�)�B���̂��߁A���Ǖa�@�ɂ́u�V�^�R���i�a���v���c������Ȃ��̂��������Ǝv���܂��B
�܂��A����܂ŐV�^�R���i�m����f�Ă��Ȃ������a�@�Ōl�h����K�ɒ��E���Ė����̓��@�P�A���\���ƌ����ƁA�Ȃ��Ȃ��n�[�h���������Ǝv���Ă��܂��B�S���ʼn@���N���X�^�[�̐��������邩������܂���B
�V�^�R���i���҂����낢��ȕa�@�ɕ��U����邽�߁A�Z���I�ɂ͐V�^�R���i�̐f�ÂŔ敾���Ă���a�@�̋Ɩ����S�͌���ł��傤�B�������A�x�����҂���̐�ΐ��������Ă���ƁA���炭���ċ}�����a�@�����Z�ɂȂ邩������܂���B���K�͂̋}�����a�@���V�^�R���i���炯�A�Ƃ������ԂɊׂ�\��������܂��B
����Ô�̎��ȕ��S��������
���݂̘g�g�݂ł͈�Ô�͂��ׂČ���ŕ��S����Ă��܂��B���̂��߁APCR�������Ă��A�R���i�a���ɓ��@���Ă��A���z�ȓ_�H���Â��Ă��A�����͂�����܂���B
�������A5�ފ����ǂɂ����ꍇ�A������p(PCR�����A�摜�����A���t�����Ȃ�)�A����(��F�����f�V�r����5�����ÂŖ�38���~�̖�)�A�_�f���^�A�l�H�ċz�Ǘ��Ȃǂ͍Œ�3�����S�̎x�����ɂȂ�܂��B��Ô���z�ɂȂ邽�߁A�����炭���z�×{��x��p���邱�ƂɂȂ�܂����A����ł��u�����A����Ȃɍ����́I�v�ƃr�b�N�����鎩�ȕ��S�z�ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
����Ƃ��āA�V�^�R���i�͂��炭����ŕ₤�Ȃǂ̗�O����邱�Ƃ��ł���A���̖��͉������邩������܂���B
���܂Ƃ�
����܂łɂȂ������͂ƒv�����������������ǂł��邽�߁A���s�̘g�g�݂ł��`�[�����Ă��镔���������V�^�R���i�B
�g���ƂɋN�����ÕN���@����ׂ��L�������E��Ë@�ւɐV�^�R���i������Ă��炤�u5�ފ����ǂւ̃_�E���O���[�h�v�ɂ�銴���Ґ����������ފQ�ƁA���s�̂܂܂̈�Ë@�ւŐf�Â��ē��@�������Ȃ��V�^�R���i���҂����ł��܂��Q�́A�ǂ��炪���{�ɂƂ��Ă܂����Ƃ����b�ɂȂ�܂��B
�c�������J����b�́u���N�`���ڎ킪���i�ꍇ�Ɍ���������������悤�ȕK�v������v�Ƃ���������Ă��܂��B
����5�ފ����ǂɃ_�E���O���[�h����ɂ��Ă��A�S�̂̎����Đ��Y�������m�Ɍ���{�ғ����Ă����ԂŁA�����I��5�ފ����ǂ̕����֊Ă����b���������̗v���Ǝv���܂��B���邢�͐��x�I�ɂ͌��s�̂܂ܓ��e��5�ފ����ǂɋ߂Â���A�Ȃǂ̈Ă��l�����܂��B
���R���i�����̕ی����x�����}���A3������350���~���c�@8/11
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ی����̎x�������A���N4�`6����3�����Ԃ�350���~�������Ƃ��킩�����B�e�����[���ɂȂ�����N3�����獡�N3���܂ł̎x�����z�͖�481���~�ŁA���N�x�͔��N�������炸�ɂ��̋��z��˔j���������B
��������42�Ђ��������鐶���ی�����ɂ��ƁA���N4�`6���̐V�^�R���i�����ɔ����ی����̎x����������10��6800���B����͎��S�ی���4215���Ōv��248���~�A���@���t����10��2585���Ōv��103���~�������B
7���ȍ~�A�����͂��]������苭���f���^�����L����A�V�K�����҂��}�����Ă���A�u�ی����̎x�������}�s�b�`�ő����Ă���v(��萶�ۍL��)�Ƃ����B
��萶�ۂ����\����21�N4�`6�������Z�ɂ��ƁA�R���i�֘A�̎x���z�́A�ő��̓��{�����ی�����74���~�A�Z�F�����ی�����34���~�A�������c�����ی�����28���~�������B
���ۊe�Ђ́A�V�^�R���i������A���S�����ۂ̕ی�������@���̋��t�������łȂ��A�a���̕N��(�Ђ��ς�)�Ŏ���×{���銴���҂ɂ����@���t�����x��������[�u���u���Ă���B
�������s �V�^�R���i 4200�l�����m�F �d�ǎ҂͍ő��X�V197�l�� �@8/11
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g�傪���������s���ł�11���A�V����4200�l�̊������m�F����܂����B����A�s�̊�ŏW�v����11�����_�̏d�ǂ̊��҂�197�l�ƂȂ�A10���ɑ����ĉߋ��ő����X�V���܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ30���70��̒j��2�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��A���̂���30��̒j���͎���ŗ×{���ɖS���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
�����s��11���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��4200�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B4000�l����̂�3���O�̍���8���ȗ��ł��B1�T�ԑO�̐��j������34�l�����āA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B11���܂ł�7���ԕ��ς́A3983.6�l�ŁA�O�̏T��114.5���ł��B����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A25��8981�l�ƂȂ�܂����B
����A�s�̊�ŏW�v����11�����_�̏d�ǂ̊��҂́A10�����21�l������197�l�ƂȂ�܂����B10���ɑ����ĉߋ��ő����X�V���d�NJ��҂̑������~�܂�܂���B����1����101�l�ŁA11���܂łɔ{�߂��ɑ����Ă��܂��B�s���A���݊m�ۂ��Ă���d�NJ��җp�̕a���̎g�p���́A��3�g�̂��Ƃ�1��31���ȗ�50������50.3���ɂȂ�܂����B
�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ30���70��̒j��2�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���̂���30��̒j���͎���ŗ×{���Ă��Č��N�ώ@�𑱂��Ă��܂������A�e�̂��}�ς��ĖS���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2319�l�ɂȂ�܂����B
�s�̊�ŏW�v�����d�NJ��҂��ߋ��ő��ɂȂ������Ƃɂ��āA�����s�̏��r�m���͋L�Ғc�ɑ��āu�S�̂̊����҂������Ă��Ă��āA�d�ǂ�200�l�ɋ߂��������B��Ë@�ւ���͒ʏ�̐f�Â�f������A��p��摗�肵���肷��Ȃǂ̎��ԂɊׂ�Ƃ��������Ă���B���傤�͏d�ǎ҂̂����A50�オ3����1���߂Ă���B40������̂������C��9�l�����Ă���B��b�����������Ă������^�o�R���z���Ă�������C�����Ă������������v�Əq�ׂ܂����B
������ �V�^�R���i 4200�l�����m�F ����×{���̒j�����S �@8/11
�����s���ł�11���V����4200�l�̊������m�F����A�����̋}�g�傪�����Ă���ق��A�s�̊�ŏW�v����11�����_�̏d�ǂ̊��҂͉ߋ��ő���197�l�ƂȂ�A��Ò̐��̂Ђ���������ɐi��ł��܂��B�܂��A����ŗ×{���Ă�����b�����̂Ȃ�30��̒j�����S���Ȃ�A��5�g�œs���c����������×{���̎��S��3�l�ɂȂ�܂����B
�����s�́A11���s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��4200�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B
4000�l����̂�3���O�̍���8���ȗ��ł��B
1�T�ԑO�̐��j������34�l�����āA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B
11���܂ł�7���ԕ��ς́A3983.6�l�ŁA�O�̏T��114.5���ł��B
11����4200�l�̔N��ʂ́A10�Ζ�����206�l�A10�オ397�l�A20�オ1262�l�A30�オ867�l�A40�オ727�l�A50�オ485�l�A60�オ146�l�A70�オ55�l�A80�オ43�l�A90�オ9�l�A100�Έȏオ3�l�ł��B
�����o�H���킩���Ă���1541�l�̓���́u�ƒ���v���ł�����936�l�A�u�E����v��277�l�A�u�{�ݓ��v��99�l�A�u��H�v��41�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�����I�����s�b�N�֘A�ł�6�l�̊������m�F����A�O���l�̋��Z�W�҂�3�l�A���{�l�̑g�D�ψ���E����2�l�A�ϑ��Ǝ҂�1�l�ł��B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A25��8981�l�ƂȂ�܂����B
����A11�����_�œ��@���Ă���l��3667�l�ƁA10�����73�l�����A5���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��61.5���ł��B
�܂��A�s�̊�ŏW�v����11�����_�̏d�ǂ̊��҂�10�����21�l������197�l�ƂȂ�܂����B
10���ɑ����ĉߋ��ő����X�V���d�NJ��҂̑������~�܂�܂���B
����1����101�l�ŁA11���܂łɔ{�߂��ɑ����Ă��܂��B
�s���A���݊m�ۂ��Ă���d�NJ��җp�̕a���̎g�p���́A��3�g�̂��Ƃ�1��31���ȗ�50�����āA50.3���ɂȂ�A��Ò̐��̂Ђ���������ɐi��ł��܂��B
�d�NJ��҂̔N��ʂ́A10�オ1�l�A20�オ5�l�A30�オ14�l�A40�オ52�l�A50�オ67�l�A60�オ36�l�A70�オ18�l�A80�オ4�l�ł��B
40���50������킹��ƑS�̂̂��悻60�����߂Ă��܂��B
�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ30���70��̒j��2�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
���̂���30��̒j���͐挎28���ɗz���Ɗm�F���ꂽ�Ƃ��ɂ͔��M������y�ǂł����B
����ŗ×{�𑱂��Ă��܂���������6���ɘA�������Ȃ����Ƃ�s�R�Ɏv�����Ƒ��������K�˂��Ƃ���A���łɎ��S���Ă����Ƃ������Ƃł��B
�ی����ɂ�閈���̌��N�ώ@�ł͓��i�A�̒��̕ω��͂Ȃ��A�S���Ȃ�O����5���ɂ͕s����i���Ă������̂́A���̂ق��ɂُ̈�͊m�F����Ȃ������Ƃ������ƂŁA�s�́A�e�̂��}�ς����ƌ��Ă��܂��B
�j����1�l��炵�Ŋ�b�����͂Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
����ŁA����̑�5�g�Ŏ���×{���ɖS���Ȃ����l�œs���c�������̂�3�l�ɂȂ�܂����B
�s�̒S���҂́u�O���܂ő̒������肵�Ă����l���S���Ȃ���B���߂āA�|���a�C���Ƃ�����@�ӎ������L���A�����h�~��Ɏ��g��łق����v�Ƙb���Ă��܂��B
����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2319�l�ɂȂ�܂����B
���u�ً}���ԁv9�������_����@�Ώےn��g����{�����@8/11
���{�͐V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��ً}���Ԑ錾���߂���A�Ώےn��̊g����������A���T�ɂ����߂�����Œ������Ă���B31���Ƃ��Ă��������9���܂ł̉����_�����シ��B�����s��4��ڂ̐錾���߂���12����1�J���ƂȂ邪�A�J��Ԃ����Ώۊg��Ɗ��������B���`��(�����E�悵�Ђ�)�̌����u�Ō�̐錾�v�͂��I���̂��A�����ɕs���Ƃ��炾�������B
�lj������n��́A����(�܂�)�h�~���d�_�[�u���K�p����13���{�������S���B���t���[�̎���(10�����_)�ɂ��ƁA1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ��́A13���{���S�ĂŃX�e�[�W4(�����I�����g��)�B�����̂����a���g�p���ł͕����A���A�ȖA�Q�n�A�ΐ�A���s�A�����7�{���ŃX�e�[�W4�ƂȂ��Ă���B
�錾�̌��ʂ�����ɂ͐������ԂȂǂ��܂ߍŒ�3�T�Ԃ͕K�v�Ƃ����B���̂��߁A�g��𗈏T���߂��ꍇ�A�lj��n��̊�����9���ɂȂ�̂͂قڊm�����B�錾���ߒ���6�s�{���ł������g�傪�����Ă���A�n��̒lj��ɍ��킹��`�ŁA��������������͔̂�����ꂻ�����Ȃ��B
�c�����v�����J������11���A���J�Ȃɏ���������Ƒg�D�̉�Łu�V�K�����Ґ�����ԓI��1���l���S���I�Ɋ������g�債�Ă���B�����͌������������Ă���A�����̏ɋ߂Â��Ă��鎩���̂����X�Ƒ����Ă���v�Ɗ�@�����������B���{���ɂ͐錾�̑S���K�p�����߂鐺�����邪�A�W�t������́u�錾��S���ɏo���Ă������҂͌���Ȃ����낤�B���N�������ł��Ȃ����ԂɂȂ肩�˂Ȃ��v�Ƃ̐����R���B
�d�ǎ҂������Ă���A10�����_�̏d�ǎ҂�1332�l��21���A���ő��������B�C���h�R���̕ψي�(�f���^��)���҈Ђ�U�邤���A���Ăł̓��N�`����2��ڎ킵���l�̊�����6���߂��ɂȂ��Ă��A�������~�܂�Ȃ��Ƃ����B
�c������11���̃e���r�����ԑg�Łu����Ƃ��ăR���i�ƕt�������Ă�������ɂȂ�v�Ƃ��āA�R���i��p�a�@�̊J�݂��u���}�Ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B�R���i�Ƌ�������Љ�݂̍���������̂͋}���ƂȂ��Ă���B
�����Ɖ�u�����̖����~���Ȃ��Ȃ�悤�Ȋ�@�I�뜜�v�@8/11
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ���1�T�Ԉȏ�A�����đS����1���l����ȂNj}���Ȋ����g�傪�������A��ɂ��ď�����������J���Ȃ̐��Ɖ���J����܂����B���݂̏ɂ��āA�u���͂�ЊQ���̏ɋ߂��ǖʂ��}���Ă���v�Ƃ��āA��Â̂Ђ����ő����̖����~���Ȃ��Ȃ�Ƃ���������@���������������ŁA���~�Ȃǂ̋A�Ȃ͉������A���łɃ��N�`����ڎ킵���l���܂߂ă}�X�N�Ȃǂ̊�{�I�Ȋ������O�ꂷ��K�v�����������܂����B
11���J���ꂽ���Ɖ�ł́A�S���̊����ɂ��āA�u�S���̂قڂ��ׂĂ̒n��ŐV�K�����Ґ����}���ɑ������A����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��ƂȂ��Ă���v�ƕ��͂��܂����B
���̂����ŁA����܂ŒႭ�}�����Ă����d�ǎҐ����}���ɑ������A���@�������̐l�̐����}���ɑ�������ȂǁA��s���𒆐S�Ɍ��O�q�����Â̑̐������Ɍ������A�u���͂�ЊQ���̏ɋ߂��ǖʂ��}���Ă���v�Ƌ�����@���������܂����B
�n��ʂɂ݂�ƁA�����s�ł͉ߋ��ő�K�͂̊����g��œ��@���ҁA�d�ǎ҂Ƃ��ɉߋ��ő��̐����ƂȂ�A����×{�̊��҂��}���ɑ������Ă���ق��A�V���ȓ��@�̎���A�~�}����������ȃP�[�X��A��ʈ�Â𐧌����鎖�Ԃ��N���Ă���Ƃ��Ă��܂��B
�܂��A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�ł��d�Ǖa���̎g�p�����������Ă��āA�����ł͖�Ԃ̐l�o�̌������O��ً̋}���Ԑ錾���̐����ɂ͓͂����A20���30�ゾ���łȂ��A�d�lj����郊�X�N�̍���40���50��̊����������Ȃ��Ă��āA��s���ł͓��ʂ͊����g�傪�����Ǝw�E���Ă��܂��B
���ꌧ�͐l��������̊����Ґ����S���ōł������A�ߋ��ɗ�̂Ȃ������ƂȂ��Ă��āA���@���Ґ����}���ɑ������A�a���g�p�����������ƂȂ��Ă������A��Ԃ̐l�o�͌����ɓ]���Ă���Ƃ��Ă��܂��B
���{�ł��A�}���Ȋ����g�傪�����A���@�Ґ���d�ǎҐ����������Ă��āA��Ԃ̐l�o�͌����ɓ]�������̂̈ˑR�������߁A�����g�傪�������Ƃ��\�������Ƃ��Ă��܂��B
���Ɖ�́A�����͂������ψكE�C���X�A�f���^���ւ̒u������肪�i�ޒ��A�ً}���Ԑ錾�Ȃǂɂ��l�o�̌����͌���I�ŁA����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��̋ǖʂ��}���Ă���Ƃ��������ŁA��Ñ̐��̊g�[�����E�����邽�ߏd�ǎҐ��̋}���ȑ����Łu�����̖����~���Ȃ��Ȃ�悤�Ȋ�@�I�ȏ����뜜�����v�ƁA����܂łɂȂ��\���ŋ�����@���������A�ꍏ�����������g���}���邱�Ƃ��K�v���Ƒi���܂����B
���̂����ŁA���Ɖ�́A�K�v�ȑ�Ƃ��Ă��~��ċx�݂ɂ��������z����ړ���O�o���T���A�A�Ȃ͉�������������悤���߂܂����B
�܂��A���������H�̏�ʂ����łȂ��A���Ǝ{�݂�E��A�w�Z�Ȃǂł��}���ɍL�����Ă���Ƃ��āA���N�`����ڎ킵���l���܂߂ă}�X�N�̒��p����ŁA�l�Ƃ̋����̊m�ۂ⊷�C�Ȃǂ̊�{�I�ȑ��O�ꂷ�邱�ƁA����ɐE��ł̉�c�͌����I�����C���ōs�����Ƃ�e�����[�N�̐��i�A�Ǐ�̂���l�̏o�Ў��l�̓O��Ȃǂ����߂Ă��܂��B
����ɁA�ŋߏ��F���ꂽ�d�lj���h�����ʂ����҂����R�̈��̊��p��A�d�lj��ɐv���ɑΉ��ł���̐��𑁋}�ɐ������āA�K�v�Ȉ�Â��m�ۂ���K�v�����w�E���܂����B
���e�c�����u�g�ЊQ��ÂɕC�G����h�Ƃ̈ӌ����v
�����J���Ȃ̐���̂��Ƙe�c��������������A��Ñ̐��̌���ɂ��āA�u���Ɍ����������������A����A�V�^�R���i�̈�Âƈ�ʈ�Â̗������ł���̂��A����������ꍇ�ɂǂ����D�悷�ׂ����Ƃ������A����܂ł͏o�����Ƃ̂Ȃ��c�_���������B���R�A�ł��邩�����ʂ̈�Â��]���ɂ����ɃR���i�̈�Â��i�߂Ă����̐������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̂��߂ɂ͊����҂��ł��邾�����炷�K�v������B���łɈꕔ�ł́A�~�}��ÂɃA�N�Z�X�ł��Ȃ���@�I�ȏɂ���A�w�ЊQ��ÂɕC�G����ł͂Ȃ����x�ƕ\�����郁���o�[�����������B���Ƃ̊�@������ʂ̕��X�Ƌ��L�ł��Ă��Ȃ�������v���v�Ƙb���Ă��܂����B
���̂����ŁA�u�����s���̖�Ԃ̑ؗ��l���̃f�[�^���͂ɂ��ƎႢ���ゾ���łȂ��A��r�I�A�d�lj��̃��X�N������40���50��̐l���������Ȃ��Ă���B�V�^�R���i�E�C���X�̓C���t���G���U�Ƃ͈���Ċ��������l�̐��������S����悤�Ȋ����ǂŁA�v�������Ⴂ�a�C�ł͂Ȃ��B�������ȉƑ�����邽�߂Ɋ������X�N�������s�����Ƃ��Ăق����v�ƌĂт����܂����B
���������~�߂����炸�@���Ƒg�D�u�ЊQ���ɋ߂��ǖʁv�@8/11
�V�^�R���i�E�C���X��������J���Ȃɏ���������Ƒg�D��11���̉�ŁA���݂̊����ɂ��āA��s���𒆐S�Ɂu���͂�ЊQ���̏ɋ߂��ǖʁv���Ƌ�����@�����������B31�s���{���ŐV�K�����Ґ����ł��[���ȁu�X�e�[�W4(��������)�v�ɑ������A1�T�ԑO��23����}���B�l�̉�����������Ƃ݂��邨�~�̎�����O�ɁA�S���I�Ȋ����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ���Ԃ��B
���Ƒg�D�́A�}���Ȋ����g��ŏd�ǎ҂���@�҂��̐l���}�����A��ʈ�Â̐�����~�}����������Ȏ���������Ă���Ǝw�E�B�u�����̖����~���Ȃ��Ȃ�悤�Ȋ�@�I�ȏ����뜜�����v�Ƃ��āA���~�Ɍ������܂������ړ���O�o���T����悤���߂��B
10���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����҂͑S���Ől��10���l������77�E60�l�B�O�T��1�E33�{�ƂȂ����B31�s���{�����A�X�e�[�W4�̎w�W�ƂȂ�25�l�����B�ً}���Ԑ錾���o�Ă���n��ł́A���ꌧ247�E83�l�A�����s200�E06�l�A�_�ސ쌧140�E27�l�A��ʌ�119�E66�l�A��t��107�E27�l�A���{86�E25�l�ŁA��������O�T���1�E2�`1�E4�{���x�������B�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��ł��A������94�E77�l�A���s�{70�E54�l�A��錧61�E29�l�A���Ɍ�51�E45�l�A�Q�n��50�E15�l�ȂǂقƂ�ǂőO�T��葝�����B
���������nj������ɂ��ƁA1�l�����l�Ɋ��������邩��\���u�����Đ��Y���v�́A�S���I�ɏ㏸�X���������A�S�s���{����1�������Ă���B1�������Ȃ���Ί����Ґ��͌���Ȃ��B
���@���҂������A��Â̕N��(�Ђ��ς�)�����O�����B�a���g�p���́A��s���̂ق����ꌧ�╟�����ȂǏ��Ȃ��Ƃ�16�s�{����5�������B���ꌧ86�E3%�A���ꌧ81�E0%�A������79�E2%�A�_�ސ쌧69�E1%�ȂǁB�d�ǎ҂̕a���g�p�����A���ꌧ78�E2%�A�_�ސ쌧75�E9%�A�����s72�E5%�Ȃnj������Ȃ��Ă���B
�����s�̍���ɂ��Ă͌��������ʂ����o���B���Y���E���s�勳����̗\���ł́A�C���h�Ŋm�F����ē��{�ł��L�����Ă���f���^���̊����͂Ȃǂ�������Đ��Y����1�E7�Ɛݒ肵���ꍇ�A�l�o�̗}���ȂǂŎ����Đ��Y����30%������ꂽ�Ƃ��Ă����҂����������A9����{�ɂ͏d�Ǖa�������ׂĖ��܂�B���@���҂Ǝ���×{�҂̍��v�́A8�����{�ɂ͊m�ەa����400%����Ƃ����B
�����s��w�����������ɂ��ƁA�s���̖��(�ߌ�6���`�ߑO0��)�̔ɉ؊X�̐l�o�͑O�T����4�E5%���������A�O��ً̋}���Ԑ錾�̊��Ԓ��ōł��l�o�����Ȃ��������ɂ͋y�Ȃ��B�[��(�ߌ�10���`�ߑO0��)�̐l�o�͑O�T���3�E2%�����ɓ]���Ă����B
�p���Ō��������A���t�@���ƁA�f���^���̊����҂ŏǏ���ׂ�ƁA���M�A�����A���ɁA�k�o(���イ����)�E���o��Q�̏Ǐ�́A�A���t�@�������f���^���̊����҂ɑ����X�����������B
�f���^���̒u���������i��ł���B���������nj������͊֓��n���ł͖�9���Ƃ��Ă������A���n���ł������҂̖�8�����߂�Ɛ��v�����B�f���^���̋^���̂���E�C���X�Ɋ��������l��10���܂ł̗ݐς́APCR�X�N���[�j���O������2��5598�l�B�O�T��1�E9�{�������B
�c�����v���J���́A�f���^���̊����͂͏]�������97%�����Ȃ��Ă���Ƃ��āA���Ђ������B�u�}�X�N�����ł͑ʖځB���C����������Ƃ��Ăق����v�Əq�ׁA���~�̉�H�͔�����悤�Ăт������B
����A��ł̓��N�`���ڎ�̌��ʂ������ꂽ�B���J�Ȃ�6���̎b��W�v�ł́A���ڎ�Ŋ������������5387�l�̂����S���Ȃ����̂�232�l(4�E31%)���������A2��ڎ킵��������112�l�ł�1�l(0�E89%)�������B1��ڎ킵��������857�l�ł͎��S��26�l(3�E03%)�B�R������邽�߁A���l�͕ς��\��������Ƃ��Ă���B
�������s�A�h���×{�{�݂̊��p�����݁@�Ō�t�s���A�u���a�@���v��q�@8/11
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪���������s�ŁA�h���×{�{�݂̊��p���i��ł��Ȃ��B�Ō�t�s����w�i�ɁA�×{�҂͎���\�l����6�����x�ɂƂǂ܂�B�s�͊����҂�d�ǎ҂̑����ɔ����a���N��(�Ђ��ς�)���A�ꕔ�̏h���{�݂��u���a�@���v����ً}�̐��ւ̈ڍs��ڎw�����A�����Ɍ����Ă��Ō�t�s�������O�ޗ��ɂȂ��Ă���B
�u�h���×{�𑝂₵�������A�z�e���ɔz�u����Ō�t�̊m�ۂ����ɓ���B��Ë@�ւ����łȂ��l�ޔh����Ђɂ��˗����Ċm�ۂ��}���ł��邪�A����×{�ւ̑Ή���N�`���ڎ�ȂǕK�v�ȏ�ʂ������A�D�������̏��v�B�s�̒S���҂͌���������ł�������B
�s�́A��b����������Ȃǎ���×{����������҂�Ώۂɏh���×{��i�߂Ă���B12�����_�Ŋm�ۂ����z�e����16�{�݁A6240���B�����҂̓���ւ��ɂ͏��ō�ƂȂǂ��������Ȃ����߁A�^�p��̎�������3210�l�ƒ�߂Ă���B
����ɑ��A10�����_�̏h���×{�҂�1820�l�B�u�ғ����v�͎���\�l���̖�6���A�m�ۂ����������̖�3���ɂ����Ȃ��B�w�i�ɂ���̂��Ō�t�̕s�����B
�����҂��h���{�݂ɓ���ہA�Ō�t�͌��N�ώ@���s���B�ΖʂŎ��a�╞�p������ق��A�����҂̕s���⌒�N���k�ɉ�����Ȃ�1���Ԉȏォ����P�[�X�����Ȃ��Ȃ��B�Ō�t1�l��1���ɑΖʂł���̂́A4�`5�l���x�ƂȂ�B
1�{�݂ɂ��A���[�_�[���܂߂�10�l��z�u�ł����1��500�l�O��̎��ꂪ�\���B���ϑ؍ݓ�����6���̂��߁A�t���ғ��ƂȂ�z�肾�����B�Ƃ��낪���ۂɂ͊Ō�t���\���ɔz�u�ł����A1��100�l�O��̎���ɂƂǂ܂�B
�s���ł͊����҂�d�ǎ҂̑����ɂ���āA�a�����N�����Ă���B�s��8���ȍ~�A��Õ��������邽�߂ً̋}�̐��Ɉڍs����ƕ\���B���̈���A�ꕔ�̏h���{�݂́u���a�@���v���B�_�f�Z�k���z������t�̉��f�̐��𐮂���ȂǁA��Ë@�\��t�����ĕa���������肷��_��������B
�����A����ɂ���ÃX�^�b�t�A���ɊŌ�t�̔z�u�͌������Ȃ��B�s�͂ǂ̒��x�̐l�����K�v�ɂȂ邩�����������A���i�K�̏h���×{�{�݂ł��������ɔz�u�ł��Ă��Ȃ��ȏ�A��q�͕K�����B�s�̒S���҂́u������W�@�ւɋ��͂����肢���Ă����W�߂�v�Ƌ������邪�A���a�@���́u�G�ɕ`�����݁v�ɏI���\��������B
����Ñ̐��u���͂�ЊQ���v�@�A�ȉ����A���O�ꋁ�߂�@�@8/11
�V�^�R���i�E�C���X���������������J���Ȃ̐��Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v��11���A��s���Ȃǂ̈�Ò̐��ɂ��āu���͂�ЊQ���ɋ߂��v�Ƃ̌������܂Ƃ߂��B
����́u�����̖����~���Ȃ���@�I�ȏ����뜜�����v�Ƌ������O�������A���~���Ԓ��̋A�ȉ�����}�X�N���p�ȂNJ�����̓O��������ɋ��߂��B
���Ƒg�D�́A�S���̐V�K�����҂Ɋւ��A�u�}���ȃX�s�[�h�ő����X�����p�����Ă���v�Ǝw�E�B�����s�ł̓C���h�R���̃f���^���Ɋ��������l�̊������V�K�����҂�95���ɓ��B�����Ɛ��v����A�u�قڒu����������ƍl������v�Ƃ����B
���Ƒg�D�̍����߂�e�c�����E���������nj��������͋L�҉�ŁA24���J���̓����p�������s�b�N�ɂ��āu�l�I�ɂ�(���ϋq�������ܗւ�)�������]�܂����̂ł͂Ǝv���v�Əq�ׂ��B
����A���J�Ȃɂ��ƁA6���ɕ��ꂽ65�Έȏ�̊����҂̂����A���N�`�����ڎ�҂�5387�l�ŁA2��ڂ�ł��I�����l��112�l�B�v�������r����ƁA���ڎ�҂�4�D31������������A���������l��0�D89����5����1���x�ɒቺ�����B�e�c�����́u�Ǘ��ςݏd�˂�K�v�����邪�A���N�`���ŏd�lj��\�h�⎀�S��}������ʂ�����Ǝv����v�Ǝw�E�����B
10���܂ł�1�T�ԂɊm�F���ꂽ�l��10���l������̐V�K�����҂́A������200�D06�l�A���ꂪ247�D83�l��200�l��ƂȂ����B���(119�D66�l)�A��t(107�D27�l)�A�_�ސ�(140�D27�l)�̎�s��3����100�l���A���(86�D25�l)�A����(94�D77�l)�ȂǂƑS���I�Ȋg��X���Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B
����Q�Ҏ{�݂ŐV���ȃN���X�^�[���A�������g��@�ߋ��ő��̋��s�@8/11
���s�{�Ƌ��s�s��11���A10�Ζ�������90���341�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1���̊����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��B�{���̊����Ґ��͌v2��969�l�ƂȂ����B
�{�̔��\����174�l�ŁA���߂�100�l�����B�����o�H�s����120�l�B�����ǂ�2�l�ŁA�ق��͒��������y�ǂ܂��͖��Ǐ����B���Z�n�ʂł͉F���s32�l�A�T���s21�l�A�����s16�l�A���c�ӎs�ƖؒÐ�s���e13�l�A���s�s12�l�A��z�s�Ɠ�O�s���e10�l�A�����s8�l�A���ߎs�A�v��R���A���ؒ����e7�l�ȂǁB
��O�s�̏�Q�Ҏ{�݁u�����ڂ̊w���v�ŐE���Ɨ��p��10�l���������A�{�̓N���X�^�[(�����ҏW�c)���V���ɔ��������Ƃ݂Ă���B���㎩�q����v�ے��Ԓn(�F���s)�ł͊����҂�5�l�����Čv15�l�ƂȂ����ق��A���ߎs�̕a�@�ł�5�l�����Čv11�l�ƂȂ����B���s�s�̔��\����167�l�������B
���u�ً}���ԁv9�������_����@�Ώےn��g����{�����@8/11
���{�͐V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��ً}���Ԑ錾���߂���A�Ώےn��̊g����������A���T�ɂ����߂�����Œ������Ă���B31���Ƃ��Ă��������9���܂ł̉����_�����シ��B�����s��4��ڂ̐錾���߂���12����1�J���ƂȂ邪�A�J��Ԃ����Ώۊg��Ɗ��������B���`��(�����E�悵�Ђ�)�̌����u�Ō�̐錾�v�͂��I���̂��A�����ɕs���Ƃ��炾�������B
�lj������n��́A����(�܂�)�h�~���d�_�[�u���K�p����13���{�������S���B���t���[�̎���(10�����_)�ɂ��ƁA1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ��́A13���{���S�ĂŃX�e�[�W4(�����I�����g��)�B�����̂����a���g�p���ł͕����A���A�ȖA�Q�n�A�ΐ�A���s�A�����7�{���ŃX�e�[�W4�ƂȂ��Ă���B
�錾�̌��ʂ�����ɂ͐������ԂȂǂ��܂ߍŒ�3�T�Ԃ͕K�v�Ƃ����B���̂��߁A�g��𗈏T���߂��ꍇ�A�lj��n��̊�����9���ɂȂ�̂͂قڊm�����B�錾���ߒ���6�s�{���ł������g�傪�����Ă���A�n��̒lj��ɍ��킹��`�ŁA��������������͔̂�����ꂻ�����Ȃ��B
�c�����v�����J������11���A���J�Ȃɏ���������Ƒg�D�̉�Łu�V�K�����Ґ�����ԓI��1���l���S���I�Ɋ������g�債�Ă���B�����͌������������Ă���A�����̏ɋ߂Â��Ă��鎩���̂����X�Ƒ����Ă���v�Ɗ�@�����������B���{���ɂ͐錾�̑S���K�p�����߂鐺�����邪�A�W�t������́u�錾��S���ɏo���Ă������҂͌���Ȃ����낤�B���N�������ł��Ȃ����ԂɂȂ肩�˂Ȃ��v�Ƃ̐����R���B
�d�ǎ҂������Ă���A10�����_�̏d�ǎ҂�1332�l��21���A���ő��������B�C���h�R���̕ψي�(�f���^��)���҈Ђ�U�邤���A���Ăł̓��N�`����2��ڎ킵���l�̊�����6���߂��ɂȂ��Ă��A�������~�܂�Ȃ��Ƃ����B
�c������11���̃e���r�����ԑg�Łu����Ƃ��ăR���i�ƕt�������Ă�������ɂȂ�v�Ƃ��āA�R���i��p�a�@�̊J�݂��u���}�Ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B�R���i�Ƌ�������Љ�݂̍���������̂͋}���ƂȂ��Ă���B
���R���i�����u�ЊQ���ɋ߂��ǖʁv�@�e�c�����@�p�������s�b�N�u���ϋq�]�܂����v 8/11
�V�^�R���i�E�C���X�̊����͂��A�����J���Ȃɏ���������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v��11���A�u�����Ґ��̋}���ȑ����ɔ����A�d�ǎҐ����}���ɑ����B��Ò̐�����s���𒆐S�ɔ��Ɍ������A���͂�ЊQ���̏ɋ߂��ǖʁv�Ƃ̕]�����܂Ƃ߂��B�u�����̖����~���Ȃ��Ȃ��@�I�ȏ����뜜�����v�Ƃ��Ă���B(��c��H)
���̋L�҉�ŁA�����̘e�c�����E���������nj��������́u���Ɍ������c�_���������v�Ɛ�o�����B���߂̑S���̐V�K�����Ґ��͑O�T��Ŗ�3�������Ă���B�e�c���́u�ߋ��ő�̐����̍X�V�������A�S���I�ɂقڑS�Ă̒n��ŐV�K�����Ґ����}���ɑ������Ă���B����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������g��v�Ƌ��������B
�����s���̓��@�������̊��҂�1���l���Ă���B��ł́u�V�^�R���i�ƈ�ʈ�Â̗����͉\���A�ǂ����D�悷�邩�v�Ƃ����A����܂łȂ������c�_�����킳�ꂽ�Ƃ����B
�s���̖�Ԃ̐l�̗���͌����X�����������A�O��錾���̐����ɂ͓͂��Ă��Ȃ��B���W���[�ړI�Ŕɉ؊X�ɌJ��o���͎̂�҂����łȂ��A�d�lj�����@���X�N������40�`50��������Ƃ����B�e�c���́u�V�^�R���i�͋G�ߐ��C���t���G���U�ƈႢ�A�����x�͎��S����B�����ƉƑ������s�����v�ƌĂъ|�����B
24���ɂ̓p�������s�b�N���J������B���������߂�ꂽ�e�c���́u�ܗւ����ϋq������A����Ɠ������]�܂����ƌl�I�ɂ͍l����B�ܗւϋq�ł���Ċ����g�債�Ă��钆�A�p�������s�b�N�͗L�ϋq�łł���ƁA�����߂������Ȃ��v�Əq�ׂ��B
����܂ł̉�ł́A���g�E���{���ȉ��畡���̐��Ƃ����ɗ��Ă������A�����g����A�����ȊO�͑S���I�����C���ŎQ�������B
���ߋ��ő��X�V�@�É�����288�l�����@�N���X�^�[���������@8/11
�����̊g�傪����ɉ������Ă��܂��B8��11���̌����̐V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�288�l�ʼnߋ��ő����X�V���܂����B�A�Ȃ�O��PCR��������l�������Ă��܂����A���Ƃ͌������ʂ��ߐM�������Ȃ��悤�ɂƌĂт����Ă��܂��B
�����N�������@�㓡�����Q���u�Z���t���b�N�_�E���B�����̐g����邽�߉Ƃ���͏o�Ȃ��v
���Ƃɂ����܂Ō��킹��قǂ̐q��łȂ��X�s�[�h�Ŋ������L�����Ă��܂��B11���̐V���Ȋ����҂������̕ʂɌ��܂��ƁA�l���s��65�l�A�É��s��50�l�A���Îs��28�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B�l���s�A�É��s�Ƃ���1��������̊����Ґ����ߋ��ő��ł��B���}�s���̊w�Z�̕�������12�l�̊����������A�x�m�s�̐ڑ҂����H�X�u�e�B�A���c�[�v��14�l�̊������m�F����A����2�����V���ȃN���X�^�[�ƔF�肳��܂����B
�����N�������@�㓡�����Q���u4�A�x�A3�A�x�������l���������Ċ������Ȃ����Ă������v
����ɉ����Ă���u���Ƃ����v�ƂȂ��Ă���̂�PCR�����̈������ł��B�����Ȃǎ�s���ł͂��~�̋A�Ȃ�O��PCR��������l�������Ă��܂��B�������A�l���s�ł�PCR�������A���������̂ŋA�Ȃ����l���A�A�Ȍ�ɗz���Ɗm�F�����Ⴊ���T����ڗ����n�߂Ă���Ƃ������Ƃł��B
�l����ÃZ���^�[�����NJǗ����ʌږ�@���M�v��t�uPCR�������A�ȑO�ɂ���ĉA����������S���Č����ɖ߂��Ă���l�����邪�APCR�A���͂��̓��������ʂ��ۏ���Ȃ��B���̓��͗z���ɂȂ邩������Ȃ��B���s�n��A���Ɋ֓�����̋A�Ȃ͂��̉Ă͂�߂Ă������������v
���͊����̃s�[�N�͂܂��悾�Ƃ݂āA���C��s�D�z�}�X�N�̒��p�A�l�Ɛڂ��鎞�Ԃ����炷�Ȃǂ̑���Ăъ|���Ă��܂��B
���V�^�R���i�����Ċg��@���~��O�ɑ啪�����̊ό��n�͋��@8/11
�V�^�R���i�̕ψكE�C���X�̊������S���Ŋg�傷�钆�Ō}���邨�~�x�݁[�B�啪�����̊ό��n����͍Ăѐ�s���ɕs���̐����オ���Ă��܂��B
�R���i�БO�̑啪���ʕ{�s�ɂ͂��̎����A�����̊ό��q���K��Ă��܂�����10���̓S�։���X�̐l�o�͂܂�ł����B���������Ɉ��H�X�̊W�҂���͗��_���鐺��������܂����B
���H�X�W�ҁu�������炨�~�x�݂ɂ��܂��B���q���S�R���Ȃ�����₵���ł��ˁB�̂ɔ�ׂ���3����1�ȉ��ɂȂ��Ă��܂��B�v
�ʕ{�s�̊ό������̈�u�C�n���v�B7���̗���Ґ��͋��N�̓��������ɔ��1�D7�{�ɑ����܂������A���N�̉ċx�݂͗�N��5�����x�Ƌ���\�z���Ă��܂��B
�C�n���E���`�L�{�݉^�c�����u��N�ɔ�ׂ�Ώ��Ȃ��ł������X�ɊF�l���o�����悤�ɂȂ肨�q�l�����X�ɑ����Ă��Ă���B�����\�h�����Ă��܂������݂��ɋC�����Ȃ��痷�s�ɗ��Ă������������B�v
���N�̃S�[���f���E�B�[�N�����ȍ~�A�ψكE�C���X���g�債���e���ł��悻1�����ԋx�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�ʕ{�s�́u���ɂ�܃z�e���v�B8���͔N�Ԃōł��\���������ł����A��N��3�����x�ɂƂǂ܂��Ă��܂��B
�q�u����������҂������邩������Ȃ��̂ł��傤���s�ɗ��܂����B�v�u���~�̎������Ɛl�̈ړ��������̂ŏ����O�̂��̎����ɂ��܂����B�l�������܂ő����Ȃ��̂ň��S���ĉ߂����܂����B�v�u�I�V���C�͐l���Ă��đ݂���̏�Ԃł����B�v
���ɂ�܃z�e���ł͋q�����������钆�A���N�̉ċx�݂͗�N�ɂȂ�����ω�������ƕ��͂��Ă��܂��B
�u�ǂ����炨�����ɂȂ�܂������H�v
�q�u�ʕ{�ł��B�����̐l�͊����̃v�����������Ĉ������܂�邩�痈�܂����B�v
������Ώۂɏh���������ő��1��5000�~�̊�����2000�~�̒n��N�[�|����������u�V�����������������v�B���̃v�����𗘗p���錧���q�������Ă���Ƙb���܂��B
�q�������x�z�l�u��N�̉ċx�݂͊֓��E���E�����̂��q�l���قƂ�ǂ��߁A�����̂��q�l��2�A3���ɉ߂��Ȃ��X���ł������N�͌����̂��q�l�����ł�20���ȏエ�����ł��̂ŗ����̌��ʂ��\���ɔ�������Ă���B�v
�z�e���ł͂��̎x����̌��ʂɍ�������҂��Ă��܂��B
�q�������x�z�l�u�ŋ߃��N�`���̐ڎ헦���������Ă��܂���11�����炢����͒ʔN�̂��q�l�̗\��Ɋ��҂��Ă܂��͌����̕�����ċx�㔼��A���z������������B�v
����A�啪�s�̗��s��ЃI�[�V�[�g���x���B8���̗\��̓R���i�БO��2019�N�Ɣ�ׁA���悻3���ɂ܂ŗ�������ł��܂��B���ɉƑ����s�̐\�����݂́A�قƂ�ǂȂ��������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�I�[�V�[�g���x����敔�E�g���G���ے��u��N�ł���ΉƑ��A��̃f�B�Y�j�[�����h��USJ�Ȃǂ̐\���݂�����܂����A���������R���i�ЂƂ������Ƃœ������Ȃ��e�ЂƂ��������Ă���B�v
���̂悤�Ȓ��A�����̗��s��Ђł��u�V�����������������v�̖₢���킹���������ł��܂����A�V�K�����҂̑������뜜���Ă��܂��B
�I�[�V�[�g���x����敔�E�g���G���ے��u5���̎��͐V�������������������X�e�[�W2����X�e�[�W3�֏������グ��ꂽ���Ƃɂ���ė��p����~�ɂȂ�܂����̂ʼn��Ƃ��X�e�[�W2���ێ�����ĐV�������������������p������邱�Ƃ��F�����B�v
�ψكE�C���X�̊����g�傪�������A���N���R���i�ЂŌ}���邨�~�x�݁B�����̊ό��n�͂܂��܂���s�������ʂ��Ȃ��Ɍ������Ă��܂��B�@
�@
|
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i�����}�g��ł���Ȃ�a���m�ۂ͓�q �@8/12
�����s���ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g��œ��@���҂��ߋ��ő����X�V�������Ă��āA�s�͕a��������ɑ��₷���ߒ����𑱂��Ă��܂����A��Ë@�ւ���͐l���̊m�ۂ�����ȂǂƂ����������������������Ă��āA����Ȃ�a���̊m�ۂ͓�q���Ă��܂��B
11���̎��_�ŁA�s���̓��@���҂�3667�l�ƂȂ�A5���A���ʼnߋ��ő����X�V�����ق��A�s�̊�ŏW�v�����d�ǂ̊��҂�197�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B
�s�́A�V�^�R���i�E�C���X�̊��҂�����邽�߂̕a�������݁A5967���m�ۂ��Ă��܂����A����ɂ��悻400�����₵�Ă���܂łōő��ƂȂ�6406���Ɉ����グ�����l���ł��B
�s�͈�Ë@�ւɑ��āA�ʏ��Â̐���������ɁA8��6�������h�Ƃ��ĕa���̒lj��̊m�ۂ�v�����Ă��܂������A11���̒i�K�ł܂������������Ă��܂��B
�s�ɂ��܂��ƁA��Ì��ꂩ��͐l���̊m�ۂ�����ʏ�̈�ÂƂ̗������ł��Ȃ��Ȃ�ȂǂƂ���������������������A����Ȃ�a���̊m�ۂ͓�q���Ă���Ƃ������Ƃł��B
�s���̈�Ò̐��̂Ђ���������ɐi�ނȂ��A���Ƃ̒��ɂ́u�ЊQ���Ɠ������v�Ƃ�����������A�s�͕a���̊m�ۂ��}�����Ƃɂ��Ă��܂��B
�������s��t��Ȃǂ�����×{�Ҏx����ۑ�ŋً}��c�@8/12
�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�����������×{�҂��}�����钆�A�����s��t��Ȃǂً͋}�̃I�����C����c���J������×{�҂��x���邽�߂̉ۑ�ɂ��Ĉӌ������킵�܂����B
�V�^�R���i�̊����g�傪��������×{�҂��}�����Ă��邱�Ƃ��āA�����s��t���11���A�s����47�̒n���t��Ⓦ���s�A����Ɍ����J���ȂƋً}�̃I�����C����c���J���܂����B
���̒��ŁA�����s��t��͕ی��������S�ɍs���Ă��鎩��×{�҂̌��N�ώ@��e�̂̈����ɂ����@�̕K�v���̔��f�Ȃǂ��A���M�O���̂����Ë@�ւ₩�������Ȃǂɂ��\�Ȕ͈͂ŋ��͂���悤���߂܂����B
����ɑ��A�n���t���́A���@���K�v���Ɣ��f���Ă����@�ł��Ȃ����҂�����̂ŕa���𑝂₵�Ăق����Ƃ��A���@���҂Ɍ����Ďg�p����Ă���u�R�̃J�N�e���Ö@�v�Ƃ������Ö@����@���҈ȊO�ɂ��g�p�ł���悤�ɂ��Ăق����Ƃ������ӌ����o����܂����B
��c�̂��ƁA�����s��t��̔��莡�v��́u�ۑ�͑���������ŏd�lj����Ă��̂܂܂ɂȂ��Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�̐�����i�߂����v�Ƙb���Ă��܂����B
���S���̐V�K�����ҁA�ő�1��5812�l�c���J�ȁu��Ñ̐��͍ЊQ���ɋ߂��v �@8/12
�V�^�R���i�E�C���X�̑S���̐V�K�����Ґ���11���A1��5812�l�ƂȂ�A�ߋ��ő��ƂȂ����B9�{���ł��ߋ��ő����X�V����ȂǁA�S���I�ɐV�K�����Ґ����}���ɑ������Ă���A�����J���Ȃ̏����@�ւ͓����A�u����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��ŁA��s���𒆐S�Ɉ�Ò̐��͍ЊQ���̏ɋ߂��v�ƌx����炵���B
�����s�ł�11���A�V�K�����҂�4200�l�m�F���ꂽ�B����1�T�Ԃ̕��ςł͑O�T����14�E5���������B�����҂̋}���ȑ����ɔ����ďd�ǎ҂��}�����Ă���A40�A50�Α�𒆐S�ɁA�s��̏d�ǎ҂�197�l�ƁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B
�d�ǎҌ����a���̎g�p����50�E3���ƂȂ�A�s�̊W�҂���́u��Ï]���҂̊m�ۂ�����ŁA����ȏ�̏d�ǎ҂̑����ɑΉ�����͓̂���Ȃ��Ă���v�Ƃ̐����オ���Ă���B
�V���ȓ��@�̎���⒲��������ɂȂ��Ă���B����×{�҂�1�����O�̖�12�{�ɂ�����1��9396�l�ƂȂ����B
��t�A�_�ސ염���ł�20�A30�Α�𒆐S�ɐV�K�����҂��}�����A�d�ǎҐ����ߋ��ő����X�V�B�d�Ǖa���g�p�����㏸���Ă���B
���{�ł��A�Ⴂ����𒆐S�ɋ}���ɐV�K�����Ґ����������Ă���B���@�ҁA�d�ǎ҂Ƃ��ɑ������A��Ԃ̐l�o���������߁A�����g�傪�������Ƃ��\�z�����B
���ꌧ�ł́A10���܂ł�1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���247�E83�l�őS���ő��ŁA�ߋ��ɗ�̂Ȃ������B��Ò̐����S���ōł����������B
�����@�ւ̍����߂�e�c�����E���������nj��������́u�R���i�̏Ǐo�ċ~�}�Ԃ��Ă�ł��A���@�ł��Ȃ��ɂȂ����B��ʈ�Â̐����������Ă���B������Ƒ�����邽�߁A�������X�N������邱�Ƃ��K�v���v�Ƒi�����B
���錾1�J���Ŋ�����5.5�{�@���Ɓu������v�f�Ȃ��v�@8/12
�����s�ł�4��ڂً̋}���Ԑ錾���n�܂��āA12����1�J���ɂȂ�B����܂ł̐錾�ł͊��Ԓ��ɐl�o������A�����҂����������A����͐l�o�����قnj��炸�A�ψكE�C���X�̖҈ЂŊ����҂͈ٗ�̋}���𑱂��Ă���B�����͓s�s������n���ɍL�����Ă���A���ʂ͏o�Ă��Ȃ��B
����܂ł̉ߋ�3��ً̋}���Ԑ錾�ł́A�錾���o��O���납��l�X�̎��l���n�܂��Đl�o������A����ɒx��Ċ����҂����闬�ꂾ�����B�ߋ�3��̐錾�J�n���Ƃ���4�T�Ԍ�̊����Ґ�(����1�T�ԕ���)���ׂ�ƁA2��ڂ͖�6�����A3��ڂ�1�����������B
����A4��ڂƂȂ鍡��B�錾�J�n���̊����Ґ�(��)��757�l�Ȃ̂ɑ��A4�T�Ԍ��4135�l�Ƌt�ɖ�5�E5�{�������B�����͂������f���^�����L���������Ƃ��w�i�ɂ���B�����J���Ȃ̐��Ƒg�D�́u����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��̋ǖʁv�Ɗ�@�����������A�Z�����Ă��Ȃ��̂����B
����𗠕t����悤�ɐl�o������Ȃ��BNTT�h�R���̌g�ѓd�b�̈ʒu��琄�v�����f�[�^�����ƂɌ�����ƁA�s���̔ɉ؊X�̐l�o�́A�錾������d�˂邲�Ƃɂ��̌�������݂��Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����������B
�����Ґ��������X���ɂ���ɂ�������炸�A���N�ɓ����ďo���ꂽ2��ڂ�3��ڂ̐錾�O��̐l�o�̌�����́A��N��1��ڂ̎��قnj����ł͂Ȃ��B�����҂̑���������������͂���Ɍ�������ɂ₩�ŁA�ċx�݂₨�~�̋A�ȃV�[�Y���œs�S�̐l���������N�̏ƁA���܂�ς��Ȃ��X���������Ă���B
�s���̎�Ȕɉ؊X�ł́A1��ڂ̐錾��30���Ԃ̐l�o���A�錾�O��30���ԂƔ�ׂ�63�E2%���������A����̌��蕝��9�E4%�ɂƂǂ܂����B�s�S�߂��̍s�y�n�ł�40�E3%����5�E5%�AJR�̎�v�w�ł�65�E1%����7�E9%�Ƃ��ꂼ�ꌸ�蕝���k�������B
����A���̉Ăɋx�ɂ�A�ȂŎ�s���𗣂��l�́A��N���������Ă���B����̐錾���o�Ă����30���Ԃ��݂�ƁA���Z�n�̓����A��t�A��ʁA�_�ސ��1�s3���𗣂�A�ق��̓��{���ɑ؍݂��Ă����l(�ߌ�3����)�́A��N�̓����ԂƔ�ׂ�22�E5%�����B8��8���ȍ~��150���l������������Ă���B
11���̌��J�Ȃ̐��Ƒg�D�́u���~�͌������z�����ړ��A�O�o���T���āv�Ɗ�@��i�����B
����A����܂łƏ��Ⴄ�̂́A����҂̃��N�`���ڎ킪�i�e���ŁA60�Έȏ�̓��@���҂̊����������Ă��邱�Ƃ��B3���͔N��ʂ�4����3���߂����A���݂͖�2���B����҂����������ƂŁA7�A8���̎��Ґ��������Ă���B
���{�����݂̍j�Ƃ��郏�N�`���ڎ�́A2��ڎ���I��������҂�82�E3%(10�����_)�ɒB���Ă��邪�A�S��(��Ï]���҂�����)�ł�29�E3%(����26�E3%)���B
11���̐��Ƒg�D�̉�ŁA���s��̐��Y�������́A����̊����̎��Z���������B���s�Ɠ����y�[�X�ő����Ă������ꍇ�A�����s�ł�8�����{��1��������1���l���A9�����߂�2���l�ɒB���錩�ʂ����Ƃ����B���~�Ō������Ȃǂ͌���Ƃ̌���������B���Ƒg�D�̊ړc�ꔎ�E���M�勳���́u�����Ґ��͂���������悤�Ɍ����āA���̌�܂�������B������v�f�͂Ȃ��v�Ƙb�����B
����������91�l�����@�V�^�R���i�A���Z�^�����N���X�^�[10�l�Ɋg��@8/12
����11���A������91�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B10���ɗz���Ɣ����B�����̊����m�F�͉���6710�l�ƂȂ����B
�������ō��̉^�����Ŕ��������N���X�^�[(�����ҏW�c)�ŐV���ɐ��k3�l�̊������m�F����A�v10�l�Ɋg�債���B���킫�s��10�����\�������Ə�(112����)�̃N���X�^�[�ɂ��āA���Ȃ�11���A���Ȕ������Ƃɏ]������֘A��ƂƔ��\�B���Ə��ł͐V���ɒj��1�l�̊������m�F����A�v9�l�ƂȂ����B
91�l�̓���͂��킫�s43�l�A�S�R�s11�l�A�����s10�l�A��Îᏼ�s7�l�A������4�l�A�{���s�A�쑊�n�s�e3�l�ȂǁB32�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B
10�����݂̓��@�Ґ��͏d��14�l���܂�397�l�B94�l���h���×{���ŁA322�l������×{���Ă���B60�l���×{�撲�����B�����܂ł�59�l���މ@�A18�l���h���×{�{�݂�ޏ����A22�l�̎���×{�����������B
������̃R���i�����Ґ��A1�J����1���l���̉\���@8/12
���ꌧ��11���A�V����10�Ζ����`90��̒j��638�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����Ґ��ł�5����648�l�Ɏ�����2�Ԗڂ̑����ŁA��T�̐��j�����36�l�����B���@����h���{�ݗ×{���Ȃǂ��܂ޗ×{�Ґ���4840�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����X�V�����B
�����̗v�����Ґ���3��43�l�ƂȂ����B��1���l����2���l����܂�74�������������A��2���l����3���l�܂ł�53���Ƒ啝�ɒZ�k�B���̎�������ËZ�Ắu�����͂̋����f���^�����v���ŁA����܂łɂȂ������ōL�����Ă���B���̂܂��܂�Ȃ����1�J����1���l����\��������v�ƌx���������߂��B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���246�E84�l�őS���ő��̏������B2�Ԗڂɑ��������s��199�E35�l�B
����{���̃R���i�a����L���͏d�Ǘp85���A�����Ǘp93�E8���A�y�Ǘp87�E3���ƕN��(�Ђ��ς�)�������Ă���B���@�E�×{��������1932�l�ʼnߋ��ő����X�V�����B
����1������{�����ʼn^�p�ĊJ�����A���@�������Ɉꎞ�ҋ@����u���@�ҋ@�X�e�[�V�����v��11���ߌ�9���܂łɌv70�l�����p�B10��������11�l�����p�����B����×{��h���×{�{�݂ŏǏ������~�}��������銳�҂ŁA�_�f���^���K�v�Ȍy�E�����NJ��҂��ΏہB���͌y�ǎҌ����h���×{�{�݂Ƃ��āA����s���̃z�e����V���Ɋm�ۂ��A12������^�p���n�߂�B�h���×{�{�݂͌���7�J���ځB
�V�K������638�l�Ŋ����o�H���ǂ����̂�242�l�ʼnƑ������ő�124�l�B�N��ʂł�20�オ143�l�ōł������A30��119�l�A40��94�l�ȂǁB�ČR�W�͐V����21�l�̊������������B
���A�Ȃ◷�s�Ŋ����ґ����A�m���u���Ԑ[���v�@����123�l�����@8/12
���ŐV�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�5��20���ȗ��A83���Ԃ��100�l����11���A�Óc���m���͋L�҉�Łu�f���^���̊����͂������A���Ԃ͐[�����v�Ɗ�@���������ɂ����B�����͂��~�V�[�Y����O�ɋA�Ȃ�o���A���s�A���W���[�֘A�ɂ�銴���҂��������Ă���B������𗬃T�C�g(�r�m�r)����g���ă��X�N�̍����s���̎��l�𑣂��Ă������́A�}�g��̋ǖʂ��}���������̑�5�g�ɑ��A��i�̑��𔗂��Ă���B
�u������A�̈�a�������������A�����g��n�悩�猧���ɋA�Ȃ��A�Ƒ��ɂ��g�債���v�u����ߐ����܂܃h���C�u�����āA����҂����ǁv�B�����^�p���A��������`����c�C�b�^�[�u�������E�R���i�m�d�v�r�v�ł́A���Ă̎�Ȋ���������Љ�Ă���B�c�C�b�^�[�ł͂��̂ق��A�P�g���C���l���ł̗��s�A�h���C�u�Ȃǂɂ�銴�����g�債���P�[�X�����グ�A�u�����g��n�悩��̋A�Ȃ͎��l���v�u�̒��s�ǎ��͍s�����X�g�b�v�v�ȂǂƌĂъ|���Ă����B
�����ł�7�����獡��5���܂ł̊����҂̂����A���O����̋A�Ȃ⌧�O�ւ̗��s�A�o�������ފ����҂����ɏ�邪�A�Óc�m����11���A�u���݂����̌X���̉�������ɂ���v�Ǝw�E�B�u���N�̊����g��ƈႢ�A���N�`���ڎ킪�i�݁A����̊����҂͌������Ă��邪�A�����̃X�s�[�h�������v�Ƌ����x�����������B
�Óc�m���͍���̑Ή��ɂ��āA�u����܂łƓ��l�ɁA�}���ȕω��ɑ��đ��߂Ɏ��łv�Ƃ��āA���Ǝ��̔�펖�Ԑ錾�̔��߂̂ق��A���ɑ��Ă͂܂h�~���d�_�[�u��ً}���Ԑ錾�̗v��������Ɍ���������j���������B�u(13���ɂ��J��)���Ɖ�c�ł͂���ɋ������K�v�ȑ���c�_����v�Ƃ��A�����ɂ́u��{�I�Ȋ�����⊴����h�����߂̍s�������肢�������v�Ɖ��߂ČĂъ|�����B
�������s �V�^�R���i 4200�l�����m�F �d�ǎ҂͍ő��X�V197�l�� �@8/12
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g�傪���������s���ł�11���A�V����4200�l�̊������m�F����܂����B����A�s�̊�ŏW�v����11�����_�̏d�ǂ̊��҂�197�l�ƂȂ�A10���ɑ����ĉߋ��ő����X�V���܂����B�܂��s�́A�������m�F���ꂽ30���70��̒j��2�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��A���̂���30��̒j���͎���ŗ×{���ɖS���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
�����s��11���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��4200�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B4000�l����̂�3���O�̍���8���ȗ��ł��B1�T�ԑO�̐��j������34�l�����āA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B11���܂ł�7���ԕ��ς́A3983.6�l�ŁA�O�̏T��114.5���ł��B����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A25��8981�l�ƂȂ�܂����B
����A�s�̊�ŏW�v����11�����_�̏d�ǂ̊��҂́A10�����21�l������197�l�ƂȂ�܂����B10���ɑ����ĉߋ��ő����X�V���d�NJ��҂̑������~�܂�܂���B����1����101�l�ŁA11���܂łɔ{�߂��ɑ����Ă��܂��B�s���A���݊m�ۂ��Ă���d�NJ��җp�̕a���̎g�p���́A��3�g�̂��Ƃ�1��31���ȗ�50������50.3���ɂȂ�܂����B
�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ30���70��̒j��2�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���̂���30��̒j���͎���ŗ×{���Ă��Č��N�ώ@�𑱂��Ă��܂������A�e�̂��}�ς��ĖS���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2319�l�ɂȂ�܂����B
�s�̊�ŏW�v�����d�NJ��҂��ߋ��ő��ɂȂ������Ƃɂ��āA�����s�̏��r�m���͋L�Ғc�ɑ��āu�S�̂̊����҂������Ă��Ă��āA�d�ǂ�200�l�ɋ߂��������B��Ë@�ւ���͒ʏ�̐f�Â�f������A��p��摗�肵���肷��Ȃǂ̎��ԂɊׂ�Ƃ��������Ă���B���傤�͏d�ǎ҂̂����A50�オ3����1���߂Ă���B40������̂������C��9�l�����Ă���B��b�����������Ă������^�o�R���z���Ă�������C�����Ă������������v�Əq�ׂ܂����B
�������s ����×{�҂��}�� �_�f���^�܂ŏǏ������Ă� �@8/12
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��œs���ł͎���ŗ×{����l����������܂łōł�����2���l���A�}�����Ă��܂��B�_�f�̓��^���s���܂ŏǏ������Ȃ�����A����ŗ×{����������Ȃ����҂̎p���݂��Ă��܂��B
��s���𒆐S�ɕ����̈�Ë@�ւƘA�g���Ė�Ԃ�x���A��t�ɉ��f�����Ă�����Ă����Ђł́A�����s�̈ϑ����ēo�^�����t���V�^�R���i�̎���×{�҂�K�₵�f�Â��s���Ă��܂��B
�ی���������@���K�v�Ɣ��f���ꂽ���̂̎����̒��������Ȃ��P�[�X���������A8���ɓ����Ă����1�T�Ԃʼn��f������s���̎���×{�҂̂����A�x���Ȃǂ��������_�f�̓��^���s��ꂽ�̂�35���������Ƃ������Ƃł��B
���̂���1�l��炵��40��̒j���͂��悻1�T�ԁA�×{�������Ă��āA���f�����������������ނȂǏǏ����������ߎ_�f�̓��^���s��ꂽ�ق��A60��̕v�w��40��̑��q�����������P�[�X�ł́A���q��2�l�����@���K�v�ȏ�Ԃł����������������Ƒ�3�l�Ŏ���×{�𑱂��Ă��܂����B
��4�g�ł͑��ō���҂𒆐S�Ɏ���×{�҂��}�����܂������A��5�g�ł͊�b�����̂Ȃ�30���40��̊��҂Ŏ_�f�𓊗^����܂ŏǏ��������P�[�X�������ł���Ƃ������Ƃł��B
���f���s���Ă���u�t�@�X�g�h�N�^�[�v�̑�\�A�e�r����t�́u����ȏ�A�����Ґ�������������Ɗ��҂��K�ȏꏊ�œK�Ȉ�Â����Ȃ��Ƃ������ɂȂ�A�������������������Ȃ����Ƃ��o�Ă��邩������Ȃ��B�ł��邩����̈�Â���Ď���Ă�����Ǝv�����A������̓O������肢�������v�Ƙb���Ă��܂����B
���ی��������@���f��1�T�� ��������
�����s����ϑ����Ĉ�t������×{�҂̉��f���s����Ђ��B�e�����f���ɂ́A�_�f�̓��^���s���܂ŏǏ������Ȃ��������ŗ×{����������Ȃ����҂̎p���݂��܂����B
�s����1�l��炵�����Ă���40��̒j���͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������ی���������@���K�v�Ɣ��f����܂������A�������������悻1�T�ԁA����ŗ×{�𑱂��Ă��܂����B
���M���o�Čċz���ꂵ���Ƒi���Ă��Ĉ�t�����f����Ԃ����܁A��������������ł��܂����B
���t���̎_�f�̒l���p���X�I�L�V���[�^�[�ő��肷��Ɛ��l��90���O���ɉ������Ă��āA���Â��n�߂Ȃ���Ώd�lj��ɂȂ��肩�˂Ȃ���Ԃ��Ɣ��f����܂����B
���̂��߁u�_�f�Z�k���u�v�ƌĂ���Ë@�����������ŁA���҂̕@�Ƀ`���[�u�����Ď_�f�𓊗^���_�f�̗ʂ𑝂₵�Ă����܂����B����ƁA�_�f�̐��l�͎��������Ă����܂����B
�����A���Ǐ������邩�����炸�Ō�t��3���Ԃ��Ƃɓd�b�Ȃǂŏ�Ԃ̊m�F���s�����Ƃɂ����Ƃ������Ƃł��B
���f�����e�r����t�́u�������ċz���40�x�̔��M������A���Ȃ�x�����i��ł��邱�Ƃ��^�킹��Ǐ����B���@�������̂悤�����Ȃ��Ȃ����Ԃ��������Ă����ԂŁA�v�������Ȃ��Ƃ͎v�����ł��邩����Ή����Ă��������v�Ƙb���Ă��܂����B
����ƑS�������� ���@�K�v������ŗ×{
�s���ŕ�炷60��̕v�w��40��̑��q�̉Ƒ�3�l�͈�ƑS�����������A����ŗ×{�𑱂��Ă��܂��B
40��̑��q��37�x��̔��M������A���̂����肪�C�����������Ƒi���Ă��܂����B
60��̕��e�͏Ǐ�͏o�Ă��܂��A60��̕�e��39�x�̔��M�Ƒ��ꂵ����i���Ă��܂����B
���q�ƕ�e�͎��܁A�������������ޏ�ԂŋC���������ĐH�����Ƃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�ی�������͕�e�Ƒ��q�ɂ��Ă͓��@���K�v�Ɣ��f����܂������A������������t�͉��}�[�u�Ƃ��āu�_�f�Z�k���u�v�Ŏ_�f�𓊗^���_�H���s���Ă��܂����B
60��̕�e�͌��t���̎_�f�̒l��80���㔼�ɒቺ���Ă��āA40��̑��q�����l��90���O���ɉ������Ă��܂����B
60��̕��e�͉��f�����X�^�b�t�ɑ��āu3�l�Ŋ������Ă��܂��O�ɂ��o���Ȃ����A�ǂ������炢������������Ȃ������v�Ƙb���Ă��܂����B
���f�����e�r����t�́u���@���K�v�Ȋ��҂����@�ł��Ȃ��Ď���ɂ��ӂ�Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B�������������҂ɂǂ̂悤�Ȉ�Îx�������Ă������B���҂͕s���ɉ����Ԃ��ꂻ���ɂȂ��Ă�����������݂���B�����̕a�ǂꂭ�炢�̂Ƃ���ɂ��荡��ǂ��Ȃ��Ă����̂������炸�A�{���ɂ炢�Ő�������Ă���Ǝv���B����������Y���ĐS�̃P�A���܂߂Ď��Â��Ă��������v�Ƙb���Ă��܂����B
���V�^�R���i�u�ЊQ���x���̔�펖�ԁv �����s�̐��Ƃ�������@���@8/12
�����̊g�傪�~�܂�܂���B�����s�̐��Ƃ���́u�ЊQ���x���Ŗ҈Ђ�U�邤��펖�ԁv�ƁA����܂łɂȂ��قǂ̋�����@����������Ă��܂��B
�����E��蒬�ɂ��鎩�q���̑�K�͐ڎ�Z���^�[�B�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���ڎ�̂��߁A12�����吨���K��Ă��܂����B�����s��12���A�V���ɔ��\���������҂�4989�l�B�d�ǎ҂�218�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�d�ǎ҂̔N��w�͈ȑO���Ⴍ�Ȃ��Ă��āA40���50�オ����6�����߂Ă��܂��B
�u�܂����N�`�������ЁA�Ⴂ�����ł��Ē��������v(���r�S���q�s�m�� �挎28��)
�u40��50��̐ڎ���Ă��Ȃ����X�ɂ́A���N�`���ڎ���ł��邾���������肢�������v(���r�S���q�s�m�� ����2��)
���r�m���͏d�lj����Ă���40����50��̂قƂ�ǂ����N�`�����ڎ�ł���Ƃ��Đڎ���Ăт����܂����A12���A���̑�K�͐ڎ�Z���^�[�ɗ��Ă����l�ɘb���ƁE�E�E
�u(�ǂ̋�ł�)�\����ɂ��Ă���A�����ė~�����B���������A(�\��)���₷���悤�ɂ��Ē�����v(40�� �����悩�痈���l)
�u�\�����ς��ŁA��̐ڎ�������ς��ł����A��̕a�@���\��9���Ƃ�10���Ƃ��łȂ��Ǝ��Ȃ���ԁv(50�� �����悩�痈���l)
���������Z��ł��鎩���̂ŁA�Ȃ��Ȃ��ڎ�̗\���Ȃ��Ƃ�����������������܂����B�����A�����g��͑҂����Ȃ��̏ł��B
�ŐV�̊����͂��铌���s�̃��j�^�����O��c�B���Ƃ���o���̂́A����܂łɖ����������t�ł����B
�u�g�ЊQ���x���h�Ŋ������҈Ђ�U�邤��펖�Ԃł���B���͂�ЊQ���Ɠ��l�ɁA�����̐g�͎����Ŏ��B�����\�h�̂��߂̍s�����K�v�Ȓi�K�ł���v(�������ۈ�Ì����Z���^�[ ��ȋM�v ��t)
�g�ЊQ���x���h�̔�펖�ԁB7���ԕ��ς̐V�K�����Ґ����A����2�T�ԂŔ{�����Ă���Ƃ��āA�����̐g�͎����Ŏ��s�����K�v�Ƒi���܂����B
�����������A12���ɉ���s�����͓̂s��6�̎����̂̋撷��B���݂̓R���i�Ђ̒��ōł��[���ȏł���Ƃ��āA�S���ւ̊����g���h�����ߓ����Ȃǁu���������G���A�v�ւ̃��N�`���d�_�z�z��i���܂����B�܂��A���@�ҋ@���̗z���҂Ɏ_�f���^���s���u�_�f�X�e�[�V�����v�̑��݂Ȃǂ���܂����B(12��17:25)
���u�����̊����g�� ����s�\�v�@�s�̃��j�^�����O��c�@8/12
�����s�̃��j�^�����O��c�ŁA���Ƃ́u���ĂȂ��قǂ̑��x�Ŋ����g�傪�i�݁A����s�\�ȏŁA�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ�U�邤��펖�Ԃ��v�Ǝw�E���������Łu��Ò̐����[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���v�Ƃ��āA�ɂ߂ċ�����@���������܂����B12���ɊJ���ꂽ��c�̒��ŁA���Ƃ́A�s���̊����ƈ�Ò̐����������4�i�K�̂����ł������x�����x���ňێ����܂����B�V�K�z���҂�7���ԕ��ς́A11�����_�ł��悻3934�l��2�T�ԂŔ{�����Ă���Ɛ������u���ĂȂ��قǂ̑��x�Ŋ����g�傪�i�݁A�V�K�z���҂��}�����Ă���A����s�\�ȏ��v�Ǝw�E���܂����B
���u�ЊQ���Ɠ��l �����̐g�͎����Ŏ��s�����K�v�Ȓi�K�v
���̂����Łu�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ��ӂ邤��펖�Ԃ��B���͂�A�ЊQ���Ɠ��l�ɁA�����̐g�͎����Ŏ�銴���\�h�̂��߂̍s�����K�v�Ȓi�K���v�Əq�ׂ܂����B�܂��A11�����_�ŁA���@���҂͉ߋ��ő���3667�l�ƂȂ�u�s�̓��@�����{���ł́A�����ȍ~�̒����ւ̌J��z���⎩��ł̑ҋ@��]�V�Ȃ�����鎖�Ⴊ���������Ă���v�Ǝw�E���܂����B���Ƃ́u���ɏd�NJ��҂̓��@����������ɂȂ��Ă���B����×{���ɗe�̂������������҂̎��������Ȃ��Ă��āA����Ȃǂł̑̒��̈����𑁊��ɔc�����A���₩�Ɏ�f�ł���̐�������ɋ������A����×{���̏d�lj���\�h����K�v������v�Ƃ��Ă��܂��B
���g��@���������̂��̂Ƃ��ċ��L����K�v�h
�܂��A���Ƃ́A11�����_�ŏd�ǂ̊��҂�197�l�A�l�H�ċz��Ȃǂɂ�鎡�Â��܂��Ȃ��K�v�ɂȂ�\�����������҂�461�l�Ƒ啝�ɑ������Ă���Ƃ��āuICU�Ȃǂ̕a���̕s�����뜜�����v�Əq�ׂ܂����B�����āu�ʏ��Â��܂߂Ĉ�Ò̐����[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���B����Ȃ�d�NJ��҂̑����͈�Ò̐��̊�@�������A�~���ł���\�������鑽���̖����������ƂɂȂ�v�Əq�ׁA�ɂ߂ċ�����@���������������ŁA��@���������̂��̂Ƃ��ċ��L����K�v������Ƌ������܂����B
���l�H�ċz��Ŏ��Ẩ\���̐l �ߋ��ő���
�s���̓��@���҂̂����A�l�H�ċz��Ȃǂɂ�鎡�Â��܂��Ȃ��K�v�ɂȂ�\����������Ԃ̐l�́A11�����_�ʼnߋ��ő���461�l�ɏ��A1�T�Ԃ�1.4�{�ɑ������Ă��܂��B�s�̐��Ƃ͖��T�s���郂�j�^�����O��c�ŁA��Ë@�ւŏW���I�ȊǗ����s���Ă���u�d�NJ��҂ɏ����銳�ҁv�̐l�������\���Ă��܂��B���̂����A�l�H�ċz��܂���ECMO�ɂ�鎡�Â��܂��Ȃ��K�v�ɂȂ�\����������Ԃ̊��҂́A11�����_�ʼnߋ��ő���461�l�ƂȂ�܂����B318�l������1�T�ԑO�̍���4�������C��140�l�ȏ㑝����1.4�{�ɑ������܂����B�ߋ��ő����X�V����̂�2�T�A���ł��B461�l�̂����A���悻������236�l�͕@���獂�Z�x�̎_�f���ʂɑ��荞�ށu�l�[�U���n�C�t���[�v�Ƃ������u���g�������Â��s���Ă���Ƃ������Ƃł��B
�����r�m���u�l�� �ً}���Ԑ錾�J�n���O��5���Ɂv
���j�^�����O��c�̂��ƁA�����s�̏��r�m���́u�܂��Ȃ����~���n�܂邪�A���̊��Ԓ��̓X�e�C�z�[����O�ꂵ�A���s��A�Ȃ̒��~���������肢�������B�l�Ɛl�Ƃ̐ڐG�������Ɍ��炵�Ă������������h�~�ɂȂ���̂ŁA�l�����ً}���Ԑ錾�̊J�n���O��5���ɍ팸���邱�Ƃ�O�ꂵ�Ăق����v�Əq�ׂ܂����B�܂��u�����̐l�����p���鏤�Ǝ{�݂ɂ́A���ꐮ���̓O���q�ɒZ���Ԃ̗��p���Ăт����Ă��������悤�A���肢���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
���u�ЊQ���x���Ŋ����҈Ёv�@�s��������@���@8/12
�����s�́A�V�^�R���i�̊����͂����c���J���A���Ƃ́A�u�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ�U�邤��펖�ԁv�ƁA������@���������܂����B
�������ۈ�Ì����Z���^�[�E��ȋM�v��t�u���ĂȂ��قǂ̑��x�Ŋ����g�傪�i�݁A����s�\�ȏł��B�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ�U�邤��펖�Ԃł���܂��B�ЊQ���Ɠ��l�Ɏ����̐g�͎����Ŏ��B�����\�h�̂��߂̍s�����K�v�Ȓi�K�ł���܂��v
�����s��t��E�������F����u�d�NJ��҂��}���ɑ������Ă���A��Ò̐����[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���B����ɂ����鎀�S�҂������������Ă��܂��v
�����҂�7���ԕ��ς́A�O��̂��悻3443�l����A3934�l�ɑ傫�������A�������114���ƈˑR�Ƃ��č��������ɂ���A���Ƃ́A�u�ЊQ���Ɠ��l�ɁA�����̐g�͎����Ŏ��A�����\�h�̂��߂̍s�����K�v�Ȓi�K�v�Ǝw�E���܂����B
�܂��A�f���^���̊����́A81�D7���ŁA�s���̊����́u�f���^���ɒu����������v�Ǝw�E���܂����B�d�NJ��҂��A����4�����_��115�l����197�l�Ƒ傫���������A���Ƃ́u��Ò̐����[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���v�Ƌ�����@���������Ă��܂��B
����A�ɉ؊X�̖�Ԃ̃��W���[�ړI�̐l���́A�d�lj����X�N�̍���40����64�̒����N�w�̊������A�ł������Ǝw�E����܂����B
���s���̐l�o�A2�T�Ԃ́u�錾�O�̔����Ɂv�@���ȉ�@8/12
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ��12���A�����g�傪�[���ȓ����s�ō���2�T�ԁA�W���I�ɑ���������A�l�o���ً}���Ԑ錾���n�܂钼�O��5���܂Ō��炷�K�v������Ƃ���ً}�����\�����B���g�Ή�́A����×{�҂��}�����A���@����������Ȃ��Ă���Ƃ��āA�u�~���閽���~���Ȃ��Ȃ�悤�ȏɂȂ�n�߂Ă���v�Ƌ�����@�����������B
�ł́A��N�w�����łȂ��A���N�`�����ڎ�ŏd�lj����X�N���������s�N�w���O�o�������Ă���Ǝw�E���A���⎩���́A��ʎs���ɑ��A�Z���W���̑������߂Ă���B�l�o�́u5�����v�́A1�l�����l�Ɋ��������邩�������u�����Đ��Y���v��1�������A�����Ґ�������n�߂�ƍl�����鐅���ŁA�Œ���K�v�Ƃ����B���g���͂��łɐl�o�́u�������������Ă��Ă���v�Ƃ��A�u�l�X�ɗ����⋦�͂��Ă��炤�v���߂ɂ��̊����ɂƂǂ߂��Ɛ��������B
��̍�Ƃ��Ĉ�ʎs���ɁA���G�����ꏊ�ւ̊O�o�@��̔��������߁A���ɓ����Ƒ��ȊO�Ƃ̈��H���A�����ԁE��l�����W�܂��ʂȂǂ͔�����ׂ����Ƌ��������B�u5�����v�̒B���ցA�S�ݓX�̒n���̐H���i������V���b�s���O���[���Ȃǂւ̐l�o���u���͂ɗ}���v���邱�Ƃ�A�e�����[�N�̋������Ăт������B
����A���X�N��}���Ȃ��瑱�������̓I�ȃC�x���g��{�݂������B�ϋq�������o���Ȃ��R���T�[�g�≉���A�f��فA������}���قȂǂ��������B
�܂��A�l�X����̋��͂邽�߂ɂ܂��͍��⎩���̂������K�v������Ƃ��A��Ò̐��̋��������߂��B�R���i�Ή��́u�ЊQ��Áv���Ƃ��āA�R���i���ÂɌg����Ă��Ȃ���Ë@�ւ��Ï]���҂�ɂ����͂�v�����ׂ����Ƃ����B
���łɂ��~�̋A�ȃV�[�Y���ɓ����Ă��邪�A���g���͐��{�ƒ������钆�Œ����̃^�C�~���O�ɂȂ����Ɛ����B�錾���������}����8�����܂łɌ��ʂ邽�߂́u���肬��Ō�̃^�C�~���O���v�Ƙb�����B
�����N���o�ύĐ����́u�l���̗}���ɂ��Ē��~�߂đΉ��������v�Ƃ��Ȃ�����A�u����܂ł��e�����̂ŏ�悹�̑[�u���Ȃ���Ă���B�m����Ƌٖ��ɘA�g�������v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߁A���哱�̐V���ȑΉ��ɂ͓��ݍ��܂Ȃ������B
�������Ƀ��N�`���W�����@�s���A�^��}�ɋً}�@8/12
�V�^�R���i�E�C���X�̊����ҋ}�����A�����s���c�J��Ȃ�6�����̂̎�12���A�s���ŋL�҉���A�����ȂNJ����g��n��Ƀ��N�`���������W�������邱�Ƃ����߂�ً}�\�����B
�����A�����}�Ɨ�������}�ɑ��t�����Ƃ����B
�ً}�ł́A���N�`�������̏W���ɉ����A�}�����鎩��×{�҂ւ̃I�����C���f�Â�R�̃J�N�e���Ö@���\�Ƃ��鐧�x�����A���@�҂��̊��҂��_�f�z���ł���{�݂̑��݂Ȃǂ����߂��B�@
���R���i���N�`���ڎ�̎�҂Ƀ|�C���g�t�^�@20�`30��A�A�v���Ł\�����s�@8/12
�����s��12���A�V�^�R���i�E�C���X���N�`����ڎ킵��20�`30��̎�҂ɁA�X�}�[�g�t�H���A�v���Ń|�C���g��N�[�|����t�^����L�����y�[�����Ƃ��s�����j�𖾂炩�ɂ����B�s���̊����҂̖�7����30��ȉ��ŁA�����g��̗v���ƂȂ��Ă���B����A�e�풲���Ŏ�҂��ڎ�����߂炤�X���ɂ��邱�Ƃ���A�s�́u�C���Z���e�B�u(���@�t��)��^���邱�ƂŃ��N�`���ڎ�𑣐i�������v�Ƃ��Ă���B
�s�ɂ��ƁA�s���ݏZ��20�`30��̖�340���l���ΏۂɂȂ�B�ڎ�L�^�A�v���ɓo�^����ƁA���σA�v���Ȃǂɋ��^��Ƃ���|�C���g��N�[�|�����͂��d�g�݂�z��B��������e�̏ڍׂ͍���A��������B�s��8����\�Z�ĂɊJ����Ƃ���2��5000���~���v�サ���B
�s��2�`3���ɍs�����C���^�[�l�b�g�����ł́A���N�`�����u�K���ڎ킷��v�u�����炭�ڎ킷��v�Ɠ�����������65�Έȏ�̍���҂�86�D5�����������A�Ⴍ�Ȃ�قǒቺ��20���62�D0���������B�s�͂����������ʂ����܂��āA�C���^�[�l�b�g�𗬃T�C�g(�r�m�r)�Ȃǂ�ʂ����[���������W�J����Ƃ����B
���u����s�\�v�u�ЊQ���x���v�����g��ɐ��Ƃ�������@�� �@8/12
���u���䂪�s�\�ȏv�u�ЊQ���x���v
�u���ĂȂ��قǂ̑��x�Ŋ����g�傪�i�݁A�V�K�z���Ґ����}�����Ă��萧�䂪�s�\�ȏł���܂��v�����s�̐V�^�R���i�E�C���X���j�^�����O��c�ł́A�V�K�����҂�7���ԕ��ς�3934�l�ɂȂ�A2�T�ԂŔ{���A�������114���ŁA7�T�A����100�������Ƃ̕��͂������ꂽ�B�u�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ�U�邤��펖�Ԃł���܂��v�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���ۊ����ǃZ���^�[���́A�d�˂ċ�����@���������������Łu���̊�@���������̂��̂Ƃ��ĊF�ŋ��L���v�Ƒi�����B
��10�Ζ��������ґ����A�ۈ牀�A�w���N���u�ł̑��
�����o�H�ʂł́A�ƒ����������6���ƍł���������ŁA10�Ζ����̎{�ݓ��������O���82�l����189�l�ɑ傫�������B�ۈ牀�A�w���N���u���ł̊����\�h��̓O�ꂪ�K�v�A�Ƃ̎w�E�������ꂽ�B
����Ò̐��͐[���ȋ@�\�s�S
��Ò̐��ɂ��ẮA�d�ǎ҂��}���ɑ������Ă���A�~�}��Â�\���p���̒ʏ��Â��܂߂Ĉ�Ò̐����[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă��āA���̊��������������ł��̐��̈ێ�������ɂȂ�A�Ɣ��Ɍ������������ꂽ�B
�����r�m���u�R�̃J�N�e���Ö@���h���×{�ł��v
�u�d�ǂɂȂ���͍��̂Ƃ���͌��Ă��Ȃ��v���ڂ��W�܂��Ă���R�̃J�N�e���Ö@�ɂ��đ�ȃZ���^�[���́A�o���͔��Ɍ����Ă���ƑO�u�����������ŁA���X�N�̍������҂ɓ��^�����Ƃ���d�ǂɂȂ����l�͌��Ă��Ȃ��A�Ƃ������ŁA���^���24���Ԍo�ߊώ@�̕K�v������A���^�ɂ���Âւ̕��ׂ̏d�������炩�ɂ����B�u�R�̃J�N�e�����㏸��}���邱�ƂɌq����A����͈�Ò̐��̕��S���y�����邱�ƂɂȂ�v���r�m���́A���̍R�̃J�N�e���Ö@���120�J���̓��@�d�_��Ë@�ւŎ��{�ł���悤��܂��m�ہA�s�����Еa�@�Ő�p�a����20���m�ہA����Ɉꕔ�̏h���×{�{�݂ł��Ή��ł���悤�̐�������A�Ɩ��炩�ɂ����B
�����@�Ƃ͎�������Ⴄ ����×{���҂�f�邽�߂�
�u����ς���@���Ă���̂Ƃ͂��̎�����Ƃ����낢��Ⴂ�܂��̂ŁA���낢�����Ă͂���܂�����ǂ��Ȃ��Ȃ��肪�͂��Ȃ��Ƃ����������A�܂��ɍЊQ�ƌ����̂ɂӂ��킵���ɂȂ��Ă��܂��v�����s�̊����Ґ��̑����ɔ�Ⴕ�đ��������Ă��鎩��×{�ҁB11���ɂ́A��b�����̂Ȃ�30��j��������×{���Ɏ��S���Ă���B�����s��t��̒������F����́u����×{�̊��҂����f�邽�߂ɁA��������s�����čl��������@���낢�������Ă���܂��v�ƁA��ÕN���̒��ł̎���×{�ґΉ��̑̐����ɂ��ǂ��錻���b�����B
����̔ɉ؊X�A�ł������̂͒����N
�u��ԑؗ��l����N��K�w�ʂɕ��͂���ƒ����N�w�̊������ł������v��̔ɉ؊X���o�����Ă���l�̂����A20������22����15����39��43���A40����64��49���A22������24����15����39��44���A40����64��47���A�Ƃ̕��͂���������s��w�����������Љ�N��w�����Z���^�[�̐��c�~�u�Z���^�[���́u��N�w�݂̂Ȃ炸�����N�w�̈�w�̋��͂��K�v�v�Ǝw�E�����B
���u�l����5���팸���v
�u�l����5���팸�Ƃ������Ƃ��A���̊ԓO�ꂵ�Ă��肢�������v�s�p�s�}�̊O�o���l��A�ȁE���s�̒��~�E�����ƂƂ��ɋً}���Ԑ錾�J�n�O��5���ɐl����}����悤���߂����r�m���B�������ɂ��Ă��A�����s���Ă���l��3����1��A�Ƒ��݂�Ȃł������ɏ��l���ɂ��邱�ƁA�ȂǂƘb�����B���̈���Łu�����͂����肢����Ƃ����̂��䂪���̖@�̗��ĕt���v�Ƃ��b���A�����͂��Ȃ����Ƃ̓�������߂ğ��܂����B
�������̐g�͎����Ŏ��
�u���͂�A�ЊQ���Ɠ��l�ɁA�����̐g�͎����Ŏ�銴���\�h�̂��߂̍s�����K�v�Ȓi�K�v�����A��Ò�̗����Łu�ЊQ�v�Ƃ������t���g��ꂽ�����A���������܂��o����̂́u�o���邾���l�Ɖ�킸�v�u�o���邾������ɂ���v�B�����Ď�A���ŁA�}�X�N�̐��������p�A��������O�̂��ƂƂ��Ē��J�ɂ��肩�����Ă��������Ȃ��B
��10�l�͓������ʓ��K���c�V�^�R���i �x�R�����g�ߋ��ő��h�@8/12
�V�^�R���i�E�C���X�A12���͌����ł͉ߋ��ő��ƂȂ�71�l�̊������V���Ɋm�F����܂����B���@�Ґ������߂�200�l���A���́u���̃y�[�X�������A�Ǝ��̌x�����x�����X�e�[�W3�Ɉ����グ��\��������v�Ƃ��Ă��܂��B
12���������m�F���ꂽ�̂͒������ƏM����������13�̎s�ƒ��A����ɁA�ΐ쌧�ƕ�������10�Ζ�������70��܂ł̒j�����킹��71�l�ł��B
���̂����A4�l���x���Ȃǂ̏Ǐ��i�������ǂł��B
1���Ɋm�F���ꂽ�����Ґ��́A5��23���ƍ���6����64�l������ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
71�l�̂���9����50��ȉ��A�Ȃ��ł�20���30�オ�����߂����߂Ă��܂��B
�܂��A�����ݏZ��10�l�������s�A��ʌ��ȂNJ������g�債�Ă���n���K��A�ΐ쌧�ƕ������ݏZ��2�l�͍���6���ɗ������Ă��܂��B
�v�̊����Ґ���2766�l�A�V����92�l���C���h�R���̃f���^���̋^�������邱�Ƃ��킩��܂����B
���@�҂̐��͏��߂�200�l���A�����d�ǎ҂�8�l�ł��B
���Ǝ��̌x�����x���͌��݃X�e�[�W2�ł����A�d�Ǖa���ғ�����������3�̎w�W�ł̓X�e�[�W3�ֈ����グ�̊���Ă��܂��B
�����̏d�Ǖa����36������A����1�T�Ԃ�30���A11�l����ƃX�e�[�W3�̊�ɓ��B���܂��B
���́A�u���̃y�[�X�������A�X�e�[�W3�ڍs�̉\��������v�Ƃ�����ŁA�u���~�̎��������A�����̈ړ��͍T���A���i�����Ă��Ȃ��l�Ƃ̉�H�͍T���Ăق����v�ƒ��ӂ��Ăт����Ă��܂��B
���u�����͊������Ȃ��v40~50��Ŕ������c�}���̃~�h������Ŋ�@�������@8/12
�����s�Ȃǂ�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o�āA12����1�������o�߂��܂����B�V�^�R���i�E�C���X�̊����́A���܂�ǂ��납�}���Ȋg��̂܂��������ɂ���܂��B����Ȓ��A����40��E50��̓������傫�ȃJ�M�������Ă��܂��B
���ڂ�ς��u�d�lj�����N��v
�܂��A�ŐV�̐V�^�R���i�E�C���X���������`�����܂��B
11���A�����s�ł͐V����4200�l�̊������m�F����܂����B���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�A�[���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B
�܂��A�V����30���70��A2�l�̎��S���m�F����܂����B���̂���30��̒j���́A37�x��O���̔��M������A�y�ǂƐf�f����A����×{�����Ă��܂����B�������A����6���A�j���ƘA�������Ȃ��Ȃ����Ƒ��������K�˂��Ƃ���A���S���Ă����Ƃ������Ƃł��B
�ی����́A���N��Ԃ��m�F���Ă��āA�j���͎��S����O���ɕs����i���Ă����Ƃ������Ƃł��B�܂��A���̒j���́A�u��b�����v���Ȃ��A�u���N�`���ڎ���v���Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
���݁A�s���̎���×{�҂�1��9396�l�ɏ��A1�����O�Ɣ�ׁA���悻�u12�{�v�ɋ}�����Ă��Ă��܂��B�����s�́A��t�ɂ�鉝�f�ȂǁA�t�H���[�̐��̋�����i�߂Ă��܂��B
�܂��A�����s�ł͏d�ǎ҂��}�����Ă���A11����197�l�ƁA�O���ɑ����ĉߋ��ő����X�V���܂����B���̏d�ǎ҂̔N��ł����A��3�g�̃s�[�N���������N1��20���Ɣ�ׂ�ƁA���Ȃ�ω����Ă��܂��B
1��20�����_�ł́A�d�ǎ҂̂قƂ�ǂ�����҂ŁA40��E50���15%�ł����B���ꂪ�A11���́A40��E50�オ��߂銄���͂��悻�u60%�v�ɂȂ��Ă��܂����B�Ⴂ�N����d�lj�����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
����̔ɉ؊X�Ƀ��W���[�ړI�Łc���N�w������
12���A�����s�ŊJ���ꂽ�����͂����c�ł́A���Ƃ�������@���������܂����B
�������ۈ�Ì����Z���^�[�E��ȋM�v��t�u���ĂȂ��قǂ̑��x�Ŋ����g�傪�i�݁A�V�K�z���Ґ����}�����Ă���܂��B����s�\�ȏł���܂��v
�����s��t��E�������F����u40��E50��𒆐S�ɁA�d�NJ��҂��}���ɑ������Ă���A�~�}��Â�\���p���̒ʏ��Â��܂߂āA��Ò̐����[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă��܂��v
���ɁA40��E50��̏d�NJ��҂��}���ɑ����Ă���Ƃ������Ƃł��B
11���ɊJ���ꂽ�����J���Ȃ̐��Ɖ�c�ł́A���̂悤�ȃf�[�^��������܂����B�s���̔ɉ؊X�ɁA�ʋΒʊw�������ă��W���[�ړI�ŏo�����Ă���l���A�N��ʂ̊����ł݂��O���t�ł��B
�ߌ�8������10���̎��ԑт��݂Ă݂�ƁA40����64�̒��N�w�̕����A��҂��������o�����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B����ɒx�����ԑт̌ߌ�10������ߑO0�����݂Ă݂�ƁA��҂������Ă���Ƃ͂����A���N�w���������Ƃ��킩��܂��B
���߂ł݂Ă��A�Ⴂ������A���N�w�̊����������Ƒ����Ă��܂��B�l���̑����Ƃ����ƁA�Ⴂ����̕��������o�����Ă���悤�ȃC���[�W�������ł����A�����ł͂Ȃ��悤�ł��B
���u�����͊������Ȃ��v�Ⴂ�������@������
�����������A40��E50��̃R���i�ɑ����@�ӎ��ɂ��āA�����[���������ʂ�������܂����B���ۈ�Õ�����w���挎���{�A��s����1�s3����20�ォ��60��̒j�����悻3000�l��Ώۂɍs�����A���P�[�g�ł��B
�u���������퐶���ŐV�^�R���i�Ɋ�������Ǝv�����v�ƕ������Ƃ���A�u�v��Ȃ��v�u���܂�v��Ȃ��v�Ɠ������l�́A30��ł͒j���Ƃ���40%��ł����A40��ł͒j��52%�A������48%�Ƒ����A�����50��ɂȂ�ƁA�j����55%�A������60%�ɁB�j���Ƃ���40��E50��̕����A�Ⴂ�������@������r�I�����Ƃ������ʂɂȂ�܂����B
�܂��A�m�荇���Ɋ����҂��o���l�ł́A�u�����͊�������Ƃ͎v��Ȃ��v�u���܂�v��Ȃ��v�Ɠ������l���A20��E30��ł͒j��32%�A����37%�ł����A40��E50��ł͒j��51%�A����56%�Ɣ������Ă��܂��B�g�߂Ɋ����҂�����ꍇ�ł��A�~�h������͎Ⴂ������A�����͊������Ȃ��Ǝv���Ă���l�̊������������ʂɂȂ��Ă��܂��B
�������s�����a�c�k�������́A�u���X�N��F�����Ă��Ȃ��̂��A����Ƃ��ߐM������̂����R�͂킩��Ȃ��v�Ƃ��A�u�~�h���̔N��́A��Ђł͊Ǘ��E�̐l�������̂ŁA��������Ɗ���������Ė͔͂������A����ɂ��ǂ��e�����o��̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂��B
�o���l���������炱���A���܂Œʂ�̂��Ƃ�����Ă���Α��v�Ǝv���Ă��܂���������܂��A�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��ẮA�킩��Ȃ����Ƃ������̂ŁA���߂Ċ���������������Ƃ���ł��B
40��E50��ƌ����A�܂��ɎЉ�̒��j��S������ł����A���̐l�������A���܍ł����@��d�lj�����������ƂȂ��Ă��܂��B��Ƃ�ƒ�ł��A�ӔC���闧��ʼne���͂��傫���N�ゾ���炱���A�����͑��v�Ɩ��S�����A�������ƂƂ��Ċ�@�ӎ������L�������Ǝv���܂��B
�������̐V�K�����A�ߋ��ő���1��8888�l�c20�{���ōő��X�V�@8/12
�����̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�12���A�S�s���{���Ƌ�`���u�ŐV����1��8888�l�m�F����A����܂łōł������Ȃ����B20�{���ʼnߋ��ő����X�V���Ă���A�S���I�Ɋ������}�g�債�Ă�����Ԃ��N���ɂȂ����B
�V�K�����Ґ����ő��ƂȂ����̂́A�{��A�����A��ʁA�V���A�x�R�A����A�É��A���m�A�O�d�A����A���s�A���A���ɁA���R�A�����A����A����A�F�{�A�������A����̊e�{���B
���{�ł�1654�l�̊������������A�ő��X�V��2���A���ƂȂ����B1�T�ԑO���569�l�������A�V�K�����҂�6������30�Α�ȉ�����߂��B
�܂��A�����s�̐V�K������4989�l�̂����A�N��ʂōő��������̂́A20�Α��1490�l�B30�Αオ1031�l�A40�Αオ865�l�ő������B65�Έȏ��3���ɓ�����161�l�������B
���S���m�F���ꂽ�̂�50�`80�Α�̒j��6�l�ŁA���̂���60�Α�̒j���́A6�����{�܂łɃ��N�`����2��ڎ킵�Ă����Ƃ����B
���V���ɃN���X�^�[6���@����122�l�����u�����I�����g��v�@8/12
���Ɗs��12���A����26�s���ȂǂŐV����122�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B�V�K�����Ґ���100�l����̂�2���A���ŁA�����̊����҂͗v1��304�l�ƂȂ����B���̒���1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���26�E18�l�ƂȂ�A���̊�ŃX�e�[�W4(�����I�����g��)�̖ڈ��ƂȂ�25�l��5��27���ȗ��A77���Ԃ�ɒ������B
11�����_�̕a���g�p���͑O����1�E6�|�C���g����29�E8���ŁA����ŃX�e�[�W3(�����}��)�̐����B12�����_�̏d�ǎ҂�4�l�B����13���ɐ��Ɖ�c���J�Â��A����̑����������B
�����N�������̖x�T�s�����́u��N�w�ł��_�f�z�����K�v�Ȓ����ǂ̊��҂������Ă���B���̂܂܊����҂�������A���@�ł��Ȃ���Ԃ��N���肤��v�Ǝw�E�B�u�����̃s�[�N�������ł��Ⴍ�A���|���ɂł���悤�A���܈�x�A�A�Ȃ╁�i���Ȃ��l�Ƃ̐H���Ȃǂ͍T���Ăق����v�ƌx�����Ăъ|�����B
�V����6���̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F�����B���Ð�s�̑�w�̉^�����֘A�ł́A����2�l�Ƃ��̉Ƒ�4�l�̌v6�l�̊��������������B���m���̑�w�֘A�ł͉^�������ƗF�l��5�l�̊��������������B�܂��A�s�̐E��ł͈ꏏ�ɉ^�������Ă���13�l�̂����A5�l�̊��������������B���̑��A�E��֘A�ł͑������s��6�l�A�H���s�A���S�䐓���Ŋe5�l�̊��������������B
�g�債���N���X�^�[��6���B���̂����A���Ð�s�̈��H�X�֘A�ł͐V����5�l�̊�����������A�v19�l�ƂȂ����B���͈��������A�����҂̒����̂��ߓX�����\�����߂Ă���B�s�̕a�@�ł�1�l�����Čv10�l�ƂȂ����B�I�������N���X�^�[��1���B
�V�K�����҂̋��Z�n�ʂ́A�s34�l�A��_�s13�l�A���Ð�s11�l�A�������s10�l�A�e�����s6�l�A�֎s�A����s���e4�l�A�H���s�A�y��s�A�R���s�A�{���s�A�H���S��쒬�A���S�}�������e3�l�A���s�A�C�Îs�A�����S�������A���ΌS���@�����e2�l�A���Z�s�A�b�ߎs�A���Z���Ύs�A��ˎs�A���C�s�A�{�V�S�{�V���A�K��S��쒬�A�{���S�k�����A���ΌS���쒬���e1�l�A���m��3�l�A�����s���A���{���e1�l�B
�N��ʂ�10�Ζ���3�l�A10��13�l�A20��35�l�A30��25�l�A40��18�l�A50��16�l�A60��8�l�A70��3�l�A80��1�l�B
�܂��A����11�����\����������1�l�ɂ��āA���Z�n���e�����s����{���s�ɒ��������B
�����A���ی㎙���N���u�ŃN���X�^�[���@���Ə��ł������g��@8/12
��錧��12���A�����̐V�^�R���i�E�C���X�V�K������274�l�̂���6�l�͂����݂�����s���̕��ی㎙���N���u�̎����Ɩ��炩�ɂ����B�܂��A�푍�s���̎��Ə��ł͏]�ƈ�4�l�̊������V���ɔ��������B���͂�����ɂ��Ă��N���X�^�[(�����ҏW�c)�����̉\��������Ƃ݂Ă���B
���ɂ��ƁA�����N���u�ł͊��Ɏ����A�E���e1�l�̊������m�F����Ă���A��A�̊����҂�8�l�ɑ������B�������������������Ə��]�ƈ��͌v5�l�ƂȂ����B
�܂��A�N���X�^�[�������������Ύs���̑�w�o�X�P�b�g�{�[�����ł͊w��1�l�̗z����������A�������ł̊����҂͌v31�l�ƂȂ����B
���_�ސ쌧 �V�^�R���i�����g�ЊQ���x���ň�Õ�����h�@8/12
�_�ސ쌧���ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g��Ɏ��~�߂������炸�A�Ǐ������Ă������ɓ��@�ł��Ȃ����ԂɂȂ��Ă��܂��B�����ÊW�҂́u���͂�ЊQ���x���ŁA�ʏ�̈�Â�������v�Ɗ�@�������߂Ă��܂��B
�_�ސ쌧�ł͐挎���犴���̋}���Ȋg�傪�����A���@���҂�11���̎��_��1344�l��1�����O�̂��悻2.7�{�ɑ����Ă��܂��B�ŏ��͌y�ǂ△�Ǐ����l���}���Ɉ�������P�[�X�������Ă��āA�����Ɏg����a���̎g�p����79���܂ŏオ��܂����B���ł��d�NJ��҂͂���܂łōő���182�l�ɏ���Ă��āA�a���̎g�p����97���Ƃقږ����̏�Ԃł��B�Ǐ������Ă������ɓ��@�ł��Ȃ��P�[�X�������Ă��āA���͐�T�A�V�^�R���i�E�C���X�̊��҂�����Ă���186�̈�Ë@�ւɑ��A�a���𑝂₷�ƂƂ��ɁA�������ł�����@���p�ɂ��Ă�3�������x�����悤�v�����܂����B�܂��A���̕a�@�����11���A�u����܂Ŋ��҂�����Ă��Ȃ������a�@���܂߂āA���ׂĂ̕a�@�őΉ����Ăق����v�ƈٗ�̒��o���܂������A�ݔ���l��̖��ŁA�����ɑ��₷�͓̂���̂�����ł��B�_�ސ쌧��Ê�@���������̈���p����t�́A�u���͍ЊQ���x���̊��Ҕ����ŁA����ꂪ��낤�Ƃ��Ă�����Ñ̐�������Ă���B�a�@�Ƒ��k���Ȃ���a���𑝂₷�w�͂���X�����Ă������A����ȏ�Ɋ��҂���������~�߂Ȃ���A�ǂ�����Ă�����Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂��B
�����҂̋}���ŏǏ������Ă������ɕa�@�ɂ��ǂ���Ȃ����Ԃ��������ł��܂��B�_�ސ쌧�ł͐V�^�R���i�̊��҂ɂ��āA�n��Ŏ���悪������Ȃ��ꍇ��A����×{���Ɉ��������ꍇ�́A�����ɐݒu����24���ԑԐ��̈�Ê�@���{���Ō����S��Ŏ�����T���Ă��܂��B�������A����Ȃǂŗ×{���̊��҂�1��2000�l���A�e�̂���������l���}�����Ă��邱�Ƃ���A�z���C�g�{�[�h�ɏ����ꂽ�e�a�@�̎���\�Ȋ��Ґ��̗��ɂ̓[��������ł��܂��B���ɏd�Ǘp�̕a���͂قږ����̏�ԂŁA11���͒S���̈�t���d�lj�����50��̒j��������Ă����a�@��T���āA�d�b�����������Ă��܂����B���@�悪���̓��̂����Ɍ�����Ȃ����҂́A��������100�l�߂��ɏ���Ă��āA2�����O�Ȃ炷���ɓ��@�����Ă����悤�ȗe�̂̐l�ł��A�ł��邾������×{�𑱂��Ă�����Ă���Ƃ����܂��B�S���̈�t�́A�u�d�NJ��҂͂�����{�I�ɍs���Ƃ��낪����܂���B����ɉ��x���d�b���āA���܂��܋��Ƃ���ɂȂ�Ƃ�����Ă�����Ă���̂�����ł��B����ŏǏ��������l�ɁA�w����������Ǝ���ł����܂��傤�x�ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�������炢�ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�����̋}�g����Ċe�n�̕a�@�ł͕a���𑝂₵�Ă��܂����A���҂�������X�s�[�h���͂邩�ɏ���A����ł��Ȃ���ԂɂȂ��Ă��܂��B���l�s�ߌ���ɂ���u�ϐ���l�s�����a�@�v�ł́A�~���~�}�Z���^�[�Ȃǂɂ��킹��22���̃R���i�p�a����p�ӂ��Ă��܂������A�����g�����11���܂ł�28���ɑ��₵�܂����B�������A��������߂�d�b�������瑊�����ŁA���₵���a���͂����ɖ��܂�A����������11���̗v����f��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�e���͐V�^�R���i�ȊO�̋~�}��Âɂ��y��ł��܂��B�V�^�R���i�̎��Âɂ͐l�肪�����邱�Ƃ���A�Z���^�[�Ŏ���邱�Ƃ��ł���R���i�ȊO�̋~�}���҂͒ʏ�̔����ȉ��ɂȂ��Ă��āA��ʎ��̂�}�a�Ȃǂ̊��҂����Ȃ��P�[�X���o�Ă���Ƃ������Ƃł��B�������K�~���~�}�Z���^�[���́A�u���Ȃ芳�҂���̎����f�炴������Ȃ��ɂȂ��Ă��܂��B�a�@�Ƃ��Ă͍ő���a���𑝂₵�Ă��āA�܂������g��̃s�[�N�������Ȃ����ŁA���ꂩ���ǂ��Ή����邩����Y�܂��Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
�����܂�Ȃ������g��A�����ܗւƂ̃����N�����邩�@8/12
�j�b�|�������u�ѓc�_�i��OK! Cozy up!�v(8��12������)�ɐ_�ˑ�w��w�@�@�w�����ȋ�����NPO�@�l�C���h�����m��茤�����������������r�m���o���B8��11���ɓ����Ŋm�F���ꂽ�d�ǎҐ���1��������̉ߋ��ō����L�^�����V�^�R���i�E�C���X�ɂ��ĉ�������B
8��11���ɑS���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����ҁAPCR�z���҂�1��5800�l����1��������ߋ��ő��ƂȂ����B�܂��A�����s���ł�11����4200�l�̊������m�F����Ă���B11�����_�ł̏d�ǎҐ���197�l�ƂȂ�A�O���ɑ����ߋ��ő����X�V�����B
�ѓc)4200�l�̓��������ƁA20��`30�オ2129�l�ƂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ɐ������肪���o���ɏo�ė���Ƃ��������́A�ǂ̂悤�ɂ����ɂȂ�܂����H
����)���ꂾ������Ƌ��낵���Ȃ�܂����A�����Ƃ����̂́A�ǂ̂悤�Ȍ`�Œ��邩�Ƃ������Ƃ��厖�ł��B�R���e�N�X�g�ł��ˁB�u�d�ǎ҂��ő��X�V��197�l�v�Ƃ�������������ƁA�u���v�Ȃ̂��ȁA���ꂩ���ǂ̂悤�ɂȂ��čs���̂��ȁv�Ǝv���A�u���S�҂����l����̂��v�Ƃ���������Ă��܂��B��قǒ��ׂ��Ƃ���A(�����s��)11���̎��S�҂�2�l�Ȃ̂ł��B�������A2�l�̖��͑傫���̂ł����A������2021�N2�����炢�̃s�[�N�̎��S�Ґ�����40�l�������Ƃ������Ƃ��l����ƁA�S�̓I�ȃR���e�N�X�g�̂Ȃ��ɗ��Ƃ����ޕK�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����)�l�I�ɂ́A�V�K�����҂̂����A�u���N�`����2��ڎ킵���l�͂ǂ̂��炢����̂��v�Ƃ������Ƃ��m�肽���ł��ˁB�����g�����N�`����2��ڎ킵�Ă��܂����A�����҂̐�����������ɂ́A�V���̌��o���ɂ�����܂������A�ً}���Ԑ錾�̉����ł͂Ȃ��A���N�`���ڎ����葁���s���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�ѓc)65�Έȏ�̃��X�N�������Ƃ���Ă��܂������A11���̐������猩�Ă�60�Έȏ�̊����҂�256�l�ƁA�S�̂̐��̂Ȃ��ōl����Ɗ����Ƃ��Ă͑������Ȃ��B���̕ӂ�̐��ゾ�ƁA2��ڂ̐ڎ킪�ق�7���قǏI����Ă���Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�܂��B�����l����ƃ��N�`���̌��ʂ͐����ɕ\��ė��Ă��܂���B
����)������Ƃ��Ă��d�lj����Ȃ��Ƃ����̂͑傫�Ȃ��Ƃł��̂ŁA���N�`���ڎ���}���ŗ~�����ł��ˁB
�ѓc)���N�`���ڎ�̒x��ƁA��������߂��̂ɂǂ��܂ŃX�s�[�h���グ����̂��A���̕ӂɂ������ė���Ƃ������Ƃł����H
����)�������Ǝv���܂��B
����)�I�����s�b�N���I���A�V�^�R���i�ɂǂ����Ă��t�H�[�J�X���Ă��܂������Ȃ̂ł����A�����Ŏ����S�z���Ă���̂́A���{�o�ςɑ���e���͂ǂ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃł��B���̎؋����c���ł���Ƃ����j���[�X���������܂����B���̕ӂ�̎��Ԃ͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B�ً}���Ԑ錾������ƁA�ǂ����Ă��o�ςւ̉e���������ł��Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���̕ӂ�̃o�����X�ł͂Ȃ��̂��ȂƂ͎v���܂��B
�ѓc)�u�ً}���Ԑ錾���o�܂��v�Ƃ����Ƃ��́A���H�X�Ȃǂɒ��p�ɍs�����肵�āA�u����Ȃɍ����Ă��܂��v�Ƃ������Ƃ��t�H�[�J�X����B�����ŁA���܂̂悤�ɋً}���Ԑ錾���o�����Ă���Ȃ��Ŋ����Ґ���������ƁA�������肪�t�H�[�J�X�����B�{���͌o�ςƂ̃o�����X�����Ȃ�������Ȃ��B
����)�������o�����X���厖�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ѓc)���ĂƓ��{�Ƃł́A���̈Ⴂ�̂悤�Ȃ��̂͂���܂����H
����)�����̎��ɂ��I�����s�b�N�̓p���ł͂Ȃ��ł����B�����f�����ςĂ���ƁA�}�X�N�����Ȃ��l���������܂��B
�ѓc)��̉f���Ȃǂł������ł����ˁB
����)�A�����J�̉f�����ς�ƁA�A�����J�ł����܃f���^���ő�ςȂ��ƂɂȂ��Ă���̂ł����A�u�����}�X�N�͂��Ȃ���v�Ƃ����l�����Ȃ肢�܂��B����ɖ߂肽���Ƃ����C�����������͂ł��܂��B�^�ĂɃ}�X�N�Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ���ςł͂Ȃ��ł����B
�ѓc)���ʂɂ���ǂ��ł���ˁB���(11��)�̂悤��36�x�A37�x�܂ōs���ƁB
����)�O�������Ȃ�܂���ˁB
�ѓc)���̕ӂ̃L�[�Ƃ��ă��N�`��������͂��Ȃ̂ł����A�������Ȃ��Ȃ��B
����)�I�����s�b�N���������̂ŁA���Ԓ��Ɏ��l�C���͗N���ė��܂����ˁB���������{�����Ȃ茒�����܂������A�����_���������l��܂����B����ȂȂ��Łu���ʂɂȂ��ė��Ă���̂��v�Ƃ����C�����ɂȂ��Ă��܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̈Ӗ��ł́A�����I�����s�b�N�Ƃ̃����N�͂���̂����m��܂���B
��2���A���ʼnߋ��ő��A�����̃N���X�^�[�g��@372�l�R���i�����̋��s�@8/12
���s�{�Ƌ��s�s��12���A���A�w������90���372�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1���̊����Ґ��Ƃ��Ă�2���A���ʼnߋ��ő��B�������̐l�������ΑS�����y�ǂ����Ǐ�ŁA239�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B�{���̊����҂͌v2��1341�l�ƂȂ����B
���s�s�̔��\����227�l�B����20�l�̊������������Ă��闤�㎩�q���j���Ԓn(������)�ŐV����1�l�̗z���������B�s���̊�ƂƉ^�������ł��A���̓��܂łɊe6�l�̊�����������A�s�̓N���X�^�[(�����ҏW�c)�̔����Ƃ݂Ă���B
���s�{�̔��\����145�l�B���Z�n�ʂł͉F���s31�l�A�T���s�ƖؒÐ�s�e14�l�A���ߎs�Ə�z�s�A��O�s�e9�l�A���s�s�Ɣ����s�A���c�ӎs�e8�l�A�����s7�l�A�������s6�l�ȂǁB�N���X�^�[���������Ă���F���s�̗��㎩�q����v�ے��Ԓn�Ŋ����҂�7�l�����A�v22�l�ƂȂ����B��O�s�̏�Q�Ҏ{�݁u�����ڂ̊w���v�ł�7�l�����Čv18�l�A���ߎs�̕a�@�ł�2�l�����Čv13�l�ƂȂ����B
�����ɂƋ��s�ً͋}���Ԑ錾�g�v�������h�@�u�܂h�~�v�őΉ��@8/12
���Ɍ���12���A�V�^�R���i�E�C���X�̑��{����c���J���A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώۋ����g�傷��ƌ��߂܂����B
16������́A�O�g��W�H�n��Ȃǂł����H�X�Ɏ�ނ̒�~��ߌ�8���܂ł̉c�Ƃ����߂܂��B
���ɋً}���Ԑ錾�̔��o��v�����邱�Ƃ͌�����܂����B
���ɁE�֓��m���u�܂h�~���d�_�[�u�̑Ή��Ƌً}���Ԑ錾�̑Ή��Ƃ����͓̂��e�ɂ����܂ō��ق������B(����)���c���������肵�Ă������Ƃ��厖���ȂƁv�B
����A���s�{���A12���̐V�K�����Ґ����ߋ��ő���372�l�ƂȂ�A�a���̎g�p����7�����錵�����ƂȂ��Ă��܂��B
12���̑��{����c�Ő��e�m���́A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώۋ��ɁA����܂ł̋��s�s�ȊO�ɓ암�̉F���s������s�Ȃ�7�̎s��lj����邱�Ƃ����߂܂����B
���s�{���ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v���ɂ��Ă͌�����A����A���Ƌ��c��i�߂�Ƃ��Ă��܂��B
���ߋ��ő��̊����Ґ����y���������z�͂��~�����H�@�������@8/12
8��11���ɕ������ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�����Ґ���230�l�B�ߋ��ő��̐��ƂȂ����B�O�̏T�̓����j������������������������A���̊g��̃X�s�[�h�������B
�s8���̊����Ґ��t7�����{���犴���҂̑������n�܂�8��2����114�l�Ə��߂�3���̊����҂��m�F�B���ꂩ��A�킸��10���Ԃ�2�{��230�l�Ƒ啝�ɉߋ��ő������������B
�s�������[�g�t����1�T�Ԃ̊����҂��ő���718�l�B�ƒ������31�E5��(226��)�o�H�s��31�E8��(228��)�ƍ��킹��6�����߂Ă���B�ċx�݊��ԂŎ���ňꏏ�ɉ߂������Ԃ������Ă��āA�ƒ���ł̊������������Ă���B���E��W16�E4��(118��)�A�m�l7�E7��(55��)�A���̑�12�E7��(91��)
�s�ߋ��ő��ƂȂ���230�l�̓���Ɗ����������w�W�t���킫�s�����ōł�����97�l�A�S�R�s36�l�A��Îᏼ�s29�l�A�{�{�s27�l�A�����s7�l�ȂǁB�����������w�W�́A�a���g�p���͊m�ەa���𑝂₵����66�D2���B�×{�Ґ��A�V�K�z���Ґ��ƂƂ��ɈˑR�Ƃ��āy�X�e�[�W4�z�̏������Ă���B
��8��11���܂łɔ����E�g�債���N���X�^�[
�@��Îᏼ�s�E�邪���E�a�@�@25�l������31�l��
�@���킫�s�E�����J�Еa�@�@2�l������23�l��
�@���킫�s�E���Ə��@2�l������11�l��
�@���k�Ǔ��̎��Ə��@34�l����38�l��
���ߋ��ő�230�l�̊����Ґ��ɕ��������́c
�@�u������Ƃт�����ł���ˁB����ς�v
�@�u�ǂ������ĂĂ��A�F�R���i�Ȃ�Ȃ����Ȃ݂����ȁv
�@�u�Z���Ԃł���Ȃɑ����Ă���̂ŁA�l���������e���Ȃ̂��Ȃ��Ċ����Ă܂��v
�@�u�����ŗ}���Ƃ��Ȃ��ƁA�܂���X�����҂������āA�����Ƒ�ςɂȂ��Ȃ����Ƃ����̂�����܂����ˁv
����ÊW�҂̊Ԃɂ́A����܂łɂȂ���@�����L����
��������t��E����������u�������Ƃ��Ă̊�{�͓��@��������ł����ǁA������Ȃ��Ȃ����Ȃ��Ȃ��Ԃɋ߂Â��Ă��܂��B���̂܂ܑ����Έ�Â��Ђ����ǂ��낶��Ȃ��āA�����j�łł��ˁv
�g��D�h�Ƃ���郏�N�`����2��ڎ킵����ÊW�҂ɂ��������L���������킫�s�̕a�@�N���X�^�[�ɂ́A�ψكE�C���X�̉e�����������ƍl���Ă���B
��������t��E����������u�f���^���͂ǂ������N�`���̌��ʂ����҂���Ȃ���Ȃ����Ƃ������Ƃ������Ă��܂����ǁA�{���ɂ܂��ɂ��ꂪ�������Ƃ������Ƃ𗠕t����悤�Ȍ��ʂ���Ȃ��ł��傤���v
���̏�ŁA�����͂���Ɋg�傷��Ƃ݂Ă���B
��������t��E����������u�s�[�N�͂��ꂩ�炶��Ȃ��ł����B�l�̈ړ������~�����ɂ��Ă��ꂩ�炠��Ǝv����ł��B8�������s�[�N�ɂȂ邩���킩��܂���v
�������ґ����̏��M�s�ƐΎ�n����"�܂h�~�[�u"�̑ΏۂɁ@8/12
�k�C����8��12���A�V�^�R���i�E�C���X���k�C�����Ŋ����g�債�Ă��邱�Ƃ��āA���M�s�ƐΎ�n�����A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��֒lj�������j�Ō������Ă��܂��B�S���̊O�o���l�v��������������j�ł��B
�k�C�����ł�8��12���A�V�K�����҂�480�l��5��27���ȗ��A77���Ԃ��450�l���銴���҂��m�F����Ă��܂��B
�W�҂ɂ��܂��ƁA�����������Ԃ��Ėk�C���͌��݁A�D�y�s��K�p���Ă���u�܂h�~���d�_�[�u�v�����M�s�ƐΎ�n�����Ώےn��֒lj�������j�Ŏs�����Ƌ��c���Ă��܂��B
�܂��A�k�C���S��ɑ��āu�������X�N������ł��Ȃ��ꍇ�v�s�v�s�}�̊O�o�E�ړ����T����悤���߂Ă��܂������A�u�������X�N�ɂ�����炸�v�s�v�s�}�̊O�o�E�ړ��̎��l�ւƋ���������j�ł��B
�k�C���́A13���ɂ����{����c���J�����肷�錩���݂ł��B
�܂��A�k�C���́A�V�^�R���i�E�C���X�̐��Ƒg�D�̉��8��11���A�k�C�����ً}���Ԑ錾�̒n��ɒlj����A9���܂ʼn�������ӌ������Ƃ���o���ꂽ���ƂȂǂ��āA���{�Ƃ̋��c���J�n���Ă��܂��B
�����̐V�^�R���i�V�K�z���҂�1654�l�A�g���m���u40��A50��͊ۗ��v�@8/12
���{��8��12���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�z���҂�1654�l�Ɣ��\(�v�z���Ґ���12��7294�l)�B�܂��V���ɕ��ꂽ���S�҂�4�l�ŁA�v���Ґ���2739�l�ƂȂ����B
���̓��̌�������1��6665���ŁA�z������9.9���B�N��ʂɌ����20�オ465�l�œˏo���Ă���A������30�オ285�l�A40�オ256�l�A10�オ243�l�A50�オ190�l�ŁA�����X���ɂ��関�A�w����62�l�ƂȂ����B���ݓ��@���̏d�ǎ҂�129�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����40.3���B
�s�����ʂɌ���ƁA���s��622�l�Ƃ����Ƃ������A��s��117�l�A�����s��113�l�A���c�s��78�l�������B�܂��A���̓��m�F���ꂽ�V�K�z���҂͑O�����164�l�����A2���A���ʼnߋ��ő����X�V���邱�ƂƂȂ����B
�}���Ȋ����g��ɂ��ċg���m���̓c�C�b�^�[�Łu�f���^���̋}�g�傪�����Ă��܂��B�w����҂ւ̃��N�`���ŏd�ǎ҂͏��Ȃ��ł���B�x�Ƃ̈ӌ�������܂����A40��A50��͊ۗ��ł��B����m���ɏd�ǎ҂͑������܂��B���҂��}������ƈ�Â͑Ή��ł��܂���B��@�͂����ɂ���܂��B�������Ȃ��w�͂����肢���܂��v�Ƒi�����B
��8���̐V�K�����҂̖�6����30��ȉ��@�O�d���ł͎�҂Ɋ����L����@8/12
�O�d���ł��C�ɂȂ銴�����cCBC�e���r�̏W�v�ł́A8���Ɋ������m�F���ꂽ748�l�̂����A30��ȉ��̐l�̐�߂銄������6���ɒB���Ă���ق��A���E���E���Z�E��w�ɒʂ��w����̊����҂����킹��100�l�ȏ�B��҂ւ̊����g�傪�����ƂȂ��Ă��܂��B
����ɁA�O�d���ł�11���̊����Ґ������߂�100�l���܂������A12���͂��������ɏ���A�ߋ��ő���131�l�ƂȂ�܂����B
���̊����g��ɊX�̐l�́c
�u����ς�S�z�ł��ˁB�ǂ�ǂ��̎���ɃR���i���߂Â��Ă����悤�ȋC�����āv(60�㏗��)
�u�Œ���C��t���Ă���A�Ȃ�Ƃ����z�����邩�ȂƎv���v(�A�Ȃ��Ă���j�q�w��)
�������m���u�ɂ߂Đ[���v�@���������̃R���i�����ҁ@�ߋ��ő���1040�l�@8/12
�������̕����m���́A�����̊����҂��ߋ��ő���1040�l�ɒB�������Ƃ��āA��قǕw�̎�ނɓ����܂���
�u�����I�Ȋ����̊g��̗l����悵�Ă��āA�ɂ߂Đ[���ȏł���v�u���̃f���^���Ƃ������̂̔��Ɋ����͂̋����Ƃ����̂����ɂ��낤���Ɓv�u������b�Ɩ{���b�������Ă����������B��b�Ƃ̘b�̒��ŁA�������̊�@�I�ɂ��Ċ�@���������Ă���Ƃ̂��ƁA���킹�Đ��{�Ƃ��Ă�����̑[�u��舵���ɂ��ĉs�ӌ�����i�߂Ă���Ɓv
�������ҁA15�s�{�����z�蒴���@�R���i�ً}���V�i���I�j�]�@8/12
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���12���A�����A���Ȃ�15�s�{����1��������̍ő�z�芴���Ґ������B���ꌧ�͑z���63���A�É�����57���������B�e�s���{���͂��̑z�萔����ɋً}���̕a���m�یv����쐬�B�V�i���I�̊�b���j�]�����`�ŁA��Ñ̐��͔��Ɋ댯�ȏ�ԂƂ�����B�����̒����͌������A�a���N���ɂ���Ď���×{�҂�����ɑ����A�}�σ��X�N���g�傷�鋰����o�Ă����B
12���̐V�K�����Ґ���1��8��l����2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�A�ő����X�V���������̂�20�{���ɏ��B���{�̓��N�`���ڎ��������̐�D�Ƃ��邪��l�܂�ƂȂ��Ă���A�������K�����B
���V�^�R���i�V�K������189�l�ߋ��ő��Ɂ@�m�����Վ��̉�ői���@�F�{�@8/12
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�����Ȃ��A�A�ȂȂǂŐl�̓����������ɂȂ邨�~�̎�����O�ɁA�����m�����Վ��̉���J���A���߂ĕs�v�s�}�̊O�o�̎��l�����߂܂����B
�u�����������ɓ]���邩�A����ɑ������邩�́A�܂��ɂ��̎����̂���l����l�̍s���ɂ������Ă��܂��v
�F�{���ɂ́A����8������u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����Ă��܂����A�����͂̋����f���^���̉e��������A�����Ґ��͑����X���ɂ���܂��B
11���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��́A869�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ�A�l��10���l������̊����Ґ���49�D7�l�ŁA�ً}���Ԑ錾���o���ꂽ���{��7�������̐��l�ɕC�G���郌�x���ŁA�ɂ߂Đ[���ȏł��B
�u���N�̂��~�́A���ꂼ��̂��ƒ�ɂ����ĉ��₩�ɉ߂����Ă��������悤���肢���܂��v(�����m��)
�����m���́A�ړ����H�̋@�������Ɗ���������Ɋg�傷�鋰�ꂪ����Ƃ��āA�s�v�s�}�̊O�o���T����悤�Ăт����܂����B
�����ł�12���V����189�l�̊���������A1���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B���̂����A�s�����ʂł͌F�{�s��120�l�ƍł������Ȃ��Ă��܂��B�@
�����N�`���ڎ킵�ăJ���I�P�c�����@�V�N���X�^�[�����A���1227�l�����@8/12
��ʌ��Ȃǂ�11���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă���1�l�̎��S�ƁA�V����1227�l�̊������m�F�����Ɣ��\�����B���ɂ��ƁA�����҂̓���́A�����\��789�l�A�������s307�l�A����s58�l�A��z�s19�l�A�z�J�s54�l�B
����܂łɊm�F���ꂽ�����҂�6��9675�l(�`���[�^�[�A���Ҋ܂�)�A���҂�858�l(11���ߌ�7������)�B
10���ߌ�9�����_�̏d�ǎ҂�102�l�A�����҂̓��@��1082�l�A�z�e���×{555�l�A����×{1��1315�l�B�މ@�E�×{�I����5��1349�l�B
���ɂ��ƁA�ψي������҂�2�`8����1�T�Ԃ�3398�l�B��������C�O�n�q���͂Ȃ��A�f���^���Ɋ������Ă���Ƃ݂���B�ψي��o�b�q�������{����48���ŁA�z������85�E4��(�O�T73�E8��)�������B
���NJ��ŏڍׂ����������͖̂��A�w���`90��̒j��677�l�B�N���X�^�[(�����ҏW�c)�֘A�ł́A������Q�ҕ����{�݂œ�����2�l���������A�v27�l�ɂȂ����B�����������Z�ł�10�㏗���̎������k6�l���������A�v16�l�ɂȂ����B�����̐H�i���H�H��ł́A�����A�p�[�g�ɏZ�ފO���Ђ�20��j��5�l�����������B��H�֘A�ł�17�l�����������Ƃ݂��A���̂����J���I�P�𗘗p����70��j��1�l�̓��N�`���ڎ�ς݂������B
�������s�ɂ��ƁA���������������̂�10�Ζ����`90��̒j��307�l�B4����290�l������A���s�̉ߋ��ō����X�V�����B50�A60��j��2�l�͏d�ǁA8�l�������ǁB�N��ʂł�20�`50�オ222�l�Ŗ�7�����߁A60�`90��͌v15�l�������B��̕ۈ珊�ŕۈ�m1�l�A3�`5�̉���11�l�̌v12�l���z���������Ƃ��āA�s�̓N���X�^�[�ƔF�肵���B�{�ݖ��͔���\�B�Ώێ�108�l�̌����Ŕ������A���ݎc���4�l��������\�肵�Ă���B���̃N���X�^�[�֘A�ł́A���㎩�q����{���Ԓn�ŐV���Ɏ��q����7�l�̊����������A�z���҂͌v40�l�ƂȂ����B
����s�ɂ��ƁA80��̏�����8���Ɏ��S�����B���������������̂́A���A�w������80��܂Œj��58�l�B
��z�s�ɂ��ƁA10�Ζ����`50��̒j��19�l�̊������m�F�����B
�z�J�s�ɂ��ƁA�V���Ɋ��������������̂́A10�Ζ����`70��̒j��54�l�B
�������Ċg��̒����Łu�R���i�Ƃ̋����v��i���鐺���o�Ă������R�@8/12
�����ŐV�^�R���i�E�C���X�E�f���^���̊��������킶��L�����Ă���B���Ɖq�����N�ψ���̔��\�ł́A8��9�������ŐV���Ȗ{�y�����m��f�f��(�m�f)�͑S����108�l�B����3�J���ȗ��A�S���ł̐V���Ȋm�f�Ⴊ100�����̂͏��߂Ă��Ƃ����B
���{�͓����s������1������l�̐V�K�����҂𐔂��Ă���̂�����A�ȂA������100�l���A�Ǝv����������Ȃ��B�����A���̂킸���Ȋ����҂̂��߂ɁA�����͍����̐����ƌo�ς��]���ɂ����O�ꂵ�����b�N�_�E����S�s����ΏۂƂ���PCR���������{���āA�u�[�������v��ڎw���Ă���B
����ł������҂��o�����Ă���A�Ƃ����̂ł���A���̃f���^���������Ɏ育�킢�E�C���X�ł��邩�A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B�����āA����ȏ�̊����͂Ƃ����\�̃����_���̋��Ђ͌��킸�����Ȃ��낤�B
�����O����鐅�Q��Вn�̊����g��
�����ɂ����鍡��̃f���^�������g��̔��[�́A7��10���ɓ싞���ۋ�`�ɓ����������V�A����̗��q�@�ɐV�^�R���i�����҂����悵�Ă������Ƃ������B7�l�̗��q��������̌����ŗz���Ƃ킩��A���₩�Ɋu�����ꂽ�B�����A���̂̂��A7��20���܂łɂ��̋@���̐��|�ɂ����������|��9�l�̃f���^���������m�F���ꂽ�B���|����͖h�앞�����Ă����͂������A���E�̎��̕s���ӂŊ��������͗l�B�ނ����������������Ƒ��A�u�����ꂽ���A����܂ł̊ԂɊ����͍L�����Ă����B
7��21������싞�s�͑S��920���l��Ώۂ�PCR�������J�n���A�싞�s�̊����Ҕ����n��͂����ɕ������ꂽ�B����ł��킸��10���قǂŊ����͊e�n�ɔ�щA�]�h�ȁA�Γ�ȁA�͓�ȁA�Ζk�ȂȂǂ�20�s�s�ŗv200�l�ȏ�Ɋ������L�������B
�Γ�Ȋ��F�s�ł�8��2������120���l�̎s����3�T�Ԃ̊O�o���l�����߂�ꂽ�B�ό��V�[�Y���^�������̒��ƊE���A�������g�債�����߁u�x���v��ԂƂȂ�A�ό��ɖK��Ă������q�̓z�e�����ł̑ҋ@�𖽂���ꂽ�B���ƊE�s��7��29������8��10���܂łɊm�F���ꂽ�����҂͖�50�l�ɒB���Ă���B
2020�N���߂̃R���i�����̋��|�̋L�����܂��c��Ζk�ȕ����s�ł́A��1100���l�̑S�s����PCR���������{�����B�k���ł́A�n�C���X�N�n��Ƃ̔�s�@�A�����S���̉������ꎞ��~����[�u���Ƃ�A���ۉf��ՂȂǑ�^�C�x���g�����������B
�����ō���ԐS�z����Ă���̂́A�吅�Q�̏��Ղ��܂������Ă��Ȃ��͓�ȓA�B�̊������B8��8���Ɋm�F���ꂽ�V�K�̖{�y�S�̂̊����҂�94�l�����A���̂���41�l���͓�Ȃ̊����҂ł���B8��9���ɂ�108�l�̖{�y�����҂��m�F���ꂽ���A�͓�Ȃ�37�l���߂�B�قƂ�ǂ����Ǐ��A���Q�ɂ���ĉq����Ԃ���������Ë@�ւ����S�ɕ������Ă��Ȃ��A�B�s���ӂŗL�Ǐ�̊����҂�����������A��K�͂Ȋ��������ɂȂ��肩�˂Ȃ��B�͓�ȓ��ǂƂ��Ă�8�����Ƀ[��������ڎw���Ƃ��Ă���B
�A�B�s�ł́A���ׂĂ̏���(��)�Ƀ��b�N�_�E�����{��ʒB���A�l�̗�������������A�s���̌��i�ȑ̉��Ǘ����s���A�Ƃ��Ă���B�e���т�1�ʂ̊O�o����z�z���A1��1��A�e���т�1�l�����ɐ����K���i�w���̂��߂̊O�o�������A�s�K�v�ȊO�o�͋ւ���A�Ƃ����B
�A�B�s�̏ꍇ�A�S���ɑ���PCR������1��ł͂Ȃ��A�ꕔ�s���͂��ł�3��ڂ�PCR�������Ă���B�����A����Z���́u��������Ƃ���100�l�ȏオ���ɂȂ�A������̕����������X�N������Ǝv���v�ƃ��f�B�A�ɕs�������炵�Ă����B
���R���i�Ƃ̋�����i����ӌ��ɑ����̎x��
�����������܂œO�ꂵ�ă[���E�R���i�ɂ������̂́A���N(2022�N)2���̖k���~�G�ܗւ�L�ϋq�œ����ܗւ����X�������h�ɊJ�Â������A�Ƃ�����]�����낤�B�܂����������N�`���̗\�h���ʂ��t�@�C�U�[��f���i��肩�Ȃ�Ⴂ�Ƃ�����������B�����̃��N�`���ڎ헦��40�����Ă��邪�A���̂Ƃ���2��ڎ����������m�F���ꂽ��͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B���ǁA�������{�Ƃ��ẮA���N�`���ڎ헦�ɊW�Ȃ��A���PCR�����ƃ��b�N�_�E���ɂ��O��Ǘ���������炴��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ����B����́A���{�͐^���������Ă����Ȃ��B���Ў�`���Ƃ̖\�͓I�Ȃ܂ł̓����͂������Ă����\�ȕ������B
�����A�ŋ߂ɂȂ��Ē����ŁA���́u�[���E�R���i�v�u���ɋ^���悷��ӌ����o�Ă����B���U��w�����؎R��@�����Ȏ�C�̒����G��7�����A������SNS�̔����Łu�g�R���i�Ƌ����h�̏�����������������v�ƒB���ꂪ�A�����̃l�b�g�����狭���x�����B
�����G�́A�u���E�͐V�^�R���i�����̃R���g���[���Ɏ��s���Ă���A�����̓E�C���X�Ƃ̋������������ׂ����B����܂Ōo���������Ƃ́A�ł�����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B����ɍ���Ȃ̂́A�����ɃE�C���X�Ƌ�������q�d���i�邱�Ƃ��v�Ƃ����B�����G�͓싞�Ńf���^���̊������g�債�Ă��邱�Ƃ܂��āA�u���N�`���ł̓E�C���X�͊��S�ɖh��ł��Ȃ��B�����d�lj����������邾���Ȃ̂��v�Ƒi���Ă����B
����ɑ��@�������q�������̍����͐l������ւ̊�e��ʂ��ċ���ɔ��������B�����́A���E�Ńp���f�~�b�N�����܂�Ȃ��̂́A�p����č��������҂������Ă���ɂ�������炸�A���N�`���ڎ헦�̍����ɗ����āA�����R���g���[���[�u������������ɘa�����肵�āA������u�E�C���X�Ƌ�������v�����ɂ��邱�Ƃ��������A�Ɣᔻ����B
����Ɂu�E�C���X�Ƌ����Ȃǐ�ɂ��肦�Ȃ��B�E�C���X�Ɛl�ނ́A���O�����ʂ��������ʂ��̊W�ł����Ȃ��v�u�����ׂ����ƂɁA���������Ƃ̒��ɂ��f���^���̋��Ђɂ��Č��Ȃ���A���ƂɁg�E�C���X�Ƃ̒��������h�헪���Ă���l��������v�Ƃ��āA���w���������Ȃ������������G��ᔻ�����B
�����G�̔����́A�ǂ݂悤�ɂ���ẮA�O�ꂵ�����b�N�_�E����PCR�����ɂ�鍡�̒������ǂ́u�[���E�R���i�v�����ᔻ���Ă���悤�ɂ�����B���̂��Ƃ���A�l�b�g���̒��ɂ́u�����G�͐����I�Ɋ�Ȃ���������Ȃ��v�ƐS�z���鐺���o�Ă���B
���傫������o�ϓI�]��
�������A���Ў�`�̐��̖\�͐��𗘗p�����O��I�ȊǗ��R���g���[���ɂ���ă[���E�R���i����W�J���Ă������A�˔@���������ӌ�������l�b�g�Ő���オ��w�i�ɂ́A���̒��������́u�R�X�g�̍����v�ւ̌��O���\�o���Ă������炾�B
��N�t�����K�͂ȃ��b�N�_�E�����e�n�ŌJ��Ԃ��A�ǂ̍����������V�^�R���i�x���̊g���}���ł������Ƃ���A�����o�ς͂ǂ���������V�����A�p�Čo�ς̉ƍ������邱�Ƃ��ł���Ƃ��������Ă��������Ǒ��ɂ͂������B����͒Z���Ԃ̃��b�N�_�E���Ń[���E�R���i��B�������ꍇ�ɂ͉\���B
�����f���^���́A���̑̐��̗D�ʐ��𗘗p�������|�I�ȑR���i�Ǘ��R���g���[���\�͂̕ǂ�j���āA�Ăђ��������Ŋ����g�債�n�߂��B�č�����{�ȂǂƔ�ׂ�ƐV�K�����Ґ��͔��ɏ��Ȃ����̂́A�[������������f����ȏ�A����܂ł̂悤�ɓO��I�Ɍ���������l�I������}������������Ȃ��B���̌o�ϓI�R�X�g�͒������z�肷����傫�������悤���B
�E�H�[���E�X�g���[�g�E�W���[�i��(8��11���t)�����Ƃ���ɂ��A�S�[���h�}���T�b�N�X�ƃ����K���X�^�����[�́A��T�A�����̔N�Ԍo�ϐ������\�������ꂼ��8.6������8.3���ցA8.7������8.2���ւƉ����C�������B
���̂Ƃ��돬���̈��������������A�f���^��������ɋ��������͂������A����Ȃ�o�ςւ̈��e���͔������Ȃ��ƃ����K���X�^�����[�Ȃǂ͎w�E���Ă���B
�S�[���h�}���T�b�N�X�̃f�[�^�ɂ��A8�����{��1�T�ԂŒ���100�s�s�Ō�ʏa���������A��C�A�싞�A�A�B�Ȃǂ�6��s�s�̒n���S��~���͑O�N������ł��悻12�����������Ƃ����B�P����s(����)�̎�ȃG�R�m�~�X�g���O�́A�ŐV�̃f���^�������g��ɂ���Ē����Ꮚ���҂̎��Ɨ����㏸���A���̉e���͔_���n��ő傫���A�Ǝw�E���Ă����B
�����o�ς͍��N8���ȏ�̐����������܂��Ɛ��E��s�Ȃǂ��\�����Ă������A�������{�����N�̑S�l��őł��o�����������ڕW��6���B�������{�́A�Ђ���Ƃ���ƁA�����������Ԃ��z�肵�Ă����̂�������Ȃ��B
���܂��܂������Љ�Ɛ藣����Ă���
�����͂��̂܂܂ł́A�č��Ȃǂ����킸���̊����҂����o���Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A���Ă̂ǂ̍������o�ς��]���ɂ��錵�������������ɋ����Ă������ƂɂȂ�B������������ׂ����A�Ƃ����ӌ����o�Ă��Ă����R��������Ȃ��B
�o�ς��Ƃ邩�A�[���E�R���i���Ƃ邩�B�����A�ă��f�B�A�̃��W�I�E�t���[�E�A�W�A�ɂ��A�����G���x������ӌ���SNS�Ȃǂō폜����Ă���Ƃ����B�������ǂƂ��Ă͓��ʁA�u�R���i�Ƌ����v�H���ɓ]���������͂Ȃ��������B
�����A�č��₻�̑��̐����Љ�A���N�`���̗͂ŏd�ǎ҂⎀�҂̑�����}�����A������x�̊����g���e�F���A�o�ϊ�����l�̉�����F�߂�����ɓ����A����Œ������[���E�R���i������т��Ȃ�A����͐l�I�����̃f�J�b�v�����O�ɂ��Ȃ���A�{���ɒ����̍������オ�������邩������Ȃ��B���ہA�����͕s�v�s�}�̏o�����T����悤���łɍ����ɒʒB���A�ꕔ�ł̓p�X�|�[�g�̍X�V�����ۂ����r�W�l�X�}���◯�w��������Ƃ����B
�������u�[���E�R���i�v�ɂ������̂́A�V�^�R���i�̕������߂��ړI�̂悤�Ɍ����āA���͒��������𐼑��Љ�牓�����A���̈ړ��⓮�Â���茵�����Ǘ��������Ƃ��������I�Ȏv�f������̂�������Ȃ��B
���{�̏ꍇ�́A���ۊǗ��������Ǘ����O�_�O�_�̂܂܌ܗւ��J�Â�����A6���ȏ�̍������J�Â��Ă悩�����Ɗ����A�X�e�C�z�[�����Ăт�������A���͂�l�o��}���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ɂȂ��Ă���B�������A�������R���i�͋G�ߐ��C���t���G���U�̂悤�Ȃ��̂ƍl���Ă݂悤�ƁA�����ǂƂ��Ă̊댯�x��2�ޑ�������5�ނɕς���ׂ����Ƃ����c�_���n�܂��Ă���B�v���A�ŏ�����A�Ȃ������I�Ɂu�R���i�Ƌ����v���B�����l���猩��Α����N���C�W�[�Ɍ����邩������Ȃ��B�����A�l���C����E�C���X�܂ł��A���S�ɃR���g���[�����悤�Ƃ��钆�����Y�}���x�z����Љ���͂܂��߂����₷�����̒��ł͂Ȃ����A�Ǝv�����������̂������B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���R���i�����ҋ}���@��Ấu�[���ȋ@�\�s�S�v�@�����̏d�ǎ҉ߋ��ő��@8/13
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�~�܂�Ȃ��B���`�ً̎͋}���Ԑ錾�n��̒lj������߂��挎�̋L�҉�Łu���N�`���ڎ�̌��ʂ������ɕ\��Ă���v�Ɠ����s�̏d�ǎ҂̏��Ȃ��������������A�ڎ킪�i�܂Ȃ�40�`50��𒆐S�ɏd�ǎ҂͋}���B12���ɂ�218�l�Ɖߋ��ő����X�V�����B50��ȉ��͉���l�������A����ł͎��҂͑�3�g�Ɣ�ׂď��Ȃ����A�a�������܂�Ώ����閽��������Ȃ��Ȃ�B(���q��r�A����䕶�F)
���u����s�\�A�ЊQ���x���v���ĂȂ������\��
�u�V�K�z���Ґ����}�����Ă���A����s�\�ȏB�ЊQ���x���̔�펖�Ԃ��v�B12���̓����s�̃��j�^�����O��c�̖`���A�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v��t�́A���ĂȂ������\���Ōx�������������B�u���͂�A�ЊQ���Ɠ��l�ɁA�����̐g�͎����Ŏ��w�����\�h�̂��߂̍s���x���K�v�Ȓi�K���v�����̐V�K�����Ґ���7���ԕ��ς́A11�����_��1��������3934�l�B2�T�ԑO�̖�2�{�A�O�T��1�E14�{���B���j�^�����O��c�ŕ��ꂽ���Z�ł́A���̃y�[�X�������A2�T�Ԍ�ɂ�1��������5113�l�ɂȂ�B
���u�R�̃J�N�e���Ö@�v�s��120�a�@��
�����̏d�ǎҐ��͂���܂ŁA��3�g��1��20����160�l���s�[�N�������B��4�g�ł�90�l�ȓ����������A���݂̑�5�g�ł͎̋L�҉������7��31����90�l���A8��10���ɍő����X�V�����B12���܂ł�3���Ԃ́A������20�l�������Ă���B���Ґ��̖ڗ����������͂Ȃ��B�s�ɂ��ƁA���S���ʂ̉ߋ��ő���1��31����38�l�B��3�g��10�l��������������Ȃ��������A7���ȍ~��6�l�ȉ��Ő��ڂ��Ă���B�������A��������҂������Ȃ��ۏ͂Ȃ��B�s��t��̒������F����́u����×{���ɗe�̂����������R���i���҂̔�������ꂪ����ɂȂ��Ă���v�Ǝw�E����B�u�~�}��Â�\�肵����p�Ȃǒʏ�̈�Â��܂߁A��Ò̐��͐[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ����v�Ɗ�@�������߂�B���r�S���q�m����12���A�w�ɑ��A�d�lj���h�����ʂ�����V���Ö�́u�R�̃J�N�e���Ö@�v���A�s����120�a�@�Ȃǂōs����̐��������Ɛ��������B����ł��V�K�����҂�����������Εa���͖��܂�A���ÂɂȂ����Ȃ��Ȃ�B
�����҂͖ڗ����������Ȃ��@�d�ǎ҂͑S���ł��}��
�d�ǎ҂͑S���ł��}�����Ă���B7�����{��500�l�O��Ő��ڂ��Ă������A8��11�����_�ł�1404�l�ŁA�ߋ��ő���1413�l(5��25��)�ɔ���B���҂͑�3�g�ł�100�l����������Ȃ��Ȃ��������A8����20�l�ȉ��Ő��ڂ���B�e�n�̈�Ò̐����N���Ђ��ς����Ă���B�����J���Ȃɏ���������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v��11���̉�Łu�̐��̊g�[�ɂ��Ή��ɂ͌��E������A�����̖����~���Ȃ��Ȃ�悤�Ȋ�@�I�ȏ����뜜�����v�ƕ��́B�u�ꍏ�����������g��𑬂₩�ɗ}���邱�Ƃ��K�v���v�ƌx����炵���B
�����r�m���u�R���i�͍ЊQ�A�O�o�T���āv�@�����̊����g��u����s�\�v�Ł@ 8/13
�����s�̏��r�S���q�m����13���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ň�Ñ̐����Ђ������Ă��邱�Ƃɂ��āu�O�o���T���Ă��������B��������������̐l���o�Ă����܂����A��J���R���i�������ł��B�ЊQ�ɂȂ�܂��B��낵�����肢���܂��v�ƌĂъ|�����B�s���ŋL�Ғc�̎���ɓ������B
�s���̊������߂����ẮA12���ɊJ���ꂽ���j�^�����O��c�Ő��Ƃ��u����s�\�ȏ��B�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ�U�邤��펖�ԁv�ŁA��Ò̐��ɂ��āu�[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���v�ƕ����B���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ���A�����킸�A�l�o���ً}���Ԑ錾���O��7���O���Ɣ��5�����炷�K�v������Ƃ��Ă���B
���������̒��A���r�m���́u���~�ŁA�A�Ȃɂ��ẮA����ւ̂��܂��܂ȉe�����y�Ȃ��悤�ɁA�܂����~�����Ă��������悤�ɂ��肢���܂��v�Əq�ׂ��B
�������s �V�^�R���i 5773�l�����m�F �ߋ��ő� �d�ǎ҂��ő��X�V �@8/13
�����s��13���A�ߋ��ő��ƂȂ�5773�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B5000�l������̂́A5042�l��������T�̖ؗj���ȗ��A2��ڂł��B1�T�ԑO�̋��j�����1258�l�����Ă��āA�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B
����A�s�̊�ŏW�v����13�����_�̏d�ǂ̊��҂�12�����9�l������227�l�ł����B4���A���ʼnߋ��ő����X�V���A�d�NJ��҂̑������~�܂�܂���B
�������s�A�R���i�u���@�ҋ@�X�e�[�V�����v�����ց@��������ɑΉ��@8/13
���r�S���q�����m����12���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŕN��(�Ђ��ς�)�������s���̈�Â���邽�߂̑̐������ȂǁA�V���ȐV�^�R���i��\�����B�~�}������̈�Ë@�ւ�������Ȃ����Ă��������邽�߁A�~�}������v�����������ꍇ�͕K�������u��������Ή����@�ҋ@�X�e�[�V�����v��V���ɐ����B����×{�҂̃t�H���[�̐�����������B
���r����12���̓s���j�^�����O��c��A��𖾂炩�ɂ����B�s�ɂ��ƁA���X�e�[�V�����͓s���E���Еa�@11�J���Ɍv36�̐�p�a����ݒ肵�A����悪������Ȃ����҂������B�a���͈�ʐf�Â𐧌����Ċm�ۂ���Ƃ����B�}�����鎩��×{�҂ɂ��ẮA�s��t���n��̈�t��ƘA�g���ĖK��f�Ñ̐�����������B
�l�̗���������邽�߁A��������3����1��ɂ��邱�Ƃ⏤�Ǝ{�݂̓��ꐮ���̓O��Ȃǂ�s���⎖�Ǝ҂ɌĂъ|����B���r���́u���~�x�݂̎����͐l�̗��ꂪ�傫���ω�����B���̋@��𑨂��Đl�Ɛl�Ƃ̐ڐG�����I�Ɍ��炵�Ă����v�ƌ�����B
���j�^�����O��c�ł́A�V�K�����҂̒���7���ԕ��ς�11�����_��3933�E9�l�ƑO�T�����500�l�����������ƂȂǂ�����A�����A��Ò̐��̌x�����x���͂Ƃ��ɍł��[�����ێ������B
�܂��A�s��12���A�V�^�R���i��Ƃ��đ��z1556���~�̕�\�Z�Ă\�����B18���ɊJ��\��̓s�c��Վ���ɒ�o����B
20�`30������̃��N�`���ڎ푣�i���Ƃɂ�10���~���v��B�ڎ�҂��o�^�ł���A�v�����J�����A�|�C���g�t�^���Ƃ̊����T�[�r�X�Ȃǂ�����悤�ɂ���B���N�`���̈��S����L������`����E�F�u�L���⓮��z�M�Ȃǂ��W���I�Ɏ��{����B
����グ����������������Ƃ��ޔ̔����Ǝ҂Ɏx�����Ă��錎���x�����t���ɂ��ẮA������g�[���邽�߂̔�p�Ƃ���303���~�荞�B
�������s �V�^�R���i 5773�l�����m�F �ߋ��ő� �d�ǎ҂��ő��X�V �@8/13
�����s���ł�13���A�ߋ��ő��ƂȂ�5773�l�̊������m�F���ꂽ�ق��A�s�̊�ŏW�v����13�����_�̏d�ǂ̊��҂�227�l�ƂȂ�A4���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ50�ォ��90��܂ł̒j��7�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s��13���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł̒j�����킹��5773�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B����܂łōł�����������T�E�ؗj����5042�l���ĉߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂��A1�T�ԑO�̋��j�����1258�l�����Ă��āA�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B13���܂ł�7���ԕ��ς͍Ă�4000�l����4155.7�l�ƂȂ�܂����B�O�̏T��108.8���ł��B
����A�s�̊�ŏW�v����13�����_�̏d�ǂ̊��҂�12�����9�l������227�l�ł����B4���A���ʼnߋ��ő����X�V���A�d�NJ��҂̑������~�܂�܂���B�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ50�ォ��90��܂ł̒j��7�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2332�l�ɂȂ�܂����B
�����s�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l���ߋ��ő����X�V���钆�A��������b��13���ߌ�A������b���@�ŁA�����o�ύĐ��S����b��c�������J����b��W�t���ƁA1���Ԕ��]��ɂ킽���āA�Ή������c���܂����B
�������s�ʼnߋ��ő���5773�l�̗z���ҁB������m��A4�̃f�[�^�@8/13
8��13���A�ߋ��ő��ƂȂ�5773�l(�����A65�Έȏ��203�l)�̐V�^�R���i�E�C���X�z���҂����ꂽ�����s�B�d�ǎҐ���12����218�l���炳��ɑ������A227�l�ƂȂ���(�s�́A�d�Ǖa����392���m�ۂ��Ă���)�B���r�S���q�����s�m����13���ߌ�2��������̋L�҉���J���A�Ђ������銴���ւ̊�@���Ɗ�����̓O���i�����B�ً}���Ԑ錾���ɂ���Ȃ���������Ґ��Ɍ����X�����݂��Ȃ������s�B�����̐l���A�x�d�Ȃ鎩�l�v����V�^�R���i�E�C���X�����s���Ă��钆�ł̐����Ɋ���Ă��܂��Ă��鑤�ʂ����邩������Ȃ����A�s�̊����̌����m���ŏd�v��4�̃f�[�^�����ė~�����B
��1.���߂̊����Ґ��̑�����͔������A�z������20%����
8��13����5773�l�̗z���҂����ꂽ�����s�B����1�T�Ԃ̈ړ����ς́A4155.7�l�ƑO�T���108.8%�������B�O�T�䂪200%�߂��ɂ܂ŏ㏸���Ă���8��1�T�ڂƔ�r����ƁA������͗��������Ă����B�������A100%�������Ă���ȏ�A�����Ґ��͑��������Ă��܂����߁A�܂��s�����Ă���ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�܂��A�������ɑ���z���Ґ�(�z����)��20%�ȏ�Ɣ��ɍ����������Ă���B7���㔼���猟�������̂͑����Ă������A�z����������ɉ�����Ȃ����Ƃ��l����ƁA���X����Ă���z���Ґ��ȏ�ɕ⑫������Ă��Ȃ��z���҂����邱�Ƃ��z�肳���B
��2.�d�ǎ҂�6����40��〜50��
�z���҂̔N��ʃf�[�^������ƁA20��〜30��̊������ڗ��B�������A�d�ǎҐ��̓���ł�40��〜50�オ6�����߂Ă���B����҂ɑ��郏�N�`���̐ڎ킪�i���ƂŁA�����Ґ��ɑ���d�ǎҐ��̊����͏��Ȃ����̂́A20��Ȃǂɔ�ׂă��X�N�������A���N�`�����ڎ�҂�����40��〜50��̊������L����A���̕���Â͈��������B�Ȃ��A�����ǂƂ��ē��A�a�⍂�����A�C�ǎx�b���A�i�����A�얞(BMI��30�ȏ�)�̐l�͂ǂ̔N��ł����Ă��d�lj����X�N�͍����Ƃ���Ă���B
��3.�d�lj����X�N�̍����N��̖�ԑؗ��l��������
�����s���̔ɉ؊X�ɂ�����N��ʂ̖�̑ؗ���������ƁA����̏d�ǎ҂̑唼���߂钆���N�������������߂Ă���B�ߌ�10��〜�ߑO0���̐[��тɂ́A15��〜39��40��〜64�̐l�����قړ��������ɂȂ���̂́A�ߌ�6��〜�ߌ�8���̎��ԑтɂ͒����N��̕���16%�������B�����g���h���Ƃ����Ӗ��ł́A�N��Ɍ��炸�l�Ƃ̐ڐG�����Ȃ����邱�Ƃ����߂��Ă���ł͂��邪�A�Ⴂ���オ�X�P�[�v�S�[�g�ɂ��ꂪ���Ȓ��ŁA��Ò̐��̂Ђ����ɒ�������d�lj����₷���N��̋��͂����߂��Ă���Ƃ������邾�낤�B
��4.�����s�̊����A�f���^����8����
�����͂��]���̃E�C���X�ɔ�ׂ�1.5�{�قNj����Ƃ���Ă���f���^���B�����s�ł́A���łɗz���҂�8���ȏオ�f���^���ɒu��������Ă�����B�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̎����ɂ��ƁA�f���^������̂ɂȂ����Ƃ��Ă��A�����g�僊�X�N��������ʂ͈ˑR�Ƃ��Ĉȉ��̏�ʂ��Ƃ��Ă���B
1.���i����ꏏ�ɂ��Ȃ��l(�����Ƒ��ȊO��)�Ƃ̈��H���B
2.�����ԁE��l�����W�܂��ʁB
3.���G�����ꏊ�y�ю��ԑсB
4.�x�e����i�����A�X�ߎ��ł̃}�X�N���O������b�B
�������A�����͂̍��܂�ɔ����A����܂ł̓N���X�^�[���������Ă��Ȃ������ꏊ�ł��A�N���X�^�[������������������Ă��Ă���B12���ɊJ���ꂽ���{���ȉ�̔��g�Ή�̋L�҉�ł́A�S�ݓX�Ȃǂ̒n���H�i�����(������f�p�n��)�ł̊������ڗ��Ƃ��āA�l�o��}������K�v������Ƒi�����B�Ȃ��A13���̓s�̋L�҉�ɂ����āA���r�s�m���͎��Ǝ҂ɑ��ăe�����[�N�̂���Ȃ���{��\�[�V�����f�B�X�^���X��1.2���[�g������1.8���[�g���Ɋg�傷�邱�ƁA����ɕS�ݓX�Ȃǂ̏��Ǝ{�݂ɂ�����ؗ����Ԃ��ł��邾������������悤�˗�������j��������B
�������A�c�Ƃ̐����ɑ���lj��̋��͋��̗L���Ȃǂɂ��ẮA��{�݂̕��Ƃ̋��͂Ƃ������ƂŐi�߂Ă���Ƃ���ł������܂��B���Ǝ҂݂̂Ȃ��܂ɂ�����܂��ẮA��������������Ǝ���Ă����Ƃ������Ƃ��A�R���v���C�A���X��K�v�ȑ�Ƃ��Ă����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��(���r�s�m��)�Ƃ����B
�Ȃ��A13���̉�ł́A�~�}�����̎���悪������Ȃ��ꍇ�Ɋ��҂�������颔�������Ή����@�ҋ@�X�e�[�V������̐V�݂�A�h���×{�{�݂̊m��(16�{�݁A��6200��)�A�ꕔ�̏h���×{�{�݂ł̍R�̃J�N�e���Ö@���{�Ɍ������̐�������i�߂Ă������Ƃ�B�����āA��Ë@�ւ�h���{�݂̖����̖��m�����i�߂Ă����Ƃ��Ă���B
���R�̃J�N�e���A�h���×{�ł��@�R���i�����g��u�ő勉�̊�@�v���r�s�m���@8/13
�����s�̏��r�S���q�m����13���̒��L�҉�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ�����ɂ��āu��N�R���i���P���Ă��Ĉȗ��́A�܂��ɍő勉�A�ЊQ���̊�@���}���Ă���v�Əq�ׁA�s���ɓO�ꂵ������������߂��B���̏�ŁA�����҂̏d�lj���h���u�R�̃J�N�e���Ö@�v�̎��{����Ë@�ւɉ����A�h���×{�{�݂Ɋg�[����l�����������B
�R�̃J�N�e���Ö@�Ɋւ��ẮA�s����120�J���̓��@�d�_��Ë@�ւɖ�܂����������j��A�s���E���Еa�@��20�����x�̐�p�a�����m�ۂ������Ƃ�����B13������ꕔ�̏h���×{�{�݂Ɉ�t��z�u����ȂǁA���Ö@�����{�ł���Ԑ��𐮂������Ƃ����炩�ɂ����B���r���́u���N�`���ڎ�ɍR�̃J�N�e���Ö@���������U�߂̐헪�ŏd�lj���h���ł����v�ƌ�����B
���r���́u(�����{�ŋN���Ă���)���J��Q���R���i�̔�Q�������ЊQ���v�Ǝw�E�B�u�l����������Ό��ʂƂ��ĕa�����ӂ�����A�~���閽���~���Ȃ��Ȃ�v�Ɗ�@����\���A�A�Ȃ◷�s���܂ފO�o�̎��l�����߂ēs���ɗv�������B
�������s �V�^�R���i 7�l���S �ߋ��ő�5773�l�����m�F�@8/13
�����s���ł�13���A�ߋ��ő��ƂȂ�5773�l�̊������m�F���ꂽ�ق��A�s�̊�ŏW�v����13�����_�̏d�ǂ̊��҂�227�l�ƂȂ�A4���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�܂��A����ŗ×{���Ă���50��̒j�����S���Ȃ�A��5�g�œs���c����������×{���̎��S��4�l�ɂȂ�܂����B
�����s�́A13���s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł̒j�����킹��5773�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B
����܂łōł�����������T�E�ؗj����5042�l���ĉߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�܂��A1�T�ԑO�̋��j�����1258�l�����Ă��āA�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B
13���܂ł�7���ԕ��ς͂ӂ�����4000�l����4155.7�l�ƂȂ�܂����B
�O�̏T��108.8���ł��B
�s�̒S���҂́u�܂������g�傪�����Ă�����B�l�ƐڐG����Ί������郊�X�N�͍��܂�B�ǂ����Ă��O�o����ꍇ�͒Z�����ԁA���l���ɂ���悤���肢�������v�Ƙb���Ă��܂��B
13����5773�l�̔N��ʂ́A10�Ζ�����276�l�A10�オ526�l�A20�オ1810�l�A30�オ1189�l�A40�オ955�l�A50�オ689�l�A60�オ188�l�A70�オ76�l�A80�オ50�l�A90�オ14�l�ł��B
�����o�H���킩���Ă���2209�l�̓���́u�ƒ���v���ł�����1401�l�A�u�E����v��372�l�A�u�{�ݓ��v��115�l�A�u��H�v��56�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̊֘A�ł͊O���l�̋��Z�W�҂�1�l�A���{�l�̈ϑ��Ǝ҂�2�l�̂��킹��3�l�̊������m�F����܂����B
����A13�����_�œ��@���Ă���l��3727�l�ƁA12�����59�l�����A7���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��62.5���ł��B
�܂��A�s�̊�ŏW�v����13�����_�̏d�ǂ̊��҂�12�����9�l������227�l�ł����B
4���A���ʼnߋ��ő����X�V���A�d�NJ��҂̑������~�܂�܂���B
�s���A���݊m�ۂ��Ă���d�NJ��җp�̕a���̎g�p����57.9���ƂȂ�܂����B
�d�NJ��҂̔N��ʂ́A10�オ1�l�A20�オ6�l�A30�オ21�l�A40�オ50�l�A50�オ82�l�A60�オ39�l�A70�オ23�l�A80�オ5�l�ł��B
�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ50�ォ��90��܂ł̒j��7�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
���̂����A50��̒j���͎���ŗ×{���ɓ|��Ă���̂�����Ƒ��������܂������A���̌�A���S���m�F����܂����B
�j���͗z���Ɣ��������Ƃ��A�����ƔM�̏Ǐ���܂������A�y�ǂ������Ƃ������Ƃł��B
�s�ɂ��܂��ƁA�j���ɂ͎����ُ�ǂ̊�b�������������Ƃ������Ƃł����A�ی����̖����̊ώ@�ł͏Ǐ�̈�����ċz��Q�̑i���͂Ȃ������Ƃ������ƂŁA�s�́A�Ǐ}�ς����ƌ��Ă��܂��B
��5�g�œs���c����������×{���̎��S��4�l�ɂȂ�܂����B
����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2332�l�ɂȂ�܂����B
���V�^�R���i ������454�l�����m�F 2���A����450�l�����@8/13
�k�C���ł�13���A�V����454�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\����܂����B�����̈���̊����m�F��450�l����̂�2���A���ŁA�����g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
�����ł́A�D�y�s�ōėz����2�l���܂�248�l�A����s��41�l�A���َs��13�l�A���M�s��3�l�A�\���n����35�l�A�Ύ�n����33�l�A���H�n����16�l�A��m�n���ƒ_�U�n���ł��ꂼ��14�l�A���n����7�l�A�I�z�[�c�N�n����6�l�A�n���n����5�l�A��u�n���A�����n���A�����n���ł��ꂼ��2�l�A�O�R�n����1�l�A����ɓ����u���̑��v�Ƃ��Ĕ��\�������O��7�l���܂�12�l�́A���킹��454�l�̊������m�F����܂����B
�D�y�s�∮��s�𒆐S�Ɋ����g�傪�����Ă��āA�����̈���̊����m�F��450�l����̂�2���A���ł��B
1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��́A�����S�̂�10���l������49.0�l�A�D�y�s��10���l������84.1�l�ƁA�s���{���̊������������̃X�e�[�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ��ƂȂ��Ă���10���l������25�l��傫�������Ă��܂��B
13���A�����ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���鎀�҂̔��\�͂���܂���ł����B
����ŁA�����̊����҂͎D�y�s�̂̂�3��681�l���܂ނ̂�4��8707�l�ƂȂ�A���S�����̂�1429�l�ƂȂ��Ă��܂��B
����A�ψكE�C���X�̃f���^���ɂ��āA�V���ɎD�y�s��98�l�A����s��19�l�A���َs��9�l�A����7�l�A���M�s��1�l�́A���킹��134�l���������Ă���^�������邱�Ƃ�������܂����B
�����ŁA���̕ψكE�C���X�Ɋ������Ă���^��������Ɣ��\���ꂽ�̂�2303�l�ŁA�������m�肵���̂�168�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���w�W�Ō��铹���̊�����
12�����_�̓����̊������A���{�̕��ȉ�������̎w�W�����ƂɌ��Ă����܂��B�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂�13�����_�̐����ł��B
�a���g�p���@/�@�܂���Â̂Ђ�����ł��B�a���g�p���̓X�e�[�W3��20���ȏ�A�ł��[���ȏ������X�e�[�W4��50���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������31.2���ƂȂ��Ă��܂��B
���@���@/�@���@���̓X�e�[�W3��40���ȉ��A�X�e�[�W4��25���ȉ����ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������18.9���ƂȂ��Ă��܂��B
�d�ǎҕa���g�p���@/�@�d�ǎ҂̕a���g�p���̓X�e�[�W3��20���ȏ�A�X�e�[�W4��50���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������11.5���ƂȂ��Ă��܂��B
�×{�Ґ��@/�@�l��10���l������̗×{�Ґ��̓X�e�[�W3��20�l�ȏ�A�X�e�[�W4��30�l�ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������63.0�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����z�����@/�@����1�T�Ԃ̂o�b�q�����Ȃǂ̗z�����̓X�e�[�W3��5���ȏ�A�X�e�[�W4��10���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������9.5���ƂȂ��Ă��܂��B
�V�K�����Ґ��@/�@�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂̓X�e�[�W3��15�l�ȏ�A�X�e�[�W4��25�l�ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A13�����_�œ�����49.0�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����o�H�s���҂̊����@/�@�����o�H���s���Ȑl�̊����̓X�e�[�W3�A�X�e�[�W4�Ƃ���50�����ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������42.8���ƂȂ��Ă��܂��B
���D�y248�l�m�F�@����ł��Ƃ��ő��@�V�^�R���i�������S���Ɋg��@8/13
13���A�k�C���ł͐V����454�l�̊������m�F����A2���A����400�l�����A����ł͂��Ƃ��ő���41�l�𐔂��܂����B�S���Ȃ������͂��܂���ł����B
�E�D�y�s�@248�l(�o�H�s��129�l)
�E����s�@41�l
�E���َs�@13�l
�E���M�s�@3�l
�E�\���Ǔ��@35�l
�E�Ύ�Ǔ��@33�l
�E�E�E
�E���̑��@
���̎��Ԃ܂łɔ��\����Ă���V���ȃN���X�^�[��3���ł��B
����1�T�Ԃ�10���l������̊����Ґ��́A�D�y��84�D1�l�A�S����49�D0�l�Ƃǂ�����X�e�[�W4�E�ً}���Ԑ錾�̖ڈ��ƂȂ�25�l��傫�������Ă��܂��B�a���g�p���͎D�y��42�D5���A�S����38�D3���ƎD�y�ً͋}���Ԑ錾�̖ڈ��ɂ��Ȃ�߂Â��Ă��܂��B�����Ƃ̊����Ґ����J�����_�[�Ō��Ă݂�ƁA13���͐�T�̋��j�����170�l�ȏ㑝���B�A���A�����X���ł��邱�Ƃ��킩��܂��B7����3�A�x����3�T�ԁA�k�C���̊����Ґ���454�l�ƍ��~�܂肵�Ă��܂��B
��13���͐X������45�l�̊����m�F�@�N���X�^�[���g��@8/13
�V�^�R���i�E�C���X�̐X�����̊����ɂ��Ăł��B�V���Ȋ����̊m�F�́A3���A����40�l���Ă��܂��B
12����42�l�ŁA13����45�l�̊������m�F����܂����B�������m�F���ꂽ�l�͍��킹��3073�l�ƂȂ�܂����B
�X���ɂ��܂��ƁA�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�O�O�ی����Ǔ���13�l�A���ˎs��11�l�A�X�s��9�l�A�O�˒n���ی����Ǔ���3�l�A�ނی����Ǔ���2�l�A���쌴�ی����Ǔ��Ə�\�O�ی����Ǔ��ł��ꂼ��1�l�A����ƐX���O��5�l�̍��킹��45�l�ł��B
���̂����A�O�O�ی����Ǔ��̏�Q�Ҏ{�݃N���X�^�[�ł́A�V����5�l�̊������m�F����A�֘A���܂߂��l����21�l�ƂȂ�܂����B
�܂��A�E��N���X�^�[�֘A�ł́A4�l�̊������m�F����A�֘A���܂߂��l����11�l�ƂȂ�܂����B���ˎs�̑�w�N���X�^�[�ł́A���O��3�l�̊������m�F����A���̃N���X�^�[�͊֘A���܂�20�l�Ɋg�債�܂����B�܂��A���Z�N���X�^�[�ł́A��\�O�ی����Ǔ���1�l�̊������m�F���A�֘A���܂߂��l����28�l�ƂȂ�܂����B
�a���g�p����31.6���ŁA���̎w�W�Ŋ����ҋ}����\���u�X�e�[�W3�v��20����9���A���Œ����Ă��܂��B
���N���X�^�[�����Ɗg����@12����116�l�������@�������@8/13
8��12���ɕ������Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A���킫�s46�l�E�S�R�s29�l�E�����s9�l�ȂǁA���킹��116�l�B
����116�l�Ƃ͕ʂɁA���킫�s�̎����{�݂ł͂���܂łɗ��p�҂ȂǍ��킹��7�l�̊������m�F����A�V���ȃN���X�^�[�ƂȂ����B
�܂����k�ی����Ǔ��̎��Ə��Ŕ��������N���X�^�[�́A�V����1�l�̊������m�F����39�l�Ɋg�債���B
8���̕��������̊����҂�1224�l�ŁA���ʂƂ��čő�������5����1179�l�����łɏ���A�����I�Ɋ������g�債�Ă���B���@���Ă���l�͏d�ǂ�14�l���܂�398�l�ŁA�a���̎g�p����66�D7���Ɉ������Ă���B
�������͌����S��Ɂu��펖�Ԑ錾�v�߂��Ă��āA���~���Ԃ̋A�Ȃ◷�s�͒��~����ȂǑ�̓O����Ăъ|���Ă���B
�������g�傪�����Έ�ʂ̋~�}�����̎��ꍢ��� ��� �y�Y �@8/13
��錧�ł��V�^�R���i�E�C���X�̊������}���Ɋg�傷�钆�A���암�̓y�Y�s�̕a�@�ł͓��@���҂ւ̑Ή��ƁA�V���Ȋ��҂̐f�@�̗����̕��S�������Ă��܂��B�a�@���́A�����̊g�傪�~�܂�Ȃ���Έ�ʂ̋~�}������������Ȃ��Ȃ�Ɗ�@�������߂Ă��܂��B
�y�Y�s�ɂ���y�Y�����a�@�́A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������҂̓��@�������ł����ɑ�������Ă��܂��B
8���ɓ���A����܂ł̂��悻40���̐�p�a���́A�قږ����̓��������Ă��܂����B
�����������@���҂ւ̑Ή��ɉ����A�a�@�ł́A����������V���Ȋ����҂̌�����f�@�̑Ή��ɂ��ǂ��Ă��܂��B
�A���A40�l�قǂ̊��҂ɔx�̃G�b�N�X���B�e�ȂǁA�d�lj��̃��X�N���Ȃ����̌������s���Ă��āA���ԁA�ʏ�̐f�Â�S��������t���ÃX�^�b�t���A�[������[��1������܂őΉ������������Ƃ������Ƃł��B
����ɓy�Y�����a�@�ł͌��̗v�����āA13������V�^�R���i��p�̕a��������܂ł̔{�ɑ��₷���Ƃ����߂܂����B
���̂��߁A�����g�傪�~�܂�Ȃ���A�߂������ɏd�NJ��҂̎��ÂɎg���Ă���W�����Î������ׂăR���i�̊��҂Ŗ��܂�A��ʂ̋~�}������������Ȃ��Ȃ邨���ꂪ����Ƃ������Ƃł��B
�y�Y�����a�@�͓̉��q�s�a�@���́u���̑Ή��͐E���̕��S���d���A����������Εa�@�̑Ԑ��͔j�]���܂��B���̂܂܂ł́A���ׂĂ�V�^�R���i�̑Ή��Ɋ������ƂɂȂ��āA��ʂ̋~�}�Ή����]���ɂ���������Ȃ��Ȃ�܂��v�Ƙb���Ă��܂��B
���Ȗ،����A�v������1���l�����@�V�^�R���i�u��5�g�v�җ�@8/13
�Ȗ،��ƉF�s�{�s��13���A�V����174�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1��������̔��\���ł͉ߋ�2�Ԗڂ̑����ŁA�v�����Ґ���1��21�l�ƂȂ����B�����͂̋����ψي��u�f���^���v�̊����͖�8���Ƃقڒu��������Ă���A���݂́u��5�g�v�͖җ�ȑ����Ŋ����҂����������Ă���B�S�×{�Ґ���1600�l���ĉߋ��ő��ƂȂ�A����×{�҂���@�������͖�1100�l�ɏ���Ă���B���͈�Õ��ԋ߂ɔ����Ă���Ƃ��āA�����Ɋ����h�~��̓O��������Ăъ|���Ă���B
7��27����1���̐V�K�����Ґ���100�l���A18���Ԃ�1�����ς�130�l�B�a���g�p����55.6���ƈ�Ò̐����N��(�Ђ��ς�)���A���@����16.5���Ɖ����葱���Ă���B����×{�҂��}�����A�e�̂��}�ς��Ď��S����������N�����B
�����ł̊������m�F�͍�N2��22���B��l�ɒB����܂Ŗ�10�J����v�������A�N���N�n�́u��3�g�v�Ŋ����������I�ɍL����A��1�J���Ŋ����҂�2��l�������B2�x�ڂً̋}���Ԑ錾���߂��o�āA�V�K�����Ґ��͌����ɓ]�����B
�������ψي��̗��s��5���́u��4�g�v�������B���̌㌸���������̂́A7�����{�ȍ~�A�V���ȕψي��f���^���̖҈Ђŏ͈�ς����B�����}�g����A8������V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p���ꂽ�B
�v�̎��Ґ���13�����_��93�l�B�����J���Ȃ̃f�[�^(10������)�ɂ��ƁA�N��ʂł�80�オ28�l(�j��18�l�A����10�l)�ōő��B������70��23�l(18�l�A5�l)�A90��ȏ�18�l(7�l�A11�l)�B���̂ق��A60��j��7�l�A50��j��5�l���S���Ȃ����B4�l�ȉ��̔N��E���ʂ͔���\�B
13���̐V�K�����҂�10�Ζ����`80��̒j���B����܂ł̊����҂̂����f���^���^����10�Ζ����`60��̒j��63�l���m�F���ꂽ�B�����s�Ɛ^���s�̎��Ə��Ō���97�A98��ڂ̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�����������B
���ƉF�s�{�s�͓����A�v238��������(�ϑ��̖��W�v���͏���)�B�v����������36��7216���A�މ@��8419�l�A���@��256�l�A�h���×{��150�l�A����×{��948�l�A���@������221�l�A�d�ǎ�17�l�B
����� ���m�� �����g��ő�K�͏��Ǝ{�݂ɑ�̋����v�� �@8/13
��ʌ��́A�ً}���Ԑ錾���o�����Ƃ������g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����Ƃ���A��K�͂ȏ��Ǝ{�݂ɑ��āA�K���Ƃɐl���̏����݂���ȂǑ�̋�����v�����܂����B
��ʌ��ł́A����2������ً}���Ԑ錾���o����Ă��܂����A����ɔ��\����銴���Ґ��͘A��1000�l���A13����1696�l�ƁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V����ȂNJ����g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
���̂��߁A���͂���܂ł̗v���̓��e������ɋ��߁A��^�̏����X��S�ݓX�Ȃǂ̑�K�͂ȏ��Ǝ{�݂ɑ��ē���̊K�Ɉ�x�ɗ��p�҂��W�����Ȃ��悤��̋�����v�����܂����B
��̓I�ɂ͂���܂ŁA���Ǝ{�ݑS�̂œ��ꂷ��q�̐��𐧌�����悤���߂Ă����̂����߁A�K���Ƃɐl���̏����݂��A�ɖZ���̔������x�Ƃ���悤�v�����Ă��܂��B
���ԏ�ɂ��Ă��������ɖZ���̔������x�̗��p�Ƃ���悤���߂Ă��܂��B
�܂��A�w�Z�̕������ɂ��Ă͍���16���ȍ~�A����R���N�[���Ȃǂɏo�ꂷ��ꍇ�������ďT2���ȓ��ɂƂǂ߂邱�Ƃ����߂Ă��܂��B
����ɁA���{�ɑ��ẮA�l�̗����}������L���ȑ[�u���s����悤1�s3���ŗv�������Ƃ������Ƃł��B
���m���́u����ȏ㊴���g�傪�����Η��T�ɂ���Õ���ɒ��ʂ���\�����o�Ă��Ă���B���̏܂����߂ċ��͂����肢�������v�Əq�ׂ܂����B
���_�ސ쌧���̊C�����ꂷ�ׂĕ��� �����}�g��Ől���}���� �@8/13
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g����āA�_�ސ쌧����s����3�̊C�����ꂪ8��16�����������邱�ƂɂȂ�܂����B����Ő_�ސ쌧����25�̊C������͂��ׂĕ��ƂȂ�܂��B
������邱�ƂɂȂ����̂́A����s�́A�А����l�C������А����l�A�����C������A����ɁA�ғ��C�������3�̊C������ł��B
�_�ސ쌧���ł́A���Ƃ��A25����C������̂����A15�̊C�����ꂪ�c�Ƃ��Ă��܂������A8��2���Ɍ����ً}���Ԑ錾�̑Ώۂɉ�����ꂽ���ƂȂǂ��āA�قƂ�ǂ̊C�����ꂪ���ƂȂ�܂����B
�����āA�c�Ƃ𑱂��Ă�������s����3�̊C�������8��16���ɕ�����邱�ƂɂȂ�A�_�ސ쌧���ł͊C������͂��ׂĕ��ƂȂ�܂��B
����s��C������̑g���ɂ��ƁA�C������̕�����O�̂��߃��C�t�K�[�h�͔z�u����Ƃ������ƂŁA����s�ό��ۂ̖ؑ��Õ��ے��́u�����҂������I�ɑ����A������Â��Ђ������Ă���B�l����}���������̂ŁA�F����Ɏ��������s�������肢�������v�Ƙb���Ă��܂����B
���É��E�V�^�R���i�@�V�K�����ҏ���300�l��@�����o�H�s���E��������56%�@8/13
�����̊g��͑����A12�����ߋ��ő����X�V�ł��B�V�^�R���i�̐V�K�����҂�354�l�ŁA�͂��߂�300�l������܂����B
�É������Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�̐V�K�����҂́A�l���s��79�l�A�É��s��73�l�Ȃljߋ��ő���354�l�ł����B7�����{����}�����A11����288�l��啝�ɏ����Ă��܂��B
�܂�������354�l�̂���199�l���A�����_�Ŋ����o�H���s���܂��͒������ƂȂ��Ă��܂��B�a���g�p���͌��S�̂�5�����A���́u����ȏ�a���𑝂₷���Ƃ͓����@�I�ȏv���Ƃ��Ă��܂��B
���Ȃǂ͈�Ñ̐����ێ����邽�߂ɂ��ő���̌x���Ƒ�̓O�������悤�Ăт����Ă��܂��B
�����쌧�ŏ���100�l���@�V�K������109�l�@2���A���ʼnߋ��ő��X�V�@8/13
13���A���쌧���ŐV����109�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��܂����B1���̔��\��100�l����̂͏��߂ĂŁA2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�����@���~�߂�����ʊ����g��@�a���g�p�����}�㏸���@8/13
�A���A�ߋ��ő��̐V�K�����҂��X�V���Ă���V�^�R���i�E�C���X�̊����g��B��Ñ̐��̕N��(�Ђ��ς�)�������Ȃ��A���{�͊��҂��h���×{�ɂȂ���V���Ȏd�g�݂��n�߂Ă���B
�h���×{�ɗp����Ă���z�e���ł́[�B�u�P�~�߂̖�Ƃ�������Ă܂����H�����Ȃ��Ȃ����B�P�~�߂̖����]�����Ƃ������Ƃł��ˁv�B�Ή�����̈�t�̑�����V����B
���{�ł́A15�̎{�݁A��4000�����m�ۂ��A���_�ƂȂ�z�e����2�l�̈�t��z�u���āA24���ԑ̐��ŃI�����C���f�@���s���B�Ō�t���풓���Ă��ĕa��̋}�ςɂ��������Ή��ł���B
�h���×{�҂̐��́A����������������������6�����ɂ͖�200�l�ɂ܂Ō����������A12�����_��2520�l�܂ő����A�g�p����6�������B������t�́u1�����悪�s�[�N��������A�܂��A4�g�ɑ����ߎS�ȏɂȂ�\���͏\���ɂ���v�Ɗ�@����i����B
����܂ł̌o�������ĉ��P���ꂽ�d�g�݂�����B��4�g�̍ۂ́A�h���×{�̒������X���[�Y�ɍs���Ȃ��������ƂȂǂ���A�����҂��}�����Ă����ɂ��ւ�炸�A�m�ۂ���������5���قǂ����g���Ȃ������B
�����ŕ{��7������V���ɓ��������̂��u�×{�ҏ��V�X�e���v���B����͊��҂̏���z�e���̋��ꌳ�Ǘ��ł���B
���{���N��Õ��̐��쐽�����́u�ی������h���×{�̌�����������ƂɁA�{���̂ق��ɏh���̃I�[�_�[�������ł��B���̊Ԃɂ����Ɛl����Ă����āA���̊ԃ��[���ł��Ƃ肵�Ă��āA���Ɏ��Ԃ�������Ɓc�v�Ǝ�������B
����܂ł́A�ی����ŏh���×{���K�v�Ɣ��f���ꂽ��A�{���z�e����^�N�V�[����z���A�����̓��[���ōs���Ă����B���̂��߁A�葱���Ɏ�Ԃ�������A�h���×{�ɓ���܂ň�T�ԋ߂�������P�[�X���������B
�V�����V�X�e���ł͕ی��������҂̏�����͂��邾���ŁA�����I�Ɏ�z���\�Ȃ��߁A�{�͓����������ɂ͎{�݂ɓ����Ƃ��Ă���B���ہA�V�X�e�����g�p����L���s�ی����́A�×{�悪���܂�܂ł̃X�s�[�h�������Ȃ����Ǝ������Ă���B
���s�ی����̏������Y�����́u��4�g�̎��́A��ԂЂǂ����͈�T�ԂƂ��������̂ŁA���������Ă����������ɂ͗×{�����������������B�����������Ƃł�������Ƃ���������ł����ǁA�����������Ԃ͔������Ă�v�Ɛ������Ă���B
�����A�A��1000�l���銴���҂��m�F����钆�A�ʂ̕ی����œ��������́u�V�X�e���͂��łɂ��܂��ғ����Ȃ��Ȃ��Ă���v�ƘR�炷�B����E���͓����Łu���Ƃ��ƃV�X�e�����āA��������Ƃ�����Ԃ̖ړI�͂��̓��ɓ��͂�����A���̓��ɓ����ł���ƃz�e���ɁB�����������Ƃ�搂��Ă��Ǝv����ł��ˁB�������ȂA3����Ƃ��A������ۏȂ��ł���̘b�ł���v
���݁A�{���m�ۂ��Ă��镔����4���قǂ͋Ă��܂����A���҂��g�p���������̐��|���ǂ��t�����A�����܂ł�3���ȏ�҂ꍇ������Ƃ����B��̐E���́u�Ⴞ����ɓ���Ȃ��l�������Ă����āA���̃N���[���̈�؍��A�S���ی����ŁA�]�v�Ɏd�������Ă��ł���B�����������ɂȂ������낤�A�����ǂ��Ȃ������낤�A���ꂪ���������낤�ƍl�����Ƃ��ɂ���������ĂȂ��ȂƂ����̂��A����̎����ł��v�ƕs�����Ԃ��܂���B
�����������_���A�g���m���m����13���A�u���A���������Ċm���ɓ��������Ƃ����͓̂���͎̂��ԂƂ��Ă���܂��B������������邽�߂ɁA40�Έȏ�̕��A�l�炭�炢�̐��ォ���̐���̕�����ς�l���艺�̐���ł����Ă��A��b���������Ă���l�Ƃ��A�����������Ƃ��ɍi�荞�݂������邱�Ƃɂ���āA�z�e���×{�̃X�s�[�h�����߂Ă��������Ǝv���Ă���v�ƌ���������ŁA8�����Ƀz�e���̕����̐����6000���ɑ��₵�A�z�e���×{�A����×{�Ƃ��ɉ��f�Ȃǂ̈�Ñ̐�����������Ƃ����B
���L�������s��17�l�����A13���V�^�R���i�@��ޒX�̃N���X�^�[�g��@8/13
�L�������s��13���A�s���ŐV���ɉ����⎙���A10�`50��̌v17�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����������1�l�A������4�l�B12���ɃN���X�^�[(�����ҏW�c)������F�肵���s���̎�ޒX�̊W�҂�1�l�ŁA���X�ł̊����m�F�͌v16�l�ƂȂ����B���s�ł�12���ɁA�s����1��������ōő��ƂȂ�19�l�̊����\���Ă���B
���V�^�R���i�V�K������207�l�ߋ��ő��@�f���^���̋��Ё@�F�{�@8/13
13�������ŐV���Ɋ��������ꂽ�l���́A����200�l������܂����B3���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
13���������\�����V�^�R���i�̐V���Ȋ����҂́A207�l��1���Ɋm�F���ꂽ�����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B207�l�̂����s�����ʂł́A�F�{�s��127�l�Ɠ��ɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�u200�l�͑z��͈͓̔��A250�l�܂ł͍l���Ă��Ȃ��̂ŁA���ꂩ�琔���Ԃ������ɂȂ�v�Əq�ׂ��ؑ����m���B
�������g�債�Ă���̂́A�挎���{�ɐl�̗��ꂪ���������Ƃ��������Ƃ����܂��B
����ŁA�挎29������F�{�s�̈��H�X�ɗv������Ă��鎞�Z�c�Ƃ̌��ʂ��A���T������o��̂ł͂Ȃ����Ƃ݂Ă��܂��B
�����A�u�f���^���v�ɂ��}���Ȋ����g��ɏP���Ă��āA���̐��Ɖ�c�͎s���������N����₷���Ȃ�\��������Ƃ݂Čx�����Ăт����Ă��܂��B
���݁A�����̕a���g�p����41�D5���B�F�{�s�����ł݂�ƁA60�D6���ƌ������ł��B
���V�^�R���i�@�{�茧���ŐV����63�l�����@�{�茧�@8/13
�{�茧���ł�13���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂���5�g�ōł�����63�l�m�F����܂����B�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����A���́A�{��s�̈��H�X�Ȃǂɏo���Ă���c�Ǝ��ԒZ�k�v����S�s�����Ɋg�傷��Ɣ��\���܂����B
�V���Ȋ����҂́A���Z�n�ʂŋ{��s��26�l�A�����s��9�l�A���O����̗��K�҂�8�l�A�s��s��6�l�A�V�x����5�l�A���璬��3�l�ȂǁA���킹��63�l�ł��B���璬�̈��H�X�ł́A����܂łɏ]�ƈ�5�l�̊������m�F����A���̓N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B�]�ƈ��͋x�e���Ń}�X�N���͂�����ʂ�����A���́A�Ǐ���̂ɋΖ��𑱂��Ă������Ƃ������g��Ɍq�������Ƃ݂Ă��܂��B���́A���H�X�W�̊������������ł���Ƃ��āA�{��s�̈��H�X�Ȃǂɏo���Ă���c�Ǝ��ԒZ�k�v����14������S�s�����Ɋg�傷��Ɣ��\���܂����B���Ԃ͍���24���܂łŁA�ߌ�8���ȍ~�͉c�Ƃ��s��Ȃ��悤���߂܂��B���͋��́A���ꂼ��̓X�܂̔���グ�K�͂ɉ����Ďx������܂��B
�͖�r�k�m���u���̐l�̈ړ��A�������e���ł̏W�܂�ȂǑ�l���ł̉���z�肳���悤�ȏ̒��ł́A�����g�僊�X�N���\�Ȍ��艺����Ƃ����_�ɂ������Ƃ����͂����肢���܂��v
12�����_�ŏd�ǎ�1�l���܂�53�l�����@���A232�l���h���{�݂⎩��ŗ×{���ƂȂ��Ă��܂��B
������R���i�A�q��Đ���ŋ}�g�� ������8����40��ȉ��@8/13
12���ɐV���Ȋ������m�F���ꂽ732�l�̂����A8����40��ȉ�����߁A�q�ǂ��Ƃ��̐e�ɓ����鐢��Ŋ������}�g�債�Ă���B�ʏ�f�j�[�m���͉�Łu�q�ǂ������̂͑�l�̐ӔC���B�w�Z��ۈ珊�A�ƒ���Ŏq�ǂ����������������Ȃ����߁A�����g�݂�i�߂Ă����v�Ƌ��������B�ۈ珊����ی㎙���N���u�Ȃǂւ̍R���ȈՃL�b�g�̓����A�w�ZPCR�����̕ۈ珊�ւ̊g�[�\���A�����\�h�̓O����Ăъ|�����B
732�l�̐���ʓ���́A�ő���20�オ183�l�ŁA30�オ142�l�A40�オ98�l�A10�Ζ�����85�l�A10�オ83�l�Ƒ����B40��ȉ��̊����͑S�̂�80�E7���ƂȂ����B
���芴���o�H���������Ă���͖̂�4����305�l�B����͉ƒ��192�l�A�E��46�l�A�{�ݓ�16�l�A�F�l�m�l39�l�A���H7�l�A���̑���5�l�B
���̎�������ËZ�Ắu���Ȃ�̋}�g�傾�B���{���Ƃ��Ă����Ɋ�@���������Ă���v�ƌ��O���������B
�ČR�W�͉Î�[��n�ƃL�����v�E�t�H�X�^�[�A�g���C�ʐM�{�݂Ŋe3�l�A�L�����v�E�L���U�[�ƃL�����v�E�R�[�g�j�[�Ŋe2�l�A���̑�1�l�̌v14�l�̊��������ꂽ�B
�����{�A�V�K�z����1��8822�l�c�u���ĂȂ����x�A����s�\�v�@8/13
���{�̐V�^�R���i�E�C���X������(�V�^�x��)�̈���̗z������Ґ���12���A�Ăэő��L�^���X�V�����B
12���A�m�g�j�ɂ��ƁA���̓��A���{�̐V�^�R���i�����҂��ߌ�6��50���܂łɐV����1��8822�l�m�F���ꂽ�B
����ɂ��A���{�̗ݐϊ����҂�109��224�l�ɑ������B���S�҂�24�l�����A1��5372�l�ɂȂ����B
���{�̈���̐V�K�����҂͑O���ɑ���2���A���ōő��L�^���X�V�����B�ŋ߈�T�ԂŐV�K�����҂�10��3136�l���������B
���̓��A�S��47�s���{����20�{���ŐV�K�����ҍő��L�^���X�V�����B
��s�E�����s�͂��̓��A�����4989�l�̊����҂����ꂽ�B�O����4200�l�ɑ����A2���A����4000�l�����B
�����s���V�^�R���i�����g��͂��邽�߂ɊJ�������j�^�����O��c�ł́A���Ƃ��u���ĂȂ��قǂ̑��x�Ŋ����g�傪�i�݁A����s�\�ȏŁA�ЊQ���x���ł̊������҈Ђ�U�邤�ً}���ԁv�Ǝw�E�����B
���V�^�R���i�̊����g��Ɍx���u���ƞH���A�ЊQ���x���A����s�\�v�@8/13
�������i���ƂŃ^�����g�̍��c���F����13���܂łɎ��g�̃c�C�b�^�[���X�V�B��5�g�Ƃ�������V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɂ��āA�R�����g�����B�@���̓��A12���ɓ����s���m�F�����V���Ȋ����҂�4989�l�̏��A�d�ǎ҂̐������߂�200�l�����Ƃ����L����\��t�������c���B�u���ƞH���A�ЊQ���x���A����s�\�v�ƒZ�����t�Ōx����炵�Ă����B
���u�S���ɋً}���Ԑ錾�v���ā@�u���܂܂ł̐���A�N�������Ă���Ȃ��v�@8/13
�����s��t��̔��莡�v���13���A�L�҉���A�u����1�����撣���Ă��炦�A�����҂�����\�����o�Ă���͂�������A��������������Ƃ�B���������͂����肵���o���헪�������Ă������������v�Ɛ��{�ɋ��߂��B���̂����ŁA47�s���{���̂قƂ�ǂŎ����Đ��Y��(1�l�̊��҂����l�Ɋ��������邩)��1���Ă���Ƃ��������ŁA�S���ɋً}���Ԑ錾�����Ȃǂ̑[�u���K�v�Ƃ̔F�����������B
�����́u���܂̈�Ë@�ցA�a�@�A�f�Ï��A����͑�ςȏɂȂ��Ă���B�F��ȋ��͗v������Ë@�ւɂ��Ă��邪�A�{���ɂ��܂͎肢���ς��B���N�`���͑ł��Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�ʏ�̊��҂���������v�u�~�}���҂�������܂�����҂��Ă��������Ƃ͌����Ȃ��v�Ȃǂƈ�Ì���̂Ђ����������B
�V�^�R���i�̊����g��ɂ��Ắu���܂܂ł̂悤�ɓ����𒆐S�Ƃ����s���A���𒆐S�Ƃ���ߋE���A�����A�k�C���A����Ƃ������ł͂Ȃ��B���łɑS���I�ȍL����������Ă���B�]���āA�S�����ЊQ�Ɍ������Ă���Ƃ������ƍl���āA�S���I�ȁA�Ȃ�炩�̗}���[�u�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����l�����\���ł���v�Əq�ׂ��B�����āu���̏ꍇ�́A�S���I�ȋً}���Ԑ錾���o���Ƃ��v�Ƌً}���Ԑ錾�̑S���֊g�傷��Ȃǂ̑[�u���K�v���Ƒi�����B
�S���ւ̓K�����ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ݏd�ǎ҂�����40��50��ɑ��A���N�`���̗D��ڎ�A�e�����[�N�Ȃǂɂ��l�Ƃ̐ڐG�����炷���Ƃ��厖���Ƃ�������B
���݂̃R���i��ɂ��Ắu���܂܂Ō����Ă����悤�Ȑ���͂����N���������Ƃ��Ă���Ȃ��v�Ǝw�E�B�u���N�̑�1�g��4�����炢�̊����ŁA�{���ɐl����}������悤�Ȃ��Ƃ�(����K�v������)�B���܂܂ł̃R���i�E�C���X�Ƃ͈Ⴄ�B�V�����f���^���̃E�C���X�͈Ⴄ�^�C�v�̋����E�C���X�ł���Ƃ����F���̂��Ƃɂ�����x�d�蒼���Đ����W�J������K�v������v�Əq�ׂ��B
���S���̐V�^�R���i�V�K�����҂��ߋ��ő��@8/13
�����g�傪�~�܂�Ȃ��B12���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��S����1��8,000�l�����߂Ē����A�ߋ��ő��ƂȂ����B12���A�S���ł́A����܂łōł�����1��8,863�l�̐V���Ȋ����ƁA24�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
�����s�ł́A�V����4,989�l�̊������m�F����A��T�ؗj����5,042�l�ɑ����A�ߋ�2�Ԗڂ̐��ƂȂ��Ă���B�܂��A�d�ǎ҂�218�l�ƁA���߂�200�l���������ق��A�V����6�l�̎��S���m�F���ꂽ�B���̂���60��̒j�����A8��6���ɗz���Ɛf�f����A10���ɖS���Ȃ������A6����2��ڂ̃��N�`���ڎ���I���Ă����Ƃ����B2��ڂ̐ڎ���I�����l�̎��S���s���Ŋm�F���ꂽ�̂́A���߂āB
����A�e�n�ł������g��̌X���͑����Ă��āA���{��1,654�l�A��������1,040�l�ȂǁA���킹��20�̕{���ŐV�K�����Ґ����ߋ��ő��ƂȂ��Ă���B
��31�s���{���@�ł��[���X�e�[�W4�@�a���g�p��5�����@16�s�{���@8/13
�S���̂قƂ�ǂ̓s���{���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����������������Ă��܂��B�����J���Ȃ�11���܂łɂ܂Ƃ߂������̎����ł́A10�����_�̐V�K�����Ґ���31�s���{���ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�ɑ������A1�T�ԑO��23�s���{�����猃���B���Ƃ�͊����ɂ��āA�u�S���I�ɂقڂ��ׂĂ̒n��ŐV�K�����Ґ����}���ɑ������Ă���A����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��v�Ǝw�E���A���ɋ�����@���������܂����B���������nj������ɂ��ƁA�����͂̍����f���^���́A�֓��n���Ŗ�9���A���n���ł���8���ɒu����������Ƃ���A����������g�傪�����\���������Ƃ݂��Ă��܂��B
10���܂ł�1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ��͑S����77�E6�l�B�O�T��58�E54�l��1�E33�{�ƂȂ�܂����B41�s���{���őO�T��傫�����銴���Ґ����m�F����A31�s���{�����X�e�[�W4�ƂȂ鍑�̎w�W��25�l���܂����B
�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��͂��ׂāA�܂h�~���d�_�[�u�͂قƂ�ǂ̒n��őO�T�����������g�債�Ă��܂��B
�����Ґ��̋}���ȑ����ɔ����A�d�ǎҐ����������Ă��܂��B�����s�ł́A12����218�l�Ɖߋ��ő���3���A���ōX�V�B����܂ŁA���`�̎���ȂǂŌJ��Ԃ��Ă����u���N�`���ɂ���ďd�ǎ҂��������Ă���v�Ƃ��Ă����y�Ϙ_�́A�傫������Ă��܂��B
�d�ǎ҂���@�҂��̊��҂͑S���ł��}�����A��ʈ�Â̐�����~�}����������Ȏ���������Ă��܂��B�a���g�p����11���܂ł̕ɂ��ƁA��s���𒆐S�ɑ��{�≫�ꌧ�Ȃ�16�s�{����5�����ɁB���ꌧ�ł�8�����A�d�Ǖa���g�p����6�����߂܂��B��s���̕a���g�p���͐_�ސ�75�E08��(�d�Ǖa���g�p��91�E46��)�A�����s55�E7��(��78�E3��)�Ȃǂƌ������𑝂��Ă��܂��B
�d�Ǖa���g�p���́A��s����ߋE���Ȃǂ�7�s�{����5���ȏ�ƂȂ�A���Ƃ́u�ЊQ���̏ɋ߂��ǖʁv�ƕ��͂��܂��B�{���ΐ�A�R���A�O�d�A����A�F�{�Ȃǒn���̊e���ł��a���͂Ђ������Ă��܂��B���̏������炵���̂́A�g���R�ЊQ�h�Ȃǂł͂Ȃ��A�������̖��ז���A�g�l�Ёh�ł��B�ً}���Ԑ錾���ɓ����ܗւ����s�J�Â��A�����������b�Z�[�W�����������ƂŁA�l���g���h���܂���ł����B�ߋ��ň��̊��������������N�����Ȃ���A��̓I�Ȋ�����͍u�����A�����́g���ȐӔC�h�ɓ]�ł��鐭�{�̖��ӔC���͏d��ł��B
���V�^�R���i4�{���ʼnߋ��ő��@���ɁE���s�͑[�u�Ώےn��g��@8/13
��2�{4���ł�12���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂����Ƌ��s�Ǝ���A����ɕ��ɂʼnߋ��ő����X�V���A�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B���Ɍ��Ƌ��s�{�ł́A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��̊g������߂�ȂǁA�e�{���ł͊�����̂���Ȃ�O��������Ăт����Ă��܂��B
����12�����\���ꂽ�V���Ȋ����҂́A��オ1654�l�A���ɂ�728�l�A���s��372�l�A���ꂪ164�l�A�ޗǂ�114�l�A�a�̎R��31�l�̂��킹��3063�l�ł���܂łōł������Ȃ�܂����B
1���̊����Ґ��Ƃ��ẮA���Ƌ��s�A����Ɏ����2���A���ʼnߋ��ő����X�V���A���ɂł��ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
���������Ȃ����s�{�ƕ��Ɍ���12���J�������{����c�ŁA�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn����g�傷�邱�Ƃ����肷��ƂƂ��ɁA����A�ً}���Ԑ錾�̔��o������ɁA���Ƌ��c���Ă������Ƃ����߂܂����B
�e�{���ł́A�����̋}�g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����āA���~�̊��Ԓ����s�v�s�}�̊O�o�͎��l���A�s���{�����܂����ړ��͋ɗ͍T����ȂǁA�����������ɓO�ꂷ��悤�����Ăт����Ă��܂��B
���V�^�R���i �V�K�����Ґ�1�T�ԕ��� 42�s���{���Ŋ����g�呱�� �@8/13
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�����s�łً͋}���Ԑ錾���o�����1�����]�肽���Ă��A�ߋ��ő��̊����Ґ����X�V���钆�ł̊����g�傪�����Ă���ق��A�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���o����Ă���n����܂�42�̓s���{���Ŋ����g�傪�����Ă��܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S��
�S���ł́A�挎15���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�1.41�{�A�挎22����1.56�{�A�挎29����1.69�{�A����5����1.83�{�A12���܂łł�1.24�{�ŁA7�T�A���ő������Ă��Ċ����Ґ����ߋ��ő��ƂȂ��Ă��钆�ł�����Ɋg�債�Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1��4728�l�ƂȂ��Ă��āA42�̓s���{���Ŋ����g�傪�����Ă��܂��B
���ً}���Ԑ錾�̒n��
�����s�͐挎12���ɋً}���Ԑ錾���o���ꂽ���Ƃ������҂��������A�挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.62�{�A����5����1.64�{�A12���܂łł�1.09�{�Ƒ����̃y�[�X�͂��ɂ₩�ɂȂ������̂́A8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ���3976�l�ƁA��T��肨�悻330�l�����A����1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ���199.93�l�ƁA�����������ƂȂ��Ă��܂��B5��23������ً}���Ԑ錾�������Ă��鉫�ꌧ�ł́A�挎���{����Ăё����ɓ]���挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��2.19�{�A����5����1.93�{�A12���܂łł�1.19�{��5�T�A���Ŋ������g�債�Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻532�l�ŁA����1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ���256.09�l�ƑS���ōł���������܂ō����̂ǂ̒n��ł��o���������Ƃ̂Ȃ��K�͂̊����g�傪�����Ă��܂��B����2������ً}���Ԑ錾���o����Ă����s����3���Ƒ��{�ł������̃y�[�X�͂��ɂ₩�ɂȂ������̂́A�����g�傪�����Ă��܂��B
�_�ސ쌧�͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.52�{�A����5����2.02�{�A12���܂łł�1.22�{��7�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1849�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��ʌ��͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.73�{�A����5����1.77�{�A12���܂łł�1.30�{��8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1301�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��t���͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.61�{�A����5����1.90�{�A12���܂łł�1.22�{��10�T�A���Ŋ������g�債�Ă���1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻989�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���{�͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.67�{�A����5����1.67�{�A12���܂łł�1.27�{��6�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻1205�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���d�_�[�u�̒n��
�܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă���قƂ�ǂ̒n��Ŋ����g�傪�����Ă��܂��B
�k�C���͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.48�{�A����5����1.81�{�A12���܂łł�1.25�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻347�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�ΐ쌧�͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.89�{�A����5����1.19�{�A12���܂łł�0.80�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻70�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���s�{�͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.88�{�A����5����2.06�{�A12���܂łł�1.42�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻283�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���Ɍ��͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.59�{�A����5����2.11�{�A12���܂łł�1.36�{��1��������̐V�K�����Ґ���466�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�������͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��2.62�{�A����5����2.36�{�A12���܂łł�1.37�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻734�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����T����d�_�[�u�̒n��
���T����V���ɏd�_�[�u���K�p���ꂽ�n��ł��A�����g�傪�����Ă��܂��B
�������͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��3.42�{�A����5����1.84�{�A12���܂łł�1.13�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻103�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��錧�͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.82�{�A����5����2.05�{�A12���܂łł�1.20�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻247�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�Ȗ،��͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��2.54�{�A����5����1.70�{�A12���܂łł�1.06�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻133�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�Q�n���͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��3.24�{�A����5����2.49�{�A12���܂łł�1.14�{�ŁA1��������̐V�K�����Ґ���136�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�É����͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��2.00�{�A����5����1.76�{�A12���܂łł�1.65�{�ŁA1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻235�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���m���͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.62�{�A����5����1.88�{�A12���܂łł�1.56�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻422�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���ꌧ�͐挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��2.13�{�A����5����2.66�{�A12���܂łł�1.68�{��1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻112�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�F�{���́A�挎29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��4.83�{�A����5����2.40�{�A12���܂łł�1.44�{��1��������̐V�K�����Ґ���129�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����{���ȉ� �ړc�����u���~�͈ړ��T���A�������O����v
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́A���݂̊����ɂ��āu�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u���o����Ă���n��ȊO�ł��������}���ɑ������A�S���I�ɑ�5�g�̊��������������Ă���悤�ȏ��B�����s�ł�PCR�����̗z������20�����Ă��āA�\���Ɍ�������Ă��Ȃ��\��������B��������Ă��Ȃ��l�����̊Ԃł���Ɋ������L�����Ă���\���◈�T�A���~�����ȍ~�ɋ}���ȑ����Ƃ��Č����Ă���\�����l���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B
�܂��A��Ñ̐��ɂ��āu��4�g�̂Ƃ��ɑ�����Ŕ��Ɍ������ɂȂ����̂Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ�����s���Ō����A�S���I�ɔ��Ɍ������Ɍ���������B�����s�ł͂���܂łɂȂ��d�ǎҐ��ɂȂ��Ă��āA���@���܂܂Ȃ�Ȃ����ŁA�d�lj����邢�͖S���Ȃ�l���o�Ă���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�F������K�v������B�܂��A���ꌧ�ł͈�Â̋����̐���������ȕ���������A�d�NJ��҂�����ɑ����Ă��Ă�����l����ƁA��Â̂Ђ����������ɂȂ���Ȃ��悤���ܑȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƌ������܂����B
���̂����Ŋړc�����́u�Ƃɂ�������1�T�ԁA2�T�Ԃ����ɑ厖�Ȏ����ɂȂ�B�S�ݓX�ȂǑ�K�͏��Ǝ{�݂��܂߂Đl���W�܂�ꏊ�ɑ��ċx�Ɨv��������Ȃǂ��Đl�̓������~�߂邱�Ƃ��l���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B����1�N���ł��������ɂȂ����Ƃ������Ƃ����L���Ă��������āA���~�͂ł��邾���ړ����T���A����̎���̋ߏ�ʼn߂����Ăق����B�}�X�N��K�Ɏg�����Ƃ͂������A���C��l�Ɛl�Ƃ̋��������A�l�ƐڐG���鎞�Ԃ�Z������A�����̊������O�ꂷ�邱�Ƃ��d�v���v�Ƒi���܂����B
���V�^�R���i����2���l���� ����×{�҂ւ̉��f�́H��s�x���́H �@8/13
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�~�܂�܂���B�����s�͉ߋ��ő���5773�l�B�S���ł����߂�2���l���A1���̔��\�Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�܂����B����×{�҂��}�����钆�A���f�ɓ�����f�Ï��┃�����Ȃǂ̑�s���s���Ă��鎩���̂́A�Ή��ɒǂ��Ă��܂��B
13���͌ߌ�8�����݁A�S����20365�l�̊��������\����܂����B5773�l�ƂȂ��������s�̂ق��A�_�ސ쌧(2281�l)�A��ʌ�(1696�l)�A��t��(1089�l)�Ȃǂł��ߋ��ő����X�V���܂����B
��1�T�ԕ��ςŔ�r���Ă��c
1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ����S���ő��������Ă��܂��BNHK�͊e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ƂɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă��܂��B8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T�Ɣ�ׂ�1.24�{�ƂȂ�A�O�T�䂪1�{����u�����v��7�T�ԑ����Ă��܂��B
�������̎���×{�� 2���l����
�}���Ȋ����g�傪���������s���ł́A����ŗ×{����l��12���A���߂�2���l���܂����B1�����O��11.3�{�ɋ}�����Ă��āA���@�̒�������q������ł̗×{��]�V�Ȃ������l���������ł��܂��B����̑�5�g�ł́A����ŗ×{���ɖS���Ȃ�l���s���c�����Ă��邾���ł����ł�3�l���āA�̒��̋}�ςɕی�����s�̃t�H���[�A�b�v�Z���^�[�̑Ή����ǂ����Ȃ��P�[�X���o�Ă��܂��B���Ƃ́A�s���̈�Ò̐��́u�[���ȋ@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���v�Ǝw�E���Ă��āA�~�}���҂̎��������ƂȂ�Ȃ��A����×{�҂̑̒��̈������@�m���āA�K�v�Ȉ�Â𑬂₩�ɓ͂��邱�Ƃ��}���ƂȂ��Ă��܂��B
���K��f�ÂȂ�ł͂̓����
����×{�҂ւ̖K��f�Â��s���Ă����t�͊�@�������߂Ă��܂��B�����E����ōݑ��Â��s���u��������O�f�Ï��v�́A�s�̈˗����ĐV�^�R���i�E�C���X�̎���×{�҂̉��f���s���Ă��܂��B���Ƃ�6���܂ł�2�����ԂɑΉ������͍̂��킹��2���ł������A�挎�̘A�x���������C�ɑ����A���ł͑�������1��10���ɂ̂ڂ�Ƃ������Ƃł��B����×{�҂̋}���ɑΉ����邽�߁A�ӂ���f�Ă��銳�҂̂�����Ԃ����肵�Ă���l�ɂ͖�̏����݂̂��s���Ȃǂ��ĖK�␔�����ɐ�������������Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł����A����ł��ǂ����Ȃ��قLj˗����������ł���Ƃ������Ƃł��B�f�Ï��̗�ؗz�ꕛ�@���́u�������}�g�債�Ď���×{�҂������Ă������Ƃ͗\�z���Ă������A���̉Q���ɓ����Ă݂�Ƃ��Ȃ茵�������B�ʏ�̒���I�Ȑf�Â�������x�������Ȃ��Ǝ���×{�҂�f�邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�Ȃ�Ƃ�������o�Ȃ��悤�ɂ������B�ݑ�f�Â�20�N�߂�����Ă��邪�A���ڂ�Ă��܂��l������̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă���v�Ƙb���Ă��܂��B����ɂ́A�ݑ�Őf�@���������B11���ɕی����̈˗��ŖK�₵�����҂̂Ȃ��ɂ́A����8�����̐Ԃ�����܂����B�Ƒ�3�l�S�������������Ƃ������ƂŁA�Ԃ����͍��M�Ɖ����������Ă��܂����A���t���̎_�f�O�a�x���͂���p���X�I�L�V���[�^�[�͓͂��Ă��܂���ł����B��t�͎������킹�Ă����p���X�I�L�V���[�^�[��Ԃ����̎w�ɂ͂߂悤�Ƃ��܂��������܂��������A���肷�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�K���A���f�łُ͈�͂Ȃ��ċz�����肵�Ă������߁A���������ݑ�ŗl�q�����邱�ƂɂȂ�܂����B
�܂��A60��̒j���͌����̎_�f�O�a�x�̒l���Ⴍ�A���f�����Ƃ���x�����N�����Ă���\�����������Ƃ��킩��܂����B���A�a�Ȃǂ̎��a�����邽�ߓ��@���K�v���Ɣ��f���ĕی����ɘA�����܂������A���̓��͎���悪������܂���ł����B��t�͋}����A����Ŏ_�f���z���ł���@�����z���悤�Ƃ��܂����A�ɂ����Ȃ��͂��邱�Ƃ��ł��Ă���ԂɂȂ�ƌ����A�ʂ̉�ЂɈ˗����ĂȂ�Ƃ��Ή����邱�Ƃ��ł��܂����B��ؕ��@���́u�x�̉摜�f�f���s���Ȃ��ȂǕa�@�Ɠ����悤�ɂ͂������A�����̔��f���{���ɐ������̂��A����Ɗ�����B���@���Ă����疈������I�ɖ�����ċz�Ȃǂ̐��l���m�F���邪�A�ݑ�ł͕K�����������ł͂Ȃ��A�}�ς����ꍇ�ɒN���C�t���̂��Ƃ����낤��������v�Ǝw�E���܂��B
����ɁA����×{�҂̐f�@�͂��̂ǐV�����h�앞�𒅂āA�f�@���I���Ƃ����C�̗��܂ŏ��ł���ȂNJ������O�ꂵ�Ȃ���s���܂��B�ی����ւ̘A�����̏����Ȃǂ��܂߂��1��������ʏ�̖K��f�Â̔{�ȏ�̎��Ԃ�������Ƃ������Ƃł��B��ؕ��@���́u�V�^�R���i�͂����Ƃ͈Ⴂ�A�M�₹�������������̂Ŏ���×{�ł͕s��������Ǝv�����A����ȂȂ��ŕی����ɘA�����Ƃ�Â炭�Ȃ��Ă�������@�����Â炭�Ȃ��Ă����肷��̂ŁA�Ȃ�����s���ɂȂ�̂������ł��܂��B���̏����̒��A�̗͂͏��Ղ��邪�ł��邩����͂𒍂��ł��������v�Ƙb���Ă��܂����B
�������̂̑�s�x�� ��]�҂��}��
�_�ސ쌧�C�V���s�ł́A�s�̐E�����H���i����������S�~�o�����s�����肷��x������]����l���}�����Ă��܂��B�_�ސ쌧�ł�1���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�13���܂�17���A����1000�l���A12���̎��_�Ŏ���ŗ×{���Ă���̂�1��1900�l�]��ɂ̂ڂ�܂��B
�����������A�_�ސ쌧�C�V���s�͎���ŗ×{���Ă���l�̂����A�Ƒ��̎x���������Ȃ��l��ΏۂɁA�s�̐E�����H���i����p�i�̔������A�S�~�o���̑�s�̎x�����s���Ă��܂��B12���́A����ŗ×{���Ă���l����A���ݕ��̍w���˗�������A�S���҂��s���̃X�[�p�[���狍���Ȃǂ�͂��Ă��܂����B
���Ή��E�����₵�̐�������
�C�V���s�́A��������ꂽ���X�g�����Ƃ�6�`�[���A12�l�̐E�����d�b�������Ă��܂����A�x���̊�]�͑��������Ă���Ƃ������Ƃł��B�̒��̈�����i����l���~�}�������ꂽ�P�[�X������Ƃ������ƂŎs�͑Ή�����E���𑝂₵�Ďx���̐�������������j�ł��B
�C�V���s��@�Ǘ��ۂ̎u�������W���́A�u�e�̂̋}�ς�������āA�����d�b�������Ăق����Ɗ�]����l�������Ă��ď��h�Ƃ��A�g���Ă���B�s���Ɋ��Y���������x�����������v�Ƙb���Ă��܂����B
���ړc�����u����1�N���ł��������ɂȂ����v
�V�^�R���i�E�C���X��ɂ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́A��Ñ̐��ɂ��āu��4�g�̂Ƃ��ɑ�����Ŕ��Ɍ������ɂȂ����̂Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ�����s���Ō����A�S���I�ɔ��Ɍ������Ɍ���������B�����s�ł͂���܂łɂȂ��d�ǎҐ��ɂȂ��Ă��āA���@���܂܂Ȃ�Ȃ����ŁA�d�lj����邢�͖S���Ȃ�l���o�Ă���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�F������K�v������B�܂��A���ꌧ�ł͈�Â̋����̐���������ȕ���������A�d�NJ��҂�����ɑ����Ă��Ă�����l����ƁA��Â̂Ђ����������ɂȂ���Ȃ��悤���ܑȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƌ������܂����B
���̂����Ŋړc�����́u�Ƃɂ�������1�T�ԁA2�T�Ԃ����ɑ厖�Ȏ����ɂȂ�B�S�ݓX�ȂǑ�K�͏��Ǝ{�݂��܂߂Đl���W�܂�ꏊ�ɑ��ċx�Ɨv��������Ȃǂ��Đl�̓������~�߂邱�Ƃ��l���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B����1�N���ł��������ɂȂ����Ƃ������Ƃ����L���Ă��������āA���~�͂ł��邾���ړ����T���A����̎���̋ߏ�ʼn߂����Ăق����B�}�X�N��K�Ɏg�����Ƃ͂������A���C��l�Ɛl�Ƃ̋��������A�l�ƐڐG���鎞�Ԃ�Z������A�����̊������O�ꂷ�邱�Ƃ��d�v���v�Ƒi���܂����B
�����{�A�ً}���Ԃ̑Ώۊg��������@���������͍���@8/13
���{��13���A�V�^�R���i�E�C���X�̑S���I�Ȋ����}�����A�����A���Ȃ�6�s�{���ɔ��ߒ��ً̋}���Ԑ錾�̑Ώےn��g��Ɍ����������ɓ������B
�����̂̏�T�d�Ɍ��ɂ߂A���T�ɂ��ۂf����B31���܂ł̊����ɂ��ẮA��������Ƃ̌������o�Ă���B
���`�̎�13���A�����N���o�ύĐ��S������W�t���Ǝ��@�ŋ��c�����B���̌�A�L�Ғc�Ɂu�����̈�Ñ̐��͋ɂ߂Č������ɂ���v�Ɗ�@���������B�s�v�s�}�̊O�o���l�Ȃǂ����߂ČĂъ|�����B
���t���[�̎���(12�����_)�ɂ��ƁA�܂h�~���d�_�[�u��K�p����13���{���ł́A�l��10���l������̗×{�Ґ��A10���l������̐V�K�����Ґ�(����1�T��)�̊������A��������錾���߂̖ڈ��ƂȂ�u�X�e�[�W4�v�����ƂȂ����B���̂������A�����͊��ɁA�錾���߂����ɗv���B���s�A���ɂ��v��������ɁA���Ƌ��c������j���B
�錾�g��ɂ��āA���{���ɂ́u���ʂ����ʂ��Ȃ���ΈӖ����Ȃ��v(�W��)�ȂǂƐT�d�ӌ�������B����ɑ��A��������12���A�L�Ғc�Ɂu�K�v�ƂȂ�@���I�ɑΉ��������v�Ɩ��������B
�錾�n��ł͈ˑR�A���������̒����������Ȃ��B�����̐V�K�����Ґ���13���A5773�l�Ɖߋ��ő����X�V�B���Ԃ̐[�����͖��炩�ŁA���{�W�҂́u�錾�̌��������͂��Ȃ����v�Ƃ̔F�����������B
���{�̐V�^�R���i�����ȉ��12���A�����ł̐l�o�����Ȃǂ����߂�ً}�����\�����B������A��13���A�L�Ғc�Ɂu���Ǝ{�݂Ȃǂł̐l���}���ɂ���������g�݂����v�ƕ\���B����A�W���I�ɑ���}������ŁA���̌��ʂ܂��Đ錾�̈��������肷����j���B�@
���Ȃ�5���팸�H�u�����Ȃǂ̐l�o��5���팸�v���ȉ�̗��R �@8/13
�V�^�R���i�E�C���X�̊����������I�ɑ������A��Â̂Ђ������[�������Ă��܂��B��@�I�ȏ��������K�v������Ƃ��āA���{�̕��ȉ�́A����2�T�ԁA�����s�ȂǂŐl�o��7���O���ɔ�ׂ�5�����炷���ƂȂǁA����������߂�ً}�̒��o���܂����B���ȉ�͂Ȃ��u5���팸�v�Ƃ����̂��B�Ȋw�������̐���Y���L�҂�������܂��B
���u5���팸�v�̈Ӗ��́A�g5���̌�����Ɠ����x�h
���ȉ�u�l�o��5�����炷�v���Ƃ����߂��̂ɂ́A�Ƃɂ����}���ɐڐG�̋@������炵�A�ꍏ���������������炷�K�v������A�Ƃ������Ƃ�����܂��B���̃O���t�́A�����̎�Ȕɉ؊X�̐l�o�̐��ڂ��A���ԑѕʂɎ������O���t�ł��B���̒��̎��F�̐܂���́A��8������10���̐l�o�̐��ڂł��B����ً̋}���Ԑ錾���o��7���O���ƁA���̎��_���ׂ�ƁA25�����������Ă��܂���B����ł͂��������͌���Ȃ���Ԃ��Ƃ������Ƃł��B���ȉ�́A�ً}���Ԑ錾�O��5�����炳�Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B���ꂪ�ǂꂭ�炢���Ƃ����ƁA�O��A4���ɏo���ꂽ�錾�̂��ƁA�ł��傫����������5����{���݂̐l�o�܂Ō��炷���Ƃ����߂Ă��܂��B�����͑�^�A�x�̊��Ԃő傫���l�o�������āA���̌�A5�����{�ɂ�1�T�ԕ��ς̊����Ґ��������ɓ]���܂����B���������2�T�ԂŐl�o��5�����炵�A�Ȃ�Ƃ������������̕����ɓ]�����������Ƃ��Ă��܂��B
���R���i�ȊO�̋}�a�₯�������Î��Ȃ�������
���܁A���ȉ�̐��Ƃ́u�~���閽���~���Ȃ��Ȃ�悤�ȏɂȂ����v�Ƃ����A���ɍ�����������@���������Ă��܂��B�S���ł��A�����͏��Ȃ��ƌ����Ă����d�ǎ҂��A�ߋ��ő��ɔ����Ă��āA40���50��A�����肳��ɎႢ����ŖS���Ȃ�l���o�Ă��Ă��܂��B��s���A����Ȃǂł͎���ҋ@�҂��}���ɑ����āA���Â����Ȃ��܂���ŖS���Ȃ�l�����ۂɏo�Ă��Ă��܂��B����ɁA�R���i�Ɋ������Ă��Ȃ��Ă��A�}�a�ɂȂ����莖�̂ł����������肵�Ă��A���Â����Ȃ������ꂪ����܂��B�����ŏd�NJ��҂̎��Âɂ������Ă����A�������ۈ�Ì����Z���^�[�̐X���T��Y��t�́u���܂܂łɂȂ����炢�A�����������@���ł��Ȃ��\���������Ǝv���܂��B�R���i�ɂȂ��Ă��܂��ē��@�ł����Ƃ��Ă��A��Ë@��s�����Î҂̕s������A�\���Ȉ�Â����Ȃ��\�����o�Ă��Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂��B
���u����ł���ꏊ�ɍs���@����Ɂv
������Ƒ�����邽�߂ɁA�������ׂ����B�Ƃɂ����u�l�Ƃ̐ڐG���\�Ȍ��茸�炷�v�Ƃ������Ƃł��B�����͂̋����f���^�����嗬�ɂȂ��āA�w�K�m��g�f�p�n���h�Ƃ������A����܂łȂ������悤�ȂƂ���ł��������N���Ă��܂��B���~�x�݂��n�܂��Ă��܂����A���̊��ԂɁA�������z����ړ������Ȃ������łȂ��A�ł������O�ɏo��@������炷���Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B���ȉ�̔��g��́u����ł���ꏊ�ɍs���@����Ɂv�ƌĂт����Ă��܂��B
�����܁A�܂��Ɂu�ЊQ�̂悤�ȁv�i�K��
�����Ƒ����āu���܂ʼn䖝��������v�Ɣ[���ł��Ȃ��v�������l�����ɑ����Ǝv���܂��B�������A�����I�Ȋ����g��ŁA���łɂ��܁A�N�ɂƂ��Ă��A���������̉Ƒ��̐g����邽�߂ɂ���������Ƃ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��A�܂��Ɂu�ЊQ�̂悤�ȁv�i�K�ɓ������ƁA���Ƃ͌x�����Ă��܂��B
�������o�H�s���A�����̈�r�@���X�N�����s����ڗ��@8/13
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��߂����ẮA���Ƃ������g��̎w�W�̈�Ƃ��āA�ڐG��s���҂̐��Ƒ�����ɒ��ڂ��Ă���B�����o�H�̓���́A���ʓI�Ȋ�����ɂ��Ȃ��邪�A�ڐG��s���Ґ��͑����̈�r�����ǂ�A���݂�1���������2500�l�ɏ��B���Ƃ́u�o�H�̒ǂ��Ȃ����ݓI�Ȋ����g�傪�����Ă���v�Ɗ�@���������B
�����s�ł͊����̍L����f����ƂƂ��ɁA�V���ȃN���X�^�[���`������Ă���\����T�邽�߁A�ڐG��s���҂̐��Ƒ�������Ď����Ă���B
�s���ł́A3��ڂً̋}���Ԑ錾������(�܂�)�h�~���d�_�[�u�Ɉڍs���������6��23�����_��7�����ςŁA�ڐG��s���҂�1��������260�E6�l�B����܂ł̉ߋ��ő���������3�g��1192�E4�l(1��11�����_)��������Ă����B
�������A���̌�A�s���Ґ��͑������A3�T�Ԍ��7��14�����_�ł�502�l�Ƃقڔ{���B�����2�T�Ԍ�̓���28�����_�ł�1246�l�ɏ�����B
8���ɓ����Ă�����s���Ґ��͑����𑱂��A11�����_��2484�E6�l�B�����͂̋����C���h�R���̕ψي��u�f���^���v�̊g��ŐV�K�����Ґ��������������Ƃ��w�i�ɂ��邪�A�����o�H��ǂ��Ȃ��s���Ґ��̋}���͑z����銴���g��̃��X�N���͂�݁A�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���ۊ����ǃZ���^�[���́u���d�Ȍx�����K�v�v�Ɗ�@���������B
�s���̊����͂���12���̃��j�^�����O��c�́u�ڐG��s���҂̑����䂪100�����邱�Ƃ͊����g��̎w�W�ƂȂ�v�ƃR�����g�B�s���Ґ���2�J���ȏ㑝�������A�������100�������鐅���Ő��ڂ��Ă���Ƃ��āA�O�ꂵ���l�o�̗}���Ɗ����h�~����Ăт����Ă���B
�V�K�����҂ɐ�߂銴���o�H�s���҂̊��������������ɂ���A11�����_��63�E1���B�������݂鍑�̎w�W�ł�50������ƁA�����̃X�e�[�W3(�����ҋ}��)��4(�����I�����g��)�ɊY������B
�܂��A�������ۈ�Ì����Z���^�[�̌����O���[�v��5��22������6��29���ɓ��Z���^�[�̕a�@�ɓ��@�������҂̂����A�����o�H���������Ă��Ȃ�����22�l�ɂ��ďڂ��������B64���ɂ�����14�l�Ɋ������X�N�̍����s�������������Ƃ����B���̂����A88�������H�֘A�ŁA�قƂ�ǂ��}�X�N��t���Ă��Ȃ������Ƃ����B
���������s������������R��������Ƃ���A�u�O�H�������̃��X�N���Ƃ͒m��Ȃ������v�u�d���̌�Ȃ�E�����m�Ń}�X�N�Ȃ��Řb���Ă����v���낤�v�Ƃ��������������Ƃ����B
�Z���^�[�ł͒������ʂ���A�u�����ɂ͈��H�������̎���ŊW���Ă��邱�Ƃ����������v�Ƃ�����ŁA�u�����h�~�ɑ���ӎ��t����\���Ȓm�����s�����Ă���A����������ׂ��ۑ�Ƃ�����v�Ƃ��Ă���B
���u�S���ɋً}���Ԑ錾�v���ā@�����s��t��E�����@8/13
�����s��t��̔��莡�v���13���A�L�҉���A�u����1�����撣���Ă��炦�A�����҂�����\�����o�Ă���͂�������A��������������Ƃ�B���������͂����肵���o���헪�������Ă������������v�Ɛ��{�ɋ��߂��B���̂����ŁA47�s���{���̂قƂ�ǂŎ����Đ��Y��(1�l�̊��҂����l�Ɋ��������邩)��1���Ă���Ƃ��������ŁA�S���ɋً}���Ԑ錾�����Ȃǂ̑[�u���K�v�Ƃ̔F�����������B
�����́u���܂̈�Ë@�ցA�a�@�A�f�Ï��A����͑�ςȏɂȂ��Ă���B�F��ȋ��͗v������Ë@�ւɂ��Ă��邪�A�{���ɂ��܂͎肢���ς��B���N�`���͑ł��Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�ʏ�̊��҂���������v�u�~�}���҂�������܂�����҂��Ă��������Ƃ͌����Ȃ��v�Ȃǂƈ�Ì���̂Ђ����������B
�V�^�R���i�̊����g��ɂ��Ắu���܂܂ł̂悤�ɓ����𒆐S�Ƃ����s���A���𒆐S�Ƃ���ߋE���A�����A�k�C���A����Ƃ������ł͂Ȃ��B���łɑS���I�ȍL����������Ă���B�]���āA�S�����ЊQ�Ɍ������Ă���Ƃ������ƍl���āA�S���I�ȁA�Ȃ�炩�̗}���[�u�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����l�����\���ł���v�Əq�ׂ��B�����āu���̏ꍇ�́A�S���I�ȋً}���Ԑ錾���o���Ƃ��v�Ƌً}���Ԑ錾�̑S���֊g�傷��Ȃǂ̑[�u���K�v���Ƒi�����B
�S���ւ̓K�����ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ݏd�ǎ҂�����40��50��ɑ��A���N�`���̗D��ڎ�A�e�����[�N�Ȃǂɂ��l�Ƃ̐ڐG�����炷���Ƃ��厖���Ƃ�������B
���݂̃R���i��ɂ��Ắu���܂܂Ō����Ă����悤�Ȑ���͂����N���������Ƃ��Ă���Ȃ��v�Ǝw�E�B�u���N�̑�1�g��4�����炢�̊����ŁA�{���ɐl����}������悤�Ȃ��Ƃ�(����K�v������)�B���܂܂ł̃R���i�E�C���X�Ƃ͈Ⴄ�B�V�����f���^���̃E�C���X�͈Ⴄ�^�C�v�̋����E�C���X�ł���Ƃ����F���̂��Ƃɂ�����x�d�蒼���Đ����W�J������K�v������v�Əq�ׂ��B
�����r�s�m���A�R���i�͑�J�Ɓu���ʂƂ��ē����ЊQ�v�p���ɂ����y�@8/13
�����s�̏��r�S���q�m��(69)��13���A�s���Œ�����s���A���݂̐V�^�R���i�E�C���X�����g����u�ЊQ���v�ƈʒu�t�����B
��J�̉e���ȂǂŔ�Ђ��Ă���l�X�ɔz�����������Łu�����邩�A�����Ȃ����̈Ⴂ�B�J�����d�Ȃ��Đ����ɂȂ�A1�l1�l�̍s���ɂ���Đl����������B���ʂƂ��ē����ЊQ�v�B�������L����f���^���ւ̍�����s���̈ӎ������߂�Ⴆ�Ƃ��āA�u�J�͂��V���l�̋C�ۏ����A�R���i�͎������̈ӎv������Ώ����邱�Ƃ��o����B�y���~�肪�����Ă��钆�ŁA�Ƃ̒����O��������Ƃ����ĎP���������ɊO�ɂ͏o�Ă����Ȃ��B(�R���i��)�����Ȃ�����ǂ��A���̂������J�B(�f���^����)�������Ⴄ�v�B���ӊ��N���Ăъ|���A�O�o���l�Ȃǂ̊�{���������B
�O��12���̏d�ǎҐ��͑S����1478�l�A�����s��218�l�ŁA��������ߋ��ő��B�u��N�͂��߂���̃R���i�ŁA�ő勉�A�ЊQ���B�ő���̃��x���œG���Ⴄ�B�������s�����Ȃ���悤�ɂ��肢�v���܂��v�ƌ�C�����߂��B
�܂�����24���ɊJ�����铌���p�������s�b�N�ɂ����y�����B����A�ϋq�̗L���Ɋւ��Ă͌�������邪�A�w�Z�A�g�����v���O�����Ɋւ��āu�p�������s�b�N�̋��Z���������Ă͂����Ȃ��̂ł��傤���A�͂����茾���Ċ������܂���B�l�Ԃ̒���̂������A�T�|�[�g����l������B�q�ǂ������Ɍ����Ă��������B�����A������w�Z�̈ӌ�������܂��̂ŁA�b�������Ȃ���ɂȂ�܂����v�ƑO�����Ɍ�������l�����������B
����Õ���n�܂�A���̖ڂɂ͗͂Ȃ��c�ň��Ɍ������ē˂��i�ޓ��{�@8/13
�u����s�\�ȏv�u�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ��ӂ邤��펖�ԁv�u�ЊQ���Ɠ��l�ɁA�����̐g�͎����Ŏ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�B12���ɊJ���ꂽ�����s�̐V�^�R���i�E�C���X������(�V�^�x��)���j�^�����O��c�ł��ӂꂽ���Ƃ����̌������f�f���B���{�̐V�^�R���i�͎肪�����Ȃ��قLj������Ă���B12���A����������4989�l�̊����҂�����A�S���I�ɂ�1��8822�l���m�F�����2���l�ɔ����Ă���B����������2���l���銳�҂��a����T��������ŗ×{����ȂLj�Õ�������������Ă���B
���u�����閽��������Ȃ��Ȃ�v
13���A�����V���ɂ��ƁA12������Ƃ��ē����s�Ŏ���×{���̃R���i���҂�2��726�l�B�����s�̏d�NJ��҂�218�l�ŗ��ő��ƂȂ��Ă���B�S���d�ǎҐ���1404�l�ɒB���ĉߋ��ő�������1413�l(5��25��)�ɔ����Ă���B�d�NJ��҂̑啔���͂܂����N�`����ڎ�ł��Ă��Ȃ�40�`50�ゾ�Ɠ��{���f�B�A�͓`�����B����x�{���ɏ�Ԃ��������ċ~�}�Ԃ��Ă������̕a�@�������炸�X�����܂悤��������o���Ă���B13���A�����V���ɂ��ƁA��t���Ȃǎ�s���ł͍��T�ȍ~�A�a�@30�`60�J���ɓd�b�������Ȃ��ƕa����T�����Ƃ��ł��Ȃ��������Ă���B�S���a�@����c�ł́u�ʏ�ł͏����閽��������Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����ؔ������f�f���o�Ă����B
���u�ً}���Ԃł͂Ȃ��ʏ펖�ԁv
���͌����ŊJ������@��������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���{�ł͂��łɑS��47�s���{���̂����������܂�6�s�{���ɐV�^�R���i�h�u�[�u�̍ō��i�K�ł���u�ً}���Ԑ錾�v����������Ă��āA���s�Ȃ�13���{���ɂ͂��̉��̒i�K�ł���u�܂h�~���d�_�[�u�v�����{����Ă���B�����A�I�����s�b�N(�ܗ�)�ɂ���āu���l�̕��͋C�v�͊��S�ɂȂ��Ȃ�A9������15���܂ł̒����A�x�u���~�x�݁v�ŋA�Ȃ�x�ɂ̐l�g�������Ă���B���{�ً͋}���Ԓn���啝�Ɋg�債�A���Ԃ����݂�8��������9�����܂ʼn���������Ă��l���������A���{���ł��炷�łɁu�w�ً}���ԁx�ł͂Ȃ��w�ʏ펖�ԁx�v�Ƃ������}�܂ŏo�Ă��Ă�����B���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��12���A���ݓ��{���Ɋ�@�������L����Ă��Ȃ����Ƃ����O���Ȃ���u�����s�̐l�o�𒋖���킸�ً}���Ԑ錾���O��7���O���ɔ�ׂ�5�����炷�K�v������v�Ƌ����x�����b�Z�[�W���o�����B
���u�ڂɗ͂��Ȃ��v���`�̎̌��N���������O
�I�����s�b�N(�ܗ�)�ȍ~�A�V�^�R���i�̔����I�g�傪�\�z����Ă����ɂ�������炸�J�Â����s�������`�̎͌�����Ă���B�R���i�Ŋ��S�ȋx�ɂ͏o�����Ƃ��ł��Ȃ����ߑO�x���o���Čߌ㑁���ދ���u�ċx�݃��[�h�v�ő����Ă���B13���A�ǔ��V���ɂ��ƁA���͓��j�����������N3��28�����Ō�Ɋ��S�ȋx���𑗂������Ƃ��Ȃ��A12���܂�137���A���Ŏ����ɗՂ�ł���B���ƕp�ɂɑΖʂ���t���̊Ԃł́u�͂�ꂽ�悤�Ɍ�����B�ڂɗ͂��Ȃ��Ȃ����v�Ƃ����b���o��B��J���~�ς������߂��A��c���ɂ����ĂɏW���ł������q��������قǒW�X�Ƃ����ʉ�ɂȂ�ꍇ���������Ă���Ƃ����B����1948�N12�����܂�Ŗ�72���B�ǔ��V���͈��{�W�O�O���V�^�R���i��147���A���Ŏ���������A���a�ł����ᇐ��咰�����������đސw�������������グ�Ȃ���A�ߘJ�ɂ�鐛�̌��N������S�z�����B
���R���i�����u����s�\�ȏv���A���{�̓��b�N�_�E�������ɐT�d�@8/13
�ܗւ����������{�ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊������ߋ��ň��̃��x���Ŋg�債�Ă���B�����̂⎩���}���Ȃǂ��牢�B�e�����s�������b�N�_�E��(�s�s����)�̂悤�ȋ����[�u����̌��������߂铮�������邪�A�L���҂̔������s�����Ȃ��Ƃ�����A�O�@�I��ڑO�ɍT���鐛�`�̎͌����_�ŐT�d�Ȏp��������Ă��Ȃ��B
��N����̃p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�ʼn��B�e����������������ɓ��ݐ����̂ɑ��A���{�͕s�v�s�}�̊O�o���l���Ăъ|����ȂNj����͂̂Ȃ����@�ŗՂB�l���������̉p���͎���13���l�A������600���l�]����L�^���Ă���̂ɑ��A���{�̎��Ґ��͖�1��5000�l�A�����Ґ��͖�100���l���B
�ǖʂ��ς�����̂͊e���Ŗ҈Ђ�U�邤�f���^���̊����g�傾�B������4��ڂً̋}���Ԑ錾�����߂���Ă���1�J�����o�߂������A13���̐V�K�����Ґ���5773�l�A�d�ǎҐ���227�l�Ƃ�������ߋ��ő����X�V�����B�S���̊����Ґ���1���l���̓��������Ă���B
���ő勉�E�ЊQ���̊�@
�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���ۊ����ǃZ���^�[���́A���j�^�����O��c�ŁA�u����s�\�ȏv�Ǝw�E�B���r�S���q�m����13���̋L�҉�Łu���܂��ɍő勉�A�ЊQ���̊�@���}���Ă���v�Ƙb�����B
���{�͈�A�ً̋}���Ԑ錾�œs���{���m���ɑ����Ǝ҂��K�����錠����^�������A�l�̊�����d�g�݂͂Ȃ��B�ŋ߂͈��H�X�ɑ��A�A���R�[���̒�~�ƌߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k�ɏd�_�I�Ɏ��g��ł����B���߂Ɉᔽ�����ꍇ��30���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ������K������邪�A�]��Ȃ����H�X�����o�����B
�S���m�����1���ɂ܂Ƃ߂��ً}�ŁA�f���^���ɂ�銴���Ċg�傪�S���̑����̒n��ŋ}���ɐi��ł���Ǝw�E�B�O�ꂵ������s�����߁A�ً}���Ԑ錾�̋@���I�Ȕ�����^�p���P�A����ɋ����[�u�ƂȂ�u���b�N�_�E���̂悤�Ȏ�@�̂�����v�ɂ��Ă���������悤���߂��B�����}�̉��������������4���A�a�r�t�W�̔ԑg�ŋً}���Ԑ錾�ɂ��āu������ʂ��Ȃ��Ȃ����v�Ƃ��āA�������O�o�֎~�߂̖@�������������ׂ����Ƃ̔F�����������B
�i�m�m��7�A8�����ɍs�������_�����ɂ��ƁA4��ڂƂȂ錻�݂̐錾�ɂ��āu���܂���ʂ͂Ȃ��v�u�S�����ʂ͂Ȃ��v�Ƃ͍̉��킹��76���B�����s�ȂǂŎ��{���Ă���[�u�́u�ɂ�����v�Ƃ����l��49���A�u�Ó����v��41���������B
�����@�̐���
��̉��ɐ��肳�ꂽ���@����22���ňړ]�̎��R��ۏႵ�Ă��邱�Ƃ��A���{�ŋ����I�ȑ[�u�ɓ��ݐ��Q�Ƃ���Ă����B����Ō��@�́A�������O�q���̌��エ��ё��i�Ɂu�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��K�肵�Ă���B�ٌ�m�̉i��K�����͌��s���@���ł����b�N�_�E���̓����͉\�����A�����[�u�ł��邱�Ƃ���@���̐�����K�v�ƂȂ�A�Ō�̎�i�Ƃ��Ďc���ׂ����Ǝw�E����B���̕��@���܂��͖͍����ׂ����Ƃ̍l�����B
���{�͓��ʁA���s�@�̘g�g�݂őΉ�������j���B����7��30���̋L�҉�ŁA���B�ȂǍs��ꂽ���b�N�_�E���Ɋւ��ĉ�����Ɍ�����ēx�̊����g��Łu�Ȃ��Ȃ��o���������Ȃ������v�Ǝw�E���A���{�ł͓��l�̎�@�́u�Ȃ��܂Ȃ��v�ƌ�����B�u���N�`�������m�Ɍ����Ƃ����͓̂��{�ł����ʂ��o�Ă���v�Ƃ��āA����������A��l�ł������̍������ڎ�ł���悤�ȑ̐���g�ނ��Ƃ��u��ԑ厖���v�Ƙb���B
�V�^�R���i�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��12���A�����̐l����2�T�Ԃ�7���O���̖�5���ɍ팸����悤�Ăъ|����\�����B��̓I�ɂ̓f�p�[�g�̒n���H�i�����(�f�p�n��)��V���b�s���O���[���̐l�o�����͂ɗ}�����邱�ƂȂǂ��������B�R���i���ÂɊւ���Ă��Ȃ�������Ë@�ւɋ��͂����߂�悤���⎩���̂ɑ������B
���R���i���Â̈�Ï]���ҁA�Z���ڐG�҂̐������ɘa�@8/13
�V�^�R���i�E�C���X�̎��Âɂ������Ï]���҂����N�`���ڎ���I���Ă���ꍇ�A�Z���ڐG�҂ƔF�肳��Ă�14���Ԃ̎���ҋ@�������t���Ŋɘa����ƁA�����J���Ȃ�13���A�s���{���Ȃǂɒʒm�����B�����s�ȂNJ������g�傷��n��ň�Â̕N��(�Ђ��ς�)���[���ɂȂ钆�A�S������m�ۂ���˂炢������B
2��̐ڎ��A���ʂ�������Ƃ����14���Ԃ��o�߂��Ă���K�v������B�R���i���Âɂ������Ă���A�R���i�a���ɋΖ����Ă��Ȃ��Ă��悢�B�ǏȂ��A�Ɩ��O�ɖ����APCR������R����ʌ����ʼnA�����m�F���邱�ƂȂǂ������ɁA�Ζ����\�ɂ���B�}�X�N���w���łȂǂ̊�{�I�Ȋ�����̓O���A�ʋΎ��Ɍ�����ʋ@�ւ��g��Ȃ����ƂȂǂ����߂�B�u�ً}�I�ȑΉ��v�Ƃ��Ă���B
��Ï]���҂̔Z���ڐG�҂̈����́A���J�Ȃ̐��Ƒg�D��11���ɋc�_�B�Ƒ��炪�������Ĉ�Ï]���҂��Z���ڐG�҂ƂȂ�A���ꂩ�璷�����E����ƁA��Â̒Ɏx�Ⴊ�o��Ƃ��āA���̏����̂��Ɗɘa����悤���߂鐺���オ���Ă����B
�����Ɂc �V�^�R���i�����A1��2���l�����ɑ��R�@8/13
�����g��̑����V�^�R���i�E�C���X�B13���A�����s�ʼnߋ��ő��ƂȂ�5773�l�Ɣ��\���ꂽ�ق��A�_�ސ쌧��2281�l�ȂǑS���e�n�ōő��̊����Ґ������X�Ɣ��\���ꂽ�BNHK�͌ߌ�5��40���߂��Ɂu1���̊����҂�2���l�����v�ƃj���[�X������o���ASNS�ł́u2���l�v���g�����h���[�h�ɁB�u1����2���l���R���i�ɂ�����Ƃ��A�C�O���x���ɂȂ��Ăċ��낵������v�Ȃǂ̐����オ�����B
�c�C�b�^�[�ł́u�V�����A2���l�c�Ȃ�˂��v�u�N���N�n�̑�3�g�ł��s�[�N��8000�l�ɓ͂��Ă��Ȃ������̂��l����ƁA���낵�����Ԃł��v�u1���l�s���Ă��甼����2���l���B���̃y�[�X�Ȃ痈���͖���5���l�Ƃ��ɂȂ肻���v�u1��2���l�o����50����100���l�ł���A���������Ă����������Ȃ����炢����ˁv�Ȃǂ̃R�����g�����X�ƁB
�܂��u2���l�����đƏo��Ȃ��Ĉ�N���������Ƃ��������ĂȂ��B���C���Ȃ��Ȃ玫�߂Ă������������B�{�C�ō����̖��Ɛ�����D�悵����������ӎu�̂���l�ɕς���Ă��������v�ƗL���ȑo���Ȃ��������Ɍ����������˂�����ꂽ�B
���u�����g��̔��Ȃ��Ȃ���A�����̐��͂��Ȃ��v�@8/13
�����ŏ��߂ĐV�^�R���i�E�C���X�����҂�2���l�m�F���ꂽ13���A���`�̎́A���@�ŋL�Ғc�̈͂ݎ�ނɉ������B�����͂���܂ł̎��g�݂ւ̑��������߂�ꂽ�̂ɑ��A�u�����g�A���ȕ]�����邱�Ƃ͙G�z���Ǝv���v�ƕ]����������B
�L�҂́u�����g�������������܂ł̑����┽�Ȃ��Ȃ���A�����ɐ����̐����͂��Ȃ��B����܂ł̎��g�݂����ʂ��ǂ̂悤�Ɏ��ȕ]������Ă��܂����v�Ǝ��₵���B
����ɑ��A�����́u���ȕ]�����邱�Ƃ͙G�z���v�Ƃ�����ŁA�u��͂胏�N�`�����Ƃ������ƂŁA�l���̗}���Ɠ����ɁA�����������Ƃ���������S�͂Ŏ��g��ł��Ă��܂��v�Ƃ���܂Ői�߂Ă������N�`���ڎ�̎��g�݂������B�u�����̊F����ɁA��ς��s�������낤���Ǝv���܂����ǂ��A���N�`���ł�10���̏��{�܂łɂ́A���{�����S����2��A8���̊�]������ɑłĂ�悤�ȑԐ�������Ă���B�Ƃɂ����S�͂Ŏ��g��ł������v�Əq�ׂ��B
�܂����́u�����̈�Ñ̐��͋ɂ߂Č������v�Ɗ�@�����������B���̏�Łu�����̖�����邱�Ƃ����{�̍ő�̐Ӗ��v�Ƃ��A����×{���̊��҂ւ̎_�f���^���\�Ƃ��邽�߂Ɏ_�f�X�e�[�V�����̑Ԑ����\�z����悤�W�t���Ɏw���������Ƃ𖾂炩�ɂ����B
����Ɂu���~�x�݂͊����h�~�̑厖�Ȏ������B�A�Ȃ◷�s���ɗ͔����A�s�v�s�}�̊O�o���ł��邾���T���Ăق����v�Əq�ׂ��ق��A�u���Ǝ{�݂Ȃǂ̐l���}���ɂ���������g�ށv�ƌ�����B
�����ƋL�Ғc�Ƃ̎�Ȃ����
�p�@�{���A�����̃R���i�����Ґ����ߋ��ő����X�V�����B�S���̃R���i�����Ґ��͖{���A2���l���͂��߂Ē������B�����͏d�ǎҐ����ߋ��ő��ƂȂ�A���Ƃ���͋~���閽���~���Ȃ��ɂȂ����Ƃ��������オ���Ă�B���{�̌���F���́H
�`�@�܂��e�n�ŁA�ߋ��ő�̊����Ґ��������Ă���B����ɔ����āA�d�ǎҐ������������Ă���B�����̈�Ñ̐��A�ɂ߂Č������ɂ���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă���B�����������ɂ����āA�����̐�������邱�ꂪ���{�̍ő�̐Ӗ��ł���܂��B�����������ŁA�W�t���Ƌc�_�����B����ɂ��銳�҂ɂ́A�K���A��������悤�ɂ��A�����̂ƘA�g�����ėႦ�Ύ_�f�̓��^���K�v�ɂȂ����ꍇ�A�_�f�X�e�[�V������ݒu���āA�����őΏ�����B���������̐��𑬂₩�ɍ\�z����悤�ɊW��b�Ɏw�������B�܂��A���ɏd�lj��h�~�Ɍ��ʂ�����ƌ�����A�V������A���a�R�̖�͈�Ë@�ւ̒��Ŏ��Âł���悤�ɂ���B�����ɁA���̂��߂̏W���I�Ɏg�p�ł��鋒�_������āA�����ł��s�����Ƃ��ł���悤�ɁA���������̐����߂������ɐ���������B����̕��ȉ�A���g��̒��āA�W�c�̂Ƃ�������A�g���āA���Ǝ{�݂Ȃǂɂ��l���̗}���͂���������g��ł��������B���~�x�݂̕����A��������������B�����������ɂ����āA������h�~����ɂ߂đ厖�Ȏ����ł�����B�����̊F����ɂ͂��s�ւ������܂�����ǂ��A�A�Ȃ◷�s�A�ɗ͔����Ă��������āA�����āA�s�v�s�}�̊O�o���ł��邾���A�T���Ă��������悤�ɁA���{�Ƃ��Ă����肢��\���グ�����B
�p�@4��ڂً̋}���Ԑ錾�ł����A���ʂ����܂�o�Ă��Ȃ����A�l�������炷���ƂɊւ��āA�����V���ȑ�Ƃ����͎̂��Ȃ��̂��B
�`�@���A���\���グ�܂����悤�ɁA��Ñ̐��͂�������Ԑ����c�_���āA�����������ƂɑS�͂�s�����A�K��������ɂ�����ɂ́A�A��������悤�ȑ̐��������̂ƘA�g���Ă���Ă����B�d�lj��ɔ��Ɍ��ʂ�����Ƃ�����A���̒��a�R�̖�A��������������Ώۂ̊��҂̊F����ɂ́A���^�ł���A���������̐����\�z���Ă���B
�p�@�����g�������������܂ł̑����┽�Ȃ��Ȃ���A�����ɐ����̐����͂��Ȃ��Ǝv���܂��B����܂ł̎��g�݂ƁA���̌��ʂ𑍗������g�A�ǂ̂悤�Ɏ��ȕ]�����邩�B
�`�@�����g�A���ȕ]�����邱�Ƃ͙G�z���Ǝv���B���{������Ă��Ă���A�Ⴆ���̃��N�`���ڎ�A����҂ɂ�7�������ς��ŁA�S�ē��^����A�������������������������B�܂�1��100�����ڎw���Ƃ����������B�����130����Ƃ��A���邢�͂��̊�ƐE��Ȃǂɂ̓v���X20����Ƃ��B���������`��1�l�ł������̕���1���������ڎ������B����Ɠ����ɁA���E�Ń��b�N�_�E��������A�O�o�֎~�ɔ��������Ă��A�Ȃ��Ȃ���邱�Ƃ��ł��Ȃ���������Ȃ��ł����B����ɑ��đΉ����邽�߂ɁA��͂胏�N�`�����Ƃ������ƂŁA�l���̗}���Ɠ����ɂ�������S�͂Ŏ��g��ł��Ă��܂��B�����̊F����ɁA��ς��s�������낤���Ǝv���܂����ǂ��A���N�`���ł�10���̏��{�܂łɂ́A���{�����S����2��A8���̊�]������ɑłĂ�悤�ȑ̐�������Ă܂�����B�Ƃɂ����S�͂Ŏ��g��ł������A���̂悤�Ɏv���܂��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���V�^�R���i �����s5094�l�����m�F �y�j���ő��@8/14
�����s���ł�14���A5094�l�̊������m�F���ꂽ�ق��A�s�̊�ŏW�v�������傤���_�̏d�ǂ̊��҂�245�l�ŁA�ߋ��ő����X�V���܂����B�s�̒S���҂́u�V�K�̊����҂��ꍏ���������炳�Ȃ��Əd�ǎ҂����炸�A�S���Ȃ�l���o�Ă���\��������v�Ƃ��Ă��܂��B
�����s�́A14���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��5094�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B5000�l����̂�2���A���ł��B�܂��A1�T�ԑO���528�l�����āA�y�j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B14���܂ł�7���ԕ��ς�4231.1�l�ƂȂ�܂����B�O�̏T�Ɣ�ׂ�8.7�������܂����B
�s�̒S���҂́u���̂��A�ߋ��ő����X�V���A���傤��5000�l�ȏ�B���������K�͂̊����҂������ƍő����X�V���Ă��w����ς�ȁx�Ǝv���Ă��܂���������Ȃ����A�Ƃ�ł��Ȃ����ƔF�����Ăق����B�V�K�̊����҂��ꍏ���������炳�Ȃ��Əd�ǎ҂����炸�A�S���Ȃ�l�����ꂩ��o�Ă���\��������v�Ƙb���Ă��܂��B
14����5094�l�̔N��ʂ́A10�Ζ�����271�l�A10�オ468�l�A20�オ1568�l�A30�オ1079�l�A40�オ824�l�A50�オ583�l�A60�オ164�l�A70�オ63�l�A80�オ49�l�A90�オ24�l�A100�Έȏオ1�l�ł��B
�����o�H���킩���Ă���1941�l�̓���́u�ƒ���v���ł�����1305�l�A�u�E����v��270�l�A�u�{�ݓ��v��93�l�A�u��H�v��51�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
���̂����u��H�v�ł́A20��̉�Ј��̏������F�l�̉Ƃ�5�l�ŐH�������A5�l�S���̊������m�F���ꂽ�P�[�X������Ă��܂��B
�s�̒S���҂́u���߂̂��~�Őe�ʂ̉ƂɏW�܂�����A�F�l�Ɨ��s�ɍs�����肵�Ċ��������P�[�X�����ۂɕ���Ă���B���s��A�Ȃ͍T���A�l�Ƃ̐ڐG���Ȃ������Ƃɗ͂����đ�����Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B
�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̊֘A�ł͊O���l�̃��f�B�A�W��1�l�A���{�l�̈ϑ��Ǝ�1�l�̂��킹��2�l�̊������m�F����܂����B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A27��4837�l�ƂȂ�܂����B
����A14�����_�œ��@���Ă���l��3762�l�ŁA13�����35�l�����A8���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��63.0���ł��B
�܂��A�s�̊�ŏW�v����14�����_�̏d�ǂ̊��҂�13�����18�l������245�l�ŁA5���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B�s���A���݊m�ۂ��Ă���d�NJ��җp�̕a���̎g�p����62.5���ƂȂ�܂����B
�������s �ی����̋Ɩ��Ђ����ŔZ���ڐG�҂Ȃǂ̒������k���@8/14
�V�^�R���i�E�C���X�̋}���Ȋ����g��ŕی����̋Ɩ����Ђ������Ă��邽�߁A�����s�́A�ی������s�������҂̔Z���ڐG�҂Ȃǂ̒����̏k�������߂����Ƃ��W�҂ւ̎�ނŕ�����܂����B�e�ی����͊��҂̌��N�Ǘ��ɂ��d�_��u���Ƃ��Ă��܂��B
�}���Ȋ����g��ɔ����A���@��������q���Ď���ҋ@�̊��҂����������Ă��đ����̕ی����ł͂��̑Ή��ɒǂ���ȂǁA�Ɩ����Ђ������Ă��܂��B
���̏��āA�����s�́A�e�ی����ł͊��҂̕a���d�lj����X�N��c�����āA���₩�ɓK�Ȉ�ÂɂȂ��邱�Ƃɏd�_��u���A�Z���ڐG�҂⊴���o�H�ׂ�ϋɓI�u�w�����́u�D��x���l�����Č��ʓI�������I�ɍs���v�Ƃ�������������10���t���œs���̕ی������Ăɏo���Ă������Ƃ�������܂����B
�s�̊W�҂ɂ��܂��ƁA�ϋɓI�u�w�����̑Ώۂ́A�����҂Ɠ�������Ƒ��̂ق��A�w�Z�A��Ë@�ցA����ɍ���Ҏ{�݂ȂǂɂƂǂ߁A�E����H�ȂǂŊ��������ꍇ�ɂ́A���͂ւ̒����͍s��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�ϋɓI�u�w�����́A�����̉\��������l�Ɏ���őҋ@���Ă��炤�ȂǁA�傫�ȃN���X�^�[�����Ȃ���ɖ𗧂Ă��Ă��܂������A�����̊g��ɔ����Ɩ��̂Ђ����ō�ʌ����k�������߂Ă��܂��B
���������Ή��ɂ��ē����̒�����ی����̋g��G�v���N���i�ے��́u����×{�Ōċz�����i���銳�҂ւ̑Ή��Ŏ��t�ŁA��ނ����Ȃ����f���Ǝv���v�Ƙb���Ă��܂����B
���������A�V�^�R���i116�l�����@���ʍő�1224�l�A���v7056�l�@8/14
����13���A������116�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B12���ɗz���Ɣ��������B8���̊����Ґ���1224�l�ƁA���ʂōő�������5����1179�l���2�T�Ԃŏ������B
����1�T��(6�`12��)�̐l��10���l������̐V�K�z���Ґ���40�D90�l�Ə��߂�40�l��ɏ��A�}���Ȋ����g��Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B
�����̊����m�F�͉���7056�l�ŁA7000�l�����B�l��10���l������̗×{�Ґ���54�D71�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����X�V�����B����Ŋ������������̎w�W�̂����A�V�K�z���Ґ��Ɨ×{�Ґ��A�a���g�p��(66�D7��)�̎O���X�e�[�W4(�����I�Ȋ����g��)�A���@���Əd�ǎҗp�a���g�p���APCR�z�����̎O���X�e�[�W3(�����҂̋}��)�̐����ɂ���A��@�I�ȏ������Ă���B
12�����݂̓��@�Ґ��͏d��14�l���܂�398�l�ŁA136�l���h���×{���A321�l������×{���Ă���B�×{�撲������155�l���܂߂��×{�Ґ��́A1010�l�ɏ���Ă���B���́A�����͂̋����ψي��u�f���^���v�̍L����₨�~���ԑO�̐l���̑����������g��̔w�i�ɂ���Ƃ��āA�����ɗ��s��A�Ȃ̌������~�܂��͉��������߂Ă���B
�z���Ɣ�������116�l�̓���́A���킫�s46�l�A�S�R�s29�l�A�����s9�l�A�{�{�s7�l�A��Îᏼ�s6�l�A��{���s3�l�A�{���A�쑊�n�A�֒�A�����̊e�s������2�l�A��ʁA��Í≺�A��Ô����A�ʐ�A�O�t�A�L��̊e������1�l�A���O2�l�B46�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B
����117���ڂ̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�������������k�̎��Ə��ŏ]�ƈ�1�l�̊�����������A�N���X�^�[�͌v39�l�Ɋg�債���B12���܂ł�45�l���މ@�A9�l���h���×{�{�݂�ޏ����A54�l�̎���×{���������ꂽ�B
���V�^�R���i�@���A�ۈ�{�݂ŃN���X�^�[���@�����犴����5�l�Ɂ@��錧�@8/14
��錧��14���A�����̐V�^�R���i�E�C���X�����̔��\�ŁA�}���s���̕ۈ�{�݂Ə푍�s���̎��Ə��ŐV���ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)�����̉\��������Ƃ̔F�����������B
���ɂ��ƁA�ۈ�{�݂ł͐V���ɉ���1�l�̊�����������A�{�ݓ��̊����҂͐E��3�l���܂ތv5�l�ɑ������B���Ə��ł��V����1�l���z���ƂȂ�A�]�ƈ��̊����͌v5�l�ƂȂ����B���͂��̎��Ə��ɂ��āA�u���i�̐����̏�ł��ڐG�������Ƃ݂���v�Ɛ����B
���̂ق��A�푍�s���̍��Z�ł͉ۊO���Ƃ��Ă������k1�l���z���ƂȂ�A���ƎQ�����k�̊����͌v7�l�ƂȂ����B���Ύs���̑�w�o�X�P�b�g�{�[�����ł������҂�1�l�����A�v32�l�Ɋg�債���B
����^���Ǝ{�݂̃t���A�ɓ��ꐧ�����@���A���̊�@�ɒ��ʁc��ʌ��@8/14
��ʌ���13���̐V�^�R���i�E�C���X���{����c(���ʊJ��)�ŁA��^���Ǝ{�݂̃t���A���Ƃ̓��ꐧ���O��ȂǁA�ً}���Ԑ錾�ɔ��������[�u�̋��������߂��B�܂��A��쌳�T�m�����s��1�s3���m���͓����A�l���}�������͂ɐi�߂邽�߁A��{�I�Ώ����j�̕ύX�𐭕{�ɗv�������B������2������31���܂ŁA�ً}���Ԑ錾�̑Ώۋ��ƂȂ�A�s�v�s�}�̊O�o���l���ނ������H�X�ɋx�Ƃ�v������ȂNJ����g��h�~����s���Ă��邪�A13���ɂ͌����̐V�K�z���҂��ߋ��ő���1696�l�ƂȂ�ȂǁA�����g��Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B
���m���͋L�Ғc�Ɂu�������͍��A���̊�@�ɒ��ʂ��Ă���B����ȏ㊴���g�傪�����ꍇ�A��Õ���ɂȂ���\�����o�Ă��Ă���B�����A���Ǝ҂ɂ͍��̏��l���A���͂����肢�������v�Ɗ�@�������������B
���͏��ʐ�1�畽�����[�g���ȏ��1150�X�܂�ΏۂɁA�V�^�R���i���[�@�Ɋ�Â��A��K(�t���A)���Ƃɗ��X�q���ɖZ���̔������x�ƂȂ�悤�A���ꐮ���̓O������߂�B���ԏ�̗��p���ɖZ���̔������x�̑䐔��ڈ��Ƃ��A���ԏꐮ���̓O������߂�B
4�s���m���������N���o�ύĐ��S�����ɒ�o�����v�����ł́A12���̐��{���ȉ�̒��A�S�ݓX�̐H���i������V���b�s���O���[���Ȃǂւ̐l�o�����͂ɗ}�����邽�߂̗L���ȑ[�u�����{�ł���悤�A���{����{�I�Ώ����j��ύX����悤�v���B�l���}���̂��ߓs���{�����V���ɍs���[�u�ɁA�����S�ʓI�����[�u���u���邱�Ƃ�A�s���{���Ԃ��܂����������ړ������炷���߁A�q��@��S���Ȃnj�����ʋ@�ւ̗��p�}�����{������u���邱�Ƃ����荞�܂ꂽ�B
7������13����1�T�Ԃ̌����V�K�z���҂�9590�l(1������1370�l)�B�V�K�����ҋ}���ɔ����A��Ë@�ււ̕��S�������Ă���A12�����_�̌����m�ەa���g�p����68�E7��(1159�l�^1688��)�A�����d�ǎ҂�62�E9��(107�l�^170��)�ƂȂ��Ă���B
����A���c���F�����璷��13���A�������k�̊������}�����Ă��邱�Ƃ���A�������Z�̉ċx�ݒ��̕������ɂ��āA����R���N�[���ɏo�ꂷ��ꍇ���������������݂̏T4���ȓ�����T2���ȓ��Ƃ��A���K�����͋֎~����ƕ\���B�s�������ςɂ͌����w�Z�ɏ������Ή���v�����A�����w�Z�ɂ����͂����߂�Ƃ����B�@
���É�����318�l�@�����}�g�傪�����@3���A����300�l���@8/14
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂́A14���V����318�l�m�F����܂����B300�l���3���A���ł��B14���́A�l���s��71�l�A�É��s��65�l�ȂǁA���킹��318�l�̊������m�F����܂����B12����354�l�A13����379�l�ɑ����āA300�l����̂�3���A���ƂȂ�܂��B
�l���s�ŋN���Ă���w�K�m�̃N���X�^�[�͉Ƒ��Ȃ�2�l�̊������V���ɕ�����A��A�̊����҂�2���������܂߂�57�l�ƂȂ�܂����B
�O���s�̎��Ə��ł́A���킹��5�l�̗z���҂��������A���͐V���ȃN���X�^�[�ɔF�肵�Ă��܂��B���C��ɎQ�������]�ƈ��𒆐S�ɁA�������L�����Ă���Ƃ������Ƃł��B
�a���̎g�p���́A����54�D3�p�[�Z���g�A����59�D6�p�[�Z���g�A����61�D6�p�[�Z���g�A���S�̂�58�D2�p�[�Z���g�ƂȂ��Ă��܂��B
���V�^�R���i�����A����100�l���@�f���^���Ŋg��@���쌧�@8/14
���쌧���Ŋm�F���ꂽ�����Ґ���13���A109�l�ɏ��A1��������̐l���Ƃ��Ă͏��߂�100�l�����B���͊����͂̋����f���^���̊g�傪�v���Ƃ݂Ă���B���́A�V���ɐz�K������Ŏ�ނ������H�X�ɋx�Ƃ�c�Ǝ��ԒZ�k��v�����邱�Ƃ����߂��B
13���Ɍ��ƒ���A���{�s�����\�����V�K�����҂́A10�Ζ����`80���109�l�B84�l������12��������A2���A���ʼnߋ��ő��̐l���ƂȂ����B�����̊����Ґ��͉���6037�l(�ėz���҂��܂�)�B
13���̐V�K�����҂̓���́A�d��1�l�A������2�l�ŁA�ق��͌y�ǂ����Ǐ�B���ɂ��ƁA13���[���_�ŏd�ǎ҂�1�l�A�����ǎ҂͌v44�l�Ƃ����B
�܂��A13�����\���̂��������o�H�s���҂�42�l(39%)�ɏ�����B����7�`13���ɔ��\���������҂̂����A���߂Ɍ��O�Ƃ̉������������̂�66�l�ŁA���̂���20�l���u�A�ȁv�𗝗R�ɂ��Ă����B���́A���O�Ƃ̉����������g��̈���Ƃ݂Ă���A�A�Ȃ��T����悤�Ăт����Ă���B
13�����\�̐V�K�����҂ɂ́A������{�Ɉɓߕی����Ǔ��ł������h���{�݂ł̍s���̎Q����4�l���܂܂��B���̍s���ł́A���ł�1�l�̊������m�F�B�v��50�l�̎Q���ґS�������O����K��Ă����Ƃ����B�s���̒��Ń}�X�N���O�������ԑт��������Ƃ����A�������i�߂��Ă���B
�܂��A���{�s�̊�����12�l�̂���4�l�́A����܂�6�l�̊������������Ă������s���̍��Z�̉^�����̐��k�B�����̊����҂͌v10�l�ɂȂ����B
��ނ������H�X��ΏۂɁA�����x�Ƃ⎞�Z�̗v����V���ɏo���̂́A�z�K�A���J�A����A���z�K�A�x�m���A����6�s�����B���Ԃ�16�`26���B�v���ɉ������ꍇ�A�����X�܂Ȃ甄��グ�K�͂ɉ�����1��������2�E5���`7�E5���~�̋��͋����x������B����13���A�z�K����ɑ��錧�Ǝ��̊����x�����x�����u5�v(���ʌx��U)�Ɉ����グ���B
���A����100�l�ȏ�@���쌧�Ŋ����ҋ}���@�O�T353�l�����T489�l�@8/14
14���A���쌧���ŐV����100�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��܂����B1��������̐V�K�����҂�2���A����100�l�ȏ�ƂȂ�܂����B
�����ł������g�傪�~�܂�܂���B���T1�T��(8��8������14��)�ɔ��\���ꂽ�V�K�����҂�489�l�őO�T��353�l��傫������܂����B12���ɉߋ��ő���84�l���m�F����A��13���ɂ͏��߂�100�l���܂����B
���傤14�����\�̐V�K������100�l�̂����A�����o�H�s����31�l��3���ȏ���߂Ă��܂��B���O�����̂���l��9�l�B���O�ݏZ�҂�13�l�ŁA�u���O�R���v�Ƃ݂��銴�����ڗ����Ă��܂��B���O�����̂́A���������l�Ƃ̐ڐG�ɂ��A�ƒ���A�E����Ȃǂł̊����g��ł��B
�����m����13���A�u����܂łɂȂ��傫�ȐV�^�R���i�̔g�����Ă���v�Ƌ�����@���������A����܂ňȏ�Ɍ��i�Ȋ�����ւ̋��͂������ɋ��߂�ƂƂ��ɁA�u�����ւ̋A�ȁA���O�Ƃ̉����͂ł��邾���T���Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
�����������͉ߋ��ő�2677���c�V�^�R���i �ΐ쌧�ŐV�K������86�l�@8/14
�ΐ쌧�͐V����86�l���V�^�R���i�Ɋ������A1�l�����S�����Ɣ��\���܂����B���������͉ߋ��ő��ł��B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂͋���s�⏬���s�ȂǂɏZ��1�Ζ�������70��܂ł̒j��86�l�ł��B����͊����o�H��������Ȃ��l��31�l�B�Z���ڐG�҂Ȃǂ�45�l�B����s���������s��֘A�̃N���X�^�[��10�l�ł��B����������2677���Ɖߋ��ő��ƂȂ�܂����B���̂�������s���������s��֘A�ł�382���̌������s���A���̂قƂ�ǂ�12������n�܂�����Ăo�b�q�����ł��B
���ɂ��܂��ƁA��Ăo�b�q�����̌��ʂ��܂��o�Ă��Ȃ��l��200�l�قǂ���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�V����1�l�̎��S���m�F����܂����B���̃��j�^�����O�w�W�͐V�K�����Ґ��ƌo�H�s���Ґ����X�e�[�W4�ƂȂ��Ă��܂��B
���A�Ȃ����Ƒ��炪�N���X�^�[�@����123�l�����@8/14
���Ɗs��14���A����27�s���ȂǂŌv123�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B�V�K�����҂�100�l����̂�4���A���B�����҂͗v1��562�l�ƂȂ����B
�����҂̂����A20���48�l�A10���22�l�Ǝ�҂������A30��ȉ��͖�8�����߂��B60��ȏ��2�l�������B
13�����_�̕a���g�p���͑O����4�E8�|�C���g����37�E2���ŁA9���A���ŏ㏸���Ă���B�h���×{�{�݂�318�l���������A5��23���ȗ�83���Ԃ��300�l�����B14�����_�̏d�ǎ҂�4�l�̂܂܁B
14���͐V���ɃN���X�^�[(�����ҏW�c)3�����m�F�����B���s�{�Ɖ��ꌧ��������ɋA�Ȃ����l�₻�̉Ƒ��̌v5�l�Ɋ������L�������B�{���s�̐E��֘A�ł�6�l�̊��������������B���ɂ��ƁA���̂���5�l��10�l�ŐH������J���Ă����B���̑��A���Q�s�̉Ƒ��֘A��5�l�����������B
�����N�������̖x�T�s�����́u�A�Ȃ�E��ȂǂŐH���ɂ�銴�����ڗ����Ă���B���̂܂܊����҂�����������A���@�ł��Ȃ����Ԃ��N���肤��B�����Ŋ����̊g���h���ł��������v�Ƌ��������B
�g�債���N���X�^�[��8���B�e�����s�̕ۈ牀��֎s�̕����{�݂ł͗��p�҂̉Ƒ���4�l�̊������V���ɕ�����A�v23�l�ƂȂ����B�������s�̏K���������������Ă͐V����4�l�̊������������A�v10�l�ƂȂ����B
�f���^���̉\��������u�k452�q�ψي��v�̗z���҂͐V����49�l���m�F���A�v137�l�ƂȂ����B
�V�K�����҂̋��Z�n�ʂ́A�s23�l�A�������s17�l�A�e�����s13�l�A��_�s12�l�A���Ð�s6�l�A����s5�l�A���Z���Ύs�A���s�A�S��s���e4�l�A�֎s�A�H���s�A�y��s�A�H���S�}�������e3�l�A�R���s�A�H���S��쒬�A�����S�������A���S�䐓�����e2�l�A���Z�s�A���Q�s�A�b�ߎs�A�{���s�A�C�Îs�A�{�V�S�{�V���A�����S�֔V�����A���ΌS�x�����A���S���@���A���S���S�Ò����e1�l�B�����s�A���m�����e2�l�A�k�C��1�l�B
�N��ʂ�10�Ζ���6�l�A10��22�l�A20��48�l�A30��19�l�A40��15�l�A50��11�l�A60��A80�オ�e1�l�B
���w���ۈ珊�ŃN���X�^�[�g��A�ߋ��ő�179�l�����@����@8/14
���ꌧ��14���A�V����10�Ζ����`90�Έȏ�̒j��179�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����Ґ��̉ߋ��ő�(12����164�l)���X�V�����B�����ǂ�1�l�ȊO�͌y�ǂ����Ǐ�B����×{�҂͑O������172�l�����āA456�l�ɂȂ����B�����ł̊����m�F�͌v7505�l�B
���Z�n�ʂł́A��Îs71�l�A���Îs19�l�A���ߍ]�s17�l�ȂǁB�N���X�^�[(�����ҏW�c)�֘A�ł́A���ߍ]�s�̊w���ۈ珊�u�\�o�쓌���ǂ��̉Ɓv�Ŏ���1�l�̊������������Čv36�l�ƂȂ����B
�܂��A���̓f���^���̋^��������E�C���X�������̒j��33�l����V���Ɍ��o����A�v363�l�ɂȂ����Ɣ��\�����B
�����s�s���̍���Ҏ{�݂ŃN���X�^�[�g��A2�l�������ǁ@8/14
���s�{�Ƌ��s�s��14���A���A�w������90��ȏ�̒j���v378�l���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������A�Ɣ��\�����B238�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B�Ǐ��2�l�������ǁA301�l���y�ǂ����Ǐ�ŁA75�l���������B�{���̊����҂�2��2169�l�ƂȂ����B
�s���\����229�l�ŁA���Z�n�͎s��219�l�̂ق��A�F���s5�l�A���{3�l�A���c�ӎs�Ǝ��ꌧ���e1�l�B���ɃN���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă��鋞�s�s���̍���Ҏ{�݂Ŋ����҂�2�l�����A�v9�l�ƂȂ����B13���܂ł�8�l�̊������������Ă���s���̉^���{�݂�1�l�̊������V���ɕ��������B
�{���\����149�l�B���Z�n�͉F���s29�l�A�T���s22�l�A���ߎs19�l�A��z�s14�l�A�������s�Ɣ����s���e12�l�A���s�s8�l�A���c�ӎs�ƖؒÐ�s���e7�l�A�����s4�l�A���ؒ�3�l�A���{�Ƌ��O��s���e2�l�A���m�R�s�A�����s�A��O�s�A��R�蒬�A�v��R���A�F���c�����A�^�Ӗ쒬�A�_�ސ쌧���e1�l�������B�N���X�^�[���������Ă��闤�㎩�q����v�ے��Ԓn(�F���s)�Ŋ����҂�1�l�����v25�l�A�����߈㐽��a�@(���ߎs)��6�l�����v21�l�A��Q�Ҏ{�݂����ڂ̊w��(��O�s)��1�l�����Čv18�l�ɂȂ����B
�����s�Y�����̃N���X�^�[�g��A�V���ɍ���Ҏ{�݂ł��@���s�@8/14
���s�{�Ƌ��s�s��13���A10�Ζ�������90�Έȏ�̒j���v450�l���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������A�Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����Ґ������߂�400�l���A3���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B272�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B�Ǐ��359�l���y�ǂ����Ǐ�ŁA91�l���������B�{���̊����҂�2��1791�l�ƂȂ����B
�s���\����266�l�ŁA���Z�n�͎s��258�l�̂ق��A���{2�l�A�F���s�Ƌ��c�ӎs�A�����s�A���ꌧ�A�ޗnj��A��t�����e1�l�B���ɃN���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă��鋞�s�Y����(�R�ȋ�)�ŐE��1�l�̊�����������A�����҂͌v9�l�ƂȂ����B13���܂ł�7�l���z���ƂȂ����s���̍���Ҏ{�݂ŃN���X�^�[�̔�����F�肵���B
�{���\����184�l�B���Z�n�͉F���s29�l�A�T���s�ƒ������s���e21�l�A��z�s19�l�A���ߎs18�l�A���s�s14�l�A�����s13�l�A�ؒÐ�s11�l�A���c�ӎs9�l�A�����s6�l�A�v��R��4�l�A��O�s3�l�A���m�R�s�Ƒ�R�蒬�A���ؒ��A���O�g���A���{�A�_�ސ쌧���e2�l�A�����s�Ƙa�����A�^�Ӗ쒬�A���ꌧ���e1�l�������B���㎩�q����v�ے��Ԓn(�F���s)�Ŋ����҂�2�l�����v24�l�A�����߈㐽��a�@(���ߎs)��2�l�����v15�l�ɂȂ����B
�܂��A�{��6��28���`8��1���̕{���V�K�����҂̂���80�l����A�C���h�R���̕ψي��u�f���^���v��lj��Ŋm�F�����A�Ɣ��\�����B�f���^���̗z�������͗v125�l�ƂȂ����B
��������a�@�ȂǂŃN���X�^�[�g�呱���@�V�^�R���i�E���s�@8/14
���s�{�Ƌ��s�s��14���A�V���ɒj���v378�l���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������A�Ɣ��\�����B�{���̊����҂�2��2169�l�ƂȂ����B
�{���\����149�l�B���Z�n�͉F���s29�l�A�T���s22�l�A���ߎs19�l�A��z�s14�l�A�������s�Ɣ����s���e12�l�A���s�s8�l�A���c�ӎs�ƖؒÐ�s���e7�l�A�����s4�l�A���ؒ�3�l�A���{�Ƌ��O��s���e2�l�A���m�R�s�A�����s�A��O�s�A��R�蒬�A�v��R���A�F���c�����A�^�Ӗ쒬�A�_�ސ쌧���e1�l�������B�N���X�^�[���������Ă��闤�㎩�q����v�ے��Ԓn(�F���s)�Ŋ����҂�1�l�����v25�l�A�����߈㐽��a�@(���ߎs)��6�l�����v21�l�A��Q�Ҏ{�݂����ڂ̊w��(��O�s)��1�l�����Čv19�l�ɂȂ����B�s���\����229�l�B
���V�^�R���i���������̑��́c�ߋ��ő�1828�l�m�F�@8/14
���{��14���A�V����1828�l�̐V�^�R���i�E�C���X�̊������m�F�����Ɣ��\���܂����B�N��ʂōł������̂�20���487�l�A������30���329�l�A40���277�l�A�܂����A�w����111�l�A�A�w��72�l�̊������m�F����Ă��܂��B�S���Ȃ����l��0�l�A�d�ǎ҂̊��҂͐V���Ɋ�b�����̂Ȃ�40��j��3�l���܂�138�l�ŁA�d�Ǖa���^�p����43.4���A�܂��y�ǁE�����ǂ̊��҂�1706�l�ŕa���^�p����71.5���ƂȂ��Ă��܂��B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g����A���̕S�ݓX�ł́A�ꕔ�����ւ̓���𐧌����铮�����L�����Ă��܂��B��}���߂��{�X�ł́A���{�̕��ȉ�̒Ȃǂ���13������A�n��2�K�E�n��1�K�ɂ���H�i�����ւ̓���𐧌�����Ή����n�߂Ă��܂��B�n���̃t���A�s���̃G�X�J���[�^�[�Ȃǂ��~���A�q��1�K�̓���̓��������̂ݐH�i�����ɓ����Ȃǂ̑[�u���Ƃ��Ă��܂��B�܂����������X���A�n��1�K�̐H���i����ꂪ���G�����ꍇ�A���ʂ̊ԁA���ꐧ�����s���Ƃ������Ƃł��B
�����̈�Ñ̐��A�����������@���@�E�h���×{�𐧌��@8/14
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��B1��������̐V�K�����҂�4���A����1400�l���������B�a���̕N���͉������Ă���A�{�͓��@��h���×{�{�݂̓����𐧌���������ɑ�(����)������B
�{���̐V�K�����҂͖�2�T�Ԃɂ킽��A��1��l������B14���̐V�K�����҂�1828�l�ŁA�u��4�g�v�̃s�[�N����1260�l��傫������B�ً}���Ԑ錾�̉��ł��A���������̒����͌����Ȃ��B�g���m���m����13���A�L�Ғc�̎�ނɁu���Ɍ��������B�a�����Ȃ��Ȃ������Ȃ��Ȃ��Ă���v�ƌ�����B
14�����_�̏d�NJ��҂͑O�����3�l����138�l�A�ő�m�ەa���̎g�p����23�E5%�B�y�ǁE�����NJ��҂�68�l����1706�l�A�a���g�p����67�E3%�ɂ̂ڂ�B�{�͊����g�傪�����A�y�ǁE�����Ǖa���ɑ����A�d�Ǖa�����N�����Ă���ƌx������B
����܂ł́A�������Âŏd�lj��Ɠ��@��������h�����ƕ��L�����@��h���×{������Ă������A13���ɕ��j��]�������B65�Έȏ�͌������@���������A�����Ljȏォ�d�lj����X�N�̂���l�ɐ����B���@�̕K�v���Ȃ��l�͏h���×{�Ƃ����������������A40�Έȏ��X�N�̂���l�ɍi��B
�{�����́u���Â⌒�N�ώ@���K�v�Ȑl�ւ̑Ή����x��Ȃ��悤�ɓ�������i�炴��Ȃ��v�Ƙb���B�����A�����������܂�鎩��×{�҂̏Ǐ�}�ςɏ\���Ή��ł���̂��Ƃ����ۑ�͎c�����܂܂��B
�������҂̔���20��ȉ��@�R���i��5�g�A���d�ł��g��@8/14
�V�^�R���i�E�C���X�����́u��5�g�v���A���Ɍ��̓��d�n��ł��g�債�Ă���B7���ȍ~�̐V�K�����҂́A���N�`���ڎ킪�i��ł��Ȃ�50��ȉ���9�����A����20��ȉ��������߂�B8��1���ɂ܂h�~���d�_�[�u���Ɋ܂܂�A���H�X�ɂ͎��Z�c�ƂƎ�ޒ֎~���v�����ꂽ���A��N�w�𒆐S�ɍL�����Ă���B���~�̋A�ȂŐl�̈ړ���������\��������A������̓O�ꂪ���߂���B(��ъ��v)
���d2�s2���̒���1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ�������ƁA���Ɍ��ɑ���3�x�ڂƂȂ����ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ��I������6��20������͌����X�����������A7���ɓ���A�ēx�����ɓ]�����B�����y�[�X�͓���ǂ����Ƃɑ傫���Ȃ��Ă���B
�����\�h�ɗL���Ƃ���郏�N�`���ɂ��āA2�s2���̐ڎ�́A7�������_��65�Έȏ�̍���҂͂����ނ�8����2��ڂ��I�������A��N�w�̐ڎ킪�{�i������̂͂��ꂩ��B��5�g���܂�7��1���`8��12���A�N��ʂ̊����҂�60��ȏオ6�E8���ƁA��4�g�܂łƔ�ׂđ傫���}�����Ă���̂ɑ��A20��ȉ���49�E8�����߂�B
�N��ʂł́A20�ぁ28�E0���A50�ぁ17�E5���A30�ぁ14�E2���A10�ぁ13�E8���A40�ぁ11�E7���|�Ƒ����B
8��2�T�ڂ̏T�����͐V�K�����Ґ����ꎞ�I�Ɍ��������A12���ɂ�88���Ԃ��30�l�ȏ�ƂȂ�36�l���m�F���ꂽ�B���\�����V�K�����҂̂����A�����ȏ�̊����o�H���������Ă��Ȃ���������A�����ւ̌x�����K�v�ȏ͑����B
���V�^�R���i�̊����g�呱���@�V�K�����҂�46�l�@�{�茧�@8/14
14���A�{�茧���ŐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊������V����46�l�m�F����܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�Ζ�������60��܂ł̒j�����킹��46�l�ł��B���Z�n�ʂł͋{��s��27�l�A�����s��5�l�A�����s�E�O�Ғ��E����s�����ꂼ��2�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B�V�K�����҂̂����Ƒ���m�l�E�����ȂǂƂ̐ڐG��28�l�̊������������܂����B���܂̂Ƃ��늴���o�H�s����13�l�Ō��O�ւ̖K����◈���҂Ƃ̐ڐG������l��5�l�ƂȂ��Ă��܂��B�C���h�R���̕ψكE�C���X�f���^���^�����V����27�l�m�F����܂����B
�������ǑE�L�����㎺���u����ȏ�̊����g���h�����ߌ������퐶�������ʼn߂����Ă��������ĉƑ��Ȃǂ����g�߂ɂ���l�ȊO�Ƃ̐ڐG�@����ɗ͌��炵�Ă���������悤�d�˂Ă��肢�\���グ�܂��B�v
13�����_�ŏd�ǎ�1�l���܂�70�l�����@���Ă��܂��B�z�e���⎩��Ȃǂ�245�l���×{���Ă��܂��B
���R���i�����g��@���ݕa����������×{���点 �@8/14
�����I�Ȋ����g�傪�����Ă���B���{���擪�ɗ����A�����̂��ÊW�҂ƘA�g���ė}�~�ɑ��͂������˂Ȃ�Ȃ��B
�V�^�R���i�E�C���X�́u��5�g�v�͎�s������e�n�ɍL����A�d�ǎ҂͘A���ߋ��ő����X�V���Ă���B���@�悪������Ȃ�����×{�҂��}�����A����ł̎��S���������ł���B
���{�̐V�^�R���i�����ȉ�́A����܂ŃR���i�̐f�ÂɊւ���Ă��Ȃ�������Ë@�ւɂ����͂�v������\�����B�����s�ȂNJ������g�債�Ă���n��ł́A�l�o��7���O����5���Ɍ��炷���Ƃ����߂Ă���B
���Ƃ́u�ЊQ���v�u����s�\�v�Ƒi���Ă��邪�A���l���Ăт����邾���ł́A���ʂ͏オ��܂��B�ЊQ���Ȃ�ЊQ���ɂӂ��킵����Ñ̐����\�z����K�v������B
�a���� �N���Ђ��ς� ��������A�K�Ȉ�Â�����悤�ɂ��邱�Ƃ��}�����B����×{�ł́A�e�̂��}�ς������ɑΉ����ɂ����A�Ƒ���ɂ������������B�����҂͊u������̂������ł���B
�z�e���Ȃǂ̏h���×{�{�݂��g�[����ƂƂ��ɁA���݂̈�Î{�݂𑁋}�ɐݒu���ׂ����B
���䌧�́A�̈�ق�100���̗Վ���Î{�݂Ƃ��Ċ��p����v���i�߂Ă���B�n���̈�t���Ō싦��A�a�@�̋��͂Ől�����m�ۂ��A�ً}���Ɏg���\�肾�B
�{�ݓ��̑S�̂����n���邽�߁A�h���×{�{�݂������Ȃ���Ï]���҂őΉ����\���Ƃ����B�e�����̂̎Q�l�ƂȂ낤�B
�e��Ë@�ւ́A����Ȃ�a���̊m�ۂɓw�߂邱�Ƃ�����B
���������ǖ@�́A�����J�����ƒm������Ë@�ւɑ��A���̗͂v���⊩�����ł���K��荞��ł���B���{�Ɠs���{���́A�K�v�Ɣ��f�����ꍇ�A�@�Ɋ�Â��������������߂���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�_�ސ쌧�≫�ꌧ�ł́A�ЊQ�h����Ã`�[���̈�t��Ō�t�炪�������Ă���B�s���{�����z���āA��Ï]���҂�v���ɔh���ł���̐��𐮂��邱�Ƃ��d�v���B
���Ö�͗L���Ɋ��p�������B�挎���F���ꂽ�u�R�̃J�N�e���Ö@�v�́A�d�lj��̗\�h�����҂ł���B���������Ɏg���A�����ɔM�����������Ƃ������o�Ă���B�h���×{�{�݂��܂߁A���L���g����悤�ɂ��Ă��炢�����B
�����}�~�ɂ́A���N�`�������̖ڋl�܂���������A��҂⒆���N�ւ̐ڎ���~���ɐi�߂邱�Ƃ��s�����B��5�g�ł́A�Ⴂ����ł��d�lj�����Ⴊ�ڗ����Ă���B�S�Ă̐l�������̐g����邽�߁A�������O�ꂵ�Ăق����B
�����{�ŐV�^�R���i��1���̐V�K�����҂�2���l��˔j�c�@8/14
���{�����̐V�^�R���i��1���ɂ�����V�K�����҂�2���l����ȂǐV�^�R���i�̊g�U�X�������܂�ƁA���{���{���ً}���Ԑ錾�̔��ߒn��g����������Ă��邱�Ƃ����������B14����NHK�Ƌ����ʐM�Ȃǂ̕ɂ��ƁA���`�̎͗��T�A�ً}���Ԕ��߂̊g����Ȃǂ��W�t���Ƌ��c������̂Ƃ݂��Ă���B
���łɓ��{�ł͌��݁A�����s���͂��ߐ_�ސ쌧�A��ʌ��A��t���A���{�A���ꌧ��6�s�{���ɊO�o�����Ȃǂ����q�Ƃ����ً}���Ԑ錾�����߂���Ă���B�������A�S���I�ɐV�^�R���i�̐V�K�����҂��}������ƁA�ً}���Ԑ錾�̔��ߒn��g������߂鐺�����܂��Ă���B�ꕔ�̍L�掩���̂́A���{�ɋً}���Ԑ錾�̔��߂�v�����悤�Ƃ��铮���������Ă���ƕ��ꂽ�B
NHK�̏W�v�ɂ��ƁA�O���̓��{�S��ɂ�����V�^�R���i�̐V�K�����҂�2��365�l�ŁA�V�^�R���i�̊����ҏW�v�ȗ����߂�1���̊����҂�2���l�����B�n��ʂɂ͓����s(5773�l)�A�_�ސ쌧(2281�l)�A��ʌ�(1696�l)�A��t��(1089�l)�Ȃǎ�s���̐V�K�����҂�1��839�l�ŁA�S�̂̔����ȏ���߂��B�܂��A�V�^�R���i�̏d�NJ��҂�1478�l�ƁA�j��ō��l���L�^�����B
���͑O���̗[���A���@�ŋL�Ғc�Ɂu�����̈�Ñ̐��͔��Ɍ������v�Ƃ��A�ċx�݃V�[�Y���̗��s��A�Ȃ���������悤�v�������B
�܂��A�d�x���h�~�Ɍ��ʂ�����Ƃ����g�R�̃J�N�e���Ö@�h���W���I�Ɏ{�s�ł��鋒�_���߂���������Ƃ����l�����`�����B�R�̃J�N�e���Ö@�Ƃ́A�A�����J�̐����Ѓ��W�F�l�����E�t�@�[�}�V���[�e�B�J���Y���E�C���X���זE�Ɋ�������̂�}�����鑽�l�Ȓ��a�R�̂̂����A���ʂ��D��Ă��邱�ƂŒm����u�J�V���r�}�u�v�Ɓu�C���f�r�}�u�v��g�ݍ��킹�����Í܂�V�^�R���i�����҂ɓ��^���邱�Ƃ������B���킹�āA���͎���×{���̐V�^�R���i�����҂Ɏ_�f�𓊗^�ł���悤�ɂ���u�_�f�X�e�[�V�����v�̍\�z���w�������B�ً}���Ԑ錾�����߂��ꂽ�n��ŐV�^�R���i�̊g�U�X�������܂�Ȃ����Ƃɂ��āu���Ǝ{�݂Ȃǂ̐l�g�}���̂��߂Ɋm���ɑΏ�����v�Ƌ��������B
����ɐ旧���A���{���{�ɐV�^�R���i�Ɋւ������������镪�ȉ�͍���12���A�u2�T�ԁA�W���I�ȑ���ʂ��āA�����s�Ȃǂ̐l�o��挎�O������50%�Ɍ��炷�K�v������v�Ə��������B���ȉ�͓����s���͂��߂Ƃ���ً}���Ԑ錾���ߒn�悩��̊O�o�������A�����̊댯���������n��̐l�o�����炷�K�v���ƒ�Ă����B�f�p�[�g��H�i�����A�V���b�s���O���[���Ȃǂ̐l�o�������}����ׂ����Ƃ��v�������B���݁A�����̃f�p�[�g�ł͎�ɒn��1�A2�K�ɂ���A�n���S�̉w�ƂȂ����Ă���H�i���ꂪ�������ʼnc�Ƃ𒆎~���Ă���B
�������R���i�����ҁA�A��2���l���@34�s���{���u�����I�g��v�@8/14
�����͂������C���h�R���̃f���^�����҈Ђ�U�邤�V�^�R���i��14���A�����ŐV���Ɋ�����2��147�l���m�F����A2���A����2���l�����B34�s���{���Ŋ����҂������I�Ɋg�債�Ă���l�����B�d�ǎҐ��͑O������43�l�����đS��1521�l(13�����_)�ƂȂ�A2���A���ʼnߋ��ő����X�V�B��5�g�̐[�����͍��X�Ƒ����Ă���B
�s���{���ʂ̊����Ґ��͓���5094�l�A�_�ސ�2356�l�A���1828�l�A���1800�l�ȂǁB���ő��ƂȂ����͈̂��A�ȖA��ʁA��t�A�_�ސ�A�R���A�O�d�A����A���A����A�������A����̌v12�{���ɏ�����B���҂͐�t5�l�Ȃnjv18�l�ƂȂ����B
���̔��M�u�~�X���[�h�v�A�p���J�Ấu�����v�@�����s��t��E���莡�v� �@8/14
�V�^�R���i�E�C���X�̋}���Ȋ����g�傪�������A�����s��t��̔��莡�v�(69)���{���̃C���^�r���[�ɉ������B�u��t��Ƃ��ĕa�@�A�f�Ï�����ۂƂȂ�A�R���i�f�ÂɑS�͂ł������Ă���v�Ƃ�����ŁA���{�̃R���i��⍑��ł̗^��}�̋c�_���u�����Ƃ�邱�Ƃ�����͂����v�Ǝw�E�B�����ܗւ��������ɉe�������Ƃ̌����������A24���ɊJ������p�������s�b�N�ɂ��Ắu���̂悤�Ȋ����ł͖������Ǝv���v�ƊJ�Âɋ^���悵���B
�\�\�����ܗւ������g��ɗ^�����e�����A�ǂ̂悤�Ɍ��邩�B
���ړI�Ɋ������L������A���{�̈�Ñ̐����N���Ђ��ς������肷�錴���ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤���B�����ܗւ͍ՓT�Ȃ̂ŁA�ɂޕ����ɉe����^�������Ƃ́A�ے�͂ł��Ȃ��B�ԐړI�Ȋ����҂������錴���ɂ͂Ȃ����Ǝv���B
�\�\�s���̐V�K�����Ґ��́A�������ɂ�5000�l�ɒB���Ă���B
��͂�A�]�������f���^���͊����͂������B���Ƃ͊����Ґ��̑�����\�����Ă����̂ɁA���������ɑ��A��Ñ̐��ւ̉e���Ȃǂ̒��ӊ��N���\���ɂ��Ă��Ȃ������B���`�̎́u�����҂͑����Ă��邯��ǂ��A����҂����N�`����ł��I�����邩��A�d�ǎ҂͑����Ȃ��B�S���Ȃ�l�������Ȃ���A�����v�Ƃ������b�Z�[�W�����o���Ȃ������B���ɂ���̂̓~�X���[�h���āA���ꂾ�������҂�d�ǎ҂𑝂₵�Ȃ���A�����҂����炷����Ƃ��Ă��Ȃ��B������߃��[�h�Łu���N�`�����ǂ�ǂ�ł��܂��傤�v��������Ȃ��B
�\�\���������Ɍ����Ă���̂��B
�����g�傪�n�܂���1�N�ȏソ���A���͊����ǂƐ키�̐������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�o���헪��`���͍̂��̖����Ȃ̂ɁA�����ɂ́u�~������܂���A���܂ł́v�݂����Ȏ��l�v�������邾���B������A�ǂ�����Ί�����}���邱�Ƃ��ł��邩�A�l�������点�邩�A�^��}�܂߂Ă����Ɛ^���ɋc�_����ׂ����B�����Ȃǂ���ΏۊO�̒n��ɏo�|����l������A�������ǂ�ǂ�L�����Ă���B���{���ɐ錾���o���A�l�̗�������͂ɖh�������ł��Ȃ��ƁA�n���ł������Ɉ�Â��ʖڂɂȂ�B
�\�\�p�������s�b�N�J�Â̐���́B
�܂����N�`����ł��Ă��Ȃ��l�����\����B�p�����ɁA�����͌ܗւ̎��������炭�����Ȃ��Ă���B�ܗւŃo�u������������Ă����\�Ȋ����҂��o�Ă���A���ꂪ����ɑ����邩������Ȃ��B�����ł͓��@�������ԁB���̂悤�ȏŊJ�Â͖������Ǝv���B���������߂邱�Ƃ����A��ÃT�C�h�Ƃ��Ắu����v�Ɣ��f����̂��Ó��ł͂Ȃ����B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���V�^�R���i�V����20�l�@�����n���Ŋ������g��@��N�w�����S�@�R�`�@8/15
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�R�`����15���A�V����20�l�̊����\�B2�P�^�̊������\��16���A���B
�V���Ɋ��������\���ꂽ�̂́A�߉��s��6�l�A��c�s��4�l�A���O�ݏZ��5�l�A�R�`�s�A��R�s�A�V���s�A�͖k���A��]����1�l�̒j�����킹��20�l�B
���̂�����]����20�㏗�����A14���ɃN���X�^�[�̔��\���������R�`�s�́u�Z�J���h�n�E�X�ʗS��(�����)����̉Ƃmorth�v�̊֘A�B
15���ɔ��\���ꂽ20�l�̂���16�l��40�Ζ����ŁA����������N�w�Ɋ������L�����Ă���B�܂��A������10�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B
�����̗v�̊����҂�2548�l�ɁB���ݏd�ǂ�7�l���܂�102�l�����@���Ă���B�h���E�ݑ�×{�͌v182�l�ŁA���@��������20�l�B���҂̔��\�͂Ȃ������B
�a����L���͌��S�̂�43�D0���ƍ�����Ԃ������Ă���B
����������121�l�̐V�^�R���i�����@�a���g�p��64�E0���@8/15
�������͌�����121�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ��14���A���\�����B121�l�̗z����13���܂łɔ��������B1��������̐V�K�����Ґ���3���A����100�l���A�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��������Ă���B�����̊����҂͗v7177�l�ƂȂ����B
13�����݂̓��@�҂�382�l�ŁA���̊m�ەa��597���̎g�p����64�E0��(�O����2�E7�|�C���g��)�ŁA�ˑR�Ƃ��ăX�e�[�W4(�����I�����g��)�̎w�W�u50���ȏ�v��傫�������Ă���B���@�҂̂����d�ǎ҂�13�l�B����×{�҂�358�l�A�×{�撲������155�l�ƂȂ��Ă���B
�V�K������121�l�̂��������o�H�s����45�l�������B
�����킫�̃R���i�����g�厕�~�߂����炸�@�N���X�^�[�����������@�������@8/15
���킫�s�̊����g��́A���~�߂�������Ȃ����B8���ɓ����Ă���14���܂ł�12���̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ŕ��������B1��������̊����Ґ���40�l�O��̍��������������A11���ɂ͉ߋ��ő���101�l(�s�Z��)���m�F���ꂽ�B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�z���Ґ��́A13�����݂�108�D14�l�ƂȂ��Ă���B�a���g�p���́A����\���𑝂₵���ɂ�������炸�A14�����݂�74�D03���ƂȂ��Ă���B��������X�e�[�W4(�����I�Ȋ����g��)�̎w�W��傫�������鍂�������Ő��ڂ��Ă���B
�s�ł́A�s���}���̌��ʂ��o��܂�2�T�Ԓ��x�����邽�߁A�d�_�[�u�̌��ʂ��o�n�߂�͍̂��������납��Ƃ݂Ă���B�S���҂́u�n���Âɉe�����o���˂Ȃ��B�J��Ԃ��A�s�����l�ւ̋��͂��Ăъ|�������v�Ƃ��Ă���B
���X�E���E�H�c�E�R�`�E�����̊����ҁ@8/15
���X56�l
�X���Ȃǂ�14���A10�Ζ�������80�Έȏ�̒j��56�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B6�l�������o�H�s���B����͐X�s20�l�A���ˎs12�l�A�O�O�ی����Ǔ�10�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v3129�l�B�X�s�̐X�����w�@��̍d���싅���ŁA���\�ς݂��܂�12�l�̃N���X�^�[���N�����ƔF�肳�ꂽ�B�������ȂǂŊ��������Ƃ݂���B���ˎs�̕ۈ�{�݂œ�9�l�A�ނی����Ǔ��̗����e�X�œ�5�l�̃N���X�^�[�����������B
�����51�l
��茧�Ɛ����s��14���A10�Ζ����`80��̒j��51�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͉��B�s6�l�A��D�n�s4�l�A�����A��ցA�{�ÁA�k��4�s�Ŋe3�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v2386�l�B��b�����̂���65�Ζ����̊���1�l�̎��S���m�F����A���҂͌v48�l�ƂȂ����B���B�ی����Ǔ��̐ڑ҂����H�X�œ����܂ł�10�l�̊������������A���̓N���X�^�[�����������Ɣ��f�����B
���H�c20�l
�H�c���ƏH�c�s��14���A10�`60��̒j��19�l�ƔN��A���ʔ���\��1�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�����̊����m�F�͌v1174�l�B�����҂̓���́A�H�c�s6�l�A��ٕی����Ǔ�5�l�A�\��ی����Ǔ�3�l�A�k�H�c�ی����Ǔ��Ƒ��ی����Ǔ����e2�l�A����ی����Ǔ��ƏH�c�����ی���(����s)�Ǔ����e1�l�B
���R�`29�l
�R�`���ƎR�`�s��14���A�c������70��܂ł̒j��29�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B����͎R�`�s15�l�A������5�l�A��c�s3�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v2528�l�B�R�`�s�̕��ی�f�C�T�[�r�X�u�Z�J���h�n�E�X�ʗS���@����̉Ɓ@�m���������v��14���܂łɐE���Ǝ����v8�l�̊������������A�s�͐V���ɃN���X�^�[�����������Ɣ��\�����B�u�k452�q�v�ψي��͐V����21���m�F����Čv161���ƂȂ����B
������121�l
��������14���A10�Ζ����`80��̒j��121�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1��������̊����m�F�Ƃ��Ă�12�����\��230�l�Ɏ�����2�Ԗڂɑ����B����͂��킫�s55�l�A�S�R�s30�l�A�����s12�l�ȂǁB�����̊����m�F�͌v7177�l�B���킫�s���̎����{�݂ƈ��H�X�A���Ə��Ōv3���̃N���X�^�[���������A�����̂���܂ł̃N���X�^�[�͌v121���ƂȂ����B���킫�s�̕����J�Еa�@�̃N���X�^�[�́A�V����2�l�̗z�����������v25�l�Ɋg�債���B���@���҂�382�l�ŕa���g�p��64���̓X�e�[�W4(�����I�����g��)�̂܂܁B����×{�҂�358�l�A�×{�撲������155�l�B
�����~�����ɂ���Õ���c���m������@���@��ʌ��@8/15
��ʌ����̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����җv��14���܂ł�7��4��l�����B�S����(��734���l)�̂��悻100�l��1�l�����������v�Z���B1���̐V�K�����҂͂���1�J����5�{�ȏ�ɑ����A�a���g�p����7���ɔ����Ă���B�����͂̋����f���^��(�C���h��)�̉e�����傫���Ƃ݂���B����×{�҂�1���l���Ă���A���͏d�lj��h�~�Ɍ������u�R�̃J�N�e���Ö@�v�̓���������ɓ���邪�A�����͂Ȃ����ʂ��Ă��Ȃ��B
�u����ȏ㊴���g�債������ꍇ�A���~�����̗��T�ɂ���Õ���ɒ��ʂ���\�����o�Ă��Ă���v�B���̐V�^�R���i���c���J���ꂽ13���A��쌳�T�m���͊�@�������ɂ��A���~���Ԃ̋A�Ȃ◷�s�̒��~�Ȃǂ��Ăъ|�����B
1�J���O�ɓ�����7��15�����_�̊m�ەa���g�p����30�E1��(503�l�^1666��)�A�����d�ǂ�14�E5��(24�l�^165��)�������B�����ɂ́u�܂h�~���d�_�[�u�v���o����A�������܁A�����2�s��[�u���Ƃ��������g��h�~�s���Ă����B�����̌����̐V�K�����҂�328�l�������B
���������̊����͋}�g��Ɍ������B��22���̐V�K�����҂�1���ȗ���500�l�����ƂȂ�510�l�B��31���ɂ͏��߂Đ�l��1036�l�A8��13����1696�l��5�{�ȏ�ɑ��������B7��20���ɂ͓��d�_�[�u��悪����20�s���Ɋg��B����ł��g��X���Ɏ��~�߂͂����炸�A2������͌����S�悪�Ώۂً̋}���Ԑ錾���o���ꂽ�B
�m�ەa���g�p�������܂��Ă���B13�����_�ł�69�E7��(1177�l�^1689��)�A�����d�ǂ�64�E9��(111�l�^171��)�ƂȂ��Ă���A��1�J���Ŏg�p���A�l���Ƃ��{�ȏ�ƂȂ����B�d�ǎҐ��͍���10����102�l�ƂȂ�A�ő����X�V�����B7��15�����_�̃z�e���×{��450�l�A����×{��471�l�B13�����_�ł͂��ꂼ��624�l�A1��3059�l�Ƒ啝�ɑ����Ă���B
���͍���6���A����܂ŕی��������{���Ă����u�ϋɓI�u�w�����v���k���B�s�����������̂ڂ芴������������Ɩ�������߂��B���ی���Ð���ۂɂ���13���܂łɁA�����Ǝs��������ő�133�l�̉����v��������13�ی����ɑ���A�����͂̂����������܂łɐV�K�z���҂Ƃ̃t�@�[�X�g�R���^�N�g������̐��Â�����m�ۂ��Ă���B
�f���^����2�`8����1�T�Ԃ̗z������85�E4���ŁA�命�����]��������u����������Ƃ݂���B
�������J���郏�N�`���ڎ�ɂ��ƁA13�����_�Ō���1��ڎ헦��35�E47���A2��ڎ헦��26�E88���B65�Έȏ�͂��ꂼ��88�E64���A83�E03�����B
���͐V���ɁA�d�lj���h�����ʂ�����V���Ö�́u�R�̃J�N�e���Ö@�v�̋��_������i�߂�ӌ��������A��Ë@�ւ̕N��(�Ђ��ς�)�������d�ǎ҂̔����h�~��ڎw���Ƃ����B
�������}���@�ی����N���@�ǐՒ����k���̌��O���@�V�����@8/15
�V�������̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�14���A5��l�ɒB�����B�킸��2�T�ԂŐ�l�Ƃ����}���ȑ����ƂȂ�A�����̊e�ی����͗z���҂ւ̕������Ȃǂɓ��X�ǂ���B�������A���̂܂܂̃y�[�X�Ŋ����g�傪�����A�Z���ڐG�҂�ǂ��Ȃ����Ԃɂ��Ȃ肩�˂��A�W�҂͌��O�����߂Ă���B
������7��31���A�v�̊����҂�4��l�ɒB���A2�T�Ԍ�̍���14����5��l�������O���t�Q�Ɓ��B�����҂̑����ɔ����A�����̕ی����̕��ׂ����܂��Ă���B
�������L���钷���s�⏬��J�s�Ȃǂ��NJ����钷���ی����́A���i��5�l�قǂ̑̐��ŗz���҂ւ̍s��������Ǐ�̕�������A�o�b�q�����̒i���Ȃǂ����Ă���B
7���㔼���犴���Ґ����}���������߁A��������ʂ̕ی������牞�������炢�A��������10�l�قǂőΉ�����B���z�q�����́u�ǂ��̕ی������Z�����Ȃ��Ă��āA���������炤�̂�����Ȃ��Ă���v�ƌ��B
12���ɊJ���ꂽ���̑��{����c��A���Ƃ́u���̂܂܂̃y�[�X�Ŋg�傪������2�T�Ԍ��1�T�Ԃ̊��Ґ���1500�l���A1��250�l�߂��܂ő�����v�Ƃ̎��Z���������B
�V���s�ی����ی��Ǘ��ۂ̓c�Ӕ��ے��́u1�������Ȃ牽�Ƃ��Ȃ邩������Ȃ����A�����ƂȂ���Ȃ肫���v�Ɠf�I����B
����Ò����{���̒S���҂́u���͉��Ƃ��Ή��ł��Ă��邪�A���Z�ʂ�̐����ɂȂ�Εی������z���҂�ǂ��Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ����v�Ǝw�E�B���݂͗z���҂̍s�������ߋ�2�T�ԕ����ׂĂ��邪�A�l�肪����Ȃ��Ȃ�Œ���ɂƂǂ߂�K�v���o�Ă���Ƃ����B
�����g���}���邽�߂ɂ́A�o�b�q�����ȂǂŁA��葁���̊����m�F���������Ȃ��B�A�Ȃ⌧�O�ւ̏A�E�����̂��߁A����I�Ȃo�b�q�����̗��p���v�����܂��Ă���B
�i�q�V���w����߂��́u�ɂ������o�b�q�����Z���^�[�v�́A1��100���̌������\�����A8�����܂łقڗ\��ł����ς��ƂȂ��Ă���B
�����N���������ʂ悤�A�o�b�q�����Ԑ��̊g�[���i�߂Ă���B1��100���̌��̍̎悪�\�ȑ�K�͂o�b�q�Z���^�[��������3�J���݂��Ă��邪�A���z�n���̃Z���^�[��10������150�l�܂Řg�𑝂₵���B
�������ی����̏��{���������́u�����̃L���p�V�e�B�[���Ԃɍ����悤�A�K�X�g�債�Ă��������v�Ƙb���Ă���B
�������킸�O�o���l���@�m���u��ÕN�����ڑO�v�@�x�R���@8/15
�ō��̌x�����x���u�S���狦�͂��肢�v�@�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g����A�x�R����16���ߑO0�����猧�Ǝ��̌x�����x�����ł������u�X�e�[�W3�v�Ɉ����グ��B�����ɒ�����킸�s�v�s�}�̊O�o���l�����߂�B�u3�v�ւ̈����グ�́A��N5��13���Ɍ����x�����x����ڍs����߁A��15���Ɂu2�v�ֈ��������Ĉȗ��ƂȂ�B14���Ɍ����ʼn�����V�c���N�m���́u�o���̂Ȃ������҂̋}���ň�Ò̐����N��(�Ђ��ς�)����ڑO�ƂȂ��Ă���v�Əq�ׁA�����̎����Ɍ����Č����ɗ����Ƌ��͂����߂��B
�V�c�m����7���ȍ~�̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�̖�4�������H�X�ȂǂŔ������Ă��邱�Ƃ��A�u�X�e�[�W3�v�ւ̈ڍs�ɔ����A���Z�c�Ƃ�v��������j���������B�ΏۋƎ��v�����ԁA�Z�k���ԁA�v���ɉ������X�܂Ɏx�������͋��̎x���z�ȂNJT�v�͏T�����̑����i�K�ō��Ƃ̋��c������������\���A�T���Ɏ��{����B��ނ̒��l�͋��߂Ȃ��B
�V�c�m���͋��͋��ɂ��āu1���Ɏ��Z�v���������ۂ͈ꗥ(1��������)4���~�Ƃ������A�ŋ߂�(�����ł�)����グ�K�͂ɂ���ĕς�邱�Ƃ�����v�Əq�ׁA���z�ɕ����������邱�Ƃ����������B�W�҂ɂ��ƁA1��2��5��~����7��5��~�̕��Ƃ�������Œ������Ă���A�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�͌ߌ�8���ȍ~�̉c�Ǝ��l�����߂�����Ō������Ă���B�����S��̖�3��X���ΏۂƂȂ�A20���~�K�̗͂\�Z�͐ꌈ�������錩�ʂ����B
�R���i���Ŕ敾������H�X�ɍĂю��Z�v�������邱�Ƃɂ��ẮA�X�܂��o�c����F�l���狇����悭�����Ă���Ƃ��u�X�Ɨ��p���鑤�������R���i���~�߂悤�Ƃ����C�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�X�ɂ͋�J�������邪�������������A�S���炨�肢�������v�Ƙb�����B
���̂ق��A�����ɑ��āA�A�Ȃ����Ƒ��╁�i����Ă��Ȃ��e�ʂ�F�l�Ɖ�H�����ꍇ�A2�T�Ԃ͑̉�����Ȃǂ̌��N�Ǘ��A�Ζ����w�Z�ł̊����h�~�̓O������߁A���N�`���ڎ������������}�X�N���p�Ȃǂ����炽�߂ėv�������B���Ǝ҂ɂ͐E���x�e���A�Ј����ł̊����h�~��̍Ċm�F�Ə]�ƈ��ւ̎��m�O��A�ݑ�Ζ��⎞���o�̐��i�A�o���̃����[�g�ւ̐�ւ��Ȃǂ��Ăъ|�����B
���Ǝ��̌x�����x����7��3���ɍł��Ⴂ�u1�v�Ɉ���������ꂽ���A�����̍Ċg����A����5���Ɂu2�v�ֈڍs�����B�����҂̑����͎~�܂炸�A���͓�10���Ɂu�����g����ʌx��v���o�������A��12���̐V�K�����Ґ���1��������ő���71�l�ƂȂ�ȂǁA���~�߂��������Ă��Ȃ��B
8�����f���^���@���{����c�ł́A8���̌����̊����҂͖�8�����uL452R�ψي��v�ƕ��ꂽ�B�����͂̋����f���^���Ƃ݂��A7����3�`4������}�������B
�u�X�e�[�W3�v�ڍs�̌��ʂ��o��܂ł͈��̊��Ԃ��K�v�ŁA����Ȃ銴���g�傪���O�����B�V�c�m���́A��苭�͂ȑ[�u���K�v�ƍl������ꍇ�A���ɂ܂h�~���d�_�[�u�̓K�p��v������Əq�ׂ��B
����w�Ŕ��������N���X�^�[17�l�Ɋg��c ���m�ŐV�K������698�l�@8/15
���m���ł�14���A�V����698�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B3��������600�l������܂����B
���������������̂́A10�Ζ�������80���698�l�ŁA���É��s��264�l�A��{�s��37�l�A�L�c�s��30�l�A����s��20�l�A�L���s��15�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
���É��s�ɏZ��10�Ζ����̏��̎q�́A�N���X�^�[�����������s���̕ۈ�{�݂𗘗p���Ă��āA�֘A���銴���҂�12�l�ɂȂ�܂����B
�L�c�s�̑�w�̃N���X�^�[�ł́A�V���Ɋw��2�l�̊������m�F����܂����B���̃N���X�^�[��17�l�ɂȂ�܂����B
����s�̑�w�̉^�����̃N���X�^�[�ł́A�V���ɊW�҂̖L���s��10��j���ɗz�����������܂����B
�ق��ɂ��L���s�̈�Ë@�ւ��{�s�̎��Ə��̃N���X�^�[�ł��A���ꂼ��1�l���V���Ɋ����҂��m�F����Ă��܂��B
13�����_�̕a���g�p����29.7���ŁA�d�ǎ҂�26�l�ł��B
���O�d���u�܂h�~�v��v���@�V�^�R���i�g��Ő��{�Ɂ@8/15
�O�d����14���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g������u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�𐭕{�ɗv�������B�K�p���Ԃ͖���ŁA��ނ̒�~�Ȃǂ����߂�d�_�[�u�̎��{���ɂ�7�s8�����������Ă���B
���ɂ��ƁA��؉p�h�m����14���ߑO�A�����N���o�ύĐ��S�����Ɠd�b�ʼn�k���A�d�_�[�u�̓K�p��v�������B�d�_�[�u�̓K�p��v������̂�2��ځB�����҂̋}����a���g�p���̍����Ȃǂ܂���13���ɗv�������߂��B
�����������Ă���d�_�[�u�̎��{���͌K���A���ȂׁA�ؑ]���A�����A�Ԗ�A�����A��z�A�l���s�A�鎭�A�T�R�A�ÁA����A���C�A���a�A���̊e�s���B�K���A�l���s�A�鎭�A�ÁA�����5�ی������NJ�����S�Ă̎s����ΏۂƂ����B
�����5�ی����Ǔ��ł́A����2�T�Ԃ̐l��10���l�����芴���Ґ���15�l�ȏ�ƂȂ��Ă���ق��A����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���25�l�ȏ�ƂȂ��Ă���B
��ؒm����14���̂Ԃ牺�����Łu(��������)���Ԃɂ��Ă͓��ɘb���Ă��Ȃ��B��b���}���Ή����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ƃ���Ɋ�@���������Ă����v�Ƌ����B���{�ɂ́u�����ɓK�p���Ă��炤���Ƃ��肤�v�Əq�ׂ��B
�����̊����ɂ��āu���ĂȂ������̊g�傪���Ɋւ���Ă�����Ɍ������A�ɂ߂Đ[���ȏƍl���Ă���v�Ƌ����B�d�_�[�u�̎��{���ł̗v�����e�́u�O��������ݍ��݁A���j���[�𑝂₷�B�[�u�ł��邱�Ƃ͂����ނ˂��v�Ɛ��������B
����ɐ旧���A����13����A�����ǂ̐��Ƃ�o�ϒc�̂̑�\��ł��錟����c���J���A�ψ�����܂h�~���d�_�[�u�̗v���ւ̈ӌ���������B6�ψ�����́u���֗v�����ׂ��v�Ƃ̈ӌ��ň�v�����Ƃ����B
��c�͖`���̂������Ɗ����̐����������Ĕ���J�B�ψ�����́u����Ɋ������g�傷��\��������̂ŗ}�����ޕK�v������v�u���Ǝ҂̐S���܂�Ȃ��悤�Ɏx�������Ăق����v�Ƃ̐����������B
�����Ɍ��u�܂h�~�v16������g��@15�s����36�s���@8/15
�V�^�R���i�E�C���X�����́u��5�g�v���{�i�����钆�A���Ɍ���16������A���̂܂h�~���d�_�[�u�̑[�u�����A���݂�15�s������A�n�n�������36�s���ɍL����B�_�ˁA�P�H�s�A��_�A���d���n��ő����Ă�����ޒ̋֎~�v����O�g�A�W�H�n��ȂǂɐV���ɓK�p����B31���܂ŁB
����ő[�u���͐_�ˎs�ƍ�_�E�d���E�O�g�E�W�H�n��̌v36�s���ɂȂ�A����������H�X�ɑ��Ď�ޒ̋֎~��ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ����߂�B
�A�n��5�s��(�L���A�{���A�����s�A�����A�V����)�ɂ́A�ߌ�9���܂ł̎��Z�c�ƂƁA�ߌ�8���܂ł̎�ޒ������������߂�B
�����ł́A�A�n�ȊO�̃G���A�Ől��10���l������̊����Ґ����啝�ɑ������B�قƂ�ǂ̒n��Ŋ����������w�W���X�e�[�W4(�����I�����g��)�ƂȂ��Ă���B
13���ߑO0�����_�̕a���g�p����56�E9���B�d�Ǖa���̎g�p����28�E1���ŁA�h���×{�{�݂ł�48�E8���ɏ��B
���}�g��A�Ή��ɋꗶ���@�ړ����l�v���ɗ����҂�@������`�@���������@8/15
�S���I�ɐV�^�R���i�E�C���X�������}�g�傷�钆�A���~���Ԃ��}���Ă���B���������ł�13���A���Ǝ��ً̋}���Ԑ錾�����߁B�����s�}�����̉�����`�ł�14���A��N�قǂ̍��G�͌����Ȃ����̂́A�ό��q��A�Ȏ҂��悹����s�@�����X�Ɠ����B�����s�v�s�}�̈ړ��̎��l���Ăт����钆�A�����҂���}�Ȋ����g��ւ̑Ή��ɁA�ꗶ�����l�q������ꂽ�B
������`�̓������r�[�ł́A��^�̃X�[�c�P�[�X����ɂ����Ƒ��A����҂Ȃǂ̎p���ڗ������B�o���ŗ������{�̒j��(32)�́u���~�ł���������Ȏ����ɖ{���͗������Ȃ��������A�厖�ȋq�Ƃ̑ł����킹�ŕύX�ł��Ȃ������v�Ƙb�����B
�������ւō~�藧�����j���͉Ƒ�4�l�ŗ������u�ǂ����痈�����͂��������Ȃ��v�Əq�ׁAPCR�������ė������Ƃ𖾂������u��������(�{�y)�́A��J�Ɗ����g��ő�ςȂ��ƂɂȂ��Ă���B(1�J���قǑO����\�肵�Ă����ɂ��ւ�炸)�Ȃ������̂������ł��悭�킩��Ȃ��v�ƌ��t���Ȃ������B
�A�Ȃ��閺�Ƒ����}���ɂ����}������60��v�w�́u(���������҂�)�����ł̋}�Ȋg��ɂ͋����Ă���B�����Ƒ����ɂ킩���Ă����(���l�ɂ��Ă�)�Ή�������̂����c�v���S�O�����l�q�Řb�����B
���́A�ċx�݂₨�~���Ԃ��}���������z����s�����̊����҂��������Ă���Ǝw�E�B���b�Z�[�W�ł́A���O�ւ̕s�v�s�}�̈ړ������l���A�ً}���Ԑ錾��܂h�~���d�_�[�u�̑Ώۋ��Ƃ̉����������悤�Ăъ|���Ă���B
�܂����́A��ނ�������������l�ɂ��Ă�PCR�����̎�v���B8�����܂ł͌������p�����̈ꕔ�S�B���{�ꏊ�͉H�c��`�A�ɒO��`�ȂǂŁA�ڂ����͌��z�[���y�[�W�Ŋm�F�ł���B
���V�^�R���i�V�K�����ҁ@�s��5094�l �S��12�{���ōő�2��151�l�@8/15
14���ɑS���Ŋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂́A2��151�l�ŁA2���A����2���l�����B
14���ɓ����s�Ŋm�F���ꂽ�V�K�����҂�5,094�l�ŁA��T�y�j��(7��)��4,566�l����528�l�����A�ߋ�2�Ԗڂɑ����l���ƂȂ����B
�܂��A�_�ސ쌧��2,356�l�A��ʌ���1,800�l�A��t����1,272�l�ȂǁA��������ߋ��ő�������A��s���𒆐S�Ɋ����̊g�傪�����Ă���B
�ق��ɂ����{��1,828�l�A���ꌧ��752�l�ȂǁA12�̕{���ŐV�K�����Ґ����ő��ƂȂ��Ă���B
�S���ł́A�V����2��151�l�̊������m�F����A2���A����2���l�����B
�܂��A���҂�18�l�ŁA�d�ǎ҂�1,521�l�ƁA2���A���ōő��ƂȂ��Ă���B
�������g��ɂ������𑱂���Ȃ�u�l�Ђƌ��킴��Ȃ��v�@8/15
���ۈ�Õ�����w�̏��{�N�Ƌ�����15���A�u�T���f�[���[�j���O�v�ɐ��o�������B
�ԑg�ł́A���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή���}���Ȋ����g����A����2�T�Ԃ͓����s�̐l�����u7���O���̖�5���ɂ���K�v������v�ƒ������Ƃ���B���̏�ŕS�ݓX�̒n���H�i�����Ȃǂ̗��p���T����悤���߂��ق��A���~�̎����ɋA�Ȃ◷�s�Ȃǂ������邱�Ƃ�O���ɁA�������z����ړ������l����悤�Ăт������B
�o���҂��犴���̊g��ɂ�����J���Ă��Ȃ����Ƃɋ^��̐����o���B�i��̊��G���獑����Ă�����ꂽ���{���́u1��2���l�̊����҂��o�āA�����ł�����ŗ×{����Ă�����������Ȑ�2���l�̕��A������1������l�̕������@�������A�{���ɍЊQ���x���̏��Ǝv���܂��v�Ƃ�����Łu���{�Ȃǂ����̂܂܍���Ȃǂ��J�����A��̓I�ȍ�������Ɍ��Ă����̂ł���ΐl�Ђƌ��킴��Ȃ��B���ꂾ���̏�F�����Ă���������̂ł���A���}�ɋ�̓I�ɉ��炩�̊�����}������̍����������Ή����Ă������������v�ƒ��Ă����B
���K�͏k���œs��v�ҒǓ������{�@���r�s�m���@8/15
�I�킩��76�N��15���A�����s�͓s���Łu��v�ҒǓ����v���s�����B
���T�ɂ́A���r�S���q�s�m����⑰��\�҂炪�Q��B�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɂ��A��N����Q��҂��10����1�Ɍ��炵�Ă���A���N��90�l����v�҂Ɍ��Ԃ��s�����B�܂��A��N�Ɠ��l�ɃC���^�[�l�b�g���p�����{���ꂽ�B
���r���́A���`���Łu�����s�����\���āA��̑��ŖS���Ȃ�ꂽ�S�Ă̌��(�݂���)�ɑ��A�ނ�ň����̐�������܂��v�Ǝ������q�ׂ��B�܂��A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�剺�ōs��ꂽ�����ܗցE�p�������s�b�N�̊J�ÂɐG��u���̃��K�V�[��ƂɁA��ǂ𐢊E����ۂƂȂ��ď��z���A���Ɗ�]�ɂ��ӂꂽ���a�Ȑ��E�������\�Ȃ��̂Ƃ��āA�����̎q�������ւƈ����p���ł������Ƃ��������\���グ�܂��v�ƌ�����B
��v�҈⑰��\�ł��������s�����ؑ��S���q����́A���܂��O�ɕ��e���t�B���s�����\�����Ő펀�B���76�N���}���A�푈��m��Ȃ����オ�����Ă��钆�u�ȑO�A�m�g�j���s�����X���C���^�r���[�ŁA8��15���͉��̓��ƕ�����A�w������Ȃ��x�Ƃ��w�N���̒a�����H�x�Ɠ�������҂����܂����B�����́A�I��L�O���Ȃ̂ł��v�Ƒi���A���E�̍P�v���a��������B
�������g��A�����_���̌��\�x����u���߂������Ă��Վ�����J����Ȃ��v 8/15
�t�H�g�W���[�i���X�g�ŊC�O�A���{�ŕn����ЊQ�A�������ނ��Ă�����c�ؒËI����15���ATBS�n�u�T���f�[���[�j���O�v(���j�O8�E00)�Ƀ����[�g�o���B�����s��14���ɐV�^�R���i�E�C���X�����҂��V����5094�l���ꂽ���ƂɌ��y�����B
�O��13����5773�l�Ɏ�����2�Ԗڂɑ��������҂ŁA13���Ɣ�ׁA���@���҂�35�l������3762�l�A�����d�ǎ҂�18�l����245�l�ŁA��������ߋ��ő����X�V�����B���҂͂̕Ȃ������B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����҂�4231�E1�l�Ə㏸���A�O�T��108�E7���B����×{�҂�2��1729�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ��Ă���B
���c����́u30��ł����Ă��d�����ǂɋꂵ��ł����������̂ŁA�����������Ӗ��ł����ɑ傫�Ȍ��O������B���̊ԁA�R���i��������ł����A����܂ŊJ�Â���Ă����ܗւɊւ��Ă�����Ɉ��S�E���S���Ă������Ƃ��f�����Ă������A���S�E���S�Ƃ����͓̂K�ȏ�L���Ȃ���ď��߂Đ��藧���̂łȂ����ȂƎv���v�Ǝw�E�B�����āu���A��������ďd�ǎҐ��������Ă�����Ă����̂̓f���^�����҈Ђ��ӂ���Ă��邩�炾�Ƃ������Ƃ��Ǝv����ł�������A�����Ń����_���Ƃ����ʂ̕ψي����m�F���ꂽ�B���̃����_�����m�F���ꂽ�̂��ܗ֊W�҂Ƃ����̂��ŋ߂ɂȂ��Č��\���ꂽ�B���\�̒x����ĉʂ����Ėh���Ȃ������̂��A�l�o��5�����������A�x���Ƃ��Ė炳��Ă���킯�ł����ǁA���̂悤�ɑ傫�ȑ����J�Â��Ă����Ƃ������Ƃ��^�t�̃��b�Z�[�W�ɂȂ���Ȃ������A�����ȋ^���₢�������A��������܂܁B���߂������Ă��Վ�����J����Ȃ��B���ꂾ���̏ɂȂ��Ă��A�Ȃ��c�_�̏ꂪ���߂��Ă���Ƃ������Ǝ��́A�l���̌y���ł͂Ȃ����Ǝv���v�Ǝ��g�̌������q�ׂ��B
���R���i����̐�������ǂ����ރ��C�h�V���[�@�������ԑg�ƃk�����ԑg�@8/15
�u�s��������Ă���v�Ɣᔻ����邪�A�V�^�R���i�E�C���X�̏��L�����グ�A�����g��̊�@��K���ɑi���Ă����̂́A�e���r�̃��C�h�V���[�ł���B���T�ɂ͓����̐V�K�����҂�1���l�������ŁA�R�����e�[�^�[�͐��`�̖̎��ז����ᔻ���A�����ǐ��Ƃ͂��̑�5�g���ǂ��܂ōL����̂���\���A���|�[�^�[�͈�Õ���̌��ꂩ��`���A�L���X�^�[�́u�����̖�������āv�Ɛ������炵�Ă���B
�V�^�R���i�̊������n�܂�����N�~�A���{�����u������Əd���C���t���G���U�v���x�ɍl���Ă������ɁA������̉��c���b������r�ܑ�J�N���j�b�N�̑�J�`�v�@����A���o�ꂳ���āA�u�C���t���Ƃ͂܂������Ⴄ�|���a�C�B�Â����Ă̓_���I�v�ƁA���������x����炵���̂����C�h�V���[�������BPCR���������ׂĂ̐l�Ɏ��{���ׂ��ƃL�����y�[����A���r���[�ȋً}���Ԑ錾�ł͊����Ɏ��~�߂͂�����Ȃ��Ǝw�E�A���N�`���m�ۂ��}���Ƃ��咣�����B���͂��Ƃ��Ƃ������������A���C�h�V���[���������������Ƃ͂��܂▾�炩�ł���B
�ł͂��܁A�R���i�����\�h�ɖ𗧂��C�h�V���[�͂ǂꂩ�B��������͂����Ă����e���r�����n�u�H���T�ꃂ�[�j���O�V���[�v�ɁA��͂����̒�������B�����ӂ̉H���p�l���̉���͗v�̂悭�܂Ƃ߂��Ă��āA�S���̊����҂�8���A����1���l���������́A�R���i����1���Ԉȏ㊄���āA�u�d�ǎҍő��v�u�c���ł��Ȃ�����v�u���b�N�_�E�����ݑ���v�u����͓��@���~�v�Ȃǂ����X�Ɏ��グ���B�e���r�����R�����e�[�^�[�̋ʐ�O���u���[�j���O�V���[�����Ă�����������́A��@�����\�������Ă�������Ǝv���܂��v�Ǝ��掩�^�������Ȃ�̂��킩��B
�Ƃ��낪�A�X�|�[�c�ǂ̑�o�J�Ј����A�ܗ֑ł��グ���݉���J���A�]�����̂܂ŋN�����āA���̎��тɓD��h���Ă��܂����B�R�����e�[�^�[�̒�������������������Ƃ��낤�B
���{�e���r�n�unewsevery.�v�́A����ψ��̏������䂪�R���i�ŐV�����������̂���ԂƂȂ��Ă��āA�ߌ�4��45���ɂ͓����s�̂��̓��̊����Ґ����ǂ����������`����B���͑����BTBS�n�uN�X�^�v���قړ������e�ł���B
��������J���Ȃɕ��������Ďd�����Ȃ��Ƃ��������́A�t�W�e���r�n�u�o�C�L���OMORE�v���I�X�X���B���C�h�V���[��MC�̒��ŁA���܍��E���ł���N�s���B
�t�ɁA�ʂ邢�̂̓t�W�e���r�n�u�߂��܂�8�v�ŁA�����O�̒��L�オ���邳���A���ʂ͏��Ȃ��B���Ƃ��ƃG���^���d���̓��{�e���r�n�́u�X�b�L���v���A�R���i���|�\�l�^�D��ł���B
�������}�g��Ɂu�Ⴂ����̏d�lj����A���ꂩ�炩�Ȃ�[���ɂȂ��Ă���v�@8/15
���ۈ�Õ�����̏��{�N�Ǝ�C����(�����NJw)��15���ATBS�n�u�T���f�[���[�j���O�v�Ƀ����[�g�o���B�����s��14���ɐV�^�R���i�E�C���X�����҂��V����5094�l���ꂽ���ƂɌ��y�����B
�O��13����5773�l�Ɏ�����2�Ԗڂɑ��������҂ŁA13���Ɣ�ׁA���@���҂�35�l������3762�l�A�����d�ǎ҂�18�l����245�l�ŁA��������ߋ��ő����X�V�����B���҂͂̕Ȃ������B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����҂�4231�E1�l�Ə㏸���A�O�T��108�E7���B����×{�҂�2��1729�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ��Ă���B
���{���́A�����̋}�g��ɂ��āu�f���^���̉e�����傫���Ǝv���܂��B�d�lj����X�N�͊C�O�̃f�[�^�ł�2�{����5�{�Ƃ����ӂ��Ɍ����Ă��܂����A��͂芴���͂������̂ł��ꂾ�������Ґ������ꂾ���̋K�͂ɑ����Ă��܂��B��������Ɗ������Ă���l�����Ȃ葽���o�Ă��āA����ɏd�lj����郊�X�N�������Ƃ����f���^���̉e�����o�Ă���ƎႢ����ł���r�I�ɏd�lj�����Ⴊ������40��A50��̕��������C���ɂȂ��Ă��܂��B60��̕��������Ă��邩���Ă����ƌ����Ă����ł͂Ȃ������猾���Ύ��͑����Ă��܂��B�����������Ƃ��l����ƍ��͈̏��S�ł���ɂ���܂��A����Ɋւ��Ă͎Ⴂ����̏d�lj����A���ꂩ�炩�Ȃ�[���ɂȂ��Ă����Ȃ����Ǝv���܂��v�Ǝ��g�̌������q�ׂ��B
���u�[���R���i���ē���B�ǂ����������Ă����̂����l���Ă����Ȃ��Ɓv�@8/15
�̎�̐���M��(50)��15�������̃t�W�e���r�u���C�h�i�V���[�v�ɏo���B�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��̏ɂ��Č������������B
�ԑg�ł́A1���̐V�K�����҂��S����2���l����ȂǁA�����g�傪�����̒��A���ۃI�����s�b�N�ψ���(IOC)�̃o�b�n��������ܗ֕��̗�9���[�ɓ����E������U�A�l�����肪�ł��A�g��u�������h�ɁB�ې���ܗ֑���10���̋L�҉�Łu�s�v�s�}�ł��邩�ǂ����́A�������育�{�l�����f���ׂ����́v�Əq�ׂ��ȂǂƂ����グ���B
����̓o�b�n���̍s���ɂ��āu������������^�c���Ă��������Č���Ŋ撣���Ă�����Ⴝ���́A�������������̊W�҂ł���悤�ȁA���p���œd�ԏ�����肵�āA�������t�Ō���ꂽ��Ƃ�����������ł����āB�������������ł��A���_�������ɁA�Ђ�����I��̂��߂Ɋ撣���ĉ^�c����Ă����B���������l�����ɑ��āA���������s���������Ă����̂͂�����Ɓv�Ǝ���Ђ˂����B
���̂����Łu���{�̕����_�u���X�^���_�[�g�Ƃ������A�ǂ��ڎw�����낤�ƁB�[���R���i���ē���B�ǂ������ӂ��Ɍ��������Ă����̂����l���Ă����Ȃ��ƁB�����Ґ��������������Ă���̂͂������m���Ă�B�ł��A�ǂ������ӂ��ɑΉ����āA���N���ė��N������𑱂���́H���āB�����������Ƃ��w�j�Ƃ��Č��߂Ă��������Ȃ��Ɓv�Ɠ����������B
�Љ�w�҂̌Îs������(36)���u�[���͓���v�Ƃ��������Łu���낻��R���i�Ƃ̕t�����������l�����ق��������v�Ǝw�E�B�u����Ȃɔߊς��Ă��Ȃ��āA���N�`���ڎ킪�i��ł���̂ŁA10���̏I���Ƃ�11�����炢�ɂ͊�]����l�݂�ȑłĂ�悤�ɂȂ�Ǝv���B���N�`���A�łĂ�l��2��ł����i�K��������A�����������ɎЉ���~�߂Ă��u���������͂Ȃ��Ȃ�Ǝv���B����ł����N�`���ł������Ȃ��l�Ƃ��C��t����l�͋C��t��������Ǝv�����A�Љ�݂�Ȃ��~�߂Ă��������������Ȃ�v�ƌ������������B
�������s�A�ϋɓI�u�w�����̋K�͏k���@�R���i�}�g��ŕی����ɒʒm �@8/15
�����s��15���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ɔ����ی����Ɩ��̕N�����A�Z���ڐG�҂⊴���o�H���ڂ������ׂ�u�ϋɓI�u�w�����v�̋K�͂��k��������j��s���̊e�ی����ɒʒm�����Ɩ��炩�ɂ����B�ʒm��1�O���t�B�d�lj����X�N�̍����l��������Ë@�ւ⍂��Ҏ{�݂ł̎���̒�����D�悳���A�ی����̕��S���y������_���B
�s�ɂ��ƁA�ʒm�ł͐ϋɓI�u�w�����ɂ��āA�u�D��x���l�����Č��ʓI�A�����I�Ɏ��{�v�Ǝw���B���҂̃P�A���d�����邽�߁A�a���d�lj����X�N��c�����A��ÂɂȂ��邱�Ƃɏd�_��u�����ƂƂ��Ă���B
�s�̒S���҂́u�D�揇�ʂ������������ŁA�K�v�Ȍ����͎��{�����v�Ƙb�����B
��ʌ���6������A�ی����Ɩ��̕N���𗝗R�ɐϋɓI�u�w�����͈̔͂��k�����Ă���B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
��������2962�l�����A5�l���S�@8/16
�����s��16���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2962�l���ꂽ�Ɣ��\�����B5�l�̎��S���m�F���ꂽ�B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���16�����_��4275�E�O�l�ƂȂ�A�O�T���1�O3�E4���B
�s���ً͋}���Ԑ錾�̔��߂���1�J���ȏオ�o�߁B�ɉ؊X�̐l�o�͂�⌸�������A�����͂������C���h�R���̃f���^�����}�g�債�A�����ґ��Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B
�������s�� ����҂̊��� �l���Ăё��� �d�NJ��҂��{�ȏ�� �@8/16
�����s���ł́A���N�`���ڎ킪�i���Ƃ��犴���ґS�̂ɐ�߂鍂��҂̊����͑啝�ɉ������Ă������A�l���͍Ăё������Ă��܂��B�d�ǂ̊��҂������̑����������A���Ƃ͊�@���������Ă��܂��B
�s����65�Έȏ�̊����҂́A����15���܂ł̔�����2062�l�ɏ��A���Ƃ�5���ȗ�2000�l���Ă��āA6��1�����Ԃ�2.4�{�A7����1.4�{�ł��B
����҂̃��N�`���ڎ킪�i���Ƃ���A�����ґS�̂ɐ�߂銄���͍�����3.4���ƍł������������Ƃ�2����25.2������啝�ɉ������Ă��܂����A�����̋}�g��Ől���͍Ăё������Ă��܂��B
����ɔ����č���̐���̏d�NJ��҂��������Ă��܂��B60��ȏ�̏d�NJ��҂͐挎��30�l�O��Ő��ڂ��Ă����̂��A����15�����_�ł�74�l�ƈ�C�ɔ{�ȏ�ɂȂ�܂����B
�s�̐��Ƃ́u����҂͏d�lj����X�N���������@���Ԃ����������邱�Ƃ�����̂ŁA����̗z���҂̑������뜜�����v�Ƃ��Ċ�@���������Ă��܂��B
�������s ���N�`����K�͐ڎ� �Ώێ҂�p���������Ǝ҂ȂǂɊg�� �@8/16
�����s�͐V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���̑�K�͐ڎ���Őڎ킷��Ώێ҂�p���������Ƃ�A���e����e�A����Ƀo�X��^�N�V�[�Ȃǂ̉^���Ƃɏ]������l�ɍL���邱�ƂɂȂ�܂����B
�s�́A����16�����ŐV�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���̑�K�͐ڎ����݂��Ċw�Z�W�҂Ȃǂɐڎ���s���Ă��܂��B
�s�́A����������K�͐ڎ���ł̐ڎ�Ώۂ��A18������A�p���������Ƃ◝�e����e�Ȃǂ̐����֘A�T�[�r�X�A����Ƀg���b�N��o�X�A�^�N�V�[�Ȃǂ̉^���Ƃɏ]������l�ɂ��L���邱�ƂɂȂ�܂����B
����A�V���ɑΏۂƂȂ�l�����̐ڎ���́A�s���̖k�Ɠ�̓W�]���ƁA�`���R�̖��ԃr���uWeWork�T�؍�v��2�K�ɐV���ɐ݂�������ł��B�\��̓C���^�[�l�b�g�ōs���܂��B
���̂ق��A�E��ڎ�ȂǂŃ��f���i���̃��N�`����1��ڎ킵���l�̒��ŁA��������2��ڂ̐ڎ���邱�Ƃ�����Ȃ����l���V���ɑΏۂɂ��܂��B
�����َs�ŐV�^�R���i�����}�g�� �����͂��łɐ挎��2�{���@8/16
���َs�ł́A�����ɓ����ĐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l�̐������łɐ挎1������2�{���A�������}�g�債�Ă��܂��B�s�����ٕی����́u�ق��̒n��Ƃ̉����Ŋ�������P�[�X���قƂ�ǂ��v�Ƃ��āA�����g��n��Ƃ̉������T����悤�Ăт����Ă��܂��B
���َs��16���A�V���Ɏs����27�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
����Ɋ������m�F���ꂽ�l�̐���2�O�l����͍̂���5���ȗ��ŁA�ߋ�2�Ԗڂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
����Ŏs���Ŋ������m�F���ꂽ�l�̐��͉���1153�l�ƂȂ�܂����B
�����ɓ����Ďs���Ŋ������m�F���ꂽ�l�̐���2�O�O�l�ɏ��A���łɁA92�l�������挎1������2�{�ȏ�ɂȂ�ȂNJ����҂̐����}���ɑ������Ă��āA���َs���̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂�1�O���l������39.3�l�Ɗ������������̃X�e�[�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ��ƂȂ��Ă���1�O���l������25�l��傫�������Ă��܂��B
16���̓N���X�^�[�������҂̏W�c�̊m�F���������A���̂������ٌܗŊs�a�@�ł͍���1�O������15���ɂ����ĊŌ�t4�l�Ɗ���1�O�l�̊������m�F����܂����B
�a�@�ɂ��܂��ƁA����14���Ɍċz����ȂŋΖ����鏗���Ō�t1�l�ɔ��M�Ȃǂ̏Ǐ���ꂽ���߁A�o�b�q���������{�����Ƃ���z�����m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
���̌�A�����Ō�t�ƐڐG�̂������E������@���҂��킹�Ă��悻15�O�l�Ɍ������s�����Ƃ���A�ċz����ȂŋΖ�����Ō�t3�l�Ɠ��@����9�l�̊������m�F���ꂽ�ق��A��T�މ@���Ă�������1�l���������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�Ǐ�͂�������y�ǂ����Ǐ�ŁA�a�@���Ŋ������X�N�̍����G���A�Ɣ�r�I���S�ȃG���A����u�]�[�j���O�v���s���Ď��Âɂ������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�a�@�́A16������1�T�ԐV�K�̓��@���~����ق��A�ꕔ�̊O���f�Â��~���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�܂��A�s���ł͂��̂ق��w���ۈ珊��5�l�A�s�����H�X��8�l�̊������m�F����Ă��āA�s�͂��ꂼ��N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B
�s�����ٕی����́u�ق��̒n��Ƃ̉����Ŋ������A��Г��ȂǂōL����P�[�X���قƂ�ǂ��߂Ă���B�d����A�ȂȂNjً}���Ԑ錾���o����Ă���n��Ȃǂɏo�����邱�Ƃ͂��̕K�v���ɂ��Ă�����x�l���Ăق����B�ǂ����Ă��Ƃ����l�ȊO�͊����g��n��Ƃ̉����͍T���Ăق����v�Ƙb���Ă��܂��B
�܂��A����16���A�V���ɓn���n���3�l���������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B
���V�^�R���i�̎���×{�҂��}���ɑ������钆�Łc�@�ی��Ɩ��@���m�@8/16
�u��ی��Z���^�[�ł��v�u���ꂵ�������Ƃ��A�ǂ��ł����v�u�ǏA�Ԃ�Ԃ��₷����ł��ˁv(�E��)
�₦�ԂȂ��������Ă���z���҂���̓d�b�B
���É��s���̓�ی��Z���^�[�ł́A1����1�O�l�̐E��������×{�҂̑̉���_�f�O�a�x���L�^����ȂǁA���N�Ǘ����s���Ă��܂��B
�u1���Ԏ��5�l�̐V�K�̊��҂��������Ă��܂��B����1�T�Ԃ��炢�́A�����Ƃ���Ȋ����̃y�[�X�v(�ی��t�@�␣�^������)
���m���ł͐V�K�����Ґ��̋}�g��ɔ����A����×{�҂̐����}���ɑ����Ă��āA15�����_��35�O�O�l���Ă��܂��B���̂����A��ی��Z���^�[�Ŏ����Ă���̂�8�O�l�ŁA����1�����ԂŖ�1�O�{�ɁB��������̐��オ���S���Ƃ����܂��B����×{�҂̑̒����������āA���@���K�v�ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�����̕a�@��T���܂����c�B
�u���@����a�@�����܂�܂łɁA���Ԃ������邱�Ƃ��N�����Ă���v(�ی��t�@�␣�^������)
��ی��Z���^�[�ł͑��ɂ��Z���ڐG�҂Ɠ��肳�ꂽ�l��PCR�������s���Ă��āA���̌������啝�ɑ����B�E���͑����Ԃ��Ȃ��Ɩ��������Ă��āA����×{�҂̐������̃y�[�X�ő����������ꍇ�ɂ́A�Ή����x���\��������Ƃ������Ƃł��B
�u�d�����̓R���i�Ή��ɉ����āA���i�̕ی����Ɩ���������t�B�ƂɋA�����牽���ł��Ȃ��A�Ǝ��͑S�Ă�������v(�ی��t�@�␣�^������)
���V�K�����҂��ߋ��ő����L�^����Ȃnj������̈��m���@8/16
�u���T�O���ɂ��A����܂ł̐��l������ (�܂h�~��)�d�_�[�u���́A�g�傷������Ō����������v(�呺�G�͈��m���m��)
���m���̑呺�m���́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑Ώۋ����g�傷����j�������܂����B
���݁A���É��s�Ȃ�12�̎s������Ώۋ��Ɏw�肵�Ă��܂����A�V�K�����҂�8��12���ɉߋ��ő���7�O2�l���L�^����ȂǁA���m�����̌������������A���߂̊����܂��āA�g������߂�Ƃ������Ƃł��B
��16���V�^�R���i�����ҁ@���m��567�l�@��116�l�@�O�d��1�O8�l�@8/16
���C3����16���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ��́A���킹��791�l�ł����B�@�@
���m����567�l�ŁA���̂������É��s��26�O�l�A����s��25�l�A��{�s��21�l�A�L�c�s��44�l�A�L���s��9�l�ŁA���̂ق���2�O8�l�ł����B���m���ł͑O�T�̌��j���A8��9���̊����Ґ���255�l�ł������A����2�{�ȏ�ƂȂ�܂����B
����116�l�A�O�d����1�O8�l�ŁA�����Ƃ�1���̊����Ґ���1�O�O�l����̂�6���A���ƂȂ�܂��B
��������a�@�A��Q�Ҏ{�݂ŃN���X�^�[�g��@���s�@8/16
���s�{�Ƌ��s�s��16���A�j���v321�l���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B���j�̊����Ґ��Ƃ��Ă͍ő��B�{���̊����҂�2��29�O4�l�ƂȂ����B
�{���\����10�Ζ�������9�O���95�l�ŁA61�l�̊����o�H���s���������B�Ǐ�͒����ǂ�1�l�A�y�ǁE���Ǐ�56�l�A������38�l�B���Z�n�͉F���s15�l�A�T���s12�l�A�������s11�l�A��z�s1�O�l�A���s�s7�l�A���ߎs�ƌ����s�A�ؒÐ�s���e6�l�A��O�s5�l�A�����s�Ƌ��c�ӎs�A���ؒ����e4�l�A��R�蒬2�l�A���m�R�s�Ƌ��O��s�A���O�g�����e1�l�������B
���ɃN���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă��闤�㎩�q����v�ے��Ԓn(�F���s)�Ŋ����҂�1�l�����v26�l�A�����߈㐽��a�@(���ߎs)�ł�5�l�����v27�l�A��Q�Ҏ{�݂����ڂ̊w��(��O�s)�ł�4�l�����v23�l�ɂȂ����B���s�s�̔��\����226�l�������B
���V�^�R���i�����g�呱�� ���Ɍ��u�܂h�~�v36�s���Ɂ@8/16
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A���Ɍ��ł́A16������A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn�悪�A36�̎s�ƒ��Ɋg�傳��܂����B�Ώےn��̈��H�X�ɂ́A��ނ̒��l�Ȃǂ��v������A���́A���L���n��Ŋ����g��̗}�����݂�}�肽���l���ł��B
���Ɍ����ł́A14���̓y�j����628�l�A15���̓��j����517�l�̐V�^�R���i�̐V���Ȋ����҂��m�F�����ȂǁA�����g�傪�����Ă��܂��B
�����������A���Ɍ��́A16������A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn����A���k���̒A�n�n�������36�̎s�ƒ��Ɋg�債�܂����B
�Ώےn��̈��H�X�Ȃǂɂ́A�c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łƂ��A��ނ͎̒��l����悤�v�����s���܂��B
���́A�d�_�[�u�̊����ƂȂ鍡�����܂ł̊ԂɁA���L���n��Ŋ����̗}�����݂�}�����A�g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��ꍇ�́A���ɂɋً}���Ԑ錾�����o����邱�Ƃ�����ɁA���Ƌ��c�𑱂��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�V���ɂ܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��ƂȂ������Ɍ��F�{�s�̃o�[�́A�����̃e�C�N�A�E�g���n�߂܂����B
���Ƃ�4���ɃI�[�v�������F�{�s�ɂ���o�[�u�o�[�� ���B�A �R�X�^�v�͋��N�A�V�^�R���i�̉e����2�x�ɂ킽���ăI�[�v�������������ق��A�J�X����ً}���Ԑ錾���o����ċx�Ƃ���Ȃǂ̑Ή�������Ă��܂����B
�X�̔���グ�̂��悻6������ނ��Ƃ������ƂŁA����A�F�{�s���V���ɂ܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��ƂȂ�A��ނ̒��֎~����邱�Ƃ��炢������͋x�Ƃ��������܂����B
�������A�X�^�b�t�̌ٗp����邽�߁A�[����1���Ԃ̂ݓX���J���A�����̃e�C�N�A�E�g�̔����n�߂邱�Ƃɂ��܂����B
�I�[�i�[�̈�ٍK������́u�{���A���̎����͊ό��q�������A�ɖZ���ł����A�ɂȎ����Ɣ�ׂĂ�����グ�͈����ł��B�܂h�~���d�_�[�u�̑ΏۂƂȂ����̂́A�c�O�ȋC�����ł����ς��ł���������������܂���B�d�_�[�u���I��������Ƃ̂��Ƃ��l���X�^�b�t��X�̂��߂ɉc�Ƃ𑱂������Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B
���R���i�����}�g��Ł@�u�Ă̍b�q���v����҂�����ɐ����ց@8/16
�R���i�����̋}�g����ĉĂ̍��Z�싅�́A����5���ڂ���w�Z�W�҂̓��������ɐ�������ƁA���{�������\���܂����B
����܂Ŋw�Z���̍ٗʂŁA�w�Z�W�҂Ƃ��čs���W�҂�m�l�Ȃǂ����ꂪ�F�߂��Ă��܂������A��5���ڂ���͐��k�E�ی�ҁE���E���E�싅���n�a�E�n�f�ȂǂɌ��肵�A�A����̊Ǘ����w�Z���ɋ��߂Ă��܂��B
�܂����Ȃ̊Ԋu���A����܂ł��L�����悤�ɂ���Ƃ������Ƃł��B�@
������{���̏d�ǎҕa�����ׂĖ��܂� �v�_�f���^�̒����Ǖa���� �@8/16
���ꌧ�̉���{���ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŁA�d�ǂ�_�f�̓��^���K�v�Ȓ����ǂ̊��Ҍ����̕a�������ׂĖ��܂鎖�ԂƂȂ�A��Ò̐�����@�I�ȏɂ��炳��Ă��܂��B
���ꌧ��15�����\�����V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���661�l�ŁA��T�̓��j�����87�l�����A���j���̔��\���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�����̑S����r�ł́A�l��10���l������̊����Ґ���14���܂ł�1�T�Ԃ�279.74�l�ƂȂ�A�S���ōň��̊����������Ă��܂��B
�����ł�15���̎��_�ŁA�×{�Ґ���5783�l��5���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�܂��A649�l���a�@�ɓ��@���Ă��āA�����җp�̕a���̗��p���́A���S�̂�83.4���ƂȂ��Ă��܂��B
�����A����{���Ɍ���Əd�ǂ̊��҂�A�_�f�̓��^���K�v�Ȓ����ǂ̊��Ҍ����̕a�����A���ׂĖ��܂鎖�ԂɂȂ��Ă���Ƃ������ƂŁA��Ò̐�����@�I�ȏɂ��炳��Ă��܂��B
���̑��{���ł́u�����h���{�݂ŗ×{���Ă��銳�҂̎�f�̒��������ɍ���ȏƂȂ��Ă���B��Ò̐��̂Ђ����̏�F�����ĕs�v�s�}�̊O�o���T���Ă������������v�ƌĂт����Ă��܂��B
���u�g���ŃK�`���h�������̂Ɂc�v��M����R���i�o���҂̎v���@8/16
�����g�傪�~�܂�Ȃ��V�^�R���i�B13���ɂ͓����s�̐V�K�����Ґ���5000�l�����B�����A�Ԃ牺�����ނɉ������������́A���~�̋A�Ȃ◷�A�s�v�s�}�̊O�o���ł��邾���T����悤�Ăт����B���łɊ�����������×{�҂ɂ��Ắu�K���A��������悤�ɁA�����̂ƘA�g����v�Ƃ��āA�u�_�f�̓��^���K�v�ɂȂ����ꍇ�A�_�f�X�e�[�V������ݒu����B���̑̐������ꂩ�瑬�₩�ɍ\�z����悤�ɊW��b�Ɏw���������v�Ɩ��������B
����Ȓ��A�l�b�g��Łg���錾�t�h���L����������Ă���B���ꂪ�n�b�V���^�O�u#�R���i���a���݂̂�ȂŘb�����v���B����́A�V�^�R���i�Ɋ��������l�X��Twitter�Ŏ���̑̒���A����łǂ̂悤�ɉ߂����Ă��邩�Ƃ��������M�B�s���Ȗ������߂������A���g�ɂƂ��Ă��g�߂ȏ��āA�����n�b�V���^�O���������[�U�[�����݂����܂��������[�u�����g�ɂȂ��Ă���B
�挎30���Ɋ������A����×{�𑱂��Ă���10��̏����̓��e�ɂ́A���X�̑̒��̕ω����ԗ��X�ɂÂ��Ă���B
�u���A���A�A���ɂ��ł��B���M�̑O�������̊߂��ɂ������L��������܂��v
�܂��A����4���ɂ́u�k�o�����S�ɂȂ��Ȃ����v�Ɠ��e�B���݂ł͑̒������A�O�o���ł���悤�ɂȂ������A���߂ĐV�^�R���i�̋��낵����Ɋ����Ă���Ƃ����B
�u�ċx�݂����l���ĕ����ł��}�X�N�t���āA����ŃK�`���������������������́c�����^����c���njo�H�����s�������c�v
SNS��ʂ��čL����Ȃ���̗ցB����ȂȂ���Ɂu�E�C�Â���ꂽ�v�Ƙb���̂́A����10���ɐV�^�R���i�̗z���Ɛf�f���ꂽ�A���G����(����)���B
�u(���N�`����)�ڎ�͑�����6���̓����炢�ɂ�2��ڂ��I����Ă��܂����B���ꂩ��2�J�����炢�Ŋ������Ă��܂��܂����B���͎���×{�𑱂��Ă��܂��v
���N�`����2��ڎ킵����Ɋ��������A���G����B������g�u���[�N�X���[�����h���B�u�����̂Ȃǂ̎x���������Ɏ��ĂȂ��v�Ƙb�����A�A���G����̓l�b�g�̗͂ɂ������������Ă���Ƃ����B
�u�V�^�R���i�ɂ�����Ɓw�邪�|���x�Ƃ����l��������ł��B��ɂȂ�ƌċz�����ɂ����Ȃ�ȂǁA�݂�ȏǏ�������̂ŁA���������b��(�����)�Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ�����ATwitter���炢�������U����ꂪ�Ȃ��B���������l�������������BTwitter�Ŏ����Ɠ����悤�ȏ�Ԃ��������ǁA������������ėǂ��Ȃ��Ă���c�C�[�g������ƁA��������݂ɂȂ��āA�������E�C�Â����܂��v
�����āA�A���G���g���×{���̐H���̓��e�Ȃǂ�Twitter�Ŕ��M�B�������E�C�Â���ꂽ�悤�ɁA�N���̗͂ɂȂ肽���Ƙb���B
�u�R���i�ɂȂ��āA����ς���肩�獷�ʕΌ��I�Ȗڂ������Ȃ����ƁA���낢��l���Ă��܂��āB�R���i�ɂȂ����l����Ȃ��ƁA���̂炳��Љ�I�ȗ��ꂪ�����������Ȃ��Ǝv���܂��B���͍K���A���Ƃŗ×{���邱�Ƃ��ł��Ă���̂ŁA�R���i�ɂȂ��Ă��Ă��H�~���N���A���C�ɂȂ�悤�ȐH����S�����Ă��܂��B���̃��j���[���ʐ^�ŃA�b�v������A���͎���×{3���ڂł����A�����������o���Ŕ��M�ł��邱�Ƃ�����������Ȃƍl���Ă��܂��v
���ܗւƐl�o�u��ۘ_�v�咣�̒m���@���Ԓ��ɍ��~�܂肵���[��̔ɉ؊X�@8/16
�����s�ł̐V�^�R���i�E�C���X�̊����g��́A���ƂɁu����s�\�ȏv�Ǝw�E����郌�x���ɂ܂Ŏ������B���r�S���q�m���́A�����I�����s�b�N(�ܗ�)�̊J�ÂƐl�o�̊W��ے肵�A�ܗ֊��Ԓ��ɐl�o�͌��������Ƃ̕��͂��A�s�[������B�����A���߂̊����Ґ����݂�ƁA�ܗ֊��Ԓ��Ɋ��������l�́A����܂łɂȂ���K�͂Ȑl���ɒB�����Ƃ݂���B
�u��ۘ_�ł���������Ă���B������͐l�����ǂ����������m�F���Ă���v�u�G�s�\�[�h(�o����)�x�[�X�ł͂Ȃ��G�r�f���X(�؋�)�x�[�X�Ō�邱�Ƃ��d�v���v
13���̒���ŁA���r�m���͋��������ł����݂������B�O���ɂ������s�̃��j�^�����O��c�ŁA�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v�����u���Z��̎��ӂ≈���ɑ����̐l���W�܂艞������p������ꂽ�v�Əq�ׂ����Ƃ���ꂽ�ۂ��B
�ً}���Ԑ錾���ł̎��l���������������A�ܗ֊J�Âɂ���Đl�o�������A�����g��̗v���ɂȂ�Ƃ̌����ɑ��A���r�m���͂���܂Łu�ܗւ̎�������20%���Ă���A�X�e�C�z�[���Ɉ���Ă���v�Ƌ������Ă����B13���̉�ł��u�e�����[�N�Ȃǂ̐��i������A�X�e�C�z�[���ʼn������Ē������������オ�����v�Ɖ��߂ďq�ׂ��B
����ɁA�s�͂��̓��A���r�m���̎咣���㉟������f�[�^��˔@���\�����B
�ܗ֊��Ԓ��̐l�o�ɂ��āA���Z����ӂ�s�S���ł̑��O�Ƃ̐l�o���r�����������ʂ��B�J���H�㋣�Z�Ȃǂŏu�ԓI�ɐl�o���������ꏊ�⎞�ԑт͂��������̂́A�����ԑS�̂Ƃ��Ă͑��O�����l�o�͌��������ƌ��_�Â����B
��������ŁA�������X�N�������[��т̔ɉ؊X�ł̐l�o�́A�����Ԓ��ɍ��~�܂肵�Ă����Ƃ̃f�[�^������B
�s��w�����������̒����ɂ��ƁA7��12���ɋً}���Ԑ錾���o��4�T�Ԍ�(8��1�`7��)�̃��W���[�ړI�̑ؗ��l���́A�錾���O��1�T�ԑO�Ɣ�ׂ�17�E6%���B�����錾���O��1�T�ԑO�Ɣ�ׂ�3�T�Ԍ�(7��25�`31��)��20�E8%�������A�������͉��������B
���R���i���̓����p���A���Ɓu�ł��Ȃ��Ƃ͌���Ȃ����v�@8/16
24���J���̓����p�������s�b�N�ɂ��āA���{�A�����s�A���g�D�ψ���A���ۃp�������s�b�N�ψ���(IPC)��4�҂̑�\�ҋ��c��16���A�����s���ł���A���ׂẲ��ň�ʂ̊ϋq�����Ȃ����Ƃ����߂��B
�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾���o�Ă����s���̉��Ɉ�ʋq�����Ȃ����Ƃ́A�����I�����s�b�N(�ܗ�)�̕����_�Ŋ���H���������B����ɐ쏟�����m�������ɋً}���Ԑ錾�̓K�p��v�����A�Ώےn��ɒlj����������ƂȂ����É����ɂ��Ă��A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A�L�ϋq������j�]�������B�w�Z�A�g�ϐ�v���O�����́u����I�ȈӖ��������傫���v�Ƒg�D�ςȂǂ������̉\����T���Ă������A�f���^���̍L����Ȃǂ�����A�����̂�w�Z�ݒu�҂ɔ��f���ς˂�`��������B
�g�D�ς͓����A�ܗւƃp�������s�b�N�Ōv900���~�̃`�P�b�g������������ł������A�قƂ�ǂ����ϋq�ɂȂ������ƂŐ��S���~�K�͂̐Ԏ��ɂȂ�Ƃ̌����Ă�����A����ɓs�ƍ������c���錩�ʂ����B
���������A�����������N���Ă����s���Ńp�������s�b�N���J�Âł���̂��B���ۈ�Õ�����̏��{�N�Ƌ���(�����NJw)�́u�ł��Ȃ��Ƃ͌���Ȃ����A���Ȃ�ܗւ̌o�������A����Ɉ��S�ʂ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƙb���B
�I����O���Ɗu������u�o�u���v�����ɂ��āA�ܗւł͈ꕔ�̑I�肪�W�܂��Ĉ�������ȂǁA�������X�N������s����}���ł��Ă��Ȃ������_�������A�u�Ď��Ԑ��ɕs�����������v�Ǝw�E�B�u��K�͂ȃN���X�^�[���N���āA�ܗւ͎��s���ƌ����Ă����������Ȃ������B�����҂����Ȃ����܂����̂͌��ʘ_���v�Ƃ݂�B
��IPC�p�[�\���Y��������@�����p���A�ϋq�̈������c�@8/16
24���ɊJ�����铌���p�������s�b�N�Ɍ����āA���ۃp�������s�b�N�ψ���(IPC)�̃p�[�\���Y���16���A�H�c��`���̍q��@�ŗ��������B���I���܂ő؍݂���B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A�ϋq�̎���ɂ��āA���{�A�����s�A���g�D�ψ���AIPC��16����ɑ�\�҂ɂ�鋦�c���J���A���j�����肷��\��B8���ɕ����������ܗւ́A�啔���̉�ꂪ���ϋq�ŊJ�Â��ꂽ�B
�p�������s�b�N�ً͋}���Ԑ錾�����߂���Ă��铌���s�ƍ�ʁA��t�����́A��ʊϋq����ꂸ�ɊJ�Â�������ƂȂ��Ă���B�u�w�Z�A�g�ϐ�v���O�����v�͎��{��������Œ������Ă���B
���ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��g�� ���{�����T�O���ɂ����� �@8/16
�V�^�R���i�E�C���X�̋}���Ȋ����g�傪�e�n�ő����A�d�ǎ҂̐����������Ă��邱�Ƃ��āA���{�́A���T�O���ɂ��W�t���ɂ�����J���ċً}���Ԑ錾�̑Ώےn��̊g��Ȃǂ��������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���15���A�����s���ŁA���j���Ƃ��Ă͍ł�����4295�l�ƂȂ����ق��A14���ɂ�10����{���ʼnߋ��ő��ƂȂ�ȂǁA�e�n�ŋ}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B
�S���̏d�ǎ҂̐������̂����_��1563�l�ƁA3���A���ōő����X�V���Ă��āA��������b�́A���̂��A�����J���Ȃ̒M�����������炩��A�e�n�̈�Ò̐��Ȃǂɂ��āA1���ԋ߂��ɂ킽���ĕ��܂����B
���{�́A���T�O���ɂ��A��������b�Ɛ����o�ύĐ��S����b�A����ɓc�������J����b��W�t��������J���A������a���̂Ђ��������܂��A��������Ȃ�6�s�{���ɏo����Ă���ً}���Ԑ錾��A13���{���ɏo����Ă���A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��̊g����������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���ً}���Ԑ錾��9�����܂ʼn����ցA3�{�����lj��|�@8/16
���{���V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ً}���Ԑ錾�̊�����9�����܂ʼn�����������Œ����ɓ������A�ƎY�o�V���d�q�ł������̐��{�W�҂̏�����ɕ��B
�ɂ��Ɠ����s�Ȃǂɉ����A����31���܂ł������Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p���Ă��鋞�s�{�ƕ��ɁA���������ɂ��V���ɐ錾�߂�������Ō������Ă���B���`�̎͊W�t���ƑΉ������c������ŁA17���ɂ����Ƃł����{�I�Ώ����j���ȉ�Ɏ���A������������Γ����̑��{���Ő������肷��B
����16���A�s���̊����}�����u�S���̊����g���}���邱�ƂɂȂ���v�Əq�ׁA�s�ƘA�g���Ĉ�Ò̐��Ȃǂ̍\�z��i�߂�l�����������B�d�lj��̖h�~���ʂ�����R�̃J�N�e���Ö@���s�����Ƃ��ł���Վ��{�݂�S���̋��_�ɐ�������Ƃ��b�����B�S����1000�̕a�@��4000�l�ɓ��^���A���ʂ��������Ƃ����B���Ö@�ɂ�铊����J�n�����z�e�����̎{�݂����r�S���q�m���Ƌ��Ɏ��@��A�L�Ғc�Ɍ�����B
7��12���ɔ��߂���4��ڂً̋}���Ԑ錾�͓���8��22�����������������A�����g�傪���������Ƃ���31���܂ʼn������Ă����B16���ɔ��\�����s���̐V�K�����Ґ���2962�l�A�d�ǎҐ���7���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�268�l�������B�S����1��������V�K�����Ґ���13�A14�̗�����2���l�����B
�錾�����������ΏH�̐��������ɂ��e����^����B�����ʐM�ɂ��ƁA�����}�͐��̑��ٔC�������ɔ������ّI�Ɋւ��āu9��17�������|29�����J�[�v�����Ɍ����ɓ����Ă���B����ɏO�@�����U����A���ّI�͏O�@�I��Ɏ��{����錩�ʂ��Ƃ��Ă��邪�A�������܂Ő錾��������5���̓����p�������s�b�N���̉��U�͍���ƂȂ肻�����B
�����t�̎x�����͎����ʐM��6�|9���ɍs�������_�����őO����0.3�|�C���g����29.0���B�����^�c������ȁu�댯����v�Ƃ�����3����2�J���A���ʼn�������B
���錾�u9��12���܂ʼn����v�ā@�\���u�_�f�X�e�[�V�����v�Ƃ́@8/16
�����Ȃ�6�̓s�{���ɔ��ߒ��ً̋}���Ԑ錾�́A�Ăщ�������錩�ʂ��B�������́A9��12���܂łƂ���Ă����{���Ō�������Ă���B����16���A���r�m����ƂƂ��ɁA�����E�`��̃z�e�����ɐݒu���ꂽ�×{�{�݂ցB�d�lj��h�~�̌��ʂ�����u�R�̃J�N�e���Ö@�v�̎��{�Ȃǂ����@�������ƁA������ĉ�ɗՂ݁A����̊�����ɂ��Ęb�����B
���`�̎u�܂������̊�����}���邱�Ƃ��A�S���̊����g���}���邱�ƂɂȂ���v
���r�S���q�s�m���u���ƘA�g��}�邱�Ƃ��A�s���̖��A�����Č��N����邱�ƂɂȂ����Ă���v
16���A�����s�ł́A�V����2,962�l�̊������m�F�B���j���Ƃ��ẮA�ő��̐����B�S���̏d�ǎ҂��A�O�̓�����40�l������1,603�l�ƂȂ�A4���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�ȂǁA�����̋}�g�傪�~�܂�Ȃ��B�s���ł́A����×{�҂��A��T���߂�2���l��˔j�B���̊�@�I�ɁA���͂�����ł��o�����B
���`�̎u(����×{�҂ւ̑��?)�Ⴆ�A�_�f�̓��^���K�v�ɂȂ����ꍇ�A�_�f�X�e�[�V������ݒu���āv
����×{�҂Ɏ_�f�𓊗^���邽�߂́u�_�f�X�e�[�V�����v�̐����B���́A�_�ސ쌧�ŁA���łɉ^�p���n�܂��Ă����B���@���K�v�Ȋ��҂ɑ��A�����悪���܂�܂ł̊ԁA���}���u�Ƃ��Ď_�f���^������ً}�{�݂Ƃ����ʒu�Â��B
���{�W�҂́A�u�|�[�^�u���̎_�f��u���Ă��B�����s�̃R���i��p�a�@�Ƃ��a�����Ă��ˁB���������Ƃ�������p������������邵�A�_�f�ʂ��W�߂āA�ǂ����̌����ł�邱�Ƃ����邩���B���A�����s�Ƃ��b�����Ă���v�Ɛ����B
���������Ƃ���́A���O�̐����オ���Ă���B���a��w�E��ؖF�l�q�������u�_�f���^�͊�{�I�Ɏ��ÂƂ������A���҂���̏Ǐ���ɘa���邾���̗Ö@�ł�����A��͂肻�ꂾ���ł͕s�\���B�K�v�Ȋ��҂��s�����邩�ǂ����Ƃ����Ƃ�����傢�ɋ^��ł���ˁv����ɁA�{�݂̊J�݂ɂ��A��t��Ō�t�s�����������邨���������A����ł́A������x�̎��Â��ł���{�݂𑝂₷���Ƃ��}�����Ǝw�E����B
�����ŕ��シ��̂��A�����s�ł�7������ݒu���n�܂�A���݁A���ꌧ�Ȃǂʼn^�p���n�܂��Ă���u���@�ҋ@�X�e�[�V�����v�B�̈�ق�a�@���̋��������p���A����×{�Ȃǂŗe�̂������������҂̓��@�悪������Ȃ����ɁA�ꎞ�I�Ȏ��Â��s���A����Ζ��a�@�I�{�݁B
���{�́A�ً}���Ԑ錾�̊��������ɉ����A�V���ɋ��s�{�ƕ��Ɍ��A�����������ɁA�錾�̑Ώۊg��������B17���ɊJ�����{���{���ŁA�������肷������B������...�B
���a��w�E��؋����u(�ً}���Ԑ錾�ɂ��Ă�?)�����P�ɒn�����Ԃ����������Ƃ��������ł́A���͂قƂ�Ǎ��̃^�C�~���O�ł͌��ʂ������Ȃ��Ǝv���v
��T�A���́A�����郍�b�N�_�E��(�s�s����)�ɂ��āA�u���E�Ń��b�N�_�E������A�O�o�֎~�ɔ��������Ă��A�Ȃ��Ȃ���邱�Ƃ��ł��Ȃ���������Ȃ��ł����B��͂胏�N�`�����Ƃ������ƂŁA�l���̗}���Ɠ����ɁA�������������ƂɁA��������S�͂Ŏ��g��ł��Ă��܂��v�Əq�ׂ��B
���ً}���Ԑ錾�A9�����܂ʼn����ց@���s�A���ɁA�������lj��@8/16
���{�́A�S���ŐV�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂��}�����Ă���̂��A�V�^�R���i���ʑ[�u�@�Ɋ�Â������A�_�ސ�A��t�A��ʂ�1�s3���Ƒ��{�A���ꌧ�ɔ��ߒ��ً̋}���Ԑ錾�̊�����9�����܂ʼn�����������Œ����ɓ������B�܂��A����31���܂ł������Ɂu����(�܂�)�h�~���d�_�[�u�v��K�p���Ă��鋞�s�{�ƕ��ɁA���������ɂ��V���ɐ錾�߂�������Ō������Ă���B�����̐��{�W�҂�16���A���炩�ɂ����B
���`��(�����E�悵�Ђ�)�͐����N���o�ύĐ��S������c�����v�����J������W�t���ƑΉ������c������ŁA17���ɂ����Ƃł����{�I�Ώ����j���ȉ�(���g�Ή)�Ɏ���A�����������������o�ē����̑��{���Ő������肷��B
1��������̍����̐V�K�����Ґ���13���ɏ��߂�2���l��˔j�B7��29����1���l���Ĉȗ��A2�T�ԗ]��Ŗ�2�{�ɒB�����B����ɔ����A�S���̎���×{�Ґ�������11���ߑO�O�����_��7��4�O63�l�ƂȂ�A�O�̏T(4�����_)�����2��8�O�O�O�l�����B�l��1�O���l������̗×{�Ґ���33�s���{���Ő��{�̐V�^�R���i�����ȉ�����X�e�[�W4(�����I�����g��)�ƂȂ��Ă���B
65�Έȏ�̃��N�`���ڎ킪�L���莀�Ґ��͌�����������A�C���h�R���̕ψي�(�f���^��)���҈Ђ�U�邤���ŎႢ����̊������}�g��B�{���͓��@���K�v�Ȋ��҂��a���s���œ��@�ł��Ȃ��P�[�X���������ł���B���{�͐V���Ȋ����҂�}���A�a���m�ۂ��m���ɂ��邽�߂ɂ͐錾�������s���Ɣ��f�����Ƃ݂���B
���{�͐錾�����ɍ��킹�A�k�C���A�����A���A�ȖA�Q�n�A�É��A���m�A�ΐ�A����A�F�{��1�O�����ɓK�p���̖����h�~���d�_�[�u�ɂ��Ă�9�����܂ʼn������錩�ʂ����B
���ً}���Ԑ錾�͔N�������ς��������A���N�`��8��������11���܂ł��c�@8/16
�₯�̂��ς��Ȃ̂��A�E�B�Y�R���i�Ȃ̂��B�ɉ؊X����l���������A�V�^�R���i�E�C���X�̊��������͎��܂�C�z���Ȃ��B6�s�{���ɔ��߂���Ă��鍡�����������ً̋}���Ԑ錾���A���͂≄���m���̏�ɂȂ��Ă����B���������A���܂ʼn������ꂻ���Ȃ̂��B
�������Ƃ�킯�[���Ȃ̂������s�Ɖ��ꌧ���B����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ�(14������)��212.76�l��280.87�l�ŁA�t�Ɋ������������C���h�̃s�[�N��198.5�l��傫�������Ă���B������15���̐V�K�����Ґ���4295�l�ŁA���j���̍ő����X�V�B�s�̊�ɂ��d�ǎҐ���6���A���̍ő��X�V�ŁA251�l�ɑ������B��������j�Ƃ��Ă͉ߋ��ő���661�l�̊��������������B�u���Ƃ���͔N�������ς��̐錾���������߂鐺���オ���Ă��܂��B�����I�ȗ��R�ł��ꂪ�������Ƃ����̂ł���A�����w�S������8���ڎ튮���x�̖ڕW�����Ɍf����w10������11���܂ł̑��������x�܂ʼn�������K�v������A�Ƃ̑i��������B�ł����A�����}���ّI�ƏO�@�I���T���钆�ł̒��������́w�o���Ȃ��x�w�ł�Ȃ��x�ƔF�߂�悤�Ȃ��́B9�����܂ł�1�J�������������I�I���ɂȂ肻���ł��B�����A1�J���̉����ōςނ̂��ǂ����B�f���^���̊����͔͂��[����Ȃ��B�ĉ����ɒǂ����܂�鋰�ꂪ����܂��v(���J�ȊW��)
����1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ����X�e�[�W4�̖ڈ��ƂȂ�25�l�ȏ�������̂ɁA�C���h�ł̓s�[�N����2�J����v���Ă���B
�|���č����ł�35�s���{�����X�e�[�W4�A10�����X�e�[�W3���x���B�����g���}������ł���̂͏H�c�Ɠ����̗����������B�f���^�����҈Ђ�U�邤��5�g���A����1�J�����ŗ}�����ނ̂́A����܂��y�ϓI�߂���V�i���I�Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�����Ґ��̑������O���t������ƎR�`�Ȑ���`�����߁A�g�ɗႦ����B��1�g�����4�g�܂ł́A2�J���قǂ͈̔͂Ɏ��܂�A�R�͂����ނˍ��E�Ώ́B�s�[�N�ȑO�ƃs�[�N�ȍ~��1�J�������������Ă����B�������A7��12����4��ڂ̐錾�������ɔ��߂����1�J�����߂������A��5�g�͂��܂��Ƀs�[�N�͌����Ă��Ȃ��B
���a���w���q�������̓�ؖF�l��(�Տ������NJw)�͌����B�u�������{�ɂ̓s�[�N�ɒB����ƌ��Ă��܂����A24���ɊJ�����T����p�������s�b�N�������ɂǂ��e�����邩�B�錾�̊���������������A�Ώۂ��g�債���Ƃ���ŁA����ł͋�̓I�ȑ�ɖR�����A�����}�~���ʂ͂��͂���҂ł��Ȃ��B�v���X�|�[�c�C�x���g�̒��~��V����y�{�݂̋x�ƂȂǁA�s���葽���̐l���W�܂�@����Ȃ��������������B�ڂɌ�����`�ŋ���ȃ��b�Z�[�W��ł��o���K�v������̂ł͂Ȃ����v
���O�ʂ�A�����ܗ��s�Ŋ��������B������S�}�J�����߂ɂ܂�����̏��o����o���ł́A�~����͂��̖����ǂ�ǂ�~���Ȃ��Ȃ�B
���ً}���ԁA�É��E���ɁE�����Ȃ�7�{���lj��@����12���܂ŁA�����Ȃlj����@8/16
���{��16���A�V�^�R���i�E�C���X�����̋}�g����A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��Ɉ��A�ȖA�Q�n�A�É��A���s�A���ɁA������7�{����lj�������j���ł߂��B���Ԃ�2�O������9��12���܂ŁB�����A���Ȃ�6�s�{���ɔ��ߒ��̐錾���A�����܂ł̊���������ɍ��킹�ĉ����B�܂��A�{��Ȃ�1�O���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v��V���ɓK�p����B17���ɐ��Ƃ�ɂ���{�I�Ώ����j���ȉ�Ɏ�������Ő������肷��B
���`�̎�16���A�����N���o�ύĐ��S������W�t���Ǝ��@�ŋ��c�B���̌�A�L�Ғc�Ɂu�S���I�ɉߋ��ő�̊����g�傪�������A�錾��d�_�[�u�ɂ���17���̕��ȉ�ɂ����邱�Ƃ����肵���v�ƕ\�������B
�́A���N�`���ڎ�̉������Ȃǁu�����ɉe�����Ȃ��悤�ɂ��邽�ߑS�͂Ŏ��g��ł���v�Ɛ����B�u�ڐ�̂��Ƃ̉����Ɍ����đS�͂ł��̂����̐Ӗ����v�Ƌ��������B
�d�_�[�u�͌��݁A13���{���ɓK�p���B���̂���7�{����錾�ɐ�ւ��A�c��6�����͌p������B
�V���ɏd�_�[�u��K�p����̂́A�{��A�x�R�A�R���A�A�O�d�A���R�A�L���A����A���Q�A��������1�O���B���Ԃ�2�O������9��12���܂ŁB
����ɂ��A�錾��13�s�{���A�d�_�[�u��16�����ɁA���ꂼ��g��B�S�s���{���̖�6�����錾�E�d�_�[�u�̑ΏۂƂȂ�B
����A�S���I�Ȋ����g��܂��A���{��t��Ȃǂ͑S���ւ̐錾�g��̌��������߂Ă��邪�A���{�͐T�d���B���ӂ́u�S���ꗥ�̐錾�͍l���Ă��Ȃ��v�ƒf�������B
���ً}���Ԑ錾�Ƃ܂h�~�[�u
�y�ً}���Ԑ錾��13�s�{���Ɋg��z
6�s�{���������������A��ʁA��t�A�_�ސ�A���A����̊�����8��������9��12����
7�{����lj������A�ȖA�Q�n�A�É��A���s�A���ɁA����(�܂h�~���d�_�[�u�����ւ��B9��12���܂�)
�y�܂h�~���d�_�[�u��16�����Ɋg��z
6�������������k�C���A�����A�ΐ�A���m�A����A�F�{�̊�����8��������9��12���ɉ���
10����lj����{��A�x�R�A�R���A�A�O�d�A���R�A�L���A����A���Q�A������(9��12���܂�)�B
���R���i�}�g��ł������Ґ��ɘa�̕@1��2000�l��3500�l�Ɂ@8/16
�ً}���Ԑ錾�̐^���������ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̐��ۍ�킪�����ɘa���ꂽ�悤���BNHK�ɂ��ƁA1�����悻2000�l�ɗ}�����Ă��������҂̏���ɂ��āA���́A2021�N8��16�����炨�悻3500�l�ɍL���邱�Ƃɂ����Ƃ����B�R���i�Ђ��ő勉�Ɋg�債�A�f���^���ɉ����ă����_���ȂǐV���ȕψي��̋��Ђ������Ă��邾���ɁA�C���^�[�l�b�g�ŋ^��̐����o�Ă���B
���̃j���[�X��NHK��14���A�u�W�҂ɂ��Ɓv�Ƃ����`�ŕ��B�����I�����s�b�N�������Č��u�̑Ԑ��ɗ]�T���ł������Ƃ�A�C�O�ɂ�����{�l�̋A�����v�����܂��Ă��邱�ƂȂǂ��ɘa�̗��R���Ƃ����B
���{�͍��N3���ȍ~�A�V�^�R���i�E�C���X����������邽�߁A�����Ґ��̑������A���{�l�ƁA�ݗ����i������O���l�̍ē������܂߁A1��2000�l�ȉ��ɗ}���A���ې����^�q���Ă���q���Ђɓ���Ґ��̐�����v�����Ă����B
�q��̏���z�M����uAviation Wire�v�ɂ��ƁAANA(�S����)��JAL(���{�q��)�́A���ې���1�T�ԓ�����̓���Ґ���1�Г�����3400�l�ɗ}���Ă������A16�������6100�l���Ɋɘa�����B
�C�O�̍q���Ђ́A����܂�1�ւ�����40�l���������A16������31���܂ł͓�70�l�Ɋɘa�B9��1������30���܂ł͓�80�l�ƂȂ錩�ʂ����Ƃ����B
�R���i�ЂŌo�c�I�ɋꂵ��ł����q���ЂɂƂ��ẮA�킸���Ƃ͂����A�������������߂�B
�����҂��������{�����ł́A���ĂȂ������ŃR���i�̊����҂��������Ă���B�C�O���玝�����܂ꂽ�f���^���ɂ����̂��B�ŋ߂́A�V���Ƀy���[����̗����҂��A����Ă𒆐S�ɖ҈Ђ�U�邤�����_���Ɋ������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�������B
�C�O����N�����Ă���ψي��ɁA�ő勉�̌x�����v������Ă��鎞�Ȃ̂ɁA���˂ɓ����ɘa�����܂������Ƃɑ��A�l�b�g�ł͋^��̐����o�Ă���B
�u�ً}���Ԑ錾�Ȃ̂ɓ����ɘa�͂Ȃ��v�u�f�p�[�g�͓���K���A�C�O����͓����ɘa�v�u�����ɂ͎��l����A�O�o����Ȃƌ����Ă�̂Ɂv�u�����_���������ɘa�v�ȂLj�a����i���鐺�������B
���{�͂��łɁu���N�`���p�X�|�[�g�v��7��26������X�^�[�g���Ă���B�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���ڎ�������Ƃ��ؖ�������̂��B���O���ɓ������₷���Ȃ邪�A���p�\�ȍ��͂܂������͂Ȃ��B
���������u�ɘa�[�u�v�͊�{�I�ɑ��ݎ�`�Ȃ̂ŁA���{����������₷�����𑝂₷�ɂ́A���{������������Ȃǂ��ɘa����K�v������B���̂��߃l�b�g�ł́A�u�����ɘa�ŁA�C���o�E���h�o�ς������ł������̂ł��傤�v�ȂǂƂ����������o�Ă����B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������Ŋ����g����܂炸�@���A���r�s�m���Ɂu���\������v�Ɣᔻ�@8/17
���r�S���q�m���ւ̕��������ς���Ă��Ă���B�����g�傷��V�^�R���i�E�C���X�ւ̑Ή����傫�ȗv�����낤�B�����s���ł�8��16���A���j�ł͉ߋ��ő���2962�l�̐V�K�����Ґ����m�F���ꂽ�ق��A�d�ǎҐ���7���A���ʼnߋ��ő���268�l���m�F���ꂽ�B
�ً}���Ԑ錾���o�Ă���ɂ�������炸�A�s���̌��i�ɂ͕ω����݂���B�w�ł͒ʋ��b�V�����������Ȃ��A�����[�g���[�N���i��ł���Ƃ͌�����Ȃ��B���H�X�͎�ނ̒�~�ƌߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ��v������Ă��邪�A�ɉ؊X�̉f�����f���o�����ƁA�[��܂ʼnc�Ƃ��Ă�����H�X�̐��������A20��̎�҂𒆐S�ɘH����s�������l�̐��������B�����ł��H����݂̌��i��������B
�u�ً}���Ԑ錾�������Ɏ��������Ō��͂��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�\���Ȑ����ӔC���Ȃ��܂ܓ����ܗւ��J�Â����㏞�͑傫���B�����̊ԂŐ����s�M�����A���Ⓦ���s�̌Ăт����Ɏ����X���Ȃ��Ȃ��Ă���B���H�X�̌o�c�҂ɘb���ƁA�w�������r����̘b�͕����Ă����Ȃ��B�[������������Ȃ��A�䖝���Ă���̈�_����B����Ȃ�A�Ȃ����{�ƈꏏ�ɓ����ܗ֊J�ÂɎ^�������̂��B����ȏ�䖝���Ă�����X���Ԃ�Ă��܂��x�Ƙb���Ă��܂����B�������łȂ��A���r�s�m�����s���̋��S�͂������Ă��Ă���ł��v(�e���r�ǂ̐������L��)
���r�s�m����13���ɋL�Ғc����R���i�̊����g��ň�Ñ̐����Ђ������Ă��邱�ƂɎ��₪�y�ԂƁA�u�O�o���T���Ă��������B��������������̐l���o�Ă����܂����A��J���R���i�������ł��B�ЊQ�ɂȂ�܂��B��낵�����肢���܂��v�ƌĂъ|�����B�����A���̍ЊQ�Ƒ������R���i�����g��̏ŁA���{�Ƌ��ɓ����ܗ֊J�Â֓˂��i�B���̖����ɑ��A�����ӔC���ʂ����Ă��邾�낤���B
12���̓����s�̃��j�^�����O��c�ł́A�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v�E���ۊ����ǃZ���^�[�����ܗւ̉e���ɂ��Č��y�B�u�������X�N�������ɂ�������炸�A�ܗ��Z��̎��ӂ≈���ł́A�吨�̐l���W�܂�A��������p������ꂽ�B���܈�x�A���O�ł����Ă����W�E���ڂ��邱�Ƃ́A�������X�N���������Ƃ��[������K�v������v�ƌx����炷�ƁA���r�s�m���͐^��������ے肵���B�u��Ȑ搶�͈�ۘ_�ł���������Ă���v�ƃo�b�T���B�u��ʎ��v�}�l�W�����g���l���}���ɖ𗧂����B�����ɂ��\��Ă���B�e�����[�N�̐��i���}�����B���C�u�T�C�g���������A�X�e�C�z�[���ʼn������Ă������������炱���A���������オ�����v�Ƌ���������ŁA�u�G�s�\�[�h�x�[�X�ł͂Ȃ��G�r�f���X�x�[�X�Ō�邱�Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ��B
���̏��r�s�m���̑Ή��ɑ��ASNS�A�l�b�g��ł́A�u�e�����[�N�͐Z�����Ă��Ȃ����A�e���r�̎��������オ���������̐Ǝ�ȍ������G�r�f���X�x�[�X�Ƃ������Ȃ�B����Ȑl���s�m���ł��邱�Ƃ��p���������B����������r���������Ă��邱�Ƃ͍���������t�Ȃł��邱�Ƃ���Ŗ��\������B�����N���������Ƃ��Ȃ���(�����}�})�v�A�u�s���⍑���̎��l�w�͂��A�I���p�����s�J�ÂŖ��ɂ���B�ɂ�������炸�A�l�����`�A���l���ꂪ�`�A��҂��`�A�Ǝ������l�̂����ɂ���ẮA���͂���C���b���C�������Ȃ�̂́A���R�̎����Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��傤���ˁA���r�������B�t�M���������̂͂�����ł���(�����}�})�v�Ȃǔᔻ�I�ȃR�����g���E�����鎖�ԂɂȂ����B
7��4���ɓ��J�[���ꂽ�s�c��c���I���ł́A���r�s�m�����x����n�搭�}�E�s���t�@�[�X�g�̉�����Ƃ킸��2�c�ȍ��̑�2�}�B�����O�̏�����ȂǂŁu���������E�s���t�@�S�s�v�Ƃ̗\�������ʂɂȂ����B�������O�ɉߘJ�œ��@�������A�I���I�ՂŌ����ɕ��A�������r�m���͍ŏI���ɓs���t�@���̉����ɋ삯�t���ė����ς����B�u���r�}�W�b�N�v�̌��݂Ԃ�����������B
�����A�O�o�̐������L�҂́u�s���t�@�[�X�g�̉�P�킵���̂͏��r����̗͂����ł͂Ȃ��v�Ƙb���B
�u���̎��͓����ܗւŊϋq�����ĊJ�Â��邱�ƂɑO�������������ւ̓{���s���Ŏ����}�����ł����������������B���͏��r�s�m���ɑ��Ă������̕s�M��������Ă���B�R���i��Ő��O����}���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��v
���r�s�m���͂��̋t�������z���邱�Ƃ��ł��邩�B
�������s�u�u�w�������d�NJ��ґΉ���D��v�ی����Ɏw���@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�����҂������I�ɍL�����Ă��铌���s���A�e�ی����ɑ��Z���ڐG�҂̉u�w�����ł͂Ȃ��d�NJ��҂ɑ���Ή���D�悷��悤�ʒm�����Ɠ`����ꂽ�B�����҂̋}���ɑ��E�����s�����Ă���ی����̌����f�������̂ŁA�����̐V�^�R���i�̏��댯���ʂɒB�������Ƃ������Ă���B
�Y�o�V���́A�����s���u�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ɔ����ی����Ɩ��̕N�����A�Z���ڐG�҂⊴���o�H���ڂ������ׂ�w�ϋɓI�u�w�����x�̋K�͂��k��������j��s���̊e�ی����ɒʒm�����v��16�������B�����҂��}�����ĉu�w�����ɑ����̎��Ԃ��������Ă�������A����͊w�Z�⍂��Ҏ{�݂ȂǏW�c�����̃��X�N�������Ƃ���𒆐S�ɒ�������v�悾�B������A���K�͊����̒��������������Ƃ������Ƃ��B
����Ɋe�ی����́A�����҂̕a��d�ǂɐi�ރ��X�N������ꍇ�A��Ë@�ւɘA������Ɩ��ɏW��������j���B�����̂Ƃ���A�����҂͑����Ă��邪��Ë@�ււ̓��@������Ȃ��Ă���A���Â����Ȃ��܂��S���鎖�Ⴊ�o��ȂǁA��ÃV�X�e���ɑ���s�������܂��Ă���B�����ʐM�́u�s���̎���×{�҂���@�E�h���×{�҂��̊����҂�15�����_��3��5000�l�����v�Ɠ`�����B
���{�łً͋}���Ԑ錾�ȂNj��͂Ȗh�u�{�s����Ă��邪�A�����𒆐S�ɂȂ��Ȃ��V�^�R���i�̊g�U�X���Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B�킸��1�J���O�܂ł͈���̐V�K�����҂�1��l�]�肾���������́A����4��`5��l��ɑ����Ă���B13���ɂ�5773�l�ʼnߋ��ō����L�^���A15����4295�l�œ��j����ōł����������B
�ŋ߁A���{�S��ŐV�^�R���i�����҂������2���l���L�^���A���{���{�͋߂������ɋً}���Ԑ錾�̑Ώےn����g�傷����Ă��������邱�Ƃɂ�����NHK�����̓������B���݁A�����A���Ȃ�6�s�{���ɋً}���Ԃ��錾����Ă���A13���{���ɋً}���Ԃɏ�����u�܂h�~���d�_�[�u�v��������Ă���B
�������ً̋}���Ԑ錾��9��12���܂ʼn����A�S�ݓX�̓��ꐧ���O��@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A���{�͓����s�Ȃ�6�s�{���ɔ��ߒ��ً̋}���Ԑ錾��9��12���܂ʼn�������B���s�A�����Ȃ�7�{�����Ώۂɒlj�����B
17���[�̐��{���{���Ō��肵���B���`�̎́u�ŗD��̉ۑ�͊��҂̖����~�����߂̈�Ñ̐��̍\�z���v�Əq�ׁA�z�e���×{���܂߂��ő���̕a����ς݂��s���Əq�ׂ��B�����h�~�̓O��ƃ��N�`���ڎ�ƍ��킹�A3�{���ő��i�߂�Ƃ�������B
��ނ̒��l�ɉ����A�S�ݓX�ȂǑ�^���Ǝ{�݂̓��ꐧ���̓O��⍬�G�����ꏊ�ւ̊O�o�@��̔������Ăъ|����B7��12���ɔ��߂���4��ڂً̋}���Ԑ錾�͓���8��22�����������������A31���܂ʼn������Ă����B
�����͂̋����f���^���ɂ��A�����Ґ��͑S���I�Ɋg�債�Ă���B17�����\�̓s���̐V�K�����Ґ���4377�l�A�d�ǎҐ���8���A���ʼnߋ��ő���276�l�������B
��ꐶ���o�ό������̉i�l���L��ȃG�R�m�~�X�g�͐錾�����ƑΏےn��g��ɂ��A���������Y(�f�c�o)�����z��0.75���~����1.2���~���x�Ɋg�傷��Ǝ��Z�B7�|9�����̂f�c�o��0.9�����x�A�N�����Z��3.6�����x����������Ƃ̌������������B
���V�^�R���i �����Ŕ��\���ꂽ�����҂̏��@8/17
�������2�N���X�^�[����
����s�́A�s���ŐV���ɐV�^�R���i�E�C���X�̃N���X�^�[��2���������Ɣ��\���܂����B���̂����A�s��38��ڂƂȂ�N���X�^�[�͍�����{�Ɏs���̈��H�X�ŊJ���ꂽ��H�̉��Ŕ������A����܂łɎQ����9�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�Ǐ�́A��������y�ǂ܂��͖��ǏƂ������Ƃł��B�܂��A�s���̌��݉�Ђł́A�s��39��ڂƂȂ�N���X�^�[���������܂����B�]�ƈ��Ȃ�5�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�Ǐ�́A��������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
���D�y �����ŃN���X�^�[����
�D�y�s�́A�D�y�s������̗��㎩�q�����Ԓn�Ŏs��384��ڂƂȂ�N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B�s�ɂ��܂��ƁA���̒��Ԓn�ł�20�ォ��30��̐E�����킹��10�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�s�́A�Z���ڐG���������ꂪ����ق��̐E��11�l�ɂ��Ă������A�o�b�q������i�߂Ă��܂��B
���k�l�̎��Ə��ŃN���X�^�[����
���͐V���ȃN���X�^�[1�����������Ɣ��\���܂����B���������͖̂k�l�s�̎��Ə��ŁA16���A20�ォ��30��̏]�ƈ�5�l�̊������m�F����܂����B�Ǐ�͂�������y�ǂ��Ƃ������Ƃł��B���͔Z���ڐG����������̂���l��c���ł��Ă���Ƃ��āA���Ə��̖��O�����\���Ă��܂���B
������ ���H�X�̃N���X�^�[�g��
���َs�́A�N���X�^�[���������Ă���s���̈��H�X�ŐV����5�l�̊������m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����ŁA���̃N���X�^�[�Ɋ֘A���銴���҂͂��킹��13�l�ƂȂ�܂����B
������ ���H�X�̃N���X�^�[�g��
����s�ł́A�s��37��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���J���I�P�����H�X�ŐV����4�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͋q�Ə]�ƈ��Ȃǂ��킹��15�l�ƂȂ�܂����B
�������\��3�N���X�^�[�g��
���́A����܂łɔ������Ă���3�̃N���X�^�[�ŐV���Ȋ����҂��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�Ϗ��q�s�ō����J���ꂽ�u�S�������w�Z�I���A�C�X�z�b�P�[���v�ɎQ�����Ă������E���Ȃ�1�l�ł��B����ŁA���̃N���X�^�[�Ɋ֘A���銴���҂͐��k111�l�Ƌ��E���Ȃ�11�l�A����ɑ��W�҂Ȃ�7�l�̂��킹��129�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�k���s�̎��Ə��ł��V���ɏ]�ƈ�1�l�̊������m�F����܂����B����ŁA���̃N���X�^�[�Ɋ֘A���銴���҂́A�]�ƈ����킹��6�l�ƂȂ�܂����B����ɁA���H�s�̈��H�X�ł��V���ɗ��p�q1�l�̊������m�F����܂����B����ŁA���̃N���X�^�[�Ɋ֘A���銴���҂́A���p�q11�l�ƌo�c��1�l�̂��킹��12�l�ƂȂ�܂����B
���D�y 2�N���X�^�[�ŐV���Ȋ�����
�D�y�s�́A����܂łɔ������Ă���2�̃N���X�^�[�ŐV���Ȋ����҂��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B���̂����A�s��359��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���R�[���Z���^�[�ł͐V���ɏ]�ƈ�1�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͏]�ƈ�59�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�s��381��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���X�[�p�[�ł͐V���ɏ]�ƈ�1�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͏]�ƈ�16�l�ƂȂ�܂����B
���X�X�L�m�֘A �V����2�l
�D�y�s�ɂ��܂��ƁA�ɉ؊X�E�X�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�Ɋ֘A���銴���҂��V����2�l�m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B����ŁA�X�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�Ɋ֘A���銴���҂�336�X�܂�1289�l�ƂȂ�܂����B
���D�y ���w�Z�̃N���X�^�[����
�D�y�s�́A�s���̐��w�Z�Ŕ������Ă����s��363��ڂ̃N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B���̐��w�Z�ł͊w��13�l�̊������m�F����Ă��܂����B
���V�^�R���i �_�U�E�����n���ł������g�呱���@8/17
�_�U�E�����n���ł�17���A�V���ɂ��킹��18�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�_�U�n���ł́A1�T�ԘA����1���̐V�K�����҂��ӂ����ƂȂ�ȂǁA�������g�債�Ă��܂��B
���ɂ��܂��ƁA17���A�_�U�n����15�l�A�����n����3�l�̊������V���Ɋm�F����܂����B�����ɓ����Ă���̊����Ґ��́A�_�U�n����181�l�A�����n����37�l�ŁA��������挎�̊����Ґ������łɏ����Ă��܂��B
�_�U�n���ł́A1�T�ԘA���łӂ����̊������m�F����A����1�T�Ԃ̐V�K�����҂�10���l������24.5�l�ƁA�s���{���̊������������̃X�e�[�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ��ƂȂ��Ă���10���l������25�l�ɔ����Ă��܂��B
�܂��A����14���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��������̕ʂɌ��Ă݂�ƁA�Ϗ��q�s��58�l�Œ_�U�S�̂�8���ȏ���߁A�����Ŏ����s�ƐV�Ђ�������7�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�����g�傪�������A���́A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��ł���D�y�s�Ȃǂƕs�v�s�}�̉������T���邱�Ƃ�A�}�X�N�̒��p���ȂǁA��{�I�Ȋ�����̓O����Ăт����Ă��܂��B
�����E�a�@�A����48�l�Ɋg��@�V�^�R���i�A�����J�Еa�@��30�l�Ɂ@�������@8/17
����15�A16�̗����ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ��A����܂łɔ��������N���X�^�[(�����ҏW�c)�Ŋ����҂̑������ڗ������B��Îᏼ�s�̂邪���E�a�@�ł́A�V���Ɋ���13�l�ƐE��4�l�̊�����������A�N���X�^�[�͌v48�l�ɍL�������B
�܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă��邢�킫�s�ł́A�����J�Еa�@�̃N���X�^�[�ŐV���ɐE��3�l�Ɗ���2�l���z���ƂȂ�A�v30�l�ƂȂ����B�����{��(����119����)�ł͎���16�l�ƐE��1�l�̊����ɂ��v25�l�Ɋg�債���B�ʂ̎����{��(108����)�A���Ȕ������Ƃ̊֘A���(112����)�ł������Ґ����������B���̂ق��A���k�̎��Ə�(117����)���v42�l�A�S�R�s�̎��Ə�(122����)���v9�l�ɂ��ꂼ��g�債���B
���É͂̎��Ə��ŃN���X�^�\�@�푍�̍��Z�A���ˌY�����ł������g��@��錧�@8/17
��錧�Ɛ��ˎs��17���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ҍv260�l�̂����A1�l�͌É͎s���̎��Ə��̏]�ƈ��ŁA�����Ə����̊����҂͏]�ƈ��v7�l(�����m�F��1�l�܂�)�ɍL�������B���͐V���ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)�����̉\��������Ƃ����B
�������������푍�s���̍��Z�ł͐V���ɐ��k2�l�̊������������A���Z���̊����҂͐��k�v16�l�Ɋg�債���B
���ˌY����(�Ђ����Ȃ��s)�ł��V���ɐE��1�l�̊��������炩�ɂȂ�A�{�ݓ��̊����҂͔���e��10�l�A�E��5�l�̌v15�l�ɑ��������B
�����݂�����s���̕��ی㎙���N���u�ł�����1�l�̊�����������A�����҂͎���8�l�A�E��1�l�̌v9�l�ɑ������B
���V�^�R���i�����g�� �i�K�I�Ȉ�Ñ̐��̋��������@��ʌ��@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g����A����17�����Ɖ�c���J���A����̊����g����ÂЂ����ɔ����i�K�I�Ɉ�Ñ̐�������������j�������܂����B
�����̊����ҋ}�����āA17���̉�c�ł́A����A�V�K�z���҂Ɨ×{�҂̑����ɍ��킹�āA�i�K�I�Ɉ�Ñ̐��Ȃǂ��������錧�̕��j��������܂����B
�܂��́A���݂̊������āA����×{���̒����NJ��҂ɑ��錒�N�ώ@�Ȃǂɂ����鋦�͈�Ë@�ւ𑝂₵�܂��B
�܂��A��������×{�ŏǏ��������z���҂ɑ��A���@�悪���܂�܂ňꎞ�I�Ɏ���A�_�f���^�Ȃǂ��s���u�_�f�X�e�[�V�����v�������ɐݒu������j�ł��B
�����āA����Ȃ�a���̂Ђ������z�肳���ꍇ�A��p�̉����ȂLj�ʈ�Â̐����ɂ���ĕa�����m�ۂ��邱�Ƃ��������Ă��܂��B
���N���X�^�[2�Z�A�����Ŋg��@���1634�l�����c�@��ʌ��@8/17
��ʌ��Ȃǂ�17���A�V����1634�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B�V�K�����҂̓���͌����\��1168�l�A�������s307�l�A����s47�l�A��z�s33�l�A�z�J�s79�l�B
����܂łɊm�F���ꂽ�����҂�7��9376�l(�`���[�^�[�A���Ҋ܂�)�A���҂�864�l(17���ߌ�6������)�B
17���ߌ�9�����_�̏d�ǎ҂�125�l�A�����҂̓��@��1188�l�A�h���×{627�l�A����×{1��5354�l�B�މ@�E�×{�I����5��6540�l�B
���ɂ��ƁA���NJ��ŏڍׂ����������͖̂��A�w���`90��̒j��854�l�B�N���X�^�[(�����ҏW�c)�֘A�ł́A�����̊w�Z�œ��������ɏ������鏗�q�w��2�l���������A�v12�l�ɂȂ����B�����̐H�i���H��Ђł�4�l�����������B�����̊w�Z�œ��������ɏ�������j�q�w��4�l���������A�v6�l�ɂȂ����B��H�ł�12�l�A�o�[�x�L���[�ł�2�l�����������Ƃ݂��Ă���B32�l�̓��N�`����2��ڎ�ς݂������B
�������s�ɂ��ƁA���������������̂�10�Ζ����`90���307�l�B13�����\��1�l����艺�����B�d��1�l�A�����ǂ�9�l�B���N�`����2��ڎ킵�Ċ��������̂�10�l�������B�N���X�^�[�֘A�ł́A��{�o���a�@�ŁA70��j���̗z�����V���ɔ������A�����Ґ��͌v22�l�B�j���͗z�����҂Ɠ����ŁA����7���ɑމ@���14���ɔ��ǂ����B�����ǂœ��@�\��Ƃ��Ă���B���㎩�q����{���Ԓn�ő���1�l�̊������������A�����Ґ��͌v49�l�ƂȂ����B
����s�ɂ��ƁA���������������̂�10�Ζ����`90��̒j��47�l�B�s�㉺�����ǂ�50��j���E���̗z�������������B��z�s�ɂ��ƁA���������������̂�10�Ζ����`80��̒j��33�l�B
�z�J�s�ɂ��ƁA���������������͖̂��A�w�`70��̒j��79�l�B�s�s�������x���ۂ̏����E���A���h������������30��j���E�����V���Ɋ��������B�j���E���͋~�}�Ɩ��Ɍg����Ă���A�Z���ڐG�҂Ƃ��ꂽ�E��2�l�͂o�b�q�����҂��Ŏ���ҋ@���Ă���B
�������ҋ}���ŕی����̕��S���}���@���𗎂Ƃ��ό��n�@�É����@8/17
�����҂̋}���ŁA�ی������ʏ�Ɩ��Ɏx����������ȂNJ����g�傪�~�܂�Ȃ��ɁA���{�ً͋}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɐÉ�����lj����܂��B
�ی����E���u���N�ώ@�̂��d�b�ł��B�̉��͂������ł����v
�ߋ��ő����X�V�����É��s�̕ی����ł��B����×{������l�ւ̌o�ߊώ@��S������E����7���܂�5�l�ȉ��ł������A8���ɓ���{�ȏ�ɑ��₵�܂����B�E����35�l������24����365���Ή����Ă��܂����A���S����������ł��B
�É��s�ی����ی��\�h�ہ@���{�ËT�ے��⍲�u��T���甚���I�ɑ����Ă���܂��āA���R�A���҂���̔����Ƃ��킹�Ă�����̑Ή�����x���܂Ŗ��������Ă���Ƃ����v
�V�^�R���i�E�C���X�֘A�̋Ɩ������������A��Ô�̏����葱����\�h�ڎ�̎�z�ȂǁA�ʏ�Ɩ��ɑΉ����鎞�Ԃ������Ȃ�قǂ��Ƃ����܂��B
�É��s�ی����ی��\�h�ہ@���{�ËT�ے��⍲���W���u���I��邩�킩��Ȃ��̂ŁA�{���ɂ݂Ȃ���̂����͂Ƃ���������Ȃ��炱�̏�Ŕj�ł���悤�Ɋ撣���Ă��������Ǝv���܂��v
�J����1�T�Ԍ�ɔ��铌���p�������s�b�N�́A���ƂȂ铌���E��ʁE��t�E�É����ً}���Ԑ錾���ƂȂ邱�Ƃ܂��A�S�Ẳ��ϋq�Ƃ��邱�Ƃ����܂�܂����B
�����̊J�Òn�̈�A�ɓ��s�ł́A�V�^�R���i�̊������g�傷�钆�A��ނȂ��Ƃ�������������������܂����B
�ɓ��s���u(���ϋq��)�����Ǝv���܂��B(�ܗւƂ�)���Ⴂ�܂��B���̂ق����S�R(�����҂�)�����Ă��āv�u���̕��������ł���A���߂ł���B���ꂽ��L�������Ⴄ����v
�p�������s�b�N�ł͏����w�������Z���ϐ킷��u�w�Z�A�g�ϐ�v���O�����v�͊w�Z���̊�]�Ŏ��{�ł���Ƃ��Ă��܂����A�����ł�17���܂ł�1�Z�������Ă��ׂĂ̏����w�Z������߂Ă��܂��B���Îs���̖�r���w�Z��16���A�ŏI�I�ɒ��~�����߂܂����B
���Îs����r���w�Z�@��t�_�������u�q�ǂ������̈��S�A���S����ɍl����ƒ��~������Ȃ������B(���Z��)���ŁA�܊��Ŋ������邱�Ƃ͏d�v���Ǝv���Ă����̂ŁA�c�O�Ɏv���Ă���v
��r���ł͍���A���Ƃ̒��Ńp�������s�b�N�ɂ��Ċw�ԋ@�������Ă����l���ł��B
2020�N��4������5���ɋً}���Ԑ錾���o�������ό��{�݂́A�\�z���Ă����Ƃ͂����A2��ڂ̐錾�̕��j�Ɍ��𗎂Ƃ��Ă��܂��B
���c�C�������ف@��ؔ����x�z�l�u��͂���҂��Ă����ċx�݁A�㔼�Ƃ͌����ǂ����q�l�͌��邾�낤�ȂƂ������ƂŁA���Ȃ�V���b�N���Ă���͎̂����ł��B���Z�Ȃ̂��x�ƂȂ̂��A�ǂ̂悤�ȗv��������̂��A���͑z�����ł��Ă��Ȃ��ł����A��{�I�ɂ͗v���ɏ]���đΉ�����\��ł��v
�l�X�ȉe�����\�z����钆�A�������ꂼ��ɖ�����邱�Ƃ��ŗD��ɃR���i��Ɏ��g�ފ��Ԃ��͂��܂�܂��B
���V����69�l�����m�F �������ۈ牀�ł��@�V�����@8/17
�V�������ł�17���A�V����69�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B�V���s�͊����҂��ƒ��E��Ȃǂł���Ɋ������g�傳����P�[�X���ڗ��Ƃ��āA��̓O����Ăъ|���܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�69�l�ł��B���̂����V���s�ł�45�l�ŁA�������15�l�A����E�H�t��ł��ꂼ��8�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B���̑��̎s�����ł͒����s��5�l�A�V���c�s�E����J�s�E�싛���s�ł��ꂼ��3�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B�����̊����҂͗v5287�l�ƂȂ�܂����B
�V���s����Ɩk���10���40��̍��킹��5�l�͐V���s�̉��y�����֘A�ŁA�֘A�̊����҂�40�l�ɂ܂Ŋg�債�܂����B�܂��A�]����10�Ζ����̒j�̎q��40��̐V���s�E��2�l�͍]���̕ۈ牀�̉����ƐE���ŁA���̕ۈ牀�̊֘A��4�l�ɂȂ�܂����B
�V���s��17���Ɋ������m�F���ꂽ45�l�̂���34�l�͔Z���ڐG�҂ŁA��������������Ƒ���E��̊W�҂ł����B
�V���ی��q�����@�쓇���q�����u���O�ɏo���ɍs���Ă����Ƃ��A���O�����̂������l�Ɖ���Ă����Ƃ��A(����)���X�N�̂���l�������Ƃ��ɉƒ���Ŋ������L����Ȃ��悤�ɋC��t����v
�ƒ���Ɋ����̃��X�N������l������ꍇ�A���̐l�̓����̏��Ԃ��Ō�ɂ�����H���̎��Ԃ����炵����Ƃ������H�v�����Ăق����Ƃ��Ă��܂��B
����Ō��ɂ��܂��ƁA�O��ی����Ǔ��ɂ��钬����̊֘A��11�l�̊������m�F����Ă��܂��B������ł͍s����C�x���g���s���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł����A���͋ߏ��t�������Ŋ������L�����Ă���Ƃ݂Ă��܂��B
����s���Ȃnj��O�����A�o�H�s���҂���Ƒ��E�E��̓����Ɋ����g��@���쌧�@8/17
���쌧��16���A����1�T��(8��9���`15��)�̐V�^�R���i�E�C���X�̔��������\���܂����B
����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���565�l�őO�T��360�l��啝�ɏ���܂����B���������������x�́A�S���Łu�����v�A����ʂł͏��{�E��M�B���u�����v�A���v�E�k�A���v�X�E���삪�u�}���v�ƂȂ��Ă��܂��B
�N��ʂł́A�ł������̂�20���133�l(23.5��)�A������10��97�l(17.1��)�A40��96�l(17.0��)�A30��80�l(14.2��)�A50��71�l(12.6��)�A10�Ζ���39�l(7.0��)�A60��33�l(6.0��)�A70��9�l(2.0��)�A80�Έȏ�7�l(1.0��)�ł��B
�l�����銴���o�H�́A�����Ҋ�126�l(26.8��)�A�����O122�l(26.0��)�A�s��101�l(21.5��)�A���O93�l(19.8��)�A���H�֘A28�l(6.0��)�ł��B��������95�l�͕ꐔ���珜��
���́A�A�Ȃ�d���Ȃǂɂ���s���Ȃnj��O�Ƃ̉�����������l�̊������Ⴊ�����m�F����Ă���ق��A�����o�H�s���̐l����Ƒ���E��̓����Ɋ������g�傷��P�[�X�������Ă���Ƃ��āA����̂���Ȃ銴���g������O���Ă��܂��B
��{�I�Ȋ�����̊m�F�A�O������߂�ƂƂ��ɁA���O�ւ̉����͂ł��邾���T���Ăق����ƌĂъ|���Ă��܂��B
�������ݏZ�̐l���c�V�^�R���i �ߋ��ő��̐V�K������78�l �x�R���@8/17
�����g�傪�~�܂�Ȃ��V�^�R���i�E�C���X�B���{�́A�x�R���ɂ܂h�~���d�_�[�u��K�p������j���ł߂܂����B�����������A�����ł́A16���ɑ���17�����ߋ��ő��ƂȂ�78�l�̊������m�F����܂����B
�V���Ɋ������m�F���ꂽ�͕̂x�R�s�A����s�Ȃ�9�̎s�ƒ��Ⓦ���s�ɏZ�ށA10�Ζ�������90�Έȏ��78�l�ł��B1���̐V�K�����҂�70�l������̂�3���A���ł��B�����҂̋��Z�n�ʂł͕x�R�s���ł�����43�l�B�܂��A�N��ʂł�20�オ�ł������S�̂�36���A10�ォ��40��̊����҂��S�̂̂��悻8�����߂Ă��܂��B
����A�����o�H�ʂł͉ƒ��������19�l�A����܂łɊ����������҂ƐڐG���������l��21�l�A�N���X�^�[�֘A��1�l�A�����o�H���������Ă��Ȃ��l��37�l�ł��B�Ƃ���ŁA���������a�@�Ɠ�v�s���a�@�ŐE���������������Ƃ�������܂����B���������a�@��20��̏����Ō�t�ŁA�Z���ڐG�҂͓����̊Ō�t1�l�̂݁A���҂ł͂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�܂��A��v�s���a�@�ł͐E��͖��炩�ɂ���Ă��܂��E��1�l���������܂����B�E���Ɗւ�̂������E���⊳�҂�77�l���āA����܂ł̌����ł͑S�����A���Ɗm�F����Ă��܂��B
����ŗv�̊����Ґ���3114�l�A���@�܂��͓��@��������561�l�A�d�ǎ҂�16������3�l����10�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����䌧���R���i�����ҁA3�J�����炸�Ŕ{���@�v2000�l���@���䌧�@8/17
���䌧���̐V�^�R���i�E�C���X�̗v�����Ґ���2��l���A8��16�����_��2031�l�ƂȂ����B���N5��19���ɐ�l��˔j���Ă���3�J�����炸�Ŕ{�����A����7�����{�ȍ~�͊����͂̋����C���h�R���̃f���^���̑S���I�ȋ}�g��̉e�����Ă���B
�����̗v�����Ґ��́A��N3���̏��m�F�����1�N2�J����ɐ�l�ɒB���A���̌��2�J����1500�l���A�����3�T�ԑ��炸��2��l���������B���̊ԁA�p���R���̃A���t�@�������N3���A�f���^����7���ɏ��m�F�B�����y�[�X�̋}�����́A�E�C���X���S���Ɠ��l�ɕψي��ɒu��������Ă������Ƃ��w�i�ɂ���B
�����ł́A7��25������23���A����10�l�ȏ�̊������m�F����A��Ƃ���H�X�A�w�Z�A���ǂ����ȂǂŃN���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă���B����1�T�Ԃ̊����Ґ���a����L�����A���̎w�W�ŃX�e�[�W4(�����I�����g��)�̐�����������݂�ꂽ�B
�ߋ��ő��ƂȂ�43�l�����\���ꂽ8��3���A���͓Ǝ��́u�����g����ʌx��v�߁B����ɁA6����4�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o���A�������܂������s��A�Ȃ̌������~�A���������߂Ă���B�����S��̈��H�X�ɑ���11�`24���̊��ԁA�c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂ŁA��ޒ�7���܂łƂ���悤�v�����Ă���B
�����ōő�324�l�����u�z��O�̋}���v�@�����ȂǂŃN���X�^�[5���@���@8/17
���Ɗs��17���A����33�s���ȂǂŌv324�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B1��������̊����Ґ��Ƃ��Ă͏��߂�300�l������A5��14����155�l���ĉߋ��ő��ƂȂ����B�܂��A���@���Ă����s��80�㏗���̎��S���m�F���ꂽ�B�����҂͗v1��1132�l�A���҂�191�l�ƂȂ����B�Óc���m���͋L�҉�Łu�z����͂邩�ɒ�����}���v�Ƌ�����@���������A�����Ɋ�����̓O���O�o�̔��������炽�߂ċ��߂��B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A�ߋ��ō���54�E01�l�B16�����_�̓��@���҂�373�l�ŁA�a���g�p����47�E6���ƂȂ����B�d�ǎ҂�2�l�B
�V�K�����Ґ��̔N��ʂ́A20�オ101�l�ƍł������A30��ȉ����S�̂�3����2���߂�B
�V����5���̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F�����B�s�̈��H�X�ɏW�܂��ĉ�H���������̐e����8�l��A�����̐e���Ȃǂ��W�܂��ĉ�H�����s�̉Ƒ���7�l�̊����������B�ق��Ɋs�̍��Z�̕�������11�l�A�ꏏ�Ɍ��O�ɏo�|������쒬�̐E��̓�����6�l�A�������s�̓�����6�l�̊��������������B
�g�債���N���X�^�[��14���B�����s�̎R�c�a�@�ł͊��҂ƐE���e1�l�̊�����������25�l�A�e�����s�̍���ҕ����{�݊֘A��1�l������20�l�ɍL�������B
�f���^���̉\��������u�k452�q�ψي��v�̗z���҂͐V����17�l���m�F���A�v169�l�ƂȂ����B
�V�K�����҂̋��Z�n�ʂ͊s86�l�A�e�����s33�l�A��_�s27�l�A�������s24�l�A�H���s14�l�A���Z���Ύs11�l�A���Ð�s�A�H���S��쒬���e10�l�A�֎s�A����s���e9�l�A���s8�l�A���R�s�A�y��s�A�H���S�}�����A���m�����e7�l�A�K��S��쒬6�l�A�C�Îs�A���ΌS��j�����e5�l�A�{���s�A�s�j�S���䒬�A�{���S�k�������e4�l�A���Q�s�A�b�ߎs�A�S��s�A�����s���e3�l�A��ˎs�A�{�V�S�{�V���A�����S�_�˒��A���ΌS�x�������e2�l�A���C�s�A�����S�֔V�����A���S�������A�K��S�K��쒬�A���S�r�c���A���ΌS��Ӓ��A���쌧���e1�l�B
�N��ʂ�1�Ζ���1�l�A1�`10�Ζ���23�l�A10��51�l�A20��101�l�A30��42�l�A40��49�l�A50��37�l�A60��9�l�A70��5�l�A80��4�l�A90��2�l�B
�܂��A����16�����\�̊��҂ɂ��āA���Z�n����{����S��s�ɒ��������B
���l���s�ʼnߋ��ő�118�l�����@�V�^�R���i�E�C���X�A����3���@8/17
�l���s��17���A�V����118�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B���s��1��������̊����Ґ��Ƃ��Ă�13����82�l������A�ߋ��ő����X�V�����B100�l�����̂͏��߂āB�s�ɂ��ƁA�V�K�����҂̂�����1�l�́A�N���X�^�[(�����ҏW�c)������F�肵������̃J���I�P�o�[�u���J�t�F�v�֘A�������B
���s�ł�7�����{���犴���҂��}�����A�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ���Ԃ������Ă���B�@
���V�^�R���i�����}�g�� ���m���u�܂h�~�v����39�s���Ɋg��@���m���@8/17
���m���́A�V�^�R���i�E�C���X�����g��h�~�̂��߁A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑Ώۋ��̎����̂��A���݂�12����39�Ɋg�傷�邱�Ƃ��W�҂ւ̎�ނł킩��܂����B
���m����16���܂�6���A���ŁA1���̐V�K�����҂�500�l���錵���������������Ă��܂��B
���m���͌��݁A7��29������8��4���܂ł̊����ŁA�l��10���l�������1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���25�l�ȏ�́u�X�e�[�W4�v�ɂ����閼�É��s�ȂǁA12�̎s�������u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑Ώۋ��Ɏw�肵�Ă��܂��B
������A8��21������9��12���܂ŁA�u39�̎s���v�Ɋg�傷�邱�Ƃ��W�҂ւ̎�ނł킩��܂����B
8��21������u�܂h�~���d�_�[�u�v�̑Ώۋ��ɂȂ�39�̎s���́A8��8������w�肳��Ă������É��s�A�t����s�A�]��s�A��{�s�A�������s�A���i�s�A���{�s�A���s�A���v��s�A�������A�厡���̑��A�V���ɒlj�����鉪��s�A��{�s�A���ˎs�A���c�s�A�Ó��s�A���J�s�A�L�c�s�A���S�s�A���R�s�A�튊�s�A���q�s�A���s�A���C�s�A�m���s�A���l�s�A��q�s�A�L���s�A�����s�A�k���É��s�A�L�R���A������A�}�K���A�I�]���A���v�䒬�A��m�����A���l���A���L���A���h���ł��B
8��8�����瓖���A�Ώۋ��Ɏw�肳��Ă������́A���������P���ꂽ���ߑΏۋ�悩��O��܂��B
���m���͏d�_�[�u�̑Ώۋ��ł́A���H�X�Ɏ�ނ���Ȃ����Ƃ̂ق��A�c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łƂ���悤�v�����܂��B
�����m�E�呺�m���A�ً}���Ԑ錾��v���ց@���������u�Ռ��I�Ȑ��l�v�@8/17
���C3����17���A�V���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�����҂͂�������ߋ��ő���啝�ɏ���A�v1499�l�ƂȂ����B�ł�5��14����155�l����324�l�ɔ{�����A�O�d��208�l�Ə��߂�200�l�����B���m�ł�8��12����703�l����967�l�Ɍ������A�呺�G�͒m���͋L�҉�Łu�Ռ��I�Ȑ��l�B����ׂ����̂������Ǝ~�߂Ă���v�Əq�ׁA�߂����ɋً}���Ԑ錾�̔��߂�v������l�����������B
���̓��A���{���A�O�d��V���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�̑Ώۂɉ������ق��A���ɑΏۂƂȂ��Ă��鈤�m�ł��[�u�̊�����9��12���܂ʼn��������B
���m���́A�d�_�[�u����8��21���ȍ~�A������8���ȏ���J�o�[����39�s��(���݂�12�s����)�Ɋg�傷��B16�����݁A�V�K�����Ґ���7���ԕ��ς�4�i�K�̎w�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4(��������)�v�A���@���Ґ���2�Ԗڂ́u�X�e�[�W3(�����}��)�v�B�呺�m���͓��@���Ґ��̏��݂āA�������ɂ����ւ̐錾�v���ɓ��ݐ�ӌ����������B
���́A�V�K�����҂�6���ȏオ�����͂̋����ψي��u�f���^���v�Ɛ���B�Óc���m����17���̋L�҉�Łu�����҂��z����͂邩�ɒ����ċ}�����Ă���B������Ƒ��A�F�l�̖��Ɋւ���Ă���ƍĊm�F���A����u���Ăق����v�Ɗ�@���������ɂ����B
���͊A��_�A�e�����Ȃ�15�s�����d�_�[�u���Ƃ��A17��������H�X�Ɍߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v�������ق��A20�������ނ̒�~�����߂�B17���܂�1�T�Ԃ̐V�K�����҂́u�X�e�[�W4�v�A15�����݂̕a���g�p����44�E8���Łu�X�e�[�W3�v�̏��Ƃ����B
�O�d���͏d�_�[�u�����l���s��鎭�A�ÁA����A�ɉ�Ȃ�17�s���ƌ��߁A��ނ̒֎~��J���I�P�ݔ��̗��p��~�A��������̌ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k�Ȃǂ����߂�B�S�ݓX�̐H�i�������K�͏��Ǝ{�݂ł��q�̗U���Ȃǂ�v������B��؉p�h�m���́u���ĂȂ������g��ŁA��Ɉꍏ�̗P�\���Ȃ��B�ł����͑S�čs���A�S���Ŏ��g�ށv�Ƌ��������B
����Q�Ҏ{�݂̃N���X�^�[�g��A���Z�ۊO�����ł������L����@���s�{�@8/17
���s�{�Ƌ��s�s��17���A�V����10�Ζ����`90��̒j���v420�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1���̔��\���Ƃ��Ă�8��13����450�l�Ɏ����A�ߋ�2�Ԗڂ̑����B�����o�H�s����275�l�ŁA�Ǐ�͒�����2�l�A�y��242�l�A���Ǐ�42�l�A��������134�l�B�{���̊����҂͌v2��3324�l�ƂȂ����B
�{���\����203�l�B���Z�n�͉F���s39�l�A�T���s31�l�A�ؒÐ�s20�l�A���c�ӎs18�l�A�����s16�l�A��z�s15�l�A�������s13�l�A��O�s10�l�A�v��R��9�l�A���s�s�ƕ��m�R�s���e7�l�A�����s�Ɛ��ؒ����e3�l�A�����s�A��R�蒬�A���{�A���Ɍ����e2�l�A���ߎs�A���O��s�A�F���c�����A���O�g�����e1�l�������B
���s�s���\����217�l�B���Z�n�͋��s�s206�l�A�F���s�A�����s�A�������s�Ƒ��{�A���ꌧ���e2�l�A���c�ӎs��1�l�������B
�N���X�^�[(�����ҏW�c)�֘A�́A����24�l�̊������������Ă��闤�㎩�q���̌j���Ԓn(���s�s������)�ŐV����1�l�̗z���������B��Q�Ҏ{�݂����ڂ̊w��(��O�s)�ł�2�l�̗z���������������҂͌v25�l�ɂȂ����B���̂ق����Z�̉ۊO�����ł��������L�������B
���錾4��ڂ̕����@��t�u�ЊQ���x�����v�@���M�O���̔������z���@�������@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�Ă��镟������4��ڂً̋}���Ԑ錾�����߂���邱�Ƃ�17���A���܂����B����×{�҂��܂ފ��Ґ���8000�l�ɔ��钆�A�W�҂́u�����I�����ɑΉ����ǂ����Ă��Ȃ��v�Ɗ�@���������ɂ���B
�u�ł�����~�O�ɔ��f���Ăق��������v�B5���ɐ錾���߂𐭕{�ɗv�����Ă����������̕��������Y�m����17���̋L�҉�ŁA���̃^�C�~���O�ł̐錾���ߌ���ɕs�����B���Ȃ������B���͓����A�錾���Ԓ��͌��S��̈��H�X�ɑ��A��ނ̒��l�ƌߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k��v�����A�S�ݓX�Ȃǂ̑�^���Ǝ{�݂ɂ��ߌ�8���܂ł̎��Z�c�ƂƁA���q���������Ȃ�ꍇ�̓��ꐧ���Ȃǂ����߂�ƌ��߂��B
�m�����ł�̂́A8���ɓ����Ă���̌����̋}���Ȋ����g��Ɏ����̒����������Ȃ����炾�B12���ɂ͉ߋ��ő���1040�l�̐V�K�������m�F����A17����716�l�̊����������B�f���^���̗��s�ŎႢ����Ɋ������L���钆�A����×{�Ґ�(�ҋ@���܂�)�͑�4�g�̃s�[�N��4227�l��傫��������15�����݁A5380�l�ɒB�����B���@(825�l)�A�h���×{(1468�l)�ƍ��킹�����Ґ���7673�l�ɖc��ށB
����A�����̕a���g�p����16������60�E7���ɒB���A�ߋ��ő��y�[�X�ő��������鎩��×{�҂̗e�̋}�ςɍ���A�Ή��ł��Ȃ��Ȃ鋰�������B���ۂɕ����s���ł́A�R���i���҂Ŕ����悪������Ȃ��u�~�}��������āv��15���܂ł�1�T�Ԃ�55���ƁA7�����̏T��2�E9�{�ɑ����Ă���B
��Ì���̊�@���͐[�����B�u�����̈�@������1����40�`50�l�̊����҂��o���B�f���^���̉e�����낤���A�܂��ɍЊQ���x�����v�B�����s������́u�Ƃ݂����ȃN���j�b�N�v�������A�x�c���j��t�͒Q���B������20�`30�l�A���͂̕a�@������x���ɂ�100�l���炢�����M�O����K��邪�A�����߂����z���ƂȂ�20�`30�オ�ł������Ƃ����B
�z�����������Ă��A�ی���������@�Ȃǂ̏������`������̂Ɏ��Ԃ�������A���̊Ԃ̊��҂��I�����C���ȂǂŐf��@����������B�u(�s����z�z����錌���_�f�O�a�x�𑪂�)�p���X�I�L�V���[�^�[���茳�ɂȂ��l�����āA��f�Ő��m�ȏ����ɂ߂�͓̂���v�Ƒł�������B
�ǂ��l�߂�ꂽ���ً̋}���Ԑ錾�������ʂ͖��m�����B���H�X�ւ̎�ޒ��l�⎞�Z�v���́A�܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă���22�s�����ł͊���2������n�܂��Ă����ŁA���l����4����3�ȏ���߂邱���̒n��ɂƂ��đ傫�ȕω��͂Ȃ��B
�e�����[�N�Ȃǂɂ��l�o�}�����������Ȃ����A�\�t�g�o���N�̎q��Ёu�A�O�[�v�v�̐��v�f�[�^�ɂ��ƁA�O��̐錾���Ԓ��AJR�����w���ӂ̒ʋΎ��ԑт̐l�o�́A�錾�O�Ɣ��5�`15�����ɂƂǂ܂����B�����m���͋L�҉�Łu�E��ł̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă���B�o�Ύ�7���̍팸��ڎw���A�o����ꍇ���l�Ƃ̐ڐG�����炷���g�݂����Ăق����v�ƌĂт������B
���R���i�����}�g�� �����ׂ����Ƃ́E�E ���茧��t��ɕ����@���茧�@8/17
���茧���ł͏��߂āA����̊������\�Ґ���100�l���܂����B
���茧��t��̐X�� ���K ��͎Ⴂ�����A�܂����N�`����ł��Ă��Ȃ��l�𒆐S�Ɋ������L�����Ă���Ƃ��āA���N�`���ڎ�̏d�v�����Ăт����Ă��܂��B
���茧��t���8��12���A���茧���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ������������ɁA��Ê�@�I�錾���o���܂����B
���茧��t��@�X�� ���K � �u����A��Ê�@�I�錾���o�����̂́A���k�̕a�����Ђ�����������v
15���ߌ�7�����_�ł̒��茧�k��Ì��̓��@��ḮA93�̊m�ەa�����ɑ��āA���@���҂�58�l�ƕa���̎g�p����6�����Ă��܂��B
�X�� � �u��4�g�͒����Ì��Ŋ����g�傪�������B���̌�A�����ۂ̌��k�Ɉڂ����B���肪�����g�傪�������Ƃ��́A����̊��҂��I�[�o�[�t���[�������́A�����A����ł����Ă�������B����A�Ⴄ�̂́A�����Ì��A���k��Ì��A�������A���ׂĂł�����x�A�����҂��o�Ă���B�⊮���������Ƃ�����v
��4�g�ł́A�a�@�ȂǂŊ������g�債���̂ɑ��A��5�g�ł́A�E���ƒ���ȂǂŊ������L�����Ă���Ɋ�@���������Ă��܂��B
�X�� � �u���Z�����������āA���ꂳ�� ��������Ɋ������邱�Ƃ��N���Ă���B��҂͏Ǐo�ɂ����̂Ŗ��Ǐ��ǂ��A����������z���������A�������ėz����������A2���O�͊����͂��傫���B���̎����ɒm�炸�ɂ��ꂳ�ڐG���Ċ��������Ƃ������Ƃ��A���̐g�߂ȂƂ���ł������Ă���v
100�l���銴���҂����\����A�����g��̏I��肪�����Ȃ����A�X�� ��͓��ɎႢ����ւ̃��N�`���ڎ��i�߂Ă������Ƃւ̏d�v���������Ă��܂��B
�X�� � �u�R���i�E�C���X�ɂ芳����ƁA10������14���Ԃ͊u�������A�E��ɂ��o���Ȃ��A�w�Z�������ł��Ȃ��A�������A������C�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B10���ȏソ���Ă����ǂȂǐF�X�A�Y�܂����B���ǂɂ��Ă͔��N�A1�N�����Ƃ������Ă���B���ǂ��l����ƃ��N�`�����ǂ�ǂ�Ⴂ�l�ɑł��Ăق����v
�X�� ��́A��5�g�́A�a�@�ȂǂŊ������g�債������܂łƈقȂ�A�E���ƒ���ȂǂŊ������L�����Ă���ɋ�����@���������Ă��܂��B
�u�����閽���~���Ȃ��Ȃ�v���N����n�߂Ă���Ƃ��āA���N�`���̐ڎ�ƂƂ��ɁA��{�I�Ȋ����h�~��̓O����i���Ă��܂��B
���R���i�����Ґ��ߋ��ő��őz��O�̗̈�ց@�܂h�~�[�u�����@�F�{���@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�~�܂�܂���B���̑z����A�����҂��ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂����{�́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̊������A����12���܂ʼn������܂��B
17���������\�����V�^�R���i�̐V�K�����҂́A271�l��16�����119�l�����A1���̊����Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő����X�V���܂����B
�ؑ����m���͐�T�A��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂����B
�u200�l�͑z�肵�Ă������A250�l�͑z�肵�Ă��Ȃ��̂ŁA�����������E�E�E�v(�ؑ��h�@���m��)
�����z�肵�Ă��Ȃ������A1���̊����Ґ�250�l���B�w�a���g�p���x�͌������悻5���A�F�{�s��7���ƌ������������Ă��܂��B�N���X�^�[���������Ă��܂��B���Ԃ��^�c����F�{�s�̕��ی㎙���N���u�ŁA�����E�E�����킹��12�l�̊��������炩�ɂȂ�܂����B
�����g�傪�~�܂�Ȃ��Ȃ��A���{�͌����ɍ���8������K�p����Ă���u�܂h�~�[�u�v�ɂ��āA����31���܂ł������������A����12���܂łɉ������Ă��܂��B
�����������ɂ܂h�~�K�p 17������ց@���������@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�̋}���Ȋ����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����������ɁA���{�́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p��17�����肳��錩�ʂ��ƂȂ����B����16�����_�ŗv�����Ă��Ȃ����̂́A�����ł̊����ґ��Ȃǂ��l�����ꂽ�Ƃ݂���B���c�N��m���͓�����A����{�V���̎�ނɁu�����ɘA���͂Ȃ����A�Ή����Ă��炦��̂ł�����肪�����v�Əq�ׁA�����h�~�����������l�����������B���͑ΏۂƂ���s�������A�����܂��Ďw�肷����j�B
�܂h�~���d�_�[�u�K�p�ɂ��A�m���͎s�撬���P�ʂȂǂɔ͈͂��i��A���H�X�Ȃǂւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�̗v���E���߂̌��������B���߂ɉ����Ȃ����20���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ����Ƃ��ł���B���c�m���͎�ނɁA�����ȓK�p�v���͂��Ă��Ȃ��Ɩ��������B���́u������̘A�����āA�Ώۂ̎s���������߂�v�Ƃ��Ă���B
�d�_�[�u�̒lj��K�p�ɁA�����}�̐X�R�T���Έψ���(�O�@������4��)�́u����������A�N���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă���B���}���Ȃ��ƁA�܂����Ƃ̔��f���낤�v�Əq�ׂ��B
�d�_�[�u�̓K�p�v�������ɋ��߂Ă�������t��̒r�c��Ɖ�́u�}�~�͂Ƃ��Č����̐S�ɂ���@�I��i������B�s���A��ÊE�A���������͂��ĐV�^�R���i��}������ł��������v�Ƙb�����B
���c�m���́A1��������̐V�K�����Ґ���100�l����8���A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p������ɐ��{�Ƌ��c���n�߂��Ɩ��炩�ɂ��A�����҂��}�����鎭�����s�Ȃǂ�Ώۂɑz�肵�Ă���Ƃ����B�����A���{�͈��H�X�ւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�ɂ�銴���h�~��̌��ʌ��ɂ߂����߂Ă���A���Ǝ��́u�ً}���Ԑ錾�v�߂���13�����v�����������Ă����B
���N���X�^�[�����̕a�@�œ��@����64�l���S ���ꌧ ����� �@8/17
���ꌧ�ł́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŕa�����Ђ������钆�A����s�̈�Ë@�ւő�K�͂ȃN���X�^�[���������A����܂łɓ��@����64�l�����S�������Ƃ��킩��܂����B
���ꌧ����s�ɂ���A����܋L�O�a�@�ł́A�挎���{�A�����͂������C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�u�f���^���v�ɐE���������������Ƃ�������A���̌�A�������}���ɍL�����āA�����ł͉ߋ��ő�K�͂̃N���X�^�[���������Ă��܂��B
���ꌧ�ɂ��܂��ƁA����܂łɓ��@����173�l�A�E��26�l�́A���킹��199�l�̊������m�F����Ă��āA�����������@���҂̂���64�l�����S�����Ƃ������Ƃł��B
�a�@�ɂ��܂��ƁA�挎���{�ɐE���̂ق����@���҂ł��������m�F����A����ȍ~�A�����҂Ƃ���ȊO�̊��҂̕a������[�u���Ƃ��Ă��܂����B
�������A�挎30���܂ł�5�l�̎��S���m�F����A���̌�������������҂̎��S���������ŁA����11���̎��_�ł�42�l�̎��S���m�F����Ă����Ƃ������Ƃł��B
���S����64�l�͂قƂ�ǂ�����̊��҂ŁA�����͂��̕a�@�œ��@���ɖS���Ȃ��Ă��܂����A�ꕔ�͊�����ɂق��̕a�@�Ɉڂ������Ǝ��S�����P�[�X������Ƃ������Ƃł��B
�����̈�Ñ̐����Ђ������Ă��邱�Ƃ���A�����̊����҂��ق��̈�Ë@�ւɓ]�@�����邱�Ƃ��ł����A�a�@�ł͈�t��Ō�t�̉������ĉ@���őΉ����Ă��܂��B
�a�@�̒S���҂́u�������Ȃ���A�܂��܂����̕a�@�ŗ×{�𑱂��Ă����͂��̊��҂������S���Ȃ�A�{�l�₲�Ƒ��ɑ�ϐ\����Ȃ��B�����Ɍ����Ăł��邩����̑Ή����Ƃ��Ă����v�Ƙb���Ă��܂����B
���u���@��Ȃ��v�I�𔗂���Ƒ��c�錾�̊g��Ɖ����@8/17
���{��17���A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɁA���A�ȖA�Q�n�A�É��A���s�A���ɁA������7�{����lj����邱�Ƃ����߂܂����B�܂��A�g�܂h�~���d�_�[�u�h��16�����ɓK�p����܂��B���łɑΏۂƂȂ��Ă���n�����������������A����12���܂łƂȂ�܂����B
�����A�������Ă��A���̌��ʂ͖��m���ł��B�����s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o����Ă���A1�J�����܂�o���܂������A17���ɓ����s���m�F�����V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�4377�l�B�Ηj���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ł��B
�S���ł������g��͎~�܂炸�A���Ȃ�18�{���ʼnߋ��ő��B�d�ǎ҂������43�l�����A1646�l�ƂȂ��Ă��܂��B�����Ő��{������ɂ��āA�������́A�����q�ׂ܂����B
�������u�g��Ñ̐��̍\�z�h�g�����h�~�̓O��h�g���N�`���ڎ�h��3�{�̒��Ƃ��đ��i�߂Ă����v
�����h�~��Ɉʒu�t����̂��A�]�ƈ��̃N���X�^�[���������Ŕ������Ă���f�p�[�g�ȂǁA��^���Ǝ{�݂ɑ�����ꐧ���̗v���ł��B�����A���ȉ�̐��Ƃ���́A��蓥�ݍ��K�v�Ƃ̐����オ���Ă��܂��B
�V�^�R���i�S���E������b�u����܂ŐV�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊��҂̈����ɏ��ɓI��������Ë@�ւɑ��A�f�Âւ̎Q���𑣂��[�u���������ׂ��ł���Ƃ������c�_���������v
�c�������J����b�u���b�N�_�E���̂��ӌ�������������������ǁA�Ȃ��Ȃ��������������[�u�Ƃ����͓̂���B�^�p��ł��ł��邱�Ƃ�����̂ŁA���g����^�p���܂߂Č��������Ă������Ɓv
�������ł��[���ȉ��ꌧ�ł́A���@���҂�2�����S���Ȃ�a�@�N���X�^�[���������Ă��܂��B�������@�̔F�m�NJ��҂𒆐S�Ɏ���Ă��邤��܋L�O�a�@�B���@����173�l���������A64�l���S���Ȃ�܂����B�܂��A�E��26�l�̊������m�F����Ă��܂��B
���ꌧ�E��������ËZ�āu���@�����E��Â��Ђ������Ă���̂Ȃ��ŁA���̂܂{�ݓ��ł̗×{��I������l�������B�}�ώ��̑Ή��ɂ��āA���O�Ɏ厡��Ƙb�������āA�ϋɓI�Ɏ��Â��s�����ǂ����Ɋ�Â��đI�������Ɓv
�ŏ��Ɋ������m�F���ꂽ�̂͐挎19���B�����ɂ́A�������{���𗧂��グ�܂������A���̎��_�Ŋ����͍L�����Ă����Ƃ����܂��B
���ꌧ�S���ҁu���@���҂̑����͑啔���ɐQ������̏�ԂŁA�����Ȃ����߃]�[�j���O����������v
�܂��A�����������҂̖�9���́A2��̃��N�`���ڎ���I���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
�����g��ƂƂ��ɑ��������鎩��×{�ҁB�����s���ɏZ�ޒj��(39)�́A10����ɋ~�}�����Ă��̂́A���@�悪�����炸�A�����܂ŋ~�}�����_�f�̓��^�𑱂��Ă��܂����B�j���́A�얞�̂ق��Ɋ�b�����͂Ȃ��Ƃ����܂��B�{���x�Ŏ_�f�𑗂�܂����A�����̎_�f�O�a�x��94���B�_�f�Z�k�킪�͂��܂ŁA����ł��̂���������܂���B5���o����16���A�܂����@��͌������Ă��܂���ł����B�삯�t������e����ӎ��������낤�Ƃ��Ă���ƘA��������܂����B�_�f�Z�k��̓��^�ʂ��ő�ɂ��Ă��܂����A�_�f�O�a�x��90���Ɖ������Ă��܂����B
�����s����2�̑I������������܂����B��t����e�ɁA�����������܂����B
��t�u�{����������l�H�ċz�Ƃ����l����悤�ȏB�m��͂ł��Ȃ����ǁA��������������@�ł���Ƃ��낪��������Ȃ��B�����A�l�H�ċz�Ƃ�ECMO�Ƃ��͂ł��Ȃ��B�����������Â��ł����ɏ������Ȃ��\��������B������́A�l�H�ċz�Ƃ��ł���悤�ȂƂ���œ��@���āA��A�Ƃ͌����Ȃ����ǁA�������ɂ����Ă݂�B�����A����Ӗ��A�o��B���ꂳ��ɂ���Ȃ��ƌ����Ȃ�āA��Ґl���ŏ��߂āB�N�����������茾��Ȃ��ƁA����ς肢���Ȃ��B����Ȃ́A�����Ȃ肨�ꂳ��Ɂw�l����x�ƌ����Ă���������ˁv
��e�u������Ȃ牽�ł������B�����Ă��������v
�Ƒ��̖���������������I���B��e�͍ŏI�I�Ɉ���҂��āA�l�H�ċz��Ȃǂ�������a�@�ɓ��@���邱�Ƃ�I�т܂������A���ǁA17���ɂȂ��Ă����@��͌������Ă��܂���B
�ЂȂ��ݑ�N���j�b�N�R���E�c��a�n�@���u�����̏ꍇ�A�_�f���v�̂��钆����II�̊��҂���ł�����×{���������Ă���BSOS���͂��Ȃ����҂����ꂽ�Ƃ��ɁA��X�̑Ή����邱�ƂȂ��A�N�ɂ��C�Â���Ȃ��Ƃ���ŋꂵ�݂Ȃ���A���̊�@�ɂЂ�����o�Ă���Ɗ뜜���Ă���v
���R���i�u��5�g�v�ł��e�����[�N�g�傹���@�ܗւ̉e��������I�@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�u��5�g�v�ɔ���7������ً̋}���Ԑ錾�Ⓦ���ܗւ̊J�ẤA�e�����[�N���{���ɂقƂ�lje�����Ȃ������\�\�p�[�\��������������8��17���A����Ȓ������ʂ\�����B
�����͌ܗ֊��Ԓ���2021�N7��30������8��1���ɁA�]�ƈ�10�l�ȏ�̊�Ƃɋ߂�20�`59�̒j��2��5809�l��ΏۂɁA�C���^�[�l�b�g�Ŏ��{�����B
���Ј��̃e�����[�N���{���͑S������27.5���ŁA20�N11���̑O������2.8�|�C���g�̑����ɂƂǂ܂����B�s���{���ʂł́A�ً}���Ԑ錾���̓����s��47.3����1�ʂŁA20�N11�����������1.5�|�C���g���������A20�N4���̍ŏ��ً̋}���Ԑ錾���Ɣ�ׂ��1.8�|�C���g�����Ă����B
���Ђ́u�ܗ֊J�ÁE�ً}���Ԑ錾�E���������ȂǏo�Ђ̗}���ɂȂ��肻���ȏ�����������Ă������A���Ј��̃e�����[�N���{���͂قډ����������v�Ǝw�E�B�R���i��5�g�ɔ����A7��12�����瓌���s�ɋً}���Ԑ錾�����߂��ꂽ���̂́A�e�����[�N�ւ̌��ʂ́u�ɂ߂Č���I�v�������Ƃ݂Ă���B
�e�����[�N���{�����Ǝ�ʂŌ���ƁA�u���ʐM�Ɓv��60���ƍő��A�����Őŗ��m�Ȃǁu�w�p�����A���E�Z�p�T�[�r�X�Ɓv����41���A�u���Z�ƁA�ی��Ɓv����36���������B20�N11���̒������瑝�������ő��������̂́u���Ɓv�Ŗ�8�|�C���g���A�����Łu���Z�ƁA�ی��Ɓv����6�|�C���g���A�u���ʐM�Ɓv����4�|�C���g���������B
�e�����[�N���s���Ă��Ȃ��l�ɗ��R�����Ƃ���A�u�e�����[�N�ł���Ɩ��ł͂Ȃ��v����47���ƍő��������B20�N3���̒����Ɣ�ׂ�Ɓu�e�����[�N���x����������ĂȂ��v�͖�10�|�C���g�����A�uICT������������Ă��Ȃ��v�͖�5�|�C���g�������A�e�����[�N���̐����͐i��ł���悤���B
���~�܂Ȃ��d�b�A���@��Ȃ��c�����}�g��ŕی������E�@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�����g�傪���������s�ŁA�ی����̍s���m�F�̓d�b�ɏo�Ȃ��P�[�X���������A�Z���ڐG�҂⊴���o�H�̓��肪��q���Ă���B�}����������×{�̊��҂̃P�A�〈����Ȃ����@��̒����ɂ��l�肪�������ی����B��Ñ̐����u�@�\�s�S�v�A�������u����s�\�v�Ǝw�E���ꂽ������5�g�܂��������̓s���̕ی�������ނ���ƁA���S�����E���}�����錻�����B
�s���ʼnߋ��ő��̐V�K�����҂����\���ꂽ����13���B�݂Ȃƕی���(�`��)�ł͌ߑO8�����̎n�ƂƂƂ��ɓd�b����n�߂��B
�u�Ǐ�͂���܂����H�v�d�b��������E���͋斯�̕s���̐��ɉ����Ă����B�u���������Ή����Ă�����Ɋ����҂͌���Ȃ��B�I���̂Ȃ��킢�ɐE���̌��E�����Ă���v�B���{���㏊���͒Q���B
�݂Ȃƕی����ɂ͌��݁A1����120�`130���̐V�^�R���i�����Ҕ����͂���Ë@�ւ���͂��B�E���͓͂��o�����ƂɁA���҂ɓd�b�������ē��@�����⊴���o�H�̔c���Ȃǂ��s���B�����A�����͓͂d�b�ԍ����Ԉ���Ă�����A���Ǔ���������Ȃ�������ƕs���������B�u���Y�ҏZ���@�V���̃z�e��(�z�e���s��)�v�Ə����ꂽ���̂�����A���ꏊ��������Ȃ����Ƃ��������B
�����҂Ɏ�҂̔䗦�����������ƂŁA�d�b�ɏo�Ȃ��P�[�X�������Ȃ����B�Ȃ���Ȃ��Ƃ��̓V���[�g���b�Z�[�W�Łu�x�@�ƂƂ��Ɉ��ۊm�F�����܂��v�ȂǂƑ��M����ƕԐM�����邱�Ƃ�����Ƃ����B
���ې�ܗ֑��̓��N�`���ڎ헦�u�c�����ĂȂ��v�@����œ����p�����v�H �@8/17
�����s�̐V�^�R���i�E�C���X�����g�傪�u�ЊQ���v�ƌ����钆�A�d�lj����X�N�������I�������p�������s�b�N�͈��S�ɊJ�Âł���̂��B�����ܗւɈ��������A���{����g�D�ψ���ł͍ĉ����⒆�~������c�_�����ꂸ�A�����p�������s�b�N�͓����A��ʁA��t�A�É���1�s3���̑S���Ō������ϋq�ł̊J�Â����܂����B�@
�ې���ܗ֑���16����4�ҋ��c��A���~��ĉ������c�_���Ȃ��������R����ꂽ���A�u�����̃C�x���g��������e��50����5000�l�̏��Ȃ����Ŏ��{���Ă���v�ƁA���ʂ��瓚���Ȃ������B�{�b�`���ȂNj��Z�ɂ���Ă͌ċz��n�̏�Q������I������Ȃ��Ȃ��B��N7���ɂ͍��ۃp�������s�b�N�ψ���(�h�o�b)�̈�w�ψ���Ԃ����̑I��ɑ����������d�lj����X�N�����߂�\��������Ƃ��w�E�B�������Z�ł��I��̏�Q�ɂ���ă��X�N�͂��܂��܂ŁA��҂ƒ������ԐڐG������A��w���ł���������肵�āA����I�Ȋ����h�~����Ƃ�ɂ����I�������B�������d�lj����X�N�������郏�N�`���̐ڎ헦�ɂ��Ċې쎁��g�D�ς̕����q�Y���������͋L�҉�Łu�c�����Ă��Ȃ��v�ƉB�g�D�ς���Â⊴���ǂ̐��Ƃ��W�߂āA�R���i���b�������u���ƃ��E���h�e�[�u���v��6��18�����Ō�ɊJ����Ă��Ȃ��B���́u���S�v�𗠕t����Ȋw�I�����͖R�����B
�s�̈�Â͕N�����Ă���B�ܗւ��J������7��23����2558�l���������@�Ґ��͍���16����3881�l�܂ő��������B�s�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�����ǂ̒S���҂́u��Ò̐�������ɕN�������ꍇ�A���@������Ă��炦�邩���O�͂��邪�A���@�ł��Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ��N���Ȃ��悤�S�͂�s�����v�ƁA���@���m��ł��Ȃ����B�p�������s�b�N�̑I��͖�4400�l�A��������W�҂͖�1��2000�l�B�������́u����A���@���K�v�ȑI�肪�o���ꍇ�ɂ͒n���Âɉe�����o�Ȃ��悤�ɑΉ�����v�Ǝ��ꂪ���������B
����A�������k��Ɋϐ�@������u�w�Z�A�g�ϐ�v���O�����v�́A�����̂�w�Z����]����ꍇ�Ɏ��{���邱�Ƃō��ӂ����B�����s�̏��r�S���q�m���́u�q�ǂ������ɋ����Љ�Ƃ������t�����łȂ��A�ڂ̑O�ł��̂��Ƃ�̌�����Ƃ����@������Ă��炢�����v�Ƙb�����B�ˌ����Z���s�����ʌ��̑�쌳�T�m���������Љ�̌`�����f����p�������s�b�N�̐��_�Ɋ�Â��A�u(���Ҋϐ��)���{���邱�Ƃ͂ӂ��킵���v�Ɣ��f�����Ƃ����B��ʌ��͍���A6�����_�ŎQ������]���Ă�������2�Z�Ɉӌ����m�F����B
�������ܗ֊W�҂���V�^�R���i�̊������g�債���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��@8/17
�����s��t���Łu�������Εa�@�v�������̒������F����8��10���A�j�b�|�������u���[�j���O���C�t�A�b�v �����̑��N���h�N�^�[�v�ɏo���B�V�^�R���i�V�K�z���҂̌���ɂ��ĉ�������B
�ѓc�_�i�A�i�E���T�[)����҂̕��̃��N�`���ڎ킪�i��ŁA����̕��̏d�lj��⊴���҂͏��Ȃ��Ȃ��Ă���ƌ����Ă��܂����A���ۂ̂Ƃ���͂ǂ��ł����H
����)�����ǁA�d�ǂ̕��͊����Ƃ��Ă͏��Ȃ��Ǝv���܂�����ǂ��A���@���Ă��銳�҂����3500�l���Ă���܂��̂ŁA�g�[�^���ł́A���Ȃ�̓��@���Ґ��ɂȂ��Ă��܂��B60��ȉ��̊����҂�95�����炢�Ȃ̂ł�����ǂ��A���@���Ă�����Ō����܂��ƁA50��ȉ���80���A�ł��d�ǂ̊��҂����50�Έȉ��̕������ŁA��60���ȏ�ł��B
�ѓc)50�Έȉ����B
����)���N�`�����i��ō���҂̕������̊����Əd�lj��͏��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A40��`50��̕������̊����������Ă��܂��B���̕�������20��`30��ɔ�ׂďd�lj����₷���̂ŁA�d�ǂ̊��҂���������Ă���Ƃ����ł��B
�ѓc)�u�I�����s�b�N�̊W�҂ŃN���X�^�[���o���v�Ƃ������Ƃ��傫�����܂����B���ꂪ�Ƃ��������悤�Ȍ`�Łu�I�����s�b�N�Ŋ������g�債���v�Ȃǂƌ���ꂽ������܂����A���ہA�����Ō���Ƃǂ��ł����H
����)���낢�뒲�ׂĂ��܂�����ǂ��A�����̂��낢��ȂƂ���̃X�N���[�j���O�Ɣ�ׂĂ��m���͒Ⴂ�ł���ˁB�I�����s�b�N�W�҂����ɑ傫�ȃN���X�^�[���������Ƃ��A�����̊m���������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
����)��Â̗���Ƃ��ẮA�������o�u���̂Ȃ��ɓ����ăN���X�^�[�Ȃǂ�����Ȃ��悤�ɂ���Ƃ������Ƃ͂������ł�����ǂ��A����ŁA�p�������s�b�N�Ƃ������̂̏d�v������Ðl�Ƃ��Ă͂悭�킩���Ă������ł��B���̂ł���A�p�������s�b�N�Ŋ������g�傷��Ƃ������Ƃ��Ȃ��悤�ɁA��������悤�ɉ����������Ǝv���܂��B
���J��Ԃ����ꓖ����Ή��@�錾�g��Ɖ����ɐ헪�Ȃ��@8/17
���{�͐V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��ً}���Ԑ錾���߂���A�Ώۊg��Ɗ���������]�V�Ȃ����ꂽ�B�����A�V�K�����Ґ����s�[�N�A�E�g������͍̂���Ƃ̌����͋����A����̊�ڂ͏d�ǎҐ���}�����A�u��Õ���v��j�~���邱�Ƃɂ���B�����Ƃ��A�d�ǎҐ��͐V�K�����Ґ�����ǂ�����`�ő����Ă������߁A�����͓��ʑ������Ƃ��\�z�����B�W�]�����ʂ��Ȃ��܂܁A���Ԃ������߂��Ă���B
�u���N�`���ƈ�Ñ̐��̏[�������Ȃ���ȁv
�d�ꂵ����C����ݍ��ޒ��A���`�̎�16���[�̊W�t���Ƃ̋��c�ł����Ԃ₢���B�����̊�����31���B���X�ƑΏۊg��Ɗ������������߂����Ƃ́A���Ԃ����X�������Ă��邱�Ƃ𗠕t���Ă���B
���c�ł͑S���ւ̓K�p�����߂�ӌ����o�����A�u�ǂ�����ĉ�������v�Ƃ������ɂ��������ꂽ�B�����A��s�������ł�9��12���ɉ����ł��錩�ʂ��͗����Ă��炸�A�������ĉ����_�������Ԃ�B
����Ȓ��A���N�`���ڎ�̐i�W��w�i�ɁA�V�K�����Ґ������A�ނ���d�ǎҐ���}���邱�ƂɎ�����u���A�R���i�Ƌ�����������ɂ������ׂ����Ƃ̐������{���ɋ��܂��Ă���B�����͂̋����C���h�R���̕ψي�(�f���^��)�̓o��ŋǖʂ͕ς�����B�����̖ڈ��ƂȂ�X�e�[�W�ʎw�W�̌������͋}�����B
�����Ƃ��A�d�ǎҐ��������X���ɂ���A�����J���Ȃɂ��ƍ���16�����_��1646�l��5���A���A�ő����X�V�B��{�I�Ώ����j���ȉ�̔��g�Ή��17���̕��ȉ��A�L�Ғc�Ɂu��Ë@�ւɋ��͂��Ă��炦��@�I�ȐV���Ȏd�g�݂̍\�z��A�����ǖ@�Ȃnj��s�̖@���̊��p�������������Ăق����v�Ɩ@�����̕K�v���Ɍ��y�����B
�Ō�̂Ƃ�ł͎��Ö낤�B���J�Ȃ͏d�lj���h�����ʂ�����y�ǁE�����nj����́u�R�̃J�N�e���Ö@�v���h���×{�{�݂Ŏg�p���邱�Ƃ͔F�߂����A�o�ߊώ@���K�v�ȏ�A�_�H��ł����邽�߁A����ł̓��^��F�߂Ă��Ȃ��B�W�t���́u�R�E�C���X�܂̌o�����p������Ώ͕ς��v�Ɗ��҂��邪�A�܂���̘b���B
���N�`���������ɍs���͂��A�y�ǎҌ����̌o�����p������܂ł̊ԁA�e�n��ɑ��錾�■���h�~���d�_�[�u�̓K�p�A�����A�����������J��Ԃ��|�B����ȏꓖ����I�ȑΉ��ł͍������痝���͓���ꂸ�A�����ɐ헪����������Ȃ��B
���T�b�J�[�E�C���^�[�n�C�ŕ����̐V�^�R���i�E�C���X�����ҁ@8/17
���{�T�b�J�[�����17���A�T�b�J�[�̑S�������w�Z�����̈���(�C���^�[�n�C)��S������R����3������V�^�R���i�E�C���X�z���������o���Ɣ��\�����B
����́u���Y�҂͍��8��16���ɂo�b�q��������f���z�����m�F���ꂽ���̂ł��B����܂ł̂Ƃ���A���Y�҈ȊO�̑I���W�҂���̒��s�ǂȂǂ͂̕���܂��A�Z���ڐG�҂̓���Ȃǂ��܂߁A���������A�ی����̎w���ɏ]���ĕK�v�ȑ[�u���u���Ă܂���܂��v�Ɛ��������B
�u����������g��h�~�ƈ��S�m�ۂ��ŗD��ɁA����Ȃ钍�ӊ��N�Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA�����J���Ȃ�ی����A�W���ǂ̕��j�Ɋ�Â��đΉ����Ă܂���܂��v�Ɗ����������ɓO�ꂷ����j���������B
�����A�I���W�҂͑S������W�܂��Ă��邤���A���Z���s���Ă��镟��ł��V�^�R���i�����҂��}�����Ă���A����͓�����^�c�𔗂�ꂻ�����B
������ ����9���߂ǂɉ �u�錾�v�g��ō����ɋ��͌Ăт��� �@8/17
�V�^�R���i�E�C���X����߂���A���{�́A17���ߌ�6��������A���{�����J���A���̌�A�ߌ�9�����߂ǂɐ�������b���L�҉����Ɣ��\���܂����B
��������b�́A�L�҉�ŁA�e�n�ŋ}���Ȋ����g�傪�����Ă��钆�A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn����g�傷�邱�ƂȂǂ�������A�����ɗ����Ƌ��͂��Ăт����錩�ʂ��ł��B
�����}�̎R����\�́A�L�҉�Łu�f���^���ւ̒u�������̃X�s�[�h��A�����͂̋����ɂ���Ċ������}���ɑ��債�Ă���B���{�Ƃ��Ď����ɓ������߂̌��ʂ���T���Ă����p�����d�v���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁA�錾�̊��Ԃ�����12���܂łƂȂ邱�Ƃɂ��Ắu���{���v�����Ă����A���~�x�݂܂ł̐l���̗}�����ʂ��A�������茩�ɂ߂Ă������Ԃ�����B�p�������s�b�N�I����̏����ɂ߂�K�v������A�������̊ϓ_����݂���ꂽ���Ԃ��v�Ǝw�E���܂����B
����A�O�c�@�̉��U�����ւ̉e���ɂ��Ắu��������b�̓��ʂ̑Ή����j�́A�R���i��ɑ����čŗD��ł�����Ƃ������Ƃň�т��Ă���A���̒��ōŏI�I�Ȕ��f���Ȃ����Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
�������͂́u�ʂ̃E�C���X���݁v�c�҈АU�邤�g�f���^���h�@8/17
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ɏ��~�߂�������Ȃ����R�̈�ɁA��4�g�Ƒ�5�g�̑傫�ȈႢ������܂����B���A�������͉������ׂ����A�R���i���Â̍őO���ɗ���t�ɂ��b���f���܂����B
���c��ȑ�w�a�@�̊�c���@���u��s���Ɠ����悤�ɂ�邱�Ƃ���邵���Ȃ��ƁB�������߂�Ƃ���v
�g��X���Ɏ��~�߂�������Ȃ��V�^�R���i�E�C���X�B���c��ȑ�w�a�@�̊�c�[�i���@���������̈�ƍl����̂��A�����͂������Ƃ����C���h�R���̃f���^���ł��B
��c���@���u�����͂Ɋւ��ẮA�f���^���͕ʂ̃E�C���X�ƍl�����ق����������炢�����͂������B��萔�̊����̐l�����̊댯�ɂ��炳���B���������Ӗ��ł̋��낵���E�C���X�v
���c��ȑ�w�a�@�ł͌��݁A�����Ljȏ�̊��җp�̃x�b�h44�����m�ۂ��Ă��܂����A���̂���15�������܂�����Ԃł��B�x�b�h���ɑ����@���҂�3���قǁB�������c�B
��c���@���u��s���̈�Î҂����̘b���ƁA1�T�Ԃ�(�a����)��C�ɖ��܂����ƕ����̂ŁA�����҂̑������ɂ����(��ÂЂ�����)�\���ɂ��蓾��B(���@���҂̔N���)30��㔼����50�オ�����āv
�V�^�R���i��5�g�̓����́A��r�I�Ⴂ�N��ւ̊����������Ă��邱�ƁB
��4�g�Ƒ�5�g�̊����҂�N��ʂɕ\�����O���t������ƁA��4�g�Ɣ�ב�5�g��40��ȉ��̎Ⴂ����ւ̊����g�傪�N���ɂȂ��Ă��܂��B���N���ւ̊����������Ă���̂́A���m�����̍���҂̂��悻8����2�x�̃��N�`���ڎ���I���Ă��āA���̌��ʂ��Ƃ݂��Ă��܂��B
��c���@���u���N�`����ł��I���ĂȂ��Ⴂ����ł��A����҂ɔ�ׂ�Əd�lj�����l�͏��Ȃ����A��萔�����҂�����Ώd�lj�����l������v
�����ґ����̗v���Ƃ��݂���l�o�̑������Ⴂ���オ��߂Ă��āA��c���@���͊�@�����点�܂��B
��c���@���u��J���ʌx��̎��́w�F����͐�ɋ߂Â��Ȃ��悤�Ɂx�ƌ���Ȃ��Ă��߂Â��Ȃ��B����Ɠ������炢�E�C���X���X�ɂ��ӂ�Ă��邪�A�����Ȃ�����s���Ă��܂��B�����̖��̊댯�ƌ��������Ȃ�Ďv��Ȃ�(�Ⴂ)����̕����A�����ƌ�������Ȃ�������Ȃ������肷��v
���ɂȂ����炱�̏����܂�̂��B��c���@���͐V�^�R���i�ɑ���ӎ��̕ϗe���K�v�Ƃ��������ŁA���N�`������̏͑����Ƃ����܂��B
��c���@���u���N�`���ڎ킪�i�݁A�������̎�̂ƂȂ��Ă���(�Ⴂ)����̊����҂����Ȃ��Ȃ��Ă����B���ꂪ9�������炢�ɂȂ�Ηǂ��ȂƁv
���C��t�������t�[�h�R�[�g�ł̐V�^�R���i�������X�N�@8/17
���ċx�݂ő�����t�[�h�R�[�g�̗��p
�S���e�n�ŐV�^�R���i��5�g���L�����Ă��܂����A���~�̋A�Ȃ�ċx�݂ŗ��p�����t�[�h�R�[�g�ł̊���������悭���ɂ���悤�ɂȂ�܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�́A��ɔ����ƐڐG�������z�肳��Ă��܂��B�G�A���]�����z�����邱�Ƃɂ�銴�����X�N���d�v������Ă��܂��B������ɂ��Ă��A�\�[�V�����f�B�X�^���X�̊m�ۂ��d�v�ł��B
���J�Ȃ́u�Ă̊����g��h�~���݃T�C�g�v(1)�ɂ����āA�����O�H����Ƃ��Ă��u���C���ǂ��A���ȊԂ̋������\���ŁA�K�ȑ傫���̃A�N�������ݒu����A���G���Ă��Ȃ��X��I�����Ă��������v�Ɩ������Ă��܂��B
���̂��߁A�����̎����̂́u�e�[�u���Ԃ�1���[�g���ȏ�̊Ԋu�������邩�A�A�N�������ŋ��v�Ȃǂ̑Ή������Ă��܂��B
�����ɂ��������āA�t�[�h�R�[�g�ł��h�~�̂��߂̃A�N������p��������݂��Ă��܂��B�p���f�~�b�N�����͂��܂茩���Ȃ����i�ł������A�ŋ߂�1�̃e�[�u���ɂ������̃A�N�������ݒu����Ă��邱�Ƃ������ł��ˁB
�A�N���������������������閾�m�ȃG�r�f���X�͂Ȃ��̂ł����A�X�[�p�[�R���s���[�^�[�x�x�̎��Z�ł́A�����炢�̍���������ΑΖʂ���͖̔h����Ƃ��Ă��܂�(2)�B
���e�[�u����A�N�����ɒ���
�t�[�h�R�[�g���ʏ�̈��H�X�ƈقȂ�ӓ_������܂��B����́A���p�����l���邢�͎��ɗ��p����l���e�[�u����@���Ȃ����Ƃ�����Ƃ����_�ł��B
�����������ɂ���Ƒ����m���A�A�N�������g���Č݂��̔�h�~����Ӗ��͂��قǂ���܂���B��������A�Ⴄ�Ƒ����g������̃e�[�u����A�N�����ɐV�^�R���i�E�C���X�����Ă���\�����l���Ȃ��Ƃ����܂���(�})�B
�����Ȏq���́A�e�[�u����A�N�������x�^�x�^�ƕ��C�ŐG��܂��B�����ɃE�C���X���t�����Ă���ꍇ�A�q����������}��郊�X�N�͍����Ȃ�܂��B
���ŔG�炵���G�ЂŐ����Ă������̓E�C���X�������ł��܂����A�d�v�Ȃ̂̓e�[�u�����A���R�[���Ő@���グ��Ƃ�����Ƃł��B�t�[�h�R�[�g�����Ă��Ă��A�Ƒ�����ւ��邽�тɂ��ꂪ�s���Ă���킯�ł͂���܂���B����I�ɏ��ł��Ă���{�݂�����܂����A�����܂Ńt�[�h�R�[�g�S�̂̊������X�N���������点�邾���ŁA���̑��ɗ���̂͏����E�C���v��܂��B
�A�N������ݒu���邱�Ƃ��d�v�ł����A�t�[�h�R�[�g�ł͎g�p�O��̃e�[�u���\�ʂ��A���R�[�����ł���ق������|�I�Ɍ��ʓI�ł��B�������p����̂ł���A�Z�x70���ȏ�95%�ȉ��̃G�^�m�[�����܂܂ꂽ���i��������Ă������Ƃ��]�܂����ł�(�Z�x70���ȏ�̐��i������ł��Ȃ��ꍇ�́A�Z�x60���ȏ�̐��i�ł��\���܂���)�B
�������A�����܂Ŋ�����̈ӎ��������̂ł���A�����������Ȏ��ԑтɃt�[�h�R�[�g�ɍs���Ȃ����Ƃ̂ق����d�v��������܂���B��قǂ́u�Ă̊����g��h�~���݃T�C�g�v(1)�ɂ����Ă��A�u�Ƒ��⓯���҈ȊO�Ƃ̑�l���E�����Ԃ̏W�܂���H�͍T���āv�Ɩ��L����Ă��܂��B
���ً}����13�s�{���Ɋg��@�Z������₩�u����Ă��Ă���v�@8/17
�����E�g�傪�J��Ԃ����V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾�B�V���Ɉ��A�ȖA�Q�n�̖k�֓�3����É����������A�錾�̑Ώۂ�13�s�{���ɍL���邱�ƂɂȂ����B�k�֓�3���ƐÉ����ł͂܂h�~���d�_�[�u���K�p���ꂽ����8���ȍ~�������g��X���Ɏ��~�߂������炸�A�e�m���͐錾�ւ̐�ւ������߂Ă����B�����A�Z������͐錾�̌��ʂ��^�⎋���鐺��u�����̐g�͎����Ŏ�邵���Ȃ��v�Ƃ̗�߂��ӌ����������B
�É�����17���̐V�K�����҂��ߋ��ő���435�l�ƂȂ����B�����p�������s�b�N�̉��͖��ϋq�ɁB16�����_��1570�l������ŗ×{���A���@�Ȃǂ̒�����ҋ@����l��544�l�ɏ��B�É��s����̉�Ј��A�͌����Ƃ���(56)�́A�d���̉�H�͂قڍT���Ă���Ƃ����A�u��⊷�C�Ȃǂł��邱�Ƃ�����Đg����邵���Ȃ��v�B��������É��s�ɋA�Ȓ��̏��q��w��(20)�́u�É��w�O�������E�a�J���l�o�̓R���i���s�O�ƕς��Ȃ��v�Ɛ錾�̌��ʂɋ^���悷��B
�Ȗ،��ł�14����1��������̊����҂��ő���195�l�ƂȂ����B�a���g�p���͉ߋ��ň���6�����ƂȂ�A����×{�҂Ɠ��@�������̊��҂͌v1000�l���̏�Ԃ������B�F�s�{�s���̃M���[�U�X�ł���u�F�s�{�L�q��v�����ǒ��̗�؏͍O����(49)�́u�܂h�~�[�u���K�p���ꂽ���_�Ŏ�x��B���̑�͊Â��A�����ɂ͊��ꂪ�����Ă���v�B�s���̑�w���A�쑺���t(�݂�)����(21)�́u�܂h�~�ŏI���Ǝv���Ă����̂ŋ������B�����̑c����ɂ����Ȃ��悤�O�o���T�������v�Ƙb�����B
��錧�ł͎�s��1�s3���ɋ߂����암�𒆐S�Ɋ������g��B14���ɂ�1��������̊����҂�391�l�ƂȂ�A�ő����X�V�����B17�����݁A�m�ۂ����a����7������419�����g���A���ً͋}���̒Ⴂ���@�E��p�̉������Ăт����Ă���B������̊C������߂��ŗm�H�X���c�ލ���m������(35)�́u�錾�͎d���Ȃ������ʂ͋^��v�Ƙb���B������ŊC������͕�����A���q�͗�N��3�����x�B�u��̌��ʂ��������Ȃ��v
�Q�n���ł�8���ɓ����Ă���̊����҂�2500�l���ɁB��p�a���̉ғ�������7���ƍ������������B����s��45�N�ɂ킽��i���X���o�c���鉀���b����(73)�́u�q�͌��������R�[�q�[���̎����A��̔̔����͔{�߂��ɂȂ����v�ƕ��G�ȕ\��B�V���b�s���O���[����K�ꂽ�O���s�̎�w�A�L���ӎ�����(26)�́u���~�̐e�ʂƂ̏W�܂���T�������A�錾���ǂ��܂Ō��ʂ�����̂��s���v�Ƙb�����B
����A�錾�̉��������܂��������s�́A�S�ݓX�̐H���i������V���b�s���O���[���̓���҂�7����{�Ɣ�ׂ�5���팸����悤�v������B�s���S�ݓX�ɋ߂�j���Ј�(40)�́u�H�i�����ȂǂŎ��ۂɃN���X�^�[(�����ҏW�c)�����������ȏ��ނȂ��B�x�Ɨv�������͔��������v�Ƙb���B
��ނ̒�~�Ɖc�Ǝ��ԒZ�k�̗v���ɏ]���V�h��̋������̒j���X��(60)�́u���̏͂��܂ő����̂��v�B5���ȍ~�A�[��c�Ƃ𑱂���a�J��̋������̒j���]�ƈ�(34)�́u���̐錾���ƈ���Đl�o�͑����B�������Ă������ς��Ȃ��v�Ɠf���̂Ă�悤�Ɍ������B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���V�^�R���i �����s�ŐV����5386�l�����m�F ���j�ł͉ߋ��ő� 8/18
�����s�ŁA18���A�V����5386�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��킩�����B��T���j����4200�l����1186�l�����Đ��j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ����B
�܂��A�d�ǎ҂͂��̂�����1�l������275�l�ƂȂ����ق��A�V���Ɏ��S���m�F���ꂽ�̂�6�l�������B
�������́u��Ô�펖�ԁv�Ή��@�錾�����E�g����j�@�e�����́@8/18
���{���A�V�^�R���i�E�C���X��Ƃ��ē����Ȃ�6�s�{���ɔ��ߒ��ً̋}���Ԑ錾�̑Ώۂ�7�{����lj����A��������������̂ɔ����A�W�����̂͑������Ή������߂��B
�����s��17���̑��{����c�ŁA��Ò̐������Ől�����m�ۂ��邽�߁A�K�v�ɉ����ēs���̋Ɩ����~�����艄�������肷��u��Ô�펖�ԁv�Ή��̐���ł��o�����B
���r�S���q�s�m���͉�c��A�L�Ғc�Ɂu���҂�d�ǎ҂��o���Ȃ����Ƃ��ŗD��ɍl���A�S����̂Ŏ��g�ށv�Ƌ����B�a�@�ւ̋~�}���������߂Ă��鎩��×{���̊����҂ŁA�y�ǂƔ��f���ꂽ���҂��ꎞ�I�Ɏ���Ď_�f���^���s���u�_�f�X�e�[�V�����v���a�J����ɐݒu����ӌ����������B
�s�͐��{���ȉ�̒܂��A�l�o��5���팸���̒��ɐ�����B�S�ݓX�ȂǑ�^���Ǝ{�݂ɂ͈��������A�����K���i�����������ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v���B���̏�Œn���H�i�����(�f�p�n��)�Ȃǂ͓���Ґ��̔��������߂�B
���{�̋g���m���m���́A�{���̏d�NJ��Ҍ����a���̎g�p����50���������_�ŁA��K�͏��Ǝ{�݂�C�x���g�ɋx�Ƃ�v������Ɛ����B�u�d�lj���h�����g�݂�O�ꂵ����Ŋ����g�傪�~�܂�Ȃ���A���b�N�_�E��(�s�s����)���݂̑[�u����邵���Ȃ��v�Əq�ׂ��B�{�����݊m�ۂ��Ă���d�Ǖa����587���ŁA17�����_�̎g�p����26�D7���B
�V���ɐ錾���K�p����镺�Ɍ��͓Ǝ��̑�Ƃ��āA���H�X�ȂǂɃ}�X�N���p�̓O������߁A��b���ɖ����p�̋q�������ꍇ�͑ޓX�˗���v������ƌ��߂��B
���ꌧ�̋ʏ�f�j�[�m���́A�ċx�ݖ����Ɍ����w�Z�ŕ��U�o�Z�����{����Ɣ��\�B10��̊������g�債�Ă��邽�߁A�o�Z���鐶�k��5���팸��ڎw���B�_�ސ쌧��2�w������A�����w�Z�ŒZ�k���Ƃ�������j���������B�@
���s5386�l�@3��w�̉^�����ŃN���X�^�[�@8/18
�V�^�R���i�E�C���X�̐[���Ȋ����g�傪���������s����18���A�ߋ�2�Ԗڂɑ���5386�l�̊������m�F����܂����B
�����s���̐V���Ȋ����҂́A10�Ζ�������90��܂ł�5386�l�ŁA�ߋ�2�Ԗڂɑ����l���ł��B��T���j��(11��)�����1186�l�����Ă��āA�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��ł��B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς��A�ߋ��ő���4696�D6�l�ƂȂ�܂����B
3�̑�w�̉^�����ŃN���X�^�[����������ȂǁA18���͑�w�̕������◾�����Ŋw��40�l�̊������m�F����܂����B�܂��A40��̒j���́A�m�l10�l�ƃo�[�x�L���[�����āA����8�l������������A���~�x�݂̋A�Ȃ◷�s�Ŋ��������肵���P�[�X���o�Ă��܂��B
�d�ǎ҂́A�O������1�l������275�l�ƂȂ�܂����B�N��ʂł́A40���50��̏d�ǎ҂�6���߂����߂Ă��܂��B
����A60�ォ��80���6�l�̎��S���m�F����܂����B�s���̓��@���҂�3815�l�A����×{�҂͍X�ɑ�����2��2226�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���V�^�R���i �D�w�̊����Ґ� �����ōő��� �g�ϋɓI�ɐڎ���h 8/18
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A�����s�ŐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������D�w�̐��́A�挎1�����Ԃł��悻100�l�ɏ��A�ߋ��ő��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�������܂����B���Ƃ́u�D�w�͏d�lj��̃��X�N���������߁A�ϋɓI�Ƀ��N�`����ڎ킵�Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B���{�Y�w�l�Ȉ��Ȃǂɂ��܂��ƁA�����s���ŐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊��������ꂽ�D�w�̌����Ƃ̐��́A���Ƃ�7����1�����Ԃ�98�l�ɏ�����Ƃ������Ƃł��B�s���̔D�w�̊����́A���s�̑�3�g�ōł������������N12����46�l�A��4�g�ōł������������Ƃ�5����50�l�ƂȂ��Ă��܂������A�挎�͂�����2�{�߂��ɏ��A�ߋ��ő����������Ƃ�������܂����B�܂��A���N4������挎�܂łɊ��������D�w�́A�s���ō��킹��460�l�ɏ�����Ƃ������Ƃł��B�D�w�̊����ɂ��ē��{�Y�w�l�Ȉ��Ȃǂł́u�D�P���A���ɔD�P����Ɋ�������Əd�lj����₷���Ƃ���Ă���v�Ƃ��Ă��āA�D�w�͎������킸���N�`����ڎ킷�邱�Ƃ𐄏����Ă��܂��B
���{�Y�w�l�Ȉ��햱�����œ��{��ȑ�w�̒���͐l�����́u���������͔̂D�w�͈�ʂ̐l���Ⴍ�K�Ȋ�������Ƃ��Ă���Ƃ݂��邪�A�������}�g�債�Ă��钆�ŔD�w�̊����������Ă���̂����B�D�P���͊������Ă��g�p�ł��Ȃ����Ö�������̂ŁA�D�w�Ƃ��̃p�[�g�i�[�͐ϋɓI�Ƀ��N�`����ڎ킵�Ăق����v�Ƙb���Ă��܂����B
�����s���ő����̏d�NJ��҂�����Ă��铌���E����̓��{��w��w���������a�@�ł́A���Ƃ�6���܂ł͊��������D�w�̓��@�͍��킹��2�l�����ł������A��5�g�ł͔D�w�����������P�[�X���������ł��Đ挎��1�l�A������18���܂ł�7�l�����@�����Ƃ������Ƃł��B���̂����D�P8������30��̏����͐挎���{�ɐV�^�R���i�̒����ǂœ��@���A���̌���č����މ@���܂����B������NHK�̎�ނɑ��u�����o�H���킩�炸�A�܂����������Ƃ��������ł����B�����ŋ����ɂ������̂ł����A������肨�Ȃ��̒��̎q�ǂ��������ł����Ăق����Ƃ����v���ł����ς��ł����B���N�`���͔D�P���ɑł̂͏����s���ŁA�Y��ɑłƂ��ƍl���Ă��܂������A�������Ă��܂��܂����v�Ƙb���Ă��܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���̔D�w�ւ̐ڎ�ɂ��āA�Y�w�l�Ȃ̈�t�Ȃǂō��w��Ȃǂ́A�D�w�͔D�P�̎������킸���N�`���ڎ�����߂�ȂǂƂ���V���Ȓ����\���܂����B�V���Ȓ��܂Ƃ߂��̂́A���{�Y�ȕw�l�Ȋw��Ɠ��{�Y�w�l�Ȉ��A����ɓ��{�Y�w�l�Ȋ����NJw��ł��B�ł́A�D�P���A���ɔD�P����ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������Əd�lj����₷���Ƃ���Ă���Ƃ��������ŁA�D�w�����N�`����ڎ킵�Ă��������͈�ʂ̐l�ƍ����������Ƃ�A���Y�⑁�Y�Ȃǂ̕p�x�͍��������ƕ���Ă���Ƃ��܂����B������CDC���A�����J���a��Z���^�[���D�w�ւ̃��N�`���ڎ�������������Ă���Ƃ��āA���{�ł��D�P�̎����ɂ�����炸���N�`���̐ڎ�����߂�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�D�w�̊����͂��悻8�����v��p�[�g�i�[����̊������Ƃ��āA�D�w�����łȂ��v��p�[�g�i�[�ɂ��Ă����N�`����ڎ킷��悤�Ăт����Ă��܂��B�ڎ����]����ۂ̒��ӓ_�Ƃ��āA���炩���ߌ��f���Ă���a�@�̈�t�ɑ��k���A�ڎ킵�Ă��悢�Ƃ����ΐڎ���̖�f��ɓ`���Đڎ���邱�Ƃ�A2��̃��N�`���ڎ���I�������Ƃ�����܂łƓ��l�ɁA�}�X�N�̒��p��l���݂������Ȃǂ̑�𑱂��邱�ƂȂǂ������Ă��܂��B
����ґΏہ@�a�J�w���ӂɐڎ�����J�݂ց@8/18
�V�^�R���i�E�C���X�̐[���Ȋ����g����A�����s�́A�����҂�������҂�ΏۂɁA�\��Ȃ��Ń��N�`���ڎ킪��������a�J�w���ӂɁA�߂��J�݂��܂��B
�����s�E���r�m���u�ډ��A�������g�債�Ă����Ґ���ɂ����������N�`����Z��������B���̂��߂ɁA�����A�a�J�w�t�߂Ɏ��O�\��Ȃ��Őڎ�\�Ȏ�N�w��p�̉����J�݂���v
�����I�Ȋ����g�傪���������s���ł́A�����҂̂����A20��A30��̎Ⴂ�l�����悻�������߂Ă��܂��B
����ŁA�Ⴂ����ւ̃��N�`���ڎ킪�i��ł��Ȃ����Ƃ���A�����s�́A�����A�a�J�w���ӂ�20��A30��̎Ⴂ�l��ΏۂƂ������N�`���ڎ�����J�݂��܂��B
�ڎ팔�����Q����A1��ڂ͗\��Ȃ��Őڎ킪���A2��ڂ͗\����t���܂��B���̉��ł́A�t�@�C�U�[���̃��N�`�����g�p����\��ł��B
���V�^�R���i �����Ŕ��\���ꂽ�����҂̏�� �@�k�C���@8/18
18���ɓ����Ŕ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂Ɋւ�������܂Ƃ߂܂����B
�������\ �V����3�N���X�^�[
���͐V���ȃN���X�^�[3�����������Ɣ��\���܂����B���̂����n���n���̗V�Z�{�݂ł�16���A�]�ƈ�4�l�̊������m�F����A�ق��̏]�ƈ��ɂ��o�b�q������i�߂��Ƃ���ŏ���4�l���܂�30�ォ��50��̏]�ƈ�7�l�̊������m�F����܂����B�Ǐ�͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B���͔Z���ڐG�����\��������l��c���ł��Ă���Ƃ��Ď{�ݖ������\���Ă��܂���B�эL�s�́u�Љ���@�l�эL�ۈ玖�Ƌ�����ڂ̕ۈ牀�v�ł́A����13���ɉ���1�l�̊������m�F����A�ۈ牀�ɒʂ��ق��̉�����E���ɂo�b�q���������{�����Ƃ���18���܂łɉ���22�l�ƐE��1�l�̍��킹��23�l�̊������m�F����܂����B�Ǐ�͂�������y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B���H�n���̎��Ə��ł�16���ɏ]�ƈ�2�l�̊������m�F����A���̎��Ə��̂ق��̏]�ƈ��ɂo�b�q���������{�����Ƃ���A18���܂łɍŏ���2�l���܂ޏ]�ƈ�7�l�̊������m�F����܂����B���͔Z���ڐG�����\��������l��c���ł��Ă���Ƃ��Ď��Ə��������\���Ă��܂���B
���D�y��2�N���X�^�[����
�D�y�s�͎s���ŐV����2�̃N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B���̂����s���̃R�[���Z���^�[�Ŏs��385��ڂ̃N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B�s�ɂ��܂��ƁA���̃R�[���Z���^�[�ł�20�ォ��50��̏]�ƈ����킹��5�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�s�͔Z���ڐG���������ꂪ����ق��̐E��37�l�ɂ��Ă������A�o�b�q������i�߂Ă��܂��B�܂��A�s���̔F�ۈ�{�݂Ŏs��386��ڂƂȂ�N���X�^�[���������܂����B�s�ɂ��܂��ƁA���̕ۈ�{�݂ł͉���2�l�ƐE��3�l�̍��킹��5�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�s�͔Z���ڐG�����\��������ق��̉���36�l�ƐE��13�l�ɂ��Ă������A�o�b�q������i�߂Ă��܂��B
���D�y 4�N���X�^�[�g��
�D�y�s�͂���܂łɔ������Ă���4�̃N���X�^�[�ŐV���Ȋ������m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B���̂����s��359��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���R�[���Z���^�[�ł͐V���ɏ]�ƈ�1�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͏]�ƈ�60�l�ƂȂ�܂����B�s��362��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���R�[���Z���^�[�ł͐V���ɏ]�ƈ�1�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͏]�ƈ�35�l�ƂȂ�܂����B�s��367��ڂ̃N���X�^�[���������Ă��鍂�Z�ł͐V���ɐ��k1�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͐��k11�l�ƐE��1�l�̍��킹��12�l�ƂȂ�܂����B�s��381��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���X�[�p�[�ł͐V���ɏ]�ƈ�1�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͏]�ƈ�17�l�ƂȂ�܂����B
�������\ 2�N���X�^�[�ŐV���Ȋ�����
���͂���܂łɔ������Ă���2�̃N���X�^�[�ŐV���Ȋ����҂��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B���̂����Ϗ��q�s�ō����J���ꂽ�u�S�������w�Z�I���A�C�X�z�b�P�[���v�Ŕ��������N���X�^�[�ł́A�V���ɐ��k5�l�̊������m�F����܂����B����ł��̃N���X�^�[�Ɋ֘A���銴���҂͐��k116�l�Ƌ��E���Ȃ�11�l�A����ɑ��W�҂Ȃ�7�l�̍��킹��134�l�ƂȂ�܂����B�܂��A�k�l�s�̎��Ə��ł͐V���ɏ]�ƈ�9�l�̊������m�F����A���̃N���X�^�[�Ɋ֘A���銴���҂͏]�ƈ����킹��14�l�ƂȂ�܂����B
������ 2�N���X�^�[�g��
����s�͂���܂łɔ������Ă���2�̃N���X�^�[�ŐV���Ȋ����҂��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B���̂����s��37��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���J���I�P�����H�X�ł́A�V����2�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͋q��]�ƈ��ȂǍ��킹��17�l�ƂȂ�܂����B�s��38��ڂ̈��H�X�ł̉�H�ł͐V����1�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͍��킹��13�l�ƂȂ�܂����B
������ ���H�X�̃N���X�^�[�g��
���َs�̓N���X�^�[���������Ă���s���̈��H�X�ŐV����2�l�̊������m�F���ꂽ�Ɣ��\���A�֘A���銴���҂͍��킹��15�l�ƂȂ�܂����B
���X�X�L�m�֘A �V����13�l
�D�y�s�ɂ��܂��ƁA�ɉ؊X�E�X�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�Ɋ֘A���銴���҂��V����13�l�m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B����ŃX�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�Ɋ֘A���銴���҂�339�X�܂�1302�l�ƂȂ�܂����B
���D�y�Y���x���ŐV����2�l
�D�y�Y���x���͐V���Ɏ�Y��1�l�ƐE��1�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\���܂����B�D�y�Y���x���ɂ��܂��ƁA�������킩�����̂�60��̏�����Y�҂�20��̏����E����2�l�ł��B���̂���60��̎�Y�҂͍���15���ɔ��M�̏Ǐ��i���A�o�b�q�������s�������ʁA17���ɗz���Ɣ��������Ƃ������Ƃł��B���݂͔M�͉����������̂́A������A�̒ɂ݂�i���Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A20��̐E���͖��Ǐ�ł����A����10���Ɋ������m�F���ꂽ�E���Ɠ��������ŋΖ����Ă������߁A10�����玩��ҋ@�̑[�u���Ƃ�o�b�q���������{�����Ƃ���A17���ɗz���Ɣ��������Ƃ������Ƃł��B�E���͍Ō�ɏo����10���܂Ŏ�Ɏ�Y�҂Ɛڂ���Ɩ��ɂ������Ă����Ƃ������ƂŁA�D�y�Y���x���͔Z���ڐG�҂����Ȃ����ǂ���������i�߂Ă��܂��B
���D�y 3�N���X�^�[����
�D�y�s�͎s���Ŕ������Ă���3�̃N���X�^�[��18���܂łɎ��������Ɣ��\���܂����B�s��354��ڂ̃N���X�^�[���������Ă����R�[���Z���^�[�ł́A����܂łɏ]�ƈ�11�l�̊������m�F����Ă��܂����B�s��365��ڂ̃N���X�^�[���������Ă�����w�ł́A����܂łɊw��14�l�̊������m�F����Ă��܂����B�s��371��ڂ̃N���X�^�[���������Ă������w�Z�ł́A����܂łɊw��8�l�̊������m�F����Ă��܂����B
���k�C��595�l�m�F�@�L��Ŋ����g��@�D�y��309�l�@8/18
�V�^�R���i�E�C���X��18���̊����҂́A�k�C����595�l�m�F���ꂽ���Ƃ��킩��܂����B�D�y�s�̊����҂�309�l�ł��B
�����҂̒n��ʂ̓���ł��B
�D�y�s�@309�l / ����s�@56�l / ���َs�@20�l / ���M�s�@12�l / ��m�Ǔ��@14�l / �Ύ�Ǔ��@54�l / ��u�Ǔ��@4�l / �_�U�Ǔ��@26�l / �����Ǔ��@3�l / �n���Ǔ��@15�l / �w�R�Ǔ��@0�l / ���Ǔ��@11�l / ���G�Ǔ��@0�l / �@�J�Ǔ��@3�l / �I�z�[�c�N�Ǔ��@16�l / �\���Ǔ��@23�l / ���H�Ǔ��@18�l / �����Ǔ��@3�l / ���̑��@8�l�B
���{��Ŏ~�܂�ʊ����g��A��Ò̐����N���@�ő���271�l�m�F�@8/18
�{�錧�Ɛ��s��18���A�ߋ��ő��ƂȂ�271�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B���s�͊���1�l�̎��S�����\���A�����̎��҂͌v94�l�A�����m�F�͗v1��2151�l�ƂȂ����B���s�����ł��ߋ��ő���168�l�̊������m�F����A��Ò̐����N�����Ă���B���{�͌��ɑ��ĐV�^�R���i���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��u����(�܂�)�h�~���d�_�[�u�v�̍ēK�p��17���Ɍ��肵�����肾���A���ʂ͌������������������B
�u�����������Ȃ��A��ό��������v�B20������̏d�_�[�u�̍ēK�p���A���s��18���ɊJ�Â����V�^�R���i�����Ǒ��c�ŌS�a�q�s���͊�@���������ɂ����B
�s�ɂ��ƁA���̓��m�F���ꂽ168�l�̂����A�N��ʂł�20�オ�ő���61�l�B�����o�H���s���Ȋ����҂�138�l�ɏ�����B
�����g��ɔ����A��Ò̐����������𑝂��Ă���B���ɂ��ƁA�����ɓ��@���\�ȁu����\�a���v�̕a���g�p���́A����Ì�(���s�Ǝ��ӂ̌v14�s����)�ł�89�E3��(18���ߌ�3�����_)�ɒB���Ă���B
18���̑��c�ł́A���H�X��C�x���g�{�݂ւ̉c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���̂ق��A��ޒ̏I����~�Ƃ����������h�~����m�F�����B
��c��ɕw�̎�ނɉ������S�s���́A�ߋ��ő��ƂȂ��������Ґ��ɂ��āu�ψي��ւ̒u������肪�i�݁A�Ⴄ�X�e�[�W�ɓ�������ۂ��v�Əq�ׂ��B
�������Ǒ�A�Y�ޕۈ�̌���@�V�^�R���i�@�������@���킫�s�@8/18
���킫�s�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�����Ă���B7�����{���獡��17���܂łɖ��炩�ɂȂ����N���X�^�[(�����ҏW�c)��19���ŁA���̂���6���͎����{�݂������B�q�ǂ��Ƃ̐ڐG�������̂�����ۈ�̌���ł́A�W�҂������Ǒ�̗����Ɋ����𑱂��Ȃ���q�ǂ�����邽�߂̕����T���Ă���B
�u�G�ꍇ�����������Ȃ��d�������炱���������O�ꂵ�Ă����B����ł��~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������v�B�������c�t��(���킫�s)�̋g�c��(����)����(52)�͂����U��Ԃ�B�����ł͍����A�����⋳�E���v6�l�̊��������o�����B
7��19������ċx�݂̗a����ۈ���n�߁A�ŏ��̗z���҂����������͍̂���2���̒��������B�a����ۈ�𗘗p���Ă����ی�҂���̃��[���ŁA�g�c�����͉���2�l�̊�����m�����B�����������Ă���������ی�ҁA���E���ɘA�����A3���ɂ͌v35�l���o�b�q���������B��4���A�V���ɉ���3�l�Ƌ��E��1�l�̊��������������B�K���ɂ��g�c�������܂߁A�c��31�l��2��ڂ̌����ł��A���������B
�����͐V�^�R���i�̊����g���A�ł������̊����Ǒ������Ă����B�o���O�̉ƒ�ł̌�����}�X�N���p���͂��߁A������ߋ�Ȃǂ̏��ł�O�ꂵ�A���H���ɂ͉����̊Ԃɂ����Ă�u�����B�����ۈ�̍ۂ̉����Ƃ̐ڐG�͔������Ȃ������B
�u�q�ǂ����]�Ƃ��A1���[�g������āw���v�H�x�Ɛ����|���Ă��q�ǂ��̋C�����͖����Ȃ��B��������w���������邱�ƂŋC�����𗎂��������邱�Ƃ��ł���v�Ƌg�c�����͌��B�r����@�������ލۂɂ����E���̕⏕�͌������Ȃ��B�V�ԂƂ��ɉ������m�̋������߂��Ȃ�����A�������ɓ���Ă��܂����肷��ꍇ������B����͊������X�N�Ə�ɗׂ荇�킹�ɂ���B
�s�ی����̒S���҂́u(�������g�傷��)�ψي��͊����͂������B����10�Ζ����̎q�ǂ��͊�������A���ȐڐG�����������{�݂ɃE�C���X���������܂��ƍL����₷���v�Ǝw�E����B7���̎s���̊����Ґ���216�l�ŁA���̂����q��Đ����30�㖢����7�����߂��B���i�ꏏ�ɂ��Ȃ��l�Ƃ̈��H��s�O�Ƃ̉����ɂ�銴���������A�e�ƒ�ő�l����q�ǂ��ɍL�����Ă���Ƃ݂���Ƃ����B
�g�c������3��ڂ̂o�b�q�������s�������17���A�����̗a���悪�Ȃ��ی�Ҍ����̗a����ۈ���悤�₭�ĊJ�����B�u�������ʂ�Ɏq�ǂ������̎p���߂��Ă��Ăق����Ǝv�����ʁA���~�����ɂ͂���Ȃ銴���g������O�����B�ǂ�������q�ǂ����������邩�v�ƕs���͏����Ȃ��B
���V�^�R���i�V����117�l�m�F�@�a�@�N���X�^�[�g�傩�@�������@8/18
�����ł́A17���A�V����117�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ�������܂����B17���A�������m�F���ꂽ�̂́A���킫�s��42�l�A�S�R�s��21�l�A�����s��17�l�ȂǁA���킹��117�l�ł����B���̒��ɂ́A�N���X�^�[������������Îᏼ�s�́A�邪���E�a�@�̓��@���҂��܂܂�Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A���킫�s�̕����J�Еa�@�ł��A�N���X�^�[���g�債���Ƃ݂��A�����ڂ������ׂĂ��܂��B17�����_�ł̓��@�Ґ���366�l�ŁA�a���g�p����61�D3���A����×{�҂�395�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�d�ǎҐ��́A16������5�l������16�l�ƂȂ��Ă��܂��B9��12���܂ł̉��������܂����A�܂h�~���d�_�[�u�ɂ��āA���́A�Ǝ���̉������܂߁A����̑Ή��ɂ��Č������Ă��܂��B
�����s�A�V�K�z����8�T�A���ő����@�u��@�I�ȏv �@�_�ސ쌧�@8/18
���s�����\�������߈�T��(��〜�\�ܓ�)�̐V�K�z���Ґ��͎O���S��\�l�Ɣ��T�A���ő����A�ߋ��ő����X�V�������Ƃ��\�����A���������B���̓��̑��{����c�ɏo�Ȃ����s���N���S�������̉����M�F�����́u�z���҂��}������A�d�ǎ҂��}������B�s���͊�@�I�ȏv�Ǝw�E�����B(�������q)
�s�ɂ��ƁA���@�Əh���E����×{���܂ޏ\�ܓ����݂̗×{�Ґ����A�O�T��蔪�S���\���l�����O��ܕS���\�l�ƂȂ����B�s�����a�@�ŘZ�����璆���Ǘp�̓]�p�Ȃǂŏd�Ǘp�a�����\�O�������\���ɑ��₷�ȂǕa���̊m�ۂɓw�߂Ă��邪�A�s���̏d�Ǘp�a���̎g�p����100�������B�Վ��ɃR���i�p�łȂ��W�����Î�(�h�b�t)���g����ԂƂȂ��Ă���Ƃ����B
�z���Ґ������������Ŋ������z������42�E9���B��������s���s����Ë@�ւ���s�O���_�Ō��������͂��o���������邱�Ƃ���u�s���̎��Ԃɑ����Ă��Ȃ��v�Ƃ��āA����s�O���̗z���Ґ����Ȃ��Ƃ����B
�s���ł͎���×{���̎l�\��j���̗e�̂��������A�~�}������̕a�@�ŏ\�l���ɖS���Ȃ鎖�Ԃ��N�����B���c�I�F�s���͉�c��A�L�Ғc�Ɂu�����������F�肵�����B�s���S�͂������Ă��邪�A������l������P�[�X�B�ЊQ�ɋ߂��ŁA�������Ȃ��댯�������܂��Ă���v�Əq�ׂ��B
�傫�ȉ����g����������u���a�@�v��_�f�Z���^�[���s�Ƃ��ĉ^�c���邱�Ƃɂ��Ắu��Î������͊����Ă���B�a����������x�Ȃ��ƁA���ߒu�������ƂȂ��ċ@�\���Ȃ��v�Ɣے�I�Ȍ����������A�s����Ë@�ւɌĂт����A����a���̊g��ɓw�߂Ă���Ƃ����B
���É��E�V�^�R���i�@����×{��1625�l�@�V�K�����҂ƂƂ��ɋ}���@8/18
�É������ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�Ƃ܂炸�A18���̐V�K�����҂�590�l��2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�V�K�����҂̋}���ɔ����A�����Ă���̂������̎���×{�Ґ��ł��B8��18���̌��̔��\�ł�1625�l�ɒB���܂����B
7����{�ɂ�100�l�ȓ��Ɏ��܂��Ă��܂������A7�����{���瑝���n�߁A8��3����500�l��˔j�������ƁA�킸��2�T�Ԃ�3�{�ȏ�ɋ}�����Ă��܂��B
�����ł̓R���i���җp�̕a����40�{�݂�569���m�ۂ���Ă��܂����A8��18�����݂�319�l�����@���Ă��āA���S�̂̕a����L����56�D1���ł��B
�V����90���]����m�ۂł��錩�ʂ������A�a������634���܂ő����܂����A���́A���̂܂܂̃y�[�X�Ŋ����g�傪�i�ނ�9�����{�ɂ͕a��������Ȃ��Ȃ�Ƃ݂Ă��܂��B
����́A���������鎩��×{�҂̕a��c�����d�v�ȉۑ�ƂȂ�A���́A�n��̈�Ë@�ւ��a��c���ɋ��͂��Ă����悤�A�˗����Ă��܂��B
���u�K�v�Ȑl�̎��Â��c�v�@���쌧�ʼnߋ��ő�152�l�����@8/18
18���A���쌧���̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�152�l�B1���̔��\�ʼnߋ��ő����X�V���܂����B�ی����́u����������ΕK�v�Ȑl�����Â����Ȃ��Ȃ�v�Ƃ��A��@�������߂Ă��܂��B
����s�ی����E���їǐ������u�ō����x���̊����g��v
���{�s�ی����E�˓c���及���u�����g��̃s�[�N�����ʂ��Ȃ��v
18���A�����Ŕ��\���ꂽ�V�K�����҂�152�l�B1���̔��\�ł́A����13����109�l��啝�ɏ���A�ߋ��ő����X�V���܂����B
�������킩�����̂́A10�Ζ�������90�Έȏ�̒j��152�l�ł��B���{�s�ʼnߋ��ő���32�l�A����s26�l�A��c�s12�l�A�z�K�s8�l�A���J�s6�l�A�����s5�l�A���K�s5�l�A���ܖ�s5�l�A�{��s3�l�A��Ȏs3�l�A����s3�l�A�ѓc�s3�l�A�ɓߎs2�l�A�y���2�l�A���v�䒬2�l�A���2�l�A���쑺2�l�A����s1�l�A����s1�l�A�咬�s1�l�A��P���s1�l�A�R�m����1�l�A���a��1�l�A���c��1�l�A���Ȓ�1�l�A���C��1�l�A���֒�1�l�A���n��1�l�A�L�u��1�l�ŁA���O�ݏZ�҂͓����s8�l�A�_�ސ쌧4�l�A��ʌ�3�l�A������1�l�A���m��1�l�A���{1�l�A���Ɍ�1�l�ł��B
���̂���74�l������܂ł̊����҂̔Z���ڐG�҂܂��͐ڐG�ҁB���O�����̂���l��21�l�A�����o�H�s����50�l�A�܂��A���O�ݏZ�҂�19�l�ł��̂������Ȃ��Ƃ�8�l���A�Ȃł��B(�d������)
�}���ȃX�s�[�h�Ŋg�傷��u��5�g�v�B�����̐V�K�����҂�18���܂ł�1238�l�m�F����A10���ȏ���c���āA�ł���������1����1105�l������܂����B
�����҂��}�����Ă��鏼�{�s�ł́A�u20��A30�オ�������Ă��āA��H�ł̊������ڗ��v�Ƃ������Ƃł��B
����s�́A�u����������Έ�Ñ̐��ɉe������v�Ƌ�����@���������܂����B
����s�ی����E���їǐ������u����ȏ�A�����҂�������ƁA�K�v�ȕ��̎��Â��\���Ɏ��Ȃ��Ȃ���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�����҂̗v��6532�l�B���@����214�l�A�h���×{293�l�A����×{142�l�A������136�l�ł��B���̂����A�d��3�l�A������43�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�m�ەa���g�p����45.1���B�����ǂ�y�NJ��҂�������ʕa���̎g�p���́A�n��ʂɖk�M70.3���A���M54.9���A���M37.2���A��M43.4���ƂȂ��Ă��܂��B
���u�����s�[�N���ʂ��Ȃ��v�@���{�s�ʼnߋ��ő�32�l�����c�@8/18
���{�s��18���A�V����32�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\���܂����B1��������̔��\�ł́A8��14����30�l������ߋ��ő����X�V���܂����B
�������킩�����̂́A10�Ζ�������60��̒j��32�l�ł��B���̂���13�l������܂ł̊����҂̔Z���ڐG�҂܂��͐ڐG�ҁB���O�؍ݗ�������l��4�l�A�����s�ݏZ1�l�A�����o�H�s����14�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���{�s�ی����̒˓c���及���́u�����̃s�[�N�����ʂ��Ȃ��B���コ��ɗz���҂��������鋭�����O������v�Əq�ׁA��@�������߂Ă��܂��B
�����g��̗v���́A�u7����4�A�x�ȍ~�A���O�����̂���l���瓯���̐l�A�m�l�ɍL�����Ă���v�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�u20��A30��ő������Ă��āA�}�X�N�Ȃ��̉�H�ł̊������ڗ��v�Ƃ������Ƃł��B
���~�x�݁A�ċx�݂��I���A���퐶�����ĊJ����邱�Ƃ���A����Ȃ銴���̊g�傪�뜜����܂��B
�˓c�����́u���コ��ɗz���҂��g�傷��A��Ñ̐����ؔ����A�\���Ɉ�Ñ̐������Ȃ��Ȃ邾���ł͂Ȃ��A��ʐf�Âւ̌��O������v�Əq�ׁA����w�̊�������s���ɌĂт����܂����B
��30��ȉ���7�����@�J���I�P���H�A�h���C�u... ���ʼnߋ��ő������@8/18
���Ɗs��18���A����35�s���ȂǂŌv338�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B1��������̊����Ґ���2���A����300�l������A17�����\��324�l���ĉߋ��ő����X�V�����B�����҂͗v1��1470�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����҂��O����54�E01�l����啝�ɑ�������64�E83�l�ɏ㏸���A�ߋ��ő����X�V�B17�����_�̓��@���҂�384�l�ŁA�a���g�p���͍��̊�ŃX�e�[�W4(�����I�����g��)�́u50���ȏ�v�ɔ���49���ƂȂ����B
�N��ʂł́A20�オ120�l�ƍł������A40��52�l�A10��49�l�A30��46�l�A50��28�l�Ƒ����A30��ȉ��őS�̂�70�E1�����߂��B�N���X�^�[(�����ҏW�c)�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����A�F�l�ƃJ���I�P��h���C�u�A��H��������A���O�̊����g��n��ɏo�|�����肵����҂���������Ƃ����B
�����N�������̖x�T�s�����́u�J��Ԃ����ӂ����肢���Ă�����H�Ȃǂ̍s�����̂���l�̊����������B�l�������Ȃ���Α��v�Ƃ�����ł͂Ȃ��v�Ƌ����B��Ò̐��ɂ��Ắu���@���҂�h���×{�{�݂̗��p�҂��}�����Ă���B�ی��������@�A�����̎葱�����ŗD��ɑΉ����Ă��邪�A���܂�ɑ��������傫���A�����œ��݂Ƃǂ܂�Ȃ��Ƃ��Ȃ茵�����v�Ƙb�����B
�V����5���̃N���X�^�[���m�F���ꂽ�B���̂����������s�Ɖ��s�ł́A���ꂼ���H�������F�l��ɂ��5�l���̃N���X�^�[�������B�����̑g�ݍ��킹�ŏo�|�����肵���s��H���s�̗F�l�ƁA���̉Ƒ���9�l�̊��������������B���Ɋ֎s�̐E��̓�����6�l�A���ΌS���@���̉Ƒ���5�l�̊��������������B
�g�債���N���X�^�[��10���B�����s�̎R�c�a�@�ł͓��@���҂ƐE���̌v6�l�̊������������A31�l�ƂȂ����B
�V�K�����҂̋��Z�n�ʂ͊s77�l�A��_�s45�l�A���Ð�s20�l�A�e�����s�A���s���e17�l�A�֎s16�l�A�H���s14�l�A����s12�l�A�������s11�l�A���Z���Ύs9�l�A���Q�s�A�s�j�S���䒬�A�{���S�k�������e8�l�A�C�Îs�A�H���S�}�������e7�l�A���R�s�A�b�ߎs�A�S��s���e6�l�A�y��s5�l�A�R���s�A�����S���������e4�l�A���Z�s�A�{���s�A���C�s�A�K��S��쒬�A���S�䐓�����e3�l�A�H���S��쒬�A�{�V�S�{�V���A�����S�֔V�����A�K��S�K��쒬�A���S�r�c�����e2�l�A�����S�_�˒��A���ΌS��j���A���S�x�����A���S���@���A�_�ސ쌧�A���m�����e1�l�B
�N��ʂ�1�Ζ���2�l�A1�`10�Ζ���20�l�A10��49�l�A20��120�l�A30��46�l�A40��52�l�A50��28�l�A60��A80�オ�e7�l�A70��6�l�A90��1�l�B
���ޗnj��@�R���i�ߋ��ő�162�l�@50��ȉ���9���@8/18
�S���I�ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����A�ޗnj��Ɠޗǎs��18���A162�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1���̊����Ґ��ł͉ߋ��ő��B18���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����҂̂����A50��ȉ����S�̂�9�����߂Ă���A�����E��Ґ���̊����������ƂȂ��Ă���B
�u�����ɂ́A�����̘A����f���邽�߂̎��g�݂̓O������肢�������v
���̓��A�����ŋً}�L�҉���������ב��E��@�Ǘ��Ă͂����Ăт������B
�����ł�11����138�l�̊����҂��m�F���Ĉȍ~�A16����������1���̊����Ґ���100�l���鍂�~�܂�̏�ԂƂȂ��Ă���B�����̗z����(7���ԕ���)��13���O��ŁA���ł�3�`6���́u��4�g�v�̃s�[�N���������Ă���B
8���̊����҂̌X�����݂�ƁA�N��ʂł�20�オ20�����čł������A30�`50������������ƂȂ��Ă���B�܂��A2�`8����1�T�ԂɎ��{���������҂̃X�N���[�j���O�����ł́A5���ȏオ�����͂̋����C���h�R���̃f���^���̋^��������A�����ł��}�����Ă��邱�Ƃ����������B
��Ò̐����N�����Ă���B18�����_�̏d�Ǖa���̎g�p����32�������A�d�Ǖa�����܂߂��S�̂̕a���g�p����65���ɒB���A������߂�X�e�[�W4(�����I�����g��)�̖ڈ��ł���u50���ȏ�v�������Ă���B
�܂��A���@������ҋ@���̊��҂��}�����Ă���B18�����_�̏h���×{�{�݂̎g�p����61���ŁA�ҋ@���̊��҂�363�l�ɏ�����B�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ���A����ҋ@�҂�����ɑ������鋰�ꂪ����Ƃ����B
���͏h���×{�{�݂̕������̊g����}���ق��A�a���m�ۂɂ��Ă��a�@���Ƌ��c�𑱂��Ă���B
��ŁA���ė��E��Ð���ǒ��́u�R���i�Ή��ƒʏ��Ẫo�����X���l���Ȃ���a�@�Ƒ��k���Ă���v�Ƙb�����B
������@�Ǘ��ẮA���ȂNJ����g��n��Ƃ̉������T���邱�Ƃ�A�ƒ���ł̊����h�~��O�ꂷ��悤�Ăт������B����A���ւً̋}���Ԑ錾���߂̗v���ɂ��ẮA�u�ޗnj��Ɍ��ʂ�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��B�����_�ŗv������Ƃ�������͂���Ă��Ȃ��v�ƐT�d�ȍl�����q�ׂ��B
�����}�����A����20���ɐV�^�R���i���c���J���A����̋�̓I�Ȋ����h�~������c������j�B
����҂̃R���i�����g��̃y�[�X�����A���{�u���䍢��ȃ��x���v�@8/18
�V�^�R���i�E�C���X�Ή��ً̋}���Ԑ錾��9��12���܂ʼn������ꂽ���Ƃ��A���{��18���A���{����c���J�����B�{�͍s���͈͂̍L����҂𒆐S�Ɋ������L����A�R���g���[���������Ȃ��Ȃ��Ă���Ɗ뜜�B�N���X�^�[(�����ҏW�c)������Ҏ{�݂��傾�������t�̑�4�g�Ƃ͈قȂ�A�w�Z���ƂȂǂɃV�t�g���Ă���A���𐢑�ւ̂���Ȃ銴���g��Ɍ��O���L�����Ă���B
�u20��A30��̊����͐��䍢��ȃ��x���ɂȂ��Ă���v�B�{���N��Õ��̓���r�q�����͉�c�Ŋ�@���������ɂ����B
�{�ɂ��ƁA17���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͌v1��1117�l�ƂȂ�A���߂�1���l�����B
�����̒��S�ƂȂ��Ă���̂�30��ȉ��̎�҂��B20�`30��̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑O�T��1�E48�{�B�O�T��O�X�T�Ɣ�ׂ��1�E15�{�ŁA�����g��̃y�[�X���������Ă���B30��ȉ��̐V�K�����҂́A��4�g(3��1���`6��20��)�ł͑S�N���47�E7�����������A��5�g(6��21���`8��15��)�ł�65�E0���ɏ��B
����5�g�@��ƁA��w�E�w�Z�ŃN���X�^�[��
�ǂ��Ŋ������L�����Ă���̂��B���̈�[������������f�[�^�����̓��̉�c�Ŏ����ꂽ�B�N���X�^�[�̔����ꏊ���4�g�Ƒ�5�g�Ŕ�r����ƁA�����҂̃��N�`���ڎ킪�i�ލ���Ҏ{�݂̊������N���X�^�[�S�̂�39������8���ɑ啝���ƂȂ�������A��Ƃ�16������33���ɁA��w�E�w�Z��8������19���ɁA���ꂼ��}�������B��w�E�w�Z�ł�8��16���܂ł̖�2�J���Ԃ�18���̃N���X�^�[���m�F����A���̂�����������4����3���߂��B
�{�́A��5�g�̊����҂Ɋ��������\��������ꏊ��o������������B����742�l���A�ł����������̂��A�u�S�ݓX��V���b�s���O���[���Ȃǂł̋Ζ��v��34���ɓ�����249�l�ɏ�����B�u�C������h���C�u�Ȃǂ̗��s�v��28��(207�l)���u�o���v��17��(123�l)���u�A�ȁE�������E�@���Ȃǐe�ʂ̏W�܂�v��10��(72�l)�\�\�Ȃǂ������B
�R���M�F���m���͌J��Ԃ����ً}���Ԑ錾�Ɋւ��A�u�{���ɂ́w�܂����x�Ɗ�@�������L����Ȃ����������邩������Ȃ����A�����̓������l����A�A�N�e�B�u��40�A50����w����ɂ�������Ăъ|���邱�Ƃ��厖���v�Ƒi�����B
���d�lj��h�����ߍR�̃J�N�e���Ö@�ɒ���
�����g��ɔ����A�a�������X�ɖ��܂�n�߂Ă���B�{���m�ۍς݂̏d�Ǖa��587���ɂ�18�����_��158�l������A�g�p����26�E9���B���Ґ���1�J���O��40�l���x����}�����A��5�g�ł�40�A50�オ�S�̂�53�E1���ɏ��B�m�ۍς݂̕a���ɂ͕ʂ̎��a�̊��҂����p���Ă�����̂��܂܂�A�R���i�p�ɂ����Ɏg������̂Ɍ����325���ŁA�g�p����48�E6���ɂ͂ˏオ��B�{�͕a���m�یv��Ɋ�Â��A�����ɗ��p�ł���d�Ǖa��������ʈ�Âɉe����^���Ȃ��u�t�F�[�Y3�v�őΉ����Ă������A18���ɂ͔�펖�Ԃɓ�����u�t�F�[�Y4�v�Ɉ����グ�A420���܂ő��₷�悤��Ë@�ւɗv�������B
�d�Ǖa���̕N��(�Ђ��ς�)��h�����߁A�{���͂�����̂����҂̏d�lj���h���R�̃J�N�e���Ö@���B�{��125�̈�Ë@�ւŎ��{���Ă���ق��A8�����{����h���×{�{��1�J���Ŏn�߂�B�g���m���m���́u�����邩���ʂ��̐��ˍۂŖ������̂��d�Ǖa�����B�E���オ��̏d�ǎҐ��𑁊����Âɂ���ė}���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƌ�����B
���V�^�R���i�����m�F ���߂�1000�l������ �@���Ɍ��@8/18
���Ɍ���18���A�����ŁA����Ƃ��Ă͏��߂�1000�l���銴���҂��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B17����853�l�������ĉߋ��ő��ƂȂ�A�����̋}���Ȋg��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
�����R���A�w�W������3���ڂŃX�e�[�W4�����@8/18
���R����18���Ɍ��\��������1�T��(11�`17���A����l)�̐V�^�R���i�E�C���X�̌��������ɂ��ƁA�w�W6���ڂ̂���3���ڂ��X�e�[�W4(�����I�����g��)�̊���������B����10���l������̐V�K�����҂Ɨ×{�҂͊��2�{�ȏ�ɒB���A��Ì���̕N�������O�����Ƃ����B�S�̂̔��f�̓X�e�[�W3(�����}��)���ێ��������̂́A�܂h�~���d�_�[�u(20���`9��12��)�̓K�p������炭���������Ԃ��������ʂ����B
�X�e�[�W4�����̂́A10���l������̐V�K�����Ґ�(63�E17�l)��10���l������̗×{�Ґ�(68�E62�l)�APCR�z����(12�E3��)�B��Â̕N���x�����������a���g�p����33�E4���ŃX�e�[�W3�̊���������B
1�T�ԓ�����̊����Ґ���1194�l�B����11���ȍ~�A�A��100�l���A18���ɂ͉ߋ��ő���307�l�̊��������������B�����͂������C���h�R���̕ψي��u�f���^���v�ւ̒u������肪�}���ɐi�݁A�g��Ɏ��~�߂��������Ă��Ȃ��B
���@�҂̏��������Ă���B�d�ǎҗp�̕a���g�p��(10�E3��)�̓X�e�[�W3�̊���Ⴍ�}�����Ă�����̂́A�y�ǎ҂ł�����×{���ɗe�Ԃ��}�ς��ċ~�}��������鎖����������Ƃ����B
����A�����g�ѓd�b�̈ʒu���f�[�^�͂����Ƃ���A���~���Ԃɂ͑�������̗��������펞��2�`4�{�ɋ}���B�A�Ȃ◷�s�Ŋ������A�Ƒ���F�l�֍L����P�[�X���ڗ����n�߂Ă���u���T�����痈�T�ɂ����Ă���Ɋ����҂������Ă������Ƃ����O�����v(���ی�������)���B
�Ɍ��ؗ����m���͕w�ɑ��u��s���ł͓��@���ׂ����҂����@�ł��Ȃ����Ԃ��N���Ă���B�d�_�[�u���g���Ċ�����}���Ȃ���Αł�͂Ȃ��A�����̖������Ȃ��B�^����ꂽ�������ő���g���A�����g����~�߂����v�Əq�ׂ��B
���������́g�V�K�R���i�����ҁh1253�l�@�ߋ��ő����X�V�@8/18
�V�^�R���i�E�C���X�̏��ł��B��������18���̊����҂�1253�l�A�ߋ��ő����X�V���Ă��܂��B
������1253�l�̓���͕ی����̊NJ��ʂɕ����s625�l�A�k��B�s229�l�A�v���Ďs59�l�A���̂ق��̒n���340�l�ƂȂ��Ă��܂��B��������7849���ŗz������16�D0���ł����B70��̒j��1�l���S���Ȃ��Ă��܂��B�V�K������1253�l�́A6���O�ɏ��߂�1000�l���Ĉȗ��̉ߋ��ő��ŁA8��11���Ɣ�ׂĈ�C��500�l�ȏ㑝���Ă��܂��B
�������̒S���ҁu�ɂ߂Đ[���ȏƍl���Ă���B�����������I�Ȋ����g��B�v
�������ł�3�A�x�₨�~�ȂǂŐl���������������Ƃ������g��̌����̈�Ƃ�����ŁA�u���N�`����ڎ킵���l���������O�ꂵ�Ăق����v�ƌĂт����܂����B
�����ꌧ�A���H�X�Ɏ��Z�v���ց@8��20������@8/18
���~���Ԃ������Ă��獲�ꌧ���ŐV�^�R���i�E�C���X�������g�債�Ă��邱�Ƃ��A����20�����猧���S��̈��H�X�ɉc�Ǝ��ԒZ�k��v��������j���ł߂����Ƃ�17���A�W�҂ւ̎�ނŕ��������B���Ԃ�8�����܂ł�z�肷��B����܂Ŋ����ґS���ɓ��@���z�e���×{�őΉ����Ă������A�N��(�Ђ��ς�)�����Ò̐�����邽�߁A����×{��g�ݍ��ށB�������18���̊����܂��čŏI�������A�ߌォ��̑��{����c�Ő����Ɍ��肷�錩�ʂ��B
����17���A�V����121�l�̊������m�F�����B1��������̊����Ґ���2���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B�a���g�p����57�E4���Ɖߋ��ō����X�V�����B
���Z�v���͌��Ǝ��́u��Ë@�ւ���邽�߂̔��x���[�u�v�̔��߂ɔ������{����B���H�X�ɂ͋��͋����x�����A�����ɂ͐V�^�R���i�Ή��̒n���n���Վ���t�����[�Ă���j�B
�W�҂ɂ��ƁA���Îs�ŕ����̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F�����ȂNJ����g�傪���ɐ[�������Ă��邱�Ƃ���A���Òn��̉c�Ǝ��Ԃ𑼂̒n����Z���ݒ肷�邱�Ƃ�����Ɍ������Ă���B
�R���ˋ`�m����12���̗Վ��L�҉�ŁA���~���Ԃ�15���܂ŊO�o���l��v���������A16���ȍ~�A2���A����3���̊����҂��m�F���ꂽ�B��ł́u�s�s��������Ǝ��Z�v���̌��ʂ��ǂꂾ������̂����^�I�����A���ꂩ�琔���Ԃ̏����Č�������v�Ƃ��Ă����B���̌�A���H�X�ł̃N���X�^�[�����Îs��3���A����s��1���m�F���ꂽ���Ƃ����Z�v���ɓ��ݐ�v���ɂȂ����Ƃ݂���B
�����͕a���g�p����17���܂�2���A���ʼnߋ��ō��ƂȂ�A�a���̕N���x�����܂��Ă���B����܂Ŋ����҂̎���ҋ@�[�����������Ă������A�����Ljȏ�̊��҂����@�����Ë@�ւƁA�y�ǁE���Ǐ�Ҍ����̗×{�z�e���ɉ����A����×{��g�ݍ��V���Ȉ�Ò̐��̃V�X�e���ɂ��Ă��A18���̑��{����c�őł��o�����ʂ��B
�����Îs�Ǝ��́u�ً}�錾�v���\�@�z���ҋ}���@���ꌧ�@8/18
�V�^�R���i�E�C���X�̗z���҂����Îs�ŋ}�����Ă��邱�Ƃ��A���s�̕��B�Y�s����17���A�s�Ǝ��́u�ً}�錾�v�\���A�����g��Ɋ�@�����������B�l��10���l������̐V�K�����Ґ�(1�T�Ԃ̍��v)�����������ɁA�s���̊����́u�����s�ƕC�G����v�Ƌ����A���߂Ċ����h�~���O�ꂷ��悤�Ăъ|�����B
�s���ł�3�A�x���10�����犴���҂������Ă���A��s���́u�������Ɨאڂ��Ă��邪�����R���łȂ��A���ɋ����Îs���Ŋ������g�債�Ă���v�Ƃ̔F�����������B�s�̐l���͖�12���l�A10�`16���̊����Ґ��͌v200�l�ŁA10���l�������166�l�B�����s��10���l������214�E4�l(15�����_�A�s�����ی��ǔ��\)�ƂȂ��Ă���B
��s���͉�H�A�s�v�s�}�̊O�o���T���邱�Ƃ�}�X�N���p�̓O��Ȃǂ��Ăъ|���A�u�����o�H���s���Ȑl���������Ă���B���}�ɐl����}�����邱�Ƃ��ő�̖h��ɂȂ���v�Ƙb�����B��̓I�ȑ�͈�t��ȂǂƋ��c���Ȃ��猟�����Ă����B
������@�V�^�R���i89�l�V�K�����@�N���X�^�[�g��@8/18
���茧�Ȃǂ�18���A�V���Ɍ���11�s4����89�l���V�^�R���i�Ɋ��������Ɣ��\���܂����B17����104�l�Ɏ����ʼnߋ�2�Ԗڂ̑����ŁA����s������ܓ������Ԋw�Z�̃N���X�^�[���g�債�Ă��܂��B
89�l�̓���͒���s���ł�����20�l�A�|���s18�l�A�ܓ��s16�l�A�����ێs12�l�A�呺�s6�l�A�쓇���s�ƒ��^����3�l���A�����s�A�_��s�A���Y�s��2�l���A���ދn���A��I���A���X���A���s�A�Δn�s��1�l���ł��B�����҂ƐڐG�����Ƃ��Č��������l��59�l�A�����o�H���킩���Ă��Ȃ��l��30�l�ł��B�d�ǎ҂͂��܂���B�N��ʂł́A����\�������ł������̂�20���18�l�ŁA������10�オ14�l�A40�オ11�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B(10�Ζ���1�l�A30��10�l�A50��6�l�A60��2�l�A70��4�l�A80��3�l�A����\20�l)�B
����s��17���s�����{�ق�5�K�ŃN���X�^�[�������������Ƃ��ڐG�҂ȂǂɊւ�炸5�K�ɋΖ�����E��80�l��PCR�������܂����B���̌��ʁA�V���ɓy�ؕ���20��j���E��1�l�A30��j���E��1�l�A40��j���E��2�l�A����������������20�㏗���E��1�l�̍��킹��5�l�̗z�����������A�N���X�^�[��11�l�ƂȂ�܂����B5�l�Ƃ����Ɩ���H������̊Ǘ��ēƖ��A�H���v��Ɩ���S�����Ă��Ďs���⎖�Ǝ҂Ƃ̐ڐG�͂Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B�s�͍X�ɐڐG�̂�������20�l�̐E���ɑ������̏�����i�߂Ă��܂��B�V�^�R���i�̊����g����A�s��23��(��)�܂łƂ��Ă����O���o�[���⌴�������قȂNJό��{�݂̋x�ق̉������������Ă��܂��B
17���ɃN���X�^�[�ƌ��\���ꂽ�A�ܓ��s�̌ܓ������Ԋw�Z�ł́A�V���ɖƋ����h�ɎQ�����Ă������p��11�l�A�E��1�l�̊������킩��A�W��103�l�̂��������҂�18�l�ƂȂ�܂����B�V���Ɋ����������p��11�l��10�ォ��20��A�܂��͔���\�̒j���A���Ǐ�̐l������Δ��M��P�A���o��k�o�ɏ�Q���o�Ă���l�����܂��B���p�҂͌��O�ݏZ�҂������A�ܓ��s���̎����ʊw���Ă��闘�p��16�l�͑S���A���ł����B�ܓ��s�̊����҂�17����18����23�l�Ƌ}�����Ă��āA���茧�͌ܓ��n��̑Ή��t�F�[�Y���u2�v����ő�́u4�v�ɏグ�A�m�ەa����10������23���ɑ��₵�܂����B(�ً}���Ή��ł́{2��)���̂���43����10�������܂��Ă���ł��B
18�l�̐V�K���������\���ꂽ�|���s�ł́A������9�l���A�ȂȂǂ̌��O�ړ����������Ƃ������Ƃł��B
�����Ǐ�z���A1���~�܂�@�����c�����s�\�����@8/18
�������}�g�傷��V�^�R���i�E�C���X�̑�5�g�ŁA�����s�̌����ŗz���m�F���ɖ��Ǐ�̐l����1���ɂƂǂ܂��Ă���B�{���͖��Ǐ�̊����҂�3�����x����Ƃ���邽�߁A�����҂��ꕔ�����c���ł��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B�ی����ɂ��Z���ڐG�҂̒��������Ă��邱�Ƃ������Ƃ݂���B���{�ً͋}���Ԑ錾�̉����ƑΏۊg������߂����A�s���ɑ����閳�Ǐ�҂����ӎ��̂����Ɋ������L���Ă���\�}�������ԁB
�s�̃��j�^�����O��c�͍�N7���ȍ~��1�T�ԓ�����̊����Ґ��Ɩ��Ǐ�҂̊��������\�B���Ǐ�҂̊�����1�T�Ԃ̊����҂��v1���l����7�����{�ȍ~�A12�E2��(7��20�`26��)��11�E4��(��27���`8��2��)��12�E4��(��3�`9��)�|�Ɖߋ��Œᐅ���������B
�����J���Ȃ́u�f�Â̎�����v�ɂ��ƁA���Ǐ�҂̊�����30���O��Ɛ���B���������������Ă���3����20�A21����Ő��ڂ���ȂǁA��萔�͕ߑ�����Ă����B����܂ł������Ґ��̋}���Ŗ��Ǐ�҂̊�������������X���͂���A�N���N�n�̑�3�g�ł�23�E2��(12����{)����16�E4��(1����{)�ɒቺ�B�����A�����6��������13���䂪�p�����Ă���B
�s�͍���10���t�ŔZ���ڐG�҂⊴���o�H���ڂ������ׂ�u�ϋɓI�u�w�����v�̋K�͏k�����j���e�ی����ɒʒm�������A���̑O�i�K�ŕی����̕��ׂ��}�����A�Z���ڐG�҂�̊m�F�����ɉ�炴��Ȃ����������Ƃ�����������B
�ی����Ɩ��̕N��(�Ђ��ς�)�͗z�����̍�����������ĂƂ��B8����1�T�ԕ��ς�20�����������A���߂ł�24�E0���ɋy�ԁB�z�����̍��܂�́A�s���������Ǐ���ȂNJ����̉\���������l�̗z�����m�F����Ƃ������ʂ����܂���邱�Ƃ������Ă���B
���M�Ȃǂ̗L�Ǐ�҂͑������A�s�́u���M���k�Z���^�[�v�ɂ�7�����{����2�T�Ԉȏ�ɂ킽���ĘA���A���ϖ�3�猏�̑��k������B1����{�̃s�[�N�̓���2700���A5����{�̓���2300���������Ă���B
�V�^�R���i�͔��ǑO�△�Ǐ�̐l���犴�����郊�X�N������̂��������B�]�����̖�2�{�A�p������1�E5�{���x�̊����͂�����C���h�R���̃f���^���͊֓��Œu������肪��9���ɒB�����Ƃ݂��Ă���B�f���^���ɂ��ĊC�O�ł́u�]����1200�{�E�C���X�ʂ������v(����)�A�u�p�����ɔ�ׂē��@���X�N�������v(�p�X�R�b�g�����h)�Ȃǂ̌������ʂ����邪�A�a�����������Ȃ��Ă��邩�┭�ǂ��₷�����͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B
������ȑ���_�c�ĘY���C����(�n�q��w)�́u�Z���ڐG�҂̐o�����\���ɍs���Ζ��Ǐ�҂��m�F�ł��邪�A�ی����̋Ɩ��������Ē��א�Ă��Ȃ��B���͂Ŋ����҂��o���ꍇ�A�s���ɔC����̂ł͂Ȃ���Ƃ�w�Z�A�ł���Ήƒ�ł����Ԃ̌�������ׂ����B��p���S�͐����邪�A�����̉�𑁊��ɓE�ނ��Ƃ��d�v�v�Ǝw�E�����B
���u����s�\�ȏv���{�A�V�^�R���i�ً}���Ԃ�啝�Ɋg��E�����@8/18
���{���{���V�^�R���i�ً̋}���Ԕ��ߒn���啝�Ɋg�債�Ċ������������{�܂ʼn�������B�����p�������s�b�N�̊J������T�ԍT���A�A���V�K�����Ґ����}�����Ă��邱�ƂɂƂ��Ȃ��[�u���B
���`�̎�17���A�V�^�R���i���{����c���J���Ĉ��E�ȖE�Q�n�E�É��E���s�E���ɁE�������Ȃ�7�n����ً}���Ԑ錾�n��ɒlj����邱�Ƃ����߂��B���Ԃ�20�����痈��12���܂ł��B
����ŋً}���Ԑ錾�n��͌��݁A�����s����{�A��ʁE��t�E�_�ސ�E���ꌧ�Ȃ�6�n����܂��13�����̂ɑ����邱�ƂɂȂ����B����6�n��̊�����8�������痂��12���ɉ������ꂽ�B
�܂��A�������Ԃɋ{�錧���͂��߂Ƃ���10�n��ɐV���ȋً}���Ԃ̑O�i�K�ł���u�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p������j���B����ɔ����A�d�_�[�u�K�p�n������Ėk�C�����Ȃ�6�n�悩��v16�n��ɑ�����B
���{�̐V�^�R���i�g��X���͐��Ƃ̕\���Łu���䂪�ł��Ȃ��v���B17���A�����ł�4377�l�̊����҂��������A�Ηj������Ƃ��ĉߋ��ő��ƂȂ����B���̓��A�S���ł�1��9955�l(�ߌ�6��30�����݂m�g�j�W�v)���m�F����A��͂�Ηj������ɉߋ��ő��������B1�T�ԑO�ɔ�ׂ��90�����}�������B
�V�^�R���i�̐����S�����鐼���N���o�ύĐ�����17���u�A������߂č��������ŁA���t�ǂ���ɒ������������g�債�Ă���v�Ƃ��āu��Ò̐��͎�s���𒆐S�ɔ��ɐ[���ȏv�ƌ��O���������B
24�����痂��5���܂ŊJ����铌���p�������s�b�N�����ϋq�ŊJ����邱�ƂɂȂ����B�I�����s�b�N(�ܗ�)�Ɠ��l�ɂ��ׂẲ��ň�ʊϋq����ꂸ�ɒn�������̂Ɗw�Z����]����ꍇ�A���k�̓���𐧌��I�ɋ��e����B
���Ƃ�ً͋}���Ԃ̊g�储��щ������j�ɂ����{�̐V�^�R���i�g��X���͓����������̂Ɨ\�z���Ă���B�ܗֈȍ~�u���l�̕��͋C�v�͊��S�ɏ����A���{�̌Ăт����ɂ���Čߌ�8���܂ʼnc�Ƃ��Ă������H�X���u��������ȏ�͑ς����Ȃ��v�Ƃ��ĉߑӋ����o�債�ēX���^�c���Ă���B
�����V���͍������߁A�����s�S�̔ɉ؊X�ɂ�����H�X��500�J�������Ŋm�F�������ʁA40���ȏオ�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���ɉ������A�قƂ�ǂ������Ă�����17���`�����B
���̂悤�ȏŁA���{���{�̓��N�`���Ɏ����������Ă���B11���܂Őڎ����]���邷�ׂĂ̍����Ƀ��N�`��2��ڂ̐ڎ���I���A���̌�ɂ͈�Ï]���҂�65����҂���3��ڂ̐ڎ�(�u�[�X�^�[�V���b�g)���n�߂���j�����������B
���N�`���ڎ�ӔC�҂ł���͖쑾�Y�s�����v�S������16���A����ԑg�ɏo������3��ڂ̐ڎ�̂��߂ɗ��N��1��2000���̃��N�`����lj��������邱�ƂŃt�@�C�U�[���ƍ��ӂ����Ƃ��u�߂������ɓ��e�����J�ł���v�Ƙb�����B
���@�ɂ��ƁA17������ɓ��{�̃��N�`��1��ڂ̐ڎ헦��49�D7���A2��ڂ̐ڎ튮����37�D6�����B
���ً}�錾���g��@�~�܂�ʑ�̖��� �@8/18
�l�x�ڂً̋}���Ԑ錾�̓�x�ڂ̉����ł���B�����𑱂��鐭�{�̑Ή������Ă���ƁA�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�{�C�ŗ}���������Ƃ��Ă���̂��s�M�����B
���{�͍������Ɋ������}���铌���s�ȂǘZ�s�{���ւ̐錾���ߊ������㌎�\����܂ʼn�������B�Ώےn���������\��������A�ȖA�Q�n�A�É��A���s�A���ɁA�����̎��{���֊g�傷��B
�����̋}�g�傪�[�������Ă���B�́u�ЊQ���x���v�ł���B��Â̕N��(�Ђ��ς�)���l����A�錾�����Ɗg��͂�ނȂ��B
�����A���̊Ԃ̐��{�Ή��͋^����肾�B�Z����\���ɑO��̐錾�������������A�����҂��\���Ɍ��炳�Ȃ��܂܂ł̔��f�������B�{���͐錾���p�����\���Ɋ�����}�����ޕK�v���������͂����B
���������Ɏl�x�ڂ̐錾���߂����߂��ۂ������A���{�͂܂h�~���d�_�[�u�̉����ŏ��낤�ƍl���Ă����B
���~�̎������߂�������̐錾�g��͒x�����Ȃ����B������ɉ���Ă���B�K�v�Ȉ�Ò�����ɂȂ��Ă��钆�A���{�͋}����A���@�������������Čy�ǎ҂�͎���×{�������Ƃ����B
����܂ł͌y�ǂ△�Ǐ�̐l�͏h���×{����{�������B���Ǐ������邩������Ȃ��̂����̊����ǂ̕|�����B�{���́A��Ï]���҂��풓����h���×{�̊g�[�����ׂ������A���̓w�͂�ӂ�A����×{��ɓ]����̂͘b���t���B
�܂��Ď���×{�҂��x����ɂ͊J�ƈ��K��Ō�Ȃǂ̐l�ނ��s�������A���̘A�g�Â�����x��Ă���B�x�ꂽ�c�P�����҂ɉ��������Ă͂��܂�Ȃ��B���{�Ǝ����̂̐ӔC�͖Ƃ�܂��B
�t�́u��l�g�v�ł͊��Ŋ����҂��}�������@�ł����Ɏ���ŖS���Ȃ�l�������B��Â̎���\�͂��銴���g����o�������̂ɁA���P�����Ă��Ȃ��B
�����Ǒ�ł́A�ň��̎��Ԃ�z�肵�����������ׂ������A���`�̎͊y�ϓI�Ȍ����Ɏ������Ă���B�����͂������������g�傳���Ă���f���^���ւ̌x�����Â������ƌ��킴��Ȃ��B
�����̗}�����݂ɂ͊����҂����炷�d�v�����A����̐錾�g��ł��V���ȑ�͖R�����B
�s�s�����Ȃǂ̋����͂ɗ���Ȃ����{�̑�͍����̗����Ƌ��͂��v���B�������[�_�[�����t��s���������邱�Ƃ���ɂȂ���Ɗ̂ɖ�����ׂ����B
���R���i���ȉ�u���N�`���ڎ��̎��v���낭�Ɍ����������Ȃ����e���@8/18
�V�^�R���i���N�`���̐ڎ킪�i�ނ����ۂ��A���{�╪�ȉ�͑��ς�炸���l�A�l���}���Ȃǂ̋����^�̋K����i������肾�B���_�Ȉ�̘a�c�G������́u�ނ�͕a���N���ւ̑��s�������̊ɘa�Ȃǂɑ��錚�ݓI�Ȓ��قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ��B�v900�l���́g���N�`���ڎ��̎��h���낭�Ɍ����Ă��Ȃ��v�Ƃ����\�\�B
���R���i�z���҂ɑ��鎀�Ґ���0.1�`0.2���u�G�ߐ��C���t���Ɠ����x�v
�R���i�̊������̑������Ƃǂ܂�Ƃ����m�炸�A�ً}���Ԑ錾�Ώےn��̊g��������Ă���B�܂��e�n�ŕa���m�ۂ̍�������A����ҋ@�҂����������Ă���B���N�`���̐ڎ�͂����ނˏ����ɐi��ł���悤�����A����ȏ�Ƀf���^���̊����͂��������߁A���̂悤�ȏɂȂ��Ă���Ɛ�������Ă���B
�m���Ɋ����Ґ��͖c��Ȑ��ł���A�d�ǎҐ����ߋ��ō����L�^�����B�����ۂ����Ґ��̂ق��������ǂ��悤�ɑ����Ă��邪�A�܂�5���̃s�[�N����10����1���x���B�z���҂ɑ��鎀�Ґ���0.1������0.2���Ő��ڂ��Ă��āA�G�ߐ��C���t���G���U�ƕς��Ȃ��Ȃ����B
�x�b�h���ɂ������R�̂ЂƂ́A�����ǖ@��ł̃R���i�̈������B�����SARS(�d�Nj}���ċz��nj�Q)���́u2�ށv�����Ƃ���Ă��邪�A���܂��܂ȋK�����e���݂����A�v�������ɂ߂č����G�{���o���M���́u1�ށv�����̈����Ƃ����Ă悢�B�ő勉�̌x�����B
�d�lj����E�v��������������҂ւ̃��N�`���ڎ킪�����ނˏI���A�v�������G�ߐ��C���t���G���U���ɂȂ����B�܂����ꑤ�̈�Ï]���҂��قƂ�ǃ��N�`���ڎ킪�I����Ă���̂Ŋ������Ă��d�lj�����댯���ȑO�Ɣ�ׂĂ͂邩�ɒႭ�Ȃ��Ă���͎̂������낤�B�������������␔�����A���{������������x��ÂɌ��߂�ׂ��ł͂Ȃ����B
�������������ǖ@��̕��ނ́A��Ï]���҂���@���҂ւ̊����Ƃ���ɂ�鎀�S�Ȃǂɑ��đΉ�������̂Ƃ����B�G�ߐ��C���t���G���U�ɂ��Ă��u5�ށv�����ł��N��3000�`6000�l���A���ꂪ���ڎ����ŖS���Ȃ��Ă���A�R���i���l�ɐl�H�ċz����g�����Ƃ�����B
�܂������I�Ɏ��Ö�̂Ȃ�MRSA(���`�V�����ϐ����F�u�h�E����)�Ȃǂ̑ϐ��ۂɂ��x���́u5�ށv�����ɂ���Ȃ��Ă��Ȃ��B��������������ӂ݂�A�R���i���G�ߐ��C���t���G���U���́u5�ށv�����Ɉ���������A���Ȃ��Ƃ��a���s�����̑��̖��͉�������\���������A�Ǝ��͍l���Ă���B
�Ȃ���������̂��B����́A�ی����̕��S���啝�Ɍ���A���҂���ʂ̊J�ƈ�ň������A�܂��ʏ�̕a���ւ̓��@���ł���悤�ɂȂ邩�炾�B�C���t���G���U�Ȃǂł�(�`���ł͂Ȃ���)�A�Ȃ�ׂ��ʂ̕a�C�œ��@���Ă���l�Ɠ����ɂ��Ȃ��Ȃǂ̑Ή������Ă����̂ŁA����Ɠ��l�ɂ�������B�܂��A�����t���A�ɓ��@���Ă��銳�҂̃��N�`���ڎ킪�ς�ł���Α傫�Ȗ��������Ȃ��B
���u���N�`���ڎ��̎��S�v��������ƌ����������Ă��Ȃ�
���������Ŗ��ɂ������̂́A���Ɖ�c�����N�`���̐ڎ��i�߂Ȃ���A���ς�炸���l�A�l���}���Ȃǂ̋����^�̋K�������i���A�a���N���ւ̑��s�������̊ɘa�Ȃǂɑ��錚�ݓI�Ȓ��قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ����Ƃ��B
�C�O�ł́A���̖��ɑ��邳�܂��܂Ȍ������s���A�s�������̊ɘa���s���Ă���B�|���g�K���ł́A�{���ɃR���i�E�C���X���|���a�C�������̂��Ƃ������̂��߁A�R���i�Ŏ��Ƃ��ꂽ�l�̐^�̎��������̌������s���Ă���B�C�X���G���̂悤��3��ڂ̃��N�`���ڎ�ɓ��ݐ�����������B�����āA�C�M���X��V���K�|�[���̂悤�ɂقƂ�ǂ̋K�����ɘa������������B
���{�́u���Ɓv���A���Ă�芴���҂����҂��͂邩�ɏ��Ȃ��̂Ɍ������K���̊������s�������A�u1�ށv���������Ă���̂́A���ꂾ���l��������ƍl���Ă��邩�炾�Ƃ���Ă������A����ɂ��Ă͂��e���ȓ_������B
���́A���N�`���ڎ��̎��S�ɑ��āA������ƌ����������s���Ă���悤�Ɏv���Ȃ��̂��B���N�`���ڎ�Ńt�@�C�U�[��4���A���f���i�ł�8�����̐l���M�����Ă���B���ꂾ���łȂ�7��30�����݁A���N�`���ڎ��̎��S��900�l����(7��26������30����5���Ԃ�����84�l���S���Ȃ��Ă���B����͓��������̃R���i���Ґ���葽��)���A���Ƃ��ă��N�`���ڎ�Ƃ̈��ʊW���ے�ł��Ȃ��Ƃ����]�������Ă��炸(�C�O�Ŗ��ɂȂ��Ă��錌����������݂̏o�����̃P�[�X�ł��炻�������]���ɂȂ��Ă��Ȃ�)�A3��ň��ʊW���ے肳��Ă��邪�A����ȊO�̂��ׂẴP�[�X���u���s�����ɂ�胏�N�`���Ǝ��S�Ƃ̈��ʊW���]���ł��Ȃ����́v�Ƃ���Ă���B
���N�`�����ȉ������������J����邽�тɂ��̐��������Ă���B�u���s���v�Ȃ�����Ə����W�߂�ׂ��Ȃ̂ɁA����������`�Ղ��Ȃ��܂܂Ɂu���ʊW���]���ł��Ȃ��v���S�Ⴊ�ς݂������Ă���B
�{���ɐl�̖�����Ȃ�A���R�g���N�`�����h�ɑ��Ă��^���Ɍ������������̋��������ׂ������A�낭�Ɍ����������Ɂu���ʊW���]���ł��Ȃ��v�ŕ��u����Ă���̂͊ʼn߂ł��Ȃ��B20��̏ꍇ�A2��ڎ�������l�͌���܂�1���O�ゾ���A���ł�4�l���S���Ȃ��Ă���B�ڎ�����ގႢ���オ�����̂������͂Ȃ��̂��B
����̃��N�`���ɂ��āA���͂��Ƃ��Ɖ��Ă̐l�Ƒ̏d���̊i���Ⴄ�̂ɓ����ʂł����̂��A�Ƃ����^�������Ă����B�����ӌ��̈�t�����Ȃ��Ȃ����A����ɂ��Č��������`�Ղ��Ȃ��B
���u���ȉ�̐��Ƃ͓����Â��v���g�Ή�͓K�C�ƌ�����̂��낤��
���Ƃ����͂��������������Ă���̂��낤���B
���͓��{�̐���u���[���̑I�ѕ��ɑ傫�Ȗ�肪����ƌ��Ă���B�����f������̂́A��L�̂悤�ȁg���������h�����Ή��̒x�����������R�ł͂Ȃ��B
�����Ɍ����A����u���[���ł�����Ƃ����́A�����Â��̂��B
�ނ炪���݂̃|�W�V�����ɏA�����̂́A����Ȃ�̎��͂��Ă���ƔF�߂�ꂽ���炾�낤���A����͌����_�ł̌����\�͂���ʂł͂Ȃ��A�u�̂̎��сv�₻�ꂪ���f���ꂽ�������傫�ȉe����^�����Ǝv����B�����A�ߋ��Ɏ��т�����l���A���݂����т⌋�ʂ��o���Ă��邩�ǂ����͂킩��Ȃ��B���ƂƂ����ǂ��A����x��̑��݂ƂȂ邱�Ƃ�����B
���ہA�C�O�ł͓�����O�ɍs���Ă����r�����̂悤�Ȃ��̂����{�ł͂قƂ��(���Ȃ��Ƃ��ނ�̎哱�ł�)�s���Ȃ��ȂǁA�u���[���̔��z�͑����ČÏL�����̂ɉf��B
�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή�́A20���I���ɐ������m�n��ł̃|���I�̍����B������ȂljX�������т������Ă���B����ɂ����WHO�̐������m�n��̎����ǒ��ȂǂɑI��Ă��邪�A�����20�N�ȏ�̑O��1998�N�̘b���B���̌���A�_�����������Ă݂Ă������̂悤�Ȃ��͕̂ʂƂ��Č����_���̔��\��20���I�ɂȂ��Ă���͌������Ȃ��B
�R���i�̂悤�ɐV�����a���̂ɑΉ�����̂ɁA���������l�ނ��K�Ȃ̂��ǂ����B�����A������l�ނ���̒n�ʂɔz�u����Ă���̂ł���A���̑��݂𗊂�Ƃ�����{�́A���ʓI�ɑ����̐i�m�����������҂̃T���^�������邵���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�����ނ���20�N�ȏソ�����I��̕]�_�Ƃ����ȉ�̃g�b�v
����������������������Ȃ�悤�Ȑ��{�⍑�̑Ή��͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B
�A�����J��C�M���X��1980�N��Ɏ�����A��Ƃ苳��I�ȋ������߁A���{�^�̏�����������������ꂽ������v���s�����̂ɁA���{�ł͋t��1998�N�ɂ�Ƃ苳��Ƃ�����w�K�w���v�̂𐧒肵�A2002�N����f�s���ꂽ�B
�Ȃ��A����ȓڒ����Ȏ��Ԃ��N����̂��B
�����炭�R�c��̈ψ��ł��鋳��w���̋����������Ⴂ���ɗ��w���āA���̍��̉��Ă̋���𗝑z�����A�����ɂȂ��Ă���낭�ɍŐV�̏�����Ă��Ȃ�����C�O�̋�����v�̗���ɋC�Â��Ȃ������̂��낤�B
�����ċ��獑����c�����Ƃ��Ă��̐����i�߂��A�m�[�x����҂̍]��扗�ގ��ɂ��Ă��A������������ɂ��Ă͌o�����Ȃ��A�ނ��w���߂Ă����}�g��w�A�ʼnY�H�Ƒ�w�A�����Č��ݏ������鉡�l��ȑ�w�̋��炪���i������Ă���Ƃ����b�͕����Ȃ��B
�m�[�x���܊w�҂Ƃ����̂́A���̕���ł����ꂽ�����������l�ɗ^��������̂�(�������ʏ��20�N�ȏ�O�̌�����)�A�ق��̕���ŗD��Ă���Ƃ����ۏ͂Ȃ��͂����B
����ɑ��āA���E��̋`������ƌ�����t�B�������h�ł́A3�N�ȏ�̋����o�����Ȃ��ƍ��Ƌ���ψ���̃����o�[�ɂȂ�Ȃ��B
���������A�ߋ��̎��т͂��������ƂĂ������̌����҂ƌ����Ȃ��悤�Ȑl�Ⓦ��̂悤�Ȉꗬ�Ƃ�����w�̋���(���ꂾ���āA�����ɂȂ��Ă���͎G���ɒǂ��ĂقƂ�ǎ����ł͌��������Ȃ��l������)�𐭍�u���[���ɂ���̂���߂āA�����̌����҂�Տ���A���邢�̓r�W�l�X�p�[�\�����d�p���Ȃ��ƁA�C�O�Ɣ�ׂĂ��낢��ȓ_�ł܂��܂��x����Ƃ邾�낤�B
�C�O���o���o���̌���I��̃`�[���Ȃ̂ɁA������͈��ނ���20�N�ȏソ�����I��̕]�_�Ƃ̃`�[���Ő���Ă���悤�Ȃ��̂��B
�����������ۂ͎��̌���Ƃ���A��w�̐��E�Ō������B��w�̋������l�����������Ă���̂ŁA�V�������_���X�^���_�[�h�ɂȂ邽�߂ɂ́A���������l���������ނ���̂�҂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B��t�ŋߓ����������̏����ł���ߓ����搶�����[�����Ö@�ɂ��Ă̊C�O�̘_�����Љ�Ă���A���ꂪ�����ŕW�����ÂɂȂ�܂ł�15�N���������Ă���B
���[��S�����Ȃ��Ƃ��Ĕ�����Ɗ��҂ɐ������Ă������Ђ̊O�Ȉソ���������c��ׂ��ꂽ�Ɠ{��A�ނ炪���ނ���܂ŕ����������u�x�����������炾�B
���͌��݁A���̋ߓ��搶�ƑΒk�`���̏��Ђ�����Ă���B�����҂����猾���킯�ł͂Ȃ����A�ߓ��搶�̃R���i�̕a�Ԃ�N�`���ɑ���Ǐ��ʂɂ͖{���ɐ�������B
���́u����̊w�ҁv����ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�厖�Ȃ̂́A�������ǂ������B����ł������̊w�҂͐��E���ɂ���B
�C�O�̎��̍����G��(��w�����Ȃǂ̘_���ň��p�������G��)�Ɍf�ڂ���鍑�ʂ̃����L���O�ł͒������g�b�v���B���{�͍ŋ߁A�C���h�ɂ�������10�ʂɂȂ����B�l�������������Ȃ��؍��ɂ���������Ă���B
���{�ɂ����āA�u�̖̂��O�ŏo�Ă��܂��v�̂悤�Ȋw�҂𗊂�ɂ��Ă��傫�Ȗ��ɂȂ�Ȃ��悤�Ȏ���͂Ƃ����ɏI����Ă���B�����́A�����Ƃ⊯��������Ȃ�ɔ\�͂������A�����ɖ��Ԃ̌�����J���\�͂����E���w�̃��x�����������A���͂����]�ނׂ����Ȃ��B
�{�A�ڂł��q�ב����Ă����悤�ɁA�u�����l�ł��˔@�o�J�ɂȂ�v�Ƃ������Ƃ͒������Ȃ��B���̎���͕��������Ă��Ȃ��ƌ����l���ȒP�Ƀo�J�ƌ����郌�x���ɓ]�������˂Ȃ����ゾ�B
�|�X�g���N�`���̓��{�̃R���i����܂߁A���{�͌ÏL�����_�ɂƂ���邱�ƂȂ��A�V�������l�Ȉӌ���ϋɓI�Ɏ��������V�X�e�����̗p���ׂ����B
���V�K������9���ȏオ�f���^���Ɛ���u���S�ґ������O�v�@8/18
�����̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���18���A�ߌ�8�����_��2��3��l���A�ߋ��ő����X�V�����B�����̃s�[�N���݂��Ȃ��܂d�NJ��҂��}�����A�e�n�ň�Ñ̐����N��(�Ђ��ς�)���Ă���B�R���i��������J���Ȃɏ���������Ƒg�D��18���̉�ŁA�u�����g��̎��~�߂�������Ȃ��v�Ƃ̌��O���������B
����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���40�s���{���ōł��[���ȁu�X�e�[�W4(��������)�v�ɑ������A�O�T��31���炳��ɑ������B17���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����҂͑O�T�ɔ�ׂđS����1�E31�{�ɑ������B�s���{���ʂ�1�{����������͕̂��䌧(0�E84�{)�ƒ��挧(0�E76�{)�����B�����s��1�E14�{�Ő��Ƒg�D�����̘e�c�����E���������nj��������͋L�҉�Łu�����͏����x���I�ȏɂȂ��Ă���v�Əq�ׂ��B
�S���̏d�NJ��҂�17�����_��1716�l�B��3�g�ōő�������1��26����1043�l�A���t�̑�4�g�ōő���5��25����1413�l��傫���������B���ɓ����s�������A�ߋ��̊g����ōő�������1��20����160�l�ɑ��āA8��17����276�l�B
�a���g�p�������܂��Ă���B���Ȃ��Ƃ�25�s�{����5�������B���ɍ����̂͐_�ސ쌧��82�E7%�A���ꌧ83�E3%�A���ꌧ86�E2%�ȂǁB�����s��60�E6%���������A�d�Ǖa���g�p����84�E9%�ɒB�����B
��������8�����{���_�ŁA�S���̐V�K�����҂̂���9���ȏオ�����͂̋����f���^���ɒu����������Ɛ��肵���B����A8��17����1��������̎��S�Ґ��͌��J�Ȃ̎����ɂ���36�l�B��3�g�̃s�[�N��100�l���A��4�g�̃s�[�N��200�l���������B�d�lj���h�����N�`���̌��ʂ��o�Ă���悤�����A��������8��23���܂ł�1��������̎��S�҂͍ő��43�l�ɑ�����Ɛ��肵���B�e�c�����͉�Łu���コ��ɁA���S�Ґ����������邱�Ƃ����O���Ă���v�Əq�ׂ��B
���S�������A�ő�2��3918�l�@����5386�l�A��㏉��2000�l���@8/18
�����ł�18���A�V����2��3918�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�B
1��������̐V�K�����҂�2��3000�l�����̂͏��߂ĂŁA����܂ł̍ő�������13��(2��361�l)��啝�ɏ������B�d�ǎ҂��O����70�l����1716�l�ŁA6���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B���҂�30�l�m�F���ꂽ�B
�����͂������C���h�R���̃f���^���̗��s�őS���I�Ȋ����g�傪�����A�V�K�����҂͓��k�����B�܂ł�25�{���ʼnߋ��ő��ƂȂ�A2���ōő��ƕ��B���{(2296�l)�ł͏��߂�2000�l��˔j���A���m(1227�l)�A����(1088�l)�����͏��߂�1000�l�����B
�����s�ł́A�ߋ�2�Ԗڂɑ���5386�l�̊����������B1�T�ԑO���1186�l�����A���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ����B�V�K�����҂̒���1�T�ԕ��ς�4696�D6�l�ŁA�O�T��17�D9�����B�s��̏d�ǎ҂͑O������1�l������275�l�������B
�s�̐V�K�����҂�N��ʂɌ���ƁA20�オ1661�l�ƍő��ŁA30��1137�l�A40��892�l�A50��610�l�Ƒ������B65�Έȏ��210�l�������B�@
�������}�g��g�e�n�ōЊQ���x���̔F���K�v�h ���J�Ȑ��Ɖ �@8/18
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����S���ŘA���A�ߋ��ő����X�V����ȂNj}���Ȋ����g�傪�������A��ɂ��ď�����������J���Ȃ̐��Ɖ���J����܂����B�d�ǎҐ����ߋ��ő�K�͂ɂȂ��ĖS���Ȃ�l�̐������㑝�����邱�Ƃ����O����邽�߁u�S���e�n�ōЊQ���x���̏ɂ���Ƃ̔F���ł̑Ή����K�v���v�Ƃ��āA������Ƒ�����邽�߂ɂ��O�o�⌧�����z�����ړ����T���A�ł��邾������ʼn߂����悤�Ăт����܂����B
18���J���ꂽ���Ɖ�ł́A�����ɂ��āu�S���I�ɂقڂ��ׂĂ̒n��ŐV�K�����Ґ����}���ɑ������Ă���A����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��ƂȂ��Ă���B���~�̉e���ō��コ��ɑ������邱�Ƃ��z�肳���v�ƕ��͂��܂����B
���̂����ŏd�ǎ҂̐����ߋ��ő�K�͂ɂȂ荂��̊����Ґ����������A�S���Ȃ�l�̑����X���������n�߁A���コ��ɑ����邱�Ƃ����O�����Ƃ��āu�S���e�n�ōЊQ���x���̏ɂ���Ƃ̔F���ł̑Ή����K�v���v�Ƃ����F���������Ă��܂��B
����ɁA�����ǂ�d�ǂ̊��҂̓��@����������ɂȂ�A��ʂ̈�Â𐧌����A�~�}����������ȃP�[�X���o�Ă��Ă���Ƃ��āu�~���閽���~���Ȃ��Ȃ�悤�Ȋ�@�I�ȏ����뜜�����v�Ƃ����\���ŁA�ɂ߂ċ�����@���������܂����B
�n��ʂɌ���ƁA�����s�ł͉ߋ��ő�K�͂̊����g��ŁA���@�Ґ���20�ォ��50��𒆐S�ɁA�l�H�ċz��Ȃǂ��g�p���Ă���d�ǎҐ���40�ォ��60��𒆐S�Ƃ��đ������p�����ĉߋ��ő��̐������X�V�������A�V���ȓ��@�̎����~�}����������ȃP�[�X��A��ʈ�Â𐧌����鎖�Ԃ��N���Ă��܂��B
�܂��A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�ł��a���̎g�p�����}�����Ă��āA�����ł͖�Ԃ̐l�o�͒����Ɍ����Ă�����̂́A�O��ً̋}���Ԑ錾���̐����ɂ͓͂��Ă��Ȃ��Ǝw�E���Ă��܂��B
���ꌧ�͉ߋ��ɗ�̂Ȃ������̊����ƂȂ��Ă��āA�a���g�p����8������ɂ�������炸��Ԃ̐l�o���Ăё����X���ɓ]���A�����g�傪�����\��������Ƃ��Ă��܂��B
���Ɖ�́A��s���≫�ꌧ�ł�PCR�����̗z������20���ȏ�Ȃǂƍ����Ȃ��Ă��āA�����ł̊����Ґ��̔c�����s�\���ƍl�����A���ۂ̊����Ґ����ߏ��ɕ]������Ă���Ƃ����w�E������Ƃ��Ă��܂��B
���̂����Ő��Ɖ�́A�K�v�ȑ�ɂ��āA�����͂������f���^���́u����܂łƂ͈Ⴄ���x���̃E�C���X�ł���v�Ƃ�����@�����s���Ǝs�������L���A������Ƒ�����邽�߂ɁA���N�`����ڎ킵���l���܂߂ĊO�o���ȉ��ɂ��āA�ӂ�����Ȃ��l�Ɖ�@����ł��邾�����炵�A�����z�����ړ����T���邱�ƁA�E��ł͉�c�������I�����C���ōs���A�e�����[�N�𐄐i���A�Ǐ���l�̏o�Ў��l��O�ꂷ��悤���߂܂����B
�܂��A�s���{������̂ƂȂ��Ēn��̈�Î������ő�����p���A�S���I�Ɍ��������������ʂ͑����Ƃ����O��ŁA�Վ��̈�Î{�݂Ȃǂ̐����Ȃǂ̑��i�߂�K�v������Ƃ��Ă��܂��B
��̂��Ɖ�����e�c���������͌��݂̊����Ƒ�ɂ��āu��s���≫��ł͊������w�x���x�ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����Ă��邪�A�ق��̒n��ł͋}���Ȋg�傪�����Ă��āA�����ł����Ȃ葽�������Ґ�������Ă���̂ō���������������Ƃ��������݂��b������ꂽ�B����܂ł̊������O�ꂷ��̂ɉ����ē��ʂ͐ڐG�����炵�Ă��炤�����Ȃ��B���{�̕��ȉ����������悤�ɊO�o�̋@����ɂ��Ă��炤���Ƃ����S�ɂȂ�B���݁A��Â̏́w�ЊQ���x���x�Ƃ�����Ɍ����Ă��邪�A��ʂ̈�Â����������悤�ȏ��Ƃ������Ƃ�F�����čs�����Ăق����v�Ƙb���Ă��܂����B���̂����ŁA���b�N�_�E���̂悤�ȋ���������̎d�g�݂��K�v���Ƃ��������o�Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�u���H�X�Ȃǂɂ͋����������Ƃ������ŁA�l�ɑ��Ă͊O�o�����Ȃǂ̋�����͂ł����A���l�����肢����`�Ői�߂Ă����B���݂̔����I�Ȋ����g��ɊԂɍ����悤�ɐV���Ȏd�g�݂̋c�_������͓̂�����ߍ��̖@�I�Șg�g�݂̒��łȂ�Ƃ����������P�����邱�ƂɂȂ�B���傤�̉�ŋc�_���������킯�ł͂Ȃ����A����̊����ǂւ̑���l����ƌl�̍s����������x�A��������悤�Ȗ@�I�Șg�g�݂��K�v�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���v�Ƙb���Ă��܂����B
���Ɖ�Ŏ����ꂽ�����ɂ��܂��ƁA�V�K�����Ґ���17���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T�Ɣ�ׂđS���ł�1.31�{�Ɗ����̊g�傪�����Ă��܂��B���݂̊�����l��10���l������̒���1�T�Ԃ̊����Ґ��Ō���ƁA���ꌧ��311.56�l�ƁA���߂�300�l����ߋ��ɂȂ��K�͂̊����g��ɂȂ��Ă���ق��A�����s��227.64�l�A�_�ސ쌧��159.68�l�A��ʌ���149.10�l�A��t����138.06�l�A���{��126.20�l�A��������111.62�l�A���s�{��104.37�l��100�l���Ă��āA�S���ł�101.26�l�Ə��߂�100�l���܂����B�������ł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ���25�l���Ă���̂́A40�̓s���{���ƂȂ��Ă��܂��B
�����͂̋����ψكE�C���X�u�f���^���v�́A��s�������łȂ����∤�m�A�����A����ȂǁA�e�n�Ŋ����S�̂�90���ȏ���߁A�قڒu����������Ɛ��肳��Ă��܂��B���������nj����������Ԃ̌������7�Ђ́u�ψي��X�N���[�j���O�����v�̃f�[�^�����Ƀf���^���ł݂���uL452R�v�̕ψق��܂܂ꂽ�E�C���X���ǂꂭ�炢�̊������߂Ă��邩���肵�����ʂ��A���Ɖ�Ŏ����܂����B����ɂ��܂��ƁA�����s�ł̓f���^���Ȃǂ����ł�98���A�_�ސ쌧�A��ʌ��A��t�����܂߂���s����1�s3���ł�98���Ƃقڂ��ׂĂ��u��������Ă��܂��B�܂��A���{�A���s�{�A���Ɍ��̊���2�{1���ł��A�挎��{�܂ł͏��Ȃ���Ԃł������A�}���ɍL�����āA���ł�92���Ƃقڒu����������Ƃ��Ă��܂��B����ɁA���ꌧ�ł��ł�99���A��������97���A���m����94���Ƃقڒu����������ق��A�k�C���ł�85���Ɛ��肳��Ă��āA�f���^���̊����̊g��ƂƂ��Ɋ����҂̋}���ƂƂ��ɓ��@���҂��}�����A�����s�Ȃǂň�Ñ̐�����@�I�ȏɂȂ��Ă��邱�ƂɂȂ����Ă���Ǝw�E����Ă��܂��B
��40�s���{���Ŋ��������@���Ƒg�D�u�o���������Ƃ̂Ȃ��g��v�@8/18
�����J���ȂɐV�^�R���i�E�C���X�������������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h(AB)�v(�������e�c�����E���������nj�������)��18���A�J���ꂽ�B�����ɂ��āu�����g��̎��~�߂������炸�A�S���I�ɂقڑS�Ă̒n��ŐV�K�����Ґ����}���ɑ������Ă���A����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g��ƂȂ��Ă���v�ƕ��͂��A�������������\�h��̓O������߂Ă���B
AB�̎����ɂ��ƁA����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ����u�X�e�[�W4(��������)�v���Ă���̂́A����(312�l)�Ⓦ��(228�l)�Ȃ�40�s���{���B�C���h�Ŋm�F���ꂽ�����͂������ψي��u�f���^���v�͑S����9���ȏ�Œu����������Ɛ��肳�ꂽ�Ƃ̕��������B
���\���ꂽ���Y���E���s�勳���̎��Z�ł́A�����s���ł͏d�NJ��Ҍ����̕a�����߂������ɂȂ�Ƃ���A������1�l���牽�l�Ɋ��������邩�������u�����Đ��Y���v�����݂��3�����炵���Ƃ��Ă�8�����{�ɏd�ǎҌ����Ɋm�ۂ����a���̎g�p����100���ɒB���A10����{�܂�100���ȏ�̏�Ԃ������Ƃ����B
�܂��A8��10�`12���̐V�K������5��7293�l�̂����A���N�`����1��ڎ킵���l��2956�l(��5��)�A2��ڎ킵���l��1768�l(��3��)���������Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B�R���i���ÂɌg���A���N�`���ڎ���I���Ă����Ï]���҂ɂ��āA�Z���ڐG�҂ƔF�肳��Ă���ւ�����ꍇ�Ȃǂ͋Ɩ��̏]����F�߂���j�����ꂽ�B
��25�{���Łu�ߋ��ő��X�V�v�@�R���i�����ҁ@8/18
�V�^�R���i�E�C���X������18�����e�n�Ŋg�債���B���2296�l�A���m1227�l�A����1088�l�Ȃǁu���v��˔j���������̂����o�B25�{�������\�����u�ߋ��ő��X�V�v(���̂ق�2���͍ő��ɕ���)��SNS�̃g�����h���[�h�ƂȂ�A�u����Ă���j���[�X���S���ߋ��ő��X�V�v�u�S���I�ɉߋ��ő��X�V���܂����ȁB���킽�ȁv�Ƃ��������オ�����B
�S���̊����Ґ����ߋ��ő��ƂȂ�2��3000�l�����B�c�C�b�^�[�ł́u���m�������ߋ��ő��X�V���Ă邵�A�����ŋ߂����ƉJ�����A�n�k���N���Ă邵�A���{��Ύ���Ă邾��B�������P���������������v�u�n�������X�Ɖߋ��ő��X�V������ƁA����ς�ً}���Ԃ̒n�悩��l�̈ړ��������������Ă��Ƃ��v�u�ߗ����ߋ��ő��X�V���Ăă}�W�ł��O�ł�Ȃ��ȁv�u�܂���w�������D����v�Ȃǂ̃R�����g�����X�ƁB
�܂��u���j���őS���I�ɉߋ��ő��X�V�Ƃ��A�s�����Ȃ��H�@�����ǂ��Ȃ�̂��ˁv�ƁA���T�V�K�����҂��������\�����ؗj���̊����Ґ����뜜���鐺���オ�����B
�����ł��R���i�����}�g��@���@�ߋ��ő�2296�l�̊������m�F�@8/18
���{�ŁA18���A�ߋ��ő��ƂȂ�2296�l�̐V�^�R���i�E�C���X�̊������m�F�����ȂǁA���ŋ}�g�傪�i��Ă��܂��B���{�ł́A18���A�ߋ��ő��ƂȂ�2296�l�̊�����5�l�̎��S���m�F����܂����B1���̊����Ґ���2000�l����̂͏��߂Ăł��B�y�ǒ����Ǖa���̎g�p����69���ŁA����ŗ×{���Ă���l�̐���17�����_��1���l���Ă��܂��B
���Ɍ��ł��ߋ��ő��ƂȂ�1088�l�̊������m�F����Ă��āA��Ñ̐��̂Ђ������i�ނ��Ƃ���A���Ɍ��̍֓��m���͍������ɂ��A�����a�@�Łu�R�̃J�N�e���Ö@�v���n�߂�l���������܂����B
���̂ق��ߋE�Ɠ����ł́A���ꌧ��207�l�A�ޗnj���162�l�Ƃ��ꂼ��ߋ��ő��̊������������Ă��܂��B
�܂��A���s�{��421�l�̊�����1�l�̎��S���m�F���ꂽ�ق��A�a�̎R����64�l�A��������37�l�̊������������Ă��܂��B
�����������́u��s�����v�@���g���A���i���@�O�@���t�ρ@8/18
�O�@���t�ψ����18���̕�R���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̔����I�Ȋ����g��Ȃǂɂ��ċc�_�����B
���{���ȉ�̔��g�Ή�͋}���ȐV�K�����҂̑������u�ЊQ�v�ƕ\���B�u��s�����v�Ƃ̔F���������A����i�����B
��������}�̍����l���́A�u�������b�Z�[�W���K�v���v�Ƃ��đS���ւً̋}���Ԑ錾���߂����߂��B����ɑ��A���g���́u���̖��͑��ς�炸��s����肾�v�Ǝw�E�B�錾���߂������Ԃɋy�ԓ����s�ȂǂŁu�K���������ʂ��o�Ă��Ȃ��B��̂ǂ����邩�ɋc�_�̖{��������ׂ����v�ƌ�����B
���g���́A�����Ɋւ��u�����̋����̐����Ԃɍ����Ă��炸�A������ϋɓI�ɎȂ�����������v�Ƃ��āA�u���ۂɕ���Ă�����������Ґ��͂������������v�Ƃ̌������������B�@
���ً}���Ԋg��@���ܖ��������@8/18
���{�́A�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɁA���s�Ȃ�7�{����lj������B
�����Ȃǎ�s���𒆐S�Ƃ��������u��5�g�v�͑S���Ɋg�債�Ă���A���~�߂�������Ȃ��B
�����͂̋����f���^���ɂ�锚���I�Ȋ����g���}����ꂸ�A�錾�lj���]�V�Ȃ����ꂽ�`���B���Ƃ̉Ȋw�I�f�[�^�Ɋ�Â��x�����y�����ʂł���A���ʂ��̊Â����܂����I�悵���ƌ�����B
�Ώۂɒlj����ꂽ�̂́A���s�̂ق����A�ȖA�Q�n�A�É��A���ɁA�����ŁA�����������1�T�ԓ��ɉߋ��ő��̊����҂��o�Ă���B���ߒ��̓����A���Ȃǂƍ��킹��13�s�{���ƂȂ����B
�����ɂ܂h�~���d�_�[�u��10�����lj�����A����Ȃnjv16�����ɑ������B�lj��̐錾�Əd�_�[�u��20������ŁA�S�Ċ�����9��12���܂ʼn������ꂽ�B
�������}�g�傷��O�ɒlj��w��ł��Ȃ������̂��B�挎29���ɐV�K�����҂�1���l���A����13���ɂ�2���l��˔j�����B�d�ǎ҂�1600�l�ȏ�ƂȂ�A15�����_��5���A���ʼnߋ��ő����X�V���Ă���B��Ë@�ւ��N��(�Ђ��ς�)���錜�O�����܂��Ă���̂����B
�������A�錾��lj��������̂́A�͋�����͌�������Ȃ��B��ޒX�̋x�Ɨv���ȂǏ]���ʂ肪�����A�V���ɕS�ݓX�ȂǑ�^���Ǝ{�݂̓��ꐧ����v������ɂ��Ă����ʂ̂قǂ͕s�����B
���`�̎́u�ڐ�̂��Ƃ������Ɍ������đS�͂ł��̂����̐Ӗ����v�Ƌ������Ă݂����B�ڐ�Ƃ����Ȃ�A���N�`���ڎ퐄�i���J��Ԃ������łȂ��A������������Ì���̋����ŊJ���������}���s���ׂ����B
�a���g�p�������E�ɋ߂Â��A�_�f���^���K�v�Ȓ����ǂł��~�}�����悪�����炸�A����×{���������銴���҂������Ă���B�����Ɋւ�鎖�Ԃł���A����̐����A��Ò̐��̋������}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���s�{�͂��傤�A��t���z�u�������@�ҋ@�ꏊ���J�݂���B���������e�n�̎��g�݂𐭕{�͕��S���ʂŎx������K�v������B
�����ʐM�ɂ��ŐV�̐��_�������݂�ƁA���{�̕a���m�ۍ�Ɂu�s����������v�Ƃ̉���8���ɏ��B���̓��N�`���ڎ킪�i��ł���Ƃ������A�u�x���Ǝv���v����N�w�Ŗ�7���A�����N�w��8���߂��ɂȂ�B
���{�ւ̐M�����Ⴂ�悤�ł́A�錾�̌��͂͏��������̂ɂȂ�B�������ؖ]����R���i��Ƃ̃M���b�v�͂Ȃ����낤���B�@
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i 5534�l�����m�F 2���A����5000�l�� 8/19
�����s��19���A����܂ł�2�Ԗڂɑ���5534�l���s���ŐV���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B5000�l����̂�2���A���ŁA�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ4�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�����s��19���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł̒j�����킹��5534�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B����܂ł�2�Ԗڂɑ���2���A����5000�l���Ă��āA�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B�܂��A1�T�ԑO�̖ؗj�����545�l�����A�ؗj���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B19���܂ł�7���ԕ��ς�4774.4�l�ōő����X�V���܂����B�O�̏T��120.1���ł��B����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A29��7391�l�ƂȂ�܂����B
����A�s�̊�ŏW�v����19�����_�̏d�ǂ̊��҂�18�����1�l������274�l�ł����B�܂��A�s�͊������m�F���ꂽ70���80��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2358�l�ɂȂ�܂����B
�������s ��K�͐ڎ�p���N�`���������̂ɗZ�ʂց@8/19
�������}���Ɋg�傷�钆�A�����s�͐�T�A�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���ɂ���10����{�܂ł̋�s�����ւ̔z���������܂����B�������A�����̂���́A�u�\��̗ʂɑ��肸�A�v��ǂ���ɐڎ���I�����Ȃ��v�Ƃ����������A�s����K�͐ڎ�̂��߂Ɋm�ۂ��Ă������N�`���̈ꕔ����]���鎩���̂ɗZ�ʂ�����j�����߂����Ƃ�������܂����B
����12�Έȏ�̐l��8����2��̐ڎ���I����̂ɕK�v�ȃ��N�`����10����{�܂łɓs���{���ɔz��������j�ł��B�����s�ɂ́A���킹��2114����247��3000�̃t�@�C�U�[�̃��N�`�����͂��\��ŁA�s�͍���10���A��s�����̐l����ڎ헦�Ȃǂ܂��āA���ꂼ��ւ̊��蓖�Ă������܂����B����ɑ��A������␢�c�J��A�����A�V�h��A���n��A�]�ː��Ȃǂ���́A�u�\�肵�Ă����ʂɂ͑��肸�A�ڎ���v��ǂ���ɏI�����Ȃ��v�ȂǂƂ��������o�Ă��܂����B����ŁA�s����K�͐ڎ���p�Ɋm�ۂ��Ă���800����93��6000�ɂ��āA�z�����Ăق����Ƃ��������o�Ă��āA�s�͈ꕔ����]�����s�����ɗZ�ʂ�����j�����߂܂����B��s�����ɂ͓`���n�߂Ă��܂����A��]�ǂ���̗ʂ�Z�ʂł��Ȃ������̂�����Ƃ������Ƃł��B�����s�́u���łɐڎ�̑̐��𐮂��Ă����s��������̋����v�]�ƂƂ��ɁA�S�̍œK���l���ēs���S�̂Őڎ�𑣐i�����Ă������߂̑Ή����v�Ƃ��Ă��܂��B
����10���ɓ����s���������v��ɂ��܂��ƁA������ł́A����30������10��10���ɂ����āA���킹��78����9��1260�̃t�@�C�U�[�̃��N�`�������蓖�Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B���̌�A�s����A�����10����1��1700��Z�ʂ���ƘA�������Ƃ������Ƃł��B����ł��悪��]���Ă����ʂɂ͓͂��Ă��܂���B��ɂ��܂��ƁA�ڎ�ΏۂƂȂ�l�̂���2��̐ڎ���I�����̂́A����16���̎��_��3���ɂ����邨�悻15��5200�l�ŁA�Ώێ҂�7�����ڎ����]����ƌ�����ŗ������܂łɐڎ����������\��ł����B��ł́A1�T�Ԃ����肨�悻4����̐ڎ���ł���̐����Ƃ��Ă��܂������A�s����z������郏�N�`���͂��悻1��7000�ɂƂǂ܂�A�ڎ�\��̘g�����������������Ă���Ƃ������Ƃł��B���̌��ʁA�ڎ�̊����͔N���ɂ��ꍞ�ނ����ꂪ����Ƃ��Ă��܂��B��̌����c�C�b�^�[�ɂ́A�u���̂܂܃��N�`���łĂȂ��ƃR���i�ɂȂ��č��Ƌ�����̂����Ŏ��Ⴄ�낤�Ȃ��v�Ƃ��A�u���ɂȂ�����ڎ�ł���̂ł��傤���c�v�u�S�R�łĂȂ��B�R���ŃR���i�ɒ��ӂƂ������Ă��������v�ȂǂƂ��������e�����Ă��܂��B������̓c���Nj撷�́u�������̃��N�`�����s�����A�\���ɂ����Ƃ�����������斯������Ă���B����Ȏv���������Ȃ��悤���N�`���������������A�ڎ�ł���̐����Ƃ��Ă��������ɉ������Ƃ����C����������v�Ƙb���Ă��܂��B
�����s�͂��Ƃ�6�����烏�N�`���̑�K�͐ڎ���͂��߁A���݂�16�̉��ň��H�X�̊W�҂�w�Z�̋��E���A����ɕ����T�[�r�X�Ɋւ��l�Ȃǂ�ΏۂɎ��{���Ă��܂��B����17���܂ł�45����]��̐ڎ킪�s���A2��ڂ܂ŏI�����l��15��5470�l�ł��B����A��K�͐ڎ�p�Ɋm�ۂ������N�`������s�����ɗZ�ʂ��邱�ƂɂȂ������R�ɂ��āA�s�́u�ڎ�̑̐��������Ă����s��������̋����v�]������A�s���S�̂Őڎ�𑣐i�����Ă������߁v�Ɛ������Ă��܂��B�s�͓����A��K�͐ڎ�ł͍��̕��j�ɏ]���ă��f���i�̃��N�`�����g���\��ł����B�������A���f���i�̔z�����ǂ��������A������̓t�@�C�U�[����������Ă��܂��B����A���̃t�@�C�U�[���g���Ă����s��������͑���Ȃ��Ƃ���������������܂��B�s�����͓s�̑�K�͐ڎ핪�̃t�@�C�U�[�̃��N�`�����\�Ȃ�����Z�ʂ���悤�v�]���o�Ă��܂����B�s�̒S���҂́u�����̌v��ǂ���A�t�@�C�U�[�ł͂Ȃ����f���i�̃��N�`���œs�̑�K�͐ڎ킪�s���Ă���A��s�����̐ڎ�v��ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�s�Ƃ��Ă��t�@�C�U�[���g���Ă��邱�Ƃ͖{�ӂł͂Ȃ��A�ł�����f���i���������Ăق��������v�Ƙb���Ă��܂��B
���́u�s���{���P�ʂŌ���ƁA���f���i�̃��N�`�����܂߂�ΕK�v�ȗʂ͑����Ă���͂��ŁA����Ȃ��Ƃ������Ƃ͐M���������B�s���{�������܂��z������A�����̂ɏ\���ȃ��N�`�����͂��͂����v�Ƃ��Ă��܂��B
�����r�s�m�� �q�ǂ������̃p���ϐ�́g�\��ǂ���h ���� �@8/19
�����p�������s�b�N�̉��Ŏq�ǂ������ɋ��Z�����Ă��炤�s�̕��j�ɑ��A�s�̋���ψ�����V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g��𗝗R�ɔ��̈ӌ����o�����Ƃɂ��āA���r�m���́u�����S�E���S�Ȍ`�łł���悤�ɏ�����i�߂Ă����v�Əq�ׁA�\��ǂ�����{����l�����������܂����B
24���ɊJ�����铌���p�������s�b�N�͌������ϋq�ƂȂ�������A�s�͋���I�ȈӋ`���d�����Ċ�]����q�ǂ������ɂ͉��ŋ��Z�����Ă��炤���j�ł����A18����J���ꂽ�s�̗Վ��̋���ψ���ł́A�����̋}�g��Ȃǂ𗝗R�ɏo�Ȃ���4�l�̈ψ��S�����甽�̈ӌ����o�܂����B
����ɂ��āA���r�m����19���A�s���ŋL�Ғc�ɑ��u���̂��̗Վ��̋���ψ���ňӌ����f�������A�����ŔF�߂邤��ʂ�ł͂Ȃ��v�Əq�ׁA�q�ǂ������ɋ��Z�����Ă��炤���j�͋���ψ��ւ̕������Ɛ������܂����B
���̂����Łu����ψ��̈ӌ����Q�l�ɂ��Ȃ���A�q�ǂ��������p�������s�b�N�̑I��̎p�����邱�Ƃ������S�E���S�Ȍ`�łł���悤�ɏ�����i�߂Ă����v�Əq�ׁA�\��ǂ�����{����l�����������܂����B
���C�w���s�Ɠ����A�s�m�����s����������{�̒��~�E�������Ăт����@8/19
�����s�̏��r�m����2021�N8��19���̓s�c��ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�Ă��邱�Ƃ���A�s�ƌ����܂����C�w���s�̒��~���邢�͉��������߂ċ��߂��B
���r�m���́u�q�ǂ������̐S�g�̌��N�̂��߁A�w�Z����ɂ����čH�v���Ȃ���A�w�Z�s�����s���Ă������Ƃ��K�v�ƍl����v�Ɣ��������B
�s����ψ���́A���łɓs���w�Z�ɑ��ăK�C�h���C���ŏC�w���s�Ȃǂ̏h�����s���͒��~�܂��͉��������߂Ă���B�ً}���Ԑ錾�̂��ƕs�v�s�}�̊O�o��s�E�����܂����ړ��̎��l��i���Ă��邱�Ƃ���A�s�m�������߂ďC�w���s�̒��~�E�������Ăт��������̂��B
���s�̋~�}�v���҂�6�����������ꂸ�Ɂu����×{����ԕ|���Ǝv���܂��v�@8/19
19�������̂s�a�r�n���ԑg�u�S�S�X�}�v�ł́A�S���ʼnߋ��ő��̊����Ґ����L�^����ȂǁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�~�܂�Ȃ��������B
�R�����e�[�^�[�ŏo���̌��{�茧�m���Ń^�����g�̓������p�v���͓����s�̃R���i���҂�6�����~�}�v������������Ȃ������Ƃ����f�[�^�Ɂu�l�͎���×{����ԕ|���Ǝv���܂��B�Ƃ��炵�̕������A�{���ɕs�����Ǝv����ł��ˁv�Ƙb���o���ƁA�u���������A�J�ƈ�̕��������P�A������Č�����ł����ǁA�l���I�ȃ��\�[�X�ɂ����E������܂�����肪���Ȃ��炵����ł���B�z�e���Ƃ������ɂȂ��Ă���̂ŁA���n����悤�Ȏ{�݂��K�v�ł���҂���A�Ō�t����̊m�ۂ��K�v�ƂȂ��Ă��܂��v�Ƒ������B
���̏�Łu��������肢�x�[�X�ł��̂��A�@�������ċ����I�Ɉ�Ë@�ւ��Ƃ��x������Ă���Ō�t����₨��҂���ɋ����I�Ȗ@����������̂��͋c�_�̗]�n������܂��v�Ƙb�����B
���X���E�O���m���u���������g��h�~�̎R��v�@8/19
�S���łً̋}���Ԑ錾�̉����Ȃǂ܂��A�X�����ł͊�@���{����c���J����܂����B
�O���m��
�u���������g��h�~�̎R��Ƃ����ɂȂ��Ă܂���܂����v�u�ň��̎��Ԃ�������邽�߂ɉ��Ƃ��Ă����݂Ƃǂ܂�Ȃ�������Ȃ��Ɓv
�X�����ł�17���A�ߋ��ő��ƂȂ�91�l�̊������m�F����A����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ��́A���̎w�W�̃X�e�[�W4����ȂǁA�a���̂Ђ����A��Õ����O����Ă��܂��B
8���̌����̊����҂̂����A10�Ζ����A10�オ28���A20��A30�オ39���ƁA7���߂���30��ȉ��ƂȂ��Ă��܂��B����A60��ȏ�̊����҂�9���ɗ��܂��Ă��܂����A���N�`����2��ڎ킵���l�ł�30�l���������Ă��܂��B
��c�ł́A���N�`����ڎ킵�Ă���{�I�ȑ���p�����邱�ƁA�X���O���痈���l�Ƃ̐ڐG���n�߂Ƃ��銴�����X�N��������邱�ƂƂ��������ӂ��Ăъ|���܂����B
�܂��A�����g�傪�����ꍇ�A���̎{�݂̋x�ق�w�Z�ɂ����镔������C�x���g�̋֎~�A�Љ�o�ϊ����̗}���Ȃǂ��z�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��܂����B
���R�`���m���ƈ�Ð��Ƃ̈ӌ�������@8/19
�R�`�����̐V�^�R���i�����҂̑������A19���ߌ�5������g���m������Ð��ƂƂ̈ӌ���������J�����B
�I�����C���ŊJ���ꂽ��c�ɂ́A�R�`����t��⌧�������a�@�Ȃǂ������6�l���o�Ȃ��A����J�ňӌ�������s��ꂽ�B
�g���R�`���m���u�������鎩��×{�҂̑Ή���A����̊����g��h�~��Ȃǂɂ��āA��Ð��Ƃ݂̂Ȃ��܂��炲�ӌ��Ղ��āA������ӂ܂��č���̌��̑Ή����j�����肵�����v
��c�͌ߌ�6��20���ɏI�����A�R�`���̒S���҂ɂ��܂��ƁA�����h�~�̌���Ƒ�A�a���̌���Ƒ�ɂ��Ĉӌ����o���Ƃ����B
�ƒ��E��E�w�Z�ȂǂŊ����o�H���킩��Ȃ����Ⴊ�����Ă��邱�Ƃ���A�}�X�N�▧����̓O��Ȃǂɉ����A���O�Ƃ̉������H�������ȂǁA��̓I�Ȑ��l���o���Č��ʂ��o��܂ő�����K�v������Ƃ����ӌ����o���B
�܂��A�a���ɂ��Ă͏h���⎩��×{�����p���Ȃ����t�̔h�����������Ă����K�v������Ǝw�E�����B
�R�`����20���ߌ�A��@���{����c���J���A�Ǝ��ً̋}���Ԑ錾���܂߁A�V���Ȋ�����̕��j�������\��B
������×{���Ɏ��S�A50��̉�Ј����c��ʉ���2170�l�����@8/19
��ʌ��Ȃǂ�19���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă���2�l�̎��S�ƁA�V����2170�l�̊������m�F�����Ɣ��\�����B1��������̊����҂Ƃ��Ă͍ő����X�V���A���߂�2��l�����B�����҂̓���́A�����\��1540�l�A�������s358�l�A����s95�l�A��z�s82�l�A�z�J�s95�l�B
�������s�ʼnߋ��̗z����1�l�̎�艺��������A����܂łɊm�F���ꂽ�����҂�8��2996�l(�`���[�^�[�A���Ҋ܂�)�A���҂�866�l(19���ߌ�7������)�ƂȂ����B
18���ߌ�9�����_�̏d�ǎ҂�126�l�A�����҂̓��@��1220�l�A�z�e���×{644�l�A����×{1��5280�l�B�މ@�E�×{�I����5��8070�l�B
���ɂ��ƁA70�㏗��1�l�����S�����B���NJ��ŏڍׂ����������͖̂��A�w���`90��̒j��1139�l�B�����̑�w�œ������ɏZ��10�`20��̏��q�w��4�l�����������B��H�ł�10�`70��̒j��22�l�����������Ƃ݂��A����1�l�̓o�[�x�L���[���s���Ă����B
�������Ǒ�ۂ́u�����X�s�[�h�������A1���̊����Ґ���12����1500�l���Ă���킸��1�T�Ԃ�2��l�����v�Ƃ��A�u��Ñ̐��ɉe�����o�Ă���B����܂ňȏ�Ɏ��~�߂�������K�v������v�Ɗ�����̓O����Ăъ|�����B
�������s�ɂ��ƁA���������������̂�10�Ζ����`90��̒j��358�l�B17�����\��1�l����艺�����B�d��1�l�A������14�l�B�N��ʂł�20�オ�ő���109�l�A50��܂łŖ�95�����߂��B�ƒ��������43�l�A��������268�l�B20�`90���14�l�����N�`����2��ڎ킵�Ă����B
����s�ɂ��ƁA����×{��������50��̉�Ј��j����15���Ɏ��S�����B�V���Ɋ������m�F�����̂�10�Ζ����̖��A�w������80��܂ł̒j��95�l�B
��z�s�ɂ��ƁA10�Ζ����`80��̒j��82�l�̊������m�F�����B1��������̔��\�Ґ��Ƃ��Ă͉ߋ��ő����X�V�����B
�z�J�s�ɂ��ƁA���������������͖̂��A�w���`60��̒j��95�l�B�s�s�������x���ۂ�40��j���E�����V���Ɋ��������Ɣ��\�����B
���_�ސ� ���͌� �����w�Z�������܂ŗՎ��x�Z �����}�g��� �@8/19
�V�^�R���i�E�C���X�����̋}�g����āA���͌��s�͍���25������2�w�����n�܂�\�肾�������͌��s���̏����w�Z�ɂ��āA�������܂ŗՎ��x�Z�ɂ��邱�Ƃ����߂܂����B
���͌��s���ł͐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�����w�����A1�w����1��1�l�قǂł������A�ċx�݂ɓ�����6�{�ȏ�ɑ����܂����B
2�w���͍���25������n�܂�\��ł������A�s�͊����̋}�g����āA���͌��s���̏����w�Z�Ȃ�106�Z���������܂ŗՎ��x�Z�ɂ��邱�Ƃ����߂܂����B�����ȍ~�͕��U�o�Z�Ȃǂ������ꂽ�����ōĊJ����\��ł����A����̊����ɂ���Ă͋x�Z�������\��������Ƃ������Ƃł��B
�Վ��x�Z�̊��Ԓ��͊w�Z�ł̎��Ƃ͍s��Ȃ����̂́A��]����ƒ�̎q�ǂ��́A���Ƃ�����\�肾�������ԑтɊw�Z�ŗa���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���͌��s����ψ���́u�q�ǂ������̊w�т�ۏႷ�邱�Ƃ��Ӗ������A���̊������l���āA��ނ������x�Z�����f�����B�ł��邩���葁���A���܂łǂ���̊w�Z���������߂���悤�ɓw�߂Ă����v�Ƙb���Ă��܂����B
�����͌��s�@�����w�Z�̉ċx�݂�1�T�ԉ����@�V�^�R���i�����g�� �@8/19
���͌��s��19���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ŏs���̎�����k�̊����������Ă��邱�Ƃ���A�s�������w�Z�A�`������w�Z�v106�Z��2�w���̎n�Ƃ�1�T�Ԓx�点�A9��1���ɂ���Ɣ��\�����B
�s�ɂ��ƁA�s���̏����w����1�����ς̊����Ґ���1�w����0�E9�l�������̂ɑ��A�ċx�݊��Ԃ�7��21���`8��16����5�E6�l�ɋ}�������B�ŋ߂�10�l������������B
�x�点��1�T�ԕ��̊w�K�́A�J���L��������g�ݑւ��đΉ����邽�ߖ��Ȃ��Ƃ����B
��19���̐��@1�l���S631�l�����@�k���s��������ł��m�F�@8/19
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�����A���s��19���A1�l�̎��S�ƁA�V����10�Ζ����`90��̒j��631�l�̊������m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�S�����y�ǂ����Ǐ�Ƃ݂��A�������Ă���B�����o�H�s����515�l�������B�s���\�̎��S�҂͗v203�l�A�����҂�2��8366�l�ƂȂ����B
���S�����͓̂����s���ɏZ��70��j���ŁA���M�̏Ǐ������B11���Ɏs����Ë@�ւ���f���A�z�������������B�j���͏d�ǂŁA���@���Ď��Â𑱂������A18���ߑO9��50������Ɏ��S���m�F���ꂽ�B
�E���Ɨ��p�Ҍv5�l�̊������m�F����Ă���������̏��K�͑��@�\�^������{�݂ł́A�V����90�㏗�����p��1�l�̊������������A�����҂͌v6�l�ƂȂ����B�s�͐V���ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)�����������Ƃ݂Ă���B
�V���Ɋm�F���ꂽ�����҂̔N���20�オ180�l�A30�オ146�l�A40�オ96�l�A50�オ82�l�A10�オ60�l�A10�Ζ�����31�l�A60�オ13�l�A70�オ12�l�A80�オ10�l�A90�オ1�l�������B
���Z�n�ʂł͐���114�l�A���Ë�94�l�A������89�l�A�{�O��77�l�A�K��42�l�A������40�l�A������19�l�A���l�s114�l�A����s8�l�A���͌��s5�l�A���q�s4�l�A���P��s3�l�A���{��E�C�V���s���e2�l�A�t�R���E���c���E��a�s�A��t�E���m�����e1�l�A�����s����13�l�������B
�����o�H���������Ă���l�̂����A�ƒ��������92�l�A�z���҂Ƃ̐ڐG��24�l�������B
�ۈ�{�݂Ȃǂł̊������g�債���B���s��19���A��肨������ۈ牀(����)�A�V���{�ۈ牀(������)�A�~�A�w���T�ۈ牀�Ђт����Z�g(������)�A�����Â����͂ȕۈ牀(���Ë�)�A�A�X�N�{�O�������܂��ۈ牀(�{�O��)�A���L�n���Ђ��ܕۈ牀(��)�̊W�҂̗z�����������A�e�{�݂�����Վ��x������Ɣ��\�����B
�s���������s��k���s��(�{�O��)�ł́A�̔��Ɩ�����H��ƂȂǂ��s��30�`50��̒j���E��5�l�̊��������������B
�K������ł́A30��̏����E���A40��̒j���E���̊������m�F���ꂽ�B�K������ł�10�`13���ɐE��5�l�̊����������B30�㏗���E����5�l�Ɠ���̎������ŋΖ����Ă����B������ł́A�Ɩ��͒ʏ�ʂ�s���Ƃ��Ă���B
�����l�E�C�V���s�A�����E���k�̃p�������s�b�N�ϐ풆�~�@�����g��Ō���@8/19
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A���l�s�ƊC�V���s�́A������k�ɓ����p�������s�b�N�̊ϐ�@������u�w�Z�A�g�ϐ�v���O�����v�ւ̎Q�����~�����߂��B
�_�ސ쌧���̎����̂ł́A���s�����v���O�����ւ̎Q������]�B�����ɋ��Z��ꂪ�Ȃ����߁A���s���̎s���������Z�̎������k��ی�ҁA�t���Y���̋��@�Ȃnjv���l���V�������Z��(�����s�V�h��)�ŗ��㋣�Z���ϐ킷��\��Ƃ��Ă����B
�C�V���s��13���A���l�s��17���ɒ��~�����߂��B
���u�����ł�9����{�����v�@�É����A��Õ����@�@8/19
�É������ł̐V�^�R���i�E�C���X�̔����I�����g��́u��Õ���v���߂������ɂȂ蓾��Ƃ���܂ō��܂��Ă����B�V�K�����҂͘A���̉ߋ��ő��X�V��500�l��ƂȂ�A����3��l�߂��S�×{�҂�����ɑ���������Ȃ�����18���A���̂܂܂ł͑Ή��a�����u9����{�ɖ����ɂȂ�v�Ƃ̌��������Z�\�B��@�I�ɁA����̂��߂̈�Êm�ۍ��A20������ً̋}���Ԑ錾�ɂ��ꕔ�Ǝ�ւ̋x�Ƃ���ꐧ���̗v�������肵���B�~���閽���~���Ȃ��Ȃ鎖�Ԃ̉���ցA�����ɂȂ���u�l�Ƃ̐ڐG�v��h��������Ή����}���ƂȂ��Ă���B
����18���̊����Ǒ��{������c�ŁA�V�^�R���i�E�C���X���ґΉ��a���̑����\���B�����Ă��A���@���҂����݂̃y�[�X�ő����������9����{�ɂ͊m�ەa��������Ƃ̎��Z�𖾂炩�ɂ����B�����Ĉ�ÒԐ������O�̊�@�I�Ƃ̔F���̂��ƁA�������܂Ƃ߂��B
�쏟�����m���͐V�^�R���i�̑Ή��a����543��������10���A�����̑S�a�@�ɑ��A�@���Ɋ�Â��a���m�ۋ��͗v�������{�B���̌��ʁA92����i�K�I�Ɋm�ۂ���߂ǂ��������B����ɂ�荡�����{��594���A9�����{��624���A�����{����ɂ�635���܂ŁA�m�ۂł��錩�ʂ��ƂȂ����B
�Ƃ��낪���@���҂̑����y�[�X�������A18�����ߎ��_�ŕa���g�p����56�E1��(�����d�Ǘp33�E3���A������53�E6���A����66�E1���A����49�E5��)�ƂȂ��Ă��邪26����85�����ɒB���A9��2�����ɂ͖����ɂȂ�v�Z���Ƃ����B�y�[�X������ɑ��܂�A��葁���ɓ��@���s�\�ɂȂ�B
����18���̐V�K�����m�F��590�l�B4�����_�ł�25�E4�l����������1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���74�E6�l�ŁA�O�T��1�E84�{�ɒB�����B
�쏟�m���́u������{���ʂ��Ċ����Ґ��������ɓ]�������A��ÒԐ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׁA�u���̂܂܂ł͋~���閽���~���Ȃ��Ȃ鎖�Ԃɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�v�Ƃ����y�B����w�������B
��͋�̓I�ɂ́A�Ǐ��P�X���ƂȂ������@���҂�����܂ł�葁���h���×{�{�݂⎩��ł̗×{�ɐ�ւ�����A�Վ��I�ȑΉ��a�����m�ۂ����肷��B
�y�ǎ҂͓��@�����Ƃ��K�Ȉ�Â�����悤�A�h���×{�⎩��×{�̑Ή��������B�h���×{�{�݂ł́A�d�lj��}�����ʂ����҂����_�H���Áu�R�̃J�N�e���Ö@�v��_�f���^�����{�ł���Ԑ��𐮂���B����×{�҂͋߂��̐f�Ï��ȂǂŎ�f�ł���d�g�݂Ȃǂ��\�z����B
����ł͒����NJ��҂͓��@�ł��Ă��邪�A���͍���́u�y�ǎ҂̓z�e���ŗ×{�A���@�͒����Ljȏ�ɏW��v�Ƃ��Ă���A���@����i���͔������Ȃ��B
���������܂��A�����N�������̌㓡�����Q���́u�������͋ɗ́A������Ƃ��o���A�Ƒ��ȊO�Ƃ̖ʉ�����炵�Ăق����B�����̖��������Ŏ��i�K�ɂȂ��Ă���A�O�o�͖`���B�����̊�@�Ɋׂ錜�O������Ɨ������Ăق����v�Ƈ��Z���t���b�N�_�E�������H�����߂��B
���É���677�l�����@�����g��~�܂炸1�T�Ԃ̊����Ґ��͑O�T��1�D84�{�@8/19
�É������ł�19���A�V����677�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����A����20�����猧���S��ŋً}���Ԑ錾���K�p����܂��B�V�K�����҂�677�l�ŁA���߂�600�l����3���A���ʼnߋ��ő����X�V���Ă��܂��B���Z���鎩���̕ʂł͕l���s��160�l�A�É��s��134�l�A�x�m�s��43�l�A�֓c�s��36�l�A���Îs��30�l�Ȃǂł��B
160�l�̊����҂��m�F���ꂽ�l���s�ł�3���A���ʼnߋ��ő����X�V���A��T�̖ؗj��(��T��79�l)�Ɣ�חz���҂��{�����Ă��܂��B�s�_�ƐU���ۂɋΖ�����E��2�l�̊������m�F����܂������A�s���Ƃ̐ڐG�͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�É��s�ł́A���̂�18����141�l�Ɏ����ʼnߋ�2�Ԗڂɑ��������҂ƂȂ�A2���A����100�l���܂����B����1�T�Ԃ�10���l������̊����Ґ���88�D73�l�ƁA9���A���ʼnߋ��ő����X�V���Ă��܂��B������134�l�̂���1�l�́A�㉺�����ǂ��q�l�T�[�r�X�ۂ�20��̒j���E���ŁA�s���Ƃ̐ڐG�͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�܂��A1�l�̎��S���m�F����A�����̎��҂͂��킹��160�l�ɂȂ�܂����B�V���ȃN���X�^�[��1���m�F����A���蒬���̋A�Ȃ����F�l�̏W�܂��8�l���z���ƂȂ��Ă��܂��B�����ł́A����1�T�Ԃ̐V�K�����҂��O�̏T�ɔ�ׂ�1�E84�{�̃y�[�X�ő������Ă��āA�l��10���l������ł�83�E5�l�ƁA��������ߋ��ő����X�V�������Ă��܂��B
�����쌧 �ό��n���v�w�Ŋ����h�~�Ăт��� �V�^�R���i�}�g��� �@8/19
���쌧���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������}���ɍL���钆�A���̐E��������s�̑P�����Ȃǂ�����Ċ����h�~��̓O����Ăт����܂����B
���쌧���ł�18���A����ɔ��\���ꂽ�l���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�152�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����ȂNJ������}���Ɋg�債�Ă��܂��B
�����������A19���A���쌧�̐E�������O����̊ό��q���K��钷��s�̑P������JR����w�O���Ԃʼn���āA�����ŎႢ����𒆐S�Ƃ����������L�����Ă��邱�Ƃ�A�������L�����Ă���n��Ƃ̉�����ӂ�����Ȃ��l�Ƃ̉�H�����l����悤�Ăт����܂����B
���쌧�͍���22���܂ł��u���������ԁv�Ƃ��Ă��āA�����e�n�̊ό��n���v�ȉw�ȂǂŌĂт������s�����Ƃɂ��Ă��܂��B
���쌧����n��U���ǂ̋g�ǒ��́u�����҂̑����̑���������܂łƂ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǑ����Ȃ��Ă��܂��B��{�I�Ȋ��������l��l���O�ꂵ�Ăق����ł��v�Ƙb���Ă��܂����B
�������}�g��@�ی����u���@�ł��Ȃ����ԋ߂Ɂc�v�@����s�@8/19
19���A����s��23�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��܂����B
����s�Ŋ������킩�����̂́A10�Ζ�������60��̒j��23�l�ł��B���̂���11�l������܂ł̊����҂̔Z���ڐG�҂܂��͐ڐG�ҁA���O�����̂���l��4�l�A���O�ݏZ�҂͓����s2�l�Ɛ_�ސ쌧1�l�̌v3�l�A�܂��A8�l�������o�H�s���ł��B(�d������)
����s�ی����́A����ȏ�A�����Ґ���������ƁA�u��Ò̐��ɉe������v����@�������߂Ă��܂��B
����s�ی����E���їǐ������u���͓��@���K�v�Ȃ̂ɁA���@�ł��Ȃ��Ƃ����l�͂��Ȃ��B�������A���������͊ԋ߂ɔ����Ă���v
���я����́A��Ò̐����ێ����邽�߂ɁA��{�I�Ȋ�����̊m�F�A�O��ƂƂ��ɁA�����܂����ړ��͐T�d�ɔ��f���Ă��ق����v�ƌĂт����܂����B
���E��N���X�^�[���e�n�ő����@����322�l�����@8/19
���Ɗs��19���A����32�s���ȂǂŌv322�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B1��������̊����Ґ���300�l����̂�3���A���B18�����_�̓��@���҂�420�l�ŁA�a���g�p����53�E6���ɏ㏸���A���̊�ŃX�e�[�W4(�����I�����g��)�ƂȂ�50�������B�����҂͗v1��1792�l�ƂȂ����B
20������̂܂h�~���d�_�[�u�K�p(9��12���܂�)��O�ɁA�����ł͒���1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���74�E90�l�ƂȂ�A3�������ĉߋ��ő����X�V�B���ɃX�e�[�W4�̖ڈ��ƂȂ�25�l��啝�ɏ����Ă���B�N��ʂł́A20�オ126�l�ƍł������A10��50�l�A30��45�l�A40��40�l�Ƒ����B30��ȉ��őS�̂�74�E2�����߁A��҂̊��������������ۗ����Ă���B
�a���g�p���͍�����{�ɃX�e�[�W2(�Q��)���������A�}���Ɉ������A��2�J�����Ԃ�ɃX�e�[�W4�ɒB�����B�����N�������̖x�T�s�����́u��҂̊�������̂ŁA�h���×{�{�݂̗��p�҂����ɑ����Ă���B�w����×{�҃[���x���ێ����Ă������A�a���ɂ��h���×{�{�݂ɂ����肪����A����ŗ×{���Ă���킴��Ȃ��\�����o�Ă���v�Ƙb�����B
�V����7���̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F�����B���̂����s�⍂�R�s�A�֎s�ł́A���ꂼ��E��̓�����ɂ��5�A6�l�̃N���X�^�[�������B���m������S��s�ɋA�Ȃ����l�₻�̉Ƒ��A�F�l��̌v9�l�Ɋ������L������������������B�܂��A���s�̎���ɕ����̉Ƒ���10�l���W�܂�A����5�l�̊��������������P�[�X���m�F���ꂽ�B
�g�債���N���X�^�[��13���������B
�܂��A�h���×{�{�݂�688�l�Ɣ��\�������A�W�v���̂��߁A����ɐ��\�l�����錩���݁B
�V�K�����҂̋��Z�n�ʂ͊s78�l�A��_�s33�l�A�e�����s29�l�A�������s22�l�A���Z���Ύs18�l�A���s14�l�A�֎s13�l�A�H���s11�l�A���Ð�s�A���Q�s�A�b�ߎs�A�y��s�A����s�A�S��s���e8�l�A���R�s7�l�A�C�Îs�A�H���S�}�����A�s�j�S���䒬�A�����S���������e5�l�A�����S�_�˒��Ɖ��ΌS��j�����e4�l�A�H���S��쒬�ƗK��S�r�c�����e3�l�A�K��S��쒬�Ɖ��ΌS��Ӓ����e2�l�A�R���s�A�{���s�A�{���S�k�����A�����S�֔V�����A���ΌS�x�����A���S���쒬�A���S�䐓���A�������A�����s�A���m�����e1�l�B
�N��ʂ�10�Ζ���18�l�A10��50�l�A20��126�l�A30��45�l�A40��40�l�A50��30�l�A60��5�l�A70��7�l�A80��1�l�B
�����Z�̓I�����C�����Ɓ@�ċx��A9��12���܂Ł@���@8/19
������ψ����19���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A�������Z�̉ċx�ݖ����̎��Ƃ���{�I�ɃI�����C���Ƃ�����j���������B�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p���Ԃ��ΏۂŁA�����w�Z�͒n��̊����ɉ����đΉ����A�I�����C���̊��p��w�N�ʁA�ʊw�Ǖʂ̓o�Z���������Ă��炤�B�d�_�[�u�K�p�ɔ����A�w�Z�̊����h�~������c���鋳�琄�i���c��Ŗ��炩�ɂ����B
���Z�͍L�͈͂��琶�k���ʊw���Ă���A�S�Z���k�ɂ���ēo�Z��������邽�߁A���Ƃ�z�[�����[�������̓I�����C������{�Ƃ����B�I�����C��������i�H�����Ȃǂ͊������O�ꂵ����Ōʂɍs���B�����������������n��ł͑Ζʎ��Ƃ��\�Ƃ����B
����A�����w�Z�Ȃǂ͎����A���k�������n�悩��ʂ��Ă���Ƃ��A�n��̎���ɉ������Ή������߂�B
�܂��A�d�_�[�u���K�p�����9��12���܂ł̊��ԁA�̈�Ղ�^����A�����Ղ͉����܂��͒��~�Ƃ����B�����⒆�~������ꍇ�́A�I�����C���̊��p�▧�W�A�ڐG����������Z��ڂ̐ݒ�A����҂̐����Ȃǂ����߂�B�������ɂ��Ă͎��ɂȂ�����Ȃ��ꍇ�A�����Ƃ��Ċ������x�~�Ƃ����B�C�w���s�����{�}�j���A���Ɋ�Â��A�����Ƃ��ĉ����A���~�Ƃ���B
��c�ł́A���ӑ������f�Z���^�[�̑���[�Y�������w�Z���ł̒��ӊ��N�̌f���⊷�C�Ƃ�������̓O��Ɋւ��u�w�Z�������ă��x���A�b�v���Ă������������v�ƌĂъ|�����B
�Óc���m���́u�����g��̒��S�͎�҂ŁA����̐��E�łǂ��Ή����Ă��������ɏd�v�B�d�_�[�u�̊��Ԃ���������邱�Ƃ�����ɓ���Ȃ���Ă������Ƃ��厖�ɂȂ�v�Əq�ׂ��B
���ΐ쌧���R���i�����g�呱���@�u�V�K�����҂Ȃ����~�܂�H�v�@8/19
�ΐ쌧���ł������g��X���͎��܂炸�A�E��Ȃǂł̃N���X�^�\���������Ŋm�F����Ă�����Ƃ͌�����ǂ����Ă���̂��낤���B
�������}�g�債�A�V�K�����Ґ������~�܂肵�Ă���ɂ��āA�����w�̎s���G���C�����ɕ������B
�s�����C�����́u�����͂����ɋ����f���^�����s���ɂ܂��Ă��邽�߂ɂ��܂��܂ȐE��ŃN���X�^�[���N�����Ă��Ă���ƍl������v�u���̃f���^���͊�������E�C���X�̒��ł��g�b�v�N���X�̊����͂������vጂ̃E�C���X�Ɠ����̊����͂����ƌ����Ă���v�u�܂��ċx�݂Ƃ��~�������Ċ����g�傪�����Ă���B�n��Ƃ̐l���̗}�����\���łȂ��������Ƃ����R�̂ЂƂɂ�������Ǝv���v�Ƙb���B
�܂��A8���ɓ���A�E��ł̃N���X�^�\���������ł��邱�Ƃɂ��ẮB�u����́A��͂芴���͂̋����̃f���^���̎s�������ɂ����̂ƍl������v�u��Ƃ��Ă̓e�����[�N��[�e�[�V�����A�Ζ������o�̐��i�A���ꂩ��x�e���Ƃ��I�t�B�X��i�����Ȃǂł̃}�X�N�̒��p�A3���̉���Ȃǂ������\�h���O�ꂷ�邱�ƁB�܂��Ǝ�ʂ̃K�C�h���C������߂��Ă���̂ł��̏���Ȃǂ����߂���v�Ƙb���B�܂��A���N�`���ɂ��ẮA�u���ݍ����Ŏg���Ă��邍�q�m�`���N�`���Ƃ����̂͋}���ɍL�����Ă���f���^���ɑ��ẮA�����┭�ǂ�h�����ʂ���◎����\�������邪�A�d�lj��\�h�̍������ʂ͈ێ�����Ă���̂ŁA�ł��邾�������̐l�Ƀ��N�`���ڎ�����Ă��炢�����v�Ƙb���Ă����B
�����āA�s�����C�����́u��l��l������܂ł̊����\�h���O�ꂷ��A�ΐ쌧�ł͑�܂̎����Ƃ����̂��\�ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă���v�Ƃ����l�����q�ׂ��B
�����ł̕a���g�p���ɂ��ẮA�܂����������Ă�����̂́A��Î����ɂ͌��E������A�����Ŋ����g���}���邱�Ƃ��d�v���Ƃ��Ă���B
���L���s�E�ߋ��ő�203�l�̐V�^�R���i�����ҁ@9����59�Έȉ��@8/19
�L���s�͐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂��A19���ߋ��ő����X�V�������Ƃ𖾂炩�ɂ��A���߂Ċ����g��h�~�Ɍ������s�����Ăт����܂����B
����s���u�{�����\�̐V�K�����҂͉ߋ��ő���203�l(�ėz��1�l�܂�)�ƂȂ�܂����B����܂ōő�168�l�ł������A�����啝�ɏ���ɂ���v
����s����19���̉�ł��̂悤�ɏq�ׁA�ŋ߂̊����ґ����̎�ȗv���͋A�Ȃ◷�s�A���W���[�ɂ����̂ŁA�Ƒ���F�l�A�E��̓����ւ̊������}�g�債�Ă���Ǝw�E�B�V�K�����҂�9����59�Έȉ��̐l�ł���Ƃ��Ă��܂��B
18�����݁A�L���s��65�Έȏ�̃��N�`���ڎ헦��1��ڂ�84�E1���A2��ڂ�79�E7���܂Ői����A12�Έȏ�64�Έȉ��ł�1��ڂ�26�E1���A2��ڂ�10�E4���ł��B
���V�^�R���i�E���֎s���u�����I�Ȋ����g��̋ǖʁv�@�R�����@8/19
1��������ʼnߋ��ő��ƂȂ�A61�l�̊����\�������֎s�B�O�c�s���ً͋}�̉�ŁA������@���������܂����B�O�c�W���Y�E���֎s���u����܂ł̍ő����ł��������́A�����2�{�ȏ�ƂȂ��Ă���A�z������X�s�[�h�Ŋ����҂��}�����Ă��āA�܂��ɔ����I�Ȋ����g��̋ǖʂ��}�����ƌ��킴��Ȃ��v�V���Ɏs��2�̈�Ë@�ւŁA�N���X�^�[���F�肳��܂����B���傤�܂łɁu���֕a�@�v��10�l�A�u���a�a�@�v��12�l�ƁA��Ï]���҂⊳�҂̊������m�F����܂����B2�̕a�@�ŁA���킹��180�l�قǂ̌������i�߂��Ă��܂��B�O�c�W���Y�E���֎s���u��Ñ̐��̂Ђ����A��ʂ̕��X�̕a�@���g���Ȃ��Ɍ��т��Ă���B����ȏ㊴�����L���Ȃ��悤�ɁA�̐����������Ă����K�v������Ǝv���Ă���v�܂��A���傤�s�����\���������ȏ��31�l�́A���̂Ƃ��늴���o�H���킩���Ă��܂���B�O�c�s���́u��l���ł̉�H�̎��l�v��u���O�����ł͂Ȃ��s���ł��s�v�s�}�̈ړ��͍T���āv�ȂǂƌĂт����܂����B
���R���i�����ő��A�����x���Ăт����@��N�҂ɍL����@�������@8/19
���������̐V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���18���A1��l��啝�ɏ���1253�l�𐔂��A�ߋ��ő����X�V�����B�����ł�20������ً}���Ԑ錾���K�p����邪�A�����Ґ��͋}�J�[�u��`���悤�ɏ㏸�𑱂��Ă���A���̒S���҂͏ő������点�Ă���B
�u�������g�Ƒ�Ȑl�̖�����邽�߁A�������ƍs�������肢�������v�B18���[�̋L�҉�B���ŃR���i������锒�Δ����E�ی���É�암���͂����i����ƁA�s�v�s�}�̊O�o���l�⎞�Z�c�Ƃɉ����Ȃ����H�X�̗��p���T����悤���߂ČĂт������B
�����ł�2������u�܂h�~���d�_�[�u�v���K�p����A���͕����s��k��B�s�Ȃǂ̋��_�����̂𒆐S�ɁA���H�X�ւ̎��̒�~��ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ����߂Ă����B���������d�_�[�u�̌��ʂɂ��āA���Ύ��́u(�V�K�����҂�)�����Ƃ��Ă͌����Ă��炸�A�\���Ȍ��ʂ������Ă��Ȃ��v�ƔF�߂��B
��Ì���ւ̕��S�x�����������a���g�p���⒆���ǎҐ��A�d�ǎҐ��́A�������2�����_����2�{�ȏ�̐L�тƂȂ��Ă���A��Ò̐��́u�ɂ߂Đ[���ȏɂ���v�ƌ�����B
�����}�g��̗v���Ƃ����ψي�(�f���^��)�́A�ŋ߂̐V�K�����҂�8�����Ă���A���Ύ��́u(�s���̃E�C���X��)�����͂̍����f���^���ɂقڒu����������B�����I�Ȋ����g��͂��̉e���v�Ɛ��������B
����18���A���N5������̊����̐��ڂ����\�����B�u��5�g�v���L���钼��1�T��(9���`15��)�̐V�K�����Ґ���5378�l�ŁA��4�g�̃s�[�N����3408�l(5��10���`16��)��1�E5�{�ȏ�������B
��5�g�ł́A�Ƃ�킯��N�w�ւ̊����̍L���肪�����ŁA����1�T�Ԃ̐V�K�����҂̂���30��ȉ���66%���߂��B���̊ԂɋN�����N���X�^�[(�����ҏW�c)�͌v23���B����͎�N�w���������������ƁE��������13���A�w�Z�E����{�݂�7���ɂ̂ڂ����B
����A����҂ɂ��Ă̓��N�`���ڎ킪�i�݁A�V�K�����҂ɐ�߂�60��ȏ�̊����́A5������20%�O�ォ�璼�߂ł�7%�ɁB�d�ǎ҂ɐ�߂�60��ȏ�̊������A5������70%�O�ォ��8��15�����_��26%�ɒቺ�����B�����̒��S����N�w�Ɉڍs���A����1�T�Ԃ̎��Ґ���10�l�Ƒ�4�g�̃s�[�N����33�l(5��24���`30��)����啝�Ɍ��������B
����ł��a�@�ւ̕��S���傫���d�ǎ҂�15�����_�Ōv24�l�B�����20�`30�オ8%�ŁA���a������l������40�`50�オ67%�ƍ����������߂Ă���B
���H�X�ւ̎��Z�v����l���}���̌Ăт����̌��ʂ��オ��Ȃ����A���́u���ꂩ��{�i�I�Ƀ��N�`���ڎ킪�n�܂��N�w�ɂ́A���Аڎ�ɂ����͂������v�ƌĂт�����B
���V�^�R���i�����}�g��@���Ƃ��w�E����3�̌����@�啪���@8/19
�啪�����ł��V�^�R���i�̊������}���Ɉ������Ă���B���݂̏Ȃǂɂ��Đ��Ƃɕ������B
�啪��w��w���@�����W�����u�g�̌`�Ƃ��Ă�5�g�����A��s�s���Ɠ������������v�����b���̂͑啪��w��w���̐����W�����B3���A���ʼnߋ��ő����X�V�����V�^�R���i�̊����Ґ��B�}�����錴���ɂ��Đ��������͎���3�_��������B
���������u(1)�l�̓��������܂�ς��Ȃ������B(2)���嗬�ƂȂ��Ă���f���^���̊����͂̋�������ȗv���B(3)���N�`���̌��ʂ��܂��W�c�Ɖu�Ƃ������̂Ɏ���܂łɂ͏\���B���Ă��Ȃ��v
���������ɂ��ƏW�c�Ɖu��ɂ�7���ȏ�̐l���Ɖu�������Ƃ��K�v���Ƃ����B���̂��߂ɂ̓��N�`���ڎ킪�J�M�����邪�A�啪������2��I�����l�͍���҂ł�87.17���B����A�S�̂ł�36.74���ƂȂ��Ă���B
���������u����҂̏d�ǎ҂͔��ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��邵�A����҂̐V�K�����҂����Ƃ��Ă͏��Ȃ��̂Ń��N�`���̂�����x�̌��ʂ͏o�Ă���Ǝv���̂ŁA�����S�l���ɍL����Ƃ����̂��厖�v
�����ł�20��������H�X�ւ̎��Z�v�����Ăюn�܂�ȂNJ����h�~��������邪�A��Ȃ��Ƃ�1�l1�l���ӎ������߂邱�Ƃ��Ǝw�E����B
���������u�A���t�@�^�ƌ����Ă����C�M���X���A���ꂪ(�ŏ��Ɋm�F���ꂽ�E�C���X��)1.5�`1.6�{�A�}�b�N�X��2�{�̊����́B���̃f���^�^�̓C�M���X�^�ɔ�ׂĂ�͂�1.5�`1.6�{�B�}�b�N�X��2�{�ƍl����ƁA2��2�悾������4�{�B4�{�L����₷���B(�l��)���4����1�Ƃ��S��4����1�݂����ȃC���[�W�B�����܂ł���Ă����Ȃ��ƐV�K�����҂͌���Ȃ��v
�����茧��15�s���@89�l�R���i�����@�N���X�^�[�g��@8/19
���茧�Ȃǂ�18���A����11�s4���ŐV���Ɍv89�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B���ɔ������Ă��钷��s�����ƌܓ��s�̎����Ԋw�Z�̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�����ꂼ��g�債���B
����s�����֘A�ł́A�V����20�`40��̒j���v5�l�̗z���������B�s�E���̊����҂͌v11�l�ƂȂ����B��������s�����{��5�K�t���A�Ζ��ŁA�s���葽���̎s����Ƃ̐ڐG�͊m�F����Ă��Ȃ��B�z���҂ƊW���铯�t���A�̐E��16�l�̌�����i�߂Ă���B
�ܓ��s�̌ܓ������Ԋw�Z�ł́A�^�]�Ƌ����h�ɓ��O����Q�����Ă������K��11�l�ƐE��1�l�̗z�����m�F����A�����҂͌v18�l�ƂȂ����B���Z�ɂ��ƊW�҂̌����͑S�ďI���A�Ǐ�̌y���z���҂ƔZ���ڐG�҂ɂ��Ă͕ی����̎w���ɏ]���A���Z�̏h���{�݂Ō��u������Ƃ����B
����18���A�ܓ���Ì��̕a���m�ۂ̃t�F�[�Y���u2�v����u4�v�Ɉ����グ�A�m�ەa����10����23�ɑ��₵���B
�����ێs��12�l�B���̂��������o�H�s����5�l�A����1�l�͎s�O����s���̐e�����K��Ă���30��̏�����Ï]���ҁB���̏����Ɠ��s���Ă��ĔZ���ڐG�҂Ƃ��Č��������Ƒ���10�Ζ����j����40��j����Ј��̂ق��A�e����70�㏗���̊��������������B
�|���s��18�l�ŁA���̂���7�l�͊����o�H�s���B
���{�Ó��u�ό��ړI�̗������~���v�@�V�^�R���i�}�g��@8/19
�V�^�R���i�E�C���X�̊����ҋ}�����A�{�Ó��s�̍��얡��K�s����18���A�ً}���b�Z�[�W�\���A���~�ł̋A�Ȃ�ό��ړI�̗����𒆎~����悤���߂��B����܂ł́u���l�v�𑣂��Ă������A��Ñ̐�����@�I�ȏɂ���Ƃ��č���́u���~�v�ɕύX�����B���얡�s���́u����͋������b�Z�[�W�ɂ����B�ً}���Ԑ錾���͋{�Ó��ɗ��Ȃ��ł������������v�Ƒi�����B
18�����_�ŁA�{�Ó��s�̒���1�T�ԓ�����V�K�����Ґ�(�l��10���l������)�́A���O�ݏZ�̊����҂��܂ނ�457.37�l�B�S�����[�X�g�̉��ꌧ(310.32�l)��啝�ɏ����Ă���B���얡�s���́u���E�ň��̊����n��v�Ƌ��������B�s���̎���×{�҂�151�l�Ƃ����B
���~�ɂ��āA�s��13���ɍs���������{�Õa�@�Ƃ̋�����Łu�R���i�Ђł̋��~�ł̉߂������v�\�B�A�Ȃ̒��~�ɉ����A�e���ꓯ�ł̈��H���T���邱�ƂȂǂ��s���ɌĂъ|���Ă���B
���얡�s���́u��Ñ̐����Ǝ�(�������Ⴍ)�ȗ����ł͍��A���ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�s����o�g�ҁA�ό��q�ɂ����l�ɗ������Ȃ��悤���߂����B��l��l�̊����ɑ��鎩�o�ƍs�������݂��̖��ƌ��N�����v�Əq�ׁA�O�ꂵ��������ƃ��N�`���ڎ�𐄏������B
�d���W�ł̑؍ݎ҂ɂ͐ڋq�ƂȂǂŊ������g�債�Ă���Ƃ��āA�u�ł������O�o���T���A�s����Ƃ̐ڐG������邱�Ɓv�Ƌ��������B
���Ȃ������T�q���璷�́A9������̐V�w���ɂ��āu���U�o�Z�ɂ��Ă�8�����{�̎s���̊��������ɂ߂āA���f�������B�����_�ŕ��U�o�Z�͍l���Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ��B
���H�Ƃɑ��ẮA���̗v���ɏ]���A�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k���ނ�J���I�P�̒֎~�̓O���i�����B���[�������Ȃ����H�X�܂ł̊������[���ȏƂ��āA���ƘA�g���ăp�g���[�����Ă����l���B
�s���ό��n�̃V�����[���Ȃǂ́A�ً}���Ԑ錾���͕�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B
���{�Ó��s�A���E�ň����̊����g��@�l����444�l�œ�����2�{�@8/19
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ����A���ߋ��ő����X�V�������鉫�ꌧ���ł�18���A����1�T�Ԃ̐l��10���l������V�K�����Ґ���310�E32�l�ɒB���A���߂�300�l�����B���Ɋ����҂��}������{�Ó��s��444�E85�l�ƂȂ��Ă���B�w�W�͈����������Ă���A�����s�œ��t�������E�������ɂ��C�G����B����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��̎����͌����S�̂ŁA17���܂ł�4527�l�A�{�Ó��s��18���܂ł�243�l�������B
�����J���Ȍ��u�����E�F�u�T�C�g�Ō��\���鐢�E�e�n��Ŋ����Ґ����������Ɣ�r����ƁA�����̊����̌�������������B�V�K�����Ґ����3�J���̒���1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ����݂�ƁA�����S�̂̐��l���������̂̓{�c���i��675�E4�l�A�V�^�R���i���s�����Ƃ��ē��t�������E�����}���[�V�A��403�E4�l��2�J�������������B�{�Ó��s�͐l����ł̓}���[�V�A���������B
�l���K�͂⌟���̐��Ȃǂ��قȂ邽�ߒP����r�͂ł��Ȃ����A�����̐V�K�����҂̑������ۗ����Ă���B
�����{�l�̓R���i��C�����ւ̊�@�����Ȃ�������@8/19
�V�^�R���i�E�C���X(�ȉ��A�R���i)�̊����g�傪�~�܂�Ȃ��B8��12���A�R���i�����Ǒ����ȉ�́A�l����5���팸�A����ш��H�X�ɉ����A�S�ݓX�n���̐H�i�����(�f�p�n��)��V���b�s���O���[���ւ̐l�o�����͂ɗ}�����邱�Ƃ𐭕{�ɋ��߂��B���́A���̒��Ĉ��W(����)����C�����ɂȂ����B���������Ȃ��A���E�W���Ƃ������ꂽ�����炾�B�f���^���̏o���ɂ��A��i���ł͊����҂��g�債�Ă���(�}1)�B�Ƃ��낪�A�K�����������Ă���͓̂��{�������B�a�J���i�E���L���O�X�J���b�W�E�����h�������́A�u���B�͎Љ�o�ς��Ȃ�����ؓI�f�[�^�����A����Ȋw�I�ɃO���[�h�A�b�v���Ă���v�Ƃ����B
���l���Ɗ����Ґ��̖��炩�ȑ���
���{�ɑ���Ȃ��͍̂��������B�R���i�����Ǒ����ȉ���߂��K���ɂ́A�ǂ̒��x������������̂��낤�B�}2�́A�����s�̐V�K�����Ґ��ƃ^�[�~�i���w�̐l���������̊W�ׂ����̂��B�����������߂��ÃK�o�i���X�������̌������ł���R�����肩���쐬�����B�ꌩ���Ă킩��悤�ɁA�l���ƐV�K�����Ґ��ɖ��炩�ȑ��ւ͌����Ȃ��B����͓��R���B�R���i�����ɂ̓z�b�g�X�|�b�g�����݂���B��݂����ɐl����}������͔̂�������B�R���i�ɂ��āA�\���ȏ�Ȃ��������s�����Ȃ�Ƃ������A�����ɂȂ��ċc�_����{��ł͂Ȃ��B������O�ꂵ�A�z�b�g�X�|�b�g�肵�������ł̏d�_�I�ȉ�����K�v�Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪�A���{�͂��܂��Ɍ�����}�����Ă���B�}3�͎�v��i7�J��(G7)����ё�p�̌������̐��ڂ��B���{�̐l��1000�l������̌�������0.71��(8��11��)�ŁA�ł������C�M���X(10.97��)��15����1���B����ɁA���ڂ��ׂ��͑�p(0.79��)�̌������ɂ����邱�Ƃ��B���ۑ�ɐ������Ă�����p�́A�����Ɋ����҂����Ȃ����߁A�����̐����������Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪�A�����Ɋ������g�債��5���ȍ~�A�����̐��̐����ɏ��o���A�킸��2�T�Ԃœ��{�̌�������ǂ��������B�����āA��2�J���Ŋ����������������B���̂��Ƃ́A���̋C�ɂȂ�A�������͗e�Ղɑ��₷���Ƃ��ł��邱�Ƃ��Ӗ�����B���{���{�͈Ӑ}�I�ɃT�{�^�[�W�����Ă����̂��B�����Ǒ�̊�{�͌����E�u�����B��{���O������͎��s����B
���N���X�^�[��ɂ��܂ł������̂�
�����̐������ł͂Ȃ��A�N���X�^�[����I���O��Ă���B�����J���Ȃ́A3��(���A���W�A����)���莋���A�S���̕ی��������āA�Z���ڐG�ҒT���ɖ�����ꂽ�B�R���i�����Ǒ����ȉ�̈ψ��߂鉟�J�m�E���k��w��w�@�����́A2020�N3��22����NHK�X�y�V�����w�g�p���f�~�b�N�h�Ƃ̓����`�����g��͕������߂��邩�`�x�ɏo�����A�u���ׂĂ̊����҂������Ȃ�������Ȃ��Ƃ����E�C���X�ł͂Ȃ���ł��ˁB�N���X�^�[���������Ă���A������x�̐��䂪�ł���v�Əq�ׂ����炢���B�Ƃ��낪�A��q����悤�ɁA�R���i�����̎�̂́A���܂�Z���ڐG�҂���̔����ł͂Ȃ��A��C�����ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���B���҂̗\�h�ɕK�v�ȑΉ��͈قȂ�B�N���X�^�[���������Ă���A���䂪�ł���Ƃ��������͉Ȋw�I�ɊԈ���Ă���B������ɁA���J�Ȃ͂��܂��ɕ��j�]�������Ă��Ȃ��B���J�Ȃ́u�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�v�Ƃ����T�C�g�ɂ́u�ψي��ɑΉ����邽�߂̊�����v�Ƃ��āA�u�}�X�N���p�A��A�w���x�̉���ȂǁA��{�I�Ȋ�����̓O������肢���܂��v�Ƃ���A�\������x�Ɂu�����ł͊��C���悭���āv�Ə�����Ă���B�M�҂��A���J�Ȃ̊�����̖����ے�����ƍl����̂́A�����ܗւō̗p���ꂽ�u�o�u�������v���B�I���W�҂̍s�������Z���A���K��A�I�葺�E�z�e���ȂǍŏ����ɐ������A�ړ��͐�p�ԗ���p���邱�ƂƂ����B�ᔽ�����ꍇ�ɂ́A���ً���o���~�Ȃǂ̏������ۂ��B�����҂Ƃ̐ڐG��f���Ƃ��A�u�o�u���v�ɂȂ��炦�Ă���̂����A�ܗ֊J���O���犴���҂����o���A�u�w�o�u���x�̖h����E�v(�����V��7��23��)�Ȃǂ̔ᔻ�𗁂т��B����ɑ��A�����ܗ֑g�D�ψ���́A�u15�����[���v��P�邱�ƂőΉ������B�u15�����[���v�Ƃ́A�w�A�X���[�g�E�`�[�����������v���C�u�b�N�x�ŔF�߂��Ă���A15���ȓ��̒P�Ƃł̊O�o�̂��Ƃ��B�����ܗւł́A�I���X�^�b�t�̊O�o�ɂ́A�Ď��X�^�b�t�̓��s���`���Â����Ă��邪�A15���ȓ��͗�O�I�ɔF�߂��Ă����B�g�D�ψ���́A�u�o�u���v����́A���̂悤�ȋK���ɘa�������ƍl�����̂��낤�B
�����������łȂ���C�������Ă���
���̎咣�͍����I�łȂ��B��C�����̑��݂����Ă��邩�炾�B�u�o�u�������v�́A�R���i�����ɂ͊����҂Ƃ̐ڐG���K�{�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���B����́A���ɂ��������d������]���̌��J�Ȃ̎p���P�������̂��B�Ƃ��낪�A�O�q�����悤�Ɍ������i�݁A�����̑������G�A���]���������C�����ɂ�邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B�G�A���]���́A�Œ��3���Ԓ��x�A���������ێ����Ȃ���V���A���������ړ�����B���u�̂��߂̏h���{�݂ŁA���݂��ɖʎ����Ȃ��l�̊ԂŊ������g�債����A�o�X��q��@�̒��ʼn����Ȃ����ꂽ�l�����������肷��̂͋�C�������������BSARS�E�C���X�͋�C�������邱�Ƃ��ؖ�����Ă���A���̗މ��E�C���X�ł���R���i����C�������Ă��A�܂��������������Ȃ��B�G�A���]���̐��Ƃ����́A���s��������A���̉\�����w�E���Ă������A���،������d������Տ���w�̐��E�ŃR���Z���T�X�ƂȂ�ɂ͎��Ԃ����������B�R���Z���T�X�ƂȂ����̂́A�C�M���X�́w�u���e�B�b�V���E���f�B�J���E�W���[�i���x��4��14���Ɂu�R���i��C�����̍Ē�`�v�A�������C�M���X�w�����Z�b�g�x��5��1���Ɂu�R���i����C�������邱�Ƃ�����10�̗��R�v�Ƃ����u�_�l�v���f�ڂ��������B���̌�A7��6���ɂ́A���E32�J���̉Ȋw��239�l���A�u ���E�ی��@��(WHO)��e���̓R���i����C�����Ŋg�傷�邱�Ƃ�F�����ׂ� �v �Ƃ̘_�l���A�A�����J�́w�Տ������NJw���x�ɔ��\�����B�A�����J�E�e�L�T�XA��M��w�̌����҂炪�A�A�����J�́w�Ȋw�A�J�f�~�[�I�v�x�Ɂu��C���������A�R���i�����g��̎�v�ȃ��[�g�v�Ƃ����_�����f�ڂ���ȂǁA��C�������R���i�����g��̑傫�ȗv���ł��邱�Ƃ́A���܂��w�E�̃R���Z���T�X���B�����炱���A�e�j�X�̑S���I�[�v���ł́A��s�@�̓���҂ɗz���҂��o�āA�ѐD�\�I���S����2�T�Ԃ̊u���ƂȂ����B����͋�C�������l���������炾�B�R���i����C��������Ȃ�A����܂ł̃N���X�^�[���{���̊�����ł͕s�\�����B�u�o�u�������v�����i�Ɏ��s���Ă��A�K�������͋N����B�ܗ։���I�葺�ɂ́A�Ǝ҂Ȃǂ��܂��܂Ȑl�X���o���肵�A�����ނ�̒��ɖ��nj��҂�������A�G�A���]������Ċ������g�傷�邩�炾�B�Ă̒�A�����ܗւł͑����̊����҂��o�����B8��16�����݁A540���̊������m�F����A���̂����I���28�l���B�����ܗ֊W�҂͐����l���낤����A��������1���O�ゾ�B����͂��Ȃ�̊����������A�啔���̃P�[�X�Ŋ����o�H�͕s�����B�u�o�u�������v���ł̊���������A�����o�H�̑����͋�C�����̋^�����Z���B
����C�����̃��X�N���ǂ����炷�����c�_����Ă��Ȃ�
��C������h���ɂ́A���C���邵���Ȃ��B�Ƃ��낪�A���̂�����A�قƂ�Njc�_����Ă��Ȃ��B����͑傫�Ȗ�肾�B�Ȃ��Ȃ�A�^�Ă̓��{�Ŋ��C����������͓̂�����炾�B�O�C�Ɣ�ׁA�ቷ�̋�C����w�ɒ�������ď�ɂ́A5���ԁA����S�J�ɂ��Ă��A����ւ���C�͖�3���ɂ����Ȃ��B�T�[�L�����[�^�[����W�t�[�h���ғ������Ă���������7�����B������ɂ͂��܂߂Ɋ��C���邵���Ȃ����A�ǂ̒��x�̎��������͂͂����肵�Ȃ��B���݁A���E�����s���낵�Ă���̂́A�����ɂ��Ċ��C���������߂āA��C�����̃��X�N�����炷�����B���̂��߂̌��������E���Ői��ł���B���̂�����A���{�łقƂ�Njc�_����Ă��Ȃ����ƂƂ͑ΏۓI���B�����āA���܂��ɂ��イ�����ɋ߂��u�l���}���v��A������ΏۂƂ����u3����v�𑱂��Ă���B�Ȋw�I�ɍ����I�łȂ��Ή��͕K�����s����B�R���i��́A�Ȋw�I�ȃG�r�f���X�Ɋ�Â��A���{�I�Ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���R���i�̗��s�͂��܂ő����̂��H�\�I���ł͂Ȃ������ւ̐헪�ύX�@8/19
�V�^�R���i�E�C���X�̃f���^�^�ψي������E�I�ɖ҈Ђ��ӂ���Ă��܂��B���܂Ŋ����Ґ������Ȃ���������A�W�A�ł��g�債�Ă���ƂƂ��ɁA���N�`���ڎ�ŗ��s������������������ď����ł����s�̍ĔR���݂��Ă��܂��B���{�ł�7�������s���ȂǂŔ��������f���^���̗��s�́A8���ɂ͓��{�S���ɔg�y���A8�����{�̎��_�œ���2���l�ȏ�̊����҂�����Ă��܂��B�V�^�R���i�̗��s���n�܂���1�N���ȏオ�o�߂��Ă��܂����A���̗��s�͂��܂ő����̂ł��傤���B�����̊F������悪�����Ȃ����A���_�I�ɂ��Ȃ���Ă��Ă���Ǝv���܂��B�����ō���́A����̃R���i���s�̌��ʂ��ɂ��ĉ�����܂��B
���z��O�̃f���^�����s
���N��3�����܂ŁA�V�^�R���i�̗��s�͔N���ɏI������ƍl�����Ă��܂����B���N�`���ڎ킪��N�����瑽���̍��Ŏn�܂�A���̍Ő�[���s���C�X���G���ł͐ڎ헦�̑����ƂƂ��ɁA�V���������҂��قƂ�ǔ������Ȃ��Ȃ����̂ł��B����̓C�M���X��č��ł����l�ł����B���̎��_�ŃA���t�@�^�̕ψي������E�I�ɗ��s���Ă��܂������A���N�`���̌��ʂ͏\���ɂ���܂����B���{�ł����N10���܂łɂ͐ڎ튮���҂�6���ɒB���A���s�I���Ƃ������ʂ�������Ă����̂ł��B�Ƃ��낪�A���̗\�z��������̂��A4���ɃC���h�ő嗬�s���N�������f���^���̏o���ł����B���̌�A�f���^���͐��E�e�n�Ɋg�債�A8�����{�ɂ�140�J���ȏ�ŗ��s���Ă��܂��B������܂ŒZ���ԂɊg�債���̂͊����͂̋����ɂ����̂ŁA�]���̃E�C���X��2�{�ȏ�̊����͂�����ƍl�����Ă��܂��B�܂��A���N�`���̌��ʂ��f���^���ɑ��Ă͌��サ�Ă���Ƃ���f�[�^�������݂��܂��B���̂悤�ɁA�f���^���̊g��ɂ��A�R���i�̗��s�\�����傫���ς��A����ƂƂ��ɁA���s�I���̂��߂̐헪�ɂ��ύX���K�v�ɂȂ��Ă��܂����B
�����s�I���̂��߂̐헪
�V�^�R���i�̗��s���n�܂��Ă���A���{���͂��ߑ����̍��ł́A�}�X�N���p�Ƃ������\�h���l���}���Ȃǂŗ��s��}���A���N�`���ڎ�Ƃ�����D�ŗ��s���I��������헪���Ƃ��Ă��܂����B�������C��������a�C�́A�W�c���ň�芄���̐l���Ɖu�����ĂA���s������ȏ�͍L����Ȃ��Ȃ�܂��B������W�c�Ɖu�ƌĂсA�����ƂȂ�a���̂̊����͂ł��̊��������܂�܂��B���Ƃ��A���]�͊����͂���ϋ����̂ŁA�W�c��9���ȏオ�Ɖu�������Ȃ��ƏI�����܂���B�C���t���G���U�͂��̊�����6���Ƃ���Ă��܂��B�V�^�R���i�̏ꍇ�́A�C���t���G���U�Ɠ��l�ɖ�6���ƍl�����Ă��܂����B���̖Ɖu�����l�̐��́A�u���������l�v�Ɓu���N�`���ڎ�����l�v�̍��v�ɂȂ�܂��B�������A���N�`���Ɋ����\�h���ʂ��Ȃ��ƁA���N�`���ڎ���Ă��Ă��Ɖu�̂���l�ɂ̓J�E���g�ł��Ȃ��̂ł��B���̓C���t���G���U���N�`���ɂ͔��Ǘ\�h���ʂ�d�lj��\�h���ʂ�����܂����A�����\�h���ʂ͏ؖ�����Ă��܂���B�R���i���N�`���͂ǂ����Ƃ����ƁA�C�X���G����č��Ȃǂł̎g�p�o������A�����\�h���ʂ�����Ƃ��钲�����ʂ�����Ă��܂����B���̂悤�ȉȊw�I�w�i����A���s�I���̐헪�Ƃ��ẮA�R���i���N�`���̐ڎ헦�����コ���A����ɂ���ďW�c�Ɖu�̊�����6���ȏ�ɂ�����@���Ƃ��Ă����̂ł��B
���f���^���o��ɂ��헪�ύX
�������A�f���^���̏o���ɂ���Ă��̐헪�ɑ傫�ȕύX���K�v�ɂȂ��Ă��܂��B�f���^���̊����͂��炷��ƁA�W�c�Ɖu�ɂ�闬�s�I���ɂ�8���ȏ�̐l���Ɖu�������Ă���K�v�����邩��ł��B�܂��A�R���i���N�`���ɂ��Ă��A�f���^���ɑ��Ă͊����\�h���ʂ��ቺ���Ă���\��������̂ł��B�܂�A���N�`�������ŏW�c�Ɖu��B������̂́A���Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��B���̂��ߐڎ튮���҂�6���ȏ�ɂȂ��Ă���C�X���G����A6���ɋ߂��C�M���X��č��ł��A�f���^���ɂ�闬�s��6�������납��N���Ă��܂��B���N�`���ڎ���Ă���l�̊����͏��Ȃ��ł����A�]���̊����ł͏W�c�Ɖu���B���ł��Ȃ����Ƃ��������ʂɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ɁA�f���^���̗��s�����ɂ��A�V���ȃR���i�헪�����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂ���܂��B
�����s�I���ł͂Ȃ�������
���̐헪�ύX�ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�f���^���̔����ɂ��R���i���s�̏I���͂��Ȃ��ɂȂ�\�����������Ƃł��B�I���ɕK�v�ȏW�c�Ɖu���ɒB���邽�߂ɂ́A�N�P�ʂ̎��Ԃ��K�v�ɂȂ�ł��傤�B�����ł���Ȃ�A���͏I�������҂�������V�^�R���i�̗��s�Ƌ������Ă������Ƃ�����Ǝv���܂��B�������A����ً͋}���Ԑ錾����������o������A�}�X�N�Ȃǂ̗\�h����펞�s�����肷��悤�ȋ����ł͂���܂���B���������ς킵������펞���邱�ƂȂ���������ɂ́A�V�^�R���i���C���t���G���U�Ɠ��l�Ȋ����ǂɂ��邱�Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B�C���t���G���U�͒��N���s���Ă��銴���ǂ̂��߁A�������͈��̊�b�Ɖu�������Ă��܂��B�����犴���͂͂���قNj�������܂��A�d�lj�����l���ق�̈ꕔ�ł��B���̈���A�V�^�R���i�͐V���������ǂȂ̂ŁA�������͂قƂ�ǖƉu�������Ă��܂���B�����ŁA�܂��̓R���i���N�`���ڎ���g�傳���A�����̍��������̖Ɖu���x���ɂ܂œ��B������̂ł��B�R���i���N�`���̔��Ǘ\�h���ʂ̓f���^���ɑ��Ă��ቺ���Ă��܂����A�܂��L���Ȉ�ɂ���܂��B�����č���A�V�^�R���i�̗��s���ĔR���Ă�����A���N�`���̒lj��ڎ��}�X�N�Ȃǂ̗\�h��������đΏ�����̂ł��B�����������s�Ƃ̋����̓C�X���G����C�M���X�Ō��݁A�s���Ă���A�f���^���ɂ�銴���҂͑����X���ɂ���܂����A�d�ǎ҂⎀�S�҂͏��Ȃ��}�����Ă��܂��B
�����{�ł̍���̌��ʂ�
�ł́A���������헪�̂��ƁA���{�ł̗��s�͍���ǂ��Ȃ��Ă����ł��傤���B����̑�5�g�̗��s�́A8�����͑����Ɨ\�z����Ă��܂��B���̗��s��}����ɂ͐l���}����e���̗\�h��ɗ��邵������܂���B����ƕ��s���ă��N�`���ڎ���g�傳���A10�����܂łɂ͍�����6���ȏオ�ڎ����������K�v������܂��B����͏W�c�Ɖu�̂��߂ł͂Ȃ��A�V�^�R���i���C���t���G���U�Ɠ��l�̊����ǂɂ��邽�߂ł��B11���ȍ~�A�~�̋G�߂��}����ƁA�V�^�R���i�̗��s�͍����m���ōĔR����ƍl�����܂��B���̎��܂łɃ��N�`���ڎ���Ă����A���ǂ͂��Ȃ�}�����܂����A���Ȃ��Ƃ��d�ǂɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���N�`���ڎ���Ȃ������l�́A�e���̗\�h�����������悤�ɂ��Ă��������B����A�V���ȕψي������s����ȂǍĂёz��O�̎��Ԃ��N���邱�Ƃ��l�����܂����A���ꂩ��͐V�^�R���i�̗��s�Ƌ�������헪���K�v�Ȃ̂ł��B
�������҂܂��ߋ��ő��̓��{�u��҂ɗ\��Ȃ��Ń��N�`���ڎ�v�@8/19
�����s���A��҂������W�܂�a�J�w�߂���20�`30�オ�\��s�v�ŐV�^�R���i�E�C���X���N�`����ڎ�ł���ڎ�����J�݂���B�ŋ߂̊����҂�70����30��ȉ��ƌ����ȂǁA�Ⴂ�w�𒆐S�ɐV�^�R���i�E�C���X���}���ɍL�����Ă���̂ɂƂ��Ȃ��[�u���B
�����ʐM�ȂǓ��{���f�B�A��19���ɓ`�����Ƃ���ɂ��ƁA�����s�͍������ɏa�J�w�̋߂���20�`30���p�̐V�^�R���i�E�C���X���N�`���ڎ�����J�݂���B���N�`���̎�ނ̓t�@�C�U�[�ŁA1��ڂɌ���\��s�v�ł��̏�Ŏt���Đڎ킪�\���B���r�S���q�����s�m����18���[���u�������L�����Ă���Ⴂ����ɂǂ̂悤�ɑ������N�`���y�ł��邩���l���Ă���v�Ƃ��Ȃ��炱�������v��\�����B
���{�ł�1��100���l�K�͂Ń��N�`���ڎ킪�s���Ă���ɂ�������炸�����Ґ��͘A���ߋ��ő����L�^���Ă���B18���ɓ��{�S��ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�����҂�2��3917�l�ŁA13����2��361�l���V�^�R���i�E�C���X���s��ōł����������B
�����ł͂��̓�5386�l�̊����҂��m�F����4���Ԃ��5000�l��ɏ�����B�V�K�����҂̂���70����30��ȉ��������Ɠ����s�͖��炩�ɂ����B
����ɔ����A���{���{�͐V�^�R���i�E�C���X�̋}����}���鋆�ɂ̑�Ƃ��ă��N�`���ڎ�ɑ��͂������Ă���B���{�ł�18���܂ł�1��ڂ̃��N�`���ڎ���I�����l��50�D3���A2��ڂ̐ڎ�܂Ŋ��������l��38�D8���ɒB����B���{���{�͍������܂łɑS�����̔�����2��ڂ̐ڎ���I����Ί����g��X�����݉�����Ɗ��҂��Ă���B
���������͂������f���^���̗��s��2��ڂ̐ڎ�̊�����50�����Ă������҂͌���Ȃ���������Ȃ��Ƃ̌x�����o�Ă���B���{���{�̐V�^�R���i�E�C���X���Ɖ�c�̔��g�Ή��17���̕����Łu�S������70�����ڎ���I��������Ɗ����g�傪���������Ƃ͒f���ł��Ȃ��v�Ƃ��Ȃ��犴���\�h�Ɏ����I�ɋC������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƌ��������B
���u��5�g�v�q������e�֊��������@�V�w���O�ɕ��s���A�V�^�R���i�@8/19
�S���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A�]���������q���̊������X�N�������Ƃ����C���h�R���̕ψي��u�f���^���v�ւ̒u������肪�i�݁A�q������e�Ɋ������L���鎖�Ⴊ�����n�߂��B��Ì��ꂩ��́A�����g��́u��5�g�v�Łu���܂łƋǖʂ��ς�����v�Ƃ̎w�E���B�q�����m�̐ڐG��������V�w����O�ɁA�W�҂͂ǂ̂悤�Ɏq���̊�����h������Y���Ă���B
�����J���Ȃ̂܂Ƃ߂Ȃǂɂ��ƁA�V�K�z���ґS�̂ɐ�߂�10��ȉ��̊����́A7��12�`18����14�E7�����������A8��2�`8���ɂ�17�E1���ɑ����B1�J�����Ƃ̐�����3���ȍ~�A�����������Ă���A7���ɂ͉ߋ��ō���14�E8���ƂȂ����B
��9�Έȉ���1��l��
���s����E�C���X�̖�8�����f���^���ɒu������������{�ł͓���7�����{�ȍ~�A9�Έȉ��̎q���̊����҂��}�����Ă���B8��2�`15����2�T�Ԃɕ{���Ŋm�F���ꂽ9�Έȉ��̊����҂́A��l�����B�����͐e�Ȃǂ���̉ƒ�����������A��2���͊����o�H���s���B�ۈ牀�Ȃǂł̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�������m�F����Ă���B
���Ɍ������ǂ��a�@�Ŋ����Ǔ��ȕ����߂�}�䐳�u��t�́u��5�g�̓�����i�K�Ŏq���̊����҂������A����܂łƋǖʂ��ς������ۂ��v�Ǝw�E����B�d�lj��͂��Ȃ��Ă����M���o��q��������Ƃ����A�u�q�����e����Ɋ������A�ƒ���ōL����p�^�[���������Ă���B�f���^���͊����͂������A�Ƒ��S�����������邱�Ƃ����肤��v�ƌx����炷�B
���a�@�ł͐V�^�R���i�Ɋ��������q�������@�ł���悤�A7�����m�ہB18�����݁A�����ɂ͎����Ă��Ȃ����A�e�n�̕a�@�Ŏ��ꂪ����q���𑽂������邱�ƂɂȂ�A�a�����N�����鎖�Ԃ��z�肳���B�V�w�����n�܂����Ɏq���̊����҂�������\��������A�}���t�́u�R���i�Ɋ��������q�����������a�@�͏��Ȃ��B�ǂ�����Ďq�������̂��Ƃ������_�ő���l����K�v������v�Ƙb���B
�����Ȃ��d�lj�
�����A�q���̏d�lj�����͂قƂ�ǂȂ��A�����̊w�Z�ł͊������O�ꂵ�Ȃ���V�w���̒ʏ���Ƃ��n�߂錩�ʂ����B���{�̋g���m���m����18���̑��{����c��̋L�҉�ŁA�u�q�����m�Ŋ������L����A�ƒ�Ɏ����A��A�d�lj����₷���e����ɍL�߂Ă��܂��v�ƌx�����������A�w�Z�ɑ��Ċ�����̓O��ƁA����̊����g��ɔ������I�����C���w�K�̏����Ȃǂ̑Ή������߂��B
�w�Z����ł��x�������߂Ă���B������s�����̍Z���́u�w�Z�ŃN���X�^�[���������A�����̊w�����ɂȂ邱�Ƃ��l������v�Ƌ�Y�B�}�X�N����łƂ������]���̊�����ɉ����A�u�������ɍR�E�C���X���H���{���ȂǐV���ȑ���u����K�v������v�Ƙb�����B�����ւ̋��|���珬�w6�N�̎���(12)�����Ȃ������ɂȂ����Ƃ�����e(44)�����{���c�s���́u�\���ȑȂ��܂܊w�Z���n�܂�͕̂s���B��������C�ɍL�����Ă��܂��̂ł́v�ƌ��O�����ɂ����B(�m���߂��݁A���䍹�D�A�n�喾��)
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i 5534�l�����m�F 2���A��5000�l�� ���S��4�l �@8/20
�����s���ł�19���A����܂ł�2�Ԗڂɑ���5534�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B2���A����5000�l���A19���܂ł�7���ԕ��ς�4700�l���čő����X�V���A�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B�܂��A����ŗ×{���Ă���l��2��4000�l������A18����肳���2000�l�߂������āA2���A���ōő����X�V���܂����B
�����s�́A19���A�s���ŐV����10�Ζ�������90��܂ł̒j�����킹��5534�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B����܂ł�2�Ԗڂɑ����A2���A����5000�l���܂����B�܂��A1�T�ԑO�̖ؗj�����545�l�����A�ؗj���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B19���܂ł�7���ԕ��ς�4774.4�l�ŁA�ő����X�V���܂����B�O�̏T��120.1���ŁA�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B
�����o�H���킩���Ă���2193�l�̓���́A�u�ƒ���v���ł�����1471�l�A�u�E����v��249�l�A�u�{�ݓ��v��152�l�A�u��H�v��60�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̊֘A�ł͐V����9�l�̊������m�F����܂����B����́A�O���l���A���Z�W��3�l�A�ϑ��Ǝ�1�l�A���{�l���A�ϑ��Ǝ�3�l�A���Z�W��1�l�A�g�D�ψ���̐E��1�l�ł��B
�s�̒S���҂́u�����̔����������Ă��ăs�[�N�A�E�g���������A���邫���������킩��Ȃ��悤�ȏ��B����A�����Ƒ�������A���̂܂܂̍��������Ő��ڂ����肷��\��������B�F�l�Ƃ̈��݉�◷�s���s�v�s�}�ł͂Ȃ����ǂ������l���āA���܈�x�A�s�����������Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B
����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂́A29��7391�l�ƂȂ�܂����B����A19�����_�œ��@���Ă���l�́A18�����49�l������3864�l�ƂȂ�܂����B�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��64.8���ł��B
�s�̊�ŏW�v����19�����_�̏d�ǂ̊��҂́A18�����1�l������274�l�ŁA�d�NJ��җp�̕a���ɐ�߂銄����69.9���ƂȂ��Ă��܂��B���̂ق��A����ŗ×{���Ă���l�́A19�����_��2��4172�l�ƂȂ�A�ߋ��ő�������18����肳���1946�l�����āA2���A���ōő����X�V���܂����B
�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ70���80��̒j�����킹��4�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���̂����A70��̏����́A6�����{�܂ł�2��̃��N�`���ڎ���I���Ă����Ƃ������Ƃł��B���N�`����2��ڎ킵���l�̎��S��s���m�F�����̂�2�l�ڂł��B����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2358�l�ɂȂ�܂����B
���k�C���̃R���i���҂̎��S���͂ǂ����č����H����҂́g��������h���c�@8/20
�����҂̋^���Y�݁A��炵�̒��̃n�e�i�H������u�����������v�ł��B�V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ��A�����ł͂���܂�1434�l���S���Ȃ�A���S���͑S���I�ɂ������ł��B�w�i�ɂ͖k�C���́A����n�掖�����܂����B�x�b�h�ɉ�����銳�ҁB�ׂł͊Ō�t���h�앞�𒅂ăP�A�ɂ�����܂��B
�u���҂̓_�H�j����Ƃ���ł��v(�Ō�t)
�〈��̖k�C�������J�Еa�@�A�V�^�R���i�a���ł��B���̓��̍ō��C����33�x�B�^�ē����A2�T�ԋ߂������Ă��܂����B
�u�肪�ׂ��ׂ����Ď�܂��j���܂��v(�Ō�t)
�u���͂���v(�Ō�t)
�u���҂���͔������ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA���܂ꂽ���̂��Ō�t�������ė��܂��v(�Ō�t)
�����ł́A�����ǂ܂ł̊����҂�����Ă��܂��B�������A���N�H�A�O���f�Â��~���鎖�Ԃɒǂ����܂�܂����B
�u�k�C�������J�Еa�@�ŋN�����N���X�^�[�ł́A42�l�������B���@���҂����𗎂Ƃ��܂����v(�L�҃��|�[�g)
�k�C�������J�Еa�@�ɂ́A�x����ⓜ�A�a�Ȃǂ̊�b������������A80���鍂��҂��������@���Ă��܂��B�����ɁA�N���X�^�[���N���܂����B
�u(�V�^�R���i�Ɋ��������)���ɓ��Ɉ����Ȃ��Ă����āA�}�ς���B�����������̂ł͂Ȃ����A�Ƒ��ɂƂ��Ă��{�l�ɂƂ��Ă��v(�k�C�������J�Еa�@�E��ˋ`�I�@��)
�a�@�ł͂��̌�A���M�����l�̏����ꌳ��������A�����҂��o���a���S�̂̍R���������s�����肵�āA�N���X�^�[�̍Ĕ���h���ł��܂��B
�u���S��19�l�ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����v(5��31�������́u�����h�L�b�I�v)
�����ł́A8��18���܂ł�1430�l����l���V�^�R���i�Ɋ������Ď��S�B����́A�s���{���ʂ�3�Ԗڂɑ������ł��B�u�����������v���A�����҂̂������S�����l�̊������u���S���v�ׂ��Ƃ���A�k�C���S�̂ł́A3.21�p�[�Z���g�B�s���{���ʂ�2�Ԗڂɍ����A�S�����ςƔ�ׂ��2�{�߂������ł����B�Ȃ��A���S���������̂��H�����̕a�@�ɃA���P�[�g�����������Ƃ���A���鋤�ʓ_�������Ă��܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ��u���S���v�B�k�C���́A�s���{���ʂ�2�Ԗڂ̍����ł��B���S���̍����ɂ��āA�u�����������v�́A����29�̑�2�튴���ǎw���Ë@�ւɃA���P�[�g�������s���A12�̕a�@����܂����B�����ɂ́A���鋤�ʓ_���c
�u(�����̎��S���������v���͉����Ǝv���܂����H)�u����Ҏ{�y�э���҂���r�I�������@���Ă�����E�������a�@�ł̃N���X�^�[�������������Ƃ��v���ƍl���܂��v(�s������a�@�̉�)
5�̕a�@���u�{�݂�a�@�ł́A����҂̃N���X�^�[�v�𗝗R�ɂ������̂ł��B�����ł́A�����g�傩��܂��Ȃ����N4���A�D�y�̉��{�݂ŃN���X�^�[���������A92�l�������B����̊�a�@�ł́A11���ȍ~�A311�l���������A�����A�����ő�K�͂̃N���X�^�[�ɂȂ�܂����B
�u����Ҏ{�݂��Ë@�ւŊ������L����ƁA����҂��������₷�������܂��B���ꂪ���S��(�̍���)�ɂȂ����Ă���v(�k�C���ی��������E�A���F�Z��)
�ł́A�Ȃ��k�C���ŁA�����̃N���X�^�[���N�����̂��B
�u���ς��Ȃ��߂����Ă��܂����H�v(���������N���j�b�N�E�r�c�T��Y�@��)
�u�͂��A���v�ł���v(�����)
�N���X�^�[���N��������Ҏ{�݂ŖK��f�Â𑱂��Ă����A�r�c��t�ł��B����҂̊����g��ɂ́A�����Ȃ�ł͂̎���W���Ă���Ƙb���܂��B
�u����҂̎{�݁A���ʗ{��V�l�z�[�����܂߁A�T�[�r�X�t������ҏZ��̓������A�D�y�̐��́A�ق��̐��ߎw��s�s�ɔ�ׂĂ����ɑ����s�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��v(���������N���j�b�N�E�r�c�T��Y�@��)
�����Œ��ڂ���̂́A�����ɏZ�ލ���҂̉Ƒ��\���ł��B�����J���Ȃ̎�����65�Έȏ�̐l�̉Ƒ��\���ׂĂ݂�ƁA�q�ǂ��Ƃ̓��������Ⴂ���Ƃ��킩��܂��B���̔��ʁA�L���V�l�z�[���̐��́A�����ȂǂƔ�ׂĂ������̂ł��B��삪�K�v�ɂȂ�����A�܂��Ⴉ���ȂǓ~�̐������������Ȃ����肵������҂��A�D�y�ȂǓs�s���̘V�l�z�[���ŏW�c�����𑗂�A�����������{�݂Ŋ������g�債���c����ȍ\�}�������Ă��܂��B����ł́A����Ҏ{�݂�a�@�ɁA�E�C���X���������܂�闝�R�͉��Ȃ̂��B�����Ǘ������̒˖{�����͂����w�E���܂��B
�u�s�������������ƁA����Ҏ{�݂�a�@��(�E�C���X��)�������܂��\�������������ƌ�����B�ό��q������Ƃ������Ƃł́A�k�C���́A���������s���������L���郊�X�N������v(�k�C����Ñ�w�E�˖{�e�q����)
���~�}�O���A������E�@�É������V�^�R���i�g��~�܂炸�@8/20
�É������̐V�^�R���i�E�C���X�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��B19���̐V�K�����҂�3���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�677�l�B����×{�҂��������A�e�̋}�ώ��̑Ή��̏d�v�x���������A��Ë@�ւł͋}�������҂������~�}�O���ō���̑̐��ێ������ʂ��Ȃ������܂�Ă���B��ÊW�҂́u���̂܂܂ł͎���ɐ�����������\��������v�ƁA��@���������ɂ���B
�u�~�}�O���Őf�Â��銳�҂��z���ƂȂ�P�[�X���A��T����m���ɑ����Ă���v�B�É��ϐ�����a�@(�É��s�x�͋�)�̉��{�D�j�a�@���́A�S�����܂�銳�҂̊����}����������������B���a�@�̋~���~�}�Z���^�[�́A�����̋^�������銳�҂ɂ�PCR���������{���Ȃ���A�����\�h��O�ꂵ�ċ~�}�O���f�Â𑱂��Ă���B�����A�����҂̋}���������u�R���i�ȊO�̐f�Â𐧌�������Ȃ���Ԃ���������v�ƌ��O����B
�l����ÃZ���^�[�̋~���~�}�Z���^�[(�l���s����)�́A�~���a��30���̂���10�����A�R���i�̏d�ǎҗp�̕a����3���m�ۂ����B���̂��ߓ��a���̎��e�l���͒ʏ��3����2�ɏk�����Ă����ԁB�����r�ƃZ���^�[���́u�}���p���[�ɂ����E������B���Ƃ��Ή����Ă��邪�A���̂܂܊����g�傪�����}����������Ȃ��v�ƕs�����B���Ȃ��B
�����ł́A���M���������Ƃ𗝗R�ɔ]�����̊��҂��]�O�ȕa�@�Ŏ����ꂸ�A�n��̒��j�a�@�ɔ��������P�[�X�Ȃǂ��o�Ă���B
�l���s���h�ǂ̒S���҂́A����̔����Ɩ��ɂ��āu�Ǐ������������҂�119�Ԃ��d�Ȃ�A�~�}���̓������Ԃɉe�����o��\���͂���v�Ƙb���B
�����͂̋����C���h�R���̃f���^���̉e���ŁA�Ⴂ������d�lj�����P�[�X�������Ă���B���{�a�@���́u������͎������g�����łȂ��A��Ȑl����邱�ƂɂȂ���B���N�`�����@������ƂȂ��ł��Ăق����v�ƌĂъ|����B
������@��5�g�A�g��~�܂炸�@�����Ґ��A�����ɑ�4�g������ �@8/20
�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂͏\����A�V���ɕS�\���l���m�F���ꂽ�B��ܔg���n�܂�����������ȍ~�̊����Ґ��͌v��Z�S�\�O�l�ɏ��A���ɍł�����������l�g(�O�����〜�Z���O�\��)�̊����Ґ��̘Z���ȏ�ɒB���Ă���B���Ƃ́u�܂��s�[�N�͌����Ă��炸�A�������ɂ���l�g�̊����Ґ�����\���������v�ƌx����炷�B
��ܔg�͊����͂̋����C���h�R���́u�f���^���v�̉e���Ŋ����҂̑����X�s�[�h�������A�����Ǝ��̊����x�����x����5(���ʌx��U)�Ƃ�������ł��������~�܂�Ȃ��B�M�B��a�@�������䎺�̋���M��Y�������́u���g〜�l�g�ł͊����g��̗}�����݂��ł��Ă������A���͂���܂ł̑��ʂ����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���v�Ɗ�@���������ɂ���B
�����g��̂��������ɂ��āA���͎������{�̎l�A�x�₨�~�ɐl�̈ړ����������e�����傫���Ƃ݂Ă���B���䂳��́u�f���^���͌��O�R�������łȂ������ł��������L�����Ă���B���O�Ƃ̉����̎��l�����߂邾���ł͑�Ƃ��ĕs�\�����v�Ǝw�E����B���̏�ŁA�ċx�ݖ����̏������Z�ȂǂŏW�c�����ɂȂ���A�����҂��}�����鋰�ꂪ����Ƃ��āu�x�Z�[�u��I�����C�����Ƃւ̐�ւ����@�E�E�E
���d�ǎҐ��d���́u�댯�ȍl�������v ����m���A���{�̎w�W������������ᔻ�@8/20
���{���V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԑ錾�̉�����Ƃ��āA�V�K�����Ґ������d�ǎҐ���N�`���ڎ���d������w�W�Â�����������Ă��邱�Ƃɂ��āA���挧�̕���L���m����19���A�u�����Ґ���}���Ȃ��ƈ�ÕN����h���Ȃ��B�댯�ȍl�������v�Ɣᔻ�����B
�L�҉�ŕ���m���́A��Ò̐����}���ɕN��������s���Ȃǂ̏�O���Ɂu�����Ƀu���[�L�������Ȃ��ƁA������a����p�ӂ��Ă�����Ȃ��Ȃ�B�d�ǎҐ��͌ォ��ǂ������Ă���v�Ǝw�E�B�u������v�ƂȂ銴���Ґ����y������邱�ƂɌ��O���������B
�����}����Ƃ��āu�ی����̋@�\���������A�����̘A����f����̂��L���v�Ɖ��߂ċ����B�u���ꂪ�Ԃɍ���Ȃ���A�ڐG�̋@������炷���Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��āA�������}�g�傷��s�s���ł́A��K�͓X�܂⋳��{�݂̕��Ȃǁu���b�N�_�E���ɋ߂���@��������ׂ����v�Əq�ׂ��B
�L�����̓���p�F�m����19���A�����ŋL�Ғc�ɁA���������V�K�����҂��d�����ׂ����Ƃ̔F�����������B�u�d�ǎ҂�}����ɂ́A�V�K�����҂�}���邵���Ȃ��v�Ǝ咣�B�d�ǎ҂͊����҂̑����ɒx��đ����邽�߁A�w�W�ɂ���Ȃ�A���Ȃ�Ⴂ���x���̊�ɐݒ肷��K�v������Ǝw�E�����B�@
���ً}���Ԑ錾��13�s�{���Ɋg��A10���́u�܂h�~�v�c�@8/20
���{��20���A�V�^�R���i�E�C���X��Ƃ��ē����Ȃ�6�s�{���ɔ��ߒ��ً̋}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɁA���A�ȖA�Q�n�A�É��A���s�A���ɁA������7�{����lj�����B�{��A���R�Ȃ�10���ɂ́A�u�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p����B����������Ԃ�9��12���܂ŁB�l���̗}���𒆐S�ɑ����������B
�S���ł�19���A�V����2��5156�l�̊����҂��m�F���ꂽ�B18�����1200�l����A2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ����B�d�ǎ҂�1765�l�ŁA�O�����49�l�����A7���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ����B
����19���A�o�ϓ��F��̍��c�����\�����Ɠ����s���ʼn�k���A�u�����͂��ɂ߂ċ����f���^���ɂ���Ċ����Ґ����}���ɑ������Ă���B��Ñ̐��A�����h�~�A���N�`���ڎ��3�{���Ƃ��Ċ����������Ɍ����Ă��������v�Əq�ׂ��B
�錾�̑Ώےn��ɒlj������7�{���́A��������d�_�[�u����ڍs����B�錾�̔��ߒn���13�s�{���A�d�_�[�u��16�����ƂȂ�B
�錾�Əd�_�[�u�̑Ώےn��ł́A�l�̗�������炷����Ƃ�B1000�������[�g���ȏ�̑�K�͏��Ǝ{�݂ɂ́A�m�������ꐧ���Ȃǂ�v������B�N���X�^�[(�����W�c)���������Ă���f�p�[�g�̒n���H�i�����Ȃǂ�z�肵�Ă���B
���G�����ꏊ�ւ̊O�o�̔�����v������ق��A�o�ϒc�̂�ʂ��Ċ�Ƃɏo�Ύ҂�7���팸�����߂�B
��Ñ̐��̋����ł́A�����h���{�݂ŗ×{���銳�҂̑����܂��A�I�����C���f�Â̐f�Õ�V�������グ�邱�Ƃ����߂��B�d�NJ��җp�̕a����1��������ő�1950���~���x������⏕���́A��������B�d�lj��\�h�̌��ʂ����҂����u�R�̃J�N�e���Ö@�v�ƌĂ��_�H����ϋɓI�Ɏg�p����B
�����͂�u��s�����v�ł͂Ȃ��c40�s���{���Ŋ��������@8/20
�V�^�R���i�E�C���X�̊����́u���ς�炸��s����肾�v�Ɛ��{���ȉ�̔��g�Ή�͔����������A���ɑS���ւƊg�債�Ă���B�ً}���Ԑ錾��20������13�s�{���ɁA�܂h�~���d�_�[�u��16�����ɑΏےn�悪�g�傳���B�����J���Ȃɏ���������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�́u�S���e�n�ōЊQ���x���̏ɂ���v�ƕ]���B�����g�傪�����������̂��A���Ƃ����ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă���B(����䕶�F�A�������A�P���S�i)
����s���ȊO��9���Ŋ����Ҕ{��
���J�Ȃɂ��ƁA�l��10���l������̐V�K�����Ґ�(����1�T��)��17�����_�ŁA40�s���{���ŃX�e�[�W4(��������)�̊�u25�l�v�����B10�����_����9���������B17�����_�̑S���̐V�K�����Ґ�(����1�T��)��10�����_�Ɣ�ׂ��1�D31�{�B�s���{���ʂł́A����2�D88�{�Ƒ傫���A�X�A�����A�R���A�����A���m�A����A�啪�A��������8����2�{�ȏ�B����A��s����1�s3����1�D14�`1�D29�{�ƑS�����ς���������B�e�n�ň�Ò̐��͈������Ă���B���J�Ȃɂ��ƁA16�����_�̊m�ەa���g�p���́A25�s�{����50���߁B�a���N���Ŏ���×{�҂�������B11�����_�ł́A��s����1�s3������4��8000�l�Ƒ����̂͊m�������A�ق���30���{���ł��v��2��6000�l�ɂȂ����B13���ł͎���×{�҂͂��Ȃ��B
�����Ǐ�҂�c���ł��������g�傩
�����s���j�^�����O��c�̎����ɂ��ƁA7�����{�ȍ~�A1�T�Ԃ�����̐V�K�����Ґ��̂����̖��Ǐ�҂̊�����12�`11���䂾�B���J�ȁu�f�Â̎�����v�͖��Ǐ�̊����҂̊������u30���O��v�Ɛ���B�������c������Ȃ����Ǐ�҂������A���i�ʂ萶�����Ċ������L���Ă���\���������B�s���̂o�b�q�����̗z������8����{�ȍ~�A�A��20�����ŁA�X�e�[�W4���10��������B���g����18���̏O�@���t�ψ����R���ŁA�z�����△�Ǐ�҂ɐG��u�����̋������Ԃɍ����Ă��Ȃ��̂ɉ����A�ꕔ�̐l���ϋɓI�Ɏ悤�Ƃ��Ȃ��B����Ă�������A�����҂͂������������Ǝv���v�ƌx����炵���B
����҂ł͂Ȃ������N�̊O�o��
�����s��w�����������ɂ��ƁA�ً}���Ԑ錾�̔��߈ȍ~�A�s���̔ɉ؊X�̐l�o�͒���Ƃ������X���������B�����A�錾�O����̌������͖�Ԃ�35�D8���A���Ԃ�24�D7���ɂƂǂ܂�A���ȉ���߂�u50�����v�ɓ͂��Ă��Ȃ��B��҂̊O�o�������g��̗v�����Ƃ̎w�E�����邪�A40�`50��̐l�o�������B�s���̎�Ȕɉ؊X�̖�ԑؗ��l����N��ʂɂ݂�ƁA�ߌ�6���`��10���́A40�`64��15�`39������B�ߌ�10���`�ߑO0���͋t�]�����B���������̐��c�~�u�E�Љ�N��w�����Z���^�[���́u�����N�����A�����A�ɉ؊X�Ɋ���Ă���B40�`64�͏d�lj����낮����A�[���Ȗ�肾�v�Ɖ��߂ĊO�o���l���Ăъ|�����B�u��5�g�v�͂��R���z����̂��\�B19���̎Q�@���t�ςŁA�������ꂽ���g���́u�s�[�N�A�E�g�𐳊m�ɗ\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ɠ������B
���u���[�N�X���[���������E�ő����� ���N�`���ڎ�͖{���ɕK�v�Ȃ̂��H�@8/20
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɑ���B��̑R��i�Ƃ��Ċ��҂���Ă������N�`���ւ̐M�����h�炢�ł����B
�C�X���G����p�ĕ��Ƃ��������N�`����i���Ŋ����҂��Ăъg�債�A2�x�̃��N�`���ڎ�ōR�̂����������͂��̐l�����̖h�䂪�˔j���ꊴ������u�u���[�N�X���[�����v�����E���ŕ���Ă��邩�炾�B�������A���Ȃ��Ȃ����N�`���̕�����������Ă���B���N�`���ڎ�͖{���ɕK�v�Ȃ̂��H
���N�`���ɂ��Đ��Ƃ������̋O���C�����n�߂Ă���B
�č��̐V�^�R���i��̐ӔC�҂ŕč����A�����M�[�����nj������E�t�@�E�`������12���̉�Łu�Ɖu���Ⴂ�l�ȊO�͒lj��ڎ�̕K�v�͂Ȃ��v�Ƃ�������܂ł̔�����|���A�u2�x�ł͕s�\���ł�����S����3�x�ڂ̃��N�`���ڎ킪�K�v�ƂȂ�v�Ƃ̔F�����������B
���R�͊����͂̋����ψكE�C���X�E�f���^���̑��݂��B�]�����������N�`�����ʂ��Ⴂ���Ƃ����炩�ɂȂ������炾�B���̌��ʁA���N�`����ڎ킵���ɂ�������炸�z���������o��u�u���[�N�X���[�����v���������Ă���B
�č����a��Z���^�[(CDC)��5���ȍ~�A���N�`���ڎ�����������l�ɂ��Ă͓��@�܂��͎��S����������ɍi���Ē������Ă��邪�A7��26���܂ł�6587���̃u���[�N�X���[��������Ă���B���̂������@�������҂�6239�l�A���҂�1263�l�������B�č����ł͓����܂łɁA1��6300���l�����N�`���ڎ���ς܂��Ă����B
���Ȃ݂Ƀu���[�N�X���[�����̖�74����65�Έȏ�̃O���[�v�ŋN���Ă����Ƃ����B
�܂��A���E�ő��̃��N�`���ڎ�ɂ��1���̐V�K�����Ґ���1���܂łɌ��������C�X���G���ł̓f���^���̏o����8000�l����V�K�����҂��o�Ă���B���̂���2��ڐڎ킩��5�J���ȏ�o�߂����l�ւ�3��ڐڎ���n�߂Ă���B
���{�ł��A���������nj�������6�����܂ł�3�J���Ԃ�67�l�m�F���ꂽ���Ƃ���Ă���B
70���̐l�����N�`���ڎ������Ύc��30���̐l�����N�`���ڎ�ł��Ȃ��Ă������A�Ƃ���W�c�Ɖu�ɂ��āA���{�̃R���i���ȉ�̔��g�Ή��8��11����NHK�̔ԑg�Łu��]�ґS�������N�`���ڎ���ς܂��Ă��W�c�Ɖu���l������͓̂���v�Ɣ������Ă���B
���{�̃��N�`���ڎ�X�P�W���[���ɂ��ƁA8��9�����_��65�Έȏ�̍���҂�81.6����2��ڐڎ���I���Ă���A12�`64�ɑ��Ă�11�����܂łɂ͊�]�ґS�����ڎ���I���邱�ƂɂȂ��Ă���B
�܂�͓��{�ŏW�c�Ɖu����������ł��낤�����ɂȂ��āu�W�c�Ɖu�͓���v�Ƃ����̂��B����ł́A���N�`���ɕs�M�������l���o�Ă��Ă��s�v�c�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�������A���N�`���ڎ��̎��S���Ⴊ1000���ɔ���Ȃ���A���ʊW�����炩�ɂȂ����̂̓[���B���̑��̕���������������Ȃ�����n�b�L���������ʊW�͂킩���Ă��Ȃ��B�O�M��@(�����E����)�̗щ�V�@���������B
�u���_�������A���N�`����ł����b�g�͈ˑR�Ƃ��Ă���ƍl���Ă��܂��B�����������N�`���̖{���̖ړI�͊������Ă��d�lj����Ȃ��ł��ނ��Ƃɂ���܂��B���Ƀf���^���ɑ��郏�N�`�����ʂ�90���䂩��60����ɉ��������Ƃ��Ă��A���ʂ�ے肷����̂ł͂���܂���B�����_�ł̓��N�`���ɂ͌��ʂ�����A�V�^�R���i����g�����L���Ȏ�i���ƍl���Ă��܂��v
���N�`���̌��ʂ͓����s�̃��N�`���ڎ�҂ƐV�K�����ҁA���@�҂̔N��ʂ̊���������������������Ɩ��炩���B
�Ⴆ�A8��1�����݂�65�Έȏ�̃��N�`���ڎ�҂�84��(����2���҂�75��)�B
����A�V�K�����҂̂���65�Έȏ�̊����̓��N�`���N�[�|��������҂ɔz���n�߂�4��20�`26����11.4�������ɉE��������ɂȂ�A7��27���`8��2���ł�2.7���ɒቺ���Ă���B���@���҂̒���60�Έȏ�̊����͍��N2����70�����A7��28����22���ƂȂ��Ă���B
�u�������A���N�`���ڎ�͎���������Ȃ��E�����Ȃ����߂ɍs�����̂ł��B���g�̔��f�E�ӔC�Őڎ�����߂邱�Ƃ���ł��B�������ɂ��Ă͌����ɊW�Ȃ������ɋN���Ă���ȏ�A���ӂ��K�v�ł��B�ǂ̂悤�Ȑl�ɕ��������o�₷���̂��A�ڎ��͂ǂ̂悤�ɉ߂����̂��A�ǂ̂��炢�̊��Ԉ��Âɂ��Ă����ׂ����B�\���ɏ����W�߁A�̒��ɂ���Ă͐ڎ����������T�d�����K�v���Ǝv���܂��v(�щ@��)
���u�������������犴���g��ƌܗւ͖��W�v�̊ې��b�Ɂu�S���ʂ̒n���v�@8/20
��������}�̘@�u�Q�c�@�c����20���A�c�C�b�^�[�ɐV�K���e�B�����}�̊ې���ܗ֒S������19���̎Q�@���t�ψ����R���ŁA�����ܗ֊J�ÂƐV�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ��}�������W�Ƃ��������̍����Ƃ��āu�e���r�̍��������v�����������ƂȂǂ��A�ې쎁�̔F�����u�S���ʂ̒n���v�ɂ���Ǝw�E�����B
�@�u���́u����������������ϐ�(������)�g��ƌܗւ͊W�Ȃ�(�����}�})�v�u�p�����ň�t120�l�A�Ō�t150�l�m�ہB����͒n���ÂɎx��������Ȃ��v�u���c�I���p�����i�{�������ǒ��̌��p�ԂŖ����S���t���K�Ƃ������������͍��Ȃ������W�v�ƁA�ې쎁����������3�_�������A�u�ې삳��̔F�����w�S���ʂ̒n���x�ƋC�t���ׂ��ł��v�Ƒi�����B
����ɁA�@�u���͓����̕ʓ��e�ŁA�����s�̏��r�S���q�m���������p�������s�b�N�̊ϐ�@���������k�ɒ���u�w�Z�A�g�ϐ�v���O�����v�ɂ��āu�����S���S�Ȍ`�łł���悤�ɏ�����i�߂�v�Əq�ׂ����Ƃɑ��A�u��߂��ق��������v�Ɣ������B
�@�u���́u�e�ɂƂ��Ďq�ǂ��̌��N�͉�������ł��������̂Ȃ����̂ł��B���̊����g��̍Œ��A���ϋq�Ƃ̔��f��������Ȃ������ɂ��ւ�炸�q�ǂ������Ɋϐ킳����̂͊J�Ô��f���w�������x�������Ƃ��������Ȃ��v�Ƃ��A�u�D�悷�ׂ��͖������{��ł��v�Ǝ咣�����B
����ɘ@�u���́u�������͓}�_��1964�N�̓����I�����s�b�N�̎v���o���X�ƌ��܂������A���܂͖���^����Ƃ��̐��_�_�ł͂Ȃ��������X�N�̉Ȋw���d�����鎞�ł��v�ƘA�����e�����B
����t�Ƌ������Ă�������ƁA���{�̃R���i�_���ȗ��R�@8/20
8��12���A������Ɩڂ��^�����o�������E�ɔ�э���ł��܂����B�����s�̊����g��u����s�\�v�ȏɁA�����u���Ɓv�������Ă���Ƃ����̂ł��B���˓I�Ɏv�����̂́u�����g��𐧌䂵�Ă����̐��Ɓv���Ƃ������ƁB����ł��Ȃ��Ȃ�A�����̑f�l�̂���������̏W�c�ł��傤�B�����u���j�^�����O��c�v�������m�F���āA���Ɏc�O�Ȕ[���������Ă��܂��܂����B��c�ɏo�Ă����u���Ɓv�́A�܂��ԈႢ�Ȃ��A�������g�Ŏ��܂Ƃ߂��̂ł͂Ȃ��A�X�^�b�t���グ�Ă����p���[�|�C���g�ƃV�i���I��ǂݏグ����ŁA���̏�Ŏ����I�ȋc�_�ȂǂȂ���邱�Ƃ͂���܂���ł����B
����ɁA�����Ԑl�X���ǂ̂悤�ȁu���Ɓv�ł��邩�A�������āA������[���������܂����B�S���u��t�v�ł��邱�ƁB�܂��قڑS�����u�Տ���v(������OB)�ł��邱�ƁB�܂�A�����̊�b��w�����҂�A����̌��O�q����A��t�ł͂Ȃ��A�s�s�h�u�̊ϓ_����p���f�~�b�N������}��E�C���X�w�̐��ƂȂǂ͈�l�����Ȃ��悤�Ɍ��܂����B�����s�Ŋg��̈�r�����ǂ銴��������������V�r���E�G���W�j�A�����O�A�s�s�q���́u���Ɓv����������Ȃ��B�u�@�������v�Ȃǂ̐��ł���\���͂���Ǝv���܂����A���������l�������A���G����ɂ킽���疜��s�s�Ŏs����������V�^�R���i�̊g��Ɂu����s�\�v�ƌ����Ă���B�܂�u����\�Ȑ��v�ł͂Ȃ��A�ʂ̐��Ƃ���������ׂāA�����Łu����s�\�v�ƌ��킹�Ă���B���ɂ͐��_�Ȉ���������Ă��܂����B�m���ɁA���������̂Ȃ��A�s���̐S�̌��N�͂ƂĂ��厖�ł��B
�ł��A�����������Ă̑���́A�ǂ�����Ċ������g�傳�����A�k�������邩�ł����āA����ɐϋɓI�ɖ𗧂��̊��E�C���X�w�҂Ȃǂ����炸�A�u�ł�Ȃ��v�Ɣ����ŗ�����グ�Ă��܂��̂ł���A����͂�����ƈႤ�̂ł͂Ȃ����H�@���炭�O�ɁAYahoo!�ŁA���̘A�ڂ́u���Ɓv�̂��̂ł͂Ȃ��̂Ŏ��グ�Ȃ��Ƃ����������悤�ł��B�Ƃ��낪�A�v���t�B�[���ɓ���̐E�ʂ��ڂ���Ƒԓx���ς��悤�Ȕ����炢�u���v���f�ŁA�������������s�ʂ��Ă������Ȃ̂ł��傤�H�@�s�̐��Ƃɂ��E�C���X�ւ́u�S�ʍ~���v����ɂ́u���ꂩ��͎����̐g�͎����Ŏ��A�����\�h�̂��߂̍s�����K�v�Ȓi�K�v�Ƃ����A����Ӗ�������O�ł�����A�܂��s��������������Ƃ����̂́A���肷��ƐӔC�̑S�ʕ����Ƃ����ꂩ�˂Ȃ��A�ǂ����悤���Ȃ��u���j�^�����O��c�v�ɂȂ�ʂĂĂ��܂����B������������͉������B�������������܂���B
���V�r���E�G���W�j�A�����O�s�݂̓s�s�h�u
����ɂ��Ă��A�����s�̊����g��́A�{���ɐ���s�\�Ȃ̂ł��傤���H�@����Ȃ��Ƃ͂���܂���B�@�������̎�@�ł́A�ł�͂Ȃ��Ǝv���邩������܂��A�Ⴆ��2011�N�A�V�^�C���t���G���U�̗��s�ɑ��āA���y��ʐ��������Ƃ�܂Ƃ߂��u�ʋΎ��̐V�^�C���t���G���U��Ɋւ��钲������(��s��)�v�Ƃ�������������������܂��B
�����Ɏ����ꂽ�悤�ȕ��j��2021�N�̐V�^�R���i�E�C���X��ɓK�p���āA�s�c�n���S��s�o�X�ȂǂɓO��I�ȁu���փ_�C���v���~���ꂽ�肵�Ă���ł��傤���H���邢�́AJR�⎄�S�e�ЂɁA�O�ꂵ���Ԉ����^�]�ɂ��l���팸�̑[�u���u�����Ă��邩�H�d�Ԃ�o�X�����ł͂���܂���B�����Ԍ�ʂȂǂɂ��Ă��A��s���̓�������◿���ݒ�ȂǁA�l�������炷�u���@�v�́A�R�̂悤�ɑ��݂��܂��B���������ɁA�ˋ�̃V�~�����[�V�����Ō������āA����u����̂ł����Ă��A�܂��������Ȃ����̓}�V�ł��傤�B�����A���H�X�̉c�Ƃ�8���܂łƂ��A��ނ̒́E�E�E�Ƃ������A���̌��p�ɉ��̉Ȋw�I�������Ȃ��u���Z�v�Ɠ��l�A�U���̐���œ`���a��}�����ނ��Ƃ͍���ł��傤�B
�a���̂̕����A�͂邩�����ρA���I���ł��B�ނ�̃E���������A�L���ŃT�C�G���X�ɗ��t����ꂽ�A���X���X�ω����銴���f����u�����l�v�Ɋ�Â�����A�Ⴆ�u�l������v�ł���A�u�ψي���v�ł���A����ɂ͊��҂̐�ΐ������ɂ���Ĉ����N������Ă���u�ݑ���Áv�ɑ�����������ł���E�E�E�Ƃ��������̂��A�\���ɍ̂��Ă��邾�낤���B���悻�A�̂��Ă��Ȃ��B�ł�͂܂��A������ł�����̂ɁA����Ɏ肪�S�����Ă��Ȃ��B���ꂪ�A���{�Љ�R���i�ɑł������Ƃ��ł��Ȃ��傫�ȗv���ł͂Ȃ����Ǝw�E������Ƃ����l�������܂��B���{�̃R���i�́u���Ɓv�̃^�R�c�{�c����ŁA�g���������Ȃ��܂܁A�����X�������Ă����B�C�X���G����p�Ă̂悤�ȁA�Ȋw�I�ɐ��������S�̑������R���i��ȂǁA���̍��ɂ́u���̂܂����v�ɗ��܂�̂ł��傤���H
���V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̒m���\����
�����ł悭��������Ⴆ�����������ɏo���܂��傤�B50�N�O�Ȃ�A�e���r���̏Ⴕ���Ƃ����Ƃ��A�X�̓d�C�����O���̃J�o�[���O���āA���̑f�q����芷���ďC���ł��܂����B���������ĕ�����̂͒����N�ȏゾ���ł��傤�B���܁u�e���r�v����ꂽ���ԑ����̂́u�̂ĂĎ����v�Ƃ��������@�ł��傤�B���P�̍�Ƃ��āu�������̊����芷����v�̂����邩������܂���B���܂�e���r����l�ł��ׂė������A���i���x�����璼����Ƃ����u�d�C������v���u�G���W�j�A�v�����݂��Ȃ��B���ꂭ�炢�A�ʁu���W���[���v�͐[���E�i���𐋂��Ă��āA���łɈ�l�́u���Ɓv���J�o�[�ł����Ԃł͂Ȃ��킯�ł��B���x���������Ă����{�ł����u�V�^�R���i�E�C���X�����ǁv�̐��ƂȂǂƂ������̂����݂���Ǝv���Ă���܂Ƃ��ȑ�w�����҂͂��܂���B��w�����ōl���Ă��A����������ɒn���Ȏd����ςݏグ��u��b������v�A�a�@�Ŋ��҂̖���a����u�Տ����È�v�ƁA�ی���������J���ȂŌ��O�q���s���ɐӔC�����u�ی��q����v�͑S���ʂ̎d���ŁA�e�X�L��ȗ̈悪����A�����������t���炵�Ĉ���Ă��܂��B�Ⴆ�A���Ö�p���Ė{���_�����̂ƈႤ���ʂ��o��u����p�v�ł����A���N�`���̏ꍇ�͗��j�I�Ȍo�܂Łu�������v�ƌĂ�܂��B���̍��̓g���f���p�����ь����Ă���悤�Łu�R���i�̕���p�v�Ȃ���{���ڂɂ��ċV���܂����B
�����Ԃɂ́u�g���f����v���M�̏���
������u�R���i�v�͎��Ö�ɂȂ����̂��H�f�l����ɉ��ł����ꂻ���Ȉӏ�����ׂđK�������Ƃ���A�ڂ��������͒P�ɂ����܂��������łȂ��A�f�}���܂��U�炷�Ƃ����ϓ_����͏��R�ƗL�Q���v�ł��B����ȃg���f����I�Ȃ��̂͘_�O�Ƃ��Ă��A��b�ƗՏ��A�ی��s���Ƃ̊Ԃɂ͂��悻���߂������a������܂��B�܂��A���ׂĂ̊�b��w�҂��R���i�����Ȋw�̍ł����k�ȕ��q�A���q���x���̃��J�j�Y���𗝉����Ă��邩�Ɩ����A�������Ȃ��Ƃ͂���܂���B���{�̃m�[�x����w�����w�܂����Ă��A������i����͗��w�����w�ȑ��Ńm��MD�A�܂肨��҂���ł͂���܂���B�R���i�h�u�̎x���Ƃ����ׂ�mRNA���N�`�������p�����A2021�N�x�m�[�x����w�����w�܂̖{���Ɖ\�����A�r�I���e�b�N�Ђ̕��В��A�J�^�����E�J���R���m������҂���ł͂Ȃ��B���q�����w�҂͕K��������t�ł͂Ȃ����A���ׂĂ̈�t���V�^�R���i�̍őO�������q�⌴�q�A�d�q�̃��x�����痝�����Ă���킯�ł͑S���Ȃ��B���{�̃��f�B�A�́A���肷��ƈ�҂ł͂Ȃ��Ƃ������R�����ŃJ���R���m���u���Ƃł͂Ȃ��v�Ƌ敪������x�̐����ɂ���܂��B�܂���t�ł���Ƃ��������Ő��ƔF�肳�ꂽ�A�������Ȍ|���̐l���A�u�R���i���N�`���v�ŕ���p���o��l�Əo�Ȃ��l��������悤�Ȕ���������Ă݂��������B���S��������܂ŁA�����l�W���ɂ�ł��邱�Ƃ����O���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��B
(�����܂ł�����܂��A����̃A�����M�[�ȂǗ�O�������āA�V�^�R���i�E���N�`����ڎ킵���ہA�ǂ̐l�ɂǂ̂悤�ȕ��������o�邩�ȂǁA�Ȋw�I�ɗ\���Ȃǂ͈�ʂɂł��܂���)
����̒��j�ɋ߂��ꏊ�ɂ��Ă��A�����g��ɐ�����@���Ȃ���A���̕���Ɋւ��Ă͐��Ƃł͂Ȃ��P�Ȃ閳���k��̑f�l�ƕς�肪�Ȃ��B�܂���t�Ƌ��������Ȃ���A�������ȏ��@�ʼnc������҂�����A�l���ɜ��鏊�Ƃƌ���˂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���{�͂��������u��含�v�Ƃ������O�ŁA�������͂��킪��Ă��錜�O���@���܂���B�Ȋw�I�ɋؓ��̒ʂ��������Ǒ�̂��߂ɂ́A�u�R���i�s�v�v�ł�����������������V����K�v������悤�Ɏv���܂��B
���C�O�̊����g�傪�Ԑ��Y�ɑŌ��c���ƒ�~������ �@8/20
�x�g�i����}���[�V�A�ȂǓ���A�W�A�ł̐V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�A���������ԑ��̐��Y�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��n�߂��B���E�I�Ȕ����̕s������������Ă��Ȃ��B��s�������ʂ��Ȃ������������錜�O������A�e�Ђ͌v��̗��蒼���ɒǂ��Ă���B
�g���^�����Ԃ̒��c�y�E���s������19���A����̌��Y�̌����͐V�^�R���i���Ƃ��āA�u�e�����z����������[�������v�ƌ�����B
����A�W�A�ł́A�����Ԋ֘A�̍H�ꂪ�W�ς���n��Ń��b�N�_�E��(�s�s����)�����{����A�֘A���i�̐��Y������Ȃ��Ă���B�x�g�i���ł́A�암�z�[�`�~���ߍx�̍H�ƒc�n�Ȃǂ𒆐S�ɁA�]�ƈ����V�^�R���i�Ɋ����������Ƃɂ�鑀�ƒ�~���������ł���B
�g���^�́A�ʂ̒n�悩��̒��B���}���ł��邪�A���Ă��镔�i�͕������邱�Ƃ���A�m�ۂɎ��Ԃ��������Ă���B
�z���_��O�H�����Ԃ́A���b�N�_�E���ɂ��A�����ԍH����ғ��ł��Ȃ��������B
�x�g�i���́A�����Ԋ֘A�Y�ƂW�����邽�߁A���i���[�J�[�̗U�v��i�߂Ă����B����̃��b�N�_�E���́u���Ђɂ��e�����L����\���������v(���������ԑ��)�Ƃ݂���B
���i���[�J�[���W�܂�^�C�ł́A��ƈ����p�o�X�ő��}������A�H��~�n���ɏh���������肷��u�o�u���E�A���h�E�V�[���v�ƌĂ����g�݂Ŋ����҂��o���Ȃ��悤�s�͂��Ă��邪�A���ƌp���͍j�n��̏��B
�����̕s���ɂ��e�����������Ă���B
�}�c�_��19���A�����̕s���ɂ��A8���Ƀ^�C�H���10���ԁA���L�V�R�H���9���Ԃ̑��ƒ�~���v�悵�Ă���Ɩ��炩�ɂ����B
���̂ق��A�X�Y�L�����N�x��35����A���Y�����Ԃ�25����̌��Y���ʂ������\����ȂǁA�e�Ђ��傫�ȑŌ����Ă���B
�����̂́A�Ɠd��Q�[���@������̎��v���}�����Ă���A�D�������̏ƂȂ��Ă���B�u�s���������������̂́A2022�N�H�ȍ~�v(�A�i���X�g)�Ƃ̌������o�Ă���B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������s �V�^�R���i������4���A��5000�l���@�S����2���l���@8/21
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�21���A����܂łɑS����2���l���Ă���B2���l������4���A���B
�����s�ŐV���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�5,074�l�ŁA��T�y�j��14����5,094�l����20�l���������A4���A����5,000�l�����B
�s���̏d�ǎ҂́A�O�̓�����3�l����A270�l�������B
�܂��O�d���ł́A427�l�̊��������\����A����400�l��ƂȂ����B
�����g����A�O�d����9���ɗ\�肳��Ă����u���́v�ɂ��āA���ȏȂɒ��~��\������A���ɋً}���Ԑ錾��v�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B
�܂��A���m����1,445�l�A�Q�n����325�l�A�啪����215�l�ȂǁA9�̌��ŁA�V�K�����҂��ł������Ȃ��Ă���B
���̂ق��A����܂łɑS���ł́A��t����1,761�l�A���Ɍ���1,025�l�ȂǁA2��677�l�̊�����17�l�̎��S���m�F����Ă���B
�S���̐V�K�����҂�2���l����̂́A4���A���B
����A�����J���Ȃɂ��ƁA20�����_�ł̑S���̏d�ǎҐ��́A�O�̓�����72�l�����A1,888�l�ŁA9���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ��Ă���B
�������s�R���i����6�l�@�S���ڎ�Ȃ��@8/21
�V�^�R���i�E�C���X�̐[���Ȋ����g�傪���������s���ŁA�V����5074�l�̊������m�F����܂����B
�s���̐V���Ȋ����҂�10�Ζ�������90��܂ł�5074�l�ŁA4���A��5000�l���܂����B
�ꏏ�ɐH���������e�����������A10�Ζ����̏��̎q�̊���������������A10��̒j�����F�l5�l�Ɖ���đS������������ƁA���~�����⊴���͂̋����ψي��ɂ܂�銴���Ⴊ�݂���Ƃ������Ƃł��B
�d�ǎ҂�20�����3�l������270�l�ł����B
�܂��A30�ォ��80���6�l�̕��̎��S���m�F����܂������A�S�����N�`���͐ڎ킵�Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B
���̂���30��j���́A����ŐS�x��~�ƂȂ��Ĕ�����̕a�@�Ŏ��S���A���̌�̌����Ŋ������������܂����B�얞�₺���̊�b�������������Ƃ������Ƃł��B
���k�C�� ������579�l 4���A��500�l���� �O�T���100�l�����@8/21
�k�C������8��21���A�V�^�R���i�E�C���X��579�l�̊������m�F����܂����B
500�l����̂�4���A���ł��B����s��65�l�ŁA���s�̍ő����X�V���܂����B
1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ���64.25�l�ł��B
�������m�F���ꂽ�͖̂k�C�����\��174�l�A�D�y�s321�l�A����s65�l�A���َs9�l�A���M�s10�l�ł��B
�k�C���S�̂�1�T�ԑO�̓y�j��479�l����100�l�������܂����B�D�y�s�ւ́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p����20���ځB�����X���������Ă��܂��B
�����͂������Ƃ����C���h�^�̕ψكE�C���X�E�f���^���^���́A�k�C�����\����98�l�A�D�y�s��258�l�A���َs��12�l�A���M�s��5�l�ŁA�v373�l�ł��B
����s�ŁA�N��ʔ���\�܂�20�`60��̒j��5�l�ɂ��ăf���^���ւ̊������m�F����܂����B
�k�C���S�̂̎g�p�a������8��20����775���ƑO����779�l����4���������܂������A�k�C���Ǝ��̌x���X�e�[�W4�̖ڈ��u350���v��27���A���Œ����Ă��܂��B
��4�g�̎��́A5��9����500�l���A����12����Ƀs�[�N��727�l���m�F����Ă��܂��B
���{�́u�ً}���Ԑ錾�v�𓌋��s�A���ꌧ�A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{�ɉ����A��錧�A�Ȗ،��A�Q�n���A�É����A���s�{�A���Ɍ��A��������7�{����20������lj����܂����B���߂�13�s�{���ł��B
�u�܂h�~���d�_�[�u�v�́A�k�C���A�ΐ쌧�A�������A���m���A���ꌧ�A�F�{���ɉ����A�{�錧�A�R�����A�x�R���Ȃ�10����lj����A�Ώےn���16�����Ɋg��B�k�C�����܂ߓ���31���܂ł��������Ԃ́A9��12���܂łɉ�������܂����B
�k�C����2������D�y�s�ɁA14�����珬�M�s�ƐΎ�n��(�]�ʎs�A��Ύs�A�b��s�A�k�L���s�A�Ύ�s�A���ʒ��A�V�Ñ�)�ɁA20�����爮��s���u�܂h�~�v�̓K�p�n��ɒlj��B
�����g�傪�����Ă��邱�Ƃ���19���A��ؒm���͍��Ɂu�ً}���ԁv�̗v�������Ă��܂��B�k�C�����̊����҂́A�v52591�l�ƂȂ�܂����B
�����{��ōő�159�l�����@��w�̃N���X�^�[�g��@8/21
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�����A�_�ސ쌧���{��s��21���A�V����10�Ζ����`80��̒j��159�l�̊����ƁA����1�l�̎��S���m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����Ґ��Ƃ��ẮA�ߋ��ő����X�V�����B
���S����1�l������158�l�̏Ǐ�͒�����4�l�A�y��130�l�A���Ǐ�20�l��4�l���������B�����o�H��105�l���������Ă��炸�A54�l�͉ƒ�������������B
�s�ɂ��ƁA�S���Ȃ����̂͐��s�ݏZ��40��j���B16���Ɏ��S���A�����͐V�^�R���i�E�C���X�����ǂ������B�@
���{��s���̑�w�Ŕ��������N���X�^�[(�����ҏW�c)�͐V����6�l�̊�����������A�����҂�22�l�ƂȂ����B�@
���u�����I�v�����g��c�V�^�R���i�@���쌧�̐V�K�����ҁ@����1�T��840�l�@8/21
21���A���쌧���S�̂Ŕ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����҂�150�l�B4���A����100�l���܂����B
�����I�Ɋ����҂��������Ă���u��5�g�v�B������1��������̐V�K�����҂́A18�����炫�傤21���܂�4���A����100�l���A�����g��̎��~�߂�����܂���B
15������21���܂ł�1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���840�l�A�O�T��489�l��1.7�{�ŋ}���Ɋ����̃X�s�[�h���������Ă��܂��B(���\���x�[�X)
����20���A�����̊�����6�i�K�Ŏ��������x�����x����S���u5�v�Ƃ��܂����B�܂��A��ÒԐ����N�����錜�O������Ƃ��āA�S���Ɂu��Ô�펖�Ԑ錾�v���o���܂����B
���́A�����g���H���~�߂邽�߁A�����Ɂu������̓O��v�������Ăт����Ă��܂��B
�����~�A�ċx�݂̉e�����c�V�^�R���i�g��@���쌧�̐V�K����150�l�@8/21
21���A���쌧���ŐV����150�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��܂����B4���A����100�l���܂����B�܂��A�×{�҂͏��߂�1000�l���A��ÒԐ��ւ̉e�������O����܂��B
�������킩�����̂́A10�Ζ�������80��܂ł̒j��150�l�ł��B���Z�n�ʂł͏��{�s27�l�A����s22�l�A��c�s17�l�A���ܖ�s14�l�A���J�s9�l�A�ѓc�s7�l�A��Ȏs�E�����s�E���v�s�Ŋe4�l�A����s�E�ɓߎs�Ŋe3�l�A���K�s�A��P���s�E�эj���E��钬�E�y��E���z�K���E���n���E�얥�֑��Ŋe2�l�A�{��s�E�z�K�s�E����s�E�R�m�����E���z�{���E�C�쒬�E�ѓ����E���X���E���쑺�E�R�`���E�������Ŋe1�l�B�܂��A���Ɍ�2�l�A�������E��ʌ��E�����s�E��t���E�_�ސ쌧�E���R���E�{�茧�Ŋe1�l�̊������m�F����܂����B
�u�W�c�����v���N�������{�s���̍��Z�̉^�����ł́A�V���ɐ��k1�l�̊������m�F����A���v26�l�ɂȂ�܂����B���̐��k��3��ڂ̌����ŗz�����������܂����B
21�����\�̐V�K�����҂̂����A����܂ł̊����҂̔Z���ڐG�҂܂��͐ڐG�҂�78�l�A���O�Ƃ̉����A�؍݂��������l��20�l�A���O�ݏZ�҂�9�l�A�����o�H�s����50�l�ł��B(�d������)
����s�ی����̏��їǐ������́A�����҂̔��Ǐ�s�������݂�ƁA�u���~��ċx�݂ł̉e���ł̊������l������v�Əq�ׂ܂����B�܂��A�u��5�g�v�̊����g��ɂ��āA������@���������A����w�̊�����̓O��A�����āA���O�Ƃ̉����͐T�d�ɂ��Ăق����ƒ��ӂ��Ăт����܂����B
�����̊����҂̗v��6976�l�ƂȂ�܂����B
21���ߌ�4�����_�ŗ×{���Ă���l��1018�l�ŏ��߂�1000�l���܂����B
����͓��@��249�l�A�h���×{��278�l�A����×{��257�l�A������234�l�ƂȂ��Ă��܂��B�d�ǂ�6�l�A�����ǂ�51�l�ł��B(21���ߌ�4�����_)
�m�ەa���g�p����48.6%�B�����ǁA�y�NJ��҂�������ʕa���̎g�p���͒n��ʂɖk�M68.5���A���M53.5���A���M46.5���A��M47.5���ƂȂ��Ă��܂��B
���S���I�Ɋ����g��~�܂炸 ������9���ōő��X�V�@8/21
�S���̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂́A21����9�̌��ʼnߋ��ő����X�V���Ă��āA�i�m�m�̂܂Ƃ߂ł��ł�2���l���Ă��܂��B
�����s��21���A�V���ɔ��\���������҂�5074�l�ŁA4���A����5000�l������܂����B�s�̊�ɂ��u�d�ǎҁv��270�l�ŁA30��̒j��1�l���܂�6�l�̎��S�����\����Ă��܂��B
�܂��A����܂łɑS����2���l���銴�������\����Ă��āA���m�ʼnߋ��ő���1439�l�A�O�d�ł�5���A���ōő����X�V��427�l�B���̂ق��A�R�`�A�Q�n�A�A�L���A���m�A�啪�A�{��ʼnߋ��ő����X�V���Ă��܂��B
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA�S���̏d�ǎ҂�1888�l�ŁA9���A���ʼnߋ��ő����X�V���Ă��܂��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
������ �V�^�R���i4392�l���� ���@��h���×{�Ȃǐl���ő��@8/22
�����s���ł�22���A���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł�����4392�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B���@���҂�h���×{�ҁA����ɓ��@����̂��A�����h���{�݂ŗ×{����̂��Ȃǂ����̐l�̐�����������ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂��A1�l��炵�Ŏ���ŗ×{���Ă���60��̒j�����S���Ȃ�A�����A����×{���Ɏ��S�����l�́A�����9�l���Ƃ������Ƃł��B
�����s�́A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��4392�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B1�T�ԑO�̓��j�����97�l�����āA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B22���܂ł�7���ԕ��ς�4732.9�l�ƂȂ�A�O�̏T��111.0���ŁA�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B���̓���4392�l�̔N��ʂ́A10�Ζ�����277�l�A10�オ484�l�A20�オ1341�l�A30�オ845�l�A40�オ711�l�A50�オ444�l�A60�オ119�l�A70�オ83�l�A80�オ63�l�A90�オ19�l�A100�Έȏオ6�l�ł��B�����o�H���킩���Ă���1900�l�̓���́A�u�ƒ���v���ł�����1233�l�A�u�E����v��208�l�A�u�{�ݓ��v��128�l�A�u��H�v��58�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B�s�̒S���҂́u�ЊQ���x���̊������҈Ђ�U�邤�ُ펖�Ԃ������Ă���B�ƒ�������������Ƃ��Ă͍������A�E����H�A���s��O�o�Ŋ������ĉƒ���Ɏ�������ł���B�ǂ��ŒN���������Ă����������Ȃ��Ȃ̂ŁA���������O�o���l�����肢�������v�ƌĂт����Ă��܂��B�����p�������s�b�N�̊֘A�ł�15�l�̊������m�F����܂����B����́A���{�l�̋Ɩ��ϑ��̎��Ǝ�10�l�ƁA���f�B�A�W��1�l�A�O���l�̋��Z�W��2�l�A���f�B�A�W��1�l�A�{�����e�B�A1�l�ł��B����œs���Ŋ������m�F���ꂽ�̂�31��2262�l�ɂȂ�܂����B
����A22�����_�œ��@���Ă���l�́A�ߋ��ő��������O����肳���4�l������3968�l�ŁA�ő����X�V���܂����B�u���݊m�ۂ��Ă���a���ɐ�߂銄���v��66.5���ł��B�s�̊�ŏW�v����22�����_�̏d�ǂ̊��҂́A�O�����1�l������271�l�ŁA�d�NJ��җp�̕a���ɐ�߂銄����69.1���ƂȂ��Ă��܂��B�d�NJ��҂̔N��ʂ́A10�オ1�l�A20�オ3�l�A30�オ21�l�A40�オ43�l�A50�オ119�l�A60�オ55�l�A70�オ20�l�A80�オ9�l�ł��B���̂ق��A�z�e���Ȃǂŏh���×{���Ă���l��22�����_��1975�l�ŁA����܂łōł������Ȃ�܂����B�܂��A����ŗ×{���Ă���l��22�����_��2��4704�l�ŁA�ߋ��ő��������O�����1705�l���Ȃ��Ȃ�܂����B����×{�҂Ƃ͕ʂɁA�s�́A���@����̂��A�����h���{�݂ŗ×{����̂��Ȃǂ����̐l�̐������\���Ă��܂����A22�����_��1��4726�l�ƂȂ�A����܂łōł������Ȃ�܂����B
�܂��A�s�́A�������m�F���ꂽ30��ƁA60�ォ��80��̒j�����킹��8�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���̂���60��̒j����1�l��炵�ŁA�������m�F����Ď���ŗ×{���A�ی��������N�ώ@�����Ă��܂������A�A�����Ƃ�Ȃ��Ȃ������ߎ����K�₵���Ƃ���S���Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B��5�g�ɓ����āA�����A����×{���Ɏ��S�����l�́A�s�ɂ��܂��ƁA�����9�l���Ƃ������Ƃł��B�s�̒S���҂́u1�l��炵�ŗ×{���Ă���l�ɑ��ẮA����ďZ�މƑ���E��̓����Ȃǂ����܂߂ɘA�����Ƃ��ď��m�F���Ă��炦��Ƃ��肪�����v�ƌĂт����Ă��܂��B����œs���Ŋ������Ď��S�����l��2379�l�ɂȂ�܂����B
���ܗ֊֘A�{�݁A�R���i�a�@�ɓ]�p�@�p������A�s�������@8/22
�����s���V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ɔ�����Ò̐��̕N���ɑ��A�Վ���Î{�݂̐ݒu�Ɍ����������n�߂����Ƃ�21���A�W�҂ւ̎�ނŕ��������B�����ܗցE�p�������s�b�N�̋��Z���ȂNJ֘A�{�݂̓]�p�Ă����サ�Ă���B��Ì����̗��p���z�肳��Ă��Ȃ������̍\����X�^�b�t�̊m�ۂȂljۑ�������A������u���a�@�v�֓]�p���\���T�d�Ɍ��ɂ߂�B
�s��֘A�c�̂��ۗL�E�Ǘ�����ܗցE�p�������s�b�N�̋��Z���́A�����A�N�A�e�B�N�X�Z���^�[(�]����)�═����̐X�����X�|�[�c�v���U(���z�s)�ȂǓs���̍L�͈͂ɓ_�݂���B�~�}��Â̖ʂ��痘���̍����ꏊ�������A��ÊW�҂炩��Վ���Î{�݂Ƃ��Ă̎g�p�����߂鐺�����˂ďオ���Ă����B
�s�͌������}�����A24���ɊJ������p�������s�b�N��9��5���܂ōs���邽�߁A���Z����֘A�{�݂̓]�p�͑����Ă�����6���ȍ~�ƂȂ�B�W�@�ւƂ̒����������A�J�݂܂łɎ��Ԃ�v����\��������B
�܂��A���ꂼ��̋��Z���̓A�X���[�g��ϐ�҂�����Ɍ�������A�V�^�R���i�̈�Î{�݂Ƃ��Ďg�p����ꍇ�́A�����Ȋ�����ƍ��x�̈�Ðݔ����K�v�ƂȂ�B��t��Ō�t�瑽���̈�ÃX�^�b�t�̊m�ۂ��傫�ȉۑ肾�B
�����͂������C���h�R���̕ψي��u�f���^���v�̍L����ŐV�^�R���i�̊����g��͎��~�߂������炸�A�s���̎���×{�҂͑����������B����12���ɂ�2���l���A����×{���ɏǏ}���Ɉ������Ď��S����P�[�X���N���Ă���B
����×{�҂̋}���͑S���I�ȉۑ�ƂȂ��Ă���A�c�����v�����J������20���̋L�҉�ŁA�u�Վ��̈�Î{�݂̊m�ۂ��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝw�E���A�e�����̂ɑ��}�̎{�ݐ��������߂��B���{��t��̒���r�j���18���̋L�҉�ŁA�u��K�̓C�x���g����̈�قȂǂ�Վ��̈�Î{�݂Ƃ��Ċm�ۂ��邱�Ƃ�(�e�����̂�)��Ă���v�Əq�ׂ��B
�s�W�҂́u��Ò̐��̕N���Ɍ��O�̐����W�܂钆�ŁA�a���̊m�ۂ͋i�ق̖��ƂȂ��Ă���B������\����T�肽���v�Ƙb���Ă���B
�����������V�w���@��������g�q�ǂ��̊����h�Ɍ��O�@8/22
�����s��22���A�V���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂́A4392�l�Ɛ�T���j�����97�l�����A6���A����4000�l���܂����B�d�ǎ҂�271�l�A8�l�̎��S���m�F����Ă��܂��B���̂ق��A����܂łɔ��\����Ă��銴���Ґ��͐�t��1246�l�A�܂��O�d�Ɠޗǂʼnߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B�d�ǎ҂͌ߑO0�����_��1891�l�ƑO�̓����3�l�����A10���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�{�錧�ł̓��N�`���̋��������Ȃ��Ȃ�A�ꎞ���~����Ă����ڎ킪�ĊJ����܂����B
���s���N�����ǁE����K��Y�����F�u����܂ŎႢ���ɂ��҂������Ă������A���N�`���ڎ킪��̑傫�ȕ���ɂȂ�̂ŁA���АϋɓI�ɐڎ��i�߂Ē��������v
�����g���h���ɂ̓��N�`���̐ڎ�ɉ����A�l�̗����}���邱�Ƃ��L���ł����A1�C�ɂȂ�f�[�^������܂��B�g�ѓd�b�̈ʒu���𗘗p�����f�[�^�ł́A21���ߌ�3����̐l�o�͓����E�����5.8���̑����B�a�J�Z���^�[�X�A�V�h�ł������X���ɂ��邱�Ƃ�������܂����B�����s�łً͋}���Ԑ錾���ɂ���Ȃ���A�l�̗����}���ł��Ă���Ƃ͌�����ł��B
�S���K�͂ł̊����g��̉e���͂���ȂƂ���ɂ��B
���͍��A�ۈ�{�݂̋x�����}�����Ă��܂��B����5�����_�̑S���̕ۈ�{�݂̋x������108�J���B��4�g�̖�2�{�ɂ��Ȃ�܂��B
���w1�N��3�̕�e�F�u���̂��A�E���̕����R���i�̗z���������������B�A�������������A���͂���3��ځB�a�����Ē�����̂����肪�����̂ŁA���ʂɒʂ킹�Ă���v
�����J���Ȃɂ��܂��ƁA11������17����1�T�Ԃ�10�Ζ����̐V�K�����҂�7441�l�B�q�ǂ��͉ƒ���ł̊����������ƌ����Ă��܂����A���Ƃ̓N���X�^�[�����̉\�����w�E���܂��B
���M��w��������w�E���ѓЂĂ����F�u�f���^���̊����͂��������Ƃ�10�Ζ����̎q�ǂ��ɂ��������L�����Ă���v���B(�q�ǂ���)�}�X�N���O���Ă��܂��Ƃ��A�ǂ����Ă������キ�Ȃ��Ă��܂��B�S�̂Ƃ��Ċ����҂����炵�Ă����Ȃ��ƃN���X�^�[���N����\���͔ے�ł��Ȃ��v
���k�C����529�l�����m�F �ˑR�����g�呱���@8/22
�k�C����22���A�V���ɔ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����m�F��529�l�ł����B1���̊����m�F��500�l����̂�5���A���ŁA�ˑR�Ƃ��Ċ����g�傪�����Ă��܂��B
�����Ŋ������m�F���ꂽ529�l�̓���́A�D�y�s�ōėz����1�l���܂�293�l�A����s��43�l�A���َs��16�l�A���M�s��12�l�A�Ύ�n���Ə\���n���ł��ꂼ��38�l�A�_�U�n����22�l�A�I�z�[�c�N�n����14�l�A��m�n���Ƌ��H�n���ł��ꂼ��9�l�A�����n����8�l�A���n����6�l�A��u�n����5�l�A�n���n����4�l�A�����n����3�l�A�@�J�n����2�l�A����ɁA�����u���̑��v�Ƃ��Ĕ��\�����A���O��7�l�ł��B
1���̊����m�F��500�l����̂�5���A���ŁA�O�̏T�̓����j�����163�l�����Ă��܂��B
�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂́A�����S�̂�67.3�l�A�D�y�s��99.5�l�ƁA�s���{���̊������������̃X�e�[�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ��ƂȂ��Ă���10���l������25�l��傫�������Ă��܂��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�������m�F���ꂽ529�l�̂�����������7�l�������āA�����ǂ�3�l�ł��̂ق��͌y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
�܂�529�l�̂���218�l�͊����o�H���킩���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
��������4049���ł����B
����A�ψكE�C���X�̃f���^���ɂ��āA�V���ɓ���33�l�A���M�s��9�l�̂��킹��42�l���������Ă���^�������邱�Ƃ�������܂����B
�����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�3��3154�l���܂ށA�̂�5��3120�l�ƂȂ�A���S�����̂�1435�l�A���Â��I�����l�͂̂�4��6786�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����̎w�W�ł݂銴����
21�����_�̓����̊������A���{�̕��ȉ�������̎w�W�����ƂɌ��Ă����܂��B�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂�22�����_�̐����ł��B
�a���g�p�� / �܂���Â̂Ђ�����ł��B�a���g�p���́A�X�e�[�W3��20���ȏ�A�ł��[���ȏ������X�e�[�W4��50���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������40�D4���ƂȂ��Ă��܂��B
���@�� / ���@���̓X�e�[�W3��40���ȉ��A�X�e�[�W4��25���ȉ����ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������17�D1���ƂȂ��Ă��܂��B
�d�ǎҕa���g�p�� / �d�ǎ҂̕a���g�p���̓X�e�[�W3��20���ȏ�A�X�e�[�W4��50���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������9�D8���ƂȂ��Ă��܂��B
�×{�Ґ� / �l��10���l������̗×{�Ґ��̓X�e�[�W3��20�l�ȏ�A�X�e�[�W4��30�l�ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������90�D1�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����z���� / ����1�T�Ԃ̂o�b�q�����Ȃǂ̗z�����́A�X�e�[�W3��5���ȏ�A�X�e�[�W4��10���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������10�D5���ƂȂ��Ă��܂��B
�V�K�����Ґ� / �l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂́A�X�e�[�W3��15�l�ȏ�A�X�e�[�W4��25�l�ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A22�����_�ŁA������67�D3�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����o�H�s���҂̊��� / �����o�H���s���Ȑl�̊����́A�X�e�[�W3�A�X�e�[�W4�Ƃ���50�����ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������42�D9���ƂȂ��Ă��܂��B
�����1696�l�����A���N�`���ڎ��50�l���@�w�Z�̕����Ŋg��@40�㎀�S�@8/22
��ʌ��Ȃǂ�22���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă���40��j��1�l�����S�A�V����1696�l�̊������m�F�����Ɣ��\�����B20���A���Ő�l�������A54���Ԃ�ɑO�T�̓����j���̊����Ґ�����������B�V�K�����҂̓���͌����\��994�l�A�������s336�l�A����s190�l�A��z�s76�l�A�z�J�s100�l�B
����܂łɊm�F���ꂽ�����҂�8��8390�l(�`���[�^�[�A���Ҋ܂�)�A���҂�869�l(22���ߌ�6������)�B
22���ߌ�9�����_�̏d�ǎ҂�155�l�A�����҂̓��@��1283�l�A�h���×{668�l�A����×{2��758�l�B�މ@�E�×{�I����5��8775�l�B
���ɂ��ƁA���NJ��ł́A�O���ߌ㕪���܂�22���ɏڍׂ����������͖̂��A�w���`90��̒j��1101�l�B�����̊w�Z�ł͉^���n�̕����ɏ�������10��j���w��5�l���������A�v27�l�ɂȂ����B�����̏�Q�Ҏ{�݂ł�10�`60��̒j��15�l���������A�v34�l�ɂȂ����B��H�֘A�ł́A8����{�ɗF�l�ƊC����������20��j��1�l���܂ށA���A�w���`60��j��18�l�����������Ƃ݂���B���N�`���ڎ�ς݂�20�`80��j��47�l�����������B
�������s�ɂ��ƁA���������������͖̂��A�w���`80��̒j��336�l�B�N���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă��闤�㎩�q����{���Ԓn�ŐV���ɐE��1�l�̊������������v52�l�A��{�o���a�@�ł��V���Ɋ���1�l�̊������������v33�l�ƂȂ����B�s���̎��������{�݂ɒʂ�����8�l�̗z�����m�F���ꂽ�B
����s�ɂ��ƁA���������������͖̂��A�w���`80���190�l�B�������N�`���ڎ�ς݂�3�l�����������B
��z�s�ɂ��ƁA���������������̂�10�Ζ����`80��̒j��76�l�B����12�g27�l�͐e�q�A�v�w��Ƒ��B�s���ݏZ��68�l�̂���35�l�͉Ƒ���E��A�w�Z�Ȃǂɗz���҂������B
�z�J�s�ɂ��ƁA40��̒j��1�l�����S�B���������������͖̂��A�w���`70��̒j��100�l�B����20�㖳�E�̒j���������ǂŗ×{�撲�����B
���x�R�A105�l�����@1�l���S�@5���A��100�l���@�@8/22
�x�R����22���A�����ŐV�^�R���i�E�C���X�̊�����105�l���m�F�����Ɣ��\�����B1�l��21���ɖS���Ȃ����Ɩ��炩�ɂ����B�V�K�����҂�100�l����̂́A5���A���B�����̎��҂͌v39�l�A�����҂̗v��3736�l�ƂȂ����B
���Ɍ��\���ꂽ�����s���̍���Ҏ{�݂̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�ŐV����60��`90�Έȏ��7�l�̗z�����V���ɔ������A�����҂͌v14�l�Ɗg�債���B
�V���Ɋ��������̂́A�x�R�A�����A�ː��A���ÁA����A����A���R�A��s�A�����̊e�s���Ɠ����s�ݏZ��10�Ζ����`90�Έȏ�̒j���B�N��ʂł�20�オ29�l�ƍł������A������10��ȉ���21�l�A40���18�l�A30���12�l�ȂǂƑ������B�Ǐ�͒����ǂ�1�l�A�y�ǂ�91�l�A���Ǐ�13�l�B
���̂ق��A�V���Ƀf���^���̋^��������ψي���52�l���猩�������B
22�����݁A���@�Ґ���260�l(�O����3�l��)�A�����d�ǎ҂�9�l(��1�l��)�ƂȂ��Ă���B
�����Ԓn�⒆�������s��̃N���X�^�[�g��c �ΐ�ŐV�K������66�l�@8/22
�ΐ쌧�ł�22���A�V����66�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������܂����B
�ΐ쌧�ɂ��܂��ƁA22���ߑO10���܂ł�466���̌������s���A���̂���66�l���z���ł����B
����͌o�H�s����24�l�A�Z���ڐG�ғ���39�l�ŁA�N���X�^�[�W�ł͋��Ԓn�֘A�A����s���������s��֘A�A�E��֘A�����ꂼ��1�l�ł����B
����Ō����̊����҂�6764�l�ƂȂ�܂����B
������276�l�����A����×{74�l�@�E��N���X�^�[54�l�Ɋg��@8/22
���Ɗs��22���A����33�s���ȂǂŌv276�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B�V�K�����Ґ���6���Ԃ��300�l�����������A���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ŁA�����Ґ��͗v1��2723�l�B�܂��A21������n�܂����d�lj����X�N���Ⴂ��N�w�Ŗ��Ǐ��y�ǂ̊��҂�Ώۂɂ�������×{�́A�������_��74�l�Ɣ��\�����B
�����̍����̊����Ґ�(���\���x�[�X)��22�����_��3135�l�ŁA��4�g��5����2860�l���Č��ʂōő��ƂȂ����B21�����_�̕a���g�p���͑O����1�E4�|�C���g����58�E0���B�d�ǎ҂�4�l�̂܂܁B
���ɂ��ƁA����×{�҂�22�����_�ł͂���ɑ�����100�l�K�͂ƂȂ錩���݁B�×{�҂̔����͊s�ŁA���Z�⒆�Z�A���Z����̋��Z�҂�����B����×{���ɑ̒��������������߁A1�l���a�@�ɔ������ꂽ�B
�V���Ɋm�F�����N���X�^�[(�����ҏW�c)��3���B���R�s�̐ڑ҂����H�X�ŏ]�ƈ��◘�p�҂�v10�l�̊����������B���ΌS��Ӓ��̉Ƒ��𒆐S�ɁA�H����̎Q���҂�O���Ђ�8�l�̊��������������B�܂��������s�̃J���I�P�̗��p�҂�6�l�̊������m�F���ꂽ�B
�g�債���N���X�^�[��10���B�{���s�̐E��֘A�̃N���X�^�[�́A�ʂ̊s�̉Ƒ��֘A�̃N���X�^�[�Ɗ֘A���Ă��邱�Ƃ����������B�K�͂�54�l�Ɋg�債�A���ɂ��Ɗ����҂͊O���Ђ����S�Ƃ����B
�b�ߎs�̉Ƒ���E��֘A�ƁA�o�[�x�L���[�����Ă������Z���Ύs�␐��s�Ȃǐe���ɂ��N���X�^�[�́A�V���Ȋ����҂��m�F���ꂸ�I�������B
�������g�呱���@�l���s��94�l�@�V�^�R���i 8/22
�l���s�s��8��22���A���s���ɏZ��10�Ζ�������70��̒j��94�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1���̊����҂͑O����101�l�Ɏ����ߋ�2�Ԗڂɑ��������Ґ��ŁA���s���̊����҂͉���2097�l�ƂȂ����B
���\�ɂ��ƁA�V�K�����҂̔N��ʓ���́A10�Ζ���6�l�A10��13�l�A20��26�l�A30��19�l�A40��18�l�A50��9�l�A60��2�l�A70��1�l�B20�ォ��40��̊����҂��S�̂̔����ȏ���߁A28�l�������Ƒ��A9�l���Z���ڐG�҂������B
�s����8��16������22���܂�1�T�Ԃ̊����҂͌v501�l�B�O�T�䑝������262���A�l��10���l������̐V�K�����Ґ���161.6�l�ŁA���̎w�W�Łu�X�e�[�W�W�v�ɑ�������u���������i�K�v������25�l�ȏ��6�{������A�ł����������ƂȂ����B
���ߋ�3�Ԗڂ̑����@��Q�Ҏ{�݃N���X�^�[�g��@���s�̐V�^�R���i�@8/22
���s�{�Ƌ��s�s��22���A�j���v542�l���V���ɐV�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1��������̐V�K�����҂�500�l����̂�3���A���ŁA�ߋ�3�Ԗڂ̑����������B�{���̊����҂͌v2��5788�l�ƂȂ����B
�{���\����10�Ζ����`80���194�l�B�������������y�ǂ����Ǐ�B�����o�H�s����145�l�B���Z�n�ʂ͉F���s29�l�A�T���s21�l�A��z�s�Ɣ����s�Ŋe18�l�A���ߎs15�l�A���c�ӎs�Ƌ��s�s�Ŋe12�l�A�������s11�l�A�ؒÐ�s�A���O��s�A�v��R���Ŋe9�l�B�����s7�l�A��O�s5�l�A���m�R�s�A�{�Îs�A���ؒ��Ŋe3�l�A��R�蒬�Ƌ��O�g���Ŋe2�l�A�^�Ӗ쒬�Ɠ�R�鑺�e1�l�A���{4�l�B�N���X�^�[(�����ҏW�c)�W�́A��Q�Ҏ{�݂����ڂ̊w��(��O�s)��1�l�����v30�l�ƂȂ����B
���s�s���\���́A348�l�������B
���u�����_�f�v�v������Ȃ��I�R���i�Ŏ��v���܂�20�{���Y�ł��ǂ������@8/22
�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɂ�鎩��×{���҂̋}���ɔ����A�������̎_�f�O�a�x(SpO2)�𑪒肷��p���X�I�L�V���[�^�[�̋������ǂ����Ȃ����ԂƂȂ��Ă���B�R�j�J�~�m���^�A���r���f�B�J��(�����s�]�ː��)�A���{��������(�Q�n���a��s)�Ȃǂ́A���Y��g�̂ɑΉ�������̂́A�O��̂Ȃ����v�}�������܂ő������ǂݐꂸ�A����Ȃ�ݔ���������ɂ͓�̑���ł�����B�e�ЂƂ�������f�ɔ����Ă���B
�R�j�J�~�m���^��4������i�K�I�ɐ��Y�\�͂����߁A6������̓R���i�БO�̖�20�{�ƂȂ錎�Y������Y���Ă���B8����{�ɐ����䃌�x���̒����������̂��炠��A�ɂ��قƂ�ǂȂ��ƂȂ����B9�����������������x�̐��Y���p������\�肾�B�H��ł͊�����̍H����24���ԑ̐�������Ă���B
�����V�F�A��ʂ̓��{��������͐ݔ�������������A�{�ЍH��̐��Y�\�͂�2020�N���1�E5�{�܂ō��߂��B�R���i�БO��1�E5�{���x�̒����������Ԃ����A�}�C�R�����͂��߂Ƃ��锼���̂��s�����A�ėp�i�ő�ւ��Ă���B�����������㏸�������A���i�͐����u�����B
�I�������w���X�P�A(���s�{�����s)�A���r���f�B�J���͒������[�J�[��OEM(�����u�����h)��������B�I�������w���X�P�A�ł́A4������v����2�{�̒����������Ă���B���r���f�B�J����8���ȍ~�A�R���i�БO�ɔ�ׂĒ�������5�{�ɋ}���B1�E5�\2�J�������x�̍ɂ��m�ۂ��Ă������A�ɂ��قƂ�ǂȂ��ƂȂ����B
�p���X�I�L�V���[�^�[�̊m�ۂ�i�߂铌���s�͖�7����ۗL���A���̂������ɖ�4�������s�����Ȃǂɑ݂��o���Ă���B�n�c��͖�900����m�ہB��400����Z���ɑ݂��o���Ă���A������m�ۂ𑱂���\�肾�B
�����J���Ȃɂ��ƁA����×{���҂�11���̒i�K�őS���ɖ�7��4000�l����Ƃ��Ă���B�V�K�����҂̃s�[�N�͂��܂������Ă��炸�A������p���X�I�L�V���[�^�[�̎��v�����܂邱�Ƃ��\�z�����B
�e�ЂƂ��ɂ��Ȃ����v�ɑΉ�������Ă��Ȃ������A���v�̐�s�����ǂ߂Ȃ����Ƃ┼���̕s���Ȃǂ���A����Ȃ�ݔ��̑����A�����ɂ͏��ɓI�Ȏp���B�i�����͍�����p�����������B
���u�ً}���Ԑ錾�v�g��㏉�̓y�j 21���̐l�o �����̒n�_�Ō��� �@8/22
�V�^�R���i��Ƃ��ċً}���Ԑ錾�̑Ώےn�悪13�s�{���Ɋg�傳��ď��߂Ă̓y�j���ƂȂ���21���̐l�o�́A��������ȂǑ����̒n�_�őO��4�T�Ԃ̓y���j���̕��ς�茸�����܂����B
NHK��IT�֘A��Ƃ́uAgoop�v���A���p�҂̋��Čl�����肳��Ȃ��`�ŏW�߂��g�ѓd�b�̈ʒu���̃f�[�^���g���āA��Ȓn�_�̐l�̐��͂��܂����B
�����������Ԃ́A�������ߑO6������ߌ�6���܂ŁA��Ԃ��ߌ�6�����痂���̌ߑO0���܂łł��B
���̂����A����12���܂ŋً}���Ԑ錾���������ꂽ��������Ȃ�6�s�{����21���y�j���̐l�o�́A�O��4�T�Ԃ̓y���j���̕��ςƔ�ׂČ��������n�_�������Ȃ�܂����B
�����w�t�߂͓�����8�������A��Ԃ�9������
�a�J�X�N�����u�������_�t�߂͓�����10�������A��Ԃ�8���̌����ł����B
��{�w�t�߂ł͓�����8�������A��Ԃ�18������
��t�w�t�߂͓�����8�������A��Ԃ�5������
���l�w�t�߂͓�����11�������A��Ԃ�15������
���~�c�w�t�߂͓�����14�������A��Ԃ�13������
�ߔe�s�̌����O�w�t�߂œ�����18�������A��Ԃ�6���̑����ł����B
�܂��A20������錾�̑Ώےn��ɒlj����ꂽ7�{���̐l�o�͂�������������܂����B
���ˉw�t�߂͓�����48�������A��Ԃ�62������
�F�s�{�w�t�߂͓�����8�������A��Ԃ�10������
�O���w�t�߂͓�����37�������A��Ԃ�46������
�É��w�t�߂͓�����20�������A��Ԃ�31������
���s�w�t�߂͓�����22�������A��Ԃ�25������
�_�ˎs�̎O�m�{�w�t�߂͓�����21�������A��Ԃ�12������
�����w�t�߂͓�����16�������A��Ԃ�26���̌����ł����B
�������g��̌����ł���҂ɐl�C�̃E���^���}�X�N�@8/22
�����s�Ȃ�6�s�{���ɉ����āA����20������ً͋}���Ԑ錾�Ώےn�悪13�s�{���Ɋg�傳�ꂽ�B�錾���ł������������Ȃ���ܔg�̓����Ƃ��āA��҂̊����Ґ����������Ƃ���������B�ŋ߂̓����s�̊����҂ɂ����ẮA30��ȉ���7���ɂ�������B��҂̊����g��ɂ́A�l�X�ȗ��R�����邾�낤���A����1�Ɏ�҂ɐl�C�̃}�X�N����������Ƃ�����B
�u�E���^���}�X�N�𒅗p����l�������Ƃ������Ƃ��A��҂Ɋ����҂�������̗��R�ɂȂ��Ă���\���������ł��v
�������̂́A�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�E�C���X�Z���^�[���̐����G�ꎁ�ł���B
�u��N12���A�����w�������̃X�[�p�[�R���s���[�^�[�w�x�x�x�ɂ��}�X�N�̑f�ނ��Ƃɔh�~���ʂ̈Ⴂ���r�����V�~�����[�V���������\����܂����B����ɂ���āA�E���^���}�X�N�́A�s�D�z�}�X�N�ɔ�ׂĔh�~���ʂ��ɂ߂ĒႢ���Ƃ�������܂����B�����ʼn�X�́A���ۂɎ�������Ƃǂ̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�̂���m�邽�߂ɁA�s�̂���Ă���l�X�ȑf�ނ̃}�X�N���g���A�����������邩������Ȃ��z�����ݗ��ɍi���Čv�����܂����v(��)
�������̎����ł��A�E���^���}�X�N�̑f�ނł���|���E���^���́A���q�̏������\���ɂ߂ĒႢ�Ƃ������ʂ�����ꂽ�B�u�x�x�v�̃V�~�����[�V���������A�s�D�z�Ƃ̍��͖��炩�ɑ傫�����Ƃ����������̂��B
�u�s�D�z�}�X�N�́A5㎛(�}�C�N�����[�g��)�ȉ��̗��q�ŏ�������99.1���ł��B����A�|���E���^���͏�������1���ȉ��B�܂�A�E���^���}�X�N�͂قƂ�nj��ʂ������̂ł��B�������A�E���^���}�X�N�̊����h�~���ʂ��s�\���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă�����A�X���ł̓E���^���}�X�N�𒅗p���Ă���l������������܂���B���ɎႢ����ł́A�j����킸�E���^���}�X�N�𒅂��Ă���l�������Ƃ�����ۂ�����܂��v(��)
�����Ґ��͍ő����X�V�������Ă��錻�݂ł��A���͕̏ς��Ȃ��B�����������A����18���ɂ́A���������^���҂�1�l�Ƃ��āu�ŐV�̒m���Ɋ�Â����R���i�����Ǒ�����߂�Ȋw�҂ً̋}�����v�Ƃ�������t���[�Ȃǂɏo�����B
�u��ܔg�̊����g��̂��Ȃ��ɂ����āA���{��ꕔ�̈�w�W�҂���́A�w�����ł肪�Ȃ��x�ƁA����ΐV�^�R���i�ɔ������グ�����̂悤�ȑΉ��������܂��B�����������Ă���Ȃ��Ƃ͖����A�������炱���ŐV�̒m���Ɋ�Â���������K�v������Ǝv���̂ł��B����1���}�X�N�̐��\�ɂ��Ċ�������A�|���E���^���Ȃǐ��\���Ⴂ�}�X�N�ɂ��Ă̒��ӂ𐭕{�������ɌĂт����邱�Ƃ��ƍl���Ă��܂��B�����g�厞�̃h�C�c�ł́A�����̏���ʋ@�֓��ł́A���ȏ�̐��\�����}�X�N�̒��p���`���t�����A�E���^���}�X�N�Ȃǂ̒��p�͔����t���ŋ֎~����Ă��܂��B���{�ł́A�}�X�N�̐��\�ɂ��Đ������Ăт������Ȃ���Ă��炸�A���ꂪ���ɎႢ����ł̊����g��̈���ɂȂ��Ă���\���������ł��v(��)
�ǂ����ăE���^���}�X�N�͎�҂𒆐S�ɍ������l�C������̂��낤���B
��N12���A�J�l�{�E���ϕi(�ԉ��������)�́uKATE�v�́A�|���G�X�e���ƃ|���E���^�����ŁA�J��Ԃ�����Ďg����u����V���G�b�g�}�X�N�v�������B����21���ɂ́A���V���[�Y��3�e�̃}�X�N(2������E�ō�990�~)�������B���ɃC���X�^�O�����ł́uKATE�}�X�N���r���[�v���������e����Ă���A���ɎႢ���ォ��l�C���������Ƃ�������B
�u��1�e��SNS�ő傫�Șb��ɂȂ�A���������܂����B���ϕi�ƃ}�X�N�̊|�����킹���y���ނƂ�������┧�𖾂邭������J���[�A������ʂ̂���`�Ⴂ�����𒆐S�Ɏx�����ꂽ�̂��Ǝv���܂��B���������3�e�̏��i�́A�u���b�N�A���x���_�[�A�s���N�A�u���E����4�F�ŁA���Ƀu���b�N�͒j������������l�C���Ă��܂��v(�ԉ�������ЁEKATE�S����)
���������}�X�N�̑f�ނ́A�|���G�X�e��90���A�|���E���^��10���̕z���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����h�~���ʂɕs���̐����オ���Ă���B���̓_�ɂ��ẮA
�u�q�}�X�N�͊���(�N��)�����S�ɖh�����̂ł͂���܂���B�r�Ƃ������ӕ\�L���p�b�P�[�W�̕\�ʂɋL�ڂ��Ă���܂��B���q���܂���s���̐������Ȃ��炸�����Ă���̂ŁA�z�[���y�[�W��ɂ́A�q�E�C���X�h�~�̃t�B���^�[�͎g�p���Ă��܂���B�r�Ƃ����������V���Ɍf�ڂ��邱�ƂɂȂ�܂����v(��)
��̐������́A�u��ʂɃE���^���}�X�N�́A�t���S�n���_�炩���A�������₷���̂Œ����Ă��Ċy�ł��B�ł��A�������₷���Ƃ������Ƃ́A�E�C���X���ȒP�ɒʂ��Ă��܂��\���������Ƃ������ƂȂ̂ł��B�s�̂̃}�X�N�ɂ́A���I�ɖ��m�ȕi������݂����Ă��Ȃ��Ƃ������͂���܂����A���߂ĕs�D�z�̃}�X�N�𒅗p���܂��傤�B�}�X�N���Ԓ�����̂͋ꂵ�����̂ł�����A����ɒN�����Ȃ�����g�C���̒��ȂǂŊO���ċx�e��������Ǝv���܂��B�ǂ����Ă��E���^���}�X�N�𒅂������Ƃ������Ƃł���A�s�D�z�̃}�X�N�̏ォ�牟����������Ƃ��ďd�˕t������̂��ǂ��Ǝv���܂��v
�@ |
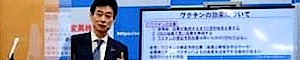 |


 �@
�@ |
��20��ȉ��̊���44�E5���@8���̕��������@�A�Ȃ��H�ő����@8/23
�������͌�����94�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ��22���A���\�����B94�l�̗z����21���܂łɔ��������B�����̐V�K�����Ґ��̗v��21�����_��2146�l�B���̂���20��ȉ��̊����Ґ���956�l��44�E5�����߂��B�u��4�g�v�̃s�[�N�ƂȂ���4����23�E6���ɔ�ׁA20�E9�|�C���g���B�w����̋A�ȁA�Ƒ��E�e�ʊԂł̉�H�Ȃǂɂ���N�w�ւ̊����������Ă���B
�N��ʂ̊����Ґ��́y�O���t�z�̒ʂ�B����܂Ō��ʂ̊����Ґ����ő�������5����20��ȉ��̊����Ґ���278�l(23�E6��)�A30��ȉ���429�l(36�E4��)�������B����21�����_��30��ȉ���1294�l(60�E3��)�ŁA�S�̂�6�����߂��B
���͊����͂������ψي��u�f���^���v���S���Ŗ҈Ђ�U�邤���A�����I�Ȋ����g�傪������s���Ȃǂ��猧�����܂����ŋA�Ȃ����l���犴�����L�������̂��v���̈�Ƃ݂Ă���B
�A�ȂȂǂ̉e���͌��O���Z�҂̌����ł̊��������ɂ��Ȃ����Ă���B���O���Z�҂̊����͒���1�J��(7��22���`8��21��)��80�l�ɏ�����B���O�����җv126�l��63�E5�����߂��B����1�J����80�l��N��ʂł݂�ƁA20�オ36�l�ƍł������A10�オ17�l�Ƒ������B
���ɂ��ƁA���O���猧���ɋA�Ȍ�A�F�l�Ƃ̉�H��o�[�x�L���[���s���������g�債�����Ⴊ�������B����ɁA���~����ȂǂŏW�܂����e�ʂƉ�H���ďW�c�������A���̌�ɉƑ��A�m�l�A�E��Ɋ����g�債���P�[�X���������Ƃ����B
���̂悤�ȏȂǂ��A�����s��20��̃��N�`���ڎ��D�悵�čs���A��N�w�̊����g��h�~�ɓw�߂�B�s�ɂ��ƁA�D��ڎ�̑Ώۂ�19����29�̎s����2��8100�l�B13������\����J�n���A22���܂łɖ�3600�l��1��ځA�܂���2��ڂ̐ڎ�\��������B�����A�c���2��4500�l�͗\�Ă��Ȃ����B
���͎�҂��Ӌ`�𗝉�������Őڎ�ɗՂ߂�悤�A������𗬃T�C�g(�r�m�r)�Ȃǂ����p���ă��N�`���̐��������ȂǂM����l�����B���V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ��{���̒S���҂́u������₷����M�ɓw�߂�B�����̌����Ƀ��N�`����ڎ킵�Ă��炢�����v�Ƙb�����B
�����茧���R���i����68�l�@���ẪN���X�^�[�g�� 8/23
���茧�Ȃǂ�22���A����6�s5���Ōv68�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����A�Ɣ��\�����B���̂����A23�l�͊����o�H���s���B���ގ��Ò��̗V���{�݂Ŕ��������N���X�^�[(�����ҏW�c)�́A�V���ɗ��p�҂̊�����������A�g�債���B
���Ò��̗V���{�݂̃N���X�^�[�֘A�ł́A�V���ɗ��p��4�l�̊����������B�����҂͏]�ƈ�1�l�Ɨ��p��26�l�̌v27�l�ƂȂ����B���ɂ��ƁA�J���I�P��r�����[�h�Ȃǂ��y���߂�{�݂ŁA����o�^���̂��ߗ��p�҂��c���ł��Ă���Ƃ��āA�{�ݖ��͌��\���Ă��Ȃ��B
����s�̐V�K�����҂�25�l�B����1�l�́A�����ǂ�����ǂɋΖ�����60�㏗���E���B���ɂ��ƁA�����Ɛڂ���Ɩ��ɂ͏]�����Ă��Ȃ��B���O�K��⌧�O�̐l�Ƃ̐ڐG�A��H�͂Ȃ������B����21���ɂ����ǂ̌��E��1�l�̊��������\�������A�֘A�͂Ȃ��Ƃ����B�ڐG�҂Ȃǂ����B
�����ێs��18�l�B���̂����s�s����������50�㏗���E���́A8��5�`7���Ɍ��O�ɏo���B�Ɩ��ŐڐG�����s���͓��肵�A���ɒ��ɂ̏��ł��ς܂����B
���̂ق��A���x�͐V��ܓ�����30��j���x�@���̊����\�B���M�̏Ǐ���A���ǂ���20���ȍ~�A�����╔�O�҂Ƃ̋Ɩ���ł̐ڐG�͊m�F����Ă��Ȃ��Ƃ����B
���ً}���ԉ��̓����ܗւ̓R���i�g������������̂��|�@8/23
�ً}���Ԑ錾���ł̓����ܗւ�������A�ً}���Ԃ͈̔͂��g��E��������钆�Ńp�������s�b�N��24���ɊJ������B���`�̎́u�ܗւ������g��ɂȂ����Ă���Ƃ̍l�����͂��Ă��Ȃ��v�Ƃ��Ă�����̂́A���Ƃ̊Ԃł͌���������Ă���B�����ܗցE�p�������s�b�N�g�D�ψ�����\�������v�ɂ��ƁA���W�҂ŐV�^�R���i�E�C���X�����ǂւ̊������m�F���ꂽ�̂�7��1���ȍ~����8��22���܂ł�547�l�ŁA���̂����A�I�葺�Ŋm�F���ꂽ�̂�36�l�������B�p�������s�b�N�̊W�҂�8��12���ȍ~��30�l�̊����������B�z���҂̑唼�͍����ݏZ�҂ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�g�D�ςŊ����Ǒ�ɓ�������Ƃ�̉~���c�ō����߂鉪���M�F�E���s���N���S���������̓u���[���o�[�O�̎�ނɁu�W�҂̐������璼�ډe�����y�ڂ��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������v�Ƃ�����ŁA�قږ��ϋq�Ȃ�����N���X�^�[(�W�c����)���������ɑ����J�Âł������Ƃ́u��̐����ƌ����ėǂ��v�Ƒ��������B����ŁA���̊J�Â��ԐړI�ɉe�����y�ڂ��A�l�X�̈ӎ��̒o�݂ɂȂ������Ƃ̐����������B�R���i�����ȉ�̔��g�Ή�́A�ܗւ̊����g��ւ̉e����ے肵�����ʁA�u�l���Ƃ����Ӗ��ŁA�ܗւ̊J�Â��l�X�̈ӎ��ɗ^�����e���̋c�_�ł����A�������͂������Ǝv���v�Əq�ׂ��B
�����s�̊����Ґ��͌ܗ֊J�ÑO���瑝�����Ă���A���{�͓s�ɑ�4��ڂً̋}���Ԑ錾��7��12���ɔ��߂��Ă����B�ܗւ��J������23���̒��O�ɂ́A�s���̐V�K�����Ґ���1����2000�l�߂��ɒB�����B����ɁA8���ȍ~�͊����͂̋����f���^�ψي��̊������}�g�債�����Ƃ�����A�����ł�1���̐V�K�����Ґ���5000�l������������B�k����w�̒��R�N�v���C����(�E�C���X��������w)�́A�u��Ԃ̌����͌ܗ֑O�̘A�x�Ől�X�����l���ł��������ɏo�Ă������ƁB�������犴�����������Ă���Ɍܗւ��ւ��|���Ċ����������v�ƐU��Ԃ�B�u���l���Ȃ���ܗւ����Ƃ����̂́A�_���I�ɔj�]���Ă���v�Ǝw�E�����B�g�D�ω~���c�̉��������u�w�ܗւ���Ă���̂ɉ������ǂ����Ď�����ł͂����Ȃ��x�Ƃ����^��͂�������������Ȃ��v�ƔF�߁A�ϐ킵�����C�������������錜�O�������āu���Z��̂��ɍs������A���j�������g�Ŏʐ^���B������A���X�N�̍����s����U���Ă��܂�����������Ȃ��v�Əq�ׂ��B����ł��������́A�����ǂ��嗬�s���钆�ŊJ�Â������߂Ă̌ܗ֑��Ƃ��āA�I���^�c�W�҂��u������o�u�������̗̍p�ȂǁA�u�㐢�Ɏc�����̂͏o�����v�ƌ�����B
������w�̓�������C�u�t�ƒ��c�חS�y�����͌ܗւɂ�鍑�������ւ̉e�����J��O�ɕ��͂��Ă���A�ܗ֊W�̓����҂ɂ�钼�ړI�ȍ����̈���̐V�K�����Ґ��ւ̉e����15�l���x���Ǝ��Z���Ă����B���c���́A���W�҂̎��ۂ̊����Ґ���1�����ςŖ�12�l�ł���A���͒ʂ�u���ډe���͂�͂����I�������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ�������ŁA�ܗւ��Ȃ������ꍇ�Ƃ̔�r���K�v�ɂȂ邽�߁A�ԐړI�ȉe�����u��ʉ�����͓̂���v�Əq�ׂ��B�W���[�W�A�B����w�̃z���[�E�E�B���L���y����(�w���X�E�R�~���j�P�[�V����)�́A�u��N�ܗւ��������ꂽ�̂́A�J�Â����S�łȂ��Ɣ��f���ꂽ���炾�B���N�̊J�ẤA�l�X�ɂ������S���ƌ������b�Z�[�W�𑗂��Ă��邱�ƂɂȂ�v�Ƃ�����ŁA�R���i�̋��Ђւ̍l�����ɉe����^���A�s�������̕K�v���ɂ��Ắu�p����ς��Ă��܂��\��������v�Ǝw�E����B�ԓx�̕ω��͍s���⊴���ɂ��e����^����B���c���炪�ً}���Ԑ錾�̍ĉ��������܂���17���ɍs�����ŐV�̃V�~�����[�V�����ł́A�y�ϓI�ȉ���ł������͂������f���^���ɑ��錾���Ԓ���1���̐V�K�����Ґ��͑傫������Ȃ��Ǝ��Z�����B���c���͍���A�ً}���Ԑ錾���H�ɂ���������������Ɖ��肵���ꍇ�A�~�ɂ́u�����傫�Ȋ����̔g������\���������v�Ǝw�E�����B
�����{�̈�ÃV�X�e��������c�~�}�ԌĂ�ł��d�ǎ҂�63���͕a�@�s�����@8/23
���{�̐V�^�R���i�����҂�����܂łōł������Ă��钆�A���{�̈�ÃV�X�e��������ɑς����ꂸ�ɕ�����ƌ��O�̐����オ���Ă���B�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ��������̂ɕa���s���Ŏ���×{���銴���҂�10���l�ɔ���A�a�@�Ŏ��Â���ꂸ�Ɏ���Ŏ��S���銴���҂����o���Ă���B�V�^�R���i�Ɋ��������D�w�̓��@�悪������Ȃ��܂���ő��Y���A�V���������S����Ƃ������̂��N�����B��Ð��Ƃ̊Ԃł́u���̏�Ԃ������Έ�Õ�����Ĉ�Ôj��Ɏ��邾�낤�v�Ƃ̎w�E������B���{�Љ�ł́u���{�̐V�^�R���i�̏͊��ɐ���s�\�̏�ԂɊׂ����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����s�����L�����Ă���B
NHK�ȂǓ��{�̃��f�B�A�ɂ��ƁA21���̓��{�̐V�^�R���i�V�K�����Ґ���2��5292�l�Ɗm�F���ꂽ�Ƃ����B�ߋ��ő������ҋL�^���X�V�����O��(2��5871�l)�ɑ����A����A���Ŗ�2��5000�l���V���Ɋ��������Ƃ������Ƃ��B�ŋ�7���Ԃ̕��ψ���V�K�����Ґ���2��1865�l�ŁA�����ܗ֊J�����O�A�����Ɖ���ɋً}���Ԑ錾���o������(7��12�|18���A2988�l)��7�{�ɑ������B
�����҂������I�ɑ������A�u��Õ���v��������������B�����J���Ȃ́A�Ǐ[���łȂ��V�^�R���i�����҂͎���ɂƂǂ܂�u����×{�v�������Ƃ��Ă��邪�A���̎���×{�Ґ���10���l�ɒB���Ă���B�d�ǎ҂�21����1888�l�ƏW�v����A9���A���ōő����X�V�����B���́A����ŕa�������āA�_�f�O�a�x���댯�ȃ��x���ɉ������Ă����@����a�@���Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�����Ґ������������s���s���̐_�ސ�E��t�E��ʂ�3���̏ꍇ�A���T�͏d�ǎ҂̕a�����p����70�������B�d�Ǖa�����̒��ɂ͏����ȗp�Ȃǂ̓���ȕa�������܂܂�Ă���A��Ï]���҂̊Ԃł́u�̊��ł̏d�Ǖa���ғ�����100���v�Ƃ��������������B
���̂��߁A�����s�ł͍���9�|15���A����×{���̏Ǐ��ŋ~�}������v�������l��2259�l�ɒB�������A���̂���1414�l(62.6��)�����@�ł��Ȃ��������Ƃ����������B10�l�̂���6�l�ȏオ119�Ԃɓd�b���Ă������Ă��炦�Ȃ������Ƃ������Ƃ��B�a�@�ɔ������ꂽ845�l�̂���280�l���a�@��������̂�3���Ԉȏ�҂����Ƃ����B�����V���ɂ��ƁA�����s�Ǝ�s��3���ł͐挎���班�Ȃ��Ƃ�18�l������×{���Ɏ��S�������Ƃ����������B�a�@�œK�Ȏ��Â���ꂸ�Ɏ��S�������̂��B17���ɂ͐�t���Ŏ���×{���̔D�w������ɂ����ĔD�P8�J���ő��Y���A�q�����S�����B���̔D�w�͓���O����d�b�ł�������̕a�@��ی����Ȃǂɓ��@��v���������A���@�悪������Ȃ������Ƃ̂��Ƃ��B
���ɓ��{�ł́u���݂̊����g��͍ЊQ�����v�Ƃ������Ƃ̌x�����������ł���B���ł��[���ȓ����s�ł́u����s�\�̏�ԁv�Ƃ�������������B���{������50���ȏオ1��ȏハ�N�`����ł����̂ɂ�������炸�A�����҂������𑱂��Ă���̂́A�f���^�ψي����x�z���ɂȂ������Ƃɂ����̂��B���������nj������́A��s���̊����҂�95���A���ߗׂ̊����҂�80������f���^�ψي����m�F���ꂽ�Ɛ���A���\�����B
65�Έȏ�̍���w����r�I���N�`���ڎ헦���Ⴂ20�|50��̊O�����������点�Ȃ����Ƃ����_�Ƃ��Ďw�E����Ă���B7���ً̋}���Ԑ錾��������s���̎�ȊX�̗����l���́u�錾�O��50�������v�Ƃ������{�ڕW�B���Ɏ��s�����B���{��8�����߁A�ً}���Ԑ錾�n���6�s�{���Ɋg�債�����A�ܗփ��[�h�g�U��8���̂��~���Ԃ��d�Ȃ�A���̌��ʂ��オ���Ă��Ȃ��B
�ً}���Ԑ錾������1�N���̊Ԃɐ���J��Ԃ���Ă��邽�߁A�L�������ɂȂ����Ƃ����w�E�������B�u����Ă����Ȃ��Ă������錾�v���Ƃ������Ƃ��B���̂��߁A�S���̒n�������c�g�b�v�͐��{�ɊO�o���֎~����u���b�N�_�E���v�����@�������ׂ����Ǝ咣���Ă��邪�A���`�̎́u�l�̎����������I�ɐ�������͓̂���v�Ɠ�F�������Ă���B���̑���ɁA���{���{�̓��N�`���ڎ헦��10���܂łɑS������80���Ɉ����グ�đΉ�����Ƃ������j���B��Õ�������������邽�߁A���T���瓌���s����n�߂ɐV�^�R���i�����҂Ɏ_�f����������ꎞ�I�Ȏ{�݁u�_�f�X�e�[�V�����v���^�c����B�����ł́A�h�u����̊�����݂̐V�K�����Ґ����S����d�ǎҒ��S�ɉ�������Ă����������Ɠ`����ꂽ�B
���D�w�̗D��ڎ�A�e�n�ōL����c�u�f���^���v�Ŋ����g��E�s��3�E4�{�Ɂ@8/23
�D�w�ɁA�V�^�R���i�E�C���X���N�`����D��I�ɐڎ킷����g�݂��A�e�n�Ŏn�܂��Ă���B�Ⴂ���オ�ڎ����]���Ă��\���Â炢������������A�D�w�̊�����d�lj���h���̂��_���B��t���ŐV�^�R���i�Ɋ��������D�w�����@�ł�������ő��Y���A�V���������S���������A����ɍL���錩�ʂ����B
�N��3000���̂��Y�������Ă�������a�@(�����s�`��)��25������A���a�@����f���̔D�w��p�[�g�i�[��ΏۂɃ��N�`���̐ڎ���n�߂�B�d�lj����X�N�������Ƃ����D�P����̔D�w��D�悷��B
���{�Q����s��13������A�D�w�̐ڎ�\�����݂�D��I�Ɏt���Ă���B�É����x�m�s�́A�D�w�ƃp�[�g�i�[�̗D��t����21���Ɏn�߂��B���Ɍ��P�H�s���D�w�̗D��t�������Ă���A�����̎����̂Ŏ��{�̌������i�ށB
�w�i�ɂ́A�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)��11���A�D�w�̐ڎ�Ɋւ��錩�����u�l�̔��f�ɂ��v����u�����v�ɐ�ւ������Ƃ�����B���Y�̃��X�N�͍����Ȃ�Ȃ��Ƃ��錤�����ʂ܂����C�����Ƃ����B������A���{�Y�ȕw�l�Ȋw���14���t�ŁA�D�P�������킸�ڎ�����߂鐺���\�����B
�����͂������ψكE�C���X�u�f���^���v�̍L����ŁA��������D�w�������Ă��邱�Ƃ��e�����Ă���B���{�Y�w�l�Ȉ��ɂ��ƁA�����s����7���Ɋ��������������D�w��98�l�ƑO����3�E4�{�ŁA�ߋ��ő��������B
����a�@���^�c�����q�����̒��ѐ��Y������q�ی��Z���^�[�����́u�a�� �N���Ђ��ς� �̉e���ŁA�d�lj������D�w�̎�����������̂�����Ȃ��Ă���B�ڎ�ɂ��d�lj���h�����Ƃ��d�v���v�Ƙb���Ă���B
�����̊����ǖ@�Ɋ�Â����͗v���� ���Ɠs ��Ë@�ւȂǂɑ� �@8/23
�V�^�R���i�E�C���X�����̋}�g��ŕa�����Ђ������钆�A�c�������J����b�Ɠ����s�̏��r�m���͂�����ċL�Ғc�̎�ނɉ����A���Ɠ����s���A���œs�����ׂĂ̈�Ë@�ւȂǂɑ����@���҂̎����a���m�ۂ̂��߂̋��͂�v������l���������܂����B
�����ǖ@�Ɋ�Â����͗v��������s���s���̂͏��߂Ăł��B
�c�������J����b�Ɠ����s�̏��r�m���́A23���ߌ�A��k�������ƁA������ċL�Ғc�̎�ނɉ����܂����B
�����āA��Ò̐�����i�ƌ������Ȃ��Ă���Ƃ��āA���������ǖ@�Ɋ�Â��A�s�����ׂĂ̈�Ë@�ւ�f�Ï��A��Ï]���҂ɑ��A���@���҂̍ő���̎���₳��Ȃ�a���̊m�ہA�h���×{�{�݂Ȃǂւ̔h���ɂ��āA���Ɠ����s���A���ŋ��͂�v������l���������܂����B
���������ǖ@�ł́A�����J����b��m������Ë@�ւɕK�v�ȋ��͂����߂邱�Ƃ��ł��A�����ȗ��R�Ȃ������Ȃ������ꍇ�ɂ͊������������ŁA�]��Ȃ������ꍇ�͈�Ë@�֖������\�ł���K�肪���荞�܂�Ă��܂��B
���Ƃ�2���ɉ������ꂽ�����ǖ@�Ɋ�Â����͗v��������s���s���̂͏��߂Ăł��B
�c����b�́u���Ɠs�A��ÊE����ۂƂȂ�A�ЊQ�ɋ߂��ɑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł̗v�����B���̌����������邽�߂ɂ��A����Ȃ�͓Y�������肢�������v�Əq�ׂ܂����B
���r�m���́A�L�Ғc�ɑ��u�f���^���̊����͂͋ɂ߂ċ����A�s���ł͐V�K�z���Ґ���5000�l����ߋ��ő�̐����ɂȂ��Ă��āA����ɔ����A����×{�҂�d�ǎ҂������Ă��Ă���B�_�f�X�e�[�V�����Ȃǂ́w���x�������Ă���t��Ō�t�����Ȃ���Ό��ǂ͓����Ȃ��B�K�v�Ȉ�Â̎{�݂ɂ����Ĉ�Ï]���҂̋��͂��������߂�B�ő�̊�@�����z���邽�߂ɁA���A�s�A��Ë@�ւ����łɘA�g���đ��͐�ł��������Ă����v�Əq�ׂ܂����B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������p���J�����s���̐��c�I�葺�ł͊������@8/24
24���A�����s�ł͐V����4220�l�̐V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F����܂����B����ŁA�����p�������s�b�N���A24����A�J����}���܂��B�I�����s�b�N�̊J��ɔ�ׁA3�{�ȏ�̐V�K�����҂��m�F�����ȂǁA�����g�傷�钆�̊J�ÂɁA�W�҂���͕s���̐����オ���Ă��܂��B
24���A�����E���z�s�̏��w�Z�ɒʂ����������e���畷���ꂽ�̂̈́��B�u���(�ċx��)�����ɂȂ邩��A�w�����A�������炢���̂ɂȁx���ĒU�߂ƌ����ĂāB���f�x�������A�݂����Șb�����Ăāv
���w���̑��q�������e����̈́��B�u���d�����Ă邨�ꂳ��Ƃ��́A�����ƑΉ�����ς�������Ȃ����ȁv
24���A�͂������[���ɂ́A�ċG�x�Ɠ��̉����Ə�����Ă��܂����B�����҂��}�����Ă��钲�z�s�́A26���܂łƂ��Ă����A�s���̏��E���w�Z�̉ċx�݂��A����5���܂ʼn������邱�Ƃ����߂��̂ł��B����ɁA���z�s�͋x�ݖ����ɂ́A�I�����C�����Ƃ��s���Ƃ��Ă��܂��B
��u���w�Z�̒�w�N�ɃI�����C���ł̎��Ƃ́A���Ԃ�Ӗ��Ȃ��Ƃ������A�ł��Ȃ��Ǝv���܂����ǂˁv
�������������́A����s�A�����s�ł�����܂����B�����24���ߌ�A�]����́A25������ĊJ����\�肾�����旧�̏��w�Z�A���w�Z�A�c�t�����A����3���܂ŗՎ��x�Z�ɂ��邱�Ƃ����\����܂����B�q���̊����������Ă��āA�q���̖�����邽�߂��Ƃ��Ă��܂��B�����ł́A�����̊g��ɂ��x�Z�̓������L����܂��B24���̊����҂�4220�l�ŁA17����4377�l����≺���܂������A9�l���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���ɋً}���Ԑ錾��v�����Ă���A���m���ł͉ߋ��ő����X�V���A1617�l�̊������m�F����Ă��܂��B�ł��A382�l�Ɖߋ��ő��ƂȂ�܂����B
�����g��̒��A�p�������s�b�N�́A24����J�����܂����B24���ߌ�2�������A�����̋�ɂ���Ă����̂́A�q�q���̃u���[�C���p���X�ł��B3�F�̃X���[�N�˂��Ȃ���A���ŁA�ؗ�Ƀ^�[�����A�����A�����̋�Ɂu�X���[�A�M�g�X�v��`���܂����B
�ϗ������l�X�̈́��B�u�������܂����B�܂������ɔ��łāv�u3�F���������L���C�ŁA�R���i���I��肻���Ɗ�]�����Ă܂����v
�s�S�̏���1�������A���悻15���Ԃ̔�s�ł����B���ɂ́A�����^���[�Ƃ̃R���g���X�g���I�݂ɎB�e�����l�����܂����B����ŁA�u���[�C���p���X�̔�s�́A�����̐l�o���Ă�ł��܂��A�����͓�d�ɂ��O�d�ɂ��l���A�Ȃ��Ă��܂����B���Z����ӂ�A�s���̃����h�}�[�N�ɂ͑吨�̐l�X�����W���Ă��܂��܂����B�܂��A�J���ɂ��킹�A�]����C�ɂ́A�p�������s�b�N���Z�̑̌��{�݂��I�[�v���B��ނ��������L���X�^�[�́A�Ԃ����o�X�P�b�g�ɒ��킵�܂����B�ʏ�̃o�X�P�ƈႢ�A�W�����v�ł��Ȃ����ƂŁA�������o���A��x���J�S�ɓ͂��܂���B�I�����s�b�N�̋��Z�Ƃ͂ЂƖ��Ⴄ���������܂��B
�Ԃ����o�X�P��̌��u�����S�[���ɓ���Â炩�����ł��B���������ς����v���o���Ȃ���(���Z��)�������ł��v
�����āA�p�������s�b�N�̊J��̉����ӂł́A�ߌ�5���̎��_�ŁA�l�X���W�܂�o���Ă��܂����B
�ߏ��̈��H�X�̈́��B����ƁE���萳�O����u�s���ł���B(���i��)100�{���炢�����Ȃ��ł����v
�l�X�������邱�Ƃւ̕s�������ɂ��܂����B�܂��A�s���̎���߂Ȃǂ��������ł��܂��B��قǁA�����E�]�����]�ː��́A�����炪�Q���\�肾�������Z�̊w�Z�A�g�ϐ�𒆎~����Ɣ��\���܂����B�܂��A�p�������s�b�N�̃j���[�W�[�����h�I��c�́A�����ւ̌��O����A�J��̎Q��������߂܂����B
�p�������s�b�N�W�҂ւ̊������L�����Ă��܂��B24���A�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂�10�l�ŁA���̂���1�l�́A�I�葺�ɑ؍݂���I��ł��B�I�葺�őI��̊������m�F�����̂́A���ꂪ���߂Ă��Ƃ����܂��B���������ł̊J�Âɕs���̐����グ��l�����܂��B�]����ɂ���A�Ґ������Ґ��̃g���[�j���O�W���̑�\�ł��B�����̃p���A�[�`�F���[�ɏo�ꂷ��A���舤�q�I��ȂǁA�����̃A�X���[�g���T�|�[�g���Ă����Ƃ����܂��B
�i�\�v�������������@�ɍ���N��\�u(�Ґ������҂̒��ɂ�)�ċz���邽�߂̑̊��̋ؓ����}�q���Ă����������������̂ŁB��������ƃ��X�N�������Ƃ��������A���\��������Ⴂ�܂��̂Łv
���g���ߋ��ɐҐ������������Ƃ�����A�W���ł�������ɋC��t���Ȃ���A�g���[�j���O���s���Ă����Ƃ����܂��B
�ɍ���N��\�u����҂̃A�X���[�g�ɔ�ׂāA�ċz�킾������Ƃ��A��b���������łɂ���Ƃ������X���W�܂���ł��̂ŁA�S�z�͂���ȂƁB�I�����s�b�N�ȏ�̑��O�ꂵ�Ă����Ȃ���A�����ɋ��Z�������ނ��Ƃ��y���݂ɂ��Ă���܂��v
��̓O������߂鐺�́A����×{�҂ւ̉��f���s����t��������B
�t�@�X�g�h�N�^�[��\�E�e�r����t�u(�V�^�R���i��)���҂�����ɂ��ӂ�Ă���ȁA�Ƃ����ӂ��Ɋ����Ă��܂��B(�p�������s�b�N��)��������Ǝ���ŊO�o���T���Ȃ��牞�����Ă����Ƃ����Ƃ���ŁA�������O�ꂵ�Ă����Ƃ������@���g�݂��K�v�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��v
�s����50��̏����B�z�����������Ă���A1�T�Ԉȏ�A����ł̗×{�𑱂��Ă��܂��B20���A�z�c�ʼn��ɂȂ��Ă��܂����B50�㏗���u�H���͂قƂ�ǂł��Ă��Ȃ��ł��B�N���オ��̂������炢�̂ƁA�ڂ��J���Ă���̂��炢�̂Łv����Ʉ��B�u�S�z���A�S�z���v
��t�@�u���_�f�̏������܂�����ˁv�x���̋^�������邽�ߎ_�f���^���s���܂����B�����āA20���A�ꏏ�ɕ�炷�v�̗z�����m�F����܂����B���̂Ƃ���Ǐ�͌y���Ƃ����܂����A�Ȃ͕v�ɑ��Ą��B50�㏗���u(������v��)���N�Ǘ����Ă������āB�������@���Ă����v�c�v
�s���̎���×{�҂́A23�����_�ŁA2��5156�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���u�ً}���Ԑ錾�v���o�ց@�u�����҂͂���ȏ㑝���Ăق����Ȃ��v�k�C���@8/24
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����������{�́A�k�C���Ȃǂ��u�ً}���Ԑ錾�v�̑Ώےn��ɒlj���������Ō������Ă��܂��B
����×{�҂̑�����D�w�̊����������钆�A�V�^�R���i�Ɋ��������D�w�����ꎡ�Â����t����@�������܂����B
�k�C����w�a�@�@�n�l����t�u�ʏ�̊��҂ł�����̌ċz��Ԃ��悭���邱�Ƃ����l����������A�D�w�̏ꍇ�͑̂̎_�f�Z�x�����Ȃ��Ȃ��Ă���ƐԂ����Ȃ��Ȃ�v
�D�w�̊����g��Ɋ�@���������k�C����w�a�@�̎Y�Ȉ�n�l����t�ł��B7�����m�����\�h�����k��a�@�ł͐V�^�R���i�Ɋ��������D�y���̔D�w������Ă��܂��B��Â̕N���ƂƂ��ɕ�q�Ƃ��ɊǗ�����Ƃ������x�Ȉ�Â��K�v�Ƃ���邽�ߑS���Ŋ��������D�w�̎��ꂪ�ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�n�l����t�u���܂̊����ł���Ύ����Ԃ͏\���@�\���Ă���B�������t�݂����Ɋ����҂������͂��߂��Ƃ��ɁA��ʂ̔D�w�َ̑����Â��������̂Ŋ����҂͂���ȏ㑝���Ăق����Ȃ��v
���{�́A�ً}���Ԑ錾�̔��o��v�������k�C���Ȃǂɂ��đΏےn��ɒlj���������Ō������Ă��܂��B�k�C���ɐ錾�����o�������N4������5���A���Ƃ�5������6���ɑ�����3��ڂƂȂ�܂��B��������͔��o�̃^�C�~���O�ɂ��ĕ����s���̐���������܂����B
�D�y�s���u�x���Ǝv���܂��B���ꂾ��(�����g���)�Ȃ��Ă���o���Ă��݂�Ȃ����͂��Ă���邩�ǂ����v
�Ϗ��q�s���u5�����S�[���f���E�C�[�N���Ƃɏo�����B��������~�̂��ƁB�o���^�C�~���O���ԈႦ�Ă���C������v
�錾�����o�����Έ��H�X�ւ̋x�Ɨv���ȂNj����[�u�����߂��܂��B���{�́A25�����Ƃɂ͂����������ő��{�����J���A�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��g��𐳎����肷�錩�ʂ��ł��B
���w�Z�ł̊����}���Ɋg�� �ċx�ݖ����c"�w����" �D�y�s��21�Z�Ɂ@8/24
�D�y�s���Ŋw�Z�ł̊����g�傪�����Ă��܂��B�ċx�ݖ����̊w�����͎D�y�s����21�Z�B���~�߂�������Ȃ������ɐ��{�͖k�C����3�x�ڂً̋}���Ԑ錾��K�p������j��8��25���ɂ��������肷�錩�ʂ��ł��B
�S���I�Ɋ����g�傪�����V�^�R���i�E�C���X�B���{�ً͋}���Ԑ錾�ɐV���ɖk�C���ƈ��m���ȂǓ��C3��������������Œ�����i�߂Ă��āA8��25���ɂ��������肷����j�ł��B
2020�N4����2021�N5���ɑ����A3��ڂً̋}���Ԑ錾�̓K�p���D�y�s���͂ǂ��~�߂Ă���ł��傤��?
�D�y�s���u�����Ґ��������Ă���̂őÓ����Ǝv���v�u(���Ԃ�)�Z�����邵�A3��ڂ����B(��)�����Ń����n�����Ȃ��v���H�X�̏]�ƈ��u��̃X�X�L�m�̓T�����[�}�����������B����������̂ł͂ƃq���q�����Ă���v
�k�C�����ł�8��24���A�V�^�R���i�E�C���X��1�l�̎��S�ƁA�V���ɎD�y220�l�A����s60�l�Ȃnjv426�l�̊������m�F����܂����B
���̂����A�D�y�s�ł͎����w�Z�Ȃnjv8�Z�̏��w�Z�Ŏ����̊������m�F����A�w�����ƂȂ�܂����B
�s���̏��w�Z�ł�18���ɐV�w�����n�܂��Ĉȍ~�A8��24���܂ł�21�Z�Ŏ����Ƌ��E���v22�l���������Ă��܂��B�����̔g�͊w�т̏�ɂ��}���Ɋg�債�Ă��܂��B
�����قŊ����}�g�� �s���g�D�y�����s���Ƃ̉����T���āh�@8/24
���َs�̍H�������s����24������J���A�s���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�}���ɐi��ł���Ƃ��āA�u�D�y�����s���Ƃ̉����͎d�����܂߂Ăł������T���Ăق����v�Ƃ��炽�߂ČĂт����܂����B
�L�҉�ōH���s���́A�挎25������24���܂ł�1�����Ԃ̊����Ґ���356�l�ɏ��A�����̊����Ґ��͂���܂łōł������Ȃ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�N��ʂɂ݂܂��ƁA20�オ98�l�ƍł������A������40�オ57�l�A10�オ51�l�A30�オ46�l�ƂȂ��Ă��āA�Ⴂ����𒆐S�Ɋ������g�債�Ă��܂��B
�����̗v���ʂł́A�A�Ȃ◷�s�Ȃǂłق��̒n��Ƃ̉����ɂ���Ċ��������l��146�l�ƑS�̂�4���]����߁A�����Ŏ{�݂�E��ł̊�����77�l�A�ƒ��������58�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
����ŁA�s���ł̊����g��̔��[�͂ق��̒n��Ƃ̉����ɂ����̂��قƂ�ǂ��Ƃ��āA�H���s���́u�������g�債�Ă���D�y�����s���Ƃ̉����͎d�����܂߂Ăł������T���Ăق����B�����Ƒ��ȊO�Ƃ̐H�������̎����͍T���Ă��炢�����v�ƌĂт����Ă��܂��B
�܂��A���{���ً}���Ԑ錾�̑Ώےn����g�傷�邩�������Ă��邱�Ƃɂ��āA�H���s���́u�錾�����߂��ꂽ�ꍇ�ɂǂ̂悤�Ȑ�����v��������̂��A�܂��������Ă��Ȃ��B���⓹�̏𒍎����A�ڍׂ������������Ƃɔ��f�������v�Əq�ׂ܂����B
��8���̃R���i�����ҁA���̐�l���@�X�����@8/24
�X����24���A�����ŐV����81�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B�P���Ƃ��ĉߋ��ő��ƂȂ��Ă���8���̊����҂͓������݂�1010�l�ƁA���߂Đ�l�����B�����m�F�v3708�l�̂��悻3�����߂�B�����N�������̌Ð���O�����͋L�҉�Łu�S���I�ɐV�K�z���҂��m�F����Ă���A������\�f�������Ȃ��v�Ɗ�@�����������B�����͔��ˎs��2���A�O�O�ی����Ǔ���1���̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�����������B
����܂Ō��ʂōő��������̂�5����776�l�B8���́A�A�ȂȂǂŐl�̗��ꂪ���������Ƃ�A�����͂������f���^���Ƃ݂���L452R�ψي��ւ̒u�������ɂ��A5����傫������y�[�X�Ŋ������g�債�Ă���B
24���̊�����81�l�́A3��31�����\���ƕ��щߋ�3�Ԗڂ̑����B���̂���35�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B
�V�K�����҂����Z�n�ʂɂ݂�ƁA���ˎs��32�l�ƍł������A�����čO�O�Ǔ�18�l�A�X�s12�l�ȂǁB���̂ق��A�X���ȊO�̓��k�n���A�֓��A�������痈������9�l�̗z�������������B
���\�ς݂̃N���X�^�[�ł́A���ˊw�@��w�j�q�T�b�J�[����20�㕔��1�l�̊������������A�����҂͌v8�l�ƂȂ����B20�����\�̔��ˎs�̋���ۈ�{�݃N���X�^�[�ł́A�֘A����30��j���̊�����������A�S�̂̊����҂͌v19�l�ƂȂ����B��80�l�̌������I�����A��70�l�����ʑ҂��ƂȂ��Ă���B
���@�Ґ���110�l�ƑO�����3�l�������B�a���g�p����36.4���ŁA�a���̕N��(�Ђ��ς�)�x�������������̎w�W�ł̓X�e�[�W3(�����}��)�����������Ă���B
����f���������g�傷��P�[�X���u�Ǐ�o���瑊�k���v�@�V�����@8/24
24���A�V�������ŐV���ɐV�^�R���i���������\���ꂽ�̂͐V���s��44�l�A�����s��14�l�A�ܐ�s��8�l�ȂǁA���킹��113�l�ŁA�Ηj���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�܂��B
1���̐V�K�����Ґ���100�l����̂�3���Ԃ�ł��B���̂������O�Ƃ̉������������̂�19�l�ŁA�����_��35�l�̊����o�H���������Ă��܂���B�N��ʂł�40�オ24�l�ƍł������A������30�オ23�l�B50��ȉ�����9�����߂Ă��܂��B
���́A�����┭�M�Ȃǂ̏Ǐo�Ă���l���A�����Ɉ�Ë@�ւ���f�����Ɋ������L���Ă���P�[�X������Ƃ��āA���߂̑��k���f���Ăт����Ă��܂��B
�������Ǒ�E�ہ@�����H�F �ے��u�����l�͔��ǂ���1�T�ԁ`10�������Ă����f���Ă���B�V�^�R���i��f���k�Z���^�[�͖���24���Ԃ���Ă��āA�y�����f�Ă��������鏊���ē�����̂ŁA���₩�Ȏ�f�E���k�����肢�������v
����Ń��N�`���ڎ�̉����ցA�V���s�ł�24������50��̏W�c�ڎ킪�n�܂�܂����B
�V���s�ی��q�����@�쓇���q �����u���N�`���ڎ킪�����ɐi��ł����A���ꂪ�����Ґ���(������)�e�����o�Ă��邱�Ƃ����҂��Ă���v
�܂��A����30���Ɍ����ŏ��߂ăA�X�g���[�l�J�А��̃��N�`���ڎ�Z���^�[���s�ɐݒu����Ɣ��\���܂����B40�Έȏ�̐l�Ȃǂ�Ώۂ�500�l���̐ڎ��\�肵�Ă��܂��B
�����V�^�R���i2368�l�̊����m�F�@������邱�Ƃ���ԂɁc�@8/24
���{��24���A�V����2368�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����A5�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B�܂������p�������s�b�N���J�����铌���s�ł�4220�l�̊������A���Ɍ��ł͐V����1079�l�̊������m�F����܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�̏]�ƈ��̃N���X�^�[�����ŁA�Վ��x�Ƃ��Ă�����}�S�ݓX���߂��{�X1�K�����̉c�Ƃ��ĊJ����܂����B�c�Ƃ��ĊJ�����̂�1�K�ɂ���A�N�Z�T���[�ƎG�ݔ����ł��B���̔����ƒn��1�K�̐H�i�����ł͐V�^�R���i�̏]�ƈ��̃N���X�^�[�������������߁A8��17������Վ��x�Ƃ��Ă��܂������A�o�b�q�����ʼnA�����m�F�ł����]�ƈ���1�K�̂ݍĊJ����Ƃ������Ƃł��B
�K�ꂽ�q�́u�t�ɁA�����Ă���Ǝv�������痈���v�u1�K����炸�ǂ��ɂ���炸�A���ϕi������2�K��������ăp�b�Əo���v
�V�^�R���i�����g����A�Q����s�̏��w�Z�ł̓I�����C�����Ƃ��s���Ă��܂��B�Q����s��36�̏��E���w�Z�ł�23������2�w�����n�܂�܂������A�q���ւ̊������L�����Ă��邱�Ƃ��A8��27���܂œo�Z�������킹�A��ĂɃI�����C���ł̎��Ƃɐ�ւ��܂����B���w�Z���@�u������邱�Ƃ���ԂɁB�ł��q�ǂ��̊w�т͎~�߂��ɂł��邱�Ƃ�����Ă��������v
8��30������A�o�Z���ĊJ����\��ł��B
���V�^�R���i�����}�g�� ���e�n �w�Z�̑Ή��́@8/24
�����{���ꕔ�����̂ŃI�����C������
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g����A���{���̈ꕔ�̎����̂ŏ����w�Z�̉ċx�݂�����������A�x�ݖ����̎��Ƃ��I�����C���ɐ�ւ����肷��ȂǑΉ��ɒǂ��Ă��܂��B
���E�Q����s�́A�ċx�ݖ�����23�����獡��27���܂ŁA���킹��36����s���̏����w�Z�Ŏ������k�̓o�Z�������킹��[�u�����A���Ƃ��I�����C���ɐ�ւ��܂����B
���̂����s���x�a���w�Z�ł́A�S�C�̋��@���r�f�I��c�V�X�e�����g���Ď��Ƃ��s���A5�N����2�N���X���킹��47�l�̎��������͎���ō���̎��Ƃ��Ă��܂����B
�����ł͋��@�����j�^�[�z���Ɏ����̈ӌ�������A�o���ꂽ�ӌ������ɏ����Đ��������肵�Ă��܂����B
�S�C�̉������� ���@�́A�u�q�ǂ������ɉ�Ȃ��̂͂ƂĂ��c�O�ł����A������邱�Ƃ��������ŁA�I�����C���ł��q�ǂ��������y����Ŋw�ׂ���@��������H�v���Ă��������v�Ƙb���Ă��܂����B
���{���ł́A�ق��ɂ����c�s���s���̏����w�Z�̉ċx�݂�1�T�ԉ�������ȂǁA�������}�g�傷�钆�A�e�����̂��Ή��ɒǂ��Ă��܂��B
�����{���̏����w�Z �ċx�݉����╪�U�o�Z��
���{���ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g����ď����w�Z�̉ċx�݂����������蕪�U�o�Z�����߂��肷��ȂǁA�x�ݖ����̊w�Z�ł̑Ή����}����ύX���铮�����o�Ă��܂��B
���̂������c�s�͎s���ŋ}���Ɋ������L�����Ă��邱�Ƃ���A24���܂łƂȂ��Ă��������w�Z�̉ċx�݂��������܂����B
�������Ԃ�7���ԂŁA����1���Ɏn�Ǝ����s���\�肾�Ƃ������Ƃł��B
���c�s�ł͍�N�x�A������k�Ƀ^�u���b�g�[����p�\�R����z�����Ă��ăI�����C���w�K��k�̌��N��Ԃ̊m�F�Ɋ��p�ł���悤������i�߂�Ƃ̂��Ƃł��B
�܂��A��؎s�̏����w�Z�ł�25���n�Ǝ����s�������ƁA26������ً}���Ԑ錾���Ԃ̗���12���܂ŁA������k��2�̃O���[�v�ɕ�����1����ւŕ��U�o�Z���邱�Ƃ����߂܂����B
���Ƃ̃J���L�������ɂ͑傫�ȉe���͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�o�Z���Ȃ��O���[�v���z������Ă���[���Ńz�[�����[���̎��ԂȂǂɃI�����C���~�[�e�B���O���s���Ƃ������Ƃł��B
����A���s�Ȃǂ͗\��ǂ���25�����珬���w�Z��2�w�����n�߂邱�Ƃɂ��Ă��Ĉ�ċx�Z�Ȃǂ̑[�u�͍s��Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
���a�̎R �����w�Z�̉ċx��8�����܂ʼn���
�a�̎R������ψ���́A�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�Ă���Ƃ��āA�ċx�݂̊��Ԃ��������܂ʼn������邱�Ƃ����߂܂����B
�a�̎R���ł�24���̐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��ߋ��ő��ɂȂ��90�l�ƂȂ�ȂNJ������}�g�債�Ă��āA�Ȃ��ł��q�ǂ��̊������������Ă��܂��B
���̂��߁A�a�̎R������ψ���͌����̍��Z�⒆�w�Z�A����ɓ��ʎx���w�Z�̂��킹��37�Z�ɂ��āA2�w���̊J�n��x�点�A�ċx�݂��������܂ʼn������邱�Ƃ����߂܂����B
�܂��A��������́A�w�N���Ƃɓo�Z����o�Z���Ԃ�ς��镪�U�o�Z��I�����C���w�K�Ȃǂ����A���Ƃ�i�߂�\�肾�Ƃ������Ƃł��B
�a�̎R�����ł́A�a�̎R�s�Ɗ�o�s����ɋI�̐�s�ł����ׂĂ̌����̏����w�Z���ċx�݂��������܂ʼn��������ق��A�R�ǒ��̏����w�Z�͍���29���܂ʼnċx�݂��������邱�Ƃ����߂Ă��܂��B
���ޗǎs�Ɛ���s �����w�Z���� ���ʒZ�k��
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A�ޗǎs�Ɠޗnj�����s�́A25������n�܂鏬���w�Z��2�w���ɂ��đΖʂł̎��Ƃ͓��ʁA�ߑO�������ɒZ�k���邱�Ƃ����߂܂����B
�ޗnj����ł́A�����̌����̏����w�Z��25������2�w�����n�܂�܂����A�V�^�R���i�̊������}�g�傷�钆�A�ޗǎs����ψ���́A����3���܂ł͌ߌ�̎��Ƃ��s�킸�A�ߑO�������ɒZ�k���邱�Ƃ����߂܂����B
���w�Z�̕������͌����A����3���܂Œ��~���A�ߌ�́A�I�����C�������p���Ċw�K�x�����s���Ƃ������Ƃł��B
�܂��A����s���A����12���܂Ŋw�Z�ł̎��Ƃ͌ߑO�������Ƃ��A����1������́A�ߌ�̓I�����C���Ŏ��Ƃ��s���Ƃ��Ă��܂��B
�����s���͉�ŁA�u�ی�҂���w�Z��ʏ�ǂ���ĊJ���邱�Ƃɕs���̐������Ă���B�ЂƂ܂��͌ߑO�̂ݓo�Z���A���H�͐H�ׂ��ɋA��̂��Ó��ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ܂����B
���a�̎R�� �����}�g��ŃR���i�h���×{ 9������J�n�� �@8/24
�a�̎R���́A�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�債�A��Ò̐��̈ێ�������Ȃ��Ă���Ƃ��āA�����ґS������@�����邱��܂ł̕��j�����߁A��������z�e���ł̏h���×{�����邱�Ƃ����߂܂����B
����͘a�̎R���̐m��m����24���̋L�҉�Ŗ��炩�ɂ��܂����B
�a�̎R���͂���܂ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂��A�����A�S�����@�����Ă��܂������A�}���Ȋ����g��ŕa���g�p����90�����A��Ò̐��̈ێ�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B
�m��m���͉�ŁA�u����܂ł̓��@��100���͖������ȂƂ����Ƃ���܂Œǂ����܂�Ă���B��ނ����Ȃ����Ǐ������Ȃ��Ǝv���銳�҂���ɂ́A�z�e���Ɉڂ��Ă��炤�v�Əq�ׁA����1������h���×{���n�߂邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
��̓I�ɂ͘a�̎R�s�̃z�e���u�����h�m�m �i�q�a�̎R�w�����v��151�����m�ۂ��A�Ō�t���풓�����������ŁA�V�K�̊����҂Ŗ��Ǐ��y�ǂ̐l�������ق��A�a�@�ɓ��@���Ă���l���A���nj�5������7���������A���Ǐ��y�ǂ̏ꍇ�́A��t�̔��f�Ńz�e���Ɉڂ��Ă��炤�Ƃ������Ƃł��B
���V�^�R���i��N�w�̊����g���2�w���ɂ��e���@�w�Z����@����E������@8/24
�R�A�����̏����w�Z�⍂�Z�́A����2�w�����X�^�[�g���Ă��܂��B��N�w�Ŗڗ������m�F�ɁA�w�Z����͂���܂łɂȂ�������𔗂��Ă��܂��B
����k���E�剖�W�Z���u2�w�����V�^�R���i�E�C���X�̊����h�~�𑱂��Ă����w���ɂ��܂��傤�v
�����͒��挧������ɂ������k���w�Z�B1�����]��̉ċx�݂��I���A24������2�w���ł��B�V�^�R���i��Ƃ��Ďn�Ǝ��̓����[�g�Ŏ��{�B��200�l�̎������e�����ŁA�Z���搶�̌��t�Ɏ����X���܂����B
�S���I�Ȋ����}�g��̎����ɏd�Ȃ������N�̉ċx�݁B�ǂ��߂������ł��傤���H�@6�N�̎����ɕ����܂����B
�����u�R���i�̂��߂��܂�O�ɏo���ɉƂʼn߂����Ă����v�u�߂��̉Y�x�C�݂ȂǂŗV�B�R���i�����s���Ă��ĉ����ɍs���Ɗ�Ȃ��̂Łv
�f���^�����傫���W���Ă��鍡��̑�5�g�ł́A��N�w�̊����������Ă��܂��B���挧���ł����̂Ƃ���50��ȉ��������ґS�̂�8�����߁A10��ȉ���2���߂��ɒB���Ă��܂��B�w�Z����͂���܂łɂȂ���𔗂��Ă��܂��B������̏��w�Z��2�w���������Ă����̈��B3��ɕ������̎��A�^�̎��ɂ́u������������Ƃ��͂��̎����g���܂���v�Ƃ������莆������܂��B
�剖�W�Z���u���H�̌�Ɏq�������������������Ă�����������̂����ɂȂ�B��Ƃ��Ďg���Ă��炤�v
�w�Z�ł͂��̑��A�E�����ɂ���d�b�ɂ��āA�g�p����x�ɏ��ł���[�u���n�߂܂����B
�剖�W�Z���u�V���ȑ���Β����ɐi�߂Ă����B��{�ɗ����Ԃ�A���邱�Ƃ��m���ɍs���A�q�ǂ������̌��N�ƈ��S������Ă����v
�w�Z�����͂��ĂȂ��قǂ̕s���R�����������Ă��܂��B
�����E���w�Z �V�^�R���i�����g��ʼnċx�݉�����Վ��x�Z�̓��� �@8/24
�ً}���Ԑ錾������1�s6���ł́A�ċx�݂��������w�Z�J�n�̎�����x�点����A�I�����C�����Ƃ������肷�鎩���̂̓������o�Ă��܂��B
�����@/�@�����s���ł́A���T���痈�T�ɂ����āA�����̏����w�Z�œ����̗\��ǂ���w�Z���n�܂�܂����A���z�A�����A�����3�̎s���ċx�݂��������Ċw�Z�̊J�n��x�点�邱�Ƃ����߂܂����B���̂������z�s�́A����27���Ɏn�Ǝ��̗\��ł������A�ċx�݂�10���ԉ������A����6���Ɋw�Z���J�n���܂��B����Ɋw�Z�J�n����A����10���܂ł̓I�����C�����Ƃ����{���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
�_�ސ�@/�@�_�ސ쌧���ł͉��l�s�A���s�A���͌��s�A����ɑ�a�s���ċx�ݖ����̗Վ��x�Z�����߂��̂ɑ����A�쑫���s�������w�Z�̗Վ��x�Z�����߂܂����B�쑫���s�ł͉ċx�ݖ����̍���30�����痈��3���܂ł�Վ��x�Z�Ƃ��邱�Ƃ����߁A�w�Z���ĊJ�������Ƃ�����10���܂ł͌ߑO���ƂƂ���ق��A���w�Z�̕������ɂ��Ă͓��ʁA�����Ƃ��Ē��~�ɂ��܂��B
��ʁ@/�@��ʌ����ł͉z�J�s��O���s�Ȃ�7�̎s�ƒ��ŁA�w�Z�̊J�n������x�点�܂��B�܂��A�������s�ł́A����26������2�w�����n�܂�܂����A�ً}���Ԑ錾���́A�o�Z���邩�ǂ����͎��R�Ƃ��āA����ɂ���q�ǂ������͎��Ƃ��I�����C���Ŏ���Ƃ������Ƃł��B��ʌ���25���J����錧�̐��Ɖ�c�ʼnċx�ݖ����̊w�Z�ł̊�����̕��j�ɂ��Ęb�������A�s�����̊e����ψ���ɒʒm���o�����Ƃɂ��Ă��܂��B
��t�@/�@��t�����ł͕x�Îs�̏����w�Z2�Z���ċx�ݖ����̗Վ��x�Z�����߁A���̂ق������̏����w�Z�ł͕��U�o�Z��Z�k���ƂȂǂ̑Ή����������Ă��܂��B��t���͌����̎s�����̊e����ψ���ɑ��Ď����E���k�̊������X�N���������g�݂�O�ꂷ��悤���߂�ʒm���o���Ă��āA�e����ψ���͉ċx�ݖ����̑Ή��ɂ��Č�����i�߂Ă��܂��B
���@/�@��錧���ł́A�������ً}���Ԑ錾�̊��Ԓ��Վ��x�Z�ɂ���ق��A���ˎs�A���v�s�A�����������������ς��Վ��x�Z�ɂ��邱�Ƃ��킩��܂����B����A��J�s�͓����̗\��ǂ���A25��������Ƃ��ĊJ���܂����A�^�u���b�g�[�����g���ăI�����C���Ŏ��Ƃ��s���Ƃ������Ƃł��B
�Ȗ@/�@�Ȗ،����ł͂�����s�Ɖ��J���͍���27����Վ��x�Z�Ƃ��A�n�Ɠ�������30���ɕύX���邱�Ƃ����߂܂����B�܂��A����12���܂ł̊ԁA�p�����͎q�ǂ������̓o�Z������߁A�I�����C���Ŏ��Ƃ��s���ق��A����s�͕��U�o�Z��I�����C�����Ƃ��s�����Ƃɂ��Ă��܂��B
�Q�n�@/�@�Q�n���ł͉ċx�ݖ����ɏ����w�Z�̋x�Z�����߂������̂͂���܂���B�ٗюs�Ƒ�Ȃ�6�̎s���������U�o�Z�����{����ق��A���c�s�́A���w�Z�͒ʏ�ǂ���ł������w�Z�͕��U�Ƃ��邱�Ƃ�24�����߂܂����B
�܂��A�ꕔ�̎����̂ł͎��Ǝ��Ԃ�Z�k����Ƃ��������Ƃ������Ƃł��B
���p�������s�b�N�̊w�Z�ϐ�A���~�̓����������@�����}�g��Ɍ��O�@8/24
�V�^�R���i�E�C���X�����̋}�g�傪�������A�����s���ł́A24���J���̓����p�������s�b�N�Ŏ��{����鎙�����k�����́u�w�Z�A�g�ϐ�v���O�����v�ɂ��āA�Q���������鎩���̂��������ł���B18�����_��8�����̂��Q���\�肾�������A24���A�]����ƍ]�ː�悪���~��\���B�n�c��͊��Ɏ���߂����߂Ă���A��������ł́A���コ��ɑ�����\��������B
���~�̗��R�Ƃ��āA�]�ː��͐V�^�R���i�̊����g����Ñ̐��̕N��(�Ђ��ς�)�������A�u�q�ǂ������ɂƂ��đf���炵���@��Ǝv���A���O�܂Ō������d�˂������~�Ɏ������v�B�]����́u�q�ǂ��̈��S���S���l�������v�Ƃ��Ă���B
����A�a�J��͗\��ʂ�Q��������j�B��9000�l�̎q�ǂ����ϐ킷������Œ������Ă���B�S���҂́u����܂ʼn��N�ɂ��킽��A�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N��������{���Ă����B�ϐ�͎q�ǂ��ɂƂ��đ傫�ȈӋ`������v�ƌ��B������͊w�Z��ʂ��ی�҂̊�]���m�F�������A�S���҂́u�ϐ킵�����q�ǂ�������Ȃ�@���^�������v�Ƌ������Ă���B
�v���O������25������9��5���܂ł̗\��ŁA��]���鎙�����k�ɑ��A�s�����ł̋��Z�ϐ�̋@������B�s�ɂ��ƁA24���ߌ�3�����_�ŎQ���̈ӌ��������Ă���̂͐V�h�A�a�J�A�����A�����q4�s��Ɠs���w�Z6�Z�ŁA�ő��2���l���ϐ�\��B�`��́u�������v�Ƃ����B18�����_�ł�8�����̂Ɠs���w�Z23�Z�̍ő��13��2000�l���ϐ�\�肾�����B
���������Ȃ��͂��ł́c�R���i��5�g�Ŏq�ǂ��̊����}���@8/24
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�钆�A���Ắu���܂芴�����Ȃ��v�u�d�lj��̉\�����Ⴂ�v�Ƃ���Ă����A�q�ǂ������̊����������Ă��܂��B�ċx�݂��I���̎����ƂȂ�A2�w�����n�܂�ƁA����Ɋg�傷�鋰�ꂪ���肻���ł��B�q�ǂ��̊��������̎���⊴���h�~��ɂ��āA��ÃW���[�i���X�g�̐X�܂ǂ�����ɕ����܂����B
Q.�q�ǂ������̊����������Ă���͎̂����ł��傤���B
�X����u�g��5�g�h�Ƃ����錻�݂̗��s�ł́A10���10�Ζ����ł̐V�K�z���҂̐��A�������Ƃ��ɑ����Ă��܂��B�����s�́A����܂Ŋ������g�債�������̃f�[�^���r����ƁA���݂̗��s�ł�10��ȉ��̑����X�������炩�ł��B��1�g�̃s�[�N�ł�������N4���A�����s�Ŋ������m�F���ꂽ10���1�J����55�l�A���ς����1.8�l�^���ł����B8���̑�2�g�ł�9.9�l�^���A���s�̔g���傫���������N1���̑�3�g�ł�70.5�l�^���A5���̑�4�g�ł�47.5�l�^���ł����B�������A����1�J��(7��21������8��20��)�ł́A10��̊����҂̍��v��9969�l�ŁA1��������321.6�l�ɂȂ�܂��B����͑�3�g�̖�4.6�{�ł���A�S�����҂ɂ�����10��̊������A8��10������8��16���̕ł�9.3���ƁA60��ȏ��5.9����荂���Ȃ��Ă��܂��B�����悤��10�Ζ����̐����r����ƁA��N4����1�J����1��������1.8�l�A��N8����5.3�l�^���A���N1����36.1�l�^���A5����26.2�l�^���ł������A����1�J���ł�5085�l�̊������m�F����A1��������164.0�l�A��3�g�̖�4.5�{�ƂȂ�܂��B10�Ζ����̊����҂̊��������߂�5.0���A60��(3.2��)��荂�������ł��B���̂悤��10��ȉ��̊����҂̑����͓����s�����łȂ��A�S���I�Ɍ�����X���ł��B����A10��ȉ��̏d�lj��̓[���ł͂���܂��A�܂�ł��B�����s�V�^�R���i�E�C���X�����ǃ��j�^�����O��c�ł́A6����10��̏d�ǎ҂�1�l����A7���Ɋ�b�����̂Ȃ�10�㖢���ŏ��߂ďd�ǎ҂�����A8���ɓ���A10��̏d�ǎ҂�2�l����܂����B7���ɓ����Ă����20��A30��̎�N�w�ł��d�ǎ҂������A�p���I�ɕ���A����҂Ɍ��炸�A�S����ŏd�lj����X�N�����邱�Ƃɒ��ӂ��Ăъ|�����Ă��܂��B�������A10��ȉ��͊����҂��}�����Ă�����̂́A�d�lj��̊����ɂ��Ă͌��݂̂Ƃ���A����܂łƑ傫�ȕω��͂Ȃ��ƌ����܂��v
Q.�u�q�ǂ��͊������ɂ����v�ƌ����Ă��܂������A�����N���Ă���̂ł��傤���B
�X����u���݂̊����̎�̂ƂȂ��Ă���w�f���^��(L452R�ψق����ψكE�C���X)�x�̉e�����l�����܂��B�����s�ł͖�9�����f���^���ɒu����������ƍl�����Ă��܂����A�S���I�Ƀf���^���ւ̒u������肪�}���ɐi��ł���Ǝw�E����Ă��܂��B�f���^���͊����͂��������Ƃ��������Ă��āA�ŏ��ɗ��s�����V�^�R���i�E�C���X(�]����)��2�{���x�A�f���^���̑O�ɗ��s���Ă����w�A���t�@��(N501Y�ψق����ψكE�C���X)�x��1.5�{���x�̊����͂�����ƍl�����Ă��܂��B�A�����J���a��Z���^�[(CDC)�̕ł́A�]������1�l�̊����҂��畽��1.4�`3.5�l���炢�Ɋ��������܂����A�f���^����1�l���畽��5�`9�l�Ɋ��������鋭���������Ƃ�������A����͋�C�������鐅�ڂ������Ɠ����x�ƍl�����܂��B���̂悤�Ȋ����͂̋����f���^���̊����́A��������Ƒ�����q�ǂ��Ɋ������邾���ł͂Ȃ��A�q�ǂ��̃R�~���j�e�B�[�Łw�q�ǂ�����q�ǂ��ւ��L�����Ă���x�ƍl�����Ă��܂��B�������g�債�Ă���n��ł́A�����Ȋ�������ۈ牀��c�t���A���邢�͕�������w�Z�s���A�m�A�K�����Ȃǂ��܂��܂ȏ�ʂɂ����āA�����X�s�[�h�ōL����P�[�X�������A�N���X�^�[�������������Ă��܂��B����ɁA�q�ǂ�����e�֊���������P�[�X���������_���A����܂ł̗��s�ƈقȂ�����ƍl�����Ă��܂��B��q�����悤�ɁA�d�lj��ɂ��Ă͂܂�ł���A���{�ł͌��݁A�f���^���̗��s�ɂ���āA�q�ǂ��̏d�ǎ҂��������Ă���Ƃ����͂���܂���B�������A���{��藬�s�K�͂��傫���C�O�̍��ł́A�q�ǂ��̏d�lj����������Ă���Ƃ���������܂��B�����҂���������A�q�ǂ��̏d�NJ��҂����R������ƍl�����邽�߁A����ȏ�̊����g���h�����Ƃ����ɏd�v�ł��v
Q.���M�����ۂȂǁA�q�ǂ��̏ꍇ�͂��A���ׂ��ƐM������ł��܂��P�[�X�����肻���ł��B�V�^�R���i���^���ׂ��P�[�X�Ȃǂ������Ă��������B
�X����u����܂ŁA�w�q�ǂ��͖��Ǐ�̊����������x�ƕ���Ă��܂������A���݂́A���M�����������ɐV�^�R���i�̐f�f�Ɏ���P�[�X�������悤�ł��B���M�ȊO�̐V�^�R���i�̏Ǐ�Ƃ��ẮA�����A�@���A�����A�����f�A���ɂȂǂ��������܂��B���̂ǂ�����A�R���i�ȊO�ł��q�ǂ����N�����₷���Ǐ�ł��邽�߁A�e�����f���邱�Ƃ͓���Ǝv���܂��B��q�̒ʂ�A�e�̔Z���ڐG�҂ƂȂ����q�ǂ����������邾���łȂ��A�q�ǂ����犴�����n�܂邱�Ƃ����邽�߁A���M�Ȃǂ̏Ǐ���ꍇ�͐e�����Ȕ��f�����A��������̏����ȂɁA�܂��͓d�b�ő��k���邱�Ƃ��������߂��܂��v
Q.��s���𒆐S�Ɉ�Ñ̐����N��(�Ђ��ς�)���A�����҂̓��@������Ȃ��Ă��܂��B�q�ǂ����������Ď���×{�ƂȂ����ۂ̒��ӎ����������Ă��������B
�X����u�q�ǂ��͑������y�ǂł���ƕ���Ă��܂����A�}�ȏǏ�̕ω����������Ȃ����߂ɁA����×{���̌��N�ώ@����ł��B���������Ì����Z���^�[�̓z�[���y�[�W��Łw�ӎ����͂����肵�Ȃ��A�@���������A�H�~���ቺ���Ă���A�������Ƃ�Ȃ��A��F�������A���ꂵ�����A�����f���J��Ԃ��Ȃǂ̏ꍇ�͒S���ی����A�܂��͂��������ɑ��߂ɑ��k���Ă��������x�Ɗώ@�̃|�C���g���܂Ƃ߂Ă��܂��B�܂��A����iCDC���ƃ{�[�h(�s�̊����Ǒ�ɂ��Ē�����Ƃ̉�c)���܂Ƃ߁A�����s�����s����w����×{�Ҍ����̃n���h�u�b�N�x�ł́A�ƒ���������L���Ȃ����߂̃|�C���g��8�����Ă��܂��B
�E�����҂̐��b������l�͌���ꂽ�l�ɂ���
�E�����ҁA���b������l�͂��݂��Ƀ}�X�N��t����(�������A2�Ζ����̎q�ǂ��̃}�X�N���p�͊댯������̂Ń}�X�N�͂����Ȃ�)
�E���܂߂Ɏ���
�E�����͂ł��邾�����C������
�E�悭�G��鋤�p������|���A���ł���
�E���ꂽ�ߕ��A���l�������
�E���݂͖����Ď̂Ă�
�ȏ�ł��B�q�ǂ����������ꍇ�́A���ނ�ւ���Ƃ���̂�@���Ƃ��ȂǂɁA�}�X�N�ɉ����āA1�������₷���g����Ȃǂ̎�܂�G�v�����𒅗p���邱�Ƃ�������̏�ő�ł��v
Q.�ċx�ݖ����A�w�Z���n�܂����ۂɒ��ӂ��ׂ��_�������Ă��������B
�X����u�W�c�����̂��߁A�����̋@������܂��B�}�X�N�̒��p�A�����ŁA�����̊��C�A�̒��������Ƃ��͓o�Z���Ȃ��Ȃǂ̊�{�I�Ȋ�����ƂƂ��ɁA���ƈȊO�̊���̏�ʂœ��ɒ��ӂ��K�v�Ȃ��Ƃ�����܂��B���H�₨�ٓ���H�ׂ鎞�Ԃ́A���������č���Ȃ����Ƃ��b���T���邱��(�ِH)�A�̈�̎��Ƃ╔�����̂Ƃ��A���ɍX�ߎ��╔���Ȃǂ̋�����ԂŁw���x�ɂȂ��āA��b���Ȃ��璅�ւ��Ȃ����ƂȂǁA�s���ɂ͏\�����ӂ��Ă��������B�w���ۈ��K�����A�m�Ȃǂł����l�̒��ӂ��K�v�ł��B�ً}���Ԑ錾�n��ŁA�q�ǂ��̊���������ڂ̓�����ɂ��Ă��鏬���Ȃ̈�t����ނ���Ɓw�����Z���͒��Ԃƈꏏ�̂Ƃ��͊{�}�X�N�������悤�Ɍ����܂��B�q�ǂ�����@�ӎ������̂͂Ȃ��Ȃ������������܂��A���݂̊����Ŕ�(�Ђ܂�)����ь�����b�͊댯�ɂ܂�Ȃ��B�ǂ����A�s�D�z�}�X�N�̐��������p(�@�A���A�{���������蕢��)�ƁA�\�[�V�����f�B�X�^���X�̓O����ӎ����Ăق����x�ƁA�q�ǂ������Ɋ������O�ꂷ�邱�Ƃ̑����`�������Ƒi���Ă��܂����B�����āA�w���X�N�ƃx�l�t�B�b�g���l�����ꍇ�A��͂�A���N�`���̌��ʂ͂���̂ŁA12����15���ϋɓI�ɐڎ���������Ăق����x�Ƃ��b���Ă��܂��v
���ً}���Ԑ錾�����ł̓_���c���{������73�����u���b�N�_�E�����ׂ��v�@8/24
���{�ŐV�^�R���i�̗z�������f�f���ꂽ�l���}�����钆�A���{������10�l��7�l���g���b�N�_�E��(�s�s����)�h���ׂ����ƍl���Ă��邱�Ƃ����������B�ꕔ�̐����Ƃ��u���b�N�_�E���Ȃ��ł����{�͂��܂�����v�Ǝ咣�������ƂƂ͑������閯�S���B
24���t�̎Y�o�V���́A�t�W�j���[�X�l�b�g���[�N(FNN)��21�`22���ɓ��{�̗L���҂ɑ��Ď��{�������_�����̌��ʂ\�����B73.6%�͊����g���h�����߂ɊO�o�𐧌����郍�b�N�_�E�����ł���悤�ɖ@�����ׂ����Ɠ������B���b�N�_�E���̍�������邽�߂̖@���͕K�v�Ȃ��Ƃ����ӌ���22.3%�Ɏ~�܂����B
���b�N�_�E�������Ȃ��Ă����{���V�^�R���i�ɂ悭�Ή����Ă���Ƃ����ꕔ�����Ƃ̎咣���Ӗ��̂Ȃ����̂ɂȂ����������ʂ��B����ɐ旧���A�������Y����������b�͐V�^�R���i�̖h�u�ɂ����āA���{�������Љ�����D��Ă���Ƃ�����|�̎咣���s���Ĕ�]�̑ΏۂɂȂ����B���{�͊����g�U��h�����߂ɏZ���̊O�o���֎~�����苭���I�ɓs�s���������Ȃ��Ă����S�Ґ��������ɔ�ׂď��Ȃ��Ƃ����̂������������̐������B
�����������͐V�^�R���i�g�U���ԏ����̍�N6���A�O������u���Ȃ�����������(�R���i����)��������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ悭�d�b���������Ă���B����Ȑl�����̎���ɑ���"���Ȃ��̍��Ɠ��{�͖��x�̃��x�����Ⴄ�ƌ����A�݂�Ȍ������ށv�ƎQ�c�@�������Z�ψ���ɏo�Ȃ�����Ŕ���������������B
���{���{�̎��M�ɂ�������炸�A�L���҂͐��{�̖h�u�[�u��M�����Ȃ��ł���B��N����4�߂���Ă���ً}���Ԑ錾�ɂ��ւ�炸�A�V�^�R���i�g�U�̐��������܂�Ȃ����߂��B�҂�80%�ȏ�͓��{���{�����{�����ً}���Ԑ錾�͌��ʂ��Ȃ��Ɠ������B�ŋ߁A���{�����ً̋}���Ԑ錾���ߒn����g�債�A�����𗈌�12���܂ʼn����������Ƃɂ��Ă�70%�ȏ�́u���ʂ��Ȃ��v�Ɠ������B
���{�ɂ�����V�^�R���i�����҂�20����2��5871�l�������A�ߋ��ő����L�^�����B�O���ɂ͊����҂�1��6841�l�Ɍ��������A16������23���ɂ����āA�z������҂�15��9511�l���������B�����2�����O��6��23�����1�T�Ԃɂ�����V�K������(1��79�l)�̖�15.8�{�̐������B���̔����Ґ��Ɋւ��Ă��A�������\���ɍs���Ă��炸�A�������\���Ɏ����Ă��Ȃ��Ƃ����w�E���o�Ă���B
���{���{�ً͋}���Ԑ錾�̑Ώےn����g�傷��K�v�����邩�����������B���`�̎͂��̓��A�����N���o�ύĐ���b��c�����v�����J����b��W�t���Ƌc�_���A25���̐��ƕ��ȉ�ɏ��������߁A�ً}���Ԑ錾�Ώےn��̊g�储��щ����𐳎��Ɍ��肷����j���B
���u�e�q���q�ǂ����m�̊u������v�q�ǂ������g��@8/24
���܁A�f���^���̗��s�ŁA�q�ǂ������ɂ��������L�����Ă��܂��B
�s���ɂ���N���j�b�N�ɂ́A�����̂悤�ɔ��M�����q�ǂ�����������Ă��܂��B�挎���{�ȍ~�A���̃N���j�b�N�Ō��������q�ǂ��̒�����23�l�̗z�����킩�����Ƃ����܂��B
���ނ��@�E�c�����@���u7�����{����A�q�ǂ��̔��M���ŏ��B���̂��Ƃɐe�ɂ���ǗႪ�o�Ă����B�ԈႢ�Ȃ��f���^���̊����́B���́A��������A���ꂳ��ɂ������ہA�d�lj�����\�������邱�Ɓv
���ۂɐe�q�Ŋ������o��������e�ɘb���܂����B�s���ɏZ�ޏ����̕v�͒P�g���C���ŁA10�̒�����2�̎����ƏZ��ł��܂��B8����{�ɏ����ƒ����̃R���i�������킩��܂����B�����͉A���ł����B�����͖��Ǐ�ł������A�����͉Ǝ����ł��Ȃ����炢�A�������ӊ��⑧�ꂪ�������Ƃ����܂��B
���g�ƒ����������E�̕�e�u�������{���ɒ��q�����������Ƃ��́A�q�ǂ��̂��Ƃ܂ŁA�C������Ă��Ȃ��Ƃ����̂������ȂƂ���B���̃X�}�z�Ǝq�ǂ���ipad�ŁA�r�f�I�ʘb�Ōq�����̂ŁA�������̕����ŐQ�Ă��āA�w������������d�b���Ă��āx�w�J�����z���Ŋm�F�ł���悤�ɂ��悤�ˁx�݂����Ȃ͎̂��O�ɘb���Ă����v
�C������Ȃ̂́A�R���i�Ɋ������Ă��Ȃ������̂��Ƃł��B
���g�ƒ����������E�̕�e�u���2�l�y�A�łׂ����肭�����Ă�̂ŁA�u���͐�Ζ������ȂƁB����ŏǏo�Ă��Ȃ����Ƃ��F��݂̂Ƃ��������������B��̎q�����̎q�ɂ����H�ׂ������肷�邱�Ƃ����邵�A�e�Ǝq�̊u�������A�q�ǂ����m�̊u���̕��������Ɠ���v
��q�Ƃ��ɁA23���܂łɗ×{���Ԃ��I�����Ƃ����܂��B
�������A���������q�ǂ������@�ƂȂ�A�Ƒ��Ɨ���Ĉ�l�ʼn߂����Ȃ���Ȃ�܂���B�_�ސ쌧���{��s�̕a�@�ł́A���w���̏��̎q���V�^�R���i�Ɋ������A���@���Ă��܂����B���@����10�����܂�B���e�ɉ�Ȃ��₵����s���͕�����ł��B
����܂��a�@���Ǘ��ҁE�{�{���K������ÃZ���^�[���u�����a������O�ł͂Ȃ��āA���@������e�̖ʉ�ł��Ȃ��̂Łg�I�����C���ʉ�h�Ƃ��A���������̂𗘗p���āA�ʉ�̋@�����Ă���Ƃ����̂����݁B�X�g���X��S���I���S�����邩��A������ɘa�ł���悤�Ȑf�ÂƊŌ�����v
���̎q�͑މ@�B12���Ԃ�ɕ�e�̌��A�邱�Ƃ��ł��܂����B
����܂��a�@���Ǘ��ҁE�{�{���K������ÃZ���^�[���u������������Α�����قǁA���x�͎q�ǂ������̒��ł̏d�ǂ��\��Ă���̂ł͂Ȃ����B���ܑ�l�̓��@�����������ԂȂ̂ŁA����������Ԃ��q�ǂ������ŋN����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��Ƃ����̂��A���܊뜜���邱�Ɓv
�����͂̋����f���^���̗��s�ɔ����A20�Ζ����̊����Ґ��́A������1�J����6�{�ȏ�ɋ}�����Ă��܂��B
�R���i����q�ǂ�����邽�߂ɂǂ������炢���̂��B�e�n�̊w�Z�ł́A�͍����Ȃ���ċx�ݖ����̏������}���Ă��܂��B�ً}���Ԑ錾���o����Ă����錧���̒��w�Z�ł͐��k��o�Z�������A�I�����C���ł̎��Ƃ𗈌�10���܂ōs�����Ƃɂ��܂����B��T�A���{�͊����҂������ɔ������邽�߁A�c�t���⏬���w�Z�ɍR�������L�b�g��z�z������j��ł��o���܂����B
��J���w�Z�E���r�`���Z���u�����ȂƂ���A��X�A����̂Ƃ���܂ŋ�̓I�ȏ�`����Ă��Ă��Ȃ��B���O�ޗ��Ƃ��Č����L�b�g�ɂ���āA�������琶�k�̐S���I�ȕ��S��������A�w�Z�����Ńg���u���̈������ɂȂ��Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ͔�����ׂ��B���ƌ��N�͉����ɂ��ウ�������B�����x�X�g�Ȃ̂��B����͑厖�ɁA�T�d�ɔ��f���A���f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�g�ċx�݉����h�����߂������̂�����܂��B�����s���z�s��26���܂ł������ċx�݂��A����5���܂ʼn�������ƌ��߂܂����B�V�w���X�^�[�g�̂킸��4���O�̌��f�ł��B���z�s�ł́A���ł�12�`18�܂ł̃��N�`���ڎ킪�n�܂��Ă��܂��B39�D1�p�[�Z���g��1��ڂ��I�����Ƃ����܂��B
�@ |
 �@ �@ |


 �@
�@ |
���V�^�R���i�@���ŐV����247�l�����@��Q�������{�݂Ŋg��@��錧�@8/25
��錧�Ɛ��ˎs��24���A�����ŐV�^�R���i�E�C���X�����҂��V���Ɍv247�l�m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�O�T�̓����j��(260�l)�Ƃقړ����K�͂Ŋ����҂̗v��1��8867�l�ƂȂ����B
���ɂ��ƁA�V�K�����҂̂���103�l���o�H�s���B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���317�E1�l�ŁA�O�T��119�E2%�B
�N���X�^�[(�����ҏW�c)�������������Ύs���̏�Q�������{�݂ł́A�V���ɓ�����2�l���������A�{�ݓ��̗z���҂͌v38�l�Ɋg��B���Ύs���Ɠ����s���̎��Ə��ł͗z���҂����ꂼ��v8�l�ɑ������B
�ق��ɁA24���܂łɊm�F���ꂽ�����҂̂����V����141�l��L452R�ψي��z���Ɣ����B�v��2825�l�ƂȂ����B�܂��A�����҂̂����V����279�l�����A�����̑މ@�E�ޏ��Ȃǂ͌v1��5912�l�ƂȂ����B
�����Îs���H�������z�B�@���@�������A����×{���̃R���i�����ҁ@8/25
���Îs��24���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂œ��@�������⎩��×{���̎s����ΏۂɁA�H���i������܂Ŗ����z�B������g�݂��n�߂��B�s���ł�8���ɓ����Ċ������}�g�債�����Ƃŕx�R�J�Еa�@(���s)�̃R���i�Ή��a���͂Ђ������A���@�ł��Ȃ��s�������邱�Ƃ��犴���҂̕s���ƕs�ւ̉����ɂȂ���B�s�ɂ��ƁA����ҋ@�҂ւ̎x���͕x�R�������Ƃ݂���B
���Îs�ł�8���ɓ����Ă���2�A3���������Ė��������҂�����A24���܂ł�98�l�̊������m�F�B�l��10���l������̐V�K�����Ґ��͌�����ʂƂȂ�Ȃǎ��~�߂��������Ă��Ȃ��B�s�Ȃǂɂ��ƁA18�����_��15�l�̎s�������@�������܂��͎���×{���ŁA�����ɂ͎s�ƕx�R�J�Еa�@���A���ŕa�����Ђ������Ă��錻���`���A�������O�ꂷ��悤�Ăъ|���郁�b�Z�[�W���o�����B�������A���a�@�ɐ݂���ꂽ�R���i�a��15���͗]�T���Ȃ��ŁA���̔��\�ɂ��ƁA�s���̌y�ǎ҂͓��@�ł��Ȃ���Ԃ������Ă���B
�S���I�ɂ́A�������g�債�Ă��铌������ȂǂŐH���̔z�z���s���Ă��邱�Ƃ���A�s�Ƃ��Ď���ҋ@�҂��x�����悤�ƁA�H����z�B���邱�Ƃɂ����B
�Ώێ҂́A����ҋ@�҂̒��ŁA�Ƌ���Ƒ��S������������ȂǐH�����B������Ȏs���B�z�B����̂̓p�b�N���т�g���g�H�i�A�َq�p���Ȃǂ����ɐH�ׂ邱�Ƃ̂ł���20�_�̋l�ߍ��킹�ŁA1�`2�l���т�1���A3�l�ȏ�̐��т�2���܂Œ����ł���B
��]�҂��s�Љ���ۂɌߑO8�����`���߂܂łɐ\�����߂A�ߌ�ɂ͐E��������ɓ͂���B���{���Ԃ͓��ʂ̊ԂŁA���Ɣ�͓����\�Z�̗��p�őΉ�����B
������24���́A�v�]��������2���тɎs�E����3����͂����B����A�������Z���^�[�������҂ɑ��Ď��{���Ă��錒�N�ώ@�ɍ��킹�Đ��x�����m���Ă��炢���p���i��}��B�s�Љ���ۂ̓c�����q�ے��́u�H������邱�ƂŁA�������Z���^�[�̌��N�Ǘ��ƍ��킹�ĕs������菜���Ă��������v�Ƙb�����B
���Z���ڐG�҂ɘA���u�����҂����āv�@�ی����A�Ɩ��N���Ł@���m���@8/25
�V�^�R���i�E�C���X�������}�g�傷�鈤�m���ŕی����Ɩ����N��(�Ђ��ς�)���A�Z���ڐG�҂ւ̒�����A�����ǂ����Ȃ���ԂɂȂ��Ă���B����ҋ@�����߂�A�����A�����҂��炵�Ă��炤�悤�˗����Ă���B���S���҂́u�l�I�Ɍ��E�B�����ɗ��炴��Ȃ��v�Ƃ���B
����܂Ŋ����҂��o����A�ی��������N��s�����A�ڐG�҂̗L�������A�Z���ڐG�҂ɂ��A���A���N��Ԃ��m�F���A������2�T�Ԃ̎���ҋ@�����߂邱�ƂŊ����g���h���ł����B
���ɂ��ƁA���������猧�NJ��ی����̔����߂�����u�Ή��ł��Ȃ��v�Ƃ̐�������悤�ɂȂ����B�����́A�������{��1���̊����҂�500�l���A18������͘A��1��l�����������B����×{�҂�8919�l(23������)�ɒB���Ă���B
�����҂ւ̕�����蒲����1�l�����ނ�2�`3���Ԃ��K�v�B������1�l�ɑ���Z���ڐG�҂�4�`5�l�o�Ă���Ƃ����A���S���҂́u�����҂�4�`5�{�̎��Ԃ��̓d�b�ɔ�₷���ƂɂȂ�1��24���Ԃł͑���Ȃ��v�Ƒł�������B
�����������������̎��Ԃ�z�肵�����������nj������̗v�̂Ɋ�Â��A���͔Z���ڐG�҂ɗD�揇�ʂ����ĘA���A��������悤�N������ی����ɓ`���Ă���B�����҂ւ̕������ŁA(1)����҂��b����������ȂǏd�lj����X�N������l�ɔg�y���鋰�ꂪ����(2)�ڑ҂����H�X�ȂNJ����g�債�₷���ɂ������A�Ƃ����Z���ڐG�҂ɂ͕ی������A�������B�����Ƒ����̊�������x�̘A���Œ������ςނ��߁A�ی������Ή����Ă���B
����ɓ��Ă͂܂�Ȃ��ꍇ�A�Ⴆ�Ή�Г��Ŋ����g�債�Ă���ꍇ�́A��ƂɔZ���ڐG�҂ւ̘A���⒲�����ς˂�P�[�X������B
�܂��A��ғ��m�̃o�[�x�L���[�⒇�Ԃ����ł̉�H�A���݉�A���O����u���m���ɔZ���ڐG�҂�����v�ƘA�������悤�ȔZ���ڐG�҂́A�u�n��ɂ���Ă͕ی�������A���͂܂��ł��Ă��Ȃ��v�Ƃ��Ă���B
���̏ꍇ�A���������������l����Z���ڐG�҂ɘA�����Ă��炢�A����ҋ@�����߂�悤�`���Ă���B�����҂��A�����Ȃ���A�Z���ڐG�҂�����m��Ȃ��܂ܓ��퐶���𑗂鋰�������B���S���҂́u���P���ŐM���邵���Ȃ��B�̒��Ɉٕς��o����A�����Ō������Ă��炤�����Ȃ��v�Ƃ���B�@
���ċx�݉����A���U�o�Z���@�R���i�g��ŕs���L����@8/25
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g�傪���܂�Ȃ����A�ċx�ݖ����̊w�Z�ĊJ�Ɍ����A�S���̎����̂��Ή��ɋꗶ���Ă���B���{�͑S����Ă̋x�Z�͗v�������A�����̂ɑΉ����ς˂�ӌ��B����Ŏq�ǂ���ʂ��ĉƒ�Ɋ������L���錜�O������A�ċx�݂̉����╪�U�o�Z�����߂鎩���̂��o�Ă���B
�V�w���̑Ή��ɂ��āA�����c���ꕶ���Ȋw����20���A�u�n��̎���ɍ��킹�Ĕ��f��ς��Ă����Ƃ������ƂŁA���Ƃ��Ă̈�ċx�Z�͍s��Ȃ��v�Ɛ����B���̂��ߎ����̂̔��f��������Ă���B
�D�y�s�ł͗\��ʂ�A23�����璆�w�Z��2�w�����n�܂����B����A�����s�͌����_�ň�ċx�Z�͋��߂��A�ɉ����Ď����o�Z��Z�k���Ƃ̌�����v������ʒm���o�����B���{����ċx�Z�͂��Ȃ����A�C�w���s���������������ق��A�������̈ꕔ�𒆎~�ɁB���m�����C�w���s�̋x�~����������ȂǁA�s���������������͍L�����Ă���B
����A���l�s�͎s���̏����w�Z�Ȃǖ�500�Z��ΏۂɁA26���܂ł̉ċx�݂�������31���܂ŗՎ��x�Z�ɂ����B�s���ς̒S���҂́u�������������A�ی�҂���ĊJ��s�������鐺����ꂽ�v�Ɩ������B�_�ސ쌧���ł͐��A���͌����s�������w�Z��8�����܂ł̋x�Z������B�����s���z�s�͏����w�Z��9��5���܂ŋx�Z�ɂ����B
���U�o�Z�ɓ��ݐ�P�[�X�������B�Q�n���̌����w�Z�ł�2�w���̎n�Ǝ�����9��12���܂ŁA���k����Č��œo�Z�B�F�{�s�ł͏����w�Z�ɂ��āA�I�����C�����ƂƓo�Z�����w�N���Ƃɕ����������1������10���܂œ�������B
���ł́A�������Z��2�w���̎��ƂʃI�����C���Ŏ��{�B�����ς̒S���҂́u���Z�͒ʊw�G���A���L���A�������X�N�������w�Z��荂���v�Ɛ������Ă���B���{�Q����s���ċx�ݖ����̓o�Z�������킹�A�����w�Z��8��27���܂ŃI�����C�����ƂƂ��Ă���B
���{�͊w�Z�ł̊����h�~��Ƃ��ď����w�Z�ɍR�������̊ȈՃL�b�g��z�z������j�B���E���̃��N�`���ڎ���������A10��ȉ��̎q�ǂ��̊������}�����钆�A�����̂���́u�ʼn߂ł��Ȃ��ɂȂ�Έ�ċx�Z�����f�Ƃ��Ă��蓾��v(�g���m�����{�m��)�Ƃ̐����o�Ă���B
��8�����ً}���Ԑ錾�g��A���{�����ȉ�ɒc�܂h�~��4���lj� �@8/25
���{��25���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A�k�C���A�{��A�A���m�A�O�d�A����A���R�A�L����8�����ɋً}���Ԑ錾�߂���Ă���Ƃł����{�I�Ώ����j���ȉ�Ɏ������B
���{�Ăł́A�錾�ɏ������u�܂h�~���d�_�[�u�v�����m�A����A�{��A�����4���ɒlj�����B���Ԃ͂������27������9��12���܂ŁB���{�Ă��������肳���A�錾�͔��ߒ��̓����s�Ȃǂ��܂߂�21�s���{���A�d�_�[�u��12���Ɋg�傷��B
���R���i�ɑł�͂���I�@��ԃ��b�N�_�E���Łu������9�����v�̎��Z�@8/25
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɑł�Ȃ��̐��`�̎B����I�ł����b�N�_�E��������ɓ���Ă悳���������A��̑I���������������ɂ͂��̑I���͖����Ȃ悤���B
�u30��A40��̊��҂Ɂw�ň��̃P�[�X���o�債�Ă��������x�ƌ����͖̂{���ɂ炢�v
�����b���̂́A��s���𒆐S�ɍݑ��ÃN���j�b�N���^�c����I�ĉ�̍��X�؏~��t���B
�]�����ɔ�ׂĊ����͂������f���^���́A�Ⴂ����ł��d�lj�����P�[�X�������Ă���B���X�؈�t��������B
�u����×{�����Ă���l�̐f�Âɍs���ƁA�_�f�O�a�x��90������Ă���l������B�{���Ȃ瑦���@�ł����A�x�b�h�ɋ��Ȃ��B�_�f���z�����A���ǂ�h�����߂̃X�e���C�h�܂𓊓����Ă��a��������l������v
9��6709�l�B����͌����J���Ȃ�8��20���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�����Ŏ���×{�����Ă���l�̐���(18���ߑO0�����_)�B�O�T����2��2646�l�̑����ŁA10���l��˔j����͎̂��Ԃ̖�肾�B
�u���̓����́A�\�����͕��a�Ɍ����܂��B�������A���Ԃ͐V�^�R���i�œK�Ȉ�Â����Ȃ��l����������B���������Ƃ����g���ꂫ�h�̉��ɁA�����l���̐l��������Ă����Ԃł��v(���X�؈�t)
��t�����s�ł́A�V�^�R���i�Ɋ�������30��̔D�w���A�̒����}�ς������ߓ��@���T�������A�v9�J���̈�Ë@�ւɖ����Ȃǂ𗝗R�ɒf���A���@�悪�݂���Ȃ��܂���ŏo�Y���A�V�������S���Ȃ����B
20���ɂ͑S���m����I�����C����c���J���A�u�ً}���Ԑ錾�Ō��ʂ����������Ȃ����Ƃ������v�Ǝw�E�B���������銴���҂�}���邽�߁A���b�N�_�E��(�s�s����)�̂悤�Ȑl�������炷��̎��{�𐭕{�ɋ��߂邱�Ƃň�v�����B
�����A���`�̎̓��b�N�_�E���ɔے�I���B���@�W�҂͂����b���B
�u���b�N�_�E���͌o�ςւ̉e�����傫�����ɁA�����Ґ���}������ʂ͏��Ȃ��B���͂����l���Ă���B�I����O�ɁA���������ɐT�d�Ȍ����}�ւ̔z��������B���b�N�_�E���͕���p���傫���A�⏞��������(������)�ɂȂ邱�Ƃ����ɓI�ȗ��R�ł��傤�v
���̂��Ƃ��ے�����悤�ȏ�ʂ��������B���͊����}���̂��߂̃��b�N�_�E���ɂ��ċL�҂��畷�����ƁA�E��̌��������āu���E�Ń��b�N�_�E��������A�O�o�֎~�ɔ��������Ă��Ȃ��Ȃ���邱�Ƃ��ł��Ȃ���������Ȃ��ł����v�ƌ�C�����߂��B�j���[�W�[�����h�ȂǁA���b�N�_�E���Ŋ�����}�������͂�������B�������A���̂��Ƃɂ͐G��邱�Ƃ͂Ȃ������B
24���ɂ͓����p�������s�b�N���J���B���W�҂͂����b���B
�u�I�����s�b�N�������Ă��A���̖�2�T�Ԍ�Ɏn�܂�p�������s�b�N�ł͊����҂��}������͍̂ŏ�����킩���Ă����B�Ȃ̂ɐ��{�͔��{�I�ȑ���������Ă��Ȃ��B�ň��̏ł̑��ɂȂ��Ă��܂����v
�����A���������������̂��̂ɂȂ������̏ł��A���邱�Ƃ͂܂�����B����ȉ\������������������B
�}�g��̑q���ߖ狳��(�Љ�V�~�����[�V�����w)�́A����I�ȃ��b�N�_�E���������ꍇ�A�����s��15�Έȏ�̊����Ґ��Əd�ǎҐ��̐��ڂɂ��āAAI(�l�H�m�\)���g���ė\�������B
���Z�ł́A8��13��19�����_�̓����s���̎�v�ɉ؊X�̑ؗ��l������ɂ��āA�l�o���ǂ̒��x�������犴���Ґ����}������邩���V�~�����[�V���������B
���̌��ʂ͋����ׂ����̂��B�ؗ��l��������Ȃ��ꍇ�A�����s�̐V�K�����҂�10��1���ɖ�1��5��l�ɂȂ�A�s�[�N�ƂȂ�12��1����2��8636�l�܂ő���������B����A�ؗ��l����4�����炷��10��1���ɂ�1500�l�ȉ��܂Ō����B���̌�͓����x�̐����Ő��ڂ��Ă����B10��1�����_�Ŗ�10�{�̍����o�邱�ƂɂȂ�B�q�������͌����B
�u�ߋ��̃f�[�^�����Ă��A���Ԃ̑ؗ��l���͊����Ґ��̑����ɑ傫�ȉe����^���܂���B��Г��ł́A�}�X�N����łȂǂ̊����O�ꂳ��Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B����A19�����_�̑ؗ��l�����������炷�����ŁA�����Ґ��̑����ɑ傫�ȕω������邱�Ƃ��킩��܂����v
���̂悤�ɁA�n��⎞�Ԃ����肵�����b�N�_�E���͐��E�Ŏ��{����Ă���B�q�������͑�����B
�u�����}���ɐ������Ă����p�ł��A�������m�F���ꂽ�n���Ǝ�Ƀs���|�C���g�Ō��i�Ȍx���[�u�����{���Đ��ʂ������Ă��܂��B���{�ł�����p�̏��Ȃ��`�ł̃��b�N�_�E���͉\�ł��傤�v
���́A���ۂɂǂ̂悤�ɂ��Đl�̈ړ������炷�����B����܂ŌJ��Ԃ���Ă����ً}���Ԑ錾�ŁA�����Ɂu���l�v�𑣂��Ă����ʂ�����Ă��邩�炾�B
�����ǖ@��V�^�C���t���G���U�������ʑ[�u�@�ł́A�l�ɔ����t���̍s���������ۂ����Ƃ͂ł��Ȃ��B������Ƃ����āA�����ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�ЊQ���̖@���^�p�ɏڂ����Ëv��i�ٌ�m�͌����B
�u�䕗�㗤���\�z�����ƁA�S����Ђ͌v��^�x�����܂��B����Ɠ��l�ɁA�V�^�R���i���ЊQ�ƂƂ炦�A�d�Ԃ�3�����x�^�x����ΐl�̓�����}���邱�Ƃ͉\�ł��v
�Ëv�䎁�́A�Z���W���^�̃��b�N�_�E�����咣����B
�u���ً̋}���Ԑ錾�́A�I��肪�������A�_���_���Ƒ����Ă���B��������Z���W���Ńs���|�C���g�Ŏ��{�����ق������̉e���͗}������B���{�́A���̏��ЊQ�ł���ƔF�����āA�������̂��������Ă����ׂ��ł��v
�^�}���ɂ́A���b�N�_�E���ɂ͌��@���������ċً}���ԏ���������K�v������Ƃ����ӌ�������B��������}�̉�h�ɏ������鍂�䐒�u�O�@�c���́A����ɑ��Ă������_����B
�u�����d�͕�����ꌴ�����̂ł́A���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@�ɂ���āA���ӂ̏Z���͍��ł��A�������Ă��܂���B���s���@�ł��A�����̈��S�Ɋւ�邱�Ƃ͈����x�̎��������͔F�߂��Ă��܂��B���b�N�_�E�������s���@�ʼn\�ŁA�⏞�Ɣ������Z�b�g�ɂ����@����^��}�����͂��Ă����ɂ���ׂ��ł��v
�����A���͖�}�����߂Ă���Վ�����̊J������ۂ������Ă���B�����ɂ́A�R���i��̑��������s�Ŕ����ӂ�����ɂȂ�A�����I�ɋ��n�ɗ�������Ă��܂������̋ꋫ������B
9��5���Ƀp�������s�b�N�������A����9�����Ɏ����}���قƂ��Ă̔C���������}����B����܂łɓ}���ّI�����{���A11���܂łɑ��I�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ّI���߂����ẮA��������������⍂�s���c�O�������炪�o�n�̈ӌ���\�����A���NJ܂݂��B�����}�W�҂́u���̂܂ܐ����O�@�I�́w��x�ɂ���̂��B�������낵���n�܂��Ă����������Ȃ��v�Ƙb���B
����A�Δj�Ό��������⏬��i���Y���������X�Ɛ������x����\������ȂǁA���ّI���[�ŏ��낤�Ƃ��铮���������B�ꂷ��B
�����w����w�Z�p���w�Z�����Z�Z���̒����p�b��(�����NJw)�͌����B�u�f���^���͎q�������ǂ��A�ƒ��������h�����Ƃ͓���B�ɂ�������炸�A�����w����Ƀp�������s�b�N���ϐ킳���悤�Ƃ��Ă���B���̐����I���f�̎��s�̂��߂Ɏq���������]���ɂ��Ă����̂��B�����ɖ����w���S�E���S�x�̑��J�Â͎��s���܂����v
�������E�ݓc���@�R���i�Ђ̌o�ς́g���厑�{��`�h�����߁u��蕪�z���ӎ��v�@8/25
�����}���ّI�̓�����26���Ɍ��܂�B�����[�����߂鐺�����邪�A���������ڂ����ݓc���Y��(64)�ɁA���ّI�ւ̈ӗ~���ɂ��ĕ������BAERA 2021�N8��30�����̋L�����Љ��B
�������{�̐V�^�R���i�E�C���X��́A�ǂ��l���Ă��܂����B
�������𒆐S�ɖڂɌ����Ȃ��G�Ƃ̐킢�ɍőP��s�����Ă���Ǝv���܂��B����ō����̕s�����L�����Ă��邱�Ƃ������ł��B��肵������Ɗ����h�~�A�o�ϑ��i�߂Ă����Ȃ�������܂���B�����h�~�ɂ��ẮA���N�`���̐ڎ�͑�ϗL���ł����A���̓_�ɂ��ẮA���������������[�_�[�V�b�v�����Ă���Ǝv���܂��B
�������ɉ���Ă���Ƃ̎w�E������܂��B
��������ƍ����ɐ������A�����ɋ������Ă��炢�A�����ɋ��͂��Ă����Ȃ���A�ǂ̐�������܂������܂���B�����̋��͂ɂȂ��Ă������ƂɁA���w�͂����Ă������Ƃ��厖�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
������̓I�ȑ�́B
���N�`�������łȂ��A�a���̊g��A�V�K�����҂̊g��h�~�A���Ö�̊J�����͂����Ȃ�������܂���B���̎l�̐�����o�����X�悭�i�߁A��̓I�Ȑi�W�������Ă������Ƃ������̈��S�ɂȂ��Ă������߂ɏd�v�ł��B�n���Ǝ�ɂƂ���Ȃ��A���Ƃ̋K�͂⌸���̋K�͂����Ă����x�����߂���B�������������̂��p�b�P�[�W�Ƃ��Ď������Ƃ��厖�ł��B
����6���Ɂu�V���Ȏ��{��`��n��c���A���v�𗧂��グ�܂����B
�A�x�m�~�N�X�͓��{�̌o�ς𐬒��������傫�Ȑ������Ǝv���Ă��܂��B�����A����̎��{��`�͎q�ǂ��̕n�����͂��ߊi���̖��A���z�̖�肪�傫�ȉۑ�ł��B���������i���ɂ���ď���g�債�Ȃ��A�o�ς̍D�z���������Ȃ��B�i���ɂ���Đ�����Љ�s����ɂȂ��Ă���Ǝw�E����Ă��܂����B�����ĐV�^�R���i���ǂ��ł��������A�i�����g�傳���Ă��܂����B���ꂩ��܂��o�ς𐬒������邱�Ƃ��l�����ꍇ�A���z�ɂ��Ă���������l���Ă����Ȃ��ƁA�܂��܂����̎��{��`�̖��_��傫�����Ă��܂��B�i���̖��ɓK�ɑΉ����邱�Ƃɂ���āA�Љ�̈�̊�����������m�ۂ��Ă����K�v������Ƌ����v���Ă��܂��B
�����ǂ�Ȑ�����l���Ă��܂����B
���Ԃɂ����镪�z���l�����ꍇ�A������Ђ̂���悤���l���Ȃ�������܂���B�V���R��`�E�s�ꌴ����`�̂��ƂŁA�����̉ʎ��͊���A���邢�͌o�c�҂��Ɛ肷�邱�Ƃ����`�ł��邩�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����ł͂Ȃ��āA�]�ƈ���n��A�����ȂǗl�X�ȃX�e�[�N�z���_�[�ɉʎ������z����銔����ЁA���{��`���l���Ă����K�v������܂��B�Ő��ɂ����ẮA�������ґw�ƒ��ԑw�A�Ꮚ���ґw�̊ԂœK�ɕ��z���s���Ă���̂��낤���B������1���~����Ɛŕ��S��������u1���~�̕ǁv���w�E����Ă��܂����B�Z��⋳��̕��S�͒��ԑw���ł��傫���Ƃ̎w�E������܂��B���Ăł́A�V�z�����łȂ����݂⒆�ÏZ��̗��ʂł����ԑw�𒆐S�Ɏx�����Ă��܂��B���{�ł����������������x�����邱�Ƃ��l�����܂��B��������ɂ����Ă��A(�w��������ɉ����Č㕥������)�I�[�X�g�����A�́uHECS(�������狒�o�����x)�v������������ǂ����B
�����A�x�m�~�N�X�ł́A�L���Ȏ҂��x�߂Εn�����҂ɂ��x���H�藎����Ƃ����u�g���N���_�E���v�������Ă��܂����B
�A�x�m�~�N�X��������Ȃ��āA��������̐V���R��`�A�o�ϑ����Ƃ����Ӗ��ł́A�傫�ȈӖ����������Ǝv���܂��B�����A�g���N���_�E���͋N����ƌ���������ǁA���Ȃ��Ƃ����͂܂��N���Ă��Ȃ��B�V�^�R���i�Ŋi�����傫���Ȃ�������A��蕪�z���ӎ����Ȃ��Ƃ����܂���B
���������}�̒��N�̐����ς���Ƃ������Ƃł����B
����A�����}�͌o�ς̐��������[�h�����_�ł͑傫�Ȗ������ʂ������Ǝv���܂��B���z������̂����炸���ĕ��z�Ƌ���ł��A�����͒N�����Ă��Ȃ������Ƃ����̂����̖�}�̂���悤�ł��B�����}�����z�������Ă����A��̓I�Ȍ��ʂɂȂ���ƐM���Ă��܂��B
�����u�����E�����E�����v���f���鐛�ւ̑R�ł����B
������Ƃ̑Η����Ƃ������ƂŐ�����l���Ă��܂���B�����Ƃ����l�����͑�Ϗd�v�ȍl�������Ǝv���܂����A�������̓R���i�Ђ̒��ʼn��߂ĉƑ��⒇�Ԃ̋��͂��J�̑����Ɋ����܂����B���݂��ɏ��������Љ�A�����݂̂���Љ�A�F��⋦�͂̉���������������悤�ȎЉ����������ڎw���Ă����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
���f���^���u����܂łƈႤ���x���v�@�~�����Ŋ����ґ��̌��O���@8/25
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����A���{�ً͋}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɁA���m�A�L���Ȃ�8������lj�����B�����J���ȂɐV�^�R���i�������������Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h(AB)�v��25���̉�ŁA�S���̐V�K�����Ґ��ɂ��āu1�J���߂��ߋ��ő�̐������X�V�������Ă���v�Ƃ��A��s���Ɣ�ׂĂ��̑��̒n��̑��������傫���Ȃ��Ă���ƕ��́B����̌��ʂ��ɂ��āu���~�����̎Љ���̑����ɂ��A����Ɋ����Ґ�����������\��������v�ƌx����炷�B
�u�����͂�����(�C���h�R����)�f���^��������܂łƂ͈Ⴄ���x���̃E�C���X���Ƃ�����@�����s���Ǝs�������L���Ăق����v�BAB�����̘e�c�����E���������nj��������͉��̋L�҉�ł����Ăт����A�s����������Ƒ�����邽�߂ɊO�o������܂ł̔����ȉ��Ɍ��炷�悤���߂��B
����1�T��(18�`24��)�̐l��10���l������̐V�K�����Ґ����A���������������u�X�e�[�W4�v(25�l�ȏ�)�̐����ɒB�����̂�44�s���{���A100�l�ȏ�ƂȂ����̂�17�s�{���������B���ꌧ��314�l�A�����s��233�l�Ɗ�@�I�Ȑ����B���A�����A�ΐ�A���������43�s���{���ŁA����1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ����O�T(11�`17��)���������Ă����B�����X�s�[�h���݉����Ă���悤�ɂ݂��鉫��A�����ɂ��āu�����Ґ��̋}���⌟���z�������㏸���Ă���ł́A���ۂ̊����Ґ����ߏ��ɕ]������Ă���v�Ƃ̎w�E���������B
�����҂̔����I�ȑ����ɔ����A�S���̏d�ǎҐ��͘A���ő����X�V�B24�����_��1964�l�ƂȂ�A���҂̑��������O�����B���������͉�ŁA����܂ŕ��ꂽ���Ґ��⒆���ǁE�d�ǎҐ�����A24�`30���̎��Ґ���1��������ő�őS��45�l�A����10�l�������܂��Ƃ����\�����������B
�����s��w�����������ɂ��ƁA�����̎�v�ɉ؊X�̖�ԑؗ��l���́A�~�����̂킸��1�T�Ԃ�6�E2���������Ă���A�錾�O�Ɣ�ׂĂ���3�����̐����ɂƂǂ܂��Ă���B
�����A�ċx�ݖ����̊w�Z�ĊJ�ɂ��āA�e�c�����́u�f���^���̗��s�ł����Ă��A���s��}���邽�߂̋x�Z��w�Z���͕K�v���Ȃ��v�ƕ��́B������͏������Z�A��w�ňقȂ�Ƃ��āA�u��w�ł͂Ȃ�ׂ������[�g���Ƃ��K�v�Ƃ����c�_���������B������S�����ł��N���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă���A�����ɉ����ĉ����⒆�~���������Ăق����v�ƌ�����B
���u����邽�ߕK�v�ȍs�����v�V�^�R���i ���J�Ȑ��Ɖ �@8/25
�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����S���ŘA���A�ߋ��ő����X�V����ȂNj}���Ȋ����g�傪�������A��ɂ��ď�����������J���Ȃ̐��Ɖ���J����܂����B�S���I�ɂقڂ��ׂĂ̒n��ł���܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������g�傪�����A���S����l�̐�������傫���������邱�Ƃ����O�����Ƃ��āA�u������邽�ߕK�v�ȍs�����v�Ƃ�������܂łɂȂ������\���ŁA�O�o���Œ�ł�����܂ł̔����ȉ��̕p�x�ɂ���Ȃǂ̑�����悤�Ăт����܂����B
���Ɖ�́A�����ɂ��ĐV�K�����Ґ���1�����߂��ߋ��ő��̐������X�V�������A����܂œ��ɑ������ڗ�������s�������łȂ��A���ɒ������ȂǑ��̒n��ł������̃y�[�X�����܂��Ă��āu�S���I�ɂقڂ��ׂĂ̒n��ł���܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������g�傪�p�����Ă���v�Ǝw�E���܂����B
���~�����ɐl�o���������Ă��č��コ��Ɋ����Ґ�����������\��������A�d�ǎ҂̐����ߋ��ő��ɂȂ荂��̊����҂⍂��Ҏ{�݂ł̃N���X�^�[���������Ă��邱�Ƃ���A����A�S���Ȃ�l������ɑ傫���������邱�Ƃ����O�����Ƃ��āu����܂łɂȂ��ЊQ���x���̏ɂ���Ƃ̔F���ł̑Ή����K�v���v�Ƃ����F���������Ă��܂��B
����ɁA�V�^�R���i�Ɋ������������ǂ�d�ǂ̊��҂̓��@����������ɂȂ��Ă������A����A����Ɉ�ʂ̈�Â���������A�~�}����������ɂȂ�P�[�X���o�邱�Ƃ��\�z�����Ƃ��āA�u�ꍏ���������܂̊����g���}���邱�Ƃ��K�v���v�Ɗ�@���������܂����B
�n��ʂɌ���ƁA�����s�ł͊��������̃X�s�[�h�͂��݉����Ă�����̂́A�����X���͑����Ă��āA���@�Ґ���20�ォ��50��𒆐S�ɑ����������A�l�H�ċz��Ȃǂ��g�p���Ă���d�ǎҐ���40�ォ��60��𒆐S�Ƃ��č��~�܂�̏�Ԃʼnߋ��ő��̐����������Ă���A�V���ȓ��@�̎����~�}����������ȃP�[�X��A��ʈ�Â𐧌����鎖�Ԃ��N���Ă��܂��B
�܂��A��ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�ł��a���̎g�p�����}�����Ă��āA�����s�Ɛ�t���ł͂��~��������ɉ؊X�Ȃǂł̖�Ԃ̐l�o�������ɓ]���Ă���Ƃ��Ă��܂��B
���ꌧ�́A�ߋ��ɗ�̂Ȃ������̊����ŕa���g�p����9���߂��ɂȂ��Ă������A��Ԃ̐l�o�͂��~�������猸���ɓ]���Ă��Ċ����̌����ɂȂ��邩�������K�v�Ƃ��Ă��܂��B
���Ɖ�́A��s���≫�ꌧ�Ȃǂł͎��ۂ̊����Ґ����ߏ��ɕ]������Ă���Ƃ����w�E������A�����̕��͂ɂ͒��ӂ��K�v���Ƃ��Ă��܂��B
�܂��A���m����É����Ȃǂ̒����n������{�Ȃǂł������҂̋}���ȑ����������A����������g�傪�p������\��������Ƃ��Ă��܂��B
���̂��߁A���Ɖ�́u������邽�߂ɕK�v�ȍs�����v�Ƃ�������܂łɂȂ������\���ŁA�ӂ�����Ȃ��l�Ɖ�@����ł��邾�����炷���Ƃ�A���łɃ��N�`����ڎ킵���l���܂߂ĊO�o���Œ�ł�����܂ł̔����ȉ��̕p�x�ɂ���悤�Ăт����܂����B
����Ɋ����͂̋����f���^�������s����10��ȉ��̊����Ґ��������X���ɂ��邽�߁A��w�Ȃǂł̃I�����C���ł̎��Ƃ̎��{��A�ߓx�ɖ��W����C�x���g�̉����⒆�~�̌����A���C�Ȃǂ̑�̓O������߂܂����B
�܂��A�s���{������̂ƂȂ��Ēn��̈�Î������ő�����p���A�d�lj���h�����Ƃ����҂����R�̃J�N�e���Ö@�̗��p��A�d�lj��ɐv���ɑΉ��ł���̐��̐����ȂǁA�S���I�Ɍ��������������ʑ����Ƃ����O��ŁA�Վ��̈�Î{�݂Ȃǂ̐����Ȃǂ̑��i�߂�K�v�����������܂����B
���ɉ؊X�́g�ؗ��l���h �����ł͖�Ԃ̐l�o���Ăё���
���Ɖ�ł́A����22���܂ł̑S���̎�v�Ȕɉ؊X�̐l�o�̃f�[�^��������܂����B�����s�ł͖�Ԃ̐l�o���Ăё������Ă��܂��B���̃f�[�^�́A�����s��w�����������Љ�N��w�����Z���^�[���A25���̌����J���Ȃ̐��Ɖ�Ŏ����܂����B�e�����̂̎�v�Ȕɉ؊X��ΏۂɌl����肵�Ȃ��`�œ���ꂽ�g�ѓd�b�̈ʒu���A�E��⎩��ȊO��15���ȏ�؍݂��Ă����l�̐����u�ؗ��l���v�Ƃ���500���[�g�����b�V���Ŏ��Ԃ��Ƃɕ��͂��Ă��܂��B����A���͂̑ΏۂƂȂ����̂͂����������22���܂ł̃f�[�^�ł��B
����s����
�����s�ł́A�V�h��a�J�A�Z�{�Ȃ�7�����̔ɉ؊X�̃f�[�^�����ɕ��͂��Ă��܂��B�s���ł͖�Ԃ̑ؗ��l�������~������1�T�Ԃ�6.2���������A7�T�����Ă��������X���������ɓ]���Ă��܂��B���ɁA�����̃��X�N�������Ƃ����ߌ�10������[��0���܂ł̎��ԑтł͑O�̏T����10.6�������Ă��āA����1�T�ԂŌ����ɑ������܂����B�܂��A���Ԃ̑ؗ��l�������~������1�T�Ԃ�5.3���������܂����B�܂��A���{�̕��ȉ�͓����s�̐l�o������ً̋}���Ԑ錾�̒��O��7���O���ɔ�ׂ�50�����炷�悤���߂Ă��܂����A��Ԃ̑ؗ��l���͐錾�O�����29.6���̌����A���Ԃ̑ؗ��l�����錾�O����19.4���̌����ɂƂǂ܂�܂����B
��t���ł́A��Ԃ̑ؗ��l�������~�������瑝���ɓ]���Ă��܂��B���Ԃ̑ؗ��l���������ɓ]���܂����B
�_�ސ쌧�ƍ�ʌ��͖�Ԃ̑ؗ��l���͂��~���������������A��4�g�̍ۂ̍Œᐅ���߂��ʼn����Ő��ڂ��Ă��܂��B���Ԃ̑ؗ��l���͑������n�߂Ă��܂��B
������
���{�ł́A�ً}���Ԑ錾���o����Ĉȍ~��Ԃ̑ؗ��l����2�T�A���Ŋɂ₩�Ɍ������Ă��܂������A���~������1�T�Ԃʼn����~�܂��Ă��܂��B���Ԃ̑ؗ��l���������ɓ]���Ă��āA���A��Ƃ��ɍ��������ƂȂ��Ă��܂��B
���Ɍ��ł͖�ԁA���ԂƂ��ɑؗ��l����2�T�A���ő傫���������Ă��܂������A���~�����̒���1�T�Ԃł͉����~�܂��Ă��܂��B
���s�{�ł͖�Ԃ̑ؗ��l���͊ɂ₩�Ɍ������Ă�����̂̉����肫�炸�A��4�g�̍ۂ̍Œᐅ���Ɣ�ׂ�ƈˑR�Ƃ��č��������Ő��ڂ��Ă��܂��B
����B��
�������ł͖�Ԃ̑ؗ��l�������~������1�T�Ԃő����ɓ]���Ă��܂��B���Ԃ̑ؗ��l�����}���ɑ����ɓ]���Ă��܂��B
���ꌧ�ł͖�Ԃ̑ؗ��l�������~���Ԓ��������Ă��܂��������~�����̒���1�T�Ԃł͍Ăь����ɓ]���A���N��1��ڂً̋}���Ԑ錾�̍ۂ̍Œᐅ����������Ă��܂��B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
�������s�[�N�A�E�g�̒������@�V�K�����ҁA3���A���őO�T�̓����j�������@8/26
�����s��25���̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ���4228�l�������B23������3���A���őO�T�̓����j����������Ă���B���@���҂�d�ǎ҂͉ߋ��ő��ƂȂ�ȂLj�Ñ̐��͋ɂ߂Č��������A�����͂悤�₭�������肪�����Ă����̂��B
�V�K�����҂̒���7���ԕ��ς͑O�T��95�E2����4471�E4�l�ŁA6��19���ȗ���2�J���Ԃ�ɑO�T����������B
1�l�����l�ɂ����������������Đ��Y����1�ߕӂ܂ʼn������Ă����B�����g��̐�s�w�W�̈�Ƃ���锭�M���k�̌��������~�܂肵�Ă��邪�A24����2734����2�T�ԂԂ��3000������������B
�s���ً͋}���Ԑ錾�̔��߂���1�J���ȏオ�o�߁B�����͂������f���^�����}�g�債�A8�������Ŋ����Ґ���10���l���Ă��邪�A�����̖ʂł̓s�[�N�A�E�g������悤�ɂ��݂���B
�����A�����m�F���ǂ����Ă��炸�A�u�B��z���ҁv���������邱�Ƃ��l������B���~�x�݂���2�T�Ԃ��o�߂��A���ꂩ�犴���������鋰�������B���̂Ƃ���q���̊������}�����Ă���A�ċx�ݖ����̊w�Z�ł̃N���X�^�[�����O�����Ȃǖ��f�͋֕����B
�ڂ̑O�̊������[�����B25�����_�œ��@���҂�30�l����4154�l�A�d�ǎ҂�9�l����277�l�ł�������ߋ��ő��B����×{����30��j�����܂�11�l�̎��S���m�F�����Ȃǎ��҂������Ă����B
�S���I�ɂ݂�Ɗ����͊g��̈�r���B���{��25���̐V�K�����҂�2808�l�Ɖߋ��ő��ƂȂ����B�{�錧�∤�m���A���ꌧ�ł��ߋ��ő����L�^�����B
���{��27������ً}���Ԑ錾��21�s���{���A����(�܂�)�h�~���d�_�[�u��12���ɂ��ꂼ��g�傷��B47�s���{���̖�7���ōs�������̑[�u������邱�ƂɂȂ������A�ǂ��܂Ō��ʂ����邩�͋^���������Ă���B�K�}���̓��X�͂܂������������B
�������s�ŐV����4704�l�����@�d�ǎ�276�l 8/26
�����s��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����4704�l�A����11�l���m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B���ݓ��@���Ă���d�NJ��҂�276�l�B�V�K�����Ґ�(1�T�ԕ���)��4352.9�l�ŁA26�����_�őΑO�T��91.2���ƂȂ����B�s���̗v�̊��Ґ���32��7861�l�B
�N��ʂł́A20�オ1330�l�A30�オ896�l�A40�オ811�l�A50�オ512�l�ȂǂƂȂ��Ă���B65�Έȏ�̍���҂�248�l�������B���҂�50��j��3�l���܂�11�l�������B
������3717�l�ւ̃X�N���[�j���O�����ł́A�ψي��u�f���^���v�ɂ݂���ψفu�k452�q�v��3487�l�Ŋm�F����A�����͖�93.8���������B
��������v���Ɏ�ꂸ�����̊����Ґ��݂̉\�� - �@8/26
�����s�V�^�R���i�E�C���X�����ǃ��j�^�����O��c(��60��)��26���A�s���ŊJ���ꂽ�B���\���ꂽ�u���Ƃɂ�郂�j�^�����O�R�����g�E�ӌ��v�ł́A�V�K�z���Ґ��Ɋւ��āu������v���Ɏ��Ȃ����Ƃɂ��A����ɑ����̊����҂����݂��Ă���\��������v�Ǝw�E�B�u�ی����̑Ή��\�͂��͂邩�ɒ����鑬�x�ŐV�K�z���Ґ����������Ă���B�s�A�����s��t��A�n���t��A�����s��t����A�g���A�x�����Ă����K�v������v�Ƃ��Ă���B
�R�����g�E�ӌ��ł́A1��������4300�l����V�K�z���҂��p�����Ĕ������Ă��邱�Ƃ����グ�A�u���T�Ԃɂ킽��A����s�\�ȏ������Ă���v�Ǝw�E�B�u�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ�U�邤��펖�Ԃ����T�ԑ����Ă���B���͂�A�ЊQ���Ɠ��l�ɁA�����\�h�̂��߂̍s�����Ƃ邱�ƂŁA�����̐g�͂܂������Ŏ�邱�Ƃ��K�v�ł���v�Ƃ��A�s�D�z�}�X�N�̒��p��w�Z�����ł̊����h�~��̓O��Ȃǂ�v�]�B�u�Љ�S�̂Łw�q�������x�Ƃ����ӎ��̌[�����K�v�ł���v�Ƃ��Ă���B
�����̐��ɂ����y���Ă���A�u�s��PCR���̌����\�͂�ʏ펞7����/���A�ő�ғ���9��7�猏/���m�ۂ��Ă���v�Ǝw�E�B�u�����\�͂��ő�����p���A�������K�v�ȓs�������₩�Ɏł���̐��������K�v�ł���v�Ƃ��Ă���B�܂��A�s�����_�ȕa�@��×{�a�������a�@�A����Ҏ{�݂��Q�Ҏ{�݂̐E����Ώۂɒ���I�ȃX�N���[�j���O�������s���Ă��邱�Ƃɂ��G��A�u�����g���h�~���邽�߁A��葽���̎{�݂����������Q������K�v������v�Ƃ��Ă���B
���@���Ґ��ɂ��ẮA�O��(18�����_)��3815�l����25�����_��4154�l�Ƒ����X���ɂ��邱�Ƃ��w�E�B�u����×{���ɗe�̂����������V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊��҂̋~�}�����A���@����ꂪ����ɂȂ��Ă���v�u���@�d�_��Ë@�ւ̑������ʏ�̋~�}���҂̎������s���a�@�ł�����A�ً}��v��������a�C�̊��҂̋~�}�����A�����ɂ��傫�Ȏx�Ⴊ�����Ă���v�Ƃ��A�u�ЊQ���x���Ŋ������҈Ђ�U�邤��펖�Ԃ������Ă���v�Ƃ̌����������Ă���B
�d�NJ���(�l�H�ċz��܂���ECMO�g�p)�́A25�����_�őO�����2�l����277�l�ƂȂ��Ă���A�u�ɂ߂č��������Ő��ڂ��Ă���v�Ǝw�E�B17������23���܂ł�1�T�ԂɁA�V���Ɋ���183�l(�O�T��231�l)���l�H�ċz�����������ŁA137�l(��132�l)���l�H�ċz�킩�痣�E�����B�l�H�ċz��g�p���Ɏ��S�������҂�35�l(��12�l)�����B���̊��ԂɐV����ECMO(�̊O�����^�l�H�x)���������҂�17�l�A���E�������҂�13�l�����B25���̎��_��30�l��ECMO���g�p���Ă���B
�d�NJ��҂̔N��ʂ̓���ɂ��ẮA50�Αオ109�l�A60�Αオ58�l�A40�Αオ49�l�A70�Αオ27�l�A30�Αオ23�l�A80�Αオ6�l�A20�Αオ4�l�A10�Αオ1�l�ƂȂ��Ă���B�z������������l�H�ċz��̑����܂ŕ���6.0���A���@����l�H�ċz�푕���܂ŕ���2.0���ł��������Ƃɂ��G��A�u�a�����N�����A����×{��]�V�Ȃ�����Ă���×{�҂��d�lj����Ă���\��������v�Ƃ��Ă���B
���V�h��ŃR���i�����u22�l��1�l�v�@���y�X��������Ȃ��A������ł������@8/26
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g���2021�N8��25���A�ً}���Ԑ錾�̑Ώۂ�21�s���{���ɍL�������B���ł��[���Ȃ̂����ꂾ�B�������A���܂����Ă��Ȃ����A����23��̒��ɂ͂��łɉ���ȏ�Ƃ������銴���̂Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��B
���a�J��A�`��...�s�S�ɑ���
�R���i�����ȗ��̑S���s���{���̊����Ґ��́A��ΐ��ł͓�����1�ʁA2�ʂ���ゾ�B�������A�l��10���l������Ōv�Z����Ɖ���̊����҂�2658�l�Ńg�b�v�A������2307�l��2�ʂɂȂ�B�����́A�n��ɂ���Ă��Ȃ芴���Ґ����قȂ�B�s�S�悪�����A�����̎O�����͏��Ȃ��B�����V���̃r�W���A���f�[�^�T�C�g�u�����s���̐V�^�R���i�����܂Ƃ߁v�ɂ͓s�������̂̐l��10���l������̊����Ґ����o�Ă���B8��25�����݂ōł������̂́A�V�h��ŁA�l��10���l������4476�l�B�����ďa�J��3683�l�A�`��3507�l�B���̂ق��ڍ���A������3000�l���A�L����A������Ȃǂ��܂��Ȃ�3000�l��ɓ���B����͌��S�̂̃f�[�^�ł���A23��ƒP����r�͂ł��Ȃ����A�����ł͔ɉ؊X�⊽�y�X��������Ŋ����҂̔䗦���������Ƃ��킩��B�V�h��̐l���ɑ��銴���҂̊�����4.48���B��22�l��1�l�Ƃ��������ɂȂ��Ă���B
�������Ɩ������S�̕���
�s���e��̃E�F�u�T�C�g�ɂ́A���I�{�݂Ɋ֘A���銴����f�ڂ���Ă���B8���ɓ����Ă���̏��݂�ƁA�V�h��ł͋�������ő����̊������o�Ă���̂��ڗ��B���\��������ƁA�u�Ŗ��ہv�u���ی��ہv�u���������ہv�u��Õی��N���ہv�u�ی�S���ہv�ȂNj�����e�ۂ̖��O����ڂȂ����ԁB�����̊����҂��o���Ă���ۂ������B���ɍۗ��̂��u�ːЏZ���ہv���B���v10�l�ȏ�̊����҂��o�Ă���B�����Ɩ������S�ŁA���K�҂Ƃ̐ڐG���������������ɁA�����Əڂ�������m�肽���Ǝv���斯������ɈႢ�Ȃ��B�V�h�ł̓f�p�[�g�Ȃǂ̑�^���Ǝ{�݂Ȃǂł��������������Ă��邪�A�����������Ԃ̏͋�̃T�C�g�ł͂킩��Ȃ��B
���w�Z�ϐ����߂����
�����悤�ɏa�J��̃T�C�g������ƁA�旧�́u�ʏ����{�݁v�u�K���쎖�Ə��v�u�Ⴊ���ҕ����{�݁v�Ȃǂŕp�����Ă��邱�Ƃ��킩��B�E���◘�p�҂̊������A�قږ����̂悤�ɔ������Ă���B�`��ł́u�ۈ�{�݁v�u�q��Ċ֘A�{�݁v���ˏo���Ă���B8���ɓ����Ă���A��������قږ����A���킹�Đ��\���������Ă���B�ی�҂ɂƂ��Ă͕s�������B�`��̓p�������s�b�N�́u�w�Z�ϐ�v��\�肵�Ă������A���j����]�O�]�A�ŏI�I��24����A����߂Ă���B�����̂��Ƃ̊����̌��\�́A�S���ł��Ȃ�̗���������B���s�̃T�C�g������ƁA�u�V�^�R���i�E�C���X�����Ґ����悲�ƂɌ��\���Ăق����v�Ƃ����u�s���̐��v���f�ڂ���Ă���B
�s���̉Ƃ��āA�u�������̌��\�Ɋւ��ẮA�����ǖ@�ɂ����āA�������𖾂炩�ɂ��A�����Ƀ��X�N��F�m���Ă��炤����ŁA�����ғ��ɑ��ĕs���ȍ��ʁE�Ό��������Ȃ��悤�\���ɗ��ӂ��ׂ����Ƃ���߂��Ă���܂��v�u�s���悲�Ƃ̊����Ґ������\���邱�Ƃɂ��܂��ẮA�s���悲�Ƃ̊����Ґ��̑��ǂɂ��A�s���ȍ��ʁE�Ό��ɂȂ��鋰�ꂪ����ƍl�����Ă��邽�߁A�T�d�Ɍ������Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��v
���V�^�R���i ����504�l�����m�F �ˑR�����g�呱���@�k�C���@8/26
�����ł�26���A�V����504�l���V�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�Ɣ��\����܂����B�ˑR�Ƃ��Ċ����̊g�傪�����Ă��܂��B
�����̐V���Ȋ����m�F�́A�D�y�s�ōėz����4�l���܂�285�l�A����s��59�l�A���َs��20�l�A���M�s��15�l�A�Ύ�n����29�l�A�\���n����28�l�A�_�U�n����17�l�A�����n����16�l�A��m�n����10�l�A�I�z�[�c�N�n����7�l�A�@�J�n���Ƌ��H�n���ł��ꂼ��5�l�A��u�n���Ɠn���n���ł��ꂼ��2�l�A���n���Ɨ��G�n���ł��ꂼ��1�l�A����ɓ����u���̑��v�Ƃ��Ĕ��\�������O��1�l���܂�2�l�̂��킹��504�l�ł��B
����̊����m�F��500�l����̂�2���A���ƂȂ�A�ˑR�A�����g�傪�����Ă��܂��B
�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂́A�����S�̂�66.9�l�A�D�y�s��100.1�l�ƁA�s���{���̊������������̃X�e�[�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ��ƂȂ��Ă���10���l������25�l��傫�������Ă��܂��B
�܂��A�ψكE�C���X�̃f���^���ɂ��ĐV���ɁA�D�y�s��156�l�A����54�l�A���َs�Ə��M�s�ł��ꂼ��9�l�̂��킹��228�l���������Ă���^�������邱�Ƃ�������܂����B
����s�ł͌����̐����Ђ������Ă��邽�߁A���݁A�f���^���Ɋւ��錟���͍s���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
����A26���A�����ł͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ֘A���鎀�҂̔��\�͂���܂���ł����B
����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�3��4201�l���܂ނ̂�5��5038�l�ƂȂ�A���S�����̂�1437�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��������
25�����_�̓����̊����𐭕{�̕��ȉ�������̎w�W�����ƂɌ��Ă����܂��B�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂�26�����_�̐����ł��B
�a���g�p���@/�@�܂��A��Â̂Ђ�����ł��B�u�a���g�p���v�̓X�e�[�W3��20���ȏ�A�ł��[���ȏ������X�e�[�W4��50���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������44.8���ƂȂ��Ă��܂��B
���@���@/�@�u���@���v�̓X�e�[�W3��40���ȉ��A�X�e�[�W4��25���ȉ����ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������17.7���ƂȂ��Ă��܂��B
�d�ǎҕa���g�p���@/�@�u�d�ǎ҂̕a���g�p���v�̓X�e�[�W3��20���ȏ�A�X�e�[�W4��50���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������12.5���ƂȂ��Ă��܂��B
�×{�Ґ��@/�@�u�l��10���l������̗×{�Ґ��v�̓X�e�[�W3��20�l�ȏ�A�X�e�[�W4��30�l�ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������96.7�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����z�����@/�@�u����1�T�Ԃ̂o�b�q�����Ȃǂ̗z�����v�̓X�e�[�W3��5���ȏ�A�X�e�[�W4��10���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������10.2���ƂȂ��Ă��܂��B
�V�K�����Ґ��@/�@�u�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����ҁv�̓X�e�[�W3��15�l�ȏ�A�X�e�[�W4��25�l�ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A26�����_�œ�����66.9�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����o�H�s���҂̊����@/�@�u�����o�H���s���Ȑl�̊����v�́A�X�e�[�W3�A�X�e�[�W4�Ƃ���50�����ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������43.5���ƂȂ��Ă��܂��B
���O�d���́E���̒��~����@�R���i�}�g��ŊJ�Í���@�O�d���@8/26
�O�d�Ƃ��킩���́E�Ƃ��킩���(�S����Q�҃X�|�[�c���)�ɂ��āA��Â���O�d������{�X�|�[�c����Ȃ�4�҂�25���A�V�^�R���i�E�C���X�̋}�g��ŗ����̊J�Â͍���Ɣ��f���A���~�����肵���B
���͍̂�N�̎��������̂��V�^�R���i�̊����g��ŊJ�Â������������߁A2�N�A���̒��~�B��Q�҃X�|�[�c���́A�ߘa���N�̈����䕗�̐ڋ߂Œ��~�ƂȂ������߁A3�N�A���ƂȂ�B
���ɂ��ƁA���͈̂ꕔ���Z��������9��25���\10��5���A��Q�҃X�|�[�c����10��23�\25���ɊJ�Â���\�肾�����B���͊����҂̋}�����A21���ɕ��ȏȂȂǂɒ��~��\�����ꂽ�B
���̓��́A���Ɠ��{�X�|�[�c����A���{�Ⴊ���҃X�|�[�c����A�X�|�[�c����4�҂��I�����C���ŋ��c�B�`���������J����A��؉p�h�m�����u�f���̎v�������A�����̖�����蔲���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B
4�҂͑S���ł̋}���Ȋ����g��⌧���̈�Ò̐��ւ̕��ׂȂǂ܂��āu�J�Â��邱�Ƃ�����v�Ɣ��f�B����3�҂���́u��ώc�O�����A���~�͂�ނȂ��v�Ȃǂ̐����������Ƃ����B
���͗������s�ψ���̑�����߂��J���A�����J�Â���{�X�|�[�c����ɗv�]���邩���j�����߂�B�����ɂȂ�Ηߘa9�N�̊J�ÂƂȂ錩�ʂ��B
��؉p�h�m���͋��c��̂Ԃ牺�����ŁA�����̒��~����Ɂu���������Ă����I��A�����Ɏx���Ă����w���҂�ی�ҁA�y���݂ɂ��Ă��������̊F����ɑ�ϐ\����Ȃ��v���v�Ɠ����������B
����12���Ɏ��E���T���钆�A�����̐���ɂ��Ắu�����ƂƂ��āA6�N��̂��Ƃ�ސE�������܂��Ă���l�Ԃ��ŏI���f����͓̂K�ł͂Ȃ��B�O�����łł��邱�Ƃ͂��������肽���v�Əq�ׂ��B�@
�������}�g��łЂ��� �s���̌���g���E�h�߂Â��@�O�d���@8/26
�V���[�Y�u���ꂩ��v�ł��B�V�^�R���i�̊����̋}�g�傪�e�n�ő����Ȃ��A�O�d���̕ی����ł͋Ɩ����Ђ������A�Z���ڐG�҂ɑ���o�b�q�������x���ȂǁA�s���̑Ή������E�ɋ߂Â��Ă��܂��B
�O�d�� ��؉p�h�m���u����I�E�����I�Ȋ����g���(�����Ґ���)���オ�܂������Ȃ��v
�V�^�R���i�̊����҂��A���A�ߋ��ő����X�V���Ă���O�d���B
�ی����E���u���������܂��ƁA���ܑ�ςЂ������Ă܂��āA����(���N�ώ@��)�d�b���������Ȃ���ԁv
�Îs�̕ی����ł́A20�l�قǂ̐E�����ق�1�����A�d�b�@��������܂���B
�ی����E���u�o�b�q�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ŁA���X�g���p���N��ԁv
������{�ɗz�������������Îs�ɏZ�ޒj��(30��)�B�Ȃ�3�l�̎q�ǂ��ƕ�炵�Ă��܂����E�E�E�B
������{�ɗz�������� �j��(30��)�u�Ƒ��͊��S�ȔZ���ڐG�҂���Ȃ��ł����B�ی�������2�`3���A�o�b�q�������ł��Ȃ��ƁB���̊Ԃ�(�Ȃ�)���M�������āA�w�����ς��Ȃ̂ŁA���傤�͂o�b�q�����ł��Ȃ��x�̈�_����v
���ǁA�Ȃ�3����A�q�ǂ���1�T�Ԍ�ɂ悤�₭�o�b�q�������A�ȂƎq�ǂ�1�l�̗z���������B�Ȃ͗e�̂��������A�ꎞ���@���܂����B
������{�ɗz�������� �j��(30��)�u�s���ł���ˁB�w�����Ƃ���ǂ��Ȃ��Ă�����d�b���������x�Ƃ��A����ȕԓ��Ȃ�Łv
�����̂̐E���͂ǂ̂悤�ȘJ�����Ȃ̂��H�i�m�m�͈��m�E�E�O�d��125�S�Ă̎s�����ɃA���P�[�g�𑗂�A9���ȏ�̎����̂���܂����B
�������������̂ŐV�^�R���i��ɏ]������E����4684�l�B���̂����A����1�N�Ԃ̎��ԊO�J���Łu�ߘJ�����C���v�ƌĂ�錎80���Ԃ��Ă����E���́A�̂�1697�l�ɏ��܂����B
���C�n���̕ی����E���u���������o�^�o�^������ԂŁA�����������邱�Ƃő��̐l�ɖ��f��������ƁA�Ȃ��Ȃ��x�݂����Ȃ��v
�����b���̂́A���C�n���̕ی����ŃR���i�Ή��ɂ�����j���B�ŋ߁A�Ⴂ����𒆐S�ɁA�ی�������̓d�b��������A�����̐\����������Ƃ��������Ⴊ�p�����Ă���Ƃ����܂��B
���C�n���̕ی����E���u�e�ɒm����ƍ���Ƃ��A�E��ɒm����ƍ���Ƃ��A�����������E�B�w��������������ĉ��H�x�Ƃ����悤�ȁv
���s���͎�҈ȊO�ł��E�E�E�B
���C�n���̕ی����E���u������l�ł��w����×{����Ă��܂��x�ƌ����āA�d�b�̌��Ńp�`���R�̉�������������Ƃ��͕��ʂɁE�E�E�B�����̕��͋��͂��Ă���邪�A�ꕔ�̂��������������邱�ƂŁA�����g���h�~���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�ǂ�ǂ�L�����Ă��܂��v
�ߘJ�����C�������Ζ��𑱂���ی����E���̗̑͂ɂ����E���߂Â��Ă��܂��B
���ۈ�{�݂�9�l�����@���Ə��N���X�^�[��33�l�Ɋg��@���ꌧ�@8/26
���ꌧ��26���A�V����10�Ζ����`90�Έȏ�̒j��215�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�V�K�����Ґ���200�l����̂�3���A���B�����̊����m�F�͌v9786�l�ƂȂ����B�V�K�����҂͑S�����y�ǂ����Ǐ�B����×{�Ґ���1608�l�ŁA�ߋ��ő��̑O������125�l�������B
���Z�n�ʂł́A��Îs51�l�A���Îs28�l�ȂǁB�N���X�^�[(�����ҏW�c)�W�ł́A�V���ɑ�Îs�̕ۈ�֘A�{�݂ŐE���Ǝq�ǂ��v9�l�̊������܂łɊm�F�B�b��s�̐����Ǝ��Ə��ŏ]�ƈ�1�l�̊����������A�v33�l�ƂȂ����B
����21�A24���ɐV�K�����҂Ƃ��Ĕ��\�����e1�l���lj������ʼnA���Ɣ��f���ꂽ�ȂǂƂ��Ď�艺�����B
���V�^�R���i�����}�g�� ���@�܂ł̊��ԉ��ё������Ó���@���{�@8/26
�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�钆�A�����ǂ̊��҂̎��Âɂ������Ă�����s���̕a�@�ł́A�{���̊��҂̋}���œ��@�܂ł̊��Ԃ����т�悤�ɂȂ�A�����Ɏ��Â��n�߂�̂�����Ȃ��Ă���Ɗ�@�����点�Ă��܂��B
���{�ł͌y�ǁE�����ǂ̕a���̉^�p����25�����_��76.1���ƂЂ������A�����ǂ̊��҂𒆐S�Ɏ���Ă�����E�����̎s���\�O�s���a�@�ł�26���̎��_��70���̔��������܂��Ă��܂��B
���̕a�@�ł́A�d�lj���h���ړI��2��ނ̍R�̂𓊗^����A�u�R�̃J�N�e���Ö@�v������܂�62�l�̊��҂ɍs���A���̂���82���ɂ�����51�l�͉��ďǏ��܂����Ƃ������Ƃł��B
���̎��Â͌��ʂ邽�߂ɂ͔��ǂ���7���ȓ��ɍs���K�v������܂����A7���ڂɎ��Â������҂Ɍ����6�l�̂����A3�l�̏Ǐ������Ď_�f���^���K�v�ɂȂ�܂����B
�a�@�ɂ��܂��ƁA�{���̊����҂̋}���ɂ���Ċ��҂����@����܂ł̊��Ԃ�����6����7��������P�[�X�������Ă��āA�����Ɏ��Â��n�߂�̂�����Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
�����K�Y �a�@���́A�u�����Ґ������ꂾ��������ƁA��������܂ł̊��Ԃ⌟���ŗz���Ƃ킩���Ă�����@����܂ł̊��Ԃ��ǂ����Ă����сA���Â��x��Ă��܂��v�Ƃ��āA���Â̒x�ꂪ�d�NJ��҂̑����ɂȂ��肩�˂Ȃ��Ɗ�@���������܂����B
���̂����ŁA�u�a�����Ђ������Ă��Ă���̂ł����Ɏ��Â�����Ƃ͌���Ȃ��B�Ⴂ�l�ł��ˑR�d�lj�����P�[�X������̂ŁA�\�Ȑl�̓��N�`���ڎ���A�������O�ꂵ�Ăق����v�Ƒi���Ă��܂����B
�R�̃J�N�e���Ö@���߂����ẮA�a���̂Ђ���������邽�߂��̕a�@���܂ߑ��{����12�̕a�@��1��2�����x�̒Z�����@�Ŏ��Â��s���A��ɏh���×{�{�݂ɂ܂���Ă��炤���g�݂��n�܂��Ă��܂����A���̕a�@�őΏۂƂȂ������҂͂���܂�1�l�ɂƂǂ܂��Ă���Ƃ������Ƃł��B
�����V�^�R���i2830�l�̊����m�F�@��4�{���m�����ً}���b�Z�[�W�c�@8/26
���{��26���A�V����2830�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����A6�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B1���̊����҂͉ߋ��ő����X�V���܂����B�܂������p�������s�b�N���J�Â���Ă��铌���s�ł�4704�l�̊������A���Ɍ��ł͐V����1007�l�̊������m�F����܂����B
���E�g���m���u�l�Ɛl�̐ڐG�����点�����̂ɖ{���I�ȕ��j�������Ȃ��v
26���A�J���ꂽ���L��A���̉�c�B�V�^�R���i��̋�̓I�ȃ��b�Z�[�W�������玦����Ȃ��Ƃ����ӌ����������܂����B�����Łc
���ꌧ�E�O�����m���u�{�����܂����ړ��͍ŏ����ł��肢���܂��I�v
27������ً}���Ԑ錾�̑ΏۂƂȂ鎠����܂ށA4�{���̒m�����������킹�܂����B
4�{���m���u���Ȃ��̑�Ȑl�����܂��傤�I�v
�e���r�b�l��r�m�r�Ȃǂŗ����\��̂��̃��b�Z�[�W�ŁA�����g���}�����߂�ł��傤���B
�����茧��13�s�� 73�l�R���i�����@�e�n�̃N���X�^�[�g��@8/26
���茧�Ȃǂ�25���A����13�s���ŐV���Ɍv73�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B����s�⍲���ێs�ȂǂŔ������Ă���N���X�^�[(�����ҏW�c)�����ꂼ��g��B�����Ґ��͈����������~�܂�̏������Ă���B
����s�����{��5�K�t���A�̃N���X�^�[�ł́A�V����20��j���E���̊�����������A�v20�l�ƂȂ����B�j���E����17���A�������������̐ڐG�҂Ƃ��Ăo�b�q���������ۂ͉A�����������ߋΖ����p���B23���ɖ��o��Q���o�čēx�������A24���ɗz���ƂȂ����B�s���⎖�Ǝ҂Ƃ̐ڐG�͊m�F����Ă��Ȃ����A�E���̐ڐG�҂͌��ݒ������B
�����ێs�̕����{�݁u�G�R�X�p�����ہv�̃v�[���𗘗p����10�Ζ����̒j�����������A�v12�l�Ɋg��B���ގ��Ò��̗V���{�݂͐V���ɗ��p�q2�l�̊������������A�v30�l(���p�q29�A�]�ƈ�1)�ɖc��B�ܓ��s�̃o�[�u�V���g�[�v�͗��p�q1�l���z���ƂȂ�A�v7�l(�]�ƈ�5�A���]�ƈ�1�A���p�q1)�ƂȂ����B
����s�̐V�K28�l��5�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��B�����ێs��21�l�̂���1�l��30��j���C��ۈ����B��7�Nj�C��ۈ��{���ɂ��ƁA���ÊC��ۈ����̐E���ŁA20���܂ŋΖ��B�s���Ƃ̐ڐG�͊m�F����Ă��Ȃ��B�������ی�����60��j���E�����|���s�ݏZ���������B�����Ɛڂ���Ɩ��ł͂Ȃ��B
�����������@���܂��z�����@���g���A�ꌾ���X�u���{�͐��Ƃ��y�ϓI�v�@8/26
�V�^�R���i�E�C���X�ً̋}���Ԃ̑Ώےn��̊����́A27������lj������8�������܂߂Đ[�����B���Ƃ̓R���i���������鐭�{�̌��ʂ��̊Â����w�E���A�����E���k��̃p�������s�b�N�ϐ�ɋ^��𓊂�������B
���ً}���Ԃ�21�s���{���ŃX�e�[�W4
���t���[�̎����ɂ��ƁA23�����_�̐l��10���l������̐V�K�����Ґ�(����1�T��)�͑S�����ς�126�l�B�X�e�[�W4(��������)�̊�u25�l�v�̖�5�{�̑������B�n��ʂłً͋}�錾�Ώۂ̑S21�s���{���ŃX�e�[�W4�B�ő��͉���(310�l)�ŁA��s���̓����s�A�_�ސ�A��t�A��ʌ�����{�������B�����s�̐V�K�����Ґ���25���܂�3���A���ŁA�O�T�̓����j���Ɣ�ׂČ��������̂̌������͏������A�R���z�����Ƃ͌����������B�����J���Ȃɏ���������Ƒg�D�ɒ�o���ꂽ�����ɂ��ƁA8�`14���̓����̔ɉ؊X�̖�ԑؗ��l���́A���~�����ł�����A�ً}�錾���ߒ��O�̈�T�ԂƔ�ׂ�35�D8���������B�����A18�`24����22�����Ɛl�o�͍Ăё����Ă���A����̊����g��ɂȂ��鋰�ꂪ����B�m�ەa���̂����d�ǎҗp�a���g�p����23�����_�ŁA7�s�{�����X�e�[�W4(50��)�B�����ǂȂǂ��܂߂��a���S�̂ł́A�܂h�~���d�_�[�u�̒n����܂߂�24�s�{�����X�e�[�W4�ɓ˓����Ă���B����×{�҂����������ŁA18�����_�őS���Ŗ�9��7000�l�B���̂����A��s����1�s3������5��8000�l�Ɣ����ȏ���߂Ă���B
���u�o�b�n����������K�v�������̂��v
���{�̐V�^�R���i�E�C���X�����ȉ�̔��g�Ή��25���A�O�@�����J���ψ���̕�R���ŁA�������̊�����̔��ȓ_�����u���X�A���Ƃ��A���y�ϓI�ȏ��͂������̂ł͂Ȃ����B���P���ׂ��_���������̂ł͂Ȃ����v�Ƌꌾ��悵���B���g���̓R���i���ł̓����ܗ֊J�Â�O���Ɂu������ƌo�ϊ����̗����͓�����A���X�A�����������b�Z�[�W�ɂȂ����v�Ƃ��w�E�����B�����������Ɋ����g��h�~�ւ̋��͂��Ăт����钆�A���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�̃o�b�n����ė������A�p�������s�b�N�J��ɏo�Ȃ������Ƃ�Ꭶ���āu�Ȃ��I�����C���ł������ł��Ȃ��̂��B�����Ƀe�����[�N�����肢���Ă���̂�������A�Ȃ��ܗւ̃��[�_�[�̃o�b�n���͂킴�킴����̂��v�Ɣᔻ�����B
���u�q�ǂ��p���ϐ�A�Ȃ����̎����Ɂv
�����E���k��̃p�������s�b�N�ϐ�v����u�Ȃ����̎����Ɂv�Ɩ�莋�B�u���̖{���́A�����Ŋ������N���邩�N���Ȃ����ł͂Ȃ��B��ʂ̐l�ɂǂ��������b�Z�[�W�ɂȂ邩���v�Ƌ��������B�����̊w�Z���V�w�����}���邱�ƂɊւ��Ắu�������g�債�A����Ɉ�Â̕N�������蓾��v�ƌ��O�����B��ċx�Z�̕K�v���ł́u�w�K�̋@���D���̂͋C�̓ł����A����1�_�ŃR���i�ɗ������������Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ɣے�I�Ȍ����������A�������ł��o�������E���ւ̃��N�`���D��ڎ�A�w�Z����ł̍R���������i�Ȃǂ̑���i�����B
���n���Ɋ����}�g��@43�s���{���A�V�K�����҃X�e�[�W4�Ɂ@8/26
�V�^�R���i�E�C���X�����g��́u��5�g�v���S���ɔg�y���Ă���B�C���h�^(�f���^�^)�ψكE�C���X���n���ɍL����A43�s���{���ŐV�K�����Ґ�������ōł��[���ȁu�X�e�[�W4(��������)�v�ɒB�����B�n�����a���N�����������A����E�h���×{�̏[�����܂ވ�Ñ̐��������ۑ肾�B
25���͑S����2��4000�l���̐V�K�����҂��m�F���ꂽ�B���{��{�錧�A�V�����ʼnߋ��ő����X�V�����B8�����{�ȍ~�A�S���̐V�K�����҂�2���l��������ڗ��B�����s�̑����y�[�X�ɓ݉��̒������o�Ă������ʁA�����̒n��ő�����������B
���{�o�ϐV���̏W�v�ɂ��ƁA�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂��X�e�[�W4(25�l�ȏ�)�ɂ�����̂�24�����_�Ŋ��A�H�c�A����A����������43�s���{���B1�����_��17�s���{���������̂��A3�T�Ԃ��܂��2.5�{�ɑ������B
�����J���Ȃ̐��Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v��25���A����ɂ��āu�قڑS�Ă̒n��ł���܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ������g�傪�p�����Ă���v�Ƃ̕��͂��������B��Ò̐����u�ЊQ���̏ɋ߂��ǖʁv�Ǝw�E�����B
�A�h�o�C�U���[�{�[�h�̎����ɂ��ƁA�ψٌ^�̍L����ׂ�X�N���[�j���O�����ŁA9�`15���Ɋ����҂�85%����f���^�^�Ɠ����ψق��݂������B�f���^�^�̍L���肪�����g��y�[�X�����������Ă���B
1��������̐V�K�����Ґ��̐��ڂ��݂�ƁA����24�����_��307.43�l(7���ԕ���)��1�����_��13�{�ɖc��B�O�d����11�{�A�L������6.5�{�A�{�錧��5.9�{�ɑ������B�������Ԃɓ�����5�����������̂ɔ�ׁA�n���̑����Ԃ肪�������B
�L�����ɂ��ƁA���~���Ԃɑ��Ⓦ�����瑽���̐l��������K�ꂽ���Ƃ������ґ����̎�ȗv�����Ƃ����B���~��ċx�݂œs���{�������܂����l�̗��ꂪ�������A�f���^�^�̊g��ɂȂ������\��������B
���J�Ȃ̏W�v�ɂ��ƁA23�����_��33�s�{�����a���g�p���̃X�e�[�W4�ɑ�������50%�����B��5�g���{�i������O��7��20�����_�ł̓X�e�[�W4�̓s���{���͂Ȃ��A1�J�����܂�ŕa���̕N��������C�ɋ��܂����i�D���B
�c���14�������a���g�p��20%�ȏ�́u�X�e�[�W3�v�ɑ������A�����҂�����}������Εa���N���ɂȂ��邨���ꂪ����B�a���m�ۂ⎩��E�h���×{�҂ւ̈�Îx���̏[���͂��܂�S�����ʂ̉ۑ�ɂȂ��Ă���B
���u�S�����@�v�������@�����A����×{��
�V�^�R���i�E�C���X�̊����ґS������@��h���×{�{�݂Ŏ���錴�����f���Ă����n���̎����̂��������ɓ����Ă���B�����͂̋����C���h�^(�f���^�^)�ψكE�C���X�̉e���Œn���ł��������}�g�債�Ă���A�S�����@�𑱂���Εa�����N�����鋰�ꂪ�����Ă��邽�߂��B
���{��25���ɋً}���Ԑ錾�̓K�p�����߂����ꌧ�́A40�Ζ����łقږ��Ǐ�̊����҂̎���×{��F�߂�悤�Ή����j���ւ����B�����Ƃ��đS�Ă̊����҂���@���h���{�݂ł̗×{�őΉ����Ă������A�����̊����Ґ��͌���4���ɒ�߂��ő�z��������Ԃ������B���@���K�v�ȏǏ�̊��҂�������Ƃ݂ĕ��j�]�������B���͍ő��2600�l������×{�ɂȂ�Ƃ݂Ă���B
���ꌧ�Ɠ��l�A25���ɋً}���Ԑ錾�̓K�p�����܂��������A21�����玩��×{�҂������Ă���B����܂ł́u����×{�҃[���v���f���A��Ë@�ւ�h���×{�{�݂Ŏ���Ă������u�d�ǎҁA�����Ljȏ�̊��҂ɔ����ăx�b�h���m�ۂ���K�v������v(�Óc���m��)�B������������×{�̓��������߂��B
���I�ȐV�^�R���i��Œm����a�̎R�����A9������h���×{�����߂ē�������B8��25���̐V�K�����҂�85�l�ƍ��������ŁA���@�Ґ��͉ߋ��ő���558�l�ɒB���Ă���B�a�����͌v560�ŁA�a�����ɕC�G������@�Ґ��ƂȂ��Ă���B
���͔��nj�5�`7�����o�߂������Ǐ�E�y�ǎ҂��A��t�̔��f���o�ďh���×{���Ă��炤�B�u�S�����@�̕�����ɂ����v�Ƃ��Ă����m��g�L�m�������A�������́u��ނȂ��v�Ƙb���B
�V���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�����܂������ꌧ�́A�n��̈�t�Ƃ̘A�g������×{�ɐ������B�����́u�������@�E�z�e���×{�v���������A���~������18�����玩��×{�����Ă���B24�����_�őΏێ҂�454�l�B�y�ǁE���Ǐ�œ����Ƒ������邱�Ƃ��������B�ЂƂ��炵�̊����҂͕a��}�ςւ̑Ή���������߁A�z�e���×{�Ƃ��Ă���B
�������ɐV�݂����u����×{�x���Z���^�[�v�̊Ō�t�⌧�E����50�l���x���A�d�b�Ō��N�ώ@�ɂ���������A�p���X�I�L�V���[�^�[��s�̂̉�M�܂Ȃǂ�͂����肷�������S���Ă���B�����͐V�^�R���i���N�`���ڎ�ł������i�K�����t��ȂǂƘA�g���A�S���I�ɍ����ڎ헦�ɂȂ��Ă���B����×{�ł��K�v�ɉ����āA�n��̈�t��ɉ��f��d�b�f�ÂȂǂ��˗�����B���S���҂́u��t�Ƃ̘A�g���L���ɋ@�\����̂ł͂Ȃ����v�Ɗ��҂��Ă���B
���Ώۊg��8��3�x�ځc�S���ꗥ���݁g���݂��ꎮ�h�����R���i�����́@8/26
�����͂̋����f���^���ɂ��V�^�R���i�E�C���X�́u��5�g�v���~�߂�ꂸ�A���`�̎�8���ɓ���3�x�ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾�̊g���]�V�Ȃ����ꂽ�B�Љ�o�ϊ������l�����A�S���ꗥ�łȂ��A���������������n��Ɍ��肵�Đ錾��܂h�~���d�_�[�u���o���Ă����u�����̃R���i��v(����)�́A���ʂƂ��Č��ɉ�����B
�Ȃ��A�S���ꗥ�ɐ錾��d�_�[�u���o���Ȃ������̂��|�B
25���ߌ�9������̋L�҉�Ŏ�������́A�u�������Ñ̐��͒n��ɂ���đ傫�ȍ�������B�ꕔ�̌��ŁA�F����ɉߏ�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂����������B�����������ō���̔��f�������v�B�����q�ׂāA�����܂ő�̑Ó������咣�����B�S���m�������Ƃ͑S���ꗥ�g������߂Ă������̂́A��т��Ď͂����ނ��A�n�悲�Ƃɂ��ߍׂ����K�p�̉ۂf�������I���������Ă���B
�����A��s���ɔ������f���^�����n���ɐZ�����Ă����X�s�[�h�͐��{�̑z����͂邩�ɒ��߁B�����^�����������N�`���ڎ킪�A�ڂɌ�����u�Ώ������ʁv�����鎞�ԓI�]�T�͂Ȃ������B�ɂ߂ĒZ���ԂŊ����Ɋւ���w�W���}���Ɉ�������n�悪�������A�L���Ȃ�5����20���̏d�_�[�u�̓K�p����킸��1�T�ԂŐ錾�ɐ�ւ�����Ȃ������B
���{�̊����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��25���̏O�@�����J���ψ���ŁA���Ŏ����銴���}�~�ƌo�ϑ�̗������u�������Ƀ��b�Z�[�W���W������������A�����������b�Z�[�W���������v�Ƌ^�⎋�B���̏�ŁA���{�̑Ή����u���Ƃ̕��͂��A���y�ϓI�ȏ��͂����ꂽ�v�Ɨe�͂Ȃ��f�����B
��
25���A�����s�̐V�K�����Ґ���4228�l�ƁA3���A���őO�T�̓����j������������B����ł������J���Ȃ̐��Ɖ�c�́u�������x�͂��݉����Ă��邪�A�����X���͌p�����Ă���v�ƕ��͂��A�y�Ϙ_�����ɉ��߂�B
�s�[�N�A�E�g�Ɍ����Ă̓��N�`���i�W�Ɠ������s�Ŋ�����̌��_�ɗ����߂�A�l�̗����}�����Đl�Ɛl�̐ڐG�@������I�Ɍ��炷�����Ȃ��B���g���͊����������S���ɍL����n�߂Ă���12���A�����s�̐l�o������2�T�Ԃ̂����ɁA�錾�O��7���O�����_���5�����炷�K�v������Ƃ̒����\���Ă����B�������A�l�X�̍s���͗e�Ղɕϗe�����A�ŋ߂̌�������20����ɂƂǂ܂��Ă���B
���݂��A���{���ɂ́u�錾�ɔ����x�Ɨv���̑Ώۂ��g�傷��ׂ����v�Ȃǐl�̗���������}�����ނ悤�������ƁA�u�n���ł͐l�o�������Ă���̂ɁA�����Ґ�������Ȃ��P�[�X���o�Ă��Ă���A�����b�g���������v�ƐT�d�Ȑ�����������B�ċx�݂������Ċw�Z���ĊJ���A����͎q�ǂ������̓����������ɂȂ�B���݂̊�����9��12���܂łɁA�錾�Əd�_�[�u�������ł��邩�͌��ʂ��Ȃ��B
�������̊������A�S�̂̌��ʔ��f�@�f���^���e���̃f�[�^�Ȃ��@���J�����ɕ����@8/26
�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������20�Ζ����̎q�ǂ�(����)�͉ƒ�O�ł̊����g��ɗ^����e�����������Ƃ��铌�k�匤���`�[���̒������ʂ��A21���̖{�������ŏЉ���B����A�������������Ƃ����f���^���ŏ����̊����͑����X���ɂ���B�`�[���ӔC�҂̓����w�@��w�n�����Ȃ̉��J�m����(�E�C���X�w)�ɒ������ʂƂ̊֘A����q�˂��B
�\�\�����̊������ڗ����Ă����B
�u�f���^���̗��s�ɂ��S�N��w�Ŋ����Ґ����������B�����̊��������͉p�ĂȂǂł������蒍�ڂ���Ă��邪�A�����_�Ńf���^���������Ŋ������������Ƃ̖��m�ȉȊw�I�f�[�^�͂Ȃ��B�č��̌����@�ւȂǂ́A�S�N��w�̑����X���̒��ŏ������������Ƃ݂Ă���v�u���{�ł������̊����҂����̔N��w�ɔ�ׂČ����ɑ��������킯�ł͂Ȃ��B���l�A���Ƀ��N�`���ڎ킪�i����҂̊������ő��ΓI�ɏ��������҂̊����������A�����X�����݂�ꂽ�ƍl������v
�\�\�w�Z�ł̃N���X�^�[���������O�����B
�u�������d�lj����銄���͔��ɒႢ���A�������҂̐�ΐ���������Ώd�NJ��҂���萔�̔������\�z�����B���ۂɕč��ł͏d�ǂ̏������҂������Ă���B���{�ł��������g�傷��A�����ɂȂ邱�Ƃ��뜜�����v
�\�\�����`�[���́u�����ɂ��ƒ�O�ł̊����g��ւ̉e���͏������v�Ƃ����B
�u�f���^���̗��s���ł������͎�ɉƒ���������A�ƒ�O�����͑��ΓI�ɕp�x���Ⴂ�ƍl������B�C���t���G���U�̗��s�͊w���Ԃ̊������ƒ���o�Ďs���ɍL���邽�߁A�x�Z�͎s�������̊g����~�߂���ʂ�����B����A�����̃R���i�����͑����̏ꍇ�A�s���������ƒ���Ɏ������܂ꂽ���ʂƍl������v
�u�x�Z�̓N���X�^�[�̔�����g��̗\�h���ʂ͂����Ă��A�s���S�̂̊����g����ŏ����ɂ�����ʂ��]�߂邩�͋c�_�̑ΏۂƂȂ��Ă���B�����`�[���̃f�[�^�ł͓��ɏ��w���ȉ��̏����͓������N�����������Ⴍ�A�n��̊����g��ւ̉e���͌���I�Ƃ݂Ă���v
�\�\�w�Z�ł̗��ӓ_�́B
�u�f���^�����s�O�̊e���̕ł́A�w�Z�ł̃N���X�^�[�͒Z���ԂŏI�����邱�Ƃ��m���Ă��邪�A�f���^���ł����l���͌����_�Ŕ��f�ł��Ȃ��B�����҂��ŏ����ɗ}����ɂ́A�w�Z�ŗ��s�𑁊��Ɍ��m���đΉ����A�����̘A����f���邱�Ƃ��d�v���v
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������s�̃��j�^�����O�����A�R���i�z������2������18�{�Ɂc�@8/27
�����s���ɉ؊X�ȂǂŎ��{����V�^�R���i�E�C���X�̃��j�^�����O�����ŁA�z�������E���オ��ɂȂ��Ă���B7�����{�Ɣ�חz�����͖�18�{�ɂȂ�A�X���o�������Ǐ�҂��}���B�s���̐V�K�����҂͉��������A���ۂɂ͂����Ƒ����Ƃ݂���B�s���̊����ɂ��Đ��Ƃ́u����s�\�ȏ͑����Ă���B�S�̂̐���ǂ��Ă��Ȃ��\�����l���Ȃ�������Ȃ��v�Ǝw�E���Ă���B
�s�͔�r�I�������X�N�������ꏊ�Ƃ��āA�l���������ɉ؊X����H�X�A�w�O�A��`�Ȃǂ�PCR���������Ă���B���Ǐ�҂��ΏۂŁA�����g��̗\�������ނ��߂ɍ��N�t����n�߂��B
�s�̎����ɂ��ƁA7����1�T�̊����Ґ��̊�����0.05���ŁA�����������悻1992�l��1�l���������Ă���v�Z�������B���T����0.09���A0.15���Ɗ����͏㏸���A8���̑�3�T�ł�0.89���ƂȂ����B�����������悻113�l��1�l���������Ă���v�Z�ŁA7����1�T�̖�18�{�ɂȂ����B
����ŁA�����s�̃��j�^�����O��c�ŕ��ꂽ�s����7���ԕ��ς̐V�K�����Ґ���25�����_��1��������4388�l�ƍ����������������A��T18����4630�l�Ɣ�ׂ�ƁA�����������̂悤�Ɍ�����B
�������A�����҂̋}���ŁA�s���̕ی����͔Z���ڐG�҂⊴���o�H��T�钲���̋K�͂��k�����Ă���B�����������A���Ǐ�Ŋ����ɋC�t�����ɊO�o����l�������Ă���Ƃ݂���B���j�^�����O��c�ł��u������v���Ɏ��Ȃ����Ƃɂ��A����ɑ����̊����҂����݂��Ă���\��������v�Ǝw�E����Ă���B
�������ۈ�Ì����Z���^�[�̑�ȋM�v���ۊ����ǃZ���^�[����25���̃��j�^�����O��c��̎�ނŁA�����ɂ��āu�����䂾���݂�Ɖ����Ɍ����邪�A�����������B���ۂɂ͂܂��������ĂȂ��������Ȃ肢��������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���v�Ƃ̔F�����������B
����ɁA�u�v�͍��̐������݂�Ɣ��ɒ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��B����̓����Ɋւ��ẮA����ς肩�Ȃ�S�z�v�Ɛ�s���Ɍ��O���������B
���ċx�ݖ����g�匜�O �q�ǂ�������3�T�A���Ŋ������� �@8/27
�����s�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂̂����q�ǂ��̊�����3�T�A���ő����Ă��邱�Ƃ�������A���Ƃ͐V�w���̊w�Z�ł̊����g����x�����Ă��܂��B�����s��26���A�V����4704�l�̊������m�F����A�d�ǎ҂�276�l�ɂȂ����Ɣ��\���܂����B
�s���ł�26���A�����͂����c���J����A�����҂̂���10��ȉ��̎q�ǂ��̊����������Ă���Ƃ����f�[�^��������܂����B3�T�ԑO��12.1���ł������A��������13.1���A14.3���A15.8���ƏT��ǂ����Ƃɑ����Ă��܂��B
���Ƃ͉ċx�ݖ����̊w�Z�Ŋ������g�傷�錜�O�������A�Z���̊�����̏d�v����i���܂����B���̂����Łu�Љ�S�̂Łw�q�ǂ��̖������x�Ƃ����ӎ��̌[�����K�v���v�Ƙb���܂����B
���w�Z�ĊJ�ŁA�R���i��5�g�̊����g�傪�뜜����郁�J�j�Y���@ 8/27
�������s��7�����_�̎O�労���o�H�͉ƒ�E�E��E�w�Z�܂ށu�{�݁v
������̂��Ƃł����B��r�I�����Ă���R����ňړ����A�������������O�̍��Ȃɍ����Ă���j�����}�X�N���������Ȃ��炵����ɊP�����n�߂܂����B�R����Ŏg����E235�n�ԗ��̏��̕���2.58���[�g���ł��B�܂�2�����炢�̋����ł̘b�ł��B
���ܗ��s��̃f���^���́A�]������������͂������A�̊댯�x�������ƍ����Ƃ����Ă��܂��B�u����ŃR���i�ɂ��������犴���o�H�͂Ȃ�ƕ�������낤�H�v�Ƃڂ���Ǝv���Ȃ���A�~�Ԃ����w�̃g�C���łƂ肠���������������Ă����܂����B���̌�A�����Ȃ������̂ŞX�J�ɂ�������o�����ł͂���܂����B
�f���^���̏o���ŁA���ǂ��ŃR���i�ɂ��������̂����킩��Ȃ��l�������Ă��܂��B���߂̓����s�̊����o�H�s���҂̔䗦�͖�6���B���o�̂Ȃ��܂܊�������l�̕��������Ȃ̂ł����āA�����炱���������������͓̂���Ǝv���Ă���悤�ȏł��B
�����A�c��̃P�[�X�ł͊����o�H���������Ă��܂��B�����s�̏ꍇ�A��ԑ����̂��ƒ���A�����E��A������7���܂ł͊w�Z���܂ށu�{�݁v�Ƃ����J�e�S���[���E��Ɠ������炢�̔䗦���߂Ă��܂����B����3�Ŋ����o�H��7�`8���̐��������Ă����킯�ł��B
�܂薾�m�ȗ���Ƃ��āu�Ƒ��̒N�����d����w�Z�ɏo�����A�����Ŋ������A���̉Ƒ��ɂ������Ă��܂��v�Ƃ����p�^�[���������o�H�̍ő�P�[�X�������̂ł��B
���Ȃ݂ɑ����̓��{�l���u�ً}���Ԑ錾�̌��ʂ������߂Ȃ��v�ƍl���Ă���̂͂��ꂪ���R�ł��B�ً}���Ԑ錾�̎�ȗv�����e�́A�O�o�����A���Ǝ{�݂̓��ꐧ���A���H�X�̎��Z�c�ƁA�C�x���g�̓��ꐧ���Ȃ̂ł����A�����͂��łɊ����o�H�̏�ʂł͂Ȃ��B��ԃo�b�V���O�������Ă������H�X�͓X�ܑ��̓w�͂ƌڋq���̋��͂ŁA���܂ł͊����o�H�Ƃ��Ă�5�`10�����x�܂ŏ������Ȃ��Ă��Ă���̂ł��B
���S�ݓX�̃N���X�^�[�́u�E��ł̃N���X�^�[�����v�̈��
��������ł͑�5�g�̎����A�S�ݓX�ł̃N���X�^�[���������ɂȂ��Ă��܂����B�ȑO�̈��ʊW�ł͕S�ݓX�͌ڋq�Ŗ��ɂȂ邩��댯���Ƃ����l���������킯�ł����A��5�g�̏ɂ��Ă͕ʂ̐������K�v��������܂���B
�m���ɍŏ��̊����́A���ɂȂ��������ŊO������R���i���������܂�ĕS�ݓX�̏]�ƈ��Ɋ����҂��o���̂�������܂���B�����A���̌�w�E���ꂽ���Ƃ́A���ꂪ�N���X�^�[�ɂȂ����̂͐E�������������Ƃ��������ł��B
�S�ݓX�̃o�b�N���[�h�ɍs�������Ƃ�����l�͂��������Ǝv���܂����A�]�ƈ��̂��߂̍X�ߎ���x�e���͂���قǍL���͂Ȃ��A�x�e���Ԃɂ͑��X�܂̏]�ƈ��Ɠ��������ꏊ�ɏW�܂邱�ƂɂȂ�܂��B�ڋq���͏]�ƈ����m�͋������ۂĂĂ��Ă��A���ۂɂ͐E����Ŗ��ɂȂ鎞�Ԃ��ł��Ă��܂��B�܂�S�ݓX�ł̃N���X�^�[�����́A����ȊO�̐E��ł̃N���X�^�[�����ƃ��J�j�Y���͓������Ƃ����߂ł���̂ł��B
���̂悤�ȏɂȂ������A�R���i�����ɂ́u�E��A�w�Z�A�ƒ������v�Ƃ������Ƃ����Ȃ��킯�ŁA����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ�����Ƃ����܂��Ƃ��Ȕ��_���甼�ΐ��{������グ��ԂɂȂ��Ă����킯�ł��B
���R���i�Ђ̊w�Z�ĊJ�Ŋ뜜����邱��
���āA�����ł���ɖ��ɂȂ�͂��߂Ă���̂��u�w�Z��2�w���̍ĊJ��x�点����ǂ����낤���H�v�Ƃ����ӌ��ł��B
���{���ȉ�̔��g�Ή���u�w�Z���n�܂��Ă��邱�ƂŁA�܂������g����ÕN�������蓾��v�Əq�ׂĊe�����̂Ɋw�Z�ĊJ�������������悤�ɋ��߂����Ƃ��j���[�X�ɂȂ�܂����B
����͎��ۂɗ��t���̂���b�ł��B�����ق�7���܂ł͉ƒ�A�E��A�w�Z��3�労���o�H�������Əq�ׂ܂����B���ꂪ�A�ċx�݂ɂ͂�����8���̃f�[�^���݂�Ɗe�s���{���Ō����Ɋw�Z�o�H�̊����������Ă���̂ł��B���Ƃ����łȂ��������ۊO���Ƃ��T���Ă��邹���ŏ��Ȃ��Ƃ�3�̂�����1�̊�������1�J�������}�����ނ��Ƃ��ł����B���̈���Ńf���^�����}�g�債���̂�8���ł��B
�����đ����̑�5�g�̓����́A�����s�̏ꍇ�A��҂̊����҂��������ƂŁA��̓I�ɂ�10��A20��A30��őS�̂�3����2���߂Ă��܂��B10�ゾ���ł�14���ƁA���͂⏭�Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��\������߂Ă��܂��B
���̏Ŏ��Ƃ��ĊJ������ƁA�u�w�Z�v���f���^��������Ɋg�U�����郊�X�N�ɂȂ�\��������B����͘_���I�ɂ͏\���ɗ\���ł��邱�Ƃł��B����̑�5�g�ʼnƒ���Ŕ��������������A���k���m�Ŋ����g�債�A���ꂪ�ʂ̉ƒ�ɓ`����Ă��̉Ƒ��ɂ���������B�E�ꁨ�ƒ끨�w�Z���ƒ끨�E��Ƃ������[�v�������Ɋg�傷�邱�Ƃ��뜜�����̂ł��B
�������A�ɂ�������炸2�w���̍ĊJ�^�C�~���O�͊e�����̂̔��f�ɂ䂾�˂��Ă��܂��B�����s�ł͈ꕔ�̎����̂ň�T�ԂقNJJ�n��x�点�锻�f�����Ă���Ƃ���͂���܂����A�唼�̎����̂�9��1���Ɏ��ƍĊJ��\�肵���܂܂ł��B
�����܂Ń��J�j�Y�����킩���Ă���̂ɁA�Ȃ����{�͐V�����R���i���\�����Ȃ��̂ł��傤���H
��������͎��̉ߋ��̌o���ɉ������������Ɛ\���グ�Ă����܂��B
�����{���w�Z�ĊJ�̔��f���e�����̂Ɉς˂闝�R
���͉ߋ��A���{�L���̑��Ƃ̃g�b�v�̈ӎv����̏�ʂɗ�����Ƃ����o�������Ă��܂����B���̌o���ł킩�������Ƃ�\���グ��ƁA�g�D�̏オ�����猩�Ă������Ȕ��f�����Ă�悤�Ɍ�����Ƃ���A���f���x���v����Ƃ��ɂ́A���̑唼�̃P�[�X�͎��̓g�b�v�����ɂ͏o���Ȃ����炩�̈ӎv����������Ă���ꍇ���Ƃ������Ƃł��B
����̃P�[�X�ŁA�Ȃ�������J����b�A�����Ȋw��b�����Ƃ��Ċw�Z�ĊJ�̈ꎞ��~��v�����Ȃ��̂��H���ȉ�̔��g������ꂾ���댯��\�����Ă���ɂ�������炸�A�Ȃ��e�����̂ɔ��f��C���Ă���̂��H
����͂����炭�A�u2�w����9��1���ɍĊJ�����č\��Ȃ��v�Ƃ�����������łɉ����Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B�ᔻ���o��̂Ō��ɂ͏o���Ȃ��B����ǂ��������߂Ă���B�����܂Ŏ��̌o���ɉ����������ł͂���̂ł����A�����Ƃ����v���Ȃ��̂ł��B
���̓f���^���ɂ���5�g�ŁA���{�ɂƂ��đłĂ��͂ӂ������Ȃ��Ȃ�܂����B���d�ȃ��b�N�_�E���ɓ��ݐ邩�A����Ƃ�����̂܂܂��ێ����邩�ł��B�O�҂͌o�ς��]���ɂȂ�̂ŁA�������ݐ��Ă��܂��ƃR���i����͓�����Ă����{�͕ʂ̌`�Ŋ�@���}���邩������܂���B
����Ō���ێ��̏ꍇ�ɂ́A���Ԃ����ĂΏ͏������ł͂���܂������P�͂��Ă����܂��B���̗��R�̓��N�`���ڎ헦�̌���ł��B�����c�O�Ȃ��ƂɁA���{�����҂��Ă��������A�����ł̓��N�`���̓���͒x��Ă��܂��B
�����_�Ō����J���Ȃ����\���Ă��鋟�����ʂ��ł́A���N�`����2�T�Ԃ�1�����̃y�[�X�ł��B�����1�J���Ɋ��Z�����1200���l��2��ڎ�ł���y�[�X�ł��B
���A������2��ڎ킪���������l�̐��͖�5000���l�B�����đ�5�g�̏d�NJ��҂̑唼���ڎ킪�ς�ł��Ȃ��l���Ƃ�������������܂��B��6000���`7000���l�̖��ڎ�҂̊ԂŋN���Ă���̂����̑�5�g�ł���ȏ�A���̑w�Ƀ��N�`���ڎ킪�������Ȃ���Ύ������܂���B
�����ă��N�`������̃y�[�X����A���̃S�[���܂łɂ͂܂�4�`5�J�������肻���Ȃ̂ł��B
�܂�A�_���I�ɂ�2�w���̊J�n�𐔏T�Ԓx�点���ꍇ�ł��A�x�点�Ȃ��Ă��A�ǂ���̏ꍇ�ł��V�^�R���i�̎��������͑傫���͕ς��Ȃ��B�ł�͂Ȃ��A���Ԃ��i��ŁA���N�`���ڎ킪�i�ނ��Ƃ��Ђ�����҂Ƃ������Ƃ��A���A�킽�����������Ă���䖝�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B
����҃��N�`���ڎ�X�^�[�g�@��]�ҎE���A4���ԑO�ɒ��ߐ�ō����@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A�����s��27���A��N�w����̃��N�`���W�c�ڎ���X�^�[�g�������B�\��s�v�̎�y��������A�������������]�҂��E���B�\���4���Ԉȏ�O�Ɏt�������ߐ��A�E����͐����ɒǂ�ꂽ�B�s�͉^�c���@�̌������𔗂�ꂽ���̂́A�ڎ�g���g�債�Ȃ���A�����҂̔������߂�10�`30��ւ̐ڎ������������B
�{���A���N�`���\��̎t���͏I�����Ă��܂��|�B�ߑO9��������A16�`39��Ώۂɂ����s�́u��҃��N�`���ڎ�Z���^�[�v���݂���ꂽ�旧�ΘJ�������(�a�J��)�O�ŁA�S���E���͐���グ���B
�{���͓�11��50���Ɏt�����n�߁A���߂���^�p����\�肾�������A�ߑO4�����_�Ŗ�15�l���ҋ@�B1��200�l���x�̐ڎ�g�ɑ��A��7��������ɂ͖�300�l�����ђ��ւ̗�ƂȂ������߁A�s�͐�������z�z���Ďt�����I�������B
�]�ː��̉�Ј��A���(��傤��)����(23)�͌ߑO3�������ɕ��B���߉߂��ɐڎ���I���ĉ�����ɂ��A�u�n���̎����̂ŗ\��ꂸ�A���̃Z���^�[�Ɍ����Ă����̂ŁA�m���ɑłĂ����Ȏ��Ԃɗ����B�����ɑł��Ƃ��ł��Ĉ��S�����v�Ƙb�����B
3�T�ԑO�ɐڎ팔���͂����Ƃ�����t�����s�̒j����Ј�(28)�͌ߑO7������ɉ��ɓ����A���肬��Ő���������ɂ����B�u�Ζ���̂���s���Őڎ�ł����̂́A���������肪�����v�Ɗ��ӂ����B
����A�ߑO10�������ɖK��A�t���I�������ꂽ������̉�Ј��A�Љ��G��������(37)�́u���������d�����x��ł����̂Ɂc�B�\�Ȃ��őłĂ�ƕ����Ă����̂ɁA�����������ł���l�����Ɍ���z���ďI���Ȃ�ĂЂǂ��v�ƕs����R�炵���B
�s�͍��G����őO�|������\�������O�ɗ\�����Ă������A�Ԃɍ���Ȃ������l�̈ꕔ���E���ɋl�ߊ��ȂǍ����͂��炭�������B�s�����ی��ǂ̒S���҂́u��N�w��������x�ڎ킪�i�݁A�ߑO���̓����͓݂��ƍl���Ă����B�����܂ł̗�ɂȂ�̂͑z��ł��Ȃ������v�Ǝߖ������B
�s����N�w�ւ̃��N�`���ڎ���}���̂́A�����g��h�~�̉ۑ肪����҂����N�w�Ɉڂ������Ƃɂ���B27���ɕ��ꂽ�s���̐V�K������4227�l�̂����A10�`30���2420�l�Ɣ�������B�����A�e�����̂ł̓��N�`���̋����s���Ȃǂŗ\����ƂȂ��Ă���B
�]�ː��̃X�|�[�c�N���u�R�[�`�̏���(24)�́u�����ڎ킵�������A�n���ł͂����ɗ\�ł��Ȃ��B����̐l���ł������̂ɑłĂȂ��v�Ƒł�������B
����ŕ������ւ̌��O�Ȃǂ���A�ڎ�Ɍ������Ȏ�N�w�����Ȃ��Ȃ��B
�a�J��̍��Z2�N�̏��q���k(17)�́u������蕛�����̂ق����|���B����̗F�l���ł��Ă��Ȃ����A�����͏��ł��������肵�Ă���̂ŁA���̂Ƃ��냏�N�`����ł\��͂Ȃ��v�Ƙb�����B
���@��싅����33�l�R���i�����A�������Ŋg�傩�@8/27
�����Z��w�싅���[�O�̖@��d���싅���ɏ�������w��33�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ�26���A���������B����20�����畔�������~���A�����S���Ɏ���ҋ@�̑[�u���u���Ă���B9��11���ɊJ������H�G���[�O��ւ̏o��ɂ��Ă͖��肾���A��2�T�Ԍ�ɔ����Ă���A�o�ꂪ��Ԃ܂�鎖�Ԃɒ��ʂ��Ă���B
�J���܂Ŗ�2�T�ԁB�����Z��w�싅���[�O�ő���ƕ���ōő�46�x�̗D�����ւ�@�傪�N���X�^�[�Ɍ�����ꂽ�B��w�͌����T�C�g��ŁA�d���싅���ɏ�������w��33�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ\�����B
��������u���Ă��Ă��A�h���Ȃ��E�C���X�̋��ЁB�e��w�̖싅���������͗������𑗂��Ă��邾���ɁA�����g��̃X�s�[�h�����������B���s�ɗ�������@���22���܂łɖ싅����10�l�̊������m�F�B���̌�A�ی����̒����⌟���������ʁA24���܂łɊ����҂�33�l�ɍL�������Ƃ����B����20������싅���͊������~���A�S�����͎���ҋ@�B�\�肳��Ă����I�[�v����͑S�Ē��~�ƂȂ�A�ی����̎w���ɉ����āA�����ĊJ�̎��������ɂ߂���j���B�����d�Y�ḗu(�����̓R���i)��ɋC�����Ȃ������Ă����B���͊w������邱�Ƃ���ɍl���Ă���Ă����v�Ƙb�����B
�H�G���[�O���9��11���ɊJ�����邪�A�@��͌��i�K�Ń��[�O��o��ɂ��āu����v�Ƃ��Ă���B1925�N(��14)�Ɏn�܂��������[�O�ŁA�����C�O�����Ȃǂɂ��6��w�������Ȃ�������͉ߋ��ɂ��邪�A46�N�ȍ~��6�Z�ɂ��R�킪�������Ă����B
�����ĊJ�����������Ȃ����ŁA���[�O��ɏo��ł��Ȃ����ԂƂȂ�ΐ�㏉�߂ĂƂȂ�B�@���4�N���ɂ́A���H�h���t�g���ɋ�����O�Y���A�R���P(�Ђ���)����炪�ݐЂ��Ă���B10��11���̃h���t�g��c�܂ŁA�Ō�̃A�s�[���ƂȂ�ꂪ�Ȃ��Ȃ�\�����o�Ă����B
��w�싅�E�͍�N���瑱���R���i�̉e�����Ă���B���t��8���ɊJ�Â��������Z��w���������[�O�����~�ƂȂ�A�S���{��w�싅�I�茠�A�����_�{�������~�ɒǂ����܂ꂽ�B���t���[�O��ł͓����V��w�싅���[�O�̑n���傪�o�ꎫ�ނɁB�Ă̍b�q���ł��{�菤�Ɠ��k�w�@(�{��)���R���i�����ŏo�ꎫ�ނ��A�Â��e�𗎂Ƃ������肾�B�@���9��11������̊J���T�ő���Ƃ̑ΐ킪�\�肳��Ă���B�������l��������ł̔��f�ƂȂ邪�A�Z��w��������ďo��ł��Ȃ����n�ɗ������ꂽ�B
���H�G���[�O�����@�����_���͍̗p�����A���H�A���t�ɑ���2��퐧�̑�������B�e��w��10������킢�A�D���𑈂��B����1�|�C���g�A��������0.5�|�C���g�A�s��0�|�C���g�Ń|�C���g��������w���D�����A2�Z�����ꍇ�͗D�����������{�B3�Z�����ꍇ�͗D���a����ƂȂ�B���e�l���͐��{�̃C�x���g�J�Ð����ɏ�����B
���@��싅���@�n����1915�N(��4)�B60�N�ォ�瓪�p�������A65�`68�N�ɍݐЂ����c���K��A�R�{�_��A�x�c���̃X���b�K�[3�l�́u�@��3�H�K���X�v�ƌĂ�A����w���狰���ꂽ�B�Z��w�j��ő���48�����������R�����|��i����69�N�H���烊�[�O��4�A�e��B���B���̌�A76�N�t�`77�N�H���]����̊����4�A�e��B�������B���K�O���E���h�A���h���͂���������s�ɂ���A�����̓}�l�W���[���܂ߖ�140�l�B
����w�X�|�[�c�̎�ȃN���X�^�[
���n����@4��26���ɖ싅����2�l�̗z���������B���̌�A�����x�~�Ƃ������A29���܂łɖ싅���W��24�l�̊������m�F���ꂽ�B�싅�����ł̃N���X�^�[�ƔF�肳��A�J�Ò��̏t�G���[�O��̏o������ށB����܂ł͎�ʂ𑖂��Ă������A�c��3�J�[�h���s��s�ƂȂ����B
�����{������@����16���A���O�r�[���̉��h��ŃN���X�^�[�������������Ƃ����炩�ɁB�܂��A24���ɂ͖싅�����ŕ���14�l�̊������m�F����A�啪����83��ڂ̃N���X�^�[�ɔF�肳�ꂽ�B���̖싅�����ɂ��Ă͉A���Ɣ��\�B
���V����@��N8���Ƀ��O�r�[���ŃN���X�^�[�������B62�l�̊������m�F���ꊈ�����l��]�V�Ȃ����ꂽ���A���N1���̑�w�I�茠�ł͋������z�����{��B�܂����N3��23������4��16���܂ł�5�̉^�����Ōv62�l�������B�w���Ԃ̊����g������O������w���́A19�`25����1�T�ԁA��ċx�Z�̑[�u��������B
���u���ɗ��Ȃ��łق����v���}�����@�����g��ŗv�� �@8/27
�����E���}���̓��ł��V�^�R���i�E�C���X�̊������g�債�Ă��܂��B���}�����́u�R���i��|���ԁv�Ƃ��āu���ɗ��Ȃ��łق����v�ƈٗ�̌Ăъ|�������Ă��܂��B
���}�����̊����҂͐挎�܂ł͗v��5�l�����ł������A�����ɓ����Ă��瑊�����ŏZ��5�l�̊������m�F����܂����B
�����̋}�g����đ��͍��T����2�T�ԁA�Z�������ɖ߂邱�Ƃ��܂߁A��ނȂ��ꍇ�ȊO�͓��ɗ��Ȃ��悤�Ăъ|���Ă��܂��B
���}�������Ɍ����ďT��2��o�Ă������D��27���ɏo�q���܂������A��q�͂킸��29�l�ł����B
���}�����ό�����E���эL������u(���N�̉Ă�)��N���͊ό��q�����������͎̂����Ȃ�ł����A�ŏI�I�ɂ͂�����ƃR���i���������Ă��܂����Ƃ����̂�����ł��B�ꌾ�Ō����Ă��܂��A������Ǝc�O�Ƃ������A�������ɂȂ��Ă���̂��ȂƂ͎v���܂��v
�s���ł͌y�ǎ҂̎���×{���������܂����A���������g���H���~�߂悤�Ƃ���w�i�ɂ͈�Ò̐��̖�������܂��B
���эL������u�������Ă���^���ƂȂ�ƁA�{�y�Ƃ͑S�R�A��������āA�܂��w���Ƃ��ʼn^��Ă�莞�Ԃ��������Ă��܂��̂ŐS�z�v
���������̎��l�������v������̂́A�R���i�̊����g��O���܂ߏ��߂Ă��Ƃ������Ƃł��B
���V�^�R���i382�l���� 11���Ԃ�300�l��������g�呱���@�k�C���@8/27
�����ł�27���A�V����382�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ����\����܂����B����̊����m�F��400�l�������̂�11���Ԃ�ł����A�ˑR�Ƃ��Ċ����̊g�傪�����Ă��܂��B
�����̐V���Ȋ����m�F�́A�D�y�s��186�l�A����s�ōėz��1�l���܂�45�l�A���َs��19�l�A���M�s��3�l�A�Ύ�n����31�l�A�\���n����28�l�A�_�U�n����16�l�A��m�n����9�l�A�n���n���ƃI�z�[�c�N�n���ł��ꂼ��8�l�A���n���ƍ����n���ł��ꂼ��6�l�A��u�n���Ɠ����n���A����ɋ��H�n���ł��ꂼ��3�l�A�@�J�n����1�l�A����ɓ����u���̑��v�Ƃ��Ĕ��\�������O��5�l���܂�7�l�̂��킹��382�l�ł��B
����̊����m�F��400�l�������͍̂���16���ȗ�11���Ԃ�ł����A�ˑR�Ƃ��Ċ����̊g�傪�����Ă��܂��B
�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂́A�����S�̂�64.2�l�A�D�y�s��94.4�l�ƁA�s���{���̊������������̃X�e�[�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̖ڈ��ƂȂ��Ă���10���l������25�l��傫�������Ă��܂��B
���Ȃǂɂ��܂��ƁA�������m�F���ꂽ382�l�̂�����������4�l�������āA�����ǂ�7�l�A���̂ق��͌y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B
�܂��A382�l�̂���170�l�͊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������6370���ł����B
�܂��A�ψكE�C���X�̃f���^���ɂ��ĐV���ɁA�D�y�s��84�l�A����122�l�A���َs��15�l�A���M�s��4�l�̂��킹��225�l���������Ă���^�������邱�Ƃ�������܂����B
����s�ł͌����̐����Ђ������Ă��邽�߁A���݁A�f���^���Ɋւ��錟���͍s���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
����A���َs�͂���܂łɊ������m�F����Ă����l�̂����A�s���ɏZ�ޔN���ʂ�����\��1�l���S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B
����œ����̊����҂́A�D�y�s�̂̂�3��4387�l���܂ނ̂�5��5420�l�ƂȂ�A���S�����̂�1438�l�A���Â��I�����l�͂̂�4��8838�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�������̊�����
26�����_�̓����̊����𐭕{�̕��ȉ�������̎w�W�����ƂɌ��Ă����܂��B�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����҂�27�����_�̐����ł��B
�a���g�p���@/�@�܂��A��Â̂Ђ�����ł��B�u�a���g�p���v�̓X�e�[�W3��20���ȏ�A�ł��[���ȏ������X�e�[�W4��50���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������46.7���ƂȂ��Ă��܂��B
���@���@/�@�u���@���v�̓X�e�[�W3��40���ȉ��A�X�e�[�W4��25���ȉ����ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������18.1���ƂȂ��Ă��܂��B
�d�ǎҕa���g�p���@/�@�u�d�ǎ҂̕a���g�p���v�̓X�e�[�W3��20���ȏ�A�X�e�[�W4��50���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������11.2���ƂȂ��Ă��܂��B
�×{�Ґ��@/�@�u�l��10���l������̗×{�Ґ��v�̓X�e�[�W3��20�l�ȏ�A�X�e�[�W4��30�l�ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������98.1�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����z�����@/�@�u����1�T�Ԃ̂o�b�q�����Ȃǂ̗z�����v�̓X�e�[�W3��5���ȏ�A�X�e�[�W4��10���ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������9.3���ƂȂ��Ă��܂��B
�V�K�����Ґ��@/�@�u�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����ҁv�̓X�e�[�W3��15�l�ȏ�A�X�e�[�W4��25�l�ȏオ�ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A27�����_�œ�����64.2�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����o�H�s���҂̊����@/�@�u�����o�H���s���Ȑl�̊����v�́A�X�e�[�W3�A�X�e�[�W4�Ƃ���50�����ڈ��ƂȂ��Ă���̂ɑ��A������42.9���ƂȂ��Ă��܂��B
��27���͐X�����ŐV����103�l�̊������m�F�@3���A����100�l�����@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ��ł��B
26���͉ߋ��ő���139�l�̊������m�F����܂����B27����103�l�ƁA3���A����100�l���܂����B�X�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A���łɉ����l�Ȃǂ��܂߂āA���킹��4054�l��4000�l���܂����B
�X���ɂ��܂��ƁA�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A���ˎs��57�l�A�X�s��14�l�A�O�O�ی����Ǔ���11�l�A��\�O�ی����Ǔ���7�l�ȂǁA���킹��103�l�ł��B���ɂ��܂��ƁA�������m�F���ꂽ103�l�̂����A��������56�l�̊����o�H�͕������Ă��܂���B�����o�H�s���͔��ˎs��34�l�A��\�O�ی����Ǔ���6�l�A�O�O�ی����Ǔ���5�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B
����ɔ��ˎs�ł́A24���Ɋm�F���ꂽ�ڑ҂����H�X�Ŕ�������2���̃N���X�^�[���A���ꂼ��g�債�Ă��܂��B1���ڂ̈��H�X�N���X�^�[�̊֘A�ł́A�V����3�l�̊������m�F����A�֘A���܂߂�41�l�Ɋg�債�܂����B
2���ڂ̈��H�X�N���X�^�[�̊֘A�ł͐V����2�l�̊������m�F����A�֘A���܂߂�26�l�ƂȂ�܂����B���ɂ��܂��ƁA28���͈�t��ی��]���҂Ȃ�5�l�Ԑ��Ŕ��ˎs�̎x���ɓ�����Ƃ������Ƃł��B
���@�Ґ��͉ߋ��ő���126�l�ŁA�d�ǂ�1�l�A�����ǂ�16�l�ƂȂ��Ă��܂��B�a���g�p���́A���̎w�W�Ŋ����ҋ}����\���u�X�e�[�W3�v��20������A41.7���ƂȂ��Ă��܂��B
���V����19�l�̃R���i�E�C���X�̊������m�F�@�����g�储���܂炸�@�H�c���@8/27
�H�c�����ł�27���A�V����19�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ����������B�H�c���R���{���s�̈��H�X�Ŕ��������ʓI�N���X�^�[�ł́A�V����2�l�̊������m�F����Ă���B�܂��A25������Վ��x�Z�ƂȂ��Ă���R���{���s���̏����w�Z�́A8�������ς��܂ŋx�Z�̑[�u������邱�ƂɂȂ����B
�H�c�����ŐV���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A10�Ζ�������70��ƔN�����\�̒j���̌v19�l�B���̂����A�R���{���s�Ŕ������������̈��H�X�����ޖʓI�N���X�^�[�ł́A�������50��ň��H�X�̏����o�c�҂Ə����q�A2�l�̊������m�F���ꂽ�B���̃N���X�^�[�ł̓X�i�b�N�Ȃ�23�X�܂ɏ��A�����҂͏]�ƈ���q�Ȃnjv39�l�ƂȂ����B�܂��A8��25������Վ��x�Z�ƂȂ��Ă���R���{���s���̏��E���w�Z�́A8��31���܂ŋx�Z�����������B����A�R���{���s���̌������Z�́A8��29���ɋx�Z�𑱂��邩�f����B
���̂ق���17�l�̂����A13�l�͂���܂łɊ������m�F����Ă���l�̔Z���ڐG�҂ŁA�c��4�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B27���Ɋ����̔��\��������19�l�̒��ŁA�Ǐ�̏d���l�͂��Ȃ��B
�H�c�����ł̊����m�F�͉���1557�l�B2021�N8���ɓ����Ă���̊����m�F��537�l�ƂȂ����B8�����{�ȍ~�Ɋ����҂����������Ă��āA8��15�������1�T�Ԃ�206�l�̊��������������B�܂��A2021�N8�������Ŋ����҂̗v��3���ȏ�A537�l�̊������m�F����Ă���B8��24���ɂ͏H�c�s�Ŕ���������ƑD�̃N���X�^�[�𒆐S�ɁA�ߋ��ő��ƂȂ�50�l�����������B���̂ق��A�R���{���s�̈��H�X�N���X�^�[�����܂炸�A�����Ґ��������グ��`�ƂȂ����B
8��26�����_�̊����Ґ���296�l�B���̂���103�l�����@���Ă��āA���̂���2�l���d�ǂƂȂ��Ă���B�m�ۂ���Ă���273�a���ɑ���g�p���́A37.7�p�[�Z���g�ɏ���Ă��܂��B
���R���i�����}�g��ɑΉ��@149���~������@�Ȗ،��@8/27
���c���26���A�Վ���c���J���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ɑΉ����邽�߂ɂ��悻149���~��lj������\�Z�Ă������܂����B
���͕�\�Z�Ă̒��Ō����ƌ���ɐV�^�R���i�E�C���X�����ǂ̌y�ǎҌ����̏h���×{�{�݂�V�݂����p�Ƃ���43���~���v�サ�܂����B
�܂��A���}�����Ă��鎩��×{���ɗe�̂����������ۂɔ����A�~�}����������Ď_�f���^�Ȃǂ��s����Ë@�ւ�1��������50���~�����͋��Ƃ��Ďx�����܂��B
�ق��ɂً͋}���ԑ[�u�ɔ����x�ƁE�c�Ǝ��ԒZ�k�v���ɉ��������H�X���K�͎{�݂Ȃǂւ̋��͋��Ƃ��Ă��悻80���~�荞�ނȂ�149��1700���~��lj������\�Z�Ă�Ґ����܂����B
���͌��c��Վ���c�ɂ��̕�\�Z�Ă��o���A�S����v�ʼn�����܂����B
���N�x�̐V�^�R���i�W�̕��7��ڂŕ��̈�ʉ�v�̗\�Z���z��1��763��9740���~�ƂȂ�܂��B
���_�ސ��2�l���S�A2662�l�����@�o�H�s��1787�l �@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�����A�_�ސ쌧����27���A�V����2�l�̎��S�ƁA10�Ζ����`100�Έȏ�̒j��2662�l�̊������m�F���ꂽ�B���������o�H�s����1787�l�B
���l�s��70��j���̎��S�\�B���S�����j���̓N���X�^�[(�����ҏW�c)��������������̕a�@�̓��@���҂ŁA16���̌����ŗz���Ɣ����A22���Ɏ��S�����B�p�[�L���\���a�Ȃǂ̊�b�������������Ƃ����B
���P��s��90�㏗���̎��S�\�B�����̓N���X�^�[������������Î{�݂ɐV�^�R���i�ȊO�̎����œ��@����7��24���ɗz���������B�����͖��Ǐ������A8��25���Ɏ��S�����B
���͌��s��30��̒j���s�c�̊����\�B�s�c��25���ɔ��M������A26���ɗz���Ɣ��������B�y�ǂŁA����×{���B�c���T���������̒j���s�c1�����Z���ڐG�҂ɔF�肳��A���̎s�c�͌��ݎ���Ō��N�ώ@���Ƃ����B
���{��s�ł́A�s���̍��Z�ɒʂ����k1�l�̗z�����������A���Z�̊����҂͌v14�l�ɁB���㎩�q���̎s���̕����ł�27���܂ł�12�l�̗z�����������A�s�͂��ꂼ��V���ȃN���X�^�[�ƔF�肵���B
�܂��A�����q�ی������������Ǔ��̊w�K�m�ƁA�����˕ی������������Ǔ��̕a�@�ŐV���ȃN���X�^�[�����������B
�ݓ��ĊC�R���{���n��27���A����n��24���ȍ~�V���ɊW��12�l�̊������m�F�����Ɣ��\�B�܂��ݓ��ĊC�R���؊�n��27���A��n�W��2�l�̊�����V���Ɋm�F�����Ɣ��\�����B
��27���̉��l�A70��j�����S�@1165�l�̊����m�F�A���{�̃N���X�^�[�g��@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�����A���l�s��27���A�s���ݏZ��70��j���̎��S�ƁA10�Ζ����`90��̒j��1165�l�̊�����V���Ɋm�F�����Ɣ��\�����B�d��2�l�A������11�l�A�y��985�l�A���Ǐ�49�l�ŁA118�l�̏Ǐ������Ă��Ȃ��B����781�l�̊����o�H���s���B
�s�ɂ��ƁA���S�����j���̓N���X�^�[(�����ҏW�c)��������������̕a�@�̓��@���҂ŁA16���̌����ŗz���Ɣ����A22���ɖS���Ȃ����B�p�[�L���\���a�Ȃǂ̊�b�������������Ƃ����B���a�@�Ɋ֘A���������҂͌v47�l�ŁA�S���Ȃ����̂�2�l�ځB
�s��10�l�̊��������������ʏ����{�݁A9�l�̊������m�F���ꂽ���ʗ{��V�l�z�[����V���ȃN���X�^�[�ƔF�肵���B
�s��26���܂łɔ��\�������҂̋�ʏZ���n�����́A���̒ʂ�B
�ߌ��恁4545�l�A�_�ސ�恁3898�l�A���恁2011�l�A���恁3400�l�A��恁3982�l�A�`��恁2828�l�A�ۓy�P�J�恁2879�l�A���恁3217�l�A��q�恁2404�l�A����恁2190�l�A�`�k�恁4994�l�A�恁2390�l�A�t�恁3868�l�A�s�}�恁2776�l�A�˒ˋ恁3447�l�A�h�恁1152�l�A��恁1745�l�A���J�恁1397�l�A�s�O��3037�l
�����ʌx�� �ΏۃG���A�g��ց@�V�����@8/27
�V�������̐V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ������~�܂肵�Ă��邱�Ƃ��A�����V���A�����A����J��3�s�ɔ��߂��Ă��錧�Ǝ��́u���ʌx��v�ɂ��āA�ΏۃG���A�̊g����������Ă��邱�Ƃ�26���A���������B��ނ������H�X�ɉc�Ǝ��Ԃ̒Z�k��v������s�������L���A�����ł̊����҂̑�����}�����݂����l�����B���́A27���ȍ~�̊�����s�����̈ӌ����m�F������ŁA�T�����ɂ����{����c���J���A�ŏI���f����B�����̌����������炩�ɂ����B
���ʌx��̊g��ɓ��ݐ�ꍇ�A������Η��T���ɂ��g��n��̈��H�X�Ɏ��Z�c�Ƃ�v�����錩�ʂ��B�g��͈͂ɂ��Ă͈ꕔ�n��Ɍ���Ă̂ق��A�S���ɍL����Ă�����A�����Ȃǂ�T�d�Ɍ��ɂ߂�B
�ً}���Ԑ錾�ɏ������[�u���\�ƂȂ�u�܂h�~���d�_�[�u�v�ɂ��Đ��{�ɓK�p��v�����邩�ǂ������A���̑��{����c�Ɍ����čŏI�����ɓ������͗l���B
������8���ɓ����Ċ����҂��}���B12����1��������̐V�K�����Ґ���100�l���A���̌��100�l�����̓����������B
������A����20���A�V���s�ɏo���Ă������ʌx���2�T�ԉ���������ŁA�����A����J���s�ɂ����ʌx��߂����B�������A���̌�������Ґ��͌����ɓ]�����A25���ɂ͉ߋ��ő��ƂȂ�159�l�̊����҂��m�F����A��苭�͂ȑ[�u�ւ̈ڍs�͕s���ȏ�ƂȂ����B
�����̕a���g�p���͏��X�ɍ��܂��Ă���A��Ì���ւ̕��ׂ����܂��Ă���B���͈�Õ����������邽�߁A�܂h�~���d�_�[�u�̖{���ւ̓K�p�ɂ��Ă����{�Ƌ��c�𑱂��Ă���B
��������ł́A�d�_�[�u�K�p�̖ڈ����ꕔ�w�W���������Ă��Ȃ����߁A�v�����Ă��K�p���F�߂��Ȃ��\��������B���̏ꍇ�ł��A���Ǝ��Ɉ��H�X�ւ̎��Z�v���͈̔͂��L���邱�ƂŊ����̗}�����݂�}��Ƃ݂���B
�Ԋp�p���m����26���A��������ƑΉ������c�B�I����A�Ԋp�m���͕w�Ɂu������i�����[�u�����K�v������v�ƌ�����B
���u���ʌx��g����j�v�ɗ������@�V�����@8/27
�����̐V�^�R���i�E�C���X�̊����ҋ}�����A���͐V���A�����A����J��3�s�ɔ��߂��Ă��錧�Ǝ��́u���ʌx��v�̑Ώےn���S���Ɋg�傷����j���ł߂��B�����̕�����27���A�u�ꕔ�n�悾���Ŋ�����}�����ނ̂͑�������v�u�����̈ӎ���ς���K�v������v�Ƃ��A�S�����܂߂��G���A�̊g��ɗ������������B�������g�債�Ă���n��̎���́A��苭��������߂鐺���オ�����B
�u���~�߂�����A���ɓ��ʌx����o���悤���肢���Ă����v�ƌ����̂́A�����҂��}������ܐ�s�̈ɓ������s���B����1�T�ԁA�h�Ж�����[���Œ��ӊ��N�𑱂��邪�A�u�s���ɋ�����@���������Ă��炤�K�v������v�Ƒi���A�Ώےn��g������߂��B
����1�T�ԂŊ����҂��o�Ă��Ȃ����n�s�̓n�ӗ��s�����u���ʌx��͑S���Ɋg�債�A�����ɋ������b�Z�[�W���o���ׂ����v�Ƌ�������B����܂ł̊����҂�5�l�ɂƂǂ܂��Ă��鈢�꒬�̐_�c��H�����́u���͊����g���}�����Ă��邪�A���̑Ή��ɋ��͂������v�Ƙb�����B
���͎s�����̈ӌ����m�F������ŁA30���ɑ��{����c���J���A�ŏI���f����B��z�s�̑��R�G�K�s���́u�V���ȑΉ������Ȃ���Ί������g�債�A�s���ɕs�����L����B���̉�c�ł�������c�_�����ׂ����v�ƌ��̔��f�𒍎�����l�����������B
����ŁA���ً͋}���Ԑ錾�ɏ������[�u���\�ƂȂ�u�܂h�~���d�_�[�u�v�ɂ��Ă��A���{�ɓK�p��v�����邩�ǂ����A�l�߂̋��c�����Ă���B
���ɓ��ʌx�o�Ă���V���s�́A��ނ������H�X�Ȃǂɉc�Ǝ��Ԃ̒Z�k��v�����Ă���B27����ɔɉ؊X�Ŏ�҂�Ɋ������O����Ăъ|������������s���́A�u���~�̋A�Ȃ�ċx�݂̉e��������A���Z�̌��ʂ͂܂��\���ɕ\��Ă͂��Ȃ��v�Ǝw�E�B���̏�Łu����ȏ㊴�����g�債���ꍇ�ɂ́A�d�_�[�u�ȂǂŎs���ɋ��������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�����s�̈�c�B�L�s���́A��������l�̉����������A�����g��ɂȂ����Ă���Ƃ݂āA�u���͑S���ɋً}���Ԑ錾���o���A��������ړ���}���Ă����ׂ����v�Ƃ̌������������B
�������{�݂�6�l�����@���Ə�23�l�Ɋg��@�×{�ҁu�ő�1126�l�v�@���쌧�@8/27
���쌧���ŐV����117�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��܂����B3���A����100�l�ȏ�ł��B�×{���̐l�́A1126�l�ƂȂ�2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
�������킩�����̂́A10�Ζ�������90�Έȏ�̒j��117�l�ł��B27�̎s�����Ŋm�F����A���{�s24�l�A����s18�l�A���ܖ�s12�l�A��c�s9�l�A��Ȏs7�l�A�ɓߎs4�l�A���v�s�E�z�K�s�E�y��E�ؑ��E�}�k���E���쑺�Ŋe3�l�A�咬�s�E����s�E�C�쒬�E���ؑ��Ŋe2�l�A���K�s�E����s�E�ѓc�s�E���Ȓ��E���a���E�r�c���E�x�m�����E���֒��E���쒬�E���J���E���쑺�Ŋe1�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����s�E�_�ސ쌧�Ŋe2�l�A��t���E���{�Ŋe1�l�̊������킩��܂����B
1���̔��\�ł́A3���A����100�l������A���~�܂肪�����Ă��܂��B
���́A����ی����Ǔ��̕����{�݂ł���܂łɐE��3�l�A���p��3�l�̍��v6�l�̊������m�F�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���͎{�ݓ��̖�30�l�̌�����\�肵�Ă��܂��B
����܂ł�20�l�̊������m�F����Ă��鏼�{�ی����Ǔ��̎��Ə��ł́A�V���ɏ]�ƈ�3�l�̊������킩��A���v23�l�ɂȂ�܂����B��180�l�̌�����\�肵�Ă��āA����܂ł�30�l�̌������I���܂����B
27�����\�̐V�K�����҂̂����A68�l������܂ł̊����҂̔Z���ڐG�҂܂��͐ڐG�ҁA���O�Ƃ̉����A�؍݂��������l��12�l�A���O���Z�҂�6�l�A�����o�H�s����30�l�ƂȂ��Ă��܂��B����A�]�ƈ���̊������������A����26���ɓX�������\�����ѓc�s���̈��H�X�uClub Lucina�v(�N���u�@���L�i)�ɂ��āA�A�����Ƃ�Ă��Ȃ��������p�q11�l�̂���8�l����A�����������Ƃ������Ƃł��B���́A����21���ɂ��̓X��K�ꂽ�l�́A�Ǐ�̗L���ɂ�����炸�A�Ŋ��̕ی����ɘA�����Ăق����ƌĂъ|���Ă��܂��B
�����̊����҂̗v��7617�l�ɂȂ�܂����B�×{���Ă���l��1126�l�ƂȂ�A2���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B����͓��@��242�l�A�h���×{��242�l�A����×{��356�l�A������286�l�ƂȂ��Ă��܂��B�d�ǂ�4�l�A�����ǂ�55�l�ł��B(27���ߌ�4�����_)
�����S�̂̊m�ەa���g�p���͑O�����1.6�|�C���g����51.0%�B�����ǁA�y�NJ��҂�������ʕa���̎g�p���͒n��ʂɖk�M71.2���A���M59.2���A���M47.3��
���R���i�����ҁ@���C3����3040�l�A�e���Ƃ��ߋ��ő��@8/27
���C3���ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�~�܂炸26���A���m�E�E�O�d���Ŋm�F���ꂽ�V�K�����҂́A����������̉ߋ��ő����X�V���܂����B
���C3���ł�26���A����܂łōł�����3040�l�̊������m�F�B�܂��A�V����3�l�̊����҂����S���Ă������Ƃ�������܂����B
���m���ł͓����A�ߋ��ő���2141�l�̊������m�F�B2000�l����̂͏��߂Ăł��B�܂��A����12���Ɋ������Ă��������1�l�����S���Ă������Ƃ�������܂����B
���ł͉ߋ��ő���384�l�̊������m�F�B�܂��A25���ɂ͊s��90��̒j�������S���Ă��������Ƃ�������܂����B
�O�d���ł͉ߋ��ő���515�l�̊������m�F�B25���ɂ�70��̒j�������S���Ă������Ƃ�������܂����B
���ۈ牀��w�K�m�ŐV���ȃN���X�^�[�@����308�l�����@8/27
���Ɗs��27���A����29�s���ȂǂŌv308�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B1��������̊����҂͉ߋ��ő����X�V�����O������76�l���������A4���A����300�l�����B�����҂͗v1��4358�l�ƂȂ����B
����1�T�Ԃ̐l��10���l������̐V�K�����Ґ���113�E56�l�B26�����_�̓��@���҂�500�l�ŁA�a���g�p����63�E9���ɏ㏸�����B����×{�҂͑O����162�l����685�l�ƂȂ����B�d�ǎ҂�7�l�̂܂܂����A50��̊���1�l���l�H�S�x���u�u�d�b�l�n(�G�N��)�v���g�������ÂƂȂ����B
�V����5���̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F�����B���̂����e�����s�̊w�K�m�Œ��w���⏬�w���̐��k14�l�ƁA�u�t1�l�̊����������B���k�̉Ƒ�1�l�ɂ��L����A�v16�l�̃N���X�^�[�ƂȂ����B���̊w�K�m�ł͍u�t�A���k�Ƃ��}�X�N�𒅗p���A�����J���Ċ��C�����Ă����Ƃ����B
���ɔ��Z���Ύs�̕ۈ牀�ɒʂ�����5�l�ƐE��2�l��9�l�̃N���X�^�[��A�y��s�̕����{�݂̗��p��4�l�ƐE��1�l���܂�10�l�̃N���X�^�[���m�F�����B
�g�債���N���X�^�[��12���B2���̃N���X�^�[�͐V���Ȋ����҂��m�F���ꂸ�A�I�������B
�����N�������̖x�T�s�����́A�w�K�m�Ŕ��������N���X�^�[�ɂ��āu�ォ��U��Ԃ�ΏǏ������̂ɍs���Ă������k������B�̒��������l�͏o�|���Ȃ����Ƃ��厖�v�Ƙb�����B
�V�K�����҂̋��Z�n�ʂ͊s80�l�A�e�����s38�l�A��_�s31�l�A���s25�l�A���Z���Ύs18�l�A�H���S��쒬11�l�A�������s�A�C�Îs���e10�l�A���R�s�A�֎s�A���Ð�s�A�b�ߎs���e7�l�A�{�V�S�{�V���A�s�j�S���䒬���e6�l�A�H���s�A����s���e5�l�A���Q�s�A�y��s�A�H���S�}�������e4�l�A���Z�s�A�S��s�A�K��S��쒬���e3�l�A���C�s�A�s�j�S�փP�����A���S�䐓�����e2�l�A�R���s�A�{���s�A�����S�������A�K��S�r�c�����e1�l�B���m��4�l�B
�N��ʂ�10�Ζ���25�l�A10��55�l�A20��72�l�A30��50�l�A40��47�l�A50��38�l�A60��10�l�A70��2�l�A80��6�l�A90��3�l�B
��������v�ے��Ԓn�ŃN���X�^�[�g��@524�l�V�K�����@���s�{�@8/27
���s�{�Ƌ��s�s��27���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă���1�l�����S���A�V���ɒj��524�l�����������Ɣ��\�����B�{���̊����Ґ��͌v2��8398�l�ƂȂ����B
�{���\����10�Ζ�������80��܂ł�167�l�B�Ǐ�͒������������y��66�l�A���Ǐ�7�l�B�����o�H�s����121�l�B�N���X�^�[(�����ҏW�c)�֘A�ł́A����܂�30�l�̗z�����������Ă������㎩�q����v�ے��Ԓn(�F���s)�ŐV����5�l���������A�v35�l�ƂȂ����B���Z�n�ʂ́A�F���s29�l�A�������s16�l�A���s�s�Ɣ����s�e15�l�A�T���s13�l�A���c�ӎs12�l�A��z�s10�l�ȂǁB
�܂��{���ς�27���A�k���㍂(�E����)�œ����������ɏ������鐶�k11�l�̊�����������A�v20�l�ɂȂ����Ɣ��\�����B
���s�s���\����357�l�������B
���V�^�R���i���������̑��I3���A��2800�l���I�c�@���{�@8/27
���{��27���A�V����2814�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\���܂����B�܂������p�������s�b�N���J�Â���Ă��铌���s�ł�4227�l�̊������A���Ɍ��ł͐V����1061�l�̊������m�F����܂����B
�N��ʂōł������̂�20���727�l�A������10���491�l�A30���451�l�ł��B�܂����A�w��142�l�A�A�w��99�l�̊������m�F����Ă��܂��B�S���Ȃ����l��2�l�A�d�ǎ҂̊��҂͌v202�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����34�D4���B�܂�����×{�҂�17046�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����g�傪�~�܂�Ȃ��A���c�@���{�̐V�K�����҂͘A���A2800�l���Ă��܂��B�܂��A6��2���ȗ��A200�l���������d�ǎҁB���̓��A26�����_�ŏd�lj������l��23�l��7�l��40��ȉ��B���ɂ͊�b�����̂Ȃ�20��̒j�����B����ɖS���Ȃ���6�l�̂���3�l��40��ƂȂ��Ă��܂��B�L����Ⴂ����ւ̊����B���ł��D�w�̊����҂������Ă��܂��B
�g���m���́c�u���N�`���Ɋւ��ĔD�w�E�p�[�g�i�[�̃��N�`���ڎ�D����J�n���܂��B1��300��D�w�D��̃��N�`���Ƃ��Đڎ�����Ă��������v
���Z��q�ɉ^�A�^���{����s�ŏ]�ƈ����V�^�R���i�����@ 8/27
�Z��q�ɉ^�A��8��27���A���{����s�̎��Ə��ɋΖ�����]�ƈ�1���̐V�^�R���i�E�C���X������8��26���Ɋm�F�����Ɣ��\�����B
�Z��q�ɉ^�A�́A8���ł�19���ɑ��{����s�̎��Ə��ɋΖ��̃O���[�v��Ђ̏]�ƈ�1���A3���ɂ͑��{�ےÎs�̎��Ə��ɋΖ�����O���[�v��Ђ̏]�ƈ�1���̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���Ă���B
���Ђł́A�V�^�R���i�����g��h�~��Ƃ��āu���Ə�̊��C�Ƌ��L�����̏��ł̓O��v�u�����O�o���̎��l�v�u�����o�̗�s�v�u�Г���c�Ȃǂ�Web��c�V�X�e���Ŏ��{�v�u�o�БO�̑̉�����̎��{�v�u���ŗp��ނ̑S���Ə��z���v�u�E��̕��U���A�ʋΎ�i�̕ύX�v�u�r�j�[���J�[�e���̐ݒu�ȂǁA3���̓O�����v�����{���Ă���A�����ǂ̗��s(��イ����)���I������܂Ōp������B
�܂��A������]�ƈ��ƊW�҂̈��S�m�ۂ��ŗD��ɁA�V���Ȋ����Ҕ����̑j�~�Ɗ����g��h�~�̎��g�݂��������Ă����Ƃ��Ă���B
���q�ǂ��̊����g��A��4�g��3�{�@�d�lj����X�N�͒Ⴂ�����N�`���ڎ�@���Ɍ��@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����͂������Ƃ����f���^���̉e���ŁA���Ɍ����ł��S���Ɠ��l��20�Ζ����̎q�ǂ��̊������}�g�債�Ă���B�����ł͑�4�g�̃s�[�N��3�{�߂��q�ǂ��̊����҂��m�F����A�V�K���҂�2������B�s��������ی�҂͑������A�����_�ŏd�lj�������͂قڂȂ��Ƃ����B����ŁA�q�ǂ��̊������ƒ��������w�Z�ł̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�ɂȂ��鋰�ꂪ���邽�߁A��t�͈��������\�h�̓O����Ăъ|���Ă���B
���t�̑�4�g�ŁA20�Ζ����̐V�K�����҂��ł����������̂�4��17����102�l�B7������̑�5�g�̊����g����A8��24���ɂ�282�l���m�F���ꂽ�B
�����̏�����ÊW�҂ɂ��ƁA��24�����_�Ō����œ��@����15�Έȉ��̊��҂�5�l���x�B�_�ˎs�ی����̓��@�����̐ӔC�҂́u�����͐e�ƂƂ��Ɏ���×{���Ă���v�Ƙb���B
�������ǂ��a�@(�_�ˎs������)�ł�1��8���`8��26���ɏ�������18�l�����ꂽ�B1�Έȉ���7�����A�S���y�ǂ������B
�����Ǔ��Ȃ̊}�䐳�u����(49)�����������NJw��������u���Â͂قƂ�ǕK�v�Ȃ������v�Ɛ����B��5�g�ł́A���M���o����q�f�����肷��q�ǂ����������A�_�H���M�܂Ŏ��邽�߁A�R���i���Ö���g�������Ƃ͂Ȃ��Ƃ����B
�����u��b�����̂���q�����������ꍇ�A�G�N��(�l�H�S�x���u)���K�v�ȃP�[�X������Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��v�Ɗ}�䕔���B�V�w���ɓ���A�N���X�^�[���N����\��������B�u5�g�͊����̑����������B���������łȂ��A������q�f�ȂǏ����ł��̒��������Ȃ�R���i���^���Ċw�Z���x��łق����v�Ƒi�����B
������葍����ÃZ���^�[(���s)�������R���i�a����3�������邪�A�قƂ�ǎg���Ă��Ȃ��B��N4�����獡�N8��26���܂ł�23�l������A�S�����y�ǁB���������e�Ƒ�l�̕a���ɓ���q���唼�������B
���������Ǔ��Ȃ̈ɓ��Y��Ȓ�(42)�́u�q�ǂ��̏d�lj����X�N���̂͒Ⴂ�v�Ƃ��A�ƒ���Ŏq�ǂ����犴��������l���d�lj�������A�q�ǂ��̊����g��Ŋw�Z�s���ɉe�����o���肷�邱�Ƃ����O�B�_�ˎs��P�H�s�ŊԂ��Ȃ��n�܂�12�Έȏ�̃��N�`���ڎ�ɐG��A�u�Ƒ��̖���w�Z��������邽�߂Ɋ��߂����v�Ƙb���B
���ێR�������m���A���r�����s�m���̃R���i�Ή���Ҕᔻ�@8/27
�������̊ێR�B��m����26���A����̑S���m����̑�������j�̐���������A�u47�s���{������v�������ĐV�^�R���i�E�C���X�̊�����Ɏ��g�ށv�Ƃ�����|�̕������폜����悤���߂�l���𖾂炩�ɂ����B�V�^�R���i�E�C���X��������߂��鏬�r�S���q�E�����s�m���̎p���ɑ���s�M��������悤���B
26���ɓ��������ł������L�҉�ŏq�ׂ��B
�ێR���́A�����ܗցE�p�������s�b�N�g�D�ψ���s���ō��ۃp�������s�b�N�ψ���(IPC)�W�҂̊��}����J������A���r���炪�o�Ȃ����肵�����ƂɌ��y���A�u����Ȃ��Ƃ����Ă���ꍇ���v�ƌ������ᔻ�����B
�ێR���́A���r�����s�c��ŁA�����ܗ֊J�Âɂ��āu�����̒�͂��������v�Ɣ����������Ƃɂ��G��A�u���̒�͂�10����1�ł�10����2�ł��V�^�R���i�����g��h�~�ɐU������Ăق��������v�Əq�ׂ��B
�s�Ȃǂ��p�������s�b�N��������k�Ɋϐ킵�Ă��炤�u�w�Z�A�g�ϐ�v���O�����v��i�߂Ă��邱�Ƃɂ��Ă��A�u�{���ɐV�K�����҂����炻���Ǝv���Ă���l������Ă��邱�ƂƂ͎v���Ȃ��v�Ǝw�E���A�u���̑S���m�����������A47�s���{������v�������Ċ�����Ɏ��g�ށA�Ƃ��������𗎂Ƃ��ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���v�Əq�ׂ��B
�ێR�m���͈ȑO����A�����s��{�̐V�^�R���i�E�C���X���ᔻ���Ă����B���������ł̓����ܗ������[�̒��~����������ƕ\���������Ƃ��������B
���u�w�т̋@��v�ǂ��ۏ�@�R���i�����g��̒��n�܂�V�w���@���茧 8/27
�V�^�R���i�E�C���X���҈Ђ��ӂ邤���A���茧���̑����̊w�Z��9��1���ɐV�w�����}����B�S���I�Ɏq�ǂ��̊������Ⴊ�����Ă��邾���ɁA����́u�w�т̋@��v��ۏ��邽�߁A�����̓O�����Ƃ̃I�����C�����Ȃǂ��܂��܂ȍ���u���Ă���B
���ő���x��
�呺�s���̏����w�Z��26���A2�w�����X�^�[�g�B���H��27������n�߂邪�A�����}�g����A8�����͌ߑO�܂ł̎��ƂƂ���B���s�蓇1���ڂ̎s���呺���ł́A����������ł̌������ʂ��L�������J�[�h�����Q���ēo�Z�B�C���O�ŋ��t���o�}���A�Y�ꂽ�q�̑̉��𑪂����B�n�Ǝ��̓����[�g�`���B�����M���Z���͉�ʉz���Ɂu(������)�w�ЊQ���x�ƌ����钆�A��l��l�������ɂł���\�h����l���邱�Ƃ��厖�B�͂����킹�ď��낤�v�ƌĂъ|�����B6�N�̎R�������N(12)�́u�R���i��͖ʓ|�ȂƂ��낪���邯�ǁA��������C��t���Ă��������v�Ƙb�����B���s���ςɂ��ƁA�s�������w�Z���E���̓��N�`���̐�s�ڎ���A74����2��ڂ܂ōς܂����B�����ς�18���A���c�C�O���璷�ً̋}���b�Z�[�W�������w�Z�ɏo�����B�ċx�ݖ�����2�T�Ԃ���ɒ��ӂ��A�Z����ƒ���ł̊����g��Ɂu�ő���̌x���v���悤���߂��B����s���R5���ڂ̌������蓌����20��������Ƃ��ĊJ�B9��3���܂ł��u�����g��h�~�O����ԁv�Ƃ��A���֎��ӂɌ[���|�X�^�[��o�����B����܂ł��}�X�N���p�⊷�C�̓O��A���H���́u�ِH�v�ȂǂɎ��g��ł���u�V���ȑ�����͓̂�����A���k�ɋC���������ߒ����Ă��炤�v�B
���I�����C��
���ƂɃI�����C�������铮��������B���s�������̒����t�����E����9��1�`6���A�o�Z������߁A1�l���z�������m�[�g�p�\�R���Ŋw�Z�Ǝ���Ȃǂ��Ȃ����Ƃ��s���B���勳��w���̓��{�o�w�����́u�ƒ�����̈�Ď��{�͏��߂Ă����A��N10���ȍ~�A���ƂŃp�\�R����ϋɊ��p���Ă���A���Ȃ��ƍl���Ă���v�Ƙb���B����A����A�����ۗ��s���̎s�����A���w�Z�͗\��ʂ�9��1������2�w�����n�߂�B�����ێs���ς́A���s��27������A�܂h�~���d�_�[�u���ɂȂ�̂܂��A���U�E�����o�Z���������������������B�S���҂́u�܂��͂���܂ł̊������O�ꂵ�Ă��炤�B���S�E���S���d�����Ȃ���w�т̋@�����Ă��������v�Ƙb���B
���������w��
���O����i�w����72�l�́u�������w���v���ʂ��Δn�s�������̌����Δn���B�A�Ȃ��I���Ė߂������k�ɂ͍R����ʌ����������A�w�Z���ł͌������ʂ��o���낤�܂ŐH���ł̐H�����ւ��A�e�����Łu�H�v�Ƃ����B�A���M�s�Z���́u�����̈�Ñ̐����l����A�����g��͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƙb�����B
���F�{�����u�����I�����g��v�����@�����@2�T�����ďT1500�l�� �@8/27
�F�{����27���A�����̐V�^�R���i�E�C���X�������A���{���ȉ�w�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4(�����I�����g��)�v�ɂ���Ƃ̔��f���ێ�����Ɣ��\�����B�X�e�[�W4��4�T�A���B1�T�ԓ�����̐V�K�����҂�2�T������1500�l���������B
25���܂�1�T�Ԃ̊����҂�1628�l�ƁA�O�T��1513�l���瑝���B�X�e�[�W4�(1�T�Ԃ�437�l)��3�E7�{�ɒB�����B���Ǝ��̃��X�N���x�����ŏ�ʂ́u���x��5(�����x��)�v���ێ������B
�ی����ʂł́A11�J����8�J�����X�e�[�W4�(10���l������25�l)�ɊY�����A2�J�����X�e�[�W3�(��15�l)�ƂȂ����B
���ƌF�{�s�̐��Ɖ�c�̔n��G�v����(�F�{��w�a�@��)�́u����Ȃ銴���g�傪�N����A��Õ������I�ƂȂ�v�Ǝw�E�B���N�`���ڎ�̐��i��l���m�̐ڐG�@��̍팸�����߂��B
��8�������A19�Έȉ���23���@�u��l�o�R�v�ŋ}�g��@���������@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�́u��5�g�v�ŁA������ɂ����Ƃ���Ă����q�ǂ��̊����������������ő����Ă���B8���̊����҂ɐ�߂�19�Έȉ��̊�����2�����A�ی����́u�e����q�ǂ��ւ̉ƒ���������}���ɍL�����Ă���v�Ǝw�E�B�����͂������f���^�����܂��钆�A�V�w�����T���A���Ƃ͋��E�����l�̃��N�`���ڎ킪�d�v�Ƌ�������B
����{�V���̂܂Ƃ߂ɂ��ƁA8��1�`26���Ɍ��\���ꂽ19�Έȉ��̊����҂�837�l�ŁA�S�̂�23.4���B�u��4�g�v�̎����ɓ�����4��27���`5��31����165�l�̖�5�{�ŁA�S�̂ɐ�߂銄����10.6�|�C���g�������B8���͎q�ǂ�����̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���A�w�Z�̉ۊO�����╔�����A�����{�݂Ŋm�F���ꂽ�B
�u����܂ŁA�e�����������ꍇ�ɉƒ���Ŏq�ւ����̂�1���ɖ����Ȃ���ۂ��������A���͂قڑS�Ă����Ă���v�B�������s�ی����̐����u�E�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ��͘b���B
�f���^�������҂̃E�C���X�r�o�ʂ́A�]�����̖��{�Ƃ̕�����B�}�X�N���O���Ƃ̒��ł́A��C���Ɋ܂܂��E�C���X�ʂ������Ȃ肪�����B�������́u�ċx�݂Őe�q�ꏏ�ɉ߂������Ԃ������A�������₷���Ȃ��Ă���v�Ƃ݂�B
�����ǂɏڂ�����������w��w�@�̐�����Y�����́u�q�ǂ�����q�ǂ��ւ̊����g��͂قƂ�NJm�F����Ă��Ȃ��v�Ǝw�E�B�w�Z����ł̑�́u���E�������N�`����2��ڎ���ς܂��A��H�ȂNJ������X�N�̍����s�������Ȃ����Ƃ������厖�v�Ƌ�������B
�����\�h���ʂ������s�D�z���}�X�N�̒��p�����߁A�����ł̕������́A���̌x������u�X�e�[�W4(�����Ҕ����I�g��)�v�̊Ԃ̎��l�����߂�B�������́u�q�ǂ��{�l�͂������A���������l�ɔ��M�Ȃǂ̏Ǐ���Γo�Z�����Ȃ��łق����v�ƌĂъ|���Ă���B
���V�^�R���i �S���Ŗ�2��5000�l������ �Ⴂ����̊����g��@ 8/27
�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��đS���ł��̂��A2��4969�l�̊��������\����܂����B
���̂��A�����s�ł�4704�l�̊������V���ɔ��\����܂����B�N��ʂł�20�オ1330�l�ƍő��ŁA���̂ق�10���481�l�A10�Ζ����ł�328�l�ȂǁA�Ⴂ����ւ̊����g��Ɏ��~�߂��������Ă��܂���B
�s���{���ʂł́A���傤����ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��ɂȂ鈤�m���ł͏��߂�2000�l���܂����B���̂ق����A���s�A�O�d�Ȃ�8�{���ʼnߋ��ő����X�V���Ă��āA�S���ł͂��̂��V����2��4969�l�̊��������\����܂����B
�܂��A�S���œ��@���Ă��銴���҂̂����u�d�ǎҁv�Ƃ����l��1974�l�ƁA14���A���ʼnߋ��ő����X�V���܂����B
���V�^�R���i�}�g��ŘI�悵�����{��Â̂��낳�@ 8/27
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̃f���^�ψي��g��ŕa�@�̕N������������{�̈�ÃV�X�e���̐Ǝコ���I�悵���B���E�I�Ɍ��ď���ȕa����������Ȃ��礋~�}�����҂����@�ł��Ȃ��P�[�X���������̂͂Ȃ����B�ЂƂ��ɋً}���Ԃւ̔�����ӂ��Ă�����Ð���ɕs��������Ƃ̐����オ���Ă���B
��t��w��w�������a�@(��t�s)�̒��c�F���~�}�Ȓ��ɂ��Ƥ�ŋ߂͢�~�}�ԓ��ʼn����Ԃ��߂����Ƃ����̂͂悭���飂��Ƃ��Ƃ����B���ɂ͗e�̂̈��������R���i���҂@�������Ŏ����ꂸ��l�H�ċz������Ȃ���������҂��������܂ł�16���Ԃ�v��������������B
�S���̏d�ǎҐ���2000�l�߂��ɒB����N��ʂł�65�Έȉ����ڗ����Ă���B��t��a�@�̏W�����Î�(ICU)�ł�30�|50��̊��҂������B���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l���d�lj����₷���ICU�̊��҂͐ڎ킵�ĂȂ��\��������ƒ��c���͐������邪��e�̂̈��������b���܂܂Ȃ炸��ڎ�͏\���ɔc������Ă��Ȃ��B
�����ȏ��h���̓��v�łͤ22���܂ł�1�T�ԂɋN���������s�̋~�}��������Č���1645���ƍ�N�̓����ԂƔ�ה{�������BTBS�̕ɂ��Τ�����ɓ��褓s���ł͎���×{����11�l���S���Ȃ����B
���{��t�1���Ɍ��\���������ɂ��Ƥ���{�͐l��1000�l������̕a������13���Ƥ��v7�J��(G7)���Œf�g�c�B��������f���^���̖҈ЂőS����1���̐V�K�����Ґ��͘A��2���l�Ƌ}�����Ă��褕a�����̂̕s������邢�͐l�ޕs���Ŋm�ۂ����a�����\���Ɋ��p�ł��Ȃ����ԂɊׂ��Ă���B
�J�ƈ�ň�Ìo�σW���[�i���X�g�̐X�c�m�V���ͤG7�̏Ɣ�r���Ȃ��礓��{�͑��ΓI�ɢ�a�����������Ċ����Ґ��͏��Ȃ���ƕ��́B�{���͗]�T�������ē��@�҂̑����ɑΏ��ł����ɂ�������炸���ÕN���������N�������̂͢�m���Ɉ�Ãf�U�C���̖��ł��褐��x���Ŗ�肪����ƌ��킴��Ȃ���Ǝw�E����B
�X�c���ɂ��Ƥ�p���Ȃlj��B�ł͌��I�Ȉ�Î{�݂�������a�������̍ۂɂ͐��{���a�@�ɒ��ڎw������V�^�R���i�p�̕a����v���ɑ��₷���Ƃ��\���B�������{�̏ꍇ�͑唼�����ԕa�@�Ť���{�͋����w�����o���闧��ɂȂ���l��������̕a���������Ă�����͕⏕���ŗU�������i�����Ȃ��B
2019�N10�����_�̌����J���Ȃ̒����ɂ��Ƥ�S����8300����a�@�̂����5894�{�݂̊J�ݎ҂͖@�l�������͌l�������B���Â��s��V�X�e���ɔC������������Ă��Ă��飂ƐX�c���͌����B
�V�^�R���i��Ƃ��č��͑��z��3���~�̢�ً}��x����t��(��Õ�)�����������d�NJ��җp�̕a���ɑ�1���ő�1950���~��a�@���Ɏx�����Ă���B��t��a�@�ł�ICU��S�ăR���i�����ɓ]����������ŕa������6������10���Ɋg�債���B�V�^�R���i�����ǂ̑Ή��ɂ͏]�����l��������邽�ߤ�Ō�t�̐����\���l�܂ő��₵��Ή����Ă���B
�������X�c���ͤ�R���i���҂�f�Â���a�@�ɂ��Ă͊��������ꑼ�̊��҂��f�@���ɗ��Ȃ��Ȃ�ȂǕ��]��Q���L����\�������褕⏕�������ł͌��ʂ�������Ƃ݂Ă���B
��t��a�@�łͤ������i�̊����g��ɔ�������𑝂₷�����͂��Ă�����̤̂���̃X�^�b�t��Ō�t�̉������K�v�Ť�R���i�ȊO�̈�ÃT�[�r�X�𒆎~������Ȃ��ɂ��Ȃ��Ă���B
�܂���R���i��p�a���ɂ͐��|��Ƃ̕��S���d���Ƃ�����������B���@�ŐV�^�R���i�Ή����w�����钖��p�r�������䕔���ͤ�Ō�t���{���̋Ɩ��ɐ�O�ł��������`�x�[�V�����̒ቺ�ɂ��Ȃ�������Ɖ�ځB�悤�₭�ŋ߂ɂȂ褐��|����Ǝ҂Ɉϑ����邱�Ƃ��ł����Ƃ����B
���뎁�ͤ�h���×{�{�݂ł������悤�Ȗ�肪����Ǝw�E�B�Ǝ҂ɂ�鐴�|�̓t���A���Ƃɍs����ȂǢ�`�F�b�N�A�E�g���Ă����Ɏ��̊��҂������悤�ȉ^�p�ɂȂ��Ă��Ȃ�����ߤ�ғ������オ��Ȃ��Ƃ����B
��Ñ̐��͌������𑝂��������������̐V�K�����Ґ��ɑ���1���̎��S�Ґ��͍�N5���̔����ȉ��ɂƂǂ܂褊C�O�Ɣ�ׂĂ����ΓI�ɗ}�����Ă���B���{�łͤ�d�lj����X�N�̍���65�Έȏ�̍���҂ɑ��郏�N�`���ڎ��D��I�ɐi�߂Ă����B
��ÃK�o�i���X�������������̏㏹�L��t�͢���{�̎��Ґ���G7�̒��Ńh�C�c��葽�����2�Ԗڂɏ��Ȃ���Ƃ�����N�`���̐ڎ���i�ݤ����̑�5�g�͍�N���̂悤�ɍ���҂������S���Ȃ鎖�Ԃɂ͎����Ă��Ȃ��Ƃ݂Ă���B
����������͂��Âɗ��邱�Ǝ��̂Ɍ��E������Ƙb�����Ƃ�����B������w��w�@�̍⌳�������C������(���O�q���w)�͢�ǂ�قLj�ÃV�X�e�����������ĂऐV�^�R���i�̂悤�Ȋ����ǂ��}�����Ă͑Ή�����Ȃ���Ǝw�E�B�����̊g���h�����Ƃ�����Əq�ׂ��B
���ҋ@�������ߋ��ŏ� �R���i�����s���ŕۈ珊���p�T�������@8/27
�ۈ珊�Ȃǂ̋�҂u�ҋ@�����v�͂��Ƃ�4���̎��_�őS����5600�l�]��Ƌ��N���6000�l�ȏ㌸��������܂łōł����Ȃ��Ȃ������Ƃ��킩��܂����B�����J���Ȃ́A�ۈ�̎M�̊g���V�^�R���i�E�C���X�̊����ւ̕s������A�ۈ珊�̗��p���T����ی�҂��������啝�Ɍ��������Ƃ݂Ă��܂��B
�����J���Ȃɂ��܂��ƕۈ珊�Ȃǂ̋�҂u�ҋ@�����v�͂��Ƃ�4���̎��_�őS����5634�l�ł����B���N4���Ɣ�ׂ�6805�l�������A����܂łōł����Ȃ��Ȃ�܂����B�ҋ@�������O�̔N��茸�����̂�4�N�A���ŁA�������͍��̕��@�Œ������n�߂�2002�N�ȍ~�ōł��傫���Ȃ��Ă��܂��B�s���{���ʂł݂�ƁA�ҋ@�������ł����������͓̂�����969�l(�O�N��−1374�l)�A�����ŕ��ɂ�769�l(�O�N��−759�l)�A������625�l(�O�N��−564�l)�ŁA36�̓s���{���őO�̔N��茸�����܂����B����A�ҋ@���������Ȃ������̂͐X�A�R�`�A�ȖA�V���A�x�R�A�ΐ�A����A�R���A�A����A����A�啪��12�̌��ł����B�����J���Ȃ́u�ҋ@���������炷���߂̕ۈ�̎M�̊g���V�^�R���i�E�C���X�̊����ւ̕s������ۈ珊�̗��p���T����ی�҂��������啝�Ȍ����ɂȂ����v�Ƃ݂Ă��܂��B����ŁA�����J���Ȃɂ��܂���25����44�܂ł̏����̏A�Ɨ��͂��Ƃ��͏㏸����X���ƂȂ��Ă��āA�ۈ珊�Ȃǂ̗��p�̐\�����݂͍Ăё�������\��������Ƃ������Ƃł��B�����J���Ȃ́u�ҋ@�����̏Ȃǂ��m�F���Ȃ���K�v�ȕۈ�̎M�̊m�ۂ��i�ނ悤�Ɏ����̂̎x�����s���Ă��������v�Ƃ��Ă��܂��B
�ҋ@�����̌���ɏڂ����ی�҂Ȃǂł���u�ۈ牀���l����e�̉�v�̕����@���I��\�́u�M�̐������������Ǝv���������g�傪�������A�����Ȏq�ǂ���ۈ珊�ɗa���邱�Ƃɕs���������Ĉ玙�x�Ƃ�����������d������߂��肵���l�����Ȃ��Ȃ��Ǝv���B�����������ʁA�ҋ@�����̑啝�Ȍ����ƂȂ����̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂��B���̂����Łu�V�^�R���i�E�C���X�̉e���Ŏq�ǂ��̖ʓ|���݂邽�߂Ɏd�������߂��l�͓������Ƃ��ł���ɂȂ�����ɂł����������Ƃ����l�������B���̃j�[�Y�ɂ����ɑΉ��ł���悤�ɂ��Ă������Ƃ��K�v���B�ی�҂͈��S���Ďq�ǂ���a������{�݂𗘗p�������ƍl���Ă���̂ŁA�����Ǝ��ɒ��ڂ��Ē��J�Ȑ��������Ă��炢�����v�Ƙb���Ă��܂����B�܂������J���Ȃ́A����܂Ō��\���s���Ă���10�����_�̑ҋ@�����̐��ɂ��č��N������\���Ȃ����j�𖾂炩�ɂ��܂����B����ɂ��Ắu�ƒ��e�̏ŔN�x�̓r���ł����Ă��ۈ炪�K�v�ȏ͏o�Ă���B���ł����S���ĕۈ珊�𗘗p�ł���Ƃ������Ƃ��q��ĂɂƂ��Ă͂�����厖�Ȃ��ƂȂ̂ŁA10�����_�̑ҋ@�����������Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ͖{���ɍ����Ă���l�̑��݂������ɂ����Ȃ��Ă��܂��v�ƌ��O�������܂����B
�ҋ@�����̐����啝�Ɍ����������R�ɂ��āA�����J���Ȃ͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�e�����Ă���Ƃ݂Ă��܂��B�����J���Ȃ͑ҋ@�����̐������N4���Ɣ�ׂ�10�l�ȏ㌸�����S��180�̎����̂ɁA�ҋ@�����������������R�ɂ��ăA���P�[�g�������s���܂����B����ɂ��܂��ƁA�ҋ@�����������������R���ŕ������Ƃ���u�ۈ珊�̐V�݂◘�p����̊g��v��87.6�p�[�Z���g�ƍł������A�����Łu�\���Ґ����z��قǑ����Ȃ�������A�z��ȏ�Ɍ��������v��43.3���ƂȂ��Ă��܂��B�ۈ珊�̗��p�̐\�����݂��z�����������Ɖ��������̂ɂ��̗��R�����Ƃ���A�u�ۈ珊�ł̊��������O���ė��p���T����ی�҂̑����v��74���A�u�玙�x�Ƃ�\���蒷���擾����ی�҂̑����v��57.1���ȂǂƂȂ�܂����B�����J���Ȃɂ��܂��ƁA���Ƃ�4���̎��_�ŕۈ珊�̗��p��\�����l�͑S����282��8166�l�ƁA���N4�����1��4042�l�����āA�W�v���n�߂�2009�N�ȍ~���߂Č������܂����B0�Ύ�����2�Ύ��܂ł̐\�����݂������Ă��āA�Ƃ���0�Ύ���159��384�l�ƁA7346�l���Ȃ��Ȃ�啝�Ɍ������Ă��܂��B�����J���Ȃ́A�V�^�R���i�E�C���X�̊����ւ̕s������ۈ珊�̗��p���T�����ی�҂����������Ƃ��Ă��܂��B�����ĕۈ珊�𗘗p�ł���悤�ɋ��������Ⴂ��N��̂����ɗ��p�̐\�����݂�����ی�҂�����܂ł͑����������A�ҋ@�����̌����X���������Ă��������\�����݂������Ă������Ƃ��w�i�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ݂Ă��܂��B
��4��ڂً̋}���Ԑ錾�ŐV�^�R���i�Ɋւ���Љ�I����ɕω��́@8/27
�V�^�R���i�̖������~�܂�܂���B���N�`�����~����ɂȂ邩�Ǝv������A���S���͌����������̂̊����Ґ��͂��܂��s�[�N�A�E�g�����Ƃ͌�������Ȃ��̂悤�ł��B�f���^����A�l�X�̖��f�A�R���i���ȂǗl�X�ȉe���������Ă��܂��B�����ŁA�\�[�V�����Z���T�̍l����p���āA�c�C�b�^�[��ł̐l�X�̊���ǂ̂悤�ɕω����Ă���̂����͂��Ă݂܂����B
���c�C�[�g���Ɗ����Ґ�
�܂��A�R���i�����Ґ��ƃc�C�[�g���̊W�ɂ��Ă݂Ă݂܂��傤�B������A��͂芴���Ґ��̑����ɔ����Ċ֘A�c�C�[�g���������Ă��邱�Ƃ�������܂��B�c�C�b�^�[��ł̃R���i�Ɋւ��铊�e�͂���Ȃ�ɎЉ�I��\���Ă���Ƃ�����ł��傤�B
������̗ގ����̕ω�
�ł́A���ɁA�l�X���ǂ̂悤�Ȋ���������Ă����̂��c�C�b�^�[���琄�肵�Ă݂܂��傤�B�����ł́A�c�C�[�g�Ɋ܂܂�Ă��銴��𒊏o���A���̕ω������Ă݂܂����B��T�Ԃ��Ƃ̃c�C�[�g���g���āA�e�c�C�[�g�Ɋ܂܂�銴����ML-Ask��p���Ē��o���Ă��܂��B�Ȃ��A�l�X�̊���͂���ۂɁA���c�C�[�g��j���[�X�L���Ȃ�URL���܂c�C�[�g�̓m�C�Y�ƂȂ��Ă��܂����߁A�I���W�i���c�C�[�g����URL���܂܂Ȃ��c�C�[�g�݂̂�ΏۂƂ��ĕ��͂����Ă݂܂��B�����œ���ꂽ����ߋ��̂ǂ̎��_�Ɨގ����Ă��邩�ɂ���āA�ǂ�Ȋ�������̂������Ă݂܂��傤�B�܂��A���߂ōł������҂����Ȃ�����2�����O��6��24���̊���������Ĕ�r���Ă݂܂��B
�܂��A2021�N8��24�����݂̊�����Ɨގ����Ă��邩������ŕ\���Ă��܂��B1�ɋ߂��قǂ��̓���8��24�����ގ����Ă��邱�Ƃ������܂��B���������Ă����ƁA��r�I���Ă���̂͂�����������Ґ��������X������s�[�N�ɒB���邠����ł��邱�Ƃ�������܂��B���̈Ӗ��ł́A���̏��ߋ��Ɣ�r���đ傫�����f���Ă���ł���Ƃ͌����Ȃ����ł��B���ɗގ����Ă���̂���1�g�Ƒ�3�g�̃s�[�N�t�߂ł��̂ŁA��r�I�ْ������傫���o�Ă���Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ɁA7��8���Ɉ�C�Ɋ���ω����Ă��܂����A���̓��͂܂��ɋً}���Ԑ錾���o���ꂽ���ł��B�u�ً}���Ԑ錾�Ɋ���Ă��܂��Č��ʂ������Ȃ��Ă���v�ƌ����Ă��܂����A����ʂ��猩�����ً}���Ԑ錾�ɂ����̌��ʂ͂������Ƃ��������ł��B����A�����Ґ��������}����ꂽ6��24���Ƃ̗ގ��������Ă݂܂��傤�B����͗̃��C���Ŏ����ꂽ���̂ŁA1�ɋ߂��قǗގ����Ă��邱�Ƃ������܂��B������A��4�g�̏I��肩������ގ���������ƂȂ��Ă��܂����A�����ƍł��ގ���������o�Ă���̂͂Ȃ��2021�N�̌��U�ł��B��A���`���U�͂��Ȃ����Ȋ���\�o����u�����ꂽ�v�����Ȃ̂ł����A����Ɨގ�������������Ƃ������Ƃ́A���N�`���ڎ킪�i���Ƃ⊴���҂������X���ɂ��������ƁA�I�����s�b�N�Ȃǂ��e�����Ă����̂�������܂���B��̓I�Ȉ��ʊW�͕�����܂��B
������p�^�[���̃N���X�^�����O
�Ō�ɁA�ގ���������o�����ނ��āA�ǂ̂悤�Ȋ���p�^�[�����������̂������Ă܂��傤�B������Ƃɕ\�o��������̊����Ɋ�Â���X-Means�Ƃ�����@���g���ăN���X�^�����O���s���܂����B���̌��ʁA9�̃p�^�[���������܂����B���ꂼ��̊���p�^�[�������o���̂����������̂����̃O���t�ł��B
������Ƃ�9��ނ̊���p�^�[���̂��������o�Ă���̂��������Ă܂��B���������ƁA��5�g���n�܂������납��̃p�^�[��5���������Ă��邱�Ƃ�������܂��B�܂��A���������F�̃p�^�[��7�������܂��B�����̃p�^�[���ɂ͂ǂ�Ȋ���܂܂�Ă���̂��������̂�������B
���������ƁA�p�^�[��5�Ɋ܂܂�銴��͕|�������\�o���Ă���A�p�^�[��7�ł͍V�������\�o���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�p�^�[��7�ɂȂ��Ă�����́A7��23�`25���A8��8�`9���ł��̂ł���͖��炩�ɃI�����s�b�N�̊J���̉e���ł��傤�B����ł���ȊO�̓��͂����܂Łu�V�v�̊���傫���킯�ł��Ȃ����Ƃ���A�I�����s�b�N�̍ŏ��ƍŌ�͂��Ă����A���Ԓ������ƕ�����Ă����킯�ł͂Ȃ������Ȃ��Ƃ�������܂��B����ɁA�I�����s�b�N���I����Ċ����g�傪�~�܂�Ȃ�8��19�`22��������ł͑�3�g�A��4�g�������X���ɂ���Ƃ��ɏo�Ă����p�^�[��2�������݂��A��@�����㏸���Ă���\������������܂��B���Ƀp�^�[��2�͑S�̓I�ɑ����̊���܂܂�Ă��邱�Ƃ���A8���O���Ɣ�r���Ċ���I���e���܂ރc�C�[�g�̊������������Ă���Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��������
���߂̃c�C�[�g�f�[�^��p���āA�V�^�R���i�Ɋւ���Љ�I����ǂ̂悤�ɕω����Ă���̂��͂��Ă݂܂����B�������A�l�b�g��ɕ\�o���銴��͎Љ�S�̂̈ꕔ�ł����A���ꎩ�̂��Љ�̂��ׂĂ�\���Ă���킯�ł͂���܂��A���̈ꕔ����������L���Ȏ�i�̈�Ƃ͌����邩�Ǝv���܂��B���ʂƂ��ẮA����͂̌��ʂ���͉ߋ�4��̃s�[�N���Ɨގ���������\�o���Ă��邱�Ƃ�������܂��B�܂��A�I�����s�b�N�̉e�����傫���o���̂͊J�����A����キ�炢�̂悤�ł��B����A���ʂ��Ȃ��ƌ����Ă����ً}���Ԑ錾�ł����A�\�[�V�����Z���T�Ō�����芴��ʂɂ͈��̌��ʂ������炵���Ƃ͌��������ł��B�����A���ꂪ�����h�~�ɒ��ڌ��т��Ă���̂��ƌ�����Ɠ���Ƃ���ł����E�E�E
�f���^���̖���������A�܂��܂��V�^�R���i�����ւ̓��̂�͌��������ł����A�ߓx�̖��f������Ȃ��牽�炩�̌`�Ŏ�������悤�ɂ��������̂ł��B
���x�Z���f�̃K�C�h���C�� ����ψ���Ȃǂɒʒm�� �@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����̋}�g��Ŏq�ǂ��̊����������钆�A�����c�����Ȋw��b�́A�ċx�ݖ����̊w�Z����Ŋ����҂��o���ꍇ�ɔ����A�x�Z�Ȃǂf���邽�߂̃K�C�h���C�����A27�����ɁA����ψ���Ȃǂɒʒm����l���������܂����B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����ɂ��x�Z��w�����̔��f�́A����ψ���Ȃǂ��ی����̒����Ȃǂ����Ƃɍs���Ă��܂����A�������}�g�債�Ă���n��ł́A�ی����̋Ɩ����Ђ������A���������������\���ɍs���Ȃ����߁A����ψ���Ȃǂ��Ǝ��ɑΉ�����K�v�������܂��Ă��܂��B
�����������A�����c�����Ȋw��b�͊t�c�̂��Ƃ̋L�҉�Łu�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��Ȃǂł͕ی����̋Ɩ��̂Ђ����ɂ�蒲�����x��邨���ꂪ����A�������g�債�Ă���\���������ꍇ�̗Վ��x�Z�̍l�������������Ƃɂ����v�Əq�ׁA�x�Z��w�����f���邽�߂̃K�C�h���C�����A27�����ɁA����ψ���Ȃǂɒʒm����l���������܂����B
�����āA�����c��b�́u�K�C�h���C�����Q�Ƃ��A��펞�ł�������k�̊w�т��Ƃ߂Ȃ��悤�m���Ɏ��g��łق����v�Əq�ׂ܂����B�@
�������g��Ŗ{�i�����鏬�w�Z�̃I�����C�����Ɓ@ICT����@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�~�܂�Ȃ����Ƃ��A�w�Z�̉ċx�݉������c�_����A�ċx�ݖ����̎��Ƃ��I�����C���Ŏ��{���邱�Ƃ����߂������̂�����܂��B�p�\�R����C���^�[�l�b�g�ȂǁAICT(���ʐM�Z�p)���w�Z����Ɋ��p����Ӌ`�◘�_�A�����Đe���m���Ă����ׂ��S�\���Ƃ́\�\�B�wAERA English���ʍ��u�p��ɋ����Ȃ鏬�w�Z�I��2022�v�x�ł́A���猻��̑����Ńf�W�^������̊w�т�i�߂��l�̋��t�ɘb���܂����B�w�Z�����ICT���ō������w�̏[���x���ւ���w�����w�Z�̕S��������ƁA�����Z�Ȃ���ICT����̍Ő�[�����������s������s���O�����w�Z��ICT��C�߂�����͌Ⴓ���܂��B
��
�S���@�����߂���w�����w�Z�ł́A6�N�قǑO����ICT�����s�I�ɓ������܂����B�d�q������X�^�[�g���A�����͋���̈�Ƃ��ă^�u���b�g�������A�d�q���ƃ����N�����Ȃ��犈�p���n�߂܂����B���������Ɏg�킹���͎̂��̃X�e�b�v�ł����ˁB���肳��́A���w�Z�ɂ�����ICT���̗�����ǂ̂悤�Ɍ����Ă��܂������H
����@����4�N�O��ICT��i�Z�ł���O�����w�Z�ֈٓ������̂ł����A�����͐��ԓI�ɂ��AICT�ւ̗����͂܂��܂��ł����B����2�A3�N�ň�C�ɗ��ꂪ�ς��A������1�l1��̒[�������w�Z�������܂�����ˁB
�S���@��X�������݂͑��o���@�ł������A2020�N����1�l1��ƂȂ�܂����B
����@�����ɂ������āA����͂���܂���ł������H
�S���@�ȑO����ی�҂�ΏۂƂ���ICT������⌤�C������{���Ă�����ł��B�����Łu�����̋��ނƂ��ĕK�{�ɂȂ�v�Ɠ`���Ă��܂������A�R���i�ЂƂ���������A�}�s�b�`���A�X���[�Y�ɐi�߂邱�Ƃ��ł��܂����ˁB���̌��ʁA��N��4���̎n�Ǝ��ȍ~�A�S�w�N��Zoom��ʂ��Ď��Ƃ����{�ł��܂����B
����@���̏����Ǝ��s�͂͂������ł��ˁB�܂��ɂ��̂���A�����Z�ł́u�I�����C�����Ƃ���肽���Ă��ł��Ȃ��v�Ƃ��������̐����S������オ���Ă��܂����B
�S���@���w�����w�Z�̋����ɂ��A�I�����C���Ŏ��Ƃ�z�M�������Ƃ����傫�ȃp���[������܂����ˁB���̂Ȃ��œ��ɍl��������ꂽ�̂́A�u���̂��߂Ɋw�Z�͂���̂��H�v�Ƃ������Ƃł����B���Ƃ��s�����Ƃ��d�v�ł����A�����ɋ����Ǝ����A�����Ď������m�̂Ȃ�����A�����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂��Ƃ��炽�߂ċC�Â�����܂����B�ł�����A���ƈȊO�ɂ������x�ݎ��ԂȂǂ�݂��A���ԑтɂ���Ă̓I�����C����ʂ��Ď��K�����ݒu���܂����BICT�ƃR���i�Ђ�ʂ��āA�w�Z�̑��݈Ӌ`�����������Ƃ��ł����悤�ȋC�����܂��B
����@���͎��Ƃ�i�߂�Ȃ��ŁAICT�̊��p�ɂ�肷�ׂĂ̎����̐����z���グ����悤�ɂȂ����͔̂��ɑ傫�Ȃ��Ƃ��Ɗ����܂����B�]���̋��猻��ł́A���t�ł̂���肪�����A���̑傫�Ȏq�A������ׂ�Ȏq���ڗ����܂����B���\���Ȃ���Έӌ����Ȃ��̂Ɠ����悤�Ɍ����A���ɏ���g��(�������)�ǂƂ�������̏ł͘b���ł��Ȃ������ɂƂ��Ă͓�����ł����B���ꂪ���ł́A�A�v����ɏ������Ƃł��̎����̈ӌ����E���グ���A�����ɃN���X�S�����������Ԃɂ���B���ɏo���Ȃ��Ă��`���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�����ł��B
�S���@ICT��ʂ��āA��l�ЂƂ肪���M����@��A�Ǝ��̔��M�̎d�������܂�܂���ˁB��X���������Ă��郍�C���m�[�g�E�X�N�[���̂悤�ȃA�v�������p���邱�ƂŁA������Ƃ����Ȃ���e�����R�����g���邱�Ƃ��ł��܂��B���\�̎d�����A�g�[�N�����ӂȎq������A�v���[���̂悤�Ȏ�@��A���ŋ��̂悤�ȃN���G�[�e�B�u�Ȍ`�œW�J����q�����܂��BICT�ɂ��A�e���̑n�������̐��A����L�����Ƃ��ł��Ă��܂��B
�S���@ICT���炪�L����Ȃ��A�ی�҂̗����⋦�͕͂s���ł��B�����̎g�p�Ɋւ��ẮA�[���̕s�K�Ȏg�p�A�L�Q�T�C�g�ւ̃A�N�Z�X�����O����܂��B�ی�҂���e���V�[�����߁A�g������g�p���ԂȂǂ��q�ǂ��ƈꏏ�ɍl���Ă����K�v������܂��B
����@�ꏏ�ɁA�Ƃ����������|�C���g�ł���ˁB�q�ǂ��Ɠ����y�U�ɗ����A�Ƃ��ɂ͎���⑊�k�����邱�Ƃ��厖�B�ی�҂�ICT������ꏏ�ɑ̌����Ȃ���A�킪�q�ɕK�v�Ȃ��ƁA�����łȂ����Ƃ���̑I�����Ă����ׂ��ł��B
�S���@�قƂ�ǂ̕ی�҂�ICT��������Ɉ炿�܂����B�����̌o�������ŕ����𑨂���ƁA����̎q�ǂ��Ƃ͑傫�Ȃ���Ⴂ�������܂��B�q�ǂ������̌��݂Ə��������߂邽�߂ɂ��A�ی�҂͏�Ɏ��g���A�b�v�f�[�g����p������ł��ˁB
����@�����ł��B���̌o����A�킪�q���w��ł��邱�ƁA�V���Ɏ��g��ł��邱�Ƃɕی�҂��ϋɓI�ɊS����ƒ�ł́A�q�ǂ������̂т̂тƐ����𑗂��ۂ�����܂��B�ꏏ�ɍl���A�w�Ԉӎ����A�q�ǂ������ɂ����e����^���邱�ƂɂȂ���܂��B
�S���@�����Ȋw�Ȃ͊w�Z�����ʂ��āA�v�l�́A���f�́A�\���͂��琬���邱�Ƃ��������Ă��܂��B���肳��́AICT�͂����̈琬�ɂǂ��֗^�ł���Ɗ����Ă��܂����H
����@���̎O�͋�����Đg�ɂ���͂Ƃ��������A���Ƃ��u����l���Ă��̂���遨�搶��F�l����t�B�[�h�o�b�N���遨��������ƂɎ��͉�����낤���ƍl����v�Ƃ����T�C�N����1�������Ƃ��ɏ��߂Ĉ�܂����̂��ƍl���Ă��܂��BICT�����p���邱�ƂŁA����܂ł������̃T�C�N�����i�i�ɑ������Ƃ��\�ɂȂ�܂����B
�S���@���̃T�C�N���̑f������]�́A�q�ǂ������̂��C�ɂ����������ł���ˁB
����@���������Ƃ���ł��B�����Ƀt�B�[�h�o�b�N�����邱�ƂŁA��������������̂�l�������̂����悭���悤�A�C�����悤�Ƃ����ӗ~�����߂܂��B�����ɁA���̏u�Ԃɂ����v�l�́A���f�́A�\���͂͐L�т�̂��Ǝv���܂��B
�S���@ICT����̐Z���ɂ���āA���w�Z�ł̊w�т͍�����ω����Ă��������ł��ˁB
����@�]���̃A�i���O����̂܂܂ł́A�q�ǂ������͑�l���m���Ă��邱�Ƃ������Ƃ����g�̊w�K�������܂��B�f�W�^��������Ă����q�ǂ������ɑ��A�w�Z���������w�ё����A�Ő�[�̊�����Ȃ���Ȃ�܂���BICT��ʂ��A���l�Ȍo����\���ɐG�ꂳ���邱�Ƃ�����Ǝv���Ă��܂��B
�S���@���肳�����Ƃ���AICT�̊��p�ɂ���āu������v�����łȂ��A�u�w�ԁv�@����n�o�����ł��傤�B���������璲�ׁA���\���A�𗬂������@������Ă����͂��ł��B�����ł͋��ȉ��f�^�ƂƂ��ɁA�q�ǂ������́u�₢�v����n�܂�A�g�������w�сh�� �g�����I�Ȋw�сh����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���V�^�R���i��Õ���̌����͊J�ƈ�̕s��ׂ��@ 8/27
�V�^�R���i�E�C���X�E�f���^���̗��s�ŘA���̂悤�Ɉ�Ì���̋��`�����Ă���B��Ò̐��̖�肪�w�E����Ȃ���g�傪�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ��B �����s�͉��������ǖ@16����2�Ɋ�Â����ԕa�@�ւ̋��͂�v�����������ʂ͂���̂��낤���B������A�s��̑����̐f�Ï���N���j�b�N��1�N���ȏ���u�M�̂�����͕ی����֘A�����v�ƒ��莆�����܂܁A�j���ނ肵�ĐV�^�R���i�̐f�Âɋ��͂��Ă��Ȃ��B�����▼�O�̌��\���炢�ł͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�܂��A��K�͕a�@��×{�{�݂ւ̉����A�ݑ�×{�҂ւ̃I�����C���ɂ��f�Îx���Ƃ��������x�ł͕s�\�����B��ʂ̐f�Ï��̊J�ƈオ�C���t���G���U�̏ꍇ�Ɠ��l�ɊO���f�Â≝�f�ɉ�����̐������K�v������B����ŁA���ȉ�̈�t�̈ꕔ��m���Ȃǂ��咣���鍑���ւ̂�苭�͂Ȋ��������A���b�N�_�E���Ȃǂ͂��ׂ��łȂ��B�ȉ��A�����������B
�������͂������Ȃ����A�v�����͒ቺ
�܂��A�V�^�R���i�̔�Q�͑�4�g�܂łƌ���̑�5�g�Ƃł͑傫���قȂ�B�Ȍ��Ɍ����A�V�^�R���i�͂��L�܂�₷����莀�ɂɂ����a�C�ɂȂ����B�e���r��V���̑������V�^�R���i�̃f���^���ɂ��ăl�K�e�B�u�ȍޗ�������������ĕ��Ă��邪�A�f�[�^����͈قȂ�p�������Ă���B
5�����{���s�[�N�Ƃ����4�g�ɂ��ăf�[�^��7���ړ����ςŌ���ƃs�[�N���ɂ͊����Ґ�(�����z���Ґ�)��6400�l�A���Ґ��̃s�[�N��100�l�O��Ő��ڂ����B����ɑ��A8��20���͊����Ґ���4�{��2.5���l�ɒB���A���̌��2.2�`2.3���l�Ő��ڂ��Ă��邪�A���Ґ���30�`35�l�Ő��ڂ��A�z���Ґ��ɑ��鎀�Ґ��̔䗦�͈��|�I�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă���B���̃O���t�̎R�̑傫��������Ƃ킩��₷���B���������ďd�ǎ҂̐��͑������Ă��邪�䗦�ł݂�Ə������Ȃ��Ă���̂��B
�G�ߐ��C���t���G���U�����s����ƍ�����1�N�Ԃ�1000���`1500���l���늳���A��1���l���S���Ȃ�(��)�B���N�`���⎡�Ö�ɂ����E�����邩�炾���A�ق��̕a�C�Ɠ��l�ɊO���f�Â��s���Ă���B�V�^�R���i�����N�`����d�lj���h������������邵�A��Ì���ɂ͊��C��h�앞�ȂNJ�����������Ȃ��玡�Âɂ������ĉ𑣂��m�E�n�E���A�ςݏオ���Ă��Ă���B�܂�A�C���t���G���U���݂ɐf�Âł����������������B
(��)�C���t���G���U�̎��҂�2018��3325�l�A2019�N��3575�l�Ȃ̂ŐV�^�R���i�����啝�ɏ��Ȃ��Ƃ����R�����g���܂܌����邪����̓f�[�^�̔w�i��������肾�B�V�^�R���i�͗z���҂̑S�����`���Â����A2020�N6��18���ȍ~�͌��J�Ȃ̎����A���Ō����z���҂̎��͂��ׂĐV�^�R���i�ɂ�鎀�ƕ��Ă悢���ƂɂȂ�A�ߏ�v��ƂȂ��Ă���B�����A�C���t���G���U�̏ꍇ�͊��҂��i��Őf�Â��A���A�ق��̎���������Ă����ꍇ�ɂ͈�t�ɂ�錟���Ŋm�肳�ꂽ���̂Ɍ�����B���������nj������ł͒��ߎ��S�T�O�ŃC���t���G���U�̎��ҔN�Ԗ�1���l�Ɛ��v���Ă���B
���ړ������ł������}�~�͂ł����A�o�ς�ׂ�
�����A���������L�܂�₷���E�C���X��l�̈ړ������ŗ}�����ނ͍̂���B�l�̈ړ��Ɗ����g��Ƃ̘A�����������Ă��邱�Ƃ��f�[�^�Ŋm�F�ł���B
�l�̈ړ������͌��ʂ������̂ɑ��Čo�ςɋy�ڂ��Ō����傫���A�ɂ߂Ĕ�����Ȃ̂��B���O���̃��b�N�_�E�����ψي����͂�邽�тɌJ��Ԃ��H�ڂɊׂ��Ă���B�B
�����Ǒ�Ɍg����t�́A�u�X�l�����a2���[�g���ȓ��̊�����A���Ȃ킿�}�X�N���p�ɂ���Ĕ𗁂тȂ��A���܂߂Ȏ�A���C����������s�����Ƃ̌��ʂ͂ƂĂ������B�{���͂��ꂳ���ł���A�l�̈ړ��𐧌����邱�Ƃ͕K�v�Ȃ��v�Ƙb���B
����ɁA�u�q�ǂ��̊��������ɂȂ��Ă��邪�A10��ȉ��̎q�ǂ��͐V�^�R���i��1�l������ł��Ȃ��B�������A�G�ߐ��̃C���t���G���U�ł͓��c����10��ȉ��̎q�ǂ����������ʁB2019�N�ɂ�65�l���S���Ȃ��Ă���B�q�ǂ��ɂƂ��Ă͖��炩�ɋG�ߐ��C���t���G���U�̂ق����|���v�Ƃ����B
�V�^�R���i�̔�Q�A�l����Ō��������Ґ��A�d�ǎҐ��A���Ґ������˂ĉ��Ă����啝�ɏ��Ȃ��͎̂��m�̂Ƃ��肾�B����͍����ς��Ȃ��B����A���{�̐l��������a������OECD(�o�ϋ��͊J���@�\)�������ōő��A��t���͂�⏭�Ȃ����A�����J�Ƃقړ����x���B�a���̑�����130�����A��t����32���l�ł���B
�Ƃ��낪�A�����œ��@���Â�v���銳�҂�21���l�A�d�ǎ҂�2000�l�ɂ������Ȃ��ŁA��Õ��N����̂́A�V�^�R���i�ɑΉ��ł���a���������Ȃ��A�f�ÂɌg����t���ɒ[�ɏ��Ȃ����炾�B8��18�����_�̕ŁA�V�^�R���i�����ɂ����ɑΉ��ł���a�����Ƃ��Ċm�ۂ���Ă���̂�3��6314���A�d�ǎҗp�ł�5176���ɂ������A�h���×{�{�݂�3��8577�����B���{�̓����͕a�@��81�������Ԃł���A�܂��a���������Ȃ��f�Ï����V�^�R���i�f�ÂɌg����Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����B
����EU(���B�A��)�����ł͌��I�a�@��66���ł���B���̂����ŁA���łɍ�N���牢�Đ�i���ł͐V�^�R���i���҂̑����͎���ŗ×{���A�O���f�ÁE���f�Ŏ��Â��A�����E�d�lj��̒������o������@����`���B���{�Ŏ���×{�����Ȃ̂́A��t���f�Â����s���Ȃ܂ܕ��u����A���������Ƃ��ɂ͎�x��Ƃ�����ԂɂȂ邩�炾�B�������y�ǂŎ���̂�����O���f�Â≝�f���ł���A��Ԃɉ����ē��@��ICU�ł̑[�u�����߂���̂őΉ����X���[�Y�ɂȂ�B
���J�ƈ�ƋΖ���̊i���A�c�����z��
���{�̈�Ò̐������قȂ̂ɂ͗��R������B���A�n���Â��Č����邽�߁A�J�ƈ�͗D���Ő��A�f�Õ�V���x�ŕی삳�ꂽ�B�����������ŁA���{��t��͎����͂����A���̐��������₪�c���ɂȂ�Ƃ������`�ŁA��������s�����Ɏ���܂ł̑傫�Ȑ����I�e���͂����Ɏ������B
�����A�������~�}��Â�S�����{�̌����a�@�̋Ζ��̌n�͉ߍ��ŁA����͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B�V�^�R���i�̗��s�ȑO�����莋����Ă����B���������v�ň�ʘJ���҂̎��ԊO�J���͔N��360���Ԃ܂ŁA��O�I�ȏꍇ�̏����720���ԂƂȂ������A��a�@�̋~�}�~����⌤�C��Ȃǂ͎��ԊO�J���̏�����N��1860���ԂŁA���ꎩ�̂��ߘJ�����x�����B���ۂɂ͂�����ē����A�ߘJ����ߘJ���E�Ɏ���P�[�X������B
���̂悤�ȏȂ̂ŁA�����̂���l�͎����̋Ζ������R�ɊǗ��ł���J�ƈ��I�сA���̌��ʁA�J�ƈ�̐��͗]��ɂȂ�A���_�Ȍ����A���_�ȓ���Ŏ��v���m�ۂ��A�o�c�𐬂藧�����悤�Ƃ���B���{�̎Љ�ۏ��̖c���̑傫�ȗv����1�Ƃ��Ȃ�A���z�������Ă���B
��Ís������ɂ��ڂ����s�N�e���M�����ږ�̃G�R�m�~�X�g�A�s������V�j�A�E�t�F���[�́u���i�̌n���Ԉ���Ă���̂Ŏ����z�����䂪��ł���B�n��̊J�ƈオ�����悤�Ɍ��艿�i��t���Ă��܂��Ă��邪�䂦�ɁA��a�@�̐�������Ȃ��Ȃ�A�V�^�R���i�̈�ÕN���E����Ƃ������Ԃɂ��Ȃ����Ă���B�ߍ��ȋΖ������Ă����t�̒������オ��Ȃ��̂ɁA��Ô�̃��_�����͑����Ă���v�Ǝw�E����B
���łɌ����A�f�Õ�V���x�̈��������ɂ͓��{��t���R���邽�߁A���������Œ��K�����킹�邱�Ƃ������B�����Ђ��V����J�����Ă������ɂ��܂�ׂ���Ȃ��Ȃ邽�߁A���N�`����V����J������C���Z���e�B�u�������Ă��܂��Ă���Ƃ������Ԃ�����B
���{��t��͈�t�������\����ʒu�Â��Ƃ��āA���{�ɑΉ����Ă��邪�A���ۂɂ͔C�Ӓc�̂�32���l�̈�t�̂��������17���l���B�����J�ƈ�8��3000�l�A�c��͋Ζ���⌤�C�ゾ���A�Ζ���͈�t��ɓ����Ă��Ă��Z������t��̊����Ȃǂł��Ȃ��̂ŁA���������J�ƈ�̗����c�̂ɂȂ��Ă���B�܂�͐V�^�R���i�ɂ��Ă͉��̋�J�����Ă��Ȃ���t�������ق���g�D�ł���B
��������ɏڂ�����t�́u�����s��t��̔��莡�v��́w��t��͔C�Ӊ����c�̂��������ɋ����Ȃ�Ăł��Ȃ��B�F�̈ӌ���`���邾���̒c�̂��x�ƌ����Ă���B����Ȃ�A��t�̑�\�Ƃ��Đ��{�Ƃ̌��̑����ɂȂ��Ă���̂͂��������ł͂Ȃ����v�ƕ���B
������œ����Ȃ���t�����艿�i�Ŏ�葱����̂�
���f�B�A�̑����͐V�^�R���i�Ɠ��������a�@�̈�t�E�Ō�t�����̎p����ނ��āA����ƑΔ䂵�āu�����̊�@�ӎ����Ⴂ�v�Ƃ������p�����B���������Η��\�������o���Ă���̂��A�L�҂̎�ނɑ��u�����̋C�̊ɂ݁v�Ƃ������������J��Ԃ����{��t��̒���r�j����͂��߂Ƃ��銲����{�̑����ȉ�̈�t�����ł���_�ɂ͒��ӂ��K�v���B
���̈���ŁA��t��╪�ȉ�͂���1�N���A��Ñ̐��̊g�[�ɖ{�C�Ŏ��g�܂��A���{�⎩���̂́u���肢�v�ɑ��lj��蓖����v�����Ă����B���ԕa�@��J�ƈ�̐f�Âւ̎Q���͐S���邲���ꕔ�̈�t�ɂ�鎩��I�Ȃ��̂ɂƂǂ܂��Ă���B���Ԍo�c�Ƃ͂����Ă��A���I�C���t���Ƃ��Đf�Õ�V�Ŏ���Ă���̂�����A�p���f�~�b�N��@�Ƃ�������œ����Ȃ��̂Ȃ�A������������Đf�Õ�V���x�̔��{�I�Ȍ��������s���ׂ����B
��胁�f�B�A�͐��ƁA���ƂƎ����グ�邪�A�u���ԂŐf��͖̂����v�Ƃł��Ȃ����R�������炤�l�X���^�̃v���t�F�b�V���i���Ƃ�����̂��낤���B�܂��A���܂ł��̓�������𑱂�����肾�낤���B�ǂ�ȋƊE�ł��v���ł���ł���悤�ɂ��܂��܂ȘA�g�⋦�́A�H�v�����炵�ĉ����ɓw�͂�����̂��B���ۂɂ������Ă����t�����Ȃ������݂���B
���N2���ɐV�^�R���i�͖@�I�Ɂu�V�^�C���t���G���U�������ǁv�Ƃ��Ĉʒu�Â����A�����Ǒ�Ƃ��ẮA�����̎������ő���ɐ����ł���悤�ɂȂ����B�Ƃ��낪�A�V�^�R���i�����Ǒ����ȉ�̔��g�Ή��m�������͂����Ɛ����ł���悤�@��������Ƃ����B�S�̎�`���Ƃ�ڎw���Ƃ����̂��B
�w�Z�̊w�Z�̉ċx�݂���������Ƃ������g���̔��������ڂ���Ă��邪�A���т��т̑Ζʎ��Ƃ̍팸�́A������S���q�ǂ������̋���ɉЍ����c������B�V�^�R���i�̂܂h�~�̊ϓ_�����ł͌��߂��Ȃ����Ƃň�a��������B���̂悤�Ȏ��Ԃ������Ă���̂́A���{�����f�͂��������ɁA���ȉ�ɗ����Ă��邽�߂��B�u���{����Ăȉ�Ɏ���A�Ƃ�����Ԃ͊��S�ɖ������]�|���Ă���B��}������Ŕ��g����ɓ���������̂����������B���@���܂������@�\���Ȃ��Ȃ��Ă���v�ƃs�N�e�̎s�쎁�͎w�E����B
�{���A���ȉ�͂����܂ł������ǂ̐��ƂƂ��Đ��{�Ɉӌ�����\���闧�ꂾ�B�V�^�R���i�ɑ��Ăǂ������헪�����̂��ɂ��ẮA�����ǂ̐��Ƃ̈ӌ��̂ق��ɂ��Љ�I�A�o�ϓI�A�����I�Ȃ��܂��܂Ȋϓ_�̏��E�ӌ�����������I�ɍl���āA���{�A�܂�͐����ŏI�I�Ɍ��f���ׂ����̂��B
����Â̂��߂̍����ł͂Ȃ��A�����̂��߂̈�Â�
���{�͐V�^�R���i���瓦���Ă����Ï]���҂ɂ����Ƌ����������s�g����ׂ����B��ÊW�҂Ɉ�Â̒�v������@���̏Ƃ��ẮA���������ǖ@16����2�̑��ɁA�V�^�C���t���G���U�������ʑ[�u�@31��������B ���̖@���ł̓R���i�f�Â��A���ڂɖ@�I�S���͂������Ĉ�Î҂ɋ������邱�Ƃ��ł���B���̕s���]�ɂ͍s���������s���Ƃ����^�p�����肤��B���Ȃ݂ɁA���[�@�̉����ō��N2���ɂ͈��H�E�h���Ǝ҂Ȃǂ�O���Ɏ��Ǝ҂��]��Ȃ��ꍇ�̉ߗ����߂��B
��ʂ̎���Ă��Ȃ����Ǝ҂�ΏۂɁA�\���ȕ⏞�������ɑf�����ߗ��̋K������Ă����āA�Ȃ��A���I���x�Ŏ���Ă����t�ɋ����͂����悤�Ƃ��Ȃ��̂��B���[�@31�������̕ɂ��Ă������ɁA���̉^�p����������ׂ����B�u�������v��ł��j��v�ƏA�C���Ɍ�������̐����͂������B
���R���i �����≫��Ȃǂō��~�܂�� 39���{���Ŋ����g�呱�� 8/27
�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�����Ґ���1�T�ԕ��ςŔ�r����ƁA�����s�≫�ꌧ�Ȃǂłقډ�������킸���Ɍ������A�����Ґ���������Ԃō��~�܂�ƂȂ��Ă��܂��B����ŁA27������ً}���Ԑ錾�̑ΏۂƂȂ����n����܂߁A39���{���Ŋ����̊g�傪�����Ă��܂��B�e�n�̎����̂Ŕ��\���ꂽ�����Ґ������ɁA1�T�ԕ��ςł̐V�K�����Ґ��̌X���ɂ��đO�̏T�Ɣ�r���Ă܂Ƃ߂܂����B
���S�� �����̃y�[�X�͉������ 9�T�A���ő���
�S���ł�7��29���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T�Ɣ�ׂ�1.69�{�A8��5����1.83�{�A8��12����1.24�{�A8��19����1.38�{�A26���܂łł�1.13�{�ŁA�����̃y�[�X�͉������Ă��܂����A�ߋ��ő����X�V�������Ă���9�T�A���ő������Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻2��3035�l�ƂȂ��Ă��āA39�̓��{���Ŋ������g�債�Ă��܂��B
���ً}���Ԑ錾���o����Ă���n��
�ً}���Ԑ錾���o����Ă���n��ł́A�����s�Ɖ��ꌧ�A����ɍ�ʌ��łقډ�������킸���Ɍ������܂������A�ق��̂��ׂĂ̕{���Ŋg�債�Ă��܂��B
�����s�́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.09�{�A8��19����1.20�{��9�T�A���Ŋ����̊g�傪�����Ă��܂������A26���܂łł�0.91�{�ƁA�킸���Ɍ������܂����B1��������̐V�K�����Ґ��͂��悻4353�l�ƁA��T���420�l�]�茸�������̂́A�ˑR������Ԃō��~�܂�ƂȂ��Ă��āA����1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ���218.88�l�ƁA�����������ƂȂ��Ă��܂��B5��23������ً}���Ԑ錾�������Ă��鉫�ꌧ�́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.19�{�A8��19����1.26�{�ƁA6�T�A���Ŋ����̊g�傪�����Ă��܂������A26���܂łł�0.97�{�ƁA�قډ����ƂȂ��Ă��܂��B1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻647�l�ƁA������Ԃō��~�܂肵�Ă��āA����1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ���311.49�l�ƁA�S���ōł������A����܂ō����̂ǂ̒n��ł��o���������Ƃ̂Ȃ��K�͂̊����ƂȂ��Ă��܂��B
�_�ސ쌧�́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.22�{�A8��19����1.21�{�A26���܂łł�1.12�{�ƁA9�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻2510�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��ʌ��́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.30�{�A8��19����1.30�{�ƁA9�T�A���Ŋ������g�債�Ă��܂������A26���܂łł�0.96�{�ƁA�قډ����ƂȂ�A1��������̐V�K�����Ґ���1623�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��t���́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł͑O�̏T��1.22�{�A8��19����1.41�{�A26���܂łł�1.05�{�ƁA12�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻1467�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���{�́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.27�{��8��19����1.51�{�A26���܂łł�1.33�{�ƁA8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ���2418�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���s�{�́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.42�{�A8��19����1.42�{�A26���܂łł�1.33�{�ƁA9�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻533�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���Ɍ��́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.36�{�A8��19����1.61�{�A26���܂łł�1.27�{�ƁA9�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻954�l�ƂȂ��Ă��܂��B
��錧�́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.20�{�A8��19����1.18�{�A26���܂łł�1.04�{�ƁA7�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻304�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�Ȗ،��́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.06�{�A8��19����1.29�{�A26���܂łł�1.22�{�ƁA6�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻210�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�Q�n���́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.14�{�A8��19����1.72�{�A26���܂łł�1.18�{�ƁA8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻276�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�É����́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.65�{�A8��19����1.84�{�A26���܂łł�1.25�{�ƁA7�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻540�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�������́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.37�{�A8��19����1.23�{�A26���܂łł�1.15�{�ƁA8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ���1038�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���V���ɋً}���Ԑ錾���o���ꂽ�n��
27������V���ɋً}���Ԑ錾���o���ꂽ8�����ł́A���ׂĂ̒n��Ŋ������g�債�Ă��܂��B
�k�C���́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.25�{�A8��19����1.33�{�A26���܂łł�1.10�{�ƁA8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ���507�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�{�錧�́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.90�{�A8��19����1.57�{�A26���܂łł�1.22�{�ƁA4�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻229�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��2.10�{�A8��19����2.86�{�A26���܂łł�1.52�{�ƁA7�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻323�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���m���́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.56�{�A8��19����2.01�{�A26���܂łł�1.79�{�ƁA8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ���1518�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�O�d���́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.78�{�A8��19����2.19�{�A26���܂łł�2.09�{�ƁA5�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻400�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���ꌧ�́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.68�{�A8��19����1.51�{�A26���܂łł�1.21�{�ƁA8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻205�l�ƂȂ��Ă��܂��B
���R���́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.39�{�A8��19����1.72�{�A26���܂łł�1.15�{�ƁA8�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ��́A���悻229�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�L�����́A8��12���܂ł�1�T�Ԃł́A�O�̏T��1.49�{�A8��19����2.16�{�A26���܂łł�1.52�{�ƁA7�T�A���Ŋ������g�債�Ă��āA1��������̐V�K�����Ґ���340�l�ƂȂ��Ă��܂��B
�����M��w �ړc�ꔎ�����u�S���y�ςł��� ��@�I�v
�V�^�R���i�E�C���X��ɓ����鐭�{�̕��ȉ�̃����o�[�ŁA���M��w�̊ړc�ꔎ�����́A���݂̊����ɂ��āu��s����1�s3�������łȂ��A���m�𒆐S�Ƃ��钆���A���𒆐S�Ƃ�����A�����𒆐S�Ƃ����B�ł��A��s�s�������Ɋ������g�y���S���I�Ȋ����̍L���肪�����Ă���B�S���y�ςł����A�����̔����������Ă�����B�����ł͔����I�ȑ�������i���������A���ł�1��4000�l���銴���҂������Ă���A��Ì���̂Ђ����́A�܂��܂��傫���Ȃ��Ă���B�������Ă��銴���Ґ��͂��~�̍��Ɋ��������l�����ŁA�ꎞ�I�ɐl�������Ȃ��Ȃ����e���������ł̉����̏�ԂɂȂ����Ă��邩������Ȃ��B�l���߂��Ă��Ċw�Z���n�܂�ȂǁA�l�̓����������ɂȂ�ƍđ������݂��郊�X�N���l���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B���̂����ň�Â̏ɂ��āu���A�d�lj������P�[�X��3����2��50��ȉ��ŁA�Ⴂ�l�ł��d�lj����Ă��܂��B���ǂ��Ŏ������������邩�킩��Ȃ����A�������đ����ꂵ���Ȃ��Ď_�f���K�v�ł�����Ă����a�@���Ȃ��A����������Ԃ��N������B��Ë@�ւł͐V�^�R���i�Ɍ��炸�A��ʎ��̂�S�؍[�ǂȂǂ̊��҂�����邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă��āA�܂��Ɉ�Õ��߂Â��Ă���B��l��l����@�I�ȏɂ���Ƃ������Ƃ����L���āA��{�I�ȑ��O�ꂷ��悤���肢�������v�Ƙb���Ă��܂��B�܂��A�ړc�����́u���̑�Ō��ʂ������Ȃ���A�e�s���{���̒m�����n���Ǝ�����肵�ċx�Ɨv����������Ȃǂ̋�������s�����Ƃ��l���Ă����Ȃ�������Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B
���R���i�}�g��g�w�����͊��������m�F��5�`7�����x�h��� �@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�̋}�g��Ŏq�ǂ��̊����������Ă��钆�A�����Ȋw�Ȃ͊w�����Ȃǂf���邽�߂̊�����߂Ď����܂����B�w���Ŋ����҂������m�F���ꂽ�ꍇ�Ȃǂ�5������7�����x��ڈ��Ɏ��{����������Ƃ��Ă��܂��B
�������k�⋳�E���̊������m�F���ꂽ�ꍇ�̊w������x�Z���߂����ẮA����܂ł͋���ψ���Ȃǂ��A�ی����ɂ�钲����Z���ڐG�҂̓�����A�����������ŕK�v���f���Ă��܂����B
�������A�������}�g�債�Ă���ً}���Ԑ錾���o�Ă���n��ȂǂŁA�ی����̋Ɩ����Ђ������������x��邨���ꂪ����Ƃ��ĕ����Ȋw�Ȃ͌����J���ȂƋ��c�̂����A���߂ċ�̓I�Ȕ��f����쐬���܂����B
���̒��ł́A�Z���ڐG�҂⌟���Ώێ҂̌��̃��X�g���w�Z�Ȃǂ��쐬����ۂ̋�̗Ⴊ������A�����̌��҂̓��肪����ꍇ�͊����҂�1�l�ł��w���S���������̑ΏۂƂł���Ƃ��Ă��܂��B
���̂����Ŋw�����ɂ��Ă͓����w���̒��ŕ����̎�����k�̊��������������ꍇ��A�����҂�1�l�ł������������Ȃǂ̏Ǐ��i���Ă�����A�����̔Z���ڐG�҂������肷��ȂǁA�w�����Ŋ������L���邨���ꂪ�����ꍇ�Ɏ��{����������Ƃ��Ă��܂��B
���Ԃɂ��Ă�5������7�����x��ڈ��Ƃ��Ď����Ă��܂��B
�܂��w�N���́A�����̊w���������ȂNJw�N�Ŋ������L�����Ă���\���������ꍇ�Ɏ��{���A�w�Z�S�̂ł̗Վ��x�Z�́A�����̊w�N���Ȃǂ����������ꍇ�Ɏ��{����Ƃ��Ă��܂��B
�����Ȋw�Ȃ͂��̊��27���A�S���̋���ψ���Ȃǂɒʒm���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���͎q�ǂ��̊������������钆�A�ċx�ݖ����̐V�w���ɂ��킹�A9����{����c�t���⏬���w�Z�Ȃǂɂ��悻80���̍R�������L�b�g��z�z���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
����ɂ��ĕ����Ȋw�Ȃ́A�����̑Ώۂ͋��E������{�Ƃ���Ƃ��Ă��āA�������k�ɂ��Ă͑̒��������Ȃ����瑬�₩�ɋA��Ĉ�Ë@�ւ���f����悤�w�����邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă��܂��B
�����A�����Ō��̂��̎�ł��鏬�w4�N���ȏ�ł����ɋA��邱�Ƃ����������鎙�����k�ɂ��ẮA�����̑ΏۂƂ���Ƃ��Ă��܂��B
�����̎��{���@�ɂ��ẮA���E���͖{�l���A�������k�����E��������̂��Ɩ{�l�����̂��̎悷��Ƃ��Ă��āA���E�����������k�̌��̂��̎悷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
���̏�ŁA�R�������ŗz���ƂȂ����ꍇ�͑��₩�ɋA���Ë@�ւŊm��f�f���s���Ȃǂ̑Ή����Ƃ��ė~�����Ƃ��Ă��܂��B
���u�R���i�͋�C�������傽��o�H�v�@�����҂炪���@8/27
�V�^�R���i�E�C���X�̊�����ɂ��āA�����ǂ�Ȋw�Z�p�Љ�_�Ȃǂ̌����҂炪�A�u��C��������Ȋ����o�H�v�Ƃ����O��ł���Ȃ������߂鐺�����o�����B�u���܂��l�X�ȕ��@���c����Ă���A�����ɂ�銴���g��̑j�~�͉\�ł���v�Ƒi���Ă���B
�����́A���k��̖{���B�y�����ƍ��G�l���M�[�����팤���@�\�̕��c���i�����܂Ƃ߁A�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�̐����G��E�E�C���X�Z���^�[���犴���ǂ̐��Ƃ��t��32�l���^���҂Ƃ��Ė���A�˂��B27���ɃI�����C���ŋL�҉���J���A���������B
��C�����́A�E�C���X���܂ޔ��ׂȗ��q�u�G�A���]���v���z�����ނ��ƂŊ������邱�Ƃ��w���B�G�A���]���̑傫����5�}�C�N�����[�g��(0.005�~��)�ȉ��Ƃ���A�������ԁA��C���������悤�B
�����J���Ȃ̃E�F�u�T�C�g�ł́A�V�^�R���i�̊����o�H�Ƃ��āA������݂Ȃǂŏo��傫�Ȃ��Ԃ�������u��(�Ђ܂�)�����v��A�E�C���X�̕t�������ꏊ�ɐG�ꂽ��ŕ@�����G�邱�Ƃɂ��u�ڐG�����v����ʓI�Ɛ�������Ă���B
����A���E�ی��@��(WHO)��Ď��a��Z���^�[(CDC)�͂��ꂼ��A�E�C���X���܂G�A���]���̋z���ɂ��Ă��A�����o�H���Ɩ��L���Ă���B
�����́A��C�������V�^�R���i�́u�傽�銴���o�H�ƍl������悤�ɂȂ��Ă���v�Ǝw�E�B�l�����Ă���ȏ�ɋ���������Ă��Ă��������X�N�͂���A�t�ɋ�C���̃G�A���]���̗ʂ����炷�悤�ȑ�Ŋ����}�����ł���Ƃ����B
���̂����ŁA���⎩���̂ɑ��āA�E���^������z���̂��̂������Ԃ̂Ȃ��s�D�z�}�X�N�Ȃǂ̒��p�O��̎��m�����C���u���C����@�Ȃǂ𐳂������p���邽�߂̏��̎��m��������̌��ʂ𒆗��ȑg�D�ɂ���Č����邱�Ƃ����߂��B�����́A���t���[�A���J�Ȃ╶���Ȋw�Ȃɑ��t�����Ƃ����B
��t�Ŗ��@�E�㎖�@�����̕đ����l�E���勳�����^���҂̈�l�B�đ�����͐��{�̑�́u�}�N����̈�ł���ً}���Ԑ錾�ɑ啝�Ɉˑ����Ă���v�Ǝw�E�B�l�̊����ږh�����߂̑�̓O���A�O���̎���̌����Ȃǂ����߂���Əq�ׂ��B
�^���҂̐������́u�l����(�����g��Ƃ���)���ʂ̊Ԃɂ͂������̃v���Z�X������B���̈����Ԃ��Ă������Ƃ��ƂĂ��厖�B���̂��߂ɂ́A�w������x�̂Ƃ���̋�C�����ւ̑��������Ƃ��Ȃ�������Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������A�V�K�R���i����3581�l�@20��܂�19�l���S 8/28
�����s��28���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����3581�l���ꂽ�Ɣ��\�����B�O���Ɣ�ׁA���@���҂̂����d�ǎ҂�3�l����297�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����X�V�B20��̒j�����܂�19�l�̎��S���m�F���ꂽ�B
����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���4��l����������3971.3�l�Ɍ������A�O�T���84.2���B
�s���ً͋}���Ԑ錾�̔��߂���1�J���ȏオ�o�߁B�����͂������C���h�R���̃f���^�����}�g�債�A8�������Ŋ����Ґ���11���l���A��Ò̐��̌������������Ă���B
�������s���̔D�w�����ҁA7���͏��Ȃ��Ƃ�98�l�ʼnߋ��ő��@8/28
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŁA�����s����7���̔D�w�̊����Ґ������Ȃ��Ƃ�98�l�ƁA��N4���ȍ~�ő����������Ƃ��A�s���̕a�@���̒����ŕ��������B��t�����s�Ŋ��������D�w�̓��@�悪�����炸�A����ő��Y�����Ԃ�����S���������A���`�̎͊��������D�w�ɑ����Ñ̐�������i�߂���j��\�������B�����A�����̎��Ԃ͔c���ł��Ă��Ȃ��B�a�@���́u�n��̔D�w�̏����m�ɕ�����Ȃ���A�������̍�����Ñ̐��͂���Ȃ��v�ƁA���Ԕc���̕K�v����i����B
�����́A���{��ȑ命���i�R�a�@(�����s)�̒���͐l�@��(�Y�w�l��)���A�s�Ɍ����Ƃ̑���l������Ă܂Ƃ߂��B���Ԃ�ׂł���s����Ë@�ւ��ΏہB�W�v���n�߂���N4���ȍ~�Ŋ����҂͌v460�l�������B�u��5�g�v���n�܂����Ƃ݂���7����98�l�́A5����2�{�B�����Ώۂ͂����ꕔ�̈�Ë@�ւŁA���ۂ̊����҂͂���ɑ����\��������B
���������D�w�̂���438�l(95�D2��)�͓��@�A22�l(4�D8��)�͎q��ĂȂǂ̗��R�Ŏ���×{�������B�������ɏo�Y����77�l�̂���8�����鉤�؊J�����Ă������Ƃ����������B
�s�Ȃǂɂ��ƁA���������D�w�̔��������͂Ȃ����̂́A����@���́u8���ɓ���A��������̎Y�w�l�Ȉ㎩�炪���҂̓��@���T�����k���邱�Ƃ��������v�Ƙb���Ă���B
�D�w�̊����Ґ��͌����J���Ȃ⑽���̓s���{���Ō��\����Ă��Ȃ��B����@���́A�K�v�Ȉ�Ò̂��ߎ��Ԃ�c�����悤�Ɠs�ɕ�����蒲�����邪�A�f�[�^�W�v�͌����ƂŁA�v���ȑΉ��Ɍ��ѕt���ɂ����B�u�D�P�T����Ǐ�ɂ���đΉ��ł�����Y���̈�Ë@�ւ͌����A�����ǑΉ����\�ƂȂ�Ƃ���ɏ��Ȃ��B����s�͊����D�w���ׁA��Ë@�ւɐ��m�ȏ�������ׂ����v�Ƒi����B
���J�Ȃ́A���s�ł̎����A�m���Ȏ��Y����Ñ̐��̊m�ۂ̂ق��A�����҂̔����͂ŔD�P�̗L�����m���ɔc������悤�s���{���ɒʒm�����B�����ی����Ȃnj���̋Ɩ��������邱�Ƃ�u���ꂩ��オ��f�[�^�̐M�������s���v(�R���i�����i�{��)�Ƃ��A������D�w�̊������W�v�A���\����\��͂Ȃ��Ƃ����B
�s�����ی��ǂ����\�̗\��͂Ȃ��Ƃ��Ă���B����Ő_�ސ쌧��13���A���N4�����獡��10���܂ł̊ԁA���������҂̂����̔D�w�̐������\�B7����130�l�ŁA���Ԃ̍��v��289�l�������B
���u�V���ɍ��̗v�����c�v���g���@�����铌�a�@�A�R���i���a�@���Ł@8/28
�����s�ȂǂŐV�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊����g�傪�����Ȃ��A���{���ȉ��̔��g�Ύ����������߂�Ɨ��s���@�l�P���̓����s���̕a�@���A�R���i���a�@�ƂȂ邱�Ƃ����܂����B�����ł͂���܂ŁA�ꕔ�̓s���a�@�Ȃǂ������I�ȃR���i���a�@�Ƃ��ĉғ����Ă������A�����Ґ��̋}���ŕa���s�����[���ɂȂ��Ă���B���g���̓R�����g�\�B�u�V���ɍ��̗v�����A�����铌�a�@���p�a�@�ɂ��邱�Ƃɂ��܂����v�u�ő�50�����x�̕a�������\��ł��v�Ƃ��Ă���B
�����s�ɂ��ƁA8��27�����_�ł̓s���̓��@�Ґ���4226�l(�m�ەa����5967)�B2��5040�l������×{���A2006�l���z�e���Ȃǂŏh���×{�����Ă���B�����1��614�l���A���@��×{���ł����������ƂȂ��Ă���B
�s���L���a�@��A�����s�ی���Ì��Ђ��^�c����L���a�@�A�`���a�@�A���s���{���È�Z���^�[�A���C���w���t�������a�@���A�����I�ɃR���i���̕a�@�Ƃ��ĉ^�c����Ă��邪�A�a���s���͐[�����B
����Ȓ��A���{���ȉ��̔��g�Ύ����������߂�Ɨ��s���@�l�E�n���Ð��i�@�\(JCHO)�̓����铌�a�@(�����s�]����)���A�V���ɃR���i���a�@�Ƃ��Đ�������邱�ƂƂȂ����B�V�^�R���i�ȊO�̊��҂̓��@�E�f�Â����ׂċx�~��������Œ������i�߂��Ă���Ƃ����B
���g����28���A�uJCHO�ɂ�����V�^�R���i�E�C���X�����Ǖa���̊m�ۏɂ��āv�Ƒ肵�������\�����B
����܂ŁAJCHO�S57�a�@�Ōv870���A���������s���ł�5�a�@�Ōv187�����m�ۂ��Ă����Ƃ����������ŁA�u�X�ɁA���̓x�A�V���ɍ��̗v�����A�����铌�a�@���p�a�@�ɂ��邱�Ƃɂ��܂����v�Ƃ��Ă���B
�u9������ړr�ɁA�ő�50�����x�̕a�������\��ł��B����ɂ��A�S���ł�920�����x�A�����s���ɂ��Ă�240�����x�̕a�����m�ۂł���\��ł��v
�uJCHO�́A����܂ł��n��̃j�[�Y�ɉ����āA�~�}��Â�ݑ��ÂȂǁA���ꂼ��̕a�@���@�\���ʂ����Ă���A����Ƃ��V�^�R���i�E�C���X�����ǑΉ��ɂ��Ă��A�ϋɓI�ɖ������ʂ����Ă܂���܂��v
���g����8��19���ABuzzFeed News�̎�ނɎ��̂悤�Ɍ���Ă����B
�u�����g����}������Ò̐��́A����1�N����ł����Ԃ�����Ă��܂����B�����ɔ�ׂ��2�{�߂��܂ŕa���͑������B�������A�����g��̃X�s�[�h�����ɑ������߂ɁA�ǂ����Ă��܂���v
�u��������g���H���~�߂邽�߂̑�����������d�v�ł��B�����ɁA��Ò̐��̐����𑁋}�ɐi�߂Ă����K�v������܂��v
�ЊQ���x���̊����g�傪�������A���g���͂��łɗl�X�ȕ��S���������Ă����Ë@�ւɂ���Ȃ鋦�͂����߂邱�Ƃ��K�v�s���ł���Ƃ��Ă����B
���g���͎��g���g�b�v�߂�JCHO�P���̕a�@�ŐV�^�R���i���҂����ꑝ���͂��邱�ƂŁA�����������b�Z�[�W�̔��M�����߂����������B
�����铌�a�@�������ẮA�c�����v���J����8��27����BS-TBS�u��1930�v�ŁA�u������(�a����)�܂��܂�����Ȃ��v�Ƃ�����ŁA�u�Ȃ��Ȃ��a�@����R���i���Ƃ����͓̂�����A�����铌�a�@�Ƃ����a�@�A�R���i���Ŋ��҂�����Ă��������v�ƌ�����B
���u���ɗ��Ȃ��Łv�����g��̏��}�����ɒ���D�����@8/28
�V�^�R���i�̊������g�債�A�u���ɗ��Ȃ��łق����v�ƌĂъ|���铌���E���}�����ɒ���D���������܂����B
����D�͏T��2��̉^�q�ŁA27���ɓ����E�|�ł��o�q���A28���ߑO10���������ɏ��}�����ɓ������܂����B
���̊����҂͗v�ō���5�l����10�l�ւƋ}�����A���T����2�T�Ԃ͏Z�����܂߁A��ނȂ��ꍇ�������ē��ɗ��Ȃ��悤�Ăъ|���Ă��܂��B
���}�����ό�����E���эL������u���C�����H��(�ό������)�����ڂ̑O�̓��H�Ȃ�ł����ǂ��A���܂�l�������Ȃ��ł��ˁB�������ł�����܂��̂ŁA����������(������)�L���鎞�͈�u���Ă����̂����X�I�ɂ͊F��������Ă���Ǝv���܂��v
�y�ǎ҂͎���×{�ɂȂ�܂����A�Ǐ��������ꍇ�͎��q���̃w���R�v�^�[�Ȃǂ��g���A��10���Ԃ�����23����̕a�@�ɔ�������K�v������܂��B
�s�̒S���҂́A�u�����Ɏ��Ԃ͂����邪�A���̎���×{�҂ƈႤ���ʈ������ł��Ȃ��v�Ɠ����啔�̈�Ò̐��̓����b���Ă��܂����B�@
�����͌���192�l�����@��Q�Ҏx���{�݂̃N���X�^�[�g�� �@8/28
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�����A���͌��s��28���A10�Ζ����`80��̒j��192�l�̊������m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B������5�l�A�y��185�l�A���Ǐ�2�l�B�����o�H�s����124�l�B
�N���X�^�[(�����ҏW�c)���������Ă����̏�Q�Ҏx���{�݂ŐV���ɐE��1�l�̊������������A���{�݊֘A�ł̗z���҂͌v70�l�ɂȂ����B
�������ً}���Ԑ錾�̓��C3���ŃR���i�����g��@���m��2347�l�@8/28
���C3����27�����獑�ً̋}���Ԑ錾�̑Ώۂɒlj�����A���C3���ł͓����A�V����3000�l����V�^�R���i�E�C���X�̊����҂����\����܂����B
���m���ł́A�V���ɉߋ��ő��ƂȂ�2347�l�̊������m�F����A1�l�̎��S�����\����܂����B���É��s�ł͏��߂Ċ����҂�1000�l���A�����̎���×{�҂�1���Ŗ�1000�l������ȂǁA�����̋}�g�傪�����Ă��܂��B
���ł�4���A����300�l����308�l�A�O�d���ł�423�l�̊������m�F����Ă��܂��B
�����������Ǝ��ً̋}���Ԑ錾����2�T�ԁ@���c�m���u�����̒��������Ȃ��v�@8/28
�V�^�R���i�E�C���X�̔����I�g��ŁA�����������x������ō��ƂȂ�X�e�[�W4�Ɉ����グ�A�Ǝ��ً̋}���Ԑ錾�߂��Ă���27����2�T�ԁB�����Ҍ����Ɍ��������ɗv�����d�˂邪���ʂ͕\��Ă��Ȃ��B���̐V���ȑ�\���������̉�ʼn��c�N��m���́u�����̒����������Ă��Ȃ��B�����������Ԃ�������v�Ƃ̔F���������A�s������h���×{�{�݂̊m�ۂ�����ɐi�߂�l�����������B
�����x������X�e�[�W3�ȏ�Ɉ����グ�A���H�X�ւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�Ȃǂ̗v���������̂�1���A5���A8��6�A13���̌v4��B1�A5���̗v����͂����ɐV�K�����҂������X���ɓ]�����B
����8���͈قȂ�B�u3�v�Ɉ����グ�u�����I�����g��x��v�߂���6���ȍ~�������҂͉E���オ��B13���ɂ͌x������u4�v�ɏグ�A�Ǝ��ً̋}���Ԑ錾���o�����B���̌��140�`251�l�ƍ��~�܂肪�����B
���c�m���́u�Ⴂ���̊������L�����ăf���^���̉e�������Ȃ肠��B���܂łƈ���Ďs��������4�����炢����v�Ɛ����B1����250�l�̊����҂������ƁA�K�v�ȕa�����Əh���×{�{�݂�600����2400���ɂȂ�Ƃ̎��Z���������B
���ɏh���{�݂�8�������犴���҂̋}���Ɋm�ۂ��ǂ����Ă��炸�A26�����_��1396�l���̎���ҋ@�҂�ł���B28����351����lj���1209���ɂȂ邪�A�ڕW�ɂ͒������B
�u�ǂ��ł��邩������Ȃ��v�B�m���͏h���{�݂̊m�ۂƂƂ��ɁA��Ò̐��[���Ɗ����h�~�̕K�v�����q�ׁA���N�`���ɂ��d�lj��h�~���Ăъ|�����B
���q�ǂ��̃R���i������1�J���Ŗ�5.5�{�ɁI 9�����ƍĊJ�Łg��ƑS�Łh�̋���@8/28
�ċx�ݖ����̊w�Z�ĊJ������A�l�b�g��ł́q����x�Z�r���b�肾�B�q�ǂ����������@����厖�����A10��ȉ��̐V�^�R���i�E�C���X�̊������g�咆�B�q�ǂ����痼�e�ɂ���g��ƑS�Łh�̃P�[�X�܂ŏo�Ă����B
���{�͉ċx�݂̉�����Վ��x�Z�̔��f�ɂ��āA�w�Z�⎩���̂Ɋۓ������B�R���i���ȉ�̔��g��͍���Łu�\�ł���A�ċx�݂̉����v�Ǝ咣��������A���́u������S����Ă̋x�Z��v�����邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v�Ɛ����B�q�ǂ��̊������X�N���l����A�e���q����x�Z�r���������Ǝv���̂����R���B
���ہA1��������̐V�K�z���҂ɐ�߂�10��ȉ��͋}�����Ă���B���J�Ȃɂ��ƁA10��ȉ��̐V�K�����Ґ���25���܂ł�1�T�Ԃ�3���l��˔j�B1�J���O�̖�5.5�{�ɒB�����B�����s���̐V�K�����҂ɐ�߂�10��ȉ��̊�����13.1��(8��3�`9��)��14.3��(��10�`16��)��15.8��(��17�`23��)�Ɗg��X�����B
�C�O�ł͎��ƍĊJ�ɂ��q�ǂ��̊����}���ɒ��ʂ��Ă���Ƃ��������B
�pBBC(25���t)�ɂ��ƁA�X�R�b�g�����h��25���ɐV�K�����Ґ���5021�l�ɏ��A�ߋ��ő����X�V�B16�A17�̖�42����1��ڂ̃��N�`���ڎ���I���Ă����ɂ�������炸�A�V�K�����҂̂���19�Έȉ���3����1���߂��Ƃ����B�X�R�b�g�����h�̃W�����E�X�E�B�j�[����BBC�̎�ނɁu�w�Z�ɐl���W�܂邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�����g��������炩�������邾�낤���A(�����҂ɂ�����)��N�̊������݂Ă����炩���v�Ǝw�E�����B
���{�����ł����ƍĊJ�ɂ���āA�q�ǂ��̊������}�����鋰�ꂪ����B�s���ł͏K�����ɍs�����q�ǂ����������A���e�Ǝq�ǂ�2�l�̈��4�l�����������P�[�X�����łɏo�Ă���B�����w����w�Z�p���w�Z�����Z�Z���̒����p�b��(�����NJw)�����������B
�u�w�Z�͈ꗥ�ɋx�Z����K�v�͂Ȃ��Ǝv�����A�����҂��o���瑦�����ł���̐���O��Ƃ��āA�N���X��1�l�ł������҂��o����w��������ׂ����Ǝv���܂��B���Ƃ��o�Z������Ƃ��Ă��A�q�ǂ�������������ƒ���ł̊u���͓�����߁A�e��Z�����������\�����������Ƃ͗��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���v
�g��ƑS�Łh�����͐�ɔ��������B
��10�Ζ��������g��ŕۈ�180�{�݃R���i�x���c�����e�a����Ȃ��x�E �@8/28
�V�^�R���i�E�C���X�́u��5�g�v�ŕۈ�{�݂̋x�����������ł���B�����J���Ȃ̏W�v�ł�26�����_�ŗՎ��x�����Ă���ۈ�{�݂͑S����180�����ɏ��B�����ی�҂ւ̉e���͑傫���A���{���{�݂ւ̊������i�߂Ă��邪�A�c���q�ǂ����߂�����Ŋ��S�ɖh���͓̂���̂�����B
���ˑR�̃��[��
�u�ˑR�A�������āA�ǂ����悤���Ȃ������v�B8�����{�A����(4)��ʂ킹��ۈ牀���Վ��x���ƂȂ������s�s�̊Ō�t����(32)�͂��ߑ��������B�����珗���̌g�ѓd�b�Ƀ��[�����͂����̂͋x���O���̖�B����1�l�����������̂ŗՎ��x������Ƃ����m�点�������B���Ƃ͉����ɂ���A�}����q�ǂ���a�������Ȃ����߁A��ނȂ��������ɋΖ���ɘA���B��i�Ƒ��k���A�ĊJ����܂Ŏd�����x�ނ��Ƃɂ����B�@�x�����Ԃ͓���2�T�Ԃ̗\�肾���A����ɉ��т�\��������B�����́u�Ζ���̕a�@�̓R���i�Ή��ő�ςȎ����ŁA�����ɖ��f��������B�L���x�ɂ͎g�����Ă���A�������������Ă��܂��̂ŁA�Ƃɂ����ꍏ�������ĊJ���Ăق����v�Ɛ؎��ɑi����B
����4�g��3�{
���J�Ȃ̏W�v�ł́A�Վ��x������ۈ�{�݂�8���ɓ���}���B26�����_��14�s���{����179�����ɏ��A��4�g�̃s�[�N(56�{��)�̖�3�{�ƂȂ��Ă���B��5�g�ł�10�Ζ����̐V�K�����Ґ���18�`24����1�T�ԂŌv9657�l�ŁA�t�̑�4�g�̃s�[�N�̖�6�{���B�����҂��o���ꍇ�ɋx�����邩�͎s�����ňقȂ邪�A�N���X�^�[(�����W�c)���������Ă��Ȃ��Ă��x���ɂȂ�P�[�X�������B�����͂������ψكE�C���X�u�f���^���v�̓o��ŁA�ۈ�{�ݓ��Ŋ������L���鋰������܂��Ă���B���{���̕ی����̒S���҂́u����܂Ŋ����͐E��ȂǂŊ��������e����q�ւ̃P�[�X�������������A��5�g�ł͉������m�̊������ڗ����Ă��Ă���v�Ƃ��A�u�{�݂ōL�������E�C���X���q�ǂ�������Ɏ����A��A�e����Ŋ����g�傷��Ƃ����w�t���x�̃��X�N�����܂��Ă���v�Ǝw�E����B
�������
���s�s���͂��ߑ����̎����͕̂ۈ�m��ΏۂɃ��N�`���̗D��ڎ��i�߂Ă���A���{�͍�������A����Ҏ{�݂ł̊�����Ɋ��p���Ă����v�������L�b�g�̔z�z�Ώۂɕۈ�{�݂������A�N���X�^�[����h�����g�݂��n�߂Ă���B����ł��c���q�ǂ�����Ɋ�����̓O��͓���A���s�s���̕ۈ牀���́u�ł������̑������Ă��A�S�z�̎�͐s���Ȃ��v�Ƙb���B155�l���ʂ������ł́A�����̎�⊷�C�Ȃǂ�O�ꂵ�Ă������A���N1���ɕۈ�m�Ɖ�����2�l���������A��2�T�ԗՎ��x�������B�ĊJ��́A�����ɋ�C����@��ݒu����ȂǑ���������Ă��邪�A12�Ζ����̓��N�`���ڎ�̑ΏۊO�ŁA���J�Ȃ�2�Ζ����̃}�X�N���p�́A�����Ȃǂ̊댯��������Ƃ��Đ������Ă��Ȃ��B�����́u�������Ƃ��ėV������A�E�����������������ɐ��b���邱�Ƃ͌����I�ɓ���A��Ɋ������X�N�������Ă���v�ƁA�������\��Ō�����B
�����ԒP�ʂ̗L�x �������x�ɂ�
���������q�ǂ��̊ŕa��ۈ�{�݂̋x���ŁA�d�����x�܂���Ȃ��ی�҂̂��߁A�x�����x��݂��Ă����Ƃ�����B�����C������Еی�(����)�͍�N3���A�x�Z��x���̍ۂɗ��p�ł�����ʗL���x�ɂ�n�݂����B���������͂Ȃ��A1���ԒP�ʂł��擾�ł���B�Q�[���\�t�g���̃J�v�R��(���s)�͏��w���ȉ��̎q�ǂ��̋x�Z��ۈ�{�݂̋x���Ȃǂŏo�Ђł��Ȃ��]�ƈ��͌����A�ݑ�Ζ��Ƃ��A�ݑ�Ζ�������ꍇ�͓��ʋx�ɂ�^���Ă���B�d�q���i���̑��c���쏊(���s�{�������s)�͏]�ƈ��̉ƒ�̎���ɉ����A���ʖ����x�ɂ����Ŏ擾�ł���悤�ɂ��Ă���B�����J���Ȃ����t�A�����ی�҂��x�����邽�߁A�N���L���x�ɂƂ͕ʂɁA�R���i�Ή��p�̗L���x�ɐ��x��݂�����ƂɁA�ő�50���~���x�����鐧�x��������B
�@ |
 |


 �@
�@ |
���s���̐l�o�u�����v�����@���N�`���ڎ�i�݁u���|�v����H�@�����s�@8/29
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�������A�����s���̔ɉ؊X�̐l�o�������ɓ]���A���{�̑����ȉ���߂�u5���팸�v�̒B���ɂ͂قlj�����ԂƂȂ��Ă���B�����N�w�ȂǂŐi�ރ��N�`���ڎ킪�R���i�ւ́u���|�S�v�𔖂ꂳ���A�l�o������W���Ă���\��������A��ÕN��(�Ђ��ς�)�̎��ԂȂǁu�����������v���߂̏�M�݂̍��������Ă���B
4��ڂً̋}���Ԑ錾����(7��12��)�O�̓����O���Ɣ�ׁA�s���̐l�o5���팸�̒������ꂽ�͍̂���12���B�V�X�e����Ёu�A�O�[�v�v�����\�����X�}�[�g�t�H���̈ʒu������ɂ����l�o�f�[�^����s���ɉ؊X(�a�J�Z���^�[�X�A����w)�̋��j�Ɠy�j�̌ߌ�3���̐l�o�͂����Ƃ���A��B���ł��Ă���Ƃ͂����Ȃ��B
���j��7��9���A�y�j��7��10���̐l�o��100�Ƃ����ꍇ�A���߂�8��27���͏a�J81�E6�A���88�E6�A8��28���͏a�J72�E5�A���74�E3�B���ȉ�̒��ゾ����13���A14���Ɣ�ׁA���j�̏a�J�͂�⌸���������̂́A����ȊO�͂ނ��둝�����Ă����B
29���̓s���̐V�K�����҂�3081�l���������A8���ɓ���5000�l�O�オ�������������B�������g�債�Ă��l�o�̌����ɂȂ���Ȃ��w�i�ɂ��āA�ꋴ��̍��v�批(�������E�ꂨ)�y����(��Ìo�ϊw)�́u�d�lj���h�����N�`���ڎ킪����҂𒆐S�ɐi�݁A�R���i�ɑ���l�X�̋��|�S�����炢�����Ƃ��e�����Ă���\��������v�Ɛ�������B
�R���i�ւ̋��|�S�������\�h�s���̍��ɏo�Ă���Ƃ̃f�[�^������B�C���^�[�l�b�g�����őS����15�`79�̖�2���l������������Ă���l�Ƌ���Ă��Ȃ��l�ɕ��ނ��A��N9���ƍ��N2���̋��������p�����ׂ��Ƃ���A�����������������Ă��Ȃ��l�̕���3���ȏ㍂�������B�������ʂ͂������v���́u���N�`���ڎ킪����ɐi�݁A�R���i�ւ̋��|�S�Ɍl�����o�Ă���ł́A�l�X�̍s���}���ɗ���Ή��ɂ͌��E������v�Ǝw�E����B
�}�g��̌��c���V����(�Տ��S���w)���u�o���̐ςݏd�˂Łw���|�S�x�͕ω�����B���N�`���ڎ�ň��S����͓̂��R�̐S�������A���̊����ł͊����h������Ȃ��Ă��悢���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�������w�����������x�p�����K�v�ł͂Ȃ����v�Ƒi����B
���c���̓R���i�Ɋ��������D�w�̑��Y���Ȃǂ��ɋ����A�u�����Ґ��Ȃǂ̑���f���̂Ȃ��f�[�^���A�w����x�̂��郁�b�Z�[�W�̕����L���ȏꍇ������B�����̐S����ԁA�s���Ȋw�Ɋ�Â�����Ɩ��m�ȃr�W�����̒����߂���v�Ƌ��������B�@
�������铌�a�@ �R���i���҂̐�p�a�@�Ƃ��ĉ^�p�� ���������� �@8/29
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ň�Ñ̐�����@�I�ȏɂȂ��Ă��邱�Ƃ��āA���� �]����̓����铌�a�@������������R���i���҂̐�p�a�@�Ƃ��ĉ^�p����邱�ƂɂȂ�܂����B���Ɠ����s�������ǖ@�Ɋ�Â��ĕa���m�ۂւ̋��͂�v�������̂��ĐV���ɐ�p�a�@���ł���̂͏��߂Ă��Ƃ������Ƃł��B
�V���ɃR���i���Ґ�p�ƂȂ�͓̂��� �]����̓����铌�a�@�ŁA���ݓ��@���Ă��銳�҂ɓ]�@���Ă��炤�Ȃǂ��ė���������ő�50�����x���m�ۂ���Ƃ��Ă��܂��B
���̕a�@�͐��{���ȉ�̔��g�Ή�����������Ƃ߂�n���Ë@�\���i�@�\�̎P���̕a�@�ŁA���Ɠ����s������23���A�s�����ׂĂ̈�Ë@�ւȂǂɑ������ǖ@�Ɋ�Â��ē��@���҂̎����a���m�ۂ̂��߂̋��͂�v�������̂��ăR���i���Ґ�p�ɂ��邱�Ƃ����߂��Ƃ������Ƃł��B
�n���Ë@�\���i�@�\�͂���܂őS����57�̕a�@�̂���870�����R���i���җp�Ɋm�ۂ��Ă��āA�����s���ł͎P���̕a�@�ō��킹�Ă��悻240�����R���i���Ґ�p�ɂȂ�Ƃ��Ă��܂��B
�s���ł͂���܂łɏa�J��̓s���L���a�@�Ȃ�5�̈�Ë@�ւ������I�ɃR���i���Ґ�p�ƂȂ��Ă��܂������A�����s�ɂ��܂��ƁA����̗v�����ăR���i���Ґ�p�̕a�@�Ƃ��Ẳ^�p�����܂����̂͏��߂Ă��Ƃ������Ƃł��B
���V�^�R���i�@��錧�������A2���l�����@����1�J��8122�l�@�u��5�g�v�Ŋg��@8/29
��錧���̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�28���A�v��2���l�����B7�����{����n�܂������s�u��5�g�v�Ŕ����I�Ɋ������L����A7��29���ȍ~�̒���1�J���̊����҂́A�v��4�����߂��B������9�����ψي��ɒu�������A���������ʂ��Ȃ��������B����ŁA����҂𒆐S�Ƀ��N�`���ڎ킪�i�݁A�����҂�50��ȉ����������߂�X���ɂ���B
�����ł͍�N3��17����1��ڂ��m�F�B��1�N3�J����̍��N6��10���ɗv1���l��˔j���Ă���A�킸��2�J�����ł����1���l�����邱�ƂƂȂ����B
��5�g�̎��������ʂ��Ȃ��v���̈�ɁA�����͂������Ƃ����ψي��̊g�傪����B���ɂ��ƁA�V�K�����҂̂����ψي�������9���ɏ��A�u������肪�i��ł���B
���ɁA����1�J��(7��29���`8��28��)�̊����Ґ��͌v8122�l�ɏ��A�v�����Ґ���4�����锚���I�Ȋg���������B1��������̐V�K�����Ґ���3������ԉ����A�ߋ��ő��ƂȂ���8��14���ɂ�391�l��400�l�ɔ������B
����1�J���ɂ����銴���҂�N��ʂɌ���ƁA20�オ25%�ōő��B�����ŁA30���40�オ17%�A10���50�オ13%�A10�Ζ�����7%�Ƒ����B����҂𒆐S�Ƀ��N�`���ڎ킪�i���Ƃɂ��A50��ȉ���92%���߂Ă���B
�܂��A�n��ʂł́A���Ύs931�l�A�y�Y�s645�l�A�_���s502�l�A���ˎs477�l�A�É͎s465�l�̏��ɑ����A�����̍L����͌����S��ɋy�ԁB
28�����_�ł̌����ɂ�����1��������̗z���Ґ�(�T����)��287.7�l�ŁA25���A����200�l������B���@���҂�1�J���O��3�{���ƂȂ�476�l�A�d�ǎ҂�26�l�ŁA�Ƃ��Ɍ��w�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̏ɂ���B���̂ق��h���×{�҂�236�l�A����×{�҂�1746�l�ɏ��B
���y�Y�ƍⓌ�̎��Ə��ŃN���X�^�[���@���P��x�@���A��w�T�b�J�[���@���@8/29
��錧�Ɛ��ˎs��29���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ҍv221�l�̂����A6�l�͓y�Y�s���̎��Ə��œ����Z�\���K���ŁA���͎��Ə����ŐV���ȃN���X�^�[�����������\��������Ƃ��Ă���B
�Ⓦ�s���̎��Ə��ł��]�ƈ�5�l�̊����������A���͎��Ə����ŐV���ȃN���X�^�[�����������\�����w�E���Ă���B
�����������������s���̎��Ə��ł͏]�ƈ�3�l�̊��������炩�ɂȂ�A28���܂łɌ��\���ꂽ6�l�ƍ��킹�A���Ə����̊����҂͏]�ƈ��v9�l�Ɋg�債���B
���P��x�@���ł��V���ɗ��u��1�l�̊�����������A27���܂łɌ��\���ꂽ8�l��������ƁA�����̊����҂͗��u��8�l�A�E��1�l�̌v9�l�ɍL�������B
�N���X�^�[�������������P��s���̑�w�T�b�J�[���ł́A�V���Ɋw��1�l�̊��������o���A26���܂łɌ��\���ꂽ12�l�𑫂��ƁA�����̊����҂͊w���v13�l�ƂȂ����B
�������� 20��ȉ���4�����@�Ȗ،���8���̐V�^�R���i�@8/29
�Ȗ،����ō����ȍ~�Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�����҂̂����A20��ȉ��̊����͑S�̂�45�E5�����߁A�u��3�g�v�̃s�[�N������1����26������啝�ɑ����������Ƃ��A28���܂ł̌��̂܂Ƃ߂ŕ��������B20�オ�ł��������A1�����_�ł͂킸��������10��A10�Ζ����������Ă���B��N�w�̑����̗v���ɂ��Č��́A20��͍s���͈͂��L���A10��ȉ��̎q�ǂ��͓��ɉƒ���������ڗ��ƕ��͂��Ă���B
����22�����_�ł̐V�K�����Ґ���N��ʂɏW�v�����B����1�`22���܂ł�20��ȉ��̊����҂͌v1538�l�B20���25�E9��(876�l)�ƑS�N��ʂōł������B1����16�E8�����瑝���������Ă���B
10���12�E5��(422�l)�A10�Ζ�����7�E1��(240�l)�B1�����_�ł͂��ꂼ��6�E2���A3���ŁA�����͔{�����Ă���B�����͂̋����f���^���̉e���Ŏq�ǂ��ɂ��g��B���N�`���ڎ킪�i����҂̊����͉�����������A��N�w�̊������ڗ��悤�ɂȂ��Ă���B
�q�ǂ����֘A����N���X�^�[(�����ҏW�c)��7���ȍ~�������ł���A�ۈ牀�╔�����ȂǂŌv9�����������B
�������Ǒ�ۂɂ��ƁA20�オ�����҂̑������߂钆�A�ƒ�������ɂ��e���オ�d�lj����郊�X�N������B1���͏d�ǎ҂̑���������҂��������A�����͑唼��60�Ζ����Ƃ����B
�����S���2�w�����n�܂�A�q�ǂ��̊����g������O�����B���ۂ́u�q�ǂ��⓭�����オ�������n�߂�Ɗ����̓��������܂��B�l�Ƃ̋�����}�X�N�̒��p�Ȃ�1�l1�l�̐S�|�����d�v�ɂȂ�v�Ɖ��߂Ċ�����̓O���i���Ă���B
���w�Z����A�Ή��͍��@�ċx�ݖ����̊����g��Ɍx���@�É����@8/29
�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ɔ����A�É����ɂ�9��12���܂ŁA���t�ɑ���2�x�ڂً̋}���Ԑ錾�����߂���Ă���B�����͂̋����C���h�R���̃f���^���֒u�������A���Ə���q�ǂ��̊w�т̏�ȂǁA���N�`�����ڎ�̐��オ�W�܂�ꏊ�ŃN���X�^�[���������A�ƒ���������ۗ��B����܂łɂȂ���@�I�Ƃ�������u��5�g�v�Ɋw�Z����͑Ή���͍����A�����Ȃ̐f�Â��ْ���Ԃ������Ă���B
���s�u��5�g�v�̒������n�߂�7�����{�̌����̃f���^���̗z������40�����������A8�����{�ɂ�94���ɒB�����B�����Ґ��̍ő��X�V��������15�`21����1�T�Ԃ̌��̂܂Ƃ߂ł́A�S�����҂̖����߂��̂�0�`29�B65�Έȏ�̃��N�`���ڎ�ςݐ���̊���������A4�����{�Ƃ͊������t�]���Ă���B
�N��ʐl��10���l������̊������݂Ă�20��O�����ˏo���A20��㔼��16�`19�Α�̍��Z���N�オ�����B
�N���X�^�[�̔����ꏊ�����H�X�⎖�Ə��ɉ����A��N�w���W�܂�w�Z��ۈ牀�Ŗڗ��B���C�Ȃǂ̑����̑�����Ă��h���Ȃ��������Ⴊ�������B�������Ń}�X�N���O�����ȂǁA�M���ǖh�~�̂��߂̍s�����������ăN���X�^�[��������������������B
���ċx�݉���
�����Ґ���19���ɉߋ��ő���675�l�ɖc��݁A���Îs�A�ĒÎs�A��O��s�Ȃǂ͎��Ԃ��d���݂āA�����܂ł̉ċx�݉��������߂��B�����͏Ǐy�����Ƃ������u������Ƃ����̒��s�ǂ����͊����������v�Ƃ����P�[�X������B�ƒ�������̊g�傪�[���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�e�s���̋���ψ���͖{�l�����łȂ��Ƒ��ɂ��ڂ������u�{�l��Ƒ��ɕs���̎q���������́A�o�Z���T���Ď�f���āv�ƁA���O�Ȍ��N�ώ@�������Ăъ|����B�e�w�Z�Ƃ�������̂�������c�_���Ă���B���犈���͕����Ȋw�Ȃ̃K�C�h���C���Ɋ�Â��A�������K�ɉ����s�A�j�J��R�[�_�[�̉��t�A�ߋ����ł̒����Ԃ̃O���[�v�g�[�N���T����B
���I�����C���w�K
������Ƃ��ẴI�����C���w�K�����X�ɍL�����Ă���B2�w�����n�܂����g�c���͊�]�҂���A30��������Ƃ����C�u�z�M����B�������k�͎���Ŏ������A���ƂŔ��\���邱�Ƃ��ł���B9��1������ĊJ������Îs�͊w�Z���ƂɊe�ƒ�ƃI�����C���ڑ��������݂���Ȃǂ��ď�����i�߂Ă���B�����Ȋw�Ȃ͏����w�̃I�����C���w�K�ɂ��Ċw�Z�ĊJ��A�蒅�x�������m�F����A�Ζʎ��Ƃň���Ȃ��Ă悢�Ƃ��Ă���B
���ْ����̏����Ȉ�Á@�g�Ƒ��o�R�h�x��
�����}�g����A�����Ȉ�@�ŊO���̗z�����҂�f��@������Ă���B�u�q�ǂ��͏Ǐy������ɂ����Ƃ���Ă������A�f���^���͕��ʂɉƑ����炤��B����͂����O���ɒu���悤�ɂȂ����v�ƁA�É��s�É���t����̉͌��G�r��t�͏����Ȉ�Ì���ْ̋�����\�������B�u���Ƒ��ɑ̒��s�ǂ̕��͂��܂����v�u�ۈ牀���̏͂ǂ��ł����v�\�B�É��s�x�͋�̂���͂��@�̎�t�����ł́A��f�҂����邽�тɁA�X�^�b�t���Ǐ��łȂ��s������Ƒ��A�ۈ�{�݂̏Ȃǂ��m�F����B7���ȍ~�A����Ŏq�ǂ��̗z�����m�F�����ۂɎ�t�Łu�Ƒ����������Ă���v�ƕ��������ƂŁA�ق��̊��҂Ƃ̓��������Ȃǐv���ȑΉ��ɂȂ����B��������ƒ�������ŁA�u�s���͈͂����肳�����c���͂������A�����w�����Ƒ����Ɗm�F���邱�Ƃ��d�v�v�Ɖ͌���t�͎w�E����B���N�ώ@����������×{�̎q�͔�r�I���C�ɉ߂����Ă����Ƃ����B���݈�@�ɂ͔��M�A�P�ł̗��@�������A�u�V�^�R���i�Ƃ̌����������ɂ����A���M���҂̒��ɗz���҂����Ȃ����A���������T�d�ɐf�f����K�v������v�Ɖ͌���t�B�����w�Z�Ȃljċx�ݖ����̍ĊJ�������}���A�ی�҂�Ɍ����Ắu�{�l��Ƒ��ɑ̒��s�ǂ������ł��݂�ꂽ�ꍇ�A�o���A�o�Z�����Ȃ����Ƃ������g��h�~�Ɍ������Ȃ��v�Ƌ��������B
���C���^�r���[�@�É��������ǂ��a�@�@���i�M��E������
�����}�g��������Ă���C���h�R���̃f���^���́A�����҂̑̓��ő��B����ʂ����ɑ����A�]������1000�{�Ƃ̕�����B���̂��ߏǏ�͂�苭������A�l�ɂ���₷���B�V�^�R���i���ǂ����ɂ�����炸�A�K�v�Ȉ�Â����Ȃ��Ȃ�����É����ɂ������Ă���B
�f���^���̂܂ɂ���āA���O���ł͎��S�����オ���Ă���B�����ɂ��Ă͍��̂Ƃ���A�M���ł���f�[�^���o������Ă��Ȃ��B�]�����Ɣ�ׂĐ������Ԃ�3�`4���ƒZ���A���Ǐ�҂͏��Ȃ����Ƃ��������Ă���B����܂Ŏq�ǂ��͑唼�����Ǐ������A���o��Q�┭�M������鎖�Ⴊ�����Ă����Ǝ�������B
�V�^�R���i�͂��Ƃ��ƁA���nj�1�T�ԑO��ŋ}���ɔx�����������Ē�_�f��Ԃ��i�s���邱�Ƃ�����B�S�؍[�ǂ�]�[�ǂ����郊�X�N�����܂�B�f���^���́A�d�lj�����X�s�[�h��������ہB�Ɖu���Ȃ������ł���قǁA�얞���b�����̂�����قǏd�lj�����X���͕ς��Ȃ��B�������֓����𒆐S�Ɋ����Ґ����������A���@���Â����Ȃ����߂ɖS���Ȃ�P�[�X���o�Ă���B
�����o�H�͏]�����Ɠ������A��(�Ђ܂�)�������ڐG�����B�����҂̂₭����݂��ځA�@�A���̔S���ɕt�����Ă���������قƂ�ǂ��B�]������1�l������2�l�ɂ����v�Z���������A�f���^����5�`9�l�ɂ����B����͋�C�������鐅��(���ڂ�����)�ɋ߂��l�B�ƒ�Ɏ������܂ꂽ��A�Ɖu���Ȃ�����S����������B�����������ƈ���ċ�C�����͂��Ȃ��B��C�̗��ꂪ�������Ȋ��ł́A�����Ȕu�G�A���]���v�������ԕY���A�������L���邱�Ƃ����邪�A�u��C�����v�Ƃ͈قȂ�B
����܂ł̂悤�ɉ�b���̃}�X�N���p��3�������O�ꂷ��Ζh���邪�A�E�C���X�ʂ̑����f���^���́A�����҂̔��������т������ł����Ă��܂��B��w������ڐG�����̊����͒Ⴂ���߁A�h�A�m�u����A�����Ȃǁu���\�ʁv�̏��łɐ_�o���ɂȂ�K�v�͂Ȃ��B�ڕ@����G��O�̎����w���ł𑱂��悤�B
�����ł����Ə�����H�X�ł̃N���X�^�[�����ɉ����āA�����͈͂̍L����l����q�ǂ��ւ̉ƒ���������ڗ��B�f���^���͏]�����ƈقȂ�A�q�ǂ�����q�ǂ��ɂ��L����B����ł��q�ǂ����d�lj����邱�Ƃ͂قڂȂ��B�q�ǂ��ɂƂ��Ă̓C���t���G���U�����͂邩�ɐg�̓I�e�������Ȃ��B�����͎q�ǂ�������l���m�̕����L����₷���A�u��l����q�ǂ��v�ɂ��銄�����������Ƃɕς��͂Ȃ��B����������l�̊����h�~��D�悷�ׂ��ŁA�q�ǂ����������ɂȂ邩��Ƃ�����l�̓s���ŋx�Z��x�������āA�q�ǂ��炵��������D���ׂ��ł͂Ȃ��ƍl����B
�L���Ɗ��҂����R�̃J�N�e���Ö@�͋����ʂɌ��肪����A���^�̑Ώۂ͊�b�����ȂǏd�lj����郊�X�N��������B���s�̎����ɂ́A���N�`���ڎ��i�߂ďW�c�Ɖu��ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��B���N�`���̓f���^���ɂ������B���ɏd�lj��Ǝ��S��h�����ʂ́A�]�����ɗ��Ȃ��B�ł��邾�������ڎ킵�āA�����g�����łȂ��A��ȕ��̖�������Ăق����B
���K���������ŃN���X�^�[6�l�z���@����268�l�����@8/29
���Ɗs��29���A����29�s���ȂǂŌv268�l�̐V�^�R���i�E�C���X�����ƁA���@���Ă����R���s��80�㏗���ƌ�����70��j����2�l�̎��S���m�F�����Ɣ��\�����B�����҂͗v1��4967�l�A���҂͌v200�l�ƂȂ����B�V�K�����Ґ���6���Ԃ��300�l������������A��T�̓��j���ɑ���200�l�����B
�����̎��S�҂͍�N4���ɏ��߂Ċm�F����Ĉȍ~�A�����g����𒆐S�ɑ����B�����̎��S�҂�12�l�A�d�ǎ҂�8�l�ő����X���ɂ���B���ɂ��ƁA�����̏d�ǎ҂̂����A���N�`���ڎ킪2��ςl�̒��ŏd�lj���������͂Ȃ��Ƃ����B�����N�������̖x�T�s�����́u��5�g�ł͂���܂Ō����Ȃ�����20�`40�オ�d�lj�����P�[�X�������Ă���B�����҂̈�萔�ŏǏ����Ȃ�̂ŁA�����őS�̂̊����Ґ���}���Ȃ������Ɍ������Ȃ�v�ƌx�������߂Ă���B�a���g�p����28�����_��2�E5�|�C���g����68�E3���B�h���×{�{�݂̓����҂�679�l�Ɍ����������A����×{�҂�932�l�ɑ����Ă���B
�V���Ɋm�F�����N���X�^�[(�����ҏW�c)��6���B�E��֘A�ł́A���ΌS���S�Ò��ŐE����Ƒ���17�l�A��_�s��5�l�A���s��5�l�̊��������������B�b�ߎs�ł͐ڑ҂����H�X��5�l�̊����������B���s�ł́A�K���������̏��w������30��̐��k��6�l�A�O���Ђ̉Ƒ���5�l�̊��������炩�ɂȂ����B
�g�債���N���X�^�[��11���B�e�����s�̊w�K�m�֘A�ł͐��k3�l�̊�����������25�l�K�͂ƂȂ����B��_�s�̍���ҕ����{�݂ł�3�l������40�l�ƂȂ����B
2���̃N���X�^�[�́A�V���Ȋ����҂��m�F���ꂸ�ɏI�������B
�V�K�����҂̓���́A�s83�l�A��_�s23�l�A���R�s 2�l�A�������s 12�l�A�֎s 7�l�A���Ð�s 12�l�A���Q�s 2�l�A�H���s 7�l�A�b�ߎs 5�l�A���Z���Ύs 12�l�A�y��s 9�l�A�e�����s 16�l�A���s 8�l�A�R���s 2�l�A����s 11�l�A�{���s 3�l�A���C�s 2�l�A�C�Îs 9�l�A��쒬 4�l�A�}���� 1�l�A�{�V�� 3�l�A���䒬 11�l�A�փP���� 3�l�A�_�˒� 3�l�A������ 3�l�A�K��쒬 1�l�A��쒬 1�l�A�r�c�� 6�l�A�䐓�� 2�l�ŁA���O��5�l�B
�N��ʂł́A10�Ζ��� 34�l�A10�� 59�l�A20�� 44�l�A30�� 38�l�A40�� 40�l�A50�� 30�l�A60�� 13�l�A70�� 5�l�A80�� 4�l�A90�� 1�l�B
���u�x�Z�̕��������g��Ɍ��O������v�s�������Ȃ���Ζʎ��Ƃց@���Ɍ� 8/29
�V�^�R���i�E�C���X�̊�����10��ȉ��ɂ��L���钆�A���Ɍ����ł�9��1���ɂ͂قƂ�ǂ̊w�Z��2�w�����}����B�w�Z�ł̊����g������O���鐺�͍��������A������ψ���́u������̖{���͐l�i�`���B�l�ƌ���钆�Ŋw�ԋ@���ۏ������v�ƑΖʎ��Ƃ̏d�v���������B���O�ꂵ����ŁA��ċx�Z�Ȃǂ͎��{���Ȃ��l�����B
�����ōł�����8��23���ɒ��w�Z�̎n�Ǝ����s�������Ύs�B���s���ς͉Ƒ��̑̒��s�ǂł����k�̓o�Z���T��������ȂǁA�������O�ꂳ���Ď��Ƃ𑱂���B�����s���Ȃǂ𗝗R�ɓo�Z�ł��Ȃ����k�����邪�A�唼�͕��Âɉ߂����Ă���Ƃ����B
���s���ɂ��钆�w�Z�̍Z���́u�H�����͐Â������A�F�l���m�Ŏ���Ȃ��p���������B���w���炵�����䖝�����Ă���̂͐\����Ȃ����A�}�X�N�z���Ɏq�ǂ��̕\������ċC�����Ɋ��Y���Ă���v�Ƙb���B
�����A��ċx�Z���Ȃ����j�\�����֓����F�m���̃c�C�b�^�[�ɂ́u�q�ǂ��̒������ʊw���ƒ늴���̌����ɂȂ�v�u�I�����C�����Ƃp���āv�Ȃǂ̏������݂�����ȂǁA�����g���s�������鐺�͏��Ȃ��Ȃ��B�����Ȋw�Ȃ�27���A�����ɂ���Ă͎������k2�`3�l�̊����������������_�ł��A�������Ԃ��l�����āA5�`7���Ԃ�ڈ��Ɋw��������������悤�A�e�����̂֒ʒm�����B
�����ς��A�����g��̒��o��ΐv���Ɏ��Ƃ��~�߂�Ƃ������A�u�w�͌��ゾ���Ȃ�I�����C���ł��ł��邪�A�S�̐����ɂ͐l�Ƃ̂ӂꂠ�����K�v�v�ƁA�u������킹���v�̏d�v������������B
����܂ł̊�����ɂ����̎艞���������B�f���^���͊����͂������Ƃ���A7���ȍ~�́u��5�g�v�ŁA�����ł�19�Έȉ��̊����҂�8��16���܂ł�2116�l�ɏ��B�����������Ȃǂł̃N���X�^�[(�����ҏW�c)��7��88�l�ɂƂǂ܂��Ă���B�u�����ł̒��ւ��͐l���⎞�Ԃ𐧌�����v�Ȃǂ̑��O�ꂵ�Ă���A�ƒ�Ŋ����������k���ċx�݂̕������ɎQ�����Ă��Ă��A�����ŗz���҂��o�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������Ƃ����B
�����ς́u�x�Z���ċ��t�̖ڂ��s���͂��Ȃ��Ȃ���������g��̌��O������v�Ƃ��w�E�B���w4�N�̒��j������_�ˎs�̏���(29)�́u��N�̈�ċx�Z�ł͐e�q�Ƃ��X�g���X�����܂����B�q�ǂ��͐l�Ƃ̊ւ�肪�Ȃ��Ȃ�Ɖe�����傫���v�Ɨ����������B
����A�쐼�s���ς�9������A�Ζʎ��ƂƃI�����C���̑I�𐧂�����B���s���ς��w�т̕ۏɂ͑Ζʂ̕��������I�ł��邱�Ƃ�F�߂邪�u����܂ł̊����f���^���ɒʗp���邩���O������B�ƒ�̗v�]�����܂��A���l�Ȋw�ѕ���������v�Ƃ���B
���R���i�����}�g��@�~�}�����ɂ��e���@�{��s�@8/29
�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂̋}�����A�{��s���̋~�}�����ɉe�����y�ڂ��Ă���B�s���h�NJǓ��ŁA�~�}�������҂���������Ë@�ւ����܂炸�A����ɒ����ԂƂǂ܂�P�[�X�������Ă���B
�������̂�����̌ߌ�A�s���h�ǂɕ����{�݂���V�^�R���i���҂̋~�}�����̗v�����s�ی����o�R�œ������B������͑S�g��h�앞�ƃS�[�O���A�S����܂ŕ����A���̘I�o���ɗ͏��Ȃ����ĎԂɏ�荞�B
���݁A�s���h�ǂ̑��������͕K�������h�~������Č���ɏo������B�V�^�R���i�̊����}�g����A�V�^�R���i�ł͂Ȃ��v���ŋ~�}�o����������A�����Ŋ��҂̃R���i�z�����킩�����Ⴊ���������炾�Ƃ����B
���̎��͑��₩�Ɏs���̕a�@�ɉ^�э��ނ��Ƃ��ł������A�ŋ߂͋~�}�������鎖��������Ă���B
�s���h�ǂ̂܂Ƃ߂ł́A8���̋~�}�o����24�����݂Ōv1212���B���̂���22���܂ł�1�T�Ԃł́A�����ȏ��h������`����14�J���ȏ�̈�Ë@�ւɎ����f��ꂽ�A����2�����30���ȏ�؍݂����u�~�}��������āv��13�����������Ƃ����B
1��2�̂����ꂩ�̗��R�ŋ~�}�������x�ꂽ�P�[�X��6�{�߂���75���ɂ̂ڂ�B�O�̏T��48���A���̑O�T��38���Ə��X�ɑ����B75���̔����߂���38���́A���M��ċz����ȂǃR���i�̋^�������銳�҂������B
�s���S�����Ǔ��̖k���h���ł́A��Ë@�ւɎ��ꂪ�\���ǂ���10��ȏ�₢���킹�Ă����܂炸�A�����4���Ԉȏ���؍݂������Ƃ��������Ƃ����B
����~�}�����́A���M�������҂̎������Ë@�ւɒf���邱�Ƃ������Ă���Ɗ����Ă���B�����́u���҂�����炻�������A�Ƒ����s������B�����������Ă��������Ă��A����悪���܂�Ȃ��W�����}������v�Ɩ������B
�s���h�Nj~�}�~����掺�ɂ��ƁA�s���ł͊e���h���Əo�����̋~�}�Ԍv10��ŋ}�a�̊��҂�������Ă��āA���̂Ƃ���~�}�Ԃ�����Ȃ����Ԃ͋N���Ă��Ȃ��Ƃ����B�����A�����h�O�����́u���̂܂܊����̋}�g��ň�Â̕N��(�Ђ��ς�)�Ǝ���×{�ґ����������A��������ȃP�[�X������������B��s�s�Ō����ɂȂ��Ă���~���閽���~���Ȃ��Ȃ鎖�Ԃ́A���{��ŋN���Ă����������Ȃ��v�Ƙb�����B
�������}�g��̎�q���@�����ŏ��i���A���������ɕs�M���@8/29
���������̐V�^�R���i�E�C���X������Ή��ɁA��q���ŕs�����Q�����Ă���B������������1�s2���ŏ��ʂɍ������邩�炾�B�ł��o������͓��S�̂��������ޓ��e�Ȃ���A�����҂̑������V�\�s�ƌ��Ō�������A����q�A���q�����͌����ɓd�b�ŊT�v��m�炳���P�[�X���������B�Ή��ɒǂ��闼������́u�I�����C���ł��ł��Ȃ����v�ƁA���P�����߂鐺���オ��B
�����ł�8���ɓ���A60�l�ȏ�̊����҂��m�F����A���V�\�s����8�����߂�B���͎s�̗v���ɉ�����`�ŁA�������H�X�ւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�̗v����y�ǁA���Ǐ�Ҍ����̏h���×{�{��(���ԃz�e��37��)�̐ݒu�����߂��B
�����̗×{�{��
�����̊����h�~������c����ɓ�����A�g�ᒠ�̊O�h�ɒu�����`�ɂȂ��������́A�h���×{�{�݂̑I��o�܂ɋ^�������B��q���ł͍�N7�����A����1�s2���Ɖ��v�����A��Ë@�ւȂǂ̊W�҂����V�\�s�̌����{�݂ɏW�܂�A�����҂̎���Ɣ����̌P���������B�e�s���͕ی�������̗v���ŁA����\�Ȍ����{�݂��I�сA�Q���e���r�Ȃǂ����낦�Ċ����g��ɔ������B�ی����̒S���҂͊e�����{�݂����@�������A�g���邩�ǂ������Ȃ��܂܁A����̃z�e�����p�����܂����Ƃ����B�n���̖���E���́u����܂ł̘J�͂�\�Z�͉��������̂��v�Ƃ������B�����ɂ��ƁA������h���×{�{�݂̐ݒu�̘A�����������̂͊J����3�A4���O�B���Z�v�����܂߁A�����ւ̘A�����͖{����������A�F�юx����������Ƃ��ŁA��������������ɂȂ��Ă���B
���l���̕�
�R���i������������������̂ɂƂ��ẮA���̌l���̎�舵�����Y�݂̎킾�B�����҂��m�F���ꂽ�ꍇ�A�ی����͋��Z�n�̎����̂ɐl����N��A���ʂ݂̂�m�点�Ă���B��������́u�Ǝ��̑��ł��߂ɁA�����o�H�܂œ`���Ăق����v�Ȃǂ̈ӌ����������B���q���͊����Ҏx���̈�ŁA���O�×{���������Ɍ�ʔ��Г��ő�8000�~�������鐧�x��݂����B�������A�N���ǂ��Ŏ��Â����������炸�A���m���ł��Ă��Ȃ��B�������́u�l���̎�舵�����܂߁A�M���Ȃ����Č��Ƃ̘A�g�͐��藧���Ȃ��v�ƕs����R�炷�B���������n���̐��ɑ��A���c�N��m����27���̒���Łu�N���X�^�[(�����ҏW�c)�̋����A�w�Z�A�c�t���Ȃǎs�������^�c�Ɋւ����͂ł��邾�����L�������������v�Ɛ����B���̏�Łu���P�_�������������Ή�����B(�l���ɂ��Ă�)�s�����Ƙb���A�ǂ�Ȍ`�ł�邩�����������v�Əq�ׂ��B
����t��A10���O��̎Љ���̒�~���߂�@���ꌧ�@8/29
�V�^�R���i�E�C���X�����g����A���ꌧ�ƌ�����Ë@�ւ̕a�@���ō\������a�@����c��28����A�앗�����̌���t��قŊJ����A�ʏ�f�j�[�m���͊e�a�@���ɑ��R���i�a���̂���Ȃ�m�ۂ�v�������B����t��̈����N�D��͗�������������A�����g��̖h�~��Ƃ���10���O��̎Љ����~�ȂǓƎ��̍�̌��������߂��B
�ʏ�m���́u�l�ԃh�b�N���~��\���p�E���@�̉����A��ʊO�����~�Ȃǂ��u���A�ő���̃R���i�a���̊m�ۂ��v�Ɨv�������B
��͔���J�B���ɂ��ƁA��ÊW�҂���͓��@���ɏǏ���P���݂��銳�҂��h���×{�{�݂ɉ��Ƃŕa����]�����グ��Ȃǂ̒�Ă��������B����Łu�悪��������Õ��������Ă��钆�A�a����5��10�����₵�Ăǂ��Ȃ�̂��v�Ƃ̎w�E������A�����̍s����}�������̓I�ȕ�������߂鐺�����������Ƃ����B
������͉��̉�Łu��Ì���͔�펖�Ԃ��Ƌ��������ɗ������Ă������������̂���Ԃ̊�]���B���̉�����ɒm���ɗv�]���������s���̗}��������v�Ƙb�����B
��ł́A�d�lj���h���y�ǎҌ����̍R�̃J�N�e���Ö@�ɂ��Ă̌��̑Ώ����j�Ă��c�_�B���̑Ώ����j�Ă�(1)��Ë@�ւ��K�v�Ɣ��f�����ꍇ�ɍ��ɖ��v������(2)��Ë@�֓��̊�����N���X�^�[(�����ҏW�c)�����������ꍇ�Ɍy�ǎ҂ɓ��^����|��2�_���������ꂽ�B�O�����Âɂ��Ă͈�Ì���̕��S��������\��������Ƃ��A�������������𑱂���B
�܂��A���̃��N�`���ڎ�̉����̂��ߌ��̍L��ڎ���ŕ����̌ߌ�6���J�n�Ƃ��Ă���^�c���Ԃ��A9�����琅�A�ؗj�͌ߌ�3���J�n�ƂȂ邱�Ƃ����\���ꂽ�B
���錾�����A12���́u����v�@���J���A�����̔F�������@8/29
�V�^�R���i�E�C���X�Ή��̓��ʑ[�u�@�Ɋ�Â��A�����s�Ȃ�21�s���{���ɏo�Ă���ً}���Ԑ錾�̉��������ɂ��āA�c�����v�����J������29���A�u��������Ƃ��Ă݂Ă�(1��������V�K�����Ґ���)500�l�����ɂȂ�Ȃ��Ɖ����ł��Ȃ��B������l����Ƒ������Ȃ����v�Əq�ׁA�����Ƃ���9��12���̉����͓���Ƃ̔F�����������B
�ً}���Ԑ錾�̉����ɂ��Đ��{�́A�V�K�����Ґ���a���̎g�p���Ȃǂ�ڈ��ɑ����I�ɔ��f����p�����BNHK�́u���j���_�v�œc�����́u9������͊w�Z���n�܂�ȂǁA�l�̍s�����ς��܂��L���肪�o��̂ŁA�܂��܂��������������v�Ƙb�����B
�c�����͂܂��A�u�a�@�ŕa���𑝂₷�Ƃق��̈�ʈ�Âɂ��Ȃ�e�����o��̂ŁA�Վ���Î{�݂Ȃǂŕa�����𑝂₷���Ƃ��d�v�v�Ɛ����B�u(�����g�傪)���܂�����߂�̂ł͂Ȃ��A���ł��Ή��ł���悤�ȑԐ����Ƃ�v�Ƃ̍l�����������B
��2�w����q�ǂ��̊����g��h�~��Ɍ������Ȃ����_�@8/29
9������̐V�w�����T���A�u�q�ǂ��������A�w�Z�ɍs�����Ă����v�ł��傤���v�Ǝ��₳��邱�Ƃ��������B���͓̉���B�����̃��X�N�ጸ�Ƌ���@��̑r���̓g���[�h�I�t�̊W�ɂ���A��T�ɂ͌����Ȃ����炾�B�ŏI�I�ɂ͐��k�ƕی�ҁA����ɋ��������Ō��߂邵���Ȃ����A�ŐV�̌����܂��A���悤�͂���B�{�e�Ř_�������B
�V�^�R���i�E�C���X(�ȉ��A�R���i)�̑�5�g�ł́A�q�ǂ��̊������g�債�Ă���B�f���^���̖������������B8��20���A�ǔ��V���́u�����J���Ȃɂ��ƁA�S���ō���12�`18����1�T�ԂɊ������m�F���ꂽ20�Ζ�����2��2960�l�ɂ̂ڂ�A��4�g�ōő�������5347�l(5��13�`19��)��4�{���ɑ������v�ƕĂ���B
�q�ǂ��̊������g�債�Ă���̂́A���{�Ɍ������b�ł͂Ȃ��B�A�����J�ł��}�����Ă���B8��5���܂ł�1�T�ԂŁA�q�ǂ��̐V�K�����҂͖�9��4000�l�ŁA���߂ōŒႾ����6��24���̏T��11�{���B�q�ǂ��̊����͑S�̂�15�����߂�B
�����A����͉ߏ��]���̉\���������B8��17���A�J�i�_�̈�t�����́A2020�N3������12���ɃJ�i�_�̃I���^���I�B�Ŏ��{���ꂽ���ׂĂ�PCR�����̌��ʂ�p���āA�N��w���̊������̈Ⴂ�Ɍ����̕p�x���A�ǂ̒��x�A�e�����Ă��邩���ׂ��B�ڍׂ͏ȗ����邪�A10�Έȉ���80�Έȏ�Ō��������Ȃ��A�����̖��Ǐ��҂������Ƃ��Ă���ƌ��_���Ă���B�����̊����́A����ꂪ�l���Ă�����͂邩�ɑ����B
���d�lj�����q�ǂ���
����ɖ��Ȃ̂́A�d�lj�����q�ǂ������������Ƃ��B�O�o�̓ǔ��V���̋L���ł��u20�Ζ����̎��҂͊m�F����Ă��Ȃ����A�s���ł�7���A10�Ζ����̏���2�l���d�ǂƂȂ������Ƃ��m�F���ꂽ�v�ƕĂ��邵�A8��14���A�A�����J�ł͏����̃R���i���҂̓��@��1902�l�ɑ����A�A�����J�ɂ�����R���i���@��2.4%���߂����Ƃ��傫����ꂽ�B�A�����J�̏����Ȋw��ʼn�߂��T���[�E�S�U���́A�u�ډ��̃R���i�����͍�N�Ƃ͕ʕ��v�ƃR�����g���Ă���B
�u�ʕ��v�ł��闝�R�́A�����̎�̂��f���^�������炾�B�f���^���͊����͂������A�����ɂ���������B���ꂪ�A���E�Ŏq�ǂ��̊������g�債�Ă��闝�R���B�q�ǂ����m�ł���������B8��25���̖����V���̋L���ɂ��ƁA8��19�����݁A�S����165�̕ۈ牀�Ȃǂ̎{�݂��Վ��x���ƂȂ��Ă���A1�J���O��4�{���B
�����̊������Ԃɂ��Ă��A�������i��ł���B8��16���A�J�i�_�̌��O�q�����ǂ��A�����J�́w��t������ȔŁx�ɔ��\���������ɂ��ƁA�����̊������m�F����6280���т̂����A1717����(27.3%)��2���������m�F���ꂽ�B���͂ɂ����₷���̂�0�`3�Ύ��ŁA14�`17�Ɣ�r�����ꍇ�̊����g�僊�X�N��1.43�{�������B�Ȃ��A���̔N��̊����҂��A���͂ɂ����₷���̂��͌����_�ł͂킩��Ȃ��B
�����Ȃ�ƁA9���ɐV�w�����n�܂�A�w�Z�Ŋ������g�傷��͔̂�����ꂻ���ɂȂ��B
�A�����J�E�e�l�V�[�B�i�b�V���r���ł́A�w�Z���ĊJ���ꂽ�ŏ���2�T�ԂŁA602�l�̐��k��119�l�̐E���̊������������Ă��邵�A�@����w�싅���ł�33�l�̏W�c�������m�F����Ă���B
�Վ��x�Z���A�I�����C���Ŏ��Ƃ��s���ׂ����낤���B���͎^���ł��Ȃ��B����֗^����e�����傫�����炾�B�����g���h�����߁A�����[�g�Ŏ��Ƃ��s���AiPad��p�\�R���Ȃǂ��w���ł���T���ȉƒ�̎q�ǂ��ƁA���̂悤�ȋ@��������ł��Ȃ��o�ϓI�ɍ��������ƒ�̎q�ǂ��ł́A�傫�Ȋi���������Ă��܂��B����i���́A�����i���⌒�N�i�����A�Љ�̊i�����Œ肵�Ă��܂��B�q�ǂ������ɂ́A�Ζʂɂ�鋳��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�������E�u���ƃ��N�`���ڎ킪�K�v
�ǂ���������̂��B��{�ɗ����Ԃ邵���Ȃ��B�����E�u���ƃ��N�`�����B
�����ɂł���̂͌����̊g�[���B���{�́A��������ő��80���̍R�������L�b�g�����猻��ɔz�z������j��\�����Ă��邪�A����ł͕s�\�����B���ʂ̃E�C���X�ł������ł���PCR�����ƈقȂ�A�R���������z���ɂȂ�ɂ͈��ʂ̃E�C���X�����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���N1���A�A�����J���a��Z���^�[(CDC)�́A���M�Ȃǂ̏Ǐ���l�̏ꍇ�A�R��������PCR�����z���҂�80%�ŗz���ƂȂ邪�A���Ǐ��҂̏ꍇ�ɂ�41%�܂Œቺ���Ă����ƕ��Ă��邵�A6���ɂ́A�A�����J�E�v���t�b�g�{�[�����[�O(NFL)�ɏ��������t�������A��N8���`11���܂łɎ��{������63����̌������ʂ��܂Ƃ߁A�R�������͊��������𒆐S�Ƃ���42���̗z���҂������Ƃ��Ă����ƃA�����J�́w���Ȋw��x�ɔ��\���Ă���B
�R�������́A���̏�Ō������ʂ��킩�邽�߁A�N���j�b�N�Ȃǂł̐v���f�f�ɗL�p���B�����A�w�Z�ł̃X�N���[�j���O�ȂǁA���ԓI�ȗP�\���������ŁAPCR����������A�R�������𗘗p���鍇���I�ȗ��R�͂Ȃ��B
�ł́A�Ȃ��A���{���{�͍R�������ɂ������̂��낤���B���͌��J�Ȃ̓s����D�悵�����߂��ƍl���Ă���B�R���i���s�ȍ~�A���J�Ȃ�PCR������}�����A�R�������̎g�p�𐄏��������Ă����B�ی����̕��S�����炵�������J�ȂɂƂ��āA�ی����̎��ς킹���A���̍̎挻��Ō����ł���R�������͍D�s�����B
�ߘa2(2020)�N�x�̑�2����\�Z�ł́A�R�������̊m�ۂ̂���179���~���[�u����Ă���A��ʂ̍ɂ�����Ă���B���Ƃ����Ďg����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B1��22���ɂ́A�u���Ǐ�҂ɑ���R���ȈՃL�b�g�̎g�p�v�𐄏�����ʒm�܂ŏo���Ă���B���x�ACDC���A���Ǐ��҂ɑ���R�������̌��E�������_���\���������ɐ����̒ʒm���o���Ă������ƂɂȂ�B�Ɉ�|���ړI�ƌ����Ă��d���Ȃ��B�c�O�Ȃ���A���g�R���i�����ȉ��Ȃǂ̐��Ƃ�����A���̂悤�Ȑ��͕������Ă��Ȃ��B
�����ƕ��ԏd�v�ȑ��N�`���ڎ킾�B�f���^�g�ɑ��ẮA���N�`����ł��Ă������͊��S�ɂ͗\�h�ł��Ȃ��B���̂��Ƃ𐢊E���v���m�����̂́A7�����{�ɁA�A�����J�ŊJ�Â��ꂽ�Ɨ��L�O���̃C�x���g��469�l�̏W�c���������������Ƃ����B���L���ׂ��́A346�l���ڎ���ς܂��Ă��āA�ނ炪�r�o����E�C���X�ʂ��A�ڎ�҂Ƒ卷�Ȃ��������Ƃ��B���N�`����ł��Ă��A�f���^���ɂ͊������邵�A���͂ɂ������Ă��܂��B�W�c�Ɖu�헪�͌�������邱�ƂɂȂ����B
�����A���N�`���̈Ӗ����Ȃ��Ȃ������ƌ����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���N�`����łĂA�d�lj��͗\�h�ł��邩�炾�B�C�X���G���̕ɂ��ƁA60�Έȏ�̖��ڎ�҂̏d�Ǘ��10���l������85.6�l�����A�ڎ튮���҂�16.3�l�ƁA81%�������Ă���B����́A���{�̈�t�̊��o�Ƃ���v����B
�A�����J�̐��{�n�@�ւ▯�Ԋ�ƂȂǂŃ��N�`���ڎ�̋`�������i��ł���̂́A�W�c�Ɖu�̂��߂ł͂Ȃ��B�l����邽�߂��B�J�i�_�A�M���{���ڎ���`�����������A�M���V���ł͖��ڎ�҂̏A�J�𐧌���������Œ������i��ł���B
���A�����J�A�C�X���G���Ȃǂ�12�Έȏ�փ��N�`���ڎ�
�q�ǂ�����O�ł͂Ȃ��BCDC�́A5��12����12�`15�ɑ��āA���N�`���ڎ���������A6��21���A�C�X���G�����{������ɕ�����B���̑O���ɁA���{�ł͕��ȏȂ��A�ڎ�ւ̓������͂�����āA�w�Z�ł̏W�c�ڎ�𐄏����Ȃ��Ɣ��\�����̂Ƃ͑ΏƓI���B���f�̊�����N�`���̌��ʂ���S���łȂ��̂����{�炵���B���̌�A�x����Ȃ���A8��16���ɂ̓h�C�c��12�`17�̑S���Ƀ��N�`���ڎ�𐄏������B
�������A�q�ǂ��ւ̐ڎ�ɂ͌��O������B����͈��S�����B����������q�ǂ������ւ̐ڎ�͐T�d�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���݁A�ǂ̒��x�܂Ń��X�N���킩���Ă���̂��낤���B���_���炢���ƁA���Ȃ���S�����A���X�N�͔ے�ł��Ȃ��B
�Տ���w�ł́A���i�̈��S���E�L�����͗Տ������Ō�����B���N�`������O�ł͂Ȃ��B�t�@�C�U�[���̃R���i���N�`���̏ꍇ�A12�`15�̏�����ΏۂƂ����Տ������̌��ʂ��A5��27���ɃA�����J�́w�j���[�C���O�����h��w��(NEJM)�x�ŕ���Ă���B�wNEJM�x�͐��E�ō���̈�w�����B
���̗Տ������ł́A����2260�l�����N�`���Q�ƃv���Z�{�Q�Ƀ����_���Ɋ���t�����A���ʂ���ш��S�����]������Ă���B���Ȃ݂ɓ��^�ʂ͐��l�Ɠ���30��g(�}�C�N���O����)���B���B�r���12�`15�ɁA���l�Ɠ��ʂ̃��N�`����łĂΉߗʂɂȂ邩������Ȃ��Ƃ������O���������B
���̎����ł́A2��ڐڎ���38�x�ȏ�̔��M��20���A���ӊ���66���ŔF�߂�ꂽ���A�����18�`65��ΏۂƂ����s�����ł�17���A75���Ɠ����x���������B���O���ꂽ�������͖��ƂȂ�Ȃ������B
����A���ʂɊւ��ẮA�v���Z�{�Q�ł�16�l���R���i�Ɋ��������̂ɁA���N�`���ڎ�Q�ł͒N���������Ȃ������B�L������100���Ƃ������ƂɂȂ�B���̗Տ������̓f���^�����s�ȑO�̂��̂ł���A�L�����̕]���͒��ӂ��K�v�����A���S���Ɋւ��Ă͗L�]�Ȍ��ʂ��B
�t�@�C�U�[�ƕ��у��N�`���J�������[�h���郂�f���i�̕����l���B�ނ炪5��25���ɔ��\�����Տ������ɂ́A12�`18�̖�3700�l���o�^���ꂽ���A2��ڎ��̃R���i�\�h���ʂ�100���ŁA���������傫�Ȗ��Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B
���̂悤�ȗՏ������̌��ʂ��āA5��10���A�A�����J�H�i���i��(FDA)�́A12�`15�ɑ���t�@�C�U�[���̃��N�`���ً̋}�g�p����F�߂Ă��邵�A6��10���ɂ̓��f���i��FDA�ɋً}�g�p����\�������B
�A�����J�́A����N��w�ւ̐ڎ���i�߂Ă���B�t�@�C�U�[�ƃ��f���i�͎������g�債�Ă���A5�`11�ł��i�s�����B������A�~��̗��s���܂łɂً͋}�g�p���������B
�����O�͐S�؉��E�S����
�����̂��Ƃ��A�A�����J�ł͏����ւ̐ڎ��ϋɓI�ɐ��i���Ă���B�ł́A�����_�ŁA�������ƂȂ��Ă���̂��낤���B���E�̐��Ƃ̊S���W�߂Ă���̂͐S�؉��E�S�������B�S�؉��E�S�����́A�E�C���X�����ɔ������ȖƉu������A�R���i�ȊO�̃��N�`���ڎ��ɂ����ǂ��邱�Ƃ��m���Ă���Ɖu�����ǂ��B�����͖��Ǐ�A���邢�͌y�ǂŁA���ǂȂ��������邪�A�܂�ɏd�lj����邱�Ƃ�����B
6��10���ACDC�́A30�Έȉ��Ńt�@�C�U�[���邢�̓��f���i����mRNA���N�`����ڎ킵���l�̂����A475�l���S�؉��E�S�����Ɛf�f���ꂽ�Ɣ��\�����B�قƂ�ǂ͌��ǂȂ����Ă������A15�l�͌������\�̎��_�œ��@���A3�l�͏W�����Î��ɓ����Ă����B
���L���ׂ��́A�唼����N�҂�2��ڐڎ��ɋN�����Ă������Ƃ��B���̂��Ƃɂ��ẮA�C�X���G����������l�̌������ʂ�����Ă���B
�����炭�A�������N�`���ڎ�ł̍ő�̖��́A���̐S�؉��E�S�������낤�B�����A����ɂ��Ă��������i�݁A�ڎ�𐄏����邱�Ƃ��R���Z���T�X�ɂȂ肻�����B���̍����́A8��25���ɃC�X���G���̌����҂��A�w�j���[�C���O�����h��w���x�ɔ��\�����������B
���̌����ɂ��A�R���i���N�`����ڎ킷�邱�ƂŁA�S�؉��E�S�����̃��X�N��3.24�{�㏸���邪�A�R���i�ɜ늳�����ꍇ�A���̃��X�N��18.3�{��������B�f���^���̗��s���l����A�ǂ���̂ق������X�N���Ⴂ���͋c�_�̗]�n�͂Ȃ��B
�ł́A�q�ǂ������ւ̃��N�`���ڎ�́A�ǂ���������̂��B�ڎ��]�҂�ی�҂Ƒ��k���A�ʂɔ��f���邵���Ȃ����A���{�⎩���̂́A���k��ی�҂��ڎ킵�₷���悤�Ȋ�����邱�Ƃ��B
���{�ł��ꕔ�̎����̂́A�����ւ̐ڎ�𐄐i���Ă���B�M�҂��ڎ������`�����Ă��镟�������n�s�ł́A6��19�����獂�Z���A7��27�����璆�w����ΏۂƂ����W�c�ڎ킪�n�܂�A�ċx�ݒ��ɐڎ���I����B
���ȏȂ��S�O����T��A�Ȃ��A���n�s�ł͎q�ǂ������ɏW�c�ڎ�ł���̂��B����́A���n�s�Ő��l�ɑ���W�c�ڎ킪�i��ł��邩�炾�B6��1������͊�b�����̂Ȃ�64�Έȉ��̎s���ɑ���ڎ킪�n�܂�A7��17���ɂ͏W�c�ڎ���I�����B16�Έȏ�̊�]�҂�93.5���ɐڎ킵���B
���A���`���N�`���^���ɂǂ��Ή����邩
�q�ǂ������Ƀ��N�`���ڎ�𑣐i����ɂ́A�Љ��ѕی�҂̃��N�`���ɑ��鐳�m�ȗ������������Ȃ��B�R���i���N�`���ڎ��i�߂鐢�E�e���ŁA�傫�ȏ�Q�ƂȂ��Ă���̂̓A���`���N�`���^�����B
�l�b�g��ɂ́A�u���N�`����łƕs�D�ɂȂ�v��u��`�q��������������v�Ƃ������f�}�����ӂ�Ă���B��t����Ƃ̒��ɂ��A�ߓx�ɃR���i���N�`���̊댯�������`����l������B���̂悤�ȕΌ������咣���A�����̐l�X��s���ɂ����A���N�`���ڎ���S�O������B�q�ǂ������ւ̐ڎ�ł́A���ɖ��ɂȂ�₷���B�A���`���N�`����́A���E����������O�q���̏d��Ȗ�肾�B
���́A����Ȃ��Ƃɂ܂Ő��E�ł͎��،������i��ł���B5��25���A�A�����J�́w��t�(JAMA)�x�́u�M���ƃ��N�`���ڎ�A�A�����J�ɂ�����10��14������3��29���̌o���v�Ƃ����_�����f�ڂ����B
�_���̌��_�́A���ɐ^�����Ȃ��̂������B���҂����́A�A�����J�ł͓��ǂ����N�`����K�Ȏ葱�����o�ď��F���A��ʐڎ���l�X�Ɛi�߂邱�ƂŁA�Љ�̃��N�`���ւ̐M�����������ꂽ�ƌ��_���Ă���B�����ɐڎ��i�߂邱�Ƃ��A�A���`���N�`���h�̐��͂����傷�鎞�ԓI�]�T��^���Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B
�܂��ɑ��n�s������Ă������ƂƓ������B���n�s�ł������s���̒��ɂ́u���N�`����ł��Ă悩�����B�q�ǂ������ɂ����߂����v�Ƃ����ی�҂����Ȃ��Ȃ��B
�q�ǂ������ւ̃R���i���N�`���ڎ�ɂ��ẮA�����ȍl���������邾�낤�B�����A�𑍍��I�ɍl����A���̓��N�`���ڎ�����߂����B���X�N�ȏ�Ƀ����b�g���傫�����炾�B�����N��1�N�Ԃ͑傫���B���N�`����ڎ킵�A����ۊO�����ɋ���ł��炢�����B
���q�ǂ��͐V�^�R���i���N�`����ڎ킵�������ǂ��H�@�����b�g�ƃf�����b�g�@8/29
�V�w�����n�܂邱�ƂŊw�Z���ł̐V�^�R���i�g�傪���O����Ă��܂��B���݁A���{�����ł�12�Έȏ�ł�����N�`���ڎ�͉\�ł����A���w���⍂�Z���̓��N�`���ڎ킵�������ǂ��̂ł��傤���H
�������͐��l�Ɣ�ׂďd�lj����ɂ���
�q�ǂ��͑�l�Ɣ�ׂďd�lj����ɂ������Ƃ��������Ă��܂��B�����J���Ȃ̔��\�����ɂ��Ύq�ǂ��̏d�lj����X�N�́A30�����Ƃ���ƁA10�Ζ����͏d�lj����X�N��0.5�{�A10���0.2�{�Ƃ���܂��B�������A���l�Ɣ�ׂĖ��炩�ɏd�lj��͂��ɂ������̂́A�d�lj����Ȃ��킯�ł͂���܂���B���{�����ł�20�Ζ����̐V�^�R���i�����҂ŖS���Ȃ������͂��܂��A��芴���҂̋K�͂��傫���A�����J�ł�0〜17�̐V�^�R���i����122����̂���178��(0.014%)���S���Ȃ��Ă��܂��B�܂��A�E�얞�E��`�������E�_�o��Q�E��`����ӏ�Q�E����Ԍ����ǁE��V���S�����E���A�a�E�����t���a�E�����x�����E������ᇂ�Ɖu�}����ɂ��Ɖu�}����ԂȂǂ̎��a�̂���q�ǂ��ł͏d�lj����X�N�������Ƃ���Ă���A���ɒ��ӂ��K�v�ł��B
������a�̂Ȃ��q�ǂ��ł����Ă��������Ȃ��ɉz�������Ƃ͂���܂���B��������Δ��ǂ���Œ�10���͎���×{���K�v�ɂȂ�܂����A��l�����p�x�͒Ⴂ���̂̎q�ǂ��ł����ǂɔY�܂���邱�Ƃ͂���܂��B�܂��H�ł͂���܂����A���w�Z���w�N〜���Z�����炢�̔N��ł͐V�^�R���i���������ɐ��a�̕a�ԂɎ������n�����ǐ��nj�Q(MIS-C)�Ƃ����d�ǂ̕a�Ԃ������邱�Ƃ�����܂��B
���q�ǂ������N�`���ڎ������Ӌ`�͎���ɍL���ɂ����Ȃ邱��
���̂悤�ɁA�q�ǂ����g�ɂƂ��Ă̓��N�`���ڎ킷��Ӌ`�͑�l�Ɣ�ׂđ��ΓI�ɒႢ�ƌ����܂��B�ł͑��Ɏq�ǂ����ڎ킷��Ӌ`�ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����̂ł��傤���B�ő�̈Ӌ`�́A����Ɋ������L���ɂ����Ȃ邱�Ƃł��傤�B�����AmRNA���N�`���́u���ǂ�h���v�̂ł����Ċ������̂��̂�h�����ǂ����͕������Ă��Ȃ��A�ƌ����Ă��܂������A������h�����ʂ��������Ă��܂����B�������ɂ����Ȃ�Ƃ������Ƃ́A�ڎ�҂����̎���̐l�Ɋ������L����\�����Ⴍ�Ȃ�܂��B
������₷�����߉Ƃ̗�ōl���Ă݂܂��傤�B���ɂ͒��w���̖���2�l���܂����A���Ɏ��a������킯�ł��Ȃ��̂ŁA���������Ƃ��Ă��w�Z���x�ޕK�v�͂���܂����A�d�lj�����\���͂��Ȃ�Ⴂ�ł��B2�l�̖����ڎ킷�郁���b�g�́A�j���ō������̎��a�������얞�ł�����(�ŋ߂�����Ƃ₹�܂���)�����������ďd�lj�����̂�h���Ƃ����Ӌ`������킯�ł��B���a�̂Ȃ��q�ǂ��ɂƂ��ẮA�ڎ킷�鎩�g���������I�ȈӋ`���傫���Ƃ������Ƃ��q�ǂ��ɂ��������Ă��������Őڎ���������Ȃ���Ȃ�܂���B�܂������R���i�Ɋ������Ď��疺����������킯�ł�����A���������Ӗ��ł͉�����Ď��g�̂��߂ƌ����Ȃ����Ȃ���������܂���B���ۂ̃��N�`���ڎ�̌��ʂƕ������ɂ��ẮA12����15�ւ̐V�^�R���i���N�`���ڎ�̑�3�������ł́A���N�`���̔��Ǘ\�h���ʂ͔��ɍ�������ŁA���l�Ɠ����x�ɂ��邳�┭�M�Ȃǂ̕��������݂�ꂽ�ƕ���Ă��܂��B����ɁA���N�`���ڎ��̐S�؉���S����������Ă��܂����A10��E20��̓��ɒj���ŕp�x������(100���l������41�l)���Ƃ��������Ă��܂��B
���q�ǂ��̃��N�`���ڎ�́A����̑�l���ڎ킵�Ă��邱�Ƃ��O��
�Ƃ����킯�ŁA�q�ǂ����V�^�R���i���N�`���̐ڎ����������ꍇ�A���̎���̑�l�����N�`���ڎ���������Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ�܂��B�C�O�ł��f���^�����L�����Ĉȍ~�Ɋw�Z�̋������ł̃N���X�^�[���Ⴊ����Ă��܂����A���̎���͂Ƃ��ǂ��}�X�N���O���Ă������t�����[�ƂȂ��āA���k12�l�Ɋ������L�������Ƃ������̂ł��B�f���^�����L����q�ǂ����������₷���Ȃ����ƌ����ǁA�����u�q�ǂ����q�ǂ��v�u�q�ǂ�����l�v�ւ̊��������u��l���q�ǂ��v�ւ̊����̕����N����₷�����Ƃ͕ς�肠��܂���B�w�Z�̍ĊJ�ɓ������Ă̊������X�N���l�������ꍇ�A�q�ǂ������܂��͐�Ɋw�Z�E���Ȃǎq�ǂ��ɐڂ����l�̃��N�`���ڎ��D�悷�ׂ��ł��傤�B���̏�ŁA�ڎ킷�郁���b�g�ƃf�����b�g���q�ǂ����g�Ƃ��̐e���\������������Őڎ����������悤�ɂ��܂��傤�B
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������s�̃��N�`����K�͐ڎ�A�{��10������Ώێ҂���҂Ɋg�� 8/30
�����s��8��30��10������A�s���s���V�^�R���i���N�`���̑�K�͐ڎ�ɂ�����ڎ�Ώێ҂��g�傷��Ɣ��\�����B����������C���^�[�l�b�g�ŗ\��̎�t���J�n����B
����܂ł͐E��Őڎ�Ώێ҂��i���Ă������A�s���ݏZ�E�E�݊w��16����39�܂ł�Ώۂɂ���B���͓s����W�]�����N�`���ڎ�Z���^�[�A�s���k�W�]�����N�`���ڎ�Z���^�[�A�T�؍�N�`���ڎ����3�J���B���f���i�А��̃��N�`������舵���B
�s��8��27�����瓌���E�a�J�Ŏ��(16����39�܂�)�����Ƀ��N�`���ڎ�Z���^�[���J�݂������A1���̐ڎ�\�K�͂�300�l(�撅)���������Ƃ�����A�������瑽���̐l�����э������������ԂƂȂ����B28�������9���`10��30���̊Ԃɒ��I����z�z����d�g�݂ɕύX�B11��30������ɒ��I���ʂ�LINE��Twitter�Œm�点��悤�ɂ����B
�������A�d�g�݂�ύX���Ă��a�J�ɂ͍s�ł��A���ʓI�ɐl���𑝂₵�Ă���B����ɂ��Ă͍���A�s�̑�K�͐ڎ���̑Ώێ҂��g�債�����ƂŎ��Ԃ͊ɘa����邩������Ȃ��B�����A����A�ق��̎����̂Ȃǂŗ\��s�v�̃��N�`���ڎ�����{����ꍇ�͒��ӂ���K�v�����邾�낤�B
�������s�A��Ґڎ�Ńh�^�o�^�@�Ǝ��헪�őz��̊Â��I��\�@8/30
�V�^�R���i�E�C���X���҈Ђ�U�邤���A�����҂��S���ő��̓����s�ł́A�V�K�����̔������x��20�`30�オ��߂Ă���B�s�́A��N�w�ւ̃��N�`���ڎ�������J�M������Ƃ��āA��Ҍ����ɗ\��s�v�̉����J�݂������A�z�������l���E�����A����͍����B������̋����s���������A�ڎ푣�i�̑������ƂȂ��Ă���B
�s��7�����{�����C���^�[�l�b�g�����ɂ��ƁA���N�`���ڎ���u��]����v�Ɠ������l�́A60�`64��9���ȏ�ɒB�����̂ɑ��A20�`30��ł�8���O�ゾ�����B
�u�������}�g�債�Ă����Ґ���ɁA�����������N�`����Z��������v�B���r�S���q�m����8��18���̓s�c��ŁA�V���ɗ\��s�v�̎�Ґ�p�ڎ�����a�J��ɐݒu������j��錾�B�C�y�ɐڎ�ł�����݂��邱�ƂŁA��҂ɏd�������グ������_�����������B
�Ƃ��낪�A������27���ɂ͑������璷�ւ̗ł��A�ߑO11��50���Ɏt�����J�n����\�肪�A��7�����ɂ͎t����ł��鎖�ԂɁB�s�͋}����A2���ڂ��璊�I���ɐ�ւ������A����Œ��I����z��������������߁A28���ɂ͂܂���������ƂȂ�A�{����6�{�����B�ҏ��̒��A�����ɗ��I�����l�̊Ԃ���́u�s�̂����͂��������v�Ƃ̐������o�����B
�s��8���A�s����3��w�ƘA�g���A�w�������ڎ�������X�ƊJ�݁B�S�Ẳ��ŗ\��g��9�����{�܂Ŗ��܂��Ă���Ƃ����B
�s�͂���ɁA�������10�����{����A�ڎ킵��20�`30������ɃN�[�|����t�^����L�����y�[�������{����v��𗧂ĂĂ��邪�A������̋����ʂ͕K�v�ʂ������������B�S���҂́u�����ł���ʂȂǏ����āA�J�n������x�点��\��������v�ƌ��t������B
����A�s���ł́A�������V�h�悪��҂̐ڎ�\��J�n�����𑁂߂�Ǝ��̍H�v���Â炵���B�����ł́A7�����߂�60�`64�ɑ����A����6������12�`39�̗\����t���A40�`50���14������Ƃ����B
�����A����Ƃ��u�ǂ̔N��ł��ݒ肵���\��g���A��]�҂̕������|�I�ɑ����A������̋������ǂ��t���Ă��Ȃ��v�ƒQ���B������̒S���҂́u��N�w�̐ڎ튩������荹������Ă��邪�A���N�`�����Ȃ���o�q���ł��Ȃ��B����������v�����v�Ɩ��������B
���V�^�R���i�����Ŕ��\�̊����ҏ�� 30�� �N���X�^�[�������@8/30
30���ɓ����Ŕ��\���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂Ɋւ�������܂Ƃ߂܂����B
������̕a�@�ŃN���X�^�[
����s�͎s���́u������X�R�������A���a�@�v�ŐV�^�R���i�E�C���X�̃N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B�a�@�ɂ��܂��ƁA����������n�r���e�[�V�����a���̓��@����5�l�Ɨ��w�Ö@�m3�l�A�Ō�t2�l�̍��킹��10�l�̊���������܂łɊm�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�S�����y�ǁA�܂��͖��ǏƂ������Ƃł����A���̂���6�l�͂��łɃ��N�`���ڎ��2��ς܂��Ă����Ƃ������Ƃł��B�a�@�͊���������ȏ�L�����Ă��Ȃ����Ƃ��m�F�ł���܂œ��ʁA�O���f�Â�ʉ�Ȃǂ��x�~����Ƃ��Ă��܂��B
���D�y �V����2�N���X�^�[
�D�y�s�͎s���ŐV����2�̃N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B�s��410��ڂ̃N���X�^�[�����������R�[���Z���^�[�ł́A����܂ł�30�ォ��50��̏]�ƈ�9�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�s�͔Z���ڐG�����\��������ق��̏]�ƈ�121�l�ɑ��A�����o�b�q������i�߂Ă��܂��B�s��411��ڂ̃N���X�^�[�����������R�[���Z���^�[�ł́A����܂ł�20�ォ��50��̏]�ƈ�7�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�s�͔Z���ڐG�����\��������ق��̏]�ƈ�50�l�ɑ��A�����o�b�q������i�߂Ă��܂��B������̃N���X�^�[�ɂ��Ă��A�s�͔Z���ڐG�����\��������l��c���ł��Ă���Ƃ��Ď{�݂�X�̖��O�����\���Ă��܂���B
���� �V����3�N���X�^�[����
���͓����ŐV����3�̃N���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B�����n���̐V�Ђ������̈��H�X�ł͍���27���ɗ��p�q1�l�̊������������A�]�ƈ��Ɨ��p�q�ɂo�b�q�������s�����Ƃ���A�ŏ���1�l���܂ނ������20��̗��p�q5�l�Ə]�ƈ�1�l�̍��킹��6�l�̊������m�F����܂����B�Ǐ�͌y�ǂ����ǏƂ������Ƃł��B�эL�s�̈��H�X�ł͍���16���ɏ]�ƈ�1�l�̊������������A�ق��̏]�ƈ��ɂo�b�q�������s�����Ƃ���A�ŏ���1�l���܂�10�ォ��30��̏]�ƈ����킹��5�l�̊������m�F����܂����B�Ǐ�͂�������y�ǂ��Ƃ������Ƃł��B�эL�s�̑эL���t���Z�ł͍���19���ɐ��k1�l�̊������������A�ق��̐��k�⋳�E���ɂo�b�q�������s�����Ƃ���A�ŏ���1�l���܂ސ��k���킹��6�l�̊������m�F����܂����B�Ǐ�͂�������y�ǂ��Ƃ������Ƃł��B
�������2�N���X�^�[�g��
����s��30���A�s���Ŕ������Ă���2�̃N���X�^�[�ŐV���Ȋ����҂��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B���̂����s��45��ڂ̃N���X�^�[���������Ă��鈮���w�̉^�����ł͐V���Ɋw��2�l�̊������m�F����A����ł��̃N���X�^�[�Ɋ֘A���銴���҂͊w��12�l�ƂȂ�܂����B48��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���ڑ҂����H�X�ł��V����1�l�̊������m�F����A���̃N���X�^�[�Ɋ֘A���銴���҂͏]�ƈ��Ȃ�8�l�ƂȂ�܂����B����A����s��30���A�V���Ɏs���ɏZ��47�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B��������y�ǁA�܂��͖��ǏƂ������Ƃł��B�܂��A���̂���1�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���D�y �R�[���Z���^�[�̃N���X�^�[�g��
�D�y�s�ł͎s��399��ڂ̃N���X�^�[���������Ă���R�[���Z���^�[�ŐV���ɏ]�ƈ�1�l�̊������m�F����A�֘A���銴���҂͏]�ƈ����킹��30�l�ƂȂ�܂����B
���D�y �W�c�ڎ���ʼn^�c����4�l����
�D�y�s�͏W�c�ڎ���̉^�c�ɏ]������ϑ����Ǝ҂̐E��4�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B4�l�̂���2�l�́u�D�y�R���x���V�����Z���^�[�v�ʼn^�c�ɏ]�����邢�����30��̒j���ŁA�ق���2�l�́u�ǁ[�ށv�ʼn^�c�ɏ]�����邢������N��Ɛ��ʂ�����\�̐E���ƊŌ�t�ł��B�D�y�s�ɂ��܂��ƁA������̐E�������Ǔ��ȍ~�͋Ζ��ɂ������Ă��炸�A�Ɩ����̓}�X�N��t�F�C�X�V�[���h�Ȃǂ𒅗p����������s���Ă������ƂȂǂ���A�s�͂���܂ł̂Ƃ���A����K�ꂽ�s���ŔZ���ڐG�҂͂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̏��ō�Ƃ����炽�߂čs������ŁA������̉����ʏ�ʂ�^�c���Ă���Ƃ������Ƃł��B
���C���h�^(�f���^��)�̏�
�ψكE�C���X�̃f���^���ɂ��ĐV���ɁA�D�y�s��187�l�A����85�l�̂��킹��272�l���������Ă���^�������邱�Ƃ�������܂����B����s�ł͎s���Ŋ������m�F����Ă���E�C���X�������ނ˃f���^���ɒu��������Ă���Ɣ��f���Ă���̂ɉ����A�����Ԑ����Ђ������Ă��邽�ߌ��݁A�f���^���Ɋւ��錟���͍s���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���X�X�L�m���H�X�֘A�ŐV����1�l
�D�y�s�ɂ��܂��ƁA�ɉ؊X�E�X�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�Ɋ֘A���銴���҂��V����1�l�m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B����ŁA�X�X�L�m�̐ڑ҂����H�X�Ɋ֘A���銴���҂�351�X�܂�1364�l�ƂȂ�܂����B
���V�^�R���i�@�V����20�l�̊������\�@���w���`���Z���Ŋg��@�R�`�@8/30
20�Ζ����̎q�ǂ�����ւ̊g�傪�ڗ����Ă���B�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��āA�R�`�����ł�30���A�V���ɎR�`�s��4�l�A���͍]�s�A�����s�A�͖k���A�đ�s�A��z�s�A��c�s��2�l�Ȃǂ��킹��20�l�̊��������\���ꂽ�B
���̂����N���X�^�[�֘A�́A�V���s�́u�o�e�b�z�X�s�^���v��1�l�A�͖k���́u���ی㎙���N���u�v��2�l�A��c�s�́u���w�Z�v��1�l�A�đ�s�́u�㗢�w�����Z�v��4�l�B30���ɔ��\���ꂽ20�l�̂���������10�l���u���w�����獂�Z���v�B
(28���̌��)�u(�N���X�^�[������)��c�s�̒��w�Z�v
(29���̌��)�u�đ�s�̋㗢�w�����Z�v
�R�`�����ł�28����29���ɐV����4���́u�N���X�^�[�v�����\����A���̂���2���͒��E�����́u�������v�B������u��5�g�v�ł́A�挎���{����m�F���ꂽ21���̃N���X�^�[�̂����A8�����u��������X�|�[�c�v�Ɋւ����̂ŁA�ċx�݂����������܁A���߂Ďq�ǂ������̊�������Ă���B
�R�`�����̊����҂͍���������1000�l��30�����_�Łu1003�l�v�ƂȂ�A�v�ł�3144�l�A���@���͏d�ǂ�5�l���܂�122�l�B�a����L���͌��S�̂Łu51�D5���v�Ɛ��{�̎w�W�ōł��[���ȁu�X�e�[�W4�v�̐������Ă���B�h���E�ݑ�×{�͂��킹��268�l�ŁA���@��������24�l�B
�����������A�R�`�����ł̃��N�`���̑�K�͐ڎ�ɒlj����ꂽ60�l�́u�D�w�g�v�̗\��̎t����30���ߑO9���Ɏn�܂�10��50���ɂ��ׂĖ��܂����B�D�w�g�̒lj��͐�t���Ŏ���×{���̔D�w�����Y���Ԃ���S���Ȃ������Ƃ��Ă̑Ή��B�R�`���̑��A�����s��V���s�Ȃǂ��D�w�ɐڎ팔��D�悵�đ����Ă��āu�����������N�`����ڎ킵�āA���S���ďo�Y���v�Ƃ̓������L�����Ă���B
�����ی㎙���N���u�ŏ��w���̊����g��A�������싅���͏o������ށ@�R�`���@8/30
�R�`���ƎR�`�s��29���A���w������60�Α�܂ł̒j��30�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�đ�s�哌���̋㗢�w�����Z�ł́A�N���X�^�[(�����W�c)�����������B�v�����҂�3124�l�ŁA���@���҂�121�l�A�d�ǂ�5�l�B
�V���Ȋ����҂̓���́A�߉��s��6�l�A�đ�s�ƐV���s���e5�l�A��c�s��4�l�A�R�`�A�V���A�͖k��3�s���Ŋe2�l�A���͍]�A��z�A�����A�����4�s���Ŋe1�l�B��������9�l�������A��������Ǐ�͂Ȃ����A�d���Ȃ��B
�㗢�w�����ł́A�싅���̒j�q���k��6�l���������A�H�G���Z�싅�����n��\�I�ւ̏o������ނ����B9��3���܂ŋx�Z����B
�N���X�^�[�֘A�ł́A�͖k���̕��ی㎙���N���u�𗘗p���鏬�w���j��2�l�̊������������A�v9�l�Ɋg��B�V���s���c�̐��_�ȕa�@�u�o�e�b�@�g�n�r�o�h�s�`�k�v�ł��A���@����3�l���������A�v��10�l�B��c�s���̒��w�Z�ł́A����܂ł̊����҂Ɠ��������ɏ�������j�q���k3�l���������A�v��12�l�ƂȂ����B
���ɂ��ƁA�C���h�R���̕ψكE�C���X�u�f���^���v�̋^��������ψكE�C���X�u�k452�q�v�́A�V����5�l���猟�o����A�v��351�l�ƂȂ����B
���������̎���×{�ҁA�ő�506�l�@�N���X�^�[�g��A70�l�����@8/30
����29���A�����ŐV����70�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B28���ɗz�����������A�����̊����m�F�͉���8604�l�ƂȂ����B����×{�҂�500�l���A�ߋ��ő���506�l�ƂȂ����B
70�l�̓���͌S�R�s16�l�A���킫�s15�l�A�����s10�l�A��Îᏼ�s8�l�A�{�{�s�ƒ��c�㒬�e5�l�A���͎s3�l�A�ɒB�s�Ƒ�ʑ��e2�l�A�֒A��Í≺���A�������A������e1�l�B20�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B
�N���X�^�[(�����ҏW�c)�W�ł́A����141���ڂ̌S�R�s�̎��Ə���2�l���̌v7�l�Ɋg��B���̂ق��A137���ڂ̒��c�㒬���̎��Ə���6�l���̌v16�l�A135���ڂ̌��k�n���̎��Ə���2�l���̌v9�l�A131���ڂ̉�Îᏼ�s�̃V�F�A�n�E�X��1�l���̌v13�l�A138���ڂ̌���n���̎��Ə���1�l���̌v8�l�ɂ��ꂼ��g�債���B
28�����݂̓��@�Ґ��͏d��16�l���܂�347�l�ŁA�a���g�p����54�D5���ƈˑR�Ƃ��ăX�e�[�W4(�����I�Ȋ����g��)�̐����ɂ���B106�l���h���×{���Ă���A88�l���×{������B����1�T��(22�`28��)�̐l��10���l������̐V�K�z���Ґ���33�D91�l�A�×{�Ґ���56�D72�l�œ��l�ɃX�e�[�W4�̏ƂȂ��Ă���B
28���܂ł�28�l���މ@�A22�l���h���×{�{�݂�ޏ����A17�l�̎���×{���������ꂽ�B
���Ђ����Ȃ��̎��Ə��ŃN���X�^�\�@���P��̑�w�T�b�J�[���ł��@���@8/30
��錧�Ɛ��ˎs��30���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ҍv227�l�̂����A2�l�͂Ђ����Ȃ��s���̎��Ə��̏]�ƈ��ŁA28���܂łɌ��\���ꂽ10�l�������A���Ə����̊����҂͏]�ƈ��v12�l�ɍL�������B���͐V���ȃN���X�^�[�����������Ƃ݂Ă���B
�����������������s���̎��Ə��ł́A�V����1�l�̊������������A29���܂łɌ��\���ꂽ10�l�𑫂��ƁA���Ə����̊����҂͏]�ƈ��v11�l�Ɋg�債���B
�Ⓦ�s���̎��Ə��ł͐V����2�l�̊�����������A29���܂łɌ��\���ꂽ5�l�����킹��ƁA���Ə����̊����҂͏]�ƈ��v7�l�ɑ������B
���P��s���̑�w�T�b�J�[���ł͐V���Ɋw��12�l�̊��������炩�ɂȂ�A�����̊����҂͊w���v25�l�ɑ��������B
�����N�`���u�\��ł��Ȃ��v�F�s�{�ł͔D�w�ɗD��ڎ�@8/30
�����s�ł�30���A�V����1915�l�̐V�^�R���i�����҂��m�F����܂����B8���A���ŁA�O�̏T�̓����j����������Ă��܂��B�d�ǎ҂�287�l�ŁA29�����9�l����܂����B�����g���}���邽�߁A�e�n�Ń��N�`���ڎ킪�i�߂��Ă��܂��B�����E�a�J�̑�K�͐ڎ���́A���I����z������ɕς��܂����B���j���͋x�݂ł����A���ɗ����l�����܂����B
�ڎ���ɗ����l�u(�d����)�s��x�ŁA���������^�C�~���O�ł��������Ȃ��B���傤�͋x�݂��ƒm��Ȃ������v
�ڎ���ɗ����l�u����ς�s�ւ��Ǝv���܂��ˁB�������������Ȃ��̂ŁA�l�b�g�Œ��I���Ă������������A���ʂȐl�����h����Ǝv���̂ł������Ǝv���v
�����s�ł́A30������V���ɁA�s����T�؍�̉��ŁA16�`39�܂ł̓s���ݏZ�҂�w���Ȃǂ��A�ڎ�̑Ώۂɉ����܂����B�\��̓C���^�[�l�b�g�Ŏt���Ă��܂��B
�ڎ���ɗ����l�u�w��ύ��ݍ����Ă܂��x�ƂȂ��Ă܂��B�\��̓��͂ł��Ȃ����ł��B�F�A���N�`�����ł������Ȃ��ŁA���������͑������P���Ăق����B���ꂾ��(������)�L�����Ă���̂ŁA�ł��Ă���̂������ȂƂ���v
3�̉��ŁA��҂��܂߁A����̗\��g��4100�l�B�g����̂́A���f���i���̃��N�`���ł��B�Ȗ،��F�s�{�s�ł�30������A�s��13�J���̎Y�w�l�ȂŁA�D�w����ւ̗D��ڎ킪�n�܂�܂����B������́A�t�@�C�U�[���̃��N�`���ł��B
�w�A���e�~�X�F�s�{�N���j�b�N�x�ؓ��֕v�@���u(���N�`����)�ł��Ƃ��Q�͂Ȃ����A�ł��������������Ƃ������₪�A�����̂悤�Ɋ��Ă���v
���߂ďo�Y����D�w�u�Ƒ��͐ڎ킵�Ă��܂����A�������D�w�Ƃ������ƂŐڎ킪�ł��Ă��Ȃ������̂ŁA�łĂ�Ȃ�ł������Ə������B�o�Y�O��2��ڂ����傤�Ǒł��I���^�C�~���O�ŁA����͂��Бł������Ǝv���A���肢���܂����v
���{�ł́A�������Ǝ{�݂̏W�c�ڎ���ŁA����40�Έȏ��ΏۂɁA�A�X�g���[�l�J���̃��N�`���ڎ킪�n�܂�܂����B�s���ł�2�J���ڂł��B�A�X�g���[�l�J���̃��N�`���́A����2�Ɣ�ׂėL�������Ⴍ�A�����܂�Ɍ������ł��郊�X�N������Ƃ̎w�E������܂��B
�ڎ���ɗ����l�u����2��(�L������)90�����炢�ŁA�{���͂��������ǂ��������A�łĂ邩�łĂȂ���������Ȃ��B�\������Ȃ��̂ŁA�ň�����ł������ȂƎv���Ă��傤�����v
�ڎ���ɗ����l�u�s���͂��邪�A���̎��ɂȂ�Ȃ��ƕ�����Ȃ����A����őł��Ȃ��I�����͂Ȃ������̂ŁA�o������߂đł��ɗ����v
���Â̌���ł��A�V���ȓ���������܂����B��Ɍy�ǎҌ����ɍs����w�R�̃J�N�e���Ö@�x�́A����܂œ��@�ȂǂőΉ����Ă��܂������A���a��w�a�@�́A�O���f�Âōs�����Ƃ����߂܂����B
���a��w�a�@�E���ǔ��T�@���u������II�E�d�ǂ̊��҂����炷���ƂɊ�^���邾�낤�ƁB(�_�H��A�������)2���Ԃ��炢�Ŏ���ɋA�邱�Ƃ��ł����ł́v
�d�lj��h�~�̐�D�Ƃ������܂����A��]�҂Ȃ�N�ł��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�ی��������f�������҂��ΏۂƂȂ�܂��B�����31������n�܂�A����A���10�l���x��ڎw�������Ƃ��Ă��܂��B
���V���� �Ǝ��́g���ʌx��h�S���Ɋg��ց@8/30
�V�������̐V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ґ���8��24���܂ł�1�T�Ԃʼnߋ��ő���798�l�ɏ��ȂǁA�����̊g�傪�����Ă��܂��B
���̏��A�Ԋp�m����30���ߑO�A�����V�^�R���i���S�����ɁA��i�����[�u�ƂȂ�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̓K�p�ɂ��ēd�b�ő��k���܂����B
�������A�����̊����Ȃǂ͍�����߂��ɖ������Ă��Ȃ����Ƃ���A�K�p�͌�����ɁB
���̂��߁A���͐V���s�E�����s�E����J�s�ɏo����Ă�����ʌx���S���Ɋg�債�A9��3��������H�X��ΏۂɎ��Z�c�Ƃ�v��������j���ł߂܂����B
����ɔ����A���łɎ��Z�v�����o����Ă���3�̎s�͊��Ԃ���������܂��B
����30���ߌォ����{����c���J���A�����Ɍ��肷��\��ł��B
�����ʌx��S���Ɋg��A���������x�~�@�V�����@8/30
�V������30���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�����Ă��邱�Ƃ��A���Ǝ��̌x�����x���̂����ł��������u���ʌx��v�������S��Ɋg�債�Ĕ��߂����B�S�s������ΏۂƂ���̂͏��߂āB���S��̎�ނ������H�X�Ȃǂ�9��3�`16����14���ԁA�����ߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v������B�܂����Ԓ��A�����{�݂������x�ق���B������ψ���́A���Z�Ȃnj����w�Z107�Z�ɑ��A���Ԓ��̕��������x�~����悤���߂�B
30���Ɍ����ŊJ���ꂽ�V�^�E�C���X�̑��{����c�Ō��肵���B�Ԋp�p���m���͉�c��̋L�҉�Łu��Âւ̕��ׂ����肬��̏��ɗ��Ă��āA�ʏ��Â����Ȃ�������Ȃ������܂�Ă��Ă���B�������������ė}�����ނƂ����p���������K�v������v�Ƌ��������B
�����̊����Ґ���24�`28����5���A����1��100�l���A�m�ەa���̎g�p����29�����_�ŁA�X�e�[�W4(�����I�����g��A50���ȏ�)�ڑO��49�E9���ɒB���Ă���B��Ñ̐��̕N��(�Ђ��ς�)���[���Ȃ��Ƃ���A���S�̂ւ̋����[�u���K�v�Ɣ��f�����B
����ŁA�ً}���Ԑ錾�ɏ������[�u���\�ƂȂ�u�܂h�~���d�_�[�u�v�ɂ��ẮA���Ƒ��k�������ʁA���̓s���{���Ɣ�ׂĊ����g��̃X�s�[�h���}�����Ă���ȂǂƂ��āA�����_�ł̐\�������������B�@���ʌx��̑S���g����A���ɓ��ʌx���߂���A���Z�v�����̐V���A�����A����J��3�s�ł́A���̗v�����Ԃ�16���܂ʼn��������B�c�Ǝ��Ԃ͑S���Ōߌ�8���܂ł̒Z�k�����߂��邪�A���̊������F�ؐ��x��\�������X�܂͌ߌ�9���܂ł�1���ԉ����ł���B���͒Z�k�ɉ������X�܂ɑ��A���㍂�Ȃǂɉ�����1��������2��5��`20���~�̋��͋����x������B
�����w�Z�̕������x�~���j��30���A����c��ʂ��Ďs�������ɂ����ꂽ�B�����w�Z�Ȃǎs�������w�Z�ł̑Ή��́A�e�s�������ς����㔻�f����B
�����ς̈�בP�V���璷�͉�c��̉�ŁA�������x�~�̗��R�ɂ��āu8���ɓ��莙�����k�̊��������������B������}�����݁A�x�Z��������邽�߂̑[�u���v�Ɛ��������B
�����{�݂̋x�قɂ��ẮA��������A�W�҂Ƌ��c���đΏێ{�݂����߂�B�s�����ɂ����l�̑Ή�����������悤���߂�B
30���̑��{����c�͖`���������Ĕ���J�ōs��ꂽ�B����30�s�����̎���I�����C���ŏo�Ȃ����B
���V����53�l�����m�F ��ЂŊ����g�呱�� �V�^�R���i�E�C���X�@8/30
�V�������ł�30���A�V����53�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F����܂����B�V���s�͉�Ђł̊����g�傪�����Ă���Ƃ��Ē��ӂ��Ăъ|���Ă��܂��B
�V���Ɋ������m�F�ꂽ53�l�̂����V���s��16�l�ŁA�����6�l�A�����5�l�Ȃǂł��B���̑��̎s������37�l�ŁA�����s��13�l�A�V���c�s��6�l�A��z�s��5�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B1���̊����m�F��50�l��ƂȂ�̂�8��16���ȗ��A2�T�ԂԂ�ł��B
53�l�̂������O�Ƃ̉������������̂�5�l�ŁA�����o�H���������Ă��Ȃ��̂�15�l�ł��B�܂��A�قƂ�ǂ̐l���y�ǂ܂��͖��Ǐ�ł����A�V���s�ɂ��܂���1�l�������ǂ��Ƃ������Ƃł��B
�V���s�ł͘A���̂悤��50�l�O��̊������m�F����Ă��܂������A30����16�l�Ƃ����Ɂc�B
�V���s�ی��Ǘ��ہ@�c�Ӕ��ے��u�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�ɋ��͂��������Ă��邱�ƁA�s������͊����g��h�~�Ƃ������Ƃł��낢��ȋ��͂̕\�ꂾ�Ǝv���B���ꂩ�猸���Ă������͂����A�������Ă̏𒍎����Ȃ���v
����ŁA�V���s�͉�Ђł̊����g�傪�����Ă���Ƃ��Ē��ӂ��Ăъ|���܂����B8���ɓ���A29�̉�Ђł��킹��210�l�̊������m�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
�܂����ɂ��܂��ƁA����܂ŕ����̊����҂��m�F����Ă��钷���s�̊w�Z�ŁA�V����4�l�̊������m�F����܂����B���͕������̒��Ŋ������L�������Ƃ݂Ă��āA���̊w�Z�֘A�ł͍��킹��22�l�̊����m�F�ƂȂ�܂����B
���ΐ쌧���N���X�^�[100���Ɂ@��X�N�ł����������@�u�s���������g��v�@8/30
�ΐ쌧��29���A����s�̔F�肱�ǂ����u��쒬���ǂ����v�ŐV�^�R���i�E�C���X�̃N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F�����Ɣ��\���A�����̔F��͍�N4������v100���ƂȂ����B7������́u��5�g�v�ł́A�a�@�⍂��Ҏ{�݂ł̔��������Ȃ�����A�E���w�Z�W���}�����Ă���B���Ƃ́u�f���^���̎s���������L�܂�A��r�I��X�N�ȏ�ʂł��������������v�Ǝw�E���A2�w���̎n�܂�9���ȍ~�̊����g��Ɍ��O�������B
100���̓���́A���H�X�ƐE�ꂪ�e23���ōł������A�����{��13���A��H12���A�a�@10���ȂǂƑ����B���s�̑�3�g(��N12���`���N2��)�ł́A���l���ɔ�����H�����s�В��̈��H�X�Ȃǂ𒆐S�Ɋg��B��4�g(4�`6��)�ł́A�����ő�̃N���X�^�[�ƂȂ����q�ΐ�(�֓��s)�̂ق��A�a�@�╟���{�݂ł̔��������������B
��5�g�́A7���Ɉ��H�X��w�Z�W���������A8���ɓ����ĐE�ꂪ�}�����Ă���B����A�a�@�ł̔����͂Ȃ��A����Ҏ{�݂�1���ɂƂǂ܂�B���N�`���ڎ킪�i���Ƃ��e�����Ă���Ƃ݂���B
�����A�������ǐ��Ɖ�c�����̒J���]���G��=���啍���a�@���a�@��=�́u�E���w�Z�́A��H�Ⓑ���ԑ؍݂���a�@�A�����{�݂Ɣ�ׂă��X�N���Ⴂ�B�Ȃ̂ɂ��ꂾ���N���X�^�[�������Ă���̂́A�s�����������Ȃ�L�܂��Ă��錻�ꂾ�v�Ǝw�E����B
��쒬���ǂ���35�l�Ɋ����g��@29���Ɍ��\���ꂽ��쒬���ǂ����ł́A������ۈ�m�A�����҂�35�l�̊��������������B�����̃N���X�^�[������17���ŁA���ʂ̍ő����X�V�����B�����ʼn���������N�������̖k���������́u�f���^���̏o���Łw�q�ǂ��͂�����ɂ����x�Ƃ����������̏���ω����Ă���v�Əq�ׁA�����Ɋ�����̓O����Ăъ|�����B
�x�R53���A����49���@�k���O���ł̃N���X�^�[�F��́A�x�R����53���A���䌧��49���ŁA�ΐ쌧���ˏo���Ă���B
���R���i�����g��Ō����Ԃ̎��ꒆ�~�≄���������@���䌧�@8/30
�V�^�R���i�E�C���X�����g��̉e���ŁA���䌧���Ō����Ԃ̎��ꒆ�~�≄�����������ł���B�O�o�T��������A������7���̍̌����т͌v����187�l��(1�l����200�~�����b�g�����Z)���Ȃ������B�}���ł͂Ȃ���p�̐摗��⌧�O�Ƃ̒����ɂ��A�A���Ȃǂɉe�����o��ɂׂ͊��Ă��Ȃ����̂́A8���������X���������B���ԏ\�����t�Z���^�[�́u�ǂ�Ȏ��ł����ʂ̌��t�͕K�v�B���Ћ��͂��Ăق����v�ƌĂъ|���Ă���B
�A���p�̌��t�́A���C�k����ߋE�ȂǑS����7�u���b�N�ɕ����ĔN�Ԃ̎��v�������݁A�����Ƃ̍̌��̌v�����тɊ�Â��ďT�P�ʂŒ������Ă���B7���͕��䌧����3350�l���̍̌����v�悵�Ă������A3163�l���ɂƂǂ܂����B
��N�Ȃ�8���㔼�͍��Z�̊w�Z�Ղɍ��킹�Č����Ԃ�z�u���邪�A�V�^�R���i�̉e���Œ��~�≄�����������ł���B�������X�N���l�����Ċ�Ƃ̏W�c���������~�ɂȂ�A8�����v��������͔������Ȃ��Ƃ����B�Վ��Ō�����V���b�s���O�Z���^�[�Ɉ˗����A�����Ԃ�z�u���Ă���B21�A22���ɂ͕���s�̃x���ōs�����B
���ԏ\�����t�Z���^�[�������i�ۂ̖q�c���ے��́u�e�u���b�N�Œ������Ă��邪�A�S���I�ɗ]�T�͂Ȃ��������B�ł������̊����\�h�����Ă���̂ň��S���Č������Ăق����v�Ƙb���Ă���B���Z���^�[�ł͋��j�������Č������t���Ă���B
�����J���Ȃ�7�����{�A�V�^�R���i�����҂́A�ǏȂ��Ȃ���4�T�Ԃ��ĂΌ����ł���ƌ��߁A8�����{�ɑS���̎����̂ɒʒm�����B�{�s��9��8������B�t�@�C�U�[�A���f���i���̃��N�`���ڎ�҂͕��������l�����A�ڎ��48���Ԃ��ĂΌ����ł���B
���V�^�R���i�̏h���×{�{�݂��s�ɊJ�݁A140�����m�ہ@���@8/30
����30���A�V�^�R���i�E�C���X�̌y�ǎ҂△�Ǐ�҂������h���×{�{�݂Ƃ��āA�s�̃z�e�����[�g�C���������9��1���ɐݒu����Ɣ��\�����B140�����m�ۂ��A�����̏h���×{�{�݂�8�{�݂�1271���ƂȂ�B
�����̏h���×{�{�݂͌��݁A����ł͉H���s�̃z�e���R�[���[�{��(285��)�ƕʊ�(185��)�A�A�p�z�e���H���w�O(146��)�A�z�e�����[�g�C���H���w�O(184��)�A���Z�ł͑�_�s�̃z�e�����[�g�C����_�C���^�[(140��)�A���Z�ł͑������s�̃g���^�����Ԍ��C�p�h���{��(135��)�A��˂ł͍��R�s�̍��R�ό��z�e��(56��)��7�{�݂�����B
����̑����ŁA�����̕a���Əh���×{�{�݂͌v2054��(�a��783���A�h���×{�{��1271��)�ƂȂ�B�����̏h���×{�{�݂ɂ�29�����_��658�l���������Ă���B
���^�A�Ǝ��Ə��ŃN���X�^�[�A������Ò��Ԓn�ł͊g��@���ꌧ�@8/30
���ꌧ��30���A�V����10�Ζ����`80��̒j��113�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B1�l�������ǁB�����̊����m�F�͌v1��453�l�ƂȂ����B
����29���ɃN���X�^�[(�����ҏW�c)�Ɣ��\�����s���@�ւ́A���㎩�q����Ò��Ԓn(��Îs)���������Ƃ����������B30���ɂ͐V���ɑ���3�l�̊������������A�v13�l�ɂȂ����B
���ߍ]�s�̉^�A�Ǝ��Ə��œ����܂łɏ]�ƈ�43�l�̊������m�F����A���͐V���ȃN���X�^�[�ƔF�肵���B�N���X�^�[�֘A�ł́A��Îs�̕ۈ�֘A�{�݂Ŏq�ǂ�1�l�������Čv30�l�ɁA�F���s�̐����Ǝ��Ə��ŏ]�ƈ�2�l�������Čv25�l�ɂȂ����B
�V�K�����҂͋��Z�n�ʂł͑�Îs39�l�A���Îs12�l�A�b��s11�l�A�I���s10�l�ȂǁB����×{�Ґ��͑O�����144�l������1546�l�ɂȂ����B
�܂��A���Îs��30���A����2�l�̊��������������}�D������31���`9��4���̊ԁA�w�Z���ɂ���Ɣ��\�����B2�l�͓����w���ۈ珊�ɒʂ��A���w�N�ɂ������g��̌��O�����邽�߂Ƃ����B
�����̃N���X�^�[�͋��L�X�y�[�X�Ŋg�傩�c �O�d�ŐV�K������181�l�@8/30
�O�d���ł�30���A�V����181�l�ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������킩��܂����B8��16���ȗ��A14���Ԃ��200�l�������܂����B
�������킩�����̂́A�l���s�s��K���s�ȂǂɏZ��10�Ζ�������90��܂ł�181�l�ł��B
����͎l���s�s79�l�A�K���s19�l�A�Îs17�l�A�鎭�s17�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B181�l�̔����߂�83�l���A���̂Ƃ��늴���o�H������ł��Ă��܂���B
�l���s�s��40�ォ��70��܂ł̒j��8�l�́A�s���̓��������{�݂̓����҂ŁA�ʂ̓����҂Ɋ������킩�������߁A�������ėz�����������܂����B
���̎{�݂ł̊����҂�9�l�ɂȂ�A�s�͎c��̓����҂�\���l�̌�����i�߂Ă��܂��B���́u����N���X�^�[�ɂȂ�\��������v�Ƃ��Ă��܂��B
28���܂łɊ��������\����Ă���20�ォ��30��܂ł̒j��13�l�́A�Îs�̓��������Ƃ̗��ɏZ�ޏ]�ƈ��ŁA���͗��̐����Ȃǂ̋��L�X�y�[�X�Ŋ������L�������Ƃ݂āA106��ڂ̃N���X�^�[�Ƃ��܂����B
30���͓��@���Ă���80���60��̒j��3�l���A29���ɖS���Ȃ������Ƃ����\����܂����B
60��̒j���́A�f���^�����܂ޕψي������ŗz�����m�F����Ă��āA�d�ǂɂȂ��Ă��܂����B
30�����_�ł̕a���g�p���́A�O������7�D7�|�C���g������58�D7���ɂȂ�܂������A����×{���܂ޓ��@�������̊��҂�86�l������4231�l�ɂȂ��Ă��܂��B
1��������̐V�K�����Ґ��́A8��16���ȗ�14���Ԃ��200�l�������܂������A��ؒm���͉�Łu�s�[�N���牺�����Ă����F���ł��Ȃ��A�܂��܂������x���𑱂��Ă����K�v������v�Ƙb���܂����B
�����E�V�^�R���i1605�l�����@�q�ǂ��̊����g��c�@���s�@8/30
���{��30���A�V����1605�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\���܂����B���j���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ƂȂ�܂��B�N��ʂōł������̂�20���375�l�A������30���280�l�A10���260�l�ł��B
�S���Ȃ����l��2�l�A�d�ǎ҂̊��҂͐V���Ɋ�b�����̂Ȃ�30��j��3�l���܂ތv218�l�ŁA�d�Ǖa���g�p����37.1���A����×{�҂�17188�l�ƂȂ��Ă��܂��B�܂����A�w��110�l�A�A�w��76�l�̊������m�F����Ă��܂��B
�w�Z���ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������L�����Ă��邱�Ƃ��A���s��30���A�w�Z�̋x�Z�ɂ��Ċ���������܂����B���s�ł�30���̎��_�ŏ��w�Z��24�Z�A���w�Z16�Z���x�Z�[�u���Ƃ��Ă��܂��B
���s�̐V���ȋx�Z�̊�ł́A�����N���X�Ő��k�̊����҂�2�l�ȏ�ƂȂ����ꍇ�⊴���҂�1�l�ł��Z���ڐG�҂������l�m�F���ꂽ�ꍇ�ɂ́A5�`7�����x�w����������Ƃ������Ƃł��B�܂��A2�ȏ�̃N���X���w�����ƂȂ����ꍇ��1�w�N�S�̂���A�������w�N�������ɓn��ꍇ�́A�w�Z�S�̂��x�Z�ɂ���Ƃ������Ƃł��B���̊��9��1������K�p����܂��B
���L�����ŐV����5���̃N���X�^�[�@�L���s�ƕ��R�s�̕ۈ�{�݂ʼn����Ɋ����@8/30
�L��������30���A256�l�̐V�^�R���i�E�C���X���������\���ꂽ�B29��(284�l)�ɑ�����2���A����200�l��B1�T�ԑO��23��(275�l)�Ɣ�ׂ�6�E9���������B
�L���s�́A�����̈�Ë@�ւɓ��@���Ă�������1�l�����S�����Ɩ��炩�ɂ����B�����ɓ����Č����Ŏ��҂����\���ꂽ�̂́A7���̌��s��1�l�ȗ���2�l�ځB�����̎��҂̗v��181�l�ƂȂ����B
���S�̂̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��́A�l��10���l������79�E9�l�ƂȂ����B���{���ȉ���������ŁA�ł��[���ȁu�X�e�[�W4�v(�����I�����g��)�̎w�W25�l��傫�����������Ă���B
30�����\�̊����҂̋��Z�n�ʂ́A�L���s144�l�A���R�s60�l�A�����s18�l�A���s14�l�A���L���s7�l�A�����s�s3�l�A�{�����A�k�L�����e2�l�A�O���s�A��|�s�A���|���c�s�A�]�c���s�A�F�쒬�A�����s�e1�l�B������1�l�A�y��208�l�A���Ǐ�47�l�Ƃ����B
�L���s��144�l�̔N��ʂ́A20��37�l�A30��27�l�A10��23�l�A40��22�l�A50��13�l�A10�Ζ���11�l�A60���70�オ�e4�l�A80��2�l�A90��ȏ�1�l�B10��1�l�������ǁB122�l���y�ǁA21�l�����Ǐ�Ƃ����B52�l�̊����o�H������ł��Ă��Ȃ��B
�s���̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͐l��10���l������97�E0�l�ŁA�X�e�[�W4�̎w�W25�l��22���A���ŏ������B
���s��14�l�̔N��ʂ͉�����1�l�A���w����4�l�̂ق��A10��A40��A50�オ�e1�l�A20��A30��A60�オ�e2�l�B�������w��2�l�Ɖ����A30��A50��A60��e1�l�̌v6�l�����Ǐ�ŁA�ق���8�l�͌y�ǂƂ����B29���ɐ��k1�l�̊��������\���ꂽ�L�������ł́A�V���ɐ��k3�l�̊��������炩�ɂȂ����B
���R�s��60�l�̔N��ʂ�10�Ζ�����19�l�ōł������A3����1�߂����߂��B�ق���10��8�l�A20��5�l�A30��9�l�A40��6�l�A50��9�l�A60��2�l�A70��1�l�A80��1�l�B����43�l���y�ǂŁA17�l�����Ǐ����B�s���̂��ǂ����ł͉���1�l�̊����������������߁A9��3���܂ŗՎ��x���Ƃ����B
���̂ق���7�s3���Ɠ����s�ݏZ�̌v38�l�͌������\�����B�N��ʂ́A10�Ζ���9�l�A10��3�l�A20��11�l�A30��3�l�A40��4�l�A50��4�l�A60��3�l�A70��1�l�������B�y�ǂ�35�l�A���Ǐ�3�l�B5�l�̊����o�H���������Ă��Ȃ��Ƃ����B
����Ƃ͕ʂɁA���͐E��2�l�̊��������\�����B
1�l�͕��R�s�ݏZ�̌����N�����ǂ�50��ŁA�{���ɋΖ��B�x�ɂ�����25���Ɉ����ɂƂ����̏Ǐo�����A�M�͂Ȃ���������26���ɏo�����B���̓��̌ߌ�ɔ��M������A��ʼn�M�����B27���ɋx�ɂ����APCR�����������B�M�͉������Ă�������28���͏o���A�[���ɗz�������������B������̑̒��s�ǎ҂͂��Ȃ��Ƃ����B
����1�l�͍L���s�ݏZ�̌��n�搭��ǂ�30��B27���ɐڐG�҂̗z����������A�ޒ��B28����PCR�������A29���ɗz�������������Ƃ����B
����2�l�͂��ꂼ��A���R�s�A�L���s��30���Ɍ��\���������҂Ɋ܂܂��B
�N���X�^�[(�����ҏW�c)�̊֘A�ł́A�����ŐV����5�����F�肳�ꂽ�B����́A�L���s����3���A���R�s����1���A���L���s����1���ƂȂ�B
�L���s����3���́A���Ə�2���Ɩ��ԕۈ�{��1���B���Ə��ł́A�ԓ��ł̒��H���⎖�Ə����Ń}�X�N�𒅂����ɉ�b����Ȃǂ���10���20��̏]�ƈ��v6�l�����������B�ʂ̎��Ə��ł̓}�X�N���O���ċΖ�����Ȃǂ���20�`50��̏]�ƈ��v7�l�̊��������������B���ԕۈ�{�݂ł͉���6�l�Ɋ������L�������B
���R�s��1����24���ɉ���1�l���������A�x�����Ă����_�ӕۈ珊�B���̌�ɉ���6�l���z���ƂȂ�A�����҂��v7�l�ƂȂ����B����ȏ�̊����g��͂Ȃ��Ƃ��A30���ɍĊJ�����B
���L���s��1���͌����F�肵����������_�ƍ��̉^�����B�����ςɂ��ƁA�����̐��k18�l��40��̕��S�����E��1�l�̌v19�l�����������B���Z�n�ʂ͓��L���s14�l�A�L���s�ƌ��s�e2�l�A�����s1�l�B��������L���s�A���s�A����30���܂łɔ��\���������Ґ��Ɋ܂܂�Ă���B
24���ɐ��k1�l�̊��������������B������ڐG�����������k119�l�Ƌ��E��12�l�̌v131�l��PCR�������A28���܂ł�19�l���z���ƂȂ����B�c��112�l�͉A���������Ƃ��Ă���B���Z��25������9��3���܂ŗՎ��x�Z���Ă���B
���������s�@�V�^�R���i���N�`���W�c�ڎ���@��t���Ԃ��g��@8/30
�������s�̉��ߎs���́A30������12�Έȏ�̐V�^�R���i���N�`���̐ڎ�\�n�܂������Ƃ��A9���ȍ~�A�W�c�ڎ���ł̎�t���Ԃ��g�傷��ȂǁA��N�w���ڎ킵�₷�����𐮂�����j�������܂����B
�����30���̉�ʼn��ߎs�������炩�ɂ������̂ł��B
�������s�ł́A�V�^�R���i�����҂��o���ƒ�̖�8���ʼnƒ���������������Ă���Ƃ��āA���ߎs���́A�s�v�s�}�̊O�o���T���邱�Ƃ�A��̎�A���܂߂Ȋ��C�Ȃljƒ��������h�����߂Ɋ�{�I�Ȋ����Ǒ��O�ꂷ��悤���߂ČĂт����܂����B
���N�`���ڎ�ɂ��ẮA30������12�Έȏ�̎s���̗\�\�ɂȂ������Ƃ����N�w���ڎ킵�₷�����𐮂���Ƃ��܂����B
��̓I�ɂ́A�������s���ݒu�����W�c�ڎ���ł́A�\�Ԃ�9�����{�ȍ~�A���݂��1���Ԋg�債�Čߌ�8���܂łƂ��A��Ë@�ւɂ͎��ԊO��x���̗\��g�̊m�ۂ��˗�����Ƃ��Ă��܂��B
�܂�9����{����A�������s�̃z�[���y�[�W�Ǝs�̌����k�h�m�d�ł̃��N�`���ڎ��]�҂̃L�����Z���҂��o�^�V�X�e�����^�p���鏀����i�߂Ă���Ƃ������Ƃł��B
���I���p���_�@�A�o���A�t���[�i�W�@�R���i�Ŏ������\�@8/30
�l���⎋�o�Ȃǂɏ�Q��������I�肪����𑱂��铌���p�������s�b�N�B���v���肩��8�N�������A�����̌�����ʋ@�ւ�h���{�݂̃o���A�t���[���ɂ͐i�W�������邪�A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ő������u��v�ɂȂ������̂�����B���Ƃ�͊֘A�@�̕s�\�����Ə�Q�ւ̗����̑��i���ۑ�ɋ�����B
�u�I���p�����Ȃ���ΑS���Ⴄ���������v�B��Q�Ғc�́u�c�o�h���{��c�v�����ǒ��ŁA9����Ԃ����𗘗p���鍲��������(54)�̓n�[�h�ʂ̐i�W�������]������B
�o���A�t���[�@�͏��v������2018�N��20�N�A2�x�ɂ킽���ĉ�������A�S���w�͋K�͂ɉ����A�����̃o���A�t���[�o�H�̐����ƃG���x�[�^�[�̑�^�����`���t����ꂽ�B������炵���z�[���ɂ��ǂ蒅���Ȃ������i�q�V�h�w(�����s�V�h��)�œ����A��������̃��[�g���m�ۂ��ꂽ�̂��u�ے��I�������v�Ƃ����B
�����_�@�Ɋ����P�����������Ƃ����A�u������������ꂪ�����Ăق����v�Ɗ肤�B
�z�e���◷�قȂǂ̏h���{�݁B�Ԃ����Ή��q���̐ݒu�����������A�ƊE�c�̂ɂ��ƁA�C���o�E���h���v���������Ă���19�N���܂ł͊e�{�݂��ϋɓI�Ƀo���A�t���[����i�߂��B�������A�R���i�E�C���X�̂܂Ŏ��v���������ނƁA���g�݂͎����B���̐���������̊g��h�~�ɏd�S���ڂ�A�u�D�揇�ʂ��ς���Č�ɂ�����Ȃ��Ȃ����v(�ƊE�c�̊W��)�Ƃ����B
�o���A�t���[�ɏڂ������m��̐�����F�q���������́A���Ǝ{�ݓ��ɂ�����H�X�Ȃǂɂ��āA�u������܂ł̌o�H�̓o���A�t���[�ł��A���ɂ͒i��������v�Ǝw�E�B���K�͓X�����̐������`���t�����K��͂Ȃ��A�u�ړ��ł��錠���͐l�����v�ƁA����Ȃ�@�����̕K�v����i����B
�c�o�h���{��c�̍�������́u�i�W�͂�����̂́A�X�̐l���Ԃ����ړ����������ʂ͂���قǑ����Ă��Ȃ���ۂ��B�ړ���i�������Ă��邱�Ƃ��L���������Ăق����v�Ƙb���Ă���B
���R���i����́u�|�Y�v�V�펯�A��Ȃ���Ђ��������g����h�����ρI�@8/30
���R���i�ЂƘA�x���R�ɗ��K���ہ@���S���̂���1�J���Ŕj�Y�葱���J�n
�u�S�[���f���E�B�[�N�y�ѐV�^�R���i�E�C���X�����NJg��h�~�̂��߁A5��12���܂ʼnc�Ǝ��l�ƂȂ�܂��v�\�\�B
4�����{�A�_�ސ쌧���͌��s�̌��z�H���ƁA�����n���̃z�[���y�[�W�ɂ���Ȉꕶ���f�ڂ��ꂽ(���݂̓z�[���y�[�W���폜)�B
���Ђ�4��17���ɓ����s�����q�s�Ŕ��������A�A�p�[�g�K�i�������S���̂̎{�H��Ђ��B���ǁA5��13���ɂȂ��Ă��c�Ƃ͍ĊJ���ꂸ�A���̓��Ɏ��Ȕj�Y��\���B���l�n�ق�19���t�Ŕj�Y�葱���J�n�����肵���B
�u��^�A�x���ɉ�Ђ���ނ��Ƃ͐̂��炠��W���N�X���B�����āA�R���i�Ђ𗝗R�ɑ�O�҂̗��K�����ۂ��Ă���B�������Ȃƌx�����Ă�����A�j�Y�\�������v�ƒ鍑�f�[�^�o���N���l�x�X��̓����C�����͐U��Ԃ�B
�����n����2000�N�n�ƁB�鍑�f�[�^�o���N�ɂ��A�ؑ��A�p�[�g�̌��z�P���ɂ����ē��Ƒ��Ђ���20���ȏ�����A1��������250���~�Ƃ����ቿ�i��Ɏ��Ƃ��g��B17�N4�����̔��㍂�͖�20.5���~�ɒB�����B
�������A�L���i�̍�ƐӔC�҂�u�����ɍ�Ƃ������Ƃ��đ��͌��J����ē��ɘJ�����S�q���@�ᔽ�ŏ��ޑ��������ȂǕs�ˎ������o�B20�N4�����̔��㍂�͖�9.8���~��3�N�Ŕ������A�H������̎x�����x�����ԉ��B�����̊ԂŐM�p���ь����u�|�Y�x�������v�ɂȂ��Ă����B
���y��ʏȂɂ��A�����n������|����166���̏W���Z��̂����A���Ȃ��Ƃ�57���ŊK�i�̗��m�F���ꂽ�B�������A���Ђ��j�Y�������߁A�A�p�[�g�̃I�[�i�[����C��p�𐿋����Ă��x�����邩�ǂ����͕s�������B
���S���̂����1�J���Ŕj�Y�\�����������n���ɂ��āA�ԉH��Í��y��ʑ��́A�u�{���Ȃ�Ύ{�H�ɂ��ẴI�[�i�[�ւ̐�����A��C�Ή�������K�v�����钆�A�ӔC���ʂ������Ɏ��Ȕj�Y�\�����邱�Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƕs�����������ɂ����B
�����n�����{�H�����A�p�[�g�̃I�[�i�[�̂悤�ɁA�����̓|�Y�Ɋ������܂��ƁA��Ƃ͎�ɂ��_���[�W��H����Ă��܂��B
����悪�M�p�ɒl�����Ƃ��ǂ��������������Ƃ́A���Ђ̎��������E����K�{�X�L�����B
�������A��Ƃ̓|�Y���X�N�ׂ悤�ɂ��A�ǂ�����ă`�F�b�N����������������낤�B�����āA�R���i�ЂŊ�Ƃ̎��Ԃ������ɂ����Ȃ��Ă���ƁA�M�p������Ђ̒S���҂͌������낦��B
�g��Ȃ��h��Ђ��������v�������ɁA�ŐV�̐M�p�����̃`�F�b�N�|�C���g��`�����Ă�������B
���{�ƈ����ł������A�ߏ�����}���c�@���ς����g��Ȃ��h��Ƃ̃`�F�b�N�|�C���g
��ڂ́A�u�������v�v��Ƃ̋}�����B�������H���T�[�`����3.9���Ђ�21�N3�����̌��Z�͂����Ƃ���A����(���{��1���~�ȏ�)�A������Ƌ��ɖ�7���̊�Ƃ����㍂��O���������Ƃ��u�����v�ɂȂ����B����ŁA���v���O��������u���v�v��Ƃ̊����́A���Ƃ��O������9.1�|�C���g�オ��53.9���A������Ƃ���5.0�|�C���g����49.5���ƁA�������v�̌X�������܂��Ă���B
�R���i�x���̕⏕���⋋�t���Ȃǂɉ����A�s���Y�Ȃǎ��Y���p�ɒ��肵�ē��ʗ��v���v�サ�����Ƃ�A���۔��o����Ȃǂ̃R�X�g�팸���i���߂��B
���Z����ł͍������g�債�Ă��Ă��A�{�Ƃ�����������Ƃ͑����Ă���B�����̍ŏI���v�ɂƂ��ꂸ�A�ǂ�����ė��v���m�ۂ��Ă��邩���`�F�b�N����ׂ����B
��ڂ́A�u���a���̑����v�ɖڂ�D���Ȃ����Ƃ��B�����̎茳�̌��a��������������Ƃ����āA�x�����\�͂͑��v���ƈ��S���邱�Ƃ͑��v���B
�Ƃ����̂��A�����q�E���S�ۗZ��(�[���[���Z��)�Ȃǂ̎����J��x���[���������ƂŁA�����}�����ĉߏ���ɂȂ�����Ƃ������Ă��邩�炾�B
�������T�[�`��8���ɒ�����Ɩ�8000�Ђ�ΏۂɎ��{���������ɂ��A�u�ߏ���v�Ɖ�����Ƃ�35.7���B����3�Ђ�1�Ђ��ߏ���Ɋׂ��Ă���B
�����493�Ђ��|�Y�g�댯����h�@13�Ǝ�ʓ|�Y�댯�x�����L���O
�w�T���_�C�������h�x9��4�����̑�1���W�́u�p�Ƌ}���̃E���@�|�Y�댯�x�����L���O�v�ł��B�i�C����������Ί�Ƃ̓|�Y�͑�����B����ȓ�����O�̂悤�ȏ펯���A�V�^�R���i�E�C���X�̐��E�I�Ȋ����g��ɔ�����@�Œʗp���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�o�c���X�N�̍�����Ƃ��������������ƂȂ�̂��A���J���Z�o�����u�|�Y�댯�x(Z�X�R�A)�v�B�_�C�������h�ҏW���������3787�Ђ̓|�Y�댯�x�_�������Ƃ���A493�Ђ��g�댯����h�Ɣ��肳��܂����B
���W�ł�493�Ђ̎����������L���O�`���œ͂���ƂƂ��ɁA�|�Y�댯�x�������������[�X�g��ʊ�Ƃ̗��R��[�@��B�܂���ʊ�Ƃւ̒�����ނ����s���A�o�c��@�̗��R��ŊJ����܂����B
�܂��A�R���i�Ђłǂꂾ���e�ƊE���Ō���������T�邽�߁A�����Ԃ�q��E�S���A�S�|�A�����́E�d�q���i�A������A�A�p�����A�O�H�A�Ȃǎ�v13�Ǝ�̊댯�x�����L���O���쐬�B�ƊE���Ƃ̓|�Y����ƋƊE���̏��������ɂ��Ă��܂��B
����A2020�N�ɋ}�������p�ƁB�������ɕ����������Ȕp�Ƃł����A���܂����p����Ύ茳�Ɏ������c��g�n�b�s�[���^�C�A�h���҂��Ă��܂��B850�Ђ̔p�ƂȂǂ̎葱�����x�����Ă����g��Ƃ̂�����тƁh�̃v���t�F�b�V���i�����A�u�����g�p�Ɓv����̍ŐV�e�N�j�b�N��`���BM&A����U�A�j�Y�ȂǁA��Ђ̏I���𐬌������āu�|�Y�n���v���������|�C���g���܂Ƃ߂܂����B
�|�Y�̍ŐV����ɔ���������ł��B���Ђ���ǂ��������B
���R���i�e�� �t�@�~���X�̓X�ܐ� �����g��O���8���]���� �@8/30
�V�^�R���i�E�C���X�̉e�������������钆�A��ȊO�H�`�F�[�����W�J����t�@�~���[���X�g�����̓X�ܐ��������g��O�ɔ�ׂ�790�X�]��A���ɂ���8�����������Ƃ��M�p������Ђ̂܂Ƃ߂ŕ�����܂����B
���Ԃ̐M�p������Ёu�������H���T�[�`�v�̂܂Ƃ߂ɂ��܂��ƁA�����،�������ȂǂɊ�������ꂵ�Ă���O�H�`�F�[���̂����A���11�Ђ��W�J����t�@�~���[���X�g�����̓X�ܐ��͂��Ƃ�3�������_�ō��킹��8322�X�ł����B
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��O�̂��ƂƂ�12�������_�ɔ�ׂāA793�X�A���ɂ���8.6���̌����ł��B
�����ɂ킽��O�H���T�����Ă��邤���A�ɉ؊X��I�t�B�X�X�ł̐[��܂ł̉c�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邽�߁A�s�̎Z�̓X�܂���铮�����L�����Ă���Ƃ������Ƃł��B
���ɂ́A�����g��O�ɔ�ׂēX�ܐ���2���]�茸�炵����Ђ�����A���v�̊m�ۂɌ����āA��z���Ƃ̋�����ƑԂ̓]���Ȃǂ��ۑ�ɂȂ��Ă���Ƃ��Ă��܂��B
������S��������؏͋g����́u�X�ܐ��̌����́A���Ȃ��Ƃ����Ƃ������ς��͑����̂ł͂Ȃ����B�O�H�Y�Ƃ̌ٗp�͐��K�A�K���킸�i���Ă��āA�������Ɗ�����v�Ƙb���Ă��܂��B
���R���i���� �Ƒ�������ҋ@�ɂȂ�����c�u�ߋ����ł̋�C�����ɒ��Ӂv�@8/30
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŁA�����������ł������҂̎���ҋ@���}���B�ƒ���ł̊����g�傪���O����Ă���B���Ƃ́u�ڐG�����炷�����łȂ��A�߂������ł̋�C�����ɂ��C��t���āv�ƌĂъ|���Ă���B
�u�ʎ��Ɋu�����邱�Ƃ����v�B�����ǂɏڂ�����������w�̐�����Y�����͘b���B��������l���K��������������킯�ł͂Ȃ��Ƃ��u���C��S�|���A�s�D�z�}�X�N���g�����Ƃ��d�v���v�ƌ��B
�g�C���╗�C�Ƃ��������p���������҂��g�p������͊��C��ŋ�C�����ւ��A����ɑ��̐l���g��Ȃ��悤�ɂ���B�������́u�H�����ʁX�Ɏ����������v�Ə�������B
���t�Ȃǂ�����ڐG�������N���肤�邽�߁A�����҂��G�ꂽ�ꏊ��G���������Ŏ��B�^�I�����ʂɗp�ӂ��A���u���V��u���ʒu���ς���B
����ҋ@���́A�Ǐ�̈����ɂ��z�����K�v�B��l��1���Ԃ�22��ȏ�̑����ċz(�p�ċz)�����Ă���ꍇ�A�ʕK�v�ƂȂ�P�[�X���B�u�����悤�Ȃ�A���o�̂Ȃ������ɔx�����N�����Ă���\���������v�Ɛ������B�u�Z���ڐG�҂ɂȂ�Ƒ������������ʂ��A���ł����Ă��A���f������𑱂��āv�ƒ��ӂ𑣂��Ă���B
���ً}���Ԑ錾�ĉ����̌��Z�@�w�W������12���ȍ~�ɐ摗��@8/30
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����߂����Ă͎��������ʂ����A��2�T�Ԍ�ɔ�����9��12���ً̋}���Ԑ錾�̊����͍ĉ����������Z���傫���Ȃ����B���{���錾�̓K�p������̖ڈ��ɂ��Ă��銴���������X�e�[�W�ʎw�W�̌������ɂ��ẮA���Ƃ̊ԂɐT�d�_���������A12���ȍ~�ɐ摗�肳��錩�ʂ����B�a���g�[�ɂ��Ȃ����Ԃ������肻�����B���{�͗��T�A���{�����J���A�Ή������߂�B
���t���[�̃X�e�[�W�ʎw�W�̎����ɂ��ƁA21�s���{���ɏ��錾�n��̒���1�T�Ԃ�10���l������̐V�K�����Ґ�(����29�����_)�͂�������X�e�[�W4(�����I�����g��A25�l�ȏ�)�B���ꌧ��306�l�Ɠˏo���č����A�����ő��{198�l�A�����s190�l�ȂǂƂȂ��Ă���B
�c�����v�����J������29���̂m�g�j�ԑg�Łu�V�K�����҂̊������ƁA������Ƃ��Ă�(1��������)500�l�����ɂȂ�Ȃ��Ɖ����ł��Ȃ��B������l����Ƃ��Ȃ����v�ƌ���Ă���A���݂̎w�W�̂܂܂ł͓��ʉ����ł������ɂȂ��B
�����s��30���ɔ��\�����V�K�����Ґ���1915�l��8���A���A�O�̏T�̓����j��������������A�����N���o�ύĐ��S������30���̂s�a�r�ԑg�Łu���~�ɓs�S�͐l������ʋq���������B���̔��f�����o�Ă���v�ƕ��́B�c�����͂m�g�j�ԑg�Łu�w�Z���n�܂�l�̍s�����ς��Ɗ����͂܂��L����B9�����܂߂Č������������v�Əq�ׂ��B
�����āA�H�Ɍ����Ĉꎞ�I�Ɋ����Ґ����������Ƃ��Ă��A�~�͉ē��l�Ɋ��C�����܂肹���ɃG�A�R���Ȃǂ�����P�[�X���������Ƃ݂��A���łO�ɑS���I�Ɋ������g�傷��\��������B
�����Ő��{�́A�w�W�̌������������B�d�lj��\�h�Ɍ��ʂ����郏�N�`���ڎ킪�i��ł��邱�Ƃ܂��A���`��(�����E�悵�Ђ�)��17���̋L�҉�Łu��Ò̐��̕��ׂɒ��ڂ��A�a���g�p����N�`���ڎ�̏A�d�ǎҐ��Ȃǂ͂�����őΉ�����v�ƌ���Ă����B
�����A���̎����̌������́u�������邽�߂Ɋ��ς���v�Ǝ��ꂩ�˂��A���J�Ȋ����͐��Ƃ���u�����ł��Ȃ�����(���)�����������ς��܂��傤�Ƃ����c�_������Ă����Ă����Ȃ��v�ƌ���ꂽ�Ƃ����B�t���́u�w�W��ς��������A���Ƃ�����Ă���Ȃ��v�ƘR�炷�B
�����Ƃ��a���g�p���ł�21�s���{�����A20�s�{�����X�e�[�W4(50���ȏ�)�ŁA�a���g�p�����d��ɂ��Ă��A����ɘa���邩�A�啝�ɕa�����𑝂₳�Ȃ�����A�����͓���B���J�Ȃ�30���ɔ��\�����S���̏d�ǎҐ���2075�l��18���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B�a���̃j�[�Y�͍��܂����ƂȂ��Ă���B
����5�g�g�s�[�N�A�E�g�hor�g���~�܂�h���Ƃɕ����@8/30
�����s�̐V�^�R���i�V�K�����Ґ��́A30����1915�l�ł����B7���ԕ��ς́A8���A���Ō������Ă��܂��B����A�����Ґ��͂ǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă����̂ł��傤���B�����lju�w�����ŁAWHO(���E�ی��@��)�ł�������Ɍg����Ă����A�哌������w�̒�����q�����ɘb���܂��B
Q.�����Ґ��́g�s�[�N�A�E�g�h���g���~�܂�h���A�ǂ����Ă��܂����H
������q�����u����1�T�ԁA�����������Ă��܂����A���S�͂ł��܂���B����2�T�Ԃ��炢�͓����s���̐l���������Ă��܂��B���̌�Ɋ����҂������邱�Ƃ������Ă��܂��̂ŁA���f�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B��������8���͂��~��A�x������A���s�̗\�������ɂ��������������Ƃ�����܂��v
�d�ǎ҂̐��ڂ����Ă݂�ƁA��3�g��160�l(1��20��)�A��4�g��86�l(5��12��)���ő��ł����B���݂̑�5�g�ł́A30����287�l�ƂȂ��Ă��āA�����͑O����茸��܂������A�S���ł�18���A���ʼnߋ��ő����X�V�������Ă��܂��B
Q.�d�ǎґ����̗v���́A�ǂ��ɂ���Ǝv���܂����H
������q�����u�d�ǎ҂͑����Ă��܂����A�܂����N�`����łĂĂ��Ȃ�40�`50�オ���S�ł��B����ŁA60��ȏ�̐l�ւ̃��N�`���ڎ�̐i���ƂŁA���Ґ��͌����Ă��܂��B���Õ��@�����Ȃ�m�����Ă���̂ŁA�a�@�Őf�Â���Ɨǂ��Ȃ��Ă����܂��B�S�z�Ȃ̂́A���@�ł��Ȃ�����×{�̐l�������Ă��邱�Ƃł��v
�����s�ł́A20�Ζ����̊����Ґ����A8����1��8317�l�ƁA7����3�{�ȏ�ɂȂ��Ă��܂��B
Q.���ꂩ��{�i�I�Ɋw�Z���ĊJ����܂����A�����g��ւ̉e���͂ǂ�قǂ���Ǝv���܂����H
������q�����u��5�g�ł́A�f���^���̉e���Ŏq�ǂ��ւ̊����������Ă��āA���@���Ă���q�ǂ������܂��B�w�Z���ĊJ�����ƁA�����x�̊������N����Ɨ\�z����܂��B�����A�d�v�Ȃ̂́A����܂ł̌��ʂł́A�����̒��Ŋ�������Ƃ��������A�O�ŗF�B�Ɖ������A�������Ȃǂł̊������X�N���傫���Ǝv���܂��B������^�����Ȃǂł̊��������������s�����Ƃ�A���Ȃǂ̉�������������̂��ǂ��Ǝv���܂��B�q�ǂ��̋���̏�ł́A��l���q�ǂ������Ƃ������_���厖�ŁA���E�������N�`����ł�����A�����[�g�����p����ȂǁA�����̋@������炷���Ƃ��厖���Ǝv���܂��v
���N�`���ڎ�́A29���܂łɁA1��ڂ��I�����l��55.6���A2��ڂ��I�����l��44.6���ƂȂ��Ă��܂��B
Q.���̐ڎ헦�͂ǂ��]�����܂����H
������q�����u���N�`�������Ńf���^���̗��s���R���g���[������͓̂������ł��v
���N�`���ڎ킪�i��ł���A�C�M���X�ł́A16�Έȏ��2��ڂ̐ڎ���I�����l���A28�����_��78.4���A�C�X���G���ł�30�����_�ŁA12�Έȏオ75.5���ƂȂ��Ă��܂��B�����A�ǂ���̍��ł��A�V�K�����Ґ��́A�������J���ŋ}���ɑ����Ă��܂��B
Q.���N�`�������Ńf���^����}���邱�Ƃ͂ł��܂��H
������q�����u�f���^���̉e���͐[�����Ǝv���܂��B�f���^���͊����͂������A���N�`���̌��ʂ����シ�邱�Ƃ��v���ł��B�����āA�����̍��ł́A�l�������Ċ����̋@����������Ƃ��v���̈���Ǝv���܂��B�f���^�����o��O�͊����Ґ��������Ă����̂ŁA�f���^���̏o���ɂ���đ傫�����ς���Ă��܂����A���E���ς�����ƍl����ׂ����Ǝv���܂��v
Q.���{�ł͂��̐�A�ǂ������ɂȂ�Ǝv���܂����H
������q�����u�܂��A���N�`���𑽂��̐l���ڎ���邱�Ƃ��厖�ł��B���̂����ŁA���̏H����~�ɂ����āA���N�`���ڎ킪�i�Ƃ��Ă��A���ꂾ���ŗ��s��}����͓̂���ł��B����ɁA�~��ɂȂ�ƁA�V�^�R���i�͗��s���₷���Ȃ�܂��B�~��́A�]������S�؍[�ǂ̃��X�N�����܂�̂ŁA�R���i�����łȂ��A��ʐf�Â̋~�}�Ȃǂ��܂߂āA�f�Â̗������K�v���Ǝv���܂��B���̂��߂ɂ́A���N�`���ڎ��i�߂Ȃ���A�}�X�N��O���������A���C�A��w�q���ȂǁA���������������Ă������Ƃ�����Ǝv���܂��v
�@ |
 |


 �@
�@ |
�������s�ŐV����2909�l�����A15�l���S�@�d�ǎ҂�287�l�ʼn��������@8/31
�����s��31���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����2909�l�A����15�l���m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B���ݓ��@���Ă���d�NJ��҂�287�l�B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���3520�D7�l�ŁA31�����_�őΑO�T��75�D9���ƂȂ����B
�N��ʂł́A20�オ791�l�A30�オ588�l�A40�オ497�l�A50�オ332�l�ȂǂƂȂ��Ă���B65�Έȏ�̍���҂�142�l�������B���҂�40��j��1�l�A50��j��2�l���܂�15�l�B
������1261�l�ւ̃X�N���[�j���O�����ł́A�ψي��u�f���^���v�ɂ݂���ψفu�k452�q�v��1190�l�Ŋm�F����A�����͖�94�D4���������B
���s��t��u�Վ���Î{�݁A����āv�@�����NJ��҂�����@8/31
�����s��t��̔��莡�v���31���̋L�҉�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɂ���Ò̐����N��(�Ђ��ς�)���Ă��邱�Ƃ܂��A�u���Â��ł���悤�Ȓ����nj����̗Վ���Î{�݂��A���Ђ���������Ă������������v�Əq�ׂ��B
�����g�傪�����Ă���s���ł́A���@���Ґ��A�d�NJ��Ґ��Ƃ��ɍ��������ɂ���B���莁�͓��@���Âł�����������āA�d�lj���h�������l�����������B
��8���̊�����1658�l�A�N���X�^�[39���@�X�� �@8/31
�X����31���A�����ŐV����84�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B���ʂʼnߋ��ő����X�V�������Ă���8���̊����Ґ��͂����1658�l�ƂȂ�A����܂ōő�������5����776�l��2�{���ƂȂ����B���ˎs�ł͐V����2���̃N���X�^�[(�����ҏW�c)�������B8���̌����̃N���X�^�[��39���ƂȂ�A���ʂʼnߋ��ő�������5����22����傫���������B�����̊����m�F�v��4356�l�B
8���́A��{���������Ґ���10�`30�l��O���Ő��ڂ��Ă������A���~�����̒��{�ȍ~���瑝���A25�������3���A����3���𐔂����B�w�i�ɂ́A�A�ȂȂǂɔ����l���̑�����A�����͂̋����f���^���Ƃ݂���L452R�ψي��ւ̒u������������Ƃ݂���B����A����܂Ō��ʂōő�������5���Ɣ�r����ƁA8���͎�N�w�̊�����N���X�^�[�����������Ƃ����B
8���̃N���X�^�[��ی����Ǔ��ʂɂ݂�ƁA�ő��͔��ˎs��14���B�X�s12���A�O�O�ی����Ǔ�4���A��\�O�ی����Ǔ�3���A�ނی����Ǔ��ƎO�˒n���ی����Ǔ����e2���A���쌴�ی����Ǔ��Ɠ��n���ی����Ǔ����e1���Ƒ����A������8�ی����S�ĂŃN���X�^�[�����������B���e�����H�X��E��A�^���{�݁A����ۈ�{�݁A�w�Z�A��H�ȂǑ���ɋy�ԁB
���̐�J�a�F�V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�ẮA�u���̂܂܊����g�傪�p������ƕa���̕N��(�Ђ��ς�)�ɂȂ��肩�˂Ȃ��B����������g��̕������߂��s���Ă����B��Ò̐��̊m�ۂɂ��Ă����������a���A�h���×{�{�݂̊m�ۂɌ����A���c��i�߂�v�Ƌ��������B
31�����_�̎���×{�Ґ���291�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����X�V�B���@�Ґ��͑O������3�l����136�l�B�a���g�p����45.0���������B�l��10���l�������1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��́A�������Z�ł�52.01�l�ƂȂ�A�O���ɑ�����50�l�����B
���V�^�R���i����47�l�@�m���u�������ɕς��͂Ȃ��v�@�������@8/31
����30���A�����ŐV����47�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F�����Ɣ��\�����B29���ɗz���������B1���̊����Ґ��Ƃ��Ă�7��26����41�l�ȗ���1�J���Ԃ��50�l������������A���x��Y�m����30���̒��L�҉�ŁA�×{�҂̌����ɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��Ƃ��āu�������ɕς��͂Ȃ��v�Ƃ̔F�����������B
�����Ґ��͉���8651�l�B29�����_�̓��@�Ґ��͏d��16�l���܂�351�l�ŁA�a���g�p����55�D1���ƃX�e�[�W4(�����I�Ȋ����g��)�̐����������B����×{�҂�481�l�A�h���×{�҂�107�l�A�×{�撲������79�l�ŁA�×{�ґS�̂ł�1018�l�ɏ��B
�×{�Ґ����������Ő��ڂ��钆�A���͏h���×{�{�݂�503���Ɋg��B���x�m���́u(����×{�҂�)�̒��������悤�ȏꍇ�A���₩�Ɏ������Ԑ����\�z���Ă���v�Əq�ׁA�h���×{�{�݂��ő�����p����l�����������B
��Í≺���Ŏ��Ə��֘A�̃N���X�^�[(�����ҏW�c)2�����F�肳�ꂽ�B�����̎Ј�����5�l�A�ʂ̎��Ə��ł�5�l�̊����������B�����̃N���X�^�[�͌v144���B���́A�ċG�x�ɖ����Ɍy���ȑ̒��̕ω������o���Ȃ�����o�Ђ��A�������L����P�[�X������Ƃ��Ē��ӂ��Ăъ|���Ă���B
29���ɗz������������47�l�̓���͌S�R�s18�l�A���킫�s11�l�A�����s�A�c���s���e5�l�A���Β�3�l�ȂǁB11�l�̊����o�H���s���B29���܂ł�18�l���މ@�A18�l���h���×{�{�݂�ޏ����A40�l�̎���×{���������ꂽ�B
�����P��ʼn�H�N���X�^�[�������@�����̎��Ə��Ŋ����g��@��錧�@8/31
��錧�Ɛ��ˎs��31���ɔ��\�����V�^�R���i�E�C���X�V�K�����Ҍv160�l�̂����A���P��s��20��j��5�l(��������E�Ɣ���\)�͓����̃A�p�[�g�ŊJ���ꂽ��H�ɎQ�����Ă���A27���܂łɌ��\���ꂽ1�l�𑫂��ƁA�����҂͌v6�l�ɍL�������B���͉�H���ł̃N���X�^�[�����̉\�����w�E���Ă���B
�����s���̎��Ə��ł͏]�ƈ�1�l�̊������������A30���܂łɌ��\���ꂽ8�l��������ƁA���Ə����̊����҂͏]�ƈ��v9�l�Ɋg�債���B���͓������m�̉�H�ȂǂŊ��������\��������Ƃ݂Ă���B
�Ⓦ�s���̎��Ə��ł͐V���ɏ]�ƈ�2�l�̊��������炩�ɂȂ�A30���܂łɌ��\���ꂽ7�l�����킹��ƁA���Ə����̊����҂͏]�ƈ��v9�l�ɑ������B
��~�s���̎��Ə����ł͓�����4�l�̊�����������A�����̊����҂͌v9�l�ɑ��������B�Ђ����Ȃ��s���̎��Ə��ł��]�ƈ�1�l���������A���Ə����̊����҂͏]�ƈ��v13�l�ƂȂ����B
���܂h�~ �V�����A�\��������@�d�ǎҏ��Ȃ�������F�@�V�����@8/31
�V������30���A�V�^�R���i�E�C���X�̓��ʌx��̑Ώۂ�S���Ɋg�債������ŁA�ً}���Ԑ錾�ɏ����������[�u���\�ƂȂ�u�܂h�~���d�_�[�u�v�̖{���K�p�����ɐ\�����邱�Ƃ͌��������B�����ɂ͐\�������߂鐺�����������A�����{���̊����ł͎��������Ɣ��f�������Ƃ��w�i�ɂ���B�������A�����Ċy�ώ��ł���ł͂Ȃ����Ƃ���A���͈������������𒍎����Ă���B
���ʌx��̑S���g��𐳎����肷��O����29���A�Ԋp�p���m���͐����N���o�ύĐ��S�����Ɠd�b�ʼn�k�����B���̋����͂��Ή�������u�d�_�[�u�v�̑Ώۂɖ{�����Ȃ蓾��̂���q�˂��B�����̓m�[�������B
���͊�����c�������i�Ƃ��āA��Â̕N��(�Ђ��ς�)���V�K�����Ґ��Ȃ�7���ڂ̎w�W�������Ă���B���̎w�W����ɃX�e�[�W3�������d�_�[�u�A����Ɉ��������X�e�[�W4(�����I�����g��)�������ً}���Ԑ錾�̓K�p�ڈ��Ƃ��Ă���B
�{���͐l��10���l������̗×{�Ґ���V�K�����Ґ����X�e�[�W4�ɑ����B�m�ەa���̎g�p����o�b�q�����̗z�����̓X�e�[�W3�ɑ������Ă��遁�\(1)�Q�Ɓ��B
���������́A�{���ł͏d�ǎҐ������Ȃ��_��A�����o�H�s������3����ɂƂǂ܂��Ă��邱�ƂȂǂ���A���̓s���{���Ɣ�ׂĂ��d�_�[�u��K�p����ł͂Ȃ��Ɣ��f���Ă����B
�����ق��ɏd�������_�͊����Ґ��̑��������B������8���̐V�K�����Ґ���1�`7�����O�T��56�E7�����A8�`14������32�E5�����Ɩ��T�g��𑱂������A�������������I�ɐL�т邱�Ƃ͂Ȃ��������\(2)�Q�Ɓ��B
�����A��Ñ̐��̕N���͓��X�A�[�����𑝂��A�l�̓�����}���邽�߂̋����[�u���}���ɂȂ��Ă����B�d�_�[�u���K�p�����A��^���Ǝ{�݂Ȃǂւ̉c�Ǝ��ԒZ�k�v�����\�ƂȂ�ق��A�����Ȃ����Ǝ҂ɑ��Ė��߂��ł��A�ᔽ����Ήȗ����Ȃ�����B
���̎������Ƃ̋��c�i�K�ł́A�����Ɂu������F�߂��Ȃ��Ă��{�C�x�������Ӗ��Ő\�����ׂ����v�Ƃ̈ӌ����������B�����A�����S���������m�ɔے肵�����ƂŌ����肪���܂����B
�������ی����̏��{���������́A30���̑��{�����̋L�҉�Łu�l���̓I�Ɏ~�߂�ɂȂ��Ƃ����̂����̔��f���Ǝv�����A(������)���Ƃ��ς��Ă�����B���ɋꂵ���v�Ɠf�I�����B
�����ł̊����͈��������\�f�������Ȃ����B�Ԋp�m���͓����A����̏d�_�[�u�̐\���ɂ��āu������Ɉ�������A���R���肢���邱�Ƃ͂��蓾��v�Əq�ׂ��B
�������ʏ��{�݂��Ë@�ւŃN���X�^�[�g��@�V�^�R���i�@���s�{�@8/31
���s�s��30�����\���ł́A�s���ݏZ�Ŋ�b�����̂���70�㏗�������S���A���A�w������80��̒j��251�l���V���Ɋ��������B�Ǐ�͒������������d��1�l�A������6�l�A�y��201�l�A���Ǐ�33�l�B�����o�H�s����167�l�������B
�N���X�^�[(�����ҏW�c)�֘A�ł́A�����̒ʏ��{�݂ŐV���Ɏ���1�l�̊�����������v9�l�ƂȂ����ق��A��w�̉ۊO�����ŐV����2�l����������18�l�ɂȂ����B����܂�7�l���������Ă�����Ë@�ւŐV���Ɋ���2�l�̗z���������A5�l�̗z�����m�F���Ă�����Ë@�ւł��V���Ɋ���1�l�����������B
���Z�n�ʂ͋��s�s241�l�A�����s4�l�A�F���s3�l�A���ꌧ1�l�A���{2�l�B
���R���i�����g�咆��2�w���J�n�@���ӓ_�́H�@���茧�@8/31
�V�^�R���i�E�C���X�̊������g�傷�钆�A���茧��19���A�����S��ɓƎ��ً̋}���Ԑ錾���o���܂����B����ɐ��{��27���A�܂h�~���d�_�[�u�̑Ώۂɖ{����lj����A����A�����ۗ��s���Ώۋ��ɂȂ�܂����B�����������A�����ł͑����̊w�Z��9��1����2�w�����n�܂�܂��B�q�ǂ��̊������Ⴊ�����A�s���������l������Ǝv���܂��B�ǂ�ȓ_�ɒ��ӂ����炢�����������ς▯�Ԓc�̂Ȃǂɕ����܂����B
�\�\�o�Z�O�ɂ�邱�Ƃ́B
�ی�҂͌�����������A�q�ǂ��̗l�q�������肵�Č��N��Ԃ�c�����܂��傤�B���N�Ǘ��\�Ȃǂ����p���Ă��������B
�\�\�q�ǂ���Ƒ��ɔ��M�Ȃǂ̕��Ǐ�������B
�{�l�̏ꍇ�͎���ł̋x�{��O�ꂵ�Ă��������B�ƒ���̊������L����P�[�X�������Ă��܂��B�����Ƒ��ɏǏ���ꍇ���q�ǂ��̓o�Z�͍T�������܂��傤�B
�\�\�w�Z���x�猇�Ȉ����ɂȂ�܂����B
�����Ȋw�Ȃ̃K�C�h���C���͐V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̑Ή��ŋx�ꍇ�A���Ȃł͂Ȃ��o�Ȓ�~�[�u�����悤�Ɏ����Ă��܂��B�����ς�18���ɏo�����u���璷�ً}���b�Z�[�W�v�œ��l�̑Ή����w�Z�ɗv�����Ă��܂��B
�\�\�w�Z��ƒ�ŋC��t���邱�Ƃ́B
���璷���b�Z�[�W�ł͋��犈���ĊJ���2�T�Ԃ��u�����g��h�~�O����ԁv�Ƃ��Z���ōő���̌x�������肢���Ă��܂��B�����ł��u������肪�i��ł���u�f���^���v�͊����͂��������Ƃ��������Ă��܂��B����܂ňȏ�Ɏ�₹���G�`�P�b�g�ȂNJ�{�I�Ȋ������O�ꂵ�Ă��������B���H���͉�b���T����ȂǁA�}�X�N���O������ʂł͓��ɒ��ӂ��K�v�ł��B���퐶���ŏ\���Ȑ�����o�����X�̎�ꂽ�H����S�|���A�Ɖu�͂����߂邱�Ƃ���ł��B
�\�\�ċx�ݖ����͊w�Z�ɑ��������Ȃ��l������Ǝv���܂��B�R���i�ЂŃX�g���X��s���������Ă���q�ǂ��������̂ł́B
9��30���܂ŊJ�݂������݃T�C�g�u�w�Z�����ł����������v�ł́A�w�Z��ƒ�̂ق��ɂ��A�S���Ɉ��S�ł��鋏�ꏊ�⑊�k�ꏊ�����邱�Ƃ��Љ�Ă��܂��B����s�̂m�o�n�@�l�u�q�ǂ��̌����I���u�Y�p�[�\���Ȃ������v��1���ߑO7������I���u�Y���[�����J�����A���k���t���܂��B
�������V�^�R���i�����g��~�܂炸�@�����琬�N���u�ł̓N���X�^�[�@�F�{���@8/31
�V�^�R���i�E�C���X�����̊����Ґ��́A���j������2�������Ă�100�l��ƌ������Ă��܂������A31���͂܂�200�l��ƁA�����g�傪�����Ă��܂��B�����ł�31���V���ɁA238�l�̊��������炩�ɂȂ�܂����B30�������117�l�ɑ������A��T�̉Ηj�������2�l�������Ă��܂��B���̂����A���悻6����145�l���F�{�s�ł��B
���̌F�{�s�ł́A�k��̐A�؏������琬�N���u�ŃN���X�^�[���N���Ă��āA����10�l�̊������������Ă��܂��B�܂��A�q�j�j�̏]�ƈ�1�l���������Ă������Ƃ�����܂����B���������̂͏����X�^�b�t�ŁA�Ɩ���A�ЊO�Ƃ̐ڐG�͂���܂���B����26�����甭�M������A��27���Ɉ�Ë@�ւŎ�f���A31���A�o�b�q�����ŗz���Ɣ������܂����B
���{�茧���̐V�K�����҂�105�l�@�a���g�p������50�������@�{�茧�@8/31
�{�茧���ł�31���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�105�l�m�F����܂����B�����I�Ȋ����g��ŁA�����̓��@�a���g�p�������߂�50�����܂����B
�������m�F���ꂽ�̂́A10�Ζ�������90��̒j��105�l�ŁA1���̊����Ґ���100�l�����̂�4���Ԃ�ł��B���ѕی����Ǔ��ł́A���~���Ԃ���8�����{�ɂ����Č��O����A�Ȃ���20��j��5�l�̊������m�F����A���̓N���X�^�[�ƔF�肵�܂����B����5�l�͍��ꌧ�Ŋ������m�F���ꂽ�F�l���܂߂āA6�l�ňꏏ�ɏ��юs�₦�т̎s�ŐH����h���C�u�����Ă����Ƃ������Ƃł��B�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����A��Õ���̊�@�������Ă��܂��B30�����_�ŐV�^�R���i�ɑΉ��������@�a��307���̂����A�ߋ��ő���155�������܂�A�����̕a���g�p�������߂�50�����܂����B���ł́A����ȏ��Âɕ��ׂ�������ƒʏ�f�Âɂ��x������������ꂪ����Ɗ�@�����点�Ă��܂��B
�������Ǒ@�L�����㎺���u��Â̕N�����킪�g�ɍ~�肩�����Ă���Ǝ����̂��ƂƂ��Ď~�߂Ă������������v
�s�����ʂ̊����҂̓���́A�{��s��57�l�A�����s�Ɠ����s�����ꂼ��11�l�A��쒬��5�l�ȂǂƂȂ��Ă��܂��B30�����_�ŁA�d�ǎ�8�l���܂�155�l�����@���A905�l���h���{�݂⎩��Ȃǂŗ×{���ƂȂ��Ă��܂��B
�������ŐV����78�l�@2���A����100�l�����@���������@8/31
�����������ł�31���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����78�l���\����A30����49�l�ɑ����A2���A����100�l�������܂����B
78�l�̓���́A�������s��36�l�A��E���Ɖ����s��6�l�A��蒬��5�l�A�����s��4�l�A�삳�s�A�F������s�A�����s��3�l�A���ǎs��2�l�A���u�s�A���B�s�A�w�h�s�A�ɍ��s�A�̕t���A�����s�A�]���s�A���˓����A���V�\�s�A���{��1�l���ł��B
�܂��A����31���A�����s�̊w�Z�̕������ŐV���ɃN���X�^�[�����������Ɣ��\���܂����B����܂ł�10�ォ��40��̏���15�l�̊������m�F����Ă��āA�������k��13�l�A�w���҂�2�l�ł��B�x�e����X�ߎ��ł̃}�X�N���p���s�\�����������Ƃ������g��̌����Ƃ݂��Ă��܂��B
�����̊����҂͗v8105�l�ƂȂ�܂����B30�����_�ň�Ë@�ւȂǂŗ×{���Ă���l��853�l�ŁA�����d�ǂ�5�l�A�_�f���^���K�v�Ȓ����ǂ�100�l�ł��B����ҋ@���Ă���l��691�l�ł��B
���R���i�a���N���@�ŊJ�֗Վ���Î{�݂��@8/31
�����s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾�����߂���Ă���1�J�������߂��A�Ώےn���21�s���{���Ɋg�債���B��s������𒆐S�ɕa�����N��(�Ђ��ς�)���A���{�͊����}�g��n��ł͗Վ���Î{�݂̐������܂ޑ��i�߂�ƕ\�������B
�u��5�g�v�ɋꂵ�ވ�Ì���ɓ˂��グ��ꂽ�`���B���{�������ȂǑ����̓s���{�������ɉ�����ƌ��킴��Ȃ��B����ł������ҋ}���ɒǂ����Ȃ���Ñ̐��̕����Ԃ̑ŊJ�ɂ́A�ʏ��Â�������x�������Ăł��u���a�@�v�̂悤�ȗՎ���Î{�݂����芳�ҁA��Ï]���҂��W�������邱�Ƃ͗L�����B�����Ɏ��s���Ăق����B
�����J���Ȃ͓s�ƘA���ŁA�s���̑S��Ë@�ւɃR���i�����a���̊m�ۂ�v�������B�l���s���Ȃǐ����ȗ��R�Ȃ��v�������ꍇ�͊������A�]��Ȃ���Έ�Ë@�֖������\�ł���Ƃ������������ǖ@�Ɋ�Â����Ƃ��ď��̑[�u���B����ɂ��s�́A�R���i�a�����600����ς݂��v7�珰�m�ۂ������Ƃ��Ă���B
�s���{�����x���̗v���ł͍��t�A�ޗnj�����50���A���{����550�����m�ہB�������{��8���̗v���́A�a�@�����u�Ō�t���m�ۂł��Ȃ��v�u���̊��҂Ɠ��������Ȃ��v�Ƃ��ē�q���Ă���B�܂������s�����݊m�ۂ���R���i�a����6400���͎g�p��60�����Ő�����]�T�����邪�A�l���z�u���Ԃɍ���Ȃ��Ȃǂ̂��ߎ��ۂ͕N����Ԃ��B�����a�@�̕a����ς݂͍�������������ƍl������܂��B
�����Ő��{���a����̂�����̒��Ƃ����̂��u�l���h���v���B�R���i���ғ��@�ɑΉ��ł��Ȃ�������A�R���i�f�Î��̂Ɋ֗^���Ă��Ȃ������肵���a�@�A�f�Ï��ɂ́A�����l�̓]�@��m�ۂ̂ق��A��t�A�Ō�t�h���ŋ��͂����߂�B�x�b�h�������Ȃ�l�ނ��A�Ƃ������z�̓]�����B
��t��Ō�t�́A�S����11���l��������×{�҂̃P�A�Ɉ����肠�܂��Ȃق��A�ݑ�҂����ꂵ���Ȃ����ꍇ�Ɏ_�f�z��������u�_�f�X�e�[�V�����v�Ȃǂւ̔z�u�����߂��Ă����B
���̏�ŁA���҂����܂�̂��Վ���Î{�݂ւ̔h�����B���l�̎{�݂͉p����X�y�C�����݉c���A���{�ł����{����^�W����ɐ珰�K�͂̐�����\���A���䌧��100���̌v������肵���B���f��K��Ō삪�K�v�ȍݑ�҂��L��1�J���ɏW�߂Đf�邱�Ƃ��ł���A���Ȃ���Ï]���҂Ō����I�Ȏ��ÁA�e�̋}�ςւ̑Ώ����\�ɂȂ�B����ł͓���R�̃J�N�e���Ö@�ɂ��Ή��ł���B
���{��t���o�ϊE�����͂�\�����Ă���A�e�n�ւ̐������}���ׂ����B�������A�R���i�ȊO�ɂ��[���ȕa�C�₯���͂���B�ʏ��Âɂ��������Ï]���҂������͂����悤�ɂ��ē������邱�Ƃ́A�����ɖ@���Ɋ�Â��v���ł����Ă��A��t��Ō�t��ɉߑ�ȕ��S���������ɂ͎������Ȃ��B
���ǂ��̐��ۂ����߂�̂͐����̃��[�_�[�V�b�v���B�S�Ă̍����Ɍ���������𗦒��ɓ`���A��Ï]���҂Ɍ��g�I�ȋ��͂��~�����Ƒi���Đ�������B����́A���`�̎����g�̌��t�̗͂Ŏ��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����͂��̋ǖʂł��u���N�`���ڎ�̎��g�݂͗ǂ������v�Ɛ��ʂ��������A�u������͂͂�����ƌ����n�߂��v�Ɗy�ϓI���ʂ������B��@�����������[�_�[�̌��t�ł͐l�͓����Ȃ��Ǝw�E������Ȃ��B
���V�c�É��́u���G�ȕ\����Ȃ����Ă����v ���ւ́g��a���h�@8/31
�V�c�É��́A��������������ċG�Ɠ~�G�̃I�����s�b�N���ϐ�Ȃ��邱�Ƃ����D���������B
�O��A�����I�����s�b�N���J�Â��ꂽ�̂́A���x�o�ϐ����̐^���������ɂ�����1964(���a39)�N�B�É��͖�4�ɂȂ�ꂽ�N�������B��c��c�@���É��Ƃ��ꏏ�Ƀ}���\����n�p���Z�����Ŋϐ킳�ꂽ���Ƃ�������Ȏv���o�̂ЂƂƂ���Ă���B
�җ���}����ꂽ��N2���̉�ł��A�����q�ׂ�ꂽ�B
�u����܂ł�60�N��U��Ԃ��Ă݂܂��ƁA�c�����̋L���Ƃ��āA���a39�N�̓����I�����s�b�N�⏺�a45�N�̑�㖜�����������܂��B���ɂƂ��āA�����I�����s�b�N�͏��߂Ă̐��E�Ƃ̏o��ł���A��㖜���͐��E�Ƃ̏��߂Ă̐G�ꍇ���̏�ł������Ɗ����Ă���܂��v
���u�V�c�v�ƌܗւ́u���_���فv
��̍ۂɂ́A����c�É�����A�e���̑I��c�������Ƃł͂Ȃ������荇���Ē��ǂ��s�i���邱�Ƃ�������ꂽ���Ƃ���ې[���L������Ă���Ƃ����B���̂Ƃ��ڂɂ��ꂽ���i�́A���E�̕��a��Ɋ肤���݂̋C�����̌��ƂȂ��Ă��邻�����B
���̌�A�D�y�̓~�G���(1972�N)��o���Z���i�ܗ�(1992�N)�̎��͌��n�ɕ����ꂽ�B��q�c�@�ƌ�������Ă���́A�c���q���v�ȂƂ��Ē���̓~�G���ŃX�P�[�g��W�����v���Z�������ɂȂ�A���{�I��̃��_���l���̏�ʂɂ���������Ă���B���q���e�����c��������e���r�ϐ킳��Ă����Ƃ����B
�������A����̓����ܗւ́A�V�^�R���i�E�C���X�Ƃ̓����ɂȂ��Ă��܂����B7��23���A�ً}���Ԑ錾���ŊJ��ɗՂ܂ꂽ���A���̂Ƃ��É�����������Ă����̂́A����܂ł̂悤�ɋ��Z���y���ނ��Ƃł͂Ȃ��A���Z���I�葺�ȂǂŊ����g�傪�N��Ȃ����Ƃ������B�u���Ə��̓��������I�葺�̊�����ȂǂɊւ��Ă��A�J�ÑO������X�Ȃ�ʊS��������Ă����Ƃ����B
�u�V�c�v�ƌܗւ́u���_���فv�Ƃ���2�̂�����́A�����ɂ͑z������ł��Ȃ��d�ӂȂ̂��낤�B
�u�J������ɁA�I�肽���ɋ`���t�����Ă���������PCR�������A�L�b�g�s������s���Ă��Ȃ����Ƃ����o���܂������A���̂��Ƃ́A�J��ɗՂޒ��O�̕É��ɂ��`����ꂽ�Ƃ����܂��B�É��́A�I�葺�Ɋ����҂������Ă��Ȃ����Ƃ��S�z����A�L�b�g���s���������R���W�҂ɂ��m�F����Ă��܂����B����̑I�肽��������܂Őςݏグ�Ă����͂��o�����悤�őP�̊��������邱�Ƃ́A�������J�Í��̖��߂Ȃ̂��Ƃ������Ƃ����߂ċC�Â����ꂽ�C�����܂��v(���{�W��)
�����O�ɏ������ꂽ��������
�V�c�É��Ɠ����ܗւɊւ��ẮA6��24���̐����וF�{���������́u�q�@�����v�����c���������B
�u�V�c�É��́A�����̐V�^�R���i�E�C���X�̊������ϐS�z����Ă����܂��B�����̊Ԃɕs���̐������钆�ŁA�����g�����_���ق������߂ɂȂ�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̊J�Â������g��ɂȂ���Ȃ����A�����O����Ă���A���S�z�ł���Ɣq�@���Ă��܂��B���Ƃ��܂��ẮA�É������_���ق������߂ɂȂ�I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�Ŋ������g�傷��悤�Ȏ��ԂɂȂ�Ȃ��悤�A�g�D�ψ�����͂��ߊW�@�ւ��A�g���Ċ����h�~�ɖ��S�������Ă������������A���̂悤�ɍl���Ă��܂��v
���̔����̂��������_�ŊJ�Â͊m��������Ă������A�ϋq���͂܂��Еt���Ă��Ȃ������B���̂��ߔq�@�����́u�É��̂����O�v�Ƃ��ďu���Ԃɉi�c����}�X�R�~�ɓ`���A�傫�Ȕg��ւƍL�������B
�V�c�É��͖{���Ɍ��O����Ă���̂��H�@�����̌l�I�Ȕ����ł͂Ȃ��̂��H�@�V�c�������̏�ł̒��������Ȃ̂��H�@�u�J�Áv�܂œ��ݍ��̂͐����I�����ł͂Ȃ����H
���������̔����͒���ł̂��Ƃ������B���̂��ߋ{���L�҂���́u�É��̂��l���Ȃ̂��v�Ɗm�F���鎿�₪����A�����́u�É����璼�ڂ������������t�������Ƃ͂���܂���v�ƌJ��Ԃ��A�u�q�@�������̂ɉ߂��Ȃ��v�u���������o�ł��������Ă���悤�Ȃ��́v�Ɛ��������B
���`�̎��������M���[�������A�u�{�����������g�̍l�����q�ׂ�ꂽ�Ə��m���Ă���v�ƌ�����B
�����A���̔����͂�������̌l�I�Ȏv������������̂ł͂Ȃ������B�{�������œ��O�ɏ������ꂽ���̂��Ƃ����B
�u���̍��A�{���������\���ׂ����Ƃ�3����܂����B�É��̊J����ՐȂ̌��A�c�@�É��̊J����o���̌��A�����č���̒��������ɂȂ������É��̓����ܗ֊J�Âɑ��邨�l����3�ł��B������ǂ̂悤�ȏ��Ԃł����\���Ă������A6���ɓ����Ă���É��ƒ����̊Ԃŋc�_���d�˂��܂����B�ܗ֊J�Âɔ����鍑���̐����傫�����ŁA�É��Ƃ��ẮA�����g�̂��C���������炩�̌`�ō����ɓ`�������Ǝv���Ă���ꂽ�̂ł��v(���{�W��)
�������O�̎n�܂��3������
�É����y�X�ɔ��f���ꂽ�킯�ł͂Ȃ������Ƃ����B���̔����ɂ�����܂łɂ́A6���������ƑO����̒����O�i���������悤���B
���Ԃł́A�������ւ́u�����v�ᔻ�����H�������Ă��邪�A�V�c�É������{�̃R���i��Ɋ�@��������Ă��邱�Ƃ����͂ɓ`������̂́A���N3�����{�̂��Ƃ������Ƃ����B
3��21���A��s����1�s3���ł́A���悻2�J�����ɂ킽����2��ڂً̋}���Ԑ錾���������ꂽ�B3��20���̓����s�̐V�K�����Ґ���342�l�B�����O�����Ԃ̑ؗ��l���͑��������Ă������Ƃ���A���o�E���h���傫���Ȃ邱�Ƃ͑z������Ƃ���ꂽ�B
���̍��A���É��̓j���[�X�̒��ŁA�X�̗l�q��^���ɂ����ɂȂ��Ă����Ƃ����B���{�����H�X�̉c�Ǝ��ԒZ�k�v�����ɘa�������Ƃ�����A��܂ŊO�o����Ⴂ�l�����͑��������B�f���ɂ́A�t�x�݂ɓ������w����ň��Ԃ�X�̗l�q���f���o����Ă����Ƃ����B
�É��́A�I�����s�b�N���{���ɗL�ϋq�ōs����̂������S�z����Ă����悤���B
�u���̎��_(3��)�ŁA�I�����s�b�N�J�Â܂łɁA3��ڂً̋}���Ԑ錾���o������Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ��A�錾���ł̃I�����s�b�N�J�Ẩ\�������邩������Ȃ��Ƃ���������Ă��������ł��B�{����������W�҂�ɐ��{�̑Ή��⓮����p�ɂɊm�F�Ȃ����Ă��܂����v(���{�W��)
���傤�NJϋq�̈����ɂ��Ă̋c�_���n�܂������낾�����B3��20���ɂ́A���{���{�A�����s�A�g�D�ψ���AIOC�AIPC�ɂ��5�ҋ��c���J����A�C�O�ϋq�̎���f�O������B�����A�����ϋq�̕������ɂ��Ă͐摗�肳��Ă����B
��4���̓��t�ł̈�a��
4��20���ߑO10��30���A�É��͍c���E�{�a�u�P���̊ԁv�ŁA�������20���́u���t�v����ꂽ�B�����O�̏�������t�̓��e�́A�u�V�c�̐������p�ɂȂ���v���Ƃ�����\����Ȃ��B
2�l�́A�P���̊Ԃ�2�r�����u���ꂽ�֎q�ɍ������A�����Ȋۂ��e�[�u�������݂Ȃ��猾�t�����킳�ꂽ�B
�u�������́A���̓��ߌ�̏O�@�{��c�ɏo�Ȃ��A�����ܗցE�p�������s�b�N�J�Âɂ��āw�l�ނ��V�^�R���i�E�C���X�ɑł��������Ƃ��Ď������錈�ӂɉ���ς��͂Ȃ��x�Əq�ׂĂ��܂��v(�������L��)
����ȋ��C�̔����Ƃ͂���͂�ɁA���ۂ̊����͓������Ɍ������Ȃ���肾�����B4���ɓ����đ�4�g���{�i�����A�V�K�����Ґ�����C�ɑ����B���{�ɂ͑���1200�l���āA�a�@�Ŏ��Â����Ȃ����҂����o�����Õ��N���Ă����B
�ʏ�̓��t�ł́A����̘b���ɗ��߂邱�Ƃ������Ƃ����B���̓��A�É����R���i��̂�������Ȃ��������ǂ����͂킩��Ȃ����A�{�����W�҂ɂ��A�u���̐������D�ɗ����Ȃ��悤�ŁA���G�ȕ\����Ȃ����Ă����v�Ƃ����B
�����É��̂��M���������̂́c�c
�É���m�錳�{�����E���͂����b���B
�u�É��͘_���I�Ȃ��l����������Ȃ̂ŁA�������́w�R���i�ɑł��������̃I�����s�b�N�J�Áx�Ƃ��������̂Ȃ����M�́A��̂ǂ����痈��̂��Ǝv��ꂽ��������܂���B
���É��̂��M���������̂́A���{�̃R���i�����ȉ�̔��g�Ή�ł��B��N4����11���ɂ������ɂȂ�A���i�u�O�ɂ́A���É������낢�ō����O�̃f�[�^����A���̃E�C���X�Ƃ̂������Ȃǂ������ׂɂȂ��������ŗՂ�ł���ꂽ�B���i�u�̌�́A�ψي��ɂ��Ă��S��������Ă��܂����B
�É��͂܂��m�����Ă���A���Ɍ���œ����Ă����ÁA�ۈ�A��앪��̕������ɃI�����C���s�K���Ȃ���A���Ƃ��䏊�ɏ����Ęb���Ă����܂����B����Ŗ����ăR���i�ƌ��������Ă���W�҂̒��ɓ����čs����A��J��߂��݂̐��Ɏ����X���A�J���ė����̂ł��B���ꂾ���ɑ\���ɍs���Ă���̂��ǂ����A���S�z�Ȃ̂ł��v
��q�c�@�͓��{�ԏ\���Ж��_���قł���A��N11���ɂ́A�É��Ƌ��ɓ��Ԉ�ÃZ���^�[���I�����C���Ŏ��@�B���̌�A���Ԋ֘A��3�a�@���Ȃ��ŊŌ�t���畷���ꂽ����̘b�͂�2�l�ɑN��Ȉ�ۂ��c�����悤���B
���f���^���ψق����u�������v�o��c�����҂̔����œ��{�g��펖�ԁh�@8/31
�V�^�R���i�E�C���X������(�V�^�x��)�ō����������������Ċg�債�Ă���f���^�����܂��ψق����B�f���^���̕ψي��E�C���X�͓��{�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�B
31���A�m�g�j�����ɂ��ƁA������Ȏ��ȑ�w�����`�[���͍��N8�����{�A����w�t���a�@�Őf�Î����銳�҂���̎悵���f���^���̈�`�q���͂�ʂ��āu�m501�r�v�Ƃ����V���ȕψي��������B
�����`�[���͈�`�q�̓����Ȃǂ��l�������ꍇ�A���{�ŐV���ȕψي������������Ƃ݂Ă���B�����͂Ȃǂɑ��Ă͂܂��������Ă��Ȃ��B
�����`�[���̕��������E�y�����́u�������L����ƍ����ł����X�ƐV���ȕψي����o��\��������̂ŁA�Ȃ�Ƃ�������}����K�v������v�Ƙb�����B
���킹�ĕ������͈�`�q�͂���E�C���X�Ď��̐�������Ɋg�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������������炩�ɂ����Ƃm�g�j�͓`�����B
���{�͓����I�����s�b�N(�ܗ�)�ȍ~���V�^�R���i�̑����X�������������Ȃ��ł���B30���A�m�g�j�ɂ��ƁA�d�NJ��҂�18���A���ōő��L�^���X�V���Ă���B30���ɂ�1��3638�l�̊����҂��V���ɕ��ꂽ�B�d�NJ����҂�2075�l�ɒB����B
��7���̏h���Ґ� �V�^�R���i�O��4���� �ό��Ƃւ̐[���ȉe������ �@8/31
7���ɍ����̃z�e���◷�قȂǂɏh�������l�́A����3092���l�ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��O�̂��ƂƂ�7���Ɣ�ׂ�ƁA40���]�艺����Ă��āA�ό��Ƃւ̐[���ȉe���������Ă��܂��B
�ό����ɂ��܂��ƁA7���ɍ����̃z�e���◷�قȂǂɏh�������l�́A����l�ʼn���3092���l�ŁA���N�̓���������32.2�������܂����B�����A�����g��O�̂��ƂƂ�7���Ƃ̔�r�ł�40.3��������Ă��āA�ˑR�Ƃ��ĒႢ�����������Ă��܂��B���ł��A�O���l�̏h���Ґ��́A���ƂƂ�7������92.1�����Ȃ�85���l�ɂƂǂ܂�A�L�^�I�ȗ������݂������Ă��܂��B
�܂��A�S���̏h���{�݂̋q���ғ�����38.6���ŁA���N�̓������������Ă��܂����A63.3�����������ƂƂ�7���Ɣ�ׂ�ƒႢ�����ƂȂ��Ă��܂��B
���{�́A�����g����ċً}���Ԑ錾�̑Ώےn��������g�債�A���݂�21�̓s���{���ɐ錾���o����Ă��āA�h�����v�̉��ˑR�Ƃ��Č��ʂ��Ȃ��ł��B���{�́A������Ɏ��g�ޏh�����Ǝ҂ւ̎x�����s���s���{���������ʂŕ⏕����ȂǁA�x���𑱂��邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���ĂŃf���^���g��@���@���҂����������10���l���@8/31
�V�^�R���i�E�C���X�̃f���^���̊g��ŁA�����҂��Ăё������Ă���A�����J�ł͈��������̓��@���Ґ���10���l���܂����B
30���t�̃j���[���[�N�E�^�C���Y�ɂ��܂��ƁA�S�ĂŐV�^�R���i�Ɋ����������@���҂̐���2�J���O����500���������A29�����_��7���ԕ��ς͈��������10���l������܂����B�f���^���̊g����ē��@���Ґ����}�����A2���̐����ɋt�߂肷��`�ɂȂ�܂����B
2���̕a�@��ICU(�W�����Î�)��95�������܂�A�ꕔ�ł͐V�^�R���i�ȊO�̒ʏ�̈�ÑΉ����ł��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��AICU�ɓ���d�NJ��҂̑��������N�`����ڎ킵�Ă��炸�A�S�Ă̎��҂͈��������1000�l���Ă��܂��B
���V�^�R���i�u�Ⴍ�Ă��d�lj��v�A�y�ǂł��|���u���ǂ̃��X�N�v�@8/31
�V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̊����g�傪�����Ă��܂����A�u�Ⴂ�l�͏d�lj����Ȃ�����|���Ȃ��v�Ƃ������������悭���ɂ��܂��B����͖{���ł��傤���H
Q. �Ⴂ�l�́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɜ���Ă��d�lj����Ȃ�����A�|���Ȃ��H
A. �u�d�lj����Ȃ���Ε��C�v�ƍl���Ă���̂ł���A�傫�Ȋ��Ⴂ�ł��B�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ́A�Ⴂ�l�ł͏d�lj����ɂ����X��������Ƃ����͎̂����ł����A�d�lj����ɂ�������Ƃ����āg���ǂ��Ă������Ō��̐����ɖ߂��h�Ƃ������F���ł���Ɣ��Ɋ댯�ł��B�܂��A���������g�d�lj��h�̈Ӗ��𐳂��������ł��Ă��Ȃ����Ƃ������_�ɒ��ӂ��K�v�ł��B
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ́A����҂قǎ��S�E�d�lj����X�N�������X���ɂ���܂��B�������A���̂��Ƃ́u�Ⴂ�l�Ȃ玀�ȂȂ����d�lj������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���킯�ł͂���܂���B�����܂Łu���ɂɂ����v�u�d�lj����ɂ����v�Ƃ��������Ȃ̂ŁA�����E���ǂ���l��������A�S���Ȃ�l��d�lj�����l���K���ǂ����̃^�C�~���O�ŏo�Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���ہA�ψي��̉e���������āA����ł�20��ł�12.8���A30��ł�19.4���������Ljȏ�Ɉ������ē��@���Ă���Ƃ����f�[�^���o�Ă��܂��B
�܂��A�u�d�lj����Ȃ���A���ǂ��Ă������Ō��̐����ɖ߂��v�Ƃ����F�����A�Ԉ���Ă��܂��B�V�^�R���i�E�C���X�����ǂǂ����ꍇ�A��J����ċz����E�ߒɁA���o��Q�Ȃǂ̌��ǂ����������̂������c��A�����������ǂɂ���Đ����̎�(QOL)���ቺ����A���̎d���ɖ߂�Ȃ��Ƃ������g���u���̌����ƂȂ邱�Ƃ��m���Ă��܂��B
�����������ǂ́A�Ȃɂ�����҂ɂ��茻��Ă���킯�ł͂���܂���B�����A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̏Ǐy�ǂ��������߂Ɏ���×{������30�Έȉ��̎Ⴂ�l�����ł��A�����ȏ�̐l�����o��k�o�̑r���A�ċz����A�W���͂̒ቺ�A�L����Q�Ƃ��������ǂ�6�����ȏ���ꂵ��ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B�܂�A����×{���ł���قǂ̌y���Ǐ�ōςƂ��Ă��A���̌��6�����ȏ�����̐����ɂ͖߂�Ȃ����X�N������A�Ƃ������Ƃł��B
����ɁA�����Ŏg���Ă���u�d�lj��v�̈Ӗ���������Ă���l�����Ȃ�����܂���B�u�d�lj��v�Ƃ́A38������M���o����A�����ߒɂ�ؓ��ɁE���ɂ����ꂽ�肵�Ă����Ԃ̂��Ƃł͂���܂���B�����������ƁA�l�H�ċz��Ȃǂ̌����Â̂������łȂ�Ƃ����Ȃ��ɍς�ł���Ƃ����g�m���h�̏�Ԃ̂��Ƃ��Ӗ����܂��B
����A40���̍��M���o�āA�Ђǂ��P�Ƌ����ߒɁE�ؓ��ɂŖ�����ꂸ�A�H�����S���A��ʂ�Ȃ��E�E�E�Ƃ�����Ԃł����Ă��A�ċz����̏ǏȂ���u�y�ǁv�ɕ��ނ���܂��B�����̌��N�ȎႢ�l�ɁA�l���ōł�����ǂ��������v���o���Ă��炤�ƁA�C���t���G���U�Ȃǂɜ����39�����鍂�M���o���Ƃ���������l�͑����Ǝv���܂����A����́u�����ǁv�ł���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�܂�A�u�Ⴂ�l�͏d�lj����ɂ����v�Ƃ����̂��A�u�Ⴏ�����ǂ��ڂɑ������Ƃ͂Ȃ��A������Ƃ������ג��x�̏Ǐ�ɂ����Ȃ�Ȃ��v�ƔF�����Ă���̂ł���A����͑傫�ȊԈႢ�ł��B
���������u�d�lj��v��h���ɂ́A���N�`���ڎ킪�ɂ߂ėL���ł��B���ܖ��ƂȂ��Ă���f���^���ɑ��ẮA���N�`���̌��ʂ�����܂��Ă���X���ɂ͂���܂����A����ł��S���̖��Ӗ��ɂȂ����킯�ł͂���܂���B2��ڎ킩��2�T�Ԃ��o�߂���A80���߂������\�h���ʂ������邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B���̂��߁A�@�����Ă������_�ŁA���N�`���̐ڎ���ς܂��Ă������Ƃ����������߂��܂��B
�Ȃ����N�`���ڎ��A����2��ڐڎ�̗����`���X���ɂ�38�����锭�M������邱�Ƃ�����܂�(�����������������ɂ�锭�M�́A�ʏ�3���قǂŎ��܂�܂�)�̂ŁA���̓��͎d���Ȃǂ����x�݂ɂ��Ă����Ɨǂ��ł��傤�B�@
��1�����Ŋ��������͉\�H�@���N�`��3��ڂ͕K�v�H�@8/31
�����s��t�31���A�s���ŗՎ��L�҉���s���A���Ɠ����s����̗v���ɔ�����2���l�̉�������������Ë@�ւ�1�����ԁA�a���m�ۂ�l�ޔh���Ȃǂ̋��͂����߂����Ƃ\�����B1�����Ɗ�����݂������Ƃɂ��āA�����s��t��̔��莡�v��́u�������w�I�ȍ���������킯�ł͂Ȃ����A���̂��炢�Ȃ牽�Ƃ��K���Ɋ撣���B1�����̊Ԃɉ��炩�̌��������Ăق����v�ƍs����s���̋��͂����߂����A�����I��1�����Ŋ�����}���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂��B�W�c�ڎ킪�i�ރ��N�`���̌��ʂ����o��̂��A��ɏo�Ȃ��������s��t��̊p�c�O����������B
�\�\���L������Ń��N�`���ڎ킪�i��ł��邪�A�����g�傪�~�܂�Ȃ����R�́B
�u���N�`���͊����\�h�ɂ��d�lj��\�h�ɂ����ʂ�����܂��B�����A100��������Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�����I�Ɋ������L����Ȃ��A�����҂̕��ꂪ������Ώd�lj�����l��a���̂Ђ����Ƃ����������N���Ă��܂��v
�\�\���ɂȂ����烏�N�`���ڎ�ɂ��W�c�Ɖu�̌��ʂ��o��̂��B
�u���嗬�̃f���^����1�l���畽��5�l�Ɋ�������قNJ����͂������B���s�Đ��Y����1�ȉ��ɁA�܂�1�l���炤��l����1�l�ȉ��ɉ�������Ί����͌������Ă����B�P���v�Z�Ŋ�������5�l�̂�����4�l�A�l����80�������N�`����ł��I���A�f���^���̊g��͗}�����܂��B�����ɐi�߂�10�������ς��Ŋ�]�ҕ��̃��N�`���������̂ɍs���n��A11�����ɂ͐ڎ킪��������Ǝv���܂��v
�\�\�N���ɂ̓}�X�N�����Ȃ��Ă��悭�Ȃ�̂��B
�u�V�K�����Ґ��Əd�NJ��Ґ��̐��ڊώ@���ɂ߂ďd�v�B���ꂪ���炩�ɉ������Ă���A�ȑO�̐����ɖ߂��Ă��悭�Ȃ�Ǝv���܂��B�����A�t�@�C�U�[��2��ڎ��94���������܂����A�t�Ɍ�����6���̐l�ɂ͌����Ȃ��B�C���t���G���U�╗�ׂ��͂�鎞���ł��̂ŁA�������炭�}�X�N�͕K�{�ł��ˁv
�\�\3��ڈȍ~�̃��N�`���ڎ�͕K�v���B
�u����͕K�v���Ǝv���܂��B2��ڈȍ~�̐ڎ���u�[�X�^�[�ƌ����܂����A���������ƍR�̉�������I�ɏオ��B�����A���Ԃ��o�ɂꏙ�X�ɉ������Ă��āA���ɂ͂�����������l������B���Ăł�2��ڂ̐ڎ킩��8�������炢��3��ڂ̐ڎ��i�߂Ă��܂��B���N1��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���\���͂���܂��v
�\�\�������͑ł��тɂЂǂ��Ȃ�̂��B
�u����̓f�[�^���R�����A�܂��������Ă���܂���B�����A��x���������l�����N�`����łƋ����o��Ƃ����X���͂���B2��ڂ̕������������A�S�z�ȏꍇ�͐ڎ킷��O�ɍR�̉��𑪂��Ă݂�̂������߂��܂��B������ɂ���A�����ł͂Ȃ������g�̔��f�łƂ������ƂɂȂ�ł��傤�v
��10���̓��{�I�茠�����[�AU16�����[�̒��~�\�@8/31
���{���A�́A10��22������24���ɂ����Ĉ��Q��(�����^���������㋣�Z��)�ŊJ�Â�\�肵�Ă�����105����{�I�茠�����[�ƁA��52��U16������4�~100m�����[�̒��~�\�����B
�������ł�U18�E16��������Â���邪�A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��h�~�̊ϓ_����u���Ɋւ��l(�I��E�����ҁE���Z�����Ȃ�)��5000���ȉ��ɏk�����邽�߁v�ɒ��~�����߂��B�Ȃ��AU18�E16���̌l��ڂ͌����_�Ŗ��ϋq�����ł̊J�ÂɌ����ď������i�߂��Ă���B�܂��R���i�Ђő������~�E�����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ╔������~�ɂ��o�ꎑ�i�������Ȃ��Ƃ������������A�o�ꎑ�i�̈ꕔ�������B�܂��A�����ɎQ������I�肨��ш����҂͈��Q���ւ̗���72���Ԉȓ���PCR�����܂��͍R����ʌ������`���Â��A�A�����ʂ���������̎�t���ɒ�o���邱�Ƃ����߂��B
U18�E16����18�Ζ���(�j��15���)�A16�Ζ���(�j��11���)���o�ꂷ��S�����BU20���{�I�茠��6���ɓ��{�I�茠�ƕ��Â���Ă���B��N�����̌`���ŊJ�Â�\�肵�Ă������R���i�ЂʼnẴC���^�[�n�C�E�S�������~�ƂȂ������Ƃ��A�H�ɑ�֑��Ƃ��đS�����Z���A�S�����w���������{�������߁AU20�A18�A16�̑��͊J�Â���Ȃ������B���{�I�茠�����[�͍��Z�A��w�A���ƒc�܂ł��ꓰ�ɉ�ă����[���{��������A�j����4�~100m�����[�A4�~400m�����[�����{����Ă���B
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@ |


 �@
�@ |
|
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
|
�������h�~���d�_�[�u
|
|
���{���{���V�^�C���t���G���U�������ʑ[�u�@�̉����ɔ����A�V�^�C���t���G���U���ً}���Ԑ錾(�ً}���Ԑ錾�Ƃ�)�̎��ɎЉ�E�o�ϊ����ւ̉e���������炷�����g��(�p���f�~�b�N / �I�[�o�[�V���[�g)��h���[�u�̂��ƂŁA�S���I���}���Ȃ܂�h�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ă�����̂ł���B���̂́u�}���{�E�v(�܂�h�A���h)�B��q�̖�������u�܂h�~�[�u�v�u�܂h�~�v�u�d�_�[�u�v�ȂǂƗ�����邱�Ƃ�����B
|
�����̌o��
�s���Ăŋ�̓I�ȑ����Ȃ��Ƃ���Ă������{�̐V�^�R���i�E�C���X��̎������̌���Ƌً}���Ԑ錾�Ɏ���Ȃ��i�K�Ŋ����g���}�~���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����V�^�C���t���G���U�������ʑ[�u�@�A�����ǂ̗\�h�y�ъ����҂̊��҂ɑ����ÂɊւ���@��(�����ǖ@)�A���u�@�̉����@���A2021�N2��3���̎Q�c�@�{��c�Ŏ��R����}�A�����}�̗��}�Ɨ�������}�Ȃǂ̎^�������ʼn��A�������A�V�݂��ꂽ�B
|
�����ߗv��
���炩���ߊw���o���҂���Ƃ̈ӌ�������ōs�����ƂƂ��A�܂h�~���d�_�[�u�́A������߂������g��̎w�W�ł���4�i�K�̌x�����x���̂����A�ォ��2�Ԗڂɓ�����u�X�e�[�W3�v�����œK�p����B
����ɂ́A�錾���ߑO�̒n��̂ق��錾������̒n����ΏۂɂȂ肤��B
�܂��A�}���Ȋ����̊g��̒������킸���ɂł���������̂́A���ۂɊ������g�債�Ă��Ȃ��ꍇ(�X�e�[�W2����)�ł��K�p����\��������Ƃ��Ă���B
���{�́A�ً}���Ԑ錾���o���O�̗\�h�I�ȑ[�u�A�����g��������x�h�����߂̑[�u�Ƃ��ēK�p��ڎw���Ƃ݂��Ă���B
�������A�s���{���m������̔��ߗv�������ꍇ�́A�v�����ő�����d���āA���₩�Ɍ�������ƂƂ��ɁA�v���ɉ����Ȃ��ꍇ�́A�v�����s�����s���{���m���ɑ��A���̎�|�Ɨ��R���������Ƃ����߂��Ă���B
�@�@�@���̎����������ւ̌x���w�W
�x�����x���@/�@�u�w�@/�@��Ò̐� �@/�@�ڈ�
�X�e�[�W�W(��������) / ���҂������I�ɑ��� / ��Ñ̐������� / �ً}���Ԑ錾����
�X�e�[�W�V(�����}��) / �����҂��}���ɑ��� / ��Ñ̐��̕N�� / �����h�~���d�_�[�u����
�X�e�[�W�U(�����Q��) / �����҂����X�ɑ��� / ��Ñ̐��ւ̕��S���� / �����h�~���d�_�[�u����
�X�e�[�W�T(�����U��) / �����҂��U���I�ɔ��� / �ʏ��Ñ̐� / ����ȊO
|
�����߃G���A
�ً}���Ԑ錾�́A�s���{���P�ʂŔ��߂������̂́A�����h�~���d�_�[�u�́A���{���ΏۂƂ����s���{���̒m�����A�s�撬���ȂǓ���̒n������肷�邱�Ƃ��ł����{���ڎw���Ă���A������I�E�W���I�ȑ[�u�ƂȂ�B�܂��A���ԁE���A�ƑԂ��i�����[�u���@���I�Ɏ��{�ł���B
|
�����ߕ��@
�ً}���Ԑ錾�́A���{���{�������ً}���Ԕ����Ƌ��A���Ԃ�����������ɕ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂́A�����h�~���d�_�[�u�ł́A�����݂̂ō���ւ͖̕@�肳��Ă��Ȃ��B�������A�V�^�C���t���G���U�������ʑ[�u�@��R�c�����O�c�@���t�ψ���(2021�N(�ߘa3�N)2��1��)�y�юQ�c�@���t�ψ���(����4��)���ꂼ��̕��ь��c�ɂ����č���ւ̑��₩�ȕ����߂��Ă���A���c��S����b�́u���̎�|���\�����d���Ă܂��肽���v�Ɣ������Ă���B�������A���ь��c�ւ͖̕@�I�S���͂�����킯�ł͂Ȃ��A���ꂼ��̏����C�ӂ̂��̂ł���B
|
�����ߊ���
�ً}���Ԑ錾��2�N�ȓ��̔��߂��\�����A�����h�~���d�_�[�u�ł́A6�J���ȓ��ł̔��߂��\�ł���B�܂��A�ً}���Ԑ錾�ł́A���v1�N���Ȃ��͈͂ŕ��������邱�Ƃ��ł��邪�A�����h�~���d�_�[�u�Ɍ����ẮA����ł��������邱�Ƃ��\�B
|
���c�Ǝ��ԒZ�k
���c�Ǝ��Z�v��
�ً}���Ԑ錾�Ɠ��l�ŁA���H�X�Ȃǂł̊������X�N��}���邽�߁A�w�肳�ꂽ�s���{���̒m���͈��H�X�Ȃǂɉc�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v�����o�����Ƃ��\�ł���B��Ɍߌ�8���܂ł̎��Z�v����z�肵�Ă���B
���c�Ǝ��Z����
�ً}���Ԑ錾�Ɠ��l�ŁA���H�X�ł̊������X�N��}���邽�߁A�w�肳�ꂽ�s���{���̒m���͈��H�X�Ȃǂɉc�Ǝ��Ԃ̒Z�k���߂��o�����Ƃ��\�ł���B��Ɍߌ�8���܂ł̎��Z���߂�z�肵�Ă���B�܂��A���߂ɍۂ��ė������茟�����\�Ƃ��Ă��āA��������ꍇ�͉ߗ����Ȃ����B
|
���X�܋x��
���x�Ɨv��
�ً}���Ԑ錾�ł́A���H�X�Ȃǂł̊������X�N��}���邽�߁A�w�肳�ꂽ�s���{���̒m���͈��H�X�Ȃǂɋx�Ƃ̗v�����s�����Ƃ��\���������A�����h�~���d�_�[�u�ł́A�x�Ƃ̗v�����s�����Ƃ͏o���Ȃ��B
���x�Ɩ���
�x�Ɨv���Ɠ��l�ŁA�ً}���Ԑ錾�ł́A���H�X�Ȃǂł̊������X�N��}���邽�߁A�w�肳�ꂽ�s���{���̒m���͈��H�X�Ȃǂɋx�Ƃ̖��߂��s�����Ƃ��\���������A�����h�~���d�_�[�u�ł́A�x�Ƃ̖��߂��s�����Ƃ͏o���Ȃ��B
|
���{�ݎg�p
���{�ݎg�p��~�v��
�ً}���Ԑ錾�ł́A�C�x���g�ȂǂŎg�p����{�݂̎g�p���~����v�����ł��邪�A�C�x���g�Ȃǂɂ��{�݂̎g�p��~��v�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B
���{�ݎg�p��~����
�ً}���Ԑ錾�ōs�����Ƃ��ł���{�݂̎g�p���~���閽�߂́A�����h�~���d�_�[�u�ōs�����Ƃ͏o���Ȃ��B
|
���O�o�K��
���O�o���l�v��
�ً}���Ԑ錾���̂悤�ȑ�K�͂ȊO�o���l��v�����邱�Ƃ͏o�����A���i����s���Ă���s���{���m����e�����̂̎s�撬�����̊O�o�̎��l��v���ł���悤�ȏ��K�͂ȑ傫�ȉe���͂������Ȃ��v���݂̂Ɍ�����B
���O�o�֎~�v��
�ً}���Ԑ錾�����l�A�O�o���֎~����@�I�S���͂�����悤�Ȃ��Ƃ��s�����Ƃ͖@����ł��o���Ȃ��B
���O�o�֎~����
�ً}���Ԑ錾�����l�A�@�I�S���͂����悤�ȊO�o�֎~�𖽗߂���悤�Ȃ��Ƃ͏o���Ȃ��B
|
�����ߒ��̍s��
�E�Z�v��������Ă��鎞�ԑтɈ��H�X�ɖς�ɏo���肵�Ȃ�����
�E�s�v�s�}�̊O�o�E�ړ��̎��l
�E���G���Ă���ꏊ�⎞�Ԃ�����čs�����邱��
�����߂��Ă���B
|
�����ߒ��̓X�܊�����
�E���H�X�ɂ�����20���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k�v��
�E�{���S�̂ł̃C�x���g�̐l������
�E�A�N�����̐ݒu���܂߂��K�C�h���C���̏���̓O��
�E�����g��n��ɂ����郂�j�^�����O�����̊g�[
�E����Ҏ{�ݓ��̏]�Ǝғ��ɑ��錟���̕p����{
�ȂǁA���i�̊�{�I�������������w���ݍ���������s�����Ƃ����߂��Ă���B
|
�����ߒ��̊�����
�E�e�s���{���m������߂���Ԃ�[�u���ɂ����ẮA���H�X�Ȃǂł�20���܂ʼnc�Ǝ��Ԃ̒Z�k�����A��ނ̒�11������19���܂łƂ��邱��
�E���J���I�P�ȂǂŃN���X�^�[���������Ă���Ɋӂ݁A���c�Ƃ̃X�i�b�N�A�J���I�P�i���ȂǁA���H����Ƃ��ċƂƂ��Ă���X�܂ɂ����āA�J���I�P���s���ݔ�����Ă���ꍇ�A���Y�ݔ��̗��p�͎��l���邱��
�E�e�s���{��������H�X�ɑ��āA�u���������҂̐����Ȃǁv�u���������҂ɑ���}�X�N�̒��p�̎��m�v�u�����h�~�[�u�����{���Ȃ��҂̓���̋֎~�v�u��b���̔ɂ�銴���̖h�~�Ɍ��ʂ̂���[�u(���Ղ邱�Ƃ��ł���Ȃǂ̐ݒu�܂��́A���p�҂̓K�ȋ����̊m��)�v�Ȃǂ̑[�u�̗v�����������ꍇ�́A���͂��邱��
�E��K�͂ȏW�q�{�݂ɂ����āA�e�s���{������c�Ǝ��Ԃ���ꐮ���Ȃǂɂ��ē����������������ꍇ�́A���͂��邱��
�E�Ǝ�ʃK�C�h���C���̏��炵�A�����Ƃ��đ[�u�����̑S�Ă̈��H�X���ɑ��Ď��n�œ����������s���A�K�C�h���C�������炵�Ă��Ȃ����H�X���ɂ��ẮA�ʂɗv�����s�����Ƃ�����
�E�Z���́A���Z�v��������Ă��鎞�ԑтɁA���H�X�ɂ݂���ɏo���肵����A�������܂߂��s�v�s�}�̊O�o�E�ړ��̎��l�⍬�G���Ă���ꏊ�⎞�Ԃ�����čs�����A�����O�ꂳ��Ă��Ȃ����H�X�̗��p�͎��l����
�E�m������߂���ԋy�ы��ōs����Õ�)�ɂ��ẮA��ẤA���肵���K�͗v���ɉ����ĊJ�Â���
�E���Ǝ҂́A�E��ւ̏o�Γ��ɂ��āA�u�o�ΎҐ���7���팸�v��ڎw�����Ƃ��܂ߐڐG�@��̒ጸ�Ɍ����A�ݑ�Ζ�(�e�����[�N)��A�o���K�v�ƂȂ�E��ł����[�e�[�V�����Ζ�����O�ꂷ�邱��
�ȂǁA�l�X�ȋً}���Ԑ錾���Ɠ����悤�Ȍ������������߂��Ă���B
|
�������K��
�ً}���Ԑ錾�ł́A�s���{���̒m���̗v���▽�߂ɓ��i�̗��R���Ȃ������Ȃ������ꍇ30���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ���邪�A�����h�~���d�_�[�u�ł́A20���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ����B��̓I�ɂ́A���H�X�Ȃǂ̎��Ǝ҂��A�s���{���m������o�鎞�Z�v���ȂǂɁu�����ȗ��R�Ȃ��v�����Ȃ������ꍇ�ɉȂ���邱�Ƃ�����B�������A�ߗ��̓K�p�ɓ������ẮA�����̎��R�ƌ������N�Q����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�T�d�ɉ^�p���邱�ƂƁA�s���̐\���Ă�A���̑��̋~�ς̌�����ۏႷ�邱�Ƃ���߂��Ă���B
|
�����͋�
�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���ɉ��������H�X�ɂ�1���ő�6���~�̋��͋����͎x�������j���������̂́A����ő�4���~�̋��͋��Ɍ��z�ƂȂ����B�܂��A�ً}���Ԑ錾�̎��̋��͋���6���~�ƂȂ����B
|
�����߂̎���
���{��2021�N4��1���A�{�錧�A���{�A���Ɍ���3�{���ɑ��A4��5������5��5���܂ł̗\��ŁA���߂Ă܂h�~���d�_�[�u�߂��邱�ƂƂȂ����B
����1��̔���
2021�N3����{�ȍ~�ɋ{�錧�A3�����{�ȍ~�ɁA3��1����2�x�ڂً̋}���Ԑ錾���������ꂽ���{�ƕ��Ɍ��ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����Ґ����}���������Ƃ���A2021�N4��1���A���{�͋{�錧�A���{�A���Ɍ���3�{���ɑ��A4��5������5��5���܂ł̗\��œK�p�����B�Ώۂ̎����͉̂��L�̒ʂ�ł���B
�{�錧�@���s
���{�@���s
���Ɍ��@���s�E���{�s�E�����s�E�_�ˎs
|
�������҂̓��@
�����h�~���d�_�[�u���ߎ��Ɍ��炸�A���̑��̏ꍇ�ł��K�p����邪�A���@�����ۂ�����A���@�悩�瓦�����肵���ꍇ�A���̊����҂�50���~�ȉ��̉ߗ����Ȃ����Ƃɂ���Ă���B�������A��Ì���ʼn~���ɉ^�p���Ȃ����悤�ɁA���̎菇�Ȃǂ���₷�������ƂƂ��ɁA�K�p�ɂ��Ă̋�̓I�ȗ�ȂǁA�K�p�̓K�ۂf����ޗ����ł�����薾�m�Ɏ����A�h���{�݂⊴���҂̎���Ȃǂ̏��܂߁A�{�l��A���̎q���⍂��҂Ȃǂ̐����ێ��ɔz������ƂƂ��ɁA�K�v�ȑΉ����s�����Ƃ���߂��Ă���B
|
���Վ���Î{�݂̐ݒu
�Վ��̈�Î{�݂𐭕{���{�����ݒu���ꂽ�i�K����J�݂ł��邱�Ƃ��ً}���Ԑ錾���͔F�߂��Ă�����̂́A�����_�ł͂܂h�~���d�_�[�u���ߒ��̏ꍇ�ł��Վ��̈�Î{�݂�ݒu���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B
|
���ϋɓI�u�w����
�����h�~���d�_�[�u���ߎ��݂̂Ȃ炸�A���̑��̏ꍇ�̏ꍇ�ł��Ȃ���邪�A�ی����������o�H�ׁA�Z���ڐG�҂̓���⊴�����ׂ��肷��u�ϋɓI�u�w�����v�����ꍇ��30���~�ȉ��̉ߗ��Ƃ����B�������A�|�������[�[�A����������(PCR����)�Ȃǂ̌������ۂɂȂ��邨�����ی����̑Ή��\�͂����܂��A�T�d�ɍs�����ƂƂ��A����ʼn~���ɉ^�p���Ȃ����悤�A���̎菇�Ȃǂ���₷�������ƂƂ��ɁA�K�p�ɂ��Ă̋�̗�ȂǁA�K�p�̓K�ۂ̔��f�ޗ����ł�����薾�m�Ɏ������Ƃ���߂Ă���B
|
���a���m��
�����h�~���d�_�[�u���ߎ��݂̂Ȃ炸�A���̑��̏ꍇ�ł��K�p����邪�A�V�^�R���i�E�C���X���@���ҕa���̊m�ۂ̂��߂Ɍ����J����b�Ȃǂ���Ë@�ւɊ���������A����ɉ����Ȃ��@�֖������\������ł���悤�ɂ����B
|
�����̑�
���{�́A�����h�~���d�_�[�u�̑Ώےn��ł́A�{�ݏ]�ƈ��̌�����f�����߁A�}�X�N���p�ȂNJ����h�~�ɕK�v�ȑ[�u���Ƃ�Ȃ��l�͓�����֎~����[�u���Ƃ�Ɣ��\�����B�������A�����Ƃ��ė�����̓��ӂčs�����ƂƂ��āA���ӂ������Ȃ��ꍇ�������͂̍s�g�Ȃǂ͍s��Ȃ����Ƃ���߂��Ă���B
|
���܂h�~���d�_�[�u�̐Z����
�܂h�~���d�_�[�u�́A�Ⴂ����𒆐S�ɐZ�����Ă��炸�A�F�m�x���Ⴂ���Ƃ����O����Ă���B�܂��A���̂��Ƃ���A��@�������炢�ł���Ƃ������ƂɊւ��Ă��뜜������Ă���B
|
�����́u�܂�h�v���߂�����
�O�q�̒ʂ�A2021�N4���ɂ܂h�~���d�_�[�u�����K�p�ƂȂ邱�Ƃ���A�}�X�R�~�Ȃǂł́u�܂�h�v�u�}���{�E�v�ȂǂƗ�����ċL���ɋL�ڂ���邱�Ƃ��������B���̗��̂͊������S������V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ����i���̂�����t���[������J���ȂȂǐ��{���œ��N1�������痪�̂��g���n�߁A�������̂��������߁A�S���҂̊ԂŁu���ցv�Ŏg�����̂������������ʁA�u�܂�h�v�ƂȂ����Ƃ����B���������ł́A�u�܂�d(�܂イ)�v�����サ�Ă����Ƃ����B���̗��ꂪ�ɂ킩�ɒ��ڂ���o�����̂́A���N3��18���̋L�҉�ŐV�^�R���i�E�C���X�����ȉ�̔��g���u�܂�h�v�Ƃ��т��є����������ƂƂ����B
�������A���̗��̂ɂ��Ắu��@����ٔ����ɂ�����v�ƌ������ᔻ�I�Ȉӌ�������A4��1���̎Q�c�@�c���^�c�ψ���Ő����N���V�^�R���i�E�C���X���S����b���u�w�܂�h�x�Ƃ����������͊�{�I�Ɏg��Ȃ��悤�ɂ��Ă���B������Ƃӂ������悤�ȕ��͋C������v�Ɣ�������ȂǁA�t���E�����̎���ᔻ���o�Ă���A���т��юg�p���Ă������g���u�w�܂�h�x�Ƃ������t�̎g�������K�ł͂Ȃ��B�w�d�_�[�u�x�̕����ǂ��v�Ɨ�����g��Ȃ����Ƃ�\�����Ă���B�܂��A���ނ̃}���{�E�����̉w��J�C�݂̃g���[�h�}�[�N�ɂȂ��Ă���{�錧�C����s���u(�����{��k�Ђ����)�ċN���������̉w�ɂƂ��Ă��}�C�i�X�C���[�W�ƂȂ肩�˂Ȃ��v�Ƃ��āA����3���܂łɁA�e�ЂɌ����āu�w�܂h�~���d�_�[�u�x���w�܂�h�x�Ɨ������ƂɐT�d�ɂȂ��Ăق����v�Ɨv�]���镶�����o���Ă���B
���̈���ŁA�܂h�~���d�_�[�u�ɏ悶�āA�]�ˎ���̍�i�u�u�a�����}���{�E�v���a�̎R�s�������قœW�����s����Ȃǂ̔���������B �@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
|
�����b�N�_�E�� 1 |
�����NJg��h�~�Ȃǂ̂��߁A�l�X�̊O�o��s���𐧌�����[�u�B�V�^�R���i�E�C���X�̊�����}���������ƁA�e���͂���܂ŊO�o�֎~�߂Ȃnj������[�u�����ō̗p�����B�p����t�����X�͕K�{�̔����o���Ȃǂ������ĊO�o���ւ��A�ᔽ�҂ɂ͔������Ȃ����B�č��̃j���[���[�N�B�̓X�[�p�[���ǂȂǂ������B���̑S���Ǝ҂ɁA�S�Ă̘J���҂̍ݑ�Ζ����`���t�����B�����҂̌����Ȃǂ��ď����������Ă���B
���{�͖@����̃n�[�h��������A�C�O�̂悤�ȃ��b�N�_�E���͂ł��Ȃ��B�ً}���Ԑ錾�Ɋ�Â��ĕs�v�s�}�̊O�o���l��v������ɂƂǂ߁A�x�Ɨv���Ō������o�c�ɂ��鎖�Ǝ҂ւ̋��t���ȂǂŎ��������������悤�Ƃ����B��p�����b�N�_�E���͂����A��^�̓W����̎��l��i�C�g�N���u�ȂLjꕔ�Ǝ�̉c�ƒ�~�Ƃ������h�u�[�u�Ŋ����҂����炵���B
�s�s�����ɂ��Ă��ً}���Ԑ錾�ɂ��Ă��A�l�X�̐ڐG�����炷��ł͗L���Ȉ���A�o�ς�ٗp�ɂ����炷�e�����r��Ȃ���n�̌����B�u�����͂ł��Ȃ����A�g�������Ȃ��v(�W�����\���p��)�Ƃ����v���͑����̍��ɋ��ʂ���B�������Ċg�債�Ă��鑫���ł��S���K�͂ł̐����[�u�͔����A�o�ςƂ̗�����T�鎎�݂������B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����b�N�_�E�� 2 (lockdown) |
�댯�⍷�����������ЁE���X�N�Ȃǂ𗝗R�ɁA������G���A�֓�������A��������o����A���̒����ړ�������(���̂����ꂩ��܂��͕���)�����R�ɂł��Ȃ��ً}�̏������B�s�s�S�̂�����ꍇ�͓s�s�����Ƃ��Ă�邪�A���{��̎����ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A���݂̂Ƃ����`���Ȃ��B
�l�X�̈ړ���A���O��������{�I�ɐ��{�⎩���̂������I�ɋ֎~���邱�Ƃ��Ӗ�����ꍇ������B�܂��A�ً}���Ԃɂ����Đl�̈ړ��E��Ɗ���������@�I�����������čs����Ƃ̌���������B���{�ɂ�����u�ً}���Ԑ錾�v�u���l�v���v�Ƃ͈قȂ�Ƃ��錩��������B
�����̕����̏ꍇ�A�O�ɏo��h�A�����b�N���o����ł��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��u�h�����E���b�N�_�E��(drill lockdown)�v�Ƃ����B�u�t���E���b�N�_�E��(full lockdown)�v�́A�l�X�����݂̏ꏊ�ɂƂǂ܂�A�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ����߂��A�o����͋֎~�����B
|
�����
�ً}���b�N�_�E�� (emergency lockdown) �Ɨ\�h���b�N�_�E�� (preventive lockdown) �Ƃ�����B
���\�h���b�N�_�E��
�\�h���b�N�_�E���ł́A���S���m�ۂ��邽�߂ɁA�l���������ł̂�����댯��������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�ň��̃V�i���I��V�X�e���̐Ǝ㐫�ɑΏ������\�h�[�u�ł���B�\�h���b�N�_�E���̌v�悪�Ȃ���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�l���̑����Ȃǂ��}���ɃG�X�J���[�g����\��������B
���ً}���b�N�_�E��
�ً}���b�N�_�E���́A�l���ɑ��鍷�����������Ђ܂��̓��X�N������ꍇ�Ɏ��{�����B�O������̐N���҂ɑ��Ă̊w�Z�ɂ�����ً}���b�N�_�E���̎菇�́A�Z���ȒP�ł���K�v������B�ȒP�Ȏ菇�́A�����ɂ킽��P���̑���ɁA����I�ȗ��K�Ŏ��m���邱�Ƃ��ł���B1999�N�̃R�����o�C�����Z�e���ˎ����ȍ~�A�A�����J�̊w�Z�ł́A�ً}���b�N�_�E���̎菇���w�Z�ɂ���ĈقȂ�A�W���I�Ȏ菇�𑱂�����̂�����A���Ђɑ���ϋɓI�ȃA�v���[�`�𐄏�����w�Z������B
���Y����
�p�ꌗ�ł͈�ʂɃ��b�N�_�E���Ƃ����p��́A�Y�����ł̎��l�̈ړ��̐�����Ӗ�����B���l�̖\���ł̓t���E���b�N�_�E�������{�����B
���a�@
�a�@�̃��b�N�_�E���ɂ��ẴA�����J���O���̃K�C�h���C���ł́A��d�A�n�k�A�^���A�Ύ��A���e��l���ɂ�鋺���A�e���˂Ȃǂ̃A�N�e�B�u�V���[�^�[ (active shooter) �Ȃǂ̃P�[�X���L�ڂ���Ă���B�ق��A���炩�̊�Q�̍l�����镨���Ȃǂɂ�鉘���A�\���A�q�ǂ��Ȃǂ̗U�����Ăɂ��Ă��l������Ă���B�����Ƃł́A������W���������肷�邽�߂ɐ������~���ĉ��P���邱�Ƃ��w���B���b�N�_�E���C�x���g (lockdown event) �ƌĂ��B
|
�����{��
���A�����J���������e������
2001�N�ɃA�����J���������e�������������������ɂ͖��ԗ̋�3���ԕ������ꂽ�B
���N���i���\��(�V�h�j�[)
2005�N�ɂ̓I�[�X�g�����A�̃V�h�j�[�ŁA���o�m���n��҂Ɣ��l��҂Ƃ̊ԂŃN���i���\�������������B�j���[�T�E�X�E�F�[���Y�B���{�́A�ً}���ԂɊւ��ďB���̓���n��Ɠ��H�����b�N�_�E�����錠�����x�@�ɗ^���A�x�@�̓T�U�����h�E�V���C�A�Ȃǂ����b�N�_�E�������B2008�N1��30���A�u���e�B�b�V���R�����r�A��w (UBC) �ŋ��Ђ����������Ƃ��ĉ����J�i�_�R�n�x�@��6���ԃ��b�N�_�E�����A�E����w����͌������ɑҋ@�����B
���{�X�g���}���\�����e�e������
2013�N�̃{�X�g���}���\�����e�e�������ł̓{�X�g���s���S�悪���b�N�_�E������A�e�����X�g�̒T�����Ȃ��ꂽ�B
���p�����������e������
2015�N�̃p�����������e�������̍ۂ́A�x���M�[�Ń��b�N�_�E����2���ԑ�����ꂽ�B���N�A���T���[���X����w�悪�e���̋��Ђɂ�蕕�����ꂽ�B
���V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̐��E�I���s
���ؐl�����a��(�ȉ��A����)�̌Ζk�ȕ����s��2019�N���ɔ�������SARS�R���i�E�C���X2�ɂ��V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̗��s�ł�2020�N�ɓ����Ă���p���f�~�b�N(���E�I���s)�������N�����A�����A�C�M���X�AEU�A�}���[�V�A�A�A�����J���O���̃J���t�H���j�A�B��j���[���[�N�B�A�k���N�̊J��s�A�C���h�ȂǂŃ��b�N�_�E���[�u�����{���ꂽ�B�܂��������ɂ͔�펖�Ԑ錾�����߂������A�����҂������X���Ɍ���ꂽ���ߌo�ϊ����D��Ƃ��ꕔ�ɘa����Ȃǂ����B���������̌�A�����҂��}���ɑ����������߁A�C�M���X��h�C�c�A�t�����X�Ƃ��������[���b�p�Ȃǂł͍Ăу��b�N�_�E�������s�����B�R���i�E�V���b�N�ƌĂ����̐��E�I�Ȍo�ύ���Ɋׂ��Ă��邽�߁A1�x�ڂ����K�����ɘa�������b�N�_�E�������s�������������B
�����I�ȃ��b�N�_�E���E�������� (partial lockdown) �ł́A�Z���̊����̈ꕔ�����������B��ԊO�o�֎~�߂Ȃǂ����̗�ł���B
���S�����A�t���E���b�N�_�E���ł́A�Z���̂قƂ�ǂ̊����𐧌����邪�A�Љ�̊�{�C���t���X�g���N�`���[(���{�ł����Ƃ���́A�����郉�C�t���C��)�Ȃǂ̋@�\���~���邱�Ƃ͂��Ȃ��B��ǁA��X�A�H���i�X�A�����p�i�X�A���ݎs��A�K�\�����X�^���h�A�C���X�A�a�@�A�f�Ï��A��s�A�،���ЁA�ی���ЁA�x����ЁA������ʋ@�ցA�X�ցA�����A�ʐM�A�@�ցA�_�ƁA�{�Y�A���Y�A�H�i���Y�A����A�����p�i���Y�A�d�͉�ЁA�K�X��ЁA�S�~�����A�Α���A�x�@�A���h�A���h�A�����x���A���x���A�ŊցA�������Ȃǂ̓��b�N�_�E�����Ԓ�����O�Ƃ��Ċ����g��h�~����u���ċ@�\���ێ�����B �܂����H�X�Ȃǂ͓X�����H�͔F�߂��Ȃ����A�����A��Əo�O�ɂ��Ă͔F�߂��鎖������B
|
�����{�ł̎��{�ɂ���
���{�ɂ����ă��b�N�_�E�����s���邱�Ƃ͂Ȃ��A�����������̂悤�ȏ��ɒu����鎖���ʏ�Ȃ����A2020�N�̐V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̗��s�ł�4���ɓ����̈��{�W�O������b(�ȉ��A���{����)�����ً̋}���Ԑ錾�߂����B�������A���O���̂悤�ȊO�o�����𐧒肵�A�ᔽ�҂ɔ������x��݂��郍�b�N�_�E���͓��{�ł͍s���Ă��Ȃ��B���{���{����́u�O�o���l�v���v�Ƃ̌`�ōs���Ă���A�����⋭���͂����R�Ȃ��B
���{�����ɂ��ƁA���{�����@����і@����A���b�N�_�E����O�o�����A�ᔽ�҂ւ̔������x�ȂLj�؏o���Ȃ��ƌ�����B���{����O�̑���{�鍑���@�ɂ͍��Ƌً}���̋K�肪���������A���{�����@�ɂ͑��݂��Ȃ����߃��b�N�_�E���͕s�\�Ƃ������ł���(����E���̔��Ȃ��獑�Ƃ̖\����h���ӎ����������Ƃ����)�B���̂��ߓ��{�ł͐��A��ЊQ�ȂǗL���̍ۂ͌ʂ̖@����V�݁A�������đΉ����Ă����o�܂�����B
|
���e��
���S���I�e��
���_�Ȉ�{���X�E�V�������j�N�́A���b�N�_�E���͐����̂��߂ɕK�v�ȑ[�u�����A�l�̐S�����낵���قLj������A���ɂ��Ƃ��ƐS�̕s�����������l�A�c�����̃g���E�}������l�A�b�܂�Ȃ����ň�����l�A�ƒ���ɕs�a������l�A�o�ϓI�ɕs����Ȑl�Ȃǂɗ^����_���[�W���傫���A�p�j�b�N��Q���Ĕ�������A�}���̍�����ԂɂȂ����肵���P�[�X���������Ǝw�E���Ă���B���̌����Ƃ��Ċ�����̎h�����Ȃ��Ȃ�����A����������v�֓����������Ȃ��Ȃ����肷�銴�o�Ւf������A����͓Ɩ[�̎��l�A�����͏�g���A��ɂɒ����؍݂��錤���ҁA���m�q�C�D���Ȃǂ��o�����邱�ƂŁA�s����Q�Ɋׂ����肷��B
���o�ϓI�e��
���b�N�_�E���́A�o�ς�ٗp�̈����Ȃǐr��ȉe����^���镛��p���͂�ނƎw�E����Ă���B
|
���R���s���[�^
�R���s���[�^�Ȃǂ�IT�ɂ����āA�Z�L�����e�B�����̂��߂�OS��A�v���P�[�V�����Ȃǂ̋@�\�𐧌�����d�g�݂̂��ƁB
�@ |
|
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
 �R���i�Њg��@�ً}���Ԑ錾�u���܂��Ȃ��v
�R���i�Њg��@�ً}���Ԑ錾�u���܂��Ȃ��v �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@



 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@




 �@
�@ �@
�@




 �@
�@ �@
�@





 �@
�@ �@
�@




 �@
�@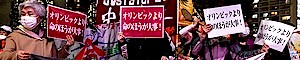 �@
�@




 �@
�@ �@
�@




 �@
�@ �@
�@




 �@
�@ �@
�@

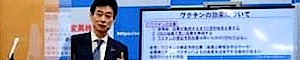

 �@
�@ �@
�@ �@
�@





 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@

 �@
�@

 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@