 �@ �@
���_�O���X�E�}�b�J�[�T�[ �@ |
|
[Douglas MacArthur / 1880-1964]�@�A�����J�̌R�l�A���R�����B�A�����R�ō��i�ߊ��߂��B�R�[���p�C�v���g���[�h�}�[�N�ł������B�}�b�J�[�T�[�̃J�i�\�L�̓}�b�N�A�[�T�[�Ƃ���Ă���ꍇ������B �@ |
����������
�}�b�J�[�T�[�Ƃ͌��X�̓X�R�b�g�����h�M���̌��ŁA�L�����x�������̗�������݁A�X�R�b�g�����h�Ɨ��푈�Ń��o�[�g1���ɗ^���čL��ȗ̓y�����A���̌�͗̎哯�m�̐��͑����ɔs��A�v�������Ɠ`�����Ă���B1815�N�ɑc���̃A�[�T�[�E�}�b�J�[�T�[�E�V�j�A(�p���)�̑�ɃX�R�b�g�����h����A�����J�Ɉږ����A�}�b�J�[�T�[�Ƃ̓A�����J�����ƂȂ����B�Ȃ��A�����X�R�b�g�����h�n�̃t�����N�����E���[�Y�x���g�Ƃ�7�̉ƌn�A�E�B���X�g���E�`���[�`���Ƃ�8�̉ƌn���u�Ă����ʊW�ɂ�����B
���A�[�T�[�E�}�b�J�[�T�[�E�W���j�A��16�̂���ɓ�k�푈�ɏ]�R������������̌R�l�ł���A��k�푈���I����Ĉ�U�͏������A�c���Ɠ��l�ɖ@���̕��������������������A1866�N�ɂ͌R�ɍē������Ă���B1875�N�Ƀj���[�I�[�����Y�̃W���N�\�����ɂɋΖ����ɁA���@�[�W�j�A�B�m�[�t�H�[�N���܂�Ń{���`���A�̕x�T�ȖȉԋƎ҂̖��ł��������A���[�E�s���N�j�[�E�n�[�f�B�ƌ������A1880�N�ɌR�l�ł��镃�̔C�n�ł������A�[�J���\�[�B���g�����b�N�̕���ɂ̕��c�Ń}�b�J�[�T�[�Ƃ̎O�j�Ƃ��ă_�O���X�E�}�b�J�[�T�[���a�������B���̍��͐����J��̖����ŁA�C���f�B�A���Ƃ̐킢�̂��߁A�����n��̂����炱����ɌR�̍Ԃ��z����Ă���A�}�b�J�[�T�[�����܂��5�����̎��A��Ƃ̓j���[���L�V�R�B�̃E�B���Q�[�g�ԂɌ��������ƂƂȂ������A���̒n��1883�N�Ɏ��j�̃}���R�����a�����Ă���B�}���R���̕a���͕ꃁ�A���[�ɑ傫�ȏՌ���^���A�c��2�l�̑��q�A���ɎO�j�_�O���X��M������悤�ɂȂ����B�����Ńt�H�[�g�E�Z���f���̍Ԃɕ��A�[�T�[���]���ƂȂ�A�Ƒ����t���Ă������B���̂��߃_�O���X�́A�c�����̂قƂ�ǂ��R�̍Ԃ̒��Ő������邱�ƂƂȂ����B
���̌����Ƃ͑S���̔C�n��]�X�Ƃ��邪�A1898�N�ɕĐ��푈���n�܂�ƕ��A�[�T�[�͏y���ƂȂ�A�X�y�C���̐A���n�ł������t�B���s���ɏo���A�}�b�J�[�T�[�Ƃƃt�B���s���̐[�����̎n�܂�ƂȂ����B�푈���I���A�t�B���s�����X�y�C�����A�����J�Ɋ��������ƁA�����ɏ��i���t�c���ɂȂ��Ă������A�[�T�[�͂��̌�Ɏn�܂����Ĕ�푈�ł����A�݃t�B���s���̃A�����J�R�i�ߊ��ɏ��i�����B�������A1892�N�ɌZ�A�[�T�[�̓A�i�|���X�C�R���w�Z�ɓ��w���A1896�N�ɂ͊C�R���тƂ��ĔC�����A��_�O���X���E�F�X�g�|�C���g���R�m���w�Z��ڎw���������������Ƃ���A�Ƒ��̓t�B���s���ɕt���Ă����Ȃ������B
�Ȃ��A�_�O���X�͗c�����A�ꃁ�A���[�ɂ���ăt�����X�̕��K�ɕ킢�A���q�̊i�D���������Ă����B���̂��Ƃ̐l�i�`���ւ̈��e�����뜜�������ɂ���āA���R�m���w�Z�ɓ��w�������邱�ƂɂȂ����Ƃ������Ă���B �@ |
�����R����
1896�N�A�}�b�J�[�T�[�͐��e�L�T�X�m���w�Z���ƌ�A�E�F�X�g�|�C���g�̃A�����J���R�m���w�Z�ɕK�v�ȑ哝�̂�L�͋c���̐��E�����Ȃ��������߁A�ꃁ�A���[�Ƌ��ɗL�͐����Ƃ̃R�l��������}�b�J�[�T�[�Ƃ̒n���~���E�H�[�L�[�ɋA��A�ꃁ�A���[���`���ʂ��Ď莆���������Ƃ���A���@�c���V�I�{���h�E�I�[�`�F���̐��E�邱�Ƃɐ��������B���̌�A�E�F�X�g�T�C�h�����w�Z�ɓ��w�A1�N�����̊��Ԏ����A1899�N��750�_���_��700�_�̍����_�Ńg�b�v���w�����B���q��M�����S�z����ꃁ�A���[�́A�킴�킴�w�Z�̋߂��̃N���j�[�Y�E�z�e���Ɉڂ�Z�݁A���q�̊w�������ɖڂ����点�邱�ƂƂ����B���ǃ}�b�J�[�T�[�����Ƃ���܂ŗ���Ȃ��������߁A�u�m���w�Z�̗��j�ŏ��߂ĕ�e�ƈꏏ�ɑ��Ƃ����v�Ƃ��炩���邱�ƂƂȂ����B
�����̃E�F�X�g�|�C���g�͋��ԈˑR�Ƃ����g�D�ł���A�㋉���ɂ�鉺�����ւ̂������Ƃ������̂����߂����s���Ă����B���e���L���ŁA��e���߂��̃z�e���ɏ풓���t���Y���Ă���Ƃ����ڗ����݂ł������}�b�J�[�T�[�́A���ɔO����ɂ������ꂽ�B���̂������́A�����E�F�X�g�|�C���g�̗��j�̒���100�ȏ���l�Ă���A��Ȃ��̂ł́u�{�N�V���O�I��ɂ��S�����فv�u���ꂽ�K���X�̏�ɕG�����đO��������v�u�Ώ�����M���̏������C�ӂ߁v�u�������ꂾ�����̏��S���ŃX���C�f�B���O������v�Ȃǐ��܂������̂ł������B���̂��������s���镺�ɂ͐��k��������u��b���Ɂv�ƌĂ�Ă����B�}�b�J�[�T�[�͂悭�����ɑς������A�Ō���z�����N�����Ď��_�����B�}�b�J�[�T�[�͎��_�ōς��A�V�����̒��ł������ɂ�鎀�S�҂��o�Ė�艻���邱�ƂɂȂ����B��������ɌR�@��c���J����A�ł������������������}�b�J�[�T�[���ؐl�Ƃ��ČĂꂽ���A�}�b�J�[�T�[�͌������Njy�ɂ�������炸�A�������������㋉���̖����Ō�܂Ŗ��������A�S�Z���k���瑸�h����������Ă���B
�݊w���͐��є��Q�ŁA4�N�̍݊w���Ԓ��A3�N�͐��уg�b�v�ł������B�X�|�[�c�����ӂł��������A��ԍD�X�|�[�c�͖싅�ł������B�o�b�e�B���O�����ŁA�����Ē��S�I��ł͂Ȃ��������A�ϋɉʊ��œ����g�����v���[�����ӂł���u�s�ޓ]�̃_�O�v�ƌĂ�A�����ł͊��Ă����B�������싅�ɔM�����邠�܂萬�т����������߁A4�N���ɂ͖싅�������ς�Ǝ~�߁A1903�N�ɍ݊w���Ԓ���2,470�_���_�̂���2,424.2�_�̓��_��98.14%�Ƃ������т����߁A94���̐��k�̎�Ȃő��Ƃ����B���̃}�b�J�[�T�[�ȏ�̐��тő��Ƃ����҂͂���܂�2���������Ȃ�(���o�[�g�E���[�����̂����̈�l�ł���)�B���ƌ�͗��R���тŔC�������B
�����̃A�����J���R�ł͍H�������G���[�g�E�O���[�v�Ƃ݂Ȃ���Ă����̂ŁA�}�b�J�[�T�[�͍H�������u�肵�A��3�H����������ƂȂ�A�A�����J�̐A���n�ł������t�B���s���ɔz�����ꂽ�B�����t�B���s�������̎n�܂�ł������B1905�N�ɕ������I�푈�̊ϐ�C���̂��߂̒����A�����J���O����g�ٕt�������ƂȂ����B�}�b�J�[�T�[�������Ƃ��ē��{�̓����ŋΖ������B�}�b�J�[�T�[�͓��I�푈���ϐ킵���Ǝ���̉�z�L�ɏ����Ă��邪�A�ނ����{�ɓ��������̂�1905�N10���ŁA�|�[�c�}�X����ł���A�L���Ⴂ�Ǝv����B���̌�}�b�J�[�T�[�ƉƑ��͓��{���o�����A�����Ⓦ��A�W�A���o�R���ăC���h�܂�8���������āA�e���̌R����n�����@���s���Ă���A���̎��̌o�����}�b�J�[�T�[�̌�̌R���ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ����B�܂��A���̗��s�̍ۂɓ��{�œ��������Y�A��R�ށA�T�؊�T�A���؈������I�푈�Ŋ����i�ߊ������Ɩʒk���A�i�v�ɏ����邱�Ƃ��Ȃ����������Ƃ��Ă���]�B
���̌�A�����J�ɋA�������}�b�J�[�T�[��1906�N�ɃZ�I�h�A�E���[�Y�x���g�̗v���ŁA�哝�̌R���ږ�̕⍲���ɔC����ꂽ�B�}�b�J�[�T�[�̎�ۂ̂悢�d���Ԃ�������]���������[�Y�x���g�̓}�b�J�[�T�[�Ɂu���сA�N�͑f���炵���O�������B�N�͑�g�ɂȂ�ׂ����B�v�Ə̎^�̌��t�������Ă���B�����ȌR�������ł����}�b�J�[�T�[�ł��������A1907�N�Ƀ~���E�H�[�L�[�̒n��H�����ɔz�������ƁA�~���E�H�[�L�[�ɍݏZ���Ă����T���ȉƒ�̖��t�@�j�[�x���E���@���E�_�C�N�E�X�`�����[�g�ɐS��D���A�R���ɐg�������Ă��Ȃ����Ƃ��㊯�̃E�B���A���EV�E�W���h�\�������Ɍ�������Ă��܂��A�W���h�\���͍H�����i�ߊ��ɑ��āu�w�K�ӗ~�Ɍ����v�u�Ζ����Ԃ����Ď������e�͈͂ƍl���鎞�Ԃ߂��Ď�����ɖ߂炸�v�u�}�b�J�[�T�[���т̋Ζ��ԓx�͖����������̂ł͂Ȃ������B�v�ƕ��Ă���B���̕ɑ��ă}�b�J�[�T�[�͌������R�c�������A�}�b�J�[�T�[���~���E�H�[�L�[�ɂ������Ԃ͌R���ɑS���S���������A�X�`�����[�g�����������Ƃ����ɊS���W�����Ă������Ƃ͎����ł���A���̐l���]���͍H�����i�ߕ��ɐ��F���ꂽ�B����܂ŏ����ł������}�b�J�[�T�[�̌R���̏��߂Ă��T���ł���A���ǂ́A�����܂œ��ꍞ���������炸�A���܂ł̐l���ő����������Ƃ̂Ȃ��厸�s�ɒ��ʂ������ƂƂȂ����B�����̌o���ւ̈��e�������O�����}�b�J�[�T�[�͈�O���N���A�����̕]����҉邽�ߍH�����̃}�j���A���u�R���I�j��v���쐬���H�������̎w�����ɒ�o�����Ƃ���A���̃}�j���A���͗��R�P���w�Z�̋��ނɍ̗p����邱�ƂƂȂ����B���̃}�j���A���ɂ���č��܂���킸�����N��Ƀ}�b�J�[�T�[�͍��܂��������A�Ăэ����]�����邱�ƂƂȂ����B���̌�A�}�b�J�[�T�[��1911�N�ɑ�тɏ��i����ƁA��3�H�����̕����y�эH���P���w�Z�̋����ɔC������A1912�N�ɂ͗��R�Ȃɉh�]����ȂNj}���ɏo���X����i��ł������ƂƂȂ����B �@ |
����ꎟ���E���
1913�N�Ɏn�܂������L�V�R�v���Ńr�N�g���A�[�m�E�E�G���^���R�����͂������������A�E�G���^���������F���Ȃ��A�����J�̃E�b�h���E�E�E�B���\���哝�̂ƑΗ����邱�ƂƂȂ������߁A�E�G���^�ɒ����𐾂����L�V�R�����A�����J�R�̊C�������m���S�����A�^���s�R���������������B�A�����J�̓��L�V�R�ɕ��m�̉���Ǝ����ւ̎Ӎ߁A����ɐ������ɑ���21���̗�C��v���������A���L�V�R�͕��m�̉���ƌ��n�i�ߊ��̎Ӎ߂ɂ͉���������C�͋��ۂ����B���S�����E�B���\���͑吼�m�͑���1�͑��i�߃t�����N�EF�E�t���b�`���[�Ƀx���N���X�̐�̂𖽂���(�A�����J���O���ɂ��x���N���X���(�p���))�B
�������s�X��ɂ���̂����x���N���X�� ���I�i���h�E�E�b�h(�p���) �Q�d�����͑����𑗂荞���A������2�t�c�̑�5���c�ɒ�@�v���Ƃ��āA������тł������}�b�J�[�T�[��ѓ��������B�}�b�J�[�T�[�̔C���́u���s���ɗL�v�Ȃ����������肷��v�Ƃ����������W����ȔC���ł��������A�}�b�J�[�T�[�̓x���N���X�ɓ���������5���c���A���͕s���ɂ�蓮�������Ȃ����Ƃ�m��A���L�V�R�R�̏��C�@�֎Ԃ�D�悷�邱�Ƃ��v���������B�}�b�J�[�T�[�̓��L�V�R�l�̓S���J���Ґ��l������ƁA�P�g�Ńx���N���X���65�q���ꂽ�A���o���[�h�܂Ő����A���ʎ҂̎x���ɂ��3���̏��C�@�֎Ԃ̒D��ɐ��������B���̌�A�}�b�J�[�T�[���g�̏،��ł͒nj����Ă����R�n���ƌ������e����̏�A�}�b�J�[�T�[��3�����e�e���R�����ђʂ���������ŋR�n�������ނ��A�����Ƀx���N���X�܂ŋ@�֎Ԃ������A���Ă����B�}�b�J�[�T�[�͂��̊���ɂ�蓖�R���_�M�͂����炦����̂Ɗ��҂��Ă������A��5���c�̗��c�������̂悤�Ȗ��߂������Ă��Ȃ��Ə،��������ƁA�܂��e����̌������ʎ҂̃��L�V�R�l�ȊO�ɏؐl�͂��炸�M�����ɖR�������Ƃ��A���_�M�͂̎��^�͌������A�}�b�J�[�T�[�͎��]���邱�ƂƂȂ����B
���̌�Ƀ}�b�J�[�T�[�͗��R�Ȃɖ߂�A���R���������E�L��ǒ��ɏA�����B1917�N4���ɃA�����J���C�M���X��t�����X�A���{�ȂǂƂƂ��ɘA�����̈ꍑ�Ƃ��đ�ꎟ���E���ɎQ�킷�邱�Ƃ����܂����B�A�����J�͐푈�����̂��ߋ}����1917�N5���ɑI�������@�𐧒肵�����A�����������P�����I���Đ��ɔh�������ɂ�1�N�͕K�v�Ǝv��ꂽ�B
�}�b�J�[�T�[�̓j���[�g���E�f�B�[���E�x�C�J�[���R�����Ƌ��Ƀz���C�g�n�E�X�֍s���āA�E�B���\���Ɂu�S��26�B�̏B�����������s���R�Ƃ��ă��[���b�p�ɔh�����ׂ��v�ƒ�Ă����B�E�B���\���̓x�C�J�[�ƃ}�b�J�[�T�[�̒�Ă��̗p�����̎��s���w���������A�ǂ̏B�̕������ŏ��Ƀt�����X�ɔh�����ׂ������Y�܂������Ƃ��ĕ��サ���B�x�C�J�[�͏B���ǒ��E�B���A���EA�E�}��(�p���)�y���ƃ}�b�J�[�T�[�Ɉӌ������߂����A�}�b�J�[�T�[�͒P�Ƃ̏B�ł͂Ȃ��������̏B�̕����Ŏt�c��Ґ����邱�Ƃ��Ă��A���̒�ĂɎ^�������}�����u�S26�B�̕����ŕҐ����Ă͂ǂ����v�ƕ⑫����ƁA�}�b�J�[�T�[�́u����͂����ł��ˁA��������Ύt�c�͑S���ɓ��̂悤�ɂ����邱�ƂɂȂ�܂��B�v�ƌ������B�x�C�J�[�͂��̈Ă��̗p����42�t�c(�p���)��Ґ������B�t�c���ɂ̓}���A�����ď����������}�b�J�[�T�[���K�����i�����卲�Ƃ��Q�d���ɔC�������B�푈�ɎQ���������Ă��܂炸�A�m�荇���̋L�҂Ɂu�^�̏��i�̓t�����X�ɍs�����҂ɗ^������ł��낤�B�v�Ǝv���̂�����ł������Ă����}�b�J�[�T�[�ɂ͊�]�ʂ�̐l���ł������B��42�t�c�́u���C���{�[�t�c�v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ����B
��42�t�c��1918�N2���ɐ�������ɎQ�킵���B�}�b�J�[�T�[���艖�ɂ����Ĉ琬�������m�͗E�҂ɐ킢�A�����̎����҂��o���Ȃ���������B�A�����J����ꎟ���E���Ńt�����X�ɔh�����������̒��ł́A���K�R�ƊC�����ŕҐ����ꂽ���s����������2�t�c�Ɏ����v���x�Ƃ��ꂽ�B�}�b�J�[�T�[���Q�d���ł���ɂ�������炸�A�O���ɏo���������B���K�̌R���͐g�ɒ������A�w�����b�g���炸��ɌR�X�𒅗p���A�������^�[�g���l�b�N�̃Z�[�^�[�ɕꃁ�A���[���҂�2�������钷���}�t���[����Ɋ����A����̂���J�[�t�u�[�c�𗚂��āA����̑���ɏ�n�ڂ�������肵�߂Ă���Ƃ����ڗ��i�D�ł������B
�}�b�J�[�T�[�͑O���̒�@�����璼�ڍs�����Ƃ�����A�x�X�댯�Ȗڂɂ����Ă���B�ԗ��ɏ���Ē�@�����ۂɂ̓h�C�c�R�̋@�֏e�Ɏˌ�����A�ԗ��͔j�ꂽ���}�b�J�[�T�[�͊�ՓI�ɖ����ł������B�܂������̃p�g���[�������𗦂��Ė�Ԓ�@�����ۂɂ́A�h�C�c�R�̓ŃK�X�U�����A�}�b�J�[�T�[�ȊO�̕��m�͑S���펀�����Ƃ������Ƃ��������B�}�b�J�[�T�[�͂��̌�A��42�t�c�̑�84���c�̗��c���ɏA�C���A�x��O�ɂ͈ꎞ�I�Ɏt�c�����s�݂ƂȂ������߁A�y���Ȃ����42�t�c�𗦂������Ƃ��������B�}�b�J�[�T�[�͑�ꎟ���E��풆�ɐ��ɂ�����2�����A�O���̌M�͂��܂߂�15�̌M�͂���͂����B
���̃��[���b�p�h���R(AEF) �̑��i�ߊ��̓W�����E�p�[�V���O�ł��������A�p�[�V���O�͑O������y������Ŏw�����Ƃ�A�O���̖��w�����̋�\�������Αނ������Ƃ���A�����Ƃ̊Ԃ��a瀂������邱�Ƃ��������Ƃ����A���Ƀ}�b�J�[�T�[�͂��ꂪ�����Ńp�[�V���O�ɔᔻ�I�ԓx���Ƃ�悤�ɂȂ�B
�������A�}�b�J�[�T�[�̕ꃁ�A���[�́A�v�A�[�T�[���݃t�B���s���̃A�����J�R�i�ߊ�����������ɁA������тł������p�[�V���O�̖ʓ|���݂Ă����Ƃ����`��𗊂��āA�}�b�J�[�T�[�𑁂����i������悤�ɂƒQ�肷��莆�����т��ё����Ă����B�܂��x�C�J�[�ɂ������悤�Ȏ莆�����ʂ������Ă���B���̂��������A��풆�Ƀ}�b�J�[�T�[�͏y���ɏ��i���Ă���A���A���[�̓p�[�V���O�Ɂu���q�͋M���̊��҂𗠐�Ȃ��͂��ł��B�v�Ƃ�������̎莆�𑗂��Ă���B�܂��A����Ƀp�[�V���O���Q�d�����ɏA�C����ƁA�u���q�𑁂������ɏ��i�����ė~�����v�Ƃ̎莆�������Ă���B���A���[�̓}�b�J�[�T�[��M�����邠�܂�ߕی�ł���A���O��1909�N�ɕv�A�[�T�[���R��ޖ������ۂɂ́A�}�b�J�[�T�[�̏�����J���āA�S�����G�h���[�h�E�w�����[�E�n���}���Ɂu���R�������Əo���������d���ɏA���������A�M���̑s��Ȋ�Ƃ̂ǂ����Ōق��Ă͂��炦�Ȃ����낤���v�Ƃ����莆�������Ă����B �@ |
����Ԋ�
����Ƀ}�b�J�[�T�[�́A��Z�ł��闤�R�m���w�Z�̍Z���ɏA�C����(1919�N - 1922�N)�B����39�ƎႩ�����}�b�J�[�T�[��煘r��U�邢�A�m���w�Z�̌Â��̎������v���Č���I�ȌR�l���琬�����ւƕϖe�������B�}�b�J�[�T�[���݊w���ɒɂ߂���ꂽ�������̈��K�����S�ɔp�~����A�������̕���ƂȂ��Ă�����b���ɂ��������B����ɋ��Z�X�|�[�c�ɗ͂�����A���Z��ڂ�3���(�싅�E�t�b�g�{�[���E�o�X�P�b�g�{�[��)����17��ڂɑ��₵�A�S���Q���̍Z�����Z�����J�Â��邱�ƂŒc���S���{��ꂽ�B���̎w�����j�͌��i�ł���A�����̐��k�́u�D���������k����R���镔���Ƀ}�b�J�[�T�[�������Ă���ƁA5�������Ȃ������ɑS���̐S���̂悤�ɐ��C�ɂ��������B����Ȃ��Ƃ��ł����̂͐��E���Ń}�b�J�[�T�[������l�ł��������낤�B�v�Ɖ�z���Ă���B�}�b�J�[�T�[�͂��̎w�����j�Ŏm�����̊Ԃł͕s�l�C�ł���A������A�m�������l���}�b�J�[�T�[�ɍR�c�ɂ������Ƃ����������A�}�b�J�[�T�[�͌���̌�����������Ɂu���{�Ƃ̐푈�͕s���ł���B���̎��ɂȂ�A�����J�͐��I�ȌP����ςm�����K�v�ƂȂ�B�E�F�X�g�E�|�C���g���L�\�Ȏm���̔y�o�Ƃ����g�����ǂꂾ���ʂ����������푈�̋A���������邱�ƂɂȂ�B�v�ƌ����ĕ�������ƁA����͔[�����āA����ȍ~�͕s�������킸�Ɏw���ɏ]�����B
���̌�A1922�N�ɉ��̐[���t�B���s���̃}�j���R�Nj�i�ߊ��ɔC�����ꒅ�C����B���̍ہA���N���������ŏ��̍ȃ��C�[�Y�E�N�����E�F���E�u���b�N�X(�p���)���Ẵt�B���s���s���ƂȂ����B���C�[�Y�͑�x���̖��ŎЌ��E�̉ԂƌĂ�Ă������߁A2�l�̌����́u�R�_�ƕS�����҂̌����v�Ƒ����ꂽ�B���̐l���ɂ��ẮA���C�[�Y���p�[�V���O�Q�d�����̌����l�ł���A�����D�����}�b�J�[�T�[�ɑ��鎄���̐l���ƐV���ɏ������Ă��A�p�[�V���O�͂킴�킴�V�����ʏ�Ŕے肹����Ȃ��Ȃ����B�������A�����p�[�V���O�̓��C�[�Y�ƕʂ�20�̃��[�}�j�A�����ƌ��ۂ��Ă���A���C�[�Y�̓p�[�V���O�ƕʂꂽ��A�p�[�V���O�̕����W�����E�L���[�N�}�C���[���܂ސ��l�̌R�l�ƊW����ȂǗ����������ł������B
���̃t�B���s���Ζ��Ń}�b�J�[�T�[�́A��̃t�B���s���E�R�����E�F���X(�Ɨ��������{)����哝�̃}�j���G���E�P�\���Ȃǃt�B���s���ɐl������邱�Ƃ��ł����B��1923�N�ɂ͊֓���k�Ђ������A�}�b�J�[�T�[�̓t�B���s�������{�ւ̋~�������A���̎w�����Ƃ��Ă���B�����̌��т��F�߂��A1925�N�ɃA�����J���R�j��ŔN���ƂȂ�44�ł̏����ւ̏��i���ʂ����A�č��{�y�֓]���ƂȂ����B
�����ɂȂ����}�b�J�[�T�[�ɍŏ��ɖ�����ꂽ�C���́A�F�l�ł���E�B���A���E�~�b�`�F���̌R�@��c�ł������B�~�b�`�F���͍q��啺�_�̔M�S�Ș_�҂ŁA�����̗��_�̐��������������߁A������͂�W�I�͂��q��@�̔����ɂ�茂������f�����X�g���[�V�������s�Ȃ��A��ꎟ���E��풆�ɃA�����J�ɋ�R�̊�ՂƂȂ�ׂ����̂����ꂽ�ɂ�������炸�A���{�����̌�̋�R�͂̔��W��ӂ����Ƃ��āA�������ᔻ���Ă����B�R�ɑ��Ă��n���C�A�I�A�t���̖h��̐���}���ӌ������\������A�R���q����̗v������\�Z�����F���Ȃ��͔̂ƍߍs�ׂɓ������A�ȂǂƉߌ��Ȕ������J��Ԃ��A���̎��Ɉ߂𒅂��ʔ������w�R�ւ̐M�������Ă����x�w�R�̒����ƋK���ɗL�Q�ȍs�ׁx�ƊŘ�A�R�@��c�ɂ������邱�ƂƂȂ����̂ł���B�}�b�J�[�T�[�́A���A�[�T�[�ƃ~�b�`�F���̕��e�������ł������W�ŁA�~�b�`�F���Ə��N���ォ��F�B�t�����������Ă���A���̌R�@��c�̔����ƂȂ�C�����u���������߂̒��ň�Ԃ�肫��Ȃ����߁v�ƌ����Ă���B�}�b�J�[�T�[�͔����̒��ŗB��u���߁v�̕[�𓊂������~�b�`�F���͗L�߂ƂȂ�1926�N�ɏ��������B���̌�A�~�b�`�F���̗\���ʂ�q��@�̎��オ�������A�~�b�`�F���͂��̐挩�̖����F�߂��A����10�N��ƂȂ�1946�N�ɖ��_����āA�����̊K���Ƌc��_�����M�͂��②���ꂽ�B
1928�N�̃A���X�e���_���I�����s�b�N�ł̓A�����J�I��c�c���ƂȂ������A�A���X�e���_���ŐV���L�҂Ɉ͂܂ꂽ�ہu��X�������֗����̂͂���i�ɔs���邽�߂ł͂Ȃ��B��X�͏����߂ɗ����̂��B���������I�ɏ����߂Ɂv�Ɠ������B�������A�}�b�J�[�T�[�̈ӋC���ݒʂ�Ƃ͂Ȃ炸�A�A�����J�͑O��̃p���I�����s�b�N�̋����_��45����22�ɔ������A�O�]���̊��ɂ͐��т͐U���Ȃ������B�A�����J�����̎��]�͑傫���A�I��c�ɘA�����̐�����ꂽ�B���̑��ł͓��{�����i���A�j�㏉�̋����_����2�l�����Ă���B�����_�����O�i���Ŋl�������D�c���Y�͏I�펞�ɁA�}�b�J�[�T�[���A�����J�̏��R�ł��������Ƃɋ������Ƃ����B
�}�b�J�[�T�[���I�����s�b�N�ŃA���X�e���_���ɂ������A�ȃ��C�[�Y���A�����J�ɂĕ����̒j���ƕ��C�����Ă����ƐV���̃S�V�b�v���ŕ�ꂽ�B���C�[�Y�͐V�������͒m�l��ʂ��A�����̗��R�����W�����E�E�B���Q�C�g�E�E�B�[�N�X�ɁA�u�_�O���X�����i�ł���悤�Ɉꔧ�E���łق����A�H���͂����琿�����Ă���Ă��悢�v�Ɠ���������قǁA�v�}�b�J�[�T�[�ɐs�������Ƃ��Ă������A�ؔ��Ȑ��������߂����C�[�Y�ƃ}�b�J�[�T�[�͐��i�����킸�A1929�N�ɂ͗������������Ă���B���C�[�Y�Ƃ̕v�w�����ł̘b�͌�ɃS�V�b�v�����A�ʔ����������}�X�R�~�Ɏ��グ���ă}�b�J�[�T�[��Y�܂��邱�ƂɂȂ�B
�����̂��������ŏ��S�̃}�b�J�[�T�[�ɁA�݃t�B���s���E�A�����J���R�i�ߊ��Ƃ��čēx�t�B���s���Ζ���������ꂽ���A�}�b�J�[�T�[�͂��̈ٓ����u���ɂƂ��Ă���قǂ�낱�����C���͂Ȃ������B�v�Ɗ��}���Ă���B�}�b�J�[�T�[�͓����̃A�����J�l�Ƃ��Ă͐�i�I�ŁA�A�W�A�l�ɑ��鍷�ʈӎ������Ȃ��A�P�\����t�B���s���l�G���[�g�ƑΓ��ɕt�������F���[�߂��B�܂��A�A�����J���R�t�B���s���l����(�t�B���s���E�X�J�E�g)�̑ҋ������P���A������}���Ă���B���̓����͓��{���}���ɐ��͂�L���A�t�B���s���ɂ����{�l�̔_�ƘJ���҂⏤���l�������ږ����Ă��Ă���A�}�b�J�[�T�[�͋��ЂɊ����Ėh�q�͂̋������K�v�ƍl���Ă������A�A�����J�{���̓t�B���s���h�q�ɏ��ɓI�ŁA�t�B���s���ɂ�17,000���̕��͂�19�@�̍q��@�����Ȃ��A�}�b�J�[�T�[�̓��V���g���Ɂu�Q���킵���قǂɎ�́v�Ƌ����R�c���Ă���B�P�\���͂��̂悤�Ƀt�B���s���ɑ��Đe�g�ȃ}�b�J�[�T�[�ɋ������A�w�����[�E�X�e�B���\���̌�C�̃t�B���s�����ɏA�C���邱�Ƃ�������B�}�b�J�[�T�[���A���ĕ��A�[�T�[���A�C�������̍�����]���Ă���A�P�\����Ɉ˗����t�B���s�����}�b�J�[�T�[�̐��E��𑗂点�Ă���B�������H��͎��炸�A���ɂ͑O���R�����̃h���C�g�E�t�B���[�E�f�C���B�X���A�C�����B
�������ł́A1929�N�Ƀ}�j���ō����̏��D�G���U�x�X�E�C�U�x���E�N�[�p�[(�p���)�Ƃ̌��ۂ��n�܂������A�}�b�J�[�T�[49�ɑ��A�C�U�x���͓���16�ł������B �@ |
�����R�Q�d����
1930�N�A�哝�̃n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�ɂ��A�A�����J���R�ŔN����50�ŎQ�d�����ɔC�����ꂽ�B���̃|�X�g�͑叫�E�ł��邽�߁A�������璆�����o���ɁA�ꎞ�I�ɑ叫�ɏ��i�����B1933�N���畛���ɂ́A��̑哝�̃h���C�g�ED�E�A�C�[���n���[���t�����B
�O�N�́u�Í��̖ؗj���v�ɒ[�������E���Q�ɂ��A���R�ɂ��R�k�̈��͂������Ă������A�}�b�J�[�T�[�͋c��ȂnjR�k�����߂鐨�͂��u���a��`�҂Ƃ��̓��ҁv�ƌĂсA�����͋��Y��`�ɓł���Ă���ƒf���A�������G�ӂ��ނ��o���ɂ��Ă����B�����A�A�����J���R�͐��E��17�Ԗڂ̋K�͂����Ȃ��A�|���g�K�����R��M���V�����R�ƕς��Ȃ��Ȃ��Ă����B�܂�����������ł���A�ΖC�͑�ꎟ���E��펞�Ɏg�p�������̂����S�ŁA��Ԃ�12�������Ȃ������B�������c��͂���Ȃ�R����팸�����܂�A�}�b�J�[�T�[�̎Q�d�����ݔC���̎�Ȏd���́A���̏������R���̋K�͂���邱�ƂɂȂ����B
1932�N�ɁA�ޖ��R�l�̒c�̂������O���������߂ă��V���g��D.C.�ɋ����鎖��(�{�[�i�X�A�[�~�[)�����������B�S������W�܂����ޖ��R�l�Ƃ��̉Ƒ��͈ꎞ�A22,000���ɂ�������B���Ɏv�z�����Ȃ����̍��^���ł��������A�}�b�J�[�T�[�́A�{�[�i�X�A�[�~�[�͋��Y��`�҂ɐ����A�A�M���{�ɑ���v���s��������Ă���A�ƍ����̂Ȃ����������Ȃ����B�ޖ��R�l��̓e���g��������ă��V���g��D.C�ɋ����������A�A��̌�ʔ�̎x���Ȃǂ̉��_��ŁA�������ł��邪���U���čs�����B�������A�t�[���@�[��}�b�J�[�T�[���䖝�����҂����̂ɂ�������炸10,000�����c�������߁A�Ƃ��ς₵���t�[���@�[�哝�̂��x�@�ƌR�ɁA�f�����̔r���𖽗߂����B�}�b�J�[�T�[�̓W���[�W�E�p�b�g���������w����������A�R���A�@�B���������v1,000���̕����𓊓����A���Ŗ���R�̑ޖ��R�l���ǂ��U�炵�����A�����̃A�C�[���n���[��̒������������A�t�[���@�[����̖��߂ɔ����A�A�i�R�X�e�B�A���n�͂��đޖ��R�l��̃e���g�����Ă������A�ޖ��R�l��ɐ����̎��҂Ƒ����̕����҂��������B�}�b�J�[�T�[�͖�̋L�҉�ŁA�u�v���̃G�[�e���Ōە����ꂽ�\�k����������v�ƒ����s���͐����ł���Ǝ咣�������A��肷���Ƃ������̐��͓����ɍ��܂邱�ƂƂȂ����B
�}�b�J�[�T�[�͎����ւ̔��̒��É���}�邽�߁A�{�[�i�X�A�[�~�[�ł̑Ή��Ŕ���L�����������W���[�i���X�g�̃h���r�[�E�s�A�\���ƃ��o�[�g�ES�E�A�����ɑ��A���_�����̑i�ׂ��N�������A�������ăW���[�i���X�g���G�ɉ��ƂɂȂ�A�s�A�\����͓����W���j�ǂ��Ă����}�b�J�[�T�[�̗��l�C�U�x���̑��݂グ��ƁA�}�b�J�[�T�[���哝�̂◤�R�����Ȃǖڏ�ɑ��ĕ��J�I�Ȍ��������Ă������Ƃ�A�������ɂ��Ă̏����C�U�x�������肵�Ă���B���̌�A�}�b�J�[�T�[�ƃs�A�\����͖��_�����̑i�ׂ���艺�������ɁA�X�L�����_���Ƃ��ċL���ɂ��Ȃ����Ƃ�C�U�x���ɈԎӗ������ƂŘa�����Ă���B
�t�[���@�[�̓{�[�i�X�A�[�~�[�ł̑Ή��̕s��ۂ�A���Q�ɑ���L���Ȑ�����Ƃ�Ȃ��������߁A�t�����N�����E���[�Y�x���g�ɑ哝�̑I�ŗ��j�I��s���i���Đ��E�����������A���[�Y�x���g���t�[���@�[�Ɠ��l�ɁA�s����Ə̂��ČR���\�Z�팸�̕��j�ł������B�}�b�J�[�T�[�̓��[�Y�x���g�Ɂu�哝�͍̂��̈��S���������Ă���A�A�����J�����̐푈�ɕ����ĕ������������ʑO�Ɍ����̌��t�͑哝�̖̂��O���v�Ǝ��C�o��ŋl�ߊ�邪�A���Ǘ��R�\�Z�͍팸���ꂽ�B�}�b�J�[�T�[�̓��[�Y�x���g���i�߂�j���[�f�B�[������ɂ͏I�n���̎p���ł��������A���[�Y�x���g���j���[�f�B�[������̈�Ƃ��čs���� CCC(���Ԏ����ۑ���)�ɂ�鎸�Ǝҋ~�ςɑ��A���R�̑g�D�͂�w���͂����p���ċ��͂��A�����̐����ɑ傫���v�����Ă���B
�}�b�J�[�T�[�͎j�㏉�̎Q�d�����ĔC����]���A���[�Y�x���g���܂��ӌ��͍���Ȃ��Ȃ�������̔\�͂������]�����Ă���A�b��I��1�N�ԁA�Q�d�����̔C�����������Ă���B �@ |
���t�B���s������
1935�N�ɎQ�d������ޔC���ď����̊K���ɖ߂�A�t�B���s���R�̌R���ږ�ɏA�C�����B�A�����J�͎����̐A���n�ł���t�B���s����1946�N�ɓƗ������邱�Ƃ����肵�����߁A�t�B���s�������ɂ��R���K�v�ł������B����哝�̂ɂ̓P�\�����\�肳��Ă������A�P�\���̓}�b�J�[�T�[�̗F�l�ł���A�R���ږ�̈˗��̓P�\���ɂ����̂������B�}�b�J�[�T�[�̓P�\��������ꂽ�A18,000�h���̋��^�A15,000�h���̌��۔�A���n�̍ō����z�e���ŃP�\�����I�[�i�[�ƂȂ��Ă����}�j���E�z�e���̃X�C�[�g�E���[���̑؍ݔ�ɉ����Ĕ閧�̕�V�Ƃ����j�i�̏����ɋ������A��Ɍo�ϓI�ȗ��R�ɂ��R���ږ�c�ւ̏A�C���������Ă���B
�t�B���s���ɂ͎Q�d�������ォ����������āA�A�C�[���n���[�ƃW�F�[���Y�ED�E�I�[�h���������Ƃ��Ďw�����ѓ��������B�A�C�[���n���[�͍s�������Ȃ��ƍl���Ă���u�Q�d��������ɋt��������炵�߂悤�Ƃ��Ďw�������v�Ɗ������ƌ�Ɍ���Ă���B
�t�B���s���s���̉q�D�u�v���W�f���g�E�t�[�o�[ (S.S. President Hoover) �v�ɂ�2�Ԗڂ̍ȂƂȂ�W�[���E�}���[�E�t�F�A�N���X������Ă���A�D���2�l�͈ӋC�������āA2�N���1937�N�Ɍ������Ă���B�܂��A�ꃁ�A���[�����悵�Ă������A���ɑ̒�������Ă��蒷���̔��������Ă��A�}�b�J�[�T�[�炪�}�j���ɓ�������1������ɖS���Ȃ��Ă���B
1936�N2���Ƀ}�b�J�[�T�[�́A�ނ̂��߂ɂ킴�킴�݂���ꂽ�t�B���s�����R�����ɔC�����ꂽ�B�����̃A�C�[���n���[�́A���݂����Ȃ��R���̌����ɂȂ�Ȃǔn�����Ă���ƍl���A�}�b�J�[�T�[�ɔC����f��悤�����������A����������Ȃ������B��N�P�\���ɐq�˂��Ƃ���A����̓}�b�J�[�T�[���g���P�\���ɔ��Ă������̂������B�������̐S�̌R���͐����́A��Ɏ�����̖��ň���ɐi�܂Ȃ������B�}�b�J�[�T�[��50�ǂ̋������A250�@�̍q��@�A40,000���̐��K����419,300���̃Q�����ŁA�U�߂Ă�����{�R�ɏ\���R�ł���Ɩ��z���Ă������A���ۂɃA�C�[���n���[�畛�����R���͐����̂��߂�2,500���h���̖h�q�\�Z���K�v�ƒ���ƁA�P�\���ƃ}�b�J�[�T�[��800���h���ɍ��Ɩ����A1941�N�ɂ�100���h���ɂȂ��Ă����B
�R�ɂ͋��͂Ȃ��������A�}�b�J�[�T�[�l�̓A�����J���{�̍݃t�B���s����Ƃɓ������s���A���z�̗��v�Ă����B1936�N1��17���ɂ̓}�j���ŃA�����J�n�t���[���C�\���ɉ����A600���̃}�X�^�[���Q�������Ƃ����B3��13���ɂ͑�14�K��(�K�N�\�������K������)�Ɉٗᏸ�i�����B
1937�N12���Ƀ}�b�J�[�T�[�͗��R��ފ�����ƂȂ�A�A�����J�{�y�ւ̋A�҂�]���A�V��������悪������Ȃ������B�����ŃP�\�����R�����E�F���X�ŌR���ږ�Ƃ��Ē��ڌٗp����Ɛ\���o���A���̂܂܃t�B���s���Ɏc�邱�ƂƂȂ����B�A�C�[���n���[�畛�������̂܂ܗ��C�ƂȂ����B1938�N1���Ƀ}�b�J�[�T�[���R���͐����̐��ʂ������邽�߂ɁA�}�j���ő�K�͂ȌR���p���[�h���v�悵���B�A�C�[���n���[�畛���́A���̔�p���S�ŌR���\�Z���j�Y����A�ƃ}�b�J�[�T�[���|�߂���������ꂸ�A������Ƀp���[�h�̏����𖽗߂����B����������P�\�����A�����̋��Ȃ��Ɍv���i�߂Ă������ƂɌ��{���ă}�b�J�[�T�[�ɕ���������ƁA�}�b�J�[�T�[�͎����͂���Ȗ��߂������o�����Ȃ��A�ƃA�C�[���n���[��ɐӔC��]�ł����B���̂��ƂŁA�}�b�J�[�T�[�ƃA�����J�R�̌R���ږ▋�������Ƃ̌���͌���I�ƂȂ�A�A�C�[���n���[�͗F�l�I�[�h�̍q�̎�������A�t�B���s�������錈�ӂ������B1939�N�ɑ���E��킪�J�킷��ƁA�A�����J�{���Ɉٓ���\���o�āA��ɘA���������R�ō��i�ߕ� (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force) �ō��i�ߊ��ƂȂ����B�A�C�[���n���[�̌�C�ɂ̓��`���[�h�E�T�U�����h�卲���A�����B �@ |
 |
�������m�푈 (�哌���푈)
�����A
����E��킪�n�܂��Ă������ɗ\�Z�s���������ŁA�t�B���s���R�͋������i�܂Ȃ��������A���ƈɎO����������������A���{�R�ɂ�镧��i�����s����ƁA���[�Y�x���g�͋��d�Ȏ�i�����A�Ζ��̋֗A�Ɠ��{�̍ݕĎ��Y�𓀌����A���Ēʏ��q�C���̎����������ċɓ���͈�C�ɋْ������B�p���I�ȓ��Č��ɂ��ŊJ���͍��̓w�͂�������ꂽ���A���{�Ƃ̐푈�ƂȂ����ꍇ�A�t�B���s���̌���͂ł̓I�����W�v����s���͍̂���ł���ƃ��V���g���͔F�����A�}篃t�B���s���̐�͑������}���邱�ƂƂȂ����B�}�b�J�[�T�[�����̗���̒��ŁA1941�N7���Ƀ��[�Y�x���g�̗v�����A�����Ƃ��Č����ɕ��A(7��26���t�ŏ����Ƃ��ď��W�A�����t�Œ����ɏ��i�A12��18���ɑ叫�ɏ��i)�����B����ō݃t�B���s���̃A�����J�R�ƃt�B���s���R�������A�����J�ɓ����R�̎i�ߊ��ƂȂ����B
����܂Ńt�B���s���ɖ��S�ł��������V���g���ł��������A�W���[�W�E�}�[�V�������R�Q�d�����́u�t�B���s���̖h�q�̓A�����J�̍���ł���v�Ɛ錾���A�A�����J�{�����18,000���̍ŐV�����̏B���������ɑ���ƃ}�b�J�[�T�[�ɓ`�������A�}�b�J�[�T�[�͑��������t�B���s���R�����̑����̏[�����}�[�V�����ɗv�����������ꂽ�B�܂��A�����J���R�q������w���ԗv�ǁx�ƌւ��Ă����V����̑�^�����@B-17�̏W���z�����v�悵���B���R�q����i�߃w�����[�E�A�[�m���h�����́u��ɓ��莟��AB-17���ł��邾�������t�B���s���ɑ���v�Ɩ��߂��A�v��ł�74�@��B-17��z�����A�t�B���s���͐��E�̂ǂ������d�����@�̐�͂��W�����Ă���n��ƂȂ�\��ł������B���ɂ��}�~�������@A-24�A�퓬�@P-40�ȂǁA�����̃n���C��������207�@�̍q��@����������A���̑����ꗗ�\�������ă}�j����K�ꂽ���C�X�E�u���A�g��(�p���)�����ɁA�}�b�J�[�T�[�͋����̂��܂�����璵�яオ������t�����قǂł������B
�}�[�V������B-17���ߐM���邠�܂���{�R�q��@���ߏ��]�����Ă���A�u�푈���n�܂��B-17�͂������ɓ��{�̊C�R��n���U�����A���{�̎��̏��s�s���Ă������v�ƌ������Ă���BB-17�ɂ̓t�B���s���Ɠ��{����������q�������͖����������A�����@���͓��{������A�\�r�G�g�A�M�̃E���W�I�X�g�N�܂Ŕ��ŁA�t�B���s���ƃE���W�I�X�g�N��A���������ē��{����������Ɗy�ϓI�ɍl���Ă����B���̊y�Ϙ_�̓}�b�J�[�T�[���S�������Łu12�����ɂ͗��R�Ȃ̓t�B���s���͈��ׂł���ƍl����Ɏ���ł��낤(����)�A�����J�̍����x���s���锚�����͑��₩�ɓ��{�ɑ�Ō���^���邱�Ƃ��ł���B�������{�Ƃ̐푈���n�܂�A�A�����J�C�R�͑債�ĕK�v���Ȃ��Ȃ�B�A�����J�̔������͖w�ǒP�Ƃŏ����̍U����W�J�ł���v�Ƃ����\�z���q�ׂĂ��邪�A���̎��R�ւ̉ߐM�ƓG�ւ̖��f�͌�Ƀ}�b�J�[�T�[�֍Ђ��Ƃ��č~�肩���邱�ƂɂȂ����B
�܂������ɁA�C�R�̃A�W�A�͑�(�p���)�̑������}���A������23�ǂ������邱�ƂƂȂ�A�A�����J�C�R�ōő�̐����͑��ƂȂ����B�A�W�A�͑��i�ߒ����́A�}�b�J�[�T�[�̒m�荇���ł��������g�[�}�X�EC�E�n�[�g�ł��������A�}�b�J�[�T�[�͎����������Ȃ̂Ƀn�[�g���叫�Ȃ̂��C�ɓ���Ȃ������Ƃ����B���̂��߃}�b�J�[�T�[�́uSmall fleet, Big Admiral(�������Ȋ͑��̂����ɊC�R�叫)�v�ƁA�n�[�g��A�W�A�͑��𝈝����Ă����B
�}�b�J�[�T�[�͐�͂̏[���ɂ��A�]���̐�p��傫���]�����邱�ƂƂ����B����̃y�[�X�Ő�͑������i�߂�1942�N4���ɂ�20���l�̃t�B���s���R�̓������ł��A�}�[�V�����̖ʂ�q��@�Ɛ�Ԃ��z�������A�㗤���Ă�����{�R���C�݂őj�~�ł���Ƃ����ژ_�݂Ɋ�Â��v��ł������B�����̃I�����W�v��ł͓����ł̖h�q����v�悵�Ă���A������H�Ƃ͗L���̍ۂɂ͋��łɐw�n������Ă���o�^�[�������ɏW������\��ł��������A�}�b�J�[�T�[�̐V�v��ł͐��ی��ł̐ϋɓI�Ȗh�q��ƂȂ邽�߁A�����͊C�݂ɂ��߂����n�ɏW���������邱�ƂƂȂ����B���̓]���͌�ɁA�}�b�J�[�T�[�ƃA�����J�R�E�t�B���s���R���m���ꂵ�߂邱�ƂƂȂ������A�}�b�J�[�T�[�̍��ύX�̒�ĂɃ}�[�V�����͓��ӂ����B�����Ƃ��d�v�Ȏ�s�}�j���𒆐S�Ƃ��郋�\�����k���ɂ̓W���i�T���E�E�F�C�����C�g����������t�B���s���R4�t�c���z�u���ꂽ�B���{�R�̐N�U�̉\������ԍ����n��ł��������A�E�F�C�����C�g�����Ȃ�������Ȃ��C�ݐ��̒�����480�q�̒����ɒB���Ă���A�C���ꂽ���͂ł͓����͕s���ł������B�������A�}�b�J�[�T�[�̓E�F�C�����C�g�Ɂu�ǂ�ȋ]�����Ă��C�ݐ������炵�A��Ɍ�ނ͂���ȁB�v�Ɩ����Ă����B
�}�b�J�[�T�[����͂̏[���ɂ��h�q�̎��M��[�߂Ă����̂Ƃ͗����ɁA�t�B���s���R�͕̏s�\���ł������B�}�b�J�[�T�[�炪3�N�����P�����Ă������̂́A���̌P���͌X�̕��m�̌P���Ɏ~�܂蕔���Ƃ��Ă̌P���͖w�ǂȂ���Ă��Ȃ������B�t�c�P�ʂ̌P����C���Ȃǂ̑����ȂƂ̋����P���̌o���͖w�ǖ��������B���m�̖w�ǂ��l���ŏ��߂Ċv�C�𗚂����ׁA�����̕��m������ɂ߂Ă���A�e�j�X�E�V���[�Y�◇���ōs�R���镺�m�����������B�܂��e�t�B���s���R�t�c�ɂ͕������P������ׁA���\�l�̃A�����J�R�m����100���̉��m�����z������Ă������A�t�B���s�����͉p���w�ǘb���Ȃ��׃R�~���j�P�[�V�������\���Ɏ��Ȃ������B�܂��A�t�B���s�������m���������Ⴆ�Ό��ꂪ�ʂ��Ȃ������B�}�b�J�[�T�[�̓t�B���s���R�̎��͂Ɍ��z������Ă͖����������A���R��������ʂ̑����������������A�������P�����鎞�Ԃ��\���Ɏ���t�B���s���̖h�q�͉\�Ǝv���n�߂Ă����B���ۂ�1941�N11���̎��_��10���g���̑����������t�B���s���Ɍ������Ă���A100���g�����t�B���s���֗A������邽�߃A�����J���C�݂ɕu���ɎR�ς݂���Ă����B
|
���J��
1941�N12��8���A���{�R���C�M���X�̃}�����ƃn���C�B�̐^��p�Ȃǂɑ��čU���������Ȃ������m�푈 (�哌���푈)���n�܂����B
12��8���t�B���s�����Ԃ�3��30���ɕ����̃T�U�[�����h�̓��W�I�Ńp�[���n�[�o�[�̍U����m��}�b�J�[�T�[�ɕA���V���g�������3��40���Ƀ}�b�J�[�T�[���ēd�b�����������A�}�b�J�[�T�[�̓p�[���n�[�o�[�œ��{�R�����ނ����ƍl���A���̕�҂����ԂʂɘQ����B���̊ԁA�A�����J�ɓ���R�̎i�߂ɏA�C���Ă����u���A�g���������AB-17�������ɔ��i�����A��p�ɂ�����{�R��n�ɐ搧�U����������ׂ���2�����Ă������}�b�J�[�T�[�͂��̂��тɋp�������B
�邪������8������A�u���A�g���̖��߂ɂ��B-17�͓��{�R�̍U���������ׂɋҋ@���Ă������A�u���A�g����3��ڂ̒�Ăł悤�₭�}�b�J�[�T�[����p�U�������������߁AB-17��11������N���[�N�t�B�[���h�ɒ��������e�𓋍ڂ��͂��߂��BB-17�S�@�ƂȂ�35�@�Ƒ唼�̐퓬�@����s��ɕ���12��30���ɓ��{�R�̊C�R�q����̗��84�@�ƈꎮ����U���@�E��Z������U���@���v106�@���N���[�N�t�B�[���h�ƃC�o�t�B�[���h���P�������B�s�ӂ�˂��ꂽ�������ƂȂ����A�����J�R�͐��@�̐퓬�@�𗣗�������̂�����Ƃł��������A���̗��������퓬�@���w�ǂ����Ă���A���U�̔����Ɨ��ɂ��@�e�|�˂Ŏ��X�ƌ��j����Ă������B���̍U����B-17��18�@�AP-40��P-35�̐퓬�@58�@�A���̑�32�@�A���v108�@�������A�����ōq���͂��������鎖�ƂȂ����B���̌�����{�R�ɂ��q��U���͑������A12��13���ɂ͎c���@��20�@�ȉ��ƂȂ�A�A�����J�ɓ���R�͉��琬�ʂ��グ�鎖�Ȃ���ł����B
�l�퍷�ʓI���z������{�l���������Ă����}�b�J�[�T�[�́A�u�퓬�@�𑀏c���Ă���̂�(���{�̓�������)�h�C�c�l���v�ƐM���A���̎|������B�܂��A�u���{�R�̗��R�A�C�R�@���킹��751�@�����A�މ�̍���7��3�Ƃ������|�I�s���ȏ��ɂ������v�Ǝ��ۂƂ͈قȂ�����Ă���B
�}�[�V�����̖��Ă������͑����ɂ͂قlj����������A�}�b�J�[�T�[�͗D���ȍq�͂�15���̕Ĕ�R�ŏ㗤������{�R��@���̂߂���Ǝ��M�������Ă����B�������A���݂̍q���͂͏��Ղł��������ł��Ă��܂��A���{�R��12��10���Ƀ��\�����k���̃A�o���ƃr�K���A12���ɂ͓암�̃��K�X�s�ɏ㗤���Ă����B�}�b�J�[�T�[�̓}�j�����牓�����ꂽ�����̒n��ւ̏㗤�́A�߂������ɍs�����K�͏㗤���̎x���ړI�Ɣ��f���Čx�������������B�}�b�J�[�T�[�͓��{�R��͂̏㗤��12��28�����Ɨ\�z���Ă������A�{�ԉ됰�����������14�R��͂́A�}�b�J�[�T�[�̗\�z���6��������22�����Ƀ����K�G���p����㗤���Ă����B�㗤���Ă�����14�R�͑�16�t�c�Ƒ�48�t�c��2�t�c�����A���Ɉꕔ�̕��������\�����k���ɏ㗤���Ă���A9�t�c��L���郋�\�����h�q�R�ɑ��Ă͋��͂ȕ����ɂ͌����Ȃ��������A�㗤���Ă������{�R���C�݂Ō}���������A�����J�R�ƃt�B���s���R�́A�P���s���ł��낭���s�ꋎ��A���ɓ����o�����B�{���̐����Ői�R���Ă�����{�R�ɑ��ă}�b�J�[�T�[�́A���s�͌������ƌ��Ǝ����̍l�Ă������ۍ�����߁A�����̃I�����W�v��ɖ߂����ƂƂ��A�}�j����������ăo�^�[�������ƃR���q�h�[�������ď邷��悤�ɖ������B �E�F�C�����C�g�̍I�݂ȑދp��ɂ��A�o�^�[�������ɂقƂ�ǂ̐�͂��y���ȑ��Q�őދp�ł������A����Ń}�b�J�[�T�[�̍��ɂ�蕽�n�ɏW�������Ă����H�Ƃ╨���̗A�����A�}�b�J�[�T�[�i�ߕ��̖��ߕs�O���P�\���̕s��ۂȂǂł��܂��������A�ݒu����Ă�����⋊�n�ɂ͐H�Ƃ╨���₻���A������g���b�N�܂ł����Ă������A������قƂ�ǗA�����邱�Ƃ��ł������{�R�ɐڎ�����Ă��܂����B���̓��̂ЂƂA�������\������ɂ������J�o�i�`���A�������W�Ϗ������ł��Ă�5,000���u�b�V�F�������������A����͕Ĕ�S�R��4�N���̐H�Ƃɂ�����ʂł������B
�o�^�[�������ɂ́A�I�����W�v��ɂ��40,000���̕��m�����N�Ԏ����������邾���̕������~�ς���Ă������A�S���z��O��10���l�ȏ�̃A�����J�R�E�t�B���s���R���m�Ɣ��������Ă��邱�ƂƂȂ����B�}�b�J�[�T�[�͏����ł������H�Ƃ��������邽�߁A�H�Ƃ̔z�����ɂ��邱�Ƃ𖽂������A����ł�4�����͂����Ȃ��Ǝv��ꂽ�B���i���𑱂�����{�R�͑�14�R��͂������K�G���p�ɏ㗤���Ă킸��11�����1942�N1��2���ɁA���h���s�s�錾�����Ă����}�j�����̂����B�{�Ԃ̓}�b�J�[�T�[���؍݂��Ă����}�j���E�z�e���̍ŏ�K�ɓ��͊����f�����������A�����o�ዾ�Ŋm�F�����}�b�J�[�T�[�́A����Ƃ��Ă����X�C�[�g���[���̌��փz�[���ɏ����Ă������A�[�T�[��1905�N�ɖ����V�c������^���ꂽ�ԕr�ɁA�{�Ԃ͋C���t���ē���������낤���H�ƍl���Ċ܂ݏ��������B
�}�b�J�[�T�[�̓}�j���ח���A�Ĕ�R���o�^�[�������ɓP�ނ���������1��6���̑O�ɁA�R���q�h�[�����̃}�����^�E�g���l��(�p���)���ɐ݂���ꂽ�n���i�ߕ��ɁA�ȃW�[���Ǝq���̃A�[�T�[�E�}�b�J�[�T�[4����A��Ĉړ��������A�R���q�h�[������������[�A�i�߂̏��߂ɂ��ւ�炸�A�Z���͒n�������ł͂Ȃ��n��ɂ������o���K���[���̏h�ɂƂ����B������͓��{�R�̔����̖ڕW�ɂȂ�Ɩ|�ӂ𑣂������}�b�J�[�T�[�͕�������Ȃ������B�}�b�J�[�T�[�͓��{�R�̋�P������Ɩh�ɂ����炸�A�I�R�Ɣ����̗l�q���ώ@���Ă����B���鎞�ɂ̓}�b�J�[�T�[�̋߂��Ŕ��e���������A�}�b�J�[�T�[��݂����]���̌R�����g����ƂȂ��ĕ������邱�Ƃ��������B�ꏏ�Ƀ}�����^�E�g���l���ɓP�ނ��Ă����P�\���͂���ȃ}�b�J�[�T�[�̗l�q�����Ė��d���Ƌl�������A�}�b�J�[�T�[�́u�i�ߊ��͕K�v�Ȏ��Ɋ댯���������Ȃ�������Ȃ����Ƃ�����B�����ɐg�������Ĕ͂��������߂��B�v�Ɠ����Ă���B
�}�b�J�[�T�[�͓��{�R�̐�͂��ߑ�ɕ]�����Ă���A6�t�c���㗤���Ă����ƍl���Ă������A���ۂ�2�t�c������40,000���ł������B����ŁA���{�R�͋t�ɃA�����J�E�t�B���s���R���ߏ��]�����Ă���A�c�����͂�25,000���ƌ��ς����Ă������A���ۂ�80,000���ȏ�̕������o�^�[���ƃR���q�h�[���ɗ����Ă����Ă����B��������A��14�R��2�t�c�̓��A��͂̋@�B���t�c��48�t�c�́A�t�B���s���U����ɗ�����ɓ]�킷��v��ł��������A�o�^�[�������ɃA�����J�E�t�B���s���R�������Ă������̂ɂ��ւ�炸�A��{�c�͐�͂̉ߏ��]���Ɋ�Â��A�v��ʂ��48�t�c�𗖈���Ɉ��������Ă��܂����B�{�Ԃ���͂��ߏ��]�����Ă����̂ŁA1942�N1�������65���c�Ńo�^�[�������ɍU�������������A�G���\�z�O�ɑ�������������ł��������߁A�呹�Q�����Č��ނ���Ă���B���̌�A���{�R�̓o�^�[���ƃR���q�h�[���Ɍ������C���Ɣ��������������A�n��R�ɂ��U����3�T�Ԃ��x�~���邱�ƂƂȂ����B
���̊ԁA���{�R�Ƃ̐킢���Q��Ƃ̐킢�ɖ�������o�^�[�������̕Ĕ�R�́A���n���O�̕ĂƌR�p�n��H�אs�����A����ɖ쐶�̎��Ɖ����H���Ƃ���ł����Ă��܂����B�}�b�J�[�T�[��́u2�����ɂ킽���ē��{���R��Ɂw�P��x���Ă���v�ƁA�A�����J�{���ł́u�p�Y�v�Ƃ��Ĕh��ɐ�`����A���܂ꂽ�j�̎q�Ɂu�_�O���X�v�Ɩ��t����e�����o�������A���ۂɂ̓A�����J�R�͊e�n�œ��{�R�Ɋ��S�Ɉ��|����A�~���̗��Ȃ��킢�ɋꂵ�݁A���̂܂܂ł̓}�b�J�[�T�[����ߗ��ɂȂ肩�˂Ȃ���Ԃł������B���V���g���ł̓t�B���s���̑Ή��ɋꗶ���Ă���A�^���̂悤�ɐ틵�≇�R�v���̓d����œd���Ă���}�b�J�[�T�[����₩�Ɍ��Ă����B���Ƀ}�b�J�[�T�[���悭�m��A�C�[���n���[�́u�F�X�ȈӖ��Ń}�b�J�[�T�[�͂��ĂȂ��قǑ傫�ȃx�C�r�[�ɂȂ��Ă���B��������X�͔ނ����Đ�킹��悤�Ɏd�����Ă���v�Ɠ����̓��L�ɏ����L���Ă���B
���������̓����A�o�^�[�������ƃR���q�h�[�����͍U�������߂鐕�����ɑ���B��̒�R���_�ƂȂ��Ă���A�C�M���X�E�B���X�g���E�`���[�`�����u�}�b�J�[�T�[���R�w�����̎㏬�ȃA�����J�R�������������ׂ��E�C�Ɛ킢�Ԃ�ɏ̎^�̌��t�𑗂肽���v�Ƌc��ʼn�������Ȃǒ��ڂ���Ă����B���V���g�����l�X�ȋ~������������A12��28���ɂ̓t�B���s���Ɍ����ă��[�Y�x���g���u���̓t�B���s�������Ɍ��l�ɐ����A���N��̎��R�͕ێ�����A�Ɨ��͒B������A�����ł��낤�B�A�����J�͕��͂Ǝ��ނ̑S�Ă�q���Đ����v�Ƒœd���A�}�b�J�[�T�[�ƃP�\���͋��삵�����A���ۂɂ͏d���y���T�R�[���Ɍ�q����}�j���֑�ʂ̉ΖC�Ȃǂ̕������^��ł����A���D�c���A�댯������ăI�[�X�g�����A�Ɍ����킳���ȂǁA�~����͋�̓I�ɂ͉����Ȃ���Ȃ������B
|
���t�B���s���E�o
�}�b�J�[�T�[���R���q�h�[���ɓP�ނ������ɂ́A�n�[�g�̃A�W�A�͑��͊��Ƀt�B���s���𗣂�I�����_�̓��C���h�ɓP�ނ��A�����m�͑���͂��p�[���n�[�o�[�Ŏ����Q���傫�����ăt�B���s���~�o�͕s�\�ł���A���[�Y�x���g�ƌR��]�̓t�B���s���͂�������ꂽ���̂ƒ��߂Ă����B�}�[�V�����̓}�b�J�[�T�[�����ʂ������{�R�̕ߗ��ƂȂ邱�Ƃ��Ă��Ă������A����̓}�b�J�[�T�[���A�����J�����ʼnp�Y������A�A���}�b�J�[�T�[���~�o����Ƃ��������V�����ʏ����킵�Ă���A�ߗ��ɂȂ����ꍇ�A�����╺�m�̎m�C�Ɉ����e����������ƂƂ��ɁA�A�����J���R�ɉi���̒p�J�������炷�ƌ��O������������ł���B�������}�b�J�[�T�[�͍~������C�͂Ȃ��A1942�N1��10���ɖ{�Ԃ��������~�������̏��Ȃ�َE���Ă��邪�A����̓A�����J�{������̎x��������ƌł��M���Ă�������ł������B�t�B���s���ւ̎x�����s���C�������}�[�V�����痤�R�Ȃ́A���̎��_�Ń}�b�J�[�T�[���I�[�X�g�����A�ɓ��������Ƃ��l���n�߁A2��4���Ƀ}�b�J�[�T�[�ɃI�[�X�g�����A�ŐV�����i�ߕ���ݒu����悤�ɑŐf�������}�b�J�[�T�[�͂�������ہA�t�ɊC�R�������m�����ōU���ɏo�āA���{�R�̕�����˔j����悤�ɗv�����Ă���B
�R���q�h�[���̗v�ǂɓ�������ł��炭����ƁA�P�\���̓��[�Y�x���g���t�B���s�����~��������肪�Ȃ�����m���ċC��a�݁A�}�b�J�[�T�[�Ɂu���̐푈�͓��{�ƕč��̐킢���B�t�B���s�����m�ɕ����u���č~������悤�\������B���Ă̓t�B���s���̒��������F���Ăق����B�v�Ɛ\���o���B�}�b�J�[�T�[�͂��̐\���o�����[�Y�x���g�ɕ���̂��S�O�������A�A�����J�{�����t�B���s�����~��������肪�Ȃ��̂Ȃ�A�R���I�ϓ_���炱�̃P�\���̐\���o�̓A�����J�ɂƂ��Ď������͉̂����Ȃ��Ɣ��f���A���[�Y�x���g�ɕ����B���������̕������[�Y�x���g�͐v��������ȁu�A�����J�͒�R�̉\���������(�t�B���s������)�������~�낷����͂Ȃ��v�Ƃ����Ԏ����P�\���ɍs���A�}�b�J�[�T�[�ւ̓}�[�V������ʂ��āu�P�\�����t�B���s�����ޔ�������v�Ƃ̎w�����Ȃ��ꂽ�B �}�b�J�[�T�[�̓P�\���哝�̂ɒE�o�𑣂��Ƌ��ɁA�R���ږ�A�C���ɖ����閧�̕�V�̎x������v�������B�b�������̌��ʁA�}�b�J�[�T�[50���h���A�������14���h���x�����鎖�ƂȂ�A2��13���ɂ�������鑤�̃}�b�J�[�T�[���炪�����T�U�[�����h�ɖ����A�}�b�J�[�T�[���64���h�����t�B���s���̍��ɂ��x�����Ƃ���t�B���s���E�R�����E�F���X�s�����ߑ�1������点�y���b�g 2014, p. 521�A2��15���A�P�\���̓j���[���[�N�̃`�F�[�X�E�i�V���i����s�̃t�B���s�����{�̌�������P�~�J���E�i�V���i����s�̃}�b�J�[�T�[�̌l������50���h����U�荞�ގ葱���������B�P�\����2��20���ɃA�����J�R�̐����̓\�[�h�t�B�b�V���ŃR���q�h�[������E�o�����B
�P�\���͌�ɋ�H�ŃA�����J�E���V���g���Ɍ������A���Ẵ}�b�J�[�T�[�̕����A�C�[���n���[�ƍĉ�A�}�b�J�[�T�[��ɑ����n�����悤�ɃA�C�[���n���[�ɂ����J���Ƃ������ڂ�6���h����n�����Ƃ������A�A�C�[���n���[�͒f�łƂ��ċ��ۂ��Ă���B�P�\���͂��̌�A���C�e�ւ̐i�U���O��1944�N8���Ƀj���[���[�N�ŕa������x�ƃt�B���s���̓y�ނ��Ƃ͖��������B
���[�Y�x���g�̓}�b�J�[�T�[�ɍ~���̌����͗^���Ă������A���R�Ȃ���Ă����I�[�X�g�����A�ւ̒E�o�͍l���Ă��Ȃ������B������̋L�҉�Łu�}�b�J�[�T�[���R�Ƀt�B���s������E�o�𖽂��S�R�̎w������^����l���͂Ȃ��̂��v�Ƃ̋L�҂̎���Ɂu���⎄�͂����͎v��Ȃ��A����͗ǂ������m��Ȃ��҂��������Ƃ��v�Ɣے�I�ȉ����Ă���B����̓��[�Y�x���g�́u�������邱�Ƃ͔��l���ɓ��ł͊��S�ɖʎq���������ƂƂȂ�B���l���m������́A�키���̂ŁA�����o�����ƂȂǂł��Ȃ��v�Ƃ����l���Ɋ�Â����̂ł������B
�ŏI�I�Ƀ��[�Y�x���g���l����ς����̂́A�`���[�`�����A���{�R�̉��i���Œ��ڂ̋��Ђ��邱�ƂƂȂ����I�[�X�g�����A���k�A�t���J����ɑ����Ă���3�t�c�̑���ɁA�A�����J���I�[�X�g�����A�̖h�q���x�����ė~�����Ƃ̗v��������A���̎i�ߊ��Ƃ��ă`���[�`�����}�b�J�[�T�[���w���������߂ł���B1942�N2��21���A���[�Y�x���g�̓`���[�`������̋��߂�A�}�[�V�����痤�R�̐���������}�b�J�[�T�[�ɃI�[�X�g�����A�֒E�o����悤�������B�}�b�J�[�T�[�́u���Ǝ��̉Ƒ��͕����Ɖ^�������ɂ��邱�Ƃ����ӂ����v�Ɩ��߈ᔽ��Ƃ��R�Ђ�ԏサ�ċ`�E���Ƃ��Đ킨���Ƃ��l�������A��������I�[�X�g�����A�ɑނ��A���R��A��ăt�B���s���ɋ~���ɖ߂��ė��悤�Ƃ����l���ɗ��������A���[�Y�x���g�̖��߂��邱�ƂƂ����B
�}�b�J�[�T�[���E�o������Ă���Ԃɂ���ǂ͈����������ŁA�Q��Ɖu�a�ɉ����A�����J�E�t�B���s���R�̕��m���ꂵ�߂��̂́A���{�R�̐₦�ԂȂ��C���ɂ�鐇���s���ł������B���͂�o�^�[���̕��m���ׂĂ��a�l�ƂȂ����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��������A�}�b�J�[�T�[�̎i�ߕ��͉R�̏����̏����A�����J�̃}�X�R�~�ɗ����������B12��10���̃r�K���㗤��펞�ɃA�����J�R�q��@���y���m�͖���������ߒe�����A�U���@�����Ă��ꂽ���߂��̐�ʂ���͐Y�������ƌ�F���ĕ����ƁA�}�b�J�[�T�[�i�ߕ��͂��̏��ɔ�ѕt����X�I�ɐ�`�����B���̌���M�������[�Y�x���g�ɂ���Đ펀�����U���@�̃p�C���b�g�P���[��тɂ͖��_�M�͂����^�����ȂǁA�}�b�J�[�T�[�i�ߕ��͌p�����āu�W���b�v�ɑ呹�Q��^�����v�ƌ��\���Ă������A3��8���ɂ͑S���E�Ɍ��������W�I�����Łu���\�����U���̓��{�R�i�ߊ��{�ԉ됰�͔s�k�̂��߂ɖʖڂ������A�n���L���i�C�t�Ńn���L�����Ď��ɂ����Ă���v�Ɛ������o���A����ɂ��̌�u�}�b�J�[�T�[�叫�̓t�B���s���ɂ�������{�R�̑��i�ߊ��{�ԉ됰�����̓n���L�������Ƃ̕��J��Ԃ�������B���ɂ��Ɠ������̑��V��2��26���Ƀ}�j���Ŏ��s���ꂽ�B�v�ƌ��������\�����B����ɗ����ɂ́u�t�B���s���ɂ�������{�R�̐V�����i�ߊ��͎R���ł���B�v�ƉR�̌�C�܂Ŕ��\����O�̓���悤�ł������B
�R�̌������\������̂ƕ��s���ă}�b�J�[�T�[�͒E�o�̏�����i�߂Ă����B�R���q�h�[���ɂ̓A�����J�C�R�̐����͂����ʂ̐H�Ƃƒe����^��ł����A��ɁA��ʂ̏��a�҂�E�o�����邱�Ƃ��Ȃ��������^�яo���Ă����B��ɒE�o�ɐ��������P�\���̂悤�ɂ��̐����͂ɓ��悷��̂���Ԉ��S�ȒE�o�@�ł��������A�}�b�J�[�T�[�͐��܂���Ă̕����|�ǂł���A�E�o���@�͎����Ō��߂����Ăق����ƃ}�[�V�����ɐ\���o�������ꂽ�B�}�b�J�[�T�[�́A�Ƒ��▋���B�Ƌ��ɋ������Ń~���_�i�I���ɒE�o���鎖�Ƃ����B3��11���Ƀ}�b�J�[�T�[�ƉƑ��Ǝg�p�l�A�[�E�`���[�����悷��PT-41(�p���)�ƃ}�b�J�[�T�[�̖���(���R���Z13���A�C�R���Z2���A�Z�p���m��1��)�����悷�鑼3�ǂ̋������̓~���_�i�I���Ɍ��������B�ꏏ�ɒE�o���������́w�o�^�[���E�M�����O(�܂��̓o�^�[���E�{�[�C�Y)�x�ƌĂ�A���̒E�o�s�̌ォ��}�b�J�[�T�[�����N�푈�ōX�R�����܂ŁA�}�b�J�[�T�[�̌����M���ƒ������d�p����邱�ƂƂȂ����B���[�Y�x���g���E�o�𖽂����̂̓}�b�J�[�T�[�Ƃ��̉Ƒ������ŁA������̒E�o�͌����ɂ����Ζ��߈ᔽ�ł��������A�}�[�V�����͌�ɂ��̎�����m���āu�������v�ƌ����������ŕs��Ƃ��Ă���B
����������800�q�̊댯�ȍq�C���ɐ��������A�~���_�i�I�����R�i�ߊ��E�B���A���E�V���[�v�y���̏o�}���������A�q�C���Ƀ}�b�J�[�T�[�͎�ו��������A�������ɏ������Ă����ו��͏A�Q�p�̃}�b�g���X�����ł������B�~���_�i�I���ɂ͋}�����ꂽ�f�������e��s�ꂪ����A�}�b�J�[�T�[�͂�������B-17�ŃI�[�X�g�����A�܂ŒE�o����v��ł��������A�I�[�X�g�����A�̃A�����J���R�q����i�߃W���[�W�E�u���b�g������������B-17�͋����ł���A�o������4�@�̓�2�@���̏�A1�@���ė����A���{�R�Ƃ̋�ő�������1�@���悤�₭���������Ƃ����L�l�ŁA�ƂĂ������ɃI�[�X�g�����A�ɔ�s�ł��Ȃ��ƍl�����}�b�J�[�T�[�́A�}�[�V�����ɃA�����J�{�y���n���C����V�i��B-17��3�@�lj��Ō����悤�ɍ��肵�����ʁA�I�[�X�g�����A�ŊC�R�̊Ǘ����ɂ�����B-17��3�@�lj��h������邱�ƂƂȂ����B����3�@��1�@���̏Ⴕ�����߁A3��16����2�@���f�������e�ɓ��������B����2�@�ɃR���q�h�[����E�o������s�ƁA��ɒE�o���Ă����P�\�����������l�ߍ��܂ꂽ�B��荞���̃}�b�J�[�T�[�̉ו��̓R���q�h�[���E�o����莝���Ă����A�Q�p�}�b�g���X1�������ł��������A��ɂ��̃}�b�g���X�ɋ��݂��l�ߍ��܂�Ă����Ƃ����\���L���邱�ƂƂȂ����B
�I�[�X�g�����A�܂�10���Ԃ����Ĕ�s������A��s�͗�Ԃňړ����A3��20���ɃI�[�X�g�����A�̃A�f���[�h�w�ɓ�������ƁA�}�b�J�[�T�[�͏W�܂����w�Ɍ����Ď��̂悤�ɐ錾�����B
�u���̓A�����J�哝�̂���A���{�̐����˔j���ăR���q�h�[������I�[�X�g�����A�ɍs���Ɩ�����ꂽ�B���̖ړI�́A���̗�������Ƃ���ł́A���{�ɑ���A�����J�̍U�����������邱�ƂŁA���̍ő�̖ړI�̓t�B���s���̋~���ɂ���B���͂���Ă������A�K���⎄�͖߂邾�낤(I shall return)�v
���̓��{�R�̍U����O�ɂ����G�O���S�́A�}�b�J�[�T�[�̌R���̐����Ȃ����ԂƂȂ����B�ނ�10���]��̏������̂Ăē������ڋ��҂ƌ���ꂽ�B�܂��A�uI shall return�v�͕ĕ��̊Ԃł͓G�O���S�̈Ӗ��Ŏg��ꂽ�B����܂ł��A���S�ȃR���q�h�[�����Ă��đO���ɂ��o�Ă��Ȃ��ނ𝈝����uDugout Doug(�����Ă����܂o�Ă��Ȃ��_�O���X)�v�Ƃ�����������t�����A�̂܂ō���ĕ��m�̊Ԃŗ��s���Ă����B��p�@�Ƀo�^�[�����Ɩ��t����Ȃǃo�^�[����������ʂȒn�Ƃ��Ă����}�b�J�[�T�[�ł��������A���ۂɃR���q�h�[���v�ǂ���o�ăo�^�[�������ɗ����̂�1���Ȃ������B
�I�[�X�g�����A�œ쐼�����m���ʂ̘A�����R���i�ߊ��ɏA�C�����}�b�J�[�T�[�́A�I�[�X�g�����A�ɂ̓t�B���s���~���ǂ��납�A�I�[�X�g�����A�{������h�q�ł��邩�^�킵�����x�̐�͂����Ȃ��ƒm�蜱�R�Ƃ����B���̎��̃}�b�J�[�T�[�̗l�q���A���ӂɂ��Ă����W���[�i���X�g�̃N���[�N�E���[�́u���悤�Ɋ炪���߁A�G�̓K�N�K�N���A�O�̓s�N�s�N�z�����Ă����B�����Ԗق��Ă���A����Ȑ��łԂ₢���u�_�悠���݂��܂��v�v�Ɖ�z���Ă���B
�t�B���s���~���͐�]�I�ł��������A�}�b�J�[�T�[�͎c���Ă����W���i�T���E�E�F�C�����C�g�����ȉ��̃A�����J�R�E�t�B���s���R�Ɂu�����Ȃ�����ł��~������ȁA�H�Ƃ��Ȃ��Ȃ�����A�G�R���U������v�Ƃ�����d���œd���Ă���B�������A���{�R��14�R�͑�4�t�c�ƍ��`�̐킢�Ŋ�����1�C�����̑�����Ƒ��U�����J�n���A4��9���Ƀo�^�[����������������G�h���[�h�EP�E�L���O�������~������ƁA�}�b�J�[�T�[�͍������A�{��A���f�����B�R��͂��ׂ����E�F�C�����C�g���Ȃ����ׂȂ��A5��6���ɍ~�������B����������Ȃ��}�b�J�[�T�[�́A�c��~���_�i�I��������̃V���[�v�y���ɓO��R����w�����邪�A�V���[�v�̓E�F�C�����C�g�̑S�R�~���̃��W�I�����ɏ]���~�����A�t�B���s��������S�R���~�������B���ǁA�t�B���s�������{�R�̌v���傫�����߂��A5�����Ԃ��U���Ɏ��Ԃ�v�����̂́A�}�b�J�[�T�[�̍��w�����D��Ă����̂ł͂Ȃ��A��{�c�̃A�����J�E�t�B���s���R�̐�͉ߏ��]���ɂ���14�R��͂̑�48�t�c���o�^�[�������U���O�ɗ���Ɉ��������ꂽ�̂���ԑ傫�ȗv���ƂȂ����B
�}�b�J�[�T�[�͂��̍~���Ɍ��{���A�}�b�J�[�T�[�E�o����ꂵ���킢�𑱂��Ă����E�F�C�����C�g��������Ȃ������E�F�C�����C�g�ɂ��ẮA�I���Ƀw�����[�E�X�e�B���\�����R������}�[�V�����̎��萬��������A�~�����T�ɓ��Ȃ����A���_�M�͏��M���F�߂����A�L���O��ɂ��Ă͏I�����}�b�J�[�T�[���͂��Ȃ��������߁A���i���邱�Ƃ��Ȃ��I�풼��ɑޖ���]�V�Ȃ�����Ă���B
�I�����_�̓��C���h�Ɍ�ނ��A�A�����R�͑��ƕĉp���� (ABDA) �͑���Ґ����Ă����n�[�g�̃A�W�A�͑���1942�N2��27������3��1���̃X���o�����C��E�o�^�r�A���C��ʼn�ł��A�}�b�J�[�T�[���I�[�X�g�����A�ɓ�������܂łɃI�����_�̓��C���h�����{�R�ɐ�̂���Ă����B�}�b�J�[�T�[�͔s��ɂ��ėl�X�ȗ��R�Â����������A�A�����J�ƘA�������t�B���s���Ɛ������m�ŎS�s�����Ƃ��������͕�����̂ł͂Ȃ������B�������A�A�����J�{���ł̃}�b�J�[�T�[�̕]���́A�A�����J�����̈����S�̋Ր��ɋ����G�ꂽ���ƁA�܂��A�p�[���n�[�o�[�ȍ~�̃A�����J�ƘA�����������ނ�������̑��Q�Ɍ�����ꂽ�A�����J�l�̌��{�Ƃ����т��A�A�����J�j������Ƃ��ɗ�Ȕs�k���i�����s���ɂ��S��炸�A�p�Y�Ƃ��ĔM���I�Ɏx�����ꂽ�B���̗l�q���������[�Y�x���g�͋����Ȃ�����A�}�b�J�[�T�[�̐�`���l���푈���s�ɑ傫�����ɗ��ƔF�������p���邱�ƂƂ��A1942�N4��1���ɖ��_�M�͂����^���Ă���B |
�����U
1942�N4��18���A�쐼�����m���ʂ̃A�����J�R�A�I�[�X�g�����A�R�A�C�M���X�R�A�I�����_�R���w������쐼�����m���ʍō��i�ߊ�(Commander IN Chief, SouthWest Pacific Area ���� CINCSWPA)�ɔC������A���{�̍~����������̓��܂ł��̒n�ʂɂ������B
1943�N3���̃r�X�}���N�C�C��(������_���s�[���C���̔ߌ�)�̏����̕���A��5�q��R�i�ߊ��W���[�W�E�P�j�[�ɂ��A�u�ނ�����قNJ�̂́A�ق��ɂ͌������Ƃ��Ȃ��v�Ƃ������炢�ɋ��에�������B�������Ǝv���A�����ʂ̊C�R����(��̑�7�͑�)�̃g�b�v���(�}�b�J�[�T�[�̗v���ɂ��)�̍ہA�u��C�Ƃ��ăg�[�}�X�EC�E�L���P�C�h���A�C����v�Ƃ������\���ƁA�����ɉ��̑��k���Ȃ�����Ɍ��߂�ꂽ�l�����Ƃ������ƂŌ��{�����B
�}�b�J�[�T�[�͘A���R�̖L�x�ȋ�E�C��͂����܂����p���A���{�R�̎�����ł��Ƃ����������ĕ�͂��⋋�H��f���āA���{�R���Q��Ŏ�̉�����̂�҂����B�}�b�J�[�T�[�͗��C��̓��������w�O�����̐헪�\�z�x�A���ʍU����������{�R�̐Ǝ�ȏ����U�������@���w�^��э��x�ƌĂ�ł����B���{�R�͋�E�C�ł̂��яd�Ȃ�ɔs��ɐ�͂����Ղ��A���E���C���������Ă������߁A�}�b�J�[�T�[�̐�p�ɑR�ł����A�}�b�J�[�T�[�̎v�f�ʂ�A�j���[�M�j�A�̐킢�ł͑����̉쎀�ҁE�a���҂��o�����ƂƂȂ����B���̏����́A�t�B���s���̔s��ő��Ȃ��Ă����}�b�J�[�T�[�̎w���\�͂ɑ���]���Ɩ�����傢�ɍ��߂��B
|
��I shall return
1944�N�̃t�B���s���ւ̔��U���ɂ��āA�A�����J���R�Q�d�{���ł́u�헪��K�v�Ȃ��v�Ƃ̔��f�ł��������A�C�R���g�b�v�̃A�[�l�X�g�E�L���O��핔�����͂��߂Ƃ��Ă���ɓ��ӂ���ӌ��������������A�}�b�J�[�T�[�́u�t�B���s�������Ƃ̖v�̗��s�𗝗R�ɂ�����咣�����B�}�b�J�[�T�[�����̍������艟���������R�Ƃ��ẮA�t�B���s������̓G�O���S���s�������������������ƂƁA�����̗����������Ă����t�B���s���ɂ����闘���̉�2���������ƌ����Ă���B���[�Y�x���g��1944�N�̑哝�̑I���T���Ă����̂ŁA�����ɐl�C������}�b�J�[�T�[�̗v�������Ԃ��ԓۂƌ����Ă���B
�}�b�J�[�T�[��10��23���ɃZ���q�I�E�I�X���j���ƂƂ��Ƀ��C�e���̃��C�e�p�ɏ㗤�����B�}�b�J�[�T�[�͓��{�R�̑_���������ޒ��Ő������ĉ��A�_�����ꂽ���Ƃ����������A�e������邽�߂ɕ����邱�Ƃ����Ȃ������Ƃ����B���̌�Ɋ��͂Ƃ��Ă����y���i�b�V���r���̒ʐM�ݔ����g���āA�������t�B���s�������Ɍ����ĕ��������B���̉����̏o�����́u�t�B���s���������N�A���͋A���Ă����B�v�ł��������A�����̂��܂�肪�k�������ジ�������߁A�ꑧ���ꂽ��ɉ������ĊJ�����B���{�̌R���̎��s�ɂ��n����Q��ɋꂵ�߂��Ă��������̃t�B���s�������́A�M���I�Ƀ}�b�J�[�T�[�̋A�҂����}�����B
���̌�̃��C�e���̐킢�́A���{�R�͑�p���q���̉ߑ��ʂ̋�����x����A��{�c�̉����Ō��n�̎R���i�ߊ��̔���������A���C�e�������Ƃ��ăA�����J�R�Ɍ���ނ��ƂƂ��A���ꍆ���������B�A���͑��̎�͂��A�����J�A���͑������ŁA�����ŗ��R�̓��\������菇�����������C�e�ɔh�����A�㗤�R�̌��ł�}�������A���C�e���C��ŘA���͑����S�s�����E���C���������ƁA�������C��A�����ɗA���D���ƌ�������A���C�e���̓��{�R�͌Ǘ����钆�ň��|�I�ȃA�����J�R�̉Η͂ƁA�Q���ƕa�C�ɕ��m�͎��X�Ɠ|��Ă������B
���C�e���U�������}�b�J�[�T�[�́A�O��̃��\�����D�ҍ����J�n�����B���C�e�Ő�͂����Ղ������{�R�͊C�ݐ��ł̌��������A�R�x�n�тł̒x�ؐ�p���Ƃ邱�ƂƂ����B�i�ߊ��̎R���͎�s�}�j����퓬�Ɋ������܂Ȃ����߂ɖh�q����߁A������ɂ��P�ޖ��߂��o�������A���C�R�̍��s����ł���͗��s���ꂸ�A�C�R������𒆐S�Ƃ�����{�R14,000�����}�j���ɗ����Ă������B�}�j���D�҂ɏł�}�b�J�[�T�[�́A�s���ւ̏d�C�ɂ��C���������A�������s�X��̏�ŏZ��n��80%�A�H���75%�A���Ǝ{�݂͂قڑS�Ă��j�ꂽ�B�}�j���s���̋]����10���l�ɂ���������A���̒��ɂ͐�]�I�ɂȂ������{���ɂ��c�s�s�ׂ̑��A�A�����J�R���x���������T�b�t�F�E�Q�����ƃt�N�o���n�b�v�E�Q�����Ɏ���Ă������{�R�̃Q���������ɂ��]���҂��܂܂�Ă����B�����Q�����̒����ɔY�ޓ��{�R�ł��������A�Q�����Ƃ��̈�ʎs���̋�ʂ������A�V��j���\�킸�E�Q�����B�}�b�J�[�T�[�͓��{�R�̃Q�����������u���͂Ŗ����߂Ȑ�͂���Ȏ�i�ɑi�����v�u�R�l�͓G������킸�A�カ�ҁA�������̎҂����`���������Ă���c�c(���{�R���Ƃ���)�ƍ߂͌R�l�̐E�Ƃ������A�����̉��_�ƂȂ�v�ƌ������������A���̖������Ŏカ�҂��������̂̓}�b�J�[�T�[�ł���A���ɂ��̍߂����Đ�ƂƂȂ����R���̍ٔ��ł́A�R���ٌ̕쑤����A�}�b�J�[�T�[�̕��A�[�T�[���t�B���s���̃A�����J�R�̎i�ߊ��ł��������Ƀt�B���s���̓Ɨ��^�����A�����J���e���������̗���o����u���Ȃ܂������w�t�B���s���̔����x�̊��ԁA�t�B���s����������邽�߂ɁA�A�����J�l���l�Ă��p����ꂽ���@���A���{�R�͖͕킵���悤�Ȃ��̂ł���v�u�A�����J�R�̓������̎w�����X�~�X�y���́u���e�����Ă�҂͑S�ĎE���v�Ƃ������߂��o�����v�Ǝw�E����A�}�b�J�[�T�[�͌��{���Ă���B
���{�R�͂��̌�����|�I�ȉΗ͂̃A�����J�R�ƁA���\���l�ɂ��c��オ�����t�B���s���E�Q�����Ɉ��|����Ȃ����]�I�Ȑ킢�𑱂��A�����ł���ʂ̉쎀�ҁE�a���҂��o���A���\�����R���ɌǗ����邱�ƂƂȂ����B�j���[�M�j�A�̐킢�ɑ����A�}�b�J�[�T�[�͌���I�ȏ�����͂݁A���̖�����Ќ��͂���ɍ��܂����B�������A�t�B���s���D�҂����[�Y�x���g�ɒ��i�����ۂɁA�傫�ȑ��Q�����O�������[�Y�x���g�ɑ��}�b�J�[�T�[�́u�哝�̊t���A���̏o�����Q�͂���܂ňȏ�ɑ傫�Ȃ��̂Ƃ͂Ȃ�܂���c�c�悢�w�����͑傫�ȑ������o���܂���v�ƍ��ꂵ�Ă������A�A�����J�R�̑���E���̐킢�̒��ł͍ő勉�̐l�I���Q�ƂȂ�A�퓬�ł̎���79,104���A��a��퓬�O�ł̕���93,422���Ƃ����傫�ȑ�����������ɁA�������}�b�J�[�T�[���R�̈ꕔ�ƔF�肵����ȕ���╨�����������A�u�t�B���s����ɂ����ĉ�X�͂قƂ�ǂ�����t�B���s���̎s�����ŋ��͂ȗ��̕��͂̎x�����Ă���A���̕��͉͂䂪������O�i����ɂ�ēG�̌���ɑ�Ō���������Ԑ��ɂ���A�����ɌR���ڕW�ɋߐڂ��Ė����̑傫���n�_���m�ۂ��ĉ䂪������~�������ꍇ�ɂ́A�������ɕی�Ɖ�����^���Ă����B�v�u���͂�����j�ɂ��܂�ȁA�̑�ȋP���������ʂf���炵�����_�͂��A�����Ɍ��ɔF�߂Ċ��ӂ̈ӂ�\����B�v�u�k���\���̃Q�������͗D�ɑ�����1�t�c�̉��l���������B�v�ȂǂƃA�����J�R�Ƌ��ɐ킢�A���̌��т�傫���]�����Ă����t�B���s���E�Q������A�Q�������x�����Ă����t�B���s�������̑����͐r��ł������B�������A�u�A�����J�R17�t�c�œ��{�R23�t�c��ł��j��A���{�R�̐l�I�����Ɣ�r����Ɖ䂪���̑��Q�͏��Ȃ������v�Ɖ�ژ^�Ŏ��^����}�b�J�[�T�[�ɂ́A�t�B���s���l���̔���������͓��ɂȂ������B
6��28���Ƀ}�b�J�[�T�[�̓��\�����ł̐퓬�̏I���錾���s�Ȃ��A�u�A�����J�j������Ƃ����������Ȃ܂������킢�̈�c�c��103,475㎢�̖ʐς�800���l�̐l����i���郋�\�����S��͂��ɉ�����ꂽ�B�v�ƐU��Ԃ������A���ǂ͂��̌�����{�R�̎c�������̓��\�����̎R�x�n�тŒ�R�𑱂��A�A�����J���R��6�R(�p���)��3�t�c�͏I��܂Ń��\�����ɑ��~�߂���邱�ƂƂȂ����B
�t�B���s���풆��12���ɁA�}�b�J�[�T�[�͌����ɏ��i���Ă���(�A�����J���R���̐�C���ʂł́A�Q�d�����̃W���[�W�E�}�[�V���������Ɏ���2�Ԗ�)�B
|
���_�E���t�H�[�����
������l�̑����m���ɂ�����R�i�߂ƂȂ��������m���ʌR�i�ߊ��`�F�X�^�[�E�j�~�b�c���������̐킢�̌���𐧂��A����Ɍ������Ă������A���̓��{�{�y�i�U���̑��i�ߊ���N�ɂ��邩�Ŗ㒅���N���Ă����B�d�a�ɂ�莀�̕��ɂ��������[�Y�x���g�̖��߂ŁA���C�R�Œ����𑱂��Ă����������������A���ǃ}�b�J�[�T�[�̐������m���ʌR�ƃj�~�b�c�̑����m���ʌR�����A�S���R���}�b�J�[�T�[�A�S�C�R���j�~�b�c�A�헪�����R���J�[�`�X�E�����C�����ꂼ��w�����A�O�ҊԂŋٖ��ɘA�g�����Ƃ����ʒ��F�̌��_�ł�������͓��ӂ������B������1945�N4��12���Ƀ��[�Y�x���g����������ƁA�܂����̖��͏����Ԃ���A�W�F�[���Y�E�t�H���X�^���C�R�����ɂ��A�}�b�J�[�T�[�������{�{�y�i�U�ɍۂ��Ă͊C�R�͊C�㉇��C���Ɍ��肵�A�}�b�J�[�T�[�ɋS��͂̎w������^����悤�ɗv�����Ă����̂ɑ��A���R�A�C�R�Ɛ헪�����R�͌�������R�����B�}�b�J�[�T�[�͊C�R�̊�Ȃȑԓx�����āu�C�R���_���Ă���̂́A�푈���I������痤�R�ɍ����̖h���������āA�C�R���C�O�̗ǂ��Ƃ����Ƃ��߂���C���B�v�u�C�R�͗��R�̎���肸�ɓ��{�ɏ��Ƃ��Ƃ��Ă���v�ȂǂƋ^���Ă����B���ǃ}�b�J�[�T�[�̋����\���o�ɂ��j�~�b�c�͋������A�}�b�J�[�T�[�͂��̗v������艺�����B
���悤�Ȏw�����ɂ�����哱�������ƕ��s���āA���{�{�y�i�U���̏ڍׂȍ��v��̍쐬���i�߂��A��햼�̓_�E���t�H�[�����Ƃ����Í������t����ꂽ�B�_�E���t�H�[�����͓암��B�U�����ł���u�I�����s�b�N���v�Ɗ֓��n���U�����ł���u�R���l�b�g���v�ō\������Ă������A�܂��u�I�����s�b�N���v�ɂ���16��18���ɋ}���������[�Y�x���g�ɑ����đ哝�̂ɏ��i�����n���[�ES�E�g���[�}�������F���A7��24���Ƀ|�c�_����k�ɂ����ĉp���E�B���X�g���E�`���[�`���ƍĊm�F�����B�}�b�J�[�T�[���W���[�W�E�}�[�V�����Q�d��������u�I�����s�b�N���v�ɂ��Ă̈ӌ������߂�ꂽ���A�}�b�J�[�T�[�́u���͂��̍��́A���ɒ���Ă���ǂ�ȍ����A�ߏ�ȑ��Ղ�����댯����菭�Ȃ����̂ł��邱�Ɓc�c�܂����͂��̍��́A�\�Ȃ��̂̂��������Ƃ����̓w�͂Ɛ����ɂ����Čo�ϓI�ł���ƍl���Ă���c�c���̈ӌ��ł́A�I�����s�b�N����ύX���ׂ��ł���Ƃ̍l�����A���������ł��������ׂ��ł͂Ȃ��v�Ɖ��Ă���B
�}�b�J�[�T�[�̉��ɂ͏]���̑����m�̃A�����J���R��͂̑��ɁA�h�C�c��ł��j�������[���b�p����̐��s30�t�c���������Ă����B�u�I�����s�b�N���v�ł̓}�b�J�[�T�[��764,000�����̃A�����J�R�㗤�������w�����邱�ƂƂȂ��Ă������A�w�����ƂȂ�\��ł������R�[�g�j�[�E�z�b�W�X�叫�Ȃǂ̃��[���b�p����̎w������ɂ́A�������ł���A�C�[���n���[�ւ̑R�ӎ����炩�u���[���b�p�̐헪�͋����ɂ��G�̍ŋ��̂Ƃ���ɓ˂�����ł������B�v�u�k�A�t���J�ɑ���ꂽ��͂������ɗ^�����Ă�����3�����Ńt�B���s����D�҂ł����B�v�Ȃǂƌ����������ᔻ���s���ȂǕ]�����h煂ŁA���܂�����Ă����邩�͋^�╄�����Ă����B
�����m���ł̃A�����J�R�n�㕔���̕����̎������́A���[���b�p����傫�������Ă���A�}�b�J�[�T�[�͓��{�R�Ƃ̎����ɂ��o��������A�u�_�E���t�H�[�����v�̐���s���Ɋւ��Ă͑S�����z������Ă��炸�A�w�����[�E�X�e�B���\�����R�����ɑ��u�A�����J�R�����ł�100���l�̎����҂͊o�債�Ȃ�������Ȃ��B�v�Əq�ׂĂ���B
�������A�L���s�ւ̌��q���e�������O�܂Ń}�b�J�[�T�[��j�~�b�c�猻��ӔC�҂ɂ��ڍׂ�m�炳��Ă��Ȃ������A�}���n�b�^���v��ɂ����{�ւ̌��q���e�����ƃ\�A�Γ��Q��ŁA���{�̓|�c�_���錾��������A�u�I�����s�b�N���v���J�n����邱�Ƃ͂Ȃ������B �@ |
 |
���A�����R�ō��i�ߊ� (SCAP)
1945�N8��14���ɓ��{�͘A�����ɑ��A�|�c�_���錾�̎�������肵���B�푈�I���̂��߂̒����A9��2���ɓ����p��̐�̓~�Y�[���͏�őS���E�d����(���{���{)�A�~�Ô����Y(��{�c)���C�M���X��A�����J�A���ؖ�����I�[�X�g�����A�Ȃǂ̘A������\��ɍs�Ȃ��A�����ȍ~���֎������B�������Ă������ɁA���{�̓A�����J�R��C�M���X�R(�C�M���X�A�M��̌R)�A���ؖ����R��t�����X�R�𒆐S�Ƃ���A���R�̐�̉��ɓ��邱�ƂƂȂ�B
�}�b�J�[�T�[�́A�~�������̒���ɐ旧��8��30���ɐ�p�@�u�o�^�[�����v�Ő_�ސ쌧�̌��؊C�R��s��ɓ��������B���ɍ~�藧�����}�b�J�[�T�[�́A�L�Ғc�ɑ��đ�ꐺ���ȉ��̂悤�ɓ������B
�u�����{�������瓌���܂ł͒������̂肾�����B������������ȓ��������B����������Ŗ����I������悤���B�e�n��ɂ�������{�R�̍~���͗\��ʂ�i�����A�O�s�n��ɂ����Ă��퓬�͂قƂ�ǏI�����A���{�R�͑��X�~�����Ă���B���̒n��(�֓�)�ɂ����Ă͓��{��������������������A���ꂼ�ꕜ�����݂��B���{���͔��ɐ��ӂ��ȂĂ��Ƃɓ������Ă���₤�ŁA��s�K�v�ȗ����̎S�����邱�ƂȂ�������������ł��炤���Ƃ����҂��� �v— �����V��(1945�N8��31��)
���̌�A���l�́u�z�e���j���[�O�����h�v�ɑ؍݂��A�~�������̒��ɃA�����J��\�Ƃ��ė����������ɓ����ɓ���A�Ȍ�͘A�����R���ڎ������c���O�̑�ꐶ���ٓ��̎������ŁA1951�N4��11���܂ŘA�����R�ō��i�ߊ��Ƃ��ē��{��̂ɓ��������B
|
�����{��̕��j
�}�b�J�[�T�[�ɂ͑哝�̃n���[�ES�E�g���[�}������č��j���O�̑S�����^�����Ă����B
�V�c�Ɠ��{���{�̓������̓}�b�J�[�T�[�ɗꑮ���Ă���A���̌��͂��v���ʂ�ɍs�g�ł���B��X�Ɠ��{�̊W�͏����t���̂��̂ł͂Ȃ��A�������~���Ɋ�Â��Ă���B�}�b�J�[�T�[�̌��͍͂ō��ł���A���{���ɉ��̋^�O���������Ă͂Ȃ�ʁB
���{�̎x�z�́A�������ׂ����ʂ�������A���{���{��ʂ��čs����ׂ��ł���B�����K�v�ł���A���ڍs�����Ă��悢�B�o�������߂͕��͍s�g���܂ߕK�v�Ǝv�����@�Ŏ��{����B
�A�����ō��i�ߊ������ږ�c���ʕ⍲���Ƃ��ă}�b�J�[�T�[��⍲���Ă����E�B���A���E�W���Z�t�E�V�[�{���h�́u���������͂������B�A�����J�j��A��l�̎�ɂ���قNj���Ő�ΓI�Ȍ��͂�����ꂽ��͂Ȃ������B�v�ƕ]�����B
��̍s���ɂ��ẮA�h�C�c�ł̌o�����璼�ړ����ł͂Ȃ��A�����̓��{�̑̐��𗘗p�����Ԑړ����̂ق����~���ɐi�ނƂ̌����I���f�ɗ����������B�����̑̐��̈ێ��ƂȂ�Ɣ����Ēʂ�Ȃ��̂��A�V�c���̑��u�Ə��a�V�c�̐푈�ӔC���ł��邪�A�������I��1�N6�����O��1944�N2��18���̍����Ȃ̕����w�V�c���x�Łu�V�c���ɑ���ŏI����ɂ͘A�����̈ӌ��̈�v���K�v�ł���v�Ƃ��Ȃ�����u���{���_�͈��|�I�ɓV�c���p�~�ɔ��ł���c�c�����������ēV�c����p�~���V�c��ވʂ����Ă��A��̐���ւ̌��ʂ͋^�킵���B�v�ƓV�c���ێ��̕����ł̈ӌ����o���Ă���B�܂�1945�N�ɓ���ƁA���{�̐�̐�������c���鍑���E���E�C�R3�Ȓ����ψ���(SWNCC)�ɂ����āu��̖ړI�ɖ𗧂���V�c�𗘗p����̂��D�܂����v�u�V�c���ވʂ��Ă����炩�ȏ؋����o�Ȃ�����͐�ƍٔ��ɂ�����ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ�����{�F���̌��ŋ��c���d�˂��A�푈�̊��S�I���ƕ����ȓ��{�����̂��߂ɂ́A�V�c�̈АM�ƓV�c�ɑ��鍑���̐e���̏�s���Ƃ̒m���h�̍��������㗝�W���Z�t�E�O���[��̐i��������A���ʂ͓V�c���͈ێ����ď��a�V�c�̐푈�ӔC�͕s��Ƃ�����j�ƂȂ����B����̓}�b�J�[�T�[�����ӌ��ł��������A�ق��̘A������Γ����d�h��A�����J�̑����̍������V�c�̐푈�ӔC�Njy�����߂Ă������߁A�A�����S�̂̕��j�Ƃ��Č��肷��܂łɂ����]�Ȑ܂��������B
|
���푈�ƍ߂̒Njy
�܂��}�b�J�[�T�[�����肵���͓̂��{�R�̕��������ł��������A�R���͂̂قƂ�ǂ���ł��Ă����h�C�c���h�R�ƈقȂ�A���{�R�͓��O��154�t�c700�����̕��͂��c�����Ă����B��q���\�z���ꂽ���A���C�R�ȂȂǂ̊����g�D�𗘗p���邱�Ƃɂ�蕽�������ɕ��������͐i�݁A�킸��2�J���œ��n��257�����̕��������ƕ��������������B
���ɗD�悳�ꂽ�̂͐푈�ƍߐl�̑ߕ߂ŁA�I��O����A�����J���R�h������(�p���)(����CIC)�����X�g���쐬�A����ɍ����Ȃ��v���������A9��11���ɂ͑�ꎟA�����38���̑ߕ߂ɓ��ݐ����B�����������p�@�����E�����A����e�F�Ƌ��c�M�F2�������E�����B�ŏI�I�ɑߕ߂���A����Ƃ�126���ƂȂ������A��Ƒߕ߂��w������CIC�����\�[�v�́A��Ƃ炪�k�y�@�ōق���邱�Ƃɋ^��������A�}�b�J�[�T�[�Ɂu��Ƃ�S�������Ă͂ǂ����H�v�ƒ�Ă������Ƃ����������A�}�b�J�[�T�[�́u�������邽�߂ɂ͎����͕͗s�����A�A���R�̘A���͌��ɋQ���Ă���v��A����Ƒi�ǂɔᔻ�I�ȉ������Ƃ����B
A����Ƃɓ���I�������}�b�J�[�T�[���A�t�B���s����Ɋւ���푈�ƍߑi�ǂɂ̓t�B���s�������Ɂu�푈�ƍߐl�͕K��������v�Ɩ��������ɔ��ɔM�S�ł������B�}�b�J�[�T�[�R�����\���R���ɏI��܂ő��~�߂��u�R���j��ő�̈����L�����v���w�������R���叫�ƁA�����m�푈���ՂɃ}�b�J�[�T�[�ɋ��J��^�����{�ԉ됰������2�l�̏��R�ɂ��ẮA�푈�I���O����i�ǂ̂��߂̏������s���Ă����B
�R����1945�N9��3���Ƀt�B���s���̃o�M�I�ɂč~�������I����ۂ�A���̂܂ܑߕ߂�������ꂽ�B�R���́u��x�R�����肽��A�G�͓�x�Ǝߕ��͂��܂��v�Ɗo��͂��Ă������A�ߕ߂̍ߏ�ł���}�j����s�E�Ȃǂ̓��{�R�̎c�s�s�ׂɂ��Ă͔c�����Ă��Ȃ������B�������}�b�J�[�T�[�������A�������m���O�����R�i�ߊ��E�B���A���ED�E�X�e�C���[�������J�삵���}�j���R���@��́A����܂łɔ�����Ȃ������A�����������Ȃ����s�ׂ͂��ׂĎw�����̐ӔC�ɋA����Ƃ����u�w�����ӔC�_�v�Ŏ��Y�������������B���Y������������5�l�̌R���@��̍ٔ����́A�}�b�J�[�T�[��X�e�C���[�̑��̂��������@���o�����S���Ȃ��E�ƌR�l�ł���A�T�^�I�ȃJ���K���[�@��(����ٔ��F�@�������čs���鎄�I�ٔ�)�ł������B
�܂��A�}�j���ɂ��Ă͂��̋]���҂̑������A���{�R�̎c�s�s�ׂł͂Ȃ��A�����J�R�̖C�����̋]���҂ł������Ƃ����w�E������A�R���ɑS�ӔC�킹�A�A�����J�R�̂����Ȃ����}�j���j�����{�R�ɓ]�ł��邽�߂Ƃ̌���������B�}�b�J�[�T�[�͎R���̍i��Y�ɍۂ��āA�����J�𖡂�킹��悤�Ɂu�R���A�M�͂ȂnjR���Ɋւ�����̂�S�Ĕ������v�Ɩ��߂��A�R���͎��l���̂܂܃}���S�[�̖ōi��Y�����s���ꂽ�B
�{�Ԃɂ��Ă����l�ŁA�{�l���\���ɔc�����Ă��Ȃ������A������o�^�[�����̍s�i�̐ӔC�҂Ƃ��ꂽ�B�}�b�J�[�T�[�����̍s�i�̐ӔC�҂��邱�Ƃ��u���Ȃ�`���v�ƈӋC����ł������ƂƁA�}�b�J�[�T�[��B��j�����R�l�ł���A�Ȃɂ�肻�̎��~���Ă������߁A�}�b�J�[�T�[�ɂƂ��Ă͈�Γ̍ٔ��ƂȂ����B�{�Ԃ̍ȁE�x�m�q�́A�{�Ԃٌ̕�m��1�l�t�����N�E�R�[�_��т̗v���ɂ��A�{�Ԃ̐l�Ԑ��̏،��̂��ߖ@��ɗ����ƂƂȂ����B�R���@�삪�J�삳��Ă���}�j���֏o���O�ɁA�����V���̎�ނɑ��x�m�q�́u���͌����Ď�l�̖���ɍs���Ƃ����C�����͖ѓ��������܂���B�{�Ԃ��ǂ������l�Ԃł��邩�A����C�̂Ȃ��^���̖{�Ԃ����̗͂őS���E�̐l�ɑ����m���Ē��������̂ł��B�v�Ɠ����Ă������A���ǂ͎R���ٔ��Ɠ��l�ɃJ���K���[�@��ɂ��A�����͎��Y�ł������B������x�m�q�́A�ٌ�m�̈�l�t�@�[�l�X��тƘA�ꂾ���ă}�b�J�[�T�[�ɉ�����B�}�b�J�[�T�[�̉�z�ł́A�x�m�q�͖{�Ԃ̖���ɗ����Ƃ������Ƃɂ���Ă��邪�A�x�m�q�ɂ��Ɓu�v�͓G���̑O�ōȂ����������悤�Ȏ����ł������̂Ŗ���Ȃ��Ă��Ȃ��B�㐢�̂��߂ɍٔ��L�^�̃R�s�[���ق����Ɛ\���o�����A�}�b�J�[�T�[����͏��̂����Ɍ����o���Ȃ݂����Ȏ�������ꋑ�ۂ��ꂽ�v�Ƃ̂��Ƃł������B���̂����̂��������͕s�������A�}�b�J�[�T�[�̖��߂ɂ��{�Ԃ͎R���̂悤�ɕs���_�ȏ��Y�ł͂Ȃ��A�R���𒅗p�̏�ŏe�E�Y�ɏ�����ꂽ�B���Y���s��ɕx�m�q�́u�ٔ��͐��ɕ��Q�I�Ȃ��̂ł����B���ڂ͕ߗ��s�E�Ƃ������̂ł������A�}�b�J�[�T�[�����̋P��������тɕ�����Ƃ�����������̉��_��t�����{�Ԃɑ��镜�Q�ٔ��������̂ł��B�v�Ɗ��z���q�ׂĂ���B
��ɂ��̍ٔ��́A�A�����J�����ł��٘_���o����u�@�ƌ��@�̓`���ɏƂ炵�āA�ٔ��ƌ�������̂ł͂Ȃ��v�u�@�I�葱�����Ƃ��������`�v�ȂǂƂ�����ꂽ�B
1949�N�ɎR���ٌ̕�l�̓���1�l�ł�����A�E�t�����N�E���[����т��R���ٔ��̐^�����A�����J�����ɖ₤���߂Ɂw�R���ٔ��x�Ƃ����{���o�ł����B���{�ł��|��o�ł̓�������������GHQ���������A���{�ŏo�ł��ꂽ�̂�GHQ�̐�̂��I�����1952�N�ł������B
|
�����a�V�c�Ƃ̏���k
GHQ�́A�x�z�҃}�b�J�[�T�[��S���{�����ɒm�炵�߂邽�߁A���I�ȏo�������K�v�ƍl���A���a�V�c�̉�k��]��ł����B���a�V�c���}�b�J�[�T�[�Ƃ̉�k��]��ł���A�ǂ��炪�C�j�V�A�`�u���Ƃ������͕s���ł��邪�A�V�c���A�����J���ɉ��\���o���B�}�b�J�[�T�[�l�́u�V�c����k�ɌĂѕt����Γ��{��������݂ɂ��邱�ƂɂȂ�c�c���͑҂Ƃ��A���̂����V�c�̕������ɗ��邾�낤�v�ƍl���Ă����Ƃ������ƂŁA�}�b�J�[�T�[�̗v�]�ʂ菺�a�V�c������̐\���o�����������ɂ́A�}�b�J�[�T�[�Ɩ��������͑傢�Ɋ�ы��������B���a�V�c����͖ڗ���ꐶ���قł͂Ȃ��A�����A�����J��g���@�ʼn�k�������Ƃ̐\���o�ł������B���������{���̋L�^�ɂ��ƁA�O����b�ɏA�C��������̋g�c���A��ꐶ���قŃ}�b�J�[�T�[�Ɩʒk�����ۂɁA�}�b�J�[�T�[�����������������Ɂu���W���W�v���Ă����̂ŁA�ӂ�����ŏ��a�V�c�̖K���\���o�A�}�b�J�[�T�[�����璓���A�����J��g�ق��w�����ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA���ĂŐH������Ă���B
1945�N9��27���A��g�ٌ��@�ɖK�ꂽ���a�V�c���}�b�J�[�T�[�͏o�}���͂��Ȃ��������A�V�c�̑ޏo���ɂ́A���猺�ւ܂œV�c��������Ƃ��������\��ɂȂ������s��������čD�ӂ�\�����B��k�̓��e�ɂ��Ă͓��{�ƃA�����J���W�҂��A���e�̈قȂ�l�X�ȏ،����Ȃ���Ă���(#���a�V�c�Ƃ̉�k�̓��e�ɂ��Ă��Q��)�A�ڍׂȂ����͐����̈���o�Ȃ����A�}�b�J�[�T�[�Ə��a�V�c�͌l�I�ȐM���W��z���A���̌㍇�v11��ɂ킽���ĉ�k���J��Ԃ��A�}�b�J�[�T�[�͏��a�V�c�͓��{�̐�̓����̂��߂ɐ�ɕK�v�ȑ��݂ł���Ƃ����F����[�߂錋�ʂɂȂ����B
���̍ۂɗ����Ń����b�N�X���Ă���}�b�J�[�T�[�ƁA�畞�ɐg���ْ����Ē����s���̏��a�V�c���ʂ��ꂽ�ʐ^�����X���A29���̐V���L���Ɍf�ڂ��ꂽ���߁A�����̍����ɃV���b�N��^�����B�̐l�̍֓��g�͂��̓��̓��L�Ɂu�E�k�I�}�b�J�[�T�[�m��Y�v�Ə������ނقǂł��������A�����̓��{�����͂��̎ʐ^�����ē��{�̔s������߂Ď������AGHQ�̖ژ_���ʂ�A���{�̐^�̎x�z�҂͒N�Ȃ̂��v���m�炳��邱�ƂƂȂ����B
�A�����R�ɂ���̉��̓��{�ł́AGHQ/SCAP�Ђ��Ă̓}�b�J�[�T�[�̎w�߂͐���������߁A�T�����[�}���̊Ԃł́u�}�b�J�[�T�[���R�̖��ɂ��v�Ƃ������t�����s�����B�u�V�c���̂��}�b�J�[�T�[�v�Ǝ��s�A���邢�͔�������߂ČĂ�Ă����B�܂��A�����p�@�����l�̖��a�@(�����l�s���咹���w�Z)�ɓ��@���Ă���ۂɃ}�b�J�[�T�[���������ɖK��A��ɓ����͏d�����Ƃ̉�b�̒��Łu�č��ɂ����h�ȕ��m��������v�Ɗ������Ă����Ƃ����B
|
�����a�V�c��S���瑸�h���]�����}�b�J�[�T�[
�I�풼���1945�N9��27���A���a�V�c��GHQ�ō��i�ߊ��_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�Ɖ�k�B�u�S�Ă̐푈�ӔC���v�Ƃ̕É��̔����Ƀ}�b�J�[�T�[�͑傢�Ɋ������A�u���͂��̏u�ԁA���̑O�ɂ���V�c���A�l�̎��i�ɂ����Ă����{�̍ŏ�̐a�m�ł��邱�Ƃ�����������̂ł���B�v�ƌ�N�A������B
1945(���a20)�N8��15���A���a�V�c(1901-1989)�ɂ��ʉ������������ă|�c�_���錾�����\�����A���{�͔s�k������A�哌���푈�͏I�������B8��30���A�A�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ�(GHQ) �̃_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�����{�ɐi�������B�}�b�J�[�T�[�͑�ꐶ���r��(���c��L�y��1-3-1)�ɂf�g�p���i�ߕ���݂��A�c���������낷6�K�̎������ŁA���{�̐�̐���ɒ��肵���B
9��27���A�s�퍑�̍����ƂȂ������a�V�c�́A�G���}�b�J�[�T�[�ɉ���߂ɁA�A�����J��g�ٌ��@��K�ꂽ�B��g���@�̌��ւŏ��a�V�c���o�}�����̂́A�}�b�J�[�T�[�ł͂Ȃ��A�킸��2�l�̕��������������B
�}�b�J�[�T�[�ɉ�������a�V�c�́A����������Ɠ`�����Ă���B
�u���́A���{�̐푈���s�ɔ��������Ȃ邱�Ƃɂ��A�܂������ɂ��S�ӔC���Ƃ�܂��B�܂����͓��{�̖��ɂ����ĂȂ��ꂽ���ׂĂ̌R���w�����A�R�l����ѐ����Ƃ̍s�ׂɑ��Ă����ڂɐӔC���܂��B�������g�̉^���ɂ��ċM���̔��f���@���l�̂��̂ł��낤�Ƃ��A����͎����ɂ͖��ł͂Ȃ��B�\�킸�ɑ��Ă̎���i�߂Ă������������B���͑S�ӔC���܂��v
���̌��t�ɁA�}�b�J�[�T�[�͋������B�ނ́A���a�V�c������ɂ���̂��낤�ƍl���Ă������炾�B����̖��ƈ��������ɁA���������~�����Ƃ����������A���E�̗��j�゠�������낤���B�}�b�J�[�T�[�͂��̎��̊������A�w��z�L�x�ɂ����L���Ă���B
�u���͑傫�������ɂ䂷�Ԃ�ꂽ�B�����Ƃ��Ȃ��قǂ̐ӔC�A��������̒m��s�����Ă��鏔�����ɏƂ炵�āA���炩�ɁA�V�c�ɋA���ׂ��ł͂Ȃ��ӔC�܂ł����悤�Ƃ��ꂽ�B���̗E�C�ɖ������ԓx�ɁA���̍��̐��܂ł���蓮�����ꂽ�B���͂��̏u�ԁA���̊�O�ɂ���V�c���A�l�̎��i�ɂ����Ă����{�ɂ�����ō��̐a�m�ł���A�Ǝv�����v
���̎��}�b�J�[�T�[�́A���̂悤�ɕԓ������Ƃ����B
�u���āA�킢�s�ꂽ���̌���ŁA���̂悤�Ȍ��t���q�ׂ�ꂽ���Ƃ́A���E�̗��j�ɂ��O��̂Ȃ����ƂƎv���B���͕É��Ɋ��Ӑ\�������B��̌R�̐i�������Ȃ��I�����̂��A���{�R�̕����������ɐi�s���Ă���̂��A���ꑍ�ĕÉ��̂��͓Y���ł���B���ꂩ��̐�̐���̐��s�ɂ��A�É��̂��͂����˂Ȃ�ʂ��Ƃ͑����B�ǂ����A��낵�����肢�v�������v(���c���]���ɂ��w���]���̉�z�x)
�}�b�J�[�T�[�́A�����オ���ď��a�V�c�̑O�i�݁A�����������ɓV�c�̎�����肵�߂āA�u���́A���߂Đ_�̔@���鉤�������v�Əq�ׂ��B�킸��37���Ԃ̉�ŁA�}�b�J�[�T�[�̏��a�V�c�ɑ���ԓx�́A�܂������ς���Ă����B��O�͘��R�Ƃӂ肩�����Ă����ȑԓx���Ƃ��Ă����}�b�J�[�T�[���A���ɂ͏��a�V�c�̂��ߌ�������悤�Ȍh�i�ŏ_�a�ȑԓx�ŁA��ꂩ��o�ė����Ƃ����B���A�}�b�J�[�T�[�͗\���ύX���āA���珺�a�V�c�����ւ܂Ō��������B
�����A�\�A��A�����J�{���́u�V�c�����Y���ׂ����v�Ǝ咣���Ă������A���a�V�c�̑ԓx�Ɋ��������}�b�J�[�T�[�́A�����̈ӌ���ނ��āA����V�c�����̐擪�ɗ������B
�s�풼��A�p�ЂƉ������X�ŁA�l�X�͋Q���ɋꂵ��ł����B12�����A���a�V�c�͏������O�_�ё�b(����)�ɁA�u�����̉쎀�҂��o���悤�Ȃ��Ƃ͂ǂ����Ă������ɂ͂����������v�Əq�ׂ�ꂽ�B�����āA�c���̌䕨�̖ژ^��_�ё�b�ɓn����A�u�����㏞�Ƃ��ăA�����J�ɓn���A�H�Ƃɂ����č����̋Q�������ł����̂��悤�ɂ������v�Ƃ�����������B���̌�A������(����)���A�}�b�J�[�T�[�䕨�̖ژ^�������o���ƁA���������}�b�J�[�T�[�́A�u���������݂̔C���ɂ��Ă���ȏ�́A�f���ē��{�̍����̒��ɉ쎀�҂��o���悤�Ȃ��Ƃ͂����ʁB���Ȃ炸�H�Ƃ�{������ړ�������@���u����v�Ɛ����������Ƃ����B�����_�ё�b���������w�O���ژ^�x�ɂ́A�u����܂ŐӔC�҂̎��͂������A������b�A�O����b�����S�x��ŁA�����ǂ���ꐶ�����ɍ����������A�������ď����̐F�������Ȃ������̂ɁA�É��̍������v�����S�����ł���āA�����A����ɉ쎀�҂��o���ʂ���A�É�������S�����悤�ɁE�E�E�E�E�E���Ƃ����̂��B�E�E�E�E�E�E���ꂩ��͂ǂ�ǂ�A�����J�{������̐H�Ƃ��ړ�����A���{�̐H�Ɗ�@�͂悤�₭�������ꂽ�̂ł������v�ƋL����Ă���B���a�V�c�̎̂Đg�̌�S���A�}�b�J�[�T�[���i�ߊ��̐S�����A�Q���������ɐH�Ƃ��͂���ꂽ�̂��B
���ꂩ���6�N���1951�N4���A�A�����J�{���̃g���[�}���哝�̂ƑΗ�����悤�ɂȂ����}�b�J�[�T�[�́A�哝�̂���X�R���w������A���{�𗣂ꂽ�B
1955�N�A�d���O��(����)�͈��ۏ�����Ɍ����A�_���X���������Ɖ�k���邽�߂ɃA�����J�֓n�����B�d���O���͖K�đO�ɁA���a�V�c�ɔq�y�����B���a�V�c�́A�u�����A�}�b�J�[�T�[�����Ɖ�̋@�������A�����͕č��l�̗F���Y�ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B�č��Ƃ̗F�D�W�͏I�n�d��Ƃ���ł���B���Ɍ����̗F�����Ɋ��ӂ��āA���̌��N���F���Ă���A�Ɠ`���Ă��炢�����v�ƁA�O���ɓ`�����B
�d���O���͖K�Ă���ƁA�j���[���[�N�ɂ����}�b�J�[�T�[��K�ˁA���a�V�c�̌䌾�t��`�����B�}�b�J�[�T�[�́A�u���͕É��ɂ��o����Ĉȗ��A���̓��{�̍K���ɍł��v�������l�͓V�c�É��Ȃ�ƒf������ɜ݂�Ȃ��̂ł���v�ƌ�����B����ɁA�}�b�J�[�T�[�͏��a�V�c�Ə��߂ĉ����������z���A���a�V�c���u�����͂ǂ��Ȃ��Ă����܂�Ȃ��B�����͑S�ӔC���v�Əq�ׂ�ꂽ���ƂɐG��āA�d���O���ɁA����������B
�u���́A������āA�����̗]��A�É��ɃL�X���悤�Ƃ����ʂł��B�������̍߂��܂����Ƃ��o����ΐi��ōi���ɏオ�邱�Ƃ�\���o��Ƃ����A���̓��{�̌���ɑ����̌R�̎i�ߊ��Ƃ��Ă̎��̑��h�̔O�́A���̌�܂��܂����܂����ł����B�É��͌䎩�g�ɑ��āA���܂����ĉ��b�����ɗv���������Ƃ͂���܂���ł����B�ƂƂ��Ɍ����āA���̑������������s�ׂɏo�����Ƃ�����܂���ł����B�ǂ������{�ɂ��A��̏�́A�����̉����������A�Ɛe���݂̏��É��ɂ��`���������B���̍ہA�����̐S����Ȃ鑸�h�̔O���������ɕ����ĉ������v�@ |
���ǐ�
�o�M�I�Ő�ƂƂ��ĎR�����ߕ߂��ꂽ����A9��16���̓��{�̐V���e���Ɉ�ĂɁu�䓇���{���̖\��v�Ƃ������o���ŁA�t�B���s���ɂ�������{���̎c�s�s�ׂɊւ���L�����f�ڂ��ꂽ�B�����GHQ�̔��\���f�ڂ������̂ŁA�R���ٔ���O�ɂ��̈Ӌ`����{�����ɒm�炵�߁A�ٔ��͐����ł���Ƃ�������Ȑ��_�H��ł������B�����V���̐X����(�����{�ЎЉ��)�ɂ��A����̓}�b�J�[�T�[�̎i�ߕ�������ǂ�ʂ��ĕK���V�����Ɍf�ڂ���悤�ɂƖ��߂���A�L���ɂ��Ȃ��V���͔��s������}������Ƌ�������Ă����Ƃ����B
���ۂɒ����V���͂���GHQ�̎w���ɂ��āA�u�����˔@�Ƃ��ĕČR������\����Ɏ������^�ӂ͂ǂ��ɂ��邩�Ƃ������Ƃł���B(�A���R���m�ɂ��)�\�s�����̔����ƁA���{�R�̔�s�̔��\�Ƃ́A���炩�̊W������̂ł͂Ȃ����v�Ɛ�̊J�n�ȍ~�ɕp�����Ă����A���R���m�ɂ��ƍ߂ƁA�t�B���s���ɂ�������{�R�̖\�s�s�ׂ̕w���Ƃ̊֘A�����^���_�����L���ɓ��ꂽ�Ƃ���A�}�b�J�[�T�[�͒����V����1945�N9��19����20����2���Ԃ̔��s��~�����Ƃ��Ă���B
���̌�A�}�b�J�[�T�[�Ə��a�V�c�̏��ʒk�̍ۂɎB�e���ꂽ�ʐ^���f�ڂ��ꂽ�V���ɂ��āA������b�̎R��ނ��ꑽ���Ƃ��ĐV���̔̔��֎~�������Ƃ������A�A�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ��̔������������ƂɂȂ�A���v王{���t�̑ސw�̗��R�̂ЂƂƂ��Ȃ����B��������������Ƃ���GHQ�́u�V���ƌ��_�̎��R�Ɋւ���V�[�u�v(SCAPIN-66)���w�߂��A���{���{�ɂ�錟�{���~�����AGHQ�����{���s�����ƂƂ��A���{�̕��x�z���ɒu�����B�܂��A�A�����ƒ������̋L�҂̂��߂ɓ��{�O�����h������̑n�݂��w�������B
�}�b�J�[�T�[�̓��{�̃}�X�R�~�ɑ�����j��@���ɕ\���Ă���̂́A�����ʐM�Ђ��s�����A���R�ɔᔻ�I�ȕɑ��A1945�N9��15���ɃA�����J���R�ΓG���̖��Ԍ��{��C�h�i���h�E�t�[�o�[�卲���A�͑��B�v���Ǒ��فA�勴���Y���{���������A�Ö�ɔV�������ʐM�Ђ��Ăт��Đ\���n�����ʍ��ł��邪�u�����͕̎��R�ɋ����S�������A�A���R�����̂��߂ɐ���Ă����B�������A���O�����͕̎��R����E����s�ׂ��s���Ă���A�̎��R�ɔ����ӔC��������Ă���B�]���Č����͂�茵�������{���w�߂��ꂽ�B�����͓��{��Γ��Ƃ͌��Ă��Ȃ����A���{�͂܂����������肷�鎑�i�͂Ȃ��A�ƍl���Ă�����B���̓_���悭�������Ă����B�V���A���W�I�ɑ�100%�̌��{�����{����B�R�����������A�A���R�ɑ��邢���Ȃ�ᔻ��������Ȃ��B�v�Ƌ��������Ő\���n���Ă���B
|
���A���R��̉��̓��{
�}�b�J�[�T�[�̋��͂Ȏw���͂̉��ŁA�ܑ���v�Ȃǂ̓��{�̖��剻���}���A���{�����@�����z���ꂽ�B �@ |
���哝�̑I
�A�����R�ō��i�ߊ��Ƃ��Ă̔C�����Ԓ��A�}�b�J�[�T�[���g��1948�N�̑哝�̑I���ւ̏o�n��]��ł����B�������A�����R�l�͑哝�̂ɂȂ�Ȃ����Ƃ���A��̍s���̑����I���ƊM���A����]�B���̂��߁A1947�N����}�b�J�[�T�[�͂��т��сu���{�̐�̓����͔��ɂ��܂��s���Ă���v�u���{���R�����ƂɂȂ�S�z�͂Ȃ��v�ȂǂƐ������o���A�A�����J�{���������ē��{�ւ̐�̂��I��点��悤���b�Z�[�W�𑗂葱�����B
1948�N3��9���A�}�b�J�[�T�[�͌��Ɏw�������Α哝�̑I�ɏo�n����|�𐺖������B���̐����ɍł��ߕq�ɔ��������͓̂��{�l�ł������B���X�̏��X�ɂ́u�}������哝�̂Ɂv�Ƃ������ꖋ���x������A���{�̐V���̓}�b�J�[�T�[���哝�̂ɑI�o����邱�Ƃ����҂��镶�͂ł��ӂꂽ�B�����āA4���̃E�B�X�R���V���B�̗\���I���Ń}�b�J�[�T�[�͋��a�}���Ƃ��ēo�^���ꂽ�B
�}�b�J�[�T�[���x�����Ă���l���ɂ́A�R��{���̉E�h�𒆐S�ɁA�V�J�S�E�g���r���[���Ў�̃��o�[�g�ER�E�}�R�[�~�b�N(�p���)��A��͂�V���Ў�̃E�B���A���E�����h���t�E�n�[�X�g�������B�w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x�����}�b�J�[�T�[���L�͌��ł��邱�Ƃ������A�E�B�X�R���V���ł͏�������Ɨ\�z���Ă������A27���̑�c�m�̂����Ń}�b�J�[�T�[�ɓ��[�����̂͂킸��8���ƎS�s�A���ʂ͂ǂ̏B�ł�1�ʂ��Ƃ邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B5��10���ɂ͗��R�Q�d�����ɂȂ��Ă����A�C�[���n���[�������������A�}�b�J�[�T�[�Ɩʒk�����ۂɁu�����Ȃ�R�l���A�����J�̑哝�̂ɂȂ낤�ȂǂƖ�S���N�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƓB���h���Ă���B�������}�b�J�[�T�[�́A���̃A�C�[���n���[�̂��̒����Ɍx���̐F���ׁA����邱�Ƃ͂Ȃ������B
6���̋��a�}���ł́A�}�b�J�[�T�[�𐄂��n�[�X�g�����S�����̃`���V���������A�n��̐V���w�t�B���f���t�B�A�E�C���N���C�A���[�x�̐V���z�B���܂œ������I���^���������Ȃ��A�}�b�J�[�T�[�̉��������̂��߂ɁA���{�R�̕ߗ����e�����������ꂽ����̒��s���ɋꂵ�ރW���i�T���E�E�F�C�����C�g���Ăꂽ���A��1�[��1,094�[�̂���11�[������ꂸ�A��2���7�[�A��3���0�[�Ƃ����S�s���i���A���Ǒ�1�[��434�[���l�������g�[�}�X�EE�E�f���[�C���哝�̌��ɑI�o���ꂽ�B
���{�ł́A�}�b�J�[�T�[�ւ̔ᔻ�L���͌��{����Ă������߁A�I����̏�𐳊m�ɓ`���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�w�^�C���x���́u�}�b�J�[�T�[��哝�̂ɂƂ��������A�����]�܂Ȃ��ƌ������̕����傫���v�Ɗ��ɍŏ��̃E�B�X�R���V���̎S�s���ɕ��Ă������A���{�ł̓}�b�J�[�T�[���L�͌��҂ł������A�[�T�[�E���@���f���o�[�O��o�[�g�E�^�t�g�̉e�͋}���ɔ����Ȃ��Ă������A�ȂǂƎ����Ɣ�������Ȃ���Ă����B���̌��ʁA�����̓��{���������a�}���ł̎S�s�ɋ������ꂽ�B���̌��i�������w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x�́u���{�l�̋����͑����A��i�Ƒ傫���������Ƃ��낤�B�c�c���{�̐V���͌��{�ɂ���āA�A�����J���炭��}�b�J�[�T�[�����x���̋L���ȊO�́A���̔��\���ւ����Ă�������ł���B���̂��߁A�}�b�J�[�T�[�����ɂ͂قƂ�ǔ������Ȃ��̂��Ƃ�����ۂ��^����ꂽ�B�v�ƕĂ���B
�哝�̑I�̌��ʁA�哝�̂ɑI�ꂽ�̂͌��E�̃g���[�}���ł������B�}�b�J�[�T�[�ƃg���[�}���́A�����m�푈���������̍s���Ɏ���܂ŁA�����Ɣ��肪����Ȃ������B�}�b�J�[�T�[�͑哝�̂ւ̓�������ꂽ���A�܂肻��́A���͂�A�����J�̍�������Ƃ̎������C�ɂ����ɓ��{�̐�̐�����{�s�ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���A���{�̘J�����c�̒e���Ȃǂ𐄂��i�߂邱�ƂƂȂ����B�C�M���X��\�A�A���ؖ����Ȃǂ̑��̘A�����͂��̎��_�ɂ����āA�}�b�J�[�T�[�̎哱�ɂ����{��̂ɑ��Ĉًc�������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă����B �@ |
 |
�����N�푈
���k���N�ɂ���P�U��
����E����ɓ�k(�؍��Ɩk���N)�ɕ����Ɨ��������N�����ɂ����āA1950�N6��25���ɁA�\�A�̃��V�t�E�X�^�[�����̋����������������钩�N�l���R(�k���N�R)���؍��ɐN�U���J�n���A���N�푈���u�������B
�����}�b�J�[�T�[�́A�A�����J�������� (CIA) ��}�b�J�[�T�[�����̒���@�� (Z�@��) ����A�k���N�̓�i�����̕��ĎO�Ȃ���Ă����ɂ�������炸�A�u���N�����ł͌R���s���͔������Ȃ��v�ƐM���A�^���Ɍ������悤�Ƃ͂��Ă��Ȃ������B�k���N�R�̐N�U��m�点��d�b��������ہu�l�����������l�ɂ����Ă���v�ƌ����A���{�̍~������5�N�ŕ��a���j��ꂽ���ƂɏՌ����Ă����Ƃ����B�ނ͂ǂ��Ή����Ă����̂��킩��Ȃ��܂܊ۈ�����߂����B
�������̌�́A�u�؍��R�͊�P���Ĉꎞ�I�ɃV���b�N���Ă��邾���ł���A���ꂪ���܂�ΕK�����������ɈႢ�Ȃ��v�ƍl���A���܂�틵��S�z����l�q��\�ɏo���Ȃ������B6��27���Ƀ}�b�J�[�T�[�́A���N�����ɂ�����A�����J�R�̑S�w���������h���Ȃ���t�^����A�������ɌR�������ً̋}�A���ƃA�����J�̖��Ԑl�~�o�̂��߂̑D���A��s�@�̎�z���s�����B�Ȃ��A���N�����ɂ͍��A�R�Ƃ��āA�C�M���X�R��I�[�X�g�����A�R�𒆐S�Ƃ����C�M���X�A�M�R��A�x���M�[�R�Ȃǂ��Q�R�W�J�����B
28���Ƀ\�E�����k���N�R�ɐ�̂��ꂽ�B�킸���̊��ԂŊ؍��̎�s����̂���Ă��܂������Ƃɋ����A���̐[�������ĔF�������}�b�J�[�T�[�́A�{�i�I�R���s���ɏ��o���ׂ��\�E������̐�����s��ɔ�сA�����ӑ哝�̂�v�l�Ƃ̉�k���s�����B���ă}�b�J�[�T�[�͗����ӂ�ɁA1948�N8��15���ɍs��ꂽ��ؖ����̐������T�Łu�M���Ƃ�1882�N�ȗ��A�F�l�ł���v�Ɖ������A�L���̍ۂ̉��R����Ă����B���̌��t�ʂ�A�}�b�J�[�T�[�͂����ɍ��A�R���i�ߊ��Ƃ��Đ푈���w�����A���̌�O�����@���s���A���m������ە����Ă������ܓ����֖߂����B
�}�b�J�[�T�[�͂��̌�A�C���t�����n��ȏ�ɐ푈�Ŕj�ꂽ���N�����ɗ��܂邱�Ƃ������A��炵���ꂽ���������_�Ƃ��Đ���Ɍ������A���A��œ����֖߂�Ƃ����w���`�Ԃ��J��Ԃ����B�����̍s���͏𗝉�����W���ƂȂ�A���f�����A��ɐ����Ԃ��Ȃ����ؐl�����a���̒����l���u��R(�R�������`�E�R)�Q�����������Ƃ��Ȃ����B
|
���m��㗤���
7���ɓ���Ɩk���N�R�̓d���I�N�U�ɑ��āA�؍��R�ƍ݊A�����J�R�A�C�M���X�R�𒆐S�Ƃ������A�R�͐�]�I�Ɋׂ����B�}�b�J�[�T�[�͋}篍ݓ��A�����J�R�攪�R�����R�Ƃ��Ĕh�������ق��A�C�M���X�R��I�[�X�g�����A�R�𒆐S�Ƃ����C�M���X�A�M�R���lj��h�����邪�A�������\���ɐ����Ă��Ȃ��������ߐi����j�ނ��Ƃ͏o�����A���R���ӂ̒n����m�ۂ���̂Ŏ��t�ł������B
�����Ń}�b�J�[�T�[�͂��̏�ŊJ���ׂ��A�\�E���ߍx�̐m��ւ̏㗤��������B���̍��͖{�l���u������0.02%�v�Ƃ����قǂ̎���ȍ��ł���A�����Q�d�{���ƊC�R�͔��ŁA���V���g������͗��R�Q�d�����W���[�[�t�E���[�g���E�R�����Y�ƊC�R��핔���t�H���X�g�E�V���[�}���A�n���C����͑����m�͑��i�ߒ����A�[�T�[�EW�E���h�t�H�[�h�Ƒ����m�͑��C�����i�ߊ��V�F�p�[�h�𓌋��ɑ����Ă܂Œ��~�ɂ����悤�Ƃ������A�}�b�J�[�T�[�͍������s�����B
�}�b�J�[�T�[���g�����������Ⴂ�ƌ��ς����Ă������̍��͑听���ɏI���A��ǂ͈�C�ɋt�]�A9���ɂȂ�ƍ��A�R�̓\�E���̒D��ɐ��������B����̓}�b�J�[�T�[�̖����Ɛl�C��傫�����߂��B
|
�������l���u��R�̎Q��
�m��㗤���̑听���ɂ��}�b�J�[�T�[�̎��M�͔�剻���A���֑̌�Ȑ틵�Ƀ��V���g�������������A�����Q�d�{���͍��A���c��҂����A9��28���t�Ŗk���N�ł̌R���s�����������B�푈�ړI���u�k���N�R�̐N���̑j�~�v����u�k���N�R�̉�Łv�ɃG�X�J���[�g�����̂ł���B���h�����W���[�W�E�}�[�V�����̓}�b�J�[�T�[�Ɂu38�x���Ȗk�ɑO�i���邱�ƂɊւ��āA�M���ɂ͐헪�I�E��p�I�ɉ��̖W�����Ȃ����̂ƍl���Ă������������v�Ƌɔ�d��łƁA�}�b�J�[�T�[�́u�G���~������܂ŁA���N�S�y���䂪�R�����ɊJ����Ă�����̂Ɨ�������v�Ɖ��Ă���B�������A���\�̑S�ʉ���������g���[�}���́A�u���C�R�͂�����̏ꍇ���������z���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�u�����t�߂ł͊؍��R�ȊO�̕����͎g�p���Ȃ��v�u�������k������у\�A�̈�ւ̋�C����̍U�����֎~����v�Ƃ���������݂����B���\�̑S�ʉ���̖h�~�̑��ɂ��A�z�C�g�E���@���f���o�[�O�A�����J��R�Q�d�����́A��R�̍�����g�傷�邱�ƂŎ��R�E�퓬�����ŋ�R�͂����Ղ��A���̕�[�̂��߂�2�N�Ԃ̓��[���b�p���ʂ̖h��͂����ɂȂ�ƍl���A���h���Ȃ����̍l�����x�����A�}�b�J�[�T�[�ɂ��`����ꂽ�B���������̍�퐧���́A�S�ʐ푈�ŏ������邱�Ƃ��M���̃}�b�J�[�T�[�ɂ́A�����ȊO�̉����ɂ��������Ȃ������B
10��15���ɃE�F�[�N���ŁA�g���[�}���ƃ}�b�J�[�T�[�͒��N�푈�ɂ��ċ��c���s�����B�g���[�}���͑哝�̂ɏA�C����5�N�����o�߂��Ă������A�܂��}�b�J�[�T�[�Ɖ�������Ƃ��Ȃ��A2�x�ɂ킽��}�b�J�[�T�[�ɋA���𑣂������A�}�b�J�[�T�[�̓g���[�}���̖��߂�f���Ă����B�������A�m��㗤���ō��܂��Ă����}�b�J�[�T�[�̍����I�l�C��11���̒��ԑI���ɗ��p���悤�ƍl�����g���[�}���́A����}�b�J�[�T�[�Ƃ̉�k�����������A�A�����a��}�b�J�[�T�[�̂��߂ɉ�k�ꏊ�͖{�y�̊O�ł悢�Ɛ\���o���B�g���[�}�����̓n���C����]���Ă������A�}�b�J�[�T�[�͖�̔�s�@�����ʼn����ɂ͍s�������Ȃ��Əa��A���ǃg���[�}�������܂�āA���V���g������7,500km�A���������3,000km�̃E�F�[�N������k�ꏊ�ƂȂ����B
�g���[�}�����傢�ɑË������ɂ�������炸�A�}�b�J�[�T�[�͂��̉�k��s�����Ɏv���Ă���A�E�F�[�N���Ɍ������r���������炳�܂ɋ@�������������B���悵�Ă����؍����ݑ�g�W�����E�W���Z�t�E���`�I�ɁA�u(�g���[�}����)�����I���R�̂��߂ɂ���ȉ����܂ŌĂяo����Ď��Ԃ̖��ʂ��v�ƕs�������炵�A�g���[�}���������̏�(����)�܂ŗ��Ă�����ׂ����ƍl���Ă����B�g���[�}���̋@���ɒ��������邽�߂ɓ��̏��Ń}�b�J�[�T�[�@�����Ă����A��k��1���Ԓx��ē����������߃g���[�}�������{���āu�ō��i�ߊ���҂�����悤�Ȃ��Ƃ��x�Ƃ���ȁB�킩�������v�ƈꊅ�����Ȃǂ̃G�s�\�[�h�����z����Ă��邪����͍��b�ł���B���ۂɂ̓}�b�J�[�T�[�̓g���[�}���@�̓����������H��ŏo�}���A���̂܂܋��ɉ�k���s��ꂽ�q���Ў������Ɍ������Ă���B
���̌�̉�k�ł̓}�b�J�[�T�[���A�u�ǂ�Ȏ��ԂɂȂ��Ă������R�͉�����Ȃ��v�u�푈�͊��ӍՂ܂łɏI���A���m�̓N���X�}�X�܂łɂ͋A���ł���v�ƌ��������B�g���[�}���́u����߂Ė������ׂ������ȉ�k�������v�ƌ����c���ċ@��̐l�ƂȂ������A�{�S�ł̓}�b�J�[�T�[�̕s���ȑԓx�ɕs�M�������߁A�܂��}�b�J�[�T�[�̕������g���[�}���ւ̓G�ӂ����߁A�j�ǂ͕b�ǂ݂ƂȂ����B
���̌���}�b�J�[�T�[�́u���ؐl�����a���ɂ��Q��͂Ȃ��v�ƐM���Ă������Ƃ�����A�⋋�����L�т�̂��\�킸�ɒ��ؐl�����a���Ƃ̍����̊��]�ɂ܂Ŕ������B��Ƀ\�A�ɒn��R�h����v�����Ēf���Ă����������́A1950�N9��30���ɒ�����g�قŊJ�Â��ꂽ���ؐl�����a������1���N���Z�v�V�����ɏo�Ȃ��A���̐ȂŒ����̕����h����v�����A����Ɏ���ёɕ����h���̗v���̎莆�������ƁA���̎莆��p���i�ɑ����Ėk���ɔ�����B�ё͂����ɍs�����N�����A10��2���ɒ������Y�}���������Ǐ햱�ψ�������W����Ɓu����̒x�ꂪ�����ɂƂ��Č���I�v���ɂȂ�v�u�����𑗂邩�ǂ��������ł͂Ȃ��A�����邩�A�N���i�ߊ��ɂȂ邩���v�Ɛ����ψ���ɐ������B�����ψ�����A�A�����J�R�����]�ɓ��B����ΐ��n���Ē����ɐN�U���Ă���A�����j�~����ɂ͕����h��������K�v������A�Ƃ̍l���ɌX���A�ё̌��f�ʂ蕔���h�������߁A10��8���ɋ������ɒʒm�����B�������A�����J�Ƃ̑S�ʏՓ˂�����邽�߁A���ؐl�����a���̍��R�ł��钆���l������R����g�D���邪�A�`����͋`�E���Ƃ����u�����l���u��R�v(�R�������`�E�R)�̔h���Ƃ����B�ё̓��V�t�E�X�^�[�����ɍq��x����v�����邪�A�X�^�[�����̓A�����J�Ƃ̒��ڑΌ���]��ł��炸�A�ёɒ��������ł̏��x���ƕ���E�����̎x���݂̂ɗ��߂���̕ԓ����Ă���B�����R�̎w�����ƂȂ����d�����́A�\�A�̍q��x���Ȃ��ł͍��ɕs���������Ă������A�����h���͖ё̋����ӎv�ŗ\��ʂ�s���邱�ƂƂȂ����B����ɖё͖k���N�R�̎w�������d�����Ɉ�C���邱�Ƃƌ��߁A�푈�͒����̎w�����ɒu����邱�ƂƂȂ����B
10��10���ɖ�18���l�̒�������4�R�����]���z���Ėk���N���肵�A���̐��͌��30���l�܂Ŗc��オ�����B�}�b�J�[�T�[�͂��̊댯�Ȓ�����@�m���Ă������A�G�̈Ӑ}��ǂݎ�邱�Ƃ��o�����A��w�U���I�ɂȂ����B�����̓g���[�}���̎w���ʂ�A�����t�߂ł̕����g�p���؍��R�݂̂Ƃ��邽�߁A������������40����60�}�C��(64km����97km)���ꂽ�ꏊ���؍��R�ȊO�̍��A�R�̍Ő[���B�_�ƌ��߂����A10��17���ɂ̓g���[�}���̎w����j��A���̍Ő[���B�_�𒆊ԓ_�ɕς��A����ɍ����[���O�i����悤�Ɋe�����i�ߊ��ɖ��߂����B���������ɋ߂Â��߂Â��قǒn�`�͋}�s�ƂȂ�A�⋋������ƂȂ��Ă��������A�}�b�J�[�T�[�͂��̎������y�������B�}�b�J�[�T�[�̂��̍��w���́A�ё̎v���ڂł������B���Ėё��Q�d�̗��p�v�Ƀ}�b�J�[�T�[�̐l���ɂ��Đq�ˁA���p�v���u�����Ƌ���ŗL���ł��B�v�Ɖ���ƁA�ё́u����ł���D�s�����A�����ȓG�����̂͊ȒP���B�v�Ɩ������ɓ������Ƃ������Ƃ����������A���܂⒆�����]�ނ̂͂���Ƀ}�b�J�[�T�[���k��𖽗߂��A�⋋���C�����댯�Ȃ܂łɐL�т��邱�Ƃł������B������������㩂ɂ͂܂�悤�ȃ}�b�J�[�T�[�̖��߈ᔽ�ɁA�\�����Ĕ��̐��͏o�Ȃ������B�}�b�J�[�T�[�̈��|�I�Ȗ����ɃA�����J�R���ł��،h�̔O�������������ƁA�܂�����ȃ}�b�J�[�T�[�Ɉӌ�����͖̂��v���Ƃ������߂̋C�������������Ƃ����B���̂悤�Ȓ��ł����Q�d���̃}�V���[�E���b�W�E�F�C�͈٘_�����������A�ӌ������グ���邱�Ƃ͂Ȃ������B
�҂��钆���l���u��R�̑�R�́A�~��ς����Ƃ��̎��R�����I�݂ɗ��p���A�A�����J�R�ɋC�Â���邱�ƂȂ��ڋ߂��邱�Ƃɐ��������BS.L.A�}�[�V����(�p���)�͂��̌����ȑg�D�͂��w�e�����H��x�ƌ`�e���u���̕��́A�ʒu�A�ǂ��ɑ�ꌂ�������Ă��邩�̔閧�͊��S�ɕۂ���Ă��āA��d�ɕ������Ă���ɓ����������v�Ə܂��Ă���B10��26���ɂ͊؍��R�ƒ����R�̏����荇��������A��������18����ߗ��ɂ��A�~���ɋ삯�����A�����J�R��1�C���t�c�͒����R�̐�Ԃ����j���Ă���B�܂��A�����J��8�R�i�߃E�H���g���E�E�H�[�J�[�����͔��ɗD�G�Ȓ����R�����������t�߂ɑ��݂��邱�Ƃ�q���Ɋ�������Ă���A�T�d�ɐi�����Ă������A�����̏�d�v������邱�Ƃ͂Ȃ������B�Ƃ����̂��A�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ��Q�d��2�� (G2) �����`���[���Y�E�E�B���r�[��}�b�J�[�T�[�̖�����́A�}�b�J�[�T�[�̐���ςɋ^�������ނ悤�ȕ��ŏ����ɗ��߁A�}�b�J�[�T�[�ɐ��m�ȏ�͂��Ȃ��������Ƃ�����ł������B�ʏ�̎w�����ł���ł��邾�������̐��m�ȏ���~�����邪�A�}�b�J�[�T�[�͏��������̍s�����Ƃ��Ă��邱�ƂɊ��S�ɗZ�����Ă���̂�]��ł����B�E�B���r�[��̓}�b�J�[�T�[�̐��i���n�m���Ă���A�}�b�J�[�T�[����낤�Ƃ��Ă��銛�]�ւ̍Ō�̐i����W�Q����悤�ȏ������̂܂グ�邱�Ƃ͂����A�T�d�ɍH���ꂽ�����}�b�J�[�T�[�ɕ��Ă������߁A�}�b�J�[�T�[�ɐ��m�ȏ�͂��Ă��Ȃ������B���̂��߁A�V���e������ɒ����R�̕s���ȓ������@�m���L���ɂ������AGHQ�̓��V���g���Ɂu�m�F����Ă��Ȃ��v�Ɗy�ϓI�ȕ����Ă���B
���̂悤�ȏ��ŁA11��1���ɒ����l���u��R���؍��R���R�c�ɏP�����������A�؍��R3�t�c�͑�����������đS�ʓI�ɔs�������B���N�����͍����ɋ߂Â��قǖk�ɍL�����Ă��邽�߁A�����Ɍ����Đi�����Ă����A�����J��8�R�Ƒ�10�R�̊Ԃ͂��Ȃ�J���Ă����B���̑�8�R�̉E���ɓW�J���Ă����؍��R������ƁA�����l���u��R�͓J��h�ڂ�炵�Ȃ����8�R�̑��ʂɓˌ����Ă����B��8�R�͐l�C��p�̑O�ɁA�����܂��呹�Q�������B�}�b�J�[�T�[�͒����R�̑�U���J�n�̕��Ă����A�������{�i�I�ɉ�����Ă����̂��ǂ������f���邱�Ƃ��o�����A�������g�ō������Ă��邱�Ƃ�F�߂��B���̂��߁A�O�������ւ̓I�m�Ȏw�����x��A���̊ԂɊe�����͑傫�ȑ��Q���邱�ƂƂȂ����B�틵�̐[�������悤�₭�F�������}�b�J�[�T�[�͍��h���ȂɁu����܂œ��i�ߕ��͂ł������̂��Ƃ����Ă������A���܂⎖�Ԃ͂��̌����Ɨ͂���Ƃ��܂ŗ��Ă���v�u�����͑S���V�����푈�ɒ��ʂ��Ă���v�Ƃ��������q�X�e���b�N�ȑœd���s���Ă���B
|
���X�R
11��28���ɂȂ��āA�悤�₭�}�b�J�[�T�[�͌R�i�߂ɓP�ނ��鋖��^���A��8�R�͕����������A���̌�38�x���̌���ɓP�ނ����B�I�݂ɓP�ސ���w�����Ă�����8�R�i�ߊ��̃E�H���g���E�E�H�[�J�[�����ł��������A12��23���A�������ɌR�p�W�[�v�Ō�ʎ��̎������B�}�b�J�[�T�[�͂��̕���ƁA�ȑO���猈�߂Ă����ʂ�A�����Ɍ�C�Ƃ��ĎQ�d�{�����Q�d���}�V���[�E���b�W�E�F�C�����𐄑E�����B�}篃A�����J���瓌���ɔ���b�W�E�F�C�́A12��26���Ƀ}�b�J�[�T�[�Ɩʒk�����B�}�b�J�[�T�[�́u�}�b�g�A�N���ǂ��Ǝv�������Ƃ���肽�܂��v�ƃ}�b�J�[�T�[�̎����Ă�����p��̑S�w�����ƌ��������b�W�E�F�C�ɗ^�����B���b�W�E�F�C�̓}�b�J�[�T�[�̉߂����J��Ԃ��Ȃ����߂ɁA�����ɑO���ɔ��ŕ����̏��m�F�������A�z���ȏ�ɍ����ŁA�s�k��`���������A�m�C�͒ቺ���A�w������͗L�Ӌ`�ȏ���S�������Ȃ��Ƃ����L�l�������B���b�W�E�F�C�͌R�̗��Ē����͓I�ɍs�������A�����l���u��R�̐����͎~�܂炸�A1950�N1��2���̓\�E���ɔ����Ă����B���b�W�E�F�C�̓\�E���̖h�q����ߓP�ނ𖽂��A1��4���Ƀ\�E���͒����l���u��R�ɐ�̂���邱�ƂƂȂ����B
�����̋`�E�R�̐l�C��p�ɉ�����A�}�b�J�[�T�[�ƃ��V���g���̓p�j�b�N��ԂɊׂ��Ă����B�}�b�J�[�T�[�͑�K�͂ȑ����ƁA�����g�p���܂߂��������k�����咣�������A����E����ɏ���R�̑啝�ȏk�����s�Ȃ��A���\���b�p�Ń\�A�ƌ��������A�����J�R�ɁA��K�͂ȑ����𑗂�]�T�͂Ȃ������B�������k���ւ̔����͐푈�̊g����܂˂��A�܂������ɂ��ẮA���N�̒n���ƏW��ڕW���Ȃ����ߌ����I�ł͂Ȃ��Ɣی����ꂽ�B�}�b�J�[�T�[�͎G���̃C���^�r���[�ɓ�����`�Łu�������k���ɑ����P�̋֎~�́A�j�ォ�ĂȂ��n���f�B�L���b�v�ł���v�ƍ��ɐ�����݂��Ă���g���[�}�����������낵�A�܂������R�ɒǂ��s�����Ă���̂ɂ�������炸�u��p�I�ȓP�ނł���A�s���ȂǂƍL����`����Ă���̂͑S���̃i���Z���X���v�ƚ������B�g���[�}���͌��{���A���V���g�������̃}�b�J�[�T�[�ւ̌��Ŋ��͑����Ă������B�}�b�J�[�T�[����̔ᔻ�Ɍ��{�����g���[�}���́A�����Q�d�{���ɖ����ă}�b�J�[�T�[�ɑ��A�����I�Ȉӌ��\��������ꍇ�͏㋉�@�ւ̗�����悤�ɂƎw�����������A�}�b�J�[�T�[�͂��̎w�������A���̌�������I�Ȕ������J��Ԃ����B
�\�E������P�ނ������b�W�E�F�C�ł��������A�P�ނ͂����܂łŁA���A�R�𗧂����点��ƁA1��26���ɂ͐푈�̎哱����D���Ԃ����߂̔��]�U���T���_�[�{���g�����J�n���A�����̋`�E�R�̍U�����������߂��B�}�b�J�[�T�[�͂��̎��_�Œ������S�ʓI�ɉ�����Ă��Ă���ƍl���A���V���g���ɍēx�O�̘b�������Ԃ��A�u���A�R�����W����Ȃ����߂ɂ́A�������݂����A�͖C�ˌ��ƋŐ푈���s�ɕK�v�ȍH�Ɨ͂�j��v���邱�Ƃƍ����}�R���Q�킳����ȂǁA�����Ƃ̑S�ʐ푈�˓����咣�����B�������g���[�}���̕��j�́A���{����p�����������ΑΒ����̖{�i�I���ɓ˓����邪�A����ȊO�ł͕����͒��N�����̒��Ɍ��肷��Ƃ̈ӌ��ł���A�}�b�J�[�T�[�ɂ����Ȃ߂�悤�Ȓ����̕ԓ������Ă���B�Q�d�����I�}�[���E�u���b�h���[�̓}�b�J�[�T�[�̐푈�g��v���́A�푈�̏��ނ���u�����̂悤�ȌR���I�V�˂������ɂ��������g�R�̏��R�����ւ̕v�ɊW������Ɛ������Ă����B
�������A���b�W�E�F�C�͌��L�ʏ��͂ł��؍����m�ۂ��邱�Ƃ͏\���\�ł���Ɣ��f���Ă���A�����R�̑�3���U�������j�����2�����Ŏ��n�����߂��A1951�N3���ɂ͒����R��38�x���܂ʼn����Ԃ����B�틵�̉̓��b�W�E�G�C�̍��w���ɂ����̂ŁA�}�b�J�[�T�[�̏o�Ԃ͂Ȃ��������߁A�����s���Ǝv�����}�b�J�[�T�[�͋r���𗁂т邽�߂��A�������疋���ƕw��A��đO����K�ꂽ�B���������鎞�A���b�W�E�F�C���v�悵�����J�n�O�Ƀ}�b�J�[�T�[���O���ɖK��ĕw�ɍ��̊J�n������R�炵�Ă��܂��A���b�W�E�F�C���玩�d���Ăق����Ƃ����Ȃ߂��Ă���B�}�b�J�[�T�[�̌R���̒��ŁA�^�������畔���ɔ��R���ꂽ�̂͂��ꂪ���߂Ăł������B���b�W�E�F�C�͎��`�Ń}�b�J�[�T�[���u�����ł�����̂ł͂Ȃ��s�ׂɑ��Ă��A���_���咣���Ă����������v�ƕ]���Ă���B
���V���g���́A���̎��_�ł͒��N�����̕��͓���ɂ͋������������A�A�����J�R������P�ނ�������悤�ȍ��ӂ�M�]���Ă����B����}�b�J�[�T�[�́A���b�W�E�F�C�̐��������炩�ɂȂ�ƁA�����̑��݊����A�s�[�����邽�߂��u������1�N�Ԃŋ���������V�����\�z�v�����肵���ƃV�[�{���h�ɘb���Ă���B�̂��ɂ���́u�Œ��ł�10���Ő폟�ł���v�ɒZ�k���ꂽ�B���̍\�z�Ƃ́A���}�b�J�[�T�[��������Ƃ���ɂ��A���B��50���̌����𓊉������\�̋�R�͂���ł�������A�C�����ƒ��������}�R���v50�����Œ����R�̔w��ɏ㗤���ĕ⋋�H��f���A38�x������i�����Ă����攪�R�ƒ����R���͟r�ŁA���̌�ɓ��{�C���物�C�܂Œ��N���������f���ĕ��ː��R�o���g���U�z���A���\�R�̐N����h���Ƃ������̂ŁA���̐헪�ɂ��60�N�Ԃ͒��N�����͈��肪�ۂĂ�Ƃ��Ă����B
�܂��A��N���b�W�E�F�C�́u�}�b�J�[�T�[�́A�������k���̋�R��n�ƍH�ƒn�т������ƋŔj����͎c��̍H�ƒn�т��j�A���Y��`�x�z�̑Ŕj��ڎw���Ă����v�u�\�A�͎Q�킵�Ă��Ȃ��ƍl���Ă������A�����Q�킵�ė�����\�A�U���̂��߂̑[�u��������v�Ɛ��@���Ă���B���̍l���Ɋ�Â��}�b�J�[�T�[�́A���x�ڂɂȂ邩�킩��Ȃ������̑O���ւ̈ڑ��Ǝg�p�����g���[�}���ɋ��߂����A�g���[�}���͕Ԏ���ۗ������B
�}�b�J�[�T�[�ւ̕ԓ��O�ɁA�g���[�}���͒��N�������̓����J�����ߒ����Ăт����邱�ƂƂ��A3��20���ɓ����Q�d�{����ʂ��ă}�b�J�[�T�[�ɂ����̓��e���`����ꂽ�B�g���[�}���Ƃ̑Ό��p����N���ɂ��Ă����}�b�J�[�T�[�́A���̒��H���W�Q���ăg���[�}���𑫌�����Ђ�����Ԃ����Ɖ��A1951�N3��24���Ɉ�R�i�ߊ��Ƃ��Ă͈ٗ�́u���A�R�͐������ɂ����Ă������R�����|���A�����͒��N�����͕s�\�Ȃ��Ƃ����炩�ɂȂ����v�u�������R���I����̐��ˍۂɒǂ����܂�Ă��邱�Ƃ�Ɋ��ł��Ă���͂��v�u���͓G�̎i�ߊ��Ƃ��ł���k����p�ӂ�����v�Ȃǂ́u�R���I����f�v�\�������A����͒����ւ̎����I�ȁu�Ō�ʒ��v�ɓ������A�����������h�������B�܂��A��}���a�}�̕ێ�h�̏d���W���[�[�t�E�E�B���A���E�}�[�e�B���E�W���j�A�O���@�c������}�b�J�[�T�[�Ɉ��Ă��A��p�̍����}���͂𗘗p�����Ăƃg���[�}�������̃��[���b�p�d������ւ̔ᔻ�̎莆�ɑ��A�}�b�J�[�T�[���}�[�e�B���̈ӌ��ւ̎^���ƃg���[�}�������ᔻ�̕Ԏ����o���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�A��R�i�ߊ������̐���Ɍ����o���������ȃV�r���A���E�R���g���[���ᔽ���������ōs��ꂽ�B����́A1950�N12���Ƀg���[�}���������Q�d�{����ʂ��Ďw�������u�����I�Ȉӌ��\���͏㋉�@�ւ̗����Ă���v�ɂ������A�g���[�}���́u���͂��͂�ނ̕s���]�ɉ䖝�ł��Ȃ��Ȃ����v�ƌ��{�����B
�܂����̍��ɂȂ�ƃC�M���X�Ȃǂ̓������́A�}�b�J�[�T�[�������Ƃ̑S�ʐ푈��]��ł��邪�g���[�}���̓}�b�J�[�T�[���R���g���[���ł��Ă��Ȃ��A�Ƃ̌��O�����A�u�A�����J�̐����I���f�Ǝw���҂̎��v�ɑ��郈�[���b�p�������̐M���͒ቺ���Ă����B���͂�}�b�J�[�T�[��S���M�����Ă��Ȃ������g���[�}���́A�}�b�J�[�T�[�̉�C�����ӂ����B
4��6������9���ɂ����ăg���[�}���́A���������f�B�[���E�A�`�\���A���h�����W���[�W�E�}�[�V�����A�Q�d�����I�}�[���E�u���b�h���[��ƁA�}�b�J�[�T�[�̈����ɂ��ċ��c�����B�����o�[�̓}�b�J�[�T�[�̉�C�͓��R�ƍl���Ă������A��������{��������Ƃ������ȕ��@�ɂ��Ęb������ꂽ�B�܂�����ɂ����̍��Ƀ}�b�J�[�T�[�̍\�z���㉟������悤�ɁA�����R���������k���ɕ��͂����A�\�A�R���ɓ��Ɍ��������ڂł���헪�����@���܂ލq��@500�@��z���A�������k���ɂ͍ŐV���[�_�[�ݔ����ݒu���A���{�C�ɐ����͂��K�͏W�����n�߂��B�����̋��ЂɑR���ׂ��A��ނȂ��}�b�J�[�T�[�̐\���o�ʂ�4��6���Ɍ���9���O�A���Ɉڑ����錈������Ă���B�������A�}�b�J�[�T�[�����܂������f�����Ȃ��悤�����x�����A�ڑ��̓}�b�J�[�T�[�ɂ͒m�点���A�܂������̓}�b�J�[�T�[�̎w�����ɂ͂������헪��R�̎w�����ɒu���Ƃ����ی��������Ă���B
4��10���A�z���C�g�n�E�X�͋L�҉�̏��������Ă������A���̏���O�ɘR��A�g���[�}�������ɔᔻ�I�������w�V�J�S�E�g���r���[���x�������̒����ɋL���ɂ���Ƃ�������m�����u���b�h���[���A�}�b�J�[�T�[����Ƃ����O�Ɏ��C���邩���m��Ȃ��ƃg���[�}���ɍ�����ƁA�g���[�}���͊����I��ɂ��āu���̖�Y�����Ɏ��\������������悤�Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��A�����z�����тɂ��Ă��̂��v�ƃu���b�h���[�Ɍ������B�g���[�}����4��11���[��0��56���Ɉٗ�̋L�҉���s���A�}�b�J�[�T�[��C�\�����B��C�̗��R�́u�������ɂ��đS�ʓI�Ŋ����ȓ��_���s���̂́A�䂪�����`�̗�����`�Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃł��邪�A�R�i�ߊ����@���Ȃ�тɌ��@�ɋK�肳�ꂽ�����ŏo����鐭��Ǝw�߂̎x�z�������˂Ȃ�ʂƂ������Ƃ́A��{�I���ł���B�v�ƃV�r���A���E�R���g���[���ᔽ�����ڂ̗��R�Ƃ��ꂽ�B
���{���Ԍߌ�3���A���̕�͓��{�ɒB�������A�}�b�J�[�T�[�͂��̂Ƃ��Ȃ̃W�[���Ƌ��ɁA����������@�c���E�H�[�����E�}�O�i�\���ƃm�[�X�E�G�X�g�q��В��̃X�^�[���Y�Ɖ�H�����Ă����B�����̃V�h�j�[�E�n�t�卲�́A�����オ�����W�[���ɉ�C�̃j���[�X��m�点�A�u���}��v�Ə����ꂽ��������n���A�v�l�͂��̒��������}�b�J�[�T�[�ɖق��ēn�����B���e��ǂݏI�����}�b�J�[�T�[�͂��炭���ق��Ă������A�₪�ĕv�l�Ɍ������āu�W�[���A����ŋA����v�ƌ������Ɠ`�����Ă���B�u���b�h���[�����́u�}�b�J�[�T�[��C�͓��R�ł���v�Ǝ咣�����B
|
���A��
4��16���Ƀ}�b�J�[�T�[�̓��b�W�E�F�C�����ɋƖ������p���œ������ۋ�`�����������A���̍ۂɂ͉�����20���l�̓��{�l���l�߂����A�w�����V���x�Ɓw�����V���x�̓}�b�J�[�T�[�Ɋ��ӂ��镶�͂��f�ڂ����B�}�b�J�[�T�[�������ɐZ���Ă����̂��A�����̌�������u200���l�̓��{�l�������ɂт�����ƕ���Ŏ��U��v�Ǝ���̉�ژ^�Ɍ֒����ď����Ă���B�������A�����ɕ��w����͊w�Z����̎w���ɂ�铮���ł������Ƃ����،�������B
�̋g�c�́u�M�����A��X�̒n����Q���������A���̑O�G����Ȃ��o�������̂����āA�����ǂꂾ���Ռ��������A�ǂꂾ���߂����A�M���ɍ����錾�t������܂���B�v�Ƃ����ʂ��߂��ގ莆���}�b�J�[�T�[�ɓn���A4��16���ɂ͏O�Q���c�@���}�b�J�[�T�[�Ɋ��ӌ��c���悷��ƌ��c���A�����s�c�����{�o�ϒc�̘A��������ӕ��\���Ă���B
�}�b�J�[�T�[�͋�`�œ��ėv�l��Ȃ̊ȒP�Ȋ������̌�ɁA���@�o�^�[�����œ��{�𗣂ꂽ�B���悵�Ă����}�b�J�[�T�[�ƈꏏ�Ɏ��C�����R�[�g�j�[�E�z�C�b�g�j�[�O�����Njǒ��ցu���{��������x������̂́A����������̂��Ƃ��낤�ȁv�ƌ�������A���ۂɃ}�b�J�[�T�[���ēx���{��K�ꂽ�̂�1961�N�Ƀt�B���s������Ɨ�15���N�̋L�O���T�ɍ��o�Ƃ��ď����ꂽ�ہA�t�B���s���Ɍ������r���ŏ����n�ɋx�e�ɗ������A�A��ɉ��c��n��1���������ł������̂ŁA11�N��ƂȂ����B�������Z�����j�[���Ȃ��A�قƂ�ǂ̓��{�l���m��Ȃ��܂܂ł̍ė���(�Ō�̗���)�ł������B
�}�b�J�[�T�[���A����������A5���ɓ����ċg�c���t�́A�}�b�J�[�T�[�Ɂu���_�����v�̏̍���^����u�I�g���o�Ɋւ���@���āv���t�c���肵�A���{�ȊO�ł��u#�}�b�J�[�T�[�L�O�فv�����݂��悤�Ƃ����������������B�}�b�J�[�T�[�ɂ��̌v��ɑ���l����Őf�����Ƃ���A�z�C�b�g�j�[��ʂ��āu�����͂��̐\���o�ɂ��đ�ό��h�Ɏv���Ă���B�v�Ƃ����Ԏ��������Ă���B �@ |
 |
���ޔC
1951�N4��19���A���V���g��D.C.�̏㉺�@�̍�����c�ɏo�Ȃ����}�b�J�[�T�[�́A�ޔC�������s�����B�Ō�ɁA�E�F�X�g�|�C���g�Ɏ��g���ݐЂ��Ă�������(19���I��)�A���m�̊Ԃŗ��s���Ă������h�̂̃t���[�Y�����p���āA�u�V���͎��Ȃ��A������������̂݁v�Əq�ׁA�L���ɂȂ����B
���ƂȂ����u�́v�ɂ͉��ʂ肩�̉̎�������B�v���
�u�����ɂ���Âڂ����H���ŁA��������1��3�x�A�Ɠ������H���B�r�[�t�X�e�[�L�Ȃ�Đ�Ώo�Ȃ��B�{���A�����Ƃ�����g���ɓ���镪�����Ȃ��B������A���ꂽ���Ꮽ���������Ă����B�V���͎��Ȃ��A������������̂݁B���l�͖����r�[�������߂�A�ޒ��l�͎����̋L�͂���D�����B�R���l�͌P������D�����A�����Ɠz��͂��܂ł������Ȃ낤�B�����牴�����͂����P���A�P���B���������Ă��܂��܂ŁB�v
�Ƃ������̂ł���B
�c�ꂩ��o�Ďs�����p���[�h����ƁA���V���g�����݈ȗ���50���l�̎s�����W�܂�A�����Ɣ���𑗂����B�����ɂ̓j���[���[�N�̃}���n�b�^�����p���[�h���A�A�C�[���n���[�M����4�{�A��700���l���W�܂��ă}�b�J�[�T�[���j�������B���̓��r������~�蒍�����������e�[�v�́A���|�ǂ̕ɂ���2,859�g���ɂ��Ȃ����B�܂��A1942�N�Ƀ}�b�J�[�T�[���R���q�h�[���ŌnjR�����������I�l�C���Ă������ɁA�R�[���p�C�v��}�b�J�[�T�[��͂����W���b�L�Ȃǂ̃L�����N�^�[�O�b�Y�Ŗׂ����Ǝ҂��A�܂���ʂ̃}�b�J�[�T�[�E�O�b�Y��̔��������A��Ԃ悤�ɔ��ꂽ�B���̒��ɂ̓}�b�J�[�T�[�̉����ɂ��o�ꂵ���R�́u�V���͎��Ȃ��A������������̂݁v�̃��R�[�h�����������A5��ނ��̉����Ŕ̔����ꂽ�B���ɂ�1948�N�̑哝�̌��ƂȂ��ė��I�����ۂɔ���c���Ă����ɂ��������Ǝ҂������Ƃ����B�Z���Ƃ��Ă����}���n�b�^���̍����z�e���u�E�H���h���t���A�X�g���A�v�̃X�C�[�g���[���ɂ�15���ʂ̎莆��2���ʂ̓d��Ɩ���3,000���̓d�b���E�����A�Ƒ��ɂ��e�E����c��Ȑ��̃v���[���g�������Ă���قǁA�}�b�J�[�T�[�̍����I�l�C�͒��_�ɒB�����B
5��3������A�}�b�J�[�T�[�ɂƂ��čŌ�̌����ƂȂ�A��@�̊O���ψ���ƌR���ψ���̍���������ɏo�Ȃ����B�c��́u�}�b�J�[�T�[�̉�C�v�Ɓu�ɓ��̌R����v�ɂ��Ăł��邪�A�}�b�J�[�T�[��C�������ł���Ƃ���g���[�}���疯��}�ɑ��A���̌�����Ƃ������ւ̍U���Ɍq���������a�}�̐����V���[�Ƃ̈Ӗ����������������B�������A���̌�����ɐ旧��4��21���ɁA�g���[�}���������̃��[�N�ɂ��j���[���[�N�E�^�C���Y���Ƀg���[�}���ƃ}�b�J�[�T�[�ɂ��g���b�N����k�̑��L�^���L���Ƃ��Čf�ڂ��ꂽ�B����܂Ń}�b�J�[�T�[�́u�����̎Q��͂Ȃ��Ǝ����͌����Ă��Ȃ��v�ƉR�̎咣���s���Ă���A���̑��L�^�ɂ�肱��܂ł̎咣���ꂽ�}�b�J�[�T�[�́u�������v�ƌ��{���K���ɔے肵�����A���̋L���͎����ł���A���̋L�����������j���[���[�N�E�^�C���Y�̋L�҃g�j�[�E�����B�G����1952�N�Ƀs���[���b�c�@�[�܂���܂��Ă���B���̋L���ɂ��A�}�b�J�[�T�[�̍����I�l�C��w�i�ɂ��������͍킪��Ă����B
������n�܂�ƁA�}�b�J�[�T�[�́u�\�A�͒��N�푈�ɐ[���֗^���Ă��Ȃ��v�u���������N��������ǂ��o����邭�炢�̔s�k�̓\�A�ɑ債���e���͗^���Ȃ��v�u�ɓ��n��̃\�A�R�ɃA�����J�R�Ɛ키�����̎��͂͂Ȃ��A�j���������Ă���A�]���ă\�A�Ɛ키�̂Ȃ獡�̕����悢�A���ԂƋ��ɃA�����J�̗D�ʐ��͎����Ă����v�ȂǁA���g�̃\�A�ւ̕]���Ə���f��Y�قɏ،��������A�����Q�d�{���Ƌc���ɂ̓\�A���Ⴆ�}�b�J�[�T�[�̕��͒ʂ�ł������Ƃ��Ă����卑�\�A���h������o��͂Ȃ��A�}�b�J�[�T�[�̑�_�Ȓ�Ă��������ꂵ�Ă���Ƃ����l�����吨���߂Ă����B�u���b�h���[�̓}�b�J�[�T�[�̒�Ă��u��X��������ꏊ�ŁA����������ɁA������G�Ƃ̌�����푈�Ɋ������ނ��ƂɂȂ����ł��낤�v�Ɛ�̂ĂĂ���B�܂��A�}�b�J�[�T�[�̃\�A�ւ̉ߏ��]�����A���O�ɓ��{���ߏ��]�����Ĕs�k�����}�b�J�[�T�[�̑O�̉߂����v���o���c�������������B�������A�Y�قɌ���������[�h���Ă����}�b�J�[�T�[���A����}�̃u���C�A���E�}�N�}�[����@�c������́A�j���[���[�N�E�^�C���Y�̋L���ɏ����ꂽ�ʂ�u���Ȃ��͒����͎Q�킵�Ȃ��Ɗm�M���Ă����̂ł͂Ȃ������̂��H�v�Ƃ̎������ƁA����܂ł̂悤�ɔے肷�邱�Ƃ��ł����u���͒����̎Q��͂Ȃ��Ǝv���Ă����v�ƔF�߂���Ȃ��Ȃ����B���̔���ɂ��}�b�J�[�T�[�̗���͎キ�Ȃ��Ă����A�}�N�}�[���������݂�����悤�Ɂu���R�̓A�����J�Ɛ����A���R�������[���b�p�Ń\�A�R�̍U���ɑς��邱�Ƃ��ł���Ƃ��v�����H�v�Ǝ��₷��ƁA�}�b�J�[�T�[�́u���̐ӔC�n��(�ɓ�)�ȊO�̂��ƂɊ������܂Ȃ��łق����B�O���[�o���Ȗh�q�Ɋւ��錩���͂����ŏ،����ׂ����Ƃł͂Ȃ��v�Ɠ��������A�����h���EB�E�W�����\����@�c������̂��̐ӔC�n��́u�����R�����]�Ȗk�ɒǂ����ꂽ�ꍇ�A�����R�͍ēx��������˔j�����N�����ɍU�ߍ���ł͂��Ȃ��̂��H�v�Ƃ�������ɑ��ẮA�܂Ƃ��ȕԓ����s�����Ƃ��ł��Ȃ������B����܂Ő��Ƃ����F��������Y�قɌ���Ă������C�Ȏp���͊��S�Ɏ����A�������̖���}�̗e�͂Ȃ�����Ɉ���I�Ȏ琨�ƂȂ��Ă������B
�}�b�J�[�T�[�ւ̎��^��3���Ԃɂ킽��A�g���[�}�������̓}�b�J�[�T�[�ɑ����������߂����A����Ńg���[�}�����ӔC�Njy���瓦���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A���]����ł̔s�k�̓}�b�J�[�T�[�Ɠ��l�Ƀg���[�}�����������j�A���̌㖯��}�͐������������ƂƂȂ�B�������A�}�b�J�[�T�[��C�����́u����قǕs�l�C�Ȑl��������قǐl�C������l������C�����̂͂͂��߂Ă��v�ƃ^�C�����ɏ������قǂ̕s�l�C���ŁA�哝�̍đI��f�O�����g���[�}�����A���������̊�{���O�����A���R�ƃ}�b�J�[�T�[�ɗ��������������Ƃ�����ɕ]������Ă����A�ݐE���̕s���Ȓ�]����������A�����ł̓A�����J����������哝�̂̒��ŗ��h�ȑ哝�̂�1�l�ƊŘ��悤�ɂȂ��Ă���B
���̌�����̊��Ԓ��A�o�Ȏ҂̓}�b�J�[�T�[�̒�ĂŒ��x�݂���炸�A�T���h�C�b�`�ƃR�[�q�[�����ɉ^���Ē��H�Ƃ��A�x�݂Ȃ����^�𑱂����B���Ƀ}�b�J�[�T�[�́A���^���ɂ͈�x�Ƃ��ăg�C���ɂ���s�����A�Ƃ���c������u������71�Ȃ̂ɑ�w���̂悤���N���������Ă���v�ƕςȊ��S������Ă���B����3���Ԃɂ킽�鎿�^���ɁA�����ł��悭���{�ň��p�����u�����ɑ��Ă̊C���헪�v��u���{�l��12�v�،����Ȃ���Ă���B���̒�����̌�͌R�l�Ƃ��Ċ������邱�Ƃ͂Ȃ��A������ޖ��������A�A�����J�R�ɂ����Č����ɂ͈��ނ̐��x���Ȃ����߁A�R�Ђ��̂��̂͐��U�ێ����ꂽ�B
|
���_�O���X�E�}�b�J�[�T�[���R�@�E�@�A�M�c��ł̗��C�����@1951/4/19
���N�푈�̏���������A�}�b�J�[�T�[�A�����R�ō��i�� ���Ƃ͊��x�ƂȂ����_�����킳��Ă���(�}�b�J�[�T�[�� �����ڈ�������A�Ӊ���x���Ɏ�荞�ނ��Ƃ�]�� ��)�̂Ńg���[�}���ɂ��}�b�J�[�T�[�̉�C�͗\�z�O�� ���Ƃł͂Ȃ��������A�Ռ���a�炰�邱�Ƃ͂Ȃ������B�m �点�͕s�K�Ȍ`�Ń}�b�J�[�T�[�̂��Ƃɓ͂����B���C�� ����Đ���z����邱�Ƃ�����A�g���[�}���͌����ʒm�� �}�b�J�[�T�[�ɓ͂��O�Ɍ�������\�����B�g���[�}���͒� ��̌R�̌o�H�Œʒm���邱�Ƃ�]�܂Ȃ��������߁A�؍��� �ʂ����I��H���g�킴����A���̂��ߑ��B���x�ꂽ�� �炾�B
1951 �N4 ��11 ���ߌ�3 ���A�}�b�J�[�T�[�̓m�[�X �E�F�X�g�q��̎В��E�C���A���E�X�^�[���Y�Ə�@�c�� �E�H�[�����E�}�O�i�\���Ƃ̉�H���I���悤�Ƃ��Ă����B �V�b�h�E�n�t�͌ߌ�3 ���̃j���[�X�Œm�点���A�}�b�J�[�T�[�v�l�ɓd�b�ŘA�������B���x���̎��A �n�t�̓I�}�[���E�u���b�h���[���璼�ڌ��d�����A����������ċ���Ɍ����������A�����ɂ͂��� ���łɋL�҂������Q�����Ă����B�d���ǂނƁA�}�b�J�[�T�[�͑f���C�����������B�u�W�[�j�[�A����ƋA ��邼�v
5 ����A�ߑO6�����A�}�b�J�[�T�[�͎�����o�ĉH�c��`�Ɍ��������B���悻25���l�̐l�X���A��`�� ����12 �}�C���̓���10 ����̗������Ă����B1 ���Ԍ�A�u�o�^�[���v�Ɖ��̂��ꂽ�\�ȑO��SCAP �ƌ� ��Ă����\��s�@�ɏ��A�}�b�J�[�T�[�̓n���C�A�T���t�����V�X�R�Ɍ����Ĕ�ї������B
1951 �N4 ��19 ���A���V���g��DC �̏㉺�@�̍�����c�ɏo�Ȃ����}�b�J�[�T�[�́A�ޔC�ɍۂ��Ẳ� �����s�����B
��
��@�c���t���A���@�c���t���A�Ȃ�тɘA�M�c��c���̊F�l
���͐[���������Ƒ傫�Ȍւ�������A���̉��d�ɗ����Ă��܂��B����܂łɁA�����ɗ������č��̗��j�̈̑�ȍ\�z�҂����̂��Ƃ��v���A�����ɂ� �炴��܂���B���@�{�̋c�_���s���邱�̏ꏊ���A����܂łōł������Ȍ`�Ől�Ԃ̎��R��̌����Ă��邱�Ƃ��v���A�ւ���o������܂���B���� �ɂ͑S�l�ނ̊��҂Ɗ�]�ƐM�`���Ïk���Ă��܂��B���͂����Ȃ�}�h�I�ȑ�`�̏����҂Ƃ��Ă��A�����ɗ����Ă͂��܂���B�Ȃ��Ȃ�A���_�ƂȂ��Ă���͍̂� �{�I�Ȗ��ł���A�}�h�I�ȍl���͈̔͂�傫����������̂ł��邩��ł��B��X�̐i�ޓ������S�ł��邱�Ƃ��ؖ����A��X�̖�������낤�Ƃ���Ȃ�A����� �̖��͍ō������̍��v�Ɋ�Â��ĉ�������Ȃ���Ȃ�܂���B�]���āA���������ɏq�ׂ邱�Ƃ́A������č��������n������������\�����Ă�����̂ƁA�F �l�������Ɏ~�߂Ă������邱�Ƃ��m�M���Ă��܂��B
�l���̂������ꎞ�ɂ����ʼn�������ɂ�����A���ɂ͉��̈⍦����a������܂���B�S�ɂ���̂́A����1�A���̂��߂ɐs�����Ƃ����ړI�����ł��B�� �ۑ�͐��E�I�ȋK�͂ɍL����A���܂�ɂ��[�����ݍ����Ă��邽�߁A�ق��̑��ʂ��C�ɂ��~�߂���1�̑��ʂ������������邱�Ƃ́A�S�̂̔j�]���������Ƃł� ������܂���B�A�W�A�͈�ʓI�ɉ��B�ւ̌����ƌĂ�Ă��܂����A����ɗ�炸���B���A�W�A�ւ̌����ł��邱�Ƃ��܂������ł��B����̍L�͂ȉe������ ���ɋy�Ȃ����Ƃ͂��蓾�܂���B�킪���̌R���͂́A����2�̑O�������ɂ͕s�K�ł���A��X�̓w�͂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƌ����l�����܂��B�� ��͔s�k��`�̕\���̍ł�����̂ł��B�������z�G�������̌R���͂�2�̑O���ɕ����邱�Ƃ��ł���̂Ȃ�A������}�����Ă����̂ł��B���Y��`�̋��Ђ� �n���K�͂̂��̂ł��B���Y��`����̒n��Ői�o�ɐ�������A���̂��ׂĂ̒n�悪�j��鋰�ꂪ����܂��B�A�W�A�ŋ��Y��`�ɏ����A���邢�͍~������ ���Ƃ́A�����ɉ��B�ɂ����Ă��̐i�o��j�މ�X�̓w�͂ʂɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B
����������ʓI�ȓ������w�E������ŁA�A�W�A�S�ʂ̂��ƂɌ����Ę_�������Ǝv���܂��B���ܑ��݂��Ă�����q�ϓI�ɕ]������ɂ́A���̑O�ɁA�A�W �A�̉ߋ��ƁA���݂܂łɍۗ����Ă����v���I�ȕω��ɂ��āA�����Ȃ�Ƃ��������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�A�W�A�����̍����́A������A���n���͂��璷 ���ԍ�悳��Ă��Ă���A�t�B���s���ɂ�����킪�����ȕč��������w�j�Ƃ��Ă����Љ�`��l�̑����A���������̉��P�Ȃǂ��A�B������@����قƂ�Ǘ^ �����Ă��܂���ł����B�����Ă悤�₭�A��̐푈�ɐA���n��`�̑����������������@������o���܂����B���A�V���ȋ@��̓����ƁA����܂Ŋ����邱�� �̂Ȃ����������ƁA�����I���R�ɍ����������S��ڂ̓�����ɂ��Ă���킯�ł��B
�n���̐l���̔����ƁA�V�R������60�p�[�Z���g���W�܂������̒n��ŁA�A�W�A�̐l�X�͕��S���ʂŐV���ȗ͂��}���Ɍ��W�����Ă���A�����p���Đ��� ���������コ���A�ߑ㉻�̍\�z���m�����A����̓Ɠ��̕����I���ɓK�������悤�Ƃ��Ă��܂��B�A���n���̊T�O�Ɏ�������l�����悤�Ƃ��܂��ƁA���ꂪ�A�W �A�̐i�ޕ����ł���A���̓������~�߂邱�Ƃ͂ł��܂���B����͐��E�o�ς̕Ӌ����ړ����邱�Ƃ̓��R�̋A���ł���A���E��̑S�̓I�Ȓ��S�́A���菄�� �āA���ꂪ�n�܂����n��ɖ߂���̂Ȃ̂ł��B
���̂悤�ȏɂ����āA�킪���Ƃ��ẮA�A���n���オ���łɉߋ��̂��̂ɂȂ����ȏ�A�A�W�A�����̍��������͂Ŏ��R�ȉ^�����`��錠����ؖ]���� ����Ƃ��������ɖڂ�w����H�������̂ł͂Ȃ��A����������{�I�Ȑi���̏ɋ�����悤�ɁA�����̐�������킹�Ă������Ƃ������I�ɏd�v�ɂȂ�� ���B�ނ炪�����߂Ă���̂́A�F�D�I�Ȏw���A�����A�x���ł���A����Ȏw�}�ł͂���܂���B��������Γ��ł���A�ꑮ�Ƃ����p�J�ł͂Ȃ��̂ł��B�ނ�̐� �O�̐��������͈���ȂقǒႢ���̂ł������A�푈���I��������A�푈�̎c�����S�ЂŁA���������͉ʂĂ��Ȃ��������Ă��܂��B���E���̂��܂��܂ȃC�f�I�� �M�[�̓A�W�A�l�̎v�l�ɂقƂ�lje�����y�ڂ��Ă��܂��A����������Ă��܂���B�A�W�A�̐l�X�����߂Ă���̂́A�������������̐H�Ƃ��ݑ܂ɓ���邱 �ƁA���������܂Ƃ��Ȉߕ���g�ɒ����邱�ƁA�����������ȉ����̉��ŐQ�N�����邱�ƁA�����Đ����I���R�����߂鐳��Ȗ����I�~������������@��邱 �ƂȂ̂ł��B���̂悤�Ȑ����I�E�Љ�I�́A�킪���̈��S�ۏ�ɂƂ��ĊԐړI�ȈӖ���������܂��A����͖ډ��̌v��̔w�i���Ȃ����̂ł���A��X�� ����`�̗��Ƃ�����������悤�Ƃ���Ȃ�A�����T�d�Ɍ������Ȃ���Ȃ�܂���B
�킪���̈��S�ۏ�ɂ�蒼�ړI�ȈӖ������̂́A��̐푈���ɋN�����A�����m�̐헪�I���ݔ\�͂̕ω��ł��B����܂ł́A�č��̐����̐헪�I�����́A �����ʂ�A��k�A�����J�嗤�̋��E���ł���A�댯�ɂ��炳�ꂽ����̓ˏo���Ƃ��āA�n���C�A�~�b�h�E�F�[�A�O�A�����o�ăt�B���s���܂łȂ��铇�X������ �܂����B���̐���̓ˏo���́A�킪���̋��͂ȑO���n�ł͂Ȃ��A�G��������ʂ��čU�����邱�Ƃ��ł���A�����Ď��ۂɍU�����Ă����A�킪���̎コ���������� ���邱�Ƃ�������܂����B
�����m�́A�אڂ��闤�n���U������Ӑ}�����������D�R�ɂƂ��āA���ݓI�Ȑi�U�n��ł����B���̏́A��X�̑����m�ł̏����ň�ς��܂����B���� �āA�킪�R�̐헪�I�Ӌ��͈ړ����đ����m�S������͂݁A�ێ��������킪�������L��ȍ�(�ق�)�ƂȂ�܂����B���ۂ���́A�A�����J�嗤�S�̂Ƒ����m �n��ɂ��邷�ׂĂ̎��R�ȓy�n�ɂƂ��ẮA�h��p�̏��̖������ʂ����Ă��܂��B�킪���Ǝ��R�ȓ������������L����A�A�����[�V��������}���A�i������ �ŃA�[�`��ɉ��т��A�̓��X�ɂ���āA��X�̓A�W�A�̊C�݂܂ł̑����m�n����x�z���Ă��܂��B���̈�A�̓��X�����X�́A�C�R�͂Ƌ�R�͂ɂ���āA�E�� �W�I�X�g�N����V���K�|�[���Ɏ��邷�ׂẴA�W�A�̍`���x�z���\ �J��Ԃ��܂����A�C�R�͂Ƌ�R�͂ɂ���āA�E���W�I�X�g�N����V���K�|�[���܂ł̂��ׂĂ̍`���x�z���\ �����m�ɓG�ΓI�ȓ��������荞�ނ̂�j�~���邱�Ƃ��ł��܂��B
�A�W�A����̗��D�I�ȍU���͏㗤���ɂȂ�ɈႢ����܂���B�i�H��ɂ���V�[���[���Ƃ��̏������ɒu�����ɁA�㗤�U���𐬌������邱�Ƃ͂� ���܂���B��X���C�R�͂Ƌ�R�̗͂D�ʂƁA��n����邠����x�̗��R������i���Ă���A�A�W�A�嗤����킪���ւ́A���邢�͑����m�̗F�M�ւ̑�K�͂ȍU ���́A���ׂĎ��s�ɏI���ł��傤�B
�����������ł́A�����m�͂��͂�A���ݓI�ȐN���҂��߂Â��댯�Ȓʂ蓹�ɂ͂Ȃ�܂���B�t�ɁA���₩�Ȍ̐e�����ȗl����ттĂ��܂��B�킪�� �̖h�q���͎��R�̂��̂ł���A�Œ���̌R���I�w�͂ƌR����ňێ����邱�Ƃ��ł��܂��B����́A�����Ȃ鑊��ɑ���U�����z�肵�Ă��炸�A�i�U���ɕs�� ���ȗv�ǂ������Ă��܂��A�K�Ɉێ�����A�N���ɑ��閳�G�̖h���i�ƂȂ�ł��傤�B���̕����ʂ�̖h�q���𐼑����m�Ɉێ����邱�Ƃ��ł��邩�� �����́A���̂��ׂĂ̕������ێ��ł��邩�ǂ����ɂ������Ă��܂��B��F�D�I�ȗ͂ɂ���Ă��̖h�q�����ꕔ�ł��傫���j����A�ق��̂������v������ ����I�ȍU�����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
���̒m�����A���̌R���I�]���ɑ��ẮA���܂��ɂ����Ȃ�R�̎w���҂��ًc�����������Ƃ�����܂���B�����炱�����͂���܂ŁA�R���I�ȋً}���� ���āA�����Ȃ邱�Ƃ����낤�Ƃ���p�����Y��`�҂̎x�z���ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƌ����������Ă����̂ł��B���������������ԂɂȂ�A�����Ƀt�B���s���� ���R�����Ђɂ��炳��A���{�������A��X�̐����̍őO���̓J���t�H���j�A�A�I���S���A���V���g���e�B�̉��ݕ��܂Ō�ނ�]�V�Ȃ���������ł��傤�B
���ܒ����嗤�Ō�����ω��𗝉����邽�߂ɂ́A�ߋ�50�N�Ԃɂ킽�钆���l�̋C���ƕ����̕ω��𗝉����Ȃ���Ȃ�܂���B50�N�O�܂ł̒��� �́A�S���ώ������������A�݂��Ɉӌ����Η����邢�����̃O���[�v�ɕ�����Ă��܂����B�ނ�͎̗��z�ł��镽�a��`�I�����̋����ɏ]���Ă������߁A�� �����N�����悤�Ȑ����͂قƂ�ǂ݂��܂���ł����B�Ƃ��낪20���I�̏��߁A�������������ŋώ��������߂�w�͂��s��ꂽ���ʁA������`�I�ȏՓ������� ��܂����B�Ӊ�̎w���̂��ƁA���̏Փ�������ɑ傫���L���邱�Ƃɐ������܂������A���ꂪ���������Ō����Ɍ������A���܂ł́A���x�z�I�ōU���I�Ȑ��� �������ꂵ��������`�̐��i��тт�Ƃ������ԂɎ����Ă��܂��B
�������ĉߋ�50�N�̊ԂɁA�����l�͌R����`�I�ȊT�O�Ɨ��z�����悤�ɂȂ�܂����B�ނ�͌��݁A�L�\�ȎQ�d�Ǝw���������A�D�G�ȕ��m�ɂȂ��Ă� �܂��B����ɂ���āA�A�W�A�ɐV���ȋ���Ȑ��͂����ݏo����܂����B���̐��͂́A�Ǝ��̖ړI�̂��߂Ƀ\�A�Ɠ���������ł��܂����A�v�z�Ǝ�i�̖ʂł͒鍑 ��`�I�ȍD�퐫�����߂Ă���A���̎�̒鍑��`�ɂ����́A�̓y�g���Ɨ͂̑�������]���Ă��܂��B
�����l�̋C���ɂ́A�����Ȃ���̂ł���A�C�f�I���M�[�I�ȊT�O�͂قƂ�ǂ���܂���B�������������܂�ɂ��Ⴍ�A�푈�ɂ���Ď��{�̒~�ς����܂�� �����S�ɏ����������Ă��܂������߁A��O�͐�]���Ă���A�n���̋��R�𑽏��Ȃ�Ƃ��y�����Ă��ꂻ���Ȏw���҂ł���A�N�ɂł����ŏ]�����Ƃ��Ă��� ���B
���͍ŏ�����A�������Y�}�ɂ��k���N�x���͌���I�Ȃ��̂��ƍl���Ă��܂����B���̂Ƃ���A�ނ�̗��Q�̓\�A�ƋO����ɂ��Ă��܂��B�������A���N�� �������łȂ��A�C���h�V�i��`�x�b�g�ł��ߔN������A���܂��Ɍ������Ă���U�����́A���Â̐̂���A�����҂����Ƃ���҂���藧�ĂĂ����A�͂̊g�� �ւ̗~�]�̕\��ɂق��Ȃ�Ȃ��A�Ǝ��͎v���܂��B
���A���{�����́A�ߑ�j�ɋL�^���ꂽ���ł́A�ł��傫�ȉ��v��̌����Ă��܂����B�����Ȉӎu�ƔM�S�Ȋw�K�ӗ~�A�����ċ����ׂ�����͂ɂ���āA�� �{�l�́A���̏Ă��Ղ̒����痧���オ���āA�l�̎��R�Ɛl�Ԃ̑����̗D�ʐ��Ɍ��g����a������{�ɑł����Ă܂����B�����āA���̌�̉ߒ��ŁA���������A �o�ϊ����̎��R�A�Љ�`�̐��i�𐾂��A�^�ɍ������\���鐭�{������܂����B
������{�́A�����I�ɂ��A�o�ϓI�ɂ��A�����ĎЉ�I�ɂ��A�n����̑����̎��R�ȍ��X�ƌ�����ׂĂ��܂��B���E�̐M���𗠐�悤�Ȃ��Ƃ�2�x�ƂȂ� �ł��傤�B�ŋ߂̐푈�A�Љ�s���A�����ȂǂɎ�芪����Ȃ�����A����ɑΏ����A�O�i������݂��ق�̏������ɂ߂邱�ƂȂ��A���Y��`�������ŐH���~�߂� �ۂ̌����ȑԓx�́A���{���A�W�A�̐����ɔ��ɗL�v�ȉe�����y�ڂ����Ƃ����҂ł��邱�Ƃ𗧏��Ă��܂��B���͐�̌R��4�t�c�����ׂĒ��N�����̐��� ����܂������A���̌��ʁA���{�ɐ�����͂̋̉e���ɂ��āA���̂��߂炢������܂���ł����B���ʂ͂܂��ɁA�����m�M���Ă����ʂ�ł����B���{�قlj� �₩�Œ����������A�Εׂȍ���m��܂���B�܂��A�l�ނ̐i���ɑ��ď����A�ϋɓI�ɍv�����邱�Ƃ�����قǑ傫�����҂ł��鍑���ق��ɒm��܂���B
���Ă킪�����㌩���Ă����t�B���s���ɂ��ẮA���݂̍����������A�����ɂ킽��푈�̋��낵���j��́A��蒷���]�g�̒�����A�������S�ȍ����� �܂��ƁA�m�M�������Ċ��҂��邱�Ƃ��ł��܂��B��X�́A�h�����������������A�����Ĕނ�����]�����Ă͂����܂���B���������K�v�Ƃ��Ă���Ƃ��ɂ́A�� ��͎����������]�����Ȃ������̂ł�����B�L���X�g�����ł���t�B���s���́A�ɓ��ɂ�����L���X�g���̋���Ȗh�g��ƂȂ��Ă���A�A�W�A�ɂ����ē����I�� �������[�_�[�V�b�v�����閳���̗͂��߂Ă��܂��B
��p�Ɋւ��ẮA���ؖ������{�́A�����嗤�ɂ����铯�����{�̎w���͂�傫�����Ȃ������ӂ���S�V�b�v�̑唼�ɂ��āA�s���ɂ���Ĕ��_����@��� ���܂����B��p�̐l�X�́A���{�@�ւɑ����h����\���o���Ƃ��������Ō����Ȑ�����Ղ��Ă���A�����I�ɂ��A�o�ϓI�ɂ��A�Љ�I�ɂ��A���S�Ō��ݓI�ȘH���� �����Đi��ł���悤�ł��B
�ȏ�A���Ӓn��ɂ��ĒZ�����@����������ŁA���N�����ł̌R���Փ˂ɘb��]�������Ǝv���܂��B��ؖ������x�����ĉ������Ƃ��������哝�̂��� ���O�ɁA���͂Ȃ�瑊�k���Ă��܂���ł����B���̌���́A�킪�R���N���҂������߂��A���̌R���͂̑��������E�������Ƃɂ��A�R���I�Ȋϓ_���琳�� ���������Ƃ��ؖ�����܂����B�킪���̏����͌���I���������A�ړI�̒B���͖ڑO�������̂ł����A�������Y�������A���̏�ł͏��闤�R�͂ʼn�����Ă��� �̂ł��B
���̒�������ɂ���āA�V���Ȑ푈�ƁA�S���V���������o����܂����B����́A�k���N�̐N���҂ɑ��Ă킪�R���������ꂽ�Ƃ��ɂ͍l�������Ȃ������ł��B�����ČR���헪�������ɑ����ďC�����邽�߂ɊO��ʂŐV���Ȍ��肪���߂���ƂȂ�܂����B
������������́A���܂������ꂻ��������܂���B
�n�㕔���𒆍��嗤�ɑ��荞�ނ��Ƃɐ��C�Ŏ^������l�͂��Ȃ��ł��傤�B���ہA�����������Ƃ́A��x����������܂���ł����B����������ς��� ���A���Ă̌Â��G��|�����悤�ɁA���̐V���ȓG��ł��j�邱�Ƃ��킪���̐����ڕW�ł���Ȃ�A�헪�v��̍��{�I�ȕύX���ً}�ɔ����Ă����̂ł��B
���������Ƃ���A���]�̖k�ɂ���G�ɗ^����ꂽ�ی삳�ꂽ����͉����邱�Ƃ��R����K�v�������ق��A�푈��i�߂��ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ��K�v ���Ɗ����܂����B��1�́A�����ɑ���o�ϕ����̋����ł��B��2�͒������ݕ��ɑ���C�㕕���B��3�́A�������ݒn��Ɩ��B�ɑ���q���@�����̓P�p�B �����đ�4�́A��p�̒��ؖ����R�ɑ��鐧����P�p���A���ʂ̓G�ɑ��ē��R���L���ȍ�����邱�Ƃ��ł���悤�ȁA��⋖ʂł̎x�����s�����Ƃł����B
�����̂��ׂĂ̌����́A���N�����ɑ���ꂽ�킪�R���x�����A�č�����ѓ����������̖����̐l���Ȃ����ƂȂ��A�ł��邾�����������ɐ퓬�s�ׂ� �I��点�邱�Ƃ��Ӑ}���āA�E�ƌR�l�̗���ōl�������̂ł����B�R���I�Ȋϓ_����݂�ƁA�킪���̓����Q�d�{�����܂߁A���N�푈�Ɋւ�����قڂ��ׂĂ̌R ���w���҂��A�ߋ��ɂ���Ɠ��������������Ă����Ǝ��͗������Ă��܂��B�ɂ�������炸�A���������l������������ƂŁA���͎�ɊC�O�̑f�l����A�������� ������Ă��܂����B
���͑��������߂܂������A���R�͓����Ȃ����Ƃ�m�炳��܂����B���������]�̖k�ɓG�����݂�����n��j�邱�Ƃ��F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł� ��A��������p�ɂ����60���̗F�D�I�Ȓ����R�𗘗p���邱�Ƃ��F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�������������Y�}���O�����片�������Ȃ��悤�� ���邽�߂ɒ������݂����邱�Ƃ��F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�����āA��������K�͂ȑ����𑗂��Ă��炦�錩���݂��Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�R�� �I�ɂ݂āA������W�����͎̂i�ߕ��̑ԓx�ł���Ǝ��͖������܂����B
�r��邱�ƂȂ����s���𑱂���A�؍��ł��A�킪�R�̕⋋���������G�̕⋋�����ア���Ӓn��ł́A�G��}���邱�Ƃ��ł����ł��傤�B�������A�� ���G���S�R���͂�p�����ꍇ�A����������X�Ɋ��҂ł���̂́A�킪�R���Ђǂ����Ղ���������A����͂Ɍ������R����킾���������̂ł��B���̖��̉����� �s���ȐV���Ȑ������f���A���͐₦���v�����Ă��܂����B
���̗����c�Ȃ����邽�߂̓w�͂��s���܂����B�v����Ɏ��́A�D���`�҂ł���ƌ����Ă����̂ł��B����قǁA�������牓�����Ƃ́A�ق��ɂ��� �܂���B���́A���ܐ����Ă���N�����A�푈�ɂ��Ă͒m���Ă��܂��B���ɂƂ��ẮA����قnj������ׂ����̂́A�ق��ɂ���܂���B���͒��N�ɂ킽��A�� ���̊��S�Ȗo�ł�i���Ă��܂����B�G���������j�邪�䂦�ɁA�푈�͍��ە����̉�����i�Ƃ��Ă͖��p�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂�������ł��B���ہA1945�N 9��2���A���{����̓~�Y�[������ō~�������ɏ�����������A���͎��̂悤�Ɍ����Ɍx�����܂����B
�u�l�Ԃ́A�L�j�ȗ��A���a�����߂Ă����B���ƊԂ̕�����h���A���邢�͉������鍑�ێ葱�������o�����߁A���܂��܂ȕ��@��������Ď�����Ă� ���B�X�̎s���Ɋւ��ẮA������������\�ȕ��@�����������B�������A���L�����ۓI�ȍL���������i�̎d�g�݂́A��x�������������Ƃ��Ȃ������B �R�������A���͋ύt�A���ۘA���ȂǁA���ׂĂ������玟�ւƎ��s�ɏI���A�c���ꂽ�̂͐푈�Ƃ����������������o�铹�����������B���܂�푈�̓O��I�Ȕj�� �͂ɂ���āA���̑I������������Ă��܂����B�����Ō�̃`�����X���B�����ƗD�ꂽ�����Ȑ��x����X�����o���Ȃ���A�n���}�Q�h���͌����ɔ����Ă� �邾�낤�B���́A��{�I�ɐ_�w�I�Ȃ��̂ł���A�ߋ�2000�N�̉Ȋw�A�|�p�A���w�A�����ĕ����I�A�����I���W�́A��ނ̂Ȃ��O�i�Ɠ�������A���_�I�Đ� �Ɛl�Ԑ��̉��P�ɊW���Ă���B���̂��~�����Ƃ���Ȃ�A����͐��_��ʂ��Ăł���v
�������A��������푈����X�ɉ����t������A�����v���ɏI��点�邽�߂ɂ́A�g���邷�ׂĂ̎�i���g���ȊO�ɑI�����͂���܂���B
�푈�̖ړI�́A�܂��ɏ����ł���A���r���[�ȏ�Ԃ������邱�Ƃł͂���܂���B
�푈�ł́A�����ɑ�����̂͂���܂���B
���܂��܂ȗ��R���f���āA���Y�����ƗG�a���悤�Ƃ���l�����܂��B�ނ�́A���j�̖����ȋ��P�ɑ��ĖӖڂȂ̂ł��B�Ȃ��Ȃ�A�G�a����͐V���ȁA�� ��Ɍ��Ȃ܂������푈�������������Ƃ������Ƃ��A���j�͂͂�����Ƌ������ċ����Ă��邩��ł��B���̂悤�Ȍ��ʂ������炷��i�������������悤�ȗ�A�G �a�����������̕��a�ȏ�̐��ʂ������炵����́A���j��1������܂���B�����Ɠ��l�A�G�a����́A���傫���V���ȗv�������X�ɏ��������ƂȂ�A�� �I�I�ɂ́A�����Ɠ����悤�ɁA�\�͂��B��̎�肤��I�����ƂȂ��Ă��܂��܂��B
���́A���m�������畷����܂����B�u�Ȃ����̓G�ɁA�R���I�ȗL�����𖾂��n���Ă��܂��̂ł����v ���͓������܂���ł����B
�����������Ƃ̑S�ʐ푈�ɂ܂Ŋg�傷��̂�����邽�߂��A�ƌ����l�����邩������܂���B�܂��A�\�A�̉����h�����߂��A�Ƃ����l������ł��傤�B �ǂ���̐����������ȍ���������Ƃ͎v���܂���B�Ȃ��Ȃ�A���łɒ����́A�S���͂𓊓����Č�킵�Ă��邩��ł���A�\�A�͕K����������̍s������X�̓� ���ɍ��킹�Ă���悤�Ƃ��Ȃ�����ł��B�V���ȓG�������ł��傤�B�ނ�́A�R�u���̂悤�ɁA���E�I�ȋK�͂ł݂āA���������̌R�����̑��̗͂����ΓI�ɗL ���ł���Ɗ�����A�����ɍU�����d�|���Ă���ł��傤�B
���N�ł̔ߌ��́A���̍������̒��ɌR���s�������肳��Ă��邱�Ƃɂ���āA����ɍ��߂��Ă��܂��B��X���~���Ƃ��邱�̍����A�C�Ƌ�̑�K�͔����ɂ��j��ɋꂵ��ł���̂ɁA�G�̐���́A���������U����j�犮�S�Ɏ���Ă���̂ł��B
���E���̍��ŁA����܂ł̂Ƃ��낷�ׂĂ�q���ċ��Y��`�Ɛ���Ă����̂͊؍������ł��B�؍��l�̗E�C�ƕs���̐��_�͌����ł���A�M��ɐs�����܂���B
�ނ�́A�z��ɂȂ�������̊댯��`�����Ƃ�I�т܂����B�ނ�̎��ɑ���Ō�̌��t�́u�����m�����̂ĂȂ��łق����v�ł����B
���́A��n�Ő키�F�l�̑��q�����N�����Ɏc���Ă����Ƃ���ł��B�ނ�͂����ł����鎎���ɑς��Ă��܂����B�ނ�͂�����Ӗ��ɂ����ėD��Ă���ƁA���͍��A�Ȃ�̂��߂炢�������A�F�l�ɕ��邱�Ƃ��ł��܂��B
���͔ނ�����A���̎c���Ȑ퓬���A�ւ荂���A�ŏ����̎��ԂƐl���̋]���ŏI�点��悤�A��ɓw�͂��Ă��܂����B�����̑���́A���ɁA���̏�Ȃ��[����Y�ƕs���������炵�܂����B
���͂��̂悤�ȗE�܂������m�̂��Ƃ������Ύv���N�����A�����F����������邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
���͍��A52�N�ɂ킽��R�����I���悤�Ƃ��Ă��܂��B�����I�ɓ���O�Ɏ������R�ɓ��������Ƃ��A����͎��̏��N����̊�]�Ɩ������A�����u�Ԃł� ���B�����E�F�X�g�|�C���g(���R�m���w�Z)�ŕ��m�ɂȂ�鐾�����Ĉȗ��A���E�͉��x��������ς��A��]�▲�͂����ƑO�ɏ��������Ă��܂��܂����B�������A �������c�ōł��l�C�����������o���[�h�̈�߂����ł��o���Ă��܂��B����͌ւ荂���A�����̂��グ�Ă��܂��B�u�V���͎��Ȃ��B������������̂݁v�ƁB
�����Ă��̃o���[�h�̘V���̂悤�ɁA�������܁A���̌R������A��������܂��B�_�����ŏƂ炵�Ă��ꂽ�C�����ʂ������Ƃ���1�l�̘V���Ƃ��āB
���悤�Ȃ�B�@ |
�����{�ւ̎Ӎ߁E�_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�̍���
�@1951/5/3
�@�A�����J��@�R�������ψ���̌�����ɂā@
�����ٔ�����3�N��A�f�g�p�̍ō��i�ߊ��������_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�́A�č���@�R�������ψ���̌�����Łu�^���̏،��v�����Ă����B�������A���{�̃}�X�R�~�ŕ���邱�ƂȂ��A���ȏ��ɋL�ڂ���邱�Ƃ��Ȃ������B���ꂪ�䂪���̃}�X�R�~�ŕ��A���ȏ��Ɍf�ڂ���čL�������̒m��Ƃ���ƂȂ��Ă���A���ݖ����鎩�s�j�ς���E���A�܂��Ƃ��ȓƗ����ƂȂ��Ă������낤�Ɂc
���{�̊F����A��̑��̓A�����J�����������̂ł��B���{�͂Ȃɂ���������܂���B���q�푈�������̂ł��B�C�M���X�̃`���[�`���ɗ��܂�āA�h�C�c�Q��̌����Ƃ��āA���{��ΕĐ푈�ɒǂ����̂ł��B
�A�����J�͓��{��푈�ɗU�����ނ��߃C�W���ɃC�W���ʂ��܂����B�����čŌ�ʒ��Ƃ��ăn���m�[�g��˂����܂����B�����嗤����o�Ă������́A�Ζ���A�������Ȃ��ȂǁA�A�����J�ɂȂ�̌������������Ƃ����̂ł��傤�B�����A�A�W�A�̂قƂ�ǂ̍������l�̐A���n�ł����B���l�͗ǂ��āA���{�l�͋����Ȃ������̂ł��B�n���m�[�g�̂��Ƃ͎����A�����J�̍������m��܂���ł����B����Ȃ��̂�˂�����ꂽ��A�ǂ�ȏ����ȍ��ł��푈�ɗ����オ��ł��傤�B�@�푈�ɂȂ�Έ��|�I�ȕ��͂ŃA�����J�������Ƃ͐키�O���番�����Ă��܂����B��X�͐��A���{����x�Ɣ��l�x�z�̋��ЂƂȂ�Ȃ��悤�����Ȍv������Ă܂����B
�A�����J�͒m���Ă����̂ł��B������̉������Ԃ̕��@�́A���̍����玩�M�ƌւ��D���A���j��s�����邱�Ƃ��ƁB���A�����J�͂���𒉎��Ɏ��s���Ă����܂����B
�܂��A���{�̎w���҂͊Ԉ�����R����`���Ƃ��ăA�W�A��N�����Ă������ƉR�̐�`�H������܂����B���{���A�W�A�𔒐l�̐A���n�����������Ƃ����{���̗��R���B�����߁u�哌���푈�v�Ƃ������̂��֎~���A����Ɂu�����m�푈�v�Ƃ������̂��g�킹�܂����B
�����ٔ��͂��ŋ��������̂ł��B�A�����J����������@����{�ɉ����t���A�푈���ł��Ȃ����ɂ��܂����B���E�Ǖ������Ă܂Ƃ��ȓ��{�l��ǂ������A����ɔ����I�ȍ������q���w�Ȃǂ�v�E�ɂ�T���܂����B���̋����q���������A�}�X�R�~�E���E�ȂǂŔ������������Ă���̂ł��B
�O��I�Ɍ��{���s���A�A�����J�ɂƂ��ēs���̈������͓��{�����ɒm�点�Ȃ��悤�ɂ��܂����B���W�I�E�e���r���g���Đ�O�̓��{�͈������������B�푈�ɕ����ėǂ������̂��Ɠ��{�������x���܂����B
�����̐�����t���A���Ɏ���܂œƗ����Ƃ��Ď����ł��Ȃ���Ԃ������Ă���̂ł��B���͔��Ȃ��Ă��܂��B���s�j�ς����ׂ��͓��{�ł͂Ȃ��A�A�����J�Ȃ̂ł��B�푈�I���ɕs�K�v�Ȍ��q���e�����g���ĉ��\���l�Ƃ������Ԑl���s�E���܂����B�Ō�Ɏ��������Ă����Ƃ��̏،����L���āA�Ӎ߂̌��t�Ƃ������Ǝv���܂��B
�w���͓��{��������Ă��܂����B���{�̐푈�ړI�͐N���łȂ����q�̂��߂������̂ł��B �����m�ɂ����ĕč����ߋ��S�N�ԂɔƂ����ő�̉߂��́A���Y��`�𒆍��ɂ���ċ��傳�������Ƃł����B�����ٔ��͌�肾�����̂ł��B
���{�͔��疜�l�߂��c��Ȑl��������A���̔������_�Ɛl���ŁA���Ƃ̔������H�Ɛ��Y�ɏ]�����Ă��܂����B���ݓI�ɁA���{�̗i����J���͂͗ʓI�ɂ����I�ɂ��A��������܂Őڂ�������ɂ����ʗD�G�Ȃ��̂ł��B���j��̂ǂ̎��_�ɂ����Ă��A���{�̘J���͂͐l�Ԃ��ӂ��Ă���Ƃ����������A���Y���Ă��鎞�̕����K���Ȃ̂��Ƃ������ƁB�܂�A�J���̑����ƌĂ�ł悢�悤�Ȃ��̂����Ă����̂ł��B����܂ŋ���ȘJ���͂������Ă���Ƃ������Ƃ́A�ނ�ɂ͉����������߂̍ޗ����K�v���Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B�ނ�͍H������݂��A�J���͂�L���Ă��܂����B�������ނ�ɂ͎��������ׂ��ޗ��邱�Ƃ��o���܂���ł����B���{���Y�̓��A���́A�\�������ĂقƂ�ǂȂ������R�ł����B�Ȃ��Ȃ��A�r�т��Ȃ��A�Ζ��̎Y�o���Ȃ��A�����Ȃ��A�S�����Ȃ��A���ɂ��Ȃ����̂���ł����B���̑S�Ă��A�W�A�̊C��ɑ��݂����̂ł��B�@���������̌����̋�����f����ꂽ��A��疜�������S���̎��Ǝ҂����{�ɔ�������ł��낤���Ɣނ�͋��ꂽ�̂ł��B
�]���āA���{���푈�ɔ�э���ł��������@�́A�啔�������S�ۏ�̕K�v�ɔ����Ă̂��Ƃ������̂ł��B�x�@ |
���V���E�}�b�J�[�T�[�͂Ȃ��u���{�͎��q�̐푈�������v�Ə،������̂��c
�u�V���͎��Ȃ��B���������䂭�̂݁B�_�������Ƃ���ɏ]�����Ȃ̔C�����ʂ�����Ǝ��݂���l�̘V���Ƃ��āB���悤�Ȃ�v
1951�N4��19���B�ď㉺�@������c�ŁA�A�����R�ō��i�ߊ�(�r�b�`�o)�Ƃ��ē��{���̓����������R�����̃_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�͔����Ԃ̑ޔC�������������߂��������B
��ɑ�37��哝�̂ƂȂ鋤�a�}��@�c���̃��`���[�h�E�j�N�\���͉������A���̊����͎����u�w���҂Ƃ́v�ɂ����L�����B
�u�}�b�J�[�T�[�͌Ñ�_�b�̉p�Y�̂悤�������B�ނ̌��t�͗͋����c��S�̂����p�ɂ��т�A�����͉��x������Œ��f���ꂽ�B�����@�c���́w���a�}���͊����ł܂Ԃ���G�炵�A����}���͋��|�Ńp���c��G�炵���x�ƌ�����c�v
8���O��11���A�}�b�J�[�T�[�͑�33��đ哝�́A�n���[�E�g���[�}���ɑS�Ă̖�E����C����A�A�������B�l���̉��������������鉉�������A�S���͓����S�ł݂Ȃ����Ă����B
�}�b�J�[�T�[��52�N�̑哝�̑I�ɋ��a�}����o�n���A����}���Ƃ��čđI��_���ł��낤�g���[�}���������Ȃ��܂łɒ@���ׂ����Â��肾�����̂��B�����ł��u���̒��N�����������������炷�B�������̐���͒����I���̂Ȃ��푈���p�����邾�����v�ƃg���[�}����ᔻ�����B
�č����̃}�b�J�[�T�[�l�C�͐�傾�����B���@�u�o�^�[�����v���T���t�����V�X�R�ɓ��������ۂ�50���l�ȏオ�o�}���A���V���g���A�j���[���[�N�A�V�J�S�A�~���E�H�[�L�[�̊e�n�ōs��ꂽ�p���[�h�ɂ͑������S���l���W�܂����B�t�Ɂu�p�Y�v����C�����g���[�}���ɐ��_�͗��₩�ŁA�}�b�J�[�T�[�̑��̐l���͏��������Ɍ������B
��
�ď�@�R���E�O�������ψ���̓}�b�J�[�T�[����ɏ��������B�e�[�}�́u�ɓ��̌R����ƃ}�b�J�[�T�[�̉�C�v�B�w�i�ɂ̓g���[�}�������ɑŌ���^���悤�Ƃ������a�}�̍��d���������B
�}�b�J�[�T�[�͉��������B�哝�̑I�̎w�������ɗL�����ƍl�������炾�B�_���ʂ�A���E���̃��f�B�A��������̓����ɒ��ڂ��A���O�����X�I�ɕ��B
5��3���̒�������B�،���ɗ������}�b�J�[�T�[�͎���ɐ����ɉ����A1950�N6���ɖu���������N�푈�̌o�܂���ǂ݂Ȃ��������������B
����҂̋��a�}��@�c���A�o�[�N�E�q�b�P�����[�p�[�́u�ԉ��������C�Ƌ畕������Ƃ��������̒�Ă͕č��������m�œ��{��ɏ��������߂��ۂ̐헪�Ɠ����ł͂Ȃ����v�Ǝ������B
�}�b�J�[�T�[�̐헪�̐�������⋭����̂��_�����������A�}�b�J�[�T�[�̉͗\�z�O�������B
�u���{��4�̏��������X��8�疜�l�߂��l��������Ă������Ƃ𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�u���{�̘J���͂͐��ݓI�ɗʂƎ��̗��ʂōŗǂ��B�ނ�͍H������݂��A�J���͂����A�����������Ă��Ȃ������B�Ȃ��Ȃ��A�r�т��Ȃ��A�Ζ��̎Y�o���Ȃ��A�X�Y���Ȃ��A�S�����Ȃ��A���ɂ��Ȃ����̂��肾�����B���̑S�Ă��A�W�A�̊C��ɑ��݂��Ă����v
�u��������������f����ꂽ��1000���`1200���l�̎��Ǝ҂����{�Ŕ������邾�낤�B�����ނ�͋��ꂽ�B�]���ē��{��푈�ɋ�藧�Ă����@�́A�啔�������S�ۏ��̕K�v�ɔ����Ă̂��Ƃ������v
��ꂪ�ǂ�߂����B�،��ʂ�Ȃ�A���{�͐N���ł͂Ȃ��A���q�̂��߂ɐ푈�������ƂɂȂ�B����́u�N�����ƁE���{��ł������������`�̐푈�v�Ƃ�����̑��̑O������ꂩ�畢���ǂ��납�A�����ٔ�(�ɓ����یR���ٔ�)�܂Ő������������Ă��܂��B
�����ƌ����A5�N8�J���ɂ킽����{���̓������u���剻�v�Ɓu��R�����v�𐬂��������Ƃ����}�b�J�[�T�[�̋Ɛт܂ł��ے肵���˂Ȃ��B
���̔����͋��a�}�̊��҂𗠐�A�������{������B�}�b�J�[�T�[�l�C�͂��̌�}���ɂ��ڂ݁A�哝�̖̂��ׂ͒����B
��
�Ȃ��}�b�J�[�T�[�͂��̂悤�ȏ،��������̂��B
���{�́u���q�푈�v��F�߂����R�ɂ��ă}�b�J�[�T�[�͉�ژ^�ł��G��Ă��Ȃ��B�����A�}�b�J�[�T�[�����N�푈�łǂ̂悤�Ȑ헪��`��������R�����Ɠ����������Ă���B
�}�b�J�[�T�[�́A���N�푈��ʂ��Ėk���N�̔w��ɂ���\�A�A����(���ؐl�����a��)�Ƃ������Y��`���̋��Ђ�Ɋ������B
���N�Ƒ�p�����Y��`���̎�ɗ�����A���{���낤���A�ɓ��ł̕č��̐w�n�͎����A�h�q���͕Đ��C�݂܂Ō�ނ����˂Ȃ��B�����h���ɂ͒��N���������炷�邵���Ȃ��B���̌����͍����Ȃ⍑�h���Ȃɂ��������������B
�Ƃ��낪�A�g���[�}���́A�k�吼�m���@�\(�m�`�s�n)���������u���\�ƓO��I�ɑΗ�����A���B�̓\�A�̕U�������˂Ȃ��v�Ɠ��h�������Ƃ�����A�k��38�x���t�߂Łu�ɂݕ����v�ɂ���������Ă����B
����ɑ��āA�}�b�J�[�T�[�͒������C�Ƌ�ŕ������߁A�ё����鋤�Y�}������|���˂A�����̕č��̈��S���������Ǝ咣���ď���Ȃ������B���ꂪ�g���[�}�����}�b�J�[�T�[����C�������R�������B
��
�}�b�J�[�T�[�̎咣�́A���̌�̗��j�����ǂ��Ă������͂�����B�����A���N���������炵�A�嗤�̒��\�ƑΛ�����Ƃ����헪�́A���{���{���Ɨ�����邽�߂ɓ����푈�ȗ��Ƃ��Ă����헪�ƕς��Ȃ��B
�u�ߋ�100�N�ɕč��������m�n��ŔƂ����ő�̐����I�߂��͋��Y���͂𒆍��ő��傳�������Ƃ��B����100�N�ő㏞��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�v
�}�b�J�[�T�[�͂�����������B����́u�č��͐키������Ԉ�����B�^�̓G�͓��{�ł͂Ȃ��\�A�⒆�����Y�}�������v�ƌ����Ă���̂ɓ������B
�}�b�J�[�T�[�͓��{�̐�̓����ƒ��N�푈��ʂ��ē��{�̒n���w�I�ȏd�v���ɋC�Â����ɈႢ�Ȃ��B�u���q�푈�v�����́A����̐헪�̗D�ʐ���Y�قɌ�邤���Ƀ|�����Ɩ{�����o���Ƃ݂�ׂ����낤�B
��
���ɂ��}�b�J�[�T�[�͏d�v�ȏ،����c�����B
����}��@�c���A���b�Z���E�����O���u�A�����R���i�ߕ�(�f�g�p)�͎j��ނ����Ȃ��قǐ��������Ǝw�E����Ă���v�Ə̂����Ƃ���A�}�b�J�[�T�[�͐^��������ے肵���B
�u���������]�������͎���Ȃ��B�����������Ƃ��s�퍑���̂���Ƃ����l�������悢���ʂݏo�����Ƃ͂Ȃ��B��������O�����邾�����v
�u���I����́A�����I�Ӗ�������A��̍��̓���̐l���ɑ��鍦�݂��������ނׂ��ł͂Ȃ��v
����Ȃ�Γ��{�̐�̓����Ⓦ���ٔ��͈�̉��������̂��ƂȂ邪�A����ȏ�̒Njy�͂Ȃ������B
�ʂ̏�@�c������L���A����̌�����Q������Ɓu�n�m���Ă���B���͗��n��ňقȂ邪�A�s�E�͂ǂ���̒n��ł��c���ɂ܂���̂������v�Ɠ������B�����������w�������g���[�}����ᔻ�����������悤�����A�������u�s�E�v�ƕ\�������Ӌ`�͑傫���B
���̂悤��3���ԑ�����������ł̃}�b�J�[�T�[�،��͓��{�l����������A���锭���ň�]���Č������{��Ǝ��]���������B
�u�Ȋw�A�|�p�A�_�w�A�����ɂ����ăA���O���T�N�\����45���Ƃ���A�h�C�c�l�������x�ɐ��n���Ă����B���{�l�͂܂�������45�ɑ���12�̏��N�̂悤�ł���v
�����A���̔����̑O��Łu�w�т̒i�K�ɐV�����v�l�l�����������̂��_��B���{�l�͐V�����v�l�ɑ��Ĕ��ɒe�͐��ɕx�݁A��e�͂�����v�Ƃ��q�ׂĂ���B�u���{�l�̏_��v���悢�Ӗ��ŏ��N�ɗႦ���Ƃ����Ȃ����Ȃ��B
���{�l�͑��ŗE�҂ɐ킢�A�ČR��k�������Ȃ���A�s���͋����قǏ]���Ń}�b�J�[�T�[�̎������̎^�����B�}�b�J�[�T�[�ɂ͂��̎p���u12�̏��N�v�ɉf�����̂ł͂Ȃ����B
��
1952�N7���̋��a�}���ŁA���Ă̕����ʼn��B����̍ō��i�ߊ��߂��h���C�g�E�A�C�[���n���[���w������A1953�N�ɑ�34��哝�̂ɏA�C�����B
�}�b�J�[�T�[�͈��ނ��A�j���[���[�N�̃z�e���E�E�H���h�[�t�E�A�X�g���A�̃X�C�[�g���[���ň��ȃW�[���Ɨ]�����߂������B�R�l����Ɠ�������ɋ��Ԃ�������A���Q���������Ȃ��K�������������𑗂����B
�}�b�J�[�T�[�h����j�N�\���́A�f�g�p�����ǒ��������R�[�g�j�[�E�z�C�b�g�j�[��ʂ��ăz�e���̎����ɏ�����A���̌㉽�x�������𐿂����B�����A���_���������Ă����B
�u�}�b�J�[�T�[�̍ő�̉ߌ�͐����I��S�����R�Ǝ����A�R���I���]�𐭎��I���Y�ɓ]���悤�Ƃ������Ƃ������c�v
1964�N4��5���ߌ�2��39���A�}�b�J�[�T�[�̓��V���g���ߍx�̃E�H���^�[�E���[�h���R�a�@��84�N�̐��U������B�|�g�}�b�N��݂͍������J�������B
���A�g�c�͎Y�o�V���Ɂu�V�c����������l�v�Ƒ肵���Ǔ��������B���a�V�c���đ哝�̈��ɒ��d��ł����B���V��8���ɕċc��c�����ʼnc�܂�A�g�c���Q���B
�ʗ_�J��(����ق��ւ�)�̌������l���������B�}�b�J�[�T�[�̕]���͓��{�ł��Ȃ���܂�Ȃ��B�����A��@������ł̏،��͌R�l�}�b�J�[�T�[�̋U�炴��v���ł���A���̜���(����)�������̂�������Ȃ��B���̈�̂̓o�[�W�j�A�B�m�[�t�H�[�N�̃}�b�J�[�T�[�L�O�قɃW�[���ƂƂ��ɑ����Ă���B�@ |
���ޔC��
�}�b�J�[�T�[�͂��̌�A�S���V���̗��ɏo�������B�e�L�T�X�B�����11�B����������A������X�ŔM���I�Ȋ��}�����B�}�b�J�[�T�[�͊e�n�̉�����1952�N�̑哝�̑I���������āA��@������ł͗}���Ă����g���[�}���ւ̌l�U���⍂���A�M�ł̔ᔻ�ȂǁA��N�s�������I�������J��Ԃ������A�����o�ɂꎟ��ɒ��O�͌������Ă������B
1951�N9���ɃT���t�����V�X�R�œ��{���Ƃ̕��a��������ꂽ���A���̎���Ƀ}�b�J�[�T�[�͏�����Ȃ������B�g���[�}�������̓}�b�J�[�T�[�ɂƂ��Ƃ��W�ł���A�t�����N�����E���[�Y���F���g�̌��哝�̌ږ�o�[�i�[�h�E�o���[�N�Ȃǂ̓g���[�}�������Ƀ}�b�J�[�T�[�ɂ����T�ւ̏��ҏ�𑗂�悤�ɂƋ����i�����Ă������A�f�B�[���E�A�`�\�����������͂����f���Ă���B��ȑS���ł������g�c���A�}�b�J�[�T�[�Ɩʒk�����a���ɂ��Ă̊��ӂ�\�������ƍ����ȂɑŐf�������A�����Ȃ��́u�]�܂����Ȃ��v�Ƌ��ۂ����قǂ̓O��Ԃ�ł������B���̍��A�}�b�J�[�T�[�͑S���V���̗��̓r���ł��������A�T���t�����V�X�R�ɏ��҂���Ȃ��������Ƃɂ��ĕ������Ɓu�����炭�N�����Y�ꂽ�̂ł��낤�v�Ƒf���C�Ȃ������Ă���B
���̌�����ς�炸�}�b�J�[�T�[�̐����ᔻ�͑��������A�p�Y�}�b�J�[�T�[�̊M�����M���I�Ɋ��}���Ă����S�Ă̎s�����A1952�N�ɓ��鍠�ɂ͔M�C����ߎn�߂Ă���A�W���N�\���ōs��ꂽ�����͔��̋��ѐ��Ȃǂ�25������������f�����A�Ɓw�j���[���[�N�E�^�C���Y�x���ŕ�ꂽ�B�}�b�J�[�T�[�ɑ��鋤�a�}���̎x���͍L����Ȃ��������A�哝�̂̍��ɕ��X�Ȃ�ʎ����������A�������ł��������҃��o�[�g�E�^�t�g�ƑI�����̖͂�����s���ȂǍŌ�̔҉�����݁A7���̃V�J�S�ł��������a�}���̊�����̃`�����X��^����ꂽ���A���̉������`��ʼn������ȃ}�b�J�[�T�[�̂��̂Ƃ͎v���Ȃ��������̂ŁA�����ɏW���ł��Ȃ����O���r�����玄������킵�n�߁A�Ō�͉������������Ȃ��قǂ܂łɂȂ����B�}�b�J�[�T�[���s�k�����ƂЂǂ����_�������̂́A�����Ƀj���[���[�N�ɖ߂�A���Nj��a�}�̑哝�̌��ɂ͌������̃A�C�[���n���[���I�o���ꂽ�B
�哝�̌��ƂȂ����A�C�[���n���[�ƃ}�b�J�[�T�[�́A���a�}�����11����6�N�Ԃ�ɍĉ���B���Ă̏�i�̊�𗧂Ă�Ӗ��ł������̂��A�A�C�[���n���[����̉�k�̐\���o�ł��������A�}�b�J�[�T�[�̓A�C�[���n���[�Ɏ��炪�쐬����14�ӏ��̊o������n�����B���̓��e�́A���V�t�E�X�^�[�����Ǝ�]��k���J���A�u�����h�C�c�y�ѓ�k���N�̓���v�u�A�����J�ƃ\�A�̌��@�Ɍ�팠�ے�̏�����lj��v�Ȃǂ��Ă��A�X�^�[�������K���݂���悤�ł���Ζk���N�Ŋj������g�p����A�ȂǂƂ����A��_���Ƃ����ȊO�͉��̉��l���Ȃ���Ăł������B���̌�A�A�C�[���n���[�͑哝�̖{�I�ɂ��������đ�34��哝�̂ɏA�C�������A�A�C�[���n���[��z���C�g�n�E�X���y���^�S�����}�b�J�[�T�[�Ɉӌ������߂�悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B
1952�N�Ƀ}�b�J�[�T�[�̓��~���g�������h��(�^�C�v���C�^�[�y�уR���s���[�^���[�J�[)�̉�Ɍ}����ꂽ�B���̌�A���~���g�������h�̓X�y���[�Ђɔ������ꂽ���A�}�b�J�[�T�[�̓X�y���\�Ђ̎В��Ɍ}����ꂽ�B�X�y���\�Ђ̎�v�����̓y���^�S���ł���A�}�b�J�[�T�[���ق͓V����̈Ӗ������������A�N���10���h���ƍ��z�Ȃ������Ɩ��ɂ͉��̖������������ꂸ�A�T��3 -4���A4���Ԓ��x�o�Ђ����ۏ�ɂ��ď������邾���̎d���ł������B���̈��Ԃɗ]�T�����������A�S���Ƃ͖싅��{�N�V���O�Ȃǂ̃X�|�[�c�ϐ�Ɍ����Ă����B
1955�N�̃~�Y�[�����ł̍~�����T�Ɠ������ɁA���{����O���̏d�������}�b�J�[�T�[��K�˂��B�}�b�J�[�T�[�͊����I�ɓ��{��̎������z���A���a�V�c�Ƃ̏���k�̗l�q��b���A�ɓ����یR���ٔ��͎��s�ł������Ɖ����ł���B1960�N�ɂ͌M�ꓙ�����ˉԑ���͂������u�ŋ߂܂Ő푈��Ԃɂ������̑�ȍ����A���Ă̓G�i�ߊ��ɂ��̂悤�ȉh�_��^������́A���̒m�������j�㑼�ɗႪ�Ȃ��v�Ƒ傰���Ɋ��ł݂����B
�g���[�}���A�A�C�[���n���[�������̓}�b�J�[�T�[�ɑ���W�ȑԓx�ɏI�n�������A��35��哝�̃W�����EF�E�P�l�f�B���}�b�J�[�T�[�ɍD�ӂ�����Ă��炸�A�ނ��둸��ʼnߑ�]�����ꂽ���݂Ƃ̔F���ł������B�������A1961�N4���Ƀj���[���[�N�ʼn�k����ƃP�l�f�B�̃}�b�J�[�T�[�ɑ��錩�����傫���ς��A1961�N7���ɂ̓z���C�g�n�E�X�̒��H��ɏ��҂��Ă���B���̐ȂŃP�l�f�B�ƃ}�b�J�[�T�[�͈ӋC�������A���H���I�������A3���Ԃ��b������ł���B���ɓD�������������x�g�i����ł̈ӌ������̒��ŁA�}�b�J�[�T�[�̓��o�[�g�E�}�N�i�}�����h������P�l�f�B���߂��咣���Ă���h�~�m���_����������u�A�W�A�嗤�ɃA�����J�̒n��R�𓊓����悤�ƍl����҂͓��̌����ł����Ă���������������v�Ǝ��������N�����Ŏ��s�����ꂢ�o�������������������s�������A���̓I���˂������͌ڂ݂��邱�Ƃ͂Ȃ��A��͈����̈�r��H��A�P�l�f�B�̈ÎE��A��C�̃����h���EB�E�W�����\���哝�̂̎���ɃA�����J�̓x�g�i���푈�̓D���ɂ͂܂荞��ł������B �@ |
������
�}�b�J�[�T�[�L�O�ٓ��̃}�b�J�[�T�[�ƍȃW�[���̕�B�W�[���͋��N101�Ƃ��������ł������B
1962�N5���A�}�b�J�[�T�[�́A����̉X�����R���̍ŏ��̒n�ƂȂ�A���Ď������Z���߂��E�F�X�g�|�C���g���R�m���w�Z����A���Z�ōō��̏܂ƂȂ�V���o�k�X�Z�C���[��(�p���)���A�m���w�Z���k��O�ɐl���Ō�̉{���Ɖ������s�����B
�u���������̎v���o�͂����E�F�X�g�|�C���g�ɋA���Ă���A�����ɂ͂��́w�`���E���_�E�c���x�Ƃ������t���J��Ԃ������܂���B�����͎��ɂƂ��ď��N�Ƃ̍Ō�̓_�ĂƂȂ�B��������������H�̐���z���鎞�A���̈ӎ��ɍŌ�܂Ŏc���Ă���͎̂m���w�Z���k���N�̂��ƁA�����m���w�Z���k���N�̂��Ƃ��Ə��N��ɏ��m���Ă��炢�����B�ł͏��N�A����B�v
1964�N3��6���ɁA�V���ɂ��̑��E�t���̋@�\�s�S�Ń��V���g��D.C.�̃E�H���^�[���[�h���R�a�@�ɓ��@�����B3��29���̎�p�͒���2.4m������ȂǑ傪����Ȃ��̂ŁA�p�セ�̂܂܊�ĂƂȂ�A3��30���ɂ͐t�@�\���قƂ�ǒ�~����3�x�ڂ̎�p�����B4���ɓ����Ĉ�U�͈ӎ������߂������̂́A4��3���Ɉӎ��s���ƂȂ�A4��5���ߌ�2��39����84�Ŏ��������B
�����A��̂̓j���[���[�N�̃��j�o�[�T���t���l��������ֈڑ�����č��ʎ����s������A4��8���Ƀ��V���g��D.C.�ɖ߂���ĘA�M�c��c�����Ɉ��u���ꂽ�B�����ė�4��9���Ƀo�[�W�j�A�B�m�[�t�H�[�N�܂ʼn^��A4��11���ɐ��|�[������ő哝�̃����h���EB�E�W�����\���ق�����l���Q�č���������s��ꂽ�B���{����͑�\�Ƃ��ċg�c���o�Ȃ����B �@ |
 �@ �@
���}�b�J�[�T�[�̐�̓�����@ �@ |
�����a�V�c�Ƃ̉�k�̓��e�ɂ���
���a�V�c�ƃ}�b�J�[�T�[�̉�k�ɂ��ẮA�l�X�ȊW�҂�����e���`�����Ă���B�����҂ł��鏺�a�V�c�́u�j�̖v�Ƃ��ďI�����Ȃ��������A����̃}�b�J�[�T�[�͑����̊W�҂ɘb���A1964�N�Ɏ��M�����w��ژ^�x�ł���I���Ă���B����ɂ��Ə��a�V�c�́u���́A�������푈���s�ɂ������āA�����A�R�����ʂōs�������ׂĂ̌���ƍs���ɑ���S�ӔC�����̂Ƃ��āA�����g���A���Ȃ��̑�\���鏔���̍̌��Ɉς˂邽�߁A�������˂����v�Ɣ��������Ƃ���A��������}�b�J�[�T�[�́A�V�c������ɋA���ׂ��ł͂Ȃ��ӔC���������悤�Ƃ���E�C�Ɛ����ȑԓx�Ɂu���̐��܂Łv�������A�u���{�̍ŏ�̐a�m�v�ł���ƌh�������B�}�b�J�[�T�[�͌��ւ܂ŏo�Ȃ����肾�������A��k���I������Ƃ��ɂ͓V�c���Ԃ܂Ō�����A�Q�ĂĖ߂����Ƃ�����B
�������A�}�b�J�[�T�[�́w��ژ^�x�͑����́u�֒��v�u�v���Ⴂ�v�u�����ƑS���t�v������A���ȕٖ��Ǝ����Ǝ�����Ɉ��Ă���A�j���I�ȉ��l�͒Ⴂ���̂Ƃ̎w�E������A���̏��a�V�c�Ƃ̂����ɂ��Ă��A��i���҂ł��������a�V�c�Ƀ}�b�J�[�T�[���A�����J���̃^�o�R�����߁A���a�V�c���k������Ń^�o�R���z�����ƌ����Ă���Ȃǎ����Ƃ��ċ^�킵���L�q������B
�}�b�J�[�T�[�����k�̓��e�����W�҂͂��Ȃ�̐��ɏ�邪�A���̓��e���e�l�ɂ���Ă��Ȃ�قȂ��Ă���B
��Ԑg�߂ȊW�҂͍Ȃ̃W�[���E�}�b�J�[�T�[�ŁA�}�b�J�[�T�[�L�O�َ����ǂ�1984�N��41��ɂ��킽���ăW�[���ɏ��̃����O�C���^�r���[���s���Ă��邪�B�W�[���͂��̓��̗l�q���A���{�l�̎g�p�l���V�c�Ɗ�����킹�Ȃ��悤1�����ɕ����߂Ă����Ƃ����w�����}�b�J�[�T�[���炠�������Ƃ�A���a�V�c�͒��J�ŗ�V�������l���ƕ����Ă���A�ŏ��ɏo������l���ɐ[�������V������Ɨ\�z����邽�߁A�h�A���J���ēV�c���}����̂̓t�B���s���l�̃{�[�C�ł͂Ȃ��A�}�b�J�[�T�[�̕����̃{�i�[�E�t�F���[�Y�y���ƒʖ�̃t�H�[�r�A���E�o���[�Y�����ɂ��悤�Ƃ����ł����킹���������ƂȂǑN���ɋL�����Ă���A�،��̐M�����������Ǝv����B�W�[���Ƒ��ߌR�ネ�W���[�EO�E�G�O�o�[�O�͉�̏ꏊ�ƂȂ����T�����ɑ������ڊԂ̃J�[�e���̗�����A���̉���̂��������Ă������A�����������Ęb�͂قƂ�Ǖ������Ȃ������B�������I�n�a�₩�ȕ��͋C�ʼn�k�͐i�߂��Ă����̂��m�F���Ă���B�V�c���A������A�W�[���̓}�b�J�[�T�[����V�c�̔����̓��e�����ꂽ���A�w��ژ^�x�Ƃقړ������e�ł������Ƃ����B�܂��A�W�[���Ɖ�����ƍc�@����]���Ă����Ƃ̂��Ƃł��������A�W�[���ɂ��̋C�͂Ȃ��A���ǎ������Ȃ������B
�}�b�J�[�T�[�Ə��a�V�c���ꏏ�ɏo�}����(��k�ɂ͓��Ȃ��Ă��Ȃ�)�}�b�J�[�T�[�̐ꑮ�ʖ�Łu�̕�����~�����j�v�Ƃ��ėL���ȃt�H�[�r�A���E�o���[�Y�������A�}�b�J�[�T�[���畷�����b�Ƃ��āu�����Y�����ɂ���l�ɂ����A���̖���D���Ă��������B�ޓ��̐푈���̍s�ׂ͎��̖��ɂ����ĂȂ��ꂽ�B�ӔC�͎��ɂ���B�ނ���Ȃ��łق����B�����Ă��������B�v�Ə��a�V�c��������Ə،����Ă���B
�ɓ����یR���ٔ��̎�Ȍ����W���Z�t�E�L�[�i���͓c�����g�������Ɂu�}�b�J�[�T�[�����ɖʉ���ہA�����͂����������B�����͍�N9�����ɓ��{�̓V�c�ɖʉ���B�V�c�͂��̐푈�͎��̖��߂ōs�������̂ł��邩��A��Ǝ҂݂͂Ȏߕ����āA�������������Ă��炢�����ƌ������B�����V�c���ٔ��ɕt���A�ٔ��̖@��œV�c�͂��̂悤�Ɏ咣����ł��낤�B�����Ȃ�A���̍ٔ��͐������Ȃ��Ȃ邩��A���{�̓V�c�͍ٔ��ɏo�삳���Ă͂Ȃ�ʁB���͌����̌�������A���{�ɂ��Ă��炠������@�œV�c�̂��Ƃ��������A�V�c�͕��a��`�҂ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�c�c���Ƃ��ẮA�V�c�߂ɂ������B�M�N�����̂悤�ɓw�͂��Ăق����B�v�ƌ������Ƃ����B
1955�N8���ɓn�Ă��������̊O����b�d�����̓A�����J�Ń}�b�J�[�T�[�Ɖ�k�������A���̐Ȃł̃}�b�J�[�T�[�̔����Ƃ��āA�u�É��͂܂��푈�Ӎ݂̊J������玝���o����A���̂悤�ɂ������Ⴂ�܂����B����ɂ͎��ɂт����肳�����܂����B���Ȃ킿�u���͓��{�̐푈���s�ɔ��������Ȃ邱�Ƃɂ��A�܂������ɂ��S�ӔC���Ƃ�܂��B�܂����͓��{�̖��ɂ����ĂȂ��ꂽ���ׂĂ̌R���w�����A�R�l����ѐ����Ƃ̍s�ׂɑ��Ă����ڂɐӔC���܂��B�������g�̉^���ɂ��āA�M���̔��f���@���l�̂��̂ł��낤�Ƃ��A����͎����ɂƂ��Ė��łȂ��B�\�킸�ɑ��Ă̎���i�߂Ă������������B�v���ꂪ�É��̂����t�ł����B���͂�����ċ����̗]��A�É��ɃL�X���悤�Ƃ����ʂł��B�������̍߂������̂����Ƃ��o����ΐi��ŏ،���ɏ�邱�Ƃ�\���o��Ƃ����A���̓��{�̌���ɑ����̌R�̎i�ߊ��Ƃ��Ă̎��̑��h�̔O�́A���̌�܂��܂����܂����ł����B�v�Ƃ����b���������ƌ���Ă���B
�ȏ�A���e�͏،����ƂɈقȂ邪�g���a�V�c���S�ӔC���h�Ƃ�����{�I�ȕ����̓}�b�J�[�T�[�́w��ژ^�x�ɉ������،��������B���������ɂ́A�}�b�J�[�T�[�̐����ږ�W���[�W�E�A�`�\�����}�b�J�[�T�[���畷�����b�Ƃ��āu�T�m���}�b�J�[�T�[��K�₵���Ƃ��A�V�c�̓}�b�J�[�T�[���҂��Ă�����g�@�̉��ڎ��ɓ���ƍŌh�炵���B������������������ƁA�V�c�́w���͍��O�����{�����{�̐��z�������O�ɐ^��p���U���������͂Ȃ��������A�������������܂����̂��B���������͐Ӎ݂�Ƃ�邽�߂ɂ���Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���͓��{�����̎w���҂ł���A�����̍s���ɐӍ݂�����x�ƌ������B�v�Ɠ����p�@�ɂ��ӔC������Ƃ����锭���������Ƃ̏،�������B���̏،��́A�w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x�����a�V�c�E�}�b�J�[�T�[��k��2���O�ɁA�P�ƃC���^�r���[��V�c�ɍs���A���̍ۂɋL�҂��u���ُ̏����^��p�̍U�����J�n���邽�߂ɓ����叫���g�p�����@���g�p�����Ƃ����̂́A�É��̂��ӎv�ł���܂������H�v�Ǝ��₵���̂ɑ��A�V�c���u���ُ̏��𓌞��叫���g�p�����@����(��P�U���̂���)�g�p����ӎv�͂Ȃ������v�Ɠ��������߁A�V������Ɂu�q���q�g�A�^��p��P�̐ӔC���g�[�W���[�ɂ�������v�Ƃ����匩�o������邱�ƂƂȂ��������ƕ������Ă���A���̍ۂ̏��a�V�c�̔����������āA�V�c�̓}�b�J�[�T�[�Ƃ̉�ł������ɐӔC�������t����悤�Ȕ����������Ǝ咣���錤���҂�����B
����œ��{���́A���a�V�c�̑��ɒʖ�Ƃ��ĊO���Ȃ̉������������Ȃ����B���̉�������k�̓��e����k��ɂ܂Ƃ߁A�O���ȂƋ{�������ۊǂ��Ă����w���^�x��2002�N�ɏ����J���ꂽ���A���̒��ɂ̓}�b�J�[�T�[�́w��ژ^�x�ɂ���悤�ȏ��a�V�c�̑S�ӔC�����͂Ȃ��A�푈�ӔC�Ɋւ��锭���Ƃ��Ắu���m�푈�j�t�e�n�A�����g�V�e�n�ɗ͔V�����P�x�C�l�f�A���}�V�^�K�푈�g�i���m���ʃ����}�V�^�R�g�n�����m�Ń��⊶�g�X�����f�A���}�X�B�v�u�������{�������s��m�������\���F���V�e�����R�g�n�\�X�����A���}�Z���B����n���a�m��b�m���V���{�����݃X���ׁA���g�V�e���o���������A�̓��s�V�^�C�g�v�q�}�X�B�v�Ƃ��Ȃ�g�[���_�E�����Ă���B����́A��ƁE��������1975�N�Ɏ�ސ����\�ł����ϔ������X�N�[�v�Ƃقړ������e�ł��������A�����̌���p���œV�c�̒ʖ�߂��O���Ȃ̏��䖾���A�V�c�ƃ}�b�J�[�T�[�A���b�W�E�F�C�Ƃ̉�̏ڍׂ��L�q�����w���䕶���x�ɂ��A���䂪�u�V�c����̐ӔC����Ƃ��������ɂ��ẮA���̏d�傳���ڗ��������̔��f�ŋL�^����폜�����B�v�Ɖ������璼�ڕ������ƋL�q���Ă���B
�܂��A���̉�ɓ��s����(��̏�ɓ��Ȃ͂��Ă��Ȃ�)���]���E���c�����̒����w���]���̉�z�x�ɂ��A�u�O���Ȃł܂Ƃ߂���̖͗l�v�����5���ɂ܂Ƃ߂��Ă������A���̂܂Ƃ߂ɂ��Ə��a�V�c�̔����́u�s��Ɏ������푈�́A�F�X�ȐӔC���Njy����Ă��邪�A�ӔC�͑S�Ď��ɂ���B�����S���́A���̔C������Ƃ��낾����A�ނ�ɐӔC�͂Ȃ��B���̈�g�͂ǂ��Ȃ낤�ƍ\��Ȃ��B���͋M���ɂ��ς�����B���̏�́A�ǂ��������������ɍ���ʂ悤�A�A�����̉��������肢�������B�v�ł������Ƃ����B���̕�Ⳃ͏��a�V�c�̌䗗�ɋ��������A���̂܂ܓ��c�̎茳�ɂ͕Ԃ��Ă��Ȃ������Ƃ̂��Ƃł������B�������A���̋L�q�͊O���Ȍ��J�́u���^�v�̓��e�Ƃ͈�v���Ȃ����߁A�Ⴄ���������p�����\�����w�E����Ă���B
������ɂ��Ă��A���a�V�c�Ƃ̑�1���k�̌�ɁA�}�b�J�[�T�[�̓V�c�ւ̌h���̏�͐[�܂����悤�ŁA�ʖ�̉��������ɂ��Α�1���k�̍ۂɂ͓V�c���uYou�v�ƌĂсA�����ɒʖ�����߂鎞���uTell The Emperor(�V�c�ɍ�����)�v�ƍ����I���������A���̌�͓V�c���ĂԂƂ��́uYour Majesty(�É�)�v�Ƒ��������߂ČĂԂ悤�ɂȂ����Ə،����Ă���B
�����ă}�b�J�[�T�[�́A1946�N1��25���ɗ��R�Ȉ��ĂɓV�c�Ɋւ��钷���̋ɔ�d����ł������A���̓��e�́u�V�c���ƂƂ��č�������A���{�����̊Ԃɑz�������Ȃ��قǂ̓��h�������N�������ł��낤�B���̌��ʂ����炳��鍬������߂�͕̂s�\�ł���B�v�u�V�c�𑒂�Γ��{���Ƃ͕�������B�v�u���{�̏��@�\�͕��A���������͒�~���A���ז������͂���Ɉ������A�R�x�n�т�n���ŃQ�����킪��������B�v�u���̍l����Ƃ���A�ߑ�I�Ȗ����`������Ƃ�������]�͂��Ƃ��Ƃ���������A�����ꂽ�����̒����狤�Y��`�H���ɉ��������łȐ��{�����܂��ł��낤�B�v�u�����̎��Ԃ��u�������ꍇ�A100���l�̌R�������i�v�I�ɒ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƃ��V���g�����������e�ŁA�A�����J���{���ł̓V�c�̐�Ɩ��́A���̓d���ɂ��s��Ƃ̕��j�ő���̍��ӂ��`�����ꂽ�B�~��ꂽ�̂͏��a�V�c����łȂ��A�V�c�Ȃ��ł͕��������Ȑ�̓����͕s�\�������}�b�J�[�T�[���~��ꂽ���ƂɂȂ�A���̉�k�̈Ӌ`�͋ɂ߂đ傫�������Ƃ�����B �@ |
���}�����l�C
��̓����A�}�b�J�[�T�[�͑����̓��{�������u�}�����v�ƕ���A���Ȑl�C�Ă����BGHQ���i�ߕ��{�����u���ꂽ��ꐶ���ق̑O�́A�}�b�J�[�T�[������ׂɏW�܂��������̌Q�O�œ�����Ă����B�s��ɂ�肻��܂ł̉��l�ς�S�Ĕے肳�ꂽ���{�l�ɂƂ��āA�}�b�J�[�T�[�͐����҂ł͂Ȃ��A�V�������͂Ȏw���҂Ɍ������̂����̐l�C�̗v���ł���Ƃ̎w�E��A�u�킢���������G���G�������Ęa�������́A�s�҂ɑ��Ď��������v�Ƃ����A�����J�R�̓`���Ɋ�Â����̐H�Ǝx���ȂǂŁA���{�����̕ی�҂Ƃ��Ă̈�ʂ����{�l�̐S���Ƃ炦���A�Ƃ����w�E�����邪�A���R�����I�Ȑl�C�ł͂Ȃ��A�����̐l�C��_�o���ɋC�ɂ���}�b�J�[�T�[�ׂ̈ɁAGHQ�̖��ԏ��� (CIE) ���d�������Ƃ����w�E������B
�}�b�J�[�T�[��GHQ�͐펞���̓��{�R�ߗ��̐q��ȂǂŁA���{�l�̈����𗝉����Ă���A���R�̑g�D�Ƃ��ē��{�̃}�X�R�~�����Ǘ��E�ē��Ă���CIE�ƁA���{�����ɂ͔铽���ꂽ�g�D�ł��������Ԍ��{�x��(CCD)���I�݂ɗ��p���A�d��݂ɓ��{�l�̎v�z�����E�s��������s�������A�����Ƃ��d�v�����ꂽ�̂��}�b�J�[�T�[�Ɋւ�����ł������B CIE�����ɐ_�o���Ƃ��点�Ă����̂́A�}�b�J�[�T�[�̓��{�����ɑ���C���[�W�헪�ł���A�}�b�J�[�T�[�̑��݂�����P�����̂Ƃ��ē��{�l�ɐA���t���悤�ƕ��S���Ă����B�Ⴆ�}�b�J�[�T�[�͘V��ł�����O���̔��������Ȃ�C�ɂ��Ă������߁A�X�q�����Ԃ��Ă��Ȃ��ʐ^�́u�Ќ��������v�Ƃ��ĐV���ւ̌f�ڂ������Ȃ������B�܂��A�g����180cm�ƃA�����J�l�Ƃ��Ă͌����đ啿�ł͂Ȃ��������߁A�ʐ^���B�鎞�͉����炠�����ĎB�e����H�v�����炵�Ă����B ���{�l�ɂ��GHQ�����ւ̑����͓��풃�ю��ł��������A�}�b�J�[�T�[�ɑ��鑡���ɂ��Ắ̕u�C���[�W�˂�v�Ƃ��Č��{�̑ΏۂɂȂ邱�Ƃ��������B�Ⴆ�A�u��ʌ��ݏZ�̉�Ƃ��A�����I�o�̎R����c�m�ƈꏏ��GHQ��K��A�}�b�J�[�T�[�Ɏ����̍�i�������v�Ƃ����L���͌��{�Ō��\�֎~�Ƃ���Ă���B
�}�b�J�[�T�[�ւ̔��E�U���̋L���͂��@�x�ŁA�����ʐM�Ђ��u�}�b�J�[�T�[������_�̔@�����ߗ��Ă�͓̂��{�̖����`�̂��߂ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����А����ڂ��悤�Ƃ����Ƃ���A�������{��ʉ߂������̂́A�Q�d��2�� (G2) �����̃`���[���Y�E�E�B���r�[�̖ڂɎ~�܂�A����50,000��������ݎԂɐς܂�Ă����������ċp����悤�ɖ����Ă���B
����Ŏ^���̕͏��コ��Ă����B������A��ꐶ���ّO�œ��{�̏������}�b�J�[�T�[�̑O�ŕ��������ۂɁA�}�b�J�[�T�[�͂��̏����Ɏ�������L�ׂė����オ�点�āA�`�����Ă������Ɂu�����������Ƃ͂��Ȃ��悤�Ɂv�Ə����Ɍ����ĕ������A���������������Ƃ������o������A��������ꐶ���قŁA�}�b�J�[�T�[���G���x�[�^�[�ɏ�����ۂɁA��ɏ���Ă������{�l�̑�H���������āA�����V�����Ȃ���G���x�[�^�[���~��悤�Ƃ����̂��}�b�J�[�T�[���~�߁A���̂܂܈ꏏ�ɏ�邱�Ƃ����������Ƃ����������A��ɂ��̑�H����u���ꂩ���T�ԂƂ������́A���Ȃ��l�̗�߈��邲���ӂɂ��ē������炵�Ă���܂����B���{�̌R�l�ł����猈���ē������Ƃ͂��Ȃ������Ǝv���܂��B�v�Ƃ������ӂ̎莆��������Ƃ����ׂȏo�������A�}�b�J�[�T�[�哱�ő�X�I�ɕ���邱�Ƃ��������B���ɑ�H�̊��ӏ�̕ɂ��ẮA�����̓��{�Ń}�b�J�[�T�[�̖ژ_���ʂ�A�L���m��n���邱�ƂƂȂ�A�ŋ������ꂽ��A�Ƃ����Ƃ��w�G���x�[�^�[�ł̑Ζʁx�Ƃ����G���`���A���̕��������{�̉ƒ�ŏ���ꂽ�肵���B
�������^����F�ł̓A�����J�{������h�����甽�����A�䂭�䂭�͓��{�l����̐l�C���������˂Ȃ��ƔF�����Ă����}�b�J�[�T�[�́A�ߓx�̎^���ɂ��Ă��K�����s���Ă���B���{�̌���̋L�҂�́A���̔����ȃo�����X���ɔY�܂���鎖�ƂȂ����B���̂����ɓ��{�̃}�X�R�~�́A��ꕨ�ɐG�炸�Ƃ����p�����炩����K���ɂ��A�}�b�J�[�T�[�Ɋւ����GHQ�̌������\���C�O�̍D�ӓI�ȋL���̖|��Ɍ��������߁A�}�b�J�[�T�[�̃C���[�W�헪�Ɏ��݂��`�ƂȂ�A���{�����̃}�b�J�[�T�[�M��傢�ɐ���錋�ʂ��������B
GHQ�̓}�b�J�[�T�[�̈ӌ��ɂ��A�}�b�J�[�T�[�̐_�b�̍\�z�ɗl�X�ȍ��M���Ă���A���̌��ʂƂ��đ����̓��{�����ɁA�}�b�J�[�T�[�͓V�c�ȏ�̃J���X�}�����������u�ɂ��ڂ̑�N�v�ƈ�ەt����ꂽ�B���̈�ۍ\�z�̎菕���ƂȂ����̂́A���a�V�c�ƃ}�b�J�[�T�[����k���ɎB�e���ꂽ�A�����Œ����s���̏��a�V�c�ɑ��A�J�݂̌R���ō��Ɏ�ėI�R�Ƃ��Ă���}�b�J�[�T�[�̎ʐ^�ł������B �@ |
���}�b�J�[�T�[�ւ�50���ʂ̎莆
�}�b�J�[�T�[�̂Ƃ���ɑ����Ă�����{�̒c�́E�l�����ꂽ�莆�͑S�ĉp��āA�d�v�Ȃ��̂̓}�b�J�[�T�[�̖ڂɒʂ���A���̈ꕔ���ۑ�����Ă����B ���̎莆�̈ꕔ�̓��e������ѓ�Y�̒����ɂ�薾�炩�ɂ��ꂽ�B�������莆�̑����ɂ��ẮA�A���R�|��ʐM�� (ATIS)�̎���(�_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�L�O�ُ���)��1946�N5�� -1950�N12���܂łɎ�����莆��411,816�ʂƂ̋L�ڂ�����A����͏I�킩��1946�N4���܂łɎ�����莆��10���ʂƐ��肵�č��v50���ʂƂ��Ă��邪�ACIE�̏W�v�ɂ��A�I�킩��1946�N5�����܂łɊ�ꂽ�莆��4,600�ʂɉ߂����A���v���Ă�50���ʂɂ͋y�Ȃ��B�܂��莆�̈���ɂ��Ă��A�}�b�J�[�T�[�l�������ł͂Ȃ��AGHQ�̊e���ǂ�����Ƃ�����E����E�����E�����̑��ɁA�n���R�����i�����n���R����������Ƃ����莆���������ɏ���Ă���B
�}�b�J�[�T�[��GHQ���ǂւ̓��{�l�̓����̂��������́A1945�N8���̏I�풼��ɓ��v王{���F��������b�������Ɍ����āu���͍������N���璼�ڎ莆��Ղ������A���������ƁA�߂������ƁA�s���ł��s���ł����ł��X�����B�����ł����\�������̖��ł��悢�E�E�E��ʂ̍����̊F�l��������ڈӌ����Đ���������Ă�����̎Q�l�Ƃ������v�ƐV���L�����g���ē������Ăъ|�������Ƃɂ������B���̌Ăъ|���ɂ��A���v王{���t�ւ̓����ƕ��s���āA�}�b�J�[�T�[��GHQ�ɂ����{�l����̎莆���͂��悤�ɂȂ����B�������A�����̓}�b�J�[�T�[��GHQ�ɓ͂��莆�̐��͏��Ȃ��A1945�N���܂ł�800�ʑ��炸�ɉ߂��Ȃ������B�������A11�����ɂ͓��v王{���t�ɑ��铊�����������A�s�[�N���ň��1,371�ʂ��̑�ʂ̎莆���͂��悤�ɂȂ�ƁA�}�b�J�[�T�[��GHQ�ւ̎莆�������n�߁A���v王{���t�����X�ɓ|���ƁA���{���{�ɎE�����Ă����莆���}�b�J�[�T�[��GHQ�ɑ�����悤�ɂȂ����B�}�b�J�[�T�[��GHQ�Ɏ莆����ʂɓ͂��悤�ȗ����������͓̂��v王{���F���ł��邪�A���{�����̓}�b�J�[�T�[��GHQ�̈ӌ��ő��X�Ɠ|�����{�̓��t�����A���{�̎����I�Ȏx�z�҂ł������}�b�J�[�T�[��GHQ�𗊂�Ƃ��邱�ƂƂȂ����̂ł���B
�}�b�J�[�T�[��GHQ�ւ̓����̓��e�͑���ɓn�邪�A�������������Ȃ�����1945�N10���̓����̓��e�ɂ��āA������UP�d���Ă���B�ɂ��u�}�����ւ̓����A�푈�ƍߐl�����A�z�����x�������A1�����]���300�ʁv���̓��u���{��ŏ����ꂽ���̂�100�ʁv�ł���A�u���R����`28�ʁv�u�A���R�̐�̕��тɃ}�����ւ̎^��25�ʁv����u�ߎ��Ƌ֎��̔M�]2�ʁv�܂ŁA���e�͂����܂���21�ʂ�ɕ���Ă����B���ł�GHQ�������Ƃ��S�����������V�c�Ɋւ��铊���ł���A�w�q���q�g�V�c�Ɋւ�����{�l�̓����x�Ƃ�����������t����A�ɓ����یR���ٔ��̍��ی��@��(IPS)�̏d�v�����Ƃ��ĊǗ��E�ۊǂ���Ă���A1975�N�܂Ŕ閧���������ł������B���a�V�c���l�Ԑ錾���s�����ȍ~�́A���{�����̊ԂœV�c���ɑ���S�����܂�A1945�N11������1946�N1���܂ł�GHQ�ւ̓���1,488�ʂ̓��ŁA�����Ƃ�����22.6%�ɂ�����337�ʂ��V�c���Ɋւ�����̂ł������B�����͂���CIE���A�V�c�������Ɣp�~�E�ے�̈ӌ��͂قړ���Ă����A�Ƃ������Ƃł��������ACIE�́u���̗l�Ș_���̌��������ɂ��ẮA�̐���ϊv���悤�Ƃ��Ă����(�V�c���p�~�咣�h)���̐���������(�����h)��萷��Ɏ咣����X��������v�Ɨ�Âɕ��͂��Ă���A1946�N2���ɓV�c���̐���ɂ��Đ��_�����������Ƃ���A�x��91% ����9%�Ő��_�͈��|�I�ɓV�c�����������������B�莆�������h�̕��������ŔM��Ȃ��̂������A���ɂ́u�A�����J�Ƃ������̏���C�Ԃ��Ɏ��������Ċ����Ă������A�����䖝���ł��Ȃ��v��u�É��ɂ����w��{�ł������Ă݂邪�����A���͂ǂ�Ȋ댯���������Ă��}�b�J�[�T�[���h���Ă��v�Ƃ����ߌ��Ȃ��̂��������B
�V�c�������{�����@���z�ɂ���i������ƁA�����Ƃ������莆�͒Q��ƂȂ�A�����̎��㑊������킵����X�̒Q�肪�Ȃ��ꂽ�B���̓��e�́u�p����w�т������ɏA�E���������Ăق����v�u�����̂��߂��Ƃ��������Ăق����v�u�A���S���E�T�M�̎���Ɏx�����v�u�����̈ʂ̈ێ�����̂��ߓ��{�����Ɏ����[���̐ێ揧����v�ȂǂƓ��e�͐�������Ȃ��قǑ���ɓn�������A1946�N�㔼���畜�����{�i������ƁA���̊֘A�̗v�]�E�Q�肪���������B1947�N�ȍ~�͕����֘A�̗v�]�E�Q��̎莆���S�̂�90%�ɂ��B���Ă���B���Ƀ\�A�ɂ��V�x���A�}���ɂ��ẮA���̍��������g�����i�ׂ̈ɑS���ɂ������̒c�̂��g�D����AGHQ�ɂ������g�����i�̒Q��̓�������ʂɂȂ����悤�ɂȂ��Ă���B�܂��A�O�n�Ői�s���Ă���BC����ƍٔ��̔퍐���Y�҂̉Ƒ��ɂ�鏕���E�Y�̌y���Q���A�����̒����v���Ȃǂ̓������������Ă���B
�]���āA�ꕔ�Ŏ�����F������悤�ɁAGHQ�Ɉ���ɉ��S�ʂƓ͂��莆�̓}�b�J�[�T�[�l�ւ̃t�@�����^�[�����ł͂Ȃ��A��̌R�̑g�D�S�̂ɑ���ꂽ���{�l�̐؎��Ȓ�E����E�����E���������|�I���������A���V�A�X�ED�E�N���C(�p���)�������������h�C�c�ł͌���I�ɂ��������Ȃ��������ۂł���A�}�b�J�[�T�[�̋���Ȍ��ɂ��A���{�l�ɁA�}�b�J�[�T�[�Ȃ�ǂ�ȒQ��ł���������Ă���邾�낤�Ǝv�킹�鎥�݂͂����Ȃ��̂��������Ƃ����w�E������B�}�b�J�[�T�[�l���Ăɑ����Ă����莆�ɂ́A�u�}�b�J�[�T�[�����̓��������肽���v�u���Ȃ��̎q�������݂���(�A�������͑��݂���)�v�u���E���̎�l�ł��点���܂��}�b�J�[�T�[�����l�v�u�ᓙ�̈̑�Ȃ����҃}�b�J�[�T�[�����t���v�Ɠ����̃}�b�J�[�T�[�ւ̔M��Ȑl�C������M�����������킹����̂�����A���̑����̌��͎҂Ɠ��l�ɁA�����ւ̎^���E�^���D�}�b�J�[�T�[�́A���̂悤�Ȏ莆�𒆐S�ɁA�C�ɓ������������Ă̎莆3,500�ʂ��t�@�C�����I������Ƃɒu���Ă���A����̓}�b�J�[�T�[�L�O�قŕۑ�����Ă��邪�A�O�q�̒ʂ�A���̗l�Ȏ莆�͑S�̂Ƃ��Ă͏����ł������B�}�b�J�[�T�[�͑����Ă����莆�������ǂނ̂ł͂Ȃ��A���e�͂��A���_�▯�剻�̐i�s�x�𑪂��i�̈�Ƃ��ďd�v������̐����i�߂Ă��������ł��܂����p���Ă���B �@ |
���}�b�J�[�T�[�l�C�̏I��
���{�̒�����S����CCD��1949�N10���ɔp�~����A�}�b�J�[�T�[���X�R����ċA�����鍠�͊���GHQ�̌��{�͗L�����������Ă���A�}�b�J�[�T�[�ɑ��Ă���Âȕ��s���@�ւ��o�Ă����B���Ƃ��w�k�C���V���x�Ȃǂ́A�}�b�J�[�T�[�����̐�����Ɂu�_�i���͂�߂悤�v�Ƃ����R�������f�ڂ��u�@���̎��R������ȏ�A�����Ȃ�_�̎��q�ɂȂ�̂����肾���A���{�̖��剻�ɂƂ��đ厖�Ȏ��͍�����l��l���������g�̐S�̒��Ɏ����́w�_�x����Ă邱�Ƃł��낤�B�v�Ə@�����ɂ��āA�ÂɃ}�b�J�[�T�[�̖Ӗڐ��q�ւ̔ᔻ���s���Ă����B�������A�ˑR�Ƃ��đ����̃}�X�R�~������K���ɂ��}�b�J�[�T�[�ւ̕\�������ᔻ�͔����Ă���A�����}�b�J�[�T�[�������ɂ́u�̐搶�ɑւ�ꂽ���w���̂悤�ɁA�}�����ɖ��c��ɂ��ނ��Ƃł������B��������J�l�̃_���X��g�͋A���̓��u�����͓��{�̓}�����̎v���ł����ς����낤���玄�͉�������ʁv�Ǝ@���̂悢���Ƃ��������v��u�����}�b�J�[�T�[�����A���{�������ƋQ�삩�炷�����グ�Ă��ꂽ�����A�����I ���̑�����A�������������ɂ��悢�ł���̂������ɂȂ�܂������B���N���݂̂�͖L���ł��傤�B����݂͂Ȍ����̌ܔN�������̂ɂ킽��w�͂̎��ł���A�����ɓ��{�����̊��ӂ̂��邵�ł�����̂ł��B�����I�ǂ����A�����炾�����厖�Ɂv�Ȃǂƕʂ��傰���ɐɂ��ޕ������Ȃ��@�ւ����������B
�A�������}�b�J�[�T�[���A1951�N5��3������J�Â��ꂽ��@�̊O���ψ���ƌR���ψ���̍���������Łu#���{�l��12�v�،����s�������Ƃ����{�ɓ`���ƁA���̏،������{�l�A���Ƀ}�X�R�~�ɗ^�����Ռ��͑傫���A�w�����V���x��5��16���t�̐V��1�ʂɑ傫���y�}�����̓��{�ρz�Ƃ������W�L�����f�ڂ��u�������x�́g���N�h�v�Ɠ��{�l�ɑ��ے�I�ȕ������������ĕ��B����ɎА��Łu�}�����͕ċc��̏،��Łu���{�l�͏��҂ɂւ炢�A�s�҂���������X��������v�Ƃ��u���{�l�͌��㕶���̕W������݂Ă܂�12�̏��N�ł���v�Ȃǂƌ����Ă���B�����͓��{�l�ɑ����̔��_���������邱�Ƃ��悭���m���Ă��邪�A�\���Ɉ�l�O���Ƃ��v���Ă��Ȃ��悤���B���{�l�ւ݂̂₰���b�Ƃ��Ă������������v������������̂ł͂Ȃ��A�S����f���Ɋ���悤�ɁA�����ƕ��@���悭�l������K�v�����낤�B�v�ƈ�]���ă}�b�J�[�T�[�ɑ��ꌾ��悷��ȂǁA���{�̃}�X�R�~�ɂ�����}�b�J�[�T�[�ւ̎���K�����a�炬�A���j���ω����Ă����ɘA��āA���{�����́A�����҂ł������}�b�J�[�T�[�ɂ������Ă������Ƃ�p���āA�}�b�J�[�T�[�M�͈�C�ɗ�p�����邱�ƂƂȂ����B
���̂��߁A���{���v�悵�Ă����u�I�g���o�ҋ��̑���v�͐摗��u�}�b�J�[�T�[�L�O�ق̌��݁v�v��͂قڔ����P��ƂȂ�A�O���A���{���w�H��(���j�R��)�A���̑f��3�Ђ��u12�ł͂���܂���v�Ɩ��ł��A�^�J�W�A�X�^�[�[�A�j�b�R�[���A���̑f��3���i�����ۓI�ɍ����]�����Ă���|���`���鋤���L����V���ɏo�������ɂȂ����B �@ |
 �@ �@
���Ƒ� �@ |
����e
�}�b�J�[�T�[�̐l�i�`���ɑ傫�ȉe����^�����̂��ꃁ�A���[�E�s���N�j�[�E�n�[�f�B(�ʏ̃s���L�[)�ł���A�}�b�J�[�T�[�͏�Ƀ}�U�[�R���v���b�N�X�ɂƂ���Ă����Ƃ����w�E������قǂ������B�}�b�J�[�T�[�͗c���̍��ɌR�̍ԓ��Ő������Ă������߁A�}�b�J�[�T�[��6�ɂȂ�܂Ńs���L�[�����������Ă����B�s���L�[�͂��̊ԁA�}�b�J�[�T�[�������Ɉˑ�������Ԃ������邽�߁A�����J�[�����������ɂ����A�X�J�[�g���͂����Ă����B
���̌�A���e�A�[�T�[�����V���g���ɓ]�������Ƃ�����A�}�b�J�[�T�[��8�ɏ��w�Z�ɓ��w����ƁA���̌�̓E�F�X�g�E�e�L�T�X�R�l�{���w�Z�ɐi�w���R�l�ւ̓���i��ł������ƂƂȂ������A�s���L�[�͈��������}�b�J�[�T�[�ɋ����e�����y�ڂ��������B���̈��Ƃ��āA�}�b�J�[�T�[��13�̎��ɏ������҂��̂��߂ɐV������̃A���o�C�g���������Ƃ����������A���̃A���o�C�g�̊w����ɔ̔����тŃ}�b�J�[�T�[�����������Ƃ��s���L�[���m��ƁA�u����������x�s���ĐV����S�������Ă��Ȃ����B���肫��܂ŋA���Ă��Ă͂����܂���v�ƌ��������������B�}�b�J�[�T�[�͗����̖�ɂȂ��Ă���A���̓{���{���ł��������ɐ���������Ȃ������e�̌������ʂ�V����S��������Ă���A����B�s���L�[�͂��̂悤�Ȍ�����������j�ɂ��A�}�b�J�[�T�[�����܂ꎝ���Ă��������ւ̋������O���A����Ɉ琬�������Ă������B�}�b�J�[�T�[�̓E�F�X�g�E�e�L�T�X�R�l�{���w�Z�ɓ��w�������͕��ʂ̐��тł��������A�s���L�[�ɖ����ꂽ������C�ŕ��ɑł����݂����ƁA�����Ȓm���~���h������A������ʂ�2�N���ɐi�w���鍠�ɂ͗D�����ƂȂ��Ă����B
�s���L�[�̋�����j�̓}�b�J�[�T�[��D�G�Ȑl�ԂɈ琬��������ŁA����Ȃ����Ȓ��S�I�Ŏ��I�Ȑl�Ԃɂ��Ă������B�}�b�J�[�T�[�͎����̊ԈႢ��F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�ԂƂȂ��Ă����A��Ɂu���Ԃ̐l�Ԃ͎������ׂ�悤�Ƃ��Ă���v�Ɣ�Q�ϑz������悤�ɂȂ��Ă����B���̂����Ń}�b�J�[�T�[�̓E�F�X�g�E�e�L�T�X�R�l�{���w�Z����i�w�����E�G�X�g�E�|�C���g�œ������̒��ŌǗ����Ă���A�E�G�X�g�E�|�C���g�̑��Ɛ��̌������ł́A���Ɛ��̒c���͂f���ăN���X���C�g�B�̉₩�ȎЌ��̏�ƂȂ�̂��ʗ�ł��邪�A�}�b�J�[�T�[�̌������ɂ͂�����1���̓����������o�Ȃ��Ȃ������B�s���L�[�̋���́A�}�b�J�[�T�[�ɏ����ȓ��u�I�F����\�z����\�͂����R���������A�}�b�J�[�T�[���g���F�l��K�v�Ƃ͂��Ȃ������B
�}�b�J�[�T�[�̎������ɂ��s���L�[�͑���ȉe�����y�ڂ��Ă����B�s���L�[�̓}�b�J�[�T�[�̍ŏ��̌������胋�C�[�Y���C�ɓ��炸�A�����ƕ������Ƃ��ɏ��S�̂��܂�ɕa���ɂ����قǂł������B���C�[�Y�����Y�Ƃł��������ߎ��͍��Ȃ��̂ł��������A�s���L�[�͏��҂�f�莮�ɂ͎Q�Ȃ������B�������Ă�����s���L�[�ƃ��C�[�Y�̂���͍��킸�A���C�[�Y�͌�ɗ����Ɏ����������Ƃ��āu�`��(�s���L�[)�����낢����o������̂ŁA�������̌����͔j�ǂ��}���邱�ƂƂȂ����v�Ƙb���Ă���B
�}�b�J�[�T�[��2�x�ڂ̃t�B���s���Ζ����ɁA������33�Ή���16�̃C�U�x�������l�Ƃ��A�������A�����J�{�y�Ɉٓ��ƂȂ�ƁA�C�U�x�����A�����J�ɌĂъ����A�s���L�[�ɒm��ꂽ���Ȃ��������߁A�s���L�[�Ɠ������Ă��鎩��ɌĂъ邱�Ƃ��ł����ɁA�W���[�W�^�E�� (���V���g��D.C.)�ɃA�p�[�g���肻���ň͂�˂Ȃ�Ȃ������B �s���L�[�̖ڂ𓐂�Ŗ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ƁA�}�b�J�[�T�[���Q�d�����ɏA�C�����Z�ɂȂ������߁A����Ƀ}�b�J�[�T�[�ƃC�U�x���͑a���ƂȂ��Ă������B�}�b�J�[�T�[�̓C�U�x�����t�B���s���ɋA�点�悤�ƃt�B���s���s���̑D�̃`�P�b�g��n�������A�C�U�x���̓t�B���s���ɋA�炸�}�b�J�[�T�[�ɋ��S���Ă������߁A�������}�b�J�[�T�[�̓C�U�x���Ɍo�ϓI�Ȏ����𑣂����Ƌ��l���̃`���V�𑗂���Ă���B���ǁA�C�U�x���̓}�b�J�[�T�[�ƓG�����W���[�i���X�g�ɋ��͂��A�X�L�����_���ƂȂ��Đ��Ԃ�s���L�[�ɃC�U�x���Ƃ̊W��m��ꂽ���Ȃ������}�b�J�[�T�[�̎�݂ɕt������15,000�h���̈Ԏӗ�����邱�Ƃɐ������Ă���B
�}�b�J�[�T�[���R���ږ�ɏA�C��3��ڂ̃t�B���s���s���ƂȂ����Ƃ��A82�ƂȂ��Ă����s���L�[�͕t���Ă������ƂƂ������A�t�B���s���Ɍ������D���ŏ��߂ĉ�����W�[�����s���L�[�͑����ɋC�ɓ���A�s���L�[�̂��n�t���ƂȂ����W�[���ƃ}�b�J�[�T�[�͑D���ňӋC���������ۂ��J�n�A���̌�W�[���̓}�b�J�[�T�[��2�Ԗڂ̍ȂƂȂ������A�s���L�[�͂��̌��������邱�ƂȂ�1935�N11���Ƀt�B���s���ɓ�����������ɖS���Ȃ��Ă���B�}�b�J�[�T�[�̗������ݕ��͑����Ȃ��̂ŁA�t�B���s���Ń}�b�J�[�T�[�̕��������Ă����A�C�[���n���[�́u���R�̋C�����ɉ��������̊ԁA�e�����y�ڂ����v�Ə����L�����قǂł������B �@ |
�����̑�
�Z�̃A�[�T�[�E�}�b�J�[�T�[3���̓A�����J�C�R���w�Z�ɓ��w���A�C�R�卲�ɏ��i�������A1923�N�ɕa�������B��}���R����1883�N�Ɏ��S���Ă���B�Z�A�[�T�[�̎O�j�ł���_�O���X�E�}�b�J�[�T�[2���͒����A�����J��g�ƂȂ����B
1938�N�Ƀ}�j���ōȃW�[���Ƃ̊Ԃɏo�������j������B�}�b�J�[�T�[�Ƃ͑�X�A�ƒ��Ƃ��̒��j���A�[�T�[�E�}�b�J�[�T�[�𖼏���Ă������A�Z�A�[�T�[�E�}�b�J�[�T�[3���̎O�j���_�O���X�E�}�b�J�[�T�[2���ɂȂ�A�O�j�ł���_�O���X�̒��j���A�[�T�[4���ɂȂ��Ă���B
���̃A�[�T�[�E�}�b�J�[�T�[4���́A���{�ݏZ�̎��ɂ̓}�b�J�[�T�[�����̒��j�Ƃ��ē��{�̃}�X���f�B�A�Ŏ��グ���邱�Ƃ��������B�}�b�J�[�T�[�ƃW�[���͕��e��Ɠ��l�ɌR�l�ɂȂ邱�Ƃ���������A���̌��тɂ�薳�����œ��w�ł������R�m���w�Z�ɂ͐i�܂��A�R�����r�A��w���y�Ȃɐi�݁A�W���Y�E�s�A�j�X�g�ƂȂ����B�}�b�J�[�T�[�̓A�[�T�[�̑I����e�F�������A���̂��Ƃɂ��Ė����Ɓu���͕�̊��҂���ςȕ��S�ł������B��ԂɂȂ�Ƃ������Ƃ͖{���ɂ炢���Ƃ���B���͑��q�ɂ���Ȏv���͂��������Ȃ������B�v�Ɠ������Ƃ����B����ł��}�b�J�[�T�[�Ƃ������O�̓A�[�T�[�ɂƂ��Ă͕��S�ł����Ȃ������̂��A�}�b�J�[�T�[�̎���͖��O�ƏZ����ς��A�O���j�b�W�E���B���b�W�ɏW�܂�q�b�s�[�̈�l�ɂȂ����ƌ����Ă���B�@ |
 �@ �@
���}�b�J�[�T�[�̃A�����J�c��،��^�@ |
|
���i�ߊ���C���1951�N5��3������A�}�b�J�[�T�[���ؐl�Ƃ�����@�̌R���O�������ψ���J�Â��ꂽ�B��ȋc��́u�}�b�J�[�T�[�̉�C�̐���v�Ɓu�ɓ��̌R����v�ɂ��Ăł��邪�A���{�ɂ��Ă̎��^���s���Ă���B�@ |
�����{���푈�ɓ˓������ړI�͎�Ƃ��Ĉ��S�ۏ�(security)�ɂ�����
����҂�蒩�N�푈�ɂ����钆�ؐl�����a��(�ԉ�����)�ɑ��Ă̊C���헪�ɂ��Ă̈ӌ������A�����m�푈�ł̌o���������Ȃ��牺�L�̂悤�ɓ����Ă���B
�uSTRATEGY AGAINST JAPAN IN WORLD WAR II
Senator Hicknlooper. Question No.5: Isn't your proposal for sea and air blockade of Red China the same strategy by which Americans achieved victory over the Japanese in the Pacific?
(�q�b�N�����[�p�[��@�c���E��5����F�ԉ������ɑ���C���Ƃ������Ȃ��̒�ẮA�A�����J�������m�ɂ����ē��{�ɏ��������̂Ɠ����헪�ł͂���܂���?)General MacArthur. Yes, sir. In the Pacific we by-passed them. We closed in.���
There is practically nothing indigenous to Japan except the silkworm. They lack cotton, they lack wool, they lack petroleum products, they lack tin, they lack rubber, they lack great many other things, all of which was in the Asiatic basin.They feared that if those supplies were cut off, there would be 10 to 12 million people unoccupied in Japan. Their purpose, therefore in going to war was largely dictated by security.The raw materials -- those countries which furnished raw materials for their manufacture -- such countries as Malaya, Indonesia, the Philippines, and so on -- they, with the advantage of preparedness and surprise, seized all those bases, and their general strategic concept was to hold those outlying bastions, the islands of the Pacific, so that we would bleed ourselves white in trying to reconquer them, and that the losses would be so tremendous that we would ultimately acquiesce in a treaty which would allow them to control the basic products of the places they had captured.In meeting that, we evolved an entirely new strategy. They held certain bastion points, and what we did was to evade those points, and go around them.We came in behind them, and we crept up and crept up, and crept up, always approaching the lanes of communication which led from those countries, conquered countries, to Japan.(�}�b�J�[�T�[���R�F�͂��B�����m�ɂ����āA��X�́A�ނ��������āA������͂��܂����B(����)������{�͎Y�i���قƂ�lj�������܂���A�\�������āB���{�ɂ͖Ȃ��Ȃ��A�r�т��Ȃ��A�Ζ����i���Ȃ��A�X�Y���Ȃ��A�S�����Ȃ��A���̑������̕����Ȃ��A���A���̑S�Ă��A�W�A�n��ɂ͂������B���{�͋���Ă��܂����B�����A�����̋������f����ꂽ��A���{�ł�1000���l����1200���l�̎��Ǝ҂�������B����䂦�A���{���푈�ɓ˓������ړI�́A��Ƃ��Ĉ��S�ۏ�(security)�ɂ����̂ł����B���ޗ��A���Ȃ킿�A���{�̐����ƂɕK�v�Ȍ��ޗ��A�������鍑�X�ł���A�}���[�A�C���h�l�V�A�A�t�B���s���Ȃǂ́A���O�����Ɗ�P�̗D�ʂɂ����{����̂��Ă��܂����B���{�̈�ʓI�Ȑ헪���j�́A�����m��̓��X���O�s�w�n�Ƃ��Ċm�ۂ��A��X�����̑S�Ă�D���Ԃ��ɂ͑���̑�����������Ǝv�킹�邱�Ƃɂ���āA���{����̒n���猴�ޗ����m�ۂ��邱�Ƃ���X�ɖٔF������A�Ƃ������̂ł����B����ɑ��āA��X�͑S���V�K�̐헪��҂ݏo���܂����B���{�R������w�n��ێ����Ă��Ă��A��X�͂�����щz���Ă����܂����B��X�͓��{�R�̔w��ւƔE�ъ��A�E�ъ��A�E�ъ��A��ɓ��{�Ƃ����̍��X�A��̒n�����ԕ⋋���ɐڋ߂��܂����B)�v— p.170�AGeneral Macarthur Speeches & Reports: 1908-1964
�`��F�́A���x�j��Y�Ȃǂ̓����ٔ��ᔻ���s���_�q���������̔������u(�}�b�J�[�T�[�������m�푈��)���q�푈�Ƃ��ĔF�����Ă����؋��v�Ƃ��Ď��グ��_�_�ł���Ǝw�E���Ă���B���x�͂��̌����u�����̌����̋�����f����ꂽ��A��疜�������S���̎��Ǝ҂���������ł��炤���Ƃ�ނ�(���{���{�E�R��)�͋���Ă�܂����B�������Ĕނ炪�푈�ɔ�э���ł������@�́A�啔����security(���S�ۏ�)�̕K�v�ɔ����Ă̂��Ƃ����̂ł��v�ƖĂ���B�܂��A�č��l�̃P���g�E�M���o�[�g�́A�u���{�̐푈�́A���S�ۏ�(���q)�����@�������v�ƖĂ���B�@ |
�����{�l��12��
������3���ڂ�5��5���̌ߑO10��35������n�܂�A�ߑO12��45������ߌ�1��20���܂ŋx�e������ɁA�}�b�J�[�T�[�̓��{�����ɂ��Ă̎��^���s��ꂽ�B�}�b�J�[�T�[�͂��̎��^�̒��ŁA�l�ނ̗��j�ɂ����Đ�̂̓��������܂����������߂����Ȃ����A��O�Ƃ��ăW�����A�X�E�V�[�U�[�̐�̂ƁA����̓��{����������Ƃ��A���̐��ʂɂ���x�����`���������{���A�����J���̐w�c����o�Ă������Ƃ͂Ȃ��Ƌ����������A����҂̃����O�ψ���胔�@�C�}�����a���Ŗ����`����ɂ��Ȃ���i�`�Y���ɑ������h�C�c���ɋ����A��������ۂ̎��^�����L�̒ʂ�ł���B
�uRELATIVE MATURITY OF JAPANESE AND OTHER NATIONS
Senator Long.(�����O��@�c��)
Germany might be cited as an exception to that, however. Have you considered the fact that Germany at one time had a democratic government after World War I and later followed Hitler, and enthusiastically apparently at one time.(�������h�C�c�͂���ɑ����O�Ƃ��ċ������邩���m��܂���B�h�C�c�͈�x�A��ꎟ���E���̌�ɖ����`�̐��{��L�����̂ɁA���̌�A�ꎞ�͔M���I�Ƀq�g���[�̌��ǂ����Ƃ������������Ȃ��͍l�����܂�����?)General MacArthur. (�}�b�J�[�T�[����)
Well, the German problem is a completely and entirely different one from the Japanese problem. The German people were a mature race. If the Anglo-Saxon was say 45 years of age in his development, in the sciences, the arts, divinity, culture, the Germans were quite as mature.The Japanese, however, in spite of their antiquity measured by time, were in a very tuitionary condition. Measured by the standards of modern civilization, they would be like a boy of 12 as compared with our development of 45 years.Like any tuitionary period, they were susceptible to following new models, new ideas. You can implant basic concepts there. They were still close enough to origin to be elastic and acceptable to new concepts.The German was quite as mature as we ware. Whatever the German did in dereliction of the standards of modern morality, the international standards, he did deliberately.He didn't do it because of a lack of knowledge of the world. He didn't do it because he stumbled into it to some extent as the Japanese did. He did it as a considered policy in which he believed in his own military might, in which he believed that its application would be a short cut to the power and economic domination that he desired.Now you are not going to change the German nature. He will come back to the path that he believes is correct by the pressure of public opinion, by the pressure of world philosophies, by his own interests and many other reasons, and he, in my belief, will develop his own Germanic tribe along the lines that he himself believes in which do not in many basic ways differ from our own.But the Japanese were entirely different. There is no similarity. One of the great mistakes that was made was to try to apply the same policies which were so successful in Japan to Germany, where they were not quite so successful,to say the least.They were working on a different level.(�܂��A�h�C�c�̖��͓��{�̖��Ɗ��S�ɁA�����āA�S�R�قȂ���̂ł����B�h�C�c�l�͐��n�����l��ł����B�A���O���T�N�\�����Ȋw�A�|�p�A�_�w�A�����ɂ�����45�˂̔N��ɒB���Ă���Ƃ���A�h�C�c�l�͓������炢���n���Ă��܂����B���������{�l�͗��j�͌Â��ɂ�������炸�A��������ׂ��ɂ���܂����B���㕶������Ƃ���Ȃ�A���(�A���O���T�N�\��)��45�̔N��ɒB���Ă���̂Ɣ�r���ē��{�l��12�̏��N�̂悤�Ȃ��̂ł��B���̂ǂ̂悤�ȋ������Ă���ԂƓ��l�ɁA�ޓ��͐V�������f���ɉe������₷���A��{�I�ȊT�O��A���t���鎖���ł��܂��B���{�l�͐V�����T�O������鎖���ł���قǔ����ɋ߂��A�_�������܂����B�h�C�c�l�͉�X�ƑS���������炢���n���Ă��܂����B�h�C�c�l������̍��ۓI�ȋK�͂⓹������������Ƃ��́A����͌̈ӂɂ����̂ł����B�h�C�c�l�͍��ۓI�Ȓm�����s�����Ă������炻�̂悤�Ȏ��������킯�ł͂���܂���B���{�l�������炩�͂����ł������悤�ɁA���߂��Ă�����킯�ł�����܂���B�h�C�c���g�̌R���͂�p���邱�Ƃ��A�ޓ�����]�������͂ƌo�ώx�z�ւ̋ߓ��ł���Ǝv���Ă���A�n�l�̏�ɌR���͂��s�g�����̂ł��B���݁A���Ȃ����̓h�C�c�l�̐��i��ς��悤�Ƃ͂��Ȃ��͂��ł��B�h�C�c�l�͐��E�N�w�̈��͂Ɛ��_�̈��͂Ɣގ��g�̗��v�Ƒ����̑��̗��R�ɂ���āA�ޓ����������Ǝv���Ă��铹�ɖ߂��Ă����͂��ł��B�����āA��X�̂��̂Ƃ͑����͕ς��Ȃ��ޓ����g���l����H���ɉ����āA�ޓ����g�̐M�O�ŃQ���}�����������グ��ł��傤�B�������A���{�l�͂܂������قȂ�܂����B�S���ގ���������܂���B�傫�ȊԈႢ�̈�̓h�C�c�ł����{�Ő������Ă����������j��K�p���悤�Ƃ������Ƃł����B�T���ڂɌ����Ă��A�h�C�c�ł͓�������ł��������Ă��܂���ł����B�h�C�c�l�͈قȂ郌�x���Ŋ������Ă�������ł��B)�v— p.312�AMilitary situation in the Far East. Corporate Author: United States.(1951)
���̔����������̓��{�l�ɂ͔ے�I�Ɏ���A���{�ɂ�����}�b�J�[�T�[�l�C��p���̑傫�ȗv���ƂȂ���(#�}�b�J�[�T�[�l�C�̏I��)�B�����̓��{�l�͂��̔����ɂ��A�}�b�J�[�T�[���爤����Ă����̂ł͂Ȃ��A�g����̓G�͍����̗F�h�ƗF���������Ă����̂ł��Ȃ��A�y�̂���Ă����ɉ߂��Ȃ��������Ƃ�m�����Ƃ����w�E������B
����Ƀ}�b�J�[�T�[�́A�������̌�����̒��Łu���{�l��12�v�����̑O�ɂ��u���{�l�͑S�Ă̓��m�l�Ɠ��l�ɏ��҂ɒǏ]���s�҂��ő���Ɍ�������X���������Ă���B�A�����J�l�����M�A���������A�����I�Ȏ����̑ԓx�������Č��ꂽ���A���{�l�ɋ�����ۂ�^�����B�v�u����͂���߂ČǗ����i���̒x�ꂽ����(���{�l)���A�A�����J�l�Ȃ�Ԃ�V�̎�����m���Ă���w���R�x�����߂Ė��킢�A�y���݁A���s����@����Ƃ����Ӗ��ł���B�v�ȂǂƓ��{�l��c�t�ƌ������āA�u���{�l��12�v������苭�����{�l�J�����Ǝ���Ȃ��˂Ȃ��������s���Ă����B
�܂��A�����̓��{�̐�̓������V�[�U�[�̈̋ƂƔ䌨����Ǝ���������A�u(���{�Ń}�b�J�[�T�[���s�������v��)�C�M���X�����Ɏ��R�������}�O�i�E�J���^�A�t�����X�����Ɏ��R�Ɣ����������t�����X�v���A�n���匠�̊T�O�������䂪���̃A�����J�Ɨ��푈�A��X���o���������E�̈̑�Ȋv���Ƃ̂ݔ�ׂ邱�Ƃ��ł���B�v�Ə،����Ă���A�}�b�J�[�T�[�͏،��ŁA���g�����{�Ő����������ƍl���Ă����Ɛт�ٌ삵�Ă����Ƃ������߂�����B
����ŁA�}�b�J�[�T�[�́u�V���͎��Ȃ��c�c�v�̃t���[�Y�ŗL����1951�N4��19���̏㉺���@�c����O�ɂ��������ł́u�푈�ȗ��A���{�l�͋ߑ�j�ɋL�^���ꂽ���ōł����h�ȉ��v�𐬂��������v��u�^�ɑ���ӎu�ƁA�w�K�ӗ~�ƁA������ł�����͂������āA���{�l�͐푈���c�����D�̒�����A�l�̎��R�Ɛl�i�̑����Ɍ������傫�Ȍ����������݂����B�����I�ɂ��A�o�ϓI�ɂ��A�����ĎЉ�I�ɂ��A������{�͒n����ɂ��鑽���̎��R���Ƃƌ�����ׂĂ���A�����čĂѐ��E�̐M���𗠐鎖�͂Ȃ��ł��낤�B�v�Ɠ��{���̎^���Ă���A�u���{�l��12�v�����͓��{�l�̓h�C�c�l���M���ł��邱�Ƃ��������������������Ń}�b�J�[�T�[�̐^�ӂ����܂��`���Ȃ������Ƃ������߂�A�}�b�J�[�T�[�ƊW���[�������g�c�̂悤�Ɂu�����̉����̏ڍׂ�ǂ�ł݂�Ɓu���R��`�▯���`�����Ƃ����悤�ȓ_�ł́A���{�l�͂܂��Ⴂ����ǁv�Ƃ����Ӗ��ł����āu�Â��Ǝ��̕����ƗD�G�ȑf���Ƃ������Ă��邩��A���m���̕������x�̏�ł��A���{�l�̏����̔��W�͐���L�]�ł���v�Ƃ������Ƃ��������Ă���A�ˑR�Ƃ��ē��{�l�ɑ��鍂���]���Ɗ��҂�ς��Ă��Ȃ��̂����̐^�ӂł���B�v�ƍD�ӓI�ȉ��߂�����B�Ȃ��}�b�J�[�T�[���u12�v�ƌ����āu13�v�łȂ������̂��́A�p��̊��o�Ō�����12�́u�e�B�[���G�C�W���[�v�ł͂܂��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�܂����_�N��n�������Ă��炸�A�V��������������邱�Ƃ��\���Ƌ������Ă���̂ł���B�@ |
 �@ �@
���}�b�J�[�T�[�L�O�ف@ |
�m�[�t�H�[�N�̃m�[�e�B�J�X���瓌�֖�400m�s�����Ƃ���ɂ���_�E���^�E���̃}�b�J�[�T�[�E�X�N�G�A�ɂ́A19���I�̎s���ɂ����̂܂܋L�O�قƂ����_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�L�O�ق����n���Ă���B�ٓ��ɂ̓}�b�J�[�T�[�v�Ȃ̕��A�����فA�}���ق��݂����Ă���B�����قɂ͌R�֘A�i�����łȂ��A�}�b�J�[�T�[�̃g���[�h�}�[�N�ł������R�[���p�C�v�Ȃǂ̎����������W������Ă���B�܂��A�ɖ����A��J�A�F���̎����L������ȂǁA�}�b�J�[�T�[�������A�������{�̍H�|�i���W������Ă���B�����́u���m�[�t�H�[�N�s���Ɂv�Ƃ��č��Ɨ��j�o�^���Ɏw�肳��Ă���B�L�O�ق̐��ʂɂ̓}�b�J�[�T�[�̓����������Ă���B
���{�ł��}�b�J�[�T�[��C�O��Ɂu�}�b�J�[�T�[�L�O�فv�����݂���v�悪���������B���̌��ݔ��N�l�ɂ͒����{�A�c���k���Y�ō��ٔ��������A���X�����Y��������}���يْ��A�쑺�g�O�Y�����đ�g�A�{�c�e�j�����V���В��A���J���������V���В���e�E�̗L�͎҂�����A�˂Ă����B���̎{�݂́u�}�b�J�[�T�[�_�Ёv�ƌď̂���Ă��邱�Ƃ����邪�A���̌v��́A�}�b�J�[�T�[�ݔC������u�j���[�E�t�@�~���[�E�Z���^�[�v�Ƃ����c�̂��v�悵�Ă����u�N�̉Ɓv�Ƃ������N�̌[�֎{�݂̌��v��W���������̂ł���A�u�����̌��т��i���ɋL�O���邽�߁A�Ќ��Ɣ��������������тƋ��{�̓a���ɂ������B�v�Ƃ�����|�̉��ŁA�L�O�فA����A�v�[���A�^���{�݁A�h���{�݂�������̂ł����āA���ɏ@���F�̂Ȃ��v��ł������B
���̌�ɓ�����14���̔��N�l�ɉ����A���R����Y���{���H��c����A�����Y�Љ�}���L���A���䐽��Y�����s�m������Q�����āu�}�b�J�[�T�[��ٌ��݊�����v�������A�܂��͑����Ɣ�4��5,000���~�������ĎO���̎Q�d�{���ՂɓS�R���N���[�g��3�K���r�������Ă�v��ŕ�����������A����J�n���u���{�l��12�v�����Ń}�b�J�[�T�[�M���}���ɗ�p�����Ă���1952�N2���ł���A60���~�̐�`��������ďW�܂�������͂킸��84,000�~�ƎS�邽��L�l�������B1�N��ɂ͕���ǂ��납�؋���300���~�܂Ŗc��݁A�v��͗��������ɂȂ����B���ɂ������p�Ɂu�}�b�J�[�T�[����v�����݂��A�~�����̍ۂɐ�̓~�Y�[�����┑�����ӂ���i���ɏƂ炷�v���A�܂��u�}�b�J�[�T�[�L�O�فv��u�}�b�J�[�T�[����v�̌v����O��1949�N�ɂ͕l���{�Ɏ��R�̏��_���Ɠ��������̃}�b�J�[�T�[�̓��������݂��悤�Ƃ���u�}�b�J�[�T�[�����������݉�v���������Ă����B���M�ƍ��c�ۂɂ��ψ��A�C�̊��U���Ȃ����ȂǍL���͈͂ɐ����������(���������c�͈ψ��A�C��������)������J�n���ꂽ���A��������̌v��Ɠ��������ɗ��������ɂȂ�A�W�܂�������̍s�����ǂ��Ȃ������s���ł���B�@ |
 �@ �@
���l���]�@ |
�}�b�J�[�T�[�̉��ő����m�푈��������5��R�i�߂̃W���[�W�E�P�j�[(�p���) �������}�b�J�[�T�[�ɂ��āu�_�O���X�E�}�b�J�[�T�[��{���ɒm��҂͂����킸���������Ȃ��B�ނ�m��ҁA�܂��͒m���Ă���Ǝv���҂́A�ނ��^�����邩�������̂ǂ��炩�Œ��Ԃ͂��蓾�Ȃ��B�v�ƕ]���Ă���悤�ɁA�]���������l���ł���B
�}�b�J�[�T�[�ɂƂ��Ē����S�Ƃ͕����������I�Ɍ���������̂Ƃ̔F���ł���A�������d���Ă���͂��̑哝�̂�R��w���ɑ��钉���S�������Ƃ͂Ȃ��������߁A�}�b�J�[�T�[�ɑ�����哝�̂�R��w���̐l���]�͖F�������̂ł͂Ȃ������B
���[�Y�x���g�́u�}�b�J�[�T�[�͎g���ׂ��ŐM�����ׂ��ł͂Ȃ��B�v�u�䂪���ōł��댯�Ȑl��2�l�̓q���[�C�E�����O�ƃ_�O���X�E�}�b�J�[�T�[���B�v�ƃ}�b�J�[�T�[�̔\�͂̍�����]�����Ȃ���M�p�͂��Ă͂��炸�A������ɔ����ă}�b�J�[�T�[�������m�푈�J��O�ɌR�ɒ�o�����w���{�R���䂪���ׂւ̋�P�\�͂��������߁A�t�B���s���͕ێ��ł���x�Ƃ�����������Ƃɕۊǂ��Ă����B�܂��A�����ւ̐i�o�Ƀ}�b�J�[�T�[��������S������Ă���̂��������āu�_�O���X�A�N�͉䂪���ō��̏��R�����A�䂪���ň��̐����ƂɂȂ�Ǝv����v �ƓB���h�������Ƃ��������B
�X�R�Ɏ���܂Ō������}�b�J�[�T�[�ƑΗ����Ă����g���[�}���̕]���͂����Ɛh煂ŁA�A�C�Ԃ��Ȃ�1945�N�ɖ������ډ�������Ƃ��Ȃ��}�b�J�[�T�[�ɑ��u���̂��ʂڂ����A���̂悤�Ȓn�ʂɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ́B�Ȃ����[�Y�x���g�̓}�b�J�[�T�[���݂��݂��~���̃q�[���[�����Ă������̂��A���ɂ͂킩��Ȃ��E�E�E������X�Ƀ}�b�J�[�T�[�̂悤�Ȗ��Ҍ��y�e���t�ł͂Ȃ��E�F�C�����C�g�������Ȃ�A�ނ������^�̏��R�A�키�j�������B�v�Ɣے�I�ȕ]�������Ă����B�������}�b�J�[�T�[�̈��|�I�Ȏ��тƐl�C�ɁA�S���C���i�܂Ȃ�������GHQ�̍ō��i�ߊ��ɔC�����Ă���B�g���[�}���̃}�b�J�[�T�[�ւ̕]���͈������鎖�͂����Ă����P���邱�Ƃ͂Ȃ��A1948�N�ɂ̓}�b�J�[�T�[��ޖ������A���h�C�c�̌R���i�ߊ����V�A�X�ED�E�N���C��GHQ�ō��i�ߊ��̌�C�ɂ��悤�Ɖ�����Ƃ����������A�g���[�}���̑Őf���N���C�͒f������͂��Ȃ������B
���N�푈�ɂ����āA�����͎Q�d�{�����Q�d���Ƃ��ă}�b�J�[�T�[�̓ƒf��s�ɐU���A��Ƀ}�b�J�[�T�[�̌�C�Ƃ��č��A�R�𗦂������b�W�E�F�C�̓}�b�J�[�T�[�̐��i�ɂ��āA�u������������̂ł͂Ȃ��s�ׂɂ��Ă����_������������A���炩�Ȏ����̌��ɑ��Ă��ӔC��۔F���悤�Ƃ����^�ւ̊��]�v�u�����̏����̑O�ŏ�Ƀ|�[�Y���Ƃ肽����A�l�ڂɂ�����ւ̎����v�u�V�˂ɕK�v�ȌǓƂ�������X���v�u�_���I�Ȏv�l�����ĂȂɂ��̂��ɌŎ�����A����Ȑ����v�u����T�̐M�O����������A�������g�ɑ��鎩�M�v�ƕ��͂��Ă����B����ŁA�}�b�J�[�T�[�̖��̊j�S�𖾂炩�ɂ���\�͂ƁA�ڕW�Ɍ������Đv���E�ʊ��ɍs������ϋɐ��ɑ��āA���̐l�̓}�b�J�[�T�[�������������A�����������邱�Ƃ͍���ł����āA�}�b�J�[�T�[�ɋ^����������̂͋t�Ɏ������g���^�킹�Ă��܂��قǐ^�Ɉ̑�ȏ����̈�l�ł������Ə^�����Ă���B
��i�ɂ�����l�����̕]��������������ŁA�����炩��̕]����M���͍��������BGHQ�Ń}�b�J�[�T�[�̉��œ������ɓ���R�i�߂̃W���[�W.E.�X�g���g���C���[(�p���) �����́u�A�����J�j�ɂ�����ł��̑�Ȏw���҂ł���A�ł��̑�Ȏw�����ł���A�����Ƃ��̑�ȉp�Y�v�Ə̂��A��10�R�i�ߊ��G�h���[�h�E�A�[�����h�����́u�c�O�Ȃ��玞�オ�Ⴄ�̂ŁA�i�|���I���E�{�i�p���g��n���j�o����L�j�ȗ��̈̑�ȏ��R��Ɠ���ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�}�b�J�[�T�[����20���I�ł����Ƃ��̑�ȌR���I�V�˂ł���B�v�ƃ��C�t���̎�ނɓ����Ă���B
���Ƀt�B���s�����ォ��}�b�J�[�T�[�ɏd�p����Ă����w�o�^�[���E�M�����O�x�ƌĂꂽGHQ���������̃}�b�J�[�T�[�ɑ���]���ƐM���͋ɂ߂č����A���̓��̈�l�ł���E�B���r�[�́A�}�b�J�[�T�[�ɏo�����莆�Ɂu���Ȃ��ɕC�G����l���͒N�����܂���A���ǐl�X���������o����͈̂̑�Ȏw���ҁA�v�z�ł͂Ȃ��A�l�Ԃł��B�E�E�E�a�m(�E�B���r�[�̂���)�͑��(�}�b�J�[�T�[)�Ɏd���邱�Ƃ��ł��܂��B���̂悤�Ȍ`�ŋ߂��I���邱�Ƃ��ł���Ζ{�]�ł��B�v�Ə������قǂł������B
�������A�E�B���r�[��̂悤�ɖӖړI�ɏ]���Ă���Ă���悤�ȕ����ł����Ă��A�}�b�J�[�T�[�͕����Ǝ蕿�����������Ƃ����F���͂Ȃ��A������������ł�������̂ɔC�����A�C�[���n���[�ƑΏƓI�������B�Ⴆ�A�}�b�J�[�T�[�̔z���ő�8�R���w���������o�[�g�E�A�C�P���o�[�K�[�叫���A�T�^�f�[�E�C�u�j���O�E�|�X�g(�p���)�Ȃǂ̎G���ɂƂ肠����ꂽ���Ƃ����������A���ꂪ�}�b�J�[�T�[�̕s�����A�}�b�J�[�T�[�̓A�C�P���o�[�K�[���Ăт���Ɓu���͖����ɂł��N��卲�ɍ~�i�����ċA�������邱�Ƃ��o����B�����Ă���̂��H�v�Ǝ��ӂ������Ƃ��������B���ӂ����A�C�P���o�[�K�[�́u��폟��Ɏ����̖��O���ڗ����炢�Ȃ�|�P�b�g�ɐ������K���K���w�r�����Ă�����������܂��܂����B�v�ƕ����̍L��m���Ɍ���Ă���B
�}�b�J�[�T�[�̎w�����ŏ㗤���̎w�����������A�����J�C�R��7�������p�����i�߃_�j�G���E�o�[�x�C(�p���)�����́A�C�R�̗��ꂩ��A���̂悤�ȃ}�b�J�[�T�[�Ɨ��R�̕��������Ƃ̊W���ÂɊώ@���Ă���A�u�}�b�J�[�T�[�������̑��߂����Ɛe�������Ԉӎ��������Ƃ͌����ĂȂ������B�ނ͑��h����͂������A�����̋����Ɨ����邱�Ƃ͖����������A����������Ȃ������B�ނ̑ԓx�͂��܂�ɂ��悻�悻�������A���̌����͂������A�����Ɏ���܂Ō��������߂����B�v�ƕ]���Ă���B
�@ |
���}�b�J�[�T�[�ƃA�C�[���n���[
�}�b�J�[�T�[���ł��悭�m��҂�1�l��7�N�Ԃɓn���ĕ������߂��A�C�[���n���[�ł������B�A�C�[���n���[�̓}�b�J�[�T�[�Q�d�����̕��������U��Ԃ��āA�u�}�b�J�[�T�[���R�͉��Ɏd����҂Ƃ��ē����b��̂���l���ł���B�}�b�J�[�T�[�͈�x�C����^���Ă��܂��Ǝ��Ԃ͋C�ɂ����A��Ŏ��₷�邱�Ƃ��Ȃ��A�d����������ƂȂ���邱�Ƃ��������߂�ꂽ�B�v�u�C�������ł���A���R�̒m���͂��������قǕ��L���A�T�ː��m�ŁA�������r��邱�ƂȂ����t�ƂȂ��ďo�Ă����B�v�u���R�̔\�قƎ����́A���ɗ�̂Ȃ����ٓI�ȋL���͂̂��܂��̂ł������B�����╶�͂̑��e�́A��x�ǂނƒ���I�ɌJ��Ԃ����Ƃ��ł����B�v�Ə^���Ă���B
�������A�C�[���n���[�́A�}�b�J�[�T�[�̑��߂Ƃ��Ē��N�����Ȃ���A�u�o�^�[���E�M�����O�v�̃T�U�[�����h��z�C�b�g�j�[�ɂ悤�ɁA�}�b�J�[�T�[�̖��͂ɗ��߂Ƃ��Ȃ����������Ȃ���O�ł���A�t�B���s���ł̕�������́A�u�o�^�[���E�M�����O�v�̖�����Ƃ͈قȂ�A�}�b�J�[�T�[�Ƃ̋c�_���}��Ȃ������B �A�C�[���n���[�̃}�b�J�[�T�[�ɑ���v���̑傫�ȓ]���_�ƂȂ����̂��A�}�b�J�[�T�[�����e�����[�E�_�C�W�F�X�g(�p���) �Ƃ����G���̋L�����L�ۂ݂ɂ��A1936�N�A�����J���O���哝�̑I���Ń��[�Y�x���g�����I����Ƃ����������L�߂Ă����̂��A�C�[���n���[���~�߂�悤�ɏ��������̂ɑ��A�}�b�J�[�T�[�͋t�ɃA�C�[���n���[��{��������Ƃł������B���̓��ȍ~�A�A�C�[���n���[�̓}�b�J�[�T�[�̉��œ����̂�焈ՂƂ����f�U��������A���N��̗��R�Ŗ{���ւ̋A�҂�\���o�����A�A�C�[���n���[�̎����\�͂��d�Ă����}�b�J�[�T�[�͍Q�ĂĈ������߂�}���Ă���B���҂̊W������Â����̂́A���̌�ɋN�������A�}�b�J�[�T�[�ƒf�ł̃t�B���s���R�ɂ��}�j���s�i�v�悪�P�\���̓{��������߁A�A�C�[���n���[�畛���ɐӔC�]�ł����������ł���(#�t�B���s������)�A�A�C�[���n���[�͂��̎����Łu�����čĂсA��X�͂���܂łƓ����������A�S����̗F�l�W�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�v�Ɖ�z���Ă���B
���̌�A�A���������R�ō��i�ߊ��A�A�����J���R�Q�d�����Ə����Ɍo�����d�˂Ă����A�C�[���n���[�́A�}�b�J�[�T�[�̉��œ�����7�N�Ԃ��u�}�b�J�[�T�[�̉���7�N�Ԃɓn���Ċw���̂͂��ŋ������ł���B�v�Ƒ��������Ƃ��`�����Ă���B
�����A�����̃A�����J�̈ꕔ�}�X�R�~���Ă������͗��ҊԂɋ����m���͂Ȃ������悤�ŁA�A�C�[���n���[�͎Q�d�����ݔC���ɉ��x���}�b�J�[�T�[�Ɉӌ������߂�莆��A�Q�d�����ޔC���ɂ́A�}�b�J�[�T�[�ƃA�C�[���n���[�̑Η���ے肷��莆���o���ȂǁA���҂͌p�����ĘA������荇���Ă����B�������A�A�C�[���n���[����34��A�����J���O���哝�̂ɒ��C����ƁA���̕t�������͕\�ʓI�Ȃ��̂ƂȂ�A�A�C�[���n���[���}�b�J�[�T�[���z���C�g�n�E�X�ɒ��H�ɏ������ۂɂ́A�����ɏ������s���}�b�J�[�T�[�Ɏ���݂����Ƃ͂Ȃ��������߁A�}�b�J�[�T�[�͒��H�̐Ȃ𗧂�����ɁA�L�Ғc�ɑ��āu�ӔC�͌��͂ƂƂ��ɂ���B���͂��͂⌠�͂̏�ɂ͂��Ȃ��̂��B�v�ƕs�@�������Ɍ���Ă���B�@ |
 �@ �@
���G�s�\�[�h�@ |
�����{�ł̐���
�A�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ�����������ꐶ����(1950�N���B�e)���{�؍ݎ��̃}�b�J�[�T�[�̐����́A��8���ɋN���A�Ƒ��ƒx�����H���Ƃ���10���ɘA�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ��̂����ꐶ���قɏo�A14���܂Ŏd��������ƁA���x�݂̂��߂ɓ��{�؍ݒ��̏Z���ł������A�����J��g���@�ɋA��A���H�̌㒋�Q�A16���ɍēx�o���A�Ζ�������20������A��A�[�H�̌�A�ȃW�[���╛���ƃA�����J��������f����ς�A�Ƃ����̂����ۂ������B�D���ȉf��͐������ł������B�}�b�J�[�T�[�͂��̃X�P�W���[����y�����Ȃ������J��Ԃ��A�x�݂����Ȃ������B���{�����̗��s�͈�����A���o�͌���H�c�ɏd�v�ȗ��q���}���ɍs���Ƃ������ŁA���O�ւ����N�푈���n�܂�܂ł́A�t�B���s���Ɗ؍��̓Ɨ����T�ɏo�Ȃ����������������B��������O�Ƃ��āA�~�Y�[���͏�ł̍~�����������I������Ɋ��q�̒߉������{���ƂƂ��ɎQ�q�������Ƃ��A1945�N9��18���́w�ǔ���m�x�ŕ��Ă���B�}�b�J�[�T�[�ɂƂ���40�N�Ԃ�̖K�₾�����Ƃ�����B
���{�ł̏Z���͒����A�����J���O����g�ٌ��@�ƂȂ������A�����O�͑�8�R�i�ߊ��A�C�P���o�[�K�[�Ɂu���͍c���ɏZ�ނ��肾�v�Ƌ������Č���Ă����B��g���@��1930�N�ɓ����̑哝�̃t�[���@�[���A�����J�̍��͂���{�Ɍ֎�����ׁA�����̋��z��100���h���̋�������Č��z�����ϐk�\���̊��ȑ���ł���A��P�ł��S��͂��Ȃ��������A���e�₻�̔j�Ђ��������ђʂ������͐��Z���ɂȂ��ĉƋ�ނ͑S�ł��Ă����B�C���̂��߂ɑ����̓��{�l�̐E�l���W�߂��ďC�U�H�����s��ꂽ���A�e�[�u���N���X�E�J�[�e���̓n���C�A�h��֎q�̓u���X�x���Ȃǐ��E������Ƌ�⎺�����������A�܂��������߂�����������H��Ȃǂ̍���������������ꂽ�B�܂����j�A�[�T�[�̊ߋ�Ƀ}�b�J�[�T�[���p�̃R�[���p�C�v��͂�����̃p�C�v��ۉ�ō�����l�`�Ȃǂ�������ꂽ�B�R���q�h�[������̒E�o�ɓ��s���������l�g�p�l�̃A�[�E�`�������������g�p�l�Ƃ��Ĉꏏ�ɗ��������ق��A�}�j���E�z�e���Ń{�[�C�����Ă����J�����X���ĂъA���{�l���g���N�j�ƃL���Ƃ����������܂ߐ������ٗp���ꂽ���A���{�l���g�̓A�����J�̖�͂��h�J���ꂽ���F�̒��������j�z�[���Ƃ��Ē������Ă����B�A�����J���������ɂ���Ă����z�[�}�[�E�t�@�K�\�\����@�c���́A���̂悤�ȃ}�b�J�[�T�[�̍����Ȑ����Ԃ�����āu���̑f���炵���{�a�͂��������N�̂��̂��ˁH�v�Ɣ�������������߁AGHQ�̃E�B���A���E�W���Z�t�E�V�[�{���h�O���ǒ����t�H���[���Ă���B
�}�b�J�[�T�[�͍��z�����������K�����Ȃ��������߁A�������͍Ȃ̃W�[�����S�čs���Ă����B�W�[���͍ō��i�ߊ��̍Ȃɂ��ւ�炸�A�����s�������J�݂ɍs���ĉƌv���Ǘ����APX�̒����s��ɕ���ł����BPX�̃}�l�[�W���[�͂���ȃW�[�������āu���{�ɂ��鏫�R�̕v�l�̒��ŁA���ʑҋ��������߂ɂȂ�Ȃ��̂͋M�������ł��B�v�Ɗ��S���Ă���B�}�b�J�[�T�[���o��Ŕ�����������K�v���������Ƃ��́A���������đւ��āA��ɃW�[�������Ɏx�����Ă���]�B
�}�b�J�[�T�[�����{�l�Ɖ���Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A����I�ɂ����Ă����̂͏��a�V�c�Ƌg�c���炢�ł������B���͕s����Ɋt����A�����Q�����ɂ�菉���I����35���̏����c����A���j�̑S�đI�茠�o��̌Ë��L�V�i����{�I��c�Ȃǂ������ĉ���x�ł������B�Ë���Ɩʒk�����}�b�J�[�T�[�́u����(�p�X�|�[�g)�Ɏ����T�C������Əo���邩��A�s���Ă����B���̑���A�������炾�߂��B�����Ă��ڋ��ɂȂ��Ă͂����Ȃ��B����������Ƃ����Ă������Ă͂��߂��B�s���ȏ�͊撣��B��������A�Ђ���Ƃ��ċA��̃r�U�͎������ɂȂ邩���킩��Ȃ��v�Ə�k�������Ȃ���I��c���܂��Ă�B
�}�b�J�[�T�[�͓��{�؍ݒ���2���a�C�ɜ���Ă���B��x�ڂ͎��ɔ^ᇂ��ł����������Ƃ��ŁA������x���A�Ƀ����T���ۂ����������Ƃ��ł��邪�A�}�b�J�[�T�[�͈�Ҍ����ł���A��ꎟ���E���ȍ~�ɂ܂Ƃ��ɐg�̌������炵�Ă��Ȃ������قǂł������B�M���o�����ߌR�オ�y�j�V�����𒍎˂��悤�Ƃ����Ƃ���A�}�b�J�[�T�[�͒��˂�����Ă���u�j���g�̂Ɏh����Ȃ�ĐM�����Ȃ��v�ƌ����Ē��˂����ۂ��A���܂������������Ă���������A����ɏǏ�͈�����40�x�̍��M�ƂȂ������߁A�d���Ȃ����˂��Đ�����ɉ��������B
���{�؍ݒ��A�}�b�J�[�T�[�͏H�c���̃E�L�A�Č��ƃe���A�̎G��̃u���E�j�[�A�A�����J���E�R�b�J�[�E�X�p�j�G���̃u���b�L�[�A�X�p�j�G���n�̃R�[�m��4�C�̌��������Ă����B���̓��Ń}�b�J�[�T�[�̈�Ԃ̂��C�ɓ���̓A�����J���E�R�b�J�[�E�X�p�j�G���̃u���b�L�[�ł������B�܂��A�Ȗ،��ݏZ�̈�t����J�i���A���Ď����Ă������A1�N��ɍX�R����ċA�����邱�ƂƂȂ������߁A���̃J�i���A�͑�g���@�Ń`�[�t�E�R�b�N�����Ă����ђ���ɉ����n����A�т͌̋��ɘA��ċA���Ď��炵���B
���N�푈���J�n����Ă�����A���N�푈�̎w����C���ꂽ���i�ߊ��ɂ�������炸�A���N�������������}�b�J�[�T�[�͈�x�����N�ɏh�����邱�Ƃ��Ȃ������B����������Ύw���⎋�@�ŁA���N��K��Ă���ɓ��A��ŁA�K����ɂ͓��{�ɖ߂��Ă����B���ׂ̈ɐ��̗l�q���\���ɔc�����邱�Ƃ��ł����A�����`�E�R�Q��ɂ����̑傫�ȗv���ƂȂ����B�@ |
���ڋʏĂ�����
���ؔ�s��ɍ~�藧�����}�b�J�[�T�[�́A���ړ����ɂ͓��炸�A���l�́u�z�e���j���[�O�����h�v315������12�������B�؍ݒ��̂�����A�}�b�J�[�T�[�͒��H�Ɂu2�ڋʂ̖ڋʏĂ��v�Ɓu�X�N�����u���G�b�O�v�����N�G�X�g�������A���H�Œ����̕i�����Ԃ��Ƃ͂Ȃ��A�����߂��Ă悤�₭�u1�ڋʂ̖ڋʏĂ��v�������^��Ă����B�}�b�J�[�T�[�́A�����l���Ăяo���Ė₢���������Ƃ���A�����l�́u���R���疽�߂��Ă��獡�܂Ŕ������s�����āA�悤�₭�������ɓ���܂����v�Ɠ������B���̏u�ԁA�}�b�J�[�T�[�́A���{�����ݒu����Ă���ƁA�����ׂ̈��ׂ��d���𗝉������Ƃ����B�������A���̃G�s�\�[�h�������Ƃ��ďؖ�����W�҂̏،��͂Ȃ��B
�����̃z�e���j���[�O�����h��̖쑺�m�O�̉�z�ɂ��A�}�b�J�[�T�[���j���[�O�����h�ɒ����čŏ��ɏo���ꂽ�H���͗Ⓚ�̃X�P�\�E�_���ƃT�o�A�|���������L���E���A�����Č~���̃X�e�[�L�ł���A�}�b�J�[�T�[�̓X�e�[�L����������H�ׂ�Ɩ����ɂȂ�A��͎�����Ȃ������B����3����A���l�`�ɒ┑���Ă����R�͂���R�̂悤�ɐH�����חg�����ꂽ�Ƃ����B�܂��A���ۂɃe�[�u���ɂ͏o����Ȃ��������̂́A�쑺�̓}�b�J�[�T�[����}���鏀���Ƃ��āA���g�����������Ă������l�P�Ӊ@���痑��10�Z�ʂ��Ă�����Ă���B
�܂��A�}�b�J�[�T�[��̃j���[�O�����h�ł̏��߂Ă̐H���̃E�F�C�g���X�������������q�ɂ��A�o�����̂̓X�P�\�E�_���ƃ|�e�g�ƃX�[�v�ł���A�}�b�J�[�T�[�̓X�P�\�E�_��������Ȃ�u����͂ȂH�v�ƕ����A�������u�X�P�\�E�_���ł��v�Ɠ�����ƁA�u����Ȃ��̐H�ׂ��邩�v�Ƃ���������Ď���t�����ق��Ă����B���̌�A�H��̃f�U�[�g�ɏo�����P�[�L�ɂ����t�����A�ق��ĐȂ𗧂��Ă���B
�}�b�J�[�T�[�̑��ߌR�ネ�W���[�EO�E�G�O�o�[�O��t�����̐H���̐Ȃɓ��Ȃ��Ă������A�o���ꂽ�̂̓X�[�v�ƃo�^�[�t���p���ƗⓀ�̕��H�������Ə،����Ă���B�܂����̓��̗[�H�́A�R�[�g�j�[�E�z�C�b�g�j�[�ɂ��r�[�t�X�e�[�L�ł���A�z�C�b�g�j�[�̓}�b�J�[�T�[�̗����ɓł������Ă��Ȃ����S�z���A�m�F�������Ɛ\���o��ƁA�}�b�J�[�T�[�́u�N���i���ɂ͐������Ȃ���v�ƌ����č\�킸���t�����B���̓��̋L���̓}�b�J�[�T�[���g�ɂ͂Ȃ������悤�ŁA���̃z�C�b�g�j�[�̋L�������g�̉�z�^�Ɉ��p���Ă���B�@ |
���}�b�J�[�T�[�����t�X�|�[�c���Z��
���̎��Ɖƒr�c���O���X�|�[�c�ɂ����{�̕����Ɋ�^���悤�ƁA�S���K�͂ł̃X�|�[�c���̊J�Â��v�悵���B�r�c�̓}�b�J�[�T�[���h�����Ă������Ƃ���A�����w�}�b�J�[�T�[�����t���Z�x�Ƃ��邱�Ƃ�]�݁A�m�l�̃A�����J�l���ƉƃE�B���A���E�������E���H�[���Y��ʂ��}�b�J�[�T�[�Ɩʉ��@��āA����ō쐬�������̃J�b�v�����Q�����Z��J�Âk���������ʁA�}�b�J�[�T�[�����J�Âƃ}�b�J�[�T�[�̖��O����Ƃ��邱�Ƃ������ꂽ�B
���̎�ڂ́A�r�c�Ƃ̊W���[��������e�j�X�A�d���e�j�X�A�싅��3��ڂƂȂ����B�r�c�͎�������100���~�̎����ƁA�}�b�J�[�T�[�̃T�C�������3�̋�J�b�v�������������A�w�}�b�J�[�T�[�����t�x�Ɗ����������Ă��AGHQ�͉^�c�ʂł̎x���͂����A1948�N8���J�Â̑���̐��{���̉^�c��24���~�̓�20���~�͒r�c����̎x���A�c��͑������Řd��ꂽ�B
�����̓��{�ł́AGHQ�ɂ��S�̓I�s�i�A�@���I�s���A���Ɛď��A�����̌f�g�Ȃǂ��֎~����Ă���A���s�ŊJ�Â��ꂽ��1���̈���̊J��͉��y���Ȃ��A�I��鐾�ƊW�҈��A�̎��f�Ȃ��̂ł��������A�}�����t�͓��ʂɓ���s�i��������A�A�����J�R�̌R�y���ɂ�鉉�t�A�}�b�J�[�T�[�A������b�A������b(��������㗝)�ɂ��j�����A�s��Ԃ��Ȃ������Ƃ��ẮA�X�|�[�c���炵����ʈ�࣍��ȊJ��ƂȂ����B���Z��ɂ͒j�q271�����q120�����v391�����Q��������ɍs��ꂽ�B�D���҂ɂ͋�J�b�v�̑��Ƀ}�b�J�[�T�[�̉��炪���ꂽ���_���Ə�����^���ꂽ�B
�}�b�J�[�T�[�����ڋ��������ł��������߂��A��2��ڂ̓������͓��ʂɍc�����ŊJ�Â��ꂽ�B�����2016�N���_�ōc�����ōs��ꂽ�B��̑S���K�͂̃X�|�[�c���ƂȂ�B���̌�͑����哱���Ă������{�̈狦��̐s�͂�����A��6��̒�����܂Ŋe�n���s�s�ŊJ�Â���A�n���s�s�ł̃X�|�[�c�U���ɍv�����邱�ƂƂȂ����B�������A�}�b�J�[�T�[���X�R����A���{�l��12�Δ����œ��{�ł̐l�C����������ƁA�w�}�b�J�[�T�[�����t�x�Ƃ����������������Ƃ����������n�܂�A��7�R���ł́w�}�b�J�[�T�[�L�O�t�S���s�s�R�x�Ƃ������ɉ��́A��9����̊J�Òn��Îᏼ�s����́u�}�����t�v�Ƃ������O�͍���Ƃ̐\���o������Ɏ���A1955�N�̑�9��̉�Îᏼ�s�ł̑��́w�S���s����t�x�ƃ}�b�J�[�T�[�̖��O����ؔr�������ɉ��̂���A�w�}�b�J�[�T�[�����t�x��8�N�Ŗ������낷���ƂȂ����B���̌�����̑��͌`���▼�̂�ς��Ō�́w�S���s�s�R�O���Z���x�Ƃ������̂ƂȂ�A1975�N�̑�30����(�����s)�܂Ōp�����ꂽ�B���̌�A�d���e�j�X�̑S�����݂̂��A��1976�N����J�n���ꂽ�S���{�s�s�R�e�j�X���Ɉ����p����Ă���B�@ |
���R��
�}�b�J�[�T�[�͏����Ȃ���A�����̌R���𒅗p���邱�Ƃ����Ȃ��A�������D�B��ꎟ���E���Ń��C���{�[�t�c�̎Q�d���Ƃ��ď]�R�����ۂɂ̓w�����b�g����炸�킴�ƌ`��������R�X�A�������^�[�g���l�b�N�̃Z�[�^�[�A�ꃁ�A���[���҂�2�������钷���}�t���[�𒅗p���A�����s�J�s�J�ɖ����Ă������̂���u�[�c�𗚂��āA��ɂ͏�n�ڂƂ����J�W���A���Ȋ��D�����Ă����B�����̃��C���{�[�t�c�̕��m����}�b�J�[�T�[�ɕ���ă��t�ȕ��������Ă������߁A���������@�����h���R���i�ߊ��̃p�[�V���O�́u���̎t�c�͒p���炵���A���m��̋K���͕s�\���ł��P���͕s�K�ŁA�����͍��܂Ō������ōŒႾ�v�Ǝt�c���ł͂Ȃ��A�����ƂȂ����}�b�J�[�T�[�����������ӂ������A�}�b�J�[�T�[�������̃X�^�C����ς��邱�Ƃ͂Ȃ������B
�������A���̕��ς��ȕ������댯�����������Ƃ�����A�O���Ŏw���ׂ̈ɒn�}���L���Ă����}�b�J�[�T�[�������A�����J�R�̑��̕����̕��m�炪�A���i������Ȃ��i�D�����Ă���}�b�J�[�T�[���h�C�c�R���Z�Ɗ��Ⴂ���A�e��˂��t���ߗ��Ƃ������Ƃ��������B
�����ƂȂ��Ă��A�d�v�ȉ��A�������n�ʂ������҂Ɠ��Ȃ���ꍇ�ł������ŗՂނ��Ƃ������������߂ɁA�ᔻ���ꂽ���Ƃ�����B�E�̓V�c�Ƃ̉�ʐ^�ł��A�Ă̗����Ƀm�[�l�N�^�C�Ƃ������t�Ȋi�D�ŗՂ��߁A�u����������v�u���R����ԓx�v�ł���Ƒ����̓��{�����ɏՌ���^�����B�s�h�ƍl���������Ȃ́A���̎ʐ^���f�ڂ��ꂽ�V����������悤�Ǝ��݂����AGHQ�ɂ���Đ��~���ꂽ���߁A���̎ʐ^�͓����Ȃɂ�錾�_�����̏I�����ؖ����邱�ƂɂȂ����B�������A�����̃A�����J��g�قɂ͗�[�ݔ����Ȃ��������Ƃ�����A�Ă̏���������邽�߂Ƀ}�b�J�[�T�[�͈Ӑ}���������Ō}�����Ƃ������Ă���B
���{����́A���`���[�h�E�j�N�\���̉�z�ɂ����āA�}�b�J�[�T�[�̗����R���͔ނ̊�s���K�����������̂ŁA1950�N�ɒ��N�푈���ʼn�����g���[�}���́A�ނ̃T���O���X�A�V���c�̃{�^�����O���A�����[�����炬��̖X�q�Ƃ����u19��������̒��тƓ����i�D�v�ɕ��S�����Əq�ׂĂ���B�܂��A�}�b�J�[�T�[�̕����ƃX�^�C���ɂ͈��́u�_���f�B�Y���v�Ƃ�������Ɠ��Ȑ���������A�u�V�c�̑O�ł̃X�^�C���͂����̂��̂ł��͂邩�ɂ܂��Ȃ��̂ł������v�Ƃ��w�E���Ă���B�j�N�\������z����u�T���O���X�A�F���ČR���A�J�W���A���ȖX�q�A�����ăR�[���p�C�v�v�Ƃ�������E��풆�̃}�b�J�[�T�[�̃X�^�C���́A�܂��Ɍ��ؔ�s��ɍ~�藧�������̔ނ̎p�ł������B�@ |
���R�[���p�C�v
�}�b�J�[�T�[�̃g���[�h�}�[�N�ƌ����R�[���p�C�v�ł��邪�A1911�N�Ƀe�L�T�X�B�ōs��ꂽ���K�̍ۂ̎ʐ^�ŁA���Ɉ��p���Ă���̂��m�F�ł���B�}�b�J�[�T�[�̃R�[���p�C�v�̓R�[���p�C�v���C�J�[�ő��̃~�Y�[���E���V������(�p���)�̓����ł���A�펞���ɂ��ւ�炸�A�}�b�J�[�T�[�����Ђ̃R�[���p�C�v�����킦���ʐ^���A���Ђ́w���C�t�x���̍L���Ɏg�p����Ă���B
�K�����オ��ɏ]���ăR�[���p�C�v���傫���Ȃ��Ă����A�^�o�R�t�����{�������l�߂���悤�ɐ[���Ȃ��Ă���B���݂ł͂��̂悤�Ȍ`�̃R�[���p�C�v���u�}�b�J�[�T�[�^�C�v�v�ƌĂԁB�}�b�J�[�T�[�͎����̃p�C�v�����ʂ��邽�߂ɁA�����̐^��������y���Ă��ďł��ڂ����Ĉ�Ƃ����B���݂̃}�b�J�[�T�[�^�C�v�̃R�[���p�C�v���A�@�\�ɂ͊W�Ȃ����A���̈���Ĕ̔�����Ă���B
�������A�}�b�J�[�T�[�̒ʖW���[�W�E�L�U�L�ɂ��A�}�b�J�[�T�[�͎����ł̓R�[���p�C�v�͈�؎g�킸�A�u���C����V�����̍����f�ނ̃p�C�v�����p���Ă���A���O�ł͂킴�Ƒe��ɉf��R�[���p�C�v������A�R�l�Ƃ��Ă̍r�X���������o���Ă����Ə،����Ă���B1948�N�́w���C�t�x���̕ł́A�����}�b�J�[�T�[���g�p���Ă���17�{�̃p�C�v�̓��ŃR�[���E�p�C�v�͂킸��5�{�ł������B
�}�b�J�[�T�[�L�O�قɂ̓}�b�J�[�T�[�����p�����u���C���p�C�v�ƃp�C�v���Ă��W������Ă���A�ޔC��Ɏ��l�Ƃ��āw���C�t�x���̕\���ɓo�ꂵ���ۂɂ���点�Ă����̂��u���C���p�C�v�ł������B�@ |
�����{�L���X�g������
�}�b�J�[�T�[�́A���Ɛ_�����V�c���̏@���I��b�ł���A���{�������������Ă������̂Ƃ��āASCAPIN-448�u���Ɛ_���A�_�А_���j�X�����{�m�ۏA�x���A�ۑS�A�ē��j�O�z�m�p�~�j�փX�����v(�_���w��)�Ŕp�~�𖽂����B�_�������Ƃ��番�����A���̐����I�����ɏI�~����łƂ��Ƃ���Ӑ}�Ɋ�Â��w�߂ł������B����Ń}�b�J�[�T�[�̓L���X�g��������̔M�S�ȐM�k�ł���A�L���X�g���́u�A�����J�̉ƒ�̍ł����x�ȋ��{�Ɠ��f������́v�ł���A�u�ɓ��ɂ����Ă͂܂��ア�L���X�g���������ł���A�����Ƃ��������̒x�ꂽ�l�X���A�l�Ԃ̑����A�l���̖ړI�Ƃ����V�����l����g�ɕt���A�������_�͂����悤�ɂȂ�v�ƍl���Ă����B
���̂悤�ȍl���̃}�b�J�[�T�[�ɂƂ��āA���{��̂́u�A�W�A�̐l�X�ɃL���X�g�����L�߂�̂ɁA�L���X�g���a�ȗ��́A��ނȂ��@��v�Ɖf��A�A�����J�c��Ɂu���{���������@�����A�����m�̕��a�̂��߂̋��͂Ȗh�g��ɂ���v�ƕ��Ă���B���{�̎����ō����͎҂��A���̂悤�ɓ���̏@���Ɍ����ꂷ��̂́A�}�b�J�[�T�[���g�����i���Ă����M���̎��R�Ƃ���������Ƃ����w�E���A�L���X�g���W�҂̕���������邱�ƂƂȂ������A�}�b�J�[�T�[��CIE�̏@���ۋǒ���ʂ��u����̏@����M���e������Ă���̂łȂ�����A��̌R�̓L���X�g�����L�߂邠���錠����L����v�ƕԓ����Ă���B
�}�b�J�[�T�[�͂��̌��͂��L���X�g���z�����S�O�Ȃ��s�g���A�����̓��{�͊O���̖��Ԑl�̓������������������Ă������A�}�b�J�[�T�[�̖��߂ɂ��L���X�g���̐鋳�t�ɂ��Ă͂��̐������Ə����ꂽ�B���̐���1951�N�Ƀ}�b�J�[�T�[���X�R�����܂ł�2,500���ɂ��Ȃ�A�鋳�t��̓A�����J�R�̌R�p�@��R�p��Ԃňړ����A�ČR�h�ɂ����_�ɕz���������s���ȂǕX���^����ꂽ�B�܂��|�P�b�g�����A���ɗv�����āA���{���̐�����1,000��������{�Ŗ����z�z���Ă���B
1947�N7���ɓ��{�Љ�}�̕ЎR�N����ǂƂ���ЎR���t�������������A�ЎR�̓N���X�`�����ł���A�}�b�J�[�T�[�̓N���X�`�����ЎR�̑�����b�A�C����сu���Ⓦ�m�̎O�勭���ɃL���X�g���k�o�g�̎A�����̏Ӊ�A�t�B���s���̃}�j���G���E���n�X�A���{�̕ЎR�N���a�����Ă��Ƃ͍L�����ۓI�Ȋϓ_���猩�Ă��Ӌ`���[���B����͐��Ȃ鋳�����m���ɍL�܂��Ă���ł���E�E�E����͐l�ނ̐i���ł���B�v�ƒf�����A�ЎR���t�������j���������A�}�b�J�[�T�[�̊��҂����A�ЎR���t�͂킸��9�����Ŋ��������B
�}�b�J�[�T�[�͎������g���u���[�}�@���ƍ������E�̃L���X�g�����\������w���ҁv�Ƌ���A�S�ăL���X�g�����c����}�b�J�[�T�[�ɑ��u�ɓ��̋~�ς̂��߂ɐ_�́g����̑���h�Ƃ��āA���Ȃ��������������̂��ƁA��X�͐M����B�v�Ə^���Ă������A�}�b�J�[�T�[���A�z���̐��ʂ��m�F����ׂɁACIE�̏@���ۂɓ��{�̃L���X�g���k���̒����𖽂����Ƃ���A��O��20���l�̐M�҂������̂ɑ��A���݂͋t�ɐ��������Ă���Ƃ������Ƃ��������A���̒������ʂ����@���ۋǒ��́u���i�߂͂��̕ɖ������Ȃ����A�{�邾�낤�v�Ɠ�������邱�ƂɂȂ����B�}�b�J�[�T�[��̓t�B���s���ƃC���h�V�i�ȊO�̃A�W�A�l�́A�����A�L���X�g���ɖw�ǖ��S�ŁA��ʂɔz�z���ꂽ�����̑������A�ǂ܂�邱�Ƃ��Ȃ��A���݃^�o�R�̊����ɗ��p����Ă���̂�m��Ȃ������B
�ǒ����璲������˂��Ԃ��ꂽ�@���ۂ̏��Z��́A�}�b�J�[�T�[�������邽�߂ɂ�0���������������Ɠ��c��������A���̍������Ȃ�200���l�Ƃ����L���X�g���k����s�����ĕ����B�}�b�J�[�T�[�����̐������L�ۂ݂ɂ��āA1947�N2���A���R�ȂɁu�ߋ��̐M�̕���ɂ���ē��{�l�̐����ɐ��������_�I�^�������i�Ƃ��āE�E�E�L���X�g����M����悤�ɂȂ������{�l�̐��͂܂��܂������A����200���l�����̂Ɛ��肳���̂ł���B�v�ƕ��Ă���B���ǁA�}�b�J�[�T�[�����{��������1951�N���_�ŃL���X�g���k�́A�J�g���b�N�A�v���e�X�^���g��25��7,000�l�ƁA��O��20���l�Ɣ�r�������������A��̉��ɒ����ꂽ�c��Ȏ����ƁA�����鋳�t�̓w�͂��l����ƁA�\���Ȑ��ʂƂ͌����Ȃ������B�u��̌R�̏@���v�ƊŘ�A���̏@���ɔ�ׂĈ��|�I�ɗL���ȗ���ɂ������ɂ��S�炸�A�}�b�J�[�T�[�̗��z�Ƃ����u���{�̃L���X�g�������v�͎��s�ɏI������B�@ |
�����ۊ����w
�L���X�g���̐��_�Ɋ�Â��A�@�h���z������w�����Ƃ������\�z�������t�E�f�B�b�t�F���h���t�@�[�鋳�t�𒆐S�ɐi��ł���A�u���ۊ����w ���c�v��1948�N�ɐݗ����ꂽ���A�}�b�J�[�T�[�͂��̓����Ɉ���Ȃ�ʊS�������A����w�̍��c�ɂ����閼�_��������������ƁA�č��ł̕���^���ɐs�͂����B�W�����E���b�N�t�F���[2���ɂ��x�������߂����A���̍ۂɁu�����ɒ�Ă���Ă����w�́A�L���X�g���Ƌ���̃��j�[�N�Ȍ������炵�āA���{�̏����ɂƂ��Ă܂��Ƃɏd�v�Ȗ�����K����ʂ������Ƃł���܂��傤�B�v�ƔM�ӂ̂��������莆���o���Ă���B��w���J�w�ƂȂ����̂̓}�b�J�[�T�[����C�����2�N���1953�N�ł������B�@ |
�����̑�
1946�N�ɓ�����K�ꂽ�n�[�o�[�g�E�t�[���@�[���A�u�t�����N�����E���[�Y�x���g�̓h�C�c�Ɛ푈���s�����߂ɓ��{��푈�Ɉ������荞�v�Əq�ׂ����Ƃ��A�}�b�J�[�T�[�́A�u���[�Y�x���g��1941�N�ɋ߉q�������͍��������Ď�]��k�������Ȃ��Đ푈���������w�͂����ׂ��ł������v�Ƃ����|���q�ׂĂ���B
��̓����̃}�b�J�[�T�[�̓t���[���C�\���̃t�B���s���E�O�����h���b�W (Manila Lodge No.1) �ɏ������Ă���A32�ʊK�̒n�ʂɂ������Ƃ����B�@ |
 |
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
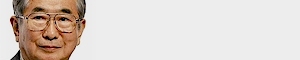 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@

 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@

 �@
�@



 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@