



「美しい国」の悪夢





神体山とは主に神道において神が宿るとされる山岳信仰や神奈備(かむなび・神々が神留まる森林を抱く山)の山をいう。






降り積もる 御雪に耐えて 色変えぬ 松ぞ雄雄しき 人も斯く在れ





















安倍総理の自己満足
安倍政権 政治の優先順位を誤る
時間の無駄遣い 法律できても 税金は増えません
景気・経済とは無縁



「真の経済政策」が急務
日本は就労人口の減少期に入りました GDP600兆円 夢のまた夢
国民一人当りの生産性 世界の中位以下
働く人が減れば GDPも低下します
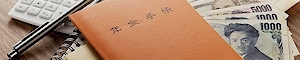


バラマキ 散財政治
経済拡大は望めないのに 国の借金は増加の一途 異常 奇妙
「財政健全化」お題目 神棚の裏に仕舞い込みました
安倍総理 お役人 忘れたふり 知らんぷり 後は野となれ山となれ



神民です
将来の安寧の絵があれば 目先の苦労を厭いません
「真の経済政策」のお札 神棚の正面に捧げましょう



時間がありません








