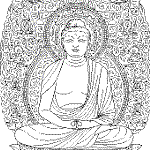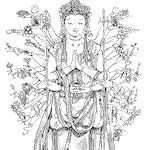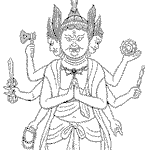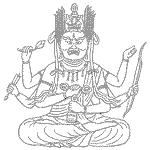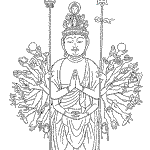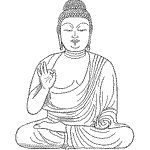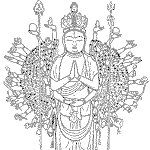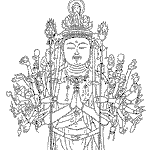
自然の法則に 逆らえば
文殊菩薩も 神の御叱りを受けます

文科省
ノーヘル賞もの 自然の法則にチャレンジ失敗
お役人の面子料 一兆円
お昼寝つづき 国民の税金で放置してきました

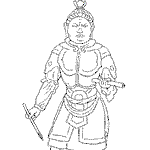

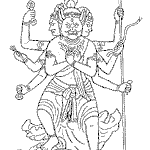
福島原発 凍土壁
太陽エネルギーにチャレンジ
( 温暖化か ロシアの永久凍土域 融けて縮小中 )

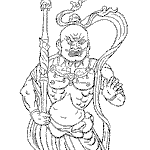

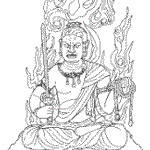
原発 既に御叱りを受けています
始まる廃炉 40-60年 コスト全て電気代に上乗せ
全国民 平伏すしかありません
電力会社 気楽な稼業です

原発導入時の売り 「安い電力供給」 ( 廃炉コストには忘れたふり )
おまけは 地球温暖化防止の一助
廃炉コストと 化石燃料の温暖化防止・付加装置コストを 比較検証してみませんか

政府は二十一日、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)について関係閣僚会議を開き、「廃炉を含め抜本的な見直しをする」とした。一方で核燃料サイクルは維持し、新設の「高速炉開発会議」で、年末までに今後の方針を出す。もんじゅにはこれまで国費一兆円以上をつぎこんだ。再稼働には数千億円の追加費用が必要。成果を得られないまま幕引きとなる。
菅義偉官房長官は閣僚会議で「高速炉開発は、原発の新基準の策定など大きな情勢変化がある。本年中に、高速炉開発会議で、廃炉を含めて抜本的な見直しを行う」と述べた。
核燃料サイクルは、原発の使用済み燃料からプルトニウムを取り出し、再利用する。プルトニウムを燃やすもんじゅはサイクルの柱だ。もんじゅに代わるものとして、フランスとの共同開発や、実験炉「常陽」(茨城県大洗町、停止中)の再稼働が検討される。
廃炉も容易ではない。もんじゅを運営する日本原子力研究開発機構の試算によると、三十年の期間と三千億円の費用がかかる。地元の福井県には、松野博一文部科学相が陳謝し、直接出向いて事情を説明した。
もんじゅは、消費した以上の燃料を生み出す「夢の原子炉」とされた。半面、危険なナトリウムを冷却材に用いる必要があり、構造も複雑。一九九四年に本格稼働したものの九五年にナトリウム漏れ事故を起こして停止した。その後もトラブルが相次ぎ、稼働日数は二百五十日にとどまる。停止状態でも一日あたり約五千万円の維持費が必要だ。
原子力規制委員会は昨年十一月、約一万点の機器点検漏れなどを受け、所管する文部科学省に新しい運営組織を示すよう勧告した。運営主体は、動力炉・核燃料開発事業団に始まり、すでに二回変更されている。文科省は新しい受け皿を探したが、電力会社は難色を示し、引き受け手はなかった。
●核燃、既に12兆円 本紙調べ
高速増殖原型炉「もんじゅ」を中心とした核燃料サイクルには、少なくとも十二兆円以上が費やされてきたことが本紙の調べで判明している。施設の維持・運営費で年間約千六百億円が新たにかかる。
本紙は一九六六年度から二〇一五年度までのもんじゅや再処理工場、取り出したプルトニウムを再利用する混合酸化物(MOX)燃料工場、高レベル廃棄物の管理施設の建設費や運営費、必要になる廃炉・解体費などを積算した。立地自治体への交付金も足しているが、通常の原発向けと判別が難しい場合は、全額を除外している。
その結果、判明しただけで総額は計約十二兆二千二百七十七億円。主なものでは、もんじゅは関連施設なども含めると約一兆二千億円。青森県六ケ所村にある再処理工場はトラブル続きで稼働していないが、七兆三千億円かかった。
核燃サイクルのコストを巡っては、電力会社などでつくる電気事業連合会が〇三年、建設から最終処分までの総額は約十九兆円と試算している。
<もんじゅと核燃料サイクル> 普通の原発は、主な燃料に「燃えるウラン」を使う。それに中性子をぶつけて、核分裂の連鎖反応を起こし、生じた熱を取り出し、タービンを回して発電する。
もんじゅでは、主な燃料がプルトニウム。中性子を高速でぶつけ、燃料周囲に置いた「燃えないウラン」をプルトニウムに変える。燃料が増えるので、「高速増殖炉」の名がある。
中性子を減速させないよう、炉内は水ではなく、高温の液体金属(ナトリウム)で満たされている。ナトリウムは水などと激しく反応し危険だ。
核燃料サイクルは、原発で燃やした使用済み燃料からプルトニウムを取り出し、もう一度高速炉で燃やそうという試み。青森県六ケ所村に、巨費を投じて再処理工場が建設されている。だが高速炉がいつまでもできないので、普通の原発にプルトニウムを含む燃料を装填(そうてん)する「プルサーマル」が行われている。
日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)について、政府の原子力関係閣僚会議は、廃炉を前提に抜本的に見直すことを決めた。関係自治体と協議の上、年内に最終決定する。
もんじゅには1兆円を超す国費が投入されたが、相次ぐ事故や不祥事で、この20年間余り、ほとんど稼働していない。再稼働には数千億円規模の追加投資が必要だという。それでも、成果が見通せない施設である。廃炉は当然だ。これまで決断を先送りしてきた政府の責任も、厳しく問われなければならない。
●決断遅れた政府に責任
原発の使用済み核燃料を再処理し、抽出したプルトニウムをウランと混ぜた混合酸化物(MOX)燃料に加工して、原発で再び燃やす。これが核燃料サイクルで、日本は国策としてきた。消費した以上のプルトニウムを生み出す高速増殖炉は、使用済み核燃料の再処理工場とともに、サイクルの中核施設となる。
閣僚会議の決定で首をひねらざるを得ないのは、もんじゅを廃炉にするにもかかわらず、核燃料サイクル政策や高速炉の研究開発は維持する方針を示していることだ。
核燃料サイクルの実現には、技術面や経済性、安全保障の観点からいくつもの課題がある。青森県六ケ所村に建設中の再処理工場も、トラブルなどで完成時期の延期を繰り返してきた。そこで目くらましとして中核施設のもんじゅを廃炉にし、破綻しているサイクル政策の延命を図るのが本当の狙いではないのか。
政府は、核燃料サイクルで取り出したプルトニウムは準国産エネルギーで、エネルギー安全保障に資するという。だが、サイクルを維持することは、エネルギー政策で原発に依存し続けることを意味する。
東京電力福島第1原発事故の教訓の一つが、地震国日本で原発に依存するリスクは高いということだ。いずれ、やめる必要がある。政府はもんじゅ廃炉を機に、核燃料サイクル政策の幕引きに踏み切るべきだ。
もんじゅは、原子炉の熱を取り出す冷却材に、空気や水に触れると燃える性質を持つ液体ナトリウムを使う。水を冷却材に使う通常の原発に比べ、高度な技術が必要だ。1995年12月にナトリウム漏れ事故を起こして停止して以来、ほとんど稼働していない。維持管理費だけで年間約200億円かかっている。
多数の機器点検漏れなど安全管理上の不備が相次ぎ、原子力規制委員会は昨年11月、所管の文部科学省に運営主体の変更を勧告していた。
文科省は、電力会社など民間の協力を得て新法人をつくる案を模索した。しかし、電力自由化で競争環境が厳しさを増す中、電力会社に運営主体となる選択肢はなかった。
再稼働には、規制委の新規制基準にも合格しなければならない。政府の試算では、耐震補強工事などで約5800億円が必要となる。追加費用の多額さも、廃炉論を加速した。
もんじゅ廃炉後の焦点は、再処理で抽出したプルトニウムをどのように消費するかだ。英仏に委託した使用済み核燃料の再処理などで、日本は既に国内外で約48トンの余剰プルトニウムを抱える。テロや核兵器への転用の懸念を解消するため、政府は「余剰プルトニウムは持たない」と国際社会に繰り返し訴えてきた。
●安全保障上の懸念も
電力会社でつくる電気事業連合会はMOX燃料を通常の原発で使う計画を立て、全国で16〜18基の原発に導入する予定だったが、福島第1原発事故の影響で崩れた。国内で稼働中の原発でMOX燃料を使っているのは、現時点で四国電力伊方原発3号機(愛媛県)だけだ。プルトニウムの消費は進んでいない。
政府は、フランスが建設予定の新型高速炉計画「ASTRID(アストリッド)」での共同研究などにより、高速炉の研究開発に引き続き取り組むという。だが、ASTRIDが順調に進む保証はない。
そもそも、福島第1原発事故後に政府の原子力委員会が実施した核燃料サイクル政策の評価によれば、経済面からは、使用済み核燃料を再処理するより、直接処分する方が有利との結果が出ている。
非核保有国の日本が再処理できるのは、88年に発効した日米原子力協定で認められているからだ。協定は2年後に改定時期を迎える。11月の米大統領選で選ばれる新政権がどう対応するかは分からない。
国内の政治家や外交当局には、将来の核保有を選択肢として残しておくべきだという意見もあるが、日本が核保有を選択すれば、世界から孤立する。現実的議論ではない。
核燃料サイクルを見直す上で、最大の課題は、関連施設を受け入れてきた地元への対応だろう。
もんじゅの関係自治体は、存続を要望している。再処理工場が立地する青森県は、核燃料サイクルを前提に、工場への使用済み核燃料受け入れを了承してきた。サイクル断念となれば、青森県は核のごみ捨て場になりかねない。電力会社も容易には使用済み燃料を引き取れない。
政府は、核燃料サイクルの継続にこだわるよりも、こうした問題の解決策にこそ知恵を絞るべきだ。

政府の原子力関係閣僚会議は9月21日、高速増殖炉「もんじゅ」について「本年中に廃炉を含めて抜本的見直しを行なう」との方針を決定した。しかし、「核燃料サイクル」の推進と「高速炉」の研究開発の計画は維持するのだという。
おかしな話だ。核燃サイクルの中心的コンセプトは、使用済み核燃料を再処理して取り出したプルトニウムを燃料にして高速増殖炉で発電を行ない、消費した以上のプルトニウムを生産することであり、「準国産エネルギー」と言われたゆえんだ。増殖しない高速炉(高速の中性子による核分裂反応が起きることからそう呼ばれる)でプルトニウムを燃やすだけでよいとするのは政策的位置付けの本質的変更に当たり、しかも、新炉を国内に設置する現実的なあてはないに等しい。
他方、プルトニウムをウランと混ぜて普通の原発で燃やす「プルサーマル」も、現状国内だけでプロセスが回らないのに加え、プルトニウムの消費量は限られる。プルトニウム増殖を断念し、消費を目的に据えても、余剰プルトニウム問題は解決できず、プルトニウム抽出・利用政策の破綻は隠しようがない。核燃サイクルの看板を掲げ続ける意味など、もう失われているのだ。
もんじゅをめぐってはこの間、「運転継続には10年間で6000億円必要」との情報がリークされるとともに、田中規制委員長も既存施設では新規制基準の適合性審査に合格する見通しはないとの認識を示すなど、廃炉に向けた包囲網は明らかに狭まりつつあった。だが、年末までに廃炉が決まりさえすれば、それでよいというわけではない。もともと規制委は昨年11月の対文科相勧告で、新たな運転主体の具体的特定が困難ならば「もんじゅが有する安全上のリスクを明確に減少させるよう」もんじゅのあり方を抜本的に見直すべきだとしており、もんじゅが現在抱えている危険性を低減する必要があるのだ。
ところが、新主体探しの迷走ぶりばかりが注目される中、安全確保の問題はなおざりにされた。だから原水禁や原子力資料情報室、原子力発電に反対する福井県民会議など6団体は9月7日、もんじゅの核燃料と冷却材ナトリウムを取り出し、別の安全なところに保管するよう命じることを、規制委に申し入れている。
六ヶ所再処理工場を含め核燃サイクルはきっぱり断念、放棄し、もんじゅの安全な廃炉プロセスに入る。これが最も合理的政策だ。
自民党行政改革推進本部(本部長・河野太郎前行革担当相)は十三日、二〇一七年度予算編成に向け、文部科学省や経済産業省が要求している原子力関係予算の無駄を洗い出す会合を開いた。文科省は高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)に関し、存廃にかかわらず、新規制基準に対応する準備費五十億円の要求を取り下げない方針を示した。行革本部側は「廃炉はほぼ決まっており、不必要だ」と見直しを求めた。
政府は九月、もんじゅに関し、廃炉を含め抜本的に見直す方針を決定。新設の高速炉開発会議が、もんじゅの最終的な扱いやもんじゅに代わる高速炉開発方針の検討を始めており、年末までに結論を出す。文科省は八月、一七年度予算の概算要求で、もんじゅの新規制基準策定に備え、地震や津波、噴火に対する安全性を解析・評価する費用五十億円を計上していた。
文科省の担当者は行革本部の会合で「得られるデータは廃炉になった場合も有効だ」と述べ、仮に廃炉が決まった場合でも五十億円の要求を見直さない姿勢を示した。これに対し、秋本真利本部長補佐は「項目だけ要求し、本当に必要になったら補正予算で要求すればよい」と批判した。
会合では、使用済み核燃料運搬船「開栄丸」の本年度の関連経費六億円が支出できずにいる問題も取り上げた。文科省の担当者は「事業主体の日本原子力研究開発機構と船を所有する運送会社『原燃輸送』との協議が整っていない。早期に協議を終了できるように調整したい」と説明した。
核燃料サイクル推進は「堅持」 科学技術
政府は9月21日開いた原子力関係閣僚会議で、日本原子力研究開発機構が運営する高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)に代わる新たな高速炉の研究開発方針を、年内に策定することを決めた。新方針が決まり次第、もんじゅの廃炉を正式決定する。核燃料サイクル推進の政府方針は堅持し、新方針は経済産業相を中心とした官民の「高速炉開発会議」を設置して検討を進める。
国内の大手メディアによると、新方針を巡る議論はフランスが計画している新型高速炉「ASTRID(アストリッド)」の共同研究を軸に進む見通しという。もんじゅはこれまで1兆円を超える巨費が投入されたが、トラブル続きでほとんど稼働しなかった。廃炉は日本のエネルギー政策の転換点とも位置付けられる。
●事故・トラブル相次ぎ、22年間で運転わずか250日
核燃料サイクルでは、原子力発電所の使用済み核燃料を再処理し、取り出したウランやプルトニウムを再び原発の燃料として利用することを想定。発電しながら消費量以上の燃料(プルトニウム)を生み出す高速増殖炉は政府の核燃料サイクル政策の中核施設で、「夢の原子炉」と呼ばれて1960年代から研究開発が推進された。
もんじゅは実験炉「常陽」(1970年着工、77年臨界、現在停止中)に続く第2段階の「原型炉」で、1980年に着工。研究開発が順調なら、第3段階の「実証炉」、第4段階の「実用炉」と進むはずだった。
もんじゅは95年8月に発電を開始したが、わずか4カ月で冷却材のナトリウム漏れ事故が発生。2010年には14年ぶりに運転再開にこぎ着けたものの、再度の事故で運転を停止した。その後もトラブルが相次ぎ、これまでの運転実績は22年間でわずか250日にとどまっている。
●耐震補強に膨大なコスト、存続は困難に
今回「廃炉もやむなし」と決まった背景には、2つの大きな要因がある。安全管理の組織的な不備と、存続させた場合には膨大なコストがかかることだ。
もんじゅでは2012年、保安規定に基づく機器の点検漏れが9679個もあったことが発覚。13年に原子力規制委員会が施設を立ち入り検査したところ、安全上最も重要とされる機器について、さらなる点検漏れがあったことが確認された。14年には、施設内の監視カメラが50台以上も故障したまま放置されていたことも判明。規制委は15年11月、運営主体の変更を文部科学省に勧告したが、同省は具体策を打ち出せなかった。
また、東日本大震災(2011年3月)の東京電力福島第1原発事故を踏まえた新規制基準が導入された結果、もんじゅ再稼働には耐震補強など大幅な改修工事が必要となった。政府の試算では約5800億円の追加費用が必要で、再稼働までには10年はかかる。施設の維持費だけでも年200億円が必要で、政府・与党内では廃炉を求める声が高まっていた。
敦賀市の区長連合会や漁業協同組合などでつくる市原子力発電所懇談会の百十三回会合が十八日、同市の敦賀美方消防組合消防本部講堂であった。政府が廃炉を含めた抜本的な見直しを決めた高速増殖原型炉もんじゅを巡り、所管の文部科学省に対して、委員から地元の意見を反映するよう求める声が上がった。
文科省の高谷浩樹研究開発戦略官は、地元説明が遅れたことを陳謝。政府の高速炉開発会議の初会合の概要を説明した。
質疑で、委員からはもんじゅの方針決定に対し「一方的に地元の説明なしになされ、大きな不信感を抱かざるを得ない」などと批判した。高谷戦略官が「(地元の意見を)高速炉開発会議に出る大臣にフィードバックしていく」と答えると、座長の渕上隆信市長は「高速炉開発会議は技術的な話。もんじゅの扱いは原子力関係閣僚会議で決める。地元の意見をどうやって吸い上げるのかをきちんと明示してほしい」と迫った。
このほか、委員を務める福井大付属国際原子力工学研究所の竹田敏一特任教授が、もんじゅの利活用について提案。実証炉に不可欠となる安全性のデータを取得できると主張。京大や名大の研究者へのヒアリングから、もんじゅに幅広い研究課題があることを示し、研究開発炉としての必要性を説いた。

事の正否は別にして、転んでもただでは起きないとはまさにこのことかと、いささか感心してしまう。
鳴かず飛ばずのありさまだった高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」(福井県)の廃炉がほぼ確定的になったと思ったら、国はまたも高速炉の開発に乗り出すという。
今月立ち上げた「高速炉開発会議」で年内に方針を決める予定だが、フランスとの共同研究や高速増殖炉の実験炉「常陽」(茨城県)の再活用という案が浮かんでいる。
「もんじゅ」は廃炉でも核燃料サイクル政策は堅持というのが国の考えだが、それがそもそも無理がある。無理を押し通そうとすれば原子力の在り方をさらにゆがめ、解決が迫られている課題を先延ばしにするだけだ。
「もんじゅ」に代わって唐突に浮上したのが、フランスが計画している「アストリッド(ASTRID)」と呼ばれる原子炉。資源エネルギー庁によれば、「放射性廃棄物の減容や有害度低減に向けた研究開発」のための実証炉で、2019年に建設するかどうか決まるという。
発電だけでなく放射性元素の分離や変換も目指すらしいが、技術的にはそう簡単でないはず。高いエネルギーの中性子を用いる「高速炉」になるが、「もんじゅ」のような核燃料の増殖は目的にしていないようだ。
実用化できたとしても原子炉だけでは役に立たない。専用の再処理工場や核燃料製造工場が必要になる可能性が高い。これまでとは別の核燃料サイクルになるわけだから、費用は膨大だろう。
新型高速炉の技術開発と言えば聞こえはいいが、全体のコストや必要性、本当に実現できるのかどうかを厳しく見極めないと、とんでもないことになりかねない。
本来であれば「もんじゅ」の廃炉と共に核燃料サイクル政策を断念すべきだった。それができない一因は、再処理工場などが集中立地する青森県との関わりにある。
核燃サイクル政策をやめれば、使用済み核燃料からプルトニウムを取り出す再処理工場の存在意義が宙に浮く。青森県はおそらく、全国の原発から運ばれた使用済み核燃料の搬出を求めるだろう。
そうなったら各原発は窮地に陥る。使用済み核燃料を敷地内に保管するしかないが、いずれ満杯になって運転継続が不可能になってしまう。
核燃サイクルは今や、原発の運転を可能にする方便のようになってしまった。それなのにまた、実現が不明確な核燃サイクルに乗り出すことなどあり得ない。
国民の側から見れば、原子力の最優先課題は核燃サイクルでも高速炉でもなく、福島第1原発事故の後始末だろう。気が遠くなるような費用と年月がかかる。新型原子炉にうつつを抜かしている場合ではないのだ。
原子力の未来をビジネスライクに考える
高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の廃炉が実質的に決まったのを受けて、10月7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。世耕弘成経済産業相は「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べ、従来の高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開発することを示唆した。
しかし現実に検討されているのは、フランスの開発している「ASTRID」と呼ばれる高速増殖炉だ。それをあえて「増殖炉」と呼ばないところに、原子力産業の窮状があらわれている。かつて「燃やせば燃やすほど燃料が増える夢のエネルギー」といわれた高速増殖炉の夢は幻に終わったのだ。
●高速増殖炉は死んだ
高速増殖炉とは「高速の中性子を使って燃料を増殖させる原子炉」という意味で、燃料にはウランを再処理してつくったプルトニウムを使う。FBRでウランに中性子を当てるとプルトニウムに変わり、プルトニウムが燃料より「増殖」するのが売り物だ。
この反応を起こすのに必要な「高速」の中性子を使う原子炉を広く「高速炉」と呼ぶ。普通の原子炉(軽水炉)と違う特徴は、原子炉を冷やすのに液体のナトリウムを使うことだが、ナトリウムは配管から漏れると、酸素や水と反応すると燃え上がる厄介な性質がある。
これは軽水炉で水が漏れるのと同じで、重大な事故に発展するおそれはないが、火災が起こるとマスコミが騒ぎ、地元が心配する。もんじゅも1995年にナトリウムが漏れて火災が発生し、その後も20年以上、止まったままだ。FBRで「増殖」するプルトニウムの効率は悪く、核燃料サイクルへの巨額の投資に見合わない。
原子力規制委員会もさじを投げ、「運営主体を変更すべきだ」と提言したが、今からもんじゅを引き受ける電力会社はなく、政府も否定的だ。こうして20年たってやっと撤退が決まったのだが、再処理工場はFBRでプルトニウムが増殖することを前提にして建設されたので、その挫折で核燃料サイクルは宙に浮いてしまった。
これは「ダイヤモンドをつくる工場」を前提にしてその関連施設を数兆円かけてつくったら、肝心のダイヤモンドがつくれなかったような話だ。本当にFBRが実用化できるのかどうか確認しないで、先に再処理工場をつくったのが失敗だった。
●ウランは9000年分ある
原子力の先進国であるフランスでも、「増殖」を目指したFBR「スーパーフェニックス」は断念した。その代わりに開発されているのが、使用済み核燃料からつくるMOX燃料(ウランとプルトニウムの混合燃料)を燃料にしてプルトニウムを効率的に使うASTRIDだ。
しかしASTRIDを本当に建設するかどうかはまだ決まっていない。フランス政府は2019年に判断するとしているが、実用化の見通しははっきりしない。その開発・建設にかかる巨額の経費の半分を日本に負担してほしいという打診もあったという。
もちろん原発をやめる必要はない。気候変動のリスクを考えると、化石燃料の消費をこれから増やすことには問題がある。軽水炉は安定した技術なので、安全施設を多重化すれば、火力発電よりリスクは小さい。
ただ核燃料サイクルを維持すべきかどうかは別の問題だ。仮にASTRIDが実用化しても、それはプルトニウムを再利用して長持ちさせるだけの技術だから、これはその再利用による節約のメリットが巨額の投資に見合うかという経済問題である。
根本的な疑問は、政府が核燃料サイクル計画の前提にしている天然ウランの埋蔵量が正しいのかということだ。
文部科学省の参照したOECDの推定によれば、在来型資源総量は1670万トンで、世界の需要の100年分以上ある。さらに非在来型ウランが2200万トンあり、合計すると図のように3870万トンで、少なくとも230年分ある。非在来型の価格は在来型より高いが、その85%以上はモロッコの燐灰土に場所が特定されているので採掘可能だ。
さらに海水ウランの資源量はほぼ無尽蔵(9000年分)であり、それを精製する膜技術は急速に進歩している。この分野では日本が最先進国で、在来型ウランの2倍まで価格は下がっている。これも技術や価格の不確実性はあるが、これから(もっと不確実な)核燃料サイクルに莫大な投資をするよりましだろう。
●「全量再処理」は危険なギャンブル
要するに核燃料サイクルは、安全性以前に不要になるリスクが大きいのだ。高速炉以外の(トリウム炉や進行波炉などの)技術ではプルトニウムは必要ないので、軍事転用できる危険物質を日本が生産する積極的な理由はない(核武装するとしても今ある量で十分)。
だからウランを全量再処理することは危険なギャンブルであり、なるべく多様なポートフォリオをもったほうがよい。軽水炉を更新すれば、あと50年はもつので、それまでに実用化のめどを立てれば十分だ。
では使用済み核燃料はどう処理するのか。それは多くの関係者が(密かに)合意しているように、現在の再処理工場のある青森県六ヶ所村に燃料棒のまま保管すればいい。そのコストは再処理するより8兆円ぐらい安く、テロリストが核兵器に転用することも不可能だ。
今でも青森県むつ市には中間貯蔵施設がある。ここに貯蔵されている使用済み核燃料は「乾式処理」と呼ばれる空冷の施設で、技術は確立している。これは学術会議などの反原発派が主張する「暫定保管」と同じで、六ヶ所村には300年分の使用済み核燃料を安全に保管できる土地がある。
だからビジネスライクに考えれば、答は1つしかない。全量再処理をやめ、六ヶ所村を中間貯蔵に転用できるように青森県との覚書を修正することだ。もちろん青森県にも六ヶ所村にも、新たな名目の交付金を出せばいい。迷惑施設に迷惑料を払うのは当たり前で、それ以外の解決法はない。
最後に残る問題は、今まで核燃料サイクルの開発に取り組んできた技術者の処遇だが、原子力工学の基礎知識は原子炉も再処理も同じだ。これからまたゴミ処理の技術を開発するより、第4世代の新しい原子炉技術に取り組むほうが、若者も集まるだろう。
重量あたりのエネルギーが石炭の300万倍もある原子力の可能性は大きく、まだ日本が世界のトップに立っている数少ない技術だ。今までイノベーションを妨げてきた国策民営の不透明な運営をやめ、ビル・ゲイツのような投資家の資金も募って民間ベースで基礎技術を開発し、実用化も電力会社に任せるガバナンスの改革が必要だ。

近く関係閣僚会議で正式決定
政府は19日、日本原子力研究開発機構の高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市)に代わる高速炉の方向性を議論する「高速炉開発会議」で、今後の開発方針案を示した。研究開発の継続に必要な知見は「もんじゅ再開によらない新たな方策によって獲得を図る」と明記し、廃炉の方針を明確にした。近く原子力関係閣僚会議で正式に決定する。
また、文部科学省は会議でもんじゅ廃止措置の行程表を示した。5年半で使用済み燃料を取り出し、30年で廃炉にする。施設の解体費や工事中の維持管理費などで総額約3750億円超のコストがかかるという。
高速炉開発会議には、世耕弘成経済産業相、松野博一文科相、電気事業連合会の勝野哲会長(中部電力社長)らが参加した。
世耕弘成経産相は、「高速炉開発会議の議論はこれで一区切り。今後はより技術的な具体論に議論を落とし込む」と述べた。
政府は核燃料サイクル政策の推進を堅持するとともに、もんじゅの代替高速炉の開発に向け、作業部会を設置。年明けから工程表の策定を始め、2018年をめどに取りまとめる。
フランスの実証炉「ASTRID(アストリッド)」との共同研究や、もんじゅの前段階の高速実験炉「常陽」(茨城県)などを活用し、原型炉であるもんじゅの次段階に位置する実証炉を国内に建設するとしている。
高速増殖炉もんじゅについて、政府はきょう、正式に廃炉にする方針を表明。その一方で高速炉開発と核燃料サイクルは続け、もんじゅの後継として実用化手前の実証炉の開発を目指す方針も。もんじゅをなくすのに、政策を見直すこともなく高速炉開発にこだわって、この先失敗を繰り返すことにならないのか。
政府の高速炉開発会議がまとめた開発案のポイントは
○ 高速炉は放射性廃棄物を減らせ、エネルギーも有効利用できることから意義がある
○ もんじゅがなくてもほかの設備で実証炉開発は可能で、2018年までに工程表を作成する。
あくまで高速炉開発にこだわり、核燃料サイクルを堅持するとしている。
もんじゅについては正式に廃炉にする方針を表明。しかし福井県知事は立地に協力してきたのに、地元への説明も不十分で拙速すぎるなどと反発。政府はあらためて協議の場を設けるものの、廃炉の方針自体は変えないという。
この一連の方針は多くの問題を抱えている。
日本は、原発の使用済み燃料を再処理工場に運んでプルトニウムを取り出し、もんじゅのようにプルトニウムを増やすことができる高速増殖炉で繰り返し使う「核燃料サイクル」を基本。しかし要となるもんじゅはトラブルが相次ぎ、ほとんど運転できなかった。もんじゅ廃炉は当然の流れで、プロジェクトとしては失敗に終わったと見るべき。
要がなくなるから、当然核燃料サイクル全体の見直しが必要。ところが見直すどころか、さらに先を目指すと言う。これは原発開発の大原則を破るもの。小型の実験炉で基本性能を確認、原型炉で安全性や発電能力を検証。さらにコスト的に見合うか確認する実証炉を経て、商業炉を建設する。政府はそのように説明してきた。もんじゅは原型炉だがフルパワーで運転したことはなく、日本として高速炉の安全性や発電性能を確認できたわけではない。今、その先の実証炉が可能とは言えないはず。
ただ政府は国内の実験炉やフランスの実証炉計画に参加することで、十分知見が得られるという。本当にそうなのか。このうち40年近く前日本で初めて運転を始めた実験炉「常陽」を取材。格納容器中央部の床下に原子炉。中にはプルトニウムの燃料と冷却材のナトリウム。周りの機器を含め、全体に古さは否めないが、手入れは行き届いている印象。これまでプルトニウムが増えるか、燃料の組成がどう変化するのかなど基礎的な研究。ただ出力はもんじゅの5分の1と小型で、発電設備がない。中でも発電に必要な蒸気を作る蒸気発生器は海外でナトリウムが漏れて激しく反応する事故も報告され、安全性の高い機器の開発が必要だが、常陽ではできない。これについて政府は、フランスが計画する実証炉で確認できるというがまだ設計段階で建設されるかどうかも決まっておらず、発電設備の確認ができる保証はない。
日本のエネルギー事情からどうしても必要と言うのであれば、もんじゅの失敗を教訓に、基盤研究からやり直し、運営主体も改善して出直す、というならわからないでもないが、背伸びして一つ上に行こうとすれば、失敗を繰り返すことになりかねない。
決め方にも問題。高速炉開発会議は経済産業大臣に文部科学大臣、それに原子力機構と電力業界、三菱重工業と、これまでもんじゅを推進してきたメンバーだけで構成。しかも議論は多くが非公開。毎回数十分の会議を4回開いただけ。これでは最初から高速炉開発ありきかと。もんじゅ関係者ではない、第3者の有識者による委員会を設置し、開かれた場でもんじゅ問題の総括と政策の見直しをしなければ。政府の意思決定のどこに問題があったのかなど、政策面からももんじゅ失敗の教訓を明らかにしなければ。
その上で核燃料サイクルの見直し。ポイントとなるのは使用済み燃料の扱い。政府が核燃料サイクルを堅持しようとする大きな理由の一つが、一般の原発の再稼働。再稼働すれば使用済み燃料が出るが原発のプールは満杯に近いところもあり、運転停止に追い込まれる可能性。再処理工場持つ青森県も核燃料サイクル続けることを受け入れの条件、やめるのであれば使用済み燃料を元の原発に返すと。政府としては、高速炉開発の意思表明はしておかなければならない事情。
しかしこれでは本末転倒。使用済み燃料をすべて資源と言うのではなく放射性廃棄物として処分できるようにする必要。そしてそのための中間貯蔵と最終処分に向けた選定作業を急がなければならない。
1兆円を超える巨費が投じられた高速増殖炉「もんじゅ」。政府は、今月21日、廃炉にすることを正式に決定しました。運転開始から22年で、稼働していたのはわずか250日。それにもかかわらず、政府は、もんじゅの次の「実証炉」というステップに向け、高速炉開発を進める考えを示しました。
もんじゅが残した教訓は、今後の原子力政策に生かされるのでしょうか。
●政策の要だったもんじゅ
原子力の基本政策となる「核燃料サイクル」。福井県にある研究開発段階の高速増殖炉もんじゅは、その要となる施設でした。
エネルギー資源に乏しい日本は、原発で出る使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し、高速炉で再び利用する核燃料サイクルを推進してきました。
目指したのは高速炉の中でも、使った以上の燃料を生み出す高速増殖炉で、当初は昭和60年代に実用化する計画でした。
しかし、もんじゅの運転開始は当初の計画より遅れて平成6年。翌年にはナトリウムが漏れる事故が起き、長期停止を余儀なくされます。
その後もトラブルや安全管理上の問題が相次ぎ、政府は、今月21日、もんじゅを廃炉にすることを正式に決定。
稼働実績はわずか250日で、この間の最大の出力も40%と、役割を十分に果たせないまま、1兆円を超える巨費が投じられた巨大国家プロジェクトに幕が下ろされたのです。
●政府判断の背景は
発端は、もんじゅで相次いだ安全管理上の問題でした。
事態を重く見た原子力規制委員会は去年11月、監督官庁の文部科学省に、日本原子力研究開発機構に代わる新たな運営主体を求める異例の勧告を出します。これに対し文部科学省は、もんじゅの存続を前提に議論し、ことし5月の時点では、「関係省庁と調整し、電力会社やメーカーの協力を得て、新しい運営主体を設立する」としていました。
しかし9月、政府は「廃炉を含めて抜本的に見直す」と、方針を転換。背景に何があったのでしょうか。もんじゅを所管する文部科学省と、原子力政策を担当する経済産業省との間で、何度か協議が行われました。
経済産業省は、「電力会社やメーカーは原発再稼働で余裕がなく、規制委員会から重い課題を突きつけられたもんじゅに協力するとは考えにくい」「もんじゅを動かさなくても実証炉の開発は可能で、もんじゅに多額の投資をするのであれば、高速炉開発のための別の投資をした方ほうがよい」もんじゅにこだわらなくても、核燃料サイクルの柱となる高速炉開発はできるという考えを示したのです。
文部科学省内の検討でも、もんじゅの運転を続けるには、新しい規制基準の審査や対策に長期間を要し、5400億円以上の追加費用がかかることがわかり、運転再開は難しいとする見方が強まっていきました。
こうした議論を踏まえ、政府は、時間的・経済的コストが増大しているとして、廃炉を決めました。その一方で、核燃料サイクルを堅持するため、もんじゅの次のステップにあたる「実証炉」、つまり実用化一歩手前の高速炉の開発を続けるとしたのです。
●地元に走った衝撃
地元・福井県敦賀市には大きな衝撃が走りました。
もんじゅを中核施設として、国、電力事業者、それに地元企業などが参画する「エネルギー研究開発拠点化計画」を策定するなど、原子力やエネルギーの研究を進めるまちづくりに力を入れてきたからです。
こうした状況を踏まえ政府は、もんじゅを廃炉にしたあとも、周辺を原子力の研究や人材育成の拠点となるようもんじゅの敷地内に研究炉を新たに設置するなど、地域経済に影響が出ないよう、最大限努力するとしました。
一方、福井県の西川知事は、別の理由をあげて、廃炉の方針を「容認できない」という姿勢を示しました。廃炉作業を引き続き、原子力機構に任せるとした点です。廃炉作業に高い安全性が求められることに変わりはなく、規制委員会から、「もんじゅの運転を安全に行う資質がない」と指摘された原子力機構に任せていいのかと、疑問を呈したのです。そのうえで、廃炉の作業に入るには県が原子力機構と結んだ安全協定をもとに、政府が丁寧に説明し、地元の納得を得なければ、進めることはできないと注文をつけました。
政府は地元の理解を得るための対応を具体化していくと応じ、来年以降も議論を続けることになりました。
●廃炉作業の課題
もんじゅの廃炉作業は、およそ30年にわたって行われ、費用は少なくとも3750億円かかるとされています。
規制委員会は、今後、原子炉からの核燃料の取り出しと廃炉の計画の申請を早期に行うよう原子力機構に求める方針ですが、さまざまな課題があります。
まず、原子炉に入っている核燃料は、一般の原発と異なり、簡単には取り出せません。370体あるもんじゅの核燃料は互いが支え合うように炉内に入っているため、崩れないよう、核燃料を取り出すごとに模擬燃料を入れる必要があり、この模擬燃料を新たに作るのにおよそ2年はかかるということです。
さらに、核燃料を取り出すための機器や装置の点検などにも時間がかかり、すべての核燃料を取り出すには5年半もの時間を要するとしているのです。
原子炉を冷やすために使われていたナトリウムも課題の1つです。もんじゅでは、すべての燃料を取り除いたあとに回収することにしていますが、ナトリウムを保管する機器を新たに設置しなくてはなりません。処分方法なども決まっておらず、海外のケースを参考にしながら、進めていく必要があります。国内で高速増殖炉の廃炉の経験はなく、より長い期間に及ぶ可能性があります。
規制委員会は、廃炉が安全に進むよう規制を強化するため、作業が妥当かどうかを議論する専門の監視チームの設立や廃炉に関わる法令の改正などを検討する方針です。
●次の高速炉開発 課題は
廃炉となるもんじゅの代わりとして、政府は、次の実証炉の開発を目指し、年明けから開発作業の工程表の策定に入ることにしています。
開発は、フランスが建設を目指す高速炉「アストリッド」への協力などを通じ、新しい知見を得ながら進めるとしていますが、課題もあります。
平成26年からアストリッド計画に参加してきた「三菱FBRシステムズ」は、国内で唯一、高速炉の設計を専門としていますが、もんじゅを設計したベテランが次々と退職し、技術力の維持が大きな課題となっていて、アストリッドの開発協力を通じて技術力を高めようと考えています。
しかし、将来の高速炉の開発につながる海外の中核技術の設計にどこまで関われるかは、まだわかっていないといいます。
また、アストリッドは日本が進めてきた高速炉とは構造が異なるため、耐震などの問題からデータや経験をどこまでいかせるのか、専門家の中では疑問視する声もあります。
さらに、アストリッドの建設コストが日本円にして数千億円に上るとされている中、日本の政府関係者によると、建設にあたり、フランス側から費用の半分の負担を求めていると受け取れる考え方も示されたということです。
こうした状況から、アストリッドへの開発協力で、日本が費用に見あった技術やノウハウを本当に得られるのか不透明だという懸念があるのです。
●十分な検証と幅広い議論を
もんじゅの廃炉を決めた日、松野文部科学大臣は、記者会見で、「必ずしも、当初期待された成果まで至らなかったことは事実だが、私自身は一定の成果だったと判断している」と述べました。
確かにもんじゅを設計・建設して、最大40%の出力で運転したデータが取れたというのは事実ですが、運転を長期間続けて、安全を維持するための技術が確立されたかというと、部分的と言わざるを得ません。
国は、必要最低限の知見を得るためには、100%の出力で5年前後、運転を行う必要があるとしていました。それができずに廃炉が決まったのでは、「失敗だった」と評価されても、しかたありません。そのような状況で、政府は、一足飛びに実証炉に進もうとしています。
国の原子力委員会の委員長代理を務めた長崎大学の鈴木達治郎教授は、「高速炉開発の途上にあるもんじゅが十分な成果をあげられずに廃炉になった今、もんじゅの教訓を十分に検証し、その次のステップに進むのが妥当かどうか、根本的な政策の見直しの議論をさまざまな立場の人が参画する開かれた場で行うべきだ」と指摘しています。
福島第一原発の廃炉や事故の賠償などの費用が21兆円以上に膨らむ見通しが示されている中、高速炉の開発や核燃料サイクルの確立は、今後も多額の費用を投じようという大きな問題です。
もんじゅが残した教訓を十分に踏まえ、幅広い議論を行った上で、地元や国民に丁寧に説明することが求められています。

経済産業省と文部科学省、電気事業連合会の幹部らが、二〇〇六〜一四年に高速増殖炉の実用化に向けて話し合った「五者協議会」の議事録が作成されていないことが、本紙が経産省に行った情報公開請求で分かった。協議会は開発体制や費用の分担のあり方などを原子力委員会に報告し、実証炉開発で重要な役割を担ってきた。会合は非公開で議事録もないため、核燃料サイクル政策の意思決定過程の一部が検証不可能な「ブラックボックス」になっていた。
協議会は、日本原子力研究開発機構が高速増殖原型炉「もんじゅ」と並行し、後継となる実証炉の研究を実用化につなげるため〇六年七月に設置された。経産、文科両省と電事連、日本電機工業会、原子力機構の幹部が出席し、事務局は資源エネルギー庁原子力政策課が務めた。
エネ庁によると、一四年までに八回の会合が開かれ、高速増殖炉のほか、サイクルに必要な新しい再処理工場のあり方なども話し合われた。エネ庁の担当者は「(法定の)審議会とは違い、半分私的な研究会のような位置付け。なぜ議事録が作られなかったのかは分からない」と話す。
当初から原子力機構の副理事長として出席した岡崎俊雄氏は「新型転換炉ふげんは原型炉で成功したのに、電力会社の反対で実証炉へ進めなかった。協議会はその教訓から、着実に実用化につなげるためにできた」と説明。非公開の理由は「率直に議論する場。実効性ある議論を第一に考えた」と話す。
協議会は〇六年十二月には、実証炉の設計開発を中核企業一社に集中させることを決め、報告を受けた原子力委がこれを了承している。翌年には一カ月間の公募の結果、原子力機構幹部や学識者による選定委員会で、原発事業を手掛ける三菱重工業が中核企業に選ばれた。だが、原子力機構は入札した企業名や数などを明らかにせず、選考過程には不透明さも残る。
政府は昨年十二月、ほとんど動かせなかった原型炉もんじゅの再稼働を諦めて廃炉としつつ、一段階先の実証炉の開発を再開させることを決めた。政府方針の検討会議には三菱重工社長も出席し「中核メーカーとして取り組んでいきたい」と発言。五者協議会など従来の枠組みがある程度踏襲されるとみられる。
NPO法人原子力資料情報室の伴英幸共同代表は「たとえ公的な位置付けでなくとも議事録を残していくことで、後々の判断材料になる。今後の実証炉開発で五者協議会がどんな役割を果たすのかは不明だが、公開のもとに進めるべきだ」と指摘する。
<実証炉開発> 高速増殖炉は、使う以上の燃料を生み出す「夢の原子炉」と呼ばれ、国は基礎研究の実験炉(常陽)、発電技術を確認する原型炉(もんじゅ)、経済性を検証する実証炉の段階を踏んで実用化を目指してきた。実証炉は、もんじゅの建設が始まった1980年代に電力業界中心の開発が動きだしたが、95年のもんじゅナトリウム漏れ事故をきっかけに白紙化。99年に当時の核燃料サイクル開発機構(現日本原子力研究開発機構)を中心とした研究が再び始まったものの、2011年の東京電力福島第一原発事故で凍結されていた。
政府が福井県にある高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉を決め、高速炉開発を今後も進めるとしたことについて、13日に開かれた国の原子力委員会の会合で、委員からは、高速炉の商業化は現状では経済性がなく、原子力を取り巻く環境が大きく変わる中、急がず柔軟に進めるべきだといった慎重な意見が出されました。
原子力委員会は、国の原子力政策に専門的な立場から意見を述べるのが役割で、政府が先月、もんじゅの廃炉を決め、高速炉開発を今後も進める方針を示したことについて、13日に見解を取りまとめました。
それによりますと、高速炉開発はこれまで商業化が重視されていたとは言い難いと指摘したうえで、原発事故をへて電力自由化が進む中、今後は一般の原発よりもコストを抑えるといった目標を決めるなど、高速炉がビジネスとして成立するための条件を検討すべきだとしています。
見解の取りまとめにあたって、委員からは、「原発の燃料のウランがふんだんにある現状では経済性がないと思う」という意見が出されたほか、岡芳明委員長も「コストが高いものは使えず、ほかの電力に負けてしまう。原子力を取り巻く環境は大きく変わっており、高速炉開発は急ぐ必要はない」などと述べ、柔軟に対応すべきだという考えを示しました。
高速炉開発をめぐって、政府は、今後、工程表の策定を始めることにしていて、原子力委員会は今回の見解も参考にしてほしいとしています。
国の原子力委員会は13日、高速炉開発について、政府が昨年末に廃炉を決めた高速増殖炉原型炉「もんじゅ」(福井県)の反省を踏まえ、商業利用を念頭に研究開発を進めるべきだとの見解をまとめた。原発事故や電力自由化で電力事業の競争環境は変化しており、商業化の条件や目標を検討しながら、開発や建設コストの低減に努めることなどを求めた。
岡芳明委員長は「高速炉開発は急ぐ必要はなく、今はよく考える時期だ」と強調した。同委員会はこうした見解をもとに今春以降、原子力利用に関する基本的な考え方をまとめる方針だ。