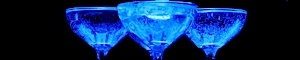一番上の特大シャンパングラス
政治屋・お役人・利権団体・大企業で一杯
溢れてどこに流れるか判りません 行方不明 無駄遣い





首相発言 好都合な「数字」を強調
見え見えの詭弁
「数字」の背景・環境は 真っ暗闇 霧の中 触れません
●
民主党時代の景気低迷を責める時は 「リーマンショック」に触れない
G7で世界景気の低迷を説明するときは 「リーマンショック」を前振りのダシにしました
●就労人口の減少期に入りました
タワーを支える 下層グラスが減少するばかり
人口比率の高齢化は右肩上がり ひ弱なグラスも増えています
タワーそのものが不安定になるばかり

人口は国力
注ぐシャンパン (お金・税金) も減少します
行政改革と質素倹約 日本の文化を取り戻しましょう



●当り前の政治
平らな所に (公平・公正)
グラスを平らに並べ (グラスは政治テーマ)
グラスにシャンパンを注いで回る (回る順序は課題の優先順位)
●
地味で票になりませんか

●アベノミクスで税収増えた? 2016/6
安倍晋三首相が経済政策「アベノミクス」の「果実」の一つとして誇示しているのが、税収増です。「この3年半のアベノミクスによって、国、地方を合わせた税収は21兆円増加した」と述べています。しかし首相の言い分をうのみにすることはできません。
財務省と総務省によれば、「税収の21兆円増加」とは、2016年度の当初予算の税収見込み額を、安倍政権発足以前の12年度の額と比べた数字です。
この間に、国の税収は42兆3千億円から57兆6千億円へ15兆3千億円増加。地方の税収は36兆4千億円から41兆9千億円へ5兆5千億円増加。合わせて20兆8千億円増えたというのです。
問題は、この税収増を経済政策の“成功の果実”だといえるのかどうかです。
●国・地方9兆円
まず、「21兆円」には安倍政権が14年4月に実施した8%への消費税率引き上げによる税収増が含まれています。消費税収は国と地方を合わせて実に9兆円も増えました。
自分で消費税率を引き上げておいて、その分の税収増まで経済政策の「果実」として扱っているのです。水増し以外の何ものでもありません。
「アベノミクス」の財政出動政策は財源を消費税増税に頼っています。その意味では、消費税増税はまさに「アベノミクス」の一環です。しかし、消費税増税による税収増は国民にとって喜べることでしょうか。
国と地方の消費税収が9兆円増えたということは、国民の所得が9兆円奪われたことを意味します。とりわけ重い負担がのしかかるのは低所得者です。
消費税増税は貧困を深刻化し、個人消費を2年連続で落ち込ませました。14年度の国内総生産(GDP)はマイナス成長に陥り、15年度も政府見通しを下回りました。9兆円の消費税収増は“成功の果実”であるどころか、むしろ“失敗の種”だといえます。
●異常事態と比較
第二に、安倍首相が現在との比較で持ち出した12年度の税収とは、リーマン・ショック(08年)後の世界的な経済危機と東日本大震災(11年)の影響で激しく落ち込んだ異常事態のときのものです。
赤字の企業が多かった12年度は、法人税収が07年度と比べて7兆6千億円も減っていました。トヨタ自動車は08〜12年度までの5年間、法人税(国税分)を1円も払っていませんでした。
リーマン・ショック前の07年度の税収見込みは、国と地方を合わせて95兆3千億円でした。これに対し、安倍首相が誇る16年度の税収見込みは99兆5千億円です。消費税の増収分9兆円を除けば、リーマン・ショック前の水準すら回復していないのです。法人税収は07年度に16兆4千億円あったのに、16年度は12兆2千億円にとどまっています。
水増し数字の独り歩きで「アベノミクス」の「果実」を印象付けようとしても、国民の生活実感からかけ離れるだけです。

●21兆円税収増の内13兆円アベノミクス 2016/6
安倍晋三総理は8日開かれた全国市長会に出席し「我々が進めてきた経済政策によってこの3年半で税収は国と地方を合わせて21兆円増えた。そのうち消費税の5%から8%への引上げによって増収したのは8兆円であり、13兆円は私たちが進めてきた経済政策による果実。この果実を地方創生のために、あるいは『介護離職ゼロ』『希望出生率1.8』の実現のために使っていく」とアベノミクスにより、税収が増えたとし、さらに、アベノミクスを進めることで「成長と分配の好循環を実現していく」とアピールした。
安倍総理は「伊勢志摩サミットではG7が協調し、金融、財政、構造の3つの政策を進めていく、『三本の矢』をG7で放っていくことで合意をした」とも語り「アベノミクスを世界に展開していくことになった」とした。
そのうえで「G7議長国として、我が国も率先し、あらゆる政策を総動員し、アベノミクスのエンジンを最大限にふかしていかなければならない」と強調。
そのために、安倍総理は「秋に総合的かつ大胆な経済政策を講じる」とするとともに「構造改革の断行、民間投資の喚起、加えて、消費税率引き上げを2019年10月まで、30か月延期すべきと判断した」と理解を求めた。
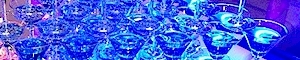
●見くびられた日本経済の実力 アベノミクス「再起動」は今しかない 2016/7
7月10日投開票の参議院選挙が間近に迫ってきた。2010年代の国政選挙の特徴は、有権者の経済問題(社会保障、雇用、景気)への関心の高さである。今回の参議院選挙も例外ではない。年代、地域を問わず、投票先を選択する際にもっとも注視する項目のトップ3には経済問題が並ぶ。これをうけて、各党の公約・主張においても経済問題への言及が目立つ。与党は3年半にわたるアベノミクスの成果と実績を訴え、野党は生活実感の悪化を非難するというのが基本的な展開である。
選挙の時期が固定されている参議院選挙には、現政権の政策を採点するという中間選挙的な役割があるのは確かだ。株価・為替・雇用・GDPが2012年以降どのように変化したか、直近の動向だけではなくやや長い、といっても5年程度の話だが、視点をもって各自検討されたい。その一方で、選挙によって決まるのは「過去の実績」ではなく「これからの政策」であることも忘れてはならない。安倍首相が強調するアベノミクスのエンジンをふかし、脱出速度を最大限に上げるために必要な政策は何か。民進党が指摘するふつうの人から豊かになる経済政策とは何か。ここでは、アベノミクスの今後(またはポスト・アベノミクス)のために必要な経済政策を考える基本について説明したい。
マクロの経済環境、例えば雇用や平均所得などは一国経済における需要(総需要)と供給能力の小さい方から決まる。誰も買わないものを作る企業はなく、みんなが欲しがるものでも作る能力がなければ供給はできないと考えれば当然のことだろう。需要と供給のいずれが経済の足かせになっているかによって、必要な経済政策は大きく異なる。結論に先回りすると、日本経済は未だ総需要不足、それも深刻な需要不足状態にあると考えられる。
2012年時点では、日本経済の需要不足状態は2年からせいぜい3年程度で解消されると考えられていた。人口減少社会に突入した日本において、労働者の供給には限りがあり、ある程度の需要改善があれば経済は「供給能力の天井」にぶつかる。需要が供給能力を上回るようになると、ディマンド・プル・インフレーションが発生する。さらに労働市場は本格的な人手不足に陥るため、賃金上昇率は高くなる。これが2012年当時想定されていたデフレからの脱却であり、そのために提示されたのがアベノミクス第一・第二の矢(大胆な金融政策・機動的な財政出動)である。そして、需要が供給を上回った後には供給能力の増強が経済成長の源泉となる。そのためには第三の矢(成長戦略)が必要となる。これがアベノミクス始動当初の政策パッケージである。
しかし、ここには大きな誤算があった。一国経済の供給能力とは、言い換えればその「経済の実力」と言い換えても良い。多くの専門家も官邸も、この日本経済の実力を過小評価していたきらいがある。金融政策によって極端な円高が是正され、雇用情勢が改善すると、これまで職に就くことをあきらめていた女性、高齢者が想定外の規模で労働市場に参入してきたのである。数年で頭打ちになると考えられていた雇用者数は2012年平均に比べ157万人(うち正社員37万人)の増加を経てなお増え続けている。「職に就くことをあきらめていた人」が働き出してみると、日本経済の供給能力、いわば日本経済の実力は事前の想定よりも高いということがわかってきた。
実力を過小評価していた――ということ自体は悪いニュースではない。その一方で、政策スケジュールは変更を迫られることになる。事前の想定よりも供給能力と需要の差が大きかったわけであるから、そのギャップを埋めるにはより長い期間とより強力な需要政策が必要とされることになる。
このように、今後のアベノミクスに必要とされる政策の姿が見えてくる。需要不足経済では、「需要を足してやる」ことで経済全体の成長を導くことが出来るからだ。そのために必要となるのが、アベノミクス第一の矢(金融政策)と第二の矢(財政政策)の再起動であり、両者の連動性を高めるための工夫である。
金融政策にはまだまだ出来ることが多い。なかでも重視すべきは、継続性への信頼を高める方法である。金融緩和がより長期にわたって継続されること、金融引締(量的緩和の縮小や利上げ)ははるかに先の話であることを市場に信用させなければならない。そのためには、政府が経済に関する明確な数値目標を設定し、その達成までは現在の金融緩和が強化されることはあっても縮小されることはないこと――それを政府・日銀が共同宣言として発表するべきだろう。目標としては、「(食料・エネルギーを除く指数で)2%のインフレが1年以上継続し、かつ名目GDPが600兆円を超えるまで」といったものや、雇用情勢とリンクさせたものが考えられる。
さらに、政府の財政政策もこのような政府・日銀共同宣言と整合的なものに改めるべきであろう。2014年の消費増税、さらに2015年以降の公的支出の停滞をみても、第二の矢は継続性・一貫性を欠いている。自民党の公約集でも触れられている財政出動について、有効性の高い分野を見極めた上で、財政支出をためらわないことが求められる。
このような政策パッケージは与党の専売特許というわけではない。野党側にとっても合理的な方針となり得る。多くの論者が指摘するように、アベノミクスの政策パッケージは海外ではむしろリベラル政党に典型的な政策方針である。例えば、中道左派政権の首班であるカナダのトルドー首相は大胆な低金利のチャンスを逃さずに財政支出を拡大すべきだと主張している。民進党であれば金融緩和をさらに拡大し、低金利を生かした国債発行や財投債発行によって資金を調達し、自民党案よりも生活支援や低所得世帯対策に予算を優先的に配分することで消費の拡大を目指すといった提案も可能だろう(ちなみに英労働党はこのような方針を「人民のための量的緩和」と呼んでいる)。
アベノミクスの三年半によって、日本経済は大きな変化の時期を迎えている。改善されたことも多い。その一方で、まだまだ満足のいくパフォーマンスではないのも確かだろう。選挙戦も残り少なくなってきたが、次の一手の経済政策について、各党の活発な論戦を期待したい。

●富裕層が豊かになるとみんなハッピーに?「トリクルダウン理論」 2016/2
安倍首相が「デフレからの脱却」「富の拡大」を目指し実施している経済政策アベノミクス。消費税が増税される一方で、法人税や贈与税を減税するなど、大企業や富裕層にとっては”おいしい”政策のようにも見えます。その背景には「トリクルダウン理論(効果)」と呼ばれる経済理論があるようです。
●「トリクルダウン理論」 「したたり効果」「おこぼれ経済」とも言われる経済理論
1714年にイギリスのバーナード・デ・マンデヴィルがこの考え方を示したとされる。トリクルダウンという言葉は2014年のユーキャン新語・流行語大賞の候補にノミネートされ、世間から注目を集めた。「トリクルダウン理論」とは、豊かな人々がもっと豊かになれば、やがてその豊かさが下にも落ちてきて貧しい人も豊かになれるという経済理論である。トリクルダウン(trickle down)という言葉には、「したたり落ちる」という意味があり、富裕層から貧困層へ富がしたたり落ちることを意味している。「金持ちを儲けさせれば貧乏人もおこぼれに与れる」と主張することから、「おこぼれ経済」とも揶揄される。
●「トリクルダウン理論」の具体例
シャンパンタワーに例えられる「トリクルダウン理論」 一番上のグラスに注がれたシャンパンは、徐々に下のグラスへとしたたり落ちていく。(大企業や富裕層に)お金を使わせることによってお金の回りが良くなり、景気が回復。企業全体の成績が上向き、従業員の給料が大幅にアップされることで更に消費が拡大。社会全体に活気があふれ、貧困層まで恩恵を受けることになる。つまり、所得税や法人税の最高税率引き下げなど、大企業や富裕層を優遇することで、富裕層らの経済活動が活性化され、最終的に貧困層を含む社会全体に富が行き渡る。例えば、アベノミクスで株が上がれば、そのおこぼれは皆に回ってくる。円安で輸出大企業が利益を上げれば、それは労働者や下請けにも回ってくるという考え方。
●アベノミクスは「トリクルダウン理論」らしい
安倍首相は"アベノミクスは「トリクルダウン理論」ではない"と言っているが… 。アベノミクスが始まって以来、「アベノミクスはトリクルダウン理論である」という言葉がよく聞かれる。しかし、2015年1月28日、国会の答弁でこう答えている。《安倍首相》「安倍政権として目指すのはトリクルダウンではなく、経済の好循環の実現であり、地方経済の底上げだ」。
●でもやっぱり"アベノミクスは「トリクルダウン理論」
大企業や富裕層を優遇しているアベノミクス、アベノミクスは、大企業や富裕層を優遇する税制改正や規制緩和を行うことで景気回復の効果を期待している。アベノミクスの法人税減税・設備投資減税によって企業の余剰を生み、社員の賃金にまわすように誘導しようとする政策はトリクルダウン政策の一つである。現在のアベノミクスは法人税減税や労働規制の緩和など、まさにトリクルダウン経済学路線をひた走っています。アベノミクスはお金をあるところからないところへ流すトリクルダウンの特徴を活用した政策といえます。
●「トリクルダウン理論」の効果に疑問
だから安倍首相は"「トリクルダウン理論」ではない"と言ったのか?
「トリクルダウン理論」には批判も多い。「トリクルダウン理論」は富裕層と貧困層の格差拡大を引き起こすという負の側面も大きい。「富裕層をさらに富ませれば貧困層の経済状況が改善する」というトリクルダウンを裏付ける有力な研究は存在しない。「トリクルダウン理論」により、経済成長の利益は自動的に社会の隅々まで行き渡るという前提は、経済理論・歴史経験に反している。
●実際に企業は「内部留保」として利益を貯め込んでいる
給料が上がるはずだったけど… 多くの人はアベノミクスの景気回復効果を実感できていない。日本企業は、今後流動化する経済に体力を温存しておくために、「内部留保」をバンバンためこんでます。特に大企業の「内部留保」は、一貫して増え続けています。とりわけ、2013年の内部留保は285兆円と前年から13兆円も増やしている。《甘利内閣府特命担当大臣》「企業収益は史上最高になっていますが、実質賃金がついてきていない。つまり、企業収益が完全に好循環を回し切っていないというところです。トリクルダウンがまだ弱いということです」。

●「シャンパンタワー政策」 2014/12
「グラスがピラミッドのように積み上げられた『シャンパンタワー』。結婚式やパーティーを彩る豪勢な飾りとして、映画やテレビドラマなどで目をした人も多いはずだ。
天辺のグラスにシャンパンを注ぐと、溢れだした滴が下のグラスに流れ落ち、そのグラスが満杯になると、さらにその下のグラスに滴が落ちる。この繰り返しによって底辺を支える多数のグラスにようやく酒が注がれる。
安倍晋三政権の経済政策『アベノミクス』は言ってみれば、こんなイメージだろう。『トリクルダウン(徐々に流れ落ちる)』 効果といわれ、大企業や富裕層がさらに豊かになれば、経済活動が活発化し、その恩恵が庶民まで広く行き渡るという考えだ」
9日付の大手新聞朝刊に、アベノミクスは「シャンパンタワー」政策であると指摘するこのような記事が掲載されています。多くの有識者達は、アベノミクスの政策について「トリクルダウン(trickle-down)」と横文字の経済用語を使って「専門家っぽく」説明していますが、一般の人がほとんど知らない経済専門用語で説明するというのは、始めから一般の方に理解して頂くことを目指していないのか、あるいは自分達の権威を保つために一般の方に理解出来ないように話していると批判されても仕方ありません。

●喧嘩のやり方を知らない野党のマニフェスト 2014/11
アベノミクス「シャンパンタワー政策」に対案を示せ!
「公約はアベノミクスに対抗する『経済政策3本柱』を打ち出した。(1)急激な円安や物価高など国民生活に配慮した『柔軟な金融政策』 (2)子育て支援や雇用の安定のための『人への投資』 (3)環境や中小企業に重点を置いた『未来につながる成長戦略』 ― を盛り込んだ」(25日付日本経済新聞 「民主、子育て・雇用重点」)
民主党は24日、「厚く、豊かな中間層の復活」を掲げたマニフェストを発表しました。「前回選挙の教訓を踏まえ、できることをしっかり絞り込んだ」ため、財源や実現時期などの数値目標の明示をしなかったとのことのようですが、「政権交代」の文字も消え、素直な印象は「政権を取れる可能性のない政党のマニフェスト」というところです。
「今、アベノミクスに対して失敗した、うまくいっていないという批判があります。しかし、ではどうすればよいのか。具体的なアイデアは残念ながら私は一度も聞いたことがありません。批判のための批判を繰り返し、立ちどまっている余裕は今の日本にはないのです。私たちが進めている経済政策が間違っているのか、正しいのか。本当にほかに選択肢があるのかどうか。この選挙戦の論戦を通じて明らかにしてまいります」(首相官邸「安倍内閣総理大臣記者会見」)
安倍総理は解散に際して、このように訴えました。総理に「具体的なアイデアは残念ながら私は一度も聞いたことがありません」「本当にほかに選択肢があるのか」と喧嘩を売られた野党第一党である民主党が「正々堂々と受けて立つ」と言うのであれば、「具体的なアイデア」「他の選択肢」を示して戦うのが喧嘩に勝つための絶対条件だと思います。
そうしたなかで「厚く、豊かな中間層の復活」などという、誰も反対しないが誰も熱烈に支持しない差し障りのないキャッチコピーを掲げて、どうやって喧嘩に勝つつもりなのでしょうか。有権者が欲しているのは「柔軟な金融政策」とか「人への投資」「未来につながる成長戦略」といった言葉のお遊びではなく、「アベノミクスに対する具体的対案」であることに気付かないのでしょうか。
「柔軟な金融政策」というのがアベノミクスに対抗する政策だというのであれば、現在の金融政策は「強硬な金融政策」ということになりますが、具体的にどこが「強硬な金融政策」で、それに対して具体的に何をどのように変更するのかが明記されていなければ対案として意味がないように思います。
「異次元の金融緩和」を中止するのか、「2%の物価安定目標」を破棄するのか。「柔軟な金融政策」の具体的な基準となるものを示さなければ、例え民主党の「アベノミクスでは持続的な成長が実現できないことが明らかだ」という主張が正しいものであったとしても、有権者に共感を与え、投票という行動に結び付けるのは難しいように思います。
第二次安倍政権が誕生した2年前、「行き過ぎた円高の是正」というのは優先順位の高い政策でした。しかし、1$=118円台まで円安が進んできた今日では、政策的優先順位は確実に落ちて来ています。そのことは、安倍政権が円安対策を打ちだすことを表明していることからも明らかです。要するに「行き過ぎた円高の是正」という役割を終えた「異次元の金融緩和」は変更されるのはある意味当然でもあります。
「異次元の金融緩和」が生み出した円安に関して、政府、日銀は「トータルで見てプラス」という見方を示しています。しかし、問題は「トータルでプラス」の中身です。現在の円安は、輸出企業、グローバル企業に対しては恩恵が及ぶ一方、国内企業や消費者にとってはコストの増加をもたらしています。つまり、アベノミクスの是非を問う上では、輸出企業、グローバル企業の収益へのプラスと、国内企業や消費者のコスト増というマイナスを足して「トータルでプラス」になっている状況を続けるべきか否かという点が議論の的になるはずで、「柔軟」か「強硬」か、という表現の違いなど議論の対象にはなりません。
個人的には、国民の財政負担のうえに実施されている「異次元の金融緩和」に伴う円安のデメリットを、新たな財政負担で埋め合わせて行こうという安倍政権の方針には強い疑問を抱いています。財政負担を掛けてあけた穴を、財政負担で埋めていく従来型の経済対策では、財政再建など期待すべくもないからです。
アベノミクスの経済政策は、「シャンパンタワー政策」になっています。積み上げられた一番上のシャンパングラス(輸出企業、グローバル企業)にシャンパン(異次元の金融緩和、円安、株高、法人税減税等)を注ぎ込み、そのお零れで下のグラス(中小企業や一般消費者)にシャンパンを注ごうとするものです。しかし、財政的な制約もあり注ぎ込めるシャンパンの量は限られていますし、一番大きなグラスが一番上におかれていたのでは、下のグラスにシャンパンが注がれていく保証はありません。
安倍総理は輸出企業、グローバル企業に並々とシャンパンを注ぎ込む「シャンパンタワー政策」について「この道しかない」と断言し、「本当にほかに選択肢があるのかどうか」を選挙戦の論争で明らかにしていくと宣言しています。このように宣戦布告している政権に対して正々堂々と戦いを挑むのであれば、「シャンパンタワー政策」以外の選択肢があることを示さなければ意味はありません。
昨日、「他の道もあります!!」という個人的な政策提言書をまとめ、お付き合いのある複数の衆議院議員に提案をさせて頂きました。提言は、「脱シャンパンタワー政策」実現のための3本柱として下記のような提案をしております。
1)財政負担のもとで実施されている「異次元の金融緩和の中止」
2)現在の消費税の中での社会保障費財源確保
3)雇用増、所得増に直接働きかける法人減税
「具体的なアイデアは残念ながら私は一度も聞いたことがありません。・・・(中略)・・・ 私たちが進めている経済政策が間違っているのか、正しいのか。本当にほかに選択肢があるのかどうか。この選挙戦の論戦を通じて明らかにしてまいります」(首相官邸「安倍内閣総理大臣記者会見」)
このように宣戦布告して衆議院解散に打って出た安倍総理に対して、野党側が具体的対案を示すことなくアベノミクス批判を続けることは、具体的なアイデアを持ち合わせていないということを示すことと同じで、アベノミクスを評価しないと答えた51%(日本経済新聞世論調査)の有権者達の受け皿になることを放棄するようなものです。
700億円ともいわれる予算を投入して行われる今回の総選挙を「大義なき解散」で終わらせるのか、「大義ある解散」に出来るのか、その責任は野党側にもあるということを強く自覚して短い選挙戦を充実したものにして頂きたいものです。