
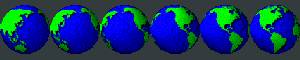


景色が変われば 解釈も変わって当たり前
揚げ足取りの 不勉強な場当たり質問
当然 妄想思い付きのご答弁


●安倍首相「決めるべき時には決める」 6/26
安倍晋三首相は26日の衆院平和安全法制特別委員会で、新たな安全保障関連法案について「どこかの時点で議論が尽くされたという判断が委員会、議会であれば、決めるべき時には決める」と述べ、今国会での成立に改めて決意を示した。首相は「過去最大幅の会期延長をし、十分な審議時間を取った。説明の機会をいただければ必ず理解される」と強調。過去のPKO協力法案の審議や日米安保条約の改定の際にも反対が多かったことを挙げ、「今では十分に国民的理解を得ている。法案が実施される中で理解が広がる側面がある」と述べた。
一方、自民党の若手議員が25日に開いた勉強会「文化芸術懇話会」では、安保関連法案への理解が広がらない現状をめぐり、出席議員が「マスコミを懲らしめるには広告料収入をなくせばいい」などと報道機関を批判した。これに野党が反発したことから、自民党は26日の特別委理事会で江渡聡徳筆頭理事が陳謝。首相は特別委の質疑で「報道の自由は民主主義の根幹であり、当然尊重されなければならない」と述べて事態の沈静化を図ったが、民主党など野党は激しく追及した。



「〜おそれ」は 恐れの認識如何で大きくブレた判断を生みます
首相答弁 ・・・閣議決定では、基本的な考え方として申し上げている。同時にわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある。まさに武力攻撃が発生するおそれのある事態において、これを排除するためにはわが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。これこそまさにこの考え方は専守防衛なんだろうと思う。 ・・・
( 恐れ / 何か悪い結果が起こるのではないかという気づかい。)



「マスコミを懲らしめるには・・・」
現代は情報戦争の真っただ中 若手政治家といっても頭は老人
情報はまき散らしたもの勝ち 情報発信の大事さを知らない
「ネット社会 政治・政策情報を発信しやすい環境 国営検索エンジンを創ろう」
「マスコミに負けない対抗情報・・・発信に注力」
とでも言ったら本物の若手政治家 応援します
●大西英男衆院議員(東京)
「マスコミを懲らしめるには、広告料収入がなくなるのが一番。政治家には言えないことで、安倍晋三首相も言えないことだが、不買運動じゃないが、日本を過つ企業に広告料を支払うなんてとんでもないと、経団連などに働きかけしてほしい」
●井上貴博衆院議員(福岡)
「福岡の青年会議所理事長の時、マスコミをたたいたことがある。日本全体でやらなきゃいけないことだが、スポンサーにならないことが一番(マスコミは)こたえることが分かった」
●長尾敬衆院議員(比例近畿ブロック)
「沖縄の特殊なメディア構造をつくったのは戦後保守の堕落だ。先生なら沖縄のゆがんだ世論を正しい方向に持っていくために、どのようなアクションを起こすか。左翼勢力に完全に乗っ取られている」
●百田尚樹氏
「本当に沖縄の二つの新聞社は絶対つぶさなあかん。沖縄県人がどう目を覚ますか。あってはいけないことだが、沖縄のどっかの島でも中国にとられてしまえば目を覚ますはずだ」
「もともと普天間基地は田んぼの中にあった。周りに何もない。基地の周りが商売になるということで、みんな住みだし、今や街の真ん中に基地がある。騒音がうるさいのは分かるが、そこを選んで住んだのは誰やと言いたくなる。基地の地主たちは大金持ちなんですよ。彼らはもし基地が出て行ったりしたら、えらいことになる。出て行きましょうかと言うと『出て行くな、置いとけ』。何がしたいのか」
「沖縄の米兵が犯したレイプ犯罪よりも、沖縄県全体で沖縄人自身が起こしたレイプ犯罪の方が、はるかに率が高い」
「政治家というのは、理念、信念、大事ですが、言葉が大事だ。戦争と愛については何をしても許されるという言葉があるが、政治家もある程度『負』の部分はネグったらいい。いかに心に届くか。その目的のためには多少……もちろんウソはダメですが」



首相 「国民的理解 ・・・ 法案が実施される中で理解が広がる側面がある」と述べた。
語るに落ちる 国民の理解は後回し
法案が実施されたら 手遅れになる側面もある



法律案文を読む 確かに内閣官房HPに掲載されていました
「由らしむべし知らしむべからず」
平和安全法制等の整備について
政府は平成27年5月14日、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制関連2法案を決定しました。 法律 / 案文(PDF)























