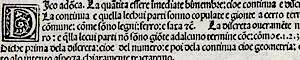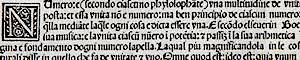●「歴史修正主義の批判免れない」
|
安倍総理の歴史認識に細野政調会長 (2015/2/4)
衆院予算委員会で4日、経済・外交等に関する集中審議が開かれ、民主党の1番手として細野豪志政策調査会長が質問に立ち、(1)過激派テロ組織ISIL(「イラクとレバントのイスラム国」)による邦人拘束事件(2)戦争責任――について、安倍総理をはじめ関係大臣の見解をただした。
ISILによる邦人拘束事件については、外務省が昨年11月に後藤氏が行方不明になり、12月3日には拘束されていることを把握、その後、後藤氏の家族と緊密に連絡を取り、家族と犯人グループとの間で交わされた10数回のメールのやりとりについても把握していたことを岸田外務大臣に確認したうえで、家族に対し身代金の要求があったかを質問。岸田外務大臣が答弁を避けたため、「事案の検証を考えた時、拘束公表前に家族に対して身代金の要求がされていたのかどうかは非常に重要なポイントだ」として、資料の提出を求めた。大島委員長は理事会で検討するとした。
安倍総理が1月17日にエジプト・カイロで行ったスピーチについては、「テロには毅然と対応していかなければいけない。人道支援も必要。一方で、人質が取られ身代金を要求され命の危機があるなかで、その人質がどういうことになるかというケーススタデイはやっておかなければならない」と主張。「難しい判断だったとは思うが、あのスピーチをしても2人が殺害されることはないと外務省として考えたのか」などと外務省の対応をただしたが、岸田外務大臣は「さまざまな状況についてはしっかり勘案し、日本の置かれている立場、日本の責任等を総合的に勘案してスピーチ等を考えた」との答弁を繰り返すのみだった。細野政調会長は安倍総理に対しても、「2人の命が危機的な状況にさらされ、そのリスクを外務省から説明を受けているなかで、その部分について配慮をした言葉を選ぶことが必要だったのではないか。どれほどの認識をもってスピーチを考えたのか」と質問。「ISILの気持ちは推測するが、彼らに気を配り、忖度(そんたく)をして彼らの意向に沿うスピーチをするつもりはない。スピーチに盛り込む言葉をさまざまな観点から選んでいく。そのなかで私たちが選んだ言葉が不適切だとは考えていない」と強弁する安倍総理に対し細野政調会長は、「テロリストの思いを忖度するなどというのは論外。国民の命を守るのが政治の役割であり、考えたうえでスピーチをするのは当然」だと断じた。
戦争責任については、自身の親族が1944年11月に戦地に赴き戦死したことにも触れ、このような召集令状によって戦地に送り込まれた者と、戦争指導者が一緒に祀られていることで靖国神社参拝の際に若干のわだかまりがあると述べた。そのうえで、2012年12月26日に安倍総理が靖国神社参拝後に発表した総理談話にある「戦争犠牲者」に戦争指導者は含まれるという考えなのかと質問。安倍総理はこれには答えず、石破地方創生担当大臣は「靖国とは別に」と断ったうえで、「何も知ることなく召集令状1枚で戦地に送られ、1発の弾も打つことなく飢えて死んでいった人たちへの責任というのは誰かが取らなければならないし、情報をきちんと知り、決断した人はそれなりの責任があると思う」との見解を述べた。
また、政府が1941年4月に各省庁から若手官僚を集めて立ち上げた「総力戦研究所」が開戦前に日米開戦をシミュレーションした結果、戦争には突入するべきではない、日米開戦は避けるべきとの結論を出したにもかかわらず、当時の近衛首相や開戦時の首相である東条英機陸相は開戦を決断したことに言及。「特にこの時にわが国は国策を誤っただろう。村山談話を離れても国策を誤った瞬間の一つであり、わが国は国策を誤ったと認めるべきだ」と迫ったが安倍総理は認めなかった。細野政調会長は「国策を誤ったという最も基本的なところを総理は認めない。戦争指導者を戦争犠牲者とすることも否定しない。いまの答弁を聞いていて総理は歴史の修正主義者だという批判を免れないと思う。これでは、この国の戦後70年をきちんと総括し、新たな歩みを前向きに政府として、国会として進むことにはできない」などと苦言を呈し、質問を終えた。 |
|
|
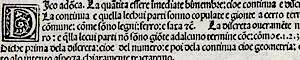
●明治7年 「台湾出兵」についての英「タイムズ」報道 |
台湾出兵(たいわんしゅっぺい)は(1874・明治7年)に明治政府による台湾への軍事出兵である。日本にとっては最初の海外派兵である。牡丹社事件(ぼたんしゃじけん)、征台の役(せいたいのえき)、台湾事件(たいわんじけん)とも呼ばれる。
1874年7月31日付、英「タイムズ」
日本の台湾遠征 臨時通信員記事、長崎、6月1日
台湾から帰還したばかりの高砂丸(元ぺニンスラ・アンド・オリエンタル汽船デルタ号)によって、日本の台湾遠征の5月27日現在における進捗状況に関し、以下のようなニュースがもたらされた。
おそらく貴紙の読者の興味をひくものと思う。しかし、詳細を述べる前に、遠征の初期の諸段階について、また、遠征開始当時日本を悩ませていた問題についてひと事触れておくのが適当だろう。
さらには、諸外国の公使によって日本の方針に差し挟まれた異議についても触れておくのがよいだろう。というのも、彼らの異議は日本のこのたびの企てにとって、また
、日本が西洋列強から得たばかりの信用にとって致命的なものになりそうだと、ひところはそう思うわれたこともあったからだ。
私が日本に住むようになってから7年が過ぎたが、その間にこの国では数々の仰天するような変化やある程度の進歩があった。しかし、疑う余地のない失敗もいくつかあった。そうした失敗の故に、日本は外国からおそらくたいした同情も示されないまま、ただ独り苦しんできたし、今もなを苦しみ続けている。しかし
、このたびの台湾遠征に関して言えば、日本に浴びせられた非難は当を得ていないように思われる。
日本が外国から反対されるなどは全くとんでもない話だ。あらゆる文明国は、たとえ物質的な援助は無理にしても精神的な支援は与えてしかるべきなのだ。それというのも、日本の目下の遠征の目的は
、台湾の野蛮人によって虐殺された日本臣民の恨みを晴らすことにあるからだ。彼らは、難破して台湾の南岸に打ち上げられた外国人を過去から現在に至るまで機会あるごとにことごとく虐殺してきたのだ。
昨年、判事が外交使節として北京に赴いた目的の1つは、台湾の南東岸で難破した日本船の乗組員約50人の虐殺に対し補償を要求するところにあった。ところが、同島のその部分は中国の管理下にはないので、その地域に関する要求は台湾に直接行ってほしいというのが副島に対する返答だった。
それ以来、台湾遠征は常にあり得べきこととなったのだ。日本はル・ジャンドル将軍という台湾通の顧問を擁していたので、遠征問題が忘れ去られたり必要な準備が不十分にしかなされなかったりするようなことはまずあり得なかった。日本はいざ出陣という段になるまで意図を隠し通したし、真のもくろみの代わりに朝鮮遠征のうわさが広まるのを放置し続けたが
、それは責めるべきではないだろう。
というのも、折あしく今年の早春に佐賀で反乱が起こり、政府軍はそれに対処しなければならなかったから、無分別で不手際なこの反乱が鎮圧されるまで台湾に関してはなにもできなかったのだ。しかし、反乱の平定後、本来の計画の遂行に対する誘因は以前にも増して大きくなったに違いない。
なぜならば、不満を抱く臣民にとって外敵の征伐に出かけることほど格好の仕事は見当たらなかったからだ。しかし、ただ1つ悔やまれたのは、台湾の気候を考えてみるとき季節が都合の悪いほうへ向かいっっあったということではあるまいか。同島南端への上陸にとって都合のよい季節風はすでに吹きやもうとしていたし、下手をすれば仕事がなしとげられる前に台風シーズンが到来するおそれがあったのだ。
にもかかわらず日本は計画の遂行を決意し、本年4月、台湾への遠征に最も便利な長崎に兵を結集させ始めた。ところが・そこにきて彼らに難儀が降りかやゝった。それも
、ほとんど予想だにしなかったようなところから。
外国の公使たちが、日本は中国が台湾の蛮人に対する管理権を否認したと言っているが、日本のそのような説明は納得できないと言い出したのだ。イギリスおよびその他の国々も
、台湾で行われた自国民の虐殺に関し中国に補償を要求したとき、同じような否認の弁を中国から幾度となく聞かされているにもかかわらずだ。
そして、日中間に生じるかもしれない紛糾といった難題を持ち出し、他の国々が即刻行動をとるようなことをなんの通告もなしに、自国の民と名誉を守るために日本はいかなる権限に基づいて行動をとるつもりかと詰問したのだった。
こうしてイギリスおよびアメリカの公使たちは、きたるべき遠征に両国の臣民が加わることを禁止する命令を発するに至ったが、アメリカの場合この禁止令は、主要な外国人顧問−元アモイ駐在アメリカ領事で台湾ではその名をとどろかせているル・ジャンドル将軍と
、アメリカ海軍では文句なしに有数の切れ者将校であるカッセル大尉−の手を引かせるという意味合いを持っていた。
しかし、この公使命令の影響力はそこにとどまらなかったように思われる。というのも、台湾に兵員を運ぶために日本が行った外国船の用船契約のうち最初の2件−ヨークシャー号とニューヨーク号−がキャンセルされてしまったからだ。これに加えるに、自前の輸送船のうちの1隻は耐航力に欠けることが畏繊到着後に判明した。そのようなわけで、自国の岸を離れる前にすでに、どう見ても日本人は完全に失敗するだろう予想された。
集合基地は台湾の南西にあるリャンキヤウ(恒春)湾こするとあらかじめ決められていた。同湾に最初の船団が到着したのは5月の10日から11日にかけてだろた。石炭を補給するためにあらかじめ基隆こ立ち寄った艦隊は目的のものを難なく手に入れたが、アモイに寄港した輸送船団は補給品をそれほどたやすくは入手できなかった。アモイでは水先案内人が
、もし日本人に手を貸せば投獄すると領事から脅されたりもした。
リャンキヤウいう村で上陸がつつがなく行われ、海岸にキャンプが設営された。日本隊はボートの賃貸料を気前よく支払ったので近隣の中国人は進んで彼らに手を貸した。
西郷従道将軍がデルタ号で到着するまでは、たいしたことはなにも起こらなかったようだ。
しかし、5月22日、彼の船が投錨するやいなや、中国のコルベェット艦が砲艦を引き連れて姿を発した。大砲を突き出したコルベット艦の乗組員は全員が部署につき、すぐにでも戦闘ができるよう準備万端を整えていた。デルタ号に乗り組んでいたヨーロッパ人数人は中国艦の準備のほどを目にすると、砲撃されるに違いないと瞬時に予想した。
中国艦のサイズから推して、そのとき湾内にあった日本艦隊が残らず捕獲されることは容易に見てとれた。しかしながら、コルベット艦は静かにいかりを下ろしたのでデルタ号の兵員は直ちに上陸を開始した。コルベェット艦の責任者として福建総督により福州から派遣された官吏が、日本の司令官に会見を申し入れた。
しかし、西郷将軍は翌日、陸の上で会いたいと言ってこの要求をすぐには受け入れなかった。会見は翌朝日本のキャンプ内で、400人の護衛兵が将軍を取り囲む中、日本の旗が揚げられた徴のテントの前で行われた。中国側の官吏はいかにもおずおずとした様子で前へ進み出てこの上なく丁寧に挨拶したが、西郷将軍はのびのびとしたヨーロッパ風の礼をもってそれに対し、手を差し出して相手に自分のテントへと招き入れた。明らかにされたところによると、この会見の大筋は以下のとおりだった。
中国側の官吏は台湾全土の所有権は中国にあると断言し、日本の遠征の目的を問いただした。それに対し西郷将軍はその種の問題は日本政府および中国のしかるべき当局間で北京において満足のいくように処理されるだろうと述べるとともに、自分は特命を帯びて当地にやってきたのだと返答した。
遠征の最終的方針に関してはいかなる約束や誓約もなされなかったが、会見はきわめて友好的な雰囲気のうちに終わり、日本隊にあらゆる援助を与えよとの布告書が官吏によって全中国人に発せられた。
その後、2隻のコルベェット艦が両国国旗に敬意を表して礼砲を放ち、中国艦隊は直ちに停泊地を後にした。中国による抵抗に関する問題はこのようにして難なく処理されたのだった。もし中国側に日本軍の上陸を阻止しようという気があったのなら、コルベェット艦が到着したときに海上にあった大量の財貨や約2000人の兵員もろともに日本艦隊全体を捕獲できるだけの力が彼らにはあった。しかし
、戦闘準備を整えてやってきた目的が何であったにせよ、彼らには戦う意志は明らかになかったのだ。
一方、日本軍は上陸後すでに敵に遭遇し、野蛮人との間に最初の衝突を起こしていた。丸腰でキャンプを迷い出た若い兵隊数人が待伏せに遭ったのだ。1人がその場で射殺されたので
、残りの者たちはあわててキャンプに戻り、死体を取り戻すよう仲間に訴えた。死体が発見されたとき首は切りとされていた。
翌朝、約50人の兵隊が呼び集められ、翌々日には100人が呼び集められた。両部隊とも、目についた野蛮人はことごとく追い立てた。野蛮人は相手との間に十分な距離が保たれている間は反撃したが、日本軍が刀を振りかざして肉薄すると逃げ去った。
日本軍は容赦なく攻撃し、2日間で16の首を戦利品としてキャンプに持ち帰った。あらゆる角度から戦いを目撃していた外国人たちの証言によると、この小遭遇戦における日本軍の突撃ぶりはあっぱれだったという。彼らほど勇猛果敢に戦える者はほかにはなかったに違いないが、ただ1つ残念だったのは
、熱意のあまりだれもかれもが最前線に群がったことだった。
デルタ号がリャンキヤウを後にするまでに、台湾のその地域の住民を構成する18部族のうち16部族までが西郷将軍に服従を誓い、残る2部族の征服に向けてあらゆる援助をしたいと自発的に申し出た。
難破船の乗組員に対し働かれてきた凶行の大部分は残る2部族のうちの牡丹族の仕業であると目されている。彼らは今や人類の共通の敵となってしまったのだ。5月27月現在・日本軍は大々的な進軍は行っていないが、牡丹族を完全に包囲するための計画は着々とできあがりつつある。現在予定されている作戦行動の結果に関しては次回の報告でお伝え、できるものと思う。
南部のいわゆる中国人村は皆、台湾に到着した日本軍を喜んで迎え入れた。この地域の住民は大部分が混血で、中国に対し忠誠の義務を感じてもいなければ、中国から保護を受けてもいないので、野蛮人たちと常に戦争状態にあり、彼らから金品をゆすられている。しかしながら、西郷将軍が兵をくり出して自分たちの村を領有し、野蛮人たちの絶えざる侵略から守ってくれるなら日本兵をいくらでも支援すると申し出たのは、住民1000人から成るl村だけだった。
デルタ号が台湾を離れるまでに日本軍の犠牲者は死者が9人、負傷者が20人から30人ほどにのぼった。看護を受けた者はわずか10人で、キャンプ内の健康状態は良好だった。しかし
、水は不足気味で質が悪く、気温は日陰でさえも95度にのぼるほどだった。
夏が終わるまでは暑さが日本軍にひどくこたえることは間違いないし、避けがたい台風が、決して安全とは言いがたい目下の錨泊地の船船に大きな被害をもたらすことも間違いなさそうだ。しかし・われわれ外国人は、この遠征を敢行した人々のエネルギーを認めねばならないし、彼らの大いなる成功を心から祈るべきだろう。
台湾が日本臣民の荒れ狂う不満のはけ口になったことは事実だが、遠征の大目的は全文明世界から擁護されてしかるべきではあるまいか。ところが、中立を守りつつ妨害を加えるというのがこれまでわれわれのとってきた唯一の行動なのだ。 |

●日清戦争 |
西欧列強の東洋侵略の最中にあって、日清両国の角逐はかれらに漁夫の利を与えるに過ぎない。日清が善隣提携のためには朝鮮における日清両国の紛争を根絶させることが急務であった。そのため明治18年4月に「天津条約」が締結されたが、締結から約10年後に生起した日清戦争は、清国がこの条約に違反したことが原因となったものである。
即ち、宗主権を維持し朝鮮は属国であると主張し続ける清国と、朝鮮を独立させこれと提携して発展の道を開拓しようとする日本との国策の衝突であると同時に、自力で収拾できなかった朝鮮内部の混乱によるものである。かくして明治27年に勃発した日清戦争は新興国日本が始めて経験した対外戦争であった。しかも相手は老いたりとはいえ「眠れる獅子」と恐れられ、人口・版図とも我の10倍はあろうかという超大国の清である。国民は不安に慄きながらも維新で築いたばかりの新生国家の命運を賭して上下・官民心を一つにして国難にあたり、連戦連勝のうちに戦争目的を完遂した。しかし戦いはこれで終わったわけではなかった。宿年の想定敵国ロシアとは早晩戦わざるをえない運命が待っていたのである。
「大韓国」の国号は、西暦1897年(明治30年・光武元年)10月12日の皇帝即位式挙行の日から起こる。それ以前は「朝鮮」である。従って「征韓論」とか、明治9年2月調印の修交条規を「日韓修交条規」と呼ぶのは厳密には正しくない。本項では上記起源に基づき「朝鮮」「韓国」を区別して呼称する。 |
●鴨緑江作戦
平壌占領後、山縣有朋大将の指揮する第1軍は第3師団、第5師団を基幹として9月末までに集結を完了、ただちに北進することに決し、第2軍(大山巌大将)の遼東半島上陸と呼応して鴨緑江渡河作戦を実施する準備を整えた。一方清国軍は平壌の敗戦後、安洲・義州で日本軍の北進に反撃した後に、宋慶を総指揮官とし、約18000で九連城を中心に二里にわたって大小50もの堅固な陣地を占領、15キロ上流の水口鎮対岸付近に依克唐阿(いこくとうあ)の指揮する約5500を配備して鴨緑右岸を防御した。
10月25日払暁 第1軍主力は敵前進陣地の虎山に対する渡河作戦を開始した。前日夜半から密かに進出していた佐藤支隊など一部前衛部隊は、南側から虎山を攻撃、敵主力の側背に迫った。日本軍の夜間軍橋構築と渡河準備に気づかなかった清国軍は虎山付近を固守し、0800頃各陣地から日本軍に対して反撃を開始した。虎山の主将は馬玉崑で、大いに奮戦し頑強な抵抗を示して第6聯隊の一部が苦境に陥る程であったが、支えることができずに九連城方面に後退した。25日夜、第3師団は迂回して九連城攻撃の布陣で露営、第5師団は馬溝から虎山にわたる地域に露営して九連城攻撃を準備した。10月26日0600 歩兵第11聯隊が九連城北側台地に進出してみると敵の抵抗はなく、城内は閑散としていて人影はなかった。清国軍は虎山の戦闘に敗退すると、老将宋慶は25日夜半鳳凰城に退却し、これを知った清国軍諸部隊も例によって戦わずして九連城を放棄して遁走したのである。この作戦で日本軍ははじめて敵地清国領内に占領地を得た。そして国境の要衝九連城の勝報がもたらされると、明治天皇は第1軍に勅語を賜った。
なお第1軍は九連城の無血占領後、直ちに追撃し鳳凰城及び大東溝を占領、清国軍はほとんど抵抗を示さずに三方面に敗走した。敵将宋慶も主力とともに奉天方面に逃れた。 |
●旅順攻略戦
黄海海戦で制海権を得た我が軍は、大山巌大将の指揮する第2軍を編成、旅順要塞を攻略するため10月24日から金州半島の花園口に上陸した。敵前上陸にもかかわらず清国軍の抵抗はほとんどなく、第1師団は11月6日には半日足らずの攻撃で金州城を占領、敵兵3500は旅順口及び大連湾方面に退却、我が死傷者は25名に留まった。敗走する清国軍を追撃する第1師団は11月8日までに大連湾諸砲台をすべて占領、戦意を失った清国軍はここでも旅順口まで敗走した。11月17日第2軍は金州を出発、途中前衛の一部が清国部隊の反撃に苦戦した他は大きな抵抗もなく20日には旅順背面防御線に進出した。
旅順は清国北洋艦隊の最重要軍港であり、巨万の財と10数年の時日を費やして当時の新式砲台を構築した東洋一の要塞で、13の永久砲台と4つの臨時砲台には、カノン砲、山砲など各種約100門が配備されていた。李鴻章は増援に努めたが、我が陸海軍に阻まれて十分な増援ができず、要塞守備隊約8000と大連の敗残兵約4000が守備していた。このうち約9000は新規徴募兵であり、守備隊指揮系統は複雑で、実質的な総指揮官は文官であり守将の決意はなく力量に欠けた。配下の将兵たちも日本軍の大連占領に狼狽して逃亡するものが相次ぎ、造船所の官吏も貴重品を盗んで逃走し、旅順市街は大混乱と化していた。
11月21日未明 旅順口攻撃の火蓋が切られた。第1旅団、第12旅団が西方東方からそれぞれ牽制する中、第1師団は旅順の弱点である西北正面から、第2旅団は案子山砲台郡の攻略を開始した。0800には椅子山を占領、松樹山、二竜山の砲台も次々陥落、半日の戦闘で正面の砲台はことごとく日本側に帰した。日本軍が砲台群を攻略して旅順市街に迫るのを知ると、清国軍部隊は潰乱しある者は軍服を脱いで市民を装って逃走した。午後になり海岸砲台の攻撃に着手し、黄金山砲台に突入、吶喊攻撃によって難なくこれを占領した。こうして海正面防備の砲台群もことごとく我が掌中に陥り、1700には大勢は決した。東洋一の大要塞は世界の軍事専門家の予想を裏切りわずか一日で陥落したのである。
この快勝は旅順要塞の軽視となり、のちの日露戦争において旅順攻撃作戦の失敗に繋がるのであった。 |
●威海衡作戦
旅順陥落後も北洋艦隊は威海衛軍港内に引き篭り渤海湾口を防護して出撃の気配はなかった。これを海上から撃滅することも湾口を完全に封鎖することも困難であり、第2軍大山司令官と聯合艦隊伊東司令長官は連名にて山東作戦/威海衛攻略の意見具申を行った。即ち清国北洋艦隊を壊滅させ、直隷平野での決戦の前提をつくり清国に講和を請わしめる目的で実施した作戦であった。
威海衛は山東省の北岸にあって海峡をへだてて旅順口と相対する直隷湾再要の要塞である。旅順に匹敵する10年余の歳月と巨費を費やして構築された要塞で、24センチカノン砲以下161門の火砲・機関砲を備えていた。ここでも指揮官は文官であり、守備兵の多くは新規徴募の者が多く相次ぐ敗戦に士気は低下していた。
陸上戦闘
1月20日から日本軍は栄城湾に上陸を開始、聯合艦隊の支援砲撃の下にまず陸戦隊が上陸、ついで第6、第2師団が上陸した。各隊は26日を期して進撃を開始、途中百尺崖において歩兵第11旅団長大寺安純少将は戦死、将官の戦死者は大東亜戦争まで大寺少将ただ一人であった。2月1日 大山軍司令官は総攻撃を開始、降雪を冒して北側要塞に向かって前進したが、清国軍のほとんどは既に退却しており大きな抵抗を受けることなく2日までに威海衛市街と堡塁群を攻略した。
海上戦闘
2月の威海衛は寒気は氷点下を示し、艦体は氷で覆い尽くされ小艦艇は航行不能の状態であった。 2月3日未明 我が水雷戦隊は荒れ狂う港内に進入、決死的な奇襲攻撃を敢行した。奇襲攻撃は5日にも実施され。0320 敵旗艦「定遠」を大破、「来遠」「威遠」ほか一隻を撃沈した。 2月7日 伊東長官は全艦隊をもって敵砲台の防御力に致命的大打撃を与え清国海軍の戦意を著しく喪失させた。9日には「靖遠」が撃沈、大破した旗艦「定遠」は自沈し艦長は自決した。2月10日 各艦長らは丁汝昌提督に降伏するように強要、既に降伏の気が清国全艦艇に蔓延しており丁提督は降伏の決意に至った。丁提督と親交のあった伊東司令長官は、葡萄酒と枯露柿を贈りその労を慰めたが、12日丁提督は、伊藤長官の友情を深く謝し、部下将兵の助命を乞うて幕僚二名とともに自決した。伊東長官は丁の死を悼み、礼を尽くしてその遺体を清国に送還した。この経緯は日清両国に深い感銘を与えた。
こうして威海衛は陥落北洋艦隊は全滅し、制海権はすべて日本に帰し、遼東半島の直隷作戦を準備した。 |
●第2期作戦計画
我が軍は陸海に全勝を収め、遼東半島内の敵を撃破し大連方面に転進した第1軍は、3月5日 牛荘を占領、9日からは田庄台付近の敵を包囲攻撃しこれを占領、満州内作戦を終了した。また3月26日には陸軍の比志島支隊によって澎湖島を占領、支那海方面における海軍根拠地とする目的を達成していた。
大本営は次の主作戦である直隷平野での野戦軍決戦のため、第2期作戦計画が実現されることになった。直隷作戦に参加予定の兵力は既に出征した4個師団に加え、近衛、第4師団ほかで全軍約20余万である。これは当時動員が予想される清国軍約20万人に比べやや優勢であると考えられた。これを統率するため、参謀総長・小松宮彰仁大将を征討大総督に、川上操六中将と樺山資紀中将を総参謀長に任じ、作戦準備中であったが、4月17日に講和条約が調印されたため、清国軍に対する作戦停止が発令された。遼東半島と威海衛に守備部隊を残し、部隊は逐次内地に凱旋帰国した。 |
●下関講和条約
日清開戦以来連戦連敗の清国は、明治27年初冬から一日も早い戦争終結を望んでいた。だが大国の体面を気にする清国は敗戦国として戦勝国たる日本に和を講じようとするほどの決意もなく、密かに欧米各国に対し仲裁の労をとって欲しいと懇願したが西欧各国はいずれもこれに応じようとはしなかった。
12月17日 天津海税務司のデトリングというドイツ人が李鴻章から伊藤博文首相への照会書を持って神戸に現れた。これは日本政府の考えている講和条件を探るためと思われ、その資格にも不審な点があったので日本政府は面会を謝絶した。清国政府はその後も数度にわたり米国公使を通じて講和を申し込んできたが、講和提議についてその誠意に疑問を持った日本政府は、清国政府に日本の意図を知らしめるため、米国公使を通じて、
『軍事賠償と朝鮮独立を確認するほか、土地の割譲と将来の国交を律する条約締結を基礎として、全権を有する使節を派遣しなければ何らの講和も無効である。』と宣言した。
2月18日 清国政府は米国公使を通じて李鴻章を全権大臣に任命したので会合場所を指示されたい、とする申し入れを行った。3月14日 李鴻章は天津を出発して下関に向かい3月20日から春帆楼で第1回会合を開いた。清国全権は講和会議の前に即時休戦を要請、日本側全権とは休戦条件で難航していたところ、3月24日 日本中を震撼させた小山六之助(豊太郎)による李鴻章狙撃事件が発生した。この事件により日本の講和外交は一気に苦境に陥り、明治天皇の聖旨によって直ちに全6条からなる休戦条約が締結され休戦が成立した。言わば李鴻章遭難事件の代償として休戦が成立したのである。その後も講和条約について協議を重ね、清国側全権の誠意のない駆け引きに対し、日本側全権が憤激して脅迫的言辞で応酬する一幕もあったが、4月17日には日清講和条約及び付属議定書の調印を終えた。
明治28年4月17日調印の講和条約の主な内容は以下のとおり。
・朝鮮独立の確認
・遼東半島、台湾、澎湖島の割譲
・賠償金2億テールの支払
・通商に関し、西欧列強と均等の権利の授与
・開港場と開市場における工業企業権の確立
・条約履行の担保として威海衛の占領 |
●三国干渉
日清の講和が成立し、全国民が戦勝に酔っていたとき、急転直下、全国民をして色を失わしめたのは、ロシア、ドイツ、フランスによる三国干渉である。4月23日 在京の三国公使は外務省に外務次官を訪ね、『日本が遼東半島を所有することは、東洋永遠の平和に害があるから速やかにこれを放棄すべきである』と勧告した。ついで清国政府もこの干渉を口実に講和条約の批准延期を要求してきた。
西欧列強が干渉にでることは以前からある程度予想されたことで、必ずしも唐突の出来事ではなかった。極東への東侵政策をとっていたロシアはかねてより日清問題には関心を示し、暫定的現状維持政策から戦争中は一応静観の立場をとっていた。ところが予想に反し日本が大勝を博すると見るや、大陸割譲は現状変更になることからロシアの態度は積極的となり、侵略的意図を剥き出しにしてきたのである。
フランスは、当時の外交関係からみてその生存上ロシアとの密接な関係があった。ロシアが干渉を決意しドイツがこれに応じる動きを示すと、勢いこの二国に従わざるを得ない立場にあった。またドイツは開戦当初から日本に好意的ではあったがその行動はあいまいな点が少なくなかった。密かに清国に対し戦時禁制品を輸出したり退役将校を清国に関係させたりして自国の利益を図っていたのである。東洋の利害関係が比較的少ないドイツにとって、露仏同盟は脅威でありこの機会に露仏二国に接近を図り、ロシアの勢力を欧州から極東に向ける必要があった。いずれも国際関係の複雑さが絡んだ結果であったが、日本の外務当局はこの複雑な国際情勢を正しく理解してはおらず、陸軍が創生期に教師国としていた独・仏の同調を衝撃的に受け止めた。
中でも公然と干渉の度を強めたのはロシアであった。日本に停泊中の艦船に出港準備を命じたり予備兵を召集するなどといった対日恫喝を具体化させており、三国干渉の張本人がロシアであることは明白であった。
4月24日 広島大本営で三国干渉のことを議する御前会議が開かれた。伊藤博文首相は採るべき案として3案を提示した。
1 たとえ新たに敵国が増加するも三国の勧告を断固拒絶する
2 列国会議を開催し遼東半島問題を協議する
3 勧告を容れ清国に恩恵的に還付する
以上3案について討議を尽くしたが、1案は、陸海軍の戦力上到底勝ち目はない。2案は、列国会議がかえって新たな干渉を導く危険性があり、結局三国の勧告を容れざるを得なかった。日本外交の敗北であった。明治28年5月10日 遼東半島還付の詔勅が下り、全国民は万斛の涙を呑んで三国の武力干渉の前に屈した。やがて、ロシア撃つべしとの声が期せずして沸き起こり、「臥薪嘗胆」は全国民の合言葉となって富国強兵に努めることとなった。
このときから日露戦争までの10年間は近代日本史上最も民族的意識の発揚した時期となり、「臥薪嘗胆」は日露戦争で辛うじて勝利を収める原動力となった。
なお大東亜戦争の動因の一つは、支那事変に対する列国の蒋介石への援助−いわゆる援蒋−の排除にあったが、支那大陸に対する我が勢力の拡大を阻止し、妨害しようとする列強の動きは、既にその45年前において見られたのである。 |
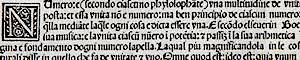
●高峰譲吉の米紙への寄稿 |
高峰譲吉は、タカジアスターゼの発明やアドレナリンの純粋抽出で世界の医薬界に大きな貢献をしたことで知られていますが、日露戦争時にアメリカ世論を味方につけるために民間大使として自費を投じて貢献した愛国者でもありました。
高峰譲吉がアメリカで没したのち、大正十一年十一月十日に、帝国ホテルで追悼会が開催されました。このとき、日露戦争時にアメリカに派遣されて、大統領と友人なのを利用するなどしてアメリカの世論を味方につけるために奔走した金子堅太郎が、高峰讓吉の民間外交を高く評価し、日本政府を批判した挨拶をしています。
「(ロシア贔屓が多かったアメリカで日本贔屓を増やすために私費をなげうって粉骨砕身した高峰讓吉の民間大使ぶりを賞賛した上で)・・・私が亜米利加より帰って来て、亜米利加に対しては国民外交をせねばならぬ、其の国民外交の無冠の大使は高峰博士であると云うことを言ふた所が、日本に於て大いに笑はれた、又攻撃された、金子が国民外交と云ふが、外交が国民外交であつて堪るものか、外交は秘密でなければならぬ、門戸を閉ぢて其中で外務大臣と大使とが話して他に漏れぬやうに機微の間にするのが外交である。国民外交とは何事か、国民が外交を知るとか、外交に喙を入れるのは間違って居ると云ふて、大いに私は攻撃された。・・・所が(いくつか例をあげて)・・・国民外交でなければ亜米利加の外交は成功しない・・・」
(没時の日本政府の高峰讓吉への顕彰は実績に比して極めて低いものでした)
アメリカとの外交では、アメリカ国民の世論を味方につける事がいかに大切かを、在米して奔走した金子堅太郎はよく知っており、したがって民間人としてその努力をした高峰譲吉を高く評価したのです。
アメリカとの外交では世論が何よりも大切なことは、高峰譲吉とは別の立場で民間外交を展開した歴史学者の朝河貫一も述べています。
産経新聞の朝河特集の中に、朝河の言葉として、「米国は与論の国であり・・・与論が政府を動かすことが多くて政府が与論を制したり導いたりすることが少ない」が引用されています。
アメリカの世論を動かすためには、政府・政治家・役人がアメリカ世論に働きかけることが必要であると同時に、日本の民間人がこれに協力すること――つまりは民間外交――が必要です。
しかし日本はこの点で大きく遅れています。
日本の在米民間人と中国の在米民間人では、アメリカ世論への働きかけがまったく違っていて、日本人は意識が低い――と親日アメリカ人が言っているそうです。
以下に、日露戦争の当時、在米日本人の中心だった高峰譲吉が、いかに民間外交に心をくだいていたかの例として、米紙への寄稿文を紹介いたします。 |
●解説
これは、日露戦争のときアメリカにあつて、いはゆる「無冠の大使」として活躍した工学博士・薬学博士高峰譲吉博士が、日露開戦後、わづかに旬日をすぎたばかりの明治三十七年二月二十八日「ニューヨーク・プレス」の日曜版に寄稿した快論文であつて、いはば高峰博士の国民外交第一ペーヂをかざる歴史的文献であると同時に、流麗暢達の筆をもつて、日本人の科学的独創性を強調し、その新兵器の鋭利を巧みに宣伝し、しかも日本人の本質が平和愛好の大理念にあることを闡明した点において、まさに愛国科学者としての高峰博士の面目躍如たる手記である。
なかんづく日本人の科学的独創性ないし「独創と模倣」の問題の扱ひ方、および下瀬火薬にはじまる一連の新兵器紹介は、科学史的に非常に貴重であると思はれるので、敢へて訳出して、清覧に供することとした。
原文はニューヨーク・プレスの日曜朝刊、全段抜きの大みだしで『日本、驚異的新爆薬を使用す』とある下に『旅順において既に使用、やがて陸戦においても露軍に満喫させん、高峰博士、暗に諷す』『種々の科学部門における日本の驚嘆すべき進歩』と小みだしをつけ、海戦の図を背景に、北里柴三郎博士と筆者高峰博士の写真を掲げてゐる。 |
●「ニューヨーク・プレス」編輯者のことば
日本人について語ることの資格において、当市居住の高峰譲吉博士の右に出づるものはない。博士は世界最大の化学者の一人であり、医学のために近代におけるもつとも重要な発見のうちの二つ、アドレナリンとタカ・ヂァスターゼをあたへてゐる。
アドレナリンは出血に対する即効薬であるほかにニトログリセリンもしくはストリキニーネ以来の強心剤である。
高峰博士の説によれば、日本人は一種の高爆薬を有し、今次の戦争にそれを使用しつつあるが、その偉大な破壊力は、ヨーロッパ諸国あるひはアメリカ合衆国に知られてゐるいかなるものより大きい。博士はそのことに通暁してゐるといふ。
また博士は、日本がこの爆薬を採用するにあたつては、諸外国によつて製出せられた既知のあらゆる強力な火薬を試みて、しかるのちにしたといつてゐる。
小銃、野砲およびありとあらゆる兵器部品において、博士の祖国は、諸外国の最善のものを雛型として、改良をなしとげたと博士は公言する。
当市における高峰博士の研究所は西百四十二番街六百十三番地にある。博士は東京帝国大学の工学士、工学博士1)である。
博士はサンデイ・プレスの読者のために、その祖国が、いかにして、また何故に五十年にも足らぬ年月のうちに、野蛮な鎖国の状態から、科学・芸術・交易・産業および戦争において第一級の地位を占めるに至つたかを説明する。 |
●高峰譲吉が「ニューヨーク・プレス」に寄稿した本文
日本における諸科学部門の驚異的発達(高峰譲吉)
日本人は偉大なる模倣家であるといふことが普通にいはれてゐる。これが事実であることには何らの疑ひもない。しかし、模倣的であるといふことは、独創的であることの先駆にほかならない。アメリカ人は世界ぢゆうを通じてその発明的天才の故を以て注目されてゐる。しかしながら、五十年あるひは七十年以前のアメリカ人を観察するならば諸君は当時彼らが非常にすぐれた模倣家であつたことを知るであらう。産業と関連した現代アメリカ合衆国の発展はおしなべてヨーロッパ諸国から由来し、導入されたものであつた。その鉄道・造船・製鉄・鉱山・紡績――事実上合衆国の大産業の大部分――は、母なる国々において使用されてゐた方法と手段の、単なる模倣の下に遂行せられたのである。
疑ひもなく、発明的天才はその当時においてもたしかに存在した。しかし、必要は発明の母なりとはいひながら、すでに存在し、かつ何時なりとも使用しえられるもの、数世紀にわたる発明と実験の結果になるものに眼を閉ぢるほど、それほどアメリカ人は愚かではなかつたのである。さりながら、ヨーロッパにおいて発展したよきものをのこる隈なく摂取したとき、アメリカはよりよき何物かを希求した。ここに発明の「母」は現れ、この母はアメリカが全世界にみづからの名声をあまねからしめるまで、発明と改良をつづけてきたのである。
これはまたまさに日本がなし遂げたところのものである。私の祖国は五十年にも足りない昔に、世界の他の部分に紹介せられた。何世紀ものあひだ、あらかじめ日本は何らの関係も、通信も、交易も、思想も(訳者註、外国から輸入することを)希望しなかつた。それで事は充分に足りたのであり、祖先伝来のことが毎日の実践であつた。古きものは新しきものよりもよかつた。なぜかならば、古きものは歳月の試練を経てをり、新しきものは一つの実験だからであつた。
そののち、日本は賢明にも近代的な方法と科学を採用し、古い封建制度を廃絶すべく決意した。多種多様な形式における近代文明を摂取し、これを前進させることにおいて、比較的わづかの年月に、日本が不思議なほど長足の進歩をなしとげたことは、誰しもしつてゐるとほりである。
これ以上詳説しないでも、一八九四年における清国との戦争、および現に進行中のロシアに対する戦争は、私の主張の正しさを証明する。数多の戦争方法はたぶん模倣の階段にあるかに思はれよう。すこぶる多くの長所を、日本が諸外国から摂取し、その利益を享受してゐることは認められなければならないが、しかし、また多くの面において、日本はこの特殊の主題については世界ぢゆうのありとあらゆるものを吸収しつくして、多くの点で、今やその必要が発明によつてのみ充たされうるところまで来てゐるのである。これこそ科学および産業の数多の部門において日本が遭遇してきたところの問題なのである。
しかしながら、まづ現下の興味ある話題として、過去二週間内外のあひだに実際に使用され、かつ奏効した二三の発明について語らなければなるまいと思ふ。こんにち日本はみづからの発明ならびに製造にかかる弾丸をもつてロシアの戦艦を撃沈しつつあるが、この飛道具を発射し、爆発せしめてゐる高爆薬がいかなる古今の火薬よりも強力であり、また広範囲の破壊力を有するとの主張は、すでに実験によつて証明されてゐるのである。またこの砲弾は、日本国内において設計製作せられた大砲を、同じ由来の砲架に載せて、撃ち出すのである。陸において、また海において露帝の軍隊は味方よりはるかに優勢な砲撃に直面するであらう。日本の兵隊の小銃は、到るところにある近代的小銃の品質と効果とを結合した連発施條銃であるが、これまた日本人の発明と設計と製作にかかるものである。ロシアの戦艦を海底に葬りさつた水雷は、天皇の海軍の将校によつて考案せられた信管を時限・触発ともに装備してゐる。もし陸上の作戦から比率を拡大していふことがゆるされるならば、日本以外の何処にも知られてゐない攻城砲は、かつてイギリスが南アフリカで用ひたこの種の火砲が全く時代おくれであることをイギリス自身に示すであらう。
かかる事態をもたらしたものは、嘗て存在した一国民としての日本人の保守主義ではない。これは純粋かつ単純に覚醒した日本における新思想の結果である。私の祖国では、世界の他の国々から提供された最善のものが試みられ、吟味せられ、何らかよりよきものへの希求は、近代の科学思想に従つて充足された。こんにちの情勢において日本の自由になる戦争手段に貢献した人々のうち、二三を紹介することにしようと思ふ。
現在手に入れうる最上の火薬として、陸海軍に使用せられてゐる新しい高爆薬は、ロシアの艦船が蒙つた損傷の大部分を、おそらくその功に帰すべきものだが、下瀬雅允の発明にかかる。彼は非常に有能な化学者で、私として誇りとしたいのは、東京の帝国大学の化学研究室で私と同窓であった2)。この爆薬は彼の姓をとつて命名せられ、東京の近郊で政府の警戒のもとに、秘密裡に製造されてゐる。下瀬の発明は天皇陛下に嘉賞せられ、もつとも高貴な勲章を授けられた。
砲兵会議々長有坂成章中将もまた、日本の戦争能力増加に貢献した注目すべき一人である。彼は大砲・砲架の両者にまたがる発明者で、これが日本の野砲および山砲の最新の発展を構成してゐる。ロシア人はやがて日本軍と陸上に相見ゆるの日、その性能を味はひつくすであらう。有坂中将はまた私がすでに言及した攻城砲をも完成してゐる。これらの火器はすべて、もつぱら日本政府直轄の砲兵工廠において製造されてゐるものである。
帝国海軍の肥後盛良大尉は、その名を負へる著発信管の発明者であるが、この信管は水雷に装備せられ、すでに敵艦の舷側にその標的を見出してゐる。
現役を退いた前田亨海軍造兵大監は、速射砲の弾丸に使用せらるべく予定された一連の時限信管および著発信管を考案した。
日本陸軍の村田経芳中将もまたすでに現役を退いて、貴族院議員となつてゐるが、彼も日本のためにその名を負へる小銃を考案し、これが陸軍の制式銃3)となつてゐる。この卒伍用の最新兵器は弾倉に十発の弾薬を包有する連発施條銃である。これは日清戦争において偉功を奏し、そののちさらに改良されてゐる。
戦闘用具の発明家のうちには、この他にも多かれ少かれ重要な人々があるが、他の線に沿つた発明の進展を示すために、戦争の技術から平和の科学へ移らせていただきたい。
電気学の分野では、たとへば、私の同国人岩田の発明した電話改良がある。この発明は送話器に関するもので、これについて、もつとも権威ある電話専門家諸氏が、ペルヴィルの装置と同じ大きさの音声を送る性能があることを認め、かつまた科学者のあひだで「ソリッド・バック」の名で知られてゐる送話器と同じ明瞭さをもつことを保証してゐる。
しかしながら、医学において、日本は世界の最新国家の一たる地位をかちえた。日本にむかつての近代文明の導入が、主として医学および医療の功績に帰せらるべきことを知るのは、多くの人に興味あることであらう。アジア諸国の門戸開放が、おもに剣の切尖と銃砲によつて行はれたことは周知の事実である。しかも、かかる場合においては、近代文明の導入が表面的にすぎなかつたことを看取しなければならない。キリスト教の宣教師団が懸命の労苦を重ねてゐるが、効果はほとんど挙つてゐない。
日本の場合には、医学がこの任務を果した。そして導入された文明は、その皮相にとどまらず、国民の心にまで入りこんだ。日本の近代文明をもたらすことに成功したものは実に医薬であつて、キリスト教でもなく、またアームストロング砲の砲口でもなかつた。一八五○年から一八六○年(訳者註、嘉永三年――萬延元年)へかけてオランダから日本に来て居留した医学者たちは、漢方薬に対する近代医薬の優位性を証明した。そして、それからまもなく、日本の医師たちはこの進歩した技術を学ぶことの重要性をさとり、みづからの体系を抛つたのである。ここでいつておくべきであらうと思ふが、それより以前、日本の開業医は薬用植物の使用と、単純な植物性の調合以上の療法をほとんど知らず、人体解剖学についてはさらに知ることがすくなかつた。治療は巧みに叡智を装つて行はれてゐたけれども、臓器病を真面目に、かつ聡明に治療するための努力はすこしもなされてゐなかつたのである。
蘭法医学ならびに薬法を導入するや、少数のオランダ医師の使徒たちは国内の諸方に散らばり、やがてまもなく患者と弟子の殺到するところとなつた。数年ならずして、「塾」と称する私立の医学研究機関が国内いたるところに設けられたが、そのあひだにも日本の中央政府(訳者註、幕府)は、なほ列強と、通商関係をひらくことさへ躊躇してゐた。実際において、当時外国と取引することは一つの犯罪であつた。海外に渡航しようと試みるものは、首を賭けなければならなかつた。しかし、かかる排外感情のまつただなかで、医学と医療は着実に地歩を築いてゐたのである。
将軍の政府がやむなく列強と通商條約を締結した時、外国の言語・技術等々に通暁する人物に対する需要は突如として増大した。需要に対する供給は、医学者とその弟子が充たした。帝国政府を維持してきた十数組の閣僚の四○パーセントないし六○パーセントは、医学者か、さもなければその出身であつた。そのなかでよく世界に名を知られてゐるものに、伊藤侯爵や大隈伯爵がある。かういふ次第で、近代日本の進歩の功を医学に帰することができるといふことは、統計的にみて正しいのである。
何処にもせよアジアの国々へ、近代文明を導入しようと欲するならば、医学者をたくさん送るのがもつとも賢策だとは、私の断固たる信念である。キリスト教やそのほかすべてのものは、自己の価値にしたがつて、あとにつづくであらう。そして、この原則には支那ももちろん例外ではないのである。もし宣教師団に費されただけの金額が医学者の派遣に利用せられたならば、支那の進歩はおそらく十倍も速かに、しかし血液や火薬を失ふことなく遂げられるであらう
世界の医学発達史には、日本が科学のこの方向における発展のうちに、一歩たりとも後退しなかつたことを証明する十二分の証拠がある。世界を通じての医学的実践を進歩せしめた顕著な発見のうちに、日本人はその役割を分担してゐる。これらの発見者もしくは発明者のなかで、世界周知の発見をなしとげてゐながら、その功績を認められることのほとんどない人、北里柴三郎博士を挙げようと思ふ。北里博士は東京大学医科大学の出身で、ヂフテリア血清療法については、ドイツの細菌学者ベーリンク教授とともに、すくなくとも共同発明者なのである4)。大学卒業後、北里博士はドイツに行き、有名なコッホ教授のもとで細菌学的研究に専念した。彼は今や、日本政府の経営する細菌研究所と、血清およびワクチン製造所の主宰者である。
血清療法発見の功労が主としてベーリンク教授に帰せられるのは、彼が各国の特許をとつたからである。彼はコッホ研究所で北里博士とともに研究をなしてゐるので、北里の探究によつて光明を投じられ、現在実用に供せられるやうになつた他の細菌学上の主題は多いのである。
もう一人日本にはすぐれた細菌学者がある。ヂフテリア以外の種々の伝染病について研究をとげ、有用な血清をたくさん発見してゐる緒方正規博士がそれである。
東京大学の医科大学医院長青山胤通博士についても語らなければならない。青山博士は腺ペストの病原菌5)を巧みに遊離したが、その研究の経緯は、一個の科学殉難史である。彼はペスト病が支那に猖獗をきはめてゐるとき、その地に派遣され、調査研究中に感染して危く生命を失ひかけた。この冒険は、しかしながら、目的の達成と将来における疾患の脅威の減少によつてかへつて栄冠をあたへられた。彼は生命のかはりに、この成果を科学の世界にあたへたのである。
私自身に関していへば私の研究の方向は、主として種々の酵素、とくに糖化性および消化性の酵素に限られてゐる。こんにち医療方面で成功をかちえてゐるものは「タカ・ヂァスターゼ」の名で知られてゐる澱粉消化酵素である。私の注意を惹いたもう一つの方向は、生化学、とくに動物臓器の化学すなはち臓器療法である。三年以前6)、いろいろの研究ののち、私は幸運にも副腎分泌腺の活性要素を純粋な結晶の形で遊離することができた。これが彼の「アドレナリン」で、こんにちまでに発達した強心剤および止血剤中、もつとも作用の強いものである。
以上私の述べたところから、日本人は一朝必要の生じたとき、その天賦の発明的才能を充分に活用する力のあることが明らかであらうと思ふが、なほ敢へて、今後何十年を閲せぬうちに、日本は世界ぢゆうでの独創的な国家の一となるであらうと、私はいひたいのである。 |
●注
1) 当時高峰博士のえてゐた学位はまだ工学博士(明治三十二年授与)だけであつた。薬学博士の授与は明治三十九年のことである。
2) 工部大学校の化学科でともに実習学をダイヴァースに授けられたといふ意味であらう。同窓といふならば高峰博士の助手清水鉄吉博士のはうがより密接な関係にある。なほ高峰博士と下瀬博士の交友関係については、書簡を参照のこと。
3) この記述は正しくない。日露戦役のとき歩兵と砲兵は有坂成章中将(当時大佐)が明治三十年に村田銃から改造した三十年式歩兵銃をもち、騎兵と輜重兵は騎銃を携へ、後備兵のみが村田式連発銃をもつて装備した。
4) この発見について、コツホは北里とベーリンクの共同論文を発表させ、功労に甲乙なしとしてゐる。
5) ペスト菌の純粋培養に成功したのは青山博士ではなく、このときやはり香港へ派遣されて来た仏領印度支那サイゴンのパスツール研究所員エルサンである。北里博士も発見の報告をしたが、記載に欠陥があつて否定された。
6) アドレナリンの発明は明治三十二年(一八九九)またタカ・ヂァスターゼの発見はそれより九年前、明治二十三年(一八九○)のことである。 |
 |