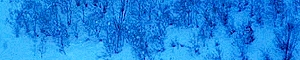|
●松岡農水相が自殺 議員宿舎で首つる 2007/5/28
28日正午ごろ、東京都港区赤坂2丁目の衆議院赤坂議員宿舎1102号室で、松岡利勝・農林水産相(62)が首をつっているのを秘書らが発見、119番通報した。警視庁によると、松岡氏は自殺を図ったとみられる。松岡氏は新宿区の慶応義塾大学病院で治療を受けていたが、午後2時、死亡が確認された。
赤坂署によると、松岡氏はこの日午前10時ごろまで、宿舎の室内で秘書と話をしていた。その後、出かける予定だったが、正午ごろになっても本人が室内から出てこないため、秘書が、警護に当たっていた警察官と一緒に室内に入ったところ、松岡氏が居間のドアの金具に、布製のひもで首をつっていたという。
松岡氏をめぐっては資金管理団体の光熱水費や事務所費の不透明な支出や、入札談合事件で理事らが逮捕された農水省所管の独立行政法人「緑資源機構」に関連する団体からの献金問題など「政治とカネ」をめぐる問題が野党から次々と追及されていた。
松岡氏の資金管理団体をめぐっては、電気代も水道代もかからない議員会館を事務所としているにもかかわらず、政治資金収支報告書には05年までの5年間に光熱水費計約2880万円がかかったと計上していた。松岡氏は国会で「ナントカ還元水とかいうものを付けている」と答弁したが、その後は「適切に報告している」などと繰り返すだけで具体的な説明は一切避けていた。
また、議員会館は家賃もかからないのに、年間約2500万〜3300万円を事務所費として支出していたと政治資金収支報告書に記載していた。
一方、緑資源機構をめぐっては、共産党が、林道などの事業と関係のある7政治団体を含む計9団体が松岡氏に約1億3000万円の政治献金をしていたと指摘している。
このほか、出資法違反容疑で福岡県警の家宅捜索を受けた会社の関連団体のNPO法人申請をめぐって、松岡氏の秘書が審査状況について照会していたことが発覚。松岡氏の後援者に対し、都内の会社経営者が「松岡氏への資金協力」として渡した100万円が使途不明になっていることが判明するなど、「政治とカネ」をめぐる問題を指摘されることが絶えなかった。
松岡氏は熊本県出身。69年、鳥取大農学部卒。69年に農林省に入り、天塩営林署長などをへて林野庁広報官を最後に88年農林水産省を退官。90年2月の総選挙で衆院議員に初当選し、当選6回。農水政務次官や衆院農水委員長、農水副大臣など一貫して農林水産畑を歩んできた。
06年9月の安倍政権発足時に初入閣し、農水相に就任。農水族の中心的な存在として知られ、対中コメ輸出や豪州などとの経済連携協定(EPA)の交渉にあたっての手腕が買われた。安倍首相は「攻めの農政を進めるうえで必要な人材」と評価し、光熱水費問題をめぐっても擁護する姿勢を貫いてきた。 |
●農水大臣松岡が議員宿舎で縊死
32%(11%減)。これは5月28日毎日新聞朝刊に載った、安倍内閣支持率に関する衝撃的な数字である。その日の昼前、農林水産大臣松岡利勝が議員宿舎で縊死した。翌日旧森林開発公団理事山崎進一が自宅マンションで墜落死。その前には熊本で松岡の資金管理団体関係者が墜落死している。警察はこれらの死亡を全て自殺としている。これらの死亡事故が全て自殺かについては、筆者を含め今なお疑問視する向きもある。しかし、この一連の事故が、現在検察が捜査を進めている「緑資源機構」談合疑惑と関連がある、と言う点には疑問はないだろう。しかも、筆者はこの中で最大の衝撃だった松岡縊死は、冒頭に挙げた内閣支持率と無関係ではなかったのではないか、と考えている。
●1、事件の発端
まず松岡事件から検討してみる。死亡事由は事件以前の経緯からみて自殺と考えられる。自殺原因としては 1) 還元水問題に関して国会質問が厳しく、精神的ストレスが溜まった、2)「緑資源機構」談合問題で地検からの聴取が迫っていた、3) 闇社会の女に引っ掛かってしまった、4) その他ややこしいプライベート問題、など色々取りざたされている。しかし、一つ一つは本当かもしれないがそれだけで自殺するほどの問題とは思えない。
一方、自殺といっても自律的自殺と他律的自殺とがある。前者は従来型で、借金に困ったとか失恋したとか、自殺原因が自分とその周辺に限定されるタイプである。後者の代表はイジメ自殺である。原因は自分にはないが、周囲の不特定多数からのプレッシャーにより、心理的に自殺に追い込まれるタイプである。両者の境界は甚だ曖昧で、最近は後者は犯罪と見なされる傾向にある。松岡のケースで検討してみよう。
1) 自殺1週間ほど前の国会衆院特別委員会TV中継画面では、今から考えると松岡はかなり強度の鬱状態にあったことが推測される。
1 表情に乏しく、目も焦点が合っていないように見受けられる。
2 答弁は例の「法規に則り適正に処理している」の繰り返しである。
要するに表情・表現に起伏が見られず、精神活動が停滞状態にあるように見受けられる(筆者は精神科医ではないので判断は避けます)。
2) 鬱状態の人間に絶対やってはならないことは、「頑張れ」とか「しっかりせよ」とかいう励ましである。励ますと、それがプレッシャーとなって鬱状態を加速し、最終的に自殺衝動に駆り立てる。これは精神医学の常識である。
3) それにも拘わらず、安倍は国会でも何処でも、松岡の処置を合法的であるとして庇い続けた。これは安倍にとっては善意の表現かもしれないが、鬱状態の人間にとっては「励まし」と映り、逆にプレッシャーとなって自殺へのイニシエーターとなったと考えられる。
4) 以上のことから、安倍が松岡を庇いすぎたためにかえって松岡の自殺を招いた、と云える。
以上のこと位は誰でも考えられる。それでは面白くもなんともない。問題は安倍とその周辺がこの程度のことを見逃していたと考えられるか、ということだ。ここで安倍とその周辺とは、現在の内閣顧問である岡崎久彦、佐々淳行、森本ナントカ、中西輝正、それと番外の小池百合子らである。これらはどれも頭は悪いが狡賢いだけは一人前。但し全員集めても私一人にはかないませんが。この連中が、鬱病患者のこのような性情を知らなかったとは考えられない。つまりこの連中が安倍を叱趨して松岡に見せかけの激励を与え、結果的に松岡を自殺に追い込んだ、というケースも考えられるのである。この場合は間接殺人になる。
事件後、松岡の部屋から8通の遺書が発見されている。その内、自民党公表分には「・・・安部総理万歳。日本国万歳」と書かれてあった。松岡は1945年2月25日生まれ。筆者と全く同じ世代である。この世代は戦後民主主義教育を、そのまま受けた世代である。それが死に当たって、このような大時代なことを書くだろうか?まして「安部総理万歳」などとあることこそ怪しい。安部は長州。松岡は肥後。肥後は南北朝時代から右翼・皇国思想の強い地域である。維新後、肥後は長州主流の維新政府に対し反抗的で、神風蓮の乱を起こし、西南戦争では西郷党に組みした。だから肥後人が長州人の風下に立つことを快く思う筈がない。彼が真の右翼・民族主義者、肥後郷党なら、現世の総理大臣より、現人神である天皇への忠誠を披瀝するだろう。従って遺書は「天皇陛下万歳。大日本帝国万歳」と結ぶはずである。従って、この遺書はねつ造の疑いが濃厚である。プライバシーの問題があるとして、公表されなかった婦人宛の遺書にこそ、真実が隠されている可能性がある。
山崎の墜落死については情報が乏しく、何とも云えない。この種の事件に付き物なのは、当局は自殺と発表するが、それがなかなか真実とは受け取って貰えないことである。典型的なのは、ライブドア事件の野口死亡事件である。今回も事件発覚直後から、松岡も山崎も、「消された」という憶測が飛び交い、今も消えていない。実は筆者自身、その疑いを持ち続けている(他殺を自殺に見せかけることは難しいことではない。しかも今回は政権中枢に警察OBがいるからなお簡単だ)。
戦後
、多くの疑獄事件が発生し、その捜査過程で多くの自殺者が出ている。その線で見れば、今回の事件は通常の疑獄事件の1パターンに過ぎない。ということは、今回の事件も、これまであった事件と同じ性格のはずである。一般にこの種事件の自殺者は、事件の周辺に位置し、中核に極めて近いが末端である。自殺の目的は、事件のそれ以上の拡大を防ぎ、中核を護ることである。自殺者は事業官庁の中堅ノンポリ、周辺の業者、議員秘書が多い。希に地方議員や国会議員のケースもある(長銀事件だったか忘れてしまったが、それの新井将孝とか)。今回松岡という現役国務大臣が自殺というのは異常で、これまでの自殺者の中では最高ポストである。従って、これが中核ではないか、と思うかもしれないが、これこそが事件黒幕の思うつぼ。松岡は国会議員と言っても、頭角を現したのは、せいぜいここ10年。昔なら未だ陣笠扱いだ。つまり彼も又、何者かを護らなければならない立場にあったのである。
●2、事件当日
緑資源機構談合疑惑が注目されだしたのは、事件の2〜3週間ぐらい前からでは無かったろうか?始めはその道のプロ以外、余り注目される事件ではなかったのだ。むしろ松岡に関しては、その前の事務所費(ナントカ還元水)問題の方が話題を集めていた。筆者はこの事務所費こそが、怪しい闇社会女問題ではないかと思っているのだが、これは本人が名乗って来ない限り、真相は分からないだろう。事務所費など金額は500ン十万程度だから、恥を覚悟で公にすれば問題はなかったかもしれない。但しカミサンが薩摩か肥後の女なら、家庭内はただでは済まないだろうが。地位と女を天秤に賭けたとき、松岡は地位を取った。女を取れば、女は惚れ直したかもしれないのに。これでは女はただでは済まさない。本間も地位と女で随分揉めた。アレじゃ女は逃げて行く。問題はやはり「緑資源機構」疑惑である。無論これの捜査情報は、刻々官邸並びに政権中枢に入ってくる。問題は、これの捜査が検察から始まったことである。警察からなら、政権中枢に警察OBがいるから握りつぶせる。しかし相手が検察ならどうにもならない。そこで彼らがやったのは、松岡に対し、あくまで「しらばっくれろ」という指示だ。それを松岡は忠実に実行した。その替わり発生したのが、松岡本人の内面へのストレス蓄積と鬱病である。自殺1週間前あたりから、松岡はかなりデスペレートな感情に落入っていたと考えられる。しかし、それでも自殺という最終行為に繋がるには、何らかのきっかけが必要である。自殺当日朝、毎日新聞は、安部内閣支持率32%という驚愕的な数字を報道した。これを見た政権中枢は狼狽し、その原因を考える。第一は年金ミス問題だが、松岡還元水問題、更に緑資源談合疑惑も無視できない。直ちにそれぞれの関係先に電話を入れ、対策を報告させる。その内の一つが松岡対策で、誰かが議員宿舎に電話する。「エライことになった!君もナントカ出来ないか?(或いはこれは君のせいだ!なんとかしろ)」。これが鬱病患者に対する死刑宣告になるのである。
●
一般ピープルの人は、キャリア官僚がどういう基準で出世するかご存じでしょうか?まず最初のハードルは会計検査です。会検を如何に上手くクリアー出きるかで、その人物の将来が決まります。会検に直接対峙するのは、出先の課長又は本省課長補佐レベルの中間管理職。上手く誤魔化せれば次の昇進は約束される。逆に会検に突っつかれて逃げ切れなければ、地方転勤で将来はなくなる。その辺りを上の連中は細かく見ている。松岡は大臣といっても安部政権成立の論功行賞大臣だから、自民党的には一人前には見られていない。只の中間管理職である。そこに事務所費問題が発生し、更に緑資源機構問題が発生した。政権中枢としては、松岡が如何にこの局面を乗り切るかを見ている。そして当日朝内閣支持率32%という数字に驚いて、松岡に状況管理能力なしと判断し、引導を渡した、というのが実相だろう。そうしないと、自分達が返り血を浴びるからである。
しかし考えてみれば、松岡自殺は検察に対する強烈な牽制である。それだけでも彼らは目的を達成したと云えるだろう。 |
●農水利権
松岡の前任者は中川昭一。昭一の父はかつての農水のドン中川一郎。そして一郎の親分が戦後日ソ漁業交渉をまとめた農水のゴッドファーザー河野一郎ではなかったかと記憶している。このうち中川一郎は謎の自殺?を遂げている。河野は児玉譽志夫なんかとの繋がり等ややこしい噂に事欠かない人物である。そもそも鳩山寄りの党人派で、保守合同で自民党に参加するが、岸内閣以降は概ね反主流派。若き中曽根が鞄持ちをやっていた。この河野一郎−中川一郎の線で、戦後農水関連闇社会(旧秩序)が形成されていった。以来戦後農水政は歴代河野派の縄張りとなった。
平成11年農用地整備公団が森林開発公団に吸収され、平成15年(独法)緑資源機構に改組される。このように組織が矢継ぎ早に変わると、組織の糸が断ち切られ、利権が分散する。そこに松岡のような新興勢力が、利権に食い込む隙間が出きるのである。
事件翌日の毎日新聞朝刊に面白い紹介記事が載っていた。平成13年、熊本県のある林道造成工事で、地元業界が押す地元業者が外され、県外の大手ゼネコンとそれに手を組んだ業者が工事を落札した。そしてこれを強引に主導したのが松岡利勝だ、というのである。これは公団合併の翌々年のことで、業界秩序も混乱していたから出来たことだろう。一見、旧秩序(伝統談合組織)に対する新興パワー(という名の新談合組織)の挑戦と受け取れる。実はこれは、昨年社会を騒がせた和歌山県談合事件構図とそっくりなのである。これも元もとあった伝統談合組織に挑戦する形で、前知事が大林組と組んで強引に県外業者を引き込んだから起こった新旧抗争事件。ここでも元和歌山県幹部が自殺?している。おそらく松岡のやり方は旧秩序を”ぶっつぶす”という形で、当時のコイズミ政権への受けはよかったのではなかったろうか。そして旧秩序への挑戦という姿勢は、安部政権下でも評価が高かっただろう。ここで勘違いしてはならないのは、松岡のやったことは談合構造そのものを壊すことではなく、業界利権を右のポケット(伝統談合組織)から左のポケット(新談合組織)に移し替えるだけのことである。ここに新旧両秩序の抗争が発生する。そこに農水利権周辺の闇社会が関与してくると、事態は急速に決定的状況に突き進む。
新秩序の代表が松岡利勝というのは概ね正しいだろう。では旧秩序の代表は誰か?血筋・筋目から云って中川昭一がそれに該当するだろう。つまり、事件の背後に中川vs松岡の確執・抗争があったと云うことだ。中川は安部の次の次の、更に次ぎ位を狙っているだろう。彼の地盤は農水利権。ここに松岡が割り込んで来ることは許されない。中川昭一と右翼・暴力団との関係は色々取りざたされている。中川が直接手を下したとは云わないが、新旧の抗争が最早抜き差しならない段階に至っていたことは、十分推測できる。翌日の仮通夜で、某TVの夕方のニュースが中川にカメラとマイクを向けていた。本来なら親分の伊吹文明とか、副総理格の麻生あたりにインタビューするのが筋なのに、何で中川にと不思議に思ったのである。ひょっとすると中川vs松岡の抗争が、業界でも話題になっていたのかもしれない。だからといって、これが松岡本人の直接自殺原因にはならない。
松岡疑惑は大きく、 1)例の事務所費、2)熊本緑資源機構談合疑惑、3)緑資源機構を使った更なる利権疑惑、の3者に分けられる。ここで1)は500ン10万の話しで、これこそ女がらみの金かもしれない。但しこの女が旧秩序に関連する闇社会からの刺客とすれば、2)と無関係ではなくなる。2)は何処にでもある話しである。無論問題としては小さくはないが、山崎が消えればそこで疑惑の線が消えるので、松岡まで自殺すべき理由はない。残るは3)のケースである。松岡は何を護ろうとしたのか?或いは護らざるを得なかったのか? |
●杉花粉対策・緑資源機構
都知事選の前、石原慎太郎が妙な構想をブチ挙げています。杉花粉対策で「・・・政府が何もしないから、都が金を出して今の杉を伐採して、(DNA操作によって)花粉の出ない杉に植え替える」というものです。例によって政府を悪者に仕立て(実は安部との出来レース)、自分は正義の味方をするポーズ。一見かっこよく見えるこの構想ですが、実はこのような問題が隠されています。
1) 新種の杉はDNA操作を伴うもので、周辺の植物相への影響が懸念される。植物生態環境への悪影響については安全性が立証されていない。永年の間に、この杉も花粉を発生する遺伝特質を獲得する可能性がある。その場合、更に新種の開発が必要になるので、問題は際限なく繰り返されることになる。
2) 花粉対策としては、間伐とか温暖化対策とか、取られるべき中間対策があるのに拘わらず、いきなり種の交替のような最終解決に向かおうとしている。
3) 新種の杉でも生育には20〜30年が必要である。その間斜面は植生が不十分になり、災害抵抗力が劣化する。しかも今後温暖化が進み、強雨が襲来するケースが多くなる。つまり、杉対策で新種杉が育つのを待っている間に、山地崩壊が進行し、災害が増えるのである。
4) これまで花粉症で死んだ人間はいない。マスクで十分防げるのである。しかも今後の日本人はDNA が進化し、いずれ対花粉能力を獲得するはずである。
つまり、こんな大げさな花粉対策は必要ではない。ところが、これには莫大な利権が絡んで来るのである。
1) 杉苗供給企業。日本にはDNA組み替え企業は未だ未成熟である。一番考えられるのはジェネンテックのような海外企業か、それと提携した商社。莫大なバックが期待出きる。ブッシュ政権への後押しにも有効だろう。
2) 既存森林の伐採と植林を請け負う緑資源機構指定林業企業。地域ごとに談合組織を作っている。
3) 森林伐採に伴って、当然防災工事が必要になる。これを請け負う土建企業。従来は地域の地場産業だが、最近は大手も黙っていない。
4) 当初は東京都だけかもしれないが、直ぐに全国規模に拡大される。莫大な利権の誕生である。
5) これらを全て取り仕切るのが、緑資源機構(だったはずだ)。
松岡が本当に隠したかったのは、この構想に関連するスキャンダルではなかったか?慎太郎は松岡死後、「潔い死だ」などと、偉く松岡を褒めちぎっているらしい。なにが潔かったのでしょうか?ほっとけば疑惑追及という花粉が飛んでくるのを防いでくれたんだから有り難いはずだ。そう言えば、最近安部はイヤに環境がお気に入りのようだ。 |
●「緑のオーナー」投資
今頃になって、昔の「緑のオーナー」投資の焦げ付きが発覚。そう言えば、何10年か前に、こんなものがあったのを思い出しました。林野庁の甘言に載せられて、ン百万か投資したところ、払い戻しが良くて60%、下手すりゃ20%。確か当時マスコミは、環境に優しい素晴らしい政策などと吹聴しまくっていたのではなかったか。それで集めた金を何に使ったか?が問題。林野工事、つまりかなりの部分が林野談合に消えたのは間違いはないだろう。まさか松岡は、これの発覚を予期して自殺したのではなかろう。しかし、仮に自殺していなくても、この問題が出てくるから国会対応は大変だ。果たして次の安倍内閣で農水相を引き受ける奇特な人はいるでしょうか? |
 |
●緑資源機構
2007/6
疑惑は緑資源機構の受注業者でつくる特定森林地域協議会(特森協)と、その政治団体・特森懇話会の存在だ。公正取引委員会が同機構に立ち入り検査に入ると、同機構の前身の森林開発公団元理事で、自殺した特森協副会長の指示で両団体とも直後に解散した。同副会長は緑資源機構主導の受注調整の仕組みをつくった人物で、政界の窓口役といわれていた。特森協には約330社が加盟、機構からの受注額2000万につき75000円が会費として徴収され、松岡氏ら林野族議員に流れる仕組みになっていたといわれる。特森懇話会の政治資金収支報告書によると、資金提供を受けていた政治家は、松岡氏のほか、中谷元・元防衛庁長官、青木幹雄参院議員会長、佐藤雄平参院議員(現福島県知事)、綿貫民輔前衆院議長など21人にのぼる。もう一つは、熊本、島根両県で進む総額約270億円の同機構発注の特定中山間保全整備事業をめぐる談合疑惑。松岡氏が自殺したのは、特捜部の家宅捜索が同事業発注元の九州整備局や、宮崎、島根の特森協元幹部の会社に及んだ直後だった。松岡氏は、同事業のうち熊本県の阿蘇小国郷区域の林道工事などを受注した業者14社から1340万の献金を受け取っていた。青木参院議員会長にも特森協松江協議会関係を中心に2000万を超す献金があった。緑資源機構が行う事業は大半が補助金で、受注企業からの献金は、いわば税金の還流と言われても、政治的道義的責任は免れられない。 |
●緑資源機構 2
独立行政法人緑資源機構が主導した林道整備業務の受注を巡る談合事件。
2007年、林道整備業務の受注を巡って、機構側主導による常態的な談合疑惑が発覚する。同年5月24日、東京地検特捜部は公正取引委員会の告発を受け、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で同機構の理事及び受注法人の担当者ら6人を逮捕し、同機構本部を強制捜査した。同日、理事長で自らも林野庁OBである前田直登は、給与の20%を3か月自主返納するが、辞任はしないとする考えを示した。
また、同機構から工事を受注する業者らが構成する特定森林地域協議会とその政治団体「特森懇話会」が、松岡利勝農林水産大臣(2007年当時、以下同じ)らに政治献金をしていたと指摘されている。後任大臣の赤城徳彦も、「特森懇話会」から約40万円分の政治資金パーティー券の購入を受けていたことが、就任初日に判明している。
林野庁や同機構OBの再就職先(天下り)を受け入れた企業を優遇し、互いに利を得るシステムの解明が始められている。
2007年5月18日に松岡利勝農林水産大臣の地元事務所関係者の損保代理店社長が自宅で自殺している。また、5月28日には松岡利勝農林水産大臣が議員会館で首つり自殺している。翌29日には、同疑惑に関連して捜査を受けていた山崎進一(前身の森林開発公団理事で同機構にも強い影響力を持っていた)が自殺している。
同年5月30日、規制改革会議が緑資源機構の林道整備と農用地整備の主要2事業の廃止を求め、事実上の組織解体を促していたところ、6月1日、農林水産大臣に就任した赤城徳彦は、農林水産省が機構の廃止を事実上決めたことを明らかにした。9月30日、林野庁長官出身の前田直登理事長が引責辞任し、民間から町田治之が理事長に就任した。
2008年3月31日、緑資源機構は廃止され、同機構の海外業務は国際農林水産業研究センターに、農用地整備等は森林農地整備センターに引き継がれた。森林農地整備センターの初代所長には緑資源機構理事長の町田治之が就任した。
|
●郵政民営化バーゲンセール「かんぽの宿」一括売却へ
2008/3
日本郵政が全国71ヵ所で営業中の「かんぽの宿」の売却準備に入った。3月中旬から、日本郵政の委託を受けた資産査定部隊が、全国の施設状況を調べている。
調査は2人1組で、実際にかんぽの宿に宿泊し、サービス内容や運営実態についてヒアリング。周辺の競合施設や観光スポットまで訪れている。次に別の調査が来て、土地、建物の現況、たとえば耐震性や設備詳細まで確認する念の入れようだ。
かんぽの宿は、簡易保険の加入者福祉施設。郵便貯金の宣伝施設「メルパルク」(旧・郵便貯金会館、現在11施設が営業中)と並ぶ郵政グループのホテルである。本省幹部、地方郵便局長、労働組合幹部まで、郵政関係者の天下り先確保のために、大量の資金が簡保、郵貯から投じられてきた。
民営化に当たって、かんぽの宿もメルパルクも、日本郵政の宿泊事業として集約され、民営化から5年以内に売却または廃止することが決まっている。まだ公表はされていないが、日本郵政は資産売却のアドバイザリー契約を結び、4月にも競争入札を実施する構えだ。
ただし、売却は難航するか、買いたたかれるのが必至である。かんぽの宿は全国に散在し、老朽化した施設が多い。しかも日本郵政は全施設の一括売却と、全従業員(もちろん天下りOBを含む)の引き受けを希望している。こんな条件をのめる企業は多くない。
加えて、今回売りに出されるのは、かんぽの宿のみ。同じ簡保が運営していた都心のシティホテル「ゆうぽうと」も、都市部の一等地で営業中のメルパルクも今回の一括入札には含まれない。「ポンコツだけ売って含み益のある物件は温存するのではないか」との疑念を関係者が抱くのも当然だ
。
仮に売れたとしても、巨額の売却損計上は避けられまい。郵貯関連のホテルで、250億円を投じたメルパール伊勢志摩が4億円、同じく210億円を投じたメルモンテ日光霧降は7億円で売った。これらの売却損は、本来なら郵貯利用者が受け取るはずだった逸失利益である。
一方、日本郵政は民営化に伴って株式公開買い付けで郵便物輸送会社「日本郵便逓送」を子会社化した。同社のもともとの筆頭株主は郵政職員の共済組合(郵政OBの天下り先ともなっている日本郵政共済組合)で、売却によって約100億円の利益を得た。
言い換えれば、簡保・郵貯利用者が本来得られたはずの逸失利益が顕在化する一方で、天下り先団体、ひいては郵政職員には巨額の利益が還元されているわけだ。
郵政民営化の一環で「ファミリー企業」と呼ばれる天下り先団体の改革に着手はしたが、その道のりは遠い、徹底的な見直しがなされべきだ。 |
●かんぽの宿
2007年10月1日の郵政民営化までは、簡易生命保険法第101条に基づき設置された、簡易保険加入者のみを対象としたもの。そのために宿泊施設として利用が可能な保養施設・老人福祉施設という「福祉施設」の位置付けであった。簡易保険加入者の福利厚生増進が目的の宿とされた一方で、郵便貯金会館やその他の官庁の「公共の宿」などと同様に、かんぽの宿が旧郵政省簡易保険局幹部の天下り先確保の目的もあったことは、旧郵政省時代の人事から明らかであ
る。天下りを防止するため日本郵政公社設立の際に旧簡易保険局から切り離されて、日本郵政公社直営となった。
民営化に際し、同趣旨で設置されたゆうぽうと(旧・東京簡易保険会館)と共にかんぽ生命保険ではなく日本郵政株式会社が運営する旅館・ホテルとなった。メルパルクとともに旅館業法に基づいて運営しており、簡易保険の加入の如何を問わず利用可能となった。
「かんぽの宿」は民営化以前は愛称であり、正式には「○○保養センター」「○○加入者ホーム」が正式名称で、民営化時に「かんぽの宿○○」が正式名称となった。
2012年9月までの期間は業務として廃止・売却を行うことが日本郵政株式会社法にて義務付けられ(期間内の全施設の廃止・売却は義務付けられていない)、年間約40億円の赤字が出ることから、2008年12月26日、2009年4月に全て一括でかんぽの宿(ラフレさいたまと首都圏の社宅9件を含
み、日本郵政算出資産総額/約93億円)をオリックス不動産に約109億円で売却することを発表した。
しかし、一括売却先が郵政民営化を検討した当時の総合規制改革会議議長・宮内義彦が最高経営責任者をつとめるオリックスグループの企業であったことから、鳩山邦夫総務大臣が「オリックスは立派な会社だが、譲渡に国民が納得するか。出来レースと受け取られかねない。率直にまずいと思う」と、売却の前提となる「日本郵政の会社分割」についての総務大臣認可に極めて慎重な姿勢を示して、売却までには紆余曲折が見られる。
なお、2007年に鳥取県岩美町の「かんぽの宿 鳥取岩井」を、東京の不動産会社が旧日本郵政公社から1万円で一括で買い上げ、直後に6千万円で鳥取市内の医療法人が同町内に設立した社会福祉法人に転売されていたことがわかっ
ている。
|
 |
|
●緑資源機構の廃止 〜廃止に至る経緯と今後の対応〜
|
●はじめに
これまで主に林道整備事業や水源林等の植林事業等を担ってきた独立行政法人緑資源機構(以下「緑資源機構」という。)が平成19 年度をもって廃止されることとなった。これを実施するために、平成20 年2月1日、「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律案」が第169 回国会に提出された。これまで独立行政法人の事業・事務の見直しに伴う組織の改廃、廃止はあったが、はじめに組織の廃止ありきで検討が進められた初めてのケースである。
緑資源機構の廃止は、平成19 年12 月24 日に閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」において、19 年度限りで廃止(解散)、その業務の一部を森林総合研究所及び国際農林水産業研究センターに承継させる等の措置を講ずることが決定されたが、廃止の実質的な原因は、平成18 年10 月に発覚した「談合事件」である。
本件は、官製談合といった構造から政治家の資金管理団体への不適正な献金など幅広い論点を含んでいるが、本稿では、いわゆる「緑資源機構」談合事件の経緯、そして緑資源機構が実施していた事業・事務の概要に絞って記した。
|
●1.独立行政法人緑資源機構の概要
緑資源機構は、「独立行政法人緑資源機構法(平成14 年法律第130 号、以下「機構法」という。)」に基づいて設立された法人である。機構の目的は、機構法第3条において次のとおり定められている。
「農林業の生産条件、森林資源及び農業資源の状況等からみてこれらの資源の保全及び利用を図ることが必要と認められる地域において、豊富な森林資源を開発するために必要な林道の開設、改良等の事業を行うとともに、水源をかん養するために必要な森林の造成に係る事業及びこれと一体として農用地、土地改良施設等を整備する事業等を行い、もって農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に資すること。」
緑資源機構は、「農用地整備公団(昭和30 年に農地開発機械公団が設立、昭和49年に同公団は農用地開発公団へ改組、昭和63 年に八郎潟新農村建設事業団を吸収改組し農用地整備公団となる)」と、「森林開発公団(昭和31 年設立、昭和57 年に海外農業開発業務、昭和63 年に農用地総合整備事業等を業務に追加)」を統合して平成11 年に設立された「緑資源公団」を前身とする。緑資源公団は、平成9年の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」を受けて統合、設立されたものであった。
その後、平成11 年の「独立行政法人通則法」の制定、そして平成13 年閣議決定「特殊法人等整理合理化計画」を受け、同公団の独立行政法人化が決定、平成15 年10 月1日、独立行政法人として改めてスタートした。
|
●2.緑資源機構の廃止決定への経緯 (後掲(参考)を参照)
平成18 年10 月31 日、緑資源機構の林道整備事業に係る「測量・建設コンサルタント業務」契約において、談合の疑いがあるとして公正取引委員会が調査を開始した。その後、本事件の概要が明らかになるにつれ、この事件が、以前の上司と部下など、特別な人間関係をもとにした事件であることが明らかになり、単なる談合事件というに留まらず、「官製談合事件」として問題とされた。
事件の発覚以来、農林水産省、緑資源機構では公正取引委員会の調査に協力するとともに、入札制度改革委員会や緑資源機構談合等の再発防止のための第三者委員会を設置、再発防止策や今後のあり方を検討していた。
その後、平成19 年5月30 日、政府の「規制改革会議」の第一次答申が公表された。ここでは、緑資源機構の「幹線林道整備事業」と「農用地整備事業」といった主要な事業の廃止を求めるものであった。ところが、その2日後の6月1日、故松岡農相の後を引き継いだ赤城新農相は就任記者会見で、緑資源機構を「廃止の方向で検討するよう事務方に指示した」と述べた。
緑資源機構の廃止は、事業・事務の必要性や組織の廃止の是非等の検討とは別次元で、急遽、組織の廃止の方向性が示された感がある。ただ、談合防止や官公庁の契約のあり方については、農林水産省や緑資源機構に設けられた委員会等で十分に検討され、農林水産省が所管する独立行政法人にコンプライアンス委員会等が設置されることとなるなど一定の改善が見られた。今後、こうした検討の結果が広く官公庁の契約事務に横断的に活かされることが重要である。
なお、農林水産省の「独立行政法人評価委員会林野分科会」は、緑資源機構の各年度の事業評価について、同機構の設立以降平成15 年、16 年、17 年度の各年度の総合的な評価をA評価(もっとも良い評価)としたが、談合事件が明らかとなった18 年度は談合問題を受け4つの項目でD評価を付け、総合評価でB評価した。
今後、評価のあり方と組織の存廃との関係が議論されてよいだろう。
(注) 評価基準(A〜Dの相違)
独立行政法人評価委員会資料によると、評価は、A:中期計画に対して概ね順調に推移している(達成割合が90%以上)、B:中期計画に対して一部遅れが見られるものの、中期目標期間において達成が可能な範囲にある(達成割合が50%以上90%未満)、C:中期計画に対して顕著な遅れが見られる(達成割合が50%未満)の三類型とされているが、C評定のうち、要因を分析し、特に業務の改善が必要と判断されるものについては、D評定とすることができるとされている。
|
●3.緑資源機構の担っていた主な業務と今後の対応
●(1)幹線林道事業
ア.本事業は、地勢等の地理的条件が悪く、かつ豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域において、林道ネットワークの軸となる幹線林道を整備する事業である。全体計画は32 路線ですでに5路線が完成、計画延長2,013km に対し1,312km が整備されており、進捗率は65.2%である。
イ.緑資源機構廃止後は、独立行政法人が行う事業ではなくなり、関係地方公共団体が事業継続の是非を判断し、必要とされた場合には、国の補助事業として実施することとされ、未整備区間の27 路線、約700km について、事業の実施主体が北海道等15 道県に移管されることとなった。
最近5ヵ年の整備延長(km)と事業費(百万円)の実績(平成19 年度は当初)
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
延長 28.2 27.4 25.0 24.7 27.1
事業費 16,620 16,180 15,048 14,553 14,114
●(2)水源林造成事業
ア.本事業は、水源地の森林を復旧し水源をかん養するため、森林所有者自らによる造林が困難な奥地水源地域での造林事業であり、緑資源機構が「分収林特別措置法(昭和33 年法律第57 号)」に基づく分収造林契約の当事者となり水源の森を整備する事業である。これまで45 万ha で実施、今後6万ha の植栽を計画している。
イ.本事業は今後の森林整備における「基幹的事業」と考えられており、緑資源機構廃止後も当面は森林総合研究所が実施することとされている。そして、平成22 年度に行われる予定の国有林野事業特別会計の見直し(同特会事業の独法化等)の際、改めて事業継続の是非が検討される。
最近5ヵ年の新植面積(ha)と事業費(百万円)の実績(平成19 年度は当初)
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
新植面積 4,443 4,435 4,498 3,923 3,620
事業費 40,914 40,372 39,607 45,010 38,207
●(3)特定中山間保全整備事業
ア.本事業は、森林と農用地が混在する中山間地域において、農林業の一体的振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進を図るため、「森林整備」、「農用地整備」、「土地改良施設整備」等を一体的に実施する事業であり、全国3区域(熊本県阿蘇小国郷区域、島根県邑智西部区域及び北海道南富良野区域)で実施している。
イ.緑資源機構廃止後は、森林総合研究所が実施することとされているが、実施中の3区域の完了をもって廃止することとされた。
最近5ヵ年の事業区域(件数)と事業費(百万円)の実績(平成19 年度は当初)
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
事業区域 1 1 2 2 3
事業費 651 1,279 2,293 2,738 3,663
●(4)農用地総合整備事業
ア.本事業は、農業生産基盤(農用地)の整備を急速に図ることが必要かつ効果的と認められる農業地域内において、農用地及び土地改良施設の整備を総合的かつ集中的に行う事業で、これまで全国20 区域で実施、20 年度以降の残区域は6区域である。これまで農用地整備は3,471ha、農業用道路整備は315km が整備されている。
イ.本事業は、15 年度の1案件の採択以降、新規採択はなされておらず、緑資源機構廃止後は、森林総合研究所で実施するが、現在実施中の区域の完了をもって廃止することとされた。
最近5ヵ年の事業区域(件数)と事業費(百万円)の実績(平成19 年度は当初)
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
事業区域 13 10 8 7 7
事業費 25,598 24,006 21,938 21,197 20,148
●(5)海外農業開発事業
ア.本事業は、途上国での砂漠化防止や農業農村開発といった海外農業開発を促進するための事業である。これまでエチオピアやマリでの砂漠化防止事業、ボリビアやパラグアイでの土壌侵食防止事業等を実施するとともに、アフガニスタンや東ティモールで農民参加型むらづくり手法の実証調査を行っている。
イ.本事業は、途上国の砂漠化地域における植林による緑化等を行ってきたが、これは、「独立行政法人国際農林水産業研究センター」の農村開発事業等と同様、政府開発援助の実施であり、緑資源機構廃止後は、同センターが引き続き実施する。
最近5ヵ年の事業数(件数)と事業費(百万円)の実績(平成19 年度は当初)
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
事業数 8 12 15 24 17
事業費 648 781 904 910 894 |
●4.今後の林野関係独立行政法人のあり方
●(1)森林総合研究所の事業・事務の確保
森林総合研究所は、森林に求められる機能、すなわち、地球温暖化対策に係るCO2吸収源対策の基礎研究、ストレスの低減など森林の健康増進作用をはじめとする新機能の研究、無花粉スギの開発や林業におけるコスト低減策や効果的な間伐実施方法、さらに種の保存といった様々な分野にかかる研究が期待されている。今回、緑資源機構が廃止されることで、本研究所が、一定期間ではあるが「事業」の実施主体となること、また、同機構の負担金等にかかる債権債務の管理事務といった、研究以外の業務が本来の事務である研究業務にどういった影響を与えるかが懸念される。そこで今回承継される「事業」の実施については、研究業務への影響度合を適宜チェックして、業務の見直し、必要であれば「事業」の特別会計等、国の直轄業務としての移管が検討されるべきであろう。
●(2)今後の水源林造成事業の事業主体
水源林造成事業は、執行の透明性、効率性を徹底したうえで森林総合研究所が経過的に実施、平成22 年度に「国有林野事業特別会計」の組織の見直し(独法化・一般会計化)とともに、整理される予定となっている。この、国有林野事業特別会計は、国の直轄事業として公共事業の「治山事業」を実施しており、水源林造成という「事業」を実施するには適当と考えられよう。ただ、同特別会計は、多額の累積債務の処理に取り組んでいるところでもある。すなわち、平成10 年に、同特別会計の累積債務3兆8千億円を整理するため関連法を制定、同特別会計の運営の重点を「木材生産」から「森林の公益的機能の維持増進」に転換するとともに、累積債務を整理するため、一般会計にその債務の一部を承継させ、それ以外の債務につき同特別会計が一般会計より利子補給を受けつつ50 年の長期にわたり返済することとされた。同特別会計の平成17 年度末現在の債務残高は1兆2,796 億円となっている。今後、緑資源機構の事業等を引き継ぐことで、この累積債務の処理に影響が出ないかが心配である。そこで、事業内容の必要性、費用対効果等を十分に検討し、独法で実施するべきものと国が直轄して実施するものを改めて検討する必要があろう。
●(3)幹線林道事業の地方負担
幹線林道事業については、地方公共団体を事業主体とする補助事業に移行することとしたが、これについては、「関係する地方公共団体との合意形成もないままに、一方的に補助事業に移行させる」ものとの声もある。「地方に新たな負担を強いることなく、国直轄事業への移行など国の責任において事業を継続すること」とする地方の意見も強い(高知県議会意見書(平成19 年10 月10 日等))。今後、林道網の整備は、日本全国での間伐の推進といった面から考えて、一地方に負担を押し付けるものであってはならない。地方の自主性・自律性を尊重しつつも、国の関与度合をどう維持するのか、慎重に検討する必要がある。
|
 |
●参考 / 緑資源機構談合事件の経緯
○平成18年10月31日 公正取引委員会が、緑資源機構が発注する林道事業の「地質調査・調査測量設計業務」に関する談合の疑いで、同機構のほか、受注公益法人(6公益法人)、民間事業体に立ち入り調査を実施。
○平成18年11月 1日 農林水産大臣から緑資源機構理事長に対し、公正取引委員会の調査に全面的に協力するよう指示。
○平成19年 1月10日 緑資源機構に「入札制度改革委員会」を設置。
○平成19年 3月27日 「入札制度改革委員会」が「中間とりまとめ」公表。
○平成19年 4月 2日 公正取引委員会が行政調査から犯則調査に切り替えるとの報道。
○平成19年 4月 2日 農林水産大臣から緑資源機構理事長に対し、公正取引委員会の調査に全面的に協力するよう再度指示。
○平成19年 4月19日 公正取引委員会が緑資源機構や受注法人に対し強制調査を開始。
○平成19年 4月27日 農林水産省に「緑資源機構談合等の再発防止のための第三者委員会」を設置。
○平成19年 5月24日 公正取引委員会が受注4法人を独占禁止法違反で刑事告発(財団法人である林業土木コンサルタンツと森公弘済会、そして民間企業のフォレステックと片平エンジニアリング)。東京地検が緑資源機構及び受注法人の役職員等6名(緑資源機構元理事と元課長、林業土木コンサルタンツ元環境部長、森公弘済会業務第2部長、フォレステック元技術本部長、片平エンジニアリング企画営業部技師長)を逮捕。
○平成19年 5月24日 「緑資源機構問題について」とする松岡農林水産大臣(当時)の談話を公表。本件を「公共工事の入札に絡む談合事案であるということだけでなく、発注者側がこれに深く関与していた、いわゆる官製談合」とし、「抜本的な再発防止策を検討」としていた。また、本件の事態を厳しく受け止め、農林水産大臣が給与月額の3か月分を自主返納するとともに、山本、国井両副大臣、福井、永岡両政務官、さらに事務次官及び林野庁長官もおのおの自主的に給与の一部分を返納することとした。
○平成19年 5月30日 内閣府の「規制改革会議」が「規制改革推進のための第1次答申」を公表。幹線林道事業と農用地整備事業について「今後、新規採択は行わず、既着工路線・地区についても費用便益分析を実施して、費用便益比の低い路線・地区の工事の中止等必要に応じて事業規模・規格の見直し・縮小を行い、緑資源幹線林道事業は現在の着工路線の工事が終了した段階で、農用地総合整備事業は既着工地区が終了した段階で、事業の廃止を決定すべき」とした。
○平成19年 5月31日 緑資源機構に「入札談合再発防止対策等委員会」を設置。
○平成19年 6月 1日 故松岡農相の後を受けて新たに就任した赤城徳彦農相が、就任記者会見で「(緑資源機構は)廃止の方向で検討するよう事務方に指示した」と述べた。
○平成19年 6月13日 公正取引委員会が緑資源機構及び受注法人の役職員等7名を刑事告発。東京地検が受注4法人及び関係者7名を独占禁止法違反(不当な取引制限)で起訴(5月に逮捕された6人のほか林業土木コンサルタンツ元環境部長)。
○平成19年 6月22日 政府が閣議決定で「規制改革推進3カ年計画」を決定、緑資源機構の主要事業の廃止について、19年度内に結論を得て速やかに措置することが決定された。
○平成19年 7月26日 農林水産省「緑資源機構談合等の再発防止のための第三者委員会」が「中間とりまとめ」を公表。
○平成19年 8月 9日 緑資源機構「入札談合再発防止対策等委員会」が「中間とりまとめ」を公表。
○平成19年 9月27日 農林水産省に「緑資源機構の入札監視のための委員会」を設置。
○平成19年11月 1日 機構元理事及び元課長の2名、関係4法人及び同役職員5名に対し有罪(執行猶予)の判決。判決では「血税を無駄に費やす官製談合を続け、国民の犠牲の上に自分たちの組織の温存を図ろうとした恥ずべき犯行」とした。
○平成19年12月24日 「独立行政法人整理合理化計画」閣議決定において、緑資源機構の廃止の方針が最終的に決定された。
○平成19年12月25日 緑資源機構「入札談合再発防止対策等委員会」が「入札談合再発防止対策に関する調査報告書」を公表。
○平成19年12月25日 公正取引委員会は、21法人が独占禁止法違反に関与したと認定、解散が決まっていた2法人を除く19法人に独占禁止法第7条第2項に基づく排除措置命令、うち13法人に対し独占禁止法第7条の2第1項に基づく課徴金納付(計9,612億円)を命じた。緑資源機構に対して入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為を認めたものの19年度末に解散されることから同法に基づく改善措置は求めないこととされた。
○平成20年 2月 1日 「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律案」を閣議決定、同日、第169回国会に提出された(閣法第22号)。 |
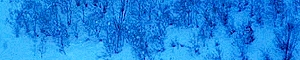 |