���Ɋy��y1�E�Ɋy��y2�E�Ɋy��y3�E����̐��E�E�։�Ə�y���E�E�E
������̐��E�E�։��]���E���{�l�̎���̐��E�E�����ւ̐������E����̍Ղ����E����̐��E�T���E�썰�̂䂭���E���Ƃ����E�E�E
�@
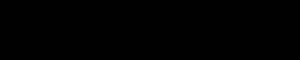
�e���r�@�S�ǁ@
�����@�����ҁE���l��

���̂g�o�@���炭���x��
�ł�����̂Ȃ�@�E�E�E

�����̃R�����e�[�^�[�@�e�X�̉f�郂�j�^�[�@�ԑg��ʂɕ���
�g�@�z�@�B�ɕ����߂���

���� �E �s�� �E ���� �E ���ɂ��� �E �蔲��
�������� �E �ق����炩�� �E ������ςȂ� �E �������� �E ������ �E �ӑ� �E �Ӗ� �E �ӂ���

���̒��̏펯
�����ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ�

���ʂ͎葫�@�A�C�f�A�͔F�߂��Ȃ��@����
�]���Ȃ��Ƃ͍l���Ȃ��Ȃ����@����

�_���̐��E�@���ׂ�

 �V�@�@�@
�V�@�@�@�@�@�@
 �����@�@�@
�����@�@�@�@�@�@
 �m���̌��t�@�@�@
�m���̌��t�@�@�@�@�@�@
 �Ɋy��y�ƓV���@�@�@
�Ɋy��y�ƓV���@�@�@�@�@�@
 ��ƗH���@�@�@
��ƗH���@�@�@�@�@�@
 �Z���̒��@�@�@
�Z���̒��@�@�@�@�@�@
 �����@�@�@
�����@�@�@�@�@�@
 ��(����)
��(����)�@�@�@
 ���@�E���O
���@�E���O�@�@�@
 �����E��͔���
�����E��͔����@�@�@
 ���r / ���c�S�ԁE�䐶�_�E���r�̔�r
���r / ���c�S�ԁE�䐶�_�E���r�̔�r �@
�@ �@
�@

�ߑ��̒a���ɂ��ėl�X�ȓ`��������܂��B�`���͗��j�I�����ł͂���܂���B�������A�P�Ȃ���b�ł͂Ȃ��A�^����`���悤�Ƃ������̂ł��B�@
�ߑ��͒a������Ƃ����ɁA�������邢�āA�E��œV���w���A����Œn���w���āA�u�V��V���@�B��Ƒ�(�V�ɂ��n�ɂ�������Ƃ葸��)�v�Ɛ錾���ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B�����Ă��̎��A�V�͊������A�ØI�̉J���~�点���ƌ����܂��B�@
�ߑ��̒a���ɂ��āA�l�X�ȓ`�����`����Ă��܂��B�`���ł�����A���j�I�����ł͂���܂���B�������A�P�Ȃ���b�ł͂���܂���B�`���́A������`���悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�^����`���悤�Ƃ��Ă���̂ł��B�ł�����A���̓`��������`���悤�Ƃ��Ă���̂�������Ă������Ƃ���Ȃ̂ł��B�@
�u�������邢���v�Ƃ������ƂA�����̐��E�ł���Z��(�n���E��S�E�{���E�C���E�l�ԁE�V��)�����Ƃ������Ƃ�\���܂��B�a���Ɠ����ɖ������Č����J�����킯�ł͂���܂��A��Ɍ����J���ĕ���(�ڊo�߂���)�Ɛ������ƌ������Ƃ��A�a���̏��Ɉ����ĕ\�����Ă���̂ł��B�@
�u�V��V���@�B��Ƒ��v�Ƃ����錾�́A�����āu���l�Ɣ�ׂāA���̐��̒��Ŏ�������ԑ����v�Ƃ����햝�ȈӖ��ł͂���܂���B�u���̂��̂��́A�V�ɂ��n�ɂ��A���̐��̒��ɂ�����������Ȃ��A���������̂Ȃ����̂��ł���B�������A���̂��̂��͖����̈Ӗ����e�������Ă���B�����炱�����̂��̂��͑����v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��B�����āA����́A���̂��̂��ɂ̂����邱�Ƃł͂Ȃ��A�u���ׂĂ̂��̂��́A���������̂Ȃ��������̂ł���v�Ƃ������ƂɂȂ���̂ł��B�@
���Z���ɂ��ā@
�O��(��������)�����ꂼ��̍s�ׂɂ���Ď���������̐��E�̂��ƂŁA�Z��Ƃ������܂��B�@
�@�@�@�n���|�ꂵ�݂̋ɂ܂������E�B�@
�@�@�@��S�|�Q�������ɋꂵ��ł��鐢�E�B�@
�@�@�@�{���|�p������Ȃ����E�B�@
�@�@�@�C��(���C��)�|�����̐��E�B�@
�@�@�@�l��(�l)�B�@
�@�@�@�V��(�V)�|��т̐��E�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�ϔY�𗣂�Ă��Ȃ��̂ŁA�₪�ĕ����B����������̐��E)�B�@
�Z���ɂ��ẮA�����̂��ƂƂ��Ăł͂Ȃ��A�����݁A���̂悤�Ȑ��E�Ɏ�悤�ȐS���A�s�ׂ����Ă���Ƃ������Ƃ��l���Ă݂邱�Ƃ���ł��B

���B�̐S�ɂ͏\�̐��E������Ƃ����Ă��܂����A���l�̋������܂ł͘Z���ƌ����ĘZ�̐��E���s�����藈���肵�Ă��܂��B�@
���Z���@
�@�@�@�n���E / �{��̐S�@
�@�@�@��S�E / �×~�ȐS�@
�@�@�@�{���E / �����ȐS�@
�@�@�@�C���E / �����̐S�@
�@�@�@�l�E / ���₩�ȐS�@
�@�@�@�V��E / ��тŖ�������Ă���S�@
���l���@
�@�@�@�����E / ���l�̋������Đ��̂킸�炢�𗣂ꂽ�ҁ@
�@�@�@���o�E / ���l�̋������čX�Ɏ����̓��X�o�����Ƃ���̏o�����Ǝv��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���킹�Ă��̉��Ɉ����Ċo��悤�ɏC�s����l�@
�@�@�@��F�E / ���������ڎw���ďC�s���Ȃ�������҂����߂̐S�Ő�ɋ~�����Ƃ���l�@
�@�@�@���E / ��Ε����̋��n�ɂ���O����厜��߂ŋ~�ς��鋫�E �@
�l�Ԃ͒ʏ�A�l�E�ɏZ���܂��̂œ{����×~�Ȃǂ��o���Ȃ��悤�ɗǎ�������A�����ȐS�ł���̂��{���ł����A���l�̋������Ȃ���Ή��ɂ���Đl�艅�݂���������A��s����������ƁA�����S���g���Ă��܂��܂��B�@
�V��E�͐_�X�̐��E�ł����A�V��E���Z���̒��ɓ����Ă���̂́A�������������Ƃ�����A�V�ɂ�����v�������邩�Ǝv���A���̏u�ԂɎ����ɕs���Ȃ��Ƃ�������ƁA�����ɂ���ē{����o������ƁA�n���E�ƓV�E���s�����藈���肷�邩��ł��B �@
�×~�E�т�E��s�̎O�ł��A�n���E��S�E�{���̋��E�ɑ������܂����A���߉ޗl�͂��ꂪ�ꂵ�݂̂��Ƃł���Ɛ�����܂����B�@
�u���~�͋�Ȃ�A�����̔�J���×~��肨����B���~�ɂ��Ė��ׂȂ�ΐg�S���݂Ȃ�Ɗo�m����B�v(����l�o�o) �@
�u�����l�A�S���邱�ƂȂ���A�����������߂č߈������B��F�͂����炸�A��ɒm����O���A�n�Ɉ��������A�����d�̂ݐ���ƂȂ�Ɗo�m���B�v(����l�o�o)�@
�u�Ðl�����W�ߓ��āA����邨���������A�����̈ŁA�S��^�|���āA��ɐN���đ����Ƃ�O���A���݂͉��������A�g���̂ĂĂ͈����ɑA���̌̂ɒq�҂͂܂��ɒm����O���ׂ��B�v(�q�o)�@
�u�т���悭���琧���邱�ƁA�����Ԃ��~�߂邪�@�����A�����P�����ƂƂȂ��B���������ĂČ��ɂ͂���B�v(�@��o) �@
�u�Ⴕ�ќ����Ȃ����Έ����ɖ��邱�Ƃ�B�ќ����Ȃ����ΐl�����Ċ�������߂�B�ќ��͓ł̖{�Ȃ�B������Ȃ����҂͉䂪�J�߂�Ƃ���Ȃ�B�v(�G���܌o) �@
�u�ܗ~���Ò����Ď������Ȃ�O���́A�ׂɕs��̋��E���������B�v(�،��o) �@
���B�͐g�E���E��(����E���E��)�̎O�ƂőP�Ƃ����Ƃ��ςނ��ƂɂȂ�܂����A���Ƃɂ͐g�ŎO�A���Ŏl�A�ӂŎO�̏\���������Ă��܂��B �@
�\���Ƃ́@
�g�ɂ͎O�� / �u�E���v�u����(���イ�Ƃ�)�v�u���v�@
���ɂ͎l�� / �u����(������)�v�u�ό�(�R)�v�u����(��)�v�u�Y��v�@
�ӂɂ͎O�� / �u�×~(�Ƃ�悭)�v�u�ќ�(�����)�v�u��s�v�@
�������A���߉ޗl�́A�O�������̂悤�Ȉ��Ƃ�ς�ł��܂��̂������ɂ��Ƃ���A�ߑ��̋����ɂ���ď����ȉ���̂āA�{���̎��Ȃ��u���v�ł��邱�ɋC�Â��ƁA���̐��͕����Ŗ��������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���R�Ǝ���̕��X�ɂ����l�ɐڂ���悤�Ɋ��ӂ��ĕ�����q�݂����č�����q���Ă����悤�ɂȂ�A���̐������̂܂�y�ƂȂ�̂ł�(�O�k������y)�B �@
 �@
�@ �@
�@

�Z���։�(�낭�ǂ�-����)�͕��������Ƃ�����Ǝv���܂��B���͘Z���։�͂��߉ނ��܂������������Ƃł��B�����ɂ����A�ܓ��։������A��Ɉ��C���E���g�ݍ��܂�ĘZ���։�ɂȂ��Ă��܂��B
���߉ނ��܈ȑO�̃C���h�ł́A�������։�v�z�͂���܂������A�����ƃV���v���ȗ։��]���̎v�z�ł��B�V�E�Ɛl�ԊE�ƒn����3�̐��E���s��������f�p�ȗ։�v�z�ł����B
���������߉ނ��܂́u��(�Z)���։�v�������܂��B��(�Z)���։�Ƃ́A�n���A�{���A��S�A�l�ԁA�V�E��5�ł��B����Ɉ��C���������ĘZ���ł��B
�����́A����6�̋��E���O���O���ƈڂ�ς���Ă����Ƃ����܂��B
���߉ނ��܂́A�h���ʂƓV��ʂƂ������\�͂������Ă����܂����B����ł��u�O����m��v�Ƃ�����܂����A���߉ނ��܂̑O�������ʂ��\�͂́A����ȃ��x���ł͂���܂���B�����̉ߋ�����������������̂ڂ�A�������������g�̑O�������łȂ��A�V��ʂƂ����\�͂ł����鐶���̑O�����������������̂ڂ茩�ʂ��Ă�����܂����B���̂��Ƃ͕��`�ق��A�p�[���o�T�ɂ͂������L�^�Ƃ��Ďc���Ă��܂��B
���߉ނ��܂��̂��������̑������܂�ς��̗l�����Ă��܂����̂ŁA�։��]���̃p�^�[�����ǂݐ��Ă����̂ł��傤�B�ł��̂ŁA���߉ނ��܂̌��t�Ƃ́A�������������̗։�̗l�܂��Č���ꂽ�����Ǝ~�߂���������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���͕����������Ƃ��M������̂��A���߉ނ��܂̓��O�������@�͂����邩��ł��B
�Ƃ���Ő������։鐔�͈�̂ǂꂭ�炢�Ȃ̂ł��傤���H�悭�։��]���̘b�����o�܂���ˁB�ߋ����̋L���ɂ����̂ڂ郏�[�N�Ƃ��Z�~�i�[������܂����A���������Ö@������܂��B���A�u�O���̂��Ȃ��͂ǂ��ǂ��Ł��������Ă��܂������v�A�Ƃ����������ł��ˁB
�������o�T�̒��ɁA�։�Ɋւ��Č��y�������o������������܂��B�����ǂ݂܂��ƁA���߉ނ��܂͂��������Ă����܂��B
�u�l������Ő��܂�ς��Ԃɗ������܂̗ʂ́A�C�̗ʂ��������v�u�w��ɂ܂y�������Ƃ���Ȃ�A�l�̗։�́A���̒n��ɂ���S�Ă̓y���������v
��
�r�����Ȃ����̐��܂�ς��ł��B�܂��ɖ����ɋ߂��։���A�����͑����Ă��邱�Ƃ����߉ނ��܂͌����Ă����܂��B
����ɁA�F���������ĕ�����A�ŏ��̐������a������b�����q�ׂĂ����܂��B���̕ӂ�́A�����̑n���L�����ڍׂȕ`�ʂɂȂ��Ă��܂��B
�����́A�F���̐��������������Ȃ��قǑ̌����Ă��āA���߉ނ��܂́A�h���ʂƓV��ʂƂ����_�ʗ͂Ō��ʂ���Ă��܂����B
����(���n����)�ł̋����Ƃ́A���߉ނ��܂̂�����������}�Ȕ\�͂܂��Ă���������Ă���Ƃ��낪����܂��B
�Z���։�͂��߉ނ��܂��ŏ��Ɍ���ꂽ�։�̗l�ł����A���߉ނ��܂��������։�́A���Ԉ�ʂɐM�����Ă���̂Ƃ͈Ⴄ�Ƃ��낪����܂��B
�܂��A�����́A�����ړI�������ē]�����Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B������������ł��V���b�N����������������邩������܂���B�ł��������ł́A���̂悤�ɐ����܂��B���̐������͂��邽�߁A�Ƃ��A�����g����ттĂ��邽�߁A�Ƃ����̂͌����I�ɂ���܂���B
�����́A�����u�����Ɩ����̔ϔY�ɂ���ė։Ă��邾���v�Ɗ��j���܂��B�͂����肢���Ė�����]������܂���B�����w���������Șb���́A���߉ނ��܂̗։��]���ɂ͂قƂ�ǂ���܂���B
�����Ƃ��։�̒��ɂ��A�ψՐ���(�ւ�ɂႭ-���傤��)�Ƃ����̂�����܂��B�ψՐ����Ƃ́A���̖�ɓ������a���ʈȏ�̐���(����)���A���邽�߂ɗ։�𑱂��邱�Ƃ������܂��B�ψՐ����͓���ȃP�[�X�ł��B
��ʓI�ɂ͕��f����(�Ԃ�-���傤��)�Ƃ����܂��B�قڂ��ׂĂ̐����͎����△���Ɋ�Â��āA�I�[�g�ɗ։��]�����J��Ԃ��Ă��܂��B���f�����̗։قƂ�ǂ��ׂĂł��B
���̕����������������ł��A�ǂ��́A�Â��C�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂ŁA���̕����I�ȗ։�̎v�z���I�ɋ��₷�����������Ȃ�܂��B�܂����y����Ȃ�������������Ⴂ�܂��B
�ł��������́A��ʁA�܂����̐^�����~�߂���ŁA�C�s���܂��傤�Ɛ����܂��B�Ƃ͂����܂��Ă��A�։�̎v�z�ɑς����Ȃ��ꍇ���o�Ă���Ǝv���܂��B�������s���⋰�|��������ꍇ�́A�X���[���Ă��������B�O�ɂ������܂������A�����Ŋm���߂��Ȃ����Ƃ͉L�ۂ݂��Ȃ��A�Ƃ����p���ł��B
�^���Ƃ͉s���n�̂悤�ł���A���Ƃ��Đl�����|�ƕs���ɒ@�����Ƃ��܂��B�����Ő����։��]���ɂ́A���ɁA�u���O�ł͏����Ȃ��قǂ̋��낵���b��������܂��B�����A�V���b�N���ăg���E�}�����������o�Ă���Ǝv���܂��B�ł��̂ŗ։��]���ɂ��Ă͐T�d�ɏ�����������Ȃ��Ȃ�܂��B
�������A���߉ނ��܂́A�ǂ����ɐ��܂�ς�葱���邽�߂́A�A�h�o�C�X�������Ă��܂��B���������̋C�ɂȂ�A�N�ɂł��ł���l����̒��ӓ_�Ə����p�ł��B
���߉ނ��܂́A�����k�ȊO�ł��N�ł��K���ɂȂ����@�������Ă��܂��B�����P�ɕs�����������Ă邾���łȂ��A�ǂ������ł���悤�ɂƁA���̂��߂̐������E�����p����������Ƃ���������Ă���̂ł��ˁB
�����������։��]���͑�Ϗs���ŁA���|���犴����Ƃ�������܂��B�ł����A���߉ނ��܂͋~������@����������Ɛ����Ă����܂��B������������M���Ȃ��l�ł��A�N�ł��ł���K���ɂȂ����@�ł��B
���ꂪ��(�܉����邢�͏\�P��)�Ǝ{(�قǂ���)�ł��B
�����āA���́u��(�܉��E�\�P��)�v�Ɓu�{�v�Ɂu�C�v�Ƃ������ґz�C�s�����������̂��u�݉Ƃ̕����v�ɂȂ�܂��B
����(�܉��E�\�P��)
�܂���(�܉��E�\�P��)�ł��B
���߉ނ��܂́A�݉Ƃɂ͌܉��A�\�P���Ƃ�����������邱�ƁA�l�ւ̎{�������ĐS�𐴂炩�ɂ��邱�Ƃ���{�I�Ȏ��H�s�Ƃ��Đ�����Ă��܂��B
���܉��Ƃ́A
1�D�ނ�݂ɐ��������E���Ȃ�
2�D���l�̕���S�E�^�����Ă��Ȃ����E�S�����Ȃ�
3�D�s�ς����Ȃ�
4�D�R�����Ȃ�
5�D�������܂Ȃ��B
�ׂ��炸�W�ł͂Ȃ��A�m��I�ȕ\��������Έȉ��̂悤�Ȍ��������ł���Ǝv���܂��B
1�D�����ɂ���@(���������E���Ȃ�)
2�D�K�v�Ȃ��̂����Ŗ�������@(���܂Ȃ�)
3�DTPO�܂��Ė{���̂��Ƃ������@(�R������Ȃ�)
4�D�ϗ������ɍ�����������������@(�s�ς����Ȃ�)
5�D����Ȕ��f�͂�ۂ悤�ɂ���@(�������܂Ȃ�)
���\�P���Ƃ́A
1�D�ނ�݂ɐ��������E���Ȃ�
2�D���l�̕���S�E�^�����Ă��Ȃ����E�S�����Ȃ�
3�D�s�ς����Ȃ�
4�D�R�����Ȃ�
5�D�܂�Ȃ��b����A���q�̗ǂ����Ƃ₨�������߂��邱�Ƃ�����Ȃ�
6�D�e��ł������藐�\�Ȍ��t���g��Ȃ�
7�D���Ⴂ�����邱�Ƃ�����Ȃ�
8�D�ُ�ȗ~�������Ȃ�
9�D�ُ�ȓ{��������Ȃ�
10�D���ʂ�ے肵���蓹����ے肷��A�ϑz�I�Ȍ���������������Ȃ��B
�ɂȂ�܂��B�\�P���͌܉��̂����l�����܂�ł��܂��B
���{(��)
�u�{�v�͕����ʂ�A�{�����s�����Ƃł��B�z�{(�ӂ�)�Ƃ����܂��B�{���ɂ́A
1�D�������قǂ���
2�D���_�I�E�S���قǂ���
3�D�@�{
����3��ނ�����܂��B�����Ƃ͕����ʂ�A�����ɂȂ�܂��B�����ł�������A���ł������肵�܂��B
���_��S���{�����Ƃ��ł��܂��B����́u�����̎��{�v�Ƃ������̂��L���ł��B�����̎��{�Ƃ́A
1�D��{(����)�E�E�E�₳�����܂Ȃ����B�K����t�������ɂނ悤�Ȗڂ������Ȃ��B
2�D�a��{(�킰��)�E�E�E�ɂ��₩�Ȋ�B���₳��������B��ڎg���̎O����̓i���Z���X�ł��B
3�D����{(��������)�E�E�E�₳�����A�v�����̂��錾�t�g���B
4�D�g�{(����)�E�E�E�����̑̂��g���đ��l�̂��߂ɓ������ƁB��d�B
5�D�S�{(����)�E�E�E���l�̂��߂ɋC�z���������A��т����L����(����)���ƁB
6�D�����{(���傤����)�E�E�E�Ȃ����邱�ƁB�܂��͎����̒n�ʂł����i�⑊��ɏ����Ă��܂��S�B
7�D�[�Ɏ{(�ڂ����Ⴙ)�E�E�E�J�������̂���{�������邱�ƁB
���[�Ɏ{�́A�̂͌���̂悤�ɗ��h�Ȍ����͉J��͖����������߁A����Ă�����̂Ǝv���܂��B����̃j���A���X�ʼn��߂��܂��ƁA�u���l�̋�ɂ�a�炰�邽�߂̔z���v�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�����7�́A�̂��猾���Ă��邨���̂�����Ȃ��S��̂��g�����{���Ƃ���Ă��܂��B�����Ă悭����ƁA�܉���\�P���Ǝ��Ă���Ƃ��낪����܂��ˁB
�Ō�̖@�{(�ق���)�Ƃ́A���͂���͕������L�̎{���ɂȂ�܂��B���������@���{���s�ׂ������܂��B
�Ƃ���Ō܉��ɂ��Ă��\�P���ɂ��Ă�����ł́A�Ȃ��Ȃ���邱�Ƃ��ł��Ȃ���������܂��B�����Ŋ撣��߂��Ď���Ă��܂����Ƃ��邱�Ƃ��łĂ��邩������܂���B
������������`�I�ɂȂ�����A�撣��߂���̂͂�낵���Ȃ��悤�ł��B�����́A�����b�N�X����S��{�����ƂƁA���ɑ��鋰��̐S(�u�Μ��v�Ƃ����܂�)��|�����ƂŁA���R�ɂł���悤�ɂȂ�܂��B
�����̂��Ƃ͔O���ɒu���āA�ł��邾���Ƃ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ������ł��ˁB�܉��Ə\�P���ɂ��ẮA������̋@��Ő������������Ǝv���܂��B
�܉��Ǝ{(�قǂ���)�́A���߉ނ��܂��݉Ƃɐ����A��{���̊�{�̋����ł��B�u���V�̋����v�Ƃ������܂��B���������A������M���Ă��Ȃ��҂ł��N�ł��A����A�K���P��(�ǂ���)���܂�ς��ƁA���߉ނ��܂͒f������Ă��܂��B
��σV���v���ł����A���̋����́A�����ɑ����։�̗l���s������������ł̃A�h�o�C�X�Ȃ̂ł��傤�B
�������āA�����̌܉��E�\�P���Ǝ{�ɉ����ĕ������ґz���s���A�u�����v�ɂȂ�܂��B
�݉Ƃ̕����Ƃ́A
�E��(����)�E�E�E�܉��E�\�P�����s������
�E�{(��)�E�E�E�z�{�̍s�ׁB�������@��Љ��l�X�ɂ��܂˂��{�������邱�ƁB
�E�C(���イ)�E�E�E�ґz���s������
����3���s�����ƂɂȂ�܂��B���̂����A���Ǝ{�́A�����łȂ��Ă������Ă��܂����A�N�ł��ł��܂��B�����čK���ɂȂ�܂��B�����ł́A�u�������ґz�v���s�����ƂŌ��Ɏ���A���ɂ̍K���ɂȂ��Ɛ����܂��B
�����������͂����Ă��A�ŏ��́u�����v���u���ꂵ���v�u���������E�E�E�Ǝv���āA�ь�������邱�Ƃ�����܂��B
�������A���̌��t�Ō����A���\�҂Ƃ����Ă��悢���߉ނ��܂�����ꂽ���Ƃł��B�ꉞ�͎����X�����ق����ǂ��悤�Ɏv���܂��B
�������̑O����������������̂ڂ��Č��ʂ���A���̐����̖����̗։��]�������ʂ��ꂽ���ł��B���߉ނ��܂͗։��]���̃p�^�[�������S�ɓǂݐ��Ă��܂��B�ł��̂ŁA���̃A�h�o�C�X�ɂ͎����X����ق����������Ǝv���܂��B
�C�������Ȃ�悤�Ȑ��܂�ς������Ă���Ȃ�A�ł��邾���ǂ������ł��葱���������̂ł����ˁB
�Ƃ͂����܂��Ă����n�����ł́A�ߐ��̏@���c�̂̂悤�ɋ��c���Ύ����邱�Ƃ͂��܂���̂ŁA�����X����X���Ȃ��́A�e�l�̎��R�ɂȂ�܂��B�ł����A�����ɑ����։�̗��̎d�g�݂ƁA��������̒E�o���@���c���ꂽ���߉ނ��܂́A��͂�̑�ł���A���̌��t�ɂ͎����X���鉿�l������Ǝv���܂��B
�u�܉��E�\�P���v�Ɓu�{�v�́A�@����@�h�ɊW�Ȃ��A�N�ł��K���ɂȂ����H�s�ł��B
�Ƒ��Ƃ͐l�ԊW�̍ŏ��P�ʂł����āA�N�����ŏ��ɑ̌�����l�ԊW�̂ЂȌ`�ł��ˁB
���e�����ǂ��A���܂̏��Ȃ��W�ł���Ȃ�A���̎q���������悤�ȃo�����X���o��|���Ă����A�����đ�l�ɂȂ��Č������A���e�Ɠ����悤�Ɍ��܂̏��Ȃ��W�ɂȂ�₷�����̂ł��B��ɂ����Ȃ�킯�ł͂���܂��A�Ȃ�₷���ł��ˁB�������̐e�q�N�ɂ킽���Ă݂Ă����܂��ƁA��L�̂��Ƃ͊Y�����܂��B
�e�q�Ƃ͑�ρA�J���[���W�ł��B�ǂ����������A�q���͗��e�̉e�����܂��B
���e�ɂ��Č��n�����ł́A�ǂ������Ă���̂ł��傤���B����͐l�ԊW�̂ЂȌ`�Ƃ��Ȃ闼�e�ɂ��Đ����������Ǝv���܂��B
��1�D���e�͞��V�̂悤�ɐڂ���
���n�����ł́A���e����ɑ�ɂ��鋳��������������܂��B���e�ɑ��ẮA���V�ɐڂ��邪�@���h���Ȃ����A���e�͑�ɁA�e�F�s�͂���A�Ƃ��������e��厖�ɂ��鋳�����������Ȃ�܂��B
���̗��R�͖����ł��B�e�͎q������Ă邽�߂ɁA�����̐g������Ă܂ł��K���ƂȂ��Đs�������炾�A�Ƃ����܂��B�����ł��ˁB���̎��������������Đ����Ă�����̂��e�́u���A�v�ł���B�������ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B�Ɩ����ɂ��߉ނ��܂͐�����܂��B
��2�D���������e��e���ɂ���ƁE�E�E
���ɁA���e��e���ɂ���ꍇ�A���ɐe���E�Q�����ꍇ�A��ςȍ߂ɂȂ�悤�ł��B���̍߂͋ɂ߂đ傫���A����A�ň��̒n��(���Ԓn��)�֍s���Ƃ���܂��B����͑����|���ł��B
�u�܋t�߁v�Ƃ����߂�����܂��B�܋t�߂Ƃ́A
1�D��e���E�Q����
2�D���e���E�Q����
3�D�u�b�_���E�Q����
4�D�u�b�_�ɉ���킹��
5�D�������������c��j��(����)������
�Ƃ����߂ł��B������Ƃ��ƁA���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A����A�K�����Ԓn���֍s���ƌo�T�ɂ͏����Ă���܂��B���e�A��ɁA��e���E�Q���邱�Ƃ͑�ςȍ߂̂悤�ł��B�u�b�_���E�Q��������߂��d�����Ƃ������܂��B
���Ȃ݂ɖ��Ԓn��(�ނ�����)�́A1��(����)�Ƃ������Ԃ̊ԁA���݂��Â���悤�ł��B1���Ƃ�43��2000���N �Ƃ����܂��B43��2000���N�̊ԁA�n���ɂ��邱�ƂɂȂ邻���ł��B
�E�E�E�E�������Ƃ͂������Ȃ��ł��ˁB
��3�D���e�Ƃ��J
�|���b���ɂȂ�܂����̂ŁA������Ƃ����Ńt�@���^�W�[�̂悤�Ȃ��b���B
���e�Ƃ��J�������킯�ł����A�p�[���o�T�ɂƂĂ��W�[���Ɨ��闼�e�Ɋւ��邨�o������܂��B����́A���Ȃ������̗��e�̌��Ɏq���Ƃ��Đ��܂�Ă���͂ǂꂭ�炢�ł��傤���H�Ƃ����₢�����ł��B
���̗��e�̌��ɐ��܂�Ă���ł��B
���̖₢���ƁA�u���H�v�Ǝv���܂��H���̗��e�̌��ɐ��܂�Ă���ł��B
���������A���̗��e�Ɠ������e�̑O�����Ă���́H�Ǝv���܂���ˁB
�Ƃ��낪���߉ނ��܂͍������悤�Ȃ��Ƃ��������Ⴂ�܂��B
���̗��e�Ɠ������e�̌��ɐ��܂�Ă����́A��n�̓y�̐����������A�Ƃ����̂ł��B
䩑R�����E�E�E
�J���������ӂ�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�Ȃ�Ƃ����c��Ȑ��Ȃ̂ł��傤���B�m�����炢���Ă��A�������e�̌��ɐ��܂�Ă���̂͋ɂ߂ď��Ȃ��͂��ł��B���̏��Ȃ��m���ł���A�c��ȉ��ƌ����̂ł��B
��́A�l�Ԃ̗։��]���̐��͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂ł��傤���B�����ɋ߂��Ƃ������Ƃ͂Ȃ�ƂȂ�������ł��傤�B
�����̗։��]���Ƃ́A���̂悤�ɃX�P�[�����r���������傫�Ȃ��̂ł��B
�������āA�������e�̌��ɐ��܂�Ă���A���̘b���A�ǂ����ŕ��������Ƃ�����܂���ˁB�։�̗Ⴆ�ł��B
�։�̐������邱�ƂȂ���A�u�������e�̌��ɐ��܂�Ă���v���c�傾�Ƃ������̋����B�{���ɁA�l�̗։�̉́A�C�������Ȃ�قǖc��Ȃ��Ƃ�������܂���ˁB�Ȃ��Ȃ�A�������e�̌��ɐ��܂�Ă������A�c��Ȃ̂ł�����B
�ł����A���̂��߉ނ��܂̂��b����A���e�Ƃ��J�͂����ɐ[������������Ǝv���܂��B���e�Ƃ̉��Ƃ́A�M�����Ȃ����炢�[���A����Ύ����̈ꕔ�̂悤�ȑ��݂Ȃ̂ł��傤�B
�ł��̂ŗ��e���E�Q����߂��d�������Ȃ�̂�������܂���B
���̂��Ȃ��̗��e�A�ߋ����ł�������Ȃ����炢�u���e�v�������킯�ł��B���Ɠ����E�Ƃ�i�łȂ������ł��傤���A�����J�́A�����ɂ����Ă��Ăь��������Ă����܂��B�����ǂ����ŁA�ĂсA�������e�̌��ɐ��܂�Ă��܂��B
�����l���܂��ƁA���e�Ƃ́u�����̉��v�ł͂Ȃ��A�u�����̈ꕔ�v�̂悤�ȑ��݂��Ǝv���܂��B
����c��e�����ɂȂ��Ă���H
���Ԃɂ́A��c�������N�����Ďq�����ꂵ�߂Ă���A�^���������Ă���A���̌����ƂƂ���������������Ƃ��������܂��B�������A���߉ނ��܂̌��t���ӂ݂܂��ƁA���������l�����͂��������܂���B���e�̂��̂܂����e�ł����c���M���Ă���Ƃ��A���ɂȂ��Ă���Ƃ����̂��͂�����ƍ����l�����ł��B��c�◼�e��e��(���҈���)�����˂Ȃ��l�����ł��B
�m���ɗ��Ƃ����鎗���P�[�X���N���邱�Ƃ�����悤�ł��B����������͋H�ł��B�{�������ł͂Ȃ���S�̊֗^�ł��B
��c��e�͂��肪�������݂ł��B�������J�̐[�����݂ł��B�厖�ɂ��܂��傤�B��ɂ��܂��傤�B
�����ĂсA�܂��e�q�Ƃ��ď����܂��B�܂������b�ɂȂ���ł��B���x���肠�����Ƃ��A�����ȏ�ɑ�Ɉ�ĂĂ��������A���S�Ɉ���Ă����������̂ł��B���e�͖{���ɑ�ɂ���K�v������܂��ˁB��ɂ��܂��傤�B
���n�����Ő�����闼�e�ɂ��Ă�m�����Ƃ��A���ӂ���C�����ň�t�ɂȂ�܂����B���̋����������Ƒ�������m�肽�������Ƃ��v���܂������A�C�t���ɒx�����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB����t�̐e�F�s�͂��������̂ł��B
�悭�u���Ȃ��̑O���́A�ǂ��ǂ��Ł��������Ă����v�ƕ����܂���ˁB�����đ��́u�l�ԁv�̐������q�ׂ܂��B
�������{���̑O���ɂ́A�K���u�Z���։�v�̐����`�Ԃ��o�Ă�����̂ł��B
�����͘Z����։Ă��܂��B�Z���։�Ƃ́A
�_�A�l�ԁA���C���A��S�A�����A�n��
����6�������܂��B�Z���։�Ƃ́A�u�����̌`�ԁv�ł�����܂��B���͑S�āA���A���ɑ��݂��鐶���Ȃ̂ł��B
�S�̏�ԂƂ��A���U�Ƃ��ł͂Ȃ��A���݂��Ă��鐶���Ȃ̂ł��B�{���ɑ��݂��Ă���̂ł��ˁB
�ł��̂ŘZ���։�Ƃ́A����6�̐����̌`�Ԃ��O���O���Ɨ։Ă���킯�ł��B
�l�Ԃ͎���A�l�Ԃɐ��܂�ς��Ƃ����ۏ͂Ȃ��A���O�̍s��(��)�ɂ���āA�Z���̂����ꂩ�ɕK���s���܂��B�m���X�g�b�v�ł��B����A�����ɕʂ̐����ɓ]�����܂��B
�H��̂悤�ɂ��܂���Ă��邱�Ƃ͂���܂���B�����ɕʂ̐����ɓ]�����Ă����܂��B�։�Ƃ͌����Ď~�܂邱�Ƃ̖��������̏z�ɂȂ�܂��B
�ł�����A���Ȃ��̑O���́A�_�A�l�ԁA���C���A��S�A�����A�n���̂����ꂩ�̉\��������̂ł��ˁB�����āu�l�ԁv�����ł͂Ȃ��̂ł��B
���������đO��������b�������ꍇ�A�K���Z���։�̌`�Ԃ��o�Ă���̂��{���ł��B�������l�Ԃ̎���̘b�������o�Ă��Ȃ��ꍇ�͕s���m�ł��B���邢�͖ϑz���z�̉\��������܂��B
�����̏C�s�ɂ́u�h���ʁv�ƌ����āA�O�������ʂ���悤�ɂȂ�C�s������܂��B��������ۂɑ̓��������̘b�����܂��ƁA�O���͐l�Ԃ̎��ゾ���łȂ��A����(��)�A�n���A��S�A�_�A�l�ԁA�Ƃ����������ł���������������邱�Ƃ�����悤�ł��B
�O�����A�C�݂ɂ����߂��t�i���V�������Ƃ����������܂��B����͖ϑz�ł͂Ȃ��A���ۂɏC�s�����đO�������Ă���m���̘b�ł��B�n���ɒĂ���40���N�ȏ�������u�M���M���v�Ƌꂵ�ݑ������O���������������܂��B
���A���ȑO���Ƃ́A�����������̂ł��B�K���Z���։������Ă��邱�Ƃ����C�t���悤�ł��B
�����͑̌���`�ł���A���߉ނ��܂����łȂ��A���̒�q�B���Ǒ̌��������̂ł��邱�Ƃ́A���łɏq�ׂĂ��܂��B
�O���������ł��B
�������Ė{���ɑO��������A�ߋ����ɂ����Đl�Ԃ����łȂ��A�����⒎�ł�������A��S�ł�������A���ɂ͞��V�Ƃ����_�ł�������A�l�X�Ȑ����̌`�Ԃł��������Ƃ�������悤�ł��B
�ł�����A�悭�u�O���������v�Ƃ����b���Ȃǂ�����܂����A���̑̌����S�Đl�Ԃł���Ȃ�A�����̉\���������Ȃ�܂��B
�܂���q�̒ʂ�u��v�ƌ����鑶�݂͂���܂���B��Ƃ́A�Z���։�ɂ��鐶����ʑ��I�ɂƂ炦���\���ɂȂ�܂��B
���̂悤�ɐ������։�Z���։�̐��E���_�Ԍ��Ă��܂����B�n�������S�A�{���A���C�������Đl�ԁA�V�E(�Z�~�E�E�F�E�E���F�E)�B
���̘Z�����O���O���Ɖ�葱���Ă���̂������ł��B�����̓S�[���̖����։��]���q�o�f(���[���v���C���O�Q�[��)�̂悤�ł��B
�Q�[���̂q�o�f�ł́A��l���̗E�҃��g�́A�����X�^�[��|���Čo���l��l�o���A�b�v�����āA�Ō�ɂ̓��X�{�X��|���ăn�b�s�[�G���h�ŏI���܂��B�Ō�Ƀt�@���t�@�[��������ăQ�[���I���B��l���̂g�o��999�܂Ń}�b�N�X�ɍ��߂��肵�ă��X�{�X��|���Ė����̎v���ɂӂ�����������܂��B
�������l���́A�I���̖����A�S�[���̖����։��]���ł��B�P�s���d�˂ēV�E�ւƐl�ԊE���������A�F�E���V��A���F�E���V�̍ō��ʂɒB���Ă��A�P�ƃp���[(�g�o)�͂���ƌ����Ă����āA�₪�Đl�Ԉȉ��ɍĂѓ]�����Ă����܂��B
�P��(�g�o)�͌����Ă��܂��̂ŁA�Ăю�l���͑P��(�g�o)�̌o���l��ς�Ń��x���A�b�v���Ă����܂��B���Ƀ��x��99�̂g�o999�ɂȂ��āA�Ăў��V�ɂȂ��Ă��A�P�Ƃ������Ȃ�G�l���M�[��ŁA�܂��l�Ԉȉ��ɖ߂��Čo���l��ς�ŁE�E�E
���̌J��Ԃ��ł��B�B�������I�ȁu�V(���傤���Ă�)�v�ɍs���A����A���ςɓ���܂��B�������V�ɓ�����@�͕��@�ɂ�邵������܂���B���ʂɗ։�����Ă���A�V�����Ă��A���̕����ɓ���J�M���������ߓ���܂���B
�V�E�̍K�^�A�K���͐l�Ԃ̉���{�Ƃ�����K�����Ȃ킯�ł����A�����V�E�ł̎������s���āA�P�Ƃ������Đl�Ԃt�߂�B�l�ԂƂȂ��ċ�y�𖡂킢�Ȃ���P�s���ł�������̂ł����A���ۂ́A���S���N�����ēV�E�ǂ��낪�n���֍s���Ă��܂����Ƃ��o�Ă���ł��傤�B
�s�m�����ȗ։�B�\�z�O�A�z��O�̏o�����ɑ������ė։�𑱂��܂��B���������Ȃ��ƂɁA��(�J���})�͎���������āA�����ɂ킽���ĉe�����y�ڂ��܂��B
�ǂ��Ƀg���b�v�������āA�ǂ�ȃJ���}�̌��ʂ��邩������Ȃ��l���B���������։���O���O���Ɩ����ɋ߂����A�����Ă���ƁA�u�b�_���w�E���܂��B
���ߑ��̏o�����ȗ։�̗��ł��B
�ł����畧���ł́A�։�̍���f����A���ς֕������Ƃ���܂��B�։�̘b���́A�������ł������Ȃ��Ƃ��������܂��B�܂������Ȃ���u�E�m�������܂��B�^�C�͍��ƓI�ɕ�������߂��Ă���e���������āA���܂�ς��(�։��]��)������Ȃ��Ƃ��������܂��B�։��ʂ̈Ӗ��ɒu�������Đ������邱�Ƃ�����܂�(�]�������ɔے�����܂�)�B����A�~�����}�[�ł͗։��]�����O��ł��B���܂�ς��͓�����O�Ƃ��Đ����Ă����X���ł��B
���̂悤�ɍ��̂���Ă��։��]���̈����͈���Ă��܂��B
���������܂�ς��͎��݂��Ă���Ǝv���܂��B�]���������Ƃ���Ȃ�A���̐l�ԁA�����̌���Ⴂ���ǂ���������̂ł��傤���B�l�Ԃɐ��܂�āA���ȂɋC�t�����Ƃ��A�u�����͂ǂ����痈���̂��낤���v�Ƃ����f�p�Ȋ��S������l�͑����ł��傤�B
�����͘A���������鑶�݂ł���A������܂��ʂ̐����ɏu���ɓ]�����A�������Â��Ă����܂��B�։�͑��݂��܂��B�]���͑��݂��܂��B
�����ĕs�m�����߂���։��]������E�o���邽�߂ɕ���������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B�@ �@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
�ϔY�ɂ܂݂ꂽ�l�ł��A�O����ɓw�߂�A���̔ފ݂Ɏ��邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ�����Ă���B�@


�����ɂ����鐢�E�ς�1�ōʼn��w�Ɉʒu���鐢�E�B�~�E�E���E�E�Z���A�܂��\�E�̍ʼn��w�ł���B��ʓI�ɁA�傢�Ȃ�߈���Ƃ����҂��A����ɐ��܂�鐢�E�Ƃ����B�ޗ��ށA�ߗ��ށA�旎�ށA�ߗ��h�ȂǂƉ��ʂ����B�ޗ��ނ��]�a���ēޗ�(�Ȃ炭)�Ƃ����ʂ���邪�A���ꂪ��ɁA�����̕���̉��̋�Ԃł���u�ޗ��v���w���Č����悤�ɂȂ����B �T���X�N���b�g��Niraya(�j����)���n�����w�����`��ł���A������͓DಁA�D�t��Ɖ��ʂ����B
�Z���̉��ʂł���O����(�O�����Ƃ��A�n���E��S�E�{��)��1�ɐ�������B���邢�͎O����ɏC�����������l�����1�A�܂��Z������C���������܈���(��)��1�ł���B����������̍ʼn��w�Ɉʒu����B
���{�̕����ŐM�����Ă��鏈�ɋ���A����A�l�Ԃ͎O�r�̐��n��A7�����Ƃ�腖����͂��߂Ƃ���\����7��̍ق����A�ŏI�I�ɍł��߂̏d�����̂͒n���ɗ��Ƃ����B�n���ɂ͂��̍߂̏d���ɂ���ĕ������ׂ��ꏊ�����܂��Ă���A�ŔM�n���A�Ɋ��n���A�̉͌��A���@�n���A�����n���Ȃǂ�����Ƃ����B�����ĕ������Ԃ��I�������̂͗։��]���ɂ���āA�Ăт��̐��E�ɐ��܂�ς��Ƃ����B
���������n���̍\���́A�C�^���A�̃_���e�́w�_�ȁx�n���тɋL���ꂽ�㌗����Ȃ�n���E�Ƃ����ʂ��邱�Ƃ����т��юw�E�����B���Ƃ��A�_���e�̒n���ɂ́A�O�r�̐�ɑ�������A�P���[���삪����A���̐��n�邱�ƂŒn���ɍs�������̂ł���B
�w�Î��L�x�ɂ͒n���Ɏ��Ă��鉩���o�ꂷ��B�������A�w���{���I�x�̒��ɔ��f����Ă�����{�_�b�̐��E�ł́A�n���͓o�ꂵ�Ȃ��B����ɏ���⹂��n���ɍ~��A腖��剤�̂��Ƃōٔ��̕⍲�����Ă����Ƃ����`����A������������F�̓����ŁA�n���֍s��������������V�c�Ƃ��̐b���Ɉ������b�Ȃǂ��c����Ă���B
���n���̐F
���A�W�A�̕����ł́A�n���̐F�͓����I�ɁA���邢�͂��̉e�������A�z���I�Ɂu���v�ŕ\���B��S�͐ԁA�{���͉��A�C���͐A���̎O�F��������ƒn���̍��ɂȂ�ƌ�����B�܂��A�ߕ��Œǂ���ԋS�A���S�A�S�͂������痈�Ă���B
�����
�O�����Z��腕���̉��A4���R�{���߂��āA�ʼn��w�ɖ��Ԓn��(�ނ�����)������A���̏c�E�L���E�[���͊e2���R�{����B ���̖��Ԓn���͈��@�n���Ɠ��ӂŁA���@�̓T���X�N���b�gavici�����ʂ������̂Ƃ���A�Ӗ��͋��Ɂu�₦�ԂȂ�����(�n��)�v�ł���B���@�n���͈�ԉ��w�ɂ���A����E�Q�ȂǍł��߂̏d���҂�������B�����ւ̗����ɓ��N���v���A�l�������Ή��ɕ�܂ꂽ�A��ԋ�ɂ̌������n���ł���B
���̏��1��9��R�{�̒��ɁA��ŔM�E�ŔM�E�勩���E�����E�O���E����E������7�̒n�����d�w���Ă���Ƃ����B����̂��Ĕ���(���M)�n���Ƃ����B�����̒n���ɂ͂��ꂼ�ꐫ��������A�����ɂ���O���̎������܂��قȂ�Ƃ����B
�܂��A���̔��M�n����4�ʂ�4�傪����A��O�Ɋe4�̏��n��������A����������ď\�Z�V���n���Ƃ���(�l��n���A�\�Z���n���Ƃ�����)�B���M�n���ƍ����ΕS�O�\�Z�n���ƂȂ�B�܂����M�n���̉��ɔ����n���܂��͏\�n��������Ƃ�������B
�܂��A�R�ԜA��ȂǂɎU�݂���n�����Ǔƒn���Ƃ����B
���n���v�z�̐���
���X��腖��剤�A�����A�n���Ȃǂ̌Ñ�C���h�̖��ԐM�ł��鎀��̐��E�̎v�z���A�����ɓ`�d���ē����Ȃǂƍ������āA�����`���̍ۂɓ��{�ɓ`����ꂽ�B
���̂��ߌ����C���h�����ɂ͖�������腖��剤�_�Ƃ��銯�����x�Ȃǂ��t��������ꂽ�B���̌�A��y�v�z�̗����ƂƂ��ɒn���v�z�͍L�܂�A���ԐM�Ƃ��Ē蒅�����B
�n���́A���{�̕����j�̒��ł͔�r�I�V�������̂ŁA���ꂪ���ɋ��������悤�ɂȂ����̂́A��������̖��@�v�z�̗��s����̂��ƂƎv����B���̗��s�̒��Ōb�S�m�s���M���܂Ƃ߂��̂��w�����v�W�x�ł���B
�n���v�z�̖ړI�́A��ɂ͏@���̈��ʉ��ł���A���̐��E�Ŏ�������Ȃ����`���`���㐢�E�Ŏ���������Ƃ����@�\�����B
�_���ł́A�]�ˌ���ɕ��c�Ĉ����֏��ł������L���X�g���W�̏������Q�l�ɂ��āA�H���R���v�z���l�Ă����B���Ȃ킿�C�G�X�̍Ō�̐R���̂悤�ɁA�卑�喽(�������ɂʂ��݂̂���)���A���҂��u�M��_�v�ȂǂɊi�t�����Ă䂭�Ƃ������z�ł���B�@

�m�����ւĂ��͂��A�Z����m��ʐl���ӂׂ��B���̐��ɂ͌܂Z�̗c�����́A���₵�����d�Ȃǂ��݂Ȓm�肽��Ȃ�B������ǂ��A���̌�O�ɂāA�m��Ȃ���A�����Ћ��͂��A�Ǝv�ւA�����\���ׂ��B�Z���Ɛ\���́A�n���E��S�E�{���E�C���E�l�ԁE�V�ケ����\���Ȃ�B���n�������������̕��̗��v�ɂ���āA���̗т��͂Ȃꂸ�A�Ԃ̒�ɂ߂��邪���Ƃ��ɂ��āA�Z���ɒ��˂���́A���@�̕���܂������肵���Ȃ�B�@�،o�ɁA �@
�@�@�@�đO�����@�։��Z� �@
�Ƃ̂��ւ�B���̐S�́A�O�����ɂ����āA�Z��ɗ։A�Ƃ̂��܂ւ�Ȃ�A�Ƃ����肯��A���̏��A�n���E��S�E�{���̂��肳�܂��������܂ق�����ցA�Ƃ��Ђ���A�Z���̎��́A�b�S�m�s�̈�㐹�����Ђ炢�Ă���ы��Ђ�A�����v�W�Ɛ\�����̂ɂ��܂��ɋL���ꂽ��B���܂������͂���B�������\���ׂ��B
��
���ɒn���Ƃ��ӂ́A����腕���̉��A���R�{�ɂ���B�����E����E�O���E�����E�勩���E�ŔM�E��ŔM�E���@���Ȃ�B�����n���Ƃ��ӂȂ�B����ɂ܂����̂��̏\�Z�̕ʏ��������B�����Ĉ�S�O�\�Z�n���Ȃ�B���̎R���C�ӂɂ��n������A�Ƃ���ɂƐ\�����ɂ͌�������B�܂��Ƃɂ������B�z�������R�̒n�����A�ߍ]�����q�̑�̂Ɛ\�����̂̂ނ��߂��A�R��ɂ��ƂÂ��Đe�̂��Ƃւ��̐\������́A���ق����n���̋ꂵ�݂́A���Ƃւ����Ƃ��A�S�疜���̒��Ɉ���\���ׂ̂������A�Ƃ����Ђ���������B����A�����n���̋ꂵ�݂����͂����Ƃ�́A��������݂̂Ȍ����͂��Ď��ʂׂ��A�Ƃ��̂��܂Ђ���B �@
�܂ÁA�n���̂��肳�܂����ӂɁA�V�ɂ͎��d�̖Ԃ��͂�A�n�ɂ͓S�邩�����Ƃ�����B�M�S������ɂ��āA�l�ʂɓ��т̂₫�Ήs�����āA���h�����̂�����邷��������ɐS�܂ǂЁA�����E�n���̂͂�����������ɂ����������ȂӁB�V�ɂ��ӂ��A�邬�̗т̗t�ӂ肭����āA�܂Ȃ���������Ԃ�B�n�ɂ��Ԃ��A�҉ΔR���o�łČ��ɓ���B�Ȃ��ނƂ���Η܂������B������Ƃ���ǂ��A����o�ł��B�{�k���߂̒����A���邵�݂Ȃ�ʌ��Ȃ��B����Ζ����Ƃ́A�Ђ܂Ȃ��Ƃ�����B����Ȃ炸�A����Ȃ炸�A���ʖ������̊ԁA���邵�݂��B���Ȃ炸�A���Ȃ炸�A�S�疜�̂��Ȃ��݂��̂т������B���@���̂��邵�݁A�Ȃ��Ȃ��\���ɂ�����B�������܂ɂ��鎖�A���N�Ȃ�B�n���̂ӂ������͂���ɂĒm��ׂ��B���̂��邵�݂���Ԃ́A�ꒆ���Ȃ�B�ꍅ�Ɛ\���́A�������l�\���A�Ђ낳�l�\���̐��A�O��̓V�߂ƂāA���͂߂Ă��낫�V�̉H�߂ɂĎO�N�Ɉꂽ�тÂȂÂ�ɁA���ꖇ�̂����قǂԂ�Ȃ�B������݂ȂȂł����Ă��鎞���A�ꍅ�Ƃ��ӂȂ�B���̊ԋꊳ�������A�\�����Ȃ��Ȃ����납�Ȃ�B �@
����A�����R�̓�����l�A�����f�H���Ă����ȂЂ��邠�Ђ��ɁA�閧��̗���ɂ���Ȃ���A���ɓ��肽�肯��ɁA�n���ɂĉ���̒�ɂ��Ђ��Ă܂肯��A���̂��܂Ђ���́A�n���ɗ�������̂͂��ւ鎖�͂Ȃ���ǂ��A�Ȃ���͂�݂��ւ�ׂ����̂Ȃ�B��A���̊����@�c�̖������ނ����Ă܂�B�����ɂ�Đ����E��b�𗬂����肵�߂̂ނ��ЂɁA�n���ɂ����āA�ꊳ�������B���̂悵���䂪�c�q�ɂ�����āA���̂��邵�݂������ӂׂ��A�Ƃ��ق�����A�������܂�Ă������܂͂肯����A���̂��܂Ђ���́A�n���ɂĂ͍߂Ȃ����̂����āA���邶�Ƃ��B��l��������܂ӂ��ƂȂ���A�Ƃ��ق����肯�邱���A���Ƃ��Ȃ����͂��ڂ����肯��B
����A���x�̐e���A����������ւ�A
�@�@�@ ���ӂȂ炭�ޗ��̂����ɂ����ʂ�Ι�������ɂ����͂炴�肯�� �@
���̉̂����Ђ��͂����āA���͂�Ȃ�B
�n���̂�A�������雠�������āA�a������߂�A �@
�@�@�@�����܂���邬�̎}�̂��͂ނ܂ł��͂Ȃɂ݂̂̂Ȃ��Ȃ���

�a���ΎR�ɎQ�肯��ɁA��Âɔ��܂�Ė�ӂ��ĕ�������A�l�̂��͂Ђ��܂����ẮT���肯���q�˂���A���l�̕Ĕ�������Ȃ�Ɛ\�������߂�
�@�@�@��̂�鏼�������ɑ�����炰�͂����ė���(���ƁT��)�ނȂ�
(�钆�A���܂�ɑ�����������A�N���Ď����ƁA���w�̏��������A���č�Ƃ����Ă���Ƃ����̂ŁB���낪���i�Ί݂̏����ŐQ�Ă��邾�낤�ɁA�N���Ă��܂��̂ł͂Ȃ�������A�S�z����B�ȑO�̒Y�Ă�����荞�̂Ƃ����A���̔_�w�ɑ��鎌���Ƃ����A�M���K���̈�ʏ����ɑ���ӎ����A�����ɂ��悭�o�Ă���B�Ȃ��A�]�ˎ�����}����܂ł́A�E�ƕ����͊ɖ��ł������B����(��)��������ɁA�邪�u�����v�ɍ�́u���сv��������B���Ɓ��u���v�ɋ[����u���Ɓv(�����)��������B�Ƃ�(��)�݂��聁�w�Ìꎫ�T�x���o����u�Ƃ�ށv�ɁA�u���ށA���ށv�����Ă���B�u�苿���B�����킽��B�吺�������đ����B�������Ă�B�v �h���`�́u�ǂ�߂��v�u�ǂ�����v�́A�����Ɏc��B�V���œ����ɂ��ƁA����������������������B)
�����������S���Č�A�㓌��@���N���뎒�͂肯��߂�S�����Ƃɂ����͂����肯��ɁA�������Ə����t�����Ď���������Ă�߂�
�@�@�@����Ƃ��ɑۂ̉��ɂ����������Ŗ�(����)�܂�ʖ������邼�߂���
(�ꏏ�ɑۂ̉��ɋ����邱�ƂȂ��A�����肪�����c���Ă��܂��āA������邱�Ƃ̂Ȃ����̖������邱�Ƃ��߂����̂ł��B�����������͐��O�㓌��@(�������q)�Ɏd���A���N�߂�������Ă������A�������N�ʂ艺�����ꂽ�B���̈߂ɏ����������̖��������t�����Ă����̂����ĉr�́B�S�[�͖���ĖڂɌ����Ȃ��Ȃ��Ă��A���҂̖��͖���邱�ƂȂ��ڂɐG��A�߂����Ǒz��U���B)
�n���G�Ɍ��̎}�ɐl�̊т��ꂽ������Ă�߂�
�@�@�@�����܂��⌕(�邬)�̎}�̂��͂ނ܂ł��͉��̐g�̂Ȃ��Ȃ���
(�Ȃ�ĂЂǂ��B���̎}������ޒ��ɐg���т���āA����͈�̂ǂ�ȍ߂�Ƃ����l�������Ȃ����̂ł��낤�B�u�邬�̎}�v�Ƃ́A�n���ɐ����Ă���Ƃ������̎��̎}�B�u�邬�v�ɖ��A�u�g�v�Ɏ��̈ӂ��|���A�u�}������ނقlj��̎����Ȃ����̂��v�̈ӂ����˂Ă���B) �@












































 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@


 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@



 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@


 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@



 �@
�@ �@
�@



 �@
�@ �@
�@ �@
�@
















































































































































































