�����̕���W�E�b�M1�E�b�M2�E�b�M3�E�b�M4�E�ЛI���E�ЛI���`��1�E�`��2�E�`��3�E�E�E
���������E�E�E
�@
 �@
�@ �@�@
�@�@
�@�@�@��������ȂΌB�̉��@�@����
�@�@�@������m�ɍs�����Ӌ��̏�@�@����
�@�@�@�������ЂƂ�s���̉��@�@���L
�@�@�@�����̖�։̔�Ԓb�艮���ȁ@�@���L
�@�@�@�����ɏƂ肻�ӊւ̂Ƃ������ȁ@�@�{��
�@�@�@�������Ђ������ȋS���@�@�ꒃ
�@�@�@�����̂������Ȃ邩�Șm���@�@���엧�q
�@�@�@�������ɂ��Â݂Ċ��̌�����@�@�ѓc���� �@
������J�R���̖̊Ԃ��
�������Ȃ����̓V����
�����⋘��̂����炳��
������͖̒��̒|�O��
������O�k�̌Q�c�̉߂Č�
���������������ΌB(����)�̉�
������m�ɍs�����Ӌ��̏�
�n�Â̊�̂Ȃ݂��₨�ڂ댎
���䂵�ē����`�܂ڂ댎
�Z�X�ޏ���͗L���ڂ댎
�悫�l���h�����Ƃ�O��
�����ʂ��𑫂łʂ����O��
���ڂ댎��͂��̂ڂ��M(���悵��)����
�鐅�Ƃ闢�l�̐���Ă̌�
����̏����Ȃ��߂Ă̌�
�ʂ������̐킽���Ă̌�
�͓��i���͂���j�̗�����h��Ă̌�
������J�𗭂���r�̂���
�����₤�����̂킽��z�K�̊C�@
������I�ɂʂ�ʂ͘I�l(��)��
�������͐l�Z�ʕ�̒���
������_�̋����
�����ɂ�̂���̂鉺����
���ۂ̍��Ղ��ނ��ӂ̌�
���܂��̒r�͈Ŗ炯�ӂ̌�
�Ԏ�͖��ɗ�邯�ӂ̌�
���l�̎�̉̂�ނ��ӂ̌�
��̌��������Ƃ̐��̒�
��̌����������l��K�Ӗ��
������Ēr�̂ЂÂ݂��̌�
�R���Ԃ̖؊Ԍ��������̌�
�\���̍����͂������̌�
�O�䎛���j�q�̖钅���̌�
���l�损�ԉ߂Ă̂��̌�
�܌��J���͂�O�ɉƓ�
�܌��J��䓤(�݂�)�̏��Ƃ̛��S����
�܌��J���C����(��)���萅
��
�����⓪������Ε�̌�
�Â��Ȃ邩���̖͂��~�̌�
�@�C�ɐ��匩����_����
����̒��@�Β|�̌�
��o�����͕̂��������Y���@
�������ʖ�̘A�F�̂��ڂꌎ
�����M�������͓�����@
���l��}��������J�̌�
���Ղ�s�͂Â�Ⓧ�̌�
��
������U�c�㐅�����
�ԉ��旄�̌䒃���̗[����
��\�L���₽��T������
����Ɍς����Ԃ⏪���� �@
����~�͖̌ɂ��ǂ錎���
�P(���炩��)����(��)�Ėڂ̂��錎��Ɓ@�@
��
���̉Ԍ��ɏ��~��ޏ�����
�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐���
���̉Ԃ�Ђ�ꂩ��̌�������
��ւ̌��������J�̐�
��
���韆�łЂƂ藈�܂���\�O��
�g�̈ł̓��Ђ��ʂ錎������
���������Č����Ȃ��Ȃ�銦��
�p�����̂��������悵����
���S���M���ɉ䌎��̂�
���_�̖邷���猎�̐璹��
�~���������ɗׂ��킷�ꂽ��
�ÎP�̔k���ƌ���̎��J��
�劦�����̌��̑l���ȁ@
���������邶�̉����o��
�Z�����̌��ɂ₨�͂��B�N�q
�t�J�₢����ӌ��̊C���i�Ȃ��j
����،���肤���j��
���X�ɂЂƂ肠�������F
���V�S�n��������ʂ肯��
�R�̒[��C�𗣂�T������
���̌�����ƂւΈ�x��
������Ȃ݂��ɍӂ���T�̋�
��s�����[�R�Ɍ�����
�l�ܐl�Ɍ��������T����ǂ��
���ɕ��Ċ^�Ȃ��ނ�c�ʂ���
�d���c���Ƃ̌��̓܂���
���ɑ��N�ɓ��ԁi�Ƃ��݁j�̐���
�J��̌��N����Ԃ��������
���c���ō��H������H���J
���������ɂ��ւ����ǂ��
�u���v�͏H�̋G�ꂾ���A�u�~�̌��v�͐g�k������悤�Ȋ��o�����X�Ƌ�ɂ��錎�̗l�q����ɉr�܂�A�������������Ă���B�]�ˎ���̍Ύ��L�ł́A�u�~�̌��v�͎O�~�i���~�A���~�A�ӓ~�j�A�u�����v�͋���11���i�V��12���j�̌��Ƃ��Ă��邪�A�����̎����͂��قnj����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B��C�����������~�̎����A���ɍႦ�n���Ă��錎�ł���u�����v�Ƃ������A�Ƃ����ӌ�������B
���t�̌�
�����͂��ڂ댎�𑽂��r�ނ��A�t�̌��͎��̈��݂̂ł���B
�@�@�@�t���������̖̊Ԃ��
������̓C���R���h�E�ƓǂށB�R�銋��S�������̎R���ɂ���Ƃ����B���̋�͐V�Í��a�̏W�̐�҂̈�l������o�Ƃ����l�̘a�̂ɂ��̂��낤���B
�@�@�@�q�˗��ĉԂɕ�点��̊Ԃ��@�҂Ƃ����Ȃ��R�̒[�̌��@
�����̋�ł́A���Ƃ͌���Ȃ��B�������A�u�̊Ԃ��v�Ƃ������ƂŁA����z�N������B �@
�ےÍ������S�єn��(���܂ނ�)(���F���{���s�s����єn��)�ɐ��܂ꂽ�B���s�{�^�Ӗ쒬(���O�㍑)�̒J���Ƃɂ́A����Ƃ������������ɕ���ɏo�Ď�l�Ƃ̊Ԃɂł����q�������Ƃ���`���ƁA����̕悪�c��B�����ɂ���{�ɂ́A�c���̕������ꎞ�a����A��N�A�O��ɖ߂�����������Ƃ��ě����G�����ƌ��`����Ă���B
20�̍��A�]�˂ɉ���A����b�l(�͂�� �͂���k�锼���v��(��͂�Ă� ������)�l)�Ɏt�����Ĕo�~���w�ԁB���{���Β��u���̏��v�ӂ̎t�̋����ɏZ�܂������B���̂Ƃ��͍ɒ��ƍ����Ă����B�o�~�̑c�E���i�哿����n�܂�A�o�����邱�Ƃւ̋������������B�������]�˂̔o�d�͒ᑭ�����Ă����B
����2�N(1742�N)27�̎��A�t���v�������Ɖ���������(���F��錧����s)�̍����哆(�������� ����Ƃ�)�̂��ƂɊ�����A�h���炤�����m�Ԃ̍s�r�����ɓ���Ă��̑��Ղ�H��A�m�̎p�ɐg��ς��ē��k�n�������V�����B�G���h��̑���ɒu���ė�������B����́A40���ĉԊJ�������̏C�s���ゾ�����B���̍ۂ̎�L�Ŋ���4�N(1744�N)�Ɋ哆�̖����ʼn��썑�F�s�{(�Ȗ،��F�s�{�s)�̍����I��(���Ƃ� �낫�イ)��ɋ��������ۂɕҏW�����w�ΒU��(�F�s�{�ΒU��)�x�ŏ��߂ĕ������������B
���̌�A�O��ɑ؍݂����B�V�����ɋ߂��{�Âɂ��錩�����̏Z�E�E�G�_�F�_(�o���F�|�k)�ɏ����ꂽ���̂ŁA���n�̔o�l(�^�Ǝ��Z�E�̍�\�A�������Z�E�̗��b��)�ƌ𗬁B�w�͂����Ă�x�Ƃ������e���c�����B�{�Îs�ƁA��̋����ŗc�������߂������Ɩڂ����^�Ӗ쒬�ɂ͕������`�����G�������c��(���������Ƃ����{�����w���m���s�V���q��}�����x�A�]���������w���|�}�����x)�B����ŁA�^�Ӗ쒬�̗��l�ɂ����܂�ĕ`�����G�̏o���Ɍ�����āA�{�ɏW�߂ĔR�₵�Ă��܂����Ƃ̓`��������B
42�̍��ɋ��s�ɋ����\���A�^�ӂ𖼏��悤�ɂȂ�B��e���O��^�ӂ̏o�g�����疼������Ƃ����������邪�肩�ł͂Ȃ��B45���Ɍ������Ĉ�l�����̂�ׂ����B51�ɂ͍Ȏq�����s�Ɏc���Ď]��ɕ����A�����̍�i����|����B�Ăы��s�ɖ߂�����A����(����)�p���ŋ��������ȂǁA�Ȍ�A���s�Ő��U���߂������B���a7�N(1770�N)�ɂ͖锼���ɐ��Ղ���Ă���B
���݂̋��s�s�����敧�����ʉG�ې������̋���ŁA�V��3�N12��25��(1784�N1��17��)�����A68�̐��U������B�����͏]���A�d�lj����ǂƐf���Ă������A�ŋ߂̒����ŐS�؍[�ǂł������Ƃ���Ă���B�����̋�́u����~�ɖ�(����)������ƂȂ�ɂ���v�B�揊�͋��s�s�������掛�̋�����(����Ղ���)�B
�����m�ԁA���шꒃ�ƕ��я̂����]�˔o�~�̋����̈�l�ł���A�]�˔o�~�����̑c�Ƃ�����B�܂��A�o��̑n�n�҂ł�����B�ʎ��I�ŊG��I�Ȕ���ӂƂ����B�Ƒn���������������̔o�~��J���u�ԕ���A�v�������A�G��p��ł���u�����_�v����ɓK�p�����V�����̔o�~���m�����������S�I�Ȑl���ł���B�G�͓Ɗw�ł������Ɛ�������Ă���B
�@�@�@���������̂������������ꎭ�̐�
�@�@�@�(���ق났)�⑊�@�����̂���鎞
�H�̎n�܂�̋傾�B�u����品v�́u���̓���炵�v�Ƃ��ǂ߂āA�u���́v�������Ă���B�u���@�����v�͎i�n���@���앶�N�̗�������您���Ēe�����Ղ̂��ƁA���̌����Ղ�Ɛꂽ���̂悤�ɃR�I���M������Ƃ�����u�̎���ł���B���̉��Ƃ������́A�����Ɩ��Ă���Ƃ������A�Ղ�Ɠr�₦���Ƃ��ɁA������̎����҂���Ɠ����B��������������Ă���ƁA�����͎��̐l�ł��������ȂƎv���Ă���B�����Ȃ̂��A�����͈ĊO�Ɏ��̐l�Ȃ̂ł���B�_�����ċ��������Z���ɋő䂪���Q�����Ă���Ƃ���ɕ�����������Ƃ��A�����́u�ۖ~�̒łɐ̂̉������ށv�Ɖr��ł���B�ő�̌��t���ۖ~�̒ł̖ؖڂ��A�����ɂ͉��Ȃ̂ł���B���Ȃ̂��B���̏������u�Ԃ�K�ꂽ�Ƃ��͎��������u�Q�Ԃ̈�{���ɖK��āv�Ƃ��āA�u��(���܂�)�������b�������̉�������v�Ɖr�B�����͎��𒍂��B�����X����̂ł͂Ȃ��A�����B�H�̋�ł͂Ȃ����A�u�����Ђ��̓�(�ӂ�����)���̂قƂ肩�ȁv��u�����Ђ��⎨�͉䂪�g�̕ӂ肩�ȁv���������B�������ɁA�������ɂȂ��Ă��āA���̎��Ɖ��̂������̋͂��ȏ����������Ă���B���̏������B�����ɂ́u���̂قƂ�v�u���̂�����v�Ƃ��������̊E�悪����B���������̐l���Ǝv�����̂́A���̂Ƃ��������B���]�ŃR�I���M���Ă�����{�l�Ƃ��Ƃ����P�`�Șb�ł͂Ȃ��B����̓��I�m�[���E�J�����g���́w�����b�p�x�Ȃ̂ł���B
��ʂɂ͕����͖ڂ̐l���Ǝv���Ă����B�����A�ނ��ڂ̐l�ł���B�������A���̖ڂɂ͂��낢��̖ڂ�����B���l�ɏ�̖ڂ̐l�Ȃ̂ł���B���̕��������𒍂��̂ɑ��āA�ڂ̕����͂������ƑS�i�������Ƃ߂�B�傫�����āA�����Ƒ�����B���邢�͊r�ׂ�B���̑傫���ڂ���������͑��̔o�l�̒ǐ��������Ȃ��B���̑傫���́A�u�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐��Ɂv��u���݂�����͂�O�ɉƓv�Œm���Ă����悤�ɁA�q���ł������킩��B���̑傫���ɂ��܂���B�킪���ɂ͌×����g�����}�h�Ƃ������̂����邯��ǁA�̉Ԃ�O�ɂ��ē��̌��Ɛ��̓�������ɕ`�����҂ȂǁA���Ȃ������B�w�R�ƒ����́x�Ɂu���͓��ɝ�͐��ɁA���Ƃ��a��͐^�Ɂv�Ƃ������Ȃ����邯��ǁA�܂��A���̂��炢���낤�B��͂ɋz�����܂��悤�ɍ~��Â���ׂ��J�̑S�i�ɁA�̉Ƃ�z�����҂��A���Ȃ������B����͐��n�R���悻�̂��̂��B�����������́A���̑傫���̍m��ŏI���̂ł͂Ȃ��B�����̉Ԃ�܌��J�̈�ۂ�ʂ̂��̂ɂ��ς��Ă����B������m��ɂ́A�ނ��낻�̕ω��������邱�Ƃł���B���Ƃ��A�����ł���B
�@�@�@�̉Ԃ�~����炸�C����
�@�@�@���݂���▼���Ȃ���̂����낵��
�~�̂��Ȃ��C�B���O�����Ă��Ȃ���B�����ɂ͂���u�s�݂̑傫���v��u�������ʂ��̂̑傫���v�������Ă��āA����ɂ��܂���B�����ɂƂ��ẮA�傫���Ə������A�����Ƌ߂��͓����ڂɎʂ鐢�E�Ȃ̂ł���B���݂ƕs�݂͓����Ɍ�������̂Ȃ̂��B�����ɂ́u���̕����v������B���́u���̕����v�������ڂ����ŋ߂ɂȂ��ċ������Ă��镓���Ȃ̂ł��邪�A���̂��Ƃɂ��Ă͂����ł͂ӂ�Ȃ��ł����B�w�R���v�z�x�Ɏw�E�����u���̎R���v�ɂ��Ă̌�����ǂ�ł��炢�����B�ꌾ���������Ă����ƁA�ڂ��͂��āA�u��(�����̂ڂ�)���̂ӂ̋�̂���ǂ���v�ɐڂ����Ƃ��ɁA��𗹉��ł����̂��B���̐l�ɂ́u�s�݂̑��݊w�v������Ƃ������Ƃ��\�\�B�Â��āA���̋�ƂƂ��Ɏ��̂悤�ȋ���m�[�g�ɔ����o���ĕ��ׂāA�܂��܂��[���������������̂ł���B���̃m�[�g�������قLj������肾������A�����A����ł����B
�@�@�@��(�����̂ڂ�)���̂ӂ̋�̂���ǂ���
�@�@�@�H�̋̂ӂ�߂��������
�@�@�@���V�S�n��������ʂ肯��
�@�@�@�����Č����Č����Ȃ��Ȃ�銦����
��1��B������グ�Ă������Ȃ��B����ǂ����̋�̂��̂�����ɁA����A�����ɁA����͑����オ���Ă����B���ꂪ�u���̂ӂ̋�̂���ǂ���v�ł���B��2��B������Ă���ƐL�����Ă���B����ǂ�����́A���̋�̑����Ɉ�H�̒߂��I�X�ƕ�����Ă����B���ꂪ�O2��́u�����Ȃ����̂������Ă���ϖ]�v�Ƃ������̂��B��2��́A���������肪����ł���B��3�傪�A�����ɂ͌������ׂĂ������炳�܂Ȃ̂ɁA���̌��̌��𗁂тĂ��钬�͉��������Ă��Ȃ��Ƃ��������ł���A��4��́A����͐V���Ȃ̂ɁA�����O���炻���ɂ͌��������Ă����āA���܂��������̌������������āA�S�ɐ��݂�悤�Ȗ銦�������c�����Ƃ��������B�����́u���̑��݂̉r�Q�v�ł���B�u���̎����̑��݊w�v�ł���B����������͕����ɂ������Ȃ��B
�傫�������ɋ����Ă��肢�Ă͂����Ȃ��B�����ɂ͑傫���ڂ��珬�����ڂւ̈ړ�������B�傫���ڂ��������ڂɈڂ��Ă��������Z������B���̃E�c���̎�@�����܂������B�܂��H�̋�ɂ��Ă������A���Ƃ��Δ��ƁA�R�ƁA�J�A�ł���B�܂��A�炫����锋���ތi�F�̂��Ƃł���B�������́u�J�̔��R�͓����ʎp���ȁv�u�����͍炭���낷�i�F���ȁv�Ƃ����ӂ��ɉr�ށB�J�������܂���Ă��āA����e�ɂ����Ɗ��B��������Ƃ��́u���̖ځv�Ɓu�c��̖ځv�̊W���g�n�h�̌��i�̂Ȃ��̓_�i�́g�}�h�̂悤�ɕ����Ԃ̂��B�����ŁA�u�J�̔��v�u�R�͓����ʁv�u���̎p�v�u���ȁv�Ƃ����ӂ��ɉr�ށB���̉r�ݕ����܂������̓ƒd��Ȃ̂ł���B�������H�̋�A�u�H���̐����̂����Ă�{���ԁv�u�H���̂��������Ă䂭�ĎR�q���ȁv�u�����G��\�l�S�̂��Ƃ����v�ȂǁA�����̖ڂ��J�����̗��Ƃ����ɂȂ��Ă���B�C������ׂ��́A�����̃J�����̃Y�[�~���O�̓v���Z�X�������ς�Ȃ����Ƃł���B������E�c���̎�@�ł���B���������Ƃ��͊���Ă���̍ו������ŏ�������B�������Ă����āu���v�̎��Ɍ����Ă���ӊO�Ƃ������̂��A�ӂ��ɉr�ށB���̂悤�ȏH�̋�͂ǂ����B�u���̍���e��肭�炫�قƂ���v�u���̗t�̂���݂��قȂ�J(������)���ȁv�B�ڂ̐l�͋e�̗t�̈Â݂������̉��̈ł̌Q�ɖڂ������̂��B����e�⊋�́u�قƂ�v��u������v�ɖڂ������̂��B�܂����������̖ڂ̓J�����E�I�u�X�L����(�܂��ɈÔ�)�Ȃ̂��Ǝv�������Ȃ���肾�B
���̂��낾�������A�������k�́w������F�x�����Ă�����A�����͊ዾ�������Ă����B�ŏ��ɂ���������Ƃ��A�ւ��A�����������̂��Ǝv�����B���k�͏������t�̂��ƁA�o�~�͂ނ��A�G�̂ق��ł������̒�q�������B�������ɕ����������ƕ`���Ă���B���ɂ��Ó��䔯�⓪�Ўp�̕����̏ё���͂��邪�A���t�ɂ͂���Ȃ��B���Ɂu���锼�����k�q�ʁv�Ƃ���B�����͓��Ђ����Ԃ��Ă�����ƔL�w�A�ǂ������R�G���^�c��z�킹�镗�e���B����Ŋዾ�������Ă���B�o�l�Ƃ��������A�̎�l�Ƃ�����ۂ��B�{����҂��c�^��́w�����x(��g�V��)�ł́A������150�Z���`���炢�������낤�Ƒz�肳��Ă���B�����������̂ł���B���A���̏�(����)�����͕����ɂӂ��킵���B�����������������ɏo�g���č]�˂ɏo�āA���̂����ڂ��y�ڂ��l�ƂȂ�A���𒍂��l�ƂȂ�A���̂������s�ɗ��������Ċዾ�������A������ƔL�w�̐l�ɂȂ��Ă������B�����������Ȃ�܂łɂ́A�����͕����Ȃ�́g�C�s�h�����Â��Ă����B������������ƁA�䂪�g�̏C�s�̕s���������������Ȃ��Ă���B
�����͔o�~�ɂ����Ă��o��ɂ����Ă��A��F�ɂ����Ă��A���������������ӂ�Ȃ������l�ł���B�łȂ���A����ȕ����͐��܂�Ȃ��B�����A���̏����������Ȃ������B���̂��߁A�ǂ��������͂ق���Ǝ��ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���B�Ս��ȏC�s�Ȃǂ�������|���������Ȃ��Ȃ��Ă���B�܂��A�o�܂������c���Ȃ������l�ł����������߁A�m�Ԃ̐l�����m���Ă�����ɂ́A�����̐l���͂܂����{�l�́u���̂قƂ�v��u�ڂ̂����݁v�܂ŗ��Ă��Ȃ��B������m�邱�Ƃ͓��{�l�̐g�̊��o���g�����}�h�ɂ��邱�ƂȂ̂Ɂ\�\�B����ɋC�������̂͐����q�K���������A�q�K�ȍ~�A���X�̕����_��������Ă��āA�����������ƂȂǂ����Əo�s�������낤�Ǝv����قǂȂ̂����A���₢��A�ǂ��������ł��Ȃ��̂ł���B�Ȃ��݂�Ȃ��݂�ȕ������������݂����āA���{�l��l��l�̕������������肵�Ă��܂����̂��B�����Ɂw�����S��W�x���������̂́A�������������̋���l�G�ɕ����A�G��ɐU���Ă��āA���ŏ����̍Z����t���Ă���̂��A�����炭�������������ǂނ̂ɍł��K�m�ȕҏW�ł͂Ȃ����Ƃ������邩�炾�B�Ύ��L�̕��ނł͂Ȃ��A�Í��W�ȗ��̕����ɂȂ��Ă��āA�����ǂ݂��Ă���ƁA�����������ǂ̂悤�ɔ���ɂ��Ă������������Ă���B��g���ɂȂǂł�������͕��������㏇�ɓǂ�ł����ǎ҂��A���Ă���������݂��݂����Ƃ����Ƃ��̈���ɂӂ��킵���B�Ō��́u�����ӂ��v�͍����w�ɋ��������Ђ̂��ƂŁA�ŋ߂ɂȂ��Ă���ȎЖ��ɂ��Ă��܂����B�����Ђ̂ق��������Ƃ悢�B
�m�Ԃ����\�ɂ����������Đ������悤�ɁA��������V(���E�V��)�ɂ����������Đ��������Ƃ́A�����̏�����m��ɂ��d�v���B�@�����͋��ی��N(1716)�ɑ��̍x�O�������єn�ɐ��܂�āA�V��3�N(1783)�ɖv�����B�g�@�����R�ɏA���Ă���c���ӎ��̐Ⓒ���܂ł������B���ɕ�V�����Ƃ��錳�\�ɂ������ɂ��܂���࣏n���̑O���ɓ�����B20�ō]�˂ɏo���B�����ɂȂ��Ă����̂��t���̑���b�l�ŁA�b�l�͔o�~���Ёu�锼���v���c��ł����B�b�l�͑v���Ƃ��������B���̂���̕����͍ɒ��Ȃ����͍ɒ��B���傱�܂��Ǝt���̐��b�������B����ǂ��b�l��5�`6�N���67�Ŗv��(����2�N)�A�����͎t���������B���ꂪ27�ł���B���̂��ƕ������ǂ̂悤�ɂ������Ƃ����̂��A�����̕��̃X�^�[�g�ɂȂ��Ă���B�����܂ł̕����͔b�l�ɂ����Ƃ͂����A�o�~�t�ł͂Ȃ��B�ŋ߂̌����ł����炩�ɂȂ��Ă����悤�ɁA��y�@�̉����[�̑m�̂ɂ����B�ꉞ�͑��o������̐t���������Ă����B����ɑ��āA�o�~�t�͐E�Ƃł���B���Ƃ��B�����̃f�U�C�i�[��ʐ^�Ƃ��e�Ղɂ͐H�ׂ��Ȃ��悤�ɁA�o�~�t�ŌЌ������̂��ƂȂ�Ƃ���Ȃ�̊o�傪����B�Ƃ������ƂŁA�b�l������Ŗ锼��������ꂽ�Ƃ����̂́A�킩��₷�������Ε������H�����ς��ꂽ�Ƃ������ƂȂ̂ł���B�����������͂�����@��ɗV�s�Ɍ��������B�������̋��_���̂Ă邱�Ƃɂ����B�K�k�̋������ď�썑��������߂���A���̂��Ƃ͓��k�ȂǂɗV�B�w�V�ԓE�x�ɂ��̂ւ�̂��Ƃ�������������ƒԂ��Ă��邪�A�悤�����27����36���炢�̏\�N�قǂ������ƕ����Ă����̂��B����͕����̓ۋC�̂悤�Ɍ����āA���́A�����L���̗p�ӎ����ȕ��ҏC�s�������B�w�˂̂������x�ɂ́A�_��(�o�~�̏@��)�ɂȂ�ɂ͍s�r�����Ė�������̂��Ȃ�������Ȃ��Ə����Ă���B�o�~�t�Ƃ��Ă̗I�R����ʉߋV�炾�����̂��B�ڂ̐l�ƂȂ肦���̂��A���̐l�Ƃ��Ȃ����̂��A���̏\�N�̒ʉߋV��̐��ʂɂ������Ă����B
�������{�i�I�Ȕo�~�t�ɂȂ��Ă���������ɂ́A�����ЂƂ傫������ł������Ƃ�����B����3�N(1743)���m�Ԃ̌܁Z����ɂ������Ă����Ƃ������Ƃ��B�e�n�ł�����ɒǑP�@�v��ǑP�����W�̕Ҏ[�������Ȃ��Ă����̂����A��������������ɑS���I�Ȕm�ԃu�[���Ƃ������ׂ����������Ă����B���������ҏC�s�����炩���I������A�����́u�m�Ԃ̌i�F�v�Ŗ��J�ɂȂ��Ă����Ƃ�������Ȃ̂ł���B�Ƃ�킯���a7�N(1770)�́w���̍ד��x�ĔłƁA���i4�N(1775)�̔m�ԁw�������x�w�O���q�x�̏��߂Ă̏o�ł��傫���B�m�Ԃ́u���Ђ��ق��ĉ�������v�u�������đ��ɕς���ׂ��v�́A����ŏ��߂Đ��ɓ`������B�u���̂��Ƃ͏��ɏK�ցv�������ŏ��߂Đ��ɒm��ꂽ�B�u�s���s�v�͗��s��ɂ���Ȃ����B������肩���a8�N�ɂ͍]�ː[��ɔm�Ԉ����Č�����A��Âɂ͌��Z�����ċ����ꂽ�B�����ő䂪�~�h���Ă���ƕ����A������K�ꂽ�������r�̂������قǂ́u�ۖ~�̒łɐ̂̉������ށv�������B�������ĕ����͔m�Ԃ̌����ɓ����Ă������̂ł���B���ꂪ���̕��ҏC�s�������낤�B�w���̍ד��x�̑��Ղ����ǂ��ĉ��B��~���������B�]�˕����Ƃ������̂́A���̂悤�ɉ��x���̍Đ��ƕ����ɂ���Ă���ƒ蒅�������̂ł���B���Ԃ����ĕS�N��̎������ł���ƒ蒅�����B�����͍����̋��݂ł��������B
�����̓]���36������ɂ���B���N(1751)�ɕ����͒��R����ʂ��ď���Ɍ������B�����̋�(���)�ɂ͌�����Ȃ��B���s�ɓ����Ēm���@�̈���ɑ����Ƃ�(��y�@����������)�A�Â��Ĕb�l�̒�q�̒��V�E�]���v���Ɏf���A�������痌�����O�̎��X��O�O�ɕ������B��������4�N�قǂ����ɕ�炵�āA���ꂩ��O��ɕ����A���N��O��E�O�g�E�ዷ�E�z�O�ɗV�s���āA���7�N�ɋ��s�ɖ߂����B���̂Ƃ������́u�^�Ӂv�𖼂̂�B��قǒO��̒n��^�ӂ̌i�F���C�ɂ������̂ł���B�O��V�s�͔o�~�����A�����炭�o��C�s�̂��߂������Ƃ�������B���̐����������u�^�ӕ����v�����悢��o�~�t�Ƃ��ē����o�����̂����a3�N(1766)�������B��_�E���g�E���E�S�m���A�O�Ƃ����u�O�َЋ��v�ł���B��_�͓����̊s�ɏZ�݁A���g�͕�����s�Ɋw�����l�A���͔Ō��u���������v��3��ځA�S�m�͈�҂ł���B�ڂ��͂��ܖ��ڋ�y�������`�@�m��A�m�ȂǂƂ����u�m�v��u�A�v��u���v��g��ł��邪�A�������n�߂�Ƃ��A�����v���o���̂��A���̕����̋����ł̊����J�n�̏�ʂ������B�������o�債�āA���̂Ƃ�����锼�����c�ނ��Ƃɂ����B���̂Ƃ���A�{���E���k�E�S�r��̎�v�����o�[�ƂȂ����g���o�g�h�������Ă����B���̌�̕������ǂ̂悤�ɓ��������́A18���I�̏�������̕��l�S�̂̃l�b�g���[�N�̏d�Ȃ��m��ׂ��ł���B�����͂��̒��S�ɂ����킯�ł͂Ȃ����A���Ȃ炸���̂ǂ����ɐȂ��߂Ă����B�܂��A���̂ǂ����ɂ��Ȃ炸�A���R�z��r����ؑ����ѓ��┄�����������B�����������Ƃɂ��ẮA�����܂��ӂ�Ă݂����B�������ĕ����͂��������̏������I���āA�^�ӕ������������ꂽ�̂ł���B�ዾ�������邱�ƂɂȂ�B�����Œ��ڂ���ׂ��́A�������悯���ȃe�L�X�g�������Ȃ��������Ƃł���B�����̃e�L�X�g�͔m�Ԃł悩��������ł���B����͐D�����˂ɗ��x�S�J���������đ�_�Ȏ��݂ɒ���ł������̂ƁA�悭���Ă��鎖��(�v��)�������悤�Ɏv����B
�Ƃ���ŁA�ڂ��̕����ɂ��Ă̈�ۂ⊴�z�́A�N�X�Ƃ͂���Ȃ��܂ł����N���ɕς���Ă����B���ꂾ���������[���Ƃ������Ƃł���A�ڂ������������̑S�e���������A�ׂ̂����Ă����Ƃ������Ƃł�����B�ŏ��̕����Ƃ̏o��͕ꂪ���������O�̋�ł������B���̂��ƁA�ꂪ�����̉��O�������Ă��ꂽ�̂��B���̎q������̂������ɂ��Ă͂��łɁw�V�w�x(���݂Ɛ��_�̌n��)�ɏ��������ƂȂ̂ł����ł͂��肩�����Ȃ����A�Ƃ������ڂ��̕����͉��O�̋�Ɏn�܂����B
�@�@�@���O�U��đł������Ȃ�ʓ�O��
�@�@�@腉�(����)�̌��≲�O��f����Ƃ�
�@�@�@�n�Ԃ̂Ƃǂ�Ƌ������O����
�@�@�@��(����)�Ƃ��ċq�̐�Ԃ̉��O����
�@�@�@�U��Ă̂����������ɂ����O����
�@�@�@�R�a�̂����炳�܂Ȃ蔒���O
���܂��Ȃ��A���ׂĐ�i�ł���Ǝv���Ă���B���O�̋�͂��܂Ȃ��N���������܂��B�����������v�������ׂ�Ȃ�A����؊x�̖n��̉��O�ƁA����K�v��쐣�q�Y�̉��O�̗��Ԃ��炢�̂��̂��낤���B���ɔ����Y�́w���D�̎��l�E�^�Ӗ앓���x�ƈ�_����́w�l�̕����蒟�x�w�V�Ύ��L�̕����w�x�ɂ䂳�Ԃ�ꂽ�B����ŕ�����{�C�œǂނ悤�ɂȂ����B���������Ă����ޑ��́w�����S�W�x���A�ڂ��̎���I�ȕ����Q���������B����Ȃ킯�Ȃ̂ŁA�����̂��ƁA�ł����1���ł�2���ł��������̂����������Ǝv���Ă���̂����A�������̂܂܂ɂȂ��Ă���B���̂܂܂ɂȂ��Ă��邾���łȂ��āA�����ɑ��錩�������N���ɕς���Ă��Ă��邽�߁A�Ȃ��Ȃ�����肪���Ȃ��ł���B���Ƃ��ΐ��N�O�ɐ��؉Z���́w�����Ɩєn�x��ǂ�ł���́A�܂�������ƌ��������ς���Ă����̂����A�܂��єn���ɂ����s���Ă��Ȃ��B�����͖єn�Ɏn�܂�єn�Ɍ���ł���l�Ȃ̂ł���B�Ƃ��Ɂw�t���n��ȁx�͂��ׂĂ̕����̏W�����B����Ȋ����o�~������̍�i�́A�����N�������Ȃ��B���Ē������c�j���w�t���n��ȁx�̊����̂Ƃ����Љ����܂���ŏ��������Ă݂������̂��������A������������A�Ȃ�Ƃ����Ă��\�z�\�����f�R�ł���B�a���N�r�̓��{�j�����B�����ō���Ƃ����Ă������낤�B�������������́u���Ȃ鑺�v�Ƃ����o�����������Ȃ̂ł���B�����͖єn�ɔ����Ėєn�̕��Ƃ��Đ����Â����l�������B�܂��A�����������Ƃ�S�����Ȃ����������Ă݂����̂��B
�Ƃ����킯�ŁA�����͂��̂��炢�ɂ��Ă������A���̂悤�ȕ����ɂ��Č����Ă��������������ƂŁA���ƂƂ����Řb�������Ƃ�����̂ŁA����ɂ��Ĉꌾ�����Ă���肽���B���܁A���̐��V���̃u�b�N�V���b�v�M�������[�g���������h�ŁA�ڂ��́u���������E������E����ꕨ�v�Ƃ��������ȃt�F�A���J����Ă���B�V���ʂ�ɋ߂��Âт���]�r���̒n���ɂ���X�y�[�X�ł���B�����ł��ƂƂ��A�ڂ��́u�{���ߋq�Ƃ��āv�Ƃ����k�b�𗊂܂ꂽ�B�����Ȃ��A����������悤�ȉ�ɂȂ����B���낢��b�����̂����A���ĕ����Ɋw���Ƃ������Ɍ������B�{���u�ߋq�v�Ƃ��ēǂޕ��@�����ꂱ��Љ�Ă݂��̂��B���̂Ƃ������́u�ӂ����Ƃ̔~�̒x�����������ȁv�Ɓu�~���������삷�ׂ��k���ׂ��v�������A�����ɂ�2���̖{���ɓǂ�ł��镓��������Ƃ�������o�����B����Ε����́u�O�㎞�ԍ��U���v���邢�́u�ٕ������U���v�ł���B���̒��Ɏ��̑���⎞�Ԃ̕ϑJ���̎����ɂ܂����錻�ۂ̔�r���r�ނƂ������@�B����͓Ǐ��̉��`�ɂ��Ȃ���B���������b�������B�T�^�I�ȋ��3�傠���Ă����B�u��͒��ʂ肯��H�̗��v�u�����₯�������l�ɍs�������Ёv�u���̂Ӊԗ�(����)�����݂��₯�ӂ̌��v�B�Ō�̋�ȂǁA�����ł���B�u���̂Ӊԁv�Ɓu���������݂��v�Ɓu���ӂ̌��v�́g�O�����L�h���A���������܂̏\�������ɓ����Ă���B�Ǐ��Ƃ������̂́A���̂悤�Ɂu����̍̉ԁv�ɑO��������A�l���������ƂȂ̂ł���B�����āu�ߋq�v�Ƃ��Ă̍����^�]�ɓ��邱�ƂȂ̂��B�����A�����ƒm����ׂ��Ă���B �@
 �@
�@ �@
�@
�� ��������͐����q�K���}�_�w���Ő��ԂɊ�o�������A�g�t���W�������ɂ��Ԃ�āu��Ȃ��ڔ����\���������������v�Ƃ����悤�Ȏ��]��̒k�ѕ��𐁂����Đ��Ԃ����Ɋ����Ă�������ł������B���̎���𗣂�Ă͗ΉJ�̂��̋�̋����͂Ȃ����A�������G�e���Ă̒��q�́@�E�E�E�@�֓��ΉJ / ���c�D��
�� ������悢��ς܂ʎ��������ƁA���т��\�R�\�R�ɘނ����ďЉ�҂̒W��������K���A�ߗ��j�V�r�̑匆��ł���ƌ����ɂ߂Č��܂��āA���̋��낵����҂͔@���Ȃ�l�����Ɛu���āA���߂čK�c�I���Ƃ����}�_�N�̏G�˂̏��߂Ă̎��݂ł���Ɖ������B�@���́@�E�E�E�@�I���̏o���� / ���c�D��
�� �������I����͂�̓ɂ�����e�����������A���������đ}�G������͌j�M�����������S������Ƃ�����Ȃ� �@�E�E�E�@���F�Ђ̉��v / ����g�t
�� ��������R�O���͋��ɂƌ_�肽�銦���q�ƑŘA�ꗧ���āA�|���̓n����ɂ�����B�ߌ�Ƃ����ɏ����o�łč���ɂ����ނ��D�Ԃɕւ�ČF�J�܂ōs����Ƃ���Ȃ�A�Ă̓��̐^����̍�����ނ��ƂƂāA�s���̐o���̂ɂ����A�n�Ԃ̑���������ȂǁA���� �@�E�E�E�@�m�X�v�I�s / �K�c�I��
�� �������͒J�ނ�r�����˂ɂ܂��Ⴆ���炵������͂������� �@�E�E�E�@���a / �k�����H
�� ���炭����Ɖ��������Ċ������������łɂȂ�܂����Ƃ����B �@�E�E�E�@��y�͔L�ł��� / �Ėڟ���
�� �Ƃ���֊������N������͎��炵�܂����Ɣ����͂����ė���B �@�E�E�E�@��y�͔L�ł��� / �Ėڟ���
�� �l��B�����Đԍ�֏o�����Ċ������N�ƌ|�҂������܂����B �@�E�E�E�@���Ύ��Ǝ� / ���l���q
�� ������ꂪ�w�L�x�̊����N�̘b���o�������̂炵���B���l����͊o���Ă����邩�ǂ�����x�����Ă݂����Ǝv���Ă���B�@���q�������������o�������́A�����͂�����ʂɏ����Ƃ������̂�ǂ܂Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA�����Ă��̍�i���⊶�Ȃ���قƂ�Ǔǂ�Ł@�E�E�E�@���l����Ǝ� / ���c�ЕF
�� ����q���̍��A�����̍Ⴆ����ȂǂɗF�B�̉Ƃ���A���ė���r���Ő쉈���̓��̐^�����������Č���Ɠy�̕\�ʂɂ��傤�ǔ����ׂ��悤�ɂ������ɔ����ۂ��F���������_���K�����������ɕ���ł���B����͐̂��̓��H�̐����������ƒႩ�������ɍ������߂��y�@�E�E�E�@�lj��̓~�� / ���c�ЕF
�� ����́u���̗͊w�v��_�����������_�������������̂Ő搶�ɕ�����A����͂������낢���猩����Ƃ����̂Ŋw�Z�����ė��ėp���Ă��B���ꂪ�u�L�v�̊����N�̍u���ɂȂ��Č����Ă���B�����w�Z����ɐ��w�̓��ӂł������搶�́A�����������̂�ǂ�@�E�E�E�@�Ėڟ��ΐ搶�̒lj� / ���c�ЕF
�� �������⋘��̂����肢��̂����炳�� �@�E�E�E�@���D�̎��l �^�ӕ��� / �����Y
�� ����[��ӂƊ�����܂��ƁA�����̏Ɏq���ɗH�ÂȌ��������Ă���̂ŁA�邪�������̂��Ǝv���āA�悭�悭����߂�ƁA���̒��ɂ͊������Ɠn���Ă����̂ɁA���̊Ԃɂ��~�o�����Ⴊ��̎��Ɨׂ̉Ƃ̉����Ƃɐς��Ă����̂ł���B�Ăъ��z�X�g�[�u�ɉ����A�ǂ݁@�E�E�E�@���Z / �i��ו�
�� ����o�~�t�ɂ͑��p���i�@�A�����Ƃɂ͋���⹑��A�K�c�I���A�D���Ƃɂ͒W������������B�F�ꎞ�̖��m�ł���B�����������l�\�O�N�������{�̐��Q�Ȍ�i�����̋����ɗ��������͍̂K�c�W�����p���̎O�Ƃ݂̂ŁA���̑��͂��������ɐ������������̂����������B���@�E�E�E�@���� / �i��ו�
�� ��������̌G�Ȃ��Ƃ�P�������̂Ȃ��ÂȔӁA���̑��������Ɛ��ݓn��[����̐F�Ƃ��A���Ƃ����킯�Ȃ��A����̍��y�Ƀm�X�^���W�b�N�ȓ���I����тт������A�����͌����̗���Ȃ�r�̂قƂ肩��A�[�����ɕ���ꂽ�u�̏�ɝ����o���āA��㏫�R�́@�E�E�E�@��_ / �i��ו�
�� �������ނ��]���K�ӓ��⏉���@��M�����ł����ӌ����ȁ@�r�r�̐��Ⓑ���̗������@�ǔ����q�ɒ�肯��H�̗� �@�S�т�V���̒��̕n�ɏ����@���H�a�ܘZ�R�������앪���ȁ@�V�E�q��֑��������ӓ~�����ȁ@������O�k�̌Q�c�̉߂��Č�@�E�E�E�@�o�l���� / �����q�K
 �@
�@ �@
�@
�E�T�M�͑�̂��Ƃ�Y��܂���ł����B�Ȃ��Ȃ�A�E�T�M�͔N���Ƃ��Ă��ė͂��Ȃ��A�܂��A�v�̂����������̂ŁA������̎��ɉ������z�{���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ŗ������Ƃ��C�ɕa��ł����̂ł��B�����������[���ɂȂ�̂ɁA�����p�ӂł��܂���ł����B�����ւ��̂��V������ė��܂����B�E�T�M�́A���錈�S�����Ă��V����Ɍ����܂����B�u���́A���z�{�ł���i���͉��������Ă��܂���B�ł����玄�̓��������グ�܂��B���炭�ǂ����ő҂��Ē�����A���̊Ԃɉ��N�����A�����Ă��Ă����܂��̂ŁA�ǂ������ɂ����ʼn������B�v�@���̌��t���Ƃ��V����́A���̒��Ŏ��� ���u(�Ƃ�)���܂����B����ƃE�T�M�̖ڂ̑O�ɑ傫�ȉ�������܂����B���̊Ԃ��猩���邨�V����̊�͋S�̂悤�ł��B�E�T�M�͋����܂������A���̂��V����͍��A�z�{���邱�Ƃ�]��ł���̂��Ǝv���܂����B�����ĉ��̂��߂炢���Ȃ��A���̒��ɐg�𓊂�����܂����B�E�T�M�͍Ŋ�(������)���}����o��ʼn��̔M�ɐg������(�䂾)�˂܂����B�����������Ƃ��M������܂���B�����������ڂ��J����ƁA���Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ��A���ނ�̏�ɐQ�����ł��邾���ł����B���V����̓E�T�M�̖T(���Ƃ�)��ɗ����Ă��܂������A�E�T�M���ڂ��J����ƉE�������Ɉ����Ēn�ʂɗ��Ђ������܂����B�����Ċz���n�ʂɂ��A�����܂ɂ���悤�ɃE�T�M���q(�炢�͂�)���܂����B
�u���V����A����́c�v�@�E�T�M������������Ƃ��V����͋N���オ��A���G�𗧂Ăė���������܂����B����Ƃ��V����̔w�͂���ƐL�сA�̍������z���A�R�̍������Ȃ������Ȃ��ēV��˂������A��ߓV(�������Ⴍ�Ă�)�̂��p�ɂȂ����̂ł��B��ߓV�͉E��̂ЂƂ����w�Ō��ɃE�T�M�̎p��`���A�R�̂ނ����֔�ы����čs���������ł��B �@
 �@
�@ �@
�@
���̐��̏��߂̍��A����тɌρE���E�e������A���ǂ����Ă��܂����B���ɒ�ߓV�����̎O�C�̒��ǂ����������悤�Ƃ��āA��l�̘V�v�Ɏp��ς�����A���������܂����A�u���͂��ܕ��������Ă��܂��B�����H�ו����������v�B�O�C�́u������Ƒ҂��ĉ������A���ܒT���Ă��܂��v�ƌ����ĐH����T���ɍs���܂����B���炭����ƁA�ς͋����A���͉ʕ��������Ă���ė��܂������A�e�����͎�Ԃ�ŋA���Ă��āA������ӂ�ŗV��ł��܂��B�V�v�́u���Ȃ����͖{���ɒ��ǂ��ł͂���܂���B�ςƉ��͏\���ɐH�ו�������܂������A�e�͉������Ă��܂���B�v�Ɠe�̈����������܂����B��������e�́A�ςƉ��Ɂu��������d���W�߂ĉ������B���ܐH�ו��������ɂ���܂��傤�v�Ɛd���W�߂����āA���ꂪ�͂��ςݏオ��Ɖ�_�������܂����B�e�́u���V�l�A���͂ǂ����Ă��H�ו���T�����Ƃ��o���܂���ł����B�ǂ������̂��̏������g�̂������Ĉ�x�̐H���ɓ��Ăĉ������v�ƌ����A�ɔ�э��݂܂����B�V�v�͍Q�Ăď����o���܂������A�����e�͐����Ă͂��܂���ł����B�V�v�̐g�̂���p��ς�����ߓV�͒Q�����āA���̎��Ղ�łڂ��Ȃ��悤�Ɍ��̒��ɓe���c���Ă������Ƃ����܂��B�����āA���̓e�́A�ߑ����܂����ɏo����O�ɁA�e�ƂȂ��ďC�s������Ă������p�ł����B(�w�哂����L�x)
���̑s��Șb�͉���`���悤�Ƃ��Ă���̂ł��傤���H���낢����߂͂���ł��傤���A���B�́A���i�������Ă��鎞�A���ł��ς≎�̂悤�ɑ�����T���Ď����ė��悤�Ƃ��Ă��Ȃ��ł��傤���B���ꂪ�Ȃ��A���ꂪ�Ȃ��Ǝ����̊O�ɗ��R�����߂Ă��Ȃ��ł��傤���B�����̍K���͂ǂ��ɂ���̂��A�ƊO����T���Ă͂��Ȃ��ł��傤���B�e�͂��ꂪ�ǂ���T���Ă������������ׂɁA�����̐g�Ɋ��ɋ����Ă��邱�ƂɋC�t�����̂ł��B�C�t�����e�͂����Q�Ă邱�Ƃ͂���܂���B�������Ԃ�(���E��������)�ŁA���˂ėV���(���̍s���g�V�ԁh�Ƃ��\������)�����̂ł��B�ՍϑT�t���u�Y������������(�Ȃɂ������傤��)�v(�w�ՍϘ^�x)�E�u�b�_�Ɣ�ׂĂ������������Ă�����̂͂Ȃ��A�ƌ����Ă��܂��B�������鎞�͓e�ɏK���āA���ׂĂ������Ă��鎩���ɏo����߁A�������������Ă݂܂��B�@
 �@
�@ �@
�@
���̉e�̖͗l���e�Ɍ����邱�Ƃ���A�u���ɂ͓e������v�Ƃ����`���̓A�W�A�e�n�ŌÂ����猾���`�����Ă���B�܂��A�e�̉��Ɍ�����e�͉P(����)�ł���Ƃ������B���̉P�ɂ��ẮA�����ł͕s�V�s���̖�̍ޗ�����n�őł��ĕ��ɂ��Ă���Ƃ���A���{�ł͖݂����Ă���p�Ƃ���Ă���B�ݝ���(�����Â�)�Ɩ]�����|�����Ƃ����Ɍ����Ă���B
�����퍑����(�I���O5���I�`�I���O3���I)�̎��W�w�^���x�V��ł͌�(���)�ɂ��Č���Ă���ӏ��Ɂu������� �������� �Η��ۉ� ���ړp�ݕ��v�Ƃ�����������A�u�ړp(����)�v�Ƃ����ꂪ�p�����Ă���B���������̌�̉��߂ɂ��Ă͕��ꑽ���u�V��ߓV�v(�w���؊w��x9(4)�A1933)�Ńq�L�K�G���̂��ƂƂ���ȂLjِ�������B���[�w�_�t�x�����т̒��ł́u���̒��ɓe�ƃq�L�K�G��������v�Ƃ��������ɂ��Č���Ă���B
�Ñ�C���h�̌���T���X�N���b�g�ł̓V���V��(śaśin�A�u�e�������́v)�A�V���V���[���J(śaśāṅka�A�u�e�̈�������́v)�Ȃǂ̌ꂪ���̕ʖ��Ƃ��Ďg����B
���{�ɂ����錎�̓e���`�ʂ��ꂽ�Â���ɂ͔���(7���I)�ɐ��삳�ꂽ�w�V������䶗��x�̌��ɕ`���ꂽ���̂Ȃǂ�����B���q�E��������ɕ����G��Ƃ��ĕ`���ꂽ�w�\��V���x�ł͓��V�E���V�̎����Ƃ��Ă̓��E���̒��ɉG�Ɠe���`�����܂�Ă�������݂���B
���B(���݂̒������k��)�ł͏H�ɖ������j���u���H�߁v�Ɂu�����n���v�Ƃ���ؔō��肪�ǂɓ\��ꂽ�肷�邪�A�����ɓe�͋n���������p�ŕ`����Ă����B
�~�����}�[�̕����G��̒��ɂ����̂Ȃ��ɂ͍E���A���̂Ȃ��͓e���`����Ă���A�{��R�𒆐S�Ƃ������E�ς������������G��Ȃǂ�ʂ��Ċe�n�ŕ`����Ă������Ƃ�����������B�^�C�ł����ɂ͓e���Z��ł���Ƃ����`��������A�G��Ȃǂɂ�������B�����`�����^�u���[���̌���(�}�Q�l)�Ɍ�����e���A���̓e���f�U�C���ɔz�������̂ł���B
�A�����J���O���ł����̓`���͒m���A�l�ގj�㏉�̌��ʒ���������O�ɃA�|��11���̉F����s�m��NASA�̊ǐ��������̓e�Ɍ��y�����L�^���c���Ă���B
���������b
���ɂȂ��e������̂������`���ɂ̓C���h�ɓ`���w�W���[�^�J�x�Ȃǂ̕������b�Ɍ����A���{�ɓn�����w���̕���W�x�Ȃǂɂ����^���ꑽ������Ă���B���̓��e�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B
���A�ρA�e��3�C���A�R�̒��ŗ͐s���ē|��Ă���݂��ڂ炵���V�l�ɏo�������B3�C�͘V�l�������悤�ƍl�����B���͖̎����W�߁A�ς͐삩�狛��߂�A���ꂼ��V�l�ɐH���Ƃ��ė^�����B�������e�����́A�ǂ�Ȃɋ�J���Ă������̂��Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����̔�͂���Q�����e�́A���Ƃ��V�l�����������ƍl��������A���A�V�l�͌�����X�����Ȃ����~���O�̑��z�A��ߓV�͌������߂���(����Ԃ���)�~����̑��z�ł���A�Ƃ������߂��Ȃ���Ă���B
���A�����J��Z���̖��b
���l�̓`���̓��L�V�R�̖��b�ɂ�������B���L�V�R�ł����̖͗l�͓e�ƍl�����Ă����B�A�X�e�J�̓`���ł́A�n��Ől�ԂƂ��Đ����Ă����P�c�@���R�A�g���_�����ɏo�āA�����ԕ��������߂ɋQ���Ɣ��ɏP��ꂽ�B���͂ɐH���������Ȃ��������߁A���ɂ����ɂȂ��Ă����B���̂Ƃ��߂��ő���H�ׂĂ����e���P�c�@���R�A�g�����~�����߂Ɏ������g��H���Ƃ��č����������B�P�c�@���R�A�g���͓e�̍��M�ȑ��蕨�Ɋ����A�e�����ɏグ����A�n��ɍ~�낵�A�u���O�͂����̓e�ɂ����Ȃ����A���̒��ɂ��O�̎p������̂ŒN�ł����ł���������Ă��O�̂��Ƃ��v���������낤�v�ƌ������B��ʂɃP�c�@���R�A�g���͋����_�ł���ƍl�����Ă��邪�A���̖��b�̏ꍇ�͏��X�Ɍ��������Ă������z�_�ł���ƍl������B
�ʂ̃��\�A�����J�̓`���ł́A��5�̑��z�̑n���ɂ����ăi�i���c�B���_���E���ɂ��������g���̒��ɓ����ĐV�������z�ɂȂ����B�������e�N�V�X�e�J�g���̕��͉̒��ɐg�𓊂���܂�4�߂炢�A5��߂ɂ悤�₭������]���ɂ��Č��ɂȂ����B�e�N�V�X�e�J�g�������a�ł��������߁A�_�X�͌������z���Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���A�_�X�̂ЂƂ肪���ɓe�𓊂����Č������炵���B���邢�́A�e�N�V�X�e�J�g�����g���e�̎p�Ŏ�����]���ɂ��Č��ɂȂ�A���̎p�����e����Ă���Ƃ������B
�l�C�e�B�u�E�A�����J���̃N���[�͂܂��ʂ́A���ɏ��肽���Ǝv�����Ⴂ�e�̓`����`����B�߂������e���^�Ԃ��Ƃ��ł������A�d���e���߂ɂ��܂��Ă������߂ɒ߂̋r�͍�����悤�ɒ����L�тĂ��܂����B���ɓ��������Ƃ��ɓe���߂̓��Ɍ��̂����r�ŐG�������߁A�߂̓��ɂ͐Ԃ��͗l���c���Ă��܂����B���̓`���ɂ��A���ꂽ��ɂ͌��̒��ɓe������Ă���̂�����������Ƃ����B
���n�앨
��L�̂悤�Ȍ��ɓe���Z��ł���Ƃ����`������b�̉e������A���{�̕��|�E���|�E�G��E���y�Ȃǂ̑n�앨�ɂ́A���̐����҂Ƃ��ēe��p������i������������B
���́u�e�̖��m�v(������ �� ������)(�w�c�N���́x 1912�N)�ł́A�݂������Ă��錎�̐��E�̓e�������o�ꂵ�āA�啟�݂������Ă���l�q��`���Ă���B �@
���q�L�K�G��
�e�̂ق��A�Ñ㒆���ł͌��ɂ���(����A(�q�L�K�G���̂���)������ł���Ƃ���Ă����B�O���̔n���͊��悩��o�y�������̂悤�ɁA�����Ő��삳�ꂽ�͗l�̒��ɂ͌��ɂ�����̂Ƃ��ēe�ƃq�L�K�G������ʓ��Ɏ��߂ēo�ꂳ���Ă�����̂�������B
 �@
�@ �@
�@
�{���A�e�̋G��́u�~�v�ł��邪�A���̕\�ʂɂ���u�C�v�ƌĂ�镔�����������̌`�Ɍ����邽�߁A���Ɠe���y�A�ɂȂ�l�q�������B���Ȃ݂ɁA���̋G��́u�H�v�ł���B �@
 �@
�@ �@
�@
���ǂ���炷�A�������Ƃ��˂Ƃ��邪���܂����B
3�C�́A�����@�u�����B���b�̎p�Ȃ̂͂Ȃ����낤�H�v�@�u�O���ʼn����������Ƃ���������ł͂Ȃ����낤���H�v�@�u����Ȃ�A���߂č�����l�̖��ɗ����Ƃ����悤�I�v�@�Ƃ������Ƃ�b�������Ă��܂����B���̘b���Ă�����ߓV(�������Ⴍ�Ă�)�́A�����ǂ����Ƃ������Ă����悤�Ǝv���V�l�Ɏp��ς���3�C�̑O�Ɍ���܂��B�����m��Ȃ�3�C�́A�ڂ̑O�̔��ʂĂ��V�l���@�u���Ȃ��������ē����Ȃ��B�����H�ו����b��łق����B�v�@�ƁA�b���ƁA����Ɛl�̖��ɗ����Ƃ��ł���I�Ɗ��ŘV�l�̂��߂ɐH�ו����W�߂ɍs���܂����B����͖ɓo���Ė̎���ʕ����A���˂͋����̂��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�����������͈ꐶ�����撣���Ă����������Ă��邱�Ƃ��ł��܂���B
�������́A������x�T���ɍs���Ă��邩����đ҂��Ă��ė~�����B�ƁA���˂Ƃ���ɘb���ďo�����Ă����܂����B�b������ƁA�������͎�Ԃ�Ŗ߂��Ă��܂����B����Ȃ��������A���˂Ƃ���͉R�����ƍU�ߗ��Ă܂��B����Ƃ������́A�u���ɂ́A�H�ו����̂�͂�����܂���B�ǂ�������H�ׂĂ��������B�v�@�ƌ����ĉ̒��ɔ�э��݁A�����̐g��V�l�ɕ����܂����B
����������V�l�́A�����ɒ�ߓV�̎p�ɖ߂�@�u���O�B�̗D�����C�����́A�ǂ��������B���x���܂�ς�鎞�ɂ́A�����Ɛl�Ԃɂ��悤�B����ɂ��Ă��A�������ɂ͉������Ȃ��Ƃ������B���̒��ɁA�������̎p���i���Ɏc���Ă�낤�B�v�@�Ƃ������Ⴂ�܂����B�������āA���ɂ͂������̎p�����ł��c���Ă���̂ł��B
���̂悤�ȕ���ŁA���߉ނ��܂͎������ɓ`���Ă��܂��B�@
 �@
�@ �@
�@

�w�́A����Ƃ���ɂ������Ƃ��˂Ƃ��邪����܂����B������A���ʂĂĐH�ו�����V�l�ɏo��A3�C�͘V�l�̂��߂ɐH�ו����W�߂܂��B����͖̎����A���˂͋����Ƃ��Ă��܂������A�������͈ꐶ�����撣���Ă��A���������Ă��邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�����ŔY�������́A�u����H�ׂĂ��������v�Ƃ����ĉ̒��ɂƂт��݁A�����̐g��V�l�ɕ������̂ł��B���́A���̘V�l�Ƃ́A3�C�̍s�����������Ƃ�����ߓV(�^�C�V���N�e��)�Ƃ����_�l�B��ߓV�́A����Ȃ�����������݁A���̒����S�点�āA�F�̎�{�ɂ����̂ł��B�x
����́A�������b���炫�Ă��邨�b�ł��B�܂��A���̂��b�ɂ͑���������A�w�����������V�l���A���̏Ă�������Ō��ɉf���A����ꂽ�������͐����Ԃ�x�Ƃ�����������܂��B������A���̔��������ł͂Ȃ��A�����������������Ȃ̂ł��ˁB
�ł́A�Ȃ��݂����Ă���̂ł��傤���H�@�u���������V�l�̂��߂ɖ݂������Ă���v�Ƃ��u���������H�ו��ɍ���Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ�����������܂����A���H�̖������L���j���ł��邱�Ƃ��l����ƁA��������̂��Ă��Ƃꂽ���ƂɊ��ӂ���ӂ����߂��Ă���悤�ł��B�@

���ɋP���u���v�́A�����m�n���̉q���Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�n������̋���38��4�C400km�B���a�́A3�C474km�B�n����4����1���̒��a�������Ă���ƌ������ŁA���z�n���ł͂��Ȃ�傫�Ȑ��ƌ����ʒu�t���ł��B�܂��n���ɂ͂����Ƃ��g�߂ŁA�Ñ��肸���ƒn���Ɋ��Y���Ă������ł��B�Â�����n���ɂ͂ƂĂ��g�߂ȑ��݂Ƃ��Ă������u���v�ł����A��͂�̂̐l�B���u���v�ɂ͐F�X�ƍl�������点�Ă������ł��傤�B�F���Ȋw�╨���I�ł́u���v�̑��݂��u�������v�ƊW���Ă���Ƃ��镶���Ȃǂɂ͏o��܂���ł�����(�����ƒ��ׂ�Ώo�ė��邩���ł���)�A��Ԃ������藈��ƌ������A�ǂ�҂���A���̂܂܂̂��b���c����Ă��܂����B
�����̕���
����́u���̕���v�ł����B�u���̕���v�́A�������㖖���ɐ��������Ƃ����u���b�W�v�ł��B�C���h�A�����A���{�ƎO���̖�1000�]��̐��b�����^����Ă���A���Ȃ�̒��҂ł��āA�����đS�Ă̐��b���u���͐́v�ƌ��������o������n�߂���ƌ���������̗R���ƌ������ł����B���̌Ñ�̐��b�W�u�V���̕��E���܁E��13�b�v�Ɂu���v�Ɓu�������v�ɂ܂��b������܂����B
���u�V���̕��E���܁E��13�b�v
���͐́B�V���ɂāu�������v�A�u���ˁv�A�u����v�̎O�C����F�C�s�����Ȃ��璇�ǂ���炵�Ă��܂����B�ƂĂ����ǂ���炵�Ă���3�C�ł����A�����b���Ă��鎖������܂����B
�u�O���ł͔Ƃ����߂ɂ���āA���̗l�Ȕڂ����b�̎p�Ő��܂�Ă��܂����B�����ł͉䂪�g���̂ĂāA�P�s���d�˗��h�ɐ����悤�B�v
���̔ނ�̍s�����u��ߓV�v���ςĂ��āA�u�ނ�͏b�̐g�ł���Ȃ���A�������ꏟ�Ȏp�ł���B�ł͈�����Ă݂悤�B�v�@�Ƃ����܂��V���Ɏp��ς��܂����B�͂Ȃ���ڂ�ڎp�ŎO�C�̏b�̋��鏊�ɕ\��A�u�킵�͔N�V�����ʂĂĂ��܂��Ă���B���O�B�ł킵��{���Ă���Ȃ����B�v�@�Ǝf���Ă݂������ł��B����ƎO�C�́A�u���ꂱ���������̖]�ގp�ł��B���������{���ďグ�܂��傤�B�v�@�ƌ����āA�u����v�͖ɓo��A�̎���ʕ�������Ă��Ă͍D���ȕ���H�ׂ����A�u���ˁv�́A����ɏo�����Ėݓ��̋����������˂Ă��ẮA�V���̎v�����܂܂ɐH�ׂ����Ă����������ł��B�V���͂������薞�����A�u���O������C�́A���Ɏ��ߐ[���B��F�ƌ����Ă������x�������B�v�@�ƖJ�߁A��������������u�������v�́A�ꐶ�����ɐ����ĐH�ו������ߖ�R���삯���������A�T�������o���܂���ł����B�������Ă��邤���ɐl�ԂɎE���ꂽ��A���̏b�ɋ��ꂽ�肵�āA���𗎂Ƃ��̂��ւ̎R�łȂ��낤���ƁA���ꂱ��Y��ł��������ł��B
������A�����̌��ӂ̌��Ɉ�̍l�������s�Ɉڂ��܂��B�u���͂��ꂩ����������������߂Ă��܂��̂ŁA���E���A���đ҂��Ă��ĉ������B�v�@���̗l�ɊF�ɓ`���Ă��̏ꂩ�痧������܂����B�����Łu����v�͖��W�߁A�u���ˁv�́A�������Ă��ĕ����t���āA�u�������v�̋A���҂��܂����B�����Ɏ�Ԃ�ŋA���Ă����u�������v�����āA�u���O�͉��������Ă��Ă͂��Ȃ��ł͂Ȃ����B�v���Ă����ʂ�A���������Đl���x���A�����Ď��������܂낤�Ƃƌ��������낤�B���炵���B�v�@�Ɓu����v�Ɓu���ˁv�͌����܂����B�����Łu�������v���A�u���͐H�������߂ė���͂�����܂���B�ł����玄�̐g�̂��Ă��ĐH�ׂĉ������B�v�@�ƌ����Ȃ�A���̉̒��ɔ�э���ŏĂ�����ł��܂��������ł��B�u�������v�͂������̂��ƁA���̂��̐g��V�l�ɐH�ׂĂ��炢�A�i�v�ɐ����։�̐��E�ɗ��E���悤�ƍl���Ă����̂ł��B���̎p��������ߓV�͌��̎p�ɖ߂�A�u�������v���̒��ɔ�э��p���u���v�Ɉڂ��A���܂˂���̏O���Ɍ����邽�߁A���̒��ɂƂǂߒu���ꂽ�ƌ������ł��B�����āA�u���̕\�ʂɂ���_�̂悤�Ȃ��̂́A���́u�������v���ɏĂ������ł���A���̒��Ɂu�������v������ƌ����̂́A���́u�������v�̎p�ł���B�N���F�A�������邽�сA���́u�������v���v�������ׂ邪�悢�v�@�ƒ�ߓV���������ƌ������ł��B
��
�������̑I���@�@�@���̘b�ɏo��������A�ǂ��ɂ����t�������Ă��܂��܂����B�u�������v�����ɔ�э��ގp�����܂�ɒɁX�����A�����Ă��Ȃ��̂ł����A�������������ē���I�ɉʂ����Ď����͏o����̂��낤���H�Ɩ{���ɐ[���l���܂����B�u���v�ƌ��������́u�X�����ہv�ł����Ȃ��Ǝv���̂ł����A�u�։�v�̖@����m���Ă����Ƃ��Ă��A�ʂ����Ă��́u�������v�̗l�ɏo����̂��낤���H�Ǝv���܂��B�u���v�Ɓu�������v�ɂ܂�邨�b�ł����A����Ȃɐ[���e�[�}���Ƃ͎v���܂���ł����B�@

�u�����l�ɂ͂��������Z��ł��āA�\�ܖ�ɂȂ�Ɩ݂��������B�v�@�u�����������ŁA�P�������āE�E�E�v�@�ƁA������܂܂ɂ����l�߂Ă���ƁA�s�v�c�Ƌn�����������������ڂɉf�����q���̍��B���{�ɌÂ�����`���u���������`���v�ɂ́A�ǂ�ȗR��������̂ł��傤�H
�����������`�� ���Ƃ��Ƃ̓C���h�̐_�b
���������`���̗R���ɂ́A�������̐�������܂����A�C���h�̃W���[�^�J�_�b�ɂ����̂��悭�m���Ă��܂��B�������ɑS���Ƃ͂����܂���̂ŁA�v�܂����B
�@�@�@���̂ނ����̃C���h�̘b�E�E�E
���ǂ���炷�A�������Ƃ��˂Ƃ��邪���܂����B3�C�́A�����@�u�����B���b�̎p�Ȃ̂͂Ȃ����낤�H�v�@ �u�O���ʼn����������Ƃ���������ł͂Ȃ����낤���H�v�@ �u����Ȃ�A���߂č�����l�̖��ɗ����Ƃ����悤�I�v�@�Ƃ������Ƃ�b�������Ă��܂����B���̘b���Ă�����ߓV�������Ⴍ�Ă�́A�����������Ƃ������Ă����悤�Ǝv���A�V�l�Ɏp��ς���3�C�̑O�Ɍ���܂��B(��ߓV���Ñ�C���h�_�b�ɂ����ẮA�ŋ��_�Ƃ���Ă��܂��B)�@�����m��Ȃ�3�C�́A�ڂ̑O�̔��ʂĂ��V�l���u���Ȃ��������ē����Ȃ��B�����H�ו����b��łق����B�v�Ƙb���ƁA����Ɛl�̖��ɗ����Ƃ��ł���I�Ɗ��ŁA�V�l�̂��߂ɐH�ו����W�߂ɍs���܂����B����͖ɓo���Ė̎���ʕ����A���˂͋����̂��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�����������͈ꐶ�����撣�����̂ɁA���������Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B�������́A�u������x�T���ɍs���Ă��邩����đ҂��Ă��ė~�����v�������˂Ƃ���ɘb���ƁA�Ăяo�����Ă����܂����B�b������ƁA�������͂܂���Ԃ�Ŗ߂��Ă��܂����B����Ȃ��������A���˂Ƃ���͉R�����I�ƍU�ߗ��Ă܂��B����Ƃ������́A�u���ɂ́A�H�ו����̂�͂�����܂���B�ǂ�������H�ׂĂ��������B�v�ƌ����ĉ̒��ɔ�э��݁A�����̐g��V�l�ɕ����܂����B����������V�l�́A�����ɒ�ߓV�̎p�ɖ߂�ƁA�u���O�B�̗D�����C�����́A�ǂ��������B���x���܂�ς�鎞�ɂ́A�����Ɛl�Ԃɂ��悤�B����ɂ��Ă��A�������ɂ͉������Ȃ��Ƃ������B���̒��ɁA�������̎p���i���Ɏc���Ă�낤�B�v�Ƃ������Ⴂ�܂����B�������āA���ɂ͂������̎p���c�邱�ƂɂȂ�܂����B
���̐_�b�E�E�E�ǂނ��т��ƂɁA�ނȂ����C�����ɂȂ�܂��B
�@�@�@�����̌イ�����͐����Ԃ����Ƃ��������I
��̘b�̍Ō�̕���������Ă����������܂��̂ŁA���Љ�����܂��B���������̒��Ɏ����̐g�𓊂��A���ł��ɂȂ�����̂��ƁE�E�E������������V�l���A�������̏Ă�������Ō��ɉf���ƁA����ꂽ�������͐����Ԃ�܂����B�Ƃ����b�ł��B
�����������`�� �Ȃ��H�������͖݂����́H�I
�������̖݂��́A�����̐_�b�ɗR�����Ă��܂��B���̂��b�́A�ƂĂ���������̐�������̂ŁA�����ł̏Љ�͊��������Ă��������܂��B
�Ñ㒆���ɂ����āA���̂������́A�n�������ĕs�V�s���̖�����Ă���ƍl�����Ă��܂����B���ꂪ�A���{�ɓ`����Ă���݂����ɕω������ƌ����Ă��܂��B���̗��R�ׂĂ݂�ƁA���{�Ŗ�����\�����t�́u�]�������Â��v���]���āu�݂��v�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B�܂��u�V�l�̂��߂ɖ݂������Ă���v�Ƃ��u���������H�ו��ɍ���Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ�����������܂��B�����A�������̍s�������n�Ղł��������Ƃ��l����ƁA��������̂��Ă��̂ꂽ���ƂɊ��ӂ���Ƃ����Ӗ������߂��Ă���̂�������Ȃ��Ȃ��`�Ɗ�����������Ă��܂��B
�����Ŗ݂������Ă���̂͂Ȃ��H
�Ñ㒆���ł́A���̂������͋n�������ĕs�V�s���̖�����Ă���ƍl�����Ă��܂����B���ꂪ�A���{�ɓ`����Ă���݂����ɕω������ƌ����Ă��܂��B���̗��R�́A���{�Ŗ�����\�����t�́u�]��(�����Â�)�v���]���āu�݂��v�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B
���{�ł́w�Î��L�x�̂悤�Ȍn���������_�b���Ҏ[����܂������A�����͒n���▯���A����ɂ���ėl�X�Ȑ_�b�����܂�A�������Ă��܂��B���ɏZ�ޓe�ɂ������̓`�����L��܂��B
�@�@�@��1�A�b�M�̉��g��
���ɓo�����b�M�́A�e�ɕϐg�������A���Ƃ��Ė����̓��ɂȂ�ƓV�E�̐_�X�̂��߂ɖ�����悤������ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B
�@�@�@��2�A�b�M�̂����� ��
���鎞�A�O�l�̐_�傪�n�����V�l�ɉ����A�ρA���A�e�ɐH�ו�����܂����B�ςƉ��͐H�ו�����܂������A�e�͉��������Ă��܂���B���̂��߁A�e�́u����H�ׂĂ��������v�ƌ����ĉɔ�э��݂܂����B��������Ċ��������_��͓e�����ɑ���A�ǓƂțb�M�ƈꏏ�ɖ�����悤�ɂ����܂����B
�@�@�@��3�A�b�M�̂����� ��
�y���́A�C�Ƃ����Đ�p�����ɂ����e�����܂����B������A���̓e�́A�V��̓{��ɐG�ꌎ�ɑ�����b�M�ɉ�܂����B�e�͛b�M������Ɏv���A�����̈�ԏ������������ɑ���A�b�M�̂����������܂����B
���b�M�`���ɂ��ِ����L��܂��B�L���Ȃ͕̂s�V�s���̖����l��߂������ŃJ�G���ɂȂ����Ƃ������ł����A�d���Ȃ���𓐂Ƃ��������L��܂��B
�@�@�@�����̈�
�b�M�̕v�E羿��9�̑��z���˗����V���̎�ƂȂ�܂����B������羿�͋��~���\�ȌN��Ől�X���猙���Ă��܂����B������A羿�͐����ꂩ��s�V�s���̖�����炢�܂��B�����m�����l�X��羿�̓V�����i���ɑ����Ǝv���Q���܂����B�b�M�͌���Ɋ������A�l�X���~�����߂ɖ�𓐂ݎ����ŐH�ׂ܂����B�V��͛b�M����𓐂߂�ӂ߂Č��ɒǕ����܂����B
�@�@�@�����̓�
羿�ƛb�M�͒��̗ǂ��v�w�ŁA羿�͕s�V�s���̖��b�M�ɗa���܂����B������A羿�̒�q�H�ւ���𓐂݂ɛb�M�̕����ɐN�����܂����B�b�M�͖H�ւɖ��n���Ȃ����߂Ɏ����ŐH�ׂ܂����B���̌��ʁA�̂��y���Ȃ�A�V�ɓo�����Ƃ����܂��B
�����̓`���ł͛b�M�͑P�l�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B3�̐�p���e���b�M����̂͂����������b���O��ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�e�̘b�ɖ߂�܂��B
�@�@�@��4�A羿�̉��g��
�b�M���s�V�s���̖��H�ׂČ��ɍs�����̂�m��A羿�͂��̌��ǂ��܂����B���̎��A羿�͛b�M���D���������e�ɉ����܂����B�������b�M�͎����̂��ɂ���e��羿�̉��g���Ƃ͉i���ɋC�����Ȃ����������ł��B
�@�@�@��5�A���W�l��
��(�u)�̎�����I��鍠�A�������͂��g�債�n�߂����̕����ɔ��W�l�Ƃ������j�����܂����B�����@���ɂ͛F�ȂƂ����L���Ȉ��Ȃ�����A�F�Ȃ͔��ڏG��Ȕ��W�l�ɖڂ����܂����B���������W�l�͈����F�Ȃ�l�|���܂����B�F�Ȃ͓{��A�v�@���ɔ��W�l�̈����������A�E�����܂����B���������W�l�̓����\�������A�������ɐH�ׂ����܂����B���̓��A�����͋C���������Ȃ�A�ˑR3�H�̓e��������f���o���܂����B�����͂��ꂪ���q�̍����ƒm��Q���߂��݂܂��B��A���_��媧�̖��߂����b�M�����ēe��A��Č��ɋA��܂����B
��
�ȏオ�e�ƌ��̓`���ł��B�����������͐�Ɂu���ɂ͓e������v�Ƃ����O�L��A�ォ����ꂽ�b�̂悤�Ɏv���܂��B����������Ƌ��炭�����́w�V��x�ɂ���u�ړp�ݕ��v�Ƃ����̂��A���ɓ���������Ƃ����L�q�̍ł��Â����̂��Ƃ���Ă��܂��B���������́u�ړp�v�������͏�������܂��B
1�A�b�M�̉��g�ł�����(�q�L�K�G��)�Ƃ�����B
2�A�u�p�v�́u�e�v�Ɠ����ŁA�u�ړp�v�Ƃ͓e�̖��O�Ƃ�����B
3�A1��2�̐ܒ����Łu�ځv�̓q�L�K�G���A�u�p�v�͓e�Ƃ�����B
�����Ƃ͑S���ʂ̐����L��܂��B�Ζk�Ȃ̑\��(�퍑����̈��)��������_�b�̊G�����@����A�����ɂ͌Ղ̂悤�ȊG���`����Ă��邻���ł��B�^�̒n�ɂ͌ՐM���L��A���̎��_�Ƃ��ČՂɎ����u�ړp(�^�̕����œp�͌Ղ̈Ӗ�)�v�Ƃ����_�b�������̂ł͂Ȃ����A�����͂�����̂����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������ł��B�����Ȃ�Ɠe�Ƃ͑S���W�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�e�̘b�ɖ߂�܂��B
����̊G�Ȃǂ�����ƁA���ƈꏏ�ɕ`�����̂̓J�G�������������ł��B�A�z�܍s�v�z�ŃJ�G���͗z�A�e�͉A�̑�\�ŕ�������Ƃ����l��������܂���(�u���A��A�勗z��A���^�\��v�w�܌o�ʋ`�x)�B�������㊿�ɂȂ�ƁA�J�G�����قƂ�nj�������Ȃ��Ȃ�܂��B�㊿�̊y�{�w�����s�x�Ɂu���\���응��虾尊ہv�Ƃ���܂����������Ă���͓̂e�����ł��B���炭�A���X�͌��ɂ����̂̓J�G���ŁA�O���̍��ɕ�������悤�ɂȂ�A�㊿�ɂ͓e�ɕς��悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Ȃ��������Ă���̂��Ƃ����̂�frogman�l���������ʂ�A���̖����������s�V�s�����ے����Ă��邩��Ƃ��A�b�M�����̂��s�V�s���̖����̂ł�����������߂Ƃ������Ă��܂��B�������炵����u�Ȃ����{�ł͂��݁H�v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�ˁB���̕ӂ�̌����ʔ������ł����A������������Ȃ��̂ŁE�E�E�B�@

�s�V�s���̖�́ABC2���I���́w�̓�q�x�����P�ɁA�|�̖���E羿(����)��������Ƃ������_�����������s�V�s���̖���A���̍ȁE姮�M(������)�������(�����)���֓������Ƃ����b������w�㊿���x�ɂ͌���姮�M����(����E�Ђ�������)�ɕϐg�����Ƃ���܂��B���ː_�b�Ƃ���܂��B
�u�̉F���ςł́A���z�̐��͑S����10����A���ŋ������Ă���Ƃ���܂����B�u�̎n�c�Ƃ����u��r(�w)�v��3�l�̍Ȃ̈�l�u㺘a��������q�Ƃ���܂��B�u�M�c�v���n��̍����Y�݁A�u�b�M(���傤��)�v��12�l�̖�(��)�Ƃ���܂��B
10�l�̑��z�́A�(���傤)�̎���Ɉ�x�ɓV�Ɍ���܂��B�l�Ԃ͔M���Ă��܂炸�A�앨���͂�Ă��܂��܂��B�ܒ��Ꟃ̊肢�Łu����v���A�V�E����|�̖����羿(����)��h�����܂��B羿��9�{�̖���g��9�̑��z���˗��Ƃ��A���z��1�ɂȂ�܂����B
�Ƃ��낪�V�邩�炷��Α��q���ˎE���ꂽ�킯�œ{����羿���V�E�ɋA��Ȃ��������߁A�ނ͕s�V�s���̗͂������܂��B羿�̍Ȃ͛b�M�Ȃ̂ł����A�ޏ����v�̍߂����đ��E�ɗ��Ƃ���܂����A�s���s�������羿�ɕ�����肢���܂��B
羿�͂������܂�Ȃ��Ȃ���Q�̂��тɏo�āA���ĎR�ɏZ�ށu������v�ɑ��k���܂��B�ޏ��͈���Ɏv��羿�ɕs�V�s���̖��^���܂��B�s���̖�͓�l�ŕ����Ĉ��߂Εs���A��l�ň��߂ΓV�ɏ���_�ɂȂ��ʂł����B�b�M�͓V�E�̕�炵���Y���ꂸ�A�������đS������ł��܂��A�V�ɏ��܂����A�������Ɉ����Ǝv�����̂��r���̌��Ɍ������܂����A���ɕt�����Ƃ�����勁E�^�Ɏp���ς���Ă��܂��܂����B���Ȃ݂ɁA羿�͋|�Ŋl����_���Ă���Œ��ɉƖl�ɎE����Ă��܂��܂��B
���ُ̈̂Ƃ��Ắu�ꂢ����v�Ƃ��Ă�A�����ł́u�Ґ�^��巁v�Ə����܂��B�u巁v�̓q�L�K�G���̂��ƂŁA�×����ɐ���ł���ƌ����Ă��鐶�����ł��B���ɐ���ł�����ʂȃq�L�K�G��(��{�)�Ƃ����Ӗ����ς��āA�u��巁v�������w���悤�ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B
�J�G�������̃E�T�M�ɂȂ������́A�����̌��炵���A�u�勁v���u�ړp�v�ƕ\�L�������߂ɁA�u�p�v���E�T�M�ƔF������A�q�L�K�G������E�T�M�ւƎ��Ⴆ��ꂽ���Ƃ��痈���Ƃ����̂�����炵���ł��B
���̏ے��̎���̓q�L�K�G������E�T�M�ւƕς��A�I���O3���I�́w�^���x�V��҂Ɍ����̓e�̂��Ƃ��̂��A�Γ�ȂŔ������ꂽ�I���O2���I�́A�n����1�E3������o�y�́A���z�ɊG��`�����u���v�ɁA�����ɓe����(����E�Ђ�������̂���)�̐}�Ă��`����Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA�v��́w��R�p�k�x�́A�n��̓e�͂��ׂĎ��ŁA���̓e�͋t�ɗY���肾����A�n��̎��e�͌��������тĔD�P����Ƃ������������^���Ă��܂��B�܂��Â������̏K���ł́A�A��8��15��(���{�̏\�ܖ�A�����ł͒��H��)�̍ہA�u�e����v�ƌĂ��e�̊�������S�y���̕��l��������Ƃ����܂��B�@

�s�җl�́@�����ԔN������Ă���悤�ł������A�����Ԃ̏C���Ł@����قǂ̎R�����炢�́@�Ƃ��ɍ��邱�Ƃ��Ȃ��@�����Ă����̂ł����E�E�A�����������́@���������@����Ɍ������R���ɁA�������Ƒ̂���������ꏊ���Ȃ��A�ق�̏����̋x��������Ắ@�܂��@�����n�߂�E�E�Ƃ������Ƃ̌J��Ԃ������Ă��܂����B
���̂��߂ł��傤�A���̖�A�Ƃ��Ƃ����̍s�җl�́A�l�Ȃnj����Ēʂ�Ȃ��悤�ȉ��[���X�̒��Ł@���ʂĂē|�ꂱ��ł��܂��܂����B
�ǂ̂��炢�������Ă����̂ł��傤�B�ǂ��������̂ق��Ł@���������Ɓ@������ł����킹��悤�ȉ������Ă��܂��B���ꂩ�@�l���߂��ɂ���̂�������Ȃ��A�ƍs�җl�́@�������Ɗ���グ�A��������݂܂킵�܂����B
����Ɓ@��C�̃E�T�M���@�ꐶ�����@�s�җl�̎����Ă����ΑŐ������ā@�����������Ƃ��Ă���Ƃ���ł����B
���̃E�T�M�͓��ɓ|��Ă������������Ȃ��l�Ԃ��������̂ŁA�F�B�̃T���ƃL�c�l���Ă�ł��āA�ǂ������炢�����@�b���������̂ł��B
�u�����Ă�́H�v�@�u����B�����Ă�Ƃ������B�v�@�u�����Ɓ@���Ȃ��������Ă��B�v�@�u�������ˁA�����Ƃ������B�v�@�u�Ȃɂ��@�H�ׂ���̂�����Ƃ����ˁB�v�@�u����A�ڂ��@��ɍs���ċ�������Ă����B�v�@�u�����@����͂����ˁB����@�l�́@�̎�����������Ƃ��Ă��悤�B�v�@�u�ڂ��́@���������Ă�����B���̐l�A�����Ƃ����������ق����������낤����E�E�B�v�@�u�������ˁB����Ă��������Ă��邵�A�̎������������H�ׂ���B����@����B�v �@����Șb�̌�A�L�c�l�͐�ցA�T���͖̎������ɐX�ɏo���������܂����B
��Ɏc�����E�T�M�́A������������ؐ���W�߁A�s�җl�̋߂��ɐς�Ł@�s�җl�̎����Ă����ΑŐ��ꐶ�����ł����킹�ā@���Ƃ������������Ƃ��Ă����̂ł����A�́@�E�T�M�ɂƂ��Ắ@�|�����́B�Ȃ��Ȃ��@���ɂł��܂���B�u�ǂ�A������낤�B�v�@�ˑR�̍s�җl�̐��Ɂ@�E�T�M�͂т����肵�ā@�ΑŐ���藎�Ƃ��Ȃ���@�҂��I���Ƌ߂��̑��ނ�̂ނ����Ɂ@���˂̂��܂����B
�u���́A�d�́E�E�@���܂�����ł��ꂽ�̂��ˁH�v�@�s�җl�̗D�������������ƃE�T�M�̎��ɕ��������̂ŁA�E�T�M�͎��̐�𑐂ނ炩�炿�傢�Ə������A�͂��ς̊Ԃ���@���̐Ԃ��ڂŁ@�������ƍs�җl���݂Ă݂܂����B�s�җl�́@�J�`�J�`�ƉΑŐ�ł����킹�āA���ɐd�ɉ����Ă��܂����B�����ā@�Ԃ������@���炿��Ƃ�����A�܂����ς��ς������Ă��邱��A�ł����Ă����T���ƃL�c�l���@���ꂼ��@��������̖̎���ہX�������������ā@�߂��Ă��܂����B
�u�s�җl�A������ǂ����B�v�@�u������������ā@�����ɂȂ�ꂽ�̂ł��傤�B�ǂ����@�����オ���Ă��������B�v�@�s�җl�́@�����̑O�ɍ����o���ꂽ�@���낢��Ȃ����������Ȗ̎��⋛���݂āA�ƂĂ��т����肵�Ă����܂����B�u�����A����́@�ƂĂ����肪�����B���O�����̐S�����ɂ́@�{���Ɂ@���ӂ����B�v�@�����ā@�̎���d�̌��Ԃɂ���A�����Ă����Ƃ��܂����B���̂Ƃ��A�s�җl�̑O�Ɂ@�������̃E�T�M������Ă��ā@�����܂����B�u�s�җl�E�E�A�\����܂���B���́@�T�������L�c�l����̂悤�Ɂ@���������̎���������������邱�Ƃ��ł��܂���B����ǂ��납�@�s�җl�̑̂����߂邽�߂́@�����������Ƃ��@�ƂĂ��@�|���ā@�ł��܂���ł����B�v�@�E�T�M�̖ڂɂ́@�����ʂ����܂�������ł��܂����B
�u�s�җl�A�ł��@���������グ������̂�����܂��B�ǂ����@����肭�������B�v�@��������������Ȃ����̂����ɁA�E�T�M�́@�̒��ɔ�э��̂ł��B
�L�c�l���T�����@�����Ƃ����Ԃ�����܂���ł����B����قǁ@�ˑR�̂��Ƃ������̂ł��B�Ԃ����ɕ�܂ꂽ�E�T�M�����������Ă��@��������̓T���ɂ��L�c�l�ɂ��ł��܂���ł����B����Ɓ@���̂Ƃ��@�ꏏ�ɂ�������Ă����s�җl���̒��Ɏ��˂�����ŁA���̒�����@�Ă����E�T�M���^�яo���܂����B�u�E�T�M��A���O�̎v���͊m���Ɏ�����B���́@���O�ɂ��̗�����悤�B�v�@���������Ȃ���@�s�җl�̑̂́@�ǂ�ǂ�傫���Ȃ��Ă����A���̓����́@�����@��������_�̏�ɏo�Ă��܂��قǂɂȂ�܂����B�傫���Ȃ����s�җl�́@������łЂƂ̎R���������般��Ƃ�ƁA��������イ���Ɖ����Ԃ��ā@�ۂ��`�ɂ����̂ł��B�����ā@���̊ۂ����̂��@�ہ`��Ƌ�ɕ��蓊����Ɓ@����́@���ɂۂ�����ƕ����āA�ƂĂ��₳�����P���n�߂܂����B
�s�җl�́@��������グ�ā@�P���ۂ����̂̏�ɃE�T�M���̂��ā@�����܂����B�u���O�͂ƂĂ������s���������B������@���́@���O���@�i���ɋP�����ɏZ�܂����Ƃ��@���̕Ƃ��ė^���悤�B�v�@�������āA���ɂ́@�E�T�M������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B
��
���̂��b�́@�����m�̕��@�������ƂƎv���܂��B�����@���x�̂��ƂȂ���@�������@���X�@������Ă���܂��B9���ł����ˁA�����������邱�Ƃ����E�E�@�ƍl���Ă�����@���������b�����������Ƃ��v���o���܂��āA�����@���̍ۂ�����Ɓ@���������@���ׂĂ݂���@���\�@���ꂪ�@���܂����b�ł͂Ȃ��̂��@�Ƃ������Ƃ��킩��܂��āE�E�B�܂�@���Ƃ��ƂƂ����̂��@���Ȃ肠���܂��Ȃ��b�̂悤�Ȃ̂ł��ˁB������@���ԓ`���Ƃ������̂̂����ɂȂ�̂��ǎv���܂����A�C���h�̘̐b�Ȃ̂��@�Ƃ��A�s�җl�ł͂Ȃ��Ă��߉ޗl�Ȃ̂��A���₢��@����̓L���X�g�l�Ȃ̂��@�Ƃ��E�E�A�O�C���@�M�S���N�������Ƃ����̂ŁA����������ɂ���Ă����V�g���Ȃ̂��E�E�Ƃ��ˁB�o�ꂷ��̂��@�E�T�M�͌��܂��ďo�Ă͂��܂����A�ق��ɂ��@���X��������^�k�L��������̏ꍇ������悤�ł����B�܂��A���̘b���ǂ��́@�Ɓ@�Nj�������̂ł�����܂��A�厖�Ȃ��Ƃ����A�܂�@�w���ɃE�T�M������킯�x�������͂����肳���悢���ƂȂ̂ŁA�ق��̂��܂��܂������Ƃ́@�K���ɉ�����������\�����肵�ā@����̂��b�ɂȂ����@�Ƃ������̂ł��B�����@�Ō�̍s�җl�������@�ˑR�傫���Ȃ��ā@�R������Ԃ��Ċۂ߂����̂��˂��ɂȂ��āE�E�Ƃ����Ƃ���́A����@���ꂱ��T���Ă݂ā@���߂Ēm��A�ƂĂ��@�ʔ������z���Ǝv�������̂ł�����A�����̂��b�́@���������Ă݂܂����B �@

 �@
�@ �@
�@

�����̖͗l���݂āA�݂������錎�������̎p���킩��܂����H
���߂�4�l�g�B����ȉ�b�����킳��Ă��܂��B
A�N�@�u������������2�C����H�v
B����u�����A����1�C���Ǝv�����ǁv
C�N�@�u�I���A�ǂ����Ă��E�T�M��������Ȃ��v
D����u���ɂ́A���ʂ��ɂ��������Ȃ����ǁv
B����u�����āA���̍����Ƃ��낪�P�Łc�c�v
C�N�@�u�������������Ȃ���!?�v
���Ȃ���������A���ƌ����ł��傤�H
�����̖͗l�̌����c�c�m���Ɍ��������͂��݂����Ă��܂�
�ӊO�Ƃ���ӂ�Ȍ��������̑��݁B�l���ꂼ�ꎩ���̎v�����݂������A�N�ɕ����Ă����ǂ͂�����킩��Ȃ��Ƃ����p�^�[���������悤�ł��B����ł́A�����ŃX�b�L�������܂��傤�B���̉摜���u���������v�ł��B���̖͗l�̍��������́u�C�v�ƌĂ���n�B���̍��������Łu�݂����Ă��邤�����v�̎p�������Ă܂��B
���ӊO�ƒm��Ȃ��I���ł��������݂����Ă��闝�R
����e�q�̉�b�ł��B
�q�@�u�˂��˂��A�ǂ����Č��ɂ�����������́H�ǂ����Ă��݂����Ă���́H�v
�e�@�u�c�c�v
�q �u�˂��A�ǂ����āH�v
�e�@�u�����ƁA�݂����D���Ȃ̂�v
�q�@�u�c�c�v
����ł͐e�̖ʖڂ������܂���B
�����������̗R���`���������`��
���������`���ɂ���������܂����A1�ԃ|�s�����[�ȗv��o�[�W���������Љ�܂��傤�B
�w�́A����Ƃ���ɃE�T�M�ƃL�c�l�ƃT��������܂����B������A���ʂĂĐH�ו�����V�l�ɏo��A3�C�͘V�l�̂��߂ɐH�ו����W�߂܂��B�T���͖̎����A�L�c�l�͋����Ƃ��Ă��܂������A�E�T�M�͈ꐶ�����撣���Ă��A���������Ă��邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�����ŔY�E�T�M�́A�u����H�ׂĂ��������v�Ƃ����ĉ̒��ɂƂт��݁A�����̐g��V�l�ɕ������̂ł��B���́A���̘V�l�Ƃ́A3�C�̍s�����������Ƃ�����ߓV(�^�C�V���N�e��)�Ƃ����_�l�B��ߓV�́A����ȃE�T�M������݁A���̒����S�点�āA�F�̎�{�ɂ����̂ł��B�x�@����́A�������b���炫�Ă��邨�b�ł��B
�܂��A���̂��b�ɂ͑���������A�w�����������V�l���A���̏Ă�������Ō��ɉf���A����ꂽ�������͐����Ԃ�x�Ƃ�����������܂��B������A���̔��������ł͂Ȃ��A�����������������Ȃ�ł��ˁB
�����ł��������݂������Ă���̂͂Ȃ��H
�ł́A�Ȃ��݂����Ă���̂ł��傤���H �u���������V�l�̂��߂ɖ݂������Ă���v�Ƃ��u���������H�ו��ɍ���Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ�����������܂����A���H�̖������L���j���ł��邱�Ƃ��l����ƁA��������̂��Ă��Ƃꂽ���ƂɊ��ӂ���ӂ����߂��Ă���悤�ł��B
�����������͖������ʂł͂Ȃ�
�����������Ȃ���A���Ђ̈Ⴄ3�l������Șb�����Ă��܂��B���{��A����u�����������āA���\����������ˁv�@�����S����B����u�Ⴄ��B����͌�����B�R�����ƌ��̌����i����v�@�A���r�A��C����u�������B����̓��C�I�����i���Ă���̂��v�@ �O�l�O�l�̌������ł����A����͂ǂ���������̂ł��B
�����{�ȊO�ł͌��̖͗l���ǂ�����́H
���͒n���ɑ��Ă��������ʂ������ĉ���Ă���̂ŁA���E���ǂ��Ō��Ă������\�ʂ����Ă��܂�(������p�x�ɑ����̈Ⴂ�͂���܂���)�B�������A���̖͗l���ǂ������邩�͍��ɂ���ėl�X�ł��B�؍��⒆���ł́A���{���l�E�T�M�Ɍ����邻���ł����A�����̃E�T�M�͂��݂����Ă���̂ł͂Ȃ��A��҂��Ă��܂��B�܂��A�����̒��ł��A�E�T�M�ł͂Ȃ��傫�Ȃ͂��݂��������u�J�j�v�Ƃ����n�������܂��B���Ăł́u�����̉���v���ƌ����Ă��܂����A�C���h�l�V�A�ł́u�ҕ������Ă��鏗�̐l�v�A�x�g�i���́u�̉��ŋx�ޒj�̐l�v�A�I�[�X�g���A�ł́u�j���������_������������肵�Ă���v�̂������ł��B���ɂ��A��{��ǂނ�������u���j�v�u���o�v�Ȃǎ��ɗl�X�B�������낢�ł���I
•���{���݂���������
•�؍����݂���������
•��������҂�������
•�����̈ꕔ���傫�ȃn�T�~�̃J�j
•�����S�����C�k
•�C���h�l�V�A���҂ݕ������Ă��鏗��
•�x�g�i�����̉��ŋx�ޒj��
•�C���h�����j
•�I�[�X�g���A���j���������_������������肵�Ă���
•�J�i�_�̐�Z�����o�P�c���^�ԏ���
•����ā����o
•�k���[���b�p���{��ǂނ�������
•�새�[���b�p���傫�Ȃ͂��݂̃J�j
•�����[���b�p�������̉���
•�A���r�A���i���Ă��郉�C�I��
•�h�C�c���d�������j
•�o�C�L���O�����������j���@

�@�@�@���ŏ��͔�
���̖��������ƒ����͊W������܂����Ƃ���A���͐��̐��ƍl�����Ă���܂��āA ���Ŋۂ���(����Łu�p���v�g�R�E)���Z��ł����ƍl�����Ă��������ł��B ����͌Ñ㒆���̌��n�M�ł��邻���ł��B �@
�@�@�@�����̓I�^�}�W���N�V
���̌É���2���ɂ��܂��Ɖ��(�J�o)������(�Z���W��)�ƂȂ�܂��B ����Ŕ�������(�I�^�}�W���N�V)������(�K�}�K�G��)�ɕϐg���܂����B
�@�@�@��3�ԖڃK�}�Ɠe
�勂̓��Ď��Ƃ��āu巓p�v�Ə����ւ����܂��āA巂Ɠp���Ƃ��Ɍ��ɏZ�ނ悤�ɂȂ����悤�ł��ˁB
�@�@�@���O���@�t�B645�N�C���h����A��B
�������p�̌��V�́A�\��V���̌��{�a�ɏZ�މ��ŁA�e�����̎g�҂Ƃ���Ă��܂��B �����O���́u�哂����L�v�ɒ�ߓV�̘b���o�Ă���̂ŁA ��ߓV�̂��b�ƌ��E�T�M�̌ꌹ�Ƃ����̎���Ɉ�v���Ă��s�v�c�͂Ȃ��悤�ł��ˁB �������퐶����̓���(���u5������)�Ɍ����������`����Ă���̂ŁA�����ƑO�̎��ォ������܂���B
�@�@�@���O�����
�E�T�M�̌ꌹ�ɂ͌Â�����2�̊O��������������悤�ł��B �Ñ㒩�N��̉G�z��(�E�K�T��)�ƞ���̎Ɏɉ�(�T�T�J)��2��ނł��B ����2�̓E�T�M�ɔ��������Ă��܂���B�V���o���m�ɂ��A �C���h�̌Ì�T���X�N���b�g�ł͌��̈ꖼ���u�E�T�M�v�Ɖ]�������ŁA �u�E�T�M�v�̈Ӗ��͒��т͂˂铮����]�������ł��B
�@�@�@�����e�ƒ�ߓV
�C���h�̃W���[�^�J�_�b����B�́u�������v�Ɓu���ˁv�Ɓu����v�� �O�C�����ǂ���炵�Ă���܂����B�O�C�͑O���̍s�����������獡�͓����̎p�ɂȂ��Ă���̂ŁA ���̂��߂̐l�ɂ��߂ɂȂ�悤�ȗǂ����Ƃ����Ƃ��Ƃ����b�������Ă���܂����B��ߓV�͂��̘b���Ă��ĉ����ǂ����Ƃ������Ă����悤�ƁA �V�l�̎p�ɂȂ��ĎO�C�̑O�Ɍ���܂����B
�O�C�͘V�l�̂��߂ɐF�X���b�����Ă����܂����B ����͖ɓo���ĉʕ���̎����̂��Ă��Ă����܂����B ���˂͐�̋����̂��Ă��Ă����܂����B�������������ɂ͂���Ƃ��������Z������܂���ł����B�������͘V�l�ɂ��������Ă��炢�u���ɂ͉��̓��Z������܂���̂ŁA ���߂Ď��̐g���Ă��Ă��̓��������オ���Ă��������v�ƌ�����A �̒��ɔ�э���ō������ɂȂ��Ă��܂��܂����B����������V�l�͒�ߓV�̎p�ɖ߂�u���O�����O�C�͂ƂĂ����S�Ȃ��̒B���B �����Ƃ��̎��ɐ��܂�ς�����Ƃ��ɂ͐l�ԂƂ��Đ��܂�Ă���悤�ɂ��Ă����悤�B �Ƃ��ɂ������̐S�����͗��h�Ȃ��̂��B ���̍������ɂȂ����p�͉i���Ɍ��̒��ɒu���Ă����邱�Ƃɂ��悤�v�Ƃ����������ł���܂��B�������Č��ɂ͍������ɂȂ����������̎p�������邻���ł��B
���{�ł͍��̕���(����������1077�N�������ꂽ����)�́A �u�V���̕��E���܁E��13�b�v�Ɍ��e�̘b������܂����B �V���̕��ł́A�{���`�̌`�Ő����I�Șb�����S�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�@����ߓV�Ɠ��I
�Ñ�C���h�œ��I�́A�C������߂Ɛ킢�j��āA������~���A�܂��Đg���B������ �ł���Ƃ����b�����邻���ł��B�Ñ�C���h�V���ł́A�����f���̂����A ��8�Ƒ�9�f�������z�ƌ���ۂݍ���ł��܂����_�ł���ƍl�����Ă���܂����B ���̈��_�̖��̓��t(Rahu)�ƌ����܂��Ď��̂悤�Ȃ��b������܂��B
���t�́A�_�X�����C�𝘝a���č�����s�V�s���̎����A�����ɂ܂�������ē��݈���ł��܂��܂����B �������_�X���C�A�ƌ��_�`�����h���Ƃ��ō��_���B�V���k�ɒm�点�܂����B �ō��_���B�V���k�͕�ւň��_���t�̎�Ǝ葫��f�����Ă��܂��܂����B �Ƃ��낪����̊���ŁA���̌����葫���s���̖������ēV���삯���A ���ɂ͍��������������⌎��ۂ�ŁA���߂Ă��T�����͂炵�Ă���ƌ��������ł�
�@�@�@����j��8�E9�f��
��j �܍s ���p �G�� ���x
���� �y �k�� �ӏH���珉�t �N��
�㎇ �� �� �� ��
�@�@�@����8��9�����S�C�P�C�g(�����H���������ˋ�̓V��)
�C���h�V���w �Ӗ� ���� �Ǖ�
Rahu ���� ��(�ڌ�) ���S
Ketu ���� �v�s �P�C�g
�Ñ�C���h�ł́A�u���z�̉����v�Ɓu���̔����v��2�̌�_�� ����(���S)�Ɨ�����2���_���Z�݁A���X���z�⌎��H�ׂ�ƍl�����Ă��������ł��B ���̃��S�E�E�P�C�g�̓�f���̓C���h�N���ŁA���j(����)�ɉ������ �㐯�ƂȂ��������ł���܂��B �@�u����̃��}���X�v���@�@�@�@�@
�@�@�@������
�@�����̒��{�������ł��B�V�����֒����J���c��(����)�ɂ͌����`���� �������ɓe��������グ�Ă���A�����ɖ�₪�`����Ă��܂��B662�N�B���ÓV�c��30�N�B�������q�̐��������̂ыk�受�Y����点�����̂Ƃ���܂��B ����Ɍ����`����A�E�Ɍj���A�����ɖ��A�E�ɓe���`����Ă���܂��B����͌Ñ㒆���ɂ����āA���œe���s���̖�𝑂��ƍl�����Ă������̂��A ���{�ɓ`����Ă���͖݂𝑂��ƕω������������̂Ɖ]���Ă��邻���ł��B �ω��̗��R�́u�����v���u�]���v�Ɖ]���܂����A���ꂪ�u�ݝ����v�Ɠ]�������Ƃ̂��Ƃł��B���̑����{�a�͌Ë��ɕ`����Ă��܂����A�N�オ�s���ł��B�u���v�Ɖ]�����t���C�ɂ�����܂��B �s���̖݂ɕω��������Ƃ́A����Ɣ���ŁA�ꉞ����I�ɂ͖������Ȃ��悤�ł��ˁB
�@�@�@���]������ݝ����ւ̓]��
�]������ݝ����ւ̓]���̐���������Ă���{�͑��Ɂw���{�̐H������n19�@�ݔ������x�@�w���{�`�������x�@�w���ׂ��̌ꌹ���T�x�Ȃǂ�����܂��B
�J�i�_�E�C���f�A���̂��b�ŁA���ɃJ�G�������邨�b������܂��B �����F�X�Ȑl�����҂����̂ł����A�����Ăщ߂��Ė��̃J�G���̋��ꏊ���Ȃ��Ȃ����̂ŁA �Z�̌��̊�ɒ�����Ă��܂����ƌ����b�ł��B
���Ƃ��ƃA�W�A�N���̂��̘b���A�V�x���A�E�A���X�J���o�ăJ�i�_�ɓ`�������������Ƃ̂��Ƃł��B ����Ɠe���J�G���ƈꏏ�ɁA�J�i�_�ւƓn�����̂ł��傤���ˁB
�����A�g���e�Ɂu���͌����Ă��܂�������悤�ɁA�l�Ԃ�����ł��܂������Ԃ邱�Ƃ��ł���v�� �l�Ԃɓ`����悤�Ɍ����܂����B�������e�͊ԈႦ�āu���͌����Ă��܂������邪�A �l�Ԃ͎��琶���Ԃ�Ȃ��v�ƌ����Ă��܂��܂����B�{�������͓e��_�Œ@���܂����B �e�͒܂Ō��������~���܂����B�e�̌�������Ă���̂͂��̂��߂ŁA ���ɍ�����������̂͂��̂��߂ł���ƌ����܂��B �A�t���J�ł��e���o�Ă���̂ɂ͋����ł��B�������̉e�͓e�̎p�ł͂Ȃ��āA�Ђ��������Ȃ̂ł��ˁB�@

�g���̓e�h�̕���́w���̕���x���܁A�܂��NJ��͂���t���̒��̂ɂ��Ă���B���̕���́A�����v�z�́w�W���[�^�J�x�k�{���(�ق傤����)�l�ɗR�����Ă���B�W���[�^�J����Ƃ͂��߉ޗl���O���ŃE�T�M�A�T���A�܂������ł����Ă���̐��ł́g��F�h�ł��������Ƃ�\�킵�Ă���b�ł���B�W���[�^�J����A�W���[�^�J�}�̓C���h�ł͋I���O�ꐢ�I���Ɏn�܂�B�����Ď������͎����I���߂̍��̖@�����̋ʒ��̐~�q�A�w�̐g���Ր}�x�A�w��R���q�{�g����}�x�ɂĂ��̂��Ƃ�m��B
�g���̓e�h�̘b�́w���̕���x�ł́A�u���͐́A�V���ɓe�E�ρE���A�O(�݂�)�̏b����āA���ɐ��̐S��(����)���ĕ�F�̓�(�ǂ�)���s�Ђ���B�v�Ǝn�܂�B�O�C�̏b�͐g��������V�l���݂�ƁA���͖̎����E���A�ς͐쌴���狛�����킦�V�l�ɂ��������B�Ƃ��낪�e�͂������������ߍs���ǂ�����������̂�����������Ȃ��B�V�l�͉��������Ă��Ȃ��e������ƁA�u���O�͂ق��̓�l�ƐS���Ⴄ�ȁv�ƂȂ������B�e�͂��Ȃ������B���ɎĂ������Ă��Ă���A�ςɂ�����Ă���Ɨ��݁A�킪�g��R����̒��ɓ������������B�̐g—�A���𓊂������ߍs�ł���B���̎��V�l�́A��ߓV�ƂȂ�A�u���̓e�̉ɓ�����`�����̒��Ɉڂ��āA���܂˂���̏O���Ɍ������߂ނ����߂Ɍ��̒�����(��)�ߋ��ЂB�R��A���̖�(������)�ɉ_�̗l�Ȃ镨�̂���͍��̓e�̉ɏĂ����鉌�Ȃ�A���A���̒��ɓe�̗L��Ƃ��ӂ͍��̓e�̌`�Ȃ�B��(����)�̐l�A�������ނ��Ƃɍ��̓e�̎��v�Ђ��Âׂ��B�v�Ƃ������Ǝ����B���̘b�́A�e�̎̐g�̐S�A���ߍs����Ă���B
�l�Ԃ����ʒ���(���Z��N)���Ĉȗ��A���̂悤�ȓ`���A�_�b�͖Y����Ă��邪�A���̉F���A��͌n�̂Ȃ��A�n���ɐ����̂���s�v�c���͂��낢��Ƙb��ɂȂ��Ă���B�ȑO�Ɂw����Ɛl�Ԃ̉Ȋw�x(�͍����Y��)��ǂ��Ƃ�����B����Ȋw�҂̌��t�ɂ��u�Ȋw�͐����Ȋw�ł͂Ȃ��Đ������łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����Ă����B�g���̓e�h�͉������̂��̔w�i�̐�����������Ă��͂��Ȃ����B �@

�T�T�E�W���[�^�J�ł́A��ߓV���o�������̎p�ƂȂ��āC���키���C�W���b�J���C���C�E�T�M�̂��ꂼ��Ɏ{�������߂��ہC�����o������̂������Ȃ��E�T�M���C�����̑̂��Ă��Ď{���ɂ��悤�Ɖɔ�т��݂܂��B�����āA���̍s�ׂ��]������ߓV���C���ʂɎR�̏`�ŃE�T�M�̎p��`���A�V�ւƋA���čs���܂��B���̘b�������ꂽ�̂��ɂ��Ă͂͂�����Ƃ͂��܂��A�W���[�^�J�Ɋ܂܂�邢�����̐��b�̌��^�͋I���O3���I����ɐ��������ƍl�����Ă���A���Ȃ�Â����Ƃ�������܂��B
�C���h�̕����Ō��̂��������q�ׂĂ���̂́A�W���[�^�J�����ł͂���܂���B�I���O6���I����ɍ��ꂽ�ƍl�����A�o���������̍��J���L�q�����A�u���[�t�}�i�Ƃ��镶���̒��ɂ��A���ɂ�����������Ƃ����L�q�������܂��B
�W���C�~�j�[���E�u���[�t�}�i�́u���̒��̓e�̕���v�ɂ́A�u���̒��ɂ�����͓̂e�ł���B���ƂȂ�A���͖������x�z���邩��ł���v�Ə�����Ă��܂����A�܂��A�V���^�p�^�E�u���[�t�}�i�ɂ��u���̒��̓e�v�Ƃ����L�q������܂��B���̂悤�ɁA�C���h�ł́A���̂������͋ɂ߂ČÂ����ォ��A�o���������̓`����ʂ��Č��p����Ă������Ƃ�������܂��B���ہA�T�T�E�W���[�^�J�ł́A��ߓV�̓o�������ɉ����ē��������ɋ߂Â��Ă���A�o���������̍l�����������b�ł���W���[�^�J�̃X�g�[���[�ɉe����^�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�e�����̐������Ƃ������R�͉��Ȃ̂ł��傤���B�W���C�~�j�[���E�u���[�t�}�i�̖�ɂ͌���(�T���X�N���b�g��)�œe�̂��Ƃ��u�V���V���v�Ƃ����A�x�z������u�V���[�X�v�Ƃ������Ƃ�������Ă��܂��B�܂�A�����������x�z(�V���[�X)���邱�ƂƁA�e(�V���V��)�̒P��̗ގ����A���҂����т��Ă���v���ƂȂ��Ă���悤�ł��B�T���X�N���b�g��ł́A���̂��Ƃ��V���V��(�e������)�Ƃ��Ă�邱�Ƃ�����ƁA��҂͏q�ׂĂ��܂��B
�Ñ�C���h�ł́A���͍��J���s���ڈ��ƂȂ��Ă���A�u���[�t�}�i�����ɂ�������V���̍��J�̂��Ƃ��ڂ����q�ׂ��Ă��܂��B�C���h�Ɍ��炸�A���͌Ñ�̐l�X�ɂƂ��ďd��ȊS���������悤�ŁA�����̒n��Ō����u���ƍĐ��v�܂��́u�L���v�̃V���{���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���[�}�j�A�o�g�̏@���w�҃~���`���E�G���A�[�f�����Ă��܂��B�����ď��ł�����A�Ăь����Ƃ������̐������A�����̖��͂������A�A���̐���Ƃ��Ή��Â���ꂽ�悤�ł��B�����������x�z����Ƃ����l���́A�o�����������͂��ߌÑ�̃C���h�ɂƂ��đ厖�Ȏv�z�������̂ł��傤�B�e���ɐB�͂��������Ƃ���A�L���̃V���{���ƂȂ�A�����悤�ȈӖ��������Ɗ֘A����悤�ɂȂ����Ƃ����l�����A�e�ƌ������т���L�͂Ȑ��ƂȂ��Ă��܂��B
�Ñ�C���h�ł͍��J�̍ہA�\�[�}�Ƃ��������������p�����܂����B���̃\�[�}�́A�C���h�_�b�ɂ����āA�C���h��(�����ł͒�ߓV)�Ɋ��͂�^����Ƃ���A�܂��A���̐_�Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B�\�[�}�̌����ɂ��Ă͕������Ă��Ȃ��悤�ł����A�C���h�̐��T�u���O���F�[�_�v�ɂ́A�\�[�}�͐A��������č����Ƃ����L�q������܂��B�W���[�^�J�ł́A��ߓV���R�̏`�Ō��ɓe�̖͗l��`���Ă��܂����A���������������ƁA�\�[�}�Ƃ̊֘A������̂�������܂���B����ɁA�e�͐�c�������H���̈�ƌ��Ȃ���Ă����悤�ŁA�ɔ�э��e�̘b���A���J�ɂ����鋟�V�̂悤�ȕ��K���e�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����(�V���V���ƃV���[�X)�ƃV���{���̈Ӗ�(�L��)�̂ǂ��炪��Ȃ̂��A�܂��ǂ̂悤�ɂ��ė��҂��֘A�Â����Ă������̂��͕s���ł����A�Ƃɂ������̂������̋N���Ƃ��ẮA�C���h���L�͂Ȍ��n�ł��邱�Ƃ͊m���ł��B�����ȊO�ɂ́A�I���O180�N������ꂽ�ƍl�����Ă���C���h�̃R�C���̒��ɁA���Ɠe�̖͗l���{���ꂽ���̂������܂��B �@

�����ɂ����錎�Ɠe�̊W�������L���ȏ����́A�퍑����̋������������Ƃ����u�^���v�ł��B���̂Ȃ��̓V��Ɂu�̗��ۂꉽ���C �����Čړp���ɍ݂�(���̂悢���Ƃ������āC�ړp�͌��̒��ɂ���̂��낤)�v�Ƃ����ꕶ������A���̂Ȃ��̌ړp(����)���������̂��Ƃ��ƍl�����Ă��܂����B�����{���ɁA�ړp���������Ȃ�A�����ł͋I���O4-3���I����ɂ́A���̂��������m���Ă������ƂɂȂ�܂��B
�������A���̂Ƃ�����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B�Ƃ����̂��A�����̌ÓT�w�҂ł��長�ꑽ(�Ԃ���)���A�ړp�͂������ł͂Ȃ��q�L�K�G��(��=����)�̂��Ƃ��w���Ă���Ǝw�E���Ă��邩��ł��B���ꑽ���ɂ��A�勂�勂Ɠe�̓ǂݕ������Ă��邽�߁A���ɓe������ƍl������悤�ɂȂ����悤�ł��B���������ł́A�e�Ƌ��Ƀq�L�K�G�������̐������Ƃ��āA�ÓT��`���̒��ŁA�����Ԍ��p����Ă��܂����B
�����ł͂�����ƌ��̂��������m�F�ł�����̂́A1970�N��ɔn���͊��悩�甭�@���ꂽ�A���(���̏�ɕ`���ꂽ�G)�ł�(�}1)�B���̛��ɂ́A�O�����ƈꏏ�Ƀq�L�K�G���Ɠe�̐}�����{����Ă��܂��B�n���͊���͒������̏告�����������̕�ł��邱�Ƃ��������Ă��邱�Ƃ���A���ɑ^���̌ړp���q�L�K�G����\���Ă���Ƃ��Ă��A�I���O2���I�ɂ́A���̂������������Œm���Ă������Ƃ�������܂��B
�C���h�ł͋I���O6���I���낷�łɁA���̂��������o���������̎v�z�̒��Ō���Ă��܂�(�C���h�ɂ����錎�̂������Q��)���A�����̋ʓe�̓C���h����`������̂ł��傤���B����Ƃ��A2�̏ꏊ�œƗ��ɔ��������̂ł��傤���B���ꑽ�̓q�L�K�G����\���ړp���A�e�ƍ�������邱�ƂŁA���̂��������a�������Ƃ��Ă��܂����A���Ɍړp���q�L�K�G�����Ƃ��Ă��A��̎���ɃC���h���猎�̂������������ɓ`������\��������܂��B
�n���͊���̛��̔N����l������ƁA�������̂������������ɓ`������Ȃ�A����͕����`����V���N���[�h�J��ȑO�ł���\�����ɂ߂č����Ȃ�܂��B�c�O�Ȃ���A�ʓe�����̓`���Ɋւ���L�^�͂���܂��A�V���N���[�h�̊J��ȑO�ɂ�����A�����Ɛ����̍��X�Ƃ̌𗬂������L�^��o�y�i�Ȃ�������c����Ă��܂��B
�܂��A�i�n�J�ɂ��j�L�̑制��`�ɂ́A�����̙��z�����ւ̋��͂����t���邽�߁A���y�������ɕ����ƁA�制�̐l�X�͊��̂��Ƃ�m���Ă��āA�f�Ղ�]��ł����Ə�����Ă��܂��B����ɒ��y�́A���(�o�N�g���A)�̎s���邛�̒|���冂̕z�������A����炪�C���h����d������Ă��邱�Ƃ�m��܂��B�܂�A���y���������s���ȑO����A�ڂ������[�g�͕�����Ȃ����̂́A�C���h���܂߂������̒n��ƒ����͉��炩�̌`�Ō𗬂��Ă����悤�Ȃ̂ł��B�܂��A�����ɂ͂͂邩�̂��A��������ʂ������炳��A���Ă̋ʂƂ��Ē��d����Ă��܂����A�C���h�Ƃ͏����ꏊ���قȂ�܂����A�A���^�C�R���̃o�W���N�Õ��Q����͒����Y�̌��D�����o�y���Ă��܂��B�o�W���N�Õ��Q�̔N��͂͂�����Ƃ͕�����Ȃ����̂́A�I���O5-4���I�A�ꕔ���I���O3���I�ƌ��ς����Ă���A���y�̉����ȑO�ł��邱�Ƃ͊m���Ȃ悤�ł��B
�����̋L�^��o�y�i����A�����ɂ̓V���N���[�h�J��ȑO����A�����Ƃ̌𗬂��������ƍl������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ƃ���ƁA���̂��������܂��A�����̕����Ƃ��Ē����ɂ����炳�ꂽ�̂�������܂���B�����̒n���������ڍׂɕ��͂����G�o�[�n���g���A���̂������͒����̊O��������Ă����ϔO�ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B�������A���ꑽ���w�E���Ă���悤�ɁA���̗ގ��ɂ���Ē��������ŋʓe�����܂ꂽ�\�����ے�͂ł��܂���B
�����ł͊���ɂȂ�ƁA�g���̍����l�����̕掺�̐ɁA�l�X�Ȗ͗l���{�����悤�ɂȂ�܂����B�����͉̐摜�ƌĂ�A�����̕�����m��肪����ƂȂ��Ă��܂��B�����āA�摜�̒��ɂ́A�ʓe���`����Ă�����̂��������݂��Ă��܂��B�܂��A����̋��ɂ��ʓe�̖�l���{����Ă��邱�Ƃ���A�N�����ǂ��ł���A�����Ō��̂��������L�܂����̂�����ł��邱�Ƃ͊m���Ȃ悤�ł��B
�����Ɍ��̂��������o�ꂷ��悤�ɂȂ�̂���͂芿�ォ��ŁA�O���̊w�҂ł��闫�����������Ƃ����u�܌o�ʋ`�v�Ɂu�����ɓe���勂ƗL��͉����v�ƌ��ɓe�����邱�Ƃ��q�ׂ��Ă��܂��B����ɁA�㊿�̎���ɂȂ�ƁA���t�́u�쌛�v�≤�[�́u�_�t�v�����̂������̂��Ƃ����y���Ă��܂�(�������A���[�͌��ɂ����������邱�Ƃɂ͔ے�I�ł���)�B �@
 �@
�@ �@
�@

�����ł͕s�V�s�������߂�u�_��v�z�v�Ƃ����l�����Â�����M����Ă���A������͂��̐_��v�z�ɂ�����受�Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B������̖{���̎p�́A�����̌���������ɂ��ւ�炸�悭�������Ă��܂���B�����Ñ�̒n�����ł���u�R�C�o�v����́A������͛��ĎR(������)�Ƃ����R�ɏZ�݁A�^�̐K����Ղ̎������A�����̂悤�ȑ��݂ł��邱�Ƃ�������܂��B���̐����ꂪ�A�_��v�z�����܂�ɂ�A�������玟��ɛ��ĎR�̐受�ɂȂ��Ă����܂����B���ĎR�͒����ł͎��҂����鐹�Ȃ�R�ƍl�����Ă��邱�Ƃ���A������ɂ����X�ɐ受�̐��i���������Ă������̂ł��傤�B
����ł͂Ȃ��A���̂������Ɛ����ꂪ���т����̂ł��傤���B�͂����肵�����Ƃ͕�����܂��A������͐受�����łȂ��A���_�Ƃ��Ă̐��i�����˔����Ă���悤�ł��B���̂��߁A���̒��ɂ���ƍl�����Ă���e�ƃq�L�K�G������������ő��ɂȂ����̂�������܂���B
������̍l�����Ƃ��ċ����[���_�́A�����ꂪ�Z�ނƂ������ĎR�̂������̓���(�V�n�����сA�l�̐�̐����ƂȂ��Ă���Ȃ�)�ɂ́A�C���h�̐��Ȃ�R�ł���{��R(����݂���)�Ƃ̋��ʓ_��������Ƃ������Ƃł��B���̂��߁A����I�ȏ؋������Ȃ����̂́A�C���h�ɂ�����{��R�̊ϔO������ȑO���璆���ɓ`����Ă���\�������邻���ł��B�����āA���̐{��R�ɂ́A�W���[�^�J�Ō��ɓe�̊G��`�����C���h��(��ߓV)������ƍl�����Ă��܂��B���̂��Ƃ���A�����{���ɛ��ĎR�̊ϔO�ɐ{��R���e����^�����Ȃ�A�C���h���ƌ��̂������̊W(�C���h�ɂ����錎�̂������Q��)�����ĎR�̐�����ɂ��������ꂽ�ƍl������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ł́A�ʓe�Ɛ��̊W�͂ǂ��ł��傤���B�P���ɐ����ꂪ�_��v�z�ɂ�����受�ɂȂ������߁A�ő��̋ʓe���s���̐������悤�ɂȂ����Ƃ��l�����܂����A�����łЂƂd�v�Ȍ���������܂��B����́A����̉摜�̐}�����ڂ������ׂĂ݂�ƁA�ʓe�̑��Ɂu�H�l�v�Ƃ����H�̐�������l���s���̐�������Ă���Ƃ������Ƃł��B�����āA���̉H�l�͑傫�Ȏ��������Ă���A�e�Ǝp�����Ă���̂ł��B����ɁA�O������̐}���ł́A�e�͌���\�����̂ł����Ȃ��A������Ƃ����ϔO�͔����悤�ł��B�����̓_����_���̒��҂́A���Ƃ��Ɛ��ƊW���[�������͉̂H�l�̕��ŁA����ɂ��Ȃ�������̏]�҂Ŏp�����Ă���ʓe���H�l�ƍ�������邱�Ƃɂ��A�ʓe���������悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝw�E���Ă��܂��B����������ƁA���̂�������������ƌ��т��Ă��邱�Ǝ��̂��A�H�l�ƍ������ꂽ���Ƃ������Ȃ̂�������܂���B
�����c�O�Ȃ����q�����悤�ɁA������̋N����受�ɂȂ��Ă����ߒ��A�O���̕����̉e���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂悭�킩���Ă��炸�A�C���h�����Ƃ̊W���܂߁A����Ȃ錤���Ɋ��҂������Ƃ���ł��B�Ⴆ�A�C���h�̍��J�ł́A�_�X�ɕs���������炷�Ƃ����u�\�[�}�v���C���h���ɕ������Ă��܂����B���̎v�z�͐�����ƕs���̐��Ƃ̊W�Ɏ��Ă��܂��B���ꑽ�̎w�E�ɂ��A�����̐_��v�z�́A�����ɏZ��ł���㳑�(���傤����)�̕��K�����ƂɂȂ��Ă���悤�ł��B���̐��͊m��I�ł͂Ȃ��悤�ł����A�_��v�z�Ɛ�����̔��W�Ɋւ��錤��������ɐi�߂A���̂������ɂ��Ă����������炩�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����܂ŋʓe�ƕs���̐��̊W�����Ă��܂����B����ł͂Ȃ��A���{�ł͌��̂��������݂𝑂��Ă���ƍl������悤�ɂȂ����̂ł��傤���B��ʓI�ɂ́A�\�ܖ�̖������Ӗ�����u�]���v�Ɓu�݁v���������Ă��邩��Ƃ��������m���Ă���悤�ł����A���ɂ��������l����ׂ��_������܂��B
���{�Ō��̂��������p�ɂɎ��グ����̂́A�\�ܖ�̂������̎��ł����A�����[���̂́A�������̎��ɒc�q�ł͂Ȃ��T�g�C�����������镗�K������Ƃ������Ƃł��B�T�g�C���͏Ĕ��_�Ƃō���Ă�����ʓI�ȍ앨�ł���炵���A�����{�⒆���암�̏Ĕ����s���Ă���n��̕����́u�Ɨt���ѕ����v�ƌĂ�A��삪�`���ȑO�̕����Ƃ��Ē��ڂ���Ă��܂����B�����āA���̏Ɨt���ѕ������ł́A�݂��ϋɓI�ɗ��p����Ă��邱�Ƃ�����Ă��܂��B�ݐ��̍�����p����n��Ƃ����̂́A���{�ȊO�ł͓���A�W�A�⒆���암�A��p�A�؍�������Ɍ����Ă���炵���A���̗��R�Ƃ��ẮA�Ĕ��_�ƂŌÂ�����͔|����Ă����T�g�C���̂悤�ȔS���̍����H�ו����D�܂ꂽ���߂ł͂Ȃ����Ǝw�E����Ă��܂��B
�����ł͓��̏I��肩��v�̎���ɂ����āA�\�ܖ�Ɏ��n�Ղ̐��i��������Ă����悤�ł��B�����āA���̏Ɨt���ѕ������ɏZ��ł���~���I����I���̑��X�ł́A�����\�ܖ�̓��ɁA�C����݂����ɋ����Ď��n�Ղ��s���Ă��邱�Ƃ�����Ă��܂��B���{�ł��A�����̌ÓT�ɉe�����A���X�ɋ{�앶���Ƃ��čs��������Ă��������������A��������̂��납����n�ՂƂ��ď����̊ԂɍL�܂��Ă����܂����B�ȏ�̂��Ƃ��l����ƁA���{�ł͋n�ƉP�ŝ������̂��Ă����ɘA�z�����̂́A��ł͂Ȃ��݂ł������݂����ł��B���ɏ����ɂƂ��ẮA���̌X�������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�܂��A�̂�����{�ł́A�݂͐������X�V�E�Đ������Ă������ʂȐH�ו��Ƃ݂Ȃ���A���܂��܂ȋV��(������n���̓�)�ŐH���ꂽ��A�_�l�ɕ�����ꂽ�肵�Ă��܂����B���̂悤�Ȗ݂̐����́A�C���h�̃\�[�}��A�����̐��Ƌɂ߂ėގ����Ă��܂��B�܂�u�����ł͐��𝑂��Ă������̂����������{�ł͖݂𝑂��悤�ɕω������v�Ƃ��������A�u���{�ł͖݂ɐ��̂悤�Ȗ������������v�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@

�ނ炪���̂悤�ɗ��h�Ȑ��������Ă����̂ɂ͗��R������܂����B�O���ł͐l�Ԃ������̂ɁA���������ɂ��Ȃ��������߂ɏb�̎p�ɂȂ��Đ��܂ꂩ��������Ƃ�m���Ă����̂ł��B
�u����ꂪ�b�̎p�ɐ��܂�ς�����̂́A�O���̍s���������������炾�B���̂��т͎����̂��Ƃ͎̂Ăđ��l�̂��߂ɑP���s����S�����A�����łӂ����ѐl�Ԃɐ��܂�ς�낤���I�v
���ꂪ�O�C�̌ł��ł������ł����B����Ȃ�����A�₹�������V�l���O�C�̑O�ɂ�����A���������܂����B
�V�l�u�킵�͂��̂悤�ɐ����Ă��܂��āA�H�ו�����ɓ���ʎn������B���Ȃ��B�͈���ݐ[���ƕ��������A�ǂ����킵��{���Ă���ʂ��H�v
��������O�C�̏b�́A�u�������P�s�����鎞���I�v�Ɗ�сA������ŘV�l��{���悤�ɂȂ�܂����B
�ؓo����̉��͂��낢��ȉʎ��ɂ̂ڂ�A������������̉ʎ�������ĘV�l�ɗ^���܂����B�m�b�̂���ς́A�l�Ԃ��������݂⋛�Ȃǂ������A��A�D���Ȃ����V�l�̑O�ɍ����o���܂����B
�Ƃ��낪�E�T�M�����́A���R�ɍs���Ƌ��낵���ō����Ђ��Ă��܂��A�S���H�ו���{���Ă��邱�Ƃ��ł��܂���B�V�l�̖��ɗ��������Ƃ�����S�ŒT���܂��̂ł����A�����A��͎�Ԃ�ł����B
�E�T�M�u���x�������������Ă��K�������������̂�{���Ă��܂��I������ς���A�͂�����߂ĉ������đ҂��Ă��Ă��������v
�E�T�M�͂�����A�Ȃɂ������ӂ�������ł��������ďo�Ă䂫�܂������A��͂艽���n�ꂸ�Ɏ�Ԃ�ŋA���Ă��܂����B�������đ҂��Ă����ςƉ��͓{��܂����B
�ρu����ς�R�������̂��ȁI�͂�؏E���Ȃǂ����₪���āv
���u���O�͂��̉Œg�܂낤�Ƃ��ĉ��������g�����낤!!�v
�e�u�������������A�����ł͂���܂���B���ɂ͂͂��߂���A�H�ׂ��̂�{���Ă���b�㐫���Ȃ��̂ł��B�ł����炲�V�́\�\�v
�E�T�M�͂��������ĘV�l�̂ق���U������Ɓu�ǂ������̑̂��Ă��ĐH�ׂĂ�������!!�v �ƁA�݂�����̒��֔�э��݁A�Ă�����ł��܂����̂ł����B
����������V�l�͂ɂ킩�əz�X�����p�ɕϐg���܂����B�V�l�̖{���̎p�́A��ߓV(�������Ⴍ�Ă�)�������̂ł��B
��ߓV�́A���l�̂��߂ɋ]���ɂȂ����E�T�M�̗����̐��_�Ɋ�������A�E�T�M���̒��ɔ�э������Ƃ������̎p�����̒��ɉi���Ɏc�����̂ł����B
��ߓV�ɂ͂���Ȏv�����������̂ł��傤�B�㐢�A�l���܂ނ��ׂĂ̐������̂��A�����Ȃ��߂邽�тɂ��̃E�T�M�̂��Ƃ��v���o���悤�Ɂc�c�B
�����đ��l�̂��߂Ɏ������]���ɂ����E�T�M�̑������_���ӂ肩����A���̒����炫���Ƒ������Ƃ��Ȃ��Ȃ�悤�Ɂc�c�B�@

���m����3�C�̓���
������A1�l�̔N�V�����m�����R�œ|��Ă��܂����B���R�ʂ肩�������̂�3�C�̓����A�E�T�M�A�L�c�l�A�T���ł����B����3�C�͑��k���A�m���������鎖�ɂ��܂����B�u�܂��H�ׂ���̂��W�߂悤�v�Ƃ������ɂȂ�A3�C�͂��ꂼ��H�������ɍs���܂����B�L�c�l�͐�ŋ���߂܂��A�T���͖̎����Ƃ��Ă��܂����B�������A�E�T�M�͉���������܂���ł����B�m�������������̂ɐH����������Ȃ������E�T�M�́A���邱�Ƃ��v�����܂����B����́A�����̑̂�����鎖�ł��B�u���̑̂��Ă��������H�ׁA�C�s�𑱂��Ă��������v�E�T�M�͑m���Ɍ����܂����B�����Ė������Ȃ��̒��ɔ�э������Ƃ������̎��A�N�V�����m���͒�ߓV�ւƎp��ς��܂����B(��ߓV�Ƃ͕����̎��_�ł��B)
�N�V�����m���̂ӂ������3�C�������Ă�����ߓV�́A�E�T�M�̌ł����ӂɊ������܂����B��ߓV�̓E�T�M��J�߁A�E�T�M�̎��ߍs�𐢊E���ɒm�炵�߂�ׂɁA���ɑ傫�ȃE�T�M�̊G��`���܂����B
�����z�{�Ƃ�
�E�T�M�͕z�{������H����������܂���ł����B�������A�����ł����@�ɍv���������ƍl���A���g�̖�������悤�Ƃ��܂����B�Ȃ��Ȃ��^���ł�����̂ł͂���܂���ˁB����Ȓ��A�������ł��ł������ȕz�{������܂��B�����̎��{(�ނ����̂�����)�E�E�E�z�{����������Ȃ��Ă��ł��鎵�̕z�{
�@�@�@��{(����)���D�����፷���Ől�Ɛڂ���A��ɂ��z�{
�@�@�@�a��{(�킰��)���a�₩�Ȋ�Ől�Ɛڂ���A��ɂ��z�{
�@�@�@����{(��������)�����̂��錾�t�����A���t�ɂ��z�{
�@�@�@�g�{(����)���g�̂Ől��������A�̂��g�����Ƃɂ��z�{
�@�@�@�S�{(����)���v�����̐S�����A�S����ɂ��z�{
�@�@�@�����{(���傤����)���Ȃ�n�ʂ����ɏ���A�ꏊ������z�{
�@�@�@�[�Ɏ{(�ڂ����Ⴙ)������ɐl���}�������A�J�h��ȂǏ��������̕z�{
�����̕z�{�Ȃ�A�������ɂ��ł������ł��ˁB3�C�̓����̂悤�ɒ��ǂ���炷�ɂ͂��݂��������������Ƃ��d�v��������܂���B���X�̐����̒��ŁA�{��⎹�i�̐S�����܂ꂽ���́A7�̕z�{���v���o���Ă݂�̂��ǂ���������܂���B�@
 �@
�@��
�E�����ɂ́A�E�T�M�̌��Ԃ�����߂Ȃ��z�{�̐S�����ĂƂ�܂��B
�E�l��ނ̈قȂ铮���������A���ǂ��������Ă���l�q���`����Ă��܂��B
�E�����ł́A�z�{�ɂ��ĎO����Ƃ����܂��B�O�ւƂ́A�u�z�{���̂��́v�Ɓu�z�{����l�v�Ɓu�z�{�����l�v�̂��Ƃł��B�����O������ł����āA�͂��߂ĕz�{����������̂ł��B
�E�u��͐l�̂��߂Ȃ炸�v�Ƃ�����悤�ɁA�������́A����̐����ɂ����āA�l�̂��߂ɉ�����������A������^�����肷��Ƃ��́A���炩�̌��Ԃ�����҂��Ă͂��Ȃ��ł��傤���B
�E�T����R���A�J���E�\�́A���������H�ו���T���Ă��ĕz�{�������Ǝv���܂��B����͕z�{���ꂽ�u���v�����ōl����Ȃ�A�E�T�M������������̑̂����傫�ȕz�{��������������܂���B�������A��ߓV�����ɕ`�����̂́A�E�T�M�̎p�ł����B�z�{�ɂ����ẮA�{�����̂��̈ȏ�ɁA�����ł����@�̋����ɍv���������Ƃ����z�{�҂̂܂����낪�A�������������̂ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B
�E�����C�s�̒��ɘZ�g�����̍s������܂��B���̒��Ɂu�z�{�v�̍s������܂��B�������͎�����]���ɂ��A���҂̂��߂Ɏ{�������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��ł�����̂ł͂���܂���B���ɓI�ȈӖ��ŕz�{�̍s���C�߂��Ƃ���J���Ă������Ƃ͋ɂ߂č���ł��B
�E����ɔ@���͂��̂悤�Ȏ������������m�ł�����A�@����F�̈��ʂɂ����āA����Z�g�����̍s���C�߂Ă��������܂����B���̌�����얳����ɕ��Ǝd�グ�āA���A�������ɓ͂����Ă��܂��B
�E�����̎��{(���̂Ȃ��҂��ł��鎵�̕z�{�B��{�A�a��{�A����{�A�g�{�A�S�{�A��{�A�[�Ɏ{�̎���)�Ƃ������Ƃ������܂��B���@�ɏo�����������ɂ́A���߂Ď{���̂܂˂��Ƃ��炢�͂����Ă����������Ƃ����S�������������̂ł��B�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@




 �@
�@ �@
�@
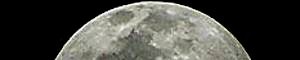 �@
�@ �@
�@
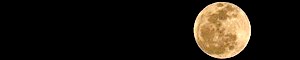 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
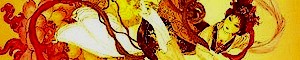 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@




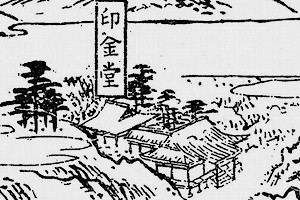 �@
�@ �@�u������v����
�@�u������v����


 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@