 �@ �@
 �@ �@
 |
|
���f�W�^���Љ� |
 |
|
��SNS�@ |
|
SNS�Ƃ́A�C���^�[�l�b�g����Đl�ԊW���\�z�ł���X�}�z�E�p�\�R���p��Web�T�[�r�X�̑��̂ł��B�Â��̓u���O��d�q�f���ł����������@�\�̈ꕔ�͎����ł��Ă��܂������ASNS�ł͓��Ɂu���̔��M�E���L�E�g�U�v�Ƃ������@�\�ɏd����u���Ă���̂������ł��B�܂��ASNS��Social Networking Service (�\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X) �̗��ŁA�\�[�V���� (�Љ�I��) �l�b�g���[�L���O (�q����) �����T�[�r�X�A�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�܂��B |
����\�I��SNS
��Twitter (�c�C�b�^�[)
Twitter��10��E20��̎�N�w�̊Ԃœ��ɗ��s���Ă���SNS�ŁA�c�C�[�g(�Ԃ₫)�ƌĂ��140�����̒Z���𓊍e���邱�ƂŋC�y�Ȑl�ԊW��z����T�[�r�X�ł��B���l�̂Ԃ₫���R�s�[�E�]�ڂł��郊�c�C�[�g�Ƃ����@�\������A��˂��ݎZ���ɍL�܂�(�g�U)�Ƃ��������������Ă��܂��B�����A���̃��c�C�[�g�ɂ��g�U�����Ԃ̎v��ʔ����݁A�����鉊��Ƃ������ۂ��N�����Ă��܂����Ƃ����Ƃ��ċ������܂��B
��Facebook (�t�F�C�X�u�b�N)
Facebook�͎��ȏЉ�(�v���t�B�[��)����L�������āA����ɑ��ăR�����g�����炤�Ƃ��������錳�cSNS�̐��E�W���ł��B����SNS���n���h���l�[���Ȃǂ̓����������Ă���̂ɑ��āAFacebook�͊�{�I�ɖ{��(����)�ł̓o�^���`�������Ă��āA30��`40��̎Љ�l�𒆐S�ɗ��p����Ă��܂��B�������ł��邱�Ƃɉ����Ċ�ʐ^���f�ڂ��Ă��郆�[�U�[���������Ƃ���A�r�W�l�X�ʂł̗��p�������Ō����Љ�ւ̉e���͂��������Ƃ������ł��B
��LINE (���C��)
LINE�͎�N�w����N�z�w�܂ł̕��L���X�}�z���[�U�[�����p���Ă���SNS�A�v���ŁA�X�^���v�ƌĂ�郆�j�[�N�ȉ摜���g�����`���b�g�@�\(�g�[�N�ƌĂ��)�������ł��B�o�^�ɂ̓P�[�^�C�ԍ����K�v�Ȃ̂ŕ����A�J�E���g���擾���邱�Ƃ�����A�Ƒ���F�l�Ƃ�������r�I�e�����ԕ��ł̃R�~���j�P�[�V�����ɗ��p����Ă��܂��B�܂��A�T�[�N����N���X���C�g�Ƃ����������l�ł̉�b�ɕ֗��ȃO���[�v�`���b�g�E�O���[�v�ʘb�Ƃ����@�\������A�����̃L�����A���[����SMS(�V���[�g���b�Z�[�W)����̒u���������i��ł��܂��B
��Instagram (�C���X�^�O����)
�C���X�^�O�����͒ʏ̃C���X�^�Ƃ��Ă��ʐ^�𒆐S�Ƃ���SNS�ŁA�e�L�X�g���S����������Ƃ͈Ⴄ�V�������[�U�[�w(���s�ɕq����20��`30��̏���)�𒆐S�ɋ}���ɗ��p���L�܂��Ă��܂��B�|�\�l��L���l�̃A�J�E���g�������X���ɂ���A�I�V�����Ō��h���̗ǂ��ʐ^���Ӗ�����C���X�^�f��(SNS�f��)�Ƃ������s��ݏo���ȂǁASNS�̒��ł��Ƃ�킯�₩�ȃC���[�W�Ō���邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B�܂��A���Ƀt�H�����[���������e���͂̋������[�U�[�̒��ɂ́A��Ƃ���̈˗������Ƃɏ��i�Љ��v�����[�V�����𐿂������ĕ�V��h�C���X�^�O���}�[�h�ƌĂ��l�������o�ꂵ�Ă��܂��B�@ |
 |
|
���f�W�^���Љ�̂������@ |
��ʂ���Z�A��ÂȂǁA�������̐������x���鑽���̕���ŁA�f�W�^���Z�p�����p�����V�����T�[�r�X���W�J����n�߂Ă��܂��B�l�b�g���[�N�ɂȂ������Z���T�AAI�A���{�b�g�Ȃǂ��Љ�̂�����Ƃ���ɓ��肱�u�f�W�^���Љ�v�ł́A�����̂��Ƃ�����������A�Љ�̍\���͑傫���ς�邱�Ƃł��傤�B�����̋Z�p��T�[�r�X�́A�₪�Đl�X�̍l������s���ɑ傫�ȉe���������炷��������܂���B�f�W�^���Љ�̂������́A�����ŕ�炷�l�X�̍l������s�����ǂ̂悤�ɕς�肤��̂������������̂ł��B�����ʂ����c�_�ɂ���āA�����̎Љ�ۑ���҂̎��_�ōl���邱�Ƃ����Ȃ����܂��B
���R�~���j�e�B�t�@�[�X�g�ȎЉ�
�R�~���j�e�B�Ƃ͏����ȃO���[�v�B�n��̒��̂Ȃ����A�u���ꂢ���ˁv�Ƃ��������Ō��т������̂Ȃǂ��낢�낾�B���Ƃ��ΐl�����������A�X�ɕ�炵�ɂ�����������悤�ɂȂ����Ƃ��悤�B�l�X�͌�ʂ��ẪV�X�e���ɐV���Ȏd�g�݂����߂邪�A���ȂǑ傫�ȎЉ�̈ӎv���肪�A�����_��ɂ����Ɋ��Y����Ƃ͌���Ȃ��̂ł͂Ȃ����H����܂Ō��݉����Ȃ������R�~���j�e�B�̈ӎv����������AI��A�a�V�ȃA�C�f�A�����IoT�Ȃǂ̃e�N�m���W�[��w�i�ɁA�R�~���j�e�B�͎��������̉��l�ςɍ��������ŁA�g������̂悢�d�g�݂�n������B�����ȋ������A�V���ȎЉ�̃X�^���_�[�h�ݏo���Љ�A������������Ă��邩������Ȃ��B
�������邱�Ƃ͑ԓx�\���̘A��
�X�|�[�c�I��̃p�t�H�[�}���X���f�[�^������Ă���̂́A���͂�펯���B�q�ϓI�Ɍv�����ꂽ�A�I��̐S�g�̏�Ԃɉ����ČJ��L������ō��̃v���[�͊ϐ�҂�M��������B�����ɁA�I�莩�g���C�Â��Ȃ����ׂȎ�_�ɂ����܂�āA���R�Ƃ���悤�Ȃ��Ƃ��������Ȃ��B�������f�[�^�����邱�Ƃ́A����܂Ō����Ȃ����������𖾂炩�ɂ���B�f�[�^��͂͐l�X�̐�����L���ɂ��锽�ʁA���ɂ͗\�z�O�̕s�s���Ȏ�����˂����Ă�����̂��B������u�d���Ȃ��v�Ǝ���邩�A�u�W�Ȃ��v�Ɩ������邩�B���ꂩ��̎������͂��̈ӎv������J��Ԃ��Đ����Ă����̂��낤�B���܂��܂ȃf�[�^�Ƃ����ɂ��������́A�������̖����̑傫�ȉۑ肾�B
�������ƕς�葱����X
�Ԃ̑����}�J�[�u�ɁA�Z������́u�������̂��N�����ˁv�Ɛ����オ��B���܂łȂ玩���̂ɑ��v�����A��ɂȂ������ɂ͂��炾���������Ă����̂��낤�B�������Z�p�̔��B�́u�������玩���ō���Ă��܂��I�v����������B3D�v�����^�͋߂������A�K�[�h���[�����炢�ȒP�ɍ��グ�邾�낤�B�Z���哱�̐V���������C���t�����ǂ�ǂ܂�A�X�̓J�X�^�}�C�Y���ꑱ����̂��B�������A��x������C���t����T�[�r�X�̈ێ��́A�V������������B�p���͂Ȃ����炾�B����ł��Z���̍������X�^�C���̕ω��ɍ��킹�������e�i���X�͔������Ȃ��B�V�������m��T�[�r�X�̒a���A�ێ��A�p�~�c���̑f�����z���A���͓I�ȊX��n������B
�������̂���K����
AI���l�Ԃ̑����̎d��������đ���悤�ɂȂ鎞��́A�����ڂ̑O���B���ɂ���́AAI�����ӂƂ����҂�ٌ�m�A�G���W�j�A�Ȃǂ̒m�I�J������i��ł����B���Ƃ��A1�l�̌����҂��C���ł���_���̐��ɂ͌��x�����邪�AAI�ł���Α�ʂɓǂ݂��Ȃ����Ƃ��ł���B��������ٕ���̒m�������т��邱�ƂŁA��a�̎��Ö@�̔�����z�������Z�p�v�V�ȂǁA�Љ�I�Ӌ`�̂��鉿�l�����ݏo�����Ɨ\�z����Ă���B���̂��߁A���R�ɂł��鎞�Ԃ�������P�[�X�������Ȃ邪�A�����ŎЉ�v���Ɏ��g��ł݂�̂͂ǂ����낤�H�g�߂Ȑl��X�̂��߂ɍv�����邱�Ƃ́A�������g�̐V���ȋ��ꏊ�̊l����K�����̎����ɂȂ�����̂ł���B
����肽�����Ƃ���͂��߂�w��
���݂̊w�Z�̎�Ȗ����́A�v�Z�╶�w�Ȃǂ̊�b�Ɖ��p�̏C�����B�������A�ŋ߂ł͕ʂ̃A�v���[�`���o�Ă��Ă���B���Ƃ��u�f�W�^���R�C������@����낤�v�ȂǁA1�l�ЂƂ肪��肽�����Ƃ��܂��ڕW�ɐ����A���̊����Ɍ������Ċ�b�m����X�L�����w�ԂƂ������̂��B�m���Ɋ�b�≞�p��ςݏd�˂Ă��Ȃ��䂦�̕s����g���u�����N���邪�A�����Ȃ�̎��H��AI������Ă���邾�낤�B�ڕW�B���܂ł̉ߒ��ł����ƒm�肽���Ǝv���A�C���^�[�l�b�g�ɂ͖����ő�w�̎��Ƃ���u�ł���d�g�݂��ł��Ă���B����A�w�Z�͊�����ׂĊw�Ԋ�b�P���ł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂪ��肽�����ƂɏW���ł���ꏊ�ɂȂ�B�����āA�W�c�����̒��Ől�Ԑ�����ނ��Ƃ���ȖړI�ƂȂ邾�낤�B
���قǂ悢�s��
�}�b�`���O�T�[�r�X�́A�����ɍ�����������Ă����B����͈ߐH�Z�Ɋւ��郂�m��T�[�r�X�ɂƂǂ܂炸�A�E�Ƃ̑I���A���ɂ͗F�l����l�T���܂ŁB�������͒Z�����ԂŁA��y�ɁA�~�����������ɏo����Ƃ��ł��A�����ɂ͖��ʂ��Ȃ��B�m���ɕ֗������A�u���ꂾ���ł����́H�v�ƍl����Ƌ^�₾�B���Ƃ��A�����̕�����I��ł��炤�T�[�r�X�𗘗p����ƁA�����ŃZ���X���A�܂��͔��f����͂������Ă͂��܂�Ȃ����낤���B���邢�́u���͍D�݂ł͂Ȃ����A������C�ɂȂ邩������Ȃ����́v�Ƃ̏o��̃`�����X�������Ă͂��Ȃ����낤���B���R�������N�������N���N���́A���ɕ֗����̏���䂭�B�قǂ悢�s�ւ��������ɂ͕K�v�Ȃ̂��B
���l�̗V�т��z���Љ�̊��
�f�W�^���Z�p�́A���퐶�������K�ɂ���u����̍H�v�v���ȒP�ɂ���B�O�o��̋C�ۏ���A�ڂ̑O�ŋN�����Ă���d�Ԃ̒x���A���邢�͂����������[���������ǂ��ɂ��邩�B1�l���u���ꂪ����Ζ������֗��Ŋy�����Ȃ邼�v�ƂЂ�߂��č�����T�C�g��A�v�����A�����Ƃ����ԂɎЉ�ɍL�����Ă��܂��̂��B�������g���u�����N����B��y�ɍ�����䂦�ɋN����A�v���̐v�~�X�ȂǁA������Ƃ����c���̊Â����v�������Ȃ����Ԃ������N�����Ă��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�����A����ȃ��X�N�������Ă��A�X�̂Ђ�߂������o���͂͂Ƃǂ܂�Ȃ��B����͐�����o�ς̐�����y�X�Ə��z���A�Љ���y�����������邾�낤�B
���u�Ԗ���
���̎��X�ŒB�����⎩���S�����u�u�Ԗ����v���A�����̃��`�x�[�V�����ƂȂ��Ă���B����SNS�Ŕ����邱�Ƃ����҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̒��S�ŁA���̂��߂ɁuSNS�f������v���X�g�����̃��j���[�◷�s�悪�I���قǂ��B���̔��ʁu�����͍����ԁv�̍����t�ƂƂ��ɁA�w�͂ƍ����ŏ��z����悤�ȃ��C�t�X�^�C�����ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă����B���⍂���Ԃ́u�R�X�p�d���v�̖��̉��ɁA�����Ȃ茎�z�ᗿ���ŏ���T�[�r�X���m�����Ă���B���ߓI�ɂ������邪�A�ނ�͎Љ�v���⎜�P�����ɂ�����������ΐϋɓI�ɎQ�����邵�A���ꂪ�Љ��ς���傫�ȗ͂ɂ��Ȃ�B�f�W�^���Z�p�͋�J�������A�u�ԓI�Ɋy���ރc�[���ɕϖe�������̂��B�@ |
 |
|
���f�W�^���Љ�����炷�ω��ւ̑Ή��@ |
���̒��̂��������(�Ɠd�A�����A�f��A�����ԁA�d�b�A�L�^�}�́A��ÁA�ݕ���)���f�W�^���ւƑ傫���V�t�g���Ă��鍡���A�Љ�̃f�W�^�����������炷�e����\�����A���肵���Ή������߂���͔̂������Ȃ��ɂȂ�܂����B�����ŁA��X�̃��C�t�X�^�C���A�r�W�l�X�̂����A�]�ɂ̉߂��������ɋN����ł��낤�ω����`�����X�Ƒ����āA����̕ω��ɒu������ɂ���Ȃ����߂̑Ή�����l���Č���ƈȉ��̂悤�ȃ|�C���g����������Ǝv���܂��B
(1)�f�W�^���������炷�ω���O�����ɍl����
�ƒ�Ŏg���A�ȂׁA���܁A�|�b�g�܂Ńf�W�^��������鎞��́A���ׂĂ̎Y�ƂɂƂ��đ傫�ȃ`�����X�ƂȂ�͂��ł��B������Ƃ̘b�ł�2005�N���ɂ́A���A�ƒ���\�����鐻�i�̂������Ȃ��Ƃ�30��ވȏオ�f�W�^��������邾�낤�Əq�ׂĂ��܂��B���̈Ӗ��ł͐����Ƃ����ʋƂ��A�T�[�r�X�Ƃ��A���炩�̃`�����X�����܂��ƑO�����ɍl����ׂ��ł��B���̃`�����X�����Ȃ̂��H�A���e�i���̂��ď������W���ׂ��ł��B
(2)�X���[�������b�g�̎���ω���F������
���m��蒆�S�̍H�Ɖ��Љ�ł́A�l�A���A���A���������Ƃ��K�����̂��펯�ł����B�������A�f�W�^�����Љ�ł́A�X���[���A�X�s�[�h�A�m�b�A����(�z����)�����ߎ�ƂȂ�Љ�ł��B���̈Ӗ��ł́A�ߋ��̐�������ɂƂ���邱�ƂȂ��A���m�̐V��������(�r�W�l�X)�ɂ��₭����ł���g�y�ȁA�l�⏬��Ƃɂ��傫�ȃ`�����X���߂��鎞��ł��B���̎���ω����͂�����ƔF�����鎖���d�v�ł��B
(3)�X�s�[�h�͍ō��̌o�c����
�f�W�^�����Љ�ł́A1������1�����炢�̊��o�ő�������X�s�[�f�B�Ȏ���ɂȂ�܂��B�܂�A�킩��₷��������5�l�ŒS�����Ă���悤�Ȏd���́A1�l�ŏ����o����悤�Ȏd���̐i�ߕ����H�v�ł��Ȃ��ƃf�W�^���Љ�ł́A���c����܂��B���̂Ȃ�A�f�W�^���Z�p�����x���p�A�X�s�[�f�B�Ɍ������p�o���Ȃ����ƁA��Ƃ͐��Ԃ��猩�̂Ă��邩��ł��B�����ɑς�����X�s�[�h���o�A�X�s�[�h�̂���o�c�����̂��߂ɂ��A�f�W�^���Z�p�ɐ��ʂ��܂��傤�B
(4)��Ƃƌl�Ɖƒ�̑�ω���F�m���܂��傤
�f�W�^���Љ�����炷�A�ő�̓����́A��Ƃƌl�Ɖƒ�Ƃ̊W��傫���ς���\��������Ƃ������ł��B�l�̓f�W�^���Z�p���g���āASOHO�ƌĂ�鎩�����[�g�I�t�B�X�Ŏd������Љ�ɂȂ�܂��B�����ł́A�g�D�����A�l����ł���Ƃ������l�ς֕ω����A����܂ł̂悤�Ȋ�Ƃƌl�Ɖƒ�̊W�ł͂Ȃ藧���Ȃ��������炩�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ȑ�ω����܂��F�m���āA������Ή�����������Ă����܂��傤�B
(5)���x��Ǝ��R���̃o�����X
���ꂩ��n�܂�{�i�I�ȃf�W�^���Љ�ɂ����ẮA����悤�ȏ��ƃX�s�[�h�d���̉��l�ς̒��ŁA�f�W�^�������Ɛl�Ԑ��̃o�����X�������₷���ɂȂ�܂��B�]���Ď��R�Ƃ̐G�ꍇ�����Ԃ��d�������A�S�̖�����A���ړI�Ȃ����������l�ԊW���傫�ȃe�[�}�ɂȂ��Ă��܂��B���̃e�[�}���ǂ̂悤�Ȍ`�Ŏ������Ă����̂��H��ڈ���̃`�����X�����ł��B
�@ |
 |
|
���f�W�^���Љ�����炷�}�C�i�X�ʁ@ |
|
�^�u���b�g��X�}�[�g�t�H���̕��y�A�𗬃T�C�g��e��A�v���̕��y�ɂ��A�����ł������ł����A���^�C���ɏ��A�N�Z�X�A��L���o����f�W�^���Љ�������Ă���B���ꂪ�����炷���̂̓v���X�ʂ����ł͂Ȃ��B�|�[���E���o�[�c���A���������u�w�Փ��x�Ɏx�z�����Љ�v�́A�~�]�ƏՓ��ɓ˂�������������҂ƁA�ڐ�̗��v�Ɗ�����ɒǂ��A�����r�W������l�ވ琬���Ȃ�������ɂ����ƂȂǁA����Љ�(���{��`�o��)�̊낤�����l�@�������Ђł���B�{���̓f�W�^���Љ�̃}�C�i�X�ʂɂ��Ă����y���Ă���B���̒������ۂɎc��b�������Љ��B
|
�������ȃR�~���j�e�B�͋ɒ[�ȕ����ɐi��
�V�J�S��w�̃L���X�E�T���X�e�B�[�����ɂ��ƁA
�u�����悤�Ȏv�l�̐l�X�̃R�~���j�e�B�́A�W�c�S���ɂ��l�������ɒ[�ɂȂ�A�قȂ�ӌ��Ɋ��e�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B���̗��R�́A�����悤�Ȏv�l�̐l�X�̃O���[�v�ɂ���ƁA�����̌����Ɏ��M�����Ă�悤�ɂȂ邩�炾�B
������Љ�̑����̖��ɂ��āA�l�͈�ʓI�ɋ����ӌ��������Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A������c�_�͂��Č��_���o���Ƃ�������ȍ�Ƃ��s���Ă��Ȃ����炾�B
���̌��ʁA�����̌����Ɏ��M�����ĂȂ��Ȃ�B�����玄�����͎��͂ɂ���l�̕��ϓI�Ȍ������̗p���Ď����̈ӌ����w�b�W����B����ƁA�l�X�Ȑl�ō\������鑽�l�ȃR�~���j�e�B�ł͎����̈ӌ��͒��S�ɋ߂Â��Ă����B
�������A�l�����̎��������̃R�~���j�e�B�ł͌l�͑��̑S���ƈӌ��������A����ɂ���Ď��M��������B�R���Z���T�X������ƁA�n�l�Ƃ�����Ƃ����Ȃ��Ƃ������̌������ǂ��ƍl����B�������A���M�����ɂ�M�O�͋��łɂȂ�B�����̏Ől�X�̈ӌ��͂��ɒ[�ɂȂ��Ă����v�Ƃ����B
���Ȃ킿�A�u�َ��ȃR�~���j�e�B�̓O���[�v�̍s���߂���}���邪�A�����ȃR�~���j�e�B�͋ɒ[�ȕ����ɓ˂��i�ށv�B
�C���^�[�l�b�g�̌𗬃T�C�g��f���ɂ́A���v�z�A�l�����������l�X���W�܂�R�~���j�e�B�[���`�������B�T���X�e�B�[�����̐��ɏ]���A���̂悤�ȃR�~���j�e�B�[��̈ӌ��͋ɒ[�ȕ����ɐi�ތX��������ƌ����邾�낤�B���ɃC���^�[�l�b�g�̏ꍇ�́A(�Ⴆ��Twitter�ɑ�\�����悤��)���̎��X�Ŏv���t�������Ƃ��A���̎��̊���ɔC���ē��e���邱�Ƃ����邩��A���̌X���͑��������\��������B�ߔN�A���{�̎Љ�͊��e�Ɨ]�T�������Ă����ƌ����邪�A���̗v���̈�Ƀl�b�g��̃R�~���j�e�B�̔��B���l������̂ł͂Ȃ����낤���B
�f�W�^���Љ�ł́A�����B�Ƃ͈قȂ�ӌ��ɂ������X���銰�e��������Ȃ��悤�A�������K�v�ł���B
|
���I�����C���ł̃R�~���j�P�[�V�������Ȃ������
�f�W�^���ł̌𗬂𐔏\�N�������Ă����Љ�w�҂ŗՏ��S���w�҂̃V�F���[�E�^�[�N�����ɂ��ƁA
�u���܂ł͂��ł����҂ƃR���^�N�g����邱�Ƃ��\�ɂȂ����̂ŁA�������͂�����ߏ�ɍs�������ŁA���Ƃ��킸���ȋ������Ă��ǓƂ������A�Y���ꂽ�Ɗ�����B�v
�u�f�W�^������ȑO�̐l�X�́A�N�����琔���Ԃ␔���ԁA���邢�͉��T�Ԃ��A�����Ȃ��Ƃ��C�|���肾�Ƃ͎v��Ȃ������B�������A�f�W�^������̐l�X�́A�����ɕԎ������Ȃ��Ɨ����������A�s���ɂȂ�B�v
����́A�Ⴆ�ALINE�Ɋւ����_�⎖����Web�Ō������Ă݂�Ε�����B�h���ǂȂ̂ɕԐM���Ă��Ȃ��h���Ƃ������ŁA���܂�g���u���ɔ��W���邱�Ƃ�����B�܂��A ���̎��̊���X�g���[�g�ɏo�Ď����ɔ��W���鎖��Ȃǂ�������B
|
��QLP (Quantitative Legal Prediction�F��ʓI�@�\��)
�uQLP�Ƃ͉f��}�l�[�{�[���ŕ`���ꂽ�싅�ɂ����铝�v���͂̂悤�Ȃ��̂ŁA���ٌ̕�m�ł̃v���Z�X�ł���v
�uQLP�̔w��ɂ���l�����̓V���v�����B����́A�ٌ�m�Ɉ˗������Ɩ��̂قƂ�ǂ͏����̗\���ł���A�Ƃ������̂��B�Ⴆ�A����̎��������Ƃɔ��f����ƁA�i�ׂ̌��ʂ͂ǂ̂悤�ɂȂ肻�����B�_�j�������m���͂ǂ̂��炢���B���̍ٔ����͂ǂ̂悤�Ȕ����������������B�v
�u���Ƃɂ��ƁA���ł����A�R���s���[�^�[��75%�̊m�x�Ŕ�����\���ł���Ƃ����B����ɑ��Đl�Ԃ̗\���̐��m����59%���B���̐V���ȘJ���͐ߌ��̋Z�p���{�i�W�J�������Ȃ��A�@���������͂�����g��Ȃ��Ƃ����I���͂ł��Ȃ����낤�B�v
�ٌ�m�̎d���ɂ͍��x�Ȑ��m���ƃX�L�����v������A�]���Ď���������Ɍ��������z�Ȃ��̂��Ǝv���Ă��邪�A�ٌ�m�̎d���̑������R���s���[�^�[�������肷������߂���������ė��邾�낤�B
�uAI(�l�H�m�\)�̐i�����l�Ԃ���d����D���v�Ƃ����ނ̘b���悭�������A����͕K�������ԈႢ�Ƃ͂����Ȃ��B�{���A�C�m�x�[�V�������N����ƐV���ȎY�Ƃ�d�������܂�A����ɔ����ĐV���Ȍٗp���n�o�����B�Y�Ɗv���ȍ~�̐����Ƃ�T�[�r�X�Ƃ̔��W(����т���ɔ����ٗp�̑n�o)���l����Ζ��炩���B
�������A������IT���p�̓������݂�ƁA�K���������̂悤�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B����́A��Ƃɂ�����IT�̗��p���A��Ƀv���Z�X�̃C�m�x�[�V�����ɗ��p����Ă�������ł���B
�v���Z�X�C�m�x�[�V�����Ƃ́A�]���̋Ɩ��v���Z�X��IT�Z�p�����p���邱�ƂŁA�d���̌����������A�K�v�Ȑl�I�������팸������g�݂ł���B�Ɩ��v���Z�X�̉��P�ɂ���Ă���Ɍg���v��(�R�X�g)����������B
�{���ɂ��A�v���_�N�g�C�m�x�[�V���������v���Z�X�C�m�x�[�V�������D�܂�闝�R�́A��Ƃ��Z�����v�Ɗ���(���嗘�v)���d�����邩��ł���B�v���_�N�g���x���̃C�m�x�[�V�����ɂ́A���E�����̎��g��(�����J����l�ވ琬)���K�v�ɂȂ�B����A�v���Z�X���x���̃C�m�x�[�V�����͔�r�I�Z���Ԃɐ��ʂ��o����B
�����̊�Ƃ́A�l�������𒆐S�Ƃ����R�X�g�팸�ɂ��Z�����v�̑��o��A���Њ������ɂ�銔���̈ێ��E����ȂǁA�ڐ�̗��v���d������X���������B�Z�����v�̒Nj����A���E�����I�Ȑ�����j�Q����Ƃ����W�����}�Ɋׂ��Ă���悤��(����͎�ɃA�����J��Ƃ̘b�ł��邪�A�������{�ŋN���Ă����Ƃ̕s�ˎ�������A���{��Ƃ������X���ɂ���ƌ��킴��Ȃ�)�B
|
���NjL 1
��L�u���O�L���ŁA��Ƃɂ�����IT�̗��p����Ƀv���Z�X�E�C�m�x�[�V�����ɗ��p����Ă������Ƃ��L�ڂ����B����ɂ���Đl����R�X�g�̍팸�͐i�ނ��A�V���Ȍٗp�̑n�o�͖]�߂Ȃ����Ƃ��L����(�V���Ȍٗp�ݏo���̂̓v���Z�X�E�C�m�x�[�V�����ł͂Ȃ��A�v���_�N�g�E�C�m�x�[�V�����ł���)�BIT�����p���郆�[�U�[��Ƃ̒c�̂ł�����{���V�X�e���E���[�U�[����(JUAS)���A�u���IT��������2018�v�\�����B����ɂ��ƁA�uIT�����ʼn����������������I�Ȍo�c�ۑ�v�̃g�b�v�́A�u�Ɩ��v���Z�X�̌�����(�ȗ͉��A�Ɩ��R�X�g�팸)�v��27.3%(2017�N�x��������5.8�|�C���g����)�ƂȂ��Ă���B�ߔN�A�J���͕s����z���C�g�J���[�̐��Y������A���邢�̓��[�N���C�t�o�����X�Ȃǂ������ɋ���AIT���Ɩ��v���Z�X�̌������ɗ��p����X�����v�X���܂��Ă���B�Ɩ��v���Z�X�̌������Ɏ�����Z�p�̂Ȃ��ō���ԃz�b�g�Ȃ̂�RPA(���{�e�B�b�N�E�v���Z�X�E�I�[�g���[�V����)���낤�BIT�n�̃��f�B�A�����Ă��Ă��ARPA�̎����ARPA������ۂ̒��ӓ_�A�Ȃǂ̋L���������Ƒ����Ă���B
���NjL 2
�u����1���~���������l�̖��H�v(��ؐM�s�A���oBP��)�Ɂu�������́v�Ɋւ���w�E������B���{�͋ɂ߂ē�������(�݂�ȂƓ������Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���b�V���[)�������B���x�˕F���́A���̗��R�̈�ɁA�����̐l�����w�Z���w�N���璆�w�Z�ɂ����đ̌�����W�c����������Ƃ����B�N���X�̒��͂������́h�r���I�W�c�h�ɕʂ�A�q�ǂ������͂����ꂩ�̑g�D�ɑ����Ȃ���Ε��a�Ȋw�Z�����𑗂�Ȃ��B���肵�ďW�c�ɑ����邽�߂ɂ́A�Ƃɂ�������Ɠ����ł��邱�Ƃ��v�������B����ƈႤ�Ƃǂ�ȂЂǂ��ڂɑ������A���̎��������̐l�͖��ӎ��̂����ɑ̂ɒ@�����܂�ĐN�����}����B�������͂͐l�X�̃X�g���X�ɂȂ��Ă���B����ɂ��̓������́A�Q�ꂽ����C������Ƃ̐��Y����j�Q����v���ɂ��Ȃ��Ă���B���{�̊�Ƃ͖��ʂȉ�c���������A����͉�c��ł����킹�Ə̂��ČQ��邱��(�ӔC�U���邱��)���D�ނ��炾�Ƃ����B�݂�Ȃ��������Ă�����v�V�I�ȃA�C�f�A�Ȃǂ����܂�Ă��Ȃ����낤�BSNS�Ȃǂ̃l�b�g��̃T�[�r�X�𗘗p����l�����������ƂŁA���̓������͂����܂��Ă���Ƃ����B�l�b�g��ɂ������̔r���I�W�c���`������A����W�c�ɑ�����l�͂��̏W�c�̍l�����ɓ�������悤�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ��낤�B��Ɉ��p�����u�����ȃR�~���j�e�B�͋ɒ[�ȕ����ɐi�ށv�Ɠ��������ł��邪�A���ꂪ����̓��{(����)�̓���(���_)�ł���Ƃ����w�E�͏d�v���B
���NjL 3
�f�W�^���Љ�����炷���̑��ʂɊւ��āA���̏��Ђ���̈��p��NjL����B
�������I�m���̌���
�u�N���E�h����̎v�l�p�v(�E�B���A���E�p�E���h�X�g�[���A�y��)�Ɉȉ��̎w�E������B�u�m����m�\�֕ω������邽�߂ɂ́A��ɕ�����ߑ����邱�Ƃ��K�v�ł���B�C���^�[�l�b�g�̒m�����댯�Ȃ̂́A���������S�ɔ����Ƃ��Ă��邱�Ƃ��B�v ���X����Â炢���������A(�����v����)�C���^�[�l�b�g��̒m�����f�ГI�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă���̂��낤�B�Ⴆ�A���錾�t(�T�O)�𗝉�����ɂ́A����Ɗ֘A����T�O��A���j�I�w�i�A�����I�w�i�Ȃǂ��������Ă����Ȃ��Ƒ̌n�I�Ő��m�Ȓm��(�m�\)�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��낤�B
�������I���m
�������A�u�N���E�h����̎v�l�p�v�Ƃ������Ђɂ́u�����I���m�v�Ɋւ��錾�y������B���ł��ǂ��ł��X�}�z��������Ώ����擾�ł���悤�ɂȂ�ƁA�V�������t��T�O���o����K�v���������Ȃ��Ȃ�B��X�̔]�͖��ӎ��̂����ɁA�킴�킴�]�ɋL�������Ȃ��Ƃ��A�K�v�Ȏ��Ƀl�b�g������o���Ηǂ��ƍl����悤�ɂȂ�悤���B
���E������ʂƋ����͒ቺ
�u�A�i���O�̋t�P�v(�f�C�r�b�h�E�T�b�N�X�A�C���^�[�V�t�g)�ɂ��A���݂̃A�����J�ł͎�҂́u�����́v���������ቺ���Ă���Ƃ����B���̎�ȗ��R�Ƃ��āA�f�W�^���e�N�m���W�[�́u�E�������(�h���ɑ��銴��A���o���݉����邱��)�v����������B�����I�Ȑl�Ԃ̌����͐[���Ȏ��Ԃ������B���ȓ����I�A���Ȓ��S�I�Ȑl�Ԃ������A���͓I�Ȑl�Ԃ�����A�\�͓I�X�������܂�A�ƌx�����Ă���B
�������i���̊g��
�������A�u�A�i���O�̋t�P�v�ɂ��A�u�f�W�^���o�ς�2�̐E��ݏo�����Ƃɒ����Ă���B1�͎Љ��w�̍������̍��x�Ȑ��E�A����1�͎Љ�̒�ӂ̒�����A��X�L���̎d���B���̌��ʂƂ��ċN����̂́A����Ȃ�i���̊g�傾�B���Ăł�1992�N����2010�N�ɂ����Ē����X�L���̌ٗp�������������ŁA���X�L���ƒ�X�L���̎d���͑����Ă���v ���{�ł����̌X����������B�R���r�j��O�H�Y�Ƃł͒�����̊O���l�J���҂��������Ă���B����͉��Ȃǂ̕���ł��O���l�J���҂̑����������܂�Ă���B���{�̏ꍇ�A��Ȍ����͐��Y�N��l���̌����ɂ��邪�A�f�W�^���Љ�ɂȂ��č������̐E��ƒ�����̐E��̊i�����L�����Ă���\���͂��肻�����B
���u�A�i���O�̋t�P�v(�f�C�r�b�h�E�T�b�N�X�A�C���^�[�V�t�g)
(�A�����J�ł�)�������̕���ŃA�i���O�̗ǂ�����������A�ĕ]�������Ƃ������ۂ�������B���R�[�h��A�^���Z�p(�A�i���O�^��)�A�ʔň���A�ʐ^�t�B�����A�{�[�h�Q�[���ȂǁB(�{����ǂ���ł�)�����A�i���O�̕����͔N�z�҂̉��Î�ł͂Ȃ��B�����̃A�i���O�̎x���҂ɂ͎�҂������Ƃ�������������A��ɃN���G�C�e�B�u�Ȋ����ɂ����ăA�i���O�̗ǂ�����������Ă���悤���B�l���Ă݂����͂���������O�̂��Ƃ��Ǝv���B�Ȃ�ł��f�W�^�����ǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ����낤�B�f�W�^���A�A�i���O���ꂼ��ɗǂ��Ƃ��낪����A�K�ޓK���Ŏg�������Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B
�@ |
 |
|
���f�W�^���Љ�ɋ��߂���l�Ƒg�D�Ƃ́@ |
���f�W�^���Љ�Ƃ�
�f�W�^���Љ�ɂ��āA�l�ɂ���đ������͈قȂ���̂́A��܂��Ɍ����A���A���ȁu���m�v��u�T�[�r�X�v���u�f�W�^����(����)�v���邱�ƂŐV�������Ɖ��l�����ݏo����A�����A�Y�ƁA�l�Ԃ̃��C�t�X�^�C������ς����Ă����Љ�ƒ�`���邱�Ƃ��ł��܂��B
���̏o���̌����͂͋ߔN�̃e�N�m���W�[�ł��B�Z���T�[��f�o�C�X�̋Z�p�i���̓��A���ȎЉ�̏�Ԃ��f�W�^���������A�����ʐM�A��������f�B�X�N�̑�e�ʉ��ɂ���āA�����̃f�W�^�������r�b�O�f�[�^�Ƃ��Ď��W���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂����B�X�ɁA�R���s���[�^���\�̌���ɂ��c��ȃr�b�O�f�[�^�̉�͂��\�ƂȂ������ƂŁA�f�B�[�v���[�j���O�Ȃǂ�AI�Z�p�W���Ă��܂����B���̂悤�ɁA�f�[�^�����p�����Y�Ɗv�����i�s������܂��B
|
���f�W�^���Љ�ɋ��߂���V���Ȏd�|��
�f�W�^���Љ�́A���l�ȏW�c���Ȃ��邱�ƂŐV���ȉ��l���n�o����Ă����Љ�ł��B�����ŋ��߂���d�|�����u�I�[�v���C�m�x�[�V�����v�ɂȂ�܂��B�I�[�v���C�m�x�[�V�����͑傫���ȉ���4�̗v�f���琬��܂��B
���r�W�l�X���f��
�e�N�m���W�[�C�m�x�[�V���������ł͂Ȃ��A�e�N�m���W�[�����p���Ď��Ɖ��l���グ�A���v���f����ϊv���邱�ƂŐV���ȃr�W�l�X�����܂�܂��B
���G�R�V�X�e��
��w�A���I�@�ցA��Ƃ��Ȃ��莑����`�x�[�V�������z����d�g�݂��d�v�ƂȂ�܂��B���̏z�̒��ŁA�ĂѐV���ȃe�N�m���W�[�����ݏo�����Ƃ��������̃T�C�N�����f�W�^���Љ���x���܂��B
���J���v���b�g�t�H�[��
�f�W�^���Љ�̓X�s�[�f�B�ɕω����A���l�ݏo�����߂̃e�N�m���W�[���ǂ�ǂ�i�����Ă����܂��B���r�q�ɗ����グ����ƌڋq����̃t�B�[�h�o�b�N���X�s�[�f�B�Ɏ�d�g�݂��K�v�ɂȂ�܂��B
���f�[�^�v���b�g�t�H�[��
�f�W�^�����̖{���̓f�[�^�ł��B�f�[�^�����p����d�g��(���W�A���́A���p)������ɂ���A���ɖc��ȃr�b�O�f�[�^����͂���f�[�^�T�C�G���X���ł��d�v�ƌ����܂��B
|
���f�W�^���Љ�ɋ��߂���g�D�Ɛl
�f�W�^���r�W�l�X�́A�����̃r�W�l�X�`�ԂƈقȂ镔���������A�]���̑g�D����V���ȑg�D�ւ̕ω������߂��܂�(�\1)�B
�@�@�@�\1�@�]���̑g�D�ƃf�W�^���Љ�ɋ��߂���g�D�̓���
�]���̑g�D�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f�W�^���Љ�ɋ��߂���g�D
�ӔC��KPI�ɂ��c����g�D�@�@�@ �t���b�g�ŃI�[�v���ȏW����
�Ȗ��Ȍv��^�E�H�[�^�[�t�H�[���@�_��ȑΉ��^�A�W���C��
�}�X�}�j���t�@�N�`�������O�@�@�@�}�X�J�X�^�}�C�[�[�V����
�������d���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�����d��
���m�v�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̌��v�l
�R���g���[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
���m���A��ꐫ�@�@�@�@�@�@�@�@�\�t�g�X�L���A���l��
��ɏq�ׂ��悤�ȃI�[�v���C�m�x�[�V�����𐄐i����l�ނƂ��āA�u�f�W�^���r�W�l�X�f�U�C�i�v�A�u�f�W�^���G���W�j�A�v�A�u�f�[�^�T�C�G���e�B�X�g�v�����߂��Ă��܂��B�O�ʈ�̂̃`�[����Ґ����A�������邱�Ƃ��ł���Ζ����̃f�W�^�����Љ�W�����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
���f�W�^���r�W�l�X�f�U�C�i
�f�W�^���r�W�l�X����悵���i���Ă����l�ށB�r�W�l�X�f�U�C���͂ɉ����Čڋq�̌��̃f�U�C���͂����߂��邽�߁A��������A�ώ@�͂⓴�@�͂�{���P�����K�v�ɂȂ�܂��B�X�ɁA�G�R�V�X�e�������グ�邽�߂̎Г��O�̗L���҂Ƃ̃R���{���[�V�����͂�t�@�V���e�[�V�����͂��g�ɕt����K�v������܂��B
���f�W�^���G���W�j�A
�f�W�^���������p�����d�g�݂�V�X�e���\��(�A�[�L�e�N�`��)��v���A�������Ă����l�ށB�Z�p�͂ɉ����āA�v����c�����邽�߂̌ڋq�̌��̗���͂�l�Ԓ��S�̃f�U�C���͂��K�v�ƂȂ�܂��B
���f�[�^�T�C�G���e�B�X�g
�f�W�^���f�[�^����Љ�ۑ�̌�����r�W�l�X���x���̗v�f�Ȃǂ��o�����߂ɁA�f�[�^���͗͂ɉ����ăr�W�l�X����ŕ����𑨂���͂��K�v�ƂȂ�܂��B
|
���Y�w�A�g�ɂ��l�ވ琬�̎d�g��
���̂悤�Ȑl�ނ͂ǂ̂悤�Ɉ琬����悢�ł��傤���B�����Ń|�C���g�ƂȂ�̂��Y�w�A�g�ł��B�f�W�^���G���W�j�A�́A�]���̈琬�̘g�g�݂𑽏��ύX����ΑΉ��ł���Ǝv����̂ŁA���̑��f�W�^���r�W�l�X�f�U�C�i�ƃf�[�^�T�C�G���e�B�X�g�̑��ʂ���l���܂��B
��1�f�W�^���r�W�l�X�f�U�C�i
���܂Ńf�U�C���X�N�[���Ȃǂ̃f�U�C�����̋���@�ւ������āA�ڋq�̌��@����\�͂�C�m�x�[�V�������N�����\�͂��ӎ��I�ɋ��炷��ꏊ�͋ɂ߂ď��Ȃ������Ǝv���܂��B�ŋ߂ł́A��Ƃł��f�U�C���v�l���܂߂��C�m�x�[�V�������炪�������{�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�܂��A�w�Z�ł��A�N�e�B�u���[�j���O�Ƃ����X�������炪���s����Ă��܂��B�������A�C�m�x�[�e�B�u�Ȑl�ނ��琬����ɂ́A�v�l�P�����s����Ƒ̌n�������v���O�������K�v�ł��B�̌n���������_�������ł����w�Ǝ��ۂɃC�m�x�[�V�������N�������Ƃ��Ă����Ƃ̋��͂����߂��Ă��܂��B
��2�f�[�^�T�C�G���e�B�X�g
���{�̓f�[�^�h���u���̍l���������t���Ă��炸�A���{�̎Љ�ɂ͐����I�Ȏv�l��f�[�^���́E���p�����f�[�^�T�C�G���e�B�X�g���ɂ߂ď��Ȃ��ƌ����܂��B��w�ł͎��r�W�l�X�Ŏg���r�b�O�f�[�^����肵�ɂ����Ƃ����ۑ肪�������A��Ƃł́A�����I�ȃ��f����A���w�A���v�w������ł���l�ނ��ɂ߂ď��Ȃ��Ƃ����ۑ肪����܂��B���݂��̉ۑ����������̂��Y�w�A�g�̊̂ɂȂ�܂��BCTC�ł��A�f�[�^�T�C�G���X����̐l�ވ琬�y�юY�w�A�g���i��ړI�Ƃ��Ď����w�ƘA�g���͂̋����������A�f�[�^�T�C�G���e�B�X�g�̈琬�ɓw�߂Ă��܂��B
�@�@�@�ۑ�����̂��߂̎Y�w�A�g���f��
�����̃f�W�^���Љ���̂���L���ȎЉ�ƂȂ邽�߂ɁA�I�[�v���ȋ��͂̂��Ƃʼn��l�̑n����}���Ă������Ƃ��A�������ɍ��K�v�Ȃ��Ƃł��B
�@ |
 |
|
���f�W�^���Љ��"����"�}�[�P�e�B���O�@ |
�f�W�^�����̐i�W�ɔ����A��Ƃ���芪���o�c�����傫���ω����Ă���B�����������A�V���Ȏs����J�����߂̕���ƂȂ�̂��f�W�^���}�[�P�e�B���O���B�������A���l���E���G�����郆�[�U�[�̓��������݁A�I�m�Ȏ��ł̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�ł́A��Ƃ̓f�W�^���}�[�P�e�B���O�Ƃǂ����������悢�̂��B���̓�����T�邽�߁A�f�W�^���}�[�P�e�B���O�̐��ƏW�c�ł���A�C���b�v�Ŏ���В��߂�i��֎��ɘb�����B
�p�\�R����X�}�[�g�t�H���Ȃǂ̕��y���̍��܂�ƂƂ��ɁA�����҂̃��f�B�A�ւ̐ڐG���@���ω����Ă���B���f�B�A���������̒����ɂ��ƁA���f�B�A���ڐG���Ԃɂ����郂�o�C���̃V�F�A���L���B�����ł�2018�N�ɏ��߂�3����1���A���o�C���V�t�g�������ɐi�s���Ă���Ƃ����B
�@�@�@���f�B�A���ڐG���Ԃ̍\����
�i�䎁�͎��̂悤�ɉ������B
�u����́A�f�W�^���Љ�̓����ɂ��A���[�U�[�̓����I�ȕω��ł��B���f�B�A�����������w���f�B�A�����t�H�[����2018�x�Ŕ��\���Ă����悤�ɁA���o�C���̎g�������ω����Ă��Ă��āA�]���͎����Ō������Ĕ\���I�ɏ������W���Ă��܂������A���o�C�����̂�������ʂ̏��������Ă��钆�ŁA�C�ɂȂ�����A�X�N���[���V���b�g�ŕۑ�������A���c�C�[�g�����肵�āA�ォ��m�F����̂��ʗ�ƂȂ��Ă��܂��B�܂�A�u�Ԃ��ƂɐG���������߂Ă����āA���ł�������悤�ɂ��Ă����B���[�U�[�����܂��܂ȍH�v�����āA���ӂ����Ƃ��܂��t�������X�^�C�����L�����Ă���̂ł��v
���o�C�����g�����w���s���ɂ��ω����N���Ă���Ƃ����B
�u�Ⴆ�A���X�܂ŏ��i���Ƃ��A�����߂��̃��[�U�[���X�}�z���g���ēX������������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�X�܂ɂӂ���Ɨ������̂ł͂Ȃ��A���O�ɃX�}�z�ŏ��i�����邩�ǂ������x���ȂǂׂēX�܂ɍs���Ƃ����P�[�X�������Ă���̂ł��v
|
���d�v�Ȃ̂̓��[�U�[�𗧑̓I�ɑ������邩�ǂ���
�ł́A�����������[�U�[�s���̕ω��ɑ��A��Ƃ͂ǂ��Ή����Ă���̂��낤���B
�u�\���ɑΉ��ł��Ă����Ƃ͂܂��܂����Ȃ��Ǝv���܂��B���[�U�[���A���A�ǂ�����A�ǂ�����Ď��Ђ̏��i��T�[�r�X�ɐڐG���Ă���̂��A�ǂ݂Â炭�Ȃ��Ă��܂��B�X�܂ȂǁA�]���̔̔��|�C���g�Ƀ��[�U�[������Ă���O��̍s�������G�ŁA����͂���ɂ͍ŐV�v���Z�p�ւ̗������K�v�ł��B����ɁA�v�������Ƃ��Ă��Ӗ���ǂݎ��ɂ́A���Ђ̃f�[�^�����ł͑���Ȃ����Ƃ������̂�����ł��B�ǂݎ��s���̂܂܁A���[�U�[�Ɉ��ՂɐڐG����ƁA���ߑ��̎���ɂ����Ă͖�������܂��B�����������ۂ��]���̃}�[�P�e�B���O��@������������v���ƂȂ��Ă��܂��v
�]������A���[�U�[�̉��l�ς͑��l���E���G�����Ă���Ƃ����Ă��邪�A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�s����ڐG�l�������l���E���G�����Ă���Ƃ����B�����炱���A���[�U�[�𗧑̓I�ɑ������邩�ǂ������d�v�Ȃ̂��B�����Œ��ڂ���Ă���̂��f�W�^���}�[�P�e�B���O�ł���B
|
���f�W�^���}�[�P�e�B���O�ʼn������Ă����ׂ��|�C���g
�u�f�W�^�����̐i�W�ɂ���āA���[�U�[�̑��ʐ����������ă}�[�P�e�B���O�������s�����߂ɂ́A��Ɠ��O�̃f�[�^�����Ȃ���Ȃ�܂��A���ꂪ���Ƃ̂ق�����̂ł��B�Ⴆ�A�e���r��X�}�z�A�X�܁AEC���[���ȂǁA���܂��܂ȃ`���l�������钆�A��C�ʊтŘA���������đΉ��ł���悤�ɂ��āA���̂Ȃ���̒��ŁA�ǂ������z�����āA�����Ƀ��[�U�[�ƌ������������l����ɂ́A��啔���̋@�\�ڕW���āA��ƑS�̂̐헪�ɗ��Ƃ����܂Ȃ���Ȃ�܂���B�������Ȃ���A�f�[�^�����ƂȂ����u�ԁA�W����������ɂ킽��Ƃ������Ƃ�����A�����Ԓ�������q����P�[�X���悭�q�����܂��v
�f�W�^���̐��E�͋Z�p�̐i���̃X�s�[�h���������߁A�e��啔���ł̃f�W�^�����ł���܂܂Ȃ�Ȃ��ꍇ�������A�S�̍œK�_�ƕ����œK�_�̃o�����X������B
�u�f�W�^���Љ�������钆�ŁA�����͑��Ђɐ�삯�ĐV���ȍL����@���p��S���Ă�����Ђł��B���ꂩ��͍L����@�ɂƂǂ܂�Ȃ������̎�@��g�ݍ��킹�邱�ƁA���邢�̓f�W�^���̘g�g�݂̒��ŏI���̂ł͂Ȃ��A��@���p���I�t���C���̈�܂ōL���邱�ƂŁA�g�[�^���ŃN���C�A���g�ɍv���ł��铝���f�W�^���}�[�P�e�B���O�̃R���T���e�B���O�T�[�r�X����Ă����܂��B�V�X�e���̊J���E��͂⎩�ГƎ��̃}�[�P�e�B���O���W�b�N���A�c�ƕ���x���ȂǁA���L����@���p�\�͂������ƂŁA�}�[�P�e�B���O�}�l�W�����g���ĕҁE���x������ׂ��N���C�A���g�ɕ������Ă܂���܂��v
|
�������悤�ɂ���Ă̓Q�[���`�F���W�̃`�����X
�C���^�[�l�b�g�L���s��ɎQ�����Ĉȗ��A�f�W�^������ɍ������g�D�ɉ��҂��Ă������ŁA�N���C�A���g�Ɠ����悤�ȔY�݂ɒ��ʂ��A�Ǝ��ɉ������Ă����o�܂�����B�����Ŕ|�������\�͂Ɠ������̃m�E�n�E���A����N���C�A���g�ɒ��Ă������j���Ƃ����B
�u�����̓����́A�f�W�^���I�y���[�V�����̎������킩���������ŁA�헪�����������g�[�^���T�|�[�g���ł��邱�Ƃł��B����ɁA�O���[�v��ƑS�̂Œ~�ς����c��ȃf�[�^����Ɛ헪�ɓ]�����A��������h��������p���m���Ɏ��s����\�͂������Ă��܂��B����A�f�[�^�Ɠ��]�A�����Ęr�͂����˔����Ă��邱�Ƃ��傫�ȋ��݂ɂȂ��Ă���̂ł��v
������̒��Ɋ��͂ތ���ł���Ƃ������Ƃɋ^����������ޗ]�n�͂Ȃ����낤�B�A�C���b�v�́A���̏���ނ��Ƃ������Ӗ��Ŏh���ł���悤�ȃ\�����[�V��������������Ђ�ڎw���Ă���Ƃ����B
�u���[�U�[�����̑��l���E���G�����͂��߂Ƃ���A��Ƃ���芪���o�c���̕ω��́A�o�c�҂�Y�܂��܂��B�������A�����悤�ɂ���Ă̓Q�[���`�F���W�̃`�����X�ł�����܂��B���j�����Ă��A�Q�[���`�F���W���ł��鎞��͂���قǕp�ɂɂ͖K��܂���B�f�[�^�ɂ���Ă�������̂���������悤�Ƃ��Ă��钆�ŁA��ʂ̍œK�����������邽�߂ɂ��A�N���C�A���g�̐V���Ȓ�����T�|�[�g�ł��鑶�݂ł��葱�������Ǝv���Ă��܂��v�@ |
 |
|
���f�W�^���Љ�ƃf�W�^�����̉��l�@ |
���T.�f�W�^���Љ�̓���
�������N�ŎЉ�̃f�W�^�����͂��̂����������Ői��ł��܂��ˁB
�d�Ԃ̒�������A�قڑS�Ă̐l���X�}�[�g�t�H����������Ă���AFacebook�Ȃǃ\�[�V�������f�B�A�ŗF�B�̋ߋ���m���Ă���B�����̃A�v���P�[�V�����Ŏ����ɓK�����L��������ƂȂ��u����A�Ƃ���Amazon�Œ��������̓��Ƀ��m���͂��B �Љ������A�f�W�^�����̑��x�͑����̐l�̑z������X�s�[�h�ŐZ�����Ă��Ă���B
����ɁA�X�}�[�g�E�H�b�`��X�}�[�g�O���X�Ȃǐg�ɕt����@������l�����AIoT(���m�̃C���^�[�l�b�g��)���i�ނƁA�l���f�W�^�������Ȃ��Ă����m�����M����悤�ɂȂ��Ă���B
�ʋ̍ہA�d�Ԃ̒��Ńf�W�^�����̐i�W��ڂɂ���킯�ł����A���āA��Ђɓ���������A�ǂ̂悤�ȃf�W�^������ڂɂ���ł��傤���H
���ނ̑��A�N���ɗ��Ă��ڕW(�ǂ��܂ŒB���ł������ǂ��킩��Ȃ�)�̓\�莆�A�Ȃ��Ȃ��~�����f�[�^�ɒH����Ȃ��Г��V�X�e���A�������u���Ă��邨�q�l��Г��W�҂Ƃ̃��[���B
��Ƃ̒������Љ�̂ق�����Ƀf�W�^�������i��ł���Ƃ����̂������ȂƂ���ł͂Ȃ��ł��傤���B �t�Ɍ����A��Ƃ��f�W�^�����̉��b����]�n���傫���Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
|
���U.�f�W�^�����̉��l
IT�Ɋւ����ł��ƃf�W�^�����̉��l�͗�������Ă�����������Ǝv���܂��̂ŁA���̂悤�ȕ��͂��͓̏͂ǂݔ���Ă��������B
�f�W�^���������Ɖ����ǂ��̂��A�Ƃ����ƁA1�����������A2�������Ă����Ȃ��A3���͂ł���(���ɗ\�����ł���)�Ƃ������_�������Ƃ��ċ������܂��B���̂悤�ȓ��������ƂɁA4�������A5�ʑΉ����A6�f�[�^���p�r�W�l�X�Ȃǂ̃r�W�l�X�ւ̓K�p�̉\��������܂��B
��̓d�Ԃ̒��̗�ł������A�l�ʂ̍L���Ȃǂ͕�����₷���Ⴞ�Ǝv���܂��B �A�i���O�̐��E�ł���A�`���V������ĐV���ɋ���ŎT���Ƃ������`����ʓI�ł����B �f�W�^��������邱�ƂŁA�z�M�R�X�g0�~(���m�ɂ͈قȂ�܂����X�I��)�A�l�ʁA�����z�M�A�N���b�N�L�^������̂Ōڋq�����ʂ̎u����X���̔c���Ȃǂ��ł��܂��B
IoT(���m�̃C���^�[�l�b�g��)�̎���ɂȂ�A�l���o�^�����f�[�^�����łȂ��A���m���̂��f�[�^�M���܂��B�܂��A���m�ɑ��Ďw�����o�����m�̓����𐧌䂷�邱�Ƃ��ł��܂��B
���̒��̕����I�ȃ��m����������f�W�^���̐��E�Ƀf�[�^�����A���������A�����A���͂��s���A�l��m�ɑ��Ďw�����o���Ă������ƂŁA�V�����r�W�l�X�̐i�ߕ���V�����r�W�l�X���f����z�����Ƃ��ł���\��������܂��B |
���V. �f�W�^���̋���
�Љ�̃f�W�^�������i�ޒ��ŁA�f�W�^���̉��l���ő�ɗ��p����V����Ƃ������Ă��܂����BUber�Ђ�Aribnb�Ђ̗�͗ǂ��m���Ă��܂�(�ڂ����́u���A���{�ɋ��߂���ϊv�̗́v��������������)�B�܂��R�}�c�Ђ̗���������グ���Ă��܂��� (�ڂ����́u����g���b�N�́u���ׂāv��24���Ԍ����鉻�v��������������)�B�����ԋƊE���傫���ς���Ă��Ă��܂� (�ڂ����́u�Ȃ���N���}���V���ȉ��l�������炷���オ�����v��������������)�B
�^�N�V�[�ƊE�A�z�e���ƊE�Ȃǂ�BtoC�̋ƊE�ɂ����āA�f�W�^�������p������Ƃ��ƊE�̍\�}��ς��ABtoB�̋ƊE���ς��悤�Ƃ��Ă���B
�f�W�^��������������������������Ƃ��A�ƊE�̊_�����A�V�������l������A�s���Z���ŐȌ����Ă��܂��Ƃ����傢�Ȃ�ω��̎��ゾ�Ǝv���܂��B
�@�@�@�����ƊE����Q������鋺��
�@�@�@���ڋq�̉��l���ς����鋺��
�@�@�@���s���Z���ԂɐȊ�����鋺��
|
���W. IT�ƃf�W�^���̈Ⴂ
���āA�����܂Ţ�f�W�^����Ƃ������t���g���Ă��܂������AIT�Ƃ͂ǂ̂悤�ɈႤ�̂ł��傤���H
�w��{�I�x�ɂ͈ꏏ�ł��ˁA����܂ł̕��̢͂�f�W�^�����IT��ƕϊ����Ă���a�����Ȃ��ł��傤�B�w��{�I�x�ɂ͈ꏏ�Ȃ̂ł����A���͑傫�ȈႢ������܂��B
����܂ł�IT���́A�l���s���Ă����L�^��W�v�̋Ɩ��̎����������l�ł����B ���ƃ\���o���̑�֕i�ł��BIT���Ȃ��Ă������̐l���w�͂���Ύ����ł��鐢�E�ł����B �܂��A�����̐l��IT�Ƀf�[�^���͂����āAIT���痘�v��l�͌����Ă���Ƃ����̂�����ł����BIT�p��ł́ASystem of Record�Ƃ��Ăт܂��B
���܋N���Ă���f�W�^�����́A�l���w�͂��Ď����ł��鐢�E���Ă��܂��B 1�����������A2�������Ă����Ȃ��A3���͂ł���(���ɗ\�����ł���)�A4�������A5�ʑΉ����A6�f�[�^���p�r�W�l�X�B�����̓����́A�l�̓w�͂̈���Ă��܂��B �܂��A�V�X�e���ɂ���v�҂������A�V�X�e���Ɛl���ꏏ�Ɋ������邱�Ƃ���ʓI�ɂȂ�܂��BIT�p��ł́ASystem of Engagement�Ƃ��Ăт܂��B
�w��{�I�x�ɂ͈ꏏ�ł����A�f�W�^���͂���܂ł�IT�Ƃ͈�����悷�T�O�Ƃ��đ����Ă��������Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�@ |
 |
|
���l�̂��߂̃f�W�^���Љ�@ |
2017�N11���ɏÓ�c��a�@�Ƃ������O�̕a�@���c��`�m��w�Ó쓡��L�����p�X(SFC)�̗אڒn�ɊJ�@�����B�אڒn�Ƃ����Ă���������������w���A��������w���A��w�@�ƊŌ��Êw���̊ԂɈʒu���Ă���̂ŁA�n������s�Ƃ��A�g����SFC�Ƃ̋���������a�@�̗��O�Ƃ��Čf���Ă��������Ă���B����a�@���ł��鏼�{���v�搶�Ƌc�_���A�䂪���̉ۑ�ł���ݑ��Â≓�u��Âւ̍v����A�g�e�[�}�̈�Ƃ���2�N�O���珀���Ɏ��g��ł����B�䂪���ɂ����鏭�q������Ô�̉ۑ�͐[���ł���A�ݑ��Â����̌��̈�ł��邱�Ƃ͋c�_�̗]�n���Ȃ��B���������̐[�����͓x�𑝂��Ă���̂ŁA�f�W�^���Z�p�ɂ��C�m�x�[�V�����A����A�v���I�ȉ��P���v������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��߂ɂ́A�l����l���Ƃ��������I�Ȍ��N�Ǘ��A�Ƒ���R�~���j�e�B�ƒn��A��Â���Ȃǂ��A�a�@�Ȃǂ̐��{�݂ƌ���ŘA�g��������C���^�[�l�b�g��ɍ\�z����K�v������B���̂悤�ȃV�X�e���̗��z���ɂ͊��ɎЉ�̒��ň��̃R���Z���T�X������ƍl���Ă���B
�T�v�Ƃ��ẮA�u���[�h�o���h�C���^�[�l�b�g��O��Ƃ��āA��l���Ƃ��̐M����Ƒ���w���p�[�A���t�A�Ō�t�A��҂Ȃǂ̃R�~���j�e�B�ƃR�~���j�P�[�V�������ł��ċL�^����Ă��邱�ƁB�����ƁA�A�㎖�̐��҂��f�W�^���f�[�^�Ƃ��̋��L�ɂ���Ď�l���̌��N�̂��߂ɍ�Ɖ\�Ȋ����\�z���邱�ƂȂǂł���B�����������������̂Ȃ�A���̂��߂̊�b�Z�p��T�[�r�X�A�v���P�[�V�����̑̌n�͂�����Ă���B�ƒ�ɂ͌��N�����j�^�[���邽�߂́AIoT(Internet of Things)�f�o�C�X�Ƃ��Ă̌��N�����A��l���Ƃ��̂܂��̃R�~���j�e�B�̉�b�⊈�����L�^����\�[�V�����l�b�g���[�N�A�d�q����蒠�Ȃǂ̖n�̃f�W�^���L�^�A�d�q�J���e���É摜�Ȃǂ̃f�W�^�����Ƃ��̊Ǘ��A��Ô�x�����̓d�q�x�����V�X�e���A��̔z���V�X�e���A�����āA�a�@�ւ̒ʉ@��ʃX�}�[�g�V�X�e���B���z�̎Љ�ւ̗v�f�͂�����Ă���悤�Ɍ����Ȃ���A�����ł��Ă��Ȃ��B������˔j����̂�Society 5.0�̐��O�ꂾ�낤�B
��N12������3�����܂ŏÓ�c��a�@�Ƌ����Ńv���g�^�C�v�̐v�E�J���Ə����Ȏ��؎������s�����B��Ï]���҂̎g�p����d�q�J���e�ƘA�g���Ă���V�X�e���ɍݑ�҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̋@�\�������A���u�Ζʂ̐f�ÁA���ґ�̃J��������A�ݑ�̌��N����@��̒~�ςƋ��L�A���Ҍl�F�ȂǁA���Ԃ���������l�ߍ��������s���AAMED(���������J���@�l���{��Ì����J���@�\)�����̎����ϗ��K��ɏ]����30���̊��҂ƒS����t�̎������o�āA�o���̑��ʂł̕]���ƒ������s�����B�����͈̔͂͌���I�����A�]������X�ŁA��҂���̋M�d�ȃA�h�o�C�X���W�߂邱�Ƃ��ł��A�ʉ@�ƍݑ�̑g�ݍ��킹����̓I�ɃC���[�W�ł������҂��傫�Ȋ��҂��Ă��ꂽ�B
�������A�Љ�̒��ʼn^�p��W�J���邽�߂ɂ͂�������̃n�[�h��������B����������ÂɂƂ��Ẳ��u�f�Â̐f�Õ�V�͏��ɂ�������B����܂ł͉��u��Â��f�W�^���Љ��O��ɋc�_����Ă��Ȃ������̂����疳�����Ȃ��B���B�̕���̎���ł���X�}�[�g�n�E�X�ƂȂ������ґ�ł��A����IoT�@��ƂȂ����ƒ�̌��N����f�o�C�X�̓f�[�^�`�����ʐM�`�����x���_�[���ƂɓƗ����Ă��ĕW��������Ă��Ȃ��B������������̈�t�Ƃ̉��u�Θb�͍���҂��ӎ����ĉƒ�̃e���r�𗘗p���Ă��邪�A�X�}�[�g�e���r�ɂ̓X�}�[�g�t�H���̂悤�ȃI�[�v���ȊJ�����͂Ȃ��B�ƒ�̓d�C�A�ȂNJ��҂̏�Ԃ�ړ���F�����ϑ��ł���f�[�^�͂��邪�A���̃f�[�^�����L�ł�����͂Ȃ��B���҂̌��N���ړI�ł����Ă��A���҂̐����̃v���C�o�V�[�Ƃ̊֘A�̍��ӌ`���̕��@�͊m�����Ă��Ȃ��B�Ƃ̊֘A�ł̏�����̂��Ƃ�����u�ŋ@�\�I�ɍs�����߂̐��x�I�ȏ����͂ł��Ă��Ȃ��B�����������l�ȃX�e�[�N�z���_�[�ɐ������Ή����x�����������ꂽ�d�q�����}�C�N���d�q�x�����̎d�g�݂͂܂��䂪���ɂ͑��݂��Ȃ��B
�����A�����܂ł���A�����ׂ��ۑ����̉��������̃A�N�V����������B�l�̌��N�Ɋւ��鐳���������̃f�[�^���a�C�ɂȂ�O���番�͂ł��A���S�ɋ��L�ł���ƂȂ�A���N�ȎЉ�ɂ͔���I�ɍv�����邵�A������x����ی����x�����{�I�ɉ��P�ł���B
2017�N�ɐ��E�̐l����51.7%���C���^�[�l�b�g���p�҂ƂȂ����B�䂪���͊���83.5%�ł���B�C���^�[�l�b�g��O��Ƃ����A�f�W�^���Љ���B�̐����ɕ��ՓI�ɍv���ł���Љ�̃C���[�W�͏��̐��ƂłȂ��Ă��f�U�C���ł���悤�ɂȂ����B���ꂩ��́A���l�Ȗ��������l���A�g���Ă��ꂩ��̃f�W�^���e�N�m���W�[���������@�\�ł���A�l�̂��߂̃f�W�^���Љ�̍\�z���J�n�����B�@ |
 |
|
���f�W�^���v���́u�������v����u���Ċ��v�ց@ |
���ߋ�20�N�Ԃ̓f�W�^���v���́u�������v
�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w(�l�h�s)���f�B�A���{�̑n�ݎҁA�j�R���X�E�l�O���|���e�����ЁwBeing Digital�x�����̂�1995�N�������B�l�O���|���e�́u�A�g��(����)����r�b�g(���)�ցv�Ƃ������t�ŁA�f�W�^�������f�B�A�A���C�t�X�^�C���A�E����Ȃǂ�����Љ�\�������{�I�ɕϗe������Ɨ\�������B
���̗\������20�N�B�C���^�[�l�b�g�A�X�}�[�g�t�H���A�L���E�����̃u���[�h�o���h�������炵���e���́A�u�f�W�^���v���v�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���܂�e���r�̓X�}�z�A�v���̈�ƂȂ�A�������Ǝ҂ƃ��b�Z���W���[�A�v�����Ǝ҂����C�o���ɂȂ��Ă���B���Z����ł́A��s�Ƃh�s��Ƃ������t�B���e�b�N�u�[�����N���Ă���B�f�W�^�����̐i�s���ƊE�̊_�����A�Љ�ɑ傫�ȉe����^������B
���������́A�ߋ�20�N�Ԃ̓f�W�^���v���́u�������v�ɂ������A�{���̈Ӗ��ł̃f�W�^���v���͂��ꂩ�疋���J����ƂƂ炦�Ă���B�܂��Ȃ��h�b�s(���ʐM�Z�p)���^��������u���Ċ��v�ɓ���A�f�W�^�����Љ�̋��X�܂ŐZ�����Ă������낤�B
����܂ł́u�������v�́A�f�W�^���v���̃C���t�������������܂ł̊��Ԃƌ��������邱�Ƃ��ł���B���̃C���t���̎�Ȓ��́A�C���^�[�l�b�g�A�X�}�[�g�t�H���A�N���E�h�A�Z���T�A�����ʐM�Ȃǂ̃e�N�m���W�[�ł���B
�C���^�[�l�b�g���o�ꂵ�����̐l���g���n�߂����Ƃɂ���āA�ʐM�������邽�߂Ɍ��t�@�C�o�ւ̓������s���A����Ȍ��t�@�C�o�Ԃ��o���オ�����B���t�@�C�o�Ԃ��[���������ƂŁA��������N���E�h�̋Z�p�����W���Ă����B
���o�C���̔��W�ɂ��A�L�����疳���ւƑǂ����A�����Z�p�����W�����B���̖����Z�p�́A�X�}�z�̕��y�ɂ���Ĕ���I�ɐ������Ă����B����ɃX�}�z�̕��y�́A�Z���T�Z�p�����߂Ă������B1��̃X�}�z�ɂ́A�����x�Z���T�A�ߐڃZ���T�A�Ɠx�Z���T�A���C�Z���T�A�w��F�Z���T�Ȃǂ��܂��܂Ȏ�ނ̃Z���T���K�v�ƂȂ�B���ꂪ�Z���T�̏��^���A�ȗ͉��A�R�X�g�_�E���𑣂����B
�������Ȃ���A�K�v�ƂȂ�Z�p�����荞��ł������B�����ɔ���Ȏ�������������A�ӂƐU��Ԃ�Ƃ���炪�C���t���ɂȂ��Ă����B����A���R�̎Y�����B�C���t���𐮂��悤�Ƃ��Čv��I�ɐ������Ă����킯�ł͂Ȃ��A���܂��������Ă��Č��݂�����B2015�N��IoT�Ƃ������t���o�Ă����̂��A�e�N�m���W�[�����n�������Ƃɂ���āA�����̃C���t�������܂��܂Ȓn��ň����ɗ��p�ł����������������Ƃ�����B
|
�����ꂩ��́u���Ċ��v�ɂ̓f�W�^�����Љ�̋��X�ɐZ�����Ă���
�C���^�[�l�b�g�̓o�ꂩ�猻�݂Ɏ���܂ŁA���܂��܂Ȃh�b�s�����ݏo����A���������Ƃɂh�s�v�����N�������B���R�}�[�X�����A���X�܂��������A�X�}�z���}���ɎЉ�ɕ��y���Ă������B�����O�܂łb�c��c�u�c�Ŋy���ނ̂�������O���������y�⓮����A���܂ł̓A�b�v��(Apple)��l�b�g�t���b�N�X(Netflix)�Ȃǂ�����X�g���[�~���O�z�M���嗬�ƂȂ����B
�����������ۂ��������A����܂ł́u�������v�ɂ��f�W�^�����͂��Ȃ�̃X�s�[�h�Ői�W���Ă����悤�Ɏv����B
���ہA�a2�b�̕���ł́A�f�W�^�����l�X�̐�����傫���ς��n�߂Ă���B�X�}�z�𗘗p���Ă��鎄�������g���A���͂�f�W�^���Ƃ͖����ł͂Ȃ��B���X�̃j���[�X��V�C�\����A���̐V����e���r�ł͂Ȃ��X�}�z�A�v���Ń`�F�b�N���Ă���l���������낤�B
�������A������������_�Ō��n���Ă݂�ƁA���̒��̓A�i���O�ň��Ă���B�����ɂ̓f�W�^��������Ă��Ȃ��c��ȗʂ̕��I���Y������B�������̎d������̂Ȃ��ɂ��A�o���⊨�ɗ����čs���Ă���c��ȗʂ̃A�i���O�v���Z�X������B����܂Ńf�W�^��������Ă����͎̂�ɃC���^�[�l�b�g��Ő������ꂽ�E�F�u�f�[�^�ł���A���A���Ȑ��E�Ńf�W�^��������Ă�����̂͂����ꕔ�ɂ����Ȃ������B
�r�W�l�X�̗̈�ł��A�f�W�^���������߂��Ă����ƊE�͏����������B�h�s��Ƃ�l�b�g��ƁA�ꕔ�̐�i�I�Ȋ�Ƃ��f�W�^����ϋɓI�Ɏ�����Ă������̂́A���̑��̑啔���̊�Ƃ͈ˑR�Ƃ��ăA�i���O�̐��E�Ńr�W�l�X��W�J���Ă����B
�������A����܂ł́u�������v���o�āA�f�W�^�����ɑǂ�邽�߂̃C���t���͐������B�f�[�^���W��f�[�^���͂̃c�[���������ɗ��p�ł���悤�ɂȂ����B�O���[�o������o�ς̐��n����w�i�Ƃ��Ċ�ƊԂ̋����͂܂��܂��������Ȃ��Ă���B�f�W�^����������Đ����c���}�낤�Ƃ����Ƃ́A�m���ɑ����Ă����B
�������N�A�O�[�O���Ȃǂ̂h�s��Ƃ��e�N�m���W�[��ɂ��ĈًƎ�ɎQ�����铮���������ɂȂ��Ă���B������f�B�X���v�V����(�n���I�j��)�ł���B�����̋ƊE�ł́A������@���������ăf�W�^������}�낤�Ƃ����Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�܂��A�����Ƃ̂Ȃ��ɂ́A�R�}�c�̂悤�ɋ������Ђɐ�삯��IoT��������A�����͂�傫�����߂���Ƃ�����n�߂Ă���B
�������������́A����A�������������Ă����B�u�������v����u���Ċ��v�ւ̈ڍs�͂��łɎn�܂��Ă��āA���ꂩ��f�W�^���͒����N���������ĎЉ�̋��X�ɐZ�����Ă������낤�B
�������A���ꂪ�ǂ̋ƊE�A�ǂ̊�Ƃ���i�ނ̂��͂킩��Ȃ��B�Ǝ���ƋK�͂Ƃ��������A���l�I�ȗv�f���傫�����炾�B�o�c�g�b�v��������@���������Ă����ƁA�f�W�^���̕K�v���������ӎ����Ă����Ƃ���A�f�W�^�������n�܂��Ă����B�����āA�����̊�Ƃ����̐��ʂ������邱�Ƃɂ���āA���܂��܂Ȋ�ƁE�ƊE�ɍL�����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
|
���f�W�^���̐Z���ɂ͒������Ԃ�������
��قǎ��́u�f�W�^���͒����N���������ĎЉ�̋��X�ɐZ�����Ă����v�Əq�ׂ��B���̍����́A�f�W�^�����𐄐i����h�b�s������ɂ�����ėp�Z�p������ł���B
�ėp�Z�p�Ƃ́A����̐��Y�������ɊW������̂ł͂Ȃ��A������o�ϊ����ŗ��p����A�֘A���镪�삪���ɍL���Z�p���w���B18���I�̎Y�Ɗv���Ő��ݏo���ꂽ���C�@�ւ�A���̌�A���C�@�ւɑ����ē������ꂽ�d�C���A��\�I�Ȕėp�Z�p�Ƃ��ċ�������B
�d�C��19���I���ɓd�����Ƃŗ��p���n�܂������A�H��̓��͂Ƃ��Ă̗��p�͒x��A�H��̓d���ɂ���ĎY�Ƃ̐��Y�����㏸�����̂�1920�N��ȍ~�̂��Ƃ������B���̊ԁA���悻40�N���o���Ă���B��������g�D�̑̐���ς��Ȃ���A�H��̏��C�@�ւ�d�C�ɑւ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������炾�B
����̎������͓d�C�̗������悭�m���Ă���̂ŁA�u�������Ɠd�C�ɑւ���悩�����̂Ɂv�Ǝv���������B�������A�d�C�ɑւ��邽�߂ɂ͍H��̐ݔ���C�A�E�g���K�����ƕς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�E�l����̓��������ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ނ�ɂ͕ς������̂��Ƃ��z���ł��Ȃ��̂ŁA�S���I�Ȓ�R�������A�Ȃ��Ȃ��ӎ���ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ėp�Z�p���s���n��܂łɒ����N����������傫�ȗv���͂����ɂ���B
����̔ėp�Z�p�ł���h�b�s�ɂ��Ă��������Ƃ�������B�f�W�^������i�߂�ɂ́A�g�D�⓭�����Ȃǂ̕ϊv���K�v�ƂȂ�B
���m�Â����Ƃł́A�f�U�C������v�A���ޗ����B�A�����A�����A�̔��Ɏ���܂ŁA������̈ӎv����̗���ɓK�����g�D���\�z����Ă���B�������A�����������m�ɃZ���T���g�ݍ��܂�A�Z���T���瓾��ꂽ�f�[�^��v����ɔ��f�ł���悤�ɂȂ�ƁA��o�����ɃX���[�Y�ɗ����K�v������B������̗���ɓK�����g�D�ł́A��o�����ɗ���ɂ����̂ŁA�œK�ȑg�D�`�Ԃ�͍����邱�Ƃ����߂���B
�g�D�̑̐���ς���A����ɍ��킹�ď]�ƈ���z�u�������K�v��������B��l�ЂƂ�̎d���̂������ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ����̔����������A�ϊv�̏�Q�ƂȂ�B�h�b�s���i������X�s�[�h�͏��C�@�ւ�d�C�����͂邩�ɑ������A�l�̈ӎ��͐̂������قƂ�Ǖς��Ȃ��B
|
���^�̃f�W�^���Љ�͂���������̂�
�ł́A�f�W�^�����Љ�ɐZ�����A�^�̈Ӗ��Ńf�W�^���Љ��������̂͂�����ɂȂ�̂��B����Y�Ƃ��o�u���̕�����o�đ䓪����܂ł̗��j��U��Ԃ�ƁA30�`40�N�Ŗ{���ɂȂ�Ƃ����������ł���B
1850�N�ɃC�M���X�Łu�S���o�u���v�������B1840�N��ɓS����Ђ��������Ń����h���s��ɏ�ꂷ��ƁA�S�����ׂ��肻�����Ƃ������Ƃœ����Ƃ��S�����ɎE�������B�S����Ђɂ������W�܂�A�e�Ђ������đS���ɐ��H��~�݂���悤�ɂȂ邪�A6000�}�C��(1���L����)���̐��H��~�݂����Ƃ���Ńo�u�����e�����B�������A���ǂ̂Ƃ���C�M���X�̓S�������������}�����̂́A���ꂩ��30�`40�N���1880�N�ォ��90�N��ɂȂ��Ă��炾�����B
1929�N�̐��E�勰�Q�́A�j���[���[�N�،�������ɂ����鎩���Ԋ��Ɠd�͊��̃o�u�����������Ƃ����������ƌ����Ă���B�����Ԋ��Ɠd�͊����}�㏸�������ƂŃo�u�����n�܂�A�ꎞ�̓A�����J�����Ŏ����ԃ��[�J�[��300�Ђ��������B���������H���ܑ�����A�������H����������Ď����Ԃ��Љ�̃C���t���ƂȂ����̂́A1950�N�ォ��60�N�ゾ�����B�Ƃ������Ƃ́A��͂�o�u�����e����30�N�قnjo���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B
�����܂���ƁA�C���^�[�l�b�g�o�u����2000�N����ɒe���A2008�N�Ƀ��[�}���V���b�N�ōĂуo�u�����e���Ă���A�܂�10�N�قǂ����o���Ă��Ȃ��B�����l����ƁA�f�W�^�����Љ�̋��X�ɍs���n��A�^�̈Ӗ��Ńf�W�^���Љ��������̂́A���܂����20�N���2040�N�ȍ~�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�����A���������Ă���̂́u�s���n��v�܂ł̊��Ԃł����āA���̓����͂��łɎn�܂��Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ЂƂ��ї��ꂪ�ł���Έ�C�ɉ������Ă����B�����̒i�K�Ŏ哱�����������҂����̂͊ԈႢ�Ȃ��B�܂�A�����������҂������A����������҂͕�����B����͂ǂ̕���̂ǂ�ȋ����ł��ς��Ȃ��B
���łɁA�f�W�^�����Ƃ͋��������肻���Ȕ_�Ƃ̕���ł��A�f�W�^�����Ɉӗ~�I�Ɏ��g��ł��鐶�Y�҂�����B���̈���Ńf�W�^�����͕K�v�Ȃ��Ƃ������Y�҂������A���̐l�����̈ӎ����ς��f�W�^�����Z������܂łɂ͒����N����������Ƃ����Ӗ����B�����������A���Ƃ������c�ꂽ�Ƃ��Ă��擪�O���[�v�𑖂�͓̂�����낤�B�@ |
 |
|
���f�W�^�����Ƃ͉����@ |
|
�ŋ߁A���m�Â���n�̎�ނ�Z�~�i�[�u�����Ă���ƁA�f�W�^������f�W�^���g�����X�t�H�[���[�V����(�]��)�Ƃ����悤�Ȍ��t�������炱���炩�畷�����Ă���B���ɂ̓f�W�^���c�C���A�T�C�o�[�t�B�W�J���V�X�e���A�Ȃǂ̌��t���o�ꂷ��B�����̌��t�́A�����G���N�g���j�N�X�Z�p�Ɍg����Ă����҂����ɂَ͈��Ȍ��t�ɕ������A����܂ŃG���N�g���j�N�X�Z�p�Ƃ͖����������l�����ɂ͐V�N�Ȍ��t�ɕ�������B�����ł́A���t�̈Ӗ��������Ɩ��炩�ɂ��Đ�������B
|
����̑O��e�R�}�[�X�A�d�q������Ȃ�
�܂��A�����̌��t�̎g�������������ς���Ă��Ă��邱�Ƃɂ����ӂ���K�v������B�Ⴆ�A�C���^�[�l�b�g���g���Č��Z����r�W�l�X���A���Ắu�d�q������v���邢�́ue�R�}�[�X�v�ƌ������B�����̓f�W�^���Ƃ������t�͂��܂�g��ꂸ�A�u�d�q�����v�ue�����v�Ƃ����Ăѕ����嗬�������̂��B���̍���ɂ�����̂́A�u�d�q�v��ue�v���\���G���N�g���j�N�X(Electronics)�Z�p�ł������B�G���N�g���j�N�X�Z�p�̃x�[�X�́A�����̏W�ω�H(IC)�Z�p�ł���Be�R�}�[�X�Ŏ��ۂɎg���Ă���̂́A�C���^�[�l�b�g�̃u���E�U�ł���A��s�����̓o�^���ɂ����Ȃ��B�u�d�q�v�ƌ����Ȃ���d�q�����ɂ���u�G���N�g���j�N�X�Z�p�v���g���Ă����ł͂Ȃ������B
�C���^�[�l�b�g�̃u���E�U��\������A�p�\�R����X�}�[�g�t�H���̊�{�Z�p�ƂȂ��Ă���n�[�h�E�G�A���G���N�g���j�N�X�Z�p�Ȃ̂ŁA�u�d�q�����v�ue�����v�ƌ������A�u�d�q�v�͊ԐړI�Ɏg���Ă��������ł������B
�������ŋ߂͓d�q�Ƃ������t�͕�����Ȃ��Ȃ�A�f�W�^������f�W�^���ϊ��Ƃ������t���g����悤�ɂȂ��Ă����B�����̌��t���u�d�q�v�Ɠ��l�ɁA����܂ŃG���N�g���j�N�X�Z�p���g���Ă��Ȃ�����������G���N�g���j�N�X�����邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B���ہA�G���N�g���j�N�X�Z�p�\�\�Z���T��A�A�i���O��H�A�f�W�^����H�ACPU�A�������Ȃǁ\�\���g���A�V�X�e����������������A�����I�ɓ��삳�����肷�邱�Ƃ��ł���B�܂�A����܂ŃG���N�g���j�N�X�Z�p�Ɩ�������������ŁA���̋Z�p���g���ĎЉ��ς��邱�Ƃ��A�f�W�^�������邢�̓f�W�^���ϊ�(�g�����X�t�H�[�����V����)�ƌĂ�ł���̂ł���B
���Ԃ��A�G���N�g���j�N�X�Z�p�Ƃ�����x���锼����IC�Z�p���A�Љ��C���t���A���݁A�z�ƁA���Z�A����ɂ͔_�Ƃ�z���C�g�J���[�̃I�t�B�X��ƁA�r���Ǘ��ȂǁA�l�Ԃ��ւ�邠����d���̕���ɋy��ł������Ƃ��Ӗ����Ă���B
|
���f�W�^�������������邽�߂ɕK�v�ȃA�i���O��H
�����炱���A���N�G���N�g���j�N�X�Ɍg����Ă����l�ԂɂƂ��āA�f�W�^�����Ƃ������t�ɂ͈�a��������悤���B�Ƃ����̂́A�X�}�[�g�t�H����IoT�[���Ɏg����A�i���O��H�͍���܂��܂������Ă������炾(�}1)�B�X�}�z��IoT�[���̒��ɓ����Ă���Z���T�́A���X�d�C(�d����d���A�d�͂Ȃ�)�ł͂Ȃ������ʂ�d�C�ɕϊ�����f�o�C�X�ł���A�قƂ�ǃA�i���O�M���Ƃ��Ď��o���Ă���B�ق��ɂ��X�}�z�ɂ́A���̓Z���T������x�Z���T�A�W���C���Z���T�A���x�Z���T�A���C�Z���T�ȂǁA���܂��܂ȃZ���T�����ڂ���Ă���A�������A�i���OIC���ӂ�ɓ����Ă���B
�@�@�@[�}1] 1980�N���猻�݂܂ŃA�i���OIC�̔䗦�͑����Ă���
�ŐV�^�̃f�W�^���@��قǁA���͂�������̃A�i���OIC���g���Ă���̂��B���[�U�[�G�N�X�y�����X�ƌĂ��l�ԂɂƂ��Đe���݂₷���@�\�́A�S�ăA�i���O��H�Ŏ������A���̌�Ńf�W�^����H�ɕϊ����Ă���B�l�Ԃ̎��R�Ȃӂ�܂��A�W�F�X�`���[��葫�̓����A�����A����U��悤�Ȃ������Ȃǂ́A�S�ăA�i���O�B�����炱���A�l�ԂƂ̃C���^�[�t�F�[�X�̓A�i���O�Ńf�[�^���E���A���Z���Ȃǂ̏�����e�Ղɂ��邽�߃f�W�^���ϊ�����B
����ł��A�V������\�����邽�߂ɁA�����āu�f�W�^���v�Ƃ������t�ŕ\�����Ă���̂�����Ȃ̂ł���B�f�W�^����IT�Ƃ������t���g���A�V�����������邩�炾�B�u�f�W�^�����V�����v�u�A�i���O���Â��v�Ƃ����}�������A���̓f�W�^���Z�p���̂��̂͂���50�N�ȏ�O���炠��B�A�i���OIC�������悤�Ȏ������炠�邪�A30�N�ȏ�O�����葱���Ă���f�[�^�ɂ��ƃA�i���OIC�͂����Ƒ��������Ă���̂��B
|
���G���N�g���j�N�X�Z�p���悤�₭�Љ�ɐZ��
�������A���܂ŃG���N�g���j�N�X�Z�p�͎Љ�܂ŐZ�����Ă��Ȃ������B�H��͎���������Ă��A�I�t�B�X�ł͐l�C��p���܂���ʂ��Ă������炾�B���āA�I�t�B�X����͎����Ȃ��Ȃ�ƌ���ꂽ���A���ۂ͎��̏���ʂ͂ނ��둝�����Ă���B���x�[�X�ō�Ƃ��Ȃ��Ǝd���������C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Â��l�Ԃ����܂��ɑ����B���̂��߁A�I�t�B�X�ւ̃G���N�g���j�N�X�Z�p�̓����͔��ɒx��Ă����̂��B
�ŋ߂ɂȂ��Ă悤�₭�I�t�B�X�Ɩ��̉��P�������悤�ɂȂ�A�ȃG�l����IT���{�b�g(RPA�F���{�e�B�b�N�E�v���Z�X�E�I�[�g���[�V�����Ƃ����A�\�t�g�E�G�A�ō�鎩���������u�̂��ƁB�t�H�[�}�b�g�̈قȂ������ɂ܂Ƃ߂�A���܂��܂ȃE�G�u�T�C�g����ȒP��URL�Ȃǂ̏�������Ă���)�̊��p�ɂ��c�ƍ팸�Ȃǂ����s�i�K�ɓ���͂��߂��B�����Ŏg���Ă���̂��R���s���[�^�Z�p�ł��邽�߁A��ʂɃf�W�^�����Ƃ����C���[�W�������Ă���̂��낤�B�������A�G���N�g���j�N�X�Z�p�Ɋ܂܂��̂́A�R���s���[�^�Z�p�����łȂ��A�ʐM�Z�p�A�����̋Z�p�A�����ăA�i���O��f�W�^���̉�H�Z�p���܂܂��B
|
���G���N�g���j�N�X���̃J�M�̓R���s���[�^
����܂ł����ꂩ����A�ő�̋Z�p�v�f�͂�͂�R���s���[�^�Z�p�ł���B�R���s���[�^�Ƃ����̂́A�n�[�h�E�G�A�����ʂɂ��āA�\�t�g�E�G�A��ς��邾���Ŏ����̗~�����}�V���ɕς�����@�B�ł���B������A�K�������u�R���s���[�^���v�Z�@�v�ł͂Ȃ��B�R���s���[�^�͂������v�Z�����邪�A�ނ��둽���̏�ʂŎg����@�\�́A�f�[�^����ʐ������鐧��@�\�ł���B�Ⴆ�A���[�v���\�t�g�ŕ����������ꍇ�A�R���s���[�^�͌v�Z�������A�L�[�{�[�h�őł��ꂽ������̕ϊ����s���Ă���ɂ����Ȃ��B�u�����v�ƑłĂu���v�u��v�u�����v�u���v�u���v�Ȃǂ̊��������Ƃ��ĕ\�����Ă��邾���ŁA�l�Ԃ����̒����琳�����w�肷��B�����ł́A������̌����������ɋL�������Ă����A�u�����v�Ɠǂފ�����ǂݏo���Ă��邾�����B�ǂ̏��Ԃŕ\�����邩�͐��䂷��\�t�g�ɂ���ĕς��邱�Ƃ��ł���B
�R���s���[�^�Z�p�͂��͂�ڂɌ����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���A�l�Ԑ����⓭���ꏊ�Ȃǂ�����Ƃ���ɖ��������悤�ɂȂ����B���̂��Ƃ��R���s���[�^�g�����X�y�A�����g�ƌĂԋƊE�l������B�ł��傫�ȃR���s���[�^�̓X�[�p�[�R���s���[�^��C���t���[���ł��邪�A�ł������ȃR���s���[�^�̓p�\�R����X�}�z�ł͂Ȃ��A�قƂ�ǂ̓d�C���i�̓����Ɏg���Ă���}�C�R���ƌĂ�锼���̃`�b�v���B���Ƃ��Ύ����Ԃɂ́A�R���s���[�^(ECU�ƌĂ��)�����\��������Ă���B
�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�R���s���[�^�Z�p�̍ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A�\�t�g�E�G�A��ς��邱�Ƃł��낢��ȗp�r�Ɏg���邱�Ƃ��B�R���s���[�^�����ݏo���ꂽ���������́A�~�T�C���̒e�����v�Z���邽�߂ł��������A���͌v�Z�����͂邩�ɐ��䂷��ړI�������Ă���B�v�Z��������\�t�g�E�G�A�ŃJ�X�^�}�C�Y�ł��邪�A�\�t�g�E�G�A�̐i�������ł͐��\�Ɍ��E������̂ŁA�n�[�h�E�G�A�ƃ\�t�g�E�G�A�́A���������킹�Ȃ���i�����Ă����B�܂��n�[�h�E�G�A�͔����̋Z�p�̐i���ɂ��A�������y���A������������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B
|
�������ȃR���s���[�^�������鏊�ɐZ��
1980�N��㔼�ɓo�ꂵ���X�[�p�[�R���s���[�^�u�N���C2�v�����A�A�b�v���Ђ�iPad�̕������\�͍����A����d�͂͒Ⴍ�A���i�͈��|�I�Ɉ����B�������A�傫�����i�i�ɏ��������邱�Ƃ��\�ɂȂ����B�܂��A�R���s���[�^�V�X�e���Ɠ����\�������Ȃ���R���s���[�^�ł͂Ȃ����u�́A�g�ݍ��݃V�X�e���ƌĂ�Ă���B���ꂪ�ʐM�@�\�����Ă�IoT�[����Z���T�[���ƌĂ�A����傫�����҂���镪��ɂȂ��Ă��邪�A��������^���ɂ������������i���B
�����������CPU�ʼn��Z�����s���R���s���[�^�V�X�e�����A�]���̂悤�Ȋ�Ƃ̑傫�ȃV�X�e�������ł͂Ȃ��A�����Ɛg�߂ɂ��郂�m�A�Ⴆ�Ό��ւ̃h�A�m�u��G�A�R���Ȃǂɂ��g�ݍ����̂�IoT�ł���(�}2)�BIoT���g�ݍ��܂ꂽ���i�́A���ǂ̂悤�ȏœ��삳�������Ƃ��������f�[�^����悤�ɂȂ�B����ƁA���[�U�[�͊O�o�悩��ł��h�A�̎{���̗L����G�A�R���̉ғ���Ԃ̊m�F�Ȃǂ��s���邵�A���[�J�[�͊e���[�U�[�̓�����m��A������}�[�P�e�B���O�ɗ��p���r�W�l�X�������グ�邱�Ƃ��ł���̂��B
�@�@�@[�}2] ���ւ̃h�A�m�u��t�@���A�G�A�R����IoT���A�C���^�[�l�b�g�ɐڑ�����
�܂�A����܂ŃG���N�g���j�N�X�Ƃ͖����������A�Ɩ���h�A�m�u�A�G�A�R���A�①�ɂȂǂɂ��G���N�g���j�N�X�┼���̂�������A�Ɩ������v������A������֗��ɂ�����ł���悤�ɂȂ������߁A�V�����C���[�W��\�����t�ł���u�f�W�^�����v���o�ꂵ�Ă����̂ł���B
|
��IT�ɑ���OT�Ƃ������t��
�C���^�[�l�b�g��R���s���[�^�𗘗p����T�[�r�X��IT(Information Technology�F���Z�p�̗��ł͂��邪�A�{���I�ɂ͋Z�p�ł͂Ȃ�)�ƌĂ�ł��邪�AIT�Ƃ������t���Z�����Ă������AIT�����p���Ȃ��J������������OT(Operational Technology�F�^�p�Z�p)�ƌĂԂ��Ƃ������Ă����B
���܁AIT�Ƃ����ׂ�3����CAD��CAE(�V�~�����[�V�����c�[��)�Ȃǂ����p���āA����(OT)�̏��p�\�R���Ȃǂ̐g�߂Ȑ��i�ŕ\���ł���悤�ɂȂ����B�Ⴆ�H��œ����l�Ԃ�C���A��Ƒ���O���t�B�b�N�X�ŕ`���A���ۂ̍�Ə��p�\�R����ʏ�̃V�~�����[�V�����c�[���Ō��邱�Ƃ��ł���B��Ƒ䂩�玟�̍H���̍�Ƒ�܂ł̋�������ʏ�ɕ\���A���̋����������ƒZ�����钷������ȂǍœK���̃V�~�����[�V�������s���A����̍�Ǝ��Ԃ̒Z�k��}��������グ��B�O���t�B�b�N�X�ɂ���ʏ�̐l�Ԃ̎�̈ʒu��g���Ȃǂ��\�����Ă����A�肪�͂��₷���ʒu�ɍ�Ƒ䂪����̂��ǂ����Ƃ��������Ƃ��킩��B����́A���ۂɍH��̃��C����v����ꍇ�ɂ����ւ�𗧂B
|
������̏�IT�ōČ�����ƃf�W�^���c�C��
���̂悤�Ɏ��ۂ̌�����R���s���[�^�őS�������悤�ɍČ�����IT�̐��E���u�f�W�^���c�C��(�f�W�^���̑o�q)�v�ƌ����B�f�W�^���c�C�����g���āA������\�z����O���猻��̍�Ƃ�i���̂��̂��V�~�����[�V�������邱�ƂŁA�v�~�X��v�ύX���Ȃ����A�Z���ԂŐ��i���s��ɏo�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B������A�]���͕��ʐ}�ɕ`�����v�}(2����CAD)�ł��������̂��A�R���s���[�^�O���t�B�b�N�X����g����3����CAD�ւƕς���Ă����B2����CAD�ł͐��Ƃ������i�⌻����C���[�W�ł��Ȃ��������A3����CAD�ɂȂ�ƌo�c�҂�ڋq�ɂ������I�ɗ������₷���B��������IT��OT�̗Z���́A�u�T�C�o�[�t�B�W�J���V�X�e���v�uIT/OT�V�X�e���v�ƌ����邱�Ƃ�����(�\1)�B
�@�@�@[�\1] ������IT�̌��t�̑Δ�
�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���z
����E�}���فE���m�@�@�@�@�@�@�C���^�[�l�b�g
OT(Operational Tech)�@�@�@�@�@IT(Information Tech)
�t�B�W�J���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�o�[
�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�~�����[�V����
�R���s���[�^(�I���v���~�X)�@�@�N���E�h
�Z�~�i�[�C�x���g�@�@�@�@�@�@�@�E�F�u����
IoT�@/�@�f�W�^���c�C���@/�@�C���_�X�g���[ 4.0 /�C���_�X�g���A���C���^�[�l�b�g�@/�@�T�C�o�[�t�B�W�J���V�X�e���@/�@AR/VR
�܂��A�o�[�`����(���z)�Ƃ����\���́A���ۂ̌�����O���t�B�b�N�X�ȂǃR���s���[�^��ʏ�ŕ\�����ƂɎg����B�O���t�B�b�N�X�Ƃ́A�R���s���[�^��ŊG�����������}�����肷��Z�p�ł���B������Q�[���@�ŗV�Ԑl�����̓O���t�B�b�N�X�Ɋ���e����ł���AVR(���z����)�Ƃ������t�ɂ���R���Ȃ��BVR�́A�܂�Ŏ���������ɂ���悤�Ȋ��o�ɂ�����}�V���ł���B���܂̂Ƃ����ȗp�r�̓Q�[���ŁA���̖v���̌������߂邽�߂ɁA�S�[�O���^�̃f�o�C�X��p���đ̌������邱�Ƃ������B�Q�[���ȊO�ł��A���z����H��Ȃǂ�Տꊴ�̂���O���t�B�b�N�X�ŕ\�����邱�Ƃ��ł��A�Ⴆ�Εs���Y���Ń}���V�����̊Ԏ���̌�������VR������B
����ɑ���AR(�g������)�́A�����̃r�f�I�f���ɃO���t�B�b�N�X���d�ˍ��킹�āA���̃O���t�B�b�N�X�摜�������Ȃǂ̕\�����s���V�X�e���ł���B�Q�[���̒��ł́u�|�P����GO�v�ɏo�Ă���L�����N�^�[��AR�̑�\��ł���B���ۂ̃J�����f���Ƀ|�P�������d�Ȃ��ē����BAR���Q�[���ȊO�̕���ł��p�����Ă���A�Ⴆ�H��̃��[�^��|���v�ȂǂɎ��t����IoT�f�o�C�X�ɃX�}�z��^�u���b�g���������ƁA���[�^�̉�]����|���v�ł��ݏグ��t�̗̂��ʂȂǂ̃f�[�^��AR�Ō�����V�X�e�������p��*1���Ă���B
[�r��] *1 �e���X�R�[�v�}�K�W��013��Series Report�A��01 ��2��u����͎Y�ƗpIoT�̐��E����v�ł����グ�Ă���B |
���r�W�l�X���f������C���_�X�g���[4.0
���Y�@�B��IoT��g�ݍ��ނ��Ƃɂ���ċ@�B�̌̏��\�m�ł���A�̏Ⴗ��O�ɕ��i����芷���邱�Ƃ��ł��A�_�E���^�C�����팸�ł���B�܂��A�����܂����������v���͂����P����A�Ǖi�������܂萶�Y�������オ��B�������\�ɂ���̂��AIoT�𗘗p���������Ƃ̊v�V�u�C���_�X�g���[4.0�v�ł���B
GE�Ђ�[���X���C�X�ЂȂǂ̑��Ƃ́A�C���_�X�g���[4.0�ɂ���ăr�W�l�X���f����ς�����B�@�B�̌̏��\�m���A�O�����ĉ���ł��낤���i����芷����悤�ɂ���A20�N�Ԍ̏Ⴕ�Ȃ��W�F�b�g�G���W���╗�͔��d�^�[�r��������悤�ɂȂ�B�G���W����^�[�r�����̔����邾���ł͂Ȃ��A�W�F�b�g�@�����}�C����Ԃ��Ƃɂ�����A���͔��d�@����kW���d���邽�тɂ�����Ƃ����]�ʐ��̗����̌n�̃r�W�l�X���\�ɂȂ��Ă����̂��B�����Ɍ̏Ⴗ��@�B�ł͎��Ԃ̒P�ʂŕۏł��Ȃ��B�C���_�X�g���[4.0�͐��Y�������グ�邾���ł͂Ȃ��A�r�W�l�X���f�����ς��Ă��܂��̂ł���B
IoT�Ƃ́A���͒P�Ȃ�Z���T�[�����Ӗ����錾�t�ł͂Ȃ��A�Z���T����̂��܂��܂ȃf�[�^�����W�A�����A�ۑ��A��͂��āA�Ӗ��̂�����ɕϊ�����V�X�e���S�̂��w�����t�ł���(�}4)�B������[���̐v�E���Y�Ǝ҂����łȂ��A�r�b�O�f�[�^����͂���Ǝ҂₻�̉�̓c�[����v�E�̔�����Ǝ҂Ȃǂ��AIoT�`�[���ɂ͉�����Ă���BIoT�Ŏ��W�����f�[�^�͏��ɕϊ�������ŁA�f�[�^�����W�����Z���T�Ƀt�B�[�h�o�b�N���ăZ���T���`���[�j���O���邱�Ƃ��������Ȃ��B
�@�@�@[�}4] IoT�V�X�e���̃R���Z�v�g�@
���̂��߁A���i���[�J�[�̓f�[�^�̈Ӗ��𗝉�����K�v������B�f�[�^����ϊ����ꂽ�d�v�ȁu���v����ɓ���A�Z���T�̃L�����u���[�V������IoT�[���̓������P�ɐ������Ȃ���AIoT�V�X�e���̎哱�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A�ڋq�̐M����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��B
|
���f�W�^�����͔����̃`�b�v�̑������Ӗ�����
�ȏ�A���Ă����悤�ɁA�u�f�W�^�����v�Ƃ������t�́A����܂ŃR���s���[�^�Ƃ͖����̐��E�ɃR���s���[�^�Z�p�������Ă������ƂŁA�g����悤�ɂȂ����Ƃ������ʂ�����B����܂łł��Ȃ��������Ƃ��A���ꂩ��͂ł���悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A�[�I�Ɏ������߂Ɏg����悤�ɂȂ����̂��B�f�W�^�������i�߂ΐi�ނقǁA�G���N�g���j�N�X�̐��E���L����A�����̃`�b�v���܂��܂������g����悤�ɂȂ�B����܂ł͗p�r�������@���Y�Ƌ@��ɂƂǂ܂��Ă����G���N�g���j�N�X���A�Љ��C���t���Ƃ������E�ɂ܂œ��荞��ł������Ƃɂ���āA�V�������t�u�f�W�^�����v���o�ꂵ���B�f�W�^���Ƃ̓G���N�g���j�N�X�̌��������ł���A�����ĐV�������t�ł͂Ȃ����A�Љ��C���t���̐��E���猩��Ɣ��ɐV������т��₷�����t�Ȃ̂��B
�f�W�^�����Ƃ����̂́A�G���N�g���j�N�X�E�����̂����y����Ƃ������Ƃł���A�����̂͂��ꂩ��̐��E�̃C���t���ƂȂ���̂��B
�@ |
 |
|
���u�f�W�^���Љ�w�W�v�Ɓu�f�W�^���j�[�Y�[���x�v�@2019�@ |
������Гd�ʂ̊C�O�{�Ёu�d�ʃC�[�W�X�E�l�b�g���[�N�v(�{���n�F�p�������h���s)�́A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�̌����@�ւł���Oxford Economics���Ƌ����ŁA���E24�J���A43�A000�l�������ɂ��ĉ���`���Ŏ��{���������Ɠf�[�^�Ɋ�Â����͂��s�Ȃ��A�u�f�W�^���Љ�w�W�v�Ɓu�f�W�^���j�[�Y�[���x�v�\���܂����B
�O�҂́u�f�W�^���Љ�w�W�v�Ƃ́A�e�����ŁA�Љ�E�l�X�Ɏ�����f�W�^���o�ς��ǂ̒��x�\�z����Ă��邩���������̂ł��B"�l"���_�ő��������ГƎ���3�̕��͎��A����1�u�_�C�i�~�Y��(�f�W�^���o�ς̐����x�����E����)�v�A2�u�C���N���[�W����(�f�W�^�������̉��b����w�̍L���A�l�X�̃f�W�^�����p�x)�v�A3�u�g���X�g(�����̊�ՂƂȂ�f�W�^���Љ�ւ̐M���x)�v)��p���āuDigital Social Index(DSI)�v�X�R�A�Ƃ��Ďw�W���������̂ł��B2018�N��10�J����Ώۂɒ������J�n���A2019�N��24�J���ւƑΏۂ��L���܂����B
��҂́u�f�W�^���j�[�Y�[���x�v�́A�f�W�^���o�ς��l�X�̃f�W�^���j�[�Y�����Ă��邩�ǂ������������̂ł��B���Ђ��}�Y���[�̗~���i�K�����Q�l�ɓƎ��J�������u��{�I�j�[�Y�v�u�S���I�j�[�Y�v�u���Ȏ����j�[�Y�v�u�Љ�ۑ�����j�[�Y�v�Ƃ���4�̐���ŁA�e���ʂɑ��肵�����̂ł��B�Ȃ��A���̏[���x�����ɂ��Ă͍����߂ĂƂȂ�܂��B
�����2�̒������͂̌��ʁA���{�́u�f�W�^���Љ�w�W�v�ł�24�J����22�ʁA�u�f�W�^���j�[�Y�[���x�v�ł�24�J����24�ʂƂȂ�܂����B���۔�r�ɂ����āA���{�̓f�W�^���o�ς��Љ�ɂ����ď�肭�@�\���Ă��炸�A�܂����{�l�̃f�W�^���j�[�Y�����܂�[���ł��Ă��Ȃ������炩�ɂȂ�܂����B
|
��1�D�u�f�W�^���Љ�w�W�v(DSI�X�R�A)�̍��ʏ���
DSI�X�R�A�̓V���K�|�[���A�č��A�������g�b�v3�ŁA�V���K�|�[����3�̕��͎����ׂĂō������l�ƂȂ�܂����B�č��́u�_�C�i�~�Y���v����������Łu�g���X�g�v�͒Ⴍ�A����͑��̐��������ł�������X���ł�����܂����B�����́u�_�C�i�~�Y���v�͒����x�ł����A�u�C���N���[�W�����v�Ɓu�g���X�g�v�͍ō����x���ƂȂ��Ă��܂��B
���{�́u�_�C�i�~�Y���v�ł͈��̕]��������܂����A�u�C���N���[�W�����v�Ɓu�g���X�g�v�͍ʼn��ʃ��x���ƂȂ��Ă��܂��B
��
�E�u�_�C�i�~�Y���v�́A�f�W�^�������̊j�ƂȂ��Ƃ̃f�W�^���Z�N�^�[�̋����������AICT�Z�N�^�[�̋K�͂�����AR&D�̓����z�A�f�W�^���Z�p�ɑ�z��������@�ւ�l���̐����x�[�X�ɂ��Ă��܂��B
�E�u�C���N���[�W�����v�́A�f�W�^���o�ςɂ���Ă����炳�ꂽ���b������ł���l�X�̑w�̕��������Ă���A�f�W�^���C���t����f�W�^������̎��Ȃǂ���܂��Ă��܂��B
�E�u�g���X�g�v�́A��ƁE�c�̂̃f�[�^�ی�E���p�Ɋւ���l�X�̐M�����A�f�W�^���Љ�����炷�����ւ̐l�X�̊��҂̑傫���A�T�C�o�[�ƍ߂̔����\���̒Ⴓ�A�f�[�^�ی�K���̌��i���A�f�[�^���p�̓���������Z�肵�Ă��܂��B
|
��2�D�u�f�W�^���j�[�Y�[���x�v�@���ʃf�W�^���j�[�Y�ւ̏[���x(%)
���E24�J���ł́A5�������̐l�X�����f�W�^���j�[�Y����������Ă��Ȃ��Ƃ������ʂɂȂ�܂����B�f�W�^���o�ς��i�W���钆�ŁA�l�X�̎��ۂ̃j�[�Y�͌��߂�����Ă���A�����I�o�ϐ����ւ̌��O�������яオ�錋�ʂƂȂ�܂����B
45%�̐l���A��ƁE�c�̂����g�̃v���C�o�V�[��ی삵�Ă����Ƃ͍l���Ă��炸�A���̐l�X���I�����C����̎��g�̃f�[�^��i�K�I�ɍ팸���Ă������ƍl���Ă��܂��B�܂��A3����1�̐l�X���A�f�W�^�������g�̌��N����̎��Ɉ��e�����y�ڂ��ƍl���Ă��܂��B����ŁA�S�̂�3����2�̐l�X���A�u�l�K�e�B�u�ȉe��������ɂ���A5�`10�N��ɂ̓f�W�^�����ɂ�鉶�b�̕����傫���v�Ƒ����Ă��邱�Ƃ�������܂����B
���E24�J����24�ʂƂȂ������{�̓����͎��̂Ƃ���ł��B
�E ���p���₷���F�f�W�^���̃C���t�������i���ł���ƍl����l�����Ȃ��B(��{�I�j�[�Y)
�E �M�����F��ƁE���{�ɂ��l�f�[�^�̎�舵���Ɋւ���M�������Ⴂ�B(��{�I�j�[�Y)
�E ����ҍs���F�f�W�^���ɑ���s����ς��悤�Ƃ���l�����Ȃ��A�f�W�^�����i�E�T�[�r�X�̗��p�����Ⴍ�Ƃǂ܂��Ă���B(�S���I�j�[�Y)
�E �X�L���^����F�����̐l�������̃f�W�^���X�L���͍����Ȃ��ƍl���Ă���A�f�W�^���X�L�������������p����A�𗧂��Ă���ƍl����l�̔䗦���Ⴂ�B(���Ȏ����j�[�Y)
�E �����̊��ҁF5�`10�N��Ƀf�W�^���Z�p���Љ�ɂƂ��ėǂ��e���������炷�ƍl����l�̔䗦���Ⴂ�B(�Љ�ۑ�����j�[�Y)
��
�E�u��{�I�j�[�Y�v�́A�f�W�^�����i��T�[�r�X�ɐڂ��邽�߂ɕK�v�Ȋ������ŁA�f�W�^���C���t����f�[�^���g�p�����ƁE�c�̂ւ̐M�����𑪂���̂ł��B
�E�u�S���I�j�[�Y�v�́A�S���ʂł̈��S�E���N��N�I���e�B�E�I�u�E���C�t(�����̎�)�ɑ���f�W�^���o�ς̊�^�A���҂̏[���x�𑪂���̂ł��B
�E�u���Ȏ����j�[�Y�v�́A���Ȃ̃X�L���E����̌���E��V�̍����d����@��̑����ւ́A�f�W�^���o�ς̊�^�A���҂̏[���x�𑪂���̂ł��B
�E�u�Љ�ۑ�����j�[�Y�v�́A�f�W�^���Z�p���Љ�ۑ��n���K�͂̉ۑ�̉�����V�����d���ݏo�����Ƃɍv�����Ă��邩�ǂ����ɂ��ẮA�l�X�̔F���𑪂���̂ł��B
|
��
�� Oxford Economics
1981�N�ݗ��B���Ԃ̓Ɨ��n�}�N���o�σV���N�^���N�Ƃ��Ă͐��E�ő��250���̃G�R�m�~�X�g�E�`�[����i����B80�J���ȏ�̑��ݍ�p���l���������E�}�N���o�σ��f�����x�[�X�ɁA200�J���ȏ�E100���̎Y�ƃZ�N�^�[�E��4�A000�s�s�Ɋւ���o�ώ��ԁE�\���̃f�[�^����Ă���B
�������T�v
���n����(�f�W�^���E�\�T�G�e�B�E�C���f�b�N�X�E�T�[�x�C�qDSI�T�[�x�C�r)�́A2018�N7�`8���ɁA24�J���A43�A000�l�ȏ��ΏۂɎ��{�B�Ώۍ��́A�A�W�A�����m�͓��{�A�I�[�X�g�����A�A�V���K�|�[���A�����A�C���h�A�^�C�A�ďB�͕č��A�J�i�_�A���L�V�R�A�u���W���A���B�͉p���A�h�C�c�A�t�����X�A�f���}�[�N�A�I�����_�A�t�B�������h�A�m���E�F�[�A�G�X�g�j�A�A�A�C�������h�A�X�y�C���A�C�^���A�A�|�[�����h�A�n���K���[�A���V�A�B�����Ώێ҂̒��o�ɓ������ẮA�e���̐l���\���ɍ��킹�đ�\����ۂĂ�悤�T���v�������B�u�f�W�^���Љ�w�W�v(DSI�X�R�A)�̎Z�o�ɂ́A��L�ɉ����ēf�[�^(��������)�𗘗p�B�f�[�^�͍ł��M���x�̍����f�[�^��(Oxford Economics�A���E��s�A���A�Ȃ�)�����s�����ł����߂œ���\�Ȃ��̂𗘗p�B�w�W�̐v�́A���ׂĂ̍��ڂŋϓ����d��K�p�B�u�f�W�^���j�[�Y�[���x�v�̎Z�o��DSI�T�[�x�C�݂̂𗘗p�B
�@ |
 |
|
���Ȋw�E�Z�p�̑������̎�@ �@ |
��1. ��i�̖ړI���������
��i�̖ړI���Ƃ́A�{�����̐��ʂ邽�߂̎�i�ł���s���ɂ��āA���̍s������ �邱�Ǝ��̂�ړI�Ƃ��Ă��܂��Љ�s���̂��Ƃł��B
���Ƃ��A�u�ړI�͉��Ȃ̂��B�v�l���o���Ƃ킩��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B�q������ ���Ă��鎞�A���̂��߂Ɏ����Ă���̂��낤�Ǝv����������܂��B�����̒��ł͂������ �����ړI����������Ȃ��̂ł��B�܂�A�u�����āv����̂ł͂Ȃ��A����ɂ܂����āu�{ ���āv���邾���Ȃ̂ł��B�ړI������A���̒B����i�Ƃ��āu����v�Ƃ����s�ׂ������ ���B�ړI���ł��Ȃ����A����͊ԈႢ�Ȃ��u�{���āv����̂ł��B�l���܂߂Ĕ��Ȃ� �Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ꂪ�Ȋw�^�Z�p�̊J���ƂȂ�A���͂���ɐ[���ł��B��i���ړI�����Ȃ��悤�� ��@�������ŏЉ�܂��B�Ȃ��A�ړI��B������Ƃ����ϓ_����́A��i�̖ړI���͖ړI ���������đ��������ʂł���Ɣᔻ�������������܂����A���Ƃ��ĕ����́A���̂悤 �ȌX�������������Ă���A��T�ɔᔻ�ł��Ȃ����ł�����A����_������̂͊m���� ���B
���ړI�Ǝ�i
�ړI�Ƃ́A�������u�ڎw�����Ɓv�ł���A���ׂĂ̖ړI�́A�ړI�|��i�̘A���̒��ɂ� ��܂��B��i�Ƃ́A�ړI�����̂��߂�(�g����)�K�v�Ȃ��ׂẮu����A�藧�āv������ �܂��B�����A�g����(�K�v��)��i��������I�Ɍ��߂��Ă͂Ȃ�܂���B�ړI�����ɗL ���Ȃ�A���ׂĂ͎�i�ƂȂ肤����̂ł����A���ׂĂ��������ԓI�A�R�X�g�I�]�T�� ���邱�Ƃ͏��Ȃ����߁A�u�ǂꂪ�ړI�����ɗL�����v�D�揇�ʂ̂������K�v�ɂȂ�܂��B
���ړI�E��i���̗͂���
�I���\�ȋ�̓I�s�����x���܂Ńu���C�N�_�E�����Ă����܂��B�����ɗL���Ȃ��̂��A�� �������菇�Ŏ��{���Ă��������v�����j���O���Ă����܂��B
��1 �u�ړI�v����������ɂ́A�u��������������v�u�ǂ����邱�Ƃ��K�v���v�ƁA���̎�i��o���܂��B
���̏ꍇ�A�����Ȃ�ו��ɓ�����A�����܂��ɕK�v�Ȃ���(���̖ړI�B���ɕK�v�ȗv�f�A�K�v�ȗv���A�K�v�Ȏ����A�K�v�Ȗ������X)��o���A��������邽�߂ɕK�v�ȍs ���A�����A�@�\�A��p��\�����܂��B
���Ƃ��A��c�𐬌�����̂ɕK�v�Ȏ�i��o���O�ɁA�����܂��ɁA�u�J�ÖړI�v�u�c��v�u�l�v�u���͋C�v�u�i�ߕ��v�u����v�u���s�v�Ƃ��������ڂ������A�u�J�ÖړI�� �m�ɂ���v�Ƃ��u�S���Ɏ��O�ɉ�c�ړI��m�点��v���Ƃ������\���ɒu�������Ă����܂��B���̍�Ƃ�ʂ��āA�ړI�|��i�̑�܂��ȏ㉺�W���}�����ł��܂��B
��2 ��i�́A(�����Ƃ���)�u�`���`����v�ƁA�u�����v�{�u�������v�ŕ\�����܂��B
�u���`���Ă���v��u�`���`�Ȃ��Ă���v�Ƃ����������ł́A��̓I�ɉ���������Ƃ� ���ӎv�������܂���B�����ł́A���͎��̂�ړI�Ƃ�����Ƃ����Ă���̂ł͂���܂���B �����́A���ꓮ��A�ɕ����܂��傤�B
��3 �d�����Ƃ̎菇�E�i�ߕ����ӎ����܂��傤�B
�ړI�E��i�̐o���́A�ړI�����Ɍ������X�g�[���[�Â���(�N���]���A�������o���A�� �₷���ێ����遨���炷)���ǂ��ݒ肷�邩�A�ɂ���܂��
�E�o�c�b�`(Plan���co���bheck��Action)�A�o�c�r(Plan���co��See)(�������A�o�c�b�`�́A�o���Ȃ��c�b�`�̂݁A�`���Ȃ��o�c�b�̂݁A�c���Ȃ��Ăo�b�̂݁A��������܂�)
�E�u���ōl����v���u�������H�v����v���u�`�F�b�N�̎d�����H�v����v���u�ċN������v
�E�u�v��𗧂Ăāv���u�v��ʂ���s���v���u�v��Ƃ̈Ⴂ���`�F�b�N���v���u�v��ɖ߂��v
�E�u�m�F����v���u�I������v���u��ɓ����v���u�`�F�b�N����v
�E�u���o���v���u�]������v���u�I������v���u���s����v
�E�u�����v���u�v���Z�X�v���u�o���v
�E�u�q�g�v���u���m�v���u�J�l�v���u�g�L�v
���Ƃ��A�u�E��̃R�~���j�P�[�V�������悭����v�Ƃ����Ƃ��A�u�R�~���j�P�[�V�� ���Ƃ͉����v�u�悭����Ƃ͉����v�u�ǂ�������Ԃ��K�v�Ȃ̂��v�u�u��������҂��K�v �Ȃ̂��v�Ƃ������^�₪�o����A��������̂܂܁A�K�v�Ȏ�i�ɁA�Ƃ肠�����u�������� �݂�(�����̌�ŁA��������A�u����������肷��)�̂��悢�ł��傤�B
��4 ���l�ł͂Ȃ����������邱�Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
��i���͂͂��ꎩ�̂��ړI�ł͂���܂���B����ɂ���ĖړI�����̎�i��o���A �����ւ̋�̓I�s���ɂȂ��邱�Ƃ��ړI�ł��B���̈Ӗ��ł́A��i���͎ҁ����s�҂ł� �邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B
��5 �ړI�|��i�̐o�����K�����ǂ����̃`�F�b�N�E���̎�i������A�ړI���B���ł���̂���₢�����A���ڂ̖ړI�|��i�̊W���`�F �b�N���܂�
�E���̎�i�̖ړI�͉�����₢�����āA���ڂ̖ړI�|��i�̊W���`�F�b�N���܂�
���Ƃ��A�u���̎�i���Ȃ�(��߂�)�ƍ��邱�Ƃ͉����v�u���ꂩ����҂ł��邱��(�� ���N���邱��)�͉����v�u����͉��̂��߂ɓ����Ă��邩�v�u����ɂ���Ăǂ��������� �ɂȂ邩�v�u���̎�i�̂��闝�R�͉����v���X�ł��B
��6 �ړI�|��i�̌n�̐������𐮂���
�ו��ɂ��������A�S�̗̂����̌n�����邱�Ƃ��s�����܂��B�S�̐}����Ղ��Ȃ� ��A�ړI�|��i�̐�����(�ړI�Ǝ�i���e�q�W�Ƃ��ēK��)�𐮂��Ă��������S�̂� �\�����݂₷���Ȃ�܂��B���Ƃ��A�u���ʂ���v�Ƃ����ړI�̎�i���͂�����ꍇ�A�� ����x�̌n�������Ƃ��A�������̃k�P���킩���Ă��邪�A��������Ă��������l���Ă� ���ŗ����~�܂�A�S�̑���`���čl����ƁA���Ƃ��u���b�̋z���v�Ƃ�������i������ �}���ł��Ă��Ȃ����ƂɋC�Â����肷����̂ł��B
����i���͂�����{��i����̉�����
��1 �s����I���\�ȂƂ���܂ŋ�̉�����
�u��ʖړI�v��B�����邽�߂̎�i��W�J�����A�ʼn���(�ǂ����ʼn��ʂ��͓W�J���Ă��� ���̂ɂ��)�̎�i�́A���̓I�ɕ����̕��@����A���̂ǂꂩ��I������������s �\�ȂƂ��룂܂ŁA��̉�����Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
��2 ��̓I�ȍs����I������
�e��i���������邽�߂ɁA������A�ǂ�����Ă���Ă��������A�D�揇�ʂ����A�I���A�� �肵�Ă����܂�����̏ꍇ�A�����I�Ȏ��s�\�������łȂ��A�������悤�Ƃ��Ă���u�ڕW�v �ɏƂ炵�āA�K�v�s���ȍs�����Ȃ����Ƃ���ł��B�����łȂ��Ă͉��̂��߂ɂ� �̕��͂������̂��̈Ӗ����Ȃ��Ȃ�܂��B�����̂ނ��������͂����Ă��A�ڕW�����ɂǂ� �����A�N�V�������K�v���̎��_��������Ȃ����Ƃł��B
��3 �����m�ɂ���
�N(�ƒN)���A�����A�ǂ��ŁA�����炢�܂ŁA�ǂꂾ���A�ǂ������菇�œ��X������ ���Ă����ɓ������āA
�s�O������t�ǂ��������Ƃ�O��ɍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ���
�s��������t�ǂ�Ȑ����邩
�s�g�p�����t�ǂ������A�����ŁA���s���Ȃ��Ă͂����Ȃ���
������A���m�ɂ��Ă������Ƃ��ł��܂��B����ɂ���āA�I�����s���|�C���g�Ɍ��肳 ��܂��B
|
��2. �Z���Ɗw��
�Z���Ƃ́A�����̈قȂ��ȏ�̂��̂��Ƃ��č��킳��ЂƂɂȂ邱�Ƃƌ����� ���܂��B�Ⴆ�Δ_�w�ƍH�w�̗Z���ɂ��A���H���V�G�l���M�[�̊J���Ȃǂ��������� ���B�܂��A�w�ۂƂ́A�����Ȃǂ��������̈قȂ�w�╪��ɂ܂������Ċւ��l�q���� ���Ă��܂��B�����̌��t�Ƒ������Ƃ̊W�͈�T�ɂ͌����܂��A���Ȃ��Ƃ��u���y �̒m�v�̗̈�ɂ����ẮA�Z����w�ۂ����L���A���G�ō��x�ȉȊw�^�Z�p�̈Ӗ���L�� �Ă���ƍl�����܂��B�܂��w�ۓI�ȕ����Z�������Ŏ��g�ނƂ������\��������܂��B
���Z��
�Z���Ƃ�������̈قȂ���̂��A���̋��E���Č����Ɏ��g�ނ̂́A���E������ �ɍs���̂ł͂Ȃ��A�V�X�e���Ƃ��ėL�v�ȖړI�����邩��ł��B���E�ɂ���ĕ����ꂽ�� ���̃Z�N�^�[�̗��Q����v���邱�Ƃ���ł��B
���E������Ƃ������Ƃ́A�R���Z�v�g��p�ꂪ�킩��Ă���Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�܂���B �������̎v�l���@�A������@�Ȃǂ��قȂ邱�Ƃ���������܂��B�v�l���@�A��@�́A�� �̕���ɂƂ��Ă��L�v�Ȃ��Ƃ����������邽�߁A�����ɓ��ꂷ��K�v�͂���܂��A�� �ʂ̃R���Z�v�g�A�ڕW�̊m����p��̓�����\�Ȍ���s�����Ƃ��]�܂����ł��B
����ɁA���E���������c�[���̊J������ł��B������i�߂��ł��A���ʂ�]�� �����ł��A�����A���؎����͕K�v�s���ł��B
�앨�ɗL�p�Ȑ��͐��������ʂ��K�v�ȃc�[���ł����A�앨�ɗL�p�ȓy�ƂȂ�A�������A ���w�Ȃǂ̎ړx���K�v�ƂȂ�܂��B�������A�ŏI�I�ɂ͎��̂悢���S�Ȕ_�앨�ƂȂ�Ƃ� �̕]���ړx�͔_�Y�����̂��̗̂ʂƎ������ƂȂ��Ă��܂��B���ʂ̃c�[���������邱 �Ƃ͈ӊO�ƍ�����ꍇ����������܂��B
�����āA���E���������ɂ́A�����̍œK���ł͂Ȃ��A�S�̂̍œK�����K�v�ƂȂ�� ���B���̂��߂ɂ͕����̍œK����}������A�g�ݍ��킹���H�v�����肷�邱�Ƃ��K�v�ɂ� ��܂��B�܂��]���ƂȂ�悤�ȑ㏞���V���Ɏx����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�������� ���B�S�̂���Ղ���A�ώ@����͂��K�v�ƂȂ�܂��B
���w��
�u�w�ہvinterdisciplinary�Ƃ́A�{���A�w��̈���̈�Ƃ���ɗאڂ��鑼�̗̈�̊Ԃ� ���݂��钆�ԗ̈���Ӗ����܂��B���������āA���̒��ԗ̈�̌��������݂悤�Ƃ���̂� �w�ۓI�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
��������ʓI�ɂ́A�w�ۓI�����́A��̖ړI�ƊS�̂��ƂɁA�����̗אڂ���w��� �悪���Ƃ��Č���������̂Ƃ���Ă��܂��B���ۂɋ��ƓI�����Ɋ�Â��w�ۓI�����́A�� �Q��肩�畽�a�����A����ɉF���J���Ȃǂ��܂��܂ȗ̈�ɂ����čs���A����Ȃ�̐� �ʂ���������܂��B
���������w�ۓI�������v�������w�i�ɂ́A����܂łɐ�剻�A�ו�����i�s�����Ă� ���w��݂̂ł͂Ƃ��Ă��Ώ��ł��Ȃ���肪�����̎Љ�̂Ȃ��ŕ��o���A�����̉𖾂� �}���Ƃ����悤�ɂȂ������Ƃ��������܂��B����䂦�ɁA�Љ��̌����I�v���͊w ��̑������u���ݏo���A�e���̈�ɂ����ĒB�����Ă������ʂ̌��W���������߂邱 �ƂɂȂ��Ă��܂��B
����A�w�ۓI�����͍L�͂ȕ���ɂ����Ă��̕K�v�������߂邱�Ƃ͂����܂ł�����܂� ��B�������A�������ɂ����ďd�v�Ȃ��Ƃ́A�ǂ̊w��̈�����Ƃ����邩�Ƃ����_�ł���A �����̋�̓I�ړI�ɂƂ��ꂷ���ċ��Ƃ͈̔͂����Ȃ����肷�邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɒ��ӂ� ��K�v������܂��B�܂�A�e�����e�[�}�ɑ��āA���R�A�Љ�A�l���̊e�Ȋw��ԗ��� ���ِ��ԋ��Ƃ�}�肤��悤�w�͂��邱�Ƃ��K�v�ł��B
�w�ی�����i�߂��ŁA�ŏ��Ɏ��g�݂₷�����@���Љ�܂��B
��1 �u���z���M�v�A�v���[�`
�Ⴆ�A�قȂ������p����g�p���Ă��鎩�R�Ȋw�Ɛl���E�Љ�Ȋw����̋����Ƃ��āA �ۑ�̂��錻�������ꍇ�A�S�s���s���A���ׂẴC�x���g�����L�̌�����u�� �S�ȋ����v�t�B�[���h����������܂��B�Q���ґS�����A�ӌ����������A�c�_�����L����� ���m�ۂ��ĖڕW�Ɖۑ�����L����̂ł��B
��2 �s���|�C���g�E�A�v���[�`
�œ_���i�����w�ۓI�����ɂ��A���l�Ȍ������I�ɑ����A���ʓI�ɉ��߂��A��I �Ȑ헪����邱�Ƃ��ł��܂��B�������A���l�ŕ��G�A���c��ȑΏۂ𑽖ʓI�ɕ��� ���邱�Ƃ͎����I�ɍ���ȂƂ��������܂��B
|
��3. ���Ɛ쉺
���Ɛ쉺�Ƃ������t�́A���ډ͐�ɂ�����㗬�Ɖ����Ƃ����W�ɂƂǂ܂炸�A���Y �҂Ə���ҁA�_���Ɠs�s�̂悤�ȊW�ɂ��Ă��g���邱�Ƃ�����܂��B�Ȋw�^�Z�p�� ����������ꍇ�ɂ��A�L�����Ղ��邽�߂ɂ́A���̐��Ɛ쉺�Ƃ������_�ł̑��������� �ɂȂ�܂��B
���쉺�ɂ���s�s�����̉��b�͐�オ�x���܂��B�����Ɍ������Ȃ������̏㐅���̐����� ���ߍH�Ɨp����_�Ƃ̂����p������ォ�痬�ꉺ��͐�Ɉˑ����Ă��܂���܂���L�� �ȐX�т�͐�́A���Ǝ����̈琬�ɂ��𗧂��Ă��܂���ߑa���ƍ�����i��Ő�㗬�悾 ���ł͎x������Ȃ��Ȃ������y�̕ۑS����Ɛ쉺����̂ƂȂ��Ģ����P�ʣ�ő��݂� �x�������V�X�e���Â��肪�i��ł��܂��
�s�s������ͤ�L���Ȏ��R���_�y��ŗt���Ƃ܂�Ȃǂ����ꂽ�`���|�\�����߂Ă����� �̋�ԂƂ��ēs�s�Ɣ_�R�����𗬂������܂���܂����ėǑ��łͤ�s�s���Ƃ̌𗬂�R���� ��������ڎw������[�L���O�z���f�[��ȂǎR���������̐V������g���͂��܂��Ă��܂�� �O���[����c�[���Y���̂��˂肪�{�茧�ɍL�����Č𗬂̗ւ��L���褍��y�����^���ɂ� �Ȃ���܂��
���Ɛ쉺����̂ƂȂ���. ���y�ۑS���x�������V�X�e���Â���. ���Ɛ쉺���A�g���� ���߂đ�͂��ێ�����邱�Ƃ�F������K�v������܂��B
���X�тƖ؍ނ̏z�����܂��Ă������߂ɂ́A�؍ނY������́u����v�Ɩ؍� �𗘗p����쉺�́u�܂��v�̘A�g���K�v�ł��B���̗���Ɍg�����X�̋Ǝ�͑��l�ł����A �����̋Ǝ�Ԃ̃l�b�g���[�N���[�������邱�Ƃ́A�e�ƊE�A�n���̊������ɂ��Ȃ��� �܂��B
���Y�ނ����Y����ďZ��ɗ��p�����܂ł̗�����A����Ɍg���Ǝ�Ƌ��ɐ}�Ƃ��� �����܂����B�܂��A ���̐}�͓����ɁA���݂̕W���I�ȍ\�@�Ō��Ă�ꂽ30�ؒ��x�̖ؑ��Z ��ɗ��p�����؍ނ��A�e�Ǝ�ɂǂ̂悤�Ɋ֘A���邩�������Ă��܂��B30 �ؒ��x�̓��{ �̈�ʓI�Ȗؑ��Z��ɒ~�ς���Ă����20m3�̖؍ނY���邽�߂ɕK�v�Ȋۑ��́A��2 �{��40m3�ł��B����́A�ۑ����琻�ޕi�������H����H���ŁA�������[�ނ₨�������Ƃ� �邽�߂ł����A�����́A�R����p���v�`�b�v���ɗ��p����܂��B
30�̖ؑ��Z��1���ɕK�v�ȗǎ��Ȋۑ����m�ۂ��邽�߂ɂ́A���{�̗ʂ̊ۑ����K�v�� �Ȃ�܂��B����́A���̂��ꂽ�ۑ��S�Ă����ނɓK�����ǎ��ȍނł͂Ȃ�����ł��B
����A���{�ōł��~�ϗʂ̑����X�M��7�`9�(31�`45�N��)�̐l�H��1ha������̒~�ϗ� �́A�S �����ςŖ�311m3�Ƃ���Ă��܂��B�����̐X�т���Ԕ��̍ۂɏo�����ۑ��� ���ޕi�Ɏg�p���邱�Ƃ�O��Ƃ��A�Ԕ��ΏۂƂȂ����؍ލސϊ�����A�ǎ��Ȋۑ��̊��� �����Ă���ƁA 30�̖ؑ��Z��1���ɕK�v�Ȋۑ����Y�o����ɂ́A��2ha�̐l�H�т��K�v�� �Ȃ�܂��B
������
��1 �n���E�n��̊�����
�؍ނ̐��Y�͐X�ю������L�x�Ȓn���ōs�������A�Z��⌚�z�ɒ~�ς����؍ނ́A ���̑������s�s���ɑ��݂��܂��B���������āA�X�сE�؍ނ̏z���������鎎�݂́A���� �܂ܒn���E�n��̊������ɂȂ���܂��B
��2 �؍ނ̏z�̒S����E��H�̈琬
�Z��⌚�z���������A�؍ނ̏z��K�ɕۂɂ́A��H�E�����Ƃ������Z�\�҂� ���ێ��Ǘ��E�X�V���������܂���B
�e�n�ɂ����ẮA�Z�\�҂���Ă邽�߂̐��Z���H�m���W�J����A�܂��A��H�E�H���X �Ɛv�ҁA�؍ޔ̔��ƎҁA���ދƎҁA�؍ސ��Y�҂̘A�g��͍����铮�����o�Ă��Ă��܂� (�u��̌�����؍ނł̉ƂÂ���v��)�B
���������������ɑ���s���ɂ��x���͍��܂ł��s���Ă��܂������A����́A�X�т� �؍ނ̏z���l�������L�����_�ł̎x�����K�v�ƂȂ��Ă��܂��B
��3 �����D�ǏZ��Ɩ؍ނ̏z��
���Y�ނ𑽂����p���邽�߂ɂ́A�Z��̎������Z�������ǂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪ �����܂����A�X�т̎���ۂ��Ȃ���z�����邱�Ƃ��l����ƁA�Z��̒��������͏d�v�� ���B�Z��̎�����30�N���x�ł́A�؍ނ��������鎞�Ԃ�����܂��A�Z��̎�����100�N �ɂȂ�A����ɗ��p����؍ނ��\���Ɉ炿�A���̖؍ނ��`�����Ă����X�т̊������� �ǍD�ȏ��ۂĂ܂��B�܂��A���������X�т��琶�Y�����n��ނ����p���邱�Ƃɂ��A �n��̑�H�E�H���X��ыƁE�؍ގY�ƂȂǑ����̊֘A�Y�Ƃ�ʂ����n��̊����������҂� ��܂��B
|
��4. �f�W�^�����̉Ȋw�^�Z�p�ɂ�����Ӗ�
����̓f�W�^���Љ�ƌ����Ă��܂��B�C���^�[�l�b�g���͂��߂Ƃ���IT���Ȃ킿��� �Z�p�̋}���Ȕ��W�Ԃ�߂�A�����������t���o�Ă���̂����R��������܂���B�� ��IT�͐����̂�����ʂɐZ�����Ă��܂��B
���f�W�^���Љ�̓����Ƃ͂����������ł��傤���B�֗��Ō����������A�Ƃ����_���܂��v �������т܂��B���Ă͐E��̏��ނ͂قƂ�ǎ菑���ł������A����𑗂�ɂ��X�ւ��� ���ł����B���̓p�\�R���ō쐬���A�d�q���[���ő���̂�������O�ł��B���ו�������� ���́A�̂̂悤�ɂ��������}���قɍs���Ȃ��Ă��l�b�g�Ō����ł��܂��B�N���ɋً}�̘A �����Ƃ�ɂ��A�g�ѓd�b�ł�����������܂��邱�Ƃ��ł��܂��B
�������܂�����A���֗̕����䂦�ɁA�������̐������ƂĂ��Z�����Ȃ������Ƃ͊m���� ���傤�B�x���ł��A���s���ł��A�d�q���[����g�ѓd�b�łЂ�ς�Ɏd���̘A���������� ���܂��B���ł��ǂ��ł��A�C�̋x�܂�ɂ͂���܂���B�܂��p�\�R���͂悭�̏Ⴕ�܂� ���A�l�b�g���Ȃ���Ȃ����Ƃ�����܂��B��������Ɨ\�肪�����č������Ă��܂��܂��B �f�W�^���Љ�ł͕����t�@�C���̐����ނ��ꋓ�ɑ����A���̊Ǘ������ł���ςł��B�p �X���[�h�Ȃǂ��܂߁A�Ǘ��͌����Ƃ��Ď��ȐӔC�Ȃ̂ŁA�������肵�ċM�d�ȃf�[�^���� �����肵�Ȃ��悤�A��ɋC��z��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
�������ăf�W�^���Љ�ł́A�֗����ƈ����ւ��ɕs����X�g���X���܂����債�Ă����� �ł��B����A�����Č����A�������͍���A�u�Z�������邽�߂ɖZ��������v�Ƃ������� �z�Ɋׂ��Ă͂��Ȃ��ł��傤���B
���f�W�^���Ƃ͉���
�p��̃f�B�W�b�g�Ƃ́u�w�v�̂��Ƃł��B�w��܂��Đ����邱�Ƃ���A�f�W�^���Ƃ́u���v ��\�����t�ł��B�ł�����A�f�W�^���Љ�Ƃ����͎̂��́u���l�Љ�v�ɑ��Ȃ�܂���B �R���s���[�^�Ƃ����̂͊�{�I�ɂ͐��l�������v�Z�@�B�ł���A���������ăR���s���[�^ �����p�����Љ�ł́A���̒��̂�����Ώۂ����l�ŕ\����邱�ƂɂȂ�܂��B
�ߔN�A�g�D��l�𐔒l�ŕ]�����A��r����X�������ɋ����Ȃ��Ă��܂����B���̂� �Ƃ͂�����s�ꌴ���ƌ��т��Ă��܂����A���ꂾ���łȂ��A�f�W�^�����Ƃ��[���W ���Ă��܂��B��ʓI�ȃf�[�^�ɂ��ƂÂ��ċ��������A�����_�����Ƃ������̂�I�����邱 �Ƃ��A�����Ƃ��q�ϓI�ō����I�ȕ��@���ƐM�����Ă��܂��B�������A�����ɗ��Ƃ����� �Ȃ��̂ł��傤���B
��Ƃł́A�悢���i��T�[�r�X����邱�Ƃ��A����グ�◘�v�𑝂��A�������� �肠���邱�Ƃ����ڕW�ƂȂ�܂��B�]�ƈ����A�����̋Ɛт̐��l�����コ���A�m���}�� �B�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�w�Z���������Ƃł��B���t�͊w���Ƃ̃R�~���j�P�[�V������ ��A���܂��܂ȕ]�����ނ��쐬���A���l�I�ȃf�[�^�������Ƃɒǂ��܂����܂��B �w���͂Ƃ����������̓_���������邱�Ƃ����ŁA�w�Ԋy�����Ȃǂǂ����ɍs���Ă��܂� �̂ł��B
�������ďW�߂�ꂽ���l�f�[�^�́A�R���s���[�^�Ŏ����I�Ɍv�Z��������A�\��O���t �̌`�Œ���܂��B���̌��ʂ����ƂɁA�Ăѐl�Ԃ̍s���v�悪���Ă��Ă����܂��B�� �܂�A�f�W�^���Љ�̒��S�͐l�Ԃł͂Ȃ��A������]����v�Z�����̃��J�j�Y�����̂��� �Ȃ̂ł��B�����l�Ԃ͂��ׂāA���̕��i�Ɖ����Ă��܂��̂ł��B����́A�����Ƃ��A �o�c�҂��A�J���҂��A����҂���O�ł͂���܂���B�`���b�v�����̃��_���^�C���Y�͓� �̘J���̋@�B����慎h�����f��ł����A���ł͒m�I�������ӂ��߁A�l�Ԃ̂����銈���� �@�B������Ă��܂��̂ł��B
���f�W�^���Љ�̓����́A�~�]���ی��Ȃ������Ă������Ƃł��B���������A�~�]�Ƃ̓f�W �^���ł͂Ȃ��A�i���O�Ȃ��̂ł���A�����x�݂������ƖO�a����̂����ʂł����B�� ��Ȃɂ����������y�����A��������t�ɂȂ�Ƃ����H�ׂ��܂���B�H�~�����łȂ��A�� �~�������~���������Ƃł��B�A�i���O�ȗ~�]�ɂ͐����I�ɃX�g�b�v��������̂ł��B���� �ǂ��~�]�́A�g�̓I�E�����I�ȃj�[�Y����ՂƂ��Ă�����̂́A�Љ�I�ȉe���̂��Ƃɂ� �����܂��B�����ăf�W�^���Љ�ł́A�~�]���ǂ��܂ł��c�����Ă������ꂪ����̂ł��B �S���~���ꉭ�~�A����ɕS���~�A�꒛�~�ƁA���l�̌��͂�����ł������Ă����܂��B�� �Ƃ̗��v���낤�ƁA�l�̏������낤�ƁA���l�𑝂��Ă�������Ɍ���͂���܂���B�A �i���O�ƃf�W�^���Ƃł́A�{���I�ȈႢ������̂ł��B
����̃W�F�l�������[�^�[�Y�̖v���ƃT�u�v���C�����[���̔j�]�́A���̈Ⴂ���ے��� �Ă��Ȃ��ł��傤���B�L���f���b�N�̂悤�ɔr�C�ʂ̑傫�����ȃN���}���^�]�������� �����̂́A�����I�ŃA�i���O�ȗ~�]�ł��B����́A������x�݂������ƖO�a���܂��B�� ���g�A�Ⴂ���A�A�����J�ő傫�ȃN���}����ď����o��������܂����A���炭 ����ƖO���Ă��܂��܂����B�A�����J�ł�1980�N�ォ��R���p�N�g�ŔR��̂悢�N���}�� ���߂���悤�ɂȂ�܂������A�W�F�l�������[�^�[�Y�̖v���̌����̈�́A�������� �A�i���O�ȗ~�]�̖O�a�ɑΏ��ł��Ȃ��������炾�ƍl�����܂��B���̌エ����ăR���p �N�g�E�J�[����������̂́A����҂̃j�[�Y���o�c�҂��Ƃ炦���Ȃ����킯�ł��B
����A�T�u�v���C�����[���̔j�]�͂܂��������i���قȂ�܂��B����͓y�n��Ɖ��Ƃ� ���A�i���O�ȕ������A�،����i�Ƃ����f�W�^���Ȑ��l�ɕϊ�����A����𑀍삵�čی��� ���l���肠���Ă������Ƃ��ړI�ƂȂ�܂����B�c��ȓ��̓f�[�^�ƕ��G�Ȍv�Z���ɂ��� �Â��A�R���s���[�^�̂Ȃ��ŎZ�肳�����Z���i�̉��i�ϓ��́A�N�ɂ��\�������܂���B
�f�W�^���ȗ~�]�ɂ͎��~�߂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B���̌��ʁA���낵���j�]�� �N���Ă��܂��܂����B���̐ӔC���A�����Ƃ���Z�ƊE�����ɕ��킹�邱�Ƃ͂ł��܂���B
�������܂ł��Ȃ����Z��IT������ɂ͕s���ł����A�g�D��l�𐔒l�ŕ]��������@�� �L���ȏꍇ������ł��傤�B�����������͂����܂ŁA�������ł�������l�Ԃ���� �悢�����������邽�߂̂��̂ł��B�����̗~�]�Ƃ͖{���̓A�i���O�Ȃ��̂ł���A�O �a���邩�炱���A�����͂���܂Ő����ė���ꂽ�̂ł��B
���l�����ɂ̖ڕW�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ��{���ɕK�v�Ƃ���ڕW�ɋC�Â��Ȃ��Ă͂� ��܂���B�l�Ԃ��@�B�����Ȃ�IT���A���܋��߂��Ă���̂ł��B
�Ȋw�^�Z�p�̑������Ɍ����Ă��A���R����A�h���A���R�̌b�݂̒��Œ��a�����c�݂� �l�Ԃ��{���K�v�Ƃ���ڕW�ł��邱�Ƃ��A�i���O�I�ɒm�邱�Ƃ���ł��B
|
��5. �펯�̔�펯
��펯�Ƃ́A�펯�I�łȂ����ƁA�Љ�\�����Ƃ��ĕK�v�Ƃ���鉿�l�ρE�m���E���f�� �������Ă��邱�ƁA�܂����̐l�̂��Ƃ������܂��B�������A�����ł́A�{��������O�ł� ��ƔF�����Ă����������A������_��ς���Ɣ�펞�ƂȂ邱�Ƃ�����Ƃ�������Řb�� ���܂��B
�����₶�̖�
�w������Ɓx�Ƃ͌����܂����A�w�j����Ɓx�Ƃ͌����܂���B����́w��Ɓx�͒j���Ȃ� ���́E�E�E�Ǝv���Ă��邩��ł��傤���B���ɂ�����܂��B�w����x�w���q�吶�x�w�� �В��x�w�w�l�x���x�ȂǂȂǁB��������ҁA��w���A�В��A�x���͒j���Ǝv���Ă��� ����ł����B
�t�ɁA�w����}�}�x��w���ӂ���̖��x�ƌ����̂́A�q���̋����H�������͕̂�e �̎d���Ƃ���Ă��邩��ł��傤���B���Ȃ��͂ǂ��v���܂����B�ꌏ������O�̂悤�ɔF �����Ă��Ă��A���ꂪ����Љ�ɂ����ẮA��펯�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���������܂��B�� �̂悤�ɍl������ƁA�܂��V���Ȕ��z�����܂�Ă�����̂ł��B
�����n�g���[�j���O�̓{�[�g�ɖ𗧂���
���n�g���[�j���O�Ƃ�2000�����̍��n�A������C���̎_�f�����̒Ⴂ�Ƃ���Ŏ�Ɏ��v �͂̃g���[�j���O�ƒ�`�ł��܂��B�ȋ�C���Ńg���[�j���O���邱�Ƃɂ��_�f�ێ� �\�͂����コ���A���̌��ʂƂ��Ď��v�͔\�͂����߂悤�Ƃ�����̂ł��B���̎��v�͌��� �͂ǂ̂悤�ȑ̂̏���������ꂽ���ʂ����l���Ȃ����Ƃɂ͂��ׂẴX�|�[�c�̎��v�̓g ���[�j���O�ɉ��p�ł��܂���B�悸���v�͂��\������v�f���܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�� ���B���n�g���[�j���O�ł͎�ɔx�̃K�X�����@�\�A�Ԍ���(�w���O���r��)�ʂ̑����ɂ� ��_�f�ێ�\�����߂邱�ƂɖړI������܂��B�������A�_�f�ێ�^��(�g�����X�|�[�e�[ �V����)�\�͂͌��N�ł���Ώ[���̗]�͂�����Ă��܂��B�܂�A�^�����͑̉��̏㏸�A ���t��pH�̕ω��ACO2���ɂ�閖���ł̌��t����̎_�f����(�_�f����)�㏸�A�x���C�A�S �����̑������X�ɂ��A���Î���20�{�͗e�Ղɉz���邱�Ƃ��ł��܂��B
�{�[�g�I���2000�����[�X���Ōċz����Ɋׂ葆���Ȃ��Ȃ����o���͂Ȃ��Ǝv���܂��B �܂�A�g�����X�|�[�e�[�V�����͑���Ă���̂ł��B�{�[�g�I�肪���n�g���[�j���O�� �ł��s���ĐԌ����𑝂₷�w�͂��ǂ�قnj��ʓI�Ȃ̂��l����ׂ��ł��B���̂��ƂŃ{�[ �g�̑I��ɂƂ��đ�Ȃ̂͌��N�ł���(�n���A�S�x�̕a�C�̗L��)���Ƃ��`�F�b�N���� ���Ƃő���܂��B
���ɍ��n�ł͔�J�𗭂߂₷���A���X�^�b�t�̊Ď��̂Ȃ��ł��Ȃ��Ǝ��s���鋰 �ꂪ����܂��B�g���[�j���O�ʂ��҂��Ȃ����߂Ƀ��[�e�B���[�[�V�����g���[�j���O���s �����邱�Ƃ��ɂ��ł��B
����ɑ����^��(���ɋZ�p�s���̏ꍇ)�ł͍��ʂ̂��ߏ[���ɑ傫�ȋؓ������đ� �����Ƃ͍��x�̋Z�p��v���܂��B���̂��ߍő�S����(HRmax)�������j���O���̂悤�ɐ� ���I���E�܂ŏ㏸���Ȃ����Ƃ������̂ł��B�܂�A�_�f�^���\�͂����\�͂𐧌����Ă� �邱�Ƃ͍l���ɂ����̂ł��B�t�ɑ�ʂ̋ؓ����������Ղ��Ǝv����X�|�[�c�̎��]�ԁA �����j���O�A���j���S�g�^�� �̎�ڂɂ����Ă͑�����荂�n�g���[�j���O�̌��ʂ����҂� ����ł��傤�B
���_�Ƃ��āA��n�Ń����O�𑆂��Ȃ��烆�[�e�B���[�[�V�����\�͂ƃe�N�j�b�N�����A �ؓ��̓����ʂ𑝂₷���Ƃɕ��̑I��͐�S����ׂ��ł��B
���펯�͂��ׂĎ̂ĂȂ���
�_�Ƃ̖ؑ��H�����͐�Εs�\�Ƃ���ꂽ�����S�̖��엿�A���_��͔|�𐬌������܂� ���B���̎���ɕĂƖ�̖��엿�A���_��͔|������A���R�͔|�̋Z�p�͂قڏI���_ �ɋ߂��Ƃ���܂ŗ����ƌ����܂��B���̖ؑ�����3�̒́A���̂悤�Ȃ��̂ł��B
��1 ���ׂĂ͊ώ@����n�܂�܂��B�����ƌ��Ă��邱�Ƃ��厖�ł��B
��2 �_�Ƃł͔�����Ȃ��̂������I�Ȃ��̂ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
��3 �����قǃo�J�ɂȂ��Ď��g�߂ΕK�������͌�����܂��B
�ؑ����̔��ł́A�����ĎG����L�ѕ���ɂ��Ă��܂��B�����ł��邾�����R�̏�Ԃɋ� �Â��邱�ƂŁA�����ɖL���Ȑ��Ԍn�����܂��Ƃ����܂��B�Q����H�ׂ�v�����ɐB���� ���ƂŁA�Q���̔�Q�͑傫���Ȃ�܂���B����ɁA�t�̕\�ʂɂ����܂��܂ȋۂ��������� ���ƂŁA�a�C�̔������}�����܂��B
�ؑ�������邱�Ƃ́A�l�H�I�ɂ����Ă�̂ł͂Ȃ��A����{�������Ă��鐶 ���͂������o���A�炿�₷�����𐮂��邱�Ƃ������ł��B�Q���̗��������������ƌ��� �Ύ�Ŏ��A�a�C�̂܂�h�����߂ɂ͐|���U�z����B���ׂẮA�O�ꂵ�����R�ώ@�� �琶�܂ꂽ�ؑ����̗��V�Ȃ̂ł��B
�u���͔̍|�͖ڂ��_��ł���A�엿�Ȃ�ł��v�������܂Œ����s���8�N�ԁA�ؑ����_����엿���g��Ȃ��͔|���m������܂łɂ́A�����s��Ȋi��������܂����B�� �āA�_����g���Ă����ؑ����B�������A���̔_��Ŕ畆�����Ԃꂽ���Ƃ����������ɁA �_����g��Ȃ��͔|�ɒ��킵�n�߂܂����B�������A3�N�����Ă�4�N�����Ă���͎� ��܂���ł����B�����̖����Ȃ����ؑ��́A�L���o���[�̌Ăэ��݂�A�o�҂��Ő������ �҂��������ł��B���̎G���ŐH����߁A�q�������͏����ȏ����S����3�ɕ����� �g���ɕn�����ƂȂ����悤�ł��B6�N�ڂ̉āA��]�����ؑ��͎������ӂ��܂����B���[�v ��Ў�Ɏ��ɏꏊ�����߂Ċ�؎R�����܂���������ł��B�����łӂƖڂɂ����h���O���� �ō͔|�̃q���g�����ށB�u�Ȃ��R�̖ɊQ�����a�C�����Ȃ��̂��낤�H�v�^��Ɏv���A ���{�̓y���@�肩�����ƁA��Ō@��Ԃ���قǏ_�炩�����������ł��B���̓y���Č����� �A�������̂ł͂Ȃ����H
�����A�R�̊��ōČ����܂����B8�N�ڂ̏t�A�ؑ��̔��Ɋ�Ղ��N����܂����B����ʂ��s������̉ԁB����͖L ���Ȏ�������A��]�̉Ԃł����B
������O�̂��Ƃ�������O�łȂ��Ȃ����̂����̔_�Ƃł��B�͎̂���ݗp�̃C�l�͗D�� ���E�����܂����B�E���̎��ɂ��݂̏������Ƃ��납��G�ۂ�����ƁA���ۂƂ����a�C ���������A�s����◧���͂�a���邩��ł��B���̒E���́A�R���o�C�������̉�] �Ŕ\���ǂ��������܂��B����݂������Ȃ����߂ɂ́A�R���o�C���̉�]�������}���Ă� ��悢�̂ł����A��������܂���B
�_�Ƃł͕a�C��h�����߁A����݂̏��ł��s���܂����A�݂Ȗ��R�Ɛ̂������Ă��� ����Ɠ����܂��B�h�~����ɂ͉����I�≷�����ł�����܂����A���͓D��(�y���)�ōs ���܂��B�C�l���̍ő�̃|�C���g�́A�K���c���������Ă���t�ɍk�N���邱�Ƃɂ���� ���B�c�N�����Ɏ������y�ł͎��s���܂��B�������c�͍D�C���ۂ������܂��B���ɂ͓y��� �����Ŋ���p���z���ł��܂��B���肠��̂悤�Ƀg���g���ɂȂ�܂ő�~�������� �l�����܂����A������l�Ԃ̏���ȑz���ł��B�e���ȕ����ԈႢ�Ȃ��悢�̂ł��B �Ȋw�^�Z�p�̑������ɂ���펯�Ȏ��_���K�v�ł���ƍl���܂��B �@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |



|

 �@ �@
 |
|
��GAFA (�K�[�t�@)�@ |
 |
|
��GAFA 1�@ |
���E�I�Ɍl�f�[�^�����|�I�ȋK�͂ŏW�߂Ă��鏟���g��Ƃ̂��Ƃ������܂��B����́A�����G���W����N���E�h�Ȃǂ����uGoogle(�O�[�O��)�v�A�f�W�^���f�o�C�X(iPhone�EiPad�EMac��)��\�t�g�E�F�A�Ȃǂ����uApple(�A�b�v��)�v�A�\�[�V�����E�l�b�g���[�N�E�T�[�r�X(SNS)�����uFacebook(�t�F�C�X�u�b�N)�v�A���E�ő�̃l�b�g�ʔ�(�d�q�����)���^�c����uAmazon.com(�A�}�]���E�h�b�g�E�R��)�v��4�Ђ̓��������Ȃ����ď�(����)�ƂȂ��Ă��܂��B
�C���^�[�l�b�g����ɂ����āA�������M�A�������̗����Ȃǂ̖c��Ȍl�f�[�^����Ƃɒ~�ς���A���ƂɊ��p����钆�AGAFA�́A�l�f�[�^���W�Ċ��p����v���b�g�t�H�[�}�[�Ƃ��āA���ꂼ��̕���Ŏs���Ȋ����Ă��܂��B���̈���ŁA�s��ł̌����ȋ�����j�Q����Ƃ̌��O���オ���Ă���A���ہA���{�ɂ����ẮA2016�N12���ɐ��������u�����f�[�^���p���i��{�@�v�́A�f�[�^���p�Ɋւ���GAFA�ւ̊�@�����w�i�ɂ���܂����B
�@ |
 |
|
��GAFA 2�@ |
�O�[�O��(Google)�A�A�b�v��(Apple)�A�t�F�[�X�u�b�N(Facebook)�A�A�}�]��(Amazon)��4�Ђ̂��ƁB������������ď̂����B��������č����\����IT��Ƃł���A4�Ђ͐��E�������z�����L���O�̏�ʂ��߂Ă���B�܂��A���E���̑����̃��[�U�[��4�Ђ̃T�[�r�X���v���b�g�t�H�[���ɂ��Ă���B
�O�[�O���́A�����G���W����I�����C���L�����Ƃ��n�߁A�X�}�[�g�t�H���̊�{�\�t�g(OS)�ł���uAndroid�v��uPixel�v�u�����h�̃X�}�[�g�t�H���A�X�}�[�g�X�s�[�J�[�́uGoogle Home�v�Ȃǂ̊J������|�����ƁB�A�b�v���́A�X�}�[�g�t�H���uiPhone�v��A�^�u���b�g�uiPad�v�A�p�\�R���uMac�v�Ȃǂ̃n�[�h�E�G�A���[�J�[�ł��鑼�ɁA�N���E�h�T�[�r�X�́uiCloud�v��AiPhone��iPad�p�̃A�v���P�[�V���������uApp Store(�A�b�v�X�g�A)�v�Ȃǂ̊J���A�̔����s���Ă���B�t�F�[�X�u�b�N�́A���E�ő��SNS(�\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X)�ł���uFacebook�v���^�c���Ă���A�A�}�]���́A���E�ő�̃C���^�[�l�b�g�ʔ̃T�C�g�uAmazon�v���^�c���鑼�A�d�q�u�b�N���[�_�[�[���́uKindle(�L���h��)�v��A�X�}�[�g�X�s�[�J�[�uAmazon Echo(�A�}�]���G�R�[)�v�̊J���A�̔����s���Ă���B
4�Ђɋ��ʂ���̂́A��������v���b�g�t�H�[����Ƃł���_���B�v���b�g�t�H�[����ƂƂ́A���i��T�[�r�X�A��������ՂƂȂ��ƂŁA���E���̑����̃��[�U�[���A4�Ђ̒���T�[�r�X���v���b�g�t�H�[���Ƃ��ė��p���Ă���B�����ŏd�v�Ȃ̂́A���[�U�[�͒P��4�Ђ̃T�[�r�X�𗘗p���Ă��邾���ł͂Ȃ��A������Z���A�u�����w���������v�u���ɋ����������Ă��邩�v�Ȃǂ̌l����4�Ђɒ��Ă���_���B�����l���́A���������łȂ��A������ʐ^�A������n�߁A���p��ʐM�L�^�Ȃǂ̃��O�ƌĂ����̂��܂ށA��e�ʂ̃r�b�O�f�[�^�ƌĂ��f�[�^�ł���A4�Ђ́A�����r�b�O�f�[�^�͂����p���Ă���B���������āAGAFA�̃T�[�r�X�́A���[�U�[�̐�����֗��ŖL���ɂ��Ă������ʁA�l����Ɛ肵�Ă��邱�Ƃ����E�e���̌��O�ޗ��ɂȂ��Ă���B���{�ł́A2016�N12����GAFA�ւ̑R��Ƃ�������u�����f�[�^���p���i��{�@�v�����������B���@�ɂ���āA����̊�Ƃ�c�̂��f�[�^���͂����ނ��Ƃ��Ȃ��悤�ɁA���⎩���̂̃f�[�^��ϋɓI�ɖ��Ԃ��J����Ƌ��ɁA��ƊԂł��݂��̃f�[�^�����p���A���͌��������߂悤�Ƃ���u�I�[�v���f�[�^�v�ɂ��헪�𐄐i�A���H���Ă���B
����A���B�A��(EU)�ł́A18�N5���ɁuEU��ʃf�[�^�ی�K��GDPR(General Data Protection Regulation)�v���{�s����A�l���̎��W�A�J���A�ۊǂȂǂ��s�����Ǝ҂́A�f�[�^�ی�Ɋւ��鑽���̋`�����ۂ����邱�ƂɂȂ����B �@ |
 |
|
��GAFA 3�@ |
��GAFA�̈Ӗ�
GAFA�Ƃ́A����E���p�Ґ������Ⴂ�̋K�͂��ւ�O���[�o��IT���4��(Google�EApple�EFacebook�EAmazon)�̂��鑢��ł��B
4�Ђ̎������z��2018�N�ɂ�3���h��(���{�~�Ŗ�330���~)�ɂ܂ŏ��A���E�̑����̍��ɂ����Ă��łɎЉ�C���t���Ƃ��Ďs�������ɂƂ��Č��������Ƃ̂ł��Ȃ����݂ɂȂ��Ă��܂��B
GAFA��TV��j���[�X�̕Ȃǂł͈�ʓI�Ɂu�K�[�t�@�v�Ɣ�������܂��B4�Ђ̃C�j�V����(������)���Ƃ���GAFA(�K�[�t�@)�ł��B
|
��GAFA��Ƃ̊T�v
��GAFA��G - Google(�O�[�O��)
Google�̎�Ȏ��Ƃ͊F����������m�̂悤�Ɍ����G���W���ł����A����ȊO�ɂ��A���o�C��OS��Android(�A���h���C�h)�⓮�拤�L�T�[�r�X��Youtube�EGoogle�}�b�v�EGmail�Ȃǎ��ɂ��܂��܂ȃI�����C���T�[�r�X�̂قƂ�ǂ��Œ��Ă��܂��B
�ߔN�ł́A���Ѓu�����h�̃X�}�[�g�t�H���uPixel(�s�N�Z��)�v�⎩���^�]�Ԃ́uWaymo(�E�F�C��)�v�A�X�}�[�g�X�s�[�J�[�́uGoogle Home�v�Ȃǃn�[�h�E�F�A�J���ɂ��͂𒍂��ł��܂��B
�܂��A��O��AI�u�[���̉Εt�����ƂȂ�͌�̃v�����m��j�������Ƃł��b��ƂȂ����f�B�[�v�}�C���h��Google�̎P����Ƃ̈�ł��B
��GAFA��A - Apple(�A�b�v��)
Apple�̑�\�I�Ȑ��i�Ƃ����Γ��{�ōł����y���Ă���X�}�[�g�t�H���ł���iPhone(�A�C�t�H��)�ł����A���̑��ɂ��^�u���b�g�[����iPad(�A�C�p�b�h)�AWindows�Ƒo�����Ȃ��p�\�R��(iMac�EMacBook Pro)�ł��L���ł��B
�܂��AApple Watch(�A�b�v���E�H�b�`)�EApple TV(�A�b�v���e�B�[�r�[)�ȂNJ����x�̍����v�V�I�Ȑ��i�𐔑����肪���AApple�M�҂ƌĂ��M���I�ȃt�@���̑��݂�Apple�Ђ̎Е�����Ă��܂��B
�����n�[�h�E�F�A���Ƃ���ՂɁA�N���E�h�T�[�r�X�́uiCloud�v��A�v���̃_�E�����[�h���ł���uApp Store(�A�b�v�X�g�A)�v�Ȃǃf�W�^���R���e���c����ɂ��i�o���Ă��܂��B
Apple�ő�̋��݂́A�����n�[�h�E�F�A�ƃ\�t�g�E�F�A�̗Z���ƁA��z�����u�����f�B���O�y�у}�[�P�e�B���O�̗͂ɂ��Ƃ��낪�傫���ƕ]������Ă��܂��B
��GAFA��F - Facebook(�t�F�C�X�u�b�N)
Facebook�͐��E�ő��SNS�Ƃ��Č��ԃA�N�e�B�u���[�U�[��(����1��ȏネ�O�C�������l)��22���l�ȏ���ւ�Ȃǂ��łɕs���̒n�ʂ��l�����Ă��āA���E�̗��p�Ґ��͍����E���オ��𑱂��Ă��܂��B
�܂��AInstagram(�C���X�^�O����)��WhatsApp(���b�c�A�b�v)�Ƃ������X�^�[�g�A�b�v��Ƃ����X�Ɣ������Ă��邱�Ƃł��m���A���Ƀ��o�C���s��ɂ�����R�~���j�P�[�V��������ւ̓����ɐϋɓI�ł��B
����ɁA���E�̃A�v���_�E�����[�h�������L���O(2018�N�܂ł�10�N��)�x�X�g5�̂�����4���A�t�F�C�X�u�b�N�y�юP���̃C���X�^�E���b�c�A�b�v�EFacebook Messenger(�t�F�C�X�u�b�N�E���b�Z���W���[)�Ő�߂��Ă���A���͂�\�[�V�������f�B�A�̐��E�ł͈�l�����Ƃ܂Ō����Ă��܂��B
��GAFA��A - Amazon(�A�}�]��)
Amazon�̎�͎��Ƃ����E�ő�̃C���^�[�l�b�g�ʔ̃T�C�g�uAmazon.com(���{�ł�Amazon.co.jp)�v�ł���̂͊��m�̎����ł����A�ߔN�́u�l�Ԃł̏o�i�E������ł���}�[�P�b�g�v���C�X�v�u����E���y�E�}���K�Ȃǂ��ǂݕ���ɂȂ������T�[�r�X(Amazon�v���C��)�v�ł̔��オ�}�g�債�Ă��܂��B
�܂��A2018�N�̐��E���Ҕԕt�ɂ����đ����Y1120���h��(��12���~)�Ő��E��ʂɂȂ����W�F�t�E�x�]�X��CEO(�ō��o�c�ӔC��)�߂邱�Ƃł��L���ł��B
����ɁA�X�}�[�g�X�s�[�J�[�́uAmazon Echo(�A�}�]���G�R�[)�v�A���l�R���r�j�́uAmazon Go(�A�}�]���S�[)�v�A�d�q���ЃT�[�r�X�́uKindle(�L���h��)�v�ȂǐV�����T�[�r�X�����X�Ɣ��\���Ă��܂��B
|
��GAFA�̋��ʓ_
GAFA4�Ђɋ��ʂ��Ă���̂́A�L���Љ�ɐZ�����v���b�g�t�H�[����ƂƂ��Ă̒n�ʂ��m�����Ă���_�ł��B
���������v���b�g�t�H�[�}�[�͂��̈��|�I�ȊJ���͂Ǝ����͂Ŏs��̑啔����Ɛ肵�A���͂⎄�B�̐����ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��C���t���̈ꕔ�ƂȂ��Ă��܂��B
����ɁAAI�EIoT�Ƃ�����IT����݂̂Ȃ炸�A�ϋɓI�Ȋ�Ɣ�����ʂ��ċ��Z(�t�B���e�b�N)�E�h���[���E�w���X�P�A�Ȃǂً̈Ǝ�ɂ��i�o�����ꂼ��̎Y�Ƃɂ����Ĕe���������J��L���Ă���_�ɂ����ڂ��W�܂��Ă��܂��B
GAFA4�Ђ̎������z3���h��(��330���~)������GDP�Ɣ�r�����ꍇ�A1�ʃA�����J�E2�ʒ����E3�ʓ��{�Ɏ����h�C�c��C�M���X�ƕ��ԋK�͂ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A2018�N�ɂ�Apple��Amazon���������Ő��E���̎������z1���h���������ʂ����b��ƂȂ�܂������A���̋��z�͓��{�̍��Ɨ\�Z100���~�ɂ��C�G������̂ł��B
|
��GAFA�̖��_
GAFA�͂��̈��|�I�ȋK�͂Ń��[�U�[���͂����ݎs���Ɛ肵�Ă���Ƃ����w�E������Ă��܂��BGAFA�̉������Ȃ̂��H�ǂ�ȉe��������̂��H�����Ă�GAFA�̖��_�ɂ��ĉ�����܂��B
��1)�l���̈���
GAFA�̃T�[�r�X�𗘗p����ۂɕK�v�ƂȂ�A�J�E���g�ɂ́u�����E���N�����E�N���W�b�g�J�[�h���v�����łȂ��u�ǂ��������L�[���[�h�Ō������������v�u�����w�����A���ɋ��������邩�v�u�N�Ƃǂ�ȉ�b�����킵�����v�Ƃ������l��~�ς���Ă��܂��B
���������c��ȏ��̓r�b�O�f�[�^�ƌĂ�A���[�U�[�̎�n�D�ɍ��킹���������ߏ��ɐ��������ȂǁA�T�[�r�X�̌���Ɍ��������Ƃ̂ł��Ȃ��d�v�ȗv�f�ƂȂ��Ă��܂��B
�������A�ߋ��ɂ́u���疜�l�K�͂ł̌l���̗��o�����v�������ȂǁAGAFA�ɂ�����l���̈�����v���C�o�V�[�ւ̔z���̒Ⴓ���x�X�N���[�Y�A�b�v����Ă����̂������ł��B
��2)�ŋ�
����ɁAGAFA�ɑ�\����鑽����IT��Ƃ͓X�܂��\����悤�ȃI�t���C�����ƂƂ͈Ⴂ�A�I�����C���ł̃r�W�l�X�𒆐S�Ƃ��Ă��܂��B
GAFA�͂��������������ő���ɗ��p���A�^�b�N�X�w�C�u���ƌĂ��ɒ[�ɐŗ��̒Ⴂ���ɖ{�Ђ��ړ]����ȂǑ��Ǝ�ł͐^���̂ł��Ȃ�����Ȑߐō���u���Ă��܂��B
���̌��ʁA���ۂɎ��v���グ�Ă���n��Ɏ��߂�ׂ��������{���̐ŋ������Ȃ�����Ƃ��āu�ېœ���v�u�ŋ�����v�ł���Ƃ����ᔻ���x�X�������Ă���̂ł��B
|
��GAFA�ւ̑�
��L�̂悤�Ȗ��ɑR���邽�߁AGAFA�̖{���n�ł���A�����J�ȊO�̍��ɂ����āA���炩�̋K�������ׂ��ł���Ƃ����c�_�������N�����Ă��܂��B
�����{�̎��g��
���{�ł́A2016�N12���Ɂu�����f�[�^���p���i��{�@�v�Ƃ���GAFA���@�Ƃ������ׂ��@�Ă��������܂����B�����f�[�^�@�̊�{���O�́u�I�[�v���f�[�^�v�ƌĂ�A�l�f�[�^����������ŐϋɓI�ɗ����p��i�ߎЉ�̔��W�ɍv��������Ƃ������̂ŁA�����GAFA�ɂ��f�[�^�̈͂����݂ɐ^��������R������̂ƂȂ��Ă��܂��B
�����B�̎��g��
EU(���B�A��)��2018�N5���A�l���̕ی��ړI�ɁuEU��ʃf�[�^�ی�K��(�ʏ́FGDPR)�v�Ƃ������[���𐧒肵�܂����BGDPR�̔����ɂ��A���B�o�ό������O�Ғn��ւ̌l�f�[�^�̈ړ��͌����֎~�ƂȂ�A�ᔽ�����ꍇ�͑��z�̐��ً����ۂ���邱�ƂƂȂ�܂����B
���f�W�^���ې�
GAFA�̂悤�ȋ����IT��Ƃɑ��āA�����̔���̐����ړI�ɒ�������f�W�^���ېłƂ����c�_�����[���b�p�����𒆐S�ɐi��ł��܂��B�C�M���X�E�t�����X�E�X�y�C���Ȃǂ�M���ɁA���������f�W�^���ېł̓����ɑO�����ȓ����������鍑���o�ꂵ�Ă��܂��B
��GAFA����
�l���x���ł̑�ɓ����o���l�������o�n�߂Ă���ƌ����Ă��܂��B�����̗��ɉB���ꂽ���X�N�ɖڂ������AGAFA�̃T�[�r�X���p�𒆎~����A�ꍇ�ɂ���Ă̓A�J�E���g���ƍ폜��GAFA�Ƃ̈�̊W��f����Ƃ����A�܂���GAFA����Ƃ��ĂԂׂ��^���ł��B�uGAFA�Ɍl���������Ă���v�Ƃ����d��Ȗ��Ɍ����������߂̐V���������̈�Ȃ̂�������܂���B
�@ |
 |
|
���GAFA�̋��낵����@ |
Google�AApple�AFacebook�AAmazon�\�\GAFA�B���݂̐��E�ōł��e���͂�����̂��A������4�Ђ��B�����4�Ђ͎������̐����ƃr�W�l�X�̃��[�������{����ς�����A���ꂩ����ς�������Ƃ����B�����GAFA�̋����̔閧�𖾂炩�ɂ��A���̉e���͂Ɍx����炷���Ёwthe four GAFA �l�R�m���n��ς������E�x�����܁A���E22�J���ő��X�Ɗ��s����A�b����W�߂Ă���B�{����ǂ݁A�u�{���ɓ��{�̑��C���^�[�l�b�g��Ƃ���x���o�ꂵ�Ȃ����Ƃ��C�����肾�v�Ǝw�E���鉖�쐽���ɁA�ǂ݂ǂ����������Ă�������B
��
���Ȃ��̐����́u�n��̐l�Ԃ��E�����Ёv��^����ꂽ�u�l�R�m�v�ɃR���g���[������Ă���B���n�l�َ̖��^�ɂȂ��炦�Č���́u�l�R�m�v�Ƃ���鋐���Ƃ��A�l�X��GAFA(�K�[�t�@)�ƌĂԁB�����A���Ȃ����悭�m���Ă���A�O�[�O���A�A�b�v���A�t�F�C�X�u�b�N�A�A�}�]���ł���B
�wthe four GAFA - �l�R�m���n��ς������E�x(�摜���N���b�N����Ɠ��݃T�C�g�ɃW�����v���܂�)
�{���̒��҃X�R�b�g�E�M�����E�F�C���́A���l�Ȕw�i������w�������B�I�����C���ʔ̉�Ђ̊��������o�������N�ƉƁA�����ē����Ƃł���A����������������ł��낤�Q�[�g�E�F�C�E�R���s���[�^�̖����߂��o��������B
����ɁA�t�@�b�V�����u�����h�̃G�f�B�[�E�o�E�A�[�ł������߁A�j���[���[�N��w�o�c��w�@(MBA)�ł̓}�[�P�e�B���O�_�A�u�����h�헪�������Ă���B
���҂̂������I�����C���ʔ̉�Ђ̓A�}�]���ɂ���đ��̍����~�߂�ꂽ�Ƃ����B���҂��������s���A�o�c���v�ɏ��o�����j���[���[�N�^�C���Y�Ђ̃R���e���c�̓O�[�O���ɂ���Ĉ�u�ɂ��Č������ʂ̉���(����)�ւƔ���ꂽ�B�l�R�m����GAFA�����ɂ́A�M�����E�F�C���قǂ����Ă��̐l�Ԃ��Ȃ��Ȃ����Ȃ����낤�B
�{���́A�_�ɂ��[������قǂ̗͂����悤�ɂȂ���GAFA�ɂ��Ă̗͍삾�B���̗��j�ƃr�W�l�X���f�����ڍׂɕ��͂��AGAFA���x�z���鐢�E�Ŋ�Ƃ͂ǂ����ׂ����A�l�͂ǂ��w�сA�ǂ������L�����A��ڎw���ׂ���������Ă���BGAFA�Ȍ�̐��E�ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ́A����l�̕K�C�Ȗڂ��ƒ��҂͌����B
���҂�MBA��2�N���ɂȂ����w�������ɁA����ȍu�`���s���Ă���悤���B������MBA2�N�ڂ̎��Ƃ́A�����w�Ɏx������u�N���v�������x���邽�߂̃v���O�����ɉ߂��Ȃ��Ǝ咣���A�������m����������ׂ����Ǝw�E���Ă���B
�]�҂��l���ōŏ��ɐG�����R���s���[�^�́A1984�N�ɒa������Apple IIc�������B�O�[�O���̒m���x���܂��Ⴍ�A�C���^�[�l�b�g�E�G�œ����l�Ԃ������Ђ�m��Ȃ�����2000�N����ɂ́A���Ђ��O���O���ƌ���ČĂԐl�Ԃ����������B
����Ȍo�������̂ŁA���̌��GAFA�̔����I�Ȑ����A�����Đl�X�̐����X�^�C����ς���܂łɎ������e���͂ɂ��āA���������l���������Ă���B
�Ȃ��ނ�͂����܂Ő����ł����̂��H �ނ�̉e���͂̌��͂ǂ��ɂ���̂��H �ނ�͐��E���ǂ��ς����̂��H �ނ炪���݂��邱�ꂩ��̐��E�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��H �ނ�ɑ�����܂̋R�m�́A���̌㌻���̂��H
�]�҂��܂ޑ����̐l�����������ł��낤����ȋ^��ɁA�^���ʂ��瓚���Ă����̂��{�����B�Ƃ����Ă��A�{���̕��͂͊w�҂ɂ�錘�ꂵ�����̂ł͂Ȃ��BGAFA�ɂ��āA���́u�Z�N�V�[���v��u���킢���v�ɂ��Ă��������y���Ă���B
���Ƃ�����ȋL�q������B���҂̓A�b�v���̌̃X�e�B�[�u�E�W���u�Y���C�m�x�[�V�����G�R�m�~�[�̃L���X�g�̂悤�ȑ��݂��Əq�ׁA�A�����J���{�ƍ������A�b�v�����Â₩���Ă���ƌ���B�����āA�u�e�N�m���W�[��Ƃ��獂���u�����h�֓]������v�Ƃ����W���u�Y�̌�����A�u�r�W�l�X�j��A�Ƃ�킯�d�v�ȁ\�\�����ĉ��l��n�������\�\�����������v�ƊŔj����B
�Ȃ��Ȃ炻�̌���ɂ��A�A�b�v���Ƃ����u�����h�̐��i���������l�Ԃ́A���E�ōł��]�������A�u�C�m�x�[�e�B�u�Ȑl�Ԃł���v�Ƃ����]������悤�ɂȂ������炾�B���҂́A�A�b�v�����i���u���e�邽�߂̃c�[���v�ƌ����Ă�̂��B�����āA�i���ō��鐻�i�ɍ����t�����l�����邱�Ƃɐ��������Ƃ��āA�A�b�v�����]����B
����A���҂͊i���p�\�R���̃f�����g���Ă���悤�ł́A�ِ��ւ̃A�s�[���x�������邾�낤�Ƃ����A�f�����[�U�[�A�W�҂ɓ�������Ȃ�悤�Ȍ������q�ׂĂ���B
�܂��A�K�͓I�ɂ�GAFA��ڎw����ʒu�ɂ��钆����ƃA���o�o�ɂ��Ă��A�u�s���ȃK�o�i���X�Ɓw�e��Ёx�ł��钆���̈���ۂ̂��߂ɋ����݂ɂ����v�ƃu�����h���l�̗����w�E����B
GAFA�͎������̐����̃C���t���̂悤�Ȃ��̂ƂȂ�A��������GAFA�ւ̈ˑ��x�͍��܂������B�ނ�͎������Ƀ����b�g�����������炵�Ă����킯�ł͂Ȃ��B
�������́AGAFA�ɑ��āA�u�P�ǂłȂ��ƒm��A�ł��v���C�x�[�g�ȗ̈�ւ̐N���h���ɋ����Ă���v�̂��B������AGAFA�������|�I�ȃp���[�䂦���낤�B
���҂̓A�}�]�������{�e�B�N�X�ŕ��������q�ɕt���̌����G���W���A�����Ēn����ő�̓X�܂ƂƂ炦��B������������Ƃ��A�l�̓O�[�O���łȂ��A�A�}�]���Ō���������悤�ɂȂ��Ă���B�����ăA�}�]���́A���̃X�g�[���[�e�����O�̏�肳����A�������{���I�Ɏ�ɓ���Ă���Ǝw�E����B
�A�b�v���̃r�W�l�X���f���̊̂́A�O�q�����Ƃ���A�r�W�l�X�E�̏펯��ł��j���āA��R�X�g�̐��i���v���~�A�����i�Ŕ���̂ɐ����������Ƃ��낤�B
�t�F�C�X�u�b�N�͂ǂ����낤���B���҂ɂ��ƁA���E�l��75���l�̂����A12���l������35���̓t�F�C�X�u�b�N�����Ă���B���y���Ǝg�p������ɂ���A���Ђ͐l�ގj��A�ł��������Ă����Ƃ��ƒ��҂͌����B
�O�[�O���Ɏ����ẮA�u����l�̐_�ł���A��X�̒m���̌��ł���v�Ƃ��āA���j��A�����܂Ő��E���̂�����₢�������Ȃ��ꂽ���Ђ͑��݂��Ȃ������ƌ����B�����G���W���ɓ��͂���鎿���1���ɖ�35���B����6��1�́A����܂ŒN���₢�����邱�Ƃ̂Ȃ������₢���������B�O�[�O���́A����قǂ́u�M���v����g�ɎĂ���Ƃ������Ƃ��B
���|�I�ȗ͂�����GAFA�ł��邪�AGAFA�̓G�͂܂���GAFA���B�����܂߁A�����Ɉ٘_�������͏��Ȃ����낤�B�O�[�O���͐��i�̌����ŃA�}�]���Ƒ����A�t�F�C�X�u�b�N�͍L���̐��x�ŃO�[�O���Ƒ����Ă���BGAFA�͎������̐����̃I�y���[�e�B���O�E�V�X�e���ɂȂ�ׂ��A�݂��ɑs��Ȑ킢��W�J���Ă���ƒ��҂͎w�E����B
�����̃I�y���[�e�B���O�E�V�X�e���ɓ��荞�ޗ�Ƃ��āA�A�}�]���̃A���N�T�������A�L����ЁA����Ҋ�Ƃ̃u�����h�}�l�[�W���[�̏��ł҂͗\������B�A���N�T�͂��鎞����u���ɏ��i��������܂���v�Ɠ�����悤�ɂȂ�B�����Ď������́A�A�}�]���̃v���C�x�[�g�u�����h���悤�ɂȂ�̂��B
�܂��t�F�C�X�u�b�N�́A���Ȃ��́u�����ˁv��150���킩��A���Ȃ��̔z��҂������Ȃ��̂��Ƃ𗝉����A300���ɂȂ�A���Ȃ��ȏ�ɂ��Ȃ��𗝉��ł���̂��Ƃ����B���ꂾ���̉e���͂������f�B�A�ł���t�F�C�X�u�b�N�A�����ăO�[�O���́A���f�B�A�ł��邱�Ƃ����ۂ��A�u�v���b�g�t�H�[���v�ƌĂ�悤�Ƃ��Ă���B
�O�[�O���͂���w�A�_�ւƋ߂Â��A�l�X�̌�����������ƍߗ\���������s����悤�ɂȂ邾�낤�B����͉f��w�}�C�m���e�B�E���|�[�g�x�Ŕƍ߂�\������҂����A�v���R�O�����݂��鐢�E�ł���B�O�[�O���̂��鐢�E�ł́A�l�X�͓V���������ɁA���ނ��A�X�}�z�����āA�_�ɋF�������邩�̂悤�ł���B
���҂͐��ȗ͂��������l�R�m(GAFA)�ɒ��ޑ�܂̋R�m�Ƃ��ăe�X����E�[�o�[�Ȃǂ̉\�������͂��Ă���A�����[���B
���҂͌���������l����B�u���D�G�Ȑl�ԂɂƂ��Ă͍ō��̎��ゾ�B���������}�Ȑl�ԂɂƂ��Ă͍ň��ł���v�ƁB�{���̌㔼�ł͂���Ȏ���Ɂu�l���������邽�߂ɕK�v�ȓ��ʓI�v�f�v�ɂ��ďڏq���Ă���B����ȂȂ��A�������Ȃ��Ɂu���Ƃœ����X�L���v�������Ă���̂Ȃ�A���̕s�����Ȑ��E�ŋN�Ƃ��邱�Ƃ��I�����Ƃ��ċ�����B
����e�N�m���W�[��Ƃ������̐����ɓ��荞�݁A���Ȃ��̐S�̒��܂ŒT�낤�Ƃ��鎞�ゾ�B�{����ǂ�ŁA�l�R�m�̂��鐢�E�ɂ��ĊT�ς���̂������Ȃ��B�ނ��A�C���^�[�l�b�g�r�W�l�X�Ɋւ��l�ԂɂƂ��Ė{���͕K�Ǐ��ł���B�����Ė{���ɓ��{�̑��C���^�[�l�b�g��Ƃ���x���o�ꂵ�Ȃ����Ƃ��C�����肾�B
�������ꂾ���ɂƂǂ܂�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�l�R�m�̂��鐢�E��`�����{���́A�r�W�l�X�p�[�\�������łȂ��A������l�X�ɊW����B���ꂽ�^����`�����u�َ��^�v�Ȃ̂�����B�@ |
 |
|
��GAFA�ƃA�����J���́u�I���̎n�܂�v�@ |
S��P500(NY�_�E�ƕ��ԃA�����J�̑�\�I�Ȋ����w��)��2013�N�`2018�N9�����܂ł̏㏸���̂����A���ɂ���4����̓A�}�]���A�A�b�v���A�A���t�@�x�b�g(�O�[�O���̎��������)�A�t�F�C�X�u�b�N�A�}�C�N���\�t�g�A�l�b�g�t���b�N�X��6�Ђ������炵�����̂ł��B
���[�}���E�V���b�N�ȍ~�A���E�I�Ɍo�ϐ������̒ቺ���w�E����Ă���Ȃ��ŁA�����6�Ђ͐V�����r�W�l�X���f����z�����������Ƃ��āA�����Ƃ̎������ߏ�Ƃ�����قǂɏW�߂邱�Ƃ��ł����̂ł��B
�������Ȃ���2018�N10���ȍ~�A�����6�Ђ̊����͑����ĉ������������߂Ă��Ă��܂��B2018�N7~9�����̌��Z�͊T�ˍD���Z�Ƃ�������e�ł��������̂́A���v�����ቺ���Ă���Ƃ������Ƃ����ޗ�������Ă��܂��Ă��邽�߂ł��B
���Ƃ��A�A�}�]����A�b�v����10���ȍ~����̂킸��1�������Ŋ�����20���߂����������Ă��܂��B�w�b�W�t�@���h�͂�����IT���Ɏ������W�������A�s�ꕽ�ς����郊�^�[���邱�Ƃ��ł��܂������A10���̉^�p���т̓}�C�i�X6���ɐڋ߂���܂łɗ������݁A2008�N�̃��[�}���E�V���b�N�Ɏ����}�C�i�X�����L�^���Ă��܂��B
�����ƂɂƂ��Đ������ƈʒu�t�����Ă���IT���̖��͂Ƃ����̂́A���̗��v���̍����Ɠ���(�R�X�g)�̏��Ȃ��ɂ���܂��B�f�[�^�Ƃ������`���Y��ɔ���ȗ��v���҂�IT��Ƃ́A�d������Ȑݔ�������鐻���Ƃ̂悤�ɑ�K�͂ȓ�����K�v�Ƃ����A�f�[�^��Ɛ肷��r�W�l�X���f���ɂ���č������𑱂��Ă��Ă��܂��B
����ɂ�������炸�A�ߓx�Ȑߐłɂ���Đ����Ȑŋ���Ȃ����肩�A���̑��ƂƔ�ׂċɂ߂ď��Ȃ��]�ƈ��Ńr�W�l�X��������Ă��܂����߁A�Љ�S�̂ւ̊Ҍ��ɂ͏��ɓI�Ȏp������葱���Ă����̂ł��B
�Ƃ��낪�ŋ߂ł́A������IT��Ƃɑ��āA�Љ�Ƌ������邽�߂̃R�X�g�����߂��n�߂Ă��܂��B���B�𒆐S�ɉېł��������悤�Ƃ��铮�����L�����Ă������ŁA���グ�ɂ��R�X�g����Ď��E��o�̑�R�X�g���c���ł��Ă���̂ł��B
���Ƃ��A���v���]�ƈ���Љ�ɊҌ����Ă��Ȃ��Ɣᔻ����Ă����A�}�]���ł́A�A�����J�����̏]�ƈ��̍Œ����������15�h���Ɉ����グ��Ƃ�����������Ă��܂��B�啝�Ȓ��グ��11��1��������{����Ƃ������Ƃł�����A2018�N10�`12�������Z����R�X�g���ɂ�闘�v���̒ቺ�͔������Ȃ����ʂ��ł��B
���Ƃ��A�U�j���[�X�̊g�U���o�̖�肪���������t�F�C�X�u�b�N�ł́A�����̖��ɑΉ����邽�߂ɐV���ɎЈ������A���Ј�����2018�N9�����Ŗ�3��3600�l��1�N�O�̖�2���l����7���߂��������Ă��܂��B���܂��ɁA���N�ɓ����ăf�[�^�̕s�����p�����o�������Ȃ���A�l�f�[�^���O�҂ɓn���Ȃ��I�����𗘗p�҂ɗ^����悤�ɂȂ�A�L�������̐L�т��݉����Ă��Ă���̂ł��B
�O�[�O���ł��l���ʂɗ��o���A���ׂẴv���b�g�t�H�[�}�[���l���ی�Ɋւ������̐ςݑ����𔗂��Ă��܂��B���̌��ʁA�`���ɋ�����6�Ђ̃R�X�g��2013�N�Ɣ�r���ėD��2�{���ɖc���ł��Ă���Ƃ����킯�ł��B
���v�����ቺ����v���́A�����̃R�X�g�������ł͂���܂���B
����IT��Ƃ͂���܂�M&A�ȊO�ł͑�K�͂ȓ���������o�����R���������̂ŁA�]�������K�͓��������Ă������Ƃ̂悤�Ȍ��i���͎������킹�Ă��Ȃ��悤�ł��B���̂��߁A�A�}�]�����L�����ƂɐV�K�ɎQ�����A�A�b�v��������z�M�Ɏ��Ƃ̊g���ڎw���ȂǁA���łɋ��͂ȃ��C�o�������鎖�Ƃɋ��z�Ɏ����𓊂��邱�Ƃɂ���āA���v���̒ቺ���������Ȃ��͎̂d�����Ȃ��ɂ���̂ł��B
����ɁA����IT��Ƃ����`���Y�̃f�[�^�ʼn҂��܂����Ă���̂ɐ����Ȑŋ����x�����Ă��Ȃ��Ƃ̔ᔻ�����܂��Ă���Ȃ��A��i�e���ł͐V���ȉېł���������Ă��܂��B
���܂ł̍��ۉېŃ��[���ł́A�����Ɏx�X��H��Ƃ������P�v�I�Ȏ{�݂��Ȃ�����A�O����Ƃ̔���グ�◘�v�ɂ͉ېłł��Ȃ��Ƃ�������������܂����B�Ƃ��낪����A���B�ł�IT��Ƃɑ��ė��v�ł͂Ȃ����㍂�ɉېł���u�f�W�^���ېŁv�Ă����サ�Ă���̂ł��B
���ۂɁA�p�������̍��X�ɐ�삯�邩�����ŁA����IT��Ƃ�Ώۂɂ����f�W�^���ېł�2020�N4�����瓱������ƌ��肵�Ă��܂��B����IT��Ƃ��p���̏���҂���҂������㍂�ɑ��āA�ꗥ��2%�̐ŗ��ʼnېł���Ƃ����̂ł��B
�p���̃f�W�^���ېł̓����́AEU���f�W�^���ېł�O�����ɐi�߂�_�@�ɂȂ�͂��ł��傤���AG20�̋c�_�ɂ��傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B���v���Ƃ����ړx�Ƃ͈قȂ�܂����A�f�W�^���ېł�IT��Ƃ̐ň�����̗��v��}����v���ɂȂ�̂͊ԈႢ����܂���B
�����֎����Ă��āA����IT��Ƃ��f�[�^���ǐ肵�Ă��闧��𗐗p���A�����ɕs���Ȏ���������Ă�������߂�����������������܂��B
�䂪���ł��o�ώY�ƏȂ����{������|����Ȓ����ɂ��A���{�̒�����Ƃ͋���IT��ƂƂ̎���ɂ����āA�s���Ȏ������������������Ƃ������Ԃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B�o�ώY�ƏȂ̒����܂��A��������ψ�������̂�������_�Ȃ����ׂ���j���Ƃ����܂��B
�������{�Ɍ��炸�A�����̍��X��IT��Ƃ̖T�ᖳ�l�����F�߂��Ȃ��ɂȂ��Ă������ƂɂȂ肻���ł��B
�����̂������̗�������Ă���ƁA����IT��Ƃ̗��v���������ቺ����X���͂��͂�~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��傤�B
���悢��A�����J���̏㏸����x���Ă����������Ƃ��Ă�IT���ւ̎����W���́A�傫�ȓ]���_���}�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��̂�������܂���B�ߋ����N�ŋ��C���т��Ă����E�H�[���X�ł��AGAFMA�� FANG�ƌĂ��IT�����ō��l���X�V��������悤�ȑ���ɖ߂�͍̂���낤�Ƃ��������������Ă��Ă���悤�ł��B
�������҂���㏸�g�����h��ۂ��Ă����A�����J���́A2019�N�ɂ͖{�i�I�Ȓ����̊��Ԃɓ���\���������ƌ��Ă���܂��BNY�_�E��S&P500�̑o���̃`���[�g���_�u���g�b�v�̌`�ɂȂ�A���N��2���̒�����������s�����s�����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�m�点�Ă���Ă��܂��B
IT���̐������҂̔������A�����J�o�ς̑匸���Ƃ����o�H��H���āA2019�N��NY�_�E��S&P500��2018�N�̍��l����2���`3�������邱�Ƃ͏\���ɂ��肦��Ɗo�債�Ă������ق�������ł��傤�B�@ |
 |
|
�����E��Ȋ�����uGAFA�^BAT�v�̋K�������A�f�W�^���͐��E���ǂ��ɓ����H�@ |
|
GAFA(�O�[�O���A�A�}�]���A�t�F�C�X�u�b�N�A�A�b�v��)�⒆����BAT(�S�x���o�C�h�D���A�����b�b���A���o�o���A���u���e���Z���g��)���\�Ƃ���f�W�^���v���b�g�t�H�[�����(�ȉ��A�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[)�̑䓪�ɂ��A���E�ŗ��ʂ���f�[�^�̗ʂ͎w�����I�ɑ������A�f�[�^�𗘗p�����r�W�l�X�̉e���͂͑傫���g�債�Ă���B�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�������炷���Ɖe���A�e���̐���̓�����ǂ݉����Ȃ���������B
|
���f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�̑䓪���烊�A���̈�ւ̎��Ɗg���
�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�̑䓪�ɂ��f�[�^�̗��p�g��ɔ����A10�N�ԂŎ������z�̐��E�g�b�v10��Ƃ͑傫���ω������B
10�N�O�͐Ζ��A�����A�ʐM�A���Z�Ƃ�������Ƃ������L���O�̒��S�ł������̂ɔ�ׁA2018�N�̓x�X�g10�̂���6�Ђ��f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�Ő�߂���B
����܂�GAFA�́A�O�[�O���͌����G���W���A�A�b�v����PC��iPhone�A�t�F�C�X�u�b�N��SNS�A�A�}�]���͓d�q������Ƃ�����Web���S�̃f�W�^���̈悪���ƋN�_�ƂȂ��Ă����B
�ߔN�A�f�W�^���̈�̎��ƋN�_������W�����c��ȃf�[�^�ƃC���t����Ղ�ɁA���ς���X�܂ł̏������IT�������Z��(�X�}�[�g�z�[��)�A�����^�]�Ƃ��������A���ȗ̈�֎��Ƃ��g�傳���Ă���B
�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�́AAI�֘A�̃T�[�r�X�ɂ��A���͂��Ă���B
�O�[�O����A�}�]���A�}�C�N���\�t�g�Ȃǂ̃N���E�h�T�[�r�X�����f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�́A�f�[�^���W��Ղ�����邾���łȂ��A�v���Z�b�T����t���[�����[�N�AAI�֘A�̋Z�p��@�\��API���A�w�K�ς݂̃��f���ȂǁA���܂��܂ȃN���E�h�T�[�r�X��ԗ����Ă���B
�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�̎��Ɗg��Ō�������̂�API���B�O�[�O����A�}�]���A�}�C�N���\�t�g�Ȃǂ́A�u�w�K�ς�AI�@�\�v���AAPI��ʂ��T�[�r�X�Ƃ��Ē���B
���ЂŊJ���E�w�K�ς݂�AI���uAPI�ƌv�Z�\�́v�Ƃ����`�Œ��邱�ƂŁAAPI���p���A�N���E�h�T�[�r�X���p�Ȃǂ̑Ή���r�W�l�X���f���ƂȂ��Ă���B
�ڋq��Ƃ���A�b�v���[�h�����f�[�^�ɂ��A�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�͎���AI�̍X�Ȃ鐸�x����������ށB����ɂ��A�ڋq��Ƃ����ЃN���E�h�T�[�r�X�֗U��������ʂ����҂ł���B
�����̃T�[�r�X�𗘗p����ڋq��ƂɂƂ��Ă��A���Ђł̐l�H�m�\�J���̃R�X�g(���ԂȂ�)���팸���邱�Ƃ��ł���Ƃ��������b�g������B
AI��API�Ō��J���邱�ƂŁA�c��Ȋw�K�ς݂̃f�[�^���f�����ڋq��Ƃ�����W���Đ��x�����コ���A����ɍL�͈͂Ȏ��ƂɊg�傷��[�[�B�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�͊����̘g�g�݂����f�[�^�G�R�V�X�e���̍D�z���f�����ݏo���Ă���B
|
���f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�������炷�����b�g�Ɩ��_
���[�U�[��Ƃ́A�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[������T�[�r�X�𗘗p���Ă��܂��܂ȃ����b�g�����Ă��邪�����ɁA���܂��܂Ȗ��_���w�E����Ă���B
��̓I�ȃ����b�g����_�ɂ��ẮA�o�ώY�ƏȂ�2018�N10���Ɏ��{�����u�I�����C���E�v���b�g�t�H�[���Ǝ��Ǝ҂̊Ԃ̎���W�Ɋւ��鎖�ƎҌ����A���P�[�g����(GAFA�Ȃǂ̃T�[�r�X���r�W�l�X�Ŋ��p���Ă��鎖�Ǝ҂��Ώ�)�v����ǂݎ���B
������ƁE�x���`���[��t���[�����X�Ȃǂ̑w�́A�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�̃T�[�r�X�𗘗p���邱�ƂŁA�u�����b�g�v�Ă���Ƃ��������������߂��B
��̓I�ɂ́A�V�K�ڋq�̊J��@��̊l���┄����̉���R�X�g�y���A����E�̔��c�[���̗��p���\�ł���_�Ȃǂ��B
���̈���ŁA�u�������f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[���ւ��邱�Ƃ�����v�Ƃ�����65%�����B
�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�Ɉˑ�������_�Ƃ��ẮA�u�ʌ�������v�u�K��Ȃǂ̈���I�ύX�v�u���p���E�萔���������v�u�������ʂ����ӓI�E�s�����v�Ƃ��������������Ȃ��Ă���B
|
�����{���i�߂�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�ɑ��郋�[������
���{�ł́A�o�ώY�ƏȂ��������ψ���A�����Ȃ𒆐S�ɁA2019�N�����̓I�[�u��i�߂�ׂ��d�v�_�_���f������{������2018�N12��18���ɍ��肵���B����A����ɉ�������̓I�[�u�𑁋}�ɐi�߂�Ƃ��Ă���B
��{�����̊T�v�͈ȉ��̂Ƃ��肾�B
����{�����̊T�v
1�D�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�Ɋւ���@�I�]���̎��_
�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[���A(1)�Љ�o�ςɕs���Ȋ�Ղ���Ă���A(2)�����̏���҂⎖�Ǝ҂��Q������ꂻ�̂��̂��A�v���^�c�E�Ǘ����鑶�݂ł���A(3)���̂悤�ȏ�́A�{���I�ɑ��쐫��Z�p�I�s������������A�Ƃ�����������L�����邱�Ƃ��l��
2�D�v���b�g�t�H�[���r�W�l�X�̓K�Ȕ��W�̑��i
�v�V�I�ȋZ�p�E��Ƃ̈琬�E�Q���ɉ����A�v���b�g�t�H�[���r�W�l�X�ɑΉ��ł��Ă��Ȃ������Ɩ@�ɂ��āA�������v�ۂ��܂߂����x�ʂ̐���������
3�D�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�Ɋւ���������m�ۂ̂��߂̓������̎���
(1)�������y�ь��������������邽�߂̏o���_�Ƃ��āA��K�͂���I�ȓO�ꂵ�������ɂ�������Ԃ�c���A(2)�e�{�Ȃ̖@���s������Ă����x�����邽�߂́A�f�W�^���Z�p��r�W�l�X���܂ޑ��l�����x�Ȓm����L������g�D���̑n�݂Ɍ��������A(3)���̏d�v�ȃ��[�������������J���E�������铙�A�������y�ь������m�ۂ̊ϓ_����̋K���̓����Ɍ�������
4�D�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�Ɋւ�����������R�ȋ����̎���
�f�[�^��C�m�x�[�V�������l��������ƌ����R����A�T�[�r�X�̑Ή��Ƃ��Ď���Ɋ֘A����f�[�^��������҂Ƃ̊W�ł̗D�z�I�n�ʂ̗��p�K���̓K�p���A�f�W�^���s��ɂ�������������R�ȋ������m�ۂ��邽�߂̓Ɛ�֎~�@�̉^�p��֘A���鐧�x�݂̍��������
5�D�f�[�^�̈ړ]�E�J�����[���̌���
�f�[�^�|�[�^�r���e�B��API�J���ɂ��āA�C�m�x�[�V�������₦�������鋣�����̐������A�l�X�Ȋϓ_���l�����Č���
6�D�o�����X�̂Ƃꂽ�_��Ŏ����I�ȃ��[���̍\�z
�f�W�^������̃C�m�x�[�V�����ɂ��\���ɔz�����A����K���Ɩ@�K����g�ݍ��킹�������K�����̏_��Ȏ�@���l�����A�����I���[���̍\�z��}��
7�D���ۓI�Ȗ@�K�p�݂̍���ƃn�[���i�C�[�[�V����
�䂪���̖@�߂̈�O�K�p�݂̍����A�����I�ȓK�p�@�߂̎��s�̎d�g�݂݂̍���ɂ��Č����B�K���̌����ɓ������Ă͍��ۓI�ȃn�[���i�C�[�[�V�������u����������Ō���
��
�����������f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�ɑ��郋�[�������Ɏ��g��ł���̂́A���{�����ł͂Ȃ��B���Ă𒆐S�ɁA�ېł⋣������A�l���̈����Ȃǂ̌������i�߂��Ă���B
���B�A��(EU)�ł́A�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[��ΏۂɁAEU����̔��㍂�ɐŗ�3%���ۂ��u�f�W�^���T�[�r�X�Łv�����c���Ă���B
3�����܂ł̍��ӂ͒f�O���Ă�����̂̔w�i�ɂ́A���s�̍��ۉېŃ��[���ł͖h�����Ƃ��ł��Ȃ��u�œ���ւ̕s�������v������Ƃ����w�E���U�������B
2019�N6���ɁA���ŊJ�Â����20�J���E�n��(G20)��]��c�ł��f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�̃f�[�^�Ɛ�ւ̑Ή��Ɋւ���c�_����������Ă���B
|
������ȃf�W�^����ԂŌJ��L������f�W�^���푈�̖��J����
GAFA�̃f�[�^�Ɛ�̋��Ђ�K���ɑ�����ߔM���A�K�����ׂ����K�肳��邱�ƂɂȂ�A�Z�p�v�V��r�W�l�X�n�o��j�Q����Ƃ����w�E�����Ȃ��͂Ȃ��B
�e���⎩��Ƃ̗��v�ɌŎ�����̂ł͂Ȃ��A���E�̐����ƌ������Ƃ̓���o�����X�̑ǎ������Ȃ���A�ǂ̂悤�Ȓ��n�_��T��̂��B
�f�W�^���v���b�g�t�H�[�}�[�̊��p�ƋK���̓����́A���E�S�̂�����������ȃf�W�^����Ԃł���L������f�W�^���푈�̖��J���ɂȂ�̂�������Ȃ��B �@ |
 |
|
��GAFA ������4�Ђ��e�������ꂽ���R�ƍ���n����ߖ����ɂ��ā@ |
�ߔNGAFA(�K�[�t�@)�Ƃ������t���悭���ɂ���悤�ɂȂ�܂����BGAFA�Ƃ́A���L�̋�����4�Ђ̑��̂ł��B
�E Google(Alphabet)
�E Amazon
�E Facebook
�E Apple
���₱��4�Ђ͔e���������Ă���Ƃ����Ă����قǐ��E�ɑ傫�ȉe���͂������Ă���AGAFA���m�ł����������Ƃ��ł��Ȃ��̈�܂Ő������܂����B�����ō����GAFA��m���Ă���悤�Œm��Ȃ����̂��߂ɁA�ǂ�����GAFA�������܂Ő����ł����̂��H���݁A�ǂ�ȕ���Ŕe���������s���A���ꂪ�������̐����ɂǂ�ȉe�����y�ڂ��̂��H�@�O�������Ă����܂��B
|
���ǂ�����GAFA�͔e�������邱�Ƃ��ł����̂��H
�E��ʂ̃r�b�O�f�[�^���W�߂ăr�W�l�X�ɂ��܂����p����B
�E�l�H�m�\�Ȃǂ̍Ő�[�̈�ɔ���ȓ��������āA���Ђ̒ǐ��������Ȃ��B
�E�����ď����ז��ɂȂ�\���̂����Ƃ�M&A�ň��ݍ���ł����c�B
���ꂪGAFA�̕K���p�^�[���ł��B
�������AGAFA���ŏ����狐���Ƃ������킯�ł͂���܂���B�ǂ�����GAFA�͔e�������邱�Ƃ��ł����̂��H�@���̊�ƂƉ����Ⴄ�̂��H�܂��͊e�Ђ̐����v�������Ă����܂��傤�B
��Google(Alphabet)
Google(���݂�Alphabet�P���ł��邪�A�ȉ��O�[�O���ƕ\�L)�̐����v���͉��L��3�ł��B
�E�C���^�[�l�b�g�̓������}����
�E�������ʂ̏��ʂɈӖ�����������
�EIT�n���L�ɍL���œK���ɐ�������
�܂������̐l�X���C���^�[�l�b�g�Ɋ���Ă��Ȃ�����ɁA�C���^�[�l�b�g�̓����(����)��}�������Ƃ��A�O�[�O���ő�̐����v���ł��傤�B�������web�͑��ɂ�����܂������A�O�[�O���͌������ʂ̏��ʂɈӖ����������邱�Ƃɂ������܂����B���[�U�[�ɂƂ��ĉ��l�������ł��낤���Ԃɕ��ׂ�ꂽ�������ʂ̐��x�͔N�X�㏸���āA���������Ђ������ނ��Ƃ���Ȃ��n�ʂ�z�����̂ł��B�܂��AIT�n���L�ɂ��ւ�炸�A���[�U�[�̌������[�h�𗘗p���邱�Ƃɂ��A�L���œK�����������܂����B���[�U�[���������邩�痘�p�҂������āA���ʂ̍����L���ɂ͂������W�܂�B�������Ĕ���ȕx����ɓ��ꂽ�̂ł��B���݂ł�YouTube��A���h���C�hOS�A�����^�]�Z�p������������������s�����Ƃ܂ŕ��L���s���A���̉e���͂�N�X���߂Ă��܂��B
��Amazon
Amazon(�ȉ��A�}�]��)�́A�e�b�N��Ƃɔ��ɒ��ڂ��W�܂��Ă���1997�N�Ƀi�X�_�b�N��ꂵ�āA���̍ۂɒ��B�������������ɁA�����ŗD��ŐԎ��𐂂ꗬ���Ȃ��琬�����Ă������ƂŗL���ł��B�A�}�]���̘b�ɂȂ�ƁA���̒��������ƈȊO��O��I�ɖ��������o�c�ɒ��ڂ��W�܂肪���ł��B�������A�A�}�]�����̗p���������O�e�[���헪�������A�����i�K�̐����ɔ��ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B�ʏ�̃��A���X�܂̏ꍇ�A����̖�8����������2���̔���؏��i�ʼn҂��̂���ʓI�ł��B���̂��߁A����؏��i���ʂɎd����āA�قƂ�ǔ���Ȃ����i�͒炳��܂���ł����B���i��X�y�[�X��L���Ɋ��p����͓̂��R�ł��ˁB����Ƃ͋t�ɁA�N�Ԓʂ��ĂقƂ�ǔ���Ȃ����i�ł��A���̏��i��������Ȃ甄��؏��i���20���̔���𗽉킷��̂������O�e�[���헪�ł��B�܂��ɐo���ς���ΎR�ƂȂ�ł��ˁB�l�b�g��ł͂�����Ă��A�قƂ�ǃT�[�o�[��͂�����܂���B���ۂ̏��i���ꓙ�n�̋����X�܂ł͂Ȃ��A1���i������̌Œ��قƂ�ǂ�����Ȃ�����q�ɂŕۊǂ��܂����B���ꂪ�A�}�]���̏����̍ő�̐����v���Ƃ�����ł��傤�B�܂��A��������Α傫�ȃ��^�[�����������Ƃ��Ă��A���s����\���������r�W�l�X�Ȃ珟�������Ȃ��`���I�Ȋ�ƂƈႢ�A��Ƒ��S�̊�@�ɂȂ�悤�Ȃ��̂łȂ���A���Ғl���d�����ăx�b�g����o�c���s���Ă��܂��B�_���Ȃ班�z�̓����ł����ɓP�ނ��A�O���ɏ��Βlj��Ŕ���Ȏ����𓊓��������ʁA�����̎��s���J��Ԃ��Ȃ���AWS(�N���E�h����)��A�}�]���G�R�[�ݏo���܂����B����Ȏ����������Ă���`���I�Ȋ�Ƃ����Њ�������z�������钆�A�Z���I�ȓ����Ƃ�O��I�ɖ������Ċ��Ғl���d���������Ƃ��A�A�}�]���鍑�����グ���̂ł��B
��Facebook
Facebook(�ȉ��t�F�C�X�u�b�N)�̐����v���́A�l�ƂȂ��肽���Ƃ��������ĂȂ��Ȃ邱�Ƃ̂Ȃ��l�Ԃ̗~���ɃA�v���[�`����̈�ŏ����������Ƃł��B�܂��A���L��3�̗v�����A�t�F�C�X�u�b�N�̍L����ɔ��Ԃ������܂����B
�E�n�[�o�[�h��w�Ƃ����u�����h
�E�D�G�Ȉِ��ƂȂ��肽���Ƃ����~��
�E���肪���p���Ă���Ǝg�킴��Ȃ�
�����A�t�F�C�X�u�b�N���N���m��Ȃ��悤�ȑ�w�Ő��܂�Ă�����A�ԈႢ�Ȃ������܂Ő������邱�Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B���Ƃ��ƃt�F�C�X�u�b�N�́A�n�[�o�[�h��w�̊w�����������p�ł���T�[�r�X�ł����B�����āA����ɗ��p�҂��L����ۂɂ��L����w�̊w�����g����悤�ɁA�I���i���čL���Ă����܂����B�t�F�C�X�u�b�N�͗��p���邱�ƂŗD�z������c�[���ł���A�����L�]�Ȓj���ƊȒP�ɂȂ����c�[���ł���A���߂ĉ��������̏����Ƃ̘A����i���ȒP�ɓ�����c�[���ł���A���p�ł���R�~���j�e�B�ɑ����Ă���Ɨ��p������Ȃ��Ȃ�c�[���ƂȂ�܂����B���܂��X�^�[�g�ł����炠�Ƃ͊ȒP�ł��BSNS���L�ُ̈�Ȃ܂ł̃X�s�[�h�ōL�����Ă����A�t�F�C�X�u�b�N�͔���Ȍl�����Ŏ�ɓ���邱�Ƃɐ��������̂ł��B���݂ł́A�A�����J�̃l�b�g�L���s��̔����ȏ���A�t�F�C�X�u�b�N�ƃO�[�O����2�Ђ����Ő�߂Ă��܂�(�ǐ���)�B
��Apple
���X�̈�b���c�����X�e�B�[�u�E�W���u�Y�ɂ��Ă͐�������܂ł�����܂���ˁB�m���ɁA�ނ��w��������Apple(�ȉ��A�b�v��)���A�v�V�I�ȏ��i�𐢂ɑ���o�������Ƃ���Ԃ̐����v���ł��傤�B�������A�{���̃A�b�v���̂������Ƃ���̓u�����f�B���O�헪�ł��B���̓A�b�v���̐��E�ł̃X�}�z�s��̃V�F�A�́A��2�����x�ł�������܂���B�������A���E�̃X�}�z�s��̗��v�̖�8����Ɛ肵�Ă��܂��B�A�b�v���̓X�}�z��P�Ȃ閳�@���ȋ@�B����A���o�b�N�̂悤�ȍ����u�����h�ɂ��邱�Ƃɐ������āA�����i�ł�����҂͊��ł������悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�����i�ł���Ȃ���O��I�ɃR�X�g��}���邱�Ƃɂ��������Ă��܂��B�A�b�v���͎��ЍH����������ɁA���E���̕��i���W�߂Ē����őg�ݗ��ĂĂ��܂��B��R�X�g�ň����ȏ��i�����̂ł͂Ȃ��A���R�X�g�ō����i�����킯�ł�����܂���B���̃X�}�z�Ɠ����悤�Ɏ����チ�C�h�C���`���C�i�ł���Ȃ���A���|�I�ȍ����i�тŔ̔����Ă���̂ł��B����قǐ��E�K�͂ŁA��R�X�g�̍����i�������������Ⴊ����ł��傤���H�������ăA�b�v���́A����ȕx��������ۂ��邱�Ƃɐ��������̂ł��B�u���E�ő�̋��v�łȂ��������`�ƃ}�J�I�@���E�L���̃��K���|���X�ɐ������邩�H
|
��GAFA�̑s��Ȕe�������Ɩ����\��
������s���GAFA�̑s��Ȕe�������́A�����̏u�Ԃ��₦���s���Ă��܂��B�ԈႢ�Ȃ����㐔�\�N�Ԃ́A�������̐����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ������邱�Ƃł��傤�B�����ł́A�l�H�m�\��ʎq�R���s���[�^�[��F���Ȃǂ̑s��Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���㎄�����̐g�߂Ȑ����ɂǂ̂悤�ȉe��������̂��H��̓I�ɉ�����Ă����܂��B
�������E�\��E������
�l�Ԃ���u�m�肽���v�Ƃ����~���������邱�Ƃ͂���܂���B���̕���ł͌��݁A�O�[�O�����e�L�X�g�Ɠ���(YouTube�ł̌�����Google�����Ɏ����Ő��E��2�Ԗڂ̃{�����[��)�Ŕe���������Ă��܂��B����O�[�O���͗\�����R�~�s��̋쒀���n�߂�ł��傤�B��̓I�ɂ́A���e�@����H�X�̗\��E���R�~�́A�O�[�O������X���[�Y�ɍs����悤�ɂ������͂��ł��B�J�J�N�R��(�H�׃��O)��N���[�g(�z�b�g�y�b�p�[�r���[�e�B�[)�́A�������ҍU�ɂ��炳���ł��傤�B�����A�����̉��҃O�[�O�������ׂł͂���܂���B����A���i���w������ۂɂ̓O�[�O���ł͂Ȃ��A���ڃA�}�]���Ō�������X�������܂�͂��ł��B���̗���͂��łɎn�܂��Ă���A�ŏI�I�ɂ͕�����ł����Ƃ��A�A�}�]���G�R�[�ŏ��i�̃A�h�o�C�X������A���̂܂ܒ�������̂���ʓI�ɂȂ�ł��傤�B�������特���̗���́A�A�b�v����Siri�ɂ������邱�Ƃł����A�O�[�O���������f�o�C�X�̔e�������ň����Ɉ����Ȃ����R�ł�����܂��B�܂��A���łɒ����I�Ȍ���(�A�p�����◿��)�ł́A�t�F�C�X�u�b�N�P���̃C���X�^�O�����Œ��ׂ��҂̑����������ŁA����̓O�[�O�������łȂ��A�A�}�]���ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��܂��B�C���X�^�O�����ŃA�p�������i�ׂāA���̂܂܂����ɍw�����闬�ꂪ��������܂�A���ꂪ�K�������邱�Ƃ��A�}�]���͖ʔ����v��Ȃ��ł��傤�B�Ȃ��Ȃ�A�A�}�]���͂��łɎ��Ђ̃A�p�����u�����h�𗧂��グ�āAEC�̒��ł����������W�������ł���A�p������}���ɗ��Ă��邩��ł��B���̗��҂̑����́AZOZO(ZOZOTOWN)��y�V(�y�V�s��)�ɂ��e����^����͂��ł��B���̂悤�Ɍ����E�\��E�������̗̈�Ŕe���������s��ꂽ���ʁA�����������ڗ~�������̂����I�Ԏ��オ�I���������邩������܂���B
�u�@���ׂ�O�ɗ~�����ł��낤����^�����A�w������O�ɓ͂���ꂽ���i����K�v�Ȃ����̂�ԕi���āA�S�n�̗ǂ��T�C�N���ŏ���ɗ\��Ă��邨�X�ɑ����^�Ԃ��ƂɂȂ�c�B�@�v
�ŏ��͒�R��������ł��傤���A�N�X�����̐��x���オ��A�N���X�g���X�������Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�����SF�̂悤�Ȑ��E��{�C�őn�����悤�Ƃ��Ă���̂�GAFA�Ȃ̂ł��B
���d���Ɖ�������
���݂͐l��s���ƌ����Ă��܂����A�߂������J���͂�����قǕK�v�Ƃ��Ȃ��Љ�`������邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B�R���r�j��X�[�p�[�̃��W�͕K�v�łȂ��Ȃ�A�^�N�V�[�⑽���̕�����AI���R���g���[������A�q�ɓ���Ƃ����ȏ�Ɏ������������ނ͂��ł��B���Ɏ�����ƂȂǂ̃z���C�g�J���[�Ɩ��̕K�v�J���͂̌����͑傫���A�����̎d����RPA(���{�e�B�N�X�E�v���Z�X�E�I�[�g���[�V����)�Ɏ���đ�����ł��傤�B���̂悤�ɘJ���̍œK�����i�݁A���{�l�̑���������(���R���E�ł�)�͉E���オ��ɂȂ�܂��BAI�ɉB�ꂪ���ł����A�������Ԃ͍����I�ő勉�̃r�W�l�X�`�����X����߂Ă��܂��B���R�AGAFA�͂�����������܂���B�J���͂̎��������哱����̂�GAFA�ł���A���܂ꂽ�������Ԃ�D�������A���̔e��������̂�GAFA�Ȃ̂ł��BYouTube��A�}�]���v���C���AIGTV(�C���X�^�O���������Ă��铮��T�[�r�X)�œ�����y���݁A�O�[�O�����g���Ē��ׂ��̂����āA�A�}�]���ōw���������Ђł���Ȃ�m���̒T�������܂��B�X�}�z�Q�[���₩�킢����������H�A�v���𗘗p����ɂ��AApp Store�ŃC���X�g�[������K�v������܂��B���s��ł̓O�[�O���}�b�v�����Ȃ���ړI�n�Ɍ������A�ό������ł̓t�F�C�X�u�b�N��C���X�^�O�����Ȃǂ�SNS�Ɏʐ^���A�b�v���܂��B������iPhone���g���čs���A����ȊO�̂قڑS�ẴX�}�z�ɂ̓O�[�O���̃A���h���C�hOS�����ڂ���Ă��܂��B���ł�GAFA�́A�������̉������ԂɐN�H���Ă���A�������邤���łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ɂȂ��Ă���̂ł��B��������̗���͕ς��Ȃ��ł��傤�B
�������^�]
���ݍł�GAFA(����ȊO�̊�Ƃ�)�����̂�������Ă���A���N��Ɏ������ɑ傫�ȉe����^����̂������^�]�ł��B�O�[�O���̃E�F�C��(Alphabet�P��)�A�A�}�]���̃I�[�����E�C�m���F�C�V����(�o��)�A�A�b�v����Project Titan(�Г�����)�ȂǁA�����͊ԈႢ�Ȃ��������̐g�߂Ȑ��������łȂ��A�����ԑ卑���{���̂��̂�h�邪�����ƂɂȂ�ł��傤�B�����^�]�͎ԑ̂��̂��̂��A�](OS)�����ɏd�v�Ȗ������ʂ����܂��B���̔]�̕����������Ă��܂��A�ԑ̂͂����̔��ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����킯�ł��B���{�̋��厩���Ԋ�Ƃ��AGAFA�̉������ɂȂ�\������ɂȂ��Ƃ͌����܂���B�����A�������̐g�߂Ȑ����Ƃ��Ď����^�]���l�����ꍇ�ɂ́A���ɖ����͖��邢�ł��傤�B�l���^�]����K�v���Ȃ��Ȃ�A���ԏ�Ɏ~�߂Ă����K�v������܂���B�����I�ɍl����A�g�p���Ă��Ȃ������^�]�Ԃ́A���̐l�X�����p���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�v����ɁA�����Ԃ⒓�ԏ�����L����K�v���Ȃ��Ȃ�킯�ł��B���R�A���L�R�X�g(�ԑ̂⒓�ԏꂾ���łȂ��A�ی���ŋ���)�͉�����A�������Ԃł̏���ɂ��������Ƃ��ł��܂��B��ʎ��̂̌����͋}���ɉ�����A���\�N��ɂ͐l�������Ԃ��^�]���邱�Ƃ�@���ŋ֎~���鍑���łĂ���ł��傤�B�������A���S�ɉ^�]���֎~����킯�ł͂Ȃ��A�Ԃɏ�肽������C�Z���X(���݂̖Ƌ��̂悤�Ȉ�ʓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ȃ�)�����A�������ԓ��Ɍ�y�Ƃ��āA�T�[�L�b�g�Ŋy���ނ��Ƃ��ł���z��������ƍl�����܂��B |
�����͂�G��GAFA�ƍ��Ƃ������Ȃ�
GAFA�͂��܂�ɂ�����ɂȂ肷���܂����B���͂�GAFA�Ƒ�����̂́AGAFA���g�����Ƃ݂̂ł��B���łɍ��Ƃɂ��GAFA��͎n�܂��Ă��܂��B������������GAFA�ɂ���č����ߖ������A�l�ނɂƂ��Ė��邢�����ɂȂ邱�Ƃ��肤����ł��B�@ |
 |
|
���uGAFA�v�ł���ɉ�����̂̓A�}�]���@ |
���}�C�N���\�t�g��4�Ђ̈Ⴂ�Ƃ�
�uGAFA�v��4������ڂɂ���@��������BGoogle�EApple�EFacebook�EAmazon��4�Ђ́A�}�C�N���\�t�g�Ƃ��킹�āA�ߔN�A���E�������z�����L���O���5�ʂ̏�A�ł���A���̓����𐢊E�����ڂ��Ă���(�O�[�O���͐e��ЃA���t�@�x�b�g�̎P��)�B
�Ȃ��}�C�N���\�t�g�����O����4�Ђ����Ƃ���b��ɏ��̂��B�������ɓ��Ђ͖�10�N�O�̐��E�������z�����L���O�ł�5�ʈȓ��ɐH������ł���A������ʂ��߂Ă����G�N�\�����[�r���AGE�A�E�H���}�[�g�E�X�g�A�[�Y�A�����ړ��Ȃǂ������L���O����p���������A�B��A���݂�5�ʓ��ɗ��܂��Ă����Ƃł���B
�������A����Windows�Ől�X�̐�����傫���ς������Ђ��APC�s��̐��ނƃX�}�z�s��̖��i�̔g�ŁA���܂␢�E��OS�̖�8���̓O�[�O����Android�ɐ�߂��Ă���B�����ĐV���uGAFA�v�ƌ���I�ɈقȂ�̂́A�u���̒���{�C�ŕς��悤�v�Ƃ�����M�̉��x���Ƃ����邩������Ȃ��B�O�o�c�Ҏ���Ƀ��C�o����ƂƂ̋����ɗ͂��X�������������}�C�N���\�t�g�ɑ��A�uGAFA�v4�Ђ͎���̗��z�m�Ɏ����A���̎�����簐i����p�������N���Ƃ������ʓ_������B
���܂⎄�����̐����͂���4�Д����ł͌��Ȃ��B�d�b�̊T�O��傫���ς����X�}�z�ݏo�����A�b�v���A����ɂ��Ȃ���C�y�ɏ��i�𒍕�����֗��Ȑ�����蒅�������A�}�]���B�O�[�O������������c��ȏ��āA�t�F�C�X�u�b�N��ʂ��Đ��E���̐l�X�ƃR�~���j�P�[�V�������鐶���́uGAFA�v�Ȃ��ł͎������Ȃ������B
��������4�Ђ͒P�Ȃ錟���G���W����Ђ�E�R�}�[�X��ƂƂ������e�ɂ͎��܂肫��Ȃ��L��������B�ނ�̎���͈͂Ƌ��݂Ǝ�݁A�����ď����������Ă݂悤�B
|
���t�F�C�X�u�b�N�͏������ɕs������H
�܂��͑n��20�N�̃O�[�O�����B���R�Ȋ�ƕ��y�̂��ƁA���E�������z�V�O�ȓV�˂������W���O�[�O���́A2015�N�ɃA���t�@�x�b�g��e��ЂƂ���g�D�ĕ҂��s�������A�ˑR�Ƃ��ē��Ђ̒��j���Ƃ͌����E�L���E�N���E�h�EAndroid�EYouTube�Ȃǂ��^�c����O�[�O�����S���A���ɔ��㍂��99����d���Ă���B�Ƃ��낪�c��̂킸��1�������̔���グ�������ݏo���Ȃ��j���ƂɁA�ϋɓI�ɐl�ށE���͂��X����̂����Ђ̓����ł�����B����͎����^�]�ԊJ���A�����Ȋw�����A��[�Z�p�����A�x���`���[�����Ȃǂ��B
���̗��O�́A�l�X�̐��������ǂ����̂ɂ��邱�Ƃƈ�т��Ă���B���Ƃ��Ύ����^�]�Ԃ̊J���ŁA�����ԃ��[�J�[�̑����͂����K�ȃh���C�u�̌���Nj����邪�A�O�[�O���͍���҂��Q�̂���l�X�ł����R�ɊO�o���y���߂邱�Ƃ�ڕW�Ɍf����B���߂̎��v�Ɍ��т����Ƃ��A�l�X��������ۑ�������������Ƃ����w�͂�ɂ��܂Ȃ��B
����ŁA�r�W�l�X��̌��O�ޗ�������B��ƑS�̂̎��v�̖�9���������L�������Ɉˑ����Ă���AYouTube����Ƀw�C�g�X�s�[�`��ߌ��h�e����������݂��Ă���Ƃ������R�ŁA����Ƃ����X�ƍL���P�ޏ��u�ɓ��ݐ�Ȃǂ���ƁA���БS�̂̎��v�ɑ傫�ȉe�����o��B�܂��Ɛ�֎~�@�ɕq����EU���甜��Ȑ��ً����Ȃ��ꂽ���ƁA����s�ꒆ���ɂ����錟�{��n�b�L���O�����N���A�ł��Ȃ��W�����}�Ȃǂ�����̉ۑ�ł���B
�����ŃA�b�v�������A���Ďa�V��PC�Ń��[�U�[�𖣗��������Ђ́A���܂₷������X�}�z��ƂƂȂ�A���Ђ̑S����グ��6����iPhone���҂��o���Ă���B�����Z�p�����p���g�ݍ��킹�邱�Ƃł��֗��ȏ��i�ݏo���́A�ō��̃f�U�C���ƃN�I���e�B��Nj�����Ë��̂Ȃ������Ђ̋��݂��B�g�ь^���y�v���[���[iPod�̔����A�y�Ȃ���Ȃ��w���ł���iTunes Store�̒a���A�����Ē�z�ۋ������y�z�M�T�[�r�XApple Music�ւ̈ڍs�ƁA���y�ƊE���ƏՓˁA�Ղ��J��Ԃ��Ȃ�������ʓI�ɑ傫�ȃr�W�l�X�`�����X�����Ă����B
�����A���̃A�b�v�����Րł͂Ȃ��B���|�I�J���X�}���œ��Ђ���������Ă����W���u�Y�S����A�ǂ��܂Ń��[�U�[�𖣗����鏤�i�ݏo���������邩���s�������ꂽ�B�͂����āA�ꎞ�l�C�������^�u���b�g�[��iPad�͕s���B�Ȃɂ��X�}�z�s��̖O�a�ɂ��A���Ђ̎�͏��iiPhone�̔��ɉA����o�n�߂Ă���B����A�����^�]�Ԃ̊J���⌒�N�E��Õ���ł̎��g�݂Ȃǂ��A���W�̌������邾�낤�B
�uGAFA�v�̒��ŁA��ԏ������Ɋ낤�������܂Ƃ��̂̓t�F�C�X�u�b�N�ł���B���܂␢�E��20���l�����[�U�[���ŁA�P����Instagram���D�������A���v��9���߂����L�������ʼn҂��r�W�l�X���f���̊댯���̓O�[�O���Ɠ��l���B����ɗ��p�҂̖������X�̃j���[�X���t�F�C�X�u�b�N�œǂޒ��A16�N�̕č��哝�̑I�ȍ~�̃t�F�C�N�j���[�X�̖����ɓ��Ђ͓���Y�܂��Ă���B��o����AEU�ɂ���ʃf�[�^�ی�K���A����ɂ͐�����̔g�������ł��Ȃ��B�t�F�C�X�u�b�N���p�҂�30�`40��w���N���Ƃ�A�����オ�t�F�C�X�u�b�N�Ƃ͈قȂ鑼�҂Ƃ̊W�������߂Ă������Ƃ��A�ς�炸SNS���҂̒n�ʂ��ێ��ł��邩�m�͂Ȃ��B���Ђ����͂��Ă���AR(�g������)��VR(���z����)�Z�p�̏��������C�ɂȂ�Ƃ��낾�B
|
�����ɂł���������A�}�]���̉\��
���āA�Ō�̓A�}�]�����B���_���炢���A����uGAFA�v�Ŕe��������͓̂��Ђł͂Ȃ����Ǝ��͍l����B���̗��R�͈�ԉ��ɂł��u��������v�ƑԂ����炾�B
1994�N�ɏ��Ђ̃l�b�g�̔�����n�܂������Ђ́A���܂┄�㍂�Ő��E�ő��̃E�H���}�[�g��Ғǂ����Ƃɐ��������B�����̔錍�́A�u�҂������v��ɂ������Ȃ��g���A�����𑱂���v���ƁB�d�q����Kindle��AAI�X�s�[�J�[Amazon Echo�A�h���}��f��ȂǑ�ʂ̉f���R���e���c���y���߂�Amazon Prime Video�ȂǁA��ȏ��i��T�[�r�X�����X�ƌJ��o������ŁA�c��ȏ��i�𐢊E���ɓ͂��邽�߁A���C�ׂĂ�ԗ������啨���V�X�e������������B����ɂȂ肷�����C���[�W�����邪�A�A�����J�̏�����S�̂ɂ�����E�R�}�[�X�s��̃V�F�A�͖�10���B�܂��܂���������]�n���c����Ă���B�����ƁE�����ƁE���f�B�A�ƁAIoT����ȂǁA�ǂ�ȕ���ɐi�o���Ă����������Ȃ��A�\���������ɍL����̂��A�}�]���Ƃ�����Ƃ̍ő�̋��݂Ƃ����邾�낤�B
18�N9�����A���m�[�A���Y�����ԁA�O�H�����Ԃ�3�ИA�����O�[�O��Android���ԍڃV�X�e���ɓ��ڂ��邱�Ƃ\�����B���ЊJ��OS�Ɏ������Ă��������ԃ��[�J�[�����ɐ��E�V�F�A8������OS�̗̍p�ɓ��ݐ����̂��B�����r�W�l�X������ȑ������o���̂��A�u�������狦�͂ցv�s�ꂪ�ԓx��ς��Ă����l��4�ЂƂ��Ɍo�����Ă���B�������鏤�i�ɑ��āu���ĂȂ��v�ƌ�����i�K�őR������g�ޑ���ւƕω�������̂ł���B
�����炱���A���ɏ����uGAFA�v�����Ă��邱�Ƃ�����Ȃ�A����͐V���Ȏs�ꂪ�o�ꂵ�A�ނ�̃r�W�l�X���p�Ȃ��ɂȂ����Ƃ��������B�A�b�v���ɂƂ��Ă̋��Ђ�iPhone���鍂�@�\�X�}�z�̓o��ł͂Ȃ��A�S�������̈قȂ�f�o�C�X�̓o��ŃX�}�z���̂��s�v�ɂȂ邱�ƂȂ̂��B
�����A������4�Ђ͋��l�ɐ������Ă���B�V�r�W�l�X�𗧂��グ�ނ�ɗ����������x���`���[��Ƃ�����Ă��A���Ƃ��Ƃ������A�z�����邾���̗͂�~���Ă���B���̌������ɂ́A�ނ炪�u����Ȃ��͔̂���Ȃ��v�Ɩ��h���ɂȂ��Ă���ӓ_���������Ȃ����낤�B���܁A���E�̂ǂ����ɑ��݂���ۑ���������鎅���������邱�ƁB�܂��ӎ��������ꂸ�T�O�����̂������Ȃ����A�傫�ȃr�W�l�X�ɔ��W���Ă��������������A�V���Ȏs���n�o���邱�ƁB�����ɂ̂݁uGAFA�v���铹���B����Ă���B�@ |
|
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@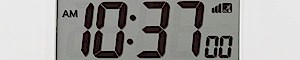 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@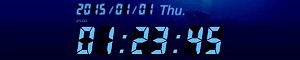
 �@
�@ �@
�@
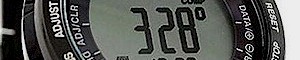 �@
�@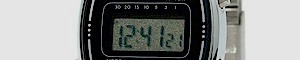 �@
�@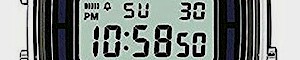
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@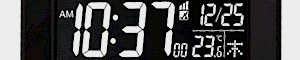 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@












 �@
�@ �@
�@

 �@
�@








 �@
�@ �@
�@