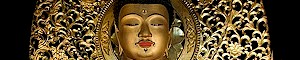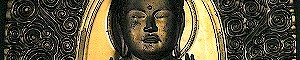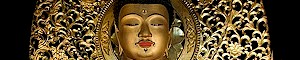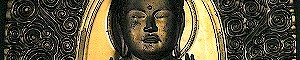|









 |






 |





 |















 |










 |
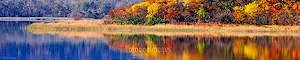











 |






 |




 |


 |



|

●法要
まずは、法事と法要についてできるだけわかりやすく説明したいと思います。一般に、私たちは「法事」と言っていますが、厳密に言いますと、住職にお経をあげてもらうことを「法要」といい、法要と後席の食事も含めた行事を「法事」と呼びます。「初七日」とか「四十九日」「一周忌」ということばは聞いたことがあると思います。故人が亡くなったあとに行う重要な法要です。そもそも法要とは、仏になった故人を供養するという意味の仏教用語で、追善供養ともいいます。法要は故人を偲び、冥福を祈るために営むものなのです。冥福とは、冥途の幸福のことで、故人があの世でよい報いを受けてもらうために、この世に残された者が供養をします。また法要は、故人が設けてくれた人と人とのご縁、「この人がいたから自分がいる」というつながりを再確認し、故人への感謝の思いを新たに、自分自身を見つめ直す場でもあります。
仏教では法要を行う日が決まっています。死後七日ごとに四十九日まで行う忌日法要(きびほうよう)と、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌などの年忌法要(ねんきほうよう)です。仏教では、死後七週間はまだ故人があの世とこの世の間をさまよっているとされています。この四十九日間を「中陰(ちゅういん)」と呼んでいます。死後七日目から七日ごとに七回、閻魔大王(えんまだいおう)をはじめとする十王から、生前の行いに対してお裁きを受け、四十九日目で来世の行き先が決まるとされています。 残された家族は故人が極楽浄土に行けるように、故人に善を送る(追善)法要を営むのです。 年忌法要は極楽浄土に行った故人がさらなる精進の道へと導くために営みます。一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌とつづき、三十三回忌で長い修行の締めくくりとして、故人は菩薩(ぼさつ)の道に入り、「ご先祖さま=守り神」となります。 仏教ではさらに、五十回忌、百回忌と続きますが、一般には三十三回忌、もしくは五十回忌をもって「弔い上げ」とし、法事の締めくくりとしています。
●法要を営む日
初七日 / しょなのか 命日も含めて7日目
二七日 / ふたなのか 命日も含めて14日目
三七日 / みなのか 命日も含めて21日目
四七日 / よなのか 命日も含めて28日目
五七日 / (=三十五日)いつなのか(さんじゅうごにち) 命日も含めて35日目
六七日 / むなのか 命日も含めて42日目
七七日 / (=四十九日)なななのか(しじゅうくにち) 命日も含めて49日目
百カ日 / ひゃっかにち 命日も含めて100日目
一周忌 / 命日から満1年目
三回忌 / 命日から満2年目
七回忌 / 命日から満6年目
十三回忌 / 命日から満12年目
十七回忌 / 命日から満16年目
二十三回忌 / 命日から満22年目
二十七回忌 / 命日から満26年目
三十三回忌 / 命日から満32年目
三十七回忌 / 命日から満36年目
四十三回忌 / 命日から満42年目
四十七回忌 / 命日から満46年目
五十回忌 / 命日から満49年目
百回忌 / 命日から満99年目
●十王審判と十三仏信仰
仏教では輪廻転生(りんねてんしょう)という考え方があり、命日から四十九日の間に、故人が次に生まれ変わる世界(来世)が決まるとされています。来世とは、天、人間、修羅(しゅら)、畜生(ちくしょう)、餓鬼(がき)、地獄の六道(ろくどう)のことです。この間故人は七日ごとに、生前の行いに対して閻魔大王をはじめとする十王からお裁きを受けるとされています。しかし、この六道の世界はどこへ行っても煩悩の苦しみがあり、それを超越した世界が極楽浄土です。残された家族は故人が極楽浄土に行けるように、このお裁きを受ける七日ごとに故人に善を送る(追善)法要を営みます。十三仏は初七日から三十三回忌までの合わせて十三回の法要の守護仏です。故人は十三の仏様に守られて極楽浄土に導かれ成仏するとされています。
十三仏は、 初七日 不動明王(ふどうみょうおう)、 二七日 釈迦如来(しゃかにょらい)、 三七日 文殊菩薩(もんじゅぼさつ)、 四七日 普賢菩薩(ふげんぼさつ)、 五七日 地蔵菩薩(じぞうぼさつ)、 六七日 弥勒菩薩(みろくぼさつ)、 七七日 薬師如来(やくしにょらい)、 百カ日 観音菩薩(かんのんぼさつ)、 一周忌 勢至菩薩(せいしぼさつ)、 三回忌 阿弥陀如来(あみだにょらい)、 七回忌 阿閃如来(あしゅくにょらい)、 十三回忌 大日如来(だいにちにょらい)、 三十三回忌 虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)です。 |

●百ケ日から三回忌
四十九日(満中陰)をむかえて一人前の仏さまとして歩みだされた人は、都卒天(とそつてん)という弥勒菩薩(みろくぼさつ)の浄土をめざして修行がはじまります。だいたい50年かかってその最終的な場所、都卒天に到着するといわれております。
●百ケ日(ひゃっかにち)
薬師如来に、長い道中をしっかり歩めよと後押しされて、最初に出会う仏さまが観音菩薩(かんのんぼさつ)であります。地方では、" 百ケ日はごくごく身内で拝めばよい" とされるところも多いようです。また、百ケ日の意味は、昔は土葬で、お棺(ひつぎ)のままお墓に埋めました。その上に石をおいて供養したのです。日が経って、だんだんとお棺が腐ってきます。そしてその中に土が入って沈むために上にのせた石がゆがんでくるのです。その土が落ち着くのがだいたい百日といわれたということです。百日目にお墓に行って供養をして、お墓の石を据えなおすという風習が百ケ日の供養であるともいわれています。
●一周忌 三回忌(いっしゅうき さんかいき)
仏教では、数を数えるのに数え年をつかいます。よって亡くなられて1年目を一周忌といい、亡くなられて2年目を三回忌というのです。亡くなられた年を一年と数えるので2年目を三回忌といいます。よって、1年目はニ回忌ですがあえて一周忌という呼び方をします。一周忌の仏さまは勢至菩薩(せいしぼさつ)で、三回忌が阿弥陀如来(あみだにょらい)が担当していただきます。
百ケ日の観音菩薩と一周忌の勢至菩薩と三回忌の阿弥陀如来の三人の仏さまをあわせて阿弥陀三尊(あみださんぞん)といいます。それは西方浄土(さいほうじょうど)に導いてくれる仏さま方なのです。三回忌で阿弥陀如来が現れるという意味は、この三回忌をもって、死後の霊は極楽(ごくらく)といわれる西方浄土に達するという考え方からきているのです。 |

●十三仏
●不動明王尊-ふどうみょうおうそん/初七日-しょなのか・・・(行者守護、悪魔退散、除災招福)亡くなった亡き人自体、遠い冥界へ旅立つ覚悟もまだ不十分ですし、残された者もその人の死を認められず、現世への未練が残っている時期です。死後の世界へと旅立たなければならない者が、再び現世に未練を持たないように不動明王尊の持つ右手の剣で迷いを切り払い、左手の縄は迷いの信者を縛って救いとり、 冥界へと引き込む役目をして下さいます。
●釈迦如来-しゃかにょらい/二七日-ふたなのか・・・(仏智悟入)実在の人物であり、その大いなる力は、全ての人々を救うための仏として存在しています。 そのために葬儀のときにあわてて戒律を授けなければならぬ者、修行をしていない者に冥界への旅立ちに際して、仏教の祖である釈迦如来が祖の本来の教えを説いて下さるのです。
●文殊菩薩-もんじゅぼさつ/三七日-みなぬか・・・(智恵、天変地異、降状)文殊菩薩は知恵の仏さまであり、釈迦が前世で子供時代に教えを受けた仏だと言われます。 また、釈迦如来を中心とし両脇侍に、文殊菩薩、普賢菩薩としてこれを"釈迦三尊仏"といい、この釈迦三尊仏が二七日から三七日を経て四七日迄の間に、 仏教徒として身につけるべきことを教え込んで下さるのです。
●普賢菩薩-ふげんぼさつ/四七日-しぬなのか・・・(仏智悟入、滅罪、大根清浄)普賢菩薩は慈悲門を司る、すなわち情を担当する仏さまで女性的なやさしい表情をしています。 たくさんの功徳を備えていて、私たちの煩悩を打ち砕き悟りの世界へと導いて下さるのです。
●地蔵菩薩-じぞうぼさつ/五七日-ごしちにち・・・(滅罪、先亡成仏、無仏時代の守護)釈迦の入滅後から弥勒菩薩が現れるまでの間、人々を救うための救世主です。四七日まで冥界への旅をしてきた亡き人が、六道へ落ちてしまった時に地蔵菩薩が救いの手を差し伸べ極楽浄土へ導いて下さいます。
●弥勒菩薩-みろくぼさつ/六七日-むなのか・・・(未来の救済)弥勒の力と如来の力を併せ持って、人々を救ってくれると信じられています。弥勒菩薩には釈迦の入滅した五六億七千万年後に、釈迦に代わってこの世を救う「未来仏」としての役割があります。
●薬師如来-やくしにょらい/七七日-しちしちにち・・・(四九日)四九日で現世とのつながりが終わりますが、まだ次の世界までは完全に入れない中間の道中の苦しみを乗り越え、極楽浄土への道を歩むための薬を与えて下さいます。
●観世音菩薩-かんぜおんぼさつ/百ヶ日・・・(除災滅罪、施餓鬼本尊)観音様は三十三に身を変え慈悲の面で亡き人を救って下さり、阿弥陀如来まで導いて下さいます。
●勢至菩薩-せいしぼさつ/一周忌・・・(往生浄土、滅罪)無限の光明と知恵によって、人々の苦しみを取り除くために努められています。
●阿弥陀如来-あみだにょらい/三回忌・・・(往生浄土、敬愛)阿弥陀とは「無量寿」「無量光」という言葉のサンスクリット語を訳したもので、寿命は限りなく、阿弥陀さまの光はあらゆる国々や人々を照らして下さいます。四八の誓願の一つに「阿弥陀如来を信じる者は、みな極楽浄土へ往生させる」があります。
●阿閦如来-あしゅくにょらい/七回忌発菩提心、悟りをめざす心をおこすことを意味します。発心を託す強い力を持った阿門さまが着ている衣を握っているのはその決意の強さを表しています。
●大日如来-だいにちにょらい/十三回忌〜二七回忌・・・(一切成就、即身成仏)別名は、昆盧流遮那如来とも言われ、天地あらゆる者、宇宙生命そのものの仏さまで太陽の様に輝いていることから、大日如来と名付けられています。これまで導いて下さった十一人の仏さまに(不動明王尊・釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩・地蔵菩薩・弥勒菩薩・薬師如来・観世音菩薩・勢至菩薩・阿弥陀如来・阿閦如来) によって教え導かれどれだけ悟りが深まっているかを観て下さり、その上にさらに導いて下さいます。
●虚空蔵菩薩-こくうぞうぼさつ/三十三回忌・・・(仏智悟入、福徳)虚空(天界・法界)のような蔵(知恵・功徳)を持ち合わせ、広大ではかり知れないお力ですばらしい記憶力と知恵を表す剣を持ち、左手には福徳を表す蓮華の上に宝球をのせて持っています。 どんな人にも仏さまになれる仏性があることを虚空蔵菩薩が教えて導いて下さり涅槃へ到着できるのです。 |

●恐山
宇曽利山湖の湖畔にある恐山菩提寺は日本三大霊場の一つであり、9世紀頃に天台宗の慈覚大師円仁が開基した。本尊は延命地蔵尊。同寺は現在は曹洞宗の寺院であり、本坊はむつ市田名部にある円通寺である。恐山は死者の集まる山とされ、7月の恐山大祭では、恐山菩提寺の境内でイタコの口寄せも行われる。
恐山は、地蔵信仰を背景にした死者への供養の場として知られ、古くから崇敬を集めてきた。下北地方では「人は死ねば(魂は)お山(恐山)さ行ぐ」と言い伝えられている。山中の奇観を仏僧が死後の世界に擬したことにより参拝者が多くなり信仰の場として知られるようになった。明治・大正期には「恐山に行けば死者に会える」「河原に石を積み上げ供物をし声を上げて泣くと先祖の声を聞くことができる」「恐山の三大不思議(夕刻に河原に小石を積み上げても翌朝には必ず崩れている、深夜地蔵尊の錫杖の音がする、夜中に雨が降ると堂内の地蔵尊の衣も濡れている)」などが俗信された。 |




 |

 |