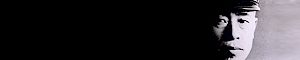●お祭り 電気担当メモ

●大原則
●電気機器は1回路 最大1.5Kw
●機器設置後 自分の目で1.5Kw以下であることを確認 それからコンセントに接続

●電気コードの引き回し(仮設) 安全確保
(コードリール・延長コード)
●仮設コードは 誰にも判るよう 大袈裟に紐止めする
●紐止めは撤収が簡単な 片結び1回とする
●仮設コード 廊下を横切るときは トラテープで固定
●仮設コード 空中を渡したときは 紐をぶら下げる

●毎年の間違い・危険
●広場の照明ランプ(1.5Kw)が2本ある これを直結してしまう 直結してないことを確認
●ホットプレート2台 フランク焼きは1台 1台で保温 担当に厳守をしつこく伝える
(人の注意力頼り 焼き始めてから再度 担当に厳守を伝える)
●突然の雨 電気コードの全ての接続部分 ゴミ袋で雨滴がかからないようにする
ゴミ袋の口 必ず地面に向けて挟み込む
(激しい雨 全てのコンセント接続を切る 当日の使用を止める)

●照明ランプ
●コードリール・延長コードで 必要な照明ランプを配置する

●危険の予防
●売店後ろの駐輪場の区分柱 頭をぶつける トラテープで注意 紐をぶら下げる
●ドアを介して仮設コードを通す ドアストッパー以外に コード1本分のスペースを作る
(誤ってドアストッパーが外れた時 仮設コードがドアに挟まれて断線?)
●勝手室は既に家電があり 複数のコンセントはあるが 使える電気容量は1.5Kw以下
●コンセント接続30分後 コード・コネクターもとのコードを素手で触る 熱くなければOK
●全コンセント接続を1時間毎に確認 コード・コネクターが正常に差し込まれているか
(誤って子供がコード・コネクターを蹴とばしたか 接続不良でコネクターが大過熱)
●人の注意力頼りの部分 嫌われますが 直接・簡潔な言葉でしつこく注意指示

山本五十六
大日本帝国海軍軍人で、太平洋戦争開戦時の際の連合艦隊司令長官を務めました。そこで真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦をはじめとした歴史的にも有名な作戦を指示したことでも有名で、アメリカと日本の実力差を熟知していたことからも最後まで戦争に反対していたとも言われています。そんな山本五十六が生前、口にした数々の名言の中でも、特に有名なのが「やってみせ」から始まる言葉です。軍人として、多くの部下を統率してきた経験があるからこそ身につけた 「いかにして人を動かすか」 のエッセンスが詰まった言葉であり、有名な格言として知られています。

●人を動かす
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。
(この言葉には次のような続きがあります)
話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。
いくらマニュアルを読ませたり、口で上手く説明したとしても、具体的な仕事のイメージが掴めなければ完璧な理解には及びません。なにより、人間の五感の中で最も情報をインプットするのが「視覚」とも言われていますので、実際の様子を見せることによって理解が進むでしょう。
どうしても時間の都合や手間を理由に、口頭説明のみで終わらせがちですが、人になにかを教える時は、まず自分が率先してやってみせることが重要です。また、相手に敬意を払うという意味でも、面倒くさがらずに見せるということを意識しましょう。
●言って聞かせる
やってみせた後は、しっかりと説明して聞かせることが重要だということです。例え、手本を見せただけでも上手く伝わっているとは限りません。テレビドラマのように職人が弟子に伝える「見て覚えろ」のような美徳は教える側の過信となっている可能性があります。そのため、見せてイメージを掴ませたあとは、言葉で補足説明をして十分に伝えましょう。
また、「言って聞かせる」という言葉からも分かるように、重要なのは相手に伝わっているかです。一方的に説明したかどうかではなく、きちんと相手に伝わっているか、理解ができたかどうかという点に注意して説明しましょう。
●させてみる
見せて聞かせたあとは、実際に相手に実践させましょう。ご自身でも、いざ、実践しようとしたら思うように出来ないという経験はないでしょうか。それは、ごく普通の流れで、結局は頭のなかで完結しているだけなので、見て聞いた内容を実践することで再現してもらいましょう。
もちろん、理解度は人それぞれですので、説明だけでも理解できる、わざわざ実践させなくてもできる、と思われるかもしれませんが、理解を深めるためにも実践してもらうことが指導の基本として覚えておきましょう。
●ほめてやる
実際にさせてみた後は、相手を褒めてあげましょう。褒めるといってもできの良さを賞賛するのではなく、相手を肯定するようなイメージです。覚えたての相手が初めから完璧に仕事ができることはなかなか無いので、褒めることを怠ってしまいがちですし、教える側としても100%のできではないにも関わらず「褒める」という行為に違和感を感じる方も少なくないでしょう。
しかし、指導において相手を褒めてあげることは非常に重要な要素の一つで、褒める=肯定してあげることが自信を持って仕事に取り組む原動力となります。褒めることに慣れない方であれば、「それで大丈夫」「そのやり方で問題ない」というようなニュアンスで相手を肯定しましょう。
●人を動かす
上記のステップを踏み、理解と信頼関係を築いたうえで相手が納得したら、ようやく”動いてもらえた”ということです。人間は、それぞれ考え方や感情を抱く意思をもっています。例え、何かしらの成果物が残せたとしても、本質を理解した仕事としていない仕事では、雲泥の差が生まれることは間違いありません。
つまり、本質を理解した行動を起こしてもらうためにも上記のステップを経て、相手の意志で自ら行動してもらう必要があります。そのためには、教える側も最適な教育方法を考え、行動していく必要があるのです。
●( 続き )
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。」という名言には続きがあります。「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。 やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」という言葉です。
つまり、これら言葉が共通して述べているのは”相手に敬意を払わないと動いてはくれない”ということです。なぜなら、相手を軽んじて言うことをきかせようとすれば、反発されたり、関係が構築できないのは当然のことでしょう。

苦しいこともあるだろう。云い度いこともあるだろう。不満なこともあるだろう。腹の立つこともあるだろう。泣き度いこともあるだろう。これらをじつとこらえてゆくのが男の修行である。
是非やれといわれれば、初めの半年や一年は、ずいぶん暴れてごらんにいれます。しかし二年、三年となっては、全く確信は持てません。三国同盟ができたのは致し方ないが、かくなった上は、日米戦争の回避に極力ご努力を願いたいと思います。
実年者は、今どきの若い者などということを絶対に言うな。なぜなら、われわれ実年者が若かった時に同じことを言われたはずだ。今どきの若者は全くしょうがない、年長者に対して礼儀を知らぬ、道で会っても挨拶もしない、いったい日本はどうなるのだ、などと言われたものだ。その若者が、こうして年を取ったまでだ。だから、実年者は若者が何をしたか、などと言うな。何ができるか、とその可能性を発見してやってくれ。
陸軍との争いを避けたいから同盟を結んだというが、内乱では国は滅びない。戦争では国が滅びる。内乱を避けるために、戦争に賭けるとは、主客転倒もはなはだしい。
博打をしないような男はろくなものじゃない。
人は神ではない。誤りをするというところに人間味がある。
ああ われ何の面目ありて見(まみ)えむ大君に 将又(はたまた)逝きし戦友の父兄に告げむ言葉なし いざまてしばし若人ら死出の名残の一戦を 華々しくも戦ひてやがてあと追ふわれなるぞ
中才は肩書によって現はれ、大才は肩書を邪魔にし、小才は肩書を汚す。