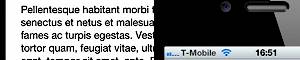● メール
長いメールほど一行で返す。
ロジックより気持ちを書く。
ひらがなの言葉にすると距離が近づく。
名詞でとめず動詞まで書く。
過去形よりも現在形で書こう「今日は楽しかったね」より「まだ余韻が続いています」。
ほめ言葉は「自分がどう変わったか」を書こう「元気ですね」より「私まで元気になった」。
●本を読み終わらないうちに感想メールを送る。
「中谷さんの本を読みました。面白かったです」というお手紙をいただきます。最後まで読みきってから、手紙を書いているのです。「最後まで読もう」という勢いで読んでいるので、うれしいことはうれしいです。でも読み始めた時の気持ちをすぐ伝えたほうが、気持ちがよりダイレクトに伝わります。私は今、読みかけの本があります。冒頭から面白いので、すぐに「この本、面白いよ」というメールを送りました。「今、きれいな月が出ているよ」とか「今、テレビで面白いのをやっているよ」と送るのと同じです。最後まで読みきってから、その中で一番面白かったことを書くよりは、一つ面白いところが見つかったら、その気持ちをすぐ伝えたほうが、より相手に伝わるのです。
●「元気ですね」より「私まで元気になった」。
「相変わらずお元気そうでした」とか「相変わらずお若いですね」というメールは100万人が書いています。これはお世辞の域を出ません。自分がどうなったかを書いたほうが、相手に伝わります。ほめ言葉は、相手のことを書くだけで終わらないようにします。ほめる相手に出会った自分が、どう変わったかです。人間は、人に影響を与えることが、うれしいのです。
●デート後のメールで次回の話はしない。
デートのあとに、男性は「また会いたいです」「また食べに行きましょう」というメールを送ります。(中略) 女性はここで少しガッカリします。女性は「まだ一緒にいるみたいです」という感覚です。このメールは今日のデートの続きです。男性は気持ちが次に行っています。「今日」を断ち切っているのです。デートのあとのメールは「今日は楽しかったね」と送ります。次のダンドリの話はしないようにします。 |


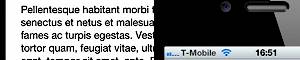
● メモ
楽しみを書こう「会いたい」より「会えるまで楽しみ」。
評価より気持ちを書こう「~がよかった」より「~がうれしかった」。
「~さんへ」より「~さんに」。
●誰もが書くであろうことは書かない。
短い文章は人の心に刺さります。誰もが書くようなことは誰かに書かせておいて、自分はその先の誰も言わないことを書きます。それが人の心に残るのです。小堺一機さんは、舞台で緊張して、セリフを忘れたことがあったそうです。その時に、萩本欽一さんは「オレ、緊張しないようなヤツ、嫌い」と言いました。小堺さんは、このひと言で勇気づけられました。そこで小堺さんが芸能人を諦めてしまうか、今の小堺一機さんになっていくかは、そのひと言の力が決め手だったのです。萩本欽一さんにとっては、何げなく言った言葉です。ほめることも、厳しいことも、ボソッと言った言葉、メールの一行、伝言メモのひと言が印象に残るのです。
●形容詞を削って動詞で書く。
「そうだ京都、行こう。」は、プロが書いたコピーです。形容詞はまったく入っていません。「アダルトなあなたに、ゴージャスでミステリアスな京都」と言われたら、安っぽいスナックの感じがします。いかに形容詞を削って、動詞で書くかです。そのためには、形容詞より動詞のボキャブラリーを増やしていきます。思考回路も、形容詞で考える生き方より、動詞で考える生き方をしたほうがいいのです。
●ほめ言葉は自分がどうなったか書く。
「相変わらずお元気そうでした」とか「相変わらずお若いですね」というメールは、100万人が書いています。これは、おせじの域を出ません。どうせ書くなら、「相変わらずお元気で、私まで元気をいただきました」とか「相変わらずお若くて、私まで10歳若返った気がしました」のほうが印象に残ります。自分がどうなったかを書いたほうが、相手に伝わります。これが「ひと言」の書き方です。
●「~さんへ」より「~さんに」。
メッセージには、通常、「○○さんへ」と書きます。それよりは、「○○さんに」と書いたほうが優しくなります。これは感性学の黒川伊保子先生に教えてもらいました。プレゼントを贈る時に、「○○さんへ」と書くと、自分を届けられません。「○○さんに」と書くと、モノと一緒に自分を届けられるのです。この話を講演ですると、みんなどよめいていました。頭の中で、自分が今まで好きな女性に送っていたメールが全部了「~へ」だったことを思い出したのです。
●「~したほうがいい」より「~したら、もっとうれしい」。
何かしてほしいことがある時に、一番強いのは「○○してよ」という命令文です。「○○したほうがいい」と言うと、命令文をやわらげることができます。「○○するだけでいい」と言うと、さらにやわらぎます。べストは「○○してくれたら、うれしい」です。その上が「○○してくれたら、もっとうれしい」です。今の状態で満足していることが前提です。
●「~がよかった」より「~がうれしかった」。
上司が部下に「○○が良かった」と褒めるのは、上から目線です。「あれが良くて、これがダメ」という評価になるのです。私の記憶に残っているのは、「中谷君が元気だと僕は嬉しい」という先輩からのメモです。「元気で良かった」よりも「元気だとうれしい」のほうが、頑張ろうという気持ちになります。感情を書くことで、伝わるのです。
●「楽しみにしています」より「ワクワクしています」。
明日誰かに会う時に、通常は「明日お会いできるのを楽しみにしています」と書きます。「楽しみにしています」は社交辞令的です。「ワクワクしています」というとオノマトペ(擬音語・擬態語)に変えた瞬間に、会う前のワクワク感が一気に伝わります。「今日お会いして楽しかったです」より「今日お会いしてドキドキしました」のほうがずっと嬉しいのです。 |



● アンケート
今日のことを書こう「前から感じていた」より「今日感じた」。
「AとB」の「と」が入ると、ありがたみがなくなる。
「参考になりました」は上から目線。
また聞きより実体験を書く。
全部より1個書こう「みんなよかった」より一番よかったものを1つ書く。
●話したことより気づいたことを書く。
私の話を聞いて、その人が気づいたことを書いてくれたほうが、「そういうふうに感じてくれたんだ」と、うれしくなります。「話を聞いて試してみたら、こんな結果が出てびっくりしました」というのは、私の知らないことなので、うれしいです。著者にあらすじを書いてきて、どうするんだという話です「この本にこういう言葉が書いてあった」と言いますが、それは自分が書いているので知っています。本に書いていないことが「気づき」です。暗記したことを害くのではなく、気づきを送ってほしいのです。
●「みんなよかった」より一番よかったものを1つ書く。
レストランにアンケートの紙が置いてあります。「みんなおいしかったです」と書くのは、聞いた側が一番つまらない感想です。「みんなおいしかった」と言えば言うほど、「どれもパッとしなかった」という印象を与えてしまうのです。「これが印象に残りました」「これが特にまた食べたい」と、1点を選んで書いたほうがシェフは喜びます。
●上から目線に感じられないか「他人の目」でチェックする。
話し言葉ではニュアンスをつけられるので、上から目線にならない言い回しでも、書き言葉では上から目線に感じてしまうことがあります。(中略) 大切なことは、上から目線で書かないことではありません。そもそも、そんな意識では書いていないからです。上から目線に読まれる可能性に、気づくことです。そのためには、「そんなつもりで書いていない」というのではなく、他人の目で、自分の文章を読むことです。 |



● 応用
究極の「おいしい」は「ん~」。
「ありがとうございました」が一番つまらない。
「昔、こんなことがあった」より「さっき、変なことがあった」。
●感動する文章には「感動」という言葉は使われていない。
「感動」という言葉を使うと、感動しません。「おいしい」と書くと、おいしさは伝わりません。「オシャレ」「カッコいい」「素敵」と言えば言うほど、ダサくなります。感情を伝えるのが、ひと言です。感情を伝えるには、感情をダイレクトに出さないことです。これが、読む時と書く時の違いです。感動が伝わった時、読み手は文章の中に「感動」という言葉が何度も出てきたと感じます。それは、錯覚なのです。一度も出てきていません。自分が、書き手にまわった時、感動を伝えようと、「感動」を連発してしまうのです。感動的な文章に、「感動」が使われていないことを、確認してみてください。
●究極の「おいしい」は「ん~」。
究極、一番おいしい時の言葉は「ん~」です。「うまい」という言葉は、もとは「ん~まい」です。「ん~」をムリヤリ言葉にしたのが「うまい」です。グルメ番組で、ぱくっと食べてすぐ「おいしい」と言われたら、視聴者は何か段取りっぽく感じます。本当においしいときは話したくないのです。今、口の中で味わっているのに、もったいないからです。
●「大丈夫です」がガッカリさせる。
原稿を届けた時に起こりがちなことがあります。「これで大丈夫でしたか」と聞くと、「大丈夫です」と返されるのです。これはガッカリします。「大丈夫」は、「ダメ」の1つ上の言葉です。ギリギリセーフということです。「大丈夫」をグッドと勘違いしないことです。
●いい例を書き始めるといい例に出会える。
メッセージを伝えたい時、2通りの方法があります。①Aではダメだよね。②Bになろうね。ダメな例をみせるか、いい例を見せるかです。ついダメな例を見せてしまいがちです。そのほうが、書きやすいからです。悪い例を書き始めると、悪い例に出会うようになります。いい例を書き始めると、いい例に出会うようになります。いい例に出会ったほうが、読み手も書き手も、精神的に健康になるのです。 |



● ブログ
答えから入ろう、タイトルは質問形より「答え形」が読まれる。
オチをじらさない、続きもので引っ張ると、読んでもらえなくなる。
「!」はびっくりされない。
(笑)は笑ってもらえない。
大勢に読んでもらおうとしない、読者が減ることで、熱烈な読者が生まれる。
●コンスタントに更新することで、信用ができる。
私が継続して読んでいるブログに、共通点があります。それは、「定期的に更新される」ことです。読むものは、新聞のように、習慣化したものが強いです。「面白いな。次も読みたいな」と思っても、いつ更新されるかわからないブログは、読まれなくなります。立て続けに更新されたかと思ったら、ぱったり間があいてしまうブログは、「行けたら、行くわ」と言う友だちみたいで、信用できません。定期的に更新されるというのは、なかなか大変なことです。だから、つい、また聞き情報を書いてしまうことになるのです。本当に書きたいことを届けたいからといって間があいてしまっても、読者への信頼感がなくなります。では、どうすればいいか。ブログは「契約書のない指切り」です。指切りを守るためには、3つのことを実行することです。
(1)定期的な頻度を決めて守る。
(2)いつもネタ探しをしておく。
(3)原稿のストックを早めに書いておく。
これが、読んでくれる人への心尽くしです。
●トーンではしゃがない。
読み手が、いまどんな状況にあるかは、その時々で変わります。あまりにハイテンションできてしまうと「なにを一人で、舞い上がってるんだろう」と、ハズしてしまうのです。深夜バラエテイーではなくNHKのニュースくらいの淡々としたトーンのほうが、毎日読んでも、しんどくならないです。それでも、面白いものは面白い。トーンではしゃがないと面白くないものは、視点そのものが、面白くないのです。 |



● メルマガ
読者の「困ったこと」を解決するために書く。
人をほめるふりをして自分の自慢話にしない。
体験を共有すると凄い感動を共有できる。
テンプレートが最初にくると読まれなくなる。
昨日の行数以上にしない、文字数の少ないメルマガほど面白い。
読まれる時間を意識しよう、読者がどこで読んでいるかを決める。
同じ時間に送ろう、1日に2通以上届くと煩わしく思われる。
●文字数の少ないメルマガほど面白い。
膨大にあるメルマガの中で、続けて読んでいるメルマガと、配信停止にするメルマガが、くっきり分かれます。続けて読んでいるメルマガは、「文字数が少ない」です。メルマガは、勝手に長くなっていきます。前回より、短くなることはないという性格があるからです。メルマガの面白さは、長さに反比例します。面白いメルマガほど、文字数が少ないのです。「文字数の多い」メルマガを書いてしまう人は、文字を増やすことが読者へのサービスと勘違いしてしまっています。それは逆なのです。文字数を少なくするコツは、3つあります。
(1)1回のメルマガは1テーマ。長い話になる時は切って分ける。
(2)抽象的な話より具体的な話。大きな話より小さな話です。
(3)ご挨拶は、要らない。
冒頭で、ご挨拶があるメルマガで、中身の面白いものはないのです。書き手が良かれと思って文字数が多くなるメルマガは、読者の気持ちを、読み違えていることが、配信停止になる原因です。前回以上、長くしないのが、コツです。 |


 |