

●エッセイ
時間調整の楽しみ
話題獲得知識を広める
時代のキーワード探し
出発は新潮と文春のコラムでしたか

山口瞳
上前淳一郎
ボブ・グリーン
ハロラン・芙美子
ポール・ボネ
マークス・寿子
司馬遼太郎




●一人の作家にのめり込む
新田次郎
山本七平
山本夏彦


●実用書・経営書
管理職になり手にしました


●専門書
三省堂で立ち読み お世話になりました
たった数ページのために何千円かの投資もしました
今は出番はありません本棚にうずくまっています
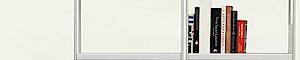


●電子書籍
読書に合理性はいらないような気がします
電子書籍に興味が湧きません







