 �@ �@
��5���~��5000���̐V���܍��`���V���܂���I
|
|
�u����ƊE�v�Ƃ����ƁA����{�����ʔň���Ƃ��������A�������͊X��̏����Ȉ����Ђ̂����ꂩ��z�����������������낤�B�ǂ�����̂��炠��u�I�[���h�G�R�m�~�[�v�̑�\��ŁA�s��K�͂����X�ɏk�����Ă���ƊE�ł�����B����Ȉ���ƊE�ō��A���ڂ���Ă���x���`���[��Ƃ����N�X�����B����͈���ݔ����������A�C���^�[�l�b�g�o�R�Ōڋq���疼�h��`���V�Ȃǂ̈�������A�A�g���������̈����ЂɈ�����˗����郂�f�����m���B�����̈����Ђ̐ݔ��̉ғ����͏�ɒႭ�A������ȂƂ���ɖڂ�t���A�H��̋��Ԃ�L�����p���悤�Ƃ������݂��B��g��������Ђ�11�����_��1600�Ђɂ܂ő������B���N�̏t�ȍ~�́A�V���̐܍��`���V��|�X�e�B���O��ቿ�i�Œ���T�[�r�X���J�n�B�ڂ����͌�q���邪�A5�`10���~���x�ŁA�w�肵���G���A��5000���̐܍��`���V��z���Ƃ����ቿ�i�������B���ꂾ��������A�l�o�c�̓X�܂Ȃǂ��A�̑��ɐ܍��`���V����y�ɗ��p�ł���悤�ɂȂ�B���O���n�R���T���e�B���O��Џo�g�ŁA�u���̐l���ł��邱�Ƃ͂����B�����������ł��邱�Ƃ���肽���v�Ƙb�����N�X���̏��{�����В��ɘb�����B
�@ |
�\�\�\�ŋ߂̃x���`���[��ƂƂ����ƁA�X�}�z�̃A�v����l�b�g�T�[�r�X�ȂǂƎv�������ł����A���{����́u����v�ɖڂ�t����ꂽ�B����͂ǂ����Ăł����H
�@
���{�F����2008�N��A.T.�J�[�j�[�Ƃ����O���n�̃R���T���e�B���O��ЂɐV���œ������̂ł����A�����ł̓R�X�g�팸�Ɋւ���v���W�F�N�g�ɑ����g�������ł��B�R�X�g�팸�Ƃ����Ă��A�����Ȕ�p���ڂ�����܂���ˁB���́A���ڍ����Ԑڍ��𒆐S�ɃR�X�g���팸����Ƃ��������Ă�����ł��B
�@
�Ԑڍ��Ƃ����Ă��A���W�X�e�B�b�N�X��������A�v�����[�V�����R�X�g��������A�����A���M��A�̊ǔ�A�V�X�e���J���A�ʐM��ȂǁA���ɕ����L���B�������������ׂ����Ƃ���܂Ō����̂ł����A���̒��Łu�����v�����ɃR�X�g�팸���ʂ������Ƃ������ƂɋC�t������ł��B
�@
�� ����ƊE�̎s��K�͂͂܂�6���~������
�@
���ׂĂ݂�ƁA���ɖʔ�����ł��B����ƊE�́A���ɔ�����A�s�����ȋƊE�Ȃ�ł��B����ł��Ďs�ꂪ6���~�������ł��B6���~������Y�Ƃ��Ď��͂���ȂɂȂ��Ǝv����ł���B
�@
����{����A�ʔň���Ȃǂ̑�肪����A�ȑO�͂��̑���3���Ђ������Ђ���������ł��B���߂̐������ƁA2���В��x�Ɍ����Ă���悤�ł��B2009�N�A2010�N�O��ŁA��ԓ|�Y�����������͈̂����Ђ�������ł��ˁB
�@
���������Ă��邯��ǁA�܂�2���Ђ�����B����ȃK���o�[�����āA���������ɂ�������Ƃ����A���тȍ\���Ȃ�ł��B�����́A�C���^�[�l�b�g���g�����Ƃő傫���ς��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl�����킯�ł��B
|
�\�\�\���Ƃ��ƋN�Ƃ������ƍl���Ă����̂ł����H�V���œ��Ђ��ꂽ�̂͊O���n�R���T���e�B���O��Ђł��ˁB
�@
���{�F��w�̂Ƃ��A�L���ȋ����▼�������l�̕��X����u�����v�ƌ����Ȃ�����A�����̊w���Ńr�W�l�X�R���e�X�g���J�Âł����o�������̂������e�����Ă��܂��B�u�[������1�v�͈ӊO�ɕ��ʂ̐l�ł�����ƁB�����āA���������Ă���̂́A���̂������y�������ƂȂƐg�������đ̌������킯�ł��B
�@
���̐���́A���́A�N�Ƃ���Ƃ����I���������܂�Ȃ����ゾ������ł��B����2008�N���ЂȂ�ł����A�A�E������2006�N�Ă��납��n�܂�����ł��B���̔N��1���ɂ̓��C�u�h�A�V���b�N���N���Ă����ł��B�Ȃ̂ŁA�u�x���`���[���Ċ�Ȃ��Ȃ��v�Ƃ������C���[�W�����l�������āA�|�W�e�B�u�ȃC���[�W�������ĂȂ�������ł��B�������������Ƃ������ăR���T���e�B���O��Ђɓ������킯�ł����A�u�[������1�v�����Ƃ����v�����Ȃ��Ȃ肫�炸�ɋN�Ƃ����킯�ł��B
�@
�� �ŏ��̔��N�́A��Аݗ�����H������������݂�200���~�ʼn߂���
�@
�X�^�[�g���́A������邩�A�r�W�l�X���f�����܂��������܂��Ă��Ȃ�������ł��B�R���T���^���g�炵����ʋN�ƂȂ�ł��ˁB2009�N��9���ɉ�Ђ�����Ă���̍ŏ��̔��N�Ԃ́A���{��200���~�ŁA��Аݗ�����H����������S�����݂Ŕ��N�߂����܂����B24�������̂ŁA���Ƃ����邱�Ƃ��ł�����ł��B
�@
�ŏ����N�͂���������Ԃ̒��ŁA����ƊE�̉������Ȃ̂���O��I�Ƀq�A�����O���܂����B�����Ă����ۑ��1���A���|�I�Ɂu�d���v�̑����ƊE���Ƃ������Ƃł��B����͉������d���̂��Ƃł��B5�d6�d�Ŕ������邱�Ƃ�����A�u�������O���ɏo�����d�����A�����̂Ƃ���ɋA���Ă���v�Ƃ����b���������ł��B
�@
���̊ԂŃ}�[�W���Ƃ�킯�ł�����A�ŏI�I�ȉ��i�͂��̂����������Ȃ�܂��B��قǏo�z�x�[�X�ł�6���~�ɂȂ�Ƙb���܂������A���Y�z�x�[�X����4���~���Ȃ�ł��ˁB2���~�߂��J���������āA���ꂪ�܂��Ɂu�d���v�̂����Ȃ�ł��B
�@
���́A1��̈���@���Ή��ł��������̕��́A����ȂɍL���Ȃ���ł��B����@�͈������̂ł͂Ȃ��āA���~�P�ʂł�����̂ł����A�Ⴆ�Ζ��h���������@�ƁA�������������@�͈Ⴂ�܂��B�����ƃ`���V���Ⴂ�܂��B�܂��A����@���āAA�ł�B�ł������āAB�ł̈���@�ŁAA4���������ƁA��������ł̃��X��������A���̃��X�����������ŁA�����Ȃ��ł��B������A����̂��鑼�̉�Ђɗ����Ă����킯�ł��B
�@
���ƁA����̎��v�́A�V�N�x���n�܂�O��3������ԑ傫���Ȃ�܂��B����Ƃ͂ǂ̉�Ђ��ݔ�����������̂��D���ŁA3�����v�ɍ��킹�Đݔ�����������̂ł����A5��6���͎��v���}�������ł���B���R�A�ғ������O���Ɖ�����B
|
�\�\�\�ŏ��́A����̉��i��r�T�C�g����n�߂�ꂽ�����ł��ˁB���̌�A�����̃T�C�g�ň�����������ʔ̂̃|�[�^���𗧂��グ���B
�@
���{�F�ŏ��́A����̈����Ђ���̔̔��㗝�X���������A�����Ђ̉��i�����W�߂Ă��āA�ň��l�ۏ������u���[�J�[(�����)��������肵�܂����B����������A�u�u���[�J�[����邭�炢�Ȃ�A����̉��i����L���Ŏg�킹�Ă���v�Ƃ����b�ɂȂ�����ł��B���i�̔�r���ɂ��������v����������ł��ˁB��������A���i��r�����ŃC���^�[�l�b�g��ɍڂ��Ă݂悤�Ǝv�����킯�ł��B����������A���q����������Ђ�������ɔ�������������ł��B�����́A�C���^�[�l�b�g�ɁA����ɓ��������{�i�I�ȃ|�[�^���T�C�g���đ��݂��Ă��Ȃ�������ł��B
�@
���̉��i��r�T�C�g�͍�������Ă��܂��B����Ή��i�R���̂悤�ȃ��f���ł��B�L�����������������Ȃ���^�c���āA�������ɂ��������āA�����`�Ŏ��Ƃ�W�J���Ă���܂����B������˗����邨�q�l�A����Ɉ����Ђ���̓o�^�������ς������āA���������p���������悤�ɂȂ����̂ł����A�����Ŗ�肪���������̂ł��B
�@
�� ����H��������Ȃ����݂�����
�@
�����ґ��̂��q�l���������x�����Ă���Ȃ��A�Ƃ�������肪�o�Ă����̂ł��B�����́A�P�Ɉ����Ђ��Љ�Ă��邾���Ȃ̂ŁA�����҂ƈ����Ђ̗����ɑ��ĉ����T�[�r�X��ł��Ȃ�������ł���B�P���ȃ}�b�`���O�ł́A���q�l�ɑ��Ă��A�����Ђ���ɂƂ��Ă��A�����T�[�r�X�������Ȃ��ƒɊ������킯�ł��B
�@
�C���^�[�l�b�g�ň�����ł�����֗��Ȋ��A�ł����킹�ȂǕs�v�ł��̏�Ŕ����āA�����ɓ͂��悤�ȃT�[�r�X����X�ō���Ă������ق�����������Ȃ����ƁB����ŁA���ЂŒ��ڔ̔����Ă�������ɕς�����ł��B���ꂪ�A���N3���ɊJ�n�������N�X���̃T�[�r�X�ł��B
�@
���h�A�`���V�A�|�X�^�[�Ȃǂ����N�X���̃E�F�u�T�C�g�Œ������t���A��g���Ă�������ЂɈ�������܂��B���N11�����_�Œ�g���Ă�������Ђ͖�1600�Ђ���܂��B��X�͈���@�������Ă��܂��A�e�����Ђ̈���\�͂𗘗p�����Ă��������Ă���킯�ł��B
|
�\�\�\��g���Ă�������ЂɂƂ��ẮA���Ђ̐ݔ���L�����p�ł��郂�f���ɂȂ��Ă���̂͂悭�킩��܂��B�����A��������邨�q�l���猩��ƁA���Ђň���@�������Ă��鑼�̈���ʔ̉�ЂƓ����Ɍ����܂��H
�@
���{�F����@��ۗL���Ă��Ȃ�����ł��邱�Ƃ�����܂��B�Ⴆ�A���Ђōs���Ă���T�[�r�X�ŁA4���Ԉȓ��ɖ��h�����͂�����Ƃ����T�[�r�X������܂��B
�@
���ʂ̈����Ђ���ł��A�o���Ԃ���Ă���Ƃ���͂���܂��B�������A�g�茳�ɓ͂��h���Ԃ͖ł��Ȃ���ł��B�Ȃ��Ȃ�A�������H�ꂩ��̋����ɂ���āA���S�~��ɔz�����Ԃ��ς���Ă��邩��ł��B�ł����A��X�͒�g��������Ђ���������܂�����A������ɋ߂������Ђ�I�ׂ܂��B���Y��1���ԁA�o�C�N�ւ�1���ԁA����Ƀo�b�t�@�[��2���ԂƂ�A4���Ԉȓ��ɓ͂����܂��B�H���1�J�����������Ă��Ȃ��ƁA�����������Ƃ��ł��Ȃ���ł��B
�@
�� �V���̐܍��`���V��ቿ�i�Ŏ���
�@
�u���������ł����ł��Ȃ����Ƃ����v�Ƃ����Ƃ���́A�������̂������l���Ă��܂��B���N��4������́A�w�肵���G���A�ŐV���܍��`���V���ł���T�[�r�X���n�߂܂����B
�@
�Ⴆ�A���͑��ƒ��c�̊Ԃ̔��a700���[�g���̃G���A�ŁA11��10���ɁAA4�T�C�Y�̗��ʂ̈������4750��������āA�ǔ��V���Ɩ����V���ɓ���Ĕz�z����Ƃ����̂��A5���~�łł����ł���B
|
�\�\�\����͈����Ȃ��ł����H10�N�قǑO�̘b�ł����A�}���V�����̉c�ƒS���̐l�ɁA�`���V��1��܂��̂�200���~���炢������ƕ��������Ƃ�����܂��B�����A���́A�܍��`���V�ɍڂ����L�����Z���Z���̃}���V����������ł��B��l�������Ă�������̂ł����A���̍ۂɃ`���V�̔�p�̘b�������Ă��ꂽ��ł��B����1��`���V���܂����Ƃ��l����A���̔�p���炢�͒l�����ł���Ƃ����킯�ł��B�z�z�����Ȃǂ͈Ⴄ�ł��傤����P����r�͂ł��܂��A�͕̂S���P�ʂ̔�p���K�v���������̂��A����5���~�ł܂����ł����B�����ł��ˁB
�@
���{�F�����Ȃ�ł��B����f�[�^��������������A5���~�Ń`���V���������āA���͑��̂��̃G���A�ɔ��a7�L���̌�����4750�����z�z����A11/10�ɐV�����J���ƃ`���V�������Ă���킯�ł��B
�@
5���~�̈Č���4���~�ȏオ�����ɂȂ��ł����A�c�Ƃ��Ԃɓ�������c�ƌ������������ăy�C���Ȃ��ł���ˁB�ł��A�C���^�[�l�b�g���g���Ήc�ƕ�����S���������Ƃ��ł����ł��B�����b�g�̐܍��`���V��A�|�X�e�B���O���ቿ�i�ʼn\�ɂȂ�܂��B
�@
5000���̃`���V��5���~�ł܂��������A���[����������ł��܂��܂��B�}�b�T�[�W��������܂��܂��B�����������e�[���̏��������Ă��钆����Ƃ̐l�������A�r�W�l�X�̏W�q��i�������Ƃ��ł���킯�ł��B
�@
�]���̐܍��`���V�́A������x�̋K�͂̃f�x���b�p�[��������A�X�[�p�[��������łȂ��Ƃ܂��Ȃ�������ł��B������A�ǂ��ɍs���Ă��A�V���ɓ����Ă���`���V�́A�m���̐R�A���j�N���A�C�I���A�C�g�[���[�J�h�[�Ȃǂňꏏ�ł���ˁB
|
�� �l�X�܂��܍��`���V�Ȃ�āA���肦�Ȃ�����
�@
�\�\�\���p�ґ����猩�Ă��A�`���V�ł̔����������܂��B�V�����X���ł�������ǁA�F�m����Ȃ��܂܂ɏ�ޓX����������Ȃ��ł����B���̍Ȃ̖��̓P�[�L��������Ă����ł����A�ŏ��͏W�q�ɋ�J������ł���B
�@
���{�F�܂��ɁA���������X�܂���Ɏg���Ă�������������ł���B���̓p�����⓮���a�@�Ȃǂł��g���Ă�����Ă܂��B�X��������Ă��ďW�q�ɋ�J���Ă���l�͔��ɑ����Ǝv���̂ł����A�܍��`���V���܂��Ȃ�Ĕ��z�Ƃ��Ďv�������Ȃ��B������ł��Ȃ��Ǝv������ł���B���ꂪ�C���^�[�l�b�g���g���ł���悤�ɂȂ��ł��B |
 �@
�@
���n�E�X�e���{�X�̍Č��@ |
�� ���b�Z�[�W�̏W��
�@
1992�N�A���H��2,200���~�������Ē��茧�����ێs�ɊJ�Ƃ����n�E�X�e���{�X(�ȉ��AHTB�Ƃ���)�͊J�ƈȗ�18���A���ŐԎ��ł����B���̊ԁA�����I�Ȍo�c�j������O�x���Ă��܂��B�o�u���̕��̈�Y�A��B�ő�̕s�Ǎ��Ƃ���ꂽHTB�𗷍s�㗝�X�g�h�r�Ƃ��̃O���[�v���Č����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
2010�N4���A�g�h�r�n�Ǝ҂Ō�����V�c�G�Y���В��ɏA�C�B�����10�N9�������Z(�ϑ��̔��N���Z)�ł����Ȃ荕�����Z�B11�N9������3�E11��k�Ђ��������ɂ�������炸�A����A���ō����ƂȂ�܂����B���f�B�A�͂�����g�V�c�}�W�b�N�h�ƌĂт܂����B
�@
11�N12���A�����V�c�}�W�b�N���w�ڂ��Ɠ��o�a�o�Ђ����n�K��Z�~�i�[���J�ÁB�M��(���i)���V�c����̍u���⌻�n���@���s��ꂽ��A�����`�F�X�^�[�헪�̐��Ƃ̗�����V�c�}�W�b�N���������u�`���s���܂����B��u�߂͒N�ł��ł�����̂ł����A��i�̎햾���������݂܂����B
�@
�V�c����͂g�h�r�n�Ƃ�1980�N�㏉���Ƀ����`�F�X�^�[�헪���w�сA���Ђ̐헪�Ɏ�����܂��B�����M�҂���C�����߂郉���`�F�X�^�[�헪�w��Ōږ�����������������Ă��܂��BHTB�Č��ɂ������`�F�X�^�[�I�Ȏv�l����������Ă���Ƃ������Ƃ���A�M�҂�������邱�ƂƂȂ����̂ł��B
�@
�n�E�X�e���{�X�Ƃ̓I�����_��Łu�X�̉Ɓv�Ƃ����Ӗ��ŁA�I�����_�̊X���݂��Č������e�[�}�p�[�N�ł��B�~�n�ʐς�152���u�Ɖ䂪���ő勉�B����ő�3���l�����e����A3,000�l���h���ł��܂��B96�N�ɂ͔N��380���l���K��A���̃f�B�Y�j�[�A����HTB�Ƃ������܂������A���̌�A�W���n�B�Ԏ��������܂��B
�@
�Ȃ��A�Ԏ��Ȃ̂��B�������������A�A�N�Z�X�������A�L���̂ŃR�X�g���ƁA���������������O�d�ꂾ����ł��B�����͎�s���̓�\���̈�ł��B�A�N�Z�X�͕����s����ԂœԁB�����`����o�X�ňꎞ�ԁB�������A��s�@��͍����A�������Ȃ��B�~�n�ʐς̍L���͈ێ��Ǘ�����������܂��B
�@
�X���݂͖{�ƃI�����_�������������̂ł����A�I�����_���̂��̂ł͂���܂���̂Ŗ{���ɂ͂��Ȃ��܂���B�~�b�L�[�}�E�X�̂悤�ȃL���[�R���e���c(�W�q�͂̂��閣�͓I�ȃ\�t�g)������܂���̂ŁA��x�͍s���Ă���x�A�O�x�ƖK���l�����Ȃ������̂ł��B
�@
�\���I�ɍ����ɂȂ�ɂ����A�O�x�������I�Ȕj�������Ƃŕ��̃C���[�W�����A�X�܂��ڗ����Ă���HTB���V�c����͂����ɂ��čČ������̂��B10�N4���A�В��ɏA�C�����V�c����́A�X�^�b�t��3�̊�{���j�������܂����B
�@
1 �|�������悤
�@
2 ���邭���C�Ɏd�������悤
�@
3 �o���2�������A�����2�����₻��
�@
���ɃV���v���ł��B�V�c����͂����܂��B�u��������A��������Ƃ����Ȃ肢���Ă��A�Ј��͍������܂��B�叫�͂܂��傫�ȖڕW���o�V�b�Ǝ����B�ׂ����w���͂��̌�ł��B�Ƃɂ����V���v���œ`��郁�b�Z�[�W�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�v
�@
���b�Z�[�W�͂��q�l�ɑ��Ă��]�ƈ��ɑ��Ă��V���v���ł킩��₷���Ȃ���Γ`���܂���B�����`�F�X�^�[�헪�ł����Ƃ���̈�_�W����`�ł��B���b�Z�[�W���W�����ׂ��Ȃ̂ł��B�����ȍ~��3�̊�{���j�̏ڍׂ�������A�܉�̃V���[�Y��HTB�Č��������`�F�X�^�[�헪�̎��_�ʼn�����܂��B�@ |
�� �}���O��Ƃ͍��ʉ��헪
�@
2010�N4���A�n�E�X�e���{�X(�ȉ��AHTB�Ƃ���)�Č��̂��ߎВ��ɏA�C�����V�c�G�Y����(�g�h�r�)�́A�X�^�b�t��3�̊�{���j�������܂����B(1)�|�������悤�A(2)���邭���C�Ɏd�������悤�A(3)�o���2�������A�����2�����₻���A�Ƃ������ɃV���v���Ȃ��̂ł����B
�@
���́u�|�������悤�v�Ƃ́u���W���Ă����Ђ͂��ꂢ�v�Ƃ����V�c����̌o��������ł��o���ꂽ���̂ł��BHTB�̓e�[�}�p�[�N�ł��B���q�l�Ɍ����镔���͂������A���ꂢ�ł����B�ł��A�o�b�N���[�h�͂܂��܂����V�c����͊����܂����B���q�l�Ɍ����Ȃ������܂ł��ꂢ�ɂ��悤�Ƃ������̂ł��B
�@
�|��������Ζׂ���Ə�����l�����܂����A����͐��_�_�݂̂Ȃ炸�A���_�I�ɗ��t�����܂��B�|���Ƃ͐����A���ځA���|�A�����̎l�̗v�f�ō\������܂��B
�@
�E�����E�E�E�v����̂Ɨv��Ȃ����̂��敪�����A�v��Ȃ����̂���������
�@
�E���ځE�E�E�v����̂�����̈ʒu�ɏ���̕��@�Ŕz�u���A�Ǘ�����
�@
�E���|�E�E�E�z�R���Ȃǂ�|�����߂�
�@
�E�����E�E�E�@���|���ȂǂŖ����グ�A�q���I�ɂ����I�ɂ�����������
�@
�l�v�f�̑|�������邱�ƂŁA�X�^�b�t�̋K�����ۂ���A�悢�K�����g�ɒ������Ƃŗ�߂��悭�Ȃ�A���S����q���ʂ����サ�܂��B�l�͒N���������ɊS������A�d�����ł����Ă����̂Ȃ��̓v���C�x�[�g�Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂����肷����̂ł��B��S�s���ɑ|�������邱�ƂŎ����̓���(�v���C�x�[�g)�Ɍ��������ȊS���O���Ɍ����܂��B����ƁA�X�^�b�t�́u�C�Â��A�C�z��A�C�����v���悭�Ȃ�܂��B���q�l�݂̂Ȃ炸�A�����ւ̔z�����s���͂��悤�ɂȂ�̂ł��B�u�������_�A�����̐S�v����܂�܂��B
�@
�g�D�ɂ͒N�����̂��A�͂����茈�܂��Ă��Ȃ�����ǁA�N�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�����R�قǂ���܂��B�����������d���͈������_���Ȃ���A�N�������̂�������Ă���邾�낤�ƂȂ�A�|�e���q�b�g�̂悤�ȃG���[�����܂�Ă��܂��܂��B�������_������A�C�Â����l�����悵�Ă��̂ŃG���[�����܂�ɂ����Ȃ�̂ł��B
�@
�N������Ă��悢�d����i��ł�邱�Ƃ��u�g�D�s�������v�Ƃ����܂����A���ꂪ�����ɍs����G���[�͌���A���Y���͏オ��A���݂������݂���z�����Ă���ƘA�шӎ������܂�A�����₷���Ȃ�̂ŏ]�ƈ������͍��܂�܂��B���̂悤�ȑg�D�̋Ɛт��オ��ʂ͂��͂���܂���B
�@
���́u���邭���C�Ɏd�������悤�v�Ƃ������Ƃ��A�e�[�}�p�[�N�Ƃ������i��A��������O�̂��Ƃł��B�X�^�b�t�͖��邭���C�ɐU�����Ă������ł����B�ł��A�O�����痈���V�c����̖ڂɂ͕s�[���ɉf��܂����B�n�ƈȗ��A�Ԏ������ŎЈ��ɕ����Ȃ����Ă����ۂł����B�u�E�\�ł��������疾�邭��낤�A����ǂ����������邭��낤�A���X����Ă��悢�d���͂ł������Ȃ��B�J�����C�ł���������A�Ƒi�����̂ł�(�V�c����)�B�v
�@
�|�������邭���C���e�[�}�p�[�N�Ƃ��Ă͂�������O�̂��ƂŁA����Ζ}���ł��B�����A���̓���O�̂��Ƃ�O�ꂵ�Čp�����Ă�蔲���ƁA���|�I�ȁA��ΓI�ȍ��ƂȂ�܂��B�}���O��͍��ʉ��헪�ł��B�����Ċ�Ɣɉh�̊�b�A��ՂƂȂ�̂ł��B
�@
���ʉ��헪�Ƃ����Ƒ��������X�点��A�C�f�B�A���l�������Ȃ���̂ł����A��b�̂��낢�A�C�f�B�A�����͒��������܂���B�}���O��̊�Ղ̏�ɗ��A�C�f�B�A����������̂ł��B�@ |
�� �I���ƏW���ƃX�s�[�h
�@
�n�E�X�e���{�X(�ȉ��AHTB�Ƃ���)�Č��̂��߂��V�c�G�Y����(�g�h�r�)��������3�̊�{���j�̑�O�́A�o���2�������A�����2�����₻���A�Ƃ������̂ł����B��������ɃV���v���ȃ��b�Z�[�W�ŁA�ǂ�ȑg�D�ł����ꂪ�o����ΐԎ��ɂ͂Ȃ�܂��A�����͈Ղ��A�s���͓�̓T�^�ł��B
�@
�ʏ�͌o���������Δ��������܂��B������u�k���ύt�v�Ƃ����܂��B����A������グ������Όo��������܂��B������グ�Ȃ���o�����������������邱�Ƃ͒N�ł��킩��܂����A���͎̂���̋Ƃł��B
�@
�u�킩��₷�����邽�߂�2���A2���Ƃ����܂������A�g�[�^����4�����P�ł���悢�̂ł��B���オ3���オ���āA�o�1���������Ă�4���̉��P�ł��v���V�c����͌����܂����A�ǂ̂悤�ɂ��Ă���𐬂��������̂��B�܂��́A�o��팸��B
�@
�V�c���Č��������鎞�_�ŁAHTB�͊J��19�N�ڂł��B����A��K�͏C�U������ނ��Ƃ͊ԈႢ����܂���B����ɉ����ĉߋ��̕����p�����A�Œ莑�Y�ł��Ȃ���Č����邱�Ƃ͕s�\�ł��B�����������A�ŋ������z�̕⏕���s������āA�����؋��[���Ŏ��Ƃ��p���܂����B�P�N�̍����ŏC�U���d����A��x�ƌo�c�j���邱�Ƃ͂���܂���B
�@
���Ɏd���������������܂��B����܂Ŏd���͒n����ƗD��ł����BHTB�͖����Ԏ��ł������A�d����Ђ͍����ł����B�Č��̂��߂ɂ͎d����ɂ����������A�n���D��ł͂Ȃ��R�X�g�D��Ŏd������[���x�[�X�Ō������܂��B�d�������͍팸�ł��܂����B
�@
���{�ő勉�̕~�n�ʐς́A���ꂾ���ێ��Ǘ�����傫�Ȃ��̂ƂȂ�܂��B���N�̕s�U�Ńe�i���g���ꕔ�A���܂炸�A��������Ԃł����B�����ŁA�S�~�n�ʐς̎O���̈���t���[�]�[���Ƃ��ĒP�Ȃ�����Ƃ��A�L���X�y�[�X���O���̓�ɍi��A�e�i���g�������ɏW��B�ێ��Ǘ����啝�ɍ팸���A��������Ԃ͉�������A���킢�����o�܂����B����u�I���ƏW���v�ł��B�L�߂�Δ��܂�܂��B�u�����Z���v�̓����`�F�X�^�[��҂̐헪���̂��̂ł��B
�@
�������ăR�X�g�̑啝���k�ɐ������܂����B�������A���ł�����ł����炵���킯�ł͂���܂���B���S�Ɣ��ς̊ϓ_����C�U��͌��点�܂���B�W�q�Ɣ��㑝�̂��߂ɐ�`���C�x���g��͌��炵�܂���ł����B�R�X�g�z�����I���ƏW���ł��B
�@
�R�X�g�팸�̎��͌������ł��B�}�l�W�����g�̒P�ʂ�E�\������G���A���ɕύX���܂��BHTB�ɂ͗V�Y�A���H�A���̂̋@�\������A�E�\�ʂɃ}�l�W�����g�����Ă��܂����B������G���A�ŋ敪���ĐE�\�����}�l�W�����g�ɕύX�����̂ł��B�Ⴆ�A���H�X������Ől������Ȃ��Ȃ�����A�߂��̏����X���牞�����o�����Ƃ��ł��܂��B�~�n���L�������ɁA���G�̎��ԑт���v���₷���E�\�ŋ敪���Ă��Ă͂ł��Ȃ��������Ƃł��B�܂��A�e�G���A�͂悢�Ӗ��ŋ�������悤�ɂȂ�A�S�̂Ƃ��Ċ��������܂����B
�@
�O��A�|�����u�g�D�s�������v��������������|�A�����܂����B�|���̓G���A���}�l�W�����g�������t����̂ł��B�܂��A�y���L���͂���Ă�����A���������œh��ȂǁA�����ł�����͓̂������A�O����̍팸���s���܂��B
�@
�X�s�[�h���d�����܂��B�u���܂ł����d���̃X�s�[�h��2���������悤�Ƒi���܂����B��������Όo���2���팸�����̂Ɠ������ʂ�����܂��B�����g���d���A�V�X�g���]�ԂŃp�[�N�����삯��邱�Ƃŗ��搂�͂��Ă��܂�(�V�c����)�B�v
�@
�u�ӎv����͑��f��������{�B�������f������A���ʂ������o��B���Ƃ����s���Ă��A�����C�����ł��܂��B���j���݂�ƁA�킢�������ł��傤�B�����ق��������Ă����B�킢�̓X�s�[�h�B�o�c���X�s�[�h�Ȃ̂ł�(�V�c����)�v
�@
�X�s�[�h�����ʉ��헪�ł��B�@ |
�� �I���ƏW���ƃX�s�[�h
�@
�n�E�X�e���{�X(�ȉ��AHTB�Ƃ���)�Č��̂��߂��V�c�G�Y����(�g�h�r�)��������3�̊�{���j�̑�O�́A�o���2�������A�����2�����₻���A�Ƃ������̂ł����B�O��͌o��팸���������܂����B����͔���g����������܂��B
�@
�e�[�}�p�[�N�̔���́u�q���~�q�P���v�Ō��܂�܂��B�܂��A�q�����グ�邽�߂��V�c����͓��ꗿ�������錈�f�����܂��B3,200�~��2,500�~��2���������܂��B���ꗿ��������q���͑����邩������Ȃ����A�q�P��������̂ŁA����܂ł̌o�c�҂͂Ȃ��Ȃ����ݐ�Ȃ��ł��܂����B�V�c����͓��ꗿ�������邱�ƂƁA�L���[�R���e���c(�W�q�͂̂��閣�͓I�ȃ\�t�g)�̓�{���ŁA�܂��͋q���𑝂₵�A���ɑ؍ݎ��Ԃ����邱�Ƃŋq�P�����グ�����u���܂��B
�@
�E�����s�[�X�E�E�E���A�q���Ɉ�Ԑl�C�̃A�j���̊C���D����݂��A�t�@�~���[�w�ɑi���B
�@
�E�`�j�a48�E�E�E���A���(���ɒj��)�Ɉ�Ԑl�C�̃A�C�h���̃R���T�[�g�J��
�@
�E�Ԃƒ뉀�E�E�E�E�]������̃`���[���b�v(���t)�ɉ����āA�S���{�̃o��(����)�A�K�[�f�j���O���E���(�H)�Ń~�h������V�j�A�w�ɑi���B
�@
�E��i�E�E�E�E�E�E�]������~�̖�̓C���~�l�[�V���������������A�K�͂��g�債���E��̃C���~�l�[�V�����ɁB(�d��820����)
�@
�ȏ�̂悤�ȁA�����ɂ����Ȃ��I�����[�����E�R���e���c��A��������Ԃ̃i���o�[�����E�R���e���c�����X�ɓ����B��Ғj���A�V�j�A�w�Ƃ������]���A�ォ�����q�w����荞�݂܂����B�܂��A�g�h�r�̗͂������āA�������͂��߂Ƃ���C�O����̗���҂������܂����B��i�𖼕������邱�ƂŎォ������Ԃ��������A��q������̑؍ݎ��Ԃ������܂����B���ʂƂ��āA�q�����q�P�����������̂ł��B
�@
�������āA10�N9�����AHTB�͊J�ƈȗ��A19���ڂɂ��č������Z�����܂��B�����������ɐ��ڂ��Ă��܂������A11�N3��11���A�����{��k�Ђ��N����܂��B��B��HTB�͑S����Ђ��܂���ł������A�[���ȉe�����o�܂����B��k�Ђɔ����������̂̉e���ŁA�����Ă����C�O����̃c�A�[�q����ŁB���Ԃ̎��l���[�h�Œc�̋q����ŁB�����{����̌l�q�������B��T�Ԃňꖜ���̃z�e�����L�����Z������܂��B
�@
���̂܂܂ł�11�N9�����͐Ԏ��ɋt�߂�ł��B�V�c����͐헪�]�����܂��B�S�Ă̏W�q�������k�Ђ̉e���̏��Ȃ������{�̌l�q�ɏW���B����ł��q�����͓���̂ŁA�q�P�����グ��d�|�������X�Ɠ����B���ʁA11�N9�����͑O����ŋq����7������180���l�Ɣ����ɂƂǂ܂�܂������A����͎O�����ŁA����A���������Z���ʂ����܂��B�X�s�[�h�o�c�A�W���헪�Ŋ�@��˔j�ł��܂����B
�@
�헪�Ƃ͉����Ɨ\���Ɋ�Â����̂ł��B���̑O���ꂽ��A�����ɐ헪�𗧂Ē����K�v������܂��B�@ |
�� �u�Ɩ�
�@
�����܂�4��ɓn��A�n�E�X�e���{�X(�ȉ��AHTB�Ƃ���)�̍Č��̂��߂��V�c�G�Y����(�g�h�r�)���s�����O�̊�{���j(1)�|�������悤�A(2)���邭���C�Ɏd�������悤�A(3)�o���2�������A�����2�����₻���A��������܂����B
�@
���́A���̎O���j�������O�ɁA�В��A�C�̑�ꐺ�Ƃ��ď]�ƈ��Ɏ��������Ƃ�����܂��B����́u�u�v�Ɓu���v�ł��B���O�������ɂ̍��ʉ��ƕM�҂͏����Ă��܂����A�V�c����͏]�ƈ��Ɏ��̂悤�Ɍ�肩�����Ƃ����܂��B
�@
�F����́A���̂��߂�HTB�œ����Ă����̂ł��傤���H
�@
���N�A�Ԏ��ŋ����������Ȃ��Ă��A�����Ŋ撣���Ă���ꂽ�̂͂Ȃ��ł����H
�@
���q�l�Ɋ�т����������Ƃ�������������邱�Ƃ�����́u�u�v�Ƃ��Ă��邩��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@
�F����ɂ́AHTB�������������Ƃ����u���v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@
���ɂ���������܂��B����HTB���u���m��̂��ꂢ�Ȋό��r�W�l�X�s�s�v�ɂ������Ƃ��������`��������A�Č������������܂����B
�@
�F����ɂ��A��������ł��傤�B
�@
���͍Č��̑����ɗ����܂��B
�@
�F����Ɓu�u�v�Ɓu���v�����L���āA���ɍČ����ʂ����܂��傤�B
�@
HTB�ɂ̓~�b�L�[�}�E�X�͂��܂���B�������������ł��B�e�[�}�p�[�N�Ƃ����y�U�Ő키����́A�f�B�Y�j�[�����h�ɂ͂��Ȃ��܂���B�������AHTB�ɂ̓f�B�Y�j�[�����h�ɂ͂Ȃ����̂�����܂��B�����͉�������Ǐ�C�͋߂��ł��B���ƃh���C����ς��A�s���ς���i���o�[�����ɂȂ邱�Ƃ͉\�ł��B���̂��Ƃ��V�c����́u���v�ƌ��܂����B��̓I�ɂ�
�@
�E����ό�
�@
�E��Êό�
�@
�E�r�W�l�X���p
�@
�E�A�E�g���b�g���[��
�@
�E��C�E����q�H�̒���A�q
�@
�ȂǁA�P�Ȃ�e�[�}�p�[�N�ł͂Ȃ��Ȃ邱�ƂŁA�V���Ȏ��v��n�o���A�����̎�����ς���i���o�[�����ɂȂ��Ƃ������Ƃł��B
�@
�u�n���C�ɍs�������Ǝv��Ȃ���A�n���C�ɂ͍s���܂���B��肽�����Ƃ��C���[�W���A�v�}������A���A�������ׂ����A���̂��Ƃ������Ă���(�V�c����)�B�v
�@
HTB�ɂ̓����[�S�[�����h(��]�ؔn)������܂��B�{�ݎ��̂͂ǂ��̗V���n�ɂ�������̂ƕς��܂���B�����AHTB�̉�]�ؔn�̉^�s�Ǘ������邨�Z����́A���Ԃ���̂����āA�ؔn������Ă���ԁA�����ƁA�ؔn�ɂ܂�����q�������Ɏ��U������A�Ђ傤����ȃ_���X�����܂��B������ł��B�q�������̏Ί�̂��߂ɁA������A�x���Ă���̂ł��B
�@
�����A�N�ɖ�����ꂽ���̂ł��Ȃ��Ƃ����B�V�c����́u�u�v�Ɓu���v�����L���A��{���j�̈�u���邭�A���C�Ɂv���A�����̗���Ŏ��g�����Ƃ����Ƃ��ɁA�ނ͗x�肾�����̂ł��BHTB�Č��̏ے����ƕM�҂͊����܂����B����Ō܉�ɓn���ĘA�ڂ����n�E�X�e���{�X�̍Č����I���܂��B�@ |
 |
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@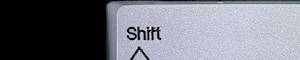 �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@

 �@
�@ �@
�@