�@

 �@
�@���P���@
�G�b�Z�C��ǂށ@
�L�[���[�h�𗅗ėv��@
�����߂͎R�{�ĕF
 �@
�@�������@
�d�v�ȏ��ɃL�[���[�h����בւ���
 �@
�@���T�v�@
��ʃL�[���[�h�S�ŋN���]���@
���͂ɂ���
 �@
�@�����͎��n�߁@
���͂�����@
���Ă��L�[���[�h���f�R���[�V�����ɍė��p�@
���͂�c��܂��@
���͂炵���Ȃ�܂�
 �@
�@���L�[���[�h�̐����M���̑f�{�ł��@
�����̐��E�@
�펯�̐��E�@
�V���E�@
�ʐ��E�@
����ɍ��킹���L�[���[�h���ӂꂽ��ō��_
 �@
�@�������̕��́@
�菇�͓����@
�������������L�[���[�h�ŗ���@
�ȉ������@
�����̐��E���n��܂�
 �@
�@�����ɂ��邱�ƂȂNJȒP�Ȃ��Ƃł�
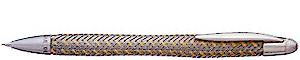 �@
�@����G�� 1968 / 2 �u���ō쐻�H���̍������v (p2-7)�@
�|�����̒m�炸�@�_�l�����Ă����ď����Ă��܂��܂����@
 �@
�@ �@
�@




 �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@