
�R�[�q�[ / �R�[�q�[�̗��j�E���{�̃R�[�q�[�j�E�R�[�q�[���̎���E���̖����E�R�[�q�[�N�w�����E�E�E
�g�� / �g�����猩��C�M���X�ƃA�����J�E�E�E
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@���m�َq
�m�َq�̎�ނ́A�`���I�Ƀp�e�B�X���[(���Fpâtisserie)�A�R���t�B�Y���[(���Fconfiserie)�A�O���X���[(���Fglacerie)�Ƃ������������ŕ��ނ����B�p�e�B�X���[�͗��蕲�َq�̈ӂŁA�������A���A�����A�����Ȃǂ��匴���Ƃ��Ċe��̐��@�Ő��n�����A�N���[����W�����Ȃǂ�Y�����Ďd�グ����̂ł���B��̓I�ɂ̓P�[�L�A�p�C�A�^���g�A�v�f�B���O�A�N���[�v�A�V���[�N���[���A�r�X�P�b�g�Ƃ��������̂��܂܂��B�܂����������g�����̂ł͂Ȃ����A�A�[�����h��w�[�[���i�b�c���琶�n�����}�J�����A�������n�̃������Q�A�f�U�[�g�َq�Ƃ������郀�[�X�A�[���[�A�o�o���A�A�J�X�^�[�h�v�f�B���O�Ȃǂ̗�ق��p�e�B�X���[�Ƃ��Ĉ����Ă���B
�R���t�B�Y���[�͍����َq�̈ӂŁA�������匴���Ƃ���َq��A�����̓��������č����َq�ނł���B��̓I�ɂ̓h���b�v�A�k�K�[�A�L���������A�}�V���}���Ȃǂ̃L�����f�B�ނ�A�`���[�C���K���ށA�`���R���[�g�ށA���|�������i�b�c��t���[�c�A�}�����O���b�Z�Ȃǂ̍����Ђ��ʎ��Ȃǂ��܂܂�A����ł͍H�ꐶ�Y�������̂��قƂ�ǂł���B�Ȃ��`���R���[�g�̓V���R���g���\(���Fchocolaterie)�Ƃ��ēƗ������ꕔ��Ƃ��邱�Ƃ�����B�O���X���[�͕X�ق̈ӂŁA�A�C�X�N���[���A�V���[�x�b�g�Ȃǂ̓��点�ĐH�ׂ�َq�ł���B
�u�p�e�B�X���[�v�u�R���t�B�Y���[�v�Ƃ��������t�́A���ꂼ�ꂱ���َ̉q�������َq�X���w���p��ł�����B���[���b�p�ł�18���I�ɃR���t�B�Y���[���p�e�B�X���[���番�����A�Ɨ������Ǝ�ƂȂ����B�����̂ق��ɗm�َq�ɑ�������̂Ƃ��āA��ɃA�����J���O���Ŕ��B�����X�i�b�N�َq(�p�Fsnack)������B���ނ������Ƃ��ĉ��h�����t��������y�H�ւ��َ̉q�ŁA�|�e�g�`�b�v�X�A�|�b�v�R�[���Ȃǂ̂��̂ł���B
���{�ł͘a�َq�Ɠ��l�A�ۑ����̊ϓ_����َq�̐����ܗL�ʂɂ��������Đ��َq�A�����َq�A���َq�Ƃ����`�ɕ��ނ���邱�Ƃ������B���َq�͉��M���Ă��Ȃ��َq�̂��Ƃł͂Ȃ��A�����̑����َq�̂��ƂŁA�����ނ�30%�ȏ�̐��������َq���Y������B�V���[�g�P�[�L��p�E���h�P�[�L�A�V���[�N���[���A�[���[�A�o�o���A�ȂǁA�p�e�B�X���[�̑����͐��َq�ł���A�u�p�e�B�X���[�v��m���َq�S�ʂ̈Ӗ��ŗp���邱�Ƃ�����B���َq�͂����ނː�����10%�ȉ��̂��̂ŁA�`���R���[�g�A�L�����f�B�A�`���[�C���K���Ȃǂ̃R���t�B�Y���[�̂ق��A�r�X�P�b�g��[�t�p�C�Ȃǂ̏Ă��َq���܂܂��B�����َq�͂��̒��ԂŁA�m�َq�ł͈ꕔ�̃X�|���W�P�[�L�⍻���Ђ��Ȃǂ��Y������B
���p�e�B�X���[
�X�|���W�P�[�L�@/�@�p�E���h�P�[�L(�J�g���J�[���Ƃ�)�@/�@���[���P�[�L�@/�@�^���g�@/�@�V���[�N���[���@/�@�G�N���A�@/�@�A�b�v���p�C�@/�@�J�X�^�[�h�v�f�B���O(�v����)�@/�@�}�J�����@/�@�[���[�@/�@���[�X�@/�@�o�o���A�@/�@�X�t���@/�@�p���i�R�b�^�@/�@�o�E���N�[�w���@/�@�r�X�P�b�g�E�N�b�L�[�@/�@�E�G�n�[�X�@/�@�v���b�c�F��
���R���t�B�Y���[
�L�����f�B�@/�@�h���b�v�@/�@�k�K�[�@/�@�^�t�B�[�@/�@�L���������@/�@�}�V���}���@/�@�O�~�@/�@�[���[�r�[���Y�@/�@�}�W�p���@/�@�h���W�F�@/�@�`���[�C���K���@/�@�`���R���[�g
���O���X���[
�A�C�X�N���[���@/�@�V���[�x�b�g�@/�@�A�C�X�L�����f�[
���X�i�b�N�َq
�|�e�g�`�b�v�X�@/�@�|�b�v�R�[���@/�@�X�i�b�N�o�[�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@�����[���b�p�َq�j
4���I�㔼�̃��[�}�鍑�̐��ނ��͂��߁A���[���b�p�͊���̉������u�����Ă͑�������ƂȂ����B�ȍ~�A���l�T���X�܂ʼnَq���ɂ����ă��[�}�̂悤�Ȗ��i�I�ȑn���͂��܂茩���Ȃ��B�܂��A���̎���͓s�s�\����Ɖ������̖ʂł���������A��ʂ̉ƁX�ɃI�[�u��������鎖�͋����ꂸ�A�_�炩�ȃp����َq���n���Ă���傫�ȃI�[�u���́A�e�n�̏C���@�⋳��A�����̗̎�Ȃǂ݂̂��������Ă����B�I�[�u���̎g�p���Ƃ��ė���I���A�`�[�Y�Ȃǂ�[�߂鎖�����߂��A���̎��͕������x�ɂ����镾�Q�ł��锽�ʁA�[�߂�ꂽ�ޗ���p���Ẳَq�����̐�Ɖ����i�݁A���ʓI�Ƀ��[�}����ɔ|��ꂽ�َq�̐����Z�p���r�ꂸ�p����Ă������ƂȂ����B�܂��A�C���@�⋳��ɂ��L���X�g���̍s����j�Փ��̂��߂َ̉q�̐����́A�t�����X�́u�K���b�g�E�f�E�����v��u�I�X�e�B�v�Ȃǂ̏@���َq���o�āA�N���X�}�X�╜���ՂȂǁA��N���[���b�p�ɂ�����L���X�g���̍s�����ʂ�l�X�ȉَq�̔��W�ւƌq�����Ă������B
���C�X���������ƍ����Ə\���R
7���I�ɃC�X�������������A�����w�i�Ƃ���C�X�����鍑���u������B�������y���V�A�ł̓T�g�E�L�r�y�����Ȃ������@���l�Ă���A�����ۑ����\�ɂȂ��������͋M�d�Ȍ��Օi�Ƃ��ăC�X�����鍑�̊g��ƂƂ��ɓ����ɍL�܂��Ă������B711�N�A�C�X�����鍑�E�}�C�����̎���ɂ́A�k�A�t���J��т����͉��Ɏ��߃C�x���A�����������A�n���C���݂ɑ傫���Ő}���L�����B���킹�ăT�g�E�L�r�͔̍|�Ɛ����Z�p���n���C���ݏ����ɍL���������A���[���b�p�ɍL���������m����悤�ɂȂ�̂́A��̏\���R�̎���ł������B
�C�X�����������ȍ~�L���X�g�����E�Ƃ̑Η��͑����A���[���b�p�ɂ����Ă悤�₭���ƓI���肪�����͂��߂�11���I����13���I�܂ł�200�N�ԁA���n�D�҂��f���Ċ��x���L���X�g�������瓌���ւƏ\���R�̉������s��ꂽ�B�l�̉����͌𗬂R�H�̔��B�͕����������A���ʂƂ��č����⍁�h�����͂��߂Ƃ��铌���̕��Y�����[���b�p�ɍL�܂鎖�ƂȂ����B�����A�C�^���A���s�s��ʂ��n���C�f�Ղł��������Ȃ������́A�M����x�T�w�̊Ԃł�����ɂł��Ȃ��M�d�i�ł���A���̂قƂ�ǂ����{�̂��߂̂���Ζ�p�Ƃ��ď����������̂ŁA�َq�����ɗ��p����̂ł͂Ȃ��A�����͂킸���ɂӂ肩����Ƃ������p�������������Ƃ��l�����Ă���B�܂��A�M�d�i�ł����������̎���͂₪�ċ���̋����ƂȂ�A�C���@�ȂǂŖ���Ƃ��č���Ă������L���[�����̍ޗ��Ƃ��č��h���Ƌ��ɗp�����鎖�ƂȂ�A��N�A�Â����L���[�����Ƃ��ĉَq���Ɋ�������鎖�ƂȂ����B
���������łȂ��A�\���R�̂����炵�������̓��[���b�p�َ̉q���ɗl�X�ȉe����^���鎖�ƂȂ����B�����̈炽�Ȃ�����n�ł��͔|�ł��鍒���A�\�o���\���R�ɂ���ă��[���b�p�ɂ����炳�ꂽ���̂ŁA�t�����X�ł̓T���U���ƌ����Ă���B�����ɂ����ăA���u���������w���T���Z���ɗR�����������ƍl�����Ă���A����ł��N���[�v�ȂǗl�X�ȉَq�ɗ��p����Ă���B�܂��A�t�����X�쐼���ɓ`���u�p�X�e�B�X�v�ƃ����b�R�ɓ`���u�p�X�e�B�����v��A�I�[�X�g���A�́u�V���g�D���[�f���v�ƃg���R�́u�o�N�����@�v�̌`�̗ގ��Ȃǂ���A�L���͈͂ł̌𗬂��������Ƃ��l�����Ă���B
�H�����̈Í����Ƃ������Ă������������A���[�}����Ɋ�{���قڊ������Ă����e��̏Ă��َq�ɂ́A������L���[���Ȃǂɂ��X�Ȃ�H�v�̑f�n���p�ӂ��ꂽ����ł�����B����ɃC���h���Y�̃I�����W������A�������Y�̃A�v���R�b�g�Ȃǂ��C�X�������E���o�R���āA����ɏ\���R�ɂ��^��A�����̍L�܂�ƂƂ��ɍ����Ђ��ɂ��ꂽ�ʎ����A�H��̃f�U�[�g�Ƃ��ėp������悤�ɂȂ�A���قƂ��Ă̊m���ɂȂ��鎖�ƂȂ�B�����āA�u�h�E����ʎ��̃W���[�X����ꂽ�e����������������X�̒��Ŋh�a����Ƃ������A����ɂ��ʂ���X�ق̐����@���`�����A�A���r�A��ň��ނ��Ӗ�����u�V�����o�v���ꌹ�ƌ�����A�t�����X�́u�\���x�v�A�p��́u�V���[�x�b�g�v�Ƃ������X�ق��C�^���A�Ȃǂō���͂��߂��B���㉢���َq�́A�������Ȃǂ̏Ă��َq����̂Ƃ����p�e�B�X���[(Patisserie)�A��������̂ƂȂ������قł���R���t�B�Y���[(Confiserie)�ƕX�قł���O���X(Glace)�Ƃ�������ʂ́A�����̏\���R�̓��������ɂ��}�炸����܂ꂽ�����𗬂ɂ���Đ������Ă������Ƃ��l�����Ă���B
�����l�T���X�Ƒ�q�C����
���[�}�̐��S�ȍ~�A�C�^���A�����͓�������������������Ă������̂́A�n���C�f�Ղ�S�����F�l�c�B�A��t�B�����c�F�Ȃǂ��s�s���ƂƂ��Ĕ��W���Ă����B14���I�ɂ����C�^���A�̓s�s���Ƃ����S�ƂȂ��ċ��������l�T���X�͐H�����ɂ��y�сA�\���R�̂����炵���C�X����������̐H�ނ�p���āA����ɍH�v���d�˂��َq���o�ꂷ�鎖�ƂȂ����B
����A���R���L�X�^�ɂ��1492�N�A�C�x���A�����̓C�X�����x�z��E���A���[���b�p�̑��̉����ɐ�삯�ċ��͂ȉ������l�������X�y�C���ƃ|���g�K���́A������`�ӎ��̍��܂��w�i�ɃC�X���[�����͂̋쒀�Ɨ̓y�g���ɏ��o�����ƂȂ����B�V�q�H�̔����͗̓y�ƌ��Օi�������炵�A�Ђ��Ă͔���ȕx�������炷�B����ɁA15���I�ɂ����ăC�X���������̈�ł������I�X�}�������鍑�Ƃ��đ䓪�A�n���C�f�Ղ��قڏ��������I�X�}���鍑�ɂ��f�Պłւ̕s���������A���[���b�p�̊e�����O�m�ւƑ���o���A��q�C����ƂȂ��Ă������B�吼�m��n��A���C���h�����̓��[���b�p�����̈��T�g�E�L�r���Y�n�ƂȂ�A�M�d�ȗA���i�ł��������������[���b�p�l���琸������ɂ��鎖�ɂȂ����B�����āA�X�y�C���ɂ��`���R���[�g�����[���b�p�ɂ����炳�ꂽ�̂����̎���ł������B
���t�����X���H�̉���
�t�����X�َq�����E�ɒm���銮���x��w�i�ɂ́A���[���b�p�����̋��S�Ɖ����Ԃ̍������������B���������Ă������t�����N�������܂Ƃ߂��J�y�[����1328�N�ɒf�₵����A�t�����X�̓C�M���X�Ƃ̕S�N�푈�ɋꂵ�ގ��ƂȂ�B1453�N�Ƀt�����X�̏����Ő푈�͏I�����A�ȍ~�A����ɍ��͂������x���C�^���A�ɍU�ߓ���A�C�^���A�푈�������N�������B1533�N�Ƀ��f�B�`�Ƃ̃J�g���[�k�E�h�E���f�B�V�X���A���������Ƃ�������`�Ńt�����X�̃A����2���ɉł��Ă���B�����I�ɂ͌�i�ł������t�����X�ɁA�i�C�t�ƃt�H�[�N���������ƌ����A���ۂɓ����̃C�^���A�̐����l�����S�čČ��ł���悤�A�����l��ِl�܂ŋ��ɂ��Ă����B�V���[�x�b�g�A�}�J�����A�t�����o�W�[�k�A�v�e�B�E�t�[���ȂǁA�����t�����X�̓`���َq�Ƃ��v���Ă���قƂ�ǂ́A�C�^���A����`��������̂��Ƃ��l�����Ă���B�����1615�N���C13���ɃX�y�C�����t�F���y3���̖��A���k�E�h�[�g���b�V���A����1660�N���C14���ɃX�y�C�����t�F���y4���̖��}���A�E�e���T���ł��A�`���R���[�g�Ƃ��̒����@���t�����X�ɓn�����B���C15���ɉł����|�[�����h���̖��}���[�E���N�`���X�L�[�͕����Ƃ��ɔ��H�Ƃł��m���Ă���A�o�o�⃔�@���[���@����n�������ƌ����Ă���B1769�N�I�[�X�g���A�̃}���[�E�A���g���l�b�g�����C16���ɉł������ŁA�h�C�c�َq�̐��@����������B���[���b�p��v���َ̉q�̐��@���t�����X�ɏW�܂�A���[���b�p�َ̉q�̏W�听�Ƃ��Ẵt�����X�َq���A���̊����ɂނ��đ傫�����i���鎖�ɂȂ�B
���َq�����̋ߑ㉻�ƎY�Ɗv��
�C�^���A���͂��ߌ��̓��[���b�p�e�n�őn�삳�ꂽ�َq���A�t�����X�َq�Ƃ��Č���ɔF�m����Ă���v���̈�ɁA�َq�̐��@���n�����ĂĂ܂Ƃߐ��m�ɓ`�d�ł���悤�ɂ����_���グ����B1784�N�A�v���O�̃t�����X�ɐ��܂ꂽ�A���g�i���E�J���[���͐��ق����łȂ������̋Z�ʂɂ����Ă��G��ł���A���ق◿���̋Z�@���L���������̒�����c�����B�V�������b�g�A�W�����A�o�o���A�A�u�����E�}���W�F�A�v�f�B���O�A���[�X�A�X�[�t���ȂǁA�܂��Ɍ���Ɏ嗬�ƂȂ��Ă����������̗ǂ��َq�����̎���Ƀf�U�[�g�Ƃ��Ē�Ă��Ă���A������݂̂Ȃ炸��َ̉q�E�l�B�ɂ��傫�ȉe����^���Ă���B
18���I�Ɏn�܂����Y�Ɗv���ɂƂ��Ȃ��A�����Y�Ƃɂ��ϊv���K���B16���I�Ɋ���n�ł��͔|�ł���[��(�T�g�E�_�C�R��)����������������ł��鎖����������Ă������A�T�g�E�L�r���z���čL�܂鎖�͂Ȃ������B�����A1806�N�C�M���X�����߃��[���b�p�̌o�ώx�z��_�����i�|���I���̑嗤�����߂ɂ�荻��������ł��Ȃ��Ȃ���������A�[�͔̍|�ɂ�鍻�����Y�����コ��鎖�ɂȂ�B19���I�����ɐ��Y���O���ɏ�萸���Y�Ƃ̍H�Ɖ����i�B���̎��͗l�X�ȃR���t�B�Y���[�͌����A�r�X�P�b�g��`���R���[�g�Ȃǂ̕��y�ւƌq����A���[�}�̐̂���x�T�w������K���̋�����̂������Â��َq���A���[���b�p���ɖL�x�ɏo���͂��߂邫�������ƂȂ����B
�p�e�B�X���[�����ăR���t�B�Y���[�̕��y�Ɗ������������Y�Ɗv�������A�X�ق�A�C�X�N���[�������Y�Ɗv���̐\���q�ƌ�����َq�ł������B1867�N�h�C�c�Ő��X�킪��������A�A�C�X�N���[�������̋@�B���͈�C�ɐi�B�A�����J�ł͊�ƂŗʎY�����悤�ɂȂ�A��ɃA�����J�̍����H�ƌ�����قǂ̕��y������B�ȍ~�A�O���X(�X��)�́A�f�U�[�g��A���g�����Ƃ��Ẵ��[���b�p���ƁA�ʎY�V�X�e���ɂ��X�i�b�N�Ƃ��ẴA�����J����2�̌X���ɕʂ�Ĕ��W���鎖�ɂȂ����B
���َq�ƌ��N
�C�M���X��16�Έȉ��ɑ���e���r�ԑg�ŃW�����N�t�[�h���R�}�[�V�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B2007�N�A�C�M���X���{�́A�����ۑ����̈������_�i�g���E���ƍ������F���̓������H�i���A�q���ɒ��ӌ��ׁE��������Q(ADHD)�������N�����Ƃ����������ʂ��āA�h�����N�₨�َq�ɂ���炪���������̂������Ƃ��Ē��ӂ𑣂��A2008�N4���A�p���H�i���(FSA)�͒��ӌ��ׁE��������Q�Ɗ֘A�̋^���鍇�����F��6��ނɂ���2009�N���܂łɃ��[�J�[������K������悤���������B�K�[�f�B�A�����ɂ��A���̐��{�����ɂ�鎩��K���̑O�ɁA��胁�[�J�[��2008�N���ɂ������̐H�i�Y��������������B����K���Ώۂ̃^�[���F�f�́A�ԐF40���A�ԐF102���A�J�����C�V���A���F4���A���F5���A�L�m�����C�G���[�ł���B
2008�N3���A������āA���B�H�i���S��(EFSA)�́A�C�M���X�ł̌������ʂ�1��������̐ێ拖�e��(ADI)�̕ύX�ɂ̂��߂̊�ɂ͂ł��Ȃ��ƕ����B�������A4���C�M���X�͍Ăєr�����ׂ����Ɗ������s���A8���ɂ͉��B�͐ێ�ʂ̌��������͂��߂����̍������F�����܂ވ��H�i�Ɂu���ӌ��ב�������Q�ɉe�����邩������Ȃ��v�Ƃ����x���\��������邱�ƂɂȂ�ƕ��ꂽ�B�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@���r�X�P�b�g
�ꌹ�̓��e����̃r�X�E�R�N�g�D�X(biscoctus)�ŁA�r�X(2�x)�E�R�N�g�D�X(�Ă��ꂽ����)�B��ɁA2�x�Ă��ꂽ�p���Ƃ����Ӗ��̃��e����r�X�R�N�g�D�X�E�p�[�j�X biscoctus panis�Ƃ�������B���݁A�t�����X��r�X�L���C(biscuit)�A�|���g�K����r�X�R�C�g(biscoito)�A�I�����_��r�X�N���B�[(biscuit/biskwie)��2�x�Ă��ꂽ�Ƃ������Ӗ��������Ă���B�@
���r�X�P�b�g�͕ۑ��H�@
�l�ނ��p�������n�߂��͍̂�����1���N���́B�o�r���j�A�l�͏������y�����錴�����m���Ă����悤�ł���B�`�O���X�A���[�t���e�X�͈�тɉh�����o�r���j�A��Ղ���́A�����������˂ăp��������������A���̗l�q��`�����lj悪��������Ă���B�@
���[���b�p�ł͌Ñォ��A�q�C�≓���̂��߂̐H�ƂƂ��āA���ۂ���ǂ����邽�߂�2�x�Ă����p�������Q���Ă����B�����̌��t�ł͐H�ƂƂ��Ẵp���ƁA�َq�Ƃ��Ẵr�X�P�b�g�Ƃ͖��Ăɋ�ʂ���Ă��Ȃ��A���p����Ă����B�@
���ꂪ�r�X�P�b�g�̋N���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�M���V�����ւă��[���b�p�ɍL�܂����r�X�P�b�g�B�T���Ƃ̃R�����u�X��}�[�������A�����q�C�ɂ̂�o�����͑�ʂ̃r�X�P�b�g��ςݍ��Ƃ����b���c���Ă���B�@
���Ȃ݂ɂP�U���I�̓��{�ɂ́A���łɓ�؉َq�Ƃ��āu�т������Ɓv���͂����Ă��Ă���B�����̂͂��߂ɂ́A���̒���Ȃ̂��r�X�P�b�g�Ɂu�d�Ė��q�v�Ƃ��������ĂĂ����B

�r�X�P�b�g���{�i�I�ɍ����悤�ɂȂ����̂͂P�U���I�B���[���b�p�̋{��Ő���ɐH�ׂ���悤�ɂȂ�A���낢��Ȗ��₨���������H�v���ꂾ�����B�C�M���X�̃G���U�x�X�����́A�Z�t�I�X�{���ɖ����ċ{��ɏĂ����܂���点�A�r�X�P�b�g���Ă������ƌ����Ă���B�܂��A�t�����X���܁A�}���[�E�A���g���l�b�g���A�{��Ńr�X�P�b�g���������Ă����Ƃ����B�r�X�P�b�g�ɃI�X�{���A�}���[�Ƃ��������c���Ă���̂��A���̂��߂��Ƃ����Ă���B�₪�ĎY�Ɗv�����N����A�����@�B�����x�����đ�ʐ��Y�����ʂɂ����y���Ă����B

�P�T�S�R�N��q���ɕY�������|���g�K���l�́A�S�C�ƂƂ��ɃJ�X�e����r�X�P�b�g�A�{�[���Ƃ��������낢��ȓ�؉َq����{�ɓ`�����B���{�ɏ㗤�����r�X�P�b�g�́A�����ł́A������ƈَ��Ȗ��������̂ŁA���܂�l�C���Ȃ������悤���B�܂��ʔ������ƂɂP�U�`�P�V���I���߂ɂ����A���{���r�X�P�b�g�����\��(�t�B���s��)�ɗA�o���Ă����Ƃ����B

���{�ł̓r�X�P�b�g�ƃN�b�L�[�����̖��O���g���Ă��邪�A�{���A����̂��̂������B������r�I����������������܂܂�Ă��āA���蕗�̊O�ς������̂��N�b�L�[�ƌĂ�ł��悢�Ƃ������܂肪����A��ʂ��Ďg���X��������B�@
�O���ł́A�r�X�P�b�g(�p)�N�b�L�[(��)�r�X�L���C(�t�����X)�r�X�L���C�[�g(��)�ȂǂƌĂ�Ă���B�A�����J�ł́A�r�X�P�b�g�Ƃ����Ƃ��炩���َq�p���̂��Ƃ��ĂсA�C�M���X�̃r�X�P�b�g�ɓ�������̂̓N�b�L�[�ƌĂ�Ă���B�C�M���X�ɂ̓N�b�L�[�Ƃ������t���̂��Ȃ��ȂǁA�r�X�P�b�g�ƃN�b�L�[�̎g�������́A���܂�͂����肵�Ă��Ȃ��悤���B

���{�ł̃r�X�P�b�g�̗��j���݂�ƁA���˔ˎm�̗���E�ēc�����Ƃ����l���łĂ���B����܂ł͒�����ӂŊO���l�����ɂ�������Ă������A���˔˂��g�ۑ��̂����H�Ɓh�Ƃ����_�ɒ��ڂ��A���̐��@�ׂ��悤���B�ēc���������藯�w���ɃI�����_�l����w�r�X�P�b�g�̍������莆�ɂ��A�����Q�N(�P�W�W�T�N)�Q���Q�W�����˔˂Ɉ��Ă��j��������B���̂��Ƃ���L�ɏ����u�������^�v�Ƃ��č��ł��c���Ă���B���ꂪ���{�Ńr�X�P�b�g�����ꂽ���Ƃ����m�ɂ킩��ł��Â��L�^�ł���B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@���R�[�q�[
 �@
�@ �@
�@ �@
�@���R�[�q�[�̗��j

�R�[�q�[�����ɂ́A����������`���̓��A���`���ƌ�������̂�����܂��B
����̓L���X�g�����ł̐��ł���u���M�����J���f�B�̘b(�G�`�I�s�A�N����)�v�ƃC�X���������̐��ł���u�m���V�F�[�N�E�I�}�[���̘b(�A���r�A�N����)�v�ł��B
�����M�����J���f�B�̘b(�G�`�I�s�A�N����)
���̐��́A���o�m���̌���w�҃t�@�E�X�g�E�i�C���j�́u�����m��Ȃ��C���@�v(1671�N)�ɋL����Ă�����̂ŁA6���I���̃G�`�I�s�A����������ł��B
���M�����J���f�B�́A��������������ɂ��Ă������M�B������̕ʂȂ��Ђǂ��������Ă���̂����܂����B
���ׂĂ݂�ƁA�ǂ����u�̒����Ɏ������Ă�����̐Ԃ�����H�ׂ��炵���̂ł��B
�߂��̏C���m�ɂ����������ƁA����ł͎����ɐH�ׂĂ݂悤�Ƃ������ƂɂȂ�A�H�ׂĂ݂�ƋC���݂͂�݂�u���ɂȂ�A�̂Ɋ��͂��݂Ȃ����Ă����̂ł��B
�m�͂��������m�@�Ɏ����A��A�ق��̑m�����ɂ����߂܂����B ���ꂩ��͓O��̏@���s���̂Ƃ��ɐ����ɋꂵ�ޑm�͂��Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł��B
���m���V�F�[�N�E�I�}�[���̘b(�A���r�A�N����)
������́A�k�A�u�_���E�J�f�B�́u�R�[�q�[�R�����v(1587�N)�ɋL����Ă��邨�b�ŁA13���I���̃C�G�����R��������ł��B
�m�̃V�F�[�N�E�I�}�[���́A�����̍߂ŃC�G�����̃��J����I�[�T�o�Ƃ����Ƃ���֒Ǖ�����Ă��܂��܂����B �H�ׂ���̂��Ȃ��R�������܂悢�����Ă���ƁA��H�̒����Ԃ��̎�������ł͗z�C�ɂ��������Ă���̂��������̂ł��B
���߂��ɂ��̎���E��ŎϏo���ƁA���Ƃ������Ȃ��Ɠ��̍��肪���A����ł݂�ƁA��ꂪ�R�̂悤�ɏ��������Č��C�����܂����B
���̌�A��҂ł��������ނ͂��̎����g���Ă�������̕a�l���~���܂����B �����č߂�������čĂу��J�A��A���҂Ƃ��Đl�X�ɂ����߂�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B
���ǂ���̓`�����������́H
�Ǘ��l�̌����ł����A�G�`�I�s�A�͐l�ނ̑c��z���E�T�s�G���X���Z��ł����Ƃ���ł�����܂��B �܂��A�쐶�̃R�[�q�[�̖́A�G�`�I�s�A���͂��߃A�t���J�嗤�̂��������Ō������Ă��܂��B
�ȒP�ł����A��L�̂��Ƃ𗝗R�ɁA�����Ɏc����Ă���`������̂ɐl�X���R�[�q�[�̐Ԃ�����H�ׂĂ��Ă����������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�R�[�q�[���j�́A�G�`�I�s�A�Ŏn�܂����ƌ����Ă悢�Ǝv���܂��B

���̌�A�R�[�q�[��10���I��������l�X�Ɉ��܂�n�߂��̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B����́A�A���r�A�̈�t���[�[�X���c�����L�^�ɁA�o���ƌĂ�銣�������R�[�q�[�̎����ӂ��Đ��ɐZ���Đ����A�o���J���ƌĂ�ň��ɂ��Ă����Ƃ�����Ă��邩��ł��B
���̖�100�N��Ɉ�w�҂œN�w�҂̃A�r�Z���i���A�o���ƃo���J���ɂ��āA��͂�u��p�v���Ə����c���Ă��܂��B
���̂悤�Ȏ�����A�R�[�q�[�����܂�n�߂������́A��Ƃ��Ĉ��܂�Ă����悤�ł��B
���̌�A�����ԃR�[�q�[�̓C�X���������@�̒������ɁA��O�s�o�̔��Ƃ��ē`�����Ă����܂����B��ʂ��s���@���V���̑O�ɖ��C�����Ƃ��Ĉ��܂ꂽ�̂ł��B����Ȓ��A��������Ĉ��ނ悤�ɂȂ����̂�13���I������ƍl�����Ă��܂��B
13���I�����ɂȂ��ď��߂āA�C�X�������̈�ʐM�҂ɂ��̑��݂��m���A���@�̉��̓R�[�q�[�̘I�V�ł��ӂꂩ����A�l�X�́A�V���I�ɂ��F��̑O�ɃR�[�q�[�����ނ悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B
���ꂩ�烁�b�J�A�J�C���A�_�}�X�J�X�ւƓ`����Ă����A 14���I�����ɂ͐��E�ŌẪR�[�q�[�X�u�J�[�l�X�v�������̃R���X�^���`�m�[�v���ɍ���܂����B
���E�I�ȍL�܂���݂��钆�A�l�X�̒��ł̃R�[�q�[�̍����l�C�Ɏ^�ۗ��_���N����A���Ƀ��b�J�̒n�������J�C���E�x�C���u�R�[�q�[�֎~�߁v�z���čŏ��̃R�[�q�[�e�������܂����B�������A�����̃G�W�v�g�����E�T���^������̃R�[�q�[�D���ł���܂����̂ŁA���́u�R�[�q�[�֎~�߁v��m���Č������{��A�������܋֎~�߂�P�āu�R�[�q�[�����ނ̂̓R�[�����̋�����@����̍߈��ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ɛ鍐���܂����B
�Ȍ�R�[�q�[�e���͉��x���J��Ԃ���܂��B���ꂾ���R�[�q�[�ɖ�������l�����������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
��������16���I������ɂ̓g���R�ցA���̌ト�[���b�p�ւƏ㗤���Ă����܂��B

���[���b�p�����ւ̃R�[�q�[�̍L����́A15���I�����̃x�l�`�A����ɁA���[���b�p�S�y�ւƐZ�����Ă����܂��B
���[�}�ł́A�C�X�������k�̈��ݕ����L���X�g���k�����ނ̂͂ǂ����ƁA�^�ۗ��_�������オ��܂��B�����̖@���N�������X8���́u�����̈��ݕ��Ƃ�����̂ɂ���Ȃɂ��������B������ً��k�ɓƐ肳���Ă����̂͂��������Ȃ��v�ƁA�R�[�q�[�ɐ�����{���ăL���X�g���k�̈��ݕ��Ƃ��Ď���܂����B
�C�M���X�ł̓R�[�q�[�n�E�X������������A�a�m�̎Ќ���Ƃ��Đl�C���܂����B�j�����͂����Ő�������蕶�w��_���A�r�W�l�X��W�J���܂����B
�����R�[�q�[�n�E�X�ɓ����̂͒j�������ŁA���ɂ͉ƂɋA�炸�ɓ���Z��j�����������n���B������1670�N��ɂ̓R�[�q�[�n�E�X�̕������߂��w�����̒Q�菑���o����Ă��܂��B
�t�����X�ɂ��g���R�E�R�[�q�[���`���܂��B�R�[�q�[�̓t�����X�㗬�K�������������Ă₪�ăT����������������A�V�������w��N�w��|�p�����܂�܂����B���̔g�͈�ʎs���ɂ��y��ŁA���ӂ��قǂ̊X�p�̃J�t�F�ݏo���Ă����܂��B
����15���I���ɒa�������u�J�t�F�E�v���R�v�v�ɂ̓��\�[��o���U�b�N�Ȃǂ̕����l�����X�ɏW���A�m�I�T�����Ƃ��Ăɂ��킢�܂����B
�₪�ăt�����X�Ńh���b�v�����A�C�^���A�ŃG�X�v���b�\���l�Ă���āA�R�[�q�[�����ރX�^�C�������X�ɕω����Ă����܂��B
���ꂾ�����E�I�ɐl�C�̂������R�[�q�[�ł�����A���͔̍|�ɋ������������l�������������܂����B13���I�ɂ̓��b�J�ւ̏���҂�������ʂ̐����������o���A���ꂪ�e�n�ɐA�����A17���I�ɂ��C���h�l�̃o�o�E�u�[�_�����C�X��������̍ۂɁA���b�J����R�[�q�[�̎��𓐂ݏo���ē�C���h�̃}�C�\�[���ɐA���Ă��܂��B
�܂��A18���I�O���ɂ̓t�����X�C�R�̏��Z�h�E�N�����[�����̈��ݐ��𒍂��ŃR�[�q�[�̕c�����A�t�����X�̃}���`�j�[�N���ɉ^�Ƃ����b���c���Ă��܂��B���ꂪ�₪�Ē���ĂւƍL�����čs���̂ł��B�������ăR�[�q�[�̍L�܂�Ɠ����ɃR�[�q�[�͔̍|�����E�e�n�Ɋg�債�Ă������̂ł��B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@�����{�̃R�[�q�[�j

�͂��߂ē��{�ɃR�[�q�[���`������̂́A�]�ˎ��㏉���̒���o���ŁA�l�X�Ɏ������悤�ɂȂ����̂́A��������ɂȂ��Ă���ł��B
���������ł̓R�[�q�[�n�E�X�����X�ƃI�[�v�����āA�R�[�q�[�����ƌĂׂ镶�w��|�p���J�Ԃ��Ă�������A���{�͍]�ˎ���ŁA��������������̐^�������ɂ���܂����B
�����Ő�[���������ݕ��̃R�[�q�[�́A����o���̃I�����_���ِݗ�(1641�N�E���i18�N)�ȍ~�I�����_���~�Ɏ������܂ꂽ���낤�Ɛ�������܂��B
�������O���l�ɐڐG�ł����̂́A��l�A���l�A�ʖ�A�V���Ȃǂ̌���ꂽ���{�l�̂݁A1776�N(���i5�N)�ɋL���ꂽ�u�c���x���O���{�I�s�v(�R�c�����E�Y�������X��)�ɂ́A�u��A�O�̒ʖ�݂̂��悤�₭�R�[�q�[�̖���m��݂̂ł���v�Ƃ���܂��B
���������o���ɓ����Ă������m�����̏ے��u�R�[�q�[�v���A�]�ˎ���̓��{�ł͕��y���܂���ł����B
�{�i�I�ȕ��y�́A�����������߂��Ă���ɂȂ�܂��B

�`�������̓R�[�q�[�ɑ��ċ��۔��������������{�l�ł������A�J�����Ė�������ɓ���ƁA���m�����̏ے��ł���R�[�q�[��ϋɓI�Ɏ���悤�Ƃ���p���������Ă��܂��B����͐��m������������A���m�l�ƐϋɓI�ɕt���������Ƃ������{�l�̕����J���ւ̓���ł�����܂����B
�����Ē���A�_�ˁA���l�A���قȂǂɎ��X�ɊO���l�����n������āA�����ŊO���l����ڑ҂�����A���ď����ւ̎g�߂⎋�@�◯�w�Ȃǂŗm���̐H�����o��������A���l�ȂǂɊO���l����̃z�e�������ꂽ��ƁA���{�l���m�H��R�[�q�[�����ɂ���@��͂ǂ�ǂ��Ă����܂����B
����ł��ŏ��́A�ق�̈ꈬ��̏㗬�K���̐l�X�̌��ɂ���A�n�C�J���ȍ��������̈���o�邱�Ƃ͂���܂���ł����B
���{�ōŏ��̖{�i�I�R�[�q�[�X�́A���{�l�̓A�i�c���������̐����咬�ɊJ�����u�ے��فv�Ƃ����X�ł����B
1888�N(����21�N)�̏t�̂��ƁA�A�����J�ɗ��w���A�A����Ɋ����⋳��҂��o�Ă��̓X���J�����A�i�c�́A���w�҂�|�p�ƒB���W���t�����X�̕��w�J�t�F���C���[�W���Ă��܂����B���������������ŁA�c�O�Ȃ��琔�N�̌�ɂ͕X����������܂���ł����B
�R�[�q�[�̗A���ʂ����Ă�����10�N�ɂ͂��߂�18�g�����A������A����21�N�����60�g�����x�ɑ����A����40�N��ɂȂ���80�g�����x�ɂ͂Ȃ�܂������A�܂��܂������Ƃ͂������A�ƂĂ���ʂ̐l�X�ɕ��y����ʂł͂���܂���ł����B
�i���X���������J�X���A�n�C�J���D���̐l�X�╶���l�A�|�p���������ɏW���A�R�[�q�[�����ƌĂׂ���̂����{�ɍ��t���n�߂��̂́A�����ɏI���ɋ߂��Ȃ������ł����B

���{�ł̃R�[�q�[�����̐�삯�́A�u�p���̉�v(�R�[�q�[���D�Ƃ̉�)�ł��B�X���O���w������1909�N(����42�N)�ɑn�����ꂽ���|�G���w�X�o���x�̃����o�[�ł���k�����H�A�ΐ��A���������Y�A�����t�v�A�i��ו��Ȃǂ����{�����Ԓ��́u���C�]�����̑��v�𗘗p���Ė�����������Ă����̂ł��B
���̓X�͖{�i�I�ȃt�����X�����Ɨm�������܂��A�R�[�q�[���{�i�I�ȃt�����X���̐[����R�[�q�[���o���Ă��܂����B���C�]�����̑��͂��Ȃ��當�m�̎Ќ��ꂾ�����̂ł��B �������ォ��吳����ɂ����āA���̂悤�ȕ����T�����̖������ʂ����J�t�F���������ł��āA���{�ɂ�����ƃJ�t�F�����̕��������Ă��܂����B �������A��������܂��܂���ʂ̐l�ɂ͕~���̍����X����ł����B
����ȂƂ���ɏo�����A�w�J�t�F �p�E���X�^�x�́A�ŏ��������m�╶�w�N�����̎Ќ���ł������A��ʂ̐l�B���C�y�ɗ�������l�i�ƕ��͋C�ŁA�����Ƃ����Ԃɑ�ɐ����āA�吳����̍Ő����ɂ͑S����20�]��̎x�X�𐔂���قǂɂȂ�܂����B�ł́A�Ȃ�����قǃp�E���X�^�͈�ʂ̐l�X�ɐl�C���Ă̂ł��傤���B
����́A�������m�����X�v�����^���̃R�[�q�[������15�K���������ɁA�p����j���[���[�N�̃J�t�F��͂��Ȃ���A�������R�[�q�[�̕��y�ƃT�[�r�X�ɓO�����p�E���X�^�ł́A5�K�ň��ނ��Ƃ��o�����̂ł��B
�O���̈�̒l�i�Ŗ{�i�I�ȍ��荂���u���W���R�[�q�[�𖡂키���Ƃ��o�����̂ŁA�S���ɎU������p�E���X�^�̓X�Ŏn�߂ăR�[�q�[�̖���m�������{�l�̐��͐�����܂���B�p�E���X�^�̓R�[�q�[�̑�O���ɔ��Ԃ��������X�Ƃ��đ傫�ȑ��Ղ��c���܂����B
�����đ吳����ɂ͊m���ɃR�[�q�[���D�Ƃ������A���a�ɓ����Ă܂��܂����v��L���܂����A����E���ŃR�[�q�[�́w�G�������x�Ƃ��ėA����~�ɂȂ�܂��B���{�l�̐�������ꎞ���R�[�q�[�͎p�������Ă��܂��܂��B
���̌�A���ł͏��a25�N����A�����n�܂�A����́u���a�̎g�ҁv�Ƃ���ɁA�l�X�����������܂����B
���݂̓��{�ł͗l�X�Ȍ`�ŃR�[�q�[�����܂�Ă��܂��B�i���X�Ɖƒ�A���M�����[�R�[�q�[�ƃC���X�^���g�R�[�q�[�A�z�[���R�[�q�[�ƃI�t�B�X�R�[�q�[�T�[�r�X�A�e��̊ʃR�[�q�[�A�����ăO�����R�[�q�[�A�t���[�o�[�R�[�q�[�Ƃ�����ł��B
�ߔN�ł̓O�����w���̐l�������Ă�������A��肨�������{�i�I�Ȃ��̂����߂�R�[�q�[�}�j�A�������Ă��Ă��܂��B
 �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@���R�[�q�[���̎��
���Y���F�G�`�I�s�A�B���A����Ƃ��D��A�R�[�q�[�̑S���Y�ʂ̖�880-90%���߂܂��B�C��800-2000���̍��n��18-25(����21�x�O��)�x�̋C�����œK�ŁA���J�ł����J�ł��Ȃ��C��A���͂��̗ǂ��X�Βn�ł͔̍|�ɓK���Ă��܂��B���i���Ŕ�r�I�����ʂŁA���E�̃R�[�q�[���Y�ɂ����Ď嗬�ƂȂ��Ă��܂����A���������̊��ɂ͓K�������A���Q�Ɏキ�A�����ɂ��ア�̂���_�B���M�����[�R�[�q�[�ɍł������g�p����Ă���i��ł��B
�����u�X�^��
�C��200-800m�̒�n�E�X�Βn�͔̍|�ɓK�����܂��B�A���r�J��Ɣ�r����ƁA�a�C�ɋ����i��Ƃ��ĕ]������Ă��܂����A���A���苤�ɃA���r�J��������Ƃ����]���ł��B�����x�����ɂ���ă��u�X�^��Ȃ�ł͂̔��������𖡂키�����o���܂��B��ʓI�ɂ̓C���X�^���g�R�[�q�[�A�ʃR�[�q�[���ɑ����g�p����Ă��܂��B
�����x���J��
���u�X�^�������n�ŕ��n�ł͔̍|�ɓK���Ă��܂��B���牠���Ŋ��K�������\�����荪���[���ƌ�����������J�̏��Ȃ��ɂ������A�Q���a�ɂ������̂ł����A������ƂɎ�Ԃ���������n�������N����K�v�Ƃ��Ă��邽�߁A���܂�l�C�̖����i��ł��B���E�̃R�[�q�[�S���Y�ʂ̖�1�����x�̐��Y�ʂƂȂ��Ă��܂��B���A���苤�ɃA���r�J�������Ă���Ƃ̕]���ł��B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@���R�[�q�[���̖���
�L���}���W�����͎_���E�Â݁E�R�N�ɗD�ꂽ�R�[�q�[���ł��B���n�ō͔|���ꂽ���̓��́A���̃o�����X�̗ǂ��_���Ƌꖡ�A�G���̖����㖡�A�L���ɍL����F���͑��̒ǐ��������Ȃ��قǗD��Ă��܂��B���̂悤�ɃL���}���W�����͐̂��琢�E���̐l�X�Ɉ�����Ă�������ł��B�����x�����́u�V�e�B���[�X�g�v��u�t���V�e�B���[�X�g�v���K���Ă���B
���O�A�e�}���@(���Y�n�F�O�A�e�}��)
�O�A�e�}���R�[�q�[�́A���̑������R�̌X�Βn�ō͔|����Ă���A�L���ȍ~�J�ʂƔ엀�ȉΎR�D�y��A�����Đ��͂��̂悳�A�����n�т̓K�x�ȋC���ȂǁA�R�[�q�[�͔̍|�ɔ��ɓK����������������Ă��܂��B�ꖡ�̃o�����X���ǂ��A�_�����������߂̃R�[�q�[�ł��B�X�g���[�g�ŖF���ȍ�������y���݂��������B�����x�����́u�n�C���[�X�g�v��u�V�e�B���[�X�g�v���K���Ă��܂��B
���u���W���@(���Y�n�F�u���W��)
���E�̃R�[�q�[���Y�ʂ�3����1�߂����������鐢�E��1�ʂ̃R�[�q�[�Y�o���B���݂ł́A�T���p�E���B�A�~�i�X�W�F���C�X�B�A�p���i�B�A�G�X�s���b�g�E�T���g�B�ȂǁA�C���̓K�����W���̍����n��ō͔|����Ă��܂��B�قǂ悢�_���Ƌꖡ������A���肪�����B�u�����h�̃x�[�X�Ƃ��Č������Ȃ��R�[�q�[�B�����x�����́u�n�C���[�X�g�v��u�V�e�B���[�X�g�v���K���Ă��܂��B
���G�������h�}�E���e���@(���Y�n�F�R�����r�A)
�G�������h�}�E���e���͔̍|�n�̓A���f�X�R�n1700m�ȏ�̍��n���I��A���n����������E���n�A�J�t�F�e�������_���▢�n����������̎�œO��I�Ɏ�菜���܂��B��ނȂ��[�����킢�ƍ���𑗂�o�����߁A���H�͌��i�ɊǗ�����A�R�����r�A�����R�[�q�[���Y�ҘA����̊Ӓ�m�ɂ��i�������ɍ��i�������̂��������߂ăG�������h�}�E���e���Ƃ��ĔF�肳��A�ቷ�R���e�i�D�ŏo�ׂ���܂��B�R�����r�A���L�̊Â�����Ɛ[���R�N�B�����Ċm���ȊÖ������˔������ō����E�H�b�V���h�A���r�J�R�[�q�[�ł��B�����x�����́u�n�C���[�X�g�v��u�V�e�B���[�X�g�v���K���Ă��܂��B
���R�i�@(���Y�n�F�n���C��)
�n���C�����̒��Łu�r�b�O�A�C�����h�v�̈��̂ŌĂ��n���C���̐����ɃR�i�n�悪����܂��B���̃R�i�n��ō͔|�����R�[�q�[���R�i�R�[�q�ŁA100�N�ȏ�̗��j�������Ă��܂��B�����̔_��Ɣ�r����ƁA�K�͂����������ׂĎ��Ƃōs���Ă���ׁA���Y�ʂ��S���E�̃R�[�q�[���Y�ʂ�1�����x���M�d�ȓ��ƂȂ��Ă��܂��B�F���ȍ���ƖL���ȃ{�f�B�A���ӂ�o���Ɠ��̎_�������I�Ȗ����ł��B�����x�����́u�V�e�B���[�X�g�v��u�t���V�e�B���[�X�g�v���K���Ă��܂��B
���u���[�}�E���e���@(���Y�n�F�W���}�C�J)
���Q�G��J���v�\�̒��ׂƂƂ��ɁA�u���[�}�E���e���́A�J���u�C�ɕ����Ԕ��������W���}�C�J�̑㖼���̂ЂƂƂł��B���Ă͉p��������p�B�Ƃ��ėp�����A���{�ł̐l�C�̍����ɐ����͂���Ȃ��ł��傤�B�������Z�ȓ썑�̊y������A�ق�̏��ʂ������Y�����A�ǎ��̍���ƒ��a�̂Ƃꂽ���킢�������A�^�ɐ��E�̍ō����i�̖���^������ɂӂ��킵���̂��w�u���[�}�E���e���x�ł��B�܂��A�u���[�}�E���e���͗A������铤�̂قƂ�ǂ����̑܂ɓ����ėA������Ă���̂ɑ��A�B��ؐ��̒M�ɓ����āA�ؖ������ŗA�������قǂ̍ō����i�ł��B�C�i���ӂ�鍁��A�R�N�A�����Ƃ�Ƃ����Â݂ƁA���ɃR�[�q�[�̉��l�ɂӂ��킵�����킢�ł��B�����x�����́u�~�f�B�A�����[�X�g�v��u�n�C���[�X�g�v���K���Ă��܂��B
�����J�@(���Y�n�F�C�G����)
�u���J�v�Ƃ́A���[���b�p�����ɃR�[�q�[����A�o���邽�߂̍`�Ƃ��ĉh�����C�G�����̒��̖��O�����ƂƂȂ�A��������o�ׂ����C�G�����ƃG�`�I�s�A�Y�̃R�[�q�[�����u���J�v�ƌĂ�Ă��܂��B���J�ł́A���J���L�̉ʎ��̗l�ȍ��肪����A���ɓ��{�ł͍����x���Ă���l�C�̍��������ł��B�����x�����́u�n�C���[�X�g�v��u�V�e�B���[�X�g�v���K���Ă��܂��B
���}���f�����@(���Y�n�F�C���h�l�V�A)
�G�L�]�`�b�N�ȃe�C�X�g�̒��ɂ��餌��݂̂���{�f�B�[���l�C�̃C���h�l�V�A�Y�R�[�q�[�ł��B�R�[�q�[���S�҂̕�����A�R�[�q�[���������̒������ŁA���L���l�C�̂�������ł���}���f�����B�ق�ꂳ�ƁA�܂����肵���R�N�������I�ł������x�����́u�V�e�B���[�X�g�v��u�t���V�e�B���[�X�g�v���K���Ă��܂��B�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@���R�[�q�[�N�w���� / ���c�ЕF�@
�n�߂Ĉ������͂�͂���݂ɂ����u��������v�ł������炵���B��������݂₷�����邽�߂Ɉ�҂͂���ɏ��ʂ̃R�[�q�[��z�܂��邱�Ƃ�Y��Ȃ������B���ɂ����R�[�q�[�����炵�ؖȁs���߂�t�̏��܂ɂق�̂ЂƂ܂݂�����҂���ꂽ�̂�M�������̒��ɐZ���āA�����̕��ז�s����������t�̂悤�ɐU��o���i��o���̂ł���B�Ƃɂ������̐��܂�Ďn�߂Ė�������R�[�q�[�̍����͂�������c�Ɂs���Ȃ��t�炿�̏��N�̎���S�������Ă��܂����B���ׂẴG�L�]�e�B�b�N�Ȃ��̂ɓ��ہs�ǂ������t�������Ă����q���S�ɁA���̓�m�I���m�I�ȍ��C�͖��m�̋Ɋy�����牓�m��n���ė����ꖬ�̌O���s����Ղ��t�̂悤�Ɋ�����ꂽ���̂̂悤�ł���B���̌�܂��Ȃ������̓c�ɂֈڂ�Z��ł���������ꍇ�̋����͌�����������ł������A�����Ŗ�������悤�ȃR�[�q�[�̍����͂���������Ȃ������炵���B�R�[�q�[���Ə̂��Ċp�����̓��ɂЂƂ܂݂̕������������̂���ʂɈ��p���ꂽ����ł����������X����͂�����L�����яL���ٗl�̕����ɕώ����Ă��܂��Ă����B �@
�����w�Z����ɂ������͂ӂ������ł������R�[�q�[�̂悤�Ȃ��������i�͗p���Ȃ������B�������ċ����ɓ���邽�߂̍����̚�s�ځt���琏���Ɏ��݂����u���V�̕��Ȃǂł��Ⴍ���o���Ă͐��̍������Ȃ߂ĉَq�̑�p�ɂ������̂ł���B�����O�Ȃǂɂ͕ʂ��č����̏�����������悤�ł���B�������߂����ĎO�\��̏t�h�C�c�ɗ��w����܂ł̊Ԃɂ�����R�[�q�[�Ǝ����Ƃ̌��ɂ��Ă͂قƂ�ǂ���Ƃ��������͋L���Ɏc���Ă��Ȃ��悤�ł���B �@
�x�������̉��h�̓m�[�����h���t�̒ҁs���t�ɋ߂��K�C�X�x���N�X�ɂ����āA�N�V������w�͗��R�����̖��S�l�ł������B�Ђǂ�������������ł��������R�[�q�[�͂悢�R�[�q�[���̂܂��Ă��ꂽ�B�����̓�K�Ŗ����Q���̂܂܂ő��O�ɂ��т��K�X�A���V���^���g�̉~�����Ȃ��߂Ȃ���X�s�Ёt�̃w���~�[�i�̎����ė���M���R�[�q�[�����ݍ������V���j�b�y�������������B��ʂɃx�������̃R�[�q�[�ƃp���͎��m�̂��Ƃ����܂����̂ł���B�㎞�\�����邢�͏\�ꎞ����n�܂��w�̍u�`���ɃE���e���E�f���E�����f���߂��܂œd�Ԃŏo������B���O�̍u�`���I����ċߏ��ŐH��������̂ł��邪�A���H�����ʂŒ��т��������A�܂��h�C�c�l�̂悤�ɒ��O�́u����v�����Ȃ�����ɂ͂��Ȃ�ł���Ƃ���֑������ʂȒ��H���������Ƃ͕K�R�̌��ʂƂ��ďd���������P������B�l������Ăюn�܂�u�`�܂ł̓�O���Ԃ����h�ɋA�낤�Ƃ���Γd�Ԃŋ��鎞�Ԃ��啔���ɂȂ�̂ŁA�قNj߂����낢��̔��p�ق�����˂�Ɍ���������A���x�������̌Â߂������X��̂��Ƃ����蛍J�s�낤�����t�����߂Ĝf�r�s�ق������t������A�e�B�A�K���e���̖ؗ�����D���Ă݂���A�܂��t���[�h���q�X��A���C�v�`�q�X�̃V���E�E�B���h�E���̂�������ł́u�x�������̃M���u���v������ق��͂Ȃ������B����ł��Ԃ�����Ȃ����Ԃ��J�t�F�[��R���f�B�g���C�̑嗝�̃e�[�u���̑O�ɉ߂����A�V���ł����Ȃ���u�~�b�g�v��u�I�[�l�v�̃R�[�q�[�����т��тȂ߂Ȃ���W�����D���Ԓ��s�܂Ⴍ�t����̂���K�ɂȂ��Ă��܂����B �@
�x�������̓~�͂���قNJ����Ƃ͎v��Ȃ��������Â��ĕ������āA�������ĕs�v�c�ȏd�ꂵ���������Z�����̂悤�ɑS�s�����߂Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B���ꂪ���ӎ��Ȍy���̖����I���D�ƍ������Ĉ����ʂȖ����ƂȂ��Ċz������������̂ł������B���̖�����ǂ��������߂ɂ͎��ۂ��̈�t�̃R�[�q�[�������ɂ͂ނ���͂Ȃ͂��K�v�ł������̂ł���B�O�����l������̃J�t�F�[�ɂ͂܂��z���S�̕���s�ӂ��t�̍����Ȃ��X�ՂƂ��Ăǂ�������Ƃ˂��݂��o�邭�炢�ł������B�R���f�B�g���C�ɂ͉ƒ�I�ȕw�l�̋q���命���łق��炩�ɂɂ��₩�ȃ\�v���m��A���g�̂������肪�����ꂽ�B �@
���X�𗷍s����Ԃɂ����̏K���������ĕ������B�X�J���f�B�i���B�A�̓c�Ɂs���Ȃ��t�ɂ͋��낵�����傤�ŕ����s�Ԃ��t�ł��������Ă����ꂻ�����Ȃ��R�[�q�[�����ɂ����Ώo������B�������Ē����̉��̌��݂ŃR�[�q�[�̖��o�ɍ����������Ƃ����������鎖����̌������B���V�A�l�̔�������R�[�t�C�����{���ɂ悭���Ă��鎖��m�����B�̂̃y�e���u���O�ꗬ�̃J�t�F�[�َ̉q�͂Ȃ��Ȃ��ɂ��������ł��܂����̂ł������B����Ȏ���������̍��̎Љ�w�̐[�����v����悤�ȋC�������B�����̏o���������̃����h���̃R�[�q�[�͑����͂܂��������B��T�̏ꍇ�͂`�a�b��C�I���̖��O�I�Ȃ�g���ʼn䖝����ق��͂Ȃ������B�p���l���펯�I���S�Ȃ͍̂g������̂�ł������Č��n�I�Ȃ�r�t�X�e�L��H���������Ƙ_����l�����邪�A���ۃv���C�Z��������̂҂�҂肵���_�o�͎��ɂ��Ƃ��܂��R�[�q�[�̎Y����������Ȃ��B�p���̒��H�̃R�[�q�[�Ƃ��̞��_�s����ڂ��t���ɂ����p���͎��m�̔����ł���B�M�����\���̃X�e�t�@�����A�u���H�A���[�E���V�E�v�ƌ����ď���ɂ̂��čs�����H�͈�����イ�̑�Ȃ�y���݂ł��������Ƃ��v���o���B�}�f���[�k�̋߂��̈ꗬ�̃J�t�F�[�ň��R�[�q�[�̂��������Ì����Ē����ƎM�s����t�Ƃ��z�������Ă��܂��āA��������Ɏ����グ��ꂽ�̂ɋ������L��������B �@
���m����A���Ă���́A���j�ɋ���s���t�̕����s�ӂ����t�ւ悭�R�[�q�[�����݂ɏo�������B�����ق��ɃR�[�q�[�炵���R�[�q�[�����܂��Ă����Ƃ�m��Ȃ������̂ł���B�X�ɂ��ƃR�[�q�[�����g��������قǂ悭�l���Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����̂��̂����܂���A�܂����ɂ͏`���s���邱�t�̖��̂�����̂����܂���鎖���������B�����ł̓h�C�c�l�̃s�A�j�X�g�r���ƃZ���X�g�v���Ƃ̕s���Ȉ���悭���������ɗ����킹�Ă����B��l����͂肱���̈�t�̃R�[�q�[�̒��Ƀx�������Ȃ������C�v�`�q�̖��𖡂���Ă���炵���v��ꂽ�B���̂���̋��d�l�͘a���Ɋp�юp�ł��������A�k�Ќ���������Ɉ����z���Ă��炻�ꂪ�^�L�V�[�h�������ɕς��Ɠ����ɂǂ��������̂������ɂ͂����̕~���������Ȃ��Ă��܂����A����ł͂܂��r�Ƃ��e�Ƃ��j�Ƃ��������������̋i���X�s�������Ă�t���ł����̂Ŏ��R�ɂ������֑����������B �@
�����̓R�[�q�[�Ɍ��炸������H���ɑ��Ă�������u�ʁv�Ƃ������̂ɂ͈���������킹���Ȃ��B�����������̓X�̂��̂��̂̃R�[�q�[�̖��ɊF��ʂ����邱�Ƃ����͎��R�ɂ킩��B�N���[���̍����ɂ��X�ɂ���Ē��������Ⴊ�����āA���ꂪ�Ȃ��Ȃ��������Ȗ��o�I�v�f�ł��邱�Ƃ������炩�͂킩��悤�ł���B�R�[�q�[�̏o�����͂������Ɉ�̌|�p�ł���B �@
�������������R�[�q�[�����ނ̂́A�ǂ����R�[�q�[�����ނ��߂ɃR�[�q�[�����ނ̂ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B��s�����t�̑䏊�ō���܂��Ă����������܂��o�����R�[�q�[���A�����U�炩�������Ԃ̏���̏�Ŗ��키�̂ł͂ǂ�������������Ȃ��āA�R�[�q�[�����C�ɂȂ肩�˂�B��͂�l���ł��}�[�u�����A���F�K���X�̃e�[�u���̏�ɋ�킪�����Ă��āA��ւ̃J�[�l�[�V�����ł��ɂ����Ă��āA�������ăr���b�t�F�ɂ���ƃK���X������̂悤�ɂ���߂��A�ĂȂ�d�����ɂ��Ȃ�A�~�Ȃ�X�g�[�����ق̂��ɂقĂ��Ă��Ȃ���ΐ���̃R�[�q�[�̖��͏o�Ȃ����̂炵���B�R�[�q�[�̖��̓R�[�q�[�ɂ���ČĂяo����錶�z�Ȃ̖��ł����āA������Ăяo�����߂ɂ͂�͂�K���Ȕ��t�������͑O�t���K�v�ł���炵���B��ƃN���X�^���K���X�Ƃ̑M���s�����t�̃A���y�W�I�͊m���ɂ��������nj��y�̈ꕔ���̖�ڂ��Ƃ߂���̂ł��낤�B �@
�������Ă���d�����s���l�܂��Ă��܂��Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��悤�Ȏ��ɁA�O�L�̈Ӗ��ł̃R�[�q�[�����ށB�R�[�q�[�����̉����܂��ɂ����т�Ƒ��G��悤�Ƃ���u�Ԃɂς��Ɠ��̒��Ɉꓹ�̌������ꍞ�ނ悤�ȋC������Ɠ����ɁA�₷�₷�Ɖ����̎�|������v�������Ƃ���������悤�ł���B �@
�����������ۂ͂�����R�[�q�[���ł̏Ǐ�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă݂����Ƃ�����B���������łł���A���܂Ȃ����̐��_�@�\�����������ނ��āA���������悤�₭����ɕ�����̂ł��낤���A���݂̏ꍇ�͂���قǂ̂��ƂłȂ��炵���B��͂肱�̋����܂̐����ȍ�p�ł��肫���ڂł���ɑ���Ȃ��B �@
�R�[�q�[�������܂ł���Ƃ͒m���Ă͂������ق�Ƃ��ɂ��̈Ӗ���̌��������Ƃ͂�����x����B�a�C�̂��߂Ɉ�N�ȏ�S���R�[�q�[�����ɂ��Ȃ��ł��āA�������Ă���H�̓��̌ߌ�v���Ԃ�ŋ���s���t�֍s���Ă��̂�����t�𖡂�����B�������ĂԂ�Ԃ�����ē���J�s�Ђт�t�ւ�܂ŗ���ƂȂ����̂ւ�̗l�q�������Ƃ͂������悤�ȋC�������B�����̖ؗ������s�������d�Ԃ����ׂĂ̏�Z�I�Ȃ��̂��Ђǂ����������邭�����Ȃ��̂̂悤�Ɏv���A�����Ă���l�Ԃ��݂�ȗ������������A�v����ɂ��̐��̒��S�̂����ׂďj���Ɗ�]�ɖ����P���Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B�C�����Ă݂�Ɨ����̎�̂Ђ�ɂ��Ԃ犾�̂悤�Ȃ��̂������ς��ɂɂ���ł����B�Ȃ�قǂ���͋��낵���Ŗ�ł���Ɗ��S�����A�܂��l�ԂƂ������̂����ɂ킸���Ȗɂ���ď���Ɏx�z����邠���ȑ��݂ł���Ƃ��v�������Ƃł���B �@
�X�|�[�c�̍D���Ȑl���X�|�[�c�����Ă���Ƃ�͂蓯�l�ȋ�����Ԃɓ�����̂炵���B�@���ɔM�������l������Ǝ�����������s�������t��Ԃ��o�����邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B���ꂪ���X�p�Ə̂���S���I�Ö@�Ȃǂɗ��p�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B �@
����R�[�q�[�̂悤�Ȃ��̂͂�����֗~��`�҂Ȃǂ̖ڂ��猩��ΐ^�ɗL�Q���v�̒�����������Ȃ��B�������A�|�p�ł��N�w�ł��@���ł����͂����̕����Ƃ悭�������ʂ�l�Ԃ̓��̂Ɛ��_�ɋy�ڂ����̂̂悤�Ɍ�����B�֗~��`�Ҏ��g�̒��ł������̋֗~��`�N�w�ɓ����̌��ʔN�̎Ⴂ�Ɏ��E�������[�}�̎��l�N�w�҂����邭�炢�ł���B�f��⏬���̌|�p�ɐ����ē�����������鏭�N������A�O���N�w�v�z�����s�߂��Ă��t���Đ��𑛂����������̂Ă���̂����Ȃ��Ȃ��B�@���ގ��̐M�ɖ����ɂȂ��ĉƑ����������邨�₶������A���邢�͊����s���t�����ĉ����Ȃ����҂��������悤�ł���B �@
�|�p�ł��N�w�ł��@���ł��A���ꂪ�l�Ԃ̐l�ԂƂ��Ă̌��ݓI���H�I�Ȋ����̌����͂Ƃ��Ă͂��炭�Ƃ��ɂ͂��߂Č����I�̈Ӌ`�����艿�l������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����A���������Ӗ����猾���Ύ����ɂƂ��Ă̓}�[�u���̑��ɂ����ꂽ��t�̃R�[�q�[�͎����̂��߂̓N�w�ł���@���ł���|�p�ł���ƌ����Ă�������������Ȃ��B����ɂ���Ď����̖{�R�̎d���������Ԃ�ł��\�����グ�邱�Ƃ��ł���A���Ȃ������g�ɂƂ��Ă͉���s�ւ��t�Ȍ|�p�┼�n�̓N�w��ʂ邢�@�������v���O�}�e�B�b�N�Ȃ��̂ł���B�������܂�Ɉ����ŊO���̈����Ӓn�̂����Ȃ������͂ł͂Ȃ����ƌ�������̂Ƃ���ł���B�����������������̂������Ă�������������Ȃ��Ƃ����܂łȂ̂ł���B �@
�@���͉��X�l�����s�߂��Ă��t�������\�Ɨ�����Ⴡs�܂Ёt������_�Ŏ��Ɏ��Ă���B�������āA�R�[�q�[�̌��ʂ͊��\���s�q�ɂ����@�s�ǂ����t�ƔF�����ɂ���_�ł����炩�N�w�Ɏ��Ă���Ƃ��l������B����@���Ől���E�����̂͑������R�[�q�[��N�w�ɐ����Ĕƍ߂������Ă�����̂͂܂�ł���B�O�҂͐M�I��ϓI�ł��邪�A��҂͉��^�I�q�ϓI�����炩������Ȃ��B �@
�|�p�Ƃ��������̔��������ɐl�𐌂킷�A���̐��킹�鐬���ɂ͑O�L�̎�������A�j�R�`���A�A�g���s���A�R�J�C���A�����t�B�����낢��̂��̂�����悤�ł���B���̐����ɂ���Č|�p�̕��ނ��ł��邩������Ȃ��B�R�J�C���|�p����t�B�����w�����܂�ɑ�����߂��ގ���ł���B �@
�R�[�q�[���M�������R�[�q�[�N�w�����̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����B�����������������t�̃R�[�q�[�̐����̌��ʂł��邩������Ȃ��B(���a���N��)�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@���g��
 �@
�@ �@
�@ �@
�@���g�����猩��C�M���X�ƃA�����J�@
�L����ch�fa�n(���H)
cha, chai, tchaĭ, chay�ȂǓ��{��A�|���g�K����A�q���Y�[��A�y���V����A�A���r�A��A���V�A��A�g���R��ւƓ`�d�B
������tay(te)�n(�C�H)
tay (te), thee, tee, tea, the�ȂǃI�����_��A�h�C�c��A�p��A�t�����X��ւƓ`�d�B
��The Oxford English Dictionary.(Vol.II)(Oxford: Clarendon Press, 1989)
Properly, the name of TEA in the Mandarin dialect Chinese, which was occasionally used in English at the first introduction of the beverage.
��The Oxford English Dictionary.(Vol.XVII)(Oxford: Clarendon Press, 1989)
tea(ti:) The original English pronunciation (te:), sometimes indicated by spelling tay, is found in rimes down to 1762, and remains in many dialects; but the current (ti:) is found already in the 17 th c., shown in rimes by the spelling tee.
��The Oxford English Dictionary. (Vol.II)(Oxford: Clarendon Press, 1989)
1.=Bohea tea. The name was given in the beginning of the 18th to the finest kinds of black tea; but he quality now known as�eBohea�fis the lowest, being the last crop of the season.
��The Oxford English Dictionary. (Vol.XVII)(Oxford: Clarendon Press, 1989)
tea(ti:) The original English pronunciation (te:), sometimes indicated by spelling tay, is found in rimes down to 1762, and remains in many dialects; but the current (ti:) is foundalready in the 17 th c., shown in rimes by the spelling tee.
A Broadsheet of Tea by Thomas Garway back to 17th Century
Following is the text of the famous broadsheet or advertising leaflet circulated by coffeehouse proprietor Thomas Garway, the first to sell tea in England, with contmporary spelling , but today's punctuation. The Drink is declared to be most wholesome, preserving in perfect health until extreme Old Age.
The particular virues are :
It maketh the Body active and lusty. It helpeth the Head-ach , giddiness and heaviness thereof.It removeth the Obstructions of the Spleen. It is very good against the Stone and Gravel, cleansing the Kidneys and Urinators being drunk with Virgin's Honey instead of sugar. It taketh away the difficulty of breathing, opening Obstructions. It is good against Lipide, Distillations, and cleareth the sight. It removeth lassitude, and cleareth and purifieth adult Homors and a hot Liver.It is good against Crudities,strengthening the weakness of the Ventricle or stomack, causing good Appetite and Digestion, and particularly for Men of corpulent Body and such as are the great eaters of Flesh.It vanquisheth heavy Dreams, easeth the Brain , and strengtheneth the Memory.
It overcometh superfluous Sleep, and prevents sleepiness in general, a draught of the Infusion being taken , so that without trouble whole nights may be spent in study without hurt to the Body, in that it moderately healeth and bindeth the mouth of the stomach.
It prevents and cures Agues, Surfeits and Fearers, by infusion a fit quantity of the Leaf, thereby provoking a most gentle Vomit and breathing of the Pores, and hath been given with wonderful seccess.
It (being prepard with Milk and Water)Strengtheneth the inward parts, and prevents consumptionk, and powerfully assuageth the pains of the Bowels, or griping of the Guts or Looseness.It is good for Colds, Dropsies and Scruffy , if properly infused purging the Blood of Sweet and Urine, and expelleth Infection.It driveth away all pains in the Colicky processding from Wind, and purgeth safely the Gall.And that the Virtures and Excellencies of this Leaf and Drink are many and great is evident and manifest by the high esteem and use of it (especially inlater years) among the Physicians and knowing men of France, Italy, Holland an dother parts of Christendom: and in England it had been sold in the Leaf for six pounds, and sometimes for ten pounds the pound weight, and in respect of its former scarceness and dearness, it hath been only used at Regalia in high Treatments and Entertianments, and Presents mad ethereof to Princes and Grandees till the year 1657 . The said thomas Garway did purchase a quantity thereof, and first publickly sold the said Tea in Leaf and Drink , made according to the directions of the most knowing Merchants and Travellers into Eastern Countries: And upon knowledge and experience of the said Garway's continued care and industry in obtaining the best Tea, and making Drink thereof , very many Noblemen, Physicians, Merchants and Gentlemen of Quality have ever since sent to him for the said Leaf and daily resort to his House in Exchange Alley aforesaid to drink the Drink thereof. And to the end that all Persons of Eminency and Quality, Gentlemen an dothers, who have occasion for Tea in Leaf may be supplied . These are given notice that the said Thomas Garway hath Tea to sell from sixteen to fifth Shillings the pound.
(Katherine of Braganza, a Portuguese princess)
�C�M���X�ɍg�����L�܂����̂̓|���g�K�������̃L���T�������C�M���X�̃`���[���Y2���ƌ�����������ł����B�L���T���������͂��Ȃ肨���D���������悤�ŁA�C�M���X�ւ̉œ��蓹��Ƃ��ċi������A�������A�����������Ă����܂����B����ɂ�肨���ɍ��������Ĉ����ґ�Ȉ��ݕ����L����A�{���㗬�K���ɋi���̕��K���L�܂����̂ł��B
(wife of the 7th Duke of Bedford , the Duchess of Bedford)
�镣�҂̍g���̘b
�������h������k��100�L�����[�g���A�x�b�h�t�H�[�h�V���[�̃E�H�[�o���E�A�r�[�ցB�����ɂ̓A�t�^�k�[���e�B�[�̑n���҂ƌ�����A����ڃx�b�h�t�H�[�h���ݕv�l�A�A���i�E�}���A���Z��ł����ق�����B
������1845�N���A���ݕv�l�͂��̊ق̉��ڎ��ɐl�������A�ߌ�̂ЂƂƂ���������ׂ�ɔ�₵���B���̎��́A�u���[�E�h���E�C���O���[���ƌĂ�A���̖͗l������߂�ꂽ�u���[�̃V���N�̕Ǖz�ɁA���������H�̊G���̓V�䂩�獋�ȃV�����f���A���݂艺�����Ă���B
�����ł��������Ɩ������C�M���X�̒��H�́A������f�B�i�[�E���j���[�ƌ�����قǐ��肾������ŁA�����`�͏����g���̎��ς킹�Ȃ��Ƃ����̂��K�����������A�ό��≹�y��I���Ă���̃f�B�i�[�́A���Ȃ�x�����ԂɂȂ����̂ŁA�����璩�H����������H�ׂĂ��Ă��ɑς���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�������Ō��ݕv�l�́A���̉��ڎ��ŁA�X�R����T���h�C�b�`�A�P�[�L�Ȃǂ��T�[�r�X���A�g���ƈꏏ�Ɋy���Ƃ̂��Ƃł���B
��1845�N�ƌ����A���ɃC���h�̃A�b�T�����͖{�i�I�Ȓ��͔|���s�Ȃ��Ă��āA��Ղƌ���ꂽ������̒������A�J���x�����m�ɂ���ă_�[�W�����n���ō͔|���������Ă����B
���u���ݕv�l�̃A�t�^�k�[���e�B�[�ł́A�����̃��v�T���X�[�`������C���h�p�ӂ���Ă����v�Ƃ���B���v�T���X�[�`�����͒������ΎR�̐��R����(�Z�C�T���V���E�V��)�Ƃ��čg���̌��c�ł���A�C���h�̃_�[�W�����́A���E�ō��̍���Ƃ��ĉ���M���ɐ��߂�ꂽ�ō������ł���B�ʂ��āA����������Ă���悤�ȃ_�[�W�����́A�t���[�c�Ƃ��Ԃ̂悤�ȂƂ������鍁����̌��ݕv�l�����́A���Ɋy����ł����̂��낤���B
�C�M���X�l�͍g���D���Œm���Ă��邪�A�N�������ɂ��A���H���ɂ��A���O�ɂ��A���H���ɂ��A�ߌ�ɂ��A�[�H���ɂ��A�A�Q�O�ɂ��A�i�����y���ޏK�������B���̏ꍇ�́A���̒��ł��ߌ�4�`5�����炢�̊ԂɌy�H�����Ȃ�����ނ����������B�㗬�⒆���K���ł�5����(five o�fclcok tea)���`���ł��������A��ʂł�4�����(four o�fclock tea)�ɂȂ�̂��ŋ߂̌X���Ƃ�������B�l���͂�����̂́A���{�̂����3���Ƃ����̂��ʗႾ���A�C�M���X�̏ꍇ��4�����Ƃ����Ă��悳�������B
�g���ƈꏏ�ɏo�����H�ׂ��̂́A�T���h�C�b�`(tea sandwich)�A�X�R�[��(scone)�A����̃P�[�L(home-made cake)�A�r�X�P�b�g(biscuit)�Ȃǂ��ʗ�B�i���X�Ȃǂł̓X�R�[����I�`2�����̂��Ƃ����邪�A�X�R�[���ɃT���h�C�b�`�ƃP�[�L��g�ݍ��킹�ďo���Ƃ��������B�������A�n�C�E�e�B�[(hightea)�Ƃ������āA�������͏o���Ȃ��̂������B
�[�H�̎x�x�Ɏ��|����O�ɁA�w�Z����A����q���ƕ�e�Ƃł��̓��̏o��������炢�Ȃ���A�o�^�[���p��(bread and butter)�ƔM���g����-��x�݂Ƃ����ƒ������B���j���ɂ͂��ꂱ���Ƒ��S�������ẮeSunday a afternoon tea�f���y���߂�킯�ł���B
�܂��A���̎��ԑтɐl�̉Ƃɏ��҂��ꂽ�ꍇ�́A�����������ȂɂȂ���̂ƐS���Ă��������悢�B�n�C�E�e�B�[(high tea)�̏ꍇ�����������A�P�Ɂetea�f�Ƃ����Ă��̂������w�����Ƃ�����A�u�������ށv�Ƃ������́u�H�ׂ�v�Ƃ����Ӗ��������������߂ɁR�eeat tea�f�Ƃ���������(��eating tea)���g����B
���̏K���̋N���ɂ��Ă�19���I�܂ł����̂ڂ��������`�������邪����̔w�i�ɂ͎��̂悤�Ȏ���������B18���I�̌㔼�ɂ͎Y�Ɗv���ɂ��H�Ɖ��̎���ƂȂ��āA�����l���ɕω��������A����܂ł͒��ł������͂��́edinner�f�̎��ԑт��A�ߌ��3�`4�����ɂȂ�A�����19���I�ɓ���Ƃ����Ƃ����ƒx���Ȃ��Ĥ8�`9�����炢�ɂȂ�����܂�A���H�͍��������������ԑтł������ɂ�������炸��[�H�͔��ɒx���Ƃ������ƂɂȂ�B7��ڃx�b�h�t�H�[�h���ݕv�l(Duchess of Bedford)�̃A���i(Anna:1788-1861)�́A�ߌ�4����(5�����Ƃ�������)�̋Ƒދ��Ƃ�킷���߂ɁA�g�������݂Ȃ���o�^�[���o����P�[�L����H�n�߂��Ƃ����B���ꂪ1840�N�̂��ƂƐ�������Ă���B���̂����ɂ��̐Ȃɂ͗F�l���������҂����悤�ɂȂ��āA�₪�Ă͂��ꂪ�㗬�K���ł̗��s�ɂȂ�A����ɂ��̌�ɒ����K���ɂ����y���č����̂悤�ɒ蒅���čs�����Ƃ���̂��ʐ��B�������A��2�����E���ȍ~�́A���퐶���̃y�[�X�������Ȃ��Ă������߁A���̏K���ɂ��A�肪�����Ă��Ă���B���ۂɁA�q���͕ʂƂ��Ă��A��ʂɂ͓��j���Ȃǂɋq�����҂����ꍇ���������܂�s�Ȃ��Ă��Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA19���I���t�̏㗬�K���ł́A���̒��Ȃ֏��҂��ꂽ�����͓��ʂȁe���(tea gown)��g�ɂ���悤�ɂȂ��Ă����B�䂪����������肵���E�F�X�g�̂����炦�ŁA���n�͏_�炩�����Γ����Č�������̂�p���A���[�X��������ɂ͉ԍj����(festoon)����������Ă����B�܂��A���̎���͔n�ԂŌߌ�̃h���C�u(afternoon drive)�֏o������K��������A���ꂪ�H�~���i�ɂ��Ȃ����āA�A���ɏo����邱�̂����͊i�ʂł������낤�ƍl������B����ɂ�������A�G�h���[�h��(Edward �Z:1901-10�݈�)�̎���ɂ́A���̂�����5�����邢�͂���ȍ~�̎��ԑт܂Ō�ނ���㗬�K���̊Ԃł͊��S�ȎЌ��̎��Ԃɂ܂łȂ��Ă��Ĥ���d���͂ނ��̂��Ɗy�m�̉��t���̒��Ȃł������B
���̎��ɍD�܂��g���̎�ނ́A�A�[���E�O���C(Earl Grey tea)�A�L�[�}��(Keemun tea)�A�I�����W�E�x�R�[(Orange Pekoe tea)�A�_�[�W����(Darjeehling tea)�A�Z�C����(Ceylon tea)�A���v�T���E�X�[�`����(Lapsang Souchong tea)�̂ق��A�`���C�i�[�E�u���b�N(China black tea)�ȂǁB
��1�@�A�b�T���g��
�A�b�T���́A�g���卑�Ƃ�����C���h�ŎY�o����Ă���g���̖����߂�قǁA�g���͔̍|������Ȓn��ŁA���E�ł��ő�̍g���̎Y�n�ƌ����Ă��܂��B���̓����́A�N�Z�����Ȃ��̂ł����A�Z���ȕ����ƍ���̂悳�A�[�݂̂���Ԃ����F���l�C�ŁA�g�����\��������Ƃ��Đ��E���ōL����������Ă��܂��B����ȃA�b�T���̔Z���Ȕ��������́A�X�g���[�g�ł��������ł����A�~���N�������Ă��g���̕����������Ȃ��̂������ł��B�A�b�T�����d���ł����ƃp���`�̂���a�����a�炮���Ƃ�����A�d�����嗬�������C�M���X�ōŏ��ɃA�b�T�����l�C�ƂȂ�܂����B�܂��A�A�b�T���͕������Z���Ȃ̂Ń^���j����J�t�F�C���������N���[���_�E�����N�����₷�����߁A�A�C�X�e�B�[�ɂ͌����܂���B�������A���������o���₷���A�e�B�[�o�b�O�⑼�̒��t�Ƃ̃u�����h�p�̍g���Ƃ��Ďg�p����Ă��܂��B
��2�@�q�D�u���[�X����(Maj.Robert Bruce)
�����o�[�g�E�u���[�X�ɂ��A�b�T����̔���
1823�N�ɂȂ�ƁA���o�[�g�E�u���[�X�������C���h�̃A�b�T���̖k���Ŏ������Ă������̖݂����܂����B���̌�A��̃`���[���Y�E�u���[�X�́A���̎����̒����⒃��q���A�J���J�b�^�A�������̃E�H�[���b�N���m�ɑ���܂����B�������A�c�O�Ȃ��炷���ɂ͔F�߂��܂���ł����B
�u���[�X�Z��̌��т��F�߂��Ȃ��������R�Ƃ��ẮA�����̃C�M���X���C���h��Ђ��������̖f�Ղ�Ɛ肵�Ă������Ƃ������āA�{�i�I�ɃC���h�ɂ����钃�̐����ɏ��o���K�v���Ȃ������Ƃ������Ƃ��������܂��B
�����ƈψ���̐ݗ�
�������A1833�N�ɂȂ�ƁA�C�M���X���C���h��Ђ͒������̖f�Ղ̓Ɛ茠�������܂����B���ꂪ�]���_�ƂȂ�A�p���l�̓C���h�Ǝ��̒��̐����ɖ{�i�I�ɒ��肵�Ă����܂��B1834�N�ɂ́A�C���h��̃E�B���A���E�x���e�B�b�N���ɂ��A�u���ƈψ���v���ݗ�����܂����B���ƈψ���̃����o�[�͒����ɑ����A������̒��̎��A�����悤�Ƃ��܂����B���ƈψ���͍ŏ��A���o�[�g�E�u���[�X���A�b�T���Ŕ����������̖̓C���h�ɌŗL�̂��̂ł͂Ȃ��ƍl���Ă��āA�C���h�Œ�����̒����͔|���悤�Ƃ����̂ł��B�������āA�����Y�̒��̎킪�J���J�b�^�̐A�����ɐA�����č͔|����܂����B
�`���[���Y�E�u���[�X�ɂ��A�b�T����͔̍|
�������Ă���ԂɁA�A�b�T���ŁA�`���[���Y�E�u���[�X�́A�������J�����邽�߂ɓy�n���J�Ă��܂����B�������Ă����A�b�T����̒��̖݂���t���ނ����Ď������s�Ȃ��Ă��܂����B�u���[�X�́A���������l�̒��̐��Ƃ��ق��A�ނ�̏����������āA�u���[�X�͒����ɒ������̔閧���w��ł����܂����B
�A�b�T����̊J���ƒ����̊J��͂ƂĂ����������̂������悤�ł��B�����œ����Ă����J���҂����ɁA�g����q���E�Ȃǂ̖ҏb���P�������邱�Ƃ�����܂����B�܂��A���A�n���n���̕��������ɂ���ďP������邱�Ƃ�����܂����B����ł��A�u���[�X�����͌����ɒ����̊J���𑱂��Ă����܂����B
���A�b�T����̐���
1838�N�ɂ́A�A�b�T���Y�̒��t���p���Ɍ����Ĕ�������܂����B���N�ɂ̓����h���̃I�[�N�V�����ɂ������āA�����̃o�C���[��������D�G�Ȓ��t�ł���Ƃ����]�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�A�b�T���Ő����ɐ���������A1850�N��ɂȂ�ƁA�q�}�����̎R�����ɂ���_�[�W�����ł��A���͔̍|���J�n����܂����B
���̌�A�C���h�̒��̗A�o�ʂ͔N�X�g��𑱂��Ă����A1885�N�ɂ͗A�o�ʂ�3��5274�g���ɂ܂łȂ�܂����B
�����A�C���h�͐��E�ōő�̒��̐��Y���̂ЂƂɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����ׂ����ƂɃC���h�ł́A��S���l�ȏ�̐l�������Ɋ֘A�����d���ɏ]�����Ă���Ƃ����Ă��܂��B
���uTea Party�v�̖�ɂ���
The Boston Tea Party�́A�u�{�X�g��������v�Ɩ�邱�Ƃ����邪�A�u����v�������ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��B�悭���̓��e�𗝉����ăJ�^�J�i�\�L��������悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv����BParty�ɂ́u�k�}�v�u�W�c�v�Ƃ������Ӗ����͂��߁A�u���}�v�Ƃ����Ӗ������邾���ɉ��[���B
���u�{�X�g���E�e�B�[�E�p�[�e�B�ƓƗ��푈�v
1769�N�̏t�A���݂̃J���t�H���j�A��[�T���f�B�G�S�p�̒��Ɉ�ǂ̃t���[�Q�[�g�������`���Ă����B��D���Ă����̂́A�J���t�H���j�A�B����ڎw���X�y�C���̒T���Ƃ������B16���I�ɂ��X�y�C���l�̓J���t�H���j�A�C�݂�D�ŒT���������A��������Ă̖w�ǂ��̂��Ă����X�y�C���ɂ��Ă݂�A�J���t�H���j�A��B������]�T���Ȃ������Ƃ����B
200�N�]�̔N�����߂��A1769�N�̉āA�T���f�B�G�S�̃v���V�f�B�I(�v��)�q���̏�ɁA�Z���_�����J���t�H���j�A�ŏ��̃~�b�V����(�`�����@)�����������B��1770�N�ɂ͖k�サ�ĕ������Z�ȃ����g���[�ɏ㗤��������́A�����ɂ��V�����~�b�V���������������B���̌�A30�N�̊ԂɍL��ȃJ���t�H���j�A�C�݂̓씼���ɓn����19�������̃~�b�V�������������Ă��܂����B�����āA����炪�C���f�B�A���B�̌��Տ���`�����ƂȂ�A�X�ɂ͐A���n���̋��_�Ƃ��Ȃ����B
1763�N�ɏW���������[���b�p��7�N�푈�̊ԂɁA�A���n�������A�����J�ł́A�C�M���X�ƃt�����X�������A�C�M���X�����������Ƃɂ��A�L��ȃJ�i�_�̐A���n����ɓ��ꂽ�B
�������Ȃ���C�M���X�́A����Ȑ��̂��߂ɍ��̍��������R�����B�����ŁA���̍����W���[�W3���́u�A���n�h�q�̂��߂̔�p�Ȃ̂�����A�A���n�̘A���ɕ��S�����悤�I�v�ƍl���A�Ŗ@�����߂Đŋ��̎�肽�Ă����������B�Ŗ@�����肳�ꂽ�̂�1765�N�B
�����A�C�M���X�̓��C���h��Ђ́A�A���n���܂ޖ{���Ƃ̒��f�Ղɂ��āA�ƂĂ��s�����ȓƐ茠���^�����Ă��āA���̍��̓��C���h��Ђ͖��A�Ƃ�����i�őR���Ă����B�A���n�̐l�X�͖��_�������āA�C�M���X����̗A���i�ɕs���^�����s�������ʁA���ł������c���ĈŖ@�͓P�p���ꂽ�B
�������A���͐A���n�̐l�����̒��ɂ����ɐZ�����Ă���A���A���̐l�C�͍��܂����A�C�M���X�̒��̔���グ�͗�������ł������B�������C�M���X���C���h��Ђ̂��߂ɁA�C�M���X�́u�{���Ɋł�Ȃ��ŁA�A�����J�ɒ����Ă��悢�v�Ɛ錾�B���K�A������钃�͈����͂Ȃ������A���A�ɏ]�����Ă����l�����͌��{����B
1770�N�A�{�X�g���s�E�����u���B�d���ŋ��ɔ������{�X�g���s���Ɖp���R���ՓˁB���m���Q�W�Ɍ������C���A����5�l�B�{�X�g��������̂��������ɂȂ�B������1773 �N12��16���̂��ƁB�u�ςׂ݉̒��������ō������킻���I�v�ƃC���f�C�A���ɕ��������l�X�͖����ŁA�_�[�g�}�X���A�G���[�i���A�r�[�o�[���ɏ���Ă�������342���C�ɓ������Ă��܂��B���̎����̌�A���̋ߕӂ̊C�Ŋl��鋛�͒��̖�������Ƃ���ꂽ�Ƃ��B���̎������_�@�Ƃ��āA�t�B���f���t�B�A�Ȃǂł��u�e�B�[�p�[�e�B�v���J����A�ŏI�I�ɂ͓Ɨ��푈�ւƔ��W�����B
1774�N�A�C�H�ƕ��s���āA���H�Ń��L�V�R�k�ӂ���J���t�H���j�A�������ɓ��B����R�[�X�����グ��K�v������A�p�Y�t�@���E�o�E�f�B�X�^�E�f�E�A���T�ɃX�y�C�����疽�߂����������B
�T�����ł��������A���T�́A�A���]�i�̓�[�ɂ���c�[�o�b�N�����n���w�����Ă����B�A���T�͖��߂����N(1774�N)��1�x�\���R�����s���B�c�[�o�b�N����74�������ă��n�x����������A���݂̃��T���[���X�ɋ߂��T���K�u���G���E�~�b�V�����ɓ��B���Ă���B
2�x�ڂ́A�܂��n�߂ɓ������[�g��H��A�ő�̖ړI�͓`���̃T���t�����V�X�R�܂ňꋓ�ɑ���L���A�����̐B���̋��_��z�����ł������B�A���T���c�[�o�b�N���o�������̂́A1775�N10��23���̎��ŁA240�l���̕������]���A1000�����̉ƒ{��A��Ă����Ƃ����B
���N4��19�������A�嗤�̔��Α��̃{�X�g���x�O�ł́A�L���ȐX�̘A�Ȃ郌�L�V���g���̌���ŁA��Ƀ~�j�b�g�}���ƌĂ��悤�ɂȂ�A���n���̖����B�ƃC�M���X���Ԓn�Ƃ̊Ԃɍŏ��̏e�����킳��A�Ɨ��ւ̊v���͔M���ΊW�͐��ė��Ƃ��ꂽ�B
����A�����m�݂Ń��V���g�����Ɨ��R�̎w�������n�߂Ă������A�����ł́A�����m�݂�ڎw�����A���T�T�������A���]�i�̍r��̒����q���E�o���[�ɉ����Đ��i��(�����͑���̍Œ��ɓ��{�l�Ɠ��n�l���������e���ꂽ�ꏊ�ł�����)�B
��������A������R�����āA�A���T�B���Ȃ��炩�ȋu�̏ォ��������T���t�����V�X�R�p�������낵���̂́A1776�N3���̎��ŁA���ꂩ��4���ւ����āA���a�ł̂ǂ��Șp�̎��ӂ����āA�Ԃƃ~�b�V���������Ă�ꏊ�����肵���B�A�����J�̓Ɨ��錾�������z�����3�����O�̎��ł���B
���ǂ��̔N��9���ɂ͍Ԃ��A10���ɂ̓~�b�V���������Ă��A�X�y�C���̃T���t�����V�X�R�̓A�����J�Ɨ��錾�̔N�ɒa�����鎖�ɂȂ����B
�����A���̃J���t�H���j�A�����Ă̓�[�܂ŗ̗L��������ȃX�y�C�����猩��A�Ɨ���������̃A�����J���O���́A���̐��ł͂Ȃ������B�������A���̌�X�y�C���̐V�嗤�ɂ����鐭���I��]�͐Ռ`���Ȃ������A�A���T�̌��т��Y�ꋎ���悤�Ƃ��Ă���B
�C�M���X�ł�19���I�ɂ͂������L�������ɕ��y���Ă��܂���(�}�\�Ǝʐ^)�B���R�A�����̗A���ʂ����債�܂����B�Ƃ��ɁA����܂ŃC�M���X�̒��f�Ղ�Ɛ肵�Ă����C�M���X���C���h��Ђ̖f�ՓƐ茠���p�~����(1833�N)��f�Ղ����R�����ɂȂ������Ƃ��傫�ȗv���ł����B
��1�@�����̈��݂����Ōo�ψ���
�����̗A���ʂ���������̕��A�o���ւ̎x�����������܂��B�����A���ۊԂ̎x�����͋�ōs���Ă���A�C�M���X�ɋ�̕s�����ڗ����Ă��܂����B���Ƃ��C�M���X�̓A�����J�Ɨ��푈�̉e���ŐA���n����̋�̋���������ɂȂ��Ă������Ƃɉ����A�Y�Ɗv���̐i�s�Ȃǂɂ��A��������̋₪�K�v�ƂȂ��Ă��܂����B�����ւ����̗A���ʂ��ӂ������߁A�����ɕ����₪������Ă����̂ł����B���C���h��Ђ͋t�ɒ��������������o�����߂ɁA�C�M���X�̗r�т�ȐD�����C���h�ցA�C���h�̃A�w���𒆍��ցA�����̂������C�M���X�ցA�Ƃ���������u�O�p�f�Ձv���l�������̂ł����B���Ƃ��ƒ����ł̓A�w���̓|���g�K�����l�ɂ���Ĉ��i�Ƃ��ėA������A���̗A���ʂ͔N�Ԗ�1000���ɉ߂��Ȃ����̂ł����B�Ƃ��낪1830�N���납��}���ɗA���ʂ����債�A�Ȃ��2�����B35�N�ɂ�3�����A39�N�ɂ�4�����ւƌ������Ă��܂����B���������ł͋t�ɋ₪���������������R����ƂƂ��ɁA�A�w������ĕ��I�̗���ȂǎЉ�������Ă��܂����B
��2�@�C�M���X�̕��͒������C���h��Ђ̓A�w������ɒ��ڂ�����炸�A��Ђ̋��̂��ƂɐV���̎��R�f�Տ��l�ɃA�w���荞�܂��Ă��܂����B���̒��ɂ͖������疾���ɓ��{�̒��f�ՂŊ����W���[�f�B���E�}�W�\����(���{�ł́u�p��Ԋفv�Ƃ��Ă���)���܂܂�Ă��܂����B1839�N�A�����ł͗ё������A�w���������������܂����B�܂��܂�A�C�M���X�l���v�����ɐ����Ē����l���E�Q���鎖�����u�����A�����̓C�M���X�ɔƐl���n���v�������ۂ��ꂽ���߁A�R���ă}�J�I�������̂ł����B���N�ɂȂ�ƃC�M���X�͊C�R��h�����A�����C�R��j��A��v�ȍ`���̂������ߒ����̓C�M���X�̏���������A1842�N��푈�͏I�����܂����B���ꂪ�u�A�w���v�푈�ł����B
��3�@�������̗A�o�͂���ɑ��傱�̌��ʁA�����́A1.�z���R�����C�M���X�ɏ���n���A2.�J���g���`�̂ق�����ɃV�����n�C�Ȃ�5�`���J�`���邱�ƂɂȂ�܂����B���������āA���̐푈���@�ɁA�������炳��ɂ����̗A�o�����傷�邱�ƂɂȂ�܂����B�Ȍ�A�����͋ꓬ�ƍ����̎�����}���邱�ƂɂȂ�܂����B�z���R���͂��ŋ߁A1999�N�����ɕԊ҂��ꂽ���Ƃ͂����m�̂Ƃ���ł��B�A�w���푈�͓��{�ɂ��傫�ȉe����^���܂����B�����A�y���[�͑��̉Y�ꗈ�q���@�ɁA�O���l�r�ˉ^���A�܂蝵�Ή^�������������̂��A�w���푈�ɂ���ĉ��ė̎��͂�m�炳�ꂽ����ł����B����قǃA�W�A�����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����A�w���푈�����̔��[�́u�C�M���X�l�̂����̈��݂����v�������̂ł��B
1559�N�W�����E�o�e�X�^�E�����W�I�w�q�C�L�x(�y���V���l���炨���̎������Ƃ������e�B�����炭�A�Β��̂���)�@�����[���b�p�ɂ�����ŏ��̒��̋L�q�B
1610�N���[���b�p�ɒ����`���B���̂Ƃ��̒��́u�Β��v�ł������悤���B
1613�N���˂̃C�M���X���ّ؍݂̃��`���[�h�E�E�B�b�J���̎莆�ɂ��ƁA�u�~���R�ŏ㓙�̂�����فv���Ă����悤�ɂƂ̈˗��̎莆���������B�u�㓙�̂����v�Ƃ͖����ł������Ɛ��������B
1658�N�w�}�[�L�����A�X�E�|���e�B�J�X�x(Mercurius Politicus)�ɐ��E�ŏ��̍g���̐V���L���B
�gThat Excellent, and by all Physitians approved, China Drink, called by the Chineans, Tcha, by other Nations Tay alias Tee, is sold at the Sultanese-head, a Cophee-house in Sweetings Rents by the Royal Exchange, London.�h�@(�����l�ɂ���āw�`���x�ق��ł́w�e�B�x�Ƃ��Ă�A���ׂĂ̈�t����܂莆������ꂽ�f���炵�������̈��ݕ����A����������̋߂��X�C�[�e�B���O�E���[���ɂ���T���^�l�X�E�w�b�h�E�R�[�q�|�E�n�E�X�Ŕ����Ă���܂��B)
1660�N�g�[�}�X�E�M�����E�F�C�A�g�����`�B
1662�N�`���[���Y2���ƃ|���g�K���A�u���K���U�̃L���T���������̌���(�L���T���������A���[���b�p�̍g���̏K�����C�M���X�ɓ`����)
1665�N�g�[�}�X�E�M�����E�G�C�ōg���̔���o��(�n�d�c�̗ᕶ�ɋL�^������)
1706�N�g���C�j���O�A�����h���Ɂu�g���Y�E�R�[�q�[�E�n�E�X�v���J�X�B(��ʎs���ւ̍g���̔̔��B�����A�R�[�q�[�E�n�E�X�͏��l��)
1717�N�g���C�j���O�u�S�[���f���E���C�I���v�J�X�B(���������̍g���̔��X)
1740�N�_���J���E�t�H�[�u�X�̎莆(�g�D�C�f�[������)
�u�g���͂��܂ł͂���������܂��ɂȂ�܂����B����ŁA�����n�R�ȘJ���҉ƒ�ł��A���͍g���ŐH�������܂��v
1750�N���l���E�e�B�E�K�[�f�������B1000�̃����v��ݒu�B
1750�N�g�[�}�X�E�V���[�g�w�g���A�����A�~���N�A���C���A���A�p���`���Ɋւ���_���x �� �C�M���X�ōŏ��̍g���Ɋւ����w�I����(�g���𐄏�)
1756�N�W���i�X�E�n���E�F�C�w�g���_�x ���g���͗L�Q�Ƃ������B
1756�N�E�F�b�W�E�b�h�A�V���[���b�g���܂��g���|�b�g�A�X�v�[���A�g���J�b�v�Ȃǂ̒�������B(������p�B�ƂȂ�)
1759�N�E�G�b�W�E�b�h�A�Ǝ��̐V�����H�[���J��(�J���t�����[�E�F�A)
1770�N�W���T�C�A�E�X�|�[�h�A����H����J���B
1772�N�W�����E�R�[�N���[�E���b�g�X���w�g���̈�w�I�����ƈ����̌��p�Ɋւ���l�@�x �� �g���𐄏�
1773�N�E�F�b�W�E�b�h�A���V�A�̏���J�e���[�i����u�f�B�i�[�E�Z�b�g�v����952�_�̒�������B
1784�N�g���ł̈�������
1790�N�x�b�h�t�H�[�h���ݎ����v�l�A�A���i�E�}���A�A�A�t�^�k�[���E�e�B�[�̏K���y������B
1793�N�g�}�X�E�~���g���A�~���g���Аݗ��B
1802�Ntea garden�̗p�Ⴊ����(�n�d�c�̗ᕶ�ɋL�^������)
1830�N�b�D�`�D�u���[�X���C���h�̃A�b�T���n���Œ������B
1834�N�g���f�Ղ̎��R���B
1836�N�W�����E�t�����V�X�E�f�B���B�X�w���ؒ鍑�Ƃ��̏Z�������̏o�łɂ��}�G����x
1840�N�`42�N�A�w���푈
1847�N���o�[�g�E�t�H�[�`�����w�O�N�Ԃɘi�钆���k�����ȕ��L�B���E���E�ؖȎY�n�ւ̖K����܂ށB�����l�̔_�ƁA����щ��|�A�V�A�����ɂ��Ă̕t���x(�w���L�x)
1848�N�T�~���G���Y�E�{�[���w�����ɂ����钃�͔̍|�Ɛ����x
1852�N���o�[�g�E�t�H�[�`�����w�����R�ƕ��ΐl���܂ޒ����̎Y���n��̗��A�q�}�����R�����̓��C���h��Ђ̒����ɂ��Ă̏��L�t���x(�w����K��L�x)
1857�N���o�[�g�E�t�H�[�`�����w�����l�̊Ԃł̑؍݁B�����ŁA�C�݂ŁA�����ĊC��ŁB1853����1856�N�ɋy��3���K��̊Ԃɂ����鏔�����Ɩ`���̕���B�����̎��R�̐��Y������є��p��i�A�{�\���̑��ɂ��Ă̊o���������܂ށB�ډ��̐푈�ɂ��Ă̒�Ă��x(�w�����l�̊Ԃł̑؍݁x)
1869�N�X�G�Y�^�͊J�ʁB����ɂ�蒆���ƃC�M���X��60���Ԃ̒Z�k�B�e�B�[�E�N���b�p�[�̐��ށB
���{�l�����߂čg�������ɂ����̂́A1791�N(����3)11��1���ƌ����Ă���B���̓��{�l�͑单�������v(1751-1828)�ł���B�I�B�˂̕ĂȂǂ�ς�ňɐ��̍��̐_���ۑD��A�单�������v��16����1782�N�ɂ͔��q�`���o���B���B��Ŗ\���J�ɂ����A���V�A�̃J���`���b�J�ɕY���B9�N��Ƀy�e���u���N�ɓ����B����G�J�e���[�i2���ɋA����������A1792�N�ɍ����ɋA�������B�A������O�N��1791�N11��1���ɑ单�������v��s�͏���G�J�e���[�i2���̋{��ł̂�����ɏ��҂��ꂽ�B���̎��ɐU����ꂽ�̂������g��(tea with milk)�ƌ����Ă���B1983�N�ɓ��{�g������͂���11��1�����u�g���̓��v�ƒ�߂��B���̌�̉e���ɂ��Ă͒肩�ł͂Ȃ����A���{�l�ƍg���̏o���1791�N�ɂ������Ƃ������Ƃ��B
�u���v�̗��j�͒����Ɏn�܂�B�������̕��ނ́A�u�ܑ咃�v�{�u�ߑ�g���v���u�Z�咃�v�ƕ����邱�Ƃ��ł��悤�B�����l�̐F�ʊ��o�Œ��t�̊O�ςɂ���ĕ��ނ��ꂽ�B�������A�g���͗�O�I�ɁA���o�������t�̐F�ɂ���ČĂі������܂����̂ł���B
�@�@�@�Β��F�s���y��(���Η���E�ɗ��t�E���R�ѕ�Ȃ�)
�@�@�@�����F�㔭�y��(�����O�E���|��j�Ȃ�)
�@�@�@�����F��㔭�y��(�N�R��j�E跎R����Ȃ�)
�@�@�@���F�����y��(���Ί⒃�E���k�S�ω��E�����G�����Ȃ�)
�@�@�@�g���F���S���y��(��g�H�v�E�p���g���E�L�[�}���g���Ȃ�)
�@�@�@�����F�㔭�y��(�Z�ƒ��E�v�[�A�����Ȃ�)
�Z�咃�̒��ł͂������A�Β��̗��j���ł��Â��A���{�ւ̎�e���ޗǎ���܂łɂ����̂ڂ邱�Ƃ��ł���B�����͍��ł͍��Z�x�̃J�e�L�����܂ނ��Ƃň�������͂��邱�ƂƂȂ����v�[�A�����Ȃǂ������ł���B�g���͌��݉�X�����ލg���ł���B���̔��˒n�͕����Ȃł���A�g�������E�ɂЂ�܂邱�ƂƂȂ邪�A���Ƃ͂��̐��Y�n�ɂ��Ăі����ς�邱�ƂƂȂ�B�܂��A�����@�I�Ȃ��Ƃ��猾���A�E����n�܂�u�Β��A�����A�����v�ƈޒ�����n�܂�u�����A���v�u�g���v�ƂȂ�B�E�́A�u���݂̂������V�N�ȗt�̒��̍y�f�����M���邱�Ƃɂ���ĎE�����Ƃł���B�v(3)����ɂ�蒃�̍��E�F�E�����l������̂ł���B�ޒ��͐V�N�ȗt�������点��H�������S�ƂȂ�B�ޒ��ɂ���Ĕ��y���i�s����̂ł���B
�u���v�̔��˒n�͒����ł���B�]���čg���̌��_���܂������ł���B���[���b�p�ɒ��������炳�ꂽ�̂�1610�N�ƌ����Ă���B�I�����_���C���h��Ђ̑D�����{�ƒ����̒��������A�����Ƃ���Ă���B�ǂ̂悤�Ȓ��̎�ނ̂��̂ł��������͂͂����肵�Ȃ����̂́A����͗Β��ł������悤���B���̌�18���I�����ɂ́ABohea tea(���Β�)�������炳��A���t�������������Ƃ���black tea�ƌĂ��悤�ɂȂ�A���ꂪ���[���b�p�̐l�ɂ͂�����(����)�g���Ƃ������ƂɂȂ�B���Β��͕����Ȃ̕��ΎR�łƂ�邢���锼���y�̉G�����̂��Ƃł���B�p��ōł����Ђ̂���p�ꎫ�TThe Oxford English Dictionary�ɁgBohea tea. The name given in the beginning of the 18th to the finest kinds of black tea�h(4)�Ƃ���B�{�q�[(���Β�)�͒��t�����������̂�black tea�ƌĂ��悤�ɂȂ����̂��B�]���āA���t���Β��Ɣ�ׂč�������[���b�p�l�ɂƂ��Ă�black tea�Ƃ������ƂɂȂ�B�������̕��ނɂ��Ƃ���̍����Ƃ͈�������̂ł���B���݂̂�����p���g����1823 �N��C.A.�u���[�X(Charles Alexander Bruce,1793-1871)���C���h�̃A�b�T���n���Œ��������A����ɒ����̒����@�𗘗p���邱�ƂŁA�C���h�g�����a�����A����������C���h�g���A�X�������J�g���ւƈڂ��Ă������ƂƂȂ�B�u���[�X�͂��̌�A���U�A�b�T���Ő����𑗂����B�����C�M���X�́A�����ɗ��炸�ɍg�����m�ۂ��邱�Ƃ��l���Ă����B���c�c�s�ɂ��A���C���h��Ђ���������A�������̂́A�eBohea�f,�eCongou�f(�eCongo�f),�eSouchong�f,�ePekoe�f(�ePecco�f)�ł���Ƃ����B����͉����Ӗ����邩�Ƃ����A����black tea�ƌĂ�ł������̂́A���ł����E�[�������̂��Ƃł������B
�����������{�ɓ`����ꂽ���A���t�͊O�����͐��`�̐F�͊��F�Ȃ��������ʂ蒃�F�ł������B�������A�Β����`����Ă��璃�t�͒��F����ւƕς�������j������B���āA���������Z�咃�ɕ��ނ���邱�Ƃ͑O�q�������A�茳�́w��g�������T�x(����)�Łu��������v���݂�Ɓu�y�g���zhongcha�v�Ƃ���B(6)���Ɂw������厫�T�x�Łghongcha�h���Ђ��u�g���v�ƂȂ�B
���{��black tea���Љ�ꂽ�o�܂ɂ́A������Ɖp��ɒ��ڂ��Ă����Ɩʔ������ƂɋC�����B�����Ƀ��[���b�p��C�M���X�Ɋւ�����̂����{�ɂ����炳���ɂ́A�����̉e��������A���R������ƃI�����_�ꂪ�A���Ō������{�̍��ی�Ƃ������ƂɂȂ�B�����ōl���Ă��������̂́Ablack tea�̒������u�����v�A�����̊ԂɁu�g���v�Ƃ�����悤�ɂȂ��������B�t�R�s�v�́w�g���̕����j�x�ɂ��A���{�ŏ��߂āu�g���v(���r�́u�ׂɂ���v)�Ƃ����\�����o�ꂵ���̂́A1868�N�́w�����V�����x��5����{���ł���B�t�R�͂���Ɋ���ɂ����ڂ��A1866����1869�N�ɂ����ďo�ł��ꂽ���u�V���C�g�́w�p�؎��T�x�ɂ�black tea�̖��͂Ȃ��A1872�N��J.�h�[���b�g���́w�p���щC�{�x(�{)�ɂ́u������Ƃ�����ꂪ����B���{�����̓��������Ă݂�ƁA1874 �N�ɂ͐��{�́w�g�����@�z�B�ĕ����@���x��{���ɔz�t���āA���̐���������B1875�N�ɂ͓��{���{������(��)���Z�p�҂������A���Z�p�`�K������Ƌ��ɑ��c���g�𒆍��ɔh���A����ɗ��N�ɂ͑��c���g�A�Ή͐����A�~�Y���ꂪ�C���h�ɂ��h�����ꂽ�B1877�N�ɋA�����A���m�����ŃC���h�ł̓`�K���@�������A�g��5000�҂�A�o���A�D�]�����B1878�N�ɂ͐��{�́w�g�����@�`�K�K���x�z���A�g���`�K�����e���ɐݒu�B����ɁA���N�ɂ͑��c���g�Ғ��w�g�����x(���_��)�A���c���g�w�g�����@�[�v�x(�㉺)�����ɏo�Ă���B�O�シ�邪�A1887�N�ɂ͓��{�ɏ��߂čg�����A�����ꂽ�B1890�N�ɂ͑��c���g���C���h���玝���A�������̎�q���������āA�����������̔_���Ȓ��c������ݒu���A�u�g���p�i��v�̈琬���͂��߂��̂ł���B���{�̍g���̎�e�ł͑��c���g�����Č�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�w�g���̎��T�x�ɂ��A���Ƌߑ㉻�̌��J�҂̑��c���g�������Ƃ��Ɂu�g���v�Ƃ������{������Ƃ������ƂɂȂ肻�����B
���t��̍g����e�j�̌��_�́Ablack tea�̖|�u�����v�ł͂Ȃ��A���c���g�ɂ���āu�g���v�Ƃ��Ė�A�蒅�����Ƃ���ɂ���悤���B������́u�g���v�͓��{����̋t�A���Ƃ������ƂɂȂ肻�����B���̂�����́A����̌����������҂����Ƃ���ł���B���{�ł͏��Ȃ��Ă�1868�N�ɂ́u�g���v���Љ�ꂽ�B������̎��T�E���T��1872�N�ɓo�ꂷ�邱�ƂɂȂ�B���������g���̗��j������ƁA���̌��_�͒����ɂ��邪�A�g���̗��z�̓C�M���X�B�����āA�u�g���v�Ƃ������t�͉p���black tea�̓��{��Ƃ��Ēa����������ł���B���̓��{�ւ̎�e�j�𒆐S�ɁA���{��Ƃ��Ắu�g���v�ɂ��Ă��l�@����ƁA�������ɓ����Ă���̓��{�́A�܂��ɕ����J�����}���A���m�������m�ɊႪ�����Ă������Ƃ͊m���ł���B�u�����g���v�ł͂Ȃ��A�u�p���g���v�����ڂ𗁂т�悤�ɂȂ����̂�������������̗��ꂩ������Ȃ��B
���݂ɂ�������{���Y�g�����Y�҂�50(2003�N3������)�𐔂���B��ʌ��ł͓����s�́u�g�쉀�v�A���Ԏs�́u�ނ����̍g���v�̖��O��������B���{�ɂ����邨���ܑ̌喼��(���R�E�É��E�F���E��B�E�ɐ�)�ł��A�u�F�͐É��A����͉F����A���̋��R�łƂǂ߂����v�ƌĂ�鋷�R���ӂōg�������Y����Ă���̂͋����[�����Ƃ���ł���B�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@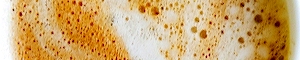 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@