 �@
�@�����b / ���F�H���E�ː������������E���B�ѐD���E�v���u�C�����E�{�^���Y�Ǝj
�@
 �@
�@������
����Ƃ́A����߂̕��D��̌��D���B����̌����́A������ʖ�����Ƃ�������������(�悱)���ɗp������v�ȎȐD��(���D)�ŁA�������ӂ̗{�\�n�т̐l�X�̎��Ɨp�̒����������B�@
��������̎ȕ��̗��s�ɏ���Ċ֓��Œ�����悤�ɂȂ�(�u�Ȗ���v)�A�吳���ɂ��R�͗l��D��o�����u�R����v�����s���A�ɐ���A�ː��A�����A�����A�����q���k���֓��𒆐S�ɐ��Y�����悤�ɂȂ����B�@
�吳�̒����Ɂu�����D/�ق�������v�̋Z�@�����������̐��Y����V���ꂽ�B�o������ׂĂ���Ȃ��悤�ɉ��D�肵����ŁA�͗l�������A���D�̈����ĉ����Ȃ���A�Ăш���ʂ��Ė{�D���邱�̋Z�@�ɂ��A��������̐F��p�������G�ȕ��̒��ڂ������悭���Y�ł���悤�ɂȂ����B���̍�����`���I�ȓV�R�����ɑ����Đ��F���������Q�ɂ悭�F�̍ʓx�������l�H�������p������悤�ɂȂ����B�@
�Z�p�v�V��w�i�ɁA�吳����-���a�����̃��_�������̗��s�ɏ�艢�Ă̗m���n�f�U�C���̉e������_�Ńn�C�J���A�F�N�₩�ȁu�͗l����v���嗬�s�����B�͗l����̃f�U�C���́A�����ł���Ȃ���A���[���b�p�A�[�g�̒����̉e�����A�吳���̖͗l����ɂ͋Ȑ��I�ȃA�[���k�[�{�[�A���a�ɂ͒����I�Ŋw�I�ȃA�[���f�R�����o�������B�@
���a�����A����S�����̒����ł́A�f�U�C���𓌋��̔��p�w�Z�ŗm����U���Ă���w���ɈϏ�������A���������t�����X�̃f�U�C�i�[�ƌ𗬂�����A�h�C�c����A�������������g�����肵�Ă����B�n���̐E�l���A���������ŐV�̃��_���f�U�C���𒅎ڂɏ悹�邱�ƂɐE�l�I�v���C�h�������āA���܂��܂ȋZ�p�I�`�������W���J��Ԃ����B���݃A���e�B�[�N�����Ƃ��Ďc�����̐F���̒��ɁA�܂�Ŗ��G���v�킹����̂�[���b�p�̓�����̃f�U�C���ɔ�ׂĂ����F�̂Ȃ����̂�����̂́A���������V�������z�Ɠw�͂̌��ʂł���B�@
�܂��A�H��ő�ʐ��Y���������Ȗ���̏o���ɂ���āA����܂ł͖ؖȂ��������Ȃ����������̏����܂ł����̒����ɑ���ʂ����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�@
�吳���-���a�������ɖ���́A�����𒆐S�ɒ��Y�K���̕��i���A�����̂�����ꒅ�A�J�t�F�̏����̎d�����Ƃ��Ēn�ʂ��m�������B�@
����́A���̑@�ې��i�̓������������ꂽ���a20�N��㔼-30�N��O��(1950-1960)�A�ɐ���𒆐S�ɐ��Y����A�A�����J�̗m���n��͕킵���啿�ʼn₩�ȃf�U�C�������s�������A���̔ɉh�͒Z�����a32�N�ɃE�[�����ڂ���������u�[���ɂȂ�ƁA���̒n�ʂ�����đւ���A���������i���ł͂Ȃ��Ȃ������a40�N��ȍ~�͂قƂ�ǎp���������B�@
���A�A���e�B�[�N�����Ƃ��Ď�Ɏ�����́A�قƂ�ǁu�͗l����v���u�R����v�ŁA���a�����̒�����70�N�O��A���̒�������40�N�̂̒����ł���B�����̂��̂قLj��̐߂��ڗ����u�ԂԂ�������(�l�b�v�ƌ���)�v�A����o�߂ƂƂ��Ɏ���Ɏ��̐߂��ڗ��������炩�Ȃ��̂������B���a�̑�ʐ��Y�i�͊��炩�Ō���̂�����̂��قƂ�ǂ����A���ɐl����p�����Ɏキ���x�s��(���͂Ɏア)�̑e���i���������o����� �B

����(�߂�����)�́A�ڐ�A�ڐ�A�ȑ@�A����ȂǂƏ�����邪�A������Ƃ������D���B�Â������ʌ�������Q�n���ɐ���ȂǂŎY�o����u���D�v�Ƃ������A���n���ȁA�l�n�ȂȂǂ��傾�����B���́A���o��̋ʎ������l���A������������p�����Ă����B�����ɓ��茦�a�����A�吳�ɓ���{�������p������悤�ɂȂ������A���̊ԁA���͐D�@�̓�������ʐ��Y�̓����J���A�J���t���ȐF�g���͗A�����ꂽ���w�������\�ɂ����B�C�O����̐V���������|�p�Ƃ����܂��ď]���̖��n�Ȃ���a�V�ȕ����L�x�ɂȂ�A��O�ߗ��̉Ԍ`�ƂȂ��Ă����B�w�i�ɁA�����A���I�푈�̈Â������̎��ォ��A�吳�f���N���V�[�Ƃ����J�����ꂽ����Ɉڂ�A���R�����琶�܂ꂽ�����̊����ɍ��v�������̂Ƃ��Ė��傪�����ꂽ�̂��B���`�A�ł��Ȗ��ɑ@�ۂ�g�D�������́u�ȑ@�v���������A���p�I�ŏ�v�ȐD�����Ӗ��������̂����A��ɕK���������̈Ӌ`�ɓK�����Ȃ��Ȃ�A�����̖��Ɛ勫�̐���Ƃ��đ��ꂵ���Ƃ����A��ʓI�ɂ́u���D�v�̑�O���ڒn�̂���Ăі��ƂȂ����B

����Ƃ́A����̕��D�茦�D���B���傪�S���I�ɗL���ɂȂ����͖̂���42�N�ɐ���ɂ����āu�����R�v(�ق���������)�̋Z�@���J������Ă���ł���B�u�����R�v�Ƃ́A���D�肵���o���ɏ���Ɠ����悤�Ɍ^���œ�������A���D��̈��������Ă���A�{�D������鏊����ق����R�ƌĂꂽ�B����܂ł́u�����R�v�u���R�v�Ɣ�ׁA���A�F�����R�ɕ��G�ȃf�U�C�����\�ƂȂ�A���Y������I�ɐL�т��B�吳-���a���ɁA�����̂�����ꒅ�Ƃ��đ嗬�s�ƂȂ�������̓����́A��_�ȕ��ƐF�g���ł���(���R�A�ِ���A���̗t��w�͗l�Ȃ�)�B���炭�S�����ւ���������펞���ɁA�����̂ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ萶�Y���r�₦�A��ア���������������~����̍D�ޗ��ƂȂ����B�����ɐ��肪���S�Y�n���������A���a30�N��ɓ���A�E�[�������̂�����̋Z�@�����̂܂���đ���A���a40�N��ɂ̓E�[�������̂��S���ƂȂ����B
 �@
�@���吳����E�D����� (��㖈���V�� 1926.12.15)
�@���s�̊@�Ƃ��ĕ����E�ɋP�������q�D���@
�n�����s���ɓV���̒��� �@
���D���̓��F �@
�����q�D���͍���S���ɂ��̖���搂��A���鏊�ɑ�D�]���Ă���̂́A�@�ƊE�̐�����m����̂̓������F�߂�Ƃ���ł���B�����q�D���͕��s����ɐ��V�ŁA���s�̐����Ȃ��Ă��邱�Ƃ͂��łɒ�]�����邪�A�n�������̏�Ȃ����x�Ő��������I����Ă���̂Ő������A�@���ɐ��肵�Ă��F����ȕ�����l�Ȏ��͐�ɂȂ��B��ɐ��F�͈�c�̐��i���ɂ����鉻�w���������Ă���ɍ��i�������݂̂̂��s��֏o���̂ł��邩��A���̌��S�x�͖w�ǐ�ΓI�Ȃ��̂ł���B �@
���D���̎�� �@
�a�m���A�w�l���Ƃ��}�Ă̕i�킪���D����A�ǂ̕��ʂɂ������̂Ŋe�ƒ��ʂ��A���p�ƐV���s�Ƃ����˂��œK�i�Ƃ��Ĉ��p����Ă���B�R�������q�͓��n���j�q�p�̌����ڂ̖{��Ƃ��Ēm���Ă��邾���ɁA�j�q���ɂ͐^�̑��̊�y���鎖�̏o���Ȃ����������Ă��邪�A�ߔN�g���̎w������Ƌ@�ƉƂ̌����ƂɈ˂��ĕw�l�����n������A�a�V�Ȉӏ����s�ƌ��k�Ȓn���Ƃő�Ɋ��}����A�́X���N�Ȃ炸���Ē����̐i���𐋂��A���s�E�̒����Ƃ��Đ��̂���Ă��鍡�d�ɐ��D�����i���������ƈ����D�A�ߎ��D�A���D���сA���сA�W�сA���o�сA�����䏢�A�䏢�A����A���[�A�ђn�A�R�[�g�n�A���z�c�n�A���n�A������ �@
���Y�z�Ɣ̘H �@
�����q�D���̊����͓V���N�Ԃɂ��łɐD���s�ꂪ�J�݂���Ă���̂����Ă��A�]���Â��������ق��Ă��邱�Ƃ͍l�@�o���邪�A�]�˂ɖ��{���J����Ĉȗ������̐i�������A�����O�\��N�܌����݂̔����q�D�����Ƒg�����n�݂��ꂽ�����̐��Y�z�͌\�����_�A�ܕS���~�ł������B�ȗ��Z�p�̐i���ƕi��̑����Ƃɂ���Ē��N�Y�z�����A��N�\�l�N�x�̐��Y�z�͓�S�Z���甪�S��\��_�A���O�S���\�O���Z��S�\�Z�~�ɒB���A���̑������͐^�ɋ��قɉ�����B�̘H�͓����A��オ�ł�����̂ŋ�B�e�n�A���É��A���s�A���l������ɂ��A�S�����鏈�Ɋ��}����A�������N�A���B���ʂɂ�����Ɏ��p����Ă���B �@
�����D�W���̐��� �@
�����q�D���͑g���̒芼�ɂ���Đ��D�W���̐���������A���d�Ȑ��i�����ɂ���đe���ƔF�߂�����͕̂s���i�Ƃ����̂ŁA�s��ɂ͗D�G�i�݂̂�������S���Ĕ����߂鎖���o����B���̑����̑g�{�݂ɂ͐����y�ѐ��F�̎w���͑f���A�V�K�D���̕ی�A���s�̌��������A���̂ق�����̐i�^�ɏ������Ă�������ʂɔ����q�D���̐U���ɓw�͂��Ă���B��ɋ��Z�i�]��̔@���͖����l�\��N�ɊJ�Â��Ĉȗ��l�\�]��ɋy�сA����d�ʂ閈�ɉv�X����̌��ʂ����ߖ��}�Ă̒������吳�ܔN�S���̑g���ɗ��悵�ĊJ�n���A�ȗ��D���̈ӏ����s�̔��B�Ɏ����Ă���͎̂��Ɍւ�Ƃ���ɑ���Ǝv�� �@
���������ւ̑�|����̏o�i�Ɗ��ɂ������� �@
�����q�D���̐^���ڎ��p�҂ɒm�炵�ނׂ��A�e�n�ɊJ�Â���鋤�i��A������ɂ͕K���o�i���ďЉ�ɓw�߂Ă���B�₦���e�n�ɑ��`����Â����ɓ����A��㋞�s�A�D�y���ɊJ���đ听�������߂����A���t����ࣖ��̌�A��B�����̒������镟���s�ɊJ�Â���铌�����Ɣ�����ɑ�X�I�o�i���ׂ��ډ��������ɂ��������J��̋łɂ͗��т̌܋@�ƒn���тɒ����A��ʁA����A�đ�A�b�㌦���̉ؗ�Ȃ�o�i�Ƌ��ɉ�̉ԂƂ��ċ�B�̓V�n�ɑ�Ȃ�l�C���ĂԎ��ł��낤�B �@
�����Ŗ��t�͑��𒆐S�ɋ��s�A�_�˓��̊���~�ɂ킽���X�I��`���o���̌v�悠����ɓ��{�����E�̐i�����B�̂��߂Ɍc�ꂷ�ׂ����ł���A�Ƌ��ɔ����q�D���̏����͉v�X���K�����ł���B�@
�@����ɓK�����鏊��D�� �@
����D���͊����̎������o�Đi�����B���Љ�̐����ɏ������Ď������S�g�D�̋Z�I�}�Ă̐��ʂƂ����˂ĈȂč����̐����g�����̂ł���Ȃ����ĕ��Ƃ��Ă͖ȏk�ޓ~���Ƃ��Ă͌��Ȍ�D�ɂĐV����(�Ό�)�̖��������Y�K���Ɉُ�̐��͂��ȂĈ��p����ꒀ�N���v�͈̔͂��g�債�����ɓ��g���͋ʎ����g�p����_�ɂ����Ă͑��̖͕킵��Z�p��L�������n��͐��F���D�̍H�ƂɓK�����Ԑ�̉͐��͍z������L�����F��V�b�I�n�ʂɑ���������h���閼�����邵�X�Ȃ�䂦��ł���@���ɑg�D�̕ϑJ�y�ю�v�D���ɂ��Ă��̊T�����L�� �@
����D�����Ƒg���͐悫�ɕ����D�����Ƒg���Ə̂������O�\�Z�N�\���ԌS�D���Ƒg���𒆐S�ɕ����ȉ��Ǒg���A���������q�D�{��g���A�������z���Ǒg������D�����g�����������đn������ꂽ����̂ɂ��đ吳�\�N�\�ꌎ���݂̏���D�����Ƒg���Ɖ��̂��� �@
���̑n�Ƃ͉������q������͂��܂肻�̓����͑����_�Ƃ̕��ƂƂ��Ď�D���ȂĂ���ꂽ����̂Ȃ���������i�̐������Ƌ��ɓ�����Ɣ��W�������݂ɂ����Ă͗͐D�@���O�S�]�䂻�̑��̐D�@���O�S��̑����𐔂��Đ��Y�ɏ]������Ɏ���Ȃč����̗�����������R���đ����i�͐~�Ȃ��ȂčŌÂ̂��̂Ƃ��������c�o�q���V�����͔������铙�̊����ϑJ�ɂ��Č��݂ɂ����鑽�푽�l�̐��i��Ɏ���A�����Ȍ�D�ɂ����ĐV����(�Ό�)�����k�A������(�V�Ό�)�ȐD���ɂ����Ă͎ȑo�q(�����V��)�ȏk�A���C�~�A���n�����v�E�ɑ��̖�������Ɏȏk�̔@���͐�ɑ��̒ǐ���e���ʗD�G�i�Ȃ���ւ�Ƃ��菮�����g���ɂ����Ă͔V�����i�͖��������Ȃ錟�����Ȃ����v�҂͏�Ɉ��S���čw��������Ɏ���� �@
�����q�͔͍H�� �@
���i���v�X���シ�ׂ������������q�ɓ��g���͔͍H���ݒu�������̌����ɁA���g�������݂̗��ւ𑪂菮�ŋ߂ɂ����Ă͐��F�H��݂��ď��H�Ȃ��؎���S��������X�����F�@����Ƃ��V���P�b�g�@��ݔ������F�̓���A��ʓI���F�ɂ��ĉ��i�̒�����v�铙��ɐ��i�̉��ǔ��B�ɓw�߂��ȏ㏊��D���̐������グ���� �@
����l�̐����̕K���i�������b�㌦�̐����@���Ƒg���̕s�f�̓w�͔N�Y�z�O�疜�~�ɒB�� �@
���N�̂�������m�P�̒n�����ߗm���̑�������H�D�A�O���A��ȃR�[�g�̗����̑��e��̈ߕ����ނɔ������悫�D���Ȃ�b�㌦�̗����g�p���Ă��邪�A����͉�����R������k�s���̗��S����Y�o������̂ł���B�������č���A�b�㌦�͌���l�̐����K���i�����Ă��܂������̉����̂���ق��Ă��邪���������B���Ă����͕̂��������̍����Ɠ`�����Ă���B���S�̒n�������A�R�����ʂȂ�k��̒n�����ɂ��āA�э��R�����A�ȂĖ������Ȃ��ɑ��炸�A�̂ɗ{�\�@�D�̋ƋN����A�j�k���E�̎��R�I���ۂ�悵�Ă����̂ł���B�b�㌦�͂�����ʂ��Ė��n�A�G�A���R�̎O��Ƃ��邪�ʏ�{�ꕨ�Ə̂������͒J���s��Ŏ�����A�܂������Ə̂�����̂͏�쌴�s��Ŏ����������̂őO�҂͕i���̗D�nj�҂͉��i����������Ċe�����Ƃ��A���̊O�Ȃ��g�c�A�����ɂ����ĎY����g�c�����O��҂Ƒ�����œ��ʂȂ�ʒu�����߂Ă���B�����O�\�ܘZ�N�܂ł͍b�㌦�����̖͗l�͊G�敗�̋ɂ߂ĒP���Ȃ���̂ɉ߂��Ȃ��������A�����O�\�����N������}�čޗ��̑I���y�єz�F�Ɉ����ǂ������A�������F�T�͗l�̉��p��������ނ�ɂ����芎���R��z���邱�ƑQ�������A�����̖��ڂ���V�����A�������Ďȍb�㌦�́A�ߔN�z�F���Ƃ����邵���i�����R�̉��p���I���ƂȂ�ǂ������ɓ������n�b�㌦�Ɏ����̑��ʎY�z����ߔN�O�������̐��i���삵�����������A��k�̓��Ƒg���͗�����ƘA��������āA���̔@�����Ƃ�����Ă���B �@
���i�y�ь������� / ���F����y�ѐ������� / ���Ǝҋy�ѐE�H�\�� / �ӏ��ی� / �}�Č��ܕ�W / �H�Ɗw�Z���k�w���⋋ / �W�{��� / �i�]��y�ы��i�� / ����y�ь����� �@
�����̔@���ɂ��Č����ɑe�������������Ƌ��Ɉ�ʂɂ͕s�f�̌����������Đ��i�̉��ǐi���y�є̘H�̊g���ɓw�͂��A���ɂ͋�����v���ȂĎ��ɓ������Ă���̂ōb�㌦�̐������N�Ƌ��ɍ��܂�s���͓��R�̌��ʂł��� �@
�@�e�K���ɉv�X���}����ė����u�����̓��F�v�@
�ΐقǐF��ƒn�����ǂ��Ȃ� �@
�����������ƂȂ���A�����{�a������ʌ��������̒����ɂ����ɂȂ��Ă��̋{���ƂȂ��ꂽ���Ƃ́A�����ꓯ�̂��̏�Ȃ����h�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��邪�A�����������ɂ͂��̌��h��S�������̂���ꂪ����B�����̊J�����͉̂Ȃ�Â��A���_�V�c�̌��m�X�v�F���������ɔC�����ē��n�ɕ��C�������Ƃɂ���Ēm�X�v���Ə̂��ꂽ���A�剻�V����x�ߎ��̓ƂȂ��Ē����ɉ��߂��Ɠ`�����A�܂�����ɂ͐�X�z�Ƃ����z��D���Ă������ƂɈ��ނƂ�����������A�e���p�Â��A�����[�����ł��邱�Ƃ͑����ʎ����ŁA�����ɐΊ��Ì��Ȃ��@���邱�Ƃ��猩�Ă�����𗠏���������̂ł���B�����̔@�����̗��j�͎Y�Ƃɕx�݁A�l�������߂ėǍD�A�{���Ɏ�点�������̂��܂��̂Ȃ��ɂ��炸�ł���B���������D�͌Â��̂��珇���ɔ��B���ė��č����̗�����悵���̂ł��邪�A���̔��B�̉ߒ��ɂ����Ă��낢��̎�ނ��ďo����A����͍��̔@�������̎�ނ��Y�o����Ɏ������A �@
�ȕ� / �����R / �H���R / �͗l�R / �吳�R / ���n / �F���D / �����D / ���D�� / �{���D / �ʌ��G�R / ���D / �ǐD / �ђn / ���C�~ �@
�������D�����Ƒg���ł́A�܊p����܂Œz�������Ă����u�����v�̖����𗎂��Ȃ��Ƌ��ɍX�Ɉ�w�̔������ނ�ׂ߂ɐ��Y�i�����d�Ɍ������D�Ǖi�@��D�ڕ��S��ȏ��ژZ���ڈȏ�A�D�Ћ㐡�Z���ȏ�Ƃ��A�D�[�ɖ{��Ȓ����̏؈�����u�{�ꒁ���v�̐��Y�i�Ȃ邱�Ƃ��m���Ȃ炵�߂Ă���B�������Đ��F�͊m���A�n�����S�A����Έ�w�F�悭�Ȃ�A�܂��n�����ז��ɂȂ邱�ƁA���ꑼ�̐D���̔�łȂ��e�K���̍L�����v�҂��犽�}���Ă��� �@
��S�N�O�����a�Ȃ̎Y�n�Ƃ��Ēm��ꔪ���q�Ɏs���L�����i�܂������q�Ɠ������吳�ܔN�܂Ŕ����q�D�����Ƒg���Ɨ������Ă��������N�������Ėk���D�����Ƒg����g�D�������q�̑�@�ƉƋv�ۓc�y�E�q�厁��g�����ɐ��������Ɏ���A�����z�c���z�c�n���̈����̐��Y�͑S�����w�Ə̂�×��㕨�Y�n�Ƃ��Ė����Ȃ��Ă��� �@
�@�킪�����y�ьo�ςɈ̑�̍v�����Ȃ��đ�̐D���Ɓ@
�u�đ�D�Ɛl�������v�̗R���L �@
�đ�D�̖��́A���w�������Ȃ��悭��������m����قǗL���Ȃ��̂ŁA�킪���D���̒n�ʂɛΑR�Ƃ��Ĕ����ׂ��炴�鐨�͂�L���Ă���B���̋N����q�ʂ���ˎ�㐙��R�����P�̏��ߕ����敾���Ă����̂ŁA�B�Y���Ƃ̓��ɂ���Ă�����~���ƁA���i�ܔN�z�㏬��J����k�t�����ق��Č��D��������`�肹���߂��B���ꂪ�����đ�D�̗��[�Ŏ����]�Ǝ҂͏���ی�̂��ƂɁA�e�������đe�����������܂��߂��̂ŁA���̐����v�X������A�̘H���X�g�債�ĔN�Y�z���ܕS���~����疜�~�̊Ԃ��������A���ʂ͖�S���_���S���\���_�A�����ː��S�ˁA�@��ܐ�����炸�A�D�ɋː��A�����A�ɐ���A�����q���ƑR����̐����ƂȂ����B�܂����{�ɂ����ĕđ�˂̒n�Ƃ��Đ�������ꂽ�l���������A�ŋߒ��X���W���č����ɂ����Ă͊��S�ɊO���i�𗽉킷��̍D���т�������Ɏ������A�鍑�l������������Ђ̐��i���킪���̌o�ϋy�ѕ����ɍv����������т͎��Ɉ̑�Ȃ���̂ł����ɕđ�̒鍑�l������������Ђ̍H��͐E�H�A���ɍH���̏��ǂƐ��Ƃɑ��ւ��ėD�G�̐��т������Ă���͊�Ԃׂ����ł���@
�@�ߎ��߂��߂����W������ʂ̐D����m�x�߈�x���ɐV�ǖʂ�ŊJ�� �@
�ߎ��A��ʐD�����Ƒg���̊���͖ڂ��܂������̂�����B�O�Ɍ����Ă͗D�ǂȂ鐻�i���o���A���ɂ����Ă͑g�����̌����v�X�łƂȂ茻�݂̑g���������玵�\�l���ŁA�������D�������ƎҔ��S�l�\�����A�D�����p�ƎҎ��\�O�����F�Ǝҋ�\�Z���A�Q���ƎҌ\�����̊����ɂȂ��Ă���B�������ĐD�@�䐔�ꖜ��S�O�\�ܑ�A���ɏ]������E�H�́A���v�ꖜ��S�l�\�Z���A�{�N����ɂ����铯�����D���̎Y�z���v�́A�ܕS��\�l���l�玵�S���_�ŁA���̉��i���O�\�l����玵�S���\�l�~�ƂȂ邪���̑啔���͎��ɍ�ʐD�����Ƒg���̐��Y�ɂ�������̂ł���B�������đg���e��̎�Ȃ鐻�i���������̒ʂ�ł���B �@
�n��@�ȑo�q�A�ȏk�A������A�R�[���V�A�^�I���A�ыy���W�V���c�n �@
�ŋ�@�R�A�o�q�A�~�z�A�ȏk �@
���P�J��@���~���ȁA���q���̑����n�A���C�~�A�� �@
�Y�a��@�R�A�o�q�A�G�C�C�A���V�A�R�Ȗ��D�� �@
�@����@���Ȍ�D���A�ȑo�q�A���ؖ� �@
��z��@�����ȁA�ȑo�q�A���V�A�R�[���V�A��q�A�ȏk �@
��{��@�ȊG�C�C�A�ȑo�q�A�ȏk �@
�E�͎�Ƃ��ē��n�����ł��邪�A�o�����Ƃ��Ă͖Ȓ��ځA�Ȗȕz�A���ȕz�A�ȕ��n�A�V���c�n�A�K�[�[�A���ؖȂȂǂ���������ŋߎx�߁A�C���h�A��m���ʂɑ�ʗA�o�̓��Ӑ悪�o���ē��g���̑O�r�͐r���j������Ă��� �@
�@����E�̔e���ɐ������V�����r�� �@
����ɐ���s�̌��� �@
�V�����ڊE�̉Ԍ`���s�����������Y�o�\�N�z�O��ܕS���~�A�S�\���D�Y���Ė��吶�Y�E�̑��ʂ���ނ���B�ɐ���͐l���ꖜ���玵�S�l�ː��O�甪�S�˂ł��邪�ŋ߂̔��W�͎��Ɉ������V�̐����Ŗ���̐����̍����Ȃ�Ƌ��Ɏs���v�X�U���{�N��������{���ʂ�̓��H���L�����������z�����̂ŗm�ٌ��̍ŐV���z�������䂵���R�Ƃ��Ėʖڂ���V���������O�l���ɐ���̒n�܂ʐl�͂��̂��܂�̑���ɋ����̐�����ł��낤�A�Ȃ������ǂƂ��Ă͋߂������ɂ����ċߑ��Z�P���\�������ċ@�ƒn�Ƃ��đ�ɐ��茚�݂̌v�撆�ł��邩��ɐ���s�ƂȂ�@�^��������ʂ̊Ԃɔ��茚�z���o��\�����]�~�𓊂��S�R���N���[�g���̑咡�ɂ����H�Q���v�H�������ɂƂ��Ă��̍G�����͐��ɑS���I�̊ςł���B �@
���Ɉɐ���͐��C�����̒��A�P���ɖ��������ł���k���ɂ͐ԏ�R������ɂ͐Y���A���`�̂������B�O�R�����������ē���͍㓌���Y�����嗘���̗�����ĕ��B�����R�����C���𖠂̔@���������Ă��铌���͊֓����삪�W�J���ĉʂ��Ȃ��n��������c���Ă���L艂ɂ��Đ����̒n������ɖ��Ȃ�@���͗ї����鉌���Ƒ��ւ��ċ@�ƒn�������ɕ������ĂĂ���\���ꂪ�ɐ������̎Y�n�ł��� �@
���D���Ə�v�ȕi�� �@
�ɐ������͏����������Ƃ��Ēn���͋��x�ł��薔���F�͑ϋv�͂ƌ����L�������ӏ��Ɏ����Ă͉��������V��ł���B�����ɐ������̃��b�g�[�ł��鎞��V���A�����{�ʁA���i����̎O���q���������̂ł��� �@
���ɐ������̌������� �@
�ߎ�����̎Y�n���B�ɏ]���Ė���̎�ނ���X�Ɩ��̂��������ċ���Ⴆ�Ό����ƖȎ��ƂŌ�D�����V����A�Ȏ��݂̂������Ƃ����Ȗ��傳�Ă͌����ׂ̍����̂ɓb���^���j�����̑��̖�i�ő��ʂ��{�������̂��� �@
�ɐ������͌����݂̂������ɗp���Đ��D�����������ł��邵�����ĕi��ʂɂ���Α�v�͍��̔@�� �@
���ɐ������̎�� �@
���ɐ���̖���ɂ͎����̔@�����i������ �@
��������A�傪����A�������菬��������A�哇������i�D�A�͗l����(�z�O�V�A����)�������傪����A���ȕ��i�q�ȁA�ۗ��ȁA�V���ȉ��Ȉ��D�ʒہA�F���n�A�����n�A�����ȁA���n�A���z�c�n�ђn�A�����䏢���ł��邪�A���u�傪����v�ƁA�u��������v�Ƃ͕��ӏ��̎a�V�Ȃ�_�ɂ����Ĉɐ������̓������������̂ʼn��������s�E�̊@�Ȃ�Ə]����A�܂���������Ǝȕ��Ƃ͎��p�i�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɍD�]���Ă���j�q���Ƃ��Ă͑哇�R������̈��p���Ă������ŋ߂ł͒i�D�̎��v���R�l�������̃T�����[�}���ɂ͔��Ȋ��}������A�ߏ���Ƃ��Ĕ������z�O�V�Ə̂���͗l�R�����Ȃ����s���Ă��邪������R�Ŏ�X�̖͗l��D�o�������̂ł���Ȃ��ŐV���s�Ƃ��āu�ł����v�ɐ���̎s�����Ɋe�n�≮���Ԃɑ��D��̍s���Ă���̂͑傪���蕗�̖͗l����Ŕ��ɉ떡�̂��镗�v�̋ɂ���������i�ł��邻�̑��q�������Ƃ��Ďl�g������A�������蓙�F���ꂼ��Ɏ��v����Ă��� �@
���ɐ������̌������� �@
�D�[(�D���ߖ��͐D�I���\��D�̏ꍇ�͗��[�ꔽ�̏ꍇ�͈�[��)�ɐ���̕����Ɛ����l�����Ƃ����悵�Đ��Y�҂̐ӔC�𖾂��ɂ����D���g���̒c�̏͂Ȃ�u�n��v�̈�����Đ��i�Ȃ邱�Ƃ��ؖ����Ă��銎�g���̌����Ɏ����Ă͌��d�ɗ�s����Ɏڕs���i��s���i�͎s��ɏo���ʎ��ɂȂ��Ă���A�����F�̓h�C�c���̑��̗D�ǐ������g�p���A���O�����̑��̉Ȋw�����ɂ����Č�������F���Ȃ����S�̕i���ȂĐ������������̏㐻�D���Ă���A�w���̕��͈ɐ���i�Ǝw�肠��Ίm���Ȃ���傪������ƈɐ���g���̑���J�����͂��� �@
�����Y�z�\�N�Ԃɏ\�{ �@
�����̐D���E�͎��ɂ��̎v�z�E�ɂ����ăv���I�v�z�������Ă���@�����傪�V�����r���Ă���R�����̖�����\���Ă���͎̂��ɂ킪�ɐ������ł���B�吳�l�N�ɂ͈�P�N���Y�z���O�S���\�]���~�ł����������\�O�N�ɂ͎l�疜�~�̋��z�ƂȂ��Ă��邩��\�N�Ԃɏ\�{�ƂȂ����̂ł���������Ώ\�N�ԂɎ��v���\�{������������Ȃ̂ł��鎧���Ė���Ƃ����Έɐ���C�Z�T�L�Ƃ����Β��ɖ����A�z����Ƃ����Ĉ��ނ̏����D���ł����鐶�Y���Ǝ��v�҂Ƃ�L����D���͈ɐ����[���đ��ɂ��̔�ނ����Ȃ��̂ł��� �@
�����s�͈ɐ��肩��ɐ���D���g���@����J�����k �@
���̒��͑��ς炸�s�i�C�ł��邪�ɐ������͑��ς炸�悢���s���������Ă��鉽���̌����X�ł��ɐ��������戵��Ȃ���Δɏ����Ȃ��Ƃ����L�l�ŏ]���Ĉɐ���i�̐��戵�X���S���ɑ��X�������邪����͈�ʎ��v�҂����O�I�D���Ƃ��ė��z�I�Ȉɐ��������悭�������Ĉɐ���i�𖼎w���Ă����߉����鏊�Ȃł����Ė������X�����ߗ��v�͑傫���Ȃ��Ƃ��ǂ����Ă��戵��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯����ł��� �@
��r�G�搶(�̔��p�����҂Ƃ��Ċ����Ă̑��l��)�̒k�Ɂu�^�����������w�Z�ٖD���@�̎����Ɉ˂�ƈɐ���i�Ƃ��̗ގ��i�Ƃł͐��k�ɍٖD�����Ă݂�Ɛ��тɔ��ȑ��Ⴊ����ɐ���i�͈�x�Ő������ٖD���o����̂ɑ��i�͍ĎO�J�Ԃ��Ă��������D���Ȃ�����͑��i�ɂ͌Ђ₻�̑��̂����ς��{���Ă���̂ł��ꂪ���ނŐD�����ώ�����ׂł��邪�ɐ���i�ɂ͊��N�o���Ă����̐S�z����ɂȂ��̂ł����Ԃ�]�����ǂ����ꂪ�בS�Z�̐��k�������Ĉɐ���i�����v���邱�ƂɂȂ����v�Ƃ���͈ɐ������̎�����������ɉ߂��Ȃ����S���̎��v�Ҋe�ʂ������o�������낤����ɐ���̕]�����܂��܂��悭���v�҂������ɑ�������̂��X�Ȃ邩�Ȃł��� �@
�������ԂŎ��ۂ킪�ɐ������͎������悭���s�͏�ɐ��V�ł�����F�܂����S�ňꓪ�n������Ƃ����Έɐ���Ƃ����l�ɂȂ�ɐ��肪����̑�\�҂ƂȂ鎟��ƂȂ���������ɑS���̑�V�����G�����D��ŋL���������悤�ɂȂ����̂ʼnv�X�ɐ���̐��������킪�ɐ������͖{�M�����E���\���闬�s���ƂȂ��ā\���s�͈ɐ��肩��E�E�E�E�E�E����ȋ��т�����̕w�l�Љ��N��悤�ɂȂ��ė��� �@
����킪�ɐ���@�ƉƂ͏�ɑg���̃��b�g�[���鎞��V���Ǝ����{�ʂƉ��i����Ƃ̎O���q����������������f���Ė��o�̐��ӂƔ������錳�C�ƂŐ������V�����ɐ������̐��Y�ɓw�͂��ċ���̂ł��� �@
�����悵�ĐD���̖��O����f�s�����W�y�D�R�͓��ɖ��������N�Y�S���~ �@
���ׂĂ̎��������O�������鍡���A�P�ɐD���ЂƂ肪�A����ɒ��R����ׂ����͂Ȃ��B�D���̖��O���I������Ȃ�Â����ォ����s���Ă���̂́A�֓��̗W�y�D�ł���B�����A�����閯�O���Ƃ����A�ɂ߂đ������}�Ȃ��̂̂悤�Ɏv���邪�A�킪�W�y�D�ɂ����Ă͑R���炸�A�i���悭�A�������̎���ɉ����Ĉďo���čs������Ƃ����͂Ȃꂽ�ʑ����̂Ƃ̓`�g����قɂ���B�W�y�D�̋N���͊��q���{����ŁA���a�̍��ɂ͐����D�Ƃ����ђn���Y�o���č]�ˎs��ɂ�����A�Ă��m���̊ԂɈ��p����ꂽ�B���̌�Q�����B���āA���ÔN�Ԃɂ͐V���ɖؖȒG�U�炵�R�̈ďo���Ȃ����B���ꂪ�L���Ȓ���D�ł���B�����̏��N�Ɏ����Ă͎�Ƃ��Ėؖȍ��D���A����𑫗��s��Ɉڏo���Ĕ̔����A�傢�ɐ��̍D�]����Ɏ���Ɠ����ɁA�z�Ƃ͔N��N�ɔ��W�������ˁA���Ō��Ȍ�D�̒��R����іȑ��D���Y�o���A�̘H�͑S���I�ɍL�����Ă����B�v���瑫������Ə̂��錋��ؖȂ�A�R�m�e�D�A�啿���n�A�ؖȏk�A�����k�A���Z���A���@�A�o�q�������̐V��ނ��Y�o�����������l�\�N�ؖȔ��R�D�����A���p�����ĕ��Ƃ��āA�傢�ɐ��Ԃ��犽�}���ꂽ�B���̑��ɂȂ����L���ׂ��i��Ƃ��ẮA�哇�R�Ə̂��錦�Ȍ�D�����A�ؖȒ��ڏk�A���Ȍ�D�Ón�ہA������A�����M�D�Ȃǂ��Y�o���邪�A���̓��F�͉�����i�����S�ɂ��ĉ��i����Ȃ�ɂ��苤�i��͔�����ŗD���܂������Ƃ��ƁX�ł���B�Ȃ��W�y�D�̔��W�ɂ��A�����ɓ��M���ׂ��͗W�y���Ƒg�����]���̑����s��ɂ�����̔���s�ւƂ��āA�����l�\�O�N�V���Ɏs����ٗђ��ɊJ�݂������ƂŁA����ɂ���đg���̏������L����̍����������������Ƃł���B�����đe��������h�~���邽�ߕs�f�ɖ�i���������ĐΌ��A�M���A�P�Ȃǂɑ��錘�S�x���������Ă���Ȃ��ŋ߂ɂ�����d�Ȃ鐻�i�͍��̒ʂ� �@
���ߎ��R / ������R / �a���R / ����k�R / �ߎ��R / �����R / �W�R / ���R / �ė��R / �R��z�Ȃ� �@
�@���O�I������̑����D���i�悭���悭�i���� �@
����z����V�ӏ��Ƒ��i�� �@
�����D���͓Ƒn�I�Ȉӏ��ŏ�ɐD���E���s�̐����Ȃ��e�K���̉ƒ��ʂ��đS���ÁX�Y�X�܂Ŕ��M�I�Ɋ��}����邾�����푽�l�ɘj����n�D���ł͐ߎ��D�A��D�A⼑��R�A��������A�䏢�A���R�A�k��z���͂��ߕ����т̗ނɎ���܂łǂ�ȕ�裂ȓy�n�ł��������̓X���ɑ����D���������ւ��Ă��邱�̔N�Y�z�O��]���~�A���̊O�ɗA�o�D���ł͖��q�A�^�t�^�A�k�ɁA�x�m���A�X�p���N���[�v���ŔN�Y�z�Z�S���~�A�A�o�ȐD���ł͂킪���ōł��Â����j��L����ȏk�ŔN�Y�z�ܕS���~�A�ˑR�Ƃ��Ă킪���@�ƊE�̌��Ђ��Ȃ��Ă��邱�̔N�Y�z���v�l�疜�~���� �@
���i���̉��P �@
�����D���̕i�����P�A���㔭�B�������邽�߂ɂ͋@�ƉƓ��l�S���������D�����Ƒg����g�D���Đ��D��̕��Q�h�~�̂��߁A���n���D���͎s��������P���̌�����ŗA�o���D���͓Ȗ،��A�o���������ŗA�o�ȐD���͓��{�A�o�ȑ����x���ňꔽ���Ɍ����Ȍ��������Ďڂ�Ђ̑���Ȃ����̐��F��D���ɕs���̂�����͉̂��Ȃ��������Ĕ��̂����ǂ���̂Ȃ����h�ȐD�������g���K��̌�����\���Ĕ��o�����ڋq�{�ʂ̐D���������Ă���B�����瑫���D���Ɩ��w���Č����X�ւ䂯�ΐM�p�̂�����S���Ĕ������Ƃ̏o����D�����R�ς����������̐D�������邽�߂ɂ͑����@�ƉƂ̑S�������̒������O�Ƃ����g���̉��Ɂu�i�悭���悭�i�����v�̕W��ō����̉������������Ɏ��������̂ł���B �@
�������D�̂͂��� �@
�����D�������̉��������������̂��ߋ������Ђ��Ƃ��ΐl�c�\�Z��m���V�c�̌��ɂ����̂ڂ�B���̖{�Ɂ\�і썑�̖��A�_�\�@�D���P�ƂƂ�����̂���B�������D���̋N���ɂ��āA�����Ŏx�ߎO�̐E�@�`�����A�l�c��\���Ԗ��V�c�̒��A�S�ύ���������̌��[����B䢂ɂ����Ėт��܂Ƃ���D�������n���ɂđ�����Ɏ���A������u�v���u�C�v���́u�V��s�Ɩ���юu���v�D�Ə̂�����\�Ə����Ă���B���̌�V���V�c�̎��ȕz���z���������o���A���炢�������d�˂Ĕ��B�������̊J���ŗA�o�D���̐������J�n���ꖾ������吳�ɂ����Đ��F�������A�O�Ɖ�H�Ɗw�Z�A�D�����Ƒg���A�H�Ǝ����ꂪ�o���Đ��D�̉��P�i���Ɛ��Y���i�̑���Ƃ��������Đ��ɐ��E�L���̑@�ۍH�ƒn�Ƃ��Ă̔��B�ƂƂ�����ł���B �@
�������̈ʒu�ƕ��� �@
�D�������̑����s�͓����s��W���ɂ���Ɛ��k�ɗ��H��\�ꗢ�w���瓌���S���𗘗p����Β��s��Ԕ��A���w���瓌�k�{���𗘗p����Ώ��R�w�ŗ��ѐ����o�ĎO���ԁA�킪�����������ɍv���������{�ŏ��̑����w�Z��Ղ�n�ǐ���̐���������B���s�̕��|���p�ƍH�|���p�����ΐ�ɂ���Đ��܂ꂽ���̂Ƃ���Α����̍H�|���p�̋@�Ƃ��܂��n�ǐ���̐����������̂łȂ���Ȃ�ʁA����������s�Ƒ��ւ��đ����������R�Ɍb�܂ꂽ�|�p�̗h�Ղł��낤�B�@
�@���挠�Ђ�����x��̏��W�ː��D�� �@
�����W�Ɍ䒍�� �@
���S���Ĕ�����D�����̐D���ː��D�����u�l�˂���x�v�̏��W���������Ĕ������Ȃ炸���S�A�i���悭�āA�������āA��v�ł���Ƃ͋ː��D�����Ƒg�����́u�W�}���v�b���̈�ł���A���l�@���ɂ����g���̌������@�͌����Ȃ錟���K��ɂ�萳�m�Ȃ���̂��u�p�X�v���Ďs��ɑ���o����ċ��邽�߂ł���A�u�l�c�˂Ƀg���{�v��̏��W�̂���i�őe���ȕi���������ꍇ�͓��g�����S�ӔC���Ƃ��̐ӂɊ����抷�������Ď����Ȃ��̂ł���A���̈��S���Ĕ�����ː��D���̋N���ƌ�������ɋL���� �@
�������̗��ɂ͂��܂� �@
�l�c��l�\����~�m�V�c�̌�F�ː��̐l�R�c�^����Ɏd����������P������Ďv���̂��܂� �@
�������́A���Ȃ� �I���A�������� �_��������� ����̕P �@
�Ɖr���ĕP�ɂ��������P�͂��̕ԉ̂Ƃ��� �@
�_����A���ɂ� �����锒��� ���݂̂͗��� �R�c���̎q�� �@
�Ɖr�����A���̎����b���ɒB������P���R�c�ɉ����������̂ŎR�c�͕P���ċ����ː��ɋA��y�����V���������𗧂Ă邱�ƂƂȂ����A����P�͗{�\�J���@�D�̋Ƃɖ��邭���l�ɂ����`�����Đ��ɋː��E�G�̎Y�ƓI��b��������B��l�P�̓���Ђ��ċ@�_�Ɛ��߂�Ɏ��葦������_�Ђ̂��鏊�Ȃł���B����_�Ђ͋ː��s�O�͓����m�c�R�ɂ��艝�Ëː��V���{�K�Ȃɂ��肵�𒆐��Ɏ��茻�݂̏��Ɉڂ������̂Ƃ����A�������ϑJ������D���E�̏d���Ƃ��Ď������ɋ����Ɏ������̂ł���A���ݐD�@�ꖜ����]��]�ƈ��ܐ�]�l�𐔂��ŋ߂̔N�Y�z��ܕS���_���i�ܐ疜�~�Y���ċ��鏮���Y�o�̕i��͕ʋL�̕��ʂɂ���ʂ葽�l�̐��i������A��ɋː��D�����n�������A�A�o���O���̊����ɂȂ��ċ��邪�A�o�i���̉H��d�́u�{�M�A�o�H��d�v�̑n�n�ł��� �@
���g���̉��v�ƕ��� �@
�ː��D�����Ƒg���͖����\��N�ː���Ђ̑n�݂ɒ[���������ϓ]���Ė����O�\�N�ː��D�����Ƒg���ݗ�����ꍡ���ɋy�ѕi����Ɏ�ޑ��l�ɘj�藘�Q�̋��ʂ��ʏꍇ������̂Ŋe�ƕʂɒc�̂�g�����A���̔��W��}�邱�ƂƂ����̔@���������{�� �@
�ꕔ�����Ɠ���ƎO���ђn�Ǝl�����D���ƌܕ��m�����ƘZ���A�o�D���Ǝ������n�D�����Ɣ����A�o�D���㕔�����Ə\�����F�Ə\�ꕔ�����Ə\���H�� �@
�����M���ׂ��� �@
�u��ʐ��Y�̓��F�͓��ꂳ�ꂽ�D�G�i������ɋ�������ɂ���v�Ƃ̎咣����D���K�i����K�������Đ��Y�̍��{����߂����Ƃł���A����ɂ��Ƃ��̑�\�D���͋ː��D�̖��̂����̓��F�����ʐ��Y�i�͋ː������D�A�Ƒn�I�V�i�͑g���o�^�ɂ���ċː��o�^�D�B�����D�o�^�D�ގ��̐D���ŁA���ꓙ�͈̔͂�N���ʐD���͋ː������D�ƁA���ꂼ��̖��̂ɂ���ē��ꂵ�����ɐ��F�@�D�Ɋւ����ʌ����K���⑫���ĐϋɓI�ɑe��������h�~���A�X�ɗA�o�D���̕��ʂ�����ɋߗ���x���N���ʂ͂����܂ł��Ȃ��x�m���̔@���͉��Ċe���ɂ܂ŋy�ю�Ɉ�x���F���̔@���͗��ђn���ɂ����Ă��ː������Y�n�ł���A����x�Ƃ��ĂȂ��čς܂ʓ���i�Ƃ��ĉv�X���̘̔H���g������ċ���A�吳�\�l�N�x�̔@���͓�\�㖜����l�S�O�\��_���i���O�S��\�㖜�O�甪�S�O�\��~�Ƃ����吳���N�̍D����������ʂ��������A���n���D���́u�����B����B�ђn�ށv����Ƃ��ċː���̂̐����������x�z����̂ł���A �@
���g�������̊�G�ꓰ�X���邻�̐w�e �@
���E�Ɏz�Ƃɂ��̐l����ƒm��ꂽ��F����Y�����g�����̉h�E�ɂ����g���֓�����v�����J�T���Y���]�c��(�g������@��)������s�A�x�S���A���P���A���c�X���Y�A��落���A�Ό��Ǎ�A�V��^���Y�A�O�H�����A�c���@�g�A���`�Y�A���������Y(�ȏ�\�ꖼ�ꖼ����)�ō��c���@�ւƂ��Ă͑g�����c���O�\�l�������ʎ����W�ɂ͐E���Ƃ��č��쎖�������� �@
��ꕔ�ː������E�E�E���O�I�����D���Ƃ��āA��ʉƒ�Ɉ��p�����ː��䏢�͕i���̗D�ǁA�ӏ��̎a�V�A���i�̒�������̎O����F�Ƃ��A���⏬��ют̐��ނɏ悶�S���e�n�̏]���Y�z�̒�������������B�ː��䏢�͓V�۔N�Ԃɑn�蓖�������k�ɂD����E�s�䏢�Ə̂��錦�Ȍ�D�i�̐��Y�Ɉڂ�����������\�����N���Ăя������i�ɕ������������̋Ȑܔg�p���o�č����ɋy���̂ł��̎�ނ͎Ȍ䏢�A�R�䏢�A��䏢�A���̑��̕ς�䏢�ɑ�ʂ���ĕi�퐔�\�ɂ킽��j���H�D�p�A���ڗm�y�є�z�n�A�R�[�g�n�A���A���z�c�n���A�p�r�ɂ߂čL�����Ɉӏ����p�̍I���Ȃ�Ɖ��i�̒���Ȃ�Ƃ͐��w�䏢�̉����ǐ����\�킴�鏊�Ƃ��ċː��䏢�͎Y�Ƃ̏œ_�ƂȂ��ċ���A�����ؓ����Y�����������x�m�g�� �@
��ː�����E�E�E�j���{�ʂ̗D�Ǖi�ː��ɂ��������K���i�͐ߎ��D���Ȃčł����j�̌Â����̂Ƃ���̂ł��邪�A���̐���������߂Ȃ������̔ӔN�Ɏ����ċː�����̖��̂ɂ��D�G�Ȃ�j���{�ʂ̎��p�i����邱�ƂƂȂ莢�����i�̉��ǁA�̘H�̊g��������ōs���A�Q���Y�z�債�āA����j������K���i���ł��M�p����D���Ƃ��đS���e�n�Y�i���Q���ċ���A���̕i���͏����{����W�Ԃ����F�̌��S��������͖ܘ_�����I���e��̕ς�n����n�����ĐV�@�����J���ω�������p���z�Ƃ��Ċ��}����ċ���̂ł���B�����r��h�ܘY���������a�c������ �@
��O���ː��ђn�z�E�̒����E�E�E�ː��ђn�̌��Ђ͐��Ԏ��m�̎����ł��铯�ђn�����߁A��q�A�䏢�㐡���ɑn���đQ�����Y��ނ��g�債�����̂Ŗ����ېV�O��ɂ����Ă��j�q�A�`�сA���A㌒����̍����ђn���Y�o����ꋞ�s�ƕ��я̂�����D�G�ȋZ�p�������������@�Ǝ{�݂̉��P�ɂ���ʎY�o�����Ƃ���Ɏ����Ċe��̌�D�i�����ꏊ����O�I���s�i���ђn�̎Y�o���ȂĖ�����g���̂ł���B��ɍŋߐl���������ł��V�����D���p�����Ƃ��Č}������Ƌ��ɋː��͗��悵�Ă����ђn�ɉ��p�����߁X�X�̚n�D�I�����𐋂�����n�D�E�̊j�S�𑨂��Ċc������Ȃ��������ʁA�����ɂ����Ă͐l�����p�ђn�͓V���ƕ��̎��p���������Ƃ��ӏ����̗D�ꂽ�����ȑђn�Ƃ��ēƓ��̋��n���ߎ��ɑ��Y�n�̒ǐ��������ʂ��̂ł��镔�����M�����A�������≺�k��Y�� �@
�@�������u����D�v �@
���̖ɁA�����͖���������̗��A�@�����ɕ������k�݁A��͏��ɒ|�Ɣ~�A�y�n�̉ԂȂ�x�̌��₷���ŁA�Q�Ȃ܂�����⎅�̋Z�A�����@��ɂ����i�q�A�����Ԃ��܂ł������͎s�A�l�̂��߂ɂƐD��k �@
���̉̂́A���m�̃}���`�F�X�^�܂��͊֓��̋��s�ƌĂ�Ă���Ȗ،����쒬�̋@�D��̌��i���̂����T�m�T�߂ł���B�����ɗ��s�����l�́A����Ƃ���ɑ�̉��̂悤�ȋ@�̉����Z�����苿���Ă��邱�ƂɋC�Â��ł��낤�B�����Ă��̎G���̒��ɍ����ċ@���艳���̉��ɂ��Ĕ��킵�����̉̂��̂ł���B���삪�����@�ƒn�Ƃ��āA�킪���ɗL���̒n�ʂ��߂Ă��邱�Ƃ͐��l�̂悭�m��ʂ�ł��邪�A���n�̐D���̓��F�͋ɂ߂Ĉ�ʓI�ł����āA�܂��O�������ł��邱�Ƃł��鑦���吳��l�N�̏㔼���ɂ͊O���ɑ��Ĉ��ܕS�\�������S�Z�\�ツ�[�h(���i�l�S��\�]�~)���F���͂��ߑS���E�ɗA�o���A�O�N�̏㔼���ɔ�ׂ�Ɣ��\���~�̑��z�ɂȂ��Ă���B�O�����������n���������̐������ȂĔN�X���W�����邪�A�O�������̐D���͍L���ؖȏk(�������A�Ȋi�q�A䈁A���A�F�T�A�ה��A�Ȋi�q�A���z����)�ŁA���n�����͍L���ؖȏk(�������A�Ȋi�q�A䈁A���A�F�T�A�ה��A�Ȋi�q�A���z�N���b�v�A���D���y���A�i�q�A�N���b�v���y���ȁA�N���b�v�F�T�A�g��i�q�A�G�D���y�їF�T)���̑��A�L���D���A���ȕz�A�V���c���n�A�q�����n�ށA���~���q�n�A�ᒠ�A�\��z�A�c��z�A�Ēg���A�ȃZ���A�����O�����p�i�܂����D���ނɂ͖{�k�ɁA����k�A�����R�y�ѕ����A�Ȃǂ��̑����\�킠��B��������D���̘̔H�𐢊E�I�Ɋg�債���̂́A�����n�̗��A�l�̘a�����ʂƂ͂����Ȃ��炱��S������D�����Ƒg�������҂̔M�S�Ȃ���ǐi���Ɋւ���w�͂Ɛ��i�ɑ��鐸���Ȃ钲�����s���͂������ʂɑ��Ȃ�ʁ@
�@���ƕ�d�̉��]�D�����t�A�o�̏ƂȂ�꒩�L���̍ۂ����ꂠ��Έ��S �@
���ɋ��ė���Y�ꂴ��́A�A�卑���̏�ɔO���ɂ����ׂ����Ƃł���B�����ď����̐푈�͗��R�ɂ��炸�A�C�R�ɂ��炸�A���ɋ�R�̗D����ɂ���āA���̏��s����������Ƃ͈�ʕ��p�Ƃ̌����Ƃ��덡���킪���ɂ����ẮA���S�ɔ�s�@����ьy�C���삷��\�͂����邪�A����ɗv����@���z�y�ы��z�Ɏ����ẮA�ł��x��Ă���B�]�������͑��Ĕ����i���g�p���Ă������̂ł��邪�A���s�Z�g��a�Ғ��̏Z�]�D��������Ђ��A���ƕ�d�̐��ӂ���A���v��x�O�����āA�V�����㔭�B�ɓw�͂������ʁA���݂ɉ��Ă͐��ɊO���i�ɏ���D�Ǖi��D��o���Ɏ��蔽�ɊC�O�֗A�o����̐����ƂȂ������Ђ̓w�͍͂��ƂƂ��ď\���ɕ\�����ׂ����̂ŁA�꒩��������ɂ����Ă��A���Ђ̌��݂������f���ċ�R�̋@���z�y�ы��z�̌��R�𗈂�������͂Ȃ��̂ł���B�X�ɂ���a�̎��ɂ����Ă݂�ƁA�����q��^���͂܂��܂�����ƂȂ��āA��ʓI�q��A���̊J�n�����邱�Ƃ����ʂ̊Ԃɂ��܂������œ��Ђ̊���Ɠw�͂ɑ҂��Ƒ���ł���B���Ђ̐��i�͂��̊O�� �@
�e��J�[�y�b�g(�O��) �@
�p�C���D���|�A�֎q���n �@
�D�ԁA�d�ԁA�����ԁA���тɋD�D�p���|���u���V���y�уe�����v�� �@
���̑��e�펺�������D���� �@
���ł��邪�A�ŋ߂킪�������������̕K�v�ɂ����āA�������邵���m���������邱�Ƃɒ����E�̔@�����i�́A�v�X���v�����Ȃ�̂ł���B�]���̔@��������C�O����X�A�����邱�ƂɂȂ����獑�ƌo�Ϗ㔜��Ȃ鑹���������̂ł��邪�A�K���ߔN�Z�]�D���̔��B�ɂ��t�A�o�̏ƂȂ������Ƃ͍ł��c�ꂷ�ׂ����Ƃł���A����Ɠ����Ɍ�l�͑O�r�m�X����u�Z�]�D���v�̂��߂ɏj�����Ă�܂ʁ@
�܂��Е����������甃�ӎ��ɒ��� / �ǔ��V�� �吳15�N12��4��(1926)�@
�����ł͖ؖȕ��̎��オ�����Ė���ƃ��X�����S���̎���ɂȂ�܂����B����ɂ�Ĉ�������A�������X������������������܂��B�N�����߂Â��Ɩ����X�����͂��Ȃ葡���i�Ƃ��ėp�����邪�A�i�������������đ���Ȃ��Ɣ�p��������������܂��B�@
�������������ɂ�---�܂È�������Ƃ��ӂ̂͝n(������)�������Ⴄ�̂ł��B���ʂ̖���͎��͈����Ƃ���{����D��̂ł����A�����̂͐D����p���Ȃ��̂ł��B�܂薼�O�����̖���ł��B�����đf�l���ɂ͕��ʂ̖���ƌ����������Ȃ����A�I�ɏo���Ă��܂��B�����炻��������ʂ̈�{���̖���ƐM������ł��������������܂��B�l���炢���Ă���{���̂��̂Ɨ]���͂��A�������͌܁A�Z�~�A�������ŏ\��A�O�~�܂ł���܂��B�@
��������킯��ɂ͂ǂ�ȕ����ǂ�ȕ��ɗp�������̂��悭���ׂ�̂ł��B�������̖���͌����̋��⌦�n�̂���n���W�ߐ^���ɕY��������A���`��������������Ȃ̂悤�ɂ��Ėa�ы@�B�Ŏ��̂悤�Ɏd�グ�����̂Ȃ̂ł��B�������{����p�������̂ƑS���n��������ЁA���ɑ����C��ꂽ��ڂ����肵�܂��B�@
�ŁA�������ɂ͐�Â��̔����̒[���玅���A�O�{���������Č��邱�Ƃł��B��{����p�������͎̂��ɍׂ��A�������Ȃ��A���܂��ɗ����̎w�ň�����ƃs���Ɛ����悭������܂����A�������ׂ͍��Ƒ������s�����ŁA������ƍׂ��������X�[�c�ƖȂ�������悤�ȋ�ɐ�Ă��܂��܂��B����͂���ł��o������@�Ő̂̔N��Ȃ��������Ƃ܂��Е������킯��ɂ悭�p���A�������Ȃǂł͂�͂葴�̕��@�ł���Ă��邻���ł��B��G���Ȃ��R�Ō��킯�鎖�̂ł��Ȃ��ꍇ�ɂ͂��̕��@�ł��̂���Ԃł��B�@
�܂��A�吳����(1920�N��O��)�Ƃ������オ�A��ʏ����̈ߕ����ؖȕ��������E���X����(���ю���p�������D�̐D��)�S���Ɉڍs�����������������Ƃ��킩��܂��B�������u�����ł́v�Ƃ���悤�ɁA���D���̕��y�ɂ��Ȃ�̒n�捷�����������Ƃ��킩��܂��B�@
�܂��A���̋L������A���傪���s����ƁA�قړ����ɑe���i���\��A�Ǖi�Ƒe���i�̋�ʂ��傫�ȊS���ɂȂ������ƁA�e���i�Ƃ������傪�u��{��(������)�v�ł͂Ȃ��u�a�ь����v(��������H�ƓI�ɍ��������)��f�ނɂ��Ă������Ƃ��킩��܂��B�@
���a�����ɋ���E���{���ɐ�������f�p�[�g(�O�z�A���≮�A�����A���؉�etc)�́A�ɐ���⒁���Ȃǂ̖���Y�n�ƒ�g���āA��K�͂ȓW���������N�ɉ��x���Â��A�t���A�ĕ��A�H�~�����ꂼ��ɁA���N�́u���s�v�������܂����B���Ȃ炳�����߁u�Z�Z�Z(�u�����h��)�t���R���N�V�����v�Ƃ����������ł��傤�B�@
�V���̏��Ǝ{�݂ł���f�p�[�g���A�^�[�Q�b�g(�ڋq)�ɂ����̂́A�����A�悤�₭�䓪���͂��߂��s�s���Y�K�w�ł����B�����ő�O�I�Ȍ��D���ł������́A���Y�K�w�̏��������̑����f�p�[�g�Ɍ����������D�̋q���i�������̂ł��B�@
�Ƃ���ŁA���̍L���ɂ́A�u�͗l����5�~80�K�`6�~50�K�v�Ƃ���܂��B���a8�N�����̕����́A�V��40�K�A����3�K�A�R���5�K�A������(������)���C��75�~�A���w�Z���@���C��50�~�������̂ŁA���݂Ƃ̔�r�͖�3500�`4000�{���x���Ɛ��肳��܂��B����Ŋ��Z����ƁA������6�~�́A�����21000�`24000�~�قǂɂȂ�܂��B�@
���݁A���̔����́A�ƂĂ�����Ȃ��ł����ǁA���̒l�i�ł͔����܂���B���K�̃��[�g�Ȃ�A�ǂ�ȂɈ����Ă��A����5�{���x�͂��܂��B���̂��Ƃ�����A�����̖��傪���D���Ƃ��Ă����Ɉ����ł��������Ƃ��킩��܂��B�@
���N�O�A�^����Y�n�ŁA���������10�����~�̒l�i�����Ĕ������悤�Ƃ��܂����B����̌��D���̉��i�펯�ɉ������l�i�t���ł��B���̘b���āA���́u����͈Ⴂ�܂���B������āA�����������������l�i�̂��̂ł͂Ȃ��ł�����A���̒l�i�ł͖���t�@���͔����܂����v�ƃA�h�o�C�X�������Ƃ�����܂����B�Ă̒�A���̒l�i�ł͔���܂���ł����B�@
�u���₵�������v�Ƃ́A�킩��₷�������A�u����{���H�Ȃ�������ˁv�Ƃ����ނ̒����̂��Ƃł��B ��̓I�Ɍ����ƁA�u��������ăI�[�N�V�����ɏo�Ă����甃�����ǁA�ȂρH�v�Ƃ��A�u���X�̐l�͑哇���Č������ǁA�����ɈႤ�̂�ˁv�Ƃ��A�u������Ă��ƂŔ������̂����ǁA���`�ޥ���v�Ƃ��������̂ł��B �A���e�B�[�N���́A���T�C�N�����̂����p����Ă�F����́A���ꂼ�ꎗ���悤�Ȃ��o��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@
���̏ꍇ�A����ȁu���₵�������v�ɊS���������̂́A������ł͂Ȃ��A������������ł����B����̂��ƂׂĂ������ɁA���a30�N��̒�����ɐ���̐��Y�\�̒��ɁA�u����v�ƕ���Łu�哇�v�Ƃ������ڂ��������̂ł��B�u�Ȃ�ŁA������ɐ���Łu�哇�v������Ă�̂��낤�H�v�Ǝv���Ē��ׂĂ݂�ƁA�����̏ꍇ�A�Ȃ�Ɓu�݂��(�[�R)�哇�v�Ƃ����u�����h�܂ł��������Ƃ��킩��܂����B�@
�u�݂�ܑ哇�v�A�������A���݁A�����哇�Ǝ������s�ŁA�肭���肵�ĐA�������Ő��߂����ŐD���Ă���u�哇�ہv(�{�ꉂ���哇�ۂƖ{��哇��)�ł͂Ȃ��A�l�H�����Ő��߂ċ@�B�D�肵���u�哇���v�̐D���Ȃ̂ł����B�u�݂�ܑ哇�v�Ƃ��Ĕ����Ă�̂ł�����u�U���v�ł͂Ȃ��̂ł��傤���ǁA�R�s�[���i�ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ����܂���B�@
�������A���̎����Ǝv���锽�����u�����Ԗ���فv�̓W�����̕Ћ��Ō����Ă��܂����̂ł��B�u���哇�v���ŁA�R�̊����Ƃ����F���Ƃ�����G��Ƃ����A�{��̑哇�ۂɂƂĂ��悭���Ă܂����B�����̏�Ԃ������̂ŁA����(�T�C�h)�̕����ɔ������ߎc��������̂��m�F�ł��܂����B�^���߂̏ꍇ�A�^�g�̕������������ߎc���Ă��܂��̂ŁA���́u���哇�v���̔����́A���Ԃ�o���𐮂����Ƃ���ʼn��D���Č^������u��������v�̋Z�@�̉��p�ō��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ȃ��A�Ƒz�����܂����B���������łȂ������ɂȂ��Ă�����A���ߎc�������͉B��Ă��܂��̂ŁA�{��̑哇�ۂƂ͂����茩�������t�����邩�A���ɂ͎��M������܂���B�@
���D�����̍����l�H�����ŁA��Ԃ������鎅������ł͂Ȃ����D�^���A�����Ď�@�ł͂Ȃ������@�B�D�@�ł�����A���Y�������R�X�g���A�{���Ƃ͔�r�ɂȂ�܂���B���̕��A��ʂɈ����s��ɋ����ł����͂��ł��B�@
���a�����A���邢�͏��a30�N��ɂ́A���x���哇�ۃu�[��������܂����B�悭�l���Ă݂�A�C���t�����ƂȂ̂ł����ǁA�哇�ۂ̐��Y�ʁA���������Y�������Ȃ���ԂŁA���������u�[�����v���܂��Ȃ���͂����Ȃ��̂ł��B�t�Ɍ����A�u�[�����v�̂��Ȃ�̕��������Ă����̂́A�ɐ���⒁���Ȃǂō��ꂽ�u�哇�ە��v�̃R�s�[���i�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@
�����̏����́A�F�A���܂���Ĕ����Ă����̂ł͂Ȃ�(���܂��ꂽ�l�������ł��傤����)�A�����u�哇�ە��v�̔����A�����u�����䕗�v�̔����Ƃ��������ŁA����y�ɔ����Ĉ��p���Ă��̂��Ǝv���܂��B�{���̑哇�ۂ≩����́A���������Ɠ����悤�ɍ����ŁA�������e�ՂɎ�̓͂��l�i���Ⴀ��܂���ł�������B�@
���݂ł����Y����Ă���u���R�哇�v�Ȃǂ́A����Ӗ��ł́A���������u�哇���v�̃R�s�[���i�̐����c��Ȃ̂ł��B���������R�s�[���i�́A�ۂɌ��炸�A�u(���w)�����v���u�[���ɂȂ�A����Ɨǂ������u��������v(�����q)���o������Ƃ��A���낢�날�����悤�ł��B�@
�����āA40�N�ȏ�̎����o������B���������R�s�[���i�́A���݁A�A���e�B�[�N�s���T�C�N���s��A���邢�̓l�b�g�E�I�[�N�V�����ȂǂɁA�܂��܂���������o����Ă���͂��Ȃ̂ł��B�@
��قǖڗ����̌Ò�������Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��悤�ȏ�o���̃R�s�[������܂��B�܂��āA���������R�s�[���i�̑��݂����ɓ����ĂȂ��Ǝ҂�������A�������͂��Ȃ��ł��傤�B�@
����̂Ȃ��悤�Ɍ����Ă����܂����A���́A���������u���₵�������v�Ɂu���܂���Ȃ��悤�C��t���܂��傤�v�ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�t�ɂȂ�ƂȂ��e���݂Ƃ������A�ʔ����������Ă��܂��̂ł��B���Ԃ�A�����g���u�{���v�̏��ł͂Ȃ��uFake(�䕨)�v������ł��傤�B

�E�[���͗r�̖т��A�a�т��Ď������D��グ���ѐD���B�E�[��(���V��)�����{�ɗA�������悤�ɂȂ����̂́A�������㖖���̂���B�|���g�K���̏��l�����{�Ɏ������̂��n�܂�B�����͓�ؓn���̗A���i�ō����i�������B���R�A�����ԏ�������������Ɛg�ɂ܂Ƃ����Ƃ͂ł��Ȃ������B�E�[���̒�������������ʓI�ɒ���悤�ɂȂ����̂́A���a�ɓ����Ă���B��O�̓Z��������X�A���X�ƌĂ�A�E�[���ƌĂ��悤�ɂȂ����̂́A���ߗ��s���̎��ɗm���n��]�p�������Ƃ���B�E�[���̂����̂͐��Ɉ����ȕ��i���Ƃ��Ė���A�����ɂ�����čL�����y�����B���a30�N��ɂ͖��傪�p���������B�R���A�哇���A���䒲�ȂǐD�����F�E�������ʂŁA��l�C�����E�[�������̐����͒Z���A���a40�N��㔼����̍��x�����̂Ȃ��ŁA������������}���A�����̂������u���ɂȂ萊�ނ��A���a50�N��ȍ~�ł͂قƂ�ǎs��Ō������Ȃ��Ȃ����B
 �@
�@��������
�Y�n�͓Ȗ،������s�A���̓����͐���D���̈��ŁA�Ȗ���A���Ȍ�D�̕�������ŗL���B�p�r�͒��ڒn�A�H�ڒn�A���z�c�n�A�O�O�n�Ȃǂł���B�����n���ł͕�������ɂ��łɑ����������Y����A��������ɂ͊��n�Ƃ��ėp�����Ă����B��������吳�ɂ����Ă͈ɐ���A�����A�����q�ƕ��Ԗ���Y�n�Ƃ��Ĕɉh�����B�Ƃ��ɕ�������͐l�C���������B���ݑ����ł́A����ɑ���g���R�b�g�̐��Y��������ł���B
�Ŗ��������A�߉��̎Й҂̏�(����)�ɁA�������n�����̋��ցA�܂Îg�������āA��������ꂽ�肯��ɁA���邶�܂�����ꂽ�肯��l�A���قɑ��(���������)�A���قɂ��сA�O�قɂ�����(������)�ɂĎ~�݂ʁB���̍��ɂ́A����v�w�A�����m���A���邶���̐l�ɂč�����ꂯ��B���āA�u�N���ƂɎ��͂鑫���̐����A�S���ƂȂ���v�Ɛ\���ꂯ��A�u�p�ӂ���v�ƂāA���낢��̐����O�\�A�O�ɂď��[�ǂ��ɏ����ɒ��������āA��ɂ��͂��ꂯ��B�@
���̎�������l�́A�������܂Ŏ��肵���A��莘�肵�Ȃ�B�@
��������@
�Ŗ����������A�߉������{�ɎQ�w�������łɁA�������n�����̉��~�ɁA���炩���ߎg�҂����킵�������ŁA�������ꂽ���Ƃ�����B���̂Ƃ��A���n�������ڑ҂Ȃ��������A���̌����͍ŏ��̂��V�ɂ͊������(�����)�A��Ԃ̂��V�ɂ͊C�V�A�O�Ԃɂ͂������������o���āA����ŏI�����B���̍��ɂ́A���̉��~�̎�l�v�w�ƁA���ّm���Ƃ���l���̐l�Ƃ��č����Ă���ꂽ�B�@
��i�����āA�Ŗ����������A�u���N���������Ă��鑫���̐������҂����������Ƃł��v�Ƃ��������ƁA�u�p�ӂ��Ă������܂��v�ƌ����āA���܂��܂̐F�ɐ��߂�����(�������)�O�\�D(�҂�)���A���̌�O�ŏ��[�ǂ��ɏ����Ɏd���Ă����āA��ł��͂��Ȃ������̂ł������B�@
���̂Ƃ��Ɉꕔ�n�I�����Ă����ЂƂ�ŁA�ŋ߂܂ő�������������l���A���ɂ��̗R��������̂ł���B�@
(�Ŗ��������͊��q���{��5�㎷���k������(1227-1263)�A�������n�����͑����`��(1189-1254)�̂��ƁB)�@
�@
 �����`���@�@
�����`���@�@�@
 �u�k�R���v�Ɍ��銙�q�@
�u�k�R���v�Ɍ��銙�q�@
�����͐̂���D���̎Y�n�Ƃ��ėL�������A�ꎞ�͕i���̂悭�Ȃ����i�����A�e�n�łЂキ���������Ƃ������Ƃ��������B���̉����𐰂炷�ׂ������̗L�͂ȒU�ߏO�������オ��A���{��̑����{������d���ďグ�A���Y�����{��ő�������̈��u�[���������N�������B���̌��ʁA���{���̈ꗬ�S�ݓX�Ȃǂł���舵����悤�ɂȂ����B�{��(���Ƃ܂�)�E�G�ɐ��o���A���@(�����)���┃�p���Ȃǂ������������B���X�͔ɐ����A��ʂ��k���ʂ�A�����ʂ�ȂǑ�ςȓ��킢��悵�Ă����B��������̉�������Ƃ�����B

���a�̂͂��߁A�������u���т̃}���`�F�X�^�[�v�Ə̂���A���E������ɓ��ꂽ�����̑����D���ƊE�ɂ����āA��������͉Ԍ`���i�������B�ɐ���A�ː��A�����A�����q�A�����đ����A�֓��ܑ�Y�n�Ƃ���ꂽ���剩�����Ɂu�ꓪ�n�������v���l�����������ɂ߂��B

���a�����܂ő�O�����ɏo���������́A�ۂ��͏_�炩���V�������Ƃ����������ƁA��_�ȊG����F�����ł͂Ƃ�킯�V�N���B�ɐ���A�ː��A�����q�Ȃǂ̎Y�n�Ƌ����A���a14�N�ɂ͓��{��̐��Y�ʂ��ւ��������ɂ͐D���ʼnh�����܂��̖ʉe������������B�����ɐ���������s�w���~��Ėk�Ɍ������ƁA������藬���n�ǐ��삪�������B�ނ�l�̎p���݂���Â��Ȑ�ӂɂ́A���č����������Ȃ�сA�L�X�Ƃ����쌴�͐���i(����)�Â���œ�������B�����D���̗��j�͓ޗǎ���ɂ͂��܂邪�A�Y�n�Ƃ��Ēm����͍̂]�ˎ���̌������B��������ɂ����͂₭�n�߂�ꂽ�H�ꐶ�Y���ɂ��A���k���瑽���̏��H���W�߂�قǂ̗��������}���Ă���B�����͗A�o���������S�ŁA�H��d�Ȃnj����͉̂��āA�C���h�A�k�̂悤�ȖؖȐD���͍��`�A��C�A�V���K�|�[���Ɛ��E�e�n�ɍL�܂����B���������ɂ͏k�ɁA�����͂������o(����)��(�ʂ�)�ِF�̎��ŋʒ��F�ɐD�肠����u�C�C�v(������)�A�\���ׂ̎��ő�ɐD��u�ʕ��v(���ӂ�)�A�^�t�^�Ɏ������̂���u���߁v�ȂǂőS���ɖ���y�����B�����̂���̊��������ɓ`����H�ꂪ�A���낤���Ĉ₳��Ă���B�����L���̌��@(���Ƃ͂�)�ł��������ǂɊ������̖ؑ��A�o�D���H��́A�������Ɏw�肳��Ă���B�����s�w�𐼂ւނ����ƁA1903�N�Ɍ��Ă�ꂽ�����͔͍H���\���X�|�[�c�N���u�ɂȂ��Ă���A��J�̕ǂɃt�����X���A�؍����ŐD���H����L�̃m�R�M�������Ƃ����a�m�ܒ����������낢�B�@
���{�ŌÂ̊w�юɂł��鑫���w�Z�Ŗ��������n�́A���@�̎q�틳��ɂ��͂𒍂����B���������̐D���Z�p���l�ҁA�ߓ������Y�������珵���đn�����ꂽ�����H�ƍ��Z�̋M�d�Ȏ������u�����܂��Ȃ��V�w�فv�ɓW������Ă���B����Ȕ����Q���@ �����邽�тɓ��̂悶���悤�ȕ��G�ȍ\���́A���Q�����߁A�D��Ȃǂ������̍H���ɍׂ��������ꂽ�D���Y�Ƃɂ�������Z�p�̍����������B���������y�납��A���{�̈ӏ��o�^��ꍆ�ł���_��D�Ȃǂ����炵���D������܂ꂽ�B�W���i/���瑐�O���ɂ�������ޖ���̃|�X�^�[�ƁA���̌����̒����A���n�ɐԍ��͂����肵���F�ƕ�����X�����B��������̓����́A�o���Ɉ���e�����D�肵�A����̂̂��������Ĉ�������������(�ق�)���Ȃ���D������D��Ƃ����Z�@�B���炩�����G���R���悤���D�肠����B�吳���ɂ́A�����R�����������������p�Ƃ������̊��̂���D������܂�đ�������̖������߁A���a14�N�ɂ͐��Y���S����̃s�[�N���}���邪�A���͌�ǂ��̓X����D�ȂǕi���������A���ڗp����ǂĂ�A���Z�ւƍ~�i���A���a40�N�ȍ~�ɂ͋ƊE�S�̂����ɂȂ����B�w�i�ɂ́A��炵�̂Ȃ��̒������ꂾ���łȂ��A�ƊE���x���Ă������w�̐l�C�����������Ƃ��傫���B�c�̂ňߑ������炦��S���̖��w�����ł́A���s�̉��̂��D�݂����E���A�~��o���j�u�[���ł͂��������蕗�Ƃ�������ɂ܂Ƃ܂��Ĕ��ꂽ�Ƃ��B���͌��������A���܂ł��s���̐D�茳�̂������͗x��̈ߑ����肪���Ă��邵�A���㌀�Ɏg����̂��A�����Y���傾�Ƃ����B�������傪�S���𐧔e�����������ȗ��R�́A�f�U�C���Ɛ�`�͂ɂ��邻�����B�}�Ă���߂̐E�l��������Ăъ����A�ꗬ��Ƃ�受�D���N�p�����|�X�^�[������A�O�z�⍂�����ƒ�g���Ē����Â��������A�n���ɂ��_�C���N�g���[���𑗂����B�s���������炷�D�P�_�Ђ́A����S�����̐D���g���ɂ��Č����ꂽ�B����̂т铌���ɐ�������܂��A�����͂��ԃV���N���[�h�Ƃ��ĕ~�݂��ꂽ���j�����B

�������̐D���Y�Ƃ̉��v
�@�@�@���ޗǎ���-��������-���q����
�����̐D���͗��j���Â��A�ޗǎ���(710-784�N)�̏��߂ɑ����n������u�ӂƂ��ʁv�����i�����Ƃ����̂Ɏn�܂�A�ޗǂ̑啧�J��̎��ɂ͓��厛�̌�̒n�Ƃ��ĐD���������Ă��܂��B����͕�������(794-1185��/1192�N)�ɓ����Ă��Ȃ�����(���q�@�̕������ɖ��L����Ă���)�A�܂����q����(1185��/1192-1333�N)�́w�k�R���x�Ɂu���ĔN���ɋ��͂鑫���̐���(�����̐D��)�v�Ƃ���̂͂��܂�ɂ��L���ł��B
�@�@�@���]�ˎ���
�]�ˎ���(1603-1868�N)�ɓ����ĉݕ��o�ς����B����Ƒ����D���́A�Ȃ̎��ŐD������̂������A�u�ؖȏk�v��u�������q�v�A�u��������v�Ȃǂ͑�ςȐl�C�ŁA�����Ƃ܂��̑��X�ō����D���́u�����D�v�Ƃ��u�����D���v�ƌĂ�A���܂ł̋M�����p�̎肩�痣��āA��ʑ�O�Ɉ��p����S���ɒm���Ă��܂����B
�@�@�@����������-�吳����
��������(1868-1912�N)�ɂȂ��Ă������ł͂��̂悤�ȖȂ̐D���̐��Y�͑������܂������A����20�N�O��̂Ђǂ��s�i�C�̎���Ɍ��D���ɗ͂����Ă����܂����B����܂ōׁX�Ƃ��������D���̐��Y���@�̉��ǁA�͐D�@�̓����������A����ɂ���ăA�����J��[���b�p�̍��X�̎s��J��ɓw�߁A���ڗA�o�̐����m�����A�A�o���g�債�Ă����܂����B���̔w�i�ɂ́A�D���̋ߑ㉻�Ƃ��Ė���18�N�̐D���u�K��(��ɓȖ،��H�Ɗw�Z�A�������H�ƍ��Z)�̐ݒu�A�����̋ߑ㉻�ł͓�21�N�̗��ѓS���̕~�݁A�����Čo�ϊ�Ղ̊m���Ƃ��ē�28�N�̑�����s�̑n�݂�����܂��B
�@�@�@�����a-����
���a(1926�N-)�ɂ͂���A�����D���͓`���I�X���Ƃ��Ď�͂͏�ɓ��n���ɒ�����A�荠�ȉ��i�̌��D���u�����D�v���ł����B�܂��A���̒��ł��f���炵���f�U�C���́u��������v�̐��Y�z�͒��N�������A���a6�E7�N�Ȍ�a�V�Ȗ͗l���傪����I�Ȕ��W�𐋂��A���ɏ��a8�E9�N���ɂ͖���̒��ł͐l�C��Ɛ肵���Ƃ����܂��B
���(1945�N-)�A���s���̎���ɖ���̐l�C���ꎞ�߂�܂����A�{�i�I�ȗm���̎���ƂȂ莟��ɐ��ނ��Ă����܂��B���a30�N�ォ��V���@�ێY�ƂƂ��Čo�������X�̔��W���݂đ����s�̊�Y�ƂƂ��ăg���R�b�g�̗���������܂����B���A�����̐l�X�́A�u�����D�v(�Ȗ،��w��`���H�|�i)�₨�ǂ�p�̒����Ɏg���D���Â���ɂ���āA�܂��A�҃������X�E���������X�E�j�b�g���i���̐��Y����F�������Y�n�Ƃ��āA���̓`���ƋZ�p�������p���A�V���ȋ@�ƒn�Ƃ��Ĕ��W���Ă���܂��B
����������̗��j
�@�@�@����������Ƃ́E�E�E
��������́A�Ȗ،��̑����Ő��Y����錦��f�ނƂ�������߂̕��D���ł��B�]�ˎ���̒��������炠�����ƌ����Ă��܂��B���Ƃ��Ƃ͑��D��(�ӂƂ�)�ƌĂ�Ă���A����Ɏ����Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ��p�������ƂȂ邱�Ƃ������u�ʖ��v��u�����v����̂�鑾��������(�悱����)�ɗp������v�ȕ��D���ł����B���̌��n�ŏ�v�ȐD���́A���Ɨp�̐D���������悤�ł��B
�]�ˎ���㔼�ƂȂ�܂��Ƃ��̑��D��(�ӂƂ�)�������̊ԂɍL�܂�A���m�����i���◪���̐��ꒅ�Ƃ��Ē��p���Ă����悤�ł��B���̍����瑾�D��(�ӂƂ�)���u���v���u�삦��v��A�z�����邽�ߏ����̈ߗ��ɂ͓K���łȂ����Ƃ���u����v�Ƃ��������p�����n�߂��Ƃ����Ă��܂��B
�o���̖{�����������k���ȐD�����������ƂɗR������悤�ɁA�ڂ��ׂ����̂Łu�ڐ�v�A�Ȑ��Łu�ڐ�v�ƌ���ꂽ�̂��]�a���āg�߂�����h�ƂȂ������A����������́u���v�Ɛ勫�ŐD���鎖��z��������悤�ȁu��v���Ƃ�A�u����v�Ƃ����Ƃ�����������A����ӗ~���������āA��������^����悤�ȓ��Ď��ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��l�����܂��B
���̍]�ˎ���㔼���疾������ɂ́A�ȕ����قƂ�ǂł������A��������吳����ɂȂ�ƌo��(���Ă���)�ƈ�(�悱����)�̎����̈ӓI�ɂ��炷���ƂŁA�F�̋��E���ڂ���悤�ȏ_�炩�����h���̖��傪�����̗��s�ƂȂ�܂����B��������́u�����R�v�����������悤�ł��B�吳2�N(1913�N)�ɂ́u�����D��v�������̍��ݓ����A��H���ɂ���ē����o��24612���ƂȂ�A���݂ł́A�Ȗ،��`���H�|�i�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�@�������D�Ƃ́E�E�E
�����D�́A�o��(���Ă���)(1,600�`1,700�{)��D�@�ɂ���Ȃ��悤�ɕ��ׂāA�e�����̈�(�悱����)�����D�肵�A��x1�����������D�@���͂����B1�����̉��D��̎����������o�����(������)�ɓ\��t���A1�F���Ƃɖ͗l�̒���ꂽ�^�����g���A�Ђ��������������w���ŕ������Ȃ���A�Z���F���甖���F�ւƌ^���߂��Ă����B���̌�A�������������A�����グ�A�F��蒅������B�ēx�A�D�@�ɂ����A���߂Ă�������(�悱����)�����D�肵����(�悱����)���ق����Ȃ���{�D��̈�(�悱����)����ꍞ�ݖ{�D�肷��B
���̉����D�Z�@���ł������Ƃŕ��̎�ނ��L�x�ɂȂ�A�ȕ�����R��������������ɋȐ��I�ȃf�U�C���̃A�[���E�k�[���H�[�Ⓖ���I���w�͗l�̃A�[���E�f�R���ł��A���ۉ�̂悤�Ȗ͗l���_�ȉԖ͗l�Ȃǂ̕����ł����Ƃ����Ă��܂��B���������Z�p�v�V�ɂ���āA�吳�����`���a�����̃��_�������̗��s�ɏ���āA���Ă̗m���n�̃f�U�C���̉e�������F�N�₩�ȁu�͗l����v���嗬�s���܂��B
�@�@�@�����w���̐����ɁE�E�E
���������̊w�K�@�́A�ؑ����w�Z�J�Ƃɑ��A���w���̒ʊw�̕������ؔ��Ȃ��Ƃ��Ƃ���A�����ґ�ȕ��������߂����Ɠ����̉@���ł������T�؏��R���ʊw���������x�ɒ�߁A���ꂪ���s�ɕq���ȏ��w���̊Ԃŏu���ԂɍL�܂����悤�ł��B�����A���̖��R�͗l�̖���Ɍюp�Ƃ������w���̎p���݂������X����X�l�Ă��A����ɖ͗l���{�����͗l������ɐ���ŏ��߂č�����Ƃ����Ă��܂��B
�@�@�@������̎Y�n�Ɠ���
�����5��Y�n�Ƃ��āA�ɐ���A�����A�����A�����q�A�ː��Ƃ���܂��B
�y��������z
�����Y�n(�Ȗ،������s�y�ю��Ӓn��́A�����I�Ȑ��Y�@���m�����đ�ʐ��Y���s���A����ɂ���Ĉ������������ꂽ�f�U�C���̖���̑�ʋ������\�ɂ��܂����B�܂��A���������Z�������l����R��G���ɓ��[���ȂǁA�����̈ꗬ���{��ƂɈ˗����A�|�X�^�[��G�t���Ƃ��đS���œW�J����ȂǁA�D�ꂽ�}�[�P�e�B���O�ő�������̖��𐢂ɒm�炵�߂��̂ł��B
�y�ɐ������z�@
�ɐ���Y�n(�Q�n���ɐ���s�y�ю��Ӓn��)�́A�F�ʖL���Ȏ�̍����R�Y���邱�Ƃ����ӂŁA����̔��W�ɑ傫�Ȗ������ʂ����܂����B���(1950-1960�N��)�ɂ́A����24�F���g�������̂Ɍ����܂��B�o���ƈ��̕��G�Ȗ͗l�����킹�Ȃ���D�邽�߁A���Ԃ��|����ƂƂ��ɏn�������D�q�̋Z�\���K�v�ŁA����̒��ł͍����Ȃ��̂ƂȂ�܂����B������������̐D��q�́A�ɐ���₻�̎��Ӓn��̑����̏��������ɂ���ĒS��ꂽ�̂ł��B
�y��������z
�����ł����Y���������Ă��钁������́A2013�N�ɍ��̓`���I�H�|�i�Ɏw�肳��܂����B�s�̒��S���ɂ��邿���Ԗ���قł́A������������Ƃ��납��D��グ��܂ŁA��������̑S����H�������邱�Ƃ��ł��܂��B���؈�ࣂȏo�Ԃ�ԉőS���I�ɗL���ȁu������Ձv�́A�ʖ��u���\�Ղ�v�ƌ����Ă܂����A����͍]�ˎ���ɍՂ�Ƌ��ɑ傫�Ȍ��̎s�����������ƂɈ���ł��܂��B���̂��Ƃ�����A�������Â�����{�\�ƂƐD���Ƃ̐���Ȓn��ł��������Ƃ��M���܂��B
�y�ː�����z�@�@�R���Ə���������
�y�����q����z�@�@�ς��D�肪����
�@�@�@������̋Z�@
�y�͗l����z
����̍ł���{�I�Ȑ��D���@�ŁA���R�Ȗ͗l���������o���Ɉ�F�̈���ł����ނ��́B�o���ɑł��������������Ȃ���{����ł����ނ��Ƃ���u�����v�u�����D�v�Ƃ������B�Ȑ��͗l�����݂ɕ\���ł������ߕ��D��ʼn���I�ȋZ�@�B
�y���p�z
�o��(���Ă���)�̖͗l�������A���͗l�����킹�Ȃ���D�荞�ނ��́B���͗l�����N���ɕ\���ł��锽�ʁA�͗l�������(�悱����)�Ɏ�Ԃ������邽�߁A�R�X�g��������B
�y�����p�z
�u���p�v�̔����Ƃ������̂Ƃ���A����͗l�ɓ������̂łȂ��A�R�ɓ�����ė��̓I�ȕ��͗l�\�����\�Ƃ���B���p�قǎ�Ԃ�������Ȃ����߁A�R�X�g��������Ȃ��̂������B���́u�����p�v�������̔����Ƃ���ꑫ������̗����҂Ƃ��Ȃ����B�@
 �@
�@�������̋@�� (�����V�� 1918.4.17-1918.4.23) �@
�Ȗ،��������ɉ��Ă͋���\�ܓ������D�H�ƂɊւ�����n���@�B���̋��i����J�Â�����B���B�J��Ɉ˂�䍑�}�S�̍H�Ƃ��@�B�A���̓r���������������A�@�B���ɔ\������V����n�ɋ��ނ�̕K�v��؎��Ɋ�����Ɏ����ƁA�m�ߐ��D�H�ƂɊւ���M�l�̌�����ɐi�݊����a�V�Ȃ锭��������Ɏ����_��茩��ł��@�X�ɓK�����鋤�i��ɂ��ċ@�B�����ƕ��ɋ@�ƉƂ���v���鏊�����炴��ׂ����^�킸�A����Ɍ���ׂ��o�i�������炴�銶�݂���Ƃ�����g�p�ҕ��ɐ����Ƃ̌����𑣂��������A��O�̍��틤�i��̊K����ׂ����̂Ƃ��đ���̈Ӌ`��L������̂Ȃ���ȂĈꃖ���̉�����������Ȃė����Ƃ��F�炴����B �@
���D���̎Y���@
���@��ɉ��đ����@�Ƃ̏�Ԃ��L����ɑ����D���̑啔���͒��@�ɐ�����@�Ǝ҂́���������͑������Y���Ȃ遠�������ɂ߂čL���������𒆐S�Ƃ��ĉ��ߏ����ɘj��אڂ́������B�ɖ��y�ׂ�ŋߎY�z�͓��n���������l���A�A�o���ꊄ�ܕ��A���ҍ��v��灠�S���~�ɒB����B�ŋߏ\�N�Ԃ̓��v������ɑ吳��N�y�юO�N�ɉ��Đ��ʁA���z���Ɍ��ނ���������l�N���͑Q���̕����ɕ����ܔN�y�јZ�N�͐��ʁA���z���ɋL�^�I����������������A���\�͍ŋߘZ�N�Ԃɉ����鑫���D�����Ƒg��������ɂ��Ďl�ܗ��N�ɉ�������z�̑��������ʂ̑���ɔ䂵���ɑ�Ȃ�͉��i�̓��M�Ɉ���▾�炩�Ȃ�B �@
���푽�l�̎Y�i ����D���̓��e�@��������ɓ��n�����ȕz�D���ł������Z�N�x�ɉ��Ă͐�S�\�l������~���Z����������̎l���������߈ȉ��ȐD���A�������A�A�o���ȐD���A�A�o�������y��D�����n���Ȗыy���ь�D���A�Ȗ���D���̏����ɂĔV�ɑ�����A�Z�N�x�̎Y�z��\������Ύ��̔@���ɂ��Ď�ނ̉��A���ʓ��ɐ����͑g���̗ޕʂɈ˂�i�ڐ��Ȃ�B �@
�������@�Ƃ̓��F�@
�ː��ɐ��蓙�אڂ̋@�ƒn�����͗A�o�������A���n�����������傽�鐻�i�ƈׂ���ƈق葫���͏�͍��M�Ȃ錦�D����艺�͈����Ȃ�ȐD���Ɏ��閘���푽�l�̐D�����Y���邱�ƑO�f�̕i�ڐ��Ɉ˂�Ă��V���M�����ׂ������Ȋe��̌�D���̒������������Ƃ����ɑ��ނ����������_�͑����̋@�Ƃ�������̂̊ʼn߂��ׂ��炴����F�Ȃ�ׂ����A��ɓ��n�����Ȍ�D���͑��������đS���@�ƒn�̊Ԃɓ���̒n�ʂ����ނ���̂ɂ��č���̖ȏk�Ƌ��ɑ����L���`�����B �@
���e��D���̏��� �@
������Ȃ��D�@
���n�����Ȍ�D���͐ߎ��D�ł������䏢�D�V��Ɏ�������A�����R�A�����сA�哈�����傽����̂Ƃ��đ吳�Z�N�x�ɉ��Ă͕i�ړ�\�Z��A���ʎO�S�O�\�ܖ��]�_�A��S�\�l������~���Z���A���傽����̂͑O�L�ߎ��D�ȉ��̘Z�i�ɂĘZ�i�̍��v�͓_���ɉ��Ă��A�����z�ɉ��Ă����Ȍ�D���̂̋㊄�O�����ލ����Z�i�̎Y�z���ɑ����ϒP�����Z�o����Ɏ��̔@���B �@
���ϒP���̋ɂ߂Ē���Ȃ�͓��ɒ��ڂ��䂭���Ȃ�ׂ��O�~�l�\�K�̐ߎ��ށA�܉~�ɖ�������䏢���͑̍قƑ���Ƃ̈z�ɋ�S���錻��l�̚n�D�ɓ������v�̑�����ׂ����Ƒz���ɓ�炸�B �@
�����ȗA�o��r�@
���Ȍ�D���Ɏ��ŎY�z��Ȃ�͓��n���ȐD���ɂ��ďk�ޑ��啔�����ށA�Y�z�̑�Ȃ�͎ȏk�̕S�~�A���R�̎l�\�O���~�A�ȐߐD�̙����~�A�ȌÓn�̓������~�A�Ȗ���̓�\�O���~������A�P���Ⴋ���z�Ƃ��Ă͑�Ȃ���̑����炴����i�ڐ��\�ɒB���_���ɉ��Ă����Ȍ�D���Ɉ��������Ȃ�B���D���͐ߎ��D���㊄���ߑ哈�A�䏢�A�ǐD�V��Ɏ������i�̔�r�I����Ȃ�ɍS��炸���I�Ȃ���̑������z�͑O�N����c�⌸����������O�S��\���~���Z���A�]���ėA�o���ɍ݂�Ă͌��D����㌎q�A�b�㌦�A�x�m���A�^�t�^�����邪���ɑ����D���Ƃ��ċ����ׂ����F�Ȃ����g�Ɍ�D���̗A�o�ɓw�ނ�̕�����͐����ɒl���ׂ����A�V��ɔ����ďk����Ƃ���A�o�ȐD���͏g�ɑ������͂�ŋߏ\�N�Ԃ�ʂ��ĉ��B�J��̓��N����吳�O�N�������Ă͏�ɑQ���̕�����H��ɂ߂Č����Ȃ锭�B�𐋂����茦�D���Ƃ̔�r�������Ύ��̔@���B �@
���e�i���Y�����@
�����e��D���̓��A��v�Ȃ�n�ʂ��ނ錦�Ȍ�D�A�ȐD�A���D�A�A�o���ȐD�̎l���I�ё����Y���ɑ��銄�����Z����Ɏ��̔@�����ʂ���B �@
�����D���̎�v�Ȃ�n�ʂ��ނ錦�Ȍ�D���y�іȐD���̑��\�z�ɑ���S�����͑O�\�̔@���Q���̌X������A����营�ꍟ���퐻�i�̌��ނ��Ӗ�������̂ɂ͔��ɗ��틤��̂ɉ��ėݔN�����̐Ղ�����������R�������@�ƉƂ������\�͂�����ɏ]�����͂��E�̗��퐻�i�ȊO�Ɍ���������M�m�����ׂ������O�\�ɂ͗���������A�o���D���y�іȖі��͖Ȗ��̌�D���͍ŋߎO�N�Ԃɉ��Ď��̔@�����\�z�S��������������B �@
�������ƌ��_ �@
���R�ۂ̖ѐD�@
���n�ɎR�ۖѐD�H�ꂠ��A�Y�z���������ɔ�嫂��K�͂��c�X����ׂ����̂���_�ɉ��č����ʂɉ��Ă͑��ɗނ������A���{���S���~�A�����O�\�ܖ��~�̊����g�D�ɂ��ĖȖуR�[�g�n�A�ȖуZ���A���ь�D�n���Y�������A���֔��o����A�J���c�������m�n���̐��i�ɔ䂵���i�c���������ь�D�i�͓��ɍD�]������Ɏ�����A�h�C�c���Z�\�C���`�D�@�l�\�]����O����\�C���`�D�@�l�\�]���L���i������H��̑Ԃ��������͉x�Ԃׂ��A�����@�Ƃ̉��v������ɐl�c��\���A�Ԗ��V�c�̒��A�S�ύ�����聠���Ə̂���D���̌��[����A�M�l�V�ɕ키�ď��߂ĐD���ɏb�т�p����Ɏ��葫���t�߂ɉ��Ă����ܖьo���̐D�����V���w�v���u�C�x���́w�V��s�Ɩ���юu���x�D�Ə̂��������͂ꂽ�肵���@���A�吳�́w�V��s�Ɖ��юu���x���֓��̋@�ƒn�ɑ��������͂��Ƃ��F��B �@
���i��̋C���@
�����̋@�Ƃ͑O�L�̔@�����n�����Ȍ�D���ɓ��ȐD������v���i�ƈׂ���W��A�����o��͑��A�����̗��n�ɏo������̎Y�z�̔����ߋ��s�A���É��V�Ɉ����A�o���Ɍ���w��ǑS�����l�֑����B�ȏ�͐����Ɉ˂鑫���@�Ƃ̊T�ς��q�ׂ�����̂Ȃ邪���Y��ԕ��ɐ����Ɋւ�����Ƃ̐����ɑ����@�ƉƂ��i��̋C���ɕx�ݏ�ɐV�@�����o���ɓw�ނ�̕�����͖��l�̔F�ނ鏊�ɂ��Đ����ɂ͋ː��A�ɐ��蓙�̋@�ƒn�Ƒ��אڂ����R�̋����ɑĖ��������ꂴ�肵�Ɉ���Ȃ����g�Ɍ��Ȍ�D���̐����ɗ͂�v��������k����Ƃ��ăC���h�A��m���ʂɗA�o����������čX�Ɉ�i�Ɛ��I�Ȃ�k���Ȃĕč����ʂɔ̘H���J���邪�@�����n�̋@�ƉƂ�����̗v���ɉ����Ĕ̘H�̊g����ӂ炴��̏Ƃ��Đ������ׂ��ߋ��ɑk��čl����������̏��N�������A���������g�p���ꎞ�e�Y�ƒn�����|����A�s�K�ɂ��ĉ��w�����̗��p�ɂ͏����[���̒m���o���Ȃ��O�ς̔��A�H���̊ȈՁA���i�̒���ɂ̂ݕ��S���đ����ڂ݂�̗]�n�Ȃ��肵�v�����炸���đe�������̕]������ڍ��𗈂���������@��ɉ��Č������H�Ɗw�Z�̑O�g������D�������N��z���̌����Ɉӂ�v����������炸���Č�N�ɉ��Ă͋ː��Ƌ��ɐV�������p�̐����ȂĖڂ����V�ɗA������ꂽ������͐悸�����n�ɉ��Ď��݁A���̎Y�n�V�ɕ키�̕��𐬂������@�����n�@�ƉƂ̌ւƈׂ��鏊�Ȃ�ׂ��B �@
���������ׂ����@
�@�Ƃ̑g�D�Ɏ���Ă͗A�o�����i�������Ă͏����������D���x�Ɉ˂���̂ɂ��čH��@�̎x�z������̋͂��ɖ�\�ɉ߂���������Ă���̂̏�Ԃ𐄂����ׂ��A�\�N�O�ɍ݂�Ă͋́X�l�\�~�̎�����ς݂���E�H�͒��ɋ@�����J���s�����ɐ��i���o�s���鎞�͓e�Ɋp�����������������ȂĎz�鏬�K�͂̋@���̐��ɂ߂đ��������̉^�p�֑̕����𗘗p���ċɓx�܂ŐM�p�𗔗p���r�����͎����̓�\�{�A�O�\�{�܂ł̎�����c�݂�����̂���A��x�s���Ɋׂ�鎞�̑Ō��̎S��͑z���ɗ]�肠��A���݂ɂ����Ă͑Q�����포�K�͂̋@��������������������S�R�ʖڂ���V����Ɏ��炸�A�@�����A���v�n�D�����̒����Ɉ˂�Đ����ɏ]�����̂Ȃ��ɔ�������͎��Ȃ̐}�Ĉӏ����ȂĎs��ɏo���K�ɍD�]���Ƃ�������̎s���ɂ͗ގ��̐��i�A��������Əo�������̋ύt��j�邪�@����Ɍ��錻�ۂȂ�Ɖ]���B���@���x�͒n������̗R������V��j�邱�Ɠ�����ׂ������i�̓�������̒��ߏ�z�錇�_����͋@�Ə�Ԃ̖��S���������ɉ��Ĉ�l�ɒl���ׂ����Ȃ�ׂ��B(��) �@
 �@
�@�����a�����̑�������ɂ��ā@
�{�e�́A����̖��͂����邽�ߑ����̗��j�A�Y�n�����A�����ʂ��Ē����̑��݂ɂ��Ď��M�҂Ȃ�̍l�����܂Ƃ߂������_���ł���B�����̑Ώۂ́A���a�����̓Ȗ،������s�ƁA�����Ő��D����Ă�����������ł���B �@
�͂��߂ɖ���Ƃ͑吳���ォ�珺�a�����ɂ����Ĉ�ʑ�O�̊Ԃő嗬�s���������t�@�b�V�����̈�ł���B�Ȗ،������s�́A���ē��{����ւ����̐��Y�n�Ƃ��āA���̖���y�����ꎞ�����������B�Ƃ��낪�A�����X�^�C���̗m�����ɂ�����̐��Y�́A�������ɐ��ނ��Ă��܂����B �@
���݁A�����ł͖��吶�n�D���Ă��Ȃ��B����̉��H��m��Z�p�҂��H���ł���B���̂܂܂��Ƒ�������͖Y�ꋎ���Ă��܂����낤�B���đ����s�̒��S�Y�ƂƂ��ĉh�����������p�I�ȉ��l������̂Ƃ��đ����āA�����Ȗ،��̕����̈�Ƃ��Ĉʒu�t����ꂽ��Ɗ���Ă���B�@
�ߔN����(1)�i���Ƃ��ăJ�W���A���ɒ����Ȃ����s������A���̂悤�Ȋ֘A�������s����Ă���(2)�B���̗��s�Őg�ɕt�����Ă����Ȓ����Ƃ����̂͌��ݍ���Ă�����̂ł͂Ȃ��A�Ò��ł�����ɒ��ڂ���Ă���̂��吳���ォ�珺�a�����̂��̂ŁA���傪���s���Ă�������̂��̂ł���B���͂��̗��s�����������ɖ���̑��݂�m�����B �@
����Ƃ͑吳���ォ�珺�a�����ɂ����Ĉ�ʑ�O�̊Ԃő嗬�s�����D���̈�ł���B����̓����͑N�₩�ȐF�ʂƁA��_�Ȗ͗l�ł���B����̖͗l�́A���{�Ɠ��̂��̂���A�[���E�f�R�܂ŕ��L�����R�Ȋ��o�������Ă���B���̂悤�Ȉӏ��̓Ɠ���������̖��͂Ƃ��đ����̌����҂ɂ���Č�������Ă����B �@
����͎��̏Z�ޓȖ،����ł����D����Ă���n���̗��j�Y�Ƃ̈�Ƃ��ċ������������B���������ݖ���̐��D�͂킸���ł������̗��j�����͍s���Ă�����̂̂��̑��݉��l�͌����č������̂Ƃ͂����Ȃ��B���đ����s�̒��S�Y�ƂƂ��Ĕ��B���Ă��������{�e�Ŏ��グ�邱�Ƃɂ���Ĕ��p�I�ȉ��l�̂�����̂Ƃ��đ����Ȗ،��̕����̈�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ��ƍl����B �@
�{�e�ł͎����Ȃ�̖���̖��͂����邽�ߗ��j�A�Y�n�����A�܂������ʂ��Ē����̑��݂ɂ��Ă��l���܂Ƃ߂����̂ŁA�����̑ΏۂƂȂ�̂͏��a�����̓Ȗ،������s�Ƃ����Ő��D����Ă�����������ɂ��Ăł���B�@
�g����h�Ƃ������O���̂��̂ɂ��������������B���̖��O�͎Y�n�ł��R���͒肩�łȂ��炵���B����͍]�ˎ���̒�����Ɍ���A���̂���̖���͎���a�т���Ƃ��ɏo����Ȃǂ��g���ĐD��ꂽ���n�ŏ�v�Ȏ��Ɨp�D���ł������B�V�ۂ̉��v�Ȍ�͓��ɏ����̊ԂɍL�����v���������B�j���Ƃ��g�ɕt���Ă���A���m�ł��������m�����i���A�����̐��ꒅ�Ƃ��Ă����悤�ł���B�܂����͐��ȂŁA�F�͒��E���E�l�ł������B �@
�ڂ��ׂ����̂Łu�ڐ�v�A�Ȑ��Łu�ڐ�v�A��������і͂����̂Łu����v�B�܂������킽�A���̈Ӗ������u蠒(����)�v�Ƃ�������p���āu蠒�@(�߂�����)�v�Ƃ��Ăꂽ�B�₪�Ė�������ɓ���Ɠs�s�ւ̔̔�������ɂȂ�A�z�㉮�O������X�Ȃǂł�������悤�ɂȂ�B����E�ۂȂǂ̔@�������������ŐD�����D���̑��̂��ӂƐD��ƌĂ�ł������u���v���u���v��A�z�����邽�ߏ����̈ߗ��ɂ͓K���łȂ��Ƃ������Ƃ������Ƃ��������p�����n�߂��Ƃ�����B���̢���壂Ƃ������͖����A�����́u���v�Ɛ勫�ŐD����Ƃ������Ƃ���勫�́u��v���Ƃ��Ė���Ɖ��߂�Ɏ������Ƃ����B ����Ƃ������O�͏���ӗ~���������Ă邽�߂̏��i���ŁA�u�߂�����v�ɍ�������^���铖�Ď��������悤�ɍl������B�@
�����s�Ŗ��傪���D����n�߂��͖̂���20�N���ł��邪����ܑ̌�Y�n(�ɐ���A�ː��A�����A�����q�A����)�̈�Ƃ��ėL���ɂȂ�̂͏��a7�N���납��ł���B����܂łɂ͑����̎��s���낪�Ȃ��ꂽ�B �@
�����������̊��� �@
�����Y�n�ɂ�1300�N�̐��D�̗��j�������p�ȎY�n�ł���ɂ��ւ�炸�l�X�Ȑ��D�i�Ɏ���o���A�����̓��Y�i�Ƃ������̂��Ȃ��A���Y�̐������r���[�Ȃ��̂ł������B��ꎟ���E���̍D�i�C�Œ��@(5)�ɂ��D���̐��Y���������Ă����������������A���̕s���ɓ���Ə�����F�����̂�����̂������s��̐M���������ԕi�������A�����X�Ȃǂ͑����̐��i����舵��Ȃ����Ƃɂ���ď���҂Ɉ��S����^����悤�ɂ܂łȂ��Ă��܂����B���̏�Ԃ�Ŕj���邽�ߏ��a2�N�����D�����Ƒg���̎��@�ƉƖΖؕx��𒆐S�Ɂu���������v�𗧂��オ�����B�Ζؕx��͂���܂ł̐��Y�̐��������������Ԍ`�D���ł���������𑫗��̓��Y�i�ɂ��邱�Ƃɂ���(6)�B �@
���������͗l�X�ȍH�v�ƌ������d�˂āu�����{����v������������B�܂��A���D����̔��Ɏ���܂ł̑S�Ă̍H���ɋK���݂��A�e�������������������܂����B���������D�������s�E���̖≮�A�S�ݓX�A�����X�֎��₵�Ă��f�������ł��������A�M�S�Ȗ����ɑ��A���s�̐D���≮�u������v���v������B�������̂ɂ��Ắu�����v���t���Ȃ����̂ɕς���ׂ��ƑE�߂��B����ɑ������͕i���̌���A�v�V��(8)������A�e�ȐD������邱�Ƃ���A���ꂪ�{���̑�������ł���Ƃ����Ӗ������߁u�����{����v���a�������̂ł������B �@
�����ď��a2�N�H�ɋ��s�Œ��E��I��J����A����ɓ����̎O�z�S�ݓX�����������a2�N�Ɂu�����{����v��������J�����B�̔������͂��Ă̑����D�����e�����O���ɏ��܂ŋ�J���d�˂��B�܂������Y�n�͑S���̐D���Y�n�ɐ悪���āA��`�|�X�^�[���ő���ɗ��p�����B����ꗬ�̓��{��ƁE���l��ƁE�m��ƁE�}�ĉ�(9)�Ɉ˗����A���_���ł����ꂽ�|�X�^�[���쐬�����B���f���́A�ꗬ�̏��D�Ɉ˗������B�܂��G�t������ʂɂ����A�傢�ɗ��p���ꂽ(10)�B�����đS���̖≮�E�S�ݓX�̊W�҂����n���@�ɏ��҂��A���Y�H���������邱�Ƃɂ��i���̊m������F�������A���̋A��ɓ����E�S�{�삩�瓌���̉̕�����▾�����A�ɓ��̉���A���ɂ͓����p���V�̏M�V�тɂ����҂����B �@
��ʑ�O�ɑ��đ����D�����Ƒg���͏��������G���u�����Ǝ�v�̕ҏW�����c�e�q�Ƌ��ɑ�������̍��k����Â����̗l�q���L�^�������q��̔������B�Q���҂́A�o�D�A��ƁA��ƁA���e�t�A�����W�҂Ȃǂœ����̗��s�̐�[�Ɉʒu����l�X���W�܂����B�����̗L���l���N�p�������̊��͑傫�Ȑ�`�͂����������Ƃł��낤(11)�B�������ď��a2�N�ɔ����������������́A�����Y�n�̒��S�I���݂ƂȂ����Ƃ�����̐��i�ɗ͂𒍂����B���̌��ʂ͌����ɉԊJ�����B�܂��A���Ԃł͖��傪�嗬�s���A�v�X��������͗͂�t�����B���̌���l�������g�p�������́A�����A�⎅��D�荞���̂�d�グ�ɏk�݉��H�Ȃǂ��{�����Z�[�~���H����Ȃǂ����ݏo�����B���̒��ł����ɗ͂���ꂽ���̂Ƃ��āu���I����(12)�v���������B�����͑�O�̐l�C���B���Y���O���ɏ��A�l�C���o�āA��ʑ�O�̕��i���̒n�ʂɒ���������ł������B���̗��R�Ƃ��Ė��傪�����ł��������Ƃ���������B���������i�̒ቺ�͕i���̒ቺ���������A�@�ƉƁA�≮�A�S�ݓX�O�҂̊Ԃɕԕi���𒆐S�Ƃ��Ă����Ε����������N�������B���̂��Ƃ͑����Y�n�����łȂ�����Y�n�̑S�ĂɌ��������Ƃ������B�l�X�Ȗ�肪�N����x�ɐV���ȉ���������āA���̂��тɓw�͂����Ă��������͑S���̖���11�Y�n�̂����g�b�v�ɂȂ�A���ʁE�i���E�ӏ��̂�����ɂ����Ă��傫�Ȑl�C����Ɏ������B�����đ����������̏��a2�N����5�N�قǂŋ}�������A��r�I�Z���ԂŐi�W���݂��̂ł������B �@
�����̊����ɂƂ��Č������Ȃ��������݂͎���3�ł���B �@
�����]�� �@
�������͂Ɏ��{�������̂ɁA�e�W�U�n�̎�����苁�]��������B�����E���E���s�E���É��ȂǑS���e�n�̏W�U�n�ŁA����P�ʂ̋��]���x�X�J�Â����B�����͂˂ɖZ�����A���Q�������{�̐D���͉���̊e�@���̎�l���炪���C�~��݂ŒS���ŁA��ԂŎ��X�ƈړ����Ă������B���̔M�S�ȋ��]�����́A�e�W�U�n�̈ӌ��E�����N�I�m�ɔc�����邱�Ƃ��\�ɂ��A�����ɂ��������̔��B�ɑ傫�ȗ͂ƂȂ����B �@
�����p�� �@
���p���Ƃ����̂͋@�ƉƂƖ≮�̒��Ԃɗ����A���i�̔�����������̂ł���B�������A�@�ƉƂƂ̎���W�͌p����K�v�Ƃ��A�ꎞ�I�Ȏ���W�͔��p�Ƃ͌���Ȃ��B�@�ƉƂ��琻�i���W�߁A�W�U�n�֔��p����B�܂��A�W�U�n�������E�f�p�[�g���璍�����Đ��i�����Ƌ��ɁA���߂ɂӂ��킵���F�A���A���s���l�����A���i�̎w�������邱�Ƃ��d�v�ȋƖ��ł���B���p���̑��݂ɂ���āA�@�ƉƂ͊e�W�U�n�ɏo�������s�����������Ԃ��Ȃ��A���D�ɐ�O���邱�Ƃ��ł����B �@
������̐}�ĉƂ��� �@
����̈ӏ��Ɋւ���L���͖��T�̂悤�Ɂw�����D���T��x�Ɍf�ڂ���Ă���B���M�҂͋��s�E���E�����E���É��̏W�U�n�̐l�X�Ƒ����̐l�X�ł������B�ނ�͂��݂��̓y�n���s�������āA���N�A���T�����T�C�N���ō�Ƃ����Ă���ɂ��ւ�炸�A��Ƃ��ē����ӏ��͑��݂��Ȃ��B���������}�Ă̐���1300����z��������͂��Ƃ��ē��������Ȃ������B���͂��̑��ɂ��������̐}�ďW��3�A4���Ȗ،��@�ۋZ�p�x���Z���^�[�ɂ������̂ő����͌v��m��Ȃ��B�܂��A����͑����Y�n�����̒����Ȃ̂ŁA���Y�n���܂߂���ǂ�قǂ̈ӏ����o�Ă���̂��\�z�����Ȃ��B����̈ӏ��̃A�C�f�A�͒��m��Ȃ��悤���B����̐}�ĉƂ́A��������ɂ�������(14)�A�����⋞�s���甃�����@���������B�܂��A�吳����̖�������A���a�����ɂ����āA���s����}�ĉƂ������ֈڏZ���Ă��邱�Ƃ��������������B���s�A�����A�����̂��̂������荇���đ�������̑��ʂȕ�������Ă������Ǝv���Βꂪ�����Ȃ��̂������ł���B�@
�펞�����ґł��Ȃ��Ȃ�����A�������������ꂽ��ƁA���吻�D�͍���őS���s���Ă��Ȃ��������낤�Ɨ\�z���Ă����B�������A�����̐V���Ȃǂ��������ʂނ��낱�̎����ɐ��D���ꂽ����̂ق����Ɠ��ȕ��͋C�������Ă��邱�Ƃ����������B �@
�����푈���N������{�͎���ɐ푈�̐F��Z�����Ă������B�����āA�o�ϓ������{�i�����A�����D���Ƃ͏��X�Ɍo�c��ƂȂ��Ă������B����͖���̌��������i�s���ɂȂ�������ł���B�A���̐����A�����A���D�@�B�V�E���݂̋֎~�A�������ȏ�̎��g�p�̋֎~�A�܂����̎��𑼐l�ɏ��n���邱�Ƃ��ւ���ꂽ�B���̂��ߏ����ȋ@���͖����Ȃ��Ă�����(15) �B���������ɂ͌o�c����ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��B�Ƃ����̂́A����̃��C�o���ł������Z���A���X�A�ȐD���Ȃǂ����ꂼ�ꌴ���ł���ȉԁE�r�т��A���������Ď��R�ɐ��Y�o���Ȃ��Ȃ�������ł���B �@
���̍��̓��{�͖ȉԂƗr�т�A���i�ɗ����Ă����̂ł���B����̌����͍��Y�̌��ł��������߂��炭�͑��̐��D�i��K�ڂɕ����̗��s��Ɛ�ł���(16)�B�������A���ƂȂ����̂����a15�N�ɔ��߂��ꂽ�u���E���֗߁v���Ɓu���ʕi�������̔������K���v�ł������B���̚��ʕi�������̔������K���ɂ́A���G�H�͗l�A�D�G�H�͗l�A�h�J�������́A�Ԃ�D�̐��i�������̔����֎~���ꂽ�B����͔̔����֎~����邱�Ƃ͂Ȃ��������A�ꔽ30�~�ȏ�̂��́A������⎅����ꂽ���͔̂̔����ł��Ȃ������B�����w�����@�ƉƂ͕��a�Y�ƂƂ��Ė��吻�D�𑱂�����̂ƁA�R���i�삷����̂Ƃɂ킩�ꂽ�B����̕���F�͍�����w�肳��A����ɂ͐��i�ԍ����݂���ꂽ�B �@
���E���֗߂̋K���������@�ƒn�͈ޏk���A�Â��n���Ȗ���𑽂����D�����B���̌��ʏW�U�n����́u��薺�͖��炵���A�N���͔N���炵���A�����������N�����āv�ƁA���߂��������������B���̂悤�Ȉ˗������@�ƒn�́u���E���֗߂ň؏k�����H�̕����E�ɖ��N�ŗ͋����V�̐��ɑ�����V�������𒍓����悤�v�A�u�Ԗ͗l�ł��P���ȕ��A���R�A�T�b�A�s�����p�B�܂��R�ɐV����^�������̂��ǂ��̂ł́v�u���邢�e�L�p�L�Ƃ������̂��ǂ��v�Ȃǁg�ȑf�̔��h�ɏd�_�������ĐF�������������N�Ȃ��̂̐��D�ɓw�߂�(17)�B �@
���̕��͂ɓK�����Ă���}�Ă����邱�Ƃ��ł����B���a9�N�̂��̂Ɣ�r����Ə��a15�N�̐}�Ăׂ͍��ȕ`���͂Ȃ��Ȃ��_�Ƀf�t�H��������Ă��邱�Ƃ��킩��B��������邩�炱���H�v���Â炵�ėǂ��i������낤�Ƃ��Ă����悤���B �@
�̔��֎~�ƂȂ��Ă��������E�⎅����̖��傪���E���֗߂̗�O�ɂȂ����B����͖��傪�ƒ�w�l�ƊW�̐[�����p�D���ł���A���E���֗߂ɂ��@�ې��i�̃X�g�b�N���ꉭ�ܐ疜�~������A�e�������Ǝ҂ւ̎��͍X���̋~�ϖ@�Ƃ��ė�O���ꂽ�B�܂��A���E�⎅����ł�����������悤��5�~�A10�~�̂悤�Ȃ��̂Ȃ��ґ�i�Ƃ͌���Ȃ��ł��낤�B�Ƃ������Ƃ���ł������B����͐펞���̂悤�Ȕ�펞�ɂł����D�����قǑ�O�ɂƂ��Ă͌������Ƃ��ł��Ȃ��ߗ��i�������悤�ł���B �@
���āA���̍��̑��������͏��a15�N7��18�����猎���܂Ő�����~�ɒǂ����܂�A���a16�N���H��b�Ɂu���U�F�\�����v���o���A���悻40�N�����������D�����Ƒg���̊������~�����B���̌�D���H�ꂾ�����{�݂͌R���ߗ����i���s�@�̕��i�����邱�ƂɂȂ�A�����ł̓p���V���[�g�D���Ă��������ł���B�܂��A�D�@���͓S�����Ƃ��Ď���ꂽ�B�@
���ђn��ł͂܂��ɐ���n�������̎Y�n������T�ԑ������D���n�߂�B����͈ɐ���̕i�����ǂ����߂ŁA����҂͂܂��ǎ��̂��̂���w������̂ł��̔N�̗��s�X����m�邱�Ƃ��o����̂��B�܂��͐V���i�̌���������o���G�߂̔��N�O����n�܂�B�V�����}�Ăƒn���̊�b�I�����Ə�����i�߁A���D�i�̔��\�����ċ�̉�����B�����Ď���A��`�B�G�ߐD���i�]��ւƑ�����ʂɔ̔������(19)�B �@
����͕��G�ȕ��Ɛ��Ő��D����Ă���B�D���Ƃ����̂͂��̓��̃v�����W�܂�Ȃ��Ƃł��Ȃ��B�����̃v�������˂Ă����̂��@�����B����͗l�X�ȉ��������o�ď��߂ĐD��n�߂邱�Ƃ��ł���̂��B �@
����̓����͂����ꂽ���ł���B����́u�����D(�ق�������)�v�Ƃ������@�ɂ���Ăł���B�����D�Ƃ����̂͐��o�����������D���^���ŕ�����߂Ă����A���D�������������Ȃ���D��̂ŁA�����D�Ƃ����B���̋Z�p�̊J���̂������Ŗ���ׂ͍��ŗl�X�ȕ���D��o�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�o���������R���g�������̂p�A�o�A�܂ǂ��炩�������R���̂��̂��p�Ƃ����B�����p�R�͑�������̓����ł���Ƃ����B���D��Ƃ����P���ȐD����ł������^��������邱�Ƃŕ��G�Ȗ͗l��D��o�����Ƃɐ��������B �@
����ł͊ȒP�ɉ����D�̍H�����݂Ă݂悤�B�܂��@�����}�Ă̊�]��}�ĉ��Ɉ˗��B���̐}�Ă����Ɍ^�����^��(20)���쐬�B���ɉ��D��͐D�@�ōs���B���o���ĉ��D�����o���Ɍ^���������B���̍H�������H�ƌĂԁB�����L�тȂ��悤�ɖ������Ŏ������点��B�F����߂鏇�͔Z���F���甖���F�ł���B�F���������قnj^���̖�����������B���̎��̐����͉��w���������蕲���������Џ�̂��̂�p����B�^���߂��������̂�����Q�����ď����B���̂Ƃ�������Ђ����C�ŗn���Ď�����{��{�ɕ�����A���ɂ͐������t���B �@
�������Đ��D�H���i�ށB�͐D�@�Ǝ�@�ł͗͐D�@�̂ق����D��ڂ̍������Ȃ��i���ł��ɂ��������d�グ��̂Ɍ����Ă���B����̐��n�͔����B����ɂ���Ɣ��G�肪�U���U���Ƃ��Ă�����d�����Ȃ��Ă��܂�(21)�B��@�ł̐��D�͑��i�폭�ʐ��Y�̔����Ώۂł���A���@�ł��邱�Ƃ������B �@
���̌㐮���A���������o�Ċe�Y�n�ւƏo�ׂ���Ă����B�@
�����m�����Ƃ��A���݂������͌Ò�����ł������B���ĎY�n�ł������ꏊ�ł͖���͋L�O�ق⎑���قɔ[�߂��Ă����B����͒����̃u�[�����N����܂Ŏ̂Ă��A�Ò����₽�̒��Ŗ����Ă���A���܂蒍�ڂ���Ă��Ȃ��������̂ł���B����͖{���ƋU���Đl���������Ƃ������A���Ԗ��E�ł悭�����Ă������A�����j����A�F������Ƃ��������C���[�W�����鎖�A�z�c�┼�V�A���i���Ƃ��ē��ɒ��������̂ł͂Ȃ��Ƃ������B��������ĕ\�Ɨ������肩�������x�������A�ڂ�ڂ�ɂȂ�܂ŕz�Ƃ��Ďg���Ă������炾�B �@
�����ڂ���Ă��闝�R�͈�̂Ȃ�Ȃ̂��B�������d�v�ł���B����͌��ݎ��A���\�̐l�������Ⴂ���ɗ��s�����D���ł��邪�A���݂̏��������ɂ��������͂�^���Ă���B��������̎�����͗��s��q���ɂƂ炦���N�G�߂��ƂɐV�����ӏ����l�Ă���Ă����B���s�x��̂��̂͌��l�������������A�V�������̂͌����ō�������ꂽ�B�܂�A���i�폭�ʐ��Y���������B���̕��͖ڗ����ߖ��x���̕���g�ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ��B�ɒ[�Ȍ�������������Ȃ�����x�����炻�ꂫ��̎g���̂Ăɋ߂��悤�Ȓ����Ȃ̂�������Ȃ��B����Ӗ��ґ�ł���B���̂��Ƃ͌��݂̃t�@�b�V�����Ǝ����Ƃ��낪����A�Ⴂ�l�̃t�@�b�V�����ɑ���l���ɂ��߂��悤�Ɏv���B �@
����̖��͂Ƃ����̂͑��ʂȈӏ��ł���B����͊m�M�ł���B�������s�������ʖ���̐����҂���ԗ͂����Ă����͈̂ӏ��ł������悤�Ɋ�����B�܂��A�����̖��匤���ҒB����_�ŐF�ʂ��N�₩�ł��邱�Ƃ�����̖��͂ł��낤�ƌ���Ă���B�������A���͑��̌����҂Ƃ͈Ⴂ���D�̌��������邱�Ƃ͍����߂Ă̎��ł���A�܂����i�A�����𒅂Đ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��B����Ȏ�������ɖ��͂������Ă���B����͖���̈ӏ��̑f���炵�������ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B�܂��A����̖��͂Ƃ������̂��ӏ������ł͂Ȃ��͂����B�X�c���܂̒����̒��� ����̐��i���L����Ă���B����́A�g���X�����h�Ƃ��g���߂��h�Ƃ����������t�ł���B �@
2005�N�����s�����p�قɂāu��������̉�������v�W���s��ꂽ�B���̓W����œW���{�����e�B�A�ɎQ�������B���̍ۖ���Ɏ��ۂɐG�ꒅ�邱�Ƃ��o�����B�܂��A�����g�ɕt���������𑽂����邱�Ƃ��ł����B������O�̂��ƂȂ̂����A��͂蒅���͒��邽�߂ɍ��ꂽ���̂Ȃ̂��B�W�������Ă��鎞�ɈÂ��F�ʂ̂��̂�ŁX���������̂��̂����������肱���{���ɒ��Ă����l�������̂��낤���Ƌ^���Ă��܂������A�����A���ۂɐl���g�ɓZ���ƁA�ƂĂ����͋C���ǂ����̂ɂȂ����B����̓W����ł͏��q�������g�ɕt���Ă������A�ޏ��B�ɂƂ��Ă��������Ă����B���炵���ĉ₩�Ŗ���𒅂�܂Ŋw�����𒅂Ă����ޏ��B�̕��͋C���K���b�ƕς����悤�Ȃ��������B�����Ƃ�Ƃ����悤�ȕ��͋C�Ŕ��������̂ł������B����̖��͂͏����̖��͂�����ɏグ��͂������Ă���Ƃ���Ȃ̂�������Ȃ��B �@
����𒅂������̓s�^�b�Ɛg�̂ɓ\��������ł���A�܂��������n�Ȃ̂Ōy���B�����g�ɂ���Ɛg�̂̌`�ɉ����ė��̓I�ɂȂ�A�������Ɠ��̌�����A���̉����Ŗ��邭�Ȃ�����Â��Ȃ����肵�Ĉ�̐F�ł��l�X�ȐF�������B�����Œ����艮�O�֏o���ق������{���������Ȃ����B�F�T�̂悤�Ȑ����͔��F���������肵�Ă��āA�ׂ�������@�ׂɒ����̏�ɕ\�����Ƃ��ł���B����͌^���ŕ��ׂ�ꂽ���ɕ�����߂ĐD���Ă����B���͂ǂ����Ă�����Ă��܂��B�������A�������邱�Ƃŗ��̓I�Ɍ�����B�{�T�{�T�Ƃ������������邪���ꂪ�t�ɏ_�炩��������B �@
����ɂ͍����_�����Ȃ��e���݂₷���B����͈�ʑ�O�����Ƃ��č���Ă������߂ł��낤�B���݂̎������̑�����������ʑ�O�ɂ�����B��������傪���݂����͓I�Ɏv����͓̂�����O�̂��ƂȂ̂�������Ȃ��B�����Ŏ�ɓ���₷���Ƃ������Ƃ͏����ɂƂ��Ĉ�ԑ�ȂƂ���ł��낤�B�������Ȃɂ�����͉₩�Ȃ̂��B���i���ŋC�y�ɒ����邱�Ƃ���A���R�ɖ���̈ӏ������R�Ȃ��̂ɂȂ����̂��낤�B�܂��A����̂悤�ȉ̂��镁�i�������ꂽ���R�͏��̎q�ɂ͂��킢���i�D�����������Ƃ����e�S�ƁA�������g�̏���Y��ł������Ƃ����C�������B���������R�ɂ����������邽�߂ɏo���������ł���Ǝv���B �@
�֓���k�Ђ��N���A�吳�f���N���V�[���N���萢�Ԃ̊��o���V�����Ȃ��Ă����A����������I�Ɋ������͂��߂�悤�ɂȂ����B���R�ɂł���悤�ɂȂ��������̉�����A����Ȃ��̂�����ɔ��f����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B����̕��ɂ͏��X�펯�j��̂悤�ȕ��͋C������B���ݏa�J��������������̂悤�ȁB �@
�������̂����݂̉�X�̐����ɂ�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���������̐l�������𒅂Ă�������ɐ��ꂽ���傾���猻�݂̂悤�Ȑ��̒��Ŗ���͐������Ȃ��B���Ė��傪���������ɂ͖߂ꂻ���ɂȂ��B����̗���ɂ͋t�炦�Ȃ����A�����ɍl����ƋZ�p�҈琬�ȂǗl�X�Ȗ�肪��������B �@
�����s�A�Ȗ،��ɂƂ��Ă̖���Ƃ͈�̂ǂ��������݂Ȃ̂ł��낤���B����͍����̃u�[���ɂ̂��Ē��������̍ޗ��ƂȂ���̂Ȃ̂ł��낤���B���̃u�[���͂��܂ő����̂ł��낤���B�ꎞ�̂��̂ŏI����Ă��܂��̂ł͂Ȃ��̂��낤���B����͓Ȗ،��ɂƂ��ĂȂ�����ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���B���̃u�[������ɂ܂��܂�������g�ɕt����l������������Ǝv���B���݂̂悤�ȃt�@�b�V�����̑��l���̎���ɖڂ̊o�߂�悤�Ȗ���͎������悤�Ɏv���̂��B�u�[���ŏI��点�邱�ƂȂ��Ȗ،��̕����̈�Ƃ��Ĉ����ׂ����B �@
�Ȗ،��Ŗ��傪�h���Ă������オ�����������B�����āA����͔������Ƃ������Ƃ��Ƃ肠���Ă����Ε����ɂȂ肤��͂����ƍl����B����҂��x���Ă������������邪�A�����̂܂��߂ȋ@�������̑��݂�m��������ɂ͔ނ�̓w�͂��Ȃ�������ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���݂̉�X�̎g���͔ނ���̂��n���̕������Ɉ������`���Ă������Ƃł���B���̘_�������̎g���̈ꕔ�ɂȂꂽ��K���ł���B�@
1�@�{�e�ł̒����Ƃ́A�m���ɑ���a���̂��ƁB �@
2�@�˓`�ЂŔ��s����Ă���u�j�h�l�n�m�n�P�v�ȂǁA�Ⴂ������ΏۂƂ������킢�炵�����̂������B �@
3�@���̘_���͕���19�N1���Ɏ��M�����C�m�_���u��������̗��j�ƈӏ��v�̗v�ł���B �@
4�@����ڋߐ������u�㊪�������Y�@�ҁ@�������s��1979�N / �u���{�̐D���v�k���N�Y�@������1988�N / �u���M�F�R���N�V�����{��N���V�b�N���p�ُ����i�W�₩�Ȕ��吳�̒������[�h�v�ďC�{��N���V�b�N���p�فE�{��s�����U�����ƒc�@�Ҍ|䇎�1996�N��� �@
5�@���@�Ƃ́A�l���@������D�@�ƈ�C���̐D�����_�ċ@��D��V�X�e���ŁA�{�ƂƂ��Ă�����̂����邪�_�Ƃ̕��Ƃł��邱�Ƃ����������B �@
6�@�w�ߑ㑫���s�j��ʎj�ҋߑ�E�O�`����x�����s�j�Ҏ[�ψ���@�ґ����s1978�N �@
7�@�w�����D����`�W�u���тĂ䂭���D�E�v�x��� �@
8�@���̊v�V���Ƃ́A�㋉���Ōo���ɏ㓙���a����p�������ƁA�o���ւ̌^���߂Ɏђ����p���A��蕡�G�Ȉӏ����\�ɂ������ƁA�Ȃǂ��w�E����Ă���B �@
9�@���{��Ƃ͖k��P�x�E�ɓ��[���E�L�ؐ����E������O�Y�E�R��G��E�����쐴�A���������Ċ����ꍲ�q��m��Ƃ͒��J�쏸�E�쓇����Y�l�X�ȃ|�X�^�[�̃f�U�C�����肪�������c�k�G�̂��̂�����B �@
10�@�|�X�^�[����̑����͑����s�����p�ق��������Ă��� �@
11�@�w�����D�������x�����D�����Ƒg�����s�@�����Ǝ�V���@���c�e�q�ҁ@���a10�N���s �@
12�@���a��N�ɖΖؕx��𒆐S�ɊJ�����ꂽ����ŏ]���̏\���Z�ł͂Ȃ���\��Z�ȏ�Ő��D���������Ȃ��̂ł������B �@
13�@���������V�����a���N�O���\�O�� �@
14�@�u���哝���@�܂��i�����ǁ@�������c��v��� �@
�����ŁA�����Y�n�̐}�ĉƂł��������������ɂ��ď����G��Ă����B �@
�u���ѐD���}�Ă̕ϑJ�@�����s�}�ĉƁ@���������v�ɂ��ėv�_�́A�����ł���B �@
��A ���ђn���̐}�Ă̌Â��A�S���\�N�̗��j�����邪�A���m�ȋL�^�Ƃ��Ă͎c���Ă��Ȃ��B �@
��A ���͗l�����łȂ���a�G����D�}�Ăɉ��p�����ː��̐}�ĉƂ̓Ƒn�I�Ȍ������ӏ��}�ĊE�Ɋv�V�������炵�A�ː��D�����e�����������B �@
��A ������������͐V�i�̋@�B�����p�������R�Ȑ}�Ă̐i���Ɖ��B����̃A�[���k�{�I�[�����͂��߂Ƃ���V�}�Ă̗����A����Ō��Ԏ��Ȃǂ̕��Ò��̓o��Ȃǎ�L���Ȑ}�Ă��o�ꂵ���B �@
��A �������ɋ��s�}�ċ���̗���������O�V�����̐s�͂ɂ�蒅�ڐ}�Ă̐U�����}��ꂽ�B �@
��A ���ђn��̐}�ĐU���ɑ����ɂ����錧���}�Ē��������傫���v�������B �@
��A ���т̋@�ƒn���S�����w�̑�Y�n�ƂȂ����̂��ӏ��}�ĉƂ̌��т���ł���B �@
��A ����(���a�l�N���_)�A���ђn���ňӏ��}�ĉƂƂ��Đ��ɏ]�����Ă���҂͋�\�]���ł���B �@
(���a�l�N�w���D�}�ĕϑJ�j�x���甲��) �@
������������ �@
�{�����Ώ��O�Y�B�����̕č����o�O�Y�̎O�j�Ƃ��Ė�����\�N(1887)�N�l������ɐ����B���O�\���N�����H�Ɗw�Z���ƌ�B�}�ĉƂ��u���B�l�\��N�������̐D�H��ɂ����Ė�l�N�Ԑ}�Ă̌����𑱂��A�����̐}�ĉƓ��c���O���ƌ𗬂���B�ꎞ���s�ɋ����ڂ��A���s�}�ċ���̎劲����O�V���̎w�����A���ڐ}�Ă̌�����i�߂�B�A����͍���O�V���������ђn��ւ̐}�ĕ��y�ւ̎��g�݂ɋ��͂��A�����y�ї��ђn��̒��ڐ}�ĐU���ɑ傢�ɍv������B�֓���ꗬ�̐}�ĉƂƂ��Đ}�ĊE�̔��W����ƌ�i�̎w���ɐs�����A�����}�ĉƂ̒c�̂ł��铯�m��̌ږ�ƂȂ�B���c����A�n�Ӊ̐�A�k��ĕ�A�g��`���A�F�����A�{�c�O��A�����ōg�����w���B�@�v�N�s�� �@
�ȏ�u���ѐD���}�ĉƂ̕ϑJ�@�����j�}�ĉƁ@���������v(���a�l�N�w���D�}�ĕϑJ�j�x����Q�l)�a�c�݂ǂ莁������ �@
15�@��6�Ɠ������ �@
16�@���������V�����a�\�O�N�ꌎ�\�� / �u�ƒ�@����̐l�C���Ė���̐i�R���b�p �����Ԑ�������v�]�@�����̉����闼�т̒n(��)�v��� �@
17�@���������V�����a�\�ܔN�㌎�O�� / �u���邭�E�����̂Ȃ���̎Ȃ��R�̕��������ꂽ�A����̐V�̐��Łv��� �@
18�@���������V�����a�\�ܔN�㌎��\�Z�� / �u�ƒ�^���E���֗߂ɗ�O�@���p�D���Ȃ�g���Ɓh�A���⎅�������p������x�́c�v��� �@
19 �w�Y�n�̏t�ďH�~�x�ɓ����ҁ@�����D�����Ƒg���@���a�\��N���s��� �@
20�@���̌^���͎O�d����x�R���̂��̂Řa�����d�˂Ċ`�a�Ő��߂�ꂽ���́B�^�����ĊJ���������ɂ͎��Ŏт��\��t���Ă���B �@
21�@����t���k �u���̐��M�v�X�c���ܒ��@�u�k��1961�N �@
22�@�u�����̐��M�v�X�c���ܒ��@���|�t�H�V��1954�N�@
 �@
�@���D�P�_�Ё@
1200�N�]�̋@��Ƃ��Ă̗��j���������B���̑����ɋ@�D�̐_�Ђ��Ȃ����ƂɋC�Â��A��i2�N(1705�N)�����ˎ�ł������˓c�������A�ɐ��_�{�̒����ł���V�Ƒ�_(���܂Ă炷�����݂���)�̌��̈߂�D���Ă����Ƃ����_���D�@�_��(����͂Ƃ�͂��ǂ̂���)�̐D�t�A�V��g��(���߂݂̂ق��݂̂���)�ƐD���A�V����X�P��(���߂̂₿���Ђ߂݂̂���)�̓����݂̑����s��4���ڂɂ��锪�_�_�Ђ֍��J�B���̌�A����12�N(1879�N)�@�_�R(�͂����݂��)(���݂̐D�P�R)�̒����ɐD�P�_�Ђ�J�{�����B
���N�̖���13�N�A�Ђɑ������{�̂܂܂ƂȂ��Ă������A���a8�N�c���q�a����~�a(���݂̏�c�É�)�������A�����̑����D�����Ƒg���g���̓a���������̐擱�ɂ��s������݂ŐV�Гa�̌����ɂ�����A���a12�N5���Ɍ��݂̐D�P�R�Ɋ����A�J�{�����B
����16�N6���A�Гa�A�_�y�a�A�Ж����A�萅�ɂ����̓o�^�L�`�������ƂȂ�B
�������D�P�_�Ђ������т̐_�ЂƉ]����R��
���Ր_�́A�@�D(�͂�����)�������ǂ�w�V��g���x�ƐD���ł���w�V����X�P���x�̓̐_�l�ł��B���̓̐_�l�͋������ĐD��(���n)��D���āA�V�Ƒ��_�Ɍ��サ���Ƃ����Ă��܂��B
�D���́A�o��(���Ă���)�ƈ�(�悱����)���D�肠���ĐD��(���n)�ƂȂ邱�Ƃ���A�j����l�̐_�l�����Ր_�Ƃ��鉏���т̐_�ЂƂ�����悤�ɂȂ�܂����B
�܂��A�D��������D�@(�������)��@�B�́A�S�łł��Ă�����̂��������Ƃ���S�Y�Ƃ̐_�l�Ƃ����7�̂��������ԎY�ƐU���Ɖ����т̐_�ЂƂ����Ă���܂��B�@
 �@
�@�ɐ������
����f�ނƂ�������̕��D���̑��̂ł��邪�A�������D���ł��O�O�n�A������Ƃ͋�ʂ��Čď̂��ꂽ�B�ꌹ�͓V������(1781-1788)�o���̐��������A���̐D�n�̖ڂׂ̍����A�k��������A�u�ڐ�v�u�ڐ�v�Ƃ���ꂽ�̂��]�a���āu�߂�����v�ɂȂ����Ƃ�����������B���̂ӂ邳�Ƃ͊֓��n���̈ɐ���A�����A�ː��A�����A�є\�ȂǂŁA�����͌Â�����̗{�\�ƐD���̎Y�n�ł������B�@
�ɐ���ł́A����N�O����_�Ƃ̐l�X���_�Պ��𗘗p���Ď��Ɨp�Ƃ��ĐD�����n�܂����Ɠ`�����A�ɐ���D���̖����L�܂����̂́A��250�N�O�̋��ہE�����N�ԂƂ�����B���Ƃ��Ƃ͑��D��(�ӂƂ�)�ƌĂ�Ă���A�l�X�͎萻�����l��(������)�A�ʎ�(�߂̂��鑾������)�����A����𑐍��ؔ�Ő��ߐ��D�����B���̍��ɂ͑��D��̎s�������A������̏M�ւō]�˂֏o�ׂ���Ă����B�@
���D��́A��D��̂�������Ƃ����������Əa���̂���ȕ��̔z�F�������Ă��āA���̏�n������v�ł��������߁A�������ڕ��Ƃ��ď����̊Ԃŗ��s�����B�l�C�����܂������Ƃŏ��i�p�Ƃ��Đ���ɐ��Y�����悤�ɂȂ�A�]�˂��͂��ߑ��⋞�s�ɂ܂ōL�܂����B����Ȓ��Ŏ����E�����E�@���Ȃǂ��܂��܂Ȑ��Ǝ҂�������A�����ȍ~�͈ɐ������(���邢�͖���)�ƂȂ��āA�n����D����ɗl�X�ȍH�v�������A���D��Ƃ͕��������O�ς��قȂ錦�D����D��o���� �B�@
���ꂪ�����̍D�]���A�ː��A�����A�����q�ł������D��悤�ɂȂ������A�Ő����̈ɐ������͔N�Y130����(��70���~)���L�^���A���{��̖��吶�Y�ʂ��ւ����B��������ɑ��D�肩�����Ɉڂ�ς���Ă������̂Ɠ����悤�ɁA����܂ł͎ȕ����嗬�ł��������A���F��D�̋Z�p������ɐi������ɂ�āA�吳�ȍ~�͒����R�E�ܑ��R�E����R�E���R�E�����R�ȂǁA���݂̈ɐ����R�p������Ă��邳�܂��܂��R�̋Z�@���Y�ݏo����A����炪���G�����A�͗l�����l�Ă����悤�ɂȂ����B�@
�D�@��������@���獂�@�Ɉڂ��Ă������̂����̎����ŁA���������ɂ͗͐D�@����������邪�A�܂����@�ł̎�D�肪���|�I�ɑ��������B�܂��A�R�Z�@�̔��B�ƌĉ�����悤�ɁA�g���鎅����a��������Q��(�a�ь����E�l�����E�Ȏ��E�i�C�������Ȃ�)�ɕς���Ă䂭�ƁA���ɑ@�ׂŁA���ߕ��ƊԈ��������k�Ȃ��̂����܂�A�������ꂽ�R�͗l������̎����͂ƂȂ�A�������珺�a�ɂ����Ĉꐢ���r�����B�@
����E��퍠�܂ŁA��ɏ����̕��i���ɑ����p����ꂽ�ق��A���n�E���n�E�O�O�n�E���ԂƂ�n�Ȃǂ̎��v�������������A���a30�N�ォ��E�[���E���w�@�ۂ̕��y�ɂ��}���Ɏs�ꂩ��p�������Ă������B�@
�܂����̈ߕ��v���́A�D���ƊE�ɑ傫�ȏՌ���^���A�����A�����ȂǁA���̖���Y�n�������������ނ��A���̐��i�ɓ]�����Ă������B���̒��ŁA�ɐ���͖���ɂƂ��Ă̍Ō�̉�������Ă����B���ꂾ���ɍ��̐[���Z�p�������Ă����Y�n�ł���B���a40�N��O���ɂ͎�@����قǂ��������A���݂ł͗͐D�@�������A�E�[�����ځA�V���N�E�[�����ڂɉ����������Ă��܂����B�@
���݂ł́A���͋@��p����E�[�������̑S�����������A�`�����R�Z�@�������ɐ����R�Ƃ��āA�����A�ʎ��A�^�ȒہA���a��(���p�R�݂̂ɗp����)�������Ƃ���D������������Ă���B(���a50�N�ɂ͓`���H�|�i�Ƃ��č��̎w�����)�@

��O�͏����̕��i���Ƃ��čL�����D����A����ƌ����Έɐ���ƌ�����قǒm���x�͍��������B���̒n���ł́A�̂���u���D�v(�ӂƂ���)�ƌĂ�錦�D�����A�_���̎��Ɨp�D���Ƃ��ĐD���A�]�ˎ������ɐ���ɂȂ�A���D�Ȃ̎s�������ɂȂ�A�D�𗘗p���č]�˂ɂ��o�ׂ��ꂽ�B�@
����̗R���́A�D��ڂ��k���ł������ׁu�ڐ�E�ڐ�v(�߂���)�ƌĂ�ł����̂ŁA���̌�C���킹���炫�����t�Ƃ���Ă���B�@
��������ɂȂ���R���D����悤�ɂȂ�A���Ɂu�ɐ��蒿�R�v(��������������)�́A�S���ɗL���ɂȂ�Ƌ��ɁA�ɐ��������S�����ƂȂ����B�R�̋Z�@���l�Ă���A��ނƂ��ĕ��p�R(�ւ��悤������)�E�ܑ��R(�悱����������)�E���R(�ق���������)�E���R�Ȃǂ��������܂��B���͋ː��䏢�Ɠ��l�ɃE�[����������D���ɉ�����A�傫����ނ����B�@
����̋Z�@�@
���p�R/���o(��������)�����o�����A�������̌^����p���ē��(�Ȃ���)���A��������ȔɊ����t���Č^��������A�������D�ŐD��グ����������B�����͑啿�ŐF�g�������ʂȓ_ �B�@
�ܑ��R/���̂��R�����g�p���A���p�R�قǑ��ʂł͂Ȃ��A3-4��ނ̐F�Ŗ͗l�̔Z�W��\�킵�Ă���B�@
���R/����Z�@�Ɣ��ߋZ�@��2��ނ�����A����Z�@�͎���}�ɂ���ē�����A���ɂ��̕��������ŕ������Ŕ����Ċ��ɓ���Đ��F����B���ߋZ�@�́A�ɒ������a�Ɏ��������t���Ă��̏�ɓ����a�̔��d�ˁA���ߕt���Đ��F����B�ň�������Ă���̂ŁA�ʖʕ����̎��͐��܂炸�����c��A���̎��ŐD��グ�R�ƂȂ�B�@
���D/�ʎ������l���Ȃǂ̋����ŐD��ꂽ���D���̑��́B

�ɐ����R�ɂ́A�u�����R�v(�����肩����)�u�����R�v�u���p�R�v(�ւ��悤������)�u�ܑ��R�v(�悱����������)��4�̋Z�@���������B�D����͂���������������A�R���̐��ߕ���p�����ɈႢ������A��������ɐ����R�̑��ʂȕ\�����Y�ݏo���ꂽ�B�@
�u�����R�v�͍ł��Â�����`������Z�@�ŁA�\���R�A�䌅�R�A�����R�Ȃǂ̊ȒP�Ȃ��̂���A���R�̂悤���k���Ȃ��̂܂ŁA���L���\���͂������A���݂��Z�@�̎嗬���߂Ă���B�@
�u���R�v�͖͗l�̍��܂ꂽ�Ɏ�������Ő��F���{���Z�@�ŁA���k�ȕ��l��\�����鎞�ɗp������B�@
�u���p�R�v�͌^����p���Čo�E�܂��ꂼ��̎�����߂�Z�@�ŁA�o�����R�����킹�Ė͗l��D��o���A�ʐF�̖L���������͂ł���B�@
�u�ܑ��R�v�͈��݂̂��R����p����Z�@�ŁA�����������������ɓ���������B�@
�R�̖͗l�́A�܂���ɐ��ߕ�����ꂽ�������Ԃ��ƂŌ`�����B�܂���ɐ��߂������R���Ƃ����B�o��(���Ă���)���R�����g���ꍇ�ł���A�����@�ɂ�����ꂽ�i�K�łقڎd�オ���Ԃ̖͗l�����邱�Ƃ��o����B����A��(�悱����)���R�����p������ꍇ�́A�����`(��)�̒��Ɋ�����Ă��邽�߁A���ۂɐD��܂ł��̖͗l�̋�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�`�����E�ɓ������J��Ԃ��ɂ��A�͗l��������B�����R���̖͗l���҂�����ƍ������Ƃ��A�������R�̏����ŁA�R�Ƃ����D���̕s�v�c�ł�����B�@
���k���R�͗l��D��o���ɂ́A���𐳊m�ɐ��ߕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���R�ł���A�͗l�������ʂ̂���ɁA����D��オ��̕z�n�̂悤�ɂт�������ׂĊ������A�����ɐZ���Đ��߂�B���������������������d�˂Ă������߂Ă���t�ɐZ�����߁A�̓ʕ����ɒ��߂���ꂽ���͐��܂炸�A���ꂪ�R�̖͗l�ƂȂ�B�@
�ܑ��R(�悱����������)�ł́A�}�Ă̏�ɑ��g�݁A�D��オ��̕z�n�̂悤�Ɉ���A���Ɉ��t���ĉ��ɒu�����}�Ă̖͗l���ʂ��B��t���̍ς���䂩��͂����A��ɍ��킹�Đ������C�荞��A�����Ėh�����{���Ď�����ߕ������肵���R��������B���邾���ł������Ԃ�������A��̂��Z�@�ł���B�������Đ��߂�ꂽ�R���́A�����R���Ƃ͂܂��Ⴄ�����������B

�ɐ������͒����ԁu���D�v�̖��ŌĂ�Ă������A1780�N��(�]�˓V���̍�)�o��(���Ă���)�̐��������A⫖�(������)��������肻�����k���ȐD�����u�ڛ��v�u�ڐ�v�Ƃ�сA����ł͂��ꂪ�u�߂�����v�ɂȂ����ƌ����Ă���B����Ɂu����v�̕������g����悤�ɂȂ����͖̂����ȍ~�̂��ƁB�@
���������A�ɐ���ł͐��Y�̑唼�͔_�Ƃ̒��@�ɂ����̂ŁA�͐D�@����������ꕔ�͍H�ꉻ���ꂽ�B����̎�ނ��Â��͎ȕ����قƂ�ǂ����A�����R�A���R�ɂ�钿�R����ɁA���p�R�A�ܑ��R����Ȃǂ̍H�|�D���������A�ɐ������̖��͑S���ɍL�܂����B�@
���a�����ɂ͖��傪��O���ڂ̒��S�ƂȂ�A���s�̍Ő�[�ł��������B�e�n�̐D���Y�n�͋����Ė��������悤�ɂȂ�A�����̃o�����X������A�l���������Ɏg�p���Ēn����ς����肷�邱�Ƃ��s����悤�ɂȂ����B�ɐ���ł����a7�N�ɐl�������A���a8�N���c�䏢���J�����ꂽ�B���������c�䏢�ȊO�̐l����D����́A�s�]�������ď��a12�N�ɂ͐��Y����Ȃ��Ȃ����B�@
�펞���̓�������(���a15-24�N)���o�āA���X�ɕ����͂������A�m�����ɂ�钅������ŁA���a30�N���ɂ͋}���ɐ��ނ����B�����ł͌��݂��������̍H��ʼn�������Ȃǒ������傪�����Ă���A�ɐ���ł͓`���H�|�i�u�ɐ����R�v�Ƃ��ē`���I�Z�@�͎p����Ă���B

1�D�ɐ���D���̋N���@
�ɐ���n���̍ŌÂ̐D���͕�����6���I�̌Õ�����o�y������(��)��a���ŐD�����z�ł��B���{���I(720�N)�ɂ͒���ɂ�������(�e�G�Ȍ��D��)�����サ����A���쎮(927�N)�̒��Ƃ��ě�(��������)���[�߂�ꂽ�L�q������A���̍����łɈɐ���ŐD��������Ă����Ɛ��@�ł��܂��B�@
�܂��A�ɐ���s�ɂ́A�Â�����@�D�肪�s���Ă������Ƃ��f���閼�Ղ�����܂��B�@
(1)��V�{���ɂ́A�`���_��(���ǂ肶��)�Ƃ������쎮�_����(����5�N�F927�N)�ɂ��ڂ��Ă���Â����Ђ�����܂��B�`���Ƃ́A���▃�Ȃǂ̑@�ۂŐD��A���̕z��Ԃ�̎Ȗڂ������z�ł��B�Â�����D���̐_�Ƃ��Ă܂�ꂽ���Ƃ��f���܂��B�@
(2)�{�O���̐ԏ�_�Ђɂ́A�厡5�N(1366�N)���̑�������܂��B����ɂ͐`(�͂�)�̖�������A�`���́A�{�\�E�@�D��̋Z�p�҂̑c��ŌÂ�����ɐ���̒n�ŐD���������Ă����Ƒz������܂��B�@
���O3�N(1333�N)�A�V�c�`��̊��g���̍ۂɒn���̔_�����������Ŋ��n�p�̌������サ���Ƃ����`�����c���Ă���܂��B�@
2�D���s�ƐD���Ɓ@
18���I����(�]�ˎ���)�ɂ́A�s�������A�ɐ���̌��D���͈ɐ����(����)��ɐ��葾�D(�ӂƂ�E�ӂƂ���)�Ƃ��ď��i������čs���܂����B���̎���̑��D�̌����́A�萻�̋ʎ������l���ȂǂŁA�����������@(�n�@)�ɂ����A�ȕ��E�i�q���E���n�����D�肾����܂����B�n������v�ŏa�݂�����Ƃ��납��A�������������A���Y�i�Ƃ��đS���ɍL�܂�܂����B�@
3�D���@���̏o���@
���̎��v����ɔ����A���̍�����A�{�\������ɂȂ�܂����B�s�ɂ͌����l���W�܂�A�����𐢘b���錦�h��D�������錳�@��(���Ƃ͂���)�������܂����B���@���́A���Ȏ����Ŏ����t���A�����������F���邩�����Ɏ����߂��˗����A�w��̎ȕ������A�_�Ƃɋ@�D����˗����܂����B�D��オ�������i�́A���@���Ŏd�グ���A�s�̌��h���o�č]�˂⋞�s�̌����≮�ɑ����܂����D�����̑��D�́A�ȕ����قƂ�ǂł������A�O��4�N(1847)�ɂ́A�n���ˑ��̗�}�`���ɂ�菉�߂ď\�������̎��̐}�Ă�D�荞�ދZ�p���m������A���ꂪ�ɐ�����R�̂͂��߂ł���Ƃ����܂��B���̋Z�@�͉��ǂ���Ȃ���p����A����2�N(1869)������E�o���Ɍ��̔Q������������A�{�i�I���R�����i������܂����B�������Č��@���̏o���ɂ���R�́A��ƍH�������Ɖ�����A�ʎY�����\�ɂȂ�܂����B���@���̒��Ԃ́A�̎�ɖ�������[�߁A���D�Ǝ҂̈琬�E�ی���肢�o�Ă���A���̎�(�O��4�N)�ɉ������Ă��錳�@����67���ŁA��ɂ�102��(�Éi���N�F1848)�ɔ��W���Ă��܂��B�@
4�D�����ېV�ƈɐ��葾�D��Ё@
�����ɓ���A���̔Q�����o���Ɏ������ꂽ���Ƃɂ��A���x�������A�z�̕\�ʂ����炩���𑝂��ĊO���͂ЂƂ���������Ȃ�A�ɐ����R�͒��d�����悤�ɂȂ����A�����ېV�̐����f���Ă����Ԃ̋����̈ӎ������ꂾ���A�l�����������ɂ��F������e���i�̗��ʂ����ɂȂ�A����13�N(1880)�A������Y��ɂ���Ĉɐ��葾�D��Ђ��ݗ�����A�i���ێ��ɂ��ɐ��葾�D�Ȃ̐M�p�̉�}��܂����B�@
����18�N(1885)�A�ɐ��葾�D��Ђ͈ɐ���D���Ƒg���ɉ��g����܂������A�D���u�K�����J�݂��Ă��܂��B�D���u�K���͖���29�N(1896)�ɐX���F���̐s�͂ɂ���Ĉɐ�����D�w�Z(�ɐ���H�ƍ��Z�̑O�g)�ɂȂ�܂����B�����āA����31�N(1898)�Ɉɐ���D�����Ƒg���Ƃ��ĉ��g���Ă��܂��B�@
�܂��A���̍�����D���̐��Y�҂Ɣ̔��ƎҁA����w����(�����X�E�f�p�[�g)�Ƃ̊Ԃ𒇉�钇����(���p��)������܂����B���p���́A�]�˒����Ɉɐ���̒n�Œ����l�I�Ȗ������ʂ��������h���O�g�ł���A��������ȍ~�̈ɐ������̔��W�ɂ������Ɋ�^���܂����B�@
5�D�ɐ������̗R���@
�ɐ��葾�D���A�u����v�̖��ŌĂ��悤�ɂȂ����̂͒肩�ł͂���܂��A����20�N���ł���Ƃ����܂��B����Ƃ́A����f�ނɂ��đ���ꂽ���D���̑��̂Ƃ��ėp�����A���Ɉɐ���͂��Ƃ�葫���A�����A�����q�ȂNJ֓��n���̐��i�ɑ��Ďg�p����Ă��܂����B�@
����̋N���́A�V���N��(1781�`1788)�ɁA�o���̐��������A⫖�(������)��������肻�����k���ȐD�����u�ڐ�v�A�u�ڐ�v�ƌĂсA���ꂪ�]�a����āu�߂�����v�ƂȂ�����������܂��B�@
�܂��A����20�N(1887)���A�ɐ��葾�D�̔̔��X���A�������{����`�n���ɊJ���ꂽ�Ƃ��ɁA�Ԓn�ɔ������Łu�߂������v�̕�������ߔ������������ĂĔ̔������̂��A��Ɂu����v�̕������g�p������ƂɂȂ����Ƃ�����������܂��B�@
6�D�Z�p�v�V�ƍH���̕��Ɖ��@
�]�˖����ɐ��F����ɂ��鍮���A����������A�@�ƍH�����番�����܂������A���������ɂ́A�@�����E�Еt���E�Q���Ȃǂ̍H�������ƂɂȂ�܂����B�D�@������20�N�Ȍ�́A������@���獂�@�Ɉڍs����܂����B�@
7�D��1����������@
���������ɂ́A�͐D�@����������A�ꕔ�͍H�ꉻ����܂������A���Y�̑唼�͔_�Ƃ̒��@�ɂ����̂ł����B�ɐ������̎�ނ��A�����R�A���R�ɂ�钿�R������͂��߁A���p�R�E�ܑ��R����Ȃǂ̍H�|�D���������A�ɐ������̖��͑S���ɍL�܂�A�吳�����܂ő�1������������}���܂����B�@
8�D��2����������@
���a�̏����ɂȂ�ƕ��D���喜�\���痧�̊��̂���V�K�D���̎��v�����܂�A���H���@���H�v������l�����������肵�Đ��c�������J������A��2������������}���܂����B�@
9�D��������@
���a12�N(1937)�ɓ��؎��ς��N���A��2�����E���ɓ˓����钆�ňɐ���D���͕s�U�Ɋׂ�A���a18�N(1943)�ɓ���ƈɐ������͓����i�ƂȂ�A�o�܂ɋ��������ĐD���������i���ґ�i�ł���Ƃ��Ĕ̔��֎~�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�@
10�D���̕����ƍ��x�������@
�I��O��̏��a20�N(1945)8��14���A�ɐ���s�X�n����P�ʼn�ŏ�ԂɂȂ�܂������A�x�O�ɓ_�݂����D�Ƃ́A���������������܂����B�����āA�N��ǂ����Ƃɐ��Y�ʂ͏㏸���A���a31�N(1956)�ɂ�292�����E50���~�ɒB���A��3�����������}���܂����B�������A���̋}���ȗ��s�̕ω��Ɛ����l���̕ϑJ�ɂ���āA���̔N�����ɉ��~�������ǂ�܂����B���̑ŊJ��Ƃ��ăE�[���R��A���T�\�u�����J�����A���a40�N�ɂ�190���_64���~�̐��Y�z�������A�����D���Y�n�Ƃ��Ă̒�͂��݂��܂������A�����ւ����v���Ȃ��A���ނ��čs���܂����B�@
11�D�`���H�|�i�u�ɐ����R�v�@
���a50�N(1975)5���A�ɐ����R���u�`���I�H�|�i�v�Ƃ��č��̎w����A�V��������ݏo���܂����B�����ɁA�u�`���H�|�m�v12�l���A������F�肳��܂����B���̐��x�́A�`���I�H�|�i������Y�n�ŁA�D�G�ȓ`���I�Z�@��ێ�����l�ɁA�Z�p�̈ێ������}���p�҂̊m�ۂ�ړI�Ƃ������̂ŁA��l����p�����`���I�Z�@������ɓ`�����A��p�҂��琬���邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă���܂��B �@
 �@
�@�ː��䏢
�ː��s�͋��s�̐��w�ƕ��Ԓ��A���j���Â��D���̒��ł���B�]�˒���(��������)�ɋ��s����w�̐D�H�����@����������ŁA�k�ɥ�W�Ȃǂ̋Z�@��`�������ɂ��n�܂����B����ɂ��A���w���Ɛ肵�Ă������@�ɂ�鍂���D�����A�ː��ŐD��n�߁A�V�۔N�Ԗ{�i�I�ɂȂ����Ƃ���Ă���B�@
�䏢�́u�䏢�k�Ɂv�̗��Ő���E����̏k�ɂł���B���ʂ̏k�ɂ��A�n���͂��d�߂ŁA�d���������邪�A�]���̐D��������Ƃ͈�����Ɠ��̕��͋C������B�䏢�́A��������Ȍ�A�吳�E���a�̑���E���܂ő�\�I�Ȓ����Ƃ��Đl�X�Ɉ����ꂽ�B�������A���Ɏn�܂����E�[�������ɉ�����A���͐D���ڂ̒n�ʂ�ۂɏ�������������B�@
�Z�@�͌o���E�����ɗ�������p���A���Q(������)���ꂽ�o���ƉE�Q��E���Q��Ƃ̉��Q�肳�ꂽ���́A���������B���ɍ����@�ۂ�p���Đ��F�����A���͐��n���E���ǂE���ѕ��������č�����u�䏢�Ёv�ŌЕt�����A�����Q���@�ŋ��Q(������)���|�����A�W���K�[�h�@�ŐD��グ����B�D��オ�����瓒�ɐZ���āA�������݁u���ڊv���s���A������ɓ��̂��E���o�������Ċ�������B

�ː��D�ɂ�7�̋Z�@(�����D�A�܋ѐD�A�o�ѐD�A���ʐD�A���o�D�A�o�R��D�A����і߂�D)������A���̒��ő�\�I�Ȃ̂��Ɠ��ׂ̍����V�{���������D�ł���B�V�{���o�����߂̈��́A�����H���ōs���鉺�Q���1m�ɂ�300-400��̔Q������A�Еt���H���ő@�ۂ̏d�ʂ̔{�̗ʂ̌Ђ����݂��ށB����͌�̔Q���̍ۂɔQ�肪�߂�̂�h�����߂ł���B������1m�ɂ�2500-3000��̋����Q���������B�Q���ɂ͂��ׂĔ����Q���@���g�p����B�@
�f�U�C���H���ł́A��l���ӏ���(���ᎆ)�Ɏʂ��Ƃ�A����ɂ��������Ė��(�䎆�Ɍo���̏グ�����̏����w�����錊��������)���s���B���݂ł́A�R���s���[�^�ō쐬�����摜�f�[�^�ڐD�@�ɑ�����@������B�@
���D�̓W���J�[�h�@�ōs���B�o���̖��x��1cm������100�{�ȏ�ł���B�D��オ�������n���ʂ�ܓ��ɐZ���A���ɕt���Ă���Ђ𗎂Ƃ����Ƃɂ���ĕ\�ʂɃV�{������A���n�͏k��Ŗ�7�����x�̕��ɂȂ�B�k���n�̂����ĕ����L���A�̑�̏�ŖؒƂŒ@���A���������o���Ċ����ƂȂ�B

�ː��́A���Ă͊֓��Y�n�̗Y�Ƃ��ČN�Ղ��Ă������A�ŋ߂ł͘a�����v�̌��ނƂƂ��ɐ��Y�ʂ͌������Ă���B�ː��Y�n�̋N����͌Â��A7���I���V�c�ƂɎd���Ă�����������P���A�����A�{�\�Ƌ@�D�l�ɓ`�������ƂɎn�܂����Ƃ���A�����J�_������_�Ђ�����1200�N�ȏ���o�����݂��A�D���̐_�l�Ƃ��Ēn���Ǝ҂̐M���W�߂Ă���B�ː��s�̍L��400�N�ȏ㑱�����Ƃ̕F���Ƃɂ͖��{���R�E�����`�P�̎������瓯�Ƃɂ��Ă��u�m�c�R�ے������v��������Ă���A�ː��Y�n���L���̐D���Y�n�ł��������Ƃ𐄑��ł���B����A�V�c�`�傪���̍�(���Q�n��)���i�_�Ђŕ����グ�����A�o�w�̊��Ƃ��ċː�����p�������A�c��5�N(1600)�̊փ����̍���ɂ��ː�������ʂɎg�p���ꂽ�ƌÕ����Ɏc����Ă���B���a��(1615)���{�ւ̔N�v�Ƃ��ċː���54��������4800���̌����[�ł���Ă���B���������Ă����n�ł̋@�D�������ɐ���ł����������Ƃ���Ă���B�@
�ː��Ɍ���3�N(1738)�ɍ��@�Z�p���������ꂽ�B���w�̐D���t�����q��������7�l�̒��Ԃ����̋Z�@���K�����A�閧���ɐ��Y���n�߂��B�����l�̐V���l�蕺�q�����w�̋@�H�g���q�������A���w�̋@�D��������A3�N��ɂ�40������k�ɁA�W�A�ш��A���W�Ȃǂ̍����i���肪���A���ɂ������̃n�V���ƂȂ����ȏk�ɂŖ����������B���F�����̋Z�p�����s����`���ƁA�����Y�n�Ƃ��Ă̊�b���ł߂Ă����B����3�N(1783)�ɂ͋g���q�����Ԃɂɂ�鐅�͔����Ԃ��l�āA���̂��Ƃ����͊v���ƂȂ萶�Y�����I�ɑ��傳�����B18���I�����̕����A�����̎���ɁA���앶���̏m�����Ƃ����܂��āA�ߐ��D���j��̉���������}���A���E�A���сA�j�q�Ȃǂ̍������p�D�����肪����悤�ɂȂ����B18���I�㔼�ɋː��n���600���̋@�����y�o���A1�������蕽��10��̋@�����L���Ă����ƌ����A���ɍ]�ˎ���ɂ͗ʎY�̐��̎Y�n�ɐ������Ă����B�Y�n�Ɋv���������炵���̂�����5�N���������ꂽ���m���̐��D�@�ŁA��10�N�̃W���K�[�h�@�̗̍p�ɂ���D�̐��D���B���̋Z�p�v�V���ː��Y�n�����Ē����Ԃ��̉�����h�邬�̂Ȃ����̂ɂ����B
796�N���ЎR�c�S��ΐ_�A���a�_�̌�������n�܂�B���̌�ː����͑����ƂɎd���ė������ւ邪1573�N�ː����͖łт�B�ٗї̂ɑg�ݓ����ꂽ��A���{�ɕ������ꂽ�肵����1722�N�O������X�̌����p�X���ː��V���ɐݒu����A1738�N���w�D���t�핺�q�E�g���q���ː��V���֍��@��`����ȂǁA���D���̃��b�J�Ƃ��Ă̒n�ʂ�z���Ă����B1739�N�ɂ͐V�������q�傪7�l�g�������ш��D���n�߂Ă���B1841�N�̋ː��V�����l�̔N�ԐD��������͖�70�����Ƃ�����35�����͍]�˂�ɂ��Ă����B
 �@
�@�����q�D��
�]�ˎ���܂Łu�K�s�v(������)�Ƃ͔����q���w�����̂������B�Â�����{�\��D��������ł��������Ƃ�\���Ă���B�����q�͊֓��R�n�ƕ������n�̋��Ɉʒu���A�R�����ōk��n�����Ȃ��������߁A�{�\��@(�͂�)�D��́A�Â�����_�Ƃ̑�Ȏd���������B�����q�D���̋N���́A��R�鉺�̎s�Ŏ�������ꂽ���낾�Ƃ����Ă���B�@
17���I�͂��߂ɐ��������u�ѐ����v(���ӂ�����)�ɁA�����̓��Y�Ƃ��āu��R���R�ۓ��v(������܂悱��܂̂ނ�����)�̖����݂���B�]�ˎ���ɔ����q�\�h���J�݂���A����4��8�̓��Ɏs���J����āA���ӂ̑��X���疚����A�D���Ȃǂ��W�܂�悤�ɂȂ����B�@
�����q�D���Ƃ́A���Ƃ͎��ӂ̑��ŐD���A�����q�̎s�ɏW�߂�ꂽ�D���̂��ƁB�����q�́A�ː��⑫���Ȃǂ̐D���Z�p�̐�i�n��A�]�˂Ƃ��������n�ɋ߂��A�D���Ƃ����W����ɂ��߂ɁA�n���I�ɂ��L���ȏ�����������Ă����B�@
���̒n���ł́A�^�Ȃ���a(��)����������߂āA��(����)�͗l�ɐD�������̂������A���̂��ߓ��n�̐D���͎ȕ��A�D���s�͎Ȏs�ȂǂƌĂꂽ�B���D���͐��F���@�ɂ���Đ��(��������)�D���ƌ��(���Ƃ���)�D���ɕ������邪�A�����q�͑O�҂𒆐S�Ƃ��A���ɒj������p�I�Ȓ����̎Y�n�������B

�����V���{�́A�x����������{���j�Ƃ��A�B�Y���Ɛ�������͂ɐi�߂��B������E�D���Ȃǂ͗A�o�i�Ƃ��ē��ɏd�v�����ꂽ�B����̈�Ƃ��āA�S���Ŋ��݂̔�����⋤�i��J�Â���A�Y�ƁE�Z�p�̋ߑ㉻�A�i���̌���ɑ傫�Ȍ��ʂƉe����^�����B�@
�������A����10�N��̔����q�ł́A�A�����ꂽ�e���ȉ��w�������ނ�݂ɗp�������߁A�i�����ቺ���A�u�����q�D����؎戵�s�\(��������)�v�Ǝs�ꂩ����ߏo����A����18�N�̌ܕi(������)���i��ł����т͑S���s�U�ł������B�@
����ɕ��N������������@�Ɖ�(�����Ǝ�)�炪���S�ƂȂ�A���F���͂��߂Ƃ��锪���q�D���S�̂̋Z�p����ƕi�����P�Ɏ��g�B����19�N�ɒ������炪�����q�D���g���������A���N�����q�D�����F�u�K�����J�݂��A�����ɎR�����Y�⒆�����Y�Ƃ������A�����̓��{�̐��F�̑��l�҂����ւ������B����32�N�����Ǝ҂��܂߂������q�D�����Ƒg�����ݗ�����A���N�A�����q�����Ƃ��Ĉ�{�㌧�A�����i��J�Â��ꂽ�B�����q���F�u�K���́A����36�N�ɂ͓����{���D���w�Z(���݁E�����q�H�ƍ����w�Z)�ƂȂ����B�������Ĕ����q�ł͎Y�n�S�̂ŋߑ㉻�Ɏ��g�݁A���X�ɐ��ʂ��グ�Ă������B�@
�D���g���𒆐S�ɋߑ㉻��i�߂������������ł��A�����q�n���ł͂܂���D��@���g���Ă����B�]�ˎ���܂ł͒n�@(����)����Ɏg���A�]�ˎ�����I��肱��ɂȂ�ƍ��@(�����͂�)�����X�ɕ��y�����B���@�͐D��肪����(��������)�ɍ��|���ĐD�邽�߁A�n�@�����i�i�ɍ�Ɣ\�����悭�A��蕡�G�ȐD����D�邱�Ƃ��o�����B�������㔼�ɂ́A�����R(�Ђ���)��h�r�[�A�W���K�[�h�Ȃǂ̊O���Z�p������A�V�����`�̎�D��@���o���������A�吳����ȍ~�A�͐D�@(�肫�������)�����y�����B

�吳����ɂȂ�ƁA�j���̕����͒�������m���ƂȂ�A�����̒����͎ȕ�����͗l���ւƕς���Ă����B�����q�͑�O�����̒���(�����p�̐D��)�́A���ɒj�����S�̎Y�n�łŁA���̂��Ƃ͑傫�Ȗ��ł������B�����q�̋@�ƉƂ����͐V����J��̕K�v�ɔ����A�܂��w�l�����ڂɊ��H�����o�����B�吳13�N(1924)�����q�D�����̉�ݗ�����A�V���i�̊J����̔����g���ɓw�߂��B�吳���ɂ͏��߂ăl�N�^�C������A���݂������q�͍����L���̃l�N�^�C�Y�n�ƂȂ��Ă���B�吳�����珺�a���ߍ��A��������Ɩ��t����ꂽ��D(����)�̐D�������������B��O�����D���̎Y�n�̂��߁A���s�Ȃǂ̉e�����₷�����������q�ɂ����āA�����Ƃ������D�葱����ꂽ�̂����̑�������ł���B�����q�̋Z�p�̏W�听�ƕ]���������A���݂��`���H�|�i�Ƃ��ĐD���Ă���B���a�̏��߂ɂ͊C�O�s����J�ׂ��A�A�o�D���̐��Y�����コ�ꂽ�B�}���ȕω��̒��ŏ]���ȏ�̌����J�����K�v�Ƃ���A���@�ւ̐ݗ����}���Ƃ���A���a3�N(1928)���_���ɓ����{�����D������(���E�����s���Y�ƋZ�p�����������q����)���ݗ����ꂽ�B

�����㑀�ƒ�~�ƂȂ��Ă��������q�D���Ƃ́A�������Z���ɂɂ��Z���Ă悤�₭�����������B�₪�đ@�ۊW�̓��������ׂēP�p����A�����Đ��̈ߗ��s������D���̎��v�����܂�A���a20�N�㔼�ɂ́A�K�`�����Ƌ@(�͂�)��D��Ζ��Ƃ���������������Ƃ����Ӗ��Łu�K�`�����v�ƕ]�����قǂ̍D�������}�����B�]������̖���ނ�䏢�Ȃǂ̂ق��A�����̐V���i�����܂�A�ĕ���z��j�����ځA�����ăl�N�^�C�𒆐S�ɎP�n�E�}�t���[�ȂǎG�ݐD���̐��Y������ɂȂ����B���a30�N�����܂ꂽ��E�[���́A�f�ނɃE�[����p������̓`����������D��̐D���ŁA40�N��ɂ����Ĕ��ꑱ���A��㔪���q�D���̍ő�̃q�b�g�ƂȂ����B�@
���a55�N�����q�́u�����D�v���ʎY�Ȃ���`���H�|�i�Ƃ��Ďw������B�����D�Ƃ́A��������E�ېD(�ނ�����)�E���ʐD(�ӂ�������)�E�ς���(�Â�)�E��(����)��D��5��ނ̐D���̑��̂ŁA�����q�D���̗��j�ƋZ�p�̌����ƌ�����B
 �@
�@��z���V
�����̊J�`�����A���l�ɏo�Č��D�������c��ł��������v���́A���Ă���A������铂�V�ɑR���ĊO���Y�̌����z�ɑ���A���V�Y�������B��z���V�Ƃ��Ė����͂��A��z�͖������珺�a�����܂Ŏ�@(�Ă�)�ɂ�铂�V�̎Y�n�Ƃ��ėL���ɂȂ����B�����v���́A�������N(1825)�Ɏu�`��(���݂̒���)�̌���(���ʂЂ�)�u���c���v�̓���E�����v���q(����)�̒��q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B��z�ł́A�]�ˎ���̒����납�猦�D��������ɂȂ����B�������������i���������D���́A��z���l�ɂ���č]�˂ɑ����傫�ȗ��v�������炵�A��X�܂Ō����X�Ƃ��Ė��𐬂����������������y�o�����B�@
�v���́A��������]�˂ɖڂ������A���{���ɓX���o�����B�����Z�N(1859)�ɉ��l���J�`���A�f�Ղ��n�܂�ƊO�����l�Ƃ̎��������l���A�n���⒁�����ʂ̐�������F���A�O�����l�ɑ������B���̑���ɋ���(���Ȃ���E�ł��ׂ����D���������ȕz)�Ⓜ�V�Ȃǂ���肵�A�O���̏��@��C�O�̓�����T��A�O���Y�̓��V�����Y�̂��̂��͂邩�ɗǎ��Œቿ�i�ł��邱�Ƃ�m��A���ĎY�ȐD���̋��낵����Ɋ��B�킪���̖ȐD���͂����܂��ł�ł��܂��Ɨ\�z���A�����ėǎ��̖Ȏ�������A�����A����œ��V��D���Ă͂ǂ����ƍl�����B�@
���V�͎������ゲ�납����{�ɓ���n�߂��A���n�ɐԂ�A���A�D�Ȃǂ��c���܂ɐD�����ȐD���B�u���v�͊O�����痈�����̂̈Ӗ��Łu�V�v�́u�V���v(����Ƃ�)�̗��ŐD���̗A�o�`�������C���h���C�݂̃Z���g�E�g�[�}�X���痈�Ă���Ƃ�����B�@
�D��グ�����V���m(���ʂ�)�őł��Ďd�グ�����߁A���̂悤�ɔ��������Ȃ₩�ŁA���{�l�̍D�݂ɍ��������炵���D�����������A�����Ă���ʂ����Ȃ������ɂ͎�̓͂��Ȃ����̂������B�@
�v���͉��l�ŗm�����A��z�n���̋@���Ɏ��D���Ă�������B���ʂ͏�X�Œl�i���A�����V���͂邩�Ɉ����o���邱�Ƃ��킩�����B�u���ꂾ�v�ƌ��߂��v���́A��ʂɗm�������ݐ�z�n���̋@�ƉƂɓ��V��D�点���B���Ƃ��ƌ��@(���ʂ�)�̂����ꂽ�`������������z�n���A�H���_�Ƃ̕��ƓI�Ȓ��@����͂������Ƃ͂����A���炵���i���̂��̂���ʂɐD��ꂽ�B�v���́A���̓��V��܂���u��z���V�v�̖������ɒm��n��u�쓂�v�Ƃ��Ă��Ă͂₳�ꂽ�B�@
�������A��z�ł͂��܂ł���@�ɗ���A�@�B�����Ȃ��������߁A�u�쓂�v�͖���26�N�̐�z������������납��}���ɐ��ނ����B
 �@
�@��������
10�㐒�_�V�c�̌��ɒm�X�v�F���������Ƃ��Ē����ɗ��C�A�Z���ɗ{�\�Ƌ@�D��̋Z�p���������̂��n�܂�Ƃ����B�����̎������H�ɉ����A�ق������H�̋Z�p��������Ă���B�@
�����ق������(���ځE���n�E���z�c�n)�@
�����̐��F�́A�������疾���ɂ����ēV�R������p���A�f�p�ȐF�ʂʼnƒ뒅�Ƃ��Ĕ��B���A�����̒����D���̊�b�ƂȂ����B�ق�������́A�`�����钁���D���̋Z�p����b�Ƃ��đn�Ă��ꂽ�B�����́A�c���ɂق����͗l�����������H�ŁA���Ď��̏�Ɍ^����u���A�����̂����n�P�ō���A�F���d�˂Đ��F���Ă������@�ŁA���D�̂悱�����ق����Ȃ���D�邱�Ƃ���u�ق�������v�ƌĂ�Ă���B�ق�������̋Z�@�́A����������@�Ɏn�܂�A���Ď�����@�E���o����@�Ɖ��ǂ�������ɂ�}���ɔ��W�����B���Ď����R�͗l���A�悱���̐F�Əd�Ȃ肠���Đ[�݂̂���F���ƂȂ��Ă���B

�u��������v�̖��Œm���钬�́A���n�ɖR�����c�ނ����Ȃ����ƁA�����n�ł���]�˂ɋ߂����Ƃ���A�]�ˎ��ォ��\�������A�������ނ��A�@(�͂�)��D�邱�Ƃ���ȎY�ƂƂ��Ă��܂����B�u�H�\(������)�������āA�������I���āA������Ղ�҂���v�Ɩ��w(��������)�ɉS���Ă���悤�ɁA��N�Ԃ̉Ս��ȗ{�\�J�����I���A���n��_�Ɋ��ӂ��A�����ƌ��̑�s�����u�����Ձv(12��3���̒������)�̍��s�ؗ킳�́A�\�ƌ��Ɏx����ꂽ���̒��̔ɉh�����ɓ`������̂ł��B�@
���w�Z�ɒʂ����̓r���ɁA�@������̍H�ꂪ����������܂����B�̌��̂��߂̋�(�̂�����)�^�����̑傫�Ȍ����̒����畷�����Ă���W���b�J�W���b�J�Ƃ��������D�@�̉��́A���܂�ɂ����Y�~�J���ŁA�����̓��قȌ`�Ƒ��܂��āA�c�ȐS�ɂ͉����s�C���Ȋ���������܂����B�@
���w�Z�̎��͂͌K���Ɣ�������ł����B���Ȃ̎��Ԃɐ搶�ɘA����āA�߂��̗{�\�_�Ƃɂ��ז����A���\�▚�������Ă���������Ƃ�����܂����B��������Ȃ����炢��������̔������\���̌K�̗t��H�ރU���U���Ƃ����������ł����Ɏc���Ă��܂��B������Ă���������A�����ɓ���Ċ��̈����o���Ɏd�����A���̂܂ܖY��āA���炭�o���ĊJ������A���������ȉ�̎��[�����̊J�������Ƃ��o�ė��āA�\����̗c���ł��邱�Ƃ����������̂����̍��ł����B

���̏��w�Z����́A���a30�N��̌㔼����40�N��̏��߂ł��B���a39�N(1964)�̓����I�����s�b�N�̑O��A���{�����̕����������S�ɒE���č��x�o�ϐ����Ɍ������]�����ł����B����(�����n)�Ƃ��Ă̖���͂��łɑS�������߂��A�D���Y�Ƃ͏��X�ɎΗz�Ɍ������A���z�c���z�c�J�o�[�Ȃǂ̐����p�i�Ɋ��H�������o���Ă��������Ǝv���܂��B�@���������̕z�c�J�o�[���������₨�Ε�Ƃ��ē͂���ꂽ�̂��o���Ă܂��B����ł��܂�4�K���Ă̐D���g���̃r���́A�c�ɒ��ł͎s�����Ɏ������w���z���������A���̗L�͎҂��@������┃�p���ȂǐD���W�̐l�B�����S�Łu�D���̒��v�Ƃ������o�́A�͂�����ƗL��܂����B�@
�Ƃ��낪�A���̍����炩�A�K������n��D���ȊO�̍H��Ȃǂɕς��A�@������̍H�ꂩ����A���̎����D�@�̉�������ɏ����Ă����܂����B�L�������ǂ�ƁA�������w�Z�𑲋Ƃ��āA�d�Ԓʊw��1���Ԕ��������鉓�����̍��Z�ɐi�w�������A���a45�N(1970)�O�ゾ�����悤�ȋC�����܂��B���̍�����A�n��Y�ƂƂ��Ă̋@�D�͋}���ɐ��ނ��Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@
����ɂ��ƁA���a30�N�ɂ͐�O�̃��x�������A�������w�����������a30�N��̏I��荠�����Y�ʂ̃s�[�N�������悤�ł��B�Ƃ��낪�A�������w�Z�ɓ��鍠�̏��a40�N��ɂ͋}���ɐ����čŐ�����2/3�Ɍ����A�����Č̋��𗣂ꂽ���a50�N���ɂ�1/3�ɂ܂Ō������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

�ޗǎ��� 713 �����������n���ɁA�嗤�A���l�ɂ��A�{�\�Ƌ@�D���`����ꂽ�@
���q���� �E �֓����m�̖{�����Ȃ��������m���w���ɒ��������̗p�����Ɠ`������@
�k������ �E �k�����M�A�����S���������É����z�邷�B �w��ɉ��c���ɂ�茦�D���̐��Y�����コ�ꂽ�Ɠ`������@
�]�ˏ��� �E �_�Չ҂��Ƃ��āA���Ƃ����o�Ɍ��A�܂ɖ����g�p�������݂����n���D����@
�]�˒��� �E �̂����E�ʎ��ɂ�锒���D��p���ė��܂��͑��ؔ�Ő��߂��Ȃ��̂��D����@
�]�ˌ�� �E ��������A�������A�������蓙���H�v����s�Ȃ�ꂽ�B�܂��A���̍��o���ɖ͗l��`���o��������͂��܂�@
�������� 1868 �����ېV�A���̍���莟��ɑ��l���R����͗l��������A���D�����@
����41�N 1908 �����S������ ��{�@���Y�̃V�S�L�����(����14632��)�̔����ɂ�茻�݂̂ق�������̋Z�@�����܂��@
������� 1911 ���т̐�i�n�����F�A������̋Z�p�҂��ڏZ���Ă����@
�吳���� 1913 �ɐ����^���E�l���ڏZ���Ă����@
�吳 5�N 1916 �ق�������ɂ��哇�ۂ�������@
�吳 8�N 1919 ������H�ɂ��吳�����肪������@
�吳����1924 ���̍��|�J�����A�܂��̓|�J�����̋Z�@�����܂��@
���a���� 1930 ����H�ɂ�邠���ڂ̐������B�����B���̍��A�������ڂ́A�}���K�����G�A�Ȃ�����A�s�[�X�ڂ������̋Z�@������ɉ��p����A�ق����������n�̓�����s�Ȃ�ꂽ ���̍��|�J�����A�܂��̓|�J�����̋Z�@�����܂��@
���a 8�N 1933 ��������n�A�͗l���n�A���z�c�n�̂ق������������ɂȂ� �@
���a10�N 1935 �����[������A�Â炵������s�Ȃ��A���̍����ь^�����܂ꂽ�@
���a15�N 1940 ����ɐ펞��������������]�p�Ǝ҂����o�����@
���a20�N 1945 ��2�����E���I��

���a23�N 1948 ���Ԃ܂��͕��ԂƂ������]���i���@�œ�����s�Ȃ�ꂽ�A���̍��ق����̐܂�t�������s�����@
���a24�N 1949 �l�����A���@���A�Ȏ����̖��n�A���z�c�n�̂ق������������ɂȂ�A����ɐ����̕ω��ɂ�蒅�ڂ��������A�Q��ނ�������@
���a27�N 1952 ���D��(�r�j�������a)�̖��n�A���z�c�n�̓���͂��܂�@
���a31�N 1956 ������������g���ݗ��A�s���{���Ŏ��ƊJ�n(5��23��)�ĕ����n�A�ĕ����z�c�n�̓���͂��܂�@
���a35�N 1960 ���{������H�Ƒg���ݗ��A�����x�������A�U�u�J�o�[�A�}�N���J�o�[�A�m�����A�n���J�`���痿�v�����g�͂��܂�@
���a36�N 1961 ��������N������@
���a40�N 1965 �t���b�L�[����ɂ��m�����A�y�i���g���̃v�����g���͂��܂�@
���a41�N 1966 �t�N�����n�̊|���s�[�X���G�͂��܂�@
���a42�N 1967 �F�T�̖��n�A���z�c�n�̓���ƃI�[�g�v�����g�͂��܂�@
���a43�N 1968 �l�N�^�C�̃v�����g���G�͂��܂�@
���a49�N 1974 �A�N�����̃R�^�c�|�A���z�c�n�̃v�����g���H�͂��܂�@
���a50�N�ȍ~ 1975 ������f�ނɃv�����g���H���\�ƂȂ�A�i���A�f�U�C���A���S���D�]���A�����ɋ����͐Q���i���嗬�Ƃ��鑎���Y�n�Ƃ��Č��݂Ɏ���
 �@
�@����̃C���[�W
��������A����42�N(1909)���̎v���o�B�ؖȂ̓����̒����𒅂Ă����c��(�k�C���D�y�s)�̏��w���ɂƂ��Ď��̂��������́u�����悤�ɔ������A��i�ł͂����肵�Ă�āA�N���ɓ����̏��w�����\���Ă��Ǝv�͂ꂽ�v�B�u�݂ǂ肢��̂ԂԂ������n�̌��̒����v�𒅂Ēʊw���Z���ɔ�����Ƃ��Ē��ӂ��ꂽ�����̏��w�Z����̓]�Z���Ƃ̊ԂŁu����A����ł����H�v�u����������B�����̏��w���̂ӂ��Ȃ̂�v�Ƃ�����b�����킵�Ă���B�c�ɂ̏��w���ɂƂ��ẮA���偁�����̏��w���Ƃ����C���[�W�������B�@
������17�ŁA���߂Ă�������̎��̖��������Ă��炢�u����̒����͎��D������������y���ĂԂԂ����肴��肪�A�����l�Ȃ��������v�Łu�����������l���ނƎv��ꂽ�v�Ƒ̊�������Ă���B�u���̂�����̖���́A���R�Ƃ��Ď����̐g�ӂɁA���炵�����߂�����C������o���₤�Ɏv�͂ꂽ�v�B�u����܂ł̎����Ƃ́A�S�R�����ӎ����������ɂ������v�Ǝ����R�̖��傪�A�������疺�ւ̊J�Ԃ̃C���[�W���Ă������Ƃ��q�ׂĂ���B�@
�ʂ̉ӏ��ł��u����ɂ͉������Џ��Ђ��������������āA�Ⴂ����V���̂ЂƂ�z���o������B�ق��̔����̂ɂ͂Ȃ����o�ŁA���ꂪ����̋����ł͂Ȃ����Ǝv�Ӂv�ƌ��A�u���C�v�u�����v�u�V�N�v�Ƃ����C���[�W�����邱�Ƃ��q�ׂĂ���B���̏��X����������́A��l�̏��ɐ������Ă������O�̖��̂���ł����āA�߂������̐��̊J�Ԃ��ق̂��ɗ\�z������u���߂�����C�v�����̂������悤���B�@
������������̃C���[�W����A����̎������͖̂��炵�����Ȃ₩�Ȋ����̐l�ŁA�����̂悤�Ɂu������ӂ܂Ŗ{�ɂ��肩������A�ٖD�̑傫�炢�ȁv�^�C�v�́A���傪������Ȃ��Ƃ��Ă���B�u����Ƃ������n�͏����I�ȁA�e���݂₷�����̂Ɏv���Ă�邯��ǁA���̐��i�̒��ɉ�������_�R�m�蕗�́A�܂肨��i�ȂƂ���v�����邩��Əq�ׂĂ���B�����āA����̎�����Ȃ��l�́u���邪�����ЁA�債�܂������͂Ȃ��v�u����̐��i�͑債�܂Ƃ����ʂ��Ă���v�Ƃ�����Ă���B�@
���̂悤�ɖ���ɑ���C���[�W�́A���Ȃ蕡�G�Ȃ��̂��������悤�ŁA�����I�ł���Ȃ���s��I�ȉƉ������������炵�������������钅�ڂƂ����C���[�W�Ɏ��ʂ���Ă���B

���̂��Ƃ͂�́A�������풅�ɒ��邯�ǂ��A����͔ޏ��ɂƂ��Ē����̏����ɉ߂����A�܂��Ȃ����R�哇�⑽������ȂǂɈڂ�A����ɖ{���̑哇�⌋��𒅂�悤�ɂȂ��Ă����A����ɑ��ē����̂��삳��́A�����ԁA����𒅂�A���삳���łȂ��V��̕w�l���A�Ȗ���̖ȓ���Ȃǂ𒅂Ă���Ƃ����̂��A����̒����������悤���B�@
�u����͊֓��̏��̈ꐶ���x�z����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��v�Ƃ����ꕶ�ł��̐��M������ł��邪�A����͊֓��̕��y�����D���ŁA���ꂪ����Ӗ��œc�Ɏ҂̏W���̂ł��铌���ň�����A���_���Ƃ����s��̃C���[�W��тт����̂́A��������ȗ��̉�₩�ȕ����̓`���������E��g�̏������ɂ͓c�ɏL��������ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B

70��̒j��(�����1932�N��)�ɘb���@��������u�l���m���Ă�̂́A�V�h�̐Ԑ������ǁA�܂��w���ŃE�u����������A�h��Ȗ���̒������Ă鏗�̐l�������Ă�̂����������ŁA�h�L�h�L��������v�ƌ���Ă��ꂽ�B�₩�Ȗ���𒅂��������F���ۂ��v���̏����Ƃ����C���[�W���������������B

��2�y�j���ł͂Ȃ�����̊X���ώ@���Ă݂Ă��������B�����p�̐l��100�l��1�l�����Ȃ��ł��傤�B�r�W�l�X�W�̐l�����������̒��Ԃ�������Ȃ�����B��100�l��1�l���o���Ȃ���������܂���B�ŋ߂́A����̃z�X�e�X������߂����蒅���𒅂Ȃ��Ȃ�܂�������A��ɂȂ��Ă�����قǒ������p�����オ�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�@
�������͑��߂ɂ݂Ă�1%�A���Ԃ�0.��%�A�܂�1000�l�ɉ��l�Ƃ������x���ł��B����̓��{�ł́A�����𒅂Ă���l�́A���炩�Ƀt�@�b�V�����E�}�C�m���e�B(�����h)�Ȃ̂ł��B�@
���������}�C�m���e�B�_�������ƁA�����ƊE�̊W�҂�M�S�Ȓ������D�Ƃ̕��Ɂu����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��I�����͓��{�̓`�������A�����ߑ����v�Ǝ�����Ǝv���܂��B�ł��A�����͌����A�ڂ��Ԃ�̂͂����~�߂܂��傤�B�@
�Z�N�V���A���E�}�C�m���e�B(���I������)�ƌ�����Q�C�^���Y�r�A���A����Ɏ��̂悤�ȃg�����X�W�F���_�[(���ʉz����)�����킹��ƁA�S�l����3%���炢�͂���͂��ł��B����Ɣ�r���Ă��A1%���邩���Ȃ����̒����l�͂܂������Ȃ����h�ȃ}�C�m���e�B�ƌ����܂��B�@
������A�����������𒅂�ӎ��������Ȃ��}�W�����e�B(�����h)�̖ڂ��炵����A�u�����Ȃ��āA�Ȃɂ����ʂȂ��ƁH�v�Ǝv���̂́A������܂��B�܂��āA����I�ɒ����𒅂Ă���l���ߏ��ɂ�����A�u�ςȐl(�ς���)�v�Ǝv���Ă��d���Ȃ��̂ł��B����̓��{�ł́A�قƂ�ǂ̐l�ɂƂ��āA�����͓���̃t�@�b�V�����I���̑Ώۂ���O��Ă��܂��B�܂�A�����͗m���ɂ��悤���A�a���ɂ��悤���ƍl����l�́A�����ق�̏����h�Ƃ������Ƃł��B�@
�����I�Ȍ��ʂ��Ƃ��āA�����������t�@�b�V�����E�}�W�����e�B�̒n�ʂ����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��ł��傤�B���D�|�p�Ƃ��Ă͖�����ۂ��Ă��A�ߕ��Ƃ��Ă̗����͔������Ȃ��Ƃ���܂ŗ��Ă��܂��B���{�̒��������̂�����������鎄�����́A�t�@�b�V�����E�}�C�m���e�B�Ƃ��Ă̎��o�������A�J�������āA���̃R�X�`���[���E�v���C�Ƃ��āA�����𒅂邱�Ƃ��y���ނׂ����Ǝv���܂��B�@
���́A21���I�ɂȂ��Ă���̒����u�[���́A���������S�Ƀt�@�b�V�����E�}�C�m���e�B�����A���퐫��r����������Ȉߕ��ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��x�[�X�ɂȂ��Đ����������̂ƍl���Ă��܂��B��ʎЉ�̃t�@�b�V�����̘g�g�݂���O��āA�����́u�ّ��v�ɂȂ��Ă��܂������炱���A������t��Ɏ���āA���Ȏ咣�A���ȕ\���̎�i�Ƃ��邱�Ƃ��\�ɂȂ����̂ł��B�@
���Ƃ��A�F�N�₩�Ől�ڂ������͗l����́A���̏��a20�N��A������L�����ɂ���K�v���������u�Ԑ�(���F�����t�n��)�v�̂����������D��Őg�ɂ��������ł����B���̎����m���Ă��錻��70�Α�㔼�ȏ�̒j���̒��ɂ́A�N�₩�Ȗ͗l����ɋ���Ȑ��I�C���[�W���o����l�����܂��B���������Z�N�V���A���ȃC���[�W�������̂��̂Ƃ��č݂�������ɂ́A�f�l�̂��삳��≜���͗l����𒅂ďo�������Ƃ͍���ł����B���̃C���[�W���Y�ꋎ��ꂽ���炱���A�h��h��t�@�b�V�����Ŗڗ����������㏗�����͗l����𒅂ċC�y�ɂ��o�|���ł���悤�ɂȂ����̂ł��B�������A�̂�m���Ă��邨�ꂳ��Ƀi���p����邩������܂��B�@
�ł͒j���́B21���I�̌���A�����p�̃��N�U�Ȃ�Č����ɂ͂قƂ�ǐ�ł��Ă��܂��B����͂����C���f��̃C���[�W�̎c���ł�������܂���B�����炱���A���C�̒j�������藴�̐}����w�ɓ������������p�ŊX�������̂ł��B�����̃��N�U�����������p��������A������Ȃ�ł��|���Ăł��Ȃ��ł��傤�B�����Ƃ��A�ÓT�I�Ȓ����p�̐e���ɓ���Ă��郄�N�U�̊����A�ɐ�����������\���͂���܂����B�@
�܂�A�����̓t�@�b�V�����E�}�C�m���e�B�ɂȂ������ƂŁA�Љ�̕����K�͂z����A�����̎��R���l���ł����̂ł��B21���I�̒����l�́u�ς��ҁv�u�O��ҁv�����炱���̎��R�i���Ȃ���A���������Ȏ咣�A���ȕ\���̎�i�Ƃ��āA�傢�Ɋ��p���ׂ��ł��傤�B�@
�Љ�̕����K�i����O�ꂽ�����́A���i�̎����Ƃ͈Ⴄ�����ɂȂ�A�܂�ϐg�̃A�C�e���Ƃ��Ă͐�D�ł��B�R�[�f�B�l�[�g�ɍH�v������A���h�ȉ�Ћ߂̒j�����u���ԂȂ����ȌZ����v�ɁA�܂Ƃ��ȉ�Ђ̂n�k�����ljƂ̉��l���u���₵��������v�ɕϐg�ł���Ȃ�āA�������f�G�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B�w�i�⏬����ɋC���g���A�����Ƃ����Ԃɏ��a�����⏺�a30�N��Ƀ^�C�����[�v���邱�Ƃ��\�ł��B�Љ�I�����ς��A�N��������āA���璴����A���A�����͐V�����͂��������̂ł��B�@
 �@
�@�^�����
���a8�N(1933)�H�������ɂ��u�^������v�̋Z�@���l�Ă���u��(����)�k(������)�R(������)�v�����i�����ꂽ�B�u�^������v�͑啿�⒆���A���F�����̖͗l�Ɍ����Ă���B�܂����͋��R�����g���A�H�������Ƃ����āA���ڕ��̋��g�Ɉ����������A�����肵���^���̒u��������Ă������F�@�ł���B�@
���^����� 2�@
�͗l�����^�����g���ē��������F�@�B�`�a��h�芣���������^���ɓ���Ђ���悵�Đ���������B���݂������D���Ȃǂɗ��p����Ă��邪�A�^���邱�ƂƁA�z�ɐF�Ђ���悷��^�t���ɏn�������Z�p���K�v�Ȃ��߁A�H�ƓI�ɂ͏��K�͂ɂȂ��Ă���B�@
���^����� 3�@
�Â�����킪���Ŕ��B�����Z�@�ŁA��N���[���b�p�ŊJ�����ꂽ�X�N���[��������A�킪���̌^������ɂȂ�������̂Ƃ����Ă���B�^������̗��j�́A�^����ʂ��Ėh���̂��z�Ɉ�悵�A�V�R�����̈������߂�Z���ɂ���Ēn���߂���������⒆�`�̋Z�p���Â��B�^����ʂ��ĐF�̂����悵�A���M�Ȃǂɂ�蒅�F�͗l����߂������ړ��(�ʂ��F�T�E�^���F�T)�������Ȃ���悤�ɂȂ����̂́A�����������J������Ă���̂��Ƃ��B�@
���āA����Z�p�̒��S�I���݂ł������^��������A���͍H�ƓI�n�ʂ��X�N���[������ɂ䂸�������A���ʑ��i��̉��H�̑�������ƊE�ł́A���`���ƂƂ��ɍ������p����Ă���B

�^�����g���������̋Z�@�B�͗l�����^����u���A�������܂܂������тŖ͗l�𐠂肱�ޕ��@�ƁA�h���Ђ��^���̏ォ��u���ČЂ̂��Ă��Ȃ����n�̕�������߂���@�A�F�Ђɍ����������Ő��n����߂���@������B�^���߂͏���E�g�^�E�^�F�T�E�^�X�сE�ʂ����߁E��@�����߂ȂǁA���܂��܂Ȑ����ɗp�����Ă���B�͗l�ɂ���Č^�����������g�ݍ��킹�ėp���A�F��͗l�ɂ���Ă͕S���ȏ�ɂ��y�ԏꍇ������B�@
���^�� 2�@
���l�����^���ɂ���ĕz�Ȃǂɖh���Ђ�u���ĐF��������@���^���Ƃ����B���̌^����p����^���́A���R����ɋZ�@���������Ă���B�Ȃ��A���q�@�̈�i�Ɍ�����X��h���܂Ƃ��ėp�����낤�(�낤����)�A���l����2���̔ɕz������Ő��߂邫�傤�(���傤����)�A���邢�͎�����(����)��p�������@�ŕ������������犙�q����ɐ��s������������G��(������)�Ȃǂ��^���ƌĂԁB�܂��A�ؔŁE�����œ��ɂ����̂����ȂǁA�^�ɂ����̂̂��Ă����ꍇ������B�@
���^�� 3�@
�^����p���Đ��߂���@�B�܂����߂����̂������B�^���̎�ނɂ͏���A�����A�g�^�A���X�сA�^�F�T�Ȃǂ�����B�Z�@�ɂ͂��낢�날�邪�A�����n�̏�Ɍ^����u���A���̏ォ��h���Ђ��ւ�ł��A�����Ă�����F������@������B�Ђ̕����������c����̂ŁA��ɏ����g�^�ɗp������B�܂��^����u�����ォ��A�������܂܂������тŐ��荞�ސ���X�тȂǂ�����B

�^�����g���āA���������ƌЂ��������ʂ��ЂŐ��ߏグ��F�T�̂��Ƃ������B�z�̏�ɒu�����^���Ɏʂ��Ђ�u���āA�Ђɍ����������n�ɐ���������B��`���F�T�ɔ�ׂėʎY���\�ŁA�����Ȃ��Ƃ���}���ɔ��W���A���݂̓���̊�b�ƂȂ����B���̋Z�@�͗F�T�ȊO�ɂ��L���p�����Ă���B�@
���^�F�T 2�@
����@�̈Ⴂ�ɂ���Č^���F�T�Ƌ@�B���(�X�N���[�����A���[���[��)������B�@
�^���F�T�ɂ��ĉ������B�^���F�T�͎ʂ��F�T�Ƃ��Ă�A�^����p���Đ�����(�F�T�Ђɐ����Ə��܂�������������)�Œ��ړ�����邩�A�܂��͖h��������@�ł���B�����^����p�������@�ɂ́A�h������Ƃ���������߁A����ɁA�����t�ɂɂ��ݎ~�߂̂��߂̑���(�Ⴆ�g���K���g�S���Ȃ�)�������Đ����p�̍��тŐ��荞��Ő��߂�A�����F�T������B�����F�T�́A�����������ۍ��т̎g�����ɍ��x�̋Z�p��K�v�Ƃ��锼�ʁA���ɑ@�ׂȖ͗l����ߏグ�邱�Ƃ��ł���B�^���ߗF�T�S�̂Ƃ��Ă݂��ꍇ�A�ق��ɒ����`(���ނō��ꂽ���̕\���ɒ��`�p�ؖȐ��n��\��L���A���̏ォ��^����p���Ėh���Ђ�u�����@)��A����(���`���n�̊��������̂����E�Ɍ��݂ɐL���Ă͐܂��݂Ȃ���A���̓s�x�A�^���Ėh���Ђ̌^����������@)�Ȃǂ̐��F�@������A�����͗��߂���߂�ꍇ�ɗp������B

���s�Ő��Y����������̑��̂Łu���F�T�v�u�����̎q�v�Ȃǂ������B���s�͌Â����當���̒��S�n�ł���A�{��̕����B����K�v����O���̍��x�ȋZ�p����������������Ă������Ƃ���A���߂̋Z�p�����W���Ă����B�܂��A���ߕ��ɕK�v�Ȑ��̎����悢���Ƃ���A�N�₩�ɐ��ߏオ��Ƃ����A�����߂͏㓙�Ȑ��ߕ����Ӗ����Ă����B�@
�����F�T�@
���s�Ő��߂���F�T���B���\����̋��s�̐�G�t�A�{��F�T�ւɂ���Ďn�����B���ڌЂŖ͗l�̐��������h���@�ŁA�F�������肠�킸���ʂȊG�͗l���\�ƂȂ����B�傫���₩�ȑ��ԕ��l�����S�ŁA�ЂƂ̖͗l�𒆑���Z���O�Ɍ����ĒW���ڂ������@�ƁA�����F�łނ�Ȃ����߂���@�Ŕz�u����Ă���B�@
�ԂŖ͗l�̉��G��`���A���̐��̏�Ɏ��ڌЂ�u���A�M�E���тōʐF�����͗l�̏�ɕ����Ђ�u���Ēn�F����߁A���C�ĂĔ��F�ƐF�ǂ߂��s���A��������B�����̐���H�������ׂĕ��Ƃōs���A���ꂼ��̐��̋Z�p�ɂ��ꖇ�̎�`���F�T���ł��オ��B�@
������F�T�@
����̋���Ŕ��B�����F�T���B�]�ˎ��㏉���ɔ��B���A�Â��́u�\�o��z�v�ɔ~�̔��`�a�Ő��߂�������߂�����B��Ɍ��ɐ��F���������̂�������A����ɋ{��F�T�ւ̎��ڌЂ̎�@���������āA����F�T�ƂȂ����B�F�ʂ��ڂ����ɂ���ĉA�e�����A�ڂ����̋Z�@�͋��F�T���������Z���O�Ɍ������ĒW���Ȃ�̂ɑ��A����F�T�͊O�����Z���A�������ĒW���Ȃ��Ă����u��ڂ����v�ł���B�F���́A�b���E���E�E���y�E�������S�Łu����܍ʁv�ƌĂ�Ă���B�h�J�┓�u���Ȃǂ��{�����A�`����鑐�Ԃ������߂ŁA�₩�ȋ��F�T�ɑ��ēƓ��̗�������������̂������B

�����������F�f�Ő��߂���̂Łu�����������߁v�Ƃ������B�����E�ؔ�E�ԉʂȂǂ��Ϗo�����t�`�ɐZ���Đ��F������̂ɂ́A���q(�����Ȃ�)�E�T��(������)�Ȃǂ�����A�t�`�Ɏ_��A���J����p���A�܂��Ҍ���p��������F���@�̂��̂ɂ́A���E�g�ԁE���E�����E�����Ȃǂ�����B�������ނ̔}���܂��g���Ĕ��F�Œ肷����@������A����ɂ͑h�F(������)�E�I��E���O�E�b�h�̎���ʊk�Ȃǂ��p������B���̋����}���̑��ؐ��͐l�����������������܂ŏd�v�Ȑ��F�@�ŁA�[�������������F�����e���܂ꍂ�����D���ɗp�����Ă����B

�]�ˎ��㖖���ɋʎ��₭�����Ȃǂ𗘗p���ĐD��ꂽ���D�肩��]�������D���ŁA�֓��̈ɐ���E�����E�ː��E�����Ȃǂ���ȎY�n�B��v�ň����Ȃ��Ƃ���L���e���܂�A�u�i�����v�u�ʕ�����v�u�W����v�Ȃǂ��܂��܂Ȏ�ނ�����A���ڂ���Ȃǂɗp����ꂽ�B

�^�������邽�߂̎����^�n���܂��͒n���Ƃ����B�^�n���́A�㎿�̞��̎荗����p����B�荗�̍ہA���̑@�ۂ͏c�ɕ��Ԃ��߁A�`�a��2�����邢��3���\�荇�킹�邱�Ƃɂ���Ď��̑@�ۂ��c���d�Ȃ�悤�ɂ���B����̂悤�ɐ}���ׂ̍������͔̂���2�������A���`�Ȃǂ�3���������p�����邱�Ƃ������B�^���́u�^�v�̎��́A�]�ˎ���͂��ׂāu�`�v��p���Ă������A���a�ɓ��������ɂ́u�^�v�Ɓu�`�v�����p����A�Ȍ㏙�X�Ɂu�^�v��p���邱�Ƃ������Ȃ����B�@
���^�t(������)�@
���n�̏�Ɍ^����u���A��(�ւ�)�ɂ���Ėh���Ђ�u���Ă�����Ƃ������B�u�Вu���v�Ƃ�������B�@
���^���@
����A�����A�^�F�T�Ȃǂ̓���ɗp����A�͗l�����^���̂��ƁB�^���́A�`�a��h��ϐ��������������A�����a���𐔖����荇�킹�A�\���Ɋ��������Ă���͗l��B�^���̐���́A�]�ˎ��ォ��I�B�̔��q�Ǝ���(�O�d���鎭�s)����Y�n�Ƃ��Ēm���A�ɐ��^�Ƃ��Č��݂Ɏ����Ă���B����́A�I�B�˂̓��ʕی쏧���ɂ����̂ł���B�@
���^����@
�^������ɂ����߂�ꂽ����B�{������͌^���̂��̂ł��邪�A����̖��̂����݂ł͎�`������A�X������܂Ŋg�債�ėp������̂ɑ��āA���Ɍ^���̏�����������ڂ̂��Ƃ������B

�^���G�t���̋Z�@�͒P�ɐ��G(���肦)�Ƃ��Ă�邵�A�^�����肠�邢�͌^�����(�Ȃ�����)�@�Ƃ��Ă��B��O�n���ł͍��H(������)����̕�����ʓI���B���̂͗l�X�����A����������l���ʂ����^������ʂɂ��āA���̏ォ��M����тŊG������肱�ދZ�@�������Ă���B�@
�^����������̊G�t���ɉ��p���ꂽ��́A���Z�n���ł�17���I�㔼���̌�[��(���ӂ�)�l���̐��i���ł������Ƃ����B���̏ꍇ�G��͓S�ł���A���F�̑��ԕ��⏬�䂪�G�t������Ă���B�Ó��Âɂ����Ă��S�G��̌^���G�t�����Ђ���������Ă���A�ʓI�ɂ͏��Ȃ����]�ˑO���ɂ͔�O�n��ł�����Ɍ^�����g�p���ꂽ������邱�Ƃ��ł���B�܂��G��ł͂Ȃ����A�������ϓy��p�����^�����іځ�1�̌Ó��Ð��i������A�Z�p�I�n�����������鎑���Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B�@
�^�����A���퐻�i�ɐ��t�Ƃ����������Ŏg��ꂽ�̂�18���I�ȍ~�Ǝv���A��i7�N(1710)�̔�����������Èɖ������̂�����Ă���B���Z���O�ňꎞ�I�ɗ��s�������̎�@�́A�]�ˌ���ɂ͎p���������B�����������O���ɕ������A�S���̎���q�Ő���ɗp����ꂽ�B��B�ł͔�O�n��͂��Ƃ��A�V���̍��l�q��F���̕����q�ł��p�����Ă���B�@
�^���G�t���́A���G�ȕ��l�ł��^������U����A�ϐ����̂��鎆�͏�v�Ȃ��߉���ł��g���A���̊G�t���͊ȒP�ő����B���i�͑�ʐ��Y�̓��p�i���قƂ�ǂł���B��������ɑ嗬�s�����^���G�t�����A���]�ʂ̓o��ɂ���đ吳����ɂ͐��ނ����B�@
�ʐ^�̉Δ��͌��a21.7cm�A����20cm�̐��t����ł���B�G�t�����̃x�^�h����̂����Ƃ��ׂČ^������ŁA�C�g(����������)�E���O�ɐ�E�����E�@�ٕ���2��4��̌^�����g���Ă���B��������肩�����ĊG�t������邪�A�����Ƙ@�ٕ��ɂ͌^�̏d�Ȃ肪�݂��A���ꂩ���̌^���̑傫�����킩��B�g��ʐ^�ł́A�^���G�t���̓��F�ł���j���ƍ��т̃^�b�`(�ԕق̉��ȁB�c�Ȃ͑f�n�̎d�グ�ɂ�����)���݂���B

����z�S�̂���F�ɐ��߂�̂ɑ��āA�������F���邱�ƂŖ͗l��\�����F�@�̑��́B�������Ђɍ����āA���ڕz�n�ɐ��������^��p���Đ��߂�B�͗l��\���Ƃ����L���Ӗ��ł́u��`���F�T�v�u�i����߁v�u�낤�����߁v�Ȃǂ�����̈��ŁA��Ɍ^���g�������̂ɑ��Ă����ꍇ�������u�^�F�T�v�u����v�u�X�сv�Ȃǂ�����B�@
����� 2�@
�z�n��i���ɐ�����痿����悵�Ė͗l���������F���@�ŁA��ʂɂ̓v�����g�ƌĂ�Ă���B�@�ۂɐ������������錴���͐Z���Ɠ��l�ɍl�����邪�A�����̈������⑀����@�͑S���قȂ�A�Z��������}�̂Ƃ���̂ɑ��āA����͌Ђ�}�̂Ƃ��Đ��F���s�Ȃ���B�͗l�����^�ł�p���ĐF�Ђ�z�n�Ɏʂ�����A�������Œ����邽�߂̏��M�������{���B���̌�A�]���ȐF�Г����������邽�߂ɐ����܂�p���Đ�s�Ȃ���B�痿��p�������́A�^�łŐF�Ђ��v�����g���邱�Ƃ܂ł͓��������A����������Ɋ��M�������{���ăv�����g���H���I���_���قȂ�B�@
���ł̌^���@
������ɓ���Ђ��ʂ��ł̌^���ɂ́A�ʔŁE���ŁE���ŁE�E�ł�����A�����̓t���b�g�̂��̂ƃ��[���`��̂��̂ɕ������B�ߔN�R���s���[�^�Z�p�̔��B�ƂƂ��ɐ��ŋZ�p���ω����A�g���[�X�t�B�������g�킸�A�R���s���[�^��ŐF���������G����ŏ�ɒ��ڑł��o������(�_�C���N�g����)���Ƃ���悤�ɂȂ��Ă����B�@
����������@
����͎����@�Ƌ@�B����@�ɑ�ʂ���A�Z�@����͒��ړ���@�A�h���@�A�����@�A�h�����@�A�^�t�Z���@�Ȃǂɕ�������B�ߔN�R���s���[�^�Z�p����g�����V���ȓ���Z�@�Ƃ��Ė��Ńv�����g(�C���N�W�F�b�g�v�����g)�����ڂ���A�Z�p�J���������߂��Ă���B�@
���̑��������Ƃ��āA�t���b�N����A�X�v���[����A�}���`�J���[�v�����g�A�I�p�[�����(���H���H)�A�ʐ^����A�Ód����Ȃǂ�����A���ʂȊG���\�����\�ɂ��Ă���B

������痿��p���đ@�ۂ��̑��̔�����ɉ��w�I���邢�͕����I�ɐF�f����F�Œ肷�邱�ƁB���̑f�ނ͑@�ۂƐ����ɓ��ʂ���邪�A�@�ۂɂ͐A�����@�ہA�������@�ہA���w�@�ۂ�����A�����ɂ͓V�R�����ƍ�������������B�����͑@�ۂ̎�ނɂ���ēK�ۂ�����A�����Ƒ@�ۂ̐����ɂ���Đ��F�@���قȂ�B�@
���F�@�͑傫��������ƁA���ڐ��@�A�}�����@�A�Ҍ����@�A���F���@�A���U�y�@��5��ɂȂ邪�A���̊�{�͐��ɗn���������̕��q���@�ۂ̂Ȃ��ɂ��݂���ő@�ە��q�ɌŒ肳��邱�Ƃł���A���̉ߒ��Ɋ܂܂�鉻�w�I�E�����I��p�̑���ɂ���ĕ��ނ����B

���n���̐�����n�������n�t���ɑ@�ۂ�Z���Đ��߂���@�B�ؖȁA�l���A���ɂ͒��ڐ����A�r�сA���ɂ͎_�������A���ɂ͉��������p���Ē��ڐ��@�Ő��߂邱�Ƃ��ł���B���Ƃ��Β��ڐ����ŖؖȂ���߂�Ƃ��́A�����n�t��80-90�x�ɉ��M����Ɠd�����̌��ʂ������Ȃ�����ʂ���������B���ߕ��Ƃ��Ă͍ł��ȒP�ȕ��@�����A���������Ɏキ�A�ϐF�E��F���������₷���B���̂��ߓ���N�����ȂNj����C�I���n�t��z���}�����n�t�œ������S�x�E���S�x�����߂�㏈�����s���A�F�~�߂��{���B�@
���}�����@�@
�������̂��̂ɑ@�ۂɑ�������͂��Ȃ��ꍇ�ɁA�}���܂�p���đ@�ۂƐ������ԐړI�Ɍ��������Đ��߂���@�B�ؖȁA�l���p�̉�������A�r�їp�̎_���}�������A�V�R�����̂قƂ�ǂ͔}���܂�K�v�Ƃ���B�}���܂Ƃ��Ă͐|�_�A���~�j�E���A�|�_�S�Ȃǂ̓S���A�N�������A�X�Y�������Ȃǂ̎㉖��E��_����p����B�@�ۂ�}���ܗn�t�ɐZ���ĉ��M����Ɣ}���܂͉����������������ċ����_�����ƂȂ�A���������n�t���ɐZ���Ɛ����Ƌ����_�������������āA�@�ۂɍ��x�̐�����^���邱�Ƃ��ł���B�@
���Ҍ����@�@
�s�n���̐�����p����ꍇ�ɁA�������Ҍ����Đ��n���̉������ɕς��đ@�ۂɐ��������A������_�����đ@�ۏ�ŐF�f���Đ����Đ��߂���@�B�ؖȂ▃�Ɍ��������◰��������p����ꍇ�A�A���J�����̃n�C�h���T���t�@�C�g�◰���i�g���E���ŊҌ�����ƁA�����͐��n���̃��C�R�������ƂȂ�@�ۂɐ��܂�B���܂����@�ۂ���C���ɂ��炷�ƁA�������������͎_������A�@�ۏ�Ō��̕s�n�������ɖ߂�F�f���Đ�����B�����������Ҍ����鑀����u���Ă�v�Ƃ����A�����������Ҍ����鑀����u�����v�܂��́u�`�I�l�[�V�����v�Ƃ������A�ߔN�ł͂��炩���ߐ��n���̃��C�R�������̌`�ɂ����n����������������A�r�їp�ȂǂɎg�p����Ă���B���̐��F�@�͓������S�x�E���S�x�Ƃ��ɂ�������p�I���l�������B�@
�����F���@�@
�s�n���̐����ŁA�Ҍ�����Ɛ������������ĐF�f�̍Đ����ł��Ȃ��ꍇ�ɁA�F�f�̌����ƂȂ镨��(�������ԕ�)��@�ۂɏ������݂��܂��A�@�ۏ�ŐF�f���������Đ��߂���@�B�ؖȂ�l���ɗp����i�t�g�[�������ɂ����F�͂��̐��F�@�̑�\��ł���B�܂��@�ۂɃJ�b�v�����O�����ƂȂ�i�t�g�[�������Ѝ܂Ƃ��Ă��݂��܂��A������W�A�]�������܂ތ��F�܂ɂ���Ƒ@�ۏ�ŕs�n���̐F�f���������ꔭ�F����B���̍������w�����Ɏg�����ԕ����i�t�g�[�������Ƃ����A��������E���F�����Ƃ�������B���ݖ�30��̉��Ѝ܂Ɩ�50��̌��F�܂��g�p����A���̑g�ݍ��킹�ɂ����1,500�̐F����������B�������S�x�E���S�x�͋������A���C�ɑ��Ă͎ア�Ƃ������_������B�@
�����U���@�@
�n���ł͂��邪�n��x�̏��������U�������E�������܂�p���Đ����ɍׂ������U�����Đ��߂���@�B�����@�ۂȂǑa�����̑@�ۂ���߂�ꍇ�́A���n���̐����ł͑@�ۂɐ������Ȃ��܂Ȃ����߁A���ɗn���ɂ��������n�t���ŕ��U�����s���A�@�ے��ɐ������q�����݂��܂�����@���Ƃ���B���̐��F�@�ł́A��C���̎_�����f�ނ̍�p�Łu�K�X=�t�F�[�f�B���N���ہv��������G�F���������̂����_�ł���B�@
�����F���@�@
���F���@�͖��n���Ɩ͗l���ɕ�������B�@
���n���̗��j�͔��ɌÂ��A�����炭�a�D�Z�p�̔����ɂ��ōs���͂��߂����̂Ǝv����B���E�ŌÂ̖��n���̈�i�Ƃ��ẮA�G�W�v�g��12����(�O1991-�O1786)�̕悩��o�y�����~�C��2�̂̉����F�̊��z������A����ɂ͍g�Ԑ��ƓS�}�������p�����Ă���B���n���͑@�ۂɂ���ĕK�v�ɉ����Đ����A�Y�����s���A������邢�͋@�B���ŐZ���E�����E�����E�p�b�f�B���O�����̑��̕��@�ɂ���Đ��߂邪�A�S�̂��ψ�ɐ��܂邱�Ƃ��d�v�ł���B�ؖȂ▃�͐��F�̑O�ɕY�����s�����A18���I�����疖�ɂ����ĕY���H�Ȃ����P����A19���I�̖a�D�̋@�B���A���������̔����ɔ������S�Ɏ�H�I���@����E�炵���B���n���p�̐��F�@�B�Ƃ��ẮA���p�Z���@�A�z�p�Z���@��2�킪����A�z�p�Z���@�ɂ́A�ѐD���p�E���D���p�E�k�D���p�̘g���@�A�W�F���p�̃p�b�f�B���O���@�A�l���ȂǑ@�ۂ̐L���x�̍����z�p�̃W�b�K�[���@�Ȃǂ�����B

�͗l���͎�ށE���@�Ƃ������A�Z�@�ɂ���ām���n�͗l�ڈ�Ԃ�����@�A�m���n�͗l�̕�����h���������Ēn��Z��������@�A�m���n�͗l�̕��������Ė��n���ɂ�����@�A�m���n���̑��̓���Ȗ͗l���ɑ�ʂł���B�m���n�ɂ͕M�A���сA���Ȃǂ�p���Ē��ږ͗l��`���Ă����`�G�A�`�X�сA�`�F�T�A�X���Ȃǂ̋Z�@�ƁA�^��p���Ē��ږ͗l����Ԃ��Ă����F�G�A�����Ȃǂ̓���Z�@������A�`�G�A�`�X�т̗ނ͂��Ȃ�Â�����G�W�v�g�A�C���h�A�y���V�A�A�����ōs���Ă����B�܂����ڈ@�̌^�Ƃ��ẮA�^��(�����^)�E�X�N���[���^(�����^)�E�،^(�ʔ�)�E����(����)�E����(�ʔ�)�E�����[���^(����)���̑�������A�ؖȂ̌��Y�n�ł���C���h�Ɏn�܂�������Z�p���G�W�v�g��C���J�܂œ`��������̂Ƃ݂��Ă���B�C���h�ɂ͖�2000�N�O�̓���(�e���R�b�^�^)���c���Ă���A�킪���ł͖،^��Ԃ̓F���z�傪���q�@�ɑ����c���Ă���B�ߐ����[���b�p�ł̓t�����X�𒆐S�ɖؔœ���Z�p�����B���W���C�X�тƂ��Ēm���A17���I���ɂ͖ȍX�т̓��œ�����e���ɕ��y�����B�܂�����Z�p�ɂ͖ȐD���H�Ƃ̔��B�ƂƂ��ɐi�W���A�Y�Ɗv�����}�����1797�N�C�M���X�ŗ֓]������@���������ꂽ�̂��͂��߁A1834�N�A�t�����X�Ńy���`������@����������A�ߔN�ł͈ꎞ��16�F���炢�܂Ő��F�\�ȑ��F����@�̏o�����݂��B�m���n�̖h���͗l���ɂ̓��E�P�c�E�㒁E�R�E�P�c��3㒂ƍi���Ȃǂ̋Z�@������A���E�P�c�ɂ͕M�E���Ȃǂ�p���Ėh���܂̘X�ڎ�`������̂ƁA�،^������^��p������̂�2�킪����B��`�A�^�g�p�Ƃ��ɖ͗l�̕����ɘX��u���n���������ƒE�X������̂����A��������Â�����L�����z���A6-7���I�G�W�v�g�Ŏg�p���ꂽ�،^���c���Ă���B�킪���ł͓��㒆������`����ꂽ�،^���E�P�c�@���������ケ��܂ōs���A�㒂͎��ŐD���̈ꕔ���������Ėh������i���̈��ŁA�ڌ��⌋�@�E�R�E�P�c�ƂƂ��ɓޗǎ��ォ��s���A���q�@��̂Ȃ��ɑ����̈�i���c���Ă���B�R�E�P�c�͕����I�ȗ͂������Ėh��������̂ŁA�܂肽���z�n��ɝp��Œ��߂Đ��߂�P���Ȕ����ƁA�͗l��z�������A�����̌^�ɝp��Ő��t���A�����ɒ������Đ��߂���̂�����A���㒆������`��������̂ƍl�����Ă���B�i���̔����̓C���h�N���Ƃ݂��Ă��邪�A�G�W�v�g�A�y���V�A�A�����A�C���h�l�V�A�����Ȃǂ���߂čL�����z���A�킪���ł��ޗǎ��ケ�납�甭�B�����B�i���̎�ނ͎��̎q�i�A�C�c�i�A�O�Y�i�A�{�V�i�A���e�i�A����i�Ȃǂ�����A����������y���R����ɂ����Đ��s�����҂��Ԑ��͐��I�ȍi���ŊG�͗l��\���A��ʐF�����������̂�F���E�D�����{�������̂����ꂽ�B�m���n�̔����@�͉��w�I�ɔ����ł����������������Ă̂��ɍs���͂��߂����̂ŁA�n��������ɔ����܂��������̂��u���A�͗l�̕����𔒔����ɂ�����̂ƁA�����̂�ɔ����ł��Ȃ��������������F�̂��p���Ē��F�������s�����̂�����B���̋Z�@�͗֓]����@�Ȃǂɗp�����A���ݍL�����p����Ă���B�m���n�̓���Ȗ͗l���Ƃ��ẮA��������̒W���A���Z�A���Z�Ȃǂ̖n��������A�~���Ă͗ʗF�T��n�������A�F�̂藬�����Ȃǂ�����B
 �@
�@�]�ˏ���
�ɂ߂čׂ����͗l��蔲�����^��(����^)��p����^���߂̈��B����Ƃ������ɁA�O�����ČЂ�h���Ēu���A���点�����т��g���āA�����t���悤�Ƃ��锒���n��\��t����B���̏�ɋɍׂ̖͗l��蔲�����^�����ڂ��A�ւ�ŌЂ��ϓ��ɂ̂�(�^�t���)�B�����n�͈ꔽ��12m�ȏ�̒���������A�^�������炵�Ĕ����n���ׂĂɓ�����Ƃ��J��Ԃ��B�^���̐蔲���ꂽ�Ƃ��낾���̐��n�ɌЂ��^�t�������B�^���̑傫���ɂ���Ă�50-100��^�������炵�Ȃ����Ƃ��J��Ԃ��B��������Ȃ��悤�A1mm�ɂ������Ȃ��_��ыقǂ̐��łł��Ă���͗l���Ԃ�Ȃ��悤�ɁA���̔����Ȃ��T�d�ȍ�Ƃ̘A���ł���B��H���Ŕ��n�S�̂ɐ������܂�ׂ�Ȃ��h��(�n�F����)�A�������ō����蒅������(����)��A����ƁA�ŏ��̍H���̌Ђ������A���̕�����������(�͗l)�Ƃ��Ďc��B���ꂪ�^���߂ł���B��̔����ɑ��Đ������^�������炵�Č^�t�������̂ŁA���̐ڑ����ŋɍׂ̕��l����a���Ȃ��Ȃ����Ă��邩�A�ɍׂ̕��l�����c��A�Ԃꂽ�肹���ɂ�����Ɠ������Ă��邩�A�ɍׂ̕��l���n�F�̟��݂��Ȃ��A��������ƕ����яオ���Ă��邩�Ȃǐ���ɂ͐��F�ƂƂ��Ă̐[���o���Ən�B�����Z�p�A�C�̉����Ȃ�悤�Ȏ�ԂƏW���́A�f�U�C���E�ʐF�E�z�F���̃Z���X���K�v�ɂȂ�B�@
�]�ˏ���͂��Ƃ��ƍ]�ˎ���ɕ��m���߂Ɏg���A���R�Ƃ��n�߁A�e�˂͓���̕����߁A���̔˂̃V���{���Ƃ��邱�Ƃ��������B�]�˒����ɂ͏����̂������ł�����ɗp�����A���ȃZ���X�������钬�l�����̔��W�ƂƂ��ɁA���̎�ނ��F�g��������I�ɑ��������B�������猩��ƈꌩ���n�Ɍ����鏬��́A�߂��Ō���Ƒ@�ׂȕ��������ɂ���߂��A���x�ɋ�g���ꂽ�Z�p�͂܂��ɍ]�˂́u���v���ے�����H�|�i�ł���B�@
����̖��Ƃ�����̂��^���ł���B�]�ˎ���ȗ��A�O�d���͈ɐ��̔��q(���E�鎭�s)�t�߂ō����ɐ��^�����g����B���̒n�͋I�B����Ƃ̔�ђn�ŁA�I�B�Ƃ̕ی쐭��ɂ��Z�p�̌p���A���オ�Ȃ���Ă����B�^���͏�v�Șa�����`�a�Ő����d�˂ē\�荇�킹���n���Ɏ��ƂŖ͗l�������̂ł���B�@
����̕��Ƃ��Ắ@
�u�L�v�@�]�ˏ���̍ł���\�I�ȕ��ŁA��ʂɍׂ����_���L�̔��ɐ��ߔ��������l�B�@
�u�p�ʂ��v�@�ׂ��������`���c���ɂȂ�������Տl�B�@
�u�s�V�ʂ��v�@��������̏����ȕ��l���A�c���ɕ���ł�����́B�@
�u����ꏬ��v�@���N�̗ǂ����́A�ڏo�x�����̂l�ɂ������́B��s����(���N�����W�߂����l)�A�|�ɐ��Ȃǂ��܂��܂̕��l������B�@
�u�і����o�v�@�]�ˎ��㈤���ꂽ�ȕ��l�B1����36�{�̋��قǂ��������̂�����B
 �@
�@���l�X�J�[�t
���l�̊J�`�������琶���͓��{�̗A�o�̎�v�i�ڂŁA���H�i�ł��錦�͍ŏ��͂��܂�A�o����Ă��Ȃ������B����6�N(1873)�̃E�B�[������������œ��{���ގсA�c��Ȃǂ̌��D�����o�i�����B���̂Ƃ�����ŃE�B�[���ɍs�����̂��Ŗ쐳���q�ł���B�Ŗ�͌��D�����O���ɏЉ�邾���łȂ��A���[���b�p�̋Z�p���K�����Ă����B���ꂩ��2�N��ɃA�����J�Ƀn���J�`��A�o�����̂��A���{����̌��n���J�`�̗A�o�̑�ꍆ�ł���B���̂���́A�܂����n�����n�̐����������B�ŏ��̕����̂͒Ŗ쐳���q���X������18�N�A�����J�ɗA�o�������̂����ڍׂ͂킩���Ă��Ȃ��B����23�N�t�����X�l�̃��j�[�����ؔł������Đ��߂��n���J�`����点�A���ꂪ�]���ɂȂ�A������F�D���̗A�o���������B�@
���l�̃X�J�[�t�͕��G�ȕ��Ƃōs���Ă���A����͗A�o���n�܂������납��̗��j�ɂ����̂��B�����A�o�̒��S�͐����Ǝ҂́u�n���J�`���v�ƌĂ��l�����ŁA�ŏ��̂���̃n���J�`���͐����Ǝ҂Ƃ�����蔄�����ŁA�O�����ق���n���J�`�̎����B���قɂ�����{�l�ԓ��Ɛe�����Ȃ�d���������B�d����������܂��A�X�P�b�`���ƌĂ��f�U�C�i�[�ɃX�P�b�`�����������B���̂��߂ɓ����낻�̍��̚n�D�̏����d����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�X�P�b�`���O���ɑ���������ł�����������āA�߂��Ă��Ă͂��߂Đ��������ɂȂ����B������n���J�`���͌������d����A��������Ǝ҂ɓn���Đ��F���Ă�������B�X�P�b�`������ۂ̌^�����̂͌^�����ƌĂ��E�l�ŁA�n���J�`�����甭�����ꂽ�B���F���I������D���ْ͍f�A�D�����s���A�D���Ǝ҂���͉�������̎d�����ƒ���E�ɍs�����B���̂悤�Ƀn���J�`���𒆐S�ɂ��܂��܂ȋƎ�̐l�̕��Ƃɂ���ăX�J�[�t�����������B���̗���͖������猻�݂��傫���͕ς���Ă��Ȃ��B�n��Ƃ��Ă͊O�����ق͎R�����̂�����A�n���J�`���͍��̊֓��w�̖k���A����Ǝ҂͑剪����q�쉈���ɂ���A���̎��͂ɉ��H�̓��E�҂������B�@
���l�ōs���Ă����̂́A�������̂��̂₻���D���ɂ���ł͂Ȃ��A���D���ꂽ���̂i�ɉ��H����Y�ƂŁA���̒��ł��͂��܂��܂ȃf�U�C���ɐ��߂��������S�������B

����́A�z�ɐ����Ő}����͗l��������邱�ƂŁA���̈���Ɠ����悤�ɂ��낢��ȕ��@���g���Ă��B����͖ؔŁA���^���o�Č��݂̓X�N���[������ɂȂ��Ă���B�@
�ŏ��͖ؔœ���ŁA���Ɉ������ؔł����p�������̂ł���B�J�`�����͒��̗A�o������ŁA�����̃��x���͖ؔł��g���č����Ă���A���̍��t���n���J�`���������悤�ł���B�u�Ŗ؉��v�����̖��g���ؔł�A���n�͂��炩���ߐ����`�ɐ��Ă����A���������̗m���Ƀ��E��h�����䎆�ɓ\����A�ؔłɐ����t���n�P�œh��A���̏�ɐ��n��\�����䎆���ڂ��A�o�����Ƃ�������ł�������@�ł���B����l�́u�ؔʼn��v�ƌĂ�Ă����B���̌�A���n���Z�C���ŏ����Ċ��������B�{���͂��̌�ɐ���ƐF���������Ȃ��̂ł����A���Ƀn���J�`�̑傫���ɐ��Ă��邽�߁A��Ő��邱�Ƃ��ł����A�F�������₷���̂����_�ł������B���ʁA�\���\�͂������A�����Ȑ}������邱�Ƃ��o�����B�ؔł͏��a20�N��܂ōs���Ă����B�@
�ؔł�������ʔň���Ȃ̂ɑ��āA���^���g���A�������������������������A�E�ň�����s��ꂽ�B�E�łł͐�����0�̂悤�ȕ���ƁA���̕��������������Ă��܂��̂ŁA�h�����߂ɐ}����2���̌^���ō��Ƃ������@���Ƃ�ꂽ�B����͒ǂ���������ƌĂ�Ă����B�^���Ɏg��ꂽ�̂͘a���Ɋ`�a��h���ē\�荇�킹�Ă����������a���ŁA����������Ő�ʂ��Č^�����A���̌�ł��邵��h���ĕ⋭�������̂ł���B�ؔłƈႢ���ڂ̕����o���A���ɂ��F������h�����Ƃ��o�����B�@
���a��������A�ؔł⎆�^�ɑ����āA�X�N���[������̋Z�p���������ꂽ�B�^���ɂ̓p���t�B�����Ƀ��b�N�X�j�X��h�������b�N�y�[�p�[�ƌ������̂��g��ꂽ�B���^���l���b�N�y�[�p�[�ڒ���A���̌�A�X�N���[���̏�Ƀ��E�ŌŒ肵�A�A�C�����ŔM�������邱�ƂŁA���b�N�y�[�p�[���X�N���[���ɓ\����^�ɂ����B���ɂȂ�ƒ������ɁA�������ł��s����悤�ɂȂ����B�ŏ��̂����͗֊s�ׂ̍����Ƃ���̂݊������ł��g���A����ȊO�̂Ƃ���͒��ڒ����Ă������A�₪�Ă��ׂĊ������ł��s���悤�ɂȂ����B����ɂ�蒤�t�̍�Ƃ͕����ʂ�u����v���Ƃ���A�g���[�X�̍�ƂɈڂ�ς�����B���݂ł���{�I�ȕ��@�͓��������A�@�B�̎��������i��ł���B

�R�������̓�����ɃC���h�̐���������B����͊֓���k�Ђ̎��̒g���������Ɋ��ӂ��ĉ��l�C���h���g�����牡�l�s�ɏ��a12�N�Ɋ��ꂽ���̂��B���̂��뉡�l�ŃC���h�̐l����������Ă����̂��ȑO����s�v�c�Ɏv���Ă������A���̓X�J�[�t�ƊW���������̂��B�֓���k�Ђʼn�œI�Ȕ�Q���������l����A���D������F�̋Ǝ҂݂̂Ȃ炸�O���̏��ق��_�˂ɔ����B�������l�`�̌��D���̗A�o��3���̓C���h�̏��ق������Ă���A��������l�ɕ��A���Ă��炤���Ƃ����l�̌��D���ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ƃ������B���̂��߁A�Z���X�܂����݂��Đ_�˂���̕��A��U�v���A���N�ɂ�16�Ђ����l�ɋA���Ă������A���̎��̈����Ɋ��ӂ��ăC���h�̏��g�����牡�l�ɑ���ꂽ�̂����̐����Ȃ̂��B
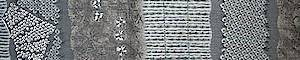
����6�N(1859)���l���J�`����āA�����̗A�o������ƂȂ�A�������猦�D���̗A�o�̗���̒��Ō��̃n���J�`�[�t�����܂ꂽ�B�E�B�[��������������_�@�ɊO���ɗA�o���ꂽ�B����10�N�ォ��A���n���߂���v�����g���̂��A�o����A�ؔœ��(�����G�ʼn�Ɠ���)����A�o����Ƌ��ɁA�^���̌^�ō��тŐ��߂�u���ѐ��v�ƂȂ�A���a�����ɃX�N���[��������J�����ꂽ�B���A�X�ɗ����ƂȂ�A�A�o�͐��E�V�F�A��80%���߂����������A����10�N���܂ł͍�����90%���߂Ă����B�ߔN�́A�O���u�����h�i���������Y�ƂȂ������Ƃ�t�@�b�V�����̕ω��Ȃǂɂ�萶�Y�͋}���Ɍ������Ă��Ă���B�@
���l�X�J�[�t�̓��F�@
���Y�\���̐�����������A�f�ށA���ŁA����A���F�����A�D���A�f�U�C�i�[�����܂��������ĎY�n�`�Ԃ��������Ă����B���Ɏ����̋Z�p��120�N�̓`���E�l�|�ŁA���̋Z�p�����̓t�����X�A�C�^���[�̐����Ɠ���ŁA���̃E�X�n�v�����g�Z�p�͐��E��ł���B
 �@
�@���s�̘a�����F��
���F�T�͉䍑�ɂ�����������̑�\�I�ȕi��ł���A���a51�N�ɓ`���I�H�|�i�w����Ă���B���Y�ʂ͑S���̐��������Y�ʂ�9���߂����߁A�����ǂ���������̑S���ő�̎Y�n���`�����Ă���B���̐��Z�@�͈�࣍��Ȃ���т₩��������Ƃ��A�����A����������̐��ȌJ��Ԃ���l�ƑΏƂ����B�����̋N���́A�Â��͕�������(9���I)�̊��c�H��܂ł����̂ڂ邱�Ƃ��ł��A�ȗ����F�ɓK�����C�y�Ɍb�܂�āu�����v�͑��l�Ȑ��F�Z�@�̓W�J���݂��B�@
���F�T�́A�����̔��W����b�Ƃ��đ��l�Ȑ��Z�@���W�听����Ȃ��ŋ{��F�T�Ă��]�˒���(17���I�㔼)�Ɋ����������̂ł���B���̋Z�@�́A�����ȗ��̌^���ߋZ�@�ɊO�����F�̍X�т̐��@�Ȃǂ������A�Вu���Z�@�Ƒ��ʂȕ��������������ꂽ���̂ŁA��{�I�ɂ͊G�搫�̋����͗l���ł���B���H�Z�@�̕ϑJ�́A�����͎�`���ŁA���������ɂȂ��Č^�����J������A����ɋ@�B����Z�p���J������Č��݂Ɏ����Ă���B�@
���^�F�T���H�Ɓ@
�^�F�T�ƊE�́A���G�ɕҐ�����Ă��鋞�F�T���H�ƊE�̒��ōő�̐��Y�ʂ�i����ƊE�ŁA�e�ƊE�̗v�Ɉʒu���Ă���B�^�F�T�́A�͗l��蔲�����^����z�̏�ɒu���āA���̏ォ���������������(�F��)�������A����̖͗l���ʂɐ��߂���̂ŁA�^������Z�@�ƌĂ�邱�̋Z�p�͖����ɓ����āA���������̕��y�ƂƂ��ɍL�������ɂ��J�����ꂽ�B��`�F�T�Ƃ��ďo�������F�T���Y�ɑ�ʐ��Y���\�Ƃ����Z�p�Ƃ��āA���݂����F�T���Y�Z�@�̎嗬���Ȃ��A�@�B����ƈقȂ�A���Y�`�Ԃ͎�H�Ƃ̈���o����̂ł͂Ȃ��B�@
����`�F�T���H�Ɓ@
��`�F�T�Z�@�́A�F�T���H�̍ł��Â��Z�@�ł��邪�A���̉��H�ƊE�͍����܂ŘA�ȂƑ������`���Y�Ƃ̑�\�I�Ǝ�Ƃ��Ă̈ʒu���m�ۂ��Ă���B��`���́A�����ȍ~�A�^���̊J���ɔ����ēƗ��Ǝ퉻�̕�������݁A���̐��Y�H��������ɍו������A���Ɛ��Y�g�D���`�����Ă����B���̐��Y�g�D�͓Ɨ��E���U����10���H������Ȃ�A���̒��_�ɐ������ʒu����\���ƂȂ��Ă���B�����͎����≮����̒������ĉ��H�H���S�̂����A��`�F�T���Y�𐋍s���鐻�������Ǝ҂Ƃ��Ĉʒu�Â�����B�e�H���̉��H�Ǝ҂͂قƂ�ǂ���H�ƂŁA�Ƒ��J����̂̓Ɨ��������ƌ`�Ԃ��Ƃ��Ă���B�ŋ߂̓I���W�i�����A�i���ō��ʉ������ꕔ��i���̂̓����͂��邪�A�S�̂Ƃ��Ă͎͌������Ă���A�������ł���B�@
���o�F�T���H�Ɓ@
�o�F�T���H�Ƃ́A�^�F�T�ƁA��`�F�T�ƂƂ������H�Z�@�ʂɂ��敪���Ƃ͈قȂ�A���ʌ`�Ԃ̍��قɂ��ʌɑg�D���ꂽ�ƊE�ŁA�d���F�T���H�ƂƑΔ䂳�����̂ł���B���H�Z�@�I�ɂ͑啔���͌^�F�T���H�ł���B�@
�o�F�T�̍Ő����͐�O�̏��a12-14�N�Ŏ��Ə������ł������������A���͎d���F�T������Ɏ嗬���߁A�ƊE�͑Q���k�����Ă��Ă���B���̂����d���F�T���H�Ƃ̌��Ƃ��唼���߁A�o��Ƃ͌����X���ɂ���B�@
�o�F�T���H�Ƃ̓����́A���H�ꎩ�g�����i�����s���Đ����{���쐬���A���̐����{������������ʂ��Ēn�������X�ɔz�z���A�����{�ɂ���ď���҂���������Ɋ�Â����F���H���s���Ƃ������`�Ԃɂ���B���H�̒��S�ƂȂ�^�F�T�ɂ��Ă̐��Y�H���́A�d���^�F�T���H�Ɗ�{�I�ɓ����ł���B

���s���F�ƊE�̒��Ő��F�̍ł���{�I�ȍH���ł��鍕���E�F����S������ƊE�ŁA�a���i�A���n�A���n�Ȃǂ̐��F���s���Ă��邪�A���̂��������ɂ��ẮA��Ƃ��đr���̐��F���s���Ă���A���a54�N�Ɂu������t���v�Ƃ��ē`���I�H�|�i�Ɏw�肳��A�Ǝ��̕�����m�����Ă���B�@
�����E�F���͋Z�@�I�ɂ͐Z���y�ш����ɂ���čs���邪�A�Z���E�����͓���ƂȂ��Ő��F�̍ł���{�I�ȋZ�@�ł���A���̉��H�@�͎��̂Ƃ���ł���B�@
�Z��/�������͐����Ɩ�i�Ƃ�n�t���ɗn�����āA���̒��ɉ�����Z���A�◁�A�����A�ϕ����ŏ������A���グ����̂Ŗ��n���̍ł���ʓI�ȋZ�@�ł���B�@
����/�͂������Œn�F����߂�Z�@�ł���A���n��A�L�q(����)�Œ���グ�A�u�n����v�Ə̂��ē��`(������)��Љt��h�z�������Ă�����M�A���Ďd�グ��B���z�̈����ɂ͎�Ƃ��Ē��ڐ����A�_�������A��������A�m�A�[���Ȃǂ��p�����A�ȕz�����ɂ̓i�t�g�[�����������p�����B�����͎�Ƃ��Ėh���Ђ��{������t�A�͗l�t�A������ȂǗF�T���̈�H����S������ق��A����̂��A�̂ڂ�ȂLj���߂ɂ����p����邱�Ƃ�����B�@
����/�����Ǝ҂͋��s�����H�Ƌ����g���ɑg�D����A���̂����Z�����H�Ǝ҂���Ƃ��āu������t���v�Ƃ��Ă̍������H��S���Ă���B�Z���̑����͋@�B������Ă���A�S���̎��v�̂قƂ�ǂ����s�Řd���Ă���B����A�������Ǝ҂͍��G�H�D�A���������̉��H�Ɍg����Ă��邪�A���Ƃ����S�ŋ@�B�����x��Ă���A�������H�̔����߂��͑����ōs���Ă���B�@
���a54�N�ɓ`���I�H�|�i�Ɏw�肳�ꂽ������t���́A��͌Вu���A��͏�G�`���Ȃǂ̎��Ƃɂ��t�щ��H���A�����H�ł͐��ߏオ��ɏd������F����悭�o�����߂ɍ����ɓ���O�ɉ����߂�����B�����߂̕��@�ɂ́A�g����(�Ԗ��̂��鍕)�Ɨ�����(���̂��鍕)������B�ŋ߂͉���I�Ȑ[�F���H���J������āA����ɔ��F���悭�Ȃ��Ă���A�[�F���H���{�������i���啝�ɑ������Ă���B�@
�F��/�F�����Z�@�I�ɂ͐Z���ƈ����ɕ�����邪�A��������F�T��v�����g���H�̈�H���Ƃ��Č����A���n�A���n�Ȃǂ̐F�E���n����S�����Ă���B

�i����ƊE�́u�����̎q�i�v�Ƃ��ď��a51�N�ɓ`���I�H�|�i�w����A���s�a���Y�n�̒��ɂ����āA�i���Z�@�ɂ������A�a�������ށA�����тȂǘa�����i�̂ق��A�Q���i��m�����i�����Y���Ă���B�@
�i����H�̌����͌��n�I�Ȃ��̂ŁA�@�B�͗p�����A�ȒP�ȓ���ƍH�v�ɂ���Đ��I�Ȃ��̂���ȗ��f�p�Ȃ��̂܂Ő��߂���B�]���āA�i���Z�p�͐��E�e�n�Ō����A���̔��˂̓C���h�Ƃ������Ƃ������Ă���B�@
�䂪���ɂ����Ă��i���Z�p�͌Â����猩���A7���I���t�̓��{���I�̒��ɍi���Ɋւ���ƌ�����L�q������A���̎��ォ����ɑ��݂��Ă������̂ƍl������B�����E���R��-�]�ˑO���ɂ����Ĉꐢ�т����u�҂��Ԑ��v�͍i������g������i�̑�\�I�Ȃ��̂ł���B�]�˒����ɂ́A���̎q��D�c�Ȃǂ̑��i���i���Ɏh�J���{�����J�i�A�F�T���H���{�����i�F�T�Ȃǂ����Y����A17���I���̌��\���_�Ƃ��đS�������}�����B�@
�����ȍ~�͕����т̊J���ȂǏ����Ȕ��W�𐋂��A�吳�����ɂ͒��N�����ɍi�����H��n�����܂łɔ��W�����B���́A���a30�N�㔼�̍��x�������ɓ����Ă���̍i�����v�̉ɔ����Z�p�ҕs������A�؍��ł̍i���ϑ����H�����a38�N�ɍĊJ�����B�؍��ւ̈ϑ����H�͍i���i�̒�����Ƒ�ʋ������\�ɂ��A���a43�N������̍i�u�[���ɓr����B�@
�]�ˎ��ォ�疼�O��m��ꂽ�i�Y�n�̑����͎p�������A���݂͋��s�Ɩ��É�(�L���E�C�i)��2��Y�n�ƂȂ��Ă��鑼�A�\�����ł����Y����Ă���B�@
�i����̉��H�H���́A������A���G�A�i���掟�A���ߕ����A���F�A���̂������Ȃ�10�]��ɕ�����A�Ƒ��J���𒆐S�Ƃ������K�͊�Ƃɂ��x�����Ă���B

�F�T���Ƃ͍]�ˎ���ɔ��B�����A���{���\���镶�l���ł��B�]�˒����ɋ{��F�T(�݂₴���䂤����)�ɂ���Ċ������ꂽ���߂����Ă�܂����A���̎�@���͍̂]�ˏ������瑶�݂��Ă��܂����B�F�̍�����h�����߂ɌЂ�p����̂������ŁA���̂��ߑ��ʂʼnؗ�ȊG���l��`���o�����Ƃ��ł��܂��B�@
���F�T���a���ȑO�@
���i���琳��(1624-1647)���Ɋ��s���ꂽ�u�ѐ����v(���ӂ�����)�Ɍ����鋞�s�̐����́A���̎q(���̂�)�̂悤�ȍi����߂������ƁA���̂قƂ�ǂ��͗l�̂Ȃ���F�̐����ł����B�Ƃ��낪���̌�A�������Ȃǂ̖͗l�������s���A����ɉؔ��Ȃ��̂��D�܂��悤�ɂȂ�܂��B�@
����ɑ��č]�˖��{�́A�V�a�N��(1681-84)�ɋ֗߂��o���A����(����)��h�J�A���i��Ȃ��ґ�Ȉߏւ́A���邱�Ƃ͂��납��邱�Ƃ����֎~���Ă��܂��܂��B�@
���̂��߁A�h�J��i��Ȃǂ��g�킸�ɁA�F�ʂ̑N�₩���ʼnؗ킳�����o����A�V���������̑n�������߂��܂����B���ꂪ�F�T���n���̉����ƂȂ�܂��B�@
���{��F�T�̓o��@
�{��F�T�͓V�a���猳�\(1681-1704)�ɂ����Ċ����G�t�ł��B���v�N�͂킩���Ă��܂���B������(1736)�N�ɁA83�˂ŋ���Ŗv�����Ƃ�����������܂����A�肩�ł͂���܂���B�ނ́A���݂ł����f�U�C�i�[�̂悤�ȑ��݂ŁA���̃f�U�C���u�b�N(���{��)�ł��鐗�`�{���������o�ł��܂����B�@
���\5(1692)�N�A�F�T���炪�o�ł������`�{�u�]��(�悹��)�Ђ��Ȃ����v�̏��ɂ́u�����q���@��O �}�K��H�F�T�v�Ƃ��邱�Ƃ���A�F�T�͒m���@��O�ɏZ��ł����Ǝv���܂��B�@
�܂��A�V�a2(1682)�N���s�̈䌴����(���͂炳������)�u�D�F���j�v�Ɂu����\��{ �S�P(�䂤����)�������G�v�Ƃ���܂��B����ɁA�勝3(1686)�N���s�́u�D�F�O��j�v�ɂ́u�����������A�䂤�����A���H����₫�A���̐��̂͂�蕨�v�Ƃ���܂��B���̍��F�T�́A��ɊG��`����G�t�����Ă���A���̐��ςȕ]���Ă������Ƃ��킩��܂��B�@
����H������H�ց@
��G�̈ӏ��Œ��ڂ��ꂽ�F�T�́A�����̃f�U�C���ɐi�o���܂��B�勝4(1687)�N���s�́u���p�P�}�b�v(����Ȃ悤�����������)�Ɂ@
�(����)�ɗF�T�Ə̂����@�t���肯�炵�A�ꗬ���ɏ��o���T���A�M�˂̒j����x�̔�����͂����O�Ԃ̐O���ق������A����Ɉ˂�Đl�̍D�߂�S�����݂āA���Y�����̖͗l������āA����������ɗ^�ւʁA������ċ�����悵����(�㗪)�@
�Ƃ���܂��B���N���s�̈ߏ��`�{�u�����ЂȂ����v�ɂ��u��݂̂������ɂ��͂��F�T���v�Ə�����Ă��邱�Ƃ���A�F�T�͂��̍����D�E�i�o�����Ƃ�����ł��傤�@
���f�U�C�i�[�F�T�@
�勝5(1688)�N���s�́u�s���l�F�T�Ђ��Ȃ����v�́A�ߏւ̕��l�ɂƂǂ܂炸�A���C�~�E��E�c��E����(�ӂ�)�E�����̕\���ȂǗl�X�ȕ��ɑ���F�T�̃f�U�C�����W�߂����̂ł��B���̂悤�ȑ����I�f�U�C���u�b�N�͍]�ˎ����ʂ��Ă����ɗႪ�Ȃ��A�F�T�̃f�U�C���ɑ��ĊS�������������Ƃ����������܂��B�@
�܂����̒��ŁA�F�T���s�̌������u�Õ����˂�����ʂ��ӂ��݂āA���l�̍��ԂȂ镨�A����(����)�ɂ��ȂЁv�Ƃ��Ă��܂��B�ÓT�I�Șa�l�����c���Ȃ�����A�����̎a�V�ʼn₩�ȃf�U�C���������ꂽ�_���A�l�X�̐S�����Ƃ����̂ł��B�@
��\�I�ȕ��l�Ƃ��ẮA�~�̒��ɉԂ�����������u�Ԃ̊ہv���������܂��B����͗F�T�̑n���������̂ł͂Ȃ��A��������̗L�E���l(�䂤��������悤)�̒��Ɏ����悤�Ȃ��̂������܂��B�����Ƃ�����^�̒��ɁA�`���̎���i���������ꂽ�A�}�b�`���O�̂������낳�����s�Ɍ��т������̂Ǝv���܂��B���̂悤�ɁA�ނ̍˔\�͏]�����炠����̂��A�����W���A�\���������Ƃ���ŏ\���ɔ������ꂽ�悤�ł��B�@
�~�ȊO�ɂ��H�`��T�b�A��Ȃǂ̊w�͗l�̒��ɑ��Ԃ��U�炷���l�����������܂��B���������������ȋ��̒��Ɏ�����Â炷�f�U�C���́A���Ƃ��Ɛ�ɊG��`���Ă����F�T�ɂƂ��Ă͗͂����₷����ł��������Ƃł��傤�B�@
���F�T���̐��ځ@
����ŁA���\5(1692)�N���s�́u���d��L�v(����Ȃ��傤�ق���)�ɂ́u�F�T���̊ېs�����A(����)���݂�ΌÂ߂��������S�Ȃ�v�Ƃ���܂��B���̂��Ƃ���A�������f�U�C���̗��s�T�C�N���������������Ƃ����������܂��B�@
�����ɂ���́A�����̃f�U�C�����F�T��ӓ|�������킯�ł͂Ȃ����Ƃ������܂����A���̌���V�������l��Z�p�ėF�T���͐����c���Ă����܂��B�@
18���I���Έȍ~�́A�]�˕��́u���v������ɂ����s���A�����̃f�U�C�������G�Ȃ��̂���P���Ȃ��̂ցA�F�����₩�Ȃ��̂���P�F�n�ւƕω����Ă����܂����B�@
���ʂ��F�T�̍l�ā@
�����ɓ��艻�w����(��������)���A������A�F�T���̐��E���傫���ω����Ă����܂��B���w�����͓��ɗn�����Β����ɐ��߂��A�Ђɍ����邱�Ƃ��\�ł����B���̓����𗘗p���āA����10(1877)�N���ɍL������(�Ђ낹�������A1822-90)���������������ʂ��Ђ�p����ʂ��F�T�̋Z�@���l�Ă��܂����B����́A�^����p���Ďʂ��Ђn�ɒu���Ă����A�����Đ�����蒅�����A���̌㐅�����ČЂ𗎂Ƃ��Ƃ����Z�@�ł��B�@
�����͋��s�̐��܂�ŁA���N�̍����F�T�Ƃ̔��㉮�ɕ�����A�̂��ɂ�����p�������߁A����(�Ԃ�)�Ƃ��Ă�܂����B���Ƃ��Ƃ͎�`�F�T�̖���Ƃ��Ēm���Ă��܂������A���������ɋ��s�{���J�݂����ɖ���(�����݂��傭)�ɏo���肵�A���w�����̎g�p�@���w�т܂����B���̌�A�x��V�O�Y(�ق肩�킵�Ԃ낤�A1851-1914)�̃��X����(���n�̖ѐD��)�F�T�̉e�����A����������ɉ��p�����ʂ��F�T�̋Z�@���J�����܂����B�@
���̋Z�@�̊J���ɂ��A���܂ł̎�`�F�T�ɔ�H�����ȗ�������A���Y�������啝�ɏオ��܂����B���̌��ʁA�F�T���̑�ʐ��Y���\�ɂȂ�A��O���ւ̓����J���܂����B�@
���̌���A�]�ˎ��ォ�猻��܂ő����V�܁u���`�v(������)�̐����`���q��(�ɂ��ނ炻����������)�ɂ��r���[�h�F�T(���r���[�h�n�ɗF�T�����{��������)�̊J����A�L���ɕ��q(�Ђ남�����ւ�)�ɂ�閳���F�T(���ڌЂ�u���Ȃ��F�T)�̔����Ȃǂɂ��Z�p�I�ɂ��傫�Ȕ��W�𐋂��Ă����܂����B�@
�����{��Ƃ̊���@
�ʂ��F�T�̍l�Ă͋Z�p�I�ɑ傫�ȈӖ��������Ă��܂����A�����Ɉӏ��̖ʂł��V���ȓW�J�������܂����B�@
�����ɓ���ƁA����܂ł̗ތ^�I�Ȃ��̂�E�����A�V�����ӏ������߂���悤�ɂȂ�܂����B�����ɓo�ꂵ���̂��A�����ېV�Ō㉇�҂����������{��d�̊G�t�����ł��B�K�씀��(�����̂��ꂢ)�⍡���i�N(���܂������˂�)�A�ݒ|��(���������ǂ�)�A�|�����P(�������������ق�)�炪�A�F�T����w�D�̉��G��`���Ă��܂����B���Ԃ╗�i���ʎ��I�E�G��I�ɕ\���ꂽ�f�U�C���́A���R�Ȕ��z�ɖ������D���ݏo���܂����B�@
���F�T�����@
��̗����ŌЂ𗎂Ƃ��F�T�������n�܂����̂́A����10�N��ɓ����Ă���ł��B�ʂ��F�T�̋Z�@���m�����ꂽ����ł���A����ȍ~���s�̕������̈�ƂȂ�܂����B�F�T�����͊��삾���łȂ��A�j��A�x��A����A������Ȃǂł��s���Ă��܂����B�@
�����j��E�x��ȂǂŗF�T�����͍s���Ă���A�j��ł͏��a40�N���܂ōs���Ă��܂����B���������a46�N�̐��������h�~�@�̎{�s�ɂ���ł͍s���Ȃ��Ȃ�A�F�T�����́A�e�H�[�������Ől�H���H��p���čs�����̂ɕω����Ă����܂����B
���w�D�Ƃ͋��s���w�̒n�Ő��Y�����D���̑��̂ł��B���w�Ƃ����n���́A���m�E�����̗�(1467-77)�̐��R�A�R���@�S(��܂Ȃ�������A���L�A1404-73)�̐w���ɗR�����A�ނ̓@��������R����(�x��ʍ��o���鐼��)�ƂƂ��ɁA���̖��c���Ƃǂ߂Ă��鐔���Ȃ��n���ł��B�@
�n���Ƃ��Ă̏����́u���y�����^�v(�����傤����ɂ��낭)����19(1487)�N����24�����ŁA����10�N�Ő��w���n�������Ă������Ƃ��킩��܂��B�]�ˎ���ɂ́A�k�͍��{�_�Ќ䗷���A��͈��ʂ��邢�͒������ʁA���͖x��ʁA���͎��{���ʂɂ킽���т𐼐w�ƌĂ�ł��܂����B�@
�������݁A���w�x�@����w�X�ǁA���w�������w�Z�Ȃǁu���w�v�̖���������{�݂͂���������܂����A���w�Ƃ����s���n���͂���܂���B�܂��A���ł͐��w�D�֘A�̋Ǝ҂́A�k�͑��(�������݂�)�A��͊ۑ����ʁA���͉G�ےʁA���͌䎺���߂ɂ܂ōL�����Ă��܂��B�@
�����w�D�̂͂��܂�@
���������̗��ߐ��̂��Ƃł́A�呠�Ȃɑ������D���i(����ׂ̂���)���ō����̐D���Y���Ă��܂����B�������A���ߑ̐��̕���ɂƂ��Ȃ��āA�������������肩�璩��͍H�[���ێ����邱�Ƃ�����Ȃ��Ă����܂����B�@
�����ŐD�H�B�͑�ɐl��(�����Ƃ˂肿�傤�A���݂̒��F�ʉ����Ғ�����)�Ɉڂ�Z�݁A�v�̈��D�Z�@��͕킵���������A�M���̑����p�ɐ��삵�܂����B���ꂪ�A���Ƃɂ�鐻�D�̂͂��܂�ł��B��k�����ɐ��������u��P�����v(�Ă������炢)����́A�u��ɐl���v��u��{���v�����̖��Y�Ƃ��ėL���ł��������Ƃ��킩��܂��B�@
���m�E�����̗��̊ԁA��ɐl���̐D�H�B�́A��Ȃǂɓ���Ă��܂����B�����I������Ƌ��s�ɖ߂�A���R�{�w�Ղ̔��_��(���݂̐V���ʍ��o���镍��)�ł͗��э�(�˂�ʂ���)���A���R�{�w�Ղ̑�{������ł͑�ɐl�����g�D����܂����B�����Ă��ꂼ�ꂪ�Η����Ȃ�����A���̋@�Ƃ����[�h���Ă����܂����B�@
16���I�ɂȂ�ƁA��ɐl�������R�ƒ����̐D�����Ɏw�肳��A�܂����T2(1571)�N�ɂ́A��ɐl��31�Ƃ̂���6�Ƃ��A�{�쑕���D����䗾�D���i(����傤������̂���)�ɔC�����܂����B����ȍ~�A����6�Ƃ𒆐S�Ƃ��Đ��w�̋@�Ƃ͔��W���Ă����܂����B�@
�����w�D�̉�������@
���y�E���R����ɂ́A����o�Ė��̋Z�p���A�����ꂽ���Ƃ���V�����D�������Ă���A���������Ȑ��w�D�̊�b���z����܂����B�@
�]�ˎ���ɓ����Ă���́A���{�̕ی�̂��Ɛ��w�̉���������}���܂����B���ɐ��w�̒��S��������{�ʍ��o������_���߂́A�痼���҂ƌĂ�Ă��܂����B���ӂ̂悤�ɉ����̎����l������Ă��āA�痼���鎅������s���Ă������Ƃ���A���̖����t����ꂽ�Ƃ����܂��B�@
�܂�������u���̒��|��v(��������)�Ƃ������t���]�ˎ���ɓo�ꂵ�܂��B�\�ԎɈ��(������Ⴂ�����A1765-1831)�́u���C�����G�I�сv(�Ƃ������ǂ����イ�Ђ����肰)�Ɂ@
���l�̂悫�߂�����͑����ƈقɂ��āA���̒�������̖��͉v�X���w�̐D�����o�@
�Ƃ���A���̐l�X�̈ߕ��ւ̊S�̍����ƂƂ��ɁA���w�𒆐S�ɂ������D���̖��������������܂��B�@
�����w�D�̊�@�@
����15(1730)�N6��20���A�㗧���ʎ��������̌�����(���ӂ��ǂ���)�啶�����ܕ��q������̎肪�オ��A�܂������Ԃɐ��w�n��̑啔�����Ă��s�����܂����B���̉Ύ��́u���w�Ă��v�ƌĂ�A���Ɩ�3800���A�D�@��7000��̂���3000��ȏオ�Ď������Ƃ����Ă��܂��B�@
��������������ɁA���X�ɐ��w�̋@�Ƃ͐��ނ��Ă����܂��B���̍��A�O��E���l�E�ː�(����イ)�E�����ȂNj��s�ȊO�̒n��Ō��D��������ɂȂ�A�Ύ��̌�ɂ͐��w�̋Z�p���D�H�ƂƂ��ɒn���֓`����Ă����܂����B����ɂ��̌�̓V��8(1788)�N�̑��A�V�ۂ̉��v�ɂ�銔���Ԃ̉��U�E���D���֎~�߂ŁA���w�͑傫�ȑŌ����܂����B�@
�����w�D�̋ߑ㉻�@
����2(1869)�N�̓����J�s�ɂ���āA���w�͍����D���̎��v�ґw��啝�Ɏ����܂����B�܂������̗A�o�����ɂƂ��Ȃ����������̉��i���������A���w�͈ȑO�ɂ��܂�����@���}���܂����B�@
�����ŁA���s�{�ɂ��ی�琬���v���邱�ƂɂȂ�A�{�͖���2(1869)�N�ɐ��w���Y��Ђ�ݗ����܂����B��5�N�ɂ͍��q�펵(������˂���)�E���ɕ��q(���̂������ւ�)�E�g�c����(�悵�����イ����)���t�����X�̃������ɗ��w�����A�t�����X���̃W���J�[�h(�䎆���g����D���u)��o�b�^��(��`<�Ƃт�>���u)�Ȃǐ��\��̐D�@���u��A�����܂����B�܂��A����6(1873)�N�A�E�C�[������������ɐ��s�����D���Ǝ҂̎l���ɒB�폕(���Ă₷���A1813-76)�́A�I�[�X�g���A���̃W���J�[�h�������A��܂����B�@
����20�N��ɂ͂��������m���Z�p���蒅���A���w�͍ŐV�ɂ��čő�̌��D���Y�n�ƂȂ��Ă����܂��B���̌���쓇�r���q(���킵�܂���ׂ�)�⍲�X�ؐ���(��������������)�炪�e�n�̔�����ɏo�i��܂��A���w�D�̖������߂܂����B�@
�������ɂ͐D�@��2�����L���A���Y�z��2000���~���܂�ŁA�S���D�������Y�z�̖�7�p�[�Z���g���߂�悤�ɂȂ�܂����B�������Đ��w�͐V�����Z�p��������邱�Ƃɂ��A��������ېV�ɂ����Ă̊�@��E�o���܂����B�@
������̐��w�@
���w�͑�2������A�@�B��������ɐi�݁A�V�����Z�p�����X�ɓ�������܂����B���݂ł́A�Z�p�̍��x���ƂƂ��ɍ�ƍH���ׂ͍������Ɖ�����A���̂قƂ�ǂ̍H���𒆏���Ƃ��ɂȂ��Ă��܂��B�@
����ŁA�J���͂����߂Ă�����u�o�@�v(�ł��A�������H��)�̒n��O�����i�݁A�Ⴆ�ΐ��w�т̖�6�������s�s�O�ŐD���Ă��܂��B�܂��ŋ߂ł͍����Ȓ�����т����ł͂Ȃ��A�l�N�^�C��o�b�O�A�J�[�e���₨���̑܂ȂǑ��l�ȐD�������������悤�ɂȂ�܂����B�Љ�̕ϗe�ɑΉ������ω����A���w�D�ɂ����߂��Ă��܂��B�@
���a51�N�ɂ͒ԐD(�Âꂨ��)�E�ѐD(�ɂ�������)�E�j�q(�ǂ�)�E�钿(���タ��)�E�Дb(���傤��)�E����(�ӂ���)�E�e��D(�����肨��)�E�{���ڐD�E�V�A�O(�r���[�h)�E�R(������)�E��(�ނ�)��11�킪�A������`���I�H�|�i�Ɏw�肳��܂����B
 �@
�@�g�^
���߂̋Z�@�A���̖��B�^�t���Ƃ�����@�ɂ���Đ��߂�ꂽ�����B������㗬�K���̏����ɂ݂̂�邳�ꂽ�ߑ��B�r���K�^�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂͑吳���゠���肩��ŁA��O�̓J�^�`�L�[ katacikii (�^�t��)�Ƃ������B�����Ő蔲�����^����z�̏�ɒu���A���̏ォ�������h���ĉԒ��R���Ȃǂ̖͗l����ߕt����B��������Ƃ�X�̂��Ƃɂ́A�J�^�`�L�[���[ katacikiijaa(�^�t����)�Ƃ������B

���M�т̎��R���琶�ݏo���ꂽ����̐����B�N�₩�Ȕ��F�̍g�^����\�I�B���M�ыC��ł��鉫��́A�����̌����ɂȂ鈟�M�ѓ��L�̐A�����L�x�Ȃ��Ƃ�A�����ɂ���Ĕ��F���L���ɂȂ邱�ƂŁA�����z���̉��œ��F��������������B�����Ƃ�����B����ł͌Â�����A��������̌����Ƃ��A�Ⴆ�Ή��F�n�����Ƀt�N�M��E�R���A���F�n�Ƀ��}�����A�n�ɗ������Ȃǂ��܂��܂ȐA����g�ݍ��킹�āA���ʂȐF�����o�����B����̐����̂Ȃ��ŁA�S���I�ɒm������̂ɍg�^������B�g�^�͉���Ǝ��̖͗l���߂ŁA��E���E���E���E��5�F����Ƃ��A���̔��F�̖L�����Ɣ�������_�Ȗ͗l������Ƃ��Ă���B���Ƃ��Ǝ�(�����)�̐E�l�������g���Ă����u�g�v�Ƃ����F���w�����t�ɁA�͗l���Ӗ�����u�J�^�v�Ƃ������t��g�ݍ��킹�āu�r���K�^�v�ƌĂ�ł������̂ŁA����Ɂu�g�^�v�Ƃ��������Ă͂߂��̂́A�吳����ɓ����Ă���Ƃ�����B�g�^��14���I���ɗ����������s�������Ղɂ��A�ߗ��O���̋Z�p��������A���{�̉��Ŋm�����ꂽ�B������m���̈ߑ�����ы{��|�\�̈ߑ��Ƃ��Ĉ��p����A�����������ے�������̂̂ЂƂł���B�g�^�̋Z�@�ɂ́A�^�����g�p����^���߂ƁA�Ђ��i��o���Đ��n�ɖ͗l��`���Ă������`���Ƃ����ӂ��̋Z�@������B��������̐}���ɂ͉�������`�[�t�Ƃ������̂͂قƂ�ǂȂ��A���{�I�Ȑ}�����������A�ŋ߂͉���炵����_�Ȑ}���̍g�^��������悤�ɂȂ����B������\��������Ƃ��ė�����������B�ق��̗��ɔ�ׂĐF���Z���A���������F�������B�������̓L�c�l�}�S�Ȃ̑��N���ŁA�쐼�����⏬�}�������Ŏ�������A���B���Ă͉���{���k���Ő���ɍ͔|���s���Ă������A���݂ł͖{����(���ƂԂ��傤)�ł킸���ɍ͔|����Ă��邾���ƂȂ����B

14���I����15���I���ɂ͂��̌��^�����o���ꂽ�Ƃ����A������\������ߕ��̂��ƁB�u�т�v�͍g(��)�����ł͂Ȃ��A�S�Ă̐F���w���A�u�^�v�͖͗l���Ӗ�����B�͗l�͏��|�~�A�e�A���O�A�˂Ȃǂ̐A�����l�A�߁A�T�A���Ȃǂ̓������l�A�R���A�����Ȃǎ��R���l����B���̓`���I�Ȑ��F���Ƃ̈Ⴂ�́A�F�Ɋ痿���g�p���邱�Ƃ�A�^����ɓ˂�������̗p���Ă��邱�Ƃ��グ����B�g�^�Ƃ͏㗬�K���̂��̂ł���A�ߑ��̖D�����������ď����̂��̂ł͂Ȃ��A�܂��L���Ē����ȂǓ��퐶���Ƃ͖����Ȕ\�����Ɠ�����@���g���Ă���B�F�ʂ����F�����S�ŁA���̐F�͉�����M���łȂ���Ύg�p�ł��Ȃ��F(����)�Ƃ��ꂽ�B
����̑�\�I�Ȑ����̈�ŁA���x��ɂ͌������Ƃ̂ł��Ȃ��ߏցB�u�т��v�܂��́u���������v�Ƃ����A500�N�ȏ�̗��j�������č��Ɍp������Ă���B1719�N���h�������̋L�^�u���R�`�M�^�v���݂�ƁA�������炷�łɍg�^�͗x��ߏւƂ��ėp�����Ă������Ƃ��킩��B

�����Ɠ��̈ӏ���\���܍ʂ̔��������F�@�ŁA����̍X�т�F�T�Ƃ̊W���[���Ƃ�����B�����ɂ͐A�����̕��E�g�ԁE���A�������̐��b���E�z�����̐Ή��E��E���y�E�n�Ȃǂ��p����ꂽ�B�g�^���̕��@�́A�z���ςĐ��ş����A����Ɍ^���āA�w���ɌЂ����Ă��荞�݊��������ƁA���`���Ђ��ČЂɈ͂܂ꂽ�Ƃ���ɐF�������Ă����B�F�͕M�ō��荞�ށB���������F������������J��Ԃ��A�I���Ɩ��H���Ђ��ĊO�Ɋ����A���̂��ƍĂъ����Ďd�グ��B�͗l�͉Ԓ������l�X�ł��̍����͐l�ڂ�D���B�g�^�͉���ŗB��̐����ł���B�������̗F�T�A�����Ē����̌^�t���̋Z�@�������������������A������L�̌��F���g�������t���Ɛ}���͏��x��̈ߏւƂ��č����g�̖ڂ��y���܂������Ƃ��낤�B�����R�͌��Վ���ɂ����炳�ꂽ�B���n���R�͏����̐������ʂ��Ƃ����A�G�x��ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ߏւł���B�E�V���`�[�ɒ��t�������A���ꏗ���̔��������������B�m�ԕz�͂�����Â�����I���W�i���̑f�ނł���B�f�p�ŗ������ȕ������́A�_�����̐S�ӋC��\�����Ă���悤�Ő��^�ŕi������B

���N���@
��15���I�����瑶�݂��Ă����ƍl�����A�����A���N�A���{�A�W�����E�X�}�g���E�p�����o��(�C���h�l�V�A)�A�V����(�^�C)�Ȃǂ̓���A�W�A�Ƃ̌��Ղ̒��ŗl�X�ȋZ�@��������A���W�����ƍl������B�����ōg�^���w�����̂ł͂Ȃ����Ƃ݂�����̂Ƃ��āu�������^�v�ł́u�I���v(1456)�u�ʊG�v(1479)�ƋL����A�V��7�N(1463)�ɒ��N�ɔh�����ꂽ�����̎g�߂��u�����̒j�͔�ࣔV��(�ʂ�̔������͗l�̈�)�𒅂�v�Əq�ׂĂ���A�u�g�����^�v(1534)�ɂ́u�ʕ��E�ʒi�v�Ƃ���B�g�^(�܂��͍g�^�𐧍삷�邱��)��\���u�^���v�̕��������߂ēo�ꂷ��̂́u�����ƕ��v�̐���12�N(1639)�A�u�������u���v(1756)�ɂ́u�����ɕ��l����߂�҂�����B�܂�5�F��p���Đ��n����߂�҂����āA�F���璅�p���Ă���B�����đ����⏤���ɂ͂����ނː��F���Ȃ��n�F�̂܂܂̐��n��p����v�Ƃ���B���ɂ��u�����낳�����v(1532)�A�u�n���ƕ��v����16�N(1751)�A�u���z�v��15���s��16�N(����32�N/1767)�A��16���s��31�N(����47/1782)�A�u�g�����L�v(1802)�ȂǂɋL�q���݂���B�@
�����́@
����w�����̑n�n�҂ł���ɔg���Q(1876-1947)�́u�����X�т̔������×����g�^���v(1928)�Ő����̌��Y�n�ł���x���K������ٕ�(�r���K���[)�̂悤�ł���Ƃ��A�����[���Ձu����āv�́u�㐅�ԕz(�X��)�v���C���h�̃x���K������n���������Ƃ���g�^�̌ꌹ�̓x���K���ɗR������Ƃ��Ă���B�����ɂ��œy�̒��A�g�^�̕����ɐs�͂�����ԉh��́u��(�h��)�͒��������Ȃ�(�т�)�Ƃ����n�����������̂Ō^���ꌹ�ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă����悤�ŁA�܂��E�l�����̊Ԃł͌����A�^���̂��Ƃ��u�^��(�J�^�`�L)�v�ƌĂсA�F���������Ƃ��g(�r��)������ƌ����Ă����B�܂��u�×����g�^�v�u���ꕶ���̈��v�̒��҂Ō^�G����Ƃ̊��q�F���Y(1898-1983)������ōg�^�������s�����吳���N�̍��A�̍���(����)�ł́u�r���K�^�v�ƌĂ�ł����̂Łu�F�ʂ̂��Ƃ��̂��čg�A���l���w���Č^�Ƃ����v���ꌹ�ł���ƍl���A���݂ł͐F�ʂ��̂��g�A���l���^�Ƃ���Ӗ��ōg�^�Ƃ������̂��g���Ă���B

�����̗瑕�E���풅�A�����c��̍����g�߂����҂���ۏ��N�B�������u�䊥�D�x�v(�����ǂ�)�Ȃǂ̗x�ߏցA���ʂȏꍇ�̂����ꂽ�����̐��ꒅ�A�_�ߏւ̑��A�����̏��Ȃ������ł͊O�݊l���̂��ߒ����ւ̋M�d�ȍv�i�Ƃ��č���Ă���(�u�g�����L�v�Ìc7�N(1802)�Ɂu���m�ԕz�v�̖��ŋL����Ă���)�B�@
���E�l�@
�g�^�����E�l�͍����ƌĂ�A�A�ߔe�ɑ��������ƍl������B���̒��ł��ɏZ�������܂����{�̊G�}��s�̊G�t(������4-5�N�G�̏C�s������)�̉��A�g�^�𐧍삵���̂��g�^�O�@�ƂƂ�����3�Ƃł���B�ł����j�����艤�Ƃ̗�杂̐����g�p�ł����ƁA�������瓂���̋Z�@�������E�j�q�����w�m�O�ƁA��ԉƂł���A�����A�i�A�e���A�e�_��(�[����)�A�Ɏ����K���̒}�o�V(�����ǂ���)�̈ʂ�^�����m���ȏ�̊K�������p����g�^�����ꂽ�B�ō��ꂽ�g�^�̑��ɉY�Y�^(�����@��p���������݂ɂ��^�t���@�ŐF���̌Œ��܂����蕲���g�����Ƃ�������^�Ƃ������A�O�^�ƂƂ��Ɍ�ɎɏZ�����ڂ��Ƃɑ�X�`�����Ă����g�^�̋N���ƍl�������@)�A�ߔe�^(17���I���s�ߔe�ō��ꂽ�����K���̒��邱�Ƃ��o����g�^�B���^�Ƃ������A�^�ƈႢ���l�E�F����������Ă����B���Օi�Ƃ��Ă̍g�^���܂�)������B�@
���^���@
�^���͊`�a�����������ɁA�������������������N�W���E�����~���ɂ��Č^���邪�A�͗l�̕�����c���A������ЂŖh�����锒�n�^�ƁA�͗l�̗֊s���݂̂�����肵�ЂŖh������(1��̌^�u���Œn���߂��\��)���n�^������A�^���̑傫���ɂ���đ�͗l�^(���̑S��1��)�A����͗l�^(����3��1�g�ɘA���������G�H��̖͗l)�A�O����^(����2/3)�A����͗l�^(����1/2)�A���͗l�^(����1/4)�A�ז͗l�^(���̑S��1/4�̑傫���ōׂ����͗l)�ƕ��ނ����B�܂��A�p�r�ɂ�閼�̂����菎�����җ�ȏ�̏j���ɒ��p�������ꂽ�j�^�A�����̎������ɗp����ꂽ�㐶(�O�\�[)�^�A�q�C�̈��S���F�肷���D�^�A�K���W�^�A�^���i�^�A���ӂ��^�A�r���C�^�A�䊥�D�^�ƁA�K���ɂ�閼�̂ł͌�a�^�A�a���^�A��O�^������B�@
�g�^�ɂ͌^����p����^���̑��ɕ��䖋��u�����キ���v�ƌĂ�镗�C�~�ȂǑ傫�ȕz����߂�Z�@�Ƃ��āA�Ђ���ꂽ�������i���(�z)�ŌЖh�����铛����(���`��)������B���F�ɂ���(���ʂ̖n)�݂̂��g�p�������^(���[����)�A���^����ɕ����̐F�ʂ���ߓ��ꂽ�g�����^(�т肦�[����)�A�Ƃɓ`��镡���̌^���Ŗ͗l����ߏd�˂�O�^(���Ԃ邪��)������A�O�^�ɂ����O�^�A�g�O�^�ȂǑ��l�Ȑ�����@������B

���n�^�̌^�����g�������@/�͗l����߂���A�ЂŖ͗l�̕������Ēn���߂���Ԃ��@
�^����(�ђ���)���n���聨�^�u(�^�t)���n����(������)���F����(���h��E1�x����)���F����(��h��E2�x����)���G��聨(����)�������Е������n���߁�(����)�����������@
���`���E���n�^�̌^�����g�������@�@
�^����(���n�^�̏ꍇ)���n���聨���`���܂��͌^�u���n����(������)���F����(���h��E1�x����)���F����(��h��E2�x����)���G��聨(����)���Е������n���߁�(����)���������� �@
�f�ށE�F�E�͗l�ɂ��ĕz�n�͖ؖȁA�����A�m�ԁA���A�˔�(�g���r����)�Ȃǂ��g���A�p�r�ɂ���Đ��߂��Ă����悤���B�n�F�͖�20�F�������Ƃ��ꔒ�n�A���F�n�A���F�n�A�ԐF�n�A�ΐF�n�A�����F�n�A��(�[)�n�A���n�A�i���n(���ߕ����n)�Ȃǂł���B��ɉ����E�m���w�l�Ȃǂ̏����A�܂��͌����O�̉����E�m���̏��N�A���{�Ɏd���鏬���Ȃǂ����p���A���F�͉����w�l�̗瑕�A���F�E��n�͓��풅�A�ԐF�E���ƋG�߂�N��ɉ����Ē��p���ꂽ�B�@
���^�A�O�^�͑�6�K���̏���(�n���̒����A�_���⏔���̎x�z�K���ɑ�����w�l����)�ɂ����p��������Ă����Ƃ���K���ɂ���Ē��p�ł���n�F�����܂��Ă����B�@
�͗l�̍ʐF�ɂ͎�Ɋ痿��p���A�痿�̏ォ��������d�˂���A�����Ɋ痿���d�˂��肵�Ȃ���ʐF�����A���̌��F�ȊO�̖͗l�ɌG�����{���͗l�ɗ��̊���^�����B�g�^�ł͋G�߂ɊW�Ȃ��t���������ɓ~�̔~�A�H�̕��̍g�t�A��ւȂǏt�ďH�~�̖͗l�������ɑ��݂��邱�Ƃ��傫�ȓ����ŁA���������Ǝ��̖����ΔZ���ł͊y�����v�킹�����Ƃ��낤�B�͗l�������A���{�̕����قƂ�ǂŗ��A�P���Ȃǂ͉��q�E���܂ɂ��������ꂸ�A�g���̍������̂قǑ傫�Ȗ͗l�ŘV�l�͏������͗l�𒅗p�����B�ޗ��͎����łƂꂽ���A�������Ȃǂ̑��A��ɒ�����������痿�E�������g���A�قƂ�ǂ̐F���𒆍��ɗ����Ă��邱�Ƃ���A�����̗����ƒ����Ƃ̖��ڂȊW������������B�@
�g�^�̈ߏւɐA�����������łȂ��G��Ɏg����痿��p�����̂́A����̋������˂��̒��A��F������������ł��킩��傫�Ȗ͗l��g���̍����l��������Ƃ���(���{�̎L����Ȃǂ̎肪���ׂ��ȍH�������Ƃ��ꂽ�����ƈႤ)�ߕ��ł���Ȃ���u����v�Ƃ������u������v�G��Ƃ��āA�Ϗ܂����ׂ����̂Ƃ��Ă̕\�������A�Ǝ��̂����炩�Ȏ��R����\�����������ɂȂ��Ă������ƍl�����B

�u�����v�̌ď̂́A�����E���̎���A���Ƃ̌��Ղ��n�܂���14���I�ȍ~�A�����������t���Ď����̍����Ƃ��u�����v��p�����Ƃ����B���̖��̂͗����������ŖS����܂łƂ��A�����ɂ́u�������v�ƌ����A�ꎞ���A��p�����܂߂��L��I���̂ł������炵���B�@
�u����v�̌ď̂́A���������ɂ���ė����������ŖS���A����ɉ��ꌧ���u���ꂽ�Ƃ��Ɂu����v�������ɍ̗p���ꂽ�B�u����v�́u�����Ȃ�v�Ƃ������̂͊��ɓޗǎ���ɂ͕����ɋL�ڂ���Ă����炵���A�u�Ӑ^�a��v�������֕Y�������ۂ̗l�q��`�L�ŁA�������u�����ޔg�v(�����Ȃ�)�Ƃ�����a���t�ŋL���ꂽ�̂����߂ł���Ƃ�����B�u����v�Ƃ����������̂́A�]�ˊ��̊w�ҁE�V�䔒���u���ƕ���v������p���A�u�����Ȃ́v�Ɂu����v�̎��Ăĕ��삵���ƌ����Ă���B���������ɂ���ė����������ŖS���A����ɉ��ꌧ���u���ꂽ�Ƃ��Ɂu����v�������ɍ̗p���ꂽ�B

����ł�16���I���̗������{����ɐg�����x���m������A���̕������g����K���ɂ���ĐF�A���͗l�A�z�n�̎�ʂ������ċ�ʂ��Ă����B�g���͉��ƁA��ʎm���A�����ɑ�ʂ���A�����A�m���̒j���p�̗畞�́A���F�n���ŏ�Ƃ��A���A�j�[�A���F�A���F���A�K���ʂɊ���тŎ������B�g�^�ߑ��́A�����w���q�̗畞�ł������Ƃ���A���F�n�A���F�A�����g�F�̏��ŁA���̕��̑召�ɂ��K�����������悤���B�m���w�����R���z���A�����͒j�����ɐA���@�ۂ̔m�ԕz�𒅗p���Ă����B�ߑ����l�A���^�₩���ɂ��Ⴂ������A�����̉��{����̖����߂̂��ė����Ƃ����A����̌��t�ł́u�E�`�i�[�X�K�C�v�ƌĂ�ł����B�@
���{����̕���������12�N(1879)�̔p�˒u���������Ĕp�~����A����̌p���ł͗����|�\���d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B

����͖��������m���ȑO�͊����ŗ����ƌĂ�A���{�{�y�̕�������u�₵�Ă�������łȂ��A����ƒ����Ƃ̌𗬂�����ŁA���̉e���������A�Z���͑�a�����Ɠ���n���ɑ�����ɂ�������炸�A�����I�ɂ͑傫�ȑ��Ⴊ����B�@
������ג��`���ɏ]���A���ג��̎q���������������J�����̂�13���I���̎��ŁA����̌��ꂪ����̓��{��Ə���������������������Ă��邱�Ƃ���A�Ñ���{�����̉e�����[�����Ƃ͒m���邪�A���N���{�Ɛ≏���Ė�(�~��)�ɒ��v�����̂ŁA���������̉e�����A14-15���I�ɂ����Ă͐���ɓ���A�W�A�e�n�ƒʏ����ē��������ێ悵���B15���I���ɏ��������N���Ďɓs�������A1606�N���Ô˂̓��������{�ɏ]���A����5�N(1872)�����˂��u����A�����Ƃ͉ؑ��ɗ��A1879�N���ꌧ���ɕύX���ꂽ�B�@
����̕����͍ŏ��ɓ���n�̃C�J�b�g�R(���іh���@�ɂ���R�̋Z�p)���w�сA�����Œ����n�̖�D����A�����̊����ɂ�问���t�@�`�}�`�⊯���Ƌ��ɁA�̉����𒆐S�ɏ㗬�K���Ɏ����ꂽ�B17���I�ɓ����Ă���A��a�n(����ł͌×��A���{���u���}�g�v�ƌĂ�)�̐F���߂̋Z�p��ېD���`�����A�����ɓ��{�ŗL�̐}�āA�����R�̐}�Ă������ĉ���̐��F�E��L�x�ɂ����ƌ������́A�ނ��뉫��͂����O�̌n����Z�����ēƓ��Ȗ��킢�[�����̂�n��o���A���E�ɋH�ȍ��x�̐��D��������z�����ƌ�����B

���f�ށ@
����ɂ͑����ł͗ނ��݂Ȃ��قǑ��l�ȐD�������݂���B�f�ނɂ́A�����A�m�ԁA���A�ؖȁA�˔ȂǑ����̎�ނ��g�p���A�p�r�ɉ������D����D���Ă����B�����g�E�q��u�썑����E���ƋZ�v�ɂ��ƁA�����͓��{�o�R�ō͔|����A�m�Ԃ̓C���h�l�V�A��̃o�i�i���w���s�T���O(��������Ńq�C�V���O)�Ɏ��邱�Ƃ���A����o�R�Ŏ������܂ꂽ�Ƃ����B���͓��{�A�ۗp�̒����͓쒆���n���N���ƍl�����A�ؖȂ͋V�Ԑ^�킪1611�N�ɎF���������������Ƃ����L�^������B�@
���̐D���Ƃ����˔�(�g���r�����܂��̓g�D���r�����E�g���o��)������B�˔͗������{���ォ���O�܂ŗp�����Ă����D���f�ނŒ�������A������Ă����B���E�㗬�K���̊ԂŎg�p����A�@�ۂ͔��ɓ����Ńn��������A�P�o���قƂ�ǂȂ��Q����������ɐD����̂������ŁA�Ɠ��̂Ђ���Ƃ����G��������ėp�f�ނƂ��Ē��d���ꂽ�B�����Q����ō���Ă��邱�Ƃɂ�����������B�@
�����ɂ͗��A�n�`�}�`�o�i(�g��)�N�[��(�g�I)�A�T��(�E�R��)�A�e�J�`(�ԗ֔~)�A�O�[���[(�T���g���C�o��)�A�k�~�A���A���E�i(�I�I�n�}�{�E)�A���q�A���{�E�C�O�Ƃ̌��Ղɂ��h�A�b���Ȃǎ�ɐA��������p���Ă����B�@
���Z�@�@
�D�̋Z�@�ł́A�������畂�D�A���i�D�A�W�A��������R�A�ԐD�A���{����ۂ�������A�ǒJ�R�ԐD(�����^���U�n�i�E�C)�A�R�D���A�̐D���m�ԑq�D�A�ԐD(�n�i�E�C)�A���[�g���D(���ԐD)�A���(�e�B�W�})�A�����h�D�b�`��(�����)�A�ԐD���(�n�i�E�C�e�B�T�[�W)�A���X�m��(�j�[�K�V�o�T�[)�n�A�{�Ï�z�A���d�R��z�A�v�ē��ہA�^�ߍ��ԐD�A�~���T�[�A���(�e�B�T�[�W)�Ȃǒn��ɂ���Č��L���Ȕ������z�����݂��D���Ă���B

�D���͍g�^�Ɠ��l�A���̑傫�Ȃ��̂قǐg���̍����l�������邱�Ƃ��ł����B�����̕����R��1����1��(�R�̒P��)�͉��ƁA�g����������ɂ�ʐ��͑����A�����͎�ɖ��n��ȁA8�ʈȏ�̏������R�Ȃǂ𒅗p�����B�@
���v�[�z�@
1609�N�̎F���N�U��͉��{�ƎF���̓�d�̎x�z�̒��ōv�[�z���x�����W���Ă������B���������͎F���ւ̍v�[�i�Ƃ��ď�z�A���z���{�ÁA���d�R�։ۂ���ꂽ�B1637�N�ɂ͋{�ÁE���d�R�ɐl���ł��ۂ����15-50�̏����͐łƂ��ĕz��[�߂��B���X�ɋ@�D�����ݒu����^���Âȏ����̒��A�D���Ɏw�����ꂽ�����B�͖�l�̌������Ď��̉��A1903�N�܂ʼnߍ��ȘJ�����ۂ���ꂽ�B(���X�V���́u�쓇�T���v�ɐD���̋L�q���݂���B)���̍v�[�z���x�ɂ��D��ꂽ��z�͎F���ɓn������z�͎F����z�̖��ŗ��ʂ����B�@
����G�}�@
�{�ÁA���d�Ƌv�ē��̏��������͂��т��������̉��A�F�@�D������ĉƌv���x���Ă����B�v�[�z�ɉ������{�̊G�t���`���u��G�}(�݂���)�v�Ƃ������R�𒆐S�Ƃ����D��{���e�Y�n�ɓn����A���}�ʂ�Ɏ�������A���߁A�@�Ɍ������z��D�邱�Ƃ�������ꂽ�B�v�[�z�ƌ�G�}�ɂ���ē��X�̏��������͂������ɋꂵ�߂�ꂽ���A���ʊe�n�ɓ������邷�炵���D���������炿�A���̌��ʂƂ��Č���ɓ`�����Ă��邱�Ƃ��ے�ł��Ȃ��B

���m�ԕz�@
���m�Ԃ������Ƃ����D���ŁA�m�ԕz�Ǝv������̂ł́u����āv��16���I�㔼�ɂ͍v���E�f�Օi�Ƃ��Ĕm�ԁu�כc�ԕz(�T�C�h���N���v)�v�̋L�q���݂���B�u�������^�v�ɂ͋v�ē��ɕY���������N�l(1456�N)�A�^�ߍ��ɕY���������N�l(1477�N)���m�Ԃƕ\�����Ă����悤�ł���B����26�N(1598�N)���J�������N�Ɂu�y���ĕz�A�m�ԓ�Z�C�v�����ƋL�����B16���I�ɂ͒����ւ̍v����f�Օi�Ƃ��Ďg�p����A1609�N�̎F���̐N�U�Ȍ�A�F���͗����ɑ��v�[�i�Ƃ��Ĕm�ԕz3000�����`���Â����B�܂��A�m�ԕz���u��ĕz�v�Ƃ��ē�������֗A�o���邱�Ƃɂ�����R��ԐD�̋Z�@�������A�邱�Ƃ��ł����Ǝv����B���F�͐A�������ŁA���A�Ԓ��F�̃e�J�`(�ԗ֔~)�A���������ł͌��̏�Œ��钩��(����)�A����ߏցA�r���A�_�ߏւȂǂɂ��m�Ԃ����p����Ă����B�g���ɂ���Ďg�p����@�ۂ̑������Ⴂ�A�����͊��̒��S���ɋ߂��㎿�ōׂ��_�炩�ȑ@�ۂŐD��ꂽ�m�ԕz�𒅗p���Ă����B���m�Ԃ͉���̋C��ɓK���Ă������߂悭�炿�A����e�n�ō͔|����A�D���p�̎��Ƃ��ė��p���ꂽ�B��O�͊�@��(�R��)�A���A�m�A��(���X�m��)�A�|�x���A���l���A�^�ߍ����Ȃǂ̔m�Ԃɓ���������B�m�Ԃ͒����������悭�������珎���܂ŕ��L�����p����Ă����B

15���I�C���h�Ȃǂ̓���n����`������ƍl�����A�u����āv����6�N(1470�N)�ɗ������u���q�ԈِF�蕝�@����A�ʐF���蕝����A�ȕz���蕝�@����v�N�ɑ��������Ƃ�A����16�N(1480�N)�V���������痮�����Ɂu�蕝�D�Ԏ����z����v������ꂽ�ƋL����Ă��邪�A���ړǒJ�R�ԐD�Ɍ��т��L�q�͏��Ȃ��ڍׂ͕s���ł���B�ǒJ�R�ԐD�͖Ȃ�f�ނɂ������D�̈��ŁA�Ȉ�(���^�W���E���̒���)�A����(�����̒Z��)�Ɏg�p���ꂽ�B�䑎�L(�ԑ��L)�ɂ��ܕ��́u�q���C�o�i(���D)�v�Z�@�ŁA�͗l�͗��n�ɔ��E�ԁE���F�E�̈ܕ����ŐD���A�͗l���Ԃɚg���ԐD�Ƃ�����B���݂ł͒��ڂƑтƂ��Ė�30��ނ̉Ԗ͗l������A��{���Ƃ��ăW���o�i�[(�K��)�A�J�W�}���[(����)�A�I�[�W�o�i(���)���m����B�ǒJ�R���(�����^���U�e�B�T�[�W)���D���Ă���A�䑎�L(�ԑ��L)�ɂ��o�܂��͈܂̕��D�ɂ��u�q���C�o�i�v�ƁA�o����|�x���ł������F����D�����͗l�����u�e�B�o�i(��ԐD�܂��͖D��D)�v�̓�̋Z�@���g���Ă���B��ЂƂ͖{�����������┯�ɂ������ʂ����ł��邪�A������������j���̂��ߎv�������߂ĐD�����E���C�e�B�T�[�W(�z�����)�ƁA�Z�킪���ɏo��Ƃ����̈��S���肢�o��(����ł͌Â����珗���͉Ƒ��̎��_�ƍl�����Ă���)���D�����E�~�i�C�e�B�T�[�W(�o����ЁE�F����)������B

15���I�O���^�C�E�}���b�J�����������R��ꂽ���Ƃ��u����āv�ɋL����Ă��邱�Ƃ������`���Ƃ���l���ƁA�}���̓W�J�������̂��̂Ɏ��Ă���Ƃ������Ƃ��璆����������A�N���͂͂����肵�Ȃ��B�R�̐}���̓g�D�C�O���[(��)�A�u�V(��)�A�o���W���E(�ԏ�)�A�g�[�j�[(�c�M�E�{�̃J�C�o��)�A�E�V�k���[�}(���n�k�̏��̎�)�Ȃǐ����Ɋւ��g�߂Ȃ��̂��ނɍ\������Ă����B�R�͐��F���Ȃ����������炩���ߕʂ̎��ł������Ėh�����A���F����B���̌�A���������������قǂ��B���̎����g���ĐD����R�͗l��D��o�����Ƃ��ł���B��������@�ȊO�ɊG�ɂ����Ď펅���|���A�n�ň�����A���̕������肭���肷��Z�@�̊G�}�R�Ƃ����Z�@������B�R�ɂ͌o�R�A���R�A�o���R������w�I�ȕ���g�ݍ��킹�ĐD���邱�Ƃɉ�����R�̓���������B�����R�Ƃ͖{������e�n(��O�̓ߔe�̎Y�n�͔��A���\�A�������Ȃ�)�ŐD�����R�̑��̂����A���A�앗�����R�D����������v�ȎY�n�ƂȂ������Ƃ���A�앗���ŐD��ꂽ�R�𗮋��R�Ƃ����悤�ɂȂ�B���݂͎�Ɍ���f�ނɐD���Ă���B�@
���̐D���@
���s�ɐ��܂ꂽ�D���Ŗ�D�Ȃǂ��g�����������D���B�ԐD�Ɋ֘A���鎑���Ƃ��āA�u���z�v6���A������12(1659�N)�̍��g���i�v�g�ƂƂ��ɒ����ɓn�蕂�D���w���Ƃ��L����Ă���B�ω��ɕx���l�ȐD�������ŁA�ԑq�D�A�ԐD(�n�i�E�C)�A���[�g���D(���ԐD)�A���(�e�B�W�})�A���̒�(�A���k�i�[�J�[)�A�����h�D�b�`��(�����)�A�ԐD���(�n�i�E�C�e�B�T�[�W)�A���X�m��(�j�[�K�V�o�T�[)�Ȃǂ�����A�Őg���̍����l�X�ɒ��p�����D���ł������B���{���ł͐D�̋Z�p�̍����n���̕����̏�����I�сu�z�D���v�Ƃ��Č�p�z�̐���ɂ����点���B�܂��A�m���K���̏������Ƒ��̂��߂ɐD�����Ƃ������A���܂≤���Ȃǂ�����a���@�Ɍ������Ă����悤���B�@
�y�W�z 2�{�̌o�������������ĐD��Z�@�B���������������̈��Ɍ��Ԃ�������l�ƂȂ�B�@
�y�ԐD�z(�n�i�E�C)�����\�ɕ����o�������ɕ������ʕ��ԐD�̂��ƂŁA���ʎg�p�ł����B�@
�y�ԑq�D�z �����g���W�D�ƉԐD���s���͗l�ɐD���A���܁E������j��(�m��)�̍ō��ʂł��長����N�����p���Ă����Ƃ������ʂȐD���B�@
�y���[�g���D(���ԐD)�z ��������`�������D�z�̗��ʂƂ��o�����������i�D�ŁA��ɏ㗬�K���̒j���̒����Ƃ��ĐD��ꂽ�B�@
�y��ȁz(�e�B�W�}) ����Ȃ̐D����2�F�̔Q�����{�������G�Ȋi�q�̒����R������D���B�@
�y�����h�D�b�`��(�����)�z ���ׂ�(����)�R(�g�D�b�`��)�̈Ӗ��B�قƂ�ǂ̌o���A�����R���ō\������A��G�}�ɂ݂���o�܂̐F�R�������B����i�q(�N�W���S�[�V)�Ƃ�������B�@
�y���X�m�ԁz(�j�[�K�V�o�T�[) �m�Ԃ̏_�炩���c�������g���D�`�ŕY���A�l�X�ȐF�ɐ��F�������A�W�D�Ȃǂɂ��ꂽ�B���͔Q��p���ō���Ă����B�@
�y�ԐD��Ёz(�n�i�E�C�e�B�T�[�W) �D��D�̋Z�@���R�A�Ȃ�g���킹����ЁB���̒n��̎�ЂƓ��l�A�v��Z��̂����̑��A�O���ւ̑����ɂ��g��ꂽ�B�ق��ɎȂƎȂƂ̊Ԃ��R����ꂽ���̒�(�A���k�i�[�J�[)�Ȃǂ̐D�����݂���B

�{�Ó��ō͔|������������т��Ď������A�芇(�Ă���)����R���Ƃ��A���������������������t�Ő��߁A���@�ŐD�肠�������̂ŁA�d�v���`�������w����Ă���B�{�Ï�z�ɂ͔��R�����邪�A�썑�̎��R�����`�[�t�Ƃ����D�蕿�ƍ��ɋ߂��Z���Ƃ��傫�ȓ����ŁA���̉��̂���[�����̐F�����́A�D��オ�����z�n�𐅐��ēb�����܂Ԃ��A�ؒƂ�1������@��������u���ʂ��ł��v����߂Ă͊��������߂Ă͊�������Ƃ�1�T�Ԃ��J��Ԃ��O�O�ȕz���߂ɂ���Đ��܂����̂ł���B�{�Ï�z�̐��Y�́A16���I�㔼���瑱�����Ă��邪�A���ݒ��ڂ̐��Y�͑啝�Ɍ������Ă���B�@
���{��z2�@
����(�����Ńu�[)�������Ƃ����D���ŁA�{�Ï�z�̋N���͈�Ƃ����������A�i�v�D���j����~�����v�̏��i�Ɋ��ӂ��A���i���Ɂu���K��z�v�Ƃ�����z��D��A���サ�����Ƃɂ͂��܂�B�����Ȃǂ̑@�ۂ��玅�����邱�Ƃ�т�(����)�Ƃ����B�����ɂ͗����g�p�������n�̏�z�������ł���B�R�͗l��1�{1�{�w��ő������k���ȕ����D��ꂽ�B�������ɉ��������@��p�����R�Z�@����������A�ׂ��ȏ\���R�́u���R�v�ɂ��{�Ï�z���D����悤�ɂȂ����B�@
�����d�R��z1�@
17���I���߁A�F���ւ̌���z�Ƃ��Ēm���Ă������d�R��z�́A�Ί_�����Y�n�ł���B�o�������A�ܒ��ю�(�����݂��E��ю�)���g���A�����Y�̍g�I���̐F�f���R���Œ��ɐ��߂����̂ŁA�킪���B��̒��R��z�ƂȂ��Ă���B�������N4���ɓ`���H�|�i�w����A���̋Z�@�͒��ю��܂��͒��������g���A�R���F�͎芇�肩�A��F�肱�݂ɂ�����Ƃ��A���̑ł����݂͎蓊�R(��)���g���ĕ��D�Ƃ���ƒ�߂��Ă���B�@
�����d�R��z2�@
�N���͒肩�łȂ����A�F���̍v�[�z�̂��ߐD��ꂽ���Ƃ��͂��܂�ƍl������B�{�Ï�z���l�������l���ł̉��A���d�R�̏����B���ߍ��ȘJ�����ۂ���ꂽ�B�v�[�z�Ƃ��ċ{�Ó��͗��n�E���d�R�͔��n��D��悤�w�肳�ꂽ�B�����͒������R�͎芇��̂��̂ƁA�����ɃN�[��(�g�I)���g�����тŒ��ڎ��ɐ��荞��(���)�����R������B�d�グ�ɊC���ɎN���C�N���ɂ���Ĕ��n�͂�蔒���A�R�̐F�͂��Z���d�グ����B�@
���v�ē��ہ@
���������Ƃ����D���ŁA15���I�����V�䉮����������{�\�Z�p���w�ѓ`���A�u��]�F�Ɖƕ��v�A�u���������L�v(1731�N)�ɂ��Ɩ���47�N(1619�N)�z��̏@������(�������F��{����)������ɓn��A���J���̒����E���߂�T��{�\�Z�p�Ă������߉��̖��ɂ��v�ē��ɗ{�\�Z�p��`�����Ƃ����B���Ɂu�������L�v(1706�N)�A�u�������R���L�v(1713�N)�A�u���������L�v(1731�N)�A�u��u�싌�L�v(1743�N)�ɋv�ē��ۂɊ֘A����L�q������B�v�ē��ۂ̐����̓e�J�`(�ԗ֔~)�A�O�[���[(�T�g���C�o��)��D�}���������̂Ŏd�グ�ɋm�ł��ŕ��������o���B�Œ��F�̒n�F����ʓI�����A��]�F�Ƃ̌�p�z���n���ɂ��Ɖ��{����̋v�ē���(��p�z)�ɂ́A���E�i���g�����O�[�Y�~���߂ɂ��D�F�R��n�F�ɍg�E���F�E���ȂǑ����̐F�����݂��Ă����B

�~���T�[�Ƃ͖�(������Ń~��)�A��(�T�[)�ŁA�ȋ��т̍בт��w���B����ł͌×�����ߕ��̒��p�ɑт͗p�����A���R�ɒ������������ރE�V���`�[�Ƃ������p�@����ʓI�ł��邪�A�������J���ɏ]�����鏎���͒����������Ȃ��悤�m�тȂǂ̑т��������߂Ă����B�c�ɂ͎��R�����ɂ�鍥�����x�ł��������߁A�������z������j���ɑт�A���[�A�V�r(�їV�сE�Ⴂ�j��������̉��A�_��ƌ�ɖ쌴�ɏW���O�����ɋ����S���x��o��̏�)�Œj�����������瑡��ꂽ�т���߁A�݂��̈�����m�F�������Ƃ��ĐD���Ă����B�j���͌��іڂ����ɂ��A�����͑O�Ō���ł����B�|�x���̒|�x�~���T�[�⏬�l���̏��l�~���T�[���R��5�ʂ�4�ʂ�1�ŁA�z��҂ƂȂ�j���Ɂu���̐��܂ł����i��.....�v�Ƃ����肢�����߂đ���ꂽ�B�т̗��[�̎Ȃ̓��J�f���l�Łu���ɂ��ʂ��v�Ƃ����Ӗ��ł��邪�A�������炱�̂悤�ȕ����D���Ă������s���ł���B���Ɏ������т��D�����ԕ��������I�ȓǒJ�R�~���T�[�A�����̖��n�̃~���T�[�A�ߔe�~���T�[�A�����ɒ��������R���l�̗^�ߍ��~���T�[�Ȃlj���e�n�ōבт��D���Ă����B�����哇�ł́A�����̐D��V�тƂ��āA�בт��D���Ă����Ƃ����L�^������B�@
���^�ߍ��D�@
�u�������^�v(1477�N)�ɗ^�ߍ����ɕY���������N�l���A�^�ߍ��⍕���ł͒����ŕz��D������ɂ͗���p���Ă���ƋL����Ă���A15���I�㔼�ɂ͐D�������݂��Ă����悤�ł���B�����͒����A�m�ԁA�ؖȁA���Ȃǂ��R�͂قƂ�nj����Ȃ��B�����ɖؖȂȂǂ̌o�Ȋi�q�ȂǏ����̎d�����ƂȂ�^�ߍ��h�D�^�e�B�A10��ނ��̉ԕ����w�ɐD��^�ߍ��ԐD�A�o�Ȃ̒��ɕv�w���R�Ō����~���T�[�D�̗^�ߍ��J�K���u�[�A����D�蕿���o�������Ђ̗^�ߍ��V�_�f�B������B

 �@
�@�X�N���[�����
���{�̏����������D��Œ��p����e�L�X�^�C������i�͑�̂ɂ����āA�X�N���[������ɂ����̂������B�X�N���[������̐��^�͓��{�̗F�T���H�Ɏg����^�������f���ɂȂ��Ă���B�X�N���[������̌��c�͓��{���Ǝ咣�����������B���s�ߑ���D�Z�p���B�j(���s�s���D�����ꔭ�s)�̒��ɂ�������Ă���B�@
����ɂ��Ɓu����40�N(1907)�ɉp���}���`�F�X�^�[�̃T�~���G����V�������A�X�N���[������Ɋւ�������Ă��邪�A���̌�A���B�𒆐S�ɃX�N���[������ɂ��Č������i�߂��A�吳14-15�N���ɑ�ʐ��Y���\�ɂ��������������t�����X�ʼnԊJ�����B���̕����̓h�C�c�ɂ��g�y�����v�Ɠ`���Ă���B�@
���{�̌^�����p�ɂ��F�T�͗l(�F��)���I�݂ɕ\������Z�p���A���B�̃X�N���[���^�g���p�̓�������ɁA�ǂ̂悤�Ɍ��т����̂���̓I�Ȏ������Ȃ��B������19���I����20���I�̏��߂ɂ����A�t�����X�₻�̎��ӂ̉��B�����ŁA���{�̕����G�̔������@�ׂȕ\���ɒ��ڂ�����Ƃ���p�W�҂����������B�����G�͊e�F�ʂɁA�^���Ƀq���g�����ł�p���A���ɑ��ĐF������d�˂邱�ƂŁA�l���A���i�������Ȃ܂łɐ����ɕ\�������B���̍��荞�Z�p���e�L�X�^�C���v�����g�ɁA�Ȃ�Ƃ����p�������ƁA�����̉��B�l�Ȃ�l�������Ȃ��Ƃł���B

�^���g���̗F�T�����ł́A��Ƃ����₷���悤�ɏ����̕z����ɓ\����A���̏�^����u���āA��x����p���ĐF�܂��^����ʂ����荞��ł����K�v������B����ł͔\���I�ȓ�����Y���o���Ȃ��B�@
���̉�����Ƃ��āA�T�C�Y�̑傫���X�N���[�����^(�V���N�юg�p)���ɒu���āA�F�Ђ���^��ɗ�������A���̐F�Ђ��_�̐�[�ɉ����(�w��)�ɂȂ��������ʼn���1��X�L�[�W���O(�~��)�œ���ł���悤�ɂ����B��悪�I���A��悵�����̗אڕ������^�����X�Ɉڂ��ăX�L�[�W���O���J��Ԃ����B���̕��@���Ɣ\�������A���ꂪ���������ł���B���̕��@����ɏ��a���̗p�����B�@
��ꎟ���E����A���������̃X�N���[����������̓C�^���A�̃R���p�����ꂽ�B�R���ł͒������e�[�u���̏�ɕz�荇�킹�A�e�[�u���̍��E�Ɉ�l�Â�Ǝ҂�z�u���āA�e�[�u���Б���1�l�����e�[�u����̃X�N���[�����^��ɐF�Ђ����A�������Ǝ҂�����ŃX�L�[�W�������悤�ɂ��ăX�L�[�W���O�A���̃X�L�[�W�e�[�u�����͂���ŁA�^�����Ɉʒu�����Ǝ҂����X�L�[�W���O�A�X�L�[�W���O���I���A���^�����X�ɗאڕ��ֈڂ��X�L�[�W���O��Ƃ��J��Ԃ����B���ꂪ�R�����ł���B�@
���̂悤�ȍ�Ƃ����コ���邽�߂ɂ́A���^�̉��v��K�v�Ƃ����B���ꂪ�h�C�c�Ō������ꂽ�ʐ^�^�Z�p�ł���B�h�C�c����ʐ^���ŋZ�p�����{�ɓ��荞��ŁA���{�̎�������(�X�N���[�����^�g�p)�����B�����B�@
���{�A�������A�R���ɂ�������������̃e�[�u���`��́A���ꂼ��قȂ����`�Ői�����W�����B�������A�R���̎����e�[�u���͕��e�[�u���Ń\�t�g�x�b�h�A���{�͌X�e�[�u���Ńn�[�h�x�b�h�Ƃ����`�ō�Ɠ��e�����ɉ������B

�ʼn�͌��݂ɂ����Č|�p�A�f�U�C���A�o�łȂǗl�X�ȕ���Ŋ��p���ꐶ�Y�����̍s�ׂƂ��đ傫�Ȗ������ʂ������W���Ă���B�ʼn�͕������삳��邱�Ƃŏ��X�Ⴍ������ʂ͂��邪�A�t�ɍ�Ƃ̈�u�̃C���X�s���[�V�����ɂ�萶�܂ꂽ��i����葽���̐l�X�ɓ`���邱�Ƃ��o������@�ł���B�ʼn悪�����܂Ŕ��W���Ă������R�Ƃ��āA�Z�@�̑��ʂ��ƕ������Y���\�ł��������炾�ƍl������B�@
���[���b�p�ł̔ʼn�̗��j�I����ƋZ�@�ɂ��ĐG���B�ʼn�̎n�܂�͐M�̕��y�Ɛ��Ȃ邵�邵�̗ʎY�A���ʎʂ��̍s�ׂ���Ƃ���Ă���ʂ�A���Ƃ��Ƃ͐������̏������Y����̔��W���炾�ƍl�����Ă���B���[���b�p�ł̏������Y�͏\�ܐ��I������܂ł́A�u�ʖ{�v�Ƃ����`�Ŏ菑���ɂ���čs���Ă����B���̍s�ׂ�������n�܂������Ƃ����̂͒肩�ł͂Ȃ����A�\�I�ȑO�̎ʖ{���Y�͏C���@�����S�ƂȂ萹���A���тȂǂ��ʖ{�Ƃ��Đ���������B�\�I�ȍ~�ɂ͊e�n�ɍ��ʐ��E�҂̗{������ړI�Ƃ����w�����܂ꋳ��ɕK�v�ȋ��ȏ����𐧍삷�鏑�ЋƎ҂������X���o���܂łɍL�������B�������A1400�N���O�ɖؔłn�ɓ]�ʂ���u����v�̋Z�p�����܂��ȂLj���p�̋����ɂ���Ďʖ{���Y�͏��ł����B�@
����̋Z�p�����܂�y�[�W���ꖇ�̔Ŗɒ���A���ɓ]�ʂ��Ĉ�x�ɑ����̓���R�s�[�ނ��Ƃ��\�ƂȂ����B����͕����̏����A���悯�̖����ʂ�������n�A����̃~�T�����s�ɏW�܂�M�k�����ɔ���ړI�Ő���ꂽ�B�ؔł͎ʖ{�ɔ�ב������Y���邱�Ƃ��o�������A�Ƃ����_�炩���f�ނ��g�p���Ă��邽�߁A�Ŗ��������ł��Ă��܂��A����A�\�荇�킹��d���Ɏ��Ԃ�������o��Ȃǂ�������Ƃ������Ƃŕʂ̎�@���͍삳���悤�ɂȂ����B

�Δʼn��1796�N�Ƀ~�����w���̌���ƃA���C�X�E�[�l�t�F���_�[(1771-1834)���A���R�̋@��ɑ嗝�Ζʂɐ��Ɩ��̔�����p�ŕ���Ȃ܂܂ɖ����C���N�̕t���Ƃ���ƕt���Ȃ��Ƃ��������A���ł̌����������B�Δł����E�I�ɍL����͔̂������甼���I���z���Ă���19���I�̑O���������B����ł����E�ɍL�����Ă���́A�V����������̋Z�p�͐ΔłƂ�����܂ł̑S������ʉ߂��Ă��� �B�@
�V���N�X�N���[���͌Â�����g���Ă����X�e���V��(�^��)�ɂ�������A���������W���������̂ł���B���̋Z�@��1910�N��ɃA�����J�ő��F���肪�����������ƁA�܂���̌^���琔�畔������ł��邱�Ƃ���A�����̍�Ƃ�E�l�B���l�X�Ȏ��������݂�悤�ɂȂ����B

�����I�ɂ͂��܂蒍�ڂ���Ă��Ȃ������ȍ~�̈��i�ł��邪�A���{�̓����j�ɂ����Ă͈ꎞ����悷�d�v�Ȉʒu�Â��̐��i�Q�ł���B�ɒ[�Ɍ����Ό���̂₫���̎Y�Ƃɒ�������q�ƋZ�p�v�V�̏��ł���B�@
�Èɖ������͂��߂Ƃ��鍜������ɋ��������l�ԂȂ�N���A�������ȍ~�̈��i�̂��Ƃ͒m���Ă���B�������A���������狻���̑ΏۊO�Ƃ��Ē��ڂ��邱�Ƃ͋H�ł���B��������Ȉ�l�ł������̂����A�t�b�Ɛ��t�̈Ƃ����̂͂ǂ�ȕ��ɍ��ꂽ�̂��Ȃƍl�������A���R�Ɓu�^�ň�����Ă�낤�ȁv�Ƃ����v�������Ȃ������B���t����Ƃ��Ď���߂Ă������ɂƂ��Ă܂��ƂɈ⊶�ȏ������B���߂Ē��ڂ��T�v��Ƃ���܂Œ��ׂ��̂ł����ɓZ�߂Ă݂��B�@
���Z�@�̕K�R���@
��������ɂȂ�Ə]���̂₫���̐��Y�̐��p�~����A���R�ɐ��Y���\�ɂȂ����B�q�̐��͋}���ɑ����A���̐��Y�ʂ͔���I�ɑ��������B����p��Ƃ��č����̎��v�̐�����v�X�L����A����ɑΉ����邽�ߑ�ʐ��Y�ւ̋Z�p�v�V�̗v�������܂����B�����ōő�̃l�b�N�ƂȂ��������Y�ʑ����ɔ����G�`���̐�ΐ��s���Ǝ�Ԃ̂�����G�t���H���̉��P�������B�����̒n��ŊG�t���Z�@�̖͍����ϋɓI�ɍs���A���������w�i�̂Ȃ�����A����̕��l���ȒP�ɌJ��Ԃ��`�����Ƃ̂ł���Z�@���J������Ă����B

�ƌĂ���i�Q�́A�傫���́u���G�v�Ɓu�]�ʁv��2�̋Z�@������B���̑��u���n�v�u�S����v���ɑ��̂��ꂪ�A�Z�@�I�ɃC���[�W�ł���ł����ł͏ȗ�����B�@
���G�]��/�u���G�v�ƌĂ��Z�@����O�ł͂��߂�ꂽ�B����͌^������Ƃ��^�G�A�^����t�Ƃ������A���l�����^������ʂɂ��ĂāA���̏ォ����тȂǂŊG������荞��ŊG�t���������́B�����́A�^���ɕ��l�肠���邱�Ƃ���A�A���������Ŗ͗l���������Ƃ��o���Ȃ��B�^�������ɂȂ�Ȃ��悤�ɕs�A���̌��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������ĕ��l���`����Ă�����̐��t�����ɂ͕K����ڂ�����A�@�ׂȕ\��������B�@
�����āu�]�ʁv�ƌĂ�铺�ň���@���p������悤�ɂȂ������A����͊G�����G�b�`���O�Z�@�ō��݉��ł�����A���̔ł�p���痿�����Ȏ��Ɉ���A����n�ɓ]�ʂ��邱�ƂŊG�t�����s�����@���B���l���S�M�ׂ̍����ō\������邽�߁A�ז��ȕ\�����\�ŁA�S�̂Ƃ��ăV���[�v�Ȋ��������������B�@
�u����v�Ƃ����Z�p�̍����͑��l�ȕϑJ���B���Ƃ��Ȃ���A����q�Ƃɂ����Ĕėp���i�̂قƂ�ǂ̊G�t�����s�����̂ƂȂ��Ă���B�@
�u���G�v�͖����̏����ɔ�O��M�̖��c�v�������n�߂��Ƃ������ƁA����7�N�ɔ�O�̏�����O�Y������(�ċ�)�����Ƃ�����������B�^�����莩�̂́A�z�̐��F�̋Z�@����]�p���ꂽ���̂Ƃ����A�Â��͍]�˒����ɂ��s���Ă����B���̎����̂��͍̂]�˒������ɂ͍s���Ȃ��Ȃ�A�Z�p�I�ɂ͓r�₵���Ɖ��߂���Ă���B������ɂ��Ă��u���G�v�͔�O�ɂ����Ė���10�N�����琶�Y���{�i�����A�ʎY�H��̊G�t���@�Ƃ��Đ���ɗp������悤�ɂȂ����B���̐��G�̋Z�@�́A����15�N���܂łɓu������Z�ȂNJe�n�̎��퐶�Y�n�ɂ��`���A�ȍ~�S���̎���Y���邳�܂��܂ȎY�n�ŗp����ꂽ�B�菑���ŕ\���ł��Ȃ��ɐ�����Ȃǐ��F�̐}����������ɉ��p����đ傢�ɗ��s�����B�������A���̌㌻�ꂽ���œ]�ʂ̋Z�@�ɑQ���ڍs���A��O����Z�ł��吳���ɂ͔p�ꂽ�悤���B

���œ]�ʂ̂ق������N���Ȑ}����`���o�����Ƃ��\�ł��邱�ƂƁA��ʐ��Y�ł͌^�̎������R�X�g�o�ϐ��ɂ����ďd�v�ȗv�f�ł��邱�Ƃ���A�^���ɔ���|�I�ϋv���������ł̗D�ʐ��ɐȊ����ꂽ�Ƃ������Ƃ��B���̌��O�q�Ƃ́A�吳10�N�����珺�a��O�Ɏ����ẴC�Q�M�S�����A����p��Ƃ��Ă̈�(���œ]��)���i�̑吶�Y�n�ƂȂ����B

���œ]�ʋZ�@�͍]�ˌ���ɂ����s���ꂽ���m������܂łɂ͎��炩�Ȃ������B���ň���́A�h�I�܂�h�������łɓS�M�ŊG���������ƁA���_���≖�����S��h���ēS�M�ՂH�������ł�����B���ɁA�ؐ��̃R�L�ƌĂ�铹��ŁA���łɊ痿�����荞�݁A����@�Řa���Ƀv���X���Ďʂ����A���̓]�ʎ�����ʂɐ����тœ\��t���A�}����t����������A�a���������͂������Ƃɂ���ĊG�t��������Ƃ������� �B�@
�ꌩ��Ԃ͂�����悤�����A��U���Ղ����ΑN���ȉ摜�̉��G�]�ʎ����e�Ղɑ�ʂɍ��邱�ƁA������g�p���邱�Ƃɂ���ĊG�t�łȂ��Ƃ����肵���G�t�����ł��邱�ƁA�^���ɔ���|�I�Ȍ��őϋv�������邱�Ƃ�����i�̎�͋Z�@�ƂȂ����悤���B�@
���̓��œ]�ʂ̋Z�@�͌���q�Ƃɂ����Ă��G�t�@�̈�Ƃ��āA���̂܂܍̗p���Ă��鐻�i�Q������A���̎������łɊG�t�Z�@�Ƃ��Ċ����m�����ꂽ�Ƃ������ƂŁA���M���ׂ��_�ł���B�@
���œ]�ʂŋ����[�������Z�p�I���������B�@
�u�痿�v�����ɂȂ��ăS�b�g�t���[�g�E���O�l���̎w���ɂ���ʓI�Ɏg�p�����悤�ɂȂ����_���R�o���g(�x����)�ɂ���āA���邭�N���Ȕ��F��������悤�ɂȂ����B�@
�u����C���N�v�痿���Ђƍ����ăy�[�X�g��ɂ��Ďg�p�����B���̌Ђ͔����Ƃ��������̋����ō��ꂽ���̂ŁA�]�ʎ��̘a���ɏ��₷���A�����тŊ�ʂɕt�����������Ǝ�������������₷���Ƃ��������������Ă����B�����͌��݂̓]�ʂł��g�p����A���̐����͑�֕i�̂Ȃ��D�ꂽ���̂��B���݂͒�������̗A���ɂ���Ă���B�@
�u�]�ʎ��v������J�����̂��]�ʎ��ł������A�h�C�c�A�t�����X�̓]�ʎ��ɕC�G���鎆������ꂸ���s������J��Ԃ����悤���B�吳�㔼�ɖ��É��̓��{���킪�����ɗ��Ȃ��]�ʎ��邱�Ƃɐ����A��i�Ɠ]�ʋZ�@�����y�����B�@
�u���G����v(���G�t�����։���)�M�A�������̂Ŋ�ʂ͋Ȗʂł���A����ɕ��ʂ̈ꖇ�̎��Ŗ͗l�����邱�Ƃ͕s�\�Ȃ��ƂŁA�͗l�͕����ɕ�������Ĉ�����ꂽ�B���̕����͗l���ʂɈ�����Ă����A�\��t���]�ʂ̍H���͊G�t�łȂ��Ƃ��o���A���ƂŌ����I�ɊG�t�����ł�悤�ɂȂ����B���i�Ŗ͗l�����ꂽ��A���Ԃ��J���Ă��肷��̂͂��̂��߂��B

���g�O���t�͌��݂̃I�t�Z�b�g����̃��[�c�ŁA���g�O���t����������Ȃ���A����̌���͑�ψ���Ă����Ǝv����B���悻�����ȊO�̃C���X�g���[�V�����A�܂莋�o�I�ȃC���[�W�A�G�Ƃ��A�}�ŁA�ʐ^�Ƃ��������̂̈���ɂ́A��Ƃ����Ă悢�قǃI�t�Z�b�g��������p����Ă���B���g�O���t��1798�N�~�����w���ɂ����ăA���C�X�E�[�l�t�F���_�[(ALoys Senefelder 1778�[1834)�ɂ���Ĕ������ꂽ���A���݂ł���m�[�x���܋��̔����ɒl����قlj���I�Ȃ��Ƃł������B�����A�����ȊO�̊G�A�}�ŁA�y���Ȃǂ̈���́A�ؔŁA���ɂ�邵���Ȃ��A�Ŏ�̐�����A��ςȎ��ԂƔ�p��K�v�Ƃ��Ă����B���̂��߁A�����ɁA�����Ă�葬���C���[�W���������Z�p�����̂��Ɨv������Ă����̂ł���B�[�l�t�F���_�[�͂��̎���̗v�������Ȃ̂��̂Ƃ��āA�H�v�A�T���̌��ʁA���g�O���t���B���R���ނɃq���g��^���A�K�v���Ǝ��R�Ƃ���̂ƂȂ��āA���̃��g�O���t�A�܂�Δʼn�͎������ꂽ�B�[�l�t�F���_�[�͔o�D�ł��������̎���A��Ƃ̐��v�𗧂ĂȂ���Ȃ�Ȃ������B�����ŁA�����납��S�̂���Y�Ȃ�y���̈���ɖڂ��������B�����ă]�[�����t�H�[�t���Y�̐ΊD��((�قƂ�ǁA�����͒Y�_�J���V�E��)��p���A�Γʔň�������݁A���X�̎����Ǝ��s�Ƃ��J��Ԃ����̂ł���B1796�N�̂�����A�����ɗp���Ă����̏�ɁA���b�N�X�A��������A�����v�u���b�N�ō�����C���N�ŏ������߂Ă������B���炭���ď����ׂ��Ɏ_�łӂ����Ƃ���A�C���N�͐ΖʂɌŒ����Ď��Ȃ��B�����Ŏ��݂Ƀv�����g�C���N�����ăC���N�̏�ɂ̂��A������ƁA�������ʂ����̂ł���B����Ƀq���g�ċ�̓I�ȋZ�p���������A�قڂ��ׂẴ��g�O���t�Z�@��1798�N�Ɋm�������̂��B

�A���C�X�E�[�l�t�F���_�[(Alois Senefelder�A�v���n���܂�1771/11/6-1834/2/26�~�����w���v)�I�[�X�g���A�鍑(���݂̃`�F�R)�̔o�D�E����Ƃł������B1796�N���R���烊�g�O���t(�Δʼn�)�����A����Z�p�̐i���ɍv�������B�o�D�ł��������e���v���n�̕���ɏo�����Ă����ۂɐ��܂ꂽ�B�ނ̓~�����w���ň炿������A�C���S���V���^�b�g�Ŗ@�w���w�ԏ��w�������B1791�N�ɕ����v����ƁA�ނ͕��8�l�̌Z��o����{�����߂Ɋw�Ƃł�����ߔo�D�ƂȂ����B�ނ̏������Y�ȁu���B�̊Ӓ�Ɓv(Connoisseur of Girls)�͑傢�ɐ��������B�����̋Y�ȁu�}�e�B���f�E�t�H���E�A���e���V���^�C���v(Mathilde von Altenstein)�̈�����߂�����ɂ��ނ͑��z�̎؋���w�����A�V�����������Y�Ȃ��o�ł���]�T���Ȃ��Ȃ����B�ނ͎���G�b�`���O�ň���p�̌��ł���낤�Ƃ��A�C���N������Ƃ��ă]�����z�[�t�F���ŎY�o����邫�߂ׂ̍����ΊD��̔����B������ނ͖����N�������ŐΊD��̏�Ƀ����������A��ŏɎ_�Ő��Ƃ����Ƃ������N�������̐Ղ��c���Ă��܂����B���̐Ղ̕����ɂ͂悭������邱�ƂɋC�t�����ނ́A�����C���N�ŐΊD���̃N�������Ղɏ����A���������t�����Ƃ��뎆�ɃC���N�̌`��]�ʂ��邱�Ƃɐ��������B�ނ͂������āA�����肵�ĉ��ʂ���炸�ɍςށA���ʂ̂܂܂̈���p���ł������@(���ň���p)�������B�ނ͎�����i�߁A�ΊD�̏�ɑώ_���̎��b�N�������Œ��ڎ��������A�ォ��A���r�A�S���ƏɎ_������������_���n�t��h�邱�ƂŐΊD��ɉ��w�ω����N����������@��҂ݏo�����B�N�������ŏ����������ɂ͎��b�ƏɎ_���������Ď��b�_���ł��A���b�_�͐ΊD��̒��̃J���V�E���Ɣ������Ė����C���N�̏��₷�����b�_�J���V�E�����ł���B����N�������ŏ����Ȃ����������ɂ͐���ۂA���r�A�S���̔疌���ł���B���̐Δ̏�ɐ��������Ղ�悹�A���[���[�Ŗ����C���N�������t����ƁA�N�������ŏ����������ɂ̓C���N�����A�����Ȃ����������͐e�����̔疌�ɂ���Đ��������C���N���͂����āA���ʃN�������ŏ��������������ɃC���N���c��B���̏ォ�玆�������t����C���N�����Ɉڂ�A�����̊����ł���B�ނ͉��y�o�ŎЂ��c��ł����A���h���ƂƋ����Ŏ���ɂ��̌��������p���ł���Z�p�ւƕς��Ă������B�ނ͐ΊD���N�����������w�ω���������@�ƁA�C���N��Δ��玆�ɓ]�ʂ���v���X�@�̎d�g�݂��������A��������S�Ȃ��̂Ƃ����B

1810�N��ɂ̓��g�O���t�͔��p�̐V�����Z�@�Ƃ��āA�܂���ʈ�����鏤�Əo�ŕ��̂��߂̊ȒP�ő����}�Ő���Z�@�Ƃ��ċ}���ɕ��y�����B�ނ̎����1837�N�A���g�O���t�͂���Ȃ���ǂɂ��A�����̔ł��g�����Ƃɂ��t���J���[������ł���悤�ɂȂ����B���̃N�������g�O���t�B�[(chromolithography)�͍ŏ��̑��F����p�ł���ACMYK�̎l�F����ɂ��v���Z�X�J���[�����������܂ł͍ł��d�v�ȃJ���[����Z�@�������B�[�l�t�F���_�[�̓o�C�G���������̍����}�N�V�~���A���E���[�[�t����M�͂��A���g�O���t�p�̐ނ��Y�o�����]�����z�[�t�F���̒��ɂ͔ނ̓��������Ă�ꂽ�B�@
�A���C�X�E�[�l�t�F���_�[�̈���ɂ�������т́A18���I�́u�X�e���I�^�C�v�v�̔����҃E�B���A���E�W�F�h(William Ged)�A���C�œ�����������@�������t���[�h���q�E�P�[�j�b�q(Friedrich Koenig)�A�����I�Ɋ����𒒑����郉�C�m�^�C�v�������I�b�g�}�[���E�}�[�Q���^�[���[(Ottmar Mergenthaler)��̌��тɕC�G����B���g�O���t�͈������l�X�̎�ɓ���₷�����̂ɂ��A���p�ƐV���̕���ɏd�v�ȉe����^�����B

�A���C�X�E�[�l�t�F���_�[(Aloys Senefelder�E1778-1834)���g�O���t�̔����ҁA�n�������A���Δň�����ݗ��A�Δň���p�A�Z�@�����o�ŁB���g�O���t�͐��Ɩ��̔�����p�𗘗p�����Ȋw�I����ł���B�ΊD���������A���b���̃N�������������n���g���ĕ`�悷��B���̏�ɃA���r�A�S���̐��n�t��2%�̏Ɏ_�����������̂�h�z�B24���Ԃ������Ɖ��w�ω��ɂ��A�G��`�����Ƃ���ɂ̓C���N���̂�A�`���Ȃ��Ƃ���͐���ۂ悤�ɂȂ�̂ŃC���N���̂�Ȃ��B���������@�ɂ����������̂��B�[�l�t�F���_�[�͉�Ƃł͂Ȃ������̂ŁA���߂���|�p��i�Ƃ��Ẵ��g�O���t������l���Ă����킯�ł͂Ȃ��������A�ケ�̋Z�@���L�܂�ɂ�A�|�p�\���ɉ��p���悤�Ƃ���l�X������ꂽ�B�[�l�t�F���_�[�ɂ���Ĕ������ꂽ���g�O���t�́A�ނ̎�𗣂�Ƃ�������n�߂��B���g�������̋Z�@�́A�I���W�i���ʼn�A�|�p��i�̕�����i�Ƃ��āA�܂��|�X�^�[�A���x���ȂǁA���܂��܂ȏ��ƈ���Ƃ��Ĕ��W�����B�@
���g�O���t�̍ő�̓����́A�ΖʂɃ��g�p�N�������܂��͉����n�ŕ`�������̂��A���̂܂ܔʼn�ɂȂ�Ƃ����_���B�`�����͎��R���݂ŁA�ʼn�̒��ł͈�ԑ��l���Ɖ\��������Ǝv���B�N��������y���`���ɂ��P���Ȑ��`�����̃f�b�T�����疾�Â̂������肵�����́A�M��z��p�������́A�ڂ������薶�𐁂�����A�z��t�ɉ����n�����ĐΖʂɉ����t�����肵�����̂ȂǂȂǁB�d���ȃ}�`�G�[�������邱�Ƃ��ł���B�܂��]�ʎ����g���A���E�t�łɂȂ�̂��C�ɂ����A���Ƀf�b�T������̂ƑS�����l�ɁA�`�������̂����g�O���t�ƂȂ�B����͖n�C���N����łȂ��A�J���[�C���N�ő��F���������A�F�N�₩�Ȗ��͓I�Ȃ��̂ɂ��Ȃ�B���݁A�|�p��i�Ƃ��Ẵ��g�O���t�́A�A�[�e�B�X�g���g���łɊG��`�������̂��I���W�i���Ƃ��Ă���B����̕��@���A�A�[�e�B�X�g�����掩���肵�����́A���̃v�����^�[���C���N���萷�肵�Ď��������@�ō��������́A���[�^�[��������@���g�������̂Ȃǂ��܂��܂ł���B
�����t�����X�ł́A�p�Y�i�|���I���̏o���ɂ��A�|�p����ɂ����g�������炳�ꂽ�B�V�ÓT�h�A���}���h�̂������������Ƃ����A�_���B�b�h�A�O���A�A���O���A�W�F���R�[�A�h���N���A�A���F���l�A�V�������Ȃǂ�y�o���A�ނ�̓��g�O���t�Z�@�ɂ�莿�̍�����i�삵���B��܂̓V�˃W�F���R�[�̓����h���̕n����n�����g�ɂ��A�F�l�ł������h���N���A���u�t�@�E�X�g�v�u�n�����b�g�v�̑}�G��`�����B���̌�u���_���A���g�D�[�����۔h�̉�Ƃ����A�}�l�A�s�T���A���m���[���A�Z�U���k�A�h�K�����g�삵�Ă���B���g�D�[���Ƀ��g�̐�������߂�ꂽ���h���́A�₪�ă��g�O���t�ɔM���A�u���̒��v�u���A���g���[�k�̗U�f�v�u�S���ɕ����v�Ȃǃ��g�O���t�W��A�Î�Ȑ��_���E��[�����̒��ɕ\�����Ă���B
 �@
�@�X��
�C�����̓`���������ߕz�A�y���V���X�сB�������A�Ɠ��̖͗l�ƐF����������l�̖ڂ��Ђ����ė����܂���B���́u�X�сv�Ƃ́A�����������Ȃ̂ł��傤�B�@
�u�X�сv�Ƃ́H���������u�X�сv�Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂ł��傤���B�@
���E�e�n�ł��܂��܂Ȕ��W�𐋂��A���{�̐��D��ɂ��[���e�����y�ڂ������́u�X�сv�A���̑��l������`���Ă͂����肵����`������Ȃ��Ă���̂ł����A�u�Ԃ�l���Ȃǂ̖͗l����߂����ؖȂ̕z�v�Ƃ����̂��A�����悻���ʂ����F���ɂȂ�Ǝv���܂��B�@
���{�Łu�X�сv�Ƃ����ƁA�����������Ȍ��̒����n���v�������ׂ�����������Ǝv���܂��B����́A�V���N���[�h�ɂ̂��ĉ^��Ă������́u�X�сv�����ٍ̈���Ől�X�𖣗����A�u�a�X�сv�ƌĂ����{�Ǝ��̍X�тW�����A����ɓ`��邩��Ȃ̂ł��B���Ƃ��Ƃ̓C���h�ō���n�߂��Ƃ������̍X�сA�V���N���[�h�ɏ���Đ��֓��։^��āA���ꂼ��̍��œƎ��̔��W�𐋂��A���̑����̓y���V���X�т̂悤�ɍ��Ȃ����߂�ꑱ���Ă��܂��B�@
���u�X�сv�̌ꌹ�@
���{��́u�X�сv�͎��́u�T���T�v�Ɋ����Ă����̂ł���A���̌ꌹ�ɂ͂��܂��܂Ȑ�������܂��B��������͂Ȃ��̂ł����A�C���h��Łu�������D���v���Ӗ�����u�T���T�[�v���ꌹ�Ƃ�����A�|���g�K����́u�������z�v�u�T���V���v���Ƃ������A�܂��̓C���h���C�݂̌Â��`���u�X���b�g�v���Ȃ܂������̂��Ƃ������Ȃǂ��ꂼ��X�т̗��j�f���Ȃ���A�Ȃ�قǂƎv�킹�鏊���ʔ����Ƃ���ł��ˁB�X�т̌��Y�n�́A�C���h�ł���ƌ����Ă��܂��B

�����̍X�т́u�J�����J��(�y���V����́u�K�����J�[���v�ł��ˁB)�ƌĂ�A�y���̂悤�ɐ�ׂ̍����̂ŕ����I�ɂ낤�����߂��g���Ă��܂����B���݂��菑���Z�@�A�ؔŃu���b�N�v�����g�p�����Z�@�A�낤�����߂Ȃǂ�����A���ɋߔN�ł͖ؔŐ��߂�����ɂȂ��Ă��܂��B�@
���́A�C���h�Ŕ��˂����X�т͐��֓��ցA���E���ɉ^��Ă��ꂼ��̒n��œƎ��̍X�тނ��ƂɂȂ�܂����B�����ւ͂܂����ׂ̃y���V���A�����đ�q�C������o�ĉ��ƃ��[���b�p�ɂ��L����܂��B�u�`���c�v�̖��Œm����C�M���X�X�сA�y���V���ŋZ�p���w�ƌ�����t�����X�̃W���[�C�X�сA�₩�ł��킢�炵���h�C�c�X�сA�����ăA�W�A�e���̍X�т����̑D�Ŏ����A���Đ��E�ɓ`���������A�I�����_�̍X�тȂǁA����̉����Ԗ͗l�v�����g�̂��������Ƃ��Ȃ��Ă������̂ł��B�@
�����ē����ł́A�����F�����^�C�̃V�����X�сA�u�o�e�B�b�N�v�̖��O�œ��{�ł��悭�m����W�����X�сA�������ꂽ�����X�сA�����ē��{�̘a�X�тȂǂ����܂�܂����B�@
���l����@�����ꂼ��̍��ł���ɓƎ��̔��W�𑱂����X�т͂��ꂼ��ꌩ�܂������ʂ̕z�̂悤�Ɍ�����̂ł����A�ǂ��ƂȂ��������o�����u�ٍ���v�A�����Ă����߂�ɐ��ߏグ���閧�x�Z�����l�Ƃ��������́A�X�т̍X�т���䂦����Ȃ��c���Ă���Ƃ�����ł��傤�B

�����Ő�������X�т̖͗l�́A��ɃC���h�X�т̂��̂ł��������̓y���V���X�т̖͗l�Ƃ��d�Ȃ���̂ɂȂ�܂��B�@
�����ؖ͗l(�����͗l)�@
�Ñ�A�����ł͎��͐�����s���̏ے��Ƃ��đ���Ă��܂����B�����Ƃ��Â����ؖ͗l�́A���̍��E�ɗL���̎��_��`�������̂Ƃ����Ă��܂��B���̎��ؖ͗l�̓C�X�����̐����Ƃ��Đ_��������Ă���A�����̖͗l�ւƂ��̓`�����p����Ă����܂��B�u�i���̐����v��\���A�C�X�����̐����ƂȂ��Ă��邱�̎����͗l�͂܂��A�y���V���ɃC�X�����������炳�ꂽ�Ƃ�����A�]���A�X�^�[���k(�q���k)�����̌`���Ȃ��炦���O�~�ɐD�荞�ނ悤�ɂȂ����Ƃ������A�����[�����̂ł��B�@
���y�C�Y���[�͗l�@
�y�C�Y���[�̔��˂ɂ��Ă͒���͂Ȃ��̂ł����A���������ɗh��Ă���l�q��\�������̂Ƃ�����ʓI�Ȑ�������܂��B�������Ȃ������悤�Ȍ`�����A�֊s���ɑ��Ԃ��`���ꂽ��A��q�̂悤�ɑ傫���y�C�Y���[�Ə������y�C�Y���[���d�˂ĕ`���ꂽ��A���܂��܂ȃo���G�[�V����������܂��B���̃y�C�Y���[�͗l�͓��ɁA�y���V���X�тɑ��������܂��B

�����͗l�͌Ñ�G�W�v�g�̃i�C����݂̃��[�^�X��`�������̂����^�ł���Ƃ����Ă��܂��B�M���V���̃p���e�m���_�a�̑����ɂ������邱�̓����͗l�̓��[�}�A���ߓ����o�Ă��܂��܂ɕω��E���W���A�C���h�ł͉₩�ȉԓ����ƂȂ�܂����B�y���V���X�тŔ��ɑ��������铂���͗l�́A�y���V���O�~�ɂ����Ă����܂��܂ȃo���G�[�V�����Ŕ������D�荞�܂�Ă��܂��B���Ƀu�h�E�̖����v�킹�A���ɉԂ�t��t���Ȃ���������������邱�̓����͗l�́A�����e���ł��ꂼ��̓�����������Ȃ���\������Ă��܂��B�@
���ԑ��͗l�@
�����͗l�ɔ�ׁA��莩�R�Ȍ`�ŕ\�������ԑ��͗l�́A�؉Ԃ̉ԑ��̌`��n�ʂ��琶�����`�ŕ\������܂��B�y���V���X�тł͐������ꂽ���͋C�̏��Ԃ�ȉԑ��͗l�������ΐ��߂��A���[���b�p�̉e���̔Z�����̂��ǂ������܂��B�@
���l���͗l�@
�C���h�X�т̐l���͗l�́A�q���Y�[���̐_�b��f�ނɂ������̂�A�ٍ��̐l�X���ނɂ������̂����������܂��B�y���V���X�тł́A���ƃ��C�I���̐}���Ȃǃy���Z�|���X��Ղ̃����[�t�͗l�Ɍ�����͗l��A�A�܂����C���[�ƃ}�W���k�[���̕���ȂǁA��������ɂ������̂����������܂��B�@
�������͗l�@
�����͗l�ł́A�g���⎭�A�A���Ȃǂ��܂��܂ȓ������ԂⓂ���A�y�C�Y���[�ȂǂƑg�ݍ��킳��Č��z�I�Ȕ��������o���Ă��܂��B

���W�����X��(�o�e�B�b�N)�@
���{�ł��u�o�e�B�b�N�v�̖��ł悭�m����W�����X�т�11-12���I����C���h����`������Ƃ����Ă��܂��B�o�e�B�b�N�Ƃ͘X���߂̂��ƂŁA�W�����X�ѓƓ��́u�`�����`���v�Ƃ����Ƃ��������̃c�{�̗l�ȓ�����g���ĘX���ׂ����炵�Đ��߂�̂����F�ƂȂ��Ă��܂��B���݂ł͖��|�Y�ƂƂ��đS���������č���A���w�����̌^���߂��قƂ�ǂ��Ƃ����Ă��܂��B�@
�͗l�͐A���A�����A�l���ȂǁA���E�ō��̑��l�����ւ��Ă��܂��B��̂͂点���ɘA�����l��z�u�������̂ŁA�A���̗t��ցA���A���R�����Ȃǂ��w���l�ɐ��ߏグ�Ă��܂��B�@
���V�����X��(�^�C)�@
�V����(�����݂̃^�C)�̍X�т́A���ۂɂ̓V�����ō��ꂽ���̂͏��Ȃ��A�قƂ�ǂ��V�����ōl�Ă����}�Ă��C���h�֒������Đ��߂����̂��Ƃ���Ă��܂��B�����v�z�ɂ�����长�������A���`�̉ԕ����b�A��F���A�쒹�Ȃǂ����ɂƂ��A���{�֓`����ꂽ�ۂɂ��������������̐e�ߊ������ꂽ�����ł��B�@
�������X�с@
���{�Łu�ԕz�v�A�u��ԕz�v�ȂǂƌĂ�钆���X�т́A�Z�@�̓C���h�X�тƓ����Ȃ���A���k�ȕ��l�͒����Ɠ��̕��͋C�������A���ɐ������ꂽ�����悤�Ȏ菑���̃^�b�`�̕��l�͂��̓`���̐[�������������܂��B���{�ɂ̓I�����_�D�ɂ���ĉ^��܂����B�@
���a�X��(���{)�@
�����E�]�ˎ���Ɂu�C�̃V���N���[�h�v�ɂ���ĉ^�ꂽ�X�т͂͂��߁u��ؓn���̔����i�v�Ƃ��Ē��d����܂������A�������ɓ��{�Ǝ��́u�a�X�сv�������悤�ɂȂ�܂����B���̕��l�����{�I�ɕω����A�Ǝ��̍\�������܂�܂������A�X�ѓ��L�́u�ٍ���v�͍��Ȃ��c����Ă��܂��B

�I��6,7���I�ɔ��p�H�|�̔��ɉh�����y���V���ł́A�I���O2��N���납��X�т����߂��n�߂Ă��܂����B���E�I�ɗD�ꂽ�O�~�A�h�J�̋Z�p�����y���V���̍X�т͔������A�D�ꂽ���̂������Ƃ���Ă��܂��B�Z�@�̓C���h�X�тƂ܂����������ŁA���l�����ʂ������̂������̂ł����A�y���V�����̕��l�����������A���[���b�p�̉e�����ăo���A�`���[���b�v�A�q���V���X�Ȃǂ̗m�Ԃ����p����Ă��܂��B�@
���I�����_�X�с@
�A�W�A�e���̍X�т�D�Ŏ����A�����I�����_�́A���ꂼ��̓������������킹�A�y���ʼn₩�ȊG�敗�̍X�тݏo���܂����B�F�����W�����ԐF���g���Ė��邭���߁A���Ԗ͗l�������̂������ƂȂ��Ă��܂��B�@
�����V�A�X�с@
���V�A�ł́A�@�B���������������������܂����B�Ԓ����������A�W���F���Ŋ��F�n�𑽗p������A�_�`�\�������l�Ɍ�����̂������ƂȂ��Ă��܂��B�@
���C�M���X�X��(�u�`���c�v)�@
�C�M���X�ł͍X�т́u�`���c�v�ƌĂ�A�o���A���A�Ȃł����Ȃǂ̑��Ԃ�z�����������ԕ��͗l�́A���[���b�p�ő嗬�s���܂����B���݂ł��u�I�[���h�E�C���O���b�V���E�`���c�v�Ƃ��ē`���I�ȍX�т����߂�ꑱ���Ă��܂��B�@
���W���[�C�X��(�t�����X)�@
�t�����X�ł̓p���x�O�̃W���[�C���ɏZ�ރI�y�[���E�J���v���y���V���X�т���Z�@���w�сA�W���[�C�X�т�听���܂����B�q�̓I�Ȑ}�ĂŎ��������Ɋ��}���ꂽ�Ƃ������̃W���[�C�X�т́A�t�����X�̎Y�ƂƂ��ăi�|���I�������҂����̂ł����A�i�|���I���̔s�ނƋ��ɏ��ł��Ă��܂��܂����B�@
���h�C�c�X�с@
�ߑ�Ȋw���������A���x�ȓ���Z�p�������Ă����h�C�c�ł́A�v�����g���l�̗p�ɂ��킢�炵���A�F���₩�ȍX�т�����܂����B

�������ォ��u�C�̃V���N���[�h�v��n���ē��{�ɉ^��n�߂��X�т́A���̂߂��炵���Ƌ���Ȍ��Ől�X�̐S�𖣗����܂����B�Ƃ͂����͂��߂͈�ʂ̐l�X�̎�̓͂����̂ł͂Ȃ��A��ؓn���̔����i�Ƃ��Ĉꕔ�̏㗬�K�������p������A���l�̊ԂŁu������v�Ƃ��Ē��d���ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B�@
���{�����ōX�т�����n�߂��̂́A�ؖȂ͔̍|�A���y���n�܂����]�ˎ���̂��Ƃł����B�͂��߂̓C���h�X�т�W�����X�т��͕킳��܂������A�������ɓ��{�Ǝ��̖͗l��\������������A���{���̕ω��𐋂��Ă����܂����B���̉ߒ��ŗF�T�̋Z�p��G�������Ƃ������Ă��܂��B�@
�ʔ������ƂɁA�����ɘa���ɕω����Ă��A�X�т́u�X�т炵���v�͈����p����A�ǂ��ƂȂ��u�ٍ���v��������������̂ɂȂ��Ă��܂��B��Ԃ�Ԃ��d����{�̔��I���o�ɑ��āA�X�т́u�ߏ�̔��v�Ƃ�������قǐF�ʖL���ɖ͗l�ߐs�����܂��B�܂����ꂪ���Ȃɒ����n�Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ������܂炸�A���炭�͒j���̉����⏬���Ƃ��ėp������݂̂ŁA���ɂȂ��Ă悤�₭���n�̏����p�̍������ڂƂ��ė��s����悤�ɂȂ�܂����B�@
�ȉ��ɁA���݂��c����{�e�n�̍X�т����������Љ�܂��B�@
���V���X��/��B�̓V��(����)�ō]�ˎ���̕����N�Ԃɐ��܂ꂽ�X�сB�ɐ��^�����g�p��������������B�@
���瓇�X��/�瓇�˂̕ی���Ȃ��甭�B�����X�сB�ؔłƌ^���p��������������B��������Ɉꎞ�r�₦�����A���ݕ�������X�ѓ��L�́u�ٍ���v�͍��Ȃ��c����Ă���B�@
�����X��/���F�T�̂悤�ȉ₩�ȍX�сB�^�����g���ē�������B�@
���]�ˍX��/30���ȏ�̑����̌^�����g���Đ��߂��铌���̍X�сB�{���̍X�т̕��͋C�������c���Ă���B
 �@
�@���ߕ���
���ߕ�������͗��h�ȐE��ł��B�`���H�|����̐��F�Ƃ��Đ��E�Ɍւ�Z�p��L���A����������̐l�X���獂���]������Ă��܂��B����ɑ��Đ��F�H�Ƃ̐�c�͒����Ŋm���������ߕ�������̋Z�p����i���A���W���܂����B�@
���̗��j�I�o�߂ɂ��āA�Љ��Ǝ��̒ʂ�ł��B���[���b�p�ɂ����ẮA18���I�ɉp���Ŕ��������Y�Ɗv���ʼnƓ��H�ƓI���F�ƁA�ߑ�I���F�H�Ƃ֕������܂����B���m�Ɍ����A1856�N�ɉp���̃p�[�L���Ƃ����l�����������̃��[�u(�Ԏ��F�E�������)�Ƃ����F�������̂��A���[���b�p�̋ߑ���F�H�Ƃ̎n�܂�ł��B���{�͖����ېV�ʼnp���^�̎Y�Ɗv�����N��܂����B���̊v���ʼnƓ��H�ƓI���F�͎�H�ƕ����ƃ��[���b�p�����̋ߑ�I���F�H�Ƃ֕����A���W���܂����B�@
���\���H�Ȋw�̐��F�U���ŋߑ�Y�ƁA�H�Ƌ����U�������@
�����ېV�̐����͋ߑ���F�Z�p�̔��W�ɂ���āA���������ƌ����Ă悢�ł��傤�B�@
�ߑ���F���\�ɂ������������͓V�R�����Ɠ����g����������ƁA���F�͎��s���܂��B���������ɍ��������̗A�����������܂������A�����̓��{�̐��߉�����́A�g�������킩�炸�r���ɕ��܂����B �@
���{�l�ɍ��������̐������g�p���@���������̂̓h�C�c���珵���ꂽ���O�l��(�p�����O�i�[)�Ƃ����l�ł��B�ނ�1868�N(�������N)�ɋ��s�ɖ��ǂɏ�����A�����̓��{�l�ɕ��L�����w�������܂����B�ނ͓��{�l�Ɍn���I�ɉ��w�𗝉����Ă��炤���߁A���s�ɖ��ǂɐ��F����������܂����B�@
���{�l�ɉ��w���������̂́A���O�l�������ł͂���܂���B�����̌c�����N�ɗ��R��s���̋����Ƃ��āA�I�����_�l�̃n���^�}�����ȁA���w����{�l�ɋ����܂����B�ނ͖���2�N�ɑ��̊J���w�Z�̋����ɂȂ��Ă��܂��B����7�N�ɉp���l�̃_�C�o�[�X���m�ƃA�g�`���\�������{�̉��w����ő傫���v�����܂����B�@
���{��������䒼�g(��ɔ��m)������13�N�A5�N�̕č����w���I���A���{�̉��w����ɗ͂����܂����B���ɍ��������ɂ����F�͓��{�̋ߑ㉻�w���W�̒��ɂȂ�Ƃ��āA���{���{�͐��F�̋Z�p�U���ɗ͂����܂����B�@
����A�D���Ƃ���������ɓ����āA��D�萶�Y����A���͗��p�̋@�B���ɂ���āA��ʐ��Y���\�ɂ��܂����B�@
�Ɠ��H�ƌ^�̐D�����Y���@�B���Y�^�֔��W����̂𑣐i�����̂͐��F�ł��B�Ȃ��Ȃ���F�͐����������m���Ɖ��w�m���Ƃ�Z��������������ɂȂ�������ł��B�@
���ꂪ�����͂ɂȂ��āA���{�o�ς͋ߑ㉻�։������܂����B2000�N��ɓ����Ė{�i�������h�s�v���ɕC�G���邮�炢�̎Y�Ɗv���������N�������Ƃ����Ă悢�ł��傤�B�@
�܂薾������ɂ����āA���F�͐������w�╪������э��킷�L���Ӗ��̏\���H�Ȋw�̏�ƂȂ����Ƃ����Ă�ł��傤�B��������ɁA���F����A�������Y�ƂƊe��H�w����@�ւ̑�����U�����������Ƃ������� ���Ă͂����܂���B�@
���\�N�O���A���F�H�Ƃ��@�ێY�Ƃ̃L�[�E�C���_�X�g���[(�Y�Ƃ̃J�i��)���Ƃ����Ă��܂����A���̌��t�́A����܂ł̗��j�I�o�߂Ő��F���ɂ߂ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă������炱���A���Â���ꂽ�Ƃ����Ă悢�ł��傤�B�@
�����ߕ����Ɛ��F���H�Ƃ̈Ⴂ�@
��������吳�A���a�Ɏ���܂ŁA���F�ɊW�����l�X�̒����甎�m���擾�҂�A�H�w�W�̑�w�����𐔑����y�o���ꂽ�B�ߑ�I���F�͓��{�̍H�ƎЉ���`�����Ă������߂̏\���H�Ȋw(�����̊w�╪�삪�������邱��)�̈ʒu�ɗ����A���{�o�ϔ��W�̈ꗃ���ׂ����Ƃ�����B�@
���ߕ����Ƌߑ���F(���͋ߑ���)���A�ǂ̕ӂ肩�番�������̂��A���_�������āA�����I�ȉ��p�ω��̈��Ƃ��āA���݂̓�����u�̐i���Ɏ���ߒ����A�ӂ�Ԃ�Ɛ��ߕ����Ƌߑ�H��ւ̕����o�߂��悭������B�@
14���I���̃C���h�ɂ���������Ƃ́A�ؔłɃf�U�C����A�ؔ\�ʂɓV�R�����t��h��A�z��ɖؔ��X�^���v�̂悤�ɉ����ē�������B������X�^���p�����Ə̂����B���݂��C���h�l�V�A�̃W�����X�т͂��̕����ɋ߂����@�ōs���Ă���B�@
�����Ō^���ɑ�������悤�Ȃ��̕���A�����t�����荞�ނ悤�ɖؐ����[���œ������(�E�ŕ���)�B���̕����ł͐����ɔS����t�^����Z�p�����B�����B�@
�X�^���p��ؐ����[�������19���I�ɓ����āA����̋������[���ɒ����������̂��g�p���郍�[���[����@�ɔ��W��������A�E�ŕ����Ɩؐ����[�������ɂ�����@��20���I�ɓ����āA�V���N�сA��Ƀ|���G�X�e���юg����(20���I�㔼)�̃t���b�g�X�N���[������@��[�^���[�X�N���[������@�i�������B

��O�A���͉��l�ɏC�s�ɍs�����Ƃ̂��ƁB�����ɖ߂�H��������A5-6�l�̐E�l���������Ă����炵���B�펞���͓����ő�ς������悤���A�H����k����1�Ԃقǖh�Ђ̂��߂̓����ŋ��o������ꂽ�B�����A�펞���ɂ��Ă��������A�H��d�́A�H��ĊJ�̎����ɂȂ����悤���B���Δ��ꂽ�����A����͑e���i�̑㖼���̂悤�Ɍ���ꂽ���Ƃ��������B���a��30�N�O�オ�s�[�N���������A�H����Z�Ɍp�����A�����Ƃ����Ԃɕ��͐������B�@
���͖����ŗǂ��e�ł͂Ȃ������A������Ɏd���������邽�ߌZ���������A�d�����̗ǂ��E�l�ł͂������B��͂����Ƒ��ƐE�l�����̎��܂Ƃߖ��������B�@
�Z�������A�E�[���A�����߁A�����ƒ��킵�����A���߂͏��a��40�N��ŏI������B�@
�^�t������Ƃ��A�o���̉��ɕ~���z���u���v�ƌĂ�ł����A���v�����Ԃ�uUnder�v�̂Ȃ܂������̂��B�@
�^�t���̌�A������蒅�����邽�ߏ��C�ŏ������B���C����2�قǂŁA�~�͒��ӂ��Ȃ��ƒg�����ŕ��ꍞ�L��������(�V�����ɕ�ݓn�ǐ���։��x���s�����ꂽ)�B�@
�c�������C�ŁA�����g�������C�ɓ��邱�Ƃ��o�����B�@
�䂪�ƂɗV�тɗ����F�B�ɁA��ŕK�����ɂ��Ԃꂽ�Ɠ{��ꂽ�B�^���Ɏ����g���Ă���A�V�����^���̊m�F�A�ۑ��^���̕�C�E�����ɁA��Ƃ̂��ߕ������Ɍ^�����L�����A��Ɏ������݂���ł����̂��B�@
�䕗�œn�ǐ��삪�×����A�H��̒�������̌��P�����\���Ղ���Ղ���A�������Ƃ��o���Ă���B���̂Ƃ��A�����Ă������u�G�X�v���������炸�F���S�z�����A�Ȃ�Ɠ�K�̋��ɐ^����ɔ��Ă������Ƃ�����A��Q�Őh�������������F�������B�@
�ǂ��D�����ƎY���̑���Ńf�p�[�g�ň������������Ƃ�����A����Ȃ������B�������̂��f�p�[�g���{�߂��l�D�Ŕ������A���ꂽ�B���a��30�N��A�����A�D���̗ǂ������������̖ڂŌ����l�����Ȃ��Ȃ�������B�@
�����ȗA�������ŐF�����A�ސF������Ђɉ��P�����A���Ђ͒����Y�Ƃ������B�Љ�l�ɂȂ����t�B�����̊W�Œ����Y�Ƃɋ@���[�߂邱�ƂɂȂ����A�Z�Ƃ̘̐b�ł߂��肠�킹���Ɖ��������Ƃ�����B

���E�o�^�L�`������(1999.11.18)/�v�H1913-1919�N(�吳8�N)/���ݒn �Ȗ،������s������/�\�� �������������Ċ����B �@
�������D�����A��ɖ����a�ч��̍H��ƂȂ�A�����m�푈���ɂ͌R���H��ɓ]�p����A���͇��g�`�Z���̏��L�ƂȂ����B�����K����̊O�ǂƖؑ��̓������g�݂���Ȃ�L��ȍH��B6�A�̂̂����艮�����A�����Ă������A��K�͂ȍH����������肾���Ă���B�Ă���܂ŗ����̂ڂ钌�^�ƌ��֕��Ƃʼn�������ǂ̃f�U�C����A�o�����E���̑傫�ȊJ��������̂܂����Ŏx�����@�ɓ��F������B�T�����H�ꓯ�l�A�吳���㏉���ɐݗ����ꂽ�����D���̗A�o�ȐD���̐��Y��ړI�Ƃ��������ōŏ��̋ߑ�H��ŁA��K�͂Ȑԃ����K�H�ꌚ�z�Q�Ƃ��ėB�ꌻ�݂܂Ŏc���Ă��錚�� �B

���J�X���[���䕗 1947/9/15�Ȗ،������s�n�ǐ���E�ܐ�̒�h�����A�����͎s�X���Ώ��Ɖ������B�n�ǐ���̎�ȍЊQ/���ҁE�s���s����709�l�A��ЉƉ���33,800���B�@
���L�e�B�䕗 1949/8/31�֓��n���ɏ㗤���傫�ȉe����^�����B8/31��A�_�ސ쌧���c���s�̐��ɏ㗤�A�k�i���F�J�A�����ʉ߂��A���{�C��֏o�ĉ��ђ�C���ƂȂ����B���䓇�ōő啗��33.2m/s(�ő�u�ԕ���47.2m/s)�A���l��35.2m/s(��44.3m/s)���ϑ������B�֓��k����V�����̎R�x���ő�J�ƂȂ�A�n����̏㗬���ł͒�h�������B�n�ǐ���̎�ȍЊQ/���ҁE�s���s����10�l�A��ЉƉ���700���B






















 �@
�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@
�@