 �@
�@�����{�̃��[�_�[�E�^��p�U���E�C�R�l���E��͑�a�E��͑�a�m�Ŋ��E�J��Ɠ��{�l
�@
 �@
�@�������m�푈�T�v
 �@
�@�������m�푈 1
�u�����m�푈�v�Ƃ������̂́A�A������̊��ɘA�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ�(GHQ)�̐�̐���œ����̓��{���̐������̂ł������u�哌���푈�v���u�����m�푈�v�����I�ɏ������������錟�{�ɂ���Ē蒅�������̂ŁA���ɂȂ���GHQ��������ď̂ł���B���ہA�펞���̃A�����J�ł͎��ꂪ�A�����J�����猩�đ����m�n��ł��������ƂɈ��ށuPacific Theater(�����m���)�v�Ƃ����p�ꂪ�L���g�p����Ă���A�����m�푈�Ƃ������̂��펞���Ɏg��ꂽ���Ƃ́A������̍��ɉ����Ă����������B �@
�푈�̊��Ԃ́u1941�N12��7��(�n���C���n���ԁB���{���Ԃł�12��8��)�������{�鍑���{���~�������ɒ���1945�N9��2���v�Ƃ���̂���ʓI�ł���B�����m�푈�����̕����Ȃǂ�����Ɓu�哌���푈�v�ȊO�ɂ��A�u���E�ېV�푈�v�A�u�����ېV�v�A�u���a�ېV�푈�v�ȂǂƂ����\����������B �@
���݂̓��{�ɂ����ẮA�푈�̌o�܂�ړI�̈Ⴂ����u�����푈�v�Ɓu�����m�푈�v�Ƃ��ʌ̐푈�Ƃ��ĔF������邱�Ƃ��������A�����g�p���ꂽ�u�哌���푈�v�́u�x�ߎ��ρv(���ݎg�p����Ă�������푈)�����̔��e�Ɋ܂ނ��̂ł������B���݂ɂ����Ă��Β��푈�ƑΕĉp�푈����ʂ��Ȃ��T�O�Ƃ��āu���a�푈�v�A�u�A�W�A�E�����m�푈�v�Ȃǂ̗p�ꂪ�g�p����Ă���B�r���}���A�W�A�Ŏ�ɉp�R�Ɛ�����푈���m�푈�ƌĂԎ��Ɉ�a��������Ƃ���ӌ������邽�߂ł���B �@
�C�M���X�ł́uWar with Japan(�Γ��푈)�v�ƌĂ�A���[���b�p�ł́A�����푈�͑���E���Ƃ͋�ʂ��ꂸ�A�����푈����������1937�N7��7��������m�푈�̎n���Ƃ݂Ȃ����Ƃ�����B �@
���ؖ�������ђ��ؐl�����a���ł́u�����푈�v�Ƃ��ĔF������A8�N�ԂƂ��Ă���B�@
���������� �@
�퓬�Q���� / ����{�鍑�A�^�C����(1942-45)�A���B���A���ؖ����싞���{�A�Î����M���{�A���R�C���h�����{�A�r���}�Ɨ��`�E�R(1941-42�̃r���}�i�U���̂�) �@
���́E�x���� / ���{(���B�V�[�������̃t�����X�A�h�C�c(���������͍�����D�Ȃ�)�A�C�^���A����(1941-1943�A���������͍��Ȃǁ�) �@
�����E�Q�����ȂǓ��{�R�x���ł���ꂽ���y�`�E�R / �C���h�����R�A�r���}�h�q�R�A���y�h�q�`�E�R(�C���h�l�V�A)�A�X�}�g���`�E�R�A�{���l�I�`�E�R�A�W�����h�q�`�E�R�A�}���[�`�E�R�A�}���[�`�E���A�z��N��N��(�x�g�i��)�A�t�B���s���l�`�E�R�q�}�J�s���r�A�䓇���E�G���哝�̕t�e�q���A�ΉƑ����n���V�A�l�`�E�R(����)�A�c���ېV�R(����)�A���ؖ����Վ����{�R�A�c���V���؋~�����R�A���F�C�X�������k�R���c �@
�A�������ɐ��z���������������m�푈�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��� / �r���}(1943-1945)�A�t�B���s����a��(1943-45)�A�x�g�i���鍑(1945-)�A���I�X����(1945-)�A�J���{�W�A����(1945-)�A�M���V���A�N���A�`�A�Ɨ����A�u���K���A(1941-1944��)�A�Ɨ��X���o�L�A(1941-1945)�A�n���K���[����(1941-1944��)�A���[�}�j�A����(1941-1944��)�A�Z���r�A�~�����{(1941-1944��)�A�s���h�X�����E�}�P�h�j�A����(1941-1944)�A�t�B�������h���a��(1941-1944��)�A���V�A����������ψ���(1944-1945) �@
���A������ �@
�퓬�Q���� / �A�����J���O���A�C�M���X�A�I�[�X�g�����A�E�j���[�W�[�����h�A���R�A�J�i�_�A�I�����_�A���ؖ����d�c���{�A�\�r�G�g�A�M(1945)�A�Ðl�����a��(1945)�A���H�R�A���R�t�����X(1945) �@
�Q�핺�͂̑������������� / (�C�M���X�̃C���h)�A�C�M���X�̃}�����A�A�����J�̃t�B���s�� �@
���̑� / ��ؖ����Վ����{�A�t�N�o���n�b�v(�t�B���s�����Y�}�̍R�������g�D)�A�R���}�����l���R(�}���[�V�A�؋��̍R�������g�D)�A�t�H�[�X136(�p�R�ɂ���ČP�����ꂽ�Q��������)�A����A�W�A�{�����e�B�A�R(�؋������g�D)�A�j���[�M�j�A������(���w�c�̌��Z�����Ƃ��ĎQ��) �@
���������ɐ��z���������������m�푈�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��� / ��A�t���J�A�M�A���o�m��(1943-45)�A�G���T���o�h���R�X�^���J�A�h�~�j�J(�C�M���X�ϔC������)�A�j�N���O�A�A�n�C�`�A�O�A�e�}���A�z���W�����X�A�p�i�}�A�L���[�o�A�m���E�F�[�A���x���A�A�G�W�v�g�����A�V���A(�t�����X�����ϔC��)�A�T�E�W�A���r�A�A�C���N�A�C�����A���L�V�R(1942-45)�A�u���W��(1942-45)�A�R�����r�A(1943-45)�A�{���r�A(1943-45)�A�C�^���A����(��1943-45)�A�t�B�������h(��1944-45)�A���[�}�j�A����(��1944-45)�A�u���K���A����(��1944-45)�A�y���[(1945)�A�x�l�Y�G��(1945)�A�E���O�A�C(1945)�A�p���O�A�C(1945)�A�G�N�A�h��(1945)�A�g���R(1945)�A�A���[���`��(1945)�A�`��(1945)�A�x���M�[(1945) �@

���J��O�j �@
�x��������c(1885�N)�ƃA�W�A�������� �@
�A�����J�̑����m�헪 �@
���B�������ƒ��ؖ��� �@
��������̓D�����ƎO�������̒��� �@
1937�N(���a12�N)�ɖu�����������푈�ɂ����āA����{�鍑���{�͓����A���n������s�g����j�ɂ���Ď��Ԃ̎��E�����݂��B�������A����{�鍑���@�̋K��ł��铝�����̓Ɨ�����A��E��Z�����Ȍォ��s����悤�ɂȂ����R���ɂ�鐭�����A��g�厖���A�b�a�����������������Ƃ��钆���嗤�ɂ����闤�R�̖\���A����Ɍĉ����ċN�����Y�V�����A�L���厖���A�ʏB�����A���C���ςɂ��ݒ��M�l�̈��S����������鎖�ԂɂȂ�B���̌��ʁA���{�͌R���s��(�Ύx�ꌂ�_)���咣���闤�R��}�����邱�Ƃ��ł����A��͓������R�ɂ���K�͂ȑS�ʏՓ�(����)�ɔ��W����B���{�R�́A�k�����C�Ȃǂ̎�v�s�s���́A�����Ē��ؖ������{�̎�s���u���ꂽ�싞���ח����������A�Ӊ�Α��������鍑���}�͎�s������̏d�c�Ɉڂ��R��𑱂����B�����}�R�̓A�����J��C�M���X�A�\�A����R��������l�I����(���Ӄ��[�g)���A�n�̗����������e�n�Œ�R�A���B���═����킪���������B�܂����K��@�ȊO�ɓ����@��Q������p�A�����p�Ȃǂ̐�p��p�����{�R�𝘗������B����A����������ʂ�����������������Ɋ�Â��������Y�}�R(���H�R)���R���̉��������_�Ɏ铿�����锪�H�R��V�l�R�����{�R�ɃQ��������d�|�����B�������ē��؎��ς̐���͐L�і��]�L�̒�����Ɋׂ��Ă����B �@
�ɂ��������ؖ����̎w���҂̏Ӊ�́A���ې��_(���Đ��_)�𖡕��ɂ��A�x���������o�����߂ɁA�����}������`�����ې�`����g�D���n���ȃv���p�K���_��p��W�J�����B���̌��ʁA�j���[���[�N�^�C���Y���͂��߁A�O���t�G�����C�t�Ȃǂ̉��Ă̖��ԃ��f�B�A�����͂����؎��ς��ނƂ����L����ʂ��Đ��_�U�����s���ǎ҂ɑ傫�ȉe��(�wPoor China(���z�Ȓ���)�x�Ƃ����W������܂ꂽ)��^���A����ɉ��Ă̐��_�͒�������A�̓��{�R�̌R���s���ɑ������������������悤�ɂȂ�A�����嗤�Ɍ��v�������X�͒�������̓P������{�ɋ��߂��B�@

1940(���a15)�N7��22���A��߉q���t�����������B�g�t��4���ڂ�7��26���t�c�Łu��{�����v�j�v�����肵���B��27���ɂ́u���E��̐��ڂɔ��ӎ��Ǐ����v�j�v�����肵���B ����A����{�鍑���{��1940�N(���a15�N)9��27���Ƀi�`�X�E�h�C�c���{��A�C�^���A�������{�Ɠ��ƈɎO���R��������������č��ۓI�Ȕ����͂����߂悤�Ƃ������A���̊O�𐭍�͂������ēƈɂƉp�ĂƂ̍��ۑΗ��Ɋ������܂��`�ƂȂ�A���ĊW�͈�w���������B��������ĊJ�킪�_�����邪���{�ƊC�R�̈ꕔ�ɂ͐T�d�_����������ŗ��R�͎��h�����������B���{�R�͑Β����E�\�A�ɕ��͂��W�������g�����ł��Ȃ��ɂ��������߁A�č��͓��{�ɑ����d�p���������悤�ɂȂ�B���{�ƒ����͋��ɃA�����J�ɕ������ˑ����Đ푈���s���Ă����B���̎��_�œ��{�͐Ζ���6���ȏ���A�����J����A�����Ă������߁A�A�����J�Ȃ��ł͂������������푈�̐��s�͕s�\�ȏł������B �@
����B����̖u���Ɖ��Ă̏ �@
1939�N�A�h�C�c�R���|�[�����h�ɐN�U�������Ƃɂ�艢�B�ł͑���E��킪�u�������B1940�N���ɂ́A�����[���b�p�̑��������̐�̉��ƂȂ�A�B��h�[�o�[�C��������ő�p�鍑���A�����Ō�̍ԂƂ��ċꂵ����R�𑱂��Ă����B����A�吼�m�����A�����J���O���ł́A1940�N10���ɍs��ꂽ�đ哝�̑I���ŎO�I���ʂ������t�����N�����E���[�Y�x���g���u�A�����J�͖����`�̕��폱(�H��)�ɂȂ�v�Ɣ��\���A�C�M���X�ւ̉��������R�ƕ\�������B���N�ɂ̓C�M���X�ւ̕���ݗ^�@�𐬗������A����ɕĉp�ō��R���Q�d��c(�ʏ�ABC��c)���J����ABC����𐬗��������B�������A�����̃A�����J�͍����̑������i�`�Y���̑䓪�ɋ��|���������ꎟ���E���̋��P���烂�����[��`�������A���B�ł̐푈�ɑ��s����]�ސ������������B���[�Y�x���g���E�B���X�g���E�`���[�`���̍ĎO�̍Ñ��ɂ�������炸�A11���̑哝�̑I���Łu���͐N��������ɑ���Ȃ��v�Ɛ錾�����I��������Œ����ɉ��B����ɉ���ł��Ȃ��ɂ������B�����Ƃ��������_�����łȂ��A�Q�킷��ɂ͗l�X�ȏ������K�v�Ń��[���b�p����ɎQ���ł���̂�1943�N7���ȍ~�ɂȂ�Ƃ݂Ă����B1941�N4���̕ĉp�̓�����c�ł͑ΓƐ�̂��ƂɁA�Γ���ɓ��邱�Ƃ����肳�ꂽ�B �@
�^�C�����ɂ��암����N�U �@
1940�N11��23���A�^�C�����̓t�����X�ɐ�̂���Ă������^�C�̉̂��߂̃t�����X�̓암����i�s�ɂ��^�C�E�t�����X�̃C���h�V�i�������u�����A1941�N5��8���ɓ��{�̒���ɂ��^�C���������n������`�Ń^�C�����ƃt�����X�̊Ԃœ�������������B �@
���Č��̌���Ɠ�i�_�̊����� �@
�č��͑Γ����헪���������A1940�N9���ɂ͓��{��(�O���ȁE�C�R)���g�p���Ă����Í���Nj@(�㎵����������@)�̃R�s�[�}�V�������������A12���܂ł�8���B�Đ��{�E�ČR�E�C�M���X���ɔz������A���̌�̑Γ��O���E�헪�Ɋ������ꂽ�B������{�́A1940�N�A�O��R��𑱂���d�c���ؖ������{�ւ̌R�������̕⋋���[�g���Ւf���邽�߂ɐe�����I�������̃��B�V�[�����Ƃ̋�������Ƃ�9���A�t�����X�̃C���h�V�i�k���ɐi�����A���ӕ��[�g���Ւf�������A�V���Ƀr���}���o�R���鉇�Ӄr���}���[�g�����ꂽ�B1941�N�A���đ�g�쑺�g�O�Y�̂��Ƃɗ��R�ȌR���ے��ł�������ȍ��Y���n�āA���Ԑl��쒉�Y��ƂƂ��ɁA�A�����J���������R�[�f���E�n���������Ĕ閧���ɂ����ĊW���P���͍����ꂽ�B���̌��ɂ����肳�ꂽ����ėȉ��ģ�ł̓z�m�����ɂ�������Ď�]��k�����̉\������������Ă������A�����O���ɂ������O���Ȃ̊����ɂ��A���̂���Ȃ�i�W���������P���x��钆�A�ƃ\�J��ƂȂ�A���E�̘g�g�݂��傫���ω����钆�A�A�����J�ɂƂ��ē��ĊW���P�͋}��v������̂ł͂Ȃ��Ȃ袓��ėȉ��ģ�͗��Y���Ă��܂����B�@
���̌�����{�̋��ʕ������t�͊W���P��ڎw���ă��V���g��D.C.�ŃA�����J�ƌ�����鑱�������A���{�R��7��2���̌�O��c�ɂ�����u��̐��ڂɔ��Ӓ鍑�����v�j�v(�\�폀���E�암����i��)�̌���ɏ]���A7��7������͖��B�Ɍ����ē��n���畺���̑�ڑ����J�n�����Ƌ��ɁA7��28���ɂ͓암����ւ��t�����X���{�Ƃ̍��ӂɊ�Â��i�������{�����B ����A�A�����J�́A7��18���A�A�����J���R�����E�C�R�������烋�[�Y�x���g�哝�̂ɒ�������A�����J�l�����c����150�@�̔����@��9������10���ɂ����ē����E���E���s�E���l�E�_�˂���P�����ŏĂ��������v�悪��o����A�哝�̂ɂ�鏳�F���Ȃ����B7��21���ɂ́A��������ɔh�����Ă����t���C���O�^�C�K�[�X�����j�Ƃ������{�{�y�ւ̐搧�U���쐬(J.B.No.355)���哝�́A�C�R�����A���R������̏����̂��ƔF���ꂽ�B�����7��25���ɂ͍ݕē��{���Y�𓀌�(�n�[�o�[�g�E�t�[�o�[�O�哝�̂̓h�C�c�Ɛ푈���邽�߂ɓ��{��푈�Ɉ������荞�����Ƃ�����̂ł������Ƃ��Ă���)�A8��1���ɂ́u�S�Ă̐N�����v�ւ̐Ζ��A�o�֎~�̕��j�����肵�A���{�ɑ��Ă��Ζ��A�o�̑S�ʋ֎~�Ƃ����������o�ϐ��ق߂��A�C�M���X�ƃI�����_���������ɓ�������(ABCD��͐w�̊���)�B���̐��ق�1940�N�̓��Ēʏ��q�C���̔j������͂��܂�A�ŏ��͍q��p�R���̒�~�A�k���i���ɔ����S�ނ̒�~�A�����ė��R�ƊO���Ȃɂ�铯�������ɔ����A�K�v������3�����߂Ă�������Ƃ̌������A���������̍��������܂��Ă�����(���ɍq��p�R���̌��R���������A�A�����J�ɂ�铭���ɂ���ė�����ł��q��R���͗v���ʂ�1/4�����m�ۂł����A����̌����ƂȂ���)�B�܂��A40�N����41�N�ɂ����Ė��ԉ�Ђ�ʂ��A�K�v�����̊J���i�߂����A�����J���{�̊��ɂ���Č_��܂ł��ǂ蒅���ȂȂ���A����ւ̘a���i���y�і��B���h�ɔ������ق����{����A�����̋��������S�ɐ₽��邱�ƂƂȂ����B�����̓��{�͎�����A�����J���畨�����w�����Ȃ���嗤�ɂ��������{�̌��v���Ӊ�ΌR�������Ă����B�Ⴆ�Γ��ĊJ�펞�̍����ɂ�����Ζ��̔��~�͖����E�R�������킹�Ă�2�N�������Ȃ����A�֗A�[�u�͓��{�o�ςɑ��j�œI�ȉe����^���鋰�ꂪ�������B�Γ����ق����߂���c�̐ȏ�A���[�Y�x���g���u����œ��{�͗���Ɍ��������낤�B����͑����m�ł̐푈���Ӗ�����v�Ɣ������Ă���B����A�A��������8��25���ɃC�M���X�ƃ\�r�G�g�͋������ăC�����i�����s���Ă��邪����ɑ��Ă͉��ė̔��͂Ȃ������B �@
9��3���A���{�ł́A��{�c���{�A����c�ɂ����Ē鍑�������s�v�̂��R�c����A9��6���̌�O��c�Łu�O�����Ɉ˂�\����{���Ɏ��������v�����ѓO������ړr�Ȃ��ꍇ�ɉ��Ă͒����ɑΕ�(�p��)�J������ӂ��v�ƌ��肳�ꂽ�B���ʂ͓��Ď�]��k�ɂ�鎖�Ԃ̉��������ӂ��Ē����A�����J��g�W���Z�t�E�O���[�Ƌɔ��k���A���Ď�]��k�̑��������������i�������A10��2���A�A�����J�����Ȃ͓��Ď�]��k�������㋑�ۂ������{���Ɏ������B �@
�푈�̌��f�𔗂�ꂽ���ʂ͑Β��P���ɂ����ɓ������߂����A����ɔ����铌���p�@�����́A�����E�������v�j�Ɋ�Â��J���v���������߁A10��16���ɋ��ʓ��t�͑����E����B��p�̓������t��18���ɐ������A11��1���̑�{�c���{�A����c�ʼn��߂āu�鍑�������s�v�́v�����肵�A�v�̂�11��5���̌�O��c�ŏ��F���ꂽ�B�ȍ~�A����{�鍑���C�R�́A12��8�����J��\����Ƃ��đΕĉp���푈�̏�����{�i���������B �@
11��6���A�������S������e�R�̎i�ߕ��̕Ґ������߂���A����R���i�ߊ��Ɏ�������叫�A��14�R�i�ߊ��ɖ{�ԉ됰�����A��15�R�i�ߊ��ɔѓc�˓�Y�����A��16�R�i�ߊ��ɍ����ϒ����A��25�R�i�ߊ��ɎR���������e�₳�ꂽ�B�����A��{�c�͓���R�A��14�R�A��15�R�A��16�R�A��25�R�A��C�x���̐퓬������A�e�R�y�юx�ߔh���R�ɑ�������̍�폀�������߂����B �@
11��20���A���{�̓A�����J�ɑ�����ŏI�Ă��b����p�ӂ��ė����O�Y�����S����g�A�쑺�g�O�Y��g�̓R�[�f���E�n�����������ɑ���t���A�ŏI���ɓ����������A�Ӊ�A�C�M���X�`���[�`���̓������������钆�A�A�����J�哝�̃��[�Y�x���g�́A11��26�����A�A�����J�C�R�����p���ɓ��{�̑D�c�̈ړ��������Ƃ�����A���[�Y�x���g�͗��ĂƂ����ۂ��A�����嗤�E�C���h�V�i����̌R�A�x�@�͂̓P�ނ���ƈɎO�������̔ے�Ȃǂ̏������܂ށA������n���E�m�[�g�𗈐��O�Y�����S����g�A�쑺�g�O�Y��g�ɒ����B���e�͓��{�֑��钆���嗤�A����̑S�ʓP�ނƁA�O�������̉����Ƃ����ɂ߂ċ��d�Ȃ��̂ł������B�č��͖��B�������F���Ă��Ȃ����߁A���B��������R��P�ނ����鎖���Ӗ�����B��̓����ٔ��ٌ̕�l�x���E�u���[�X�E�u���C�N�j�[���A�u�����A�n���E�m�[�g�̂悤�ȕ���˂�����ꂽ��A���N�Z���u���N�̂悤�ȏ�������������A�A�����J�Ɛ�������낤�B�v�Ɠ��{��ٌ삵�Ă�����ɂ߂ċ��d�ȓ��e�ł������B�����ٔ��̔����ł������B���_�E�r�m�[�h�E�p�[������Ɉ��p���Ă���B�A�����J�C�R�͓�11��26�����ɃA�W�A�̐����͕����ɑ������������͍��߂����B�������{�ɑ���Ō�ʒ��Ǝ�����������t��12��1���̌�O��c�ɂ����āA���{����12��8���̊J������肵���B�@

���{���R�����{����12��8�������ɃC�M���X�̃}���[�������k�[�̃R�^�E�o���ɐڋ߁A�ߑO1��30���ɏ㗤���C�ݐ��ʼnp��R�ƌ�킵(�}���[���)�A�C�M���X���{�ɑ�����z���O�̊�P�ɂ���đ����m�푈�̐�[���J���ꂽ�B �@
�����ē��{�C�R�q����ɂ��A�����J�̃n���C�̃I�A�t���ɂ���A�����J�R��n�ɑ���U��(�^��p�U��)���A���{����12��8���ߑO1��30��(�n���C����12��7���ߑO7��)�ɔ��i���āA���{���ԌߑO3��19��(�n���C���ԌߑO7��49��)����U�����J�n���ꂽ�B �@
���{����12��8�����j���ߑO4��20��(���V���g������12��7���ߌ�2��20��)�ɁA�����O�Y�����S����g�Ɩ쑺�g�O�Y��g���č����Ȃ̃R�[�f���E�n�����������Ɂu�ΕĊo���v����������B�ߑO3��(���V���g������12��7���ߌ�1��)�Ɏ�����邱�Ƃ����܂��Ă��āA�܂��A�A�����J�ɑ����z��������\�����������Ƃ��������Ă������A�쑺�g�O�Y�����R��v�卲�V�����g�̑��V�ɎQ�Ă������߁A�^��p�U����̎���ƂȂ����B �@
�Ȃ��A���̊o���ɂ͐푈���������킹��L�q�������A�u���z�������̂��܂������v�ł���ƃA�����J�哝�̂��c��Ŕ������Ă���B�܂��A���{���ł����z���Ǝ���Ȃ��������O���ďC�������߂鐺�����������A�O����b�����C���ʼn������Ă���B �@
�Ȃ��A���{�̓C�M���X�ɑ��ĊJ��ɐ旧���z���͍s���Ă��炸�A�Ήp�J����12��8���̒�7�����ɂȂ��ă��o�[�g�E�N���[�M�[������g���O���ȂɌĂсA���V���g���Ńn�����������Ɏ�n�����̂Ɠ����̑Εāu�o���v�̎ʂ�����n�������̂́A����͐����Ȑ��z���ł͂Ȃ������B�����ɁA�I�����_�͓��{�ɐ��z�������B �@
���J���ꂽ�������ɂ��ƁA���ɃA�����J�͊O���Ȃ̎g�p�����Í�����ǂ��Ă���A���{�ɂ��ΕČ��ł���������A3���O�ɂ͐��m�ɗ\�z���Ă����B�ΕĊo���Ɋւ��Ă��A�O���Ȃ���n�����30���O�ɂ͑S���̉�ǂ��ς܂��Ă���A���ꂪ�u�^��p�U���̊�P�����̓A�����J���ɂ��d���ł���v�Ƃ���^��p�U���A�d���̍����ƂȂ��Ă���B �@
�܂��A�^��p�U���O�̃n���C����12��7���ߑO6��40���ɁA�̊C�N�Ƃ������{�C�R�����̓�����q�����A�����J�C�R�����̋쒀�̓��[�h���ɍU�����ꌂ������鎖��(���[�h������)���������Ă��āA�Í��d��̉�ǂ��Ȃ��Ă��A�A�����J�͓��{����̍U�����@�m���邱�Ƃ��ł����Ƃ��錩��������B �@
��31��哝�̃n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�������m�푈�͑ΓƎQ��̌�����~�������Ă������[�Y�x���g�哝�̂̊�]�������Əq�ׂĂ���B�@
1940�N9���ȍ~���{�R�͕���i�����s�Ȃ��Ă���A���{�R�͗̓y�O�ɂ́A���B���A�����嗤�����A�t�����X�̃C���h�V�i�ɕ��͂�W�J���Ă����B1941�N12��8���ɓ��{���R���^�C�����߂��̉p�̃}���[�����̃R�^�o���ƁA�������������^�C�암�̃p�^�j�ƃ\���N���̗��R�����̏㗤(�}���[���̊J�n)�ƁA�����s�Ȃ�ꂽ���{�C�R�ɂ��n���C�E�^��p�̃A�����J�C�R�����m�͑��ɑ���^��p�U���A�t�B���s���ւ̋A���`�ւ̍U���J�n�A12��10���̃C�M���X�C�R���m�͑��ɑ���}���[���C��Ȃǂ̘A�����R�ɑ���킢�ŁA���{�R�͑叟�������߂��B�������A�A�W�A�̓Ɨ����ŗF�D�W�ɂ������^�C�̍��ӂ�O�ɓ��{�R���������z���ČR���N�U�������Ƃɍō��i�ߊ�(�匳��)�ł��鏺�a�V�c�̓{������B �@
�Ȃ��A�����̍��́A����ɐ旧��11��6���ɁA�C�R�R�ߕ������̉i��C�g�Ɠ��������R�Q�d�����̐��R���ɂ���t���ꂽ�ΘA���R�R�����ł���u�C�R���v��m��v�v�̓��e�ɂقډ������`�ōs��ꂽ�B�㗤���͐��z�������J�n���ꂽ�B �@
���{�C�R�́A�^��p�����_�Ƃ���A�����J�����m�͑����قډ�ł����A���8�ǂ������j����Ȃǂ̑��ʂ����������̂́A��O���U�����𑗂炸�A�I�A�t���̔R���^���N��`�p�ݔ��̔j���O��I�ɍs��Ȃ��������Ƃ�A�S�ẴA�����J�C�R�̍q���͂��^��p�O�ɏo�Ă���A�q����(�͍ڋ@���܂�)��1�ǂ��j��ł��Ȃ��������Ƃ���̐틵�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�B �@
�܂��A�������{�C�R�́A�Z���Ԃ̊Ԃɏ������d�ˁA�L���ȏ��ŃA�����J�R���͂��߂Ƃ���A�����R�ƒ��Ɏ������ނ��Ƃ���Ă������߁A���S���傫�����ɂ͐헪�I�Ӗ��������ƍl�����Ă����n���C�����ɑ���㗤���͍l���Ă��Ȃ������B�܂��A�^��p�U���̐�����A���{�C�R�̐����͖�10�ǂ��g�p���āA�T���t�����V�X�R��T���f�B�G�S�ȂǃA�����J���C�݂̓s�s���ɑ��Ĉ�ĖC�����s���v������������̂́A�^��p�U���ɂ��A�����J���C�ݕ��̌x�����������ꂽ���Ƃ�����A���̈Ă����s�Ɉڂ���邱�Ƃ͂Ȃ������B �@
���������̗l�Ȓ��ŁA�t�����N�����ED�E���[�Y�x���g�哝�̈ȉ��̃A�����J���{��]�w�́A�n���C���������łȂ��{�y���C�݂ɑ�����{�C�R�̏㗤����{�C�Ŋ뜜���A�n���C�����R�̖{�y�ւ̓P�ތv��̍����n���C�����ŗ��ʂ���Ă���h���������p�̂��̂ɕύX����ȂǁA���{�R�Ƀn���C��������̂��ꎑ�Y�Ȃǂ����{�R�̎�ɓn�����ۂ̑�𑁋}�ɍ��肵�Ă����B�܂��A�A�����J���{��]�w�y�ьR�̎�]���ɂ����ẮA���{�C�R�̋����܂ޘA���͑��ɂ��A�����J�{�y��P�ƁA����ɑ����A�����J�{�y�ւ̐N�U�v��͓������̉\���������ƕ��͂���Ă���A�푈�J�n����A���[�Y�x���g�哝�͓̂��{�R�ɂ��A�����J�{�y�ւ̏㗤���뜜���A���R��w���ɏ㗤���ł̑j�~��Őf������̂́A���R��w���́u��K�͂ȓ��{�R�̏㗤�͔������Ȃ��v�Ƃ��ē��{�R���㗤�ネ�b�L�[�R���ŁA��������Ɏ��s�����ꍇ�͒������̃V�J�S�őj�~���邱�Ƃ��������Ă���(�Ȃ��A�^��p�U���㐔�T�Ԃ̊ԁA�A�����J���C�݂ł͓��{�R�̏㗤��`�������R���ǂɓx�X����Ă���)�B�@
����A�^��p�U����2����(1941�N12��10��)�ɍs��ꂽ�}���[���C��ɂ����āA�������E�ŋ��̊C�R�����F���A�`���[�`���̋�����]�ł��̒n��ł̐퓬�̗}�~�͂Ƃ��Ĕz������Ă����C�M���X�C�R�́A�����ŐV�s�͂ł�������̓v�����X�E�I�u�E�E�F�[���Y�Ə��m��̓��p���X�́A���{�C�R(��22�q����)�̑o���̗��㔚���@(��Z������U���@�ƈꎮ����U���@)�̍I�݂ȗ��������ɂ�肠�����Ȃ��������ꂽ�B�Ȃ��A����͎j�㏉�̍s�����̐�͂ɑ��čq��@�̍U���݂̂ɂ���͂̌���(���ɂ͓��{�C�R�̐�͑�a�Ɛ�͕����̂�)�ƂȂ�A��͂ɑ��݂���Ƃ��ꂽ���ݓI�ȗ}�~�͂͑傢�ɒቺ�����Ƃ����B �Ȃ��A��ɓ����̃C�M���X�̃E�B���X�g���E�`���[�`���́A���̂��Ƃ��u����E��풆�ɃC�M���X���ł��傫�ȏՌ������s�k���v�ƌ�����B�܂������m���ł́A��͂Ƌ��̊͑��̒��ł̖���(�U����̂Ɗ͑���q)������ւ�邫�������ƂȂ����B �@
���̌���{�R�́A�A�����R�̋��_(�A���n)�ł���}���[�����A�t�B���s���A�{���l�I��(�J���}���^����)�A�W�������ƃX�}�g�����Ȃǂɂ����ăC�M���X�R�E�A�����J�R�E�I�����_�R�Ȃǂ̘A���R�ɑ����|�I�ɗD���ɐ�ǂ�i�߁A���{���R���u���ԂɃC�M���X�̂ł������V���K�|�[����}���[�����S��A�������C�M���X�̂̍��`�A�A�����J���O���̐A���n�ł������t�B���s���̏d�v���_��D�悵���B���������{�R�́A�������ł���|���g�K�����A���n�Ƃ��ē������Ă������A�I�[�X�g�����A�U���̌o�R�n�ƂȂ�\�������������e�B���[���ƁA���`�ɗאڂ��A�����嗤�ւ̑�������ƂȂ�}�J�I�ɂ��ẮA�������̐A���n�ł��邱�Ƃ𗝗R�ɐN�U���s��Ȃ������B �@
�^��p�U����}���[���C��Ȃǂɂ��A���{���A�����J��C�M���X�A�I�����_�Ȃǂ̘A�����Ƃ̊ԂɊJ�킵�����Ƃ��āA12��10���ɒ��ؖ��������{�ɑ������ɐ��z�����A12��11���ɂ͓��{�̓������̃h�C�c�ƃC�^���A���A�����J�ɐ��z���������ƂŁA����܂Ń��[���b�p����ɂ����Ă��Q��̋@����M���Ă����A�����J���A���R�̈���Ƃ��Đ����ɎQ�킵�A����ɂ�薼���Ƃ��ɐ��E���ƂȂ����B �@
�O�N12���̓��{�ƘA�������Ƃ̊J�����A����A�W�A�ɂ�����B��̓Ɨ����ł���^�C�����͒�����錾���Ă������A���{�̈��͂Ȃǂɂ��12��21���ɓ��{�Ƃ̊Ԃɓ��U�瓯������������A�����㐕�����̈ꍑ�ƂȂ������Ƃŗ�1942�N��1��8������C�M���X�R��A�����J�R���o���R�N�ȂǓs�s���ւ̍U�����J�n�B������ă^�C������1��25���ɃC�M���X�ƃA�����J�ɑ��Đ��z�������B �@
1942�N��2���ɂ́A�J��ȗ��A��A���𑱂�����{�C�R�̈ɍ���ꎵ�����͂��A�A�����J���C�݉��ݕ��̃J���t�H���j�A�B�E�T���^�o�[�o���s�ߍx�̃G���E�b�h�ɂ��鐻������C�����������̎{�݂�j���B�����ē�6���ɂ̓I���S���B�ɂ���A�����J�C�R�̊�n��C������Q���o�������Ƃ�����A�A�����J���O���͖{�y�ւ̓��{�R�̖{�i�I�ȏ㗤�ɔ��������̂́A�Z�������ɂ�鑁���a�����Ӑ}���Ă������{�C�R�̓A�����J�{�y�Ɍ����Ė{�i�I�ɐi�R����Ӑ}�͂Ȃ������B�������A�����̃A�����J�{�y�U���������炵�����{�R�̃A�����J�{�y�㗤�ɑ���A�����J���O�����{�̋��|�S�ƁA���m�ɂ��l�퍷�ʓI����A���n�l�̋������e�̖{�i���Ɍq�������Ƃ�������B �@
���{�C�R�́A�����ɍs��ꂽ�W�������C��ŃA�����J�A�C�M���X�A�I�����_�C�R�𒆐S�Ƃ���A���R�����̊͑���Ŕj����B�����X���o�����C��ł́A�A�����C�R�̏��m�͂�7�nj������ꂽ�̂ɑ��A���{�C�R���̑����͊F���ƈ��������B�܂��Ȃ��R���叫��������{���R���C�M���X�̃}�����ɏ㗤���A2��15���ɃC�M���X�̓���A�W�A�ɂ�����ő�̋��_�ł���V���K�|�[�����ח�����B�܂��A3���ɍs��ꂽ�o�^�r�A���C��ł��A�����C�R�Ɉ������A�������s�k�ɂ��A�W�A�n��̘A���R�͑��͂قډ�ł����B�܂��Ȃ��W�������ɏ㗤�������{�R�͔敾�����I�����_�R�𐧈��������S����̂���(������)�B�܂��A���̍��A���{�C�R�̓A�����J�̐A���n�ł������t�B���s���𐧈����A�����m���ʂ̘A�����R���i�ߊ��ł������_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�͑����̃A�����J�����t�B���s���Ɏc�����܂܃I�[�X�g�����A�ɓ��S�����B�܂��A���{���R��3�����ɃC�M���X�̃r���}�̎�s�ł��郉���O�[�����̂��A���{�͘A��A���̔j�|�̐����ł������B �@
�����ɂ́A�����C�M���X�̐A���n�ł������r���}(���݂̃~�����}�[)���ʂɓW�J������{���R�Ɍ�����͂���`�ŁA�C�R�̍q���͂𒆐S�Ƃ����@���͑����C���h�m�ɐi�o���A���ڋ@���C�M���X�̃Z�C����(���݂̃X�������J)�̃R�����{�A�g�����R�}���[����P�A����ɃC�M���X�C�R�̍q���̓n�[�~�[�Y�A�d���m�̓R�[���E�H�[���A�h�[�Z�b�g�V���[�ȂǂɍU�������������̊͑D����������(�Z�C�������C��)�B����ɂ��C�M���X�̓����͑��͍q���͂ɑ�Ō����āA���{�C�R�̋@�������ɑ��锽�����ł����A�����A���n���ɒu���Ă����A�t���J���݂̃P�j�A�̃L�����f�B�j�`�܂œP�ނ��邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A���̍U���ɉ�����������͂̈�ǂł���ɍ���O�Z�����͂́A���̌�8���ɐ푈�J�n�㏉�̌��Ɛ����͍��(��ꎟ���Ɛ�����)�Ƃ��ăh�C�c�ւƔh������A�G�j�O�}�Í��@�Ȃǂ������A�����B �@
���̍��C�M���X�R�́A���B�V�[�E�t�����X���������A���{�C�R�̊�n�ɂȂ�댯���̂������C���h�m�̃A�t���J���݂̃}�_�K�X�J�������A�t���J�R�̎x�����Đ�̂���(�}�_�K�X�J���̐킢)�B���̐킢�̊ԂɁA���n�̃��B�V�[�E�t�����X�R�����삷�ׂ��C�M���X�C�R��ǂ������{�C�R�̓�����q�����f�B�G�S�X�A���X�`���U�����A�C�M���X�C�R�̐�͂�1�Ǒ�j�����铙�̐�ʂ������Ă���B �@
���i���̏I����A���{�R�͑��i���Ƃ��āA�A�����J�ƃI�[�X�g�����A�̊Ԃ̃V�[���[�����Ւf���I�[�X�g�����A���Ǘ�������u�č��Ւf���v(FS���)���\�z�����B�����j�~���悤�Ƃ���A���R�Ƃ̊ԂŃ\�����������̐킢�A�j���[�M�j�A�̐킢���J�n����A���̒n��œ��{�R�͑��~�߂���A�푈���������Ղ��Ă䂭���ƂɂȂ�B �@
1942�N5���ɍs��ꂽ�X��C�C��ł́A���{�C�R�̋��@�������ƃA�����J�C�R����͂Ƃ���A���R�̋��@�����������˂��A���j�㏉�߂čq���͓��m����͂ƂȂ��Đ퓬���������B���̊C��ŃA�����J�R�͑�^��ꃌ�L�V���g�������������A���{�R�����^���˖P�������A�Ē߂����������B���̌��ʁA���{�R�͊C�H����̃|�[�g�����X�r�[�U�����𒆎~�����B���{�R�͗��H����̃|�[�g�����X�r�[�U�����𐄐i���邪�A�R���z���̍��͕⋋���r�₦���s����B�@

4���A�A�����J�̃A�����J�C�R�@�������𐧈����邽�߁A�@��������͂𓊓����~�b�h�E�F�[���U�������肷�邪�A���̒���ɋ��z�[�l�b�g���甭�i����B-25�ɂ����{�{�y�̋�P(�h�[���b�g����P)�ɏՌ�����B6���ɍs��ꂽ�~�b�h�E�F�[�C��ɂ����āA���{�C�R�@�������͎�͐��K���4��(�ԏ�A����A�����A��)�Əd���m�́u�O�G�v��r�����鎖�ԂɊׂ�B�͑D�̔�Q�����ł͂Ȃ��A�����͍̊ڋ@�Ən���p�C���b�g�����������̐퓬�͑����m�푈�̃^�[�j���O�|�C���g�ƂȂ����B�~�b�h�E�F�[�C���A���{�C�R�ۗ̕L���鐳�K���ł������Ɉړ��ł���̂͐��߁A�Ē߂݂̂ƂȂ�A�}篋��̑呝�Y���v�悳���P�A�_���A�V��A�����M���ɐM�Z��ɐ��Ȃǂ̌������s�Ȃ����A�͍ڋ@�E������E�R���̕s���ɂ��J�펞�ɕC�G����悤�Ȕ\�͂̋@�������^�p�͏I�펞�܂ō���Ȃ܂܂ł������B����A�����J�́A�I��܂łɃG�Z�b�N�X������14�nj������Ă���B�Ȃ��A��{�c�́A�����������ɕ�����������ɐ��������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA�~�b�h�E�F�[�C��ɂ������s�̎������B������B �@
�A�����J�C�R�@�ɂ����{�{�y�ւ̏���P�ɑ��āA9���ɂ͓��{�C�R�̈Ɉ�܌^�����͈ɍ����ܐ����͂̐����͓��ڒ�@�@�ł���뎮���^�����@�@�Ȃǂɂ��A�����J���C�݂̃I���S���B��2�x�ɂ킽����A�X�щЂ�������Ȃǂ̔�Q��^����(�A�����J�{�y��P)�B�Ȃ��A�A�����J���{�́A�~�b�h�E�F�[�C��ɂ����ď��������߂����̂́A��������Ɉ��e�����y�ڂ��Ȃ����߂ɁA���̏��̖{�y��P�̎��������J���Ȃ������B���̋�P�́A���݂Ɏ���܂ŃA�����J���O���{�y�ɑ���B��̊O���R�@�ɂ���P�ƂȂ��Ă���B�܂��A����ɐ旧��5���ɂ́A���{�C�R�̓�����q���ɂ��V�h�j�[�`�U�����s���A�I�[�X�g�����A�̃V�h�j�[�`�ɒ┑���Ă����I�[�X�g�����A�C�R�̑D��1�ǂ����������B �@
�~�b�h�E�F�[�C�풼���7���ɓ��{�R�͍ő吨�͔͈͂ɒB�������A�~�b�h�E�F�[�C��ɂ����{�R�̈��|�I�D�ʂɂ���������͈͂ꎞ�I�ɝh�R���A�A�����J�C�R�͓��{�C�R�̗\�z��葁�����U�����J�n���邱�ƂƂȂ�B8���ɃA�����J�C�R�͓��{�C�R�ɑ��鏉�̖{�i�I�Ȕ��U�Ƃ��āA�\�����������̃c���M������уK�_���J�i�����ɏ㗤���A���{�R�����݂��A�����ԋ߂ł�������s����̂����B����ȗ��A�K�_���J�i�����̒D���ڎw�����{�R�ƕč����R�̊ԂŁA���E�C�E��̑S�Ăɂ����Ĉ����Ր킪�J��L���邱�ƂƂȂ���(�K�_���J�i�����̐킢)�B�����ɍs��ꂽ��ꎟ�\�������C��ł͓��{�C�R�̍U���ŁA�A�����J�A�I�[�X�g�����A�C�R�Ȃǂ���Ȃ�A���R�̏d��4�ǂ��������ď�������B�������A���{�R���A���D���U�����Ȃ��������߁A�K�_���J�i�����ł̐틵�ɑ傫�ȉe���͂Ȃ��������A��\�������C��œ��{�C�R�͋�ꗴ鈂������������A��������틵�͓D��������B �@
10���ɍs��ꂽ�쑾���m�C��ł́A���{�C�R�@�������̍U���ɂ��A�A�����J�C�R�̑�^���z�[�l�b�g�������A��^���G���^�[�v���C�Y���j�������B�旧���ăT���g�K����j�A���X�v����{�����̗͂����ɂ���Ď����Ă����A�����J�C�R�́A�ꎞ�I�ɂł͂��邪�����m����ɂ�����ғ��\��ꂪ�F���Ƃ�����@�I�֊ׂ����B���{�͐��߈ȉ�5�ǂ̋���L���A���̏�ł͈��|�I�D�ʂȗ���ɗ��������A�x�d�Ȃ�C��ŏn������������Ղ��Ă��܂������Ƃƕ⋋�������т��������Ƃɂ��A�O���ւ̓������ł����V���ȍU���ɑł��ďo�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����ł��A�����Ȃ��������Ȃ�����}�s�b�`�Ŏg���܂킵���ČR�ƁA�~�b�h�E�F�[�̃g���E�}�������Ă������o���ɂ����{�R�Ƃ̍��̓\�������C��ł̌���������傫�ȗv���ɂȂ����Ƃ�����B �@
���������̌�s��ꂽ��O���\�������C��ŁA���{�C�R�͐��2�ǂ������s�k�����B�A�����J�R�̓K�_���J�i�������ӂɂ����čq��D�����l���A���{�R�̗A���D�����j���A�⋋��W�Q���A�����A�������߂��B�K�_���J�i�����ł͕⋋���o���Ȃ��Ȃ�A�쎀������{�R���m�����o�����B��Ɉꕔ�̎i�ߕ����K�_���J�i�������́u�쓇�v�Ɣ����ꂽ�B �@
1943�N1���A���{�C�R�̓\�����������̃����l�������ōs��ꂽ�����l�������C��ŃA�����J�C�R�̏d���m�̓V�J�S�����������ʂ����������A���̒D��͍ő���]�I�ƂȂ�A2���ɓ��{���R�̓K�_���J�i��������P��(�P�����)�����B���N�ɂ��y�ԏ��Ր�ɂ��A���č����R�ɑ傫�ȑ��Q�����������A���͂Ɍ��E��������{�ɂƂ��Ă͎��Ԃ��̂��Ȃ����Q�ł������B����ȍ~�A�\�����������ł̐퓬�͗��R�h�R�����܂ܑ����B �@
1943�N4��18���ɂ́A���{�C�R�̘A���͑��i�ߒ����̎R�{�\�Z�C�R�叫���A�O�����@�̂��ߖK��Ă����u�[�Q���r�������ŃA�����J�C�R���ǂɂ��Í���ǂ������b�L�[�hP-38�퓬�@�̑҂��������A��@�̈ꎮ����U���@�����Ă���펀����(�ڍׂ́u�C�R�b�����v���Q��)�B��������{�c�́A���w����̋@���ێ���A�����ɂ���`���p�̖h�~�Ȃǂ��l�����āA�R�{�����̎��̎�����1�����ȏソ����5��21���܂ŕ����Ă����B�������A���̍����{�C�R�̈Í��̑����̓A�����J�C�R���ǂɂ���ǂ���Ă���A�A�����J�R�͓��{�C�R�̖����̖T��ƈÍ��̉�ǂɂ��A���Č�Ԃ��Ȃ��R�{�����̎����@�m���Ă������Ƃ���㖾�炩�ɂȂ����B�Ȃ��A���{���{�́u�����̋w�͑��Y��(����)�v�Ƃ̕W������A�R�{�����̎����Ӎ��g�ɗ��p����B �@
1943�N5���ɂ͑O�N��6�������{�R����̂��Ă����A�����[�V�����̃A�b�c���ɕČR���㗤�B���{�R������͑S�ł�(�A�b�c���̐킢)�A��{�c���\�ɂ����ď��߂āu�ʍӁv�Ƃ������t���p����ꂽ�B���̌�A7���Ƀ\�����������ōs��ꂽ�R�����o���K�������C��ŁA���{�C�R�͒��͍I�݂ȗ����ɂ��Ċ͑��ɏ������邪�A���̍��ɂȂ�ƃ\�����������ł̐����͍ő������Ă������߁A�틵�ɂ͑傫�ȉe����^���Ȃ������B�܂��A�j���[�M�j�A���ł͓��{�R�ƃA�����J�R�A�I�[�X�g�����A�R�𒆐S�Ƃ����A���R�Ƃ̌������킢�������Ă������A8������菭�������{�R�̑ސ��ƂȂ�A�����⋋�ɍ���o�Ă����B���̔N�̕�ꂲ��ɂ́A���{�R�ɂƂ��ē쑾���m����ł̍ő��n�ł��郉�o�E���͌Ǘ������n�߂���̂́A���ӂ̓��X����̂���⋋���r�₦�����A���������̐������s���A���A���R�ƍq����W�J���A�I��܂Ŏ������������B�@
�ē����Q�d�{���̍쐬�����u���{���Ő헪�v��v�ł́A�u1�A�����A���ɓ��C���h�����n��̖��c����т��̑��̐헪�������^�ԓ��{���⋋�H�̐ؒf�@2�A���{�̏��s�s�ւ̌p���I�ȋ�P�@3�A���{�{�y�ւ̏㗤�v�ɂ���ē��{�����łł���Ƒz�肵�Ă����B�J���ɔs�k�𑱂������̂́A���̌��͂𐮂����A�����J�R��C�M���X�R�A�I�[�X�g�����A�R�𒆐S�Ƃ����A�����R�́A���̔N�̌㔼����헪�v��Ɋ�Â����U����{�i���������B �@
�쐼�����m�n��R���i�ߊ��̃_�O���X�E�}�b�J�[�T�[����悵���u��ѐ��(���{�R���v�lj�������������A�d�v���_��D�悵�ē��{�{�y�ւƌ�����)�v�ɑ��āA�ĊC�R���͈���������m�ۂ��Ȃ���łȂ���ΑO�i�ł��Ȃ��Ƃ��u�I�����W�v��(�A�����J�C�R�̑Γ��푈�v��)�v�̍ċ���}�����B���ǃj�~�b�c�C�R�叫�̒��������m�n��R���}�[�V������������}���A�i�������o�āA�}�b�J�[�T�[���R�叫�̓쐼�����m�n��R���\�����������A�j���[�M�j�A���o�ăt�B���b�s���ւƐN�U����u�����m���f�F�]�O(�E�I�b�`�^���[)���v��1943�N�Ɏ厲���Ƃ��Ĕ������ꂽ�B���̎�n�߂�43�N11��20���̓쑾���m�̃}�L�����ƃ^�������ɂ�����킢�œ��{�R��������S�ł��A�������A�����J�R�ɐ�̂���邱�ƂɂȂ�B �@
�����ɓ��{�̓����p�@�́A���B����^�C�����A�t�B���s���A�r���}�A���R�C���h�����{�A���ؖ����싞�������{�Ȃǂ̎�]�𓌋��ɏW�߂đ哌����c���J���A�哌�����h���̌������֎������B���̔N�̔N���ɂȂ�ƁA�J�퓖���̑������s�k���犮�S�ɑԐ��𗧂Ē����A���|�I�Ȑ�͂����Ɏ������A�����J�R�ɉ����A���[���b�p����Ńh�C�c�R�ɑ��čU���ɓ]������̓W�J�ɗ]�T���o�Ă����C�M���X�R��I�[�X�g�����A�R�A�j���[�W�[�����h�R�Ȃǂ̐��J������Ȃ�A���R�ƁA����������P����Ԃ�ŊJ�ł��Ȃ��܂܁A�����m����ɂ����Ă������閡�����Ȃ�������1���Ő키��A�J�퓖���̑����������̂��߂ɗ\�z���Ȃ������قǐ�������т����Ƃŕ��m�̕⋋�╺��̐��Y�A�R�������̕⋋�ɍ����������{�R�̗͊W�͈�C�ɘA�����L���ւƌX���Ă������B �@
�r���}���ʂł͓��{���R�ƃC�M���X���R�Ƃ̒n��ł̐킢�������Ă����B1944�N3���A�C���h�k�����A�b�T���n���̓s�s�ŃC���h�ɒ�������p��R�̎�v���_�ł���C���p�[���̍U����ڎw�����C���p�[�����Ƃ�����x�������A�L���u��킪�J�n���ꂽ�B�X�o�X�E�`�����h���E�{�[�X������C���h�����R�܂œ������A�ɉ��������틵��ŊJ���邽��9���l�߂������𓊓�������K�͂ȍ��ł������B�������A�⋋�����y���������d�E�m��ȍ��ɂ���3���l�ȏオ��������(�唼���쎀�ɂ�����)�ȂǁA���{���R�ɂƂ��ė��j�I�Ȕs�k�ƂȂ����B����ȍ~�A�r���}���ʂł̓��{�R�͉�ŏ�ԂƂȂ�B�����̎��s�ɂ�藂�N�A�A�E���E�T�����R������r���}�R�͘A���R�Q�Ԃ�A���ʂƂ��ė��N�ɓ��{�R�̓r���}���������ƂɂȂ�B �@
5�����ɂ́A�ČR�ɂ��ʏ��j��Ȃǂœ������̕⋋���r�₦�Ă�����������œ��{�R�̈��U�����J�n�����(�嗤�Œʍ��)�B��펩�̂͐������A�����k���ƃC���h�V�i���ʂ̗��H�ł̘A�����\�ƂȂ������A�������ʂł̍U���͂��ꂪ���E�ł������B6������͒��ؖ����E���s����n�Ƃ���B-29�ɂ��k��B�������n�܂����B �@
�A�����R�ɑ��e�n�ŗɉ����������{�̗��C�R�́A�{�y�h�q�̂��߂���ѐ푈�p���̂��߂ɕK�v�s���ł���̓y�E�n�_���߁A�h�q�𖽂����n�_�E�n��ł������h����݂����B �@
�������A6���ɂ��̍ŏd�v�n�_�ł������}���A�i�����ɃA�����J�R�����P����B���{�C�R�@�������͂���ɑ��������ׂ��}���A�i���C����N�����B���{�@�������͋��9�ǂƂ������{�C�R�j��ő�K�͂̊͑���Ґ����A�ċ@���������}���������̂́A���|�I�ȍH�Ɨ͂���ɋ��𑽐��v�H�����Ă����A�����J����15�ǂ��̋�����Ƃ��A�X�ɓ��{�̔{�߂��͑D����q�ɂ���Ƃ����Ԃ�ł������B�q��@�̎���h��V�X�e���ł��x����Ƃ��Ă������{�@�������̓A�����J�C�R�̋@�������ɎS�s���i���邱�ƂƂȂ�B���͂ł�������P�ȉ����3�ǁA���̑������͍̊ڋ@�Ən������������������{�@�������͕����ǂ����ł����B�������A��͕����͂قږ����ł��������߁A10�����̃��C�e���C��ł͐�͕�������Ƃ����͑����Ґ�����邱�ƂɂȂ�B �@
����ł́A�җ�Ȋ͖C�ˌ��A�q��x�������A�����J�C�����̑啔�����T�C�p�����A�e�j�A�����A�O�A�����Ɏ��X�ɏ㗤�B7���ɊC�R��_���ꒆ���̎��T�C�p�����ł�3���̓��{�R��������ʍӂ��A�����̔�퓬�������R�̐퓬�̒����S�����B������8���ɂ̓e�j�A�����ƃO�A�������A���R�ɐ�̂���A�����ɃA�����J�R�͓��{�R���g�p���Ă�����n�����C���A��^�����@�̔������\�Ȋ����H�̌��݂��J�n�����B���̂��Ƃɂ��k�C�����������{�̂قڑS�y��B-29�̔��������ɓ���A�{�i�I�Ȗ{�y��P�̋��Ђ���悤�ɂȂ�B���ہA���̔N�̕��ɂ́A�T�C�p�����ɐ݂���ꂽ��n�����ї������A�����J��R��B-29�������ɂ��钆����s�@�̕����쐻�쏊������ȂǁA�{�y�ւ̋��{�i������B�����m��̍ŏd�v�n�_�ł���T�C�p�������������e���͑傫���A�U���̂��߂̕z�͊��S�ɖ��͉������B �@
����ɑ��āA�A�����J��C�M���X�̂悤�ȑ�^�����@�̊J�����s���Ă��Ȃ��������{�R�́A���̍��}�s�b�`��6���G���W��������^�����@�u�x�ԁv�̊J����i�߂���̂́A�J���ɂ͎��Ԃ����������B�����œ��{�R�́A�������{�̌������������������Ă����W�F�b�g�C���𗘗p���A��^�C���ɔ��e�����č����x�ɔ���A�����J�{�y�܂ʼn^����Ƃ��������镗�D���e���J�����A���ۂɃA�����J�{�y�����Đ����������B�������l�I�A���I��Q�͐����̎s�������S���A�Ƃ���ǂ���ɎR�Ύ����N�������x�̔��X������̂ł����Ȃ������B�܂��A���{�C�R�́A���̔N�ɐi�������͓��ɍU���@�𓋍ڂ����������u�Ɏl�Z�Z�^�����́v�ɂ��A�����A�����J�������Ǘ����Ă����p�i�}�^�͂𓋍ڋ@�̐���U���@�u�����v�ōU������Ƃ��������l�Ă������A�틵�̈����ɂ�蒆�~���ꂽ�B �@
�e�n�ŗ��`�����钆�A����ɔ����Ă܂��܂��R����`�I�ȓƍّ̐����������铌���p�@�����R��b�ɑ��锽���͋����A���̔N�̏t���ɂ́A���쐳���Ȃǂ̐����Ƃ�A�C�R���Z�Ȃǂ𒆐S�Ƃ����|�t�^��������ɍs��ꂽ�B���ꂾ���łȂ��A���ʕ������̔鏑���ł������א���̑���̏،��ɂ��ƁA���������̊C�R���Z�Řa���h�ł����������{��m�e���ٔF�̏�ł̋�̓I�ȈÎE�v����������ƌ����Ă���B���������̌v�悪���s�Ɉڂ�����葁���A�T�C�p�����ח��̐ӔC����蓌���p�@�����R��b��������t�������E���A���鍑�����R�叫�ƕē������C�R��b����ǂƂ�����t�����������B �@
���̍����{�́A��N������̑������s�k�ɂ��q��ъC�R���͂̑����������Ă������̂́A��ʐ��Y�ݔ��������Ă��Ȃ��������Ƃ����蕐��e��̑��Y���v���悤�ɍs�����A���̐��Y�͂͘A���R�����̑��v�ǂ��납�C�M���X��A�����J�ꍑ�̂�������傫��������Ă����B�������{�y�ɂ����鎑�������Ȃ����ߓS�z��Ζ��Ȃǂ̎������قڊO����͌�����̗A���ɗ����Ă�����ɁA�A�����R�ɂ��ʏ��j���ɂ��O�n���玑�����^��ł���D���̑����������Ă������߂ɁA�퓬�@�ɐςޏ��x�̍����q��R������A��͂����d���̋������獢��ȏł������B �@
10���ɂ́A�A�����J�R�̓t�B���s���̃��C�e���ւ̐i�U���J�n�����B���{�R�͂����j�~���邽�߂Ɋ͑����o�������A���C�e���C�킪���������B���{�C�R�͋�ꐐ�߂���͂Ƃ���@��������ċ@���������Ђ����隙�Ɏg���A��͑�a�A��������͂Ƃ����͕���(�I�c�͑�)�ł̃��C�e���ւ̏㗤�������悹���A���D���̟r�ł��������B���̍��͐����̒��������������̂́A���njI�c�͑��̓��C�e�p�ڑO�Ŕ��]���A���s�ɏI������B���̊C��œ��{�C�R�͋��4�ǂƕ����ȉ���͐��3�ǁA�d��6�ǂȂǑ����̊͒��������������ł��A�܂������̋����͂��c�����Ă������̂́A�g�D�I�ȍ��\�͂͑r�������B�܂��A���̐킢�ɂ����ď��߂Đ_�����ʍU�������g�D����A�ĊC�R�̌�q��ꌂ���Ȃǂ̐�ʂ��グ�Ă���B �@
���C�e���C��ɏ��������A�����J�R�́A�啔�����t�B���s���{�y�֏㗤�����A���{���R�Ƃ̊ԂŌ��킪�J��L����ꂽ�B�푈�����������Ă��Ȃ������J�퓖���Ƃ͈Ⴂ�AM4����Ԃ�Ή����ˊ�ȂǁA���|�I�ȉΗ͂����͂ʼn�����A�����J�R�ɑ��A���{�R�͔s�������B�@

1944�N8���O�A�������قڐ������I�������A�A�����J�����m�͑��i�ߕ��ł�9���Ƀ��C�����h�E�X�v���[�A���X�̌���A��p�U���͊C�R���S�͑��ւ̕⋋�\�͂̌��E�ɒB���Ă��邱�Ƃ���{�{�y�ւ̉e���͍s�g�̊ϓ_����Ӗ����Ȃ��Ɣ��f���Ă����B���̂��ߎ��̍U���ڕW�͑�p�ł͂Ȃ��C�R�����ł͉���Ƃ��ꂽ�B�t�B���s�����C�e����~���h�����ɂ�����킢�ɏ��������߁A1���ɂ̓A�����J�R�̓��\�����ɏ㗤�����B�t�B���s���S�y�͂قژA���R�̎�ɓn�邱�ƂɂȂ�A���{�͓���̗v�Ղł���t�B���s�������������Ƃɂ��A�}���[������C���h�V�i�Ȃǂ̓��{�̐��͌��ɂ�����������{�{�y�ւ̑D���ɂ�鎑���A���̈��S�m�ۂ͂قڕs�\�ƂȂ�A�����̎������R�������{�̐푈�p���\�͂��r���͎̂��Ԃ̖��ƂȂ����B �@
���C�e�U���ɂ��A�قړ��{�C�R�̐퓬�\�͂͂Ȃ��Ȃ��p�U���̐헪�I�ȉ��l�͍X�ɉ����������A�����I�ɍ����I�p�Y�ƂȂ��Ă����ė��R�̃}�b�J�[�T�[�͈ˑR�Ƃ��đ�p�U�����咣���Ă������߁A�U�����j�ɂ��ē����Q�d�{���ŕĊC�R�Ɨ��R�͑Η����Ă��܂����B�������A1944�N6���̔�����P����ɂ����u���{�{�y�ւ̌p���I�Ȕ����v�͒����嗤���s��n����̎U���I�ȋɑ����āA11���̃O�A������T�C�p�����E�e�j�A�����̊�n�����ɂƂ��Ȃ��{�[�C���OB-29�����@�ł̓��{�{�y�ւ̖{�i�I�ȍU���J�n�ɂ��A�����Q�d����c�Ńw�����[�E�A�[�m���h���R�叫(�������U������)�����{�{�y�ւ̐헪�����������ʓI�ɂł���悤�ɗ������̍U�������������߂ɁA���ɊC�R���̎咣���鉫��㗤�Ƃ��̑O��̗������U�����A�����J�R�S�̂̊�{�헪�ƂȂ����B �@
1944�N��10��14���Ƀ��[�Y�x���g�͓��{�̍~���𑁂߂邽�߂ɒ��\��gW�E�A���F�����E�n���}������ăX�^�[�����ɑΓ��Q��𑣂����B��12��14���ɃX�^�[�����͕���̒Ɗ���(�T�n����)�암��瓇�̗̗L��v���A���[�Y�x���g�͐瓇���\�A�Ɉ����n�����Ƃ������ɁA���\�������̈���I�j���𑣂����B�܂��A���̂Ƃ��̕�����ӂ̓}�C���|�X�g���ӂƂ����A��45�N�ɕč��́A�������������\�A�̑D���g���ē��{�C���A�E���W�I�X�g�N��80���g���̕���e��𗤗g�������B��1945�N2��4������11���ɂ����āA�N���~�A�����̃����^�ŁA���[�Y�x���g�E�`���[�`���E�X�^�[�����ɂ�郄���^��k���J���ꂽ�B��c�ł͑���̍��ے�����A�܂��\�A�Ƃ̓��{�̗̓y�����Ȃǂɂ��Ă��b���ꂽ�B�����^��k�ł͂��ꂪ�閧����Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ(�����^��k#�ɓ�����(�����^����))�B ����㗤�ɐ�삯��1945�N2��19������3���㔼�ɂ����ė������̐킢���s��ꂽ�B�A�����J�C�R�̋��͂ȕ����ɉ��삳�ꂽ�ĊC�����ƁA����v�lj��������{���C�R������Ƃ̊ԂŌ��킪�J��L�����A���R���킹��5�����߂��̎����҂��o�����B�ŏI�I�ɓ��{�͓����s�̈ꕔ�������������A�A�����J�R�͗�������B-29�����@�̌�q��P-51D�퓬�@�̊�n�A�܂����{�{�y�ւ̔����ɍۂ��đ����E�̏Ⴕ��B-29�̕s�����n�Ƃ��Đ������邱�ƂɂȂ�B���̌��ʁA�k�}���A�i���������ї�����B-29�ւ̐퓬�@�ɂ��}���͋ɂ߂č���ƂȂ����B���{�R��B-29�����Ă��邽�߂̐V�^�퓬�@�u�k�d�v�Ȃǂ̌}���@�̊J����i�߂邱�ƂɂȂ邪�A���p���ɂ͎��炸�A�����̐퓬�@�ő̓������@�Ȃǂ�p���K���ɒ�R�������A�����x�������Ŕ��A���������ł�B-29�����Ă���͎̂���̋Ƃł������B �@
1945�N3��10���ɂ͍��ۖ@�ᔽ�ł��閳���ʔ����E�������P���s���A���ɂ���10���l�̖�������ꂽ�B����܂ł͍����x����̌R���H���_�����������������S�ł��������A�w�C�E�b�h�E�n���Z���y������J�[�`�X�E�����C������B29�ŕҐ����ꂽ��21�����W�c�̎i�ߊ��ɏA�C����ƁA���Ԑl�̎E������ړI�Ƃ��������ʔ������A��̂悤�ɍs����悤�ɂȂ����B�����ĘA���R�ɂ������͍U����A�@���̕~�݂ɂ�萧�C���������Ă������A�����A���A���É��A�_�ˁA�É��A�ȂǁA���{�S���̑����̒n�悪��P�ɂ��炳��邱�ƂɂȂ�B�����⊘�ł͐��S���������Ȃ�����A�}���p�̍q��@���^�͂̔z�����F���ɓ��������Ƃ��@�m���Ă����A�����J�R�́A�͖C�ˌ��ɂ��Βn�U�����s���B�܂��A���{�{�y�ߊC�̐��C�������S�Ɏ蒆�Ɏ��߂��A�����J�R�́A�C�M���X�R�������ēx�X���@����������{���݂ɔh�����A�͍ڋ@�ɂ��e�n�ւ̋�P��@�e�|�˂��s�����B �@
�}������퓬�@���A�n���������c�m���A�x�d�Ȃ�s�k�Ƌ�P�ɂ�鐶�Y�ቺ�Œ��˂��Ă������{�R�́A�\���Ȕ������ł��ʂ܂܁A�{�y�̐������������Ă����B���{�R�͗��K�@�����������A���U�ɂ��K���̔������s�����A���̍��ɂȂ�Ɠ��U�ւ̑��҂ݏo���Ă����p�ČR�ɑ���ʂ͏オ��Ȃ��Ȃ����B �@
���̍��A���B���͓��{�R���A�����J�R��C�M���X�R�A�I�[�X�g�����A�R�Ɛ���Ă�������������͉���������A���\��������݂��Ă������߂Ƀ\�A�̊ԂƂ͐퓬��ԂɂȂ炸�J��ȗ����Â����������A1944�N6���ɓ���ƁA���a���|��(�ƎR���S��)�Ȃǂ̏d�v�ȍH�Ɗ�n���A���ؖ����̓������ї������A���R�@�̋�P���n�߂��B�܂��A���������{�R�̐��͉��ɂ������r���}�ɂ����ẮA�J��ȗ��A���̏@�卑�ł���C�M���X�R������������{�R�Ƌ��͊W�ɂ������r���}���R�̈ꕔ�����{�R�ɑ����N�����B3�����{�ɂ́u���N���������R�ɑR���邽�߁v�Ƃ̖��ڂŁA�w���҂ł���A�E���E�T���̓r���}���R�������O�[���ɏW�����������̂́A�W������Ƒ����ɓ��{�R�ɑ��Ă̍U�����J�n���A�����ɑ��̐��͂���ĂɖI�N���C�M���X�R�Ɍĉ������R���^�����J�n���ꂽ�B�ŏI�I�ɂ�5���Ƀ����O�[��������{�R���쒀�����B �@
���̌�A5��7���Ƀi�`�X�E�h�C�c���A�����ɍ~�����A���ɓ��{�͂������ꍑ�ŃA�����J�A�C�M���X�A�t�����X�A�I�����_�A���ؖ����A�I�[�X�g�����A�Ȃǂ̘A�����ƑΛ����Ă������ƂɂȂ�B�Ƃ�킯�A�\�A�̓h�C�c�s�k�œ��{�N�U��ڎw���ĕ��͂��ɓ��ֈړ��������B���̂悤�ȏ��ŘA�����Ƃ̘a���H��ɓw�͂��鐭�}�����Ƃ������������A�s�k�ɂ��ӔC��������Â����{�c�̋c�_�͖������J��Ԃ��B����A�u�_�F�s�s�v��M��R�̋��d�h�͂Ȃ����{�y������f���āA�u���{�������S�ł���܂ň�l�c�炸��R�𑱂���ׂ����v�ƈꉭ�ʍӂ��������B���{���{�͒�����������ł����\�r�G�g�A�M�ɂ��a������̉\����T�����B���̂悤�ȍ~���̒x��́A���̌�̐��r���ɂ��{�y��P�̌����≫���̌����A���q���e�����Ȃǂ�ʂ��āA���{�R��A���R�̕��m�����łȂ��A���{�₻�̎x�z���̍��X�̈�ʎs���ɂ��r��ȎS�Ђ������炷���ƂɂȂ����B �@
�A�����J�R�𒆐S�Ƃ����A���R�͓��{�㗤�̑O��Ƃ��ĉ��ꏔ���ɐ����i�߁A����{���ւ̏㗤�����s���B�����̖��Ԑl���������������S�Ȓn��킪�s��ꂽ���ʁA���R�Ɩ��Ԑl�Ɏ����Ґ��\���l���o�����B�Ȃ��A�����͍~���O�ɂ�����B��̖��Ԑl���������n���ƂȂ����B���{�R�̌R���������������ɂ��A�A���R���͗\������x�ꂽ���̂�6��23���܂łɐ��̑唼���̂���Ɏ���A���悢����{�{�y�㗤��ڎw�����ƂɂȂ�B �@
�܂��A�����̎x���̂��߂ɉ���Ɍ��������A���͑���2�͑��̊��͂ł��鐢�E�ő�̐�͑�a��4��7���Ɍ�������A�c�������͂̒����Y���A�����A�ɐ��Ȃǂ��R���̌͊�����s���ł����A�h��C��Ƃ��ĕČR�@�̍U���ɂ��炳��邾���ł������B����œ��U����́u�k�m�v���V�E�C���Ȃǂ����Y����e�n�Ɋ�n���݉c���ꂽ�B���p�q��@�����C�R�@�ƕ������1���@�ȏ�̍q��@���c�����{�y����p�ɓ��U�@�Ƃ��̎x���@�Ƃ��ĉ�������A�ꕔ��������B29�Ȃǂւ̖h���ɂ͎Q�����Ȃ������B �@
���̍��ɂ́A���{�R�̐���C���͂قڏ������A���{�ߊC�ɔ���悤�ɂȂ����A���R�̊͒��ɑ��Ċ�{�I�ȑ��c�P�����I�����p�C���b�g�����c������U�@�ɂ��U�����c���ꂽ��ȍU����i�ƂȂ�A�A���R�͒��ɔ�Q��^����Ȃǂ������̂̓��{�R�̌R���I�Ȕs�k�͖��炩�ł������B���̑O��ɂ́A�����^��k�ł̑��̘A�����Ƃ̖���A�����^����Ɋ�Â��\�r�G�g�A�M�R�̖k������̏㗤���ɍ��킹�A�A�����J�R�𒆐S�Ƃ����A�����R�ɂ���B�n���ւ̏㗤���u�I�����s�b�N���v�ƁA���̌�ɍs����{�y�㗤��킪�v�悳�ꂽ�B1945�N7��26���ɘA�����ɂ��|�c�_���錾�����\�����B�@

�A�����J�̃n���[�ES�E�g���[�}���哝�͍̂ŏI�I�ɁA�{�y����ɂ��]���҂����炷���߂ƁA���{�̕�����̂��咣����\�r�G�g�A�M�̌����ړI�A�j�㏉�̌��q���e�̎g�p������(���{�ւ̌��q���e����)�B8��6���ɍL���s�ւ̌��q���e�����A������8��9���ɒ���s�ւ̌��q���e�������s���A��������Ɏ��S�����\�����l�ɕ����A���̌�̕��˔\�����Ȃǂ�20���l�ȏ�̎��S�҂��o�����B�Ȃ��A�R���͏��a�V�c�Ɍ����J�����ւ���ꂽ�ɂ�������炸�J�������݂������{�̌��q���e�J���͊�b�����̈���o�Ȃ������B �@
���̒���ɁA���\������������ł����\�r�G�g�A�M���A��L�̃����^��k�ł̖����^��������ɁA1946�N4���܂ŗL���ł�����\��������j�����A8��8���ɑΓ����z�������A���{�̓������̖��B���N�U���J�n����(8���̗����)�B�܂��A�\�A�R�̐N�U�ɑ��āA�����A���B���ɒ������Ă������{�̊֓��R�́A��͕�����������֔h���������ʁA��̉����Ă������ߑ�����ƂȂ�A�g�D�I�Ȓ�R���ł��Ȃ��܂܂ɔs�ނ����B�����x�ꂽ���{�l�J�̑����������̒��Ő����ʂ�A��ɒ����c���ǎ����Ƃ��Ďc�邱�ƂƂȂ����B�܂��A���̃\�r�G�g�Q��ɂ�閞�B�A�슒���A�瓇�Ȃǂōs��ꂽ�킢�œ��{�R�̖�60���l���ߗ��Ƃ��ĕ߂炦���A�V�x���A�ɗ}�����ꂽ(�V�x���A�}��)�B���̌ケ�̖�60���l�̓\�r�G�g�A�M�ɂ���ĉߍ��Ȋ��ŏd�J�����������A6���l���鎀�҂��o�����B �@
6��22���̌�O��c�ɂ����ď��a�V�c���u�푈�w���ɂ��ẮA���(6��8��)�Ō��肵�Ă��邪�A���ʁA�푈�̏I���ɂ��Ă��A���̍ۏ]���̊ϔO�ɂƂ���邱�ƂȂ��A���₩�ɋ�̓I�����𐋂��A�������������悤�w�͂���v�Ə��߂Đ푈�I���̂��Ƃ����ɂ��ꂽ�B�������A���{�R���w���w�A�Ƃ�킯�퓬�\�͂�r�������C�R�ƈ���ė��R�́A�~����������悤�Ƃ����̂Ō�O��c�ł̋c�_�͍��������B��������؊ё��Y�����a�V�c�ɔ����𑣂��A�V�c���g���a����]��ł��邱�Ƃڌ��ɂ������Ƃɂ��A�c�_�͎��������B8��14���Ƀ|�c�_���錾�̎���̈ӎv����A��8��15�����߂̏��a�V�c�ɂ��ʉ������������ă|�c�_���錾�̎����\�����A�S�Ă̐퓬�s�ׂ͒�~���ꂽ(���{�̍~��)�B�Ȃ��A���̌��؊ё��Y���t�͑����E�����B�s��Ƌʉ������̎��{��m�����ꕔ�̏��Z�O���[�v���A�ʉ��������^�����ꂽ���R�[�h�̒D�҂���������8��15�������ɋ{���ȂȂǂ��P�����鎖��(�{�鎖��)���N��������A��؎̎��@���P�����肵�����̂́A�ʉ������̌�ɂ́A���؊�n�̈ꕔ�������O��R����Ăт�����r�����T��������A���@��j���肵�Ē�R�������͑傫�Ȕ����͋N���炸�A�قڑS�Ă̓��{�R�͐퓬���~�����B �@
�����ɂ͘A�����R���������̃X�C�X��ʂ��āA��̌R�̓��{�{�y�ւ̎����e�n�ɓW�J������{�R�̕���������i�߂邽�߂̒��A���@�̔h�����˗����A19���ɂ͓��{���̒��S���ψ����ꎮ����U���@�Ńt�B���s���̃}�j���ւƌ��������A�C�M���X�R��A�����J�R�ɑ�����ƕ��������͏����ɐ��s���ꂽ�B�������A�����ł������̓��{�̓y�̐�̂���Ă����X�^�[�����̖��߂ɂ��\�A�R��8�����Ɏ���܂œ슒���E�瓇�E���B���ւ̍U�����p�������B8��14���ɂ͊����_�������N�����B���̂悤�Ȓ���8��22���ɂ͊�������̈����g���D�u���}���ہv�A�u���V���ہv�A�u�ד��ہv���\�A�����̗͂����E�C������j�A���v����(�O�D�}���)�B �@
�܂��A���{�̌�돂�����������B���͎�������A8��18���ɑވʂ����c��̈��V�o����V�疞�B����]�͓��{�ւ̓�����}����A�N�U���Ă����\�A�R�ɂ���Đg�����S�����ꂽ�B���̌�8��28���ɂ́A�A�����R�ɂ����{��̕����̑��e�Ƃ��ăA�����J�R�̐挭���������ؔ�s��ɓ������A8��30���ɂ͌�ɘA�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ�(GHQ/SCAP)�̑��i�ߊ��Ƃ��ĘA�����ɂ����{��̂̎w���ɓ����邱�ƂɂȂ�A�����J���R�̃_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�叫������n�ɓ������A�����ăC�M���X�R��I�[�X�g�����A�R�Ȃǂ̓��{��̕��������������B �@
9��2���ɂ́A�����p���ɒ┑�����A�����J�C�R�̐�̓~�Y�[���ɂ����āA�C�M���X�A�A�����J�A���ؖ����A�I�[�X�g�����A�A�t�����X�A�I�����_�Ȃǂ̘A������17�J���̑�\�c�̗ՐȂ̉��A���{���{�S���d�����O����b�ƁA��{�c�S���~�Ô����Y�Q�d�����ɂ��ΘA�����~�������ւ̒��Ȃ���A������1939�N9��1����葫����7�N�ɂ킽���đ���������E���͂��ɏI�������B�������A�슒����瓇�ł́A9��4���܂Ń\�A�R�Ƃ̊Ԃő�K�͂Ȑ퓬���s��ꂽ�B�܂��A������m�����ɂ����ẮA���m�B�ɂ��Ǐ��I�Ȑ퓬���U���I�ɑ�����ꂽ�B�C�O�̓��{�R�͍~����ɕ�����������邪�A���ď����̃A�W�A�A���n�x�z�̂��߂̎����ێ��������������A�����{�R�����ɑ����̋]���҂��o���B���̌�A�����͈����g���邪�A�C���h�l�V�A�Ɨ��푈�A�x�g�i���Ɨ��푈�A��������Ȃǂɑ����̌����{�R�������Q�����邱�ƂƂȂ����B�@�@
���C�O�ݏZ�̓��n�l �@
��O������������ł悭�����Ƃ������{�l�ږ��������̎������̐E��D���Ƃ��ăA�����J�A�I�[�X�g�����A�A�J�i�_�A�y���[�A�u���W���Ȃǂ��͂��߂Ɉږ��r�ˉ^�����s���Ă����B���̂��Ƃ́A���ĂƓ��{�̐M���W��ቺ�����邱�ƂɌq����Ƌ��Ɉږ��҂͍��ʂ�Ό����Ă���(���ӁF�����͔��l�����`�␢�����������߁A���{�l�݂̂Ɍ��炸�A�L�F�l��ɑ��鍷�ʂ�Ό�������������)�B�����m�푈���n�܂�ƃA�����J��y���[�A�J�i�_���͂��߂Ƃ����k�A�����J��13�J����I�[�X�g�����A�Ȃǂ̘A�����́A���{�l�ږ��݂̂Ȃ炸�A�����̍��̍��Ђ������n�̎������܂ł��A�u�G���s���v�Ƃ��č��Y��v������ăA�����J�⎩�����̋������e���ɋ������e������(���̍ۓ����悤�ɓG���������h�C�c�n�̏Z����C�^���A�n�̏Z���͎��e���ɑ����邱�Ƃ������������Ƃ���l�퍷�ʂ��Ƃ���ӌ������݂���)�B�A�����J�̈ږ����{�l1���͂��̍s�ׂɑ����S�����̊ۂ��f����ȂLj⊶�̈ӂ��������B���̈���ŃA�����J�炿�̈ږ����{�l2���̎�ҒB�̒��ɂ͑c���ւ̒����S���������߂Ɏu��A��442�A���퓬�c���g�D���ꉢ�B���(�ČR�͓��n���{�l�����������{���ɕt�����Ƃ����ꂽ���߁A�����m����ł͂Ȃ����B����֓������ꂽ)�̍őO���ɑ���ꂽ�B����ł̓��n�����̊���͂����܂����A�����ȏ�̋]�����͂炢���C���𐋍s���A�������ԂƋK�͂ɔ䂵�ăA�����J���R�j������Ƃ������̌M�͂��������ƂȂ����B���̂��Ƃ�2�����������ɃA�����J�l�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�����1����2���̌������Η��ݏo���Ѝ����c�����B�������A���̃A�����J���l�̓��n�l�ւ̐l�퍷�ʂƕΌ��͒����ԕς�邱�Ƃ͂Ȃ������B�@
���푈�ٔ� �@
1946�N5������1948�N�ɂ����ē��{�̐푈�ӔC��Njy���铌���ٔ����J����A��O�����{�̎w���҂炪�A�����ɂ���ƂƂ��čق��ꂽ�B�Ȃ��A���a�V�c�͍ٔ���Ƃꂽ�ق��A�w���҂ł����Ă��s�N�i�ƂȂ����҂��������B�܂��A�t�B���s���⒆�ؖ����ȂǂŔ�����̐푈�ٔ�(B�AC�����)���s��ꂽ���A�����̍ٔ��́A�ٔ��̑̂𐬂��Ă��炸�A�����̖����̐l���s�@�ɏ��Y���ꂽ�Ƃ������B�܂��A�A���R�͖����ʍU��(�������P���⌴������)���̎���@�ł͂Ȃ����ۖ@�Ɉᔽ����s�ׂɑ���ق����Ă��Ȃ����߁A���҂ɂ�����I�ȍٔ��ł������B �@
����̐���Ɛ�㏈����� �@
GHQ�͖��剻�����i�߂�Ƌ��ɁA���͂��킬�A���{����x�Ƌ��ЂƂȂ鑶�݂ɂȂ�Ȃ��悤�A�u���{��̋y�ъǗ��̂��߂̘A�����ō��i�ߊ��ɑ���~����ɂ����鏉����{�I�w�߁v�ɉ����āA��K�͂ȍ��Ɖ��������{�����B����{�鍑�̍��Ƒ̐�(����)����̂�����ŁA�V���ɘA����(���ɁA�A�����J���O��)�̔�̉��ł̍��Ƒ̐�(���̐�)���m�����邽�߂ɁA�����ێ��@�̔p�~����{�����@�̐�����s�����B�܂��A�����Ȃ̔p�~�������́A�_�n���v�Ȃǖ�p�����ɖ��剻��������{�����B���s���ē��{�l�̈ӎ����v�̂��߁A���_������������(�v���X�R�[�h�Ȃ�)�����ƂƂ��ɁA���ȏ���W�I(���W�I�����u�����͂������v��)�Ȃǂ̃��f�B�A��ʂ��A���U���ɂ�閯�剻�����{���ꂽ�B�������Ȃ���A���剻����͂��̌�̗��̐��\�z�̂��ߘH���ύX����A�x�@�\�����̐ݒu�⋤�Y�}���̌��E�Ǖ�(���b�h�p�[�W)�ɂȂ������B �@
1951�N9��8���ɒ��ꂽ�T���t�����V�X�R�u�a���ɂ��AGHQ�͔p�~����A��㏈���͏I�������B�������A��̐���Ɛ�㏈���̌��ʁA���j�F��������̊ۖ��A���q���Ǝ��q���̍s�g���A���{�����@�����_�c�ȂǍ�����������_�Ж�����{�̗��j���ȏ����Ȃǂւ̏��O���̊��Ⓦ�A�W�A�e���ɑ���㍘�O���ȂǗl�X�Șc�݂����ݏo���ꂽ�Ƃ���咣������B �@
�\�r�G�g�R�ƃA�����J�R�͒��N��������̂��A���N�l�̎�ɂ�钩�N�l�����a���̌�����F�߂��A��̂𖽂��Ēe�����s�����B1948�N8��13���̊؍��Ɨ��A1949�N9��9���̖k���N�Ɨ��������Ē��N�����͓Ɨ���������k�����Ɨ���F�߂Ȃ����͂�����A�ϏB���l�E�O�����Ȃǂ̒����������N���A�܂��Ȃ����N�푈���u�����ē�k���f���m�肵���B �@
�����{�l�̈��g���ƕ��� �@
�A�����ɍ~����\������1945�N8��14�������A�����嗤�Ⓦ��A�W�A�A�����m�̓��X�Ȃǂ̋����{�́u�O�n�v�ɂ͌R�l�E�R���E���Ԑl�����킹660���̓��{�l(�����̓��{�̑��l���̖�9%)�����c����Ă����B���{���{�͊O�n�̖M�l����̂��߂ɏ������������A�D����H�ƁA�ߗ��i�Ȃǂ��s�����p�ӂ��邱�Ƃ�����������߁A�A���R(���ɃA�����J�R)�̉������Đi�߂�ꂽ�B�������s�\���ȐH�Ǝ���ɂ��a�C��A�폟���̕A�������̕��j�ɂ���Ĉ����g������q�����n��������A�������k��(�����B)�ł́A��ނ��c���𒆍��l�ɑ������e�B����������(�����c�����{�l)�B���V�A�����R���������ق̎����ɂ��ƁA�\�A�͖��B�⊒���Ȃǂ�����{�R�����▯�Ԑl��76���l���\�A�e�n�ɋ����A�s���A��2000�����̎��e���Ȃǂŋ����J�����ۂ����B �@
�R���҂̕����Ɩ��ƌR����̌�̎c�����������ǂ����邽�߁A1945�N11���ɗ��R�ȁE�C�R�Ȃ����g������ꕜ���ȁA����Ȃ��ݒu���ꂽ�B���Ԑl�̈��g���Ɩ��ɂ��ẮA�����Ȃ����ǂ����B �@
���{��1945�N9��28���ɂ܂��A���߁A���l�A�Y��A���A���A���ցA��i�A�����A�����ہA�����������g���`�Ƃ��Ďw�肵���B10��7���ɒ��N�������R����̈��g����1�D�u�_���(���R�̕����R�l)�v�����߂ɓ��`�����̂��͂��߂ɁA���̌�͔��فA���É��A���ÁA��|�A�c�ӂȂǂł��A���g���҂̎��ꂪ�s��ꂽ�B �@
���푈�����Ɛ��⏞ �@
���퍑�ɑ��锅���Ɛ��W �@
���ؖ���(���ؐl�����a���܂�) �@
�{���Ƃ���ɐ�ċN���Ă��������푈�ł́A�����嗤�ɂ����Ē��ؖ����R�Ɠ��{�R�̊ԂŌ������U�h�킪�s���A���S���]�̋]���҂��o���Ƌ��ɁA���{�R�������̖��Ԑl�ɑ��ċs�E�E���D�������Ȃ����Ƃ���邪�A�����Ԃł͒n���K�͂Ȃǂɂ��Č����̑��Ⴊ���݂��Ă���B �@
�����m�푈���I���ƁA���ؖ����𗦂��Ă������������}�ƁA�����m�푈�O����Η����Ă����������Y�}�̊Ԃō������킪�u�������B�����āA1949�N�ɂ͒������Y�}���������Ē��ؐl�����a���𒆍��嗤�Ɏ������A�s�k���������}�͑�p�ɓ��ꂽ�B���̌��1952�N�ɁA�匠���������{�����{�́A���ؖ������u�������\���鐭�{�v�Ƃ��ď��F���A�����ɔ������̓��c���s�������A���ؖ������{�͔�������������B �@
���̌�1972�N�ɒ��ؐl�����a���̎������Ɠ��{���̓c���p�h����k���A���{�͒��ؐl�����a�����u�������\���鐭�{�v�Ƃ��ď��F���A�����Ē��ؖ����ƒf�����邱�ƂƂȂ����B�Ȃ��A���̉�k�ɂ����Ĕ������ɂ��Ă��b������ꂽ���A���ؐl�����a�����͒��ؖ����Ɠ��l�ɔ�������S�ʓI�ɒI�グ���A���{�����{�ƒ��ؐl�����a�����{�̋�������(������������)�ɂ���Ĕ����������錾���ꂽ�B����Ɂu���Ƃ��ď����������Ɓv�A�u�ߋ��̉߂��Ɣ��ȁv�Ȃǂ̗��R����A���{�����ؐl�����a���̔��W�̂��߁A���{�J������(ODA)�����{���邱�Ƃ����ꂽ�B �@
���{����1979�N���璆�ؐl�����a���ɑ��s���Ă���ODA���z�́A���݂܂ł�3���~���A�ߔN�܂ŔN��1000���~�̎��������ؐl�����a���ɉ�������Ă����B �@
�I�����_ �@
�I�����_�́A1942�N�̓��{�R�ɂ��I�����_�̓��C���h(����)�U���ɂ���āA���n���A���n�Ƃ��Ďx�z������������R66,219��(�A���R82,618��)���ߗ��Ƃ��ꂽ�ق��A���Ԑl9���l�]���߂炦���A�ނ炪���C���h�Z�������邽�߂ɐ݂����č��Ɏ��e�����Ƃ������J�𖡂�����B�Ȃ��I�����_�l���m�̈ꕔ�͒���̕ߗ����e���Ɏ��e����A�����Ŕ픚�����B�܂��A���{�R���I�����_�l�����������A�s���Ԉ��w�ɂ������n�������N�������B �@
����R������������{�́A���˂Ă���I�����_�̈������œƗ��^�����s���Ă�������̏Z���ɓƗ�����A1945�N9���ɓƗ�����^�тƂȂ��Ă����B�������A1945�N8��14���Ƀ|�c�_���錾�̒��e���ɗ\�������ƁA����3�����1945�N8��17���ɁA�X�J���m�͓Ɨ���錾�����B�������A�I�����_�R�͂����F�߂��A�X�J���m��Ɨ��^���ƂƃI�����_�R�̊ԂŃC���h�l�V�A�Ɨ��푈���u�������B���̌�I�����_�R�͔s�k���A�I�����_�̓��C���h��1949�N�ɃC���h�l�V�A�Ƃ��ēƗ����ʂ������B �@
���ƕ⏞�E���ߗ��▯�Ԑl�ւ̌������̎x�����E36���~/���a31�N(1956�N�E�����c�菑) �l�⏞�E2��5500���~/����13�N(2001�N�E��������1) �@
�I���I�����_�́A�ߗ��s�҂Ȃǂ̐^�U���s���Ăȗe�^�ŁA�����̓��{�R�l��BC����ƂƂ��ď�������(�A�������ōł�����226�l�̓��{�l�����Y)�B���Ԃ��Ȃ��̃I�����_�́A�i�`�X�E�h�C�c�R�̐N���ɂ���ĎЉ�敾���Ă����B����ȍŒ��A�ő�̐A���n���������C���h�������A�o�ς͑�Ō������B���̂��Ƃ���A�Ɨ��푈�̗v�������������{�鍑�R�ƁA�Ɨ��푈�̎w���ɂ����������{���̍s�ׂɑ���]���������A����������炭�c�����B �@
1971�N�ɁA�����m�푈�����̓��{�R�匳���ł��������a�V�c���I�����_��K�₵���ۂɂ͗������������A1986�N�ɂ̓x�A�g���N�X�����̖K���v�悪�I�����_�������_�̔������Ē��~���ꂽ�B���̌�1991�N�ɗ������������́A�T���t�����V�X�R���a���Ɠ����c�菑�ł͔�����肪�@�I�ɂ͍��ƊԂɂ����ĉ�������Ă���ɂ�������炸�A�{���ӎ`��Łu���{�̃I�����_�l�ߗ����́A�����ł͂��܂�m���Ă��Ȃ����j�̈�͂ł��v�Ƃ��Ĕ�����v�������B����ɑ��ē��{���{�́A�A�W�A��������ɂ�葍�z2��5500���~�̈�Õ����x�����l�ɑ��Ď��{�����B �@
�܂�2007�N�ɂ̓I�����_�c��@�ŁA���{���{�ɑ��u�Ԉ��w�v���Ō��Ԉ��w�ւ̎Ӎ߂ƕ⏞�Ȃǂ����߂�Ԉ��w���Ӎߗv�����c���Ȃ��ꂽ�B2008�N�ɖK�������}�L�V���E�t�F���n�[�w���O���́u�@�I�ɂ͉����ς݂����A��Q�Ҋ���͋����A60�N�ȏソ���������푈�̏��͐��X�����B�I�����_�c��E���{�͓��{���ǂɒlj��I�Ȉӎv�\�������߂�v�Əq�ׂ��B �@
�Ȃ��A�T���t�����V�X�R���a���̒������ɁA�I�����_�̐A���n�ł��������C���h�ɑ�����{�̐N�U�ɑ��āu��Q�ҁv�̗�����Ƃ�A�����ӔC�̘g���ē��{�Ɍl�����𐿋������I�����_�ɑ��āA�C���h�l�V�A���{�́A�u�C���h�l�V�A�ɑ��Ă̐A���n�x�z�ɂ͉��̔��Ȃ����Ă��Ȃ��v�Ƌ����ᔻ���Ă���B�܂��A�C���h�l�V�A�哝�̂̃I�����_�K�⎞�ɂ��A�A���n�x�z�Ɋւ��Ă̎Ӎ߂����߂Ă��邪�A�I�����_����̓C���h�l�V�A�ւ̎Ӎ߂��o�����Ƃ͖����A���l�����`���S�ʓI�ɏo�Ă���\��ƂȂ����B �@
��Ѝ��ɑ���⏞�Ɛ��W �@
���{��1952�N4��28���̃T���t�����V�X�R���a���ɂ��A���{�͑����m�푈�ɗ^������Q�ɂ��āA���{�o�ς������\�Ȕ͈͂ō����Ƃɔ���������ӔC�����B���̔���(��������)�́A�e���̋��͂Ɋ�Â����{�̕����Ȃ����Ă͎������Ȃ������B�܂����̂��Ƃ͓����ɓ���A�W�A�ւ̌o�ϐi�o�ւ̎����ƂȂ�A���{�̐�������������]�@�ƂȂ�Ƌ��ɐB���n�x�z���������̒��ŗB��A�A���n�����ꂽ���ɑ��Ӎ߂̈ӂ��������ƂƂȂ�A���ʓI�ɃA�W�A�����Ƃ̂��̌�̊O���W�Ɋ�^���邱�ƂɂȂ����B �@
�T���t�����V�X�R���a���14���Ɋ�Â��A���������߂鍑�����{�֔�����]�̈ӎv�������A����ɒ��������Ŕ��������x��������A����(���{���i�̒�A�Z�p�E�J���͂Ȃǂ̌o�ϋ���)�x�����s�����B���ɂ��ݕt�����ɂ��L���������������B �@
���̓y�Ԋ҂Ɨ̓y��� �@
���A�����ɃA�����J���R�̌����ł���_�O���X�E�}�b�J�[�T�[�i�ߊ��Ƃ���A�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ�(GHQ/SCAP)���u���ꂽ�B����A�����Q���A���}�������A�g�J���͓��{�{�y����藣����A�����J�������ɂ����ꂽ�B�����m�푈���ɐ�̂��ꂽ���}��������쐼�����A�k���̓y�̕ԊҖ��̓T���t�����V�X�R���a����������A���}��������1968�N�ɃA�����J�{�݉�������{�ɕ��A�B1972�N�ɂ́A����{�y���A�������h�쐭���̂��Ǝ��������B �������A�\�A�ɐ�̂��ꂽ�k���̓y�́A���V�A�A�M�Ɠ��{�����ӌ��ł����������A�������Ƃ��ĒI�グ����A�����ɉ������Ă��Ȃ�(�k���̓y���)�B�@

�����m�Ɖ��B�ɂ����ČJ��L����ꂽ�S���E�K�͂̏��Ր�͐��E�o�ςɑ傫�ȑŌ���^�����B���ۋ@�\�Ƃ��č��ۘA�����g�D���ꂽ�B �@
�����{�͔s�퍑�ł��邱�Ƃɉ����A�Q�[���N����A�I�풼��͍������ɂ߂��B���̓��{�́A���X�Ɍo�ςƎЉ�̕������������A����ɂ͍��x�o�ϐ������ʂ����A��ՂƂ��̂��ꂽ�B�������A�����m�푈�̕]���ɂ��ẮA���{�����Ԃł���܂��Ă��炸�A�l�X�Ș_���������Ă���B �@
������A�W�A�ɂ����ẮA���ɂ�鉢�B�����E���{�̍��͒ቺ��A�����m�푈�ɂ��o����ʂ��A�Ɨ��^�������܂�A�I�풼����e�n�œƗ��푈���u���B��q�C����ȗ��̉��Ăɂ��A���n�x�z(�鍑��`)������]�@�ƂȂ����B �@
���x�g�i���ł͑����̓��{�R���������n�Ɏc�����A�x�g�i���Ɨ��푈�ɎQ�����A�N�@���K�C���R�m���w�Z�Ȃǂ̋�����x�g�~���R�����Ƃ��ăt�����X�R�Ɛ킢�x�g�i���Ɨ��ɍv�������B��v�҂͖����_�ЂɍՂ��Ă���B �@
���C���h�l�V�A�ł͑����̓��{�R���������n�Ɏc�����A�C���h�l�V�A�Ɨ��푈�ɎQ�����A�C���h�l�V�A�R�����Ƃ��ăI�����_�R��C�M���X�R�Ɛ킢�C���h�l�V�A�Ɨ��ɍv�����A��v�������{���̓J���o�^�p�Y��n�ɍՂ��Ă���B���̌�c���������{�l�ɂ��A�C���h�l�V�A�Ƃ̉˂����ƂȂ��Ă����B �@
����p�ł́A��P�͂��������̂̒n��킪�Ȃ������A���n��ɔ�����g������`����r�I���a�ɍs��ꂽ�B���A���̌㓖�����{�����ɕς�銽�}������������ɔs�ꂽ�Ӊ�����}���{�ɂ���E��������n�܂�����߂�z����邱�Ƃɂ�蓝���̎������}���邱�ƂɂȂ�B �@
�����N�����ɂ����ẮA���{�̔s��ɔ����ݗ����{�l�̊��R�`��������g�����n�܂�B�\�A����߂���������������ԌR�ɂ�钩�N�푈��1950�N���3�N�Ԃ͂��܂�A��k���N�͕��邱�ƂƂȂ�B �@
�������嗤�ł͓��{�R��������������ɉ����Ȃǂ��āA���ؖ������{(���c)�⒆�����Y�}�R(���k����A�R�q��w�Z)�̋ߑ㉻�ɍv�������B �@
���C���h�ɂ����Ă͓��ɃC���p�[����킩��Ȃ���p�̐킢�̓C���h�ɓƗ��̉\����^���A1947�N�A�K���f�B�[�ɂ��Ɨ����ʂ����B�Ȃ������ٔ��ɂ����ăC���h�o�g�̃p�[�������͓��{���߂��咣�����B �@
���A�����J�ɂ����ẮA���{�ɂ͏����������̂̌R���Y�Ƃ̊��������͂��܂�A���̂܂܍�������̌����A���ɂ�钩�N�A�x�g�i���ł̐ԉ��̗}���ƒ��卑�ւƕϖe���Ă����B�@
�����{ �@
�����m�푈�̕]���ɂ��ẮA���j�Ƃ����łȂ��m���l�A��ƁA��ʍ������������c�_�̓I�ƂȂ��Ă���A�l�X�Ȍ����ƕ]��������B �@
1.ABCD��͖Ԃ�n���E�m�[�g�Ȃǂɂ���ē��{���ǂ��߂�ꂽ���ʂ̎��q�푈�ł������Ƃ��������A �@
2.�A�W�A�����Ă̐A���n�����������Ƃ��錩���A �@
3.���Ă̒鍑��`�҂Ɠ������A�W�A��������Ƃ��錩���A �@
4.���q�푈�ƐN���푈�̗��ʂ����Ƃ��錩���A �@
5.�č��͓��{�ɐΖ��E������̔����Ȃ���Ӊ�̒��������}�ւ����͂ȉ������p�����Ă���A�������ɕč��ƑΗ����Đ푈�p���͍ŏ����獢��ł������B�č��͓����ɑ��Č���I�ȉe���͂��J��O���玝���Ă��邽�߁A�����m�푈�͕č��̓��{�E�����o���̎�̉���ł���Ƃ̌����B �@
6.�t�����N�����E���[�Y�x���g�č��哝�̂ɂ�����(�A�d)�Ƃ��錩���B �@
������ �@
���Ăł����̐푈�ɂ��Ă͐F�X�Ȍ��������݂���B������SF��Ƃł�����j�����Ƃł�������H�EG�E�E�G���Y�́A�u�哌���푈�͑�A���n��`�ɏI�~���������A���l�ƗL�F�l��̕����������炵�A���E�A�M�̊�b��z�����v�Ƃ��āA���̐푈�������j�I�ȈӋ`�����ƕ]�����Ă���B���j�ƃA�[�m���h�EJ�E�g�C���r�[���A�u�A�W�A�ƃA�t���J���x�z���Ă������m�l���ߋ�200�N�̊ԐM�����Ă����悤�ȕs�s�̐_�ł͂Ȃ����Ƃ𐼗m�l�ȊO�̐l��ɖ��炩�ɂ����v�Əq�ׂĂ���B�p���̗��j�ƃN���X�g�t�@�[�E�\�[�����A�l��ɂ��j�㏉�߂Ă̑�K�͂Ȑ푈�ł���A����ɂ��A19���I�ȗ��̐l���`(���l���S��`)����ނ��Ă����d�v�Ȍ_�@�ɂȂ����Ƃ��Ă���B �@
�܂��A�A�����J�ł͑���E��킪�č��j��͂��߂Čo���������͐�ł��������Ƃ���A���Ƃ⍑�Ɨ��O���ے�����킢�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���A���ɑ傫�Ȕ�Q���o�����������̐킢���ނƂ������j�������g���A�����J�Ɨ��푈�̃��j�������g�ƂƂ��ɕ��ׂ��邱�Ƃ�����B�܂��A�ٕ����Ƃ̕����Փ˂̌��n����A�A�����J�l�ɂ́A���̐킢�Ō���ꂽ���{�l�̍s��(���_)�̋L�����A��ɂ��c�����Ă���A�A�����J���������e�������̍ۂɂ́AKAMIKAZE�Ƃ������t���L���Ɏg�p���ꂽ�B �@
�܂����q���e�̓s�s�ւ̓����̐������̖��ɂ��ẮA�W�����E���[���Y���͂��߁A���̐�����(�\���ȕK�v��)���c�_����Ă���B������������闝�R�̍����Ƃ��āA�l���n�тɌ��q���e�𓊉����A�З͂𗝉������~���𔗂�Γ��{�͎����ȊO�̑I���͂قƂ�ǖ��������\�����������Ƃ���������B �@
���F�m�i�����̌��J�ȍ~�A���[�Y�x���g�����̓\�A�⒆�����Y�}�ƒʂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O���m�M�ւƕς�����A���j�ς̌��������i��ł���B�܂��A���Đ푈�������N�������̂́A���[�Y�x���g���������ɂ����\�A�̃X�p�C�����ł͂Ȃ������̂��Ƃ������_�܂ŕ��サ�Ă����B �@
���A�W�A �@
���ؐl�����a��(1949�N�Ȍ�̒���)�⒩�N����(���؍��E�k���N)�ł́A�����Ƃ��ɓ��{�̐ӔC���������₤�ӌ��������B�������A�����̍��ȊO����́A���{�����Q�҂Ƃ���]�������ł͂Ȃ��A�m��I�ȕ]�����Ȃ���Ă���B���{�R�ɂ���̐���͊T�˔ے�I�ł���A���Ԓ��p�ɔ����s��(�u�тv�͑����̃A�W�A�����Ō��n�ꉻ����)�⒥���E�R�[�̐��ɂ�鋌�o�ς̍����A�_�Y�i�s��̐Ǝコ�ɔ����Q��̔����Ȃǂ��_�_�Ƃ��ċ�������(����������Q��)�B�m��I�ȕ]���Ƃ��Ă͌��n�l�ɂ�鎩�x�c�E���q�c����{�R���g�D�������ƁA���ꂪ�L�\�ō˔\���錻�n�l�̔��@�Ɍq����Ɨ��^���̒��j��S���l�ނƂȂ��Ă��������ƁA���{�R�̋����������������Ɠ��{�Z�Ƃ����A�W�A�A�т̂����A�Ƃ��ɑO�҂������ӎ��̍��g�Ɍq���������ƂȂǂ���������B�����͌��ʓI�ɕĉp�A�\�A�̉����𗘗p���ē��{��ǂ��o���A����ɉ��Đ����قƂ�Nj쒀���č��`�ƃ}�J�I�̕Ԋ҂Ŋ��S�ɊO�����͋쒀�����������B �@
�����m�푈�ő���{�鍑�ɉ�����ꂽ�x�g�i���A�t�B���s���A�}���[�V�A�A�C���h�l�V�A�A�^�C�A�r���}(�~�����}�[)�ȂǓ���A�W�A�̗��j�w�҂̑����́A�����m�푈�Ƃ���ɑ����A�W�A�e�n�̓Ɨ��푈����A�̗���Ƃ��čl���Ă���A���Ă̐폟�������{�̐푈�ӔC����邱�Ƃɂ��āA�u���Ăɂ��A�W�A�A���n�̗��j��c�Ȃ��邱�Ƃ��v�ƒf���Ă���B �@
����́A�����̃A�W�A�ɂ����đ���{�鍑�ƃ^�C������2�����ȊO�̑��ẴA�W�A�n��̓��[���b�p��A�����J�̐A���n�Ⴕ���͗ꑮ�n�ł��������߁A(1)�A���n�x�z����̉���ɑ傫����^�����Ƃ��čm��I�ɕ]�����Ă���P�[�X�A(2)���Ăɓz�ꈵ������Ă����A�W�A�̐l�X�ɁA�����{�@�ցA�R���͂𐮂������Ƃ��m�肵�Ă���P�[�X�A(3)���A�ĂуA�W�A��A���n�����悤�ƍď㗤���Ă������[���b�p�@�卑(���ɃC�M���X�A�t�����X�A�I�����_)�ɑ��āA�����{�R�̎c�}�Ƌ��ɐ�������Ƃ��D�ӓI�ɕ]�����Ă���P�[�X�A(4)���{�R�̌㏂�Ő����ɂ���������(��F�x�g�i���̃o�I�E�_�C)�̓s���Őe���I�p�����Ƃ����P�[�X�ȂǗl�X�ł���B �@
�C���h�l�V�A�ł͑����m�푈�I���A�����ɃI�����_�Ƃ̓Ɨ��푈(�C���h�l�V�A�Ɨ��푈)�ƂȂ������A�Ɨ��ɂ͎c�����{�����֗^�������Ƃ�����A���{�R��Ɨ��̉p�Y�Ƃ��ď̂����邪�A�����A���{�R�ɂ�鋭���J���ɂ��A�����̃C���h�l�V�A�̎�҂��]���ɂȂ����B���̔������ł́A�C���h�l�V�A���{�͘J���҂̑���������400���l�Ǝ咣���Ă���B �@
����p �@
�����͓��{�������ł�������p�ł͐펞���A�A�����J���O���R�ɂ���P���͂��������A�n���͍s���Ȃ������B�܂��A��p���̂���⋊�n�ł��������߁A�H�ƂȂǕ����̌��R������قǐ[���ł͂Ȃ������B�܂����̍�������Ŕs�k���A��p�Ɉڂ��Ă������������}�̋��������ɑ���ᔻ�ɂ��A���ΓI�ɓ��{�̓��������]������l������B �@
�펞�ɂ͑�p�ł���������u�蕺���x�Ȃǂɂ�铮�����s���A�����̑�p�l����n�ւƕ������B����ɂ��Ă̕]����������Ă���B�����͓��{�����ł������̂����瓖�R�̂��Ƃł͂��邪�A�s���ȋ����A�s�ł������Ɣᔻ���锽�������Ƃ�����B�u�����͓��{�����ł������̂Ɏ�������_�Ђ��J���Ȃ��͍̂��ʂł���v�Ɣᔻ������l������A���̔��Ɂu�����_�Ђւ̍��J�͏@���I�l�i���̐N�Q�ł���v�Ƃ��ē��{���{���i���Ă��锽�������Ƃ�����B�܂��A���A�R�l�����̎x���Ȃǂɂ��ē��{�l�̌R�l�R����(�u�a���ɂ����{���{����p�̓�����������������߂ɕʂ̍��ƈ����ɂȂ�������)��ʂ��Ď�舵�����Ȃ��ꂽ���Ƃɑ���ᔻ������B���ݑ�p�ł́A�����m�푈�E���̑O�i�K�̓��{��������ɂ��Ăǂ��]�����邩�ɂ��Ă͐����I�Ș_�_�̈�ƂȂ��Ă���B �@
���}���[�V�A �@
�������ō\�������}���[�V�A�ł́A�����m�푈�ɂ��Č����͑��l�ł��邪�A�T�^�I�Ȉӌ��Ƃ��ẮA���{�ɂ�铝�����A�C�M���X�E�t�����X�E�I�����_�Ȃǂ̃��[���b�p�����ɂ��A�W�A�A���n�x�z���쒀���A�A�W�A�l���g���o���������Ƃ��ĕ]��������̂�����B�Ƃ��ɁA�}���[�l�̊Ԃł́A�C�M���X�ɂ�钷���A���n�����ɂ�������Ɛ��m�����̐Z��(�����N��)�Ȃǂɂ���āA�Ǝ��̃A�C�f���e�B�e�B�[��r�������Ƃ����_���������Ƃ����B�푈�����A�}���[�l�͉p���l�Ɣ�ׂċɂ߂ĒႢ���������^����ꂸ�A������z��ł������B�����̃}���[�n�Z���͎�����x�z���鑶�݂ł���u���l�v�����G�ŁA��ΓI�ȑ��݂��ƐM���Ă����B�������A�p�����m�͑����������m�l�ł�����{�l�ɂ���Č��ł��ꂽ���Ƃ�A�C�M���X�鍑��Εs�s�_�b�̏ے��������V���K�|�[�����ח��������ƁA�C�M���X�R���œy���̂��߁A�O��I�ɔj�����d����H��Ȃǂ̓s�s�ݔ�����{�l�����Ƃ��ȒP�ɒZ���Ԃ̂����ɕ��������Ă݂������ƂȂǂ�ڂ̓�����ɂ��A�傫�ȏՌ������B���̏o�����͒����ԁA�x�z�ɊÂĂ����}���[�n�Z���̈ӎ���ς���]�@�ƂȂ�A�Ɨ��S���萶���������B �@
�ق��A�A���n�����̉ߒ��ŗ��������؋���Ȃǂٖ̈����Ƃ̍R�����o�����������Ƃ���A���[���b�p�e�����s�����s�ׂɑ���ᔻ�������A���[���b�p(���ɃC�M���X�E�t�����X�E�I�����_)�̃��f�B�A�����{�R�ɂ��푈��ᔻ���邱�Ƃɑ��ẮA���[���b�p�e�����s�����A���n�x�z�̗��j��c�Ȃ��悤�Ƃ��Ă���Ƃ��Ĕᔻ�I�ȗ�����Ƃ��Ă���B�`�����h���E���U�t�@�[�́u���B�́A���{�ƃA�W�A�f���邽�߂ɁA���{�ᔻ���J��Ԃ��Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ɣ���������A�}�n�e�B�[���E�r���E���n�}�h�́u�������ߋ��̂��Ƃ���ɂ���Ȃ�A�}���[�V�A�̓C�M���X��I�����_��|���g�K���Ƙb�����邱�Ƃ��o���Ȃ��B�c��X�͔ނ�Ɛ푈���������Ƃ����邩�炾�B�ܘ_�A���������o�������ߋ��ɂ��������Ƃ�Y�ꂽ�킯�ł͂Ȃ����A���͌��݂Ɋ�Â��ĊW��z���Ă����ׂ����B�}���[�V�A�́A���{�ɎӍ߂����߂���͂��Ȃ��B�Ӎ߂�������A�����ƎЉ�Ǝs����J�����Ă��炢�����̂��B�v�Ɣ������Ă���A�ق����b�N�C�[�X�g����Ȃǂł��M����B �@
�����A��풆�́A�����n���ɖ�킸���{�R�ɋ��͂����҂�R�������ɐg�𓊂����҂�����A���̂����R���^���ɐg�𓊂����͉̂ؐl�n�̏Z�������|�I�ɑ����A����͓����푈���e�����Ă���B�}�����̉؋��͌̍��̂��߁A�����}���{�R�ɕ��S���ʂ̉�����ɂ��܂Ȃ������B�����嗤�ɓn��R���R�ɐg�𓊂�����A���������}�g�D�Ɍ����ď�����ҁA�R���~���^���ɗ͂𒍂��l�X�������B�ؐl�n�}���[�l�̃I���E�J�e�B���Z��E�n���������́A����Y��2001�N8��13���ɖ����_�ЂɎQ�q�������A�u���́A���̗��j���ȏ��Ǝ̖����_�ЎQ�q�ւ̍R�c�̈ӎv��\������擪�ɗ��������v�u�N���푈�𐳂����푈�Ƌ����邱�Ƃ́A���̐��������ē������ƂɂȂ�v�Əq�ׂĂ���B�@
 �@
�@�������m�푈 2
1939/9/1�����A�q�g���[������i�`�X�E�h�C�c�R���˔@(�h�C�c��10�N�Ԃ̕s�N�����|�[�����h�ƒ���������1939/4/28�ɂ��̖�����ʍ�)�|�[�����h��N���A����ɑ��āA����3���ɉp�����h�C�c�ɐ��z���B�h�C�c��1940/4���k���E�����֓d������W�J�A�j�|�̐i���ŁA6���ɂ̓t�����X�����������A���[���b�p�嗤����C�M���X�R���쒀����ƂƂ��ɁA�C�M���X�{�y�㗤�ړI�̂��߂̉p�{�y��P���͂��߂��B�C�M���X�{�y��P���ăA�����J�͑�ʂ̌R���������C�M���X�ɑ���x���������߁A�h�C�c�͉p�{�y�㗤��f�O�A���������ɓƃ\������������1941/6/22�Ƀ\�A�ւ̐N�������͂��߂��B�@
�����嗤�ւ̐N�����J��Ԃ��Ă������{�́A�h�C�c�̉��i���Ńq�g���[�ɂ��V�����E�����̊m�����m�M�A�ƈɂƓ������A�p�ĂɑR����V���E�����`���̈��S���헪�����A1940/9/27���ƈɂ̎O�����������сA�A�����J�w�̏��������ہA1941/4/13���\�����������(���B�y�ъO�����S���̗̓y�ۑS�ƕs�N)�A1941/12/8�̐^��p��P�U���őΉp�Đ푈�ւƓ˂��i�B���{�̍U���Ɍĉ����ēƈɂ��A�����J�ɐ��z���A���[���b�p����ƃA�W�A�������̉����A��Q�����E�푈�́A���ƈ�(��������)�Ɓu���t�@�V�Y���v�Ō��������p�ă\��(�A������)�̑S�ʑΌ��ƂȂ����B��P�ɂ�菏��ɏ����������������̐����͒����͑����Ȃ������B�푈�̒������́A�푈���s�̐��ݓI�o�ϗ͂̍��𖾂炩�ɂ��A�₪�Đ�͂̍��ƂȂ��Č���틵�͘A���������L���ɓW�J�����B���[���b�p����́A1943/2/2�\�A�R���X�^�[�����O���[�h(�����H���S�O���[�h)�œƌR��j�������Ƃ��]�@�ƂȂ�A�h�C�c�R�͎琨�E�P�ނɒǂ����܂ꂽ�B�A�W�A�E�����m����ł�1942/6�~�b�h�E�F�C�C��ő�s�k�����������{�R��1943/2/1�K�_���J�i�����P�ނɒǂ����܂ꂽ�B1943/9/8��(�o�h���A����)�̖������~��(������ǂ�ꂽ���\���[�j�̓h�C�c�̏��͂ŃC�^���A�k���Ƀt�@�V�X�g���Ɓu�T�����a���v������)���ĘA�������́A1943/11/22�J�C����k(���[�Y�x���g�E�`���[�`���E�Ӊ��)�E28���e�w������k(���[�Y�x���g�E�`���[�`���E�X�^�[����)�A1945/2/4�����^��k(���[�Y�x���g�E�`���[�`���E�X�^�[����)�A7��17���|�c�_����k(���[�Y�x���g�E�`���[�`���E�X�^�[����)�Ȃǂ�ʂ��āA�푈���s�̐헪�Ɛ�㏈���ɂ��ċ��c���d�˂��B �@
1944/6/6�A�C�[���n���[���i�ߊ�������ĉp�𒆐S�Ƃ���A�����R���A�ΓƑ�Q������`�����A�k���m���}���f�C�[�ɏ㗤���(1941/12�A�����J�Q�펞�Ƀ\�A����Ă������)�����s�A�u�����̌ρv�ƈٖ����Ƃ��������������R�̃h�C�c�R�r�łɐ����A���[���b�p����ł̘A�������̏���������I�ɂ����B������ڑO�ɂ����A�����J�哝�̃��[�Y�x���g���A1945/4/12�W���[�W�A�B�̕ʑ��Ŕ]�쌌�ɂ�63�Ŏ�������(���N1���ɏA�C��������̕��哝�̃n���[�E�g���[�}�����哝�̂ɏA�C)����4��25����������h�C�c�ɍU���������Ă����\�A�R�Ɛ�������h�C�c�R���U�����Ă����A�����J�R���A�G���x�͔Ȃ̃g���K�E�ŏo�����A���݂������������ď������j���Ƌ��ɁA��x�Ɛ��Ȃ����Ƃ𐾂���(�u�G���x�̏o��v�u�G���x�̐����v)�B����3�����4��28�����\���[�j�����l�̃N�����E�y�^�b�`�Ƌ��ɃC�^���A�̃p���`�U���ɕ߂炦���A�C�^���A�k���̏����̃h���S�ŏ��Y����ăK���[�W�̂���ɂ邳��A2�����4��30���q�g���[���x�������̒n�����ň��l�G���@�E�u���E���Ǝ��E�A5��8���h�C�c���������~���ɒǂ����܂ꂽ�B���{��1945/4/7���{�C�R�̏ے��ł������s����́u��a�v�������A6��23�������ŎS�s�A�����E���l�E���𒆐S�Ƃ����s�s��B�|29�̋�P�ŏœy�Ɖ��������A�R���͖��d�Ȗ{�y����(�ꉭ���ʍ�)�����сA�]����ςݏd�˂Ă����B8��6���L����9������ւ̌��������ƃ����^����ɂ��ƂÂ�8���̃\�A�̎Q��(9���\�A�R�k���E�k�N�E�����N�U)�ŁA����15���|�c�_���錾������E�������~���A9��2���~�������ɒ��A��Q�����E���͏I�������B�@
��Q�����E���ł̎��҂́A�e�����{�̌������\�ɂ��A�A���������C�M���X��40���l�A�t�����X��25���l�A�I�����_��23���l�A�A�����J��55���l�A�\�A610���l�ȏ�A����1�A000���l�]�A�������������{310���l�ȏ�A�h�C�c��325���l�A�C�^���A��38���l�ɋy�сA�l�ގj��ő�̂��̂ł������B�@
 �@
�@�������m�푈 3
�֓��R���m�����n�������Ń\�A�E�����S���R�Ɛ퓬�������Ȃ��Ă��邱��A1939/8�h�C�c�ƃ\�A���ƃ\�s�N�������B�h�C�c�͓��{�E�C�^���A�ƃ\�A�ɑR���邽�߂ɖh�����������ł����̂�����A���{�ɂƂ��Ă͕s���B�����u��Y���t�͉��B��͕��G����Ɛ������đ����E���A�����M�s���t�ɂ�������B�h�C�c�́A�C�M���X�E�t�����X�Ƃ̊J��Ɍ����������Ƃ��ă\�A�Ƃ̒�g�Ƃ�����p���ꎞ�I�ɍ̗p���������̂��Ƃ������B�@
1939/9�h�C�c���|�[�����h�ɐN���A����ɑ��ăC�M���X�E�t�����X���h�C�c�ɐ��z�����A���B�푈���n�܂���(��Q�����E���Ƃ�����)�B�������t�Ƒ����ē��������t�́A���B�푈�ւ͉�����������푈�̉����ɐ�O����Ƃ̑ԓx���Ƃ����B�@
����i�_�̍��܂�@
1940/1���Ēʏ��q�C���������ƁA�R�������̊m�ۂ�����ɍ���ɂȂ����B���N3������������ȂƂ���V���������������{���싞�Ɏ�������A��⋂��m�ۂł��Ă��Ȃ����{�R�̕������D�E�c�s�s�ׂ����₽���A��̒n�s���Ɏ��s���Ă���ŁA�����푈���I��������L���Ȏ�i�Ƃ��Ȃ肦�Ȃ������B���̂����C�M���X�E�A�����J���d�c�̒����������{�ɑ��ē���A�W�A�o�R�Ŏx�������߂Ă���(���̌R�������̎x�����[�g�����Ӄ��[�g�Ƃ��)�B�����푈�̉����ւ̌��ʂ��������Ȃ��̂Ȃ��A���Ӄ��[�g�̎Ւf�ƐΖ��Ȃǂ̎����̊m�ۂ��߂�������A�W�A�i�o���句���铮��(��i�_)�����܂�B�Ƃ�킯�A���[���b�p�Ńh�C�c�R���I�����_�E�t�����X���~���������A���R���h�C�c�Ƃ̒�g�����E����A�W�A�i�o���咣���ĕē����t�ƑΗ������B

���V�̐��^���̊J�n�@
�߉q������́A�ꍑ��}�̐��ɂ��ƂÂ��V���������g�D������A�������b�Ƃ��ċ��͂ȓ��t��g�D�A�푈�E�����ɂ킽�铝��I�Ȏw�������������悤�Ƃ����B���̋߉q�V�}�Â��肪�V�̐��^�����B����ɂ͗��R��v�V���������ꂼ��̎v�f����ϋɓI�ŁA���}�̂Ȃ��ł��������}�̉������句���铮�������܂��Ă������B���������Ȃ��A���R�͌R����b�������𗘗p���ĕē����t���E�ɒǂ����ށB���r�Z���������E�����A��C�𐄑E���Ȃ������̂��B1940/7�߉q���������t��g�D���A�Εċ��d�h�̏����m�E���O���A�����p�@�������ɏA�C����(��2���߉q�������t)�B�@
���吭���^��̐����@
��2���߉q���t����������ƁA���ׂĂ̍��@���}������I�ɉ��U���A�߉q�ɂ��V�}������҂��]�B��������1940/10�߉q�𑍍قƂ��đ吭���^��������ꂽ�B����͐��{�̌����`�B���邽�߂̋@��(��Ӊ��B�@��)�ł���A�̂��ɂ͒�����E������E�בg�������g�D�ɕҐ����ꂽ�B���̌��ʁA�߉q�炪�\�z���Ă����ꍑ��}�̐����������鐭���g�D�̌����͎������Ȃ��������̂́A�鍑�c��͍s���̕⏕�@�ւƂȂ��Ă��܂����B1940/10�Y�ƕ�̒����g�D�Ƃ��đ���{�Y�ƕ�n�������ȂǁA�e����̏��c�̂̓������i�B�@
�����w�Z�̍����w�Z�ւ̉��́@
1941���w�Z�������w�Z�Ɖ��̂���u�c���b���̗����v���߂����ꂽ�B���̂Ƃ��`�����炪8�N�ɉ������ꂽ���A�푈�̌����ɂƂ��Ȃ��Ď��{����������A�������Ȃ������B

���k������i���@
��2���߉q���t�͑哌�����h���̌��݂��f���A�����푈�̉��������߂ē�i��{�i���������B�t�����X�̃C���h�V�i�̖k���n����R����̂����B�@
�k������i��/1940�n�m�C���ӂɌR����i���@
�@���ƈɎO������/1940���{�S�������m�E�O���@
�@���؊�{���/1940�������̓싞���{�����F�@
�@���\�������/1941�����m�E�O���ƃ����g�t�O���@
�@���Č��̊J�n/1941�쑺�g�O�Y���đ�g�ƃn�����������@
�k������i���ɂ�����A�A�����J�Ƃ̊W�����������邱�Ƃ��x�������߉q���t�́A1940/9���ƈɎO�����������сA�h�C�c�E�C�^���A�Ƃ̒�g�����ɂ���ăA�����J�������������A�����Ԃ̑Η������邽�߁A1941/4������Č����J�n�����B��i��i�߂邤���ł̖k������̌R���I���Ђ���߂邽�߁A1941/4���\�����������B�����O���́A���ƈɎO���R�������Ƀ\�A���������l�����������������A����ɂ��A�����J�����|���悤�Ƃ����\�z�������Ă������A���łɓƃ\�W�͌����ƂȂ��Ă����B�@
���ƃ\�푈�̊J�n�@
1941/6�h�C�c���˔@�\�A�ɐ��z���A�ƃ\�푈���n�܂����B���E�R������傫���ϓ������B����ɑ���2���߉q���t�ƌR���́A7���V�c�ՐȂ̂��Ƃŏd�v����̂��߂̉�c(��O��c)���J���A����L���ɂȂ�\�A�ɐN�U����/��i�������߂đΉp�Đ���������ƌ��肵���B�����ė��R�͊֓��R���퉉�K�̂��Ƃɖ��B�ɕ��͂��W�����������A�\���͍s�g�͒��~���ꂽ�B�@
�����Č��̓�q�@
���Č��͎O�������̉�������{�R�̒�������̓P�ނȂǂ̖����߂����ē�q���A�Εċ��d�h�̏����O�������̑ł�����咣�����B����ɑ��A���p�����咣����߉q�́A����������t�����E�������Ȃ��A�����O�����̂����������ő�3�����t�𐬗��������B�����p�������邽�߁A�A�����J�ɍD��ۂ�^���悤�Ƃ����B�Ƃ��낪�A��3���߉q���t���������7�����A���łɌ��肳��Ă����암����i�������s�����ƁA�A�����J�͓��{�ɑ���o�ϐ��ق����������B�Ζ��A�o��S�ʋ֎~���A�ݕē��{���Y�𓀌������̂��B�C�M���X�E�I�����_�̓��C���h���ǐ��������߁A�W���[�i���Y���͂`�a�b�c��͐w�Ə������č����̊�@�������������B��3���߉q���t�ƌR���́A9����O��c�Łu�鍑�������s�v�́v������A(1)���Č������̊�����10����{�Ƃ��A(2)10�����{���߂ǂɂ��ăA�����J�E�C�M���X�E�I�����_�Ƃ̊J�폀���𐮂��邱�ƂƂ����B

�����Č��̌���@
10����{�A�n���������������{�R�̒���(���B������)�E����̓P�ނ�v�����A���Č��͊��S�ɍs���Â܂����B���łɁu�鍑�������s�v�́v�̒�߂��^�C�����~�b�g���������Ă����B��3���߉q���t�́A���̑Ì����咣����߉q��ƓP�������ۂ��铌�𗤑����Η��������E�����B��p�ɂ́A�،ˍK�����b�̐����ɂ��A�Εčŋ��d�h�̓����p�@�������A�C�����B���_�҂ɂ���ĊJ��_��}������Ƃ����q���������B������t�ƌR���́A11����O��c�œ��Č����s�����̏ꍇ�ɂ�12�����{�ɕ��͂����邱�Ƃ����肵���B����ɑ��āA�A�����J�͖��B���ψȑO�̏�Ԃւ̕��A��v������(�n���E�m�[�g)�A������̍Ō�ʒ��ł���A�A�����J�͓��{����J��ɓ������Ƃɂ���Đ푈�̖����邱�Ƃ��˂���Ă����B12���P����O��c�ŊJ�������A8�����{�R�̓n���C�^��p�ƃ}���[��������P�U�������B�A�����J�E�C�M���X�E�I�����_�ɑ��Đ��z�����A�����푈���܂߂đ哌���푈�Ə̂����B�h�C�c�E�C�^���A���O���R�������ɂ��ƂÂ��ăA�����J�ɐ��z���A1942/1�A�����J�E�C�M���X�E�\�A�E�����Ȃǂ������錾���ĘA����(the United Nations)���������A�S�ʓI�Ȑ��E�푈���n�܂����B�@
������̏����@
����͓��{���ɗL���ɐi�B�C�M���X�̋��_���`�E�V���K�|�[�����ח������A1942�t�܂łɃt�B���s���E�r���}(���̃~�����}�[)�E�W�����ȂǁA����A�W�A�E�������m�n����̂����B���������N�Ă����ǂ��]�������B�~�b�h�E�F�[�C��œ��{�C�R���A�����J�C�R�ɎS�s�A�܂��A���{�R���\�����������̃K�^���J�i�����ւ̏㗤�����J�n�������A�܂��Ȃ��A�����J�R�̔��U���͂��܂����B1943/2���{�R�͂��ɃK�^���J�i��������P�ށA�Ȍ�A��ǂ̎哱�������S�ɘA�����R�ɒD����B���傤�ǃh�C�c�R���X�^�[�����O���[�h�Ń\�A�R�ɔs�k�����̂Ɠ������ł���A1943/8�ɂ̓C�^���A���~�������B �@
���哌�����h���̎��ԁ@
���{�͓���A�W�A�E�������m�̍L��Ȓn����̂���ɍۂ��A���Ăɂ��N������̃A�W�A�̉���E�哌�����h���̌��݂��句�������A��̒n�ł͐����҂Ƃ��ČN�Ղ��A�R�������{���ĐΖ��E���E�S�z�ȂǏd�v�����̊m�ۂƌ��n�R�̎�����D�悳�����B�R���S���҂͌R�[�𗐔����ĕ�����������A���n�Z�����R�p�H���ɘJ���҂Ƃ��ċ����J���������肵���B�^�C�ƃr���}���ނ��ԌR�p�S��(�זɓS��)�̌��ݍH���ɂ́A�J���҂����łȂ��A�����R�̕ߗ����������ꂽ��ɁA�ȏ����̂Ȃ��ōH�������s���ꂽ���߁A�����̘J���ҁE�ߗ������S�����B��ǂ̈����ƂƂ��ɁA���S��c������K�v�����̐����]��������B1943�r���}�E�t�B���s����Ɨ������A����ɃC���h�̓Ɨ����߂����Ď��R�C���h�����{�������������B�����ē��N11���A�����̐��{�ɉ����Ė��B���A�������������{�A�����ă^�C�̑�\�҂𓌋��ɏ����đ哌����c���J�Â����B��̒n��̌������֎����悤�Ƃ����̂��B�Ƃ͂����A�}���[��I�����_�̓��C���h(���܂̃C���h�l�V�A)�ɂ��Ă͏d�v�����̋����n�Ƃ��ē��{�̂ɕғ�������j���Ƃ��Ă���A��̒n�悷�ׂĂ̍��ƓI�Ɨ���F�߂��킯�ł͂Ȃ������B�Ɨ���F�߂炽�r���}�E�t�B���s���ł����{�̌R���I�x�z�Ƃ������Ԃ͕ς��Ȃ������B���̂��߁A��̓����͓��{�R�ɋ��͓I�������e�n�̖��O���A���҂����łɑ���A�������ɍR���̌X�������߂Ă����B

�����^�I���@
1942/4������t�͑��I���̎��{�ɍۂ��A���҂̐��E��������(���^�I��)�B���I�c���̂قƂ�ǂ��܂ޗB��̐����c�̂Ƃ��ė��^����������������A�ꍑ��}�̐����`���I�ɐ������B�@
�������̐푈�ւ̑������@
�푈�̊g��ƂƂ��ɒ����̋����E�R�����Y�̊g��ɂ��J���͂��s�������B�����w�Z�ȏ�̊w���E���k���ΘJ�����A�����̏��q�����q��g���ɕҐ����ČR���H��Ȃǂɓ������A���N�l���̉��̒����l�������A�s���čz�R�Ȃǂœ��������B��ǂ̈����ɂƂ��Ȃ��A1943��w���ƍ����w�Z�E���w�Z���k�̒����P�\����~����A�����K��̕��Ȍn�w�����R�ɏ��W���ꂽ(�w�k�o�w)�B����ɁA���N���p�ł����������������ꂽ�B���N�ł�1938�ɓ��ʎu�蕺���x�A1944�����������{����A��p�ł�1942�ɓ��ʎu�蕺���x�A1945�����������{���ꂽ�B�������A�D���̑�ʑr���ɂ��A����A�W�A�̐�̒n����Ζ��E�S�z�Ȃǂ̎����������ɗA�����邱�Ƃ��s�\�ɂȂ�A���{�o�ς͒v���I�ȑŌ����������B1944������̖{�y��P�ɂ��s�s�ł̍��������͔j�]�A�����w�Z�����̑a�J(�w���a�J)�������Ȃ�ꂽ�B

����ǂ̈����@
1944/�V�}���A�i�����̃T�C�p�������ח��B����͓������A�����R�̋�P�����ɓ��������Ƃ��Ӗ����A���{�̔s��͕K���ƂȂ����B���̌��ʁA���a�V�c�����ΓI�ȐM���Ă���������t�������E�A������ė��R�R�l���鍑���Ɖ����h�̊C�R���V�ē����������t��g�D�����B1944������}���A�i��n�̂a29�ɂ��{�y�������J�n����A1945/3�ɂ͓�������Ԃɖ����ʔ�����������(�������P)�B1945/4����{���ɃA�����J�R���㗤(�����)�B���{�R�́A���w�Z�E�t�͊w�Z�̒j�q���k��S���c���ɑg�D���Ď���ɓ����A�������w�Z�E���q�t�͊w�Z�̏��q���k���Ђ߂�蕔���ȂǂɕҐ����ď]�R�Ō�w�Ƃ��ē��������B�܂��A�A�����J�R�ɂ��Z���̖����ʎE�C�A���{�R�ɂ��Z���s�E�E�W�c�����ւ̗U���Ȃǂ������Ȃ��A�����̔�퓬�����]���ɂȂ����B�����̔s�k���͂����肵���i�K�ŁA���a�V�c���I������ӂ��A1945/4������t�ɂ�����ė�؊ё��Y���t�������B�ꉭ�ʍӂ��f���Ė{�y����̑Ԑ��𐮂��A�V�c���쎝�Ɍ����ďI��H�삪�i�߂�ꂽ�B����A���[���b�p�ł�5���h�C�c���������~�������B�@
���A�����̑Ή��@
�A�����̖ڕW�͓��{�̖������~���������B �@
�J�C���錾[1943/11]��(���[�Y���F���g)�p(�`���[�`��)��(�Ӊ��)�Γ��̓y���j(���N�̓Ɨ��Ȃ�)���{�̖������~���܂ł̍s���̑��s��\���@
�����^����[1945/2]�ĉp�\(�X�^�[����)�h�C�c�~����2-3�����ȓ��̃\�A�̑Γ��Q��E�슒���Ɛ瓇�̃\�A�A��������@
�|�c�_���錾[1945/7]��(�g���[�}��)�p�� ���{�ɖ������~�������� �@
�����{�̖������~���@
�|�c�_���錾�̔��\�ɑ��ė�ؓ��t���َE�Ƃ̑ԓx���Ƃ�ƁA�A�����J���L���E������q���e�𓊉��A�\�A�����z�����Ė��B�E���N�E�������Ő瓇�ɐN�U�����B��ؓ��t�ƌR����8��14����O��c�Ń|�c�_���錾��������肵�A�A�����ɒʍ������B�����t�Łu�I��ُ̏��v��������ꂽ�B����ɂƂ��Ȃ��ė�ؓ��t�������E���A�c�����v王{���F�������t��g�D�����B�R�����̎��_�҂̕s����s��ɂƂ��Ȃ������̓��h��}����Ӑ}���珉�̍c����Ǔ��t���g�D���ꂽ�̂��B9��2���~�������ɒ���A�A�����R�ɂ����{��̂��n�܂�B
 �@
�@�������m�푈 4
1938�N8���Aḍa������1����ɏ�C�ŐV���ȕ��͏Փ˂��N�������B������C�ɂ́A���ď�������{�����v�����d�E������A3���l�̓��{�l����炵�Ă����B���̋������ی��ړI�Ƃ�����{�R��5000�A�Ӊ�͂�������鐸�s�𑗂����B���{���R��10�����闤�R�𑗂�A��͈�C�Ɋg�傷��B�Ӊ�̉��ɂ�30�l�ɏ��h�C�c�̌R���ږ�c�������B���[�_�[�͕��������̈琬�̑��l�҂Ƃ��Ēm���ނɂ��u�������̎m�C�͍����B�O��R��̍\���͐����Ă���v�B�����A���{�Ɩh�����������ł����h�C�c�A���̈���œ��{�ɓG���钆���ɌR���x�����s���Ă����B�i�`�X�h�C�c�́u���{�Ƃ̋����W�͈ێ�����B����������Ȃǂ̒����ւ̗A�o���A�U���ł�����葱����v�Ƃ����B�h�C�c�͑��b�Ԃ�퓬�@�Ȃǂ���ʂɗA�o�A�h�C�c���w�����b�g�����Ԃ�A�R���P�����钆�����m�����ɁA�ŐV����̎g�������������s�������琬�����Bḍa�������̔��N�O�ɍ쐬���ꂽ�n�}�ɂ��A���̉��̒n��A�싞�A��C�ł͂��łɖh��w�n���z����Ă����B��C�̐��ɖh�����~���A��s�싞�����̐���~���Ă����̂ł���B�Ӊ�Γ��L�u�����k���ł�����푈�����Ă��N�����ڂ��܂���B���ۓs�s��C�Ő푈������A���ې��_�����N�ł��܂��v�u�A�W�A�̖��́A���[���b�p�A���E�e���Ƌ����ʼn�������B�����āA�N���ғ��{�����u����v�B

�Ӊ�̓A�����J��[���b�p�ɓ������������߁A��ǂ̑ŊJ��}�낤�Ƃ����B�푈�̊g�������鉢�ď������A�u�����b�Z���ō��ۉ�c���J�����Ƃ��Ă����B�Ӊ�͂��̏�œ��{�̕s������i���A���ّ[�u�������悤�Ƃ����B�쉈���Ɍ��u�l�s�q�Ɂv���ő�̌���n�ƂȂ����B���̑q�ɂ̑Ί݂ɂ͉��ď����̑d�E���������B���ď����̃��f�B�A�́A�l�s�q�ɂ̍U�h����B�e�����E�ɓ`�����B���ꂱ�����Ӊ�̑_���������B�Ӊ�̌��t�u���̏ꏊ�����炳����B��������A���E���̐l�X�Ɋ�����^���邱�Ƃ��ł���v�B�������A�u�����b�Z���ŊJ���ꂽ���ۉ�c�́A�Ӊ�̊��҂𗠐�A�e���̓��{�Ƃ̊W����������I�Ȃ��̂ɂ���o�ϐ��ق̔����ɁA���ݐ낤�Ƃ��Ȃ������B�l�s�q�ɂł̌����4���ԂŏI���A�Ӊ�̓h�C�c���̐��s�������������B���{�R��11����{��C���ח��������B���̕ӂň�x�������҂��镺�m�̎v�����悻�ɁA�l���n�i�ߊ���͐�n�g��ɓ����o���Ă����B11��22���i�ߊ��͎Q�d�{���ɓd��𑗂����u���ߐ��ɌR�𗯂߂邱�Ƃ͐�@���킷��̂݁B�싞�Ɍ������nj��͉\�Ȃ�v�B��C�Ɏ�s�싞���U�ߗ��Ƃ����Ƃ�i�������B�Q�d�{���͐��ߐ�����nj��́A���߈�E�s�ׂł���Ƃ������A���n�Ɍĉ�����r��핔���͏��a�V�c��O�ɂ�����{�c��O��c�ŁA�ƒf�Łu�V���Ȃ鏀���Ԑ��𐮂��A�싞���̑����U�����邱�Ƃ��l�����Ă��܂��v�ƕ����B


�Ӊ�͋��������A�V������s���d�c�ƒ�߁A�O��R��̌��ӂ�V���Ɂu���͋������ĖŖS���������Ď��ʂ��Ƃ�I�ԁv�B�싞�ח��͑����̊O���l�ɂ���Ėڌ�����A���ێЉ�ɔg����L���Ă������ƂɂȂ�B����h�C�c�O�������A�A�����J�l�鋳�t�ɂ���ĎB�e���ꂽ���������t�B�����Ƌ��ɁA�Ռ��I�ȗ��j�I�����Ƃ��Ė{���ɑ����̕��𑗂����B�q�g���[�͕�������ꂽ1938�N�R���ږ�c�̒����h����ł���A���{�Ƃ̊W��[�߂������B���̃t�B�����̃R�s�[���A�����J�ɓn���Ă����B�����A���{�R�̐��͊g��ɐ_�o���点�Ă����A�����J�ł́A���̃t�B�����̏�f��J��Ԃ��s��ꂽ�B�u���l���̖��Ԑl�����[�v�Ŕ����A��݂�r�̂ӂ��A�n�ɘA�s����A�@�֏e��e���A��֒e�ŎE���ꂽ�v�B���̃t�B�����Ƀ��f�B�A�����ڂ��A���{�̎c�s�s�ׂ����L�������ӂꂽ�B�@
�Ӊ�̓A�����J�̐��_�ɒ��ځA���f�B�A���͂��߃A�����J�Љ�ւ̓������������߂Ă����B�A�����J�ł͓��{���i�̕s���^�����L����A1939�N���{�͓��{�Ƃ̖f�Ղ𐧌����鐭����Ƃ�n�߂�B�ё����锪�I�R�����{�R�ɑ���Q�������W�J�B�@
�싞�ח�����4�N���1941�N�A���{�̓A�����J�Ƃ̑S�ʐ푈�ɓ˓��A���������{�ɐ��z������B���{��ḍa������n�܂������ς��琢�E�푈�ւƓ˂��i��ł������B�����͈ꌂ�œ|����Ƃ�����������ʂ��A�����ČR�̓Ƒ����~�߂邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������̂�����B���{�̐���̓A�W�A���瑾���m�ւƊg�債�A�����͎��X�Ɛ���֓�������Ă������B
 �@�@
�@�@�������m�푈 5 / ����
�ČR��A�������͑S�č����I�Ŋ����ɍ��𐋍s���Ă���悤�ȃC���[�W�����邪�A�ނ�������l�Ԃʼn��L��4�C��ő����̃~�X��Ƃ��Ă���B�@
�^��p��P/�U���̗\���͗����Ă������A���{�R���y�����߂��呹�Q�������B�~�b�h�E�F�C�C��/�~�b�h�E�F�C��n�q��������ɂ����������������B�\�������C��/�{���Ȃ�A���D�c���ƑS�ł��Ă���C��B���C�e���C��/�����Ɋ��S�Ɉ���������A���C�e�p�̊�@�������B�@
�����Ȑ킢���Ŕs�S���Ă��������Ƃ�R���͕ʂɗ��j�㒿��������ł͂Ȃ��B�ߑ��̂��ߎ����҂̐������Ⴂ�ɑ����Ȃ��w�̔ߌ��ƂȂ����B�푈�Ƃ͍���̌J��Ԃ��ŁA�ߎ��̐��ƁA���̉ߎ��̏����ɂ�菟�s�����܂���̂ŁA���܂�ɂ������Ȑl������Ƃ�����B�@
�s�K�Ȑ푈�Ŗ�300�������̖�������ꂽ�B���̂����������̎��҂�1944-45�ɂ����Ă̂��̂ł���B1945�ɓ����Ă���̓��{�̐펀�҂́A�����m�푈�̎��҂̔����𐔂��A������20���A�������P��10���A�L���A�����15���ȂǁA�ȒP�ɋ�����������300���l�̑��������߂�B���{�ɃA�����J�ɍU�ߍ��݃��V���g�����̂�����̍��͂��Ȃ��̂́A���R�ł����������Ă����͂��ł���B���̏�Ő푈�����s����̂Ȃ�A���I�푈�̂悤�ɂ͂�����Ƃ������Z�ƖړI�������Ă����Ȃ��ׂ��ł������B�@
�푈���̌R�̍s���ɂ��^�₪�c��B�����ɑ���ɒ[�Ȕ閧��`�͌R����v�̎v�z����傫������A�������������̑�{�c�����́A�R����Ǝ��g����������f����点�錋�ʂƂȂ����B
 �@
�@�������̐�
�����푈����哌���푈(�����푈�y�ё����m�푈���܂ސ푈�̓��{���{�̌ď�)�ɂ����Ă̐펞���E���ϒ��ɐݒu���ꂽ����{�鍑���R����ъC�R�̍ō������@�ւł���B�V�c�̖���(����)���{�c����(��{�c���R������(�嗤��)�A��{�c�C�R������(��C��))�Ƃ��Ĕ��߂���ō��i�ߕ��Ƃ��Ă̋@�\�����B �@
�����푈�Ɠ��I�푈�Őݒu����A�펞�̏I����ɉ��U�����B�x�ߎ��ςł͐펞�O�ł��ݒu�ł���悤���߂��A���̂܂܁A�哌���푈�I��܂ő��������B�A��������̓C���y���A���E�W�F�l�����E�w�b�h�N�H�[�^�[�Y(Imperial General Headquarters)�ƌĂꂽ�B �@
�哌���푈�����ɂ͓��{�̔s�F���Z���ɂȂ�ɂ�āA�����틵���L���ł��邩�̂悤�ȋ��U�̏�u��{�c���\�v�Ƃ��ė����ꑱ�����B���̂��Ƃ��猻�݂ł́A���͎҂����Ȃ̓s���̗ǂ��悤�ɏ������ċ��U�̏��M���邱�Ƃ𝈝����āu��{�c�v�u��{�c���\�v�Ƃ����\�����p������B �@
���T�v �@
���R����ъC�R���x�z���ɒu���펞���݂̂̓V�c�����̍ō������@�ւƂ��āA1893�N5��19���ɒ��ߑ�52���펞��{�c���ɂ���Ė@�������ꂽ�B�����푈�ɂ������{�c��1894�N6��5���ɐݒu���ꂽ�B1893�N����̊C�R�R�ߕ����ɂ�蕽���ɂ����Ă̂ݗ��C�R�̌R�߂��Γ��ƂȂ�������ł���A�펞��{�c���ɂ��펞�ɂ�����C�R�̌R�߂����������Ă������R�̎Q�d�����݂̂��������Ƃ��ꂽ�B���N9��15���A�푈�w���̋��_���L���ɒu�����߂ɓV�c���ڂ�A��{�c���L���Ɉڂ���(�L����{�c)�B1896�N4��1����{�c���U�ْ̏��ɂ���ĉ��U�����B �@
���I�푈�ɂ������{�c��1904�N2��11���ɐݒu���ꂽ�B���̂Ƃ���1903�N�̑�{�c���̉����ɂ��A�펞�ɂ����Ă��R�ߋ@�ւ��Γ��ƂȂ������Ƃ���A���R�̎Q�d�����A�C�R�̊C�R�R�ߕ����̗����Ƃ��ɖ������Ƃ��ꂽ�B1905�N12��20�����U�����B �@
�����푈(�x�ߎ���)�͐����ɂ͐푈�ł͂Ȃ��������߁A1937�N11��18���A��{�c�ݒu��펞�Ɍ��肵�Ă�����{�c���͒��ߑ�658���ɂ���Ĕp�~����A�V���ɐ펞�ȊO�Ɏ��ςł��ݒu�\�ɂ����u��{�c��(���a12�N�R�ߑ�1��)�v�����肳�ꂽ�B1937�N11��20���A��{�c���ݒu����A���̂܂ܑ哌���푈�Ɉڍs�����B�푈�����ɂ͒���s���㒬�Ɍ��݂��ꂽ�n�����ւ̑J�s���v�悳�ꂽ��(�����{�c)�A�������̂܂I����}���A1945�N9��13���ɔp�~���ꂽ�B �@
���g�D �@
��{�c�̑g�D�̎��̂͂قƂ�ǂ��Q�d�{���y�ьR�ߕ��̑g�D�ł������B��{�c��c�͓V�c�A�Q�d�����A�R�ߕ������E�Q�d�����E�R�ߕ������E�Q�d�{����1����(��핔��)�E�R�ߕ���1�����E�Q�d�{�����ے��E�R�ߕ����ے��ɂ���č\�����ꂽ(���R��b�ƊC�R��b�͉�c�ɗ����������͂Ȃ�����)�B��{�c�̑g�D�ɂ͓��t������b�A�O����b�Ȃǐ��{���̕����͊܂܂�Ȃ�(��O�Ƃ��āA������t���Ɏ���{�c�̃����o�[�ƂȂ������Ƃ�����)�B��{�c�Ɛ��{�Ƃ̈ӎv�����ړI�Ƃ��đ�{�c���{�A����c���ݒu���ꂽ�B �@
�܂���{�c�͐�ʂɊւ���L����s���Ă������A1943�N���Ոȍ~�̐틵�̈����ɔ������{�R���s���𑱂���ƁA�^����`���Ȃ��Ƃ����A������u��{�c���\�v���s�����B �@
�Ȃ��A�����̑��𗬂͏��a���͂��܂萷��ł͂Ȃ��A����ɂ����ۂ̎Q�d�����n���y�ѓG�R�̌X�����y�����Ĕc�����Ȃ��܂܍��𗧈Ă���Ƃ������ȂB�@
 �@
�@���V�r���A���R���g���[�� 1
���{��1878/�Q�d�{������̐���ɂ��A�Q�d�{���܂�R���̓Ɨ������������B���̈Ӗ��͌R��(�R�����w���������邱��)�Ɋւ��Đ��{�◤�R�Ȃ̊���F�߂Ȃ����Ƃł���B���R�Ȃ͌R��(�R���̈ێ��A�Ǘ��Ȃ�)�݂̂�S������@�ւƂ���A1893/���̊C�R�łƂ�����C�R�R�ߕ�(�R�ߕ�)���ݒu���ꂽ�B1900/���C�R�Ȃ̑�b�͌����̑叫�������Ɍ���Ƃ������x(�R����b������)�����肳�ꂽ�B����͐��{����t�̌R���������̔ے�A�V�r���A���R���g���[���̔ے�ł���B�����R�����{�ɑ���s��������A���C�R��b�̎��E�ɂ���ē��t���Ԃ����Ƃ��ł��鎖�ɂȂ�B���̈���Ƃ���1930�̃����h���R�k��c�ɂ����āA�l�����C�R�̔����������ČR�k�Ăɒ������߁A�����s���Ƃ���C�R��b�ƌR�ߕ��������E���A���̂��߂ɓ��t���|�ꂽ(���������Ɩ��)�B���̎����ɂ��A���̌�R�ɑR�ł��鐭���Ƃ��������A5�E15����(1932)�Ō��{�B���ÎE����A2�E26����(1936)�ł͐ē�������b�A���������呠��b���ÎE����A���c���t�������E�ɒǂ����܂�鎖�Ԃɋy�сA�܂��܂��C���̂��鐭���Ƃ͌��������B�����̍L�c�O�B�́A���R�̗v���ł���O���Ɩ@���̐l������������鎖�ɂ��A����Ƒg�t�ł���L�l�������B���C�R�̉����j�~�ł��Ȃ��������{�ɍő�̐ӔC�����邪�A�˔��A�R�������S�ƂȂ��Ă��鐭�{�̐����ߒ����l����Ɠ��R�Ƃ�������B�˔��Ƃ͎�ɎF���A���B�̏o�g�҂ō\�����ꂽ�����̐��E�̐��͂��w���A�R���ɂ����Ă��������͂��������B�C�R�͎F��������A���R�͒���������Ƃ����A�����ېV�ȗ��̐��͐}�ł���B�C�R�̗̑��͎R�{�����q�ŁA���R�͎R�p�L���ł���B�R�{�͔�r�I�����Ȑ��i�Ƃ���邪�A�R�p�͒��B�n�̌R�l��D�����A����ȊO�̂��̂ɑ��Ă���߂ė�W�ł������Ɠ`������B
 �@
�@�����������E�V�r���A���R���g���[�� 2



�u�����v�Ƃ�����͓��{�����@�𐧒肷��ۂɑ���ꂽ���t�ł���B�����c��ł́A��9���Ɋւ��Ĉ��c�C�����s�Ȃ�ꂽ���A���̏C���ɂ�莩�q(self-defence)�������Ƃ����R����(armed forces)�ۗL�̉\��������Ɗ뜜���������ɓ��ψ���A���c�C�������������civilian����������悤�ɋ��߂��B�����������̓��{��ɂ�civilian�ɑΉ�����ꂪ�Ȃ��������߁A�M���@�̐R�c�ł́u���݁A�R�l�ł͂Ȃ��ҁv�ɑ��������Ƃ��āu�����v�u�n���l�v�u�}�l�v�Ȃǂ̌�₪������ꂽ�B�u�����v�ł͊�����`�I�ł���Ƃ���A�u�����v�Ƃ����ꂪ�I�ꂽ�B����E���ȑO�ɂ͌R�l�����t������b�߂邱�Ƃ����X����A���̔��Ȃ��猻�s�̓��{�����@��66���2���ɂ́u���t������b���̑��̍�����b�́A�����łȂ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肳��Ă���B�u�����v�́u�����v�u��ʎs���v�u��퓬���v�̃j���A���X�������A�u�R(���݂̎��q��)�̒��ɐE�Ə�̒n�ʂ��߂Ă��Ȃ��ҁv���w���ƍl������B���������Ƃ��������ł́u�R�l�ȊO�̐l�ԁv�A��̓I�ɂ́u�����Ɓv���w���A�h�q�Ȃ́u����(�w�L�g�E����)�v���������̂ł͂Ȃ��B�ߋ��̓��{�ɂ����āu�����v�ƌ����ꍇ�Ɂu���E�ƌR�l�̌o����L���Ȃ��ҁv�ƋK�肷�邩�A���邢�́u���E�ƌR�l�̌o����L����҂ł����ČR����`�I�v�z�ɐ[�����܂��Ă���҂łȂ��ҁv�Ƃ��邩�A�ӌ���������Ă������������(1965/5/31�O�c�@�\�Z�ψ��� ���Ґ��ȁE���t�@���ǒ������قȂ�)�B���Ė쑺�g�O�Y(���C�R�叫�A�����m�푈�J�펞�̒��đ�g)�̓��t���������ꂽ���Ƃ����������A�u�����v�K��̖�肩��f�O���Ă���B���̌�A���E�Ǝ��q���̉i��Ζ�(�I�펞�͐E�ƌR�l)���@����b�ɂȂ������⒆�J�����h�q�������ƂȂ������ɂ���莋����ӌ����o���B���������̌����͍��ۓI�Ȋ������킯�ł͂Ȃ��A�Ⴆ�Εč��̍��h�����������ł��邱�Ƃ������ł��邪�A�ޖ����Ă���10���N���o�߂���ƕ����Ƃ��Ĉ�����B�܂��A�p���ł̗v���͕����������Ƃł��邱�Ƃ�v����B�@

���j�㑽���̉���M���Ȃǂ̎x�z�҂͐����Ƃł���Ɠ����ɌR�l�ł��������B�R���͂���ɏ������Ă������Ƃ��A�����I���͂̈ێ��̂��߂ɂ��K�v�ł���A�܂��O�������W����ߑ�܂ł͈��S�ۏ�̏d�v�������ȏ�ɍ����������߂ł���B�܂��R���̑g�D�����W�r��ł���A�R���헪�E���E��p�Ɋւ��闝�_�̌n�������Ă��炸�A��������n�I�Ȃ��̂ł��������߂ɐ��I�Ȓm���E�Z�\���Ȃ��Ƃ���핔���̎w�����Ƃ��Ă̎d�������Ȃ������Ƃ��傫�ȗv���ł���B�������ߐ��ȍ~�푈�����x���E���G�����Ă���ƂƂ��ɌR���Ɋւ��Đ��I�Ȓm���E�Z�\�����l�ނ̊m�ۂ��R���̋}���ƂȂ�A���x�Ȑ��m���E�Z�\���K�������E�ƌR�l���������߂�悤�ɂȂ��Ă����B����Ɠ����ɁA�܂������͌R���Ɏc���Ă���������M���Ƃ����������Ɛ��͂��R������r�����邱�Ƃ��R���̎w�������̍������̏�ŕK�v�ł���A�Ƃ������Ƃ��E�ƌR�l��������咣�����悤�ɂȂ�A�R���̐����Ƃ̕������i�B���ꂪ�R���̐�剻��i�߁A����̕��������̊�{�`�ƂȂ��Ă���B

����������17-18���I�̃C�M���X�ɂ����ēo�ꂵ���B�����̍����̌R���͗��p��N�����E�F���̓ƍِ����̉e�����獑���̏���R���댯�����鐺�����܂�A�c��ƍ����̌��͓������s��ꂽ���A1688���_�v���Ɨ��N�̌����͓T�ɂ���āA�c��R�������邱�Ƃɂ���č����̌�������̉������悤�Ƃ����B�������c��͂��̈ӎv����ɑ���Ȏ��Ԃ�������A�܂��R���Ɋւ��錈�莖���͖c��ł��邽�߂ɌR���̎d���������Α�A���nj�ɋc��͌R���̎w���ē��������ɕԊ҂����B1727�ӔC���t�����������ė��R��b���I�ꂽ���A�R���̑��i�ߊ��̐l�����Ɠ������͍����ɂ��������߁A���R��b�͌R������Ɋւ��錠���݈̂ϑ�����Ă���A�I�ȊNJ����c���Ă����B�{�i�I�ɐ��R�W��肪�����яオ�����̂�19���I�ɓ���A�v���t�F�b�V���i�����Z�c���䓪���Ă������ƂɋN������B�v���C�Z�������̏��Z�ł������J�[���E�t�H���E�N���E�[���B�b�c���u�푈�_�v�̂Ȃ��Łu�������ړI�ł����Đ푈�͎�i�ł���v�Əq�ׂĐ����̌R���ɑ���D�z��_���A���̏�Łu�푈�����ꎩ�g�̖@�����������́A�v���t�F�b�V���i���̐E�ƌR�l�ɊO������ז����ꂸ�ɂ��̖@���ɂ��������Đ��Z�p�W�����邱�Ƃ��F�߂��邱�Ƃ�v������B�v�Ƃ��ČR�����Ƒg�D�Ƃ��Ă̌R���̊m����v�������B���ꂪ����̕��������̌��^�ł���B�܂������Ɍ����I�ɌR���𐭎��̓������ɂ������߂Ɂu��������t������ׂ��ł���v�Ƙ_�����B�������N���E�[���B�b�c�̗��_�͌㐢�̌����҂����ɂ���āu�������R���s���ɕ�d�����邽�߂ɁA��������t������ׂ��ł���v�ƌ������A��ꎟ���E�������E���ɂ����鑍�͐�̗��_�ɓ]�p����A��ʎE�C�E�j��̔w�i�ƂȂ����B��ꎟ���E���O��̃h�C�c�ɂ����ẮA�������̑��x���ŁA����2���ʂ̓G�����e���j����Ƃ����R���헪���A�B��̕��@�Ƃ��Č��肳��Ă����B���̐헪���̂�ꍇ�A�����̑��x���Ɉˑ�����W�ŁA�����̐��䉺�ɂȂ��G�����������������Ă��܂��ƁA�����̐������f��҂����ɑ��A�������푈�����ɓ���˂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�A���ʓI�Ɏ����̌���ɂ��J�팈��Ƃ����A���������̊�{���̊�{���s�\�ɂȂ����B�@
�@���ɗL���Ɍ�����R���헪�ł��A���ꂪ�R���ȊO�̎���������Ȃ��ꍇ�A���Ƃ̎��������̂��̂��낤�����Ă��܂��B���̂��Ƃ́A�R���̓��������ȒP�Ɏ���ꂩ�˂Ȃ�����Ƃ��āA�������[�����P�Ƃ��ĐS�ɗ��߂Ă����ׂ����낤�B���̂悤�ȍ��𗧈Ă��Ȃ���A�������������R�l���̖��ߑ��A�d�v�ȑ������w�߂Ɋւ��āA�[���Ȍ������s��Ȃ������������̎���ł���B���ʂƂ��āA�R���헪�ȊO�̎���������̂��w���͂������Ȃ�������ꎟ���E���㔼�̃h�C�c�ɂ����ẮA�R���헪�����Ɛ헪�ɗD�悷�ׂ��ƍl�������[�f���h���t�����R�Q�d�����Ƃ��āA�������ӂ邢�A�R���I�����݂̂�Njy���ċx��ɂ�����܂łɎ��Ԃ����������B�h�C�c�R�̗D���Ȏ����ł̏����ȏ����̋@��A�A�����J�Ƃ̊O���̋@��A�Ȃǂ�S�Ă������Ă��܂��A�u�a���̒����ɂ����ẮA�A���R�ɑ啝�ȏ������������Ă���B�R���헪�ȊO�̎���������̂��w���͂������Ȃ��ꍇ�A�O���A�o�ς̖ʂł́A�������A���Ǝw���A�Ђ��Ă͌R���s���̖ړI���̂��̂����낻���ɂȂ�A���ʓI�ɔߎS�Ȍ����������炷�P�[�X�́A�D��ł���B��2������̋��Z�V�X�e���܂ŁA�푈�w���ɑg�ݍ���ŋ����A�����J���{�̗�����Ă��A�D�ꂽ�����ɂ�铝���͗D�ʂށB

�s���[���^���v��(1642)��A�N�����E�G���̓`���[���Y�ꐢ�����Y��A1655�̔������@�ɌR���ƍى��̕������Ƃ����B���̂��ߔނ̎���A����R�ɑ��鋭���x���S�����܂�A�Ȍ㍡���Ɏ���܂ŕ��͂ɂ�鐭���͒a�����Ă��Ȃ��B�p���ɂ����ăV�r���A���E�R���g���[���̍l���������߂Ė@�������ꂽ�̂͌����͓T(1689/12/16)�ł���B���̌����͓T�́A�W�F�[���Y�Q���ƍ���̍R���̌��ʐ��肳�ꂽ���̂ł��邪�A���̒��Ɏ��̂悤�ȕ������}�����ꂽ�B�u�����ɂ����āA����̏��F�Ȃ����č����ŏ���R�W���Ă�����ێ����邱�Ƃ́A�@�ɔ�����v�������č���������̊�������čs�����邱�Ƃ́A���͂�s�\�ƂȂ�A����R�͍���̃R���g���[�����ɒu����邱�ƂƂȂ����B�@

�p���ɂ�����R���͓����̐������x�Ƃ��ẮA�s���{�ɂ����ẮA��1�ɕ����ō\�����ꂽ���{��]���������ɑ��ĐӔC��L���邱�ƁA��2�ɌR��]���͂��̕������{�̎w���̉��ɂ��邱�ƁA��3�ɌR���̉^�c�͓��t�̈���ł��镶�������R���S�����̎w���ɂ�邱�Ƃł���B���@�{�ɂ����ẮA��1�ɘa��̌��褋ً}���Ԃɂ����錠���̕t�^�Ȃǂ��s���A��2�ɌR���\�Z��[�����A��3�ɌR������̎��s�ɑ��ċ��ɓI�Ȋē����s�g�ł��邱�Ƃł���B�i�@���ɂ����ẮA��1�ɍ����̖���I�Ȋ�{�I�������R�ɂ���ĐN�Q�����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�R�̐ӔC��Njy�ł��邱�ƁA��2�ɌR�l�̌����⎩�R�ɂ��ĊNJ����������Ƃł���Ƃ���Ă���B�܂������`�Љ�ɂ�����R���͓����ɂ����ẮA���̂悤�Ȑ��x��̌����̂ق��A�NJ���̔\�����ƌR���I�K�������l�����Ȃ���ΎЉ�̈��J�ƕ��a�̈ێ����Q���邱�ƂƂȂ�B��̓I�ɂ́A���h��̌���A�����i�̎擾�̕K�v���A�R�\�{���O���ւ̌R���͓����̉ۂȂǂ͋c��ɂ��R�̃V�r���A���R���g���[���ł���B�܂����낢��ȏ�ʂɂ���������I�Ȉӎv����͌��@��̌����ɂ����s�����ƂƂȂ��Ă���B�g�D�I�ɂ�1964�R�߂̑g�D�����v���ꤓ����ƕ������i�߂�ꂽ���A���I����͌��������s���A���h��b(Secretary of State for Defence)�͖h�q���B�S������(Minister of State)�A3�R�S������(Minister ofState)�A�y�ѕ�����(Parliamentary Under-Secretary of State)�Ƃ���3�����̕⍲���邱�ƂƂȂ��Ă���B���h�ψ���y�я㋉�Ǘ��@�\�́A���h��b�̉��ɕ������y�т���Ɠ��i�ŋc��ł̓��ق��s���Q�d�����A�ȉ������̍��h���B�ǒ��A�R�l�̍��h��⋋ǒ��ȂǕ����ƌR�l�̋ǒ���e�R�Q�d���ɂ���č\������Ă���B

�č��͌R����n�݂����������狭�͂ȏ���R�������Ȃ����Ƃ��f���A���̓�������`���I�ɕ��������ƂɈς˂Ă����B�Ɨ��푈�ɂ����ă��V���g�����ō��w�����ƂȂ�A��k�푈�ɂ����Ă������J�[�����푈�w�����s�����B���O�����@�ɂ����Ă͑哝�̂͌R���̍ō��w�����ł���ƒ�߂Ă���A�哝�̂��R�������A�R���̈ێ�����ѐ��z���͋c��̌����ł���ƒ�߂Ă����B���̂��߂ɑ���E��펞�̃A�����J���O���ɂ����Ă͕����������@�\���Ă���A�t�����N�����E���[�Y�x���g�哝�̂́A�E�B���A���E���[�q�����Q�d�{�c���Ƃ̋��c��ʂ��Đ푈�w�����s�����B���N�푈���ɂ����ẮA���A�R�̎i�ߊ��ł������_�O���X�E�}�b�J�[�T�[���R���I����������A�j����̎g�p���܂߂����ؐl�����a���ւ̍U�������������B����ɑ��A�g���[�}���哝�̂́A�����ւ̍U���́A�R���ʂ���͕K�v��������Ȃ����A�S�̓I�ȍ��ۏ�̊ϓ_����s���v�ƂȂ肤��ƍl���A�}�b�J�[�T�[�ƈӌ����Η��������߂ɔނ��Ƃ����B�x�g�i���푈�ɂ����Č��n�̑��i�ߊ��E�F�X�g���[�����h�́u�������K�C�_���X�������Ȃ����߂ɌR�l�������ɉ��������Ȃ������v�Ƃ��č��Ɛ헪�̕s�݂̂��߂ɌR�����̖ړI���B�������Ă����Əq�ׂĂ���A�܂������̃A�����J��7��R�i�ߊ��͐��{�̎w�߂�30����j���Ă������ƂɎ������悤�ɁA��ɕ��������������I�ɋ@�\���Ă����킯�ł͂Ȃ��B

18���I�Ɨ��O��̕č��ɂ́A����R�Ɩ����̂Q�̃^�C�v�̌R���͂����������A�����͍����ƈ�̂ƍl����ꂽ�̂ɑ��A����R�͏��ƕ��Ƃ̊Ԃɖ��m�Ȉ�����Ђ���A�����Ԃ�M���I���������ƂȂǂ���x������闧��ɂ������B�����̑嗤��c(1776/6/12)�ɂ��錾�ł́u�����ɂ��������R�́A���R�ɑ��L�Q�Ȃ��̂Ƃ��Ĕ�������ׂ��ł���A�����������Ȃ�ꍇ�ł��A�R�͕����̌��͂Ɍ��ɕ��]���A���������ׂ��ł���v�Ƃ���A�V�r���A���R���g���[���̌��������L���ꂽ�B�Ɨ��錾(1776/7/4)�̒��ɂ��p�������̍ߏ����ׂ����Ɂu���͕����ɂ����ẮA���̋c��̓��ӂȂ����āA����R�����̊Ԃɗ��߁A�R�������ĕ�������Ɨ������߁A���D�ʂȂ炵�߂��v�Ƃ����w�E������A�܂��o�[�W�j�A�����͓T(1776/6/2)�A�y���V���x�j�A�l���錾(1780/3/2)�y�у}�T�`���[�Z�b�c���@(1780/3/2)�ȂǏ��B�̌��@���ɁA����R�̊댯���ƌR���̕���(CivilPower)�ɑ��镞�]�����L����Ă���B�Ɨ��푈(1975-83)�I����̑嗤��c(1784/6/2)�ł́u�����ɂ��������R�͋��a���̂ɖ������A�����̎��R�ɂƂ��Ċ댯�ł���A����͈�ʂɓƍِ���ł����Ă邽�߂̔j��I�ȓ���ɕς��v�Ƃ����G���u���b�W�E�Q���[�̈ӌ����ʂ����B�@
1778���肳�ꂽ�A�M���@�ł́A�V�r���A���R���g���[���Ƃ����p�ꂱ���p�����͂��Ȃ��������A�����D�z�̐��_�̂��ƁA�����ɂ��I���őI���ō��̕�������哝�̂́A���O�����C�R�y�ь����ɏ��W���ꂽ�����̍ō��i�ߊ��ł���(��2��2��)�Ƃ��A�����̒��ڑI���őI�ꂽ�A�M�c��݂̂��푈��錾���A���R��E�ێ����A�C�R�����݁E���傷�邱�Ƃ��ł���(��1��8��)�Ƃ����B

��O�̓��{�ł̓h�C�c���Q�l�ɂ����C�R�̓������͓V�c�ɂ���ƒ鍑���@�Œ�߂��A�������͓Ɨ��������݂������B�鍑���@�ɂ�������t�Ƌc��͓V�c�̕�J�Ƌ��^�̂��߂̋@�ւł���A���������̊�b�Ƃ��Ă͔��Ɋ낤�����̂������B���{�̐��R�W�̓����h���C�R�R�k��c�ɂ����铝�������Ɩ��Ɍ�����悤�ɁA���т��ѐ����ƌR���̘��������ƂȂ����B���a�ȍ~�A�֓��R�͓��t�̕s�g����j�����āA����ɒ��������}���{�Ƃ̐푈�𐄐i����(���������E�����Aḍa������)�B�S�[�X�g�b�v�����̂悤�Ȃ������Ȏ����ɂ����Ă����R�W�����ƂȂ�A�܂�������`�̐N���Z�c���A�܁E������A��E��Z�������N�����ƁA�R�͓V�c�̑匠�ɂ̂ݕ����A���������ɏ]�����Ȃ����Ԃ��I�悵���B���a12�N�x�ߎ��ς̔����ɔ����đ�{�c���ݒu���ꂽ���A��{�c�̒��_�͓V�c�ł���ł͂Ȃ��A�܂��c�����t�͊֗^���Ȃ������B���R�W�͑�{�c���{�A����c��ݒu���Ĉێ�����A�V�c�E���{��]�̈ӌ��ɉ����Đ��{���j�͈͓̔��ŌR���헪��g�ݗ��Ă�̍ق��Ƃ����B�����m�푈���́A���R��b�����p�@�y�ъC�R��b���c�ɑ��Y�����ꂼ��Q�d�����E�R�ߕ����������C�����B�����E���c�����������R�l�ł��������Ƃ������āA�������̖\���Ƃ���_�����邪�A�������͐��{�̓����ɑ���]���ł���B���ہA���C�R��b�����������E�������̂ł���A��������R���R�߂̍����͈ጛ�ł���Ƃ̔ᔻ���������������B

�펞���̔��Ȃ���A���{�����@��66���Ɂu���t������b���̑��̍�����b�́A�����łȂ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肳��Ă���B���h�q�������E�h�q��b�͕����ł���A���E�̎��q���⎩�q�������A�����͔F�߂��Ȃ��B���������{�ɂ����ẮA���͑g�D�̍s���ɂ��č��h�̕��j�ɑ����Đ��������̂ł͂Ȃ��A�P�Ɂu�R���v�Ɋւ��銴��I�Ȍ��������炻�̍s���ɑ��g���������悤�Ƃ��Ă��鐨�͂��吨���߂Ă���B���q�������̏�Ŕ������邱�ƁA�ӌ����邱�Ƃ���u�V�r���A���R���g���[���̐N�Q�v�Ǝ咣���鐨�͂�����A�퓬���`����m���ł��Ă��Ȃ��傫�Ȍ����ƂȂ��Ă���B���q���E�w�����k�̐鐾�ɂ́u�����I�����Ɋ֗^�����v�̕���������B�R������ɂ��ẮA(�V�[���[���ȂǁA���{�̍�����l����Γ��{�̖h�q�͌o�ϓI�ɂ����{�Ђ��Ă͐��E�̉^�������E����ɂ�������炸)��ʓI�Ɏs�������ƗV�����Ă���Ƃ�����ۂ��傫�����߂��A�s�����x���ł̐��n�����c�_�͂Ȃ���Ă��Ȃ��̂�����ł���B

�u�����`�I�����ɂ��R���ɑ��铝���v�ɂ���āu�����ɑ���R���g�D�̉e����r������v���Ƃ��V�r���A���R���g���[���̊j�S�ł���B�R���������ړI�B���ɍł��ǂ��v�������邽�߂ɕK�v�ȌR���I�������y�ьR���I�������̒Nj��́A�V�r���A���R���g���[������E���Ȃ��͈͓��ł̂��e�����B����A�V�r���A���R���g���[���́A���̖h�q��S�����邽�߂̈�̐��x�ł��邩��A�R�����ʂ����ׂ��@�\��s���ɑj�Q���A�㉻������̂ł����Ă͂Ȃ炸�A�܂��u�������R����K�ɗp������v���x�Ɖ^�p�@�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�@
���@���̎��q���́A�����u�O����v�Ɋ֘A���Ėh�q�������a40�N�ɏO�c�@�h�q�}�㌤����蓙�\�Z���ψ���ɒ�o���������ŕ���Ă���悤�ɁA����Ƃ̊W�A���{�Ƃ̊W���тɖh�q�������̊W�v�X�ɂ����Đ��x��V�r���A���R���g���[���Ɋւ�����͂Ȃ��Ƃ���Ă��邪�A���͂��̐��x�͖����L���̐�����Ă��Ȃ��B����ǂ��납�A���a25�N�x�@�\�����̏��q�I�Ȓa���ƁA���̌�50�N�Ԃɂ킽��킪�������̌R���ɑ�����Ɏp���ɂ���āA�ł������������L���ɂ����Ă��̐��x���@���ɋ@�\���邩�̌����ς�ł��Ȃ����A�u�������R����K�ɗp����v���n����̌������I�����Ă��Ȃ��B�@
(��)���q���̒���A��v�����Ґ��̊�{�͖h�q2�@�ɂ�荑��ŋc������A�h�q�\�Z�͍���ɂ����ĐR�c����A�o���͍���̏��F��v���邱�Ƃɂ�莩�q���͍���̊ē��ɂ���A���q���̏o������y�эō��w�����́A����c���̒����獑��̋c���Ŏw�����ꂽ���t�̎�����t������b���ۗL���A���q���͕������鍑����b�Ƃ��Ă̖h�q�������̊Ǘ����ɂ���A�e���q���̖������͒����̕����ł���A��{�I���j�͑S�Ē����̌���ɂ�邱�ƂɂȂ��Ă���̂ŁA����I���������̊�͑S�Ė�������Ă���A���q���ɑ���@����̕��������͖��S�ł���Ƃ����Ă���B�@
�ߔN�킪���ɂ����Ă��A�V�h�q�v���j�ɂ�鎩�q���̖����̊g��A���Ėh�q���͎w�j�֘A�@�̐����Ɗ֘A�̘_�c�A�o�j�e���������̓����A�M�l�~���̎��ԋy�уQ�����E�e���̉\����ے肵���Ȃ�����A�����E�O����h�q�͂̊��p��K�v�Ƃ����ʂ������ɑ������Ă���ƔF�߂��A�������R���̐�含�E�Z�p���́A�v�X�i�s������̂ƌ�����B���̂��߁A�������R���̎��Ԃ��\���ɏ���������ł̔��f�E���u���K���E�K�ɍs���邱�Ƃ̏d�v������w���܂邱�Ƃ��\�z����A�L���Ⴕ���͍��ƂƂ��Ă̊�@�Ǘ����K�v�ȏ�O��Ƃ��āu�������R����K�ɗp����v���n����V�r���A���R���g���[���݂̍�������������Ƃ͋}���ł���B�@
 �@
�@���w��Ώd 1
���C�R�̎w���҂܂菫���ɂȂ�ɂ͊����̎��������z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���R�m���w�Z��C�R���w�Z�ɓ���̂́A����ɍ��i���������Ƃ���Ă����B���̏�ɗ��R��w�ƊC�R��w�����݂��A�����ɓ��邱�Ƃ͌R���̒����ɓ��邱�Ƃ��Ӗ������B�����n���ƂȂ邪�A�ƕ��ɊW�Ȃ��o���ł���Ƃ������_���������B������̐��E�ŋ��߂��鎑���́A���ꍏ�ƕω�����ɓI�m�Ȕ��f��������l�Ԃł���A�����������l�ނ̏W�ߕ��́A�����̂���肪�������Ƃ�����B�@
���R�ł͗��R��w�𑲋Ƃ������̂ɓ��ʂȋݏ͂����邱�Ƃ�F�߁A���̌`���]�ˎ���̉ݕ��u�V�ۑK�v�Ɍ`�����Ă����̂ŁA���呲�Ǝ҂͑��ɓV�ۑK�g�ƌĂ�Ă����B����ɑ�������o�Ă��Ȃ����͖̂��V�g�ƌĂ�A�o���╋�C�n�Ȃǂō��ʂ��ꂽ�B���̐��x�́A���V�g�͍c���h�A�V�ۑK�g�͓����h�ɕ����ꗤ�R�����ɑΗ��݂����v���ɂȂ��Ă����B�@
�c���h�Ƃ͓V�c��Ύ�`�̂��ƂŁA�V�c�ɐs�������Ƃ͍��Ƃɐs�������Ƃł���A���̂��߂Ȃ�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă��悭�A���ꂪ�c���̎��H�ɂȂ�Ƃ����l�����ł���B�����h�Ƃ́A�R���͏ォ�牺�ւ̖��߂��匴���ŁA���Ƃ̊�}�ɔ����A�R�����ł͂Ȃ��o�ςȂǂ��������������悤�Ƃ����l���ł���B�댯�ȍl���������A�g�D�_��펯�_����l����ƁA������`�I�ȍc���h���͂܂Ƃ��Ƃ�����B���̑Η��̌��ʁA�����h�̃��[�_�[�Ƃ����i�c�S�R�R���ǒ����A�c���h�̑���O�Y�����ɗ��R�ȓ��Ŏa�E����鎖�����N�����Ă���B2�E26�������c���h�̏��Z�����S�ƂȂ��Ă���B���{�̐i�H�����E���������̈���ɁA�o�g�Z�ŏo�������肷��Ƃ����w��Ώd��`�����������͑傢�ɒ��ڂ��ׂ����B �@
 �@
�@���w��Ώd 2 / ����{�鍑���R
����{�鍑���@����O�͂��̈ʒu�Â��������[���ł͂Ȃ��_�����������A���@�����́A�R���匠�ɂ��ẮA���@����t����Ɨ����A���ړV�c�̓������ɑ������B�ō��w�����͓V�c�ŁA�匳���Ƃ��ė��C�R������B�R�߂��Q�d�{���A�R���𗤌R�Ȃ��i�����B�Q�d�{���ɑ���������{�C�R�̑g�D�͌R�ߕ��ł���B���������āA�S�R�̍ō��i�ߊ��͑匳���̓V�c������l�ł���A������J����ō����w����(�`���I�ɂ͎Q�d)���A���R�ł͎Q�d�����A�C�R�ł͌R�ߕ������ł���B���O���̌R���̂悤�ɁA���R���i�ߊ��A�C�R�ō��i�ߊ��̂悤�ȍō��ʂ̌R�E(�|�X�g)�͑��݂��Ȃ��B�@
�n����/�鍑���R�̋N���́A�����ېV���1871�ɁA�F���E���B�E�y�����璥�W����g�D���ꂽ�V�c�����́u��e���v�ł���B���̕��͂�w�i�ɔp�˒u����f�s�����B��e���͂��̌�u�߉q�v�Ɖ��̂��ꂽ�B���̎��_�ł͎m���������̒��S�ł��������A���R�Ƃ��Ă͒������ɂ��R����ڕW�Ƃ��Ă����B�߉q�͒������m��`��������̂ƕs�����点�A���ؘ_�ɂ�鐼�������̉�����@�ɏ��Z��������ʂɎ��E�����B�Ȍ�͒������Ɋ�Â����䂪���R�R���̎�͂ƂȂ�B�����͐�獑���̎����ێ��A�������͂̒���(����푈�ق�)�Ȃǂ�S�����B

�O���̊J�n/����7�N�̑�p�o���ȍ~�A���X�ɊO���R�Ƃ��Ă̐��i��F�Z������悤�ɂȂ�A����21�N(1888)���_����̑��ʂ̋������䐧����A����x��������g�ݍ���ŋ@�����̍����t�c���ւ̉��g���s�����B�@
����27�N�����푈�J�펞�ɂ́A��ݎt�c��7�ł��������A�푈�㖾��31�N��ݎt�c6�t�c(��7�Ȃ�����12�t�c)�����݂��ꂽ�B���I�푈�ł͑S�Ă̎t�c����n�ɔh�����ꂽ���߁A���n�Ɏc������t�c���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����ŁA���I�푈���̖���38�N4����4�t�c(��13�t�c�ق�)���V�҂��ꂽ�B���^��q���čs��ꂽ���I�푈�̕�V���ɂ����鏟�����L�O���ė��R�L�O�������肳�ꂽ�B�@
���ؕ�����́A����ؒ鍑�R�l�N�R�l�Ƃ��ĕғ������B�܂��A���N�����h�q�̂���2�t�c�����Œ��N�����ɔh�����Ă������A�h��v����̒��ؖ����̍�������x�������̕K�v�������܂�㌴�E�엤����2�t�c�̑��݂𐼉������]�ɋ��߁A���̍������琼�������t�͌��ʓI�ɓ|��邱�ƂƂȂ�B���̌�A���R�Ȃ̗v�����ʂ�吳4�N���N�����ɉq������2�t�c(�암�ɑ�19�E�k���ɑ�20�t�c)���Ґ�����邱�ƂɌ��܂����B�@
�R�k��/���E�I�ȌR�k�̗���ɏ]���ĎR�����������y�щF�_�ꐬ�����̉���3���ɂ킽��R�k���s���A4�t�c(��13�t�c�E��15�t�c�E��17�t�c�E��18�t�c)���p�~����A�������͂�3����1���팸���ꂽ�B�F�_�R�k�ł́A�����ɗ��R�̋ߑ㉻��ڎw���Ă���q�Ȃ��V�݂����Ȃǂ����ق��A������������炵�L���ɂ����铮�����������m�ۂ��邽�߁A�w�Z�������x��n�݂��Ē��w�Z���ȏ�̊w�Z�ɗ��R�������Z��z�����邱�ƂƂ����B�@
���a��/���a���ɓ������̓Ɨ����f���A���{�̓�������E���ēƒf��s�̍s���������ɂȂ�B��E��Z�����ȍ~�́u�R����b�������v�����ɓ|�t���J��Ԃ��Ȃǐ��Ǎ����̌���������A�����푈���瑾���m�푈�Ɏ��閳�d�Ȑ푈�ւƓ˂��i�B�\�A�����z�G���Ƃ��ĂƂ炦�č��v��𗧈Ă��A�����ΊC�R�ƏՓ˂����B���B���ρAḍa���������o�Ē����嗤�֑�ʂɔh�����A�����m�푈(�哌���푈�^����E���)�ł͕�����������͂ɁA��ԕ�����q��������ɔh�����������������B�@
�x�ߎ��ς̒������E����̊g��ɔ����t�c�̑��݂��������A���a12�N(1937)����͗���t�c�����ɕS�ԑ�̓��ݎt�c���݂�����Ȃǂ���(��101�t�c�Ȃ�)�B�܂��A���a15�N8������8��ݎt�c�����B�鍑�ɉi�v���Ԃ��邱�ƂƂȂ����B����ɁA�����m�푈(�哌���푈)�����ɂ͖{�y����ɔ����đ�ʂɋ}���̎t�c�����݂��ꂽ�B�K�͂��g�債�����߁A�R�̏�ɕ��ʌR��R���݂���ꂽ�B

�R���E�R����`�v�z/����11�N8���ɐ��s�ł��锤�̋߉q�C�����������N�����Ƃ����|���������N����A���{�ɏՌ���^�����B�܂��A���R�����^���̉e���𗤌R���邱�Ƃ�h�����߂ɁA�R�l���@���o���ꂽ�B�����ł́u���߁E��V�E���E�E�M�`�E���f�v�̓��ڂ��f����Ƌ��ɁA���̒��Ő����s�������߂Ă����B�������Ȃ���A���R�R�l�̒��j���߂闤�R�m���́A���R�ȐE���Ƃ��Ċ����@�\�̑��ʂ��L���Ă���A�Â��͎F���ˁE���B�˓��o�g�̏��Z��Ƃ��̑��̔˖��͖��{�o�g�̏��Z��Ƃ̑Η����������Ƃ����B�܂��A���R�m���w�Z�E���R��w�Z�Ƃ����ߑ�I�m�����琧�x�m����́A���ȊԂł���Ƃ��A���R��w�Z���o���G���[�g���钆������(���R��w�Z���ƋJ�͂��V�ےʕ�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���V�ۑK�g�Ƒ��̂��ꂽ)�Ƒ��t���Z(���V�g)�Ƃ̊Ԃł���Ƃ��A�h���Ԃ̎v�z���͐l����̑Η�(�c���h�E�����h�̑Η�)�ȂǁA�����̓����I�ȍR���݂₷���ł������B�@
�֓��R�ȂǁA�O�n�ɏ��݂��錻�n�������A�����̓������[���Ɏ��ɍs������Ȃǂ̖��_�������Ă����B���̂��߁u�X�}�[�g�l�C�r�[�v��W�ԂƂ���C�R�Ƃ́A�������R���ʊC�R�P�ʘ_���ɉe������ΏƓI�ɃC���[�W����₷���A���{���R�ɑ��鈫����ۂ͈�ʓI�ł���B

 �@
�@���w��Ώd 3 / ����{�鍑�C�R

���{�͎l�����C�m�Ɉ͂܂�A���{�C�R�͐������m�̐��C�����m�ۂ��邱�Ƃɂ��G��͂�{�y�ɋ߂Â��Ȃ����Ƃ���{�I�Ȑ헪�Ƃ��āA�s���ЁE�s�N���������Ƃ��Ă����B�܂�����ʼnp���C�R�ɑ傫�ȉe�����A�퓬�ɂ����Ắu���G�K��v�Ɓu���C���̊m�ہv���d�����čU����ǂ��ƍl���Ă����B���̂��߁A�{�y�h�q�����C���͂̑�����D��I�ɍs�����B�@
���{�C�R�̐헪��p�����̌��J�҂Ƃ��č����S���Y��������������B�����������珺�a�ɂ킽��C�R�̕��p�v�z�̌����Ɍg����Ղ�z�����B����40�N�Ɂu�鍑���h�j�_�v���u�鍑���h�̖ړI�͑��̏����Ƃ͂��̎���قɂ��邪�̂ɁA�K���܂��h�玩�q���|�Ƃ��č��̂��i���Ɍ쎝���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɖ��ׁA���{�̌R���헪��R���͌��v��ɉe����^�����B

���{�_�b�ɂ�����_���V�c�̌�D�o�̒n�A�{�茧�����s���X�Â����{�C�R���˂̒n�Ƃ���Ă���A���X�Í`�ɂ͊C�R��b�ē������ɂ��u���{�C�R���˂̒n�v�肪�����B�]�ˎ���̖��ˑ̐��ɂ����Ă͍������s���A���˂̑�D�����͋֎~����Ă������A�e�n�ɊO���D�����q���Ēʏ������߂鎖�����p������悤�ɂȂ�ƁA���{�⏔�˂͊C�h�������s���悤�ɂȂ�B�R�͕�s�A����C�R�`�K�����ݒu����A�J�����s��ꂽ�̂���1860�ɂ͙��Պۂ��h�������B1864�ɂ͏��̊ϊ͎����s��ꂽ�B�������Âɂ�萬�������������{�́A�]�˖��{�̊C�R��������C�R�`�K���Ȃǂ̋@�ւ��p�����A���{�⏔�˂̌R�͂��E�Ґ������̂���b�ɂȂ�B�@
1870���C�R����������A1872�C�R�Ȃ������z�n�ɐݒu�����B�����ɂ͐쑺���`�Ə��C�M���w������B1876�ɊC�R���w�Z�A1893�ɂ͊C�R�R�ߕ������ꂼ��ݒu����B���������ɂ͗��R�ɑ��ĊC�R����ł��������A����푈�ɂ�萭�{���ŎF�������ލs����ƁA���R�d�_��`�������悤�ɂȂ�B�Q�d�{�����ݗ�����A�C�R��b�̐����]����R�{�����q�炪�C�R�������咣���A�͑��̐�����g�D���v���s���A�����푈���ɂ͌R��31�ǂɐ�����24�ǁA���I�푈���ɂ͌R��76�ǐ�����76�ǂ�ۗL����K�͂ƂȂ�B�@
���I�푈��́A1920�ɊC�R��������ł��锪���͑��Ă𐬗������A�A�����J�����z�G���Ɍ��͋������͂��߂�B1922�̃��V���g���C�R�R�k���y��1930�̃����h���C�R�R�k���ɂ���͊͂̌��͈͂ꎞ���f����邪�A�����h���C�R�R�k��c��������ɍĊJ����A�����m�푈�J�펞�ɂ͊͒�385�ǁA���Ȃǂ̍q��@3260�@�]���ۗL����K�͂ł������B

 �@
�@���O��
 �@
�@������
1937/7/7�k���s����̜I�a���œ����ԂŋN�����Փ�(�I�a������)�[�ɓ����푈���u�������B����ɑ����{���{�͎��Ԃ̂���ȏ�̓D������������A�s�g����j���Ƃ������A�ǒn��������������ŁA�����o���̏���������Ƃ������ɒ��r���[�ȍ���Ƃ����B����͗��R���d�h�̐����ɉ����ꂽ���߂Ǝv����B���̌�̊O�������A�����R�̜I�a���ւ̒��ԋ֎~��A�����̎Ӎ߂ȂǁA�Ƃ��Ă����������ۂ߂Ȃ��v���ŁA�����䂫�l�܂点���B�������{���Ōv�悳��Ă����߉q�̒����K������R�̖W�Q�ɂ�蒆�~�������Ă���B�V�c�ɍى����Ƃ����ӌ��������{����o�Ă������A�V�c�ɐӔC�킹���Ȃ��Ƃ������R�ŔF�߂��Ă��Ȃ��B���ǁA��l�܂�ɂȂ������{���{�́u�鍑���{�͎���A�������{��Ύ�Ƃ����v�Ƃ̐������o���A����a���̓�������Ă��܂��B�a���̑���̑��݂�F�߂Ȃ��Ƃ��������������j�ɂ��푈�̒��������m�肵�A�����Ԃ̐푈�͂܂��܂��D�������邱�ƂɂȂ����B

�����푈�͏��a12-20�N(1937-1945)�ɑ���{�鍑�ƒ��ؖ����̊Ԃōs��ꂽ���ϋy�ѐ푈�B���{�̌����ď͎̂x�ߎ��ρA���ؖ����⒆�ؐl�����a���ł̌ď̂͒����R���푈�������͔��N�R��B�p��ł�Second Sino-Japanese War�B���{�ł͓����A�k�x���ρA��Ɏx�ߎ��ςƏ̂��Ă���A�V�����}�X�R�~�ł͓��؎��ςȂǂ̕\�����g��ꂽ�B���ݓ��{���{�̐����Ȍď͕̂ς炸�A�h�q�Ȗh�q��������j��������J���ȉ���ǁA��������j�ł���u��j�p���v�A�����_�Ђ�e���̌썑�_�Ђł́u�x�ߎ��ρv�̌ď̂��g�p�B�}�X�R�~�ł́u�����푈�v�Ƃ����Ăѕ����L���蒅���Ă���B����͓��p�ĊԂ̊J��ƂƂ��ɁA�Ӊ�ΐ����͓��{�ɐ��z�����A���{���́u�x�ߎ��ϊJ�n���_�ɑk���č���̐푈�S�̂�哌���푈�Ə̂���v�ƒ�߂����߁A�����܂��ɐ푈�ƔF������邱�Ƃ���������ł���B�}�X�R�~�ł́u�x�߁v�Ƃ������t�̎g�p�������ē����푈�ƌ���������Ⴊ�����B�@
�u���ρv�Ƃ����ď̂��I�ꂽ�̂́A�u����{�鍑�ƒ��ؖ������݂��ɐ��z�����Ă��炸�����ɂ͐푈��ԂɂȂ��v�Ƃ�����Ԃ��A���ς̖u������������Đ푈�̊J�n�܂ł�4�N�ԁA�o�����]����ł���B���z����������̂͗������푈��Ԃɂ���Ƃ���ƁA��O���ɂ͐펞���ۖ@��̒����`���������A��퍑�ɑ��ČR���I�Ȏx�������邱�Ƃ́A�����`���ɔ�����G�s���ƂȂ邽�߂ł���B���ۓI�ȌǗ�������������{���ɂƂ��Ă��A�O���̎x���Ȃ��ɂ͐퓬���p���ł��Ȃ��Ӊ�Α��ɂƂ��Ă����z���͕s���Ƃ��ꂽ�̂ł���B

�x�ߎ��ς͓����푈�̌ď̂Ƃ��āA����{�鍑���{����߂����̂ł���B���ς́A���a12�N7����ḍa�������[�Ƃ��Ėk�x(�k�x�߁A�������̉ؖk�n��)���ӂւƊg�債�A�����Փ˂�8���̑��C���ϖu���ɂ�蒆�x(���x��)�֔�щA�₪�Ē����嗤�S�y�ւƔ�U���čs���A����{�鍑�ƒ��ؖ����Ƃ͎���ɐ푈�̗l����悵�Ă������B���������a16�N12���܂ł̊Ԃ́A�o�������z����Ō�ʒ����s�킸�A�푈�Ƃ����̍ق�]�܂Ȃ������B�푈���J�n���ꂽ�ꍇ�A��O���ɂ͐펞���ۖ@��̒����`���������A��퍑�ɑ���R���I�x���́A����ɔ�����G�s���ƂȂ邽�߂ł���B���ۓI�Ǘ�������������{���ɂƂ��Ă��A�O���̎x���Ȃ��ɐ퓬���p���ł��Ȃ��Ӊ�Α��ɂƂ��Ă��s���Ƃ��ꂽ�̂ł���B�o���Ƃ��ɐ푈�̈ӎu�͂Ȃ��A�����A�O���W���ێ��p������Ă���������������ł���B�@
���ɒ����ɂƂ��āA�A�����J���O���Œ����@�̓K�p������������Ƃ��傫���B�����@��1935�ɐ��肳�ꂽ�@���ŁA�O���Ԃ��푈��Ԃɂ���Ƃ��Ⴕ���͓������d�剻�����ꍇ�ɁA��퍑��������ւ̕��킨��ьR�������̗A�o���֎~������̂ł������B�����A�č��͓��{�ւ��̒����@�̓K�p�������������A���������ʂ̕����č�����A�����Ă������������Ĕ����͌�����ꂽ�B�@
�������A�������Ƌ��ɕĉp�͉��Ӄ��[�g�Ȃǂ�ʂ��ďd�c�������{(�Ӊ�ΐ���)�����R�Ǝx���B���{�͘a���A�h���A�����������韊�������x�����싞�������{(����������)�����F�����B���a16�N12��8���̓��ĊJ��ƂƂ��ɏӉ�ΐ�����9���A���{�ɐ��z�����A�����Ԃ͐����ɐ푈�֓˓������B��12���A���{���{�́u�����m�Εĉp�푈�y�����m���ڃj���q���N�X���R�g�A���w�L�푈�n�x�ߎ��σ����܃��哌���푈�g�ď̃X�v�ƌ��肵���B�@
���{�ł͏��ߖk�x���ρA��ɂ͎x�ߎ��ς̌ď̂�p�����B�V�����}�X�R�~�ł͓��؎��ςȂǂ̕\�����g����ꍇ���������B���ɓ��x���ςƂ��Ă��B�@
���͏��a12�N7���ȍ~���܂߂āu�����푈�v�ƌĂԌď̂��L�܂����B����́u���ρv�Ƃ����Ȃ��玖����̐푈�ł���Ƃ̎w�E�A����Ɏ�Ƃ��ă}�X�R�~���u�x�߁v�u�哌���푈�v�Ƃ������t�̎g�p��������ׂł���B�������h�q���h�q��������j��������J���ȉ���ǁA��������j�ł���u��j�p���v�A�����_�Ђ�e���̌썑�_�Ђł͌����ȁu�x�ߎ��ρv�̌ď̂��g�p���Ă���B�@

�����푈(�x�ߎ��ρE���؎���)���a12�N7��7���锼�Aḍa��(�낱�����傤/�k���̓�𗬂��I�a�͂ɉ˂��鋴)����(�u7�E7���ρv)�ɂ͂��܂���{�̖������~���ɂ�����܂ł̓��{�ƒ����̐푈�������B�@
ḍa���������������A���{���{(��P���߉q���t1937/6/4-1939/1/5)�͖k�x���ςƌĂѐ���s�g����j���Ƃ�A�܂����R�����ł��s�g��_�����������A�₪�Ē����̍R��͂��y�������ꌂ�_���䓪�A�r���p�������߂Ă����Ӊ�ΐ�����|���ĉؖk���2�̖��B���ɂ��悤�Ƃ���u�ؖk�����_�v���ƂȂ���g��_���吨���߁A���{�́A���N7/11�Ɍ��n��틦�肪���������ɂ�������炸�A���n��֓��R�E���N�R����4�t�c�E2���c(���v��10��)�̔h��������A���n�R���ēx�̏Փ˂��_�@��7/28�ɂ͑��U���ɏo�Ėk���E�V�È�т��̂���B8/13�ɂ́A��R�E�v���юˎE���������������ɏ�C�ɂ����ē��{�̏�C�C�R���ʗ�����������R�ƏՓ�(��2����C����)�A�������{�͏�C�h���R(2�t�c)�̔h�������肷��ƂƂ��ɁA�C�R��15����蒷�茧�呺��n����̓싞��P���J�n�A��͈ꋓ�ɍL�������B�@
���������Y�R�Ƃ̓���ɐ��͂�Ă����Ӊ�́A��������(1936/12/12�����Œ��w�ǂ��Ӊ���ċւ����Y�R�Ƃ̓�����~���A�R���푈�ɗ����オ�邱�Ƃ�v�����������ŁA�u�o�\��(�������イ��)�����v�Ƃ�����)���_�@�ɓ�����~�A���Y�}�Ƃ̑�2������������s���A���Y�R�ƂƂ��ɍR���푈���s�ւƐ헪��ύX�������߁A���{�R�͒����R�̌�������R�ɂ��炳��邱�ƂƂȂ����B�@
�������ē��{�͐��z���̂Ȃ��܂܁A1937/11/20�ɂ͓��I�푈�ȗ��̑�{�c��ݒu����ƂƂ��ɁA11���ɂ͂���ɑ�10�R(3�t�c��)�𓊓����A12/13�ɂ͓싞���̂���(���̍ہA��20-30���̕ߗ����퓬���̏Z�����E�Q����ƂƂ��ɗ��D�E���E�\�s�E���������𑽐��Ђ���������/�싞��s�E)�B

�����s�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�������{�͍~�������ہA��s��싞����d�c�Ɉڂ��ēO��R��𑱂������߁A���{�̌R�������͂̌��E�Ƒ��ւ��āA����͌�������ԂɎ������B���B���ς�5�����ŏI�������o�܂���A�����S�y���x�z����̂��Z���Ԃʼn\�ƍl�����ɂ߂Ĉ��Ղȍ��́A����͈��̌����ł��������B�@
���̂��ߓ��{�����ł́A1938/4���Ƒ������@�����z����A����Ɍo�ϓ��������������ƂƂ��ɁA�������_�������^���Ȃǂɂ��t�@�b�V�������܂��܂��[�������Ă����B��������{�̒����ւ̐N���́A�p�ĂȂǏ��O���̌��v��N�����Ƃ��Ӗ��������̂ɁA����͂���܂ł̃A�W�A�Ō`������Ă����Ă�[���b�p�����̔j��ł������B���̂��߁A�p�E�āE�\�͏Ӊ�ΐ����I�E�l�I�Ɏx������Ƃ���ƂȂ�B���{�R�́A�d�c�ɑ��ĊC�R��̂̐헪�����U��������ƂƂ��ɁA���a13�N�㔼����͏Ӊ��(�d�c)�����̎x���Ԃ����߂̐헪��W�J�A���a14�N�ɂ͊C�쓇�E��J�E�������́A���a15�N�ɂ͕���k���ɂ܂ŐN������B����œ��{�Ɖp�ĂƂ̑Η��͒��_�ɒB�����a16�N12���̑����m�푈�J��ւƂȂ���B�@
�Ήp�ĊJ�������{�R�ɂ��d�c�U�����͌p������邪�A�K�_���J�i���U�h��̌����ɂ�蒆�~�̂�ނȂ��Ɏ���A���̌���{�R�́A�������Y�}�̌R���ł��锪�H�R�Ȃǂ̃Q������ɑ����A���ǔs��܂ŁA70-150���̕��͂�(�����B������)��������ɂ͂���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�@
�����������œ��{�R�́A��l���I�ȁu�O�����v(���{�R���ӂ̂܂܂ɂȂ�Ȃ��u�G���v�n��ɂ����āA��ʖ��O�̐����E���Y�E���Y��Ղ̓O��I�j�ꎩ�̂�ړI�Ƃ��ČJ��L�����R�����k�u���l�扻����v�l�ŁA���{�R�ɂ��E�������k�E�������������l�Ă������k�Č������傤�����l�D�������k���������������l�����w���������̌ď́B���{�R�ł����Łk����߂��Ă��������Ɓl���ƌĂB���a15�N�k���̖k�x���ʌR�i�ߕ��ɁA�e�t�c���A���c�����W�߂��āu���ō������{���v�Ƃ̍�햽�߂��������B���߂́u�G�n��ɐN�������ۂ́A�H�Ƃ͑S�ėA�����邩�ċp���A�G�n��Ɏc���Ȃ�����/�Ɖ��͔j��܂��͏ċp���邱��/�G�n��ɂ͐l���c���Ȃ����Ɓv�ł������B

�h�C�c�̑Β��R�����͂́A1927�헪�����ǂ̃}�b�N�X�o�E�A�[Max Bauer�卲���A�Ӊ�Ɖ�k�������Ƃ���{�i���B1928�����R�̕��͂�225�������������A�P�����s���͂��Ă��Ȃ��������߁A�o�E�A�[�͏��K�͂̒��j�ƂȂ�R���̑n�݂��Ă���B1933-1935���C�}�[�����a���̃h�C�c���R���i�ߊ��������[�[�N�g���R�������ɑ؍݂����B�ړI�͒����ɂ����鋤�Y�}�R�̓����A��n�ɂ������p���n�����ƕ���̐��\�e�X�g�ł���B���I�ȃh�C�c�R���ږ�c�����������}���{�ɔh������A�t�H���E�t�@���P���n�E�[��von Falkenhausen ���R�Ȃ�20�����̌����Z��10�����̖��Ԑl����Ȃ��Ă����B��ꎟ���Ńh�C�c�͎R���Ȃɂ����āA���{�R�Ɛ킢�s�k���i���Ă�������A���{�ɑ����U�����S�O������̂͂قƂ�ǂȂ������ƍl������B�����Ƃ̕������̂��߂ɁA1935�f�Չ��HARPO(Handelsgesellschaft zur Verwertung industrieller Produkte)���ݗ�����A�h�C�c�͕���𒆍��ɑ�ʂɋ������n�߂�B1936�ƒ����{�̓n�v��������������B�h�C�c�͒����ɕ�������^���錩�Ԃ�ɁA�����u�f���A�^���O�X�e���ȂǕ��퐶�Y�ɕK�v�Ȋ�����A�����邱�Ƃ���茈�߂����ł���B�����ăh�C�c����P���}���N�̑Β��؊���������������B�O�ݎ����蓖�Ă��\�ɂȂ��������́A���Ί�A�ΖC�Ȃǂ��h�C�c����A�������B�h�C�c�R���ږ�c���A�����}�R�ɁA����A���ɐw�n�\�z�Ɋւ���L�v�ȃA�h�o�C�X�������B1937/8�ȍ~�A��C���ς�싞�U���ŋ�킵�����{���R�́A�h�C�c�̌R���ږ�c�̂������ŁA�{���͓̒����R�ł��拭�Ȓ�R���ł����ƌ����������قǂł������B�h�C�c�ƒ����̎�茈�߂ł́A1937-38�����R20�t�c���P�����邱�ƂɂȂ����������A1937�̏�C���ς̍ۂɂ́A�P�����̎t�c�͂W�t�c�����������B�ĉp���Ƃ��������ɕ��틟�^�A�R���ږ�c�h���A���Ȃǂɂ���ČR���I�Ɍ����ꂵ�A�O��I�ɂ������������߂鈳�͂��|�����B���܂茾�y����Ȃ����A1937/8/21�싞�Œ��\�s�N��������ꂽ�B����́A���{�A�h�C�c�Ƃ����G���ɓ��������܂ꂽ�\�A�ƁA���{�ƍ]��n���ő�K�͂ȓ��������Ă��������Ƃ̋��ʂ̓G�A���{�ւ̑傫�Ȉ��͂ɂȂ�B�����̓\�A����ȑO�ɂ��܂��đ����̍q��@�����ł����悤�ɂȂ����B1936���Ɩh������ɂ́A���N����C�^���A���Q�����A���ƈɎO���h������ƂȂ����B�\�A�̓A�W�A���ʂ̎�G���{�ɑR���邽�߁A���������̒����Ƃ̗F�D�����߂��Ƃ�����B�Ӊ�̔����I���i��m��Ȃ�����A�������Y�}�ɃR�~���e������ʂ��āA��������𑣂��ȂǁA�C�f�I���M�[�Ɏ���ꂸ�ɁA�����̗��v��Nj������B�ƃ\�s�N���A���\�������A�ĉp����̉�������ȂǁA�܂��ƂɃ\�A�O���͕^�ς���B1940/8�������Y�}�́A100�t�c(���{�R�̑���K�͂�10���l���x��)�̕��͂𓊓��A�ؖk�̓��{�R������w�n�A��v�Ȍ�ʋ@�ցE�S���ɍU����������u�S�c���v���s�����B�Ӊ�́A�����R���̎x���A���ې��_�A�̌R���x���������ĂɁu�Ō�̊֓��v�ɂ���čR����̊o��𐢊E�Ɍ��������B�@

���{���A���ۘA���̃��b�g�������c�����\����O��1932/9/15���{�̘��S�����ł������u���B���v�Ƃ̊ԂŁA�V��(���t)�Œ��������B����ɂ����{�́u���B���v�𐳎��ɏ��F�A�������������邱�ƂɂȂ�B�@
���̑�P���́A�u���F���n�������������ԃj�ʒi�m��胒�����Z�T���������F���̈���j���e���{�����n���{���b���J�]���m���x�ԃm���A���葴�m���m��ɋy�����m�_��j�˃��L�X����m�������v���m�F���d�X�w�V�v(�u���F���͏������������Ԃɕʒi�̖��������������薞�F���̈���ɉ��ē��{�����͓��{���b�����]���̓��x�Ԃ̏��A���葴�̑��̎�ɋy�����̌_��Ɉ˂�L�����̌������v���m�F���d���ւ��v))�ƋK�肵�A�u���B���v�����{�̊������v���m�F���d���邱�Ƃ���B�@
��Q���ł́A�u���{���y���F���n���m����m�̓y�y�����j�X����m���Ѓn�����j���m�����m���J�y�����j�X�����Ѓ^���m�������m�F�V���������V�e���ƃm�h�q�j�����w�L�R�g����X�V�J���v�m���{���R�n���F�����j���ԃX�����m�g�X�v(�u���{���y���F���͒��̈���̗̓y�y�����ɑ����̋��Ђ͓����ɒ��̑����̈��J�y�����ɑ��鋺�Ђ���̎������m�F�������������č��Ƃ̖h�q�ɓ���ւ����Ƃ�V�����v�̓��{���R�͖��F�����ɒ��Ԃ�����̂Ƃ��v)�ƋK�肳��A�����h�q����������œ��{�R�����Ԃ��邱�ƂƂ��Ă����B�@
����Ŗ��B�������{�̘��S�����ł��邱�Ƃ������Ƃ��ɖ��炩�ɂȂ������A����O�̓��N3���ɂ́u���B���v������V�Ɩ{���Ɋ֓��R�i�ߊ��̊Ԃō��h�E�����ێ��̓��{�ւ̈ϑ��A�Q�c��n�������ւ̓��{�l�̓o�p�Ɠ��{���ւ̔C�ƌ��t�^������Ă����B�@
�Ȃ��A�����c�菑�Ɠ����Ɍ��킳�ꂽ�閧�����œS���E�`�p�E���H�Ȃǂ̕~�݁E�Ǘ��̓��{���ւ̈ϑ��A�������ق̍q���Аݗ������m�F���ꂽ�B �@

���B���ς̒����ƁA���ԉ������@�����̂��ߔh�����ꂽ�C�M���X�̃T�[�E�r�N�^�[�E���b�g������c���Ƃ��鍑�ۘA���̒����c�B�@
1931/9���{�̖��B�N��(���B����)���J�n�����ƁA�������ɑI�ꂽ���蒆���͍��ۘA���ɒ�i�A��������ۘA��������͓��N12/10���n�����c��h�����邱�Ƃ��v�ō̑������B����Ɋ�Â��đg�D���ꂽ���̂��u���b�g�������c�ł������B�����͗��N2������J�n����A���b�g����s��2�����A�����ɒ����A���{�e�n�����@���āA3/14��C��������A���̌�A��C�E�싞�A�u���B���v�Ȃǂ�K�ꂽ�B1932/10/1�ʍ����ꂽ���͓��{�̖��B�ɂ�����������v��F�߂Ȃ�������{�̍s���Ɓu���B���v�͏��F���Ȃ������B�@
1933/2/14���ۘA���Վ�����ŁA���b�g�����Ɋ�Â��ē��{�R�̐�̒n�悩��̓P���ƒ����̖��B�̓����������F���銩���Ă��̑������ƁA���{�͓��N2/24���ۘA����E�ނ���B�@
 �@
�@���O���R������
�����̎v�f�Ƃ͕ʂɁA���R�͈Ⴄ�ϓ_�œ������������߂Ă����B�������[���b�p�ł͓ƌR�����|�I�D�ʂɂ��A�h�C�c�����[���b�p�ꂵ�Ă��܂��Ƃ����ӌ�����ʓI�������B����͓��{���R�̓ƒf�łȂ��A�A�����J�����������������R�l�������A�����ɂ��Ă͂��Ȃ��������ȑz��Ƃ�������Ȃ��B�h�C�c�����[���b�p�̎x�z�҂ƂȂ�A�������A�����J�ƌ��ꍇ�A���{�͐��E�ŌǗ����Ă��܂����ƂƂȂ�A�ēƂ̗v���ɍR���p�������Ă��܂��B�����Ńh�C�c�Ɠ��������ׂA�h�C�c�ƃA�����J��������Ԃ��Ƃ�W���A�A�����J���������Ă��̊Ԃɓ��m�̎x�z���ł߂邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂����R�̍l���������B�C�R�͍ő�ŋ��̉��z�G���ł���A�����J���h������Ƃ��āA���R���̗�����Ƃ����B

���ǁA�߉q��(���g�͓����ɔ�������)�����҂����C�R���A�����̐l�C�ቺ�������ꓯ���^���ɂ܂�����B�C�R�̖��ӔC�͂�������A���g�Ŕ����Ȃ������߉q�ɂ��d��ȐӔC������B�@
�����Ƃ�����ȑO�ɂǂ�قǓƈɂ��M���ł��A����ɂȂ邩���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����Ƃ̓x�������ƃ��[�}�����ԏc�̐��̂��Ƃ��w���A���{�𐕎����ƌĂԂ̂͌����ɂ͊Ԉ���Ă���B�܂��h�C�c�����Ă݂悤�B�����͖R�������A�H�ƋZ�p��R���͂Ȃǂ͓������E�Ńg�b�v�N���X�̗͂������Ă͂����B�������A�q�g���[�̃A�W�A�l�̎��̎v�z�Ȃǂ��݂�ƁA�{�C�ŐM���ł��鑊��Ƃ͌�����B���ɃC�^���A�ł��邪�A���͂̕s����푈�Ɍ����Ȃ����������l����ƁA�ƂĂ����݂ɂȂ�Ƃ͂����Ȃ��B�܂��A�}�L�A�x���Y��(���d�p���̍m��)���˂̍��ł�����B�@
�ő�̖��_�́A�����Ƃ����{���牓�����ꂽ�ꏊ�Ɉʒu���A���E�푈�ɂȂ������݂��ɋ��͂ł��Ȃ����Ƃ��B���ɑ���E���ł͂����Ȃ��Ă��܂��A�킸���ɐ����͂��h�C�c�Ɖ������������ł���(�𗬂Ɍ�������5�ǒ��A�A�҂����̂�1��)�B
 �@
�@��ABCD��͖�

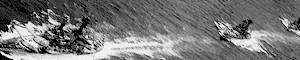 �@
�@��������
��O���߉q���t�͓�i������Ƃ�A���̃C���h�V�i�ւ̐i�����J�n�����B����̓t�����X�̃��B�V�[���{�̗����Ă������A���̃��B�V�[���{���̃i�`�X��̌�̘��S�����ŁA�����I�ɂ͓��{�R�̐N���ł���B���̍s���ɑ��A�����J�́A1941/7/25���{�̍ݕĎ��Y�𓀌������B�C�M���X�����p�ʏ����̔j����ʍ����A�I�����_�̃C���h�l�V�A�����{���Y�̓����ƐΖ�����̒�~�\�B8��1���A�����J�͓��{�ւ̐Ζ��A�o��S�ʓI�ɋ֎~����B�@
�����܂Ŏ��Ԃ��������Ă��܂��ẮA�������܂ސ�̒n����̖������P�ނ����a���̓��͂Ȃ��������A�A�����J���y�����Ă��闤�R�̔��ɂ����������A���������ł��Ȃ��Ȃ����߉q���t�͑����E����B��p�ɂ͍c�����Ƃ��������������A�c���ɐӔC�킹�����Ȃ��،ˍK�����b�ɂ��A���d�h�̓����p�@���w������A����ɂ�蕽�a�̓��͊��S�ɕ�����邱�ƂɂȂ����B
���͂��߂� �@
�{�e�́A���a��Z�N(1941)�̓��Č��Ɋւ���A�V�Ɍ��J���ꂽ�j�����Љ����̂ł���B����Љ��V�j���́A���N�O���ɓ��{�C�R��]�����������R��Y�ݕđ�g�ٕ��C�R�������̓d��ł���B�܂��A�C�R�̐�y�ł���쑺�g�O�Y���đ�g��������Ƃ����u���ʂ̊C�R�����Ƃ��Ăł͂Ȃ��v�P�߂������R�卲�́A�쑺��g�ɂ����̓d���n�����ł��낤���Ƃ́A�z���ɓ�Ȃ�1)�B �@
�����̓d��́A��������}���ق̌����������ɏ�������Ă���u�쑺�g�O�Y�W�����v(�ȉ��A�u�쑺�����v�𗪂�)�ɂ���2)�B�����Ԗ쑺�Ƃɂ͎j�����͕ۑ�����Ă��Ȃ��Ǝv���Ă������A����16�N�A���҂͌�⑰�̌�D�ӂɂ��A�쑺�̈₵��������L�^�̒����������Ȃ����Ƃ��ł��A����ɂ���āu�쑺�����v���������Ă��邱�Ƃ����������B �@
�傫�����L�A�蒠�A�o���A���ȁA�ʐ^����Ȃ��Ă���u�쑺�����v�ɂ́A���j�I�ɉ��l��������̂��������݂��Ă���B���L�ɂ��镶���́A���̈ꕔ���ł���B �@
�Љ�镶���̑����́A�w�҂ɍ��܂Ŋ��ʂ���Ă��Ȃ��������߁A���Č��̏����ɂ�������{�C�R�̖������A�����̔F���ȏ�ɏd�v�ł��������Ƃ𖾂炩�ɂ�����̂ł���B�Ȃ��A�����̕�������A�C�R��]������i�o����ƈɎO�������A�x�ߎ��ςƂ������č�������Ɉ��������Ă������ɂ��ĉ����l�����̂��A���č����ɂ��ĉ����l�����̂������A������x�������邱�Ƃ��ł��邽�߁A�L�͂ȍޗ��ƂȂ�ł��낤�B �@
���̕�����⊮����j���Ƃ��ẮA�O���Ȋ��s�́w���{�O���F���Č���1941�N�A�㊪�x��A��v�ےB�������ҏW�����w���a�Љ�o�ώj���W����\�F�C�R�Ȏ���(12)�x�A�p�c�������ҏW�����w�����m�푈�ւ̓��F�ʊ��@�����ҁx������B���̂ق��A�I�[�����E�q�X�g���[�Ƃ��āA�ǔ��V���́w���a�j�̓V�c�xvol. 30 �ɂ́A���R�C�R�������c�O�Y���R�����Ȃǂ̃C���^�r���[�����^����Ă���3)�B �@
���҂�茩�āA�Љ�镶���̂Ȃ��ɁA���ɋ����[���_�������B�@
��ڂ́A�C�R��������㐬�������ƌR�ߕ������ߓ��M�|�������l����l���ɍ쐬�����u�j��2�v�ɂ���B���̕����́A������u���ėȉ��āv�̑S���A�������͂��̏ڂ�������������Ɋւ�����܂܂�Ă����Ǝv���郏�V���g������̑�����(������������Ă��Ȃ�)�d�M�Ɋ�Â��č\������Ă�����̂ł���B���Ȃ킿�A�u�j��2�v�́A�l���ꎵ���ɖ쑺��g���O���Ȍo�R�Ő��K�ɓ����ցu�ȉ��āv���o4)����O�ɁA���łɊC�R��]�����̏����������m���Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ���B���̓_�ɂ��ẮA�J���t�H���j�A��w��Pacific Historical Review�Ɍf�ڂ����\��ł��钘�҂̘_���ŁA�ڍׂɕ��͂���Ă���5)�B���̂��߂����ł́A�쑺��g����������Ɨ����A�ƒf�Łu�ȉ��āv�쐬�Ɋ֗^���Ă����Ƃ����w�҂̒ʐ��I�����́A���ƂȂ��Ă͂܂����������̂Ȃ����̂ƂȂ����A�Ƃ����ɂƂǂ߂Ă���6)�B �@
��ڂ̋����[���_�́A�u�j��5�v�Ɓu�j��6�v�ɂ���B�����̕����́A�܌������Ƀ��V���g����g�قɑ���ꂽ�A�u�ȉ��āv�ɑ�����{���{�́u�C���āv�Ɋ֘A���Ă�����̂ł���7)�B�悭���m�ł��邻�̓�̈Ă̑��e��Ȃ����e�ɂ��Ă̕��͂ɂ́A�����ł͗�������Ȃ����Ƃɂ���B�������A�u�C���āv�����쑺��g�́A�n��(Cordell Hull)���������ɒ�o����O�A�O�������ɂ����{�̑ΓƌR�������`���������Ċm�F����鎚�����8)�B �@
����͊m���ɁA��g�Ƃ��Ă̌�������E����s���ł���B�����̊w�҂����́A�쑺���u�A�����J�̗�����l���v���邤���ŁA�u���̖쑺�����̂悤�Ȃ��Ƃ������̂����R�Ƃ��Ȃ��v�ƁA���炭�^�₵�Ă���9)�B �@
�܌�����ɍ쐬���ꂽ�u�j��5�v�́A���́u���R�Ƃ��Ȃ��v�^�������������Ă����ł��낤�B�v����ɁA�쑺�͂��̍s���ɂ���āA�܌�����Ɂu�ēƊJ�푦���ĊJ��g�l�t���n�c���Y�v�Ǝ咣�����C�R��]�ƁA���ƕs���_�҂ł��鏼���m�E�O���Ƃ̌��ꂽ�Η����A�����N�������Ƃ��Ă����̂ł��낤�B���̍H��͎���Ȃ��������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�u�j��6�v�́A�쑺�̏C���Ɋւ��銩�����܂܂�Ă����Ǝv����A���R���������(������������Ă��Ȃ�)�d��ɑ���C�R�̑Ή��ł���B�܌�����ɎO�������ɑ��錜�O��\�����C�R��]���A�܌���O���Ɋ��S�ɗ����]�����A�ΕđË���s�\�ɂ��鏼���O���Ɓu���S�j��v�v���Ă���A�Ɓu�j��6�v�ł͏q�ׂ��Ă���B���T�Ԍ�A�ƃ\�J��ɑ���Ή��Ƃ��āA���{���{������i�o(�암����i��)�����肵�A�����Ă���ɑ����Đ��{���Γ��S�ʋ֗A���s�����B���{�C�R�ɂƂ��āA�u�j��5�v�ɏƂ炷����A�S�ʋ֗A�̒f�s�͑ΕĐ�ւ̓˓����Ӗ�����10)�B �@
���_�Ƃ��āA���L�ɂ��镶���ɂ���āA�^��p�U���O��̓��Č��Ɋւ���V���Ȏ��p��ݒ肷�邱�Ƃ��ł��A���̂��߁A���Вʓǂ��Ă������������B �@
���j�� 1�@
�C�R�����L�c�原�Y���쑺��g�� �@
(���t�͕s���ł��邪�A�쑺���O�������ɔ��������O�Z���̓d��11)�Ɍ��y���Ă��邽�߁A�O�����O��ɔ��������̂ł���A�Ɛ����ł���B�Ȃ��A�N���҂��s���ł��邪�A�d��̕�������l���ĊC�R�̏o�g�҂ɂ������Ȃ��B����Ɋւ��āA���̕����́A�쑺���s��㎷�M�����w�č��Ɏg���āx�����y���Ă���A�L�c�原�Y�C�R�����Ɩ쑺�Ƃ̊ԂŌJ��L����ꂽ�A�����m�E�O���̓n���Ɋւ����A�̂����̈�ł���\���������ł��낤12)�B) �@
��A�߉q���t�ސw���ϐ��m�@�L�n�c��I���j���e�a�C���ă��j�֘A�V�ꕔ�j���z�T���^�������������j�t�L����m���j�j�˃����m��g����ᶗ̓A���V�g���ؖ]�X �@
��A�����O���n���j�փV�e�n�O���Ȍ��\�m����A����������m�ړI�n�ƈɎ�]�g��ʊO����j�t�L�u�Ӗ��L���k�����Qᥓr�u���X�R�[�v�j���e���h�W�������Z���g�X�����m�j�V�e�T�l���m�ʃ� �@
(�C)�u�q�g���[�v�u���b�u�x���v�u���b�\���j�v�u�`�A�m�v�g�Ζʌl�I�ڐG���[���e����m�O���j���X �@
(��)�u�q�g���[�v�u���b�\���j�v�m�Γ��ԓx���Őf�X���g���j�׃V�����o�Ήp�㗤��퓙�j�փX���ƃm�����˃L�~�� �@
(�n)���o�c�j�փX���u�q�g���[�v�m���Z(�ƃn�ʓI�j�u�a������Z���g�X�������n���ۉ�c����}�X������)�����L�E�j�V���m���{�m���ꃒ�L���i���V����������V�u�N�R�g �@
(�j)�Ύx�a���H��y�Αh�����j�փV�׃V���������ƃ����p�X���R�g �@
�O�A�E�j�փV�C�R�����O���j �@
(�C)�ƃm�ꕔ�j�n�ƃm�t�G�U���j�N��V�鍑���V�e�ɓ��p�̃��U���Z�V�����g�X���Ӛ��A���l�̃i����(�R���@����l��l���R�ߕ��@����O�l���ԓd�Q��13))�E�j�n���ӃV��L�R�g �@
(��)�隠���{�����j�d��_�Η��V�A���K�@�L��ۃ��o�t�������n���j�T�}���x�R�g�����N�v�]�V�A���l��l�ԓd14)�m�ʃ��j�V�e�v�X���j�C�R�g�V�e�n�������j�n��Δ��j�V�e���O������Ȏ@�V�Ƀ��e�������c�i�������������V���{�j���̓V�A������j�V�e�Θň�j�V�e���{���j���ȃe�i�~��������i���@��Q�l�� (����O���j�փV�e�n���ɋM�g�����m�܃~�g�Z�����x) �@
�l�A��s(�C�R�������V���䒆�������V�A��)�n�\����������l������ᥒ��m�\��A�V��j�˃��ƈɑh���m�O�n�m�����������j�����R�g�A�� �@
�܁A���������m�n�ăj�փV�e�n�����m��ǎ��v�X�x�L����j�˃����j�R�ߕ��������Ń`���Z�m�הh���m�\��15) �@
�Z�A�p�ăm�W�j�փV�e�n�S�N�M���j���Ӄj�V�e����j���e�p���@�L�����ăg�F�D�W���ۃ^���g�X���@�L�R�g�n�����c�ǃj���e�n�S�R�l�w�����U�����j�V�e���m���j�j�e�S�̃��w���Z�����c�c�A�� �@
���A�M�d���O�Z��16)�u�n���v�g�m��k�m�ۃj���P���u�V���K�|�[���v����j�X���隠�m�ԓx�j�փX���M�g�m��V�n�S�N�����j�V�e�����j���e�n�E���j�j���j�����V�c�c�A�� �@
���j�� 2�@
�C�R��������㐬���E�R�ߕ������ߓ��M�|���ݕđ�g�ٕ��C�R�������R��Y�� �@
�l���\�l���������������� �@
�M�d�m��|�n���������Ӄj�V�e�đ��K�M�d��O������X���j�Μ�V�e��������n�T�l���17)���ȃe���Z���g�X����|�n���X�j�K�V�^�����m�g�F�������ȃe���z�ȑ�l���ԓd18)�m�W���A���V�K���i�j��w�m�w�̓��v�T�����R�g�����҃V�A���E�C�R�����m�ӌ��g�V�e��g�j�B�w�����x���V�e�{���m���n�Ƀ��e�T�d�i�����v�X�����ȃe�߃j�䑶�m�m�R�g�i�����M���n���L������O�m���g�m�㍲�j�⊶�i�L�����Z�����x �@
��A���č����n�푈�s�g�僒��g�X���O�������m��|�j���q�s�n���x�L���m�j�V�e���ۖ{�����m��|�g�����Z���鍑�O����j�m��]���i���g�m��ۃ����[�V���U�����v�X�A �@
��A�哌���j���P���鍑�m�w���I�n�ʕ��j���������Ԑ��m�m���n�������q��m�v���j��L�鍑�s���m����j�V�e���ė����X�����E�鍑�X�j�Q�T�U���͈̓^�����v�X�A �@
�O�A�x�߃m�匠�����d�V�̓y�s�������m�F�X���n���x�w�L�i�L���č����V�e�x�ߎ��σj�e�[����Z�V�����n�����j���P���鍑�m�n�ʃj���h�Z�V�����[���g�i�����ȃe���x���ڌ��m������j�n�V�������X�����v�X(���z�ȑ�l���ԓd�Q��19)) �@
�l�A����j�V�e�n�鍑�n�o�ϓI���W����}�V�A���e���͎�i�j�i�E���Ӑ}�i�L���������V�e�鍑�����o���V�������m��j��i���x�გ�҃^�X��i�L�l�V�K�\���j�փV�e�n���j�T�d�����X���m�v�A���A �@
�܁A�č��n�����݈�m�ꍇ�j���w���K���F�V�����T��n���Q�����ʃj���e�s�ӑΓ�����������V�݃Z���g�V�c�T�A���g�F�������m���E�n�鍑�g�V�e���q��ى߃V���U�����i�����ȃe���č����j�����e�n�{�������R�l���X�x�L���m�g�F�� �@
�Z�A����m��������ǓI�ԓx���ȃe�X�����č����m��}�K�����X���o�p�b�e�ރ������Z�V�����m���ʃ��҃^�X��A�����ȃe�鍑�K���č������ŗ��V�A���K�@��ۃ��o�w�U���l���Z�p�㗯�Ӄ��v�X�A �@
���A���ۃm�Q����~�m���n���m��|�j���e�S�R�W�Ӄi�����V�K�\�����@�n���O�j�y�{�X�e�����l���V���j�T�d�����X���m�v�A���ǃe�����g�V�e�n���ăn���X�ٔ��V�c�T�A�����č����n�V���K�v�g�X���n�ܘ_�i�������ێ{���T�d�����X���R�g�̗v�g�F���A�� �@
���{�������������_���A�O�j�A���V�A���Y�O�m�� �@
���j�� 3�@
�C�R��������㐬���E�R�ߕ������ߓ��M�|���ݕđ�g�ٕ��C�R�������R��Y�� �@
�l������������������ �@
���č����j�փV���C�R���j���@��ߑ��V�T�l�l���ꎵ�����쑺��g�d�j�˃��M�n�ă���b�g�V���ĊW�������X���R�g�j�ӌ���v�V�A��20)�A�V���t�j�A�e�n�����C�����v�X�����m�A�����E�j�փV�e���߃j���C�R�ԃj���e���������V�O�������j�W�ӌ��j�V�e�{��\��������O���m᥋����փ`�ԓx���j�C����������������m��P�ߔ��o�m�^�r�g�i�������~�i�� �@
���j�� 4�@
�C�R�����V�{���Y�E�R�ߕ������ߓ��M�|���ݕđ�g�ٕ��C�R�������R��Y�� �@
�܌����ᢕԓd �@
�����j���P������m�������R�d�m�ʃ��i����21)�O���������{�c���{�A����c�J�ÃZ�����\��j�t�č����j�P�ߔ��o�m�����g�i�������ǃe�C�R�m�C���ӌ��n__�@��914�d22)�m�͈̓��o�c�����m�j�A���T�������{�m����j�旧�`�V�������X���n�K���i���T���j�t���S�t �@
���j�� 5�@
�C�R�����V�{���Y�E�R�ߕ������ߓ��M�|���ݕđ�g�ٕ��C�R�������R��Y�� �@
���a�\�Z�N�܌���������A���� �@
���m�����l���m��ăm�߃N�������g�X���ΓƑΓ��������j�փX���M���m�ώ@�����e���}�A���x �@
��A�O�����j��L�隠�m�ΓƌR�������`���n�@�I�j�n�ăK�ƃj�U���V�^���ꍇ�j�m�~ᢐ��X�����m�j�V�e���V�����ۖ�胈���X�����ēƊJ��m�ꍇ�隠�K�����x�L�ΓƉ����m���@⍃j���m���@�n�隠�Ǝ��j�V������V���x�L���j�V�e�ēƊJ�푦���ĊJ��g�l�t���c���Y�@�R���h���ēƊJ��X�����ۃ��j�S���Y�ăK�Γ��S�ʓI�֗A���s�t�ꍇ�j�n���ĊJ��s���g�i���x�V�@���m���n�j���e�ăm�Q��A�s�Q���N�n���{�m�O�������p���A�s�p���n���Ęa�탒���X�����{�v���g�n�i���Y�@�J���č��K�S�ʓI�֗A�m�Γ������m�[�u�j�o�Y���R�g�R�\���Ċԃm��@�����m�ő匴���i���@�@�ăm���ȃ��K�v�g�X �@
��A�M���ϑ��j�˃��o�����ăm�Q��n�K���j�V�e���J�X�x�J���U���K�@�L���ʃV�e�R���o���č����j�˃��č��m�Q�탒�j�~�Z���g�X���ړI�n��݃j�A�X�x�N�@�t�j�ă��V�e���B�Q��m�ꎞ���ăm�W�������Z���V�@��]�������X�����ʃj�׃��x�V �@
�O�A�ŋ߃m���ޑɁE���B���j�Γ��Ë��I�ԓx�����V�҃������j���B�J���}��n�������ݕs�N����X���@�閧���j��ăV�҃����@�����j�ēƊJ�탒�ے��X�����m�j�V�e�č������m����n�E�m�@�N�p���m��@�j���ʃV���m��j���V�A���g���F�����������j�V�e����j�O�������m�^�p�j�փX���鍑�m���M�g���Ɖ��V�@���ے鍑�g�V�e�n�ŗ��X���R�g�i�N�B�R�^���ԓx�������V�e�������V�e���č����n�푈�s�g��j���o�X�x�L���m��|�j�˃������V�N���ȃZ�V���@���m�Ήp�s�L�߃M���}���X���j�w�������v�X�g�F�� �@
�l�A�����č��m�����x�L����j�փV�e�n�ďB������c�m���_�^�����������m�Q�탒���P�ň��m�ꍇ�j�݃��e�������͒����ȃe�X���쑗�m���{���x�i���x�L�T�|�n�����j���e�����ɁW���j�V�e�E�ȊO�m�H(�܂�)������Z�o�ΓƐ��Γ��ϋɍ����������Z�n���V�g�F���A�� �@
�܁A�鍑�m�����x�L�ԓx�n�����j�����������R�g�i�N�Ǝ��m����j���e���Ɖi���m�ɉh�g���E���a�g���m���X���j�A���@���鍑�K�ƈɃg�����r�h�A�M�g���a�V�X�j�ăg�������Z���g�X�����ȃj�V�e�@�ăm�D�����j�V�]�b�e�O�������������X���R�g�\�n�T���g���j�鍑�m���Q�������V�k���j�ƈɃj�����������K�@�L�R�g�i�L�n���Ҍ����v�Z�U�����i���@�鍑�K�ăg�a�Z���g�X���M�Ӄn���s�σi���g���j�W���j�ăg���σV�N���m�M�Ӄ��L�X�x�L�����҃X�����m�i�� �@
���j�� 6�@
�C�R�����V�{���Y�E�R�ߕ������ߓ��M�|���ݕđ�g�ٕ��C�R�������R��Y�� �@
�܌��\�O�������������� �@
���\����m�l���������A�����k��j���e�����O���n�鍑�C���ăm�u���C���v�j���e���č����j�őP��ᶃX�x�L�|���M�����l�Z��23)�E�鍑�m�C���ăn�����������C�O�O�Ȋԃj���S�j�ӌ��m��v�����^�����m�i���j�t�E�O�~�m���g���㍲�V�e�C���ăm�{�|�ѓO�����V�w�̓A���x������m���M���j���P����j�փV�e�n�R�m�㋤�ב�g�i�N����A���x �@
���� �@
1) ���R��Y�w�C�A��F���R��Y�C�R������z�^�x(�����[)�B �@
2) ��������}���ٌ����������ɂ���u�쑺�g�O�Y�W�����v��2008�N3�����J���ꂽ�B �@
3) �O���ȕҁw���{�O���F���Č��A1941�N�x(�O���ȁA����3�N)�A�㊪�A�G��v�ےB�����ҁA�w���a�Љ�o�ώj���W����12���F�C�R�Ȏ���(12)�x(�哌������w���m�������A���a62�N)�G��t���v�A���ї��v�A���c�r�F�A�p�c���ҁA�w�����m�푈�ւ̓��F�ʊ��@�����ҁx(�����V���A���a38�N)�G�ǔ��V���ҁA�w���a�j�̓V�c�x(�ǔ��V���A���a49�N)vol. 30. �@
4) �O�f�A�w���{�O���F���Č��x�㊪�B �@
5) Peter r Mauch�A �gA Bolt from the Blue? The Imperial Japanese Navy and the Draft Understanding between Japan and the United States�A April 1941�A�h Pacific Historical Review�A forthcoming. �@
6) �ʐ��I�����̑�\�I�Ȃ��̂Ƃ��āA�גJ�甎�u�O���Ȃƒ��đ�g�فF1940�|41�N�v�גJ�甎�A�ē��^�A���䐴��A�X�R���Y�ҁA�w���ĊW�j�J��Ɏ���10�N1931�|41�N�x(������w�o�ʼn�)�GRobert J. C. Butow�A The John Doe Associates: Backdoor Diplomacy for Peace�A 1941�A (Stanford�A Ca.�A 1974) ���Q�Ƃ̂��ƁB �@
7) �O�f�A�w���{�O���F���Č��x�㊪�B �@
8) �쑺�g�O�Y�w�č��Ɏg���āF���Č��̉�ځx(��g���X)�B �@
9) �{�����u�A�w���ĊJ��O���̌����F���Č��̔��[����n���E�m�[�g�܂Łx(�c��ʐM)�B �@
10) ���{�C�R�̊J�팈�ӂɂ��āA���c��Y�A�w�����Ԃ̓��ĊW�F�C�R�Ɛ���ߒ��x(������w�o�ʼn�)��A�g���쐟�Y�A�w�u�哌���푈�v�̎���F�����푈������ĉp�푈�ցx(�����o�Ŏ�)���ł��ڍׂȌ����ł���B �@
11) �O�f�A�w���{�O���F���Č��x�㊪�B �@
12) �O�f�A�w�č��Ɏg���āx�B �@
13) �R���@����l��l�ԓd�́A�s���ł���B�������A�R�ߕ��@����O�l���ԓd�́A�O�f�A�w���a�Љ�o�ώj���W����\�x�B �@
14) �R���@����l��l�ԓd�́A�s���ł���B �@
15) �����ɗ\�z����Ă����������������̓n�ẮA����Ȃ������B�������A���R���⍕���Y�卲���A�����J�ɔh�����������ɁA�C�R�����������̓n�Ăɂ��čl�������Ƃ́A�����[���ł��낤�B �@
16) �O�f�A�w���{�O���F���Č��x�㊪�B �@
17) ���V���g���d��Ƒ�O���́A�s���ł���B �@
18) �O�f�A�w���{�O���F���Č��x�㊪�B �@
19) ����B �@
20) �O�f�A�w���{�O���F���Č��x�㊪�B�u�ȉ��āv�ɑ��闤�C�R�̈ӌ��Ƃ��ẮA�O�f�A�w�����m�푈�ւ̓��F�ʊ��@�����ҁx���Q�l�B �@
21) ���R�d�Ƃ́A�����炭�쑺�́w�č��Ɏg���āx�ɏ���Ă���ݕĊ⍕���Y���̓d��ł���B�O�f�A�w�č��Ɏg���āx�B �@
22) �@��914�d�́A�s���ł���B �@
23) �u�܌��\������O��A�����k��v�O�f�A�w�����m�푈�ւ̓��F�ʊ��@�����ҁx�B�@

��������D���c�����u���N��́v�����i�߂��Ă������N�ɂ����āA���̎d�グ�Ƃ��čs��ꂽ�V���ȓ��{���u���v�̑n�݂Ɠ��{���u���v�ւ̉�����������������B1939/11/10���N���{(�쎟�Y���N����)�͐��ߑ�19���u���N�����ߒ������m���v��20���u���N�l�m�����j�փX�����v���z�A1940/2/11���{�s�����B���N�l�̖��O�́A��c�̏o�g�n(�{�сE�ق�)�ƒj�������������W���ł���u���v�ƌl�ʂ́u���v���琬��A���O�͏I���s�ρA�v�w�ʐ�(�Ƒ����ɕ����u���v����)�ł��������A�n�������͑S���N�l�ɑ��āA�]���́u���v�Ƃ͕ʂɁu���v(�Ƒ��͓���u���v�̂�)�����A���{���Ɂu���v�����߂邱�Ƃ��Ӗ������B�n���͖@�I�ɋ�����������͔C�ӂƂ��ꂽ���A�����ɂ͉����������㋭�����ꂽ�B5000�N�̒��N������ے肷�鐭��́A���N�����Ɍv��m��Ȃ���ɂ������炵�A�͏o���Ԃ�1940/8/10�܂łɖ�8��322���˂̑n���������Ȃ��ꂽ�B�R�c�̎��E�A���{�l����������������u�����H�q�v�u���n���v�Ȃǂɑn���������Ē�R����l�X�������B�n���̓͂��o���Ȃ��ꍇ���A�]���́u���v���V�����u���v�Ƃ���A�������ō��ʂƋs�҂��J��Ԃ���A���̖ړI�͉Ɛ��x���؍���������{���ɉ��߂邱�Ƃɂ������B�@
1936/8���N���ɏA�C�����쎟�Y�́A���̒���ɐ_�ЋK�����������A�P�W��(����)1�Ђ�ڕW�ɐ_�Ќ��݂��s���A1937/7/7�����푈�J�n���疈��1���������̓��Ƃ��Đ_�ЎQ�q�����������B���N10���u�c���b���̐���(������)�v���߁A�w�Z�E���������͂��ߑS�Ă̐E��ł��̏��a���`���t���A���N12��23���S���N�̏����w�Z�ƒ��w�Z�Ɍ�^�e(�V�c�E�c�@�̎ʐ^)�������A���̓`�B�����s�����̍c�����u���N��́v������(�������Q�I�������{�l�Ɠ���������ۗL���邱�Ƃ͔ے�)�𐄂��i�߂��B1941/3/31�����w�Z�ł̒��N��ɂ��w�K��p�~�A1943�ɂ͕���@�����������N�ɒ��������{�s�����B
 �@
�@���R��
 �@
�@���⋋
������A�⋋���y�����錾�t�Ƃ��āu�G���^�v�Ƃ������t������B�v�͓G�̕����̗��D�ł���B�G���痪�D����Ȃ�܂������A�G�w�ɒ����܂ł́A�t�߂̏Z������D���̂ł���B�u���q�v�ɂ��u�q���͖��߂ēG�ɐH�ށ@�G�̈��(��)��H�ނ͂킪��\��(��)�ɓ�����v�Ƃ����L�q�����邪�A����͍q��@�������Ԃ�����2500�N�O�̏t�H����̘b�ŁA�����̐틵�ɂ͒ʗp���Ȃ��B����������̍��X�͔_�ƍ��Ƃ͂����A���≌���Ȃǂ���̂Ƃ����v�����e�[�V�����_�ƂȂ̂ŁA�����ɐH������ɓ����ł͂Ȃ��B�t�B���s���Ȃǂ͍����̑唼��A�����A1944�L�^�I�ȋ���Ɍ�����ꂽ�x�g�i���ł͓��{�R�̋��������ɂ��A200���l���쎀�����Ƃ���Ă���B�����ł͓��{�R���(���Ȃ��̈�)�R�ƌĂ�A�Z���̋��|�Ɣ������Ă�ł����B�@
�⋋�ʂƂ͕ʂɁA�Z���̍��݂��_�ł����̐�p�͎��s�ł���B���n�l��G�ɉď������R���͗��j��قƂ�ǂȂ��B��t�c�Ƃ͂����A�������ꖜ�l�O��ł���W�܂��ČR�c�ƂȂ����Ƃ���ŁA100��-���̒P�ʂŋ��Z���錻�n���ɔ�ׂ�ЂƂ��܂���Ȃ��B���{�͗��D�����ł͂Ȃ��A���ꋭ���ɂ�镶���N���������Ȃ��Ă���A�Z�����Q����������͕̂K�R�ł������B�����̋������{�ꋳ��ɂ��āA����Q�d�́u���t�����N���U�߂����A�����̖���'�����'���g�킹��悢�ƌ��������A�䂪�R�����̐S�ӋC�ł���v�ƕ������Ă���B�ނ͖L�b�G�g�̒��N�o���̔s��(�Z�����R�ƒ��N���R�ɂ��⋋���̐ؒf)��m��Ȃ������B

�@�@�@�@�@�@�@�ΒY�@�@�@�@�@�@�@�Ζ��@�@�@�@�@�@�@�|�� �@
���{ �@�@�@�@71,630 �@�@�@�@�@ 142�@�@�@�@�@�@�@4,720�@
�A�����J�@�@505,489 �@�@�@189,985 �@�@�@�@�@ 75,184(�N�Y�z�\�P�ʐ�g��)�@
���̂ق��A�����J�͒���āA�J�i�_�A�I�[�X�g�����A�A�p�̐A���n�Ȃǂ̎��������R�Ɏg����̂ɑ��A���{�͂��ꂩ�����������l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�܂��l���ɐ��������Ƃ��āA���{�̑��D�\�͂ł͂����̎����������A��͍̂���ł���B
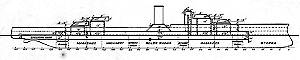
���{ �@�@�@�@336���g��(1941/12-45/8�܂�) �@
�A�����J �@10116���g��(1940/7-45/8�܂�) �@
�J�퓖���A���{�ɂ͌�q�͑������݂��Ȃ������B1942/4�ɑ�1,2��q�����ݗ�����A1943/11�C���q���i�ߕ������������B��q���̍q���(��901�q���)���ł���̂́A����1������ł���B�����������{�Ɍ�q���̊͒��͂Ȃ��A��O�͖k�m���ƕی�̂��߂ɂ������C�h�͂�4�ǂ����������ŁA���ꂪ���D��q�Ɏg��ꂽ�B���Ȃ݂�5�ǖڂ̊C�h�͂��v�H�����̂�1943/3�ł���B���܂�ɒx������Ή��ŁA���̕������܂��n�ゾ�����B���̌�A1944�ɂ�101�ǁA1945�ɂ�50�ǂƑ呝�Y���ꂽ���A�}���̂��ߕ����A���͂ɑ傫�Ȗ�肪�������B�����ʂł͑�C��債���ς�ł��Ȃ������͂ɊC��퓬�ŕ����A���͂ł͓ݑ��̂��ߗA���D�ɂ��Ă����Ȃ��ᐫ�\�Ԃ�ŁA���̖̂��ɗ����Ȃ������Ƃ�����B�����ŊC���q���i�ߕ��͍����쒀�͂̋��͂�A���͑��ɋ��߂����A�͑�������d������A���͑��͔͓I�ŁA�Q�����̋쒀�͂⋌���͂��o�����肾�����B�ŏI�I�ɓ��{�̗A���D�̔�Q��843���g���ɂ̂ڂ����B�@
�܂��A���D�͌R�������̗A���ȊO�ɍ����̖����ɂ��s���ŁA���@�̌��ς���ɂ���300���g���̑D���Œ���K�v�Ƃ���Ă������A���̌v�Z���Ⴂ�E������ӂŎd�グ�����̂Ƃ����B1943/1�ɂ͂��̍Œ�C�����犄��A�푈�o�ς��j�]���鎖�Ԃɂ�������B�I�펞��166���g���܂ŗ������݁A�����̌o�ς͊��S�ɒ���Ă����B���Ȃ݂Ɍ���ł͖�3000���g���̗A���D���g�p����Ă���(�A���ʂ�1�ǂɂ�10�{)�B�@
�×��⋋���y�������R���̖��H�͔ߎS�Ȃ��̂ŁA����E���̑��͐�I�Ȑ����ƁA���{�̒n���I�������ɔߎS�ȕ��S�������邱�ƂɂȂ����B���̓_�ŊC�R�͐푈�o�ςƂ������̂�S���������Ă��Ȃ������Ƃ�����B
 �@
�@������
�n���C�A�I���t����10�l���X�p�C�𑗂荞�������邪�A�X�p�C�Ƃ��Ď����Ⴍ�A�v���Ƃ�������̂͂قƂ�ǂ��炸�A���Lj�Ԗ��ɗ������͓̂y�Y���̂̊G�t���ŁA�^��p�U���̂Ƃ��́A���̊G�t���̃R�s�[���e�p�C���b�g�Ɏx������đ傢�ɖ��ɗ����Ă���B���̏ꍇ�͓G�̖��f�ɋ~���Ă���A�A�����J�ɂ����\�Ȗ��f������������������B�@
�ł��L���ȏ��R�k�̓~�b�h�E�F�C�C�킾�낤�B�������{�C�R���g�p���Ă����c�Í��͖��������Ƃ������̂�p���A���_���Ǖs�\�Ƃ���Ă������A���ۂ͗L���������g�p���ꗝ�_���lj\�ł������B���̏�A�������ꂽ������(��124)����Í��\����肳�ꂽ���߁A���ڕW���~�b�h�E�F�C���ł��邱�Ƃ���ǂ���Ă��܂��B���R�k���s���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�����ł��Ȃ��s����1�ɋ����邱�Ƃ��ł���B�������R�k���Ȃ���~�b�h�E�F�C���͊ȒP�ɐ�̂ł�����������Ȃ��B�����悤�Ȍo�߂ŁA�A���͑������̎R�{�\�Z�叫�̏�@�����Ă���Ă���B�@
���y���̕����́A����������瑱���A��A�����G�镗���݁A�n���ŏo���ɂȂ���Ȃ���Ƃ𑽂��̌R�l���������̂������ł���B
 �@
�@���Z�p�́E�H�Ɨ͂̊i��
���Ƀ��[�_�[�J���̒x��͒v���I�ŁA���ꂪ�X�̊C��̎�s���Ƃ�����B���{�̋Z�p�W�҂��A�J���w�͂�ӂ�Ȃ��������A�R�l�̖��������傫�ȖW���ƂȂ����B�C�R�̂Ȃ��ɂ͉�������G�������čU�����邱�Ƃ���A�ڋ��҂��g������ƕ��̂���R�l���������Ƃ����B�܂����R�Ɏ����ẮA���[�_�[�����҂�P�ɐ��l�Ƃ��Ē������A���@��Ɏg�������肵�Ă����B�P���ȋZ�p�̒x������邱�ƂȂ���A���������R�S�̂̌y�����A���[�_�[(���{�ł͓d�g�T�M�V�A�d�T�ƌď�)�J���Ɉ��e�����y�ڂ��Ă����Ƃ�����B�@
�q��@�Ɋւ��ẮA���Ȃǂ̗D�G�Ȑ퓬�@�����݂������A�푈����ɂȂ�Ƃ��̗D�ʂ����ꐧ��D��ꂽ�B���̗v����1�ɓ��{�̍q��@�S�̂̑��b�̔����ɂ���B���{�̐�p�v�z�͍q�������Ƌ�퐫�\���d�����邽�߁A���b���]���ɂ��Ď��d���y������������Ȃ������B�@
���{�C�R�ƕĊC�R�̎�͊͏�퓬�@�̏d�ʂƔn�͂��r���Ă݂�B�@
�q��@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�G���W���n��(hp)�@�@�d��(kg) �@
�뎮�͏�퓬�@21�^ �@�@ 940hp �@�@�@�@�@�@�@�@2410kg �@
F6F-3�w���L���b�g �@�@�@�@2000hp �@�@�@�@�@�@�@�@5643kg

�ΏƓI�ɕČR�̓p�C���b�g��厖�ɂ��Ă���B�l�����d�����邱�ƂȂ���A�p�C���b�g�̑������傫�ȑ㏞���Ƃ��Ȃ����Ƃ��Âɔ��f���Ă�������ł���B������l�O�̃p�C���b�g���琬����̂�2�N�̍Ό��Ɩ�75000�h��(�����2���~)�̔�p���K�v�Ƃ���Ă����B���{�R�ɂ�����𗝉����Ă����l�Ԃ��������A�G���W�����\�̒Ⴓ�ƁA�n���҂łȂ��Ǝ��E�ɓ������y��������������@�A�����Đ��_��`�����b�𑝂₷�̖W���Ă����B�Z�p�̒Ⴓ��l���ŕ₤�����Ȃ��������{�R�̔ߎS����\����ł���B�����āA���̎v�z�͋��ɂ̎��E�U���ł���u���U�v�ɂȂ��邱�ƂɂȂ�B�@
�l����ł��鏬�e�́A����38�N(1905)�ɐ����̗p���ꂽ�O���������e����Ɏg�p����A���܂�o���̂悢���̂Ƃ͂����Ȃ������B���̏e�͐v�}�̏�ł͗D�G�Ȃ��̂Ƃ���Ă��邪�A�����e�ǂ����̕��i�Ɍ݊������Ȃ��l�X�Ȗ������������B�����̓��{�̍H�ƋZ�p�ł́A�K�i�i�̐����͂���قǓ�������̂ł���B��������ȑO�ɖ�������̂��̂�1941�Ɏg�p���Ă������{���R�ɂ͋�������ł���B���̏��e�̐��\�̒Ⴓ�A����������Γ��{�̍H�Ɨ͂̒Ⴓ���u�o���U�C�U���v�̗v���̈�Ƃ�����B

�H�Ɨ͂̊i���ɂ��ē����̓��Ă̕��퐶�Y�ʂ�������B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{ �@�@�@�@�@�@�@�A�����J �@
���e���Y�� �@�@�@�@260�����@�@�@�@�@ 1700���� �@
�ΖC���Y�� �@�@�@�@�@3���� �@�@�@�@�@�@30���� �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{ �@�@�@�@�@�A�����J �@�@�@�@�@�C�M���X �@�@�@�@�h�C�c �@
�q��@���Y�� �@59000�@ �@�@�@262000�@ �@�@�@96000�@ �@�@�@�@93000�@ �@
��Ԑ��Y�� �@�@�@4000�q �@�@�@�@76000�q �@�@�@28000�q �@�@�@�@27000�q (1941-44)�@
�\�A�̐�Ԑ��Y�ʂ�83000�q�ƃA�����J���������̂��ł���(���{�͂��̂悤�ȃh�C�c�̋@�b�t�c������������悤�ȍ��ƃm�����n���Ő�Ԑ��������)�B�q��@�͂܂�����(�������y�퓬�@���헪�����@�������ɐ����Ă���̂ɒ���)���̐�Ԑ��Y�ʂ̍��ɂ͋��������B��Ԃ̐��\�ʂɂ����Ă͂����ƂЂǂ��A���{�̒���Ԃ͏��O���̊�ł͌y��Ԉ����ŁA���B����œƐ�ԂɎU�X�Ȗڂɑ������Ď�͐�ԃV���[�}�����A�����m����ł͂قږ��G�������B���ۊ�A���E�̏펯�ɑ傫���x��Ă����̂��A�����̓��{��Ԃ��B
 �@
�@�����ɂ�������_�@

�ړI/�ΕĐ�����S�������{�́A�����m�ۂ̂��ߓ���ւ̐i�o���ő�ڕW�Ƃ����B������̂��߂ɂ͕đ����m�͑��̋@��𐧂��A��������ł��ׂ��Ƃ��āA�R�{�\�Z�A���͑��i�ߒ��������d�Ɏ咣�������ł���B���{�R��Q/�q��@29�@�@���v�A������q��5�B�ČR��Q/���v�A���5�A��j�A�y��1�A�쒀��3�A���j�A���1�A���j�A���2�A�q��@479�@�B �@
���_/�ő�̎���́A���z������Ɋ�P�����������ߔڋ��ȓ��{�l�Ƃ��ăA�����J�����̓{��������ł���B�܂��A�^��p�̑��D����Ζ��^���N�Ȃǂ��Ŏc�������Ƃ�A���ӂɑ��݂���͂��̋����Ȃǂ̃~�X���ڗ��B����͎�Ɏw�����̓�_�����̃~�X�ł���B���̐��E���̋�ꕔ���̎w�����ɑI�ꂽ��_�����́A�{������(������)���̌R�l�ł���A�C�R���̏���l���ɂ��ނ��N�p�����C�R�ɐӔC������B���̑��̖��Ƃ��ẮA���S�Ȋ�P�ŁA�������n���p�C���b�g���N�p���Ă̍��Ȃ̂ɁA�͍ڋ@29�@�̑��Q�͓��{�R�̍q��@�̂��낳��I�悵�Ă���B�܂��A���ʂɂȂ���������q���͌�̐����͌y���ɂȂ��邱�Ƃɂ��Ȃ�B

�ړI/�ΕĐ푁��������ژ_�R�{�\�Z�����́A�đ����m�͑��̕�`�ł���n���C���U�����鎖���v�悵���B���̑�������Ƃ��ă~�b�h�E�F�C�����U���𗧈Ă����A���X�N�̍������̍��̎x���҂͏��Ȃ������B���傤�ǂ��̂���ČR�@����ꂩ�瓌������P��������(�h�D�[���g����P)�A�Ռ������R�ߕ��̓~�b�h�E�F�C�����Č�������B�R�{�����̐^��p�ȗ��̋��d�p��������t���A���̍��͏��F���ꂽ�B���{�R��Q/���v�A���4�A�d��1�A��j�A�d��1�A�q��@322�@�B�ČR��Q/���v�A���1�A�쒀��1�A�q��@150�@�B�@
���_/��ʂɏ���̔s�k�ȂǂƂ����Ă��邪�A�����̓��Ă̎��͍����l����Ə��Ȃ��Ƃ����v���ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��B�đ����m�͑��i�ߒ����j�~�b�c���g���u�č��̎w�����ɂƂ��āA����͕s���ȎS�������O�ɒm�����悤�Ȃ��̂ł������v�ƌ�ɏq�ׂĂ�����̐�͍������������炾�B���̍ő�̎��s�͗D�_�s�f�Ȋ͍ڋ@�̉^�p�ɂ������Ƃ�����B�G�͂�������Ȃ����߁A�͍ڋ@�̋�����Ί͔��e���~�b�h�E�F�C���̍U���̂��߂ɗ��㔚�e�ɕύX���A���̌�A�G�͔����̕�ő�����Ίӑ����ɖ߂��Ă���Œ��ɔ������A���̌��ʋ��3�ǂ���C�Ɏ������B�������͂�w�����ł����_�����̎���ł���B��2�����O�A�C���h�m�œ����悤�ȕt���ւ���Ƃ�������Ƃ�3���Ԕ����������������P�ɂȂ��Ă��Ȃ��B�܂������i�s���Ă����z�����̃A�b�c���U����ɋ���2�ǂ��������̂����ʂł���B���̏d�v�����l����A�ǂ��炪�d�v�Ȃ̂��͂����܂ł��Ȃ��A���̏؋��ɃA�b�c�͐�̌�A�債���x������ꂸ���{�R�̋ʍӑ�1���ɂȂ��Ă���B���ɂ����͑���擪�ɋN���A��͂̐�͊͑�������Ɉʒu����Ƃ����A��͕��U�̋���Ƃ��Ă��邪�A����͎i�ߊ��ł���R�{�\�Z�叫�̐ӔC�Ƃ����悤�B���̑�(���邢�͍ő��)�̗v���Ƃ��āA�ČR���Ă���������������B�^��p�̐����ɋC���悭���āu��_�͑����G�v�Ƃ��u�}���Ȃ���ΓG��������v�ƕ�������Q�d���łĂ���قǂ̖��S�́A�ڂɌ����Ȃ��Ƃ���ō��ɉe���y�ڂ��Ă����Ƃ�������B�@

�ړI/����ɂ܂Ő�����̂������{�́A�쑾���m�̐��m�ۂ̂��߁A�K�_���J�i�����ɔ�s������݂����B����1������(8/6��)�A�~�b�h�E�F�C�C��̐����ɏ�����ČR��������������̔�s����́B�����m�������{�R�̓��o�E�����O��͑�(���m�͂Ƌ쒀�͂ŕҐ�)��h�����A�g����ƒ��̕ČR�A���D�c�̌��ł��͂������B���{�R��Q/���j�A�d��1�B�č��R��Q/���v�A�d��4�A��j�A�d��1�A�쒀��1�A���j�A�쒀��1�B�@
���_/�퓬���ʂ����Ŕ��f����Ȃ�A���{�R�̈����ł���B�����Ƃ��Ă͓��{�C�R�����ӂƂ�����Ɏ������߂����ƂƁA�������ē��̐��[�_�[��ČR���g�����Ȃ��Ȃ��������Ƃł���B�������A���̍��̖{���̖ړI�ł���A���D�c���ł��ʂ����Ȃ��������Ƃ��A��̃K����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�(���ǃK���ł̓��{�R�̐펀�A��a�����҂�31000�����A21000���ł�����)�B�i�ߊ��̎O�쒆���̌������Ƃ��ẮA���ӂɂ��邩������Ȃ��@���������x�����ēP�ނ����Ƃ̂��Ƃł��邪�A���̏d�v�����l����Ί͒����]���ɂ��Ăł����s���ׂ����ł���(���������̎��A�ċ@���͑��̓K�����ӂ��P�ނ�������)�B���̎���͎O�쒆�����g�Ƃ������A�A���͌������ʂƂ݂Ȃ��Ȃ��鍑�C�R�̎p���ɖ�肪����Ƃ�����B���̊C������������A���̌�̃\�������C��ɂ�����X�̐퓬�ł̓��{�R�͏����ɂ́A������������Ñ㒆���I�ȁA�����G��|�������̐킢���ڗ��B��ԏd�v�Ȃ̂͊F���������ʂ����퓬�ړI��B���鎖�ŁA�G�𑽂��E���̂��푈�ł͂Ȃ��B���̌���ӊC��(�����K�A�c���M��)�͓��Ă��킹��50�Ljȏ�̑D�������߁A�u�S��C��(IRON BOTTOM)�v�ƌĂ��قǂ̌���n�ɂȂ����B�܂���{�R���ł������A�t�ɕČR�����ӂƂ�����Ր킪�n�܂����A1943/11/24�Z���g�W���[�W�����C��܂ŁA�\�������ł̎����͑������ƂɂȂ�B

�ړI/���̂���ČR�̍U����������ɂ߁A���{�R�̎�ȋ��_�͐�̂���邩(�T�C�p���A�^�����A�N�F�[����)�A�����ƕ⋋���Ւf�ɂ��A�����I�@�\��~(�g���b�N�A���o�E��)�Ɋׂ��Ă����B�����ɕČR�́A���ă}�j����ǂ��o���ꂽ�ƁA���n���̋~�o�̂��߂Ƀt�B���s���D����v�悵���B����̓}�j���ח��̎��A���n�i�ߊ��������}�b�J�[�T�[�����d�Ɏ咣�����Ƃ���Ă���B�����j�~���邽�ߓ��{���͏��ꍆ�����A�A���͑��̎c���͒��̂قƂ�ǂ��W�߂ĕď㗤�����̌��ł��͂������B���̍��̓���ȓ_�͚��͑����g���ĕČR�@��������U���o���A���̏�ŏ㗤���̕����ɐ�͑�a�𒆐S�Ƃ����͊͑��ŖC���������悤�Ƃ����Ƃ���ɂ���B���͑��ɋ���4�ǂ��g�p�����Ƃ���ɁA���{���������ɂ��̍��ɓq���Ă��������킩��B���{�R��Q/���v�A���4�A���3�A�d��6�A�y��4�A�쒀��4�A������5�B�ČR��Q/���v�A�y���3�A�쒀��3(�������2�ǂ͐_�����ʍU�����ɂ�����)�B�@
���_/���{�R��Q�̂����A���K���1�ǁA�y���3�ǂ̔�Q�͔C�������̂��߁A��ނȂ��Ƃ�������B���������������d�����ʂ������̂ɁA��͕��������C�e�p�ɓ˓����Ȃ��������߁A���̍�펩�̂����邱�ƂɂȂ����B��͕����i�ߊ��̌I�c�����́A�������̌�����ق��Č��Ȃ��������߁A���̍s���́u��̔��]�v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�B���̂��߃��C�e���ɂ���84000���̓��{�R�́A4000�����c���đS�ł���B���X���̍��̓A�����J�Ɉ��ėL���Șa�������������鎖���ő�̖ړI�ł���B���̂��߂ɓ��{�͎c���͒����W�߁A��匈����v�悵���B���ɎQ�������퓬�͒������œ��{�R64�ǁA�ČR218�ǂƂ������j��O�㖢���̋K�͂̊C��ł���B����ɔj�ꂽ�A���͑��͈Ȍ�A�����s�\�͂̂قƂ�ǂ��������B
 �@
�@����v���
 �@
�@���^��p�U���@
�������s���̏،�/����т����肵����B���߂Č����s�@�������̓����ꂷ��������ߔ��ł����B�������@�����ł͂Ȃ��A���@�����B���̕����ŋ��D���]�����Ă������B���̌P���͉������������B����͂��炢�P�������Ƃ�B�����Ƌ߂������ɉ����n�܂��Ȃ����Ǝv���܂�����B�@
���������̏،�/���̌P���̂Ƃ��͒�8���ɔ�ї����A���H�̂��߂ɋA���Ă���A�Ăє�ї���4���ɖ߂��Ă��獡�x�͌ߌ�8�������ԌP���ł܂���ցB�h�ɂɋA�蒅���̂�12���������B�������Č������P�����I���A�Ō�̉��K���I���A�n���C�Ɍ����Ẳ��m�q�C�ƂȂ������ǁA�^��p�U����m�炳�ꂽ�̂͏o�`���O�̋��̒��������B�@
���Č�����A11��26���P���p���o���@�������͈�H�n���C�֏��a16�N12��2���A�U������u�V���R�ヌ�v�̈Í��d�����B8���A6�ǂ̋�ꂩ���ї�����183�@�͕ČR�Ɍ����邱�Ƃ��Ȃ��܂���s���<�A�Â��ė��������͑D�ɑ��ċ�����������B��2�g171�@������ɎQ���B�������Ċ�P���͐����B�A��ʍU���@��29�@�ł������B�@
�͔������̏،�/�^��p�ɋ߂Â��Ƃ��łɑ��g�U���ɂ���Ęp�����s�ꂩ��͂����������鍕�����オ���Ă����B�p���͍����_�ɕ����Ă������A�߂Â��Ƃ���͍��p�C�e�̒e�����Ƃ킩�����B�₪�ēˌ����߂��o�Ď��͍U���ڕW��T�����B�����炵����͂������A���x4000����}�~���Ɉڂ�B������͖����̐^���ԂȂ�����������Ɍ������Ĕ��ł���B�@�̍��E�����𗧂ĂĂ����߂čs���B���x450�Ŕ��e�����A�͂����ς����c�т������B������d�͂Ŗڂ̑O���^���ÂɂȂȂ����B�����Ɍ��̎ˎ肩��u�����!�����������v�Ƃ����������������B�@
���������̏،�/�^��p�U����m�炳�ꂽ�Ƃ��ŏ��͋����������̂́A��ÂɂȂ��čl����Ƃ���ꗋ�����͂قƂ�ǖ����ɋA�҂ł��Ȃ��̂łȂ����Ǝv�����B���̓��͑�ꎟ�U�����Ƃ��ĎQ���A�n���C���ɐi�������B�U���ڕW�͋��A��͂ł���B�����ɑ����ēG�͂ɔ���B���x5m�B�������悭����Ƃ���͏��m�͂ł͂Ȃ���!��蒼���ׂ��A���͋@���㏸�������B������͂��̓G�͂ɋ����𖽒������Ă���B���������č��x�̓J���t�H���j�A�^�炵����͂ɂ˂炢������B�������ˁB�u�������� ���v������ŋ��ѐ�������B����Ɛ������V�����������Ă����B�A�r�˔@�Ƃ��Ēe�������������B�J���J���Ƃ����A�����B������Łu�A�`�B�[�v�Ƃ������ѐ��������B���Ɖ������ɂ��ʂ����e�ۂ͔ނ̔w���Ɣ�s���̓�����˂��������̂������B�܂��ɊԈꔯ�������B
 �@
�@���X��C�C��@
 �@
�@���~�b�h�E�F�[�C��@
���������̏،�/�~�b�h�E�F�[�U������A���Ă��āA�u����v�̓�����ҋ@���ɂ����Ƃ��A�h�[���Ƃ������̂������U�����������B�u���ꂽ���v�݂Ȃ̊炪�ْ����Ă���B�������͑������B�u���߂��������v���̎��A�����̈�p���j��A���ƍ������͂����Ă����B�����ł��Ȃ��B���ɂƏo���ɉ��������B����Ƃ̂��Ƃōb�ɂł�Ɗi�[�ɂŗU�����Ă���̂��A��s�b���߂��ꂠ�����Đ������ł���B����Ȓ��ŏ��Α����������ʼn��������Ƃ��Ă����B�������A�Ă��ɐ��������B���ɑދ����߂��łāA�������͊C�ɔ�э��B�@
�쒀�͏斱���̏،�/�u�ڕW�����[������!�v�����Ƃ����Ԃɍ~�����������@�͉�X�̖C������܂��Ȃ��A���e��������B����̍b����M�����������B�ԏ�A�����Ƃ����l�A���シ�鉊�͉��S���[�g���ɂ��B�����B�w�����������́u���炢���ƂɂȂ����v�Ƃ����Ă���B�����͉��Ƃ������̂悤���B�₪�ēG�@������A��X�͋��̏���~�o���n�߂��B�͂��~���āA�����҂������グ�Ă���Ƃ��A�u���Ղ�!�v�Ƃ������������B�݂�Ɠ�{�̗��Ղ̂�����{���͔��Ɍ������Ă����Ă���B�͔��ɂ͑����̋~������������������B���ɁA�K�c���Ɩ��������������͂��Ȃ������B�F�A���|�̕\��ŏォ��̂����Ă����B �@
�G���^�[�v���C�Y��s�����̏،�/����4�ǂ�����̂����A��߂�2�ǂɖڕW���߂��B���͗����@�ɂ��Ȃ��Ă����ɂ���B���b�L�[���B�ڕW���߂č~���ɓ������B���̍��ɂȂ��āA����Ƒ�C�����n�߂��B���e�𗎉������钼�O�A�b��ɍq��@�����ڂɂȂ��Ă���̂��킩�����B�}�~�������͐��������B�ӂ肩�����3�ǂ̋�ꂪ���サ�Ă����B�A�r�ɂ��ƌ�������킪�������Ă����B�������Ռ��������A����U��Ԃ�Ǝˎ肪�|��Ă����B�G���^�[�v���C�Y�ɒ��͂���ƁA���[�N�^�E�����G�U�����ɂ���Ă���Œ��������B�@
���������̏،�/�u�ԏ邪����Ă���v�Ƃ������ōb�ɂ������Ă݂�Ɖ���A�����Ƃ�����ȉΉ��������Ă����B���炭��R�Ƃ��Ă������ߒɂȋC�����̒��u�G���������˂v�ƐS�ɐ������B���͏���������B���6�@�A�͍U10�@�A������ƑO�܂�100�@�ȏ�̍q��@���������Ƃ����̂ɁE�E�E�B1���Ԃقǂ̔�s�œG��ꂪ�����Ă����B���̂Ƃ��O���}���̍U���ɍ����A�䂪�@�͌����炯�ɂȂ�A�ˎ�͑������������ꂽ�B�e���̒��ɓ˓�����Ƃ����O���}���͒ǂ��Ă��Ȃ������B��������C���A�����𓊉������B�u���[�N�^�E���v�̊͋��������ߔ�Ƃ��A����܂̑����@�����ɑ̓����肵�Ă����B�����͋��̒����t�߂ɖ��������B�����A�蒅�����͔̂����قǂł������B�@
 �@
�@���쑾���m�C��@
 �@
�@���\�������C��@
���m�͏���̏،�(��ꎟ�\�������C��)/�ł̒���3�ǂ̓G�͂������Ă����B���̊͂͐����4�{�̋����˂����B���炭����Ƌ���Ȑ������킫�N����A���ꂪ�Â܂����Ƃ��A���łɓG�͂̎p�͂Ȃ������B������ň�ĂɉΊW�����ė��Ƃ���A��C�A���p�C�A�@�e���ׂĂ�����̋����ł������B�����܂������ŋC���Ⴂ�����������B���܂��܂Ȍ����ӂ��ʂɌ������Ă����B���̐��̂��̂Ƃ͎v���ʌ��i�������B�@
�쒀�͏斱���̏،�/�G�͂Ɍ����ĒT�Ɠ����Ƃ炳�ꂽ�B�������āA������̖͂C�����n�܂����B�䂪�쒀�͓͂G�����ɓ˓��B���ɓG���݂Ȃ���A�����Č����Č����܂���B�₪�ēG�͑����痣�E���A�{�̂ɍ������悤�Ɖ����Ƃ��A�T�Ɠ��ɏƂ炳��A�C�������B���������U�����ꂽ���A�ǂ�����͖����炵���B���ߒe��H��������͈ӎ����������B�@
 �@
�@�����C�e���C��@
����͑�������̏،�/���͂ȎO���e�ł����痎�Ƃ��Ă��A�G�̔����@�͎����玟�ւƂ���Ă����B���e���~�蒍���A�͕��ɋ��������������B�G�U���@�����˂��A�o���o���ɂȂ������̂����ł���B�@�e�͏Ă��Đ^���ԂɂȂ��Ă���̂��₵�Ȃ��猂���܂����Ă���B����G���牺��ؒf���ꂽ�������@�e�e���^��ł���B�ُ�Ȍ��i���ӂ��Ɋ�����ꂽ�B�@
�����͑���͏斱���̏،�/�u�����ދ��v�͒����疽�߂��������B����������ɐÂ��ɒ���ł䂭�B�͋��̒��͂����ɍ������i�ߊ��A�͒����Â��ɂ�������ł����B��ԖC���͍Ō�܂ʼn��Ă����B��́A�͂ƈꏏ�ɒ���ōs���������E�E�E�B�����v���ƁA�ق��Ƃ����C�����ɂȂ����B�������A���͊C��Y�����ɕߗ��ƂȂ����B���̊͂̏��1400���̂��������c�������̂͂킸����10���ł������B�@
 �@
�@���K�_���J�i�����@
�K���A�ҕ��̏،�1/�唭���ŃK���Ɍ������Ă��邳�Ȃ��A�G�퓬�@���������Ă����B�o���o���b�ƒ��ŋ@�e�˂��Ă���B�����Ƃ����ԂɎ����҂����������B�M���E�M���E���߂̑唭�̒��ŁA�݂ȕK���Ŕ�������B����Ƃ̎��œ��ɒ������Ƃ������镺����1/4�����c���Ă��Ȃ������B���͊��S�ɏ�������Ă����B�@
�K���A�ҕ��̏،�2/11�����ɂȂ�Ɖ쎀�҂����o����悤�ɂȂ��Ă����B���͐H�ׂꂻ���Ȃ��͉̂��ł��H�ׂ��B�ցA�g�J�Q�A�J�G���A�I�^�}�W���N�V�A������12���ɂȂ�Ƃ��悢��H�ׂ���̂��Ȃ��Ȃ��Ă����B���ɃV���~��E�W���܂ŐH�o�����B���͂��������܂ł��Ă����B�}�����A�M�ɂ��Ȃ���Ȃ��瑁������ł��܂������Ǝv���Ă����B�܂��̐�F�͂قƂ�ǎ���ł��܂����B�@
 �@
�@���C���p�[�����
�����m�푈�������Ƃ������ȍ��̂ЂƂC���p�[�����B���܂�ɒ����⋋���͕K�����f�����B�����ȍ��Ƃ킩���Ă��Ȃ���A�����ʂ����R�i�ߊ��B�����ɂ��k���ō����I�ȍl���ł͂Ȃ��A������`���l��I�Ȃ��̂����݂��Ă����B���������o�������͊ȒP�ɒ��~���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��R�i�ߊ��̔��f�~�X�ł͓��ꂷ�܂���Ȃ��傫�ȋ]�����ł��B�펀�Ґ��̏ڍׂ͕s�������A47000-65000�l�ł͂Ȃ����Ƃ����Ă���B�@
�h�q���C���̊g��Ƃ����̂���{�\�z�����A����悭�C���h�܂Ői�s���悤�Ƃ����˂炢�����������̂Ǝv����B�Q���t�c�͑�15�C31�C33�t�c��3�t�c�B�Q���l���͍ŏI�I��88000���𐔂����B���J�n��3���Ȃ��Έʂ���ŁA1�����ȓ��ɍU���ł���Ƃ����l���ł������B������5���̖{�i�I�ȉJ�G�ɂȂ��Ă��U���ł��Ȃ������B�G�̍U���͌����������B�J�͍~�葱���A�H���͂Ƃ����ɒ�����A�`���a�����������B�R�i�ߊ��͍��s�\��i����t�c���S������C�����B�悤�₭��풆�~���߂��ł��̂́A7���Ȃ��A�O���ɒm�炳�ꂽ�̂�7���̖��ł������B��������n���̑ދp�s���n�܂����B�@
�C���p�[���A�ҕ��̏،�1/�������P�ނ��邱�ƂɂȂ����B��������X�ɂ͓ˌ����߂��łĂ����B�G�w�̒��O�őҋ@���Ă���ƁA������猃�����C�e�����ł��āA�ڂ̑O�̓G�w�n���y���B�P�ޑO�ɏW���U�����s���̂ł���B���炭���čU������B�������ˌ����悤�Ƃ����Ƃ��A���x�͓G����ĂɖC�����J�n�����B���ʂɂ��̂����킹���A�����܂����U���������B�₪�čU������݁A�i�ނ���܂��Ă���ƌ������`�߂������B�u�����̎����҂��ł�����A�{�̂ɍ������āA�P�ނ���v��X�͂ق��Ƃ����B�@
�C���p�[���A�ҕ��̏،�2/�R�������Ă���ƁA���ɏ��삪�������B�����ŋx�e�����悤�Ɨт̒���i��ł���ƁA���L���Y���Ă����B����ɂłĂ݂�ƁA�Ȃ�Ƃ����ɂ�200�l�߂����{���̎��[���������B�������A���������ł͂Ȃ������B�C���p�[���X���ɂ́A�݁X�Ǝ��[����������Ă���A�����̏�Ԃ̎҂͎��E�p�Ɂu��֒e�����������v�Ƒi�����B���߂��Ƃ����Ɓu�����E���Ă��������v�ƈ��肵�Ă����B�����R�������̒��ł��A����قǂ̎S��͏��߂Ă������B�@
�p���R���Z�̏،�/����X��ʉ߂��邳���A������550�̂̎��̂�����̂������B���̑����͐Ε��̎��͂ɏW�܂��Ă����B���̂悤�Ȍ��i�́A���������ł͂Ȃ������B������Ƃ���ɕ��u���ꂽ�܂܂̂قƂ�ǔ������������̂��������B

�C���p�[�����(��햼�E�����)�́A���a19�N3���ɓ��{���R�ɂ��J�n����6�����܂Ōp�����ꂽ�A���Ӄ��[�g�̎Ւf��헪�ړI�Ƃ��ăC���h�k�����̓s�s�C���p�[���U����ڎw�������B�⋋�����y�������m��ȍ��ɂ��A���j�I�s�k���i�����{���R�����̔��[�ƂȂ����B���d�ȍ��̑㖼���Ƃ��Ă����Έ��p�����B �C���h�k�����A�b�T���n���Ɉʒu���A�r���}����߂��C���p�[���́A�C���h�ɒ�������C�M���X�R�̎�v���_�ł������B�r���}-�C���h�Ԃ̗v�Ղɂ����ĘA�������璆���ւ̎�v�ȕ⋋�H(���Ӄ��[�g)�ł���A�������U������Β����R(�����}�R)������̉��ł���ƍl����ꂽ�B ��{�c���R���́A1943�N8���A��15�R�i�ߊ����c�����痤�R�����̗��Ă����C���p�[���U�����̏������߂����B�����B�������A���v��͋ɂ߂ēm��ł������B�앝��600m�̃`���h�E�B�����n�͂��A���̏�ŕW��2000m���̎R�X�̘A�Ȃ�}�s�ȃA���J���R�n�̃W�����O���������i�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂ�������炸�A�⋋���S���y�������ȂǁA���J�n�O������_���������w�E����Ă����B�����������_�����Ă������ƂŁA�����̓r���}���ʌR�A����R�A��{�c�Ȃǂ̏㋉�i�ߕ����Ă����̎��{�ɓ�F���������C���p�[�����ł��������A1944�N1���ɑ�{�c�ɂ���čŏI�I�ɔF���ꂽ�w�i�ɂ́A�s�k�����̐�ǂ���C�ɑŊJ�������Ƃ������R��w���̎v�f�����������Ă����B ��w���̎v�f��O�ɁA�C���p�[�����̊댯�����w�E���鐺�͎���ɂ��������ꂽ�B�r���}���ʌR�̏㋉�i�ߕ��ł��������R�ł́A�C���p�[�������{�����d�ɔ��������Q�d������c���������������p�@�ƕx�i�������R�����ɂ����1943�N10��15���ɍX�R����A��15�R�����ł����ɔ������Q�d���A�����M�Ǐ����͏A�C��͂�1�������Ŗ��c�����g�ɂ���Ē��ڔ�Ƃ��ꂽ�B �܂��A�C���p�[�����̊J�n�O�ɁA�x���(�{���̌���)�Ƃ��đ�A�L���u���(�n�����)��1944�N2���ɉԒJ���������t�c���Ƃ����55�t�c�ɂ��s�Ȃ�ꂽ�B���̎x���͎��s���A����26���ɂ͎t�c������풆�~�𖽗߂��Ă����ɂ�������炸�A�{���ł���C���p�[�����ɉ���C�����������Ȃ������B �C���p�[�����ɂ́A�C�M���X�x�z���̃C���h�Ɨ��^�����x�����邱�Ƃɂ���ăC���h���������������A�C�M���X���͂��߂Ƃ���A���R�̌���헪���h������ړI���܂܂�A�C���h�����R6000�l�����ɓ������ꂽ�B���̂����`���h�E�B���͂܂œ��B�ł����̂�2600�l(�v���@����2000�l)�ŁA���̌�펀400�l�A�쎀����ѐ�a��1500�l�̑��Q���ĉ�ł��Ă���B �Ȃ��A�A���R�͑�14�R��4�R�c(�p��R3�t�c�)�𒆐S�ɖ�15���l�����̒n��ɔz������Ă����B�@

(����21�N10��7��-���a41�N8��2��)���ꌧ�o�g�̗��R�R�l�B���R�m���w�Z(22��)���A���R��w�Z(29��)���B ḍa��������A�����m�푈�J�n���̃}���[���⓯�푈���̃C���p�[�����ɂ����ĕ������w���A�ŏI�K���͒����B�ؑ������Y��x�i�����Ɠ����������p�@�ɏd�p����A���S�̈�l�ł������B�����̑���{�鍑���R�̏����̕]���̍ۂɂ��̃��x���̒Ⴓ���ے�����l���Ƃ��āA���R���A�x�i�������Ƌ��ɐ^����ɖ��O�������邱�Ƃ������A�C���p�[�����ɂ�����l�X�Ȏ��������A��т��Ĕ��Ȃ����ى����݂�������ԓx��ʂ������Ƃ���A������ĕ]���͂��ꂸ�A�����{�R�̒��Œɗ�ȍ��]�����R�l�ł���B ��������ɃJ���`���c�J�����ɐ������A�c�f�����ɐ������Ă���B���a12�Nḍa�������Œ������ւ̍U�����u�x�ߌR�J����ˌ��X���n���R�^���G�s�׃i���@�f���퓬���J�n�V�e�i���v(�x�ߒ��ԕ������A���퓬�ڕ�)�Ƃ��ēƒf�ŋ����A�����푈�̒[�������o�����B�����m�푈�J�풼��̃V���K�|�[���U����Ŗ���y�������A�C���p�[�����ł͌���I�Ȕs�k���i�����B ��15�R�i�ߊ��ɏA�C���A���a19�N3������J�n���ꂽ�C���p�[�����ł́A�W�����O����2000m���̎R�x���A�Ȃ�n�тŕ⋋���y���������𗧈Ă����B�����A�㕔�R�ł������R�i�ߊ��⎩�R�̎Q�d�A�ꉺ�t�c�͕⋋���s�\�Ƃ������R�łقڑS�����������B���c���́u�C�M���X�R�͎ア�A�K���ދp����v�Ƌ��d�Ɏ咣�A�₪�ē���R����{�c���������F���邱�ƂɂȂ����B�뜜�ʂ��킪�ڍ�����������s�E�p�����A������O���̎t�c����r���Ŏ��X�ɍX�R�����B���̒����ɉ߂��Ȃ����c�����{���e��E(�V�c���C�Ƃ����E)�ł���t�c����ƒf�ōX�R���邱�Ƃ́A�O�㖢���̎��Ԃł������B


�C���p�[���̓r���}(���~�����}�[)�Ƃ̍����ɂ���C���h�̊X�B�����͉p�R�̍őO����n�ɂȂ��Ă����B�ǂ����ē��{���R�̓r���}�𐪕������̂��A���͓����푈��L���ɐi�߂邽�߂������B �ĉp�͒����ɑ��Đ헪�����̉������s�Ȃ��Ă����B���̕����͉p�̃r���}���獩�����o�R���ďӉ�ΌR�ɓ͂����Ă����B���{���r���}���̂���A�ĉp�͒������x���ł��Ȃ��Ȃ�A�����͐��E����Ǘ����Ă��܂��B�����ē��{�R�͂���ɐ��������B1942�N�����A �p�R�͋��͂ȓ��{�R�̑O�ɐ����p�������s�����A�r���}��������ăC���h�ɓ������B�@
1944�N�ɓ���Ə͑傫���ω������B���̍ő�̂��̂͐��ŁA�A���̂悤�ɑ�����ŁA���{�̃p�C���b�g�͎��X�Ɏ���ꂽ�B���̉������v�������펀�����̂��A�r���}���� ����B���|�I�ȕ��ʂ��ւ�A���R�́A�������r���}�̐������Ɉ���A�����Ƃ̘A���H�̒D��ɓ����o�����B�������s�̃Q�����������r���}�k���ɐ��������A����ɋ�⋋���s ���A�����R�ƘA�g�����邱�Ƃɐ��������B���̏����u���ẮA�r���}�𐪕������Ӗ��������Ȃ��Ă��܂��ƁA���{���R�́A�p�R�̍őO����n�ł���C���p�[�����U�����A�ނ�̈Ӑ}�����܂����悤�Ƃ����B�C���p�[�����́A�헪�I�ɂ͓����ɓK������킾�����B�@
���͂��̎�i�������B�r���}�ƃC���h�̍����ɂ́A�`���h�E�C���͂Ƃ�����͂��������A���������̓A���J���R�n�Ƃ����A�W��2000m���̎R�X���ނ��Ă����B�������A�܂Ƃ��ȓ��H�� �Ȃ��A�����Ԃ��Ԃ����N�ɒʂ�Ȃ������B�����������ʂ�����ĉz���邵���Ȃ������B�����œ��R���ɂȂ�̂́u�⋋�v�ł���B�O�������ɕ���e���H�ƈ��i��n���̂��⋋���̏��Z�́A�A���̂悤�ɒm�b���i ��l�����B����ꂽ���_�́u�s�\�v�������B�������A���̍��͋��s���ꂽ�B�@
1944�N3��10���̏������A�r���}-�C���h�����ɎE�������B�ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ����̂��B����Ȍ�����������l�̏��R���o�ꂷ��A���c������ł���B�݃r���}���{�R�̕Ґ��� �ȉ��̂悤�ł������B����A�W�A���ʂ�����u����R�v�Ŏ������ꌳ�����w�b�h(�e�̎�����ł̂��オ�����L�����A�Ŏ����ɋ��������Ȃ������A�V���K�|�[���Ŕ��H�Ɗό��O���̐����𑗂��Ă��������� ����)�B���̉��Ɂu�r���}���ʌR�v������A�w�b�h�͉͕Ӑ��O�����������B���̉��Ɂu��15�R�v������C���h�̃C�M���X�R�ƑΛ����Ă����B���̃w�b�h�����c�����璆���������B�͕ӂƖ��c���͐e�F�̊W�������B�C���p�[��������肽���ƌ������͖̂��c�� �������B�ނ́u���ȃC�M���X�R�ȂǁA�����Ƃ����܂ɓ|���Č�����v�ƍ��ꂵ���B����������̌g�їp�H�Ƃ����ŏ\���A�⋋�̎����l����K�v�������Ƃ����B�⋋�̐��Ƃ́A��l�c�炸�������B�������ނ�̈ӌ��َ͖E����Ă��܂����B

���{�R�͗ǂ��撣��A���J���R�n��˔j���A�C���p�[���̊X���A�k�A���A��̎O�������͂����B�C���p�[���͎R�Ԃ̖~�n�ŁA����̘A���H�͖k���̃f�B�}�v�[���ɉ��т��{������ �Ȃ������B���������̑�31�t�c�͂��̓����Ւf���A�R�q�}�����ʼnp�R��傢�ɋꂵ�߂��B�R�q�}�̐킢�́A�C�M���X�ŏo�ł�����j���ŕK���ڐ�����Ă��邻���A����قǂɌ������킢�������B�����t�c���R�q�}�� �p�R��H���~�߂Ă���ԁA�c���2�t�c���⋋��ɂȂ����C���p�[�����̂����͂����������A�v��͎��s�����B

7���ɓ���J�G���������A�W�����O���͉u�a�̑��Ɖ����A�������������{���͎��X�ɕa�ɓ|�ꂽ�B�R�q�}�̍����t�c�́A�e���Ő�Ԃɓn�荇���Ƃ����ꋫ�Ɋׂ��Ă����B�⋋�͈���ɍs�Ȃ�ꂸ�A���̂܂܂ł͑S�� �Ɣނ͔ߒɂȌ��f�������B�ƒf�őS������P�ނ������B���{���R���ˈȗ��̑厖���ŁA���c���͂���𗝗R�ɃC���p�[�����̒��~�������o�����B���{���R�͋@�\�I�g�D�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ鋤���̂Ɖ����Ă����B10���̓��{�R�����̖����ɐ��҂ł����̂�3���l �ŁA�c��̖w�ǂ��Q���ƕa�ŋA��ʐl�ƂȂ����B���{�R�̑ދp�H�́A���̂̎R���U�����u�����X���v�ƌĂ�܂����B�@
���҂��������t�c���́A���{�������������Ė��c���i�ߕ��ɏ�荞�B�u�@���a���Ă�����v�Ƃ��������ɁA���c����������艽���������ςB�����͌R�@��c�Ŏ��߂ɂȂ邱�Ƃ��o�債 �A�ٔ��̒d��ŁA���c����͕ӂ́u�ƍ߁v��e�N���Ă�낤�Ə������Ă����Ƃ����B�R�@��c���ٔ����s�Ȃ�ꂸ�A���������́u���_�a�v�Ƃ������ɂ��ꂽ�B�����̐ӔC��Njy����ƁA���c����͕ӂ��͂��� �F���ӔC�����邱�ƂɂȂ�A���������邽�߁u���́v�Ƃ��āu�����������Ɓv�ɂ��Ă��܂����悤���B�@

��2�����E��풆�C���p�[��(�C���h���k�̕Ӌ��A�}�j�v�[���y��o�ǂ����p���̎�s)���قǔߎS�Ȑ퓬�͂Ȃ������B���J�n�ȗ���15�t�c����ё�31�t�c�ɂ�1���̒e�ۂ��A1���̕Ă��⋋����Ȃ������B���d�ɂ܂�Ȃ������̍��J�n�ł��������A���̓P�ނ̌��f���x�������B ��{�c����15�t�c�ɑދp���߂��o�������a19�N7��15���A�����łɉJ���ɓ����Ă����B���{�R�́A�ʂ���݂̒��Q���Ɗ��C�Ɖp��R�̒nj��ɋꂵ�݂Ȃ���̑ދp�͐��S������߂��B�W�����O�����̓��́A�R���𒅂��܂ܔ����ƂȂ������̂�����(�펀����ѐ폝�a�œ|�ꂽ���{�R���m��72,000�l�B�����c�������m�͂킸��12,000�l�ɂ����Ȃ�����)�A���m�B�͂��̓����u�����X���v�u�����X���v�ƌĂB �H���E�e��̕⋋���S���Ȃ���ԂŁA�J�����ނ����悤�Ƃ��Ă������A��31�t�c�������K���́A�ƒf�ŃR�q�}�ւ̓P�ނ𖽂��A5���ɂ͑�15�R�i�ߊ����c������̃R�q�}����̖��߂��A�R�q�}��������ĕ⋋�\�n�܂őދp�����B���̔��f�͑S���������ދp���������͏����������A�����͒����ɔ�Ƃ���A�G�O���S�߂ŌR�@��c�ɂ�����ꂽ�����ɂȂ������A�u���_�����v�𗝗R�ɕs�N�i�����ƂȂ����B�@

(���a19�N1��-10��) �����ő哌����c���X�����J�Â��ꂽ����A�����m�Ɠ��A�W�A�̐틵�͑傫���ω����悤�Ƃ��Ă����B�A�����J�R�̓M���o�[�g�����ɏ㗤�A�{�i�I���U�ɓ]���悤�Ƃ��Ă���A�r���}����ł̓E�B���Q�[�g��g���c���A���J���R���ƃ`���h�E�B���͂��z�����{�R�̌���ɐN���A�S���j��Ȃǂ̊h�����͂��߂Ă����B�r���}�h�q�̓V���ł���A���J���R�����ȒP�ɓ˔j����A���{�R�ł͉p��R�̃r���}�D����̋��_�ł���C���p�[�����U�����A�h�q��𐼂ɐi�߂��킪�}�ɕ��ҏオ�����B�C���h�i�U���́A�ȑO�u��\�ꍆ���v�Ƃ��Č������ꂽ���A���{�R�Ɖ^�����R�̐�͂̍������肷����Ƃ������R�Ŗ�����������Ă����B1943�N3��27���Ƀr���}���ʌR���n�݂���A���ʌR�i�����ɉ͕Ӓ����A�����̑�15�R�i�ߊ��ɖ��c���������A�C�������납��A���ꂪ�C���p�[�����Ǝp��ς��A�ӂ����҃N���[�Y�A�b�v�����B ���ʌR��e�t�c�̒��ɂ͕⋋�̍���A�p��R�̑����A�q�̗͂𗝗R�Ƃ��č����s�ɂ͑����̍������Ƃ��������ˑR�Ƃ��ď��Ȃ��Ȃ��������A��15�R�i�ߊ����c�����璆���̓C���p�[�����̎��{�����͂ɉ����i�߁A�͕Ӄr���}���ʌR�i�ߊ����A�e���ʂňӋC�̂�����Ȃ��S�ʓI�틵���C���h���ʂ̍��ŕς��悤�ƍl���Ă��������␙�R�Q�d�����̈ӌ��ɂȂ�ׂ��Ȃ版�������Ƃ����C�����������B6��24���Ƀ����O�[���ňȌ�̍��\�z�����肷�镺�����K�����{���ꂽ�B�{���̓r���}�h�q������ړI�Ƃ��Ă������A���K�̓C���h�k�����̗v�ՃC���p�[�����U�����Ėh�q����O�i������\�z�Ői�߂�ꂽ�B ������8��12����{�c����폀���������A�r���}���ʌR�����15�R�ɑ��u���v�����ƌĂ��C���p�[�����̍�폀���v�j��������A��15�R�̓}���_���[�߂��̃��C�~���E��25���ɕ������K���s�Ȃ��A���c���i�ߊ��̓C���p�[���U���݂̂Ȃ炸�A����ɖk�̃f�B�}�v�[���܂œːi����\�z�ʼn��K�����[�h�����B8��26���{�[�X�͑�15�R�̐V�Q�d���v�쑺�����ƁA�]�ē����@�֒��Ƃ��ăC���h�����R�ƊW���[����������15�R�̎Q�d�̓��������̖K������B�v�쑺�����̓h�C�c���݂̌o��������A��k�̓h�C�c��Ői�߂��A�|�[�X�͖��c���R�i�ߊ��̃C���p�[���i�U���ł̓C���h�����R�Ƌٖ��ȘA�������s�������Ƃ����ӌ���`����ꂽ�B�C���h�����R�𗦂��ăC���h�̓��i�R����@���҂�������Ă����{�[�X���E�����Ƃ͈ꌾ���܂ł��Ȃ������B ���傤�ǂ���8���J�i�_�̃P�x�b�N�ōs�Ȃ�ꂽ�ĉp�����Q�d����c�ŁA�C���h�ƒ��������ԃr���}���[�g�ĊJ��ڎw���k���r���}�D���킪��1944�N2��������{�ƌ��肳�ꂽ�B�����ăC���h�̃j���[�f���[�ɓ���A�W�A�A���R�i�ߕ����ݒu����A�i�ߊ��ɂ̓C�M���X�̃}�E���g�o�b�e�����R���C�����ꂽ�B����̋@�͏n���Ă����B

12��28��������R���C���p�[����팈�s�����߁A��1944�N1��7���ɎQ�d�{�����F�A�����{���߂��o���ꂽ�B���̓��̌ߌ�A�����O�[���̃r���}���ʌR�i������K�ꂽ�{�[�X�́A�͕ӎi�ߊ��́u���悢����{�R�ƃC���h�����R������g���ăC���h�ɐi�R����Ƃ��������v�Ƃ����������ɁA�u�������ɐ_�ɋF�邱�Ƃ�����A����͈���������c���̂��߂Ɏ��̌��𗬂����߂��܂��̈�O�ɂ���v�ƌ��ӂ��q�ׂ��B �����\�肳��Ă���2�����̍��J�n�́A�Q���t�c�̓�����҂�3��8���ɂȂ����B���R�C���h�����{�ƃC���h�����R�̓����O�[���w�i�o���A���ɐ旧�����{�R�ƃC���h�����R�̍���������c������A�C���p�[���U����́A��̒n�s�����_����ꂽ�B�{�[�X�́A����܂ł̂悤�ɐ�̒n�ɓ��{�R���R����~���̂ł͂Ȃ��A�������Ɏ��R�C���h�����{�Ɍx�@���܂߁A���ׂĂ̍s������^���邱�Ƃ����߁A���ꂪ�F�߂�ꂽ�B���������A�|�[�X�͐�̒n�̕����ɕK�v�ȋZ�p�҂�t�߁A�k��J���҂⍒���̎�܂ŗp�ӂ��A����ɐ�̒n�Ŏg�������{���s�̎����̈���܂ōs�Ȃ��Ă���B�C���h�i�U��ڎw�������R��2�t�c�����łɕҐ����݂ŁA1�t�c���Ґ����������B�����̃C���h�����R�̌����͎��̂悤�ɂȂ��Ă���B�Ȃ��C���p�[�����ɎQ�������̂͑��t�c�����ł���A���̑�1�A���̐������̂̓l���[�^�����������A�����̓X�o�X�A���ƌĂҁA�|�[�X�ւ̌h���̏��\�킵�Ă����B

���v��̑�j�́A��31�t�c���C���p�[���̖k100Km�̃R�q�}�ɓːi�A��15�t�c�͓��k���ʂ���C���p�[�����U�����A��33�t�c�̎R�{�x�����p��������C���p�[���֓ːi�A��33�t�c��͂��g���U�����o�ē쐼����C���p�[�����U������Ƃ������̂������B�C���h�����R�́A��33�t�c��͂̓�A�`�����n�̃n�J�A�t�@�����n��̎���ɂ��A���̑��ʂ���������ƂƂ��ɁA��44�A45�t�c���A�L���u�œW�J����U���̖ڕW���`�b�^�S���ł���悤�Ɍ���������z�����ƌĉ����A�C�݉����Ƀ`�b�^�S�����ʂɐi�����邱�ƂɂȂ����B�{�[�X�̓����O�[���������ɏo�����邷�ׂĂ̕������{�������B�C���h�����R�̏����͂��������Ɂu�`�����[�E�f���[�v�̊����Ō���ɉ����A�}���_���[�w�i�������B ��c�������@�֒��ƂȂ������@�ւ͍��J�n�ɐ旧���āA�����R�̎u�蕺�ŕҐ������H������e���ʂɐi�o�������B�p��R�̔z�u��T��A�C��A�n�`�Ȃǂ̍�������肵�A�H�Ɗm�ۂ̂��߂̏Z���H�삪���̔C���������B ����H����́A�O�ʂ̉p��R�̃C�M���X�l��������i�ߕ��ɏo�����ė���ł���Ƃ���������肵�A��������������@�ֈ��ƂƂ��ɐQ�Ԃ�̐����ɍs�����B�ڋ߂��p��R���ˌ����͂��߂�ƁA�����R�H��������@�ֈ��̑O�ɏo�āA�q���h�D�[��Łu���{�l���E���ȁA�����C���h�l�̓Ɨ��̂��߂ɐ���Ă���v�Ƌ��ԂƁA�ˌ��͈ꎞ�͐��ނ��A���x�͐��̂�����Ɏ˂��Ă���B����ƌ��@�ֈ��������オ���ăq���h�D�[��Łu���E���˂ȁB�˂Ȃ�܂������˂āA���͂��O�����ɘb�ɍs���Ƃ��낾�B����͎����Ă��Ȃ��v�Ƌ��ԁB���̂��肩�����ɑ���͍��������A�Ƃ��Ƃ�����Ԃ̃C���h�l�������̏��ֈē�����A��ӂ�����œ��������Ƃ��A���Ɉ����S���������R�ɐQ�Ԃ�Ƃ������Ƃ��N���Ă���B

���J�n�\����ł���3��8����3���O��5���A�k���r���}�ɃE�B���O�[�g���c�̐N�����s�Ȃ�ꂽ�B83�@�̗֑��@��80�@�̃O���C�_�[�ɂ��2���c�ɂ���K�͂Ȃ��̂ŁA���͂Ȑ퓬�@�ɂ��x�����Ă����B�r���}���ʌR�̍q���͔͂����@�Ɛ퓬�@�����킹��100�@�ɖ����Ȃ��A�啔�����E�B���Q�[�g�����̍U���Ɍ��������߁A�C���p�[�����̒n�㕔���ɑ���x���ɂ͂����킸�������U��������Ȃ������B���J�n����A���͏����ɐ��ڂ��A��x�̓R�q�}�̈ꕔ����{�R���D�������A�p��R�͉~���`�w�n���\�z���A�拭�Ȓ�R�𑱂����B���f��͂����ƒ��a10��Km�̉~�`�ɏW�����A�����ɏd�C��u���A�~���ɂ͐�ԂƋ@�֏e��z�u���ē��{�R�̓ˌ���ނ��悤�Ƃ�����̂ŁA�H���E�e��͖����̂悤�ɗA���@�ŋ�A����Ƃ����A����܂ł̏펯�ł͍l�����Ȃ����������̗��̓I�h�q�퓬�@�ł���B���{�R�̊e�t�c�͌������R���̈ړ��̂��߁A�d�C���C���������A�R�C��d�@�֏e���K��̔��������g�s���Ȃ������B3�T�ԂŃC���p�[�����U������\��ł������߁A�e����ŏ��������������A20�����̐H�������p�ӂ��Ă��Ȃ������B �X���������̎w�����铌���C���h���������p��R�̊�{�\�z�́A�l�I���Q������A���f�E��͂ɂ����Ή~���`�w�n���\�z���������̋��_�Ɍ�ނ��A�����ȑ����������ɓ��{�A���v�X�ɕC�G����r���}�����̎R�x�n�т��z���A�⋋���̐L�҂����{�R�암�̏o���Ō}�����Ƃ������̂������B�V���[�C���ɗz���������{������55�t�c�̉ԒJ���t�c���́A�O����K�ꂽ���ʌR���Q�d�̑S�x���u���Ɂu�ނ����̎t�c���͍��C�Ȃ���B����8���ɂȂ�Ƃ�����ƓV������o�Ă��āA������ĉ~�`�w�n�̒����U�����Ă�����v�Ƌ���Ȃ������Ă���B���{�R�͐H����e��̕⋋���قƂ�Ǔ���ꂸ�A�Ǘ����Ă���Ƃ͂����L�x�Ȏx������~���`�w�n�ɂĂ��������B�C���p�[�����͖��c�������̍l���Ă����悤��20���ԂŏI�����Ȃ������B��33�t�c�͓����x�ꂽ��17�C���h�t�c���͂������A�拭�Ȓ�R���A��ԘA���Ȃǂ̑������G�̔����ɂ����A3�����ɑޘH���J�����Ă��܂����B3��19���ɍ�����˔j������15�t�c��23���ɂ̓C���p�[�����k�̃T���W���b�N�O�ʂɐi�o�A29���ɂ̓R�q�}�w�̊X�����Ւf�������A�p��R�̖Ҕ����ɑj������A����ȏ�i�ނ��Ƃ��ł����A���c���R�i�ߊ�����O�i���x���Ƃ������ӂ̓d����Ƃ��Ă���B�܂��k����R�q�}�Ɍ�������31�t�c��3��21���ɃE�N�������̂��A22���ɂ̓T���W���b�N�k���̍��n���U���������U���ɂ͎��s�����B4��5���A�{�菭���w�����̑�31�t�c�̎x���̓R�q�}�̈�p�ɓ˓��������A�쐼�ɋ��Ղȉ~���`�w�n��z�����p��R�͑����R�������Ĕ������A���R�͎������J��Ԃ��Ă����B

1944�N4��6������͂��ł��P����Ԃ�悵�Ă������A�|�[�X�͎i�ߕ������C�~���E�ɑO�i�����邽�߁A�����O�[�����o�������B�C���p�[����̂ɔ������R�C���h�����{�̍s���@�ւ��^�c����l�������s���Ă����B���̐��m�ȏ�m�邱�Ƃ��ł����A��15�R�i�ߕ�����̗E�܂������������Ă��Ȃ��������߂������B���̂����15�R�̎i�ߕ��ł̓R�q�}��̂����S�ɂł����Ɣ��f���A�f�B�}�v�[���i�R�𖽂������A�Ƒ������O�����r���}���ʌR�͒nj����~�𖽂��Ă���B����̋߂��ɐi�o�����{�[�X�́A�R�i�ߕ��ŕ������̂Ƃ͗l�q���قȂ�̂�m��A�C���p�[�����̓�s�ɋC�������炵���B5��10���C���h�{���łƂ���Ă����K���W�[�̎ߕ���m�����|�[�X�́A����̓C�M���X�R�����{�R�ɑ��鏟���̖ڈ����������߂Ɣ��f���A�r���}���ʌR�͕̉ӎi�ߊ��ɂ��ĂāA�C���p�[���U���̋��s�ƃC���h�����R�̑��������߂ċ�������d���ł��Ă���B �`�����n�𐧈������X�o�X�A���̑�1�����5��16���A��31�t�c�x���̂��߃R�q�}�w�̓]�i���߂����B�R�q�}�܂ł͓r���Ƀi�K�R�n���z��500Km���z������j���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A�c���i�R�ɗE�������R�́A���@���̕��m���a�@���o���Ă܂ŎQ�����ďo�������B�������A�⋋�������ɏ�������Ă��Ȃ��������߁A�����R���i�R���J�n���Ă���́A�ꗱ�̕Ă��x������Ȃ������B ����̓C���h�����R�Ɍ��炷�A���{�R�����ւ̕⋋�����l���������A���̂��߂̈ړ��͎����Ԃōs�Ȃ��A�H���̕⋋�͎w�����̐ӔC�ōs�Ȃ�����̂ƍl���鍑���R�̏����ɂƂ��ď펯���O�ꂽ���ۂ������B�����R�ƍs�������ɂ��Ă������@�ւ̏��Z�́A���y�͐H��˂ǒܗk�}�A�⋋���Ȃ���Ό��n�łȂ�Ƃ�����Ƃ������{�R�̍l�����Ƃ̔��݂ɂȂ��Ă����B���@�ւ̏��Z�͑啔�������т����т��������A�C���̓C���h�����R�ɑ���u���ʎw���v���s�Ȃ����Ƃ���Ƃ���Ă����B�������C���h�����R�ł͒P�Ȃ郊�G�]���I�t�B�T�[(�A�����Z)�Ƃ��Ĉ����A�C���h�����R�̗v������{�R�̏㕔�@�ւɓ`���邱�Ƃ����̔C���ł���ƍl���Ă������Ƃ��炭��s���Ⴂ������ɉ�����Ă����B ����ɓ��{�R�ƃC���h�����R�̍s��������ɂ����͉̂J���̑��������������B�C���h�ƃr���}�̍����n�т͔N�ԉJ�ʂ�8000mm�ɂ��B���A���n�l���u�Ղ��o�����Ȃ��v�Ƃ����قNj����J�������B���H�͐��f����A�����̏��삪�����ƂȂ�A��n�͂����܂��D���Ɖ����Ă��܂��B��N�J���̍Ő�����6������8���ɂ����Ă����A���̔N��4���ɓ���ƉJ�����{�i�����A�p��R�ɂ̓v���h�[�U�[�Ȃǂ̋@�B�͂����������A���{�R�ƃC���h�����R�ɂ͐l��ɗ���l�C��p�������@���Ȃ��A�⋋�Ȃ��ŎR�n�ōs�����镺�m�����̗̑͂�����ɏ��Ղ����B

�V���E�k���[�Y�E�J�[�������̎w������X�o�X�A���͔����̉J���̓�s�R�̖��A6���͂��߃R�q�}�̓�ɓ��������B�������A5��25����31�t�c�̍����K���t�c���́A��15�R����1�P�����ꔭ�̒e�ہA�ꗱ�̕Ă��⋋����Ȃ����Ƃ����{���u6��1���܂łɂ̓R�q�}��P�ނ��⋋������n�_�Ɍ����ړ�����v�Ƃ����d����R�i�ߕ��ɂ��łɑœd���Ă����B���c���R�i�ߊ����|�ӂ𑣂������A�����t�c���́A�u�P�트��60���ɂ���Ґl�Ԃɋ����ꂽ��ő�̔E�ς��o�Ă��������܂��s������B������̓��ɂ��Ăҗ������ĉp��ɑ��т�B��������ċ���������̂͐l�ɂ��炸�v�ƕԓd���A�t�c�ɓP�ނ𖽂����B �����t�c���̓V���E�k���[�Y�E�J�[��������K��A�t�c�ƂƂ��ɓP�ނ��邱�Ƃ����߂����A�����́u�������������͂��߂ē����̑c���̒n���狎�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƍR�c���A�u�C���p�[���U���͂�����ĊJ����邩��A���̎��ɖ{����s�����v�Ƃ��������ɂ�����݂����A�C���h�����R���t�c�i�ߕ��̈ʒu�܂Ō�߂��A���̎w�����ɕ��A���邱�Ƃ�\���o���B���̐\���o��6��22���ɋ����ꂽ���Ƃ����|�[�X�͂����Ƀr���}���ʌR�͕̉ӎi�ߊ���K��A�u�������ɑ����֎��@�ƌ���̂��ߏo���������v�Ɠ`���A�댯�ł���ƈ����~�߂�͕ӎi�ߊ��ɁA�u�c��̍������������ׂđ����ɓ����������B�w�l�����̃W�����V�[�A�������l�ł��B�����͐킢�������ɍ���ł���A�ǂ�Ȃɒ��������Ƃ��A�����������m�C�ɕς��͂Ȃ��A�Ɨ��̑�`�B���̂��߂��ꂭ�炢�̋]���͊ÎA���{�R�Ƌ��͂��ĖړI�������������v�Ƃ������ӂ��q�ׂĂ���B

�J���̍Ő����̓P�ލs�ŃX�o�X�A���͔����߂��]�����o���Ȃ���A�K���W�[�A���A�A�U�[�h�A���ւ̎x��������ڎw���ă^���ɓ����������A�����ŕ������͖̂��ߕύX�ō����R��1�t�c�ɂ͕��A�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B�V���E�k���[�Y�E�́[�����������́A���Ƃ����Ɏ����Ă͓��{�R�ƍs�������ɂ����A�X�o�X�A���͓Ǝ��ɃC�M���X�R�Ɛ킨���Ƃ������S�������B�d��ł����m�炳�ꂽ�{�[�X���J�����w�̓P�ޖ��߂��o���A�X�o�X�A���͂���Ƃ���ɏ]�����̂ł���B �p�����̉p��R�q���n���ʂɐi�o�������A�nj��C�����̑����œG�̈��|�I�ȖC�Ɍ��ނ������A����ɐ����Ă����R�{�x�����x���Ă����K���W�[�A���ƃA�U�[�h�A�����A�⋋�̏��Ȃ��ɔY�܂���Ă����B���H���ʂ��Ă������߂Ƃ��ǂ��⋋���s�Ȃ�ꂽ���A�\���ł͂Ȃ��A�q���h�D�[���k�̍ō��̋֊��ł��鐅�����E���ĐH�ׂ�قǂ������B���������R�ɓ��~�����p��R�̕��m���A�u�Ɨ��̑�`�͖����ł������A����Ȑ����ł͏����Ɋ�]���܂������Ȃ��v�Ƃ����u���莆���c���Ďp�����������Ƃ��������B �G�ɑޘH���J�����A��편�s���������33�t�c�̖��c�t�c���͍�풆�~����\���A���c���R�i�ߊ�����w�����D����A���ł�5��9���ɉ�C����Ă����B�d�a�̑�15�t�c�̎R���t�c����5��15���ɍX�R����A�ƒf�P�����߂��o������31�t�c�̍����t�c����7��7���ɉ�C���ꂽ�B��15�R�͎w������3�t�c�̑S�t�c������풆�ɉ�C���邢�͍X�R�����Ƃ����ُ�Ȏ��ԂƂȂ��āA����̖ڂɂ��C���p�[�����̎��s�͖��炩�������B�r���}���ʌR����15�R�̃C���p�[�����𒆎~���A�`���h�E�B���͂̐��܂œP�ނ��閽�߂��o���ꂽ�̂�7��12�����������A���{�R�ƃC���h�����R�̏����ɂ́A����̒nj����Ȃ���J���̔s�����c����Ă����B �C���p�[�����ɂ͖�6000���̃C���h�����R�̏������Q�������B�`���h�E�B���͂ɓ��������̂͂킸��2600���ŁA���̓�2000���͂������ɓ��@���K�v�������B400�����펀���A1500�����Q��ƕa�C�Ŏ��S���A800�������サ�ăC�M���X�R�̕ߗ��ƂȂ�A�c���700�����s���s���ƂȂ����B �@

�{�[�X�̃��W�I���� / ���R�C���h�����{�̗�����C���h�����R�́A���{���R�Ƃ̖��ڂȂ鋭�͂̂��ƂɁA���Ȃ�g���ɏo�������B�����R���������z���C���h�i�R���J�n�������̗��j�I�ȏu�Ԃɂ�����A���R�C���h�����{�͎��̂悤�ɐ�������B1857�N�̐킢�ɃC���h�R�̓C�M���X�̐N���R�ɔs�ꂽ���A�C���h���O�̓C�M���X�̎x�z�ɐ��_�I�ɂ͍~���͂��Ȃ������B��l���I�ȗ}���⋭���I�ȕ��픍�D�ɂ�������炸�A�C���h���O�̓C�M���X�̎x�z�ɑ��Ē�R���p�����������B��`�A�����A�e���A�T�{�^�[�W���Ƃ�������i�A�����ĕ��͂ɂ���R�A���邢�͍ŋ߂̃}�n�g�}�E�K���W�[�Ɏw�����ꂽ�T�`���O���n�̕s���]�^���ɂ��A�P�ɓƗ��������p�����������łȂ��A���R�l���̖ړI�Ɍ������A�傫�ȑO�i�𐋂��Ă���B�@
���̑�킪�n�܂��Ă���A�C���h���O�Ǝw���҂̓C�M���X���畽�a�̂����Ɏ��R�l���̂��߂ɂ������i��s�������B�������A�C�M���X�͒鍑��`�푈���s�̂��߂̃C���h�̎x�z���܂��܂��������A��������Ɣȗ}���ɂ��C���h������ȌR����n�����A�I�[�X�g���A�A�A�����J�A�d�c�A�A�t���J����R�����ĂсA�敾�����C���h���O�ɂ���ɑς����Ȃ��قǂ̕��S���ۂ��A�C���h�e�n�ɂ���܂łɂȂ��Q�[�������Ă���B �@
�C���h���̍ЊQ����~���Ō�̎��݂Ƃ��āA�}�n�g�}�E�K���W�[�̓C�M���X���{�ɑ��A�C���h�Ɨ��̗v����F�߁A�C���h����P�ނ��邱�Ƃ����g�����B�������C�M���X�̓K���W�[�␔���̈����҂̓����ł���ɓ������B�C�M���X���{�̔̓K���W�[�w�l�̍����ɂ��̋ɂɒB�����B

���̐퓬�ɂ���������R�̐����ɂ���āA���܂�C���h�����R�͍������z���f���[�w�̐i���𑱂��Ă���B�哌���푈�J�n�ȗ��A���j�Ɋr�ׂ���̂̂Ȃ����{�R�̏����̓A�W�A�̃C���h�l�Ɋ�����^���A���R�l���̐킢�ɎQ�����邱�Ƃ��\�ɂ����B���{���{�͒P�Ɏ��Ȗh�q�̂��߂ɐ키�����łȂ��A�p�Ē鍑��`�̃A�W�A����̖l�ł������A����ɃC���h�̊��S�Ȗ������̓Ɨ�������������̂ł���B���̐���Ɋ�Â��A���{���{�̓C���h�Ɨ������ɑ��S�ʓI�x����^����p�ӂ����邱�Ƃ������Ε\�����A���R�C���h�����{�������������ɐ����ɏ��F���A�A���_�}���A�j�R�o���������Ϗ������̂ł���B �@
���܂�C���h�����R�͍U�����J�n���A���{�R�̋��͂ė��R�͌�����ׁA�����̓G�A�����J�A�C�M���X�̘A�����ɑ���������i�߂Ă���B�O���̐N���̌R�����C���h����쒀���Ȃ�������C���h���O�̎��R�͂Ȃ��A�A�W�A�̎��R�ƈ��S���Ȃ��A�ĉp�鍑��`�Ƃ̐푈�̏I�����Ȃ��B���{�̓C���h�l�̃C���h���݂̂��߂̉��������肵�Ă���B �@
���R�C���h�����{�́A�C���h�̊��S����̓��܂ŁA���{�̗F��ƂƂ��ɐ킢�����Ƃ������l�Ȍ��ӂ������ɕ\������B

����ɂ킪�Z��ł���G�w�c�̃C���h�l�������A�\�s�Ȏx�z�҂̂��߂̐킢�����ۂ��A���݂₩�ɂ킪�w�c�ɎQ�����邱�Ƃ�v������B�����́A�C�M���X���{�ɋΖ�����C���h�l�������A���Ȃ�킢�ɂ����Ă����ɋ��͂��邱�Ƃ�v������B�����̓C���h���O���p�Ă̎��łȂ�������A�������͉̂����Ȃ����Ƃ�ۏ��A����n��ɂ͎��R�C���h�����{���������s�����s�Ȃ����Ƃ�ۏ���B �@
���R�C���h�����{�́A���E�̃C���h���O�ɑ��A�p�Ă̔�s��A�R���H��A�R�`�A�R���{�݂��牓������A�����̓G���ł̐킢�̊����Y���ɂȂ�ʂ悤�Ɋ�������B �@
�Z��o�����N�A���܂�҂��]���R�����̐�D�̋@��K��Ă���B���N�����̋@��𗘗p�����̔C���𐋍s����A���R�͉����炸�B�������ł��낤�B���̏d��ȂƂ��ɂ�����A�C���h�̓C���h�l�����̋`�����ʂ������Ƃ����҂��Ă���̂ł���B �@
���R�C���h�����{��� �C���h�����R�ō��i�ߊ� �X�o�X�E�`�����h���E�{�[�X
 �@
�@���������ʍӁ@
������������̏،�/�㗤�O3���ԁA�͖C�ˌ��ƍq��@�̔������������B���̍U���ŁA�R�̌`���ς���Ă����B�������͕K���̒�R�𑱂������A����ɒǂ��߂��Ă������B���ɂ���ƁA�}�V���K���������Ȃ���A�ĕ��������Ă����B�|�ꂽ�ӂ�����Ĕ������悤����Ƃ���Ăē��������A����ǂ͉Ή����ˊ�Ɣ���ōU�����Ă����B���̑��ɂ��K�\�����𗬂�����ʼn�������A���Ӓe�𓊂�����A�_�C�i�}�C�g���d�|�����肵�Ă����B�������͍����獈�ւƈړ��𑱂����B�@
�ĊC�������̏،�1/�g����镨��B�������Ȃ������̓��ŖC�e�����X�ƍ~�蒍���ł����B���̖C���͂���߂Đ��m�ő����̎����҂Ɛ��_�ُ�҂��o�����B���{���͓ˑR����āA�U�����Ă����B����Ƃ����{����U�肩�����āA����C�������Ɏa����Ă����B�ނ͔��˓I�Ɏ���o���Ă������낤�Ƃ������A�Ђ��܂ŁA�c�ɂ܂��Ղ��ɂ����Ă��܂����B�܂��A���{�R�̏e�e�ɂ��A��ԓ����̖C�e���y�A���ɂ�����g���͑S���[���[��̉t�̂Ɖ����Ă����B�@
�ĊC�������̏،�2/��X�͂���g�[�`�J���U�������ہA���̒��ɂ������{���̎��̂�ׂ̃g�[�`�J�ɕ��荞�݁A�o��������ǂ����B���̋߂�����n�Ƃ��Ďg���Ă������A�����炩�ςȂ��킳�������n�߂��B�o��������ǂ����g�[�`�J������{���̗삪���������̂����Ă���Ƃ����̂ł���B���傤�Lj�T�Ԃ��炢���������A���̃g�[�`�J�������Ȃ蔚�������B�����邨���钆�ׂ�ƁA��X�����荞���̂̂ق��ɂ�����̂̎��̂��������B�ނ͎�֒e�Ŏ��E�����悤�������B �@
 �@
�@����͑�a�̍Ŋ��@
��a�斱���̏،�/��a�̌X�͂���45�x���Ă��āA�قƂ�lj��|���̏�Ԃł���B�O�ɏo�Ă��悢��C�ɓ��낤�Ƃ������A�ˑR��a�����݂������B���͈̑̂ӎu�ɔ����ĊC���Ɉ��������Ă����B�������߂��Ǝv�����Ƃ��A�ˑR�z�����݂��Ȃ��Ȃ����B���ʂ߂����ĉj�����A�Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��B���x����������ł���Ƃ̎��ŊC�ʂ������o�����B��������ł���Ƃ��ɑ傫�Ȕ������������炵�����A����킩��Ȃ������B�~�������Ă���u�~���v��1�L���������ɂ����B�@
�쒀�͏斱���̏،�/��̔��e���~���Ă����B��͂��ꂽ����������O�b�ɖ��������B�t�߂ɂ������̂͐Ռ`���Ȃ��Ȃ��Ă����B���c�������Ȃ��Ȃ����B�ӂƌ���Ƒ�a�������Ă���B�ǂ��������������c�s�\�炵���B���肬��̂Ƃ����ʂ�߂��A�ق��Ƒ�a������Ƃ����炶�イ���߂��Ⴍ����ɔj��Ă����B�@�e�����ڂ���Ɨ����Ă���B���ꂩ�牽�\�����������B��a������Ƃ������Ɠ]�����Ă����B�₪�Ċ��S�ɋt���܂ɂȂ�A�D��ɂ͉��S�l���̐l�Ԃ��͂��オ���Ă����B���̂܂܂�����蒾�ނ��̂Ǝv���Ă������A�ˑR�h�h�[���Ƃ��������ƂƂ��ɑ唚�����N�����A�D��ɂ����҂�150-200m�͐��������Ă����B��X�͐����҂̋~���Ɍ��������B�@
 �@
�@�������m�푈�N�\

1940/ �@���ƈɎO�������������B���{�ł͑Ήp�Đ킪�ڕW�Ƃ����B����ɑ��č��͘A�������ɐڋ߁A���{�̓�i�����j�~����p���𖾂炩�ɂ����B �@
1940/9 �@���{�͎����m�ۂ̂��ߖk���t�����X�̃C���h�V�i(����)�ɐi���B �@
1941/4 �@���ĉ�k���n�܂邪�A����͑\�J��/���R�����ɍ����������푈�̎��E/�Ήp�Č����3�Ă̂������I�Ԃׂ����������邽�߂̎��ԉ҂��������B �@
1941/7 �@���{�R�͓암����ɂ��i���B�č��͑ԓx���d��������B �@
1941/9 �@���{���{�͌�O��c�őΉp�E�āE�I�����_�푈�̊���������B�č������{������̍U����҂��A�Q��̖��`�邱�Ƃɂ����B �@
1941/10�@���{�œ����p�@���t�����B �@
1941/11/26�@�n���E�m�[�g/���Č��ŏI�i�K�ŁA�č���������C.�n���́A�����m���Ӓn��e���̕s�N�������A�����E����̓��{�R�P�ށA�ݏd�c�������{�ȊO�̒������{�̔۔F�Ȃǂ��Ă�������(�u�n���E�m�[�g�v)���������B�@
1941/12/1�@�n���E�m�[�g���Ō�ʒ��ƌ��Ȃ��������p�@���t�́A��O��c�őΕĊJ�������B �@
1941/12/8�@�^��p�U��/���{�R�̓n���C���p�[���E�n�[�o�[(�^��p)�R�`�̊�P�U���ɐ����A�ĉp���ɐ��z���B�܂������A�t�B���s���̃_�o�I�ɂ��������s���B �@
1941/12/10�@�}���[���C��/���{�C�R�̍q����̓}���[���������C��ŁA�C�M���X���m�͑��̎�͐�̓v�����X�E�I�u�E�E�F�[���Y����у��p���X�������B���{�͓쐼�����m�̐��C�����������A�}���[�����㗤�J�n�B�J����5�����Ԃɓ��{�R�͍��`�A�}���[�����A�t�B���s���A�W�����C�r���}(�~�����}�[)�̊e�n���́A�D�����ւ�B���{���{�́A�����n��̖L���Ȏ����Œ�����Ԑ��͐������Ƌ����B �@
1942/2 ���{�R�̃V���K�|�[����́B���̒���A���{�R�͔����^���ɉ�������Ƃ����ؐl�j����A�s����ʏ��Y(�V���K�|�[���ؐl�s�E)�B���̐l���͕s���������{�������5000�l�A�V���K�|�[���������10���l�Ƃ����������o�Ă���B�@
1942/3/9�@�W��������́B

1942/6/5-7�@�~�b�h�E�F�[�C��/���������m�~�b�h�E�F�[���U���Ɍ����������{�C�R�@���������A�҂����č��C�R�@�������ƊC�����J��L���A���{�͑��͍q����4�ǁA����3500�C��s�@200�]�@(�S�@)�������A�v���I�ȑŌ������B���̐퓬�����ɑ����m����̎哱���͕č��Ɉڂ�A��ǂ͘A�����L���ɓ]���B�@
1942/8-1943/2�@�K�_���J�i����/���ė��R�̓\������������[�K�_���J�i�����������Č������킢���J��L����B���{�R�͍���Ŏ��s�A�\�������C��ɔs��A��n�q��������������ՁB�����s���A�}�����A�̊����ɂ��Y�݁A���{�R�͔h��������3����2�A�쎀�҂��܂ߖ�21000�l���������B�A���R�͑����U�̓]�@�����ށB�@
1942/8-11�@�\�������C��/�\�����������̓��{�R�́A���т������A������f����ċ��B8��8���̑�1���C��ł͓��{�͕āE���A���R�̏d���m��4�ǂ������B8��24���̑�2���ł͓��{�͋��u��鈁v�������B11��14���̑�3���͏��Ր�ƂȂ��ē��{�̗A���D�c�͑Ō����A��́u�����v�Ȃǂ��������B

1944/6-7�@�T�C�p�����ח�/6��15���A�ČR���㗤�U�����J�n�B���̍U�h��̈�Ƃ���6��19-20���A�}���A�i���œ��{�C�R�ƕč��@���͑����Փ�(�}���A�i���C��)�B���{�́u��P�v�u�Ē߁v�Ȃǂ̍q���͂�q��@�̑唼�������A�����m����̐��C����r���B���{�R�̂قƂ�ǂ��펀���錃��̖��A7��9���ČR�̓T�C�p�������́B�T�C�p�������ŕČR�ɓ��{�{�y��P�̊�n��^�������ƂɂȂ�A������t�͑����E�B�@
1944/10/12-15�@��p���q���/��p�ɂ������{�R�q����́A�ČR���C�e���㗤�x���̂��߉�����U�����Ȃ���쉺���Ă����č��@���������W���U���A2�ǂ̏��m�͂��j�����邪�A�t�ɓ��{�@�������̍q���͂̑唼�������B �@
1944/10/23-26�@���C�e�p�C��/�t�B���s���̃��C�e�����D���߂����ē��ė����C�R���قƂ�ǑS�͂������ċ�O�̑�C���W�J�B�}�b�J�[�T�[�A�����R�쐼�����m���ʎi�ߊ��́A���C�e���m�ۂɐ����B���{�͑��͓˓����Ɏ��s���A���́u�����v���͂��ߘA���͑��̎�͂������A�Ȍ�퓬�͒��Ƃ��Ă̘A���͒��͂Ȃ��Ȃ����B�܂����̐킢�ŏ��߂Đ_�����ʍU�������o��B���̍�������{�{�y���T�C�p��������n�Ƃ���ċ�R�̋�P����悤�ɂȂ�B �@
1945/2/19-3/26�@���������/��2������3�匃��̈�ɐ�������(���̓�̓X�^�[�����O���[�h�ƃG���E�A�����C��)�B���{�R21000���̎��炷�闰����(���}���������)�ɁA�ČR��3�A4�A5�C���t�c61000�����㗤�J�n�B��1�����̌���œ��{�R�̑啔���͐펀�A3��26���ɂ͎c��800�����ˌ��ʍӂ��A���{�R�͑S�ł����B�ČR�̎������r��Ŏ���29000���𐔂����B

1945/4/7-8/17�@��؊ё��Y���t/�I��̖�����ттēo�ꂵ����؎̓\�A�𒇉�Ƃ���I��H��Ɏ��s�B


1945/8/8�@�\�A�͑Γ���킵�A�|�c�_���錾�ɎQ���B


1945/9/2�@�����p�ɓ������č���̓~�Y�[������ŘA���R�ō��i�ߊ��}�b�J�[�T�[�Ɠ��{���O���d�����Ƃ̊Ԃō~�������̒��Ȃ��ꂽ�B �@
�O���ɓ���ĊC�R�ɓ�������؊ё��Y�́A�A�����J���n�ߐ��E�����ĉ�����B�����đ����m��푈�̊C�Ƃ��ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����M�O�����ɂ�����B����͍��ۋ������|�Ƃ��鏺�a�V�c�ƑS�������l���ł������B�V�c�̈ӂ��āA�ё��Y�͐푈�I���ɐs�͂����B �@
���������~�̐��_ �@
��؊ё��Y�́A�����A�吳�̎���Ɋ����C�R�̌R�l�ł���B���a�̎���ɂ́A�V�c�̎��]���ɏA�C�A���a�V�c���ł��M�������l���������B����ɐ����Ƃł��������B���{���n�߂Čo������s��A���̍ł�����Ȏ���ɐ����̑ǎ�������ꂽ�j�A���ꂪ��؊ё��Y�ł���B �@
�C�R����̔ނ̌��Ȃ��������B�u�R�l�͐����Ɋւ��ׂ��ł͂Ȃ��v�B����͔ނ̊m�ł���M�O�ł���A�����ɉ�����Ȃ���푈�ւ̓���\�������R���^�J�h�ɑ���ᔻ�ł��������B����������Ȃ��ƂɁA�ނ��ւ�������Ă������̐����ƂƂ��āA�ނ̖��͗��j�Ɏc�邱�ƂɂȂ����B���{�̗��j�́A�ނ̌����M�O���Ȃ�������قNj��͂ɔނ�K�v�Ƃ����̂ł���B�����I�삯���������ӂ������킯�ł͂Ȃ��B�s���\�͂ɗD��Ă����킯�ł��Ȃ��B�ނɂ������̂́u�������~�̐��_�v�ł������B���̐��_��ŁA���̉^����w�����ė��̂ł���B �@
���u���[�j���O�𒅂����������v �@
��؊ё��Y�́A1867�N12��24���ɐ��܂ꂽ�B�������{���ł���O�N�ł���B���܂ꂽ�ꏊ�́A���̐�B�B�����ɂȂ��Ă����A���͍]��(����)�Ɉڂ�A���̌�A��t���ɂ���֏h�Ɉڂ����B�����������̂́A�����Q�n�����ɋ߂邱�ƂɂȂ�A�O���ɏZ�ނ悤�ɂȂ��Ă���ł���B�ё��Y��11�ɂȂ��Ă����B �@
���͊ё��Y����҂ɂ������������B���炪���������Ŕ�������������ł���B�������A�ё��Y�͊C�R���u�肵���B�C�R�ɓ���A�O���ɍs����B����Ȕ��R�Ƃ����O���ւ̓��������Ă����̂ł���B������͑唽�ł���B�֓��o�g�҂ɂ͌R�l�Ƃ��Ă̗��g�o���̓��͂Ȃ��ƌ����Ă�������ł���B�����A�֓����͓��쑤�ɕt��������ł���B �@
���q�̔M�ӂɕ����܂�A�C�R���w�Z�̎����܂����B�ҕ��̍b�゠���āA1874�N�C�R���w�Z�Ɍ����ꔭ���i���ʂ������B�C�R�l���̎n�܂�ł���B �@
�C�R����A�ё��Y�ɍł��傫�ȉe����^�����l�����A�R�{�����q(�F���o�g�A��̊C�R�叫�A��)�ł������B21�̂Ƃ��A�C�́u���Y�v�̏�g���ƂȂ�A���̊͒����R�{�ł������̂��B�R�{�̌��Ȃ��A�u���̖��͐��������搶����̗a������̂��v�ł������B�u���͐����搶�ƈꏏ�Ɏ�����ŁA�����ɖ�������錈�ӂ����Ă���B������A�����|�����̂͂Ȃ��v�B�ё��Y�͒��ڐ�����m��Ȃ��B�������A�R�{�������Ƃ̎v���o���A����k�킹�A�ڂ����܂��Ȃ�����̂��āA���������M���Ȃ����B �@
��ɗ�؊ё��Y�́u���[�j���O�𒅂����������v�Ə̂��ꂽ�B���S����A�������~�̐��������A�����������v�킹������ł���B�R�{�����q������O���̂��܂��̂ł��낤�B �@
�����]���Ƃ��� �@
1929�N�A��؊ё��Y�͊C�R�̌R�ߕ����o�āA���a�V�c�̎��]���ɔC�����ꂽ�B���]���Ƃ͓V�c�̑��Ɏd���A�����Ƒ��k�ɏ��Ƃ����d�E�ł���B �@
�����A�N�Ⴋ�V�c�̗J���͐[�܂����ł������B1931�N�̖��B���ρA���N�̖��B�����݁A�����č��ۘA���̒E�ށB���R�ɂ��\���͎��~�߂������炸�A���{�͌Ǘ����̊�@�ɗ�������Ă����B���ۋ�����M�O�Ƃ���V�c�́A���ۘA���E�ނɂ͏I�n���̈ӌ��ł������B���������{�͗��R�ɉ������āA���邸��ƒE�ނ܂Ŏ����Ă��܂����̂ł���B �@
�V�c�̖���Ȃ��邪�������B��x���A�ё��Y���V�c����Ă�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������B�ё��Y���{���ɋ삯�t����ƁA�������ɜܜ����������V�c�����荞��ł���B�ё��Y�̊������ƈ��g���A���ǂɂ��Ă̈ӌ������߂邱�Ƃ��x�X�������Ƃ����B�ё��Y�͓V�c�̍ł�����鑤�߂ł���A�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ɂȂ��Ă����B �@
�ё��Y�����]�����߂���8�N�Ԃ́A�R���̃e���ɂ����t�����X�ɓ|��鋰�|�̎���ł������B1936�N�A2�E26�������u���B���Ɖ�����v������N���Z�̃N�[�f�^�[�ł���B�_��ꂽ�̂͑�����b�̉��c�[��A����b�̐ē����A�����̍��������Ȃǐ����̒����l���B����Ǝ��]���̗�؊ё��Y�ł������B �@
26�������A�����P�O���w�����Ƃ���150���̕�������ؓ@���P�����B�n�����̊ё��Y�̕����ɏ\�����̕��m�����ݍ��݁A�ё��Y�����͂B���m��2�l�����݂Ɍ��e�ˁB4����68�̘V���]���ɖ������A�ё��Y�͂��̏�ɓ|�ꂽ�B�N�����u�Ƃǂ߁A�Ƃǂ߁v�Ƌ��ԁB���m�����e���\�������̏u�ԁA�����̋��ŏe��˂������Ă����^�J�v�l���A�u���m�̏�ł��B�Ƃǂ߂����́A��߂Ă��������v�Ƌ��B �@
�����Ɏw�����̈�����т������ė��āA�����Ď���A�u�C�������I�v�ƍ��߁B���m�����͔��˓I�ɒ�������B�u�t���ɑ��āA�h��I�v�B�����āu�悵�A�����g���I�v�B���m�����͈�Ăɕ������o���B���ꂪ�ё��Y�̐���������d�ŕ������u�Ԃł������B �@
�w�����̈����́A2�N�قǑO�A�ё��Y�ɖʒk��\�������Ƃ�����B�ё��Y�̘b���������́A�u���������̂悤�ɕ��̑傫���l�����v�Ɗ��Q�����Ƃ����B���̈�������ؓ@�P����S�����邱�ƂɂȂ������Ƃ́A�s�K���̍K���ł������B �@
�u���͉^�̂����j������A���ɂ��Ă���ΊԈႢ�Ȃ��v�B�펞���A�ނ͏�ɕ����ɂ��������Č��サ���Ƃ����B���̓x�̏P���ł��A�܂��Ɂu�^�v���ނɖ��������B���˂Ȃ�Ȃ��Ō�̎d�����c����Ă������炾�B �@
����؊ё��Y���t�a�� �@
�A�����J�Ɛ푈���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���E�����ĉ�����ё��Y�̂��ꂪ���۔F���ł������B�C�R���w�Z���ƌ�A���̉��m�q�C�ŃA�����J�ɓn��A�����������Ƃ�����B���̍��́A�����ꐢ�E��̑卑�ɂȂ邾�낤�B����ȍ��Ɛ푈������A���{�͂ЂƂ��܂���Ȃ��B �@
1917�N���K�͑��̎i�ߊ��Ƃ��ăA�����J�ɓn�����ہA�T���t�����V�X�R�ł̊��}��Ŏ��̂悤�ȃX�s�[�`�������B�u���Đ푈�͍l�����Ȃ����Ƃł���B�����m�͕����ʂ�A����(���a)�̊C�ł���A�_���f�Ղ̂��߂ɑ���ꂽ�C�ł���B���̊C���R���A���Ɏg���Ƃ�����A�������ɓV������ł��낤�v�B���̍l���͐��U�ς��Ȃ��������A�ނ̊肢�ނȂ������{�͑ΕĐ푈�ɓ˓����A�����̊C��푈�̊C�ɂ��Ă��܂��̂ł���B �@
�J�퓖���̂͂ȂȂ�����ʂɍ������M�����钆�A�ё��Y�͐��߂��ڂŐ틵�߂Ă����B���Ă̍��͂̍��͗�R�Ƃ��Ă���B�����u�a�������{�̑I�����͂Ȃ��͂����B�Ƃ��낪�A����̑叟���ɐ�������āA���{�ƌR���̓����瑁���u�a���������ł��܂����B �@
�ё��Y�����O�����Ƃ���A�푈���������ɂ�틵�͐�]�I�ƂȂ����B44�N�ɓ����p�@���t�̑����E�A�������鍑�����t��1�N�����Ȃ������B��p�ɒN�𐄂����B�d�b��c(�o���҂Ȃ�)�Ŕ��H�̖�������̂��A���������@�c���̗�؊ё��Y�������B�����S�������A�V�c�̐M�C�������B����ɌR�l�o�����\�����Ȃ��B�S����v�ł������B �@
�ё��Y�́A�u�����͐����ɑa�����A���̔C�ł͂Ȃ��v�Ƃ����ς�ƌŎ������B���̕ԓ��͗\�����ꂽ���̂������B�ё��Y�͒����̐l�ł���B�V�c�̑喽������Θb�͕ʂ��B�V�c����ؓ��t�������]��ł����̂ł���B �@
�ё��Y�͓V�c�ɔq�y�����B�Ŏ�����ё��Y�ɓV�c�́A�u���ށB�ǂ����A�Ȃ��ď��m���Ă��炢�����B���̊�}�̎��A�������ɐl�����Ȃ��̂��v�ƍ��肵���B�V�c�ɍ��肳���������������Ȃ���A�u�s�ї�؊ё��Y�A�g����q���āA������\���グ�܂��v�Ɛ\���グ���B���̎��ނ́A�V�c�͐푈�̑����I����]��ł�����ƒ��������B �@
�����f���� �@
�푈���~�߂邱�Ƃ́A�n�߂���͂邩�ɓ���B���푈�I��(�~��)���������邾���ŁA�R���̃N�[�f�^�[���������A�푈�ѓO�h�ɐ����͈�����B�ё��Y�́A�邩�Ɋ�������̂��������B���̓��t�͐푈�I�����t�ł���B�������ł��A���̓��t�Ő푈���I��点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�푈�I���̃`�����X�͂����炭1�x�����B���s�͐�ɋ�����Ȃ��B���̈�x�̃`�����X�̂��߂ɁA�푈�ѓO�h�̗��R�𖡕��ɂ��Ă����K�v������B �@
�A�C�����ŁA�ё��Y�͐�Ӎ��g�������i�����B���R�����S�����邽�߂ł���B1945�N5�����̓������P�ŁA�c�����Ď�������ł���A�ё��Y�͓O��R���f�Ŏ咣�����B����ɂ͓V�c�����]�����قǂł������B�ё��Y�́A�܂����ł͂Ȃ��ƍl���Ă����̂ł���B �@
7���̖��A�A�����J����|�c�_���錾�̓��e�������ꂽ�B����͓��{�ɖ������~�������߂���̂ł��������A�V�c�ɂ��Ĉꌾ���G����Ă��Ȃ������B���̍��A���t�̈ӎv�͐푈�I���ł܂Ƃ܂��Ă����B�������V�c�̐g���ۏႪ�Ȃ����̂��A�_���͂��̈�_�ɍi���Ă����̂ł���B�L���ȏ����邽�߂ɂ́A�{�y����������Ȃ��B���ꂪ���R�̎咣�ł���B�V�c�̈��S�ɑ���m������Ȃ��ȏ�A�ё��Y���Êς��邵���Ȃ������B �@
8��6���A�������L���ɓ����B�s�X�̑唼����u�ɂ��ĉ�ł����B���ɗ���ׂ����������B��C�Ɍ��������鎞�A�푈�I���̂�������x�̃`�����X�̎��ł���B8��9���ߑO�A�ō��푈�w���҉�c���J�ÁB�|�c�_���錾����̐��_����ꂽ�B�c�_�̍Œ��A2���ڂ̌���������ɓ������ꂽ�B�ÑR����v���̒��A�d�ꂵ���c�_�����������A���_�͂��ɏo�Ȃ������B��������h��3���B�����܂ŏ�����t����ׂ��Ƃ��������h��3���B�����ĊJ�Â��ꂽ�t�c�ł����l�ɋc�_�͕����ꂽ�܂܂ł���B �@
�ё��Y�͏��߂��炱�̌��ʂ�\�z���A��O��c(�V�c�Q���̉�c)�Ō��������镠�Â���ł������B����ǂ��������Ń|�c�_���錾����������Ƃ��Ă��A���R�͖Ҕ������N�[�f�^�[�͕K���ł������B���f(�V�c�̌��f)�������Đ푈���I��点�邵���Ȃ��B���̂��߂ɂʂ���Ȃ��A�����ɏ������Ă����B�ꍏ���P�\�ł��Ȃ��B���R�ߌ��h�̊����Ԃ������蓾�邵�A�����̓��������̌��O���������B �@
���̓��̖�11�����A��O��c���J�ÁB�Q���҈ꓯ�̔������I���A�ё��Y�͂����ނ�ɗ����オ��A�V�c�̔��f�������B�V�c�̔��f�͖����������B�u����ȏ�A�푈�𑱂��Ă��������ꂵ�݂Ɋׂ�����ł���B���͗܂������đ�������Ɏ^������v�B���f���������B������������j���ꂽ���A�ё��Y�͋B�R����ԓx������Ȃ������B�܂��I����Ă��Ȃ����Ƃ�m���Ă����̂��B �@
�\�z�ʂ�A���R�̖җ�ȓ˂��グ���n�܂����B�ё��Y�́A14���Ăь�O��c���J�Â��A�V�c�̐��f��������Ȃ������B�������V�c�͏������ς���Ă��Ȃ��B�u�����͔@���ɂȂ낤�Ƃ��A�����̐��������������v�ƌ��A����ɑ����āu���̍ہA���Ƃ��āA�Ȃ��ׂ����Ƃ�����Ή��ł��}��Ȃ��v�Ƃ܂Ō��������B������A�t�������̑����͂ނ��ы����A���ɕ��ꗎ���č�������҂��������Ƃ����B����15���A�V�c�ɂ��ʉ�����������A���ɐ푈�͏I������B�����ɗ�ؓ��t�̎g�����I�������̂ł���B �@
���̓��̗[���A�ё��Y�͎Q�������B�V�c�Ɋt���S���̎��\����n�����߂ł���B�u��A�ǂ�����Ă��ꂽ�ˁv�ƓV�c�͊ё��Y���˂�������B�u�{���ɗǂ�����Ă��ꂽ�v�Ƃ�����x�������B�V�c�̖ڂɂ�������ƌ�����̂������ё��Y�́A���������݂ɐk�킹���B�嗱�̗܂��A��������悤�ɂ��ӂ�o�āA���ɂۂ��ۂ��Ɨ������B �@
3�N���1948�N4��13���A�ё��Y�͋A��ʐl�ƂȂ����B�u���U�ꎖ�v�Ƃ������t�����邪�A��؊ё��Y�́u�푈�̖������v�Ƃ����ł�����Ȏd������萋���邽�߂ɐ��܂�Ă����悤�Ȓj�ł������B�����ĐM�O�ƒ����S�������āA����������ɐ����������B�ӎ����N�O�Ƃ��钆�A�^�J�v�l�̎������Ȃ���A���킲�Ƃ̂悤�Ɂu�Ƃ�̕��a�A�Ƃ�̕��a�v�Ɣ����������Ƃ����B���ꂪ�Ŋ��̌��t�ł������B���N82�B
�@
 �@
�@�������m�E

1880�N(����13�N)�ɎR�����F�ьS���ϑ�(�̂����s����)�ɂāA���D�≮�̎l�j�Ƃ��Đ��܂��B�@
�m�E��11�̎��A���e�����ƂɎ��s���j�Y�������ƁA�e�ʂ����ɓn�Ă��Đ��������߂Ă������ƂȂǂ���1893�N(����26�N)�ɗ��w�̂��ߓn�Ă���B�A�����J�ł͎��͂̐l�X����L���X�g���̉e�����A���M�Ɏ���B���ɗ����o���̂���I���S���B�|�[�g�����h�̃A�����J�E���\�W�X�g�ē���q�t�����}���E�n���X(MerrimanColbertHarris)�̂����������M�Ɍ�����A���{���R���\�a�X�g����̎w���҂ƂȂ�͕Ӓ�g����傫�ȉe�����A��������B�ނ͉͕ӂ�M�̕��A�����ɑ�����̕��Ƃ��A�I���������ɂ����B��N�Ɏ����Ă��č��ł̓��\�W�X�g�h�̐M�҂ƌ������Ă����B�@
�I���S���B�|�[�g�����h�A�J���t�H���j�A�B�I�[�N�����h�Ȃǂŕw�̖��A�I���S����w�@�w���ɓ��w�A1900�N(����33�N)�ɑ��Ƃ���B�I���S����w�ƕ��s���đ���c��w�̖@�w�u�`�^����������ȂǁA�w�S�����ł���������A�w�����Ԃɂ��ƁA�|�[�J�[�̖��肾�����Ƃ������B���ƌ���ؕĂ��l�X�̐E��œ����Ă��邱�Ƃ���A�A�C���B�[�E���[�O���̑�w(���邢�͑�w�@)�ɐi�w���邱�Ƃ�ڎw���Ă����Ƃ��l�����邪�A��e�̌��N��Ԉ����Ȃǂ𗝗R��1902�N(����35�N)�A9�N�U��ɋA������B

�A����́A���������ɎR�����l��̗������������Ƃ�����A�x�͑�̖����@���w�Z(������w�̑O�g)�ɐЂ�u���Ȃ��瓌���鍑��w��ڎw�����Ƃɂ����B�������鍑��w�̎��Ɠ��e�ׁA������Ȃ����������m�E�͓Ɗw�ŊO����������ڎw�����Ƃ����ӁB1904�N(����37�N)�ɊO���������Ɏ�Ȃō��i���A�O���Ȃɓ��Ȃ���B�Ȃ��A���̊O���ȓ���͂���قǐϋɓI�ȓ��@�Ɋ�Â��̂łȂ��A�܂���̓��I�푈�ɑ�����̒�������I�Ӗ��������������̂ł͂Ȃ����Ƃ̐�������B�@
�O���Ȃł́A�͂��ߗ̎�����Ƃ��Ē��ؖ�����C�A���̌�֓��s�{�Ȃǂɕ��C�B���̍��A���S���ق������㓡�V����O�䕨�Y�̎R�{�Y�̒m����B�����̒����嗤�ł̋Ζ������������̂́A����ɂ͈�U�̓x���M�[�Ζ��𖽂���ꂽ���̂́u���ꂩ��̓��{�ɂ͑嗤���������v�Ƃ����Ē��ؖ����Ζ��̌p����]�Ƃ������B�Z���Ԃ̃��V�A�A�A�����J�Ζ��̌�A�������t(�O����b�͌㓡�V��)�̂Ƃ�������b�鏑�����O�����L���Ƃ��ė���b���T�|�[�g�A���ɃV�x���A�o���ɐ[���֗^�����B1919�N(�吳8�N)����̃p���u�a��c�ɂ͐���(�W��C)�Ƃ��Ĕh������A���{���{�̃X�|�[�N�X�}���Ƃ��ĉp��łِ̕�ɗ͂��A�܂������������ł������߉q�����Ƃ��o��B�A����͑��̎��Ƃ��čĂђ��ؖ����Ζ��ƂȂ邪�A1921�N(�吳10�N)�A�O���Ȃ�41�̎Ⴓ�őފ��B

�ފ���͂����ɁA��C����Ɍ�F�����R�{�Y�̈��������ɂ��A�얞�B�S��(���S)�ɗ����Ƃ��Ē��C�A1927�N(���a2�N)�ɂ͕����قƂȂ�(���ق͎R�{)�B�����{�l�������Y�z�ł̐ΒY�t���v�����g�g�[�Ȃǂ��w�����Ă����B�@
1930�N(���a5�N)�A���S��ސE�B2���̑�17��O�c�@�c�����I���ɋ����R��2�悩�痧���(���F���)�A���I����B�c����ł͑Εĉp�����E�Β������s�����j�Ƃ��镼���O�����������ᔻ���A�������犅�т𗁂т鎖�ƂȂ�B�@
���W���l�[�u����h���@
1931�N(���a6�N)�̖��B���ς������āA1932�N(���a7�N)�A���ۘA���̓��b�g�������c��h���A���̕�(�Γ�������)��9���ɒ�o����A�W���l�[�u���ʑ���ł̍̑���҂������B���̓��e�͓��{�̖��B�ɂ�������ꌠ�v�̑��݂�F�߂铙�A���{�ɂƂ��ĕK�������s���ȓ��e�ł͂Ȃ������B���A�u9��18���ȑO���A�͌����ɂ�����Ȃ��Ƃ����F���E�ޏF�̎����E���{���v�̗L������F�߁v�Ȃ�������ʂƂ��āu�ޏF�����ۊǗ����ɒu�����v���Ă��A�ޏF��ޏF���Ƃ��ĔF�߂Ȃ����e���������ߓ��{�����̐��_�͍d���A���{�͕�������o�̒��O(9��15��)�ɟޏF���𐳎����F����ȂǁA����̑I���������肳���ł������B�@
���̂悤�Ȓ���10���A�����͓�����ɓ��{��ȑS���Ƃ��Ĕh���B���̗ނ܂�ȉp��łِ̕�����҂���Ă̐l�I�ł���B�u���{�̎咣���F�߂��Ȃ��Ȃ���ۗ����E�ށv�͏����S���̒P�ƍs�ׂł͂Ȃ��A�����܂ł����{�O���Ȃ̍Ō�̕��j�ł���A�E�ނ�����H���Ƃ��ăW���l�[�u�ɕ�������ł͂Ȃ��A�����S���͂����܂ł��E�ނ��ɗ͔�������j�Ŗ]�B�@
���{�����̊��҂ɂ����킸�A�������X�̏�����12��8���A1����20���ɂ킽�錴�e�Ȃ��̉�����ōs���B����́u�\���ˏ�̓��{�v�Ƃł��肷�ׂ����̂ŁA�u���ď�����20���I�̓��{���\���ˏ�����Y�ɏ����悤�Ƃ��Ă��邪�A�C�G�X���㐢�ɂ����Ă悤�₭�������ꂽ�@���A���{�̐������͕K����ɖ��炩�ɂȂ邾�낤�v�A�Ƃ̎�|�̂��̂������B�������A���{�����ł͊��т𗁂т����̉������A���O���A���ɃL���X�g�����ɂ����Ă͂ނ���t���ʂł������Ƃ�������B�����Ƃ��A��c��ł̏����́u�\���ˏ�̓��{�v�Ƒ肹���鉉���Ɋւ��Ă͐�^�̔���ʼnQ�������B������\�{���N�[����������������߂��̂���ɁA�����̑�\�E��������������߁A�p����\�T�C�����O���A�����w�[���T�����������Ɏ^���̌��t���q�ׂ��B�Ȃ��A��������ɂ����āA�ł��Γ��ᔻ�̋}��N�ł������̂̓��[���b�p�̒������ł�����(�X�y�C���A�X�C�X�A�`�F�R�A�C���h�l�V�A�ɐA���n�ł���u�I�����_�̓��C���h�v��L����I�����_)�B�@
�����́u�\���ˏ�̓��{�v�̉����̌�A�u���b�g������s�̟ޏF���@�v�Ƃ����ޓS�O��ۂ̍쐬�����f�悪��f����A�e����\���܂ߖ�600�l�����ϗ������B�����������N���p�Ɠ���������ȊJ���Ɛ��������U����ڕW�Ƃ�����{�̖��F�J���p���ɁA���{���̋}��N�ł������`�F�R��\�x�l�V������^�Ƌ��ɓ��{�̑ΊO��`�̕s���������A�����ɂ��̊��z��`������ł������B�����̕��Y�t�H�̕ɂ��Ɓu���������Ă�����{�̓T�C�����g�ł���g�[�L�[�ɂȂ����v�Ɖ�O�͌��X�ɐ������������Ƃ����B�@
���{���{�́A���b�g�������̑����ꂽ�ꍇ�͑�\�������g���邱�Ƃ�����(1933�N2��21��)�B2��24���A�R�k���قōs��ꂽ����œ����͗\�z�ʂ�^��42�[�A����1�[(���{)�A����1�[(�V���������^�C)�A���[�s�Q��1��(�`��)�̈��|�I�����ʼn����ꂽ�B�����͗\�ߗp�ӂ̐錾����N�ǂ�����A���{��Łu�����Ȃ�!�v�Ƌ���ŋc���ޏꂵ���B�@
�����́u�錾���v���̂��̂ɂ͍��ۘA���E�ނ��������镶���͊܂܂�Ă��Ȃ����A3��8���ɓ��{���{�͒E�ނ�����(��27���A���ɒʍ�)���邱�ƂɂȂ�B�����̐V���ɂ́w�A���悳���!�^�A���A�����̑��킪��\���X�ޏꂷ�x�̕�������ʂɑ傫���f�ڂ��ꂽ�B�u�p�Y�v�Ƃ��Č}����ꂽ�A����̃C���^�r���[�ł́u�������f�\���Ă���܂��ʂ�A���̉Ԃ��U��ۂ���v�u���܂������{���_�̔��g���K�v�v�Ɠ����Ă���B42��1�͓������s��ɂȂ��C���킹�Łu�������͎��ɑ̂ł�������1�ԂȂB�v���ƈꕔ�ŕ]���ꂽ�B�@
���̌�A�W���l�[������̋A���r���ɃC�^���A�ƃC�M���X��K��A���[�}�ł͓ƍّ̐����m�����Ă����x�j�[�g�E���b�\���[�j�Ɖ���Ă���B�����h���ł́A���B�ɂ�������{�̍s���ɍR�c����p���s���ɑ������A�����́u���{�͑��̍����v�Ɣl��ꂽ�B

�A�����������́u�����ׂ����Ƃ������Ă̂����v�u�����̗����������������v���߂Ă̊O�����Ƃ��āA�����ɂ́u�W���l�[�u�̉p�Y�v�Ƃ��āA�M�����R�̂悤�ɑ劽�}���ꂽ�B���_�E�ł��A���ȂLjꕔ�̎��҂������A�����̑���ł̃p�t�H�[�}���X���x�����鐺���傾�����B�����Ƃ��{�l�́u���{�̗���𗝉������邱�Ƃ�����Ȃ������̂����玩���͔s�k�҂��B�����ɒӂ���v�Ƃ̈ӂ̃R�����g���o���Ă���B�@
�A����́u�������_�싻�A���a�ېV�v�Ȃǂ������A1933�N(���a8�N)12���ɂ͐��F��𗣓}�A�u���}�����A���v���������c�������E�����B���ꂩ��1�N�Ԃɂ킽���đS���V�����s���A���}�����A���̉����200���l�𐔂����Ƃ����B���̂��납��e�t�@�V�Y���̘_����W�J���A�u���[�}�i�R�Ȃ�ʓ����i�R���v���Ə������B���ɂ݂�ׂ������������Ȃ��܂�1935�N(���a10�N)8���ɂ͍Ăі��S�ɁA���x�͑��قƂ��Ē��C����(1939�N2���܂�)�B38�N3���̃I�g�|�[�������ł͔���G��Y�Ƌ��͂���5000�l���郆�_���l���ی삵�Ă���B�@
���O����b�A�C�@
1940�N(���a15�N)7��22���ɐ���������2���߉q���t�ŁA�����͊O����b�ɏA�C�����B���t�������O��7��19���A�߉q�������A���C�R��b�\��҂̓����p�@���R�����A�g�c�P��C�R������ʑ�O���ɏ����čs����������u���E��k�v�ŁA�����͊O���ɂ����鎩��̃��[�_�[�V�b�v�̊m�ۂ������v���A�߉q�����������Ƃ����B�@
20�N�߂����������Ă����O���ȂɃg�b�v�Ƃ��ĕ��A���������͂܂��A�����哱�̊O����r������Ƃ��āA���C��������̏d����(���C�M���X�����S����g)�ȊO�̎�v�ȍ݊O�O����40�������X�R�A��c�m��R�l�ȂNJe�E�̗v�l��V�C��g�ɔC���A�܂��u�v�V�h�O�����v�Ƃ��Ēm���Ă��������q�v���O���Ȍږ�ɔC������(�u�����l���v)�B�X�ɗL�͂ȊO���������ɂ͎��\���o�����ĊO���Ȃ���ސE�����悤�Ƃ��邪�A���\�A��g���X�R���ꂽ�����Γ���͎��\��o�����ۂ��Ē�R�����B

�h�C�c�����{�Ńq�g���[�Ƃ̉�k�ɗՂޏ��������̊O���\�z�́A�哌�����h��(���̌�厩�́A���������W�I�k�b�Ŏg�����̂����l�̌��Ƃ��Ă͏��o)�̊�����ڎw���A�����k�����狺�����\�A�Ƃ̊Ԃɉ��炩�̗����ɒB���邱�ƂŃ\�A�𒆗����A����̓\�A�ƕs�N��������ł���h�C�c�̒���ɂ���čs���A���{�\�\�A�\�ƁE�ɂƃ��[���V�A�嗤�����f���鐕�����̐��͏W�c(���[���V�A�����\�z�E�l���A���\�z)������������A����͕ĉp�𒆐S�Ƃ����u���Ă鍑�v�Ƃ̐��͋ύt��ʂ��ē��{�̈��S�ۏ�Ђ��Ă͐��E���a�E����Ɋ�^����A�Ƃ������̂ł͂Ȃ��������ƍl�����Ă���B�������ď����͓��ƈɎO���R����������ѓ��\�������̐�����簐i����B�@
���ƈɎO���R��������1940�N(���a15�N)9��27���������A�����O���͂��̗��N��1941�N(���a16�N)3��13���A���������c�j�𖼖ڂƂ��ēƈɂ��K�A�A�h���t�E�q�g���[�ƃx�j�[�g�E���b�\���[�j�̗���]�Ǝ�]��k���s���劽�}����B�A�r���X�N���ɗ������A4��13���ɂ͓��\��������d���I�ɒ���B�V�x���A�S���ŋA������ۂɂ́A�ٗ�Ȃ��ƂɃ��V�t�E�X�^�[�������炪�w���Ō�����A���i�������Ƃ�����ʂ��������B���̎��������O���̑S�����ł���A�̍����_���Ă����ƌ����Ă���B�@
�������@
��������̂��̊O�V���A���Č��ɐi�W�������Ă����B���A�����J��g�쑺�g�O�Y�ƃA�����J���������R�[�f���E�n���̉�k�Œ�Ă��ꂽ�u���ėȉ��āv(���{�ɂ�4��18���ɓ`�B)������ł���B���Ăɂ́A���{�R�̒����嗤����̒i�K�I�ȓP���A���ƈɎO�������̎�����̌`�[���ƈ��������ɁA�u�A�����J���̖��B���̎�����̏��F�v��A�u���{�̓���ɂ����镽�a�I�����m�ۂɃA�����J�����͂��邱�Ɓv�����荞�܂�Ă����B�Ȃ��A���̗ȉ��Ă��̂��͓̂��Č��J�n�̂��ߒ@����ɉ߂��Ȃ��������A������u�A�����J����āv�ƌ���������{�ł́A�ŋ��d�h�̗��R���܂߂ď���������Ď^���̏ł������B�@
�Ƃ��낪4��22���ɈӋC�g�X�ƋA�����������͂��̈ĂɖҔ�����B���炪�S���𒍂��Ő����������O��������L�������������邱�ƁA�����ĊO�����������̕s�݂̊Ԃɓ��z���Ői�߂��Ă������Ƃ������̎����S�������Ȃ������Ƃ̕]������B������1941�N(���a16�N)6��22���ɊJ�킵���ƃ\��ɂ���āA�����̃��[���V�A�����\�z���́A���̊�Ղ��犢�����邱�ƂɂȂ�B�ƃ\�J��ɂ��ẮA�h�C�c�K�⎞�Ƀ��b�x���g���b�v�O������ƃ\�W�͍���ǂ��Ȃ邩�����炸�A�ƃ\�Փ˂Ȃǂ��肦�Ȃ��ȂǂƓ��{���{�ɂ͓`���Ȃ��悤�ɂƌ����A�q�g���[���ƃ\������150�t�c��W�J�������Ƃ𖾂����ȂǁA����ƂȂ��h�C�c�����ƃ\��ɂ��āA�ɂ��킷�����������̂ɂ��ւ�炸�A�����͂����̂��Ƃ��t�c�ŕ��Ȃ��������肩�A�ƃ\�J��ɂ��Ĕے肷�锭�����J��Ԃ��Ă����B�@
����Ə����́A������������̓��\��������j�����đ\��킷�邱�Ƃ��t���Ŏ咣���A�܂��ΕČ��ł͋��d�ȁu���{�āv���A�����J�ɒ�Ă���ȂǁA���̊O���{����������������ƂƂȂ�B���Č��J�n�Ɏx��ƂȂ�Ɣ��f�����߉q�����͏����ɊO�����C�𔗂邪���ہB�߉q��7��16�����t�����E���A�����O�����͂�������ő�3���߉q���t���������B

�u�Εċ��d�h�v�u�e�Ɓv�A�u���a�V�c�Ɣ��^�v�ł̓V�c�̕]��(�Ƃ����)�ȂǁA���̏����̕]���͒������Ⴂ�B�����������͑�߉q���t�őΕĉp�푈�����O���암����i���Ɉ�l���s�ɔ������B���ꂪ�����Ŏ�����̍X�R�ƂȂ邪�A���̌�A�����̐����ʂ�Ɍ����ɑΕĉp�푈�̒��ړI�Ȍ���(�Γ��Ζ�����)�ƂȂ��Ă���B�암����i���̊댯����F���o���Ă����̂͏��������ł������B�@
�����̌�@
�Εċ��d�_�������Ă������A���\�N�Ԃ�ɕč��̗��w���K�ꂽ�ہA�u�]�͂��Đl���̔���������̒n�ʼn߂����A���U�Y��ׂ��炴�鈤���̏�����Ɏ������v�Ɣ������Ă���悤�ɁA�ŏI�I�ɂ͓��Ă����a���Ɏ�����������Ă��������́A1941�N(���a16�N)12��6���A���ĊJ��̕��j��m��u�O�������͖l�ꐶ�̕s�o�ł������v�u����ł����ɂ���Ȃ��B�É��ɑ����A��a�������疜���E�ɑ��A���Ƃ����l�т̎d�l���Ȃ��v�Ɩ��O�̎v�������͂ɘR�炵�܂𗬂����Ƃ����B�@
�������A�J�����ڂɓ��x�h��ɑ��������Ȃ��ŋߔ�������A����ɂ��Ə����͏���̏����ɋ������A����Ȑ�ʂɁu�ӊ쐝��v�ƋL���Ă���B�܂��������Ȃŏ����́A�J��Ɏ��������R�Ƃ��āA�A�����J�l���悭�����o���Ȃ��������{���{�̊O����̎��s�ł��邱�Ƃ��w�E���A�A�����J���悭�m���Ă��鎩���̊O�����A��߉q���t�ɗ������ꂸ�A���r�������Ƃւ̖��O����i���Ă���B���̈���ŊJ�킵������ɂ͂��̊O���̎��s�Ȃ��A���p�Ă̍��������������͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƒh��ɏ��������Ă���B���̂��Ƃ́A�J��O�ƌ�ł́A�����̋C�������ω��������Ƃ��f����B�@
���̌㌋�j�ɓ|�ꂽ�����͈ȑO�Ƃ͕ʐl�ƂȂ����悤�ɑ����ׂ�B1945�N�A�F�l�ł���g�c����a�����̂��߃��X�N����K���悤���k�����B���������C�ł͂��������A�\�A�����ۂ������ߌ��ɏI���B�@
�s����A����Ɨe�^�҂Ƃ���GHQ���߂ɂ��ߕ߂���A���͂Ɂu�������悢��j�ɂȂ����v�Ɨ͋������A�����v���Y���Ɍ��������B�������A���j�����̂��ߋɓ����یR���ٔ������@��ɂ͈�x�̂ݏo�Ȃ��A�ߏ�F�ۂł͉p��Ŗ��߂��咣�B1946�N(���a21�N)6��27���A�����A�����J�R�a�@����]�@�������ꂽ����a�@�ŕa���A66�ł������B�@
�����̋� �u�������Ȃ����݂��Ȃ��čs������(��݂�)�v

����Y���t���a�����Ĉȗ��A�O���ɂ����āA�Ǘ������i��ł��܂��B�A�W�A�����Ƃ̊W���P�͔ނ�����������܂Ő�]�I�ƌ����Ă��܂����A���A�ł́A2006-2007�N�̒ʏ�\�Z�Ă̐����ɑ���A�����J�ɂ��j�~�̌Ăт����ɉ������͓̂��{�����Ƃ����L�l�ł��B�@
��ܑ�哝�̈ȗ��A�Ǘ���`���O���̒��̈�Ɍf���Ă������O���͂Ƃ������A���A���S��`�������Ă������{�̂��������p���͓]���ƎƂ��Ă��d�����Ȃ��ł��傤�B����ł��āA����͓��A�W�A�����̂̑n�݂Ɉӗ~�I�ł��B�������A���_����������ƁA����̌Ǘ��O���ɕK�������ے�I�ł͂Ȃ��̂ł��B�@
���{�́A��O�A�Ǘ���`�ɌX���Ȃ���A����𐢘_���㉟�������Ƃ������j������܂��B�����ɂ́A�����m�E�Ƃ����A�W�e�[�^�[�̑��݂�����̂ł��B�@
�����m�E�́A1880�N3��4���A�R�����ɐ��܂�A�e�ʂ𗊂��āA1898�N�ɓn�Ă��A1900�N�A�I���S����w�@�w���𑲋Ƃ��A02�N�A�A�����Ă��܂��B�č��؍݂�ʂ��āA�u��������Ă��ăA�����J�l�ɏՓ˂������ɂȂ�����A��ɓ��������Ă͂����Ȃ��B����ꂽ�牣��Ԃ��Ȃ�������Ȃ��B�A�����J�ł͈�x�ł�������������A��x�Ɠ����グ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ����M�O�����̋ɒ[�ɕ����������̐N�͕������ƂɂȂ�A���������R���v���b�N�X����̊O�����ɉe�𗎂Ƃ������܂��B�@
04�N�A�O���������ɍ��i���O���Ȃɓ��Ȃ��܂��B�����A���̏A�E�Ɋւ��ẮA�O�����́u�����m�E�\�\���̐l�ԂƊO���v(�����V��)�ɂ��ƁA���I�푈�ɂ��߂̒����������^�̖ړI�������̂ł͂Ȃ����Ƃ�����������܂��B��̍��O���哝�̂��x�g�i���푈���ɃJ�i�_�֓n������A�e�L�T�X�̏B���Ɏu�肵���肷��̂Ɠ�����������Ȃ��Ƃ����킯�ł��B�@
�����鍑��w�̏o�g�҂ł��Ȃ��A�I�b�N�X�E�u���b�W��IVY���[�O�ւ̗��w�o�����Ȃ���҂ł�������A�ȓ��ŏo���͌����������̂ł�����ǂ��A�ނɂ͉p�ꂪ���\�ŁA���ɃX�s�[�`�̔\�͂������A����ɂ��L�����ڂ���n�߂Ă����܂��B1921�N�A41�̂Ƃ��ɊO���Ȃ�ފ����āA���S�ɓ���A���̖�S�Ƃ͖��B�ɂ����錠�v�g��𐄐i���܂��B�@
1930�N�A���S��ސE���A2���̑�17��O�c�@�c�����I���ɎR����悩�痧��₵�ē��I���Ă��܂��B���F��̂��̐V�l�c���͕�����d�Y�O����b�̑Εĉp�����E�Β������s�����j�����������A���̈А��̂悳���烁�f�B�A�⌾�_�l�A��O����x�����Ă����̂ł��B�@
1931�N�A���B���ς��N���܂��B���N�A���ۘA���̓��B�N�^�[�E�A���L�T���_�[�E�W���[�W�E���o�[�g�E���b�g������c���Ƃ��钲���c��h�����A9���A�ނ͕���A���ɒ�o���܂��B���̓����ɓ��{�����̐��_�͔������A���{���܂���������o�̒��O�ɖ��B���𐳎����F���Ă��܂��܂��B����̖����_�ЎQ�q�Ɍ�����ꂽ���ې��_�ɑ��锽���Ɠ��l�A���{�����v����낤�Ƃ��Ă��邾���Ȃ̂ɁA�O�����Ƃ₩�������Ƃ͉������Ƃ����킯�ł��B�@
10���A�p��ɂ��X�s�[�`���I�݂ł���Ƃ������R�ŁA�����m�E���W���l�[�u�̍��ۘA�����ʑ���Ɏ�ȑS���Ƃ��Ĕh������܂��B�ނ́A12��8���A1����20���ɋy�ԉ������������e�Ȃ��ő���ōs���̂ł��B����́A���������̐�����u�O�ʈ�̉��v�v�Ɩ��������悤�ɁA���{���\���˂̃C�G�X�E�L���X�g��栂����͂Ȃ͂��s���Ȃ��̂ł��B�@
���ď�����20���I�̓��{���\���ˏ�����Y�ɏ����悤�Ƃ��Ă��邯��ǂ��A�C�G�X���㐢�ɂȂ��ė������ꂽ�悤�ɁA���{�̐������͕K���F�߂��邾�낤�Ƃ������e�ł��B�L���X�g���Ɋւ���m�����낭�ɂȂ����{�����ł́A���̉����Ɋ��т��܂������A�����܂ł��Ȃ��A���O���A���ɃL���X�g��������͖Ҕ��������̂ł��B�@
�����v���q�́A�u���j�����������v�ɂ����āA�T���āA�p��ɒʂ��Ă���ƉߐM�����鐭���ƂɊO����̎��Ԃ������Ǝw�E���Ă��܂��B���]���N�O��{�V���A�Ό��T���Y�ȂNj�������肪����܂���B�����A�̃G�h�E�B���E���C�V�����[�����č���g�́A����قǓ��{�ꂪ���\�ł����Ă��A�����̏�ł͒ʖ����܂����B�����܂œ��{�ꂪ�l�C�e�B���Ȍ���ł͂Ȃ�����ł��B�@
���{���{�́A���b�g�������̑����ꂽ�ꍇ�͑�\�������g���邱�Ƃ����肵�Ă��܂����B���N��2��24���̑���ŁA�����͗\�z�ʂ舳�|�I�����ʼn�����܂����B�����͑O�����ėp�ӂ��Ă����錾����N�ǂ�����A��O�ɉ���ޏꂵ�܂��B���̌�A���{�͐����ɍ��ۘA������E�ނ��邱�ƂɂȂ�܂��B�@
�Ƃ��낪�A�A�����������́u�����ׂ����Ƃ��͂����茾�����v�A�u�����̗����������������v�A�u���Ăɂ��тւ�킸�A�B�R�Ƃ��Ă����v���߂Ă̊O�����Ƃ��āA�����ɔM���I�Ɋ��}����邾���łȂ��A���_�E�ł��A���X�R��ȂLjꕔ�̎��҂������A�ނ̃p�t�H�[�}���X���قƂ�ǂ��x�����Ă����̂ł��B�u�����悳��v�Ƒ匩�o���������A�������p�Y�̂悤�Ɉ������V��������܂����B���ێЉ�犮�S�ɌǗ����Ă��܂����̂ɁA���{�����ł́A����Ƀ��V�A�I�s�ׂƂ��Đ�������Ă��܂����̂ł��B�@
�����́A�u����Ȃ��\�����v�v���邢�́u�ɂ݂����v�v��낵���A�u�������_�싻�v��u���a�ېV�v�Ȃǂ������A1933�N12���A���F��𗣓}���A�u���}�����A���v���������ċc�������E���܂��B���̌��1�N�ԁA�S���V�����s���A���ӂِ̕�ɂ��A���}�����A���̉����200���l�ɂ��܂��B�����A���C�h�V���[����������A�ނ͖����̂悤�ɓo�ꂵ�Ă����ł��傤�B�@
1940�N7��22���ɐ���������߉q�������t�ŁA�����͊O����b�ɏA�C���܂��B�߉q���A�����ɗ�炸�A�����̐l�C�������A���̃C���N�푈���l�A�D���������Β��푈�Ŕ敾�������{������Ȃ�푈���s�̂��߂̍��Ƒ������̐��ւƕς��Ă����̂ɓK�C�������̂ł��B�@
���ė��т�H�킳�ꂽ�O���Ȃ̃g�b�v�ɂȂ��������͊����哱�̊O����r������Ɣ��\���A��v�ȍ݊O�O����40�������X�R�A��c�m��R�l�ȂNJe�E�̗v�l��V�C��g�ɔC�����A�R���ƘA�g���鋭�d�h�̊O�����ł��锒���q�v���O���Ȍږ�ɔC�����܂��B����ɁA�L�͂ȊO���������ɂ͎��\���o���悤�Ɉ��͂������Ă��܂��B�@
�|�[�J�[�̖���Œm���鏼���O���̊O����j�͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B�u�哌�����h���v�̊�����ڎw���A�����k�����狺�����\�A�Ƃ̊Ԃɗ���������Œ����������܂��B�@
����ɂ̓\�A�ƕs�N��������ł���h�C�c�ɒ���Ă��炢�A����ɁA�h�C�c�̗F�D���C�^���A�Ƃ���g���āA���{���\�A���h�C�c���C�^���A�Ƃ������[���V�A�嗤�����f���鐕�����͂��`�����܂��B��������A�ĉp�𒆐S�Ƃ�����i�鍑��`���͂Ƃ̋ύt�����܂�A�����ʂ��Đ��E���a�⒁���̈���Ɋ�^�ł���Ƃ������̂ł��B�@
�����́A1940�N9���A���ƈɎO���R�����������сA���N��3���ɂ͓��\��������������܂��B�����O���͓��{�������爳�|�I�Ȏx�����A���̍\�z�͊������Ǝv���܂����B����ǂ��A�h�C�c������\�A�ɐڋ߂��Ȃ��ق��������ƃA�h���@�C�X����Ă��܂����B�����͖��������̂ł����A���̗��R�������ɖ��炩�ɂȂ�܂��B1941�N6���A�h�C�c�̓o���o���b�T�����J�n���܂��B�Ƃ��낪�A���{�͒���������葱���A�V�x���A�ɕ��𑗂�Ȃ��������߁A�\�A�𓌐��ł͂��݂����ɂ���Ƃ����h�C�c�̎v�f���͂���邱�ƂɂȂ�܂��B�@
�����͑Εċ��s�ł���Ȃ���A�A�����J�Ƃ͍ŏI�I�ɋ������ׂ����ƍl���A���̈��͂Ƃ��ă��[���V�A�������g�����Ƃ��Ă����̂ł��B�������A����͓����푈�Ŕ敾�������{������Ȃ�J�^�X�g���t�ɂ���Đ��_�I�ȊJ�����悤�Ƃ�������Ɍ����킹�邱�Ƃɂ����Ȃ�܂���ł����B�@
�R�c�����Y�́A�u�l�ԗՏI�}�Ӂv�ɂ����āA�u�����͑���̎��S�R�����ɁA�Ȃ̎��������Ă��閃���ł��ł������B�ނ̓��N�}�����u���ă��N�}���ɐU�荞�v�ƌ����Ă��܂��B�O���Ƃ����u����̎�v���悭���Ȃ���Ȃ�Ȃ��s�ׂɁA�u�Ȃ̎��������Ă���v�悤�ł́A����͓ƑP�I�ɂȂ�A�Ǘ����Ă��܂��͓̂��R�̋A���ł��傤�B�@
�s���AA����ƂƂ��đߕ߂��ꂽ���̂́A���j���������A�����ٔ������@��Ɉ�x�o�Ȃ���ɂƂǂ܂�܂��B���̍ہA�ߏ�F�ۂɂ����āA�p��ŁhNotguilty�h�Ǝ咣���Ă��܂��B1946�N6��27���A�ČR�a�@����]�@�������ꂽ����a�@�ŁA66�̐��U����Ă��܂��B�u�������Ȃ����݂��Ȃ��čs������v�Ƃ��������̋���c���Ă��܂��B�@
1978�N�A�����_�Ђ�A����Ƃ�̍��J�����s���܂����B���̂Ƃ��A���a�V�c�̈ӂ����{�����́u�����m�E�v�̖����グ�č��J�ɍR�c���܂��B���݂Ɏ���܂ŁA�V�c�́A����ȗ��A�����_�ЂɎQ�q���Ă��܂���B�@
����A����́A�����_�Ђɕs��̐�����V���ɂ��邽�߂ɎQ�q�������Ă��܂��B���̓x�ɁA�A�W�A�����݂̂Ȃ炸�A�A�����J�����s�Ɣ��A���{�͌Ǘ�����[�߂Ă��܂��B��������łȂ��A�ނ̌�p�҂Ɩڂ���鐭���Ƃ́A�����Ƃ��邱�ƂɁA�u�Ȃ̎��������Ă��閃���ł��v�Ȃ̂ł��B����ǂ��A���_������̍s����K�����������ᔻ���Ă��܂��A��p�҂����ɂ����҂��Ă���̂ł��B (2005/12)�@

���N��60��ڂ́u�I��v�̔N�ł��B������u�I��L�O���v��8��15���̓|�c�_���錾��������邱�Ƃ����a�V�c���炪���W�I������ʂ��ē`�����w�ʉ������x���������ꂽ���ł��B�v����Ɂu�|�c�_���錾����L�O���v�Ȃ�ł��B�A�����Ƃ̐����Ȕs��̋V���͓����p�̐�̓~�Y�[���[�ł̍~�������9��2���ł��̂ŁA����Ӗ��ł͂����炪�����ȁu�s��L�O���v�Ƃ����C�����܂����A���͂قƂ�ǂ̓��{�l���Y��Ă�����ɂȂ�܂����B �@
�������A60�N�O��8��15���O��ɂ́A���ۂɔs�������鑤�̓��{���{�A���ɗ��C�R��]���̍����Ƃ����̂́A���ׂĂ݂�Β��ԁA�쌀�̗ނ̃I���p���[�h�B�s��Ƃ������̌��̎��ԂɎQ�l����O����Ȃ��A�ڂ����������Ȃ��R���ł́A�܂��s��̎������ɒN���o�čs���̂��ł����������N���������Ƃ͂��܂�m���Ă��܂���B �@
�u���͌�����A�����Ȃ���v�u���͗��m�Ńh�C�c�������ĂˁA�p��͕�����Ȃ����ˁE�E�E�v�u�������ɂ�������̂��A���O�̂��Ȃ����Ȃ��v�Ƃ������R�A������o�B �@
���ۂɍ~���Ɍ����Ċ��𗬂������v王{���t(�c���E���R�叫)�ŁA�|�c�_���錾�������������؊ё��Y���t��15���ɑ����E���Ă��܂��Ă��܂�������A�R�c���鑊������܂���ł����B �@
���Ǖn�R�������Ђ�����č~������̎������Ɍ����킳���R���L���X�e�B���O�́A���R���Q�d�{�������͕̉ӌՎl�Y�����B�C�R���R�ߕ������̑吼�뎡�Y�����Ƃ������ƂɌ��܂�܂����B���݂��K��������������̉����сB�C�������Ă��܂��B �@
�Ƃ��낪�A�g�ߒc���Ɍ��܂��Ă����吼�����������Ȃ蕠����Ă��܂��܂��B���̐l�͓��U�̐��݂̐e�Ɖ]���Ă��܂����A��̐l�ł������ł͗L���ŁA����o���������B�ɂ́u�K�������ォ��s���v�Ɩ��Ă����̂�Y��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��傤���B�����������͑呛���ł��B�u����������������̂�I�吼�v(���ق��������͔���܂���)�ƊC�R��w���͓��h���B���Ȃ����ŁA�Ƃɂ����㗝��{���˂Ƃ��������h�������Ƃ悤�ł��B�����Ŗڂ�t����ꂽ�̂��\�A��g�ٕt�����Ƃ��ĕ��C���鎫�߂��o���܂܁A�\�A����̃r�U������Ȃ��ŌR�ߕ��o�d(�ҋ@)�Ƃ�������ɂ����Ƃ���A14���̃\�A�Q��ōs����̖����Ȃ������R��Y�����ł��B��肢��ɔނ͕č���g�ٕt�Ƃ��ċΖ��̌o��(�⍲���ƕ���)������A�A�����J�̃G�[����w�ւ̗��w�o��������m�Ĕh�B�p�����肢�B�Ȃ����C�R�ȕ����ߕē��C�R��b�ȂǂƂ��ʎ�������B�܂��ɓV�̔z�܂��Ɖ]�����ƂŁu�������ǂ��A�����Ȃ�p��ł��o����ŁI�v(�C�R�Ȃɑ��o�g�҂��������ǂ����͏d�˂ĕs��)�Ɛ��E����邱�ƂɂȂ����B���������l�́u�G�b�A���H�v�ƍ��f���Ă���̂����ʂ��܂߂��čs������邱�ƂɌ��܂����B �@
����Ȃɉ��Ō��ɍs�������Ȃ��̂��Ɖ]���A�܂��u�p�J�v���Ƃ����̂�������l������̂����A���͂�������Ȃ��Ǝv���B���̍����Ǝg�ߒc�̈���Ɖ]�������Ŗ����ɎE����鋰�ꂪ�͂Ȃ͂��傫�������B�������A�s�����A����A���Ă�����B����ɓ��R�Ȃ���u���͐푈���I���̂Ȃ玀�ɂ����Ȃ��v�Ƃ����̂������R�l�B�̖{���ł��������낤�B����܂ł����̂��߂ɂƂ������Ă����̂ɂł���B���̕^�ς𑤂Ō��Ă��������m���͑������ł�����ꂽ�ƁA���͓��̈�l���璼�ɕ������ꂽ���Ƃ�����B�������A������l��낤���A�㐢�̉�X���ӂ߂���ނ̘b�ł��Ȃ����B �@
�g�ߒc�ɂ͔䓇�ɗ����Ƃ����w�߂����ɕČR����o�Ă����B���삷��ɂ͊C�R�@�����Ȃ��Ƃ������ƂŁA�A���@�̎�z�͊C�R�Ɍ������B�C�R�ł͌��Ǝ����̍q�����A���̎g�ߒc�̍q��@��_���Ă���\���������Ƃ������ƂŁA���Ƃ͋ɔ�ɐi�߂�ꂽ�B���߂ĘA�����ɘA�������ƁA�܂�����̈ɍ]����s��܂ŗ����Ƃ����B�����ߍx���牫��܂ň�C�ɔ�Ȃ��Ɛ�̎���Ŋ댯�����Ƃ������ƂŁA�g�p�@�͈ꎮ���U�Ɍ��܂����B���̋@�̂ɂ́w�������x(���Q�ʍq��ۏ����)�������Ɨ̏\�����@�̂ɕ`���˂Ȃ�Ȃ��B�������Ȃ��ƕČR�@�ɂ͖��m�F�@�Ƃ��ď������ꌂ�Ă��ꂩ�˂Ȃ��̂��B�������A����Ȉ������������@�̂X�Ɗ����H�ɒu���A���̋@���~�������Ɍ��������ʋ@���Ƃ����̂���ڗđR�ɂȂ�B�u����A�ǂ�����A�ǂ�����v�ƊC�R���ł͂Ȃ����B �@
�����ň�v���Ă��āA���{��ɓ�@�̈������\���@��p�ӂ��A�X�ɖ؍X�Âɂ����l�̋@����p�ӂ���\�ԍ���u���邱�Ƃɂ����B���{��̋@�̂͂����܂����؍q����ɔ�������Ă��܂��A�P�������퓬�@�̋@�e�|�˂Ō����炯�ɂ���Ă��܂����B���؋�͓O��R��h�̉�邾�����B�������ޓ����؍X�Â̋@�̂ɂ͋C�t���Ȃ������B���߂��߂Ƃ���A���̋@�̂ɏ�荞�ނ��Ƃ��o�����B�@�̂͋\�ԍq�H�����A�؍X�Â��璹���A���������q���A��q������ɍ]���Ƃ����q�H���s���Ă������B�r���A��q�����ŕČR�@����q�Ɍ����ƁA���悵�Ă����g�ߒc�ꓯ�����g�������Ƃ����B�G����q�Ɍ���Ĉ��S����Ƃ����S�����s�v�c�����A����قǖ������댯�������̂ł���B�g�ߒc�͈ɍ]���ŕČR�̗p�ӂ����b54�A���@�ɏ�芷����ƈ�H�}�j���Ɍ��������B�@���ł͔��������W���[�X�≌���ł��ĂȂ��ꂽ�炵���B �@
�}�j��������A�����i�����̌����n�܂����B�ŏ��A���R����23���̐i������]�������A���{�����������Ԃ�~�����Ɗ撣��26���Ɍ��܂����B�����i������̂��Ƃ����b�ɂȂ������A���c����߂������Ă��Ȃ��ꂽ�B�A�������͌��؊�n�ւ̐i����v�����Ă����̂ł���B�u�����������͂������v�Ɠ��{���ꓯ����������킹���B���R�����͙�l�Ɍ��͑�^�@�̒����ɂ͕s�����Ȑ퓬�@��p�̍q���n�ȂƐ������āA�i���ꏊ�̕ύX�����߂��B����͂��������ƕČR�����ꖇ�̍q��ʐ^���o���Ă����Ƃ����B�����ɂ͌��؊�n�̃G�v�����Ɏl���@�����@���Ă���p���͂�����ʂ��Ă����B�����œ��{���͂��ǂ���ǂ�ɂȂ��Ă��܂����E���葤�Ɂu����A���̊����H�͂ǂ�ʂ̌��݂̃R���N���[�g���Ă���̂��v�Ƃ�������������ƁA�C�R�����ꓯ�͊�������킹���̂��������B���͒N��������m��Ȃ������炵���B���f��ɂȂ����ޓ��͖����ɂȂ�A����Ŕ��_���~�܂����B���ǁA���ؐi�����ΈĂ͋p������Ă��܂����B���̓��͂���Ō��͏I���A�ꓯ�͏h�ɂɈړ���������B�����ɂ͐H���Ƃ悭�₦���r�[�����p�ӂ���A���c�͂ق��ƈꑧ����邱�Ƃ��o�����Ƃ����B8��19���̖�͊��ɕ��Ă����B �@
�����A�Ăщ�k�ꏊ�ɒ����Ă݂�ƁA�e�[�u���ɂ͍��̌��Ɋ�Â��č쐬���ꂽ�c���^���p�ӂ���Ă����B���Ƃ́A��y�[�W���ɓ��e���m�F����邾���̎����葱���̏�ɂȂ��Ă���B�Č���ژ_��ł������{���͌���������H������`�ɂȂ����B�p��̕�����Ȃ��͕Ӓc��(�h�C�c��͑����������炵��)�́A�C�R�̉��R�����ɉ��ʂ�a���邱�ƂɂȂ����B���R���������Ƃ������Ɠ��e�m�F�ł��^���悵�Ă݂����A�����N������ɂ��Ă���Ȃ��B���������A�����I�Ȏ葱���ŏI�n����B�ČR���ł́A���Ɍ��͏I����Ă����̂ł���B�����A�R���叫�����̐Ȃɂ�����u�x�������m�����v�Ɣ����č��f�����ɈႢ�Ȃ��B�ԂقǂŁA���̎葱�����I���ƁA�ޓ����{�g�ߒc�͋�`�ɒ��s�������A�������Ɠ�����H���ɍ]���Ɉ����Ԃ����B�ɍ]���Ɉ�������`�������U�������ƔR����⋋��ČR���̋��͂ŏI���đҋ@���Ă����B�����A��@�̓��̈�@�͈ړ����Ɋ����H�e�̓D�^�Ɏԗւ��͂܂�A�C�����K�v�ȏ�Ԃł��������A���i�Ƃ��̊W�ŋ}�̏C���͕s�\�ł���Ɖ]��ꂽ�B�ӋC���������g�ߒc�́A�d���Ȃ��������c���āA�͕ӁE���R�𒆐S�Ɏg�ߒc�̎�v�����o�[�������Ȉ�@��荞�ݖ؍X�Ê�n�֖߂邽�ߗ��������B �@
�������Ԃ�18��45��������Ă����B�v�Z�ł͖؍X�Âւ̋A�����Ԃ�23��������邱�ƂɂȂ�B��Ԕ�s�Ŗ�̊C���Ԃ̂͂ǂ����Ǝv�����@�����呀�c���{����т́A�C�݉����̍q�H�����ׂ��Ǝg�ߒc�����ō���̃t���C�g�v�������쐬�����p�C���b�g�o�g�̎��䒆���ɒ�Ă����B����͉��R�����ɁA���̈ӌ���\�����̂܂ܓ`�����B����Ɖ��R���٘_�͋��܂Ȃ������B����ŁA���̗��U�͉��H�Ƃ͈Ⴄ�C�ݓ`�����ԍq�H�H�ɑI�B���̋��R�̌��f�����͂��̌�̓��{�̖��^�����鎖�ɂȂ����B�Ƃ����̂��A�\�ȗ��オ��̐{����т╛���c���吼������(�ނ͑I������Ăm�x��q��H�w�Ȃɗ��w�o���̂���D�G�ȉ��m��)�́A�ɍ]���ł̔R���⋋�ŃK�����ƃ��b�g���̈Ⴂ�ɏ\�����ӂ�Ȃ��ł��������ŁA���͗��U�̔R���^���N�̓t���^���N�ɂȂ��Ă��Ȃ������̂��B�R���v���@���ɂ���͂��Ȃ̂Ŕ��肻���ȃ��m�����A���͗��̔R���^���N���́A���̃^���N�Ƃ͕ʌn���A�R���R�b�N���ւ��Ďg�p��������Ȃ̂ŁA���̃^���N�֔R���������Ă��Ȃ��Ɣ���Ȃ��B�s�����͗��̕��ɂ������̂ŁA�x�e�����̔ޓ������O�ɔ���Ȃ������炵���B����ɂ��Ă������O�̓_���̗����x�ł͂���̂�����A��͂�ޓ����G�n�ő����ْ����Ă����̂��낤�B �@
���@�͔R����ŁA�V����͌����瓌�֎O�L���̊C���ɕs���������B��ԂɊC�ւ̕s�����͑�ςȊ댯���̂����A�{����т͒�����Âɒ����𐬌��������B�@�O�ɒE�o�����g�ߒc�͖�̊C���j���ŊC�݂Ɍ������ƁA�����ɂ͋��t�����_�������đ҂����܂��Ă����B�����D�_���x�����ĕs�Q�Ԃ����Ă����̂��B�j���������W�c�����R������C�R�����Ȃǂ��ƒm�������t�͍Q�Ă��B�����ɒn���̐N�c�ɐl��������B�N�c���痈���l���g�ߒc�̐l�����m�F���āA���x�͌������ɘA�����s�����B�������ł����c�̑��݂͒m�炳��Ă͂��Ȃ��������A��c�ɎQ�d�{������������̂ł͕���������Ȃ��B�����ɋ߂��̕l�����R��s�w�Z(���l����n)�Ɉ�s���ē������B�����ɂ͌̏Ⴕ�ĕ��u����Ă������R�̏d������@���邾���ŁA���Ɏg�ߒc����ꂻ���ȋ@�̂͂Ȃ������B���̌�ʎ�i����z�ł������ɂȂ����Ƃ��������A�w�Z���̖��߂Ŋ�n�̐�����������������āA�O��ł��̔����@�̏C�����n�܂����B �@
���̍������ł́A�����̓��v王{�A�O���̏d���A�C���̕ē��Ȃǐ��{��]���g�ߒc�̋A����҂��Ă����B�\��̎����ɂȂ��Ă��؍X�Âɓ������Ă��Ȃ��ƌ������āA�ޓ��͋C�𝆂�ł������A�[��ɂȂ��Ă���l������������g�ߒc�����̕�����A���g�����ꓯ�ɗ��ꂽ�B���ǁA���{��]�����O��Ŕޓ��̋A���҂��ƂɂȂ����B�l����n�ł́A�܂��ɐ푈��ԂŏC�����s���Ă����B�퓬��~�ŕ��S��Ԃ̏��ɁA���̑���������A����������ɍ��������̂��낤���A�ĊO�ޓ����[�����𖡂���Ă����̂����m��Ȃ��B��u�ł���s���̕s���͖Y��Ă����낤���A�d���̎g�����ɂ��R���邱�Ƃ��o�����B�C���͒����̏��鍠�܂łɂ͏I���A�����ɗ��������d�������z��s��ɂ��ǂ蒅�����̂�21���̌ߑO�������������B �@
�g�ߒc�͑����Ԃ��d���Ăē����̑������@�Ɍ������ƁA�A�����Ƃ̌��̓��e����������B�u�ȂɁI26���Ɍ��ɐi�����Ă���̂��v�ƈꓯ�͑�Q�Ă������낤�B�Ƃɂ������Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƌ��؋�̓O��R��h�̊����ł��鏬�������卲�ɂ́A��������čS����ւ̑[�u���Ȃ��ꂽ�B����ł͕É����M�̖��ߕ�����Ĕ[���������Ƃ��]���Ă��邪�A�����͕����̖������̍s��������������炵���B�������A�����̍R��h�B�͗��R�q���̍R��h�����������R��s��(�����Ԋ�n)�Ɉ��@������ē��S���Ă������B�܂��܂������͑��������A����ł���26���Ɍ��́A���{��]���̃R���g���[�����ɒu����錩���݂����Ƃ������B�Ƃ��낪�̐S��26���ɂ́A�x�͘p�ɑ䕗���㗤���Ă��āA�������̘A���R���i����28���܂ŌJ�艄�ׂɂȂ����B�u�����A�_���������Ă��邼�v�Ǝv�����l�����������̂ł͂Ȃ����낤���B �@
����ɂ��Ă��g�ߒc�������m�̉������ɕs�������đ���Ă�����A�A���R�i�����̍����́A����Ȃ��̂ł͎��܂�Ȃ������낤�B�Ō�̍Ō�ŁA���{�̉^�͏�����Ă��Ă����̂����m��Ȃ��B8��15���̋ʉ������̌�A�䐹�f�����ŏI������肵�����{���{�̒��ł́A�����Ă͑����Ă����̂ł����B�����ɂ��Y���ꂽ���{�̗��j�̈ꕔ������B�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@���ŏ��̓��U
�ŏ��̓��U���o���̓t�B���s���̃��C�e�p�ł̐킢�ł������B�~�b�h�E�F�[�C��ȍ~�̓��{�R�͑哌���푈�����̐����͖����A�L�x�ȕ����Ƌ���ȍH�Ɨ͂����ČR�ɏ��X�ɒǂ��l�߂��Ă������B����Ȓ����a19�N6��15���A�{�y�h�q�ׂ̈̏d�v���_�ł������T�C�p�������ČR�ɍU�����ꂽ�B����ɂ��a29�ɂ��{�y�������\�ƂȂ����B �@
�ČR�̓T�C�p���ח��̌㤃}�b�J�[�T�[�̖̒n�ł���t�B���s�����U�����A���{�{�y�U���̑�������ɂ��悤�Ƃ��Ă����B�t�B���s���͓��{�Ɠ���̐Ζ����Ȃ��헪�I�ȗv���ł��褑�{�c���ČR�������̊l���ɓ������Ƃ�\�����Ă����B �@
����1����� �@
���a19�N10��17���A�ČR�̓��C�e�p���̃X���A�����ɏ㗤���J�n�����B ��18���ɑ�{�c�̓t�B���s���h�q�ׂ̈̍��u��1�����v�߂����B���̍��ł̓{���l�I���u���l�C�ŕ⋋���ς܂����I�c�͑������C�e�p�ɓ˓�����ČR�U�����������ł���Ƃ����v��ɂȂ��Ă����B���ɕĊ͑����Ђ����隙�Ƃ��ď���͑��A�V�����Ƃ��Đ����͑��A�u���͑����Q��B�����āA��n�q���ł�����q��͑��������x������Ƃ����ړI�Ő��ɉ�����Ă����B �@
�������A���q��͑��̓����̐�͂́A���34�A��@�@1�A�V�R3�A�ꎮ���U1�A���2�̍��v��40�@�����Ȃ������B�V�������čU�����������j���邽�߂ɂ́A�Ȃ�Ƃ��Ă��ċ@�������̓�����}���邵���Ȃ������B���̖�ڂ���q��͑����S���Ă����̂ł�����������ꂾ���̐�͂ł͒ʏ�̍��ł͂ǂ����悤���Ȃ��Ƃ������Ƃ͖��炩�Ǝv��ꂽ�B �@
���́A���̑��q��͑��������ŏ��̐_�����ʍU������Ґ��������ł������̂ł���B�����āA���q��͑��̎i�ߒ����͓��U�̐��݂̐e�Ƃ���ꂽ�吼�뎡�Y�����ł������̂ł���B �@
���_�����ʍU�����̕Ґ� �@
�吼�����͏��a19�N10��17���}�j���ɕ��C�����B19���ߌ�Ƀ}�o���J�b�g��s��ɏo�������B�����āA���̃}�o���J�b�g��s��̑�201�C�R�q����{���ɂ����ė��j�I�ȉ�c���s��ꂽ�̂ł���B �@
�吼�����͐��ɁA �ČR����1�T�Ԉʎg�p�s�\�ɂ��A��1�����𐬌������邽�߂Ɂu����250�������e��������đ̓���������ق��ɁA�m���ȍU���@�͂Ȃ��Ǝv�����ǂ�Ȃ��̂��낤�H�v�Ƒ̓���U�����B�ɒ�Ă����B �@
�����ׂ�����ł�����201���̋ʈ䒆���́A�ӔC�҂̎R�{�i�߂��s�݂̂��ߤ���������ł͌��߂��Ȃ��Ƒ吼�����ɘb�����B�������A�吼�����͊��ɎR�{�i�߂���͗����Ă��褂��̂��Ƃ��ʈ䒆���ɓ`�����B�ʈ䒆���͍l���鎞�Ԃ��~�����Ǝw�h��тƋ��ɉ�c�̐Ȃ𒆍������l�Řb���������s�����B�l��{���������ƌ���ꂽ�ʈ䕛���ł���������틵���l����ɑ̓���U���������@�͂Ȃ��ƌ��S�����B�����āA�����吼�����ɓ`�����̂ł���B �@
�����ɓ��ʍU�����̕Ґ��������Ɍ��肳�ꂽ�B �ʈ䒆���͎��炪�艖�ɂ����ċ���P�����s���Ă����A��10���b���s�\�ȗ��K���o�g�̓����23���ɑ��k�����B���̎��A�S����������グ�Ă��̍��Ɏ^�������B�����̐틵�A�����ē�����̎m�C�Ƃ����̂͂��̂悤�Ȃ��̂ł������B�ڍׂɂ��Ă͕ʂ̃y�[�W�ŐG�ꂽ���B �@
�w�����ɂ͊C��70���̊֍s�j��т��w�����ꂽ�B�[��A�ʈ䕛������֑�т͌Ăяo���ꂽ�B�֑�т͋ʈ䕛������w�����ɂ��đ��k���ꂽ�B�֑�т�10�b�O��A�ڂ��ނ��Ă��ނ��A�l���Ă����B�Ŋ��ɁA�u����A���ɂ�点�Ă��������v�ƌ������B�����ŁA�ŏ��̓��U���ł���24�������肵���B���̑�����_�����ʍU�����Ɩ������A���̉��ɖ{���钷�̑�a���ɂ��ĉr�����A �@
�u�~���́@��a�S���@�l��͂@�����ɓ��Ӂ@�R���ԁv �@
���A4�̕����ɂ��ꂼ�������I�����A�~�����A��a���A�������A�R�����Ɩ��t����ꂽ�B �@
���吼�뎡�Y�����̋�Y �@
�吼�����͊C�R��]�̌v�悵�����U�̑S�ӔC�킳��Ă����B�吼�͓��U�̌����A��ҒB�����n�ɑ��葱�����B�������A�吼�͓��U�̐ӔC������̖������Ƃɂ��S�������̂ł���B �@
���a19�N10��20�����A�吼�͓��U�����B���W�ߌP�������B���_�Œm���Ă����吼�͘b�̊Ԓ��A�̂������݂ɂӂ邦�A��ʂ������ň������Ă����Ƃ����B �@
�P���ł́u���{�͂܂��Ɋ�@�ł���B���̊�@���~��������̂́A��b�ł��R�ߕ������ł��A�����̂悤�Ȓn�ʂ̒Ⴂ�i�ߊ��ł��Ȃ��B���������āA�����͈ꉭ�����ɂ�����āA�݂Ȃɂ��̋]�������肢���A�݂Ȃ̐������F��B�݂Ȃ͂��łɐ_�ł��邩��A�����I�ȗ~�]�͂Ȃ����낤�B���A��������Ƃ���A����͎����̑̓����肪�����������ǂ����A�ł��낤�B�݂Ȃ͉i������ɂ��̂ł��邩��A�����m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B��X�����̌��ʂ��݂Ȃɒm�点�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����݂͂Ȃ̓w�͂��Ŋ��܂ł݂Ƃǂ��āA�㕷�ɒB����悤�ɂ��悤�B���̓_�ɂ��ẮA�݂Ȉ��S���Ă���v�ƌ������B �@
�吼�͗܂���ŁA�u�������藊�ށv�ƌ����ČP�����I������B�吼�����̓p�C���b�g�̈�l��l�ƈ��肵�Ĕނ�̕��^���F�����B �吼�͕ČR�����U����u���A���̐�ʂ��}���ɗ����Ă�������U����߂Ȃ������B�������A�吼���g �u���U�𖽂���҂͎���������ł���v �ƌ����āA������҂Ƃ��Ă̐U�镑�����ւ��Ă��邪�@���������Ƃ����B �@
���a20�N5���A�吼�͌R�ߕ������Ƃ��ē��n�ɋA�҂����B���ɂɓƋ����čȂƂ͈ꏏ�ɏZ�܂Ȃ������B��������҂��u�T�Ɉ�x�͋A��ĉ�����̉ƒ뗿����H�ׂĂ͂ǂ��ł����v�Ɗ��߂��B�吼�́u�N�A�ƒ뗿���ǂ��납�A���U�����͉ƒ됶�����m��Ȃ��Ŏ���ł�������B614�l�����B���ƈ��肵�Ă������̂�614�l�������v�Ɠ������B�吼�̖ڂɂ͗܂������ς����܂��Ă����Ƃ����B �吼�ɂ́A�Ŋ��ɂ͕K�����������U�����̌��ǂ��Ƃ����o�傪�ł��������Ă����̂ł��낤�B�������A����ɂ��̂悤�Ȋo�傪���邩��Ƃ����āA���U������������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�ނ͎��̂悤�Ɍ���Ă����悤�ł���B �@
�u���U�͓����̊O���ł���v�u�킪�����͊����Ē�܂炸�A�S�N�̂̂��A�܂��m�ȂȂ����Ƃ��v �@
�܂�A����������Ōセ�̕]���͕S�N�o���Ă���܂�Ȃ��A�N����������������Ƃ𗝉����Ȃ����낤�ƌ���Ă����̂ł���B �吼�́A�s��̗��������A����̖������Ƃɂ���ĐӔC���Ƃ����B �@
�u�ᎀ���Ȃċ������̉p��Ƃ��̈⑰�Ɏӂ���Ƃ��v ����n�܂�⏑���c���āB�@
�吼�����̓��U���̐^�ӂƂ͉��������̂��H���̓����Ƃ�������،����p�c���́u�C���̗��v���Ɍf�ڂ���Ă���B������݂�Ɗm���Ɂu���U�͓����̊O���ł���v �u�킪�����͊����Ē�܂炸�A�S�N�̂̂��A�܂��m�ȂȂ����Ƃ��v�Ƃ����吼�����̔����𗠕t���Ă���悤�ɂ��l������B�܂��A��ɊW�҂�����������Ȃ��������Ƀf���P�[�g�Ȗʂ��������Ɛ��@�����B�p�c�����u�C���̗��v���o�ł��Ă���Ǝc�������ł������ɋM�d�ȏ،��ł���B �@
���_�o�I�ɂ� �@
���a19�N11�����{�A�p�c���͓��U�����Ƃ��ĒҌ������A�鑺�����ƂƂ��Ƀ_�o�I�ɔh�����ꂽ�B����������A���}��J���ꂽ�B�i�ߕ�����̎Q���҂͎i�ߊ���쏭���A�Q�d�����c���卲�A��C�Q�d�_�c�����A��s�����Y�R��тł������B �@
�F�A��ϒg�����l�X�ŁA�����ł���ƌ��������q�������U���������ɂƁA���������ɂ͂����犩�߂Ă��Ȃ������B�܂��A��쏭�������������̑O�ňꌾ�����𗘂��Ȃ��������Ƃ��p�c���ɂƂ��Ĉ�ې[���������B���̗��R�͐��킩�邱�ƂƂȂ�B �@
����Ȓ��A���c���Q�d��������U�̎�|�ɂ��ĕ�������Ă��邩�Ƃ̎��₪����A�p�c���͗ǂ�������Ȃ������Ɠ������B�Q�d���͂��炭�l������ɘb���n�߂��B �@
�����U�̐^�� �@
�u�������A����ł͂�����x������₷��������b�����v�ƁA���t��I�Ԃ悤�ɐÂ��ɘb���������B �@
�u�F���m���Ă��邩���m��Ȃ����A�吼�����͂����֗���O�͌R���Ȃ̗v�E�ɂ����A���{�̐�͂ɂ��Ă͒N������ԗǂ��m���Ă�����B�e�������͑̕S��������A��b�ւ͕K�v�Ȃ��Ƃ�������Ă���̂ŁA����͑�b�����e�ǒ�������ԏڂ����������Ă����ł���B���̒������A�w�����푈�͑�����ׂ��ł͂Ȃ��x�Ƃ��������B�w����������u�a�����Ȃ���Ȃ�ʁB�}���A�i�������������A�G�͂��łɃT�C�p���A���s�ɂ��ł����n�����ċA����^�����@��z���Ă���B�c�O�Ȃ���A���݂̓��{�̐�͂ł͂����j�~���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����ɁA�����d���A�K�\�������A���Ɣ��N�������c���Ă��Ȃ��B �@
�R���H��̒n�����݂�i�߂Ă��邪�A���͔�s�@�����ޗ��̃A���~�j�E�������Ɣ��N�������Ȃ��̂��B�H��͂ł��Ă��A�ޗ����Ȃ��Ă͐��Y���~���Ȃ���Ȃ�ʁB�R�����A����������������^���M�Z������D�ɉ������ăX�}�g�����^�Ԍv��𗧂ĂĂ��邪�A�ƂĂ��Ԃɍ���ʁB���N��ɂ́A����ɓG���֓�����ɏ㗤���Ă��Ă��A�H�����s�@����Ԃ��R�͂������Ȃ��Ȃ�B �@
�����Ȃ��Ă���ł͒x���B�����鍡�̂����ɍu�a���Ȃ���Α�ςȂ��ƂɂȂ�B�������A�K�_���J�i���ȗ��A������ʂ��ŁA�܂���x���G�̔��R���~�߂����Ƃ��Ȃ��B���̂܂܍u�a�����̂ł́A�����ɂ���Ȃ��B��x�ŗǂ�����G�����̃��C�e����ǂ����Ƃ��A������@��ɍu�a�ɓ��肽���B �@
�G��ǂ����Ƃ����Ƃ��ł���A�����O���̍u�a���ł��邾�낤�B���A�O�Ƃ͓G�Ɏ��������ɎO���ł���B��̓I�ɂ͖��B���ς̐̂ɕԂ邱�Ƃł���B�����Ă��̏����Ȃ̂��B�c�O�Ȃ�����{�͂����܂Œǂ��߂��Ă���̂��B �@
����G��{�y�Ɍ}����悤�Ȃ��ƂɂȂ����ꍇ�A�A�����J�͓G�ɉċ��낵�����ł���B���j�Ɍ���C���f�A����n���C�����̂悤�ɁA�w���n���͐��f����A�����̂���҂͎��X�e���j����A�c��҂͏��q���ƁA�ӋC�n�̖����j�����ƂȂ�A���{�����̍ċ��̋@��͉i�v�Ɏ����Ă��܂����낤�B���̂��߂ɂ����U���s���Ăł��t�B���b�s�����Ō�̐��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@
���̂��Ƃ́A�吼��l�̔��f�ōl���o�������Ƃł͂Ȃ��B�������o������ɍۂ��A�C�R��b�ƍ����{�l�ɏ�����\���グ�A���̐^�ӂɑ����������̂ƍl���Ă���B �@
�{�l�Ƒ�b�Ƃ��^�����ꂽ�ȏ�A����͊C�R�̑��ӂƂ݂ċX�������낤�B�������A���A�����ōu�a�̂��ƂȂnj��ɏo�������̂Ȃ�A�����܂������ɕ߂܂�A���邢�͍����Ƃ��ĈÎE����Ă��܂����낤�B���ʂ��Ƃ͋���ʂ��A�푈�̌�n���͑������Ȃ���Ȃ�ʁB�{�l�Ƃ����ł��u�a�̐i���Ȃǂ��ꂽ���Ƃ����������Ȃ�A���̕ۏ͂ł����˂Ȃ���ԂȂ̂ł���B�����A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�Η��C�R�̍R�����N�����A���G��O�ɂ��ē����Ƃ��Ȃ肩�˂Ȃ��B �@
�ɂ߂ē�����ł��邪�A����͓V�c�É��䎩�猈�߂���ׂ����ƂȂ̂ł���B�{�l���b����̐i���ɂ����̂ł����Ă͂Ȃ�ʁx�Ƃ��������̂��B �@
�ł́A�ʂ����Ă��̓��U�ɂ���āA���C�e���G��ǂ����Ƃ����Ƃ��ł���ł��낤���B����͂܂������͒N�ɂ�����Ȃ��B�����̕��������ɂ��A��q�̖͂����ɂ��b���Ă��Ȃ��B�������A�w���U���o���ɂ́A�Q�d���ɔ�����ẮA�����Ɏ��ł�����͂ł��Ȃ��B���̖����̔��͉������邱�Ƃ��ł��邪�A���̎Q�d�������͎��̐^�ӂ𗝉����Ď^�����Ă��炢�����B�����͐�ɖ��p�ł���x �@
�Ƃ��āA���ɂ����b���ꂽ���Ƃł��邪�A���͒����قLjӎu�������Ȃ��B�����̋����q��(�Q�d���͏�����s�����̍��A�ꎞ��������s���K���̋������������Ƃ�����A���̒}�g���̍��͘A�����K�q�����C�Q�d�ŁA�퓬�@���c���Ɍv���s�̎w���ɓ�����ꂽ�B�����A�吼�����͎i�ߊ�������)�Ȏq�܂Ŏ̂Ăē��U�������Ă���悤�Ƃ��Ă���̂ɁA�ق葱���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̐^�ӂ�b�����B�����́A���U�ɂ�郌�C�e�h�q�ɂ��āA �@
�w����́A�㕪��А����̌����݂͂Ȃ��A���ꂪ��������Ǝv���قǑ吼�͔n���ł͂Ȃ��B�ł͉��̌����݂̂Ȃ��̂ɂ��̂悤�ȋ��s������̂��A�����ɐM���Ă悢���Ƃ������B �@
��͖�����n�m���������č������ꋋ���V�c�É��́A���̂��Ƃ��ꂽ�Ȃ�A�K���푈���~�߂�A�Ƌ�����ł��낤���ƁB �@
��͂��̌��ʂ����ɁA�����Ȃ�`�̍u�a�ɂȂ낤�Ƃ��A���{���������ɖS�т�Ƃ��鎞�ɓ������āA�g�������Ă����h������҂����������A�Ƃ��������ƁA������������ɂȂ��ĕÉ��䎩��̌�m�S�ɂ���Đ킳���~�߂�����ꂽ�Ƃ������j�̎c�����A�ܕS�N��A��N��̐��ɁA�K������{�����͍ċ�����ł��낤�A�Ƃ������Ƃł���B �@
�É����䎩��̂��ӎu�ɂ���Đ푈���~�߂�Ƌ���ꂽ�Ȃ�A�����Ȃ闤�R�ł��A�N���Z�ł��A���킴��܂��B���{�������~�������ق��ɂ���ł��낤���B�틵�͖����ɂł��u�a���������Ƃ���܂ŗ��Ă���̂ł���B �@
�������A���̂��Ƃ�����O�ɉk��āA�����̎m�C�ɉe�����������Ă͂Ȃ�ʁB����ɓG�ɒm��Ă͂Ȃ��厖�ł���B�u�a�̎������Ă��܂��B�G�ɑ��Ă͖O���܂ōŌ�̈ꕺ�܂Ő키�C鮂������Ă���˂Ȃ�ʁB�G���\���ɂ́A�܂�������肹��A�Ƃ�����������B �@
�吼�́A�㐢�j�Ƃ̂����Ȃ�ᔻ���悤�Ƃ��A�S�ƂȂ��đO���ɐ키�B�u�a�̂��ƁA�É��̑��S������邱�Ƃ́A�{�l�Ƒ�b�ƂōH�삳���ł��낤�B�V�c�É����䎩��̂��ӎu�ɂ���Đ푈���~�߂�Ƌ���ꂽ���A���͂���܂ŏ�A�É����\�����A���A�������U�葱�����߂��ӂ��A���{�����̏�����M���ĕK�����U���������̌��ǂ��ł��낤�B �@
�����A�Q�d���ɂق��ɍ����~����������Ȃ�A���͎Q�d���̌������Ƃ����A�Ȃ���Ή��Ɏ^�����Ă��炢�����x �@
�Ƌ���������B���ɍ�͂Ȃ��̂œ��ӂ����B���ꂪ���̕����������̐^�ӂł���B�����́A�w���͐����č��̍Č��ɋ߂�C�͂Ȃ��B�u�a��A���Ē����̂ł���l�͂������邪�A���̓�ǂ������҂͎������ł���B�x�ƁA�J��Ԃ��A�w��a�A�����͓G�ɓn���Ă������Ēp���������͂ł͂Ȃ��B�{�l�͐푈���I�������邽�߂ɂ͍c���̂��Ƃ͍l���Ȃ��ŋX�����Ƌ���ꂽ�x�Ƃ܂Ō���ꂽ�̂��v �@
�p�c���͏��c���Q�d���̂��̘b�́A���������݂̂ł͂Ȃ��ꌾ�����𗘂��Ȃ���쏭���ɑ��钷���̓`���ł͂Ȃ����A�܂��A���c���Q�d���������̌��ǂ��C���Ɗ������Ƃ̂��Ƃł���B �@
����� �@
�����̓��{�l�������ł������悤�Ɋp�c�������A��ςȂ���J������A�������x���Ă���ꂽ�B���a���I�Ղɍ����|���������A����̊��߂�����A��L���������܂Ƃ߂Ă����ꂽ�B���̃y�[�W�ł��Q�l�Ƃ����Ă��������Ă��āA���j�Ƃ���Ă���u�_�����ʍU�����v(�����͕��A����������)�̓��e�Ǝ��玨�ɂ��ꂽ���c���Q�d���̘b�Ƃ̑���ɂ��āA�p�c���͓����i�ߊ��ł���A�b���Ă����B��̐����҂ł����쏭���Ɋm�F����邽�߂ɕv�l�Ɉ˗������B���͓��U���ɂ͔��ł������Ƃ�����쏭���͋��R�l�炵���A�ق��Č�炸�Ƃ������ƂŊm�F���邷�ׂ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ������Ƃł������B�@
�֑�т͕~�����̑����Ƃ��Đ_�����ʍU�����̐�삯�ƂȂ����B���߂Ă̓��U���̎w�����͂��ЊC�R���w�Z�o���Ƃ������ƂɓY�����l�I�ł������B�֑�т̋�Y����p���L�^�Ɏc���Ă���B �@
���_�����ʍU�����̒a��(�ʈ䕛���Ɗ֑�т̉�b���) �@
�₪�ăR�g���R�g���Ƃ������ȑ���肪�~��Ă��āA���g�֑̊�т̎p���m�����ɂ����ꂽ�B�}�����̂��낤�A�J�[�L�F�̑�O��R�������������Ă���B�ʈ䕛���ɋߊ���āA�u����тł����H�v�ƕ������B�ʈ䕛���͂������̈֎q������ɂ����߁A���̉��̐₦����C�̐Â����̂Ȃ��ɁA�����͂ނ����������B�ʈ䕛���́A�ׂɂ�������֑�т̌�������悤�ɂ��A��A�O�x�y���������āA�u�ցA���傤�������������������ɂ���ꂽ�̂́A�w�����x���𐬌������邽�߂ɁA����250�L���̔��e�𓋍ڂ��ēG�ɑ̓���������������A�Ƃ����v����͂����邽�߂������̂��B����͋M�l�����������m���Ă��邱�Ƃ��낤�Ƃ͎v�����A�E�E�E�E�E���Ă͂��̍U�����̎w�����Ƃ��āA�M�l�ɔ��H�̖�𗧂Ă����A�ǂ����H�v�ƁA�܂���ł����˂��B�֑�т͐O���ނ���łȂ�̕Ԏ������Ȃ��B���n�����̏�ɂ��A�I�[���o�b�N�̒����𗼎�ł������āA�ڂ��ނ����܂ܐ[���l���ɒ���ł������B�g���������Ȃ��B�|�|�|�|1�b�A2�b�A3�b�A4�b�A5�b�E�E�E �ƁA����̎肪�킸���ɓ����āA�����������������Ǝv���ƁA�������ɓ������������Č������B�u���ЁA���ɂ�点�Ă��������v�������̂�ǂ݂��Ȃ����ĂȌ����ł������B�ʈ䒆�����A�����ꌾ�A�u�������I�v�Ɠ����āA�����Ɗ֑�т̊�����߂��B �@
���@
���̌�A��L���͂̍�҂ł��钖���卲�A�ʈ䒆���A�֑�т�3�l������̂��Ƃ���荇�����B���̎��A�����卲�͋ʈ䕛���ɑ��̖��O���u�_����(����Ղ�����)�Ƃ����̂͂ǂ����낤�H�v�ƒ�Ă��A�u����͂����A����Ő_�����������Ȃ�����Ȃ��Ȃ��I�v�ƌ����Ɏ^�������B �@
�����āA�����卲�͑吼�����ɕ����B���̍ہA�吼�����́u���ށv�Ɨ͋������ȂÂ����B���a19�N10��20���̌ߑO1�����߂��Ă����B�������āu�_�����ʍU�����v���a�������̂ł������B �@
���w�Z�o�֑̊�т͌R�l���_�����������܂�Ă���A���U���̑������邱�Ƃ�ȉ��������̂ƍl����B���͂��֑̊�т��{���֑̊�тł���ƍl���Ă���B�������A���R�Ȃ���֑�т���l�̐l�Ԃł���B��l�̐l�ԂƂ��Ă͖{���͂ǂ̂悤�Ɋ����Ă����ł��낤���B �@
�����֑̊�т͐V���ŁA�����q����Ƃ����V�Ȃ������B�܂��A��̃T�J�G����͎l���̐����ň�l��炵�Ă����B���̓�l�̂��Ƃ��l���Ȃ��͂��͂Ȃ��B�ʈ䒆������b�����Ƃ��A��u�ɂ��Ĕގ��g�̐l���ƌ�Ɏc�����ƂɂȂ��l�̂��Ƃ��l�����ł��낤�B�l������ŁA�ނ͐�m�Ƃ��Ă��ׂĂ̎��I������Ȃ������A���U������ɂ�点�ė~�����Ɛ\���o���̂ł���B �@
�������Ȃ���A�֑�т̋�Y�͎��̂悤�ɋL�^����Ă���B �@
�������ʐM���h���@����c���Ɗ֑�т̉�b�L�^ �@
�����ԉ����ɔY��ł����ւ́A���̓��̗[���A�}�o���J�b�g��n�o���o����̓y��œ����ʐM���h���̏���c���ɉ�����B�ւ̘b���Ԃ�́A���U�U���̂����S�ʂɂ��āA����قNjC��肵�Ă��Ȃ��l�q�ł������B�ւ͂���������B �@
�u�ڂ��̂悤�ȗD�G�ȃp�C���b�g���E���Ȃ�āA���{�������܂�����B��点�Ă����Ȃ�A�ڂ��͑̓����肵�Ȃ��Ƃ�500�L�����e�����̔�s�b�ɖ��������ċA�邱�Ƃ��ł���B�ڂ��͖����A�V�c�É��̂��߂Ƃ����{�鍑�̂��߂Ƃ��ł�����Ȃ��āA�ň��̂j�`�m�Ȃ̂��ƁA�C�R�m���̉B��|�n�̂��߂ɂ����B���{���s������A�j�`���A�����ɉ�������邩�킩���B�ڂ��͔ޏ�����邽�߂Ɏ��ʂB�v
 �@
�@�������͂�@

����@�@�@�@�@�@�@�@�@����̍� �@
�]�R����}�@�@�@�̍]�R�@��}�ɓ��� �@
�������v�y���h�@�@�@�����@���̌v�����Ă����h���y���܂� �@
�ߌN���b���@�@�@�N�ɜ߁i�˂��j���@�b�锜�ꕕ��̎��� �@
�ꏫ���������́@�@�@�ꏫ�������Ė����͂� �@
�� �@
����L������������R���A�݂�Ȑ��ɂȂ��Ă��܂����B �@
���O�͂ǂ�����ē��X�̐������y���߂�Ƃ����̂��B �@
���肢���B�N���ꂪ����ɕ�����ꂽ�Ȃ�Ęb�͂悵�Ă���B �@
��l�̏��R���蕿���������A�ł͊����Ƃ����l���r�ƂȂ��Ă���̂��B �@
�� �@
�u�ꏫ�������Ė����͂�v���̈��͂����̎�����ɂ܂łȂ��Ă܂��ˁB�u����̍v�͐���879�N�B���̍��������́y�����̗��z�ɂ�藐��܂����Ă��܂����B���̔����͓������ŖS�̂��������ƂȂ�܂��B�����B�ӓ��̎��l�B���͖����B���B�̐l�B���U�s���ŁA���N�ȐE�ɂ������A��������Q���܂����B70���߂��ĉȋ��ɍ��i������A�܂��Ȃ��S���Ȃ�܂��B�@

�@�@�@�����ׂ邻�̏���̖{���@�c��(�݂���)�̎l��(���)�����ׂ� �@
1897�N(����30�N)���R�[�쎌�́u�R�́v�ɋȂ�t���ČR�̂Ƃ��A���̌�A1897�N(����30�N)���ɁA�y�m���������̌R�y�t���������ˌ����g���V���ɍ�Ȃ��A1900�N(����33�N)�Ɂu�R�͍s�i�ȁv�Ƃ��Ēa������(���̓����A�R�y�Ȃ̍ō��K���͌R�y�t�ł������B���a18�N�ɂ͌R�y�����܂ł̊K�����݂���ꂽ�B)�B�����́A���N4���A��͕x�m��g�̌R�y���ɂ���čs��ꂽ�B��O����ɉ��t����A1941�N(���a16�N)12��8���̓��ĊJ�펞�ɂ��J��Ԃ����W�I���痬���ꂽ�B�C�R�Ȃ̐���s�i�Ȃł���A�C�㎩�q���ł��A�C�㖋���ĕ��ʒB�ɂ��V��Ȃ̈�Ƃ��āu�R�͍s�i�ȁv�̖��̂Ő��肳��Ă���A�i������o�`���T�Ȃǂőt�y����Ă��鑼�A�ω{�s�i�ȂƂ��đt�y����Ă���B���{���\����s�i�Ȃ̈�ł���A���̓p�`���R�X�Ȃǂł��������ȂǁA�L�������ɐe���܂�Ă����B
 �@
�@���u���a���R�v�̎��s
�u���B���ψȍ~�́w���a���R�x�����[�h�����̂͗��R�����̒��������O���[�v�w��[��x�B���B���ς�2�N�O��1929�N�Ɍ�������܂����B�����o�[�͓����p�@�A�i�c�S�R�A�Ό��Ύ��A�����́A�c���V����40�l�B �@
��ʓI�ɂ͓��������{��j�łɓ������悤�Ɏv���Ă��܂����A���a���R�̐헪�\�z�𗧂Ă��͉̂i�c�ƁA�Ό��A�����A�c����4�l�B�����͔ނ�̍\�z�ɏ]���ē������ɉ߂��܂���B �@
�i�c�𒆐S�ɂ����ނ�4�l�Ƃ��A�P�Ȃ�R���G���[�g�ł͂Ȃ��A�����̓��{�Љ�ł͒m���Ƌ��{�����m�I�G���[�g�ł����B��O�̗��R�͉����l�����ɖ\�������Ǝv��ꂪ���ł����A�����ł͂Ȃ������̂ł��v �@
��c���E���É���w���_�����͂������B��c���́A���70�N�ɍ��킹�āw���a���R�S�j�x�S3��(�u�k�Ќ���V��)���㈲�B�i�c�A�Ό��A�����A�c����4�l�����ɁA�Ȃ����{�����d�Ȑ푈�ɓ˂��i��ł������̂����炩�ɂ��Ă���B �@
�u��[����݊������߂��̂��A1931�N�̖��B���ς̔��[�ƂȂ����w�����Ύ����x�ł��B���B���ς͊֓��R���Q�d�������Ό��̃v�����Ɋ�Â����̂ł����B�ނ͓����Ԃŕ������Ă������֖������̂��߁A���͍s�g�ɂ��S���B��̂�ڎw���Ă����̂ł��v �@
�Ό��͊֓��R���C�O����A20���I�㔼���ɓ��ĊԂŐ푈���s����Ƃ���u���E�ŏI�푈�v�Ƃ����Ǝ��̐��E�ς������Ă����B �@
�u�Ό��͏����I�ɁA�A�W�A�̎w�����ƂƂȂ������{�ƁA���Ă��\����Ă����E�ŏI�푈��키�Ɨ\�z�B���̐푈�ɏ����߂ɂ͓S�E�ΒY�Ȃǂ̎������K�v�ŁA���̂��߂ɑS���B�̗̗L�A����ɂ͒����嗤�̎����E�Ŏ��Ȃǂ��������Ȃ�������Ȃ��ƍl�����̂ł��v �@
�Ό���̖d���A�z���s�ׂɑ��A�����̎�Η玟�Y���t�͐���́u�s�g��v�����߂����A�֓��R�͂�������Đ�����g��B���R�Ȃ̌R���ے��������i�c���A�Ό���̍s�����x�������B �@
���B���ς́A�i�c�𒆐S�Ƃ�����[��̎����ȏ����ɂ���Đ��s���ꂽ���̂������̂��B �@
�u���R�����Ă̏r�p�ƒm��ꂽ�i�c�͑�ꎟ���E���O���6�N�ԁA�h�C�c�Ȃǂɒ��݁B���̎��Ԃ��܂��܂��ƌ��܂����B �@
�l�ގj�㏉�̑��͐�ƂȂ�����ꎟ���E���Ńh�C�c���������̂́A���������������ł��Ȃ��������߁B���̐��E���͂���ɋ@�B�����i�݁A������J���͂��K�v�ɂȂ�Ɗm�M�����i�c�̓h�C�c�̓Q�܂Ȃ��悤�A�����A�@�B���Y�A�J���͂̂��ׂĂ����O�ŋ����ł���̐��𐮂��˂Ȃ�Ȃ��Ɗ�@�����点���B �@
�i�c�̖ڂɂ́A�s��ʼnߏd�Ȕ������ۂ��ꂽ�h�C�c���A���̑��̔��Γ_�ɂȂ�͕̂K���������B�����ɓ��{�͕K���������܂��B���̎��ɔ����č��Ƒ������̐��𑁊��ɐ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl�����̂ł��v �@
�����A�����̓��{�͑����̕������A�����J����̗A���ɗ���ȂǁA���������ɂ͒����������B �@
�u�����ʼni�c���l�����̂������̖��B�Ɖؖk�A�ؒ��̎������m�ۂ��邱�Ƃł����B�����A�����ł͔����i�V���i���Y��������オ��A�Ӊ�Η����鍑���}���{�������̓����ڎw���Ėk�������{�B���̓����ɉi�c��́A���{�̎����헪�����������Ƃ��Ĉ��S�ۏ��̊�@�������߂��B�i�c��Ό������B���ς��N�������̂́A����������@���ɂ����̂ł����v
����Ȉ�[��̍\�z�Ƃ͋t�ɁA�����̓��{���{�́A��ꎟ���̐�Ђ܂��Č������ꂽ���ۘA���̏�C�������Ƃ��āA���ۋ�����͍����Ă����B �@
�u���̍��̈�ʐ��_�̊��o�́A���܂̓��{�l�̊��o�Ƌ߂������B�����t�̓��V���g�����ȂǗl�X�ȍ��ۏ������сA���a��ۂ��߂ɍ��ۋ����H����i�߂Ă��āA���}�����͂���Ȃ�Ɉ��肵�Ă��܂����B �@
��[��炷��ƁA�Ƃɂ����g�������Ă܂��Ƃ�����t�A���}�����Ƃ͂��܂�ɖ��m�B���܂ł����Ă����Ƒ������̐��͂ł����A���{�͎��̑��ŖłԂ��A�O�����ɓ]������ƁA��@�������܂����������v �@
�������āA�i�c��͐��}�����ƂɂƂ��đ���A�����������R�̎�Ő������x�z���悤�Ɠ��������B �@
�u�ނ�́w�������̓Ɨ��x�Ɓw���C�R��b�������x���g���ē��t�Ɏ��X�Ȝ������J��Ԃ��A���������Ă����܂����B �@
'31�N12���ɔ����������{�B���t�ł́A��[��̐����H��ɂ��A��[������r�ؒ�v�������ɏA���A�i�c�����R�ȃi���o�[4�̏���ɏA�C�B��[��n���������R�̗v�E���قړƐ肵�Ă��܂����B���R�����́A�����Ɋ֓��R�̑S���B��̂▞�B�������̕��j�����F���܂����v �@
����ɁA'32�N5���A�N���Z�����{����E�Q����5�E15�����������B���}�����͏I�����}����B'33�N�ɂ͖��B���Ɨ�������A���{�͍��ۘA����E�ނ����B �@
���R�̎嗬�h�ɂȂ�����[��ł͌��͓����������B�c���h�Ɠ����h�ɕ����ꂽ�����̂Ȃ��ŁA�i�c�͎������Ɏa�E�����B �@
�i�c�̎���́A�Ό��ƕ������i�c�̍��Ƒ������\�z�𐄐i���Ă����B'36�N�A�c���h�̐N���Z��ɂ�锽���u2�E26�����v���N�������A�Ό��A�����͓�l�O�r�Œ�������B �@
�u�i�c�̍\�z�ڈ����p�����͕̂����ł����B�����͉i�c�̍\�z�Ɋ�Â��A'32�N�ɒa���������B���Ƃ͕ʂɁA�ؖk�n��ɐe���̘��S���{������āA�ؖk�̎������m�ۂ��悤�Ƃ����B������ؖk�����H��ł��B �@
�����������m�ۂ��}�����̂̓h�C�c�Ńi�`�X�����������A�x���T�C������j�����čČR�����s�������Ƃ��傫���B����E��킪��������ттĂ����̂ł��v
�Ƃ��낪����ɑ҂������������̂��Ό��������B�Ό��������͉ؖk�����H����x�����Ă������A�r���ł�����~�߂�B���R�́A�\�A�̑��݂������B �@
�u���B���Ɖؖk�ɐڂ���\�A�ɓ��R���A�R����啝�ɑ������Ă����̂ł��B�ؖk�����H��𑱂���ƁA��@�����������\�A��������Đ푈�ɂȂ鋰�ꂪ����Ɗ뜜�����B �@
�\�A�Ƃ̐푈�ɂȂ�A�A�����J���畨����A��������܂���B�������ؖk������i�߂�ƁA�����Ɍ��v�����p�ĂƂ̊W���ٔ����A�Ζ��̗A�������Ȃ��B����Ď��d���ׂ����Ƃ����̂��A�Ό��̍l���ł����v �@
�������Ό��́A���Ƃ����B�Ŏ��̑�킪�N�������Ƃ��Ă��A���{�͉�����ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ������ꂾ�����B �@
�u�������A�����͉��B�ő�킪�N����ΕK�����{���������܂��Ǝ咣�B�ؖk�����H����~�߂Ă��܂��ƁA���̏������ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ��ĐΌ��Ɖs���Η������̂ł��B �@
'37�N7���Aḍa���������u�����A�����푈���n�܂�܂����B�Ό��͑��₩�Ɏ��Ԃ����E�����悤�Ƃ��܂��B�Ό��́A�ؖk�ɂ͖k��������̂ŁA�������{����ɋ����Ȃ��A�K��������ɂȂ�Ɨ\�z���Ă��܂����B �@
���āA�����́w�ꌂ�Œ�����������������x�ƍ���B����̊g�傩�s�g�傩�ŁA���R��������������_���ɔ��W���܂����B��[��̃����o�[�ŁA�����Ɠ����̓c���V��������ɓ����B���ǁA�����͐Ό���r�����Ď����������B�Ό��͎��r���܂����v �@
�������A�Ό��̗\���ʂ�A�������{�͊拭�Ȓ�R���J��Ԃ��A�����푈�͓D�������Ă���—�B �@
'36�N11���A���{�͓��Ɩh�������B'38�N4���A�߉q�������t�͍��Ƒ������@�����z�B���ɍ��Ƒ������̐����X�^�[�g�����B'39�N9���A�h�C�c���|�[�����h�ɐN�U���A���B�ő���E��킪�n�܂����B�����͉i�c�⎩�����l�����ʂ�̓W�J�ɂȂ����Ƃ��āA'40�N6���A�u��������\�N�v��v�����肷��B �@
�u���̒��ŕ����́w�哌�������o�ό��x�Ƃ������t���g���A���{�A���N�A�����Ƃ��Ă��������������𓌓�A�W�A�ɂ܂Ŋg�傷��\�z�����߂Čf���܂����B���ꂪ��̑哌�����h���\�z�ł��B �@
����u���ɍ��킹�Ē������������Ƃ���A���������̂��߂ɂ͐Ζ���{�[�L�T�C�g�A�X�Y�A�ΒY��S������Ȃ����Ƃ������B����œ���A�W�A�ł��������m�ۂ��悤�Ƃ����̂ł��v �@
����ɂ̓C�M���X�̂������A����i�o�̓C�M���X�Ƃ̐푈���Ӗ������B����ŁA�����͑ΕĐ�͐�Δ�������肾�����B �@
�u�����́w�A�����J�͕����ƍ��͂Ő��E��ł���A�N�ԌR����͖�140���~(���{��20���~)�œ��{�͂��Ȃ�Ȃ��x�A�w�Ώ����ԈႦ�Γ��Đ푈���m��Ɏn�߂āA���E�l�ނ̔ߎS�Ȃ��ԂɂȂ�x�Əq�ׂĂ��܂��v �@
�����ŕ������l�����̂��A�i�`�X�h�C�c�ɃC�M���X��|���Ă��炢�A���B�ł̃A�����J�̑����������Ƃ������B �@
���{�����ƈɎO�����������̂͂��̂��߂������B�������A�����́A�O�������Ƀ\�A���������4�����A�����������āA�A�����J�����߂悤�ƍl���Ă����B���ہA�h�C�c��'39�N8���ɓƃ\�s�N��������ł����B �@
�u���{��'41�N4���A���\�����������̂ł����A���ꂩ��2������ɁA���ƃh�C�c���s�N����j�����ă\�A�Ɛ푈���n�߂��̂ł��B �@
�����́A�C�M���X�ɉ����\�A�Ƃ��푈����ʍ��́w�q�g���[�̓�������Ȃ����肠�蓾�Ȃ��x�ƍl���Ă������A���̂܂����������ɂȂ����B���̂��ߕ����̓h�C�c�Ƌ�����u�����Ƃ��咣���܂����A�c���́w���{�ƃh�C�c�Ń\�A���������ɂ��ׂ��x�Ɣ��_���A�������Η����܂����v �@
���݂̃h�C�c�ƃ\�A���푈���n�߂��̂�����A�哌�����h���\�z�͍��ꂩ�畢���������R�B�������\�A�̓C�M���X�A�A�����J�Ƌ������A�t�ɎO��������͖Ԃ��������B �@
�ɂ�������炸�A�������c��������i�o�̕��j��ς����A'41�N7���A�암����ɐi���B�A�����J�͎��O�̌x���ʂ�A�����ɐΖ����܂ޑΓ��A�o�̑S�ʋ֎~�ɓ��ݐ����B �@
�u�����͓암����ɐi���������炢�̂��ƂŁA�A�����J���Ζ����֗A����Ƃ͗\�z���ĂȂ������B�Ζ����֗A����Γ��{������A�W�A�̐Ζ������߂ē���ɐi�o���Ă���͖̂��炩�B�A�����J�̓C�M���X�������邽�߁A�܂��h�C�c��@������ŁA�ʍ��ƂȂ���{�Ƃ̐푈��]��ł��Ȃ��Ǝv������ł����̂ł��v �@
�����͊O�����ł̎��Ԃ̑ŊJ�Ɉ��~�̖]�݂�������A�c���̓A�����J�Ƃ̐푈���咣�����B���ǁA�n���č��������͓��{�R�̒����A����̖������P���A�O����������̗��E�Ȃǂ����߂�A������u�n���E�m�[�g�v������B �@
�u�c���́A��������߂Γ��{�͖��ւ̌��v�������Ă��܂��̂œ���䖝�ł��Ȃ��B�A�����J�Ɛ킦�Β�����ɂȂ菟���ڂ͂قڂȂ����A�h�C�c����ł͖��Ɉ�̏��@�����邩������Ȃ��ƍl�����B �@
�A�����J�̐푈�����������O�̗L���ȃ^�C�~���O�ŊJ�킷�ׂ��Ǝ咣���A�����s�����������J������F�B�������Ė��d�Ȑ푈�ɓ˂��i�̂ł��v
'41�N12��8���A���ɂ��̎����K���B��_���ꒆ��������@���������n���C�̃A�����J�͑�����P�B����̐�ʂɓ��{�������������A���ʂɏ���A�����J������ɍU���ɓ]���A���{�R�́u�����ė����̐J�߂����v�Ƃ�����w�P�Ɋ�Â��A�e�n�ŋʍӂ����B �@
�u�A�����J�Ƃ̐푈�ɕ������痤�R�͌��͂������B�ǂ������͂������Ȃ�A���{�����Ƃ��ǂ��S�����悤�Ƃ������_�\�������R�ɂ͂������B����������ɂ��Ă��A���R�Ƃ����g�D���c�����߂ɂł��邾���L���ȏ����ō~�����悤�Ƃ��l�����B���̂��߂ɐl�����]���ɂ����������s�������̂ł��v �@
�����m�푈�ł̔ߌ��������N�������A��[��̒������������̎��s�B����̖\���𗤌R�����͗}�����Ȃ������̂��B �@
�u���R�̃g�b�v�͉i�c���[��̑���l�`�������̂ŁA�����������\�����Ă��A������R���g���[���ł��܂���ł����B�i�c��͑��킪�K���N����Ƒz�肵�āA���������̊����Ȉ��S�ۏ�̐��̍\�z�ɂ������܂����B���ǁA�R�l�䂦�̍��������犮����ڎw�����Ƃ��āA�ڂ̑O�̎��ԂɑΏ��ł����ɏ͈������Ă������B�m���ɉi�c�̗\�z�ʂ����͋N����܂������A���{�����ۘA����E�ނ��Ă��Ȃ���A�ʂ̓W�J�ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B���G����ȍ��ۏ�̒��ŁA�����Ȉ��S�ۏ�ȂǁA���������\�������̂��B�ނ���푈���N�����Ȃ��悤�ɂ��鑽�푽�l�ȑΉ��������A���߂��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���v
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@

�u���͓��{�ɓ���邪���߁A���̈ӌ���悵���̂ł͂Ȃ��B���̐E���͐^���̔����ł���v�u�{���́A�e�퍐(������A�����)�͂��ׂċN�i�̊e�N�i�����S���ɂ��A���߂ƌ��肳��Ȃ���Ȃ炸�A�܂������̋N�i�����̑S������Ə������ׂ��ł���Ƌ����咣����v�@
�u������퓬���̐������Y�̖����ʔj��Ƃ������̂��A���܂��ɐ푈�ɂ����Ĉ�@�ł���Ȃ�A�����m�푈�ɂ����Ă͂��̌��q���e�g�p�̌��肪�A��ꎟ���E��풆�ɂ�����h�C�c�c���(�����ʎE�l��)�w�߁A����ё���E��풆�ɂ�����i�`�X�w���҂����̎w�߂ɋߎ������B��̂��̂ł���v�@
�u���{�ƃh�C�c�ɋN�������̓�̍��یR���ٔ����A���̍��̖@���w�҂����̂悤�ɏd����Ƃ��Đ^���Ɏ��グ�Ă���̂ɁA�̐S�̓��{�ɂ����āA���ꂪ����ɖ�莋����Ȃ��Ƃ����̂͂ǂ��������Ƃ��B����͔s��̕��Y���ł͂Ȃ����Ǝv���B�č��̍I���Ȃ��̐���ƁA�펞��`�A�S�����ɍЂ�����āA�ߋ��̈�����ł������Ƃ����߈����Ɋׂ�A�o�b�N�{�[������Ė��C�͂ɂȂ��Ă��܂����v
 �@
�@���C���e���W�F���X ����Ȃ��푈
�̂��ɂ��̎���̖����������A�w��������䂭���ē����x�w�O��s��x�Ȃǂ̃m���t�B�N�V������i���F�߂��āA�n�[�o�[�h��w���ۖ�茤�����Ɍ}������B���̌�h�C�c�̃{���x�ǒ��A�Ăу��V���g���x�ǒ����o�Ăm�g�j��ސE�A�m���t�B�N�V�����E�C���e���W�F���X�����ƂƂ��ċr���𗁂э����Ɏ���B�@
��������D�́A�m���L�����A�Ȃ���O���Ȑ��Ă̏�̓v���t�F�b�V���i���A���ɋ��w�̃��V�A�ʂƂ��Ċ���B�Ƃ��낪2002�N�A�w�C�ƋU�v�Z�Ɩ����̗e�^�ŋN�i����A���ݓ��Ȃ��x�ɒ������A���̑ߕߌ����u�����{���v�ƒf���āA�u���Ƃ�㩁v���㈲�A���x�X�g�Z���[�ɖ��o�A���̌�O���Ȃ̃��X�v�[�`���ƌĂ�āA�o�łɍu���ɑΒk�ɑ��Z�ȓ��X�𑗂��Ă���B�@
���ِ̈F�̓�l���A�C���e���W�F���X�̐_�������̂�����A�����p�����ʔ��͊��ň�C�ɓǂ܂��̂͗��ł���B����Ύ��͔����̊i���Ƃ��A���̎��Ă�U���Ɩh��̋Z����g���āA���݂��Ɉ���������ʍU�h���J��Ԃ��l�Ɉ��|�����v�����B�@
��X�f�l�́A�X�p�C�Ƃ��C���e���W�F���X�Ƃ����ƁA���ׂē������̂̂悤�Ɏv������ł��邪�A�������X�v�[�`���ɂ��ƁA��O�̃X�p�C�{���ړI�̒���w�Z�̢�閧��v�Ƃ������ނł́A�@
1�D�ϋɓI�u����v���|�W�e�B�u�E�C���e���W�F���X�@
2�D�u�h���v���J�E���^�[�E�C���e���W�F���X�@
3�D�u��`�v�@
4�D�u�d���v�@
��4�ɕ��ނ����̂��Ƃ����B�������X�v�[�`���́A���{�̃J�E���^�[�E�C���e���W�F���X�͂��Ȃ荂�x�Ȃ̂����A���̑����������C���e���W�F���X�ɉ������d�g�݂�A�n���������g�D�A��������@�ւ��Ȃ��A���������ꂼ��c����̕��Q�A�K�v�Ƃ����w���ɃX���[�X�ɓ͂����A���������{�ɂ͋���@�ւ��Ȃ����߁A�K�ނ�����Ă��Ȃ��Ǝw�E����B�@
���Ƀ|�W�e�B�u�E�C���e���W�F���X�ɂ��Ă��A�f��Ō���悤�ȃX�p�C�����łȂ��A�K�v�Ƃ��鎖���́A�V���ȂǂɌf�ڂ����L�����炾���ł��A���Ȃ葽���̎��n����̂��Ǝw�E����B����Ɠ��Y���̏d�v�ȃ|�W�V�����ɂ���l�����ƁA�����ɐe���ɂȂ�邩�Ƃ������Ƃ��d�v�ŁA�������ނ�̔�������A�����Ɂu���O�̈Ӗ��v�����ݎ��\�͂����邩���d�v�Ȃ̂��Ƃ����B�@
���̂��߂ɂ́A���z�͕ʂƂ��āA���R�ɂȂ�@����K�v���Ƃ����̂����A���Ă݂݂��������{�̃}�X�R�~�₻��ɗx�炳��鍑�����A����Ƃ��邩�ǂ����A�Ⴆ������{���t���M�]������{�łm�b�r�\�z�ɂ��Ă��A�����Ƃ��z�����ׂ����ł��낤�B�@
���V���g���ƃ��V�A(���X�N��)�ƁA�^���Ɉʒu���Ȃ���A���ꂼ�ꂻ�̑��݂𑁂�����F�ߍ����Ă������Ƃ��A���̑Βk�̊e���Ŏf���A���݂����ʂ������f���������Ƃɋ��������B�@
�Ƃ͌������ׂĂ��[���ł͂Ȃ��A�蓈�������̔��f�~�X���w�E�����ʂ������āA����ۂގv�������邪�A�����͂��̒���𐳖ʂ���Ĉ���������Ȃ��B�@
�Ō�ɗ��҂́A���{�łm�b�r�\�z�ɐG��邪�A���҂Ƃ����������@�\�\�z�ȑO�ɁA���Ȃ��Ƃ�200�����炢�̐�p�X�^�b�t�̏[���Ƌ�������B�@�\����s����A�哱���������Čx�@���E�h�q���A����ɊO���ȂȂǂ̍j�������s���A�֘A�e�Ȓ��́A���̒��a��Ƃ�����c����\�}����������Ȃ��ƌx�����Ă���B�@
�m���ɂ��̕��Q���w�E���鐺���������A���ɗD�G�ȃC���e���W�F���X�E�I�t�B�T�[�̑I�肪�}���ł���A�������X�v�[�`���́A�œK�̐l���g�b�v�E�I�t�B�T�[�ƂƂ��Ď蓈�𐄋����Ă���B���Ĉ��{���A���̖{��ǂ�Ŋ������Ă�������̂����B�@
����ɂ��Ă��A���̍����D�����Ď蓇����Ƃ����|�W�e�B�u�E�C���e���W�F���X�E�I�t�B�T�[�Ƃ��ē�������2�l�̐l�ނ��A���{�Ƃ������������Ĉ��{���A�ʂ����Đ������Ďg������邩�A�����ɓ��{�ƃA�����J�̗h�邬�Ȃ��A�g�ƁA�k���l�������܂ށA���V�A���̌����B����Ă���Ǝv���̂����ǂ����낤���B
�s�v�c�Ȗ{�ł���B�\�肩�炠����x�����ł���Ǝv���ēǂ�ł邤���ɁA�u�����A�����v�Ƃ����v�����������̂��A����Ɂu���Łv�Ƃ����C�ɂȂ��Ă���B�����ɂȂ�Ɓu�܂�����Ȃ��̂��v�Ƃ�������[������B���҂�1927�N(���a2�N)�������܂�A���R�m���w�Z61����(�Ō�̓��Z��)�A���啪�o�ϐ��w�Z���B�O��z�R(��)�A�O��Ζ����w�H��(��)�ɋΖ��A1987�N�ސE��A��j�����Ɋ�Â����M�����ɓ���B�@
��т��āu���R���ʁA�C�R�P�ʁv�j�ς�ᔻ�����{�s��̐^����Nj����Ă����B��v�����Ɂu�鍑�C�R�̌�Z�Ƌ\��(1995���_��)�v�A�u�鍑�C�R�u���s�v�̌���(2000���u���[)�v�A�u�����m�ɏ�������@(2003������)�v�A������A�{���͂����ɑ����u�鍑�C�R�����v�̌���łƂ����悤�B�@
���������̊�{�I�����͑���{�鍑���@�ɂ���B������(�R�̍ō��w�����ߌ�)�̓Ɨ��ł���B����͗��@�E�s���E�i�@�ɕ�������(���邢�͒��z����)��4�̌��͂ł���B(��������_���������B���@�ɓ��t������b�̋K�肪�Ȃ��A������b�̈�l�ł����Ȃ��A��b���܂Ƃ߂邾���ŗ}���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�ӌ�������Ȃ��Ɗt���s����Ƃ������Ƃœ��t�����E�ɒǂ����܂ꂽ)�B�@
�������A�����푈�ł͐��E�R�̒��������V(�ɓ������E�R���L���E��R�ށE���]�E���`���`)���s���A�R�������͗��C����Γ��ł��������A�펞��{�c���ł͎Q�d����(��)���S�R�����R�ߕ������w�����邱�Ƃ��ł����B�����푈�����Ƃ������������O�����ʼn�d���_���Ă��钆�ŁA�C�R�͗��R�̉��ɗ����Ƃ��D�܂����C�����Γ����������B�ꎞ�͍����~�݂ɂȂ������C���R�{�����q�̋��͂Ȉӌ��ł��ɐ��������B�@
���ꂪ�푈�̓���w����j�݁A�C�R�̒S������ւ̗��R�̉�������ۂ��������ɂȂ��Ă���B���I�푈�����͐h���ł������̂Ɍ��ۖʂł̉����𗝗R�Ɏ��̉��z�G���A�����J�ɂ��Đ��������}���āA�R�k���ɔ������Ɨ\�Z�̑������l�������B���̂��ߍ����I�p�Y������������荞�̂͋����Ȃ��B���ꂪ�헪�v�z�ʂł́u�͑�����v�u�ʏ��j��y���v�ƂȂ��ĕ\��A�X�Ɂu�͑��ۑS�v�u���y���v�ɂȂ������ƍl������B�@
�哌���푈�ł́A�����l�����Ă����u���₩�ɋɓ��ɂ�����ĉp���̍����ł��Ď������q���m������ƂƂ��ɍX�ɐϋɓI�[�u�ɂ��Ӑ����̋����𑣐i���ƛ��ƒ�g���Ă܂��p�̋�����}��Ă̐�ӂ�r�������ނ�ɕׂށv�Ƃ��葾���m�n��͎��v���ʂł������B������R�{�\�Z�́A�n���C��P�ɂ��J��ɐ�ւ��A�\�ʓI�ȏ����͓������R�{�̊��҂�����ӂ̑r���Ƃ͋t�ɔR���オ�点�Ă��܂����B�@
�܂��A��͓]���_(�މ�̐�͂ƕ�⋎x���͂̃o�����X���t�]���鋗��)������ɉz���Ă��̌�n���𗤌R�ɗv��������(��\�Ⴊ�K�_���J�i��)�A���E�̊C�R�̏펯�ł���ʏ��j����S���l��������̗A���D�͍q�s���R�A��̗A���D�͂قƂ�ǒ��߂���Ƃ������ʂ��ǂ��l��������̂��낤���B�@
�J�펞�̐�͂Ő키�Ƃ����l���������͂̕�[�Ƃ����_�ɍl���������Ă��Ȃ��̂����ł���B���ɁA�p�C���b�g�͐��E��̋Z�\�W�c�ł������̂Ɏ���ɏ��Ղ��A�K�ȕ�[�{�Ȃ��܂ܐ�͈͂�C�ɒቺ���Ă���B��ʊm�F���A�m�F�@��u���������ƈقȂ�e���݂̂̐̕ςݏグ�ƂȂ�ΐ�ʂ͓��R�ߑ�ƂȂ�B�@
������q�ϓI�ɕ��͂��邱�ƂȂ��˓�����������̕d����Ƃ�����I�ȏ����Ŋm�F���A����������������ł��M���Ă��܂����B�������A����ɏ�����������R�̏��s�Q�d������B�������������n�Ō������̂����C�R�̈ӌ��ɏ悶�悤�Ƃ��āA�I�����w���������҂����ł���B�����A�����A�҂Ȃǎ����̐ӔC�������邱�ƂȂ��������т����Ƃ͓��ꋖ���������B�@
�Ƃ����ӂ��ɁA���҂͊C�R���w�e�����̐����͔͂��Q�ł���B��������ŗ��R�͑P�ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��B���ɐ����I�ɓ����Đ��E�̐��_�ɗ^�����e���͖����ł��Ȃ��B
�u���@���j�̐^���v�u�V�@���j�̐^���v�ɑ����O���ڂ̐��j�̑����{�ł���B�O�쎁�̎�̎v����������������K�v�͂��邪�A�܂��͌X�����ׂ��ł��낤�B�@
���݂̂킪���̏�Ԃ͂����������ł��낤���Ƃ����Ƃ��납��n�܂�B���Ɗς̑r���A�̓y�ӎ��̊A���s�I���j�ρA�I�ȊO���A����̑ޔp�A�ϗ��̕���A�Ȃǂ̌���͉��ɋN������̂��Ƃ������n����_��i�߂Ă���B������ꌾ�Ō����A���j��Y������������ӔC�Љ�Ƃ����悤�B�@
�������̓��{�����@�Ƌ����{�@�ɋN������Ƃ����B�g�c�ɔ����銯���o�g�����Ɠ��Ɏɂ�錻�݂̎����I���ςݏd�Ȃ��Ď���ɘc�݂����Ƃ���B���s�I�ɎӍ߂͌J��Ԃ����A���{�̗����ɕ�����悤�ɐ������Ă��Ȃ��B�����J��Ԃ����ƂŒ��J�Ȑ����Ƃ����Ă��M�p�͂���Ȃ��B�����ɂ͖��Ăȍ��ƊρA���j�ς̂Ȃ������ꓖ����̂悢���Ƃ�i�߂Ă��邱�Ƃ��Ƃ����B�ŋ߂̍c���T�͉������A�����Q�q�ጛ�����ȂǗ��j�̏d�݂��l���Ȃ������ȍl�����ł���Ƃ��Ă���B�@
�ЂƂ���A�����͈ꗬ�Ƃ���ꂽ���Ƃ�����B�������������肵�Ă��邩�琭���Ƃ͎O���ł����܂�Ȃ��Ƃ������l���ł���B��b�A�C���Ɂu����������܂����ꂩ������܂��v�����C�Œʂ��Ă����B�������납�炩�A�����ɍ��Ɗς��ɂȂ�A������ǂ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B�@
�@�Ă̑啔������t��o�@�Ă���߂Ă��邪�A�قƂ�ǂ������ɂ���ė��Ă���A�^��}�̋c���ɍ����č����ʉ߂����Ă���̂����Ԃł��낤�B���@���̙ӒD�ł���B�X�ɕ|���̂͒ʒB�ł���B����͋c��Ɏ��邱�Ƃ��t�c�ɂ����邱�Ƃ��Ȃ������������o����̂ł���B�o�u������̂��������ƂȂ����̂��A�呠��(����)�̋�s�ǒ��̋��Z�@�ււ̑��ʋK���̒ʒB�ł���B���̂��Ƃɂ���Đ������o�ς̍����ɑ���ӔC�͒N������Ă��Ȃ��B����ǂ��납���̋ǒ��͍X�ɉh�i���Ă���Ǝw�E���Ă���B�@
���̊����̎嗬�͓���o�g�҂ł���B����o�����ׂĈ����킯�ł͂Ȃ����A�R�~���j�Y���ɔƂ��ꂽ���̂������̂������ł���B���ɖ@�Ȍn�̊w�҂͓��{��̉��̐��i�҂ł������Ƃ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B����ɂ͂���𐄐i���Ă������Ό����f�B�A�ɂ��Ă��G��Ă���B�����ǎ��I�Ə�������A�i���I�ƌ`�e�����肵�Đ��_���~�X���[�h�����ӔC�͏d���B�@
�������{�Đ��́u�N���Đ���v�Ƃ��Ď��̎O���グ�Ă���.�@
��ڂ́A���60�N�A�}�b�J�[�T�[�̐�㐭���ɂ��U��̗��j�ρA���̎�������̒E�p�@
��ڂ́A����������Łu�哌���푈�́A�������q�̐푈�������v�Ɛ錾���邱�Ɓ@
�O�ڂ́A�����ɐΌ��T���Y�s�m�����N�p���邱�ƁB�����I�ȑΉ����l����Έ��{�W�O���l���Ă���B�@
�����̘_�ɑ��Ă͎^�ۏ��X�ł��낤���A���_�ɕԂ��čl���Ă݂鉿�l�͂��낤�B
���60�N�A���E�e�n�ő��������푈�╴�����悻�ɁA�ЂƂ蕽�a��搉̂��Ă������{�ł́A�������u���v�Ƃ������t���������A���ɂ���邱�Ƃ��Ȃ����͂����镗�����蒅���Ă��܂��Ă����B�����������{�ł́A�u�����v���u�s���v�Ɏ���đ����A���v�E���y�E�����E���ɍ��h�E�����ȂǓ��R�̍��ƈӎ���v�z�����c�Ɏ����A�܂��Ƀ��X�g�l�[�V����(����)�E�A���`�l�[�V����(������)�Ƃ��������ԂɊׂ��Ă���B�@
�����ŋߋߕӂ��}�ɂ��킽�������Ȃ�A�����������́u�����v���A�����̍H����ɂ���ė��s�s�ɗU������Ȃ�����A30�N�ɂ��j���Ď��グ��ꂸ�ɂ����B���̂��Ƃ������Ɉُ�Ȃ��ƂȂ̂��A�N�����C�t���ׂ��ł��낤�B�@
�Δj���͌R���I�^�N�ƌĂ�ĝ��������ȂǁA�l�K�e�B���ɕ]������Ă������A������ǂތ���A�͂��߂Ė{���̖h�q�������������Ƃ����v��������B�@
�]���f�c�o��1���Ƃ����g�ɔ����Ȃ�����A�o�ϑ卑���������Ƃ���A���E2�ʂ̗\�Z�����R���卑�Ƃ����ӂ��Ɍ���Ă����B�������Ȃ���A���̗\�Z�̑傫�ȕ�����l�����߁A����������A�o���ւ����Ă��邽�ߔ��ɍ����Ȃ��̂ɂȂ邱�Ƃ���A�����I�ɂ́A�\�ʓI�Ŕh��Ȉ�ۂ�^���镪�삪��������锼�ʁA�����L���ɖ{���ɖ𗧂̂��ǂ������^�⎋����Ă����B�����������ł����������悤�ɁA���ς�炸�̏c����^�c�̂��߁A���C��̘A�g�V�X�e���ł����A�����ۂ�E�����Ă����悤���B�܂���̖{�����܂�Œm��Ȃ����������́A�S�Q�����Ĉꗘ�������ƁA���m�Ɏw�E���Ă���B�@
�����͂܂������Ƃɂ��Ă������ɂ��Ă��A���h�Ƃ����ӎ����H���ŁA���������{����芪�����̌��ςɑ��āA�_��ɑΉ�����Ƃ������z���A�����Ɍ����Ă������������Ă����B������̉����ɂ��k�����d�����d������A�Ζk���N�E�����ցA�e���헪�ւƁA�傫�Ȑ헪�]�����v�������悤�ɂȂ����B�@
����Əo�����L�����@�ɂ��Ă��A���ۉ^�c��͂����ĉ~���Ɋ��p�o����̂����_�͎R�ς��Ă��邱�Ƃ��킩��B���ĐΔj�����C�̂��ƁA�܊p�i�݂��������_�����̂��߂̎{�A���̖؈���ɂȂ�Ȃ����Ƃ��F�肽���B�@
��́u���h�q�v�Ƃ����헪���́A��U�ɋ}���ɓ��{�����ō����̋]�����o�債�Đ키�Ƃ����A�����ĂȂ��������d�Ń��X�N�̑傫���d�g�݂��Ƃ������Ƃ��A���{�l�S�̂��[�����o���Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����B
���҂͓ǔ��V���ЁE�����V���Ђ��o�Č̌ܓ������ɃX�J�E�g����A���̉����Ƃ��Đ��E�E���E�E�}�X�R�~�ɘj���Ċ��A�ܓ����̎���͒��]�����̂���ԓI���݂Ƃ��Ēm����B�@
�����͢�����ٔ�����������ᔻ�Ɏ���āA�Ȃ��̋^��Ɋ����Ȃ��������{�l�̎p�����A�����{�̗J�ꂤ�ׂ����������̂��Ƃ����Ƃ�������N�����āA���̐^���̎p�������鑷�����ɓ`�������Ƃ��āA�����������{�ɂ��Ă��܂������{�l�Ƃ��āA���E�E���E�E�}�X�R�~�Ȃǂ̍߂��ɏグ��B�����̃y�[�W���߂���A���̓`���������j�̐^���Ƃ́A���̑������łȂ��A���{�������邷�ׂĂ̐l�ɒm���Ăق������Ƃ��ƋC�t�����낤�B�@
�����͂܂������҂��s�҂��ق����ƌ������s�s����܂�Ȃ��u�����ٔ��v�̖������ƁA���{�̖��߂����u�����ٔ��v�ł�����l�̔����A�C���h�̃p�[�����m�̂��Ƃ��珑���͂��߂�B���̌���{��K�ꂽ�p�[�����m�́A�܂��L���Ō����ԗ��́u�₷�炩�ɖ����ĉ������B����܂��͂���Ԃ��܂��ʂ���v�Ƃ������t�́��܂����̌��@�ƁA���Q�ҕs�݂Ŕ�Q�҂�����܂�Ƃ������ٗl�����w�E���邪�A���ǖ�������Ă������Ƃ�₤�B�@
�����āu�����ٔ��v�ŁA���m���u�K���������Ă����v�Ǝw�E���������┻���B�ł����A��ɂ��̍ٔ��̈�@��������Ă���̂ɁA���̓��{�l�������u�����ٔ��v�ɂ܂������^����������ɁA�_���Ɏ���Ă����̂��Ƃ������Ƃ𖾔��ɂ��čs���B�@
�����ăA�����J���A�����ɍI���ɓ��{��푈�Ɋ��������A���̐푈�������ɃA�W�A�����Ɋ��ӂ��ꂽ���Ƃ��������A�悫�`���Ɛ��_��j����㋳��A�u�ێ�v�Ɓu�v�V�v���t�ɕ����ă}�X�R�~�A�c������������������͂ȂǂȂǁA���E�E���E�E��������Ƀ}�X�R�~�̏X�������Ė��\�Ńn�����`�ȗ��ʂ�O��I�ɖ\���čs���B�ɉ��Ȕ��ʈӊO�Ǝv����̂́A�g�c���(����)�����ƂƐ��Ď̂ĂĂ��邱�Ƃł���B�ނ�����{�̐��E��I�ފ����̒������n�܂����Ƃ����̂ł���B�@
���M���ׂ��́A���ɂ̂��߂Ɋ�������e�W�������̐l���A�͂�����Ɩ��O�������ďЉ�Ă��邱�Ƃł���B�����m�邾���ł����̖{��ǂމ��l������Ƃ������̂ł���B
���܂̒��E���Z�̋��ȏ��A�Ƃ�킯���j�̋��ȏ��̖��_�A���Ȃ킿���ɑ��鈤���S�Ƃ��ւ�����킹�����̎��s�I�L�q�Ɋ�@��������Ĕ��������u�V�������j���ȏ�������v���A�������҂Ƃ��Ĕ�������770�y�[�W���锗�͂ɖ������p�C���b�g�łł���B�����ȗ��x�X�g�Z���[�̃g�b�v�𑖂葱���Ă��邱�Ƃ́A�����ɑ����̐l�����{�̋�����̌�����J���A�V�������������߂Ă��邩�Ƃ����o�����[�^�[�ƂȂ邾�낤�B�@
���������X���̓o�u�����������10�N�ɂ���Ԍo�ϓI�����̒��ŁA��������Ɏ��͘T�����邱�ƂłȂ��A���̎��a��`�̌�T�̂Ȃ�ł������������ÂɌ��l�߂悤�Ƃ��铮���̈�[�Ƃ݂�ׂ��ł����āA�댯�Ȗ�����`�̑䓪�Ǝw�E����̂́A�����Đ��������̂Ƃ͈����Ȃ��B�@
�܂��{���͓ꕶ�ɔ��������{�����m�Ɉ�̕������Ƃ��đ����悤�Ƃ���Ƃ��납��X�^�[�g���A�퐶�ɔ������ƌ����Ă����R���������ꕶ�l�ɂ�������̂��ƍŐV�̔��@�̐��ʂ�(�R���c�m�`)���̓f�[�^�Ȃǂ���w�E����B�@
�����͏m������Ɏw�E���Ă���(���{�̗��j�����)���{�j�E���m�j�E���m�j�Ƃ����c����\����r�����āA���݂ɂ����錴���E���ʁE��r�Ȃǂ�܂荞�݂Ȃ���A�Ⴆ�u���̎���ɍs���Ă��������ېV�v�u���E�j�̓����S���鍑����n�܂����v�u���m�̊v�����v���I�����������ېV�v�u�A�����J����ɓ��{�����z�G���ɂ����v�ȂǁA�ǎ҂̏]���̐Ȓm���������Ɉ����͂������悤�Ȏh���I�Ŋ������͂ɂƂa�V�ȋL�q�ɖ����Ă���B�@
���{�l�͂ǂ����_���I�Ȕ��z�Ƃ���r�����_�I�ȖʂɌ����Ă���B�Ⴆ�Β����̓s��^�������鋞���畽�����܂ŁA��؏�ǂ��������Ȃ��������ƁA�����ɍc��(�䏊)�ɂ����ǂ͂��납��ؕ���炵�������������Ȃ������Ƃ������{���A��ɕ��a�I�v�l�����������Ă������ƁA���j��ʂ��ĊC�O�h���̏��Ȃ������Ȃǂɂ����Ɩڂ𒍂��ׂ����Ƃ������Ƃ�{���͋����Ă����B
�c���j�b�|���ɁA�ւ�ƈ�����@
���҂͓��}�O���[�v�����̌ܓ����̔鏑�Ƃ��č����E�Ŋ����l�ŁA�O���Ɂh�����鑷�����Ɍ���ĕ��������������{�̐^���h������B�@
�{���́A����̌R�E�������͂ɂ���Ęc�߂�ꕢ���B������A���̌ア�܂��ɓ����g�̌������㋳��ɂ�����Ȃ߂�ꑱ���Ă�����O���̓��{�̗��j�̐^�����A�Ώۂ��������X���{�l�̑S�̂ɂ܂Ŋg���ď����ꂽ���̂ł���B�����ɂ���e�͂��玄�����́A�����ɐ��������{�̎p��m��Ȃ��������ƂɊS�Q���邱�ƂɂȂ�B�@
�u���́@�����j�̑����v�ł́A������Ȃ����{�����̂悤�ȎӍߍ��ƁE���s���ƂɂȂ艺���������A���̌����Ɨ��R�ɂ��Ă������ɂ����B�߂������Ƃ����A���̂܂ܖ��C�͂Ŗ��ڕW���Ɠ��{�̂܂܂��Ɩ����͂Ȃ��Ɗ��j����B�@
�u���́@���{���������ɂ������̎w���҂����v�ł́A�����̓����̂ĂăA�����J�̔�̂��ƂŁA���l���ƂƂ��ē���I�g�c�E�r�c�E�l�E�����h��Ƃ��������o�g�̎������B�܂����{����������ւƗU���������ʐM�E�����V���Ƃ����}�X�R�~�A���Y�}�E�Љ�}�Ƃ����������}����ɓ����g�E���]�Ȃǂ̈Ö��\�I����B���̈���ŁA�}�l�h�̕����Ɋ������]���N�O�Ɣނ�����������ǎ��h���E�l���Љ��B�����āA��㐭�����뜜���āu�������o�m�v��n�����������K�V���̌��т�������B���܂��̒����́A�m���ɓ��{�̖����ɖ��邳�����������̂��B�@
�����������ŁA�����Ƃ��V���b�N�����̂́A�u�攪�́@���j����̋��P�Ɣ��ȂƊ�]�v�̒��ŁA1952�N4���ɍu�b��������Ɨ��������ہA����̑S���v�Ł��`�����܂ߐ푈�ƍߐl�Ƃ��ꂽ�l�������Ƃƌ��Ȃ��Ȃ��Ƃ������c��(���Y�}�E�Љ�}�������)�S���v�ō̑����ꂽ���Ƃ��������ł���B�������͍���������傫���グ�Ă��̎�����(��)���M���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɖ����_�Ђɗ���ŁA���X�ɓ��������s�������E�؍��ɂ́A���m�ɂ��̎�����m�炵�߂�K�v������B���⍑��c���ł��A�ێ�E�v�V���킸�푈��m��Ȃ����オ�唼���߂�B����������܂�����㋳��̂����ŁA�A�����J�́u(���{��)��x�Ɨ����オ���Ȃ����ɑ��肩����v��̐���ƁA����ɕ֏悵�����Y��`�Ƃ����s�т̐��_�����̉������C���v�b�g����Ă��Ă��܂��Ă���̂��B���̂������Ő푈�̍߂�����������쒆�L���ł������A�����Đ�O�h�łȂ������܂��Ȃɂ��킩��ʎq���ɉ߂��Ȃ������̂ł���B�@
���{�l���ׂĂ��A���Y��`�Ƃ��������̃C�f�I���M�[�ƃA�����J�^���������`�̎�������̒E�o�̂��߂ɁA���Ж{���̏n�ǂ���邱�Ƃ�������B
21���I�����̔e����`����S�l�ނ���邽�߂Ɂ@
�M�ҁE��҂Ƃ���p�o�g�B����N�Ƃ������j�̒��ŁA���߂Ė���I�ȑI���ɂ���Ď{���҂�I�ԂƂ����A�H�L�̌o����������p����̉s���Ȏ������A���劎�����Ȋ���������̌�����O�ɑ����āA�������ȑ咆�ؓI�e���w�����u�S�l�ނ̍Ж�v�Ƙ_�j����B�@
�M�҂́A�������̗p�����u���h�̐����I�K�v������E�h�̎��{��`�I�s��o�ς���荞�ށv�Ƃ����A�Ɛ���Z����̉����閵���̒��Ő��܂ꂽ�ߑ㉻���A4�̊�@�y�l�����奍����������ٗp���E�_�Ǝ����̌͊��E���R���Ԃ̔j��Ɗ������̖����E�H����@������z�Ǝw�E����B�@
���Ȃ킿�}���ȍH�Ɖ��͔_���Ƃ̋ɒ[�Ȏ����i���݁A������s�s���������Ƃ�₽���A�������R����̑����ɔ���Ⴕ�āA��x���Ɏ~�܂鋳���́A���ς�炸�Ⴂ����������]�V�Ȃ����A�Ȋw�Z�p�̐U���͂��ڂ��Ȃ��B�܂��u�}�����ׂĂ�����v�Ƃ����d�g�݂́A��Ƃ̊����E�l���̊m�ہA���Ђ̎��R�ȂNjߑ�I�Ȋ�����j�Q���A���E������s�g�Ȃǂ̕��s��������ƒ��҂͌����B�u�Љ��`�E���Y�}�v�Ƃ����ƁA�ߋ��̐�ΌN�吧�Ƃ͂܂������Ⴄ�u�l���ɑ��ӂɂ�閯��I�Ȑ����V�X�e���v�Ǝv���Ă��邪�A���̓��e�͉ߋ��̐ꐧ�����Ƃ܂������ς�炸�A�����V�������t�ŏC�������ɂ����Ȃ��B�Ⴆ���Ă̕ۍb���x(�בg�̑��݊Ď����x)�́A��ʏ���������ƋC�t���Ȃ������Ō��݂̑���(����)�ψ���ɒu���ς���������ł���Ƃ���B�܂����҂́u�ߑ㉻�v�Ƃ́A�����Ɍ�����������`�E�q���[�}�j�Y������ɖ@����`�ɂق��Ȃ�Ȃ����A�������ǂ́u�Љ��`�v�Ƃ����_���Șg����������Ƃ����u���ߑ㉻�v�����ȋʏ��Ƃ��āA����`�E�ꐧ��`�E�l����`�ɂ���āA���������������g�吭����Ƃ��Ď��Ӎ��ɋ��|�ƌx���S��^�������Ă���̂��ƌ����B�����Č��݂̐��E�̒����́A���肳�ꂽ�n��ł̏����荇���͂���A��ǓI�ɂ̓��[���b�p�ɂ�����d�b�����A���A�̊�������ɐ��E�K�͂Ő��܂�Ă��鍑�ۓI�{�g�D(�m�f�n)�̊���ȂǁA����I�E���ۓI�E�����I�ȓ������������Ă���A����������ɏ��̃O���[�o�����Ɗ�Ƃ̑����Љ��̒�������������Ă���B�M�҂́A�����������Łu�����͍��A�o�ς͉E�v�Ƃ����������������܂ł����ƌ��O��\������B���̌��ʌ��݂̒����Ŕq����`�����s���A2000�N�ɂȂ�ƁA�ԈႢ�Ȃ�2���̔_�����y�n�𗣂�Ėz���̂��Ƃ��s�s�ɗ��ꍞ�ށu�ӗ��v���N����ƌx������B�@
���_�Ƃ��Ē��҂́A����������@��������邽�߂�(�����w���҂��������F���Ɠx�ʂ̍L����������)���̒�������̂��āu7�̏������������a�����Y�v�ɂȂ邱�Ƃ����B���̒��ɂ͎����������u�E�C�O���E�`�x�b�g�E�����S���n�Ȃǂ��܂܂��B�����������������ݕ⏕���s�����Ƃ��u���E���a�Ɏ���v���炽�Ȑ����c��̓����Ɛ����B
�����푈�Ŕs�ꂽ�����́A���̗��N�ɁA�����͂�h�����A���X�N���Ń��o�m�t�S����\�Ƃ̊ԂŘI������������Ă����B1896�N5��22���Ƀ��X�N���Œ������ꂽ���́A���J�p�̃_�~�[�̏��ƌ��d�ɔ铽���ꂽ�閧���Ƃ�2��ނ��������A�Ƃ����B�閧���̍����́A�I���R�������ł���B�����G���Ƒz�肳��Ă����͓̂��{�ł���B���̔閧���̑��݂́A�����̏�w�̋ɂ߂Č���ꂽ�R�@���̐��������ɔ铽����Ă����B1900�N�̋`�a�c�̑�����������邽�߁A8�J���̋����o�����s���A������A���V�A�R�͒����̓��k������P�������A���̂܂ܒ������������B���ꂪ�A���I�푈�̌����ł��邱�Ƃ́A�N�����m�肤��\�ʓI�Ȏj���ł���B �@
���͔铽���ꂽ�閧���̑��݂𒆍��̒N���A���{���̒N�ɏ������[�N���A���{���ɓ��I�̊J��������������̂��ł���B�����������瑄�Ƃ����l���A���Ȃ킿�����͂̌Z�̖����ȂƂ���l���Ƀ��[�N���Ă����B����́A����瑄�̓��L�̈�߂ɂ���B������m���h�̒m���l�œ��{�l�ɍL���m���Ă������N�N��ʂ��A�߉q�Ė��������铌��������̏�C�ݏZ�̃����o�[�ɉk�炳�ꂽ�A�ƍl������B1902�N��蟊�N�N���g����C�Ŕ����V�A�^���������^���Ƃ��đg�D����B�������āA���I�푈�ɂ����Đ����͓��{���ɍD�ӓI�Ȓ��������ێ����邱�ƂŁA���I�閧���ɑ�������̈���\������B �@
�Ƃ���ŁA�����ł��A���̏��̒��������{�������҂̂����ꕔ�Ŋm�F���ꂽ�̂́A���ؖ����̍����}���{�̂��ƁA�O���̗��j�������J�n���ꂽ�����ł���1930�N��ł���B����ǂ��A�������ʂɌ��J���ꂽ�̂͂���ɒx���B1965�N�ɑ�k�ŏo�ł��ꂽ�w�������▧��S���x���ŏ��ł���B �@
���̔閧���̎j���W��ǂނƁA���V�A�͎O���������łȂ��Γ��̘I���R�������������ē����푈�ɂ�������{�̋ɓ����v�𐧖悤�Ƃ������Ƃ������ł���B�܂��A�����͂͐e�I�H�����Ƃ�A������Ƃ��̎t�ł��鉥���a���A������n�m���Ă������Ƃ�������B �@
���{�̊w�E�̗����ł́A1900�N�ɘI�������ꂽ�Ɖ��߂���Ă���B�����́A�����Ă����ł͂Ȃ��B1896�N�̒i�K�ŁA�I���̌R�����������łɐ������Ă����B��������ƁA���I�푈�Ƃ́A�����ȗ��̍ő�̊O���ł��郍�V�A�̋ɓ��R���N���ւ̑R��Ƃ��Ă���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B�鐭���V�A�ƌ�̃X�^�[�����̋ɓ��x�z�ւ̑R�W���A�����ɁA���{�ɂ��嗤�̌R���x�z�Ƃ��ċ����B��҂̕��̖ʂ������Ƃ肠���A���{�鍑��`�ᔻ�Ƃ��ė��j��������ƁA��ʓI�Ȏ��s�j�ςƔ���邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B �@
�鐭���V�A�̋ɓ��i�o�ƃX�^�[�����̋ɓ��x�z�ɑ��A����ɑΛ�������{���̑R��i���t�قł���Ƃ��Ă��A���{�ߑ���т��i�V���i���Y���̐������܂ł����̂ċ���A���{�鍑��`�ᔻ�݂̂ɏI�n������j�����͂ǂ����Ǝv����B�@
 �@
�@�����A���ۗ�����u5�卑���v�̋N���@
�@�A�����J���猩�������ƃt�����X�@
���E�̕��a�ƈ��S�ɑ��鍑�ۘA���̖����ɑ�����҂����܂��Ă��邪�A�����ł́A�p�ݐ푈�Ȍ�̑����ЌR�����Ƃ��ɂ��̕ώ�ł���C���N�푈�ł̗L�u�������̓����ɂƂ��Ȃ��āA���A�ɑ��錶�Ŋ��̂悤�Ȃ��̂��L�����Ă���B���A�����҂ɉ������Ă��Ȃ��w�i�ɂ́A���ێЉ�̍\���ϗe��A�����J�i�A�����J���O���j�̑ΊO�s���̕ω��ȂǑ��l�ȗv�������邪�A��̏d�v�Ȗ��Ƃ��āA���A����������u5�卑���v�Ƃ����卑���S�V�X�e�����̗p���Ă������Ƃ��w�E�ł��悤�B�u���E���a���ێ�����卑�̐ӔC�v�_�́A���A���S�ۏᗝ����ɂ�����u��C���������x�v�Ƃ����u�卑���S�̍��ۃV�X�e���v�ݏo�������A���ꂪ21���I�̍��ە��a�̑n�o�Ɋ��҂����@�\���ʂ����Ă��Ȃ��̂ł���B�ł́A�卑���S��`�̕����͉��ł������̂ł��낤���B �@
���ۘA���̐ݗ��ɍۂ��ẮA���͑�51 ���̑}�����߂��鑈���̂ق��ɁA����ł̕\�����i�\�A�v���X15 ���a���̋c�Ȃ̗v�����j�ƈ��ۗ��ł̋��ی��i���ی��̉^�p���@�j�Ɋւ���ă\�̊Ԃ̑Η����d��Ȗ��ƂȂ������A���ݑ���Ȋ��҂���ꂻ�ꂾ���ɑ����̋^�₪�˂������Ă��鍑�A�̕��a�ێ��@�\�Ƃ̊ւ��ł́A���ۗ��̍\���܂�u���ی�������C���������x�v���u5�卑���v�Ƃ��Ċm�����ꂽ���Ƃ̈Ӗ���ݗ��̗��j�ߒ��̒��Ɍ����邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B��2�����͑卑�̋��͂̂��ƂŐ��s���ꂽ�̂ł���A���A���͂́A�卑�ԋ��͂����������Đ��E���a��ۏႷ��Ƃ�������̂��Ƃɍ��ꂽ�B���������āA���ۗ��̑S���v���i���ی����j�����E���a��ۏႷ��ƍl����ꂽ�iHovet�A ���j�B�̂��̏�C�������ɋ[����ꂽ�̂́A�܂��A�吼�m���͂Ŏ哱�����������A�����J�ƃC�M���X�A�����ŁA�\�A�A�����A�����čŌ��5�Ԗڂ̍\�����ƂȂ��Č��݂Ɏ���u5�卑���v���`�������̂��t�����X�������B�ĉp�����S�ƂȂ��č\�z�������ۘA���̑g�D�I�����́A��1�ɍ��ۘA���őa�O����Ă����\�A��卑�Ƃ��ď����������ƁA��2�ɒ����ƃt�����X����C�������Ƃ����卑�ɂ������ƁA��2�_�ɏW���B���������āA���E�̕��a�ƈ��S�̈ێ��ɑ��錻�݂̍��A�̋@�\�������邽�߂ɂ́A�����ƃt�����X���Ȃ����̍��ۋ@�\�ő卑�Ƃ��Ĉ����邱�ƂƂȂ����̂��A���̌o�܂���j�ߒ��̒��ɖ��炩�ɂ��邱�Ƃ��܂����߂��悤�B�Ƃ��ɁA1944�N�Ẵ_���o�[�g�����I�[�N�X��c�܂Ńt�����X�̏�C�������Ƃ��Ă̒n�ʂ��F�߂��Ȃ������̂͂Ȃ����A�ɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@
���Ă̓A�����J�哝��FDR�i�t�����N�����ED�E���[�Y���F���g�j�̌l�I�u���i�h�S�[�������j������߂���邱�Ƃ������������A�ߔN�̌����ł́A��1�����Ńp�N�X�E�u���^�j�J���I������̎���Ɍo�ϗ͂��}�㏸�������A�����J�����E�I�ȉe���́i�e���j�̊g���ڎw���V���ȑΊO�H����͍����n�߂������Ƃ̊֘A�Œ����E�t�����X����_����X�������܂��Ă���B �@
�u���[�����\�[���́A�u����܂ł̗��j�Ƃ́AFDR�ƃh�S�[���̃p�[�\�i���e�B�̈Ⴂ���������������v�Ǝw�E���A�h�S�[���͌v�Z���ꂽ���d�ȑԓx���悭�Ƃ������A�����ɂ͐l�Ԑ��ɂ��ӂꂽ�p�[�\�i���e�B���������̂��Ƌ������āA���̂悤�Ɏ咣����BFDR�́A���͓I�ȊO�ʂ����Ă������A�����ɂ͕����Љ�̕W�����D�ދM���I�Œn��I�Ȗ{���������B����Ă����B �@
�A�����J���{���ł́A�����̃t�����X���ʂ����ׂ������ɂ��āA�t�����X��卑�Ƃ��ď������ׂ����ƍl���������Ȃɑ��āAFDR�̓t�����X�͐��x�I�ĕҐ������Ȃ�������̐����I����������ł��Ȃ��Ƃ݂ăt�����X�̑卑���ɋ^��������Ă����B�h�S�[���l�������]�����Ȃ��_�ł́A���҂͈�v���Ă����B�܂�AFDR�̑t�����X����𗝉�����J�M�́A�p�[�\�i���e�B�ł͂Ȃ��Đ���ł������iBlumenthal�A 303-304�j�B �@
�u���[�����\�[���̗��_�͂Ȃ��p�[�\�i���e�B�_�ɂƂǂ܂����ƌ��킴������Ȃ����A�t�����L���́A�A�����J�̐��E�헪�̕ω��ɒ��ڂ��āA�t�����X���̍ő�̃|�C���g���uFDR�̎��R�f�Ղւ̎u���v�ɂ������Ǝw�E���Ď��̂悤�ɏq�ׂ�BFDR�̓E�B���\���Ɠ��l�ɐ�㐢�E�ł̎��R�f�Ղ̂��߂̏\���R�ɉ���낤�Ƃ��A���Ə�̃��C�o���ł���C�M���X�̃R�����E�F���X�̐��̎���ɒ��菄�炳�ꂽ�ŏ�ǂ̏�����ڎw�����̂ł���A�ނ̐��E�I�Ȕ����i�ĉp�������j�\�z�ɂ����Ă��t�����X�̓x���M�[�A�I�����_�A�M���V���ȂǂƓ����n�ʂɈ������낳��Ă����̂��iFromkin�A 454-462�j�B �@
�����Ɋւ��āAZi�i�Y�[�j�́AFDR�̎咣�Œ������A�`���[�`���̗v���Ńt�����X���A�卑�̒��ԓ���������Ƃ����ʐ��I�ȗ�����ᔻ����B�����̑卑�Ƃ��Ă̗���́A�u3�卑�ɂ���ĔF�߂�ꂽ�v�̂ł͂Ȃ��A�t�����X���������������Ƃ̋����̐킢�ւ̍v���ɂ���Ď��炻�̒n�ʂ��l�������̂��A�Ƌ�������iZi�A 47-48�j�B �@
�h�S�[�����{�ɑ���A�����J�̑ԓx�͕Ό��Ɩ��m���琶�������̂��Ǝw�E�����E�b�h���[�h�̎咣���A�t�����X�ƒ����������I�ɑ卑�Ƃ��Ă̓����������Ă������Ƃ���������_�ł́AZi �Ƌ��ʂ���iWoodward�A 492�j�B �@
�������卑�Ƃ��Ă̎����I�ȓ��e�������Ă��Ȃ������ƌ���Q���}���́AFDR�̓`���[�`���Ɋm�M���������ĉp�ē������m���Ȃ��̂Ƃ��A�\�A�ɖ������̌R��������^���A��������ł��邾�������J�����Ƃ�������ǂ��A�Ɠ���s�k�����邽�߂ɒ������m�̑卑�ɂ��悤�Ƃ����_�ł͔��I�������A�ƌ������]���������Ă���iGellman�A 282�j�B�@
�p�[���n�[�o�[�����́A��2�����̒��ɂ��鍑�X�̊Ԃ̗͂̃o�����X��傫���ς����B�A�����J�́A�Γ����ɂ���ČǗ���`�̓`���̑������瓦��邱�Ƃ��ł��A���E�̐V���������`�������ă��[�_�[�V�b�v���Ƃ邽�߂Ɍ��R�ƍs���ł��邱�ƂƂȂ���1�j�B1937 �N�u�������̐��_���P�Ȃ�FDR�l�̈ӎv���āu�A�����J�̍\�z�v�ƂȂ����B���̑�����1942�N1���̘A�����錾�ł���A���̑傫�Ȉ����1943 �N10 ���́u���X�N���錾�v�ɂ�����V���ȍ��ۋ@�\�ݗ��̍��ӂł���B �@
�A�����J���Γ���������12 ��7���A�`���[�`����FDR�Ƒ��k���āA���₩�Ƀ`���[�`�����g���܂ރC�M���X��\�c�����V���g���֕����Đ푈���s�Ɋւ��ċ��c���邱�Ƃ����߂��i�Í����ŃA�[�J�f�B�A��c�ƌĂꂽ�j2�j�B12 ��11 ���A�h�C�c�ƃC�^���A���O�������ɏ]���ăA�����J�ɐ��z������ƁA�A�����J���哱�����Ƃ��Ď�v�Ƀh�C�c�Ɛ키���߂́u�A�����v�̌������}��ꂽ�B12 ��22 ���Ƀ��V���g���ɒ������`���[�`����FDR�̊ԂŌ�������A�\�A�̒��đ�g���g�r�m�t�̈ӌ����Ȃ���ŏI�I��26 �J���̖���1942 �N1��1���ɔ��\���ꂽ�u�A�����錾�v�́A�u�e���{�̓G���ɑ��銮�S�ȏ������A�����A���R�A�Ɨ��y�я@���I���R��i�삷�邽�߂̕��тɎ����̗̓y�y�ё����̗̓y�ɂ����Đl�ނ̌����y�ѐ��`��ێ����邽�߂Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł��邱�ƕ��тɊe���{���A���E�𐪕����悤�Ɠw�߂Ă������b�I�ȌR���ɑ��鋤���̓����Ɍ��ɏ]�����Ă�����̂ł��邱�Ɓv���m�F������ŁA�������Ɛ키���ƁA���������ƒP�Ƃ̋x��E�u�a���s��Ȃ����Ƃ��B �@
��v��FDR�ƃ`���[�`�������̐錾���쐬����ߒ��ŁA�t�����X�ƒ����Ɋւ���2�̖�肪�������B��1�́A�������̋L�ڂ̏����A��2�́A�������̎��i�ł���B �@
12 ��25 ���ɏo���オ�����錾���Ă̏������́A�ŏ��ɃA�����J�ƃC�M���X�A���ɃC�M���X�A�M�̃J�i�_�A�I�[�X�g�����A�A�j���[�W�[�����h�A��A�t���J�����сA���̂��Ƃ̓A���t�@�x�b�g���ɂȂ��Ă��č��v16 �J�����������A12 ��27 ���Ƀn���[�E�z�v�L���Y�⍲����FDR�Ƀ������o���āA�u��������у\�A�̂悤�ȍ��X���A�A���t�@�x�b�g���̂Ȃ���������グ�āA�킪������јA�������ƈꏏ�ɒu�������ƁA���͎v���܂��B���̍��ʂ́A�����ɂ����ĐϋɓI�ɐ푈�ɎQ�����Ă��鍑�ł���A�܂��A�����ɂ���ē��݂ɂ���ꂽ���X�ł���Ƃ������Ƃɂ���܂��B���̏����͋ɓx�ɏd�v�ł���A�����Ȃɂ���ĐS�����߂Đ��������ׂ��ł���ƁA���͎v���܂��v�Ǝ咣���A���̒�Ă������ꂽ�i�V���[�E�b�h�U�A11�j�B�\�����A���t�@�x�b�g�����珜�O���ē��ʈ����������Ƃ́A�A�����J���\�A�ƒ����𑼂̘A�����Ƌ�ʂ��Ĉʒu�t�������Ƃ̔��f�ł���A�܂��A���̗�������ׂē��ʈ����������ŏ��̈ӎu�\���ł��������A���̖�肪�`���[�`���Ƃ̊Ԃŏd��ȑΗ��ނ��Ƃ͂Ȃ������B �@
��2�̏������̎��i���́A�t�����X���߂���ĉp�Ԃ̈ӎv���ꗂ̏d��ȑ�1���������Ƃ����悤�B�`���[�`���́A12 ��27 ���ɐ錾�Ắu���̐錾�ɎQ������Ɨ~���鏔���{�v�ithe governments signatory hereto�j�Ƃ��������̂��ƂɁu�y�я����ǁv�iand authorities�j�Ƃ���������}�����邱�Ƃ��Ă����BFDR�́A�h�S�[���z���́u���R�t�����X�v���Q�������邽�߂̂��̒�ĂɎ^�����A���g�r�m�t�ɓ��ӂ����߂����������Ȃ��Ƃ̗��R�ŋ��ۂ���A���ǁA�}������Ȃ�����3�j�B�z�v�L���Y�́A12 ��27 ���̃����Łu�����g�̋C�����ł́A�����̂������͎��R�t�����X�͊܂܂��ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���v�i�V���[�E�b�h�A11�j�ƋL�����悤�ɁA���R�t�����X�̎Q���ɏ��ɓI�ł���A����ɁA�n���͂����Ɩ��m�Ŕ��̗��ꂾ�����B�����ɂ́AFDR�ɑ���n������э����Ȃ̑t�����X����Ɋւ���\�z�̑��Ⴊ���f���Ă���4�j�B �@
���������Ɛ키�W�c�̖��̂ɂ��āA�`���[�`���͔ނ̑c��̃}�[���{�����݂��t�����X�̃��C14 ���Ƃ̐킢�Ƀ��[���b�p���������������Ƃ��́u��A���v�iGrand Alliance�j���̗p�������Ƃ������AFDR�̓A�����J���@�ƒ�G�����˂Ȃ��u�����v�Ƃ����p��ɓ�F�������A�܂��A�ꕔ�Ō����Ă����u���͍��v�iAssociated Powers�j�͑�1����펞�̖��̂Œ����Ƃ��āA�A�����iUnited Nations�j���咣���āA�`���[�`�����^�������iHoward�A 1�j�B �@
1943�N�Ƀ��X�N���ɏW�܂���4�J���i�ĉp�\���j�̊O���́A10��30����4�卑�錾�i���X�N���錾�j�ɍ��ӂ����B���̑�4���ł́A�u���ۂ̕��a�ƈ��S���ێ����邽�߂ɁA�卑�ł��ꏬ���ł��ꂷ�ׂĂ̕��a���D���Ƃ̎匠�����̌����Ɋ�Â��A���A���̂悤�Ȃ��ׂĂ̍��ƂɊJ���ꂽ��ʓI���ۋ@�\���o������葬�₩�ɐݗ����邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ����F����v�iMangoldt�A 8�j�Əq�ׂāA���ۘA���iLeague of Nations�j�ɑ���V���ȍ��ۋ@�\��4�卑�𒆐S�ɐݗ����邱�Ƃ��ŏI�I�Ɋm�F�����B�����ɁA�̂��̍��A���A�������S�ł���4�卑�����Ƃ���\���������Ƃ����߂�ꂽ�̂ł���A���N�Ƀt�����X��卑�Ƃ��ď������邱�Ƃ��V���ɍ��ӂ����5�卑���ɂȂ���ۗ��̍\���ɑ����Ă��̈Ӗ����𖾂��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�5�j�B �@
�A�����J�����ł́A�ϋɓI�Ɉ�ʓI���ۋ@�\��ݒu���ăA�����J�����̎哱�������邱�Ƃ�ڎw�����ێ�`�I�Ȉӌ��ɑ��āA���ۋ@�\�̐ݗ�������đ卑�Ԃ̑��ݗ�����i�߂�Ώ\�����ƍl����Ǘ���`�I�Ȓ������������B���X�N���錾�̑�5�����u�@�ƒ������Ċm������ʓI�Ȉ��S�ۏ�̐����J�n����܂łɍ��ۂ̕��a�ƈ��S���ێ����邽�߂ɁA�����4�J���́A�݂��ɋ��c���A�K�v����ꍇ�ɂ͏����Ƃɑ����ċ����s�����Ƃ邽�߂ɑ��̘A�����Ƌ��c����v�Əq�ׂ��̂́A��4���ւ̒�R��������������Ӗ������������A1944 �N1���̍����ȓ��̕����ł́u�����̐��_�͑�4���ɋ����x����^���Ă���v�ƕ]�����Ă���6�j�B �@
1941 �N�̑吼�m���͂ɂ����Ďn�܂����V���ȍ��ۋ@�\�̐ݗ����܂ށu���v��v�ւ̎��g�݂́A�^��p���1942 �N�ɖ{�i�������iBennett�A 2�j�B�@
FDR�́A1942 �N�t�A�����g�t�O���Ɂu�A�����J�A�C�M���X�A�����đ��������ƕ���ŁA�\�A�͌R�������������ƂȂ�A���̍��X�͔�R��������邾�낤�B���[���b�p�����̐A���n�鍑�͐藣����A3�卑�܂���4�卑�igreat powers�j�ɓ������ϔC����邱�Ƃ��ƂȂ낤�v�Ɠ`���āA�\�A����㐢�E�ɂ�����x�@���̈�l�ƂȂ邱�Ƃ�F�߂��|�̔��������Ă���7�j�B �@
�����ŁA���Đ��E���C�M���X�鍑��z���グ���C�M���X�́A�A�����J�̑䓪���C�M���X�鍑�̌�ނɂȂ��邱�Ƃ��x�����n�߂Ă����B���ۋ@�\�̐ݗ��Ɋւ���C�M���X�O���ȓ��̌����́A1942 �N�ɏo���ꂽ�u4�卑�v�����v�Ƒ肷��W�F�b�u�E��������n�܂����B�������́A�A�����J�̎咣����u4�卑�x�z�_�v�̈Ӗ��A�L�����A�C�M���X�̍��v�Ƃ̊ւ����������āA�A�����J�������㉟�����钆�����卑�������邱�ƁA�C�M���X�̎咣����卑�t�����X���r������Ă��邱�ƁA�Ȃǂ̖��_���w�E������ŁA��ֈĂ��Ă��邱�Ƃ͓���Ƃ��āA�A�����J�̃��[���b�p����ѐ��E�ւ̃R�~�b�g���s���Ȏ��ԂɊӂ݂āA�����A�����J���R�~�b�g���Ȃ����ƂɂȂ�ƃC�M���X�̓\�A�Ɠ������Ȃ���Ȃ炸�A���̃\�A�����͂����ۂ�����C�M���X�̓h�C�c�Ƌ��͊W�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�Ɩ��̓���͂����iWoodward�A 434-435�j�B11 ��27 ���Ɏ����Đ펞���t�́A4�卑�v�������x�����āA������卑�Ƃ��ď������邱�Ƃɓ��ӂ�����j�����߂�8�j�B�������\�A�́A1943 �N10 ���̃��X�N���O����c�̒i�K�ł��A�������ɐ������郂�X�N���錾�ɒ������Q�������邱�Ƃɔ��������B �@
�A�����J�ɂƂ��ăt�����X�̏����́A�r�V�[�����Ƃ̊ւ��ŕ��G�Ȑ��i���������B�h�S�[���́A1940 �N10 ��27 ���ɁA�������t�����X�̖��ŁA���A�t�����X�̖h�q�̂��߂ɂ̂݁A�t�����X�̐푈�������w������Ɛ錾�����B�A�����J���{����{�I�Ƀh�S�[���h�ł͂Ȃ��ăr�V�[�����i�y�^�������j�Ƃ̊O���W�̈ێ���D�悳�����̂́A�r�V�[�������ł��邾�������ɂ��Ă����������ƁA����уJ���u�C��k�E���A�t���J�̃t�����X�̂��i�`�X�x�z����͂��������ƍl����������������iGellman�A 286�j�B������FDR�́A�A�����錾�̍쐬�ɍۂ��ăC�M���X�������u���R�t�����X�v�����������ɐ������ɂ��ւ�炸�r�V�[�����Ƃ̊W�ێ����l���ɓ���ċ��ۂ����̂ł���iWoodward�A 432�j�B �@
1942 �N6���i�K�ŁA�h�S�[���ւ̃t�����X�����̎x���̍��������m�ɂȂ�ƃA�����J�̓h�S�[���̎��R�����ψ�����t�����X���\����g�D�ƔF�߂����A���̈Ӗ��́A�푈���s�ɂ�����t�����X�̃��W�X�^���X�^���̏ے��Ƃ������Ƃł���A�r�V�[�����ɑ���Վ����{�Ƃ��ď��F���邱�Ƃ͉�����������B�t�����X���m���}���W�[���ʼn������ĘA�����ɎQ������̂�1945 �N1��1���̂��ƂɂȂ�B �@
�A�����J���t�����X��卑�Ƃ��ď�������ӎv�̂Ȃ��������Ƃ́A�����ȓ��ɍ��������̎���@�ւƂ��ăT���i�[�E�E�F���Y����������������1942 �N�ɐݒu���ꂽPIO�i��㍑�ۋ@�\��茟���ψ���j�̋c���^������ǂݎ���B1942 �N10 ��30 ���ɂ́A���ɐݗ������ׂ����ۋ@�\�̖��̖�肪�c�_����A�u�i���ۘA���������1918 �N�����Ɂj��A�t���J�O���i���j�̃X�}�b�c���R��United Nations ���悢�ƒ�Ă������Ƃ�����ƃV���b�g�E�F������������ƁA�}�b�N�����[�X���A���̖��̂ɂ���ƃA���[���`���A�h�C�c�A�t�����X�Ȃǂ̍��X���������ɂ����Ȃ邱�Ƃ����O�����Ɣ��������v9�j�B�����ł́A�t�����X�́A�r�V�[�����̎��ゾ�����Ƃ͂����A�G���h�C�c�⒆�����A���[���`���i�h�C�c�ւ̐e�ߊ�����A������������ۂ��Ă����j�Ɠ���̈����������B���������̉�c�ŃE�F���Y�́A�u���̂悤�ȍ��X�ɂ����������Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂��v�Ɣ������āA�t�����X�̐V���ۋ@�\���������R�̑O��ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���A���̐��E���a���哱����卑�ƌ��Ȃ����]�n�͂Ȃ�����10�j�B �@
1943 �N3��12 ���ɃC�[�f���O�������V���g���ɕ����A�n����FDR�Ɖ�k�����B3��17 ���́A�C�[�f���A�n���AFDR��k�ł́AFDR���n�����A�ɓ��̓��{��}�����邽�߂ɂ���߂Ė𗧂Ƃ����ϓ_����A������卑�Ƃ��ď������邱�Ƃ��d�������̂ɑ��āA�C�[�f���͒����̈���B���\�͂ɋ^��𓊂��A�v���̎���������邩�ǂ������莋���āA�����������m�̂��������ɏo�v���鎖�Ԃ͍D�܂����Ȃ��Ɣ��_�����i�V���[�E�b�h�U�A 267�j�B�C�[�f���́AFDR�������ɂ�����A�����J�̌��v�𗘗p���ăA�����J�����ɍ��ۓI�ӔC�킹�悤�Ƃ��Ă���Ƃ݂����A���̉��߂́AFDR�̐��\�z���A�����J�̐��E�I�Ȏ哱���̊m���ɂ��������Ƃ��M�킹��iWoodward�A 440�j�B3��27 ���̉�k�ł́AFDR�ƃE�F���Y�́A���̍��ۋ@�\���P��c�̂Ƃ��̉��̒n��g�D����\������邾�낤�Əq�ׂ��ۂɁA�ŏI�I�ɂ͕āA�p�A�\�A���������I������s���̂ł���A����4�J���͒����ɓn���Đ��E�̎����ێ��ɐӔC��˂Ȃ�Ȃ��Ȃ鍑�ł���ƌ������i�V���[�E�b�h�U�A 268�j�B�z�v�L���Y�́AFDR�������𖡕��ɂł���ƍl���������́A�������\�A�Ƃ̊Ԃɐ[���Ȑ����̕s��v�����邩��ł���Ǝw�E���Ă���i�V���[�E�b�h�U�A 268�j�B�p�\��������卑�Ƃ��ď������邱�Ƃɂ��₢��Ȃ���ŏI�I�ɔF�߂��̂́A1943 �N���X�N���O����k�̂Ƃ��ł���B�C�M���X�́A�����ɓG�ΓI�ȑԓx���Ƃ�ƒ������A�����J�ɐڋ߂��ĐA���n��`���ŋ�������̂ł͂Ȃ����Ƌ���Ă��Ԃ��ԔF�߁A���\�������Ƃ̊W�Œ����ɐڋ߂�������������������\�A�̃����g�t�O���́A������F�߂Ȃ��Ȃ�p�Ă���̉����𒆍��ɂ�葽���U������˂Ȃ�Ȃ��Ȃ肻�ꂾ���\�A��������������������Ȃ��ƃn���Ɍ����ď������邱�ƂƂȂ����iZi�A 55�j�B �@
1943 �N11 ���` 12 ���̃e�w������k�̍ۂɁA�X�^�[�����́A�t�����X�ւ̑S�ʓI�ȕs�M�������ɂ��āA�t�����X����鍑�����グ��ׂ����Ɣ��������B���̍l���́A���˂Ă���FDR���l���Ă������Ƃ��������A�`���[�`���́A���[���b�p�嗤�ɂ͋����t�����X���K�v�ł���̂ŐA���n�����グ�ăt�����X�̌ւ�����������͂Ȃ��������A�����������̈Ă͂��ׂĂ̐A���n�����ۓI�ȐM�������ֈڍs�����悤�Ƃ���FDR�̊�݂ɓ������Ă��܂����̂ƌx�������̂ł���iRoyal Institute�A 354�j�B�����t�����X�̕K�v���Ƃ́A�C�M���X�ƃ\�A�Ƃ̊Ԃ̊ɏՒn�т̕K�v���A����сA�A�����J�̉e���́E�x�z�͂̋y�тɂ������[���b�p�̍Č��ɂ̓t�����X�̐����͂��K�v���Ƃ������Ƃ��܈ӂ��Ă����B���̃e�w������k�́AFDR�����ۘA���\�z�̑�g�����߂ĕ\���������ۉ�c�ƂȂ����iPhillips�A 216�j�B �@
1944 �N6��12 ���A�n�����n���t�@�b�N�X���đ�g�ɁA�\�A�������Ɠ��Ȃ��邱�Ƃ������Ȃ�_���o�[�g�����I�[�N�X�ł̊J�Â��Ă��Ă����c�͕ĉp�\������3������k�ł��悢�Ɠ`�����Ƃ��ɁA�����Ɍ��z�͎����Ă��Ȃ����A�����J���_�͒�����3�卑�Ɠ��l�ɏ�������悤���߂Ă���Ƌ��������B�\�A�́A�ĉp����̐��������ꂽ���A�������܂߂���c��3�J����c�̂��Ƃɐݒ肵�����Ǝ咣���A�������ꂽ�B7���ɂ́A�`���[�`�����A���E�@�\�ݗ��Ɋւ����c�ւ̃t�����X�ƒ����̎Q�����咣�����C�[�f���Ăɂ��āA�t�����X�͎������{���L����b�̏�Ɋm������܂ł͎Q����F�߂�ׂ��łȂ��A������4�卑�̈�ƔF�߂�̂͂����Ă���ƁA���������Ă���11�j�B�������āA�_���o�[�g���E�I�[�N�X��c�́A���������Ƃ���Q������Ƃ����ϑ��I�ȉ�c�ƂȂ����B �@
1944 �N8��21 ���` 10 ��9���̃_���o�[�g���E�I�[�N�X��c�ŁA3�卑����ђ����ƕ���Ńt�����X�����ۗ���C�������Ƃ��邱�Ƃ����ӂ��ꂽ�B8��24 ���AFDR���܂ރz���C�g�n�E�X�̉�c�ŁA�t�����X���i���I�Ȑ��{�����������Ƃ��Ɉ��ۗ���C�������̈֎q��^���鉽�炩�̏����������ׂ����A�Ƃ������Ƃ����肳�ꂽ�iFRUS 1944 Vol.1�A 731�j�B28 ���ɂ́A�^�c�ψ���ŁA���ۋ@�\���ݗ������܂łɃt�����X�̐��{�������ɏ��F����邩�ۂ��Ɋւ�炸�t�����X�ɏ�C�������̒n�ʂ���������邱�Ƃ��]�܂����Ƃ�����ʓI�ȍ��ӂ����������iFRUS 1944 Vol.1�A 737�A740�j�B �@
�A�����J�́A���̋K�́A�l���A�����A���̏����A�A�����ւ̍v���ɏƂ炵�ău���W��������C�������ɂ��悤�Ƃ������A�p�\�ɋ��ۂ��ꂽ�iHull�A 1678�A Russell�A 443�j�B�\�A�̔��Η��R�́A��C��������4�J���܂��͍ő�5�J���Ɍ��肵�����Ƃ������Ƃ������iFRUS 1944Vol.1�A739�j�B�t�����X�̏����́A���̃u���W�����Ƃ̊֘A�������āA�����������傫���a瀂�3�卑�̊Ԃɐ��ݏo�����B �@
�t�����X�Ɋւ��ăA�����J���{�́A���ɂ�����卑�Ƃ��Ă̒n�ʂ�F�߂Ȃ��Ƃ���_�ň�v���������H���������Ă������A����̋�̉��ɓ������Ă�FDR�ƃn���̊ԂőΕ�����̍������قȂ��Ă����BFDR�̔��f�����v�Ɂu�h�S�[���]���v�ɂ������̂ɑ��āA�n���̊�́u�r�V�[�����̕]���v�ɂ������Ƃ�����B�h�S�[���]���̖ʂł́A�h�S�[���̃p�[�\�i���e�B�ɑ��锽�������A�u�t�����X�鍑����v�Ƃ������O�I�ȓ����ւ̔��������������Ƃ݂�ׂ����낤�BFDR���t�����X�ɑ��Č������ԓx���ł߂�_�@�ƂȂ����̂��A1941 �N12���̃T���E�s�G�[�����A�~�N�������苒�����ł���B�r�V�[�����̃W�����W���E���x�[����̊Ǘ����ɂ�����2�̃t�����X�̂̓��i�J�i�_�̃j���[�t�@�E���h�����h���j�̖����{�݂��h�C�c�R�ɂ���ė��p����邱�Ƃ��뜜�����J�i�_���{�́A11 ���ɁA�ĉp�̓��ӂ̂��ƂɁA�A�����̗��v�̂��߂ɗ������NJ����ɂ������Ƃ����߂����A�匠�N�Q���Ɠ{�����h�S�[���Ǝ��R�t�����X�C�R������苒������j��ł��o�����B�C�M���X�͂�ނȂ��ƒǔF���A�r�V�[�����Ƃ̊ԂŐ������ɂ�����t�����X�̓y�̕ۑS�����肵������̃A�����J�͔F�߂邱�Ƃ����ۂ������A12 ��24 ���Ɏ��R�t�����X�R�͗�����苒���Ă��܂����B�J�i�_�ƃA�����J�̋��d�Ȕ��ŁA�r�V�[�����������ւ̎x�z���������A���̉ߒ��́AFDR�Ƀh�S�[���ɑ��鋭���s�M���������炵���̂ł���B�z�v�L���Y�����҂̃V���[�E�b�h���A�u���̋���ׂ���ɕ����Ȃ����R�t�����X�̎w���҃V�������E�h�S�[�����R�v�A�u���̖��ɑ���h�S�[���̍s���͖��炩�ɖ��@�ł����ĕى��̗]�n���Ȃ��v�A�u�h�S�[�����R�̂��܂薣�͂̂Ȃ������v�i�V���[�E�b�h�U�A 39-40�A 47�j�A�Ə������̂́A�z�v�L���Y��FDR�̈ӎv�f�������̂Ɖ������B���̓����ɂ́A�t�����X�����̎x���̓h�S�[���l�ł͂Ȃ��Ď��R�t�����X�ɑ�����̂ł��������Ƃ͖����������B �@
���������A�����J���{���ł́A�t�����X�̏����ɂ��āA�卑�Ƃ��Ă̔F�m�ɐϋɓI�ȍ����ȂƏ��ɓI��FDR�Ƃ������Ⴊ�������BFDR�́A�T���E�s�G�[�����E�~�N�������苒������ʂ��ăh�S�[���̃p�[�\�i���e�B�ɑ���s�M���𑝂����BFDR�́A�t�����X�������I�Ȉ������������\�͂������Ă��邩�ǂ����ɋ^��������A�A���n�Z���̖����I�M�]�̍��܂�ɓK�ɑΏ�����\�͂Ɍ�����Ƃ݂Ă����iBlumenthal�A 303�j�B���������āA�����h�S�[�����ƌ���̂ł͂Ȃ��āA�����ʂ�́u�t�����X���v�Ƃ��čL�������邱�Ƃ��K�v�ł���B �@
�A�����J���t�����X��5�卑��1�Ƃ��Ď����܂ł̃v���Z�X�́A3���ɕ�������B��1���́A1940 �N�̃t�����X�~������1942 �N�t�ŁA�r�V�[�����ɂ����R�t�����X�ɂ��A�匠���ƂƂ��Ă̎��i��F�߂Ȃ������B��2���́A1942 �N�Ă���1944 �N�t�ŁAFCNL�iFrench Committee of National Liberation �t�����X��������ψ���@1943 �N6��2���ݗ��j���匠���Ƃ̐��{�ɏ�������̂ƔF�߂����A����͐�㐢�E�ɂ����镽�a�n���̉ۑ�Ƃ͊W�Ȃ��A�P�ɁA�t�����X���̗��v�����Ǘ�����Ƃ����u�����I�ȓ����̎�́v�Ƃ��Ă̔F�m�Ɏ~�܂����B �@
��3�����A1944 �N�āi�_���o�[�g���E�I�[�N�X��c�j����1945 �N2���i�����^��k�j�ŁA�t�����X����̍��ۋ@�\�ő卑�i���ۗ���C�������j�Ƃ��ď������邱�Ƃ�F�߂��B �@
�t�����X�̑卑����ڎw���C�M���X�́A�A�����J�́u4�卑�āv�i�t�����X�ʂ��j�ɂ͓������������������A�ŏI�I�ɂ͎��ꂴ������Ȃ������B�C�M���X�̐펞���t�́A1942 �N11��27 ���A�C�[�f���O���̒ɉ����āA���ʁA�A�����J�Ă��x�����Ă䂭���Ƃ����߂��B�@
�A�����J�ɂƂ��āA��㐢�E���哱����̂́A1941 �N�̑吼�m���͂Ɍ�����悤�ɁA�܂��ĉp��2�卑�ł������B�������A���������Ƃ̐푈�ɏ�������ϓ_�ɗ��ƁA���Ƀh�C�c�Ƃ̎������J��Ԃ��Ă���\�A�̗͂��s���ł���A�܂��A�\�A��A�����Ɉ�������Ȃ��ꍇ�ɂ̓\�A��1922 �N�̃��p������1939 �N�ƃ\�s�N���̂悤�ɍĂђP�ƂŃh�C�c�ƒ�g����댯�������O����Ă����B �@
���������āA1941 �N12 ���̘A�����錾�N���́A�ĉp�̎�]�iFDR�ƃ`���[�`���j����{�g�g�݂���肻��ɑ��ă\�A�̗��������߂�Ƃ����葱�Ői�߂��A������3�卑���S�̌��������܂ꂽ�B1943 �N11 ���̃J�T�u�����J��k��3�卑��]��k�������B1944 �N�̃_���o�[�g���E�I�[�N�X��c���A�^�c�ψ���isteering committee�j�̍\�����͕ĉp�\�ł����āA8��21���`9��28 �����ĉp�\��c�A9��29 ���` 10 ��7�����ĉp����c�ƂȂ����B������3�卑�����ӂ������e�����Ƃ���ǔF���������ŁA�����I�ɂ�3�卑��c�ł���A1945 �N2���̃����^��k��3�卑�������B���ǁA�������܂�4�卑��]��k�͈�x���J����Ȃ������B4�卑�̑�\�ɂ��d�v�ȉ�c�́A���X�N���O����c�i1943 �N10 ���j�����������B �@
3�卑�Ԃ̋����ɂ���Đ�㐢�E�̕��a���\�z����Ƃ�����{�����́A�A�����錾�̌���ێ����ꂽ���A�A�����J�ƃC�M���X�͂��ꂼ��̎v�f����u�卑�͈̔́v�̊g���}��A���ꂪ�̂��̍��ۘA����5�卑���ݏo�����B �@
�ĉp�\��3�卑���������u�卑�v�Ƃ��ď������邱�Ƃ����肵�������ɂ��ẮA��������B �@
1942 �N1���̘A�����錾�Œ������A���t�@�x�b�g���̗�O�Ƃ��Č���������4�Ԗڂɓ����ꂽ���Ƃ������āu�卑�v�Ƃ��ĔF�m���ꂽ�Ƃ�����߂����肤��B�A�����J�����������������ɂ��悤�Ƃ����̂́A�����̑Γ��푈�ւ̌���A���ɓ��{�̖�S��}�����\�A�Ƃ̋ύt��}��ɂ͋��͂ŗF�D�I�Ȓ����̑��݂��s���ł��邱�ƁA�i�V���i���Y���̑䓪����A�W�A�Ő����������x�z�I�ȗ���ɂ���Ǝv����̂�����邽�߁A�ł������iZi�A 55�j�B���̉��߂�⋭����̂��AFDR�����p�\����{�I�ɂ��̕\�������ꂽ�u4�卑�ɂ��x�@���v�ifour policemen�j�\�z�ł���B���E���a�̈ێ���ĉp�̔C���ƍl���Ă���FDR�́A1942 �N�A�u4�卑�ɂ��x�@���v�\�z���o���A���ꂪ�̂��̍��A���ۗ������ĉp���\���j�Ƃ�����̂Ƃ��č\�z����o���_�ƂȂ����iHilderbrandt�A 122�j�B�ނ́A4�卑�ȊO�̍��X�͐��ɂ͔�������邾�낤�Ƃ����O��ɗ����āA�R���͂�Ɛ肷��4�卑�����E�̊�@�̍ۂɂ͂��̌R���͂ƌo�ϗ͂��s�g����K�v������ƍl�����B �@
�t�����X�Ɋւ��ẮA�܂��A�r�V�[������肪�������B�t�����X�i�r�V�[�����j�Ƃ̊O���W�̈ێ����d�������A�����J�ɑ��āA�C�M���X�͔��p�I�ȃr�V�[�������狗���������A���̊ϓ_����h�S�[���x���X�����B���̔w�i�ɂ́A�t�����X�̑卑����F�߂�C�M���X�Ƃ���ɏ��ɓI�ȃA�����J�Ƃ���FDR�A�Ƃ����Δ䂪�������B �@
�܂�A�����̏������߂���3�卑�Ԃ̑Η��́A���ꂼ��́u���\�z�v�̈Ⴂ�ɋN�����Ă���B�[�I�ɕ\������A�u�P��̐��E�v�\�z�Ɓu���͌��v�\�z�̑����ł���A����́u���������v�_�Ɓu�A���n�ێ��v�_�̑����Ɗ֘A���Ă����B �@
�A�����̏������߂Â��A�푈�̍ŏI�I�ȏ����i�h�C�c�E���{�Ƃ̐킢�j�̂��߂�3�卑�̋��c���}�i�W���Ă���ƁA����Ɠ����ɁA��㏈���Ƃ���Ɋ�Â���㕽�a�\�z�Ɋւ���3�卑�Ԃ̈ӌ��̈Ⴂ���\�ʉ����Ă���B �@
���������ɏo���ꂽFDR��4�J���x�@���\�z�́A�u�n��I���͌��̗v�f�Ƒ卑�ԋ��̗͂v�f�̑o�����܂���v�����v�iSchild�A xi�j���������A�����́u�n��I���͌��̗v�f�v�̖ʂ���Ƃ���ƎƂ߂��A���������āA�n���̕��ՓI���E�@�\�\�z�ƑΗ�������̂ł���A�����ł́A�卑�ԋ��͂��܈ӂ��邪�䂦�Ƀ`���[�`���̒n��I���S�ۏ�@�\�\�z�Ƃ��������Ȃ����i�������Ă���12�j�B�`���[�`���́A��㐢�E�̕��a�����[���b�p�A�A�W�A�A�A�����J��3�n�悲�Ƃ̓Ɨ������u�n��@�\�v�iRegional Council�j�Ƃ��̏�ɗ������@�ւƂ��Ắu���E�@�\�v�iWorld Council�j�Ƃ�����d�\���̒��Ŏ������悤�Ƃ��Ă���13�j�B �@
���͌��\�z�Ɋ�Â��`���[�`���́u�n��@�\�v�\�z�́A��1���P�x�b�N��k�i1943 �N8��17 �| 24�j��FDR�ɋ��₳��č��܂����B���������āA���X�N���錾�i4�J���錾�@1943 �N10��30 ���j�ŁA�u����4�J���́A���ׂĂ̕��a���D���̎匠�����̌����Ɋ�Â��A���A���ۂ̕��a�ƈ��S�̈ێ��̂��߂ɁA�卑����Ə�������ƂɊւ�Ȃ����ׂĂ̍��ɊJ���ꂽ�A��ʓI�ȍ��ۋ@�\���\�Ȍ��葬�₩�ɐݗ����邱�Ƃ��K�v�ł���ƔF�����Ă���v�ƕ\�������ۂɂ́A�n��@�\�̘A���̂Ƃ������i�͊܂܂�Ă��Ȃ��B�C�M���X���{���ł́A�C�[�f���O���̓`���[�`���ƈقȂ��āAFDR�́u�P��̐��E�@�\�v�\�z�ɂ��`���[�`���̃t�����X�̋����ɂ��^�����闧����Ƃ��Ă����B�`���[�`���́u�n��@�\�v�\�z�́A���ۘA���̎��s�Ɋӂ݂āA�푈�̖h�~�ɕK�v�Ȃ̂͗͂̋ύt�ł���Ƃ���M�O�ɗ����Ă������A����EC����EU�ւ̔��W�r��Ɍ���ꂽ�悤�ɃA�����J�����[���b�p����r������̂ł͂Ȃ��āA�ނ���A�����J�����[���b�p���ɉ�������ă\�A�ƑR����͂��`������K�v�������Ă����iRoyal Institute�A 320-321�j�B�ǂ̍��ɂƂ��Ă��A�푈�̏I�����߂Â��Đ�㐢�E�ł̎����̈ʒu�����߂悤�ƍl�����Ƃ��ɂ́A�̓y�I�ȈӖ��ł́u���͌��v����1�̊S�ƂȂ�͓̂��R�ł���B �@
�X�^�[�����ƃ`���[�`���͂���ɕq���ɔ����������̂ɁA�v�z�Η����ċ��ʂ̗�������o�����B���̈�̌��ʂ��p�\�Ő��͌�����茈�߂�1944�N�́u�p�\�閧����v�ł���B����́A�폟�����̂��߂̋��͊W�̋������Ƃ��ꂽ���A�����I�ɂ́A��㐢�E�̍\�������ʂ������͌�����ł���A���剻����A�����J�ɑ��Ă��ꂼ��قȂ�X�^���X�őR���悤�Ƃ��Ă����C�M���X�ƃ\�A���o���J���n��ɑ���e���͂̊m�ۂƂ����ϓ_�ň�v�������ʂł���14�j�B �@
FDR�����͌��\�z���x�����Ȃ������̂́A�Ǘ���`�̗��j�I�o�߂��猩��Ύ��R�������B �@
�Ǘ���`����̍����ɂ́A��1�����E���ւ̎Q�킪���҂������ʂ܂Ȃ������Ƃ������Ŋ�������A����͉p���̒鍑�i�A���n�̐��j�ɑ���I�[�v���h�A�[�̗v�������ۂ��ꂽ���Ƃ���v�Ȍ����������B�Ǘ���`�҂̃W�F�����h�EP�E�i�C��@�c���́A��2�����u������ɁA�u���݂̃��[���b�p�̕����ɖ����`�̗��z���킸���ł��܂܂�Ă���ƍl����悤�Ȕn���������Ƃ͂�߂悤�B�����Ɋ܂܂�Ă���ő�̉ۑ�́A���݂̒鍑��`�ƒ鍑�̈ێ��A�����Ă�����낤������悤�ȐV���Ȓ鍑��`�ƒ鍑�̌��݂�j�~���邱�Ƃł����Ȃ��̂��v�iAppendix to the Congressional Record 1939�A 89�j�ƌ����A�c��c���^�Ɏ��^���ꂽ�A�C�I���B�̂���q�t�́u��1�����ŃA�����J�́A13 ���l���펀�����̂ɉ��̌��Ԃ���Ȃ����ӂ����ꂸ�A�������āA�Q�킪�x�������Ɣ��ꂽ���̂��B�݂��t�������\���h���̐����ԍς���錩���݂��Ȃ��v�iAppendix to the Congressional Record 1939�A 97�j�ƌ������B���̊܈ӂ́A�p���̐A���n���A�����J�̏��i�Ǝ��{�ɊJ������Ȃ������Ƃ����s���ł���BFDR�͑�����1937 �N�Ɂu�u�������v�ɂ���ă��[���b�p�̕����ւ̉���̈ӎv�����������A�����̌Ǘ���`��������A�����I�Ȓ�Ăɂ͎���Ȃ������B�ނ́A�Ǘ���`�Ƒ��������Ɍ��ʂ��Ă����ƌ����邪�A�p���̐��E�I�Ȓ鍑�̐��̉�̂�]�ޓ_�ł͈�т��Ă����B�A�����J�ɂƂ��Ă̑�2������̉ۑ�́A�R���I�Ȉ��S�ۏ�ƃA�����J�̌o�ϓI�Ȕ��W��ۏႷ�鎩�R�f�Ց̐��̍\�z�Ƃ���2�ł������B����2�̉ۑ���Ɏ����������́A�u�P��̐��E�v�\�z�ł���A����͐��͌��\�z�ƑΗ�������̂������B1944 �N�̉p�\�閧����ɂ��āAFDR�͎��O�ɃC�M���X������e��m�炳�ꂽ�Ƃ��ɖٔF����ԓx����������A���ꂪ�푈�����̂��߂̕���ł��邱�ƁA���������Đ��Ɍ��������͌��̎�茈�߂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ����ƁA�𗯕ۏ����Ƃ����̂ł���B���͌��\�z�́A�u���b�łɂ���Ď��ꂽ�s��v�����Ӗ����Ă����̂ł���A�����1 9 ���I���ȗ��A�����J���咣���Ă����u���R�s��v�\�z�ƑΗ����Ă����iRothwell�A 9�j�B �@
���������āA�u�P��̐��E�v�\�z�Ɓu�n��@�\�v�\�z�Ƃ̑Η��́A�u���������v�_�i�p���A���n�̐��̉�́j�Ɓu�A���n�ێ��v�_�A����сu���R�f�Վ�`�v�Ɓu�ی�f�Վ�`�v�Ƃ�����d�̑Η��\���̏�ɐ������Ă����Ɖ����邱�Ƃ��K�����낤�B�@
�A�����J�ƃC�M���X�̊Ԃ̑Ε�����̑���́A�u���������_�v�Ɓu�A���n�ێ��_�v�̑Η���w�i�Ƃ��Ă������A���̑Η��́A�����ɁA���E�e���Ɛ��E�s������߂�A�����J��j�~���悤�Ƃ���C�M���X�̒�R���Ӗ����Ă����B�A�����J�O���ɑ����Ă݂�ƁAFDR�̓A�����J�鍑��`�̑䓪��l����`�I�Ȍ����ŕ����B���Ă����A�Ƃ����]����^���邱�Ƃ��ł���iBlumenthal�A 311-312�j�B�Ε�����ł�����FDR�ƏՓ˂��������Ȃ́A��2������ɂ��C�O�ɗ��C�R��n���g�傷��K�v���������Ă���A�t�����X�������e���͂����k�E���A�t���J�n��ւ̐i�o���d�����闧��������ăt�����X�̑卑���ɍm��I�������B �@
���̃t�����X�̈ʒu�t���ɂ��đΗ�����FDR�ƍ����Ȃ́A�h�S�[���]���ɂ��Ă͈�v�_�����������B��������p���̈�v����苭���Ȃ�B�܂�A�u�A���n�ێ��_�v�ł̈�v�ł���B�C�M���X�́A�\�����d�p���Đ�㐢�E���\�z����A�����J�̂��ƂŃW���j�A�E�p�[�g�i�[�ɂ���Ă��܂��댯�����������A���̂悤�ȃA�����J�ɑR���邽�߂ɂ́A�嗤�ɂ����鋭�͂ȃt�����X���K�v�ł����āA�t�����X�̑卑�����A�����J�A�\�A�A�h�C�c�ɑ���ی��ɂȂ�ƍl�����̂ł��邪�iBlumenthal�A 311�j�A�h�S�[�����t�����X�鍑�̍��Y���Ȃ���t�����X�̕����͕s�\���ƍl���Ă����̂ł����āu�A���n�ێ��_�v�ʼnp���̋��ʐ����ێ����ꂽ�̂ł���B �@
�A�����J�́A�吼�m���͂Łu�ĉp���S��`�v�̐��E���\�z���A�^��p�������ĘA�����錾���쐬����ۂɃ\�A���������ށu�ĉp�\��3�卑���S��`�v�֍L���A1942 �N���ɂ���ɁA�u�������܂�4�卑���S��`�v�֊g�傳�������A���A�n�݂̊ԍۂ܂ŃA�����J���{���ł�������卑�Ƃ݂Ȃ��ӎ����ォ�������Ƃ́A1944 �N�̃_���o�[�g�����I�[�N�X��c���A�\�A�ւ̔z���������Č`���I�ɂ́A�u�ĉp�\�̑O���v�Ɓu�ĉp���̌㔼�v�ɕ������ꂽ���ƂɌ�����B �@
���[�[���}���������^��k�ɂ��ĉ�ڂ����Ƃ��ɁuFDR�̓����^�ŁA�t�����X�Ƀh�C�c��̒n���^���A�t�����X���T���t�����V�X�R��c����Â���3�卑�iBig Three Powers�j�ɉ����悤�ɂ����v�iRosenman�A 521�j�Ə������悤�ɁA��㐢�E�\�z�̊�ՂƂȂ�ׂ��u4�卑���v�������́u5�卑���v�͌���������́u���f�v���邢�́u���O�v�ł����āA3�卑�v���X1�܂���4�卑�v���X1�Ƃ����ӎ��͎c���Ă���15�j�B �@
4�卑���S��`���A�u���ی������������ۗ��v�Ƃ����Ӗ������悤�ɂȂ����̂́A1944�N�ł���B���N��9��18 ���A�\�A�O���O���N�C�R�̓X�e�e�B�j�A�X���������ɁA���ی��̂Ȃ����ۗ�����͔F�߂��Ȃ��Ɠ`���A�X�e�e�B�j�A�X�͂����Ȃ����獑�ۘA���͖��͂ɂȂ�Ɣ��_�������A�����^��k�̍ۂɃX�^�[�����͂���ɁA���A����E�ނ��錠���ƒǕ�����Ȃ������̑o����~����Əq�ׂĂ���iDallin�A 22-23�j�B���ꂾ���ɁA�u�\�A�����̐�㍑�ۋ@�\�͂��肦�Ȃ��v�Ƃ����A�����J�̌��O�������������܂�A�t�����X�ƒ�����卑�Ƃ��ď��������㐢�E�\�z�̕K�v���ƌ����������܂����Ƃ�����B�@
1�j�V���h�́A�ŏ���2���̊Ԃ́A���ێ�`�I�ΊO������u������c��⍑���̌Ǘ���`����ɑł������Ƃ��ł��Ȃ������B���ꂪ�\�ɂȂ����̂́A�^��p�����ƃA�����J�̎Q��ȍ~�̂��Ƃł���A�Əq�ׂĂ���B. �@
2�j�C�M���X�́A�h�C�c��1�̋��ʔF���ɗ����āA����ݗ^�@�ɂ�镺��̋�����D��I�ɎĂ������A�A�����J�̍`�ł��łɃC�M���X�����̑ݗ^���킪��~���߂��Ă���A�����m�d���헪�ւ̓]���̉e���ł���\�������O���ꂽ���Ƃ��A�A�[�J�f�B�A��c�J�Â̈���������B�V���[�E�b�h�A�U-2�B �@
3�j�̂��ɂȂ��āA���g�r�m�t���{����FDR�ƃ`���[�`���̗v����`���A�{�����{�͏����̕Ԏ���Ԃ��������ԓI�ɊԂɍ���Ȃ������A�Ƃ���������炩�ɂȂ�B�V���[�E�b�h�A13�B �@
4�j�E�b�h���[�h�́A�V���[�E�b�h�̐����Ƃ͈قȂ��āAFDR�̓r�V�[�����Ƃ̊W�̈ێ����d�����闧�ꂩ�玩�R�t�����X���������ɂ��邱�ƂɊ拭�ɔ������Ƃ���BWoodward�A 432. �@
5�j���������Ƃ��ĎQ�������X�e�e�B�j�A�X�́A�ĉp�\���A�����ɂ킽��ٖ��ȋ��͊W����A�펞�̋��͂���������邱�Ƃ����v�ɂƂ��Ă����a���D���̗��v�ɂƂ��Ă�����߂ďd�v�ł��邱�Ƃ��m�F�������ƂɃ��X�N���O����c�̍ő�̈Ӌ`�����o���Ă���BStettinius�A 14. �@
6�j�gPublic Attitudes Regarding Methods of Using Force to Maintain Peace and Prevent Aggression�h�A Jan. 5�A 1944�A RG 59�A General Records of the Department of States�A Records of Harley P. Notter�A Records of the Advising Committee on Post-War Foreign Policy 1942-1945�ALot 60D-224�A Box 90. �@
7�j�J�[�P���_���́A 1 9 4 2 �N�̎��_��FDR ���u4�J���x�@���\�z�v���ł߂��Ƃ݂Ă���BKirkendall�A 259. �@
8�j�t�����L���́A���̂悤�ɕ\������B�u�����̓A�����J�̎q���ŁA���ۂɂ͂����ł��Ȃ��̂ɑ卑�Ƃ��Ĉ���ꂽ�v�BFromkin�A 457. �@
9�jP-I.O Mintute 14�A Oct�A 30�A 1942�A RG 59�A General Records of the Department of States�A Records of Harley P. Notter�A Records of the Advising Committee on Post-War Foreign Policy 1942-1945�ALot 60D-224�A Box 85. �@
10�j�V���ɐݗ�����鍑�ۋ@�\�̖��̂́A1944 �N�̃_���o�[�g�����I�[�N�X��k�̍��ɂ́A�A�����J�ȊO�̍���United Nations �ł悢�Ƃ���悤�ɂȂ��Ă����B����c�ł́A�\�A�̃O�����C�R�O����World Union���ǂ��ƌ����A�C�M���X�̃J�h�K���O����Union���܂ޖ��̂ɂ������ƌ��������A���܂肱�����Ȃ������BHull�A 252. �@
11�jWoodward�A 451. �C�M���X�O���Ȃ͂��̃`���[�`���\�z�ɑ��ẮA�C�M���X�͂��Ƃ��ƃt�����X�𐢊E�@�\�̏�C�������Ƃ��邱�ƂƂ��Ă����̂ł���A�A�����J�͌��R�ƁA�\�A�͉B�R�ƃC�M���X�Ăւ̎x����\�����Ă��Ă���̂ł���i���E�@�\�̑�1���c�̂��ƂȂ�Ƃ��������Łj�A�������A�C�M���X�͒�����4�卑�̈�ƔF�߂Ă����o�߂�����̂ŁA����2�̖��Ń`���[�`���̂悤�ȍs�����Ƃ�ƁA�ΊO�I�ɍ���ȗ���Ɋׂ�댯��������ƈӌ����o���Ă���B �@
12�j�I�X�g���[���[�́A�푈�����ɂ�����FDR�̌�����`�ւ̋����X���������Ă���B�uFDR�́A�^��p�̂���2�N���o���Ȃ������ɁA���͌��Ƃ�����E�B���\���I�v������h���点�Đ�㐢�E���\�z����悤�ɂȂ����BFDR�́A���Ǝ匠�̊T�O�Ƃ��ɑ卑�̍��Ǝ匠�����������Ɉ��������͂Ȃ������B���A���X�g�̃E�H���^�[�E���b�v�}����j�R���X�E�X�p�C�N�}���́A���E�̐��_�A���ۖ@�A�V�������`�����E���a�����̃L�[�Ƃ��ď��卑�̌R���I�o�ϓI�x���ɂƂ��đ���ƐM�����E�B���\����`�҂ɓ������Ȃ��������AFDR���ނ�Ɠ��l�̊ϓ_������̕��a���l���Ă����̂ł���v�BOstrower�A 13. �@
13�j���\�E�C�M���X��g�̃T�[�E�X�^�b�t�H�[�h�E�N���b�v�X�́A5�̒n��@�\���咣�����B���[���b�p�A�A�W�A�A�A�����J�A�C�M���X�R�����E�F���X�A�\�A�̏����a���BRoyal Institute�A 435. �@
14�j�������A�ʐ��I�ȉ��߂́A�V���h�̎��̂悤�Ȑ����ł���B�u1944 �N�̃o���J���̕�����10 ���̃p�[�Z���e�[�W�������́A�`���[�`���̎傽��S���A�����ɂ�����\�A�����߂邽�߂ɁA����ꂽ���͌���F�߂邱�Ƃɂ���ăC�M���X�鍑�̗�����ێ����邱�Ƃɂ��邱�Ƃ������Ă����v�BSchild�A 46. �@
15�jZi �́A���̂悤�Ɍ����B�u�ĉp�\��3�卑�́A�卑��v�̌����ł͈�v���Ă����̂ł���A���ꂪ�{���������B������̂́A�������̌����̓K�p���@�ɂ��Ă����������v�BZi�A 51.�@





 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@