
�����b
�@

�y�ؑ��z�ؐ��̐�̂����������̑��B�́A�����ŕ����̖@�߂Ȃǂ�l���Ɏ����Ƃ��ɐU��炵���B���l���o���������������l(�_��́u�V�����ȓ�v�q��ג��ؑ���v����)�B�Љ�̎w���ҁB�@
�y�W���[�i���X�g�zjournalist�@�V���A�G���A�����Ȃǂ̐��E�Ɋւ�L�ҁE�ҏW�ҁE���̑���e�ƂȂǁB�@
�y�L�ҁz/�ʐM��/�W���[�i���X�g/�������L��/�X�|�[�c�L��/�����L��/��\��ދL��/�]�R�L��/�C�O�ʐM�L��/�ԋL��/�T�����L��/�L�҉/�L�Ғc/�L�Ґ�/�L�҃N���u/�@
�yIOJ�zInternational Organization of Journalists ���ۃW���[�i���X�g�@�\�B�@
�yIFJ�zInternational Federation of Journalists ���ۃW���[�i���X�g�A���B�@
�y�V���z(�V�����̗�)�L���ǎ҂Ɏ����Ɋւ���A�������ђm���A��y�A�L���Ȃǂ�`�B���������s���B�@
�y�V���L�ҁz�V���L���̎�ށA���M�A�ҏW�ɏ]������l�B�@
�y�V���L���z�V������Ɍf�ڂ���L���B

�y�O�ʁz�V���ŎЉ�L���������ɍڂ���y�[�W�B�Љ�ʁB�@
�y�L���z/��`/���m/���l�L��/���S�L��/���E(���l)�L��/�L�����/�L����/�L����/�L����(�X�|���T�[)/�L���}��/�L����/�L���r���A���炵�A����D/�L������/�L����/�O�s�L��/�L����/�L���ϗ�/�@
�y�ʐM�z�l�����̈ӎu��m���Ȃǂ𑼐l�ɓ`����B�X�ցA�d�M�A�d�b�Ȃǂ̎�i��p���ď���`�B����B�@
�y�ʐM���z�V���ЁA�G���ЁA�ʐM�ЂȂǂɏ������A���O�e�n�ɔh������Ă��̒n��j���[�X��{�Ђ֒ʒm����l�B
 �@
�@
�y�ʐM�@�ցz�X�ցA�d�M�A�d�b�A�D���X�ցA�����d�M�Ȃǂ̒ʐM����舵���@�ցB�@
�y�ʐM����z��������Ȃ��҂ɒʐM�ɂ���Ĉ��̋���ے��𗚏C�����悤�Ƃ��鋳��g�D�Ɗ����̑��́B�@
�y�ʐM���Ɓz�X�ցA�d�M�A�d�b����舵���Ɩ��B�V���ЁA�G���ЁA�������Ǝғ��Ƀj���[�X����ޒ���Ɩ��B�@
�y�ʐM�Ёz�V���ЁA�G���ЁA�������Ǝ҂ȂǂɁA�j���[�X�����������ЁB�@
�y�ʐM�̔��z���u�n�̏���҂ɒʐM�Œ������Ƃ�A�X���ł��̏��i�������n���̔����@�B�ʔ́B�@
�y�ʐM��z�w�Ɛ��сE�s���̏E���N��ԂȂǂ����t���L�����w�Z����ƒ�ɘA�����邽�߂̏��ށB�@
�y�]�R�z�R�ɏ�������l����n�ւ����ނ����ƁB���m�łȂ��҂��Ȃǂ̂��߂ɌR���ɂ��Đ�n�ɍs���B

�y�ۊہz�閧�Ȃ��ƁB�V���E�G���Ȃǂ̕������B�@
�y��p�E��v�z�V�c�E�{���E���{�Ȃǂ̗p���E���p��������B���͂ɂւ炢���含�̂Ȃ����̂��y�̂��Ă�����B�����u��p�w�ҁv�u��p�V���v�Ȃǐړ���I�ɗp������B�@
�����@���ƂȂ��Ăق߂��₷���ƁB�@
�y����z���̕��B�����ׂ̈ɓ����@�ցB/�V���͓V���̌��킽��/����̗��p/�V���͐��_��`�������/�@
�y���_�z/���_�̎��R(����)/�o�ť�V���̎��R/���_��/���_�E/���_�@��/�@
�y���{�z�V���E�G���E���ЁE�����E�f��E�����E�X�M���Ȃǂ̕\�����e�������I�Ɍ�������B�@
�y�L�����~�z�ƍߑ{����܂��͕K�v�ɉ����Čx�@�E���̋@�ւ��V���E�G���ɋL���̌f�ڂ��֎~����B�@
�y�ǎҁz�V���A�G���A�����Ȃǂ�ǂސl�B��݂āB�@
�y�ǎґw�z����o�ŕ���ǂސl�����̑�����������K�w�B���E�N��E���{�E�E�Ƃ̋��ʐ��Ȃǂōl����B
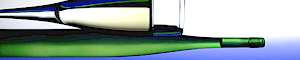 �@
�@
�y�ƊE�z����̎Y�Ƃ⏤�ƂȂǂɏ]������l�X�̎Љ�B���ƎҒ��ԁB�@
�y�ƊE���z����̋ƊE�Ɋւ���L�������V���B�@
�y�ԐV���z�����{�ʂ̖\�I�L���Ȃǂ蕨�ɂ��䂷�肽����������肷��V���B�@
�y�L���z�������������邷���ƁB�������邳�ꂽ�����₻�̕��́B�V����G���ɏ�����鎖���B/�O�ʋL��/�V���L��/����L��/�Ǖ��L��/�����L��/���S�L��/�����L��/�@
�y��ʁz�V���̃g�b�v�L���B�@
�y���z�����̓��e�E�l�q�B�Ɋւ���m���ɕω��������炷���́B�C���t�H���[�V�����B
�u��v�͐l�Ԃ����������ł���B�����̎���ɐX���O���uInformation�v���u��ɕ�s�ׁv�Ƃ��āu���v�Ɩ��̂͂��܂�ɂ��L���B�w�̈ē����u�h���������������������v�ł���A�����̓��{��Ƃ��Ắu���v�����A���ɐl�Ԃ������̂ł���B�z�X�s�^���e�B�ƑɂȂ��Ă�Ɖߓx�ɕ\�����Ă��ǂ����낤�B �@
���܂ł́u���v�͎��́u�f�[�^�v�ƒu��������Ɩ{�������ʂ���B�u�f�[�^�v�������W�Ȃǂƒu�������ē��{��ɂ��Ă��ǂ��B�}�X���f�B�A�ɑ�\�����悤�ɁA���f�B�A�̓f�[�^���^�ԁB���̃f�[�^���W�߁A���͙��g�ɂ��āA�ΊO�I�ɍĔ��M���鎞�A�u���v�ƂȂ�B �@
�����̏�͎��͎����W�̖�ςݒ~�ςł����Ȃ��A�Ĕ��M�ɂ܂�Ŗ��ɗ����Ȃ����Ƃ������B�܂��ɁA�u��ɕv�Ă��Ȃ��̂ł���B�f�[�^�͑����ʂ�����W����āA�Ĕ��M���ꂽ���ɏ��ɂȂ�B�Ĕ��M�̎d�g�݂܂ōl�����āA�����I�Ɂu��v�ł���B
 �@
�@
�y���@�ցz���̎��W�E�Еz�E�����Ȃǂ̊�����S�����鍑�Ƌ@�ցB�A�����J���O���̒�������(CIA)�ȂǁB�@
�y����z�����J����o�c�Ǘ��Ŗc��Ȏ�������K�v�Ƃ������f�������o���Z�p�BIR�B�@
�y���ʁz���̓��̏��ɒʂ��Ă���l�B�@
�y�}�X�R�~���j�P�[�V�����zmass communication�@��O�`�B�B�V���E�G���E�e���r�E���W�I�E�f��Ȃǃ}�X�]���f�B�A��p���ĕs���葽���̑�O�ɏ���`�B�����i�B�}�X�R�~�B�@
�y�}�́z�V���E�d�g�����̓}�X�R�~�}�́B

�y��O�^���z���܂��܂ȊK����K�w�ɑ�����l�X���A����̖ڕW�̂��ƂɌ��W���čs���W�c�I�^���B�@
�y��O�����z������ΏۂƂ��������|�p�̑��́B�����A�y�����A�~���[�W�J���Ȃnj�y���ɏd���������������B�@
�y��O���z���鎖������ʑ�O�̊ԂɍL���䂫�킽��e���܂����̂ɂȂ邱�ƁB��O�̂��̂ɂȂ�B�@
�y��O�ېŁz��O�̕��S�ɂȂ�悤�ȐŁB�����̏��Ȃ���ʑ�O�̕��S�ƂȂ�ŁB����łȂǁB�@
�y��O�G���z��ʑ�O�̋�����S���𒆐S�Ƃ����G���B�@
�y��O�Љ�z�Ȋw�Z�p�����B�����{��`�@�\�Ə��Ǘ����@���i�݁A�l�Ԃ�����ɑ���̑Ώۂł����Ȃ�����I�ȑ��݂Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��悤�ȎЉ�B�@
�y��O�H���z�L�͈͂̐l�ɔ�r�I�����ȐH�������H���B�@
�y��O���z��ʑ�O���������鐫�������Ȃ��Ă��邱�ƁB��ʂ̐l�X���e���݂��o����悤�ȌX���B�@
�y��O�I�z��O�ɒ�R�Ȃ�������鐫���������Ă��邳�܁B�@
�y��O���w�z�����w�ɑ��Ĉ�ʑ�O�̋����ɑi�����̗v��������A��y�I�ǂݕ��Ƃ��č��ꂽ���w�B���㏬���E�ƒ돬���E���[���A�����E�T�㏬��(��������)�ȂǁB��O���|�B�@
�y��O���z���|�A�f��A�����Ȃǂő�O�̋����ɏd�_����������i�B�@
�y��O�H���z���X�̑�O�v���ɍ��v�����т�������Ƃ�g�D���j�B�|�p��������y���Ɏ�̂���������i�B

�y������`�z�n�ʁE�g���̍��ʂȂ������̌l�ɂ���Đ�������Љ�̎������߂�����`�B�M����`�ɑ����Ŗ����Q�O�N�㓿�x�h��ɂ���ď�����ꂽ�B�@
�y�����I�z�n�ʁE�g���̏㉺�ɂƂ���Ȃ��ŋC�y�Ȃ��܁B�����Ɋi����Ȃ��ł������Ȃ��܁B�����I�B�@
�y�А��z�V���A�G���Ȃǂ��A���̎Ђ̐ӔC�ɂ����ĕ\������ӌ���咣�B�@
�y��M�z�V���ЁA�G���ЂȂǂŁA��Ȃ̋L�҂Ƃ��ĎА��E�_���̏d�v�L���̎��M�ɂ�����l�B�@
�y�_���z�V���̎А��B�@
�y�ȐS�`�S�z�����̂����ɐS�����ɓ`���B�@
�y�ĉ��z�݂����������ĕ������s���B
 �@
�@�������̐V��

��������̓��{�́A���m����̐V���Ȓm�̓����ɂ��V���ȃ��f�B�A�ł���V����K�v�Ƃ����B�܂������́A�u��i���ɒǂ����A�ǂ��z���v�Ƃ����傫�ȕ�����A���������L�ł��Ă����B���p�̐V���̈Ⴂ��ʂ��āA���{�̐V�����A���̐�i���̐V����������傫�ȃ}�X���f�B�A�Ƃ��Đ��������w�i�ɂ��čl�������B�@
�����{�̐V���̓��e�̕ϑJ�@
����܂�7��ɕ����āA�����̐V���̓��e�̕ϑJ�����Ă����̂�����ǁA�����ł�����ȒP�ɐU��Ԃ��Ă݂����B�@
���܂��A�C�O�̐V���̖|��E�ҏW�Ƃ��ăX�^�[�g�@
�������b���V�����{�U���A�V���e���@
�������̒m�����[�ւ���V�������}�����@
�����_�V��(�����h�V��VS�����h�V��)�̑S�����@
�����������V���o��O�ʋL����A�ڏ������l�C�Ɂ@
����V���Ə��V�����ڋ߁A�u�s�Εs�}�v�̐V���o��@
�������E���I�푈�Ɨ֓]�@�ŁA�}�X���f�B�A�ɐ����@
���̂悤�ɖ����̖�40�N�ԂŁA���{�̐V���̎p�͑傫���ς���Ă������B�@
���C�M���X�̐V���@
�C�M���X�́A���_�̎��R��ߑ�W���[�i���Y���̐����ɁA�傫�Ȗ������ʂ��������ł���B�@
�O���悤�ɁA�C�M���X�̐V���́A�����⋳��A���ɂ͋c���ɓ����Ȃ���A�u�V���̎��R�v���l�����Ă������B�@
�����ăC�M���X�̐V���́A���݂ł��������Ƒ�O���ɕ�����Ă���_���A���{�Ƒ傫���Ⴂ�A���s�������Ⴄ�B�@
��O���u�U�E�T���v310����/�������u�^�C���Y�v60����/�������u�t�@�C�i���V�����E�^�C���Y�v12����(���E�ł�43����)�@
�u�ǔ��V���v1002����/�u�����V���v802�����@
���l�@�@
���Ă����ŁA�Ȃ��C�M���X�̐V���́A���݂��������Ƒ�O���ɕ�����Ă���̂ɁA���{�ł͂��Ă̑�V���Ə��V���̋�ʂ��Ȃ��Ȃ蓯���ǎґw��Ώۂɂ��鋐��ȐV���ɂȂ��Ă������̂��ɂ��čl�������B�@
�悭�A�C�M���X�͊K���Љ����A�������Ƒ�O���ɕ�����Ă��āA����ɑ��ē��{�́A�ꉭ�������̍������番����Ă��Ȃ��̂��Ƃ��������A���������Ȃ̂��낤�Ǝv���Ă����B�@
�������A���{�̐V���̗��j�ׂĂ݂�ƁA���ꂾ���ł͕\�ʓI�Ȑ����ɂ����Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ�����ۂ��������B�@
(1)�����J���@
���{���C�M���X���A�V����������_���Ă������Ƃ�A�f�ՂȂǂ̌o�Ϗ����f�ڂ��Ă������ƁA��O�����ɂ̓S�V�b�v�Ȃǂ��D�܂ꂽ���Ƃ͓����Ȃ̂����A�傫���Ⴄ�_������B�@
����͓��{�̐V�����A��300�N�̍�������ڊo�߂������̓��{�l�ɁA�������X�Ɠ������ꂽ�V���ȋZ�p��Љ�x���킩��₷��������A�V�������m�I�ȍ�����`�I���l�ς╶���A�܂�V�����m�̑̌n�ɑΉ�����̂ɖ𗧂��f�B�A�������A�Ƃ������Ƃ��B�@
�������{�́A�����J�������͂ɐ����i�߂��B�@
���̂��߂ɂ́A�ߑ�I�ȉ��l��(�ΕׁA�q���A�K���Ȃ�)�ɓ��Ă��炢�A�����ӎ��������Ă��炤�K�v���������B�@
�����ւȂǂ̖�ȍs�ׂ��֎~���A�u���ԁv�̊ϔO���Ɏ������݁A�j���ɂ͍������f�g�������B�@
����́A���N�ɂ킽�鋤���̓I�Ȑ����������A���ꂩ�炭�������悤�Ȃ��̂������B�@
���z��̓����ɍ������A�d��̓o�e�����̎�p���Ƃ��т��A�����J���ɂ���Ăӂ��߂������ɂ́A���v�̓ǂݕ���D�Ԃ̏�肩�����Ă��˂��ɉ�������V�����A�M�d�ȏ�������B�@
�����Ȃ�A�����Ń��C�t�n�b�N�B�@
��������́A�m�̑̌n���ς�������炱���A�l�X���[�ւ���V�������f�B�A�ł���V�����K�v�Ƃ��ꂽ�B�@
�u(����������)�V���w�ǎ҂̐�ΐ��͏��Ȃ��������A�����͐V������ɂ��Ă݂����琶���v�V���͂���C�m�x�[�^�[�ł���A���̏���V����ǂ܂ʐl�X�ɂ�����I�s�j�I�����[�_�[�������v(�R�{�������u�V���Ɩ��O�v���)�@
�V�������{�l�́A�������ǂ߂Ȃ�������Ȃ������B�@
�w�₪���邩�Ȃ������l�Ԃ�}�郂�m�T�V�ƂȂ�A�Ȋw�I�A�����I�Ȓm������A��l/�q���̏��t�]�����B�@
����܂ő���Ă������w�̒m����ߋ��̑̌������ł́A�D�Ԃ̎d�g�݂⑾�z����������̂ɂ͏\���ł͂Ȃ��������炾�B�@
�����ŁA����̓��{�ɂ��čl���Ă݂悤�B�@
1990�N�ケ��܂ł́A���̑̐��Ƃ���Ȃ�ɘA����������������ǁA�O���[�o���[�[�V�������i�݁A�Y�ƍ\�����ω����A�I�g�ٗp��������Ă������߁A���đg�D�l�ԂƂ��Ă���Ă����l�̐����̌��́A�ʗp���Ȃ��Ȃ��Ă���B�@
�����āA�e�N�m���W�[�A���ɏ��ʐM���삪���I�ɐi���������߁A�N��������Ƃ��������ł́A�d���Ȃ��Ȃ��Ă���B���ʐM�Ɍ����Ă����A�N���҂Ǝ�҂̏���͋t�]�����Ƃ����Ă悢�B�@
�������͑��_�ł����āA70�˂��߂��Ă��Ă��A�u���O��c�C�b�^�[�Ȃǂ��g�����Ȃ��Ă�����͂������邩��A���m�ɂ����ƁA�����̉ߋ��̑̌���ƊE�̊��s�ɂ����݂��A�V�����m�����z������w�͂�ӂ����l�́A���c�����Ƃ������Ƃ��B�@
(2)�ǂ����A�ǂ��z���I�@
�����E���I�푈��ʂ��āA�V���͏����ɂ܂ōL�܂����B���I�푈��́A�u��d���_�v�������t�ɁA�����S�������łɑς����B�@
���������Ƃ��ƍ]�ˎ���ɂ́A�u���{�v�Ƃ����ӎ��͊������B�]�˂̏����ɂƂ��āu���v�Ƃ����A�����̍��Ƃ��A�����̍��Ƃ��A�����̌̋��̂��Ƃ������B�@
���ꂪ�����ɂȂ��āA�}���ɋߑ㉻�𐄂��i�ߗɑR���邽�߂ɁA�������{�́A�݂�Ȃň�v�c�������̂��߂ɐs�������Ƃ����߁A�u�����v�ӎ��̌`�����d�������B�@
�撣���āA��i���̒��ԓ�����͂����̂��I�Ƃ����C�������@
�u�����J���v�u�x�������v�u��d���_�v�u�~������܂���A���܂ł́v�u��㕜���v�u�����{���v�ȂǂƂ������X���[�K���ݏo�����B�@
����Ԃ܂Ƃ߂�ƁA�u�ǂ����A�ǂ��z���I�v�ɐs����B�@
�܂�A��i���ɕK���ł��������߂ɁA�S��������ۂƂȂ�K�v���������B�@
����͂܂�A���{���㔭���������A�Ƃ������Ƃł���B�@
�u��������ۂƂȂ��Ċ撣���āA��i���ɒǂ����v�Ƃ����u�傫�ȕ���v�����L���Ă������炱���A�}�X��ΏۂƂ����}�X���f�B�A�����������B�@
�����Đ��{�́A�����𖡕��ɂ��āA�v���p�K���_�ƃ��f�B�A�K���ɑ������B�@
�����̐��{����������Ƃ́A�s���̈������_���邽�߂����łȂ��A�����̌����̗��v�ɉ������̂ł͂������B�u�l���v�́A�傫�Ȗ��ł͂Ȃ������B�@
��������́A�����̗��v�⍑�v�Ƃ͉������A�͂����肵�Ă����B�����č����̑����A���ʂ̔\�͂ƋΕׂ��Ɛ��ӂ�����A�ړI�̂��߂ɍv���ł����B�@
����������A�u�傫�ȕ���v�͕��Ă��܂����B���{�͐�i���ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA��������{�ɂ��ׂ����͂����肵�Ȃ��B�@
�A�����J�^�̎��R�ȎЉ��ڎw���̂��A�X�E�F�[�f���^�̕������Ƃ�ڎw���̂��A�ǂ�����\���B(���s�\���ǂ����́A�܂��ʂ̘b������ǁE�E�E)�@
�܂��A�Ȋw�Z�p�Ő��E���ڎw���̂��ۂ��A�I�����s�b�N�ŋ����_�����Ƃ邱�Ƃ�ڕW�ɂ���̂��A���w�Z�̑ϐk���H���̗D�揇�ʂ͍����̂��Ⴂ�̂��A�����͂��܂��܂��B�@
���Ƃ��āA�ǂ��܂ł��ׂ��������m�ł͂Ȃ��B�@
��i��������{�Ƃ��Ă�������͖ڕW���͂����肵�Ă����̂ɁA���ł͍��Ƃ��Ă��ׂ����Ƃ����Ȃ̂����A�����Ă��Ȃ��B�@
��������ƁA�X���[�K���łЂƂɂȂ��Đi�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�@
���ẮA���Ƃɑ��Ĕ��Έӌ���\������͈̂ꕔ�̕��w�҂�Љ��`�҂ł���������ǁA���ł͈�l�ЂƂ肪����Ȃ�ɍl���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�@
��������͋��炪���y���A���������f�B�A(�V��)�ɒǂ����āA�V�����ǂ܂��悤�ɂȂ����B���͋��琅��������ɏオ���āA�}�X���f�B�A���l�X�ɒǂ��z����Ă���B�@
�u�ǂ����A�ǂ��z���I�v�Ƃ��������S�������L�ł���傫�ȕ��ꂪ�������Ƃ́A�]���^�̃}�X���f�B�A�̈ێ��������ɂȂ������Ƃ��Ӗ�����B�@
�����Ċe�����A�����̐��E�ς̂Ȃ��ŁA���܂��܂Ȏ����̈Ӗ��t����~���Ă���B����ɓ����邱�Ƃ́A�}�X���f�B�A�ɂ͓���B�@
(3)�Z�p�v�V�@
�O�X��̋L���ŁA�֓]�@�̓o��Ƃ����Z�p�v�V�ŁA�V���Ђ͎��{�͂��K�v�ƂȂ�A�c����ƂƂ��Ĕ��W���A�����ē����E���I�̗��푈���A�V�����}�X���f�B�A�ɕς����Ə������B�@
�����ĐV���̌˕ʔz�B���x���A�}�X���f�B�A�Ƃ��Ă̒n�ʂ����łȂ��̂Ƃ����B�@
���������̔w�i�ɂ́A���(1)��(2)�Ō��Ă����悤�ɁA���{���㔭���ł������Ƃ������Ƃ̓��ꐫ���������ƍl������B�@
���āA�����ŋZ�p�v�V�ɂ��čl���Ă݂悤�B�@
��������́A���ʐM�Z�p�̔��B(�d��)���e�n�ɋL�҂�h�����āA�L�����W�߂邱�Ƃ��\�ɂ����B�@
�܂��A����Z�p�̐i��(�֓]�@)���X�P�[�������b�g�ݏo���A�}�X���f�B�A�ݏo�������֍�p�����B�@
���������ł́A�C���^�[�l�b�g�̕��y�ŁA�S�Ă��t�̃x�N�g���Ɍ������Ă���B�@
�܂�A�����g��Ȃ��Ă��悭�Ȃ�A�}�X���f�B�A�ɏ������Ȃ��Ă��A���ړ����҂��A���̂�����M�ł���悤�ɂȂ����B�@
���܂Ƃ߁@
����̓��{�͐�i���̒��ԓ�����͂����A�u�ǂ����A�ǂ��z���I�v�Ƃ��������S�Ă����L�ł���ڕW��r�������B�@
�܂��A�C���^�[�l�b�g�����y���A�O���[�o�����ƎY�ƍ\���̕ω���������A�I�g�ٗp���x�A�N�����x��������}�������ƂŁA�ߋ��̐����̌����ʗp���Â炭�Ȃ��Ă���B�@
���̎���ɁA�]���^�̃}�X���f�B�A�̒n�ʂ��ቺ���A�V���ȃ��f�B�A(���C���^�[�l�b�g)���x������̂́A���R�̋A���Ƃ�����B �@

�����̐V���L�҂��w���A�u�Љ�̖ؑ��v�Ɓu�H�D�S���v�Ƃ���2�̌��t������B �u�Љ�̖ؑ��v�Ƃ́A���Ɍx����炵�A�Љ�𐳂��������ɓ����Ƃ����Ӗ��B ����A�u�H�D�S���v�́A���h�Ȑg�Ȃ�����āA�����E���̂��������Ă͋��i�������グ��S���c�L�Ƃ����Ӗ��B�@
���̂悤�ɁA�S�������̌��t���g��ꂽ�V���L�҂Ƃ́A�ǂ����������݂������̂��낤���B�@
���Љ�̖ؑ��@
���Ƃ��Ɓu�ؑ��v�Ƃ́A�u�����Ŗ@�߂Ȃǂ�l���Ɏ����Ƃ��ɖ炵����(��̕������ؐ�)�v���w���B�@
�u�_��v�̒��ɁA�����V���𑱂���E�q��s�ɁA�����̑��̖�l���A�u���ꂽ�����悤�ɁA�V�͎t��ؑ��Ƃ��ĉ����ꂽ�̂ł��v�A�Ƃ˂�������Ƃ����G�s�\�[�h������B�@
�E�q���u�ؑ��v�ɂ��Ƃ������Ƃ���A�u�ؑ��v�́A�l�X���[�ւ����������Ƃ����Ӗ��Ŏg����悤�ɂȂ����B�@
���āA���������ɂ����ꂽ�A��������ɘ_������V���̋L�҂́A�����b�ō������{�ƍ��ۓI�Ȋ��o����������ނ����������B�@
���n���s(����Y)�A�������k�A�I�{���_(���傤��)�Ȃǂ��A���̑�\�ł���B�@
�Ȃ��A���V���̐V���L�҂ƂȂ������̂́A�������]�ˎ���̋Y��҂������B�@
��ɁA�u���V�^�����v�Ƃ����V����n�������C�M���X�l�u���b�N�́A���̎����̂��Ƃ����̂悤�ɉ�z���Ă���B�@
�u�Љ�̕ϊv�����Ǝ҂Ƃ��Ď��c�������{�̂���l�X�̂Ȃ��ɁA�v�z�L���Ȓm���������Ă��邱�Ƃ��A�Ԃ��Ȃ����炩�ɂȂ����v�@
�����ېV�́A�������W�c����̂��A�l�ނ𗬓����������B�@
�m���͂��������Ɏ��Ƃ��A�����͐����ɍ�����������ǁA���̒��ō˔\�Ƃ��C�̂���l�X�́A����̏��^����ꂽ�B�@
�V�������������Y�Ƃł���V���̃X�^�[�g�A�b�v�����x�����̂́A�����̐l�X�ł������B�@
�������{�ւ̔���������ɂ͂������Ƃ��Ă��A�����̐V���L�҂����́A�V�����Ƃ�_���A���ǂ����A���_�������Ƃ�ڎw�����B�@
�ނ�̔M�ӂ́A�V���Ƌ����̈ӎ����������Ƃ�ǎ҂���āA�M�Ў����œ��������L�҂ɑ��āA����̌��t���������A�J���p���s����悤�ɂ��Ȃ����B�@
�������̂���̓ǎ҂̓��e�ɂ́A�u�ؑ��v�u���ځv�ƐV���L�҂��^���A�x��������̂�������B�@
�������A���̌�̐��{�̐V���e������_��A�����ĐV���̉c����Ƃւ̓]���ŁA�����������^�C�v�̋L�҂͏��Ȃ��Ȃ��Ă������B�@
���H�D�S���@
�����O���̐V���̎G��(�Љ�L��)�́A�V���L�҂����ڎ�ނ��Ȃ��������̂����������B�@
���̃V���[�Y�̑�1��ł́A�����Ƃ̓��e�������̐V�����ʂ̂��Ȃ���߂Ă������ƂɐG�ꂽ�B����ȊO�ɂ��A�u�T�K���v�Ə̂�����̂��A���ʼn\�b�������A���ɂ��������Ђɖ߂��ĎЈ��ɘb���A������L���ɂ���Ƃ����P�[�X���������B�@
�����̐V���Ђ́A�O���̎�ނ��s�����̂悤�ȒT�K���𑽐��������Ă����B�@
�V���L�҂́A�T�K�����W�߂Ă����V����̒�����L���ɂȂ肻���Ȃ��̂�I�сA���C�A�E�g�����߁A�L�����������B�@
�����́A�u�`�Ƃ����\�v�Ƃ��A�u�`�Ƃ����b�v�Ƃ������`�ŋL���ɂȂ����B�@
�T�K���́A���ӂ̂��̂������A�����s���m�ł��������߁A��������̐V���ɂ́A�����L������������イ�łĂ����B�@
�����āA�T�K���́A�v���m���A���������A�V���̔���q�ȂǁA�������킵���҂����āA��ނ̏�Ŗ����N�������Ƃ������������B�@
�����Ƃ��A�T�K������ꗬ�̃W���[�i���X�g�ɂȂ������̂������B�������w�Z���̏���V���́A�X�����X�⎄���A�ȂǎЉ�̒�ӂ���ނ��A����ꗬ�̎Љ�L�҂ƕ]���ꂽ�B�@
���̂悤�ȒT�K���́A�吳����ɂ͂����āA�V���̎Љ�̒n�ʂ��オ��ƁA�����Ă������B�@
�u�����V��v�ł́A1882�N(����15�N)���납��A�L�Ҏ��g�������̑��Ńl�^���W�߂Ă���悤�������A�L���̊m�����͍��܂����B�@
�u���������V���v�́A�Ėڟ����Ј��Ƃ��Č}����1907�N(����40�N)����ɁA�Î�̒T�K�������ق��A����ɁA�呲�̎��������E�x�@�Ȃǂɔz�u�����B�@
�Ƃ���ʼnH�D�S���Ƃ́A�`���������悤�ɁA��������̐V���L�҂��A�H�D�𒅂ė��h�Ȑg�Ȃ�����āA���`�̖����̂悤�ɂӂ�܂��A�����E���̂��������Ă͋��i�������グ�����Ƃ������ꂽ�����ȁB�@
���ł����C���e���E���N�U�Ƃ����������Ȃ̂��낤�B�@
�O�ʋL�����l�C�ƂȂ�������ɂ́A�ؑ�������⍋���Ȃǂ̃X�L�����_�����A�����̍ޗ��ɂ���V���L�҂��������悤�ɂȂ����B�@
�u�ǔ��V���v���o���Ă������A�Ђł́A1876�N(����9�N)�Ɏ��̂悤�ȎЍ����f����قǂł������B�@
�u�߂��됳�Y�̖����������āA���O�̉Ƃ�_�߂ĐV���ɏo������i������������́A���͗��������ȂǂŁA��ؓc��������݂��́A��������͐��Y����ؓc���Ƃ����ĕ������̂�����l�q���ƁA���ӂ̐l����C�����Ă���܂������A���Ђł͐r�����f�������܂��v�@
��ؓc���Y�́A�ǔ��V���̏���ҏW���̖��O�B�@
�ҏW���̖����������āA�L�����l�^�ɂ����������s���Ă����قǁA�l�X�̐������V���L���ɂȂ��Ă������Ƃ��킩��B�@
�܂��A�������������\�s�ׂ��s���Ă����Ƃ������Ƃ́A�V���L�҂��������s�����˂Ȃ����݂ƌ����Ă������Ƃ���������B�@
���ہA��L�̒T�K����Љ�ʒS���L�҂��A�������������X���s�ׂ��s���āA�V���L���ɂȂ邱�Ƃ��A�����������B�@
1901�N(����34�N)�ɋ{���[�������s�����u���m�V���v�́A�u�����̎��d�A�V�����̂䂷��A���\�L�����̃C�J�T�}��i�v��E�����A�l�C�����B�@
�Ȃ��A�{���͎�������ŋL���ɂ������߁A���_�ʑ��A�c�ƖW�Q�ȂǂŋN�i���ꂽ���A�ٔ��̉ߒ��Ń��C�����������炩�ɂȂ����B�@
���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�V���́u�V�����v�Ă�肳��A�L�҂͉Ƃ����Ƃ��ɐE�Ƃ��B������A���h�Ɂu�����V���L�ҁv�ł͂Ȃ��A�u�����鍑��w���o�ϊw�m�v�Ə������Ƃ��������悤�ł���B�@
���`�����@
����30�N�ɔ����q�ő�Ђ��N�������B���݂Ȃ�d�Ԃł��������鋗�������A��������ɂ͉��u�n�Ƃ����F���������炵���A��ނ��Ă����ɋL���������͍̂�������B�@
���̎������̂��A�`�����I�@
���ʐM��ꍆ�𑗂����̂́A���������̒T�K�L�҉͖쌺���B�@
�Ȍ�A����E���ɂ�����܂ŁA�`�����͐V���Ђ̒ʐM��i�Ƃ��āA�����B�@
���܂Ƃ߁@
��������̐V���L�҂́A�u�Љ�̖ؑ��v�Ƃ��u�H�D�S���v�Ƃ��Ă��A���r�o�����c�ȑ��݂������B�@
�����ېV�́A�l�X�����������D���A�l�ނ𗬓����������B�@
�m���͂��������Ɏ��Ƃ��A�����͐����ɍ�����������ǁA���̒��Ŕ\�͂Ƃ��C�̂���l�X�́A����̏��^�����A��V���Ŗ����L�҂Ƃ��Ė���y�����B�@
�Y��҂Ȃǂ́A���V���̐V���L�҂ƂȂ�A���P�����I�ȋL����\�I�L�����������B�@
����A�v���҂������A�T�K���ȂǂɂȂ�A���Ńl�^�����s�����B�@
�V�������������Y�Ƃł���V���̃X�^�[�g�A�b�v�����x�����̂́A�����̐l�X�ł������B �@

���R�������ɐ��{��ᔻ�����V���ɑ��āA���{�͒e�����邾���łȂ��A���t�@������^������A�L�҂ɖ�l�|�X�g��^�����肷��ȂǁA�V�����_��ɂƂ߂��B �V���̏��`�B�͂ɒ��ڂ����������{�ⓖ���̗L�͐����Ƃ́A�V���Ђ���ѐV���L�҂ɂ������āA���܂��܂ȓ����������s�����B�@
���V���o�c�ւ̉���@
����4�N5���A�����ېV�̗����҂������،ˍF��́A�������{�̎{��̓O��Ɛl�S�̌[����ڎw���āA�u�V���G���v�s�������B�@
���̐V���́A����8�N1���Ɂu�����ڂ́v�A���N6���ɂ́u�������V���v�ƂȂ�A�،˂����{�𗣂�Ă���́A���{��ᔻ���閯���h�V���ƂȂ����B�@
�܂����{�̗X���x�̊�b���m�������O�����́A�V���̔��W�������邽�߂ɁA1871�N(����4�N)12���ɐV���G���̒ᗿ���B�̓����J�����B�@
���̗��N6���ɂ́A����o�Ŏ҂����U���A���c���E�q��Ɂu�X�֕�m�V���v(�̂��́u��m�V���v)��n���������B�@
�ނ́A�ȑO�������悤�ɁA1873�N(����6�N)�ɂ́A�L���̎��W�����₷�����邽�߁A�����Ƃ̌��e���ő����悤�ɂ������B�@
���{�́A��p�V������邾���łȂ��A����J�݂����ԗL�͐V���̎�荞�݂��s�����B�@
�u����c�@�ݗ��������v���X�N�[�v�����s���ȁu���V�^�����v�ɑ��ẮA1875�N(����7�N)�ɐV���o�c����{�l�ɏ��邱�Ƃ������ɁA�Ў�u���b�N�����ږ�Ɍق����B�@
�����āA�@���ŐV���̎�����͓����l�Ɍ���Ƃ������Ƃ����߂�ƁA�����Ƀu���b�N�����ق����B�@
�u���b�N���A�O���l�Ƃ��Ă̓������������Ď��R�Ȍ��_��W�J���Ă������Ƃ��A��قǐ������˂��悤���B�@
��҂ł������،˂̎���o�c���������Ă����u���V���v�ɂ́A���{�������]���u���{���ɕt������A�x������v�ƗU�����B�@
�u���V���v�͐��{���ɕς��A�����̐V���L�҂���Ђ��������Ē���V���ɓ��ꂽ�B�@
���������{�����̖̂ɂ������߁A�Ăє����{�ɖ߂������A�ǎ҂͗���Ă������B�@
�����Ԃ���肩�������A���ꂾ���V���̌��_�ɑ��āA�_�o���点�Ă����̂��낤�B�@
���̂悤�ɁA�V������ʉ��B�̎�i�Ƃ݂����{�́A�V���ځE�ԐڂɎx�����������łȂ��A�V���o�c�ɂ���������B�@
�����_��@
���R�����^��������ɂȂ�ƁA�����̑�V���������{�n�ƂȂ��āA���{�ɏ��˂����B�Ƃ��ς₵�����{�́A���_�e�����s���Ɠ����ɉ��_��ɏo���B�@
���_��ɂ��ẮA���܂܂ŏڂ����q�ׂȂ������̂ŁA�����ŐG��Ă����B�@
(1)�_�ޏ��̊O�V���@
���R�����^�������ނ��邫��������������̂́A�u�_�ޏ��̊O�V���v�ł���ƌ����Ă���B�@
����15�N�A���R�}���ٔ_�ޏ��ƁA���R�}���̌㓡�ۓ�Y���A�˔@�O�V�����߂����A���̎��������{����o���ꂽ(���]�̈����ɂ��A�O���������㓡����Y�ɒ��ꂽ)�̂ł͂Ȃ����ƁA�L�͓}�������������B�@
�ނ�ɂ��Ă݂�ƁA���{�̗U�f�ɂ̂�ȂǁA�����ƂƂ��Ă͋������������̂ł������B�@
�����āA���R�}�ƑΗ�������i�}�n�́u�������l�����V���v���A�_�O�V�����L���ɂ������Ƃ������āA���̎����͓}���R���ɔ��W���A���ǐ����̓}�����}���痣�ꂽ�B�@
���ꂾ���łȂ��A���̎����Ɠ}���R���́A�����h�n�V���̓ǎ҂ɁA�V����}�ɑ��ĕs�M�������������錋�ʂɂ��Ȃ������B�@
�����h�̃C���[�W�ቺ�ɂ��A�e�V���͐��}�F�̕��@���͂���A�����^����S���Ă����u����V���v���A1883�N(����16�N)�Ɂu�s�Εs�}�v��錾�����B�@
���L�҂����l�ւ̓]�g�@
1883�N(����16�N)�̐V�������̉�������A�������{�͌��������_�e�����s�����B�@
�������A���ꂾ���ł͏\���ł͂Ȃ��Ƃ݂����{���́A�����h�L�҂ɖ�l�|�X�g��^���A���͑��ɓ]�g�������B�����̐V���L�҂̎Љ�I�n�ʂ͒Ⴉ�������߁A��l�ւ̓]�g�͖��͓I�ł������B�@
1885�N(����18�N)�̐V���ɂ́A42���̋��V���L�҂���l�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����e�̌`�Ōf�ڂ��ꂽ�B��ȗ���E���Ă݂悤�B�@
���������]�@�@ �����S�����g�@�@�@���R�V���ҁ@
�v�ۓc�ш�@�@ �������发�L���@ ���������V���@
�V��@�@�@�@�@ �Q�c�@�Z����@�@�@������Ё@
�������p���Y�@�O�����L���@�@�@�@ �]�_�V���Ё@
���@�h�@�@�@�@�@�@�V�×����@�@�@�@�@�@�哌����Ё@
���̂悤�ɁA�V���L�҂̂��������͑��ւ̓]�g�ŁA�����h�̃C���[�W�͒ቺ�����B�@
�������@
�o�c���X���Ă����u���������V���v�́A1891�N(����24�N)�Ɉɓ������̕��S�ł���A�M���@�c���ł��������ɓ����㎡���A�ɓ��ƈ��]�ɓ��������Ĕ��������B�@
�Ȍ�A�u���������V���v�͐��{�i��̘_�w�����B�������ǎ҂̐M�p�������A�ŏI�I�ɂ́A��㖈���V���ɔ�������邱�ƂƂȂ����B�@
�����t�@����@
�u���������V���v�������ɓ����㎡�́A��ɓ����t�ł͓��t���L�����ɏA�C���A���f�B�A�헪��S�����B�@
�ނ́A�o�c�̋ꂵ�������u��㒩���V���v�ɁA����15�N5������18�N4���܂ŁA���z500�~�̕⏕���Ђ����ɗ^���A���{���̒��s�����B500�~�́A���݂̉ݕ����l�ł�1000���~���x�ɂȂ�B�@
�⏕���n�܂��������́A���R�}��肾�����u��㒩���V���v���u�s�Εs�}�v�錾���s�����O�ł���B�Ȍケ�̐V���́A�����������Ȃ���A����ōI���ɐ��{���x�������B�@
���������ɁA�u���������V���v�ɂ͌��z950�~�A�u�哌�V���v�ɂ͌��z600�~���x�����ꂽ�B�@
�Ȃ��ɓ����㎡�́A�O���ʐM�Ѓ��C�^�[�ɂ��A����500�~���@����Ƃ��ēn���Ă����B�@
�܂��A��㹓삪���s����u���{�v�́A��㹓�̎v�z�ɋ������߉q�������玑���������Ă����B�@
�������A���ꂪ�ǂ̒��x�A����ł̎咣�ɉe�������̂��͂킩��Ȃ��B�@
����A�쒆�L�������A�����̕]�_�Ƃɓ��t���[��(�@����)���琔�S���~��͂��Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ������A�����悤�Ȃ��Ƃ́A�������ォ��s���Ă������ƂɂȂ�B �@

��������͌���ƈقȂ�A���E�ƃW���[�i���Y���̗����̐��E�ɁA�����ɏ������Ă����l�������B�@
���V���L�҂���c���ց@
1890�N(����23�N)�ɍs��ꂽ��1�I���ł́A�V���L�ҏo�g�̎҂�V���o�c�ɂ���������18�����I�o����Ă���B�@
���̂Ƃ��I�o���ꂽ�c����300�l�Ȃ̂ŁA���̂���6����V���W�҂���߂����ƂɂȂ�B�@
��ȐV���W�҂́A�ȉ��̒ʂ�B�@
���c�O�Y�@�u�����V���v�o�c�ҁ@
���c���c�@�u�ǔ��V���v�@
���{�@�B�@ �u����V���v�@
����s�Y�@�u����V���v�@
�ց@���F�@ �u���������V���v�@
���̌���A�V���L�҂��琭���Ƃ֓]�g����P�[�X�͑��������B�@
���h�́A�X�֕�m�V���Ђ����߂����ƁA�O���Ȃɓ���A�ޔC��1898�N�ɑ�㖈���V���̎В��ƂȂ����B1902�N�ɏO�c�@�c���ɏ����I�B1918�N(�吳7�N)�ɎɏA�C�����B�@
�����́A��l�����߂���A�ٌ�m�Ƃ��Ċ��A1882�N(����15�N)�ɂ͎��R�}�̋c���ƂȂ�A���R�V���̊����ɏA�C�B���̌�O�c�@�c���ɓ��I���A�O�c�@�c�����Ƃ߂��B�@
�呠��b�A����فA���C�������������́A���������V���̊O�M�L���Ɋւ���Ă����B�@
���푾�Y�̏����E���������́A�O�H�{�Е��x�z�l�̒n�ʂ��犯�E�A���E�֓���A�O�����Ƃ߂�ȂNJ��邩�����A���������V���̎В������߂Ă���B�@
�ނ�́A�L�ҁA�o�c�҂Ƃ��Ă��傫�Ȏ��т������A�����ƂƂ��Ă��d�v�Ȏd�����Ȃ��������B�@
���̎���̐V���L�҂́A�����Ɨ\���R�ł���A�L�҂Ƃ��Đ������邱�Ƃ́A�����Ƃւ̓o����ł������Ƃ�����B�@
�����c�O�Y�̐��������ƐV���L�����y�[���@
�����ł́A��������ɁA�����ƌ��W���[�i���X�g�Ƃ��Ċ����l���̑�\�Ƃ��āA���c�O�Y�ɂ��Č��Ă��������B�@
���c�O�Y�́A1874�N�A�u���l�����V���v�̎�M�ƂȂ�A���N��l�ƂȂ邪�A�����\�l�N�̐��ςő�G�d�M�h�Ƃ��ė@�|�Ɗ��ƂȂ�A�u���l�����V���v�ɍĂѓ��Ђ����B�@
�܂��A��1��O�c�@�I���ɓ��I���Ĉȗ��A�A��14�I���A�O�c�@�c�������߂��B�@
�ނ́A1894�N(����27�N)����1908�N(����41�N)�܂ŁA�����V���В����Ƃ߁A���������̂����܂ɘ_�����������B�@
�����V���ł́A���̎����ɁA�p���^���A�����z�Ŕ�Q�ҋ~�ω^���A�����Ƃ̕s���Ȃǂɂ��ăL�����y�[����W�J�������A����͓��c�O�Y�̐����ƂƂ��Ă̊����ƒ��ڂ�������Ă���B�@
���c�́A����̐���������₤�ړI�ŁA���f�B�A�Ƃ��Ă̖����V������g���āA���_�`����_�����B�@
���������ƐV������ł̎咣���A���c�̗��ւł������B�@
�������A�����̎Љ���L�����y�[���́A�ǎҊl���ɂ͌��т����A���ǁu��m�V���v�ɐg���肷�邱�ƂɂȂ����B�@
���l�@�@
�O��́A�V���L�҂����l�ɂȂ����P�[�X���Ƃ肠���A����͐V���L�҂��琭���ƂɂȂ����P�[�X���Ƃ肠�����B�@
�����̗Ⴉ��A��������́A�V���L�ҁA��l�A�����Ƃ̊Ԃ̊_�����Ⴉ�������Ƃ��킩��B�@
���ςŎ��r���������Ƃ�ސE������l���A�V���ƊE�Ŋ��A�Ăѐ��E�ɕԂ�炭�Ƃ�����͑����B�܂��A�����Ƃ��l�ł���Ȃ���A�V������ŕM���ӂ������A�V���̌o�c�ɂ�����������l�������B�@
����ł��A�V���Џo�g�̋c���͂��邯��ǁA�L���X�^�[���܂ރe���r�W�҂�^�����g�E�|�l�o�g�̋c���̂ق��������悤���B�@
�D�ꂽ�����������A���_�l�Ƃ��ĕ]�����ꂽ�l�������ƂɂȂ����Ƃ������́A�m���x�����ē��I�����Ƃ����\�����K�Ɏv����B�@
�������Ă݂Ă����ƁA���Ă͑啨�L�҂������A��z�������_�l�������ƂɂȂ����̂ɁA����ł͐V���L�҂����������Ă���Ƃ������_���o�������Ȃ邪�A���̈Ⴂ���l����K�v�����邾�낤�B�@
�܂��A��������͐l�ނ������I�ŁA�����Ƃ�������Ă����B����������ł́A�V���L�҂������������Ƃ��֎~����Ă���B���̂��߁A���c�O�Y�̂悤�Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�@
�܂��A����̓��{�̐V���L�҂́A���ۖʂ̋L���������ƁA�����L�����������Ƃ����Ȃ����߁A�Г��ł̏o�������ɏ��������āA�_���ψ��ɂł��Ȃ�Ȃ�����A���_�l�Ƃ��č����]���������͓̂���悤�Ɏv����B�@
�������A�L�҂̃T�����[�}�����́A�Ȃɂ����ɂȂ��Ă͂��܂����킯�ł͂Ȃ��B�@
���łɖ�������̖����ɂ́A�V���L�҂̃T�����[�}�������w�E����Ă���B �@

��������͌���ƈقȂ�A���E���邢�͊��E�A�W���[�i���Y���̐��E�ɁA�����ɏ������Ă����D�ꂽ���_�l������ �B���������������ɂ́A�V���̓X�^�[�L�҂̌l�I�\�͂ł͂Ȃ��A�g�D�͂ŏ�������悤�ɂȂ�A�L�҂̃T�����[�}�������i�B�@
���V���L�҂̃T�����[�}�����@
�����O���̋L�҂́A���̃V���[�Y��1��ڂŏ������悤�ɁA�ǎ҂���A�����ƂƂȂ�A����ɐV���L�҂ƂȂ���̂����������B�@
�V�������A���ʂ߂邽�߂ɓ����Ƃ��ɂ��A�\���Ȍf�ڗ����Ă����B�����Ƃ́A�L�҂̋������ł��������B�@
�����āA�V���L�҂͒��r�̗p�����ʂŁA�e����n��������Ƃ����������B����̉��Ă̂悤�ɁA�D�G�ȋL�҂قǁA�����̐V���Ђł̋Ζ��o�����������̂ł���B�@
���Ƃ��A�V�����ւ̔ᔻ�L���ŋŌY�����������L�S���́A�u���V���v����u����V���v�ֈڐЂ����B�@
�܂��A���R�����^���̎w���҂������A�؎}���́A�u�X�֕�m�V���v�ւ̓����œ������ꂽ���ƁA�u���R�V���v��u�y�z�V���v�̕ҏW�Ɍg������B�@
(�����Ƃ��������㔼�܂ł́A�V���Ђ̌o�c�����肵�Ă��炸�A�p���Ƒn�����J��Ԃ��Ă����Ƃ������������B�܂��A�Ў傪�ւ���ĕҏW���j����]�������߁A�V���L�҂��u���Ȃ����ɑގЂɎ���Ƃ������P�[�X��������)�@
�������A�����푈���̕���́A�V�����X�^�[�L�҂����ł͐������Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ����B�ǎ҂����߂��̂́A�����Ș_�����́A�O���ł̐킢�Ԃ�A���m�̕��E�`�Ȃǂ�`����L���ł������B�@
�܂��O�ʋL���̐l�C���A�V���L�҂ɍ��������⋳�{�����߂Ȃ��Ȃ����v���ł���B�@
���R�����^���̉₩�Ȏ���Ƃ͉߂�����A�V�����L�����y�[�����͂��Ă��A���ʂ��������Ȃ��Ȃ��Ă������B�O��݂��悤�ɁA������u�����v���Љ�̕s�������e���Ă��A�������ǐ����Ȃ��������߁A���_�̌`���ɂ͎���Ȃ������B�@
����ɁA���I�푈�ł̍��O����ł́A��ɎЈ���ҋ@�����Ă����K�v������A�V���Ђ̗͑͏����ƂȂ��Ă������B�@
�V���́A�l�̗͂ł͂Ȃ��A�g�D�͂ŏ�������悤�ɂȂ��Ă������̂ł���B�@
�����Ė��������ɂ́A�L�҂̐�����ƂƂ��ɁA�V������V���֓n������L�҂͌���A1�̐V���Ђɐ��U�Ζ�������̂������Ȃ����B�@
�u���������V���v�ł́A1907�N(����40�N)����ɁA���ʼn\�������T�K�������ق��A�呲�̎Ј��ɐ�ւ��铮�����n�܂��Ă���B�@
���㕗�ɂ����ƁA�_��Ј����琳�Ј����琬������j�ւ̓]���ł���B�@
�����ĐV���ƊE�ɔN������A�I�g�ٗp���Z������ߒ��ŁA���ЈȊO�̋Ζ��o�����������A�Г��ł̔h�������ɋC��z��g�D�l�Ԃ������Ă������B�@
�V���L�ҏo�g�̕]�_�Ƃł��钷�J��@���Ղ́A���̂悤�Ȏ�|�̂��Ƃ��q�ׂĂ���B�@
�u���{�v�ł́A�В��̗�㹓�̂��Ƃ��В��ƌĂԂ��Ƃ͂Ȃ������B�u����Ƃ����������ēǂ�ł����B�u�����v�ł��ŏ��͂����������B�@
�V���Ђ́A��`�咣�������铯�u�̏W�܂�ł���A��y�E��y�̕ʂ͂����Ă��A�K���̈Ⴂ�͍l�����Ȃ������B�@
�������A����30�N��̖��ɂ͏����̐V���Ђ��В��Ƃ����ď̂��g���o���A��ʓI�ȌĂѕ��ɂȂ��Ă������B�@
�ȑO�A�V���ƊE�ɗ֓]�@����������A���I�푈�ŐV������O�ɕ��y��������ɁA�V���Ђ����{��`�I�c����Ƃɓ]�������Ə������B�@
���I�푈���I������̂�����38�N������A��̒��J��̔����́A���̂���ɐV���Г����s���~�b�h�^�g�D�ɓ]�����A�V���L�҂͑g�D�̎��ԂƂȂ��Ă��������ƂɂȂ�B�@
�V�������l���I�Ȃ��̂���c����ƂւƓ]�����Ă����������ɁA�Г��̕��͋C���ς�����Ƃ������Ƃ��B�@
�V���Ђ̎В����܂��A���_�l�ł͂Ȃ��o�c�҂ƂȂ�A�\�Z���x�����ĉc�����ƂƂ��Čo�c��簐i�����B�@
�����āA�����̑��R�В��A��m�̎O�؎В��A��㖈���̖{�R�В��ȂǁA�o�c���o�̗D�ꂽ�В��ɗ�����ꂽ�V���Ђ��A���Ƃ��g�傳���Ă������B�@
���x�h���́A���̎���̂��Ƃ����̂悤�ɉ�z���Ă���B�@
�u�̂͐V���E�̐l���͕M������L�҂ł���A�����ł̓\���o�������o�c�҂ł���v�@
���x�h��Ⓡ�c�O�Y�̂悤�ȑ啨�L�҂͐V���E��������A���̂Ȃ��T�����[�}���L�҂�舕�����悤�ɂȂ����B�@
�������ނ�́A������ӂ܂ŋ삯���A���Օi�Ƃ��č��g����Ă����悤�ł���B�@
���V���L�҂̍��w�����@
�V���Ђ̊�Ɖ��Ƌ��ɁA�L�҂̊w���͏オ���Ă������B�@
�u���{�V���N�Ӂv�ɂ��A1922�N(�吳10�N)�ɂ́A40���ȏ����������o�g�҂���߂�悤�ɂȂ��Ă����B�@
���̎����ɂ͂��łɁA�V���Ђ̗̍p���x����������A����ɂƂ��Ȃ��ĐV���L�҂̍��w�����������Ƃ��錤��������B(�}�X�E�R�~���j�P�[�V��������No61�͍�g�I�u1920�N��ɂ�����V���L�҂̊w���v)�@
�܂����������ƁA�V���Ђ̕ҏW�E�ł͎��w�o�g�ҁA���ɑ���c��w�o�g�҂������B�@
�u�����{���ɂ�����L�͐V���E�G���Г�\�]�Ђ̋L�҂̂����A�䂪�w���o�g�҂͖���39�N�ɂ����āA150�����Ă����v(����c��w�S�N�j���)�@
�V���L�҂ɑ���c��w�o�g�҂������̂́A�������ォ��Ƃ������ƂɂȂ�B�@
���܂Ƃ߁@
�V���̉c����Ɖ����������������ɂ́A�V���̓X�^�[�L�҂̌l�I�Ȕ\�͂ł͂Ȃ��A�g�D�͂ŏ�������悤�ɂȂ�A�L�҂̃T�����[�}�������i�B�@
�����ɁA�V���Г����В��_�Ƃ���s���~�b�h�^�g�D�ɓ]�������B �@

�����㔼�̋}���Ȍo�ϔ��W�ƂƂ��ɁA�V���ƊE�ł́A�o�ϊE�Ƃ̖������݂���悤�ɂȂ����B�@
����Ɩu���Ɗ����u�[���@
1885�N(����18�N)���납��A�䂪���ł͎��{����Ƃ̐ݗ������������B�@
�u���{�鍑���v�N�Ӂv�ɂ��A1885�N����1889�N�ɂ����Ă̒Z�����ԂŁA���{�����z��5066���~����1��8361���~�ɑ������A��А���1279�Ђ���4067�ЂւƑ������B���̎����́A�y�H�Ƃ𒆐S�ɂ�������̊�Ƃ��ݗ����ꂽ�B�@
�����푈��ɂ͌R���֘A�Y�Ƃ�d�H�ƎY�Ƃ����B���A���I�푈��ɂ́A�얞�B�S���n�݂�S�����L���Ȃǂ��Ȃ���A������Аݗ��u�[����������A�����s������̂Nj}�����������B�@
���I�푈��̊����̍����́A�u��v�v���Ɨ�؋v�ܘY�Ƃ��������ݏo�����B�@
�ނ́A�����̍��Ɨ\�Z�ɕC�G����قǂ̋������Ƃ������邩��A���̂Ƃ��̊����s�ꂪ�A�����Ƀo�u�����N�����Ă��������킩�邾�낤�B�@
��v�́A1907�N(����40)�̐����ɂ́A�����A�V���A�ԍ�A���{���Ƃ������s���̈ꗬ������݂�����A�|�W�����ɗ�؉Ƃ̖����ߔ����������𒅂��A���ȂɎ��点����A�X�������������肵���B�@
����ɂ́A����500�~�̓�������������̊����A���������ɏj�V�Ƃ��ė^�����Ƃ����`��������B(���̍��̕��ʂ̐V���L�҂⏄�����C���́A����15�~�ł�����)�@
�������A�o�u���̎��ɂ̓N���b�V��������̂́A���̏�ł���B��v�̉h�������������A�S���Y���������B�@
���`���E�`���L���@
���{��`�Љ�̐i�W�́A�V���ƊE�ɂ��e����^�����B�@
�V���Ђ��c����ƂƂȂ��Ă��������Ƃ͍ĎO�������Ƃ��肾���A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�o�ϊE�ƐV���̌o�ϋL�҂Ƃ̖����݂������B�@
���{�ƁA��Ƃɂ��o�ϋL�҂ւ̋��i���݂���悤�ɂȂ����B�@
�L���Ƃ́A�c�́E��ƁE���i���邢�͌l�������グ�邽�߂ɏ����ꂽ�L���������B�L�͎҂ɛZ�тւ炤�҂ɑ���u�����v�Ƃ����̏̂ɗR������Ăѕ����B�@
�����̌o�ϐ����́A�V���ɒL����o�ꂳ�����B�@
����W�҂̒��ɂ́A�o�ϋL�҂��g���āA�����ɗL���ȋL�����f�ڂ����āA���v�悤�Ƃ�����̂�������͂��߂��B�@
��������̎G���ɂ́A���̂悤�ȋL�����f�ڂ���Ă����B�@
�u������\���N�ȍ~�A������Ђ̍łƂ����s�����鎞��ɂ����ẮA���ł���ł��ꐡ�������Ƃ�V���Ɍf����B�X���g���ɂ��̊��̒����o��B�E�E�E(����)�E�E�E�\�������牽�ł���ł���̐V��ЂN���āA���ׂ������ӂƎv�ӂ��̂́A���ԂɐV���Ђ̒T�K���ĂуS�y������v�@
(�u���o�ώG���v����32�N9��20��)�@
�M�p�͂̂Ȃ��V�K��Ƃ̎��{�Ƃ̂Ȃ��ɂ́A�L�҂Ɋ���z�邱�Ƃɂ���āA�L�����������āA�����Ƃ̓����𑣂����Ƃ�_�����҂������B�@
���L����ƐV���@
��������̐V�����A���Ɠ������A�ǎ҂̍w�Ǘ��̂ق��ɍL������������Ă����B�ŏ��̂���́A�L����͉��ϕi���Ȃǂ̏������������Ƃ����������B�@
�o�ς��{�i�I�ɐ������͂��߂�����30�N�ォ��A�V���L���͋}�����A�Ђ��`�L���A�t���L���ȂǁA�l�ڂ��Ђ����߂̊��L����������Ă����B�@
���Ȃ݂ɁA�L���㗝�X�̓d�ʂ��ݗ����ꂽ�̂́A1901�N(����34�N)�ł���B�L���̎掟�����s����Ђ��łĂ������Ƃ́A�L�����v�̑�������Ă���B�@
�܂��A���I�푈�̏I�����1905�N(����38�N)�A�u���������V���v�́A�L���̑I���f�ڂ�錾�����B�@
����́A�V�����L���}�̂Ƃ��Ă̎Љ�I�ӔC�����o���͂��߂��L���^���̂͂���Ƃ����邪�A�����ɁA���̍D�i�C�ōL�����v�������������߂Ƃ��l������B�@
1910�N(����43�N)���납��X�ɍL���s��͊g�債�A�V���Б��ł��A�o�c��Ո���̂��߂ɁA�L�������̑�����ڎw�����B���̒��ŁA�L������̋L�����A�ڂ����P�[�X���o�Ă����B�@
�u�V���Ђ̍L���W���ҏW�֍s���āu����͍L���̒ł�������o���ĉ������v�ƒᓪ��g�ŗ���ł���B�E�E�E(����)�E�E�E�h�c�J�̕Ћ��Ɏl�܍s�Ȃ�ܘZ�s�Ȃ�A�Z�������ŕ��荞�ނ̂����A�v��ł��P�ɍL������ڂ�������y���Ɍ��͂�����Ɩڂ���ċ���v(�u�V���_�v����44�N8�������)�@
���̎G���L������A�L����́A�V���̈�ʋL�����������̍L���ł���L���̌��ʂ̍�����F�����A�V���Г����ł��A�L����ւ̒L����F�m���Ă������Ƃ��킩��B�@
�������㖖�ɂȂ�ƁA�V���L�҂̎��͌��サ�A�H�D�S���̂悤�ȁA�����炳�܂ȃ��X����C���͌����������̂́A�L���́A�������đ��������悤�ł���B�@
�Ƃ���ŁA�o�ϕɌ��炸�A��ʕɂ����Ă��A��ފ���������̎҂̏��ɑ傫���ˑ�����K�����ł��Ă��܂��ƁA���҂ɓs���̂��������Ȃ���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B�@
����̓��{�̃}�X���f�B�A�́A�L�҃N���u����̏��Ɉ���I�Ɉˑ����Ă��邱�Ƃɂ�镾�Q���w�E����Ă��邪�A���̌X���͖�������ɂ��łɌ����Ă����B �@

����̓��{�̃}�X���f�B�A�́A�L�҃N���u����̏��Ɉ���I�Ɉˑ����Ă��邱�Ƃɂ�镾�Q��������w�E����Ă��邪�A���̌X���͖�������ɂ��łɎw�E����Ă����B�@
���u�V���L�ҋ����p�v�@
�܂��͂��߂ɁA1910�N(����44�N)�̎G���Ɍf�ڂ��ꂽ�A�L�҃N���u�ւ̔ᔻ�L�����Љ�悤�B�@
�u�E�E�E���Ȃɗꑮ����L�Ғc�ɑ��A��Ăɓ�������������B �����삯�̌����͑S���s�\�ƂȂ��Ȃ�B �̂ɊY��Ⴕ���͊Y��y���ɖ��O���ڂ��A��������Ɋ�o�����ւ��ċ���A�n���ł������ł��r���@�q�ȋL�҂Ɠ��������蓾��Ȃ�B ���ɑ��̎����̋L�҂��s���ŎЂ����̏ꍇ�ɂĂ��ЂɂĂ͍X�ɕs�ւ��������A�ʐM�ɂė��h�ɕv�ꂾ���̋L�����ڂ����鎖�ƂȂ��B �E�E�E(����)�E�E�E�@
�ǂ̐V�����Ă��L���͓����Ƃ���āA�����Ƃ��u�k�̖ʔ��̂��ڂ���V��������s���悵�Ɖ]����Ԃ͔J�듖�R�̂��ƂƉ]�����v(�u�V���_�v����44�N4�����S�@�ӑT�u�V���L�ҋ����p�v)�@
���̋L������A���łɖ�������̖����ɂ́A�ȉ��̂悤�ȌX��������ꂽ���Ƃ��킩��B�@
�����́A�L�҃N���u�����̋L�҂ɁA�����ɓ����������悤�ɂȂ������Ɓ@
���̂��ߎ�ޔ\�͂��Ȃ��Ă��V���L�҂��Ƃ܂�A�u���I�`(���_�l�𗎂Ƃ�)�v�̐S�z���قƂ�ǂȂ��Ȃ������Ɓ@
���̌��ʁA�����悤�ȐV���L�������������Ɓ@
���̂悤�ȋL�҃N���u���A�ǂ̂悤�Ȍo�܂łł����̂��A����ǂ��Ă݂Ă��������B�@
���L�҃N���u�̖G��@
�L�҃N���u�́A�L�ғ��m�̐e�r�A�S������̌����A��ސ�ւ̕X�v���Ȃǂ�ړI�ɁA�����I�ɔ������A����ƌ��I�@�ւ̎�ނ�Ɛ肵�Ă�������ޑg�D�ł���Ƃ�����B�@
1877�N(����10�N)�A�����ŊJ�Â��ꂽ�������Ɣ�����ł́A���{�́u���V���L�҂֏c���̎D�v��u�L�҂̋x�����v��^���āA��ނ̕X��}��A������l�C��V���Ő���グ�悤�Ƃ����B�@
�����������d�v�ȍÂ��ɂ́A���{�n�A�����{�n���킸�A�e���̋L�҂͎�ނ�������A������^����ꂽ�B�@
1882�N(����15�N)�ɂȂ�ƁA���{�͍c���̂����̂��ɏ����ȏ�����V�z���A������V���Ј��̍T�����Ƃ��āA�j���[�X��`�B�����B�@
�x�����ł��A���N�ɂ͓��l�̏ꏊ��V�݁B�@
���̗��N�ɂ͋{�����ł��u�V�����e���t��C�v�Ƃ����L���C�҂�C�����āA�L�����L�҂ɒ��ڎ�n���悤�ɂ����B�@
����10�N��㔼����20�N��O���ɂȂ�ƁA�����̖��������łȂ��A�n���̖������f����ݒu����ȂǁA�V���L�҂̎�ނɕX��}��悤�ɂȂ����B�@
���̂悤�ɁA���R�����^�������ނ������납��c��J�݊��܂ł̊ԂɁA�����A���̎�v�Ȗ����ɂ́A��ނɂ����L�҂ɕX��}��u�T�����v��f�����ݒu�����悤�ɂȂ����B�@
�������@�����z���ꂽ����ɂ́A�V���́u�s�Εs�}�v��W�Ԃ���悤�ɂȂ��Đ��}�F�͔���Ă���A�����{�I�ȑԓx����܂��Ă������Ƃ������āA���{�̐V���ւ̌������p���͂��炢�ł����̂ł���B�@
�Ƃ���ŁA���{�ł͂��߂ĊJ�݂��ꂽ�c��ɁA�ǎ҂͍����S���悹�A�������e���͋c���ނɒ��͂����B�@
�������A�c��ł́A�����̐��������������Ȃ��V���БS�̂ɂ킸��20���̖T��������t���������������B�@
���̖T�����̕��z���߂����ċL�҂��������c����ߒ��̂Ȃ��ŁA�L�҃N���u�`���ւ̓������萶�����B�@
1890�N11���Ɍ������ꂽ�A����L�҃N���u�̑c�A�u�c��o���L�Ғc�v�ł���B�@
�u�c��o���L�Ғc�v�́A���}�ɊW�Ȃ��A�S���̐V���L�҂��A�Љ�ɑ���̐ӔC���܂��Ƃ����邽�߂ɁA�c��ɖT�����z�z�Ȃǂ̕X��v������c�̂Ƃ������i�����������B�@
���L�҃N���u�̌`���@
1890(����23�N)����1900�N(����33�N)�ɂ����āA�ꕔ�̖�����}�{���u�V���L�җ����v�u�V���L�ҍT���v�Ƃ���ꏊ���a�������B�@
�ŏ��̂���́A�V���L�҂����́A���Ă���ꂽ���������ɂ����ƍT���āA������l�����g���������Ă��鎆��҂��Ă���ɂ����Ȃ������B�@
����́A�V���𐭘_�d������d���ɕς��Ă����B����𗧈Ă��A���s���钆�������̎�ނ́A�V���L�҂ɂƂ��ďd�v�Ȏd���ł������̂��B�@
�܂��A���̂���V���Ђ̊�Ɖ��A�g�D�����i�W���A�V���Ђ́A�����W�����������邽�߂ɁA�L�҂̐��S������i�߂��B�@
����܂ł̃X�^�[�L�҂̎���ɂ́A���̂悤�ȕ��Ɛ��x�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��������A�L�҂̒S�����́A�����T�����Ŋ�����킹��L�ғ��m�̌𗬂ɂ��Ȃ���A�N���u�I�ȕ��͋C����������邱�ƂɂȂ��Ă������B�@
1900�N�ɂ́A�O���ȒS���̋L�҂��u�O��������v�A�̂��́u����y���v��ݗ������B�@
�u����y���v�́A�����ɍT������v��������A�L�҂ɑ��ċ����̐����@������߂�g�D�ł������B�@
1910�N�ȍ~�́A�L�҂̏W�܂�́A�u�L�ҋ�y���v�Ƃ��u�L�҉�v�ƌĂꂾ���A�e�����A���}�A���ƂȂǂɋ}���ɕ��y�����B�`���ŏЉ���u�V���_�v�̋L�����f�ڂ��ꂽ�̂��A���̎����ł���B�@
1912�N�ɂ́A�呠�Ȃ̋L�҃N���u�ł���u������v�����ꂽ�B�@
�u���O���ƐV��v�̎В����Ƃ߂��ʓc[�L���E]���Y�ɂ��ƁA�u������v�́A�u�����y�o�ςɂ��ĐV���L�҂��\���Ȍ����𐋂��^���Ȍ�����L���V�ɂ���Đ��Ԃ̖ւ��[�����͂̏[�����W���v�肽���Ƃ����l������v�ݗ����ꂽ�B�@
�܂�u������v�́A�L�҂���������������K�v�����琶�܂ꂽ�B�]���āA���̎����ɒa�������L�҃N���u�́A�L�҂̓s���ɂ�萶�܂ꂽ�c�̂ł������Ƃ�����B�@
�����̐V���L�҂̎Љ�I�n�ʂ́A��l�ɔ�ׂ�Ƃ͂邩�ɒႩ�������߁A�P�Ƃł̎�ނ͍���ł���A�V���L�҂����͒c�����ď������߂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����w�E������B�@
�������A�L�҃N���u�����y���͂��߂�ƁA������鑤�̐��{���A�����ϋɓI�Ɋ��p����悤�ɂȂ��Ă������B �@

�L�҃N���u�́A���ƈ���āA���J���̋`���Ƃ������l���̂Ȃ�������������ɁA�������J�����邽�߂̋L�ґ��̓����ƁA����Ƃ��āA����I�Ɍ`������Ă������B �������A�L�҃N���u�����y���͂��߂�ƁA������鑤�̐��{���A�����ϋɓI�Ɋ��p����悤�ɂȂ�A�L�҃N���u�́A���������Ă������B�@
���L�҃N���u�̎�荞�݁@
�O���ȒS���L�҂̏W�܂�ł���u����y���v�ł́A���I�푈���ɂ́A���{�������C�O�d������܂Ƃ߂Ĕ��\������A�T��2��A���L�����N���u���̎���ɓ�����悤�ɂȂ����B�@
���ɂ́A�L�҂̂��߂̕���J�Â���A���{�������߂�`���邱�Ƃ��������B�@
�L�҂̎���I�ȑg�D���A���ǂ̏��ɗ��p�����悤�ɂȂ��Ă�������ł���B�@
�����āA��j���t�̂Ƃ��ɂ́A���{�́A�����̒c�̂ɑ��āA�C�X�A���̂����r�I�L���������Œ��A��C�̋��d�ɃT�[�r�X������ق��A�����A�͌�̌�y�Z�b�g�܂ŗp�ӂ��āA�T�[�r�X�����B�@
��ꎟ�j���t�́A���I�푈�ɏ����������̂́A�|�[�c�}�X���������͂��߂Ƃ��郍�V�A�Ƃ̍u�a�������_�̔ᔻ�𗁂тđސw�����B���̂Ƃ��̌o������A�̌j���Y�́A�}�X���f�B�A����荞�ނ��Ƃ̏d�v����F�������ƍl������B�@
�j���Y�́A�u�j�R�|���ɑ��v�ƌĂꂽ�B�j�R�j�R���Č����|���ƒ@���A�����Ƃ���E�l���������̂ɍI�݂��������߁A�V���ɂ��������ꂽ�ƌ����Ă���B�@
�l�S�����p�ɒ������j���Y�̐V���L�Ҏ�荞�ݐ헪�ɑ��A�V���L�҂������A�����͂��Ȃ������悤�ł���B�@
����ɋL�҃N���u�̍��e��ɂ́A��b�܂ŏo�Ȃ��A����ɋ�����悤�ɂȂ����B�@
�O��Љ���u�V���_�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�L���ɂ��ƁA���{�́u���ɍ��O�喂��(���A���A��)���I�݂Ɏg���������āA�����V���L�҂̗ǐS��Ⴢ����߁A����\�����̋����p�v�����������߁A�L�҂́u���{�ɗ��v�����̂݁v�����ʂɂ̂��A�u���{�ɕs���v�Ȃ�L���v���f���Ȃ��Ȃ����B�@
����܂ł̋L�҃N���u�́A����������͖��҈�������邱�Ƃ��������B�@
�������A��j���t�ȍ~�́A�����̋L�҃N���u�̑ҋ��́A����܂łƔ�ׂ�Ɗi�i�ɗǂ��Ȃ�A�V���L�҂́A������y���ɒ��s���A�����ł��������݂Ȃ���k������A�͌�⏫����ł����肵�ď�����̂�҂��Ă���悭�Ȃ����B�@
���������ɂ��L�҉�́A�L�҃N���u�Œ莞�ɂ����Ȃ���̂ŁA�����ɂ���A���_�l�𗎂Ƃ����Ƃ͂Ȃ���������ł���B�@
�������āA��������ނ���ɂ́A�L�҃N���u�ɑ����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă������B�@
�L�҂͔��\���ꂽ�������̂܂܁A�Ƃ��ɂ͉��M���ĎЂɎ����A��A�f�X�N�ɓn���B�j���[�X�E�\�[�X�����L�҃N���u�Ȃǂ�ʂ��Ĕ��\�E��������A���̂܂܉E���獶�ɕ��锭�\�W���[�i���Y�����͂��܂����̂��B�@
�����āA���_�l���˂���ēƎ���ނ������Ȃ��L�҂��A�j���[�X�\�[�X�ɕs�s���ȋL�����ڂ����ꍇ�́A�������肩�A�N���u����a�O�����X���������͂��߂��B�@
�u�C�T����L�҂��A���{�ɕs���v�Ȃ�L�����f�ڂ��A�����ɕS������݂��ĔV��a�O���A�ꂵ�ނ�̎�i���Ƃ�v(�u�V���_�v���)�@
�����ɕs�s���ȏ�f�ڂ���ɂ����Ȃ����̂ŁA�L�҃N���u�͖�l�ɂ����}�����悤�ɂȂ��Ă������B�@
�܂��A�L�҃N���u�̕��������̂��납�猩���Ă���B�@
�u�����̉�ɐȂ�u���ɂ́A�����ȏ�̏Љ��v���Ƃ����Ƃ��A���������~���K���Ȃǂ���Đl�I�����d�v(�u�V���_�v���)�ł���A�����ł���̂́A�L�͎���ʐM�ЂɌ����A���V���͔r������Ă����悤���B�@
���̂悤�ɂ��āA�L�҃N���u�́A���I�Ȑe�r�c�̂Ǝ�ދ@�ւ̓�ʐ������悤�ɂȂ��Ă������B�@
���V���Њ����̎�荞�݁@
���{������荞�L�҃N���u���L���ɋ@�\���邽�߂ɂ́A�����ЂƂA�K�v�Ȃ��Ƃ�����B�L�҂������A�������e���A���̂܂��ʂɌf�ڂ����悤�ɂ��Ȃ�������Ȃ��̂��B�@
��j���t�́A���̓_�ł������肪�Ȃ������B�V���Ђ̊�����_���ψ����A���{���������R�c��⋦��̈ψ��ɔC�����Ă������̂��B�@
1909�N�A���ېV������A���{�̊̂���Őݗ����ꂽ�B�@
���ېV������́u���O���ȑ��̒����̏W���v�Ɓu�V���_�v�̋L���ɝ�������Ă���B�@
��������A�e�Ђ̎В���_���ψ��ɐ��{���Ăт����āA�u�t�H��v���������ꂽ�B�@
�������āA�L�҂ɂ͓������A�����ɂ͖��_�����{����^�����邱�ƂɂȂ����B�@
�����}�̋L�҃N���u�@
�L�҃N���u��u�����̂́A���{�����ł͂Ȃ������B���}�ɂ��A�L�҃N���u�����݂���悤�ɂȂ�A���}�������u�����I�{���v��V���L�҂ɗ^�����B�@
�����̐V���E�G���ɑ����̐������h����\���Đl�C���W�߂��k��y�V�́A�u�j�ď��V���̋L�ҁv(�u�����p�b�N�v�f��)�ŁA�V�������Ȃ��߂�ׂ��u���ł��ۂ܂��ē{�点�Ȃ��l�ɂ��Ă����Ă���v�Ɨ����̂���Ɏw�����銲���̎p��`���Ă���B�@
����������̋L�҃N���u�@
�����ŁA��������̋L�҃N���u�̓������܂Ƃ߂Ă������B�@
�������A��ƁA���}�Ȃǂɏꏊ�����A�ݔ��A�l�����T�[�r�X����A�啔���ł͓d�b�コ���A�j���[�\�[�X�������@
�����ŏ�ꌳ�I�ɔ��\����A���ɂ͕�����J�����@
�������A�����ɂ���ސ���������@
�V���Б��̃����b�g�@
�����̖������ƂȂǂ̃j���[�X�\�[�X���u�����L�҃N���u�ɏo���肷��A�����Ŕz�z��������S�ē���ł��A���I�`(���_�l�𗎂Ƃ�����)���Ȃ��Ȃ�@
�L�҃N���u�ɏ����ł��Ȃ��V���⑼�̃��f�B�A�Ƃ̋����ɗL���@
�V���Б��ł̐l����A��ޔ�̐ߌ��Ȃnjo�c�������ɂ���^����@
�V���Г��m�̉ߓx�̋�����r���ł���B�@
�j���[�X�\�[�X���̃����b�g�@
������̃R���g���[�����\�ɂ��A��������₷���Ȃ�@
�����̕@�ւɂ��������Ή�����ώG������������B�@
�V���Ђƃj���[�X�\�[�X���Ƀ����b�g�̂���L�҃N���u�́A�ǎ҂́u�m�錠���v�̊ϓ_����l����ƃf�����b�g������B�@
�V���́A�p���I�ȏ������҂��āA�j���[�X�\�[�X�ɍD�ӓI�ȏ��𗬂������ɂȂ�@
���ʂ���ꉻ����@
�L�҂��A����̐ӔC�ŏ�����̑I������w�͂�ӂ邱�ƂɂȂ���B�@
���\�W���[�i���Y�����������Ă������w�i�ɂ́A�V�����Ƃ�_���鐭�_�ł͂Ȃ��A���d�����ꂽ���Ƃ�����B�@
�܂��A�V���Ђ̊�Ɖ����i�݁A�������㒆���܂łƈ���āA�o�c�҂����ւ������悤�ɂȂ��Ă������Ƃ��l������B�@
�����Ƃ��A��������̋L�҃N���u�́A���Ƃ���ׂ�ƊJ����Ă����B�����̒ʐM�Ђ̂ق��A�ƊE���Ȃǂ̓����������Ă�������ł���B�@
�����̌�̋L�҃N���u�@
�u�V���_�v�̋L�����f�ڂ��ꂽ20�N���1931�N(���a6�N)4���A�G���u�����v�Ɂu�L�҃N���u��`���v�Ƃ����L�����o�Ă���B�@
���̋L�����݂Ă��A�L�҃N���u���u�ꎺ���A���̖����A���}�A���Ђ͉�Ђ������E�E�E(����)�E�E�E���\���͈���̃N���u��ʂ��čs�͂��v�_�͕ς���Ă��Ȃ��B�@
�܂��A�u��y������v�́A�ނ����|����ɂȂ��Ă���B�@
�u�L�҃N���u�̐��x�͂ǂ����Ă��A������Ƃ�ɂ͓s���������v�Ƃ����w�E������B�@
���̌�L�҃N���u�́A�푈���̃��f�B�A�����̒��ŁA1942�N��1�Ȓ�1��y���ɍĕ҂���A���{�̏���`��i�ɑg�ݍ��܂�Ă������B�@
���l�@�@
�������{�́A���Ƃ͈���ď��J�����`�����Ƃ͍l���Ă��Ȃ������B���J���̖��m�ȃ��[�����Ȃ������悤�ł���B�@
���{�V�����2002�N�ɂ܂Ƃ߂��A�u�L�҃N���u�Ɋւ�����{�V������ҏW�ψ���̌����v�ɂ́A�u���{�̕E�ɂ́A���J���ɏ��ɓI�Ȍ��I�@�ւɑ��āA�L�҃N���u�Ƃ����`�Ō��W���Č��J�𔗂��Ă������j������܂��v�Ƃ����L�q������B�@
�L�҃N���u���A�������ڂ̌X���̂���������ɁA������肷�邽�߂ɋL�҂��c�����āA�����J��i�߂Ă��������Ƃɂ́A�傫�ȈӋ`���������ƍl������B�@
�܂��A���{�������B�����ꍇ�ɁA���̔閧���������߂ɁA�L�҃N���u�������������O�ɂ͂������B�@
�������L�҃N���u�������������I�ɂȂ�A����Ƀj���[�X�\�[�X�ɉߓx�Ɉˑ����āA���\�W���[�i���Y���Ƃ�����悤�ȕ`���݁A�j���[�X�\�[�X�ɍD�ӓI�ȋL���𗬂��Ă������Ƃ́A�傢�ɖ��ł���B�@
�܂��A���オ�Ⴄ�Ƃ͂����A�����ł̐ڑ҂�A���d�l�T�[�r�X�܂Ŏ���A���o����j���[�X�\�[�X���̕��S�ɗ������̂́A�F�����Â������Ƃ�����B�@
���̓_�Ɋւ��ẮA���݂̓��{�V������ł́A�u���p�ɕt�����Ă����鏔�o��ɂ��ẮA���������̕��S�����ׂ��ł��v�Ƃ��Ă���B(�u�L�҃N���u�Ɋւ�����{�V������ҏW�ψ���̌����v���)�@
�Ȃ��A�L�҃N���u�̕��Q�Ƃ��Ďw�E�����L���̉�ꐫ�̖��́A�{���A�����ǂ��������邩�A�����l����V���L�҂̖��ł����āA�L�҃N���u�̑��ݎ��̂����R�ł͂Ȃ��ƍl������B�@
����ɁA�_�l������(���\�W���[�i���Y��)���D�ǎ҂ɂ��A�ӔC�̈�[������Ƃ����邾�낤�B�@
�ȑO�������悤�ɁA��������ɂ��������_�𒆐S�Ƃ�����V���́A�p��Ă��������炾�B�@
���܂��܂ȕ��Q���w�E����Ă����L�҃N���u�́A�ߔN�Ɏ���܂ŁA�������ꑱ���Ă����B�@
�������L�҃N���u�́A�����ւ��Ď�������͂��߂Ă���悤�Ɍ�����B�@
�}�[�P�b�g�Ɋ֘A����L�҃N���u�̑����́A���łɂ��̑��݈Ӌ`�������Ă���B�@
��Ƃ�ΏۂƂ����L�҃N���u�Ⓦ�́u����y���v�́A�O���n�@�ւ̎Q���v���������āA�N���u���ȊO�̉�Q����F�߂�悤�ɂȂ��Ă���B�@
�܂����̂s�c�l�b�g(�K���J�����{���T�[�r�X)�ɂ���āA�C���^�[�l�b�g��������J�����i�B��Ƒ��̍L��E�h�q�̐��̐����ƂƂ��ɁA�g�o�ł̏��J�����i�݁A�L�҃N���u���ꎟ����Ɛ肷�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B�@
���݁A�r���I�ȑ̎��ɔᔻ���W�����Ă���̂́A�����ւ̎�v������i�c�����ӂ̋L�҃N���u�ł���B�@
�������A��������͕ς�����B��N�Ă̐������ȍ~�A�O���Ȃ���Z���ł́A�N���u���ȊO�̉�Q�����F�߂���ȂǁA�����������͂��߂��B�@
�挎�́A���@�����A�L�҉���I�[�v����������j���A�l�b�g��ł����\�����B�u���@���ɂ�����L�҉�ɂ���(�ō���)�v�� �u�S���̌��@���ɂ����ẮA����A�L�҃N���u�ɏ������Ă��Ȃ��L�҂��܂߂��I�[�v���Ȍ`�̋L�҉���J�Â��邱�ƂƂ��A���݁A�e���ɂ����āA���̏�����Ƃ��s���Ă��܂��B�v �ǂ��܂ł��J�������̂��A�ǂ��^�p�����̂��͖��m���ł��邪�A���ڂɒl���锭�\�ł���B�@
�L�҃N���u�J���̗v���́A�����Ƃ����ǂ��A�����ł��Ȃ�����ɂȂ��Ă���A����A���̊����ł��̐��������ɂ�A�L�҃N���u�J���͒����ɍL�����Ă����Ǝv����B�@
��100�N�O�����肪�w�E����A���v�̓����͗��j�̒��ł͂Ȃ��ł��Ȃ��������A�L�҃N���u�͑������A�V���ƊE�͎���̎�ł͖��������ł��Ȃ������B�@
100�N�����������ǂɁA�ŏ��Ɍ����������̂͊O�����f�B�A�ł���A���Ɍ����L�����̂̓C���^�[�l�b�g�̕��y�ł������B �����̊������v�́A�O���[�o�����ƃC���^�[�l�b�g�̕��y�ɂ���āA�������B�@
�V���́A����2�̑傫�ȗ���̒��ŁA����̑��݈Ӌ`��₢�����ׂ��ł��낤�B ����́A���\�W���[�i���Y���ł͂Ȃ��A�����̌���A�ꎟ�������Ƃɂ����[�����͂��������߂���̂ł͂Ȃ����낤���B�@
 �@
�@���W���[�i���Y���́u���v���猩�����E�@
����1985�N11���́A�ЂƂ̏o��������邱�Ƃ���A�{���̍ŏI�u�`���n�߂����Ǝv���܂��B �@
�ЂƂ̏o�����Ƃ����̂́A���̔N��11���ɏ��߂ăW���l�[�u�Ŏ����������[�K���E�S���o�`���t�ă\��]��k�ł��B�ă\��]��������킹��̂́A79�N6���́A�E�C�[���ł̃J�[�^�[�E�u���W�l�t��k���炢����6�N���Ԃ�ł����B������SALT�U(��2���헪���퐧�����)�̒��s�Ȃ��A��펞��̕ă\�����卑�ɂ�鐢�E�Ǘ��V�X�e���ɋْ��ɘa�̗v�����ЂƂ������ꂽ���̂Ƃ��đ傫�Ȋ��҂����܂����B�������A���̔N��11��4���A�e�w�����ŃC�����w���ɂ��A�����J��g�ِ苒�����������A�����12��24���ɂ̓\�A�R���A�t�K�j�X�^���N�U���A�ă\�W�͂܂������܂ɐ��Œ�̃��x���ɂ܂ŗ₦���čs���܂����B���̎�������80�N7���̑�22��I�����s�b�N�E���X�N�������A�A�����J��M���Ƃ��ē��{�A���h�C�c(����)�ȂǂɃ{�C�R�b�g�����邫�������ƂȂ������Ƃ��v���o���܂��B �@
85�N�̃W���l�[�u�ɂ�����ă\��]��k�́A���̂悤�ɂ��ė₦���������W��ŊJ���邽�߂̗��j�I�ȉ�k�ƂȂ�܂����B2001�N�A�����J�ŋN�����u���������e���v������9��11�����u���E���ς�������v�Ƃ��ĕ\�������C�M���X�̏T����������܂��B����Ɠ��l�ɁA���̃W���l�[�u��k���u���E���傫���ς�������v�Ƃ��āA���j�̒��Ɉʒu�Â��Ă����ł��傤�B�������A���ꂪ4�N��́A89�N11��9���E�x�������̕Ǖ���A91�N12��25���̃S���o�`���t�哝�̎��C�Ƃ���ɔ����\�r�G�g�A�M�̏��łɂȂ���Ƃ́A�����A������\���ł��܂���ł����B���̎����́A��������ƋL���ɂƂǂ߂Ă����K�v������Ǝv���܂��B �@
�_���Ⴍ���ꂱ�߁A���Ⴊ�����~��Ă���W���l�[�u�̊D�F�̋���A���܂��N���Ɋo���Ă��܂��B���͂��̔N��10���A�x�ǒ�(��ɉ��B���ǒ�)�Ƃ��ă����h���ɕ��C��������ł����B �@
���ꂩ��1�����������Ȃ������Ɂg�Ԃ����������h�̂��A���[�K���E�S���o�`���t�ă\��]��k�������̂ł��B�W���l�[�u�ɂ͎��̂ق��Ƀ��V���g������唩�r�v�A�����J���ǒ��A�ΐ�O�C(���E�ǔ����H�w�@������)�A�ē���(���E�ǔ��V�������{�ЕҏW�Ǒ���)�����h���A�����փ��X�N���x�ǒ�(���E�ǔ��V�������{�В��������{����)���W���l�[�u�ɏW�����܂����B����Ɍ��n�̒����������h�������܂����B���̂Ƃ��̑唩�r�v�A�����J���ǒ������A�����܂������u�]���v�̂�����ŏЉ���T�C�S�����h���Ƃ��ẮA���̑O�C�҂ł����y�ł��B �@
���̂悤�ɑ����̓��h������́g�����h�ɏW�����A���p�I�Ȏ��_�ŕ���P�[�X�͌����Ă܂�ł͂���܂���B���Ƃ���1975�N11���Ɏ����g���o�������p���x�O�����u�C�G�ł̑����i����]��c(�T�~�b�g)�ɂ́A�������琭�����ƌo�ϕ��̃f�X�N���܂߂�4�l�A�{���A�����h���A���V���g�����炻�ꂼ��1�l�����h�����͂��Q���A�p����(���̂Ƃ����܂�)�唩�x�ǒ��A����Ɏ������ꑍ��9�l����ށE�ɓ������Ă��܂��B �@
1973�N1��28���A�x�g�i���a���p�����肪�����������}�����Ƃ��̓ǔ��T�C�S���x�ǂɂ�9�l�̓��h�����Ђ��߂������A���ꂼ��d����U�蕪����ސ�ɎU���Ă��������̂ł����B �@
�����̋L�҂��W�܂�L���������ꍇ�A���Ƃ��ΐV�����ʂłǂ�Ȃ��Ƃ��N���邩�A�F���ӂ��Ď��ʂ����āA�l���A���͂������Ƃ�����܂����B�V���̏k���ł����o���ČÂ��L����ǂݕԂ��Ă݂�ƁA���̕ӂ̎���悭�킩��܂��B�W���l�[�u��k���n�܂���11��19���̗����̓ǔ��V���E����������ƁA1�ʃg�b�v�Ɂu�ă\��]��k�n�܂�v�u�`������2�l�Ŏ������c�v�u�\��O�̍ĉ�k�@�v2���ԁg�ǂ�����h�v�uSDI(�Đ헪�h�q�\�z)�ł͑Η����v�Ƃ������o�������Ă��āA�V���̐��E�Ō����u�������[�h�v�A�܂��k�S�̂̓�����v�܂Ƃ߂����͂����̂悤�ɑ����Ă��܂��B �@
�y�W���l�[�u19�����ǔ����h���c�z���[�K���đ哝�̂ƃS���o�`���t�E�\�A���Y�}���L���̑����]��k�́A���E���������钆�A19���ߑO10��(���{���ԓ����ߌ�6��)�߂�����A�W���l�[�u�x�O�̕ʑ��u�t���[���E�h�[(���̉�)�v�Ŏn�܂����B�ă\����]�̊獇�킹�́A����79�N�̃J�[�^�[�E�u���W�l�t��k�ȗ�6�N���Ԃ�B���[�K���A�S���o�`���t����]�͂��̓��A�`���̃T�V�̉�k�ŁA�\���15����啝�ɏ���1����4���ɂ킽���ċ��c�A����Ɍߌ�̑S�̉�c��ˊO�ōēx50���A�\�z�O�̈ٗ�̌ʉ�k�𑱂����B����]�̐����炸��k�̂ق��A�ߑO�ƌߌ��2��A�o��6�l�̑�\�c���������S�̉�c���s�Ȃ�ꂽ�B�����ɂ��A��1���̘b�������ŁA���N�A�A�����J�Ŏ����]��k���J������A�W���l�[�u�ă\��R�k������̓I�ɑO�i���������ɂ��Ă��ӌ��������s�Ȃ�ꂽ�͗l�ł���B�S���o�`���t���L���́A�ʉ�k���\����啝�ɉ��т����Ƃɂ��āu�ǂ����Ǝv���v�Ɠ������B�܂��A�\�A���X�|�[�N�X�}�����A���獇�킹���u�ǂ����͋C�̒��v�ōs�Ȃ��A�u�ă\�W�v�𒆐S�Ɉ�A�̐������ɂ��āA�u�����I�ȓ��c�v�����������Ƃ𖾂炩�ɂ����B(�֘A�L��2�E3�E5�ʂ�) �@
���̎�̏d�v��k�ł́A�������[�h�̖����ɋL����Ă���悤�ɁA��ʂ̊֘A�L�������̃y�[�W�ɂ��U�蕪�����Čf�ڂ���܂��B��]��k��ނɐ��E������W�܂����w��3400�l���z���܂����B���{�̐V���Ђł͒����A�����A�Y�o�A���o�Ƃ������S�����̂ق��ɖk�C���E�����E�����{�̃u���b�N���Ȃǂ��ǔ��Ƃقړ����K�͂̋L�Ғc�𑗂荞��ł��āANHK�A����TV���������đs��Ȏ�ލ����W�J���܂����B�Ƃ����Ă��L�Ғc����]��k�̕����Ɏ�ނ̂��߂ɂǂ��ǂ��Ɠ��ݍ��ނ��Ƃ́A���R�̂��ƂȂ��狖���ꂸ�A�������͓��݂̃v���X�Z���^�[�őҋ@�A�ă\�����X�|�[�N�X�}���̌o�ߕ�����Ƃ��������ƁA��ĂɋL�Ҏ����яo���čs���L�l�ł����B �@
��c��O�ɐw���A�܂����̏ꏊ�Ŏ�ށA�ڌ������b��́u�W���l�[�u�ւ�v�Ƃ����R�������ɏ����܂����B���Ƃ����[�K���哝�́A�S���o�`���t���L���ȉ��ă\��\6�l�������������č����e�[�u���́A���̓��̂��߂Ƀj���[���[�N�̕č��A��\������킴�킴��A�������ƁA��A�̓r���A�r����{�܂�A��k�̐挭�����n���n���������ЂƖ������������ƁA���[�K���哝�̂����}���邽�߃t���O���[�E�X�C�X�哝�̊��@�ōÂ��ꂽ18���ߌ�̎��T�ŁA�X�_��5�x�߂��̊����̂��Ƃɗ��������V�����̈�l���A�ˑR�A�C�������Ă�����|�ꂽ�A�Ƃ����b�肪20���t�̓ǔ��E�����u�W���l�[�u�ւ�v�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �@
����������5�ʂ��L����ƁA�����ɂ́u��]��k�@�ă\������Đ���グ�v�u����A����A���_�l����v�u�v���E�_�͐V��Ď����v�Ƃ������匩�o���ŁA����́u�W���l�[�u���v�ł͂Ȃ����V���g���A���X�N���Ɏc�����L�҂��œd���Ă���A�j���[���[�N���h�����u�đ哝�̃S���L���̖K�ėv���ցv�Ƃ������𗬂��Ă��܂��B���̍����Ƃ��ē��h���́A19���t�j���[���[�N�E�^�C���Y���̋L�������p���A�W���l�[�u�؍ݒ��̃z���C�g�n�E�X�����̘b�Ƃ��āu���[�K���đ哝�̂́A��A�̕ă\��]��k����߂�����ɂ������āA�S���o�`���t�E�\�A���L���̖K�Ă�v������ӌ��ł���v�Ƃ�������]�d���Ă��܂��B �@
��k�����̎��ʂ́A1�ʁA2�ʁA5�ʂ���]��k�̊֘A�j���[�X�Ŗ��ߐs�����܂����B�������A��]��k�Ŏ��ۂɉ����b������ꂽ�̂��A�̐S�̂��Ƃ͉����������܂�Ă��Ȃ����ƂɁA�F����A���łɂ��C�Â��ł��傤�B���ہA���n�̎�ތ���ɂ����������́A�قƂ�lj���������Ȃ��܂܁A��]��k�̏������I�����̂ł����B�@
�y�W���l�[�u19�����ǔ����h���c�z�̃N���W�b�g�ŏ����ꂽ20���t�����E1�ʃg�b�v�̑������[�h�́A�����{�Ѓf�X�N�ƃW���l�[�u���n�̑唩�f�X�N�̊ԂŎ����킳�ꂽ�g���h�����Ƃɏ����ꂽ���̂ł����B�������[�h�̕����Ɍ�����u�S���o�`���t���L���́A�ʉ�k���\����啝�ɉ��т����Ƃɂ��āw�ǂ����Ǝv���x�Ɠ������v�Ƃ����\����ǂތ���A���L�����L�Ғc�Ɍ������Ē��ڂɌ�肩�����悤�Ɏ��܂����A�����͂����ł͂Ȃ��A��1��S�̉�c�I�����19���ߌ�1������A�W���l�[�u���ۉ�c�Z���^�[���ŊJ���ꂽ�U�~���[�`���E�\�A�}���ۏ���̋L�҉�ł̓��e���A���̂悤�ȕ\���ŁA�����Ɍ����Ύ����ɔ������`�ł܂Ƃ߂����̂ł����B �@
���̋L�҉�ɏo�Ȃ������X�N���̏����L�҂́A����]�̉�k���u�ǂ����͋C�̒��ōs�Ȃ��A����]�͒P�ɒm�荇���������łȂ��A��A�̐������ɂ��Ď����I�ȓ��c���s�Ȃ����v�Ƃ����U�~���[�`������̘b���A���ژb�@�̌`�ł܂Ƃ߁A�ʓr�A�Ɨ������L���Ɏd���ĂĂ��܂��B �@
����A���V���g�����痈���ΐ�L�҂̓X�s�[�N�X�đ哝�̕��̋L�҉����ނ��A�u��A�̎�]��k�ɂ��Ă̔��\�́A20���̉�k�����I���܂ł͈�؍s�Ȃ�Ȃ����ƂŁA����\�c�����ӂ����Ɣ��\�����v�Ƃ����j���[�X���L���ɂ��܂����B�������L�Ғc�������́A�u���b�N�A�E�g(�ǐ�)�ł��B�ΐ�L�҂��܂Ƃ߂��X�s�[�N�X���̔����v�|�́A���̂悤�Ȃ��̂ł����B �@
��A�ă\��]��k���I������܂ŁA���ӎ������܂߉�k�̓��e�������������\���Ȃ��B�ă\�o���͂��ꂼ��̖��ɂ��Đ^���ȓ��c�����₷���悤�Ɍ��\���T���邱�Ƃň�v�����B��k�̎��ԁA�Q���Җ������ɂ��Ĕ��\����B �@
��A�ă\�o���Ƃ���k�̔w�i�������s�Ȃ�Ȃ��B�đ��͂��̍��ӂ����S�ɏ��炷����̂ł���A��k�ʼn����b����Ă��邩�A��������\���邱�Ƃ͂Ȃ��B��k���e�̔��\��2����(20��)�̉�k�I���ォ�A21�����ɂȂ邾�낤�B �@
��A��k���e�́u�u���b�N�A�E�g�v(�ǐ�)�͉�k�̖`���Ō��肳�ꂽ�B �@
�������ė��j�I�ȕă\��]��k�����̊̐S�̏��́A�ǐ��̂��Ƃɕ����B����A�V���ǎ҂Ɂu�^�̏��v�͓`�����܂���ł����B �@
�������������w�����S�ɂ���グ�ł������킯�ł͂���܂���B��k�ɐ旧���A�������͎��O�̎�ނŁA��k�ʼn����b��������̂��A���̈Ӌ`�͉����Ƃ��������Ƃ��A���ς��A�i��ς��ď����Ă��܂����B�ǔ��V���̏ꍇ�A���Ƃ��u�ă\�T�~�b�g��肤�v�Ƃ����A�ڂ����A���V���g���A���X�N���A���B�̌��������ꂼ��̒n��̓��h�������҂ɃC���^�r���[���A�܂��Ǝ��̎�ނŊW�҂̎��_���܂Ƃ߂Ă��܂��B �@
11�����{�A���̓����h������p���ɔ�сA�t�����X���ۊW������(IFRI)�̃e�B�G���E�h�����u���A�������̌��������̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B���̈ꕔ���Љ�܂��Ɓc��2������A���ې����V�X�e���̑�g�́A�ă\���������ɍ\�z����Ă����B���̊ԁA���� �@
�\�Ƃ��ɕă\�W�ْ͋��Ƌْ��ɘa�̊Ԃ�h�ꓮ�������A�ْ����������������ł����A�������S�ʓI�ɑΗ������킯�ł͂Ȃ������B�܂��A�ْ��ɘa�̎���ɂ����S�Șa�������������킯�ł͂Ȃ������B(����) �@
�����ł��d������̂́A�S���o�`���t�����ڂ����\�A�����̐��̍\���I�ȕϊv�ƁA�f�^���g���������ڂɊ֘A���Ă���_���B �@
���̂Ƃ��ă\��]��k�̍s����肤�����ŁA�N�������f�������ő�̗v���́A�S���o�`���t�E�\�A���L���̑��݂��̂��̂ł����B1982�N11���Ƀu���W�l�t���L���������A��C���L���ɃA���h���|�t�����I�o����܂������A�ނ�84�N2���ɋ}���B��C�̃`�F���l���R�����킸��1�N1�����̔C�����ʂ����������ŁA85�N3��10���ɕa�����Ă���̂ł��B�킸��2�N�����炸�̊Ԃ�3�l�̍��ƌ����������ƂɁA�ˑR�A�r���𗁂тēo�ꂵ���̂��S���o�`���t���L���ł����B85�N3���ɐV���L���ɑI�o�����8������́A�W���l�[�u�ł̕O����ł��B�u�S���o�`���t�Ƃ͈�̉��ҁH�v�u�ނ͉�����낤�Ƃ��Ă���̂��v�Ƃ����i�]�Ƌ^�₪�����N����͓̂��R�ł��B�S���o�`���t���́A�����A���܂�ɂ����ȉ߂��܂����B �@
�������A�����̐V���𒍈Ӑ[���ǂݕԂ��ƁA���L���Ɋւ��鋻���[���L�q�����������邱�ƂɋC�Â��܂��B85�N11��13���t�ǔ��V���E������4�ʂɏ����փ��X�N���x�ǒ����������u���X�N���ōl����v�Ƃ����R�����͂��̂ЂƂł��傤�B�����L�҂�11��7���́A���܁A���J���ς���Ԃ̍L��ŌJ��L����ꂽ�v���L�O���E�R���p���[�h�̖͗l���珑���o���A�����ɗ�Ȃ��Ă���\�A��]�����̎p��ڂŒǂ��Ȃ���A�u�N�������������������Ԃ����v���Ƃ��������܂��B1�N�O�A�����v���L�O���̌R���p���[�h�ɗ�Ȃ��Ă����`�F���l���R���L���A�A�O��3��]�̕��ϔN�75�������̂ɁA���ܖڂ̑O�ɗ�Ȃ���S���o�`���t�ȉ��́A�V����3��]�̕��ϔN���20����Ԃ��Ă��܂����B �@
�u�S���o�`���t���L���̓o��́A�V��A�a��Ȏw���҂ɂ��肵���\�A�������Җ]���Ă������͂Ȏw���҂̏o�����Ӗ����Ă���v�����������L�҂͏����A���C�o���ł��������}�m�t���̗L�������킹�ʉ�C�ƁA�O�����C�R���̍��ƌ���ւ́g�I�グ�h����A�`�[�z�m�t�A�o�C�o�R�t���ƌv��ψ���c���̉�C�ɂ�����X�s�[�h�l���ɁA�S���o�`���t����煘r�Ɖ��v�ւ̌��ӂ�ǂݎ���Ă��܂��B�����āu�O���͓����̉����v�Ǝ咣����S���o�`���t���ɂƂ��ă��[�K�����Ƃ̎�]��k�œ��_���҂��A�АM�����߂邱�Ƃ��u���ݐi�߂Ă�������̍r�Î��̂��߂ɑ傫�ȕ���ƂȂ낤�v�Ƃ��A��]��k�Łu�ă\�W�̈��艻�v�ւ̓����J�����Ƃ��u�Œ�����v���Ǝw�E���Ă��܂��B �@
1985�N11��21�����A�W���l�[�u�̍��ۉ�c�Z���^�[�̋������T�ɗՂ��[�K���đ哝�̂ƃS���o�`���t�E�\�A���Y�}���L���́A�u�ă\��]�A���ݖK��ō��Ӂv�����炩��搂��グ�܂����B86�N�ɃS���o�`���t���L�����K�āA��87�N�ɂ̓��[�K���哝�̂��u���̒鍑�v�ƌ��߂��Ă����\�A�̎�s���X�N����K�₷��Ƃ����̂ł��B��]��k�͂������Ė�����A13���ڂ̍��ӎ����荞���������ɂ́A�u�ă\�j�R�k���i�ň�v�v�u50%�팸�����ʊ�ՂɁv�Ƃ��������ڂ��܂܂�Ă��܂������A�ő�̐��ʂ͏����L�҂��w�E���Ă����u�ă\�W�̈��艻�v�����Ȃ�����]�E�t���̒�����c�֓����J�������Ƃł����B�@
�V���́u���E�̗��j�����ގ��v�̐j�v�̂悤�Ȃ��́A����������u���E�j�����ޕb�j�v�Ƃ���ꂽ���オ����܂��B�e���r��C���^�[�l�b�g�̎�����}���Ă��鍡���A���̕\�������܂��ʗp����̂��A��������ƌ�������K�v�͂���Ǝv���܂����A�V���L�҂Ƃ��Ď�Ƃ��ĊC�O�Ŏ�ފ����𑱂��Ă������l�̑̌��ł����A���ꍏ�Ǝ��Ԃ��ω�������j�̌���Ŏd���𑱂��Ă����Ȃ��ɂ����Ă��̎v���́A�����ς��܂���B�W���l�[�u�ł̕ă\��]��k�̗�ł���������̂悤�ɁA���ɂ͎�ސ�̕ǐ��ɂ���āA�܂Ƃ��ȋL���������Ȃ��߈����r�߂������邱�Ƃ�����܂��B���\���ꂽ����ɂ�����A���͗��ł����Ƒ厖�Ȃ��Ƃ������킳��Ă����ɂ��ւ�炸�A������@�m�ł����^���������Ȃ��܂܂ŏI���A��ɂȂ��Ď��a�肷�邱�Ƃ�����܂��B�������A��ނ̌���ɗ����A�l���A�����A�������ƁA�����������Ƃ��A����ɂ́A�Ƃ��Ɍ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�E�C�������ď����A�ǎ҂ɓ`����Ƃ�����Ƃ�ʂ��ė��j�̏ؐl�ƂȂ蓾��W���[�i���X�g�̖����ɁA���ꂩ����ω��͂Ȃ��ł��傤�B �@
�\�A�̌����ɐ�삯�ă\�A�E�������E��k�������鎖�����A1980�N�|�[�����h�ŋN���Ă��܂��B���̔N��8���A�k�C�ɖʂ���O�_�j�X�N�Ŕ����������D���J���҂̃X�g�́A�u���ԂɃ|�[�����h�S�y�ɔg�y���A�Љ��`�̐���˂����������͂ƂȂ�܂����B���̂Ƃ�������ƕς�����ׂ����A���X�����`������l�̃W���[�i���X�g�����܂����B�t�����X�E�������h���̃x���i�[���E�Q�b�^�L�҂ł��B�ނ̓����V��������A�����ăO�_�j�X�N���烋�����h���ɘA���̂悤�ɒ����̃��|���^�[�W������������A�����A�ǔ��̓����{�ЂŃf�X�N�̃|�X�g�ɂ������͓����̐쓇���Y�L�҂Ƃ��̃��|��|�A�V�]�_�Ђ���ً}�o�ł��܂����B�|����˗����Ă����̂͌��݁E�������X�̎В��A�����ǗY���ł����A���{�l�L�҂������Ȃ��������Ƃ��A�|���ʂ��Ăł����{��ɖēǎ҂ɓ`�������Ƃ��������v�����A�������ɋً}�̎d�����������������@�ł����B���ɂ͖|��Ƃ�����Ƃ��A�W���[�i���X�g�ɂƂ��Č������Ȃ��C���̂ЂƂ��Ǝ��͍l���Ă��܂��B �@
�x�g�i���푈�̎�ނŎU���Ă������J�����}�������̎ʐ^�W����N5���A�����ّ�w���a�~���[�W�A���ŊJ�Â��ꂽ���Ƃ́A�F����̋L���ɂ܂��V�����ł��傤�B���̂Ƃ��̎ʐ^��������ƂɁw���N�C�G���x�Ƒ肵���ʐ^�W(�W�p��)��97�N10���ɕāE�p�E����3�J���œ����o�ł���܂����B���̎ʐ^�W�Ɋ�ꂽ���ċL�҂����̒Ǔ�����֘A�L���̖|��������������̂������C������ł����B���̃x�g�i���̌����d�ˁA���ɎU�����J�����}�������A�ނ�̎ʐ^�ɒǓ��������������ċL�҂����́A�Ȃ��M���v���Ɏ����g�������A�|���Ƃɑł������̔N�́A�Ă̊��̌��������{��Łw���N�C�G���x�ƂȂ��āA���߂ē��{�̓ǎ҂̂��̂ƂȂ����̂ł��B �@
�����́A�������čŏI�u�`�Ƃ����V���̏�ɗ����Ă��܂��B����5�N�Ԃ�U��Ԃ�Ƌ����Ƃ��ĊF����ƌ������������Ƃ̓����Ɋ����܂����B�����Ƃ��āu������v�Ƃ����ӎ������ƁA������܂��܂�����Ă����܂����B�������A����Ƃ����玄�́u�����ƂȂ������܂��A�W���[�i���X�g�ł��葱�������v�v�������o����悤�ɂȂ�A����ȗ��A�݂Ȃ���Ǝ��R�̂ŕt��������悤�ɂȂ�܂����B �@
�����ّ�w���ۊW�w���ɂ́A�ސE���鋳���̂��߂ɋL�O�_���W��ҏW���Ďc���Ƃ������肪�������킵�����K������A���ܕҏW��Ƃ��i�߂��Ă��܂��B3���̑��Ǝ��ɂ͑��Ɛ��S���ƍ݊w���ɔz�z�����A���̋L�O�_���W�ɃW���[�i���X�g����̐�y�A�F�l�A����4�l����e���Ă���Ă��܂��B���̒��̈�l�A���ă��X�N���x�ǒ������������L�҂������Ă��ꂽ���e�ɂӂ�Ȃ���A���̂��傤�̘b���I���ɂ������Ǝv���܂��B �@
�����L�҂͌��݁A�ǔ��V�������{�Ђ̒��������{�����Ƃ�����E�ɂ��Ă��܂����A���܂Ȃ��W���[�i���X�g�Ƃ��ē��{���\���郍�V�A�����Ƃ̈�l�ł���܂��B����A�ނ́u�v�[�`���̃��V�A�v�Ƒ肵�āA400���̌��e�p����50�����z���镶�͂������Ă��܂����B���̂Ȃ��ɋ����[���L�q������܂��B�\�A�̔閧�x�@�E���ƈ��S�ۈ��ψ���(KGB)�̃G���[�g�Ƃ���16�N�Ԓ���@�ֈ��Ƃ��ē������v�[�`���́A���̌�A���X�N���Ő����̒����ɓ���A�G���c�C���̌�p�҂Ƃ��ă��V�A�哝�̂ɂȂ����l���ł����A����ȑO�ɉ߂������T���g�y�e���u���N����ɃL�b�V���W���[�����������ƑΖʂ������Ƃ�����Ƃ����܂��B���̂Ƃ����č�����������������t���w�v�[�`���A��������x(����E�w�I�g�E�s�G�����H���@�E���c�A�[�x�����{�ł�2000�N3���|�s)�̒��Łu�\�A�͓������炠��Ȃɑ����P�ނ��ׂ��łȂ������B �@
(���̌���)�����͂��܂�ɂ��������E��(�͂�)�ύt��ς��邱�ƂɂȂ�A�]�܂����Ȃ����ʂ������\�����o�Ă����B���������āA�S���o�`���t���ǂ����Ă���Ȃ��Ƃ������̂��A���܂ł������ł��Ȃ��v�Ƃ����\���ŏЉ�A�ނ́u�Ԉ���Ă��Ȃ������v�ƒf�����Ă���Ƃ����̂ł��B�����ăv�[�`���́u�����A���̎��A�傠��Ăœ����o���Ȃ�������A���̂��ƁA�����͂���߂đ����̖�肪�N����̂�����ł������낤�v�Ǝ��猋�_�Â��Ă���̂ł����A���̋L���Ƒ̌����哝�̂ɏA�C�����v�[�`���ɐ^����Ɂu�������V�A����v��ł��o�����邱�ƂɂȂ����Ə����L�҂͏����Ă��܂��B �@
�����L�҂�85�N�̃W���l�[�u��k�̂��ƃ��X�N���ɖ߂�A�S���o�`���t���L�����f�s�����y���X�g���C�J(���Ē���)�ƃO���X�m�X�`(�����J)����������ɒǂ������A�\�A�̐����ƁA���j�w�ҁA�����l�A�o�ϊw�҂�100�l���z����v�l�Ƃ̃C���^�r���[���J��Ԃ��L���ɂ��܂����B��Ɂw�\�A�m���l�@�y���X�g���C�J�����x(�ǔ��V���Ё@1990�N��)�Ƃ����{�ɂ����Ă��܂��B��������\�z�ł��Ȃ������قǂ̃X�s�[�h�Ői�S���o�`���t�̉��v���A�t�Ƀ\�r�G�g�A�M�̉�̂ƃG���c�C������̍��������������j�̔���B�����ڂ̓�����ɂ��Ă��������L�҂ɂ��������Ȃ��u�v�[�`���̃��V�A�v�ł��B �@
�u���V�A�̓I�[�v���Ńo�����X�̂Ƃꂽ�A�����ȊO���𐄐i���Ă����B���V�A�O���̒��S�́A���V�A�̗��v�����������邱�Ƃł���A��������������ʂ����Ƃł���B���V�A�O���̐V�v�f�́A���ۏ��]������ɂ������Ă̌�����`�Ɗ��S�Ȏ�����`���v�\���̌��t�̓v�[�`���V�����̊O���ɂ��ăC�[�S���E�C���m�t�O�����p�����\���ł����A2001�N�H�A�č��ŋN����9�E11���������e��������̑Ή��Ɏ��������V�A�̑ΕĐ���𗝉����邤���ŃJ�M�ƂȂ���̂ł��傤�B�u���v����`�v�O�������Ɋ�Â��A�v�[�`���哝�̂́A������A�����Ƃ����������ɃA�����J�ւ̑S�ʎx����\�����A�u�b�V�������̃e���푈�ɋ��͂���5���ڂ̌�������\���܂����B�����A�W�A�̋��\�A���a���ւ̕ČR������F�߂��̂��v�[�`���̃��V�A�ł����B�`�F�`�F�����Ƃ����g�Q����������V�A�ɂƂ��āA�Εċ�����O�ʂɏo�����Ƃ������̍��v�ɍ��v����Ƃ����v�Z�������ɓ����Ă��܂��B �@
���Ȍ�́g�A�����J��l�����h�Ƃ����鎞�オ�����������ł��A�ă\�̋��͊W�����E�̓��������E���Ă��鎖���̈�[���A���V�A�̃u�b�V�������ւ̑f�������͎p���\�����炤�������m���悤�Ɏv���܂��B2001�N��9�E11�������獡���̃A�����J�̑C���N����ɂ��ׂĂ����ʂ���`�ŁA���E�͓����Ă��܂��B���̏͂��܂��炭�����ł��傤�B����̋L�O�_���ɂ͏����L�҂̂ق��ɂ��w�O�҂̓��ʊ�e�����߁A�ɓ����F��(�a����w�����A�������V���L��)�ɂ��2002�N�̃h�C�c���I���ƃV�����[�_�[�̑C���N�ւ̎Q�틑�ې����A���q��j��(������w�����A���ǔ��V���L��)�ɂ��|���|�g���ێi�@�ٔ��A��؉떾��(�ǔ��V�������{�Љ��������)�ɂ��ߑ�g���R�q�含�r�̌n���Ɋւ���A���ꂼ�ꌻ���ނɊ�Â����͂��Ă��܂����A����炪���ׂđΕĊW�ɐ[�����т��ēW�J����Ă��邱�ƂɁA���ۊW�̓�������Ɋ����܂��B���ۊW�w���w�Ԏ�u���Ɂu���E��ǂ݉�����i�v�Ƃ��ẴW���[�i���Y���̏d�v���ƗL����������Ă������̌ܔN�Ԃł����B2003�N�����ɂ��̂悤�Ȍ`�ōŏI�u�`�����Ă��Ӗ������߂Ă��݂��߂Ȃ���A�{���̘b���I��点�Ă��������܂��B�@
 �@
�@�����E�͕���A�l�݂͂Ȗ���
���̐V���L�Ґ����͖�37�N�Ԃɂ���т܂����A�����ނ˓��ɗD�G�ȋL�҂ł������킯�ł�����܂���B�悭�u�Ȃ��L�҂ɂȂ����̂��v�ƎႢ���X�ɕ�����܂����A�����������v���A���̕���͂��܂莋��ɂȂ������ɂ���A��┙�R�Ƃ�����I�Ȃ��̂ł����B���̍��Z�����50�N������60�N�㏉�߂���A���{�Љ�ɂ��e���r���}���ɕ��y���ANHK�̃h���}�ԑg�Łu�����L�ҁv�Ƃ����̂�����A�悭���Ă��܂������A��ʂ̉�А����ƈႢ�A�d���̌��������M����ɂ��Ă��A�Ȃ�Ƃ����R�ŁA�i�D�����ȂƊ����A���ꂪ�����̐E�ƑI���̑傫�Ȃ��������ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B�������A�����L�҂ɂ������ꂽ�킯�ł�����܂���̂ŁA�L�Ґ����̑����Ƃ��Ă�������o������n���x�ǂ̌x�@�S������͖{���Ɍ˘f�����Ƃ���ł����B�V���̖��́A�����̂����u���_�l�v���ƃf�X�N����悭���B����܂������A�傫�Ȏ����𑼎Ђɔ����ꂽ���A�����L�҂Ƃ��Ă͎��i���ȂƂ˂ɓ��S�v���Ă��܂����B���Ȃ݂ɁA�}�X�R�~�ƊE�ɂ͓��_�l�ƂƂ��ɁA�u�������v�Ƃ����p�ꂪ����A�O�҂͈�Ђ����̃X�N�[�v�ł���̂ɑ��A��҂͈�Ђ������̏d�v�ȃj���[�X�𗎂Ƃ������Ƃ������̂ł��B������u�������v�̏ꍇ�͒S���L�҂͂���ɖʖڂ��������ƂɂȂ�A�f�X�N���痋�������邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂾ���͉��Ƃ��Ă����������Ǝv���Ă��܂����B �@
�����A���̌��t�͋ƊE�p��ł���A�W���[�i���Y�������̏��s�𑪂�ЂƂ̃p���_�C���ł���ɂ��Ă��A�Љ��ʂɒʂ��鋣�������ł�����̂ł��B���̂悤�ə��ė������Ă�������A�悢�̂ł��B �@
�삯�o���̂���A���Ƃ��傫�Ȗʎq�͎������ƂȂ����z���Ă�������ł����A5�N�Ԃ̒n���x�ǂ��瓌���{�Ђɓ]�ɂȂ�ہA�����������Љ�͂ǂ����Ă������Ǝv���A���ە̕�����u�]���A�^�悭�����ɂ����肱�ނ��Ƃ��ł��܂����B�����Ƃ��Ă͐V���L�҂Ƃ����A�Љ�L�҂��Ԍ`�ł�������A���ە͂���ΖT���̐��E�ł����B����ł����ɂ͑�ϋ��S�n�̂悢���E�ł����B �@
�L�����ێЉ�̐����A�o�ρA�����A�Љ���ȂǑ��l�ȃe�[�}��ǂ�������Ƃ����d���͂܂��ɖڂ̑O�̐i�s�`�̌���j�ɗ�����邱�ƂɂȂ邩��ł��B�V���̎Љ�I�����⏤�ƓI�ȉ��l�ɂ��Ă͋c�_�͑��X����܂����A��ԏd�v�ŁA����ɂ�����炸�s�ςȂ��Ƃ́u�L�^���v�ɂ���܂��B���j���L�^����Ƃ��������ł���܂��B�ނ��A����͌��t�ŕ\������̂͊ȒP�ł����A���ۂɂ͑�ϓ�����Ƃł��B�L�^�Ƃ����Ă��A���̉��l�́A��N�ǂݕԂ��Ă��\���𗧂��̂łȂ���Ȃ�Ȃ�����ł��B���z�I�Ȃ���������Ɂu���j�ɑς���L���������v�Ƃ����̂�����܂����A����Ȃ��Ƃ͂���ɂ��ł��邱�ƂłȂ����Ƃ͎����ł��傤�B����ł��A�ꉞ�̐S�\����ӋC���݂͂�������ׂ��Ȃ̂ł��B �@
���͍��ە̕���ŁA��15�N�ԁA�O����炵���o�����A���C��͍K���s�K�����E�e�n�ɂ܂�����܂����B����āA�A�t���J�A�A�W�A�A�����A�č��A���B�Ɛ��E�̑��ʂȍ��X��n������A���l�Ȑ��E���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��܂����B���E�͐�i���Ɠr�㍑�ɑ�ʂ���܂����A���̎������炷��A�l�Ԃ̊�{�I�Ȋ���ł����{���y�͂ǂ��ł������ł��B����Ȃ��Ƃ͓�����O�ł͂Ȃ����ƌ����邩���m��܂��A�ł������I�ɂ́A�l�Ԃ̐������o�ɂ͏�Ɉ��̋�����������A�����n��Ɛg�߂Ȑ��E�Ƃł͂���ł������͈Ⴂ�܂��B���̈ӎ��̋��E�������ɔ�щz���邩�͊F����������̊w���Ő�����o�ρA���邢�͕����Ȃǂ̊w��̈��ʂ��Ċw��ł��������邱�Ƃ��Ǝv���܂����A���͂����Č��������͉̂Ƒ���F�l�Ȃǂ��ꂼ��Ɉ�Ԑg�߂Ȑl�����̂��Ƃ�_���ɍl����A�������E�̐l�����̂��Ƃ����̂��Ɨ����ł���悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B�Љ�̍ŏ��P�ʂł���Ƒ��̉��l�ς𗝉����邱�Ƃ��L�����ێЉ�̗����ɂȂ���A���ꂪ�ł��d�v�ł���Ƃ������Ƃł��B�Ȃ��Ȃ琭�����o�ς����������ׂĐl�Ԃ̉c�ׂł��邩��ł��B�t���I�ɂ����Ȃ�A�������Ȃ���A���ۓI�ɂ͂킩���Ă��A�؎��ɗ������A�s�����邱�Ƃ͓����������܂���B�@
���܂�v���o���������Ȃ��o���ł����A���͐E�Ə�A�������̐푈�����A�������o�����A�����̖��̊댯��{���Ɋ��������Ƃ�����܂����B�����̃��o�m���Ƃ������ɒ��݂��Ă���1982�N6���A�ׂ̃C�X���G�����ˑR�A���o�m���N�U����W�J���A��s�x�C���[�g���Ɩڂ̑O�̒n���C�̉���������͖̊C�ˌ��A�����Ď�s���͂�����Ԃɂ��C���ƎO���ʂ���ҍU����܂����B��s�͊��I�̎R�ɂȂ�܂����B���o�m���͓����C�X���G���ƓG���Ă���PLO�i�p���X�`�i����@�\�j�A�܂�p���X�`�i�E�Q�����̍ő勒�_�ɂȂ��Ă�������ł��B �@
���̌R�����͍ł����������Ԃ����悻3���������A���̒��ŁA�d�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�A���̖C�����̍����ƂƂ��ɐ������A���鎞�ɂ͎x�nj�����Ƃ��ďZ��ł����L���}���V�����̉��ڊԂƃx�����_�����傫�ȃK���X��4�������S���[�g����ɗ�������g�����e�̔����ŁA���X�ɂȂ�܂����B�������ɑ����k���܂����B�߂��̒n�����ɉ��x����э��݂܂����B�}���V�����̕����̒����A�����̊K�i�̗x���̂ق��������͈��S���Ǝv���A�����Ԃ����ɍ��荞�݁A�g�у��W�I�Ńj���[�X���Ȃ���A�߂������Ƃ�����܂����B �@
���̊��ԁA�����̂悤�ɒf���A��d�ł��B�g�C���̐��͂��炩���ߗp�ӂ��Ă����~�l�����E�H�[�^�[���g���A�_���v�J�[�p�̑傫�ȃo�b�e���[��p�ӂ��A���̓d�͂��g���ăe���b�N�X�����A���e�𓌋��ɑ����Ă��܂����B�i�e���b�N�X�Ƃ����Ă��A�F����ɂ͂ǂ�ȋ@�B���������Ȃ��ł��傤���A��^�̃^�C�v���C�^�[�̂悤�Ȃ��̂ŁA���{��̕��͂����e�[�v�Ƀ��[�}���őł����݁A���̃e�[�v��d�b����𗘗p���đ���ƁA��̓����@�B�̃��[�����Ƀ��[�}���������B���̃��[�}���̕��͂��肪���{��ɖ߂��A���{��̋L���Ƃ��ĐV���Ɍf�ڂ���j�B �@
�p���X�`�i����j�̑傫�ȏ��ՂƂȂ����x�C���[�g�̃p���X�`�i�l�̓�L�����v�ł̑�s�E���������̎��A�������܂����BPLO�̃A���t�@�g�c���ȉ��A��v�����͂������A�����̐퓬�����`����D�ɏ悹���A�`���j�W�A�ȂNjߗׂ̃A���u�����ɒǕ�����܂����B���������^���̂��ƁA88�N�APLO�͏��߂ăC�X���G�������F���A�e���������\���A90�N��ȍ~�̃I�X�����ӂȂǂɂ��C�X���G���E�p���X�`�i�̋����̐��ւ̐V�����͍��ւƐi��ł������킯�ł��B�����A���܊F�����Ă���������悤�ɁA�܂��p���X�`�i�Ɨ����Ƃ̒a���ɂ͎����Ă��܂��A�ނ���A�\�͂̉��V�͉ߌ������A������[�߂Ă���̂�����ł��B�����Ă��̃p���X�`�i�����j�Ƃ������������̃}�O�}�͂Ȃ����E��h�邪���N���܂ł��葱���Ă��܂��B �@
�W���[�i���Y���̐��E�ɂ͐̂���u�푈�͋L�҂�b����v�Ƃ���������������܂��B�����A���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B�푈�Ƃ����̂́A�l�Ԃɑ���Ȕߌ��������炷���̂ł����A����ŁA�������̂��ׂĂ̎p�A�������o�ς��������A�D�����������A���ׂĂ��Ƃ炵�o����邱�ƂɂȂ邩��A�L�҂͂���ƕK�R�I�Ɍ��������A�����ɕ��͂��邱�ƂɂȂ�܂��B���̂��Ƃ������̂��Ǝv���܂��B������\����ς��Ă����A�W���[�i���Y���̐��E�����̂��Ƃł͂Ȃ��ł��傤�B�v�́A�l�Ԃ͎����ɂ���Đ�������̂��A�Ɨ������ׂ��Ȃ̂ł��傤�B�������A�����������Ƃ������ƁA�����ɂ��Â��b�ɂȂ�܂����A�ꍇ�ɂ���Ă͍D��I�Ȉӌ����Ǝ~�߂��Ă��܂��\��������܂��̂ŁA�ЂƂ��ƌo���̊��z�������Ă����܂��B�푈�́A�E�ƓI�ɂ͂��₩�Ȋ���ƂȂ��Ă��A���_�I�ɂ͋����������c��܂���B�v���o���������Ȃ��Ƃ������̂́A���������Ӗ��ł��B�푈�͎�ގ҂ɂ����ǂ��K������܂��B �@
�����ɁA���a�̑����͒��ۘ_�����ł͌������E�ɂ͒ʗp���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��������܂����B�@
�܂�Ȃ��b�𑱂��܂��ƁA�J���u�C�Ƀn�C�`�Ƃ������ăt�����X�A���n�����������ȍ��l�̓���������܂��B�L���[�o�ׂ̗ɂ��铇���ł��B���̍��ł͐e�q��㑱�����f���o���G�����ƌĂꂽ�ƍِ������N�Ղ��A���̓��ڂ̓ƍَ҂������̔�����86�N�ɓ|����܂����B �@
���̓ƍى����̓��ق��́A���l�Љ�`���̌��n�@�����I�݂ɑ���A�閧�x�@���g���č�����e�����Ă������Ƃł��B���̔閧�x�@�̑��݂̓C�M���X�̒����ȍ�ƃO���A���E�O���[���������u�쌀���ҁv�ŕ`�������Ƃł��L���������̂ł����A�Ƃ�����A���̓��ڐ������œ|���ꂽ�ہA��ނ����܂����B�������E�̂��߉�������č��̗͂ɉ�����A�哝�͍̂Ō�ɉƑ��Ƃ��ǂ��A�ČR�������������R�p�@�ɏ悹���A��s�̋�`����t�����X�ɖS�����܂����B �@
�哝�̂̉Ƒ������A�܂��ƍ�����Ȃǂ�ςԂ̗�`�ɓ��������ۂɖڌ��������i�͖Y����܂���B�����ȍ��ُ̈�ȓƍَ҂̂ЂƂ̏I���h���}�ł����Ȃ��̂ł����A���͂̚���Ƃ��̖��H�̔߈��̍\�}���ڂ̑O�ɍ��R�ƕ����яオ��A��R�Ƃ������o�ɏP���Ă��܂��܂����B �@
�m�����̓����N�ɂ́A�t�B���b�s���̒����ƍَ҃}���R�X�����O�Ǖ��ƂȂ�A����ɏ����O��70�N�㖖�ɂ́A�u���̒��̉��v�Ƃ���ꂽ�C�����̓ƍَ҃p�[���r�����O�Ǖ�����܂����B �@
�����̎�����U��Ԃ�A���������߂ċ����z�N����̂́A���I�������Ƀ\�A�̃S���o�`���t���Y�}���L�������h�C�c�w���҂ɑ��Č����������A�u���j�ɒx��Ă����҂́A���j�ɔ�������v�Ƃ����x��ł��B�����̖��剻�����߂č��܂鍑���̐��A�܂���j�̐V�����g�ɓ݊��Ȃ܂ܑΉ��ł��Ȃ��ƁA���̗��j�ɂ����ؕԂ�����Ƃ������Ƃł��B����ȗ��j�h���}�̃A�i���W�[�͌Í������A�ӂ�ɂ���܂����A���̃��b�Z�[�W�͉��������w���҂Ɍ��������̂ł͂Ȃ��A��ƌo�c�҂⑼�̂ǂ�ȋ@�ցA�g�D�̐ӔC�҂ɂ��ʗp�ł���̂ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���Ă��܂��B�ނ��A�F������w����Ⴂ����̕��X���悭���̋��P���w�ю��A���ꂩ��̐l���v�̎Q�l�ɂ��Ă������������Ǝv���܂��B�@
�Ƃ���ŁA���̎��Ԃ͎��Ɖ��c�搶���S�����A�O���Ȃ̊O�s�g�D�ŁA���l�ȍ��ە����𗬂̐��i�@�ւł��鍑�ی𗬊���iJF�j�̂����͂Đi�߂Ă��܂����V���[�Y�u���u�O���l�����҂��猩�����{�v�̍ŏI�҂̎��Ƃł������A���܁A�Ƃ�ł��Ȃ��ԊO�҂ƂȂ��Ă��܂��܂����B���̂܂܂ł͐\����Ȃ��̂ŁA���̎��ƂɊ֘A�����邽�߂ɁA���̑����̒m����o������l�����A����Ύ��I���ی𗬘_�����b�������Ǝv���܂��B���I�ƒf���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���ɂ͊w��I���ЂȂǂ܂������Ȃ����A�F����̎Q�l�ɂȂ邩�ǂ������킩��Ȃ�����ł����A���ɂ͂���Ȍo��������܂��B�^�C�ɒ��݂��Ă���92�N6���A���̏����O�ɃN�[�f�^�[�Ő������Ƃ����R�������ɑ��A�����̖��剻�v���^�������܂�A���l�Ȏs���O���[�v�������̂悤�Ƀo���R�N�ŊX���f�����J��L���܂����B����ɑ��ČR���͔��C���A���������ʁA��ςȗ��������ɔ��W���܂����B �@
���ꂾ�����Ɠr�㍑�̂ǂ��ɂł����邱�Ƃł����A�s���̃f���Q���҂ɁA�^�C�l�̐l�������Ƃƌ������Ă����ЂƂ�̓��{�l���������܂����B���̕v�w�̓o���R�N�̃X�����X�ŕn�����l�����̎x�����������Ă����̂ł����A���{�l�����͓����D�P���Ă���A�����A�R���ɑߕ߂����A�g�̂̈��ۂ����R���O����܂��B�����ŁA���n�̓��{��g�ق���匈�S�����A�ޏ������������g�ق̊֘A�{�݂ɕی삵�܂����B��g�ق͎��O�@���ł��̂ŁA���S�ł͂���̂ł����A���̍s�ׂ̓^�C���{����݂�A�@�I�ɂ͓������ɂȂ�\��������킯�ł��B�����W����������d��ȗv���ɂ��Ȃ�̂ł��B�܂�A�����Ɛ��{�̑Η��̒��ŁA���{��g�فA�܂�A���{���{�͎s�������ɖ��������Ƃ����߂ł��邩��ł��B�^�C���{���v������A���n��������������Ȃ���������܂���B�������Ƀ^�C���{�͂���قNj��d�Ȃ��Ƃ͈���Ȃ������̂ł����A���̂ЂƂ̔�b�͍��ی𗬂̌��������킩���Ă����������߂ɂ��`���������̂ł��B �@
�ޏ��͓���I�ɂ̓X�����Z�����x������Ƃ����C�������������Ă����̂ł���܂����A�l���x���Ƃ����Ă����̍��̐����̐��E�Ɩ����ł���킯�ɂ͂����܂���B �@
���łɌ����܂��ƁA���̗��������ł̓^�C���������ςȌh�����Ă���v�~�|���������Ō�ɐ��{�A�����{���w���҂̒���ɓ���A���{�ɗ��w���҂��Ă�ŁA�a���𑣂��܂����B �@
�����͂Ђꕚ����l�ɑ��A�u���Ȃ����̑����ň�ԑ�������̂͂���ł����v�Ɩ₢�����A�u����͍��Ƃł��v�Ɨ@���܂����B���̐ڌ��̌��i�̓e���r���p����܂������A���̂��ƁA�����ɂ͑����̎��Ԃ������܂����܂�܂����B�Ȃ�Ƃ��s�v�c�ȁA�M�����Ȃ��悤�Ȃ��Ƃł��B �@
�����ɂ͌��@��A���̐����I�Ȍ��͂�����܂���̂ŁA���͂��������Ƃł������̂ł��傤���B �@
�ނ��A����Ȃ��Ƃ͂���܂���B����͂��̍����L�̂��ƂŐ�قnj����܂����悤�ɁA�����Ɍ��͂͂Ȃ��Ă��A�����̐��Ȏx�������邩��ł��B���̃P�[�X����F������Ɂu���́v�Ɓu���Ёv�Ƃ��������l���Ăق����Ǝv���܂��B �@
�]�v�ȉ�蓹�����Ă��܂��܂������A�{�ɖ߂��āA���̌��������ЂƂ̂��Ƃ́A���ە����𗬂��l����ہA���̍��̐����A�o�ρA��������������Ɨ������Ă����Ȃ���A�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����Ƃ������t�ň�ʓI�ɑz�肳���̂́A���w�≹�y�A���p�A�f��Ȃǂł����A�ނ��덡���̐��E�͐�����o�ς��V�X�e���i���x�j�Ƃ��Ă��́A�����I�ȑ��ʂ��番�͂���K�v���܂��܂����܂��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�O���[�o���[�[�V�����̐i�W�ƂƂ��ɁA�����镪��ŃO���[�o���E�X�^���_�[�h�������ɏ������Ă��܂����A�������o�ς����x�Ƃ��Ă͊�{�I�ɓ����ł����Ă��A���ɂ���Ă��̉^�c���@�͈Ⴂ�܂��B���ꂪ�������ƍl���܂��B�����̌`���ɏ@���͑傫�Ȗ������͂����Ă���̂ł����A���{�l�͏@�����͋ɂ߂ċ��ł��B�������������āA�����܂��Ȓm����������܂���B�������A���͕����Ƃ͑傫�ȈӖ��ŁA�u���l�ρv���Ǝv���Ă��܂��B�����當���𗬂Ƃ͒P�ɕ����̑��ݗ����Ƃ������Ƃ����ł���������Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B���ی𗬂͂���Ή��l�ς̑Θb�ɂ��̖{���I�ȈӋ`������A�����Ή��l�ς͏Փ˂��A�댯�ȉΎ����������������E�ł���Ƃ������Ƃ��F�����Ăق����Ǝv���܂��B�o���R�N�̓��{�l�����̃G�s�\�[�h���炻�����������Ă������������Ǝv������ł��B �@
�������Ă݂�ƁA�����I�Ȍ𗬂��o�ό𗬂������𗬂��s���̈�̂ł��B�o�ς̐��E�ł͑��l�Ȑ��i�A���i��\�t�g�E�G�A�Ȃǂ����ۓI�ɗ��ʂ��A�ΊO�I�ȓ����������ɍs���Ă��܂��B���̐��i����z�Ⓤ���z���o�ϓI�ɂ͐����Ōv�Z����܂����A���i���̂ɂ͗����╶���I���l�Ȃǂ̈��̎v�z�Ȃǂ����ꂼ��ɉ����Ċ܈ӂ���Ă���ƍl���Ă��܂��B���{�͂��Ē����^�̃g�����W�X�^�[���W�I��E�H�[�N�}���Ȃǂ̐��i���J�����A���̕����I�ȉ��l���F�߂��āA���E�s���Ȋ����܂����B���܂͑��l�ȃR���e���c�Y�Ƃ��傫�ȈЗ͂����Ă��܂��B�A�����J�̃f�B�Y�j�[��}�N�h�i���h�Ȃǂ̎Y�Ƃ��o�ςł���ƂƂ��ɕ����ł��邱�Ƃ͂����ɂ�������ɂȂ�Ǝv���܂��B�}�N�h�i���h�Ƃ����t�@�[�X�g�t�[�h�͂��킽����������ɐ�����l�X�́A���C�t�X�^�C���Ƃ��������I���l�ɍ��v�������炱���A���ꂾ���̐��E�s��ɐi�o�ł����̂ł��傤�B�@
�������Ȃ���A���l�ςɂ͕��ՓI�Ȃ��̂�����A����f���Ĉڂ�ς����̂�����܂��B���Ƃ�l�ł����l�ς̏d�S�͈قȂ�܂��B���̍������鉿�l�ς͍����Љ�A�܂��L�����ێЉ�S�̂�s����ɂ��Ă��܂��B�O���[�o���[�[�V�����Ƃ��O���[�o���E�X�^���_�[�h�Ƒ�����Ă��A���ꂼ�ꂪ�w�����������͂����ȒP�ɂ������̋��ʍ��Ƃ��Ď��ʂ�����̂ł͂Ȃ����A�ނ���g�U���鐨���̂ق��������M���܂��B���̕Y�����鉿�l�ς͍��ƃ��x����l���x���ŃA�C�f���e�B�e�B�T���A�����T���̗��ɗU�����ۂ݁A����͂܂��܂��s�����ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�u�����̏Փˁv�_�������������_�ŏ����ꂽ���̂��Ǝv���܂����A�u�����T���v �@
�͍��Ƃ��l�����j�ɂ���Ă����m�F�ł��܂���B�����ŋ����������͍̂��ی𗬂ɂ����炸�ǂ�ȗ̈�̂��Ƃ��w�Ԃɂ������āA���j����������K�����邱�Ƃ��s���ł���Ƃ������Ƃł��B�����͐l�Ԃ̑̌��̗ݐςɂ����j�ɂ���Č`������܂��B�����͗��j�ł���A���j�͕����ł���Ƃ����܂��B�Ƃ���ƁA�ٕ��������Ƃ����̂́A�s��Ȋw�p�I��Ƃł���ƂƂ��ɁA���ꂼ��ɂƂ��Ă̈��S�ۏ�ς��������傫�Ȑ��_��Ƃ��Ǝv���܂��B �@
�����𗬂Ƃ͏]���ĉ��l�ς̑Θb�A�Z���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���A����͐����I�Ȑ��ʂɂ��Ȃ���܂��B���ăI�[�X�g���A�̃n�v�X�u���O�����͓�l�̉����A�}���[�E�A���g���l�b�g�ƃ}���[�E���C�|�[���t�����X�E�u���{�������̃��C16���ƃi�|���I���ɂ��ꂼ��ł����܂����B�����������A���������ł����A����ȓ�̐��͂��͂̏Փ˂�����A���B�̕��a��������邽�߂̂��̂ł����B���̗������Ƃ��ł��Ƃ��A�t�����X�̂ɓ��钼�O�ŁA�t�����X�̃t�@�b�V���������̈ߑ��ɒ��ւ���悤���߂���܂����B���ꂼ��̕�����ʂ������l�ς�Z�����A�����I�Ȑ��ʂ�B�����������ے�����悤�Șb�ł��B���܂ǂ��͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���A�ٕ����Ɛ����̊W���l�@����ۂɂ͏\���Q�l�ɂȂ�b�����Ǝv���܂��B �@
���{�ƃ��[���b�p�̕����I�W�j�ɂ́A���̍u���̍u�t�Ƃ��Ă��Ă����������搶�����{�̕����G����p�H�|�i��19���I�㔼���獡���I�����ɂ����A������u�W���|�j�Y���v�Ƃ��ĉ��B�̔��p�E�ɑ傫�ȉe����^�����Ƃ����b������܂����B �@
���B�͂����m�̂悤�ɍ����A���X�̓������i�W���A����Ȑ����A�o�ό��Ƃ��ĐV���Ȓn�ʂ��ւ��Ă��܂����A���̉��B�����̗��j�ɂ��A�ЂƂ�̓��{�l�����̊�����݂��܂��B����͂悭�m��ꂽ����ł����A��ꎟ���E���O��ɉ��B�����̐��I�Ȍ[�։^���A�ă��[���b�p�^���������n�v�X�u���O�鍑�����i�I�[�X�g���A�E�n���K���[��d�鍑�j�̋M���A���q�@���g�E�N�[�f���z�[�t�E�J�����M�[���݂̕�e���R���q�i�{���~�c�j�Ƃ������{�l�����ł���Ƃ�������ł��B�����ō��������c�ސR�씪�̖��ł���R�~�c�́A�O�����Ƃ���1892�N�ɓ��{�ɕ��C�����n�C�����b�q�E�N�[�f���z�[�t�E�J�����M�[���݂ƒm�荇���A���������{�œ�l�̒j�q���Y�݂܂����A���̎��j�����q�@���g�ł��B�ޏ��͌�ɔ��݂̋A���ɔ����A�̒n�Ƃ���̂���n���K���[��E�B�[���ʼn߂����A����ɐ��l�̎q���������܂����A���{�ŎY�j�q�ɂ͂��ꂼ��ɓ��{�������A���q�@���g�ɂ͉h���Y�Ƃ������{��������܂��B���B�Ń~�c�R�͕v�̎��S�ɔ�����Y�����i�ׂȂNj�J�̑�������ȉ^�������ǂ�܂����A����A�p����E�B�[���̎Ќ��E�ɂ��ؗ�ɓo�ꂵ�܂����B �@
���Ȃ݂ɁA�t�����X�̗L���ȃQ�����Ђ̍����Ɂu�~�c�R�v�Ɩ��t����ꂽ����������܂��B �@
���̍������͂���t�����X�̏����̎�l���̖��O����̂����Ƃ���Ă��܂����A���ݕv�l�~�c�R�̑��݂ɂ��e�������ƌ����Ă��܂��B���q�w���͋߂������A���̍������y���ނ��ƂɂȂ邩������܂���B �@
�܂��A���̒n�Ɉ����Č����A�R���q�͋��s�o�g�ŏ��ƁA���|�ƁA�����l�ȂǂƂ��đ��ʂȊ���������ٍˁA�k��H�D�R�l�ƌ�V�̂������Ô��p�E�̑嗧�ҐR��Y�̐e�ʂŁA�R��Y�̕�e�Ə]�o�����m�ł��B �@
��������̓��{�l�����̍��ی����̂���ȕ���������̂́A���{�ƊO���Ƃ̍��ی𗬂ɂ�20���I�͂��߂̂���A���{�莛�̖��A��J���������֔��@�̂��߂ɍs��������T�K�≓���p�i�}�^�͂̌��݂ɍv�������Z�p�҂ȂǁA�ق��ɂ������̋����[�����j��̓��{�l�����݂��A�����������j�����ǂ邱�Ƃ��A�g�߂ɂ��̕���̕w���ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv������ł��B �@
���������Ԗ��ʘb�����Ă��܂����悤�ȋC�����܂��B�ł��A��w����ł́A�����uCRITICAL�ETHINKING�i�ᔻ�I�v�l�j�v���d�v���Ƃ����Ă��܂��B������A���͂��܁A�������g�̘b���uCRITICIZE�v�i�ᔻ�j���Ă���̂ł��B�Ƃ������Ƃł��e�͂��������B���������̊��z���ЂƂ��Ƃŏq�ׂ܂��ƁA�����̎���ɂ͂������u���d�v�Ƃ������t�̎����_���Ȋ��o�͍����A���͂�����������̂ł͂Ȃ����낤���A�Ƃ����v�������邱�Ƃł��B��Љ�̒��ŁA������u�m�v�͂��łɑ�O���A���剻����Ă���̂��Ɖ��߂��Ă���킯�ł���܂��B���킯�̂킩��ɂ����������ɂȂ�܂������A����Ƃ͌����u�Θb�v�Ȃ̂��Ə���ɉ�����̂��A���̊��z�ł��B �@
���@
���͂ӂꂠ����ʂ��A�F������Ȃ獡��Љ�l�Ƃ��Ăǂ��łł�����ł���̂��낤�Ɗm�M���Ă��܂��B�����ŁA�F����ɃC�M���X�̕����V�F�N�X�s�A�̐��X�̖���ɊW�����ЂƂ̌��t�肽���Ǝv���܂��B �@
�u���E�͕���A�l�X�݂͂Ȗ��ҁi���C�ɏ����܂܁j�v�\�Ƃ������t�ł��B �@
�F��������L������ɗ����A���ێЉ�̑��l�ȕ���Ŗ����҂ƂȂ�A���ꂼ��̖L���ȁA�h���}�ɕx�l������������Ă�����邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�@
 �@
�@���吭���^�� 1
�����푈����ё����m�푈���̊������������c�́B�����푈�̒������ɂƂ��Ȃ��A���͂ɂ�鍑���̉��I�g�D���Ɛ푈�̐��ւ̓������ً}�̉ۑ�ƂȂ�A��2���߉q�������t��1940�N7��26���q��{�����v�j�r���t�c�Ō��肵�A�q���h���Ƒ̐��r�����̕��j���m�肵���B�����ĐV�̐��^���̌��ʁA�S���}�����U���A10��12���吭���^��������ꂽ�B���^��́q���h���Ƒ̐��r�̐����I���S�g�D�Ƃ��Ĉʒu�Â����A�q�吭���^�̐b�����H�r���X���[�K���ɑ吭���^�^���𐄐i�����B �@
���S�Ȏ��T�}�C�y�f�B�A �@
�����푈�̒������ɔ�����1940�N10���߉q����(���̂��ӂ݂܂�)�Ƃ��̑��߂ɂ���đg�D���ꂽ�������������g�D�B�e���}�͉�}���Ă���ɎQ���B���قɂ͎��A�e���{���x�����ɂ͒m�����A�C�A�s���⏕�I�������ʂ������B �@
���f�W�^���厫�� �@
���a15�N(1940)�߉q����(���̂��ӂ݂܂�)�炪���S�ƂȂ�A�V�̐��^�����i�̂��߂Ɍ������������g�D�B�S���}�����U���A����ɉ�������B��20�N6���A�����`�E���֔��W�I�����B �@
���厫�� �@
1940�N(���a15)10���A�߉q�����𒆐S�Ƃ���V�̐��^�����i�̂��߂ɑn�����ꂽ�g�D�B���قɂ͑�����b��������A���{���x�����͒m�������C����ȂNJ����I�ȐF�ʂ��Z���A���^�I���Ɋ��������̂��͂��߁A�Y�ƕ�E����{�w�l��E�בg�Ȃǂ��P���Ɏ��߂č��������̂��ׂĂɂ킽���ē����������A45�N�����`�E�����ł���ɋy��ʼn��U�����B �@
�����E��S�Ȏ��T���̑吭���^��̌��y �@
���y�ݓc���m�z�@�c�܂��x�X�g�Z���[�ƂȂ����s�g���t(1938)�̂ق��s�R�����]�t(1929�]30)�A�s�o�ʐ_�t(1936)�ȂǎЉ�I������������Ɠ��ȐV�������������Ă���B40�N�吭���^��ݗ�������A�R���ɂ�������h�g��Ƃ����Ӗ��ő����̒m���l�ɐ�����ĕ��������ɏA�C�����B��テ�j�[�N�ȓ��{�l�_�s���{�l�Ƃ͂Ȃɂ��t(1948)�������ĕ��d�ɕԂ�炫�A�s�߂̉ԑ��t�Ȃǂ̏������c���Ă��邪�A���̊����̒��S�͋Y�Ȃɂ�����A48�N����51�N�ɂ����ď㉉���ꂽ�s�������m�t�s�ő��ƗY�فt�s���������t�́A���̍������̂Ȃ��œ��{�l�Ƃ͉���������̏�Ŗ₤���쌀�ł����āA��㉉�����\�����i�ł���B�c �@
���y�V�̐��^���z�@�c8�����{�ɂ͐V�̐�����������������A�����ɂ͏���̐��͂����݂��Ă���A�V�̐��̕����Â����߂����Č��_�����킳�ꂽ�B���̌��ʁA�^���͑S�����������吭���^��Ƃ��邪�A���̒��j�̂ł���吭���^��̍\�����͑��ق܂�߉q���w�����邱�ƂƂȂ�A�吭���^��Ǝ��̎w����������]�n���c���ꂽ�B������10���̔���ł͋߉q���ق́q�b�����H�r�������������Ď��]���������B�c �@
���y������z�@�c�܂�������A������̎��s�g�D�Ƃ��āA10�ˑO��̗ו۔ǂ��Ґ�����A���ꂼ��̒P�ʂŏ����J�����Ƃɂ��A��Ӊ��B���~���ɍs�����Ƃ��ڂ����ꂽ(�q�בg�r�̍��Q��)�B�@�����A���N�ɋ߉q�����𒆐S�Ƃ���V�̐��^���ɂ���đ吭���^������������A����ł���Ӊ��B�A�����ʂ̂��߂̉^���g�D�Ƃ��āA������A������ɂ��̋@�\�����҂����B���̌���42�N5���̊t�c�ŁA�吭���^�������A��������w������g�D�ł��邱�Ƃ������Ɍ��肳��A8��������s���ꂽ�B�c �@
���y�@���j�z�@�c����ł͊��@(1937)�A������(1938)�A���t����(1940)�A�哌����(1942)�A�R����(1943)�Ȃǂ̋���Ȍ������������V���������@�ւ�����ꂽ����łȂ��A43�N�̐펞�s�����ʖ@�A�펞�s���E������ɂ���Ď�����Ȍ��͂����������B�����ł�1940�N�ɑS���}�����U�������A�吭���^��ɍĕ҂��ꂽ�B42�N�ɂ́A�吭���^��̖��[�g�D���A�����凌�����A����ɗבg�̑g�D�ƌ��т����̂Ƃ���A�������ׂĂ��펞�̐��ɑg�ݍ��܂ꂽ�B�c �@
���y���^�̐��z�@�c�吭���^��𒆐S�Ƃ����2�����E��풆�̐����̐��B�����푈�̒����퉻�ɂƂ��Ȃ��A�q���h���Ƒ̐��r�ƌĂꂽ���Ƒ��͐�̐��̎������K�v�ƂȂ�A���̂��߂ɂ͍���(���{)�Ɠ���(�R��)�̖������͂��߂Ƃ���x�z�w�����̑Η������ƍ����̐푈���͂ւ̎��������i���I�ɂЂ������g�D�̌������s���̉ۑ�ƂȂ����B�c
 �@
�@���吭���^�� 2
���o�� �@
�߉q�����𒆐S�Ƃ��āA���Ƒ̐��̍��V�����߂�v�V�h�𑍌��W�����ĐV�}����������\�z�͔�r�I�����i�K���猟������Ă����B1938�N�̍��Ƒ������@���O�c�@���̊������}�̔��Ŕp�Đ��O�ɒǂ����܂ꂽ�ۂɂ͗L�n���J�E��J���R�炪�߉q��}��Ƃ����V�}������ĉ��U���I�����s�����Ƃ������������A�u�߉q�V�}�v�ɓ}��������邱�Ƃ����ꂽ�������F��(���F��)�E���������}(�����})����]���ē��@�Ɏ^�����Ė@�Ă������������߂ɐV�}�̕K�v���������Ȃ������Ƃɂ���U���̌v��͔����ɖ߂邱�ƂɂȂ����B �@
�߉q�̑������C��A���[���b�p�ő���E��킪�n�܂�A���ۏ�̋ٔ����ɂƂ��Ȃ��ē��{�����͂Ȏw���̐����`������K�v������Ƃ���V�̐��^��������オ��A���̖���Ƃ��Ė���̏o�ł���l�C�������������߉q�ɑ�����҂̐������܂����B�������}���ł��߉q�ɑR��������݂�����V�̐��ɗ��悵�ĎQ�����邱�ƂŗL���ȗ�����߂�ׂ����Ƃ����ӌ������܂����B�����}���ْ��c�����Ɛ��F����h�̔��R��Y���邩�ɋ��c���ė��}����������u���߉q�V�}�v�\�z��������̂́A�����}�ł͉i������Y����}�_�������A���F����h�̑��ًv���[�V�����ē����t�|�t�ɎQ�����ċ߉q�ēo�������������߂ɍ����\�z�͎��s�ɏI���A�����}�E���F��h(�����h�E�v�V�h)�Ƃ��Ɉ�C�ɉ�}�ւƌ��������ƂɂȂ����B �@
�߉q����3���߉q���t������ɂ��̊��҂ɉ�����ׂ��V�̐��̒S����ƂȂ�ꍑ��}�g�D�̍\�z�ɒ��肷��B�Ȃ��A���̍ہA�߉q�̃u���[���ł������㓡���V������ɂ��A�߉q���Q�����Ă��������c�̏��a��������������̘_��V�̐��^�����i�Ȃǂ��������Ă����B �@
�\�z�̌��ʂƂ��đ吭���^����������������̐��̒��j�g�D�ƂȂ�B���ق͓��t������b�B�����{�������ǂ̉��ɉ����g�D�Ƃ��ē��{���x���A��s�s�x���A�s�撬���x���A������A������Ȃǂ��ݒu�����B�{���͐ڎ������������ڂɒu���ꂽ�B �@
1940�N�A���łɌ��Ђ��֎~����Ă����ΘJ�����}��E�����}�̓�������������ׂĂ̐��}�������I�ɉ��U���吭���^��ɍ������Ă����B���a��������吭���^��ɔ��W�I�ɉ�������Ƃ������ڂɂ����1940�N11���ɉ��U�����B�����Ƃ��A�c�@���̉�h�͋����̂܂ܑ������A�܂��吭���^��̂͌������Ђł��邽�ߐ��������͂����Ȃ����A�֘A�c�̂ł��闃�^�c�������Ȃǂ����������������Ȃ����B����́A�u�����n�ɏ��x���ȁv�Ƃ��������Œm���邪�A���U�����e���}������ȓ����吭���^����ɂ�����哱�������邽�ߋ��͓I�Ȏp�����Ƃ������̂́A�c�̓��͈ꖇ��ł͂Ȃ��A�ꍑ��}�_�҂̖ڎw�������̂Ƃ͑傫���قȂ��Ă����B �@
���̂悤�ɁA�吭���^��𒆐S�ɑ����m�푈���ł̌R���̕��j��ǔF���x����̐��𗃎^�̐��Ƃ����B1942�N4��30���Ɏ��{���ꂽ��21��O�c�@�c�����I���ł͗��^�����̐����c��(����)����������A466�l(����Ɠ���)�̌��҂𐄑E���A�S�c�Ȃ�81.8%�ɂ�����381�l�����I�����B �@
1942�N(���a17�N)5��26���ɂ͎P���g�D�ł�����{���w������B1942�N6��23���ɂ͑���{�Y�ƕ�E�_�ƕA���E���ƕ�E���{�C�^�c�E����{�w�l��E����{���N�c��6�c�̂��P���ɓ��������B1942�N12��23���ɂ͑���{���_��������ꂽ�B �@
���̌�A1945�N3���ɑg�D�̈ꕔ�����^����������g��������{������Ɠ�������A6���ɖ{�y����ɔ����������`�E�������ɂ����U�ƂȂ����B����������͐��{��]�ƌR���ɂ�鋭���ȓ��p���ł��������߁A����ɔ����������^������̈ꕔ���썑���u��Ȃǂ������B�R���ƌ�����{������ɑR����ȂǍ����𗈂����A���E�����Ȃ��܂ܓ��{�͏I����ނ����邱�ƂƂȂ����B �@
�Ȃ��A����ł́A�吭���^��̂悤�ȑg�D�͑��݂��Ȃ����A����Ȃǂɂ����Ă͖�}���^�}�̘A�������𝈝����錾�t�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ����܌�����[2]�B�܂��ŋ߂͂�����˂��ꍑ��ɂ�鍑����̑ŊJ��Ƃ��Đ���ɏ������Ă���^��}�̑�A���\�z�ɑ���ᔻ�ɂ��p�����鎖������B �@
������ �@
�吭���^��͐��}���ۂ��Ƃ����^��͂��̒a�������瑶�݂����B�u�ꍑ��}(���邢�͑g�D)�̋��͂Ȑ����̐���ڎw���v�Ƃ����咣�́A���ƎЉ��`�h�C�c�J���ғ}�A�t�@�V�X�g�}(���邢�͌����͂���Ȃ��������\�r�G�g�A�M���Y�})�𗝑z�̌`�Ԃƍl���鐨�͂��炵���Ό��ꂽ���A����ɑ��ẮA�u����{�鍑���@�͓V�c�e�����|�Ƃ�����̂ł����āA���w���҂Ƃ����ꍑ��}�g�D�͍��̂ɔ�����v�Ƃ��闧��(������u�ϔO�E���v)����́u�����_�ᔻ�v�����݂����B���������u�������Ёv���̂����{�Ǝ��̊T�O�������̂ł���B �@
���̑Η��͐ݗ��ߒ��ł͏[���ɉ������ꂸ�A�吭���^��̔��(1940�N10��12��)�ł́A�����g�D�ł���Γ��R����ׂ��j�́E�錾�̗ނ͎ł��藃�^��ق̋߉q�����̌�����͔��\����Ȃ������B �@
���̌���u�吭���^��ጛ�_�v�͎��܂炸�A1941�N(���a16�N)1���ɊJ���ꂽ��76�鍑�c����2��6���̋M���@�\�Z����ɂ����āA�߉q������̑吭���^��Ɍ��@��̖�肪���鎖��������F�߂��B�����āA���Ƃ��Ɛ������ЂƂ��Ă̑吭���^��ɂ͔����Ă���������b�����u��Y(����)�������x�@�@��̐������Ђł͂Ȃ��������Ђł���Ɛ錾����[3]�B���̔F��ɂƂ��Ȃ��Đ����������ւ����A�O�@�B��̉�h�u�O�c�@��y���v�͉��U�B�����O�@�c���S�����������ƂȂ�ُ펖�ԂƂȂ����B �@
���N4��1���Ɋv�V�h�̔���}���ė��^��̉��v�Ă�����A����ɐ����c�̉���ڎw���Ă����߉q���߂̗L�n���J���݂��������������C����ȂǁA�₪�Ď���ɂ��̐��i�͐��{�̎{��ɑ��ʂ��狦�͂��Ă����⊮�I�E�s���g�D�I�Ȃ��̂ɏk�ނ��Ă������B�����āA���ق����A���{���x�����{���m�������ꂼ�ꌓ�C���邱�ƂƂȂ����B �@
��L�̓_����A���̔��R�Ƃ����C���[�W�Ƃ͈قȂ�A�吭���^��̎��Ԃ̓i�`�X�̂悤�ȓƍِ��}�Ƃ͂��قȂ�l���������g�D�ł������B�������������ɂ�鍇�ӂ����A���قɂ��u�O�c���فv�ɏd����u���ȂǁA�����`�̍s���l�܂���i�`�X�I�Ȏ�@�ɋ��߂��_�͒��ڂł���B �@
 �@
�@���吭���^�� 3
�吭���^����̒��S�ƂȂ����̂́A���a�V�c�̎q���ŁA�������t������b�߂Ă������Əo�g�̋߉q�����ł���B���Ȃ݂ɁA�߉q�����̓g���E�g�}���H�쎸�s�̗v���ƌ����Ă�����A���Ƒ������@�𐬗����������t�̎����߂Ă����肷��B������A�n�R�������������ƕ\�����邩�A�߉q�������ƌ������͔��f���������Ƃ��낾���A���̍��ڂł͈���Ȃ��B �@
1940�N�A���[���b�p�ő���E��킪�J�킵�����ƂƁA�����푈���D������������{�ł́A�푈���s�̂��ߋ����w���̐������߂�ꂽ�B����ɂ́A�����ւ̐M�����ǂ��ɗ����A�R���������Ɋ����邱�Ƃ������Ȃ������ʁA�������s����ɂȂ�N�[�f�^�[�����N���������Ƃ��傢�ɊW������B�R���͏]���ȋc���~���A�c��Ɠ��t�͖��̈��S���m�ۂ�����Ŏ���̗��v��]��ł����B�����ŁA�݂�Ȃ��������͎҂Ɍ��邪�K���ɂȂ��ꍑ��}�g�D�Ƃ��đ吭���^��̌��}����ꂽ�̂ł���B �@
�������āA�R����L�͐��}�̌㉟�����A���吶�܂�̃J���X�}���哱����吭���^��ւ��a�������B����Ɂu�o�X�ɏ��x���ȁv�������t�ɂ��āA�E�h�E���h���킸�l�X�Ȑ��}�������I�ɉ��U�����������̂ł���B �@
�����A���łȑ̐�����邱�Ƃ�S��]��ł����̂͌R�������ŁA�݂�Ȃ���Ă���̂Ŏ����������ᎋ���ꂽ���Ȃ��A�Ƃ������R���獇���������}�����������B�o�X�̃n���h�������鑈�����R�����ɂ܂�Ȃ��悤�ɂ��i�s���Ă��������ʁA�吭���^��͂������݂�Ȃ�����Ă��邱�Ƃ𐋍s����g�D�ւƕϖe���A�I����}�����̂ł���B �@
���o�� �@
�����푈�J�헂�N��1938�N�A�����}�͂����ɍ~������Ƃ��������̗\�z�Ƃ͈قȂ�Ӊ�����n�ւƓ����A�푈�͎��v��ɂȂ�������B���{�����v��Ɏア���Ƃ͓��I�푈�ŘI�悵�Ă������߁A�R��������J���͂̊m�ۂ�ړI�Ƃ������Ƒ������@�̐������K�v�ƂȂ��Ă����B�����A�O�c�@�ō��Ƒ������@�̉��ɔ����鐭�}���o�āA����������Ȃ����B���̂��߁A���t������b�߂Ă����߉q������}��Ƃ������}������ďO�c�@�����U���A�J���X�}�����Ď葁���@�Ă�ʂ����Ƃ����v�悪���ꂽ�B���ǁA�������}���^���ɉ�������߂��̌v��͂Ȃ��������ƂɂȂ������A���̌v�悪�吭���^��̌��ƂȂ����B �@
�吭���^��̍\�z�������O�A�����ʂ̕s���肳����w�[�������Ă����B1932�N�̌܁E������Ō����̏퓹��������сA�R���������Ɋ����Ă��邹���Ŋe���}�͑�A��������g�݂A������Ώ����荇�����s����Ԃ������Ă����B�܂��A�����푈�J���A�펞���ł���ɂ��ւ�炸�R���̊��╡�G����ȂǂƂ��������R������t�����E�����������B �@
1939�N�Ƀ��[���b�p�ő���E��킪�J�킷��ƁA��}�ƍقɂ�鋓����v�̐���~�����Ƃ����V�̐��^���������������B�߉q�����́A�C�^���A��h�C�c�A�\�A�Ȃǂ̈�}�ƍق����E�I�Ȏ����A�܂�݂�Ȃ���Ă��邱�Ƃ��ƍl���A���^�̐��ɑO�����Ȏp���������Ă����B �@
�߉q�����̎p�������炩�ɂȂ�ƁA������x�����`�I�Ȑ��}�͔��߉q���f���Ē�R���铮�����������B���A���{�l�݂͂�Ȃ���Ă܂��Ƃ��������Ɏア�B���߉q���}�̓���������߉q�ɓ�������ӌ���߉q�ւ̎x�����o�āA���߉q���}�͉��U�Ɍ��������B�����Ȃ�ƁA�߉q�������������[�_�[�V�b�v�����Ă��āA����݂̂�Ȃ����Ă����Ă��邩��Ƃ����S�������������A���ɂ̓o�X�ɏ��x��Ȃ��悤���X�Ƒ吭���^��ɎQ�����Ă������ƂɂȂ����̂ł���B �@
������ �@
�������A�吭���^��͋߉q�������ڎw������}�ƍقƂ͈قȂ�����ւƐi��ł������B�吭���^��ɎQ�����Ă͂�����̂́A�l�����̓o���o���Ō�����n���h�������낤�ƍl���Ă���҂������A�v���悤�Ɉ�}�ƍق��s���Ȃ������B �@
���̑傫�ȗ��R�Ƃ��āA�u�吭���^��̑��ق���}�ƍقɂ�鐭����~�����Ƃ́A�V�c�e�����߂�����{�鍑���@�ɔ����A���̂�̂�ɂ��邱�ƂɂȂ�v�Ƃ����l������������ꂽ���Ƃł���B����́A�ϔO�E���Ƃ����V�c�̓����ɐS�����Ă���҂ɂ��l�����ł���A�R�����\�����V�c�����Ă���̂Ƃ͂܂��قȂ���̂ł���B�����A��ʐl���炷��ǂ������������Ƃ������Ă���悤�Ɍ����A�݂�Ȃ������Ă��邱�ƂɂȂ�B�܂��A�n���h����_���Ă���҂ɂƂ��ẮA���̎咣�ɏ������Α��ق̔����͂��킮���Ƃ��\�ɂȂ�B �@
���]�Ȑ܂��o�āA�吭���^��͐����������֎~����邱�ƂƂȂ����B�������đ吭���^��͐����I�Ȏw���͂������A�݂�Ȃ����߂���m���̃o�b�N�A�b�v�⍑�Ƒ������@�̎��{���s�������̍s���I�ȑg�D�ƂȂ����̂ł���B �@
 �@
�@���吭���^��ƕ������ / �ݓc���m
���̕�������Ƃ��ӌ��t�́A�����܂Ŏ��ې����̌����ʂł͗]��g�͂�Ă�Ȃ������t�ł���܂����A���x�߉q��������b�ɂȂ�ꂽ�ۂɉ��鐺���y�ї��^��̑��قƂ��Ă̐����̂Ȃ��ɁA�܂������������̌��t���g�͂�Ă���܂��B�܂�o�ϐ���ƕ���ŕ�������Ƃ��ӂ��Ƃ��]�͂�Ă��̂ł���܂����A����́A���{�̌��㕶���A�X�ɏ����̐V���������Ƃ��ӂ��Ƃ��l�ւāA���������̏�ɑS�ʓI�ɕ�������Ƃ��ӂ��̂���グ��ꂽ�A���炭�ŏ��̂��̂ł͂Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B�ܘ_���{�e�Ȃł͂��ꂼ�ꕶ������ɓ���ׂ����낢��ȍs���I�Ȃ��Ƃ͂�Ă��킯�ł����A���݂̐��{�̋@�\����]�āA�������ӕ���������I�Ɏ�グ��Ƃ��ӓ_�ɉ��Ă��A�܂����̊��̎��{�^�p�ɉ��Ă��A�܂��\���łȂ��Ǝv�͂��₤�ȓ_������܂��̂ŁA�吭���^��̕������Ƃ��Ă͂��̓_�ɑ傢�ɗ͂�����K�v������Ǝv�ӂ̂ł���܂��B �@
�Ƃ��낪�A��̕�������Ƃ��ӂ͔̂�r�I�����Ӗ��ōl�ւ��Ă��B�܂����̗��^��̒��̕��������A�����Ӗ��ł̕�����S�����Ă�鏈�ƍl�ւ��Ă��̂ł���܂����A��̐����ɂ���A�o�ςɂ���A�O���ɂ���A�R�����܂߂āA����͈ꍑ�̕����̈�̌���ł���ƌ��Ă�낵���B�������ӈӖ��̕����́A���Ǎ��̗͂��̂��̂Ƃ��ӂ��Ƃɂ��Ȃ�̂ł���܂��B�����Ӗ��̕�������Ƃ��ӂ��ƂɂȂ�܂��ƁA��͂�o�ψ��͐����Ƃ��ӂ₤�Ȃ��̂ƕ���̍��������̕���ł���܂��āA���ܕ������Ƃ��ẮA�o�ς���͑�̗��^��̂��̕��ɑ����Ȃ�����ƍl�ւāA���̂₤�Ȃ��̂��A�����̎d���̑ΏۂɂȂė���̂ł͂Ȃ����Ǝv�Ă�܂��B��������A�@���A�Ȋw�A�Z�p�A���w�A�|�p�A�V���A�G���A�����A�o�ŁA���ꂩ������̕��ʂł́A�J�����͌o�ς̈ꕔ��ƌ����Ƃɂ��āA���̑��̕���A������ÁA�ی��A�̈�A��y�A���ꂾ������T�A��̕�������Ƃ��ĕ������̎戵�Ӕ͈͂ɂ͂Ђ�Ǝv�Ђ܂��B �@
���^��̎v�z�����Ƃ��Ӗ��ł����A����͐捠�̋��͉�c�ł̋߉q����̂��b�A���ꂩ��L�n����̗��^��̎��H�j�̉���̂Ȃ��ɑ����ڂ����܂����m�ɏq�ׂ��Ă���܂��B���U�A���T�Ŏ����������ӂ��Ă�������߂��Đ\�グ�������Ƃ́A�������^��Ȃ���͈̂�̐����������ׂ����̂ł���Ɖ]�͂�Ă���A�܂�������ł���̂������ӕ����Ɉӌ����A�v�����₤�ł���܂����A��̂��̐������Ƃ��ӂ��ƂɏA�ẮA�����O�����̐����Ƃ��ӊT�O�ł�������߂��Ă͂����Ȃ��̂ł��āA����͂�͂���{���́A���{�Ɠ��̐������O�Ƃ��ӂ��̂ɗ��r�������̂łȂ���Ȃ�ʁB�Ƃ��ӂ̂́A����܂ł̐����ɑ���ϔO���l�ւĂ݂�ƁA�����S�́\�\�S�̂Ƃ͐\���܂��A�啔���̍����̓��̂Ȃ��ŁA���{�ƍ����Ƃ��ӂ��́T�Ԃɉ����Η��I�Ȉӎ����₦�������Ă��B�܂�A���߂鎡�߂���Ƃ��ӂ₤�Ȍ��t�ł͂܂��͂��肵�܂��A����͌��͂������A����͂��̌��͂ɕ�����Ƃ��ӂ₤�ȁA�������ӑΗ��ӎ������̂Â��炱�̐����Ƃ��ӌ��t�̂Ȃ��ɂ����B�������ӊϔO�͓��{�{���̑吭�Ƃ��ӈӖ��ɉ��鐭���Ƃ͔��ɗ��ꂽ���Ƃł���B�����ł��̓_�͏����吭���^�^����ʂ��Đ����Ƃ��ӌ��t���g�͂��ꍇ�ɂ́A��قǒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�ʂ̂ł͂Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B�����͑吭�𗃎^�����Ƃ��ӈӖ��ɉ��āA��͂�u���{�ɋ��͂���v�Ƃ��ӂ��Ƃ������̌��O�ł���B���������̋��͂̎d���͏�Ӊ��B�Ƃ��ӌ`������A�܂������ʂƂ��ӌ`�Ɉ˂Ă��ł���B���ꂪ���ɏd�v�ȓ_�ł���܂��āA���̗��^��̎v�z�����܂萭���v�z�Ƃ��Ă̂��̌����́A�������ӈӖ��ɉ��߂��Ȃ���Ȃ�ʂ̂ł͂Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B �@
���^��͍����I�X�������Ă��Ƃ̌�������邳���ł���܂��B����ɏA�Ă͕ʂɎ�����\�グ��K�v���Ȃ����Ǝv�Ђ܂����A�v����ɁA�����v������Ă�鎩�R��`�o�ρA���͎��{��`�o�ς̑S�ʓI�C���Ƃ��Ӗ����A�����Ȃ��̐��x�T���g�D�����̍��{�I�ϊv�Ƃ��ӕ��ɍl�ւĂ��܂ӂƁA���R����ɑΗ�����v�z�Ƃ��āA�����v�z�Ƃ��ӂ��̂������܂ōl�ւ��Ă�Ƃ��납��A�������ӌ�����������̂��Ǝv�Ђ܂��B���������̗��^�^����ʂ��č����܂ł̎��R��`�o�ρA���͎��{��`�o�ςƂ��ӂ��̂�ᔻ���A��������鐸�_�́A����͂��̕��Q���͕a���Ƃ��ӂ��̂ɑ��Ă̐����ł���A�E�o�ł���B���������v�z�����{��`�ƑΗ����A�����G�Ƃ���Ƃ��ӂ₤�Ȉ����Ӗ��ɉ��郉�a�J���Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�������͂����ӂ̂ł͂Ȃ����Ǝv�ӂ̂ł��B�܂����̎��{��`�o�ςƂ��ӂ��̂��A�����I�Ȋ�Ō������{��`�̑S�ʓI�Ȕے�Ƃ��ӂ��̂ƁA�������^�^���Ƃ��ӂ��̂��猩�����{��`�̑傫�ȕ��Q�a���Ƃ��ӂ��̂Ƃł́A����͂��̃C���[�W�ɉ��Ĕ��Ȉ�Ђ�����Ǝv�Ђ܂��B�ǂ�����������I�Ȑ����ɂȂ�A�܂��r�����ȗ��̍l�֕��ŁA���͌��t���s�K���ł��邩���m��܂��ʂ��A��́A���̂₤�ɍl�ւĂ���܂��B �@
���łɁA����Ɗ֘A���āA���������Ɏv�z��̕��j�Ƃ��Ӗ��ł���܂����A�v�z��Ƃ��ӂ��ƂɂȂ�ƁA����͂������^��̕������Ƃ��ӂ��̂����łȂ��A���^��S�̂ɊW������ł���܂��B�������Ƃ��Ă͖ܘ_���̓_�ɑ傢�ɗ͂𒍂��Ȃ���Ȃ�ʂ��A�����ɂ܂����^���]�����Ɋe���Ƃ̊Ԃɏ\���̘A�q��ۂāA���̕��j���ЂƂ͂��肳���Ȃ���Ȃ�ʂƎv�Ă���܂��B �@
���͐N���ォ�珊�������v�z�Ƃ��ӂ��́T�Q����ʂāA�K�ɂ��Ă������ӐF�ɐ���Ȃ��ō����܂ŗ����̂ł���܂����A�����̐g�ӂɐ����r��ł�邻�̍����I�ȗ��Ƃ��ӂ��̂�g�Ɋ�����ɂ��A���{�̐N����̂ǂ����Ă������ӊO���̎Љ��`�v�z�T���͍����v�z�Ƃ��ӂ��̂�Ῐf����A�܂��������ӂ��̂Ɉ������čs�����Ƃ��ӂ��̌o�H�Ɠ��@�A���ꂩ�炻�̍��{�̗��R�Ƃ��ӂ��̂ɏA�Ă��Â��l�ւ������A���ۂ������Ӊ^���ɓ������ҁA���͂������Ӊ^���ɓ����悤�Ƃ��Ă��ҁA�X�ɂ������Ӊ^������]�����ė����҂Ȃǂ̎����ʂ��āA���낢�낻�̎�����l�ւė����̂ł���܂��B����ł��̓_�͌�Ŏi�@���ǂ̂����ɂ���ӌ����f�Ă݂����Ǝv�Ă��̂ł���܂����A���̈�ԑ傫�������͉����ɂ��邩�Ƃ��ӂ��Ƃł���܂��B���{�̐N���w�Z�ł����Ȃ鋳����A���͂܂��A�Љ�̎v�z�Ƃ������炢���Ȃ�e�����悤�ƁA�����͓��{�l�ł���A���͓��{�̍��̂͑����ł���Ƃ��ӂ��ƂɏA�Đ�ΓI�Ȕے�ϔO�����Ă����͖̂w�ǂȂ��B�ܘ_�������ӕ\�������A���͂������ӕ\����������Ȃ��₤�Ȏ���ɗ����������̂͑��������Ǝv�Ђ܂����A�{���ɉ��Ď����͓��{�l�ł���Ƃ��ӎ��o�A����A�������ӂ��̂�{���ɂȂ����Ă��l�Ԃ͎��ɋH�ł���Ǝv�Ђ܂��B�R��A���ꂪ�ǂ����Ă������Ӎ����v�z�ɐ������B �@
��̂����͏��w�Z���o�鎞���A�̂̍������w�Z�𗹂ւ邭���̔N�y�ɂȂ�܂��ƁA�����l�Ԃ̗��z�Ƃ��ӂ₤�Ȃ��̂ɖڊo�߂čs���B�����l�Ԃ͈�̂ǂ����ӕ��ɐ�����̂���ԗ��h�ł��邩�A�������ӈ�̖ڕW���فU���̒��ɏo�����T�āA���ꂪ���̎�������i�X���m�ɂȂčs���킯�ł����A���̍��ɐl�Ԑ��Ƃ��ӂ��́T�M���Ƃ��ӂ��A���͖��͂Ƃ��ӂ��A�������ӂ��̂ɔ��ɐS���䂩���₤�ɂȂ�B�������Ă��̂₤�ȋC���̂Ȃ��ɂǂ����ӂ��̂����邩�Ƃ��ӂƁA����͍������{�ł��ϗ��ŋ��ւĂ�邱�ƂŁA�����^�P���Ƃ��ӂ₤�ȎO�̗v�f�ɑ���ɂ߂ď��^�ȓ��ۂł���܂��B���ꂪ�����w�Z�ɍs�����A���͒����w�Z�֍s���Ȃ��҂��ƒ�̎d������`�ЁA�Ⴕ���͏��X�A�H�ꓙ�ɓ����ɍs���Ƃ��Ӎ��ɂȂāA�����̐����̒��ɂ��̐^�P���Ƃ��ӂ��̂���̂ǂ����ӕ��ɂ������Ă邩�Ƃ��ӂ��ƂɏA�Ė��Ђ����B�Ƃ��ӂ̂́A�v����ɂ��̎������A�\���Ƃ��ӂ��̂�w�nj����ӂ킯�ł��B�܂�A�����ɎЉ�����A�����̎��͂����āA�����̐ڂ��邢�낢��Ȏ����A�l�ԂƂ��ӂ��́T����ɑ傫�Ȑ�]�������₤�ɂȂ���̂��A�S���Ƃ͐\���܂��ʂ��A��T�������߂�̂ł͂Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B�����ł������ӏꍇ�ɁA���ɂ��T�w���҂���Ă������ӏ��N�����̐S�̂Ȃ��̋���@�Ă�邩�A����Ƃ������Ɋ�]�����͂Ȃ��őO�r�Ɍ���簐i���鋭�x�Ȑ��_�l�����Ă���낵�����A�����Ȃ�������ŏP�͂ꂽ��]���Ɉ˂Đl�Ԃ����Ɍ����I�ɂȂ�B�����Č��Nj����ɂȂ炤�A���͂��U�o�������悤�Ƃ��ӕ��ɍl�ւāA��������A�Љ�Ƃ��ӂ��́T���z���牓�����̂ɑ��鐸�_�I�ȕ��Q�ł�����₤�ȋC���ɂȂ�B���_���̐l�Ԃ̐���Ɉ˂Ă��낢��Ɉ�Ђ܂�����ǂ��A��Ò����w�Z�𗹂ւ鍠�A���낢��ȏ�����ǂ݁A���͂��낢��ȋ��{��g�ɂ���ɏ]�āA�Љ�ɑ���ᔻ�͂��o���A�Љ�^������A�P������A����������Ȋu�肪����Ƃ��ӌ����̗l���ɑ��Ĉ�w���������̐S���ꂵ�ߎn�߂܂��B���ꂪ�����ϖ㎞��ł���܂��B���̎��ɓ��{�Ƃ��ӂ��́T�l�łɏA�Ă������ӐN�����ɏ\���M���̔O�𐁂�����ŁA�ޓ��Ɋ�]��^�ւ�A�������ӂ��T�w���҂������낵�����A�����łȂ��ꍇ�͂ǂ����B���̎��Ɉ�Ԓɐɋ��ւ�����͉̂����Ƃ��ւA���m�̕����\�\���{�͂������A���m�͂����ł͂Ȃ��Ƃ��ӁA�������Ӎl�֕��ł��B�������A�������Ӎl�֕��𐁂����܂��̂́A�����Đ��m���q�A���͐��m�]���̏�������ł͂Ȃ��B���ƍ��{�I�ɁA���{�̌���̕����\�\�`�������ł͂Ȃ�����̓��{�����A����Ɛ��m�̌��㕶���Ƃ��ӂ��́T�q�ϓI�Ȕ�r����A����͐���ė���̂ł��B �@
�ł�����A���̎��Ɏ��͍X�ɂ�����~�ӓr������Ǝv�Ђ܂��B����́A�����̒��ɐ^�P���Ƃ��ӂ��̎O�̗v�f��ڕW�Ƃ����̗��z�����邩�Ȃ����A���ꂪ�����̌����̖ʂŏ\�����Ăɂ������ӐN�����̐S�ɍ��ݍ��܂��₤�ɂ��邱�Ƃł��B�������ӐN�B�̓��̒��ɂ́A���x���̍����珉�߂Ă͂���ƕ����Ƃ��ӈӎ������܂��B�܂蕶���I�ł���Ƃ��A���͔��I�ł���Ƃ����Ӕᔻ�͂ƁA�������ӂ��̂ɑ���͂��肵���~��������ė���B��������̓��{�͕����I�ɂǂ��Ȃ�ł��炤���A�����ʂłǂ��Ȃ�ł��炤���ƍl�ւ�B���ꂩ�獡�x�͔��ɐ^���ȉ��^�T����]�������B����͖��_���ɉs�q�ȁA�����Ă��̂��悭�l�֍��ށA�����ɐ��i�I�ɂ����锽�R�I�Ȃ��̂𑠂��Ă��N�����ɓ��ɒ������B���̎��ɔޓ��͓��{�̌��y�я����Ƃ��ӂ��Ƃ��l�ւāA���{�̕����Ƃ��ӂ��̂��{���Ɍ��シ��ɂ́A�������Ӑ����ł͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��ӕ��Ɍ���B����͈��鎞�ɂ͓��{��J�ӂ鐸�_�ł�����Ǝv�ӁB�ܘ_���ƌy���Ȃ��̂�����܂����A���������ɂ͓��{��J�ӂ鐸�_����o�Ă��ꍇ������B���������ꂪ���{�̌��݂̐����Ƃ��ӂ��̂�ے莋����Ƃ��납��A���݊O���̂��Ǝv�Ђ܂��B�ł�����A���͂����̂Ƃ�����A���{�̗��j�y�ѓ��{�̐����̑傫�ȗ�����`����̕����Ƃ��āA�\����]��^�ւĂ����@������Ǝv�ӁB�܂���{�����Ƃ��ӂ��́T�����ɏA�āA�ޓ��ɏ\�����M��^�ւ邱�Ƃ͉\�ł���Ǝv�Ђ܂��B�Ƃ��낪���܂ł̋�������������͂������ӎ�i���ƂĂ�Ȃ����B���̎��ɋ�X���m�̐����A�v�z�Ɋւ��鏑���ɋ��������������āA���͍����I�ȏ�����ǂ݁A���͍����^���̒��ɐg�𓊂��Ă���y�̘b������A�������ӕ����Ɋ��ɓ��ݍ���ł��F�l�̉e�������肵�āA�S���~�ӂׂ��炴���ԂɂȂ�B�ܘ_����͑S�̂Ƃ͐\���܂��ʂ��A�命���̎҂��������ӌo�H��H��̂ł͂Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B�����ł��̎v�z��A��Ɋw���y�ѐN�ɑ���v�z�P���Ƃ��Ӗ��́A�P�Ƃɐ����v�z�T���͗ϗ��v�z�Ƃ��ӂ��̂Ɉ˂ĉ���������̂ł͂Ȃ��āA���ƍL�����ꂩ��A�����Ƃ��Ӗ��ɂ��āA���{�̌��y�я�����ʂ��Ĉ�̑傫�Ȋ�]��^�ւ�\�\�V�����L���ȕ��������ď����̓��{�����݂����A�����Ƃ͊��ɂ���ɒ��肵�ċ���A���ɂ������ӂ��Ƃ��s�͂�Ă��A�������ӂ��Ƃ���̓I�ɐN�����̓��ɂ͂��莦�����Ƃ����ɑ�ȓ_�ł͂Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B���ꂪ���߂ɂ͐����ƂƂ��A���͐��{�̓��ǎ҂Ȃǂ̍����ɑ��鐺���A�錾�A���͌P���Ƃ��ӂ₤�Ȃ��́T���ɁA���ꂪ�\���D�荞�܂�ė~�����Ǝv�Ђ܂��B �@
��ւΌ��݁A���{�̐��������낢��ᔻ����A�����m���w�̓����ɂ��Ă��A�ޓ���ʂ��ď�Ɍ����錻�ۂ́A�����ɕ��������Ȃ��Ƃ��ӂ��Ƃɑ��锽���ł���܂��B�Ƃ���ŁA�����ɉ��镶�����̌��@�Ƃ͂ǂ����ӂ��Ƃ��Ɖ]�Ђ܂��ƁA��Õ������Ƃ��ӂ��̂����`���Ă��T��˂Ȃ�܂��A���̍l�ւł́A�������Ƃ��ӂ��̂́A���ɓ��{�̓`���ɍ������������̂łȂ���Ȃ�ʂ��Ƃ͖ܘ_�Ƃ��āA���̗v�f�Ƃ��ėϗ����A�Ȋw���A�|�p���A���̎O�̂��̂������ɍ��x�̐������ȂĂ��ׂĂ̂��́T���ɂ���Ƃ��ӂ��Ƃ��Ǝv�Ђ܂��B�Ƃ��낪���T�ɗϗ����Ƃ��ӂ��̂��������āA�������A���̗ϗ����Ȃ���̂��Ȋw�I�łȂ��A���͌|�p�I�ȕ\�������Ă�Ȃ��Ƃ��ӏꍇ�ɂ́A���̗ϗ����Ƃ��ӂ��̂́A�����A��ɐN��{���ɐ�������͂������Ȃ��B�������A���݁A���{�̐����Ƃⓖ�H�҂̍����ւ̌Ăт����Ƃ��ӂ₤�Ȃ��̂ɂ́A���̎�̂��̂����ɑ����̂ł���܂��B�܂��|�p���ɂ��Ă��A�����܂ł̌|�p�����܂��ƁA�|�p���Ƃ��ӂ��̂��B��̂��̂Ƃ���Ă��B���̂Ȃ��ɂ���ϗ����Ƃ��ӂ��̂����ɒႢ�A���͊Ջp����Ă��Ƃ��ӕs���S�ȏ�ԂŁA��ɓ��{�̕��w�Ƃ��ӂ₤�Ȃ��̂́A�Ȋw���A�ϗ����Ƃ��ӓ_�ł́A�����܂Ŕ��ɕs���S�ȕa�I�ȏ�Ԃɂ����B�����œ��{�̐N�w���������̐g�Ɉ��鋳�{�����悤�Ƃ���ꍇ�A���{�̕���������͍��]���₤�Ȕ��ɕs���S�Ȃ��̂��������Ȃ��B�������ӂƂ���Ɍ��ׂ�����킯�ł���܂��āA�����\���܂��ƁA�������S���҂Ƃ��āA�܂��c�����Ɛ\���܂����A�Ȃ������������厖�ȂƂ��ӕ��ȉ]�Е��ɕ����邩���m��܂��ʂ��A�����Ƃ��ӂ��̂͐�����\���܂����₤�ɁA�����ɂ��A�o�ςɂ��A���͂܂��O���ɂ��ʂ���A���̍��q���Ȃ������̗͂ł���Ƃ��ӓ_���A�\�����l�ւ���Ђ����̂ł���܂��B���ۂɉ��āA���x�̗��^��ɕ��������o�������ƂɏA�Ă͂��낢��Ӗ�������܂����A�Ƃ�킯�����m���w�̈ꕔ�̒��ŁA��r�I���܂ŝX�˂Ă�ҁA���͉��^�I�ł����҂��A����Ɉ˂ĉ������ɐV������]�����āA���܂ł̎����̑ԓx���ꝱ���ĐV�������^�^���ɎQ���������A�������ӔM�ӂ������Ă��҂̑����Ȃ����Ƃ͎����ł��B����͖��X���{�̐����ɂ������Ƃ��ӕ��ʂ��͂Ђė����Ƃ��ӁA�������ӊ�]�̌��ꂾ�Ǝv�Ђ܂��B���̑ԓx���̂��̂͂܂��]��܂߂��܂��ʂ��A�e�Ɋp�A�������Ӕ����ȓ_������Ǝv�ӂ̂ł���܂��B �@
�������{�����͉Ȋw���Ƃ��ӓ_�ɉ��āA��_������₤�ɉ]�͂�Ă���܂����A���{�������̂��͉̂Ȋw���������Ȃ������ł͂Ȃ��Ǝv�Ђ܂��B���쎞��̐���͉Ȋw�����Ƃ��ӓ_�ɔ��ɗ͂������ꂽ���̂ł����A���ꂪ��������ɂȂāA�Ȋw�ɑ���בR����~���ƂȂČ���āA�܂�Ȋw�Ƃ��ӂ��̂�s�����̂܁T�ۂݍ���ōs���킯�ł��B�Ȋw���܂Â����ł����A�����Ɉ˂炸�A���{�ɂ͂Ȃ����O���ɂ͂���A�����v�͂��邱�Ƃ������Ȃ��B�v����Ɏ��M���������Ȃ�������Ȃ��Ǝv�ӁB�������ӈӖ��Ŗ������N�̐����Ƃ͂�͂蕶���������Ă����₤�ł��B��ւ����ɑ��鍐���ɂ��Ă��A���͂͗��h�ł��邵�A�܂����̂Ȃ��ɂ͊m�����錩���������B�����Đl�ɏ����������̂�ǂނƂ��ӂ₤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ����̂���Ȃ����Ǝv�ӁB�����Ƃ̏�M�������ɒ����`�čs���B���ꂪ�܂�|�p���ŁA�������ӓ_����قǍl�ւȂ���Ȃ�ʂ̂ł͂Ȃ����Ǝv�ӂ̂ł��B���ꂩ��A��ւΉ��y�Ɣ��p�ɏA�Ă͊����̊w�Z������܂�����ǂ��A���낢�떯�ԂɋN�Ă���܂������^���ɑ��āA���{�͂��������S�������Ȃ���Ȃ�ʂ̂���Ȃ����Ǝv�Ђ܂��B�ܘ_���̒��ɂ͂��T���̂��������̂�����܂����A���T���̂قNj�J���Ă�����ł�����A���̂��T���̂��������A�������Ă�Ƃ��ӈӐ}�𐭕{�������āA�⏕�Ƃ܂ł͍s���Ȃ��܂ł��A�������ӂ��́T���݂�F�߂āA����Ɋ�����Ă��Ƃ��ӂ��Ƃ��͂��芴��������A�������Ӑ��{�̐����I�ԓx�������ɔ��Ȋ�]��^�ւ邱�ƂɂȂ�B���̓_�ɏA�ẮA���͍��܂Ŏ��ۂɂ������Ӊ^��(�V���^�����w��)�ɊW���Ă���܂�������ǂ��A���ɖ��S�����Ǝv�Ђ܂��B�c��ł��A�������Ӗ�肪�o�����Ƃ͐�ɂȂ��B��X�c��ł������ӕ����Ƃ��A���w�Ƃ��A���͌|�p�Ƃ����Ӗ�肪�o��ƁA�c��ɚ}���N��Ƃ��ӌ��ۂ����т��ю��ɂ���̂ł����A�܂肳�����ӂ��Ƃ��]�Ӌc���͔��ɖ��ȋc�����Ƃ��ӕ��ɍl�ւ���B�������ӂ₤�Ȃ��Ƃ��N�̎v�z�ɂ͔��ɉs�������킯�ł��B�K�ɂ��Ă������ӑ吭���^�^�����N��V���ȑ̐��ɂȂāA����ꂪ���͓w�͂���A�Љ�Ƃ��ӂ��̂͂��Ɨ��z�ɋ߂����̂ɂȂ�r�������A�Ƃ��ӂ��Ƃ��]�ւ�Ǝv�Ђ܂��B �@
�]���҂̑ҋ��Ƃ��Ӗ��ɂ��ẮA���l�����ɏ\�����{�l�ł���Ƃ��ӎ��o�����Ă����̂Ȃ�A����͐���Ƃ����͂�����ꏊ��^�ւȂ���Ȃ�Ȃ����A�S�����̗͂���ɍ����₤�Ƃ��ӁA���^��̉^���̌��O����]�Ă��A�������Ӑl�X��ϋɓI�ɕ��i���čs���Ȃ���Ȃ�ʂ��̂Ǝ��͎v�Ă���܂��B�����ė��^��g���傫�Ȏ��M�������A�����̋�̓I�Ȏx���̉��ɋO���ɏ�ė���A�ܘ_�������Ӑl�������̗p�ł���̂���Ȃ����Ǝv�Ă���܂��B�������ӎ����̗���̂�҂��A�܂��������邱�Ƃɓw�͂��Ă݂����Ǝv�Ă���܂��B �@
���{�ŗL�̕����Ɛ��m�̕����Ƃ��Ӗ��ł����A�@���Ȃ镶���ɂ��낻�ꂪ�Ⴕ�s���S�Ȃ��̂Ȃ�A���{�Ƃ��Đg�ɂ��鎞�ɂ́A��͂肻�̋��{���̂��s���S�Ȃ��̂ɂȂ�B�����{�ɑ����͕̂������Ŏ҂��Ǝv�Ђ܂��B�����s���S�ȕ�����g�ɂ��āA���ꂪ�����I���{�ł���Ǝv�Ă��B�������Ӌ��{���I���Ǝv�Ă�邱�Ǝ��̂����ŏǏ�ł���B�������ӂ̂����̕����l�ɔ��ɑ����₤�Ɏv�Ђ܂��B���m�̂��̂�g�ɂ���ɂ��Ă��A����l�ԂɈ˂Ă͉v�ɂ��Ȃ�A���͊Q�ɂ��Ȃ�B���m���Ԃ�Ƃ��ӌ��ۂ͂��̌�҂ɑ����܂��B �@
���͗��^��ɂ͂Ђ�O�ɁA�����Ȃɑ��Ē�������(�u�ꍑ���Ƃ��Ă̊�]�v���w��)�����������Ƃ�����̂ł����A������ɂ��ȒP�ɐ\���܂��ƁA���R�ɂ��L�n����̗��^����H�j�̉���̒��ɁA�u����̌�������r���v�Ƃ��ӕ��傪����A���x����ɓ���̂ł��B���͂��˂��ˍl�ւĂ������Ƃł���܂����A�����G���C�l���Ɨ��h�Ȑl�ԂƂ��ӂ��́T��ʂ����ɞB���ɂȂĂ��B����ŏ��N���������w�ɂ͂Ђ鍠�ɁA�����͈�̃G���C�l���ɂȂ�̂��A���h�Ȑl�ԂɂȂ�̂��Ƃ��ӂ��ƂŁA��핪���₤�ȕ���Ȃ��₤�ȋC���̂܁T�ł��Ƌ������B�����ň̂��l���Ƃ��ӂ͍̂��ʍ����A�����A���͐��ԓI�ɗL���Ȑl�ԂƂ��ӕ��ɁA�V���ɏ������Ă���₤�Ȉ��̖����Ƃ��A���͂Ƃ��x�Ƃ����ӂ₤�Ȃ��̂ƌ��т����A�v����ɗL���ɂȂ�Ƃ����Ӗ��ň̂��l���Ƃ��ӂ��̂��q���̓��̒��Ɉ�čs���B��̂������ӂ��̂��{���Ɉ̂��l���ł��炤���B����Ƃ��A�d���͌����Ĕh��ł͂Ȃ����A��V�n�ɒp���Ȃ�����������A�����č��ƎЉ�̂��߂ɐ^�ɕK�v�Ȏd���ɖv������A�������Ӑl�Ԃ𗧔h�Ȑl�ԂƉ]�ӂ̂����T�̂��B���̓_������ł��āA���Ђ̂Ȃ��₤�ɂ��Ȃ���Ȃ�ʂƎv�ӂ̂ł��B���ꂪ���̋���ɉ��ā\�\�������ɐ搶�̐ӔC�ł���Ƃ��A���͕����Ȃ̐ӔC�ł���Ƃ����ӂ킯�ł͂Ȃ��A�v����ɎЉ�S�̂��l�Ԃ���čs�����̍����̏�ŁA���ɂ��̓_����Ă��Ǝv�ӂ̂ł���܂��B(���a�\�Z�N�O��) �@
 �@
�@���吭���^��ɑ����] / �֓����v
�u�L������L�������̐l�ނ�o�p���ĉ^���̒��j�̂�g�D���A���̏��ɋ��͂Ȃ鐭���͂Ǝ��H�͂��W�������ނ邱�Ƃ����̉^���ɕs���̏����ƂȂ�̂ł���v �@
�Ƃ��ӂ̂ł��邩��A���̉^���͏]���̐������͂�������|���ė��^�^���ɏW�����A���̒������͂��ȂĂ킪���̐������x�z���邪�@���v����B�������̌�Ɍ��ꂽ��V�^���̋K�������� �@
�u���^�^���͖������^�ꉭ��S�E������̍����g�D���m�����ȂĐb�����H�̎�����������v �@
�Ƃ���ǂ��A����͋ɂ߂Ĕ��R���镶��ł����āA�@���ɂ������̉����Ċ������J�n�����Ɏ���Ă͎��ۂ̐��s�����Ȃ���Ή��l�ɂ�����Ȃ��B�R�鏊�����^��͐����ȗ����P���̊Ԃ͐������̋@�\�𐮂��邪���߂ɗ͂𒍂��ł����炵���A���̏�ō������Ə̂�����҂͉E���A�����A�����}�����ƁA�����A���ƉƁA���̑��]���v�z������قɂ���e��̐l�X�̏W�܂�ł��邩��A���̊������@�Ɏ���Ă��ӌ��̓��ꂹ���锤�͂Ȃ��A�]���Ă��̐��i�����肵�Ȃ������L�l�ł��邩��O���Ɍ����ĉ����̊������Ȃ�����`�Ղ�������Ȃ��B ���^��̍ō������Ɍ����Ĉ�̗��^��͉����Ȃ���Ƃ�����̂ł��邩�Ɩ₦�A�������������ς蕪��Ȃ��Ɠ�����ʂł��邩��A���_�@�ւ��M�𑵂��Ă�����������Ă�ɂ��S�炸�A���l����͉�������̕���Ȃ��s�v�c�ȑ��݂̔@�������Ă����̂ł���B���̒��ɖ��X�c��J���A�M�O���@�̗\�Z�ψ���ɉ��ė��^��̐��i�ɂ��Ď�X�̎��≞�����d�˂���Ɏ����ď��߂Ă��̑S�e���c�X�����ɂȂ�悤�ɂȂ����B����Έ��̗d���ω����O�㍶�E���瑄�Ⓛ�œ˂��܂����đQ�����̐��̂��������Ɠ������Ƃł���B�����ė��^��̐��i�Ƃ��čł����{�I�Ȃ���͉̂��ł��邩�ƌ��ւA���^��͐��{�ƕ\����̂��Ȃ��A���{�����Ă�����������ɓO�ꂹ���ނ邪���ߐ��{�ɋ��͂��ׂ����̂ł����āA���{�Ɨ���ēƎ��̐����ӌ��𗧂Ăčs�����ׂ����̂ł͂Ȃ��Ƃ����̂ł���B ��������Ɋ֘A���Đ����̖�肪�����Ă��邩��ȉ�����ǂ��Ă�����������Č������B �@
�u���}�͌ʕ����I�Ȃ镔���̗��v�A������\���邱�Ƃ��ȂĂ��̖{���̒��ɑ����ċ��邩��A�����鎩�R��`��O��Ƃ��镪���I���}�������߂ɂ͋����I�S�̓I���I�ɂ��č������͂̌��W�ꌳ����ړI�Ƃ��鍑���g�D�^�����K�v�ł���v �@
�Ƃ������Ƃł��邪�A���ꂪ�����ɂ͉��̈Ӗ��ł��邩����Ȃ��B��̐��}���ʕ����I�Ȃ镔���̗��v�A������\����Ƃ͔@���Ȃ鎖���Ɋ�Č����̂ł��邩�B�������}�̒��ɂ͈��镔�����\���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ċN����̂����낤���A����͓���̐��}�ł����āA���}�{���̐��i�͌����č��l�Ȃ���̂ł͂Ȃ��B�������}�͖{�������̈ꕔ�ł͂Ȃ��S�����\����ړI���ȂċN����̂ł��邱�Ƃ͌���v���Ȃ��B�B���̎��ۍs���̏�ɉ��č������̈���K�����\���邪�@���Ɍ����邱�Ƃ����邪�A����͐��}�{���̐��i����E������s���ł����Đ��}�̖{���ł���ƌ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B���V�����̐��}�������߂ɗ��^���݂��ċ����I�S�̓I�Ȃ鍑���g�D���\������ƌ����Č����Ƃ���Ŕ@���ɂ��Ă�����������邱�Ƃ��o���邩�B���������̂킪���ɉ��ĐV���ɍ����g�D�𗧂Ă�Ƃ������@�����Ƃ����Џo���̂��Ԉ���Ă���B�����̂킪���͐V���ɍ����g�D���������ǂ���ł͂Ȃ��A�}�����E������ʂ��Ă킪���������g�D�̊������Ă��鍑�͂Ȃ��B����������Љ�I�Ɍ���Ȃ�A�����ȗ����Z�S�L�]�N�ɘi��ē��ꖯ�����c���𒆐S�ƂȂ��ďW�������A���̒��̌������W�܂��ĉƂ𐬂��A�Ƃ��W�܂č��𐬂��A�Љ�I�ɂ͐��E�ɗނȂ��łȂ鍑���g�D���������ċ���B�������I�ɂ͌×������̕ϑJ�͂��������A�ŋߐ��\�N�̊Ԃ͌��@�y�і@���̊�b�̏�ɗ����A�����̑I���Ɋ�����y�ђn���̋c��x���݂����Đ�����ɉ����鍑���g�D�͐��R�Ƃ��Ċm�����A����ȏ�Ɍ������]�n�͂Ȃ��B���̓�厖������O�ɒu���Ȃ��痃�^��V���ɍ����đg�D�����Ă�Ƃ���B���̑g�D�Ȃ���͔̂@���Ȃ���̂ł��邩�ƌ���A�����ɗ��^��{������A�e�{���s�����ɂ��̎x������A�����Ă����̖{���A�x�����\����������͍����̑I���ɂ���ďo�Â���̂ł͂Ȃ��S�����^��̑��ق��鑍����b�A�����ō��̍s�����������R����ɔC��������̂ł��邩�獑���Ƃ͉����̌�������̂ł͂Ȃ��A���̐��Ɏ����Ă������͑S�����̐番�̈�ɂ��B�������āA���̑��命���̍����͗��^��Ƃ͉����̊W��L���Ȃ��B�������̗��^��̎g���͉��ł��邩�ƌ����A�O�q����@�����̐��{�̐���������ɓO�ꂹ���߂Ă���ɋ��͂���Ƃ��鐭�{�̕����@�ւ���ɉ߂��Ȃ��B�R��ɂ����̔@����s�������̔C�����鍑���ꕔ�̑g�D���ȂĂ��ꂪ�����I�S�̓I�Ȃ鍑���g�D�ł����ċ��͂Ȃ�V�̐��ł���ƌ����Ɏ���Ă͗]��ɂ������Ɖ��������`�ł͂Ȃ��낤���B�������}�����R��`�̎Y���ƌ����Ȃ�A�����̔@���g�D�͉���`�̎Y���ł��邩�B������`���ꐧ��`���S�����̂������Ȃ��悤�Ɏv���邪�ǂ����B �@
 �@
�@�����{�̐����͗��^��`�@(�吭���^��I�Ƃ�)
�Ƃ���ŁA���Ƃ��Ƒ������Ƃ́A�R���͂Ƃ�����\��������̂ǂ�(�R���������̐��Y�́A�����̐��Y�ɋ�������鎑���A�����ĕ��m�Ƃ��đ���o�����l��)�Ƃ̊֘A�Ō�������̂ł���B����ɂ�������炸�A�吭���^��̌����Ƃ��āA�����������悤�Ƃ��鎞�ɂ́A���̌��t�̈Ӗ��͊g�����ꂽ���̂ƂȂ�B�E�E�E �@
������Ə������Ǝv���āA�������ꂾ�E�E�E�B�������̐��̂��Ƃ�����̃e�[�}�ł͖����̂ŁA����͌@�艺���Ȃ��B�ŁA���Ȃ����B �@
�����A�吭���^��Ƃ�����O�̑g�D�̖��O�����āA�����̉��炩�̑g�D��c�́A���邢�̓O���[�v�̐��i�ɏA���āA�܂��͂����ɑ�����l�B�̍s���┭���ɏA���āA���̓����������\���`�e���ɗp����̂́A��O�̂���ƍ����̂����Ƃɋ��ʂ������̂����邩��ł���B���̋��ʓ_�Ƃ��āA���̍l���Ă�����̂��A���܂蒆�g�Â����ɗ���A �@
���ɁA���{�Ƃ̊W �@
���ɁA���{�̈ӎv�Ƃ̓��ꐫ �@
��O�ɁA���{���͂ɂ���Ďx�z�E�w�������l�X�ɑ���W �@
��l�ɁA�E�E�E���łɑ��₵�Ă����傤���Ȃ��̂ŁA�����炠����܂łɂ��āE�E�E�B �@
���Ă����ɒ��g��^����ƁA�Ȃ�Ƃ����Ă��܂��ŏ��ɁA�����ɒ��ڂ��˂Ȃ�Ȃ��Ǝ��̎v���̂́A���{�ƒ��ڂɘA���������Ă��܂��Ă��邩�ǂ����A�Ƃ����_�ł���B���{�Ƃ́A�����ł͍s���@�\�ƍl���Ă�����Ă��悢���A�����ƍl���Ă�����Ă��悢�B�����āA���ڂ̘A���Ƃ́A�s���@�\�Ƃ̊W�łȂ�A���̕⏕�@�ւ��A�����g�D�̂悤�Ɏw�����ɂ���l��A�s���@�\�Ƃ��Ă͂��������Ȃ��Ƃ�����A����Ɏ��s���Ă����Ƃ�������֓I�ł���l��A���������l�q�̘A���W�ł���B�����Ƃ̊W�łȂ�E�E�E�A�܂������悤�Ȃ��Ƃł���B������ɂ���A���ЂȂ�тɎw�����߂̏㉺�Ō����A���{�������܂ł���ł���B�����ŁA���{�����������Ȃƌ����Ƃ���͐�ɂ��Ȃ��B�����Ă܂��A��ɂ��鐭�{�̑��݂�ے肵����A���R������͌����Ă��Ȃ��ԓx�����B���łɁA�����ɉ����ẮA���{���炻����������ꍇ������A���O��������̏ꍇ������B �@
���ɑ��̓_���q�ׂ�ƁA�吭���^��I�ȑg�D�A�c�́A�����ăO���[�v�A�y�т��̐����ɂ����āA�ނ�̍s���Ƃ���Ƃ���́A���{�̈ӎu���Ă�����̂Ɠ���ł���B�K�����͈̔͂ɂ����܂���݂̂̂��A�ނ�̎u������Ƃ���̂��̂ł���B���{�̈ӎv�̎����͈͂���̈�E(�s���߂�)�Ƃ��������Ƃ��܂܂���Ƃ��Ă��A�ނ�ɂ����āA�������Ă���Ƃ����ӎ��͌����Ď�����Ȃ��B�����I�ȑ������́A�ނ�̎��Ȉӎ��ɂ͑S�R�ɑ����Ȃ��B����̂ɁA��R�┽�R�̈ӎ��́A�ނ�̐�ɏ������Ȃ����̂ł���B�����Ă݂�A���S�ȉ����҂̈ӎ����A�ނ�̗L����Ƃ���̂��̂Ȃ̂ł��邪�A���ꂪ�P�Ȃ�]�����Ƃ��Ĉӎ�����Ȃ��Ƃ����s�v�c�ȓ����������ɂ���B�ƌ����̂��A�ނ�̎��ȗ����ł́A����͎�̓I�Ȃ��̂ł��邩��ł���B �@
���̓��قȎ�̐��ӎ��̐������́A�܂��Ƃɋ����̐s���ʂƂ���ł��邯��ǂ��A�܂�������@�艺���Ă���������̂ł�����̂ŁA�����~�܂炸�ɁA��O�_�Ɉڂ�B����́u���{���͂ɂ���Ďx�z�E�w�������l�X�ɑ���W�v�ƒ��X�����������A�ȒP�Ɍ����u�����ɑ���W�v�Ƃ��Ȃ�B���^��I�ӎ��̍��Ɗςɂ����č��ƂƂ́A��̖��Ȏ�̐��ӎ��̍������\�����ꂽ�A���{�Ƃ��̖��߁E�w���ɏ]���l�X�Ƃ̗��҂��Ȃ���̂ł���B���������̗��҂̊W�ł́A���o�I��̂����Ď��R�͂Ȃ��A��]�╞�]�͖������ĎQ���⋦�͂�����B��O�_�́A�����������Ɨ����ƍ����ӎ����w�E���悤�Ƃ�����̂ł���B �@
��O�_�̓����́A���邢�́u�����̒��ł́A�����ɑ���W�v�Ƃ��o����B�����Ƃ���Ƃ���́A���^��ӎ��̐l�B�́A���̐l�B�ɑ��āA����(���{�̖��߁E�w���ɕ�����l�X)�Ƃ����_�œ����n���ɂ���Ƃ��邪�A�������Ȃ���A����ł���Ȃ���A�l�X���ǂ�����ׂ����A�ǂ��s�����ׂ����A�ǂ��l����ׂ����X�ɂ��āA���̍����ɑ��Ďw���o�����z����L���Ă���Ǝ��F���Ă��邵�A�܂�����ɑ������w���ғI���������C����Ƃ���Ƃ��Ă���A�Ƃ������Ƃł���B����́A���߂��Ă�������o�ւƍč\�z���ďo���オ���̐��ӎ��̂��A���^�ӎ��ł���Ƃ������Ƃł���A���̈ӎ��ɂ���Ĕނ�́A���̈�����ق�(��̓I���Ȃ��\�z����)���ߌ`�ԂŎ��ꂽ���{�̈ӎv(����)���A���̐l�X�ɂ��܂��w���ғI�ɗ�s�A���サ�A���̎��A��������B��������ɂ�������炸�A���̍����ɑ��Ĕނ�͔ނ玩�g���A����n����̓��y�����Ƃ̂ݎ��ȗ������Ă���B�������Ƃ��J�Ԃ����A���^�ӎ��̐l�́A���{�̈ӎv�A���Ȃ킿���{�̖��߂���Ƃ�����A��̓I���o�Ƃ��Ĉӎ�����B�����Ă��̎��o�̖��Ăȏ������A�ނ�ɂƂ��āA���̐l�X�ɑ���ނ��(���y���ł�)��z���Ƃ��ӎ������̂ł���B �@
�����O�̓_���A���j��̂��̑吭���^��ƁA���݁A���̌`�e�������ČĂ��(�������̌`�e������)���̂ǂ��Ƃɋ��ʂ���Ƃ���ł���B���Ă̂��̂��푈���_�@�Ƃ��ďo���オ�������̂ł���̂ɑ��A���݂̐�����Љ�A�����ĉ�X�Ɏ���āA���ĂȐ푈�̑��݂��ӎ�����Ă��Ȃ��̂ɁA����ł����݁A�吭���^��I�Ȃ��̂ǂ�������A�o���オ�����A����������ƁA�ǂ����Č�����̂��A���������^�₪���낤�B����ɏA���ẮA�E�E�E�ŏ��̕��ł������菜�����Ƃ��Ă����āA�b�������Ȃ肻���Ȃ̂Ő�グ�Ă��܂����B��������炽�߂āE�E�E�A��͂�ȗ��B �@
���āA��̎O���~���ɑ����Ă�����̂�����A����͂܂������Ɩ����A���݂̑吭���^��ł���B�����܂��A���́A��̎O�̂����̂ǂꂩ��ł������Ɍ��o�����A����ɑ��Ă��吭���^��I�Ƃ̌`�e�������邱�Ƃɂ��Ă���B���̗��������Ȃ�A������ NGO �� NPO �́A���̓_��肵�āA�吭���^��I�ł���B����炪�����A�����I�ɐ��{���o���Ȃ��Ƃ�����s�����̂ł����āA���A����炪�s���Ƃ��낪��͂萭�{�̍s�����͈̂̔͂ɂ͌����I�Ɋ܂܂����Ȃ��Ƃ����_���A���m�ɂ���Ă��Ȃ��Ȃ�A�܂�A���{��������������ƍl���Ă��āA�܂��A���{�����������Ă悢�ƌ��Ȃ���Ă��āA����܂��āA NGO �� NPO �̊���������A���A���̊������e�����{�̍s���I�s�ׂɊ܂܂����邩���̉�����̂��̂ł���Ȃ�A (���邢�͍s���̎w���ɑ����邩�����Ă�����ԂȂ�A)NGO �� NPO �́A�吭���^��I�Ȓc�̂ł���B �@
���_�����̎w�E����A���^��I�̌`�e������ɂ́A���������̒��ӂ��K�v�ł���B���ɐ��I�e�[�}�Ɋւ��āA���{���ӎu����Ƃ���Ɠ������_�ɁA���Ƃ�w�҂�����̗��_�I�A�q�ϓI�l�@�̌��ʂɓ��B���邱�Ƃ�����̂ł���A�����ɓ������Ƃ������Ă��邩��Ƃ����āA���ꂾ���ŗ��^��I�ł����ł͖�������ł���B�����ŗႦ�A����ő��ł́A���{(������)�̈ӎv����Ƃ���ł��邪�A�����A�o�ϊw�҂�����̒����Ɨ��_�Ƃɂ���āA�������_�Ɏ��邱�Ƃ������āA���҂����ꂼ��P�Ƃ�(���e�[�}�ł��邱�Ƃɂ�鋤�ʓI�m���ƁA���肵������̋��L�ƁA�����Ă������ʏ퐶������e���W�ȏ�ɁA��������ӎv�ƊS�Ƃ�ʂ����킹��������Ƃ������̂Ŗ���)�������_�ɓ��������ǂ����̌������o�Ȃ��ƁA���łɗ��^��I�Ƃ͌��߂��Ȃ��B �@
�����I�A�Љ�I�ȗl�X�Ȃ��Ƃǂ��Ɋւ���A���_�I�A�w��I�咣�ƁA���̎咣�҂ɂ��ẮA��̎���l�����ꖳ����Ȃ�Ȃ��B�Ƃ���ŁA�����咣�̌`���I�A�����I��Ƃ����炷�邱�Ɩ������āA�o���オ�����咣��l�X�ɒm�点����������Ă���c�́A�O���[�v�Ɋւ��ẮA���̊����Ƒ��������{�Ƃ̊W�̖��ڂ��Ɋ�Â����̂ɂ����ẮA���i�̗��ӂȂ����^��I�ƌ�������B���Ȃ킿�A�����V���Ђ����߂Ƃ���V���E�e���r���̊e�탁�f�B�A�́A�l�X���ǂꂾ���̏������ׂ����A����m���Ă����ׂ����A���{�Ɗϓ_�A���l�ϓ���S�����������闧��ɂ��낤�Ɠw�߂Ă��邵�A���̗��ꂩ��̕����邱�Ƃ����āA�ނ猾���Ƃ���́q�W���[�i���Y���r�̖����Ɖ����Ă���B(���̂��Ƃ́A��t�r�f�I���o�� Wikileaks �ɍۂ��Ă̓��{���f�B�A�̔ᔻ���͂�����ƒm����B)�����ŁA�����̗��^��I���f�B�A�ɕp�ɂɓo�ꂷ��w�ҁA���Ƃ�A���f�B�A�̘_���ŔM�S�ɐ���������錩���̗L�͂ȍ\�z�҂ɂ��ẮA���̗��^���𐄒肵�Ă����Ă��悢�B �@
��O�_�̌��o�������̂ɂ��ẮA����Ղ����̂łȂ��A�Ȃ��Ȃ��ɔ���Â炢���̂��Ƃ��悤�B����͂�����l�b�g�T���N�Ƃ����l�B�ł���B�ނ�̎w���҈ӎ��́A�]�����悭�悭��������Ƃ���ł��������A�ŋ߂̃}���K�`�ʂ̋K���Ɋւ��āA���{�E�s���̌��͍s�g�ɂ��قǂ̋^����悳�Ȃ��Ƃ���ɉ����āA����Â炩�������^�����I�ɂȂ����B�Ƃ���ŁA���̔���ɂ����ɂ́A������R���������B��͍��h�v�z�̌n�������������t�����ƁA���h�̖��ݒ�Ƃ������p���ł��邵�A�����`��l���Ƃ������A���x�����I�Ȋϓ_�ɗ��悤�Ȏp�����������A�����Ĕނ�̌��_�����{�ᔻ�̎������悤�Ɍ����Ă�������ł���B�������ނ�ɂ́A�����ނ�̎u������ʂ�ɁA���{�E�s�������̎��s���͂��s�g����Ȃ�A��������}���邵�A���̎��s���͂̍s�g�ɉ��炩�̋����������邱�Ƃ��A�ނ�̎�|�ɓK���Ȃ�A���i�̖�莋�����Ȃ��Ƃ��낪����B �@
��̑O�̍��h���͂��]��ł����悤�ȏ�������s�����{���o�����Ȃ��Ԃ́A���h�I�Ȍ����́A�m���ɂ�����x��(���邢�͌��������)��R�I�Ŕ��ΓI�Ȑ��{�ᔻ�Ƃ������i��^������Ƃ��낪�������B�������Ȃ���A�������݂̐��{���A���̈ӎu����Ƃ�����A�T���N����������悤�Ȍ`�Ō����\�����A���̌��ʂɎ���������̂��T���N�̖]��ł���Ƃ���Ǝ������̂ł������肷��Ȃ�A�T���N�͂��̂܂܂ɗ��^��I�Ȗ����Ƌ@�\���A��X�ɑ��ĉʂ������ƂɂȂ낤�B���̖����Ƌ@�\�Ƃ́A���{�̈ӎu����Ƃ���̎����ɗ��^�I�ɋ��͂������(��X�ɑ��Ă������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��w���ғI�ɐ����ĉ�����)�ł���A���{�̖��߁E�w���ɍ������]���Ă����悤�ɂ��邱�Ƃ����������Ă����@�\(���s���͂̋������������I�ɑ��傳���Ă����@�\)�ł���B �@
���ĎO�_���ꂼ�ꂪ�A����ΕʌP�ƂɌ��o�������̂ǂ���Ꭶ���Ă݂����A���N�̓��{�ɂ́A���̎O�_���ׂĂ����ˎ��������̂��o������ł��낤�B��������́A����Ɩ��t�����A����Ǝw������g�D�Ƃ܂ł͂Ȃ�Ȃ��ŁA�O�̗v�f�̂ǂꂩ����苭�������̂ǂ����A�݂��ɓ����������āA����������̂��̂̔@���ɁA��X�ɑ��č�p����悤�Ȍ`�ƂȂ邩������Ȃ��B���N�̏�����̂��̍����Ԃ�Ȃǂ́A���̐�삯�I�A�\���i�K�I�Ȃ��̂ƌ�������B �@
�����Ă��̍U���̍��{�I�u���ƒʂ������Ă���̂����A���̍��̐l�X�����{�ɑ��ė��^��I�ȊW���\�z���Ă��܂��̂́A��ɂ͋c��A���邢�͗��@���͂̓����Ƃ������̂��A��X��������Ɨ������Ă��Ȃ�����ł���B���̂����������b�N�����w�̂܂��������݂��Ȃ����̔@���A���{�̐����v�z���A�����I���v��Љ��������Ă�l���A���̔M�S�ȓw�͂ɂ��ւ�炸�A������������������鐭���I��H�̕s�݂̌̂ɁA�����Ă���ł�������ڎw�������邻�̔M�ӂ̌̂ɁA���]�Ȑ܂��o�āA���^���ɍs���������Ă��܂��̂ł���B�܂���ɂ́A��\���I�ɓ����Đ������A���{�̖����Ɋւ���Ӌ`�ƕK�v���F���́A����ȑO�ɔ䂵�Ė����Ȃقǂƌ�����g�����A���^�I���z�Ƀu���[�L���|���邱�Ƃ������̂ł���B�Ō�ɂ�������A�V�c�̓���(�Ȃ�ϔO)���A�قƂ�ǎ����I�ɂ͔ے肳��邱�ƂȂ��A���ɑ�����ς��č\�z���ꂽ�V�c�������̐��{�ɂ�铝���������A���܂ł����Ă��A���^��I�s���l���ݏo������ƂȂ��Ă���̂ł���B �@
�E�E�E��̂Ƃ���܂ŏ����I������A�����������ƂɌ��U���瓪���炷�̂��قǂقǂɁA�Ƃ����C���Ő�グ�Ă��܂����B�Ƃ���Ő����C���ɂ����Z���Ă�����A�ȉ��̂��Ƃ����������Ƃ��炭�O����v���Ă����̂��A����̂悤�Ȃ��Ƃ��L���̂ɂȂ����Ă����̂��v���o�����̂ŁA��������������B �@
�吭���^��̂��Ƃɒ��ӂ��������̂́A�N�����܂��o���Ă��邱�Ƃ��Ǝv�����A���c��������}����\�Ƃ̊ԂŁA�����}�Ɩ���}�ƂŘA�����悤�Ƙb���܂Ƃ߂����ɁA�V���������đ吭���^��Ɣᔻ���Ă���̂����āA�����܂����������̒m���◝���������������ɂ�������炸�A�ǂ���������ƈႤ�Ɗ����āA�吭���^��̂��Ƃɂ��炽�߂ĊS��U����������Ƃ��n�܂�ł���B �@
���̘A���̓����Ɋւ��ẮA����ɂ���Đ�����c��̔\�͂��A�����܂ł��c��̗D�z���ɂȂ�����̂ł���Ȃ�A�܂萭�}�����}�Ƃ��Ă̂���������킸�ɂ܂Ƃ܂�Ȃ�A�����Ȃ��Ƃ��吭���^��ƌ�����悤�Ȃ��̂Ō����ĂȂ��A���̂悤�ɍl����ɓ������B(�������������Ȃ����̂ł���Ƃ��Ă��A���̓������̂��A�܂�����ɂ���Đ��������ǂ���]���邩�́A�܂��ʂɈׂ��꓾��B) �@
���č����A�����l�����������靀���ꍑ��ł̏���P��A���{�w���͂̑�����ڎw���āA���}�Ƃ̘A����͍����āA���X�Ɠn������悤�ƕ��Ă��邵�A�����Y������}�}��̎��_�Ǝ��͂���ڂ���Ă��鐭�E�ĕ҂̈Ӑ}���A���}����}�������ďo�đ��}�A���O���[�v�Ƃ̌��W�̊�}����Ƃ��鐭�NJϖ]�I�ȕ�����B�����Ă����ɂ��A���҂̓����Ƃ��ɑ吭���^��ƌ���ꂽ��A��҂݂̂�O���ɑ吭���^��ƌ���ꂽ�肷��̂��A�u���O�Ȃǂɂ��炿��ƌ�����B�@ �@
��������ɂ��Ȃ���A���N�O�̕��c���̎��̘A����ᔻ���āA�吭���^��ƌ����Ă���̂Ɠ����A����Ɣ瑊���Ƃ����͊����Ă���B��ɏq�ׂ��悤�ɁA�吭���^��I�Ȑ��i�́A�ł���v�ȓ_�́A����`���Ɋւ��āA���{�́A�L��̂Ɍ����Ċ����̉��ʂɗ����Ă��܂��Ƃ���ɂ���̂ł����āA����̗l�q�����ɂ߂Ĕ��f���Ȃ��ƁA����ł͑吭���^��Ƃ������͓I�O��ł��邵�A���̌��t���Z���Ă��镉�̃C���[�W�𗘗p�����A�����ׂɂ��郌�b�e���\��ł����Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B �@
���ݎ��_�A���Ȃ�ɔ��肷��ɁA�����Y��c�m�����S�ɂȂ��āA�V���}�ւ̌��W���N����̂ɂ��ẮA�����哱�̐��������炽�߂����Ƃ̔������{���Ȃ�A�����吭���^��Ƃ͌Ăѓ��Ȃ��B�ނ���A�����l������b�̐����w�����ێ����Ă̘A���̕����A���̓��t�Ɍ����Ɍ�����c��Ȃ�тɐ��}�̊����c�ւ̉��ʐ��̌̂ɁA�吭���^��I�Ȑ��i���������������̂ƌ����ׂ��ł���B �@
�Ƃ͂����c��Ƃ������x�ƁA�����𑫏�Ƃ��Đ����͂�L�����c�m�Ƃ������݂Ƃ́A���̐��x�Ɩ������炵�āA�吭���^��̐����̏ꏊ�ł͂Ȃ��B�����Đ��}���吭���^��ɂ܂�����萬�����Ă��܂��Ƃ����قǁA�P���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��̂ł���B�吭���^��́A����ΐ��{�̈ӎv�����s���Ă�����H�ł����āA���{�̎w���E���߂ɕ�����n�ʂ̎ҒB(�]���ҒB)�𒆐S�ɂ��Č`���������̂ł���B �@
�E�E�E��O�̐����o�܂�茾���A���a�����ɋc����E���}�����̉�H���������ɂ��ւ�炸�A���ʂ̎���Ɣ��c��̓����ɂ��A�c��Ɛ��}�Ƃɐ����̕ω��̋N�_����͂�M���Ȃ��Ȃ���(�����Ɋ��҂����ȂƎv�����܂ꂳ�ꂽ)�l�X���A�����ɕς�鐭����H���A�܂邲�ƐV�������o�����Ƃ������z�����A(�����ē��R�ɂ���Ɏ��s���A)�c��ɂ�铝����j�āA���琭�{�̏]���҂ւƗ�������ł������̂ł���B �@
�E�E�E���݁A����Ǝ������Ƃ��N���Ă���A���}�����ւ̕s�M�Ƃ������̂��A��������i�������A�V���⏑�Г��̃��f�B�A��ʂ��āA�l�X�̐��������̒��ɍL�߂��Ă���B�c��Ɛ��}�̂��Ƃɐ����̉�H�����o�����Ƃ��Ȃ��X���́A��N���A�܂��܂��������̂ƂȂ��Ă���B���܂��V���ɕ���A���̓����Ɋւ��āA�吭���^��Ƃ����������܂�[�������������Ԃ��āA����ł����Đ����̕������ɂ��Ă��̂������Ă���Ǝv���l�B�̑ԓx���A�����Ă݂�A��O�̎��琭���I��H��ł��āA���̐�ɂ��L���Ȃ��̂�����Ɩ��z���āA�����Ă���Ɏ��s�����l�B�Ɠ������̂Ȃ̂ł���B �@
�E�E�E���̓����ԓx�́A����������L�����n���Ȃ�A����}�ɉ�Ȕ����J��o������A�����}�ւ̑��ς�炸�̏s��ȋ�����J�Ԃ����肵�āA�S�ے�I�Ȑ��}�]����I�ɂ��A����ł��āA���{�̈ӎv�Ƃ��قǕς��Ȃ����j���Ɋւ��āA����̎����Ɏ^���������l�B�ɂ��A��͂茩�o������̂ł���B���łɂ�����A���Y�}��Ж��}�̎x���Ƃ������n����A����E�������̑��̐��}���A��͂�S�ے�I�ɏq�ׂ�҂��A�킸����炠�邢�͈ꌩ���}�x������̋c�_�ł��邯��ǂ��A���ۓI���ʂɉ����Ă݂�A�l�X�Ɏn�܂�A���}����āA�c���ʂ��āA��̍��̓��������������Ă����A��������������H�̔j��A�E�E�E���Ƃ��Ƃ������Ď�������̂Ƃ��đ��݂��Ă��Ȃ���������A�������������悤�A����̐�����W������̂ł����Ȃ��B���̍s�����������_�́A���̓����̎p���A���{�̈ӎv�̎���������H�������Ȃ�A���Ȃ킿�A���{����̎w���E���߁E�w���̉�H�������Ȃ鍑�̏o���ł���B �@
 �@
�@���吭���^��͂ǂ����Ă����Ȃ������̂ł��傤�H
�u�吭���^��ɂ���āA�푈���N�����ꂽ�I�v�Ƃ����悤�Ȉ�ۑ�����s���Ă��܂����A��̓I�ɂǂ�Ȉ������ۂ��N�������̂��H�����Ă��������B �@
�c��ŋc�_���s���Ȃ��Ȃ��āA�����`���@�\���Ȃ��Ȃ����A�ȂǂƂ����Ă��܂����A���_����v���Ă���Ƃ��ɂ́A�c�_�̂��߂̋c�_�͕K�v�Ȃ��Ǝv���܂��B �@
�ǂ������c�_���K�v�������̂��A��̓I�Ɏw�E�ł���ł��傤���H �@
���̋c������Ă��A�K�v�ȋc�_�ȂǑS�R�����悤�Ɍ����܂��B �@
�������R����`�Ɋׂ��Ă��āA���_����v���Ă���Ƃ��ɂ́A�吭���^��ɂȂ�̂��A���R�Ȍ��ۂ��ƁA���͎v���̂ł����A�@���ł��傤���H �@
�� �@
�펞�̐�����������A�R���̔����͂��������̂��A�Ǝv���܂��B�R�������҂ɂ��邱�Ƃʼn������悤�ȋC������̂́A��肾�Ǝv���̂ł����B �@
���������Ƃ���ł��B���^�̕���Ŏv�l��[�܂��Ă͂����Ȃ��Ƃ����T�^�ł��ˁB �@
�吭���^����\�z���������҂����ɖ{�S����R���́u�\���v����������ړI���������̂��Ƃ��Ă��A�����ɂ͂��ǂ��푈��키���߂̑g�D�ł���Ƃ��Ȃ���Ύ������Ȃ������̂����A�����̑����͂��̂悤�ȑg�D�ł���ƌ��Ȃ��A�����ۂɂ��̂��߂̑g�D�Ƃ��Đ������W�����̂ł�����A�������ɂ킽���̏������ł͎����̕Жʂ����Ƃ炦�Ă��܂���B �@
�R���Ƃ������̂͂ǂ��̍��ł��Ǝ��̔��f�œ�����������̂��Ǝv���܂����A�ǂ��܂ł��ꂪ������邩�͂��̎��X�ł̏���(�l�����܂߂�)�ɂ���ĕς��̂ł��傤�B�Ȃ��ł��A���ۂɐ푈�����Ă��邩�ǂ����͑傫�ȗv���ɂȂ�̂��ƍl���܂��B���͂̏��Ȃ��炴�镔�����X�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��푈���ɁA��K�͂ɐ키�R�����A���{��c��y�I����͓̂�����낤�Ƒz�������܂��B �@
�̐������폟�̖ړI�ɂ������Č��͋@�\�̈���̂��߂ɋ��͂ȌR����]�݁A���̌��ʌR������剻���đ̐����ɌȂ̈ӎu����������B���̏�Ԃ���U�藎�Ƃ���Ȃ����߂ɂ͌R���ɐ�ČR���̈ӎu�����Ȃ��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B���ꂪ����Ȃ�R���̋��剻�������炷�B�܂��Ƀj���g���ƃ^�}�S�̊W�ł��B �@
�X�^�[������ё͂��̉ߒ������܂�ɂ��ߏ�Ȑ������ŗ}�����݂܂���(�D�܂������ԂłȂ����Ƃ͌����܂ł�����܂���)���A�t�ɂ��������܂ł��Ȃ���ΌR�����Ǘ������ł��Ȃ������̂�������܂���B���Ȃ��Ƃ��A���l�����͂����M���܂����B �@
���̊J���ƍق܂ł�����ɓ���Ă��A������ċߑ㉻�ɏ��o���������ł́A�݂ȋ��͂ȌR���Ɏx�����ꂽ�V���{���b�N�ȃJ���X�}�I�w���҂������܂��B�R���Ɉˋ����Ȃ���R�����x�z���ɂ����A���͂̏ے��Ƃ��č����̑O�ɗ���������l���ł��B�ǂ��܂ł��ꂪ�ƍٓI���͂����邩�͈�T�Ɍ����܂��A���͂���̓I�Ȋ�������Ƃ��ǂ����Ă��K�v�Ȃ̂ł́A�ƍl���܂��B �@
���̓_�A���{�͂ǂ����������Ƃӂ�Ԃ�A�����p�@�ł͂ǂ��ɂ���s���ł��B�����̌��M�����͂܂����̎��i�����肻���ł����A�ނ炪�ޏꂷ��ɂ�R���̓����������Ȃ��Ȃ��Ă������̂͒P�Ȃ���R�ł͂Ȃ��̂�������܂���B���̕ӂ͂��܂荪���̂Ȃ��ϑz�ł����B �@
����{�鍑�Ƃ͑��`�I�ȑ��݂ł����A�����ĂЂƌ��ł����ΑS���̋��}�I�ނ�Љ���A�_�������I�ȑ������܂Ƃ����u�V�c�v�����O�Ƃ��钆���W���I�������ł������̂��ƍl���܂��B�R����`�͖{�����̈ꑤ�ʂɂ����܂���ł����B �@
�������A�������̓��������̖����Ȑ��ƂԂ�ɂ��邱�Ƃ��v���A�����@�\�ɂł��邱�Ƃ͊�{�I�ɏ̒ǔF�ł����đS�̂̍\�z�ɂ͌����Ȃ��̂ł��傤�B��O�̍����^���͑��̍��̎x�����L�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł�����l���ɂ���т܂���B�{���A�����S�����̂͐��x�I�ɂ��V�c�������̂ł��傤���A�����ɂ��̂悤�ȓW�J�͂��ǂ�܂���ł����B�c����Ƃ����͌����܂ł�����܂���B�u���x�v�Ƃ������t�͎g����������܂��A��͂荑���̐����I�ӎ����͕s���ł������ʂ͔ۂ߂܂���B �@
�x��ċߑ㉻�ɏ��o�������ł͂ǂ����R���ɕΏd���������̐����Ƃ���̂ł����A������Ƃ����ĕK���N���푈�ɏ��o���킯�ł͂���܂���B�������A�Ȃ����{�ł͈�����̂ł��傤�B�������͑傫����p���܂����A�킽���͂��̊�̂Ȃ��A�܂肾����ӔC���Ƃ�Ȃ�(�����Ȃ�)�̐��ɂ��������������̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă��܂� �@
������A���ʓI�ɖ��m�Ȉӎu��L�����ꕔ�R�l�����Ԃ����E���邱�ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����I�ӎu�̋��R����`�����ߍ��킹���̂��ƌ����邩������܂���B �@
2.26�����ŏ��a�V�c�����������m�Ȉӎu�ɌR�����R�ł��Ȃ��������Ƃ͂��̖T�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�V�c�Ƃ����l�ɗ��炸�����Ƃ����̈ӎu��ێ����Â��A������������x�������Ȃ�A���Ԃ͂܂��ς�����̂ł́A�Ƃ��z�����܂��B �@
�ߑ㍑��(��������)�̌`���͋ߑ�̑��͐�ɉ����邽�߂������Ƃ����̂́A�܂��������̂Ƃ���ƍl���܂��B���ƁA�v���ɂ͋ߑ�Y�Ƃ̈琬(�H�Ɖ�)�����ꂽ���ł��B �@
�ɂ�������炸�A�p�ĕ��ł͔�r����Γ��{�قnjR���������I�ȗ͂������܂���ł����B���Ȃ��Ƃ��A���n����������ɐ푈���n�߂Ă����ǔF���邵���Ȃ��悤�ȏ͂���܂���ł����B����珔���ł͐푈�����Ă����{�قǍ��͂��X�����Ȃ��ł����̂ŁA���ΓI�ɌR���̗͂������܂ŐL�тȂ��������ƂƁA�������܂߂Đ����̗̈�Ŏ��s��������鎞�Ԃ����������Ƃ������ƍl���܂��B �@
���̊J���ƍق̏����ł́A��͂�ă\�̓�㒴�卑���}������ł������Ƃ���Ԃ̌����ł��傤���B �@
���Ă݂�ƁA�h�C�c�͂܂��ς���ł��ˁB�r�X�}���N�A���B���w����2���A���C�}�[���̐��A�q�g���[�Ƃ��ꂼ��̎��ゲ�Ƃ̌����A����Ԃ̈��ʊW�ȂǁA�ߑ㉻�_�ŕ��͂��������͂Ȃ����̂ł��傤���B �@
���ʓI�ɂ킪���̑吭���^��͌R���ɑ��Ė��͂ł���ǂ��납���͂��A�⊮���������́A��͂�ŏI�I�Ȕj�]�����j�I�K�R�ł��������Ƃ̏ؖ��Ȃ̂�������܂���B�������A�ߌ����K�R�ł������Ƃ͎v�������Ȃ����̂ł��B �@
���肤�ׂ��ʂ̓��͂Ȃ����̂ł��傤�B�ǂ�������̔j�]��������ꂽ�̂ł��傤�B�P�Ȃ���Î�ł͂Ȃ��A����̐��X�������ӎ����Ǝv���܂��B �@
������ڐ�̂��Ƃɒǂ��Ă���܂��Ȃ��ŁA�������������I�ȃX�p���ŕ������l���邫��������^���Ă����������肪�Ƃ��������܂��B �@
 �@
�@�����^�̐��_ / �����m�푈���ɉ����鍑���^���ƒ鍑�c��
�{�_���́A�����m�푈���ɏd�_�I�ɍs��ꂽ�����^���ƒ鍑�c��̕��͂�ʂ��āA���������̎d�g�݁A�鍑�c��̌`�[���̐����ߒ��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ��A���{�t�@�V�Y���̐��̒��j���Ȃ����^�̐��̓����y�т��̎��Ԃ��l�@����B �@
�܂��A�吭���^��A����{���^�s�N�c�A���^������(�ȉ��A�吭���^��͗��^��A����{���^�s�N�c�͗��s�A���^������͗�����Ɨ��̂���)�̎O�̒c�̂Ɏx����ꂽ���^�̐��Ɋւ��錤���Ɋւ��ĐG��邱�Ƃɂ��A�{�_���̌����j��ł̈Ӌ`�m�ɂ���B���̍l�@�ɓ���܂��Ɏw�E���Ă����������Ƃ͗��^�̐��Ƃ����ꍇ�ɁA�����x�z�̐��Ƃ��Ă̑��ʂƁA�c��^�̐��Ƃ��Ă̓�̑��ʂ�L���Ă���_�ł���B�ȉ��A�{�e�ł͂��̓_�ɒ��ڂ��A�����̗��^�̐��Ɋւ��錤���j�����Ă݂����Ǝv���B �@
�܂��A�����x�z�̐��Ƃ��Ă̗��^�̐��Ɋւ��錤���̌X���́A�T�˓�ɕ����邱�Ƃ��o����Ǝv���B�܂�A���^�̐�����{�ɂ�����t�@�V�Y���̐��̐����Ƃ��ĂƂ炦�錤���ƁA�t�@�V�Y���̐�����ے肵�A���邢�̓t�@�V�Y���T�O�̗̍p�����ۂ��闧��̌����ł���B �@
���̍����x�z�̐��Ƃ��Ă̗��^�̐��Ɋւ��錤���̖��_�Ƃ��Ď��̂��Ƃ��w�E���邱�Ƃ��ł���B�@
���ɁA�t�@�V�Y���̐�����ے肵�A���邢�̓t�@�V�Y���T�O�̗̍p�����ۂ��闧��̌����ł́A���^��̐������߂��鏔�������͂̑R�W�Ƃ����ɂ�����u�v�V�v�h�̍\�z�̍��܂����ɖڂ����ς��A���������^���c�̂̐E��g�D�y�ђ�����E������A�בg�Ȃǂ̒n��g�D�𗃎^��̎w�����ɂ������Ƃɂ���āA���{�������̉��I�g�D���ɐ������A����ɂ���č����̍��������������\�ɂȂ������ʂ����̂�����Ă���A���ɗ��^����g�Ȍ�̎��ԕ��͂��s���Ă��Ȃ��_�ɑ傫�Ȗ�肪����B�܂��A�n�惌�x���ɂ����鐭���̓��Â̔c���A���邢�͒n��ŌJ��L�����Ă������s�ɑ�\�����t�@�V�Y���^���̑��݂Ƃ��̈Ӌ`�����˂Ƃ����X�������� �B���ɁA�w偂̑��̂悤�ɒ���߂��炳��Ă��������g�D�ɂ�荑�������̓O�ꂵ���������s���Ă������ʂ��S����������邱�ƂɂȂ�B �@
���ɁA�t�@�V�Y���̐��̐����ƂƂ炦�錤���ł��邪�A���{�t�@�V�Y���̏ꍇ�A���̗��j�I�������ێR�^�j�ɂ���āu�ォ��v�̃t�@�V�Y���ł���ƒ莮������Ĉȗ� �A���ꂪ���{�t�@�V�Y���Ɋւ��鋤�ʂ̗����ƂȂ����B�������A���̂悤�ȓ��{�t�@�V�Y���̐����_�@�Ƃ��āu�ォ��v�̓������d������]���̒ʐ��ɑ��A�������ɁA�u������v�̗v�f�̏d�v�������������悤�ɂȂ����B�u������v�̓������d�v�����錤���́A��ɎЉ�o�ώj�𒆐S�Ƃ����t�@�V�Y���́u�S����v�̕��͂ł��邪�A���̕��͂������Ȕ��ʁA�t�ɐ����̐��S�̂Ƃ̊֘A���y�������X��������B���ɁA�u������v�̓������������邱�Ƃɂ��ێR���w�E�����悤�ȁu�ォ��v�̓������ǂ݂Ƃ�ɂ����Ȃ������Ƃ������ł���B�������A��{�I�Ƀt�@�V�Y���Ƃ́u�ォ��v�Ɓu������v�̗����̗v�f���Ȃ��ł͐��藧�����A���҂̓����𑊌݂Ɋ֘A�Â��Ĕc������K�v�����邾�낤�B �@
����ł͎��ɗ��^�c��̐��Ɋւ��錤�����l�@���Ă݂悤�A��q�����悤�ɗ��^�̐��Ɋւ���]���̌����͎�ɁA���^��̐������߂���e�������J�̓����⍑���đg�D���̕��͂ɂ��̏œ_�����킳��A���̎����ȍ~�̋c��J�̓����̕��͂�ӂ��ė����B���̎�Ȍ����́A���^�����̒鍑�c��͌���I�ɖ��͉����A�`�[�������Ƃ����]�ނ��w�i�ɂ��邩�炾�Ǝv����B �@
�������A�ŋ߂��̐��ɋ^��������A���^�I����ʂ��Ă������̋����}���͂͐��͂��������A���鍑�����t�ȍ~�����I�L�����Ƃ����Ƃ��錤�����łĂ����A���̂悤�ȗ��^�c��Ɋւ��錤���Ɋւ��Ď��̂悤�Ȗ��_���w�E���邱�Ƃ��o���悤 �B���ɁA�����̌����͐��{�c��̑R�W�̕��͂ɏd�_��u�����Ƃɂ��E�����@�\�S�̂̒��Ő�߂�c��̈ʒu�A�܂����̕ω��̉𖾂�ӂ��Ă���B���̉𖾂Ȃ����āA�c����ɂ����鐭�����͂̓���������ǂ��Ă��A���^�c��̂��̂̓����͖��m�Ɍ����Ă��Ȃ��Ǝv���B���ɁA1���c��͂Ƃ����ǂ��A���^�c��̑O�ƌ�ł͂��̐����p���ɔ����ȕω��������邪�A���̓_�������̌����͊ʼn߂��Ă���B��O�ɁA����ɁA1942�N�̗��^�I���ɂ���ċc��͂̓����ɑ傫�ȕϓ��������������͊T���Čy������Ă���B���ہA1942�N4���ɍs��ꂽ�O�c�@�I����A���I����466�l�̏O�c�@�c���̒�199�l(��169�l�����E)���V�l���ł������B�����đ�l�ɂ́A�������E�̓��������ɏœ_�����킳��āB�n�惌�y���ɂ����鐭���I�R�W�A���ɗ��s�̊����̎��Ӗ����y������Ă��邱�Ƃł���B
�ȏ�̌������ʂ܂��Ė{�_���ł́A���̎��p���痃�^��E���s�E������̕��͂�ʂ��āA���^�̐��̎��Ԃ𖾂炩�ɂ������B �@
���ɂ́A�t�@�V�Y���̐��m�����ȍ~�̓W�J���d�����邱�Ƃł���B�]���̗��^��Ɋւ��錤���́A�����I�ɂ�1941�N4���̗��^��1�����g���܂ł̎����́A���������͂̓����ɕ��͂��W�����Ă���B���̎�Ȍ�����1�����g�ɂ�藃�^��͐����������Ƃ��A���̈Ȍ�͂����ς�s���@�\�̕⏕�@�ւ̖������ʂ����Ƃ���]�����w�i�ɂ��邩�炾�Ǝv���B�������A���ꂾ���ł͂��̑̐��̉��ŋ��͂ȍ��������E�����������\�ɂ����d�g�݂��[������������Ȃ��ł��낤�B �@
�܂��u������́v�t�@�V�Y���^�����d������{��T�����{�����̌����̏ꍇ�ł����͂̑ΏۂƂȂ鎞����1940�N�H�Ŏ~�܂��Ă���A�t�E�V�Y���̐��m�����ȍ~�̃t�@�V�Y���^���̈ʒu�t�����g���ɂȂ��Ă���B���{�t�@�V�Y�����̐��Ƃ��Ċm�������Ƃ��Ă����̊�Ղ͐Ǝ�ŕs����ł���A�����炱���E���̑̐��̐����̂��߂ɂ���Ȃ�^���̗v�f���d�������链�Ȃ��������ʂ��������Ă͂Ȃ�Ȃ����낤���͂�A�t�@�V�Y���^�����u���͂Ƒ�O���q���}��v�Ƃ݂Ȃ��A�t�@�V�Y���̐��m����̉^���͂���K�v�������� �B �@
���ɂ́A���Y���ɂ����鍑���^���̓W�J�Ƃ��̒��j�I�S����ł��������s�̊����̑S�̑�����̓I�ɖ��炩�ɂ��邱�Ƃł���B�����^���Ƃ����T�O�͎���̕ω��ɔ����ς���Ă������A���^����Ȍ�̍����^���͍��������Ɠ����Ӗ��Ŏg���Ă����B�����^����W�J���邱�Ƃɂ��A�푈�̉~���Ȑ��s�ƍ����̎x���B���悤�Ƃ��Ă�����ł��邪�A���̗��^�̐����ɉ����鍑���^���Ɋւ��錤���͂��܂��قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��B �@
�܂����s���̂Ɋւ��錤���Ƃ��ẮA�����N�v�ɂ�藃�s��������1943�N�̉��g�܂ł̌o�܂����炩�ɂ���k�͌��O�y�єg�c�i���ɂ��E���^�I���̒n��ł̎��ጤ�����s���Ă����B�������A�]���̌����ł́A���^��A���s������O�ҊԂ̑��݊W���[������ɓ��E�Ă��Ȃ����A�{�e�̏d������O�c�@�y�юs������ɂ����闃�s�W�c���̕��͂��S���s���Ă��Ȃ��B �@
��O�ɂ́A���Ɠ����@�ւ̒��ł̒鍑�c��̈ʒu�Â��m�ɂ���ƂƂ��ɁA�ψ���Ȃǂ̕��͂�ʂ��ė��^�c��̗��j�I�ʒu���l�@���邱�Ƃł���B�������@�ŋK�肳�ꂽ�鍑�c��̌����́A�@���̐�����\�Z�̐�����c��̋c�����K�v�Ƃ���Ȃ���A���@���ł͖@������Ɂu���^�v���邾���ŁA�����c���ł͗\�Z���s���������ꍇ�͐��{���O�N�x�\�Z�����s���邱�Ƃ��\�Ƃ����ȂǁA����߂Č��肳�ꂽ���̂ł������B�������Ȃ���A�@�I���ʂ��y�ڂ����Ƃ͂ł��Ȃ����A���⌠(���^��)���s�g���A�c��Ő��{�̐�������J�̏�Ŕᔻ���������鎖���鍑�c��̏d�v�Ȑ����I�@�\�ł��E�����Ƃ��ʼn߂��邱�Ƃ͏o���Ȃ��B���̋c��́u�s���Ď����v�́A�@�I���͂��Ȃ��Ƃ͂����A���̍s�g�͎����I�ɐ��{�̑S�����ɂ���Ԃ��̂ŁA���{���c������Đ���𐋍s���邱�Ƃ�}�~���鐭���I�@�\���ʂ����Ă����B���������鍑�c��̐����I�@�\�ɒ��ڂ��A���̕ω��ɂ����ӂ��Ȃ��痃�^�c��̕��͂��s�������B �@
��l�ɂ́A�����ƒn��̓�����I�ɔc�����邱�Ƃ��߂����B�]���̌����ł́A�������ǂ̐����ߒ��̕��͂̍ۂɂ́A�n��ɂ�������Ԃ̔c�����y������A���̔��ʒn��ɂ����鍑���x�z�̖��ɏd�_���u���ꂽ�����ł́A�S�̂̐����̐��Ƃ̊֘A���y�������X�����������B���̖����������A���^�̐��̑S�̑��ɂ��܂邽�߁A�����ƒn���I�ɂƂ炦��悤�S������B��ɂ��q���悤�ɗ��^�̐��͍����x�z�̐��Ƌc��^�̐��Ƃ�����̑��ʂ�L���Ă����B���̓����𖾂炩�ɂ��邽�߂ɂ́A��͂蒆���ƒn��̓�����I�ɔc������Ƃ����A�v���[�`���ǂ����Ă��K�v���낤�B
���ɁA�e�͂̓��e�ɂ��ĊȒP�ɏЉ�Ă����B��I���ł́A�����x�z���ɏœ_�����킹�A���͑ΏۂƂ��č����^�������グ�A���Ƒ��͐퉺�ł̍��������E�����̍\���𖾂炩�ɂ������̂ł���B�܂���1�͂ł́A���^�̐����Ɏ��{���ꂽ�����^���̌���A�w���A�`�B�̎d�g�݂͂��邱�ƂŁA�����^���������ɂ��č����ɓO�ꂳ�ꂽ�̂����́u��Ӊ��B�v�̉ߒ����l�@�����B��2�͂ł́A���ۂɌ��肳�ꂽ�����^�����ǂ̂悤�Ɏ��{�����̂����A�����^���̐��i�͂ƂȂ������s�̊�����ʂ��Ĕc�����Ă݂��A��3�͂ł́A��ʌ��Ƃ�����n��ł̎��ᕪ�͂�ʂ��āA���s�̒S����̖��⍑���^���̎��Ԃɂ��Ă���Ɍ@�艺���Č������Ă݂��B��4�͂ł́A�]���̌����ł͂قƂ�ǖ�������Ă����A���s�̐����J�̌���ł������ƍl�����闃�s�s������c���̕�������グ�A��ʌ�������ɁA���s�s������c���c�̌`���ߒ��Ǝ�Ɏs��ɂ����銈���͂����B �@
��H���ł́A�t�@�V�Y���̐����ł̒鍑�c��̖������グ��B��1�͂ł́A�c��͂̍ĕҐ��ߒ����A�������}���͂Ƃ��Ă̓�����ƁA�V�����͂Ƃ��Ă̗��s�c���ɏœ_�����킹�ĕ��͂��A���ĉ�̑O�g�ł��铯����̌`����������A�����ďO�c�@�ɂ����闃�s�W�c�����`�������o�܂��l�@�����B��2�͂ł́A�鍑�c��O�c�@�̒ʏ�c��y�їՎ��c��ł̐��{�y�ҏO�c�@�c������o���ꂽ�@���Ă̌����A���߂Ɩ@���Ƃ̔�r�A�ʏ�c��E�Վ��c��ɂ�����{��c�̊J������Ɖ�c������A�ʏ�c��ɂ�����ψ���̊J��Ɖ�c�����ԁA�ʏ�c��ɂ����鐿��ψ���Ȃǂ̃f�[�^���瓝���@�\�S�̂̒��Ő�߂�c��̈ʒu�̕ω��A���ɂ��̐����I�@�\�̒ቺ�𖾂炩�ɂ����B��3�͂ł́A�u��}�I�v�������͂̑��݂ɒ��ӂ��Ȃ��瓌����t���̑�80���84��܂ł̗��^�c��̐����ߒ��͂��A�������x���ł̗��s�c���c�̊������n�惌�y���ł̂���ɔ䂵�ĊT���ĕs�����ł��艸���ł��肽���ƁA�������A����ɂ�������炸������ɂ�闃�s�z���̓����ɑ��Ă͗��s�c���c�������Ȕ��Ή^����W�J�������Ƃm�ɂ����B��4�͂ł́A������t�̋c���A����ɑ��闃�s�c���A������̓�����T��A������t�ȍ~�A�m���ɋc��͂̕������݂���Ƃ͂����A����������{������ɂ�鍑���^���ꌳ���\�z�͌��ǂ͎��������A���̐��������ɂ��x���ݒu���ɂ݂���悤�ɑ傫�Ȍ��E�����������Ƃ𖾂炩�ɂ����B
�Ō�ɁA�{�_���̕��͂��ȒP�ɑ������Ă��������B �@
���ɁA�����^���Ɋւ�����ł���B�����͑����m�푈�̊J��ɔ����A�~���Ȑ푈���s�Ƌ����̐��̊m�����͂��邽�߂ɁA�����^�����������悤�Ƃ����B���̂��ߐ��������D���A�P�Ȃ�s���@�ւ̕⏕�I�@�ւɓ]�����Ă��̕������������Ă������^��̋������Ӑ}���A���������^���c�̂̐E��g�D�A������E������A�בg�Ȃǂ̒n��g�D�����̎w�����ɑg�ݍ��ނ��ƂȂǂ̋@�\���V�[�u�ɂ��A�����^���̊ēw���@�ւƂ��Ă̐��i�m�ɂ������B����ɉ����A�����^���I���^�^���̒��j�I���i�g�D�Ƃ��āA���s�������������B �@
�����^���́A���W�I�̗��p�����ʂ��č�����l��l�ɓO�ꂳ�ꂽ�A���Ȃ킿�A����́A���^��s(��)��������������E�������בg���ƒ�̌n���œ`�B���ꂽ�B���̏��͍����Ɏ��ǂ�F�������A������~���ɐZ�������邽�߂̕���ł���A���������̏�Ƃ��ċ@�\���Ă����B���̂悤�ɂ��ēW�J���ꂽ�����^���́A���J�^���ł���A���z�����A�o�ϓ����A���������A�J���͓����Ƃ������L�͈͂ɂ킽��O�ꂵ�����������ł������B���̍����^���͍����̓��퐶���ɂ܂ŐZ�����A������������A�����鍑���̃G�l���M�[��푈���s�ɓ������A�x�z�ւ̎x���B���悤�Ƃ����B�����ɁA���̎����̍����^���̐�������j�~���Ă����̂́A�u���u���s�B�`�v�̗�����Ƃ闃�s�̉����Ȋ����������̂ł���B �@
���ɁA�鍑�c��Ɋւ�����ł���B���^��̐����ȍ~�A���@�@�\�̒ቺ�E�R�c���Ԃ̒Z�k�E���茠�̌`�[���ȂǁA�鍑�c��̋@�\�͑傫���ቺ���Ă����B�c��̉^�c�͐��{�ƁA�e�R�I�ȋ����}���͂������������Ă���������Ƃ̋��͑̐��ōs���Ă����B�������A���ʓI�ɂ͐��{�̒�o�@�Ă��S���ʉ߂͂������̂́A�c����{����������@�\�����S�ɑr��������ł͂Ȃ������B�Ƃ͂����A���𐭌��̉��ł́A�������ɑ���ᔻ�̐擪�ɂ������̂́u���튮���v���̑O��Ƃ���1��������n�̉E���ł������B�����Ď��R��`�Ɩڂ��ꂽ���ĉ�͉E���c���̌������ɑ���ᔻ���A���ɓI�Ɏx���͂������̂́A�ϋɓI�ɐ擪�ɂ����Č�������ᔻ����悤�ȍs���͋N�����Ă��Ȃ������̂ł���B �@
�������A������t���ŁA������𒆐S�ɂ����c��͂͐����I�n�ʂ����߂����������A����͐�ǂ̈����f�������̂ŁA�����Ē鍑�c��̖{���̌����ł���͂��̎�����̗��@�s�ׂ�u���ӏ�B�v�̋@�\�����������킯�ł͂Ȃ������B����ɁA������͗��^��A���s�A������̉��U�ɂ�鍑���^���̈ꌳ���������A���̊�}�͎��s�ɂ�������B���̔w�i�ɂ́A�s������ɑ�ʐi�o���A�n��ŋ��͂ȍ����^����W�J���Ă������s�̑��݂Ƃ��̒�R�����������̂Ǝv����B �@
������t�̖����ȍ~�A���{�͗��s�̓����ɏ��o���A���s�̊����͑傫���K������邱�ƂɂȂ邪�A����ł��s��Ɏ���܂ŗ��s�͒n��ɉ����鐭���I�e���͂��A�k�����ꂽ�Ƃ͂����A�ێ��������̂ł���B �@
��O�ɁA���s�Ɋւ�����ł���B�����^���̎��{�͗��^��P���̊��������^���c�̂Ɨ��s�𒆐S�ɍs��ꂽ�B���ɁA���s�͐��{�̍���������^����ʂ��Ė��[�̍����܂Łu��Ӊ��B�v����Ɏ~�܂炸�A���̈���Łu���ď�ʁv�̖������͂������Ƃɂ���āA���ɂ͍s���@�\�Ƃ̊Ԃɐ[���Ȗ��C���a�I�ݏo�����̂ł���B �@
����A�O�c�@�ɂ����闃�s�c���̊����́A�c��ł͘I���ȓ��𐭌��ɑ���ᔻ�͂����Ȃ킸�A���s�c���c�Ƃ��Ă̓Ǝ��̐����I�咣���قƂ�ǂ݂��Ȃ����A�����I�����̋����ɑ��Ă͒�R�̎p�����������B�c��O�ł̊����ł́A������̍����^���̈ꌳ���̓�����j�~���邱�ƂɊ����̏d�_�������Ă����B�n��ł̗��s�̉^���������ŁA�s���@�\��������˂��グ�鑤�ʂ�����̂ɑ��A�鍑�c��ł̗��s�c���̓����͊T���ĉ����ł���A���̐����I�e���͂��s�����c��y���ɂ�����قǑ傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ������Ƃ�����B �@
���^��A���s�A������Ɏx����ꂽ���^�̐��́A�O�̒c�̂��Η������ʂ���ɕ\�o���A�]���̌����ɂ����Ă����̓_����������Ă����B�������Ȃ���A�����x�z�̖ʂł͗��^��͍����^���̊ēw���@�ւƂ��āA���s�͂��̎��s�g�D����ђn��̐������͂Ƃ��āA������͒��������̒S����Ƃ��āA�e�X���̖����𐋍s���邱�Ƃɂ��A�܂���Ȃ�ɂ������m�푈���̎x�z�̊��̒��j�Ƃ��Ă̋@�\���ʂ��������̂ł���B






 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@