�헤�Ɠ�؎��E�����m�Ɠ�؎��E���������E�k�𐭎q�E���b�E�k����E����V�c�E�E�E
���@�E��Ձ@���̐��E
�@�@�@

|
��k���T�_�E�쒩�w���҂Ɛ헪�E�ԏ��~�S�E��ؐ��V�E��ǐe���E�k�������@ �헤�Ɠ�؎��E�����m�Ɠ�؎��E���������E�k�𐭎q�E���b�E�k����E����V�c�E�E�E |
|
���@�E��Ձ@���̐��E �@�@�@  |
| �@ | 1185 | �@�R | �h�� | ���� | �e�a | ���@ | ��� | ��� | ���� | ���b |
�k���@ ���q |
�k���@ �� |
�k���@ ���� |
�V�c�@ �`�� |
����@ �V�c |
�����@ ���� |
|
���q�@ ���� |
�@ | 1133 | 1141 | �@ | 1173 | �@ | �@ | �J�c | ���c | 1173 | 1157 | 1183 | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 1200 | �@ | �@ | 1200 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| �@ | 1212 | 1215 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1222 | �@ | �@ | �@ | �@ | 1225 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1239 | 1239 | 1236 | 1232 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1242 | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 1250 | �@ | �@ | 1253 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | 1262 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1282 | 1287 | 1289 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1283 | �@ | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 1300 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1303 | 1300 | �@ | 1305 | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1319 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
|
��k���@ ���� |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1333 | 1338 | 1339 | �@ |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| 1350 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1358 |
 �@ �@����k������(1336-1392) |
|
| �����̎���敪��1�B ��ʓI�ɂ͊��q����̌�ŁA���O�̕ς⌚���̐V������k������̏o�����Ƃ��Ĉ������A���m�ɂ͉������N/����3�N(1336)�ɑ��������ɂ������V�c�̑H�N�A����V�c�̋g��J�K�ɂ�蒩�삪���Ă���A ����9�N/����3�N(1392)�ɗ��������ꂷ��܂ł̊��Ԃ��w���A��������̏����ɓ�����B���̊ԁA���{�ɂ͓쒩(��a���g��s�{)�Ɩk��(�R�鍑������)��2�̒��삪���݂��A���ꂼ�ꐳ�������咣�����B�쒩�𐳓��Ƃ���_�҂́u�g�쒩����v�Ə̂��B �@ | |
| ����k���T�_ | |
|
14���I�̓��{�������Ɋׂꂽ��k������B���{�̗��j�̓]���_�Ƃ��Ȃ�d�v�Ȏ���Ȃ̂ł����A�S�̑����݂͂ɂ����E�����̏I��肪�������u�������Ȃ��E�c�������ނ̂Ř_����̂ɔ����Ȗ�肪����Ƃ������v������h�������X��������܂��B�@ ����k������̔w�i�@ 8���I�����Ɋm�����������W���I�ȓ��ꐭ���́A9���I�ɂ͕���Ɍ������B���Y�͂̌���ɔ����n�x�̍����g�債�A�n���w���v���������Ŏ��͂�t���������n�������͔ނ���x�z���ɔ[�ߎ����̐����e�n�Ō`�������B�������{(����)�͍����B�̗�����ٔF���A�l����c������̂�f�O���ēy�n�P�ʂł̐Œ����̐��ɓ]���B�������đ�y�n���L�ҁA���Ȃ킿�L�͋M���E���Ђ�n�������ɂ��A���̖̂���Ƃ��Ē��삪���݂���̐���11���I�O���Ɋm������B�@ �₪�āA�n�������̎��͌���ɔ����ނ���x�z���ɑg�ݓ��ꂽ�R���M�����䓪�B12���I���ɂ͌R���M���̑�\�҂ł��錹���E�����ɂ��������o�āA�������������ɂ���ē����{�ɌR�������ł��銙�q���{�����������B���{�͒���̏@�匠�𖼖ڏ�͔F�߂������{�𒆐S�ɓƎ��̎x�z�̐����m���B���삪�����{�A���{�������{���x�z����`�ƂȂ�B13���I�O���ɏ��v�̗��ŌR���͂ɏ��開�{����������|���đ傫���D�ʂɗ����A����Ɏx�z�����L�����B13���I���̃����S���鍑(��)�̗��P(����)���_�@�Ƃ��Ė��{�͍��h�̕K�v�ォ��S���K�͂Ŏx�z���������A���B�����������Ɛ��͂�c�����鎖�Őꐧ�����u������悤�ɂȂ�B�@ ����ŁA�]����薋�{�ɏ]�����Ă��������B(��Ɛl)�͕��������ɂ��x�z�̈�̗���A���Ɣ��B�ɔ����n�x�̍��̊g��A�����₻�̌�̊C�x���ɂ��o�ϓI���S�������Đꐧ�����開�{�ɕs�����点�Ă����B�܂��A�o�ϐ�i�n��ł������E���𒆐S�ɁA�ݕ��o�ϔ��B�ɔ����Ĕ�_�Ɩ����x�z���ɒu�����V���������䓪�A�u���}�v�ƌĂ꒩��E���{�����������ꂸ����Y�܂���Љ�s���v�f�Ƃ݂Ȃ����悤�ɂȂ��Ă����B���{�͔ނ��_�Ɩ��̑g�ݓ���ɕ��S���Ă������A�����̔�_�Ɩ��͓`���I�ɒ���Ɛ[���q���肪�������W�������Ă��A�u���}�v�͔J������ɂ�莩��𐧕I���鑶�݂Ƃ��Ė��{�ւ̔��������҂�����������悤�ɂȂ�B�@ ����A���v�̗��ȍ~��̉����Ă�������́A�X�ɍc����L�͋M�����n�ʂ��߂����ĕ���B�c���͎����@���Ƒ�o�����ɕ�����A�ۊ։Ƃ͌ܐۉƂɕ��đΗ�����B���ł��c�ʂ�u���V�̌N�v(�c�ʂ�ނ�����c�̒��ł��V�c�̕ی�҂Ƃ��Ď������������҂������Ă�)���߂����Ă̗����̑Η��͐[���ŁA���{�ɂ�钲�����K�v�Ȃقǂł������B���̌��ʁA�v���ʂ�ɍs���Ȃ������w�c�ɂ�開�{�ւ̈⍦�ގ��ƂȂ�̂ł���B�@ �o�ϔ��B��w�i�ɐꐧ����i�߂開�{�ł��������A���̈���Ŋe�K�w���甽�����Ǘ������i��ł����̂ł���B�@ ���u�����L�v�̂��炷���@ ��o�������瑦�ʂ�������V�c�́A�ӗ~�I�ɉݕ��o�ς������ꂽ���v���s�����͂̋y�Ԕ͈͂͌����Ă����B�܂��A�ނ͑�o�����ł��T���ł��肱�̂܂܂ł͎q���ɍc�ʂ��p�������\���͂Ȃ������B�����ŁA����͒���Ɏx�z�������߂��W���I�Ȑ������������邽�߁A�����čc�ʌp���ւ̉��(����)��p���Ď���̌n���ɍc�ʂ��p�������邽�ߖ��{�œ|���u���悤�ɂȂ����B�܂�1324�N����͕s���h�𖡕��ɕt���ċ�����ژ_�ނ����O�ɘI���B���̎��͓V�c���g�ɐӂ߂͋y�Ȃ��������A���̌���V�������ɉ����o�ρE�R���I�ɑ傫�ȗ͂����@�����͂𖡕��ɕt���ē|�����s�����Ƃ��Ă����B1331�N�Ăьv�悪�I���A����͊}�u�R�ɓ���ċ������邪���{�R�ɔs�k���߂炦����B�Ȃ��A�����ɉ͓��̐V�������E��ؐ������ԍ��ŖI�N���Ă��邪���������̖��ɗ��邵�Ă���B���{�ɕ߂炦��ꂽ����͎����@���̌����V�c�ɏ��ʂ������B��ɗ����ꂽ���A���̌������̍c�q�E��ǐe�����e�n�̍��������ɋ������Ăт����ċg��ɘU�邵���B�܂�1332�N������1333�N�����ɂ����Đ������ԍ���D�҂���Ƌ��ɑ�㕽��e�n�Ŗ��{�R��j�苞���������A�瑁��ɘU��B���{�͊֓������R��h�����Ă�����U�����邪�����������A���{�̌R���I�АM�͒������ቺ�����B���̍��ɂ͔d���̐ԏ��~�S�����������U�����A�͖쐅�R�Ȃǂ������B�X�Ɍ��킪�B��E�o���Ĕ��˂̖��a���N�̔���đD��R�ɘU�����B������5���ɂ͖��{�R�Ƃ��Ĕh�����ꂽ���{���̗L�͎ҁE�������������푤�ɐQ�Ԃ��ċ��̖��{���_�ł������Z�g���T����U���A���͌�����̎�ɗ������B�������Ɋ֓��ł����̍����E�V�c�`�傪�j�|�̐i���ɂ�芙�q���U�ߗ��Ƃ��A���q���{��130�N�̗��j�ɖ������낵���B�@ �������Đ��������ɐ�����������́A�����̑��ʂ�ے肵����Ŏ���_�Ƃ���ꐧ�������݂Ɏ��g�ށB�����̐V���ł���B�ݕ��o�ς��d�����A����ƕ��ɂƂ���Ȃ��l�ދN�p���s�����A���̋����Ȑ��e���ʂ̔������B�X�ɉ��܂ɂ����鏈�������������̕s�����������B���̒��Ō�ǐe���Ƒ�������(����������)�������̎w��������Η��B���ǂ͑������x�����W�ߌ�ǂ͎��r����B�@ 1335�N���q���{�c�}�����q��D��B�����͂��������Ɍ��������̂����������Ƃ��Č��n�œƎ��̘_���s�܂��s������̐���������ڎw���B����͓��R�����ɑ��锽�t�Ƃ݂Ȃ��A�V�c�`���叫�Ƃ��铢���R��h�����邪�����͒|�m���ł����j���ď㋞�B1336�N�����ɂ͋��ɂ����đ����R�ƐV�c�E��璩��R�Ƃ̎������J��L�����邪���B����삯�t�����k�����Ƃ̕�������������������R����U�͒ǂ��U�炷�B�����͎���̑�`�������m�ۂ��邽�߂Ɏ����@���̌����@���@��(��c�A���Ȃ킿�ވʂ����V�c�ɂ�閽�ߏ�)�Ċe�n�̍����ɌĂт����Ȃ����B�ɓ��ꂽ�B�Ȃ��A���̓r��Œ����E�l���̗v�n�Ɉꑰ�E���n������z�u���Ēnj��ɔ����Ă���B�����Ĕ����ɏ㗤���������R�͌�����̋e�r���ɂ���R�𑽁X�Ǖl�Ŕj���ċ�B�𐧈��A�������R��Ґ����čĂы��������B����ŋ`��̗����钩��R�͕Ґ��Ɏ�Ԏ��nj����x��A�X�ɔd��������ő����ɖ�������ԏ��~�S�ɂ��i�R��j�܂���ɉ��B���̍ۂɐ����͑����Ƃ̘a��������ɐi�����邪������Ă��Ȃ��B5�����ɑ����̑�R�͕��ɂɎ���A�����͋����̂ĂĔ�b�R�ɓ����㕽��̓�،R�Ƌ��ɋ��̑����R���͂���헪����\���邪�p�����ꂽ�B�������ĕ��ɂɔ��鑫���Q��V�c�E��،R�͖���Ō}�����B�����̐�p�ɂ��V�c�E��ؐ��͕��f�����͂Ɋׂ�����ؐ��͈ٗ�̕�������������̂̏O�ǓG����������͗����B�������đ����̓�����h�����̂͂Ȃ��Ȃ���(����̐킢)�B����͋`��Ƌ��ɋ����b�R�ɘU�邷�邪�����R�ɂ���ĕ�͂���A�����ɂ��a����Ăɉ�����B�@ ����ő����͋��ɓ���Ǝ����@����������V�c��i�����A�a����������ƌ��킩����ʂ���(�k��)�B���̏�ő����͋��Ɏ���̐������������鎖��錾����(�������{)�B����Ō���͋���E�o���ċg��ɓ��ꎩ��̍c�ʂ��܂������ł��鎖���咣����(�쒩)�B60�N�ȏ�ɂ킽���k���̓����͂����Ɏn�܂�B����͊e�n�̖����ɋ������Ăт����ċ��D���}�����B���̎����A�k���ɐV�c�`��A���B�ɖk�����ƁA�ɐ��ɖk���e�[���L�͂ȓ쒩���Ƃ��Đ��͂��Ă���ނ�ɂ�镱�N�����҂��ꂽ�B���Ƃ�1338�N�ɉ��B����o�w���đ����R���������Ă������q���U������Ƌ��ɁA���C������C�ɐ��サ�Đ쌴(�փ���)�ő����R��j����̂̎��g���傫�ȑ��Q���ɐ��ŌR�����ĕҁB�����ēޗǂ��o�đ�㕽��ɐi�o����Ƌ��ɕʓ������Ɍ����킹�ċ��Ɉ��͂��������B�������a��ΒÂő����R�̎�́E���t���̎萨�ƌ���̖��ɔs��ē������ɁB�������ĉ��B�̓쒩���͑傫�ȑŌ������B����ŋ`��͋��_�̉z�O�������𗎂Ƃ����ȂNj����������邪�A�k���̂��Ȃ�̒n����x�z���Ɏ��߂鎖�ɐ����B������������肹�����Ƃւ̉��R�𑗂邱�Ƃ͏o���Ȃ������B������1338�N�z�O���S�����ڑO�ɂ������ŗ����ɓ�����펀����Ƃ����s�^�ȍŊ��𐋂��Ă���B�����͗Ȑ�͂Ŗ����ȍU���ɏo�����ɂ��j�]�ƌ����邩������Ȃ��B�@ ������đ����͓��N�ɐ����ɐ��Α叫�R�ɏA�C�B�쒩�ł͖k���e�[���ɐ�����֓��ɉ���A�헤�𒆐S�Ƃ������n�̐��R���͂𖡕��ɂ��Đ��͊g��Ɖ��B�ɂ�����쒩���_�Č���}��B������������1339�N���킪����A�q�̋`�ǐe�����c�ʂ��p��(�㑺��V�c)�B�G�Ȃ��������h�炵�Ă����������ԗ�̂��ߓV���������������̂͂��̎��ł���B���Ċ֓��ɂ�����e�[�͖k�֓��E���B���͂̌��鎁�ƌ���Ő��͂��L���悤�Ƃ��邪���鎁�͉��������g��������������B���̍ۂɖ����̎m�C�����߂�Ƌ��ɓ쒩�̐�������n�����������ɑi���悤�Ǝ��M�����̂��u�_�c�����L�v�ł������B�e�[�͂���ɉ����A���n�̍��������Ɋ��ʂ̒��������Ȃǂ��Ė����ɕt���悤�Ɠw�͂��邪��1343�N�֓��ɂ����鋒�_�������Ă₪�ċg��ɋA�҂��Ă���B�@ ���̍��A�쒩�͉��B�̖k�����M�A�M�Z���ӂ̏@�ǐe���A�l���̉ԉ��{�A��B�̉��ǐe���E�e�r���ȂǍc�q��M����h�����Ċe�n�ɐ��͂�}�A���悤�Ƃ�����̂̑����������|�I�D�ʂ�ۂ��Ă����B���̎����A�������{�͌R�������E�����^�������R�����ƈ�ʐ����E���̕ۏE�i�ׂ�S�����镛���R�E���`(�����̒�)�ɂ��̐�����菇���Ȑ����^�c���Ȃ���Ă����B�������A�����̌��Ђ��y������V�������𒆐S�Ƃ������t��(�����̎���)�h�ƗL�͍�����ێ�h�ɂ�钼�`�h�̑Η������̍�����[�܂�悤�ɂȂ����B�@ 1347�N�g��̓쒩���͐e�[�̎w���̉��œ�ؐ��s(�����̎q)����͂Ƃ��čēx�������J�n���������ɋ��Ђ�^���邪�A���N�����Ɏl���Ŏt���̑�R�����s����鎖�œ쒩�̍U���ׂ͒���B���̍ۂɎt���͐����ɏ���ċg��ɍU�ߓ����Ă���A�쒩�͍X�ɉ��n�̉ꖼ���ɓ��ꎩ�͂ōU���ɏo��͂��������B�������đ������̈���I�D�ʂ��m���������Ɍ��������A���̐���Ŏt���h���͂��������������h���̑Η�����C�ɕ\�ʉ�������(�ω��̏)�B���`�������ɗv�����Ďt�����Ƃ���ƁA���x��1349�N�t�����N�[�f�^�[���N�����ĕԂ�炫���`�₻�̈�}�����r�������B����ɑ���1350�N���`�͗{�q�E���~(�����͑���)�ɋ�B�Ő��͊g�傳����Ƌ��Ɏ��g�͓쒩�ƌ���Ŏt���E�����Ɛ킢�����j��B1351�N���`�͑����Ƙa�����t������E�Q���ĕ����ɐ��������B���������h���̑Η��͏C���s�\�ł���A���x�͑����ƒ��`���Փ˂���Ɏ���B���x�͑������쒩�ɍ~�����Ė������m�ۂ��A�֓��ɓ��ꂽ���`��1352�N�ɖłڂ����B�@ �������Ĉꎞ�I�Ȃ��璩��͓쒩�݂̂ɓ��ꂳ��(�����̈ꓝ)�A�O��̐_����쒩�ɐڎ����ꂽ�B�X�ɐ����Â����쒩�͋��s���R����̂��k���̏�c�E�V�c���v�c����߂炦�k��������Ă���B�`�F�͊Ԃ��Ȃ�����D�k�����Č��������̂́A�c�ʂ��ؖ�����O��̐_������ʂ𐳓�������u���V�̌N�v(�V�c�Ƃ̉ƒ�)�������Ă���Ȍ�̖k���͐������ɋ^�₪�c�鎖�ƂȂ�B����͖k���Ɍ�����F�߂��Ă��鑫�����{�̐������ɂ��e�𗎂Ƃ����ƂȂ�A�傫�Ȑ����ۑ�ƂȂ����B�@ ���ċ����`�h�͒��~�𒆐S�ɒ�R�𑱂��邪�A�������{����r������ɗ��������B�ނ�͓쒩�ɍ~�艽�x������D�����ꎞ�I�U���ɉ߂��Ȃ������B�������đ������{����������͈�i������B�@ 1358�N�������a�v���`�F�����㏫�R�Ƃ��Ė��{�w���҂̒n�ʂ��p���B���̎����A��B�ł͉��ǐe����i������e�r�����������𑝂��Ă���A1359�N�}���̐킢�ŏ���j�����̂����������ɁA��ɕ{�𐧈���1362�N�ɂ͋�B�S�y���蒆�ɂ��Ă����B����ő������{�͗L�͎ҊԂ̓����ɔY�܂����B�Ɏ肪�o���Ȃ���Ԃ������B�`�F�͗L�͎҂̓����ɋꂵ�݁A�m�؋`����א쐴���E�z�g���o��̔��t�ɔY�܂���邪���X�ؓ��_�E�ԏ����S��̋��͂����Ă���������B�א엊�V�̊���ɂ�苌���`�h�̑���O���E�R�������Ƃ�(�ނ�̊������v��F�߂����)�a�����������A�������{�͈���ւƌ������B���̎����ɂ͓쒩�Ƃ����x���a������������Ă���A1367�N�쒩�a���h�̓�ؐ��V�Ƃ̊ԂŘa���������O�܂Ŏ�����̂̒��O�ɔj�k�B�@ �`�F�̌���p������O�㏫�R�E�`���̎���ɂȂ�Ɩ��{�̗D���͊m�����Ă���A�א엊�V�̕⍲�����菫�R���͂̊m���▋�{�@�\�̐������i�߂��`���͐ꐧ�N��ւ̕��������u������悤�ɂȂ�B����œ쒩�ł͓�������ɒ��ʂ��Ă����B�㑺��V�c�����ɑ��ʂ������c�V�c�͎��h�ł���A�a���h�̓�ؐ��V�͖��{�ւ̍~����]�V�Ȃ�����Ă���B�܂��A��B�ɂ����Ă�1372�N���엹�r����B�T��Ƃ��Ĕh������Ĉȍ~�A�쒩���͎���ɗɒǂ�����Ă������B�����ČR���I����ɒ��ʂ���쒩�ł́A�Ăјa���h���͂�������T�R�V�c�̉��Řa�������Ȃ����B���{�ɂƂ��Ă��O��̐_���������k���▋�{�̐��������m�ۂ���ׂɂ��쒩�̕��a�I�z���͕K�v�ȉۑ�ł������B��������1392�N�����@���Ƒ�o�����̌��ݑ��ʂȂǂ������Ƃ��ė����͍��̂��A��T�R(�쒩)����㏬��(�k��)�ɎO��̐_�킪���n���ꂽ�B����������͎����I�ȓ쒩�̍~���ł���A���̎��̖͎��ꂸ�ȍ~�͐��k���n���ɂ���čc�ʂ͌p������Ă����B�܂��A���̓����Œ���̐����I�����͎���ꖋ�{�ɂ��ꐧ�̐�����������邪�A���{�̌��͂��L�͎҂̎x���Ɉˋ������s����Ȃ��̂ł���₪�ėL�͎ҊԂ̑����Ȃǂ�������15���I�O���ɂȂ�Ɛ���͍Ăїh�炬�����̂ł���B�@ �����w�c�̐��͍��@ �쒩�⑫�����{�̐��͌��͈��肵�Ă����Ƃ͂����Ȃ��B�Ƃ����̂́A�����̈ꑰ�����⌻�n�ł̓y�n�E���������ȂǂŊe�n�̍�������������̓s���ɉ����ė��w�c��n������Ă�������ł���B�������A��̂ɂ����đ����������|�I�ɗD���ł������_�͈�т��Ă���Ƃ����悤�B�@ �܂��A�쒩�͋E���암�̎R�Ԓn�ɋ��_��u���֘A��������a�E�I�ɁE�͓��E�a��̎R�ԕ��𒆐S�ɋɂ߂Č���ꂽ�n��ł��������Ă��Ȃ��B�����Ė{���n�������͋g��ł��������A�R���I�ɂȂ��Ă���͉ꖼ���Ɉڂ�X�ɋ�������ϐS���A�Z�g�_�ЂȂǂ�]�X�Ƃ��Ă���(�U���ɏo�邽�߂̈ړ��������T�ɗɂ��Ƃ͂����Ȃ���)�B����Œn�����_�������͉��B(�k������)��z�O(�V�c�`��)�Ȃǂ����݂�������������������̍U���ɂ�葁���i�K�ʼn�ł̗J���ڂ����Ă���B�����A��B�݂̂͑������{���h�����ꂽ��B�T��ƌ��n�L�͍����Ƃ̑Η��▋�{�����ɏ悶�ċe�r�����h�����������鎖�ɐ������Ă���B�@ �������{�͑S���̍����ɑ��ď��̂�ۏ��鎖�Ŗ����Ɉ�������鎖�ɂ��Ȃ萬�������|�I�Ȑ�͂�z�����B�������A�������R�Ƃ̒����̂͏��Ȃ����������O�܂ł͓��y�ł������L�͎҂��������݂������߁A���̌����͋ɂ߂ĕs����Ȃ��̂ł������B���v�⌠�͂𐭌������ő�����������R��쒩�ɑ����������Ό����A���ꂪ�헐�����������ɂȂ��Ă���B�@ ��k���̓����́A��̒��삪�������̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A���ꂼ�ꂪ�݊p�̐킢��������̂ł͂Ȃ������B�k���͑������{�̘��S�ƌ����Ă悢���݂ł�����(�����͑S���̖��͂ł��Ȃ������悤����)���A�쒩�Ɏ����Ă͎R�ԕ��ɂ��n�̗������Đh�����ēG�̍U����h���Ȃ���G�̕���ɏ悶�鎖�ōׁX�Ɩ�����ۂɉ߂��Ȃ������B����ň��|�I���͂��ւ鑫�����{���A���̊�Ղ͋ɂ߂ĕs����ł��蓝���B������ɂ͑����̍�����͂��ł����B���ꂪ�����͂̕s�ύt�ɂ�������炸�헐�����炭�������������ł���B�@ ���쒩�E�k�����w�c�̓���@ ���k��/�k���́A��X�����@���̍c������V�c��y�o�����B�����͂�����x�̏��̂ɑ��čٔ�����L�����s���̍s�������ۗL���Ă������A���g�̕��͂��`�����鎖�͏o�����������{�ɂ��ی삪�s���ł������B���̂��ߑ������疋�{�ɂ�鐭������������Ă���A�����ȍ~�͏��̂��n�������ɂ���đ����͐N�H����o�ϊ�Ղ����������߂����萭���I�����𑫗����{�ɒD���`�[�I�ȑ��݂ƂȂ�B�R���I�ɂ͊��S�ɑ������{�Ɉˑ����Ă���A�����ɂ����铖���҂ł͎����I�ɂ��肦�Ȃ������B�@ ���������{/�������͊��q���{�̉��ł��L���̖���Ƃ��ċ�����Ă������A�̍��ɂ������k��������͌x������Ă������B����ɂ�鈳�����̂��X�Ɏ���̐������������邽�߁A����̖I�N�ɏ悶�Ėk�����œ|�ɉ����B���������ɂ����Ă����̌��т��d����Ƌ��ɐ��͂��x������u�h���ĉ���������v�ł������B���������̒��Ő킢�œ����֓��ɂ�����������v���u���q���R�{�v(����̍c�q�E���ǐe�����Ɍ}����)�Ƃ��ĔF�߂�ꎩ��̐����I��Ղ��l���B�X�Ɍ��������ɕs�������e�n�̍����ƘA���������𑝂₵�Ă����B����ɔw���������͈�i��ނ̐킢�ł������������@���ƌ���ő�`��������ɓ���Ă���͑傫�Ȑ��͂�z�����Ɏ���̐��������������B�@ ����������͌R���I�������A�����`���S�����������ꂪ�����h�E���f�h��ێ�h�E�v�V�h�Ȃǂ̑Η������������Ɏ��錴���ƂȂ��Ă���B���̌�������ΐ������̓����ɋꂵ�߂��邪�A���ɂ͕��͂őœ|�����ɂ͗���H�킹�ċA��������ȂǍd��ʂőΉ����D�ʂ��m�����Ă������B�@ �z���̗L�͍��������͐헐�ɂ����镺�Ɗm�ۂ𖼖ڂɋM���̑����̔������蒆�Ɏ��߂�̂�F�߂��Ă���(���ϗ�)�A�����ʂ��ėL�͎҂����͂��̏��̂ɂ�����x�z���m�������悤�Ƃ����B�@ �����͍~������҂Ɋ���ŏ��̂Ɋւ��Ă��C�O�ǂ������Ƃ���Ă���A���ꂪ�����̍����𖡕��Ƃ��Ĉ������ƌ�����B�������A����͑������R�Ƃ̒����̂����Ȃ��̂ɔ��Ԃ������鑤�ʂ����݂����̂��ۂ߂Ȃ��B�܂����ē��y�ł������������z���ɂ͑����A���t�������ł������B�����ȍ~�͗i������k���̐������ɋ^�╄�����ł��������ߖ��{���g�̐������ɂ���肪����A���R�̌��Њm���ɋꗶ���鎖�ƂȂ�B���̂��߁A�k���̐����I�������m����ړI�Ƃ��ē쒩�̕��a�I�z������іk���V�c�ւ̏��ʂɋ������������B�@ �`���̎���ɗ������̂ɂ�鐭���I����ƈꉞ�̐����I������������邪�A���S�ɗL�͎҂����������߂��킯�ł͂Ȃ��ނ̎���ɂ͍ĂїL�͎҂ւ̑Ή��ɋꗶ���鎖�ƂȂ�B������15���I�O���ɂ͏��R���L�͍����ɈÎE����鎖�ԂƂȂ�A������_�@�ɏ��R�̌��Ђ͒ቺ��1467�N���11�N�����������m�̗��ɂ���Ă��̖��͉����邱�ƂƂȂ�B�@ ���쒩/��o�����̌���n���ɂ��c�ʂ��p�����ꂽ�B����͏��Ɣ��B�ɔ����䓪������_�Ɩ��𖡕��ɑg�ݓ���鎖�Ŋ��q���{��œ|�����������ɐ������邪�A����̎Љ�I���͂͒ቺ���Ă��菤�Ɛ��͂����{�S�̂�}�����ނɂ͔��B���s�\���ł������B���̂��߁A�ꐧ���u��������̂̈��肵���������͂�z�������o�����A�����𒆐S�Ƃ��锽�ΐ��͂̑O�ɔs��ċg��ɓ����B�ȍ~����_�Ɩ��𒆐S�Ƃ��Ė�����g�D���A�������{�ɑ��Ē�R�𑱂�����̂̔_�Ɛ��̗͂͂����܂��������|�I�ȗɏI�n�����B�����������Α������{�������Ɋׂ������߂��̈���Ǝ������ňꎞ�I�ȗD�������o�������Ƃ��������B�����ȍ~�̓쒩�͑������{���̕s�����q����`�����Ƃ��ėi�����鑶�݂ƂȂ�B�@ �������{�̘��S�ł������k���ƈقȂ�A�쒩�ł͓V�c���g�������̎哱�������荑�Ɛ헪��������s���Ă����B�܂��A���R���z���̔����ɔY�܂��ꂽ�������{�ƈقȂ�V�c�̌��Ђ��������b���͏o�����Ă��Ȃ��B�x�z�̈�̑�������Ă̏�[�����߂鎖�Ŏ������Ƃ��Ă���A����͑������{�ɂ����锼�ϗ߂Ƌ��ʂ���ƌ�����B�@ �c�ʂ̏ے��ł���u�O��̐_��v��ۗL�������Ă���Ǝ咣���A���������ȍ~�͖k���́u�O��̐_��v��������ėB��_��������݂ł������B���̂��ߌR���I�Ɉ��|�I�ł���Ȃ�������a�I�a���ɂ������鎖���\�ƂȂ����B�������������̌�͍u�a���̏��������̂ɂ���A�c�}�ɂ���R�����炭������(��쒩)��ɗ��j�̕\���䂩������Ă������B�@ ���v��@ ���Љ�̔��W�ɔ����A�Љ�̖T���ł��锤�̐l�X�̖��������債�Љ�I�e���͂������A���ꂪ�����̕��s�������܂��ĕs����v���ƂȂ�B�@ ���ނ�𗘗p���Đꐧ������ژ_�ތ���V�c���A���Ɛ����ɐ킢�ނ����܁B�@ �������������̕��Ɛ������v�V�h�E�ێ�h�̑Η��������ɓ˓��A�s�ꂽ����̎c�}������ɏ悶�čĂѐ��͂�L�������ǂ͔s�k �B�@ ����k���͔�_�Ɩ����_�ƎЉ�ɑR���邾���̎��͂�������ϊv���ł��邾���łȂ��A�R���I�ɂ������K�w�ł���R�n��m�̌l�I���E�ɂ��Ƃ��낪�傫���킢���� �A�����̏W�c�̐�߂���������傷�鎞��ł��B�@ �����̎���͏��Ƃ̔��B�ɂ��ݕ��o�ς��{�i���A����ɔ��������̎Љ�I���͂����サ�ĕ����I�Ȗ������傫���Ȃ�܂����B���̓��A���ԁA�o�~�A�\�E�����ȂLj�ʂɓ��{�����Ƃ��ĘA�z�������̂̋N���� �A���̎����Ɍ�����ƌ����܂��B�܂��������{�j����w�̓]���_�ł������ƌ�����̂ł��B�@ ����v�l���@ ������V�c/�c���������@���E��o�����ɕʂ�đ����Ă�������ɑ�o�����E��F���V�c�̎q�Ƃ��Đ��܂��B���͑����B�V�c�ɑ��ʂ���Ƒ씲����������r�Œ���̎x�z���y�ԋ��s���ӂŐ������v���s�������]�����B����ɂ��S���I�Ȑꐧ���������������炪�x�z�҂Ƃ��ČN�Ղ��鎖��ژ_�݊��q���{��|�����ߐ킢���d�|����B����͔s��B��ɗ��������̂̍ŏI�I�ɓ|���ɐ���������ɂ�铝�ꐭ�����������邪�A���̋����Ȑ������j�͊e���ʂ��甽�������������̔��t�ɂ�萭���͊����B�g��ɓ��ꑸ�����i�����鎝���@���̒���ƑΗ��B���������Ƃ̐킢���s���ɂȂ���钆�ŕa�v�B�@ ����������/���q���{�z���̒��ŗL���̖���ɐ��܂��B�����͖��{���ł��������A���q���{���x�z����k�����Ɏ���đ���V������邱�Ƃ��������̏h�]�ł������W���������V�c���ɐQ�Ԃ苞�s���́B����ŋE����������̎�ɗ����A�����̌��т͑傫���ƕ]�����ꂽ�B���퐭���̉��œ����͎������Ă������A�����ւ̕s�������܂钆�Ō���ɔ�����|���킢�̖��ɋ����̂�����̐����������B��͓I�D�ʂ��������쒩�Ƃ̐킢��L���ɐi�߂邪�A��E���`��Ƃ̓����ɔY�܂���钆�ŕa�v�B�@ ���������`/�����̒�B�����̐킢�ɂ����Ē����ɑ�����⍲���A���ɂ͐�ӂ�r���������������B���サ���B�����ƈقȂ�R���I�˔\�ɂ͌b�܂�Ȃ������������I��r���������^�c�ɑ傫���v���B�ێ�h�̊����Ƃ��ĒS���o����A�����₻�̎����E���t�����i������V�����͂ƑΗ����A�킢�̖��ɔs���B�@ �����䒼��/���`�h�̕����B�����E���t���ƌ������Η��B���`�v��͂��̗{�q�E���~�̔z���ƂȂ�B�ێ�h�̗L�͎҂Ƃ��ċ��d�ɁA�D��I�ɐ킢��i�߂�B�@ ���������~/�������`�̗{�q(�����͑���)�B���ۂɂ͑����̒��j�ł��邪�A��̐g�����Ⴂ���������������(����A�`�F�͐����̎q�ł�����)�B�����T��ɔC�����邪�A�ω��̏�ɂ����ė{���E���`�ƍs�������ɂ���B���`�v��͒��`�h�𗦂��ē쒩�ƌ��ы����ꎞ��̂��邪�₪�ėƂȂ�B����̏�ǂƂȂ鑸���E�`�F�Ƃ̐킢�ɉ߂����A���̈�����키�����͂Ƃ��������Ȃ��������U�ł������B�@ �����t��/�������̎����B�����ɏ]���ČR���ʂŎ�r�����A�쒩���̎�͂ł���k�����Ƃ��ؐ��s(�����̎q)�����Ȃǂ̐���������Ă���B�V���������Ɛb�Ƃ��ĕҐ����R���͂Ƃ��ē������Ă��鎖����A�ނ�̗��v���\���鑶�݂Ƃ��Ē��`��̕ێ�h�ƌ������Η��B�����̖��ɒ��`�h�ɔj��ĎE�Q�����B���������j��҂Ƃ��Ă̐��i�����������̂͒m����B�@ ���V�c�`��/�����̌��������֓��̍����B������������ɐQ�Ԃ苞��苒�����Ɠ������ɋ��������q���́A���{��ŖS������B����������V�c�ɔ��t�����ۂɂ͌�����̑��w�����Ƃ��ČR���𗦂��]�킷���������������B���킪�g��ɓ����O��Ɍ���̍c�q�E�P�ǐe�����k���ɍ~��B�ꎞ�͂��̌R����r�Ŗk���ɐ��͂��L���邪�A���ۏ�U�߂̍Œ��A��̂��ߏ����̕��őO���Ɍ������Œ��ɓG�̑�R�ɑ������펀�B�R�l�Ƃ��Ă͗D�G�ł��邪�A�����I�ȗ͗ʂ͂Ȃ��B�����ŕ����v���ł����������A�������Ȃ��������ɂ𐋂����̂��ɂ��܂��B�@ ���e���`��/�V�c�`��̒�B�`��ɏ]���A�e�n�œ]�킷��B�`��̕����Ƃ��ĕʓ����𗦂��鎖�����������B�`�厀����k���ŕ��킷�邪�y���A�l���œ쒩���̋�����}�邪�Ԃ��Ȃ��a�v�����B�E��Ԃ���`���ꌈ���Ė��\�ł͂Ȃ����A�����Ε���ȋM������x�̒Ⴂ�G���̏O�𗦂��鎖�ɂȂ������߂��A�s�k�̂������������`��̑����������錋�ʂƂȂ鎖���������̍���Ȃ����ǂ���ł���B�@ ����ؐ���/���Ƃ̔��B�ɂ��䓪�����͓��̓y���o�g�B����V�c�����q���{�ɑ����������ۂɏ���������A�ԍ��E�瑁��ł̘U���Ŗ��{�R��|�M����B���̌����Ԃ肪���q�R�̈АM�ቺ�E�e�n�ł̓|�����͖I�N�Ɍq�������Ƃ������̌��т͑傫���B���������t�����������̂��ߕ��킷��B����L���ȊԂɑ����Ƙa������A������U�����n���ĕ�͂���Ƃ���������������������ꂸ�A�s���Ȑ킢��������ꂽ���썇��ő����̑�R�̑O�ɗ͐s����B�㐢�Ɏ���܂Œ��b�Ƃ��ď̂���ꂽ�B�����̐�͂ŃQ������p�Ȃǂ�p���G��|�M���A���������ƌł��������ւ����B�܂��A�l���Ƃ��Ă������ŕ�e�͂̂���\�����Ȃ��l���Ƃ���邱�Ƃ������B�@ ����ǐe��/����V�c�̑��c�q(�ِ�����)�B����V�c�����������ۂɂ͔�b�R�E�g��Ȃǂőm���⍋�������ɖI�N���Ăт����|�����͂�g�D���A���킪�B��ɗ����ꂽ���Ԃɂ͎�����̑��i�ߊ��Ƃ��Ċ����B���퐭�����ł͑����ƑΗ����邪�A�����̌v���ɂ�肻�̐��Ђ����ЂƂ�������ɂ���ĕߔ�����A�₪�Ē��`�ɂ���ĎE�Q�����B������Ƃ��Ď�r��U�邢�傫�ȍv����������A(�{�l�̈Ӑ}�Ƃ͊W�Ȃ�)����ɂƂ��āu���q�g���̒��v�Ƃ������ʂ��������B�ېg�ɒ����Ă���Ƃ͌�������������Ɩv�����p���������̂͐ɂ��܂��B�@ ���P�ǐe��/����V�c�̍c�q�B���܁E������q�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�W������c���q�ɗ��Ă���B�����Ƃ̐킢�̒��Ō������ʂ������(�������A��ɂȂ����͂����P�������V�c�Ǝ咣)�V�c�`��Ƌ��ɖk���։���z�O�������ɘU�邪����̍ۂɕ߂�����ɏ��Y�����B�@ ���ԏ��~�S�A���S/�d���̐V�������B���S�͉~�S�̎O�j�B����V�c�����q���{�ɑ����������ہA���S�͌�ǐe���ɕt���]���s���B�~�S����ǐe���̗ߎ|���Ĕd���ŋ������A���{�����苒���鋞�s���J��Ԃ��U������B���������ɂ����ẮA���킪��ǐe�����x�����Ă������ߌ�ǔh�̐ԏ����͗�������B���̂��߁A��ǖv����͑��������ɐڋ߂�������������|������ɂ͑������Ƃ��Ċ���B�������`��ɔs�ꐼ���ɗ������т��ۂɂ́A�����@���̓V�c��i�����Ē��G�̉�����h������i��������A�d��������ŐV�c�R��H���~�߂�ȂǑ傫�Ȍ��т������Ă���B���̌�����������̉��ŗL�͎҂Ƃ��Ċ���A�ω��̏�ł��������Ƃ��Ċ��������B����p�������S�����������ŗL�͎҂Ƃ��čI�݂ɗV�j�����B���R�`�F���א쐴����쒩�R�ɂ�苞���������ۂ͗c���`����d���ŕی삵�Ă���B�ԏ����͎����ʓ��߂�ƕ��Ƃ��Ē蒅����B�@ ���k������/�k���e�[�̎q�B���퐭���ł͓��k�n�������鉜�B���R�{�ɕ��C�B������������|�����ۂɂ͏㗌�������R��V�c�`��E��ؐ�����Ƌ��ɐ����ɒǂ����Ƃ��B�������Ăы����̂���������������A�ēx�㗌�����݂��炭�͔j�|�̐i���𑱂��邪�A�ΒÂ̐킢�ō��t���ɔs�ꓢ�������B�@ ����풉���E���a���N�E����e��/���q���{�|���̍ۂɌ��т��グ����V�c��蒞������B��ؐ����Ƌ��Ɂu�O�؈ꑐ�v�ƌĂꂽ�B�����Ƃ̐킢�̒��Ő펀�B�@ ���k���e�[/����V�c�̒��b�̈�l�B���������t�����킪�g��ɓ��ꂽ�ہA�ɐ��ɓ쒩�����̐��͂�z���B���펀��A�֓��ɓ���쒩���̐��͕}�A�ɕ��S���邪�ʂ������B���̌�A�g��œ쒩���̎w������葫�����{�̓����ɏ悶�ċ��s�D��𐬌�������B�֓��o������͋M���I�E�厞��I��������A�d���߂��炷�����ڂɏo��X�������������A���̌�͋g��œ쒩�S�̂̎w�������A�G�̓����̊Ԍ����I�݂ɗ��p�����B�@ �������`�F/�����̎q�B�����̎���Ɍ�p�҂Ƃ��đ������{���㏫�R�ƂȂ�B���{���̓�����쒩�Ƃ̐킢�ɋꓬ����B���ʂƂ��Ė��{�̗D�ʊm���ɐ������Ă��薳�\�ł͂Ȃ��Ǝv���邪�A�����瓦���ۂɓV�c��s������̂�Y���ȂǏd��Ȏ��Ԃ��ڗ��B�@ �����X�ؓ��_/�ߍ]�ɋ��_�����L�͍����B���������q���{�ɔ�����|�����ۂɑ����ɏ]���A�ȍ~�������ƍs�������ɂ���B���{�����ł̓����������ɉj�������L�͎҂Ƃ��Ă̒n�ʂ��m���B�ӔN�͎Ⴂ����̌㌩��I�ȑ��݂ł������B�A�d�ƂƂ��Ēm��ꎞ�ɂ͐Q�Ԃ�������Ȃ��������A�����ɂ͊�{�I�ɒ����ł������B�����̉��l�ςɑ����Ȃ��h��ȑ����E�U�镑������k�����喼�ƌ���ꂽ�B���ʂȍ˔\�Ɍb�܂�A�v�V�I�Ȏ���̎q�ł���B�����ŕېg�̏p�ɂ������Ă����B�@ ���א쐴��/�������̈�l�B�ω��̏�ő������Ƃ��ĕ��킵������y����B�`�F�����R�ɂȂ����ۂɂ͎����Ƃ��ĕ⍲���邪�A�����Ȏ�@����������甽�����B���X�ؓ��_�̉A�d������`�F����d���l�Ƃ��ē������A�쒩�ɍ~��B�ꎞ�͋����̂��������ɗƂȂ�Ō�͍א엊�V�ɓ��������B���̗E�҂�����d���V����̊��҂̐��ł��������A���V���₷�����w�ƂȂ�j�ł̓�����ށB�@ ���R������/�V�c�ꑰ�̓y���B�������Ƃ��ĕ���B�ω��̏�ł͒��`�h�̗L�͎҂Ƃ��ė͂�U�邢�A���̌R����r�Ƌ������Ő��͂��g��B�ꎞ���͋��s���̂����Ă���B�ŏI�I�ɂ͋`�F�Ɍ`���I�ȍ~�������邪�����̐��͌���ǔF�����Ă���B�e��ŋ����Ȓ��`���̕�(�����)�ł���B�@ ������O��/����ł͕S�ω��Ƃ̖���Ƃ����B�嗤�Ƃ̖f�Ղɂ�藘�v���グ�Ă���B��k���̊Ԃ�n������A�ω��̏�ł͒��`���Ƃ��Ċ����B���̎�r�Ő��͂��g��B�ŏI�I�ɂ͋`�F�Ɍ`���I�ȍ~�������邪�����̐��͌���ǔF�����Ă���B�ێ�h�ɑ������钼�`���̗L�͎҂ł��邪�A�{�l�͊v�V�I�Ȏ���̎q�ł���B�@ ���㑺��V�c/����V�c�̍c�q�B���������A�쒩����̓V�c�ƂȂ�B��N���͖k���e�[�̕⍲���邪�A�e�[����͓쒩�̑����Ƃ��Ĉ��|�I�s���ȏ��Ő킢��i�߂�Ƌ��ɖ��{�Ƃ̘a�r���͍��B�@ ���l�𗲏r/�쒩���̌��ƁB�쒩�̐������ɋ^���������Ȃ����d�h�B�����S�ɖ��͂Ȃ��E���ł͂��邪�A��̎��Ԃ��ǂ̒��x�F���ł��Ă��邩�ɂ͋^�₪����B�@ ����ؐ��V/��ؐ����̎O�j�B�Z�E���s���펀������͓�؎�����Ƃ��ČR���I�ɓ쒩���x����B�쒩��]�E���Ƃ̋��d�Ȏ咣�ƈ��|�I�s���Ȍ����̔��݂ƂȂ��Y�A���{�Ƃ̘a����͍��B�ꎞ���͖k���ɓ��~���Ă���B�@ ���V�c�`��/�V�c�`��̎q�B�ω��̏�̍ۂɂ͖��{�����ɏ悶�Ċ֓��ŐV�c���̎c�}�𗦂��ċ����B�ꎞ���͊��q��苒���邪�����ɔs���B���̌�A���{���̓y���ɖd�E�����B�@ �����c�V�c/�㑺��V�c�̍c�q�B��O��쒩�V�c�B���d�Ȏ��h�Ƃ��Ęa���h�ƑΗ��B�틵�̈����Ƌ��ɘa���h�̌�T�R�ɏ��ʂ�]�V�Ȃ�����邪���̌�����h�̗̑��ł��葱�����悤���B����̖�]�E���̋��d���ɂ�茋�ʂƂ��ē쒩�̕�����������ʂƂȂ�B�@ ���א엊�V/�����̈��B�א쐴���̏]�Z��B�ω��̏�ő������Ƃ��Đ킢�A�����̓G���͂����_�B�������d�����N�������ۂɂ͔ނ�����Ă���B���̌�A�`�F�a�v���ɊǗ̂ƂȂ��O�㏫�R�`����⍲�B���{�̑̐��𐮂���Ƌ��ɏ�̈��艻�ɓw�߂�B�����Ƌ��ɐV����̊��҂̐��B�E�҂����L���₷�������ƈႢ�A���肵�����i�̎�����ŋ����Ȓq���Ƃ��Ċ���B�ŏI�I�Ɏ��Ԃ̈��艻�Ɉꉞ�͐����B �@ |
|
 �@ �@���쒩�̌R���w���҂Ɛ헪 |
|
|
����ǐe���@ ����V�c�̍c�q�Ƃ��ĉ��c���N(1308)�ɐ��܂��B���А��͂𖡕��ɂ������̌v��̈�Ƃ��ĉ���̍���ƂȂ�B���틓���̍ۂɂ͔�b�R�E�g��ȂǂŎ��Ђ�V�������𒆐S�ɖI�N���Ăт����ē|�����͂�g�D���A���킪�B��ɗ����ꂽ���Ԃɂ͓�ؐ����E�ԏ��~�S�̕⍲���Ď�����̑��i�ߊ��Ƃ��Ċ����B���퐭�����ł͑��������ƑΗ����邪�Ɋׂ�A�܂��炻�̐��Ђ����ЂƂ��Ă�������ɂ���Đ؎̂Ă���ߔ������B���̌�͑������̋��_�ł��銙�q�ɑ����A�₪�Č���2�N(1335)�������`�ɂ���ĎE�Q�����B�@ �헪/���q���{�̕��͂͂��܂�����ł���A���ʂ������Ă͏����ڂ͂Ȃ������B�����ŁA���ЁE�C�����Ƃ̐[���q����𗘗p���A�ނ��g�D�����ċ����ӂ𒆐S�ɑS���ŖI�N�����邱�ƂŖ��{��h���Ԃ�A�X�Ȃ�s�����q�̖I�N��U�������ď�L���ɂ���헪���Ƃ����B���ł��瑁��ő�R��ɕ��킷���ؐ����ƌJ��Ԃ��ċ��ɍU����������ԏ��~�S�͋M�d�Ȏ��ł������Ƃ�����B���������헪�͐�����̕⍲�ɂ��������ꂽ���̂Ǝv���邪�A���ʂƂ��đS���̕s�����q�����틵��ω������鎖�ɐ��������B���{�œ|��́A�S���̗L�͍����ɐl�]�̂���卋���E���������x�������炪�����𑩂˂鎖�Œ�������肳���悤�Ɛ}�����B�������������̗͂������͓̂���A���������čō��w�����Ƃ��āu�V�c�㗝�v�̖������ʂ����Ă������������Ɋ댯������Ă��莸�r���邱�ƂƂȂ����B�@ ������V�c�@ �c���������@���E��o�����ɕʂ�đ����Ă�������ɑ�o�����E��F���V�c�̎q�Ƃ��Đ������N(1288)�ɐ��܂��B���͑����B�V�c�ɑ��ʂ���Ƒ씲����������r�Œ���̎x�z���y�ԋ��s���ӂŐ������v���s�������]�����B����ɂ��S���I�Ȑꐧ���������������炪�x�z�҂Ƃ��ČN�Ղ��鎖��ژ_�݊��q���{��|�����ߐ킢���d�|����B����͔s��B��ɗ��������̂̍ŏI�I�ɓ|���ɐ���������ɂ�铝�ꐭ�����������邪�A���̋����Ȑ������j�͊e���ʂ��甽�������������̔��t�ɂ�萭���͊����B�g��ɓ��ꑸ�����i�����鎝���@���̒���ƑΗ��B���������Ƃ̐킢���s���ɂȂ���钆�ʼn���4�N(1339)�a�v�B�@ �헪/����́A�E���𒆐S�Ƃ���V�������␅�R�E�@�����͂𖡕��ɂ��鎖�œ��ꐭ�������ɐ����������A��������肳���������ێ�����ɂ͎��͕s���ł������B���������g��Ɉڂ�̂�]�V�Ȃ����ꂽ����A�V�������┽�������͂𒆐S�Ɋe�n���ɖ������͂�}�A������œs��D�悤�ƌv�悵�Ă����B�������̏�ɐ��ʂ��}�������□���Ԃ̘A�g���������������e���j����A���ӂ̂����ɖv���鎖�ƂȂ����B�Ȃ��A����͗�O�I�ȘU���ȊO�ł͑O���ɏo�Ă��炸�A���������Ƃ̐킢�Œ��ڂ̌R�w�����߂Ă����̂͐V�c�`��ł��������A�헪���茠�������Ă����͈̂�т��Č���ł���`��͐헪���x���̌���ɂ͗^�炸�����I�Ɉ���ʌR�i�ߊ��Ƒ卷�Ȃ��ł������B�@ ���k���e�[�@ �i�m���N(1293)�A�����M���̉ƕ��ɐ��܂��B����V�c�����ʂ�������ɂ͏d�b�̈�l�Ƃ��Ēm���邪�A�ꎞ���͋�����u���Ă���B���퐭��������͉��B�o����C���ꂽ���q�E���Ƃɓ������ĉ��B�ɕ������B���������t�����킪�g��ɓ��ꂽ�ہA�ɐ��ɓ쒩���̐��͂�z���Ă���B�ꎞ���A�֓��ɓ���쒩���̐��͕}�A�ɕ��S���邪�ʂ������B�g��ɋA�҂��Č���v��̓쒩�����w�����邪�Ԃ��Ȃ��E���쒩�R��͂���ł����Ă��܂��B���̌�A���������̓����ɏ悶�ċ��s�D��𐬌������邪�ꎞ�I�Ȃ��̂ɏI������B����9�N(1354)�ɖv���Ă���B�@ �헪/�����͌���̍\�z�ɉ����āA�쒩�̐������������A�W�e�[�V�������鎖�Ŋe�n�̐V�������E���������͂𖡕��ɂ��n����g�D�����悤�Ƃ��Ă����B�������A�틵���s���ł��������������䒼��̌��͋�Ԃɂ����ď\���ȉ�������Ȃ��������A�����Đe�[���g�������_�ɌŎ�����X���������������Ƃ��獋���̎x���鎖�͂ł��Ȃ������B�g��A�Ҍ�͖������͂�����̃A�W�e�[�V�������_��p���đg�D�����A�G�̓���������I���ɗ��p���ė������쒩�̗�������コ�����B�X�ɑ������̌��𒅂��Đ���7�N(1352)�ꎞ�I�Ȃ�������D��ɐ������Ă���B���������̎��������D��ɌŎ�����X��������A���ʂ��ł��Đ���3�N(1348)�l��덇��œ쒩��͂ł����ؐ��s�R��S�ł�����ƌ������Ԃ����Ă���B����ɋ��D������ǂ͈ێ����邾���̐�͂��Ȃ����s�ɏI���A���Ղ��錋�ʂɏI�����(���������̍ۂɖk���̓V�c�E�@��_�������������́A��ɑ��������̐�������D�����ɂȂ�a�����ɉe����^���Ă���)�B�܂��A���D���̋�̓I�ȓW�]�͕����Ă��Ȃ������Ǝv����B�������ɑ������Ƃ̘a�������s���Ă��邪�A�쒩�ɂ�铝��Ƃ��������_�ɂ������j�]�����Ă���B�a�����͖O���܂œG�̓����ɕt��������L���ɉ^�Ԃ��߂̋삯�����Ƃ��đ����Ă����悤���B�@ ���������~�@ �������`�̗{�q(�����͑���)�B���ۂɂ͑����̒��j�ł��邪�A��̐g�����Ⴂ���������������(����A�`�F�͐����̎q�ł�����)�B�����T��ɔC�����邪�A�����E���`���Η����đ���������������ԂɂȂ�Ɨ{���E���`�ɖ������ċ�B�E�����n���Ő��͊g���}��B���`�v��͋����`�h�𗦂��ē쒩�ɍ~���A���Ǖߎg�ɔC�����R���w���҂Ƃ����B����10�N(1355)�����ꎞ��̂��邪�₪�ėƂȂ�A�R�A�ɓ����B���v�N�͕s�ځB�@ �헪/�����`�h�Ɠ쒩�̐��͂�����������������D�悷�鎖�ɐ������Ă��邪�A�����Ɉ�A�������鎖���S�Ă������悤�ŁA�����I�ȓW�]������Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B�܂��A�����������̎�̂ł���{���I�ɂ͓쒩�R���w���҂ƌĂԂɂ͂�����Ȃ��̂ł��邪�A�X��Ƃ͌����쒩����R�����w�����̎��i��^�����헪�I���������Ă��邽�߂����ɋL�����B�@ ���א쐴���@ �����ꑰ�Ƃ��Đ��܂�A�N����葫�������z���ŕ����������E���Ƃ��Ēm��ꂽ�B�����������㏫�R�E�`�F�̎���ɂ͎����Ƃ��đ��������̉^�c�ɂ����邪�A�����ȕ��j���L�͎҂̔������Ėk���N�����N(1361�A����16�N)�Ɏ��r���쒩�ɍ~��B���N�ɓ�ؐ��V�Ƌ��ɓ쒩�R�𗦂��ċ����̂��邪�Z���ԂŒD��A�l���ɓ����B����17�N(1362)�s���B�@ �헪/����̌R���Ɠ쒩�̐��͂������������𑫗�������D�悵�Ă��邪�A�����I�ȓW�]������Ă����Ƃ͎v���Ȃ�(��ؐ��V�́A�헪�I�ɖ��Ӗ��Ƃ��ď�q�̋��U���ɔ����Ă���)�B�������������̌��͑����ɔs��đ�`���������ߓ쒩�ɋ߂Â������݂ł���{���I�ɂ͓쒩�R���w���҂ƌĂԂɂ͂�����Ȃ����A�X��Ȃ���쒩���w�����߂Đ헪�I�������^�����Ă��邽�߂����ɋL�����B�@ ����ؐ��V�@ ��ؐ����̎O�j�B�Z�E���s���펀������͓�؎�����Ƃ��ČR���I�ɓ쒩���x����B�������̕���ɏ悶�ĉ��x�����D����ʂ����Ă�����B�㑺��V�c�̓Ă��M�����A���������Ƃ̘a����͍��B�㑺�㎀��ɋ��d�h���䓪����Ɨ��ꂪ�����ƂȂ�A�ꎞ���͑������ɓ��~���Ă���B�ӔN�͍Ăѓ쒩�ɋA�Q���Ă��邪�v�N�͕s���ł���B�@ �헪/�쒩���_�ɂ�����쒩���L�͍���(��؎��͉͓��E�a������_�Ƃ��钆�������ł���A���ꂪ�쒩�L�͎҂ƂȂ��Ă��鎞�_�œ쒩�̈��|�I���f����)�̓���Ƃ��āA�e�[�v��ɓ쒩�̌R���ʂ�o���ɒS���B���̎����͑������̓����𗘗p���Ĉꎞ�I�ɋ��D����ʂ������͂�����̂́A�������Ƃ̐�͍��͊u�₵�Ă���쒩�̊����Ԃ��͐�]�I�ł������B�R���I�ɂ͐�͏��Ղ�����ĉ͓��E�I�ɁE��a�̌��j�Ȓn�`�𗘗p�����琨����{�Ƃ��Ȃ�����A�܂����đ������ɍU���ɏo�Ĉ��͂������Ă����B���N�ɂ킽��O���ɐg�������Đ틵���n�m���闧�ꂩ��A�R���I���͂������đ�������h���Ԃ����ŋ@��𑨂��Ă͘a�������s���Ă���A�쒩�̖ʖڂ����`�ł̘a�����u�����Ă����悤���B�㑺��V�c�ɂ����ȐM�C��w�i�ɂ��Đ���22�N(1367)�a��������O�܂Ō����^�Ԃ��A�܂���䓪�������d�h�̖W�Q�������Ă����s�ɏI����Ă���B�t�ɁA�㑺��̎��ɑ��ʂ������c�V�c�̉��ł͋��d�h�ƑΗ����đ������ɍ~������H�ڂɊׂ��Ă���B�쒩�ōĂјa���h�������𑝂����̂����Ă��A�Ăѓ쒩�ɖ߂��Ă��邪��k������O�ɖv�����Ƃ����B�@ �����c�V�c�@ ����4�N(1343)�㑺��V�c�̎q�Ƃ��Đ��܂��B����23�N(1368)���ʂ��A�O�a3�N(1383)���܂ō݈ʂ����悤���B�݈ʊ��Ԃɂ����Ęa�����͍s���Ă��炸�A�쒩�̎��h�ɂ��i�����ꂽ�Ɛ��肳��Ă���B��k�����ꎞ�ɂ����ɓ����s�ɓ��s�����g��ɗ��܂����Ƃ����B�@ �헪/���ʎ��_�ŁA�쒩�������͋I�ɁE��a�E�͓��E�a��̎R�ԕ��݂̂Ɏc������ɉ߂������Ő��O�̏�Ԃł������B�㑺�����ɔ����s����������̊댯�����O���ꂽ�Ǝv����B���d�Ȏ��_��O�ʂɏo�����ŁA�l�S�ꂵ���ʂ̓G�ɓ��点�ē��h��h���_���ł������낤�B�����ē쒩���ŗB��D���ɐ킢��i�ߋ�B����𐬂������Ă����e�r���ɂ�闈���𗊂݂ɒ�R������j�������ƍl������B�������A�����Ƃ̘��������������d�_���R���I��͂ł�������ؐ��V��G���ɑ��点�A�X�ɘa���h�Ƃ̑Η��ƌ����`�œ���������������͔̂���ł������B�ŏI�I�ɂ͈��|�I�ȑ������̍U���̑O�ɍ��܂�]�V�Ȃ�����Ă���B�Ȃ��A���̎����ɑO���̑��i�߂߂��͓̂�؈��̒��V�i�ł���a�c�����ł��������A�헪���x���ł̌����͂Ȃ������Ǝv����B�@ ����T�R�V�c�@ �㑺��̎q�ł���A���c�̒�ɂ�����B���h�̍��܂��čO�a3�N(1383)���ɑ��ʁB�a���h�̎x�����Ă����Ǝv���A����9�N(1392)����������̘a����������Đ_���k���E�㏬���V�c�ɏ��n�B�����ɓ�k�������͈ꉞ�̖�������B���������̌�A�a�������ł�������k���n�������݂ɑ��ʂ���Ƃ������ʂ�����Ȃ��̂�s���Ƃ��čĂыg��ɓ��ꂽ��������B���i31�N(1424)�ɖv�B�@ �헪/���̎����ɂ͋�B���������̎�ɗ�������A�E���ł͗��݂Ƃ�����؎��̋��_�����X�ɗ��Ƃ����ȂnjR���I����ɒ��ʂ��Ă����B�R���I�ɓ쒩��w������l�������݂����A��R�̗]�n�͂Ȃ��\�����̑Ζʂ�ۂ`�Řa��(������̍~��)�ɉ�����ق��I�����͂Ȃ������ƌ�����B�Ȃ��A�c�ʂ��ے�����_���ۗL���Ă����͓̂쒩�݂̂ł��������߁A���������͐_��a���ɏ����鎖�Ŗk���y�ё��������̐��������m�ۂ��鎖��]��ł����B����𗘗p���āA���n�������ő��ʁE���͓̂쒩���x�z�Ƃ����\�Ȍ���L���ȏ����������o���Ă���B���������͂̂Ȃ��g�̔߂����A���̏����͌��ʂƂ��Ĕ��̂ɂ��ꂽ�����R�ƂȂ�B�@ ���@ �ӊO�Ȏ��ɁA���ۂɐ��ɏo�������ł͂Ȃ��V�c���g�����Ɛ헪��S���w���҂ƂȂ��Ă��鎞������������������܂����B�쒩�́A���̑O�g�ł����o�������ォ��V�c�������^�c�̎哱�������`��������̂ł����A�R���ʂł������������������ꂽ�ƌ�����ł��傤�B���Ɍ���V�c�͐ꐧ�I�Ȑ����̐����u�����Ă��܂����̂ŏ��X�ł��B�������A���ꂪ��������Ό����ɂ�����Ȃ����z�_�ɗ����X�������o���A����X�ɕs���Ȃ��̂Ƃ����ʂ͔ۂ߂܂���B�@ �܂��A�Ɨ͂ŏ�ŊJ���邾���̗͂���������ɂ͑��������̓����ɏ悶��ق��R��i�������Ă��܂������A���ꂷ�����ɂ͑��������ɂ���������̔s�҂��~�����ē쒩�̎w�����߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B�쒩�������ɕt�������Ď哱�������鎖����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��������������͊_�Ԍ�����̂ł��B�@ �����̎���́A�쒩�̓������I�W�]�Ɍ������@���`�I�Ȃ��̂Ƃ����Ƃ����܂��B����A��ؐ��V�͒����I�W�]�������������Ȃ��w���҂ł������A���������ɉ߂��Ȃ��ނ��w���I����ɗ�������Ȃ����̂��쒩�̎�̂��������̂ł����B�������Č���ƁA�R���I�o���ƎЉ�I���͂����˔������쒩�����������̎w���҂́A��ǐe��������������܂���B�쒩�͑����i�K�Ŏ��ɐɂ����l�ނ��������Ƃ����܂��B�@ �쒩�Z�\�N�̍��Ɛ헪����́A�쒩�̖ڎw�����z�ƌ����̗����A�����Ă��̎�_���_�Ԍ�����ƌ��������ł��B �@ |
|
 �@ �@���ԏ��~�S (1277-1350) |
|
|
��ؐ����Ɠ��l�Ɂu���}�v�ƌĂ��V�������̏o�g�ł���Ȃ���A�쒩�ɏ}������؎��Ƃ͑ΏƓI�ɑ������Ƃ��Ċ��������������߂�L�͎��ɂ܂ł̂��オ�����ԏ��~�S�B���̐��U���T�ς���B�@ ������w�i�@ 8���I�����Ɋm�����������W���I�ȓ��ꐭ���́A9���I�ɂ͎x�z�͂���߂����ʂƂ��ĕ���Ɍ������B���Y�͂̌���ɔ����n�x�̍����g�債�A�n���w���v���������Ŏ��͂�t���������n�������͔ނ���x�z���ɔ[�ߎ����̐����e�n�Ō`�������B�������{(����)�͍����B�̗�����ٔF���A�l����c���E�x�z����̂�f�O���ēy�n�P�ʂł̐Œ����̐��ɓ]���B�������đ�y�n���L�ҁA���Ȃ킿�L�͋M���E���Ђ�n�������ɂ��A���̖̂���Ƃ��Ē��삪���݂���̐���11���I�O���Ɋm������B�@ �₪�āA�n�������̎��͌���ɔ����ނ���x�z���ɑg�ݓ��ꂽ�R���M�����䓪�B12���I���ɂ͌R���M���̑�\�҂ł��錹���E�����ɂ��������o�āA�������������ɂ���ē����{�ɌR�������ł��銙�q���{�����������B���{�͒���̏@�匠�𖼖ڏ�͔F�߂������{�𒆐S�ɓƎ��̎x�z�̐����m���B���삪�����{�A���{�������{���x�z����`�ƂȂ����B13���I�O���̏��v�̗��ȍ~�͌R���͂ɏ��開�{�����|�I�D�ʂɗ����A����ɂ��̎x�z���𐼓��{�ɂ��L���Ă����B13���I���̃����S���鍑(��)�̗��P(����)���_�@�Ƃ��Ė��{�͍��h�̕K�v�ォ��S���K�͂Ŏx�z���������A�X�ɂ��̍��ɔ��B�����������Ɛ��͂�c�����鎖�Őꐧ�����u�����Ă����B�@ ����ŁA�]����薋�{�ɏ]�����Ă��������B(��Ɛl)�͕��������ɂ��x�z�̈�̗���A���Ɣ��B�ɔ����n�x�̍��̊g��A�����₻�̌�̊C�x���ɂ��o�ϓI���S�������Đꐧ�����開�{�ɕs�����点�Ă����B�܂��A�o�ϐ�i�n��ł������E���𒆐S�ɁA�ݕ��o�ϔ��B�ɔ�����_�Ɩ����x�z���ɒu�����V���������䓪�A�`���I���͂Ƃ����ΏՓ˂��u���}�v�ƌĂꂽ�B�ޓ��͒���E���{�ł��瓝�������ꂸ����Y�܂���Љ�s���v�f�ƂȂ��Ă����B���{�͔ނ��_�Ɩ��̑g�ݓ���ɕ��S���Ă������A�����̔�_�Ɩ��͓`���I�ɒ���Ɛ[���q���肪�������W�������Ă��A�u���}�v��͔J������ɂ�莩��𐧕I���鑶�݂Ƃ��Ė��{�ւ̔��������҂�����������悤�ɂȂ�B�@ ����A���v�̗��ȍ~��̉����Ă�������́A�X�ɍc����L�͋M�����n�ʂ��߂����ĕ���B�c���͎����@���Ƒ�o�����ɕ�����A�ۊ։Ƃ͌ܐۉƂɕ��đΗ�����B���ł��c�ʂ�u���V�̌N�v(�c�ʂ�ނ�����c�̒��ł��V�c�̕ی�҂Ƃ��Ď������������҂������Ă�)���߂����Ă̗����̑Η��͐[���ŁA���{�ɂ�钲�����K�v�Ȃقǂł������B���̌��ʁA�v���ʂ�ɍs���Ȃ������w�c�ɂ�開�{�ւ̈⍦�ގ��ƂȂ�̂ł���B�@ �o�ϔ��B��w�i�ɐꐧ����i�߂開�{�ł��������A���̈���Ŋe�K�w���甽�����Ǘ������i��ł����B�l�X�̕s����Љ�s�������܂����A���{�͎��͂̓G�ӂ��Ȃ��狭���̐������z���������̂ł���B�@ ���ԏ����@ �ԏ����̋��_�Ƃ����d���́A��r�I���ɋ߂��d�������i���Ĕ_�Ɛ��Y���������B�X�ɐ��˓��ɂ�����C���ʂ̗v�n�ł�����A�����ł��d�v���̍����n��̈�ł������B�@ ���Đԏ����́u����V�c�掵�c�q��e���Z��̕c��A�]�O�ʋG�[�������v�Ə̂��Ă��������m����B�����̍������d���ɔz�������ۂɂ͍��p�S�ɋ��Z����̂��ʗ�Ƃ���Ă������A�G�[�����p�S�Ō��n�����̖��ƌ_��A���̎q�����n�œy�����Ă������Ƃ����̂ł���B���݂ɁA���̎���ɂ͌��n�̍������M��Ɩ���W�킹�Ď���̌��������߂悤�Ƃ���̂͒������Ȃ������B�G�[�̑\���ł���F�쑥�i���k���`���̎���ɍ��p���n���ƂȂ�A���̎q���ő��̖͂��q�ł���Ɣ͂����߂Đԏ����𖼏�����悤�ł���B�����A�����~�S�͉Ɣ͂���݂Ďl��ڂ̎q���ɑ�������B�@ �������Č���ƁA�ԏ��������㌹���̖���ƌ����̂͏��Ȃ��Ƃ���؎����k���Z�̖���ƌ������͐M�ߐ������肻���ł���B�������A���Ƃ��Ă����̈ꑰ��14���I�ɂ͔d���̈�y���ɉ߂��Ȃ������B�c��̐M�ߐ��͍����Ƃ��A���̎��_�ł̎Љ�I�ʒu�͓�؎��Ƒ卷�Ȃ������Ƃ����Ă悢�B�����Đԏ����͂��̈ꑰ�̒����ł��猈���ĂȂ����Ƃ̈�ɉ߂��Ȃ������̂ł���B�������疼�������Ĕd���ꍑ�̎��A�X�ɑS���L���̎��͎҂̒n�ʂ܂ŏ��l�߂��~�S�₻�̎q�E���S�̗͗ʂ͕��X�Ȃ�ʂ��̂ł���ƌ����悤�B�@ ���Đԏ��~�S�́A�v�N����t�Z����ƌ���3�N(1277)�ɐ��܂ꂽ�悤�ł���B��N���̈�b�Ƃ��ẮA�T�m�E�ᑺ�F�~�Əo������o������Ɨ\������Ă���Ɋ��ӂ����Ƃ������̂��`�����x�ł���B�~�S�̎�N���ɂ�����ᑺ�̔N�����l������ƁA�������ۂɏo����Ă���Ƃ�����ɂ����Ăł��낤�Ƃ����B���Ƃ���Α�Ԗ��̂��߂ɏ㗌���Ă������̂Ƃ��l�����A��Ɛl�ł������\�������シ��B���݂ɉ~�S�̉����T�m�ł���@�������ƍ����A�~�S�͔ނ̂��߂Ɍ������N(1319)�ɋ��̎���Ɉ����������Ă���Ă���B���ꂪ�㐢�ɂ͑哿���ɔ��W����̂ł��邪�A����͕ʂ̘b�ł���B�@ �������̖��J���@ ���̍��A��o�������瑦�ʂ�������V�c�͐e�����s�����s���ӂ̏��Ɛ��͂�ی삵�x����ՂɎ�荞�����Ɛ}��B�������āA����͂₪�Ė��{�̑œ|��ژ_�ނ悤�ɂȂ�B�T���ł������Ȃ̌����ɍc�ʂ��p�����邽�߂ł���A�c�ʌp���Ɋ����開�{��|���V�c�ɂ��ꐧ�����������邽�߂ł���B���ɖ��{�͖k�����̑y�̂ł��鍂�����a��̂��ߎw���͕s���ŁA���k�̔����⌠�͑����ɔY�܂���Ă������ɂƂ��Đ�D�̋@��Ǝv��ꂽ�B����́A�c�q�E���_�@�e����V�����Ƃ��ĉb�R�ɑ��荞�ނȂǎ��А��͂̌o�ϗ́E�R���͂𗊂݂ɂ��Ĕނ�̎�荞�݂�}������ŁA���O���N(1331)�ɋ������}�u�R�ɘU�����B���������{�̌R���͖͂������|�I�ł���}�u�͊ח����ĕ߂���A�����@���̗ʐm�e��(�����V�c)�ɏ��ʂ�����ʼnB��ɗ����ꂽ�B�@ �������A����̗U���ɉ����ĉ͓��ԍ�ŋ������Ă�����ؐ����́A�ŏ��̋������������s�\���ł��������̂̌��O3�N(1333)�ɂȂ�Ɩ��{�R���㕽��e�n�Ŗ|�M������ŋ����R�̐瑁��ɘU��B�܂��A��ǐe��(���_�@�e���A�ґ����Č�ǂƖ����)�͊e�n�̍����ɋ��������Ƌ��Ɏ��g���g��ɘU�����B����ɂ��АM��������ꂽ���{�͑�R�����g����ח���������̂́A�瑁��͍U�ߗ��Ƃ�������]�V�Ȃ�������Ԃł������B���{�ɔ��������l�X�́A��������Ė��{�̌R���I�АM�̒ቺ�����Ď���Ă���A�����ɍX�ɖ��{���ɑ��U�������҂��o�������ۂɂ͂���ɑ������̂���������ł��낤�ł������B�@ �������@ �~�S�̋��Z����d���́A�O�q�̂悤�Ȑ헪�I�d�含�������ĘZ�g���T��(���ɒu���ꂽ���{�̐����ɂ����鋒�_�A��X�k��������C)�̒����n�ł������B���̊W����ԏ����͖k�����Ƃ̊ւ����K�R�I�ɋ����Ȃ炴��Ȃ������Ǝv���邪�A���ꂾ���ɖk�����ւ̔��������܂����\���͂���B�~�S�̎O�j�E���S�͈ꑰ�̏������G�Ƌ��ɁA��ǂ��V�����ł����������炻�̑��߂Ƃ��Ďd����ǂƋ��ɋg��R����]�킵�Ă���A�����i�K�ʼn~�S��������ɐS���Ă������̂Ɛ��@�ł���B�X�ɁA�u�ԏ��L�v�ɂ��Γ��������ɒ��j�E�͎��Ǝ��j�E��͂�ےÓ��ɔh�������͕}�A�ɓw�߂Ă����Ƃ����B�ےÒ��F���̋N�����Ɂu���s�͎��v�u�y�Ǖߎg��́v�ƋL�������̂����݂��鎖��������̋L���ɐM�ߐ��͂���Ƃ�����B������܂��A������Ƃ��Ċ������邽�߂̕z�ł������̂�������Ȃ��B�@ ���Č��O3�N2�����S�͏������G�Ƌ��Ɍ�ǂ̗ߎ|�����Q���ĉ~�S�̉��ɎQ�サ���B����ɏ]���ĉ~�S�͍��p���ۓ�ɒz�邵�ċ����B�X�ɗߎ|�͔d�������̎��ЁE�����ɓ`�B����A��R�̌R�����~�S�̉��ɏW�����̂ł���B�ߎ|�ɂ͏\�������ɂ킽���ĉ��܂̖��L����Ă���A�l�X����藧�Ă�ɂ͏\���Ȍ��ʂ��������Ǝv����B�Ƃ���Ō�ǂ̗ߎ|��3��21���t�ŏo����Ă������A�����̓�����25���ɒ�߂Ă����B�o����Ă���͂�����܂ł̎��Ԃ��l������ƁA���ɉ~�S��͖I�N�����ӂ���ǂƘA���̏�ŏ����𐮂��Ă����ƍl����ׂ��ł��낤�B�@ ���ĉ~�S�͂����ɐ���E�R�̗����R���ōǂ��A�R�z�E�R�A�ƋE���Ƃ̌�ʂ��Ւf�����B��͂͑D��R�ɐw��~���A�����n������Z�g���ɒy���Q���悤�Ƃ���R�������ށA�X�Ɉɓ��ҌQ���~�点�鎖�ɐ����B�ҌQ�͔��O�O�ŖI�N���A���E�������̌R�������ނ��ĉ~�S�̔w����ł߂��B����ʼn~�S�͈��S���ċ��ɐi�o���鎖���o����悤�ɂȂ����̂ł���B�@ ���Z�g���Ƃ̐킢�@ �~�S�͂܂����ɂɐi�o���Ė���R�ɐw��~�����B�����m�����Z�g���́A���Ԃ��d�����Ėk�����m�E���X�؎��M�̗�����ܐ�̌R����h���B�[2��11���~�S�͕S�����S���x�̋|�����R����~�낵�ĘZ�g���R�ɖ���ˊ|�������A�R�֓����鎖�œG���R��ւƗU�����B�y���̐ԏ����͑����Ɏ��w�ɍ����������A�R���𒆐S�Ƃ���Z�g���R�͌������R���ɓ�a�B�����֎R���ɕ����Ă������S�E�O�Ԍ��ׂ���̉J�𗁂т�������B�����ēG�����������̂����v����Ĕ͎��E��͂��㌎�E���p�E�����E�ڋ{��ܕS�𗦂��ē˓������B�Z�g�����͓˔j����ČR�̑Ԃ��ׂ��Ȃ��Ȃ�A�呹�Q�����đދp�����̂ł���B�@ ���̏����ɏ悶�Đԏ��R�͐ےÂ̕��암�ɐi�����v�X�m�ɖ{�w��u���A�ɐ����z�u����B3��10���J���~���Ă������Ƃ�����A�~�S�͖��f���Ď��g�̎��͂ɏ����̕������z�u���Ă��Ȃ��������A�����ֈ��g����㗤�������}�����̌R������P��������B�~�S�͖ڈ�ɂȂ���̂��̂ĂēG�R�ɕ���A�����炪��E�o����ƈɒO���ʂ̎��R�ɓ������B�v��ʔs�k���i�����~�S�ł��������A�����ɋC����蒼���Đ���(���ʎs)�ɐi���B�Z�g���͑��w�Ƃ��Ĉꖜ�̑�R�����������Ă���A����ƌ��킷�邽�߂ł���B���R���ɂݍ������A���ł͐ԏ��R�͎O��Ƒ傫�����B�����ʼn~�S�͒�͂ɉF�썑���E���p�͉ƁE�O�Ԍ��ׂ�Ƌ��ɏ����̕��������A�G�w��ɉ�点��B��͂�͒|��Ԃɕ����ēG�R�ɖ���ˊ|���A�G�̓��������ꂽ����˂��đł��ďo���B�Z�g�����͒�͂炪�����ł���Ƃ͒m�炸�A�������ꂽ�ƍl���ē��h�B���̋@������~�S�͑S�R�𗦂���騂̐����グ�ēˌ������B����ŘZ�g���R�͒ב����傫�ȑ��Q���o�����̂ł���B�@ �����ő��S�̐i���ɏ]���A��C�ɋ��i�o���鎖�Ɍ��߂��~�S��12�����E�Ԉ�E�R��E�����Ƃ��������x�O�n��ɖ앚��p��������ĘZ�g������h���Ԃ�B�Z�g���͍��̕������ē̌R����Ґ����h�q�̐����Ƃ����B���ĉ~�S�͋v���E�������̓���ʂ���˓���}��B�܂��~�S���g�̗�����v�����ʂł́A�j�������ōU�ߌ��ݓG�����Ƃ�����ˊ|�����������炭���������A���S�͖O�ԋ�Y�E�ɓ����E�������G��Ƌ��ɓn�͂����s���ď㗤�ɐ����B����������ԏ��R�͗E�C�t�����Đ��n��A�Z�g���R��˔j���ċ��ɐN���A�Z�g���ɒ��߂��@�؉��@�ɂ܂Ői�o�����B����A��������ʂł��˓��ɐ������Ă���A��{�E���F�E�x��ɉ�������B���̎��̐��ƂȂ������̍����́A�����V�c�E�㕚���@�E�ԉ��@���䏊����Z�g�����ւƔ�����ł������B�����������ŘZ�g�����͋��c�E�����̎O��𐼎�����ʂցA���R�E�͖�̓���@�؉��@���ʂ֍��������Ėh��ɓ�����B���R�E�͖��͕��킵�Đԏ��������ނ��A��킵�Ă������c�E��������~�����Ď�����ʂ̐ԏ��R�����ǂ��U�炵���̂ł���B���������Z�g���R�͗����ɓ���������ԏ��R�̎�𑽐��Z���͌��ɎN�������A���̒��ɐԏ��~�S�ƎD��t����ꂽ�܂����ċ����̏��҂ƂȂ����B�~�S�̊��m��҂��Z�g�����ɋ��Ȃ��������ߐ������쌀�ł���B�@ �������ĉ~�S�͍ŏ��̋��U�h��ɂ����đ�s���A�ꎞ�͎��n���l����قǂł��������h�����Ďv���Ƃǂ܂����B���݂ɂ��̍ہA�j�R�����{�ɋF���������Ƃ���_��������A����ɏ]���Ĉȍ~�͉Ɩ�ł��鍶�����b�̊��ɑ嗴�̎p��`���đ叫���Ƃ��ėp�����ƌ����B���ċC����蒼�����~�S�͌R�����ĕҐ����A�M���ł��钆�@��\���`����̑��叫�Ƃ��ėi�����Ė����𐮂���B���̏�ŎR�肩�甪���ɂ����Ă̒n���苒���A�j�삩��ؒÐ�Ɏ��鐅���ʂ��Ւf���ċ��ƍU�߂ɂ��������Ƃ����̂ł���B�@ �~�S�����ƍU�߂ɂ����̂��ĘZ�g�����́A�Ɠ��m�ۂ̂��߂Ɍܐ�̌R���������ĎR����U��������B�}�����~�S�́A�萨���O�ɕ����ċ|���ܕS��匴��ɔz�u���A�앚�Ə����̋R������Ȃ��̕����ϐ�ɑҋ@�����A�X�ɓ��E���ŕ��������������S���������_�L��̏����ɕ����������B�܂��匴��̋|�������ꂩ��Z�g���R�ɖ���ˊ|���A�����nj�����Z�g���R�̑��ʂ𓁁E�����������Ƃ��čU���B�X�ɋR���ɗ�����ꂽ�앚�炪�w��ɉ�肱��őޘH��f�Ԑ����Ƃ����B����ŘZ�g���R�͕����������ב������̂ł���B�@ ���̏������b�R�́A�����{�h�������Â��ċ����B�퓬�ł͘Z�g�������D���ł��������A�b�R���������{�h���c�����Ă���ꖇ��ł͂Ȃ��������A�Z�g���Ƃ��Ă͓쐼�Ɩk���ɂ������ʂ̗v�n�����ꂽ�`�ƂȂ����̂ł���B�@ ����ɏ悶��悤�ɂ��āA�~�S��4��3���ɍēx���֑��U�����|�����B�a�@��ǒ�(��ǂ̑���)�E���@�蕽��i�����ɓ��E�ڋ{�����ӂ̖앚�ŕҐ����ꂽ�O�炪�����E���H���ʂ���N���B�����ĉ~�S���g��������F��E���p��O��ܕS���j���ʂ��琼�����ւƌ��������̂ł���B�Z�g���́A�����̂����O�������̉b�R�ɑ��Ċ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���ԂŌ}���Ԑ����Ƃ�B�O��Ɠ��l�ɘZ�g���R�͓�ɕ�����Ă��ꂼ��̓G�ɑΏ������B�ԏ��R�͕������������ߏ��H���ǂ��Ŏˎ��O�ʂɏo������ˊ|���A����̘Z�g���R�͋R�����������ߋ@���͂����ĉ��Ƃ���͂��悤�Ɛ}��B�������đo���Ƃ����͂�s�����Đ���Ă������A�܂��������ʂł͐��ŏ���Z�g���R���ԏ�����j���ĉF���ւƒǂ��U�炵�A�X�ɓ����ɔ����Ă����ԏ��R�����R�U�炵���B�������Ĉ�ɂ܂Ƃ܂����Z�g���R�́A���鐝�̉~�S�{�w�ւƍU�ߊ�������ށB�~�S�ɂ�鋞�U�����͂��̎����������Ȃ������B�@ ���̒���A�R�A���ʂ������̒��b�ł����풉���������̌R���𗦂��Đ��R�ɕz�w���A4��8���P�ƂōU�ߊ邪������s�ނ��Ă���B�@ �������āA���U�����͓̂�q���Ă������̂́A�~�S�̕���ɂ�菙�X�ɂ��̒n��̐틵�͌�����ɌX���Ă����̂ł���B���{�R���瑁�U�߂ɓ�q���ĈАM���ቺ�������{�h��͂Â��Ă������A�瑁��ɑ����̌R�������Ȃ��Ȃ苞���蔖�Ɉׂ��Ă��������v���Ƃ��ċ�������B�|���ւ̗���͐�������������~�S�������Ă��Ƃ����悤�B�������Ԃ��炩�����S�Ɍ`�����t�]����ɂ́A���ƈꉟ��������Ȃ��̂������ł������B�@ ���W���{�ŖS�ւ̂��˂�@ �~�S�̕�����āA�e�n�Ŗ��{�ɑ��������鍋�������o�����B�l���ł͌��O3�N2���ɁA�ԏ��R�̋����ɍ��킹��悤�ɂ��ēy���ʑ��E���\�ʍj�E���ߏd���������B���N�[2���ɂ͒���T��E�k��������Έ䖩�Ŕj��A�����Ĉɗ\���E�F�s�{��@�����ނ�����ɐi�o�����ےÂ�苒���Ă���B�������ɑ�a�̍��ԍs�G�E���S�A�I�B���͎����I�N�B�܂��֓��ł����R�����������A��B�ł����s�ɏI����Ă��邪�e�r���������T����U�����Ă���B�����������ʼnB��ɗ�����Ă������킪�E�o���Ĕ��˂̖��a���N�Ɍ}������B����ɂ���Ĕ����{���͍X�ɐ����Â��A�O�q������풉�����R���𗦂��ĘZ�g���U���ɉ�������̂ł���B�@ �ԏ����Ɛ�풉���ɂ��U�����J��Ԃ���������Ă����Z�g���T��́A���q�ɍX�Ȃ鉇�R���˗��B������āA���{�͖��z���ƂƑ������������R�Ƃ��ď㗌��������j�Ƃ����B�������͏�����č������k������|���V����_���D�@�ł�����ɂ�ł����̂ŁA�r���̎O�͂Ō���ɘA��������d�|����ɓ���Ă����B�����͂�����B���Ȃ��狞�ɓ����B�Z�g����4��27�����R�̖��z����������ʂ���A����R�̑������ܐ���������ʂ���i�R�����鎖�Ƃ����B���Ė��z�����}���������̂͐ԏ��R�ł������B�~�S�͎O��̕��𗄁E�É́E�v���ɕz�w�����A�������ɂ��Ė��z���ɖ���ˊ|����B���z���͐��̗D�ʂƋR���̍U���͂����Đ킢��i�߂悤�Ƃ��Ă������A���p�͉Ƃ��叫�E���Ƃ��˗��Ƃ����̂���|���ɂ��Ė��z���͒ב��B�ԏ����͂����nj����đ傢�ɐ�ʂ��������B�@ ����ő����R�͓r���ōs�R���~�߂ď���ώ@���Ă������A���z���̉�ł����č����͎�������Ɣ��f���O�g�ɂē|���̋����������B5��8���������͐ԏ��R�E���R�Ƌ��͂��ĘZ�g���T����U���A�Z�g�������E�킵�����̂̏O�ǓG�������ɔs�ށB�����ɐԏ������������ʂ��瑫���R�����삵�Ă����B�Z�g�����͗����傩�甪���͌��ɋy�Ԗx�E���E�t�ΖE�E�Ƃ��������ݏ�s�Ƃ����ׂ��h�q����ݒu���Ă����h���ł������A�����ɏ���ԏ��R�͒�͂̎萨�������˔j�����̂���|���ɂ��Ď����͌����ʂ֗��������B�Z�g���T��̖k�𒇎��E���v�͖h�q��f�O���A�����V�c�E�㕚���@�E�ԉ��@�����ē����ɗ������т悤�Ƃ����������̋ߍ]�ԏ�Ŗ앚�ɕ�͂��ꎩ���B������͕߂炦��ꋞ�Ɍ쑗���ꂽ�B�@ �������ĘZ�g���T��͖ŖS���ċE���͌�����̎�ɗ����A�`���͈�C�Ɍ�����ɌX�����B����ɑ����悤�ɂ��ĐV�c�`��ɂ�芙�q���ח��A����ɑ�F���E���ɂ������T����ח������B�����Ɋ��q���{��130�N�̗��j������̂ł���B�����E�~�S�ɂ���Ă�ꂽ�|���ւ̗���Ƃ����c�́A�����ɂ��ԊJ���`��ɂ�����t�����ƌ�����B��ɖ������H���[���|���ւ̌��т����ɑ傫�������l���Ƃ��č����E�`��E�����E�~�S�E���N�̌ܐl�������Ă���A���Ԉ�ʂ̖ڂɂ��ޓ��̍v�����ۗ����Č������ƌ����悤�B�@ �������������̉~�S�@ ���������ɂ�������ꂽ�Ƃ����m�点���A����͔��˂���㗌�̓r�ɂ��B���̓�����5��30���~�S��͕��ɕ������Ō���ɏ��߂Ĕq�y�����B����͏�@���ł���A�u�V�����n�̌��A�ЂƂ��ɓ����ۛ��̒���ɂ���B���܂͊e�X�̖]�݂ɔC���ׂ��B�v�Ɖ~�S�ɐ����|������𖽂����Ɓu�����L�v�͓`����B���̂Ƃ��̊��������펩�g���Y��Ȃ���A���j�̗���͏�����������̂ƂȂ�����������Ȃ��B�Ƃ�����A����͋��ɓ���Ǝ��g�̐e���ɂ�铝�ꐭ��(��������u���������v�ƌĂ��)�̌��݂ɒ��肵�悤�Ƃ��Ă����B�������Ȃ���A�|���ɑ傫�Ȍ��т̂�������ǐe���͑������Ƒ������Η����A�M�M�R�ɘU���ē����Ȃ������B����͐V���ȑ����������ׂ��A��ǂ𐪈Α叫�R�ɔC�����ĉ��_�B���̍ہA���������ǂ̌R���̐�w���߂��̂��ԏ��~�S�̎萨�ł������B�|���ɑ傫�Ȍ��𗧂Ă��Ǝ�������~�S�ɂƂ��Ă͓��ӂ̏u�Ԃł������낤�B�@ �e�����ĊJ���S���̎x�z������ɓ��ꂽ����V�c�̍ŏ��ɂ��ׂ����͓|���ɋ��͂����l�X�ւ̉��܂ł������B�S�����疳���̕��m����Ђ����т���\�����܂����߂Ă���A����ꂽ�̒n�ŏ[������ɉ�����邩�^��ȏ�Ԃł������B�������V�c�͌Ȃ̎��͊�Ղ��m������ׂɎ��g��ߐb��ɑ����̋��k�����̂�t�т����Ă����B���ꂪ���܂̌������ւ̕s����傫�����Ă����B��������������(�����A����̖��u�����v����ꕶ�������ĉ���)��V�c�`���|���ɑ傫���v�������l�X�͑���ȉ��܂�^�����Ă��邱�Ƃ����������悤���B���ɓ�ؐ����E���a���N�E����e���E��풉���͔j�i�̏o���Ƃ݂Ȃ���u�O�؈ꑐ�v�ƌĂ�Ă����B�����ĉ~�S���d�����ɔC�����ꂽ�B��q�̖ʁX�Ɣ�ׂ�Ə��Ȃ��Ƃ͂����邪�A����ł������͍��p�����ӂ݂̂ɐ��͂�A�������ꑰ�̑y�̂ł���Ȃ����������l����Ɣj�i�̏o���ł͂������B���������̔N��9���ɁA�~�S�͍����̒n���Ɉ��Ăē����g���H���̂��ߖ؍ނ̋��o�����߂������z���Ă���B�����Ƃ��A���N10���ɂ͐V�c�`�傪�d����ɔC������A���҂��d���ɂ����錻�n�x�z�𑈂��`���ɂȂ�̂ł��邪�B�@ ���Č���͎�̉����������̊�@�I��F�����A���͋�����ڎw���ĐV���Ȑ����̐����\�z���Ă����B�����ł͌o�ρE�x�@�Ȃǎ�v���E�͋ߐb���A���V�c�ɑS���͂���������l�ɐ}��A�n���ł͌��̂̒��ł��i�鍑�i�ƌR����x�@��S�����̕��u�ɂ�蕪���������������B�������Ĕ_�ƂƔ�_�Ƃ̋ύt����钆���W���I�Ȑꐧ������ژ_�݁A�u�������鏤�ƂȂǂ��R����o�ϊ�Ղɂ��Đ������x�������悤�Ƃ��Ă����̂ł���B�@ ������������ѓO����ɂ͎��͂������s�����Ă���A�}���ȉ��v�ɔ������鐨�͂͐��������݂��Ă����B���̒��ł��A�����B���疼��Ƃ��ĐM�]���W�߂鑫�����͍ő�̊댯���q�ł������B�����͋��ɕ�s����ݒu���č����B�Ǝ�]�W�����ڂ��Ƃ��Ă����ق��A�܂��V�c�`��̊��q�U�߂ɒ��j�E�����(�`�F)���Q�������đ�����Ƃ��Ċ��q�𗎂Ƃ����Ƃ����`�����֓��ɐ��͂�������̂ł���B����ƌ������Η����Ă����̂���ǐe���ł������B�ނ͑������V���ɖ��{����邱�Ƃ��x�����A�܂����炪�L�͍����B�ɂ��R���͂𑩂˂悤�Ƃ��Ă����B����ɂƂ��ẮA�����͂������A��ǂ����Ђƌ����ׂ����݂ł������B�|����ɂ����Ă͉B��ɗ����ꂽ����̕ς��ɑ��i�ߊ������߂Ă���A���ꂪ���݂ƂȂ��Ă͌���̌��Ђ��������悤�ɂȂ��Ă����B�܂��A�����𑝂₷�K�v������풆�ɉ��܂����ߎ|�𑽔����Ă����̂ł��邪�A���ꂪ�{�̈��g�Ȃǂ̍����������Ă����̂ł���B����͌�ǂɑ����r���̗�����^�����Ɓu�~���_�v�͋L���Ă��邪�A����悭�Η��҂̋��|���]��ł����\���͂���B�@ ���đ����ƌ�ǂ̑Η��́A�����B�̐M�]�ɏ��鑸������ǂ����|����`���ƂȂ��Ă������B�܂��A��ǂ͎���̍c�q���c�ʂɏA���悤�Ɩ]��ł��鈢����q(����̈���)�Ƃ��Η����Ă���A����ɌǗ����Č������B�����������Ō�ǔh�̐��͎͂���ɍ���Ă������悤�ŁA��ǂ͌������N(1334)�̌㔼�ɂȂ�Ɖ��B����k������著���Ă������B�ɐ�͂��ˑ�����L�l�ł������B�����ē��N12����ǂ͌���ɂ���ĕ߂炦��ꑫ�����̐��͔͈͂ł��銙�q�ւƌ쑗���ꂽ�̂ł���B�@ ���āA���̓��������ɉ~�S�͔d�������Ƃ���č��p���n���E�݂̂Ƃ��ꂽ�悤�ł���B���̎����ɓ��ɉ~�S�Ɏ��Ԃ��������킯�ł͂Ȃ��A�s���ȑ卶�J�ł���B�������O�q�̌�ǎ��Ăƌ��ѕt���čl����Γ����͌����Ă���B�����܂ł��Ȃ��~�S�́A��ǂ̗ߎ|�ɂ���ċ������A�ꑰ����ǂ̑��߂Ƃ��Ďd���A��Ǔ����̍ۂɂ͐�w���߂��؋�����̌�ǔh�ł���B��ǂ̐��͍팸���Ȃ�����Ƃ��āA�~�S���u�l�������v�Ɋ������܂ꂽ�̂ł��낤�B�@ �������āA���������͗L�͎ғ��m�̑Η����ł����A�܂��댯���q�̉��E�ނƂ�������̒��ŁA�|���ɑ傫�Ȍ��т���������ǂ��̂Ă鎖�ƂȂ����B�����Ă���͓������������M���̂���~�S������̂Ă鎖�Ɍq�������B����̑��߂ł��閜�����H���[���O�q�̂悤�ɓ|���ɓ��Ɍ��т��������ܐl�ɉ~�S�̖��������Č��������̂͂��̎��ł���Ƃ����B�����������~�S���̂Ă��Ɠ��l�A�~�S�������Ɍ���������悤�ł���B���ꂪ�����̕���ɏ��Ȃ���ʉe�����y�ڂ��̂ł���B�@ �������̋����@ ����2�N(1335)6���M�Z�Ŋ��q���{�c�}�ɂ���唽�����u�������B�k�������̎q�E���s���z�K���ɗi������ċ������A�֓��ɐN���B���q����鑫�����`(�����̒�)�͂���ɔs��ĎO�͂܂œ��ꂽ�B���݂ɂ��̍ۂɌ�ǂ́A�ނ����s�ɗ��p�����̂����ꂽ���`�ɂ���ĎE�Q����Ă���B������đ����́A���`���~�����֓���D�邽�߂Ɍ���̋���҂��������B���̍ہA�~�S�͒�͂��]�R�����Ă���A�����ɐڋ߂�}���Ă������Ƃ�������B���Ɍ��������Ɏ��]���Ă����~�S�́A���{�ċ����u���������Ɋ�]��������̂ł��낤�B���āA�֓���D�������͊��q�ɓ���Ǝ��̘_���s�܂��s���B���������͂����d���ł���Ƃ��ĐV�c�`��ɑ����E���`�̓����𖽂����B�����͌���ɋ|�������̂�����ŏo�w���Ȃ����������ł��������A���`���`��ɔs���n�Ɋׂ�Ƃ�����~�����ׂ��o�w���V�c�S�����j�����B���̍ہA��͔͂����|�m������Ře���`��(�`��̒�)�R�ɓˌ����ď����ɍv�����Ă���A���̌��тŒO�g�t������������^�����Ă���B�@ �V�c�R��j���������͐����ɏ���ď㗌�A�~�S�͂���ɉ����ċ������������j�R�ɓ��������ۂɂ͔͎����Q�w���Ă���B�����đ����R�͑�R�ŋ����́A�ԏ��R�͎R��̘e���`���R��˔j���ċ��ɗ������U���̑��|�����������B����͉b�R�ɓ���A�����ƐV�c�E�k�����ƁE�����Ƃ̊Ԃŋ����D�킪�s���邪�A���ǂ͑������͔s��Đ����ɓ���Ă���B���̍ہA�~�S�͑����E���`�ɖ���R�̏�ɘU�邷��悤�i�����邪�A�����̎m�C�������邱�Ƃ�����Ĕ�����҂�����~�S������ɏ]�����B�����ĉ~�S�́A�u�~���_�v�ɂ��ΐ����̗v���ɖ�����z�u���Đ��͂𐮂��鎖�Ǝ����@���̌����@����@����đ�`�����𗧂Ă邱�Ƃ����߂��B�~�S�́A�����B���u���G�v���Ȃ킿�V�c�ɋ|�������Ă��邱�Ƃ����߂����Ɍq����m�C�����Ȃ������̂�����̔s���̈�ł͂Ȃ����Ɠ���ł����̂��B�����������͊����Ă���A���̐M���͎����ꂽ�B�����͌����@�ɖ��g�𑗂�Ɠ����ɁA���˓��̗v���Ɍ��n�����Ƒ����ꑰ��z�u���Ď����ł߂����Ă����B�Ɍ��������B�l���ɍא�a���E���t�E�t���E�����E��T�A�d���ɐԏ��~�S�A���O�O�ɐ��a�`�E���c�����A�����۔��ɍ���r���E�����A���|�ɓ��䎁�E�����쎁�A���h�ɑ哈�`���E����O���A����Ɏz�g���o�E���������Ƃ����z�u�ł���B���ɔd���͒���R�������Ɍ��������ۂɍŏ��ɂ�����}�����ʒu�ɂ���A�~�S�͂��̏d�ӂ��������̂ł���B���Č�����Ƃ��ĕ��킵���ԏ����́A���͔�����̋}��N�Ƃ��čĂѕ\����ɗ��Ƃ��Ƃ��Ă����B�@ ��������@ �~�S�́A�d���h�q�̗v�Ƃ��đۓ�k���̌������R�̒��_�ɐV���ȏ�s�����݂����B���̍ۂɌ����̔������~���Ă����Ə̂�������Ɩ��t���Ă���B�X�Ɍ����̎��_�ŕ��_�ł��锪�����J��A�ȑO���猻�n�̐_�ł������t���_�Ђ������č��J���Đԏ��̎��_�Ƃ����B���炪(����)�����ł��邱�Ƃ��̗g����Ƌ��ɁA�����̓����ł��鑫�����ɓV���������Ă��邱�Ƃ������Č����̎m�C�������悤�Ƃ������̂ł��낤�B�@ ���āA�������ւ̒nj��ɑ��钩��̑Ή��͐v���Ƃ͂����Ȃ������B�V���ɍ~���҂̑g�ݓ���E�R�̍ĕҐ��E����̒��ł̕��ƏW�߁E�����ւ̒����E�k�����Ƃ���A�҂����Ẳ��B�m�ۂɗ͂𒍂��ł���A�������ł߂鎖�ɐ���t�ł������B������nj��ł����A���̐��͔҉��T�ς��邵���Ȃ��ɑ��đ����̒�����̕����͏ł�������Ă����Ǝv����B�Ⴆ�A��ؐ������V���̐l�S�͑����ɌX���Ă��邽�ߐV�c���̂ĂĂł������ƍu�a����ׂ����ƌ����Ɓu�~���_�v�͓`���Ă���A������������������̈�[���������̂ł��낤�B�u�����L�v�ɂ��`��͒��삩�玒���������E���������ւ̈��ɓM��Ă����Ƃ����A�������ւ̏ł��킹�Ă������̂����m��ʁB�@ �܂��`�厩�g���a�C�ƂȂ�o�w�ł����A3���]�c�s�`�E��َ����ɐ����^���Đ�s�����Ă����B�ޓ��́u�����L�v�ɂ���3��6�����ʎR�ɓ����B�~�S�͂�����R�U�炻���Əo�w���A���R(�K�یS)�ŏՓ˂������s�k���Ă���B����ɂ����Đ挭���������������ƂŐV�c�R�͈ӋC������A�₪�ċ`�厩�g�������̕��͂𗦂��Ĕd���ɓ��������B�`��͍O�R�ɖ{�w��u���A�܂���U�߂�����悤�Ɖ~�S�ɑ��d�����E�������Ƃ��č~������悤���������A���ꂪ���ʂƂ��ĉ~�S�ɘU���̏������Ԃ�^���邱�ƂƂȂ����B�����s���ɏI����ċ`��͔�������͂���B���������j�Ȓn�`�ɑj�܂�A�X�ɉ~�S�͕��ƁE���̔��~���\���s���Ă���|�̖���𐔑��������čR�킵�����߁A�V�c�R�͈ꃖ���ȏ�ɂ킽���čU�ߊ���̂̋]������𑝂₵��ʂ������鎖�͂ł��Ȃ������B�`��͔d����ł���A���̒n�𐧈����鎖�͈АM��ۂ�ŕs���ł���������łȂ��A��ʂ̕ւ╺�Ɗm�ۂ̓_������d�v�ł������B����������Ď��Ԃ����錋�ʂƂȂ����̂ł���B�`��͂�������߂��ׂ���E�`�����ʓ����Ƃ��Ē����n���ɔh�������R��𗎂Ƃ��Ȃǂ̐�ʂ����������̂̎��͊��ɒx���A�����͑��X�Ǖl�ŋe�r����j���ċ�B���������čď㗌�̏����ɂ������Ă����B�~�S�͂������ɕ��ƕs���Ȃǂŋꂵ���Ȃ��Ă������Ƃ�����A���S���g�҂Ƃ��đ����ɑ����̏㗌�𑣂��B������đ�����4��26����B���A���`�ɗ��R�𗦂��������g�͐��R�𗦂��Đi�������B�����Čܖ��߂���R�ł������ƌ����B5��18���ɑ����͎��Âɓ����B�`��͋t�ɕ�͂���鎖������A������̕�݂������đS�R�ɂ܂ň����グ�������B������ꂽ�~�S�͗����ɑ����̉��Ɉ��A�Ɏ�Ă���B���̍ۂɉ~�S�͓G�����u�������Ă���������𑽐����Q���đ����ɔ�I�������A�����͂�������āu���̒��ɂ͈ȑO�ɖ����������҂��������A�ꎞ�̓��邽�߂�ނȂ��`��ɑ������̂ł���A�^�ɕs���ł���B������͌����ɎQ��ł��낤����Ƃ��߂�K�v�͂Ȃ��B�v�Əq�������ƌ����B�����̓x�ʂ��m�����b�ł���B�����R�͍X�ɑO�i��5��25�����ɂ̖���ŐV�c�E��،R���Q�ɕ������킹�Č��j����ؐ������������B�������đ吨�͒�܂�A�����͍Ăы��ɓ����Ď���̐��������ɂ�����B���Đ������瑁��Ŗ��{�̑�R��|�M���ė�����������̂Ɠ��l�A�~�S��������ő������Ɏ�����Ăэ��̂ł���B�@ ���d�����E�ԏ��~�S�@ ����͐V�c�R�Ƌ��ɉb�R�ɓ���A���炭��R���邪���Ƃ��R�����Ȃ����������葸���̘a���H��ɉ����ĉ��R�A�`��͖k���ɓ��ꂽ�B�����͍c�ʂ̈�ł���O��̐_�������Ď����@���̌����V�c��i��(�k��)�B�����ɂ��V������܂����悤�Ɍ��������A����͍ĂђE�����ċg��ɓ���A���炪�����ȓV�c�ł��邱�Ƃ�錾(�쒩)�B�����ɁA���Ƌg��ɓ�l�̓V�c�����݂����k�������������J�����̂ł���B�������~�S�̏����ɂ�����Ă����헪����`��������ɓ���邽�߂Ɏ����@���Ƒ�o�����̑����A�����u�N�ƌN�Ƃ̌䑈���v��O�ʂɏo�����������̂��l����ΕK�R�̋A���ł������Ƃ�������B���̏���ŁA�����͋������_�Ƃ��Ė��{������i�߂Ă����B�@ ����܂ł̌��т�]������A���������ɂ����ĉ~�S�͔d�����A�͎��͐ےÎ��E���쌠��ɔC�����ꂽ�B�~�S�͂�����Ĕd�������̏����ɓw�߂����A�d���̍������ӂł͐V�c�ꑰ�ł�����J�o�����O���R�ɘU���Ė��̋ߍ]���ƌ��т���ɒ�R���Ă����B�~�S�͂����Ƃ̐킢�ɖZ�E����A����5�N(1338)����ɂ킽���ē쒩���̒O���R��⍁��������U�����Ă���B���̈���ŁA�ۓ�ɕ�ł���@�_���������B���̊J�R�Ƃ��ď����ꂽ�̂��A�~�S�̐N���ɏo����\�������ᑺ�F�~�ł������Ƃ����B�@ ���đ��������͓쒩�Ƃ̐킢�����|�I�D���ɐi�߁A�����^�c���R���E���܂��i�鑸���Ɩ{�̈��g�E�ٔ��E��ʐ����������`�̓̐��ŏ����ł������B�������A����ɑ����̎����Ƃ��Č�����U�邤���t���ƒ��`�̊ԂŎ哱�������鑈����������悤�ɂȂ����B�t���̉��ɂ͎��͎�`�Ō��Ђ��y��V�������������W���Ă���A�����̖��卋���𒆐S�Ɉ��肵���������u�����钼�`�Ƃ͑��e��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B��a5�N(1349)�[6���ɒ��`�������ɗv�����Ďt�����Ƃ����A����ɑ��ē��N8���Ɏt�����N�[�f�^�[���N�����ĕ��������x�͒��`�����r�����B�����������ŁA�~�S�͎t���h�ɖ������đD�⓻�̎����ł߁A�܂���͂��P�H������݂��Ă���B�����n���ő������~(���`�̗{�q)�����`�h�̐��͕}�A�ɓw�߂Ă���A����ɑ��ċ��Ƃ̘A�����̂��ړI�ł������B�������Ė��{���[���ȓ����Ɋׂ낤�Ƃ��Ă������A��a6�N(1350)1��11���ԏ��~�S�͋������̓@�ŋ}�������B74�ł������B�@ ���ԏ����S�@ �~�S����ɐԏ������p�������̂͒��j�E�͎��ł������B���ɔ͎��͂ŐےÎ�삠�������A�u�L���_�Е����v�Ɏc��䋳������͎����d�����������˂Ă�������������̂ł���B�������͎����ω�2�N(1351)�}�����A���S������p�����B���S�͉~�S�̎O�j�ł��������A���̗E�m�Ƃ��Ď��т�͗ʂ��L���F�߂��Ă����̂ł���B���݂ɔ͎��̒��j�E���͂��ےÎ����p���ł���B�@ ���āA�ԏ����ŗ��đ����ɑy�̂̌�オ�N�����Ă���ԁA���������͓D���̓����Ɋׂ��Ă����B�ω����N(1350)12������2�N(1351)2���ɂ����āA���`���쒩�Ǝ������ő����E�t����Ɛ킢�A���ɂŎt�����ł��j���đ����Ƙa�r���t�����E�Q�B���`�D�ʂ̑̐����m�����ꂽ���Ɍ��������A�����h�ƒ��`�h�̑Η��͖����ƂȂ��Ă���A���x�͑������쒩�Ɍ`����̍~�������Ė������l�����A���`�����悤�Ƃ��Ă����B�@ �ω�2�N(1351)7�������͋ߍ]�̍��X�ؓ��_���w�����̂œ�������Ə̂��ċߍ]�Ɍ������A�`�F(�����̒��j)���ԏ����S���߂Ƃ����ċ����琼�Ɍ��������B����́A���_�E���S�Ƌ��d���ċ��̒��`�𓌐����狲������̐�����������̂ł���B���`�͂����ɉz�O�ɒE�o���A�����ƌ��킷��Ԑ���������B���̍ہA���S�͌�ǐe���̎q�E���ǐe����Ă���A�쒩�Ƃ̘a�r�����߂�z��ł��Ă����B�ނ��A���̎����ɓ��_�ɓ쒩���瑸���E���`��悤�d�|���o�Ă������Ƃ��l���ɓ����ƁA�ɂ���Ă͎��ۂɓ쒩���ɐQ�Ԃ鎖������ɓ��ꂽ���̂ł����������m��ʁB�Ƃ�����A���S��̌��ɂ�葸�����Ɠ쒩�̘a�r������(�����ꓝ)�B�����͂�����Ċ֓��ɏo�w���A���`��ǂ��Ċ��q�܂Ŏ���쒩����7�N(1352)2���ɂ͓ŎE���Ă���B�@ ����A���̍��ɓ쒩�͋����U�ߗ��Ƃ��A�����ɑ������Ɠ쒩�̘a�c�͔j�ꂽ�B�`�F�͊Ԃ��Ȃ�����D�邪�A�������ƒ��`�̌���p�������~�E�쒩�Ƃ̎O�b�̌`���͑������̂ł���B���̊��ԁA���S�͈�т��đ������Ƃ��čs�����A�쒩�Ⓖ�~�R�Ɛ���Ă���B�@ �������v���ċ`�F�����㏫�R�ƂȂ�������A���S�͗L�͎��Ƃ��ďd�����Ȃ��Ă����B�N�����N(1361)�������ӂ���������E�א쐴�������X�ؓ��_��ƑΗ����Ď��r���A�쒩�ƌ���ŋ��ɍU�ߓ������B���̎��A���S�͎R�����������O���E���c����j���Ĕ���ɐN�������ہA����Ɛ���Č��ނ�����������Ă���B�܂��A�����ɂ�苞�����Ƃ��ꂽ�ۂɂ͋`�F�̒��j�E�t����(�`��)��d��������Ɍ}���ĕی삵�Ă���B���݂ɂ��̎��A�ދ�����t���ɑ��Č��n�̓c�y���Â��ĈԂ߂��Ƃ����A�`������ɂ͏��R���ԏ��@��K�₵�Ă��́u�ԏ����q�v����������̂��ʗ�ƂȂ����B�����̌��������āA���S�͔d���ɉ����Ĕ��O�̎��E��^�����Ă���B�X�ɒ厡4�N(1365)���S���㗌�����ۂɂ͏t���ۂ��ԏ��@��K�ꑥ�S�̗{�N�Ə̂��ꂽ�̂ł���B�@ �ӔN�̉���2�N(1369)���͂��쒩���ɒʂ��ċ����������߂�������ĐےÎ������C�B���N�ɂ͑T�������l�ɔC�����A���{�̏@������Ɋ֗^���邱�ƂƂȂ����B������4�N(1371)11�����S�͕a�v�B���N61�ł������B�@ ���S�́A�I�݂ɗ������Ȃ�����������Ƃ��Ċ��Đ��͂�L���A���R�Ƃ̐M�C���l�������B�X�Ɉꑰ�����̑��������p���Ď��g�̗͂�L�����������ڗ��B�܂��A��ю�����������ȂǑT��Ă��M���A����4�N(1359)�́u�V��ژa�̏W�v�ɂ͓��̘a�̂����W����ȂǓ����Ƃ��Ă͋��{�l�ł��������B������ނ̗�������L���ɂ�����ɗ������ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�ŏ��ɂ͌�ǂ̑��߂Ƃ��ēo�ꂵ�A�Ō�ɂ͑��������L�͎҂Ƃ��ė������j���ʂ����Ë��ҁE���S�B���̎p�͓������Ɂu����喼�v�ƌĂ�N�₩�ȑ��݊������������X�ؓ��_�Ƃ��d�Ȃ���̂�����B�@ �����̌�@ ���S�̌�́A���̎q�E�`�����p���N��N(1379)�����ʓ��ƂȂ薾��3�N(1392)�ɔ�����ɔC������Ȃǐԏ����̒n�ʂ�L�͎��Ƃ��Ĉ��肳�����B�`������ȍ~�A�ԏ����͋��ɁE��F�E�R���ȂǂƋ��Ɏ����ʓ����C����u�l�E�v�̉ƕ��Ƃ݂Ȃ����悤�ɂȂ�B����A�����̑��ɂ��l�X�ȏ��������݊��������悤�ɂȂ��Ă����B�Ⴆ�A���S�̎q�E�����̌n���ł����͓��ƁA���S�̎q�E�`�S�̌n���ł���L�n�ƁA�����Ē�͂̌n���ł���t�������Ȃǂ���������B�@ ���ċ`���̌���p�������S�́A�C���̍r�������葫��������l�㏫�R�E�`���Ɛ܂荇������肭�s���Ȃ������B���̈���A��q�̏����������\�͂������ďd���A���ł��t�������̎��傪�ߎ��O�Ƃ��ċ`���̒������Ă����̂ł���B���̂��߁A���S�͂����`�����甗�Q���A�ꎞ�I�ɂ͖{���ł���d���������グ��ꂽ���Ƃ��������̂ł���B��Z�㏫�R�E�`���̎���ɂȂ�ƁA����2�N(1429)�u�ԏ����q�v���ċ�����ȂǓ����͖��S�Ə��R�Ƃ̊W�͗ǍD�ł������B�������`�������R���͂̊m���̂��߂ɗL�͎҂��������A�X�ɐԏ��呺���`���ɒ�������悤�ɂȂ�Ɨ��҂̊Ԃɋْ�������B�Ëg���N(1441)6��24�����S�͋`�������@�ɏ����ĈÎE�B�Ëg�̗��ł���B���S�͓����A���R����肻�̏�œ����������ł��������A���h�������t���N���Ǔ��̕������������Ȃ��������ߔ��q�������A�����ł̌�������ӁB����Ƃ��ċ��쒩�n�̏��q�{��i�����悤�Ƃ������ʂ������A���~�̎q���ł���`���𗧂Ăċ��������B����ɑ��Ė��{�͋`���̎q�E�`������p�҂ɒ�߂ĎR�����L��叫�Ƃ��ČR�������������A���S��͒�R������̂̐��ɔs��ē����B�������Đԏ��������͈�U�ŖS�����B�@ ���̌�A�Ëg3�N(1443)�쒩�c�}���䏊�ɗ������ĎO��̐_���D���A���{�R������������̂̐_���͒D����Ƃ����������N�������B����ɑ��A�攪�㏫�R�E�`���̎���ɐԏ����c�}����ƍċ��������ɐ_���D��ɓ�����A���\2�N(1458)����𐬌�������B�������āA�ԏ���������藧�Ă��ĉ��ꔼ�����������ꉞ�̐ԏ����ċ����Ȃ����B����ɑ��A�ԏ������Ő��͂��g�債���R�����������B�����͎R���@�S�̓G��E�א쏟���Ɛڋ߂��A���m���N(1467)�ɖu���������m�̗��ł͍א���ɂ��Đ�����B���̒��Ŕd���E���O�E����肷��Ƌ��ɋ`�����玘���ʓ��ɔC�����A�ԏ����̉h�������߂����ɐ������Ă���̂ł���B�@ �������A���m�̗��ȍ~�́A���������̎��͂����Ă������Ƃ������Ď��̊e���ł̌��Ђ��ቺ�B�ݒn�����B�����͂Ő��͂�L���悤�ɂȂ��Ă����B�ԏ������ꑰ�����̑����������ė͂������A�Y�㎁��F�쑽���ɂ�����đ�����悤�ɂȂ����B16���I�̑S������ɂ������Đԏ����͐M���E�G�g�ɐb�]���Ė�����ۂ��A�փ����̐킢�ʼnF�쑽�G�Ƃɏ]���Đ��R�ɂ������ߏ��̂�v������A���̉Ɩ��͗��j����p���������̂ł���B�@ ���@ �ԏ����́A���̏o���ɂ����ē�؎��Ƌ��ʓ_�������B�ǂ���������͒Ⴂ�ƕ��Ȃ�������Ɣ��B�ɂ��䓪�����V�������ł���A�]���̐������͂���́u���}�v�ƌĂꂽ�B�܂��A�����E�U�������p������p���ǐ�ł̊���Ȃǂ����ʂ��Ă���B�]���̉��l�ςł͎��܂肫��Ȃ��ʂ��������ϊv�����ے����鑶�݂ł������B���ꂪ�A�Е��͓쒩�ɏ}���Ĉ�u�̌�䊂�����̖̂v�����A��������͌�����������đ������̗L�͎҂Ƃ��ĉh�������ށB�����͌��펩�g����M�C�����������ł��Ă���ꂽ���߁A���̉��ɕĐg��łڂ����B�~�S�́A��ǐe���̗ߎ|�ŋ��������̂��Ђ��Č��킩��������A����ɔ������đ������ɂ������Ɏ������B���҂̉^�����������̂́A����ɗD�����ꂽ���ۂ��݂̂ł���A������������ꂽ���������c�����̂ł���B�Ȃ�Ƃ������ʗ��j�̔���ł��낤�B�@ �Ɩ�̊�@�ɓ������Ă͏��R���ÎE���A���ׂ�����@���͂�ōċ����ʂ����ӂ�́A�c��̎��͎�`�⋭���������������Ɏc���Ă����Ƃ������Ƃł��낤���B�������Ȃ���A�S�N�߂����Ƃ��Ē��������̌��͂Ɉˑ����đ��݂������́A�����Ƃ��Ă̌��n����痂�������߂���������Ȃ��B���ꂪ�ŏI�I�ɂ͐퍑���ɂ�����v���E�ŖS���������̂ł��낤�B �@ |
|
 �@ �@����ؐ��V (1330-1386-?) |
|
|
�u�앗���킸�v�ƌ���ꈳ�|�I�ɒu���ꂽ�쒩�B��k�������̒�����ɁA���̓쒩���R���I�ɒ����Ŏx�����̂���ؐ����̎O�j�ł��鐳�V(�܂��̂�)�ł���B�ނ̋ꓬ�ɖ��������U���T�ς���ƂƂ��ɁA��k�����㔼�ɂ�����쒩�ɂ��Ă����Ă��������Ǝv���B�@ ������w�i�@ 11���I�����A���{�͎��������I�ɐ��͂�L�������ЁE�M����e�n�̒n���������A�����Č`���I�ɒ������{(����)���`���Ƃ�n�߂�B������12���I���ɓ����̑吨�͂ɂ�����(��������)���o�ē����ɐ���(���q���{)���������Ĉȍ~�A���{�E���삪�x�z�����d�����̑̐��ƂȂ�A���v�̗��ȍ~�͕��͂ŏ��開�{������ɑ��傫���D�ʂɗ��B�@ �X��13���I�㔼�ɂȂ�ƁA�������_�@�ɖ��{�͍��h�̂��ߓ��݂̂Ȃ炸�S���ɍL�͂ŋ��͂Ȏx�z���y�ڂ��悤�ɂȂ�B���̍��A�̒n���ɂ�葊�����Ă����n�����������̊Ԃŗ̒n�̍ו�����{�ƥ���q�̕���X�����ꑰ�����̉Ύ�ɂȂ肩�˂Ȃ������B�܂���̉ݕ��o�ς̔��W�ɔ����x�o�̑���������������ꂵ�߂Ă���A������ނ�̔�҂��開�{�ւ̕s�����点�Ă����B����ɁA�E���␣�˓��C�𒆐S�ɏ��ƁE�^���ƁE�|�\�ƂƂ����_�k�������͂�����A���̎Љ�I���݊��͕���Ȃ����̂ƂȂ��Ă����̂ł���B�ނ�́A�ݕ��o�ς̔��W��w�i�ɋE�����ӂ̔_���ɂ������݁A���{�̕��͂������������݂ƂȂ�������B���{�����Ă����k�������ނ����荞�ނ��ƂŎ��������̌��͂��������悤�Ƃ��邪�A�\���Ȏx���������Ȃ����肩�����̍�����������̔������錋�ʂƂȂ����B�X�ɒ���ł͎x�z�͂���߂��݂̂łȂ��c���������@�����o�����ɕ���A����ɍ��킹�ċM���B���������{�̒���s���ł������B�������k����������ǂƂ��铖���̖��{�͂����������ԂɗL���ȑΉ����ł����ɂ����̂ł���B�@ ������������14���I�O���ɑ�o�������瑦�ʂ�������V�c�͐e�����s���A��_�Ɩ���v�������𖡕��ɂ��Ă̊��q���{�̑œ|��ژ_�ނ悤�ɂȂ�B�c�ʌp���Ɋ����開�{��|���T���ł���Ȃ̌����ɍc�ʂ��p�����邽�߂ł���A����ɑS���x�z����Ɏ�߂����߂ł������B���O���N(1331)����͋������������{�̑�R�ɂ��s�k�A�����@���̌����V�c�ɏ��ʂ������B��ɗ����ꂽ�B�������A����̗U���ɉ����ĉ͓��ŋ���������ؐ��������O3�N(1333)���{�R���㕽��e�n�Ŗ|�M���A�����R�̐瑁��ɘU�薋�{�̑�R����ɕ����B������Ċe�n�Ŗ��{�ɕs����������͂��I�N��������B��E�o�A������������Ŗ��{���̗L�͎҂ł��鑫������(����)��������ɐQ�Ԃ苞�̖��{���_�E�Z�g���T����U���B���������Ċ֓��̍����E�V�c�`�傪���q��łڂ�����V�c�ɂ��S�����������������B�@ ����V�c�͏��H�Ƃ�ʂ��đ䓪�����_�Ɩ��𖡕��ɂ��邱�ƂŒ����W���I�Ȑꐧ�̐����u���������A�}���ŋ����ȉ��v�͍����Ɣ����������A����ⓖ���̔�_�Ɩ��͂����}������ɂ͗]��ɗ͕s���ł������B���������̊��҂͔ނ�̒��ōő�̖���ł��鑫�������ɏW�܂�B�����͊֓��ł̔������������������ɒ���ɔ�����|���B�V�c�`��E��ؐ����E�k�����Ƃ璩����͂���ɒ�R���Ĉ�i��ނ̍U�h���J��L���邪�A���썇��Ő������������ɂ���Ȃnj���I�Ȕs�k���i����B�����͎����@���E�����V�c��i�����R����(�k��)��ŋ��Ɏ���̐���(�������{)���������A����Ō���V�c�͋g��ɓ��ꎩ�炪�����̒���ł���Ǝ咣(�쒩)�B�����ɓ�k���̓������n�܂�B�@ �쒩�͏C�����ȂǏ@�����͂␅�R�E�V����������͂Ƃ����e�n�ɖ������͂̕}�A��}��ƂƂ��ɋ��D��ɑS�͂𒍂����A���ɑS���I�ȐM�]�������Ă��舳�|�I�Ō���͎��ӂ̂����ɕ���B�@ ����A�����͒�E���`�ƂƂ��ɐ����̊m����ڎw���A���H�ƒ��S�̐V�����͂���荞�݂��_�Ƃ���b�ɂ��������̍��������ɂ��z�����������^�c�Ŏ���Ɋ�Պm���𐬂���������悤�Ɍ����Ă����B�@ �����V�o��܂Ł@ ��؎��͑�㕽��A���ɉ͓��𒆐S�ɐ��͂������͐��ʂȂǂ̉^�A�␅���Ǘ��A���Ɨ��ʂ�S���Ď��͂��������������̐V�������ł������ƍl�����Ă���B���V�̕��E�����͌��킪���������ۂɐԍ��Ōĉ����A�X�Ɏl�V�����ȂǂŖ��{�R��|�M������ɐ瑁��Ŗ��{�̑�R��ɏ����̕��Ō݊p�ɐ���Ė��{�̈АM�ቺ�������A�s�����q�̖I�N��U���������Ƃ͏�q�����Ƃ���ł���B���̌��т��F�߂��Č��퐭���ł͘a��E�͓��E�ےÂ̌��v��F�߂��h���ɂ߂����A���������������ۂɂ���Ɛ���ĕ��킷������썇��ő����̑�Q��ɕ������������Ă���B�@ ���̌�͐����̒��j�E���s�𒆐S�Ƃ��ċE���ɂ�����쒩�̎�͂Ƃ��ċ@�\���A�g��̖h�q��S���B�����Đ���2�N(1347)�쒩�̏d�b�E�k���e�[�ɂ��헪�w���̉��ő�㕽��𒆐S�ɐ���ɌR���I�������J�n���A�����Α������̌R�������j���Ă���B���V�́u�����L�v�L�q����N����t�Z����ƌ���2�N(1330)���܂�ł���Ǝv���邪�A���̎����ɂ͊��ɌZ�B�̕⍲�ɉ���Ă����\���������B�@ ������̑D�o�@ �������s��Ɏ��Ԃ��d���������������͎����E���t���ɑ�R��^���Ă���ɑΏ�������B����3�N(1348)1���l���œ�،R�͂��̑�Q�Ƒ������퓬�ɓ˓��B���|�I��R�̑O�ɐ��s�E����(�����̎��j)�͏O�ǓG�����펀���A����œ쒩�̋E���ɂ������͉͂�ŁA�ȍ~�͎�̓I�ȌR���������s���邾���̎��͂��������ƂɂȂ�B����ɂ͋��d�Ȍ���ɂ��̑ŊJ��]�e�[�̍\�z���w�i�ɂ���A���ꂪ�����Ƙ������Ă������ʁA�j�]�����̂ł���B�@ ���ČZ��l���펀�������ƂŎ����I�ɐ��V����؎��̓���ƂȂ�A���̓�ǂɑΏ����邱�ƂƂȂ�B�t����͐����ɏ���ē쒩�{���܂ōU�ߊĂ���A����ɑ���R���I�Ή��𔗂�ꂽ�̂ł���B�t���ɂ���ċg��̌䏊�͏Ă������A�㑺���͉ꖼ���܂œ���邱�ƂƂȂ����B����ʼn͓��ɂ�1��14���ɓ����֍��t�ׂ��U�ߊĂ���A���V�͂���ɑ��n�`�𗘗p���Ėh�䂵�ė��N��7���܂��ɂݍ����B�܂���̌R���͑�㕽��̊e�n�œ]�킵�A����3�N5���ΐ�͌��ō��t�`������Ă���B�������čŏ��̊�@���ǂ��ɂ��������̂ł���B�@ �܂��A�s��ɔ����������͂̓��l���傫�Ȗ��ł������B�e�[����㕽��̍����E�a�c�����ɎO�͊��J���������̒n���E��^������ϐS���ɔ���������������i�����̂Ɠ������ɁA���V���������Ȃǎ��ӂ̎��@�ɏ��̈��g���s���Ă���B���V�͂��̎����ɍ��q��тɔC�����Ă���A��؎�����Ƃ��Đ��s����Ɉ��������ĉ͓��E�a��̎��ɑ������錠����L���Ă����悤���B��q�̏��̈��g������ɂ̂��Ƃ��čs��ꂽ�̂ł���B�@ ���ω��̏�@ ���̌���A���V�͋E���쒩�R�̎�͂Ƃ��đ�㕽��𒆐S�ɓ]�킵���B����3�N�ɑ��������A���`�̗{�q�E�������~���I�ɂɔh������̂��������������ւ̑Ή��ł���B�@ ���āA�ꌩ����ƈꖇ��Ɍ����Ă������������ł��邪�A�����̐�����S�����`�Ɛ펞�̐����������̎����E���t���̊ԂőΗ������݉����n�߂Ă����B�����h�E�ێ�I�ȑ卋���E�����E�y�̂����`�ɂ��X�����������̂ɑ��āA���f�h�E�V�������E�E���␣�˓��E���q���t���ƌ��т��Ă��̑Η������[���ɂ��Ă����B���Ėk����a5�N(�쒩����4�N�A1349)�[6���ɒ��`�͑����ɗv�����Ďt�������������ƁB����Ŏt�������N8���ɃN�[�f�^�[���N�����Ē��`�����ނ������̑��߂��Ǖ��A����ɑ����̒��j�E�`�F���������B�@ ����5�N10�������s���Ƃ������`�͋���E�o���đ�a�ɓ���A11���ɓ쒩�ƌ���ŋ����B12��9�����`���̓���R���ߍ]��{���狞�ɐN�����Ă��邪�A����ɓ�؎��̈ꑰ�ł���a�c����������Ă���B����ɒ��`�������ɐi�o���ċ����͂����ۂɂ́A���V�������،R������ɎQ�����Ă���悤���B���̒��`�̐����ɁA�����E�t���͑R�����ꂸ����6�N(1351)2���ɍ~�����t���͎E�Q���ꂽ�B�������Ē��`�D�ʂ̑̐����������ꂽ�̂ł���B�@ ���̌�����`�Ɠ쒩�̊ԂŘa�������̌��͌p������Ă������A���`�������𑫗����ɑ�\�����L�͍����ɔC����悤���߂��̂ɑ��ē쒩�͒���ɂ�铝�ꐭ�������d�Ɏ咣���A���ǂ͕��ʂ�ɏI������B���̍ہA���ɓ����������V�Ɛb�͒��`�Ɂu���̏�͓�������̑叫�����������Ă���������A�䂪��͌�ē�������ł��傤�v�ƌ��������Ƃ����B�쒩�ŋ��d�_���������̂͋��炭�e�[�ł��낤���A���������ӌ������Ŏ�����n�m����Ɏ��������V�ɂƂ��Ă͑ς����蛂Ȃ��̂Ɖf�����Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B��������V�͑������Ƃ̘a�����ɂ����Ċ���̂ł��邪�A�쒩�̊炪���`�ł̘a���Ƌ��d�h�ւ̕s�M�������炭���V�̐S�����߂邱�ƂƂȂ����ł��낤�B�@ �������ꓝ�@ ���đ������������ł́A���x�͑��������`�哱�̐��ɕs��������Ă����B����6�N(1351)8���������쒩�ɍ~����\���o�āA10���ɂ��ꂪ�������B������u�����ꓝ�v�ƌĂԁB����������đ����͒��`�����q�܂Œnj����Ėłڂ��Ɏ������̂ł��邪�A�������ɑS���̓쒩���͐����Â��B���̋@��𗘗p���ċ��E���q��D�悤�Ɛe�[�͖ژ_��ł����̂ł���B�@ ����7�N(1352)2��26���㑺��V�c�͉ꖼ�����o�āA�Z�g�E�l�V�������o�ĉ[2��19�������Ɏ������B����A��������͖k�����\���A�O�g����͐�팰�o�R�����ɐڋ߁B���V����㕽�삩�狞�Ɍ������Ă���B����ɑ��ċ��̋`�F�͕s���Ɏv���쒩���ƌ����d�˂邪����ȏ�̗L���Ȏ��łĂ��ɂ����B�����ĉ[2��29���A�����̌R������Ăɗ����ɐN���B�k���R�͓�������A�瑐�R�͐���������A�����Đ��V��͌j�삩��U�����J�n�����B���ɉ�����������́A�א쌰�����h�킷�邪��ؐ��͂�����͂��Č��j�B����ɍא엊�t����R���邪�A��ؐ��̕��������𗘗p���ĉƉ��̉����ɏ�肻���������J�̂悤�Ɏˊ|����̂ŋ߂Â��Ȃ��B�����֓�،R�̋R�����˓����čא쐨�������A���t������Ă���B�@ �������ē쒩�͋��D��ɐ��������B�쒩���͖k���̐_������������ƂƂ��Ɍ����@�E�����@�E�����V�c��߂��ċg��ɑ���k���������s�����B�X�ɓG����҂���͌��v�D�������A���]����҂ɂ͋����̌��v��ۏB���̎��ɐ��V����R��_�l�ɉ`�Ӗ����������������������F�߂镶���s���Ă���B�������Ĉꎞ�I�ɂł͂��邪�쒩����������ł��錻�ۂ��o�������̂ł���B���̎�����Ɂu�����ꓝ�v�ƌĂԂ̂͂��̂��߂ł���B�@ �������̍U�h�@ ���ċ`�F�͋ߍ]�ɓ���ČR�����ĕ҂��A3���ɓ���Ɣ��U�̐��ɓ���B��R�𗦂��ċ`�F���Ăы��ɓ���ƁA�����̖k�����͏�s���ƌ��ēP�ނ������o�Ĕ����̖{�R�ƍ��������B�����R�͔����̕�͂ɂ�����A������}�����ׂ����V�͍����Ȃɕz�w���u���╶�v�ɂ��Ζk�����\�͑�n�ɌR����W�J���Ă���B���đ����R�͎R�肩��m�؋`�����A�F������א쌰���������U�����J�n�B���V�͂���ɑ��č����@���čא�R���ɂݍ����A�����Ζ�P�������ē��h��U�����B�����̎���͌��łŗe�Ղɂ͊ח����Ȃ������ł��������A�����R�͑�R�ɕ������킹�ĕ��ƍU�߂��s���B����ɑ��ē�،R�͓������ɐi�o���ĉ͓��ƘA��������̐���z���Ƌ��ɐ_����ʂɂ��ɂ݂𗘂������̂ł���B�����Đ��V�͂���ɉ����ċ��_�͓̉��ʼn��R��Ґ����悤�Ɛ}�������A���n�����Ƃ̑���������ʂ����Ȃ������̂ł���B�@ �������Ă���Ԃɔ����̓쒩�R�͕��Ƃ��s�����n�߂��B5��10���ɂȂ�Ɠ��쑑�i���������ɍ~���A������_�@�ɓ쒩�͘U���f�O���ēP�ސ�ɓ������B�����R�͒����ɒnj����A��،R�͓쒩��͂Ƃ��Ă���������ɖh���ł���������̒��Ŏl�𗲎����������ɂ��Ă���B�㑺��V�c���g���Z��g�ɂ��n�ɏ���Đh�����������т�L�l�ł���A�������̋]�����o�����͖̂������Ȃ����Ƃł������B�������Ɋ֓��ŋ��������쒩�R�����l�ɔs�ނ��Ă���A�e�[�哱�ɂ�銣���ꝱ�̔��U���͎��s�ɏI������B���O�̐�͂��s�����Ă���ȏ�A�����̂���v��ł���K�R�̌��ʂƂ�������B�������ē쒩�͍Ăыg��R���ŕN�ǂ���̂�]�V�Ȃ����ꂽ�̂ł���B�@ ����E��O�����U�h��@ �����ꓝ���j�]���ċ��������������A���V�͑����R�Ƃ̏����荇���𑱂��Ă����B����7�N10���ɐԏ����͂�Γ����[�E�g�ǖ���Ƌ��ɔj���Ă���̂͂��̈��ł���B�@ ���āA�쒩�ɂƂ��čēx�̍D�@�͈ӊO�ɑ����K�ꂽ�B�����������ł̓����͂܂����܂��Ă��Ȃ������̂ł���B���X�ؓ��_�ƎR���������o�_���E�������đΗ����A�������쒩�ɍ~���B������Đ���8�N(1353)1�����V�͍��X�؏G�j��j���Đi�����A�ɐ��̖k�����\���ޗǂɐi�o�����B������5���ɓ���Ɠ�،R�͓V�������o�Ĕ����ɕz�w���A6���ɓ���ƎR���R���R�A�����̕��𗦂��ď㗌�A�ޗǂ���͎l�𗲏r���h�������B�@ ����ɑ��ċ`�F�͎O��̌R�����W�߂Ď��P�J�ŕz�w���Č}�����B6��9����E�g�ǁE�Γ��̎O��͓�̔������狞�ɐN�����A�R���R�ܐ�͐m�a���E����������i�����ė��R�͎l���ō��������P�J�̑����R�ɍU�߂��������B�܂���،R�Ƒ������̘Z�p��������Ԃɓ����đ��݂ɖ���ˊ|�������A�@�����ĎR���R���Z�p����˔j�B�����ĎR���t�����y���A��E�Γ������א쐴�������j�����B��������ĕs����������`�F�͋����̂Ăċߍ]��{�֓���A�X�ɉb�R�̓��������炩�łȂ��̂�s�������Ĕ��Z�ɓP�ނ��Ă���B�@ �������ē쒩�͎R���R�Ƌ��͂��邱�ƂōĂы����蒆�ɂ������A�哱�����߂���R���ƕs���a�����₦�Ȃ������B�X�ɋ`�F�����Z�ōĂё̐��𗧂Ē����Ĕ��U�ɏo��C�z�ł��������߁A�����ɋ������������Ȃ������B�@ ����9�N(1354)4���쒩�̎w���I�n�ʂɂ����k���e�[���v�����B�ȍ~�A�쒩�̌R���͐��V�̑o���ɂ����邱�ƂɂȂ�B���������Ă̎m�C�ቺ��J�����A���N10���㑺��͉ꖼ������������ɍs�{���ړ]�����O�i�ւ̈ӎu���������B�������͓쒩�̍ő呑���ł��锪���@�̂̈ꕔ�ł���Ƌ��ɁA�a�c���̋��_�ł�����쒩�ɂƂ��Ă͌R���I�E�o�ϓI�ɏd�v�n�_�������̂ł���B���_�A��؎��̐��͌��ł��������B�X�ɓ쒩�͖����̎m�C��������ׂ��U�����Ƃ�B�R�����������`�̗{�q�E�������~��i�����čĂѓ쒩�ɋ߂Â��Ă���A���~�ƌ���ōĂы����M�����Ƃ����̂ł���B���N9�����~�͓쒩���瑍�Ǖߎg�ɔC������A���Ƃ̓����Ƃ��č��̎w�������邱�ƂƂȂ����B�@ 12���ɓ���ƁA���~�E�R�������͎���̕��ŒA�n���o�āA�����ċ����`�h�̓��䒼��E�z�g���o�͎O��̌R���𗦂��Ėk�����狞���������B��������������͋�����肫��Ȃ��Ɣ��f���ߍ]�֓����B����10�N(1355)1��16�����䐨�����ɓ���A26�����V���l�𗲏r�E�g�ǖ���E�Γ����[�Ƌ��ɎO��̕��Ŕ����ɓ��������B�������ē쒩�͎O�x�ڂ̋��D����ʂ������B2��6���R���R�Ɠ�،R�͎O���̎R��ɕz�w����`�F�R�Ɋ�P��������B�O�q�̍א엊�V��������͑�������}�P���Ēב��A�E�҂ȎR�����ƎR�x��ɒ�������ؐ��͐����ɏ���ċ`�F�{�w���������B���������X�ؓ��_�E�ԏ����S�̎萨���J�̂悤�ɖ���ˊ|���ĕ��킵���̊Ԃɑ��̌R�������R�ɋ삯�������߁A�쒩���͐ɂ������s�k�����B�X�ɑ��������瓌�R�ɐi�o���ĕ��ƍU�߂̑̐�����蓍��E�z�g�R�ƌ�����J��L���Ă���B������͋����͂��ĕ��ƍU�߂̑̐����Ƃ������ߒ��~�E���V���3���ɂ�ނȂ��P�ށB�@ ���̐��N�ŎO�x�ɂ킽�苞�D��ɐ����������A��������Z���ԂœP�ނ�]�V�Ȃ�����Ă���B�����A���͖h�q��Ɍ����Ă��炸��蔲�����Ƃ͓���B�헪�Ƃ��ċ��ɍS�鎖���̂ɖ���������ƌ����悤�B�܂��A��x�ځE�O�x�ڂɂ��Ă����Ύ哱���������Ă����͎̂R�����ł��蒼�~�ł����āA�쒩�R�͖O���܂ŕt���I�Ȃ��̂ł������B�쒩�͑��������̕s�����q�ɑ�`������^���ď�ɕt�����邱�Ƃ͂ł��Ă����͂őŊJ����͍͂ő��Ȃ������̂ł���B�O���Ő킢���������V�͂����Ɋ����邱�ƂƂȂ����B���V�́u�����L�v�ł����u�S����������ҁv�u�e�ɑւ�A�Z�ɐ��܂ŗ���v�u�}�ɓG�ɓ���@�����v�Ɣᔻ����Ă��邪�A����������������Ă�����Ő��ł͌���I�s�k�������T�d�E�琨�I�Ȑ킢��������Ƌ��ɘa����Nj�����悤�ɂȂ����̂ł��낤�B�@ ���`�F�̓쒩��U���@ ����13�N(1358)4��30�������������v���`�F�������������㏫�R�ƂȂ����B������14�N(1359)11���`�F�͎���̌��Ђ��m�����邽�߂ɑ�R��Ґ����ē쒩�ɑ�K�͂ȍU������}����B�֓�����͔��R�����������̑�R�𗦂��Ă���ɎQ���B���̒m�点�͓쒩�̌N�b�ɓ��h��^�������A���V�͗�̋g���E���j�Ȓn�`�E�G�̕s�a�����������ɏo���V�̎��E�n�̗��E�l�̘a���S�Ė����ɗL���ł���K�������ł���Əq�ׂČ㑺������S�������B���̏�Ō���̊ϐS���ɍs�{���ڂ��I�ɗ���̍ԂƋ����R��h�q���Ƃ�����j�𗧂Ă�B�X�ɋI�m��ɂ͖앚��z�u���A���E�����E����ɂ���ǂ�ݒu���Ėh��͂����߂���ł����̂ł���B�@ �����͒n�̗������đ����̑�R��|�M���Ă������A����ɕ��͂̍�������Ȃ��Ȃ��Ă����B����͐m�؋`���ɗ��Ƃ���A������א쐴���E�ԏ��̌R�ɂ���Ċח��B�X�ɕ��Ώ����������ؐ��͐ԍ�E�瑁�𗊂݂Ƃ��Ă��ď���]�V�Ȃ�����������B�a�c�����͂��̏��ŊJ���悤�Ə����̕��ő������ɖ�P�������邪�A�吨��ς���ɂ͎���Ȃ��B���݂Ɂu�����L�v�ɂ����̍ہA�G�����������ÎE���悤�Ƃ��̈�c�ɕ��ꍞ��ł����̂ł��邪�A�����t�������Ȃ蔭���ē���̒x�ꂽ�҂Ƃ����u�����苏����v�ɂ��I�����Ď��s�ɏI������ƌ����B���V�͐瑁��œG�������t��������Ɏ�������ŏ�̕ω���҂ق��Ȃ������B�@ ����ɉ����Č�ǂ̍c�q�E���ǐe�����쒩�ɔ�����|�����̂����������ł���A�쒩�̖��^�����Ƌ͂��Ǝv��ꂽ�B�������A����15�N(1360)5�������Ɛm�؋`�����Η����ċ`���������B�������͓쒩�����ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ�}篌R���������グ��B�`���͔s��Ĉɐ��ɖ߂��ē쒩�ɍ~��A�������l�]�������Ď��r�����B�쒩�͊�@��E����Ƌ��ɍĂэU���̏����ɓ������̂ł���B�@ ���Ō�̋��U���@ ����16�N(1361)���������ł͍Ăѓ������N�����Ă����B�����E�א쐴����������U����č��X�ؓ��_��L�͎҂̔������A�d���̋^����������ꂽ�̂ł���B������9���ɓ쒩�ɍ~��A���U����i���B����ɂ��Đ��V���ӌ������߂�ꂽ���A���𗎂Ƃ������Ȃ玩�g�݂̂ł��\�ł��邪��邱�Ƃ͐����̗͂������Ă�����Əq�ׂĔ����Ă���B���������ǁA�u��邾���ł��䏊�ʼn߂����A��͂��̖�̖����Âт����v�Ƃ����㑺���M�������̋�����]�ɂ�苞�U�������肵���B����܂ł͓쒩�̌R��������苒�������Ƃ͂����Ă��A�㑺�㎩�g�������������͂Ȃ������̂ł���B�V�c�Ƃ��đ��ʂ��Ă��Ȃ���s��ǂ���N���������A��͎���ɕs���ƂȂ�쒩�ɂ�铝��̖]�݂����Ȃ��Ȃ��Ă���ȏ�A���ɓ����@�������v�肽���Ȃ�͖̂�������ʂƂ���ł�������������Ȃ��B�@ ����12�������E���V��͏Z�g�E�V�������o�Đ���̕��ŋ��i���B�X�ɐԏ��͎����ےÂ���R��i��ł����B������ċ`�F�͍��X�؍��G�ܕS��ےÈ�ɁA���엹�r�̎��S���R��ɁA�g�ǖ���E�F�s�{���n�ɔh�����Ėh�q�̐���z�����B�������א�E��،R�̐����ɉ�����Ă����̌R���͐�킸���ēP�ނ��A�`�F�͕s��������ċ����̂Ăċߍ]�ɓ��ꂽ�B12��8���쒩���͎l�x�ڂ̋��D����ʂ������B�@ ���̎��A���X�ؓ��_�͑ދ�����ɓ�����@������藧�ĂĂ���B�܂����������|���A�Z�Ԃ̋q�a�ɖ�t�̑�����ׂĒ����Ɨ��e�Ɋ|���E�ԕr�E���F�E�����E�~�𐮂����B�X�ɏ��@�ɂ͉�㺔V�M�̑����̘�E�ؖ��̊|�����A�Q���ɂ͒����̖��E�j�q�n�̖�������A�����ď\��Ԃ̖�x���ɂ͒��E�e�E賁E�����̓���3�{�̞��Ɍ�������3�̑哛�Ɏ������A���̏�Ɏ��@�m��l�𗯂ߒu���Ă��ĂȂ��l������O��U��ł������B���_�̉��~��苒�����̂͐��V�ł��������A�����m���Ċ��Q�����_�Ɏ��������������Ă������悤���߂��̂�����Ŏ���̏h���Ƃ��Ă���B�@ ���ċ����̂������̂̑S���ɂ�����쒩���͐U���ʏ�Ԃł������B�B���B�݂̂��e�r���ɂ�藲�����ւ��Ă������A�����~���ł��鋗���ł͂Ȃ��B�₪�ċ`�F�͌R�����ĕ҂��A���X�E�ԏ��𒆐S�Ƃ��ċ�����������̐����Ƃ�n�߂�����12��26���쒩�͍ĂѓP�ށB���̍ہA���V�͍��X�ؓ@��O�ȏ�ɏ��藧�Ă���ŕԗ�Ƃ��ĊZ�E������u���ė����������B�u�����L�v�͌ÒK���x����ĊZ�E���������ꂽ�Ə����̂ɂ��Ă��邪�A�����m��ʐ헐�Ő��ȐU�镑�����������G�ɐ��ŕԂ������C���ǂ���b�ł���ƌ����悤�B�@ ���̌�A�����͎l���ɓn�苒�_��z�����Ƃ��邪�א엊�V�ɔs��ē��������B����17�N(1362)���V���a�c�����Ƌ��ɔ��U�����݁A�ےÓn�Ӌ��ō��X�،R�Ɛ���Ă���B���̎��A���X�،R����������ēn�͂�h�����Ƃ���̂ɑ��A���V��͖앚����ꂽ����̌R���𗦂��Ė����ɏ㗬�œn�͂��č��X�،R�̔w��ɉ���ċ}�P�������Ĕj��A�����ĕ��ɂɐi�o���Đԏ��R�ƑΛ����Ă��邪�ꎞ�I�Ȑ��ʂɏI������B����ȍ~�A�쒩������D��@��͖K��邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B�@ ���쒩�ɂ����鐭���@�\�@ ���V���R���I��͂Ƃ��Ċ������������̓쒩�ɂ������E�����@�\�ɂ��Č���B�@ ���V���Z�B�̐펀�ɔ����ĉƓ��p�����O�ɂ����āA���ɓ쒩�͊e�n�Ŋ��F�������x�z�̈�����Ȃ����ꂽ���̂ƂȂ��Ă����B����������4�N(1343)�ɂ͖k�����͈ɐ��ʊۏ�����ׂ��đ��C��ɓP�ށA�X�Ɉɉ�ɂ����閡�����͂��k�����Ă����B�܂����B�ł�����2�N(1347)�k�����M����R�E�F�Õ�ȂNj��_�ƂȂ��������ĕN�ǂ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�O�q�̊ω��̏�ɏ悶�Ĉꎞ�͉F�Õ���D�Ă��邪����8�N(1353)�ɂ͑������Ăї��Ƃ���Ĉȍ~�͌��M�̊����������Ȃ��Ȃ�B���������ɂ����āA�쒩�̎x�z�̈�͋ɂ߂Č���ꂽ���̂ƂȂ蒆�ł���a�E�I�ɁE�͓��E�a��ɏd�_���u�����悤�ɂȂ�B�����������������ł��A�Ȃ���Ȃ�ɂ��V������鐨�͂Ƃ��āA�����Ƃ��Ă̌`�����������Ă����悤�ł���B�@ �܂��o�ϊ�Ղł��邪�A�x�z���̑����Ɂu���p���v�ƌĂ��x�o���ۂ���Ă����悤�ł���B���́u���p���v�́A�쒩�ɑ����鎛�З̂��u�ꎞ�I�Ɂv�����グ�Ă������璩��̎�����ƌ������̂ŁA�����N�Ԃ���Ŗ����̌����N��(1380�N��㔼����1392)�Ɏ���܂ł��Ȃ킿�쒩������S�̂ɂ����ĔF�߂��Ă���B�ł������헐�̒��ŁA���n�ɂ����ČR��B����K�v���炱���������x�����܂�Ă������̂ł��낤�B���V���͓��E�a��̎��ЂɁu���p���v�𖽂�����F���ȂNj��͂������ɖƏ������肷�镶�����c���Ă���B�����炭�͂��̒n��̎��Ƃ��Ē����Ɍg��������̂ł��낤�B�헐�ɂ����āu�ꎞ�I�Ɂv�s���Ƃ������ڂŎ����I�ɉi���������ł��낤���Ƃ��z���ɓ�Ȃ��B�����l����ƁA���́u���p���v�͑��������ɂ�����u���ρv(�����̔������R��Ƃ��Ď�삪��ɓ���邱�Ƃ��ł��鐧�x)�Ƌɂ߂ėގ��������i�����ƌ�����B�@ �����Ĉ�ʐ����̒��S���߂�y�n���������Ă����̂��A�u���ҏ��v�ł���B����V�c�̓��ꐭ�����ɂ͌䏊�x����S���Ƃ��ꂽ�u���ҏ��v�ł��邪�A���̎����͎l�𗲎���ɂ�菊�̈��s���s���쒩�̒��S�@�ւƂȂ��Ă����悤���B�����Ē��f���ɂ��쒩�̒��S�l�����Q�����Ă̕]�肪�s��ꂽ�B���݂Ɂu���f�v�Ƃ͓V�c�̈ӎu��������p���鎖���Ӗ����Ă���A�M�������̍��c���������S�Ƃ��Ă��������@���Ƃ͈قȂ��o�����̓`���ɂ̂��Ƃ������̂ƌ�����B���q���{�Ō������c���d��]��O�E���t�O�Ƃ������͓��@(�k�����y��)�ՐȂ̊ɋ߂����i�̍ō��ӎv����@�ւł������Ƃ����邩������Ȃ��B�@ ���Ă��̌��c�����s����̂����n�̍��i�E���ł������B�͓��E�a��ɂ����Ắu�{���R�v���d�|���m�F���钲���̂��ߍݒ����l(���{�ɋΖ����銯��)���w�����Ă���A���V���d�|�̓��e�����s�Ɉڂ��悤�����Ă���B����́u�{���R�v�����i�Ƃ��āA���V�����Ƃ��Ă��̐E�����ʂ������ƍl���Ă悢�ł��낤�B���݂ɐ���10�N(1355)�����琳�V�͉͓���ɔC�����Ă���A���E���i�����C�����ƌ��Ă悢�B�@ �����Ē����̊��E�́A�]���̒���ɏ�����ƍl���Ă悢�ł��낤�B�u�V�t�a�̏W�v����f����쒩�{��̍\�����́A�ۊ։ƂɎn�܂�k���E���C�����������Ȃǒ����M���܂ňꉞ�̐l�ނ͑����Ă����l�ł��邩��{��̌`�������K�͂Ȃ���������邱�Ƃ͂ł����ƌ�����B�@ �@���I�ɂ��A������y���Ō䔪�u(�@�،o�̍u�b)���s���@�ӗ֎��ɓ쒩�c���̕揊���u���ꂽ�ق��A�l�V�������쒩�̎x�z���ɂ������B�X�ɊϐS���E�������E�Z�g�_�Ђ��ꎞ�͓쒩�s�{�Ƃ���Ă������Ƃ��l���ɓ����ƁA������x�̋K�͂Ŋ���̏@���V���͍s���Ă����ƌ����悤�B�����ēV�c�̐g�̂���p�I�Ɏ��쎝�m�����ρE�m�_�Ȃǖ����m���߂Ă����̂ł���B�@ �X�ɒ������{�Ƃ��Ă̈АM��ۂ��߂ɕ������Ƃ�����ɍs��ꂽ�B�����Ή̍����s���@�ǐe���ɂ��u�V�t�a�̏W�v�ɓZ�߂�ꂽ�̂͗L���ł��邪�A�L���̎���{�앶���̌������s��꒷�c�V�c�̌������ꌤ���u��鏴�v�ȂǂɌ������Ă���B�@ �ȏ�̂悤�ɁA�쒩�͏��K�͂Ȃ�����������{�Ƃ��Ă̌`��������A����Ƃ��Ă̓`���I�Ȍ`�����d�Ȃ���������I�Ȗʂł͑��������Ƃ����ʂ������i�𑽂��������ł������ƌ�����B�@ ���a�����@ ���̎����A�쒩�Ƒ������̊Ԃɂ����Θa���̘b�������オ���Ă���B�ŏ��͐���3�N(1348)�ɂ�����l���ł̔s�k����ł��邪�A�u������v�ɂ��Ύt���������a��厛���V(�u���厛��X���V���v�ɂ��ΐM��)�𒇉���Ă�����@��ɓ쒩�Ƃ̘a����i�߂悤�Ƃ����Ƃ����B���������̎��ɂ͌����]��i�������l�q���Ȃ��B�@ ���͐���5�N(1350)�ω��̏�ɂ����Ē��`���쒩�ƌ��ۂ̂��ƁB���`���t�����l����������쒩�Ƃ̘a������i�߁A�쒩���̑�\�𐳋V�����߂����Ƃ͑O�q�����B���̍ۂɂ͒��`���Ƃ���������ꂵ�����@���E��o���������ōc�ʂɂ����Ƃ��咣�����̂ɑ��A�쒩������n���ɂ��c�ʌp���⒩��ɂ�铝�ꐭ�����咣�����ʂ�ɏI����Ă���B�������͂��̌���A�쒩�a���ɋz�����ē���Ɏ������ގ�����{�����Ƃ��邱�ƂɂȂ�B�@ ���N�̐���6�N���������`�ƑR���邽�߂ɓ쒩�ɍ~���A�ꎞ�I�ɖk�����p����쒩������D�邱�ƂƂȂ����B��q�̐����ꓝ�ł���B�쒩�͖k���̓V�c��@��A�ꋎ��O��̐_�������������߁A����ȍ~�̖k���V�c�͂��̐�������ۏ��鑶�݂������Ă���Ƃ�����B��{�I�ɖk���̋M�������͑��������Ɠ쒩�Ƃ̘a���ɕs�����������Ƃ��������A���̎��̂悤�ɖk�������̂Ă���`�ɂȂ�̂�����邽�߂ł���B�@ ���̎��ɘa���̘b�������オ�����̂͐���15�N(1360)�u���NjL�v�ɂ��`�F���쒩�ɑ�K�͂ȍU�������������Řa�����Ăт����Ă����Ƃ����B���̌�̐���20�N(1365)�Ɏl�V���������㓏�����㑺���Ȃ̉��ōs��ꂽ�ہA����������n�����コ�ꂽ�Ɓu�t��L�v�͓`���Ă���A���̎����ɂ͑��������Ɠ쒩�͂�����x�̕��݊��������Ă����悤���B�㑺��������킢�œ쒩�ɂƂ��Ă̌�����������F�����A���X�ɘa���ւƌX���Ă����̂�������Ȃ��B�@ �����������Ő���21�N(1366)����22�N(1367)�ɂ����Ă����Ȃ�ꂽ�a�����́A����܂łɂȂ��i�W�������̂ƂȂ����B�������̒S���͍��X�ؓ��_�ł���A�쒩���͐��V�ł���B�u�t��L�v�ɂ��Η��w�c�������ʂő�}�̓��ӂɒB���A�k���V�c�̓��ӂ�������Ŋ֓��̊�Ɉӎv���m�F���ŏI���������Ƃ����i�K�ɂ܂Ŏ������悤���B���̏Ő���22�N4��29���쒩����t���������g�҂Ƃ��ċ`�F�ɉy�����Ă��邪�A�����ŋ}�ɘa�����͔j�k�ɏI������B�u����NjL�v�́A�쒩���̕�����(�`�F��)�u�~�Q�v�Ə�����Ă������ߋ`�F���C�����Q�����̂������ƋL���Ă���B���̌�����N8���܂ňꉞ�̌��͑�����ꂽ�悤�����A���ɘa���ɂ͎���Ȃ������B�قƂ�ǘb���Z�܂��Ă��Ȃ���}�ɔj�k�ƂȂ������ɉ������������͖��炩�łȂ����A������23�N(1368)�㑺�オ���䂵�Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�����Ɍ㑺�オ�a�Ȃǂɂ��e���͂�ቺ�������h���䓪�����\�����w�E�����B���̎����͉��ǐe����i����e�r������B��x�z�����シ��C�z�������Ă������A�������������ނ�����C�ɂ����̂͑z���ɓ�Ȃ��B�@ ���V�͂����a�����̏��Ȃ��Ƃ���x�ɂ킽���ē쒩��\�߁A���̑��̎������O���ɂ��Č��Ɋ֗^�����\���͍����B�������틵���n�m���Ă��邾���ɁA���d�Ȑ킢�Ŕj�ł�������ʖڂ̗��`�ł̘a���̕��������I�ł���ƍl����悤�ɂȂ����Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B�������A�����������т����V��쒩�����Ŕ����ȗ���ɒǂ����ނ��ƂƂȂ�B�@ ���a���h�̔s�k�@ �㑺��̔ӔN�ɂ́A���V�͌㑺��Ƌɂ߂Ė��ڂȊW�����悤�ɂȂ�B����16�N(1361)���ɂ͍��n���ɔC������A����20�N(1365)���ɂ͍����q�̊��E���������Ă���B�����q�͏]�l�ʉ������ŁA�Q�c�łȂ��l���C������̂͂܂�(���q���{���㏫�R�����Ƃ���O�Ƃ��đ���)�ł������B���V�͓���ŔC����ꂽ��ł���A���`���Ō�ɔC����ꂽ���E�ł��邱�Ƃ◊�Ƃ̗���l������ƕ��Ƃ̓��������ɓ������ƌ����悤�B�X�ɐ���20�N(1365)���V���㑺����d�|�t�҂߂Ă���A���l(�V�c�̔鏑)�̖������ʂ����Ă����̂ł���B����������23�N(1368)3���㑺�オ���䂵�����e�������ʂ���(���c�V�c)�Ə͈�ς��鎖�ɂȂ�B�@ ���āA���̎����̓쒩�͎j�����R�������c���ʂ̗L���Ɋւ��Ă͒���̂Ȃ��ł��������A�吳���ɔ��㍑�����j�������Ē��c�����ۂɍ݈ʂ�������_���Ĉȍ~�͂��ꂪ����ƂȂ��Ă���B�����ŏq�ׂ��Ă���_���ɂ��Ă����ŏЉ�悤�B�܂��㔐���V�c����́u�鉤��n�}�v�Ɂu�g���@�@�c�����v�ƋL����Ă��芰���̑��ʂ��������Ă���B�����ĉ��i22�N(1415)�㏬���V�c�̖��ŕҎ[���ꂽ�u�{���c���Љ^�^�v�Ŋ����̉��Ɂu���쎩���@�����c�@�v�A��E�����̉��Ɂu���g��~�Q�A�֑����V�c�����A����T�R�@�v�ƋL����Ă���k�������̑��ʂ�F�߂��ƍl���邱�Ƃ��ł���B�X�ɁA�x���Ə����́u�V�t�W�v�ɂ����鉞�i32�N(1425)�����Ɂu�c���@�@�c��݈ʂ̎��v�Ҏ[���ꂽ�Ƃ���A���i33�N(1426)�����ŋ�����ꂽ�u�V�t�W�v�̐l�̐����҂Ɂu�c���@�@�c�v�̖��͓����Ă��Ȃ��B���̎��_�Ō�T�R�͑����ł��邩��A�u�c���@�@�c�v����T�R�łȂ����Ƃ͌��������ł���B�����āu�����L�v�ɊC��a�����u�㑺��䑷�A�c���@��q�v�ƋL�����L��������A�܂��ϐS���ɊC�傪���̂c�@�̈▽�ɂ�菈�������������c����Ă��邱�Ƃ�����u�c���@�v�͒��c�̎��ł���ނ͓쒩�ő��ʂ����ƍl���Ă悢�B�X�Ɍ����ƁA�V��3�N(1377)�ɕҎ[���ꂽ�u�Ê��@�W�v�ł́u���̌���v(�V�c)�Ɂu���c�@�v�ƒ[������Ă���A�u�X�_�S��v�Łu�V����N�哴�������v�́u�哴�v(��c)�Ɂu���c�@�v�A�u�����v�Ɂu��o���a�v�ƒ[������Ă��邱�Ƃ�����𗠕t����ƌ�����B�@ ���ɂ��݈̍ʊ��Ԃł��邪�A�O�a���N(1381)�ɕҎ[���ꂽ�u�V�t�W�v�Ɂu�O��̌��Ɏd���v�Ƃ��鎖���炱�̎����ɂ͂܂��݈ʂ��Ă����ƍl���Ă悢�B����Łu�ԉc�O��L�v�ɂ͕������N(1372)�ɓ쒩�V�c�����ʂ����Ƃ����\���L���Ă��邪�M�ߐ��ł́u�V�t�W�v�ɗ��Ƃ����悤�B�������N(1384)�ɒ��c�̉@�邪�F�߂��Ă��邱�Ƃ���A�O�a3�N(1383)�O��ɒ�E�����ɏ��ʂ����ƌ��Ă悢�ł��낤�B�@ ���̒��c���݈ʂ����Ǝv������Ԃɂ����āA�a�����͈�x���s���Ă��Ȃ��B�j�������Ȃ����ߒf�肷��̂͊댯�ł��邪�A���̓_��������c��ނ�i�������l�X�͎��h�ł������\���������B��a�E�I�ɁE�͓��E�a��̎R�ԕ��ɂ����d�|���y�Ȃ��悤�Ȏ�̐��͂ɂ����ċ��d�Ȏ��_�������鎖�́A�����������Ă��Ȃ��ƌ����Ă��d���Ȃ���������Ȃ��B�������A�ɂ߂Ď�̉����Ă��邩�炱�����d�Ȍ����I�咣�������Čە����Ȃ�������̊댯���������Ƃ����邱�Ƃ��ł���B�ނ�͋�B�̖������������鎖�Ɉ��~�̖]�݂������Ă����ł��낤�B�Ƃ�����A������������ł͘a�������������Ă����ł��낤���V�̗���͓�����̂ƂȂ�B�ނ����c�⋭�d�h�M�����牓��������悤�ɂȂ����ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�@ ���k�֑���@ ����24�N(1369)1�����V�͓˔@�Ƃ��đ������ɍ~������B��������ꂽ�̂����������ɂ����đ�O�㏫�R�`����⍲����Ǘ́E�א엊�V�ł���A���N2�����V�͘a��E�͓��̎��E��ۏ���Ă���4���ɂ͏㗌���ė��V��`���ɑΖʂ��Ă���B�܂��A�쒩����̊��E�E�����q�͕��Ƃ̓����ɑ���������̂ł���̂ŁA�k���~����͒������ɕύX�ƂȂ��Ă���B���܈ʑ����ł��邩��i�����ł͂��邪�A���Ⴉ�猾���Ď����I�ɂقړ��i�ƌ����Ă悢���E�ł���A�����������V�ɂ��Ȃ�̔z�������Ă��邱�Ƃ��f����B�쒩�̕��͂�S���Ă������V���~�����������́A�傫�Ȑ�`���ʂ����ƍl�����邽�߂����V���ɒm�炵�߂邽�߂������Ă̌����ł��낤�B�@ ���V�������Ŗk���ɍ~�����^�ӂ�m�邱�Ƃ͓���B�쒩���d�h�̑䓪���_�@�ł��邱�Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ����A���̖ړI�ɂ͏�������悤���B�쒩�̎�͂ł��鎩���������鎖�Řa���~�ނȂ��Ƃ��������ɓ������肾�����A�쒩�Řa�����̂�����ȏ�͐g���ڂ��ė��V�Ƙa���������l�߂���肾�����A�ȂǂƐF�X�����Ă����B��������q����悤�ɐϋɓI�ɓ쒩�U���ɎQ�����Ă���_���l����ƁA�����ɑ����Ȃ����d�ȋM�������̎咣�ɔ����������ʂł͂Ȃ����Ɛ�������Ă���B�l����A���������咣�ɂ���ĕ���Z�����ɒǂ�����Ă��莩�g�������Ȑ킢�ɏ]��������ꂽ�B�����Ă��̎������N�̌��J�ɂ�������炸�]�����ꂸ�����ȗ���ɗ������ꂽ�ł��낤�B���邢�͓��ʂ̋^����������ꂽ�����m��ʁB�����������N�̓{��ƕs�����A���̎��ɗՊE�_��˔j�����̂ł͂Ȃ����B���̐��V�̐U�镑���́A���̐w�ɂ����ĕЋˊ������L�b�Ƒ����̂��ߐs�͂����ɂ�������炸���ʂ��^���ē�����Ɉڂ�A�킢�ł͑���ɑ�C��ł���������z�N��������̂�����B�@ ���Đ��V���������ɐw�c��ς��������́A��؈ꑰ�̋��������ɂ���ĉ������邱�ƂƂȂ����B�k������3�N(1370�A�쒩�������N)�ɂ͘a�c�����Ɛ��V�̌R�����Փ˂��Ă���A����ɑ��ė��V�͗{�q�E�א엊������R�ɍ��������Ă���B�������������̗L�͎҂ɂ͗��V�ɔ���������̂������A���R�̏��������ϋɓI�ɐ��V�E������������悤�Ƃ��Ȃ��B���̂��ߗ��V���o�Ƃ߂����`�����G�߂邱�Ƃł悤�₭���R�������o�������ɂȂ��Ă���B���V�͑������������ŌǗ��X���ɂ��藊�V�݂̂�����ł��������Ƃ��f����B�@ �k������6�N(1373�A�쒩����2�N)8�����V�͑����R���ē����ē쒩�s�{�ł�����������U�������B���̎��ɓ쒩���d�h�ł���l�𗲏r���펀���A���c�͓V��ɓ���Ă���B�X�ɓy�ۏ�̋��{�������V�̗U���ɂ�葫�����ɍ~���A9���ɂ͋I�ɗL�c�������R�ɍ~�����B���̎����ɂ͍��엹�r�ɂ���B�o�����O���ɏ��n�߂Ă���A�쒩���̐��͓͂����ɏk�����Ă����̂ł���B�@ ���Ėk���N��N(1379�A�쒩�V��5�N)�ɊǗ́E�א엊�V�͔��Δh�̗L�͎ҒB�ɉ�����Ēn�ʂ�ǂ��A�z�g�`�����Ǘ̂ƂȂ�B���V�͂����ɔ�҂��������B�܂��a����E���䓪���������R�������ɂ���ĉi�a4�N(1378�A�쒩�V��4�N)�Ɋ��ɒD���Ă����B���������ɂ͐��V�̋��ꏊ�͍ő��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B�@ ����ɋA��@ �O�a2�N(1382)���V�͍Ăѓ쒩�ɋA�Q���Ă����悤�ł���B�������ւ̍~���ɂ��ꑰ�̗��������������⑫�����������ŌǗ����������傫�ȑŌ��ł������낤�B�����ďȂ݂āA�����͂�͂�쒩���̐l�Ԃł���Ǝv����߂����̂ł��낤�B�쒩�Ƃ��Ă����|�I�̒��ł͒��炭���͂�S���Ă������V�̑��݂͋M�d�ł��������ߌ}�������ə傩�łȂ������낤���A���h�̔����͂���܂������Ƃ����V�ɂƂ��ċA�Q�ւ̒�R�����Ȃ������ł��낤�B�ނ̎��ɏꏊ�͑��̈ꑰ�Ɠ����Ō��ǂ͓쒩�ł������B���̔N�̉[1�����V�͕����ŎR�������̌R���Ɛ���āA�ꑰ���l�E�m��140�l��������s���i���Ă���B�ő��A�쒩�������𗯂߂邱�Ƃ͒N�ɂ��ł��Ȃ������B�@ ���ē쒩�͋A�Q�������V�ɑ��ĈȑO�Ɠ��������q�Ƃ��đҋ��A�X�ɗ��O�a3�N(1383)�Q�c�ɏ��i�����ċM���ҋ��Ƃ��Ă���B��������A���c�V�c���ވʂ��������e��(��T�R�V�c)�����ʂ����B���̓V�c�̉��ōĂјa���h���͂����߂��悤�ŁA���V�͔ނ炩��̊��҂������̂ł��낤�B���̌�����V�͉͓��E�a��Ō���3�N(1386)�܂ŕ����s���Ă���̂��m���Ă��邪�A����ȍ~�̎��Ղɂ��Ă͕s���ł���B�@ �����̌�@ ����9�N(1392�A�k������3�N)�[10����T�R�͖k���E�㏬���V�c�ɎO��̐_������n�B�����ɘZ�\�]�N�ɋy��k���̑����͂�����������B�������A���̌�̓W�J�͋��쒩���ɑ傫�ȕs���������炷���ƂƂȂ����B�������̎��̖ł͍c�ʂ𗼌n�������݂Ɍp�����邱�ƂƂȂ��Ă������A���ۂɂ͎���邱�Ƃ͂Ȃ��k���n�����p���ł������B�܂��A�쒩���x�z���邱�ƂƂȂ��Ă������ɗ�(����)�������B�ɐN�H��������������Ă���o�ϓI�ɂ��ꋫ�ɂ��炳���B�@ �����������ŋ��쒩���͂������Εs�����q�ƌ��т����肵�ċ������Ă��邪�A���̒��ɓ�؎��̎p���F�߂��Ă���B���������̊Ԃ��Ȃ����i6�N(1399)�ɂ��������`�O�̔����ɓ�؈ꑰ���Q�����Ă���(���V�̎q�E�����Ƃ����)�̂��u���i�L�v����m����B����ȍ~����Ȃ��̂�����������ƁA����2�N(1429)��،�������Z�㏫�R�E�`����ޗǂňÎE���悤�Ɩd���ĕ߂炦��ꏈ�Y����Ă���B�i��9�N(1437)�͓��œ�؈ꑰ���������Ă���A�Ëg3�N(1343)�쒩�c�}�ɂ��_������������D��ꂽ�ۂ���؎��Y���֗^���Ă���B�����ĕ��a4�N(1447)��؉�y�����I�ɂŋ������ĉF�s�{�E���R�ɓ������ꂽ�B�������N(1460)�ɂ͓�ؖ^�������Ɏ��s���ď��Y����Ă���B�����ĉ��m�̗��̍Œ��ł��镶��2�N(1470)�V�c�E���R��v�������R�E�א쏟���ɑR���邽�ߐ��R�E�R���@�S�����쒩�c����i�������ۂɓ�؎���������Ă��邱�Ƃ��m���Ă���B�@ ����ȍ~�́A�������������͂����������Ƃ������Ă��̕s�����q���i�����鋌�쒩���͂��p�������Ȃ��Ȃ�B���_�A��؎����\����ɂ͌����Ȃ��Ȃ�̂ł��邪�A�i�\2�N(1559)��؎��q���Ə̂��鐳�Ղ������̒��G�͖Ƃ�v�����ėe����Ă���B��ɐ��Ղ͐D�c�M���̗S�M�Ƃ��Ċ����B�܂��A�k���e�[�Ƌ��Ɋ֓��Ŋ������Ă�����؈ꑰ�̎q�����������Ɩ���蓿����ɐ��˓���ƁE���쏫�R�ƂɎ���Ƃ��Ďg�������Ƃ��m����B���쒩�Ƃ��ė}�����Ă�����؎����A�����ŎЉ�I�ɒn�ʂ�������x�����ƌ�����̂ł���(���ۂɎq���ł��������͊m���߂邷�ׂ͂Ȃ���)�B�����Đ��˓��쎁�́u����{�j�v�Ȃǂɂ��A��؎��́u���b�v�Ƃ��ď̗g�����悤�ɂȂ�ߑ�Ɏ���B�@ ���@ ���V�͌������i�I�ɉ��a�ł������悤�ŁA�u�g��E��v�ɂ͐��V���w�Ƃ��đ_���\���Ƃ����l�������̉���ɂق�����ċA��������b���L����Ă��邵�A�u�����L�v�ɂ����V���M�ꂽ�G�����~�o���ĈߗށE�����{�����b���c���Ă���B��҂Ɋւ��Ă͕��E������Z�E���s�ɂ����l�̈�b�����݂��A��؎���X�̉ƕ��ł������ƌ����邩������Ȃ��B���������l���ɉ����ċꂵ���틵�ւ̓��@���A���V��T�d�Ȏ琨�h�E�a���h�ւƈ�Ă����̂ł��낤�B�ꎞ���ɖk���֍~�������߂ɚʗ_�J�Ȃ̂���l���ł��邪�A���̓I�Ɍ���Γ쒩�̒��Ƃ��ē�؎��y�̖̂��������Ȃ������Ƃ����邵�v���x�E�͗ʂɂ����Ă͕���Z�ɂ������ė����̂ł͂Ȃ��ƌ�����B���|�I�ɂ����ꂽ�쒩����ɂ����Ă͑��̐l���ł��낤�B �@ |
|
 �@ �@����ǐe�� (1308-1335) |
|
|
���q�����œ|�ɍۂ��Ă̎�����̎i�ߊ��ł���A���͑������댯����������E����ɂ��r�����ꂽ�ߌ��̍c�q�E��ǐe���B�@ ���a���@ ��ǂ́A���c3�N(1308)��F���@�̎q�E�����e��(��̌���V�c)�̍c�q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�Ƃ���Ă���B��͖������O�ʂƌĂꂽ�����ł��邪�A���̌o���ɂ��Ă͕s�ڂ��B�k���t�e�̖��ł���Ƃ������邪�A����o�q�������Ƃ�������B�u�����L�v�ɂ��A�c����葏���Ō���͔ނ��c���q�ɂ������Ɩ]��ł����Ƃ������A���ۂɂ͌��킪��p�҂Ƃ��Ė]�̂͌�ǂٕ̈�Z��ł��鐢�ǁE���ǂł������悤���B�Ƃ������ǂ́A����V�c�����ʂ������ɂ͕���ɓ��葸�_�@�e���Ɩ�����Ă����悤�ŁA����2�N(1325)�����Ղɓ��菳���@�e���̒�q�Ƃ��ēV�����E�e�������Ă���B���݂ɔނ��u�哃�{�v�ƌĂ��̂͂��̎��Ɋ����Ղ̑哃�ɓ����������ɗR�����Ă���B�܂��A����(�o�T�ɋL���ꂽ���̋����B�����ƑΔ䂵�Ă����Ă�)�𒇉~����w�悤���B�@ �������@ 12���I���Ɋ��q���{���������Ĉȍ~�A��ɐ���A���{���x�z����̐��������B13���I�O���ɂ����鏳�v�̗��̌�ɂ͒���ɑ��開�{�̗D�ʂ��m�����A13���I�㔼�̌������_�@�ɂ��Ėh�q�̂��ߐ����E���Ɛl�ɂ����{�͎x�z���y�ڂ��K�v�����������������đS���I�ɗ͂�L���B�����Ă��̍��A����͌�[���E�T�R�Z��̒�����������Ɏ����@���E��o�����ɕ��A���{�̒����������Ȃ��Ȃ�B�X�ɖ��{�̓��������̒��ō��i�̌����ł������c���쐬�����̎�Ɉڂ�ȂǓy�n�c���͂��ቺ�����B����Ŗ��{�́A������̑����Ɋ����܂ꂽ��A�����̏��Ɣ��W�₻��ɔ����u���}�v������_�Ɩ��̑䓪�ɂ��Љ�s���A�X�ɂ͌�Ɛl�B�ɐ����Ă����o�ϊi���ɂ��s���ɔY�܂����悤�ɂȂ����B����ɑΉ����邽�ߖ��{�̎�ǂł���k�����͈ꑰ�̑��́E���@�̉��Ŕ�_�Ɩ����x�z���ɑg�ݍ���ł̐ꐧ�̐����u������悤�ɂȂ����B����������͏]�����{�̌R���͂��x���Ă������R�̐����ɂ����Ɛl�B�̔��������ƂƂȂ�A�X�ɒ�����_�Ɩ��̕s������g�ɕ����l�ɂȂ����B����Ŕ�_�Ɩ������{��w��������̎��͂͂܂��Ȃ��A���������̋߂����v�킹���Ԃł������B�@ ���s�v�c�̖��@ �k�����Ɍ����Ă̕s�������܂���钆�A���@�����������������Ǘ̒��荂���͂���ɑ���\���ȑ��ł��o�����Ȃ������B����A��������̒��ŌZ�E����V�c�̎q����������܂ł̒��p���A���Ȃ킿�u�ꐢ����̎�v�Ƃ��đ��ʂ�������V�c�́A����ɗ��܂鎖��ǂ��Ƃ����V�c�e����i�߂�Ƌ��Ɏ��Ȃ̎q���ɂ��c�ʌp���ƑS���ꌳ�x�z��ژ_�ݓ|�����u������Ɏ������B����͖k�����ɕs���������Ɛl�B�ɐ����|����Ƌ��ɁA����ƌq���肪�[�����ЁE��_�Ɩ���̗͂�g�D���đR���悤�Ɛ}�����B�@ ������������̉×�2�N(1326)���_�͓V�����ɔC�����ꂽ�B2�N��Ɉ�U���E���Ă��邪�������N(1329)�ɍĂэ���ƂȂ��Ă���B����̈ʂɏA���Ă���ԁA���_�͖{�Ƃł���͂��̕����������u���ĕ��|�b�B�ɗ]�O���Ȃ��������ߐl�X�́u��(���܂�)�z��(������)�s�v�c�̖��͌䍿�����v�Ɖ\���������ƌ����B����͉b�R��|���̂��߂̕��͂Ƃ��Ċ��҂��Ă���A���_�̍���A�C�͉b�R�𖡕��Ɉ����鎖�����҂���Ă̐l���ł������B���_�͂�����悭���m���Ă���A�����̓��ɔ����Ď����b����Ƌ��ɕ��͂ƂȂ�m���Ƃ̒��ړI�Ȍq�������낤�Ƃ��Ă����̂ł���B�܂��A���������b�R��ޗǂɍs�K�����z�̊�i���s���Ă���A�L�͎��Ђ̕��͂�g�ݓ����H���i�߂Ă����B�@ �����O�̕ρ@ ���O���N(1331)�A����V�c�̓|���v�悪�g�c��[�̖����ɂ�薋�{�ɘR��A���{�͓���r����߂炦��ꂽ�B�V�c�̓|���v�悪�I�悵���̂͐������N(1324)�ɑ����ē�x�ڂł���A�O��Ƃ͈Ⴂ���ւȌ����͊��҂ł��Ȃ��ƍl����ꂽ�B���ہA���{���͓V�c��߂炦���ʂ����悤�ƍl���đ�R���㗌�����Ă����B���̓������b�R�̑��_�͎@�m���䏊�ɒm�点��Ƌ��ɉb�R�ւ̍s�K�����߂�B������Č���͌䏊��E�o���邪�b�R�ւ͌����킸�A�ޗǂ��o�Ċ}�u�ɘU�����B���킪�b�R�ɕ����Ȃ��������R�Ƃ��āA�܂��ח������ۂ̌�w�n�����݂��Ȃ������l������B�܂��A��s�͐ۉ͐�ɋ߂��������؎����n�߂Ƃ��閡���̓y���𗊂݂Ƃ������̂ł��낤�B����A��b�R�ɂ͉ԎR�@�t��������ɐ��肷�܂��Č������A�����ɕ�ꂽ�B�@ ���̓V�����͑��_�ٕ̈�Z��ł��鑸���@�e��(��̏@�ǐe��)�ł���A���_�͔ނƋ��͂��ĉb�R��O�̌����ɗ͂𒍂����B�V�c���g�̍s�K�ƕ������m���B�͊������Č������A�قƂ�ǂ������ɕt�����Ƃ����B����œV�c�̌䏊�E�o��m�����Z�g���T��(���ɂ��鐼���̖��{�o��@��)�́A�E�o�悪�b�R�Ƃ̏���͂ݖ�̌R�����ÁE������ʂ֍����������B�}�����b�R�����Z��̕��͂�Ґ�����B���̂������S�l�����C�Ɉ���ē���ɏo�����Z�g�����ƏՓ˂����B�b�R���͖����̂��ߋ����������邪襘H�𗘗p���ĔS��������A���̊ԂɎR�ォ�琔��̌R�������H�z�ւƎE�����a�m�E���c����͐��R����Âɉ�薋�{�R�̑ޘH��f�Ƃ��Ɠ����Ă����B��͂����댯���������Z�g�����͑ދp��]�V�Ȃ����ꂽ���A���̍ۂɒnj����đ傫�ȋ]�����o���Ɏ������B�@ ���쑤�Ƃ��Ă͍K��̗ǂ������ł��������A�b�R�ɓ������u�V�c�v���U�҂ł��鎖������ɘI���������߉b�R�@�k�͋\���ꂽ�̂�{���ĉ_�U�������A���_��͉��R���ė������т���Ȃ��Ȃ����B�U�҂̓V�c�œG�������Ō�܂ŋ\���ʂ����͓���̂͗\�z���ꂽ�ł��낤����A���炭�͓��������킪��s�ő̐��𐮂���܂ł̎��ԉ҂����ړI�������Ǝv����B���̊ԂɌ��킪�}�u�R�ɘU���Ėh���𐮂���Ƌ��ɉ͓��ԍ�ł͓�ؐ������ĉ����ċ������Ă���A���̖ړI�͏\���ɉʂ����ꂽ�ƌ����悤�B�@ �@��b�R�̓����̐���������A���_�͑����Ƌ��Ɋ}�u�R�ɕ����Č���ƍ����B�u�����v�ɂ��Α��_�͊Ԃ��Ȃ������R�̓�ؐ������U��ԍ�ւƈڂ����ƌ����B�₪�Ċ}�u�E�ԍ�Ɋ��q����h�����ꂽ��R�������A���҂͗��邵����⑸����͕߂炦��ꗬ�߂ƂȂ����B���{�͎O��̐_������킩�����Ď����@���̌����V�c�ʂ������Ԏ��E��}��B���������_����͓������т��B���_�����ɐ������Ă���ƌ����\�����ꂽ��������A�Z�g���͗����̎�������������ȂǑ傫�ȕs��������Ă����B�@ �������s�@ ���_�́A���̌�͐��������𑗂鎖�ƂȂ邪�A���̎����̏����ɂ��Ắu�����L�v�ɋL����Ă���B�܂��ޗǂɓ���ʎ�ɐ������Ă����ƌ�����B����ɋߎ����|���v��ɂ�������Ă������ς̑��������������͂��ʎ�ɂ͑��݂��Ă���A����𗊂������̂ł��낤�B���鎞�A���{���̈���@�@�@��̎萨���P���������ߕ��a�ɐg���B�����B�����ɂ͌o�T��[�߂铂�C���O����ł��肻�̂�����̊W���J���Ă���c���͕܂��Ă����B���_�͂܂��J�����C�ɓ���o�����ĉB���B�B�`�̎�����������������ۂɂ͂������n�ł���悤���ɔ��n���������Ăđ����E���Ă���ƁA�ǎ�͊W�������C���{�����ė��������Ă������B���_�͗p�S�̂��߂Ɏ��ɊW�������C�Ɉڂ����Ƃ���A�ʂ����Đ�قǂ̒ǎ肪�߂��Ă��ĊW�̊J�����C��{��������������Ȃ��B�ǎ�́u�哃�{�͂��킳���A���ɑ哂�̌����O�������킵��(�����ɂ��ꂽ�o�T�ł��邽��)�v�ƌy����@���Ȃ��痧���������Ɓu�����L�v�͓`����B�]�k�ł��邪�A�u�哃�{�v�̌ď̂́u�����Ƃ��݂̂�v�Ɠǂނ̂����ݒʗ�Ƃ���Ă��邪�A���̎��Ⴉ��́u�����Ƃ��݂̂�v�Ƃ������Ă����\�������������B�����̐l���̓ǂݕ��͂������i�ł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B�@ �낤���Ƃ���œ�ꂽ���_�́A�������́E�ԏ����S�畔���𗦂��ČF��ւƌ��������Ƃ����B�C���҂Ɏp��ς��ē����̐_�Ђɕ�������s���ӂ炸�g�����I������̂�h���̗��ł���B�u�����L�v�ɂ��A�r���ŌF��͊��q���ł���댯�ł���ƌF�쌠�����疲�ō������\�Ð�ւƖړI�n��ύX�B���炭�͌F��O�R�ł̒���x���҂���s�ɒm�点���Ƃ����̂����Ԃł��낤�B�\�Ð�ɓ����������_��́A�܂����n�̗L�͎҂ł���˖앺�q����ی�����B�˖�̉Ɛl���a�ŔY��ł����̂��F���Ŏ������ɂ��M���āA���q������ɐS���Ă���̂��m���߂���ɐg���𖾂������Ɓu�����L�v�͓`����B���q��ʂ��āA���̏f���ŏ\�Ð�̌����߂ł���|�����Y����}�����\�Ð�S�̂��y���Q�����Ƃ����B�����ő��_�͊ґ����āu��ǁv�Ɩ����A�|�����Y�̖���W�����Ɠ`������B�@ ��ǂ��\�Ð�̋����𖡕��ɂ������́A�F��ʓ��ɂ��`����ꂽ�B�ʓ��͌�ǂ�߂炦���҂ɘZ���т̏܋���������Ƌ��ɖ��{������ɐ������ԑ������܂Ƃ��ė^������|��z���������߁A�\�Ð싽���̒���������{���ɐQ�Ԃ�҂������悤�ɂȂ����B�₪�Ē|�����Y�̎q������Q�Ԃ�C�z�����������ߌ�Lj�s�͍ĂђE�o�����B�@ �r���A�̑����ɍs������Ղ�ꂽ���A���̖��Ɋ���n������Œʉ߂�F�߂�ꂽ�B����������Đ퓬�����؋��Ƃ����������{�֊�𗧂Ă邽�߂ł���(�ނ��A��ǔz���Œx��Ēʉ߂�������`�����D�҂��Ă���)�B�X�ɋʖؑ��ł��Ղ��A���i�Ɍ����Ă��邪���̎��͕s���ŏP�����Ă���B��͂��������o�債���Ƃ���ɁA�I�ɍ��̓y���ł���쒷���������S�̕��𗦂��ċ~���ɋ삯�������ߓ�ꂽ�B�u�����L�v�ɂ��A�ނ�͌�ǂ����Ƃ��Đg�ɒ����Ă����V�����_�̂������Œy���Q�����Ƃ����B�@ �u�����L�v���`�����̎����̌�ǂ̕���ɂ́A�@���I�E�����R�I�ȉe��������Ă���B��ǂ����̎����ɑ؍݂����I�ɔ����암�́A�����R�n�E�g��E�F��E����ƌ×����R�x�M���h�������n���������݂���n��ł���B���������n��͖����Ɩ��ڂɌ��т��ēƎ��̃l�b�g���[�N���\�z���Ă����B�C���҂͎��R�ɍs�������邽�߁A�L���n��ɏ���`�B����\�͂Ɛl����L���Ă����̂ł���B�܂��A���݂ɂ͌F�쐅�R�����͂��L���Ă���A�C���ʂɂ����Ă����̒n��͏d�v�Ȗ������ʂ����Ă����B�ݕ��o�ς����B���钆�ŁA�ނ�͔�_�Ɩ����x�z���ɒu������Ȃ��Љ�I���͂����悤�ɂȂ��Ă����B��ǂ����ēV�����ł����������ɓ|���ɔ����Ă����������͂Ƃ��W���\�z���Ă����ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���_�A���{�����ނ�̎�荞�݂ɂ͗͂����Ă������ߕK�������S�Ă𖡕��ɂ��邱�Ƃ��ł����킯�ł͂Ȃ����A�����ĕ���Ȃ��x����Ղ��`������Ă����ł��낤�B�u�����L�v�̃G�s�\�[�h����͏C���҂��܁X�Ō�ǂ̂��߂ɓ�����@���~���Ă����������������B�܂��A��ǎ��g���@���҂Ƃ��Ă̑f�{��L���Ă��������f���A���đm�Ƃ��đ̓������͂��ނ�𖡕��Ɉ���������ő傫���𗧂����ł��낤�Ǝv����B�@ �@���āA�쒷�����̕ی������ǂ́A�������o�ċg��̋���R�������ɓ���A���̒n�ŋ�������Ɏ���B�@ ���g��R�@ ���O3�N(1333)�������Ă�����ؐ������Ăюp�������A��㕽��̊e�n�Ŗ��{�����h������B�X�ɘZ�g���̌R����ےÓn�ӂŌ��j���A�������|�Ɋׂꂽ�B���{�͂������������Ԃ����E���邽�߂ɍĂё�R��h������K�v���������̂ł���B�����������āA�d���ł͐ԏ��~�S���A��a�ł͍��ԍs�G���A����Ɉɗ\�ł͓y���E���\�E���ߎ�����ǂ̗ߎ|�ɉ����ċ��������̂ł���B����͂��̎����͉B��ɗ��߂ƂȂ��Ă���A���������Ȃ���Ԃł������B��ǂ͐��R�𖡕��ɂ��Č���ƘA�������Ȃ���A������̑��i�ߊ��Ƃ��ď����͂ɔ����{�̋������Ăт����Ă����̂ł���B�����Ď��g�͋g��R�ɓ���U�邵���B�������ɐ����͋����R�̐瑁��ɘU���Ė��{�̑�R���}�����̐��𐮂��Ă����̂ł���B���̗��҂͘A�g���A�E���𒆐S�ɐV�������̋�����}���Ă����B�@ ���{���͐킢���n�߂�ɂ����萳����߂炦���҂ɒO�㍑�D�䑑�A��ǂ�߂炦���҂ɋߍ]�������������܂Ƃ��ė^����ƕz�����Ă���A���i�߂ƑO���ł̑��l�҂Ƃ��ē�l��F�����Ă��������m����B�����ċg��ɂ͓�K���員�������̌R���𗦂��ĎE�����U�͐���J�n�B����Ǖ��͎O����x�ł��������A�n�̗������ē�E襘H�𗘗p���|�M���Ă����B���{���ɎQ�킵�Ă����g��̎��s�E��e�ۂ͒n�����n�m���Ă������ߏ����̋���A��ė����瑠�����ɓ˓��A��Ǖ������������̂��Đ��ʂ̖��{�R���ˌ������B��ǂ͓������o�債�����B�Ǝ������J���Ă������A����`���ɊЂ߂��ĒE�o�B�`���͌�ǂ̐g����Ƃ��Ė��{�R���Ђ����Ď��Ԃ��҂�����Ŏ��n�����B���̎��ɋ`���̎q�E�`������ǂ�����ē����𐋂��Ă���B�@ �ǂ��ɂ���ꂽ��ǂ͍���R�ɓ��ꂽ�B��K���員�͒ǂ�������������č����{�������邪�A�O�k����ǂ��ʂ������߂��ɔ�������鎖�͂Ȃ������̂ł���B�@ ������{���c���q�@ ����A�瑁��̐����͖��{�̑�R��Ɉ�����������|�M���Ă����B�����Č�ǂ��A�Ăѐ������������Ȃ���g��E�\�Ð�E�F�ɂ̖앚��g�D���Ė��{�R�̗Ɠ����P�����鎖�ł�������삵���B���������n�̗������Ă̐_�o�S�v�ȃQ������̑��A�S���e�n�֗ߎ|�����Ė��{�ɕs�����������B�ɋ������Ăт����Ă����̂ł���B�����̐킢�Ԃ肪��B�Ȃlj��u�n�ɂ܂œ`��鎖�ŁA�S���I�Ȗ��{�̈АM�ቺ��������悤�ɂȂ����B�����������ŁA��ǂ̗ߎ|�͉z��̎O�Y�a�c���A�F���̋������A�}��̎O�����ɂ܂ŋy��ł����B���̎����A��B�ł͋e�r�������������đ�ɕ{���U�����Ă��邪�A�������ǂ̗ߎ|�ɂ��s���ł͂Ȃ����Ɛ�������Ă���B���{�R�̈���Ƃ��Đ瑁���͐�ɎQ�����Ă��������B�̒��ɂ������̗̒n���S�z�������薋�{������������ƌ������R�ň����グ����̂�������悤�ɂȂ����B���̐V�c�`������̈�l�ł��������A��ǂ����̍ۂɋ`��ɗ^�����������d�|(�V�c�̖��ߏ�)�̌`�����Ƃ��Ă����Ɓu�����L�v�͓`����B���̈�b�̐^�U�͂Ƃ������A���킪�s�݂̒��œV�c�㗝�Ƃ����ׂ��������ʂ�������R�̑��l�҂Ƃ��đ傫�Ȗ������ʂ����Ă����̂͋^���Ȃ��B��ǂ��u����{���c���q�v�ƋL�����������݂��Ă���A��ʂ�������������ڂŌ����Ă��������f����B�@ �₪�āA��������R�̎�����ʼnB��E�o�����˂̖��a���N�Ɍ}�����A��풉����叫�Ƃ��ċ��D��̂��ߌR����h������B�����͔d���̐ԏ����Ƌ��ɋ��U�����J��Ԃ����̂̋��B�����������Ŋ��q���疋�{�R���w�Ƃ��ď㗌������������������Ɠ��ʂ��ĐQ�Ԃ�A5��7���ɘZ�g���T����U�����ċ����蒆�ɂ����B�Z�g���T��ł������k�𒇎���͋ߍ]�ԏ�Ŏ��n�B���̒m�点�����瑁���͂��Ă������{�R�͕��A�E���̖��{�����͂͋쒀����鎖�ɂȂ�B���������ď��ŐV�c�`�傪���������q���U���A5��22���ɖk��������͈ꑰ�Ƌ��Ɏ��������q���{�͂��̗��j������B���̍ۂɋE������O�؎����V�c�R�ɎQ�����Ă���A��ǂ̎�ɂ����̂ł���ƌ����Ă���B�@ �����R�{�@ ���{�ŖS�̒��ォ��A�u���R�{�̋��ɂ��v(����������)�̂悤�Ɍ�ǂ��u���R�v�ƋL���������U�������B���̍��A�����̂��������������Z�g���T��̎����������z�����ĕ�s�����J���R����z���Ă���A��ǂ͂����ւ̐V���ȋ��ЂƔF�����Ă���ɑR���悤�Ƃ��Ă����̂ł���B�u�����L�v�͔z���ł���ǒ��̕����������ɏ��Y���ꂽ���݂���Η����n�܂����ƋL���Ă��邪�A�����Ƃ��Ă����|���ɉ߂��Ȃ��ł��낤�B���Ƃ̖���Ƃ��Ėk�����ɑ����ĕ��Ƃ𑩂˂悤�Ƃ��鑫�����ƁA����̉��ɕ��Ƃ]�����悤�Ƃ����ǂ̘H���Ƃ͑��e��锤�͂Ȃ������B�@ ����͔��˂��狞�֊M�����邪�A��ǂ͂�����o�}���邱�ƂȂ��M�M�R�ɘU���ē����Ȃ������B����͌�ǂ��Ăѕ���ɖ߂点�悤�ƍl���Ă������A��ǂ͂�������ݒ���ɂƂ��ĐV���ȋ��G�ł��鑫�������鎖���咣�����B����������ɂƂ��Ă悤�₭�����킢���������ꂽ����̒i�K�ŁA�V���Ȑ킢���n�߂�͓̂�������B�܂��A�Ō�͐����ɏ�����Ƃ͂������X��ł̏����ł��������Ƃ□���̔敾���l����Ƒ������Ƃ̑����͑傫�Ȋ댯�ł���ƌ������B�����āA�`��������t����傫�Ȍ��т������ꖾ�炩�ȍߏ�̂Ȃ����������鎖�͖������������l�X�ɑ傫�ȕs����^���鎖���\�z���ꂽ�̂ł���B����ɂƂ��āA���Ȃ��Ƃ������_�ł͍����Ƃ̐��ʑΗ��͓���ł͂Ȃ��������߁A��ǂ����Ƃ��G�߂���Ȃ������B�����ŁA6��3���Ɍ�ǂ𐪈Α叫�R�ɔC���邱�ƂőÌ�����Ɏ������B�@ ��ǂ́A����ɉ����Ęa��E�I�ɂ�m�s���Ƃ��ė^����ꂽ�B�܂��A�O��ɂ��z�������i�Ƃ��Ĕh�������`�Ղ����艶�܂Ƃ��Č�����F�߂�ꂽ�悤���B���������n������_�Ƃ��āA���E�ɓ����ȂNjE���̍������Ƃ��ĕҐ������B�܂��A���̎����ɉ��B�x�z���m�����邽�߂ɋ`�ǐe����Ėk�����Ƃ����B���R�{��ݗ����Ă��邪�A�u�ۗ�ԋL�v�ɂ�����͌�ǂ��k���e�[�Ɛ}���Č���Ɋ��߂����̂ł���ƌ����B��ǂ́A�E���E���B�𖡕��Ƃ��Čł߂鎖�ŗ���ׂ��������Ƃ̑Ό��ɔ����Ă����B�������A���̎��͐��ɖK��鎖�͂Ȃ������̂ł���B�@ ���v���@ ������ɂ����āA��ǂ��V�c�㗝�߂Ă������͑O�q�����B���̍ۂɁA��ǂ͐������̗ߎ|�z�����܂̖⏊�̈��g���s���Ă�����ł��邪�A�풆�ɖ����ɕt���悤�Ăт�������̂ł��邩��i�C�̗ǂ����`�𗐔����鎖�ɂȂ�̂͒v�����Ȃ��B���ɂȂ��ĐV���Ȓ������`������ɓ����肱����S�Ď��s����͕̂s�\�ł��������A�����B�⎛�Ђ������ߎ|���e�̎��s�����߂�͔̂ނ玩�g�̐�������邽�ߓ��R�ł������B�X�Ɍ��펩�g�����l���d�|�𐔑����o���Ă���A������d�|�ƌ�ǂ̗ߎ|�ɓ��e�̐H���Ⴂ�������Ό����Ă���(�����ċ��炭�d�|���m�E�ߎ|���m�ł��H���Ⴂ���������ł��낤)�B����������������ɏ��̈��g���d�|���K�v�ł���ƒ�߂��̂́A�ߎ|�̌��͂�@�I�ɐ������Ă����������ԂɑΏ�����Ӑ}�ł������B������������̍��������������߂V���ɂ͏������ψ��g�@���o����e�����i�̔F��ɂ䂾�˂鎖�Ƃ��Ă��邪�B�����Ă��̔N��8�����ɂ͌�ǂ̐��Α叫�R����������A�ߎ|�̖������錾���ꂽ�B��ǂ͖��炩�Ɍ��킩��������A��������n�߂Ă����B�u�����L�v�Ȃǂł͎����̎q���c���q�ɂ��悤�Ɩژ_�ތ���̈����E������q��槌��ɂ��Ƃ��Ă��邪�A�P�ɂ��ꂾ���łȂ����펩�g����ǂ��댯�����x������悤�ɂȂ������߂ł͂Ȃ��낤���B�@ ��ǂ́A����ɂ�铝�ꐭ�����m�������邽�߂ɍő�̊댯���q�ł��鑸��(�����͌��킩�疼�u�����v�̈ꎚ���������)���{�̎x�z���ɂ��������͂��z�����悤�Ɛ}���Ă����̂ł���A������̗��z�̂���簐i���Ă����̂ł��邪�A��ǎ��g�̈Ӑ}�Ƃ͊ւ��Ȃ�����ɂƂ��Č�ǂ͋��Ђł��葸���Ɠ������u���q�g���̒��v�ƂȂ��Ă����̂ł���B�@ ��ǂ����X�ɓG�����������́A���킩�猩�Ă����_�댯���q�ł������B�O�q�̂悤�Ɏ���̖��̈ꎚ��^���A�����̗�ɕ킢�����E���́E�ɓ���^���A����{���R�ɔC���Ȃ�����͂�t�������Ȃ��悤�ɋC��z���Ă����B��S���Ėʖڂ����悤�Ɍv�炢�Ȃ�����_���悤�Ɩژ_��ł����悤���B���̈���ŁA�u�~���_�v�ɂ��Ό�ǂɖ����ɓ�����^���đ����������悤�Ƃ����悤�ł���B����ɂ͐�����`��A���a���N����ꖇ����ł����悤�ł��邪�A����Ƃ��Ă͊댯���q��l�����ݍ��킹�ĕЕ���|���c�����̉������悤�Ƃ��Ă����̂ł͂���܂����B�@ ����́A���b������o�p�����H�Ƃ̒��ڎx�z�����݂���L��ȋ��k�@(�{�Ɠ���)�̂�����Ɛ肷�邱�ƂŌo�ϊ�Ղ̊m����}�����A��������y�n���ɑ��Ă͒��b�⋌���{��������Ȃ�G�i���f����݂��邱�ƂŖ@�I������ڎw�����B�܂��A���ЂɊւ��Ă�����̎x�z���ɑg�ݓ���悤�Ƃ��Ē����W���I�Ȑꐧ�̐��\�z��i�߂Ă����B�����������ŁA��ǂ͔�_�Ɩ��⎛�ЁE�C�����Ƃ̌q�����f����͂��킪��Ă������ł��낤���͑z���ɓ�Ȃ��B�����ɍ����B�̐M�]���W�߂����������Ƃ̐�͍��͐�]�I�Ȃ܂łɊJ���n�߂Ă���A��ǂɎc���ꂽ�R��i�̓e�����Y���݂̂ł������B��ǂ���������z���ɑg�ݓ���A�ނ炪���ŒҎa����s���Ă����Ƃ�����b���c���Ă��邪�A���炭�͂��̎����̘b�ł��낤�B�������N6�������̉��~���P������v�悪�Ȃ��ꂽ���A���s�ɏI����Ă���B�����������������ł���ǂ͔e�C�������Ă��Ȃ������悤�ŁA���ɑ^�r�ɎQ�T��������v�̋������Ă���u�[�������ɒʂ��A�����l�ɉ߂��v�ƍ����]������Ă���B�ނ̔߂����܂ł̌Ǎ��ȈӒn���_�Ԍ�����B�@ �����Ă��ɔj�ǂ��K���B�������N(1334)11���A��ǂ͎Q�������Ƃ���𖼘a���N�E����e���ɂ���ĕߔ����ꂽ�B�V�c�ɑ���d���̋^���ƌ����ߏ�ł������B���U�������Č��g���Ă������ɕ߂���ꂽ�����M�����Ȃ������̂��A����̎�����i�������������Ɉ��ĂċL���ĉ�������߂���̂̎��͕̂���Ȃ������B������������q�ƌ���Ō���Ɍ�ǂ�槑i�����̂������Ɓu�����L�v�͓`����B����������_��ꂽ����������ɍR�c���A���킪�̕�������ɋy�Ԃ̂�����ė�����������ǂ��̂Ă��Ƃ����̂��^���ł��낤�B��ǂɂƂ��Č���͌h�����镃�ł��茣�g�̑Ώۂł��������A����ɂƂ��Ă͎���̌��Ђɝh�R���鋺�Ђł��菜�����ׂ����̂ł����Ȃ������B��ǂ͊��q�ɂ��钼�`(�����̒�)�̌��Ɍ쑗����鎖�ƂȂ����B����͌��킪�O���܂ł�����ƌ�ǂ̎����ł���Ƃ����̂��Ӗ����Ă���A���q�g���̒��ł����ǂƐS�������ɂ͂����Ȃ������Ƃ������ł��낤�B�����Łu���Ƃ����N�̂���߂����n�点���܂Ӂv�ƌ�ǂ͏q�����Ă��邪�A���R�̐S��ł��낤�B����ɑ����āA��ǂ̕����B���d���l�Ƃ��ď��Y����Ă��邪�A�����ł͓암�E�H���Ƃ��������B�o�g�Ǝv����l���̖����ڂɕt���B����ɂ�菦�Ă̐l�����N�����������ǂɂƂ��āA���B���R�{�̖k�������瑗��ꂽ�l�X���Ō�̗��݂ł��������Ƃ��@������B�@ ����2�N(1335)�M�Z�Ŗk�������̎q�E���s���I�N�����q�ɍU�ߊ��B���q������Ă����������`�͂����h�������ł���7��22���Ɉ�U�֓�����P�ނ��鎖�ɂȂ邪�A���̍ۂɕ��Ӌ`���ɖ����ėH���Ă�����ǂ��E�Q�����Ă���B�s���ɔ��������ɕ���Ė��ȓG�����������Ƃ��A�����ɕ���Č�ǂ��~�o��������ꂽ�ՂƂȂ�̂����ꂽ���߂Ƃ�������B�u�����L�v�ɂ��A���̎��Ɍ�ǂ͌�������R���Ď��œ������ݐ܂�A����͂˂�ꂽ����ڂ����J���Đ܂ꂽ�n�����ݒ��߂��܂܂ł������Ƃ����B���ꎖ���Ƃ͎v���Ȃ���b�ł͂��邪�A��ǂ̖��O��\���ė]�肠��B�Ȃ��A����ł͕��Ӌ`���������Ɍ�ǂ��~�o�����ꂳ�����Ƃ����b�����邪�A��ǂ̂悤�Ȑl�������̓����̎���ɑ�l�����p�������Ƃ͎v���Ȃ��B������ɂ����ǂ͂��̂Ƃ�������ɗ��j����p��������x�ƌ���邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B�@ �����̌�@ ���̖k�����c�}�I�N�����������ɂ��đ����͒����𖼖ڂɊ֓��������A���q��D����ɒ���ɔ�����|���B����͌�ǂɑ���R�n�Ƃ��ĐV�c�`���I�ё����Ɛ�킹�邪�A�ŏI�I�ɐ�ǂ͒���ɗ����炸����������3�N�ŕ����������ɐ����������B����͋g��ɓ���s���ȏ��Œ�R���鎖�ƂȂ�B��k�������̖��J���ł���B�@ ������ǂ��\���Ɍ�����^�����đ����ƑR���Ă�����A�Ƃ�������͋������������邪�A���̍ۂ̌����͐_�݂̂��m��ł��낤�B�����A�����Ȃ����Ƃ��Ă���ǂ����Ƃɑ��������̃J���X�}���肦�����͋^��ł���B��ǂ�(�c�q�Ƃ��Ă̈Ќ��͂��������̂�)����̗͂Ŏ��ЁE�V�������𖡕��ɑg�ݓ��ꂽ�̂Ɣ�ׂāA�������͗��̖���ŌÂ�����L�͎҂��܂߂������B�̐l�]���W�߂Ă����B�����đ������l�C���W�߂₷���l���ł���A��ǂƂ��Ă͕������������Ǝv����B���ۂɑ����ƑR�����̂͌�ǂłȂ��`��ł������킯�����A���x�͂��̋`��ƌ�ǂ��ׂĂ݂悤�B��ǂ͌��Ђ�S���I�M�]�ł͋`��������Ă��邵�l�I���E�E�헪��ɂ����Ă͗��Ȃ��Ǝv����B���A�퓬�w�����Ƃ��Ă̌o���ł͋y����͂Ƃ��ė��݂ɂł���ꑰ�̑��݂��Ȃ��B�܂��A�`��ƈႢ���킩��x������\���ȉ�����Ȃ��\���������B�`��Ɣ�r����Ƃ��L���ł��邪�A�����傫�ȍ��͂Ȃ��������B�`�傪�����ɑ����̍��������Ă������Ƃ��l����ƁA��ǂ��\���ȏ������ő����Ɛ���Ă����Ƃ��Ă����͖Ƃ�Ȃ������ł��낤�Ǝv����B�@ ���ǂݕ��̖��@ �]�k�ɂȂ邪�A�u�哃�{��ǁv�̓ǂݕ��ɂ��Ĉꌾ�q�ׂĂ������B��O�ɂ����Ắu�����Ƃ��݂̂����Ȃ��v�Ɠǂގ�����ʂł������B�c���ɂ����āu�ǁv�̎��Ɂu�Ȃ��v�̓ǂ݂Ă鎖�͂����Ό���ꂽ���߂ł���B������80�N��Ɂu�����Ƃ��݂̂����悵�v�Ɠǂގ����㉡���h���ɂ�����A��̓h���}�u�����L�v���_�@�ɐ��Ԃɂ��蒅�����B���̘_���Ƃ��Ă͈ȉ��̒ʂ�ł���B�@�u�ї��ƕ����v�ɂ����鐳��6�N(1351)�헤�e����g�𖼂Ɂu���������݂̂�v�Ƃ��鎖�A�A�ߔ�V�{�_�Ђ̐���2�N(1347)�u��ʎ�o�v�����Ɂu�����{�v�Ƃ��鎖�A�B�u�����L�v�Îʖ{�ł��鐼���@�{�Łu�哃��i��ǁv�Ɂu�^�E�v�ƐU�艼����������������u�����Ƃ��݂̂�v�Ɠǂ����m����B�u��ǁv�ɂ��ẮA�Z��B�ɂ��Ĉȉ��̂��Ƃ��m���Ă��鎖����u����悵�v�ł���Ɨސ����ꂽ�B�@����4�N(1371)�u��n�}�v�ł͌㑺��(�`��)���u�`�V�v(�{���u�V�`�v�Ə������Ƃ����Ǝv���A�u�̂�悵�v�Ɠǂނ̂ł��낤)�ƋL���Ă��鎖�A�A���i15�N(1408)�u�l���S���L�v���㑺����u�V�ǁv�Ə����u���V�v�ƐU�艼�����Ă��鎖�A�B�u�����v�Ɂu�^�J���V�v�u�����V�v�ƐU�艼���������̂������鎖�������̍c�q�B�́u-���V�v�ƌĂ�Ă��������m��ꂽ�̂ł���B��k���ɂ�����w���E�l���]���͐�O���Ō��ς��������Ȃ��Ȃ����A��ǂ̓ǂ݂����̈�ł����O����ɂ͐V�����ǂ݂����ɂ��ăV���b�N�����Ƃ����b���������B�u���P����v�Ƃ��Ă̐��i������������O���j����Ǝ����d���㋳��̍��ق��ے�����b�ƌ����邩������Ȃ��B�@ �������ƍc�q�@ �Ƃ���ŁA�����ɂ����Ă͗L�\�ȍc�q�͗��������x���ɂȂ肤��Ɠ����ɁA���҂̌��Ђ��������҂Ƃ��đa�O�����X��������悤�ł���B�����āA���������ꍇ�ɂ����ē���E�l�C�͍c�q�ɏW�܂鎖����ʂ̂悤��(���_�A���҂ƍc�q�̂ǂ��炪�������ƌ����̂ł͂Ȃ����҂ɂ͉��҂́A�c�q�ɂ͍c�q�̎������킯�ł��邪)�B����������Ƃ��Ă͓V���V�c�̎q�ōc�@(��̎����V�c)�ɖd���̍߂𒅂���ꂽ��Íc�q���m���邵�A�����Ɍx������l�����ꂽ���`�o�����̌n���ɕ��ނ�����ł��낤�B�����āA�������������͉䂪���ɂ����Ă͓��{�����ɋ��߂���悤���B��ǂ����̗�ɘR�ꂸ�A�O�q�̂悤�Ȑ������������邱�Ƃ����������悤�ɖ��O�̓�����Ă�ł����̂ł���B�@ �ߑ�ɓ���ƁA�c���ւ̒��`���ې����邽�߂ɓ쒩�̌��b�B����������ړI�������āA��ǂ��H���ꂽ�Ƃ����`���̂���(�j���Ƃ͈قȂ�)���A���_�ЂƂ����J����悤�ɂȂ����B��ǂ��Ր_�Ƃ��銙�q�{�ł���B���{������u�ߌ��̍c�q�v�����u�쒩�̒��b�v�ȂǂƓ��l�ɁA���̔ߌ��⓯��������N�����̋����Ƃ��ė��p�����ɂ��������Ƃ�����B�@ ���@ ��ǂ́A�����ɂ����Ă͎�����̑��i�ߊ��ł������B����̍c�q�Ƃ��Ă͈ٗ�ɂ�����擪�ɗ����Đ��ɐg��u���A�e�n����Q���č����ƌ����z���ɑg�D�����B����̐������c�q�B�̒��ł����o�������݂ƌ����邵�A�c���̗��j�̒��ł����Ȃ�ۗ��������݂ł���B�������Ȃ��炻�ꂪ�Ђ����ĕ��E����̌��Ђ����������݂ƔF������ߌ��Ɍq�������B��ǂ͗]��ɂ�����Ɏ������Ă���A�����ʒu���߂������̂�������Ȃ��B �@ |
|
 �@ �@���k������ (1303-1333) |
|
|
130�N�̗��j�������q���{�A������x�z�����k�����B���̍Ō�̓���ł��鍂���̐��U���T�ς��A�₪�Ă͓�k���̓����Ɏ���14���I�̎Љ��k�����ɋ߂����_���猩��B�@ �������̏�@ �䂪���ɂ�����8���I�����Ɋ������������W���I�ȓ��ꐭ���́A������9���I�ɕ���̒������������B���Y�͂̌���ɔ����n�x�̍����g�債�A�n���w���v���������ŕx�T�������n�������ɂ�莩���̐����e�n�Ō`������Ă����B�������{(����)�͍����B�̗�����ٔF������Ȃ��Ȃ�A�l���c�����Đl���ł��Ƃ��������y�n�P�ʂŐŎ������m�ۂ���̐��ɕ��j�]�������B�������đ�y�n���L�ҁA���Ȃ킿�L�͋M���E���Ђ�n�������ɂ��A���̖̂���Ƃ��Đ��{(����)�����Ղ����u�������Ɓv��10���I����11���I�O���ɂ����Đ����B�@ �₪�āA�n�������̎��͌���ɔ����ނ���x�z���ɑg�ݓ��ꂽ�R���M�����䓪�B12���I���ɂ͌R���M���̑�\�҂ł��錹���E�����ɂ��������o�āA�����{�ɌR�������ł��銙�q���{�����������B���{�͒���̏@�匠�𖼖ڏ�͔F�߂������{�𒆐S�Ƃ����Ǝ��̎x�z�̐����m���B���삪�����{�A���{�������{���x�z����`���o���オ��B����13���I�O���̏��v�̗��ȍ~�͌R���͂ɏ��開�{�����|�I�ȗD�ʂɗ����A����ɐ����{���܂߂��L���n��Ɏx�z�����L�����B�@ ���k�����E������������@ �k�����͊��������̖���Ƃ���Ă��邪�A12���I�㔼�ɂ�����k�������̎���ɂ͈ɓ��̒��������ɉ߂��Ȃ������Ƃ�����B�����̓����ł��錹�������s��Ă��̒n�ɗ��Y�ƂȂ�A�����̖��E���q���ȂɌ}���Ă���^�����ς��n�߂�B�������������A���q�����_�Ƃ��Ċ֓��肵�X�ɕ����Ƃ̑����𐧂��R������������������ƁA�����̎�u���q�a�v�̊O�ʂƂ��ĉe���͂𑝂��悤�ɂȂ�B��������A�����E�`��(�����̎q)�E���q�͏��R(�u���q�a�v)�̊O�ʂƂ��āA�����ď��R�̋����ɔ��������Ɛl(���R�Ǝ�]�W�ɂ��鍋��)�̑�\�҂Ƃ��ď��R��Η�����L�͎҂�r�˂����{���Ő��͂����߂�B�������n���f�₷��ƁA���q�����R���͂��s���`������Ɛl�̑�\�Ƃ��Đ��������`�Ō��͂��������B���v�̗��Œ���Ɉ���������͍X�ɂ��̗͂����߁A�`���̎q�E���͗L�͌�Ɛl�Ƃ̋��͑̐������߁A���{�ɂ������{�@�ł���䐬�s���ڂŒm����悤�Ɋ��K�E�������d�鐭���^�c���s���L���x�����W�߂��B���͕]��O���A�����̎���ɂ͑i�אR�c�̂��߈��t�O��݂���ȂǁA�L�͌�Ɛl�̍��c������肻�̋c�����Ƃ��Ėk�����͒n�ʂ��m�������Ă������B���ɂ������͋��s��Ԗ��Ȃnj�Ɛl�̕��S���y��������_���̕��S�ɋC��z�芩�_���s���x�����W�߂��̂ł���B�������A����Ŗk�����ɔ������鐨�͂������A�ނ�͖��ڏ㖋�{�̎�ł��鏫�R�̌��Ђ𗧂ĂĖk�����ƑΗ�(�k���ꑰ�̒��ɂ��k�����y�̂ƑΗ������R�ɋ߂Â����̂�����)�B�O�Y�ב��ɑ�\����邻���������͂�r�˂��n�Ղ��ł߂钆�ŁA��������̌㔼�ɂ͖k�����ɂ��ꐧ���̌X����������悤�ɂȂ��Ă����B�]��O(�k���ꑰ�͑�����ɂ�19�l��5�l�ł������̂���������ɂ�13�l��5�l)����ɖk���ꑰ�̐�߂銄�������܂����̂͂��̈��ł��낤�B�@ ���k�����E���@�ꐧ�ց@ �����͏o�Ƃ��Ď���(���R��⍲�������������ځB�k��������X���̒n�ʂɂ��Ă���)����ނ����I�n�ʂ������Ȃ��Ȃ�������A���{����̎����͈��葱���Ă����B�����Ă��̎q�E���@���c��������p�҂Ƃ��Ėڂ����B�k�����������ɂ�����ō����͎҂̍��������p���ł������͌Œ�I�Ȏ����Ƃ��Ď~�߂���X���������Ȃ����̂ł���B���I�n�ʂł���u�����v�Ƃ��ĂłȂ��k�����y�̂Ƃ��ďd��ꌠ�͂�����l�q�́A����ɂ����Č��I�n�ʁu�V�c�v���c������ł���u���V�̌N�v�������������Ă����̂Ǝ��Ă���B�����������ŁA�k�����̉Ɨ߂������̑㊯�Ƃ����������ʂ����悤�ɂȂ�u���Ǘ́v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�܂��A���@(�k�����y�́A�`���̖@���ɗR��)�̎��@�Ŕ閧��c���s���A�����Ől���E�y�n���ɂ����钆���M���Ƃ̐ՁE���x�̒����ȂǏd�v�Ȑ������j����߂���悤�ɂȂ����B����͂₪�āu�v�Ƃ��Č������x������悤�ɂȂ��Ă����B�@ ���@�̎���ɂȂ�ƁA���R�E�@���e���ƑΗ��������ɏ��R��オ�s��ꂻ�̊ԂɎ��@���u���q�a�v�㗝�Ƃ��Č�Ɛl�Ƃ̎�]��������Ɏ��߂�悤�ɂȂ�B���ꂪ���̌o�߂Ƌ��ɌŒ艻�������^�E��]�W�Ƃ��������R���͂̑�s��k�����y�̂��s���悤�ɂȂ�B�܂��]���͕]��O�̎�ɂ��������ʐ��E�������R�̎�Ɉڂ������I�ɖk�����̈ӎv�����f�����悤�ɂ��Ă���B�܂���̌����ɂ�荑�Ƃ������Ėh�q�ɓ�����K�v�����������Ƃ�����A�]���͖��{�̗͂��y�Ȃ����������M���̂̍����ɂ�������������悤�ɂȂ�Ȃǐꐧ�I�ȌX�����������Ă������B�܂��A�O�I�h��̂��߂������ĎR�A�E���˓��E��B�̗v�n��k���������Ƃ��Ĕc���A��ʗv������ӂ̏��H�Ƃɏ]�����鍋���B���x�z���Ɏ��߂邱�ƂŌo�ϗ́E�x�z�͂����߂悤�Ƃ����B�Z�g���T��(���ɂ����開�{�̋��_�ŗ�㒷���͖k�������y�o)���ےÁE�O�g�E�d�����A�����T��(������ɋ�B�NJ��̂��ߐ݂����k��������C)����O������悤�ɂȂ����̂͂��̈��ł���B�@ ���@�̎q�E�厞�̎���ɂȂ�ƁA��ւ�肵�ĊԂ��Ȃ��O��7�N(1284)5���O���@�E�㔼�����R�ɑt�シ��`���ƍl������@�߂��o����A���R���Ђ̍Ċm�F�Ɠ����ɓ��@�n�ʂ̌��������}��ꂽ�B���O��8�N�ɂ͐��������Ɏc�����L�͌�Ɛl�ł�����B�א��ꑰ(�厞�̊O�ʂł����蓾�@�̐g���Ƃ������i������)���łڂ���(��������)���Ǘ́E�����j���c���̒厞��⍲����`�ŋ�����U�邤�B�S���ő����̔��Δh���ŖS�̗J���ڂɉ�A����ɓG�ł��鐨�͂͑��݂��Ȃ��Ȃ����B���̎����A���j�̎q�ł���я����@���܈ʌ����g�����ɏ��i���Ă��鎖�������̌�����@���ɕ\���Ă���B�ނ��A���j�͎���̈ꑰ�����łȂ��厞���k�����̋Ɋ����z�����]�l�ʉ��ɔC��������Ƃ̌��Џ㏸��}���Ă���B�@ �厞����������ƁA�i�m���N(1295)�ɐꌠ��U��������j��łڂ���(���T��̗�)�����@���g�̎�Ɏ��߂��B�܂��厞�͓y�n���߂���i�ׂ̑����E�������ւ̑Ή���ł��o�����B���c���̂��ߐR�c�����������Ă������t�O��p�~���A���t���l�ɂ��v���ɔ����������悤�ɂ����B����͗��N�ɂ͒��f������t�O�������������̂́A������_�@�ɒ厞������������悤�ɂȂ�B�܂��ĐR�@�ցE�z�i����p�~������l(�k�����Ǝ�]�W�ɂ��鍋��)�ܐl�ɂ�舵�킹���B�܂��A���̎����ɍ��i�ɉ����Ȃ��҂�ƍ߂Ƃ��ď��f����A�ٔ��ɂ�����咣���e�̒lj��͋֎~����A�]���͖��������ł��������c�T�S�E�H���T�S���Y�������Ƃ���Ƃ��������v���Ȃ��ꂽ�B���Ă͊��ᑸ�d�E�����Ҏ�`�Ő��m�����d�Ă����y�n�֘A�̑i�ׂ́A���̎����ɂ͋���Ȍ����͂�w�i�Ƃ����@�I�ȋ����@�ււƓ]�������̂ł���B�c��Ȑ��ɏ��y�n���ւ̑Ώ��Ƃ��Ă�ނȂ��ʂ͑傫���������A���ꂪ���@�̋����𐧓x�I�ɗ��t������̂ƂȂ����̂������ł���B�@ ���āA�y�n�֘A�̑i�ׂ����傷�錴���Ƃ��āA��Ɛl�̋��R����������B���͈̂ꑰ�ŕ�����������̂��ʏ�ł���A��ւ�薈�ɗ������͔̂������Ȃ������B�����āA���̍��ɔ��B�����ݕ��o�ςɊ������܂�o�����A�X�Ɍ����ɂ��R�S�̑����ɂ��o�ϓI�ꋫ�������|�������B�����ɂ��̒n�����債����ł͂Ȃ����߁A���܂ɓ��Ă�y�n���s�������������̖��ɔ��Ԃ��������B���R��k�����̓y�n���ꕔ�ו������ĉ��܂Ƃ�����A�d���l�Ȃǂ̏��̂�^���鎖�őΉ����Ă������ƂĂ�����Ȃ������̂ł���B������������A�{��(�y�n�Ɍ������������M��)����Ɛl�E���l�ɔ��p��������Z�Ǝ҂��������ď��̂������ꂳ�����Ɛl�����o�����B����ɍD�s���ł��鎖����؏�(������)�E�R�m�Ƃ��������Z�Ǝ҂�㊯�Ƃ��ėp���A�ނ�Ɏx�z����D���������������B���̌��ʁA�y�n�������Ȃ��u������Ɛl�v���������܂��Ɛl�̖v���������Ă����̂ł���B����������Ɛl�B�̋~�ς��d�v�Ȑ����ۑ�ł������B��Ɛl�ɂ͖��{�̐����ɂ�芯�E�ɂ���A����葱�Ȃ��ł͑ߕ߂���Ȃ��Ƃ��������������邾���łȂ��A�u���q�a�v�̒��b�Ƃ��Ă̌ւ���������Ƃ�������ӎ��������������̂���K�w�ƂȂ��Ă����͔̂ۂ߂Ȃ��B�@ ���{���R���I�Ɏx���Ă����ނ�̗v���ɉ����A�o�ϓI�E���_�I�ȋ~�ς�����K�v���������̂ł���B�厞�͖@�I�ɔނ�̌�Ɛl�g����ۏ���Ƌ��ɁA�i�m2�N(1297)�����߂z�����B���̖@�߂ł́A�܂��i�ׂ̑����┻���̕s���艻�ւ̑�Ƃ��ĉz�i(�ĐR����)���֎~���A������Ɛl�~�ς̂��߂ɔ��p�n�̕ԋp�𖽂����B�����ɂ͉��������鎖���20�N�ȏ�o�߂�������͕ԋp�ł��Ȃ��ƒ�߂����A��Ɛl�ȊO�ɔ��p�����ꍇ�͖������ŕԋp�ł���Ƃ���Ă���B�@ �܂��A�K�̑ݎɊւ���i�ׂ�s�Ƃ����B������؋��ɔY�ތ�Ɛl�ւ̋~�ς��ړI�ł��낤�B����������͋p���ĎЉ�̍����������A��N��ɒ�~������Ȃ������B�@ �܂��A�h�q��d�v�ȋ�B�𒆐S�ɁA�O�q�̂悤�ɔ��Ɛl�������������{�̎x�z���ɑg�ݓ��ꂽ��A���n�̏��q��y�̂���Ɨ����鎖���������肷��Ȃnj����I�ȑΉ���]�V�Ȃ�����Ă������A���ꂪ��Ɛl�Ɩ��{�Ƃ̎�]�W��h�邪�����ƂȂ��Ă����B�܂��A�����{�𒆐S�ɁA���Ɛl�E���H�Ǝ҂���Ɛl�ɂ����D�ɑ��Č�����������������Ⴊ�ڗ��悤�ɂȂ��Ă����B����13���I�������薋�{�E����̐�����O�ꑑ���Ɏ��͍s�g����u���}�v�����ƂȂ��Ă������A���̎���������ɖڗ��悤�ɂȂ��Ă���B�@ ����������������������ł��鉞�����N(1311)�A�厞�͕a�v�B�Ղ��p���œ��@�Ƃ��Ė��{�̒��_�ɗ������̂�����̎�l���ł��鍂���ł���B���ɋ�B�@ �����@�k�������@ �����͉Ì�3�N(1303)�厞�̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B7�Ō������āu�����v�Ɩ����A10�Ő��܈ʉ��E���n�����ɔC�������B������14�ɂȂ�Ǝ����ɏA�C��15�ő��͎�ƂȂ����B���݂ɁA���̃R�[�X�͑c���E���@�╃�E�厞�ƂقƂ�Ǔ���ł���(���@��14�ŏA�C�����̂͘A���A���Ȃ킿�������ł��邪)�A���@�̊��E�����d���ƂȂ��Ă������Ƃ��f����B�@ �������Ė��{�̒��_�ɗ����������ł��邪�A�]���͖F�����Ȃ������B�ꑰ�̋���匰�́u�c�y�̊O��������v�u�A������A�c����������������ʂƂ��s�o��A�V����v�ƋL���Ă���悤�ɁA�����E�c�y�ɋ����Đ�����a���ɂ��Ă����Ƃ�����B�u�����L�v�ɂ��Γ����ɂ��M�����A���q���Ɍ�����ꂽ�Ƃ�������B��̓���͌������ł��u���c�y�n�֓��m�@�z���t�����g�]�i�J���v�Ƃ��邽�߁A�������c�y�ɕ��ѓ������D�͎̂����ł��낤�B�܂��a�C�����ł��������悤�ō������͑��l�Ƙb�����邱�Ƃ��ł����A�u�v�䍿���Ȃ͂ʌ䎖�Ɍ�v�Ƃ��匰�͋L���Ă���A�����̕a��Ɉ���J������e�̏�����u���Ɂv�ɂ͎c����Ă���B�u�ۗ�ԋL�v�ɂ��u���S�C(����)�m軀�j�e�A���R�ƃm���������C��J���P���v�ƋL����A�u������軀�i�L�ԁA�����S�j�C�Z�e�V���m�����s�t�B�l�m�V�L�σ��P���o�A�֓��m���h���j���[�N�a���j�L�B����j�ʊ��ʊ�(�͂���)�V�J���W�i�h�\�Z���v�ƕ]����Ă���B�������t���R�m�_�ɎQ�T���A���E������D�����m���Ă���A����u��R�m�_���v��`���Ă�����B�K�������Ë��ł͂Ȃ������I�f�{�ɂ��s���͂��Ă��Ȃ������Ƃ����邪�A�S�ʓI�ɂ͏�q�̂悤�ɍ������a��̂��ߐ������Ƃ炸�A���̎w���͂ɂ����Ă͑S���]������Ă��Ȃ������Ƃ�����B�ԉ��@�����̓��L�u�ԉ��@���L�v�Łu�ߔN�����L��S�A�֓��������l�̌̂��v�ƋL���Ă���悤�ɒN�����{�����������Ă��邩���O����͌����Ȃ������Ƃ�����B�����A���̎����ɖڗ��������тƂ����Ε���2�N(1318)���猳�����N(1319)�ɂ����ē��@�@�Ƒ��@�h�Ƃ̘_���������A���@�剺�����@��_�j�������ߑ�ڂ̕s������������(���q�a���ⓚ)�ʂł���B�����Ƃ��A���炭�͑�߂Ȃ������^�c���Ȃ���Ă����Ƃ������Ƃ��o����B�@ �����@�ꐧ���̐����^�c�@ ���������@�Ƃ��ČN�Ղ��Ă��������A���{�����͂ǂ̂悤�ɍs���Ă����̂��A������������Ă݂悤�B�@ �����ɂ����Ď����I�ɍō�����@�\�������Ă����̂��u�v�ł���B��������ɂ��̎��@�Ő������j�����߂�閧��c���s�������ɒ[���邱�̉�c�́A�₪�Č����������@�E���Ǘ́E�����E�A����ꑰ�L�͎҂ɂ��s��ꂽ�B�ȑO�ɂ����Đ����ٔ��ɑ傫�Ȗ������ʂ������]��O�E���t�O���k�����̊������������A���t���l���k�����ɂ���߂���Ƌ��ɍ\�����̎�N�����i�s���Ă����B�]��O���ɂƂ�Ƌ`������ɂ�19�l��5�l�ł������̂����@����ɂ�10�l��5�l�ƂȂ��Ă���A�₪�ď\��ŕ]��O�̍����߂���������悤�ɂȂ��Ă���B����炪�����\�͂��Ɗi�ɂ��\���������肳���悤�ɂȂ�A������D���Č`�[�����Ă������Ƃ�������B�@ �܂��k���ꑰ�����E�ɐ�߂銄�����㏸���Ă����B������ɂ�39������11�����ɗ��܂��Ă����̂����@����ɂ�52������27�����ƂȂ��Ă���A��������Ɏ����Ă�57������30�����ɂ̂ڂ��Ă���B���ł����@�Ƃ͕����E�ɓ��E�x�́E�ዷ���̎��E�����C���Ă���A�o�ρE�R���͂̋��傳���f����B�@ �����������ŁA���{���̖�E����ɉƊi����߂��Ă������B�ł��i���������Ƃ����̂��u�O�v�ł���A���@�Ƃ��܂߂ĊɎQ������̂�F�߂�ꂽ�L�͈ꑰ�ł���B���@�ƁA�k���@��(���@�̒�)�n�A���z����n�A�ԋ��A�������A�k�������n�A�����n�A�啧�Ï@�n������ɓ�����B����Ɏ����̂��u�]��O�Ɓv�ł��薼�z����n�A���c�Ȃǂ�����ɑ�������B�����Ă��̉��ɂ��̑��̈ꑰ���ʒu���Ă����̂ł���B�@ �k����傾���łȂ��A����l�̊Ԃł��Ɗi��������Ă����B����(���Ǘ�)�ƂȂ肤��ƌn�Ƃ��Ē���E�z�K�E����������A����Ɏ���������⍲���鑶�݂Ƃ��Ĉ����E�H�����ʒu���Ă����B���ł��L�͂������̂����莁�ł���A���ۂɎ����ƂȂ����̂͑唼�����̈ꑰ�ł������B�ނ�͎������i�𐢏P���Ă���A�����ĊO�E�����̐E�����������̑��ݍ�p�ɂ�苭���������m�ۂ��Ă����̂ł���B�����Č���l�̋߂��E�͎��オ����ɂ�đ��債�Ă���B���q�s�����i��n��s������l����C���Ă������A�����ɂ͕]��O�̒������L���Q�ۂ����������߁A���R�ƌ�Ɛl�̎�]�W���i��䉶��s�ɂ��牖�O�����C�����Ă���B�k�����̖��{�ւ̐N�H�̐[����\���Ă���B�@ ���̎����̐����^�c�ɂ����āA�l���E���̏����E���ʏ��i�Ɋւ��Ă͒���~��E�������q����B������������⍲����`�ň����Ă����Ƃ�����B���������Ŏ��r�������̈��B�����Ăі����̗v�E�������Ă������Ƃ��āA���T��̗���ɒ厞���ނ�̕�����i�߂����Ƃ�����A�X�ɓ��Ǘ̂ƈ��B�������@��⍲����Ƃ������@����̌`������Ƃ��ďd������ƌ����Ă���B�@ �ȏォ�番����悤�ɁA���̎����̖��{�����͉Ɗi�E���d���ōs���Ă��肻�̓_�ł͒���ƕς��Ȃ��B���������Ȏ�N�Ŗ��{�̒��_�ɗ������̂�������������ɂ����̂ł���A�ގ��g�̎����\�͓͂���������҂���Ă��Ȃ������ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B����͓��@�_�Ƃ��������^�c�̐��̊����E���n���Ӗ�����Ɠ����ɁA�`�����E�d������������ł͈Ӗ����Ă����B���ꂪ����s����ɍۂ��Ă̑Ώ����������̂ł���B�@ �������̎Љ�@ 13���I�㔼����A�E���𒆐S�ɐ��Y�͌���E�C�O���Ղ�w�i�ɂ��ď��ƁE�ݕ��o�ς����B�B����Ŏ嗬�ł������_�ƌo�c���c�ލ����B�́A�ݕ��o�ςɊ������܂�ďo����債����A���������ŏ��̂��ו�������Ȃǂ̗v���Ŗv������҂�������悤�ɂȂ����B�k�����ɂ�錠�͋����͈�ʌ�Ɛl�̖v���ɔ��Ԃ��������ʂ�����A���{���ނ�̋~�ςɏ��o�������\���Ȑ��ʂ��������Ȃ��������͑O�q�����B�������Č�Ɛl�w�ɖk�����ɕs��������҂������B�@ ����A�k�����́A�ꐧ�I�Ȍ��͂��ł߂�ɓ����菤�ƁE��ʂ̗v�����̂Ƃ��đg�ݓ��ꂽ�菤�H�Ƃɏ]������V���������Ɛb�Ƃ��Ď�荞�ނȂǁA���H�Ǝ҂��x�z���ɒu�����ƂŌo�ϓI�Ȏ��͊�Ղ����悤�Ƃ����B�������A�����̐V�������͓`���I�ɒ���ƊW���[�����̂������K�����������ɂ͉^���A�J�듌�������̎�̂ł���k�����ɔ���������̂����Ȃ��Ȃ������悤�ł���B�������������̐V�������̒��ɂ́A����E���{�̌��Ђɏ]�킸���͂ŏ��̂��r�炷�s���ɏo����̂����Ȃ��炸���݂��A�Љ�s���v�f�ƂȂ��Ă����B�@ ����Œ���͋��s���ӂɎ��͂����肳��Ă���A�������c���E��v�M�������Ă���L�l�ł������B���{�͂���ɑ��ĉ�����������鎖���]�V�Ȃ�����Ă���A�Ƃ�������݂��₷���ł������B�@ ���@�����͕K���������ז���łȂ��A�V��������ɂ���Ȃ�ɑΉ���}���Ă����̂ł��邪�A�p���ČǗ��̊댯�ɎN����Ă����̂ł���B�������Ȃ���k�����A���Ȃ킿���{�ȊO�ɓ��{��������������͎҂͑��݂����A���{���|���Ζ����{��ԂɂȂ�\�������O�����A�����������ł������B�@ ��������d���@ �O�q�̂悤�ɍc���͎����@���E��o�����ɕ��Ď哱�����������Ă���A���{�̒��₪�s���ȏł������B�����������A14���I�O���ɑ�o�����������V�c�����ʁB����͐��͓I�ɉ��v�𐄂��i�߁A�����ӂ̏��H�ƎҁE���_�Ɩ��̎x�����l�����邱�ƂŐꐧ�I�Ȑ����^�c���u������B����������͑�o�����̖T���o�g�Œ��p���Ƃ��Ă̑��ʂł��������ߔނ̎q�����c�ʂɂ��\���͒ʏ�ł͍l�����Ȃ���Ԃł������B����̎q���Ɉʂ��p�������߂ɂ͍c�ʌp���̒�����ł��開�{�̑��݂͂����Ă͂Ȃ�Ȃ������B�X�ɁA�������钩�삪���͂����߂����{�̓����҂Ƃ��Ă̎��������邽�߂ɏ��H�Ɛ��͂���荞��ł̓|�����K�v�ł���ƌ���͍l�����̂ł���B�@ �������Đ������N(1324)�A����͖k�����ɕs�����������𖡕��Ɉ�������A�k��V���{�̍�ł̓��킢�ɕ���ċ�������v��𗧂Ă�B����������͂����ɘI�����A�v��҂Ō��푤�߂̓���r��E�����炪�߂炦��ꂽ�B�����̓V�c�����̐���]�����悤�ƌv�����O�㖢���̎����ł���A�l�X�́u������d���v�Ƃ����₫�������Ƃ����B����͎��Ԃ����E���邽�߂ɖ������H��[�����q�Ɏg�҂Ƃ��Ĕh���������Ɩ��W�ł���Ǝ咣�B���{�͂�����ēV�c��s��Ƃ��A���������n�֗�������叫�Ɍܐ�̕���^���Z�g���T��ɏ풓������ɗ��߂��B���Ƃ������I�ȑΉ��ł��邪�A���̎��A���{�Ƃ��Ă͌R���I���͂������Ȃ�����ɗ]��ւ�肠���Ď��Ԃ������点���Ȃ�����������̂ł���B�@ �������������̗��@ ���̍��A���{�͉��B�ł̕����ւ̑Ώ��ɔY�܂���Ă����B�����ɂ�����k�����̑㊯�E�������̓����ł���B�@ �������͋`������ɉ��B�ɑ㊯�Ƃ��ĉ������A�\�O���𒆐S�ɉ��H�E�n�����x�z���ăA�C�k�Ƃ̌��Ղɏ]���B�u�ڈΊǗ́v�u���{���R�v�ƌď̂����L�͎҂ł������B�ނ�͉��B�ɂ����ĉ��݂̖����x�z���ɒu���Č��n�̏��H�Ƃ�c�����Ă����Ǝv����B�@ 1320�N���납��A���̈����������ŏ\�O�������_�Ƃ����G(�Ìy�������A������)�Əo�H�ɐ��͂�z�����@�G�E�G�v(�H�c�������A�㍑��)�̑������N�����Ă����B���{�͂��̒����}�邪�A�s���ɏI����Ă���B���Ǘ̒��荂�����o������d�G��������̂������Ƃ�������B�₪�ė��w�c�ɉ����ĉڈ��������A���B�S�y�ɂ킽���Ă̑����ɔ��W�����B�@ ���{�͐������N�ɒ����ł����G����C���@�v��㊯�ɔC���������A���ꂪ��G�̋������R���������B�×�N(1326)�ɍH���S����h�����ċG����߂������邪�A�����헐�͒��É����Ȃ��������߂ɗ��N�ɂ͉F�s�{����E���c���m�����h�����ė��N�ɂ悤�₭�a�c�Ɏ������ނƂ��������ɂȂ��Ă���B���������k�����̐��͌��ł̖k�����Ɛb�ɂ��헐���J�����˂Ă���Ƃ������Ԃ́A���{�̈АM��ቺ�������˂Ȃ����̂ł������B����ɉ����ĐV���ȉΎ����������Ȃ��A�Ƃ����̂����틓�������̕�ɐڂ����Ƃ��̖��{��]�̖{���ł������낤�B�k����������ɋ����ԓx�������Ȃ������̂ɂ́A�����������䗠���������̂ł���B�@ �����q�����ł̈Ó��@ �×�N(1326)3�������͎����̐E��ނ��ďo�Ƃ����B�@���͏@�ӁB�a�̂��߂Ƃ���Ă��邪�A�����E���@�E�厞�������悤�ȔN��ŏo�Ƃ��Ă��肱������@�Ƃ̐��ƂȂ��Ă����\���͂���B���̎��ɐ������̗L�͌�Ɛl���t���]���o�Ƃ��Ă���B���āA��(�����̒�)�����̎����E����]������̂́A�����͔F�߂��k���ꑰ�L�͎҂ł������匰�������Ƃ����B�Ƃ͕����邩���Ȃ��A�o�Ƃ��Ă��܂����B����́A�����Ȓ匰�Ȃ瑀��₷���ƍ����������߂ƌ����Ă��邪�A�Ƃ������ɂȂ����ꍇ�ɂ͓��@�Ƃɓ��傪��l�����邱�ƂɂȂ蕪��̉Ύ�ɂȂ邱�Ƃ��\�z����Ó��Ȕ��f�ł������ƌ�����B���ďA�C���ɂ͊�т������Ă����匰�ł��邪�A�킸��1�����݈̍ʂŎ�����ނ��o�Ƃ��Ă��܂��B�����炭�͑Ɛw�c����̋������͂�������ꑱ���Ă������̂Ǝv����B����ďA�C�����̂́A��͂���̗L�͎҂ł���ԋ��玞�B���q���{�Ō�̎����ƂȂ�l���ł���B�@ �����̒n�ʂ��߂����Ėk���ꑰ���ňÓ����J��L����ꂽ4�N��̌���2�N(1330)8�����荂���E�H�����Y�炪����~��(�厞����ɓ��Ǘ̂߂��B�����̕�)�ƍ����̈ÎE���v�悵�����Ƃ��I���B�������ނ�ɖ����ē��Ǘ̕��q�����悤�Ƃ����ƌ����Ă���B���ĕ��E�厞�������j�̐ꉡ�������Ă���������������߂����O��ɕ킨���Ƃ������̂ł��낤���A���̎��͎��s�ɏI������̂ł���B�ނ��A�������Ă����Ƃ��Ă������ɂ��̌�̐��ǂ������͗ʂ����������͋ɂ߂ċ^��ł��邪�B�@ �Ƃ�����A�k�����̐����͑S���I�ɌǗ���i�߂�݂̂Ȃ炸�A���B�E�E���ɉ����ē����ɂ��Ύ�������ł������B����V�c�ɂ��Ăѓ|���������グ��ꂽ�̂́A�������������������̂ł���B�@ �������̐��ց@ ����͑O��̎��s�Œ��߂��A�Ăѓ|����ژ_��ł����B�V���Ɏ��А��͂ɍc�q�E��ǐe���ȂǑ��̊|�������l���𑗂荞��ł��̌o�ϗ́E�R���͂𗊂݂ɂ��Ĕނ�̎�荞�݂�}������ŁA���O���N(1331)�������}�u�R�ɘU�����B���̎��A����͓ޗǁE���厛���ւ�ɂ����̂ł��邪�A�k���������А��͂̔c����ӂ��Ă͂��炸���{���̗v�l�������ɑ��݂������ߊ}�u�Ɉڂ����̂ł���B���̎��_�ł��A���{�����ɂ͂Ȃ����ւȉ�����͍����铮�������������A�������Ɏ����Ă͐��ʂ���̌R���Ό��͔������Ȃ������B���{�̌R���͖͂������|�I�ł���}�u�͊ח����ĕ߂���A�����@���̗ʐm�e��(�����V�c)�ɏ��ʂ�����ʼnB��ɗ����ꂽ�B�@ �������A����̗U���ɉ����ĉ͓��ŋ������Ă�����ؐ����͌��O3�N(1333)���{�R��|�M������ŋ����R�̐瑁��ɘU��B�܂��A����̍c�q�E��ǂ͊e�n�̍����ɋ��������Ƌ��Ɏ��g���g��ɘU�����B�АM��������ꂽ���{�͑�R�����g����ח���������̂́A�瑁��͍U�߂����˂�B������āA�d���̐ԏ��~�S�̂悤�ɂ��˂Ă��疋�{�ɕs��������������e�n�ŗ����オ�����B�ޓ��͂��̍�����ɂȂ������Ƃ�w�i�Ƃ���V�������₩�Ė��{�ɓG���s���Ɋׂ����n�����������S�ł������B�₪�Č��킪�B��E�o�����a���N�Ɍ}�����Ĕ��ˑD��R�ɘU��B������̈ӋC�͓V���Ղ�����ƂȂ�A���͐ԏ����ƌ��풞�b�̐�풉���ɂ��U������ŋ��ɂ����開�{���̋��_�E�Z�g���T���芙�q�ɉ��R�˗����o�����̂ł���B�@ ���I�� ���O3�N(1333)�@ ���ւ̉��R�Ƃ��Ĕh�����ꂽ�̂͑��������ł������B�������͌����̒����ł���A�{���Ȃ�k�������Ɗi�͏�̑��݂ł���B�܂��O�́E����𒆐S�ɑ����̏��̂����L�͎҂ł���A�k��������ڒu���đ�X�����W�����шꑰ�ɏ����鈵�������Ă�������ł������B�������A�������Ƃ��Ă͖k�����ɂ�鈳�͂�₦�������Ă����ł��낤���A�L�͍��������X�ɔr�˂����̂�ڂ̓�����ɂ����͎����B�ł��낤�ƌx�������Ă����Ǝv����B�����łȂ��Ƃ��Ɗi�ŗ��k�����ɐb�]����������Ȃ�����ɕs��������Ă���A���t�̋@�����������Ă������݂ł������B���̂��߁A�k����ł��o�w�ɓ����藠����x�����ċN����(����)�Ɛl�����o�����Ă���B�@ �㗌���������́A�ʂ����Č���ƘA�����ĐQ�Ԃ�4��27���O�g���ŋ����A5��7���ԏ��E���Ƌ��͂��ĘZ�g���T����U���B�Z�g�������P�킷����̂̏O�ǓG����8���ɂ͖k�����v�E�����̗��T��͋����̂Ăē���錈�ӂ�������Ȃ������B�ނ�͒��b�ł����l�̕��𗦂��A�㕚���@�E�ԉ��@�E�����V�c�����Ċ��q�ւƓ���鎖�ɂ����B�����R�͘Z�g���R�̔�������߂邽�ߊ����ē����̑ޘH���c���Ă���A��������E�o�����̂ł���B�@ ���T��͂܂��͋ߍ]�ɓ���A���ł���Z�p���M�̌R���𗊂鎖�Ƃ����B�����������̋�W�œ��Ŗ쓐����̏P�������v�������B�܂��R�Ȏl���͌��ł��앚����U������V�c�ɏ]���M���B�͎��X�ɓ��U�����B�u�邪�֓��֗ՍK�Ȃ���ɘT�S��}��͉��҂��v�Ɣz���̕������Њd�����Ƃ���A�u��Ƃ͌������ɉ^�͐s���Ă����łł���B�ʂ��Ȃ��Ƃ͐\���ʁA�����̔n�E�b�h��S�Ď̂ĂĈ��S���ė������тȂ���v�Ƃ����}�M���Ԃ��Ă����B���{�E����̌��Ђ�����ɂ����Ȃ��w�̑��݂��@���Ɏf����B���̏�͔z��������̉B���ꏊ��������Ɩ쓐����\���Ēʉ߁B��s�͎��ŏh����藂9�����m����z���Ĕԏ�h�ɍ����|�������Ƃ���ōĂі앚�̏P�������������ߌ��ނ������A�R��܂Œnj������ۂɋъ����f�����ܐ�߂��Ǝv����R�����F�߂�ꂽ�B����������Z�g���R�͘Z�p���̍�����҂��ɂ������A�Z�p�͑҂Ăǂ�����ė��Ȃ��B������͂��͂₱��܂łƔ��f���Ĉ�Ăɕ�������B���͔ԏ�@�؎��A���������Z�g������432�l�ł���������189�l���ߋ����ɖ����L����Ă���B�V�c��@�͕߂���ꋞ�쑗���ꂽ�B���̎��ɔԏ�ŌR�����W�߂ĘZ�g���������Q�ɒǂ����̂͒N�����炩�łȂ����A�����Ɠ��ʂ��C�ɐ��͂������Ă������X�ؓ��_�ł��낤�Ɛ�������Ă���B�������ċE���ɂ����開�{�̋��_�ł���Z�g���T��͖ŖS�����B�@ �������A�֓��ł��̎肪����Ă����B5��8����썑���i�_�ЂŐV�c�`�傪�ꑰ�Ƌ��ɋ����B�V�c�����������Ɠ��l�Ɍ����̒����ɓ�����ƕ��ł��邪�A�����Ɣ�ׂ�Ɗi�i�ɕs���ł�����̗L�͓y���̈�l�ɉ߂��Ȃ������B���ċ`��͈�U���R���𐼂ɏo�ĉz��̈��ƍ���������Ŋ��q�����ē쉺�B�@ ����ɑ��Ėk����͋���叫�������E���͕ӑ����ʂɔh�����ē��֓�����V�c�̔w��ɉ�点�A����ō��c�卑�E���荂�d�����Ԑ���ʂɌ����킹���ʂ���}�����̐����Ƃ����B11������w���ŗ��R������������ƂȂ����B�k����͗p�S���Ď琨�����A����ŐV�c�R�͓��Ԑ��n��U���ɏo��B�ۈ���̐퓬�̖��ɒɂݕ����ŗ��R�͈�U�����グ�����A��12���閾���Ƌ��ɖk����͍U�����A�V�c�S�̒����˔j���������ʂƂȂ����B�@ 15�����x�͖k��Ɨ�����ꖜ�]�R�̌R�������{�͌��ŐV�c�R���}���������B�k���R�͂܂��O��̎ˎ��O�ʂɗ��ĂĖ���������ˊ|���ĐV�c�R�̏o�����~�߁A�R�n��m���U���������ĐV�c�R�����ށB���������������k��������Ȃ��炸���Q��ւ��Ă���nj�����]�͂͂Ȃ������B���ĎO�Y�`�����V�c�R�ɘZ��̌R���𗦂��č������A�����ɐ�w�Ƃ��Ėk���R�Ɋ�P���d�|�����B�O���̌���Ŕ�J���Ă����ƌR�͕s�ӂ���č����Ɋׂ�A�����`��{�R�̍U�����Ĕs�k�����B�@ 17����������Ŗk������V�c�R�ɔ����������邪�吨�ɉe�����y�ڂ��ɂ͎���Ȃ������B����œ����A�������ʂ̋���叫�̕������ߌ��Ŕs�k�B�X�ɋE���ł̘Z�g���T��ŖS�̕���A���q���͈ӋC���������B�@ 18���V�c�R�͎O�������犙�q�U���ɓ������B��ُ@���E�]�c�s�`�̈ꖜ���Ɋy�����ʁA�x���喞�E�哈��V�̈ꖜ�������C����ʁA�`�厩��̐��������ύ���ʂ���U�����������B����A���{���͋Ɋy�����ʂɑ啧�咼�̌ܐ�A�����C��ɐԋ��玞�̘Z��A���ύ�ɋ���匰�̎O���z�u�B�X�Ɏs�X�n�Ɍ�l�Ƃ��Ĉꖜ���T���������B���q�͎O�����R�E�c����C�Ɉ͂܂�A�ʘH�͋����藧�����v�Q�ł���B���{���͊X���ɋt�Ζ�����Ėh�䂵�A�C�ɂ͌R�D���ׂĎ�����ł߁A�n�̗������������ƂɍŌ�̊�]�������Ă����̂ł���B�@�@ �܂��A�ԋ��玞�������̖��Ɏ��n���ĉʂĂ��B�ނ͎����̒n�ʂɂ͂������������͓��@�����Ⓑ�蕃�q�Ɉ����Ă���A�X�ɑ��������̋`�Z�ł��������ߋ^���̖ڂ��������Ă����B�������������ȗ��ꂪ�ނ̑s��ȍŊ��ɉe�����Ă����ƌ�������������B�@ ����ŋɊy�����ʂł͐V�c�R��h���Ƃ߁A�ꎞ�V�c�R�Ɉ���肩��˓������������A�啧�咼���͉����߂��ēG���E��ُ@��������Ă���B���̒m�点�����`��́A21�������𗘗p���Ĉ�����˔j���Ċ��q�ɗ������A�e���ɉ�������B�@ �h�q����˔j���ꂽ�k����͊��q�ł̎s�X��ɓ˓��B���̒��Ŗk�����g���̎ҒB�͎��X�Ƒs��ȍŊ��𐋂��Ă������B�܂�����v�����q���G�����삯�����ĕ���̖��ɓ����B�啧�咼�́A���ߎO�\�l���ؕ����Ď�Ɏ��n�����߂��̂����Ă��̋C�̑�������A�V�c�R�ɓ˓����ĉʂĂ��B����叫���V�c�R����ɕ��킵���B�����͂��̐킢�Ԃ�Ɋ��Q���ĘZ�g���T��E��^���Ă���B���ɘZ�g���͊ח����Ă��芙�q�̖ŖS�����Ԃ̖��Ȃ��̎��_�ł́A���ۓI�ȈӖ��͂Ȃ��C���ł��������A�叫�͈ꑰ�Ԃł����_�Ƃ����n�ʂ�^���Ă��ꂽ�����̐S�����Ɋ������G�̑�R�Ƃ̐퓬�ŎU���Ă���B���̑��ɂ��A�k���(�����̕�)�E���c���S���q�E���O�������q�E��������(����l�A�`��̋`��)�c�B�������̐l�X�����q�E�k�����ɏ}���Ă���B�@ 22�������͈ꑰ���W�߂ē������ɓ��ꂽ�B���荂�d(�~��̑�)�͂���܂ł��U�X�ɐ퓬�����Ă������A�����Ɏ������߂�܂Ŏ��Q��҂悤�ɐ\���o����ŕS�\�R�𗦂��ĐV�c�{�w�ɐ��������B�`��Ǝh���Ⴆ��S�ς���ł��������A�G�ɍ��d�̊��m����̂����莸�s�B����̕�����蓌�����ɖ߂����ۂɂ͐g�̂�23�{�̖�h�����Ă����ƌ�����B���d�͔u���O�x�X���A�����ނ�ɕ�������B�אȂ̐ےÓ�����������������Ĕu���X���Đؕ�����B���ɐz�K�����������u���O�x�����Ă���\�����ɕ����B����~��͍��������ꂵ���U�镑���ɏo�Ȃ�����S�z������ꂸ�ɂ������A���̐V�E�q�傪��������ĉ~��̋����h������Ŏ��n�B������č�������������B���N31�B�k�����E�L�͌���l283�l�A����ȊO���܂�870�]�l�����̎��ɖ��𗎂Ƃ��Ă���B�����ȗ�130�]�N�̗��j���ւ������q���{�́A�����ɖŖS�����̂ł���B�@ �����̌�@ �������O�A�����͎q���̖����E�T���𗎂����т����Ă����B�����ܑ͌�@�@�ɂ̗���ɂ��߂����ď��Y����邪�A�T���͐M�Z�ɓ���z�K���̕ی�����s�Ɩ����B�@ ���Ėk�𐭌���ŖS����������V�c�͎���̐��������Ɏ���������B���H�Ɛ��͂���Ղɂ����Ă̐ꐧ�I�������u�����邪�A�}���ŋ����ȉ��v�≶�ܖ�肩��e�n�ŕs�������܂�B�@ ������Ċe�n�̖k�����c�}�������B���ł���Ȃ��̂͌���2�N(1335)���������@�Ɩk��Ƃ�����Ŗژ_����ÎE�v��ł������B����Ɏ��s��z���̖��z�������ĉ�����\��ł��������A���R�ɖ����ŘI�������s�ɏI���B���s�͈����Ɉ�����7���ɋ����B���̎��A�ۉȁE�l�{�����������ĐM�Z���E���}����@�̒��ӂ��������̊ԂɎ��s���I�N���ĐM�Z����֓��ɍU�ߓ������B����ɖk���c�}��������Đ����̌R���ƂȂ�֓����x�z���Ă��������R���e�n�Ŕj��7��25���k���R�͊��q��D�ҁA�������`�͎O�͂ɓ��ꂽ�B�@ �������k�����̍ċN�������͑����Ȃ������B�����瑫������(�����A���킩��u���v�̈ꎚ���������)����R�𗦂��čU�ߓ���A�k���R����ɘA��A���Ŋ��q���ĒD���̂��B���s�͐M�Z�ɗ������эċN�����������B�@ �₪�đ����͎���̐���������ڎw������ƓG���ċ����A������͔s�k���ē��{�͑����瑫���������i�����鋞�̒���(�����@���A�k��)�Ƌg��ɓ��ꂽ�����(��o�����A�쒩)�ɕ���B���̎��A���s�͌��킩�璩�G�͖Ƃ��d�|�������R�Ɛ���Ă���B�ނɂƂ��Ă͒��ڊ��q��łڂ����`����A���N�ɂ킽��k���̉����Ȃ���Q�Ԃ�Ō`�����߂������̕����w�G�ł������悤���B�����́A�V�c�̐b���ƂȂ�̂͏]���ʂ�Ȃ̂Ŗ��Ȃ����A�����̉����ɗ����͖k�𒄗��̌ւ肪�����Ȃ������̂�������Ȃ��B�@ ���鎞�͉��B�̖k�����ƍ������A�ʂ̎��͐V�c�R�ƍ����������A����7�N(1352)�������̓����ɏ悶�ĐV�c�R�Ƌ����Ŋ��q��D����������B���������ǂ͏O�ǓG�����Ŕs�k���A������8�N(1353)�ɕ߂�����5��20�����q���m���ŏ��Y���ꂽ�B�����ɖk���������͖ŖS�����̂ł���B�@ ���@ �k�����́A�����͈ɓ��̒��������ɉ߂��Ȃ��������A�����̊O�ʂƂ����L���ȗ���𑫂�����ɒn�ʂ��㏸�����A�₪�č����B�̑�\�҂ƌ����`�Ō��͂�͂�ł������B�I�݂ɍ����B�̗��Q�����Ďx�����W�߂鑼�A���̌��͂����肵�����̂Ƃ��邽�ߑ��̗L�͍�����r�˂��A���H�Ɛ��͂��ϋɓI�Ɏ�荞��Ōo�ϗ́E�Љ�I���͂�t���Ă������B�@ �������A�������������ł��������߂ɂ��̉ߒ��ő����Ȗ����������Ă���A�����̍������E�����]���ƂȂ����B�����B�̑�\�ł��������̖k�����́A�������ނ��}�����鑶�݂ƂȂ��Ă����ނ炩��G������悤�ɂȂ����B���_�A�k�������ނ�̑�\�҂ł��鎖�Ɏ��g�̌��͂��������Ă��鎖�͔F�����Ă���~�ϐ����ł��o���Ă��邪�A�k�����̐��͊g�傻�̂��̂���Ɛl�v���̈���ł��������Ƃ������Č��ʂ͏\���ɏ��Ȃ������B�@ �܂��A���H�ƎҁE���А��͎�荞�݂Ɋւ��Ă��A��i�n��ł���E���ł͓`���I�ɒ���Ƃ̊W�������A�O���҂ł����Ɛl�ւ̔��������݂����B�֓��̑�\�҂ł���k�����͂��̎��_�Ŕނ�̔������������鑶�݂ł���A�����̗����҂�ނ炩����o�����ƂȂ����B�@ �������āA�����Ȑ��͊g��̌��ʂƂ��Ċe���ʂ���Ǘ������̂��k�����ŖS�̍ő�̌����ł��낤�B���q�ŖS���ɖc��Ȑ��̐l�Ԃ��}���Ă��鎖����k�������x����K�w�������Ɍ`������Ă������͎@�����邪�A����ł�����̗���ɍR���鎖�͂ł��Ȃ������B�֓��͈ˑR�Ƃ��Ĕ_�ƒ��S�̍������Љ�̒��S�ł���A���H�Ǝ҂݂̂ł͑R�ł�����̂łȂ����������������悤�B�@ �����āA�k�𐭌����̂��̂������ƂȂ�@�\�̐����͂���Ă��锽�ʂŏ_������������ւ̓K�ȑΉ�������Ȃ��Ă��������傫�������B�@ �������g�ɂ�����������������͗ʂ��Ȃ������̂͊m���ł��낤���A�ނ̈Ë��̂��߂Ɋ��q���{���ŖS�����ƌ���͍̂��ł��낤�B�k�������x�z�̐����ł߂钆�ŏd�Ȃ��Ă������E���������ɕ�������Ȃ����x���܂ŒB�����ƌ���ׂ��ł���B�k�𐭌��́A���_��F�����Đ���t�̑Ή��������̂ł͂��邪�A���ɗ����炸�͋y�Ȃ������̂ł���B���������_�I�ɕs����Ȉ�ʂ�����V���ɉ��Y�ꂪ���ł������̂��A���������d������NJ����瓦��悤�Ƃ�������ł͂Ȃ������낤���B�@ �k�@�����A������������퐭���⑫�������B�ނ�̎���͏��H�Ƃ����B���嗬�ƂȂ�n�߂Ă��邪�A�Љ���x�������i�K�ɂ͎����Ă��炸�����I�Ȓn�������E���ЂƂ����������I�ȑ��݂̗͂��܂�����Ȃ��ƌ������n�Ȓi�K�ł������B�����������ŏW���̐���ڎw���ċꓬ�����ނ�́A�ߐ��ւ̐��݂̋ꂵ�݂𖡂���Ă����ƌ�����B �@ |
|
 �@ �@���헤�Ɠ�؎� |
|
|
��k���ɂ�����쒩���̑�\�I���݁E��؎��B�ނ�͉͓��̐V�������Ƃ��Ĉ�ʂɂ͔F�m����Ă��܂����A���ۂɑ啔���̊����͑�㕽���Ƃ��Ă��܂��B�������A�������ꂽ�k�֓��̏헤�ɂ����Ă���؎��̊��������������Ƃ͗]��m���Ă��܂���B�@ ���헤�Ɠ�؎��@ ���q���{�œ|�ɑ傫�ȍv����������ؐ����́A�ےÁE�͓��E�a��̎��ɔC�����͓���ƂȂ����ق��A���܂Ƃ��ĐV���ȏ��̂�^�����܂����B�����̉��܂ɂ́A�͓����V�J���E�y�������|���E�o�H�����㑑�Ƌ��ɏ헤���Z�A�����܂܂�Ă����̂ł��B�@ ���̒n�ɑ㊯�Ƃ��Ĕh�����ꂽ�Ƃ����̂������̈ꑰ(�Ǝv����)��ؐ��Ƃł��B�ނ͑�������������V�c�ɔ��t������A�������N(1336)�ɂ��̒n�ő������̍��|���Ɛ킢�܂��������ǂ͊֓��͑��������D�ʂ��m�����邱�ƂɂȂ�܂��B�@ ����œ�؎��Ə헤�̊ւ��͏I�������������Ɍ����܂����A��k���������I���������̎����ɓ�ؐ���(���V�̎q�A�����̑�)���}�g�R�̌Òʎ����J�����Ƃ����`�����c���Ă��܂��B�܂��A���̒n��o�g�̍쎌�ƁE����L��́A���Ƃ���ؐ��G(�����̒�)�̖���ł���Ə̂��Ă���e��(��؎��̉Ɩ�)���Ɩ�Ƃ��ėp���Ă��������ł��B�����āA�E��̕��m�ł���g�쎁�͓�؎��̗�������ނƓ`�����܂��B�����̘b����l����ƁA���̒n��ɂ͈�ߐ������łȂ���؎��Ƃ̊ւ�肪����\���͔ے�ł��܂���B�@ ��؎��͑�㕽��Ő�����̐����������萅���ʂ��蒆�ɂ��Đ���̌��Ղō��𐬂����ƍl�����Ă��܂����A�헤�k���ɂ�����C�����Y�o����Ă��茻�n�̔�_�Ɩ��Ƃ���؎����W�����̂ł��傤���B�܂��A�u��v���̌��ƂȂ����ł��낤�n������㕽��ɂ͔F�߂�ꂸ�A��؎��͌��͑��n��̍����������̂���Ɛl(���q���R�̉Ɛb)�܂��͌���l(���{�̎������������k�����̉Ɛb)�Ƃ��đ�㕽��ɏ��̂�^�����ڏZ�����\�����w�E����Ă��܂��B����Ɋ֘A���āu��ȋ��v�ŗ����ɏ]���ď㗌���������̒��ɔE�O�Y�E�E�ܘY�ƕ���Łu��؎l�Y�v�̖��������邱�Ƃ����ڂ���Ă���A���̐l���Ɖ͓��̓�؎��Ƃ̒��ڂ̊֘A�͕s���Ȃ��̂̓�؎��������͖k�֓��ɋ��_�������Ă����\���������яオ��̂łł��B�Ђ���Ƃ���ƈꑰ���Â�����헤�ɉ��������Ă��������m��܂���B���炩�ȏ؋��͂܂������Ȃ��A�^���͉i���̓�ł����B�@ ���헤�Ɠ쒩�@ ��؎������łȂ��A�헤�͊֓��̒��ł͓쒩�Ɖ��̐[���n��ł��B�k���e�[���ɐ�����֓��������쒩���̋��_�}�A��}�����ہA�ŏ��ɏ㗤�����̂͐_�{����ł��������̒n�͌F�쌠���ƊW�̐[���ꏊ�ł������Ƃ������Ƃł��B��������l����ƁA�e�[���^�D�c�͌F�쐅�R�ł������ƍl����̂����R�ł��傤���B��������ƁA��؎��͋I�ɂ̓��Ƃ������[�������悤�ł�����A�F�쐅�R��ʂ��đ�㕽��Ə헤�̘A��������Ă����̂�������܂���B�@ ����͂��Ă����A�֓��ɂ����Đe�[�ɖ���������͑���E�֏�E�^�Ǐ�E���Q��ł�������Y����쉈���ɏW�����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���̎��ӂ̋��ƁE���^�Ȃǂ͎����_�Ђ̐_�l(�����_���A�����͔�_�Ɩ���������߂Ă���������������������)�����v���������Ă���A�����Y���ӂ����_�Ƃ��Đ��R���Ґ����Ă����ƍl�����Ă��܂��B��؎����n�߂Ƃ��ē쒩�����\�����Ă����͔̂�_�Ɩ���ޓ��𑩂˂�V�������ł������Ƃ����Ă��܂����A�����ł��ޓ����֓��ɂ�����쒩���̎�͂ƂȂ����킯�ł��ˁB�@ �������֓��͈ˑR�Ƃ��Ĕ_�Ɩ��������卋���̗͂������A�ޓ���Ґ������������ɂ���Ă��������쒩���̔�_�Ɛ��͈͂�������s�k���i����̂ł��B�@ ���@ ��؎���������㕽��Ɖ�������Ĉꌩ���̊W���Ȃ������ȏ헤���B�����������ł���؎��̊����̉e���`���`���ƌ�����͖̂ʔ������̂ł��B�����Ă��̔w�i�ɂ͐e�[�̍R������x�������㐨�́A���ł���؎��Ƃ����̐[�������F�쐅�R�̎p���_�Ԍ�����̂ł��B����͓�؎��Ə헤�̊W�����łȂ��A���̎���ɂ�������{���݂̐��㐨�͂̎Љ�I���͂����M�킹�鋻���[�����݂Ƃ����܂��B �@ |
|
 �@ �@�������m�Ɠ�؎� |
|
|
���㌀�ʼnB���Ƃ��ēo�ꂷ��ȂǁA�V�W�}�����Ԃ�ڔ��𐁂��p�Œm���鋕���m�B���̗��j�I�N���ɓ�؎����W���Ă���Ƃ����`��������悤�ł��B�@ ���u�ڂ�ڂ�v�@ �܂��A�����m�̑O�g�ƌ�����u�ڂ�ڂ�v�ɂ��ďq�ׂ鎖�ɂ��܂��B�u�ڂ�ڂ�v�͊��q�����ɑ���������悤�ɂȂ����V�s�҂̎��ŁA�u���_���v�Ƃ��Ă�܂��B���̎��Ԃɂ��ẮA�����ɂ��ĉ�����������s���Ȃ���V�s���鎖�Ő��v�𗧂Ă�|�\�@���҂������Ɛ�������Ă��܂��B�@ �u�k�R���v�ɂ��u�ڂ�ڂ�v���o�ꂵ�܂����A�����ł͔ނ�͏W�c�ŔO�������������y�Đn�����������������������_���]���J���d�鑶�݂Ƃ���Ă��܂��B�����āu�ڂ�ڂ�̎莆�v�ɓo�ꂷ�鋕��V�́A���`���d�鑶�݂Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B�ܘ_��������Ă���̂ł��傤���A�u�ڂ�ڂ�v�ɂ͔ޓ����g�̔��w�E���l�ς����݂��������f���܂��B����u����ԐE�l�̍��v����́u�ڂ�ڂ�v���O���C�s�҂Ƌ��ɏ�����V�s���Ă������⏦�Ă͏��̎�ł������҂����������킩���Ă��܂��B���ہA���q�̖���E�O�Y�����k�����ɂ��v��������ꂽ�ۂɂ͉Ɛb�̌˕������ꎞ�����������V�s�̐g�Ƃ��ĉ߂������Ƃ����b���`�����Ă���̂ł��B�u�ڂ�ڂ�v�ɂ͎�N���������Q�l�������܂܂�Ă����̂ł��傤�B�Ȃ�قǁA�����Ŏ��@�̗x�O���W�c�����m�̉��l�ς��������킹���悤�ȑ��݂Ȗ�ł��ˁB�@ �ޓ��V�s�҂́A�e�n�̒n�����������ɂ�莡�����C������ƌ���ĎE�Q����鎖�����X�ɂ���܂����B�ޓ����W�c�ōs�����Ă����̂͂����������݂��玩�q����ׂł��������悤�ł��B�@ ���́u�ڂ�ڂ�v�̗L��l���ϖe���T�@�⒆����������������Č��ݒm���Ă��鋕���m�̌��^���o�����̂�14���I�����̎��ł����B�����āA����ɓ�ؐ������傫���ւ���Ă���ƌ����`�����c���Ă���̂ł��B�@ ����ؐ����@ ��ؐ����́A�����̑��œ쒩������R���I�Ɏx�������V�̎q�ł��B�ނ͓쒩�����������ɋ�����������A�����ւ̒�R�𑱂��`���ɔ�����|��������`�O�̌R�ɂ��Q�����Đ�������̂̔s��ē��ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B�@ ���̐����ł����A�u�����`�L�������v�ɂ���������ڔ����w�я�������V�����Ɠ`�����A�V�W����ڔ��𐁂����݂̋����m�`���̑c�Ƃ���Ă���̂ł��B�X�ɒ}�g�R�̋����m���E�Òʎ��͐������J�����ƌ����`��������A�ނ̏��Ɠ`��������̂��c����Ă��܂��B�������ǂ��l���Ă��b���o�������Ă��܂����A�V�W���o�����͓̂�����̎����ƌ����Ă��܂�����ԈႢ�Ȃ����̘b���̂͌㐢�̍�ׂł��傤�B�����A��؎��A�����������s�łȂ���r�I�}�C�i�[�Ȑ����ɑc�����߂Ă��邠����A��ɕt���Ȃ�����������l�ɂ��v���܂��B�ꕔ���ł���ɂ���A���炩�̎������܂܂�Ă���̂�������܂���B���ہA�����m���ڔ��𐁂����݂̌��^���ł߂������Ɛ������������Ƃ���鎞���͂قڈ�v���Ă���킯�ł����B�@ �����ŁA�܂��͈�ԕs�R�Ǝv����V�W�ɂ��čl���Č��܂��傤�B14���I�́u�����L�v�ɂ́A�d�����́u���}�v���Ȃ킿�������͂̎v���悤�ɂȂ�Ȃ��V�������ɂ��ċL�q������܂����A����ɂ��Δނ�́u�Z���}�����Ԃ�`��𒅂āv�u�l�ɖʂ����킹���E�т���́v�ł����������ł��B�܂�́A�u���}�v�����͊}�������B���Ă����Ƃ����̂ł��B��؎��������ȑO����u���}�v�ƌĂꂽ�V�������ł������A�����͔s�҂̎c�}�Ƃ����ׂ����݂ł�������f����B���ĉB���s���������Ƃ��Ă�������������܂���B�����̋����m�������A���̂悤�ɂ��Ċ���B���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂪ������ɂȂ��ēV�W����悤�ɂȂ����Ǝv���܂��B�������ڔ��𐁂����Ƃ����`���̐^�U�͂킩��܂��A��q�̗V�s�҂ɕ���ď����̖����ƘA����������Ƃ����\���͂Ȃ����Ȃ��̂�������܂���B����ɂ��Ă��A�Ȃ���؎��������m�ƌ��ѕt����ꂽ�̂ł��傤���B�@ �������m�Ɠ쒩�@ ���������A�����m���ɂ͓�؎������łȂ��쒩���̂��̂Ƃ̈���������悤�ł��B�Ⴆ�A�[�J�̋����m���E�������͒��c�V�c���ߎR�s���ɖ����ĊJ���������ώ����ړ]�������̂ł����A��͂苕���m���ł��鋻�������쒩�c���̋A�˂������Ƃ����Ă��܂��B�X�ɐ~�̗�@�����������������g��D���V���͓�؎��̖���Ɠ`�����܂��B�@ ���������쒩�n���̓`������������ŁA�O�q�̋������̋߂��ɖ����̗��Ŕs�ꂽ�R�����̋��b�����ƂȂ��ďZ�ݒ������Ƃ����b���c���Ă��܂��B���̎����̓쒩�ƎR�����A�ǂ���������I�s�҂Ƃ����Ă悢���݂ł��ˁB���������u�ڂ�ڂ�v�ɂ����r�������m���������ꍞ��ł��܂����B����Ɠ��������ōl������̎����ɓ쒩�W�҂������m�ƈ���������̂������ł��܂��B�@ ���̎����A�������E�쒩�Ƃ��嗤����̐V�����ł���T�@���������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����đT�@�ƂƂ��ɗl�X�ȐV��ȕ������������Ă���A�ڔ������̈�������̂ł��B���ꂪ�u�ڂ�ڂ�v�̐��E��14���I������15���I�����ɂ����ċ}���ɗ������A�V���ȏ@���|�\�Ƃ��Ďڔ����̗p���ꕁ���ڔ����T�̏C�ƂƂ��čL�����Ă����܂����B���̎����ɂ����āu�ڂ�ڂ�v�̗����ς���قǂɑ����ŐV�K�Q�����Ă����������Ȃ������I�s�k�҂Ƃ������쒩���͂����R�ł��傤�B�ނ�Ȃ�A�嗤�Ƃ̌�������V�������o�g�������ł����T�@�����̑f�{���������Ƃ��Ă��s�v�c�͂܂���������܂���B�@ �^�U�̂قǂ͖��炩�ł͂���܂��A�u�����`�L�������v�̓`���͋����m�Ƌ��쒩�Ƃ̊֘A���Î����Ă���\���͏\���ɂ��肻���ł��B�@ ���@ �u�ڂ�ڂ�v�A�����Ă��ꂪ���W���������m�̒��ɂ́A�����I�ɔs�k���g��������҂����Ȃ��炸�����悤�ł��B�u�����m�v���n���ɂ�����ő�̐����I�s�ҁA���Ȃ킿�쒩�c�}�ɂƂ��āA��؎������̐����̓A�C�h���I���݂��������Ƃ͑z���ɓ����܂���B�����āA�㐢�ɂ�����܂ŋ����m�ɂ͘Q�l�����������݂��B�����s���҂����Ȃ��炸���܂������A�����[��������悤�Șb�ł��ˁB �@ |
|
 �@ �@����������1 (1305-1358) |
|
|
���q�����������k������̕����B�������{�̏��㐪�Α叫�R�B�{���͌����B�ƌn�͐��a�����̈�ƌn�A�͓������̓����A����{���R�������Y���`�Ƃ̎q�A�`����c�Ƃ��鑫�����̒����B�������R�Ƃ̑c�B�����厁�̒��j�Ƃ��Đ��܂��B���ߎ����E�k�����������恂������Ɩ�������B���O3�N�Ɍ���V�c�����ˑD��R�ŋ��������ہA���q���{�̗L�͌�Ɛl�Ƃ��Ė��{�R�𗦂��ď㗌�������A�O�g�������{�Ŕ����{�̕��������A�Z�g���T���łڂ����B���{�ŖS�̌M�����Ƃ���A����V�c��恁E����(�����͂�)�̌�ꎚ������A�����ɉ��߂�B�@ ����V�c�ꐧ�̌����̐V�����}���Ɏx���������Ă������A�����̗�����݂Ƃ��ē������������������㊙�q�ɗ��܂�Ǝ��̐�������������\�����������B����ɂ��V�c�Ƃ̊W���������A�㗌���Ĉꎞ�͓V�c���b�R�֒ǂ���������A����V�c���͂̔��U�ɂ���U�͋�B�֗������т�B��B����Ăя㗌���A������c����ь����V�c���琪�Α叫�R�ɕ�C����V���ȕ��Ɛ���(�������{)���J�����B����V�c�͋g��֑J��쒩��n�n�����B�@ ���{���J������͒�E�������`�Ɠ�����z�������A��ɒ��`�ƑΗ����ω��̏�ւƔ��W����B���`�̎��ɂ�藐�͏I���������A���̌���쒩�Ȃǔ������͂̕�����p�����A�����̈���ɓw�߂��B����V�c�����䂵����͂��̕������ߓV�������������Ă���B�k���ɂ����Č�����V�c�̐V��ژa�̏W�͑����̎��t�ɂ����̂ŁA�Ȍ�̒���a�̏W����\���W�̍Ō�̐V���Í��a�̏W�܂őS�Ăő������R�̎��t�ɂ�邱�ƂƂȂ������[�ɂ�����B ����V�c�ɔ�����|�������Ƃ��疾���ȍ~�͋t���Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă������A�����͍m��I�ɍĕ]������Ă���悤�ɁA���j�ς̕ϑJ�ɂ���Ă��̐l�������傫���ω����Ă���B�@ ���a�����犙�q���{�ŖS�@ �����͉Ì�3�N(1305)�Ɍ�Ɛl�����厁�̎��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���a�n�͈�����(�����Ƃ��B���s�{�����s�㐙��)�A���q���A��������(�Ȗ،������s)��3��������B�u����L�v�͑������o�����ĎY���ɂ������ہA2�H�̎R�������ł���1�H�͑����̌��ɂƂ܂�1�H�͕��ۂɂƂ܂����Ƃ����`����`���Ă���B�c���͖����Y�B�������N(1319)10��10��15�̂Ƃ��������]�܈ʉ��������ɕ�C�����ƂƂ��ɁA���{�����E�k�������̕�恂����荂���Ɩ�������B���E�厁�Ƃ��̐����E�߉ޓ�(�k�������̖�)�Ƃ̊Ԃɒ��j�E�������`���������A�����������ߍ������Ɠ𑊑����邱�ƂƂȂ����B�u����L�v �͑����̑c���E�����Ǝ����O��̂��ɑ��������V������鎖������Ď��n�����Ƃ���Ă���B���O���N(1331)����V�c����x�ڂ̓|������}���A�}�u�ŋ�������(���O�̕�)�B���q���{�͗L�͌�Ɛl�ł��鍂���ɔh���𖽂��A�����͓V�c�̋���}�u�Ɠ�ؐ����̋��鉺�ԍ��̍U���ɎQ������B���̂Ƃ��A���E�厁���v��������ł��荂���͔h�������ނ��邪�A���{�͍Ȏq��l���Ƃ��ďd�˂Ĕh���𖽂����B �u�����L�v�͂���ɂ�荂�������{�ɔ��������悤�ɂȂ����ƋL���B���{�R�̍U���̌��ʁA�V�c���͂��߂Ƃ��ē|���v��Ɋւ��������r��E�~�ςȂǂ̌��Ƃ�m���������A���{�ɕߔ�����A�V�c�͗��N�B�ɗ����ꂽ(���O�̗�)�B���{�͑�o�����̌���V�c�ɑウ�Ď����@���̌����V�c��i�������B�@ ���O3�N/���c2�N(1333)����V�c�͉B��E�o���đD��R�ɘU�邵���B�����͍Ăі������A�����̓������͂�������邽�߂ɖ��z���ƂƂƂ��ɏ㗌�����B���z���Ƃ��ԏ��~�S�ɓ����ꂽ���Ƃ��@�Ƃ��āA����V�c���d�|���Ă��������͓V�c���ɂ����Ƃ����ӂ��A4��29�����̂̒O�g�������{(���s�{�T���s)�Ŕ����{�̕����������B�����ɑ����̌R���Ñ�����A�ߍ]�̍��X�ؓ��_�Ȃǂ̌�Ɛl���]���ē������A5��7���Z�g���T���ŖS�������B�������ɏ�썑�̌�Ɛl�ł���V�c�`����������Ă���A�����̒��q�Ŋ��q����E�o���������(��̋`�F)��Ċ��q�i�R���A���{��ŖS�������B���̎��A�����̑����̎q�E�|��ۂ������̍Œ��ɎE����Ă���B �����͊��q�ח���ɍא�a���E���t�E�t���̌Z���h�����ċ`����㗌�����A���q�𑫗����ɏ��������Ă���B�@ �������̐V�������k�������@ ���q���{�̖ŖS��A�����͌���V�c����M�����Ƃ���A����{���R����я]�l�ʉ������q�ɔC�����A�܂�30�ӏ��̏��̂�^����ꂽ�B����ɓV�c��恁E���������ꎚ�����葸���Ɖ��������B�����͌��������ł͐����̒�������͂Ȃ�Ă���A�����Ƃ̎����E�ł��鍂�t���E���t�Z��Ȃǂ𑗂荞�݁A��E�������`�����q���R�{�����Ƃ����B����ɂ͌���V�c���������h�������Ƃ��錩���ƁA�������g�������Ƌ�����u�����Ƃ��錩���Ƃ�����B�܂��A���Α叫�R�̐鉺���A���q�ɖ��{���J���Ӑ}���������Ƃ����������B���̏�Ԃ́u�V���ɑ����Ȃ��v�ƌ���ꂽ�B�@ ����V�c���k�����Ƃ����叫�R�ɔC���ėc���`�ǐe��(��̌㑺��V�c)������ĉ��B����Ɍ����킹��ƁA�����͒��`�ɗc�����ǐe����������q�։��������Ă���B����V�c�̍c�q�ł��蓯�������Α叫�R�E��]��ł�����ǐe���͑����ƑΗ����A�����ÎE�����݂邪�������̌x�삪���d�ʼnʂ����Ȃ������B�������N(1334)�����́A���q�P�ǐe�����c���q�Ƃ���������V�c�̒��P������q�ƌ��сA����V�c�Ƃ��m�����Ă�����ǐe����ߔ������q�̒��`�̂��ƂɗH������B�@ ����2�N(1335)�M�Z���ŁA�k�������̈⎙�k�����s��i�������k�����c�}�̔����ł��钆���̗����N����A���s�R�͊��q���ꎞ�苒����B���̍ہA���`���ƒf�Ō�ǐe�����E�����B�����͌���V�c�ɐ��Α叫�R�̊���]�ނ�����ꂸ�A8��2������Ȃ��܂܊��q�i�����A����V�c�͂�ނȂ������叫�R�̍���^�����B�����͒��`�̕��ƍ��������͐�̐킢�Ŏ��s���쒀19�����q�������B�����͏]��ʂɏ�����ꂽ�B�@ ���`�̈ӌ��������đ����͂��̂܂܊��q�ɖ{����u���A�Ǝ��ɉ��܂�^���n�ߋ��s����̏㗌�̖��߂����݁A�Ǝ��̕��Ɛ����n�n�̓����������n�߂��B���N11�������͐V�c�`����N���̛@�ł���Ƃ��Č���V�c�ɂ��̓�������t���邪�A����V�c�͋t�ɋ`��ɑ��ǐe��������đ��������𖽂��A���C�������q�����킹���B����ɉ��B����͖k�����Ƃ��쉺���n�߂Ă���A�����͎͖Ƃ����߂ĉB����錾���邪�A���`�E���t���Ȃǂ̑��������O�͍��ȂNJe�n�Ŕs��͂��߂�ƁA�����͌��������ɔ�����|�����Ƃ����ӂ���B���N12�������͐V�c�R���E�|�m���̐킢�Ŕj��A���s�i�R���n�߂��B���̊ԁA�����͎����@���̌�����c�֘A�������A���s�i�R�̐�������H������Ă���B����3�N���������͓������ʂ����A����V�c�͔�b�R�֑ނ����B�������قǂȂ����ĉ��B����㗌�����k�����ƂƓ�ؐ����E�V�c�`��̍U���ɉ���������͓��N2�����s��������Đԏ��~�S�̐i����e��ċ�B�ɉ������B�@ ��B�ւ̐����r��A���卑�ԊԊ�(�R�������֎s)�ŏ����Ɍ}�����A�}�O���@���̏@����Ћ{�i�@�����͂̎x������B�@����ЎQ�q���3�����{�}�O���X�Ǖl�̐킢�ɂ����Č���V�c���̋e�r���q��j�萨�͂𗧂Ē����������́A���ɏ��r���Ō�����c�̉@����l�����A�����̕��m���}���ɎP���ɏW�߂čĂѓ��サ���B���N4��25������̐킢�ŐV�c�`��E��ؐ����̌R��j��A���N6�����s���Ăѐ��������B�@ ���֓����������́A��b�R�ɓ���Ă�������V�c�̊�𗧂Ă�`�ł̘a�c��\�����ꂽ�B�a�c�ɉ���������V�c�͓��N11��2���Ɍ�����c�̒�����V�c�ɐ_�������A���̒����11��7�������͌������ڏ\�������߂Đ����̊�{���j�������A�V���ȕ��Ɛ����̐�����錾�����B����A����V�c�͓��N12�����s��E�o���ċg��(�ޗnj��g��S�g�쒬)�֓���A�����ɏ������O��̐_��͋U�ł��莩�炪�ѓ��������̂��^���Ɛ錾���ē쒩���J�����B�@ ���ω��̏����ӔN�@ �����͌����V�c���琪�Α叫�R�ɔC�����(�ݐE1338-1358)�����ɁA��Ɏ������{�ƌĂ�邱�ƂɂȂ镐�Ɛ����������Ƃ��ɐ��������B���N�A����V�c���g��ŕ��䂷��ƁA�����͈ԗ�̂��߂ɓV�������c���J�n�����B���c����x�ق��邽�߁A���֓V�����D���h������Ă���B �쒩�Ƃ̐킢�ł͐V�c�`��̒�E�e���`�������j���z�O����쒀���邱�Ƃɐ����B��ؐ����̈⎙�E��ؐ��s���l���œ������A�g����Ă������ɂ���Ȃǐ�ʂ��������B�@ �V�����ɂ����āA�����͐����`�ɔC���A����͕��m�̓����Ƃ��ČN�Ղ����B�����i��͂��̏�Ԃ��A��]���I�x�z�������鑸���Ɠ������I�x�z�������ǂ��钼�`�Ƃ̗��������ł���A���q���{�ȗ��A���R���L���Ă������͂̓�����������̂ƕ]�������B���������͂͏��X�ɖ��{�����̑Η����ĂыN�����Ă����A���t����̔����`�h�ƒ��`�h�̑Η��Ƃ��Č���Ă����B���̑Η��͂��Ɋω��̏�ƌĂ������R���ɔ��W�����B�����͓����A�����I���������Ă������A�t���h�ɗi������Ă��܂��B����4�N/��a5�N(1349)�P���������`�������������@���t���̕�����͂��A���`�̈��ނ����߂鎖�������������B���`�͏o�Ƃ�������ނ����ƂƂȂ������A���`�̔r���ɂ͎t���E�����̊Ԃŗ���������A�ϋɓI�ɈӐ}����Ă����Ƃ����������B�@ �����͒��`�ɑ����Đ�����S�������邽�ߒ��j�`�F�����q����Ăі߂��A����Ɏ��j��������Ċ��q�����Ƃ��A���������̂��߂̊��q�{��ݒu�����B���`�̈��ތ�A�������q�Œ��`�P�q�̒��~����B�Œ��`�h�Ƃ��Đ��͂��g�債�Ă������߁A����5�N/�ω����N(1350)�����͒��~�����̂��߂ɒ����n���։��������B����ƒ��`�͋��s��E�o���ē쒩���ɕt���A���䒼��A���R������ꕔ�̕���̕�������������ɏ]�����B���`�̐��͂�����ɂȂ�ƁA�`�F�͗ƂȂ��ċ���E�o���A���������`�ɐےÍ��ŏo�l�̐킢�Ŕs�ꂽ�B�����͍��Z��̏o�Ƃ������ɒ��`�Ƙa�r���A����6�N/�ω�2�N(1351)�a�c�����������B���Z��͌쑗���ɏ㐙�\���ɂ��d�E����Ă���B�@ ���`�͋`�F�̕⍲�Ƃ��Đ����ɕ��A�����B�����E�`�F�͍��X�ؓ��_��ԏ����S�̖d���𖼖ڂƂ��ċߍ]�E�d���֏o�w���A���ۂɂ͒��`�E���~�Ǔ�����Ăē쒩���Ƙa�r�����s�Ȃ����B���̓����ɑ��Ē��`�͖k�����ʂ֒E�o���Ċ��q�֓������B�����Ɠ쒩�̘a�r�͓��N10���ɐ������A����𐳕��ꓝ�Ƃ����B���s���đ����͒��`��ǂ��ē��C����i�݁A�x�͎F�x�R(�É����É��s������)�A���͑���K(�_�ސ쌧���c���s)�Ȃǂł̐퓬�Ō����j��A���`��߂炦�Ċ��q�ɗH�����B���`�͐���7�N/�ω�3�N(1352)2���ɋ}�������B�u�����L�v�͑����ɂ��ŎE�̋^�����L���Ă���B�@ ���̒���ɏ@�ǐe���A�V�c�`���E�`�@�A�k�����s�Ȃǂ̓쒩������P�����ꂽ�����͕������֑ދp���邪�A�������ܔ������֓��̓쒩���͂𐧈�����ƁA���s�֖߂����B���̌㑫�����~�����s�N�U���邪�A���ǒ��~�͋�B����B����9�N/���a3�N(1354)���s��쒩�Ɉꎞ�D���邪�A���N�D�҂����B�����͎��璼�~��������Ă邪�A����13�N/����3�N4��30��(1358)�A�w���ɏo�����(�悤�A�)�̂��߁A���s������H�@�ɂĎ��������B���N54�A�����̕�E�����@�B |
|
| ����������2 | |
|
�Ì�3-����3(1305-1358)���a�����B�O�́E�㑍�̎����߂������厁�̎q�B��͏㐙���d���A���q�B�����ł��������A���̐��ȂɎq���Ȃ��������ߒ��j�Ƃ��ĉƂ��p�����B�c���͖����Y�B���`�̓���Z�B�����k���������G�X�q�e�Ƃ��Č������A�����̖����ꎚ�č����𖼏��B�@ �������N(1319)�]�܈ʉ��ɏ�����A�������ɔC������B���c2�N(1333)3�����{�̖��ɂ�����V�c�����ߏ㗌������A�r���œ����ɖ|�ӁA�Z�g���T���łڂ��ċ������������B���q���{�ŖS��A���������̑���J�҂Ƃ��Č���V�c���恂̈ꎚ�����葸���Ɖ�������B���O4�N(1334)�����A���O�ʂɏ�������A���N9���ɂ͎Q�c�ɏA�C�B����2�N(1335)7���A�k�����s���M�Z�ɋ��������q���̂���ƁA���������̂��ߊ֓��ɉ����B���̍ې��Α叫�R�̒n�ʂ�]���A�V�c�͐������R�ɔC����ɗ��߂��B�����A���̖������₵�Ċ��q�ɂƂǂ܂�A���������ɔ�����|���B�₪�đ����Ǔ��ɉ��������V�c�`��̌R���ɔj��㗌�������A�k�����Ƃ�̉��H���ɔs��ċ�B�֗������т��B���̍ہA�����@�ɐV�c�`��Ǔ��̉@��𐿂��A�₪�Đ��͂�Ԃ��ےÖ���ɓ�ؐ�����|���čď㗌�B����3�N(1336)8���A�����V�c�ʂ����A���N11���A�������ڂ����z���Ď������{���J���B�����A����[���ɔC�����A������N(1338)8���A�Җ]�̐��Α叫�R�ɔC�����ꂽ�B�������O�N���Ɍ���V�c�͋����g��ɒE�o���ē쒩�������A��k�������̎��オ�����J�����B�2�N(1339)8���A����V�c�����䂷��Ƒr�ɕ����A�����@�̖��ɂ��S��������ߓV�����̑��c���v��A�N�i4�N(1345)�Ɋ��������Ė����a���Z���ɂ������B�@ ���{�̐����͒�̒��`�Ɉς˂Ă������A�₪�Ď������t���Ƃ̑Η���[�߂����`�͊ω����N(1350)�ɖI�N���A�����ꑰ��łڂ����B�����͒��`���ߓ쒩�Ƙa�r������A�֓��ɕ��𗦂����`���~��������(���N�A���`�͋}���B�����ɂ��ŎE�Ƃ�������)�B���a���N(1352)�A�����@�̑�O�c�q������V�c�̑��ʂ������B���̌�A���`�̗{�q���~�ƌ��쒩���ɋ��s��D����Ȃǂ������A���a4�N(1355)3���A�q�̋`�F�ƂƂ��ɋ��s�����������B����3�N(1358)4��30�����s������H�@�ŕa�v�B���N54�B�@���͐m�R���`�B�����@�ƍ����A���q�ł͒������a�Ə̂��ꂽ�B������b�A�̂���������b�B�揊�͓����@(���s�s�k��)�B�@ �a�́E�A�̂��D�݁A����ג�Ɏt���A�܂��ڈ������������B��a���N(1345)�~�A�ג���O��W�̓`������(�V��ڏW)�B�������N(1356)�A�V��ڏW�̐�i�����A����͒���W�̕��Ǝ��t�̐��F�ƂȂ����B���O3�N(1333)7�����@�̌����䛠���a�́A�2�N(1339)6���̎����@�a���A����2�N(1335)�̓������A�����O�N�̏Z�g�Ж@�y�a�́A�2�N(1339)�̏t����[�a�̂Ȃǂɏo�r�B��a�E�����S��ɉr�i(���Q���ޏ]�Ɂu�����@�a��S��v�Ƃ��Ď��^)�B����E��W���o�B����W�ɂ�16��A�V��ڏW�ɂ�22����W�B������W�͌v86��B �@ |
|
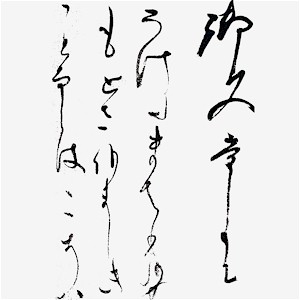 �@ �@���k�𐭎q1 |
|
|
�ی�2�N-�Ø\���N7��11��(1157-1225)�������㖖�����犙�q���㏉���̏����B���q���{���J�����������̐����B�ɓ����̍����A�k�������̒����B�q�͗��ƁA�����A��P�A�O���P�B�Z��o���ɂ͏@���A�`���A���[�A���g�ǂȂǁB�@ �ɓ��̗��l�����������̍ȂƂȂ�A���������q�ɕ��Ɛ�������������ƌ�䏊(�݂����ǂ���)�ƌĂ��B�v�̎���ɗ������ē���(���܂݂���)�ƌĂꂽ�B�@�������{�@(����ɂ傤����)�Ƃ������B�����S�����Ɛ��Α叫�R�ƂȂ������j�E���ƁA���j�E�������������ňÎE���ꂽ��́A���S���R�Ƃ��ċ����珵�����c���������o�̌㌩�ƂȂ��Ė����̎���������A���ɓR�Ə̂��ꂽ�B�@ �u���q�v�̖��͌���6�N(1218)�ɒ��삩��]�O�ʂɏ����ꂽ�ۂɁA���E�����̖�����ꎚ����Ė������ꂽ���̂ł���A����ȑO�͉��Ƃ������ł��������͕s���B�@ �����l�̍ȁ@ ���q�͈ɓ����̍����k�������̒����Ƃ��Đ��܂ꂽ�B �ɓ��̍ݒ����l�ł������������́A�����̗��Ŕs��ɓ��ɗ�����Ă����������̊Ď����ł��������A��������Ԗ��̂��ߍ����ŗ���̊Ԃɐ��q�͗����Ɨ����ɂȂ��Ă��܂��B�@ ���̍��̐��q�Ɨ����Ɋւ���j���͂Ȃ����A�u�\�䕨��v�ɂ��Ɠ�l�̓�ꏉ�߂Ƃ��āu�������v�̘b������B���q�̖�(��ɗ����̒�E����S���̍ȂƂȂ鈢�g��)�����������ɂ��ފ�Ȗ��������B�������̖��ɂ��Đ��q�ɘb���ƁA���q�͂���͉Ђ������炷���ł���̂ŁA�����ɔ���悤�Ɋ��߂��B�s�g�Ȗ���ƉЂ��]�ł���Ƃ����l�������������B���͐��q�ɖ���A���q�͑�ɏ�����^�����B���q�͋g���ƒm���Ė��̖������̂ł���B�g���̒ʂ�ɐ��q�͌�ɓV�������߂闊���ƌ��ꂽ�A�Ƃ���B�@ �������N(1177)�����Ɛ��q�̊W��m���������͕������ւ̕�����������A���q���ɓ��ڑ�̎R�،����ƌ��������悤�Ƃ����B�R�،����͌��͗��l���������A�����̈ꑰ�ł���A���������̐����ƂƂ��ɖڑ�ƂȂ�ɓ��ł̕����̑㊯�ƂȂ��Ă����B���q�͎R�̓@�֗`���ꂳ�����悤�Ƃ��邪�A���~���o�������q�͎R����z���A�����̌��֑������Ƃ����B��l�͈ɓ��R����(�ɓ��R�_��)�ɓ���ꂽ�B���q��21�̂Ƃ��ł���B�ɓ��R�͑m���̗͂������ڑ�̎R������o���Ȃ������Ƃ����B�@ ���̎��̂��Ƃɂ��āA��N�A���`�o�̈����̐Ì�O�������̓{������Ƃ��ɁA������G�߂�ׂ����q����������t�Łu�Ö���������A�J�����̂��ŋM���̏��ɂ܂���܂����v�Əq�ׂĂ���B���q�́A�܂��Ȃ������E��P���o�Y����B������2�l�̌�����F�߁A�k�����͗����̏d�v�Ȍ㉇�҂ƂȂ�B�@ ����4�N(1180)�Ȑm�����������ƕ����œ|�̋������v�悵�A�����̌����ɋ������Ăт������B�ɓ��̗����ɂ��Ȑm���̗ߎ|���͂���ꂽ���A�T�d�ȗ����͑����ɂ͉����Ȃ������B�������A�v�悪�I�����ĈȐm�����s���������Ƃɂ��A�����ɂ���@�����苓��������Ȃ��Ȃ����B�����͖ڑ�R�،����̓@���P�����Ă������邪�A�������R�̐킢�ŎS�s����B���̐킢�Œ��Z�̏@�����������Ă���B���q�͈ɓ��R�ɗ��܂�A�����̈��ۂ�S�z���ĕs���̓��X�𑗂邱�ƂɂȂ����B�@ �����͎����A�`���ƂƂ��Ɉ��[�ɓ���čċ����A�����̕��m�����͑��X�Ɨ����̌��ɎQ���A�����R�̑�R�ɖc��オ��A�����䂩��̒n�ł��銙�q�ɓ��苏���߂��B���q�����q�Ɉڂ�Z�B�����͕x�m��̐킢�ŏ������A�e�n�̔��ΐ��͂�łڂ��Ċ֓��𐧈������B�����͓����̎劙�q�a�ƌĂ�A���q�͌�䏊�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�@ ����䏊�@ �{�a2�N(1182)���q�͓�l�ڂ̎q�����D�����B�����͎O�Y�`���̊肢�ɂ�萭�q�̈��Y�F��Ƃ��āA�������̍����Ŋ��q���ɕ߂炦���Ă����ɓ��S�e�̉��͂𖽂����B�����͐��q�ƌ����ȑO�ɗS�e�̖��̔��d�P�Ɨ����ɂȂ�j�q�܂łȂ����������̓{������ꂽ�S�e�͂��̎q���E���A�����Ɣ��d�P�̒�����̕��m�Ƌ����Ɍ��������Ă��܂������Ƃ��������B�S�e�͂��͖̎Ƃ�p���Ƃ��Ď��Q���Ă��܂��B���N8���ɐ��q�͒j�q(����)���o�Y�B��̓�㏫�R���Ƃł���B�@ ���q�̔D�P���ɗ����͋T�̑O������悤�ɂȂ�A�߂��ɌĂъĒʂ��悤�ɂȂ����B����������̌�Ȃ̖q�̕�����m�炳�ꂽ���q�͎��i�ɂ����Č��{����B11���A�q�̕��̕��̖q�@�e�ɖ����ċT�̑O���Z��ł��������L�j�̓@��ł����A�T�̑O�͂ق��ق��̑̂œ����o�����B�����͌��{���Ėq�@�e���l�₵�A����̎�ŏ@�e���(���Ƃǂ�)��藎�Ƃ��p�J��^�����B�����̂��̎d�ł��Ɏ������{��A�ꑰ��A��Ĉɓ��ֈ����g���鑛���ɂȂ��Ă���B���q�̓{��͎��܂炸�A�����L�j�����]�֗��߂ɂ������B�@ ���q�̎��i�[���͈�v���Ȃ����R�����������̏����Ƃ��Ă͈ٗ�ł������B�����͐��U�ɑ����̏����ƒʂ������A���q������Ĕ��ΉB���悤�ɒʂ��Ă���B�����̋M���͕����̍ȏ��̉Ƃɒʂ��̂���ʓI�����A�L�͕��Ƃ��{�Ȃ̑��ɑ����̏��������q���Y�܂��Ĉꑰ�𑝂₷�̂����R�������B���q�̕������������̍ȏ�������A���q�ƕ��Ⴂ�̒햅�𑽂��Y�܂��Ă���B�����̕��`���������̏�������A�c���`�͎q���҂�20�l�ȏ���̎q���Y�܂��Ă���B�����A�����Ƌ`�o�̕�e�͕ʂł���B���s�Ő��܂�炿�A�����̓����ł����������ɂƂ��āA�����̏��̉Ƃɒʂ��̂͏펯�E�`���̔��e�ł���A�Љ�I�ɂ����R�̍s�ׂł��������A���q�͂���ȕv�̍s����e�F�ł��Ȃ������B�@ �����̏��q�̒�ł͐��q��݂��ďo�Ƃ�����ꂽ�B���̂��ߐ��q�͎��i�[���C���̌������@�w�̃C���[�W���������l�ɂȂ����B�@ ���i2�N(1183)�����͑Η����Ă������`���Ƙa�r���A���̏����Ƃ��ċ`���̒��q�`���Ɨ����Ɛ��q�̒�����P�̍����������B�`���͑�P�̖��Ƃ������ڂ̐l���Ƃ��Ċ��q�։���B�`����11�A��P��6�ΑO��ł���B�c���Ȃ������P�͋`����炤�悤�ɂȂ�B�@ �`���͕�����j��A������葁�����������B�����A�`���͋��̓����Ɏ��s���A�����Ɛ���Ĕs�k���A�㔒�͖@�c�Ƃ��Η������B����N(1184)�A�����͒�̔͗��A�`�o��h�����ċ`����łڂ����B�����͉Ѝ���f�ׂ����q�ɂ����`���̎E�Q�����߂邪�A����������B����R�ꕷ������P���`�������q����E�o������B���{���������̖��ɂ��x�e�Ƃ������ǂ��A�`���͐e�Ƃ̘Y�}�ł��铡�������̎�ɂ���Ďa��ꂽ�B��P�͔ߒQ�̗]��a�̏��ɂ��B���q�͋`�������ׂɑ�P���a�ɂȂ����ƕ���A�e�Ƃ̘Y�}�̕s�n���̂������Ɨ����ɋ�������A�����͂�ނȂ������������N����ɂ��Ă���B���̌��P�͐S�̕a�ƂȂ�A�����J�D�ɒ��ސg�ƂȂ����B���q�͑�P�̉���������Ă����Ύ��ЂɎQ�w���邪�A��P���������邱�Ƃ͂Ȃ������B�@ �͗��Ƌ`�o�͈�m�J�̐킢�ŕ����ɑ叟���A�ߗ��ɂȂ����O�ʒ������d�t�����q�ɑ����Ă����B�����͏d�t���������A���q�����̋M�l���Ԃ߂邽�ߎ����̐��̑O�������o���Ă���B�d�t�͌�ɔނ��Ă������������厛�֑����Ďa���邪�A���̑O�͏d�t�̎���߂��݁A�قǂȂ��������Ă���B�@ �͗��Ƌ`�o�������Ɛ���Ă���ԁA�����͓����̌o�c��i�߁A���q���Q�w�F���A���Ђ̑��c���ȂǏ��s���ɗ����Ɠ��Ȃ��Ă���B����2�N(1185)�A�`�o�͒d�m�Y�̐킢�ŕ�����łڂ����B�@ �����ŖS��A�����Ƌ`�o�͑Η����A�����Ɏ��s�����`�o�͘Y�}��ȏ���A��ēs�𗎂���B����2�N(1186)�`�o�̈����̐Ì�O���߂炦���A���q�֑���ꂽ�B���q�͔����q�̖���ł���Âɕ������]���A�a��Â�������Ă���B�x�d�Ȃ�v���ɐ܂ꂽ�Â͒߉������{�Ŕ����q�̕������I���A�����̖ڂ̑O�Łu�g��R���̔���ӂݕ��ā@����ɂ��l�̐Ղ��������v�u���Â₵�Â����̂����܂�������Ԃ��@�̂����ɂȂ��悵�����ȁv�Ƌ`�o��炤�̂��r�����B����ɗ����͌��{���邪�A���q�͗��l�ł����������Ƃ̐h����ꏉ�߂Ƌ����̂Ƃ��̕s���̓��X�����u���̂��̎��̏D���͍��̐Â̐S�Ɠ����ł��B�`�o�̑��N�̈���Y��āA���炵�Ȃ���Β受�ł͂���܂���v�ƂƂ�Ȃ����B���q�̂��̌��t�ɗ����͓{�����߂ĐÂɖJ����^�����B�@ ���q�͑�P���Ԃ߂邽�߂ɓ�䓰�ɎQ�w���A�Â͐��q�Ƒ�P�̂��߂ɓ�䓰�ɕ���[�߂Ă���B�Â͋`�o�̎q��g�������Ă���A�����͏��q�Ȃ琶�������j�q�Ȃ�ΉЍ���f���߂ɎE���悤������B�Â͒j�q�݁A���q�͎q�̏����𗊒��Ɋ肤�������ꂸ�A�q�͗R�䃖�l�Ɉ�����ꂽ�B���q�Ƒ�P�͐Â����݁A���A��Âƕ�̈�T�t�ɑ����̏d���^�����B�@ ���B�֓��ꂽ�`�o�͕���5�N(1189)4�������t�ɍU�߂�ꎩ�Q�����B�����͉��B�����̂��ߏo�w����B���q�͒߉������{�ɂ��S�x�Q�肵�Đ폟���F�肵���B�����͉��B��������łڂ��āA���q�ɊM������B���v���N(1190)�����͑�R�𗦂��ē����B�㔒�͖@�c�ɔq�y���ĉE�߉q�叫�ɔC����ꂽ�B�@ ���v3�N(1192)���q�͒j�q(�甦)�B��̎O�㏫�R�����ł���B���̐����O�ɗ����͐��Α叫�R�ɔC�����Ă���B���q�̔D�P���ɗ����͂܂�����i�ǂƂ������̂��Ƃ֒ʂ��A��i�ǂ͗����̒j�q(���)���Y�ނ��A���q��݂��ďo�Y�̋V���͏ȗ�����Ă���B��i�ǂ͐��q�̎��i������Đg���B���A�q�͐��q������ē���̂Ȃ�肪�Ȃ��ȂǁA�l�ڂ�݂�悤�ɂ��Ĉ�Ă�ꂽ�B7�ɂȂ������A���̐m�a���֑����邱�ƂɂȂ�A�o���̓��ɗ����͖����ɉ�ɗ��Ă���B�@ ���v4�N(1193)�����͕x�m�̕��ő�K�͂Ȋ������Â����B���Ƃ������˂�Ɗ�����͎g�҂𗧂ĂĐ��q�֒m�点�邪�A���q�́u���Ƃ̐Վ悪�����l�������炢�������Ƃł͂Ȃ��v�Ǝg�҂�ǂ��Ԃ��Ă���B���q�̋C�̋�����\����b�ł���B���̕x�m�̊����̍Ō�̖�ɑ\��Z�킪���̋w�̍H���S�o�������N����(�\��Z��̋w����)�B���q�ł͗������E���ꂽ�Ƃ̗���������A���q�͑�w�S�z���������q�Ɏc���Ă����͗����u�����ɂ͂킽��������܂��������S���������v�Ɛ��q���Ԃ߂��B���q�ɋA�������������q����͗��̌��t�����ȋ^�ɂ����A�͗��͈ɓ��ɗH����ĎE����Ă���B�@ ��P�͑��ς�炸�a���������A�����Ώ��ɕ����Ă����B���v5�N(1194)�A���q�͑�P�Ɨ����̉��ɂ�������Ƃ̈�����\�Ƃ̉��k�����߂邪�A��P�͋`����炢��Ȃɋ��B���q�͑�P���Ԃ߂邽�߂ɋ`���̒ǑP���{��ɍÂ����B�@ ���v6�N(1195)�A���q�͗����Ƌ��ɏ㗌���A��z��@�̐���̒O��ǂƉ���đ�P�̌㒹�H�V�c�ւ̓��������c�����B�����͐����I�ɑ傫�ȈӖ��̂��邱�̓����������]�݁A���q�����肪��Ȃ��P����Ԃ��낤�ƍl�������A��P�͏d���a�̏��ɂ��B���q�Ɨ����͉���������ĉ����F���������邪�A���v8�N(1197)�ɑ�P��20�̎Ⴓ�Ŏ��������B�u���v�L�v�ɂ��ΐ��q�͎��������̂��Ǝv���قǂɔ߂��݁A��������܂Ŏ���ł��܂��Ă͑�P�̌㐶�Ɉ�������ƊЂ߂Ă���B�@ �����͎����̎O���P����������悤�Ɛ}�邪�A����̎��͎҂ł��錹�ʐe�ɑj�܂��B�e���q�h�̊֔�������������r���A���쐭���ł̗����̌`�����������O���̓���������ȏ�ɂȂ������߂ɁA�����͍ēx�̏㗌���v�悷�邪�A���v10�N(1199)1�����n�����ŋ}�������B�u���v�L�v�ɂ��ΐ��q�́u��P�Ɨ���������Ŏ������Ŋ����Ǝv�������A�����܂Ŏ���ł��܂��Ă͗c�����Ƃ���l�̐e�������Ă��܂��B�q�����������̂Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ������v�Əq�����Ă���B�@ ������@ ���q�̗��Ƃ��Ɠ��p���B���q�͏o�Ƃ��ē�ɂȂ����ƌĂ��B�����̎�����2�����قǂ��Ď����̎O�����d�a�Ɋׂ����B���q�͊��q���̎��Ђɖ����ĉ����F���������A�㒹�H��c�ɉ@��܂ŏo�����ċ��̖�������q�ɌĂъ�B�O���͈�t�̏���������ňꎞ�����������悤�Ɍ��������A�e�Ԃ��}�ς���6���ɋ͂�14�Ŏ��������B�@ �Ⴂ���Ƃɂ��ƍقɌ�Ɛl�����̔������N���A����2�N(1200)���Ƃ̐ꐧ��}�����ׂ���]�L���A�����i���A���\���A�k�������A�k���`����V�b�ɂ��\�O�l�̍��c������߂�ꂽ�B�@ ���Ƃ����B�i���̈�����D���s�ˎ����N�����B�i��������ł���ƒm�炳�ꂽ���Ƃ͕����ē��Ƃ��Ƃ���B���q�͒���̂��ߌi���̓@�ɓ���A�g�҂𑗂��ė��Ƃ������Ђ߂āu�i���Ȃ�A�܂��킽���ɖ���˂�v�Ɛ\���������B���q�͌i����G�߂Ėd���̈ӎv�̂Ȃ��N�������������A����ŗ��Ƃ��d�˂ČP�����đ��������߂������B�@ ���ƂƘV�b�Ƃ̑Η��͑����A���Ƃ����Ɉ��������ďd�p���Ă��������i�������r���Ėłڂ��ꂽ(�����i���̕�)�B���Ƃ͗V���ɂӂ���A���ƂɏR�f���D�B���q�͂��̏R�f�������Ђ߂邪���Ƃ͕����Ȃ��B�i�ׂł̎����������A��Ɛl�̕s�������܂��Ă����B�X�ɗ��Ƃ͓���̕v�̔��\�����d�p���A�\���̖��͗��Ƃ̒��q�E�ꔦ��ŁA�������ւ��Ă����B��鎁�̑䓪�͖k�����ɂƂ��ċ��Ђł������B�@ ���m3�N(1203)���Ƃ��a�̏��ɂ���ĂɊׂ����B���q�Ǝ����͈ꔦ�Ǝ����œ��{�����邱�Ƃ����߂�B�����s���Ɏv���\���͕a���̗��Ƃɖk�����̐�f��i�����B���Ƃ������m���ē{��A�k���������𖽂����B�������q�z�������Ă������q�́A�g�҂������ɑ���A�����͍���u���Ĕ\����d�E�B���q�̖��ŕ����N�����Ĕ�鎁��łڂ��Ă��܂����B�ꔦ����鎁�ƂƂ��Ɏ���(���\���̕�)�B�@ ���Ƃ͊�Ă�����A��鎁�̖ŖS�ƈꔦ�̎���m���Č��{���A���������𖽂��邪�A���Ɏ哱���͖k�����Ɋ��S�Ɉ����Ă���A���Ƃ͐��q�̖��ŏo�Ƃ������ď��R�E��D���A�ɓ��̏C�P���ɗH����Ă��܂��B���Ƃ͌�ɈÎE����Ă���B�@ ����ď��R�鉺�����͎̂����ŁA���̎��������㎷���ɏA�C����B�����Ƃ��̍Ȃ̖q�̕��͐�����Ɛ肵�悤�Ɛ}��A���q�͎����̓@�ɂ����������}���A��߂��Ă���B���v2�N(1205)�����Ɩq�̕��͎�����p���ď����̕��꒩������R�ɗi�����悤�Ɖ��B���q�Ƌ`���͂��̉A�d��j�~���āA�������o�Ƃ����Ĉɓ��֒Ǖ������B����ċ`���������ƂȂ���(�q������)�B�@ �����͐ꉡ���ڗ��������Ƃƈ���ċ��{�ɕx���l���Œ�����d�Č��Ɛ����Ƃ̗Z�a��}�����B�㒹�H��c������Ɋ��҂��Ď�����D�����ď��i���d�˂������B�������A���Ɛ����Ƃ̉ߓx�̗Z�a�͌�Ɛl�����̗��v�ƑΗ����A�s��������Ă����B�@ ���q�͌���f���߂ɗ��Ƃ̎q������ɓ��ꂽ�B���̒��ɒ߉������{�ʓ��ƂȂ������ł�����B�@ ����6�N(1218)���q�͕a�����Ȏ����̕���������ČF����Q�w���A���ɑ؍݂��Č㒹�H��c�̓���Ō������тȂ��������q�Ɖ�k���d�˂��B���̏㗌�Ō��q�̈����ɂ���Đ��q�͏]��ʂɏ�����Ă���B�u���Ǐ��v�ɂ��A���̂Ƃ����q�͌��q�ƕa��Ŏq���Ȃ������̌�̏��R�Ƃ��Č㒹�H��c�̍c�q�𓌉������邱�Ƃ𑊒k���Ă���B�@ �����̊��ʂ̏��i�͍X�ɐi��ʼnE��b�ɓo�����B�`�����]�L���͎���������Ɏ�荞�܂�Č�Ɛl��������V�����邱�Ƃ������|���������A�����͏]��Ȃ��B�@ ����7�N(1219)�E��b�q��̎��̂��߂ɒ߉������{�ɓ����������͉��̌��łɈÎE���ꂽ�B�u���v�L�v�ɂ��ƁA���q�͂��̔ߕ�ɐ[���Q���u�q�������̒��ł�����l�c������b�a(����)����������ł����I��肾�Ǝv���܂����B���l���J���̑������̐��ɐ����˂Ȃ�Ȃ��̂��B�����ɐg�𓊂��悤�Ƃ����v�������܂����v�Əq�����Ă���B�@ ���R�@ �����̑��V���I���Ɛ��q�͎g�҂����֑���A�㒹�H��c�̍c�q�����R�Ɍ}���邱�Ƃ�������B��c�́u���̂悤�Ȃ��Ƃ�����Γ��{����邱�ƂɂȂ�v�Ƃ�������ۂ����B��c�͎g�҂����q�֑���A�c�q�����̏����Ƃ��ď�c�̈����̑����̒n���̔�Ƃ�����B�`���͂���{�̍�����h�邪���Ƌ��ہB��̎��[�ɕ���^���ď㗌�����A�d�˂čc�q�̓������������邪�A��c�͂�������ۂ����B�`���͍c�����R����߂Đۊ։Ƃ���O��(�������o)���}���邱�Ƃɂ����B���[�͎O�Ђ�A��Ċ��q�A�҂����B�O�Ђ͂܂���̗c���ł���A���q���O�Ђ��㌩���ď��R�̑�s�����邱�ƂɂȂ�A�u�R�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�B�@ ���v3�N(1221)�c���̉�]�ތ㒹�H��c�Ɩ��{�Ƃ̑Η��͐[�܂�A���ɏ�c�͋��s���ɉ���G���U�ߎE���ċ����ɓ��ݐ����B��c�͋`���Ǔ��̐�|�������̎��ƒn���ɉ����B��c�����̕���Ċ��q�̌�Ɛl�����͓��h�����B���m�����̒���ւ̈�͈ˑR�Ƃ��đ傫�������B�@ ���q�͌�Ɛl������O�Ɂu�Ŋ��̎�(���Ƃ�)�v�Ƃ��āu�̉E�叫(����)�̉��͎R���������A�C�����[���A�t�b��槌��ɂ��s�`�̐�|�������ꂽ�B�G�N�A���`(��c�̋ߐb)���āA�O�㏫�R(����)�̈�Ղ�S������B�������A�@�ɎQ�������҂͒����ɐ\���o�ĎQ���邪�悢�v�Ƃ̐����\�B����Ō�Ɛl�̓��h�͎��܂����B�u��ȋ��v��u���v�L�v�ɂ͐��q���g�����q���m��O�ɗ܂̉������s���A��Ɛl�͊F���܂����|�̋L�q������B�@ �R�c���J���ꔠ���E�����Ō}�����悤�Ƃ���h������������A��]�L���͏o�����ċ��i�R����ϋɍ���������߁A���q�ْ̍f�ŏo���ƌ��܂�A��Ɛl�ɓ����߂�����B�܂������ɍ����オ�邪�A�O�P�N�M���d�˂ďo��������A���q��������x�����Ė��{�R�͏o�������B���{�R��19���R�̑�R�ɖc��オ��B�@ �㒹�H��c�͐�|�̌��ʂ��Ύ����Ė��{�R�̏o����\�z���Ă��炸�T������B�����͖��{�̑�R�̑O�Ɋe�n�Ŕs�ނ��āA���{�R�͋����́B�㒹�H��c�͋`���Ǔ��̐�|����艺���Ď�����~�����A�B�֗����ꂽ�B�@ �k�𐭎q�̕�Ɠ`���₮��(������)���q�͋`���ƂƂ��ɐ�㏈���ɂ��������B�剞3�N(1224)�`�����}������B���j�̑��͌��������т�������҂���Ă������A�`���̌㎺�̈ɉ�̕��͎��q�̐����̎����i������āA�L�͌�Ɛl�̎O�Y�`���ƌ��ڂ��Ƃ����B�`���d���̉\���L�܂葛�R�Ƃ��邪�A���q�͋`���̓@��K�˂đ�����p�҂ƂȂ�ׂ���������A�`���������i���̉A�d�ɉ�����Ă��邩�l�₵���B�`���͕������đ��ւ̒����𐾂����B���q�͈ˑR�Ƃ��đ��R�Ƃ��邪���q���������߂������B�ɉ�̕��͈ɓ��֒Ǖ����ꂽ(�ɉꎁ�̕�)�B�@ ���͋`���̈�̔z���𐭎q�Ƒ��k���A���͒킽���̂��߂Ɏ���̔z�����i�i�ɏ��Ȃ��Ă���A���q�����S�������B�@ �Ø\���N(1225)���q�͕a�̏��ɕt���A���������B���N69�B �揊�͐_�ސ쌧���q�s�̎������Ɍ������̓���ׂ̗ɂ���B�@ ���@ �u��ȋ��v�́u�O���̘C�@�Ɠ����悤�ɓV�������߂��B�܂��͐_���c�@���Đ����ĉ䂪���̍c���i�삳����������v�Ɛ��q���̎^���Ă���B���~�́u���Ǐ��v�Ő��q�̌��������āu���l����̓��{���v�ƕ]�����B�u���v�L�v�ł́u���[(����)�̖ڏo�x����ł���v�ƕ]���Ă��邪�A���̕]�ɑ��Đ��q�Ɂu��قǐ[���߂��݂��������҂͂��̐��ɂ��܂���v�Əq�������Ă���B�@ ��������̈�����ǂ́u���̓��{���͕P�����Ƃ����B�������߂�ׂ����ƌ����悤�v�Ɛ��q���͂��ߔږ�āA�ޗǎ���̏���(�����V�c��F���V�c)�̌̎����Ђ��Ă���B�k���e�[�́u�_�c�����L�v�⍡�엹�r�́u����L�v�ł����q���{���哱�������q�̕]���͍����B�@ �]�ˎ���ɂȂ�Ǝ�w�̉e���Ől�ϓ����ςɏd����u�����悤�ɂȂ�A�u����{�j�v��V�䔒�A���R�z�Ȃǂ����q��]���Ă��邪�A�����S����Ɋ��q���{���哱�������Ƃ͕]�������A�q(���ƁA����)���ώ����č���(����)���łтāA����(�k����)������ɂƂ��đ�������Ƃ��w�l�Ƃ��Ă̐l�ςɌ����Ɣᔻ�������Ă���B�܂����̍����琭�q�̎��i�[�����ᔻ�̑ΏۂƂȂ�B���q�����x�q�◄�a�ƕ��Ԉ����Ƃ���]�����o��悤�ɂȂ����B�@ �ߑ�ɓ���ƕ����j�_�I�ȗ��ꂩ�珗�������ƂƂ��Ă̐��q�̗����]�����铮�����o�Ă����B����ŁA�c���j�ϓI�ȗ��ꂩ��͏��v�̗��Œ����ł��������O�l�̏�c�𗬍߂ɂ������Ƃ����c�̐S�Ɍ�����Ɣᔻ���ꂽ�B�@ ����ł́A��̓h���}�u���R����v�̌���ƂȂ����i��H�q�̏����u�k�𐭎q�v�Ȃǂ���ȍ�i�B�e���r�h���}�ɓo�ꂷ�鐭�q�͋C�����������~�ɕx�ނ��A����ŏ��Ƃ��Ă̗D�������̂������镡�G�Ȑ��i�̏����Ƃ��Ă����ނ˕`����Ă���B���q�ɂ��Ă͕v��q���E���ēV����D���������Ƃ��A�����Ɣ߂��݂ɖ������ǍȌ���Ƃ��l�X�ɕ]������Ă���B �@ |
|
| �������E�k�𐭎q2 �R / ���{�j���̏������[�_�[ | |
|
���������m�̐�����������R�@ ���q�͐����ɂ����Ĉ�v�̌������ɕs���ȂƂ��낪�������B����́A���q�ɂ͎��̂悤�Ȑ������O�����������炾�B�@ �����q�ɐV�������{���J�����̂́A�����܂ł������m�́E���m�ɂ��E���m�̂��߂̐����V���m�������Ƃ������Ƃ��B�@ ��������x����͓̂������m�ł����āA�����̕��m�ł͂Ȃ��B�Ƃ��ɓs�̐l�Ԃł͂Ȃ��B�@ �����q�́A���m�����s�ɓ���ƕK���������M�������đ�����A�Ǝv���Ă����B������A���s�ɐ��܂������v�̗������Ƃ��ɋ��s���������A�܂��Ƃ��ɋ��s�̏����ɐF�ڂ��g���̂��D�܂����炸�v���Ă����B�@ �������̈ɓ��ɐ��܂ꂽ���q�ɂ́A�����ł���Ȃ��瓌�����m�̏��S�E���_�̎v�z�����X�Ɨ���Ă����B�@ �����������āA���q�����q�����ɑ������̂́A���́u�������m�̏��S�E���_�������܂ł�����Ȃ��v�Ƃ������̂��B�@ ���������m�̏��S�E���_�Ƃ����̂́A���������E�s�����s�E�����g�̏������E�Ƒ��╔���ɑ������Ȃ�����Ȃǂł���B�@ �����������̈ꑰ�ł��A�ؑ\�`���E���`�o�Ȃǂ̕��m�����s�ɓ���ƕK���t�j���t�j���ɂȂ�A���ʓI�ɂ͐g���ق�ڂ��Ă��܂��B�������������Ă��āA���q�͂��悢��u���m���s�ɓ���ƕK���������ɂȂ�v�Ɗ������B�@ �����������āA���������v�����q�Ɏ����������m�̐����́A�����܂ł��o�b�N�{�[����������Ǝ������A�������m�̏��S�E���_�����Â�����̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɗ������B�@ �������āA���̂��߂ɂ́u���Ƃ������ł����Ă��A�����������I�ȏ��R�ɂȂ��Ċ��q���{����蔲���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƐS���������B�@ �����q�͂�������s�����B���̂��߁A�ޏ��͇��R���ƌĂꂽ�B �@ �������̋����@ �������㔒�͖@�c�̍c�q�Ȑm���̗ߎ|���ĕ����������̂́A�����l�i��ꔪ���j�N�����̂��Ƃł���B�Ȑm���͌������𖡕��ɂ������A��l�͂܂��Ȃ����Ƒ��̑�R�Ɉ͂܂ꂽ�B�����͐펀���A�Ȑm���͓��ꂽ�B���̈Ȑm�����N�̌����Ƃ��āA�u���Ɩ��\�̐��̒��ł́A���i������ɂ�������炸�A�Ȑm���͍c���q�ɂȂ�Ȃ��������炾�v�Ƃ�����������B�@ �����Ȃ�ƁA���̋����̓��@�́A�u�Ȑm���̎��I�Ȏ���ɂ����́v�Ƃ������ƂɂȂ邪�A�S���̏͂���Ȓ��x�̂��̂ł͂Ȃ������B�@ �u���Ƃɂ��炸��ΐl�ɂ��炸�v�ƍ��ꂷ�镽�ƈ��́A�������̍єz�ɂ���đS���̍��X�̂قƂ�ǂ̊Ǘ��҃|�X�g���߂Ă����B���ƂłȂ����m�����̕s�������������ɔ������鐡�O�ɂ������̂ł���B�@ �Ȑm���̗ߎ|���g���Ă���Ă����g�҂��}���āA�����͂��ɋ����ɓ��݂������B���̋������x�����̂��A���q�̕��k�������ł������B�����͓s�ł̑�Ԗ��ߏI��������ł���A���m�̂炳�����g�ɂ��݂Ēm���Ă����B���������āA�i�꒚����Ă݂邩�B���߂ł��Ƃ��Ƃ��j�Ƃ����_�����g�̊o������߁A������������B�����͂���ɏ��A�܂��ɓ����̖ڑゾ�����R�،������E�������B�@ �O�q�����悤�ɁA�R�،����́A�ꎞ�A�k���������A�i���l�̗����̍ȂɂȂ�����A�����Ȗ�l�ł���R�ؓa�ɉœ��肳�����ق��������j�ƍl���āA���q���œ��肳��������ł���B�����^����ɎE�����̂́A��͂�i���i���炫�������̕��j�ƍl�����������A�����ł͂Ȃ��B�R�،����͂�����Ƃ����������{�̔h��������l�ł���A�����ɕ��ƈ��ł������B���������āA�R���Ƃ͂��̂܂܁A�u���Ƃɑ��A�^�������璧�킷��v�Ƃ��������̎p�����������̂ł������B�@ �����̖k��������A�v�̌���������w���⍲���Ԃ�@ �⍲���̏d�v�ȐE���̈�́A�g�D�ړI�B���̉ߒ��ɂ�����i�s�Ǘ��ł���B���q�������{�����̌�A�Ȃ���Ȃ�ɂ������Ă����̂́A���{�n�������ɂ����鐭�q�́A�u���⍲���Ԃ�v�ɕ����Ƃ��낪�傫���B�������A���̐��q���A��V�I�ɂ��������\�͂�g�ɂ��Ă����킯�ł͂Ȃ��B��͂�A���̖k��������A�v�̌���������w�Ƃ��낪�����B����ɁA���������s���珵�����������Ƃ̑�]�L��������w�B�w���Ƃ̍ő�̂��̂́A�u�g�b�v���[�_�[�Ȃ�тɂ��̕⍲���́A�o�g�������ɖڂ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�E�H�[�����n���Ȃ�����߂��v�Ƃ������Ƃł���B�@ �������͌��������̉ߒ��ɂ����āA����ɂ͂܂������Q�����Ă��Ȃ��B�ނ��݂����獇��Ŏw�����Ƃ����̂́A�ɓ��ŖI�N�����Ƃ��������B���̌�̕��ƂƂ̏d��Ȑ킢�́A���ׂĒ�̋`�o��͗��ɔC���Ă���B�����́A�u�e���E�����Ύq�͂��̈�̂����z���ē˂��i�݁A�q���E��������ɑ������̈�̂��z���ē˂��i�ށv�Ƃ����������m�̕������炢���A�����̑ԓx�͕K�������J�߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�E�҈�r�ō����̂��Ƃ����l���Ȃ��������m�̒��ɂ́A�u���q�̌�叫�͔ڋ��҂��v�ƌ���҂��������낤�B�C�̋������q���g�A�i�킪�v���D�b��Ȃ��j�Ɗ��������Ƃ�����B�@ ���A����ɁA�������Ȃ����q���瓮���Ȃ����Ƃ������R���킩���Ă����B����́u���������̑S�̑����q�ϓI�ɋÎ�����v�Ƃ����l��������������ł���B �@ �������̖�]�͈�v�@ �u���܂��������Ȃ��������҂Ɉ�����ȁv�@ �u���ׂĕ���̂��O���ł������܂��v�@ �u�R�����v�����͏����B�����āA�u�����a�̓s�̏��q�D�����A���ǂ͂��܂��������������Ɏd���Ă��̂��v�Ə����B���q�͈�u�o�b�Ɗ��Ԃ��������A�������Ȃ������B�@ �u���̂Ƃ���ł������܂��B�ł�����A���セ�������S�z�����������Ȃ����q�������������邽�߂ɂ́A���̂��т̕���̂���ڂ͏d��ł��B���ʔ@���ɂ���Ă��ꂪ���Ȃ��܂��傤�v�@ �����������B�����͂��Ȃ������B�����ŕ����̋C�����͈�v�����B�@ �����q�����͂����܂ł��A�������m�́E�������m�ɂ��E�������m�̂��߂̐����ł���B�@ �������āA���̊��q�����ɂ��C�j�V�A�`�u������̂́A�k���ƂƂ��̎q���ł���B�@ �����̌���ɂ����ẮA���q�͒P�Ȃ闊���̍Ȃł͂Ȃ��B�����I�Ɋ��q�������哱����k���Ƃ̈���̗�����т��B�@ �����q�����́u�⍲���v�̃|�X�g�́A�����܂ł��k���ꑰ������������p���B�@ �����̂��т̖k�������̏㋞�́A���̑b��z���ړI�����킹�����Ă���B�@ �����炱���A���̎����͖����q�̊�̒�ɂ���������]���������A�i�킪���Ȃ���A�j���ɕ����Ȃ��������������Ă���j�Ɗ������̂ł���B�����Ȃ�ƁA�����̖��ɑ��錩�����ς��B�����͂��̖�͂�����ƁA�i���̖��Ɖ��̖�]�͈�v���Ă���B���q�����邱�Ƃ͖k���Ƃ̂��߂ɑ傢�ɗ��������j�Ɗ������B �@ �����ȏ�̕⍲���@ �i���ڎ������������Ȃ���A���R�̐��Ђ��ۂĂȂ��j�ƍl��������ł���B�����ւ����Ɨ����ɂ͂܂�����Ȃ��̂��Ȃ��B������A���q�͂₫�������Ă����B���q���g�ɂ���A�i���Α叫�R�Ƃ��Ă̕v�����ڊǗ��ł���y�n�Ɣ_�������������j�Ɗ肤�B�R���ɂ��Ă��������B�m���ɒ��b�͑����Ă͂������A�債�����͂ł͂Ȃ��B�꒩������Ƃ��͂��ׂČ�Ɛl�Q�̐��b�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ւ荂�����q�ɂ���A�������肫��Ȃ��v�����B���q�͎����ƂƂ��ɁA���ڂ̌R���������Ƒ������������Ɗ肢�Â��Ă����B�����āA�i����������̂����̖����Ȃ̂��j�ƌ���ł����u�⍲��I�Ӗ��v��Ɋ����Ă����B���܂ł͂Ƃɂ������̐��ɉ����ēw�͂��Ă����B���̎��������͂��Ă����B���ꂩ�炢���A���̎��������q���{���������̕⍲���Ȃ̂��B���q�͏��R�̍Ȃ�����A���̏�ʎ҂ɂȂ�B�����A�����I�ȐS�z��A���낢��ȍ�𗧂Ă�̂͐��q�̂ق��������B����ɁA���̎������A�u�킪���Ȃ���A�Ȃ��Ȃ����܂��͂悭����v�Ƃ����ċ��͂��Ă��ꂽ�B �@ ���䂪�q�E���Ƃ̍ق��~�߂���Ɛl��c�̐ݒu�@ ���q�̋��̒��ɁA���܂łȂ������₽���X�̒����������B����́A�i�ꍇ�ɂ���ẮA���Ƃ��킪�q�ł����Ă����Ƃ����f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�Ƃ������Ƃł������B���̒i�K�ɂ����āA���q�͌��l���ƂƎ��l���ƂƂɕ��f�����B�܂�A���R�ł��闊�Ƃ͌��l���B�������A���q�ł��闊�Ƃ͎��l���B���A���Ƃɂ���A��Ȃ��玩����l�̂��̂��B���������āA���q�����f���A�u���l�ł��闊�Ƃ���������v�ƌ��肵���Ƃ��́A���l�ł��闊�Ƃ������ɏ�������Ă��܂��B����͐藣�����Ƃ��ł��Ȃ��B���܂ł̐��q�́A�i���ɂ��ꂪ�ł��邾�낤���j�ƔY�B�������A�����܂ł����ȏ�A�����S�����߂�������Ȃ��B�������̂����A�u��Ɛl��c�v�́A���c�@�ւł͂��邪�A����@�ւł�����B�܂�A�u���q���{�̈ӎv�����肷��@�ցv���B��Ɛl��c���̂��̂����茠�������s�@�ւł�����̂��B�����łȂ���A���Ƃ̐e�ق��~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����炭���Ƃ͕�����������낤�B���m�����܂��B����ł͖��炩�Ɋ��q���{�̌���@�ւ��^����Ɋ���Ă��܂����炾�B���ł����A�g�b�v�}�l�W���g�����Ă��܂��B���t��������A�u���q���{�̓����v���s�Ȃ��邱�ƂɂȂ�B���A���̍�������ނ����Ȃ��Ɛ��q�͊o�債���B�@ �����ŁA���̎������畷������Ɛl��c�̋@�\�ɂ��Ē�ɘb�����B�`���͊���P�����Ęb�����B�����āA�����I���Ƒ傫�����Ȃ������B�@ �u�^���ł��v�@ �u�ł͑����A�l�I�ɓ���܂��傤�v�@ �V�����݂����Ɛl�̉�c�́A�������O�l�Ƃ��邱�Ƃɂ����B�@ �������𐪈Α叫�R�ɁA���Ƃ����̂Ă�@ �u��㏫�R���Ƌ������v�̕A���s����ɂ����炳��Ă����Ƃ������Ƃ��B�@ ���������āA���s����́A�u�}���A�O�㏫�R�̌�����s�Ȃ��悤�Ɂv�Ɩ����A����ɑ��A�k�𑤂ł́A�u�����R�̒�����������Ă���ɂ��Ă����v�ƕ����B���̕ӂ̉^�т͂����炭��]�L��������̎�ۂɂ����̂��낤�B�㌎�����ɂ́A�u�������𐪈Α叫�R�ɔC����v�Ƃ�����|�������炳�ꂽ�B���̂Ƃ��A���q�͗��Ƃ̂Ƃ���ɍs�����B�����āA�u���Ȃ��̂��C�����͂悭�킩�邯��ǁA���ێ��Ԃ͂����܂ł��Ă��܂����B�ǂ����ϔO���āA����ɂ�����Ȃ����v�Ɨ@�����B���Ƃ͒�R�����B���q���ɂ݁A�u���͎��ɑ�����ł��������Ƃ͈�x���Ȃ��B�������A���͂܂������S�ɂȂ�ꂽ�v�ƍ��݂̌��t���������B���q�͊Î��B���������Ă��d�����Ȃ��Ǝv���Ă������炾�B�@ �����ɂ܂��A�i�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��炳�́A���ꂱ�̗��Ƃɂ͂킩��Ȃ��j�Ǝv�����B �@ �����������G�Ƃ��ē|���@ �u����ɁA�����ɕs���ȏ��𗬂��ȊO�Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ����B�������q�E�`���o��ɂ́A�����Ǝv���C�����͂Ȃ��B���S�Ȑ��G�ł������B�@ �u���G�͂Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����ӎu�͈�v���Ă���B���̓_�ɂ����ẮA���łɐe�q�̏��Y�ꂽ�����ȊO�̉����̂ł��Ȃ������B���q���͂ӂ����уK�Z�l�^���\�Ƃ��ė������B����͋`�����ŏ����ꂽ�A�u�k�������͖��������������Ɏw������v�Ƃ����i�K���炳��ɔ���āA�u�����E�q�̕��v�w�́A�����̖����ł��镽�꒩����������R�ɐ������Ă悤�Ƃ͂����Ă���B���̂��߁A�ז��ɂȂ�������E�Q���傤�Ɗ�ĂĂ���v�Ƃ������낵�����̂ł������B�������Ɋ��q�͋��������B�@ �u���X�\�ɂ͕����Ă������A�������k�������a�́A�����܂Ŗq�̕��̐K�ɕ~����Ă���̂��v�Ƌ����̐���������B�����āA���̂Ƃ����܂��A�u�\�����肦�邱�Ƃ��v�Ɖ\����������ɍm�肷��҂����������B���̉\�͑O�̂悤�ɂ����ɏ����Ȃ������B����ǂ��납�A���͂��悢��Z�x��[�߁A���q�̋�C�͌����ɂȂ����B�E�܂����A������́A�u���Ƃ����q���{�n���̌��J�҂ł����Ă��A���̂悤�Ɍ�����������k�������͕s�͂��҂��B���̍ہA�v�������ĊД����ׂ����v�ȂǂƂ��������Ȉӌ��܂ŏo�͂��߂��B���q�Ƌ`���́A�u���̋@��͂̂����ʁv�ƍ��ӂ����B�@ �����ŁA���v��@�i���Z�܁j�[�����\����ɁA���q�̖��ɂ���Đ��l�̗L�͌�Ɛl���A�R���𗦂��Ď����@�ɉ����������B �@ �����v�̗��ŕ��m�̐S����ɂ������q�̑i���@ �u�݂Ȃ݂ȐS����ɂ��ď���B���̍Ō�̌��t�ł���B���̐́A���m�͑�Ԗ����O�N���߂�̂���ł������B���ꂪ���m�̐Ӗ����Ǝv���A�Ɨ���A��ċ��֏�����B�������A�O�N�̔C�������Č̋��A��Ƃ��ɂ́A���̂�̍��Y���g�������A�n�������i�������������蕥���ċ��̎҂��Ȃ��A���}����ɂ����A�݂��ڂ炵���p�Ŗ߂��Ă���̂��킾�����B��Ԗ��͋��s�ɑ؍ݒ��̔�p�����̂�ŕ��S���Ȃ���Ȃ�Ȃ���������ł���B�����S���a�i�����j�͂����Ɏv���A�O�N���킸�����N�ɏk�߂�ꂽ�B�������A�g��ɉ����Ċ��肠�āA���l��������悤�ɂȂ��ꂽ�B����Ȃ��Ƃ͂��ŋ߂̂��ƂŁA�܂��݂Ȃ݂Ȃ��悭�o���Ă����ł̂͂����B����قǏ�[������ꂽ�̓a�̂������ǂ����ĖY����悤���B�݂Ȃ݂Ȃ�A���̓a�ɑ����āA�Y���̓k�ƂȂ��ċ��s�֖�������Ȃ炻����悵�B���������l�������҂́A���̂��Ƃ����͂�����\�������Ă��̏������B�G�����𖾂炩�ɂ����v�ƌ��܂��ӂ���ďq�ח��Ă��B�@ ���q�̋C�����ɊO�A���͂Ȃ��B�{�S�ł����v���Ă����B�ޏ��̓��̒��ɂ́A�������̖ʉe���͂����肵���f���������č��肱�݁A�u���q�A����������v�Ɨ�܂��Ă����B�����̉f���Ɍ���������A���q�͎v���̂��������тÂ����B��߂����Ă�����Ɛl���m�����͈��|���ꂽ�B���̂���̕��m�͂܂�����قNj��{���Ȃ��B�낭�Ɏ����ǂ߂Ȃ���A�������Ƃ��ł��Ȃ��B�����炭�����̖���������҂�����قǑ����͂Ȃ��낤�B���������āA���������A�����̕��m���@���́A�u�m����������s���鑶�݁v�������B�����āA���ꂪ�������m�̋����̊j�ɂȂ��Ă���B�������m�������̂͂��܂�m�I�Ȏv�l�����Ȃ����߂��B���œ����B�����āA����a�s���B���������Ɗ�������A���������������h���h�����Ŏ��s����B�قƂ�ǂ̕��m�����q�̗܂Ȃ���̑剉���Ɋ��������B���̋�C������������ނƐ��q�͂������Ƃ��Ď��@�����������̘b�������B�@ �u���������āA���̂��т̏㗌�́A�ɐ���_�{�����F�߂ɂȂ艞�����Ă�������B�݂Ȃ݂Ȃ�A�����Ƃ���Ȃ����a�ɏ]���B���a�͂��łɏo�����Ă����邼�I�v�ƂЂƍې��肠�����B��ł����܂��E�H�[�Ƃ����J�̐������������B�@ ���v�O�i�����j�N�܌���\����A��Ɛl�����͐�𑈂��悤�Ɋ��q���o�����A�攭��������ǂ��͂��߂��B |
|
| ���k�𐭎q3 | |
|
�ޏ��͖k�������̖��ŁA�������̍ȂƂȂ�A���ƁE�������Y�݂܂��B�ޏ����O����グ�����������Ƃ͕ʊi�Ȃ̂́A�ޏ����v�⑧�q�����̈Ӑ}���щz���āA�����̂Ȃ��ׂ����Ƃ��Ȃ��Ƃ��čs��������ł��B�@ �k���Ƃ͕��Ƃ̈��ł����A�����̍ŏI��ɂ����ẮA�����̕ی�҂ł��������Ƃ���A�������Ƃ��Đ킢�܂��B�����Ċ��q���{������͎����Ƃ�������ɂȂ�A�`�[���������R�������u���āA���{�̎x�z�҂ɂȂ�̂ł��B�Ƃ������ƂŌ����̑����̍ŏI���҂͎��͕�����������ł��B�@ ����͂��Ă����A�k�𐭎q�͗����������Ă���Ԃ��ϋɓI�ɐ����I���ɉ�����܂������A���͂�����̂́A��͂藊���̎���ł��B�@ ���Ƃ�|���A��̋`�o���|���ēG�̂��Ȃ��Ȃ����������͐��Α叫�R�̐E�������炢�A���q�̕��̖k��������A�L�\�Ȋ����ł����]�L����𒆐S�ɐ����g�D�ł��開�{��Ґ��A���Ɛ����̊�{�\�������܂����A�n���痎���Ă������Ȃ�����ł��܂��܂��B�@ �����ŗ����̒��j�̗��Ƃ����R�E���p���̂ł����A�ނ͂������Ė��\�Ȑl���ł����B���ׁ̈A���X�ɖk�𐭎q�͕��̎����ɂ����͂��Ă��炢�A�����̎��������R����D���A���{�̐F�X�Ȍ��قɊւ��Ă͐��q�����f����悤�ȑ̐��𐮂��܂��B����ɑ��āA�ǂ��ɂ����\�ȗ��Ƃ́A�R���u�����悤�ȍ����������A�����悤�ɖ��\�Ȓ��Ԃ��W�߂đ������蕔���̍Ȃ����D�����肵�āA�Ђキ���A�Ō�͉����Ƃ��邳����Ƒc�����������Ƃ��܂��B���A�ނ��t�ɕ߂炦���A�E����܂��B�i���\���̕ρj�@�����ď��R�E�͒�̎����������p���܂��B�@ �Ƃ��낪�A���Ƃ̑��q���ł������̋w�Ƒ_���A�߉������{�ɎQ�q�ɗ��������ӂ��ł����ĈÎE���Ă��܂��܂��B�ނ����ł͌�q�̕��m�ɂ��̏�ŎE����܂����A�����̌����͂����Ƃ����Ԃɏ����Ă��܂��܂����B�@ �����Ŗk�𐭎q�͏��R�s�݂̂܂܁A�����̍Ȃł��邩��ɂ͖��{�̒��ł���Ƃ��ĕ��m�����̏�ɌN�Ղ��A���������c�������{�̐E���̐������s�Ȃ��܂����B�����đ����ċN�����㒹�H��c�ɂ�鏳�v�̕ςɂ����ẮA��Ɛl�������J���X�}�I�Ȑ����͂Ŗ����ɂ��ď�c�R��ł��j��A���q���{�̊�b���ł߂��̂ł��B���ׁ̈A�ޏ��́u�R�v�ƌĂ�A���ɑ��h����܂����B�@ �k�𐭎q���ӔN�S�̋��菊�Ƃ����̂́A���Ƃ̖��̒|�䏊�ł����B�ޏ��͍��̂��߂Ɏ����̑��q�̗��Ƃ̎E�Q�𖽂���̂ł����A����̂ɑ��q�̖Y��`���̔ޏ���̂悤�ɑ厖�Ɉ�ĂĂ��܂����B�@ �����Ėk�𐭎q�̎���A��͂菫�R��N�����ĂȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ������A�����̖Â̑��̓������𗊌o�����s����Ăꏫ�R�ɂȂ�܂����A�|�̌䏊�����̍ȂɂȂ�܂����B�ޏ��������q�����Y��ł����珫�R�Ƃ̌����͈ꉞ�����̒��n�ő����čs���Ă����Ƃ���Ȃ̂ł����A���o�̎q��g�U����A�q���͎��Y�E��������̂��Y�Ŏ��ʂƂ�����^�Ɍ������܂��B���̌��ʁA���R�E�͂��̌�A�����Ƃ͂䂩����Ȃ��V�c�Ƃ̐e������}������邱�ƂɂȂ�܂��B�@ ���ʁA���{�̎����͏��R�ł͂Ȃ��k���Ƃ̂��̂������̖��ŏ�������̐��ɂȂ��Ă����܂��B�܂��l���Ă݂�ƁA���������k�𐭎q�������ƌ������Ă��Ȃ�������A�����̖I�N�ɖk���ꑰ�����͂��邱�Ƃ��Ȃ��A�����͂����Ȃ��|����Ă����ł��傤����A�k�𐭎q�����A���q���{��������l�ƌ����Ă����������m��܂���B�@ |
|
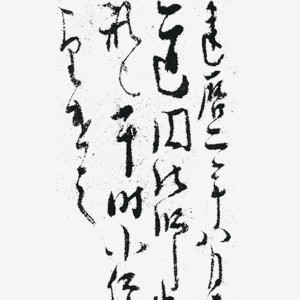 �@ �@�����b�E���{�I�v���̓N�w / �R�{���� |
|
|
�ی�(�ق�����)�̗��́A��G�c�ɂ����A���H�@�c�Ɛ���(���Ƃ�)�V�c�Ƃ̐��͑����ł���A���Ƃ����������ꂼ��ӂ��h�ɕ���Đ�����B�������́A���H�@�c�̑��ɂ��Ă̂��オ�邫�����������B���̂��Ƃ̕����̗��́A�������ƌ������������ċN�����������ł���A�������͂�����āA���͂̍����蒆�ɂ����B�Ȃ��A�������̋����́A�����ƕ��Ƃ̐킢�ł���A�u���v�Ƃ͌���Ȃ��B�����������q���{���J�����̂����㔒�͖@�c�ƌ㒹�H�V�c�̑Ԑ��͂��̂܂ܑ������̂ł���B���̌�A�㔒�͖@�c�͂Ȃ��Ȃ�A�㒹�H�V�c�����̂��Ƃ��p���Ō㒹�H�@�c�ƂȂ肷�ׂĂ̎������������B���̌㒹�H�@�c���A���m�̓��̂ł��Ȃ��k���ꑰ�����������̂ł���B�@ ����͑�ςȂ��ƂŁA�V�c���h�����ꂩ��́A�k���ꑰ�̓P�V�J�����Ƃ������ƂɂȂ锤�ł���B�������ǂ��������邩�Ƃ������Ƃ��|�C���g�ł���A���̊j�S�����ł���B�@ �R�{�����́A�ȏ�̂悤�ɁA�u�c���j�ρv�̌����Ƃ���鐅�ˊw�ɂ����āA�`���E���̂Ƃ����s���F���Ă��邳�܂��Љ�Ă���̂����A��͂�E�E�E�㒹�H�E�y���E�����̔z���قNj������ׂ������͂킪���̗��j�㑼�ɗ�����Ȃ��B�̕�(�c���@�F�����V�c�~�m��p��)�́A�c���@���V�c��H���������ł��邵�A�ی��̗��͓V�c�ł���㔒�͂���c(����)��z�����������ł���B�@ �Ƃ���ŁA���͖��b�̎v�z�ɑ傫�ȉe���������Ƃ͂Ƃɒm���Ă���B���b�Ƒ����琂́A�]��Ɂ����I���Řb�����܂��o�������Ă���̂ŁA������t�B�N�V�����Ƃ���l�����邱�Ƃ͂���B�������A���b��l�����炩�̌`�Ŗ��{������q�₳�ꂽ���Ƃ́A����߂Ă��蓾�鎖���ł���B�@ �Ƃ����̂́A������̎�������v�z�I�Z���l�Ԃ̔c���̎d���́u�@�v�����Ȃ��B����ł͂��ꂪ�ێ�Ɗv�V�A�i���Ɣ����A�^�͂ƃn�g�A�E�X�ƍ��X�A�푈���͂ƕ��a���͂Ƃ����`�ɂȂ��Ă��邪�A�@�I�c���͏��v�̕ς̎���ł������ł������B�܂��Đ퓬�ƂȂ�ΓG�Ɩ����ɕ����邵���Ȃ��B���̔c����퓬��܂ʼn����i�߂�A���쑤�Ɩ��{���Ƃ����@�����Ȃ��Ȃ�B�����Ă��������c���̎d��������Ζ��b�͖��炩�ɒ��쑤�̐l�Ԃł������B�ہA���Ȃ��Ƃ����������ē��R�̎Љ�I�n�ʂƌo���������Ă����B���̐l�Ԃɕs�R�ȓ_������A�O��c�𓇗����ɂ��A�V�c�������I�ɑވʂ������폟��遂镐�m�������A���b����̑O�Ɉ����������Ƃĕs�v�c�ł͂Ȃ��B����ɔނɁA�b�R���s�̑厛�̂悤�ȁA�z�����ׂ������I�E���͓I�w�i���Ȃ����Ƃ��A�����e�Ղɂ����ł��낤�B�@ �Ƃ��낪���̖��b�Ɋ������đ������̒�q�ƂȂ����B���̂��Ƃ̓t�B�N�V�����ł͂Ȃ��B�@ ���āA�����^�v���̑c�^�́A�̐��̊O�ɐ�Ύ�(�_)��u���A���̐�Ύ҂Ƃ̌_�X�������Ƃ����`�ł��ׂĂ���V���Ă��܂��u�\���L�^�v���v�ł���B�@ ���̏ꍇ�A����́A�����̗��Q�W����ؖ������A���j�𒆒f���ĕʂ̒����ɐ�ւ���Ƃ����`�ōs�Ȃ��邩��A�̐��̒��̉����ɐ�ΐ���u������s�Ȃ����Ȃ��B�]���Ċv���̓C�f�I���M�[���Ή����A����݂̂�B��̊�Ƃ��ĎЉ��]����Ƃ����`�ł����s�Ȃ����Ȃ��킯�ł���B�@ �̐��̓����ɐ�ΐ���u���A����́A�V�c���Ƃ��悤�Ɩ��{���Ƃ��悤�ƁA�V���������̎����͕s�\�ł���B�@ �̐��̓����ɐ�ΐ���u���Ȃ���V�����������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�V�����������m�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Â������̌p���ƐV���������̑n���A���̖������ǂ��������邩�B�����Ŗ��b�̎v�z�E�u����ׂ��悤�́v������P���ė���̂ł���B�@ ���b�̃��j�[�N���Ƃ����̂́A���Ƃ̒����̊�{�̔c�����ɂ���B���b�́u�l�̓��̒����v�̂悤�ɁA���A���R�I�����ƌ��Ă���̂ł���B���b�ɖ{���ɂ����������z���������̂ł��낤���B���̋L�q�͎j���I�ɂ͑����ɖ�肪����Ǝv���邪�A�ȏ�̔��z�́A���b���̐l�̔��z�ƌ��Ă悢�Ǝv���B�Ƃ����̂́A�u���ւ̃��u���^�[�v����������Ă���A���̃��u���^�[�̎j���I���l�͔ے�ł��Ȃ�����ł���B�@ �u���̌�A���ς育�����܂��B���ʂꂵ�܂��Č�͂悢��(�ׂ�)�������Ȃ��܂܂ɁA�����A(��������)�����������ɂ���܂��B�������������̂��̂��l���܂��Ȃ�A����͗~�E(�悭����)�Ɍq��(��������)����@�ł���A�p����(�����)���`�����Ƃ�����F(�ɂ���)����(����)���A�Z��(�������)�̈�ł���፪(����)�A�Z��(�낭����)�̈�ł���Ꭿ(����)�̂䂩�肪����A�����䐶(�����傤)�̎p�ł���܂��B�܊��ɂ���ĔF�������Ƃ͒q(��)�̓����ł���܂�������Ȃ�����(���Ƃ��炪�����Ƃ͗����Ȃ킿�����ł����āA����ɕЂ��Ƃ������Ƃ͂���܂���B�����Ȃ킿�����ł��邱�Ƃ��������Ƃ������ƂŁA�����Ƃ͉F���̖@��(�ق���)���̂��̂ł���A���ʂ̖������A�����̎��̂��O��(���ザ�傤)�̐��E�Ƃ����̂Ɖ���̑���͂���܂���B����̂ɖ�Ɠ����悤�Ɋ���������Ȃ�����Ƃ����Ĉ��(��������)�̐����Ƌ�ʂ��čl���Ă͂Ȃ�܂���B�܂��Ă⍑�y�Ƃ͎��́u�،��o(�����傤)�v�ɐ�(��)�����̏\�g���ł���ȍ��y�g�ɓ����Ă���A���I�Փߕ�(�т邵��ȂԂ�)�̂��̂̈ꕔ�ł���܂��B�Z���܂�������ƂȂ��ď�(����)��Ȃ��@������܂��Ȃ�A�����̂��̂����y�g�ŁA�ʑ��傩�炢���ΏO���g(���ザ�傤����)�E�ƕ�g(�����ق�����)�E�����g(���傤����)�E��F�g(�ڂ�����)�E�@���g(�ɂ�炢����)�E�@�g(�ق���)�E�q�g(������)�E����g(����������)�ł���܂��B�����̂��̂����̏\�g�̑�(�Ă�)�ł���܂�����A�\�g���݂ɂ߂��邪�̂ɁA�Z�ʖ��V(�䂤�����ނ�)�Œ�ߓV(�������Ⴍ�Ă�)�ɂ�����(�ق�����)��t(�����ς�)�ƂȂ�A�͂��蓾�Ȃ����̂�����܂��āA��X�̒m���̒��x���z���Ă���܂��B����̂Ɂu�،��o�v�̏\���̌��ɂ���ē��̗�(���Ƃ��)�Ƃ������Ƃ��l���܂��Ȃ�A���I�Փߔ@��(�т邵��Ȃɂ�炢)�Ƃ����܂��Ă��A���Ȃ킿�����̂��̂̊O�ɂǂ����ċ��߂��܂��傤�B���̂悤�ɐ\���܂������ł��܂��łāA�̂��ڂɂ�����܂����܂���͂����Ԃ�ƔN�����o�߂��Ă���܂��̂ŁA�C�ӂŗV�сA���ƗV���Ƃ��v���o���Ă͖Y��邱�Ƃ��ł����A��������������(����)���Ă���Ȃ�����A���ڂɂ����鎞���Ȃ��܂܂ɉ߂��Ďc�O�ł������܂��v�@ �m���ɁA����l�͖��b�̐��E�����L���邱�Ƃ͂ނ��������B�������A���b���^�Ɂu����l�i����Ώہv�ƌ��Ă������Ƃ͂���Ŗ��炩�ł��낤�B���l�ɓ��{�����̂��̂��u���y�g�v�Ƃ����l�i����Ώۂł��邩��A�܂�����Ɂu�l�i�̂���Ώہv�Ƃ��āu��҂̔@���v�ɑ��Ȃ���Ȃ�ʂƂ����̂��A���̐����N�w�̊�b�ƂȂ��Ă���B�@ ����𐭎��N�w�ƍl�����ꍇ�A����́u�Đ_�_�I�v�z�Ɋ�Â����R�I�\�蒲�a���v�Ƃł����Â��ׂ��N�w�ł��낤�B�Ƃ����̂́A���Ƃ���l�̂̂悤�Ɍ���A���N�Ȃ炻��͎��R�ɒ��a���\�肳��Ă���A��������K�v�͂Ȃ�����ł���B�O�Ɏ��́A������u���{�I�����v�z�̊�{�v�Ƃ��ăn�[�o�[�h�̃A�u���n���E�U���c�j�b�N�����ɐ��������Ƃ��A�u���̎��R�@(�i�`�������E���[)�I�v�z�v���ƌ������Ƃ���A�������́u�@(���[)�ł���܂��A����(�I�[�_�[)�ł��낤�v�ƌ���ꂽ���A�m���Ɂu���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�ւ̐�ΓI�M������{�ɂ���v�z�Ƃ���˂Ȃ�܂��B����͔��ɕs�v�c�Ȏv�z�A�u���Ԃ��v���v�z�v�Ƃ������ׂ��v�z�ł���B�@ ���āA�����I�m���Ƃ����̂́A�܂������Ȃ�A��̍l�����ɂƂ���Ȃ��ŁA���ӎ��̂����ɂ������Ȃ��Ƃ�������Ă��Ȃ���A���̂Ƃ��ǂ��̂����Ƃ��ǂ����f�����������Ƃ̂ł���m���ł���Ƃ����Ă������Ǝv���邪�A����͂܂��ɖ��b�̔��z���@�E�u����ׂ��悤�́v���̂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���{�ł́A���m�ɔ�ׂāA���݂Ȃ������I�m�����Z���ɓ����Ă���ƍl���Ă��邪�A�u���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�Ƃ��������ɗ����u���̗���ĉ����Ȃ炸�����́A���̐N���̂��ƁA��Í�����\���m�苋�ӂׂ��v�Ƃ������b�̔��z���@�ɍ����������߂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@ �킪���́A�Â��͒����A�ߔN�͉��Ă���E�E�E��ނȂ������Ȗ@�����܂˂��Ă킪���̖@���Ƃ��Ă����B���O���̖@�����܂˂������̂��u�p��@�v�Ƃ����B��ނȂ��u�p��@�v���̗p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A������Ƃ��Ă̗͊W�ɂ��B�����E����(���D)�ɂ��A�剻�E���(�����])�ɂ��A���܂��܂ȊO�����ۉ��Ȃ��@�Ƒ̐��̌p��������������Ƃ��ے�ł��Ȃ��B�ȒP�ɂ����A����ƑR����ɂ͑���Ɠ��������ɋ}���ɍ��������Ȃ���Ȃ炸�A����͑���̖@�Ƒ̐����p��̂��ł�����Ƃ葁�����@������ł���B��a�����562�N�̔C��(�݂܂�)�̖ŖS�ȗ��A���N�����Ōp���I�ȑސ��ƕs�U�ɔY�܂���Â��A������@�E���Ƃ�����鍑�̏o���͋��ЈȊO�̉����̂ł��Ȃ������B�����Ă��̌����́A663�N�̔����]�̌���I��s�ł������B����炪���܂��܂ɍ����ɍ�p����ƂƂ��ɁA�����̑�a����͂��łɁA�S���I���{�Ƃ��Ă����������o�ϓI�E�����I��Ղ��m�����Ă������Ƃ��A��߂�f�s���������R�ł��낤�B�嗤�̕������u�p�悤�Ƃ����ӎu�v�͗��j�I�ɂقڈ�т��Ď����Â����āA701�N����Ƃ��ꂪ��߂Ƃ��Č��z�����̂ł���B���̂��Ƃ��Ԉ���Ă����̂ł͂Ȃ��B�����ł͂Ȃ��āA���ꂪ�u�������S�v�ƂȂ����Ƃ��A�u���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�Ƃ��������ɗ����A�ǂ��t�](���Ԃ�)�ł��邩�ł���B�@ �V�c�́u���v�ł��蕐�m�́u���v�ł���B���߂́u���v�ł��莮�ڂ́u���v�ł���B�u���v���̂Ăāu���v�ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u���v���u���v���Ƃ�ׂ��ł���B���ꂪ�_�̏펯�ł��낤�B�u���v���u���v���Ƃ�Ƃ����t�]�A���Ԃ��Ƃ����Ă��������A���ꂪ�����^�v���ł��낤�B�������A���b�́u���Ԃ��v���v�͈Ⴄ�B�P�Ȃ�t�]�A���Ԃ��ł͂Ȃ��āA����������u�ے�̔ے�v�����̂ł���B�u���v�ł͂Ȃ��āu���v�ł���B�������A�Ȃ����A�u���v�łȂ��āu���v�ł���B�u���v�ł���Ɠ����Ɂu���v�ł���B�u���v�ł��Ȃ����u���v�ł��Ȃ��B�v�́A�����I�m�����d�v�Ȃ̂ł���B�@ ���̂悤�Ȗ��b�̋������A���ɐ��܂��߂Ɏ��s�����ŏ��̑��l���A���Ȃ̂ł���B�����Ă���͊m���ɁA���{�̐i�H�����肵�ďd�v�Ȉꕪ��_�ł������B�@ �������̂Ƃ��A���b��l�łȂ��A�ʂ̂��ꂩ�ɑ����S�����A�u���{�͂����܂œV�c���S�̗��ߍ��ƂƂ��ė��ĂȂ����˂Ȃ�ʁv�ƐM���Ă��̒ʂ���s������ǂ��Ȃ����ł��낤�B�܂��A�u���{�͒�����͔͂Ƃ��Ă��̒ʂ�ɂ��ׂ��ł���v�Ƃ����҂����āA������������s������ǂ��Ȃ��Ă����ł��낤�B���{�͗������̊؍��̂悤�ȑ̐��ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B�@ ���S�ɐV���������@�𐧒肷��A����͊��q���{�ɂƂ��Ă͂��߂Ă̌o���Ȃ�A���{�l�ɂƂ��Ă��͂��߂Ă̌o���ł������B�@ ���߂▾�����@�A�܂��V���@�̂悤�Ȍp��@�́u���̂܂˖@�v�ł��邩��A�ɒ[�ɂ����u�|��E�|�āv����悢�킯�ŁA����n�������v�l�\�͂��K�v�Ƃ����A�����ɂ����u���S�ɐV�����v�Ƃ͂����Ȃ��B����Ɍp��@�͂��̖@�̔w��ɂǂ̂悤�Ȏv�z�E�@���E�`���E�Љ�\�������邩�����ɂ��Ȃ��̂ł���B����ꂪ�V���@�̔w��ɂ���@���v�z����Ƃ����u���@��v�Ƃ����Ă���悤�ɁA�u���߁v���܂��A���̖@�̔w��ɂ��钆���v�z����Ƃ���������Ή����Ă����B����͌p��@�T���͌p��@�I�̐��̏h���ł��낤�B�@ �v�z�E�@���E�Љ�\�����Ⴆ�A�A�����ꂽ���x�́A���̗A�o���ƑS��������`�ŋ@�\���Ă��܂��B�V���@�ɂ����ꂪ���邪�A���߂ɂ����ꂪ�������B�@ �����ł́u�V�v�Ɓu�c��v�̊Ԃ����}��I�ɂȂ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�v����}��Ƃ��ĂȂ����Ă���B��Ȃ͍̂ŏI�I�ɂ͓V�ł����čc��ł͂Ȃ��B�Ƃ��낪���{�ł͂��̓����Ȍ`�ŘA�����Ă���B��������̂܂܂ɂ��Ē����̉e�������|�I�Ɏ��Ƃ������Ƃ́A���{�̗��j�ɂ����̓��ꐫ���`�������ł��낤�B���̌���ꂪ�܂��ɑ��ł���B�@ ����u�V�v�����R�I����(�i�`��������I�[�_�[)�̏ے��ł͂Ȃ��A�V�c����{�I���R�I�����̏ے��ɂ��Ă��܂����̂ł���B����́u�I�����v�����u�V�����v�ŁA��d�̉_�̏�ɂ����āA��́u�l�ԓI�ӎu�Ɛl�דI�s�ׁv�������I�ɋ֎~���Ă��܂����B�ȒP�ɂ����u�V�ӂ͎����I�ɐl�S�ɕ\����v�Ƃ����Ўq�̍l�����́u�V�c�̈ӎu�͎����I�ɐl�S�ɕ\����v�ƂȂ邩��A�V�c�l�͈ӎu�������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B����͂܂��ɏے��V�c���ł����āA���̑��I�`���͍����Â��Ă���A���ꂪ�V�c���̏d�v�ȋ@�\�ł��邱�Ƃ́A�w�u����w�̓��{�w�҃x���E�A�~�E�V���j�C���u�V�c�É��̌o�ϊw�v�̒��ł��w�E���Ă���B |
|
|
�����{�Ɋv���v�z�͂Ȃ��������@ �А搶������ꂽ�B�@ �u�\�N�̞{���E�@�����V�����������̂́A�l��������������ł���B�l�����������Ƃ́A�l���̐S�����������Ƃ��Ӗ�����B�V������ɓ����ɂ͈���̕��@������B�l������ɓ���邱�Ƃł���A������������ɓV������ɓ���邱�Ƃ��ł���B�l������ɓ����ɂ͈�̕��@������B�l���̐S����ɓ���邱�Ƃł���A��������ΐl������ɓ���邱�Ƃ��ł���B�l���̐S����ɓ����ɂ͈�̕��@������B�l���̊�]������̂�ނ�̂��߂ɏW�߂Ă��A�l���̂��₪����̂��������Ȃ��A�������ꂾ���ł�낵���B�l���̐m���ɂЂ����̂́A�܂�Ő����Ⴂ�ق��ɗ���A�b���Ђ낢����ɑ��苎��悤�Ȃ��̂��B���ɋ���ǂ����Ă�̂��A��(���키��)�ł���B�݂ɐ�(������)��ǂ����Ă�̂��A��(�Ƃ�)�ł���B�u�̓����A���̕����̂ق��ɐl����ǂ����Ă��̂��A�Ă̞{���Ɵu���@���Ƃł���B���݁A�V���̌N��̂Ȃ��Őm�����D�ނ��̂�����A����݂͂Ȃ��̌N��̂ق��ɐl����ǂ����Ă�ɂ������Ȃ��B������V���̉��ƂȂ�܂��Ƃ��Ă��A�s�\�ł��낤�B���݂̉��ƂȂ낤�Ɗ�]����҂́A���N�Ԃ̎��a���Ȃ������߁A�O�N�Ԃ��킩�����(������)���������Ă���悤�Ȃ��̂��B�������킩�炽���킦�Ă����Ȃ�������A���ʂ܂ŌÂ��(������)����ɓ���邱�Ƃ͂ł��܂��B�������m����S�|���Ȃ���A���ʂ܂Œp���邱�Ƃɂт��т����āA���Ɏ��S���Ă��܂����낤�B�@ ���o�ɁA ���̂ӂ�܂��̂ǂ��ɂ悢�Ƃ��납���낤���@ �Ƃ��ǂ��ɓM�ꎀ�ʂ��肾�@ �Ƃ��ł���̂́A���̂��܂��������̂��v�ƁB�@ �V�c�O�Ƃ��A���O��V�c�Ƃ���(�u�c����Ė��ƂȂ��A�����c�ƂȂ���v)�Ƃ��������̋t�]�錾�́A�ɗ�ȓV�c���œ|�錾�ł���A���t�錾�ł���B |
|
|
�������^�v���ƖЎq�^�v���@ ���Ўq�̊v���_�@ �O�͂ŋL�����u�v���v�̊�{�I��`��������x�v�Ă݂悤�B�@ ����͌��̐��̊O�ɉ��炩�̐�Ύ҂�u���A���̐�Ύ҂̈ӎu�Ɋ�Â��Č��̐���œ|���ĐV�̐�����������A�Ƃ������Ƃł��낤�B �Ўq�ɂƂ��Đ�Ύ҂́u�V�v�ł���A���́u�V�v�̈ӎu�͎����I�Ɂu���S�v�ɕ\���邩��A���́u���S�v�̓����Ɋ�Â��ĐV�������������Ă邱�Ƃ��u��Ύ҂̈ӎu�v�ɏ]�����Ƃł������B�@ �����Ĉȏ�́u�v���v���A�����́u�v���_�v�̊�b�ƂȂ����u�����v�ƑΔ䂵�Ă݂�ƁA���҂̈Ⴂ�͖��m�ɏo�Ă���B�����̏ꍇ���A�̐��̊O�ɐ�Ύ҂��Ȃ킿�u�_�v��u���Ă���B���̓_�܂ł͂���Ӗ��ł͗��҂ɕς�͂Ȃ��B�������A�O�͂ŋL�����悤�ɐ����ɂ͖Ўq�̂悤�ȁu�V�Ӂ����S�_�v���Ȃ킿�A��Ύ҂Ɩ��S�Ƃ������I�ɂȂ����Ă���Ƃ����v�z�͂Ȃ��B�������������I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�_�Ɛl���Ȃ����̂��u�_��(�x���[�g)�v�Ȃ̂ł���B�Ўq�̊v���_�Ɛ����̊v���_�Ƃ̌���I�ȈႢ�́u�_��v�Ƃ����l�����̗L���ɂ���ƌ����Ă悢�B�@ ���l�ލŏ��̐����^�v���@ ���̈Ⴂ���Ȃ��o�Ă������́u�����_�I�T���v�͍���͏����A����͑n���_�b�̎��ォ��́A��{�I�ȈႢ�ł���Ǝw�E����ɂƂǂ߂悤�B�����ɊS�̂�����ُ͐��u�����̏펯�v���Q�Ƃ��Ă������������B���̓_�A�Ўq�ɂ�����u�V�Ӂv�̕\�����͂���߂Ď����I�����A�����ɂ�����u�_�̈ӎv�v�̕\�����͂܂��ƂɁu��דI�v�ł����āA�u�_�v���_����X������ΎЉ�͊�{����ς���Ă��܂��킯�ł���B�@ �ł͂����ʼn��Đl����l���܂��Ď��̂悤�Ȏ�������Ă݂悤�B�u�����ɂ`�Ƃ��������������Ƃ��悤�B���̍��̂���K�����\����a�Ȃ�҂����]���Ȃ��̂ŁA�`���c�邪���̑�\�̓����𖽂��钺�����o���A���ۂɐ�[���J���ꂽ�B�Ƃ��낪���̂a�Ȃ�҂͈ꋓ�Ɏ�s�ɐi�����A�c��ꑰ��Ǖ����A�c���ވʂ����Ď����̖]�ގ҂��ʂɂ��A��������悵���҂ǂ������Y������ŁA�������i�������c������������A���̌`���I�ȔF���������Ȃ���{�@������ɔ��z���A���̖@�͉ߋ��ɂ����čc�邪���z�����@�K�Ƃ͑S�����W�Ɛ錾������A����͊v���ƌ����邩�A�����Ȃ����v�B���܂Ŏ������₵������ł́A���ׂẲ��Đl�́u�������v���ł���v�ƌ������B�@ �����v�̗��͓��{�j�ő�̎����@ �܂����ڂ��ׂ��́A���v�̗��Ƃ����������A���m�c������Ɛ��ʏՓ˂����ď������ŏ��̐푈���Ƃ������Ƃł���B����ւ̌X�̏������A�ہA�����ɑ傫�Ȕ���������܂łɂ��������A���ׂĂ͎��s�ɏI����Ă���B�܂����m�c������ɎO��c��z���ɏ����A�����V�c��ވʂ����A��x�͓V�c��i�������̂��A���̂Ƃ����͂��߂Ăł���B�@ �V�c�ɐn�������Ƃ͓����͋���ȃ^�u�[�ł���A���m�c�̒��ɁA�������|�Ɣ�ϗ��I���s�Ƃ����l�����ƁA�`���ے�Ƃ����S���I��R�������ē��R�������B�����̕��m�́A�����N���ɂ������ĕK���u�@��v�Ƃ��u�ߎ|�v�Ƃ����A���ړI�ɂ͓V�c�Ƃ̈���́u���߁v�ɂ���čs�����Ă���B���̓_�ł͗����ƂĂ���O�łȂ��A�ނ̍s�����͏�ɉ��炩�́u��`�����v��ێ����A�@���𗘗p���Ė��{����Ă�����Ƃ���������Ƃ��Ă���B�Ƃ��낪���v�̗��͂���ƑS������āA�`���Ǔ��́u�@��v�������Ă���̂ɁA������͂˂������ČR���N�����̂ł���A�ނɂ́u��`�����v�Ƃ�������̂͑S���Ȃ��B�@ ����Ɂu�g���v���傫���S���I�ɍ�p���邱�̎���ɁA�����Ƌ`���Ƃ��ׂ�A���҂̈Ⴂ�͗]��ɑ傫���B�����́u�����̒����v�u���Ƃ̓��́v�ŁA���łɉ���ɂ��킽���Ē���ƊW��������ł���B����k�����Ƃ����Έɓ��̍����ɂ������A������A�O�Y�A��t�A���R�̂悤�ɋ���ȓ����I���m�c��i���Đ��S����ꍑ�ɂ킽���Đ��͂�U�����卋���łȂ��B�������������������̍����A�������}�ȍݒn���m�A�ɓ����̍ݏ����l�ł������B���̈ɓ������������ނ̎x�z���ɂ������킯�łȂ��A���A�m�c�A�F�����A�ɓ����̍����������B�@ �����̓����̕��m�c�́A���s�ɑ��ċ����u�����I���v�������Ă����B���ꂪ���쑤�́u���ł��v���\�ɂ������A�u���ʁv�u���܁v�ł������A�`���Ƃ��Ƃ����l�Ԃ����q�̒�����o�ė��ď������s�v�c�łȂ��B��Ɛl�ɂƂ��Ă͔ނ͂����܂ł��u���y�v���u���y�v�ɂ������A�����Ă�����Ƃɍ߈�����������҂�����͂����Ȃ��B�@ �O�Y�ꑰ�̈ӎ��ł͋`���́u�ɓ��̏������A�����ȉ��̖k�����v�ɂ������A������A�u��V�m�N�m�v���v�œ����ƂɁA����ǐS�̂Ƃ��߂������Ȃ��ĕs�v�c�ł͂Ȃ��B�㒹�H��c���A�u�����v�Ƃ��Č�Ɛl���炳��������������Ă���`���Ȃǂ́A�����ɉ@��������ΊȒP�ɓ��łł���ƍl���ĕs�v�c�ł͂Ȃ������B�@ �����Ă��̗\���́A�K������������Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B���̏؋��ɏ�c�����̂Ƃ��A�����̊��q��Ɛl�����s���ɗ����Ă���B�@ ������I�����^�v���@ �u��ȋ��v�ɂ͓R���q�̌P���Ƃ��Ď��̌��t������B�u�F�A�S����ɂ��ĕ�(�������܂�)��ׂ��B����Ō�̎�(���Ƃ�)��B�̉E�叫�R���G�𐪔�(��)���A�֓��𑐑n���Ă��ȍ~�A���ʂƉ]�ЁA��\�Ɖ]�ЁA���̉����ɎR�x���������A���(�߂��ڂ�)�����[���B��ӔV�u����B������ɍ��A�t�b�V槂ɂ��A��`���d�|��������B����ɂ��ނ̑�(�₩��)�́A�����G�N�E���`������A�O�㏫�R�̈�Ղ�S�����ׂ��B�A���@���ɎQ����Ɨ~����҂́A�����\����ׂ��v�ƁB�@ ����͗L���ȁ����P����������m���Ă���l�������ł��낤�B���q���ʂ��Ă��̒ʂ�Ɍ��������ǂ����͂킩��Ȃ����A����͂����܂ł��S��ɑi����u�����̘_���v������A��͂��̒ʂ�ł��낤�B�ޏ��͂܂��u���v���Ƃ��A�u����ɂ��ނ̑��v�͂��́u���v��Y�ꂽ�u����҂̌�Ɛl�v�G���E���`�����ׂ����Ǝ咣����B�G�͌����ēV�c�ƂłȂ��A���{�ւ́u�t�b�v�ł���A�u��`���d�|�v���������̂́A���́u槁v�ɂ��̂�����A���́u�t�b�v������̂��Ƃ����_���ł���B����͊m���ɁA��Ɛl�̊���ɑi����_�ł͌��͂��������ł��낤�B�@ �������A���Ƃ��u��`���d�|�v�ł��낤�ƁA�������������ȏ�A����ɒ�R����Β�R�����҂��u�t�b�v�ł���B�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ́A�܂��~�����A���ꂪ�u�t�b��槁v�ł��邱�Ƃ�֒�ēP�Ă��炤���Ƃ��u��ʂ����v�ł��낤�B���̋c�_��W�J����̂����ł���B�Ƃ��낪����ɑ��ċ`���͎��̂悤�Ɍ������Ɓu���b��l�`�L�v�ɂ���B�@ �u��(������)�����̎����鎖�ɂĂ���ǂ��A����͌N��̐����������A���Ǝ��鎞�̎��Ȃ�B�����̌N�̌��Ɛ��āA���X���ꏊ�X�����炸�A�㉺�����D(���ꂢ)��������Ƃ��ӂ��ƂȂ��B�R��Ɋ֓��i�ނ̕�������A�ւ����̉���ɋy�����āA�������y�̂����Ђ��Ȃ���B�Ⴕ��ꓝ����A��(�킴�킢)�l�C�ɂ݂��A�킸��Ј�V�ɕ�(���܂�)�����Ĉ������ƂȂ��A�l����ɏD(���ꂤ)�ׂ��B���ꎄ�𑶂��Đ�(��������)�\������ɂ��炸�B�V���̐l�̒V(�Ȃ���)�ɂ��͂�āA���Ƃւΐg�̖���(�݂傤��)���A���𗎂Ƃ��Ƃ��ӂƂ��A�ɂމ��ɂ��炸�B������F�Ȃ��ɂ��炸�A�������E�����c�A���ɍ��̋`�ɋy�ԟb(��)�B����͗P����V�������ĉ��ʂɋ�(����)����B����͊֓��Ⴕ�^���J���Ƃ��ӂƂ��A���̌�ʂ����߂āA�ʂ̌N���ȂČ�ʂɑ�(��)���\���ׂ��B�V�Ƒ�_�E�������{�����̌�Ƃ��ߗL�ׂ��B�N������܂���ׂ��ɂ��炸�A�\��(����)�ނ�ߐb�ǂ��̈��s����ɂĂ�������v�@ ����́A�`�������̂悤�Ɍ������Ƒ������b��l�Ɍ����Ă���킯�ŁA���̍l�����`���̂��̂Ȃ̂����̂��̂Ȃ̂����炩�łȂ��B�Ƃ����̂́A���b��l�́u�`�����ᔻ�v�ɑ�����ٌ̕삾����ł���B�܂����̓`�L���̂��ǂꂾ���j���I���l�����邩�����ł��낤�B���Ɩ��b��l�Ƃ̊W�͌�ɋL�����A������������ɂ���A�����ɋL����Ă���_���͖Ўq�́u���������_�v�ł���A���̒��҂��Ўq�ɂ���ċ`���E���𐳓������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�@ �u�{�@�̓V����������́A���̖��������Ȃ�v�ɂ͂��܂�Ўq�̌��t�́u�{�@�v���u��c�v�ɂ���A�����ŋ`���������Ă���̂͂܂��ɖЎq�̌��t�ł���A�u������F�Ȃ��ɂ��炸�c�c�v�Ȃ̂ł���B��c�͂܂��ɁA�l���{�̕��֔�������Ă��܂��B�u��(����)�Ȃ�v�u����(���ɒ�)�Ȃ�v�ł���A����ɂ���Ĕۉ��Ȃ����S���W�܂��Ă������{�́u�����邱�ƂȂ����Ɨ~���Ƃ����ǂ��A���ׂ��炴��̂݁v�ɂȂ����B�����`���E���̏ꍇ�́A�V�c�Ƃ�łڂ��Ă�����Ėk��V�c�ɂȂ�A�O�̑̐������邾���ŁA���̂܂܂��̑̐����Â��Ă������킯�ł͂Ȃ��B���̓_�ł́u����I�����^�v���v�Ƃ������ׂ����̂����A���̌���͖Ўq�ɂƂ��Ắu�V�v���ނɂƂ��Ắu�V�Ƒ�_�E�������{�v�Ƃ������Ȃ̓`���ɂ������_�ɂ���ł��낤�B�����u���ځv�̔��z�Ƃ����_���猩��A����͒����̊v���v�z���z���Ă���A�u����I�����^�v���v�Ƃ�������̂ł���B |
|
|
���k����̘_���@ ���O�́u���鏊�v�Ɓu�������v�@ ���ˏ��l�ق̑O���فE�����W��(����������ς�)�́A�u����{�j�_�]�v�Ɏ��̂悤�ɋL���Ă���B�@ �u�Z���(����)�ɂ���(��̂Ȃ��Ɏ�)���A��������(������)���́A�W(����)���l�ς̑�ςȂ�B�ی��̎��A���S�Ȃ炸��B������c�̏^(������)��������́A�ł�薼�`�����B��A�߂ނ����ĔV�ɉ�����́A�V��P(���)���ĉȂ�B�S(�Ƃ�)���ĔV�𗬂���͌Ȑr(�͂Ȃ�)�������炸��B�c��(��)��A�R��(�����)(�l��)�̂��(�V�̂���Ɣs�̂���)��鏊�Ȃ�B�����M����i��(�j�F�̑���Ƃ��Ē���)���āA�����ǂ���ɕ��v�������A�������ɈϔC���āA�����ēۚ�(�ǂ�)�ɑ����A���`���E���`�o�ɕN���āA���������t�������Ɏ���ẮA�������ߗ[���A�V���A�K�](��Ƃ��ď]��)�����m��Ȃ��A�匠�A�֓��ɐ��ڂ��āA���̑_���̏p�ɑ�m�炸�B�c�ې������A�������Ƃ̌���L���ĞH���A�u��(����)�Ă����ʌ��@�t�ɕ����B��̈Ŏ傽��A�Í��ɂ��̔䏭���c�v�v�ƋL���A�������֓��Ɉڂ����̂́A�u�Ŏ�v�㔒�͒�̎����������Ƃ��Ă���B�@ �ł́A�`���E���ɔz�����ꂽ�㒹�H��c���̐l�A����ɂ�����s�Ȃ��������҂ł�����ɂ́A�ǂ̂悤�ȕ]����������Ă���̂ł��낤���B�m���ɍ��܂ł̂悤�ȗႪ����Ƃ͂����A����͂����܂ł�������̂��ƁA���Ƃ����{���ł��Ă��A���ꂪ���ړI�ɂ͒�����̈�@�ւȂ�Ƃ������A�u�V�c�����{�v�ȊO�Ɂu���{�����{�v�Ƃ������ׂ����̂��������A���b�ł���Ȃ���O��c��z���ɕt���ēV�c��ވʂ����A����ɖ@���z����Ȃǂƌ������Ƃ́A�u�c���j�ρv�̌����Ƃ���鐅�ˊw�ł͓��ꋖ���ׂ��炴�邱�Ƃł͂Ȃ��̂��H�@ ���㔒�͒�ւ̔ᔻ�@ �����W��(����������ς�)�͌㒹�H�V�c�̑��ʂُ̈킳�Ɍ��y����B�u�l�N�A�ʂɑ����ɂ́A�K�����̎n�߂𐳂������B���̎n�߂𐳂��́A���̏I��𐳂����ȂȂ�B�Â��A�����_��Ȃ����ċɂɓo��̌N���炸�B����̑H�N�́A�ꎞ�̌��ɏo�ŁA�����̖@�ƂȂ��ׂ��炸�B��������������ɋc���A�����~�ǂ������ɘ_���B�ٖM�̐l����Ȃ����V�q(�ʎ��Ȃ����̓V�q�A���͍����Ȃ�������)���c���B�����A�q�X����_������A�(����)�A���̗���d����ׂ����B����c�@�̖@���(�Ȃ�)���āA���̎n�߂𐳂�����Ȃ�c�v�ƁB�@ ���̎����́A���@���������V�c�Ɛ_��������Đ��ɑ������̂ŁA�㔒�͖@�c�����q�V�c�̑�l�q�����e���𗧂ĂēV�c�Ƃ��A�_��Ȃ��ŁA�����Q�c�̓����C�͂��ɐ��ɔh�����đ�_�{�ɐV�����V�c�𗧂Ă��ƕ��������������B���ꂪ����u���V�c�v�̌㒹�H��ŁA���������͂�����u�w�ד�}�M�V���v�ƋL���A�~�ǂ́u���(����)�}���֗��Ă��킵����A�����ݏ��ĎO�̐_��Ȃ��āA�߂��炵����ɐ��ʂׂ��v�ƋL���Ă���B����́A�����̐l�ɂ̓V���b�L���O�ȑ厖���ł������炵���A�u���������L�v���ł�����ɘ_�����Ă���B�]���ċ`���E�����A���ɂ͂��Ȃ��Ă����R�ɂ��̂��Ƃ�m���Ă���A���̐S��̂ǂ����Ɂu�㒹�H��c�͔��V�c�ɂ����Ȃ��v�Ƃ����ӎ��͂������ł��낤�B������\�ɂ����̂́A�㔒�͖@�c�ł���B�@ ����ɁA�����V�c(���p��)�����x�͓V�c�ւ̏��ʂ̋����E�V��i�����A�S���O�Ⴊ�Ȃ��������Ƃł͂Ȃ��A�Ƃ������������A���n��p���Đ����ɂ��ǂ����Ƃ��咣�������ł��낤�B�Ƃ����̂́A��x�͓V�c�̕��̌㍂�q�@�͌㒹�H�V�c�̌Z������ł���B�����ɁA���́u���V�c�v�ɂ������A�u�u�w�ד�}�M�V���v�Ƃ�����Ԃ͌㒹�H��c�ɂ���p���āA���X�ُ�ȍ��p���{�ɑ��ĂƂ点���Ƃ�������B�@ ���Ȃ����������׃^�z�����@ ����ɑ��́A���s�ɐi���������i�ߊ��ł���A���̂������삩�痧�@����D���ď���Ɂu�֓��䐬�s���ځv�Ƃ����@���z�����B�@ �������Ă���ƁA�V�c�̂ݐ����ł��ꂪ��Ȃ�A���͓��{�j��ő�̔��t�҂ł���A�ǂ̂悤�Ȕl�i�掂��������Ă��s�v�c�łȂ��͂��ł���B�@ �Ƃ��낪�܂��Ƃɕs�v�c�Ȃ��Ƃ����A���ւ̔��͂܂��Ƀ[���ɓ������B�u�c���j�ρv�̌����Ƃ���鐅�ˊw�ł��A���R�A���ւ̔ᔻ�͎��ɏs��ɂȂ肻���Ȃ��̂����A��Ȃ��ƂɁu�x�^�z���v�Ȃ̂ł���B�@ ���������l�����͂܂��ɖЎq�̊v���_�\�V�Ӂ��l�S�_�\�ł��낤�B�u���V�q�v�㒹�H��c�ւ́u�}�M�v�ƁA���̎����Ǝ����́A���ʂƂ��ĖЎq�̂����u��(����)(���키��)�Ȃ�A����(���ɒ�)(�Ƃ�)�Ȃ�v�ƂȂ��Đl���{�̕��֒ǂ�����Ă��܂����̂ŁA���{�́u�����邱�ƂȂ����Ɨ~���Ƃ����ǂ��A���ׂ��炴��̂݁v�Ƃ����`�ɂȂ����B����Ȃ̂ɋ`���͏I���u�ʁA�l�i���������v�Ŏ��炪���ɂȂ낤�Ƃ����S�Ȃ��A���m�����{�����̂͗��h�ŁA�u�V���Ɍ������Ɛ����ׂ��炸�v�Ȃ̂ł���B�`���ł��������ł���Α����u�x�^�z���v�ɂȂ��ĕs�v�c�ł͂Ȃ��B�@ �u��i���ځv�͓��쎞��ɂ��u�W���v�ł���A�L�����ԂɐZ�����A�����ܔN�܂ł͎��q���̋��ȏ��ŁA������\��N�̌��@�A��\�O�N�̖��@���z�܂œ��{�l�́u���̖@�v�̊�{�ƂȂ��Ă����B�����u��i���ځv�Ƃ����@�̌��z�ɂ́A�V�c�͈�^�b�`���Ă��Ȃ��B���{�l�͒������������{�̎�������߂��@�̉��ɂ����킯�ŁA���̎��ȍ~���u���{�@�̎���v�ƋK�肵�Ă悢�ł��낤�B�@ ���̈Ӗ��ł͊m���Ɂu�x�^�z���v�͓��R�Ȃ̂����A������u�l�_���ɕ���v�Ƃ����㒹�H��c�̍��̔ᔻ�ƑΏƂ���ƁA���{�l�̐����ӎ��Ƃ͑S���s�v�c�Ȃ��̂��Ǝv�킴��Ȃ��B�Ƃ����͓̂V�c����̒D���҂ւ́u�x�^�z���v�́A�V�c���̔ے�̂͂�������ł���B�@ ����������W��(����ς�)�́A���v�̗��ɂ�������̑ԓx�ɂ́A�����u�ٌ�̂݁v�ŁA���̂悤�ɋL���Ă���B�u���v�̕ςɁA�`�����|�����A���A�Ȃ�Ƃ����ǂ������ꂸ�B���́A������(�Ђ�)���ĉ��t�ɍR�����A���ɏ�`���w�˂���(�����V�c��ވʂ���������)�Ɏ����́A���̖{�S�ɔA���ɛ߂ނ��Ƃ���Ȃ�B�l��������Ɏ���āA������(����)��T��č�������A�y���̍c������(�悭����)���B�T�S(��������)����(�S�A�����ɂ���)�A���](��)��Ēm��ׂ��Ȃ�B���e�[�����u���v�̎��́A���̋ȁA��ɍ݂�B���͋`���̐��т������A�u�������ɗ�݁A�|�������鏊�����v�ƁB����A�ȂĒ�_�ƂȂ��ׂ��v�ƁB�@ �����{�l�̐S��ɂ��闝�z���@ �u�_�c�����L�v�̒��҂̖k���e�[�E�E�E�E���̓쒩�����_�́u���݂̐e�v�����A�ł��O�ꂵ�����ᔻ�_�҂ł����ĕs�v�c�ł͂Ȃ��B���ꂪ��͂�A�u�㒹�H��c����낵���Ȃ��v�ł���A�u���͗��h���v�Ƃ��Ă���B�@ �܂��Ƃɕs�v�c�Ȃ̂����A���̗��ꂩ�炵�ē��R�ɑ��ɓO��I�Ȕᔻ�������đR��ׂ��l�Ԃ��A���ׂāu�������͕ʁv�Ƃ��Ă���B�@ ��̂��̕s�v�c�͂ǂ�����o���̂ł��낤�\�����T������̂��{�e�̖ړI�̈�ł���B�Ƃ����̂́A���̍��̗��j�ɂ����āA�ނ̂悤�Ȉʒu�ɂ���Ȃ���u�x�^�z���v�ɂ����Ƃ������Ƃ́A���{�l�̐S��ɂ���A�����́u���z���v��ނ�����Ă����Ǝv���A���̗��z�����`�������u�v�z�v�Ɣނ̐��肵���u�@���v�����A�Ȍ�̊�ɂȂ��Ă���Ǝv���邩��ł���B�@ ���u���R�Ȃ����{�v�̎����҂@ �㒹�H��c�����҂��Ă����̂́u���{�̎���v�ł������B�����A�㒹�H��c�����ɓ������u���v�Ɓu�����́v�������Ă����炱��͉\�����������m��Ȃ��B�Ƃ����͖̂��{�̒��S����ׂ��������ɂ͎q�����Ȃ��A���́u�ے��I���S�v�͎����悤�Ƃ��Ă����B�`���͐��q�����s�ɔh�����A�����̌�p�҂Ƃ��čc�����R�𓌉������邱�Ƃ��@�̓��ǎ҂Ɩ��Ă����B����`�����g�A�����ƒ���Ƃ̊Ԃɗ�������u����I�l�ԁv��~���Ă����킯�ł���B�������������ʂƉ@�͂��̌�������ނ�ɂ��A���S�����킹�Č�Ɛl���݂𑈂킹�A���̊ԂɁA�X�ɒ��쑤�ɐQ�Ԃ点�āA�k�𐭌�������悤�Ƃ����B�@ �����Ŏ�������Ɠ����ɐےÂ̍����]�E�q�������̒n������{�ɖ������B�����̗̉Ƃ́A�@�̒�������ɉ�NjT�e�̂��̂ł��������A�n�����T�e�̖��ɏ]��Ȃ������Ƃ����̂����̗��R�ł���B�Ƃ��낪����͖��{�ɂƂ��ďd�v�Ȗ��ł���A�������ꂪ�O��ɂȂ�A�n���ւ̔C�ƌ��͎����I�ɒ���ɒD����B�]���āA�M���̏܂ɂ���ė^����ꂽ�n���E���߉ȂȂ��Ƃ��邱�Ƃ͂ł����A�`���́A��̎��[�Ɉ��R���������ď㗌�����A�@�ɋ��ۂ��������B���̗͂̌֎��ɂ�鈳�͂ł��낤�B�����Ȃ�Ɣ��Ό����Ԃł���A�@�ɂ��c�����R�̓����Ȃǂ͊��҂ł��Ȃ��B�����ŗ����̊O���̍���b��Ƃ̗c���O�Ђ����R�Ɍ}���邱�Ƃɂ����B�@ ���������~���_�҂̑��@ �㒹�H�@�́A�k�ʂ̕��m�𒆐S�ɁA���Ђ̑m����_�l�����U���A����ɏ��v�O�N�l���ɏ����V�c�������V�c�ɏ��ʂ��Ă����������Ƃ����̐����Ƃ����B���̏�ŁA�����̌�Ɛl�𖡕��ɗU���A���{�Ɛe�����������������o(�����)��H���A���N�܌��\�ܓ��A�����ɋ`���Ǔ��̉@��E��|��������A�����ɏ��v�̗��͖u�������B����Ύd�|�����̂͂����܂ł����쑤�ł���B�@ �����Ȃ�ƁA���q���������ɑΉ�����l���˂Ȃ�Ȃ��B���������͂��̂Ƃ��܂��u�������~���_�v��W�J�����Ƃ����B�@ �ʂ��Ď������ۂ��͂킩��Ȃ��B���Ɩ��b��l�����ɐe�����A���ɑ��h�������ԕ��ł��������Ƃ́A���҂����������a�̂��c���Ă��邩�玖���ł��낤���A�u���b��l�`�L�v�̒��ɋL����Ă��邱�Ƃ��A���Ƃ��Ƃ������ł͂Ȃ������m��ʁB�������A���̑��̑ԓx�́A���̎����ƑΔ䂵�Ė������Ȃ����Ƃ������Ȃ̂ł���B�ނ͂�����_�Łu���ɘ_�v�ł���A������c�������R�𓌉�������Ȃ�A�����E������h����Ƃ��Ă����h�����ƒ�Ă��Ă���B�@ �����Ă��̓_���猩��A���́u�������~���_�v�Ȃ���̂��A��ɑ����������Ƃ�������ƕς�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł���B����A����قNj����̈ӂ�\���Ă���̂ɁA�Ȃ����삪�����I�ɏo��A��Ɛl�́u�����͂킪�g���c�c�v�Ǝv���ċt�ɒc������B���̒c�������Ƃ���ŁA���r�̉����Ŕ�ꂽ�G���̎R�x�n�тŌ}������ΕK�����B��������ʼn@��E��|�̓P������߂�A�V�c�Ɛ��Œ��ړI�ɑΌ����邱�Ƃ͔�������B�������ꂪ�^���Ȃ�A���͑����ȍ�m�Ƃ������ƂɂȂ�ł��낤�B�@ ���͓�����ꂽ�@ ������ɂ���R�c�ł́A�������~���_���}���_���˂����A�o���_���̑����ꂽ�B����������͕K�����������ӌ��łȂ���]�L���������咣���A�R���q������ɓ����������߂Ǝv����B�@ ���q�̖������́u����ɂ��ނ̑�(�₩��)�́A�����G�N�E���`������A�O�㏫�R�̈�Ղ�S�����ׂ��v�@ �]�c�̌��ʂ͑��E���[��叫�R�Ƃ��A�����̌R�����W�܂肵�����o���Ƃ��܂�A���ʼn��]�E�x�́E�ɓ��E�b��E���́E���[�E�㑍�E�����E�헤�E�M�Z�E���E����E�����E�o�H�̏����ɔ�r���Ƃ��Č�Ɛl�̎Q�������߂邱�ƂɂȂ����B���ꂪ�����铌�������A�����̖��{�̒��ړI�Ȏx�z���͂킸�����ꂾ���ł���B�@ ���̏ꍇ�́A����̐�������������邩�A���{����������͂˂̂��Ēc�����邩�����s�̕���ڂł���A���̓_���猩��A���m�c���u�푈�ւƓ��ݐ点��v���Ƃ����̂͂��ł���B��]�L���͂��̓_���悭�������Ă����B�ނ͋`���Ɍ����đ����o���������咣���A���̌��ʁA���͌R���̓�����҂����A��\������ŋ��s�Ɍ����Đi�����邱�ƂɂȂ����B������o���Ƃ��A�]�����͎̂q�������ȉ��\���R�ɂ����Ȃ������Ƃ����B�܂��Ɂu��(����)�͓�����ꂽ�v�ł������낤�B�@ ���̂悤�ɂ��đ��͏o�������B�������ނ͓r���ň��Ԃ��Ă��āA��c������o�w�����Ƃ��Ɏ��ׂ��ԓx���`���ɂ����˂��B����͔ނɂƂ��Ă��A���m�c�ɂƂ��Ă��傫�Ȗ��ł������낤�B�`���͎��̂悤�ɓ������Ƃ����B�@ �u�����������₦�邨�̂����ȁB���̎��Ȃ�A�܂��ɌN�̌�`�Ɍ����ċ|���|�����Ƃ͂����������B������̎��́A���ԂƂ��ʂ��A�|�̂������āA�ЂƂ��ɂ������܂�\���āA�g��C�����Ă܂�ׂ��B���͂���ŁA�N�͓s�ɂ��킵�܂��Ȃ���A�R�������܂킹�A�������ĂĐ�l����l�ɂȂ�܂Ő키�ׂ��v�ƁB�@ �����炭�A���̂��Ƃm�c���m������m�C�̒ቺ�������ł��낤�B�Ƃ����̂́u�����������ԂɂȂ����疳�����ō~���ł���v�Ƃ����O��Ő푈�͂͂��߂�����̂ł͂Ȃ��B�����m��A�키�C�͎͂����Ă��܂��B����ɂ��̂��Ƃ����؎҂�ʂ��ēG�ɂ����A�G�͂͂��߂��炻������Ƃ��ėp����ł��낤�B���������邽�߂ɂ��̂悤�ȕ��@���Ƃ����Ƃ���A���͌����āA�P���Ȃ�u�����̐l�v�Ƃ͂������A���̓_�ł́u�����̏o�Ɓv�ȏ�̐����͂��������l�Ԃ����m��Ȃ��̂ł���B�@ ���u���v�̗��v�̐�㏈���@ 6��16���A���́A�Z�g���̉��~�ɓ����Đ�̍s�����J�n�����B����18�R�ƂƂ��Ɋ��q��i�����Ă���21���ڂ̂��Ƃł���B����������c�͑��ɒ��g��h�����A���̓����̋��͖d�b�̌v��Ŏ����̈ӎv�łȂ��A���ׂĂ͖��{�̐\���̂܂ܐ鉺����Ɛ\���ꂽ�B�@ �I�폈���̍ō����j�����肵���̂͋`���ł��������A�`���́A���ɍI���Ȃ����ŏI�폈�����s�Ȃ����B�ڂ����͏ȗ����邪�A�܂��㒹�H��c�ɕ����������������B�܂��u�㉺�v�f���Ă���u��v�̏����ɂ��������B���̕ӂ͊m���ɐh煂���܂�Ȃ��B�ނ̈Ӑ}�́A���{�̗v�������̂܂ܒʂ钩��ւƉ��g���邱�Ƃł������B�@ �����āA7��9���A�V�V�c(��x��)������₢�Ȃ�A�O��c�̔z�����������B7��13���̂��Ƃł���B�y���͑����������������A���̌�A���c�̊ҋ��^�����N���Ă���B�������͊�Ƃ��Ă�������ۂ��Ă���B�@ �Ȃ��A���{�́A���쑤�ɖ����������ƁE���m�̏��̂����Ėv�������B3000�]�P���ɂ̂ڂ����Ƃ������B�@ �������A���́A����������ł͂Ȃ������悤���B��̂ɂ����ď����̌����Ȑl�Ԃł������悤�ŁA�̂��ɋ`���̌�Ȃ̈ɉꎁ���A�`���̎���A����p���Ď����̎q�����������ɂ��悤�Ƃ����A�d�̂Ƃ��ł��A���Y�҂Ȃ��A��d�ҎO�l�ւ̗H�Ɖ����݂̂ŁA���͈�؏����Ȃ��Ŏ��������߂Ă���B���v�̕ςŏ��Y�҂����Ȃ������̂������炭�ނ̌��c�ŁA�܂��ނ́A�G���̐l�Ԃ������悤�Ƃ��܂��܂ɓw�͂��Ă���B�@ �����b��l�Ƃ̏o��@ ���������ނł����Ă��A�s�c���̏������ŏ��X��������ē���������Ύ�������u����킯�ɂ͂����Ȃ��B�Ƃ��낪�̔��̎R���ɑ����̌R�����B��Ă���Ƃ�������������A�����ň��B�i�����R�����s�Ȃ��A�ǂ����ӎ��I�ɌR���������܂��Ă���炵���m���������đߕ߂��A�������̖ʑO�Ɉ����������B���ꂪ���R���̖��b(�݂傤��)��l�ł������B���͋����Ė��b��l������ɂ����A���̔��ɂǂ����Ă悢���킩��ʑ̂ł������B��l�͐Â��Ɍ����Ǝ��̂悤�Ɍ�����(���킵���͌�ɑS�������p���邪�A�܂������ł͂��̗v�|���L���Ă�����)�B�@ �u���R���������̗��l���B���Ēu�����Ƃ������������邻�������A�����ɂ����̒ʂ�ł��낤�B��̎��́A�M�˂Ől�����ʂ��悤�Ƃ����S���N�����Ƃ����A����ɂ���܂������Ƃƍl���A���������S���������Ă��A�����ŏ������Ƃɂ��Ă���B�܂��l���牽���̉��ŋF���𗊂܂�Ă��A�����F���ď����邱�Ƃ��ł���Ȃ�A��������Ɉ�؏O�����O�r�ɒ���ŋꂵ�ނ̂�������ׂ��ŁA���̂悤�ȕ����̂����̊�Ȃǂ��F�邱�Ƃ́A�厖�̑O�̏���������������Ƃ͂Ȃ��B���̂悤�ɂ��čΌ����������ė�������A���ɋF���Ă�������ȂǂƂ����l�͂��̐��ɂ͂��Ȃ��ł��낤�B���������̎R�́A�O���i�̏��ŎE���֒f�̒n�ł���B��ɒǂ��钹���A�t�ɒǂ���b���A�݂Ȃ����ɉB��ď�����B�ł́A�G�ɒǂ�ꂽ�R�����A���낤���Ė���������A���̊ԂɉB��Ă���̂��A�킪�g�ւ̌�̙������A��e�͂Ȃ��ǂ��o���A�G�ɕ߂���ꖽ��D���Ă����R�Ƃ��Ă����悤���B���̖{�t�߉ޔ@���̐̂́A���ɑ���đS�g���̉a�Ƃ��A�܂��Q�����Ղɐg�𓊂����Ƃ����b������B����قǂ̑厜�߂ɂ͋y�Ȃ����A��������̂��Ƃ����Ȃ��ŁA�悢�ł��낤���B�B������Ȃ�A���̒��ɂ��U���̉��ɂ��B���Ă�肽���Ǝv���B���̌�������悤�B�������ꂪ�����̂��߂ɍ���ƌ����Ȃ�v�����Ȃ��B�����Ɏ��̎���͂˂�ꂽ��悩�낤�v�@ ���͐[���������A���m�̘T�Ђ�l�сA�`��p�ӂ��č��R���ɑ���Ƃǂ����B���̘b�͂ǂ��܂Ŏ������킩��Ȃ��B���������b��l�Ƒ��Ƃ̉^���I�ȏo����A�ނ��Z�g���ɋ����Ƃ��̂��Ƃł������͎̂����A�܂������S�̒ꂩ�瑸�h�����͖̂��b��l�ł���A�����ɁA���Ɍ���I�Ȋ�����^�����̂����b��l�ł������ł��낤�B����͓�l�����킵���̂ɂ��\���Ă���B�V�c����c�����ɂ͐�łȂ������B�����Đ�������̂́A�����炭���b��l�Ȃ̂ł���B |
|
|
�����b��l�̖����@ �����b��l�Ɋ������ā@ ���b��l�Ƒ����琂́A�]��Ɂ����I���Řb�����܂��o�������Ă���̂ŁA������t�B�N�V�����Ƃ���l������B���������b��l�����炩�̌`�Ŗ��{������q�₳�ꂽ���Ƃ́A����߂Ă��蓾�鎖���ł���B�@ �Ƃ����̂́A������̎�������v�z�I�Z���l�Ԃ̔c���̎d���́u�@�v�����Ȃ��B����ł͂��ꂪ�ێ�Ɗv�V�A�i���Ɣ����A�^�͂ƃn�g�A�E�X�ƍ��X�A�푈���͂ƕ��a���͂Ƃ����`�ɂȂ��Ă��邪�A�@�I�c���͏��v�̕ς̎���ł������ł������B�܂��Đ퓬�ƂȂ�ΓG�Ɩ����ɕ����邵���Ȃ��B���̔c����퓬��܂ʼn����i�߂�A���쑤�Ɩ��{���Ƃ����@�����Ȃ��Ȃ�B�����Ă��������c���̎d��������Ζ��b��l�͖��炩�ɒ��쑤�̐l�Ԃł������B�ہA���Ȃ��Ƃ����������ē��R�̎Љ�I�n�ʂƌo���������Ă����B���̐l�Ԃɕs�R�ȓ_������A�O��c�𓇗����ɂ��A�V�c�������I�ɑވʂ������폟��遂镐�m�������A���b��l����̑O�Ɉ����������Ƃĕs�v�c�ł͂Ȃ��B����ɔނɁA�b�R���s�̑厛�̂悤�ȁA�z�����ׂ������I�E���͓I�w�i���Ȃ����Ƃ��A�����e�Ղɂ����ł��낤�B �Ƃ��낪���̖��b��l�Ɋ������đ������̒�q�ƂȂ����B���̂��Ƃ̓t�B�N�V�����ł͂Ȃ��B�@ ���b��l�̑��ւ̉e���͎��ɑ傫���A���b�̒�q��C�����킵���Ƃ�����u�̔����b��l�`�L�v�ɂ��ƌ�̑��̍s�������͂��ׂĖ��b��l����o�����̂ŁA�ނ̎���ɓV�����悭���܂����̂��A�ގ��g����������������O�q�̂悤�Ɂu�x�^�z���v�ł���̂��A���ׂĖ��b�̋����ɏ]�������߂��ƌ������ƂɂȂ�B�����Ȃ�Ɓu��i���ځv�ɂ����b��l�̎v�z���[�����f���Ă��邱�ƂɂȂ邪�A���ꂪ�ʂ��Ď����ł��낤���B�@ �����Ƃ���A�ǂ̂悤�Ȏv�z�Ɋ�Â��u�@�v���A���쎞��ɂ������W��(����������ς�)�̌����悤�ɖ��̕W���ł���A�����̖��@�T�_�����疯�@�̐���܂ŁA�����ɓ��{�l���K�����Ă����̂ł��낤���B����͂����̎Љ�ɍł��������������@�ł���A�܂������K�͂ł���������A�����ɂ͍��Ȃ������́u�{���̋K�́v�̊�ƂȂ��Ă��邪�䂦�ɑ傫�Ȗ��Ǝv����@ ���b��l�����ꂽ�̂͏����O�N(��ꎵ�O�N)�A�e�a�������N�ɐ���Ă��邩���l�͓��N�ł���B������̑��G�I�Ƃ��������l�͓��������̎�����Ă����B����͏@���I�ɂ������I�ɂ��V�������{���V�����K�͂ƒ����̂��Ƃɐ���ς��u���݂̋ꂵ�݁v�̎���ł���A���̓�l�̎v�z�Ƃ����ɂ��̌�̓��{�Ɍ���I�ɉe����^�����B�@ �̔�(�Ƃ��̂�)�̍��R���̌o���ɓ`��邨�т����������̌ÓT�Ђ́A800�N�̎��Ԃɑς��ė��������̑����}���ق̑��e�����Ɏ����Ă���B���̒��S�͂����܂ł��Ȃ����b�Ƃ��̒�q�������`���������̂ł��邪�A�����͌����Ē̔��̒n�Ɏ��R�ɏW�ς������̂ł͂Ȃ��B����A�ꊪ�ɖ��b�̕��̐��U�̂��Ƃ����邳��A��q�����̐��]�̂��Ƃ����̂��B���������T�Ђ̐X�̒��ɗ��ƁA���q����̏����ɐ������čs������̐M�W�c�ْ̋��ƖL�`���Ђ��Ђ��Ɠ`����ė���B���̊j�Ƃ��������b�́A����d���̑��݂Ƃ��Ă̕����҂ł���v�E�E�E�E�ƁB�����A���̑����ژ^�̒��̖��b��l�ɂ�鏑�ʂƒ���̗ʂ��܂������ׂ����̂ł���A���������Ŏ��Z���ɋy�ԂƂ����B�@ �������I�ϊv�̗U���ҁ@ �u�Í������W�v��u���ΏW�v�ɂ�����b�͓��������̐l���m���Ă������b��l�̖ʉe�ł��낤���A�����͂܂��ƂɁu���̐�����v�̂����b�ł����āA���l�ɂ��̂悤�ɉf�����l���璼�ړI�Ȑ����I�e������ȂǂƂ́A�܂��A�l�����Ȃ�����ł���B�@ �ł͈�̂��������l���A�傫�Ȑ����I�E�Љ�I�e���͂���������̂ł��낤���B����͂��肻�����Ȃ����ƂɎv���邪�A�ł����I�Ȑl�Ԃ����A�傫�Ȑ����I�ϊv��U��������̂ł���B�@ �����^�v���̑c�^�́A�̐��̊O�ɐ�Ύ�(�_)��u���A���̐�Ύ҂Ƃ̌_�X�������Ƃ����`�ł��ׂĂ���V���Ă��܂��u�\���L�^�v���v�ł���B�@ ���̏ꍇ����́A�����̗��Q�W����ؖ������A���j�𒆒f���ĕʂ̒����ɐ�ւ���Ƃ����`�ōs�Ȃ��邩��A�̐��̒��̉����ɐ�ΐ���u������s�Ȃ����Ȃ��B�]���Ċv���̓C�f�I���M�[���Ή����A����݂̂�B��̊�Ƃ��ĎЉ��]����Ƃ����`�ł����s�Ȃ����Ȃ��킯�ł���B�@ �̐��̓����ɐ�ΐ���u���A����́A�V�c���Ƃ��悤�Ɩ��{���Ƃ��悤�ƁA�V���������̎����͕s�\�ł���B |
|
|
�������́u���Ԃ��v���v�z�v�@ �����R�I�����ւ̐�ΓI�M���@ �������ێ�����ɂ͂ǂ�������悢���@ �u����ő������ێ�����悢�v�@ �u�ł́A�������ێ�����ɂ͂ǂ�����悢���v�@ �u�����̎x����悢�v�@ �ł́A�ȏ�̂��ׂĂ̎x����ɂ͂ǂ�����悢���B���ׂĂ̐l�����������Ăق����Ƃ������҂ɓ�����悢�A���ꂾ���ɂȂ�B�ł͂ǂ�������ꂪ�\�Ȃ̂��B�@ �����ɏo�Ă���̂��u���b��l�`�L�v�̒��́A�o�q�`���Ƃ������ׂ������ł���B�@ �H�c��������@�[�o�m(���������傤�̂����ɂイ�ǂ��������ڂ�������)��(����)��ĉ](��)�͂��A�@ �u��(�₷�Ƃ�)���b(������)��(��)�ɐl(�Ђ�)�Ɉ�(��)�ЂČ�(����)�苋(����)�Ђ��́A��(���)�s��(�ӂ��傤)�֖�(�����܂�)�̐g(��)����Ȃ��玫(��)���闝(��)�Ȃ��A��(�܂育��)��(������)��ēV��(�Ă�)����(����)�߂��鎖(����)�́A���(�ЂƂ���)�ɖ��b��l(�݂傤�����傤�ɂ�)�̌䉶(������)�Ȃ�B��(��)�̌�(���)�͏��v�嗐(���傤���イ�̂������)�̛�(��)��(��)��(�������傤)�̎�(�Ƃ�)�A��(��)�ɔq�y(�͂�����)���B����(����Ƃ�)�A�@�k(�ق�����)�̎�(����)�ɁA�u�@��(����)�Ȃ����(�ق��ׂ�)����(����)�Ă��V��(�Ă�)����(����)�ނ�p(�����)��(������)�ӂׂ��v�Ɛq(����)�ː\(�܂�)�����肵���A��l(���傤�ɂ�)��(����)�����ĉ](��)�͂��A�u�@��(����)�ɋ��(����)�]�|(�Ă�ǂ�)���āA��g(��������)��(������)���Ȃ炸�a(��)�߂�a��(�т傤����)�����A�Lj�(��傤��)��(����)����(��)�āA��(��)��͊�(����)��蔭(����)�肽��A��(��)��͔M(�˂�)�ɔ�(����)���ꂽ��ƁA�a(��܂�)�̔�(����)�肽�鍪��(����)��m(��)���āA��(������)��^(����)��(���イ)����(����)�ӂ�A��(���Ȃ�)����M(�ꂢ�˂�)����a(��܂�)��(����)�邪�@(����)���A��(����)�̗�(�݂�)��ĉ�(������)���Ȃ炸��(������)���(����)���́A��(�Ȃ�)�̐N(����)����(���)���ƁA��(��)�Í���(����)��\(��)���m(��)�苋(����)�ӂׂ��B�����Ȃ��đ�(��)����(�ނ�)�ӂ܂܂ɏܔ�(���傤��)���s(������)�Ћ�(����)�͂A��T(���悢��)�l(�Ђ�)�̐S(������)�����܂���(�˂�����)��킭(�݂��肪�܂���)�ɂ̂ݐ�(��)��āA�p(�͂�)�����m(��)�炸�A�O(�܂�)����(����)�ނ�Ό�(������)��藐(�݂�)��A��(����)��G(�Ȃ�)�ނ�ΊO(����)��荦(����)�ށB����ΐ�(��)�̎�(����)�܂�Ɖ](��)�ӎ�(����)�Ȃ��B��(��)��ψ�(������)�̊��M(����˂�)���(�킫��)�ւ����āA��U(��������)���(����)�̂��鏊����(���イ)���A��(��)�Ô�(����)����(�˂�)�Ђɐ�(������)�ЂāA��(�݂�)��ɖ�(������)��^(����)�ӂ邪�@(����)���B��(���イ)��s(��)�����ė�(��傤)����(����)�ӂ�ǂ��A�a(��܂�)�̔�(����)�肽�鍪��(����)��m(��)�炴�邪��(���)�ɁA�܂��܂��a�Y(�т傤�̂�)�d(������)��Ă������邪�@(����)���B����ΐ�(��)�̗�(�݂�)��鍪��(����)�́A��(�Ȃ�)���N(����)�邼�Ɖ](��)�ւA���~(�����悭)��{(����)�Ƃ���A��(��)�̗~�S(�悭����)���(��������)�ɕ�(���܂˂�)���Ė���(��ς�)�̉�(�킴�͂�)�Ɛ�(��)��Ȃ�A��(��)��V��(�Ă�)�̑�a(�����т傤)�ɔ�(����)����B��(��)���(��傤)����Ǝv(����)�Ћ��͂A��(��)�Í�(��)�̗~�S(�悭����)����(������)�Ћ�(����)�͂A�V��(�Ă�)��(���̂Â�)���(�ꂢ)�������Ď�(������)��ׂ��v�Ɖ]�X(����ʂ�)�v�@ ���̌��t�́A�u���b��l�͂��̂悤�Ɍ�����v�Ƒ�������Ă���킯�ŁA���b��l�̌��t�����܂܂ɋL�������̂ł͂Ȃ��B���̏�A����ɂ�����@�[�o�q�����ꂩ�Ɍ��A���ꂪ�o�q�`���ƂȂ��Đ��ɓ`����Ă��́u�`�L�v�Ɏ��^���ꂽ�̂�����A���̎�����A����Ɋo�q�̉��߂��̑������R�ɓ����Ă���ł��낤�B���̂��ߑ�ςɁu�ʑ��I�P�b�v�̂悤�ɂȂ��Ă͂��邪�A���̊�{�܂ł��ǂ��Ă݂�Ɩ��b��l�̍l�����́A���Ƀ��j�[�N���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�������҂̍l�������������Ă���ƌ��āA������ꉞ�A���b�\�������v�z�Ƃ��Ă������B�@ ���j�[�N�Ƃ����̂́A���Ƃ̒����̊�{�̔c�����ŁA���b��l�́u�l�̓��̒����v�̂悤�ɁA���A���R�I�����ƌ��Ă���_�ł���B���b��l�ɖ{���ɂ����������z���������̂ł��낤���B���̋L�q�͎j���I�ɂ͑����ɖ�肪����Ǝv���邪�A�ȏ�̔��z�́A���b��l���̐l�̔��z�ƌ��Ă悢�Ǝv���B�Ƃ����̂́A�u���ւ̃��u���^�[�v����������Ă���A���̃��u���^�[�̎j���I���l�͔ے�ł��Ȃ�����ł���B�@ �u���̌�A���ς育�����܂��B���ʂꂵ�܂��Č�͂悢��(�ׂ�)�������Ȃ��܂܂ɁA�����A(��������)�����������ɂ���܂��B�������������̂��̂��l���܂��Ȃ�A����͗~�E(�悭����)�Ɍq��(��������)����@�ł���A�p����(�����)���`�����Ƃ�����F(�ɂ���)����(����)���A�Z��(�������)�̈�ł���፪(����)�A�Z��(�낭����)�̈�ł���Ꭿ(����)�̂䂩�肪����A�����䐶(�����傤)�̎p�ł���܂��B�܊��ɂ���ĔF�������Ƃ͒q(��)�̓����ł���܂�������Ȃ�����(���Ƃ��炪�����Ƃ͗����Ȃ킿�����ł����āA����ɕЂ��Ƃ������Ƃ͂���܂���B�����Ȃ킿�����ł��邱�Ƃ��������Ƃ������ƂŁA�����Ƃ͉F���̖@��(�ق���)���̂��̂ł���A���ʂ̖������A�����̎��̂��O��(���ザ�傤)�̐��E�Ƃ����̂Ɖ���̑���͂���܂���B����̂ɖ�Ɠ����悤�Ɋ���������Ȃ�����Ƃ����Ĉ��(��������)�̐����Ƌ�ʂ��čl���Ă͂Ȃ�܂���B�܂��Ă⍑�y�Ƃ͎��́u�،��o(�����傤)�v�ɐ�(��)�����̏\�g���ł���ȍ��y�g�ɓ����Ă���A���I�Փߕ�(�т邵��ȂԂ�)�̂��̂̈ꕔ�ł���܂��B�Z���܂�������ƂȂ��ď�(����)��Ȃ��@������܂��Ȃ�A�����̂��̂����y�g�ŁA�ʑ��傩�炢���ΏO���g(���ザ�傤����)�E�ƕ�g(�����ق�����)�E�����g(���傤����)�E��F�g(�ڂ�����)�E�@���g(�ɂ�炢����)�E�@�g(�ق���)�E�q�g(������)�E����g(����������)�ł���܂��B�����̂��̂����̏\�g�̑�(�Ă�)�ł���܂�����A�\�g���݂ɂ߂��邪�̂ɁA�Z�ʖ��V(�䂤�����ނ�)�Œ�ߓV(�������Ⴍ�Ă�)�ɂ�����(�ق�����)��t(�����ς�)�ƂȂ�A�͂��蓾�Ȃ����̂�����܂��āA��X�̒m���̒��x���z���Ă���܂��B����̂Ɂu�،��o�v�̏\���̌��ɂ���ē��̗�(���Ƃ��)�Ƃ������Ƃ��l���܂��Ȃ�A���I�Փߔ@��(�т邵��Ȃɂ�炢)�Ƃ����܂��Ă��A���Ȃ킿�����̂��̂̊O�ɂǂ����ċ��߂��܂��傤�B���̂悤�ɐ\���܂������ł��܂��łāA�̂��ڂɂ�����܂����܂���͂����Ԃ�ƔN�����o�߂��Ă���܂��̂ŁA�C�ӂŗV�сA���ƗV���Ƃ��v���o���Ă͖Y��邱�Ƃ��ł����A��������������(����)���Ă���Ȃ�����A���ڂɂ����鎞���Ȃ��܂܂ɉ߂��Ďc�O�ł������܂��v�@ �m���Ɍ���l�́A���b��l�̐��E�����L���邱�Ƃ͂ނ��������B���������b��l���A�^�Ɂu����l�i����Ώہv�ƌ��Ă������Ƃ͂���Ŗ��炩�ł��낤�B���l�ɓ��{�����̂��̂��u���y�g�v�Ƃ����l�i����Ώۂł��邩��A�܂�����Ɂu�l�i�̂���Ώہv�Ƃ��āu��҂̔@���v�ɑ��Ȃ���Ȃ�ʂƂ����̂��A���̐����N�w�̊�b�ƂȂ��Ă���B�@ ����𐭎��N�w�ƍl�����ꍇ�A����́u�Đ_�_�I�v�z�Ɋ�Â����R�I�\�蒲�a���v�Ƃł����Â��ׂ��N�w�ł��낤�B�Ƃ����̂́A���Ƃ���l�̂̂悤�Ɍ���A���N�Ȃ炻��͎��R�ɒ��a���\�肳��Ă���A��������K�v�͂Ȃ�����ł���B�O�Ɏ��́A������u���{�I�����v�z�̊�{�v�Ƃ��ăn�[�o�[�h�̃A�u���n���E�U���c�j�b�N�����ɐ��������Ƃ��A�u���̎��R�@(�i�`�������E���[)�I�v�z�v���ƌ������Ƃ���A�������́u�@(���[)�ł���܂��A����(�I�[�_�[)�ł��낤�v�ƌ���ꂽ���A�m���Ɂu���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�ւ̐�ΓI�M������{�ɂ���v�z�Ƃ���˂Ȃ�܂��B����͔��ɕs�v�c�Ȏv�z�A�u���Ԃ��v���v�z�v�Ƃ������ׂ��v�z�ł���B�@ �Ȃ����ꂪ�u���Ԃ��v���v�z�v�Ƃ�����̂��@ ���ŗL�@�ƌp��@�@ �v���́u�����^�v���v�Ɓu�����^�v���v�ɑ�ʂł��邪�A�`���A���̍s���͌��ۓI�ɂ͂ނ���u����I�����^�v���v�Ƃ����ׂ����B�@ �V�c���猠�͂�D�悵�Ă�������ʂɒu���A�u��i���ځv�ȂǂƂ����@������ɂ����Ȃ������V�c�̍ى��o���Ɉ���I�Ɍ��z�E�{�s���Ă��܂��ȂǂƂ����v���́A�����^�v���ɂ͂Ȃ��s����������ł���B�ł͐����^�v���Ȃ̂ł��낤���B���ۓI�E����I�ɂ͂��������邪�A�����Ă����͌����Ȃ��̂́u���b�\�������v�z�v���A�����^�v���̊�{�Ƃ͑S���Ⴄ����ł���B�@ �����^�v���̊�{�^�Ƃ������ׂ����V�����̐\���L�v���ɂ��Č����A����͂���ΐ_�a����o�Ă����u�_�Ƃ̌_�v�̒ʂ�ɎЉ����{����ς��Ă������Ƃ����v���ł���B���̍s�����́A���̌_�ɋL����Ă���u���t(�f�o���[��)�v����Ȃ̂ł���A���ɑ��݂���u���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v����Ȃ̂ł͂Ȃ��B�u�\���L�v�͂փu���C�ꐹ���̏����ł́u���t(�f�o���[��)�v�ł��邪�A�u���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�͂��́u���t(�f�o���[��)�v�Ŏ�����Ă���ʂ�ɍč\�����ׂ��ΏۂŁA���́u���t�v�̕�����ŁA�������钁���͐�ł͂Ȃ��̂ł���B���̊�{�I�ȍl�����̈Ⴂ�͍������ĂƓ��{�Ƃ̊Ԃɂ���B�@ �ł́u���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v���Ή����A�u���t�v�ɂ���č\�����ꂽ���E���t�ɔے肷��Ƃ������b�́u���Ԃ��v���v���A�ǂ����āu����I�����^�v���v�̂悤�Ȍ`�ɂȂ����̂ł��낤���B�@ �����̍��w�n�̗��j�ƈɒB��L�́A���̏��u�吨�O�]�l�v�ɂ����āA���{�̗��j���O���ɋ敪���A�u��(����)�̑�v�u�E(����)�̑�v�u���̑�v�Ƃ����B�ʔ������Ƃɔނ��܂����b��l�Ɠ����悤�ɋI�B�̏o�g�ł���A�����̐����Ɨ����@���̎����ł���B�@ ���̋敪�́A�����̌�ւłȂ��A�����`�ԂƂ����q�ϓI�Ȑ��x�̕ϊv�ɂ��{�i�I�ȗ��j�敪�ł���A��������̂܂ܗ��j�I�����Ƃ��ď��F���Ă��邩��ł���B���̌����́A�V�c�e������{�̂�����ƋK�肵�A���{������j�̌��Ƃ���c���j�ϓI�����Ƃ͊�{�I�ɑ��e��Ȃ��B�@ �ނ̎O��敪�̂��ꂼ����ȒP�ɋL���u��(����)�̑�v�Ƃ́A�Ñ�̓��{�̌ŗL�@�����Ɋ�Â����̂ŁA���̊�{�́A�����E����E�N�E�b�̂悤�ɋ��n�ƐE�����������������W�c����b�Ƃ���̐��ŁA�����g�̂ɂ��Ƃ���Ύ�(����)�������ō�(����)�͍��ɑ������A���̐E���́A�����I�n���̑����Ŏq���Ɏ����B���́u��(����)�v�͓V���V�c13�N(684�N)�ɔp����u�E(����)�̑�v�ƂȂ�B����Β��삩��u���E�v��^�����Ă͂��߂Ēn�ʂƌ����Ƃ������鎞��ł���B����684�N�Ƃ́A�N��L�I�ɋL���A681�N�ɗ���(��䌴��)������͂��߂��A682�N�ɗ�V�E����̐�����߂��A683�N�ɏ����̋��E�����߂��A684�N�ɏ����̑��������߂Ĕ��F�̐��Ƃ���A685�N�ɐe���E�����\��K�E���b�l�\���K����߂��Ă���B�����̐��x�̕ϊv���ނ̂����u�E(����)�̑�v�̂͂��܂�ł��낤�B�����đ�O�́u���̑�v�͕������N(1185�N)�A���������Z�\�]�B���Ǖߎg�ɔC����ꂽ�Ȍ�̎���ŁA�u���v�Ƃ͕��������̑喼�E�����̎���ł���B�@ �����������������ߐ��x�@ �u�p��@�v�A���̌��t�͍��X�����̕K�v�͂Ȃ��Ǝv�����u�L�����v�ł́u�����̖@���������̍������E�������ɏƂ炵�Čp���@���v�Ƃ���A�u�ŗL�@�v�ɑΗ�����T�O�Ƃ���Ă���B�����āu�Љ�̂���Ƃ���ɕK���@����v�Ȃ�A�����̖@���p��ȑO�ɂ����炩�̖@�����{�ɂ������ł��낤�B���ꂪ�u��(����)�̑�v�̖@���B�@ �嗤�̕������u�p�悤�Ƃ����ӎu�v�͂قڈ�т��Ď����Â����āA701�N����Ƃ��ꂪ��߂Ƃ��Č��z�����B�@ �����E����(���D)�ɂ��A�剻�E���(�����])�ɂ��A���܂��܂ȊO�����ۉ��Ȃ��@�Ƒ̐��̌p��������������Ƃ��ے�ł��Ȃ��B�ȒP�ɂ����A����ƑR����ɂ͑���Ɠ��������ɋ}���ɍ��������Ȃ���Ȃ炸�A����͑���̖@�Ƒ̐����p��̂��ł�����Ƃ葁�����@������ł���B��a�����562�N�̔C��(�݂܂�)�̖ŖS�ȗ��A���N�����Ōp���I�ȑސ��ƕs�U�ɔY�܂���Â��A������@�E���Ƃ�����鍑�̏o���͋��ЈȊO�̉����̂ł��Ȃ������B�����Ă��̌����́A663�N�̔����]�̌���I��s�ł������B����炪���܂��܂ɍ����ɍ�p����ƂƂ��ɁA�����̑�a����͂��łɁA�S���I���{�Ƃ��Ă����������o�ϓI�E�����I��Ղ��m�����Ă������Ƃ��A��߂�f�s���������R�ł��낤�B�@ �����剻�̉��V�́A���̊�{�ł���u���n�������v�������Ă͂��߂ċ@�\����킯�ł���A���ꂪ����Β����̋@�\�͂����܂���Ⴢ��Ă��܂��B�����Ă��̐��x�ł͂܂��A�������~�ɂ��ăy�C�p�[�v�����������A���̃v�����̕��֓����́u���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v����������ōs���Ƃ����`�ɂȂ炴��Ȃ��B����͑����ɖ����Ȃ��Ƃł���A��������s���悤�Ƃ���Δۉ��Ȃ��_���I�Ȍ[�֓I��ΌN�傪�K�v�ƂȂ�A�����ɂ��̑̐����A�����ē��̖͕�łȂ��킪���{���̑̐��ł���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����A�O�����Ή����A���̖@�Ƒ̐����p�Ă���̂ɁA�u�������Áv�œ��{�{���̎p�ɖ߂����̂��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�剻���N�̏قɁu��(�܂�)�ɏ�Ð����̐Ղɏ�(������)���ēV�̉������߁A�����ɐM�����ēV�̉������މ��v�Ƃ���A���̍s�������܂������ƕς�͂Ȃ��B�܂�����𐋍s�����V�c���u�V�q�E�V���v���_���I���̂ŌĂ�邱�Ƃ��A���������ݏo�����u���l�_�V�c���v�Ƌ��ʂ��Ă���B�@ ����͌����̈Ӗ��ł́A�����^�v���ł������^�v���ł��Ȃ��B�����A�y�C�p�[�v�����́u���t�v�̕��ցu���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v����������ł����Ƃ������ۂ͎��Ă���B�����������^�v���́A�����ɐV�������_����ɂ��Ă��悤�ƁA���̗��_�����̎Љ�琶�ꂽ���̂Ȃ�A���̎Љ�̌����ɍ��������Ă��邪�A�O���ɏo���Ă���`���I�̐����قڂ��̂܂܂ɗA�����ċ��s���邱�Ƃ́A���̎Љ�́u���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�Ɋ�b��u���Ă���Ƃ͂������������疳��������B�������A�@���A�������Ƃ��́A�̐����@�������������ɗA������Ă��̎Љ�ɍ�p���A���̎Љ�̕����I�]���������N���B�������̂悤�ȓ]���ɂ���Ĉ����N���ꂽ�V���������́A���̑̐��Ɩ@�Ƃ��\���������̂ł͂Ȃ��B���߂͕��ƂƂ����u�V�����K��(�j���[�E�N���X)�v�Ƃ������ɂ����u���ƕ����v�ȂǂƂ������̂��o�Ă��邱�Ƃ�S�R�\�z���Ă��Ȃ������B�@ �V�����K�����o�āA�V�����������v�������Ȃ�A���߂����肷��悳�����Ȃ��̂����A�p��@�͂��ꂪ�ł��Ȃ��̂����ʂł���B���R�͂܂��͂��߂��疳�������邩��A��ΓI���Ђ������ċ����I�Ɏ{�s���A���̂��߁u���l�_�̖@�v�Ƃ���邩�A�܂��́u�@���́v���u���_���v���Ă�����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B���̂��ߗ��߂��}���Ɂu�������S�v�����Ă����A����ΎЉ�Ɂu���@�v�Ɓu���@�v���ł��Ă��܂��āA�l�тƂ͒ʏ�́u���@�v�ɏ]���Ă���B�����Ă������������₵�܂Ȃ��Ȃ�B����́u���_���v���Ă���V���@�ɂ����錻�ۂł���B���Ƃ��u���a���@���Ɏ��v�Ƃ����Ă��鎄��̊w���ɁA�ł͔��\��������`�ʂ�ɏ��炵�A����ɒ�߂�ꂽ�ʂ���{���Ă�낵�����Ƃ����A�ȒP�Ɂu��낵���v�Ƃ͌����Ȃ��ł��낤�B�@ �͎��̒ʂ�ł���B�u�������̑��̌��̍��Y�́A�@����̑g�D�Ⴕ���͒c�̂̎g�p�A�։v�Ⴕ���͈ێ��̂��߁A���͌��̎x�z�ɑ����Ȃ����P�A����Ⴕ���͔����̎��Ƃɑ��A������x�o���A���͂��̗��p�ɋ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�B����ɂ��Ό����́A���̎x�z�ɑ����Ȃ����玖�ƂɎx�o���Ă͂Ȃ炸�A�]���Ď�����w�ɂ��x�o���Ă͂Ȃ�Ȃ��͂������A�������������炭�A�u����͕ʂł���v�Ƃ��܂��܂ȁu���_�v���q�ׂ���ł��낤�B����͌��ǂ��̏����̈ꕔ�����łɁu�������S�v���Ă���̂ł����āA���́u���@�v�Ƃ͈Ⴄ�u���@�v�����R�̂��ƂƂ��ĎЉ�ōs�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł���B�l�͂����s�v�c�Ƃ��Ȃ��B���A���̂��ߌ��@���������悤�Ƃ͂���Ȃ��B�������̏ꍇ�A���X���܂�̂́A�����u������Ԃ��Ă��v�Ƃ��������Ƃ��o�Ă��āA���̏��������ɁA�u����ւ̍��ƕ⏕�͌��@�ᔽ���v�Ƃ����đł���A�u���@���Ɏ��v�Ǝ咣���Ă���҂͂���ɑR�ł��Ȃ��Ƃ���������B�����Ă��ׂĂ̖@���u�������S�v�ƂȂ�A�x�z�҂͂��ׂĂ̓_�ŁA���Ȃɓs���̂悢�悤�ɖ��@�E���@�̎g���킯���ł��āA����́u���@��肱�܂�v�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă��܂��B�@ ���������S������p��@�@ ���߂ɂ͓������Ƃ�����A����Ɍ��n�������́A���Ԃ��A���ׂĂɗ������������闘�������ƂɂȂ肤��B�����A���ߐ��͂����Ȃ��čs�����B�Ƃ����̂͂��̐��x���{���ɂ��̒ʂ�Ɏ��{�����A�����c��@���ɋΕׂɍk�����ƂāA����ɂ���ē����x�ŗגn���č��Y���ӂ₷���Ƃ͂ł��Ȃ��B���������E�ɂ��ΕK�������͂��Ă܂��A�܂����܂��܂ȕs�����s�Ȃ�����B(�������S�F�\���������Ă��鎖�Ǝ��̂Ƃ�����Ȃ�����)�@ ���ߐ��͈�ʂł͗������ł���A�����ɂ��ꂪ���n�������̕���ւƂȂ������B�@ ���n�������͌����I�ɂ͓y�n�̔����͔F�߂Ă��炸�A�܂�����͊�i���邱�Ƃ��ł��Ȃ��͂��ł���B�Ƃ��낪���ꂪ�s�Ȃ��Ă��肻���œV��18�N(746�N)��������߂ċւ��A5���ɍĂыւ����B�����������ɂ́A�܂�u���@�v�Ƃ��Ă͍s�Ȃ��Ă���A�r��������ɂ́A���L�̍��c�����n�Ƃ��Ċ��ɔ���n���Ă���������B�����ēV�����N(749�N)�ɂ͏��厛�̍��c�𐧌������@�ɓy�n����i���邱�Ƃ��ւ��Ă��邪�A���������Ă��Ȃ��B�@ ���Ȃ̓`���I�ȁu���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�������p��@�ɂ́A�����ɐ_���I���Ђł�����{�s���Ă��u�������S�v�ƂȂ�A�����ɂ��̊Ԍ���D���ė������������A������Ƃ����������l����悷��B�@ ���̌����͓��{�I���R�������������߂Ƃ����p��@�́u�������S�v�ɂ���B�����ŁA�܂��u���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�Ƃ��������ɗ����u���̗���ĉ����Ȃ炸�����́A���̐N���̂��ƁA��Í�����\���m�苋�ӂׂ��v�Ƃ������z�ɂȂ�B���̖��b�\���I�����v�z�̔w��ɂ͂��̂悤�ȗ��j�I�̌�������A���ꂪ����ɐ��X�����A���v�̗��̑O��ɍČ������킯�ł���B |
|
|
���u��i���ځv�̍��{�v�z�@ �����R�I������̎v�z�@ ���͎��X�A���ܓ��{�l���u���̂悤�ȏ�ԁv�ɒu���ꂽ��ǂ�����ł��낤���Ƌ�z����B�@ ���܂����V���@�������A����Ɋ�Â��������x�������A�����^�����`�������Ă��܂��āA�u�S���V�����v�z������l���o���A����Ɋ�Â��@�N�w��n�o���A����ɂ���č��܂ł̐l�ނɂȂ��V�����@���Ɛ��x�����o���Đ��肵�A���{���悤�v�Ƃ������ƂɂȂ�����A�l�тƂ͈�̂ǂ�����ł��낤���B�@ �l�Ԃ��A�����V�������z�ŐV�������Ƃ��͂��߂悤�Ǝv���Ă��A�ߋ���S���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�@ ���̔��z��̌n��������̉����邽�߂́u�v�z�I�f�ށv�͉ߋ��Ɠ�����ɋ��߂���Ȃ��B���������̂��Ƃ́A�����̖@�Ƒ̐������̂܂܌p�邱�ƂƂ͑S���ʂł���B�p��͌����ĐV�������z�����Ȃ̒��ɑn�o�����̂łȂ��A���ȂƖ��W�̂�����̂����āA����Ɏ��Ȃ�K�������悤�Ƃ��������ł���B���̓_�A���b�\�������v�z�͑O�҂ł���A�܂��u���R�I�������(�i�`�������E�I�[�_�[)�v�Ƃ����v�z������n�o���A�������̉����邽�߂̑f�ނ���Ɖߋ��ɋ��߂��ɂ����Ȃ��B�@ �܂��u�����钁���v���u���邪�܂܂ɔF�߂�v�Ȃ�A�����������Ƃ����Ƃ����߂��A�����Ă₪�Ď��炪���o���u���ځv�̊�ɂȂ�̐����A���邪�܂܂ɂ����Ĉ���ɍ��������Ȃ��킯�ł���B���������́u���������v�Ɠ��{�l���v���o���͓̂�����ɂȂ��Ď�q�̐����_���Z�����͂��߂Ă���ł���A����܂ł́A���ꂪ���{�̎��R�I�����Ȃ炻��ł悢�Ƃ����킯�ł���B���ꂪ��́A���b�\�������v�z�̊�{�ł��낤�B�������̊�{����̉����A����������Œ����Â���ƂȂ�A���̊�{����̉�����f�ނ��K�v�ł���B�����Ă��̊�{�I�f�ނ͒����̎v�z�ɋ��߂�ꂽ�B�����A�����v�z�ɋ��߂��̂͂����܂ł��f�ނł���_���A���߂Ƃ͌���I�ɈႤ�B�����ɁA���ꂪ�{���ł����đf�ނłȂ������Ƃ�����Ă���B����͂��������A���̂悤�ȏ�Ԃɒu���ꂽ��A���̊�{�I���z�͎���n�o���Ă��A�������̉�����f�ނ͐����̐����v�z�ɋ��߂�ł��낤�Ƃ����̂Ɠ����ł���B���̂��Ƃ͍��̒i�K�ł́A�����Ƃ��ނ���o�c�҂̍s�����ɂ��邪�\�B�@ ���@���@�I�̐��͐��܂��@ �O�͂ŋL�����悤�ɁA���b��l�͑��ɁA���̎��R�I�����ɑ�������̐�����������ɂ́u��Í��̗~�S�����Ћ��͂A�V������߂������Ď���ׂ��v�ł���Ƃ����A���̔w��ɂ́A�u�����͗����ł���v�����R�Ƃ���Ă������ߐ��̋ꂢ���j�I�̌�������ł��낤�Ƃׂ̂��B���̑̌�����̑f�ނł��邪�A�Â����b��l�̌��t�ɂ͖��炩�ɁA�E�q�E�V�q�E���q�E�Ўq���̍l�����������Ă���B�@ ���Ƃ��u�Ўq�v�́u�S��{���ɂ͉Ǘ~���ŗǂ̕��@�ł���B���̐l�ƂȂ肪�Ǘ~�ł���A���Ƃ��m�`�̐S�������Ă��A���������͏��Ȃ��Ă��ށB���̐l�ƂȂ肪���~�ł���A�m�`�̐S������Ƃ��Ă�����߂Ă킸���ł���v�Ɛ����A�܂��V�q�́u���~�ɂ��ĐÂȂ�A�V����(�܂�)�Ɏ����܂��v�Ƃ����B���q���u���l�̐ÂȂ��A�Â͑P�Ȃ�ƞH�����̂̐ÂȂ�ɔB�����̈ȂĐS��(�݂�)���ɑ�����̖������̂ɐÂȂ�B�c�c���ꋕ�Ü��W�A�├���ׁA�V���̕�(�a)�Ȃ�ɂ��ē����̎�(�����)�Ȃ�v�Ƃ��Ă���B���̍l�����̔w��ɂ�����̂́A�u���R�@���͓����@���ł���v�Ƃ������z������A����͐挱�I�Ȃ��̂ł���A�u���~�v�Ȏ��R��ԂɂȂ�A���̐挱�I�����@���������ł���Ƃ����l�����ł��낤�B��ɂ����̌n�I�ȓN�w�ɂ���͎̂�q�ł��낤���A���b��l�̍l�����͂�������q�w�I�ł͂Ȃ��A�ނ���A����֎���v�z�̓��{�I�E�����I���߂ƌ���ׂ��ł��낤�B�@ �܂����b��l�͏t���喾�_�����M���Ă���A���̓_�ł͍ł������I�ȎO������_�҂ł������Ƃ�����B�����Ċ�C�̋L���Ƃ���ł́A���E����͂��Ƃ��O���̐����E�V�̋��������ׂĔ@���̒�b(���傤��)���甭�������̂��ƌł��M���Ă����炵���B�@ �������A���̍l�����������I�ɋ@�\����Ƃ��́A���炩�̏@�����Ή������u�@���@�I�̐��v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��A���̂��Ƃ��A�܂��ɑ��̐����v�z����ɖ��{�̐����v�z�̊�{�ƂȂ��Ă���B�]���đ������b��l�̉e�������������Ƃ͓��{���u�����̐��v�ɂȂ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ����A�،����w�������ē��{�́u�����_�w�v�ƂȂ��A���͂��Ƃ��Ƃ��r�˂���Ƃ������Ƃł��Ȃ��B�@ ����̐����Ƃ�ʂɂ���A���������u�`����̂��܂��m���ł������B�@ ��҂����I�Ȉʒu�ɂȂ����͓̂��쎞�ォ��ł���A�L���ȗї��R���g���ł͑m���Ŗ@��ł���A���̎q�t�ւ��@��ł������B�@ ���b��l���̋������Ƃ��A�u��i���ځv�Ɏɂ��Ă̋K�肪�Ȃ��Ă��A�����̏펯�ł͕ʂɕs�v�c�ł͂Ȃ��B�@ ���l�Ԃ͎��R�̈ꑶ�݁@ �]���ĐV���������̂��߂̍ޗ��Ƃ��ĎI���������b��l�̌�����o�ĕʂɕs�v�c�ł͂Ȃ��B�@ �u�������邱�Ə��߂邪�@��(���a�҂�����悤��)�v�͕����ւ̖Ўq�̕]�A�܂��O�q�̂悤�Ɂu���~�ɂ��ĐÂȂ�A�V����(�܂�)�Ɏ����܂��v�́u�V�q�v�A�܂��u���l�̐ÂȂ��A�Â͑P�Ȃ�ƞH(�̂���)�����̂̐ÂȂ�ɔB�����̈ȂĐS��(�݂�)���ɑ�����̖������̂ɐÂȂ�v�́u���q�v�̌��t�ł���B�܂��Ўq���Ǘ~���m�Ƌ`�̑O��ł���Ƃ��Ă���B����́A�l�Ԃ����R�̒��̈ꑶ�݂ƂƂ炦�āA���R�̒����������Ɍl�̓������̊�{�ł���A���ꂪ�܂��Љ�̒����̊�{�ł���Ƃ��钆���̊�{�I�v�z����o���l�����ł���B�������l�Ԃ͒m�o��p�����邩��A���ꂪ�o���I���E�ɔ�������B���ꂪ�u��v�ł���A�S���O���ɐG��ē����Ə�����āu�~�v��������B���́u�~�]�v�ɓ��������ƁA�l�Ԃ͎��R�̒�������{�Ƃ��铹��������͂����B�����ŐS���O���ɓ������ꂸ�A�~���N���Ȃ�����̍s�ׂ͂��̂����瓹�����ɂ��Ȃ��A���ꂪ���R�I�Ȓ������`������Ƃ����l�����ł���B�����Ă��̏�ԂɂȂ�A�l�Ԃ̓��ɂ���ĉF���̒����ƈ�̉����A����ɂ���ĎЉ�͐��X�Ɖ��̗�����Ȃ����a���ċ@�\����B���̏�Ԃ��u�q�H���A�����ׂ��ɓ����ȂĂ���A栂��Ζk�C�̂��̏��ɋ��āA�O���̂������(�߂�)�邪�@���v�Ƃ����u�_��v�̌��t�ɂ��Ȃ�B�@ �����b�́u����ׂ��悤�́v�@ �ł͐l�́u���~�Ŗ��ׁv�ł���悢�̂��B����ɑS�������~�ɂȂ��ĉB�ق��Ă��܂��悢�̂��B�ʔ������Ƃɖ��b��l�͌����Ė��ׂ�����Ȃ������B�@ �u������l���ĞH�͂��A�u��Ɉ�̖�������A��͌㐶��(������)���Ƃ͐\�����A�������ɗL��ׂ��l�ɂėL���Ɛ\���Ȃ�B����(���傤���傤)�̒��ɂ��s���ׂ��l�ɍs���A�U���ӂׂ��l�ɐU���ւƂ��������u���ꂽ��B�����ɂ͂ƂĂ������Ă�����A�㐶�v(�͂�)�莑(����)����Ɛ����ꂽ�鐹���͖����Ȃ�B��������j���ĉ�����āA���̉v������Ɛ������ւ�B��(���)�Ĉ����ӊ���F�a(����ׂ��₤��)�Ɖ]�ӎ�������(����)�ׂ��B������(����)��P�Ƃ��B�l�̂�낫�͑�(�킴)�Ƃ�낫�Ȃ�B��(�����)���͂�낫�ɔB�������Ȃ��҂��P���Ȃ��Ƃ͎v�͂���ǂ��A����ׂ��l�ɂ��ނ��Ă܂��Đ����Ȃ��B���̎�����S�ɂ����Ď�(����)���A��(��)���Ĉ��������L(��)��ׂ��炸�v�Ɖ]�X�v�ƁB�@ �܂��u��P���o�v�ɂ́u���]�A��͌㐢��������ނƉ]�҂ɂ��炸�B���U������Â���ׂ��₤�ɂĂ����Ɖ]�Җ�B�]�X�v�Ƃ���A���̌��t�͍��E�̖��̂悤�ɐ₦�����ɂ����炵���B���̍l�����͏�y���̐M�҂Ƃ͕������S���Ⴄ�B�@ �������̌��t�́A�m�ɑ��āA���ꂼ��̑f���ɉ������s(���傤)�����ĉ�E�����߂�悤�ɁA���̍s���u����ׂ��悤�Ɂv�s�Ȃ��Ƃ������Ӗ��ł͂Ȃ��������Ǝv���邪�A��ɁA��ʐl���ׂĂɋ��ʂ���K�͂Ƃ��Ď�����悤�ɂȂ����B���R�������́u�`�L�v�̒f�ȂɁu�l�͈���(����)�ւ��₤�͂Ƃ��ӎ���������(���ׂ�)��A�鉤�͒鉤�̉L�l(����ׂ��悤)�A�b���͐b���̂���ւ��₤�A�m�͑m�̂���ւ��₤�A���͑��̂���ւ��₤�A���͏��̂���ւ��₤�Ȃ�B���̂���ւ��₤���ނ���ւɈ��������v�ƋL����Ă���̂́A���̂悤�Ɏ���ꂽ�؋��ł��낤�B�����Ƃ��A����͎�������̂��̂Ƃ�����B�@ �u����ׂ��悤�́v����̉�����A�ׂ������Ƃ܂Łu��������ׂ����v�ƒ�߂����̗��@��`�ɂȂ�B�����A���b��l�ɂ͂������������`�Ȉ�ʂ�����u�����̏�ɐ���E��ܓ��̕��A�V�������ׂ��炸�B�����̉��ɐ����A�V�������ׂ��炸�B�����ȂĕM���˂ӂ�ׂ��炸�B�d�Ђƕ���Ɗȕʂ����ނׂ��c�c�v�ƌ������悤�ȁA�w�⏊�Ǝ������ɂ�����ׂ����K������߂��Ă���B����͓��R�ŁA�u����ׂ��悤�́v�͂܂�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������Ȃ��ŁA�����Ȃ莶��Ƃ�������Ƃ��������Ƃ́A���ꂱ���u�t�v�́u����ׂ��悤�́v�ɔw���ł��낤�B��������͂����闥�@��`�ł����Ă͂Ȃ炸�A�S�̂����ۂ�(���@)�Ƃ������̂���Ɉӎ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@ ���Ȃ킿�u�����S�̂��ۂ�(���@)�Ɏ�����ӂ�܂Ђ́A���̂�������@�ɕt�����ׂ���v�œ��I�K�͂����̂܂܊O�I�K�͂ł���悤�ɂȂ�̂��u����ׂ��悤�́v�ł����āA�u�S�̎��@�Ɏ�����v�U�������A�������R�I�Ȓ����ƂȂ��āA���̉��@�Ɉ�v����悤�ɐS�|����A�ł���B�]���Ă���͌�����ς���u����ׂ��悤�v�ɂ��Ă���A���R�ɂ����Ȃ�Ƃ������ƁA����������ČŒ�I�łȂ��A�u���ɗՂ݂āA����ׂ��悤�Ɂv����悢�̂ł���B�����Ėʔ������Ƃɑ��ɂƂ��Ắu�@�v���A�������������̂Ȃ̂ł���B�@ �����ߊi�������ā@ ��i���N(���O��N)�A�u���ځv�̔��z�Ɠ����ɔނ͎��̂悤�Ȏ莆��Z�g���T��̒�̏d���ɑ����Ă���B�@ �䎮�ڎ��@ �G���䐬�s(�i��)�̂������A���Ȃ��[(�Ă�)�Ȃ鎖(����|�̑i��)�����A�����͐\�Ƃ����A�カ�͂��Â���T�₤�Ɍ���A�����Ԃ�ɐ��D(��������)(�O�����)������ւǂ��A���̂Â���l�ɂ���������(�����҂̋���㉺��)�y�d�Ȃǂ̏o��(���ł�)��߂ɁA���˂Ď�����������B���̏��ʂ܂��点��B���₤�̎��ɂ́A�ނ˂�(���)�@�߂̕�(���ߊi���Ɋ�Â����Ɩ@)�ɂ��āA���̍�������ׂ��ɂČ�ɁA�(���Ȃ�)�ɂ͂��̓��������U���m�肽����́A��l���l�����ɂЂƂ肾�ɂ����肪������B�܂������Ƃ���A�����܂��ɍ߂ɒ���(���������)�ׂ����l(�ʂ���)�E�铢�[(�Ă�)�̂��Ƃ����ɂ��A�����݊�(���킾)�āT�A�g�������Ȃ��y(�Ƃ�����)���ق��݂̂�����ցB�܂��Ďq�ׂ�m���(�߂̈ӎ��̂Ȃ�)���́T����(����)�������Č��Ƃ��A���ɂ̂��݂�(�ٔ��ɂȂ���)�@�߂ɂЂ�����Ă���́U�A����(������)�ق肽��R�ɓ���āA�m�炸���Ă���������Ƃ��Ɍ�͂B���̌̂ɂ��A�叫�a(����)�̌䎞�A�@�߂����Ƃ߂�(���ߊi���̏Ɋ�Â���)�䐬�s�Ȃnj�͂��B��X���R�̌䎞�������̋V�Ȃ���ւA���܂����̌����܂˂��Ȃ�B�F����Ƃ���A�]�Ҏ�ɒ����������A�q�e�ɍF(����)����A�Ȃ͕v�ɂ������́U�A�l�̐S�̋�(�܂�)�����Ί��āA��(�Ȃ�)�������Ώ܂��āA���̂Â���y�����g�̌v�莖�ɂĂ��ƂĂ��₤�ɍ���(����)����A���ӂɂ͒�(����)�߂ĕ������m��ʈΏ^(���т�)�ǂ����������߂��邱�Ƃ�ȂƁA�A���͂�T��(����)����͂��ƁA��(�́U��)��o����ւA�T��(�����͂炢��)��(�S�Ȃ炸��)����ɂČ�ւǂ��A���˂�(�\��)��߂���͂˂A�l�ɂ������ӂ��Ƃ̏o��(���ł�)�ʂׂ���̂ɁA�����������B�֓���Ɛl�E��쏊�E�n���ɂ͂��܂˂���I(�Ђ낤)���āA���̈�(������)��������ׂ��B��(����)�͏����ʂ��āA��쏊�E�n���ɂ͖ʁX(�߂�߂�)�ɂ���āA���̍����̒n���E��ƈ�l�Ƃ��ɁA���܂߂���ׂ���B����ɂ��ꂽ�鎖��́U�A�ǂ��ċL�����ւ��ׂ�(�lj��@�����z����)�ɂČ�B�@ ���Ȃ������B�@ ��i����������������(�䔻)�@ �x�͎�a�@ �����ǂނƂ܂��Ƃɖʔ����B�܂����ߐ��͌`����`�Ȃ̂ŁA�ٔ��ɍۂ��Ă͕K���u�@�߂ɂЂ�����āv���Ȃ킿���ߊi���̏����p���āA����Ɋ�Â��ׂ����ƂɂȂ��Ă��邪�A���̖@�߂Ȃ���̂́u�(���Ȃ�)(�c��)�v�Œm���Ă�����̂͊F���ɓ������B����ɂ��́u�@�v���u�������S�v�Ƃ��Ȃ�ƁA�u���@�v�͒m�炸�ɓ��R�̂��ƂƂ��āu���@�v�ʂ�ɂ���Ă����̂ɁA�ЂƂ��эٔ��Ƃ��Ȃ�ƁA���ꂪ�u�߁v�ł���Ƃ���Ă��܂��B����ł͂܂�Łu����(������)�v���@���Ă���R�̒��ɂ���ƒm�炸�ɓ����Ă����ė������ނ̂Ɠ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�@ �����ė����ȗ��A���ߊi������ؖ������čٔ������Ă����B�����������̂悤�ȁu���Ёv�����Ȃ��Ȃ�ƁA�ǂ�Ȃɍٔ��ɔO�����Ă��u�l�ɂ��������āv���Ȃ킿�����҂̋��㍂���ɂ���ĕs�����ɂȂ�₷���B�����ŁA�����������邽�߂ɁA�\�߂�����߂��Ƃ����B�Ƃ����Ƃ���͖��b��l�́u���@�v�ɂ�����ł��낤�B�@ �����E�j��̊�Ȏ����@ �������́u���@�v�Ƃ������̂́u�S�̎��@�Ɏ�����ӂ�܂��v�����Ă���A���R�ɂ��ꂪ�A�u���@�v�ɂȂ�悤�ȁu�@�v�ł���˂Ȃ�Ȃ��B����́A���ǁA���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�����̂܂܂Ɂu���@�v�Ƃ����Ƃ������ƂɂȂ�B����A���S�̋K��(������)�ƎЉ�̒����Ǝ��R�̒�������̉�����悤�Ȍ`�ł���˂Ȃ�ʂƂ������ƁB���ꂪ�u�F����Ƃ���A�]�Ҏ�ɒ����������A�q�e�ɍF����A�Ȃ͕v�ɂ������́U�A�l�̐S�̋Ȃ����Ί��āA��(�Ȃ�)�������Ώ܂��āA���̂Â���y�����g�v�ƂȂ�A����u����ׂ��悤�́v���B�������Ƃ������Ƃł��낤�B���ɂƂ��Ắu���@�̎�|�v�Ƃ͂܂肻�ꂾ���ł������B�@ ���̎莆�̏����́u������v�ł���A�u���ځv�̖����́u�N�����v�ɂ����鏐���́u�����畽���b���v�Ȃ̂ł���B���ł����Α�́u�������m���v�ɂ����邪�A�����́u�����v�̒n�ʂ͂�������s���Ⴂ�B���Ƃ����ꂪ�u�����s�v�Ɠ��i�ł������Ƃ��Ă��A�u�m���v������ɖ@�������Č��z����Ƃ����̂́A�����_���猩��A����܂����s�ׂł���B���܂��������s�m��������Ɍ��@�z���āA���̖����Ɂu�����s�m���v�Ə������Ă�����A����ł��u����ȃo�J�Ȃ��Ƃ��ʗp���邩�v�ƌ����ł��낤�B��������́A�����͂���Ȃ��Ƃ͂����܂��B�����u�@�v�����Ɉ����Ă������Ƃ������ق��Č��������͂��͂Ȃ��B����Ƃ��̔��̖�ʂɗ��̂͘Z�g���T��̒�̏d���ł���B�����ő��́A�O�ւ̖�ꃕ����ɁA���̂悤�Ȏ莆���������Ă���B�@ �䐬�s��ׂ����X�̎�����������A�ژ^�ƂȂÂ��ׂ��ɂČ���A�������ɐ�(�܂育��)���[������(���イ��)��(�̂�)�����ւɁA���M�̐l�X��������(�����ɂ�)�����Ɛ\(������)���������Č�ԁA���̖������Ƃ��Ƃ���(�傰��)�₤�Ɋo(���ڂ�)��ɂ��Ď��ڂƂ������ւČ��B���|���䑶�m����ׂ���b(��)�B�@ ���Ă��̎��ڂ������́A�Ȃɂ�{��(���@��̓T��)�Ƃ��Ĕ풍�ڔV�R(���イ���̂�����̂悵)�A�l�����߂�掓�(�ڂ��Ȃ�)(���)��������b(��)�B��(����)�ɂ�����{��(���{��)�ɂ����肽�鎖��͂˂ǂ��A���U�����̂����Ƃ�����L(���邳��)��Җ�B���₤�Ɍ����ɒ�ߌ�͂����āA���͂��Ƃ̗������(�Ȃ�������)�ɂ��đ��l�̂悫��͂��ɂ��A���́A��ً��ӂ肽�鎖���킷�炩���Ă��������Č�(�������݂̌���m��ʊ�ōĂэٔ��Ɏ����o���悤�Ȃ��Ƃ�����)�B�����̂��Ƃ����ւɁA���˂Č䐬�s���[���߂āA�l�̍�����s�_(���)�A�ΐ�(�ւ��)�Ȃ��ْ肹����͂߂ɁA�q�L�^���������Җ�B���̏�(����)�͖@�߂̂�����(���ߊi��)�ɈႷ��Ƃ���ȂǏ��X��ւǂ��A���Ƃ��Η��ߊi���͂܂�(�^��������)������Č̂��߂ɁA�₪��(���Ȃ킿)�����������Ƃ��B���Ȃ��������镨�̂��߂ɂ́A�܂Ȃɂނ��Ќ͐l�͖ڂ���������(�ӖڂɂȂ�)�����Ƃ��ɂČ�ւA���̎��ڂ͑�(����)���Ȃ�����镨�̐��Ԃɂ��ق��Ƃ��A���܂˂��l�ɐS���₷���点�߂ɁA���Ƃ̐l�ւ̌v��Ђ̂��߂���Ɍ�B����ɂ��ċ��s�̌䍹���A���߂̂�������(��������)�����܂�ׂ��ɂ��炸���B�}(���悻)�@�߂̂�����(���ߊi��)�߂ł���(���h)��Ȃ�ǂ��A���Ƃ̂Ȃ�ЁA���Ԃ̖@�A����������U�Ђ��肽�镨�͕S�炪���Ɉꗼ�����肪������b�B��(����)���l���炸�ɁA��(�ɂ͂�)�ɖ@�ӂ����ė������(����)�ɁA�@�߂̋{�l(����̖@������)�S�ɂ܂�����(���ӓI��)�y�d�̕�(��)�ǂ����A�Ђ����ނ���Ȃ�ԁA�����^(����)�ꓯ�Ȃ炸��̂ɁA�l�F���f�Ɖ]�](����ʂ�)�A����ɂ��ĕ��ӂ̔y�����˂Ďv�҂��A�䐬�s���ρX�Ȃ炸��͂߂ɁA���̎��ڂ𒍒u(���イ������)���Җ�B���s�l�X�̒���掓����(���키��)����́U�A�������S����Č�ⓚ����ׂ���B���X�ތ��B�@ ��i���㌎�\���������݁\�@ �x�͎�a�@ ���@�̌`���Ƃ�ʎ��@�@ �܂��Ƃɖʔ����莆�ł���B�ނ́u���ځv���u�ژ^�v�Ɩ��Â��悤�Ƃ����B�ł͓����́u�ژ^�v�Ƃ������t�Ɂu�@�ߏW�v�Ƃ����Ӗ����������̂ł��낤���B���́A�Ȃ��B�u���̖ژ^�v�u�����ژ^�v���A�u�ژ^�v�̈Ӗ��Ɨp�@�͌��݂Ƃ͕ς�Ȃ��B�]���đ��ɂƂ��Ắu���ځv�Ƃ́u�@�K�ژ^�v�Ƃł������ׂ����̂ł������B�ł͂��́u�@�K�ژ^�v�͂����Ȃ�@����̓T���Ɋ�Â��Đ��肳�ꂽ�̂��B��������A�܂����ꂪ���炩�łȂ��Ɣ���Ă��A���̂悤�Ȗ@����̓T���͂Ȃ��Ɣނ͂����B���̂悤�ɖ����������@�҂͂����炭�A�l�ގj��A�ނ����ł��낤�B�����Č����u���U�����̂����Ƃ�����L(���邳��)��Җ�v�ƁB��̂��́u�����v�Ƃ͉��ł��낤���B���͂���ɂ��ĉ����L���Ă��Ȃ����A�ȒP�ɂ����u����ׂ��悤�́v�ł��낤�B�O�̎莆�ƑΔ䂵�A���܂ŋL�������b�\���I�����v�z��T���čs���A����ȊO�ɂ͍l�����܂��B������ꂪ���@��̓T���Ȃ̂ł���B�@ �ނ͗��ߊi��������߂đ̌n�I�ŗ��h�Ȃ��Ƃ͔F�߂Ă���B����������́u�����v�ŏ�����Ă���悤�Ȃ��̂Łu���ȁv�����킩��Ȃ���ʐl�ɂ͂킩��Ȃ��Ƃ����B�����ł��́u���ځv�́A�u���ȁv�����m��Ȃ������̐l���u�S���₷���点�߁v�ɐ��肵�����̂ł���Ƃ����B�������͔�g�ł����āu���ځv���܂����ۂɂ́u�����v�ŏ�����Ă���B���������ߊi����m��҂́A�u��l���l�����ɂЂƂ肾�ɂ����肪�����v�܂��u�S�炪���Ɉꗼ�����肪�����v�Ƃ�����Ԃ́A���̖@����m��҂��F���ɓ������������Ƃ������Ă���B����͎����ł��낤�B���͂��̌�̑O�́u���Ƃ̂Ȃ�ЁA���Ԃ̖@�v�Ƃ������t�ł���B����͊m���ɁA���ߊi���Ƃ͕ʂ́u���Ɩ@�Ɩ��Ԃ̊��K�@�v������Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�u���ƁE�������킸�����m��Ȃ��̂���ʓI�ł���v�Ƃ����Ӗ��ł��낤�B�ł͂��̕��ƁE���������S�Ɂu���@�v���Ƃ����ƌ����Ă����ł͂Ȃ��A���́u�@�̌`�����Ƃ�ʎ��@�v������A�Љ�͗��ߊi���ɂ�炸����ɂ���Ē�����ۂ��ė������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B���̈Ӗ��ł́u���Ɩ@�Ɩ��Ԃ̊��K�@�v�̑��݂����O�Ɏ咣���Ă���ƌ��Ă悢�ł��낤�B�@ �ȒP�ɂ������ꂪ���R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�ł���A���̂��ߋt�ɗ��߂��Z�����Ȃ������Ƃ�������B�����Đl�тƂ́A�s�\���Ȃ��炻�̒����̒��ɐ����Ă���A����R�Ƃ��Ă���̂ɉ��������Ė@��ɏo��u��ɖ@�ӂ����ė������(����)�v�ƂȂ�A�u�l�F���f�Ɖ]�]�v�Ƃ�����ԂɂȂ�B�����đ����A���̏�ԂɏI�~�������Ƃ��Ƃ������Ƃł���B�������͌����āA�u���ڐ�A��������u�֓��䐬�s���ځv�����{���ɂ�����B���̖@�ł���v�Ɛ錾�����킯�ł͂Ȃ��B�ނ͂����܂ł����̎��_�ɂ����āu������̂͂���v�Ƃ���ԓx�������Ă���B����Ώo�������������R�I���������̂܂܍m�肵�Ă���킯�ŁA���������̂܂ܕ������Ă悢�悤�ɁA�u���߁E���ځv���܂��������Ă��Ĉ���ɂ��܂�Ȃ������B�ނ́u���ځv�ւ�掓���V���������ۂ������A�Ƃ����āu���߁v��掓�������悤�Ƃ͂��Ȃ������B�������߂͌��ǁA�u�V�c�ƂƂ��̎��Ӂv�́u�Ɩ@�v�̂悤�ɂȂ��Ă����A�u���ƍ����̋���@�̃��@�`�J���v�̂悤�ɁA�₪�āA�������������ʖ@�̈���ɂȂ��čs���̂ł���B�@ �����b�Ɨ�ؐ��O���Ȃ����́@ �u���b��l�`�L�v�͖����ɏ�����Ă��܂����{�����A����܂ł͂����炭�ł��L���ǂ܂ꂽ�{�̈�ł���B�����Ƃ��łɋN���ꂽ�͓̂��쏉��(�����ܔN�E��Z�Z�ܔN)�����A����܂ł��M�ʂɂ���ĎO�S�܁A�Z�\�N�A�ǂ݂���Ă����B�@ �u����ׂ��悤�́v�͂ނ���m���ւ̌P���ł��낤���A���ꂪ�u�l�͈���(����)�ւ��₤�͂Ƃ��ӎ���������(���ׂ�)��A�鉤�͒鉤�̉L�l(����ׂ��悤)�A�b���͐b�̂���ւ��₤�c�c���̂���ւ��₤�ɂ��ނ���ւɈ��������v�Ɨ��������Ƃ���͐����̈�ʗϗ��ɂȂ�B����ɂ���Ɂu��Ɉ�̖�������A��͌㐶��(������)���Ƃ͐\�����A�����ɗL��ׂ��l�ɂėL���Ɛ\���Ȃ�v�������ƁA��ʐl�͂�����u�㐶������ĂЂ�����O���������Ă��Ă����Ӗ��ŁA����Ȃ��Ƃ�����������̐��̔C��������ׂ��悤�ɉʂ�����ł悢�v�Ƃ����l�����ɂȂ�B����͐����̔C������S�s���ɍs�Ȃ��Ώ@���I�~�ςɒʂ���Ƃ����Ӗ��ɂȂ��Ă���B���̍l�����͑O�Ɂu�ἘׂN�w�v�ŋL������ؐ��O�́u�l�����p�v�̍l�����̑c�^�Ƃ������Ƃ��ł���B��������V����͎��Ɂu��ؐ��O�͑T�@�Ƃ�������ǁA�ނ��떾�b��l�̌n�����Ђ��ƍl���������悢�̂ł͂Ȃ��̂��v�Ƃ���ꂽ���A�m���ɗ��҂̎v�z�ɂ͊֘A������Ǝv����B���������̂��Ƃ𐳎O�̒��삩������邱�Ƃ͂ނ��������B�@ �������̂ق��ɂ����ґ��Ή����Ă���l�����͑����B���Ƃ��Α��E����͂����܂ł��Ȃ��O���̐����E�V�̋��������ׂĔ@���̒�b��蔭�������́A�Ƃ����l�����͐��O�́u���j�e�]���n�A�V�q�m�����A�E�q�m�����A�̃V�V���j�����Z�V�O���m���G���A�������A��c��A���V���֎��i�V�c�c�v�Ƃ����l�����ɒʂ���ł��낤�B�����������ł�����I�ȉe���͎��R�I���������ׂĂ̊�{�ł���A���I�K��(������)���Љ��������Ɋ�Â��˂Ȃ�ʂƂ��閾�b�\���I�ȍl�����ł���B���̍l�����͏��X�ɓ��{�l�ɐZ�����A�L���V�^�����ォ�瓿�쎞��ɂ����Ă��ꂪ���{�l�ɂƂ��ē��R�̍l�����ƂȂ����B����������A���ߊi���̑��݂͔O���ɂȂ��B�����Ă��ꂪ����ΓI�Ƃ�������v�z�ɂȂ��Ă������Ƃ��A���{�l���g�����o���Ȃ��܂łɂȂ��Ă����B�@ �����āA����͊O���̎v�z�ƏՓ˂����Ƃ��ɁA���m�Ɏ���̂����ɍĔc�������Ƃ������ʂɂȂ��Ă���B���ꂪ�ł����m�ɏo�Ă���̂��L���V�^�����甽�L���V�^���ɓ]�����s���փn�r�����ł��낤�B�]������O�ɂ́A���̎��R�I��������Ƃ��āu����ׂ��悤�v�ȎЉ���`������ɂ̓L���V�^�����ł��悢���@����Ă���Ɣނ͍l���A���̂悤�Ɍ����B�@ �u(�L���V�^����)���������A�㐶�P���m�������Z�V�����׃j�O���ʂփ��@�i���o�A�O�j�n�P�j���~�A�������X�m�������փe�A���~�������A�A���E�L���X�N�C�A�L�n�}����(������)���}�P�A���j�n���A�V���m�ו��A�N�b�m�������C�m�b�e�A�F������j�V�A���L���h�C�A�˃V�L�����~�A���m���Ӄe�������烊�A�s(����)�e�����m���(�����炢)���o�j��C(���u���O�c)���̃����������J�����W�c�c�v�@ ���X�B����͑��I�ȁu����ׂ��悤�́v�ł���A�n�r�����̓L���V�^����������������Ă����ƐM�����B�@ �����ē]����́A�L���V�^���������̎��R�I�����̊�{��j����̂ƍl����B���ꂪ�`�������́u����ⓚ�v�Ɣr�돑�́u�j��F�q�v�ɕ\���Ă���B���̓��ʓǂ���ƁA�u�]�v�悤�Ɍ����āA���́A���R�I������Ƃ����_�ł͈�т��Ă���B���ꂪ���b��l���c�����ő�̈�Y�ł������낤�B�@ ���̂悤�Ȗ��b�̋������A���ɐ��܂��߂Ɏ��s�����ŏ��̑��l���A���Ȃ̂ł���B�����Ă���͊m���ɁA���{�̐i�H�����肵�ďd�v�Ȉꕪ��_�ł������B�@ �������̂Ƃ��A���b��l�łȂ��A�ʂ̂��ꂩ�ɑ����S�����A�u���{�͂����܂œV�c���S�̗��ߍ��ƂƂ��ė��ĂȂ����˂Ȃ�ʁv�ƐM���Ă��̒ʂ���s������ǂ��Ȃ����ł��낤�B�܂��A�u���{�͒�����͔͂Ƃ��Ă��̒ʂ�ɂ��ׂ��ł���v�Ƃ����҂����āA������������s������ǂ��Ȃ��Ă����ł��낤�B���{�͗������̊؍��̂悤�ȑ̐��ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B |
|
|
���ے��V�c���̑n�o�Ƃ��̐���@ ���V�c�����߂��I�����@ ���S�ɐV���������@�𐧒肷��A����͊��q���{�ɂƂ��Ă͂��߂Ă̌o���Ȃ�A���{�l�ɂƂ��Ă��͂��߂Ă̌o���ł������B�@ ���߂▾�����@�A�܂��V���@�̂悤�Ȍp��@�́u���̂܂˖@�v�ł��邩��A�ɒ[�ɂ����u�|��E�|�āv����悢�킯�ŁA����n�������v�l�\�͂��K�v�Ƃ����A�����ɂ����u���S�ɐV�����v�Ƃ͂����Ȃ��B����Ɍp��@�͂��̖@�̔w��ɂǂ̂悤�Ȏv�z�E�@���E�`���E�Љ�\�������邩�����ɂ��Ȃ��̂ł���B����ꂪ�V���@�̔w��ɂ���@���v�z����Ƃ����u���@��v�Ƃ����Ă���悤�ɁA�u���߁v���܂��A���̖@�̔w��ɂ��钆���v�z����Ƃ���������Ή����Ă����B����͌p��@�T���͌p��@�I�̐��̏h���ł��낤�B�@ �v�z�E�@���E�Љ�\�����Ⴆ�A�A�����ꂽ���x�́A���̗A�o���ƑS��������`�ŋ@�\���Ă��܂��B�V���@�ɂ����ꂪ���邪�A���߂ɂ����ꂪ�������B�@ �����ł́u�V�v�Ɓu�c��v�̊Ԃ����}��I�ɂȂ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�v����}��Ƃ��ĂȂ����Ă���B��Ȃ͍̂ŏI�I�ɂ͓V�ł����čc��ł͂Ȃ��B�Ƃ��낪���{�ł͂��̓����Ȍ`�ŘA�����Ă���B��������̂܂܂ɂ��Ē����̉e�������|�I�Ɏ��Ƃ������Ƃ́A���{�̗��j�ɂ����̓��ꐫ���`�������ł��낤�B���̌���ꂪ�܂��ɑ��ł���B�@ ����u�V�v�����R�I����(�i�`��������I�[�_�[)�̏ے��ł͂Ȃ��A�V�c����{�I���R�I�����̏ے��ɂ��Ă��܂����̂ł���B����́u�I�����v�����u�V�����v�ŁA��d�̉_�̏�ɂ����āA��́u�l�ԓI�ӎu�Ɛl�דI�s�ׁv�������I�ɋ֎~���Ă��܂����B�ȒP�ɂ����u�V�ӂ͎����I�ɐl�S�ɕ\����v�Ƃ����Ўq�̍l�����́u�V�c�̈ӎu�͎����I�ɐl�S�ɕ\����v�ƂȂ邩��A�V�c�l�͈ӎu�������Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B����͂܂��ɏے��V�c���ł����āA���̑��I�`���͍����Â��Ă���A���ꂪ�V�c���̏d�v�ȋ@�\�ł��邱�Ƃ́A�w�u����w�̓��{�w�҃x���E�A�~�E�V���j�C���u�V�c�É��̌o�ϊw�v�̒��ł��w�E���Ă���B�@ �����Ƃ�������w�E���Ă���͎̂������ł͂Ȃ��B�퍑�����ɓ��{��K�ꂽ�L���V�^���̐鋳�t�͕����喼��Ɨ����ƌ��Ȃ��Ă����B�@���I�Ȗʂ��炢�����̌����͐������A�e���������F�l�`�A��~���m��t�B�����c�F�̂悤�ȓƗ������ƌ��ē��R�ł���B�����������喼�͎������Ɨ������Ƃ����ӎ��͂Ȃ��A��͂�V�c����{�̓����̏ے��ƌ��đ������Ă������Ƃ́A�����̐l���w�E���Ă���B���͂���Η��@���E�s�����E�i�@���������Ȃ��Ă������̏ے��Ƃ͌��Ă����킯�ł���B���̏�Ԃ����o�������̂����ł���A���ꂪ���{�̓`���ƂȂ����B�@ ���̑����g�͑�ςȁu�V�c�����Ɓv�ł������Ǝv����B�O��c�𓇗����ɂ��悤�ƁA�����V�c��ވʂ����悤�ƁA�����ƂȂ̂ł���B����ł��āA�ۂ���Ȃ邪�̂ɁA�u��i���ځv�͂�����_�Ŋ��S�ɓV�c�����Ă���A�V�c�̍ى��o���A�V�c�̃T�C�������Ȃ��B���̓_�ł́u�䖼�䎣�v�����Ă���V���@���O�ꂵ�Ă���B����ɂ��̖����̋N������ǂނƁA�V�c�ɑ��Ă��̖@�̏����Ƃ��������t���S���Ȃ��B�N���̑Ώۂ́u���V�E��߁E�l��V���A�y���ē��{�����Z�\�]�B�̑召�_�_�A�ʂ��Ĉɓ��E⦍�(�͂���)���������A�O���喾�_�E�������F�E�V���厩�ݓV�_�̕����ő��v�ł���B����Ζ@�̐���ȂǂƂ����s�ׂ́A���ړI�ɂ������I�ɂ��A�V�c�Ƃ͖��W�ł������B�Ȃ������Ȃ����̂��B�@ �V�ӂ��l�S�ɂ��̂܂ܕ\����悤�ɁA�V�c�̈ӎu�����̂܂ܐl�S�ɕ\����Ȃ�A�u���ځv���z�̂Ƃ��ɂ��̏����Ƃ��āu�@��v��������Ă����������Ȃ��͂��ł���B�m���ɂ���́u���Ɩ@�v�����畐�Ƃ����肷��̂����R�Ƃ������悤���A���Ƃ͔@�W�c�łȂ��A����܂ł����͂����Αt�����ĉ@����o���Ă�����Ă���B����ɁA�㍂�q�@����x�͓V�c����������ۂ���͂��͂Ȃ��B�������ꂪ�ł��Ȃ������B���R�́A���߂ɂ͊��K����̏W�ς͖@�Ƃ͂��Ȃ��Ƃ�������������������ł���B�p��@�͂��������Ȃ�B�@ ���܂̓��{�Ŏ��q���������̔��Z�p�[�Z���g�̎x���������Ă��A�܂����ꂪ���݂��������Ă��Ă��A���@�ɂ͂���Ɋւ��������������Ȃ��̂Ǝ������ۂł��낤�B�����悤�ɓ����̎Љ�ł͂��łɌ����̎Љ�I���K�Ɛ�Ⴊ�@�ƂȂ��Ă���B�����������@�Ƃ��ĔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��������͌��ǁA�V�c�Ƃ��ǂ����߂��I��������錋�ʂƂȂ����B���̂��Ƃ͂������A���ڂ����߂�S�R�Q�l�ɂ��Ȃ������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�@�ɑ���l�����̊�{���S������Ă����Ƃ������Ƃł���B�@ ���n���ȁu������(�X�e�C�c�}��)�v�̋Ɛс@ ���͊m���ɓ��{�j�ɂ�����ł������[���l���ł���A�܂��~�����v�����]���ꂽ�悤�Ɂu���{�ōŏ��̐�����(�X�e�C�c�}��)�v�ł���A������Ӗ��ŏd�v�Ȑl���ł���B�@ ��(����)�Əf���̎��[(�A��)�A���̓�l�̐M���W�͂܂��ɐ�ΓI�ł������B�������N�̉Ăɑ������a�����Ƃ��A���[�͎������ł��������A��������߂Ȃ������B���͂��s�v�c�����Ȋ������Ɣނ́A��������������Ď�������ł�����̂����̂��������B�������瓞�ꂱ��Ȃ��Ƃ͂���Ă���Ȃ����낤�A���ꂪ�����Ō�̎������Ǝv������A�����ɍs������������ł���̂��A�Ƃ������Ƃ����B�@ �����E���́A�A���E���[���悫���k����Ƃ��āA�]��O�Ƃ̍��c���Ő������s�Ȃ����B�������A���c�������ł͔\���I�Ȑ����͍s�����Ȃ��̂ŁA����Ȃ�̂������肵�������g�D���K�v�ł��邵�A�V�c�_�Ƃ������肵�������V�X�e�����K�v�ł���B�@ ���́A�܂����{�̈ړ]���s�Ȃ��l�S�̈�V���s�Ȃ����B�������q�̒��ł͂��邪�A�呠����F�s�{�҂ɖ������ړ]�����̂ł���B���q�̎��㔼�N�̂��Ƃł���B�����ĊԔ�����ꂸ�A���R�\��҂̎O�Ђ̌����Ə��R�A�C�ł���B1219�N(���v1)���R���������ÎE����Č�A����b��Ƃ̎q�̎O�Ђ��A�������̉����ɂ�����Ƃ������R�ŁA���R�Ƃ��Ċ��q�Ɍ}����ꂽ�B�O�Ђ͓���2�ł���A�����̓R�E�k�𐭎q���������s�������A���q�̎��ɂ���āA����������O�Ђ����R�ɂ��Đ����̈����}��K�v���������̂ł���B1225�N�̕����������������A�悤�₭�O�Ђ͌������A���o�Ɖ��������B�N��8�ł���B�����ɒ���ɐ\�����ė��N��2���ɗ��o�͐��Α叫�R�ɔC����ꂽ�B�@ �����ł͂��߂āA�V�c�����R�������E�A�����]��O�Ƃ������`�������m�����A�㒹�H��c�Ƃ̔��ڈȗ��Â��Ă����ϑ��I��Ԃ͏I��A�̐��̖@�I�����͊��������B�@ ���͔h��h�肵�����Ȃ�����A�`���}���E���q�A�ҁE�ɉꎁ�̉A�d�̐����Ə����E���q�̎��E���{�̈ړ]�E�O�Ђ̌����Ə��R�C���E�V�̐��̐����������ׂ������Ői��ōs�������Ƃɐl�͈ĊO�C�Â��Ȃ��B���܂��܂ȈӖ��ł��̌��ʂ��A�v��A���u�͓I�m�ł������B�@ ����ɂ���Ė��{�͊����N�ɂ͂��܂��Q�[�ɔ����邱�Ƃ��ł����Ƃ����悤�B�����Ă��̋Q�[�̑̌��́u��i���ځv�ɐ��X�������f���Ă���B�����됶�Y�����Ⴂ����ł���B�C��s���͂����_�앨������B���̔N�͉A��̘Z������ɐႪ�~�����B���ł����Ύ������{���牺�{�A�ł������Ƃ��ł���B�Ƃ��낪�����ɂ��㌎�ɂ���J�Ŕ_�앨�͎͌����A�C�����}�ቺ���ē~�̂悤�ɂȂ����B���q�ł��\���̂��ߐl�Ƃ̔j��������������10������11���ɂȂ�ƍ��x�͒g�~�ٕςŁA���s�ł�11������12���ɍ����炫�A�䂪���Ƃ�����ԂɂȂ����B�@ ���헐���Q�[�������@ �̂�����{�l���ꂵ�߂��̂͐헐���ނ���Q�[�ł������Ǝv����B�@ ���̎��R�I����(�i�`�������E�I�[�_�[)�������Ă���ƁA����u�V�ϒn�فv���N��ƁA�@���Ƃ����������킯�ł���B����͖��{�Ƃ����ǂ����Ƃ��v�������Ȃ��B�@ �����Ȃ�Ɓu�V�ϒn�فv���Ȃ킿���R�I�����ُ̈팻�ۂɂ́A�l�Ԃ́A�I�ɂ���ɑΉ�����ȊO�ɕ��@���Ȃ����ƂɂȂ�B�����Ȃ�u���v���u�V�v�ɏ��ĂʂȂ�A�V�ϒn�ق��N������@�����ς��A�����K�͂��ς��Ă���ɑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��q����悤�Ɂu���ځv�ł͋Q�[�̎��̐l�g�����������Ă���B�@ �����̎��f�Ɩ��b�̖��~�@ ���������������P�����B�@ �܂��ނ́A�Q�[���A�Q�[���Ƃ����Ă��A�Ă��A���鏊�ɂ͂��邱�Ƃ͒m���Ă����B�܂��ނ͋��s�E���q���͂��߂Ƃ���S���̕x�҂���A�����ۏؐl�ƂȂ��ĕĂ���A������S�E���E���̉쎀���������Ă���l�ɑ݂��^�����B�ނ́A���N���N��ɂ��ǂ�Ό��������Ԕ[����A�����͎��������S���悤�Ƃ����Ă��̎ؗp���苖�ɒu�����B�@ ���������͌��ǎ��͂̂Ȃ��҂ɂ͕ԍς�Ə����A����͂��ׂĎ����ŕ��S�����̂ŁA��ςȕn�R�������B�@ �����뗘�q���S���ƕԍς̌�����肪��i���N�܂łɋ��ɂȂ�A���̂��������̗̒n�̔N�v��Ə�������������I�ɂ͑�ςł���B�@ �u�a�ɂ��炸�Ƃ����ǂ���������v�@ �����Ƃ����̌���̘b�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B�ނ͏�Ɏ��f�ŏ��炸�A�ق̑���Ȃǂ��w�NjC�ɂ����Ȃ������B�@ ����ɖ��~�Ȏ҂�������ƂƂ��ɁA��דI�ɉ����悤�Ƃ���ҁA����u�@�q�̎ҁv���������B�@ �ٔ��ɂȂ����ꍇ�ł��A�s�i�����҂������Ɏ����̔��F�߂�A���͌����Ă���ȏ�Njy���Ȃ������B�@ �����̒n���Ɨ̉Ƃ����_�����Ƃ��̉Ƃ̌����������n���������Ɂu�s���܂����v�Ƃ������B���͂��̗������Ɋ��S���āA����̐��������ق߂��Ƃ����b���u���ΏW�v�ɂ���B������̋t�̏ꍇ�A���Ȃ킿�ٔ��ɕs���Ȃ��̂����͂Œ�R����Ƌ������Ă��A�ނ͏����������Ȃ������B�k�����͐�ΓI���ЂłȂ����A����͕��͂������Ă��邩�炻�̂悤�Ȓ�R���N���ĕs�v�c�ł͂Ȃ��B���������ꍇ�̑��͎��ɋB�R�Ƃ��Ă����B����Ή�������āu���v���Ȃ���A���ꂪ�t�ɁA���ЂȂ������̔j�łɂȂ邱�Ƃ�m���Ă����̂ł���B����Δނ̈ꐶ�́A�u���������̐����Ƃ���v���т��ʂ��A���́u�����𐄂����Ɓv���т��ʂ����Ƃ��������ЂƂ��Ă����킯�ł���B���ꂪ�u���{�ŏ��̐�����(�X�e�C�c�}��)�v�Ƃ����闝�R�ł��낤�B |
|
|
�����b1(�݂傤��)�@ ����3�N-����4�N(1173-1232)�@ �a�̎R�L�c�o�g�B��s�Z�@�̉،��@(��{�R�͓��厛)�̊w�m�B�(���݂ȁA�v��̑��薼)�͍��فB���q�����̓���������@�R�A�e�a�A���@�ƈ���ĐV�@�h���J�������c�ł͂Ȃ��̂ŁA����ł͒m���x���Ⴂ����ǁA�����͋������E���̍ł��e���͂̑傫�Ȑl����1�l�������B���͕��d���A������Əo�g�B�@ 1180�N�A7�̎��ɕꂪ�a�v�A�������N��ɋ������������R�Ɛ킢�����Ŕs�����Ă��܂��B���N�A���e�����������b�́A�S���ꂪ���O�ɔނ����s�����E�_�쎛�̖�t���Ɏd����m�ɂ��������Ă������Ƃ���A�����̏f���𗊂��ĕ����@���A���m���o(����)�̒�q�ƂȂ�B�@ �� ���b�͕ꂪ���̖�t���ɋF�肵�Ď��������q�ǂ��������B�@ �M�S�ɉ،��@���w�сA16�̎��ɓ��厛�ɂ���Ӑ^����������d�@�Ō����ɏo�ƁB����܂ňȏ�ɗ͂����ďC�s���邪�A���s��ޗǂ̑m�������o�����[�X�ɖ������Ă���p�����Ĉ�a���������A1196�N(23��)�A�̋��I�B�ɖ߂�ƎR���ɏ����Ȉ������Ă����ɘU���ďC�s�𑱂����B�@ ���̎��̕��������߂�Ƃ��閾�b�̌��ӂ͑����Ȃ��̂ŁA�w���ŗL���ɂȂ�����ɂȂ���������������߂�ׂɁA�����ĐF�~�̔ϔY�ȂǑS�Ă̑��O����苎��ׂɁA���ɓ����Ă����E����藎�Ƃ��Ă���B�ނ́u����ł�����������l�O�ɏo�Ȃ��Ȃ�B�l�ڂ��͂���A�o�����悤�Ɩz�����邱�Ƃ��Ȃ��B���͐S���ア�̂ŁA�����ł����Ȃ���Γ�������Ă��܂��v�ƌ��A�����āu�ڂ�ׂ��Ƃ��o���ǂ߂Ȃ��Ȃ�B�@���Ȃ��ƕ@���������Ă��o�������B����ƈ��ׂȂ��B���͌��h���������Ȃ邾�����v�Ǝ���I���R�������Ă���B�Ȍ�A���b�͎��g�̎����u����@�t�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�@ ���S�b�z�͎��������u�{���Y(�V��)�Ƃ��Ă̎��摜�v��`���Ă���B���b�̉e���A�Ƃ����͍̂l���߂����낤���A�����Łg�V��h��m���Ă���ȏ�A�\�����S���[���Ƃ������Ȃ��B�@ 1199�N(26��)�A�_�쎛�ɋA�邪�A�t�̕��o���㒹�H��c�ւ̖d���̌��^�ŗ��Y�ƂȂ莀���A�_�쎛�͍r�p�����b�͊e�n�𗬓]����B����ɂ�����S�����̌��_�ƂȂ�߉ނ̈�Ղ����q�������Ƃ̎v�������߁A30�A32�̎���2�x�ɂ킽���ăC���h�n�q���v�悵���B�O���@�t�̗��s�L�Ȃǂ��n�ǂ��Ē�������̓����\����藷�x�x���������A�a�ɕ���������̖͂Ҕ���_���ׂ̈ɓڍ��B���ہA�嗤�̎����̓`���M�X�n���̐��͊g��Ƌ��Ɉ������Ă��藷���o����ł͂Ȃ������Ƃ����B�@ 1206�N(33��)�A�㒹�H��c���狞�s�x�O�̒̔�(�Ƃ��̂�)��^�����A�،��@�̏C�s����Ƃ��č��R�����ċ�����B���b�͍��T������Ȃ������A�������̐H�������Ԃ�̉��ɓ���ė��R�ɍs���A�u��ڈȏ゠��ŁA�������������Ƃ̂Ȃ��͂Ȃ��v�Ƃ����قǁA������킸�̏�A�̉��Ȃǂō��T���d�˂��B�@ ���b�͏�Ɏ߉ނ�[���炢�A����Ă����B�S�̒��S�ɂ����͎̂߉ނ��B�ނ͎߉ނ��h�炷�邠�܂�A���ɓ`���Ă���r���Ŏ��_�����Ƃ����B�����Ď߉ނ̌��t�𗝉�����ׂɂ��A�w��A�����A�s���d�����Ă������b�́A1212�N(39��)�A�O��(�얳����ɕ�)����������Έ���ɂ̑厜�߂ŋɊy�����ł���Ƃ����@�R�E�e�a�̏�y���֔����������A�u���ח�(����������)�v���āA��N�s���җ�ɍR�c����(���Ȃ݂ɐe�a�Ƃ͔N������)�B�@ 1215�N(42��)�A�ՍϏ@�J�c�̉h���T�t���v����B���b��30������h���ƌ𗬂�����A���b�̐������ɍ��ꍞ�h���́u�@�h�̌�p�҂ɂȂ��ė~�����v�Ɗ�������A���b�̓K������Ȃ��Ƃ�����Ŏ��B�h���́u���߂Ă��ꂾ���ł��v�ƁA�����̑�Ȗ@�߂b�ɑ������B�h���͒�q�B�Ɂu������Ȃ����Ƃ�����Ζ��b��l�ɕ����v�ƌ����c�����Ƃ���(�������M���Ԃ肾)�B�@ �h���͂܂��A�v���玝���A��������b�ɓn�����B���b�͍��R���ɒ���������č͔|���A�D�ꂽ���\��m��ƉF���ɍL�߁A��������É���e�n�ɒ����`������B���R���̂���̔��͒��̔��˒n�Ƃ��Ċ��q����ɂ͓��{�ő�̎Y�n�ƂȂ�A���N�V�c�ɂ����コ�ꂽ�B�@ 1221�N(48��)�A���v�̗��Ŗ��{�R�ɒǂ��č��R���̋����ɉB��Ă�����c���̗����҂������܂��A���b�͂��̍߂ŘZ�g��(�����@��)�̖k����̉��ɘA�s�����B���ɐ^�ӂ��������ꂽ���b�͂���������u���͐e�F�ɋF�����˗�����Ă������Ȃ��B�Ȃ����B�S�Ă̐l�X�̋ꂵ�݂��~�������d�v�ł���A����̐l�ׂ̈ɋF���Ȃǂ��Ȃ��̂��B���̐�ł��A�ǂ��炩����̖������������͂Ȃ��B���R���͎E���֒f�̒n�ł���B��ɒǂ�ꂽ���A�t���瓦���Ă����b�́A�F�����ɉB��Ė����q���ł���B�܂��Ă�l����̋��ԂɉB��Ă���̂��A�����߂ɒǂ��o���悤���B�ނ��둳�̒��ł��U���̉��ł��B���Ă����������A���͍��������������肾�B�������A���̓��R�̂��Ƃ�������ʂ̂Ȃ�A�����ɂ��̋�m�̎���͂˂���v�B���̋B�R�Ƃ����ԓx�A�����ȓ��ɑ��͋���ł���A������ӂ�ƋA��̋��Ԃ�p�ӂ��Ď��ɓ͂����B���̌�A���͖��b���t�Ƌ��A�����𐿂����߂ɂ������R���ɑ����^�B����2�N��A���b�͕v���Ŏ������Ȃ����ׂ̈ɓ�(�P����)���J�����B�@ 1231�N(59��)�A���b�͋I�B�Ŗ@�v���s�Ȃ��A�A���ė�����ɔ�ꂪ�o�ď��ɕ������B�����ė��N1���A���b�́u�����ՏI���ׂ��v�ƍ����āA��q�����Ɂu������~���ɖ���ʂ悤�Ɂv�Ɖ��߁A���炭���T��������A�u���������悤���B�E�e�����ɐg���������悤�v�Ɖ��ɂȂ�A�@�؈�ɂ���������ɒu���A�E����^�������L���A���G�������Ȃ��ďd�˂��B�Ŋ��͊�Ɋ��삪�����A���炩�ȑ剝���������Ƃ����B���b�͑T���@�̌���ɁA��q�ɂ���Ē��d�ɖ������ꂽ�B���݁A�_�O�ɂ͖��N11��8���ɒ��Ǝ҂��K��A���̔N�̐V���������錣�������s���Ă���B�@ �h�_������A���������A�Ђ�����߉ނ�炢�A�S�Â��ɏC�s�����������m�E���b�B�]������V�����̗lj��́A�@�h���قȂ�ɂ�������炸�u���̐��́A���b��l�̂悤�Ȑl�������l�ƌ����̂��v�Ə̂����Ƃ����B�@ �����̉̐l�E���b�@ ���b���܂�10�㔼�̍��A���Q�̐l�̐��s�@�t�����x���_�쎛��K��Ă���A���b�͉̓��̎w�������Ƃ����B���b�͈�Ӓ����O�ō��T��g�ނ��Ƃ������������Ƃ���A�u���̉̐l�v�ƌĂ��قnj��̉̂��ʂɉr�B���̉̍˂͒���W��27����I��Ă���قǗD��Ă���B�@ �u�R���� �H�̋� �Q���߂��� ���Ƌ��ɂ� �Ȃ���������v�@ (�R���̏H�̒��Ă��B����ʎ��͒��Ƌ��ɋ�������������)�@ �u�G���Ȃ� ���߂�S�� �P���@�䂪���Ƃ� ���v�ӂ�ށv�@ (���X�܂Ő��ݐ������̐S�̖��邢�P�����A���͎����̌��Ǝv���̂ł͂Ȃ���)�@ �u�̌��� ���͖�� ���Ƃ����� ���̌��� ���݂Ă�������v�@ (�̖K�ꂽ�p���̑��铹�B���͌��̌��ݓ����čs��)�@ �u���������� �������������� ���������� �������������� ���������⌎�v�@ (���邢�I����߂��邺�A�������܃b�I)�@ �u�_���o�ł� ��ɂƂ��Ȃ� �~�̌� ����g�ɂ��� ���₽���v�@ (�_����o�Ď��ɓ��s����~�̌���A�����g�ɟ��ނ��낤�A�Ⴊ�₽�����낤)�@ �� ��[�N���̓m�[�x�����w��܂̋L�O�u���u���������{�̎��v�̖`���ł��̖��̂��Љ���B�@ �����R���@ �����̐ΐ��@�͐�������蔲�������q���̌����ō���B�u���b��l���T���v�̂ق��A�L���ȁu���b�l���Y��v(����̌��_�I)�����̏����ŁA����܂����B���b�͗c�����Ď��ɕʂꂽ���e���悭�������݁A��̈�i�̔����������A��ɔ��g���������ɓ���Ă����B�܂����ŏC�s�ɏo�����鎞�͂����e�����o�ꂷ�邱�Ƃ���A�e��������x�ɕ���̐��܂�ς��ł͂Ȃ����Ǝv�����炵���A���b�ɋA�˂��������t�E�^�c�������Ă��ꂽ�ؒ��̎e�����A��Ɋ��̑��ɒu���đ�ɉ������Ă����Ƃ����B�����̋���e�����͌��݂����R���ɕۊǂ���Ă���B�@ �� ���ƈ�傪�䂪���̏t��搉̂��Ă������A���b�͌����@(�����̖��A�����̐���)�Ɏ���𗊂܂ꂽ�B�Ƃ��낪�A�����@�͍����̌��(�݂�)����肾�����o���Ă���A���b�͐Â��ɂ����������B�u���͒Ⴂ�g���ł����߉ނ̒�q�ƂȂ��ċv�����A�����ɏ�炸�������Ύt��Ƃ��ɍ߂ɗ�����ƌo�ɂ���܂��B�ǂ������ȊO�̖@�t��������������������v�B�т����肵�������@�͌�������яo�Ĕނ������ɍ��点�A���̌�͐[���A�˂���悤�ɂȂ����Ƃ����B�@ �� ���b��19����58�܂ł�40�N�ԁA����̖���Ԃ����B����͐��E�ŗB��̖��̓��L�A�u���L(��߂̂�)�v�Ƃ��Ēm���Ă���B�@ �� ���v�̗��̍ہA���b�͑��ւ̐��@�ŋ����ꂽ���A�㒹�H�@�͉B��ɗ�����A���̒n�Ŏ������Ă���B�@ �� ���R���͐^���@�Ɖ،��@�̎��ł��������A�]�ˎ���ɐ^���@�݂̂ɓ]�����B�@ �� �C���h���s���{�c�ɂȂ����߂��݂��Ԃ߂�悤�ɁA���b�͎����ӂ̎R�Ɏ߉ނƉ��̂���C���h�̎R�̖���t���Ă���B�@ �� ���R���ɂ͕�����́u���b�l���Y��v���W������Ă���B�I���W�i���͋��s���������قɗa�����Ă�����Ă���B�@ �� ���o(������������)�͗����ɋ����𑣂������m�B���̋w�Ƃ�������l���ɒ�q���肵���킯�����A���b����N�����m�����̂��͕s���B�_�쎛�ɓ`������������͕̂��o�q���肾�낤�B�@ �� �߉ނ͈���ɂɂ��Č���Ă��Ȃ��ȏ�A����ɂ��߉ނԖ��b�̋C���͗����ł���B�܂��A�@���̉��l���l�̋ꂵ�݂���菜�����Ƃɂ���Ȃ�A�O���ЂƂŋ~�����y�������o��ǂ߂Ȃ������̖��O��E�C�Â��������l����ƁA�v�͈�l��l�������ɂ������v�z��I�ׂ����̂��Ɩl�͎v��(��������I�Ȃ��Ă�����)�B |
|
|
�����b2�@ ���q����O���̉،��@�̑m�B�@恂͍���(�����ׂ�)�B���b��l�E�̔���l�Ƃ��Ă��B���͕��d���B��͓���@�d�̎l���B���݂̘a�̎R���L�c�쒬�o�g�B�@ ����3�N1��8��(1173)���d���Ɠ���@�d�̎l���̎q�Ƃ��ċI�ɍ��L�c�S�Ί_���g����(���F�a�̎R���L�c�쒬���쎛���z)�Ő��܂ꂽ�B�c���͖�t�ہB�@ ����4�N(1180)8�ɂ��ė��e�������A���Y�R�_�쎛�ɕ��o�̒�q��o���t�Ƃ��ďo�ƁB�@恂͐���(��A���قɉ���)�B�m�a���E���厛�Ő^��������،����w�сA���������]���ꂽ��������₿�I�ɍ��L�c�S����⓯�������ɓِ������B�߉ނւ̎v��̔O���[��2�x�V��(�C���h)�֓n�邱�Ƃ���悵�����A�t�����_�̐_�����݂�f�O�����B�@ ���i���N(1206)�㒹�H��c����R�鍑�̔�(�Ƃ��̂�)����������č��R�����J�R���A�ύs�Ɗw��ɂ͂��B�������d�A�O���̐M�k�̐i�o�ɑR���A�������@�̕����ɐs�͂����B�@�R�̏�y�@��ᔻ�����u���ח�(����������)�v�u�l���u���v�̒����A40�N�ɂ��y�Ԋύs�ł̖��z���L�^�����u���L�v�Ȃǂ�����A��q�̕M�L�ɂ��u�p�p�Y�L�v�Ȃǐ������̒���������B�a�̂��悭���ƏW�u���b��l�a�̏W�v������B�@ �R�{�������ɂ��A���v�̗��̌�A���q���̑��i�ߊ��Ō�̎O�㎷���ƂȂ�k����Əo����Ă��̑��h�A���̂��̌�̐����v�z�A���ɁA�֓��䐬�s���ڂ̐���̊�b�ƂȂ����u�����v�̎v�z�ɑ傫�ȉe����^�����Ƃ����B�@ ����4�N1��19��(1232)�����B���N60(��58�Ζv)�B |
|
| �@ | |
| ���k��� | |
|
���q����O���̕����B���q���{��2�㎷���E�k���`���̒��j�B���q���{��3�㎷���ł���(�ݔC/1224-1242�N)�B�@ ���i2�N(1183)�k���`���̒��j�Ƃ��Đ��܂��B�c���͋����B��͑����̈��g�ǂŁA�䏊�̏��[�ƋL�����݂̂ŏo���͕s���B���̋`����21�A�c���̎�����k���ꑰ�Ƌ��Ɍ������̋����ɏ]�����q���肵��4�N�ڂ̍��ł���B�@ ������10�̍��A��Ɛl����d�s�����ƎC�������ہA���n�̗�����Ȃ��������Ƃ𗊒��ə�߂�ꂽ�B�����̊O�ʂł���A���������ō����n�ʂ������Ă����k���́A���̌�Ɛl�Ƃ͏���ʼn_�D�̍�������Ɨ����͎咣���A�d�s�̍s���͋ɂ߂ė�����������̂ł���Ƌ��e�����B������梐ӂɑ��ďd�s�́A�����͔��Ƃ݂Ȃ����悤�ȍs���͂��Ă��Ȃ��A������炾�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��ƕٖ����A���ɖ₢�����悤�����ɑ������B�����ő��Ɏ��̌o�܂�₤�ƁA�d�s�͑S�������Ă��Ȃ����A��������炾�Ǝv���Ă͂��Ȃ��ƌ�����B�����������́A�d�s�͌�������̂��߂ɉR�����A���͏d�s���������Ȃ��悤�݂��Ă���Ɣ��f���A�d�s�̏��̂�v�����A���ɂ͖J���Ƃ��Č���^�����B�u��ȋ��v�Ɏ��^����邱�̈�b�́A���̍�簂Ȑl���ƁA�����̑��ɑ��钞����[�I�ɕ\�����b�ƕ]����Ă���B�@ ���v5�N2��2��(1194)13�Ō�������B���{�̏��㏫�R�ƂȂ����������G�X�q�e�ƂȂ�A�����̗��������āA�����Ɩ����B��̓I�Ȏ����͕s�������A��ɑ��ɉ��������B�����̖��ɂ�茳���Ɠ����ɎO�Y�`���̑����Ƃ̍����߂��A8�N��̌��m2�N8��23��(1202)�O�Y�`���̖�(��T��)�𐳎��Ɍ}����B���N���j���������܂�邪�A��ɎO�Y���̖��Ƃ͗��ʂ��A���ێ����̖����p���Ɍ}���Ă���B���m3�N9��(1203)���\���̕ςŔ�铢���R�ɉ����B�@ ����N(1211)�C�����ɕ�C����B����2�N5��(1212)�ٕ��Ő����̎q�ł��������Y��������3�㏫�R�E�������̓{����ĕ��`���ɋ`�₳��A���r���Ă���B����3�N(1213�N)�̘a�c����ł͕��E�`���Ƌ��ɘa�c�`����łڂ��A����ɂ�藤�����c�S�̒n���E�ɔC����ꂽ�B�@ ����6�N(1218)�����玘���̕ʓ��ɔC������B���v���N(1219)�ɏ]�܈ʏ�E�x�͎�ɏ��ʁE�C�������B�@ ���v3�N(1221)�̏��v�̗��ł́A39�̑��͖��{�R�̑��叫�Ƃ��ď㗌���A�㒹�H��c���̓|���R��j���ċ��֓������B���A�V���ɓs�ɐݒu���ꂽ�Z�g���T��k���Ƃ��ďA�C���A����������ɂ͋��ɑ叫�R�Ƃ��ď㗌�����f���̖k�����[���A�C�����B�ȍ~���ɗ��܂��Ē���̊Ď��A����̏�����E���ߍ��Ȑ��̌�Ɛl���m�̓����ɂ��������B�@ �剞3�N6��(1224)���E�`�����}���������߁A���q�ɖ߂�ƌp��̈ɉ�̕������q�̐��������������ɗi�����悤�Ƃ����ɉꎁ�̕ς��N����B����ł������E�k�𐭎q�͑��Ǝ��[���䏊�ɌĂ�Ŏ����ƘA���ɔC�����A�ɉ�̕����d���l�Ƃ��ď��������B���͐��q�̌㌩�̌��A�Ɠ𑊑�����42�ő�3�㎷���ƂȂ�B�ɉ�̕��͗H�̐g�ƂȂ������A�S���グ��ꂽ�ٕ��̐����⎖���ւ̉גS���^��ꂽ�L�͌�Ɛl�̎O�Y�`���͕s��ɕt�����A���߂ƂȂ����ɉ���@���Ԃ��Ȃ�������ĕ��A���Ă���B�`���̈�̔z���ɍۂ��đ��͒햅�ɑ����^���A�����͂����͂��ȕ��������Ȃ������B���q�͂���ɔ����Ď�蕪�𑽂����A�킽���������悤�Ƃ������A���́u�����͎����̐g�ł�����v�Ƃ��Ď��ނ����Ƃ����B�ɉꎖ���̊���ȑ[�u�A�햅�ւ̗Z�a��͓����̑��̗���̎コ�A�k�����̖��{�ɂ����錠�͂̕s���肳�̌���ł��������B���͐V���ɖk���������Ƃ̉Ɛ����i��u�Ɨ߁v��u���A�M�C�����Ɛb�̔����i�j��C�����A���̈ꑰ�ƈقȂ钄���Ƃ̗���𖾂炩�ɂ����B���ꂪ��̓��@�E���Ǘ̂̑O�g�ƂȂ�B�@ ���N�Ø\���N6��(1225)�ɗL�͖��b�E��]�L�����v���A7���ɂ͐��q�����������Ė��{�͑����đ�v�l���������B���͂��̓�ǂɂ�����A�������琭�q�ɂ�����ꐧ�̐��ɑ���A�W�c�w�����A���c������ł��o�����B�f���̎��[�����s����Ăі߂��A���ƕ��Ԏ����̒n�ʂɌ}���u�������v�ƌĂ�镡�������̐����Ƃ�A���ʂ̂��̂͌�Ɂu�A���v�ƌĂ��悤�ɂȂ�B���͑����ĎO�Y�`����L�͌�Ɛl��\�ƁA�����t���疋�{���������Ȃǂ���Ȃ鍇�v11�l�̕]��O��I��Ő����ɏo�d�����A����Ɏ���2�l��������13�l�́u�]��v��c��V�݂��Ė��{�̍ō��@�ւƂ��A�����l���̌���A�i�ׂ̍̌��A�@�߂̗��@�Ȃǂ��s�����B�@ 3�㏫�R�������ÎE��ɐV���Ȋ��q�a�Ƃ��ċ�����}�����A8�ƂȂ��Ă����O�Ђ����������A�������o�Ɩ���点���B���o�͉Ø\3�N(1226)�����ɐ��Α叫�R�ƂȂ�(�����ÎE�ȍ~6�N�]�A���{�͐��Α叫�R�s�݂ł�����)�B�����ȗ���q�ɂ��������{�̌䏊�ɑ���A�߉������{�̓�A��{��H�̓����ł���F�s�{�Ҏq�ɖ��{��V������B���o�������Ɉړ]���A���̗����ɕ]��O�ɂ��ŏ��̕]�c���s���A�Ȍ�͂��ׂďܔ��͑����g�Ō��肷��|��錾�����B���̖��{�ړ]�͋K�͂������������̂̂���ΑJ�s�ł���A���R�ƍَ��ォ��̐S�@��]��}��A���c�I�Ȏ���������������ے��I�ȏo�����������B�@ ����A�ƒ���ł͉Ø\3�N6��18��(1227)16�̎��j�������Ɛb�ɎE�Q���ꂽ�B����2�N6��18��(1230)�ɂ͒��j�̎������a�̂���28�Ŏ������A1�������7���ɎO�Y�ב��ɉł��������o�Y������q��10���]��ŖS���Ȃ�A�����g���Y��̔엧��������8��4����25�Ŏ�������ȂǁA���đ����ɕs�K�Ɍ�����ꂽ�B�@ ���䐬�s���ځ@ ���v�̗��ȍ~�A�V���ɔC�����ꂽ�n���̍s��������������Ċe�n�Ő���ɕ������N���Ă���A�܂��W�c�w���̐����s���ɂ����蒊�ۓI�w�����O���K�v�ƂȂ����B���������̂��߂ɂ͗�������́u���v����Ƃ������A���ɂ����肪����A�܂��������ȑO�Ƃ͏������ω����Ă����B���͋��s�̖@���ƂɈ˗����ė��߂Ȃǂ̋M���̖@�̗v�_�������o���Ă��炢�A�����M�S�ɕ������B���́u�����v(���m�Љ�̌��S�ȏ펯)����Ƃ��A����������Ȃ����蓝��I�ȕ��m�Љ�̊�{�ƂȂ�u�@�T�v�̕K�v�����l����悤�ɂȂ�A�]��O�̈ӌ������l�ł������B�@ ���𒆐S�Ƃ����]��O�������Ă�����ĕҏW��i�߁A��i���N(1232�N)8���A�S51��������Ȃ開�{�̐V������{�@�T�����������B�͂��߂͂����u�����v��u���ځv�ƌĂ�A�ٔ��̊�Ƃ��Ă̈Ӗ��Łu�䐬�s���ځv�ƌĂ��悤�ɂȂ�B�����ɓ������đ��͘Z�g���T��Ƃ��ċ��s�ɂ�������̏d���ɑ�����2�ʂ̎莆�̒��ŁA���ڂ̖ړI�ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B�@ �u�����̍ٔ������œ����悤�ȑi���ł������҂������A�ア�҂�������s���������A�g���̍����ɂ�����炸�A�����Ђ������������ȍٔ��������Ƃ��č�����̂����̎��ڂł���B���s�ӂ�ł́u���̂��m��ʂ����܂��т��ǂ��������������v�Ə��l�����邩���m��Ȃ����A�܂����̋K���Ƃ��Ă͂��łɗ��h�ȗ��߂�����ł͂Ȃ����Ɣ��₳��邩������Ȃ��B�������A�c�ɂł͗��߂̖@�ɒʂ��Ă���҂Ȃǖ��l�Ɉ�l�����Ȃ��̂�����ł���B����ȏ�ԂȂ̂ɗ��߂̋K���K�p���ď��������肷��̂́A�܂�ŏb��㩂ɂ�����悤�Ȃ��̂��B���́u���ځv�͊������m��ʂ��������n�����m�̂��߂ɍ��ꂽ�@���ł���A�]�҂͎�l�ɒ���s�����A�q�͐e�ɍF�������悤�ɁA�l�̐S�̐����сA�Ȃ������̂��̂ĂāA�y�������S���ĕ�点��悤�ɁA�Ƃ����������}�ȁu�����v�Ɋ�Â������̂Ȃ̂��B�v�@ �u�䐬�s���ځv�͓��{�ɂ�����ŏ��̕��Ɩ@�T�ł���B����ȑO�̗��߂�A�����ȍ~�̊e��@�߂���{�I�ɊO���̖@�߂�͔͂Ƃ��Đ��肳�ꂽ�p���@�ł���̂ɑ��A���ڂ͂킪�����Ǝ��ɐ��肵���@�߂ł���Ƃ����_�ŁA���{�̖@�̗��j�����I�Ȃ��̂ƂȂ����B�@ ���@ �Ò����N(1235)�ΐ����{�Ƌ������������A����ɔ�b�R�������������K�͂Ȏ��Б������N����ƁA�������Ď��А��͂������������B�������A������͂��߂Ƃ���m���̒����́A�@�����ȗ����삪��ɋꂵ�Ƃ���ł��������A���{���S�ʂɏ��o���đm���̕s���ȗv���ɂ͒f�ŕ��͂Œ�������Ƃ������j���Ƃ�ꂽ�B�@ �m��3�N(1242)�Ɏl��V�c�����䂵�����߁A�����V�c�̍c�q�E���������V���ȓV�c�Ƃ��ėi������悤�Ƃ��Ă������A���͕��̏����V�c�����ď��v�̗����哱������d�҂̈�l�ł��邱�Ƃ��炱��ɋ��������A�������̑��ʂ���������Ȃ�Αވʂ����s������Ƃ����ԓx�����A�M���B�̕s���Ɣ����������Č㍵��V�c�𐄑ՁA�V���ȓV�c�Ƃ��đ��ʂ������B���̋����ȑ[�u�ɂ��A��Ƃ�������o��A���s�̌��ƏO�̈ꕔ���甽���������A�ނ�Ƃ̊W����X���������B�V�V�c�̊O��(�f��)�ł���y����ʂ͑��̖��ł���|�a���ȂƂ��Ă������߁A�Ȍ���͒�ʂ�ʂ��Ē�������ɂ����͂�Z�������Ă������ƂɂȂ�B�@ ����̓V�c���̍�����ߘJ�������œ|��Ă������́A�ԗ��������đ̒��������������߁A�o�Ƃ��Ċψ��ƍ����A1��������̐m��3�N6��15��(1242)�Ɏ��������B���N60�B������A�`���A���q�A��]�L���ƁA�k���������Ő��v�Ȓn�ʂɂ������l�������Ɠ���6��~7���ɖv���Ă���A�܂����v�̗��ŎO��c���z�����ꂽ�̂������G�߂��������߁A�J�ł͏�c��̉���ɂ���M��ł͂Ȃ����Ƃ������������z�����B�@ ��4�㎷���ɂ͑������������̒��j�ł��鑷�̖k���o�����A�C�����B�@ �㔒�́A�㒹�H�@�������͂��������v�̗��ȑO�̖��{�͌�Ɛl�̌��v��i�삵�ċ����͂ƑR���闧��ɂ��������A�@���̎����I�@�\������ꂽ���v�̗��ȍ~�́A���{�͋M���E���Г��̋����͂ƁA�n���E��Ɛl���͂Ƃ̋ύt�̏�ɗ����āA���҂̑Η��₷�錠�͂Ƃ��ČŒ肵���B���̋`���̈̋Ƃ��p���Ŗk�������̐����O���ɏ悹�����́A�������Ə̂�����B�@ ����b�@ ���͐l�i�I�ɂ��D��A���Ƃ���Ƃ̑o������̐l�]�����������ƍm��I�]���������X���ɂ���B������ł́A�Q�c�E�L���o���Ȃǂ��Ñ㒆���̐��l�N�q�ɗႦ�ď^���Ă���B�@ ���̐����͓����̊��q���m�̎��������ȗ��z��̌�����Ƃ���A�ނ̂����ꂽ�l�i�������G�s�\�[�h�͑����`������B���ΏW�͑����u�܂��Ƃ̌��l�ł���B���̒Q���������̒Q���Ƃ��A���l�̕���̂悤�Ȑl�ł���v�ƕ]���A�ٔ��̍ۂɂ́u�����A�����v�ƌJ��Ԃ��A�����ɓK�����b���u�����قǂɖʔ������̂͂Ȃ��v�ƌ����Ċ������ė܂܂ŗ����Ɠ`���Ă���B�@ �Ⴆ�Ύ��̂悤�Șb�����ΏW�ɂ���B�@ 1.��B�ɒ��̎Ⴂ���m���������B�ނ̕��͍����̂��ߏ��̂蕥���j�ڂɊׂ����B�ނ͋�S���Ă�����߂����ɕԂ��Ă�����B���������͔ނɏ��̂�^�����A�ǂ��������킯���S�Ĕނ̒�ɗ^���Ă��܂������߁A�Z��̊Ԃő��_������A���̉��ōٔ��ƂȂ����B��������́A���ߌZ�̕��������������Ǝv�����B�������A��͐����̎葱�����o�Ă���A�䐬�s���ڂɏƂ炷�ƒ킪���炩�ɗL���ł���B���͌Z�ɐ[��������Ȃ������ɏ��i�̔�������������Ȃ������B���͌Z���s���łȂ�Ȃ������̂ŁA�ڂ������ĈߐH�̐��b�����Ă�����B�Z�͂��鏗���ƌ������āA���ɕn������炵���B���鎞�A��B�ɗ̎�̌������y�n�����������̂ŁA���͂�����Z�ɗ^�����B�Z�́u����2�A3�N�Ȃɂ�т����v�����肳���Ă���܂��̂ŁA�q�̒n�ŐH�����\���ɐH�ׂ����A��������Ă�肽���Ǝv���܂��v�Ɗ��ӂ��q�ׂ��B���́u���g����Ƌꂵ�����̍Ȃ�Y��Ă��܂��l�����̒��ɂ͑����B���Ȃ��̂��l���͎��ɗ��h���v�ƌ����ė��p�̔n��Ƃ̐��b�����Ă�����B�@ 2.����n���Ɨ̉Ƃ����_�����ہA�̉Ƃ̌����������n���͒����Ɂu�����܂����v�ƌ������B���́u�����ȕ������Ղ肾�B���炩�Ȕs�i�ł������������̂����ʂȂ̂ɁA�����Ŕs�i��F�߂��M�a�͎��ɗ��h�Ő����Ȑl���B�����Ƃ��Ē����ԍٔ�������Ă������A����ȂɊ��������͏��߂Ă��v�ƌ����ė܂���Ŋ��������B�@ 3.�����ƂɎd���Ă���19�̍��A���Ƃ��R�f�ɋÂ��Ė������ڂ݂Ȃ����Ƃ�J�����|���������Ƃ�����B����̋Q�[�̍ہA��Q�̌����������n��̕S���Ɋւ��Ă͐ł�Ə�������A�Ă��x�����đ����̖��O���~�����Ƃ�����b������B���̍ۂɂ͖��O�𗶂��Ď��f�сA��A�ߑ��A�G�X�q�Ȃǂ̐V��������A��͓���p�����A������V��������߂�Ȃ��ґ���֎~�����B�ӔN�ɍs�������H�H���̍ۂɂ͎���n�ɏ���ēy���^��������B�@ ���̂悤�ɐ����Ɏd�������Ȃ������ߌ��Ƃ▯�O������]�����悭�A�����A�������̓��A�ŋx�ޗ��l�����Ɋ��ӂ����b������B�@ ����������ŋ߉q�o���Ȃǂ͏��v�̗���̒���ɑ��錵���ȑ[�u�����݁A�������ɏd�˂Ĉ��]�������Ă���B���̂悤�Ȍ��Ƃ̈ꕔ�̈�����f���Ă����̎��ɍۂ��Ă͌㒹�H��c���M����\������̂������B�@ ���q���{�ŖS��A�k�����ɑ���]���͍c���ɑ��鏈���������`�����_�𒆐S�ɍs���A�k�������Ȃǂ��ÌN�Ƃ��ĕ]������Ă��邪�A���͓������]������X���ɂ���B��k������ɂ͓쒩���̖k���e�[���u�_�c�����L�v�ɂ����āA�]�ˎ���ɂ͕��Ƃ̐ꉡ��ᔻ����V�䔒���m��I�]�������Ă���B����ŁA�]�ˊ��̍��w�U���ɂ����Ă͖{���钷�◊�R�z�Ȃǂ̍��w�҂�����ᔻ����悤�ɂ��Ȃ����B�@ �܂����q���{�k�����ɂ��㐢�̕Ҏ[���u��ȋ��v�ɂ́A���Ɋւ�����k���������L����Ă��邪�A���ɂ͑��l�̃G�s�\�[�h�𗬗p���Ă����ׂ�������B �@�@ �@ |
|
| ������V�c | |
| ������V�c1�@ | |
|
���q�����������k�����㏉���ɂ����Ă̑�96��V�c�ɂ��āA�쒩�̏���V�c(�݈ʁF����2�N2��26��(1318�N3��29��) - ����4�N/�2�N8��15��(1339�N9��18��))�B�������A�ȉ��ŋL�q����Ƃ���A���j�I�����Ƃ��Ă͍݈ʓr���ɓ�x�̔p�ʂƏ��ʂ��o�Ă���B恂͑���(�����͂�)�B���q���{��|���Č����V�������{�������̂́A�Ԃ��Ȃ����������̗����ɑ��������߂ɑ�a�g��֓���A�쒩����(�g�쒩��)�����������B
�@ �����U �@ ��o�����E��F���V�c�̑��c�q�B����́A����b�ԎR�@�t�p�̗{���E�������q(�k�V��@�A�����͎Q�c�ܒҒ��p)�B�������N11��2��(1288�N11��26��)�ɒa�����A����4�N(1302�N)6��16���ɐe���鉺�B�Ì����N(1303�N)12��20���ɎO�i�ɏ��i�B�Ì�2�N(1304�N)3��7���ɑ�ɐ��ƂȂ�A���{(�����݂̂�)�ƌĂꂽ�B�܂��A����2�N(1307�N)5��15���ɂ́A�����������C���Ă���B �@ ������ �@ ����3�N(1308�N)�Ɏ����@���̉ԉ��V�c�̑��ʂɔ����čc���q�ɗ��Ă��A����2�N2��26��(1318�N3��29��)�ԉ��V�c�̏��ʂ���31�őH�N�A3��29��(4��30��)�ɑ��ʁB30��ł̑��ʂ�1068�N�̌�O��V�c��36�ł̑��ʈȗ��A250�N�Ԃ�ł������B���ʌ�3�N�Ԃ͕��̌�F���@�c���@�����s�����B��F���@�c�̈⌾��Ɋ�Â��A�͂��߂������V�c�͌Z����V�c�̈⎙�ł���c���q�M�ǐe�������l���čc�ʂɂ��܂ł̒��p���Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă����B���̂��߁A����V�c�����Ȃ̎q���ɍc�ʂ��p�����邱�Ƃ͔ے肳�ꂽ�B����V�c�͕s�����点���B���ꂪ��F���@�c�̍c�ʌp���v������F���ۏႵ�Ă��銙�q���{�ւ̔����ɂȂ����Ă䂭�B�������N(1321�N)�A��F���@�c�͉@�����~���āA����V�c�̐e�����J�n�����B�O�N�ɖM�ǐe���ɒj�q(�N�m�e��)�����܂�ĖM�ǐe���ւ̍c�ʌp���̎������n�������̎����Ɍ���V�c��������̎��V�̌N�ƂȂ������Ƃ͑傫�ȓ�Ƃ����B �@ ���|�� �@ �������N(1324�N)�A����V�c�̊��q���{�œ|�v�悪���o���āA�Z�g���T�肪�V�c���ߓ��쎑������������鐳���̕ς��N����B���̕ςł́A���{�͌���V�c�ɂ͉��̏��������Ȃ������B�V�c�͂��̌�������ɓ|�����u���A��펛�̕��ς�@�����̉~�ςȂǂ̑m���ߏK�ɋ߂Â��A����2�N(1329�N)�ɂ͒��{�̌�Y�F���Ə̂��Ė����Ɋ֓������̋F�����s���A�������≄��ȂǓ�s�E�b�R�̎��Ђɕ����Ď��А��͂Ɛڋ߂���(�������A�L�͌���ł��鐼�����Ə����̐e���͖M�ǐe���n�ɑR����L�͂ȍc�ʌp���҂ɂȂ蓾�邽�߁A���ۂɌ�Y�F�����s���Ă����\��������)�B��o�����Ɏd����M�������͂��Ƃ��ƖM�ǐe�����x������҂��命���ł���A�����@���▋�{����{�I�ɔނ���x���������߁A����V�c�͎���ɋ��n�Ɋׂ��Ă䂭�B�����ĖM�ǐe�����a���I���������ƁA�����@���̒��q�ʐm�e�������{�̎w���ōc���q�ɗ��Ă��A�ވʂ̈��͂͂����������܂����B���O���N(1331�N)�A�ēx�̓|���v�悪���ߋg�c��[�̖����ɂ�蔭�o���g�ӂɊ댯�����������ߋ}篋��s�E�o�����f�A�O��̐_��������ċ��������B�͂��ߔ�b�R�ɋ��낤�Ƃ��Ď��s���A�}�u�R(�����s�{���y�S�}�u����)���ď邷�邪�A���|�I�ȕ��͂�i�������{�R�̑O�ɗ��邵�ĕ߂炦����B��������O�̗�(���O�̕�)�ƌĂԁB �@ �����߁A�����ĕ��A �@ ���{�͌���V�c�����s���瓦�S����Ƃ������ɔp�ʂ��A�c���q�ʐm�e��(�����V�c)�ʂ������B�ߗ��ƂȂ�������́A���v�̗��̐��ɏ]���Ėd���l�Ƃ���A�����O2�N / ���c���N(1332�N)�B�ɗ����ꂽ�B���̎����A����V�c�̍c�q��ǐe����͓��̓�ؐ����A�d���̐ԏ�����(�~�S)�甽������(���})���e�n�Ŋ������Ă����B���̂悤�ȏ�̒��A����͌��O3�N / ���c2�N(1333�N)�A���a���N�疼�a�ꑰ�𗊂��ĉB����E�o���A���ˑD��R(�����挧�����S�ՉY����)�ŋ�������B�����Ǔ����邽�ߖ��{����h�����ꂽ��������(����)��������ɖ������ĘZ�g���T����U���B���̒���ɓ����ŋ��������V�c�`��͊��q���ח������Ėk������ŖS������B �@ �������̐V�� �@ �A����������V�c�́A����̑ވʂƌ����V�c�̑��ʋy�э݈ʂ�ے肵�A�������ōs��ꂽ�l����S�Ė����ɂ���ƂƂ��ɖ��{�E�ۊւ�p���Ă����錚���̐V�����J�n����B�܂��A�����@���݂̂Ȃ炸��o�����̒����ł���M�ǐe���̈⎙���������c�ʌp������O���A�{���T���ł������͂��̎����̍c�q�P�ǐe�����c���q�ɗ��āA���̈⌾�̂ɂ��Ď���̎q���ɂ��c����Ɛ肷��ӎv�m�ɂ����B �@ �����̐V���͕\�ʏ�͕��ÓI�ł��邪�A�����͒����I�ȓV�c�ꐧ��ڎw�����B���}�ȉ��v�A���܂̕s�����A���ߕ�����J��Ԃ��@�߂��A�M���E�厛�Ђ��畐�m�ɂ�����L�͂Ȑ��͂̊������̐N�Q�A���̂��߂ɕp������i�ׂւ̑Ή��̕s���A�����ς瑝�ł������Ƃ����������v��A�������s�v��̂悤�Ȕ��I�Ȍo�ϐ���ȂǁA���̎{��̑唼�������ᔻ�ւƂȂ����Ă������B���m���͂̕s�����傫�����������łȂ��A���ƒB�̑����͐����ɗ��₩�ȑԓx���Ƃ�A�܂��L���ȓ���͌��̗����ɂ݂���悤�ɂ��̖��\��ᔻ����A���Ђ�S�����Ă����B�܂��A�|���Ɍ��т̂�������ǐe�������Α叫�R�̒n�ʂ�]���߂ɐe���Ƃ̊m�����[�܂�A�������V�c�ƑΗ����Ă��������̌����Đe�������q�ɔz�����Ă���B �@ �����������̗��� �@ ����2�N(1335�N)�A�����̗��̒����̂��ߒ����Ȃ��܂ܓ����ɏo�����������������A���̒����ɕt���]�������m�Ɋ��q�œƎ��ɉ��܂�^����ȂǐV�����痣������B����V�c�͐V�c�`��ɑ����Ǔ��𖽂��A�`��͔����E�|�m���̐킢�ł͔s�����̂́A���s�œ�ؐ�����k�����Ƃ�ƘA�����đ����R��j��B�����͋�B�֗������т邪�A���N�ɋ�B�őԐ��𗧂Ē����A������c�̉@����̂��ɍĂы��s�֔���B��ؐ����͌���V�c�ɑ����Ƃ̘a�r��i�����邪����V�c�͂����ނ��A�`��Ɛ����ɑ����Ǔ��𖽂���B�������A�V�c�E��،R�͖���̐킢�Ŕs�k���A�����͓������`��͓s�֓����B �@ ����k������ �@ �����R����������ƌ���V�c�͔�b�R�ɓ���Ē�R���邪�A�������̘a�r�̗v���ɉ����ĎO��̐_��𑫗����֓n���A�����͌�����c�̉@���̂��ƂŎ����@����������V�c��V�V�c�ɗi�����A�������ڂ𐧒肵�Ė��{���J�݂���(�Ȃ��A�����L�̓`����Ƃ���ł́A����V�c�͔�b�R���牺�R����ɍۂ��A����ł��čP�ǐe���ɏ��ʂ����Ƃ����)�B�p�����͗H����Ă����ԎR�@��E�o���A�����ɓn�����_��͊䕨�ł���Ƃ��āA�g��(���ޗnj��g��S�g�쒬)�Ɏ����ɂ��钩����J���A���s����(�k��)�Ƌg�쒩��(�쒩)�����������k�����オ�n�܂�B����V�c�́A���ǐe����P�ǐe�����V�c�`��ɕ����Ėk�������킹�A���ǐe���𐪐����R�ɔC���ċ�B�ցA�@�ǐe���𓌍��ցA�`�ǐe�������B�ւƁA�e�n�Ɏ����̍c�q�𑗂��Ėk�����ɑR�����悤�Ƃ����B�������A�����Ƃ��ł��Ȃ��܂ܕa�ɓ|��A����4�N / �2�N(1339�N)8��15���A���B�Ɏ��炸�A�g��֖߂��Ă����`�ǐe��(�㑺��V�c)�ɏ��ʂ��A�����A�g����։����Œ��G���ŁE���s�D����⌾���ĕ��䂵���B���N52(��50��)�B �@ �ےÍ��̏Z�g�s�{�ɂ������㑺��V�c�́A�쒩���̏Z�g��Ђ̋{�i�ł���Î玁�̑�����y���ɂ����Č���V�c�̑�@�v���s���B�܂��A�����͌���V�c���A���s�ɓV�����c���Ă���B �@ |
|
| ������V�c2�@ | |
|
�@�N��@�@�o����
�@ �@1324�N �����̕ρA�|���̖��^�I�� �@ �@1331�N �V�c�}�u�R�ɐ����A��ؐ����ԍ��ɋ��� �@ �@1332�N �V�c�B��ɗ������A��ǐe���g��ɋ����A�����瑁��ɂ����� �@ �@1333�N �V�c�B���E�o�A���������Z�g�����U�߂�@ �@�@�@�@�@�@�V�c�`�劙�q���U�ߑq���{�łԁA�V�c���s�֊ҍK �@ �@1334�N �����̐V���͂��܂� �@ �@1335�N �����̗��A��ǐe���E�����A������������ �@ �@1336�N (1��)�@�����@���̐킢�ɔs��A��B�֗����� �@ �@�@�@�@�@�@(5��)�@�����@�ēx����A����œ�ؐ������� �@ �@�@�@�@�@�@(8��)�@�����@�����A�����V�c(�k��)��i���@ �@ �@�@�@�@�@�@(12��) ����V�c�@�g��œ쒩�����@ �@ �@1338�N �V�c�`��z�O�ɂĐ펀�A�����k����萪�Α叫�R�ɔC������ �@ �@1339�N ����V�c���� �@ >�@�@�@�@�@�g�͂��Ƃ���R�̑ۂɖ���Ƃ��@��鮂͏�ɖk荂̓V��]�܂�Ǝv���@ |
|
|
�������R��
�@ 1172�N�A����̎����������Ă����㍵���c�͌�p�҂��w�����Ȃ��܂������܂����B �@ ������ł͍c�ʌ�p�҂��߂���������N����A����͎����@���Ƒ�o�����ɕ��A140�N���̊ԑ������ƂɂȂ�܂��B1317�N�A���������삪���{�ɒ���(�V�����ł͂Ȃ�)���˗��������ʁA���{�̐ܒ��Ă�����邱�ƂɂȂ�܂��B �@ �����R��(��傤�Ƃ��Ă��)�Ƃ͍c�ʂ������@���Ƒ�o�����Ƃ�����̍c�������݂Ɍp�����Ƃ������܂��B �@ ���̕����͑�ϕ�����Â炢�̂ŁA���̌p���}�����Ȃ���䖝���ēǂ�ʼn������B�����͍c�ʌp�����ł��B �@ �㍵��V�c�͏��ʂ��Ē��j�̌�[���V�c�ʂ����܂������A���j�̋T�R�V�c��ӈ�����[���V�c����ވʂ����A�T�R�V�c�ʂ����܂����B�㍵���c�͂���ɋT�R�V�c�̍c���q�Ƃ��āA�T�R�̍c�q(��F���V�c)�𗧂Ă��̂ł��B �@ �㍵��@�c�͎��̒��O�A���̂̕��z�������݂̂ōc�ʂɊւ��Ă͖{�ӂ𖾂炩�ɂ����A�����̎���̎��V�̌N(���ۂɐ��������V�c�Ƃ̎�)�͖��{�̐��ՂɔC����Ƃ̂��Ƃł����B �@ �k�������㍵���c�̈ӂɏ]���T�R�V�c�����V�̌N�ƒ�߂�Ǝ��V�̌N�Ƃ��ĉ@����]��ł�����[����c�̎��]�s���͑傫���A���ɓV�c���Ɖ@���̑Η��ւƔ��W���čs���܂��B �@ �������T�R�V�c�͌�[����c�̕s���ɓ����F���V�c�ɏ��ʂ�����A�c���q�ɏ�c�̍c�q(�����V�c)�𗧂Ă��̂ł��B �@ ���̌㖋�{�������R���̈Ă𗧂Ă�ƁA���̈Ăɂ��ƂÂ������̑�\�҂ł���㕚����c�ƌ�F���@�c���k�����č��㗼������m���Ɍ��݂ɍc�ʂɂ����Ƃ�����܂����B(�]�k�ł����A�ڒm�ⓚ�ł��Ȃ��݂̈�x����͌㕚���V�c�̎q���ł�) |
|
|
�����ȍ~�A���q���{�̎x�z�͂͋}���ɐ����Ă����܂��B
�@ ���q���{�̖����Ƃ͊ȒP�ɂ����Ε��m�̗��v��ی삵�A�g���u��(���̑����͓y�n���)�₷�邱�Ƃł������A���ꂪ�o���ɂ����Ȃ��Ă����̂ł��B �@ �����̖��łƂ肠�����͌��R�͑ނ������̂́A�S���̕��m�B�͔敾�̋ɒn�ɂ���܂����B�ޓ��͖��{�̖��߂Ƃ͂������ɂ����p���o��킯�ł͂Ȃ��A���ׂĎ��O�Ő�����̂ł��B �@ ���{���ɂ����m�B�ɉ��܂�^���������^����y�n�͂Ȃ��A�k�����̗̒n���Ȃ�Ƃ���肭�肷��ɂ����x������܂����B�����k�����@�͎R�ς������O��34�̎Ⴓ�ʼnߘJ�����Ă��܂��܂��B �@ ���܂̓��N�ɂ��炦���A�i�ׂ��N�����Ζ��{�̗v�l�ɘd�G��������E�E�E�E�E�B �@ ���̂��߂̖��{�Ȃ̂� �@ ��Ɛl�����̖���͖k�����Ɍ������܂��B �@ ���@�̌���p�����̂͒厞�B����14�B���̌���p�����̂��Ō�̎����A�k�������ł��B |
|
|
������V�c�̗��z�ƍ���
�@ ������̎����A���m�Ƃ͕ʂ̊p�x���犙�q���{���A����A���m�̑��ݎ��̂�a�܂����v���l���o�����܂��B �@ ����V�c�ł��B �@ �����R���̌����ɏ]���ĉԉ��V�c�̏��ʂ�������đ��ʂ����̂�����V�c�ł�(1318�N)�B����V�c�̍c���q(����V�c�̍c�q)����������ƁA����͎����̍c�q���c���q�ɗ��Ă悤�Ƃ��܂������A���{�͐�̘a�k�ɏ]���Ď����@���̗ʐm�c�q���c���q�ɗ��Ă܂����B����ɂ���Č���V�c�͂Ђǂ����{�����Ƃ����܂��B�t���݂ł��ˁB �@ ���̓V�c�̒��ł��̐l�قǃC�f�I���M�[�I�Ȑl���������ł��傤�B�ނ͈ꐶ�������Ď����́u���z�v�̎�����ڎw�����ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B �@ ����������V�c�̎v���Ƃ͂���͂�ɂ��̗��z�͈ꎞ�I�ɂ͎����������̂́A���̗���ɔ����������߂ɁA���̍s�ׂ͐��\�N�ɂ킽��헐�̔��[�ƂȂ�A���ӂ̂����ɐ��U���I���܂��B �@ ����V�c�̖ڎw�������z�Ƃ͂Ȃɂ��B �@ ����͕��m�ɂ��x�z�����߁A�ĂѓV�c�_�Ƃ�����Ɛ������͂��߂邱�Ƃ������̂ł��B�����Ă���𗝘_�I�Ɏx�����̂͒�������`�����Ă�����q�w�ł����B �@ ��q�w�Ƃ͂����ɂ������܂������A����V�c�͂��̎v�z�̑�`�����_���d�����A���̍��̐����Ȏx�z�҂͒N�Ȃ̂��Ǝ��₵�܂��B���ꂩ�璼���I�ɓ��{�̐����Ȃ�x�z�҂͓V�c�Ƃł���B�V�c�͐�̐��`�ł���A�t�炤���̂͐�̈��Ȃ̂��B �@ ����͎�q�w�̗��_�ɏƂ炵�Ă��������B �@ �����̗��z�̎����ɂ͊��q���{��|���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@ �ƍl����悤�ɂȂ�ɂ́A����قǂ̎��Ԃ͂�����Ȃ������ł��傤�B �@ �����������Ō���V�c�͋���ȃW�����}�Ɋׂ�܂��B �@ �����ɖ������镐�m�����Ȃ��Ă͖��{��|���Ȃ�����ł��B �@ �V�c�ɂ͌�q���͂��Ă��A�R���͂͂���܂���B �@ �Ȃ��Ȃ獑�R�͉����́A�����V�c�̎���ɔp�~���ꂽ����ŁA���{�_�Ƃ��镐�m�c�͓V�c�̎w�����ɂ͂Ȃ���������ł��B(���Ȃ݂ɂ��̏�Ԃ̂܂ܖ�������ɂȂ�܂�) �@ ��ނȂ�����V�c�͊e�n�̗L�͍������d�|���A�|���𖽂���ȊO���@�͂���܂���ł����B���̎������͌���V�c�ƁA���{�ɕs���������m�B�̗��Q�͂Ƃ肠������v�����̂ł��B �@ ���������A�V�c�`�哙�ɂ���Ċ��q���{���|��A�k�������ŖS�����̂�1333�N5���̂��Ƃł����B |
|
|
�����s�����V��
�@ ����V�c�̐V���͌��_���猾���đ厸�s�ł����B���̓��e�͂��낢�날��܂����傫��������Ή��܂ƐV�ł��������܂����A���s�������R�͌���V�c�̐���������Ƀ}�b�`���Ă��炸�A���O�̎x�����Ȃ��������߂ł��B �@ �|���ɎQ���������m�B�͓��R�Ȃ��牶�܂�~���܂����B �@ �����ȗ��A�ޓ��̃t�g�R���͂Ђ������Ă����̂ł��B �@ ���������܂̕s�������͕��m�B�̊��҂������ɗ����Ă��܂��܂����B�������ƐV�c���͂Ƃ������A��ؐ����͂킸���ɉ͓���ɔC����ꂽ�����ł����B���܂����ł͂Ȃ��y�n�̖��`������ɕς���ꂽ��A���̊Ԃɂ���̓y�n�̖��`�������̕��m�ɂȂ��Ă������Ƃ���������ʂ��������̂ł��B �@ ���̍����ɗւ������āA�������z�̂��߂̑��ł������܂��B �@ ���̎旧�Ă͎���n���̔C���ł����A�]������̎��E�n���͂قƂ�ǂ���Ƃ���A�V���Ȏ��E�n���͒��삩��C�����ꂽ�l�B�ł����B���E�n���Ƃ����Ε������͗ǂ��ł��������̂������ǂ��킩���Ă��Ȃ����Ƃ������I�ҒB�ł��B������A���Ԃ�҂����������悤�ŁA�ޓ����C�n�łǂ̂悤�Ȏ旧�Ă��������e�Ղɑz���ł��܂��B �@ ���̂悤�ȕ��m�������V���̔w�i�ɂ́A�����̌��Ƃ����ɂ������u�I���v�z�v������܂��B���Ƃ͑I�ꂽ�҂ł���A�����̒��_�ɗ��ׂ����́A�Ƃ����v�z�ł��B����V�c�̑��ߖk���e�[�͂��̒��A�_�c�����L�ŁA���������Ă��܂��B �@ �k�����ł͕̂��m�̌��тł͂Ȃ��B�V�̈ӎu�ł���B �@ �����������m�Ȃǂ́A�ȑO�͒��G(����̓G)�ł������B �@ �V�c�ɖ��������������ĉƂ�łڂ��Ȃ����������ł����ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@ ���̏コ��ɉ��܂��~�����ȂǁA�s�͂��ł���B �@ ���ꂪ�����̌��ƈ�ʂ̍l���������̂ł��B �@ �܂������l�ԂƂ������̂͂����܂Ŏv���オ�����̂Ȃ̂��B �@ ����̊��o�ŏ��̂͊ȒP�ł����A���ꂪ�w���j�̗���x�Ƃ������̂Ȃ̂ł��傤�B �@ �����Ƃ��k���e�[��������������̂�1338�`1339�N�̂��ƂŁA���łɌ����̐V���͔j�]������V�c���g��ɖS�����������Ă���ł����B���Ɛ��������Ɏ�����Ȃ������̂ŁA�]�v���m�ɑ���s�����̂��Ă����ɈႢ����܂���B �@ ���m�̗��ꂩ�猩��A���������ɂ͔ޓ��̕s���̃G�l���M�[���M��������������q���{�������������̂ł��B���q�����͎���̗���Ƀ}�b�`���������ł����B �@ ���m�̖w�ǂ͌���V�c�̎v�z�A�V�����ւ̕�����m�炸�Ɍ���V�c�ɖ������A���q���{��|���܂����B�m��Ȃ������͖̂����̂Ȃ����ƂŁA���̎���A�I�������Ȃǂ���܂��琭���Ƃ����l�Ɏ����̍l�������(�H)��m�点��`���ȂǂȂ������̂ł��B �@ �ł���r�I����V�c�̋߂��ɂ�����ؐ����Ȃǂ́A���邢�͂����Ȃ邱�Ƃ�\�����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̑z���͂�����Ǝ��M������܂��B �@ ���ĕ��m�B�͒P�Ɋ��q���{(�k�𐭌�)�Ɏ��]���Ă��������ł���A���Ɛ������̂��̂Ɏ��]���Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ł��B �@ �ނ�͍�����Ȃ���Ɏ����B�̗��v�����l�E�E�E���q���{�ɑ���V���ȕ��Ɛ����E�E�E�������̂�ؖ]����悤�ɂȂ�܂��B�����Ă��̕��Ɛ����̑�\�҂Ƃ����A�ő�̎��͎҂ƒN�����F�߂鑫�������ȊO�ɂ͂��܂���ł����B |
|
|
����V�c�̐V���ɕs�����������͕̂��m�����ł͂���܂���ł����B
�@ �V�c�͂���܂ő��݂����֔��E��p�~���A���ƍق���悤�ɂȂ�܂��B�_�c�����L�̖k���e�[�̔ᔻ�͕��m�����ł͂Ȃ��A�V�c�����̑Ώۂł����B �@ �V�c����҂͂��̐������x���d�A�������^�c���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�V�c�͐����̐��s�ɍۂ��Ă͕⍲�̐b��I��ł����ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�O��Ƃ������̂��悭���ׂ�Ɛe�[�͌����܂��B �@ �e�[�͓`���I�ȑO���`�҂ł���A�ƍَ҂Ƃ������̂�F�߂Ȃ��ێ�I�Ȑl�Ԃ������̂ł��B �@ �ƍَ҂Ƃ͉����B�ȒP�Ɍ����w�������[���E�u�b�N�Ȃ̂��x�Ƃ������݂ł��B �@ ���{�j�ɂ͗Ⴆ�Β����c��̂悤�ȁA����Ȏ�������ƍَ҂Ƃ������̂��o�ꂵ�����Ƃ�����܂���B����͓��{�l�Ƃ������̂̐l�ԓI�Ȑ��i�ɂ����̂Ȃ̂��A���邢�͓ƍَ҂����܂�ɂ����A���܂ꂽ�Ƃ��Ă������F�߂Ȃ����y�A������������̂�������܂���B �@ ����łȂ��Ƃ������ɂ��Ď����̂��邱�Ƃɔ�������Ƃ����Ɍ���V�c���������L���Ȍ��t������܂��B �@ ���̐V�V�������̐��Ȃ� (�������ꂩ�炷�邱�Ƃ��A�����̑O��ɂȂ�̂�) �@ ���͂��̌��t���̂͂������ăL���C�ł͂���܂���B���ƂƂ������̂͂�����O���`�A�����`�ŁA�V�K�Ȃ��̂�`���I�ɋ��ۂ�����̂ł��B�O�Ⴊ�Ȃ����炱������Ă݂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂�����ˁB �@ �Ƃɂ������ɂ��A����V�c�͕��Ƃ����łȂ����Ƃ������������Ă����܂��B�O��̂Ȃ����Ƃ����X�Ɏ��s���������ł͂���܂���B����V�c�ɗD�����ꂽ�͈̂ꈬ��̌��ƁE�E�E�\�͂̂���Ȃ��ł͂Ȃ��A����V�c�ɋC�ɓ���ꂽ�l��������������ł��B����̈����A������q��������\���܂��B �@ ���̎Љ����I�݂ɔᔻ���A慎h���Č������̂��L���ȓ���͌��̗����ł��B �@ �����s�j�n�������@�铢�@�����@�d�d�|�@���l�@���n�@�������@����@�ґ��@���R�o�Ɓ@��喼�@���ҁ@���g�@���܁@���R�@�{�̃n�i���A�i�אl�@�������^�����A�Ǐ]�@槐l�@�T���m�@������X�����o�ҁE�E�E�E �@ ���̂���s�ɂ͂����́B�铢���A�����A�ɂ��̓V�c�̖��ߏ��B���l�A���n�A�Ӗ��̂Ȃ������ȂǁB �@ �܂��A�m���瑭�l�ɂ��ǂ���̂�A�t�ɁA����ɑm�ɂȂ�҂��ڂɂ��B���܂ɂ�薼���Ȃ��y������}�ɑ喼�ɂȂ����҂����邩�Ǝv���ƁA�H���ɖ����҂�����B���̂̕ۏ≶�܂ɂ������邽�߂ɁA�����̂�������\�����Ă�҂�����B �@ ���ܒS�����̌��Ƃ́A���C�ɓ���̗V������u�����l�ɐ��܂ꂽ����ɂ͈�ł���������y�n���ق����v�ƌ���ꂽ�Ƃ���A�����ɓy�n��^�����ƌ����܂��B�������Ő�������m�B�ɂ͂قƂ�Ǘ^�����Ă��Ȃ��̂ɁE�E�E�E�B |
|
|
���V���Ȑ헐
�@ 1335�N7���B���q���{���łтĂ킸��2�N��B �@ �M�Z���ɐ������Ă������q���{�Ō�̎����k�������̈⎙�k�����s�͐V���ɕs�����������B�Ƌ��Ɍ��N���A��H�쉺�����q�ɍU�ߍ��݂܂��B �@ ���q������Ă����������`�͈�킵�Ĕj��A���q��E�o���ĎO�͂܂œ����ċ��s�ɂ���Z�����ɉ��R�����߂܂��B����̍c�q��ǐe�����E���ꂽ�̂͂��̎��̂��Ƃł��B �@ �֓��̑�������߂邽�ߐ������R�ɔC������邱�Ƃ�����������ł����A���삩��p������Ă��܂��܂��B����͌���V�c�������ő�̌R�����͎҂ł����������̂���Ȃ鐨�͑�����댯���������߂ł��B �@ �����������͒���ɖ��f�ŋ��s���o�Ē��`�ƍ������A�֓��Ɍ������k���R��j��܂��B���̌㑸���͋A������Ƃ̒���̖��߂����A���q�ɂ����ēƒf�Ř_���s�܂��s���悤�ɂȂ�܂����B �@ �_���s�܂Ƃ͌��т̂���҂ɂ���ɑ����������܂�^���邱�Ƃł��B���Č����������̒��삩�炱�̌��������n���ꂽ���ƂŁA�����͑S���̕��m�ւ̖��ߌ����l�����܂����B���߂Ɖ��܂Ƃ͈�̂̂��̂ł�����ˁB����͊��q���{�����O�̏d��ȕz�������̂ł��B�ł����瑸���̍s�ׂ͒���ւ̔��t�ł����B �@ ���������ɑR�ł���̂́A���͂ł͂͂邩�ɗ��܂����V�c�`��ȊO�ɂ��܂���B����͂��炽�ɐV�c�`������R�Ƃ��鐪���R��Ґ����A�����R�Ɛ�킹�邱�ƂɂȂ�܂��B�������V�c�R�͔����|�̉��̐킢�Ŕs��A���̗]���������đ��������͋��s�ɐi�����܂��B(1335�N12��) �@ ���ɓ����������͓�ؐ����̍I�݂Ȑ�p�ɖ|�M����A����ɂ͖k���e�[�̎q�A���Ɨ�����D���ȉ��B�R�����w����Ƃ��ɂ͔s��A��B�ɗ������т܂��B�������킸���̊��Ԃő̐��𐮂��A�Ăы��s�Ɍ������Đi�����J�n���܂����B �@ ���s����E�o��������V�c�͔�b�R�Ŗ���̔s���m��A�Ƃ肠�������������Ƙa�r���邱�Ƃ��v�����܂��B����ɔ�����V�c�`��ɑ��Č���V�c�� �@ �����͂����B�ނ��A�P�ǂ�V�c�Ƃ���B���܂��͍P�ǁA���ǂƋ��ɉz�O�֍s�� �@ �ƌ����܂��B�z�O�ɂ͐V�c���̗̒n���������̂ł��B(�P�ǐe���A���ǐe���͋��Ɍ���̎q�ł�) �@ �������V�c�`�哙�����Ă��������z�O���P���͉z�O���̎z�g���o�ɕ�͂���A�������`��͏��E�o���[�R��ֈڂ�܂��B �@ �����ŕ����W�ߎz�g���o�̌R���������Ƌ������ɂ�����ł������A�啺�Ɏ�Ԏ�邤���ɋ������͗���B���ǐe���A�V�c�`��(�`��̒��j)�͎��Q���A�P�ǐe���͕߂炦���Č�ɓŎE����Ă��܂��B�P�ǐe���͂킸��14�ł����B �@ ���̈���ŗH����Ă�������V�c�́A���������ɋ��v����ĎO��̐_����ɓn���Ă��܂��܂��B���������͂��̎O��̐_��������āA������c�̒��V�c�ɑ��ʂ�����̂ł��B�����V�c�ł�(1336�N8��)�B����3������B�������̊Ď��̌������Č���V�c�͋��s��E�o���A�g��R�ŖS�����������āA�����ɓ�k�����n�܂�̂ł��B �@ ����V�c�� �@ �����ɓn�����O��̐_��̓j�Z���ŁA���������^�̓V�c�ł���B��ɒ��`��s�����Ȃ�t�������� �@ �Ɩ����܂����B�V�c�`��Ɍ������c���q���P�ǐe���Ƃ��邱�Ƃ��ł���߂ŁA�`��͌���V�c�ɗ��p����A��̂Ă�ꂽ�̂ł����B �@ ���ꂱ������V�c�Ƃ����l�̖{���Ȃ̂ł��B �@ ���̗Ⴞ���łȂ�����V�c�͋ɂ߂Ė��q�Ȑl�ł������A��l�̐l�ԂƂ��Ă݂��ꍇ�A���i��̌��ׂ��ڗ��l�ł����B �@ �����M�l���m�炸�A�Ƃ������t������܂����B �@ �g���̍����Ƃɐ��܂ꂽ�l�́A�l�ɕ�d����Ă���d�������Ƃ��Ȃ��A���̊��o�͈�ʂ̐l�Ƃ͂�������Ă��āA�l�C�ŋ]���ɂ��邱�Ƃ�����̂ł��B �@ ����V�c�̐g���肳�̋]���ɂȂ����͕̂��m�����ł͂���܂���B �@ ���q���㖖���A�|���̖��d���I�����Ė��{�ɒNj����ꂽ����V�c�͒m��ʑ����ʂʼn����ʂ��A�Ō�ɂ͖��^�͑��߂̓���r�����Ɏd�g���Ƃƌ����ē����Ă��܂��B �@ ���ꂪ�I�������̂͌���V�c�̑��߁A�g�c��[�����{�ɖ����������߂ł������A�^���͂ǂ������^���ꂻ���ɂȂ������Ƃ�m��������V�c������ł��āA�킴�Ƌg�c��[���g���Ė��{�ɖ����������悤�ł��B����V�c�̋g�c��[�ւ̐M�C�͂��̌���ς���Ă��Ȃ��̂��Ȃɂ��̏؋��ł��B�������N����Ɣ鏑�̐ӔC�ɂ��鐭���Ƃ͐̂��炢���̂ł�(��) �@ ���q���{�ŖS��A���m�B�ɂ����������܂�^���Ȃ��������Ƃ͂������Ɍ��߂��������悤�ł��B �@ ���̕s���̑�\�i�͑��������ł����B �@ ���ۂɂ͑����͂���܂ł͍����Ɩ�����Ă��܂������A����V�c�́A�u�I���̖��O�̈ꎚ����邩��s���������ȁv�Ƃ���ɖ��O�ł��鑸��(�����͂�)�̈ꎚ��^���܂��B���������������ƂȂ�̂͂��̎��̂��Ƃł��B �@ ������N�̖��O�̈ꎚ�����炤���Ƃ͔��ɖ��_�Ȃ��Ƃł����B �@ �������E�E�E�E�������ꂾ���ʼn��������I�Ȃ��̂͂Ȃ��̂ł��B�����̕s���͂���ɍ��܂��Ă����܂��B �@ ������@��������V�c�͍c�q�̌�ǐe���ɑ����ÎE�𖽂��܂��B�����������͋t�Ɍ�ǐe����d���̋^��������Ƃ��ĕ߂炦�A����V�c�ɂ́A�u����_�����͓̂V�c�̂����߂ł��傤���v�A�Ƌl�ߊ��܂��B �@ ����Ă��V�c�͂����ł��m��ʑ����ʂ������ʂ��A���̌��ʌ�ǐe���͊��q�ɗH����A��ɑ����̒�A���`�ɎE����邱�ƂɂȂ�܂��B���q�Ɍ쑗������ǐe���͈ꌾ�A������蕃������߂����A�ƘR�炵�܂����B����V�c�͑��q������̂Ă��̂ł��B |
|
|
�V�c�̎��͂����Ђƌ��͂ɓ���Ȃ�A�V�c�͌Â����猠�Ђ͂����Ă����͂̂Ȃ����݂ŁA���ۂ̐����͓V�c�̑�s�҂��S�����Ă��܂����B�������q��h�䎁��������\���܂��B
�@ ����Z�c�q�͓V�c�e��(�V�c�ɂ�钼�ڐ���)��ڎw������ɐ��������̂��剻�̉��V�ł������A10���I���납��Ăсu��s��(������)�v�ɂ�鐭�����ۊ����Ƃ��ĕ������Ă��܂��B�����������ʼn@���͐V���ȋ{��v���ł����B �@ �s�@���t �@ ����V�c(��c�A�@�c)�̎�������ԂƂ��鐭���`�ԁB���ߐ������V�c�ƋM���̋��������I���������ł���A�ۊ����㋉�����M���̉Ǔ������I�F�ʂ������̂ɑ��A���͏�c�̐ꐧ�I�����̂��Ƃɒ蒅���������`�Ԃ��㐢�̎j�Ƃ��@���Ɩ��t�����B(���}�А��E��S�Ȏ��T) �@ �@���Ƃ͎���������c(���V�̌N)���������鐭���`�Ԃł���A�V�c�Ƃ͏����u���V�̌N�v�ɂȂ邽�߂̌��K���ԂŁA�܂��������Ђ����͂������Ȃ���Ԃ������̂ł��B �@ ��k���̍R���͕ʂ̊ϓ_���猩��Ή@���h�Ɛe���h�̍R���ł�����܂����B�@����1086�N���͖@�c����n�܂�1321�N�܂ő����܂������A����͉@����ے肵�A�e�����߂����܂����B �@ 1185�N�A�d�m�Y�̍���ŎO��̐_��͈����V�c�A��ʓ�(�������̍ȁB�����V�c�̑c�ꎞ�q)�Ƌ��ɊC�ɒ��݂܂����B�������̕K���̑{���Ō��ʂƋ��͌����������̂̑��㌕�͔����ł��Ȃ��������߁A���㌕�͐����a������̌��ő�p���� ���ƂɂȂ�܂��B���̑�p���܂O��̐_��ő��ʂ����̂��㔒�͓V�c�ł��B �@ ������p�ł悢�Ȃ�A���ƌ��ʂ���p�ł��܂�Ȃ��͂��ł��B �@ �܂�O��̐_��œV�c�̐��������咣���邱�Ƃ�150�N���O����ł��Ȃ����ƂŁA�_��̎�������ނ��낿���V�̌N�Ɏw�������҂��������ȓV�c�ƍl�����Ă��܂����B�ł��������V�c���M�����O��̐_��̉��l�Ƃ͂��͂⊊�m���ł����Ȃ������̂ł��B �@ ����������(���m��)�͌㐢�ɂȂ��Ă킩�邱�ƁB �@ �����͎O��̐_��̉��l�A���Ђ͐��Ȃ��̂������Ǝv���܂��B �@ �����łȂ���Γ�؈ꑰ�̂悤�ɏ����Ȓ��`�S����ł͂Ȃ��A�Ȃ������̑��̕��m�B���쒩���x�������������ł��Ȃ�����ł��B �@ ���ǂ̂Ƃ����k���Ƃ͎�q�w�ƌ������O��s�̊w��ɂ��Ԃꂽ����V�c���A�����̑命���̎Љ�q�ł��镐�m�����ċ��s�����������̐�������͂��܂����̂ł��B����ȃo�J���������͂���ȑO�ɂ��A����ȍ~�ɂ�����܂���B����V�c�͎����̂����œ��{�����卬�����Ă��邱�Ƃɂ��������̐ӔC���������A���̎��̒��O�ɂ��������c�����悤�ł��B �@ �E�E�E�������X���X�̖ϔO�ƂȂ�ׂ��́A���G�����Ƃ��Ƃ��łڂ��āA�l�C���Ȃ炵�߂�Ǝv�ӂ���Ȃ� �@ ����v�ӌ́A�ʍ��͂��ƂГ�R�̑ۂɖ�����Ƃ��A��鮂͏�ɖk荂̓V��]�܂�Ǝv�ӁB �@ �������ɔw���`���y�A�N���p�̂̌N�ɂ��炸�A�b������̐b�ɂ��炶 �@ �䂪�肢�͒��G��łڂ��A�l�C(�l���̊C�E�E�E�V���̂���)���ɂ��邱�Ƃł��� �@ ������䂪�g�͂��Ƃ���R(�g��̂���)�̑ۂɖ�����Ă��A���͂����k�(���s�̂���)�̋�ɂ��� �@ �����䂪�⌾�ɔw���Ȃ�A�c�ʂ����ł��^�̓V�c�ł͂Ȃ��A�b�������`�̐b�Ƃ͌����Ȃ� �@ �䂪�肢�͑����̐��ł���B�䂪�q���͂����܂Ŗk���Ɛ킦�Ƃ܂Ō������̂ł��B����������(����Ƃ͈Ⴂ�A�͂����ō��킹�邱��)���ꂽ�̂�1392�N�B���������̑��A�����`���̎���ł����B �@ ����V�c�̐��U���݂�ƁA�����ƂƂ������͎̂���Ƀ}�b�`���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�܂���ʂ̍��������������Ƃ������̂͌��ǂ̂Ƃ��뒷�������Ȃ����̂��Ƃ��v���܂��B �@ �O�L�Əd�����܂����A���{�j�ɂ̓��[���b�p�⒆���ł����Ƃ���̐�Ό��͎ҁA�ƍَ҂Ƃ������̂����݂��܂���B����ł��ƍَ҂ƌ������t�ɂ����A�z����̂͐D�c�M���ƌ���V�c�ł��B���ꂾ�����̓�l�͓��{�l�Ƃ��Ă͋���Ȍ��̎�����ł���܂����B �@ �������M���͎���̗v���ɂ���Đ��܂ꂽ�Ǝv���܂����A����V�c�͎���ɖ]�܂ꂽ�l�ł͂Ȃ������̂ł��B�@ |
|
| ������V�c3�@ | |
|
����V�c ����1�N(1288)�`�2�N�^����4�N(1339)
�@ ��1�D���p���̓V�c�Ƃ��đ��� �@ ��o�����A��F���V�c�̑�2�c�q�B恂͑���(�����͂�)�B���̌�F����c�͒��q����V�c�̎q�ő��ɂ�����M�ǐe���̑��ʂ�]�ށB�M�ǐe�����c���ׂ̈ɂ��̒��p���I���݂Ƃ��āA�����e���͎����@���̉ԉ��V�c�̐Ղ����c1�N(1318)�ɑ��ʂ����B���̎��A�V�c��31�B |
|
|
��2�D�V�c�̓ƍق�ڎw���A����̉��v��f�s
�@ �����́A��q�w�Ȃǂ̎v�z��������V�c�e���ɂ��ƍِ�����ڎw���A���X�̒������v�ɒ��肵���B�M���̏���ɂƂ���Ȃ��\�͎�`�ɂ��l�ޓo�p�����{�A�g�c��[�A�������H��[�A�k���e�[�A����r��A������v�E�ɏA���A�����̍��V��}�����B���̐l���͉Ɗi�唴���d������M�����傫�Ȕ����������A�{���͑Η��҂��鎝���@���̉ԉ���c����̎x�����A�����̐V���͂܂��܂��̊���o�����������B �@ �܂��A����܂ō��Ƃ̌��đO�ł������_�앨����̔N�v�����A���ƁA���ʋƎ҂���̏�[�����d������v���I�Ȑ���̓]�����s�Ȃ��A�����X���ɂ���������̌��Ē����ɐs�͂����B |
|
|
��3�D�����̕�
�@ �������������̎��т��グ�Ă����ɂ�A�V�c�ƍقɂ����{�̑S���x�z��ڎw�������ɂƂ��āA�����𒆐S�ɑ傫�Ȑ��͂��ւ�A�V�c�̑��ʂɂ���傫�Ȕ������������{�Ƃ̑Η��͕s���̂��̂ƂȂ��Ă������B �@ ��͖���u�ƌĂ��剃���A���J���A����ɂ������ē���r��A����A���m�̓y��A������������ƌꂢ�A�����̌v���������B����1�N(1324)�A����u�ɎQ�����Ă������m�̈�l�A�y���̐Q�Ԃ�ɂ���ē����v�悪���o�A�v��̒��S�����o�[�ł���������r��A����͕ߔ��A�y��A�����������͎a�߂ɏ�������B������u�����̕ρv�Ƃ����B ���R���q���{�̑{���̎�͐^�̎�d�҂�������ɂ��L�тĂ͂������A��͕ٖ��̂��߂Ɋ��q�ɖ������H��[�g�Ƃ��Č��킵�A���{�̈ԕ��ɓw�߂��B�V�c�����Ƃɍ������o���̂͑O�㖢���̏o�����ł���B����Ɠ�������̉��̕����ɂ��������{�́A�����Œ�ƑS�ʑΌ��̎p����ł��o�����͓���ł͂Ȃ��Ɣ��f�A��ٖ̕�������āA���쎑������n�ɔz������݂̂̉��ւȏ��u�ɂƂǂ߂��B |
|
|
��4�D���O�̕�
�@ ��������͂��̎��s�ɋ����Ȃ������B���q�̌�ǐe�����b�R����̍���ɐ����A���厛�A�������Ƃ̘A�g�����߂���ƁA�m���B���͂Ƃ��ē����o����悤�ɉ���B�X�ɗ��m���ς����҂Ƃ��āA�͓��̓y����ؐ����A���{�v�l�̈ɉꌓ����̖�����������ɐ�������B�܂��A�ĉ��A�����̌���A�֏��̔p�~���s���ď��H�Ǝ҂̎x���A����r����e�n�ɔh�����Ĉ��}�C���A���k��h�̕��m�̒������s�����B �@ �������ē����Ɍ����Ď����Ȍv�悪����ꂽ���A���O1�N(1331)�A�������{�̎��͂�������̑��߁A�g�c��[�ɂ���Ė��{�ɖ�������A�v��͍Ăъ��������B�g�c��[�́A������߂�o���Ȃ��قǐ[���肷��O�Ɍv��o�����āA�����̕ς̎��̂悤�ȉ��ւȏ��u�{�Ɋ��҂����炵���B���������{�͍���͂�����������A����r����ߔ��A���q�ֈڑ��A���ɒ�̏��u���������n�߂��B �@ �ǂ��߂�ꂽ�����͊}�u�ɂċ����A��ؐ������͓��ԍ��ɂĂ���Ɍĉ������B���������݂̉�������{���ɂ��Ă��܂���ǐe����͔�b�R��E�o����H�ڂɁA��̐ԍ������{�R�̍U���̑O�ɗ��邵�A�}�u�̒���߂炦���Ă��܂��B������u���O�̕ρv�ƌĂԁB |
|
|
��5�D�B��ւ̔z�����甌�ˑD��R�ł̍ċN
�@ ���{�́A������ވʂ����A���v�̗��̌̎��ɕ���ĉB��֔z�����A�����@���̗ʐm�e���𗧂ĂČ����V�c�ƂȂ����B�����̊e�c�q���z������A����r��A����͎a�߂ɏ�����ꂽ�B���v�̗��̎�d�Ҍ㒹�H��c�́A�B��֔z�����ꂽ��͂�������ӋC���������̂Đl�Ƃ��Ď��ӂ̗]���𑗂������A�����͕s���̓��u�������z�����x�ł͑S�������Ȃ������B�܂��A���{�̋��d�ȏ��u�������{�̋C�^����C�ɍ��߁A�E�����ӂɂĖ��{���Z�g���T��ɑ��锽�����p�������B���{�̒Ǔ��ꂽ��ǐe���͋g��R�ŋ����A�e�n�̈��}�A�C���A���k��h�̕��m�ɓ������d�|�����B��ؐ������瑁������ĂĔ����{�R�̋��_�ƂȂ��Ē�R�^���𑱂��A�d���ł͍��p���n���E�ԏ���������ǐe�����d�|�Ɍĉ����ċ��ɍU�ߓ�����ʂ��������B���������̒��A�����͉B��̒E�o�ɐ������A���˂̍������a���N�Ɍ}�����đD��R�ɋ���A�������d�|���e�n�ɔ����A���q���{�ƑΌ�����p���������Ă䂭�B |
|
|
��6�D�|���̐����ƌ��������̎���
�@ ����V�c�́A���a���N�Ɍ}�����Ĕ��ˑD��R�ɋ����Ĉȗ��A�e�n�̔����{���͂��d�|�����āA�|���̒��S���͂ƂȂ����B����ɍł��悭�������̂��A�d�������p���n���E�̐ԏ��~�S�����A�͓��̈��}�A��ؐ����ł���B �@ ���̓�l�́A����ɂ��Ƌ�������̖k�����q�����̔z���ł������Ƃ����B�ނ�͈�ʓI�ȕ��m�Ƃ͈Ⴂ�A�X�����������ʍs�����������A���ƂƂɂ��鎖�ŗ��v���グ����Ɛl���͂ŁA���q���{�������A����オ��̖k�����͑��̌�Ɛl�������͂��������������߁A�ނ�𗘗p���Čo�ϊ�Ղ�傢�ɋ��������Ƃ����B �@ ���q�����ɂȂ�ƁA�k�����͑S���Ɉ��|�I�x�z��W�J�������߁A�ނ�̗͂�K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ����̂����m��Ȃ��B�����́A�ԏ��A���̖k�����ɑ���s���������āA���w�Ɋ��U�����Ƃ��l������B �@ ������ɂ���A���̓�l�͒�����ɑ���傢�Ȃ鏕�͂ƂȂ����B �@ ��ǐe���ƂƂ��ɋE���ɐ��͂�A�瑁��ɋ����Ċ��q����̑�R���������A�S��ɔS���@�ƍ̂��ؐ����B����͒�����ɂƂ��Ă��Ȃ킿���̖������ʂ������B �@ �R�z�̊X���ɐ��͂�A�ےÂ�i�����ĘZ�g���̌R���Ɛ킢�A�����ł��j���ē�x�����s�ɍU�ߓ������ԏ��~�S�B����͒���ɂƂ��āA�U�����邽�߂̕���A���Ȃ킿���̖������ʂ������B �@ ��l�̊���ɂ��A�k���̗͂��̂��̂Ǝv���Ă����e�n�̐��͂��A�|���̉\���������̂��̂Ƃ��Ċ����n�߂�B �@ ������C�^���@�m�����k���@��(���@)�̍����́A1333�N�t�A�k���ꑰ�d���̖��z���ƂƁA������Ɛl�ő�̎��͎ґ��������ɏ㋞�𖽂��A�Z�g���̋~���ɓ��ĂĐԏ��~�S������悤�Ƃ����B �@ �㋞�������������͘Z�g���ɂ͓��炸�A��̎��Ə㐙���̉Ɨ̂ł���O�g���ɓ���A�����ɒ��Ԃ����B �@ ����̖��z���Ƃ́A�ԏ��~�S�����ׂ��ނ̖{���n�ł���d���ɐi�R���A����ƍ���ɓ���B���{����̑�R�𗦂��Ĉ��|���悤�Ƃ������z���Ƃł��邪�A�ԏ��~�S�w���̑O�ɎU�X�ɑł��j���A���g���펀����Ƃ�����s���i�����B �@ �Z�g���R�����x���j��A���{����̋~���R�܂ł������j�A�叫�̖��z���Ƃ�ł�������ԏ��~�S�̌��т͐��ɑ傫�Ȃ��̂�����B�������A�ԏ����ʂ������ő�̌��т́A���̑叟�ɂ���āA���������ɖ��{�ւ̌���������������ł������B �@ ���������́A2�N�O�A���e�̑r���ł���ɂ��ւ�炸�A�����̕ςŒ���R��|����ɓ�������Ă���A����܂�����㋞�𖽂����A�]�R�������鎖�ɑ��Ėk�����ɑ��锽�������߂Ă����B1333�N4���A���z���Ƃ̔s����������́A�O�g�R�Ŕ��k���̊����N���ɂ��A�ԏ��~�S�ɋ��͂��ē����A�Z�g���T���łڂ��ċ��𐧈������B �@ �k�����ɑ����吨�͂ł��鑫���Ƃ��A���k����\�����Č���鑤�ɕt�������͑傫�������B �@ �����ƕ��Ԍ����̖����ł���Ȃ��疋�{����������Ă����V�c�Ƃ��A�����̋`�傪�����Ƃɓ������Ċ֓����Ŕ������N�����A�R���𗦂��ē쉺�A���q����C�ɍU�����Ėk��������ł������B �@ ���̎��ԂɁA�瑁������͂�ł������{�̑�R�͓��h�A��ؐ����̖Ҕ����ɂ����Ă������Ȃ�����A�_�����U����B �@ �S�ǂ̋������ւ����k�����̎x�z�́A����V�c�̕s���̓��u�ɂ��A���ɏI���̎����}���鎖�ƂȂ����B �@ ���˂̒n�ɂĖ��a���N���풉���ƂƂ��ɖ��R�ɒ�R���Ă��������́A�e�n�Œ��������������ɋy��ŗI�X�Ƌ��֓���A���{�̗i�����������V�c�̒�ʂD���āA6���A�V�c�e���̐���������錾�����B |
|
|
��7�D���������̍���
�@ �k�����ɔ��������e�n�̐��͂Ɏx�����A�Ăђ�ʂɕ����ĐV������������������V�c���������A���̐����͓��������T�������������B �@ �܂��͐���̎��s�ł���B �@ �V�c�e�����̂��̂Ƃ��悤�Ƃ�������V�c�́A�����V�c�̒��������V���A�֔���p���Ē���̋��K�����~�߂��B �@ �L�^���A���ܕ���V���ɐݗ����A���߂̕����A���Ƃ�o�p���Ă���ɓ����点�A�ŏI�I�Ȍ��茠�͓V�c�������d�|�ɑS�Ă��W�����B �@ �������A�����{���̎�������Ǖ����āA�f�l�W�c�Ŏn�߂������́A���R�̔@�������ɂ͍s���Ȃ������B �@ ���ɉ��ܕ��ł́A�e�n���珊�̂̈��g�����߂đ召�����̕��Ƃ����ɎE���������߁A�V�c�e�ق��d�|���s�͓���Ԃɍ��킸�A���������ԂɊׂ����B �@ ���ɓV�c�Ɠ����̕s�a�ł���B �@ �����ƁA�哃�{��ǐe���̔����ȑΗ����\�ʉ�����B�哃�{��ǐe���́A�E���̔����{�R�����W���邽�ߐe���̖��O�Łu�d�|�v��A���������A�{���A�u�d�|�v�����������ł���̂́A�B��V�c�݂̂ł���B�e���̂悤�ȗ���Ŋe�n�ɖ��߂������ƂȂ�A����́u�d�|�v�ł͂Ȃ��āA�u�ߎ|�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��B �@ �e���́A�ߎ|�ł̓C���p�N�g���ア���߁A�����āu�d�|�v�𖼏���Ċe���͂ɞ��������̂����A����邩�猩��A����͎���̗�������R�ƐN���s�ׂŁA�s���̋ɂ݂ł͂������B �@ �V�c�̒������鏗���A������q���A�����̎q��������̓V�c�ɏA���悤�ƁA�L�͂Ȍ��Ń��C�o���ł���哃�{�ւ�槌����ɌJ��Ԃ������߁A���悢��e���ւ̕�������͋����Ȃ�B �@ �������A�|�����͂̈ꗃ��S�����哃�{�e���̑���т����邱�Ƃ͓���ł����A�e���̗v���������Α叫�R�̒n�ʂ��A�����͔F�߂���Ȃ������B �@ ������哃�{�̗��ꂩ�炷��A�S���̕��m���������闧���V�c�̑��q�ł���e�������ĂA�����ƒ��삪���₷���Ȃ邾�낤�A�Ƃ̔z������o�����̂Ǝv���邪�A���Ƃ̓����Ƃ��������F�߂������Ă��܂����A�Ƃ����_�ɂ����āA���Ƃƕ��Ƃ̊u�ĂȂ���ʂɗ��Ƃ��Ƃ��Ă�������邩�炷��A���܂��܂�������ł������Ǝ@������B �@ �O�ڂ͐l���̎��s�ł���B �@ �E���̖��R���ނɑ���̂�������ؐ����A���ˑD��R�Ō������}�����ꂽ���a���N�A��ɋߎ����Č��т��グ������e���A���㌹���̖���Œ邩�甲�F���A��ɍs�������ɂ������Ƃ̐�풉���́A�u�O�؈ꑐ(�����̂��E�ق����E�䂤���A������)�v�ƌĂ�A����ȉ��܂Ə��������B �@ ��ؐ����́A�����g�A�͓����i�A�͓����A�a����ɔC���B���a���N�͔��ˍ��i�A�������i�A���ܕ��ɔC���B����e�������������ܕ��A��풉���͏]�O�ʁC�e����J�C�Q�c�ɔC������A�e�X�j�i�̑ҋ������B �@ �������A���̎l�l�Ɍނ���A���邢�͂�������邩�A�Ƃ������т��������l�Ԃ��A���̒��ɓ����Ă��Ȃ��B�ԏ��~�S�ł���B �@ �����͉��܂Ƃ��Ĕd����삪�^����ꂽ���̂́A�܂��Ȃ���������D����Ă���B����ɂ��A�ԏ��~�S�͑哃�{�Ƌ߂������߁A�ԏ����d�p����Α哃�{�̒�����ł̒n�ʂ��������鎖�ɂȂ�A�����ƈ�����q�́A����������Đԏ����������Ƃ�������B �@ �m���ɁA�哃�{�����Ƃ��Ĕ�b�R�ɓ����Ă���������������A�ԏ��~�S�͑��q�̑��S���o�Ƃ����ċߎ������A�哃�{�Ƃ͘A�g��[�߂Ă����B�������A�ǂ̒��x�哃�{�Ɛe���ȊW�ɂ������̂��͕s���ł���B �@ �������A�ԏ������������́A���Ƃ��ƌ��������ɈÂ��e�𗎂Ƃ��Ă����B �@ ���̏�A���k�𐨗͂��܂Ƃ߂�ő�̂��������ƂȂ��������������A�V�����̂ǂ̖�E�ɂ��A���Ȃ������B�ꉞ�A�]�O�ʕ������^�����A�����̎����ł��鑸��(�����͂�)���ꕶ���������āA�����Ɖ����������A�����̂���L�^���≶�ܕ��̏d���ɂ͓���Ȃ��B �@ ���̐��l�́A�V�����Ɂu�����i�V�v�Ɖ\�����āA���̐l����s�v�c�������B �@ ����́A�V�����̍��������z���āA�����������ނ������̂��Ƃ�������B �@ ������ɂ���A�ȏ�̂悤�ȗl�X�ȉΎ������āA����Ȃ�ƐV�������^�c�ł���킯���Ȃ������B |
|
|
��8�D�����̑����Ƒ��������Ƃ̑Η�
�@ ���Ƃƕ��Ƃ̉��܂�S���d�|�ōق����Ƃ��������ł��������A���G�ɓ��藐�ꂽ�e�n�̍����̝��ߎ����~���ɉ������鎖�́A�t���Đn�̒���ł͓���s�\�A�������V�c���߂̌��Ƃ́A���{�Ƃ�����돂�����������m�B��K�����������Ɉ���Ȃ��������߁A�㋞�������Ƃ��y���ɂ��A���͑卬���Ɋׂ����B �@ �����œV�c���d�|���\�̍l�����𑽏����߁A1333�N7���A�k�����ȊO�̖��{������o�p���A�G�i���f����݂��ĉ��܊֘A�̎����������ϔC�����B �@ �������A����͕��Ƃɑ��Ă݂̂̐��x�ɘa�ŁA�t�Ɏ��А��͂�㋉�M���ɑ��Ă͏]���̗���������ɔ��D���A�V�c�ꐧ�̏��u���ѓO���悤�Ƃ����B �@ ����1334�N�A�����ƌ�����ς��Ă���͌����̐ꐧ�ӎv�͈�w���܂�A�����(�{�a)�̑��c��n���ւ̉ېŋ����ȂǁA�����I�ɂ����������j�������܂ō̂葱�����B �@ ����ɔ����������Ɛ��͂̂����A�k���e�[�A���Ɛe�q�́A�����̎q�A�`�ǐe���𐄑Ղ��ė����ɉ������A���ڏ���������Ƃ������������R�{�����グ�A�Ɨ������n���������������������B �@ �����̌��Ɛ����ɋ��Ђ����������Ƒ����A�����̒푫�����`���A�����������̎q�ł��鐬�ǐe����Ċ��q�ɓ���A���l�ɏ��R�{������ēƗ������������\�z���Ă������B �@ �����́A�e�n�̗L�͐��͂ɑ��q��a���Ď����̌������₳�Ȃ��悤�ɁA�Ƃ�������̐헪�Ƃ���v�������߁A�V�c���g���������������A���ۂ͌��ƁA���ƂƂ��ɐV���ɑ���s�������߂Ă���A�������҂̔�r�I���ւȔ�����i�ł������Ƃ�������B �@ �����ɁA���̂悤�Ȓn��������F�߂����́A�K�R�I�ɓV�c���g�̎x�z�͂��߂���̂������B �@ ����ɁA������q�����������ƌ���ŁA�������F�����߂Ă����哃�{��������槌��������߁A1334�N10���A�V�c�͂����ߔ��A���q�̑������`�̌��ɑ���A�e����H�����B�|���̐킢�Ɍ��т�����A�c���Ȃ��琪�Α叫�R�̒n�ʂ��Ȃ��ĕ��m�ɌN�Ղ��悤�Ƃ����哃�{���A�V�c�̎�����Ȃ��ĒǕ��������͑厸�s�ƌ��킴��Ȃ������B �@ ����Ȍ�A���m�̗͕͂��m�ł������������Ȃ��Ȃ��Ă����B �@ �V�c���d�|�̉��l�͓���͌��̗����ɂ��炩����قǒn�ɗ����A�����͂��悢�捬���̋ɂ݂ɒB�����B �@ ���q���{�̖k�����Ɛe�����A���Ɛ\�����C����������Ɛ������Ƃ́A���{���ŖS������͐������牓�������A����̋ɂ݂ł��������A������@�͂����s���Ƃ��čĂіk���Ƃ̓V�����������ׂ��A���q�ŐV�c�`��ɔs�������k�������̈⎙�A�k�����s��i���Ă��ɔ������N�������B����𒆐��̗��ƌĂԁB �@ ���@�̔��ӂ͂����ɒm����n�E���ꂽ���A���s��1335�N7���ɐM�Z�ŋ������A���e�J�A����w���A�{���A������o�̑�ő������`�R��j���Ċ��q�ɓ������B �@ ���̂Ƃ��A�s�����鑫�����`�͂ǂ������ɂ܂���đ哃�{��ǐe�����a�E����ɋy�ԁB �@ ���������́A�풼�`�����q��ǂ�ꂽ���Ԃ��āA���q�̒D�Җ��߂Ɛ��Α叫�R�̔C����]���A�����̖�]���������V�c�͂���������Ȃ������B �@ �����͓{��A�V�c�ɖ��f�ŌR���𗦂��ē��C���������A�Q�Ă��V�c�́u�������R�v�Ƃ������r���[�Ȓn�ʂ��ړ����̑����ɑ���A�ނւ̈ԕ���}�����B �@ �O�͂Ŕs�����Ă������`�Ƒ����͍����A���]�A�x�́A���͂ɖk�����s�����j���Ċ��q��D�������������A����邩��̋��ւ̋A�Җ��߂��͋��ۂ��A���Α叫�R�̔C�����Ăі]�B �@ �����͂�����ƒf��A���������A���`�Z��̊��ʂ�S�Ĕ��D���A������l�̌��������ł���V�c�`����R�̒��ɔC���Ċ��q�U���Ɍ����킹��B���ɁA�����̖������R���́A���������Ɠ������ƂɂȂ����B�@ |
|
| ������V�c4�@ | |
|
�������`�����l(1288-1339)�@恁F����(�����͂�)
�@ ��F���@�̑��c�q�B��͒k�V��@�������q�B����V�c�̒�B�q�Ɍ�ǐe���E���ǐe���E���ǐe���E�@�ǐe���E��q���e��(������{)�E�ˎq���e��(�Ō�̍{)�E���ǐe���E�㑺��V�c�ق��B��o�����E�����@���n�} �@ �ꂪ��F���V�c�Ɨ������T�R�@�̂��Ƃɓ��������߁A���@�̒������Ĉ�B�����O�N(1308)�A����V�c���}������ƁA�����@���̉ԉ��V�c���H�N�������A����V�c�̈�q�M�ǐe���͗c���ł��������߁A���ʌ�M�ǂ𗧑��q�����邱�Ƃ������ɍc���q�ɗ��Ă�ꂽ�B���ۓ�N(1318)��T���A���N�O���A���ʁB��F���@���@����~�����B�������N(1321)�A��F���@�̉@����~�ɔ����A�e�����n�߂�B���̔N�A�L�^����u���đi�ׂ�e�ق���B�������N(1324)�A��F���@��������ƁA�t�{�M�ǐe����p���Ďq�����c���q�ɏA���悤�Ƃ������A���q���{�̋���ɑ����B���N�A�����̖��c���R�ꂽ���A���{�͎������ւɏ�����(�����̕�)�B�����O�N(1326)�O���A�t�{�M�ǐe�����I������ƁA���{�͗����R���̌����ɑ���A�����@���̌㕚���@�c�q�ʐm�e�����c���q�ɗ��Ă��B���{��������V�c�͍Ăѓ����v���i�߁A����r��������ɔh�����Ė��{�ɔᔻ�I�ȕ��m�������������B���O���N(1331)�A�d�͍ĂјI�����A����V�c�͊}�u�֑J�K�B�܂��Ȃ���ؐ������͓��ԍ��ɋ����������A���N�㌎�A�}�u�͗��邵�A�V�c�͕߂����Z�g���T��ɂ���ėH���ꂽ(���O�̕�)�B�\���A�����@���̌����V�c���H�N�����B �@ ���O��N(1332)�A�B�ɔz���������A��ǐe���E��ؐ��E�ԏ��~�S�炪�e�n�Ŏ��X�ɋ������A��͋}�ρB���N�B��̒E�o�ɐ���������A���������炪�Z�g�����A�V�c�`��炪���q���U�����āA���Ɋ��q���{��ŖS�ɒǂ�������B�Z���A�������Đe�����J�n(�����̐V��)�B����E�V��̎��𗝑z�Ɍf���A�����̐��̊v�V�Ɏ�肩���邪�A���܂Ɍ��������������ƂȂǂ��畐�Ƃ̔����������B������N(1335)�A�����������V�c�`����������Ƃ𖼖ڂɋ������A���O�N�����A�����@���̌����V�c��i�������B�\�ꌎ�A�����͖��{���ċ����A�����̐V���͂킸����N�܃J���Ŋ�������Ɏ������B���N�\�A����V�c�͋���E�o���ċg��Ɉڂ�A������Č�(�쒩)�B�Ȍ�A�k���Ƃ̐킪�������A����ɗɂȂ钆�A�����l�N(1339)�����\�Z���A�s�{�g�����R�������։����ɂĕ���B�\��B�Ⓔ�ɂ�����ƒǍ����ꂽ�B �@ ������N(1325)�A����ג�ɑ���E��W���i������B�V���W���o�B������W�͌v���\�O��B�܂��y����̐V�t�W�ɂ͎l�\�Z��̂��Ă���B�w�����N���s���x�w���������s���x����B |
|
|
���t
�@ ��� �@ �����Ȃׂċ�ɂ�����t�̐F�����̂��˂݂̂��Ȃ�(�����14) �@ (��̐F�A���̐F�A�R�̐F�c�c�ǂ������������t�߂������邵�������Ƃ��̂����A�����̐������������Ȃ̂��ƌ�������ɃE�O�C�X�����Ă���B )�@ �݂��̋{�Ɛ\�����肵����܂��������� �@ ���݂̂�͏t�̐[�R�݂�܂̉Ԃ��݂��݂̂ڂ�_�̏�̌�(�����178) �@ (�������܂ł��t�̐[�R�̍������Ă����悤���B�������������点�Ă���A�_�ɉB�ꂽ����B )�@ �@ �肵�炸 �@ ���͂���}�ɂ������Ԃ����炶�̂ߏt�J���������(�V�t82) �@ (���͂����}���Q���Ă��Ă���Ԃ�����܂��B�t�J���~��A�̉���ӂ���ގ����������Ƃ�m�邱�̍��B) �@ �F��̍s�{�ɂ��܂��܂����鎞�A�_��̍��ƂĐ������̂قƂ�ɗL�肯��Ԃ̍炫������䗗���Ă�܂����Ђ��� �@ �����ɂĂ��_��̍������ɂ��肽�����肻�߂̏h�Ǝv�ӂ�(�V�t83) �@ (�g��̍s�{(����)�́A���������߂̏Z�܂��Ǝv���Ă����̂ɁA�����ɂ��u�_��̍��v�ƌĂ��Ԃ��炢���̂������B) �@ |
|
|
����
�@ �F��̍s�{�ɂĂ��ւ̂��̂��ǂ����������ĉ̂�ݎ��肯����łɁA�܌��J(���݂���)�Ƃ��ӂ��Ƃ���܂��������� �@ �s���ɂ��т����肵���_�͂�ʖF��̂����̌܌��J�̔�(�V�t217) �@ (�~�J�̋G�߂Ƃ��Ȃ�A�s�ɂ��Ă����₵�������̂Ɂc�c�B�_������邱�Ƃ̂Ȃ��g��̎R���̘̂т����͂Ȃ����炾�B) �@ |
|
|
���H
�@ ������N�l�X���������Đ��̂����܂肯�鎟(����)�ɁA�H�A���Ƃ��ւ鎖����܂��������� �@ �[�Â��揬�q�̕�͖��݂̂��ĎR�̉��Ă�H�̍g�t��(�V���565) �@ (�[����A�u���Â��v�Ƃ������q(������)�̕�͖�����ŁA�R�̉��ɖ��X�ƏƂ�f����H�̍g�t��B) �@ ���O�O�N�㌎�\�O��O��̍u����ꂵ���A���O���߂Ƃ��ӂ��Ƃ� �@ �����̂тʔ���(�͂�)�㌎(�Ȃ���)�Ȃ�����̌��̖邳�ނɈ߂���(�V�t367) �@ (�����Ă���̂��h���Ȃ����B�����㌎�Ɛ[�܂�䂭�H�̖�A�₦�₦�Ƃ��������̎˂�����ɁA�m(���ʂ�)��ł����B) �@ ���O�O�N�㌎�\�O��O��̍u����ꂵ���A���O�e�ԂƂ��ւ邱�Ƃ���܂������� �@ ����͂ʐF�����݂�ꔒ�e�̉Ԃƌ��Ƃ̂��Ȃ��܂�����(�V�t386) �@ (�Ȃ��F���������A���e�̉ԂƁA���̌��Ƃ����������߂ɁB) |
|
|
���~
�@ �F��̍s�{�ɂĂ�܂��������̒��� �@ �ӂ���тʑ����ނ���̏��͂���đ��ɂ͂������R���낵�̕�(�V�t461) �@ (�h���ĐQ�Ă����Ȃ��B�����~�肽�悤�ɗ₽���Q���͍r��āA���̌��Ԃɐ�������A�������R�C�̕��B) �@ �L���߉����܂��������� �@ �V�������ނ��炵�����q�����ւ�_�H�̖������̋�(����E��454) �@ (�V�𐁂��n�镗�����Ɋ��������B�ܐ߂̕��P�������A���Ă䂭�A�������̋�̉_�̒ʂ�H��B) �@ |
|
|
���G
�@ �肵�炸 �@ �Ȃ��ނ�����Ȃ��Ƃ��点��Ë��l�����݂͂���(�V�t552) �@ (���͉�������ɂ����āA���Â��ƌ��߂Ă���\�\���̋�́A�s�Œ��߂�̂Ɠ�����Ȃ̂����ƒm�点�Ă�肽�����̂��B�����������̐l�X��A���Ȃ��������̌��߂Ă��邾�낤�B) �@ �͌�����܂������� �@ �Ă炵�݂��֑�݂�������ɂ��ތ����ɂ���ʔg�̒�̐S��(�V�t579) �@ (��֑��̖ʂɐ��e���f�������A�g�̒�܂ŏƂ炵�Ă�������A���̐쐅�̂悤�ɑ���Ȃ������ȉ䂪�S���B) �@ �肵�炸 (���) �@ �܂��Ȃ�ʂ�����̌��̂ނ玞�J���Ƃ��ɂ��ʂ�鑳����(�V�t1119) �@ (�܂�����Ȃ������̑e���ȏ����ŁA����@���ʂ�J�̉����ɂ��Ă��A�䂪�g�̋������v������A�߂����ė܂ɔG��鑳�����Ƃ�B) ��Ȗ�Ȃ̂Ȃ����߂Ȃ肵�����ɂ��҂ǂقɂȂ�[����̋�(�V�t1120) �@ (�邲�Ƃɒ��߂錎�������S�̈Ԃ߂ɂȂ����\�\���������̏o���x���Ȃ�ɂ�āA���ꂳ��������đ҂��ƂɂȂ�A�[��̋��B) ���͍����A�Â̍����z��̏h�Ƃ��ӏ��ɒ��������ЂāA�[�Â���ق̂��ɂ����������Ȃ��߂��͂��܂��B �@ ���������̌��̌������������Ȃ��s���̋�(����) �@ (�����������̂ŁA���z�̏h�̌��[�Ɏ˂��������邱�Ƃ��ł����B���ꂩ���͂ǂ��Ȃ�̂��낤���B) �@ �肵�炸 �@ ���Â����g���ΒV�����ȂׂĐ��̂����邼�炫�����̂͂�(�V�t1130) �@ (���Ⴊ�ς������\�\�䂪�g�����̂܂ܐ��ɖ�����Ă䂭�Ƃ��Ă��A�V���͂��Ȃ��B��������A���̒��������Ȃׂē܂��Ă��܂��̂��h���̂��A�����̐�͗l�̋�̂悤�ɁB) �@�@ |
|
| ������̏����W�ƍc�q�����@ | |
|
���͂��߂�
�@ �\�l���I���{���ʂ������I�Ȓ鉤�E����V�c�B�ނ͊W�����������O�\�l�ȏ�A�ׂ����q���͎O�\��l(���V�c�Ɏ��������)�Ƃ�����ł����o�������݂ł����B���̍c�q�����́A����̗��z�����߂�킢�Ɋ������܂�A����ȉ^�������ǂ鎖�ɂȂ�܂��B�����ŁA����͌���V�c�̎�v�ȏ����W�ƁA�c�q�����̗����������Ă��������Ǝv���܂��B�c�q�����ɂ͓쒩�̊����Ƃ��đ傫�Ȗ����������l���������A����̍��Ɛ헪�������ł��L�p�ł��낤���Ǝv���܂��B�Ƃ����Ă��A�u�鉤����v�����Ɍf�ڂ��ꂽ�\���ʂ��ĉ���������������ł����ǂˁB |
|
|
������ƍ@�܁E�c�q����
�@ �����{�@�������U�q(�������琬��@�A������㋞�ɉ@) �@ �֓��\���Ƃ��Ē���Ō��͂�U����Ă��������������̖��B���a��N(1313)�A���킪���Ƃ�蟲���Ď�ɂ��ꂽ�Ƃ����B���ɐ����\��B���푦�ʌ�ɂ͒��{�ƂȂ�B�Ԃɜ�q���e����ׂ����B �@ ��q���e���F��Ɍ����@�ɓ������鐭��@�ƍ�����B �@ ������q �@ ����א��̖��B����Ƃ͘a�̏@���̉ƕ��ŁA�ޏ����g���u�V���W�v�Ɍ���W����ȂǗD�ꂽ�̐l�ł������B����[���T���Ƃ��Č���V�c(����ٕ̈�Z)�Ɏd����B����������͔ޏ��ƒʂ��đ��ǐe���A�@�ǐe���A���q��ׂ��Ă���B �@ ���ǐe���F�u�����v�u�����L�v�ɂ��Α��c�q�B���킪���O���N(1331)�ɋ��������ۂɂ͏]���Ċ}�u�ɘU�����B�}�u���ח�����Ƒ������ēy���ɗ�����邪�A���O�O�N(1333)�ɒE�o���ċ�B�ɓn�茻�n�����ɗi������ċ������Ă���B�����������������Č��������������������N(1336)�ɂ͍P�ǐe���Ƌ��ɐV�c�`��ɗi����ĉz�O������ɓ����Ă���B���N�A�������ח��̍ۂɎ��n�B �@ �@�ǐe���F��O�c�q�B�����́u�����@�e���v�Ɩ����V�����Ƃ��ĉb�R�̔c�������҂����B���틓�����ɂ͉b�R�ŋ�����������s�A�}�u�Ɉڂ��Č���ɐ��s������߂炦���]��ɗ������B���킪�g��Ɉڂ��Ă���͊ґ����ĉ��]�E�M�Z�Ȃǂ𒆐S�ɍb�M�z�E�k���e�n������쒩�̋��_���݂ɏ]������B�㑺�ォ�琪�Ώ��R�ɔC�����A�������N(1352)�Ɋ֓��̓쒩������ĖI�N�����ۂɂ͂��̑��叫�߂Ă���B�Ȃ��A�{���͕��l�C���ł������悤�œ쒩���̐l�̘a�̂��f�ڂ����y����u�V�t�a�̏W�v�⎄�ƏW�u���ԏW�v��Ҏ[���Ă���B �@ ���q�F�B��ɗ����ꂽ�����炢�A�Ďq�œ�Ƃ��ĉ߂������Ƃ����B���ǁE�@�ǂɂ������鎖�ł��邪�A�q�Ƃ̊Ԃ̎q�͌���ւ̖����Ȍ��g������X���ɂ���B�܂��A��̌����p�����̂��̐l�Ƃ��Ă̑f�{���ڗ��B �@ ���V�`��@��� �@ ���������r�̖��B��F���@(����̕�)�Ɏd���Ă��̎q���Y�ށB����Ƃ̊Ԃɂ͐��ǐe���A�ӎq�A�Ñ��@�e����ׂ���B �@ ���ǐe���F�u�����v�ɂ��Α��c�q�B�������Ƃ̏������Ƃ��Ă���������ł��������Ƃ�����킩���p�҂Ƃ��Ċ��҂��ꂽ�B�����O�N(1330)�ɎႭ���ĕa�v���Ă���B �@ �Ñ��@�e���F����@��ՂƂȂ����Ƃ����B �@ ���������O�� �@ �k���e�q(�t�e�̖�)�Ƃ����B�����V�c(�����@��)�A�����ŋT�R�@(��o�����̑c�A����̑c��)�Ɏd���ċT�R�@�̎q���Y�ށB����Ƃ̊Ԃɂ͌�ǐe���A�E�q���e���Ƃ�����l�c�q��ׂ����B �@ ��ǐe���F��l�c�q�Ǝv����B�ʏ́u�哃�{�v�B�u���_�@�e���v�Ƃ��ēV�����ɔC�����b�R�𖡕��ɂ��鎖�����B���̍ہA���|�̌P���ɗ]�O���Ȃ������Ɠ`������B���킪���O���N(1331)�ɋ�������Ɖb�R�m���B���@�e��(�@�ǐe��)�Ƌ��ɑg�D���ċ������邪���s�B���̌�͓�ؐ����̐ԍ��ɓ���A�X�ɋg��R���������Č��n�����𖡕��ɂ��A�X�ɏC�����g�D�𗘗p���Đԏ��~�S���n�߂Ƃ���e�n�̍����ɋ����𑣂��đg�D�������B���킪�B��ɗ�����Ă�����Ԃɂ͑��i�߂Ƃ��Ċ������Ă���A��q�̐헪���틵�̕ω��ɑ傫���v�����鎖�ƂȂ�B���ɂ͐��Α叫�R�ɔC�����邪�A���������ƑΗ����X�Ɍ���ɂ���Ă��̐��Ђ��x������ŏI�I�ɂ͎��r�B�������̐��͌��ł��銙�q�ɑ����A������N(1335)�ɂ͎E�Q���ꂽ�B �@ ���T�R�@�c�� �@ �ڍוs���B����Ƃ̊ԂɍP���c�q��ׂ����Ƃ����B �@ �P���c�q�F��o����ՂɔC�����A���O�̕ςł͔����{�h�ɗi�����ꋓ���B�߂炦���z���ɗ�����A���Y�����B �@ ���R�K���q �@ �R�K����b�E���@���Y�̖��B�n�߂͌�F���@�Ɏd�������A����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ���B �@ ����F���@�����[���� �@ ��F���@�Ɏd���邪�A����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ���B �@ ���g�c��[�� �@ �����{�炵���g�c��[�̖��B���푦�ʎ��ɓT���Ƃ��ĎQ�������u�V�N���J�E���^�v����m���Ă��邪�A�����ł��������͊m�Ȃ��B �@ ��������q(�V�Ҍ���@) �@ �����M���E��������̖��B���{�U�q�ɓ����͎d���Ă������A����ɒ�������P�ǐe���A���ǐe���A�`�ǐe���A�ˎq���e���Ƃ�����l�c�q��ׂ��Ă���B���킪�B��ɔz�����ꂽ�܂ɂ͓��s���A���������ł͑����̏��̂�^�����B�R���錠����U�邤�B�ޏ��̎��͂ɐ�풉���E���a���N�E����e���Ȃǂ��h�����`�����A�s�����������̂��������ɂ����鍬���̈���Ƃ��ꂽ�B�ޏ����������ꂽ�W����A�����q���ꂽ�c�q�������B���̒��ł��`�ǂ͑��ʂ��ē쒩����E�㑺��V�c�ƂȂ�B �@ �P�ǐe���F�����������ōc���q�Ƃ��ė��Ă���B�������N(1336)�A���������������ۂɂ͌��킩��c�ʂ����n����ĐV�c�`��Ƌ��ɉz�O�Ɉڂ���(����������͋g��ɓ��ꂽ�ۂɍĂю��g���V�c�ł���Ǝ咣���A�P�ǂ̍c�ʂ͖�������Ă���)�B���n���d�|���č����𖡕��ɂ����_���݂ɓ����Ă��邪�A���N�ɉz�O������邪���邵���ۂɕ߂炦��ꂽ�B�u�����L�v�ɂ��Α������ɂ��ŎE���ꂽ�Ƃ���邪�A�^�U�͕s���B �@ ���ǐe���F�����������ŁA�������`�ɂ���ėi�����ꊙ�q���R�{�̒��Ƃ����B�������������킩��O��̐_�������Ď����@���E�����V�c�����ʂ����ۂɂ͑����ɂ��c���q�ɗ��Ă��Ă���B�������A���킪�g��ɓ��ꂽ��ɂ͈ʂ�p���ꂽ�悤���B�u�����L�v�ɂ��Α������ɂ��ŎE���ꂽ�Ƃ���邪�A���̌���������Ă����Ƃ����j�������݂��^�U�͕s���B �@ �`�ǐe��(�㑺��V�c)�F�����������ŁA�k�����Ƃɂ��i�����ꉜ�B���R�{�̒��ƂȂ�B���Ƃ����B���狞��ڎw���Đ��サ���ۂɓr���ŋg��Ɉڂ���Ă���A�g��ŗ����q���Ă���B���킪�a��������ɑ��ʁB�㑺��V�c�ƌĂ��B�k���e�[�̕⍲���đ������ւ̒�R���s�����A��ǂɗ����炸�g�삩��ꖼ���֍s�{���ڂ��͂߂ɂȂ��Ă���B�X�ɐ틵�ɂ���ĊϐS���E�������E�Z�g�_�ЂȂǂɍs�{���ڂ��Ă���B�������̓�������ɏ悶�ĉ��x���������߂����ɐ������Ă��邪�A��������ꎞ�I�Ȃ��̂ɏI������B�ӔN�ɂ͓�ؐ��V(�����̎q)��M�C���đ������ƑΖʂ��������Řa���g�p�Ɖ�Ă��邪�A�ʂ����ʂ����ɕa�v�����B �@ ���k����[���T�� �@ �k���t�d�̖��B �@ ���k������[�� �@ ��L�̖��B �@ �������ד��� �@ ���{�U�q�ɓ����͎d���Ă������A����Ƃ̊Ԃ��Z�ǐe���A���ǐe���ɉ����c����ׂ����B �@ �Z�ǐe���F��ɐm�a���ɓ���@�m�@�e���Ə̂����B �@ ���ǐe���F���킪�g��Ɉڂ�����A��B�ɓ쒩���̋��_�����邽�߁u�������R�v�ɔC����ꂽ�B�����O�N(1338)�Ɏl���ɓ�����̂̂����ɂ͋�B�Ɉڂꂸ���炭�ɗ\�̍��ߓ��Ő��R�̕ی����B�����O�N(1348)�ɋ�B�ɏ㗤���A�ȍ~�͋e�r���ɗi�������B���e��ڎw���B���炭�͌��n�ł̑������E�������~���E�쒩���̑����ɏ悶�Đ��͊g���}��A�����\�O�N(1358)�ɒ}��썇��ŋe�r����������j�����̂��_�@�ɓ�N��ɑ�ɕ{�𐧈�����B�S�y���\�O�N�Ԃɂ킽��x�z���Ɏ��߂��B�������������̍��엹�r�ɂ�蕶�����N(1372)�ɑ�ɕ{�������A�O�a�O�N(1383)�Ɏ��ӂ̂����ɕa�v�B��ɕ{���ג��O�A���ƍ����������u���{�����v�ɕ������Ă���A���̌㉇�ė�҉悤�Ƃ��Ă����\�����w�E�����B �@ ���������o����(��������) �@ ����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ��邪�A��ɖk����s�Ɏ���B �@ ���������� �@ ����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ���B �@ �����@��q(�]���) �@ ����b���@���ׂ̖��B���~�@�e����ׂ���B �@ ���~�@�e���F��s���������@�̖�ՂƂȂ�B �@ �������אM��(��������) �@ �����͌���V�c�Ɏd���Ă����B �@ �������e�q(���[���T��) �@ ����Ƃ̊Ԃɉԉ��{��ׂ���B �@ �ԉ��{�F�u�鉤�n�}����{�v�ɂ��Ζ��͖��ǐe���B�l���ɔh������쒩���_���݂̊���Ƃ��ꂽ���Ƃ�����悤���B �@ ������b�� �@ ����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ���B �@ �������ݒ���(��������) �@ ����Ƃ̊Ԃɐ����@�e����ׂ���B �@ ���l�𗲎��� �@ ����Ƃ̊Ԃɑ��{��ׂ���B���݂ɗ����͌���̋ߐb�ł���A��ؐ����Ƃ��W���[�������B �@ ���V���{�@�c�q���e��(�V�����@) �@ �����@���̌㕚���@�̍c���B����������������ɒ��{�U�q���v�������߁A���@�B����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ��Ă���B �@ �������h�q(�����a����) �@ �֔��E����̖��B��͋e�r�����̎o�Ƃ����������邪�^�U�s���B �@ ���������o����(�V��������) �@ �������s�[�̖��B�u�����L�v�ɂ��ΐV�c�`��Ɏ������Ƃ������^�U�s���B �@ �������ۓ���(�V�@�T��) �@ ��Ɍ�ǐe���Ɏd���ē����Ə̂����B�u�����L�v�ɂ��Ό�ǂ̍Ŋ������͂��Ă���B �@ �����@���q��(��[����) �@ �ڍוs���B �@ �����@���� �@ �ڍוs���B �@ ���V��� �@ ����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ����B �@ �����T���]�� �@ �ڍוs���B �@ �������ג���(�V�`��@���q��) �@ ����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ����B �@ �����N�q(���) �@ ���N���̖��Ƃ����B���̏ڍׂ͕s���B �@ �����N����(�ᐅ��) �@ �ڍוs���B �@ �����P��@�߉q �@ ����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ����B �@ �����@������ �@ ����Ƃ̊Ԃɍc����ׂ����B |
|
|
��������
�@ �Ȃ�Ƃ������A��͂�s�ςł��B�p�Y�F���D�ށA�̓T�^�Ƃ��������ł��ˁB���̊W�������Ƃ����Ƃ��邩������܂���B�c���╃�E�Z�̑�����A����̉ʂĂɂ͏f��ɂ܂Ŏ���o���Ă���ӂ�͗��������ɋɂ܂��ł��B���܂��ɏ\��̏������ĉ䂪���ɂ���Ƃ����u�ᎇ�v���݂̎������Ă������ŏ\�܍ΔN��̏����ɂ�����������͈͂̍L�����������t���Ă��܂��B�����܂ł���ƓV����ł��ˁB�܂��A���킾���ł͂Ȃ����̓����̋{��ɂ�����j���W�͑����ɗ���Ă����̂ł��B�Ⴆ�Ύ����@���E��o�������ꂼ��̎n�c�ł����[���E�T�R�Ƃ��ٕ�o���Ɏ���o���Ďq���Y�܂��Ă��܂��B�X�ɁA��[���̈��l�ł�������[���@����͐�����������T�R�Ƃ��W�������Ă��܂��B �@ �����Ă��̈���ŁA�����̎q���B����������Ǝ��Ƃ��ėL�����p���Ă��邠����������ł��ˁB�c�ʂ̖]�݂��Ȃ��c�q�����@�ɓ���̂͊���ł������A����̏ꍇ�͂�������А��͂�c�����Ă��̌o�ϗ́E�R���͂𖡕��ɕt����̂ɗ��p���Ă���̂ł����琦�܂����B�܂��헐�ɂȂ�Ɗe�n���ɔh������Ă��̒n��ɋ��_���݂��邱�Ƃ����҂����ȂǍc���Ƃ��Ĉٗ�Ȃقǔg������Ȑ��U��]�V�Ȃ������Ⴊ�����ł��B���������c�q�̒��ɂ͒P�Ȃ���ł͏I��炸���̌����P���������݂����l�����݂��Ă���A�����܂ŗ��j����������c���Ă���̂ł��B |
|
| �������L1 / ��ؐ����̎����Ƌ��\�@ | |
|
��ؐ����́w�����L�x�ւ̓o��́A�Ռ��I�ł���Ɠ����ɁA�_��I�ȓ`���ɕ�܂�Ă���B���O���N(��O�O��)�������{�A�Z�g���낭�͂琨�̒Njy��Ęa������̘h��R����Ԃ���ցA����ɖؒÐ�ƈɉ�X���������낷�v�Ղ̒n�}�u�R��������܂ւƕ��������킲�������V�c�́A�R��ɉ��̍c�����߂ď����̌R�����W�߂��B�}�u����ɉ�X���𐼂֑���Ɠ�R��݂Ȃ݂�܂���̖ؒÁA���������a��܂Ɠ��݂���k�i�H���Ƃ���A��։���ΓޗǁE�͓��֒ʂ��邱�Ƃ��ł���B�}�u�����s�̑m�������A����ɋߍ��̕��m�������R��ɏW�܂������A���̂����Ɛl�����ɂ�N���X�̕����͈�l���Q�サ�Ȃ��B�ł���������V�c�́A�܂ǂ�݂̒��ŕs�v�c�Ȗ�������B�{���̎����a������ł�̒�炵�����ɑ傫�ȏ�ւƂ����������A�̉A���Ђ낪����������̎}�̉��ɁA��b�ȉ��S����������Ă��邪�A����ɂ͒N�������Ă��Ȃ��B�V�c�����Ԃ������v���Ă���ƁA顂т����������l�̓��q�����R������ƓV�c�̑O�Ɍ���āA���̍��ֈē��������Ǝv���ƁA���q�͓V��֏����Ă��܂��B�ڊo�߂��V�c�͎��疲���킹������B�u�̓�v�A�܂��̖̉��ɁA��Ɍ����č���Ƃ����̂́A�V�q�Ƃ��Ă̓������߁A���{�����̎҂ǂ��������Ɏd�������悤�Ƃ̐_���̂������ɑ���Ȃ��B�����M�����V�c�́A�}�u���̑m���Ă�ŁA���̋߂��Ɂu��v�Ƃ������m�͂��Ȃ����Ɛq�ˁA�߂��ł͂Ȃ����A�͓��������R���킿�̂��ɂ�������̐��ɁA�킭���̂��������q����������̂Ђ悤���܂������Ƃ������m�����邱�Ƃ�m��B�ނ͋k���Z�����Ȃ̂��낦�̌����������ŁA�R�_������V�т������Ă�̐\���q�ł���Ƃ����B���g�������H�܂ł̂��������[�����[�ӂ��ӂ������قɌ}������ؐ����́A�����Ɋ}�u�֔E��ŎQ�サ�A�V�c�Ɂu�V�����n�̌��́A�����ƒq�d�̓�ɂČ�Ӂv�Ƒt�シ��B�܂��A���͂����Ŗ��{�R�Ɛ키�Ȃ�A�S���̕��m���W�߂��Ƃ��Ă������Ƃ͂ł��Ȃ����A�d�͂��育�Ƃ������Ă���Ώ����邱�Ƃ͂��₷���ƌ����A�����āA�u����̏K�ЂɂČ�ւA������̏������ΕK�������䗗���ׂ��炸�B������l���܂������Ă���ƕ��������H�߂���͂A���^��������͂ЂɊJ���ׂ��Ǝv���ڂ��H�߂���ցv�ƁA�������C�ɒ������āA�͓��A���čs���̂ł������B
�@ ���@�̌����A�V�c�̌䎡������������ɑ���Ȃ������Ƃ��āw�����L�x�ɂ��������Ɠo�ꂷ�鐳���́A���łɌ���V�c�Ƃ̊Ԃɉ��炩�̊W�������Ă����B�w�����x���\�܁u�ނ玞�J�v�ɂ́A�u�}�u�a�ɂ́A��a�E�͓��E�ɉ�E�ɐ��Ȃǂ��A�͕��ǂ��Q��ǂӒ��ɁA���̂͂��߂�藊�ݎv���ꂽ�肵��̖ؕ��q�����Ƃ��ӕ�����B�S�҂������悩�Ȃ镨�ɂāA�͓����ɁA���̂��ق̂�����������߂��������T�߂āA���̂��͂��܂����A�����날��ӂ����܂́A�s�K�����Ȃ���������ȂǁA�p�ӂ�����v�Ƃ���A�ԍ��ւ̍s�K���\�肵�Ă����ƋL����Ă���B����ɁA�}�u��ח��ȑO�ɁA���ǐe�������悵����̂��E��ǂ���悵�e���͏���o�āA�u��̖��قɂ��͂��܂�����v�Ƃ�����̂ŁA�������哃�{�����Ƃ��݂̂��ǐe�������Č���V�c�Ƃ̖��ڂȘA�q����̂����ōs�����Ă������Ƃ��m����̂ł���B �@ �K���ɂ��A���̍��̐����Ɋւ���m���Ȏj��������B����͐��c���N(��O�O��)�Z�����̓��t�̂���A�u�̑�ɐ��e���Ƃ��������̂�������̂������Ր쎛�̂��悤���ژ^�v(�V��������)���̘a�ᏼ��(���{��s)�Ɋւ��镔���ł���B �@ ��A����(�a��)�ᏼ�� �@ ����b�m�����S�����䂤�A���]���������\���Ɉ˂�āA����ʂ錳���O�N�\�l���A�s�����d�|����������̗R�A����y�Ԃ̊ԁA�߂��łɕ��ɂɎ{�����ɂ䂤����̒n�A�Ɍ��Y�����낢�̒i�A�V�Ȃ����\���̏��Ƃ���A�����ܓ��A�d�|�����Ƃɐ����ꗹ���͂�ʁB������Ɉ��}�핺�q�сA���������W����������̗R�A�����ӂ��Ԃ�̐��Ɉ˂āA���̐ՂƏ̂��A�����̎���㊯�A���N�㌎�̔䂱����A�N�v�ȉ������[�����ނ�̏��A�s�ւӂт�̎���Ȃ�B����㊯�A���ɓ��m�s���������₤�A�����̉ƁA�̐e���ƔN�v�O�S�A�̉ƈ�~�̒n�Ȃ�A�{�Ɛm�a���������@ �@ ������N(��O�O�Z)�㌎�\�����ɍ��R�Ɛ����������ǂ�悵�e���́A����V�c�����������]������q�ŁA�w�����x���\�܁u�ނ玞�J�v�ɂ��u��̌�q(����)������˂����Ȃǂ����Ƃ��������A���Â��₤����(�x��B������Ă��邱��)�ɕ������ւ�A�����L�^���ւ��䋟�ɂ��o�ł�����(��)�v�Ƃ���A�V�c�����퐭�������w������قǂł������B�e���̓����߂̂Ƃł������k���e�[�́A�u�䐢���ʂ�S�n���āv�A���̎��ɏo�Ƃ��Ă��܂����B���̐��ǐe���̈▽�ɂ���ėՐ쎛�Ɋ�i���ꂽ�\�������̑����̈���a�ᏼ���ł���B�ژ^�͌����͊����ŏ�����A��ӂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B �@ �ᏼ�������b���@�ʏd�Ȃ��̂���݂������̎q�ő�펛�̑m�����S���Ր쎛�����D�����Ƃ��Č���V�c�ɖ]�݁A�V�c�͗��O�N���d�|���o���ē��S�̏��L��F�߂����A�Ր쎛�̍R�c�ɂ��P��A�Ր쎛�̂ƔF�߂��B�Ƃ��낪�A�V�c�̓|���v�悪���o���āA���N�����V�c�͋{����E�o�A�}�u�ɓ���A�����͋㌎�ɐԍ��ŋ��������B����ƁA�a����́A�u���}�핺�q�сv�����̎ᏼ�������̂��Ă����Ƃ��������Ɋ�Â��A���}�������L�̓y�n�Ƃ������R�ŁA�O�N�㌎�����瑑���̔N�v�Ȃǂ�D���A���c���N�Z���̍��ɂ�����܂ŁA�{����m�s���Ă��āA���������Ƃł���B�Ȃ����̎ᏼ���͌̐e���Ƃ����̑����S�̂̈��̔N�v���[�݂̂̌��������̉ƐE�������Ă��āA���̔N�v�͎O�S�ł���A�{���E�͐m�a���������@�����L���Ă���B �@ ���̖ژ^�́A���c���N�Z���ɍ쐬����A�����@���������Ă��������@���̌㕚����c�Ɏ��̈��g����ǂ��肤�ׂ���o���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��l����K�v������B����V�c�͉B��ɗ�����Ďl�����A�����͂܂��������ł���B���̗Ր쎛�́A���ǐe���̕ʋƂ��A���̈�u�ɂ���Č���V�c�̋��Ď��ƂȂ������̂ł���B�Ր쎛�Ƃ��ẮA����V�c�ƌł����т��Ă��镶�ς���̒�q�ł��铹�S��������̑������Ǘ����Ă������Ƃ��B���A�����@�����x���開�{���͂̐N����H���~�߂�K�v���������B�����̘a����͖��{�Ō�̘A�����(������)�ł���k��Ύ������Ƃ��A����͂��̔튯�M�����̂����q��O�Y�ƍl������(�����i��w���q���{��쐧�x�̌����x)�B��o�����̐��ǐe�������L���Ă����y�n���A���Δh�̎����@���̏�c�ɔF�߂Ă��炨���Ƃ����̂ł��邩��A�Ր쎛�́u�앶�v�͂Ȃ��Ȃ�����̂ł���B���푤�̐������A�u���}�v�Ɣ��A���̍s�ׂ������Ȃ��̂ł����Ă��u���W�v(�\�͓I�ȏ��̐N��)���Ǝ咣����K�v���������B �@ �E�̕������㕚����c�̋��ɒ�o����Ĕ��N��A�������Ă��������͍Ăъ������n�߁A�\�ɂ͊�z�V�O�Ȑ�@�ɂ���āA���{���̓���蕧���悤�Ԃ�̗������Ă�����ԍ���D�҂���B�w�����L�x�ł́A���̔������O�A���O��N(���c���N)�l���̍���Ƃ��A�����̐������Ԃ���N������Z�����ɏk�߂Ă���B���̐ԍ��D�ҍ�킩�琳���̑�̋����E���킪�n�܂�̂ł���A�����O�O�N(���c��N)�ꌎ�ܓ��ɂ͓�͓��̋I�B�Ƃ̋��Ɉʒu����b�㑑���������܂�(�V��)�ŋI�ɍ��̌�Ɛl���������삯�U�炵�Ėk�サ�A�\�l���ɂ͉H�g��͂т��̎s������܂Ői�o���ĉ͓�������j��A�\�ܓ���ɂ́u��؊ۗ^�R��(�Z�g���R)������ꍇ��v(�w�������L�x���c��N�ꌎ�\�Z����)���Ă���B��ؐ��̐i���������ɐv���ł��������́A�����̋L�^�ł���w��؍��풍���x�́u��(�ꌎ)�\�ܓ��@����(�͓���)��Ɛl�@����Ƃ������q�厩�����X�@���c�n�����@�k��n���㓯�v�Ƃ����Z���L��������M�����Ƃ��ł���B���ӂ̒n�������́A��ؐ��̐i�U�ɑΉ������ꂸ�ɁA���@�ɕ����āA�����炭�͓����U�����̂ł��낤�B�\����ɂ́A�V�����ɏ�s���\�����Z�g���R�Ƃ�����ȁA�\�l���Ԃɂ���ԍ���̖��A��،R�͏��������߂�B�w�������L�x�́u��\���@�V�����R��(�Z�g���R)�ߍ~���B�����ޓ�n�ӈꑽ�Ȕ탌�n�]�X�v�ƋL���Ă���B�n�ӂ̋��l�܂ŘZ�g���R��ǂ���������ؐ��́A��\�������\����܂ł̓���ԁA�V�����ɑؐw���āA��\����ɂ͐ԍ�E�瑁�̖{���A�����B�����̓V��������͂���ŏI�����Ă���A�w�����L�x���������Ƃ��Č��`����ł�A�E�҂ȋI�����}�𗦂���F�s�{���j�Ɠ�ؐ����Ƃ̊Ԃ́A����Ζ������m�̋삯�����́A���炩�ȋ��\�ł���B �@ �����ɂ�����A�����̑f���m��j��������B��Ɉ��p�����A�O�֔����������̓��L�w�������L�x�̐��c��N�[����A���Ȃ킿�A�V��������̈ꂩ���Ə\����̋L���ł���B �@ ������N�@���l��]�A�ߓ��L��a�̈ꂭ���̖̂˂͂��܂���ɐ����̂��}������ɂƉ��̏o���� �@ �Z�g���T��ق̖�ɓ\�͂��Ă����\�����Ȃ��ł͂Ȃ����̗�����A�����ɓ`�����҂͒N���A�Ƃ����_�ɂ��������o���邪�A�����͊��z���q�ׂ��A�ӎ��I�ɂ��A����̏o���ɂ��ĉ����L���Ă��Ȃ��B�����w�҂̒���s���́A�u�����͖����ł��������A(�����L��)��҂͐�����m���Ă����B�����̏o���E�o���A���Ȃ킿�w�˂͂��܂���ɐ���x�Ƃ����ߋ��ƁA���{�𗠐��Č�����Ƃ��ċ�������������m���Ă��āA���������̂��Ƃ�S���L���Ȃ������B�����ɉ߂��Ȃ����A��҂͐����Ɋւ��Ắq����r�Ƃ����s�ׂ�`�������Ȃ������B(����)�L�������ɂ́A���������̑f����m��҂����āA���ꂪ���̗���Ƃ��Č��������̂ł��낤�v�Ɛ�������(�u�w�������L�x�̘a�̈��v�R�L�ƌ�蕨 23�@��㔪���E�O)�B���̗�����A�s�̐l�X���悭�m���Ă��āA�������A��҂��w�����L�x�̒��ňӎ��I�ɔ�I���Ȃ���������̈���Ɖ��߂���ƁA�����͍L�����Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B �@ ��ؐ��������{�̌�Ɛl��k�@�̔튯�������\���ɂ��ẮA���j�Ƃɂ���ČÂ����炢���Ă����B�Ƃ��ɖԖ�P�F���͈�т��Ă��̂��Ƃ��咣���A��O�E���̐����́u�����v����A�������R�ɂȂ��Ă悢����ł͂Ȃ����Əq�ׂĂ�����B�w��ȋ��x���v�Z�N(�����)�\�ꌎ�������Ɍ�����A�������̌�Ɛl�Ɛ��肳��闊���̐����̈�l�u��؎l�Y�v�́A�m���Ȏj���ɓo�ꂷ���؎��̏����L���ł���B�܂��A�]�ˎ���ɕҏS���ꂽ�Ƃ͂����A�����炭�͊m���Ȏ����Ɋ�Â��Ă���Ɛ��������w����t�H�ҔN�S�^�x����її��R�́w���q���R�ƕ��x�̗����Ɍ�����A�������k�������̖��ɂ���Ď����̍����n�ł���͓��������R�̘[�ӂ��Ƃ��炳�قNJu���Ă��Ȃ��ۓc���̑��i�������Ƃ����L�������A�����Ɍ�������јa�ᏼ���Ɋւ���L�^�ƍl�����킹��Ȃ�A��ؐ����́A���̌R���͂@�k����������]������Ă����͓����̑�\�I�Ȍ�Ɛl�E���@�튯�������̂ł͂���܂����B �@ �w�����L�x��҂��A�k�𐭌��ɑ������V�c�̏������m�M������l���Ƃ��Č`�ۂ����̂����̐����ł���A�����`�ۉ��̒��S���A��҂́u�s�v�c�v�Ƃ�����ɂ���đ����悤�Ƃ����B���Ƃ��ΐ瑁�鍇��ł́A�u��R�V�߃d�N���A�R�����K�׃j���L�A���m���m�k�t���A�����{�k�R���W�N�V�����j���N�_�P�^���A�����j�����\���Y�A㘂�Â��j��l�j�^���k�����j�e�A�N���߃^�m�~�A�����҃g�V�����i�L�钆�j�A�R���w�e�h�M��q�P���A��K�S�m���R�\�s�v�c�i���v(�����@�{)�̂悤�ɁA�킸���Ȏ蕺����ւ��Ő瑁�����鐳���́u�����ƒq�d�v�Ƃ��l����Ƃ��A�ƂĂ��l�Ԃ킴�Ƃ͎v���Ȃ��̂ł���B���̂悤�ɒ������I�Ȃ��̂ւ̋������u�s�v�c�v�ł���B���ꂪ�����o�ēV���{�ɂȂ�ƁA�u�킪�S�̒����������߂�����v�ƁA�����̐��_�̂���悤�ւ̎^�Q�ւƈڍs����B�����́A�u�s�v�c�v�Ƃ��������悤�̂Ȃ��u�����ƒq�d�v�ɒʒꂷ��A�ߊ�肪�����l�ԑ��݂̎��Ј������犴��������ꂪ�u�����߂��v�ł���B�����ɂ͕\���҂́A�����ւ̐[�����h�̔O��������B���́u�����߂��v�̌ꂪ�A���z�{�ł́A�u��m�S�m���R�\�s�G�i���v�ƁA�����I�ȕs㱂ӂ��̐��_�������u�s�G�v�Ƃ�����ɒu���������Ă���B�����Ă݂�A�ÑԖ{�̒������I�ȃ��x���ł̏^����A�V���{�̗ϗ��I�Ȏ��_���o�R���āA���z�{�̓���I�E�����I���x���ł̎^�Q�ւƕω����Ă���̂ł���B �@ �Ȃ��A�{���͐��{������l�ّ��V���{�w�����L�x���{�Ƃ��Ă���B�V���{�͊���̊����Ɂu�����V������I�t���V�^���V�L�v�̉�����L���A�قڑS����M�̊��{�ł���A�L���m���Ă���_�c�{���痬�z�{�Ɏ��鏔�{�Q�ƑΗ�����V���{�n�ʖ{�l�{(���͗��J��w�{�E�`�P�{�E��K�{)�̒��̍őP�{�ł���B���z�{�ɑ���V���{�̎�Ȉٕ��́w�Q�l�����L�x�̒��ŏЉ��ČÂ����璍�ڂ���Ă������A�S���������������͍̂��߂Ăł���B�@ |
|
| �������L2 / ����V�c�Ƒ��������@ | |
|
�w�����L�x�̒��Ō��킲�������V�c�̎������ł��N���ɕ`����Ă���ӏ��́A���\���́u�N���`��ɕt�����鎖�v�Ƃ��̒��O�́u�x���ҍK��}�֗��߂鎖�v�̏͒i�ł͂Ȃ��낤��(�ÑԖ{�̐����@�{�Ō���ƁA�u���R��ҍK���v�u�x�������ҍK���v�u���N��t�`�厖�v�̎O�͒i�ɑ������镔���ł���)�B�����O�N(��O�O�Z)�܌��A���̔N�A�Ăє�b�R�ɓ�����������V�c�́A�{���̓x�d�Ȃ�s��ɂ���āA�u����(������)���Ă����̒����o���ł��钹�̔@���ɉx�сA�{�����v���Ȃ��Ă����肽��b�̔@���ɏk�Â܂��v(�{���F�O����y�[�W)�Ƃ����Ɋ����������Ȃ��Ă����B�قڔ��N�ɋy�ԎR�㐶���ł���B�{���Ɉ�{�����Ă��邩�Ǝv��ꂽ�m�k�������A���R����������������������������u���ӏ��̏������v����Đ������A�u�ڂ̑O�̗~�ɐg�̌�̒p��Y��v�ĕ��ƕ��ɐQ�Ԃ������A������A�u�R��̏O�k���Y��s�����A�m���̕�����o�����Ƃ��ւǂ��A���ƁE���Ƃ̏]�ޏ㉺��\���l�ɗ]�肽��l�����A�Z���̎n�߂��\���̒��{�܂��ŗ{����₤������A�ƍ����Ƃ��Ƃ��s�����āA�Ƃ��Ɏ�z��䬂̂��܂�Ƃ��v�Ƃ����L�l�ł́A���ł��邱�Ƃł͂Ȃ������B�������o�����˂ɂ��k���X���̕����A���X�ؓ��_�E���}����@�����ނ˂ɂ����i�Ή^���̒�~�ɂ���āA�R��̌R���Ƒm�k�����͑ϖR�����̌��E���悤�Ƃ��Ă����B
�@ ����A���썇��̂̂��A���`�����悵��s�֓���A�������g�͐ΐ��������ɗ��܂��āA�Z���O���Ɍ������������c�ƖL�m�䂽�ЂƐe�����}���Ă������A�����\�l���ɏ�c�Ɛe����ē����ֈڂ����B�����āw�����L�x���Z���O�\���E�����\�O���E���\�����̎O�x�ɂ킽�鋞����ɍ\�����Ă���(�{���F�O�ܘZ�y�[�W����)�Z���O�\���̍��킪�s����̂ł��邪�A���̍���͋{������P���łȂ����ʂ��畐�ƕ��Ɛ킢�����Ō�̂��̂ŁA���a���N�Ȃ�Ȃ��Ƃ����Z���{�Ő펀���Ă���B���̓��̍����O�ɂ��āA�����A������c�Ɉ��ĂĂ������߂��Ƃ���鑸���̕������ߔN�V�����ŏ㓇�L����ɂ���Ĕ������ꂽ(�u�����V���v����Z�N�l������)�B �@ ���Z����ҏ���������̂��悤�A�d�������������̂��悤�́A������\�ܓ��A��ؔ����������͂ɂ����ē�����炵�މ��܂Ɉ��Ă��ׂ����B�����ɐV�c�`��߉����k���A�R��ɓ����Ă��墎���\�ӁB�������������ׂ��|�@��𐬂����Ȃ�B���̎|�ݕ��A�B����炵�ߋ��ӂׂ���ӁB(�����͊���) �@ ���̕����́A���m�̓������������Ƒ������i��L����V�c�`��ɂ��悵�������A������c�̉@��ɂ���Ē��G�Ƃ��Ă���_�ŁA�͒i�u�x���ҍK��}�֗��߂鎖�v�̖`���ɋL����Ă���R��̌���V�c�ւ̐���(�{���F�O���O�y�[�W)�ƋO����ɂ���B��҂́A�O�N�̏\�������̗�����߂邽�߂ɓ��������ۂɓV�c�ɔw���悤�ɂȂ����̂͋`��E�`����̂����ł��邱�ƁA�V�c�ɑ��Ă͏��������t�̈ӎu���Ȃ��������Ƃ��q�ׁA�u�����`�傪��ނ�S�ڂ��āA�����槐b����炳��Ƒ��������Ȃ�v(�{���F�O���l�y�[�W)�Ƃ����B�����āA�u�V���̐��s�v��ɂ��C�����邩�狞�֊ҍK���Ă������������A�Ə��_�����̋N������Y���č��肷��̂ł���B����V�c�́u�T�����ւ̌��V�E�q�b�ɂ������͂���ꂸ�v�A�����ɑ����̐\���o���āA�ҍK�̌��ӂ�����B�����́A�u�w���ẮA�b�q�炸�Ɛ\���ǂ��A�\���Ɉ����肯��x�Ɖx��ŁA��������ʂׂ��喼�ǂ��̋��ցA���ɐG�����f�āA�����ɏ��ʂ��Ă����͂ꂯ��v�ƁA�w�����L�x��҂͌���Ă���B����قǏ�肭�u��a�k�v(�w�����O�N�ȗ��L�x)���^�ԂƂ͎v���Ă��Ȃ������A�Ƃ����M�v�ł���B���������A�V�c���̕����ɑ��������A�U�����s���A���̌��ʂ��u�V�c�̈ꑰ�ɂāA��������̑叫�v(�{���F�O���܃y�[�W)�ł���]�c�s�`�����䂫�悵�E��َ���������������������́A�ҍK����̂��߂Ɏ������������Ă̓o�R�ƂȂ��Č���Ă���B���̂�����́w�����L�x��҂̌����͋����قǑN�₩�ł���B �@ �`��̕����ŐV�c���ꑰ�̖x���喞�ق肮�������݂��c���삯����ƁA�ҍK�̎d�x�͊������Ă����B�喞�͖P�r�ق������v�Ȃ����Ɏ����āA���N�����̋`������̂ĂāA�u��t�����̑����v�ɉb�����ڂ����Ƃ́A�ǂ̂悤�ȁu�s�`�v���`��ɂ���������Ȃ̂��Ƌl�ߊ��B�����āA�u���������ӓx�̐�ЂɁA���G������ɂ��āA���R�p��ɗ������Ќ�ӎ��A�S����Ђ̙�ɂ��炸�B�����铿�̌����鏊�Ɍ�ӂ��ɂ�āA����݂����ɎQ�鐨�̂����Ȃ��̂ɂČ�͂���v(�{���F�O�����y�[�W)�Ƃ����B����́A���̔N�̓A���������ɂ���}���֗������Ƃ��ɁA��ؐ��������̂��܂��������V�c�ɁA�������͓��E�a��̎��Ƃ��ĕ����W�߂悤�Ƃ��Ă��W�܂�Ȃ��A�s�R�̑����ɕ��m�����͎�ٓ��ŏ]���čs�����Ƃ��Ă���̂��A�ƌ����A�������V�c�Ƒ����Ƃ̒�������邩�瑸����s�ĂѕԂ��Ă������������ƌ�����������(�w�~���_�x)��ǎ҂Ɏv���N������B�w�����L�x��҂̎���F���f���Ă���\�����Ƃ����悤�B�喞�͂���ɁA�ǂ����Ă��V�c�����s�֊҂���̂Ȃ�A�`����͂��߂Ƃ���V�c���ꑰ�\�]�l�̎�͂˂Ă���ɂ��Ă������������A���|�߂��B���̂�����A�喞�̎p�́A���łɋ`��ƈ�̉����Ă���̂ł���B�����ŁA�V�c������̐F��������̂́A �@ �u�喞���������ݐ\����Ƃ���A��V���̈��ꂠ��Ɏ�����Ƃ��ւǂ��A�Ȃى����̑��炴��ɓ����v(�{���F�O�����y�[�W)�Ǝ��Ȑ��������v�邪�A�V�c���g��܂����͂�͂�����Ȃ������悤���B�u�V�^���܂������炸���ĕ����A���Дp��v(�{���F�O����y�[�W)������A�����Ɓu������a�r�̋V��d�v���̂��Ƃ����B�������čc���q�P�ǂ˂悵�e���ɏ��ʂ��āA�`��ɂ��Ėk���։��������邱�ƂŁA�`����Ԃ߂�̂ł���B�V���{�ł́A��Ђ����ɓ��g�Ђ̑�{�����ɋF�O����`��ɂ��āA�u���ɗE�m�Ƃ��N���āA�]�ނɎq�����v�ӂ��Ƃ���A�`����k���֗����āA�������Ȃ炸�͂ƁA�q���̂��߂ɋF�O��s�����ꂯ��S�̒���������Ȃ�v(�{���F�O��Z�y�[�W)�Ƒ��₵�āA�`����̂Ă����V�c�Ƃ̈Ⴂ�����킾�����悤�Ƃ��Ă���B �@ ����V�c�ҍK�̗v���͎O��_��̖k���ւ̈����n���ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��B�����V�c(�L�m�e��)�̑H�N�̋V�͂��̔N(�����O�N)�����\�ܓ��Ɍ���[�����NJ�悵���Ɠ@�ōs��ꂽ�B���̂��Ƃ͊��\��̖`���͒i�u�L�m���o�ɂ̎��v�ɏڂ������A���̓����̔����\�����ɁA�����͎��M�̊蕶�𐴐����̊ϐ�����F�̕�O�ɔ[�߂Ă���B �@ ���̐��͖��̂��Ƃ��Ɍ�B�����ɓ��S����������āA�㐶�����������͂��܂���ׂ���B�P�X�A�Ƃ��ِ���������B���S��������ׂ���B�����̉ʕ�ɑ�ւāA�㐶����������ׂ���B�����̉ʕ���A���`�ɋ������ЂāA���`�����Ɏ�点����ׂ���B �@ �@�@�@�����O�N�����\���������@(�ԉ�) �@ �@������ �@ �_�ސ쌧�̏�ՎR���ɂɑ�����Ă��邱�̊蕶�́A�����ɓ��S�������ė~�����A�����ِ����������A�����̉ʕ�͒�̒��`�ɗ^���ė~�����A�Ɗ���Ă���B���������̂�₽�ǂ��ǂ����蕶�ŁA�I��ɍs���ƕ����������������A�����ƕ����̊Ԋu���l�������̂ƂȂ��Ă��āA�͂��߂��玚�z��Ȃǂ��l���ď����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A����������Ƃ��������Ԃŏ����ꂽ���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������������B�{���̍U���ɂ悭�ς��A�Z���O�\���̑升��ɏ��������߂āA�L�m�e�����ʂɂ��邱�Ƃɂ��������A���{���J���������ڂ𐧒肷�邱�Ƃ����S�ɗ\�肳�ꂽ���̎����́A�O�\��̏��R�����ɂƂ��ē��ӂ̐Ⓒ�ɂ������̂ł͂Ȃ����Ƒz�������̂ɁA�Ȃ����̂悤�Ȋ蕶���������̂��B�O�N�㌎�A���q�Ō�����(�w�~���_�x�ł͏������)���Ă��āA����V�c�ɋ����̈ӂ�\���������̎p�ɏd�Ȃ���̂�����B �@ �����Ɍf�o�����A�Z���O�\�����퓖���Ɏ��V�̌N������c�ɕ���������́A����܂Ō����̂��Ȃ���������̒��ŁA����̖���̏ꍇ�����l���������łׂ̍₩�Ȕz���̂��Ƃɏ����L�������̂ł��낤�B��ÂɌv�Z���邱�Ƃ̂ł���A�������l�S�����ɂ����������Ƒ����v���`�����B����ɑ��Đ������ɔ[�߂��蕶�́A�O��_������������V�c�i����������ʂ������̂ł��邱�Ƃ�Ɋ����A�h�炷��A�Ȃ����͐��_�I�ɂ��炪�����Ƃ��������g�D�܂Ȃ�����V�c���\���A�ҍK��t������Ղ̓�������l���āA�����炭�͕s����Ȑ��_��Ԃ̒��ł�����������̂ł͂Ȃ����B���̊蕶�ِ͓����邱�Ƃ̑㏞�s�ׂ��ƍl�����Ȃ��ł��낤���B�u���̐��͖��v�̂悤�Ȃ��̂��Ƃ͏��m���Ă��Ă��A���N�O�ɒ}�����������Ĉȗ��̂��Ƃ��l����ƁA���̐��̓]�ρA�������ꑰ�����łȂ��A���m�K���̖�����n���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�ڂ̂���ނ悤�ȐӔC�Ȃǂ��l����ƁA����������܂炸�ɁA�蕶���������߂����Ȃ����̂ł��낤�B���̂悤�ɍl���邱�Ƃ��������Ȃ�A���g�̑����͂�����ʂ̕����̊Ԃ��������Ă��鑶�݂��Ƃ������Ƃ������悤�B �@ �ߔN�A�w�����L�x�̑S�̑����A����V�c�̕���Ƃ��ēǂ݉������Ƃ���_������ɂȂ낤�Ƃ��Ă���B���̚�������͒���s���́u�鉤����̕���\�w�����L�x���_�\�v(�u���{���w�v��㔪��E��)�ł��낤�B���͌���V�c�͍�i���Ɂu�ӎu�̐l�v�Ƃ��ēo�ꂵ�A�u�d�v�Ȕ��f��K�v�Ƃ����ʂł́A���炪�f�������^�����J���Ă���A���̈Ӗ��Ō���͕���̗����̓��������v���ƂƂ炦�A���́u�ӎu�I�E�ϋɓI�ȑԓx�́A�Ƃ�����������Ƃ̂Ȃ������S���邢�͉�ӂɔC���Ă̋��ʂ��E遖����Ȃ��Č�����v�Ƃ���B�����āA�������O���̐��E�ʼn��쉻�������́A����\�O�̖`���͒i�u�ɐ������쌱�𒍐i���鎖�v(���z�{�́u��X�F�����v)�ŁA����ƂȂ��đ�X�F���̏��������D�����Ɗ�Ă��ؐ����̌��t�Ƃ��āA�u�撩(����)�͌������ώ܂�������牤�키�̏��ςɂĂ܂��܂��A���҂ė~�E�̘Z�V�Ɍ������v�Ƃ���Ƃ�����w�E���āA�u���ϏC���͑����厩�ݓV(�V���@�_)�ŁA���E�n���Ɣj��̍ō��_�v�ł���A�u���E�ɂ����Ă�����͌��E�ɓ���������j�ƂȂ�v�ƍl����B����V�c�̕���̎p�������̃e�L�X�g�Łu���̌��ɂ͖@�Ԍo�̌܂̊������点���ЁA�E�̌��ɂ͌䌕�����v�ƂȂ��Ă���_�ɒ��ڂ������B���Êٖ{�ɂ́u�܂̊��v�͌����Ȃ�(�_�c�{�͌���)���A�w�@�،o�x��܊��͒�k�i�E�����i�E���y�s�i�E�O�o�i���܂ނ���ǂ��A�w�����L�x��҂����Ƃ���̂́A���҂��n�����猻��o�邱�Ƃ��F��O�o�i�̑��݂ł��낤�B����V�c�̖S�[��ʏ�̓�����ɑ��炸�ɁA�k�����ɂ��ēs�̕��p�ɑΛ�����������悤�ɂ����̂����̂��߂ł���B����ƂȂ��Ă̕������Î��������̂ł���A����\��ȍ~�́w�����L�x���E�́A�����������킪�A�쒩���ɑ����Ď��ӂ̂����Ɏ���ł������҂����̒��_�ɗ����Č���(���E)�ɓ���������Ƃ����\�������̂ł���B�@ |
|
| �������L3 / ���X�ؓ��_�\�\�w�����L�x�̓��ƊO�@ | |
|
��O�N(��O�l�Z)�\���Z���A����喼���X�؍��n�����������_�ǂ���(�ގ��g�̏����ł́u���_�v������)�́A�q���G�j�ЂłȂƉƐl��������Ђ��N�������@�@�{������悤���悤�@�e��(�k���̌�����c�E�����V�c�̒�)�̖V�l�Ƃ̂��������Ɏ��瓥�ݍ���ŁA�䏊�ɏđł��������B�w�����L�x����\��u���_���@�@���u�₭���v�́A���̎������ڂ����L���Ă���B���������[���ł��������ʓ~�݂Ȃ��Ƃ݂̂��ӂ�̓��L�w���@��i�L�Ȃ��̂��ۂx�̏\���Z�����ɂ́A�u��ɓ���ċ��ӂɏĖS����v(��������)�Ƃ���A���������ɏڂ����L�q������B
�@ �`�֕����A����ʂ��A���͖��@�@�{(�����e���A�哴��Z��Ȃ�)�̌䏊�A�Ă����ӂƉ]�X�B���X�؍��n��v���������X�_�A��тɓ��q����v�����G�j�A���̌䏊�Ɋ��������A�U�X�ɒǕ߁E�T�S��v���Ɖ]�X�B���̏G�j�́A����ʂ�[�A�|���̌�V�l�ƌ䏊�ӂɂ����Č��܂���B���̌̂̈ӎ�B�ݑ��Ց����̏d�D�Ў��A�����͊D���ƂȂ��B���ꓹ�f�̈��s�A����V���̏��ׂ��B����Ɉ˂ĕ��Ƃ͎G�i���~�߁A�R�k�͖I�N���Ɖ]�X�B �@ �u�䏊�Ӂv�ł́u���܁v�̈Ӑ}�����ł������̂��͋L���ꂸ�A�w�����L�x�ɂ����悤�ɁA�䏊�́u�g�t�̎}�v��܂����āA�u慉r�Ջ�v���Ă����@�e�����������A�f�Ă�����k�̉���̖@�t�ɂ���Ē@���o���ꂽ���ǂ����͖��m�ł͂Ȃ����A�����ɂ����蓾�����Ȃ��Ƃł͂���B�ʓ~�͏\����\�Z�����ɂ��̌�̂��Ƃ��ڂ��Ă���B����ɂ��ƁA�u�������n���������X�_���q�A�z���ɏ����Ɖ]�X�v�Ƃ��āA���̔z���́u������Ƃ̍����v�ł���A�R��̏O�k�͂Ȃ��u�T���v������Ă���Ƃ����B���̗��R�́A���_�̐�c��j�����Ȃ����v�N��(����Z�`���)�ɓ��g�R���̉����Бm�ł���ߍ]�������̐_�l���ɂ���E�Q���������ʼn����ƂȂ�A���̎��j��d���������͎R��̐_�l�Ɉ����n����āA��F�₷�͌������Ŏ�͂˂��Ă��邪�A�u尩��키���₭�̐_�l�v���E�Q������Ƃ��ł��炱�̂悤�ȏ��u���������̂ɁA����̎����́u�R��̊����v�Ɋւ�鎖���ł���Ȃ��由���y������Ƃ������̂ł���ƁA�O�k�̓{����Љ�āA�ʓ~�́A�u�ނ��Ƃ����̈����͂ꂠ�邩�v�Ƃ����B�܂��A���_���q�̔z���̍s���ɂ��āA�u�y�����₤���A�s�v�c�Ȃ�B�����V���̑̂Ă������Đ�ƂȂ��B���Ƃ̍����A�y���Ȃ�v�ƋL���A�u���X�Ɏ����ׂ܂����A�h�X�ɌX���M���Ă����Ԏ��q���̂˂̗��l�Ɏ��l���Ƃ��ܑւāA���X��������������v(�{���F��܃y�[�W)�ƕ`���w�����L�x�ƕ������Ă���B �@ �R���}�M���悤�낤���邽�߂ɁA�u���炳�邩�͂��ڂɉ���̍����v�������V�R�̑̂ւ̓{�肩��Ǝv���邪�A�R��ł͓��_���q�̐g�������n����ɗv������B�����ŁA���߂ď\�\����ɁA���_�̖����͏��R�����Ɠ����̍����Ȃ̂ŁA�z���ɍۂ��Ă̐��ɂȂ���Č������Ɖ������������ŁA�o�H���ւ̔z�������肵���̂ł��邪�A���_���q����������C�̂Ȃ����{�ɋt�炦�Ȃ�����̎p���A�ʓ~�͏����c���Ă���B����ɂ��A�z������������ۂɁA�鉺���̕�s�����鑾�����̑��l�́A�u���J�v(�a�C)�𗝗R�ɂ��Č��Ȃ��A���̖�l���Ȃ��Ȃ�����ʂ܂܂ɁA�����̗\�肪���ɂȂ�A����ȏ㉄���Ȃ��̂ŁA���Ƃ��`���𐮂��Đ鉺�����̂ł���B���l�̌��Ȃ��������ȗ��R�ł���A��s���ׂ��������O�闎�n�������߂ɕs�Q�Ƃ����̂��A�^�킵���悤�Ɏv����B���_���A���{�ɑ��钩�쑤�̑����ł��銩�C���o�������䂤���˂����ƁA���̎��_�ł��łɐe���������Ă������͕s���ł��邪�A���炩�̓������������������ɑ��Ă��̎����Ȃ���Ă����ł��낤���Ƃ͑z���ɂ������Ȃ��B�u�]�B�n��X���X�ؖ����m���m���v(���\���B�����@�{�ɂ��)�ł���A���@�@�̖{�R�ł��鉄��ƍ��X�؎��Ƃ̊Ԃɂ́A���l�̎x�z�A���������Đ����E�o�ϋ@�\�̎x�z���߂���ϔN�̊m�������������Ƃ����̎����̔w�i���Ȃ��Ă���B�u����E���������Ƃ��v�����_�́u���̎�̕��ǂ��v�̎䂫�N�����u���v�ɕ֏悵�����̂���đŎ����́A�����O�N(��O�O�Z)�̋ߍ]���킩��ܔN�Ԃ�ɖK�ꂽ�傫�ȕ���ł������A�Ƃ����������s�\�ł͂Ȃ��B�O��̋ߍ]����́A���_�ɂƂ��Ă܂��ƂȂ����l�x�z�̍D�@�ł������Ɠ����ɁA�ϔN�ɂ킽��R��ɑ��鍲�X�؎��̟T���𐰂炷�悢�@��ł������B�����č���̖��@�@�đŎ����́A���{���ɂ����铹�_�̏d�݂��m�F����D�@�ł������Ɠ����ɁA�R��ւ̝������E�}�̂܂��ƂȂ��@��ł������B���R�ƒ��`�����悵�ɂ͓��_����������ӎu���قƂ�ǂȂ����ƁA�ނ��돈�����邱�Ƃ̕s�\�ł��邱�Ƃ��A���炩���ߌv�Z�ɓ���Ă̗��\�ł͂Ȃ��������B�V���{�ł́u�㑍�����˂ނ��̌S���ق�֗����ꂯ��v�Ƃ��邪�A���ˌS�ɂ͍��X�؎��̏��̂�����(���{�͕��ˌS�̓�́u�R�ӌS�v�Ƃ���)�B�z���܂Ŏ��ۂɍs�������ǂ������͂����肹���A����l�N(��O�l��)�����\�l���ȑO�ɁA���`�̖��ɂ���āA�ɐ����̓�R�Ǔ��ɔ������Ă���(���ؕ����E�����@����)���Ƃ���l����A�����͌`���ɂ����Ȃ��������Ƃ��悭�����ł���B�܂��Ɂu���Ƃ̍����A�y���Ȃ�v(���@��i�L)�ł������B �@ ���@�@�đŎ�������قڏ\�N��A��a�ܔN(��O�l��)�Z���̎l���͌��̓c�y�ł��V�~���|�Ď����҂������o������(����\�Z�E�����̕ψ��тɓc�y�V�~����鎖)�A�[���邤�Z���̒��`�ɂ��t������Ȃ��̎�������Ƃɑ����āA����������悤�Ɋ������������`�h�ƍ������̎t���h�̐��ʑΌ��́A���N�����̎t���̔����A���`�̐������ނƋ`�F�悵������̏㋞�A���`�̏o��(����\�Z�E�䏊�͂ގ��E�`�F���b�㗌�̎��E���`���b�o�Ƃ̎�)�A����ɒ��`�h�̏㐙�d�\�����悵�E���R���@�����ނ˂̔z���E�Y�C�����肭�Ƃ����t���h�̓O��I�ȍs���ɂ���āA�t���h�̏����ɏI�������Ɍ��������A���`�͗��ω����N�\���Ђ����ɋ��s��E�o���đ�a�����A�\�ɓ쒩�Ǝ������(����\���E���`�T�}���d�̎��E�b���쒩�֎Q���鎖)�B�����R�ɐw���\�������`�̂��Ƃɂ͔��R�������ɂ��悪�삯���A�k�����瓍�䒼������̂������˂��U�ߏ���āA��b��{�ɓ������A�`�F��������ǂ��o�����B���`�R�͔d���̌���������A�ےÂ̑ŏo�����ō���ŁA���R�ƍs�������ɂ����t���E�t�ׂ��j��A���ɐ�ނ�����ӂŎt����͏㐙�d�\�̎q�\���悵�̂�ɂ���ĎE�Q���ꂽ(����\���E�t���t�ד��n���̎�)�B���҂ƂȂ������`�͍Ăѐ����̍��ɏA�����B�������������ɂƂ��Č`�͘a�r�Ƃ͂����A�����͎S�邽��s�k�ł��������A�����h�̐��v�����o�[�ł��铹�_�A�m�ؗ��͂ɂ���肠���E�`���悵�Ȃ��Z��A�y�N�Ƃ����₷�E�א쐴�����悤���玵�l�́A�u�ߖ���G����A���̓��������g�����ށv(�[���@��L)�Ƃ����G�Ƃ䂤�߂�[�u�邱�Ƃ��ł����B�X�Ŏ��́A�u���̊���ȑ[�u�̔w��ɁA���R�����̒��`�ɑ��鋭�͂ȗG�Ɨv�����������낤���Ƃ����������v(�w���X�ؓ��_�x��Z�y�[�W)�Ƃ�����B�w������x�ɂ��A���_�͂��̔N�ꌎ�\�Z���A�ߍ]�ɂ��鋒��(�V���{�ɂ��b�Ǒ��̋���)�߂����ĉ������Ă���A�t���Ƃ̊Ԃɋ�����ۂ��Ă������Ƃ��A��@��Ƃ꓾�������ł���B�w�����L�x����\��u���喼�s�����鎖�v�ɓK�m�ɑ������Ă���悤�ɁA���`�h�Ƒ����h�̑Η��͈ȑO�ɂ�����������ƂȂ�A���`�͓��䒼��̌���e����ēs�𗎂��A�����͂��̔N�܌��Ɍ��Ă����쒩�Ƃ̘a�r�ɐ������A���`�ǔ��̐�|�������āA�ߍ]���i�������B���̎��ɓ��_���������q�̂��Ƃ^����ɒy���Q���Ă��邱�Ƃ��琄������ƁA���̎��̑Β��`�h�ǔ��̍��͓��_����o�����̂ł͂Ȃ����ƍl������B����\��u���d�R������₠����܂������̍���̎��v�͓V���{�Ǝ��̑���ł���A�n���̏ڍׂ��A�ߍ]���̍��l�w�̊���L�q�Ȃǂ���A���X�؋��Ɏ�����̎����͂������ł��邪�A�V���{��҂��邢�͉����{����O���[�v���̐l���ɁA�������̒n��̒n���ɂ����邢�l���̂������Ƃ����������B���̏͒i�̖`���ɂ́A�u������썲�X�ؑ�v���������A���a(���A�����ƒ��`)�̕s���Ɉ�g�̐i�ޒ�߂������v�Ђ���ɂ�A����ʂ�Z����\�ܓ��ɏo�Ɠِ��̐g�ƂȂāA����R�ɕ��Ă�v�y�[�W(�{���F�l�Z�l�y�[�W)�Ƃ���A�i�ނɋ��������X�̖{�@(�Z�p��)�������A�����h�D���̒��ŁA���`�h�ł��邱�ƂɓO�����ꂸ�A�o�Ƃ̓���I���Ƃ�����Ă���B�����āA�u���̒�ܘY���q��ђ�F���������A�c�t�̉Ɠ��ۂ���܂��}�����č��̒T�肽�肵���A���]�R�𗦂��Ĕ��d�R�̒���ɒy�����͂�v�ƋL����A��������Ɠ�����ꂽ���N���f���ɏ������āA���`�h�Ƃ��ĎQ�킵���Ƃ����B���ۂ̕�͓��_�̖��ł���A���X�ؘZ�p���ƍ��X�؋��Ɏ��Ƃ́A�����߉��̐e�ʂ̒��ł́A�W�݊W�̂�┖�������̒��F�̗E�p�ɂ́A������ۂ���҂̊Ⴊ����悤�Ɏv����B �@ �����삯�߂��镐���Ƃ��Ă̓��_�łȂ��A���{�v�l�Ƃ��Ă̓��_�́A�u���Ɛ\�����������Ƃv�Ə̂��ꂽ���{����̐\������쑤�ɓ`����g�҂Ƃ��Ă̖�E�ɂ��ẮA�w�����L�x�ł͂܂������G��Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A��a�O�N(��O�l��)���������A������c�ɐV���g�Б��c������і@�����助�i�E�ɂ��ē`���A�ω����N(��O�܁Z)�\����\�����ɁA�`�F�̎g�҂Ƃ��Č�����c�ɋ�B������t�����A�\�ꌎ�\�Z���ɂ͌�����c�ɒ��`�Ǔ��̉@��𐿊肵����A���a���N(��O�ܓ�)�Z���O���E�\����Ɍ�����c�̑�O�c�q��m����ЂƐe���̑H�N���Ɋւ��Ċ��C���o����K�₵�A����ɏ\�ꌎ��\�����ɂ͐����E�����(��m)�̕�ł���z�\��@�̎����ɍۂ��āA�Ȉł�悤����̂��Ƃœ������o����K�₵���肵�āA�u���Ɛ\���v��`����Ȃǂ̂��Ƃł���B�w�����L�x�̒��ɖk���̗L�͌����Ƃ��ĕp�o���銩�C���o���̔����́A���_�Ƃ̊Ԃ̑����p�C�v���l�����킹��Əd�݂������Ă���̂ł��邪�A��҂͖��{���̑Β���̌��I�҂Ƃ��Ă̓��_��`�����ɁA���{���̗L�͎��喼�ǂ�������煘r������ӂ���������Ɠ��_��`�������Ă���B �@ ���a���N�A�R�������Ƃ������E�t�����낤�����q�����_�ɓ{���āA���q�œ쒩�ɗ^���݂����o�߂͊��O�\��u�R�����q�卲�G�Ɛ��鎖�v(�_�{���Êٖ{)�ق��ɏڂ����B���[�͏o�_���E���߂��鑈�D��ɂ���B���_�͎�������o�_���E��D���Ԃ��������łȂ��A�������g�{��������ǂ��������Ƃɐ������Ă���B�w�����L�x�̍�҂́A���̎��喼�̒ǐ��������Ȃ����_�̕����I�̈�ł���A�̂̉�⒃����A�t����{�炷����ĂɎg���Ă���B���ɁA�m�؋`�������ł��邪�A�`���́A�������ނ炢�ǂ���Ƃ��ē��_�ƍs�������ɂ��A���t���S�����Ƃ͖��{�̎����߂����͂̒�ł���B�`���ǂ������̎�d�҂͔��R�����ł���A���O�\�܁u���喼�m����Ƌ[���鎖�v�ɂ��A�u���n���������́A�g�ɂƂ�Đm�Ɏw��������h�ӂ͖�����ǂ��A�]���܂�ɖT�ᖳ�l�ɂӂ�܂ӎ����A�T�S�Ȃ�Ɩڂ����������鎞���Ȃ�v�ƕ`����Ă���B�`���Ɏ�荞�܂�Ă��āA���R�����E�y�N�E���X�؎�����̎�̓͂��Ȃ����R�`�F���A���_���`���Ɓu�R�������]��v���u�����ɂ���v��ł��Ă���ԂɁu���[�̎p�v�ɂ����`�F��E�o������A�Ƃ�����̍����@�ŋ~�����̂ł���B �@ ����ɁA�א쐴���ɑ���ǂ������H��́A���ďڂ����G�ꂽ�悤��(�u�����L�̐l���`�ہE�א쐴���v�A�w�����L�̌����x����)�A���O�\�Z�u���͎琴���B�d�I���̎��v�ɕ`����A���엹�r�́w����L�x���́u�����̖�S�A���ɂ��炴�鎖�v�ɁA�u�א쐴���́A���ۂɂ͖�S�������Ă��Ȃ������̂ł��낤�B���R�̉����]��ɂ��ߕ��Ŏv�����A��ӂɂ����ނ������߂ɁA����l���ނ̎��r��������̂ł���v�Ɩ������A�������ΐ������킵�݂������Ђ̐_�a�Ɂu�V��������ׂ��v�Ə����Ĕ[�߂����M�Ƃ����蕶�ɂ��āA�u���̊蕶�͐����̕M�ՂɂȂ���̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�S��(���A�͍�)�́A�w�蕶�ɂ��Ă��锻�`�͂悤���A�������M�̂��̂��ǂ����^��ł������x�ƁA���b�ɂȂ����v�Ə����Ƃ߂Ă���B�w�����L�x�ɕ`���ꂽ�A���_�ɂ�鐴���蕶�̂���ւ��̂ق̂߂����ƍl�����킹��ƁA���ɋ����̂���Ƃ���ł���B �@ �s���o�̂���喼���X�ؓ��_�́A�����S�����Ƃ̖��{�̑单���Ƃ��āA���̗L�͎��喼�̒N�����Ȃ����Ȃ������s�|���Ƃ��Ă̈ꐶ�𑗂�A�����Z�N(��O���O)������\�����A�ߍ]���b�ǂ����瑑�̏��y���ŁA���\���̐��U������B�T��ɂ͔ނ̔ӔN�����������̂ɂ����ł��낤�u�݂܁v�ƌĂꂽ�����������B�@ |
|
| �������L4 / �w�����L�x�ƌ����V�c�@ | |
|
���O�\��̍ŏI�͒i�u�����팵������@���@�c�R����܂��ɂɉ����ĕ���̎��v�́A���̂悤�Ȍ�肩��n�܂�B
�@ ������ɁA�����@�T�肺����₤�@�c�́A���鐳�����N�̔�A��R�ꖼ�����Ȃӂ̉����^���̎��Ƃ�͂�������ꂳ���ʂЂāA�Ҍ�Ȃ肽�肵��A���̐��̒����悢��J�����Ɏv���ڂ��H�߂��m�点�ʂЂāA�ƎˎR���₳��̉_�������A�����z�ӂ��₤�̉Ԃ��̂ĂāA�Ȃٌ�g���y��������Ƃ̌䂠��܂��̖��ʂ�āA���ڂ͂��͂��E�~����₤�̏o�o�������Ɛ��点�ʂЂ����A�����̉��A�����@�Ɛ\���H�Ղ̒n�ɂ��ڂ�Z�܂��ʂЂ���B �@ �������A���̒n���Ȃ��s�߂��A�����̏o���������₨���Ȃ��Ɏ��ɓ����Ă���̂����Ƃ܂����v���āA�u�l�H�ɂE�s�҂���̈�l���������ꂸ�A�䔺�m������l�ɂ�(�_�{���Êٖ{�u�B���o�Ɛ\����m��l���䔺�ɂāv�B���{����)�A�R��l�M�Ƃ����̂��߂ɗ����o�Łv�Ȃ������B�u�R��l�M�v�ł��邩��A�K���������߂���ړI�n����܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂��������ʂ������ɂȂ낤�ƁA�ےÓ�g�Ȃɂ�̉Y�֏o�āA�헐�̐��Ƃ͑��G�I�Ȏ��R�̔������ɋC�Â������A�S�͍���R�����₳��ւƌ����B�r���ŁA�������т��Ă���R������Ŗ����̕��m���������R�������Ɩ؏��ɋ������A �@ ���Ȃ����܂���A���̍���Ɖ]�ӂ��A�������̍c���ɂāA�V�����y���炻�Ђ����A��������̖S�����������������ɑ��āA���������Ӌ�����A�䂪�ߏ�ɂ�������� �@ �Ƃ��āu���������v�邱�Ƃ��A����R�ւ̍s�r�A�g��̓쒩�̌䏊�K��Ƃ����\�z���Ăяo���Ă���B�����A�I�ɐ�ɉ˂���ꂽ�ċ���n�肩�˂āA�ʂ肪�������앐�m�ɐ�֓˂��������Ƃ������������邩�炱���A��c�̐��݂������S�����������������v����̂ł���B�ÑԖ{���痬�z�{�Ɏ��鏔�{�ł́A���̌�A����R�̏��������q�Ȃ����Ă����c�̂��ƂցA�����̖앐�m���m�`�ɂȂ��Ďp�������A��������Ƃ����Δ�I�\�}���Ȃ��L���������A�V���{�͂��̑Δ���̂炸�A����̎}�t���������Ă���Ƃ����悤�B �@ �����V�c(��O��O�`�Z�l)�́A�㕚���V�c�̑��c�q�Ƃ��āA�×�N(��O��Z)�����R���Ă��(��o�����E�����@������ւœV�c�𗧂Ă邱�ƁB���q���{�͂�������炵��)�ɂ���āA����V�c�̍c���q�ƂȂ�A���O���N(��O�O��)�k�������ɗi������đH�N���������A���O�N�܌��A�B��ҍK��������ɔp���ꂽ�B�����O�N(��O�O�Z)���������̑t���ŁA������V�c�����ʂ��āA��c�͉@�����J�����B�ω��O�N(��O�ܓ�)�[���邤���������݂悤��c�E������������c�E���m�Ȃ��ЂƐe���ƂƂ��ɓ쒩���ɕ߂����A�Z���ɂ͉ꖼ���ֈڂ���A�܂��Ȃ��㑺��V�c�̍s�{�����ŗ������A�T���ɓ������B �@ ���̏͒i�̌������@�́A�㑺��V�c�Ƃ̑Ζʂ��j���ɒ����邱�Ƃ́A���Ȃ��Ƃ����݂܂ł̂Ƃ���ł��Ă��Ȃ��B�������A�w����{�j���x(��Z�ғ�l�A�����\���N�E�厡���N�㌎�����)�́A�@�����̋L�^�����w�Ì��L�x�̈���A �@ �N����N(�p��)�㌎����A�����@�@�c(�T�m)������Q�w(�ݔV�߉��\�]�l)���n��A���䐀���A(����)�����n����s�� �@ �������A�w�����L�x��҂��\�z�����㑺��V�c�Ƃ̑Ζʂ͂��̒���̂��̂Ɨ������Ă��邪�A�������f���鍪���͂Ȃ��B�w�����L�x�̂��̋L���ɔN�����������Ƃ́A�Ӑ}����Ă̂��Ƃł���A���̋L������҂̎v�z��\�����邽�߂ɋ��\���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��A������Ă��悤(����Ɩ{�E�ї��Ɩ{���ł́A�{���l�Z��y�[�W�̖@�c����u���������������v���A�u�厡�O�N�b�C���������v�Ɩ��L���A��҂̈Ӑ}�������͂ݏo���Ă���)�B �@ �\��ꌳ�������܂ӔϔY�̐g���ȂāA��틕�����̐o�ɂ����{�ӂƂ͑������肵���ǂ��A�O�Ƃ��ӂ̉d�����鏊�ɋ����𗣂ꌓ�˂āA�Z�ނׂ�����܂��̎R�͐S�ɂ���Ȃ���A�����҂���ʘV�̗��铹���Η��ނ�֎���Ȃ��čΌ��𑗂肵���ɁA�V������Ĉ�����x�ގ��Ȃ��肵���A���O�̏��߂͍]�B�Ԕn��܂ŗ����s���āA�l�S�l�̕��͂��̂ǂ����v�Ўv�ЂɎ��Q�������Ɍ��͂�āA�H㽂�������̌��ɐS�𐌂͂��߁A�����̖��ɂ͓��R�̗H�ՂɈ��ЂāA��秊�˂���߂���܂ŏH�Y���������̍߂ɒ_���������Ȃ߂āA������ɂ���ΐ��͂������ɂĂ��肯���ƁA���߂ċ�������Ɋo����Ђ����A�d�N���悤���̈ʂɖ]�݂����|�����A���@�̐��܂育�ƂɐS�����~�Ƃǂ߂��肵���ǂ��A��������Ȃ����ɖ{��Ƃ������A�ق̂���o�Âׂ����Ђ܂Ȃ��āA���ꑁ�ӂ����R�[�������݂��ɉ_�Џ���ׂƂ��āA�S�������U�����邷�ׂ��ƁA�S�Ɍ����Ă����O��������v�Ђ��Ƃ���ɁA�V�n���߂����v���炽�߁A���ʂ̋V�o�ŗ����肵���A孉������킢�ꎞ�Ɍ[�Ђ炯�āA���̎p�ɐ���Ă������ �@ ����̈ꐶ��U��Ԃ��Ă̖@�c�̌��t�ł���B�l�Ԃ��A�I���̔ϔY�ɋꂵ�ޔ����ȑ��݂ł���ƈӎ�����悤�ɂȂ����̂��A���ł��������G��Ă��Ȃ����A���ׂĂ��̂Ăď����s�r�ɏo���A�@�c�̐����n����̌��t�ł���A���̌�̖@�c�������錾�t�̒��̈��A�u�g�̈����鏈�A���Ȃ͂��S�����v�Ƃ̌ĉ���������B��҂́A�@�c�̎O���(�������͎����)��������V�c�ɂ���āA����������ʼnc�܂�A�V�c���炪�����Łw�@�،o�x�ꊪ�����ʂ��ċ��{�����ƌ����A�u�Z��肭����̌Q�ނ����������̗]�O�ɂ����Â����ƁA�����̋M�ˉ������ȂׂāA�F���܂�����������v�ƁA�����ł̋~�ς�\�z���āA���O�\��͕����Ă���B �@ ���̏͒i���ڍׂɕ��͂��������B�����́A�㓡�O���������āw���ƕ���x�u���悤���̂܂��v�̉e���Ɍ��y�����_���������āA�u�����@�c�ƌ㑺��V�c�Ƃ̑Θb���A�����@�ƌ㔒�͖@�c�Ƃ̑Θb�́A�P�Ȃ�`���I�ގ��ɂ����Ȃ��Ƃ����Ă悢�̂��Ƃ����A�K�����������͌������A���Ɍ����@�c�̏q���̓��e�ɂ́A���̏͂̍\���ɂ������ł������I�ȃe�[�}�������Ă���A�����ɁA�͂�����w�Z���V�����x�Ɠ����̐��E�������Ƃ邱�Ƃ��ł���̂ł���v�Ƃ��ꂽ(�u�����L�ɂ���������@���b�v�A�w�����L�̘_�x�����B���o�͈����N)�B���̘_���ĕ��c�������́A�����@�̍���R����g��ւƂ����s�r���w���ƕ���x�́u���v�匴��K�����͂炲�����ɕC�G����Ƃ��������́A�u�����@���Z�����o�������悤�Ɍ����@���l�Ԑ��E�ŁA�݈�(�V��)�A�����(�C��)�A�ԏ�ł̌��̊C(�n��)�A�@�����Ă��(�{��)�A�ꖼ���ł̐h��(��S)�̘Z�����o�����ꂽ����ł���A�ȏ�́w�����L�x�̏Ռ��I�ȋL�q���v�Z���ꂽ���̂ł������Ƃ݂邱�Ƃ��ł���v(�u�����V�c�\�\�a���̊w�ɏG�ł�\�\�v�A�w�����w���߂Ɗӏ܁x�ܘZ������)�ƁA�����@�̌����̐��U���Z�����֓I���i�����Ǝw�E���ꂽ�B �@ �����@�̐��U��Z�����ւɂ��Ă͂߂邱�Ƃ̓��ۂ͕ʂƂ��āA��X�͊���u�ԏ�ɂĕ��鎖�v�̒i�ŁA���m�������ԏ�̒ғ��̂�����Ƃ���Őؕ����邳�܂��A��R�Ƃ��Č��Ă��邾���ł����������V�c��e�Ղɑz�����邱�Ƃ��ł���B����V�c�ҍK��̒�ʂ̔��D������A���̌�A���V���Ă�̌N(�@�����s���@)�ɕԂ�炢�����Ƃ��A�u���͂�A���̎����@�a�́A��ʕ�̐l���ȁB��ɂ��R�������̈�x�������͂ŁA���R��艤�ʂ����͂点�ʂЂ��鎖��v(���\��E�L�m���o�ɂ̎�)�ƁA�u�c�ɐl�v�܂�͕��m�K���ɝ�����䂳���Ƃ���ƂȂ����B �@ ����Ɠ��l�̔�]������\�Z�u���ȓV��Ă����L�̎��v�ł��q�ׂ��Ă���A�����ł͎����@���̐����̎��Ԃ������R��������܂̓V��ɂ��u�Ȃ��Ȃ��^�̂��镐�Ƃɏ��������͂��ʂЂāA�����̑P�����Ȃ��A�ЂƂւɗc���̓����߂��̂ނ��@���A�z������r�ЂƂ����x�킽�点�ʂւA�҂��ւČ`�̔@�����S�Ɍ�����͂��܂��҂Ȃ�B�������{�ӂɂĂ͂���˂ǂ��A�������~�������͂��A���ɑł����Ă����ʂւA��^���J�����ʂӂɎ���Ɖ]�ւǂ��A�����������ɂȂ�v((3)�O�O�܃y�[�W)�Ɗ��j����Ă���B �@ �X�Ŏ��ɂ��A������c�̖���ďo���ꂽ�@��ŔN���̖��L���ꂽ���́A����і��N���Ȃ��琄��\�̂��̂́A�O�܁Z�ʂقNJm�F����Ă��āA���̐��́A���g�ł������ȂǗ������ꂽ�u����V�c�d�|�̔�ł͂Ȃ����A��ܔN�Ԃɏo���ꂽ���ɂ��Ă͗��V�c�E��c�̒��ł���ʂɃ����N����v��Ƃ���(�w��k���������W�j�̌����x����y�[�W)�B�����āA�u���̂��Ƃ͓���c�̐����^�c����X�̐�����Ȃ������r�I������悵���؍��Ƃ݂Ă悩�낤�v�Ƃ�������B��Ɉ��p���������̂����A�u�d�N�̈ʂɖ]�݂����|�����A���@�̐��ɐS�����~�߂��肵���ǂ��A��������ɖ{��Ƃ������v�]�X�Ɗւ��ƍl���Ă��悩�낤�B�@�����l�����ŁA�i�ׂɊւ��@���a�ӂǂ̒뒆�͓�k�����ɂ��̃s�[�N���}����ƍl�@����Ă��邪�A������c�@���ł̕��a�O�́A����̍ō��c���@�ւ̃����o�[�ł���]��O�Ƒ����d�Ȃ�A�]��O�̏�ʂɈʂ���ۉƂ����o�g�ҁE���������o�g�҂̒��ł��A�u���@�Ƃ̐i�o�͓��ɒ��ڂ����v(�����ꔪ�Z�y�[�W)�Ƃ����B���@�Ƃ�����Ǝ��ӂƁw�����L�x��Ҍ��Ƃ̊W���l�����(��ؓo���b�u�����L��Ҍ��̍l�@�\�\���@�Ƃ̎��Ӂ\�\�v�A�w�������w�x�O�܍�)�A�����@���߂���b�����ǂ̂����肩����ꂽ�������̗N���Ƃ���ł��邪�A�w�����L�x��҂̊S�͌����W�A���ɉ@���̎����ɂ͋y��ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B �@ ���݁A���̈ꕔ������}���قɑ������O�A�l�N(��l�܈�A�ܓ�)���ʖ{�̎ʂ��ł���A������{�w�����L�x���������A�Îʖ{�̕����ɓw�߂�����s���́A�����˂̍��w�҉͑��G�o�����i�����L���łɎʂ�������{�̐��łƂ̈ٓ�����A�{�̊��l�\�����u�����@���䎖�v�ŏI�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�w�����L�x�̐����ߒ��ɖ����N����(�u�w�����L�x�I�����̏����\�\�g�����@�s�r�̎��h���߂����ā\�\�v�A�w���{���w�x�l�Z���Z��)�B������c�̕��䂪����A�O������{�̉c�݂��A�Z���̏O�����ׂĂ̋~�ςɋy�ԂƂ��邱�̏͒i�ŁA��k�������\�N�̗��j���̖���������Ƃ���{�̍\���͖��͂�������̂Ƃ��ĉf��̂ł���B�@ |
|
| ���鉤����@ | |
|
�ʍ��n�^�g�q��R�m�ۃj�����g���A��鮃n�c�l�j�k荃m�V���]�}���g�v�t�B
�@ ����ƌ���ɓo�ꂵ�Ă��炤���Ƃɂ����B���{�j��A�ł���_�ŁA��^�ȓV�c���B�������A������k���̑����̑����ɂƂ炦�A���j�̐��ׂ̎��_�̂����Ɍ�낤�Ƃ���ƁA����߂ĕ��G�Ȗ��ƒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�B�������������ɂ�����ꖡ���S�Ƃ͉����B���R�T�S�Ƃ͉����B�����āu�ٌ`�̉����v�Ƃ͉��Ȃ̂��B�@ |
|
|
���邩�炵�炭��k���ɒ^�邱�Ƃɂ���B�����ېV�A���a�O�j�ɕC�G���āA�ł�������������ゾ�B�u�ʁv(���傭)�̌���������B
�@ ���Ƃ��Ɓw�����L�x����k�����̃}�U�[�������Ă��܂��Ă����B����ɁA���̃}�U�[�͂߂��ۂ��悭�ł��Ă����B�i���g���W�b�N�ɂ́w���ƕ���x�Ƒo�����B���̂��߁A���̓��ɂ��܂ł��Z���Ă������Ƃ����C�����ƁA���j�̌����Ƃ��Ă͂�������E���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�Ƃ����C�����Ƃ��A������������B����������A�w�����L�x���ǂ��ǂނ��Ƃ������Ƃ��A����������k�����ǂ���邩�Ƃ����o���_�ɂȂ炴������Ȃ��Ȃ��Ă���B�������A���̌��ł́A�u�ʁv�͖J�߂��₳��A�܂��Ȃ����B�����T�ȂɁw�����L�q��݁r�̉\���x�Ƃ��������[���{������̂����A�v���̖ڂ��炵�āu�ǂ݁v������Ƃ������Ƃ́A�u���v�������ł͂��܂Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��B �@ ��k�����ʂ�o��l�����炷��ƁA�ő�̎�l���͂�͂����V�c�ł���B���̔j�V�r�Ȑl���������Ă͓�k���͂��肦�Ȃ��B �@ ����ǂ��A2000�l�ɂ���ԓo��l����z�����w�����L�x�����łɂ����Ȃ��Ă���̂����A���͓�k�������ׂ���l���͂�����ł�����B��������ؐ������哃�{(�����Ƃ��݂̂�)���A���ꂼ�ꂪ���h�Ȏ�l���ɂȂ肤��B����(����)��V�c�`�傩�猩�Ă��A�o�T���喼���X�ؓ��_�����(���˂悵)�e�����猩�Ă��A��k���͖ʖږ��@����B�k�����O�������������l�ȓ�k���̒j�����������Ə����d���Ăŕ`���Ă����B���̃R���Z�v�g�A�ꌾ�ł����Ȃ�u���R�T�S�v�Ȃ̂ł���B������������A�u�ʁv�����ɂ��Ă͂߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B �@ ���{�̗��j���A100�N�����炢�̃X�p���łǂ̂悤�Ɍ��邩�Ƃ����傫�Ȏ��_�œ�k���ɂ��Ă͂߂悤�Ƃ���ƁA���x�́u�ۊւƓV�c�v��u���{�ƓV�c�v�Ƃ����Δ䎲���K�v�ɂȂ�A���̂����Łg�V�c�̐푈�h�Ƃ�����Ԗ��Ȗ������Ȃ���Ȃ��Ă���B �@ 13���I����14���I�ɂ����āA���{�́u�V�c�����{��₤������v�ɂȂ����B���ꂪ�㒹�H�@�������V�c�ɂ���сA���������k���̋T�[���Ȃ����̂ł���B �@ �������ēV�c�Ƃ̍c�����A�u�k���v(�����@��)�Ɓu�쒩�v(��o����)�̓�Ɋ���Ă��܂����̂��B���ꂪ�����I�ȏ�A60�N���������킯���B���a�̂܂邲�Ƃ���̒���R���̂Ȃ��ɂ����悤�Ȃ��́A���ꂪ���a�}�Ɩ���}����I���ɂ���ē���ւ�藧�����肷��Ƃ����Ȃ�Ƃ������A���Ԃ͉B�R�Ƃ���60�N�ɂ킽�����V�c�Ƃ́u�����R���v�Ȃ̂ł���B���{�Ƃ������Ƃ������Ɠ�V��Ղ����̂��B���̉������������A�ł��Ȃ������̂��B �@ �������j�w�ł́u��k���[(���������)���v�Ƃ����̂����A������ǂ̂悤�Ɍ�邩�ƂȂ�ƁA�u���{�Ƃ������@�v�̈�Ԑ[���Ƃ���܂Ō@�艺���������ނ��ƂɂȂ�B�̂��ɐ��ˌ����́w����{�j�x�����ʂ����̂́A���̐��[��肾�����B�V�䔒�����R�z���A���̖��ł͚X�����܂܂ɂ���B�@ |
|
|
����������k���[���������炳�܂ɕ\�ʉ������Ă��܂����̂́A���Ƃ͂Ƃ����u���v�̗��v���㒹�H�@�̉B�Y�Ƃ����ӂ��ɏ��������k���������{�̔��f������������ł���B
�@ �����ɁA�u���{�ƓV�c�v�Ƃ�����̃V�X�e�����I�݂Ƀn���h�����O���Ȃ���Ή����i�܂Ȃ��Ȃ�Ƃ����A���{�����́g�����Ȃ����j�Ձh���R�g�R�g�������ƂɂȂ����B�܂�u���������v�Ƃ͉����Ƃ�����肾�B��k�������ɂ́A���̖��n�ȃf���A���E�X�^���_�[�h�̌����ɂ����X�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@ ����Ȃ�A���̂悤�ȁu���{�̓V�v�Ȃ�傫�Ȗ��������Ď���Љ���I���j�V�G���g�Ɍ��Ă����������Ƃ����ƁA����ɂ́u���{�̒n�v�Ȃ���̂̐V���ȓ������I���j�v���[���g�ɓ����Ă����B������\����̂������̒n������绂��Ă����u���}�v�������B���{�ɂ͈ȑO����u�V�_�n�_�v�Ƃ�������������̂����A�V�_�������́A�n�_���鈫�}�ƌ��т����̂��B���ꂪ�����̂��ƂȂ̂��B �@ ����͖��ł���B�V�c�Ƌ���l(�����ɂ�)�����т��A�M�l���ːl�����[�v�������Ă���B�������A�Ԗ�P�F�����������������J��o�����̂����A�����ɂ����u���{�Ƃ������@�v�̋����ׂ��{�����������̂ł���B�@ |
|
|
�ƁA�܂��A���������������ɁA�܂��Ƃɑ��l�Ȍ������}���`���C���[�Ƀ}���`�����N�Ƀ}���`�J���`�������Ɍ��Ă����Ȃ��ƁA��k���̖{���Ȃ�āA�Ƃ��Ă��e�Ղɂ͕�������ɂł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@ �����ɉ����āA�ڂ��ɂ����Ă͂܂邱�ƂȂ̂����A���̎���̕��䂪�������n����܂���Ă����Ƃ������Ƃ�����B���̃C���E���[�V�����ȓ����̎��_�ŁA����Љ��ǂޕK�v������B�Ƃ��낪�A���ꂪ���s�l�ɂ͋��Ȃ̂ł���B �@ ���s�ɏZ��ł���ƁA���̂܂ɂ��W���}�V���Ȃ�ʃW�}���V���ɖ`����āA�Ƃ����苞�s�o�J�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��v���m�炳���B���̏Ǐ�͂��Ƃ��A�ޗǂ̌Ñ㕶�������O�������邱��(�S�l����T���ɂ͋������A���t�W��،��Ɏア)�A��╶���ɏ���ق̐l�`��ڗ����a�����Ă���̂��y�����邱��(���܂͂ǂ������m��Ȃ����A���Ă͋��s�ɂ͕��y�����̂��ޕ���Ȃ�����)�A�ߍ]��ɐ���F��ɈÂ�����(���ɐ��Q��͍D�������A����ȊO�̐_���M�ɂ͊w�ڂ��Ƃ͂��Ȃ�)�A���X�ɂ������B���̏Ǐ�A�ŋ߂܂��܂��Ђǂ��Ȃ��Ă���B �@ ���s�l�Ƃ����̂͂ǂ������킯���A�]�˕����Ⓦ�������ɂ̓Z���V�e�B�u�Ȃ̂����A�ߗׂ̋E�������ɂ͂ǂ��������݊��ŁA����W�Ȃ̂ł���B���̂��ߎ��ӂ̂��Ƃ��悭�m��Ȃ��B�ڂ����g�A�������ڗ�����ዷ�X�������߂ĖK�ꂽ�Ƃ��ɁA���R�Ɗ������B �@ �{��ǂ�ł��Ă��A�����V���b�N�ɂ����ΏP��ꂽ�B���i�̖k�̐��Y�̂��ƁA�ߍ]�����̗��j�A�͓��̌Ñ㒆���A�O�g�ƒO��̖����A�ؒÐ�̗́A���Z�Ƃ̊W�ȂǁA�����m�����Ⴂ�Ȃ������B���s���S�̗��j�Ȃ�A�ڂ��ɂ͗щ���傪���M�ҏW�����w���s�̗��j�x�S10��(�X�J���v���������s���j�Ҏ[���̎d�����܂Ƃ߂�)�Ƃ����g�B�ꂽ�閧����h�������āA���Ȃ�ׂ����Ƃ���܂ł��ł������Ă������B�������A�E����C�A��C�E���C���͂����ς�Ȃ̂��B�@ |
|
|
���ꂪ��k�������悤�Ƃ���Ƃ��̎ז��ɂȂ�B�w�����L�x�Ƃ͋��s����E���镨��ł��邩�炾�B
�@ ���́A�c�y�Ɠ����ɋ����k�������̘b����A����V�c���ؐ����̒m�d�����ʂ��āA���������̓]�g�⍲�X�ؓ��_�̃o�T���Ԃ���ւāA�ω��̏���߂���쒩���}���̐��X�̖���ʂ�h�点�����j����́A�Ȃ�قǘb�̍��i�������s�̒���̔e���𑈂�����Ȃ̂ł͂��邪�A���̎�v����͊}�u��g���͓��ԍ�ł����ċ��s�ł͂Ȃ��A����藧�Ă��͔̂d���������̂����A���Ƃɖk�����ƂƐe�[�̐e�q�̊���͖k�֓��Ⓦ�k�ŁA����̍c�q�����������쒩�̕���̂قƂ�ǂ͋�B�Ȃ̂ł���B �@ �܂�w�����L�x��ǂނƂ������Ƃ́A���s���O���猩��ڂ��Ȃ��Ɠǂ߂Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��B�@ |
|
|
�Ƃ���������ŁA���낻�덡��̖{��ɓ��肽���B�Ƃ肠����̂͑������́w�鉤����x�ł���B���R������������B
�@ �ЂƂɂ́A��͂���{�j��ő�́u�ʁv�ł�������m��Ƃ��납���k���ɓ����Ă����̂��g�����h���낤�Ƃ������ƁA����ɂ͎O���R�I�v�̐e�F�ł��������������A�����Ď��ӂ��E���ė���ɗ��肠�������̈�����������낤�Ƃ������Ƃ��B���j�����ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��A������]�`�ł��Ȃ��B�ǂ��炩�Ƃ����ΕB�j�ɋ߂��B���̂��߁u�ǂ݁v�Ɓu���v���Ԃ�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B �@ �����ЂƂɂ́A��k���̘b�͍���ł͂Ƃ��Ă��I���Ȃ��B���̂��߁A�߂����ɂ���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��̂����A����ɂ��A���̂܂�����ɂ��Ȃ��ł��������Ǝv���Ă���Ƃ������Ƃ��B�ǂ̂悤�ɂȂ����͂��܂͖������Ȃ����A���x���������炽�߂āA���̂������ˌ����́w����{�j�x�̎��ӂɋy�ڂ����Ǝv���Ă���B�r���A���ЂƂ��u��쒩�v���������ʉ߂��Ă݂����B���������g�Ȃ��h�����Ă����ɂ́A��͂���킩��n�߂�̂��������낤�Ƃ������Ƃ��B�@ |
|
|
�ł́A�n�߂悤�B����̂ڂ������N�ɒł���̂́A��k���j�̗���������Ƃ����܂�ł������ƂȂ̂ŁA���܂̂Ƃ���͂���ȏ�����҂��Ȃ��ł��炢�����B�ł��邾���킩��₷���������肾���A��͂藬��͂�╡�G�ɂȂ�B���߂āA�ǂ̂悤�Ɍ��킪�o�ꂷ�邩�A�ǂ̂悤�ɑ�������������ł������A�����ɒ��ӂ��Ă��炢�����B
�@ �ȉ��͑����̖{���̍\�������Ȃ菟��ɑg�ݑւ��Ă���B�b�́u�n�Ȃ鈫�}�v�̒�����绂���n�܂��Ă����B�w�����L�x�̖`���ɂ́A����Ȉ�߂��������B�����̎Љ�ɂ������Ă͂܂�B �@ �l�C�I�I�C�j�����e�A������C�}�_���J���Y�B�T��(�낤����)�V����(����)�V�A�ǔg(������)�n�����J�X�R�g�A���j�C�^���}�f�l�\�]�N�A��l�g�V�e�t�H�j�x�����R�g�����Y�A�����葫���[(����)�j���i�V�B �@ ���q���{��13���I�̒������爫�}�̉��s�Ɏ���Ă��悤�ɂȂ��Ă����B�E���𒆐S�ɑ䓪���Ă����ݒn�̔��t�҂����A�A�E�g���[�����ł���B���t�҂Ƃ��A�E�g���[�Ƃ����܂����������������A�R���E�C���̂������Ƃ݂Ȃ��ꂽ�B �@ �����̈��}��10�l����20�l�قǂ̏��W�c�ŁA�`�F�̕����܂Ƃ��A���ʂ����A����̂͂����������ӂ�܂킵�āA���͂̋����͂����������B���̃��[�_�[�́u���{�l�v�Ƃ��u���{�v�Ƃ���B�����������}�̂Ȃ��ɁA�̂��̓�ؐ���(�����̂��E�܂�����)�̕��e�ɂ�����ł��낤�A���̕s���̓�(�����̂�)�͓������������B �@ ���i10�N(1273)�A�k�{�͈��}�����̌������A��삪�E����Ӗ��ɂ��Ă��āA��Ɛl�炪���}��̓��ɂ����܂��Ă��邱�Ƃ��Ɣ��f���A���������}��̓��ɉB�����������Ƃ��I�����������ɂ́A���̂�3����1��v������Ƃ����ʒB���o�����B �@ ���������Ԃ͂��������ɂ����܂�Ȃ��B14���I�ɂȂ�ƁA��Ɛl���g���݂����爫�}�����Ă��邱�Ƃ��I�����Ă����B�悭���邱�Ƃ��B�h�q�Ȃ̊������h�q��H�����̂ɂ��邱�Ƃ����ڂ��Ă��܂��̂��B�����Ŋ���2�N(1304)�A���{�͈��}�̏����𗬌Y���玀�Y�ɕύX���A����1�N(1319)�ɂ́A�Z�g���T��̑啧�Ғ傪���}�����̎��B�����E���E�R�z�E��C��12�J���ɔh�����āA�ǜ�ɏ��o�����B �@ ����͋t���ʂ������B���{�̓����ɐ^��������R���鈫�}��������A�����͂������āA�������ɗ͂̂��镐���W�c�ɐ�ւ���Ă������B��q������A����(�͂��肬)����g���A���I���ɒ����Ă������B�܂�ŌÑ㒆�����q�S�Ƃ̖n�q(�ڂ���)�̏W�c���B�@ |
|
|
�ɉ�̑����ɓo�ꂵ�����c�}�Ȃǂ��A�����������}�̑�\�̂ЂƂ������B���c�}�ɂ��Ă͌������悭������ł���̂�(����X�E�w���}�x�A�V��F�d�w���}�̐��I�x�Ȃ�)�A���}�̐��Ԃ������R�~���j�e�B�Ƃǂ̂悤�Ɍ��т��Ă������́A��R�Ƃ���B
�@ ���A���ꂾ���łȂ��A���}�͓Ɠ��̃l�b�g���[�N�����т͂��߂��B���̃l�b�g���[�N�ɂ͊C�H��͐�ɋ����҂������o�����A���Ƃ��Δd���̈��}�͒A�n�E�O�g�E�����E���˂ƌ���Ő��˓��C�E���{�C���������A�E���ւ̔N�v�Ă����̃��C���őj�~���D����邱�Ƃ��p�ɂɂȂ��Ă����B�܂��ɎR���C���s�ׂ����A�A���r�A�̃������X�̗�ԍU���Ȃǂ��v�������ׂ��ق����������낤�B����͋`���������̂��B�����爫�}�̒a�����A���j�w�҂����͖ÏP���ƂƂ��ɐ����r�ꂽ�u�_���v�̗��s�ƂƂ��Ɍ�邱�Ƃ�����(109��w�_���ƈ��}�̐��I�x�Q��)�B �@ ���˂̐ԏ�����(�~�S)�┌�˂̖��a���N�Ȃǂ́A�̂��Ɍ���̈ꖡ�ƂȂ������}���������ė͗ʂ����Ă������B�w�����L�x�́u�����×�m��(����)�n�A���U����N�j���߃V�e�V���m���ڃ����J�X�v�Ə����Ă���B�@ |
|
|
���}�ɂ��Ă͂�����������Ă�������Ȃ����A���܂ڂ����������Ă����������Ƃ́A�V�c�̗��j�ƈ��}�̗��j�����r�E�X�̗ւ��Ȃ��邲�Ƃ��A�����Ɍ��邵���Ȃ����オ�������Ă����Ƃ������ƂȂ̂��B
�@ ����������������Ƃ����̂͋��s�𒆐S�ɁA�S�������������ςɏ�y���q�y(����)�ɐU�蕪�������ゾ�����B���܂͋_���ՂƂ��ėL���Ȍ�������オ���Ă����̂��A�u��Ȃ�s�v����邽�߁A�u�q�Ȃ���́v(�A���^�b�`���u��)���o�_�H�E����E�D��������ŐH���Ƃ߂悤�Ƃ��������̊��ɂ��ƂÂ��Ă����B�V�c�Ƃ̈ꑰ���u�����v(�Ȃł���)������̂��A�q�Ȃ���̂��͐�ɗ������߂������B�����������ƂɔM�S�ɂȂ�������A�t�ɂ����ɌÑ�V�c�V����������Ă������킯���B �@ ���������ꂪ�i��ł����Ē����ɂȂ�ƁA���s�̎��Ӓn��ɂ͎�ۓ��q��ɐ����q�Ƃ������z����₷��S���������邱�ƂɂȂ�A���ꂪ�V���C�����S�̎p�ƂȂ��ēs���P���Ƃ����}���ɂ��Ȃ��āA����ɂ͊e�n�̋��E�ɐ�ۂ�t���Ȃǂٌ̈`�E�ٗށE�ٕ����`���I�ɗ����オ���Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ����B �@ ���}�̒����Ƃ́A���̂悤�Ȃ��܂��܂ȉˋ�́u�q�Ȃ���́v���A���̂Ƃ���͌����̗͂������ċE���E���C�̊e���Ɉٗl�ّ̂̎҂Ƃ��ė����オ���Ă����Ƃ����b�Ƃ��āA��������ׂ��Ȃ̂ł���B�����炱���A�l�X�͑z�����Ă����ٗރ��@�[�`�����ȗ͂��e�n�ٌ̈`���A���ɂȂ��Ă������Ƃɋ������̂��B������ꌾ�ɂ́u���R�T�S�v�̕������Ƃǂ܂�Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃ��B �@ �̂��Ɍ���V�c�ƂȂ鑸��(�����͂�)�e�������܂ꂽ13���I���̐���1�N(1288)�Ƃ����̂́A�ꌾ�ł����A�����������ゾ�����̂ł���B �@ ����͑��ʂ��āA�m���Ă̂悤�ɓV�c�e�����߂����̂����A����́A�����g�q�y�̈��}�h���ӂ��߂��u���y�����v�z�v�ɂ���āA���{���Ȃׂē��ꏶ���������Ƃ������Ƃ������B�������A���͌��킻�̂��̂�����Љ�̎��R�T�S�ł���A�ٗ�҂������̂ł���B�@ |
|
|
�����͌�F���V�c�̑�2�c�q�������B��e�͌ܒҒ��p�̖��̒��q�ł���B�����ԎR�@�̌n���ɑ�����B�{���w�鉤����x�́A�`����1�s���u���s�̍��o��x��̐��k�Ɍܒ҂Ƃ�����������v�Ƃ����ӂ��ɁA���̌ܒ҉Ƃ̕��ꂩ��n�߂Ă���B�����ւ܂��o�����������B
�@ ���̑����͑c���̋T�R��c�̂��Ƃň�Ă��A�����̋g�c��[�̌O���������Đ������Ă����̂����A��1�c�q�M���e��(����V�c)������3�N(1308)�Ɏ��̂ŁA12�̉ԉ��V�c�����ʂ��āA21�̑������x�炫�̍c���q�ɗ����ƂɂȂ����B�����̗��V(��ڂ�)��20��������Ƃ����̂́A���Ȃ�̒x�炫�Ȃ̂ł���B���A�ٗ�Ȃ̂́A���̂��Ƃ����ł͂Ȃ������B �@ ���̂��낷�łɁA�V�c�̍��́u�����@���v�Ɓu��o�����v�Ƃ̗��h�ɂ���ċ����Ă����B���ꂪ�Ƃ�ł��Ȃ��^���������炵���B�ǂ����炱�̍����̑������c���I���̖��Ƃ��Ďn�܂������Ƃ����ƁA���ړI�ɂ͌㍵���c�����i9�N(1272)�Ɏ��������̂��A���̑�2�c�q�̑�89���[���V�c(�����@��)�Ƒ�3�c�q�̑�90��T�R�V�c(��o����)�����ꂼ��c�ʂɂ����悤�Ƃ��āA����ł������č����̌����������悤�ɂȂ������߂������B�܂�A���̍R���͌���̂���������̎���Ɏn�܂������肾�����B �@ �����Ƃ����ꂾ���Ȃ�A�Ñ�ȗ��A�����V�c�ɒN���A�����Ƃ������Ƃ͂܂��Ɍ��Ō�����Ƃ��ɂׂ̂����Ă����̂�����A������߂ĉ^���ɏ]�������Ȃ��b�ł�����킯�Ȃ̂����A���̎���A���́u�ʁv�̑I������Ɏ����k���̊��q���{��������Ă��܂������Ƃ��A����G�ɂ��A�[���ɂ������B �@ ����͂��Ƃ͂Ƃ����A�㒹�H�@�����Ƃ��琭����D�҂��邽�߂̏��v�̗��Ɏ��s���āA2�㎷���k���`���ɂ���ĉB��ɗ����ꂽ���ƂɋN������B�@ |
|
|
���v�̗�(1221)�̂��ƁA�`���͏��v�̗��ɂ܂������֗^���Ȃ�������x�͓V�c�𗧖�(�������)�����A���̌n�����l���Ɍp�������B
�@ �Ƃ��낪�l��V�c��12�Ŏ��B���Ƃ��c�q������͂��͂Ȃ��B�����ŁA�ې���Ƃ������̊O���ł����������V�c�̎q�̒����𗧂Ă悤�Ƃ����̂����A3�㎷���̖k����͂���ɖґR�Ɣ����A�y���̎q�̖M�m(���ɂЂ�)�𗧖V�������B���ꂪ����̂���������̌㍵��V�c�Ȃ̂ł���B�ȗ��A�������{�͓V�c�̍������E����B �@ �V�c�̍������łȂ��A�k���͐ۊ։Ƃ����łɍ��E���Ă����B�������ɂ��ې��E�֔��Ɛ�́A���̌�͓����̉ƕ������߉q�E����ɂ���ĕ��L����Ă����̂����A�k�������̎���A�߉q�����i���A���������E������o�āA�ܐۉƂ����܂����킹�ăR���g���[������悤�ɂ��Ȃ��Ă����B �@ �Ƃ��������A�����k�����V�c�̍��������̂��B�������A�c���̑Η������܂�Ɍ����ɂȂ�͖̂��{�ɂƂ��Ă͂�낵���Ȃ��B�܂�����㒹�H�@�̂悤�ɖk�ʂ̕��m���W�߂ĕ�������悤�ȓV�c���o�Ă��Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B �@ ���{�͂����Ō�s����`��낵���A����1�N(1317)�ȍ~�͌�[���n�̎����@��(��)�ƋT�R�n�̑�o����(��)���A�u�����R���v�����Ă������Ƃɂ��Ă��܂����B�����10�N�Ō�オ������悤�ɂ����B�܂��Ƃɋ@�B�I���B�c���������A��ނȂ�������̂B�������j��ł́u���ۂ̘a�k�v�Ƃ����B �@ ����ŁA�c�ʂ͓��ꂩ��藧�������A�W�O�U�O�ɐi�ނ��ƂɂȂ����B89��[��(��)�A90�T�R(��)�A91��F��(��)�A92����(��)�A93�㕚��(��)�A94����(��)�A95�ԉ�(��)�A96����(��)�Ƃ����ӂ��ɁB �@ ���Ȃ݂ɁA���̗����R���̓����̌�[���ƋT�R�̗��@���݂��Ɂu���V�̌N�v���߂���h���}�������Ă��鎖����A��l�̏��������̓��ʂ��璭�߂Ă����L�^���������B���łɁu������v�ɂ����Ղ�Ԃ�����[���@����́w�Ƃ͂�������x�ł���B �@ �����ЂƂ��Ȃ݂ɁA��������̏����̂Ƃ��A�c����肪���サ�ď����V�c�ɂ��邩�ǂ����Ƃ����c�_���₩�܂����Ȃ������Ƃ�����������ǁA�c����{�C�Ŗ��ɂ���Ȃ�A���͂��́u���ۂ̘a�k�v�܂Ŗ߂��čc�����^�̈Ӑ}�ɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B�@ |
|
|
�����͑H�N(����)���āA����2�N(1318)�Ɍ���V�c�ƂȂ����B�T�R�V�c�̍c������������o�����̑�96�ゾ�B
�@ ��o���Ƃ́A���̍��㗒�R�̑�o���̂��ƂŁA�����ɋT�R�@�̗��{�����������ƂɈ���ł���B���̋T�R���{�̂��Ƃ����܂͏����q�ɐl�C�̃��}���`�b�N�E���C�g�A�b�v�̑�o���B�������A��o�����Ƃ����͎̂����@���Ƃ͂������āA�ǂ����u�e�����Y���̃��}���v�̂ق��ɐ��������悤�ȁA����������h�������B�����@�̂ق��́A�㗧���V���̐��Ɍ�[���@���䏊�����������ƂɎn�܂��Ă���B �@ ���āA3�N��̌���1�N(1321)�A����͌�F����c���琭�����Ϗ������₢�Ȃ�A�������ɓV�c�e�����J�n�����B �@ �L�^�����ċ����A�u�_�l������~�߁v���Đ_�l(���ɂ�)�̖{��(�������L��)�ɑ��镊�ۂ�Ə����A���s�̏��H�Ǝ҂�����l(�����ɂ�)�Ƃ��ĕҐ����āA�g�V�c�̌o�ρh���m�����Ă������B �@ �l������V�����B�k���e�[�A�g�c��[�A�������H��[�A���쎑���A����r��Ȃǂ�o�p���A���X�Ɂu�ώ|�v(���)����(�e�[�E��[�E��[��3�l���u��(�̂�)�̎O�[�v�Ƃ���)�B����e���A�����ƍL���́u�쒩�̐����v�́A�˂ɂ��̗ώ|��A������Ƃ���ɓ���������B �@ �܂��ɔ�������鉤����̃X�^�[�g�������B�������A����ɐe���������킯�ł͂Ȃ��B����͖��{�����ꂩ���̂����������B�@ |
|
|
���푦�ʂ̂�����ƑO�̐��a5�N(1316)�A���q�ł�14�̖k�������������ɂȂ��Ă����B�d�G���ʂ�A�����͂����Ƃ��ɕ��s������B�����͓��Ǘ�(��������ꂢ)�̒��荂��(��������)�������Ă���B
�@ �����֒Ìy�Łu�����ꑰ�̗��v���������āA���̒��肪���Ǘ̂Ɉ˗����ꂽ�ɂ�������炸�A����(��������)�͈����ꑰ�̑Η��҂̑o������d�G���Ƃ��Ă������߁A��������������Ɂu�ڈ̔����v��������A�����ɂ��悢�抙�q���{�����\�͋@�ւł��邱�Ƃ��͂����肵�Ă����B �@ �×�1�N(1326)�A�����͂������Əo�Ƃ����B�����A�k�������ɂ�開���������Ȃ��ƌ������̂��B���ӔC�Șb�����A���߂̑�������������o����(�ŋ߂̓��{�����́A���̖k�����߂��Ă���)�B���X�؍��������̈�l�ŁA�䔯����Ɠ��_�𖼂̂�(�o�T���喼�ٖ̈����Ƃ�̂͂����Ƃ��Ƃ̂���)�B �@ �����͂�������c�y�⓬���ɋ������B�w�����L�x�ɂ́u�\�m���n�i�n�_�q��j�z�^���v�ƕ`�ʂ���Ă���B�����A�����������̏��Ƃ�s�R�Ɏv���ď�q�̌����`���Ă݂�ƁA�c�y�@�t�ƌ������̂͐l�ł͂Ȃ��A�J���X�V���R���p�ٌ̈`�ٗނ̛Z��(������)�������B���s����c�y�@�t�ɕ�����������̊Ԏ҂������A���{�̉��[���܂Ő������Ă����̂ł���B �@ ���Ԃ��}�������Ă���Ƃ����G�s�\�[�h�����A����ł������͂���ɗV�э����A�����Ƃ����q�s���ɂ͓��ɖO���A�т𒅏���������4000�C�ɋy�Ɓw�����L�x�͓`����B�����Ƃ������͓�������ɋ���������łȂ��A�T�ѕ����ɂ��X�|�����B�����a�Ƃ̂�����肪�����Ɏn�܂����B �@ �����āA���q�̖��{���ł��Ƃɂ̂��錠�͎҂Ƃ����A�Ǘ̂̒��荂���̈�h�����������B�����Ƃ������������{�̎�̂Ԃ�ɂ�������A�V�Q�̑��������Ȃǂ��䓪���Ă���̂����d�d�B�@ |
|
|
���q�̖����I�ȏ́A����Ɍ��Ă̕s������������`�����X�������炵���B�����̎Љ�ɗ����R���̃��[��������ȏ�A����͂��傹��́g���p���h�̃����[�t�V�c�Ƃ����h���������̂����A����Ȃ��Ƃ̓v���C�h�̍����鉤����ɂ̓[�b�^�C�C�ɂ���Ȃ��B
�@ �������A�������������ɂ͗����R���ɉ���������{���̂��̂�œ|��̂��邵���Ȃ��B�c�y�@�t�ɉ������Ԏ҂����q�ɐ������Ă����̂́A���̂��߂������B �@ ��̂Ƃ͂������{�����āA�u�ʁv�̂��₵�������ɂ͊Ԓ��������ނ����B���s�Œ������������͘Z�g���T��ł���B���{�͂��̋@�ւ��A�ɗz�ɂ������B�������͂̍�����}�́A�����ɕ��s���Ă��悤�Ƃ��A�Ȃ��Ȃ����̍����~��悤�Ƃ͂��Ȃ��̂��B�������{���������������������Ȃ��鉤�̓����������낤�Ƃ����͓̂��R�ł���B �@ ����A����̑��߂����͉������͂�Ȃ���A�Ђ����ɓ����̉��ɓːi���Ă������B�u����u�v�Ə̂��ėV�����Â��A�G�̖ڂ��\���Ή������̌v������グ���B�ǂ�ȗV���ł��������́A�w�����L�x�ɂ��w�����L�G���x�ɂ����������ƕ`�ʂ���Ă���B����ɂ����Η��s�C���������̂ł���(���b���̕���ɑ�Γ��������V�э����Ă����ʂ����������̂́A���̌���̖���u�P���Ă���)�B�@ |
|
|
����h�̗��s�C�����́A���̎���̗p��ł����u�ꖡ���S�v�Ƃ������̂ł���B���̗p��͂ӂ��́u�Ꝅ�v�ɂ�����B�����炻���ɂ͂��Ȃ蔽�R�I�ŁA��`�����̃C�f�I���M�[�I�ȋC�������Ђ���ł����B����͏ڂ����������Ȃ��Ă������A�Ƃ��Ɂu�v�w�v(��q�w)�̘a�w�����邢�͍��Ƃ������_���������B
�@ ���������ꖡ���S�̋C�T�Ɗ����e�n�̍����∫�}�ɐ������Ă����̂́A����r�����쎑���������B��l�́u�앚�v(�̂Ԃ���E��̎R���E�̂Ԃ�)�̊��D�����A�ߍ]����Z��O�͂�����A���C�����C���ɑ����̂����B �@ ���̂����A��l�͊e�n�̔����������ւ̊��҂ɖ����Ă��邱�Ƃ������Ă������B����ɋΉ������̔��������߂Ă݂�ƁA�鉤�ƂĈّ��͂Ȃ��B���ꂽ10�N�݈̍ʂ��A����3�N�ɔ����Ă����B�������Ė��{�̖ڂ𓐂�Ŗ���u���Ђ炩�ꂽ�̂��B �@ ����u�ɏW�܂��Ă����̂́A�w�����L�x�ɂ��ΉԎR�@�t��(���납��)�A�l�𗲎�(��������)�A���@����(�Ƃ��̂��˂�)�A����r��A�m���̗V����@�̌���A����(������)�d���A�����������Ƃ��������ߒ��̑��߂ł���B�����ɐ��厛�̒m�ł╶��(����)��̗d�m����������B �@ ���̂Ƃ����ς��Z�g���T��̕]��O�E�ɉꌓ�����������ŁA�������A�̋F�������邽�߁A�ޗǔʎ�̖{���̕�F���������Ƃ����̂��A���̂���o�Œ��ォ�炽���܂��b��ɂȂ����Ԗ�P�F����́w�ٌ`�̉����x�������炩�ɂ������Ƃł���B �@ ���ςɂ��ẮA���낢��ڂ����b���������̂����A����͉������Ă����B��펛�̍���Ƃ��Ȃ������A���Ƃ��Ė������u���여�v�ɒʂ��Ă����Ƃ������Ă����B���̂�����u�����ƓV�c�v�Ƃ������_�����シ��B�@ |
|
|
�����̌��͘Z�g���T��𗎂Ƃ����Ƃɂ������B���s�͌�F����c���S���Ȃ������Ƃ́A����4�N(1324)9��23���ƌ��܂����B�k��Ђ̍�̓��ɂ�����B��x��ŘZ�g���T�肪�蔖�ɂȂ����Ƃ����_�����Ƃ����̂��B
�@ �Ƃ��낪���낤���Ƃ��A���̌v�悪���O�ɉk�ꂽ�B�������������B����u�ɎQ�����Ă����V�납�A�y�����A�ʎ�̎҂��B�����҂̖��O��̂͂��܂Ȃ��������Ă��Ȃ��̂����A�Ƃ�����������̍ŏ��̓����v��͂��̏����[�ŘI�悵�Ă��܂����̂��B�ڍ������B �@ ���쎑���A�r��A�V��͊��q�Ɍ쑗����A��蒲�ׂ̂�����Ƃ͓��쎑���ƂȂ���(�����������Ď�Ƃ����Ԃ����̂ł��낤)�A���n�ɔz�����ꂽ�B���ꂪ������u�����̕ρv�ł���B�@ |
|
|
���{�̎����͍����ɑ����ċ���匰�ɂȂ��Ă����B����̓V��������B�d�c�Ȃǂ��Ă��Ȃ����A����Ȃ��ƂɊ֗^�����Ǝv����̂́u�X�R�u�����f�v(�ԉ��V�c���L)���Ɠ˂��ς˂��B����ǂ��A����������߂Ă͂��Ȃ��B���̈���ŁA����ɔO����̓����v��̗��ĂɂƂ肭�B
�@ �×�1�N(1326)�ɒ��{�U�q�̈��Y��S���F������Ƃ������ڂŁA�u�֓������v�̏C�@���֒����[���Ői�s�������(������d�����͕̂��ςŁA�鉤���g�������̓`�@�������Č얀�d�Ɍ�������)�A����3�N(1330)�ɂ͂�����ɓ�s�k���K��A���厛�E�������E����̑m���̌��N�⋦�͂�����Ă������B �@ ����Ƃ̐Ղɂ́A�̂��Ɍ��(����悵)�e���ƂȂ鑸�_�@�e�����t�@�V���e�[�V����������(�哃�{�Ƃ��Ăꂽ)�B��ǐe���͉×�2�N�ɓV�����ɂ��Ȃ��Ă���B �@ �����@�����͂̓�s�k��𖡕��ɂ���������ł͂Ȃ��B����͂�����ŕ��ς���āu�ٌ`�̔y�v�Ƃ��ڐG���Ă������B�u�ٌ`�̔y�v�Ƃ͔�l���܂ށB����͏㉺�M�G����ʐV����̂��߂̔w���̃l�b�g���[�N��g�ݗ��Ă悤�Ƃ����킯�ł���B���ꂪ�̂��ɓ�ؐ����E���a���N��́g�q�y�̈��}�h�Ƃ���������Ԑ��ɂ��Ȃ��Ă����B�@ |
|
|
�鉤����̃R���Z�v�g�́u���y�����v�z�v�ł���A���̗��O����������p�́u�s翍��́v�Ɓu�N�b���́v�ɂ���B
�@ ���̎���A����̖��{�═�Ƃ̎v�z�́u�����v���v�z�v�ɂ��ƂÂ��Ă����B����͖Ўq�̌������ό`�������̂ŁA�N�傪����܂���Ƃ��������́A���Ƃ��N��ł��낤�Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���L���Ȏv�z�������B�k���̎������v�ȕ���̘A���͂����ނ˂��̗�����Ŏ炵�Ă����B �@ ����ɔ䂷��ƁA����Ƃ��̑��߂����́u���y�����v�z�v�ɂ��ƂÂ��āA�킩��₷�������̂Ȃ�A�u���Ƃ��N�傪�ӂ��킵���Ȃ��҂ł��낤�Ƃ��A���Ɩ��Ƃ̊W�͈�̂ɂȂ��Ă����ׂ��ł���v�Ƃ̌��������~���ɂ����B �@ ���́u�����v���v���u���y�����v���Ƃ������Ⴊ���ꂼ��ɂ��^�ӂ́A���܂͂Ƃ肠���������Ă͂������A�܂��A�Z���v�����x�̉���ł͂��̑���̈Ӗ�����Ƃ���́A�������Ă킩��ɂ����Ȃ�̂Ő��������Ȃ��ł��܂����Ƃɂ��邪�A����ǂ��A���̖������`���鎋�_�����A���̂��Ƃ̑S���{�j����邪���Ă����R���_�ɂȂ��Ă����̂ł���B�����̐��˃C�f�I���M�[�⑸�����́A���̐������܂�̂悤�Ȃ��̂������̂��B �@ �����������Ⴊ����̐��ʂɕ��サ�����������̌���2�N(1330)�A����̓V�c�e���̑�������͑�_�Ȑ����X�ɘA�ł���Ă������B���Ƃ��Εĉ�����߁A����@�A�֏���~�߂Ȃǂ��B�ĉ��̍�����}���A���Y�̔���ɂ��݂��ւ��A�������̊֏����Ƃ��ς���Ďs�ƌ��ՂƗ��ʂ̊J����}�����̂ł���B����́u���y�����v�̃��f���Â���Ƃ�������̂ł��邪�A����������A�����𐭎��o�σZ���^�[�Ƃ���g�V�c�̌o�ρh�̊g�[���Ӗ����Ă����B�@ |
|
|
����Ȃ���A����͂ӂ����і����ɓ����̘T���������悤�Ƃ��Ă����B���ꂪ�u���O�̕ρv�̊J�����B
�@ �������s�^�ɂ��A���̌v��͂܂��܂������ɂ���Ď��O�ɉk�ꂽ�B���x�̖����҂̖��O�͂킩���Ă���B�u��̎O�[�v�̈�l�̋g�c��[�ł���B����̓����������l�����B��[�́g�V�c�̃N�[�f�^�[�h���������č���̒鉤�̗�����낤�����A���y�����v�z���ނ��닶�킹��Ƃ݂āA�����ē|���v��̎�d�҂����r��ɋA�������āA�鉤�̊�@�𖢑R�ɖh�����߂ɖ��{�Ƀ��[�N�����A�Ƃ���Ă���B�����̑O�ɂ́A��[�͌���ɊЏ�(����)�\�J�����o���Ă����B �@ �͂����Ă��ꂪ�^�ӂ�^���ł��������ǂ����͂킩��Ȃ����A���{�͂��̖����ɂ��ƂÂ��ĕ��ρE�~�ρE���~�E�q���E�V�����u�֓������v�̍߂ŕ߂炦�Ċ��q�Ɍ쑗���A�Ƃ��ɗd�m���ςɂ��Ă͍ł���C�����̗������ɗ����Ă��܂����B �@ ��d�҂ƂȂ�������r��͊��q�Ŏa��A�������e�n�̃I���O�ɏo�����Ă������쎑�����z����̍��n�Ŏa��ꂽ�B �@ ���ׂĂ����m�ő�߂���l�ł��Ԃ�������r��A�������q�Ɍ쑗����A�����o��̂����Łu��������v���Ă�����ʂ́A�w�����L�x�����Ă̖����q�ɂȂ��Ă���B����Ȋ����̓��s�����B �@ �J(����)���o�����k����m�A�փm�����j���G���e�A���n�R�H���ŏo�m�l�B�����y�j���n�Z�o�A���i���k�C�j��(����)���s�N�A�g�����M�m����(����������)�A������(�Ƃǂ�)�g�����X�B�����m�����Ń`�n���A�s�L���t�l�j�ߍ]�H���A�����E�l�m��j�N�߃��A�q���v�t�J�g�����i���d�d�B �@ ���łɎ��������͂ǂ�Ȍ��f�ɂ��D�_�s�f�ɂȂ��Ă����B�����Ƃ͌��f�͂��݂�����A�I�����Ȃ̂ł���B�u���O�̕ρv�̎��Ԃ̓W�J���K�������v���Ȃ��̂ł͂Ȃ������B�̂�̂낵�Ă����B �@ �����Ō���͂��̗D�_�s�f�𗘗p���āA�������A�ɏ悶�ĒE�o����ƁA�}�u�ɓ���A�}�u�������_�Ɍ��y�d���������邱�Ƃɂ����B�u�ʁv�̂ق����������B��͂��k���̕���͋��s�ł͂Ȃ������̂��B�������Ɂw�����L�x�̃N���C�}�b�N�X���߂Â��Ă���B �@ ����͋ߗׂ̕��m�∫�}�ɎQ�w����т������B�����Ōĉ������̂���ؐ����ł���B�����́w�����L�x�ł́A�����ŏ��߂Ċ���o���B �@ ����A���s�����킪�E�o���Ċ}�u���ď邵�āu�s�݁v(����)��݂����Ƃ����m�点�������{���́A���x�͂���Ƃ����藧�����B�܂��Z�g���T��Ɋ}�u�U�����d�|�������A���ł͑啧�咼�Ƌ����~���A����ɂ͑�������(�̂��̑���)��叫�Ƃ����㗌�R���}篌����������B�������Ă����Č���̓V�c�ʂD���A�����@���̌����V�c�𗧂Ă��B �@ �Z�g���R��7���������Ƃ����B�}�u�̍Ԃɂ͏펞���S�l�����Ȃ��B�������A�哃�{��ǐe���w�����Ƃ����}�u�͂����ɂ͗����Ȃ��B����ǂ��납�͓��̐ԍ�œ�ؐ�����������(�����͂ڂ��������Ă�����ˎR�w�@��w�̌������̑����璭�߂���ʒu�ɂ���)�A����̈�{�ł͍��R���r���������āA���킪�}�u�ɌǗ����Ȃ��悤�ɉ���ˌ����ďo���B���Ɉ��}������ƂƂ��ɍs�������������̂��B��؈ꑰ���������̂́A�O�N�ɓ���r��u�앚�v�Ɏp������Ĉꖡ���S�|���v�z�̐����ɗ������Ƃ��Ă���B �@ �₪�Ĉ��h������叫�Ƃ����㗌�R20�����}�u�E�ԍ�����͂ނƁA�������ɗ���͊ח������B����͍��x�����߂炦���A����4�N(1332)�ɉB��ɗ����ꂽ�B���v�̗��̂Ƃ��̌㒹�H�@�ȗ��́u�V�c�̉B�߁v�������B�@ |
|
|
�t���]�����͈̂�����q(�������́u���ȏ��v�������낤�Ə����Ă���)�ƁA���b��풉���Ɛ������s�[���炢�A�g�̉����x�삷��҂ƂĂ��Ȃ������B����͐�̐▽�̃s���`�ɗ������ꂽ�B
�@ ���̌���̉B��z���̓r���A��������(�����܂����̂�)���鉤�~�o���͂����Ĉ�s�̎ԉ��ǂ����Ƃ����̂��A�w�����L�x�ł͗L���Ȃ�����ɂȂ��Ă���B �@ �����͏h�ɂɔE�т��ނ̂����A�����͂��͂�����s���o���������ƂŁA��ނȂ���̍��̊�������āA���̏\�����̎��荏�݁A��������u��V�̌��v��t�������Ƃ������ӂ�����ɓ`���悤�Ƃ����Ƃ����̂�(���́u��V�v�̎v�z���̂��ɐ��˃C�f�I���M�[�ɔ�щ���)�B �@ �V(�Ă�)���H(��������)�������锜(�Ȃ�)�� �@ ��(�Ƃ�)����(�͂�ꂢ)�����ɂ�����(����)�� �@ ��ǐe���Ɠ�ؐ����̓�l�͎���悭�s��������܂����B��ǐe���͂�������a�̎R�̗R�ǂɏo�āA�C�݉����ɐؖډ��q���ւāA�s���ȌF��H(������F��Ó�)���z���ď\�Ð�̉��n�̈�s�ɓ������B���܂͑哃���ɂȂ�B�g��ɋ߂��B�������A��������p������킷�ɂ͂����Ȃ������B�����ׂ��͂�͂�B��́u�ʁv�Ȃ̂ł���B �@ ��ؐ������ǂ����Ă������́A�͂����肵�Ă������Ƃ��킩���Ă��Ȃ��B��1�N�قǂ���������B���̂������ɋ����R�̐��̎Ζʂ𒅁X�Ɨv�lj����Ă���(�����̕x�c�т�͓����삠����)�B����܂��n�q�̐�@���v�킹��B�͓��ɂЂ����ɖ߂��āA���ԍ�̍Ԃ�D�҂��Ă�����B����͔E�т̎҂̓����ɋ߂��B�������A��͂�\�����������͏����Ă����B �@ �B��ŊĎ����Ă�������́A�����̒N���������Ȃ���������Ƃ����āA����Ŗ������x�����Ƃ͟|���v���Ă��Ȃ������B�鉤�������ꕪ��b����Ƃ�������߂Ă��Ȃ������B��ǐe���ƈ��}�l�b�g���[�N�ɑ��āA���܂��܂Ȏw�߂��Ă����B�������a�̂��r�ݒ^�����㒹�H�@�Ƃ͂܂������������Ă���B����ȓV�c�͓��{�j�㏉�߂Ăł���B�@ |
|
|
�������Đ��c1�N�E���O2�N(1332)��11���A�˔@�Ƃ��Č�ǐe�����g��ɋ������A����Ɍĉ����ē�ؐ������͓��̐瑁��ōċ�����ƁA�����̈��}�Ɣ����{���͂Ƃ���ĂɖI�N���n�߂��̂��B
�@ �ނ�{�͑g�D�R�������ނ��A���̒����Ɍ������̂����A�G�̋��_�����U���Ă��ĕW�I����܂�Ȃ��B�哃�{��ǂ��e�n�Ɂu�ߎ|�v(��傤��)�����A�e�n�̖I�N���A�ł��ꂽ����ł���B�d���ł͐ԏ��������ۓ��ŋ������ċ��s���M���A���{���G���̊֓��ł͓����͖��{�R�ɉ��S���Ă����V�c���̍����V�c�`�傪���i�_�Ђɋt�]��騂��������B �@ ���ꂾ���ł͂Ȃ������B�A�l���ł͉͖�ꑰ�������{�̍s�����������A��B�ɂ��e�n�����̒����T��U�������������̂��B�Ƃ��ɓ�؈�}�̗V�����͎��Ԃ��˂Ɋh���������B �@ ���̂悤�ȁA�������ߓ����e���̈�ĖI�N�Ƃ������ׂ����ʗV����킪���t��������A��u�̃X�L�����Č���͉B���E�o���āA�o�_�ɏ㗤���Ă݂����B�܂��ɊތA�������e�E�N���X�g�̒E�o�������낤�B�@ |
|
|
�鉤���}�����̂͊C��l�b�g���[�N�̎�́E���a���N�ł���B��l�͔��˂̑D��R�ɍԂ�z���ƁA��������S���̒n���E��Ɛl�ɗώ|�M�������B
�@ �����Ȃ�Ɩ��{���Ō�̌���I�킢�ނ����Ȃ��Ȃ��Ă����B���O3�N(1333)�A���z���ƁE���������炪�㗌���Ď��Ԃ̒����Ɍ������̂����A�����ō����̌��I�Ȍ��푤�ւ̐Q�Ԃ肪�������āA�吨���傫���}�]���Ă������B�Z�g���T��̖k�𒇎��E���v�͂���ĂČ㕚���E�ԉ�����c�ƌ����V�c�����s����E�o�����邵���Ȃ��Ȃ��Ă����B �@ ���A���{�͓�������I���Ȃ̂ł���B����2����A�Z�g�����͋ߍ]�̔ԏ�ň�Ď��Q��]�V�Ȃ������B���z���Ƃ͐ԏ������Ɛ���Đ펀���A����ŘZ�g���T�肪�Ȃ��Ȃ����B �@ ���������āA�V�c�`��̈�R�����q���P�����B���{�R��5���Ԃɂ킽��퓬���܂�����ƁA�����ɂ������Ȃ����q���{����ł��Ă��܂����̂��B�k���������������ɓ����Ď��Q�����B�����ȁu���q����I���v�́A�܂��ɂ��̎��ɂȂ�B�@ |
|
|
����͖����Ƃ��Ɂu���{�鉤�̍��v�ɕԂ�炢���B�������Âł���B�������ɔN���������Ɖ��߂��B����́A�㊿�̌����邪���͂�j���Č��������������̎��ɕ���Ă����B
�@ �������Č���́u���m�V�`�n�����m���^���x�V�v�Ƃ����L���Ȑ錾������B�u�����̐V���v�̃N���C�e���A�̂��ׂĂ������ɂ������B�G�i(������)���f�����������A�ώ|�̘A���ɂ���ĉ��������`���т����B�Ƃ��ɌR���w�����Ɖ��܈��s���͓O�ꂵ�ď��������B �@ �l�����ӂ����ш�V�����B�֔��Ƒ�����b��p�~���A��������c�̉��̔���(�����E�����E�����E�����E�����E�Y���E�呠�E�{��)�̂��ׂĂɐV���ȋ�(����)���A�C�������B�܂��A��������ւ������킯���B��ؐ��������a���N����풉�����V�c�`����A�V���Ȑ����̕����ɏA�����B �@ �������g�����h�Ɩ�����V���ĉ��܂�̂����A�������瑸���̍s���͈ꌩ�A�s���Ȃ��̂ɂȂ��Ă����B�܂��v���ɂ��Ȃ��Ă����B���������̐��{�v�E�ɂ��ʂ܂܁A���g�ŕ�s����݂��Ċe�n�̕����̐S��������t���Ă�������A������Ƃ��Ċ֓��́u�����(�Ȃ�����)�̗��v�̕���Ɍ������ƁA�����ŌR���Ǝp�����Ђ邪�����āg�V�c�`�吪���h��\�����A�������̍���ɂ�������ŐV�c�R��s���������̂��B�݂̂Ȃ炸�A���̂܂܂��̔s������V�c�R��ǂ����������ŁA��s�ɓ��������B �@ �����ɍ��x�́A���s�����̂͌����̐w�c�̕��Ƃ����A���Ă̎���Ƃ͂܂������t�́A�����T��̏���o��(���������)���邱�ƂɂȂ����B �@ �����A�������Â̐����ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ����B�������̒鉤���ېg�ɑ���ȊO�ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ă���B�����Ō��킪��ނȂ��u�����n���v�̗ώ|����ƁA�`���e������k�����Ƃ��}���ŋߍ]��{�ɋ삯���A�����ɖk���R�Ƒ����R�Ƃ̐퓬���s��H�ɂ���Ђ낰����Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă����B���̂�����̂��Ƃ́w�����L�x���w�~���_�x�̂ق����ڂ����B �@ ���̊ԁA��ǐe���͊��q�ɗH����A�������`(�����̒�)�ɂ���ĎE�Q����Ă��܂��B�킸��27���B�ڂ��͂��̎Ⴋ�哃�{����D���Ȃ̂����A�����ŕ��䂩��~��Ă��܂����̂́A�����ɂ��ɂ����B�@ |
|
|
����Ƒ����̓s��ɂ����퓬�́A���̂Ƃ�����͌��푤�̌��W�͂̂ق����L���������B���������͋��s�𒀂��āA���C������B�Ɍ��������B����͊e�n�̍ݒn���͂𖡕��ɂ��邽�߂ł�����A�����̐e���̐��x�s���ɑ���j���[�V�X�e�����������邽�߂ł��������B�J�ԁA���̂���̌��퐭���͍ň��̕]���������̂�(���̂��Ƃ͂̂��ɖk���e�[���������߂��w�_�c�����L�x�ɂ������Ă���)�B
�@ ���̑����̓��������āA��ؐ����͎��Ԃ̈ӊO�ȓW�J�ɋ����A����ɑ����Ƃ̘a�r��i�����悤�Ƃ���̂����A���̌���͎Q�c�̖V�吴����̌��Ƃɂ���Ĉ���Ԃ���Ă��܂����B �@ ����3�N(1336)3���A��B�̑��X�Ǖl(���݂̔���)�ɓ����������́A�}����������̋e�n���q�R��j��ƁA�����ň�]�A�������o�����Đ��˓��C�𓌏シ��B���R7500�]�z�ɒB�����Ƃ����B���̂܂ܑ����R�����s�Ɍ��������̂ł́A����R�͂ЂƂ��܂���Ȃ������������B �@ �����œo�ꂵ�Ă���̂��A�܂������ؐ����Ȃ̂ł���B�����Ă�������́A�w�����L�x�ň�Ԑl�����Y�t������ʂɂȂ��Ă����B�����R���Ȃ�Ƃ��j�~���ׂ��A5���A�����͋��s���o�����āA�܂��͐t������̉w�ŁA�q�̐��s(�܂���)�Ƌ����ׂď����̍ċN����ĕʂ��ƁA��̐��G(�܂�����)�ƂƂ��ɕ��S�̕���700�R�݂̂𗦂��āA���ɖ���Ɍ��������̂��B �@ �����ɖ����͂��Ƃ�菳�m�̂��ƁA�����Đ����́u����̍���v�Ő��S�ɂ����n���ĉʂĂ��B���܂̖���_�Ђ��������J���Ă���(�ڂ��͂����Ŋ��̎��_�E��O�ɍu�����������Ƃ�����)�B�@ |
|
|
�����������R��6���ɓ����A�V�c�̌R���Ƃ̂����܂��������ł������B�܂��ɍŌ�̌���ł���B
�@ ���x�͓V�c�R�͂����炩�ɕs���������B����͖��a���N�E��풉���E�F�s�{���j�E��t�����Ɓu�O��̐_��v���ƁA�ߍ]��{�����b����ɓ������̂����A�����֑������`���U�����d�|�������߁A����R�̕�����͓s�ɒǂ��A���܂炸���A���N��͓������ɂ��Ă������B �@ �������w�����L�x�́A�u�J蓈ȗ��A���v(�Ђ傤����)�m�N�������V�g�C�w�h���A�����m�����n�C�}�_�L�T�U���g�R���i���v�Ə������B���s�͂܂����Ă���v�ȕ���ł͂Ȃ������̂��B �@ ������8��15���Ɍ����V�c�̗i����錾�����B11���A�������u�������ځv17�J���𐧒肵���Ƃ��A�����ɂ͂₭���������{���������邱�ƂȂ�B�j���[�V�X�e���̒a�����B�@ |
|
|
�ł́A����ł���Ƌ��s�����j�̕���ɂȂ����̂��Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B����͖k���e�[�̂����Ă̊��߂�12��21���ɂ͓~�̋g��̐l�ɂȂ����̂��B
�@ ����͋g��Ɉڂ����B���������܂�����́A���g�����{���̒鉤���邱�Ƃ�������߂Ă͂��Ȃ��B�������Ɂu���{�v��D�҂���v���������B�����Ɂu�쒩�v�Ƃ��Ă̌���h�́g�V�c�̐푈�h���J�n����B �@ �����́A���x�͖k���瓮�����B���H�ɂ����k�����Ƃ��������ē�����J�n�A����4�E����2�N(1337)�ɂ͊��q�ɓ����Ďz�g�ƒ���j��ƁA���̂܂܋x�ނ܂��Ȃ����C���𐼏サ�A���Z�̐쌴�ō��t�~�Ɠy���̌R���ƌ������܂����A�ɐ��H����ɉ���ւđ�a�Ɍ��������̂��B �@ ���������Ƃ́A���̂܂܂ł͒鉤�������ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�w���ŏ�����������߁A����ɒ����W���̕��Q������A�d�ł�Ƃ��邱�Ƃ�X�ƊБt����ƁA�����ɏP���Ă������t���ɔs��A�ΒÕl�œ������������B �@ �V�c�`��͉z�O�ɂ����B���̒n�ŋ`��́A�쒩�Ƃ��Ắu�k������v�������A�א�F��R�Ɠ����ē�������Ŗ����Ԃɑł���Đ▽�����B���݂Ƃ��Ă�����l�̓쒩�̏��̘A�������펀�ɁA����͋g��ř���B�u���ƂƂ͂�@�l�����܂�ɐ���ɂ���@�䐢�̖��̒����m����v�B�ł�������^�ɁA��҉邷�ׂ���Ȃ��Ȃ��������̂悤�������B �@ ����ł�����͕K���̎��ł����B�����̍c�q�������g�삩��e�n�ɕ��Ƃ��������ꝱ�̕��j�𗧂Ă��̂��B�@ |
|
|
�������炪��k���̖{�ԂɂȂ��Ă����B�X�ł́w�c�q�����̓�k���x(�����V��)�ɂȂ��Ă����B
�@ �`��(�̂�悵)�e���͖k���e�[�ƂƂ��ɗ����ցA�@��(�ނ˂悵)�e���͂Ɖ��]�ցA����(�݂悵)�e���͓y���ցA�����đ�����k�����M�ɑ����Ē���{���R�Ɏd���Ă�Ƃ������̂��B �@ �܂��ƂɔߒɂȌv��ł���B����ǂ��҂ĂǕ�点�ǁA�͂����������ʂ͂Ȃ��Ȃ��͂��Ă��Ȃ��B �@ �g����Ă�����2�N9�J���A����͂��ɕa�ɓ|�ꂽ�B�2�E����4�N(1339)�A�����8��15���ɍc�ʂ��`�ǐe��(�̂��̌㑺��V�c)�ɏ���ƁA���̗����A�u�����������Ƃ��Ƃ��łڂ��v�ƈꌾ�����āA�傫����������������B�܂�52�̒鉤�������B �@ �w�����L�x�́A���킪�u�ʍ��n�^�g�q��R�m�ۃj�����g���A��鮃n�c�l�j�k荃m�V���]�}���g�v�t�v�ƈ⌾���A����Ɂw�@�،o�x���̌܂�����A�E��Ɍ��������đ剝���𐋂����ƋL���Ă���B���ׂẴh���}�͋g��ɕ������̂悤�������B�@ |
|
|
���ꂪ�鉤����̐��U���B���܂�Ɏ����v���̓��X�������B�����ɂ킽�����@�V�c�ł��������B�������A��k���̗��j�́A���͂������炱���n�܂�̂ł���B�������y�v�z�́A�������炱���L����̂��B����̎��́A�쒩�̃h���}�̎n�܂�Ȃ̂ł���B
�@ �����������m�ɂ����A����3�N11���ɑ����������u�������ځv����ɂ���Ď������{�𐬗������������12���ɁA���킪�g��Ɉڂ������̂Ƃ�����A��k���Ƃ����O�㖢���̕���̎��オ�n�܂����̂ł���B �@ ��������̓쒩�̎�l���́u����̍c�q�����v�ł���A��ؐ��s���ؐ��V�ł���A�k�����\��V�c�`�@�ł���A�Ƃ�킯��B�ɓ쒩�����������������(���˂悵)�e���ɂȂ��Ă����B���ǐe���͐������R�Ƃ��Č�쒩�̍ł����I�Ȏ�l���ɂȂ��Ă���(���ǐe���̂��Ƃ�m��Ζk��B�̗��j�ς���ς��邾�낤)�B �@ �������A���̓�k������́A�܂������ɑ������R��������2��`�F�ւ́A�܂�3��`���ɂ�鎺���Љ�m������Ă��������セ�̂��̂ł��������B �@ ���̎���A�Ȃ��Ȃ����G���B���������w�����L�x�ɂ��āA����S�����Ƃ̒厡6�N(1367)�܂ŕ`���Ă���B����͋`����3�㏫�R�ɏA�C����Ƃ���܂łɂ�����B�������A����͓�k���u�����@���v(�k��)�Ɓu��o�����v(�쒩)�ɕ����܂ܑ������Ă�������ł��������̂ł���B �@ �k���͌����E�����E������E��~�Z�E�㏬���V�c��6�オ�����A�쒩�͌���E�㑺��E���c�E��T�R�V�c��4�オ�������B�@ |
|
| �������ɒ^�M��������V�c�@ | |
|
���q���{��łڂ��A�����̐V�����s��ꂽ����V�c(1288-1339)�́A�ِF�̒�ł��B
�@ �܂��A����̒Ǎ�(����ɗ^�����閼�A�������)���A����u����v�ƌ��߂�ꂽ���ƁB���V�c�͕��̉F���V�c�ƂƂ��ɁA�V�c�ɂ��e����~���A�P�����s�����Ƃ���܂��B����́A���V�c�̎��������߂��A���Ƃ̎肩����������邱�Ƃ��l���Ă���ꂽ�̂ł��B �@ �܂��A����͖����ɐ[���A�˂���܂����B����Ɩ����̂������́A������������̌�F�����^���@�䎺�h�̐m�a���ŗ���(�����~�낷)����A�����^���@�̑�o�����䏊�Ƃ��ꂽ���ƂɎn�܂�܂��B�c���q�̌���������ɐ[���A�˂��Ă����܂����B �@ ���̌���̑O�ɁA����(1278-1357)�A�~��(1281-1356)�Ƃ����m��������܂��B���ς́A���q����A�����̏����̎x���Ă����^�����@�̑m���ł������A��펛�ş��A�ِ��m�Ƃ��ĕn���~�ςȂǂ��s���Ă��܂����B�܂��~�ς͔�b�R�œ��x�������m�ł������A�̂��ɓِ��m�ƂȂ�܂����B�����̕��ρA����(�V��@)�̉~�ς͌���̐M�C�āA���������ɂ��[���֗^���܂��B �@ ���ς́A��펛�A�V�����Ȃǂ̍���ƂȂ�A�~�ς͖@�������Č����ďZ���ƂȂ�܂��B���̓�l���A����ɓ|���̌��c�������ƌ����Ă���̂ł��B �@ �p�Y�I�ȋC���������オ�A�|���̌��c�ɋ����S�����ꂽ�̂͊ԈႢ������܂���B�������Ȃ���A����̎��ӂɂ͖��{��|���悤�ȕ��͂͂���܂���ł����B���̕��͂�����ɕt�^�����̂����ς��Ƃ����Ă��܂��B �@ ���ς́A����Ő^�����여�Ƃ������h���w�т܂����B���̗��h�͕����ł͕s�����Ƃ��Čł����߂��Ă��鐫�s�ׂg�����ւ̓��ƍl����ْ[�̏@�h�ł����B���ς͊��q����ɋ��������여�������������ƌ����܂��B���여�͕��ςɂ���ċ}���ɍL����A������n�������ȂǂɔM���I�ɐM����܂��B����܂ŁA�����̋M���⌠�͎҂Ƃ͑S���ւ��̂Ȃ��������������l�X���A�|���^���ɎQ�������ƌ����Ă��܂��B���̑�\�i�����}�ƌĂꂽ��ؐ����ł���A���a���N�ł���A�ԏ��~�S�������̂ł��B �@ ���펩�g���A�^�����여�ɐ[���A�˂��ꂽ�ƌ����Ă��܂��B���Ƃ��Ƃ͒��{�E�U�q�̈��Y�ςɋF�����������Ƃ���n�܂��Ă��܂������A��������̏C�Ƃ����ꂽ�ƌ����܂��B����ɂ��Ζ����m�ɂ��u����u�v�ƌĂ��������Ȏ����ɂ��Q�����ꂽ�ƌ����܂��B�����c�����̏ё��́A�����m�̎p������Ă��܂��B �@ �܂��A����͕��ς̎�����ŁA�{���Ȃ�ΑΖʂȂǂ͋�����Ȃ�������|�l�A�V���Ƃ��𗬂��܂��B����͂��������l�X����A���O�̃p���[���������ꂽ���Ƃł��傤�B���ꂪ�|���A���̒��̕ϊv�̌��ƂȂ����̂ł��B �@ ���q���㒆���̓V�c�ł������㍵��V�c(1220-1272)�ɂ́A3�l�̍c�q�������܂����B���̂����@���e��(1242-1274)�͊��q���{�̏��R�ƂȂ�܂����B�㍵��͑ވʂ��ď�c�ƂȂ�A��[��(1243-1304)�����ʂ��܂��B�������A��[���͕a�ゾ�������߂ɑވʂ������A��̋T�R(1249-1305)�����ʂ��܂��B�T�R�̍c���q�ɂ͂��̍c�q�ł����F��(1267-1324)�������܂��B�����܂�������L���Ă����㍵���c��������x�������̂ŁA�c���͂���ŋT�R�V�c�̌n���Ɉ����p���ꂽ���Ǝv���܂������A���q���{�̕s�����ċT�R�͑ވʂɒǂ����܂�A��[���̍c�q�����������V�c(1265-1317)�����ʂ��܂��B �@ �����Ɍ�[���A�T�R�Ƃ����Z��̓V�c�̊Ԃɐ[���ȑΗ������܂�܂����B���q���{�́A����₵�A�����̌n��������ɓV�c�ʂ����郋�[��(�����R��)���߂܂����B �@ �T�R�V�c�̑��ɓ��������V�c�́A���̌�F�����玟�̓V�c�́A��[���̌n���ɏ���悤�ɖ������Ă��܂������A�V�c�e���ɂ��V�������̒����J�����ƍl���Ă�������͂��������A����F���ƕs���ɂȂ��Ă��܂��܂��B��������ɓ����Ă��A������������������k���̖��́A�X�ɒ[����̂ł��B �@ �����[���̂́A��[���̌n���������@���A�T�R�̌n������o�����ƂƂ��Ɏ��@�̖��O�ŌĂꂽ���Ƃł��B�����@�͐ۊ։Ƃ��J�������@(��������)�A��o���͍���V�c�̗��{�Ղɋ�C���J�������@�ł��B�����ɂ́A���@�͓V�c���c(���V�̌N)���Z�����A�������s���ꏊ�ƂȂ��Ă��܂����B�����ɂ��A���́A�����Ɛ[������������������@�̎p�����邱�Ƃ��o���܂��B�@ |
|
| �@ | |
 |
|


 �@�@�@
�@�@�@![]() ���ړ��e�̏ڍו\���֖߂��@�@�@
���ړ��e�̏ڍו\���֖߂��@�@�@
 �@
�@
�o�T�s�� / ���p���܂ޕ��ӂ͂��ׂē��g�o�ɂ���܂��B
�@
�@