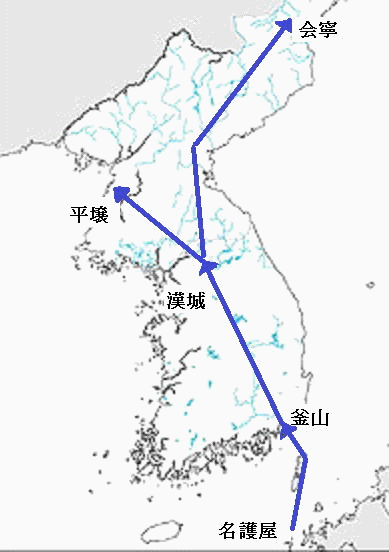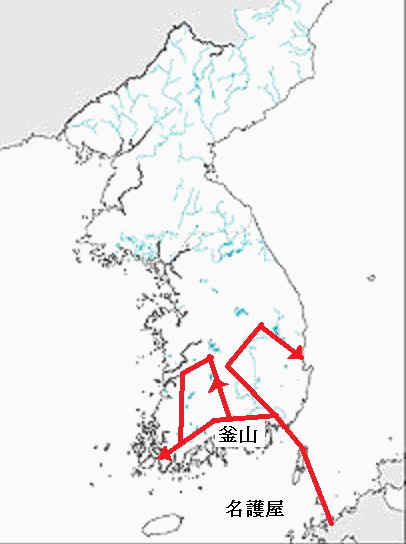|
���x�g�i�������Œ�����i���� |
   �@
�@
|
�x�g�i���̎��̈��@�x�g�i�������Œ�����i����
5�������A�����C�m�Ζ������i(CNOOC)���x�g�i����120�C���̂Ƃ���܂Œ����̍ŐV������@�푕�u���ړ����������Ƃɓ��A�W�A�͔��ɋ������B�`������Ƃ���ɂ��ƁA�����̒������x��������ьR��(����ɂ��Ƃ���)�ɂ���ĕی삳��Ȃ���̈ړ��́A�x�g�i���̕s�ӂ������̂������B�x�g�i���͒����D�ƑΛ����邽�߂������ɉ��x������h���������A�@�푕�u���ӗ�������֎~���3�C�����ʼn������D�ƏՓ˂��邱�ƂɂȂ����B�x�g�i���͌R���������������Ȃ����Ƃ�AASEAN�̕s����A�����Ɣ�ׂĊC�R�͂��ア���ƂȂǂ���R��̑I�����͌����Ă���B�������A�r���I�o�ϐ���ɂ����钆���̈���I�Ȍ@��s�ׂ�e�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Ǘ������邽�߂̊O�������ɉ����āA�x�g�i�����{�͒����̓����ɑ��ăx�g�i��������CNOOC���i���ׂ��ł���B
|
�������N�����̂��H
5��2���ACNOOC�͐Ζ��T�����OHD-981���x�g�i���̊C��ɔ��������B���̃��O��7�ǂ̌R�͂��܂�80�ǂ̒����D�Ɏ���Ă���A�w�����Ă���̂͒����̎w���҈ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��ł���B
����A�x�g�i�����́ACNOOC�ɂ��@���x�点�邩�A�W�Q���邩�A�܂��͒������̌@��p���̔�p��������ړI��29�ǂ̑D������̒n�_�ɔh�������B�������A�����̑D�����m�ɂ��Փ˄����r���I�o�ϐ��悩�瑊���ǂ��o���ۂ̕W���I�Ȏ�i�ł��鄟���͑���Ȕ�Q���������ƂɂȂ����B
�������J���̒����ƃx�g�i���̊W�͔�r�I�ǍD�������̂ŁA�������������͗\�����Ȃ����Ƃł������B�K���ɂ��đΘb�̑����͕����Ă��Ȃ��B�x�g�i���̃t�@���E�r���E�~�����͂��ْ̋����ɘa���邽�߂ɁA�����̍����ψ��k��箎�Ɠd�b�ʼn�k�����B������k�͖��ʂł������B�@�탊�O��������ꂽ�C����A�����Ƃ��Ɏ����̗̊C���Ǝ咣���Ă���͕ς��Ȃ��B
���ƓI�ɗL�]�Ȗ���������CNOOC���������Ƃ��Ă��A���ꂪ�ǂ��Ȃ邩�܂�������Ȃ��B�Ⴆ��CNOOC���V�R�K�X�������Ƃ��Ă��A�����炭�����̎s��ɒ������̃p�C�v���C���ő���K�v������A����͔��ɍ����Ȃ��̂ƂȂ邾�낤�B
�p���I�Ȍ@��s�ׂ��A�̊C���咣���������荑�ɂ��̂悤�ɋߐڂ��čs���邱�Ƃ́A��V�i�C�����̗��j�ɂ����ď��߂Ă̂��Ƃł��낤�B
|
���x�g�i���̌���ꂽ�I����
�������N�̑����̓����������V�A���L���������͂̍w���ȂDŽ����ɂ�������炸�A�x�g�i���͒����ƌR���I�ɑΌ�����ɂ͑������n��ł���B�x�g�i���̓t�B���s���ł͂Ȃ����A���������{�ł��Ȃ��B���������āA�x�g�i���͒����������I�ɓP�ނ�����R���͂��ӎv���Ȃ��悤�Ɏv����B����ɉ����āA���z�o�ϊW�������ł��邱�Ƃ�A2���ԊW�͔��ɕ��G�ł��葼�̑���̕���ɒ��������Q��^����\�����l����ƁA�����ɂ���Ĉ����N�������o�ϓI�A���͉�œI�ɂȂ�\��������B
����ł́A�x�g�i���͒����̍s�ׂ�e�F���A�����Ƌ��͂���CNOOC�̎��Ƃ𗘗p���悤�Ƃ��邱�Ƃ��l������B�����2008�N�ɁA���V�i�C�ɂ����铯�l��CNOOC���ƒn�_�œ��{���s�������Ƃł���BCNOOC���A�x�g�i���ȊO�̎s�ꂩ��̌@����c�̋������l����ƁA�x�g�i���ƃp�[�g�i�[�V�b�v��g�ނ��Ƃ͖��͓I���ƍl���邾�낤�B�������A���̑I���́A���{���o�������悤�ɁA����̒����ɂ�鎗���悤�ȓ����ɑ��ăx�g�i����Ǝ�ȏ�Ԃɂ��Ă��������ł���B
3�Ԗڂ̑I�����́A�{���s����ׂ��x�g�i���̋K���F�⑼�̃x�g�i���̖@�������炷�邱�Ƃ����߂��ɁA�g�ŋ��������h��������CNOOC���x�g�i���̍ٔ����ɒ�i���邱�Ƃł���B
���̃I�v�V�������ł��]�܂����̂ɂ�3�̗��R������B
1�ɂ́A����x�g�i���ł̃r�W�l�X�𐧌�����ł��낤������p��CNOOC�ɉۂ����Ƃɂ��A�����ւ̍R�c����������邱�Ƃł���B����ɁA�����������L�߂Ƃ����A���ۂɂ͌@�탊�O�̉���ɍۂ��Ē����ƑΗ�����Ƃ�����肪�����ӂ����邪�A�S�ۂƂ��ă��O��������������@�I�������x�g�i���ɗ^������B
��2�ɂ́A�����I�ɗD�ʂɗ��x�g�i���̗��ꂪ���߂��邱�Ƃł���B�u�@����c�͒�����1974�N����R���͂Ő�̂��Ă��鐼��������EEZ���ł���v�Ƃ��������̎咣�ɗ^���鍑�͂قƂ�ǂȂ��悤�Ɏv���邪�A�x�g�i���͂��܂��ɓƍِ����ɂ���ē�������Ă���m���ł���BCNOOC���i���邱�Ƃ́A�@�̎x�z�ƕ����̕��a�I�������x�g�i�������邱�Ƃ��������ƂɂȂ�B
�Ō�ɁA����͍ł��d�v�Ȃ��Ƃł��邪�A��i�́A�����̍s���ɓ��������O������Ă��鑽���̒n�揔������уA�����J�̈ӌ��Ɗ��S�Ɉ�v����Ƃ������Ƃł���B
�I�o�}�哝�͍̂ŋ߂̓��A�W�A������K�ɂ����āA�n��̊C�m��̕����͍��ۖ@�⒲��Ȃǂ̕��a�I��i��p���ĉ������ׂ��ł���Ƃ̐������A���{��t�B���s���A�}���[�V�A����m���ɓ��邱�Ƃ��ł����B���ɓ��{�̈��{�W�O�͖@�̎x�z�Ɋ�Â����n��̊C�m�������Ăт������B�x�g�i���̎���i�́A�����̐����ɕ�܂��ꂽ����Ɗ��S�Ɉ�v����ł��낤���A���݂̒n��I���l����ƁA��������w�Ǘ������邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�v����ɁA�x�g�i�������̖@�I�葱���𗘗p���Ē������Ǘ������邱�ƂŁA����Ȃ�N���s�ׂ��g�傷������𒆍��ɗ^�����A���̓�������̂��B
�Ƃ�킯�A���̂悤�Ȓ�i�́A�Ă�ASEAN��c���������͂������̉�c�ɎQ�����邪�����̑O�ɁA�x�g�i���ɑO�����Ď哱����^���邱�ƂɂȂ�ł��낤�B
���̂����A�x�g�i���͂���Ɋ�Â��č��ۓI�Ȗ@�I�葱�����n�߂邩�A�܂��͒����ƌW�����̃t�B���s���Ƌ��͂���ȂǁA�����l�������������X�ƘA�g���Ē���������ɌǗ��������邱�Ƃ��\�ɂȂ邩������Ȃ��B�@
�@ |
|
�������ƃ��V�A |
   �@
�@
|
�F�l�ł�����G�ł���������ȊW
�E���W�[�~���E�v�[�`�����͓����ɑǂ���Ă���B�č��͗J�����ׂ��Ȃ̂��H5��21���A�n���n������悤�Ȑ[��̐��ˍۊO���̖��ɁA�����ƃ��V�A�͐���4000���h���̉��l�������K�͂ȃK�X�_������B���̍��ӂɂ���āA���V�A�̐��{�n��ƃK�X�v������2018�N����2048�N�ɂ����āA�������c��Ƃ̒����Ζ��V�R�C�W�c(CNPC)�ɖ��N�ő�380���������[�g���̓V�R�K�X���������邱�ƂɂȂ�B�n����S�ۏ�T�~�b�g���C���ł̋����R�����K���s��ꂽ���V�A�̃E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̂�2���Ԃ̒����K��́A���̃K�X�_��������Ē��߂�����ꂽ�B�v�[�`�����͍���̌_����A���V�A�̃K�X�Y�Ǝj��ōő�K�͂ƌĂB�����A���̌_��̓��V�A�̃K�X�Y�Ƃ����x������n���w�ɂƂ��Ă��Ӌ`���������B�@ |
����K�̓K�X�_��̈Ӌ`
10�N�ɋy�Ԍ����o�āA���A���ӂɎ������̂͌����ċ��R�ł͂Ȃ��B���̌_��́A���V�A�̉��B�����K�X�A�o�ւ̈ˑ��x������������ꏕ�ƂȂ邾�낤�B�܂��A�v�[�`�������E�N���C�i�����鉢�Ă̐��ٌ��ʂ��ɘa���悤�Ƃ�����A�����ɖ��������邱�Ƃ��������ł�����B
���V�A�ƒ����͂Ƃ��ɁA�n��̑卑�ł��邱�Ƃ��֎����������Ă���B�����Ƃ��ΕĊW������ɂ������Ⴍ���Ă���A�č���������j�~���Ă���Ɣ��Ă���B���傤��40�N�]��O�A���`���[�h�E�j�N�\���ƃw�����[�E�L�b�V���W���[�͒�����������A�\�A�ɔw�������ĕč��Ǝ��g�܂����B�����̃��V�A�ƒ����̋����́A�������V���ɔ��ē����̌_������킵�����Ƃ��Ӗ�����̂��H
���ꂱ�����ԈႢ�Ȃ��A�v�[�`�������^�������Ǝv���Ă����ۂ��B�K���ɐ�삯�A�v�[�`�����͒������f�B�A�ɑ��āA�����́u���V�A�ɂƂ��ė���ɂȂ�F�l���v�ƌ��������āA�����̋��͊W�́u�����I�ɂ��킽����j��A�ō������ɒB���Ă���v�Əq�ׂ��B�������ł́A�K�ߕ�����2013�N�ɍ��Ǝ�ȂɏA�C�����ہA�ŏ��̖K���Ƀ��V�A��I�B
���ƓI�Ȍ��ѕt�������܂��Ă���B�����̓��V�A�ɂƂ��ĒP�ꍑ�Ƃ��Ă͍ő�̖f�Ց���ŁA2013�N��2���Ԗf�Ղ�900���h���ɏ�����B�K�X�_��̒����O����A������2020�N�܂łɖf�Պz��{�����������ƍl���Ă����B
����������Ă̋�s�����V�A�ɑ���V�K�Z�����a��悤�ɂȂ�����A��������̎������B���A���V�A�����߂鏕���ɂȂ邩������Ȃ��B�����́A���V�A����ʂɎ��V�R������傢�ɕK�v�Ƃ��Ă���B
����̃K�X�_��́A�R���̑唼���헪�I�ȓ�ł���}���b�J�C����ʂ��ĉ^��Ă���Ƃ��������̕s����a�炰��Ɠ����ɁA�����e�s�s�̋�C�������ΒY�R�Ă���̒E�p���\�ɂ��邩������Ȃ��B
�����͒n���w�I�ɂ�����������Ă���B������3���A���V�A���N���~�A������O�Ɏ��{���x�������Z�����[��F�߂Ȃ��Ƃ��鍑�A���S�ۏᗝ����̍̑������������B
���A���V���A�œ�����J��L����o�V�����E�A�T�h�����ɐ��ق��Ȃ����Ƃ��������A�����̓��V�A�Ƒ����𑵂݂��ċ��ی����s�g�����B�����̓C�����̊j�J���v���O�����Ȃǂ̖��ɂ��Ď����悤�ȗ��������Ă����B
�����ƃ��V�A�͎������������j�I�Ɉ̑�ȍ��ł���Ƃ��������v�������L���Ă���A���݂͕č��̉��\�ȐU�镑���ɂ���đj�Q����Ă���Ɗ����Ă���B�����͎����̗���ōD���Ȃ悤�ɐU�镑�����R��~�������Ă���B
���V�A�ɂ��N���~�A��������уE�N���C�i�����ł̍H�슈���͉��ď������������A���̌��ʁA�v�[�`�����ɂ͈ȑO�ɂ������ėF�l�����Ȃ��Ȃ����B���V�i�C����ѓ�V�i�C�ւ̒����̐i�o���A�W�A�œ��l�̌��O��ł���A��r�I�����ȋߗ����������̊g����`�ɕs��������Ă���B�@ |
���Ί�Ƃ������͏a��
�����A���Ă̓p�j�b�N�Ɋׂ�ׂ��ł͂Ȃ��B���������ɂ�������炸�A���V�A�ƒ����͂������̍��{�I�ȑ���_�����z����̂ɋ�J���邩�炾�B
�܂��A�K�X�_�̂̌o�܂�����Ƃ����B���ӂ��܂Ƃ߂�̂�10�N��v���A�܂��y�d��ɔ��\���ꂽ�Ƃ��������́A���ӂɒB����̂��ǂ�قǍ�����������������Ă���B�v�[�`���������炩�̖K���̐��ʂ������A�肽���Əł��Ă��邱�Ƃ�m���������ŁA�����͌���������i�߂��Ɖ\����Ă���B
�����W�S�ʂƓ����悤�ɁA����̌_��ł��������D�ʂȗ���ɂ������B�I�[�X�g�����A�ƒ����A�W�A�ł��K�X�̐V�K�������n�܂�B�܂��A�����̐��E�I���͂��g�債�Ă���̂ɑ��A���E�ɐI�܂�A�V�R��������o�ς𑽗l���ł��Ȃ����V�A�͐��ނ��Ă���B�������{�̓��V�A�ɁA�����������j�I�ȕω���F������悤���邾�낤�B����͒����̉����ƃ��V�A�̕���̏���Ⳃ��B
�����͕č��ɑ��Ēc�����Ă��邪�A���������̎s��A�����Ĉ��艻��p�Ƃ��Ă̕č���K�v�Ƃ��Ă���B����ɁA�����ƃ��V�A�͒����A�W�A�ʼne���͂����Ƃ��ƌ݂��ɑ����Ă���B
���������̔��ɒ����������́A��ɕς��Ȃ��s�M���̌��B�������̃��V�A���͐l�������Ȃ��ăR���f�B�e�B�[(���i)�����Ă���̂ɑ��A�������͐l�ł����ς����B���V�A�̐�p�j����̑����������Ɍ������Ă���̂́A���̂��߂��B
�����I�Ɍ���A���V�A�ƒ����́A���łȓ����W��z���̂Ɠ������炢������������\��������B����͂���w�J�����ׂ��W�]���B�@
�@ |
|
�����؊W�j |
   �@
�@
|
|
�����؊W�j�E�T�� |
|
����
|
����j����
���͒��炭���N�o�R�ƌ����Ă������A���`�q�̌�����e���Ղ���̏o�y�i�A���k�c�Ղ̏؍��Ȃǂ���A����̓���A�W�A�o�R�ɂē`�����A����ɓ��{���璩�N�ɓ`������Ƃ����w�����A�l�Êw�I�ɂ͎嗬�ƂȂ����B���̂��߁A�e����j���ȏ��̈��̓`���o�H���C���������B
�����̋L�^���قƂ�ǂȂ����ߏڍׂ͕s�������A���݂̍��ꌧ����Y�o�������j�����N����(�v�T�� ���O�� �L��)������o�y���Ă���A���Ȃ�̓ꕶ�E�퐶�l����炵�Ă����ƍl������B
|
��������E�O������
�Õ�����ɂ́A�S�⎆�̐��Y�Z�p�A�����A��w�Ȃǂ̑嗤����(���[���V�A�嗤�̕���)�́A�����嗤�⒩�N������ʂ��āA�������͒����嗤���璼�ړ��V�i�C���o�ē��{�ɓ`������Ƃ����B�₪�ē��{�̍��͂����傷��ƁA�t�ɓ��{�̕��������N�ɂ��e����^���n�߂��B�O����~���Ȃǂ��A���N���甭������Ă���B�݂��ɗ��ł�����{�ƒ��N�����Ƃ̊Ԃɂ͓`�����܂߂ė��j�I�ȊW���[���A�푈�⑊�݂̐N���̌o���������B
�_���c�@(170�N-269�N)�ɂ��V���o�����s���A�V���E�����E�S�ς��푈�ɏ����������{�ɒ��v�����Ɠ`����O�ؐ����̓`�����u���{���I�v�ɂ͋L����Ă���B
3���I�������؍������N�����암�ɑ��݂����ƒ����́u鰎u�`�l�`�v�A�u�㊿���v�ɋL����Ă���B
313�N�ɂ͍����(�I���O37�N - 668�N)���y�Q�A�ѕ��S�����Ă���B
369�N����562�N�ɂ����ĔC�ߓ��{�{�����N�����암�ɐݒu���ꂽ�B
372�N�ɕS�ς̉��q �ߋw����`���Ɏ��x����������B
391�N�ɘ`�����S�ςƂƂ��ɉ����E�V����j�蕞���������B�`���ɂ�镹���ȑO�́A���^���n�̕S�ρA�V���͓������^���n�̍����̑����Œ��v���Ă���(�D�����蕶�Q��)�B
�����A�S��(346�N - 660�N)�A�V��(356�N-935�N)���������Ă����O������́A7���I���܂ő����Ă���A�`���͕S�ςƂ̊O���W��7���I���܂ő����Ă����B�`�͕S�ς��畧��(6���I)�Ɗ���(4���I)�Ȃǂ̐�i����������A����(538�N〜710�N)���N�����A�S�ς͐V���Ƃ̐푈�̎�(7���I)�`����̌R���l�ނ���ꂽ�Ǝv����B��{�I�ɘ`���̒��N�ɑ��Ă̊O�𐭍�́A�S�ςƂ͗F�D�W�����сA�����A�V���Ƃ͓G����Ƃ������̂ł������B���{�̍���퐪������5�N���396�N�A�����̍L�J�y���͔����A�ĂѕS�ς͍����ɕ������������A399�N�ɍĂѕS�ς��Ɨ����A�����v���ɂ����{�̉��R���h��������400�N�ɍ����ɔs�k���Ă���B404�N�ɂ����{����S�ω��R�̌`�ō����ɐN�U���A�ѕ��S�܂ŐN�����邪�����̏������������B
�O������̑O���́A����킪���B�ɂ܂ŗ̓y���L���čő�̍��Ƃł��������A6���I�ɂ͐V��������ɂȂ�A�����̗̓y�����ꂽ���߁A�����͕S�ςƘ`�ɐڋ߂��A�F�D�W�����B
���̎����̒����̗��j���@���`���`�ɂ́u�V���S�Z�F�Ș`�ב嚠���������h�V�P�ʎg���ҁv(�V����S�ς͊F�A�`��卑�Œ����������Ƃ��āA������h���ď�ɒʎg���������Ă���B)�Ƃ���B
�Ȃ��A�`�ƍ����Ƃ̊W�ɂ��ẮA421�N�A�`���^�������ɂ��ē쒩�̑v�ɑ��Ďg�߂�h�������Ƃ̋L�^������A�����叫�R�`�����̕������Ă���B�܂��A478�N5���ɂ��Y���V�c�Ɩڂ����`���̎g�҂��v�ɏ�\���A�����ւ̐푈�v����֎����Ă���B
�`��528�N�ɂ��V���ɂ��N�����Ă��������h�q���邽�ߒ��N�������ʂւ̏o������}���邪�A�}�������ֈ�̖d���ɍ����A�o����W�Q����Ă���(�ֈ�̗�)�B���̔����͕����e���Η�����6���̑�R�ɂ��������ꂽ���̂́A�o���͎���߂ƂȂ�A������562�N�܂łɑS���V���ɂ�蕹������邱�ƂɂȂ�B
���̌���`�͕S�ς�550�N�ɍ�����j��A���N�����Ɉ��̐��Ђ�L���Ă���A�V�����܂�557�N�ɉe�����ɓ��ꂽ����̒���`�Ɍ�����Ȃǘ`�𗧂Ă�O�����s���Ă����B557�N�ɂ͕S�ς���`�Ɍo�_�◥�t�A�����H���������A579�N�ɂ͐V��������`�ɑ����ƕ������������Ă���B
�������A���Ò���8�N(600�N)�ɐV���ƔC�߂Ƃ̊ԂŐ�[�̉Ԃ�������Ƙ`�͔C�ߋ����R��h�����A�V����5���ł��j�����B����10�N(602�N)2���ɂ͗��ڍc�q�����V�����R�Ƃ���2��5000�̕������N�ɔh������邪��B�̒n�ŗ��ڍc�q���a�ɂȂ�R�̔h���͒��~���ꂽ�B
���̌�A�����W�͂��炭�퓬��Ԃ͎~�ނ��̂́A���̑���Ƃ��ĕS�ς���m ���ӂ������������A����킩��͑m �ܒ����������A����ɕS�ς���͖����V�̓����ɂ���y���`�����O���|�\�Ƃ��Ĕ��W���Ă������B
���̌�͂��炭�`���̂��̂ɒ��ړI�ȉe�����y�ڂ����Ƃ͂Ȃ��������̂́A�c�ɒ���2�N(643�N)6��13���A�����ɂĖd��������A�i�����ɑ��ɑ��̐�W�h���������i�����������ʂ������Ƃ����A�`�����ł����A�W�A�O���ɑ���ْ��������܂����Ƃ����B
����
���E�V���̓����Ɣ����]�̐킢
���̌�A���N�����́A�����̓��ƐV���̘A���R(���E�V���̓���)�������������Ƃœ���Ɍ����ē����o�����B���E�V���A���R�͗��m�O������R���̓���7000�Ƌ��@�q������V�������S�ςɐN�����A660�N�ɉ��s �}�]���ח������A�`�����Ƒ��q�������z�ɑ����ĕS�ς��łڂ��ꂽ�B663�N�A�S�ύċ����߂������{�͕S�ςɁA���ܘA�䗅�v�A�͕Ӑb�S�}�A���{�A�䗅�v�A�����A�F�A��N���̌R����h������ƂƂ��ɁA�S�ς̈�b �S�����M�̗v���ɂ��A���{�ւ̐l���Ƃ��Ă������S�ω��q �]�L�����쑗���鋷��A�F�P�A�`���c���Â�5000�̕ʓ�����h�����A���E�V���A���R�Ɣ����]�ɐ�����B���̔����]�̐킢�Ř`���E�S�ϘA���R��400�ǂ��̌R�D�����サ�s�k�����B�`���͓P�ނ������A�̓y�܂ł͍U�ߍ��܂ꂸ�A���Ȃ����B�`���͍����������S�ϐl�̖S���ڏZ������A����V���ɂ��N���ɔ����ċ�B�ɖh�l��z�u���A���ߐ��̐����Ȃǒ����W�����Ɖ���i�߂��B�܂��A������8���I�����ɂ͓��{�ւƉ��߂��B
|
���V���E�݊C�E�^���Ɠ��{
�����́A�S�ς��ŖS�������ƂŌR���I�ɌǗ����A668�N�ɕ��炪���~�������ƂŖłB
676�N�A�V���͓���Ǖ����Ē��N�����ꂵ���B���͂����܂����V���Ɠ��{�ْ̋��W�͑����A702�N�ɂ͌����g�����N���݂��o�R�ł��Ȃ��Ȃ�Ȃǂ̈��e�������������A���{����̌��V���g�A�V������̐V���g��9���I���܂Œf���I�ɑ������B
698�N�ɒ��N�����k���Ɍ������ꂽ�݊C�͓���V���ƑΗ��������߁A���{�݊͟C�Ɠ����W�����сA����ɟ݊C�g�E���݊C�g�����������B���{�́A7���I���ɍϏB���ɐ��������^���Ƃ̊Ԃɂ����^���g�E�^���g�����������B
���{�E�V���̍��ƊԖf��(���V���g�E�V���g)����ɔ����A���Ƃ̌��Ճ��[�g���m�����Ă������ێH�Ȃǂ̐V�����l�������B�V�����l��ʂ��A�����ɓ����Ă���y���V�A�A�C���h�ȂǓ썑�̎Y�������{�ɂ����炳�ꂽ�B�܂��~�m�́A�V�����l�̏����ɂ�蓂����̋A�����ʂ������B
�V��(731�N)3�N�A����̖���ттȂ����{���̕��D300�ǂ��˔@�A�V���ɐN�U���A��s�����Ƃ̕���ɂ����炳��A���{�C���̉��ݖh�q�ɋْ����������B���V��4�N(732�N)����͓��C���A���R���ɐߓx�g��u���Ր�Ԑ��𐮂���Ƃ����B���̌�A�V��9�N(739�N)�A����͓����̖h�l�ɑ���B�Ŗ��������V�R���̑Ō������������Ƃ��瓌���̖h�l��p�~���A���A�Δn�̖h�q�͒}���̐l�X��h�l�ɂ��邱�Ƃ����肵���B
�V������4�N(752�N)6��14���A�V�����q ���ח���320�l�̐V���g�������A�㗌�����{�ɒ��v����ȂLj��̊O���W�������邪�A���N�A�V������5�N(753�N)1��1���A�������͂��g�Ƃ��錭���g���h������A���̓s �喾�{�܌��a�ɂČ��@�̔q�y������ȏ�A���{�����g �唺�Ö��C�ƐV���g�Ƃ̊ԂŊO��Ȏ����߂��鑈�����N�������B���̎��̐Ȏ��͓��Ȃ̑�ꂪ�f�ׁA����{�Ő����̑�ꂪ�V���A���H(�T���[��)�ł������B�Ö��C�͐V���͌×��A���{�̒��v���ł���̂ɓ��{�����ʂł���̂͂��������ƍR�c���A���̏��R �������͌Ö��C�����X�����C�z���Ȃ����Ƃ���Ȏ������ߓ��{����̐ȂɕύX�����Ƃ����B���̗��N�A����c�炪���V���g�Ƃ��Ĕh������邪�V�������ւ̉y���͗�ɓK�킸�Ƃ̗��R�Ŋ���Ȃ������Ƃ����B
�����������C�ɂ��V�������v��ƈ�������ΐV���O��
�V����2�N(758�N)�A���ň��\�R�̗����N�����Ƃ̕��{�ɂ����炳��A���������C�͑�ɕ{���͂��ߏ����̖h�������ɂ��邱�Ƃ𖽂���B����ɓV����3�N(759�N)�V���g ���努�����{�ɓ����������A���V����4�N(760�N)�A��ɕ{�ɔh�����ꂽ���������C(�b������)�̎q �������낪�努��q�₵���Ƃ���A�努�͍��������Q�����A17�K��11�K�Ɖ��������ł��邱�Ƃ������������߁A�o�҂ɒl�����ƒǂ��Ԃ��Ƃ������Ƃ�����A���{�ł͂��̊O���̔��ɐV�������̋@�^�����܂����B���{�ł͂��̊O����ɐV�������̋@�^�����܂�A���V����5�N(761�N)1��9���ɂ͕����E���Z�����̏��N20�l�ɐV���������������ƂƂ��ɓ��N11��17���ɂ͓��C���A��C���A���C���ɐߓx�g��ݒu�����B�B�����đΐV�������ɌR�D394�ǁA���m4��700�l������{�i�I�ȉ����v�悪���Ă��邪�A���̉����͌�̍F����c�Ɖ����̎哱�� �����C�Ƃ̕s�a�ɂ����s���ꂸ�ɏI���B���̌����T5�N(774�N)�ĂѐV���g���������邪�܂������炪����A�����ǂ��Ԃ����Ƃ����B����18�N(799�N)�A�唺�����C���g�A�ѐ^�p�g�Ƃ��ė\�肵�Ă������V���g��˔@��~���A���{�͐V���Ƃ̍�����f�₵���B
����ŁA�����̈�b�炪�����ɉ�������Ƃ����݊C������T2�N(771�N)6��27���A325�l�A17�ǂ̎g�ߒc�œ��{�ɖK��A�o�H���\��ɕY�������Ƃ����A��T8�N(777�N)4��22���A�݊C�g�����{�ɍv����������ꂽ��A���{���@�卑�Ƃ��ċ������Ƃ��獑����f�Ղ�����ɂȂ����B�݊C�f�Ղł͓��{�̌��D�����A�o��������A�݊C����͋M���̊ԂŒ��d���ꂽ�Ղ�渂��A�����ꂽ�Ƃ����B
���V���̓���
9���I(��������)�ɓ���ƁA�V���l����B��Δn�ɐi�o���A���{�͑�ɒǂ�ꂽ�B���̐V���̓�����812�N����906�N�܂ŌJ��Ԃ��ꂽ�B���a9�N(842�N)8��15���A��������������V�����l�̓����E�f�Ղ͔F�߂Ă���������f�Ղɂ������ē��{�̐�������������V���l�̑��݂ɂ��A��ɏ����q�̑t��Ɋ�Â��A�Ȍ�̏��l�ȊO�̐V���l�̓������֎~�����B
�O�m2�N(811�N)12��6���A�V���D�O�z���Δn���̐��C�Ɍ���A���̓��̈��z�������S�̍��{�Y�ɒ��݂����B�D�ɏ\�l�قǏ���Ă���A���̓��z�͈Ŗ�ɗ���A�s����������Ȃ��Ȃ����B��12��7�������A�����Ƃ����A���A�Ȃ�����\�]�z�̑D�����̐��̊C���Ɏp�������A�����̑D�����D�ł��鎖�����������B�����ŁA��ɒ��݂����҂̂����ܐl���E�Q�������A�c��ܐl�͓������A�����l�l�͌���⑫�����B�����āA���̕��ɂ��q��A�R�m�ɓ������������B�܂������V��(���N��������)��]����ƁA���鐔�ӏ��ʼnΌ���������Ƒ�ɕ{�ɕ��ꂽ�B��ɕ{�́A���̐^�U��₤�ׂɐV����̒ʖ�ƌR�B����Δn���֔h�����A����ɋ���ɏy���ėv�Q�̌x���ɂ����ׂ������ɕ{�Ǔ��ƒ���E�Ό��E�o�_���̍��ɒʒm�����B
�O�m4�N(813�N)2��29���A��O�̌ܓ��E���ߓ�(���l�)�ɁA�V���l110�l�����z�̑D�ɏ��㗤�����B�V���̑��͓���100�]�l���E�Q�����B�����͐V���l9�l��ł��E��101�l��ߗ��ɂ����B���̓��́A����c�̍Z�ђ�|��̋�����ł������B�܂��A4��7���ɂ́A�V���l�ꐴ�A�����b�炪���{���V���A�������A�Ƒ�ɕ{�����ꂽ�B���̌���ɑ��āA�V���l���u�₵�A�A�����肤�҂͋����A�A�����肤�҂́A����ɂ�菈�u����Ǝw�������B����̑�Ƃ��Ēʖ��Δn�ɒu���A���l��Y���ҁA�A���E��ɂȂ肷�܂��Ė��N�̂悤�ɗ�������V���l�W�c��q��ł���悤�ɂ��A�܂����a2�N(835�N)�ɂ͖h�l��330�l�ɑ��������B���a5�N(838�N)�ɂ́A796�N�ȗ��₦�Ă����W�t(�ǂ�)�������A���ɔz�������B�W�t�Ƃ́A��|�̎ˌ��������鋳���ł���B
�O�m11�N(820�N)2��13���A���]�E�x�͗����Ɉڔz�����V���l�ݗ���700�l���}���Ȃ��Ĕ������N�����A�l�����E�Q���ĉ��ɂ��Ă����B�����ł͕��m�����čU���������A�������鎖���ł��Ȃ������B���͈ɓ����̍����𓐂݁A�D�ɏ���ĊC��ɏo���B�������A���́E�����������̉�������������Ǔ��������ʁA�S�����~�������B
���5�N(863�N)�ɒO�㍑�ɂ���Ă���54�l�́u�V�������̍ח����l�v�Ǝ咣�����B
���8�N(866�N)�ɂ́A��O����S�[��̎R�t�i�E���ÌS�̊��Ò�ÁE�����S�[��̑品��E�ދn�S�Z�l�i�����Â炪�A�V���l�Ƌ��d���A�Δn���U�����悤�Ƃ����v�悪���o���Ă���B
����ς̓���
���11�N(869�N)6������A�V���̊C���A�͓��z�ɏ��}�O���߉όS(����)�̍r�Âɏ㗤���A�L�O�̍v���D���P�����A�N�v�̌��Ȃ𗩒D���������B�ǐՂ������A���������Ɓw���{�O����^�x�ɋL�^������A�܂��u�����̕��v�v�A���ł���V���̐푈(����)�̂��Ƃ��w�i�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ɩm(����Ȃ�)���`�����Ƃ���B�܂��A���N�̒��11�N(869�N)5��26��(�����E�X��7��9��)�ɂ́A��ϒn�k����Œn�k���������Ă���B����ɑ����{�͎��l��v���ɖh�l�Ƃ��Ĕz�����邱�Ƃ��v�悵����A���C���S�̌x�����ł߂��ق��A�����̐V�����l������30�l��ߕ߂��������邱�ƂɌ��߁A���k���˂��u�C�ӂ̕S���܁A�Z�l�v���܂����B���̌�A�V���ɕߔ�����Ă����Δn�̗t�E�m���������C�����n�̔�Q��`�������߁A���Ǒ�ɕ{�Ǔ��̂��ׂĂ̍ݗ��V���l�����ׂė������ȂǂɈڂ������c��^���ċA�������邱�Ƃɒ�߂��B���̂Ƃ��V���͑�D�����������b�p�𐁂��炵�ČR�����K�ɗ��ł���A�₦�u�Δn�������ׂȂ�(870�N2��12����)�v�Ɠ������Ƃ����B�܂����n�̎j�����u�V�����̒��v����肵�A��ɏ������������̓��������������B
870�N2��15���A����͜W�t��h�l�̑I�m50�l��Δn�ɔz�������A�Δn�珬��t����L�͕��l���܂��Č��n���x�삷��悤�w�������B�܂��A�����A���ŁA�_���˂Ȃǂɕ���э������������A�u���{�͐_�̍��ł���A�G���̑D�͖��R�ɕY�v����v�Ƒi�����B
�܂��A��ς̓����̎O�N�O�̒��8�N(866�N)�ɂ͉��V��̕ς��N�����Ă���A�����������{�����̐����R���Ɠ������ɋN��������ς̓����Ȃǂ̑ΊO�I�ْ��̒��ŁA�V���r�ˌX�������ݏo���ꂽ�Ƃ����B
�������̓���
����5�N(893�N)5��11����ɕ{�͐V���̑����B�u�V���̑��A��㍑�O�c�S�ɉ����Đl����ĖS���B�����A��O�����Y�S�ɉ����ē�������v�B
������6�N(894�N)�N4���A�V���̑����Δn�����P���B���́A���̏��R���������V���̑D�召100�z�ɏ����2500�l�ɂ̂ڂ��R�ł������B���ݍ��Ɍx�ł𖽂��A�Q�c�������o�������Ƃ��ĉ����Ȃǂ��߂����A���͓����Ă������B���N9��5���̒��A�Δn�當���P�F(�ӂ��悵�Ƃ�)�͌S�i�m�����܂��đ��k45�z��W�����܂������S�̌R���Ō}���������B�J�̂悤�Ɏ˂�ꓦ���Ă�������nj����A220�l���ˎE�����B���͌v�A300����������B�܂��A�D11�A����50�A��1000�A�|��(��Ȃ���)�e110�A��312�ɂ��̂ڂ锜��ȕ����D���A���ЂƂ���߂����B���̊Ԍ����g����߂�ꂽ���A����ɓ��̊֗^���M�����߂ł������Ƃ������B���N9��19���A��ɕ{�̔�w(�͂₤��)�̎g���˔@�����̐�����`���A�����g�����~���ꂽ�B���N�̊���7�N(895�N)9���ɂ��A�V���̑��������P�����A���ɂ��Ă��ꂽ�B
����Z�N(906�N)7��13���A�B�̍������ҕ��������A�V�������_�̑��邪�������B�u�V���̑��D���k�C�ɂ���A��A�ނ̑���Ǒނ����ߑ啗�𐁂������v���̌�A�����������ꒅ���A�_�Ђ̑傫����m�炵�߂��B�Ɠ`�����Ă���B
|
������
935�N�ɐV�����łсA���N�ɂ͍��킪�����ꂷ��B9��23���ɍ���̓쌴�{�̙��g�]���Δn�ɕY�����A10��15���ɂ͋��C�{�̗����B����ɕ{�ɓ����͂̕����Ƃ����B����ɓV�\3�N(972�N)10��20���A����g�����{�ɓ������č��������߂�����{�͒��v�ȊO�F�߂Ȃ��Ƃ��Ă�������₵���Ƃ����B997�N����1001�N�ɂ����č���C���ɂ����{�ւ̓������������B1019�N�ɂ͍���l�Ə��^���ɂ�铁�ɂ̓������N�����Ă���B
�������̓���
����3�N(997�N)�A����l���A�Δn�A��O�A���A���A�F���A����ȂNj�B�S����P���B���Ƃ��Ă���A���Y�����D���A�j��300���������ꂽ�B���S�l�̝f�v�͑O�Ⴊ�Ȃ��B����͒����̓����܂���̓����Ƃ������A�������l�����ɎQ�����Ă����Ƃ�����B���N11���ɐ��{�͓�̓������A��9���ɂ͋M�퓇(��E��)�ɖ����ē�̕ߔ������߂��B
������3�N(1001�N)�ɂ�����l�̊C���s�ׂ������A�u���E�L�v�͍��퍑�̑��A�ƒf�肵�Ă���B
�����ɂ̓���
1019�N�ɂ͍���l�Ə��^���ɂ�铁�ɂ̓������N�����Ă���B
����4�N(1080�N)�A�����荑���̕a�ɂ�����A�Lj�̑������{�Ɉ�t�h���̗v�����͂��A����͍���Ƃ̐M�`�Ɋ�Â���t�h������U�͌��߂���̂́A�����t�ʂ��̕� �������ʂ̖������Ă�����~�߂��Ƃ̘b�������Ƃ���A�}�ɔh���ɑ���@�^�͊o�߁A���ǁA��ɂ��Ȃ킸�Ƃ��đ����i��Ԃ�������A��������ۂ����B����ɂ����{�ƍ���̊O���͂قƂ�ǒf����邱�ƂƂȂ����B
�܂�1093�N�ɂ́w����j�x���A�u�C���D�v��\�߂��^��A����A�����A�@���Ȃǂ̉ݕ���ڎ����v�l�Ɠ��{�l�̏����z��ɂ����A�ƋL�^���Ă���B�����͂��ׂē��v���Ղɂ�������{�Y�̗L�͂Ȍ��Օ��Ȃ̂Łu�C���D�v�Ƃ��ĝ\�߂����Ƃ����̂͌����ł���Ƃ����B�@ |
|
������ �@ |
   �@
�@
|
������
�����ɂ͌���1274�N��1281�N��2�x�ɂ킽����{�N���s��(����)���s���B�w����j�x�y�сw���j�x�ɂ��A�������S(����)�≤���q(�̂��̒���)���X�ȗv�������������߁A���{�N�U�����肳�ꂽ�B���̊ԁA���{�ł�1276�N3��5���ɖ��{���ō��퉓���v�悪�����オ��A����o����叫�Ƃ��ē�C���̌�Ɛl����Ɛl�̕��Ƃ����悤�Ƃ������A��Ɛl�̊ԂŔے�I�Ȕ����������A�܂��A��������B���݂ɐΗۂ�z���H�����n�܂������Ƃ�����~�߂ƂȂ����B
���ɕ������Ă�������͓��{���̍����𑗂�ȂNJO������S�����A���{�̊��q���{�͍�����َE�������߂ɐ�[���J�����B�ÏP���ɂ����Ă͍���R����v�l�ƂƂ��ɐ땺�Ƃ��ē��{�֍U�ߍ��݁A���E�Δn�┎���ɂ����ċ�B�̌�Ɛl�𒆐S�Ƃ��銙�q���{�̕��Ɛ�����B����R�͈��E�Δn�̖��̒j�͎E���A���͎�Ɍ����J���đD�̌��ɒ݂邵����ɂ����Ɠ`�����Ă���B�܂��A����q���͕ߗ��ɂ��A����R�ɘA�ꋎ��ꌣ�コ�ꂽ�B���ʓI�ɓ��{�́A���E����R�̕��͕s����\���J�����������ƂŐN����Ƃꂽ�B���E����R���\���J�ɂ���đ傫�Ȕ�Q�����ہA����l�̕��̓����S�����ƂƂ��ɎE�������A��v�̕��͕ߗ��Ƃ��ď��������B�ÏP���ɐ旧���A1271�N�ɍ���ɂ����Ĕ������S�����f���ĖI�N�����O�ʏ������{�~�������߂����A���{�̊��q���{�͂�����َE���Ă���B �@ |
���`��
���{�̓�k�����ォ�玺������ɂ́A���N�̍��킩�痛���ɂ����Ă͘`��(�O���`��)�ƌĂ��C���A�C�㐨�͂��A�������݂⒩�N�������݂��r�炵���B�`���͓��{�l�A���N�l�A�����l�A�̂����B�l�Ȃǂ����݂��Ă����B����⎺�����{�͉��_�ƒe���ő���s���B��B�T��Ƃ��Ĕh������Ă�������吢(���r)�͍���g�߂��}���Č����A�������ƂƂ��ɘ`���������B
1375�N�ɂ͓��o���U�E�����������������A����ɂ��`���̊����̊��������w�E����Ă���B
1388�N(����6�N�A�N�����N)2���ɂ͍N���̊O���������B�c���������p�З����鍂��R���p�̐��@����Δn���ɐN�����A���{�����Δn��� �@�o�̒�A�@�i��������A�a�D100�ǂ��Ă��������ꂽ�B����A����R�͍���l�ߗ��j��100�l���~�o����P���𐬌������Ă���B �@ |
���������N
����ł͘`����g�Б��̓����Ɍ��т̂����������j�炪�{���ő䓪�A�ŖS�ɕm�����������̗v���Ő����R�𗦂��Ėk�シ�邪�A�r���ň����Ԃ��Ď���������A1393�N�ɗ������N(����)��n������B
1396�N�ɗ����j�͈��E�Δn�����𖽂����B
�������������{�ɑ��Ę`���̋ֈ������߁A�܂������̖������l�̗v���������B���������v�����āA�������{�́A3�㏫�R�̑����`�����`������������B�`���͒��N�֎g�߂�h�����A�����f�Ղł������������f�Ղ��s����B����������ʐM�g���h������A�@���m�w�V�������{�s�^�x��w�C�������L�x�Ȃǂ̓��{�n���L�������ꂽ�B���{������̎g�҂ɂ͈ΐ瓇��砍��ƌĂ��l�������s�������Ƃ����邪�A���ꂪ�ǂ����������Ȃ̂��A���邢�͋U�g�Ȃ̂��͒肩�ł͂Ȃ��B
�����i�̊O��
1419�N�A�����̐��@�͘`���̍����n�ƌ��Ȃ���Ă����Δn�ɐN�U����(���i�̊O���A�Ȉ哌��)�B���N�R�͏㗤���ɑ����̖��Ƃ��Ă������Ȃǂ��ďœy����}�������Δn���̏@�吷�ɂ�锽���ɍ������ނ��ꂽ�B1443�N�ɂ͉Ëg���(ᡈ���)���������ꂽ�B
�����͎�q�w���d�����A������e���������߂ɁA���펞��̕��������������O�ɑ������o���邱�ƂɂȂ����B���ɖؔň���́w�呠�o�x����O�Ȃǂ͍��l�Ŏ�����ꂽ���߂ɑ�ʂɓ��{�ɗ��ꍞ�B�܂����{�Ƃ̌��Ղɂ�1426�N�̎O�Y(���R�Y�A�T�Y�A���Y)�𗘗p���Ă������A���n��l�̒��ߕt���������������Ƃ����B
����2�N(1470�N)�A���N���� ���c���Δn��� �@�ƂɎg�߂�h�����A���{�̖��q�҂̎����܂�����߂��B �i��6�N(1509�N)4���A���N�͑Δn���� �@�ސ��ɍݗ����������P�v�`�̋A�������߂�g�߂̔h����\�肵�Ă������A�ސ��̋}���Ŏg�ߔh������������Ƃ����B���i��7�N(1510�N)�ɂ͌��n�ݏZ�̑Δn�̖��Ȃǂɂ��O�Y�̗����������Ă���B
1544�N�̎֗��`��
1547�N�̒������
1555�N�̒B���`��
1557�N�̒������
1588�N�̏G�g�ɂ��C����~�� �@ |
|
���ߐ� �@ |
   �@
�@
|
�����\�E�c���̖�(�p�C�푈�A������)
���{�ꂵ���L�b�G�g�͖��̐�������}���A�Δn�̏@������Ē��N�ɕ��]�Ɩ������̐�N�ƂȂ邱�Ƃ����߂邪�A�ǂ����Ȃ��ׁA1592�N���璩�N�����ɐN�U����(���\�E�c���̖��^�p�C�E���U�`��)�B����œ��{�R�͊e�n�̒��N�R��j���ĕ����������܂Ői���������A��������ɖ��̋~����`�E�R�̒�R�ƌ��ɂ��⋋�����u�a����D�悳�����ׁA�������ނ������܂ܐ�ǂ��P�������B���{�R�͍ŏI�I�ɏG�g�̎����ɔ����P�ނ����B���{�ƒ����E���N�A���R�Ƃ̊ԂœW�J�������̍��ې푈��16���I���A�W�A�ő�̐퓬�Ƃ�������B
���E���N�̘A���R�Ɠ��{�R�̌��A�����Ď��������ɂ��H�ƍĕ��z�Ɛ��Y�̕���Ɩ��O�����Ȃǂ�����A���N�̍��y�͔敾�����B�܂��A���̎��̑����Ŗ����ɕۊǂ���Ă����ːЂȂǂ��R�₳��A���̌��ʒ��N�����ł͔������ጸ���A���ǂ����̂���҂����������ƌ����Ă���B ���{�R�̏��喼�͒��N�����w�҂ȂǂƋ��ɑ����̓��H��A��A��A���{�e�n�œ��|������ɂȂ�B���̂���A���h�q��^�o�R�����{���璩�N�ɓ`������B �@ |
�����쐭���ɂ�鍑����
�G�g�̎���A���{�ł�1600�N�ɓ���ƍN�ɂ�镐�Ɛ���(���얋�{)�����������B�G�g�̒��N�N�U�ɏ��ɓI�Œ��N�����ɔh�����Ă��Ȃ���������ƍN�́A���N�Ƃ̍�����]�݁A�@������Ďg�߂�h�������B�������ē���ƍN�ƒ��N�����̊Ԃō����̌����i�߂�ꂽ�B���C�N�͕ߗ��̑��҂�f�Ռ��ɉ����A1609�N�ɂ͌ȓі��������Ėf�Ղ��ĊJ����A���{�̋�ƒ����̐����⌦�Ȃǂ����ʂ���B
���𒇉�����{�̑Δn�˂́A�����̍����������邽�߂ɓ��얋�{�̍����₻��ɑ��钩�N�����̕ԓ������U���A��₂��Ă������A1635�N�ɂ͎��������o���A�W�҂�������������ꌏ���N����B����ꌏ�̂̂��ɖf�Ղ͖��{���NJ������B
1607�N�ȍ~�A�������ォ��̒��N�ʐM�g�����R�̑�ւ�育�Ƃɓ��{�֗��K����悤�ɂȂ�A�����̊O���W���ۂ��ꂽ�B1764�N�ɂ͒��N�ʐM�g�ɂ��T�c�}�C�������{���璩�N�ɓ`����ꂽ�B�����A1811�N�ɍŌ�̒ʐM�g�����K���Ĉȗ��A�����̌����ȊW�͓r�₦���B
�������N�́A��������𑱂��Ă���A�܂����\�E�c���̖�����̌x���������āA���{�l�͎�s���z(�\�E��)�ɓ��鎖�͏o�����A�Δn�����R�ɘ`�ق��\���Ă���ȊO�́A���N�Ƃ̌��Ղ���͓��肵�Â炢��Ԃł������B
�Δn�˂͖��{���璩�N�Ƃ̖f�Ղ�������A�`�قɂ��f�Ղ��s��ꂽ�B�܂��A�F���˂ɂ�镐�͐N�U�Ŗ��ˑ̐��ɑg�ݍ��܂ꂽ�����Ƃ��ʌ����L�����悤�ł���B �@ |
|
���ߑ� �@ |
   �@
�@
|
�����{�ƒ��N�̊J��
���{�͍]�ˎ��㖖���ɊJ�������B�������Âɂ�萬���������{�̐V���{�͋ߑ㉻��ڎw�����B�������N���e�����ɒu��������쉺�������葱����鐭���V�A�ɑ�����{�̍��ې���̈�Ƃ��āA���{�͒��N�����ɒ��ڂ����B���N�ł͑�@�N���r�O�I������s�������̐����ێ�����Ă������A�{�������ƂȂ�ƁA1875�N�̍]�ؓ��������o�āA76�N�ɓ����C�D���K�����ђ��N�͊J�����A�J�����s����B
1880�N�ɓ��{���g�ق�����ɐݒu����B �@ |
�������푈����؍������܂�
1894�N�ɁA���N������Η�����A�����Ɠ��{�Ƃ̊Ԃœ����푈���u�������B�����푈�œ��{�͏��������B1895�N�ɓ��{�Ɛ��͉��֏������сA���N�����Ƃ̍����̐����痣�E����Ǝ����I�ɓ��{�̉e�����ɒu���ꂽ�B����ɔ���1897�N�ɑ�ؒ鍑�ւƍ��������߂��B
���V�A�͉��֏���̎O������1900�N�̋`�a�c�̗��̌�����B(�������k��)�̐�̂𑱂����B���V�A�͒��N�ɂ��e�������߁A���{�ƑΗ�����B���{��1902�N�ɃC�M���X�Ɠ��p���������сA�A�����J��C�M���X�̎x���āA1904�N�ɊJ�킳�ꂽ���I�푈�ɂ����ď����A1905�N�̃|�[�c�}�X���ɂ����Ē��N�ɑ���r���I�w�������l������B
���̌�A�؍��c��̓n�[�O���a��c�ɁA���{�̊���r�����؍��̊O�����ی��v�����閧�g�𑗂������A�������Ȃ�����(�n�[�O���g����)�B���{��1910�N�Ɋ؍��Ɠ��ؕ�����������Œ��N��������(�؍�����)�A���炭�ꐧ�������ɂ��������N�ɂ����{���n���l�ɖ����`������Ȃǂ��Ē��N�l�ɂ��s������^�����B�܂��A���N�l�ɂ��������Z�⍂�������ւ̖�˂��J�����A��̒��N���W�̑b�ƂȂ�l�ނ�{�������B1945�N�̑���E���s�k�ɂ���ē��{�����͏I�����A�A���R�ɂ���k���f�R���������ɒu����邱�ƂƂȂ����B �@ |
�����{��������
���{�͒��N���{��ʂ��Ē��N�����S������A�����͌R���͂�O�ʂɉ����o�������f�������s�����B���̏ɑ��A���N�������1919�N�ɎO�E��Ɨ��^�����������A���N�ɂ͗����ӂɂ���ؖ����Վ����{�̐ݗ����錾���ꂽ�B���N�ɂ����钩�N�k�����疞�B�ɂ����Ă͋��������w������R���p���`�U���^�����W�J����A1920�N�ɂ̓V�y���A�ɂ������`�����ŐԌR���V�A�l�Ƌ������ē��{�R���쒀���ăj�R���G�t�X�N�̐苒�ɐ�������B���f�����̎��s�͔F������A���ۓI�ɂ͑�ꎟ���E�����Ė��������̋@�^�����܂�A���{�̍����ł͑吳�f���N���V�[�̕��������f���āA�����ʂ̈�����d���������n������`�֓]�������B
���̊��Ԃɓ��{�͒��N�����̃C���t���̐����ƎY�Ƃ̐U���������߂��B���琧�x����������A���w�Z(�����w�Z)�Ԃ⋞��鍑��w(�\�E����w�Z)�͓Ɨ���̊؍����{�Ɉ����p���ꂽ�B����������͂��ߓ��{�ꋳ��ƂƂ��ɒ��N��̋��炪�s���A�n���O���̕��y���i�B�܂��A���N�l�́A���{�R�̗��R�m���w�Z�ɓ��w���Ƃ��邱�Ƃ��ł��A���N�l�m���̑����͌�Ɋ؍��R�ɂ��̂܂܈����p���ꂽ�B�₪�Ėp�����哝�̂�M���Ɋ؍����E�̒������߂��B���{�A�A�����J�A�I�[�X�g�����A�A���[���b�p���͂��ߐ��E�̒��N�j�����ł́A���{�̃C���t�����������N�̋ߑ㉻�̊�b�ƂȂ����Ƃ����B
�Z���n�ɂ�����薳�����N�l�ɂ�1945�N�܂ŕ����͖Ə�����Ă����B�܂��A�y�n���\��h�~���邽�߂̌[���E�[�ւ��J��Ԃ��A�_�������͎����̓y�n�����ʂ���Ēn�Ђɏオ��̂����āA���ŐϋɓI�ɋ��������B
�����푈�Ȍ�A�u���N��́v�̖��̉��A����܂Ō�����ŕK�{�ȖڂƂ��ċ�������Ă������N��͒��N����߂̉����ɂ����1938�N�ɂ͐��ӉȖڂƂȂ�A�c��������Ȃǂ̓���������s��ꂽ�B���N�l�ɂ��u�蕺�̕�W���s���A�R�l�E�R���Ƃ��Đ�n�ɕ������҂����݂����B�܂��A�I��O�ɂ͒��������{�s���꒩�N�l�����c���P�����s��ꂽ���I��ɂ��퓬�ɓ�������邱�Ƃ͂Ȃ������B���q�⒥�p�ɂ����n(���{)�Ɍ��������J���҂�A�Ԉ��w�Ƃ��ē������������݂����B
1945�N9���A���{���|�c�_���錾��������đS���{�R�͘A�����ɍ~���A�������͐ԌR(�\�A�R)�̎m���Ƃ��Ē��N�k���̒��S�s�s����ɓ��邵�A�����ō~���������{�ɑ���A�����J���O�������N�����암�ŌR���������J�n����Ɨ����ӂ����Ȃǂ̓Ɨ��^���Ƃ��\�E���֖߂����B �@ |
|
������E���� �@ |
   �@
�@
|
|
1946�N2��3���ɂ͒��N�l����̂Ƃ��鋤�Y���͂ɂ����{�l����l���s�E�����ʉ��������N�����B 1948�N�̍ϏB���l�E�O�����ɂ���đ����̍ϏB�������쒩�N���{�̋s�E���瓦��邽�ߓ��{�ɖ����������B�܂��A�o�ϓI�Ȑ�����ڎw���ē쒩�N������{�ɖ�����������̂�����A�\�t�g�o���N�O���[�v�̑��ꑰ��1947�N�ɖ��q�D�œ��{�ɏ㗤���Ă���B �@ |
|
����ؖ��� �@ |
����ؖ����̌���
1948�N�A���N�����̓암�ɑ�ؖ���(�؍�)����������A�����ӂ��哝�̂ɏA�C�����B�A�����J�̋����e�����ɂ���A������`���f����_�ł͊؍��͓��{�Ƃ̋��ʐ��������������A�؍��ł͓Ɨ��^���Əo�g�̗����ӂ�M���ɔ���������������Ƃ��哱��������A���ۂ̐���ɂ����f����e�����͂͏l�����ꂽ�B�܂��A�������Ӑ����̎v�z�����s���ɑ���e�����s���A�퐅�E���V�����̂悤�Ȋ؍��R�̔��������̍ۂɂ����{�ւ̖��q�҂����ݏo���ꂽ�B1949�N1��17���A�����ӂ͑Δn�̊؍��̂��咣�����{�ɕԊҗv������B �@ |
�����N�푈
1950�N�ɂ͒��N�푈���u�����A�����̔����{�I�ȗ�����Ƃ�؍��l�����{�֖����������B���{���{�͑|�C������`�p�J���҂��؍��ɑ��荞�ނƂƂ��ɓ��{�����ł̊؍��R�̌R���P���������ȂNJ؍����x�������B1952�N�ɒ��N�푈�̋x������s���퓬���I������Ɨ����ӂ͊؍��̈���ӂ̌��C��ɗ����Ӄ��C����ݒ肷��ƁA�؍����{�ɂ����{���D�ւ̏e���E�\�ߎ������������A���\�l���E�����ꐔ��l���}�����ꂽ�B1954�N�ɂ͓����C���Ŋ؍����Ɏ�荞���{�ŗL�̗̓y�|��(�؍����F�Ɠ�)�ɌR���𑗂荞��œ�����苒�����B���̌�����݂Ɏ���܂Ŋ؍��̕����x�@�����݂��A���{�͂�����؍��̕��͂ɂ��s�@�苒�ƍR�c���Ă���(�|�����)�B1959�N�ɂ͊؍��̍H����ɂ���ĐV�����ԃZ���^�[���j���������������N�����ꂽ�B�����Ԃ̌����ȊW�́A1960�N�̗����ӎ��r�܂ł͑傫�ȉ��P�͌����Ȃ������B �@ |
��������
1961�N��5�E16�R���N�[�f�^�[�Ŋ؍��哝�̂ƂȂ����p�����́A�����{�R�o�g�ŁA���{�̎���ɂ����ʂ��Ă����B�܂��A�k�̒��N�����`�l�����a��(�k���N)����̈������獑�Ƃ���邽�߂ɂ́A���{�Ƃ̍����ɂ��o�ώx���̎������s���Ɣ��f���Ă����B����A���{�̎��R����}�������A�k���A�W�A�ł̔����������������E���ɂ����镉�̈�Y�̐��Z�̂��߂ɁA�؍��Ƃ̍�����]��ł����B1964�N3��24���Ƀ\�E����w�E�����w�E������w�̊w��5000�l�]�肪�u�Γ����J�O���v���f�����s���B1965�N�ɓ��{���Ƒ�ؖ����Ƃ̊Ԃ̊�{�W�Ɋւ�����(���؊�{���)����������A���Y�y�ѐ������Ɋւ�����̉������тɌo�ϋ��͂Ɋւ�����{���Ƒ�ؖ����Ƃ̊Ԃ̋��肪��������A���ؗ����y�т��̍����Ԃ̐������Ɋւ����肪���S���ŏI�I�ɉ������ꂽ���ƂƂȂ邱�Ƃ��m�F����ƂƂ��ɁA���{�͊؍��ɗL������5���h���̋��z���x������(���{���{�͔����ł͂Ȃ��o�ϋ��͂ƈʒu�Â��Ă���)�B���̍ہA���{�͊؍��N�����B��̍��@���{�ƔF�߂��B1966�N3��24���ɓ��ؖf�Ջ�����������B
���̓��؍��𐳏퉻�ɂ��A�؍���1979�N�܂ő����p�����̌R���ƍِ������ŁA���{����̌o�ϋ���(�~�؊��Ȃ�)�����p���Ă�e���ʃC���t��(�n���S�E�������H��)�����A�u���]�̊�Ձv�ƌĂ��H�Ɖ��E�o�ϔ��W�����������B���{�̏��Ђ͊؍��ɐi�o���A�J���͂̈����؍��͓��{�ւ̏d�v�ȗA�o��n�ƂȂ����B �@ |
������̍�������
�����͊O���Ɠ����Ɋւ��Ă͐��퉻�������̂́A���咆�����╶���������Ƃ������O����ɔ��W�����������������A�K�����������̍�������͗ǍD�ł͂Ȃ������B�𗬂̊g��ɂ͔ƍߑg�D�̍��ۉ��Ȃǂ̑��ʂ�����A���{���ł͊؍�����i�o���Ă������ꋦ��ɂ��슴���@�ᔻ���N�������B�������A���ꋦ��͍��ۏ����^���Ŏ��R����}�����ƂȂ���A���ؗ����̐������͊g��ɍv�������ʂ������Ă����B
���{�����̗����j�~�𗝗R�Ɍ�������������������Ȃ���A���{�����쌠�����L����TV�ԑg�E�̗w�ȓ��̒��앨�̕s���R�s�[�E���p�E���쓙�����s���Ă���A���̊C���ł̗��ʂ�����o���Ȃ��؍����̕����ɂ��ᔻ���N�������B1988�N�ɂ̓\�E���I�����s�b�N���s��ꂽ���A�I�l�̌��I���[�œ��{�̖��É��������ĊJ�Â��ꂽ���̑��ł͊؍��l�ϏO�ɂ����{�I��ւ̔��~�܂Ȃ������B1992�N�ɂ͊؍��������� (MBC)���A�����̖��Ⴊ�V�c��_������ԑg�w���{�̉����x��������A����Ɏ��ۂ̖��m�e���̓V�c���ʎ��̉f����p�����ׁA���{�̊O���Ȃ���R�c�����B
1995�N�A���ۃT�b�J�[�A�� (FIFA)�́A���ؗ����������������Ă���2002�N�J�Â�FIFA���[���h�J�b�v�𗼍��̋��ÂƂ��錈����s�����B����͗����ɔg����L���A���̉^�c������ď̖��ŗ����Ԃ͐[���ȑΗ�������A�u������̕��Áv�Ƃ����w�E���オ�����B�����̌o�܂�ʂ��Ċ؍��ւ̔��������߂����{�����̈ꕔ����́A�\�E���ŊJ�Â��ꂽ�J��ɓ��{�ւ̔z�����قƂ�ǖ�����A���l�ł̌�����ƕ�̍ۂɂ͋M�o�Ȓ����̍ۂɊ؍��哝�̂̋��咆����ɑ����V�c�ɐi�H�����炸�Ɏ����̌���ʂ点���g�̒��m�炸�̂��̍s�ׂ͖��炾�Ƃ������̐����o���B�������A���|�I�Ɋ؍��L���ɓ������딻���Ȃǂɂ��A�C���^�[�l�b�g�𒆐S�Ɂu���v��������������Ƃ������ł��邪�A���̃��[���h�J�b�v��ʂ��A���c�𑱂��������̑��W�҂̓w�͂́A2���J�ÂƂ����n���f�B�����z���đ��̉^�c��F�D���[�h�̑n�o��������x�����������Ƃ�������B������@�ɁA�����ɂ͒��炭�֎~����Ă������{�̕������؍��ŊJ�������悤�ɂȂ���(�u�؍��ł̓��{�����̗��������v���Q��)�����łȂ��A���{�ł��؍��̉f���h���}�������A������A�؍��̔o�D��̎肪���{�Ŋ���悤�ɂȂ����B��(��)��͊ؗ��X�^�[�Ə̎^���ꂽ�B���̑����ԂɎ��{���ꂽ�������́u����(�r�U)�Ȃ����ݖK��v�͑���ɍP�퉻����A���Ɋό��ʂł̌𗬊g��ɍv�������B�����̓s�s�ɂ͉p��ƕ���ő��荑�̌���ɂ��ē��W���Ȃǂ����������悤�ɂȂ�A����܂œ��{������̖K��l�������|���Ă����ό����A���{�̊ό��n�Ɋ؍��l�ό��q�̎p��������Ȃǂ̕ω���������悤�ɂȂ����B
1998�N10��8���A���؋����錾�������b�O�Ƌ��咆�哝�̂ɂ�蔭�\����A�����Ԃ̃p�[�g�i�[�V�b�v���Ċm�F�����B
2010�N9��10����SKE48���u2010�\�E���h���}�A���[�h�v�����Łu�����҂�v�u��Бz���v����{��ʼn̂��p���؍��̒n��g�e���r�Ő����p���ꂽ�B�؍��́A2004�N1���̓��{��O������4���J���œ��{��̉̂̕��������������A�����Ǒ��Ř^�悾���ɐ������Ă����B�����p���ꂽ�̂́A���ꂪ���߂Ăł���B���O�ɕ����ʐM�R�c�ψ����ʂ�����ŁA���������肳�ꂽ�B
���̂悤�Ȍo�܂��o�āA���؊W�͗ǍD�ɂȂ����Ƃ����邪�A�؍����ł͑��{�����ւ̔ے�(���邢�͂���ȑO����̖����I�̎�)�ɍ�������������������c���Ă���B���j���ȏ���������Q�q���A�|��(�؍����F�Ɠ�)����{�C�ď̖��(�؍����F���C)�A���{�̍��A��C�����������ւ̔����A���ł����{�������؍����˂��Ǝ咣����A�����l�������Ȃ��R���A����R���A���n�̓��E���Ǝ咣���铙�A���{�Ɗ؍��̘_��������������B�܂�ḕ��鐭���͓��{��������E�e���h���̐��Z�Ƃ��āu���鋭�艺�������s�א^�������Ɋւ�����ʖ@�v�y�сu�e���������s�ҍ��Y�̍��ƋA���Ɋւ�����ʖ@�v�𐧒肵�A�������s�הF��҂̎q���̓y�n����Y������������v�����鎖���\�ɂ��A���ۂɁu�e���h�v10�l�̎q�������L�����13��6000���~�����̓y�n��v������(2007�N8��13�� �ǔ��V��)�ȂǓK�p���͂��܂��Ă���(���鋭�艺�������s�א^�������Ɋւ�����ʖ@�y�ѐe���������s�ҍ��Y�̍��ƋA���Ɋւ�����ʖ@���Q�Ƃ̂���)�B�܂��A���{���ł̓}�X���f�B�A�Ȃǂ�ʂ��Ċ؍��̑�O�������Z���������ŁA�؍��ւ̗Z�a�p����ۂ}�X���f�B�A�ւ̕s�M�̍��܂�������āA���؊�������܂��Ă���A�C���^�[�l�b�g�ɗ����Ԃւ̋��⊴����݉�����Ȃǂ��Ă���B����ł��A�����̏Փ˂�x�z�E��R�Ƃ��������Ă̐�s�I�ȑΗ��͏��X�ɉe����߁A�ݓ��؍��l���܂߂������Ԃ̋��͂Ƌ����͏��X�ɐi�s���Ă���B���{�����̂���悤���q�ϓI�����Ɋ�Â��Ė��炩�ɂ��Ă������Ƃ���؍��l�����҂�����Ă���B2011�N�A2012�N�ɋN���������_�ЁE���{��g�ٕ��Ύ����ł͊؍����{�͓��{�ւ̗e�^�҂̈����n�������ۂ����B
2012�N�ɂ͗������哝�̂ɂ��|���㗤�ƓV�c�Ӎߗv�����s����ȂǁA�؍����{�������^���𒾐É����闧�ꂩ�甽���^����擱���闧��ɕω����Ă��Ă���B�܂��A�؍��̎i�@�����؊�{���Ŋ��S�ɉ������ꂽ�؍��l�ւ̔������ɂ��āA�\�E�����ق��V���S�Z���ɑ���4000���~�̎x�����𖽂��A��ٌؕ�m�����鰓N��������a���Ă���Ă���ȂǁA���{�ւ̑ԓx���ω����Ă��Ă���B
2013�N12���A�ǔ��V���ƃM�����b�v�������Ŏ��{�������_�����ł́A���{�Ŋ؍����u�M������v�Ƃ����l��16%�ł���A72%���u�M���ł��Ȃ��v�Ƃ����B�܂��A�u�R���I�ȋ��ЂɂȂ鍑�v�ł͒����A�k���N�Ɏ����Ŋ؍���3�ʂɂȂ�A���V�A�����錋�ʂƂȂ����B���{��Ƃ̊؍��ւ̓�������ނ�����A���{�̍��ۋ��͋�s���s�����u���{�̐����Ƃ̓����L�]�n��E�������L���O�v�̒����ɂ����āA�؍��͉ߋ��Œ��13�ʂƂȂ�A�t�B���s���A�~�����}�[�A�}���[�V�A�ɔ����ꂽ�B�؍��o�ς̕s�������ƂƂ��ɁA�p�یb�哝�̂����i���锽������̉e�����w�E����Ă���B �@ |
|
�����N�����`�l�����a�� �@ |
���̍��ڂł́A��̑�ؖ����ƑΔ䂳���邽�߁A���N�����`�l�����a���̗��̂��u���N�v�Ƃ���B
�����N�����`�l�����a���̌���
1945�N�A���N�����k���𐧈������\�A�́A�]���̓��{�ɂ�铝���V�X�e������̂��A���Y��`�ɂ��V�̐��̌��݂�i�߂��B���N�k���͋����B������̓��{�l�ڏZ�ҁE�ݏZ�҂̋A���o�R�n�Ƃ��Ȃ������A���̒��ő����̐���������ꂽ�B1949�N�ɂ͋��������Ƃ������N�����`�l�����a���������������A1950�N�ɂ͓�̑�ؖ����Ƃ̊ԂŒ��N�푈���u�����A1953�N�̋x��܂Ŏ�s������܂ލ��y�̍L���͈͂����ƂȂ����B���N�푈����1952�N�ɓ��{�̓T���t�����V�X�R���a���̔����œƗ����������A������`���ƂƂȂ������{�̎��R����}�����͒��N�����`�l�����a�������F�����A�}�X���f�B�A�Ƌ��Ɂu�k�N�v�ƌĂB����A���{�Љ�}��]�ȂǁA���{�̎Љ��`���͂�J���g���͂��̍��N�����B��̍��@�����ƍl���A�u���N�v�ƌď̂��āA��ؖ���(�؍�)���A�����J�̌R���x�z���ɂ���u�쒩�N�v�Ƃ����B �@ |
�����N���A
���N�����`�l�����a���̐����͓��{�����̐����ɂ��e����^�����B����E����ɍČ����ꂽ���{���Y�}�ɂ͑����̒��N�l�����Ƃ��������A�₪�ĕ������A���N�ւ̋A�҂����{�����ł̍ݓ����N�l�^���̓W�J��I�������B���̒��ŁA�ݓ��{���N�l��������(���N�����A���N���A)�����������B���N���A�ɂ�鋭�͂Ȏw���ɂ��A�ݓ����N�l�͖������ʉ����E�������P�Ȃǂ��߂�����������S���e�n�œW�J�������A���̎p�����\�͓I�E�����I�Ƃ�����{�l����̔����������A�ݓ����N�l�Љ�͓��{�̒��Ŋu��������W�c�ƂȂ����B�؍��ł̍����∳���͓��{�ł����Ă������߁A���N�����암�̏o�g�҂ł����N���A�ɎQ������҂����������B�Ȃ��A�������ɗ�����ꂽ���N�̎w�����}�A���N�J���}�͂₪�ē��{���Y�}�̋c��d���E���a�v���H����ᔻ���A�W��f�₵�����߁A���N�J���}�̌𗬑���͓��{�Љ�}�����S�ƂȂ����B �@ |
���A�Ҏ���
1959�N�A�ݓ����N�l�̋A�Ҏ��Ƃ��J�n���ꂽ�B����͓��{�ԏ\���Ђ����ǂ����A�؍����{�ɂ��A�ҋ��ۂɂ��A�ҏo���Ȃ������l�X�N�����`�l�����a���ւ̋A�҂��x�����鎖�ƂŁA���{���{���ϋɓI�ɋ��͂����B���\���l�̍ݓ����N�l���C��n�����Ƃ���邪�A�u�n��̊y���v�Ǝ��Ȑ�`���Ă������N���̌o�Ϗ͌������A���{�ł̕n���⍷�ʂ���̉����������Ƃ����A���҂͈�w����ȏɒǂ����܂ꂽ�B����ɁA�ƍِF�����߂�����������́A���{����̋A���҂̑������u���ݓI�X�p�C�v�Ȃǂƌ��Ȃ��Čx�����A���̑��������Y�A���邢�͋������e���ł̒����S�ւɏ������Ƃ���邪�A�肩�ł͂Ȃ��B������ɂ���A����������������������ĘR��Ă��錻�n�̏�m�����ݓ����N�l�̊Ԃł͋A���ւ̏�M�����X�ɑނ��A���x�o�ϐ����ɔ����ē��{�ł̐��������P����Ă��������������āA�A�Ҏ��Ƃ�1960�N�㔼�ɏI�������B�������A�A���҂̍ė����͎��������A���{���Ђ��������܂܉Ƒ��Ƌ��ɓn�q�����z���(���{�l��)��q�ǂ��̖�肪���������B �@ |
�����؍����ȍ~
1965�N�ɂ͓��؊�{���������A���{�͑�ؖ����Ƃ̍�������������B���̒��œ��{���{�͑�ؖ����N�����B��̍��@���{�Ƃ������߁A���N�����`�l�����a���Ƃ̍�����������߂钩�N���A����{�Љ�}�Ȃǂ̋�����R�������A�����h�쐭���͍���ł̋��s�̌��ł�������������B���̏��ɂ����{�͑�ؖ����̍��Ђ�F�߂����߁A�ݓ����N�l�̒��ɂ͒��N�Ђ���̐�ւ����s���҂��\�ꂽ�B�܂��A������@�ɑ�ؖ����́u�؍��v�Ƃ����\�L����ʂɒ蒅���A���N�����`���a���́u�k���N�v�ƕ\�L�����Ⴊ�������B
1970�N�A���{�q��̍q��@�����������Ǎ����������������B�Ɛl�͓��{�����ł̊v���^���ɍs���l�܂�A���O�ɐV���ȍ����n�����߂��c�{�����Ȃǂ̐V�����ɑ����鋤�Y��`�ғ����ԌR�h�O���[�v�ŁA���N�����`�l�����a���͔ނ�̖S������������A�@�̂����̓��{�Ԋ҂ɉ������B�c�{�B�̎v�z��s�����j�͒��N���Ƃ͈�v�����A����u�����ꂴ��q�v���������A�₪�ēc�{��͕���x�O�ɏ��O���[�v���`�����A�k���N�̈ӂ����Γ���`�E�H�슈���ɏ]�������B
1972�N�A������킪�f�^���g���ɓ���A��k���������ɂ���ؖ����Ƃ̑Η���������x�ɘa����A���{�����ؐl�����a���Ƃ̍��������钆�A�����W�����X�ɖf�Պz���g�債���B���{�̍H�Ɛ��i�����X�ɒ��N���ɓ���A���N�Y�̈����ȃ}�c�^�P��C�Y�������{�֗A�o���ꂽ�B�ݓ����N�l�̏W�c�A�����Ƃ́A���i�ɂ��c���E�e���K��ւƕω����đ��������A���N�A���҂̍ĖK���͔F�߂�ꂸ�A���ԈˑR�Ƃ����v���p�K���_��������ꂽ�B �@ |
�����{�l�f�v���
�܂��A���̍�����؍��̌o�ϗ͂����N���t�]���A�傫�����������Ă����B����Ɋ�@�������������N���͑Γ�H��ɓ��{�l��f�v���Ď���̍H����ɒu�������A�؍��ɓ��������鎖���v�悵���B1973�N�A���l�s��2���f�v���������B1975�N�A�����ێ����œ��{���D���e���E�\�߂����B1977�N�A��ɓ����������{�������F����s���ŏ��̓��{�l�f�v���������������B���N11��15���ɂ́A�V���s��13�̉��c�߂��݂��f�v����A��ɂ��̖��̃V���{���I���݂Ƃ��Ď��グ����悤�ɂȂ������A1983�N�܂ő�����A�̎��������炩�ɂȂ�̂ɂ͂���Ȃ�N����v�����B���̎����ɂ́A��Ǎ������̔Ɛl�O���[�v�A�y�т��̍ȒB���֗^�����Ƃ�����A���{�̌��@������N�i����Ă���B
��1980-90�N��
1980�N��ɓ����Ԃ̑傫�Ȍ��Ď����ɂȂ����̂́A�f�v���ł͂Ȃ��A��\���x�m�R�ێ����������B1983�N11��1���A�����Ԃ��q�s�����������{�̉ݕ��D�A��\���x�m�R�ۂ��D���ɒ��N�l���R���m���{�^�オ����ł���̂������B�{�^��͓��{�ōS�����ꂽ���A�����Ԃɂ͍����������A������{���S���\�����������߁A���{�͔ނ̍����؍݂�F�߂ĕ��Ƃ����B����A11��11���ɍĂіk���N�֓��`������\���x�m�R�ۂ͏�����S�����ꂽ�B�g���E�D���ƌI�Y�D�Y�@�֒��ɂ͒��N������f�v�����X�p�C�e�^�ŋ����J��15�N�̔�����������A�D�͖̂v�����ꂽ�B���{�̍������_�͓��{�l�D���̎ߕ������߂����A�O���W�����������Ԃł͌��̎������猩����̂���������B���̑�\���x�m�R�ێ����́A�O���ɋN�����������O�[�������A�܂��O���r���}�̊t�����������؍��哝�̑S�l���ÎE�������j�e�����������N�H����̔ƍs�Ɣ��\���ꂽ����̎����������B���̏d���œ��{�̑Β��N�x�����͍Ăэ��܂�A���{�̑Β��N�A�o�z�͌��������B����ɁA1987�N�̑�؍q��@���j�����������W��₦���܂����B�e�����s�ƂƂ��ăo�[���[���ōS������A���Ŏ��E��}�����͓̂��{�l�𖼏��u�I�J�^��v�Ɓu�I�J�^�R���v���������A�����c�����I�J�^�R���͊؍��ɑ��v����A���炪���N�H����̋����P�ł��邱�Ƃ����������B����ɁA���̍��x�ȓ��{�l������͗����b�Ƃ������{�l����������Əq�ׂ����߁A��ɕ�܂ꂽ�ޏ��̏o�����܂߁A���{���̑Β��s�M�͑��������B
��2000�N��
2002�N9���A����Y�͖k���N��K�₵�āA�����������L�Ə��̓�����]��k���������A17����������錾�ɒ����B���̖K��ŋ������͖k���N�ɂ����{�l�f�v���u�ꕔ�̉p�Y��`�҂��\�������v�Ƃ��Č����ɔF�߁A5�l�̝f�v��Q�҂̋A���ƂȂ����B�������u8�l���S�E1�l�s���s���v�Ƃ���k���N���͓̉��{�����猩�ē��ꏳ�������˂���̂ɉf��A�f�v��Q�҂̉Ƒ��̋A�������܂��ȂǁA�W�҂𒆐S�ɕs�������o���A���_���k���N�ɑ��ċ����������������B
����A2005�N���܂Ŗf�ՊW�͑��݂��Ă���A���{�ւ̑D���̓��`�͔N�Ԑ琔�S�ǂɏ���Ă����B����́A���{����̗A���͗A���@�킪���S�ŁA���{�ւ̗A�o�͐��Y�������S�ł������B
�������A2006�N10��9���̖k���N�̊j������e�|�h���Ȃǂ̃~�T�C�����ˎ������āA���{���{�͍R�c�̈ӂ�\�����A���{���t����{�i�I�ȝf�v��Q�҂̉����ڎw���A���{�Ǝ��̐��ق��s���A���{�����̖k���N�ւ̓n�q���l����������A�܂��k���N�D�Ђ̑D���̓��`�͋ւ����A�A�o������~���ꂽ�B
2009�N6���A�A�����J���ې���Z���^�[�̃Z���O�E�n���\���͕ĉ��@�O���ψ���̌�����ŏ،����A�k���N���푈��ԂɊׂ����ꍇ�A�u�k���N�͕Ƃ��Ċ؍��ł͂Ȃ����{���ݓ��ČR��n���U�����邾�낤�v�Ɨ\�������B 2009�N�t�ɂ́A�k���N�ɂ��u���2���v���ˌv��ɂ��A���A���ۗ����c��1695���Ƒ�1718���Ɋ�Â����{�͑ł��グ�̒��~��v�����A���˂̏ꍇ�͒lj����ق��s���ƕ\���������A�u���đ́v�͔��˂��ꂽ�B���k�Ⓦ���Ń~�T�C���h�q�V�X�e����z������Ȃǂ̑Ή����s�������A�nj��͍s���Ȃ������B �@
�@ |
|
������E�������N�̑Δn�N�U |
   �@
�@
|
|
14���I������15���I���߂ɂ����čs��ꂽ�A����A�������N���K�R�ɂ��Δn�ւ̐N�U�B�`���̍����n�Ɩڂ��ꂽ�Δn(�����ڕW�Ƃ��ꂽ)���U�����邱�ƂŁA���̍����}�������̂ł������B
|
��1389�N�̐N�U
�u����j�v�A�u����j�ߗv�v�ɂ���1389�N2���A���100�z�ɂ��Δn�N�U���s���A�p葳���i�ߊ��Ƃ��āA���@���A�����[�A�p�q�����]�����B
���{�D300�z�Ɖ��݂̌������Ă��s�����A�߂炦���Ă�����100�]�l���~�o�����B�A����͏������`�ŏ^����Ă���B�������A��������̐l�X�̒��ɂ́A�u�p葳�͌����ƑD���Ă��������ŁA�ߗ��ɂ����`���͂��Ȃ������B�v�Ɣᔻ�̐����������Ƃ����B
���{���j���ł́u�@���ƕ��v(1719�N)��2��18���ɍ���R��ǂ��Ԃ����Ƃ���B������̂��āu�N���̊O���v�Ƃ����B�������A����́u����j�v���Q�l�ɋL�q�������̂ŁA���̌��ł̓��{���̋L�^�͑��݂��Ȃ��������̂Ƃ݂���B�܂��A�u�ΏB�ҔN���v(1723�N)�͐{�ΎO�ʖ@��Ƒ��c���̕����A�u�Ó��I���v(1809�N)�͓��@�d�A�@�i�Ƒ��c�O��A�������y���̕����G�ɓ��������Ƃ���B�������A�������u����j�v���Q�l�ɂ�����Ō㐢�̓`�����̗p�������̂ŁA14���I�ɂ͑��݂��Ȃ������n������������ȂNJm���Ȃ��̂Ƃ͂����Ȃ��B
������؍��ł́A�u��1���Δn�����v�Ə̂��Ă���B�@ |
��1396�N�̐N�U�v��
���N�������^�ɂ���1396�N12���A�����j�����E�Δn�����𖽂����B �剺�E������m�t���ܓ����n�s�����u�g�ɔC���A��݁A�h�����A����z���ɂ��A�o���ɓ������Ă͐��j������܂Ō��������B
���{���j���ł́A���̎����ɒ��N�R�̐N�U���������Ƃ����L�^�͂Ȃ��B
���������^�ɂ͈ȉ��̋L�^������B1397�N1���Ɍc�����U�B�Y�ō~�������`����̗̂���(�i�K�I��)�A�q�̓s���V(�h�V��)�A�z���̍�����(�R���V��)����l��l���ɂ��ē��S����Ƃ������������������A2��10���ɂ͒��N�̊��E��^���ċA���������Ƃ���B�܂��A1398�N2���A�`����̘̂Z�A�����A�]����(�}���T����)���Ɋ��E��^����ƂƂ��ɁA���ꂼ�ꓡ�Z�A�щ��A�r��Ɖ����������Ƃ����B
�m�t�͗��N1��30���ɋA�҂��ďo�}�����A2��8���ɉ��Ȃ�݂����Ă���̂ŁA���炩�̌��т͔F�߂�ꂽ�悤�ł���B
������؍��ł́A�u��2���Δn�����v�Ə̂��Ă���B�����ł͈Ȍ���`���̋A����A�������i�߂邪�A�Δn�ł͏@��̎���̍����ɂ�芈��������������B�@ |
��1419�N�̐N�U / ���i�̊O��
������؍��ł́A�u��3���Δn�����v�Ə̂��Ă���B
���{�j�̎���敪�ł͎�������̉��i26�N(1419�N)�ɋN�����A�������N�ɂ��Δn�U�����w���B�Δn�̍f�x(�ʂ�����)�Ő퓬���s��ꂽ������f�x�푈�Ƃ��B���N�ł͌Ȉ哌���Ƃ����B���N�R��10���]��őΔn����P�ނ��邪�A�`���̊�����ቺ������Ƃ����ړI�͒B�����B
���w�i
�`�m�@/�@����j�ɂ��ƁA�`���͌����ȑO�ɂ����݂������`���̊������ڂɗ��قǕp�ɂɂȂ����̂́A1350�N����ł������B���̎������獂�햖�܂Ř`���̐N����500����A����1375�N����́A�`���̂����ō���̉��݂ɐl���Z�܂Ȃ��Ȃ���������Ƃ����B����ɑ��邽�߁A1389�N�ɍ���̐�͂͑Δn����N�U���A�`���D300�]�ǂƊC�ӂ̉ƁX���Ă��A�ߗ�100�]�l���~�o���ċA�҂���(�N���̊O�m)�B���킪�������N�ɑ�������ɂ��`���͔����e�n�ɔ�Q��^���邪�A�Δn�̎��@����Β��N�f�Ղ̂��߂ɘ`��������������������A���{�ő����`�����Ζ��f�Ղ̂��߂ɘ`���������܂������Ȃǂɂ��A14���I������15���I�n�߂ɂ����Ę`���͒��É����Ă������B
�������A�V���ɏ��R�ƂȂ��������`���́A���i18�N(1411�N)�ɖ��Ƃ̍�����f�₵���B�Δn�ɂ����Ă��@������i25�N(1418�N)4���ɕa�v���A��N�̏@�s�s�F��(�@�吷)���Ղ��p�������A���������������c���q�呾�Y�͘`���̎�̂ł���A������}������Ă����`���͍Ăъ���������B
���퓬�̌o��
�Δn�N�U�̌���@/�@�`���̊��������É����Ă����Ƃ͂����A���N�͑��ς�炸�`���̏P����A�N�Ă����B�����ĉ��i26�N(1419�N)5��7���A���疼�̘`�������N�̔ݐm�����P�����A�C�݂̕��D���Ă������A���̏���قڊח������A��O�̖��Ƃ𗪒D���鎖�������������B���̘`����5��12���A���N�̊C�B�ւ��N�Ƃ��A�E�Q���ꂽ��ߗ��ƂȂ������N�R��300�l�ɒB�����B���N�̉��ł��鑾�@�́A���ꂪ�Δn����̘`���Ƃ�������m��A5��14���A�Δn���������肷��B
���N����5��23���ɋ�B�T��g�߂ɑΔn�U���̗\���`���A5��29���ɂ͏@�吷�ɑ��Ă����̎|��`�B�����B����A���N�ɗ����`���W�c�́A�Ȍ�ɒ��N��E���ėɓ������֓��������A�����Ŗ��R�ɑ�s����(�]�C�Ă̐킢�A�������F�]�C�đ号)�B
�Δn�ɐN�U���钩�N�R�͎O�R(�E�R�E���R�E���R)�ŕҐ����ꗛ�]���i�ߊ��Ƃ��A�R�D227�ǁA����17285�l�̋K�͂ł���A65�����̐H�Ƃ��g�s���Ă����B
���@�͒��N�R���Δn�֍s���O�Ɂu�������݂̂āB�@�吷�ɂ͎���o�����A��B�͈��g����B�v�Ɩ������B
�Δn�㗤�ƍf�x�ł̐퓬�@/�@���N�R��6��19�����ϓ����o�q�A6��20�������ɑΔn�̊C��(����Y)�ɓ�������(����Y�͓����A���c���̗̓y�ł���A�`���̈�勒�_�ł�������)�B���̑������́A��s���钩�N�R10�ǒ��x�������ƁA���Ԃ��A���Ă����Ɗ��}�̏��������Ă������A��R�������Ĕ���ƊF���������o�����B���̒�50�l�قǂ����N�R�̏㗤�ɒ�R���邪�A�s�ꌯ�j�ȏꏊ�֑��荞�ށB�㗤�������N�R�͂܂��A�o���̗��R���L�����������g�҂Ɏ������A�Δn�̏@�吷�ɑ������B�����������Ȃ��ƁA���N�R�͓����ē���{�����A�D129�ǂ�D���A��1939�˂�R�₵�A���̑O���114�l���a��A21�l��ߗ��Ƃ����B�܂������A�`�m�ɕ߂���Ă��������l�j��131�l���~�o����B�Ȍ�A���N�R�͑D�z�ɐi�R���A���ݒu���ē��̌�ʂ��Ւf���A�������܂�ӂ������B���̌�A���]�͕����𑗂�A�����ēx�{�����A������68�˂�15�ǂ�R�₵�A9�l���a��A���N�l8�l�Ɩ����l�j��15�l���~�o����B�����Đm�ʌS�܂Ŏ���A�Ăѓ����㗤�����B���������̍��A�p���������钩�N���R���A�f�x�őΔn���̕����ɉ�s�k�A�S���\�l�����ɁA�p�O�M�A�p�Ηz�A���Y�A������4�l�̏��Z���펀�����B�������N�E�R����������������ߑΔn���͑ނ����B
�P���@/�@���N�̋L�^�ɂ��A�Δn�������N�E�R�Ƃ̐킢�őނ�����A�@�吷�͒��N�R���������܂鎖������A��������C�D��������Ƃ��Ă���A7��3���A��͂��Δn���狐�ϓ��ɖ߂��Ă����Ƃ���B�����A����̒��i��ł�6��26���̐킢�őΔn�R�͒��N�R�ɑ叟���A���N�̏��R2�����߂�ɂ�������27���ɂ͒��N�R�͓P�ނ��J�n���A7��2���ɂ͑S�Ă̓G�D���ގU�����Ƃ��Ă���B
�P���̗��R�@/�@���N�R���P���������R�ɑ��āA���N���̎j���ł́A�f�x�ł̐퓬�Ȍ�A�u7���͖\�����������߁A�����I�ɗ��܂鎖�͂Ȃ��l�Ɂv�Ə�����Ă��鑾�@�̐�|(�莆)�����N�R�ɓ͂������A�@�吷���C�D�����߂����Ȃǂ��\���B�������Ȃ�����{���̎j���ł́A�Δn���̔����ɂ��f�x�Œ��N���R����s���铙�A����������ꂽ���N�R�͓P�ނ����Ƃ��Ă���B
���Q�@/�@�o���̔�Q�͑傫����������A���{���j���w�@���ƕ��x(1719�N)�ł͓��{���̐펀�҂�123�l�Ƃ����N���̎��҂�2500�l�]��Ƃ����B����A���N���̎j���w���@���^�x(1454�N)�ł�6��26���̐킢�Ŏ��ҕS���\�l�A7��10���̋L�^�Ƃ��Đ�S��180�l�ƂȂ��Ă���B
���P����
�f�x�ł̐퓬�Ɋւ��Ē��N�ł́u�p���������鎞�A��q�����ɂ���11�l�̒����l���A�䂪�R�̔s�������Ă��܂����̂ŁA�ނ�𒆍��ɕԊ҂ł��Ȃ��v�Ƃ������c��(���ʊ���)�̎咣���������B���ׁ̈A���N�̒ʖ����l�ɏ������Ɓu����̐킢�Ŏ��҂��A�`�l20�]���A���N�l100�]���v�ƌ������B��������ƁA���_�����u�������k�������Ƃ̐킢�ŁA�����̕��m�������������Ⴊ����܂��B100�l�̎��A�����p�ɂȂ�ł��傤���H�v�ƌ����A���@������Ɏ^�����A�����l�����𖾂A���B�p���͌y���������߂ɂ�蓊�����ꗛ�]�͍��R�֘A�Ŕ�����B�������A����(�Δn����)�ɂƂ��Ĕs�k�͏��������͑��������ƁA�p���͖ƍ߁A���]�͏��i���鎖�ɂȂ����B
�Δn�Đ��v��@/�@7��4���A���̘`�m�W�c�����N���{�֍v�����^������S�����̗A���D9�ǂ𗪒D���Δn�Ɍ������čs�����B�܂�7��6���A��������߂��Ă���`�����\�ǂ����ꂽ�ƌ������A�nj��E�r�ł���ׂɑΔn�Đ������������B
�Δn�̎g�b�@/�@9���A���N�Ɂw�s�ɒ[�s�V�x�Ƃ����Δn�̎g�҂����č~���𐿂��A�M��̉��������߂��B�����ė��N�A�w�����E�s�x�Ƃ����Δn�̎g�b�����N�ɗ��āA�@�吷�����N�ւ̋A��������Ă���Ɠ`�����B�����A���̎g�b�͋U�g�ł������B
�����
���A�Δn�ƒ��N�̊Ԃɂ́A�f�Ղ��k���������̂́A�g�߂͑��ς�炸��������B ����̓��{�́A��B�T��a��`�r�Ə��傪���i�A���������̂��ߒ��N�֎g�҂𑗂�A���̐^�U���m�F�����B���N�ɂ͒��N������g�Ƃ��đv���m���h������A4�㏫�R�����`���ɔq�y���ē��{�Ƙa�������B 1426�N�A���c���q�呾�Y�̗v���Œ��N�͊��R�Y�A�T���Y�ȊO�ɂ����Y���J�`���A�����Ԃ̖f�Ղ��ēx�����������B�������A����������{�l�̐������X�����A�ڑҔ�Ȃǂ����N�ɕ��S�ƂȂ�1443�N�A���N�͑Δn�ƉËg�������щ�������B�Ȃ��A���N�͘`�m����̈�Ƃ��āA�Δn�̐F�X�Ȑl�Ɋ��E��^���A����1461�N�A�吷�̎q�A�@���E(������������)�ɂ����E��t�^�����B
�`���̐��ށ@/�@���N���A���E�~�����̐�����s�������ߘ`���͈ꉞ���ނ��Ă������A�O�Y�̗��╶�\�E�c���̖��ōĂі�肪��������B�@
�@ |
|
�����\�E�c���̖� |
   �@
�@
|
(�Ԃ�낭�E�������傤�̂���)��1592�N(���{�F���\���N�A������ђ��N�F����20�N)����1598�N(���{: �c��3�N�A������ђ��N: ����26�N)�ɂ����čs��ꂽ�푈�B���{�̖L�b�G�g���哱���鉓���R�ƁA������т��̒��v���ł��闛�����N�̌R�Ƃ̊ԂŌ��������Ȃ��璩�N������ɂ��Đ��ꂽ���̍��ې푈�́A16���I�ɂ����鐢�E�ő�̐푈�Ƃ����B���̐�͖��E�����𒆐S�Ƃ������A�W�A�̎x�z�̐��E�����ւ̏G�g�̒���ł���A���{�ƒ����̐푈�������B
���\�̖���1592�N(���\���N)�Ɏn�܂��ė�1593�N(���\2�N)�ɋx�킵���B�܂��A�c���̖���1597�N(�c��2�N)�u�a������ɂ���Ďn�܂�A1598�N(�c��3�N)�̏G�g�̎��������{�R�̓P�ނ������ďI�������B
�Ȃ��A���\���N�ւ̉�����12��8��(�O���S���I��1593�N1��10��)�ɍs��ꂽ���߁A4��12���̊��R�㗤�Ŏn�܂���������N��1592�N�̂قƂ�ǂ̏o�����͌����I�ɂ͓V��20�N�̏o�����ł���B
������
�L�b����������]�ˎ������Ɏ���܂ł́A���̐�������{�����̐�����ڎw���r��̒��N�����ōs��ꂽ���̂ł��邱�Ƃ���u������v�u����w�v�A���邢�́u����w�v�u���N�w�v�Ȃǂ̌ď̂��p�����Ă����B�G�g���g�́A�u������v�Ə̂��Ă���(��q)�B���A������̂��̂Ƃ��Ắu�喾�䓹���v�Ƃ����\��������B
���N�����Ƃ����������́A���łɍ]�ˎ��㏉����1659�N�Ɋ��s���ꂽ�x�Lj�(�x����)�w���N�����L�x�ɂ����Ă��݂���(���e������1644�N��)�B�������A�x�Lj��͂��̏��ɂ����ďG�g�̂��̐�����A�����ڂ݂��A�����m���̎v�z����ᔻ�����B
���������ɋN���������ؘ_�ɂƂ��Ȃ��A���̐�����u���v�ȂǂƌĂ��悤�ɂȂ������A�؍������Ȍ�͒��N�l�����{�����Ƃ��ꂽ���Ƃ���u���N�����v�̕\���͔������A�����đ�ꎟ�o�����u���\�̖��v�A��o�����u�c���̖��v�A�����āu���\�E�c���̖��v�Ƃ����ď̂��蒅�����B���ɂ��u���N�o���v��u���N���v�E�u���̖��v�Ƃ����Ăѕ�������B
�؍��E�k���N�ł͓����̊��x������ĕ��\�̖����u�p�C�`���v�A�c���̖����u���ј`���v�ƌĂԁB�ق��A�k���N�ł́u�p�C�c���푈�v�Ƃ��B�����ł́A�u�R�`�����v�܂��́u���N�V���v�ƌĂ��B�ߔN�A�����j�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ������ؒ����������ɂ���āA�u�p�C�푈�v�Ƃ����ď̂�����Ă���B���{�����ł����N�Ɋ��S���������҂́u���N�N���v�ƌĂсA���ȏ��L�q�ɂ����̉e����������B�@ |
|
�������W�O�j�@ |
�G�g�ɂ���ē�(����)�A�V��(�C���h)�A���(����)�ɂ�����ƍ\�z���ꂽ�嗤�i�o�ɂ��āA�G�g�͓����͍���ւ̏o���ɂ��Č��y���Ă���(��q)�B���̂悤�ȏG�g�̊C�O�o���\�z�̌`���v���ɂ��Ă͑����������B
�݂��ɗ��ł�����{�ƒ��N�����Ƃ̊Ԃɂ͓`�����܂߂ė��j�I�ȊW���[���A�푈�⑊�݂̐N���̌o���������B�G�g�������Ă��������̓��{�̔F���Ƃ��ẮA�ȉ��̏o�������֘A����O�j�Ƃ��đ��݂��Ă����B
�Ñ�ɂ́A�_���c�@(170�N-269�N)�ɂ��V���o���ƐV���E�����E�S�ς����{�ɒ��v�����Ɠ`����O�ؐ����̓`�������{���I���ɋL�ڂ���Ă���B�D�����蕶�ł͉����͘`���̎x�z�̈�ł���A391�N�ɘ`�����S�ρE�V����j�蕞���������Ƃ����L�^������(�`���ɂ�鐪���ȑO�͐V���A�S�ς͍����̐N�����]�����Ă���)�B�܂��A369�N����562�N�ɂ����ĔC�ߓ��{�{�����N�����암�ɑ��݂����B
663�N�ɁA���R�Ƙ`���E�S�ϘA���R���Փ˂��������]�̐킢������A�`���E�S�ϑ����s�k�����B
812�N����906�N�܂ŐV���̓������J��Ԃ���A997�N����1001�N�ɂ����Ă̍���C���ɂ��������������B1019�N�ɂ́A����(�y�юP���̏��^��)�ɂ�铁�ɂ̓������������B
1274�N��1281�N�ɂ̓����S���R(�����S���l�A��v�l�A����l)�����{�̋�B�k����N�U����(����)�B�����̌�A���{�͐����������ނ����A��k������ɂ͂��邪�A�`���Ƃ̂��ɌĂ��C�������������B�`���͌����ւ̕Ƃ������ʂ��������B����`���ɂ͒����l�Ɠ��{�l�Ɠ�ؐl�����݂��Ă����B1375�N�ɂ͓��o���U�E���������������B
1389�N�ɂ͍N���̊O�����A1396�N�ɂ͗����j���`���r�ł̂��߈��E�Δn�����v�悪�\�z����A1419�N�ɂ͗������N���Δn��N�U����(���i�̊O��)�B
1510�N�ɂ͒��N�������{�l�ɂ��O�Y�̗����������B 1544�N�ɂ͎֗��`�ς�����A1547�N�ɒ���������������ꂽ�B���̎��A�Δn�@�������N�ɏx�n�����߁A���N�����{�ɕ������Ă���|�𖾒��ɓ`�����Ƃ̕��s�����B����ɑ��āA�������N�̎i���{��i���ѕS��́A
�������A�`�l�A�����Ɍ����ĞH���A�u���N�͉�ɕ������A��܂��ɑ��̏�ɏ����ׂ��v�Ɖ]����ƁB�T�����҂̉���O�킸�A�����遐S���A�ǂ��㍑�ɑ����B���̌����̔@���A�O�̂�����傢�Ȃ�͔����B��ׂ̓��A���܂��ɐ߂���ׂ��A�i����\�킴���嫂��A���̎��ɋy�тẮA�ِ����邪���Ȃ�
�ƌ��{���Ă���B
�܂�1555�N�ɂ͒B���`�ς�����A1557�N�ɒ���������������ꂽ�B1588�N�A�G�g�͊C����~�߂z���Ă���B
���̑��A�����̓��{�l�ɂ�鐢�E�F����������Ƃ��ċ`�o�L�����́u�^�ɉ䂪���̎��͌��ӂɋy���A���y�V���ɂ���N�Ɏu�[���ґ�����嫂��A�z�����Ȃ��ƂāA�O����̍��̎҂ƌ��͂ꂵ�������v�Ɍ�����悤�ɓ��y(����)�E�V��(��x)�E���{(�`��)���O���ƌĂсA����������đS���E�ƕ\�����Ă������ƂȂǂ���������B
�G�g�̖������v��ɂ��āA�����{�Ɍ���ƏG�g�֑̌�ϑz�Ƃ��ĕ]�����邱�Ƃ��������A���ƒ��N�Ɠ��{�̒n�ʂɂ��ẮA���łɐ퍑����ɒ��N�������{���D�ʂł���Ƃ���F�������݂��Ă������Ƃ��ߔN�A���炩�ɂȂ��Ă��Ă���B���ł�1540�N(�V��9�N)�̎��_�ŁA�����f�Ղɏ]���������`�������̖k���֔h�������ΐS�דC���18�������g���A�u���{�͒��N��(����)�����Ă��邩��A�Ȏ��͒��N����ɂ��ׂ��v�Ɨv�����Ă����B�@ |
���V�i�C�n��̕ω�
����͉��̌����Ȃǂ���ɂ���A16���I������1501�N����1525�N���ɂ́A���A�����A���{�A�����A����A�W�A�����̊V�i�C�n��ɂ����ẮA����܂ł̊����f�ՂȂǂ̒��v�`���̖������哱�̖f�Ղł͂Ȃ��A�C����ɔ�����@�Ȓ����l�`�����l�̊�����A��┎���̍����Ȃǂ𒆐S�ɂ����l�b�g���[�N���\�z����A�܂�1510�N�ɂ͎O�Y�̗��A1511�N�ɂ̓|���g�K�����}���b�J��łڂ��ē��A�W�A�ł̌��Ղ��n�߁A1523�N�ɂ͔J�g�̗����N����ȂǁA�������̊C����ꂽ�f�Ղ��L�����Ă������B
�Ö���̎���ɁA���͂ɂ��C����̌��i�Ȏ���肪�i�ނƘ`�����ؐl�̊������ߌ������A1554�N6���ɂ͍ϏB���œ��l�Ƙ`�l�̓��悷��D�����N���R�ƏՓ˂��鎖�����N���A1555�N�ɂ͘`�m�����̓싞�⒩�N�̑S������N���Ă���(���K�̘`��)�B�@ |
���G�g�́u��������v�\�z
�G�g�����𐪕����鎖���v�悵�����R�́A���Ďd�����D�c�M���̎x�ߐ����\�z���p�����Ƃ��A���m�⑫�y�̐l�����ߏ�ɂȂ��Ă��菫���̓����┽����U������\����J���������߂Ƃ��A�����̓���푈�̉����Ƃ��čl���Ă����Ƃ������Ă���B�������O�ɂ��A�Ɛb�c�����̑Η�������������A���������ɂ������߂̘_���Ƃ��āu��������v���o�ė����Ƃ��Ă���B�܂��A�y�����߂ȂǓ��{������������̍ۂɂ��u���{�̋V�͂����ɋy���A�����܂ł���ӂ���v�Ƃ����_�@��p���Ă������Ƃ���A�嗤���܂ޓ���������ɂ���Ă����Ƃ������B
����O��ʂɂ����ẮA�G�g�͖��Ƃ͗F�D�W��z�����Ƃ��Ă���A���Ճ��[�g���r�炵�Ă����`���̎��������������B�@ |
�����������\�z�̎��n��
�G�g�́A���{�ꂷ��������Ȃ�O����嗤�N�U�v�������Ă����Ƃ�����B�G�g���܂��M���̕����ł�����1578�N����A�����n���̔e���𑈂��Ă����ї��P���ɑ��M���ɂ͖��N�U�v�悪����Ɠ`���Ă���B
�G�g�ɂ�����C�O�i�o�̍\�z��@���Ɏ��������́A�V��13�N(1585�N)�ȍ~�ł���B
�V��13�N(1585�N)�֔��A�C�����9��3���A�q�����̒��b����s��ւ̏����
�u���{�����Ƃ͐\���ɂ�����A�����܂ŋ�������S�Ɍv
�ƏG�g�͏q�ׂĂ���B
�V��14�N(1586�N)3���ɂ́A�C�G�Y�X��Nj撷�K�X�p�[���E�R�G�����ɑ��āA���������́A���{���G���ɏ���A�����̐����Ɉڂ����ŁA���̂��ߐV����2000�ǂ̑D�̌������n�߂Ă���Ƃ��������ŁA2�ǂ̑�^�D(�K���I���D)�̂���������˗����Ă���B
��4���A�ї��P���ւ̎���14�J���̂Ȃ��Łu�����n�C���v�ƋL���Ă���B6���ɂ͑Δn�@���ւ̏���ł�����ւ̔h�������B
�V��15�N(1587�N)5��9���ɏG�g�v�ȂɎd����u���فv�Ƃ��������ւ̏���ɂ�����
�u�����炢����l�����(�͂�)���̂��ɂ����Ђ͂��\����܂܁v
�ƋL���A��B����̉����Ƃ��č���(���N)����̈ӌ������鎖�������Ă���B
���N6��1���t�Ŗ{�莛���@�Ɉ��Ă�����̂Ȃ���
�u�䒩�V�o��ԍ��퍑���Q����|�����v
�ƋL���Ă���B����(���N)�����͏��喼�Ɠ����悤�ɒ���(�G�g)�ւ̏o�d�`��������ƍl���A����ɗ������N�ɑΔn�̏@������ĕ������v��v�������B
���N�ɂ͒���ړI�ŁA�G�g��26�ǂ���Ȃ�l���N��݂ɔh�����A���N�R�͖��ɂȂ�Ȃ��ƌ��_�Â��Ă���B
�V��16�N(1588�N)�ɂ͓��Î�����ė����֕������v���s���A�Ȍ㕡����v�����J��Ԃ��B
1590�N�ɏ��c����̖k�������~���������G�g�͎��̐푈�̏������J�n�����B
�V��19�N(1591�N)3������A��B�̑喼�ɖ����ĐN�U�R�̊�n�Ƃ��Ė��쉮��(�����Îs)�̌��݂��n�߂��B
���N7��25���ɂ̓|���g�K���̃C���h�����Ɉ��ĂăC�X�p�j�A���̗�����v�������B
���N9��15���A�X�y�C���̃t�B���s������(������)�ɒ��v�ƕ�����v���B���ɒ��N�Ɨ����͓��{�ɓ��v���Ă���Əq�ׂĂ���B����́A�C�O��ɏڂ����������l���c�����Y���g�҂Ƃ��ă}�j���̃X�y�C���̃t�B���s���̑��S���X�E�y���X�E�_�X�}���j���X�̂��Ƃɓ͂���ꂽ�B���c�̓_�X�}���j���X�ԏ��������ċA���B���N�̓V��20�N(1592�N)�_�X�}���j���X�̎g�߂Ƃ��ăh�~�j�R��̃t�A���E�R�{ (Juan Cobo) ���������G�g�ɉy�������B�t�B���s�����̏����n�����R�{�͏G�g����̏��Ȃ�����ċA�H�ɂ������A��p���ő�����B
�V��20�N(1592�N)5��18���t�֔��L�b�G��������ł͍���̗���ɋ{����u���A3�N��ɓV�c��k���Ɉڂ��A���̎��ӂ�10�J����i�サ�A�G����哂�̊֔��ɏA���A�k�����ӂ�100�J����^����Ƃ����B�܂��G�g���g�͖k���ɓ��������ƁA�V��(�C���h�̌Ï�)����(���[���b�p��A�W�A�܂ł��˒��ɂ���Ă����Ƃ�����)�̐����̂��߂ɔJ�g�Ɉڂ�Ƃ����B
���N�A�ї��P��������ł�
�u�����̂��Ƃ��喾�����n�����ׂ��́A�R�̗��������邪���Ƃ�����ׂ����̂Ȃ�B�����ɑ喾�݂̂ɂ��炸�A������܂��V���E������̂��Ƃ�����ׂ��v
�ƋL���Ă���B
���\2�N(1593�N)�ɂ͍��R���֕������v��v�������B�u���R���v�Ƃ͓����A��p�ɑ��݂���ƍl����ꂽ�����B���l�̌��c�����Y�ɑ�p�֓͂����������A�u���R���v�����݂��Ȃ����Ƃ��������ߌ���������邱�Ƃ��ł������̎��݂͎��s�����B���̌�̑����Y�̏����͕s�ځB�@ |
|
���R���͂ƌR����@ |
|
�ȉ��A�W���̌R���͂��L���B�Ȃ��A�����̊e���̐l���́A1600�N�̎��_�ŁA���{��2200���l�A�������N��500���l�A������1��5000���l�ł������Ɛ�������Ă���(���j��̐���n��l���Q��)�B�܂��C�x���A�鍑(�X�y�C���E�|���g�K��)��1050���l�A�I�����_��150���l�A�u���e�������S�̂�625���l�ł������B�@ |
�����{�R
��������
�G�g�́A�N�U�R�Ɨ\���R�̏h�c�n�Ƃ��ĐV���Ɍ��݂������쉮��ɌR�����W���������B
���\�̖��̓����́A9�R�c�ɕ����ꂽ����158,000�l�ŁA���̓���2�R�c21,500�l�͗\���Ƃ��āA���ꂼ��Δn�ƈ��ɒ��Ԃ����B����ɏ���(�d���O�̒���G���ق�)��12000�l�A���R9200�l�A�Γc�O�����s7200�l����l�߂Ƃ��Ė��쉮�ɍݐw���A�n�C�R�Ƒҋ@�R�Ƃ��܂߂�ƁA���v187100�l�ł������B
�c���̖��ł�141,500�l���������ꂽ�B
�������A�����͏��喼�ɕ��ۂ��ꂽ�R���̓����萔�ł����ē��������͂��̔������x�Ƃ������A���{�R�̓������ɂ͐l�v�␅�v�Ȃǔ�퓬�����܂܂�Ă���A��퓬�����S���̎l���ȏ���߂Ă������߁A���ӂ��K�v�ł���B
�ق��ɁA20��5570���܂�̕�������֓n��A���쉮�ݐw��10��2415���ŁA���v30��7985���Őw���Ă��ꂽ�Ƃ����w���Y�Î��L�x�ɂ��L�^������B
������E����
15���I����������{�͒���������(�퍑����)�ɂ��������߁A�L�b�G�g�̎w�����ɂ͎���Œb����ꂽ50���l�̌R���������ԂƂȂ��Ă���A����͓����̒n���ł͖��ƕ��эő�K�͂̌R���ł������B1543�N�̓S�C�`���œ��{�Ɏ������܂ꂽ�Γ�e(�}�X�P�b�g�e)�́A���̌㒼���ɍ��Y��������{�����ŕ��y���Ă����B�����̖f�Վ��������̐��v�Ő퍑���㖖���ɂ͓��{��50�����ȏ���������Ă����Ƃ������A�������E�ő�̏e�ۗL���ƂȂ��Ă����B�Ȃ��A�����̓��{�̕��m�l����200���l�ł���̂ɑ��āA�C�M���X�̋R�m�l����3���l�ł������B
���{�R�͕���(���y)�����S�ʼnΓ�e�Ƌ|��g�ݍ��킹�Ďg�p���A�ڋߐ�p�ɂ͒����A����p�ɂ͓��{����p�����B�Γ�e�́A�Z�擛���W���ł��������{�����̐�ŗp����ɂ͈З͕s���Ȓe�ۏd�ʓ�攼(��9.4�O����)�̈����ő�ʐ��Y�̏o�����r�I�����a�̂��̂���ɗp�����A�哛���S�C���܂ޑ����e�C���̂��悻���������̓�攼������߂��B
�푈�̏����A���{�R��500���[�g���ȏ�̍ő�˒��������A�|������ђʗ͂̂���e�̏W���g�p�ɂ���ėD�ʂɗ������B�{���̓��{�̉Γ�e�̗p�@�́A���m�ɂ�����������ɂ��e���ˌ��Ƃ͈قȂ�_���^�̂��̂ł���A�ˌ��J�n������1��(��109���[�g��)���x�ł������Ƃ���邪�A���N�ɂ����Ă͂�艓��������̎ˌ��킪�s����X���ɂ���A�������ˌ��ɂ�鐸�x�̒ቺ��₤���߂ɁA��Ă̏W���ˌ����s��ꂽ�B�������A�푈�̖����ɂȂ�ƒ��N�Ɩ����b�l�������{���Γ�e�₻���͑��������̂��̗p���Ďg�p���𑝂₵�R�����B
���{�̋R���͑���A�n��p�̏��^�e�����Ă����B�������A���{�ł͐퍑����ɏe�̏W�c�ˌ��ɑ���R���̐Ǝ㐫���o�����Ă������߁A�R���̎g�p�͌���������B
���{���R�͈���D�͈ꕔ�̏㋉�w�����̏�D�ȂǂɌ����A���^�֑̊D�⏬�^�̏����ɂ��@�����̍����퓬�����@�Ƃ��A�ڌ��荞�݂ɂ�锒����w���ŁA�\�ł���ΓG�D���b�l����X�����������B�Ȃ��A�����̐��E�̊C��Ƃ��Ă͓G�D�b�l���퓹�ł������B�J�평���A���{���R�̔C���͐H���╺���̗A���ł���A�Ί�ɂ��C���z�肵�Ă��炸�A�R�D�ɂ͊�{�I�ɑ�C�����Ă��Ȃ������B���̌�A���{�D����C���ڂ������̂́A�a�D�̐v�㍢��ŁA�Η͂�₤���ߑ���a�̉Γ�e�`���ł����S�C�������p����ꂽ�B�@ |
�����R
���N�Łu�V���v�ƌĂꂽ���R�́A���\�̖��ɂ����ẮA�c���P������5,000�l�A���@��������H�������܂�43,000�l���Q�킵�A����ɕɒ��ق̐킢��ɗ�綎������5,000�l�������Ƃ��ĐV���ɓ��������B���C�X�E�t���C�X�́A��������͂��R�̕��͂�`���Ƃ��āu���Ȃ��Ƃ�20���v�ƋL�ڂ��Ă���B
�c���̖��ɂ��ẮA�ő哮���ƂȂ����c��3�N(1598�N)9���̉U�R�E����E���V�̎O���ʓ������U�̍ۂ̕��͂��A�w��c���^�x�͐��R�����킹92,100�l�Ƃ��A�Q�d�{���Ҏ[�w���{��j ���N���x�ł͓�����64,300�l�Ƃ��Ă���B�܂����N�̎j���w�R�t���L�q�x�ł͗�����ʂ��Ă̖��̓�������221,500�]�l�Ƃ���B
���̕����́A�L��Ȓ鍑���ɂ����鑽�l�Ȑ퓬���o�����Ă��邽�߁A�l�X�ȕ�����g�p�����B��ѓ���Ƃ��ĉΓ�e�A�|�A��؎��Γ�e�A���ΖC�A��������Ƃ��đ��A�O���A�S�_�A�ˎ�̌�g�p�ɕЎ蓁�A���̑��ɑ�C�A�����e�A�蓊���e�Ȃǂł���B�������A���̉Γ�e���؎��Γ�e�͓��{�̕��Ɣ�˒����Z���З͂��ア���߂��܂���ɗ����Ȃ������B���R�̖h��͓S���̂��ߎ���͂�����A�������{�����ʂ��ɂ��������B����A�����^�͕ɒ��ق̐킢�ɂ����Đꖡ�݂̓��Z�������������Ȃ��������̖k���R�����A�O�`�l�ڂ̓��������{�R�̕����ɐl�n�̋�ʂȂ��a��|���ꂽ�Ƃ��L�^���Ă���B
���͕����̑��ɑΏ��^�p�ɐ������ꂽ�R������(�n�R)���K�͂ɐ퓬�ɓ����������A��ʂ͓����Ȃ������B���N�͎R�������A�R���̓ˌ��ɓK�������n�����Ȃ���A���{�̉Γ�e�̒��˒��ɑ��ċR�������͕s���ł��������߂ł���B�܂��A�����̌R�n��{���̂ɕK�v�ȑ��n���R�����A�x�X�n�u���������đ����̔n�C���˂ꂽ�B
�c���̖��ɂ����Ă͖����R���Q�킵�Ă���B���D�E���D�E���D�Ƃ��������̂��m���邪���ɂ��D��͑����A���͕̂s���ȓ_�������B���{���̎j���ɌŒ蔿���̍q�m�^�W�����N�D�ł͂Ȃ����Ǝv���閾�D�̋L�q�����邪�A�R�D�Ƃ��Ă͕s�K�ƕ]����Ă���B���ɌՑD�Ƃ������������������^�D����C���p�Ɏg�p���ꂽ�悤�ł���B�@ |
�����N�R
���\�̖��̑S���Ԃ̍��v�ŁA���N��172,400�l�̐��K�R��W�J���A22,400�l�̔K�R��������x�������B
���N�ɂ��Γ�e�Ɏ����Ί킪�������������̂��̂ŁA�Ί�͌���ł����u��C�v�ɕ��ނ������̂����S�ƂȂ��Ă����B�@�`�q��1589�N�Ɏg�߂Ƃ��Ē��N��K�ꂽ�ۂɐi���Ƃ��ĉΓ�e�������A���N�����͂�����R�펛(���퐻������)�ɉ����n�����݂̂ŁA�����͊J��O�ɂ��̐V����̐��ݗ͂����������Ƃ��o���Ȃ������B
���N�̕����͓��A���A�|��Ȃǂ̕�������Ă����B��͕���͋|�ł��������A���{�̔��|�ɑ�������|���邢�͌~�E���̒Z�|�ŁA���̍ő�˒���120���[�g�����x�ł���A���{�̋|��140���[�g���]�����Z�������B�������A���m���|�����ʓI�Ɏg�����Ȃ����߂ɂ́A�Γ�e������������ȌP�����K�v�ł������B���̂ق��A�t���C�X���{�j�ɂ́u�Ζ��(�p�l�[���E�f�E�|�[�����H��)(��֒e�̂悤�ȕ���)�v�u�S���̊��v�u��v�Ȕ琻�̖h��v�u�����̏��^�C�v�u����߂Ĕ��˂���ːΖC(�{���o���_)�v�Ȃǂ̋L�q��������B���N�̋R���́A�Ώ��^�p�ɖk���z������Ă���A����p�Ɋk�ƂƑ�(���{����蒷��)�����āA��������p�ɋ|������Ă����B���N�R���̐퓬�Ƃ��ẮA���B�̐킢�E�C��q�̐킢�����邪�A����������{�R���������Ă���B ���N���R�́A���펞�ォ��Θ`����ړI�ɐ�������A�P�����s���Ă���A�����Ȃ���ΖC�𑽂��������Ă������߁A���O��������{�R���悭�}�������B���N���R�͔��D(��D)�Ƃ������{�̈���D�ɑ��������^�D��p�����B�L���ł͂��邪���̕s���̋T�D���A���̔��D�������������̂Ƃ�����B���ɕ⏕�͑D�Ƃ��Ē��^�̋��D�A���^��鸍�D������B���N���R�͉Ί��|���g���Ẳ���w�����������A���N�̉ΖC�͎˒���64m〜160m�ƒZ���A���N�̊͑������{�D����̉Γ�e�E�|��Ȃǂɂ�锽���̎˒��O�������I�ɓ��{�D�����j�ł����킯�ł͂Ȃ��B���N���R�������ň��|�I�ɗL���ł������ՎR���C��ɂ����Ă���틗����100m�ɖ����Ȃ������Ő���Ă���B�܂��A���N�̉ΖC�́A�S�e�A�Βe�����߂ĎU�e�̌`�Ŏg�����Ƃ����������A��{�I�ɂ͉ΐ�(�Ζ�)�������ēG�D���Ă��������邱�Ƃ����Ƃ��Ă����B�@ |
�����N�̍��h�Ԑ�
�����̒��N�Ɩ��ɑ����ȌR���I���Ђ́A���^��k���R�n�����A�`���ł������B���^�͖k�̍����n�тŏP�����J��Ԃ��A�`���͉��ݕ���f�ՑD���P�����ė��D���Ă����B�`���ɑR���邽�߁A���N�͐��R��{�����A�`���̊�n�̂ЂƂł������Δn���U������(���i�̊O��)�B�܂��A���^�ɑ��ẮA�}��]�ɉ����Ėh�q�����\�z�����B���̊ԁA���N�ł͔�r�I���a���ۂ���Ă������߁A���N�R�͗v�ǂƌR�D�ɕΏd�����Ґ��ƂȂ��Ă����B���퉤���̊ԂɉΖ�������A���N�ł͉ΖC���J������Ă���A���ꂪ�C��ł͑傫�ȈЗ͂����A���{�R�Ƃ̊C��ɂ����钩�N�D�ʂɂȂ������B�܂��A�������ォ��퍑����ɂ����Ă̓��{�͓�����Ԃł��������߁A���N���͘`����ʂƂ���A���{��傫�ȌR���I���ЂƂ͌��Ă��Ȃ������B�G�g�����{�ꂵ�A1588�N�̓���A�C�㑯�D�֎~�߂ɂ��`���͏I���Ɍ����������A���N���͏G�g�̐N�U���`���ɂ��P���̉���������x�ɂ����l���Ă��Ȃ������B
1583�N�A�w�҂Ŗ��̍������������̕�������(���ݓ��{�̖h�q��b�ɓ�����)�����͑S���̕��͂�100,000�l�ɑ�������悤����ɐi���������A�����͐��l�h�ł��������߁A�����̐����������Ă������l�h(���������̑�)�͂��̒�Ă��p���B1588�N�ɂ͓암���݂�20�̓��������Ă��n����������o���ꂽ���p�����ꂽ�B1589�N�ɌR���P�������ݒu����邪�A�Ⴗ���邩�A�V��������̗p���A���̑��ɖ`���D���̋M���ƁA���R�����߂�z�X�K�w������݂̂ł������B1590�N�ɂ͊��R�`�p�̗v�lj��Ă��o���ꂽ���A�p�����ꂽ�B���{�̐N�U���܂��܂���������ттĂ��āA���̖��ɂ��ĕ����������������ς�������A�����I�Ȍ��͑����̂��߂̘_�����s�������ŁA���ۂ̌R���g���͕s�\���������B
�܂��A���������u(���R��)�S�l���Ă��N�����̌P�����@��m��Ȃ��v�ƒQ���قǁA���N�̌R�l�͌R���I�m�������Љ�I�Ȑl���ɂ���ď��i�����肳��Ă����Ƃ����A�R���͑g�D���ɂ݁A���m�͂قƂ�njP������Ă��炸�A�������n��ŁA���i�͏�ǂȂǂ̌��ݍH���ɏ]�����Ă����B�������̕��Q���w�E�����B
��ʓI�ɒ��N�̏�ǂ͎R��ŁA�R�̎���Ɏւ̂悤�ɏ�ǂ��߂��点����̂ł������B��ǂ͕n��ŁA(���{��m�̏�ǂ̂悤��)����\���C�̔z�u�͗p�����Ă��炸�A��ǂ̍������Ⴉ�����B�펞����Ƃ��ẮA�Z���S�����ߗׂ̏�֔��鎖�Ƃ��A���Ȃ������Z���͓G�ɋ��͂���҂Ƃ݂Ȃ��Ƃ��ꂽ���A�����̏Z���ɂƂ��ď�͉��������B�@ |
�����ǎ��R
�푈�����Ɋs�ėS�������債���B�����W�c�͈ꕔ�̒n���ŘJ����퓬�ɎQ�������B ���ǂ̎����͎�ɒ��N���K�R�̔s�c���A�햯�o�g�A���ǂ����L����z�X�A�����Љ�ł��˖��ƌ���Ă����m������\�����ꂽ�B
���\�̖��̊ԁA���N�����̒��ł͑S�����������N�U��Ƃꂽ�n��Ƃ��Ďc����Ă����B�e�n�Ŕs�������������N�R���S�����֏W�܂�A10������R��i���Ă����ׂł���A���̌���s�c�����S�����֏W�܂�X���͑������B
�s�ėS�̋����͔����Ƃ݂Ȃ���A���N���R�Ƃ̊ԂŐ퓬���N�����Ă���B�������N�̖��O�́A���삩��ۂ����z��Ȃǂ̓y�؍H���A����E���Ƃ̉^���Ȃǂ̘J�����}�����B��������͊s�ėS�ɑ��Ċ��E��������[�u���Ƃ芯�R�̕⏕��F�߂����A����ŗ�������͊s�ėS�R�����@�g���̎w�����ɂ����ē��������B�������A���\�̖���̋x����ԂɊs�ėS�R�̊���P���ŁA��������͂��̊댯����F�������������߁A�����ɂ͊��R�ɑg�ݓ�����Ɨ����������ł͂Ȃ��Ȃ����B
���A�����`���͕s���ł������B�@ |
|
���������@ |
���̐�������}���Ă����L�b�G�g�́A�V��15�N(1587�N)�̋�B�����Őb�]�������Δn�̗̎�E�@����ʂ��āA�u�������N�̕����Ɩ������̐擱(��������)�v�𖽂����B�@���͌����A���N�Ƃ̖f�ՂɌo�ς��ˑ����Ă������ߑΉ��ɋꗶ���A�Ɛb�̗M�J�N�L����{�����g�Ɏd���āA�v���̓��e�����ς��āA�V�����ƂȂ����G�g�̓��{������j�ꂷ��ʐM�g�̔h���𗛎����N���ɗv���������A���N���́A�G�g�����{�����̒n�ʂ�ӒD�������̂Ƃ݂Ȃ��A�v�������₵���B
1589�N(�V��17�N)�A�G�g���ɂ��A�@�`�q���炪�����������̊O��m�i�Q���h�A������������@���ƂƂ��ɒ��N�֓n��A�d�˂ĒʐM�g�h����v�������B��1590�N(�V��18�N)11���A�ʐM�g�Ƃ��ĉ���g�Ƌ����ꂪ�h������A�ڊy��ň��������B�@���͒ʐM�g���A�G�g�ɂ͕����g�߂��ƋU���Ėʉ���A���ւɍς܂����Ƃ����B���̂��ߏG�g�́A���N�͓��{�ɕ����������̂��Ǝv���A�������N�ɖ������̐擱������悤���߂����B�������̍������ł������������N�ɂ��̂悤�Ȉӎv�͖����A���߂͋��ۂ��ꂽ�B���̂��ߏG�g�́A���̑O�ɂ܂����N�𐪔����邱�Ƃ����߂��B
����A��1591�N(�V��19�N)3���A���N�ɋA���������N�ʐM�g�͏G�g�̂��Ƃ�������A���e��2�ɕ�����Ă����B���l�h(���g�̉���g)�͐푈���߂����Ƃ��x���������A���l�h(���g�̋�����)�́u���{�̐N���͂������Ƃ��Ă���̘b�v�Ɣے�B���ǁA�����h�����������l�h���푈�̌x�������A�Γ��{�̐푈�����͂قƂ�Ǎs���Ȃ������B���̎��A���N�ʐM�g�ɂ͓��{�l�̖��쒲�M�ƌi�Q���h�����s���Ă����̂ŁA���N���͂���ƂȂ����҂�����{�̏�����Ƃ����B����ƌ��h�́u����(��)�͋v�������{�Ƃ̍�����f���A���v��ʂ��Ă���܂���B�G�g�͂��̎��ɐS���A����ƐJ�߂������A�푈���N�������Ƃ��Ă���̂ł��B���N���܂�(���̎���)�t�����Ē��v�̓����J���Ă����Ȃ�A�����Ɖ���������܂��܂��B�����āA���{�Z�\�Z�B�̖����܂��A�푈�̘J���Ƃ�邱�Ƃ��ł��܂��傤�v�ƌ������B�������͂����ӂߗ@�������A���h�́u�́A���킪���̕���擱���ē��{���U���������Ƃ�����܂��B���{�����̉��݂N�ɕ悤�Ƃ���͓̂��R�̂��Ƃł��v�ƌ������B���N���͂���ɑ��ĉ�����킸�A���M�ƌ��h�͋A�������B
���N6���A�@�`�q�����R��K��A�u���{�͑喾�ƍ�����ʂ������B�������N�����̎��̂��߂�(����)�t�����Ă����Ȃ�ƂĂ��K���ł��邪�A���������łȂ���A�����͕��a�̋C�^���������ƂɂȂ邾�낤�B�����Ȃ�Έ�厖�ł��B������(�����͂�����)���č�����̂ł��v�ƌ������B���������N�̒���ł͓����A�ʐM�g���߁A���{�̎g�҂̘������E���炳��{��c�_���������Ă���A�`�q�ɂ͂Ȃ�̕Ԏ����^���Ȃ������B�`�q�͕s�����Ȃ���������Ă������B����ȍ~�A���{�Ƃ̒ʐM�͓r�₦�A���R�Y�̘`�قɏ펞�؍݂��Ă������{�l���\�l������ƋA�����A�قƂ�ǖ��l�ƂȂ������߁A���N�ł͂��̎���s�R�Ɏv���Ă����B�@ |
|
���N�U�̌��s�Ɩ��쉮��z���@ |
|
�@�`�q�������������G�g��8���A�u������v�𗂔N�t�Ɍ��s���邱�Ƃ�S���ɍ����A���쉮��z������B�̑喼�ɖ������B�t���C�X���u������l����������r��n�v�ƕ]�������쉮�ɂ́A�S�����喼�O���W�����A�u����R�����Ƃ��낪�Ȃ��v�Ɛ��˂̕��ˑ�r������ɋL���Ă���B������̊��Ԃ́A��O���쉮�͓��{�̐����o�ς̒��S�ƂȂ����B�@ |
|
�����\�̖��@ |
   �@
�@
|
1592(�V��20)�N1���A�G�g�͏����s���Ə@�`�q�ɁA�ēx���N�ɕ����Ɠ�����ւ̋��͂̈ӎv�m�F���s�����A�������N���]��Ȃ��Ȃ�4��1������u��ގ�����ׂ��v�Ɩ������B�����������s���炪�Δn�ɓ��������̂�3��12���ŁA23���ɂȂ��Ă悤�₭�Δn�̖k�[�̖L��Ɉړ�����ȂǁA�{�l�����͒��N�ւ͕������A���ۂ̌��ɂ��������̂͌i�Q���h�ł������B
4��7���A�i�Q���h���Δn�A�҂��A���N���̋���̈ӎu����{�ɓ`�����B������͐N�U�������J�n�����B
4��12���A���R�ɏ㗤������ԑ��E�����R�͍Ō�ʒ��N���ɓn�����A�Ԏ��͂Ȃ������B��13���A�����R�͊��R��ւ̍U�����J�n�������R���̐킢�B
4��14��-15���A���{�R�͓�����ɓ����B���{�R�́u�키�Ȃ瑊��ɂȂ낤�A���Ȃ���Γ���ʂ��v�Ə����ꂽ�؎D������֓������ꂽ���A�����{�g�E�v�ی��́u������͈Ղ��A����ʂ��͓�v�Ə����ꂽ�؎D�𓊂��Ԃ����B����������ē�����̐킢���J�n����A2���Ԃœ�����͗���B�����{�g�E�v�ی��͐펀�����B
4��24���A�����s���炪���B�̐킢�Œ��N�R�̏��@�g�E���L��j��B
4��28���A��ԑ��E�����s���炪�e�Ց�̐킢�Œ��N�R�̖����Ƃ̗_�ꍂ���O���s���ӎg�E�\砬��j��B�\砬�펀�B
���{�R�͏������d�ˁA��ԑ�(�����s���A��)�A��ԑ�(���������A��)�A�O�ԑ�(���c�����A��)���N�ɁA�O��ɕ�����ċ}�i�����B���̎����A���������̕�����1�l�����(�����P)���A���N�̕���������炢�A�G�g�̏o���ɑ�`�Ȃ��Ƃ��ĕ�3000�ƂƂ��Ɍc�����g�p�W�ɋA�t�����Ƃ����`�����c���Ă���B�@ |
�����N��s�E���鐧��
5��3���A��s�E���邪�ח����A���N�����͓��S����B�Ȃ��A�����̏G�g�ւ̕ł́u5��2��(�����̗�)�Ɋ���ɓ������v�Ƃ���B���������N�������^�ƁA��ԑ����Y���M���̋L�^�ł́A�u�����E�s���Ƃ�5��3���ɓ��邵���v�Ƃ���A�����͐�w�̎蕿�邽�߁A1�����߂ĕ����ƍl������B
���������́A�����s�����v��ʂ�Ɋ��R�őҋ@�����ɐi�����Ď蕿����������ɑ��ē{���\���Ă����B�����œ瓇���͘a���ĂƂ��āA�R����ɕ����Ă��ꂼ�ꂪ�ʂ̓����犿���ڎw�����Ƃ��āA����ɑ������������ȕ��̓��������������ԑ�����鎖���Ă����B�������Ĉ�ԑ��Ɠ�ԑ���5��8���ɏo�����A����܂ŋ����ƂȂ����B���������͊��]��n��Z������I�сA�����s���͏㗬�������Đ��ʂ̏��Ȃ��ꏊ��n�鎖�Ƃ����B���ǁA�D���Ȃ����߂ɓ�ԑ������]�ő��~�߂���Ă���ԂɁA5��10���ɏ����s���̕�����Ɋ���ɓ��������B
��ԑ�������ɓ������Ă݂�ƁA���͌��������Ă������̂̎�����͂��Ȃ������B���̐���ɐ�c���͕���֓���邽�߂ɏo�����Ă����̂ł���B���{�R�͏�ǂɂ����������Ȑ�����ē���A������������J�����B���ǁA��ԑ��Ɠ�������ʂ��ė����������ԑ��͗����Ɋ���ɓ����B���̗����ɎO�ԑ��A�l�ԑ������������B�ܔԑ��A�Z�ԑ��A���ԑ��A���ԑ������R�֏㗤���A��ԑ��͗\���Ƃ��Ĉ��ɒ����𑱂����B
����͊��Ɉꕔ(�Ⴆ�A�z�X�̋L�^��ۑ����Ă�������@��A����ɂȂ�)�����D�E������Ă���A�Z�������炸��������Ă����B���]�h�q�̔C�ɓ������Ă������������R�͑ދp���Ă������A���̉Ɛb�����͉����̒{�ɂɂ����ƒ{�𓐂�ŁA��������ɓ��S�����B���X�ŁA���̈�s�͏Z���Əo��������A�Z�������͉����������̂Ăē����邱�Ƃ�߂��݁A�����}�����@�����Ȃ������B�u��c���^�v�ɂ��ƁA���̂Ƃ����N�̖��O�͒��N���{��������A���{�R�ɋ��͂���҂����o�����B���C�X�E�t���C�X���A���N�̖��́u���|���s�����������ɁA����i��Őe�ɐ��ӂ������ĕ��m��ɐH����z�z���A��^���łȂɂ��K�v�Ȃ��̂͂Ȃ����Ɛu�˂�L�l�ŁA���{�l�̕����ʐH����Ă����v�ƋL�^���Ă���B
�܂��A���̒��N�x���R���삯����ƁA�ӂ�ɎU����̖w�ǂ����N�̖��ł������Ə�����Ă���B�i���{�E�����{�E���c�{�̎O���{�́A���{�R�̓���O�ɂ͂��łɊD���ƂȂ��Ă���A�z�X(�z��̈��)�́A���{�R������R�Ƃ��Č}���A�z�X�̐g���䒠��ۊǂ��Ă�������@�ɉ�������A�Ƃ���B
5��5���A�����s���Ɖ��������͋��c���A���������O�ɐw�n���ڂ��A��O�ɖ؎D�𗧂āA���S�������N�l�̊ҏZ���v�����B
���N���́A����̏����k�𗬂��ՒÍ]�����Ȃ�h�q���Ƃ��邽�߁A�ՒÍ]��݂̈�т��Ă������āA���{�R���n�͂̎��ނ��Ȃ��悤�ɂ����B�����ċ��������R�͐쉈����12,000�l�̕���5�ӏ��ɕ����Ĕz�u�����B
5��18���A�����������钩�N�R�͊J���h�q���ׂ��ՒÍ]�ɖh�q���邪�A��ԑ��E���������炪�ՒÍ]�̐킢�Œ��N�R�����j���A28���ɂ͗ՒÍ]��n�����B�Ȃ��A�킢�̑O�ɏ����s�������N���ɏ��Ȃ𑗂�A�����J�n���悤�Ƃ��������ۂ���Ă���B(���̌�A6��1����6��11���ɂ�����𑗂��Ă��邪�A����������ۂ��ꂽ)
5��29���A��ԑ��E���������炪�J�鐧���B
���{�R������i�����Ă���ԁA�S�������������͌R����s�֔h�����ē��{�R��H���~�߂悤�Ƃ������A��s�ח��Ƃ̕�ɐڂ��A�ދp�����B�������A�u�蕺���W�߂����Ƃɂ��R����50,000�l�ɏ���Ă������߁A�����Ɩ����̎w���҂����͖ڕW������D�҂ƒ�߁A���邩��42km����̐����ɌR��i�߂��B
6��4���A�O�q1,900�l���ߍx�̗��m�̏��D�悵�悤�Ƃ������A�e������w�����̎����600�l�́A���{�R�̉��R����������6��5���܂Œ��N�R�Ƃ̌���������B���{�R�͒��N�R�ɔ������Ē��N�R��j��A���N�R�͕�����̂Ăđދp����(���m�̐킢 )�B�@ |
����������
�J��ח���A���{�̏����͊���ɂČR�c���J���A�e���ʌR�ɂ�锪�������ƌĂ�鐧���ڕW�����߂��B
�������ֈ�ԑ������s�����A
�������֓�ԑ������������A
���C���֎O�ԑ����c�������A
�]�����֎l�ԑ��ї��g�����A
�������ܔԑ������������A
�S�����֘Z�ԑ������엲�i���A
�c�����֎��ԑ��ї��P���A
���E���֔��ԑ��F�쑽�G�ƁB�@ |
���������ƈ�ԑ�
�����s�����������ԑ����k�i���A���C���̕��R�A �����A�P�R�A���B���̂��A����ɕ������ɓ����Ē��a���̂����B���a�ɂč��c����������O�ԑ�����ԑ��ƍ������A�哯�]�̖k�݂ɂ��镽��i�R�����B30,000�l�̓��{�R�ɑ��āA���L���������̗�����10,000�l�̒��N�R�������������Ă����B���N�R�̖h�폀���ɂ���āA���{�R���g����D�͑S���Ȃ������B���{�R�̐i��������ɔ���Ɛ�c�͗ɓ��Ƃ̍����ł���k�[�̕������E�`�B�ւƓ��S���A�����Ɋ�Â��Ė��ɋ~����v�������B
1592�N7��22��(����)��A���N�R�͖����ɐ��n����{�R�h�c�n����P�������A���̓��{�R�������삯�t���Ē��N�R�̔w�ォ��U�����A�X�ɉ͂�n����������N���̉��R�����j����(�哯�]�̐킢)�B�����ŁA�c���Ă������N�R�����͕���֑ދp�������A���{�R�͒��N�R�̒nj����~���āA���N�R���ǂ̂悤�ɐ��n���ċA�邩���ώ@�����B�����A��ӂɒ��N�R���ދp����l�q���ώ@�������ʂɊ�āA���{�R�͐�̐��g���Đ��R�ƕ�����Ί݂i�ߎn�߂��B���̏��āA���̖�ɒ��N�R�͕������������B
7��24��(����)�A��ԑ��ƎO�ԑ��͊��ɕ�������Ă�������֓������B
6��15���A��ԑ��E�����s���炪����𐧈�����B
���N�֔h�����ꂽ�����͔���������ڕW�ɗv�Ղ𐧈����Ă��������A�����s���͓����͗������N�A��ɂ͖��Ƃ̘a������͍����ĕ���Ŗk�i���~�����B�@ |
���������Ɠ�ԑ�
��ԑ��E����������́A���ӂɓ������A�������瓌�C�݂ɉ����Ėk�i�����J�n�����B���̊Ԃɐ�̂�����̈�������ł���B�����œ�ԑ��̈ꕔ�͖h�q�Ɩ����ɓ����鎖�ƂȂ����B
7��17��-18���A��ԑ��̈ꕔ10,000�l�͍X�ɖk�i�𑱂��A7��17���ɂ͊؍�����������������̖k�R�y�ѓ�R�ƁA���(���݂̋���)�ɂĐ�����B���N�̋R���������R�ː�@�ɂ���Â̕��n�ŗD�ʂɗ����A���{�R�͍����q�ɂ����ɂ��Ă����h�����B���{�R�͑q�ɂɂ������ĕU��p���ď�ǂ����A�R���̓ˌ����Γ�e�Ō��ނ����B���N�R�������ɍēx�̍U�����|���悤�ƌv�悵�Ă���ԂɁA���������͕�������܂��Ē��N�R��҂��A��ԑ��͏��n�ɖʂ��镔���������Ċ��S�ɒ��N�R���͂��A���j����(�C��q�̐킢)�B
���������N�R�̕��m�����̎�����ɔs���`�������߁A���̎�����͓��{�R�������悤�ɂȂ����B���̎�����`���ē��{�R�͗e�Ղɋg�B�A����A������̂����B7��23���A��ԑ��͉�J�ɓ���A�����ʼn��������́A���ɒn���Z����ɂ���ĕ߂炦���Ă�����l�̉��q�ƙ������ώ@�g���i����������B
7��23���A���N�̃j���q��ߔ����邽�߂ɁA9000�̕��Ŗk�i���Ă������������́A��J�ʼn��q���ߔ��B
�������ł́A�ȑO����A��������h�����ꂽ�����ƒn����(���N�l�{���^��)�Ƃ̊Ԃ����܂������Ă��炸�A�����Α������N�����Ă����B�������͂܂����J�n�E���Y�n�ł�����A���J�l�E���Y�l�����͒����ɕs��������n�����ƌ��т����B����ə������o�g�҂͉ȋ��Ɏ��Ă����E�ɂ��Ȃ��Ƃ������ʂ�����A�������͗������N�ɕs��������҂����̉����ɂȂ��Ă����B
�]��̌�A���{�R�͓����ɂƂ߂��B�����͙������k���̒n���̈����ƕ��Y�̏��Ȃ������āA����Ƃ���Ȗk�ɂ͐Q�Ԃ��Ă������N�l�ɊǗ�������ȂǁA�ꕔ�n��ɒ��N�l�̎�����F�߂��B���������͙��������u���{�ɂĂ͔��䂪���A���������Ȃǂ̗l�Ȃ闬�ߐl�̔z���v�ƕ��Ă���B���̏�����A���N�R�̕��m�̈�c�������̒��N�̏��R�̎�������o���A�X�Ɋ؍������R����Ŕ����č����o�����B�@ |
���]�����Ǝl�ԑ�
�ї��g����������l�ԑ���7���Ɋ�����o�����ē��������A���N�������݂̏�����ӂ���O蠂܂Ő�̂����B���̌�A�l�ԑ��͓����������A�ՑP�A�J�z�A�������̂��A�]�����̓s�ł��������B�ɒ��������B�����Ŗї��g���͖������s���A���{�ɏ������g�����x�����A�X�ɍ��y�������s�����B�l�ԑ��̑叫�̈�l�ł��铇�Ë`�O�͔~�k�Ꝅ�̂��߂ɒx��č]�����֓��������B���Ð����t����̂��č]�����ł̍��͏I�������B
9��15���A����̐킢�B
10��6-10���A�W�B��̐킢(��ꎟ�W�B��U�h��)�B���{�R�́A���R�����̐�������āA�W�B��̍U����}��(�א쒉���w���̓��{�R�����q�w���̒��N�R)���A���N�R�A�h�q�ɐ����B
10��16���A�����̐킢�B
11��15���A�g�B���̐킢�B�@ |
���S�����ƘZ�ԑ�
�����엲�i������Z�ԑ����A�S���������̔C�ɓ����鎖�ƂȂ�A�Z�ԑ��͊��ɎO�ԑ����ʉ߂��Ă������{�R�̈ړ����[�g��ʂ��ď��B�֍s�R���A�������̋юR�ɒB�����B�����엲�i�́A������������đS�����ł̍��̏o����n�Ƃ��邱�Ƃɂ����B
7��7���A�юR�̐킢�B�u�F���A�����̐킢�v�Ƃ��B
7��10���A�����R�ƍ��h���A�⌛�̎����́A7��8���̗����̐킢(�юR�̐킢)�œ��{�R�ɔs�k���A���h���͐펀�����B
�Z�ԑ��́A���m�̐킢����ދp����5���̕����������e�n����̔s�c��15����i���đS�����̎����ł߂����ɂɂ���čU����j�܂�A�юR�ɂ����ė����R��j�邪�A�쉺���閾�R�̍U���ɑΉ����邽�߁A7�����{�ɂ͎叫�̗��i��������������A���̍ۂɗ����R�͖�P���|�������@�m���Ă����Z�ԑ��ɏ������[�Ō}���������s���i�����B9�����{�ɂ͎c���Ă������ԏ@�Γ���������������B�@ |
�����N���R�̓���
5��7���A�C�݈ړ����s���Ă������{�A���D�c�ɑ��ė��w�b�����钩�N���R91�NJ͑����U���A�C���z�肵�Ă��Ȃ�����50�ǂ̓��{�A���D�c�͒�����15�z�����j�����(�ʉY�̐킢)�B
5��8���A���N���R�͐Ԓ��Y�ɂ�����{�A���D13�ǂ��U���A���{�D11�ǂ͌��j�����B
5��29���A���w�b�����钩�N���R�����{�A���D�c���U���B����C��B
6��2���A���Y�̊C��B
6��5���A��1�������Y�C��B
6��7���A�I�Y�C��B
7��7���A�C��p�̐��R�⒩�N���݂𐼐i������������Ȃ��������{�R�́A���핔�������ŗA���C���ɂ������Ă�����������}篐��R��Ґ����đR�����B�������A�e������̔����삯����Ȍ����ƂȂ���{���R���s�k��������Y�̐킢�B
���N�̘`����őD�̔j��̂��߂̉���w���̒��N���R�ɑ��āA�D�������̂��߂̋ߐ�w���̓��{���R�ł͑������p�̍��������āA���ʏՓ˂̊C�������Ɠ��{���R���s���ł������B7��7���̊ՎR���C��œ��{���R���s�k����Ɠ��{�R�͊C��̕s��������āA�o����p���琅�������h���p�֕��j��ύX�����B�����ŋ��ϓ��ɏ�s�����݂��A�����ɖL�b�G���̌R����u���A���{���R�Ƃ̘A�g��[�߂������B�����̑D�͍q�C�͂����n�ŁA����ւ̈ˑ����������ߐ��������h���p�͗L���ɋ@�\�����B
9��1���A���w�b�����钩�N���R���A���{�R�̗A�����_�ł��銘�R�Y�̐�����ڎw���ē��{�R�ɍU�����d�|���A���N���R�͎������ˁE�A�^���펀����ȂǑ��Q�𑽂��o���Ĕs�ނ���(���R�Y�̐킢)�B���̔s�ނ��_�@�Ɉȍ~�A���N���R�̏o���͌������A���N���R�̃Q���������͒��É������B�@ |
�����R�Q��
7��16���A���R���������A���R�����فE�c���P������ɓ��̖��R5000����������}�P�������A�������ԑ��̏����s���炪�傢�ɔj����(��ꎟ�����̐킢)�B
���R�̎Q����āA���{�R�́A�����̍��c�̌��ʁA�N���̐i���͕���܂łŒ�~���A����̖h�����ł߂邱�ƂƂȂ����B
�����A������͑c���P��7��16���̕����̔s�k�Ƃ������ԂɁA���Ҍh���\�ɗ��āA���{�R�ɍu�a���āB�ȍ~�A���{�Ɩ��Ƃ̊ԂɌ���������鎖�ɂȂ�B�@ |
���I�����J�C�N�U
7�����{����8�����{�܂ł̊��ԁA���������́A�u�I�����J�C(���^��)�v�̐�͂��������߂ɁA�����]��n���Ė��B�ɓ���A�ߍ݂̏��^���̏���U�������B���݂̋ǎq�X�t�߂ł���Ƃ����B ����܂ŏ��^�͓x�X�������z���Ē��N���P�����Ă������߁A�������̒��N�l3,000�l�������(���������̌R��8,000�l��)��������B�܂��Ȃ��A���R�͏���ח������A�����t�߂ɏh�c�������A���{�R�͏��^����̕U���ɔY�܂��ꂽ�B�ˑR�D�ʂɂ͗����Ă������̂́A�P�ނ����B��ԑ��͓��������A�ߏ�A����A�c���A�c�����̂��A�Ō�ɓ����]�̉͌��̃\�X�|�ɒB�����B���̌�A�����͏G�g�Ɂu�I�����J�C���疾�ɓ���͖̂����ł���v�ƏG�g�ɕ��Ă���A��������������ł͂Ȃ��A���ւ̐i�U���[�g��T���ړI���������Ǝv����B
���̏��^�N�U���āA���^���̒��k���n�`�͖��ƒ��N�Ɏx����\���o���B�������Ȃ���A�����Ƃ����̐\���o��f�����B���ɒ��N�͖k���́u��ؐl�v�̏��������͕̂s���_�Ȏ����ƍl�����ƌ����Ă���B�@ |
�����{�R�̌R�]��
���R�̎Q����A���N��s�ł���Γc�O���E���c�����E��J�g�p�A�Ȃ�тɏG�g�̏�g�E���c�F����́A����ɏ������ĂсA�R�]����J�����B
���̕]��Łu���N���̓�����̉����v�u�G�g�̒��N����̒��~�v�A����2���G�g�ɐi�����邱�Ƃ����܂����B
���c�F���́A���邩��k��1���ȓ��̋����ɍԂ�z���A����̎���ɗ͂𒍂����Ƃ��āB�����������s���͖��R�̋~���Ȃǂ��肦�Ȃ��Ǝ咣���A����ɖ߂��Ă��܂����B
�Ȃ��A���������̓I�����J�C�ɍs���Ă������߁A���̕]��ɎQ���ł��Ȃ������B��ɐΓc�O����͐�����i�����ہA���R��1�Ƃ��Ă��̌��������Ă���B
8��22���A�����̐킢�B
8��29���A���щY�C��B�@ |
�����{�R�E���R�x��
8��29���A���Ҍh�Ə����s���Ƃ̊Ԃ�50���Ԃ̋x�킪���ꂽ�B�������N�͂��̋x��ɔ��������A�@�卑�ł��閾�ɉ�����ꂽ�B�����A���̗��@���͂��̊��Ԓ��ɓ��{�R�̟r�ō���i�߂Ă���B�@ |
���ɒ��ق̐킢
�����R�Ƃ��ė_�ꍂ�����@���̌R�͑�����4��3,000�l�ŁA���Ƃ̎q���̎����ɂ���č\������Ă���A���s����̌R�Ƃ��Ēm���Ă����B1592�N(���\���N)12��23���A���]��n���Ē��N�ɓ���A����Ɍ��������B
�����\2�N(1593�N)�����A�����R�́A�g����x�O�̏����ɔh�����A�����삪�u�a�������A�g�҂��₪�ē������邱�Ƃ������R�ɓ`�����B����Ɋ������3���A�|���g���q��g��20���������ɔh���B�������|����͕����ɐ����߂�ɂ����B�ꕔ���˔j�ɐ����������ɓ`����B�����A�����ɂ́A�ق��@�`�q�A���Y���M�A�L�n���M�A�呺��O�A�ܓ�������z��15000���قǂł������B
1��6�����퓬���J�n���ꂽ�B���R�͕��T�@(�t�����L)�C�A�叫�R�C�A���̖C�Ȃǂ̉Ί�̍U���ɂ���ĕ����̊O�s����͔j���A�����R�͓�����Ă����B�������A���{�R�̓S�C�Ί킪�\�z�O�̑����ł��������߁A�����R�͖����U�߂ɂ�鎩�R�̋]�����l�����A��͂̈ꕔ�������āA�����R�̑ދp�𑣂��A�nj���Ƃ��邱�Ƃɂ����B
1��7����A�����R�͒E�o�����B�����A���R�͐��R3000�l�Œnj����J�n�A���{�R��360�]�������ꂽ(�ِ�����)�B���̂Ƃ��A���B�ɂ�����F�`���͖��R�P���ɍۂ��A�����R�̎��e�������ɑދp����Ƃ������Ԃ�Ƃ���(�����)�B�����R�͗��_�������A����ɑދp�𑱂��A����R��ɍݐw���鍕�c�����Ɍ}����ꂽ�B��c�ł́A�ЂƂ܂��J��܂œP�ނ��A����ɏW�����邱�ƂƂ����B����ł͐Γc�O����͘U�����A�����엲�i��Z�ԑ��͑O�i�}���푈���������B���ƕs���̂��߁A�吨���}�����I�B
1��18���A���R�A�J�����B
1��25���A���R�Ɠ��{�̐ˌ�R���ڐG�B��26�������A���ԏ@�Α�2000�����i�R�J�n�����B�ߑO6�����11���܂ł̌�����o�āA�ʕ�����F�쑽�G�Ƃ��w��������{�R4��������x�O�̕ɒ��قŌ}���A��匈��ƂȂ���{�R����������(�ɒ��ق̐킢)�B���R�̑��i�ߊ��E���@���͂��̐킢�Ŋ낤���������ɐ��O�܂Œǂ����܂ꂽ���A����܂őދp�����B
2��12���A�K�B�̐킢�B���N�R��1���ڂ̍U�������ނ������̂́A���ɂ͓��{�R�̍U�����뜜���ď��������A���B�܂őދp�����B�����^�ɂ��A���ɂ͂��̐퓬��A���{���̎��̂��W�߁A�u���̂�ėт̖̂��������Ɋ|�������A���̕�����͂炵���v�Ƃ����B�@ |
�����{�E���u�a����
���\2�N(1593�N)3���A����̓��{�R�̐H�������ɂł��������R�̑q�ɂR�ɏĂ���A���������{�R�͍u�a�����J�n����B������Ė��R���Ăђ��Ҍh��h���A�����E�����̎O�҂ʼn�k���s���A4���Ɏ��̏����ō��ӂ����B
���{�R�͒��N���q�Ƃ��̏]�҂�Ԋ҂���
���{�R�͊��R�܂Ō��
���R�͊J��܂Ō��
��������{�Ɏg�߂�h������
�����ł͑v�����E���Ҍh�����d���A�����̎ӗp���Ə���т��c�邩��̒��g�ɋU�����ē��{�ɔh�����邱�Ƃɂ����B����A���{�̏G�g�ɂ́A���̒��g�́u�̂ь��v��`����҂��ƕ���Ă����B
4��18���A���ӏ����Ɋ�Â��A���{�R�͊�����o�āA���̒��g�E���Ҍh�E���N�̓q�ƂƂ��Ɋ��R�܂Ō�ނ����B5��8���A�����s���ƐΓc�O���E���c�����E��J�g�p�̎O��s�͖����g�ƂƂ��ɓ��{�֏o���B
5��15���A�����g�͖��쉮�ŏG�g�Ɖ�B�G�g�͈ȉ���7�̏���������B
���̍c����V�c�̔܂Ƃ��đ��邱��
�����f�Ղ������邱��
���{�Ɩ��A�o���̑�b���������Ƃ肩�킷����
���N�����̂�����̎l������{�Ɋ������A���̎l������ъ���N�ɕԊ҂��邱��
���N���q����щƘV��1�A2���A���{�ɐl���Ƃ��č����o������
�ߗ��ɂ������N���q2�l�͒��Ҍh��ʂ��Ē��N�ɕԊ҂��邱��
���N�̏d�b�����ɁA������{�ɔw���Ȃ����Ƃ��邱��
�Γc�E������́A�{���ɂ͏��������ĕ���悢�Ɛi���B6��28���ɏ����s���̉Ɛb�����@����g�Ƃ��Ėk���֔h�����邱�ƂƂ����B7�����{�A���R�ɖ߂��Ă������g�ɒ��N�̓q�������n���ꂽ�B
����A���������������@���͏G�g�́u�[���\�v�������Ă������A���̑v�����͏G�g�̍~���������������K�v���Ǝ咣�B�����s���́u�֔��~�\�v���U�삵�ē����ɑ����A�����͗�1594�N(���\3�N)��12���ɖk���ɓ��������B�@ |
����W�B��̐킢�Ɛ���P��
����A���̍��A�G�g�����N�암�̎x�z�m�ۂ͕K�{�Ƃ��āA�W�B��U���𖽂���B�퓬�v��42491�l�̐w�e�ł������A�ߗׂɂ͊��R����̗A�������̎���ɓ����镔�������݂����B�����͊��������ێ������܂ܓ��{�{�y����̐V��͂𓊓�����v��ł������B
���{�R��6��21������29���Ɋ|���͂�8��(�퓬�J�n����3��)�ōU������(��W�B�鍇��)�B6���ɂ͖��R���쉺���Ă���A�������N�R�͋~����v���������u�����ɂ��āA�킢�������̂��Ǎ�v�Ƃ̕ԓ����B���{�R�͐W�B����U������ƍX�ɑS�������M���e�n�̏���U���A���R���i�o����Ɛ�����P�����x����ɓ������B
7��5���ɂ͋���A7���ɂ͒J��i�o���A���R�y�ђ��N�R�����j�����B�������A�쌴�̎�肪�����ƌ����9���ɂ͐W�B��֓P�ނ����B �Ȍ�A���{�R�͍P�v�I�Ȏx�z�ƍݐw�ׂ̈ɒ��N�����암�̊e�n�ɋ��_�ƂȂ��̒z����J�n���A�z�邪�n�܂�Ɩh�q�͂̎ア�W�B��͖��p�Ƃ���j�p���ꂽ�B�@ |
|
��������ƍďo���@ |
�G�g�͖��~���Ƃ������A������͓��{�~���Ƃ������Ă����B����͓����o���̍u�a�S���҂����ւɍu�a���s�����߂ɂ��ꂼ��U��̕������ׂł���B
���ǁA���{�̌��S���҂́u�֔��~�\�v�Ƃ����U��̍~���������쐬���A�����ɂ͏G�g�̘a�������́u�����f�Ղ̍ĊJ�v�Ƃ��������݂̂ł���Ɠ`����ꂽ�B�u�G�g�̍~���v���m�F�������͒��c�̌��ʁu���͋������v�͋����Ȃ��v(���̍����̐����ɓ��鎖�͔F�߂邪�����f�Ղ͔F�߂Ȃ�)�ƌ��߁A�G�g�ɑ����{����(������)�̏̍��Ƌ���������邽�ߓ��{�Ɏg�߂�h�������B���\5�N(1596�N)9���A�G�g�͗����������g�߂Ɖy���B�����̗v�����S��������Ă��Ȃ��̂�m�范�{�B�g�҂�ǂ��Ԃ����N�ւ̍ēx�o�������肵���B�Ȃ����Ҍh�͋A����A�����{�ɂ���ď��Y�����B
���n�k�Ɖ���
�Ȃ��A��1596�N9��1��(����[7��9��)�A�c���ɗ\�n�k�������BM 7.0�A��t���{����m����A�߉������{���|��B3�����9��4���Ɍc���L��n�k�������BM 7.0〜7.8�A����710�l�A�n�k�ƒÔg�ɂ���ĉZ�����Ƌv������2�̓������Ƃ����B
������9��5���ߑO0�����A�c�������n�k(�c��������n�k)�������BM 7.0〜7.1�ŁA���s���Ŏ��ҍ��v1,000�l�ȏ�B������̓V���Ί_�A���L���̑啧���|��B�]�k�����N�t�܂ő����B�����̑傫�Ȓn�k�������������ƂŌc���ɉ������ꂽ(���̂��߁A�n�k�́u�c���v�������Ă���)�B
�Ȃ��A���̒n�k���ȑO�A�����������Γc�O���E�����s����ɑi�����ē��{�ŋސT���Ă������A�����͒n�k���N�����ۂɏG�g�̌��삯���ĕٖ����s���A�ސT��������A�c���̖��ɂ��o�w���邱�ƂƂȂ����B�@ |
|
���c���̖��@ |
   �@
�@
|
�a����������Ɛ��������ɓ����߂��������A�c��2�N(1597�N)�i�U��킪�J�n�����B���ڕW�͏����ɔ�����ꂽ2��21���t����ɂ��ƁA�u�S�������c�����������s���A����ɒ������₻�̑��ɂ��i�U����B�v�Ƃ������̂ŁA���ڕW�̒B����͎d�u���̏�(�`��)��z�邵�A�ݔԂ̏��(��Ƃ��ċ�B�̑喼)���߂āA���̏����͋A������Ƃ����v�悪��߂�ꂽ�B
��B�E�l���E�������𒆐S�ɕҐ����ꂽ����14���l����R���͒����Δn�C����n�芘�R�Y���o�ĔC�n���������B�@ |
���S�����E�������|����
�������N�����ł͊��R�ɏW�����̓��{�R�N���R�ōU������悤�ɖ��߂������A�x�d�Ȃ閽�ߋ��ۂ̂��߂ɎO�����R�����g�̗��w�b�͔�Ƃ���A��C�Ɍ��ς��C�����ꂽ�B
���N���R�������p�������ς��U�����a�������A����7���ɏo�����s�����B�������U���͎��s���A�A�H�ɋ��ϓ����̎�����Œ┑���Ă����B���̏������{�R�͐�������U��������𗧂āA7��16���C�ォ��͓������ՁE�e������E�����Ö����̐��R���U�����A���ォ������Ë`�O�E�����s�������U�������B���̎�����C��͓��{�R�̑叟�ƂȂ蒩�N���R�̊����w�����A���ρA�����Q�A����펀�����A�R�D�̂قƂ�ǂ��������ĉ�œI�Ō���^�����B
�C�ォ�璩�N���R�̐��͂���|�������{�R�́A��8���A�E�R�ƍ��R(�y�ѐ��R)�̓���ɕʂ�c��������S�����Ɍ������Đi�����J�n�����B���閾�E���N�R�͓����t�߂̉��ΎR��Ɠ쌴��Ŏ����ł߂����A���{�̉E�R��8��16�����ΎR���(���ΎR��̐킢)�A���R�y�я㗤�������R������8��12������쌴����U��(�쌴��̐킢)�A�����܂������ח������S�B��ɔ���ƁA��������閾�R�͓������A8��19��������̂���B�쌴�ƑS�B�̊ח��ɂ�薾�E���N�R�̑S�������ʂɂ�����g�D�I�h�q�͂͊��������B
���{�̏����͑S�B�ŌR�c���s���A�E�R�A���R�A���R�A���R�ɕʂꏔ���̐i���H�Ɛ�������n���̕��S���s���A����S�������ߑS�����E���������u���Ԃɐ�̂����B�k�サ�����{�R�Ɉꎞ�͊���̕������l�������R�ł��������A���Ǔ쉺���Ă̍R������ӂ��A9��7���ɐ挭���̖����E�ƍ��c�����̕������������Ƌ��E���̓����t�߂��l�R�ő�����ƂȂ�A�ї��G�����}��~�����Ė��R�𐅌��Ɍ�ނ�����(�l�R�̐킢)�B
����C��ł́A���N���R�̎c���͑����O�����R�����g�ɕԂ�炢�����w�b�������đS���E���c�ɋ����Ă����B���w�b�́A�쌴�邩��쉺������A�Ăя�D���Đ��i���Ă������{���R���A9��17�����C���Ō}�������A����ɒɑł�^����Ƒ��₩�ɑދp�����B���̖��C��̗����A���{���R�͒��N���R�̋������S���E���c���̂���B����ɁA���{�̗��R�ɂ��S�������݂����������ƒ��N���R�͋��_�������A���w�b���S�����k�[�܂Ō�ނ��A���{���R�͑S�������݂܂Ői�o�����B
�l�R�ɓ��{�R���i�o����ƁA���E���N�R�͊��]����h�q���Ƃ��Ď����ł߂����A����ł̓p�j�b�N�ƂȂ�s�������S���J�n���鎖�ԂɊׂ��Ă����B���̎��A���N�ł͊�����ێ��ł����ԂɂȂ��A���b�����͂���ɓs���o�Ĕ��邱�Ƃ������B
�������ē��{�R�͏G�g�̍��ڕW�ʂ�S�����E�������𐬔s���A����ɋ��E���܂Ői�o����ƁA�c��������S�����̉��ݕ��֓P�����A���\�̖��̍ۂɒz���ꂽ��s�Q��̊O����(���͉U�R���琼�͏��V�Ɏ���͈�)�ɁA�v��ʂ�V���ȏ�s�Q��z���čP�v�̓y����ڎw�����B��s�Q�̊�����͊e��̍ݔԌR�ȊO�͋A������\��ŁA���c��3�N(1598�N)���͍U�����s��Ȃ����j�𗧂ĂĂ����B�@ |
���U�R���
�z����}�����{�R�ɑ��āA���R�ƒ��N�R�͍U����������B12��22���A�������O�̉U�R�`��(���{����s)�𖾁E���N�A���R5��6,900�l���P�����A�U�����J�n���邪�A�}篓��邵�������������n�ߓ��{�R�̌����h��̑O�ɑ傫�ȑ��Q�������������ꂽ�B���̂��ߖ��E���N�A���R�͋��P���������A��͐�ɐ�ւ���B���̂Ƃ��U�R��͖������ł���A�H���������o���Ă��Ȃ��܂܂��ď��œ��{�R�͋ꋫ�Ɋׂ�B�N�����������c��3�N(1598�N)1���ɂȂ�ƉU�R��͋Q��ɂ�藎�鐡�O�܂Œǂ��߂��Ă����B�������A1��3���ї��G�����������鉇�R���������A��4���������疾�E���N�A���R���U���s������2���l�̑��Q��^���ď�������(�U�R��̐킢)�B�킢�̌�A�F�쑽�G�ƂȂ�13�l�́A���n��ˏo���Ă���U�R�E���V�E���R�̎O������R�̍���𗝗R�Ƃ��ĕ�������Ă�L�b�G�g�ɏ�\���Ă��邪�A����ɏ����s���A�@�`�q�A�����Ö��A���ԏ@�Γ��͔����A�G�g�͂��̈Ă��p������\�҂����ӂ����B���{�R�̊e��s�ł́A��̑����H���A�Ί�̑����A���Ƃ̔��~���i�߂�ꋭ�łȖh�q�̐����������Ă������B�e��s�̖h�q�̐��������ƁA��B�O����̎���̂���6��4�炠�܂�̌R���N�����̍ݔԂƂ��Đ����u���A7���̎l���O�E�����O�Ə�����G�H�́A�\��ʂ菇���A�����ė��N�ȍ~�̍Ĕh���ɔ������B�@ |
���O�H�̐킢
�G�g�͗��c��4�N(1599�N)�ɑ�R���Ĕh�����čU�����s���v��\���Ă����B�������L�b�G�g��8��18���Ɏ����B���̌�A�ܑ�V��ܕ�s�𒆐S�ɓP�ނ����肳��A�����ɒ��N����̓P���������J�n���ꂽ�B�����Ƃ��A�G�g�̎��͔铽���꒩�N�ɔh������Ă������{�R�ɂ��m�炳��Ȃ������B
9���ɓ���Ɩ��E���N�A���R�͌R���O�H�ɕ������A�U�R�A����A���V�֑��͂��������U���ɏo���B�}�������{�R�͉��ݕ��ɒz������̌��łȎ��ɏ������A��U�R��̐킢�ł́A�������������E���N�A���R�����ނ��h�q�ɐ����B
����̐킢�ł͓��ÌR7000�����ő傫�����閾�E���N�A���R���}���B���R�ʼnΖ�̔������̂�A���ÌR�̕�����p�Ȃǂɂ��A���R�������B���ÌR���叟�����B
���V������Ă����̂͏����s���ł��������A���{�R�ō����Ɉʒu���邽�߁A�V���ɔh�����ꂽ�����R������萅������̌������U�����邪�h�q�ɐ������A�悸���E���N���R���ދp�A�����Đ��R���Í����܂őދp����(���V��̐킢)�B�Ȍ�A���E���N�A���R�͏��V�`����������ɊĎ�����݂̂ƂȂ�B
���̎O�铯���U���ł́A���E���N�A���R���������������͂�11�����A�O���E�����ʂ��čő�K�͂ɒB���Ă����B�܂����Ƃ�U�����\���ɏ������Ă̂��̂ł��������A�S�Ă̍U���Ŕs�ނ����B����ɂ��A�O�H�ɕ������ꂽ���E���N�R�͗n����悤�ɋ��ɒׂ��A�l�S�͜���(���X)�ƂȂ�A�����̏����������Ƃ����B�@ |
���푈�̏I��
�U�R�A����A���V�ւ̍U����ނ������{�R�ł��������A8���ɏG�g���������Ĉȍ~�A�c���̖L�b�G��������p�����L�b�����ł́A�喼�Ԃ̌��͂��߂���Η������݉����A������͕s���Ȃ��̂ƂȂ��Ă���A���͂�ΊO�푈�𑱂���ɂ͂Ȃ������B�����ł���10��15���A�G�g�̎��͔铽���ꂽ�܂܌ܑ�V�ɂ��A�����߂����߂��ꂽ�B
10�����{�A�A�����߂���̂��������s���́A���R�̗�����綎�Ƃ̌��ɂ�薳���P�ނ̖����t���A�l������̂��ēP�ނ̏����Ɏ��|�����Ă����B�Ƃ��낪�A�Í����ɑދp���Ă������E���N���R�́A���{�R�P�ނ̓�����m��ƁA11��10���Ăя��V��̑O�m�ɕ\��C�㕕�������{���ĊC�H�P�ނ̖W�Q���s�����B�����ŏ����s���́A�����R�̒�璘�ƌ��┃���Ŗ����P�ނ̖����t���A�l������̂��邪�A���̍����{���P�ނ̓���(�G�g�̎�)�͖��E���N�����m��Ƃ���ƂȂ�A���ۂɂ͖��E���N���R�͌�ނ����ɊC�㕕�����p�������B
�����R�̒E�o���j�܂�Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɵ��삩��P�ނ��Ă������Ë`�O�A���ԏ@�A���������A����L���A�@�`�q��̏����͋~���Ɍ��������߂ɐ��R��Ґ����Đi�������B���Ë`�O�A���ԏ@��̋~���R���߂Â��̂�m��Ɩ��E���N���R�͏��V�̊C�㕕���������Č}�����s���A���R��11��18����ԁA�I���C���ɂ����ďՓ˂���B
���̘I���C��œ��Ð��R�͋�킵�����A���E���N�������R�̕����A���q���⒩�N���R�̎O�����R�����g�̗��w�b���܂ޕ����̊������펀�����B���E���N���R���o���������Ƃɂ���ď��V�̊C�㕕�������������Ƃ�m���������s���́A�C��C�������ĊC�H�E�o�ɐ��������B
����A�������ʂ̏����́A��������11��15�����납��e�����O�������Ɋ��R�Ɍ������Ă���B
11��23�����������������R���A24���ї��g���������R���A25�������s���A���Ë`�O�������R���B�������āA���{�̏o���喼�B�͒��N��ދ����ē��{�A�����A�L�b�G�g�̉���������A���N�����v��͐����Ɏ���ʂ܂܁A�G�g�̎��ɂ���ďI�������B
���̐푈�ɂ��āw���j�x�́u�L�b�G�g�ɂ�钩�N�o�����J�n����Ĉȗ�7�N�A(���ł�)�\���̏�����r�����A�S���̕��Ƃ�J�����A����(��)�Ƒ���(���N)�ɏ��Z�͖����A�����֔�(�L�b�G�g)����������Ɏ��藐�Ђ͏I�������B�v�Ƒ��]����B�@ |
���c��4�N(1599�N)�̍ďo���v��
�G�g�͌c���̖��̊J�n�̍����琔�x�̏o�����v�悵�Ă���A�U�R����̌�ɂ�6��4��]�̏����N�����̍ݔԂƂ��ċ��_�ƂȂ��s�Q�Ɏc���h�����ł߂��������A7���]�̏�����{�y�ɋA�҂����Ă����B����͏G�g���c��4�N(1599�N)�ɂ���K�͂ȌR���s�����v�悵�Ă������߂ł������B���{�R�̑��i�ߊ��ɂ͐Γc�O���╟���������C������Ă����B���̍ďo���v��Ɍ����Ē��N�����̘`��ɕ��Ƃ�ʖ�Ȃǂ������ɔ��~����悤�ɖ����Ă������A�v����{�O�ɏG�g�������������ߎ��{����邱�Ƃ͂Ȃ������B�@ |
|
�������̘a�����@ |
�a�����͓���ƍN�ɂ���ĈϔC�����Δn�̏@���ƒ��N���ǂ̊ԂŐi�߂�ꂽ�B�Ƃ͂����A���{�����ł́u����ƍN���ďo�����v�悵�A�Η����Ă��鏔�喼�����N�ɑ��荞�����Ƃ��Ă���v�Ƃ����s���ȉ\������Ă����B
���{�͒f�₵�Ă����������N�Ƃ̍��������ׂ��A���N���ɒʐM�g�̔h����Őf���A������Ē��N����͂܂����{�̓���T���̂���1604�N�ɒT���g�Ƃ��ĈҐ���Δn�ɔh���������A���Α叫�R����ƍN�͏@�`�q�ɖ����ċ��܂ŌĂъA��1605�N(�c��10�N)�㗌���ĕ�����ʼn�����B�Ґ��͓��{���̎���������Ɉڂ������ƂƉƍN�̘a���̈ӌ����m�F���A���̌㒩�N��萳���Ȏg�߂ł�������Ҏg���h������Ęa�����ʂ����ꂽ�̂́A1607�N(�c��12�N)��㏫�R����G���ɑ��Ăł������B
���͓��{�ƍ��������Ȃ��܂ܖŖS���A���ɑ����Ē������x�z����悤�ɂȂ������́A���łɓ��{����������������ߖf�Ղ͍s�����A�����ȍ��������Ƃ��Ƃ͂��Ȃ������B�@ |
|
���e���@ |
   �@
�@
|
|
�x��������6�N�ɋy�푈�́A���{�E���E���N�̎O���ɏd��ȉe�����y�ڂ����B
�@ |
�����{������ւ̉e��
���o���O��ɐ������e��
���璆�̑喼�̒n�ɑ��}���n���s���A�L�b�����̓����͂Ɗ����I�ȏW�c���������ꂽ�B���������ɂ͂��̐푈�ɉߑ�ȕ������ۂ���ꂽ�����喼���敾���A�Ɛb�c��������������u������喼���o��ȂǁA�������ĖL�b�����̊�Ղ��낤�����錋�ʂƂȂ����B
����ŁA���喼���ő�̐��������Ȃ���A��B�ւ̏o�w�~�܂�Œ��N�֏o�����Ȃ���������ƍN���B�R����͂����悤�ɂȂ����B�����喼���o���Ŕ敾��������ŁA���Ղ�Ƃꂽ���Ƃ�����ƍN����ɓV�������v���̈�ƂȂ����B
�ܑ�V�̕M���ƂȂ����ƍN�͏G�g����̘a�����ł��哱��������A�����I�Ȑ����^�c�҂ւƂ̂��オ���Ă䂭�B���̊����W�c�ƉƍN�̋}�����́A�L�b����������}�銯���W�c(��ɐΓc�O��)�Ǝ���������_���ƍN�Ƃ̑Η��ɔ��W���A�փ����̐킢�c��5�N(1600�N)�Ɏ������B�킢�Ɉ��������ƍN�͓��{�����ŕs���̒n�ʂA�c��8�N(1603�N)�ɒ����萪�Α叫�R�ɔC����꓿�얋�{��n�݂����B����ɉƍN�͑��̐w�c��19-20�N(1614-1615�N)�ŖL�b����ŖS�����邱�Ƃœ��쎁�ɂ�鍑���e�����m�������B�������đו��̍]�ˎ��オ�n�܂�B
�܂��A�o���ɎQ�������喼�����ɂ���ĘA��Ă���ꂽ��A�喼�ƌٗp�W�����肵�Ď��痈���������N�l����l�X�ȋZ�\���`����ꂽ�B ���N�l��w�҂Ƃ̊w��⏑�敶�|�ł̌𗬁A�����ē��H���嗤���̎���̐��@�A���̑����Ȃǂ�`�������Ƃœ��{�̕����ɐV���Ȉ�ʂ��������B���̈���A�����̒��N�l�ߗ�������Ŏ���ꂽ�����̘J���͂�₤���߂Ɏg������A�܂��z��Ƃ��ĊC�O�ɔ���ꂽ���Ƃ��������B
���J����̑嗤�i�o�ւ̉e��
�]�ˎ��㖖���E��������̊J���ɂ��嗤��ւ̊W���s���Ȃ��̂ƂȂ�ƁA�����̕����B���O�ؐ�����z�N�����悤�ɁA�G�g�̒��N�o�������ڂ����悤�ɂȂ�A�嗤�i�o�͖L�b�G�g�̈�u���p���s�����ƍl������̂������Ȃ����B�؍��������������ہA���㑍�������B�́u������A�����A���������ɂ���A�����̌��������ɂ݂���(�G�g���̒��N�����ɎQ�����ꂽ������E�����E�����̏������������Ă���A���N����{�̂��̂Ƃ������̖�̌����ǂ̂悤�ȋC�����ł݂��邾�낤��)�v�Ɖ̂��r�݁A�O�����������������͂���ɕԉ̂��āA�u���}��n�����N����������ȍ���(����)��܍����̂ڂ���̊�(���}�a����h�点�����\���グ�������̂��A���N�̎R�X�ɍ����|����̊ۂ�)�v�Ɖ̂��A�؍����������������Ƃ���B�@ |
�����ւ̉e��
���N�ւ̉������A�������ɍs��ꂽ�J�Ẵ{�n�C�̗��A�d�B(�l���)�̗k�����̗��̓�̔����̒����Ƃ��킹�āA�u����̎O�吪�v�ƌĂ�ł���B�w���j�x�������`�ɂ��Ɓu�J�ėp��(�{�n�C�̗�)�A��\�]���A���N�V�����S���\�]���A�d�B�V��(�k�����̗�)��S�]���v�A�w���j�x���`�ɂ́u�J�ėp��(�{�n�C�̗�)�C������S�]�݁B���~�B���N�p���C������N�C�������S�]�݁B��\���N�C�d�B�p��(�k�����̗�)�C��������O�S�݁v�Ƃ���A�����ɈႢ�͂��邪�A����̎O�吪�̒��ł����̐�����{�n�C�̗��Ɨk�����̗��Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǍ�����ɑ傫�ȕ��S�ł������ƔF������Ă������Ƃ��M����B
�����̖c��ȌR����̎x�o�y�ѐ펀�҂��o�������Ƃƍc�閜���̚��ʂ͖��̍��͂���������17���I�O���̏��^�̋��剻�ɑς���Ȃ��قǂ́A���̋}���Ȏ�̉��̏d�v�Ȍ����ƂȂ����ƍl�����Ă���B�@ |
�����N�����ւ̉e��
���ƂȂ������N�����ł͓����s�S�ɂ���Ď������������A�s�����ǂ�퍷�ʊK���A���������_���A�����ɂ�锽���A�I�N�A�y�ђ��N�R�ɂ�邻�̒����A�܂����N���������̐����ɂ��l���⏈�Y�Ȃǂ��s���A���N�Љ�̖��������o�����B
�������N�͋ɒ[�ɒ����W�������i�݊K�����ʂƉߍ��ȍ��ɂ���Ĕ_�������N�t�ɂ͕K���Q����(�u�t���v)�قǂŁA���y�̊J�����ӂ��Ă����B�܂��A���ʌo�ς������B�Ŗ��O�̐����͎�����������{�ł����Ȃǂ̉ݕ��ɂ�����������������N���O�Ƃ͕��X�����ȂǂŐH���̒��B���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�푈���J�n�����ƁA���N�E���R�E���{�R���H���̌��n���B���s�����B�H���s���Ǝ��������̂��߂ɔ_�����k���������邱�Ƃŗ����ƂȂ����B
���R�̕��Ƌ����͗������N�����������߁A���N���{�͉ߍ��ȐH�����B���s�����B���̂��ߖ��R�̗��D�ƍ��킹�ē��{�R���N�U���Ă��Ȃ����������r�p���Đl�����������Ă���B�܂����N�R��薾�R�ɗD��I�ɐH���������s��ꂽ���Ƃ���A���N�R�̐�Ӓቺ�͏��Ȃ���ʂ��̂��������B���N�ɒ��Ԃ������R�ɂ�钩�N���O�ɑ��閳�����ȗ��D�Ȃǂ����s���A���N�̖��O�͓��{����Ԃ̐N���҂Ƃ��Ȃ�����A���R�����̐N���҂ł���Ƃ��đ��B
�܂����{�R�̐N�����͂��܂�ƁA���ɐg�����ʂɋꂵ���N�̉��w���O�͍����ɏ悶�Ċ�����g�����������ނ̏����q�ɂ��Ă��������B�܂����{�R�͋`���̒�R�Ɏ���Ă������߁A�Z���̋s�E�⑺�̏Ă������Ȃǂ��s�����Ƃ��������B����̏ؖ��Ƃ��Ă͂Ȃ������s��ꂽ���A����͌c���̖��Ȍ�̕s�����O���Ꝅ�ƔF�����ē��������ۂ̘b�ł���A�����͓��{�̍����퓯�l�ɔ�퓬���ł��閯�O�͕ی�̑Ώۂł���E�C�͋֎~����Ă����B�����A���ə������Ɍ��Ă�ꂽ���{�R���ދL�O��̖k�֑号��ɂ͉����̐퓬�Ŏa�E�������{�����獶��825������Ē��N���֑������L�^���c���Ă���B�܂��A���{���̎�ɏ܋����|�������ߓs�s���Œ��N�R�E���R�ɂ��U����̋]���ƂȂ������N�̖��̎����̂����o�����Ɠ`������B
���N�R�ɓ��~���߂���ꂽ���{�̏���(�~�`)�͓��������ɏ��Y����Ă������A�~�`�𗘗p���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���1591�N10���ɍ~�`������ɎE�������ւ��閽�߂��o���ꂽ�B�Ȍ�A�~�`�̂����C�p�⌕�p�Ȃǂ̋Z�\��L����҂͌P���s�Ă�R�펛�ɔz������A�~�`����̋Z�\�K�����}��ꂽ�B����ɂ����{�̉Γ�e�̋Z�p�����N�ɓ`��邱�ƂƂȂ����B�܂�����Z�\�̂Ȃ��~�`�͖k���̍����x�����␅�R�̑D�̑�����Ƃ��ꂽ�B�~�`�̒��ɂ͒��N�����ɒ����𐾂��ē��{�R�Ɛ키�Ȃǂ��āA���N��������D������Ē��N�ɒ蒅����҂������B
����Ȍ�A���N�ł͓��{�ɑ���G�ӂ����܂�A���a�Ȗf�ՊW��]�ޑΔn�̏@�������N�����ɋ����x������A���{�g�߂̏㋞�͋ւ����A�f�ՂɖK�ꂽ���{�l�����R�ɐ݂���ꂽ�`�قɍs���𐧌����ꂽ�B ����A���N�̗��NJK�w(�x�z�w)�̊Ԃł͖��̉��R�̂������ɂ�蒩�N�͖ŖS��Ƃꂽ�̂��Ƃ����ӎ�(�u�đ��V���v)����������A���ւ̉��`���d������v�z���L�܂�A�����Ƃ��Ă̗��ꂪ�����Ȃ����B����͒����Ƃ̊Ԃł̒��N�O���̐j�H�ɑ���ȉe����^���邱�ƂƂȂ����B
�܂��A�����ʂł����N�����ɑ���ȉe���������炵���B���h�q�����\�E�c���̖��̓��{�R�ɂ���Ē��N�����ɂ������炳��A�L���`���̊؍��E���N�����̑b��z�����B�܂��R���ʂł́A�����̉Ί�̐����E�^�p�Z�p�����{�l����`���A�����ނɂ��Ă����{�������^�Ƃ����`�����̔h��������ꂽ�B���݂ł������̏�s�Ղ����N�����e�n�Ɏc������{�l�ɂ�铝���̑��Ղ��c���Ă���B���\�E�c���̖��͌��݂̒��N��������(���N�����`�l�����a���A��ؖ���)�ɂ����锽������̌��_�Ƃ��ꔽ������ł��܂��ŏ��ɒ��N�o�����������鎖�������Ƃ����B�@ |
�����N�ƌ���E���ւ̕���
���N�Ɩ������\�E�c���̖��ɂ���č��͂�敾������ƁA���^���̃k���n�`���䓪���A1616�N�܂łɖ�����̓Ɨ����A�A�C�V����(aisin gurun, �����B���)�����������B1619�N�̖��ƃA�C�V�����̐푈�ł���T���t�̐킢�ŁA���͖��ɏ�������B���N�͉��R�𖾂ɑ����Ă������A���ɍ~�����u���N�͐키�ӎu�͖����A���̋����I�ȗv���ɂ���ĉ��R�𑗂����v�ƕٖ������B�k���n�`�͂���������A����͒��N�N�U���s��Ȃ������B���������̌�A���N�ŃN�[�f�^�[���N���A�����E�e��������Ƃ�悤�ɂȂ�B1624�N�̐m�c�ɑ��闛适�̔������N���A�����������ꂽ���A����ɓ��������t�҂����N�N�U��i���A�z���^�C�W��1627�N�ɒ��N�ɐN�U����(���K�ӗ�)�B����R������ɓ��B����ƁA�m�c�͍~�����A������Z�A���N���Ƃ���Z�퍑�Ƃ��Ă̖���A�������N�͉�����l���Ƃ��č����o�����ƂȂǂ����ӂ��ꂽ�B�������A���N�ɂ͔������������c�����B
1636�N�Ɍ�������ƍ�����ύX���A���N�ɑ��Đ��ւ̕��]�ƒ��v�A�y�і��֔h�����镺3����v�����Ă����ۂɒ��N�͂����f��A����12���̌R�Œ��N�ɐN������(���q�ӗ�)�B���N����45���ō~�����A���N�͈Ȍ�A���̑����ƂȂ����B�m�c�̓z���^�C�W�ɑ��O���@���̗�����A���c������F���鐾��������(�吴�c�������)�B���ւ̕����͓��{�������푈�Ő��ɏ������A���N�����̍����̐����痣�E����1895�N�܂ő������B�@
�@ |
|
���G�g�̒��N�o���E����1 |
   �@
�@
|
�ŋ߂̊؍��ŁA�����Ƃ������Ă�����{�̐l���̑�\�Ƃ����A�L�b�G�g���������܂��B
���R�́A���\�A�c���̖�(�Ԃ�낭�A�������傤�̂���)�Œ��N�����ɍU�ߍ�����Ȃ̂������ł��B
����A���̏o���ɍۂ��A���{�ƒ��N�����̊C���Ő�������w�b�́A�܂��Ƀq�[���[�Ƃ���Ă��邻���ł��B
�ނ�̌������ɂ��ƁA���w�b�̐킢�ɂ���āA���{�͊C�������A���N�����ւ̕⋋�H��f���ꂽ���{�́A��������̔s�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ����Ȃ̂������ł��B
�܂��A�؍��l�ɂƂ��Ă͗��j�̓t�@���^�W�[�ł�����A�����u�v�����݂����v�C�������킩��Ȃ��ł�����܂���B
����ǁA�����W�͂܂�ňقȂ�܂��B
���w�b�ɂ��Ă����A�Ȃ�قǒ��N�̊C���Ƃ��ĕ��\��(1592)�N8��29���Ɋ��R�`���̂��Ă������{�R�ɐ킢��ł��܂����A�����Ȃ��s�ނ��Ă��܂��B
�܂��A�c��3(1598)�N)�N11��18���̘I���C��(���傤��������)�ł́A�����ƒ��N�̘A���R�̎w��������Ȃ���A���{�R�̈��|�I�Ȑ�͂̑O�ɁA�펀���Ă��܂��B
���w�b�ɂ���āA���{���C��⋋�H��f���ꂽ�Ƃ��������́A�ǂ��ɂ��Ȃ��̂ł��B
���������A�G�g�̒��N�o���ɂ��Ă��A����ƕΌ����܂���Ƃ����Ă��܂��B
�퍑�����G�g��`�������j�����ɂ����Ă��A���������G�g�̒��N�o�����u�Ȃ��s�Ȃ�ꂽ���v�ɂ��āA������Ɠ��ݍ���ŏ����Ă�����̂͂����ւȂ��B
���������́A�G�g�̒��N�o���́A
���G�g������Ă������߂ɋN�������킢�������A
���G�g�̐�����`���Ђ��N�����g����Ȓ��N�����̐킢�ł������A
���킢���D�ސ퍑���m�c�N�A�x�߂ɒǂ������E���Đ������炷���߂̐킢������
�ȂǂƁA�قƂ�LjӖ��s���̉�����Ȃ���Ă���悤�ł��B
�܂��ɁA�����ĐX�������A�ł��B
���������A���ɏG�g�������ł������Ƃ��Ă��A�����̓��{�́A�]�˓��{���܂߂āA�e�˂����ꂼ��Ɨ��������Ƃ��c��ł����̂ł��B
����W�W�C�̐��������ŁA�喇���͂����Ē��N�܂Ńm�R�m�R�o�Ă������o�J�ȑ喼�́A�S���ǂ��ɂ����܂���B
�G�g�̐����u�����������Ƃ�������ɂ��Ă��A�M������G�g�Ƒ����̐��́A�_�Əd���Ƃ����������ʎw�������Ȃ苭�������̐��ł���A�̒n�����炦�Ȃ��Ă��A���ꂼ��̑喼�́A���Ƃɂ��ݕ��o�ςɂ���Ă��Ȃ�̕x���~�ςł����킯�ł��B
���������܂����Ƃ͂悭���������̂ŁA�H���ɍ���Ȃ��A�����ɍ���Ȃ��L���Ȑ����i�ł��Ă���̂ɁA�����āA�푈�ȂǁA�N���D���D��ōs�����̂ł͂���܂���B
�ł́A�Ȃ��G�g�͒��N�o�����s�Ȃ��A���̑喼�������A����ɒǏ]�����̂������ƂȂ�܂��B
���́A���̂��Ƃ��l����ɂ́A���{���������̎����������l���Ă������͂łĂ��܂���B
���������Ȃ��A�G�g�̎���ɓ��{���ꍑ�ɂ܂Ƃ܂����̂��A�����Ē��N�o��������Ɏ������w�i�ɂ͉����������̂��B
���͂����ɂ́A�����̃A�W�A��Ƃ������ې������傫���e�����Ă����̂ł��B
�����Ă����������̓��O�̎���𗝉��������炱���A���k�̑喼�����܂ł����A�G�g�̒��N�o���ɑO�����ɋ��͂��A�����o���Ă���̂ł��B
���������A��x�ɂ킽��G�g�̒��N�o��(���\�A�c���̖�)�Ƃ����̂́A16���I�ɂ����铌�A�W�A�ł̍ő�̐킢�ł��B
���{����͖�16���̑�R�����N�����ɑ��荞�܂ꂽ���A���N�Ɩ����̘A���R�́A���25���̑�R�ł��B
�V�������ڂ̐킢�Ƃ�����փ����̐킢�ɂ��Ă��A���R7���A���R8���̌��˂ł�����A�����ɒ��N�o���̋K�͂��傫�����������킩��܂��B
���̎���A���E�S�̂����n���A�܂��ɃX�y�C���������A���E�𐧂�������ł��B
���E��8���́A�X�y�C���̐A���n�ƂȂ��Ă��܂����B
���̃X�y�C���́A�����n��ł́A���\��(���܂̃t�B���s��)�ɁA���A�W�A�n��S�̂̐헪�����{�S�ł��鑍�{��u���Ă��܂����B
�����ĐM���A�G�g�̎���A�X�y�C���ɂ���Ă܂���������Ă��Ȃ������̂́A�����ł́A�����Ɠ��{�����ƂȂ��Ă����̂ł��B
���̃X�y�C�����A���{�ɍŏ��ɂ���Ă����̂́A�V��18(1549)�N�̂��Ƃł��B
���{�ł́A�鋳�t�̃t�����V�X�R�U�r�G���̗����Ƃ��ė��j�ɋL�^����Ă��܂��B
�����̃X�y�C���鋳�t�Ƃ����̂́A�\�����̖����̓L���X�g���̓`���ł����A���ł͗��h�ȌR���g�D�����A�m���R�c�ł��B
���ۂ̃L���X�g���̓`���Ƃ͈قȂ�A���ꂼ��̍����Ɏ�����₷�����Ȓ��q�̗ǂ����Ƃ������ĉ��@�����A�����������v����āA�R���𑗂荞�݁A�l���̎E�C�����̋��D�A�Ђ��Ă͐A���n��̂����Ă����̂ł��B
���{�������ɖ������Ă�������̐퍑�喼�����́A�ŏ��́A�鋳�t�����ɂ��Ă��A�����̂��̂߂��炵����������܂���B
�U�r�G���́A���������̑喼�ɏ�����A�喼�������L���X�g���̐M�҂ɂȂ���������āA�`���t��������������Ă��܂����B
�Ƃ��낪�B��A���{�����̍��X�ƈ���Ă����̂́A�ނ炪�������S�C�Ƃ���������A���{�l�͂܂������܂ɃR�s�[���A�����ʎY���Ă��܂������Ƃł��B
�C�����A���{�̓S�C�������́A�Ȃ�ƁA���E�S�̂̔������߂锜��Ȑ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�鋳�t�������A�������ɂ���ɂ͋������l�q�ŁA�C�G�Y�X��̃h���E���h���S�A�t�����V�X�R��̃t���C�E���C�X�E�\�e���炪�A�X�y�C�������ɑ������㏑�ɂ��A���̂��Ƃɂ��Ă͖��m�ȋL�q������܂��B�@ |
�X�y�C�������É��A�É�����{�̌N��Ƃ��邱�Ƃ͖]�܂������Ƃł����A���{�͏Z���������A��s�����łŁA�R���̗͂ɂ��N���͍���ł��B
����ĕ������`�������������āA���{�l���É��ɉx��Őb������悤�Ɏd�����邵������܂���B�@ |
�Z�����������Ȃ�A��Ă�C���h�̕����͂邩�ɏZ�����������킯�ŁA��ǂ̌��ł����A���{�̕���́A�A�W�A�A���[���b�p�̏�ǂɂ͓G���܂���B
�ɂ�������炸�A�ނ炪�u���{�͏Z���������A��s�����łŁA�R���̗͂ɂ��N���͍���v�Ə����Ă���̂́A�P���ɁA�S�C�̐������|�I�ŁA�ƂĂ��R���͂œ��{�ɂ͓G��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
������A�u�������`�������������āA���{�l���É��ɉx��Őb������悤�Ɏd������v�Ƃ����̂ł��B
�������ăX�y�C���́A���{�ł̕z�������ɁA�܂����͂��Ă����܂��B
����A������܂��̂��Ƃł����A�X�y�C���̑_���͓��{�����ł͂���܂���B
���ׂ̖������A�X�y�C���͐A���n����_���Ă��܂��B
������́A�S�C���R�s�[����悤�Ȕ\�͂͂Ȃ��A�P�ɐl�C��p�A�܂�l�̐������������ł��B
�����A�嗤�͍L���A���̒����ɂ͎�Ԃ�������B
���Ȃ݂ɓ����̃X�y�C���ɂƂ��āA���N�����͑ΏۊO�ł��B
���N�����́A�����̎x�z���������킯�ł�����A����������Β��N�����́A�����I�Ɏ�ɓ���B
���ꂾ���̂��Ƃł��B
���Ă��̃X�y�C���ł����A�������U������ɂ�����A�����A���E�ő�̕���(�Η�)�������Ă������{�ɁA�ꏏ�ɖ�����D��Ȃ����A�Ǝ��������Ă��܂��B
�Ƃ��낪���{�ɂ́A�܂�ł���Ȃ��ƂɊS���Ȃ��B
���������M���A�G�g�Ƒ����퍑�̐킢�́A���{�����̐퍑�̐��������ɏI��点�A�����Ɏ��������邩�ɂ������̂ł��B
�M���́A��b�R���U�߂���A�{�莛���U�߂���ƁA�܂�ő�Z�V�̖����ł��邩�̂悤�ɕ`����邱�Ƃ������ł����A���ۂɂ́A���X�ƍs�Ȃ����M���̐킢�̖ړI�́A����������헐�̐����I��点�邱�Ƃɐs�����B
�����炱���A�����̐l�X���M���ɏ]�����Ƃ������Ƃ��A�ŋ߂ɂȂ��Ĕ������ꂽ�e�핶������A����ɂ����炩�ɂ���Ă��Ă��܂��B
���̂��Ƃ͏G�g�����l�ŁA�Ȃ��G�g���l�C�����������Ƃ����A�S���̑�\������S���̋C�������킩��B
�헐�ɂ���Ĕ_�n���r����邱�Ƃ𑽂��̖��O�������Ă��邱�Ƃ��A�����Ƃ킩���Ă���Ă���l�����������炱���A�G�g�l�C�͂������̂ł��B
�v����ɁA�����̓��{�̎{���҂ɂƂ��ẮA���{��������Ǝ����̉����������g���������킯�ŁA�킴�킴���܂ŏo�����čs�����R�͂ЂƂ��Ȃ��B
�Ƃ��낪�A���{���G�g�ɂ���ē��ꂳ��A�Ȃ�Ƃ����̎����Ƒ���������ƁA���x�́A�Ζ����ւ̑傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA�X�y�C�������{�ɍU�߂ė����Ƃ��Ă��A�ނ�͊C��n���Ă���Ă��܂��B
�X�y�C���Ƃ̒��ڑΌ��Ȃ�A�C��n���Ă���ė���X�y�C���l�́A���̂������炢���Ώ����ł���A�ΉA���͂Ƃ��ɓ��{�̕������|�I�ɏ�ʂł��B
�]���āA���{���X�y�C���ɍU�������S�z�͂܂�łȂ��B
�Ƃ��낪�A�X�y�C����������A���n�Ƃ��Ďx�z���ɂ����߂�ƁA�l�q������Ă��܂��B
�����ɐ������̓S�C����{�������Ă���Ƃ͂����A�X�y�C���Ɏx�z���ꂽ���������A���̗͂Ƀ��m�����킹�ē��{�ɍU�ߍ���ł�����A����͂����ւ�Ȃ��ƂɂȂ�B
�����̍ė��ł��B
����͋��قł��B
�ƂȂ�A���̋��ق���菜���ɂ́A�X�y�C��������ɖ�������{�̎x�z���ɒu�������Ȃ��B
�ΉA���͂ɗD�ꂽ���{�ɂ́A����͏\���\�Ȃ��Ƃ����A���ꖾ���܂ōU�ߍ��ނ��Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ��Ă��A�n���w�I�ɒ��N��������{�Ɩ��̊ɏՒn�тƂ��Ă������ƂŁA���{�ւ̐N���A�N����h�����Ƃ��ł���B
���̂��Ƃ́A���V�A�̓쉺�����h�����߂ɁA�������{���s�Ȃ�������ƁA�����̏��������Ă��邱�Ƃ�����킵�܂��B
����ɂ����A�G�g�́A���łɂ��̎��_�ŃX�y�C���̌ւ閳�G�͑����A�p���Ƃ̐푈�ɔj��X�y�C�����̂��C�R�͂�啝�ɒቺ�����Ă��邱�Ƃ�m���Ă��܂��B
�ł�����A�X�y�C�����C�R�͂œ��{�Ɛ�[��������\���́A�܂�����܂���B
����A���������헐�̐����I��点�悤�Ƃ���G�g�́A�S���œ��������{���A���{�̏������畐�͂�D���Ă��܂��B
����͂܂�A���{�ɑ����̐���z�����߂ɕK�v�Ȃ��Ƃł������킯�ł����A�����ɂ��̂��Ƃ́A�������{�������N�N�̓�ɂ������Ƃ��́A���{�̐�͂�傫���킮���Ƃɂ��Ȃ����Ă��܂��̂ł��B
�Ȃ�A���͂��܂��L�x�Ȃ����ɁA�]���͂�p���āA���N�o�����s�Ȃ��A���N���疾���܂ł���{�̎x�z���ɒu���Ă��܂����ƁB
����͉䂪���̈��S�ۏ��A�K�v�Ȃ��ƁA�ł������킯�ł��B
�������ďG�g�́A���\�̖�(1592〜1593)�A�c���̖�(1597〜1598)�Ɠ�x�ɂ킽�钩�N�o�����s�Ȃ��̂ł����A�����ɏG�g�́A�X�y�C���Ƃ��ʊ��Ȑ����I�����s�Ȃ��Ă��܂��B
�����������Ƃ����ƁA�X�y�C���ɑ��āA���{�ɐb���Ƃ��Ă̗���Ƃ�I�Ɛ\���o���̂ł��B
�ŏ��ɂ�����s�Ȃ����̂��A���\�̖��ɐ旧��1�N�O�A�V��18(1591)�N9���̂��Ƃł��B
�G�g�̓X�y�C���̓����n��̋��_�ł��郋�\��(�t�B���s��)���{�ɁA���c�����Y��h�����A�u�X�y�C���̃��\�����{�́A���{�ɓ��v����v�Ƃ̍�������n���܂��B
���E�𐧂����鍑�̃X�y�C���ɑ��A�^���ʂ��瓰�X�Ɓu���������Đb���̗���Ƃ��ē��v����v�ȂǂƂ�����̂́A�����炭�A���E�L���Ƃ����ǂ��A���{���炢�Ȃ��̂ł��B
�܂��ɁA�C�F�s��Ƃ����ׂ��ł��B
����X�y�C�����{�ɂ��Ă݂�ƁA����͂���߂ĕ������������Ƃ�����ǁA���łɖ��G�͑������ł��A�C�R�͂�啝�ɒቺ�����Ă��錻��ɂ����ẮA���{�ɑ��ĕI���u���Ƃ�邾���̗͂͂���܂���B
����������ǁA���u���邵���Ȃ��B
����ƏG�g�́A���̗��N�ɁA���N�o�����J�n����̂ł��B
�������̂̓��\���̃X�y�C�����{�ł��B
���{���A���N�A�����𐪂���A���̍��͂����A�����ő�̐����I�A�R���I���͂ƂȂ邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă��܂��B
�������A�C��n�������N�o���Ƃ������Ƃ́A���A���\�����̃X�y�C�����{�ɓ��{���U�߂ė��Ă����������Ȃ��B
�Q�Ă��X�y�C�����{�́A�������\���ɏZ��ł������{�l�������A�}�j���s���̃f�B�I���n��ɁA�W�c�ŋ����ڏZ�����Ă��܂��B
���ꂪ�}�j���̓��{�l���̎n�܂�ł��B
����ɃX�y�C�����{�́A���N7���ɂ́A�h�~�j�R��m�̐鋳�t�A�t�A���E�R�|�X����{�ɔh�����A�G�g�ɗF�D�W�������������Ƃ��鏑�M��͂��Ă��܂��B
���̂Ƃ��A�c��ȑ��������Q���Ă���B
�����ɃX�y�C�������{��������Ă������A�Ƃ������Ƃł��B
����ǏG�g�́A����ȑ��蕨���炢���x����܂���B
�d�˂ăX�y�C���̓��{�ɑ�����v�̍Ñ��̏��Ȃ���n���܂��B
���̓��e�������܂����ł��B
�X�y�C�������́A���{�ƗF�D�W��ł����āA�}�j���ɂ���X�y�C�����{�́A���{�ɐb���Ƃ��Ă̗���Ƃ�A�Ƃ����̂ł��B
�����āA���ꂪ�����Ȃ�A���{�̓}�j���ɍU�߂��ނ��A���̂��Ƃ��X�y�C�������ɂ����Ɠ`����A�Ƃ����̂ł��B
���̏G�g�̏��Ȃ�������R�|�X�́A�A�H�A����܂��B
�{���ɊC��̂ő�����̂��A�ԏ��̓��e��100���X�y�C�������̌��{�����Ƃ��킩���āA�̈ӂɑ�������Ƃɂ����̂��́A���܂ƂȂ��Ă͕s���ł��B
����ǂ����炭����͌�҂ł͂Ȃ����Ǝ��͌��Ă��܂��B
���āA�R�|�X�̑���̂������ŁA�G�g�̏��Ȃ́A�X�y�C�����{�ɂ͓͂��Ȃ������킯�ł����A���R�̂��ƂȂ���A�X�y�C�����{����̕ԏ�������܂���B
����ǁA�ԏ����Ȃ�����ƁA���u����قNJÂ��G�g�ł͂���܂���B
�G�g�́A10���ɂ́A���c��E�q����}�j���ɔh�����A�m���ɏ��Ȃ{�ɓ͂��������̂ł��B
���\2(1592)�N4���A���c��E�q��́A�}�j���ɓ������܂����B
�����Ă��̂Ƃ��A���܂��܍݃}�j���̎x�ߐl��2000�l(��������h�����ꂽ���K���������Ƃ����Ă��܂�)����ĖI�N���āA�X�y�C���̑��{���P�����̂ł��B
�X�y�C�����́A���킵�܂����A�����ɖ����ł��B
������������c��E�q��́A�萨�𗦂��ăX�y�C�����ɉ������A�܂������ԂɎx�ߕ���r�ł��Ă��܂��܂��B
���{�����B
���c��E�q���̈��|�I�ȋ�����ڂ̓�����ɂ����X�y�C���̃S���X���́A���{�̋����ɋ��|���܂��B
����ǁA�S���X�́A�X�y�C����鍑����h������Ă��鑍�ł��B
���E�𐧂����鍑���ɁA���{�ɐb���Ƃ��Ă̗���Ƃ点��ȂǁA�ƂĂ�����Ȃ����ł��邱�Ƃł͂���܂���B
�S���X�́A�Ȃ�Ƃ����Ԃ����������Ƃ��܂��B
�����āA�����\3(1594)�N4���ɁA�V���Ƀt�����V�X�R��m�̃y�h���E�o�E�`�X�^�E�x���X�P�X����g�ɔC�����A���{�h�����܂��B
�v����ɁA���g�̔h�����J��Ԃ����ŁA�����ł����ԉ҂������悤�����̂ł��B
���쉮�Ńy�h���Ɖ�����G�g�̑O�ŁA�y�h���́A�X�y�C���������A���܂␢�E�𐧂����鍑�ł��邱�ƁA���{�Ƃ͂����܂ł��u�Γ��ȁv�W��z�������Ɛ\���q�ׂ܂��B
���ʂɍl����A���E�𐧂����鍑�̃X�y�C���������A���{�Ƃ������m�̏����Ɓu�Γ��ȊW�v�Ƃ��������ł��A���̂����������ł��B
����ǁA�G�g�͕������������Ȃ��B�@ |
�y�h���ɑ��A�d�˂ăX�y�C�������̓��{�ւ̕��]�Ɠ��v��v�����܂��B
�Ȃ��G�g�́A�����܂ŃX�y�C���ɑ��ċ��d�������̂ł��傤���B
���R������܂��B
���ɁA���ۊW�ɂ����āA�Γ��ȊW�Ƃ������̂͑��݂��Ȃ��̂ł��B
���̎���ɂ����鍑�ۊW�Ƃ����̂́A��邩����邩�A�܂�㉺�̊W��������܂���B
���Ƃ����{�������ł������Ƃ��Ă��A��鍑�̃X�y�C���ɓ��{���U�߂����Ȃ����߂ɂ́A���{�����|�I�ȋ����ł��邱�Ƃ��A�v���m�点�邵���Ȃ������̂ł��B
���ɁA�����A�G�g�����r���[�Ɂu�Γ��ȊW�v�̍\�z��}�낤�Ƃ���Ȃ�A�X�y�C���͓��R�̂��Ƃ����a���g�Ə̂��Đ鋳�t����{�ɔh�����܂��B
�����Đ鋳�t�����́A���{�̓������������H��(�܂��ɂ��x�߂�؍��ɂ���čs�Ȃ��Ă�����{��̍H��Ɠ���)���s�Ȃ��B
���ɁA���E�̂����鍑�Ƃ��A���̕��@�ŃX�y�C���̐A���n�ɂ���Ă����̂ł��B
�ł�����A���{���X�y�C���̋��ق��瓦��铹�́A�����ЂƂB
�����܂ŃX�y�C���ɑ��āA���d�Ȏp��������Ȃ����ƁB
���ꂵ���Ȃ������̂ł��B
��O�ɁA�G�g���ڎw�����̂́A�����܂ł��u��̂Ȃ����̒��v�ł������Ƃ������Ƃł��B
���݂���G�́A���|�I�ȕ��͂Ő�������B
���̏�ŁA���͂��̂��̂��D���Ă��܂��B
�܂�u�����v���s���A�������邱�ƂŏG�g�́A�u��̂Ȃ����̒��v���������悤�Ƃ��Ă��܂��B
����ǁA�����ɓ��������ē��{�l���畐�͂�D�����Ƃ́A����ɂ����ē��{�l���㉻�����邱�Ƃ��Ӗ����܂��B
�Ȃ�A���{�����ɕ���������Ȃ����a�ȍ����������邽�߂ɂ́A���ۓI�ȕ��͏Փ˂̊댯����{����o������艓������K�v������B
���쉮�ɂ�����y�h���E�o�E�`�X�^�E�x���X�P�X�Ƃ̉���A���s���ƂȂ����X�y�C���̃S���X��́A���{�Ƃ̓��ȊO���p�����߂��A�X�y�C�������ɂ���čX�R����Ă��܂��܂��B
�����Č�C�̒�Ƃ��Ă���Ă����̂��A���C�X�E�_�X�}���j���X�ł��B
���C�X�E�_�X�}���j���X�́A�A�E�O�X�e�C���E���h���Q�X���g�҂Ƃ��ē��{�ɔh�����A�̈���������}��ƂƂ��ɁA���{�̐�͂��Âɕ��͂��܂��B
�����āA�S���X�̕��͒ʂ�A�������{�ƃX�y�C�����A�����Ő��ʂ���Փ˂���A�ނ���X�y�C�����ɏ����ڂ��Ȃ����Ƃ�m��܂��B
�����Ń��C�X�́A�G�g�Ƃ̒��ڌ��͔����A�ЂƂ�A�܂��ЂƂ�ƁA�鋳�t����{�ɔh������Ƃ����헪���Ƃ�B
�܂�A���Ԃ��҂��A���̊ԂɁA�����̐헪�ʂ�A���{�ɐ鋳�����Ă������Ƃ����̂ł��B
���\3(1594)�N�ɂ́A���C�X��̈ӌ����āA�w���j���E�f�E�w�X�X�ȉ��̃t�����V�X�R��C���m4�l���A���{�ɔh������A���{�ł̕z�����ĊJ���܂����B
�G�g���A����͔F�߂Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A�c����(1596)�N�̂��Ƃł��B
�X�y�C���̉ݕ��D�A�T���E�t�F���[�y�����A�ו��ڂ����܂ܑ���A�y���̉Y�˂ɕY�������̂ł��B
�~�������D���������A�G�g�̌ܕ�s�̈�l�ł��鑝�c��������蒲�ׂɂ�����܂����B
�����ŋ����ׂ������������炩�ɂȂ�܂��B
�Ȃ�ƃT���E�t�F���[�y���̐���ē��l���A���c�����ɐ��E�n�}�������A
�u�X�y�C�������́A�܂��鋳�t��h�����A�L���V�^����������ƁA���͌R���𑗂�A�M�҂ɓ��������āA���̓`���n�̍��y�𐪕����邩��A���E���ɂ킽���ė̓y���̂ł����̂��v�Ə،������̂ł��B
�����G�g�́A�����ɃL���V�^��26�l��ߕ߂��܂����B
�����Ĕނ��ɑ���܂����B
�L���V�^���𑱂������Ȃ�A�O���֏o�čs���B
���{�Ɏc�肽���Ȃ�A���@����A�Ƃ����킯�ł��B
����26���ɑ��A����̃C�G�Y�X��́A����26���̎��߂��s�ɐ\���o�܂��B
磷�t�ɂ��āA�N���Ăق����ƁA�\�����ꂽ�̂ł��B
�C�G�X�Y��̕��͂����ł��B
26���̐M�҂��A�C�G�X�̏\���˂ɂȂ��炦�Č������ɂ��A�ԈႢ�Ȃ��V���ɍs�����Ƃ��ł����Ɛ�`����B
�������邱�ƂŁA�L���X�g���k�Ƃ��Ẳh���ɋP���p����ۂÂ��A�N�U�ɂ��c���S�������߂�B
�܂��A���̂�����̘b�́A�{�肩�炩�Ȃ肻���̂ŁA�܂����x�ڂ����������ƂƂ��āA�v����ɏG�g�̒��N�o���́A�X�y�C���ɂ�铌�m�̎x�z�ɑ��āA���ꍑ�Ƃ�����ƌ`���������{���A�����ɍ�����邩���l������ł̌��f�ł������A�Ƃ������Ƃł��B
���̂��Ƃ́A�P�ɓ��{�⒩�N�̍�������������Ă��A�܂������킩��܂���B
�����̐��E��A���������̏���݂Ȃ���A�G�g���Ȃ����N�o�������ӂ����̂��A�����đ����̑喼�������A�Ȃ����̏G�g�ɏ]���A�����o���A�E�҉ʊ��ɑ����ɏo�Đ�����̂����A�����ł��Ȃ��B
�����Ƃ����Ȃ�A���{�������Ƃ������ꍑ�Ƃ��`�����Ă��璩�N������̗L����܂ł̓����ƁA�G�g�̒��N�o�������̐��E�̓����́A�X�y�C�������V�A�ƕς���������ŁA�܂������������Ƃ����j��A�J��Ԃ��ꂽ�A�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�����A�G�g�����N�o�����s�Ȃ킸�A���{�̍��͂��X�y�C���Ɍ������Ȃ���A�ǂ��Ȃ��Ă������B
�X�y�C���́A���R�̂��ƂȂ���A������A���n�Ƃ��Ă̎x�z���ɒu�������Ƃł��傤���A���R�̂��ƂȂ���A���N�������A�X�y�C���̎x�z�n�ƂȂ������Ƃł��傤�B
�����ăX�y�C���̎x�z�n�ƂȂ邱�Ƃ��A�����Ȃ�Ӗ������̂��B
���̂��Ƃ́A��Ă̗l�q���A�����ɂ܂Ō���ɓ`���Ă��܂��B
���܁A��Ăɓ�Đl�̏�����͑��݂��܂���B
���l��Ƃ̍����킾���ł��B
�A���[���`����E���O�A�C�ł́A��Z�������قڊ����ɖ��E����Ă��܂��܂����B
���̃G���A�̏��������́A�蓖���肵�����������ꂽ�������A�q���Y�ޑO�ɎE�C���ꂽ�̂ł��B
�ł�����A���Z��ł���̂́A�قڔ��l��ł��B
�u���W���A�G�N�A�h���A�y���[�A�{���r�A�́A�S�����A��Z�����Ƃ̍����ł��B
������͂��܂���B
��������A���u����A�q���Y�݁A���܂Ɏ����Ă��܂��B
���{���x�߂����N���A���ꂼ��ɏ������ۂ��Ȃ���A���܂Ɏ����Ă��܂��B
�Ȃ������Ȃ������Ƃ����A�G�g�������A�X�y�C���Ɛ^��������키�p���m�Ɍ��������߂ł��B
���Ȃ݂ɁA�c���̖��́A�G�g�̎����ɂƂ��Ȃ��āA���~�ƂȂ�A���{�͒��N��������P�����܂����B
������A����͏G�g�̋C�܂���ł������푈���Ƃ����̂́A�傫�ȊԈႢ�ł��B
�����ɏo�������喼�����́A���ꂼ��ɐ^���ɐ�����̂ł��B
�ł͂Ȃ����{���P���������B
�������͊ȒP�ł��B
�X�y�C�����̂��A�p����I�����_�ɉ�����āA���͂�ቺ�����A���͂Ⓦ���ɍ\���Ă����Ȃ��Ȃ����̂ł��B
�킽�������́A���܁A�X�y�C���Ƃ������E�ŋ��̑�鍑�ɑ��A������ނ����A�ނ���b�]����Ɣ������G�g�̑s��ȋC�F�ƌւ���A���܂������K���ׂ��Ƃ��ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@
�@ |
|
���G�g�̒��N�o���E����2 |
   �@
�@
|
�G�g�̒��N�o���͂Ȃ����s�����̂�
�L�b�G�g�́A�ӔN�A1592�N(���\�̖�)��1597�N(�c���̖�)�̓��ɂ킽���āA�����x�z���邽�߂ɒ��N�����ɕ��𑗂������A��ʂ͖F�����Ȃ��A�G�g�̎���A���{�R�͒��N��������P�ނ����B�Ȃ��A�G�g�͂��̂悤�ȏo�����s���A�����Ď��s�����̂��낤���B�@ |
�� 1. �D�c�M���̖����̃v���W�F�N�g
�G�g�̒��N�o���ɂ��ẮA�l�X�Ȑ����o����Ă��邪�A�S����������̒z��Ɠ��l�A�D�c�M���̖����̃v���W�F�N�g�������p�����Ƃ����̂��^���ɋ߂��悤���B
���C�X�E�t���C�X�́w���{�j�x�ɂ��A�M���́u�ї��肵�āA���{�Z�\�Z�������x�z������A���͑���Ґ����āA�����͂Ő�������B���{�͉䂪�q�����ɕ������^����v�Ǝ���̍\�z������Ă����Ƃ̂��Ƃł���B�t���C�X�͒��ڐM���Ɖ�����l���Ȃ̂�����A���̋L�q�͐M�p���Ă悢�B�ł́A�M���́A�Ȃ������𐪕����悤�ƍl�����̂��B
�M���́A���{�j�����҂̊Ԃł́A�^�j��Ȋv�����Ƃ��ĔF������Ă���B�����I�ɂ͂��̕]���͊Ԉ���Ă��Ȃ��̂����A���E�I�Ɍ���Ȃ�A�M���́A�����̐�i���̃O���[�o���E�X�^���_�[�h�ł����Ή�����ڎw���Ă����킯�ŁA���̈Ӗ��ł́A�ނ���I�[�\�h�b�N�X�ȘH�������ł����Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B�܂�A�M���́A�|���g�K����X�y�C�����s�����悤�ȊC�O�N������ĂĂ����킯���B���ہA�t���C�X�́A�M���̂��Ƃ��ΌN��ƌĂ�ł����B
��Ή����Ƃ́A����������������ߑ㖯���`�����ւ̈ڍs��(16-18���I)�Ɍ��ꂽ�A��ΌN��ɂ�钆���W�������̂��Ƃł���B�C��j�I�Ɍ���A��Ή����̎����͋ߑ㏬�X���̍Ő���(�}�E���_�[�ɏ���)�ƈ�v���Ă���B�n�������I�ȕ����̐����璆���W���I�Ȑ�Ύ�`���o�Čl�����I�Ȗ����`�ւ�����v���Z�X�́A���≻�͌��͂̏W�����A���g���͌��͂̕��U�������炷�Ƃ����C��j�̖@���ɍ��v���Ă���B
��Ή����́AA. ����R�AB. �������AC. �d����`�AD. �A���n�l���AE. �����_�����Ȃǂ�����Ƃ��邪�A�����́A�M�������s�������܂��͎��s���悤�Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�A�M���́A
A.���̐퍑�喼�ɐ�삯�ĕ��_�������s���A�_�Պ��ȊO�ł���R���ł���悤�ɂ��āA�ߑ�I�ȏ���R��ݗ������B
B.�Ɛb��y�n����藣���A���y�鉺�ɏZ�܂킹�A�����W���I�Ȋ���������낤�Ƃ����B
C.�y�s�y���ɂ�荑���Y�Ƃ̈琬�ɗ͂����A�����Ƃ������L�]�Ȗf�Ս`���x�z���邱�ƂɁA�M�ӂ��������B
D.������A���n�����悤�Ɗ��ł����B
E.�V�c�₻�̑��̊����̏@���I���Ђ�ے肵�A��������l�_�Ƃ��Đ��߂�V�@������낤�Ƃ����B
A����C�́A�悭�w�E�����̂ŁA�����R�����g���邱�Ƃ͂Ȃ��BD�ɂ��Ă͂��ꂩ��ڂ����q�ׂ邱�Ƃɂ��āAE�ɂ��ď����⑫���Ă������B���[���b�p�ɂ����āA���{�̓V�c�ɑ�������@���I���Ђ́A���[�}���c�ł���B���[�}���c�́A�\���R�����ȍ~�A�����I���͂����������̂́A�@���I���Ђ͈ˑR�Ƃ��ĕێ����Ă����B���l�ɁA���{�̓V�c���A�����̐V���ȍ~�A�����I���͂����������̂́A�@���I���Ђ͈ˑR�Ƃ��ĕێ����Ă����B�X�y�C�������́A���[�}�J�g���b�N����M���������A�C�M���X�̃w�����[8���́A�l�I�ȗ�����肪�����Ƃ͂����A�C�M���X�������ݗ����A���[�}���c�ƌ��ʂ����B���̈Ⴂ���A�C�M���X���X�y�C�����琢�E�o�ς̃w�Q���j�[(�e��)��D����̗v���ƂȂ�̂����A�M�����A�V�c�̌��Ђ�X�I�ɗ��p���邱�Ƃ͂����Ă��A���̎P���ɓ��邱�ƂȂ��A�ނ���A��������l�_�Ƃ��Ĕq�܂����ʌ����������������炢�ł��邩��A�C�M���X�^�̉����_�����Ɋ�Â��āA����̌��͂�_�������悤�Ƃ����ƍl���邱�Ƃ��ł���B�@ |
�� 2. ���N�o���ƃA���}�_�̊C��
�D�c�M��(1534�N���܂�)����̃C�M���X�̐�ΌN��A�G���U�x�X1��(1533�N���܂�)�Ɣ�ׂĂ݂�ƁA�ʔ������ʓ_�ɋC���t���B�����̃C�M���X�́A�㏬�ȓ����ŁA����ɑ��ăt�F���y2�����N�Ղ���X�y�C���E�n�v�X�u���N���́A�|���g�K���Ƃ��̐A���n�����āA���E�ŋ��̒鍑�A�����u���z�̖v���邱�Ƃ̂Ȃ����v�ƂȂ��Ă����B�C�M���X�́A�X�y�C���̂̃l�[�f�������h�ŋN�����I�����_�Ɨ��푈�ŁA�V�������x���������߂ɁA�X�y�C���ƑΗ����邱�ƂɂȂ�̂����A�C�M���X���X�y�C���̃w�Q���j�[�ɒ��킷��Ƃ������Ƃ́A���A�W�A�̃w�Q���j�[�鍑�ł��钆���ɁA�㏬�ȓ����E���{�����킷��̂Ɠ��l�ɁA���X�N�̑傫���`���������B
�G���U�x�X1���́A�h�G�X�y�C���ɑŌ��������邽�߂ɁA�C���Ɏ����������^���A�X�y�C���̏��D���P�킹���B�C�M���X�̊C���̂Ȃ��ł��A�h���C�N�ƃz�[�L���Y�͗L���ŁA�ނ�́A��ɃC�M���X�͑����X�y�C���̖��G�͑���j��A���}�_�̊C��Ŋ���B�D�c�M�����A�ɐ��E�u�������_�Ƃ���C����������S�×���D�c���R�̑��i�ߊ��ɔ��F���A�����D(�S��A���͂ȑ�C�𓋍ڂ��������ŋ��̌R��)�����������A��ؒÉ͌��̊C��Ŗї����R��j�邱�Ƃɐ������Ă���B
�Ƃ��낪�A�L�b�G�g�́A���Ƃ̐푈�ŁA�C���̗͂����p���邱�Ƃ͂Ȃ������B�ނ���t�Ɂu�C���@�x�v���o���āA�C���̊������֎~���Ă��܂����B�����A�����`����ɋ�S���Ă������Ƃ��v���ƁA�G�ɉ��𑗂�悤�ȋ���Ȃ̂����A�G�g�����́u�C���@�x�v���o�������@�́A�����ɏo�����u����߁v�̏ꍇ�Ɠ����ŁA�����ɂ����镺�_�����ƊK�����x�̌Œ�ł������B�M�����s�������_�����Ƃ͈قȂ��āA�G�g���s�������_�����́A������̐����I��点�邽�߂̂��̂������B�ߑ�I�ȕ��Ƃɂ��@�\�����ƑO�ߑ�I�Ȑg���̌Œ艻�͎��Ĕ�Ȃ鐭��ł���B
�M�����A���̐��̌��Ђƒ��������āA�L�\�Ō��т̂���l�ނ�������ł���藧�Ă悤�Ƃ����̂ɑ��āA�G�g�́A���̐��̌��Ђƒ����d���A�g���̌Œ艻��}�����B�w��p���}�L�x�ɂ���ȃG�s�\�[�h������B�˃��Ԃ̍���ŁA�ēc���Ƒ��ɂ��Đ�������v�Ԑ����́A���ܖړ��Ă̕S���ɕ߂炦��ꂽ�B����ƁA�G�g�́A�������a��ƂƂ��ɁA�u�S���ɂ͎����͂��鎖���d�o��������̂��ȁB�������߂̂��߁A�J���̂��߁A�͂����ɂ�����v�ƌ����āA���̕S��12�l�����ɂ����B�G�g���g�A����_�̎q�ł��������A�������͂������Ă��܂��ƁA���������̊������v����邽�߂ɁA�g���̕ǂ̉z����F�߂Ȃ��Ȃ����킯���B
�M���ƏG�g�̊Ԃɂ��邱�̊i�����C�M���X�ƃX�y�C���̊Ԃɂ������邱�Ƃ��ł���B�G���U�x�X������̃C�M���X�ɂ��A�������A�g�����x�̕ǂ͂������B�������A�h���C�N�������ł������悤�ɁA�_���̎q�Ƃ��Đ��܂�Ă��A���т�����A�M���Ƃ��Ă̏̍�������ꂽ���A�t�ɋM���̎q���ł����Ă��A���т��Ȃ���A�̍��Ɠy�n�������A�����̐g���ɖv�������B����ɑ��āA�X�y�C���̊K�����x�͌��i�ŁA������˔\�ƌo���������Ă��A�������R�̎w���҂ƂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������B
���̈Ⴂ���A�A���}�_�̊C��̏��s�ɂȂ������B���G�͑��ɏ�荞�X�y�C���̋M�������́A�����̌o���͖L�x���������A�C���̌o���͏��Ȃ��������A������ƌ����čq�C�o���̂��镽�����w���҂ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�h���C�N�́A�C��ɂ������C�̏d�v����F�m���Ă������A�X�y�C���̐�m�ł���M�������́A��C���̕���Ƃ��Čy�̂��A�d��������g�D���āA�G�D�̍b�ɏ��ڂ�A�����œ��e������悤�Ƃ����A�܂�C���𗤏��ɂ��悤�Ƃ����̂��B�������A�C�M���X�D�̑�C�̎˒������͒����A�X�y�C���D�́A�C�M���X�D�ɋ߂Â��O�ɁA���j���ꂽ�B�������āA�A���}�_�̊C��́A�X�y�C���̊��s�ɏI������B
�G�g�̒��N�o���́A�A���}�_�̊C���4�N��ɍs��ꂽ�B���{�R�́A�����ł͘A��A���ł������ɂ�������炸�A�C���ł͗��w�b�������钩�N���R�ɘA�s���A���̂��ߕ⋋�H���f����A���܂ōU�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�ł́A�Ȃ����{�̐��R�́A�A�s�����̂��B���N�̋T�b�D���D�G���������炩�B�����ł͂Ȃ��B���w�b���ꎞ���r�������A���{�̐��R�ɂ���ċT�b�D�̊͑����S�ł��Ă���B���{���R�����C�����������̂́A���w�b�ɕC�G����A���邢�̓h���C�N�ɕC�G����C��̃G�L�X�p�[�g�����Ȃ��������炾�B�@ |
�� 3. �������M���������������Ă����Ȃ��
�M���Ȃ�A���Ԃ�A���N�E�����̉��݂ɏڂ����`�������p���Ă����ł��낤�B�������A�G�g�͂������Ȃ������B���łɑ喼�ɂȂ��Ă�����S�×��́A���{�����̊C���̏o�g����������A���N���݂̎���͏ڂ����Ȃ������B����ɑ��A���w�b�́A���̗���̋t�]�𗘗p����ȂǁA�n���ł��闘�_�𗘗p���āA�����̋T�b�D�œ��{�̑�R��j�����B
���́A�����̓��{�ɒ����Ɛ키�K�v�����������Ƃ͎v��Ȃ��B�����A�����ł͐푈���ꎩ�̂̐����_���邱�Ƃ͂�߂悤�B�������ɂ������̂́A�푈�̂����ł���B�����A���{���G���U�x�X1���Ɠ������@��p���Ă�����ǂ��Ȃ��Ă��������V�~�����[�V�������悤�B�����̘`���ɂ́A���������{�l���������A���̑����́A���ɕs�����������l�ŁA����Δ��̐��Q�����g�D�������B�����A���{���`����w�ォ��x��������A���́A���Ԃ����N�ƂƂ��Ɋ͑��𗦂��ē��{�𐪔����悤�Ƃ����ł��낤�B�M���́A�G��U���Ē@����@���悭�̂������A���̕��@�Ȃ�A�����̎��Ɠ��l�A���{���n�̗������āA���Ă����낤�B�����āA�G�̐��R�͂��킢�ł���ł���A���ɑ���N���푈�͐���������������Ȃ��B
�G�g�͐M���̃v���W�F�N�g���u���^���v�������A�M���̐��_���p���Ȃ������B�G�g�̒��N�o�������s�����̂́A�ЂƂ��ɏG�g�̓����Â���������ł���B�������āA���{�͊C�O�N���Ɏ��s���A�����x���ł̑ΊO�i�o��f�O���A�����ւ̓�����ށB�����A�X�y�C����j�����C�M���X�́A�V���ȃw�Q���j�[���Ƃ��āA�ΊO�ϋɍ�ɏo��B�������āA���[���V�A�嗤���͂��ޓ�̓����́A���̌�A�ΏƓI�ȉ^�������ǂ邱�ƂɂȂ�B
�@ |
|
���G�g�̒��N�o���E����3 |
   �@
�@
|
�� 1
�F����́A�L�b�G�g�Ƃ������O�����ۂɁA�܂������v�������ׂ܂����H
���ʂ̓��{�l�Ȃ�u�V������𐬂��������̂��l�v�u�Ⴂ�g������֔��ɂ܂ŏo�����������l�v���邢�́u����(���݂̑���)��z�����l�v�ȂǁA�T�˗ǂ��]��������邱�Ƃ������Ǝv���܂��B
���Ɏ����Z�ޑ��ł́A�G�g�́u�L���喾�_�v�Ƃ��Đ_�l�̈������Ă���A�܂��A�֔��̌o���҂Ƃ����Ӗ��́u���}����v�Ƃ��āA21���I�̍��ł������l�C���ւ��Ă��܂��B
�������A��l�̐l���ɑ���]���Ƃ������̂́A�����Ⴆ�Έӌ���������邱�Ƃ��悭����܂��B�Ȃ��ł��G�g�̏ꍇ�́A���鍑�ł́u�⍓����ȐN���ҁv�Ƃ��āA���݂ł������̂悤�Ɍ����Ă���̂ł��B
����͂ǂ��̍����Ƃ����A���N�����ɂ���k���N�Ɗ؍��ł��B�Ȃ��G�g�́A���N�����ɂ����Ă���قǂ܂łɌ����Ă���̂ł��傤���H�@ |
�� 2
�L�b�G�g�ɂ����j�I�����ɂ́A�V������Ƃ����̋Ƃ̂ق��ɁA�����Ēʂ�Ȃ��ΊO������܂��B����́A1592�N�̕��\�̖��ƁA1597�N�̌c���̖��Ƃ����A��x�ɂ킽�钩�N�����ւ̏o���ł��B
�G�g�ɂ�钩�N�o�������ʓI�Ɏ��s�ɏI��������ƂŁA���N�����̍��y��l�X�̐������r�p�����݂̂Ȃ炸�A����Ȏ����╺�͂��₵���L�b�Ƃ̎x�z�ɂ�����ȉe���������炵�A��ɓ���Ƃɂ���Ėłڂ���錴���̈�ƂȂ�܂����B
�G�g�̏o���ɂ���đ傫�Ȕ�Q�������N�����̐l�X�̍��݂͐[���A���\�̖��͐p�C�`��(�C���W���E�F����)�A�c���̖��͒��ј`��(�`�������E�F����)�ƌĂ��ȂǁA���N�����ɂ����ďG�g��21���I�̌��݂ł�����ꑱ���Ă���̂ł��B
����A�G�g�̍s�ׂ͉䂪���ɂ����Ă��u����s�\�ȍő�̋��s�v�u�ӔN�̏G�g������Ȋ��o�����������Ƃɂ��ϑz�v�ȂǂƎU�X�Ȉ������Ă���A�䂪���̗��j���ȏ��ɂ����Ă��u���N�N���v�Ə������ȂǁA�G�g�ɂ��o�������N�����ւ̐N���s�ׂƂ݂Ȃ���Ă���̂������ł��B
�������A�G�g�ɂ�钩�N�o�����A���̂悤�Ȉ���I�Ȏ���Œf�߂��邾���ŏI��点�Ė{���ɗǂ��̂ł��傤���H
����̍u���ł́A�G�g�����N�o�������ӂ����u�{���̗��R�v��T��ƂƂ��ɁA���N�o�����Ȃ����̂悤�Ȉ���I�Ȉ�������Ɏ������̂��Ƃ�����ɂ��Ă��𖾂��Ă��������Ǝv���܂��B�@ |
�� 3
�G�g�ɂ�钩�N�o���𗝉����悤�Ƃ���A�����Ė������邱�Ƃ̂ł��Ȃ���́u�傫�ȗ���v������̂ł����A����͂����������Ȃ̂����F����͂����m�ł��傤���H
���̍u�����܂߂āA���{�j���w�K���悤�Ƃ���ۂɂ́A�䂪���̏o�����ɂ������߂��邱�Ƃɂ���āA�����Y�ꂪ���ɂȂ��Ă��܂����̂�����܂��B
�����́u���E�j�̗���v�ł��B���{�j�Ȃ̂ɂȂ����E�j���o�Ă���̂��A�Ǝv���l�X��������������܂��A���{�j�𗝉����悤�Ǝv���A���E�j�̗���������ɗ������Ȃ���A���̎����������Ă��Ȃ����Ƃ�����̂ł��B
�Ⴆ�A�������q�ɂ�錭�@�g�ɂ��Ă��A�����̒����嗤���@�ɂ���Ė�300�N�Ԃ�ɓ��ꂳ�ꂽ���ƂŁA�䂪�����܂ޓ��A�W�A�̏����ɋْ��������Ă������ƁA�܂��@�ƒ��N�����̍����Ƃ��푈���ł���A�@���䂪���ɍU�ߍ��ޗ]�T���Ȃ������Ƃ������������������炱���A�������q�����얅�q��ʂ��đΓ��O����ڎw�����������@������ɑ���������Ƃ̐^�ӂ������ł���̂ł��B
�Ƃ����15���I�̖�����G�g���V���ꂵ��16���I�����̉��B(���[���b�p�̂���)�́A��ʂɂ͑�q�C����Ă�Ă��܂��B
���O����������A��C���ɐV���Ȋ�]�������悤�Ƃ����J��̎���Ƃ����ǂ���ۂ���̂ł����A���͂��̎���ɂ́A�����̐l�X���s�E���ꂽ�Ƃ�������ׂ����ʂ��B����Ă���̂ł��B�@ |
�� 4
��q�C����ɂ́A���������̈�ƂȂ����傫�ȏo����������܂����B����̓��^�[�ɂ��L���X�g���̏@�����v�ł��B
�u�_�̋~���̓��[�}���c�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�X�̐M�A���Ȃ킿�����̒��ɂ�������v�Ƃ������^�[�̍l���́A�v���e�X�^���g�Ƃ������̐V���Ƃ��Ď�����A�����ƌĂꂽ�]���̋����ł���J�g���b�N�Ƃ̊ԂŁA���Ō���@���푈���N����܂����B
�����Ԃ���}�肽���J�g���b�N�́A1534�N�ɃC�G�Y�X���n�݂��A���B�ȊO�̊e�n�ł̕z����ڎw���܂������A���̓����ɍ��킹�邩�̂悤�ɁA��q�C����̖��O�ǂ���ɐ��E�����q�C���āA�e�n�̑嗤�̐��������������鍑�X������܂����B����̓X�y�C���ƃ|���g�K���ł��B
�C�G�Y�X��n�݂��O��1494�N�A�X�y�C���ƃ|���g�K���ɂ���đ吼�m�𓌐��ɕ������{�̐���������A���̐����瓌���Ŕ����������̂͂��ׂă|���g�K���ɁA�����Ŕ����������̂͂��ׂăX�y�C���ɑ�����Ƃ�����茈�߂��A���[�}���c�̏��F�ɂ���ė����̂������Ō���܂����B������g���f�V�����X���Ƃ����܂��B
�܂�Œn�����\�����Ɋ��邩�̂悤�ɕ�������Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ����z�ł����A����͓����̔��l�����`�ɂ��l�퍷�ʂɊ�Â����R�̎v�z�ł�����܂����B�����āA���̋���ׂ��l���́A�X�y�C���ƃ|���g�K���̗����ɂ���āA�����ɍs���Ă������̂ł��B�@ |
�� 5
���Ă̒n���ɂ́A���݂̓�đ嗤�����ɂ̓C���J�鍑�A���L�V�R�������ɂ̓A�X�e�J�鍑�Ƃ�����̍����h���Ă��܂����B�������A�����͂������16���I�ɃX�y�C���ɂ���Ėłڂ���A�����̐�������Y�A����ɕ����͉i���Ɏ����Ă��܂��܂����B�܂��A�A�t���J�嗤�����B�ɂ�鐪�����āA�����̌��n�l���z��Ƃ��Ĕ��������ȂǁA���B�ɂ��L�F�l��̍���l�X�̎x�z�͗��܂�Ƃ����m��܂���ł����B
�����������őn�݂��ꂽ�C�G�Y�X��ɂ��u�_�̖��̉��Ɂv�z�������𐢊E���ōs���Ƃ����ړI�́A21���I�̌���ɂ�����펯�ł͍l���ɂ������Ƃł͂���܂����A�����̌��ʂƂ��đ�q�C����ɂ����鉢�B�Ƃ̗��Q�ɂ���ނ��ƂƂȂ�A�J�g���b�N�̕z���Ɣ��F�l��ɂ�鐢�E�e�n�̐N���Ƃ��A�������������Z�b�g�̂悤�ɂ��Đi��ł������ƂɂȂ�܂����B
�Ⴆ�A���n�̍����ɃJ�g���b�N��M�����邱�Ƃɐ������āA�������������āu�_�̐M�ҁv�ƂȂ�����ɁA���B�̍��X���u�_�̖��̉��Ɂv�N���푈���d�|����A�M�҂Ɖ����������͂ǂ���̖���������ł��傤���H
�������Đ��E�e�n�̎x�z���g�債�Ă��������B�e���̂����A�X�y�C���̓����̍����ł������t�F���y2���́A�₪�ăA�����J�嗤���x�z�����݂̂Ȃ炸�A1580�N�ɂ̓|���g�K���̉��ʂ����C����ȂǁA�܂��ɐⒸ���ɂ���܂����B
����ȃt�F���y2�������Ɏx�z��_�����n�悱�����A�䂪�����܂ރA�W�A�̍��X�������̂ł��B�@ |
�� 6
�C�G�Y�X��̐鋳�t�ł���t�����V�X�R���U�r�G����1549�N�ɉ䂪���ŃJ�g���b�N�̕z�����n�߂����́A�����̐퍑�喼�͉��B�ɂ�锒�l�x�z�̖�]�ɋC�Â����Ƃ��Ȃ��A��ؖf�Ղɂ���ĉ��B�n���̒������������ɓ���邽�߂ɁA�x�z�n�ł̃J�g���b�N�̕z����������ƂƂ��ɁA�喼���炪�J�g���b�N��M����҂�����܂����B�ނ�̂��Ƃ��u�L���V�^���喼�v�Ƃ����܂��B
�V�������ڎw�����D�c�M�����������R�Ŏx�z�n�ɂ�����J�g���b�N�̕z���������A�M���̌���p�����G�g���A�����̓J�g���b�N�̕z����F�߂Ă����̂ł����A����Ȕނ��₪�ăJ�g���b�N�ɐ��ރX�y�C���ɂ�鐢�E�N���̖�]�ɋC�Â���������ė����̂ł����B
1587�N�A��B����ɏ�荞�G�g���A�C�G�Y�X��̐鋳�t�������̉䂪���ɑ��݂��Ȃ��ŐV�s�̌R�͂��������ďo�}���܂����B���̑s�傳�ɋ������G�g�́A�C�G�Y�X��ɂ��z�������ɂ̓X�y�C���ɂ��䂪���ւ̐N������߂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ^�O�������n�߂܂����B
�����āA���n�����@�����G�g��҂��Ă����u3�̐M�����Ȃ��o�����v��ڂɂ��邱�ƂŁA�G�g�̋^�O�͊m�M�ւƕω����Ă������̂ł��B�@ |
�� 7
��B�ɂ��钷��́A�O���ւ̌����Ƃ��ĉh�����`���ł����A�퍑����ɂ̓L���V�^���喼�ł������呺�������x�z���Ă��܂����B�����́A�J�g���b�N��[���M���邠�܂�A����̒n���C�G�Y�X��Ɋ�i���Ă����̂ł��B
�䂪���×��̗̒n���A�M�̂��߂Ƃ͂����O���̏��L�ɔC����Ƃ����s�ׂ́A�V�������ڎw�����G�g�ɂƂ��Ă͗L�蓾�Ȃ����Ƃł���A�܂��X�y�C����C�G�Y�X��̗̓y�I��S�ɋ��|�������܂����B
���ɏG�g��҂��Ă����̂́A�L���V�^���喼�̗̓��ɂ����āA�����̐_�Ђ⎛���Ă���Ă���Ƃ��������ł����B�J�g���b�N�̗R���ł���L���X�g���́A���������L���X�g�݂̂�_�Ƃ����_���ł���A����ȊO�̐M�ƂȂ�Ώۂ���؋����Ȃ��������߂ɋN�����ߌ��ł�����܂����B���������s�ׂ́A�G�g�̖ڂ���́u�䂪���̓`���╶����j�鋖���Ȃ��s���v�Ƃ����f��܂���ł����B
����ɏG�g�����������̂́A�|���g�K���̏��l�������̓��{�l��z��Ƃ��ċ����I�ɘA�s���Ă��������ł����B���l���炷��A�x�z�n�̗L�F�l���z�ꈵ������͓̂��R�̍s�ׂł����Ă��A�V�������ڎw���ƂƂ��ɁA�����̐�������Y�����`��������Ǝ��o���Ă����G�g�ɂƂ��Ă͐�ɔF�߂��Ȃ��s�ׂł����B
�C�G�Y�X��ƃX�y�C���Ƃɂ��䂪���N���̖�]�ɋC�Â����G�g�́A�����̎����Ɍ��{����ƂƂ��ɁA�����ɃJ�g���b�N�̐M���֎~���A������C�G�Y�X���v�����ďG�g�̒����n�Ƃ����̂ł����B�@ |
�� 8
���āA�G�g���C�Â����X�y�C���ɂ��䂪���N���̖�]�ł����A���ۂɃX�y�C����C�G�Y�X��͂ǂ��������̂ł��傤���B���́A�����̃X�y�C���͉䂪�����ɐ������邱�Ƃ͕s�\�ƍl���Ă��܂����B�Ȃ��Ȃ�A�䂪���͐퍑����̐^���Œ��ł���A���\���̐����ȌR���̂ق��ɁA10��������Ƃ������E�ɗ�̂Ȃ������̓S�C�����L���Ă�������ł��B
�������A�䂪���̐N����������߂Ȃ������X�y�C���́A�䂪���ȊO�ɃA�W�A�ōL��ȗ̓y���������̖��ɒ��ڂ��܂����B����ł������ł����A�l���������A�������L�x�ɂ��閾�́A�X�y�C���ɂƂ��Ă͖��͓I�ȗ̒n�̌��ł�����܂����B
�����A�����U�߂悤�ɂ��A�����̃X�y�C���̌R�����������܂ʼn^�Ԃ��Ƃ͕����I�ɂ͕s�\�Șb�ł����A�ނ�ɂ͉䂪���ł̕z���ɐ��������L���V�^���喼�ɂ�镺�͂�����܂����B�ނ���g���Ė��𐪕����A���������_�ɂ��ĉ䂪�����U�߂邱�Ƃ��ł���A����Ȑ������\�ɂȂ�ƍl�����̂ł��B
���������X�y�C���̓���������ł����G�g�ɂ́A��@���Əő���������܂����B���������X�y�C���ɐ�������Ă��܂��A���͉䂪�����_����͖̂��炩����������ł��B���̍\�}�́A�܂��Ɋ��q����ɋN�����������̂��̂ł�����܂����B�@ |
�� 9
�Ƃ���ŁA�����̃X�y�C���͒����嗤�֒��ڍU�ߍ��߂邾���̑傫�ȌR�͂������Ă��܂������A��q�̂Ƃ��蕺�͂��s�����Ă��܂����B����̉䂪���́A���͂����͏[�����Ă��܂������A�O�q�p�̑傫�ȑD���������邾���̔\�͂������͂���܂���ł����B
�����̓_�ɖڂ������G�g�́A�܂��̓X�y�C���Ƃ̊O���ɂ��Ë���ڎw���܂����B�܂�A�X�y�C���Ɖ䂪���Ƃ����������Ԃ��Ƃɂ���āA�������������Ė��𐪕����A���͖������ł̃J�g���b�N�̕z������������ɁA�X�y�C�����L�̊O�q�p�̌R�͂p���Ă��炤�Ƃ����������������̂ł��B
�������A�G�g�̒�Ă̓X�y�C���ɂ���ċ��ۂ���܂����B�X�y�C���͕��͂ɂ��䂪���̐�����f�O���Ă��Ȃ���������ł��B
�X�y�C���Ƃ̓����Ɏ��s�����G�g�́A�����X�y�C���ɐ��������̂�ق��Č��Ă�������A�@��𐧂��Ď��������𐪕����Ă��܂��ȊO�ɁA�䂪�����X�y�C���ɂ��N������~�����͂Ȃ��Ɗo������߂܂����B�S���ꂵ���ނ̕��͂́A�S�̂Ő��\���l�ɂ܂Ŗc��オ���Ă���A�����̐��s�𓊓�����A�䂪���P�Ƃł̒����嗤�̐������s�\�ł͂Ȃ��ƍl��������ł��B
�����āA���������G�g�̌��f�́A�V�������ꂳ�ꂽ���Ƃŗ͂����ė]���Ă������m�����ɂƂ��Ă��A�V���ȗ̓y����ɓ����\�����o�Ă������ƂōD�ӓI�Ɍ}�����܂����B�G�g�̌��f�́A�Ñ�}�P�h�j�A�̃A���N�T���h���X�剤��A�����S���̉p�Y�`���M�X���n�[���Ɠ��l�ɁA����ȕ��͂����l�Ԃ����R�̂悤�ɍs�������ł��������̂ł��B�@ |
�� 10
���̐��������f�����G�g�́A����̍s�ׂ��u������v�Ɩ��t���܂����B�������A��q�����悤�ɁA�䂪���͖��֒��ڍU�ߍ��ނ��Ƃ��\�ȑ傫�ȑD�̌����\�͂������͂���܂���ł����B���Ƃ���A�䂪���ƒn���I�ɋ߂����N�������o�R���čU�ߍ��ވȊO�ɕ��@������܂���B
�G�g�͓����̒��N�������x�z���Ă����������N�ɑ��āu�䂪�������R���𑗂邩�狦�͂��Ăق����v�Ǝg�҂��o���܂������A�����͖����@�卑�Ƌ��ł����������N�ɂ͏o���Ȃ����k�ł����B
�i�ނ���܂����G�g�́A���𐪕�����O��Ƃ��āA��ނȂ����N��������U�ߍ���ł������̂ł��B���ꂱ�����A1592�N�ɋN�������ڂ̒��N�o���ł��镶�\�̖��̖{���̗��R�ł����B
�����͉䂪�������|�����킢�ł������A�������N�̖����ł��闛�w�b(�C�E�X���V��)�̊���������A�c�ɐL�т������䂪���̌R���̕⋋�H���f���ꂽ���ƂŁA�����̕����Q���⊦���ɋꂵ�肷��ȂǁA�킢���P��������ԂɂȂ�A�₪�ċx��ƂȂ�܂����B
���̌�A�䂪���Ɨ������N�▾�Ƃ̊ԂŘa�������s���܂������A���s�ɏI��������ƂŁA1597�N�ɏG�g�͍Ăђ��N�������U�߂܂����B���ꂪ�c���̖��ł��B�킢�͈�i��ނ��J��Ԃ��܂������A1598�N�ɏG�g���S���Ȃ������Ƃŋx��ƂȂ�A�䂪���͒��N��������P��(�Ă�����)���܂����B
����������x�ɂ킽�钩�N�o���́A�G�g�̔ߊ�ł����������́u������v�̖ړI���ʂ����Ȃ��������肩�A���N�����֑���ȉe�����y�ڂ��������łȂ��A�䂪���ɂ��L�b�Ƃ��n�߂Ƃ��đ����̑��Q�������炵�����ʂƂȂ��Ă��܂��܂����B����ɁA���́u���s�v�����̐l�X�̊ԂɁu�����C�v�������炷���ƂɂȂ����̂ł��B�@ |
�� 11
���āA�����ŊF����ɂ������������̂ł����A�F�������Ђ̎Ј��������Ƃ��܂��傤�B���̉�Ђ̎В��̓J���X�}�I�ȑ��݂ł���A�_������Ȑ��������X�Ƒ�������ɁA���ɂ͈��ł��̉�Ђꗬ�̊�ƂւƊg�傳���邱�Ƃɐ������܂����B�����āA���̎В����V���ɎЉ^��q(��)�����傫�ȃv���W�F�N�g�\�����Ƃ��܂��傤�B
���̃v���W�F�N�g�ɑ��āA�F����͂ǂ��v���܂����H
����܂ł�鎖�Ȃ����������葱�����В��̌������Ƃł���A�܂����ꂾ���̐M������т�����܂��B���Ƃ���A�����n�ɏ���Ƃ������ɊF���������ăv���W�F�N�g�ɎQ�����悤�Ƃ��܂���ˁB���ɂ̓v���W�F�N�g�̏d�v�Ȗ�ڂ�����u�肷��Ј�������ł��傤�B
�������A���ʂƂ��Ă��̃v���W�F�N�g�͑厸�s�ɏI����ĎВ��͋}�����A�Љ^����C�ɌX�����ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B�K���ɂ��ʂ̊�Ƃ̎В����Đ��ɏ��o�������Ƃʼn�Ђ��̂��̂͂Ȃ�Ƃ��������܂������A�����Ȃ�ƁA����܂Ńv���W�F�N�g�Ɏ^�����Ă����l�X�͂ǂ��l����ł��傤���B
�����������v���W�F�N�g�ɐϋɓI���������Ƃ����Ԃɒm���ẮA�ƂԂ��p���������ƂɂȂ�܂����A�܂��V���ȎВ��ɂɂ�܂�ĉ�Ђ����߂������邩������܂���B���Ƃ���u���͂��̎��͖{���͔��������B�ł��В����������������猙�X�]�������Ȃ������v�Ƃ��A���邢�́u���͂��̎��������B������(�{���͎��͕s���ŎQ���ł��Ȃ���������)�v���W�F�N�g�ɂ��Q�����Ȃ������v�ȂǂƎ����������ł��ǂ������悤�͎v���܂��H
���͂���Ɠ������Ƃ��A�G�g������ɂ��s���Ă����̂ł��B�@ |
�� 12
�G�g�̒��N�o����ɉ䂪�����x�z��������ƍN�́A����܂ł̏G�g�̐���̑����������p������ŁA����̈ꕔ��ے肷�邱�ƂŎ����̎��͂��������Ƃ��܂����B
���ɖL�b�Ƃ��łڂ��ꂽ��́A�G�g�̂��Ƃ��^������e�����ɂ�����A���͂��c�����肷�邾���Ŏ��ׂ����\��������܂�������A�e���̑喼�́A���Ă͏G�g�̒��N�o���Ɏ^�����Ă����Ƃ���������O�ꂵ�ĉB���悤�ɂȂ肵���B
�܂��A�G�g�̏o���ɂ���Ĉ������Ă����������N�Ƃ̊W�C����ڎw���ĉƍN���������ۂɂ��A���������N�����ɍU�ߍ��܂Ȃ������Ƃ���������A�L�b�Ƃ�|���Ď��g���V���ȉ䂪���̎x�z�҂ƂȂ������Ƃ��������邱�ƂŁA�����̉ɐ������܂����B
���̂����A�ƍN�����N�������U�߂Ȃ������͎̂����ł����A����͋t�Ɂu�U�߂����Ă��炦�Ȃ������v�Ƃ�����������܂��B�Ȃ��Ȃ�A�G�g�͖��̐����ɐ�������Ɗm�M���Ă���A�h�G�ł���ƍN�ɗ̒n�̊g���F�߂�悤�Ȑ퓬�s�ׂ����������Ȃ��������炾�Ƃ������������邩��ł��B
������ɂ���A�ƍN���ŏI�I�ɉ䂪���̎x�z�҂ƂȂ������ƂŁA�G�g�ɂ�钩�N�o���͂��̈Ӌ`�����ׂĔے肳��邾���łȂ��A�u���v�Ȑ킢�v�u�ӔN�̋��s�v�Ƃ����c�����Y��ʂ���������������Ȃ��Ȃ��Ă����܂����B�����āA���̌���������ɂ��������������ƂȂ����u���鎖���v��20���I�ɋN���Ă���̂ł��B�@ |
�� 13
���N(����22�N�A����2010�N)�́A������j�I��������100���N���}���܂��B����́A����43(1910)�N�ɉ䂪���������̒��N�������x�z���Ă�����ؒ鍑�������Ƃ���A��������ؕ����̂��Ƃł��B
�䂪�����؍�������Ɏ��������̂�ɂ��Ă͕ʂ̋@��ŏڂ����Љ��\��ł����A�ԈႢ�Ȃ������邱�Ƃ́A���ؕ����Ƃ��������ɂ���āA����E����ɒ��N�������Ɨ���������A��X���{�l�̑��������N�����̐l�X�ɑ��āA������x�́u�����ځv�������Ă��邱�Ƃł��B
�����āA���̕����ڂ���Ȃ̂��A�䂪���͖k���N��؍��ɂ����j�F���ɑ��đ����Ɣ�ׂċ����ԓx�ɏo�邱�Ƃ��Ȃ��A���̌��ʂƂ��ďG�g�ɂ�钩�N�o�����A�k���N��؍����咣����܂܂Ɂu���N�N���v�ƕ\�����A�䂪���̗��j���ȏ��ɂ��̗p����Ă��邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B
�������A��X���{�l�̒��N�����̐l�X�ւ̌l�I�Ȋ���͂Ƃ������Ƃ��āA�G�g�̍s�ׂ��̂��̂��A�ʂ����Ė{���Ɂu���N�N���v�������Ƃ�����̂ł��傤���H�@ |
�� 14
��q�����Ƃ���A�G�g�ɂƂ��Ă̍ŏI�ڕW�͖��𐪕����邱�ƁA���Ȃ킿�u������v�ɂ���܂����B�G�g�����N�����֍U�ߍ��̂́A�������N���䂪���̕��j�ɔ���������ł���A�\���̗L���͂Ƃ������Ƃ��āA���ɗ������N���^�����Ă���A�G�g����U�߂��邱�Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B
���Ƃ���A�G�g�͖����u�N���v����ӎv�͂������Ƃ��Ă��A���N�������̂��̂�N������Ƃ����T�O�͂Ȃ������Ƃ����܂��B����Ȃ̂ɁA�G�g�̍s�ׂ��u���N�N���v�ƒf�����邱�Ƃ́A�G�g�̐^�ӂ�����邾���ł͂Ȃ��A���j�I�ɂ��������\���Ƃ͂����܂���B�]���āA�����͂�͂�u���N�o���v�ƕ\�����ׂ��Ȃ̂ł��B
�������A����ɂ��Ȃ��钩�N�����̐l�X�̏G�g�ɑ��鍦�݂���݂͗������Ȃ���Ȃ�܂��A���̈���Ő��E�j�ɂ͋��ʂ̌���������̂������ł��B����́u���閯���ɂƂ��Ẳp�Y�́A�������ɂƂ��Ă̋s�E��(���푈������)�ł���v�Ƃ������Ƃł��B
�G�g�́A���N�����̐l�X���猩��Ίm���ɋ����ꂴ��N���҂ł͂���܂����A���̈���ŁA�䂪���ɂƂ��Ă͓V��������ʂ������p�Y�ł���A�퍑�̗��������������̒��ɕ��a�������炷���������������Ă��ꂽ���l�ł�����܂��B
�܂��A��q�����A���N�T���h���X�剤��`���M�X���n�[�����p�Y�Ƃ��Ă̊��������ŁA�ނ�ɂ���ċs�E����A�łڂ��ꂽ�������吨���܂��B���������������l����A�䂪���Ɋւ�炸�A�Ⴄ�����m�ŋ��ʂ������j�F�������Ƃ������z�́A���ǂ̂Ƃ���͕s�\�Ƃ�����̂�������܂���B�@ |
�� 15
�������A������Ƃ����đ����̗��j�F��������I�ɊԈႢ�ƌ��ߕt���邱�Ƃ͌����ċ�����܂���B���̍��ɂ͂��̍��Ō��p���ׂ����j�����邩��ł��B �Ƃ������Ƃ́A�t�ɂ����Ή䂪���������ɑ��Ă���Ӗ��ւ肭�����Ă܂ŁA�����̗��j�F���ɍ��킹��K�v���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�Ȃ��Ȃ�A���������ւ肭�������s�ׂ͏G�g�̒��N�o���ɔ�߂�ꂽ�^�ӂ��n�߂Ƃ���A��X�̑c�悪��X�o�g�����Ȃ��悤�ɂ��đ����Ă����A�䂪���̓Ɨ�����邽�߂̌��̂ɂ��ނ悤�ȓw�͂̈�����ʂł���ƒf������ɓ���������ł��B
����̏G�g�ɂ��u���N�o���v�Ɍ��炸�A��X�͓��{�l�Ȃ̂ł�����A�����̊���ɂ͗������������A�䂪���̗���œ��X�Ɨ��j�F�������Ă悢�̂ł��B
�܂��A�䂪���ɂ͗l�X�Ȏ���ʼni�Z�����������O���Ђ̐l�X����炵�Ă���A�ނ�̎q���������䂪���̊w�Z�Ŋw��ł���@��������ł����A�䂪���̌�����ł���ȏ�́A���̔z���͕K�v���Ƃ��Ă��A�����ɉ�������K�v�͂Ȃ��ł��傤�B �����Ђ̐l�Ԃɑ��鍷�ʂ͂����Ă͂����܂��A����Ɖ䂪���ɂ����j�F���Ƃ͕ʖ��ł���A��ʂ��邱�Ƃ͌����ĊԈ���Ă͂��Ȃ�����ł��B
�Ƃ���ŁA�G�g�ɂ�钩�N�o���͎��s�ɏI���܂������A���Ƃ���Α҂��Ă��܂����Ƃ���ɃX�y�C�����䂪���Ƃ̐킢�ő̗͂̎���������U�ߍ��݂����Ȃ��̂ł���ˁB�������A�����ɂ̓X�y�C��������N�����邱�Ƃ͂���܂���ł����B�Ȃ����Ǝv���܂����H
����́A�G�g�����S�������܂łɁA�X�y�C���̐��͂������������n�߂Ă�������Ȃ̂ł��B�@ |
�� 16
�G�g�����S����1598�N�ɂ����̂ڂ邱��10�N�O��1588�N�A�X�y�C���̖��G�͑����C�M���X�Ƃ̃A���}�_�̊C��Ŕs�k���܂����B ���̐킢�́A�X�y�C���ƃC�M���X�Ƃ̐��͂��t�]���邫�������ƂȂ�A����ȍ~�̃X�y�C���́A���m�ɌR���͂������]�T���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B
�����X�y�C�����A���}�_�̊C��ɏ������Ă���A���̐������������Ă�����������܂���B �����Ȃ�Ή䂪���̉^�����ǂ��Ȃ����̂����������܂��A�ԈႢ�Ȃ��f���ł��邱�Ƃ́A�A���}�_�̊C��̌��ʂ��A�����䂪���ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ����Ƃ������Ƃł��B
�܂��A���͏G�g�̏o��������I���1644�N�ɖ��B(���݂̒������k��)�̏��^���̃k���n�`�ɂ���Ėłڂ���A�V���ɐ����a������킯�ł����A���������ł��������̈�ɁA�����䂪���Ɛ�������ƂŐ��͂��ቺ���Ă����Ƃ���������������Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�����̎�����m��Βm��قǁA���E�̗��j�ɂ��傫�ȗ��ꂪ����A���ꂪ�䂪���ɂ�������j�ɂ��ׂĂȂ����Ă��邱�Ƃ��悭�����ł��܂��ˁB �u���}�a���̖��v��q�����G�g�ɂ�钩�N�ւ̏o�����E�j�̃��x�����猩��ׂ����Ǝ��͎v���܂��B�@ |
|
�@ |
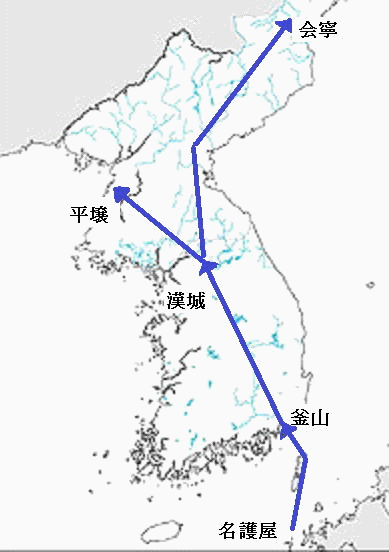 �@���\�̖� �@���\�̖� |
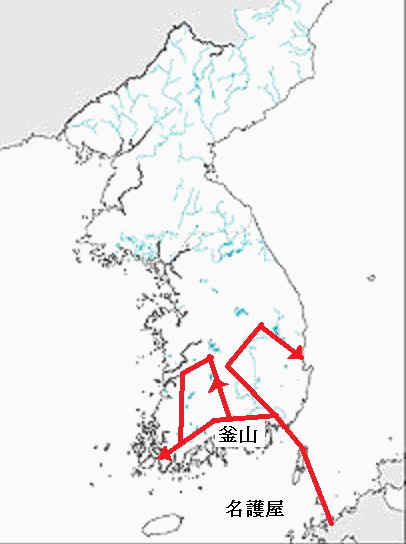 �@�c���̖� �@�c���̖�
�@ |
���������A���{�ɂ�����ŏ��̒��N�l�J����
�@���ꌧ���ҒY�B�̒Y�B�v |
   �@
�@
|
��1 �͂��߂�
�����ȍ~�̋ߑ���{�ɂ����āA���N�l�J���҂̍ŏ��̏W�c�ړ��������ł������̂��A�������炩�ɂ���Ă��Ȃ��B���N�l�J���҂̓n���͖���43�N�i1910�j�̓��ؕ����Ȍ�ł���Ƃ����̂��ʐ��ł���B���̗��R�Ƃ���
�A�p�݈ꎁ������������͖���32�N�i 1899)7��28���̒���352���u����n���s�j�˃��͏Z�m���R�A�L�Z�Uj���O���l�m���Z�y�c�Ɠ��j�փX�����v�̑�l���ɂ��O���l�J���҂̓�������������Ă������Ƃ��w�E����Ă���B���̒��ߑ�1���Ƃ�
�O���l�n����N�n���s�j�˃����Z�m���R���L�Z�T���҃g��A�]�O�m�����n�y�G���n�ȊO�j���e���Z�ړ]�c�Ƒ��m���m�s�׃��׃X�R�g����
�A�V�A�J���҃n���j�s�������m������N���j��T���n�]�O�m�����n�y�G���n�ȊO�j���e���Z�V�A���n���m�Ɩ����s�t�R�g�����X
�Ƃ������̂ł������B���̒A���ɂ���Đ�������Ă����J���҂��A���ؕ����ɂ�蒩�N�l�Ɍ���K�p����Ȃ��Ȃ������Ƃɒ��ڂ���̂ł���B�����Ėp�݈ꎁ��p�c�A����
�A�W�c�ړ��̐����A���c�s�Y�u�����l�J���ғ��n�n�q�̕K�R�I�X���v�Ɉˋ�����
�@�@�@����44�N�ےÖa�ё��ؒÐ�H��
�@�@�@�吳���N���Ɍ������H��
�@�@�@�吳2�N���R�����m�ٗӐ��H��
�@�@�@�吳3�N���{���m�a�A���Ɍ���葢�D��
�Ƃ���B
�������E�̒��ߑ�1���́A��Ɍ��邲�Ƃ��A�ĉp�����I���̏������ђ��Ԑl��ΏۂƂ������̂ŁA���N�l��ΏۂƂ������̂ł͂Ȃ������Ǝv����B�����Ă킪���̐ΒY�Y�Ǝj�ɂ����Ă�
�A�E�̒��ߔ��߈ȑO�ɒ��N�l�J���҂��n�����Ă������Ƃ��m���Ă���B�т������A�����͍���]��Y�w�}�L�Y�ώ��n�̉��R�c�Y�B�Ɋւ��閾��31�N�i1898)2��������������u���N�J���ҁv�Ƒ肷�鎟�̋L�q�������čł��Â��L�^�ł���Ƃ����B
�{�B�ɏׂŒ}�L�l�S�Ɍ�������́[����A���N�̘J���ґ�������Ȃ�Ƃ��A�ډ��̌����͓�\�㖼�ɂ��āA���V���Ɉ�̔[�������z���A��l�̖{�M�l�V���ē��ē���������
�A���̖��Ƃ͉�����������ɂ��āA�J�����Ԃ��ԂƂ�����̒��K�l�\�ܑK���x������A���̎g���̌��ʂɂ��Ζw��ǖ{�M�l�ɈقȂ炸�A���Ԃ�ǍD�Ȃ肵���Ȃė��ɔV�킹��Ƃ��ߔʗ����Ɏ葱���Ȃ�Ɖ]�ւ�
�A�����炸���čX�Ɋ����̒��N�B�v������Ɏ���ׂ�
����ł͏�L�J���҂͉����ǂ̂悤�ɓn�q�����̂ł��낤���B����31�N1��13���̐V���w��i�V��J�͎��̔@���L���Ă���B
���R�c�Y�B���N�B�v���قӒ}�L�Y�B�Ɏ̂Ē��N�J���҂��ٓ���A�ΒY�̌@�̋Ƃɏ]�������ނ�v�悠��͔X���ɕ����A�É͎s���q���̏��L�ɌW�鉺�R�c�Y�B�ɂĂ͑��ɗ��悵�Ď����I�Ɏg�p���鎖�ƂȂ�
�A�����l���ؒn�ɔh���ė�����Ȃ肵���A�ٓ��_��𗹂肵���̐��鑽���A������\�㖼�͗��O���O���R���n�i�M�Ғ��A��i�`�j�ɓ��肽��D�D�䒆�ۂɂĕ��Y�l�ꖼ�ƕʂɒʖ�҈ꖼ�Ƌ��ɒ���
�A�ꎞ�\����i���̋�S�D�ԂɂĐܔ��ɕ����A�����ɂĒ}�L�x���ɏ�ւ։O��w�ɂĉ��Ԃ��A�S�w���k�����R�c�Y�B�ɓ����A���������͌��������̊ؑ��ɂ��āA���ɂ͎�@�t��j��肹����̂���������肫
�A���ّS�Y�B�ɂĂ͒ǁX�������N�̘J���҂��ٓ���r�̌v�悠��Ɖ]�ւ�
���̋L���ɂ��ƁA���R�c�Y�B�̒��N�l�J���҂͊��R����i�o�R�Ŗ���31�N�i1898) 1��10���������������Ƃ��킩��B�w�}�L�Y�֎�j�̋L���͂܂��Ƀz�b�g�j���[�X�ł������̂ł���
�A�����ɂ킪���̐ΒY�Y�ƂɂƂ��ďd��Ȓ��ڂ��ׂ����Ƃ��Ă����������ꂽ���̂Ǝv����B
���R�c�Y�B�́A����27�N(1894�j�É͎s���q�����R����������R�c�A���痼�z��945,950�́A�������Õ�S�F�c�������R�c�i���݁A�R�c�s�j�Ɉʒu����É͂̒}�L�i�o�̐�산�ƂȂ����Y�z�ł���B����31�N2������
�A�B�v��350�l�A�����d�J����Ƃ��Ă��Ė{�i�I�o�Y�̒i�K�Ɏ����Ă��炸�A�o�Y����1�����ϖ�380,000�ҁi228�g���j�A�킪���ŏ��̒Y�z�d������}���ēd�C�r��
�A�d�C���g�̏������ł������B���̂��߁w�}�L�Y�ώ�J�̒��N�l�B�v�̖��Ƃ́u�����������j�ł������B������4�����ɂ͍̒Y�����{�i���������߂����̂悤�ȐV���L��������B
��N���S�Y�B�i�Z�A���R�c�Y�B�j�ɏׂŒ��N�B�v���㖼���ٓ��ꂽ�鎖�͓����̎���Ɍf�������A�S�Y�B�ɂĂ͓����̊ԁA���B�O�̎��ƂɎd�����đ��n����҂��r���肵�ɁA�������]���Y�B�̎���ɒʂ�
�A�B�O�ɐf�ď]�Ƃ�����J��̒Y���Ȃ��̗��v�������莩��B���ɓ���Ƃ���ӂ��̂���Ɏ��肵���A�q�����{�i���A 4���j���̒Y���Ɏg���Ȃ������A�ޓ��͈�Ӓ��~���Ȃ��ċA������Ƃ̖ړI�Ȃ���
�A�����ɂĂ͔��ɕחサ����R�A�˂Ď������ɏׂł�����ׂ����z�̒��~���Ȃ����߂�ƂĕX��^�����A���B�v���̏]������B�ɂ͑��̓��{�B�v�Ƌ�ʂ��Ȃ��āA���ܑ��_��\�h����
�A���ɋL���A��\�㖼�̓������ʕٓ��ɏ]��������̌ܖ�����A���ۍ̌@�ɏ]������n��\���Ȃ�
�E�ɂ��ƁA 4�����{�����29����20�����̒Y�v�ƂȂ������A���{�l�B�v�Ƃ̖�Ɍ��ܓ����������悤�ŁA�[�������łȂ��A�̌@����i�؉H�j���ʂɂȂ��Ă������Ƃ��킩��B�c�O�Ȃ���
�A���̌É͉��R�c�Y�B�̍B�v�̂��̌�������j���͑S�����݂��Ȃ��B
���������N�l�B�v�̌ٗb�͌É͉��R�c�Y�B������ł������̂ł͂Ȃ��B���̋L��������B
�i�O���j :t�S�Y�B�v���R�ׂ̈ߍz�Ǝ҂̍���͈�w�̎��Ȃ邪�A�������Ɉ˂�A�}�L�Y�B��̒��Ƀn�ނ̓����Q�ꎁ�����ҒY�B�Ɍٓ��ꂽ�钩�N�B�v�D���тȂ�����ĒǁX�������N�B�v�������Ƃ̋c����
�A�e�Ɋp���ҒY�B�̎������ɑ��ٓ��̎葱�����邽�ߋߓ��̓������ψ���h������R�Ȃ�
����͌É͉��R�c�Y�B������31�N1���}�L�ōŏ��ɒ��N�l�B�v�������O�N�A����30�N(1897�j�H�̂��Ƃł���B���̋L�����́u�}�L�Y�B��v���É͉��R�c�Y�B�ł��������ۂ��͖��m�ł͂Ȃ���
�A���B�ɐ�삯�āA�����Q�[�����ҒY�B�Œ��N�l�B�v���ٓ���Ă��邱�ƁA�����}�L�̒Y�z�o�c�҂��������Ă���̂ł���B���̒��ҒY�B�̒��N�l�ٗb�ɂ��Ă͒n���V���w���ꎩ�R�x���u�W���B�v�ɊO���l�Ȃ钩�N�l���ٓ��ꂵ�n��B�݂̂��n�e�{���Ƃ��△�̂��Ƃɂ�
�A���i���A�����Q��j�������ɑ�����Ȃ�ׂ��v�ƋL���A���}�L�n���ł͌É͉��R�c�Y�B���ŏ��ł������Ƃ���O�f�w�}�L�Y�ώ�J��w��i�V��x�̋L�q�����炵�Ă��A���ҒY�B�����N�l�J���Ҍٗb�̐��ł��������Ƃ͖��m�ł���B
�����ŏ��e�͒��ҒY�B�̒��N�l�J���҂̓����o�߂Ǝ��Ԃ��Љ�悤�Ƃ�����̂ł���B�j���́w��i�V��x����ɖ���30�N9��19�����10��1���܂�10��ɂ킽���ĘA�ڂ��ꂽ�h��q�u���ҒY�B�ɑق��钩�N�J���ҁv���n�߂Ƃ�
�A���̑啔����V���Ɉˋ����Ă���B�V���̎j�����l�ɂ��Ă͎�X�̋c�_�͂��邪�A�V���L���ȊO�ɂقƂ�Nj���ׂ����̂��Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠��������Ɉˋ����Ȃ���A����j���̔��@�ɓw�߂����B
�@ |
��2 ���ҒY�B�ƌo�c�ғ����Q�[
���ҒY�B�́A�ɖ����p�̐��݁A���ꌧ�����Y�S���R�㑺�厚��i���݁A�ɖ����s�j�ɂ������B���B�ɂ��āA���̊J�B�A�R�̌�����o�c�𖾂炩�ɂ���j���͂Ȃ�
�A�V���L����w�z��ꗗ�x�Ȃǂ���A�킸���ɂ��̈�[���M�����Ƃ��ł��邾���ł���B�u�z�R���v���v�ɂ��ƁA�����Y�S�̐ΒY�̌@�̗��j�͓V��10�N(1839�j���܂ők�邱�Ƃ��ł���B���i���Y�Ƃ��Ă̐ΒY�̌@���s����悤�ɂȂ�͖̂������N����10�N�ɂ����Ăł���B��ł�
�A����7�N�i1874�j�ɐΒY����������A��8�N�̌@���J�n���A 14�N�i1881�j���ɂ͖}��100�l�̍B�v������ɏ]�����Ă���B������10�N��㔼�ɂ͂����ׂĂ���������
�A�ĊJ�����̂�20�N��㔼�ɂȂ��Ă���ł���B
���ҒY�B�̖��̂̏����͖���27�N�i1894�j�́u���@�̌@�̎�ꗗ�\�v�ł���B���̎��A���R�㑺�厚�v������̍z�R���̂��g���ҁh�A�z�Ɛl�������g�����Q�[�h�ƂȂ��Ă���B��28�N(1895)6��
�A���ҒY�B�͐V����1�T�Ԃɂ킽��u�B�O���ىҐl��W�L���v���o���B
�j���V�ᐔ�S�l��W����A�j�q�͏E�l�A�܍Έȏ�̂��̂Ȃ�n��X�K���̎G���ɏ]�������ށA�g�̋��s�̂��̃n�ΒY���d�Ɏg�����A���q�n�\���ȏ�̂��̃n�V�c���n���I�Y�ɏ]��������
�A�����n���Z�t�̔@���ɂ�葊���̒��K�������A�ł��j�q�s���̂��̃n�����E���K�ȏ�Q�E�K�܂āA���q�n�Q�K�ȏ�E��K���Ƃ��A�d����̏n�B����ɐ��БQ���������A�Ƒ���S���z�����̂͐Q��H������Q����ΉƔ��m�A�ݓn��
�A���ĕ֗��Ɏ�v�\�A�]�~�̎҃n���}�\������ׂ��i�㗪�j
�������̐V���j��ɂ�����Y�z�J���ҕ�W�L���͒��������̂ł���B�Y�z�J���҂͂����Ƃ����������Ⴂ�K�w�ł���������A���R�L���̑ΏۂƎ�ӂ́u�e�n�L�u�Ə��N�A��ߖT�ɐԕn�̂��̂ɂČ��Ђɍ�����[����̂���n���L���̎�ӂ��䎦������Ƃ���]���v��Ƃ���ɂ������̂ł���B
�����炭���̍����ҒY�B�͖{�i�I�ɉҋƂ��J�n�������̂Ǝv����B���̂Ȃ�A���̂悤�Ȏa�V�Ȏv���������L�����݂邱�Ƃ��ł��邾���łȂ��A���̂悤�ȏ����邩��ł���B�B�哌���Q�[�������ɍz����l������̂�
�A����23�N�i1890) 2�����ꌧ����S�ʕ{���̌É�R�Y�B���O�H�Ђɏ��n���Č�̂��Ƃ��Ǝv����̂ŁA���ҒY�B�̊J�B�͖���23�N����28�N�̕��Ƃ������ƂɂȂ�B������
�A 24�N����6�N�܂ŒY���͒�����Ă����̂ŐV�K�J�B�͍���ł������ł��낤�B�����炭�{�i�I�ҋƂ̊J�n�͓����푈�����푈�����27,8�N���ł������낤�B29�N10���ɂ́u�]���̌@�����肵�Y�w���ɒ��Đ��鏃�ǂȂ�Y�c����
�A�V���ɍB���J�@���v�ŁA���̍B���͗�11���ɒ��ҒY�B������S���\���̂Ƃ���u��v���Y�C�݁v�Ɋ��������B
����30�N�i1897�j�ɂ͍B�v400���ȏ���ٗb���A�����̏o�Y��120�g���]�A��v�̘H��d�B���c�Ƃ���ɖ����Y�c���ő�̒Y�B�ł������B�V���͎��̂悤�ɕĂ���B
�����Y�S��v���k���Y�S���˂Ɏ��鎡�݂ɂ��鐔�S�̒Y�B�͊T���ĐΒY�̍̌@���͌��p������ɔ����A�d�B�n�����c�̌i�C���������ׂ߁A�ΒY���ς̖ړI�ɗ����D���͉��݈�тɑ�����
�A���X�̎��v���[������������Y�B�͓����Q�ꎁ�̏��L�ɌW�钷�ҒY�B�݂̂ɂāA�ډ��B�v�̌ٓ����ꂽ��Ҏl�S�]���A�����̏o�Y����\���҈ȏ�ɋy�ы����i�㗪�j
���������̌�̒��ҒY�B�Ɋւ���L���͋ɂ߂ď��Ȃ��R�N�������炩�ł͂Ȃ��B���������͖��m�ł͂Ȃ����A�u�s�K�ɂ��āA��X�V�Ђ̐N�����ƂȂ�āA�厸�s�𗈂���
�A�p�Ƃ̎~�ނȂ��Ɏ�j�����悤�ł���B
���ҒY�B�̎����I�o�c�ғ����Q�[�͐��N���c�N���s���ł���B��O������S���h�����i���݁A����s���h�j�o�g�̎m���ŁA����20�N�����͌����ł������B�����炭�\�𗣂ꂽ��̐��v�̓���Y�z�o�c�ɋ��߂��̂ł��낤�B����8�N(1875�j����S���v�������r�J��5000�̍z����l�����ĒY�z�o�c���n�߂��B���B�͈Ȍ㖈���}��20���ҁi120�g���j���o�Y��
�A����14�N����30���̍B�v���g�����Ă����B�܂�����9�N(1876�j�N�ɂ͓��S���������I�m���̖I�m���Y�B�i�z��ؐ�1���j�����A���B�����āu�Z�N�m�������Y�������V
�A�Q�N����S���җ]�o�Y�Z�V���A���\�N�O�䕨�Y��Ѓg���̔��A�ȃe���ʖڃ���ρv�������߁A����S���w�̒Y�B�Ƃ����B�����11�N�i1878�j�ɂ͓����M�m�،�������J��2700�̍B����l����
�A���v�n���ɂ���������Ƃ��L�͂ȒY�z�o�c�҂ƂȂ����B
�ނ����đ��v�n���̂����Ƃ��L�͂Ȍo�c�҂��炵�߂��̂́A�����ȖI�m���Y�B�̌o�c�ƂƂ��ɁA���������v�n���ΒY�̘̔H�̊J��ɓw�͂������Ƃɂ������B�����̒Y�B���n������S�ʕ{������є[�����̐ΒY�≮�Ɉˑ����Ă�����
�A�ނ͔~��`���A�g���v�ׁA���������A�����N��O9���̍B��ƘA�g���ĎO�䕨�Y�Ƃ̕��Ɂu��O���v�ΒY��菑j�����сA�������A���v�����̌@�ΒY�̐V�̘H���J���B���̌_���
�A����10�N(1877) 2��26�����_��A 3���ɖ{�_��ɉ��߂�ꂽ�B�ނ����̌_��̎各�i�҂ł��������Ƃ́A�����̒n���o�c�҂����������āA�u�����Y�B�刽�n�Ґl�㗝j�̕M���_��҂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��琄���ł���B�ނ͉E�̍B�傽���ƂƂ���
�A����11�N6���ɂ͈�]���ĉ]�H�ЂƂ̊W���Z���ȁg�^�Y�Ɂh��g�D���A�u�^�Y�m�ی샒�ꃉ�g�V�A�e�B�m�o�Y���R��A�������y��j�����V�A�㉺�m�i�ރ����`�A�i�ʑ����m���㉿���胁
�A�����n�V�������m���A�Z�m�]��������y�_�ˑ����m�����G�^���V�A�e�㉿�m�������Z�V�����g�v�����B�������Y�z�傪�������Ĉ���I�̘H�̊m���ɓw�͂����̂ł���B
�������ނ͂���ɂ������炸�A�ݗ���1�N���܂�ʼn^�Y�ɂ��痣�E���A�P�ƂŒ���Ɏx�X��ݒu�����B�u�z�R���v���v�͖I�m���Y�B�ɂ�
���N�i�M�Ғ��A 11�N�j�����������n�e�B�Ɛl���^�Y�Ƀ��ݗ��V�A���n�B�Y���e����O���l�y�q�O�H��ЃG����`�j���e�̔��A���\��N�㌎�^�Y���������V�A�X�j����`�j�x�X���݃P
�A���`�H�앪�Njy�O�H��ЁA���������H���ȓ��G�̔��v
�ƋL���Ă���B�����̑��v�n���̏��Y�z��ɂ͌����Ȃ��ϋɓI�o�c�ł���B�Ƃꂪ���s�����̂��A����16�N�̒i�K�ł́A�I�m���Y�B����͊��ɓP�ނ��Ă���A�O�q���r�J�Y�B�Ə����������Y�B�̂o�c���Ă���B������19�N�́w�z�R�؋�ꗗ�\j�ɔނ̖��O�����o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B���̈����
�A 17�N�ɌÉ�R�Y�B�i����S�ʕ{���A�؋�l�䌴�����A�ēc���Z�A�؋�ʐ�440,360�]�j�̉ҋƐl�ƂȂ�A�����23�N(1890) 120,000�~�ŎO�H�m�ɏ��n���Ă���B�����炭���̌�ɖ����n���ɐV���ɒY�B�����߂����̂Ǝv����B�Ȍ�O�q�̂��Ƃ�����27,8�N����蒷�ҒY�B�̌o�c�҂Ƃ��Ċ���B
����30�N�i1897�j�V���w���ꎩ�Rj�͌����e����i�_�ƁA�H�ƁA��s�Ȃ�10����j�Ŋ�����ƉƎO����ǎғ��[�ɂ���đI�o�����B�����Q�[�͂��̐ϋƕ����
�A�`���ƂƂ��čō��_�Ă���B���͕̓q���ƍ���ɍD�A�L���ƍ���ɍD�ł���������A�����F�m�J�A���m�A�M�m�،��A�ԍ�����̏��Y�B���o�c���A���ÐΒY�z�Ƒg�����ł���������ɍD�ɔ䌨����
�A�����ł͋ɂ߂Ē����ȒY�z�o�c�҂ł������B�g�`���Ɓh�ɂ́A�{�e�̃e�[�}�ł��钩�N�l�J���҂̈ړ����傫���]������Ă�����������Ȃ��B�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�O�q�^�Y�ɂ̐ݗ��Ǝ��s
�A����`�ɂ�����P�Ɣ̔��̎��݁A���D�Ƃ̌��c�ɂ݂�悤�ɁA�`�����͔ނ̌o�c�p���Ƃ��ĂƂɒ����ł������̂ŁA����B���̂��Ƃ͌���ނ̊C��Y�c�J���v��Ɋւ��āA�V�����u�e���p���悵�đ��l�̊�ē�����̋Ƃ�����_�l�̔@�����ɂ��炳��Δ\�͂��邱�ƂȂ�ׂ��v�ƕ]���Ă��邱�Ƃɂ��M����B
�ނ͍��ꌧ�ΒY�Ǝґg���̐ݗ��ɓ����Ă͕]�c���ƂȂ�A����ɍ��ꌧ�ΒY���Ƒg���̑n���̂��߂ɂ͍���ɍD�A�͑�����Y�A���c�����Ƌ��ɔ��N�l�Ƃ��ė͂�s�������B �@ |
��3 ���N�l�J���҂̓����o��
�����푈��̐ΒY�Y�Ƃ͎s��̊g��ɂ���Ė��]�L�̍D����悵���B�u����������ʎ��ƃm�u���g���ɐΒY�m���v�ڃj�����V�A�����O��E��N�m�@�L�n�z�ƃm�S�����Ƀ��v���̂ł���
�A�܂��u��\��N���O�\�N�A�O�\��N�̍��ɂ����ẮA�Y����ɐU�ӂĎz�Ƃ̗����O�Âɔ�ȁv�������̂ł���B
������D�����ō��ꌧ���̍B�v�s���͈�w�����ł������悤�ł���B����29�N����30�N1���ɂ����Ắu���ꌧ���̍z�Ƒ吨�v����V���͎��̔@���L���Ă���B
��N�ďH�̌�i�M�Ғ��A����30�N�j��}�L�l�S�͍���艽��̒Y�B�ɂł��z�v�̌��R�Ƀn���ɍ���𗈂�������A���ꌧ���ɉ��Ă͈�w�r�������A�����ʂƂ��Ċe�S�̍z�ƉƂ͎ƁX�W��ċ��c���鏈������[���̌��ʂ�����
�A�ډ��}�L�e�Y�R���z�v�̋����ɋꂵ�ނ�ɂ��S�͂炸�A���ꌧ���̊e�Y�B�ɑقĂ͍����ّ����R�ɋ�߂���́r�@��
���̍��ꌧ�������ɔ䂵��w�B�v�s���ɋꂵ���̌����͍���̖��Ƃ��āA�����ŊJ���邽�ߒ��ҒY�B�́u�����I�z�ƉƁv�����Q�[�͊O���l�J���҂̏W�c�ړ���}�����B
���̌o�߂��u���ҒY�B�ɉ����钩�N�J���ҁv�ɂ���Đ�������Ǝ��̒ʂ�ł���B
������29�N12�������l�J���Ҍٓ����}��A��X���꒷�茧�m���ɑ��k�B
����X�m���͒��N�l�J���Ҍٓ�������߁A������n���茧�O���ے����^���B
�����N�l�J���ґw����Ɍ��肵�A����s���S������r��Y�i�Δn�o�g�A���ɓ������N�l�����N�J����2����b���j�Ɉ˗�����B����w�͂�����i�W�����B
������30�N5���A��R�z��s���L�c�����풩�N�A���h�߂̂��ߗL�c�Đ����t�͕��Ƃ��ĐE�H�ٓ���̂��ߗ����B���R��R�فA�ʖ�����ƒ��ҒY�B���@�B
�������Q�[����эB�匴����i�����Q�꒷�j�j�͏����ɒ��N�l�J���Ҍٓ�����˗��B������2�E300�l�Ȃ�\�ƈ˗������B
�E�̂��Ƃ��o�߂̌�A����������W�����l�Ƃ��Ă��悢��J���ҕ�W����̉������̂ł������B
�����炭�����Q�[�͓����푈�̌��ʂ��璆���l�J���҂̓�������悵���̂ł��낤�B����ɑ��A��X���茧�m���̋����́u�x�ߐl���ٓ����ɂ͏��ł�����ȂĎ�X�̎葱��v����Ɉ��ւ�
�A���N�m�A����Ȃ���Ȃč����ʓ|�̎��Ȃ��ɏA���A���������֗��Ȃ��j �Ƃ������̂ł������B�����A�V���{�͖���4�N�i1871)���łƏC�D���K�A�ʏ��͒��ɒ��邪
�A�ĉp���I���Ɠ��l�ɁA�����l�̋����n�O�̋��Z�A�ʏ��𐧌����Ă����B����ɑ��A���N���Ƃ͖���9�N�i1876) 2���ɏC�D���K�A�X�Ɉ�����8��24���ɏC�D���K�t�^�ɒ��邪
�A���N�l�ٗb�Ɋւ��Ă͂��̕t�^��5���ŁA���N�����{�̗������݂̂ł悢���ƂɂȂ��Ă����B
��܊��c��V�^�����N���e�`�j�E�e���{���l���n���N���l�������كX�������փV�A���N���l�������{�m�������n���{���j�������W���V
�����Q�[�̓����̗\��́u�O���l�ٓ���͐V�K�̎��ɂāA�ޓ����\���p�����ۍƍ�����s�\��j�t�A���x�͎����ׂ̈ߌ\�l������ٓ���A�s���X������ΌܕS�l���ٓ��x�v�Ƃ������̂�
�A�����I��50�l���x�ٓ���A�J���Ҏ���ŒY�B�S�̂N�l�B�v�ɂ���Čo�c���悤�Ƃ�����̂ł������B���̂��ߏ������A����͂�2�T�Ԃ�200�l�̌ٓ��ꂪ�o�������Ƃ�m�点�ė������ɂ�
�A�����́u���N�l�ٓ���̎�����O��Ȃ����ɂ��āA�ʂ��čD���ʂ��o���Ȃ����Ȃ�c�c��ØZ�\���䂯�n�q���ׂ��|�����v�̂ł������B���̂悤�Ɂu�`���I�z�Ɖ�J�����Q�[�����Ă�
�A�O���l�J���Ҏ����ɂ��Ă͑傫�ȕs��������A�T�d���炬��Ȃ������B
�������đ���59�l�i����2�l�͐������̂��߁j�B�v57����2�ǂɕʂ�ė��������Bl��20���͒��c�ʖ�̈����ŁA����30�N�i1897) 8��2���m�씭�̗X�D�f��ۂɏ�D
�A 6������`���A�����ɊC��Ő��c��ۂɏ�ւ��A 7���ɖ����p���璷�ҒY�B�ɓ��������B2��37���͏������삪�������ē�z�ۂɏ�D�A 8��11������`���A 1�Ǔ��l�̕��@�ňɖ����p�ɓ��`�����B����ɂ�
�A�������Y���g�A����A�m��̊e�̎��A���{�Ԑ����Y�S���A�X�D����x�X�x�z�l�g���q�����̉���������A�X���[�Y�ɐi�s�����B
�����Q�[�͎���꒼��Ɏ��̂��Ƃ��͏����O����b���ɍ��o�����B��X���茧�m���̎����̂��Ƃ��A�����葱�͂���݂̂ŏI�����A�����̖ʓ|���Ȃ��A�����ĊȒP�Ȃ��̂ł������B
�@�@�@���
���ʒ��N�����j�\�����ʎ��̒ʂ�b���A���L�̎����v��ɕt�A���i�y���͌��
��Ɩ��͍B���ɉ��č̒Y�̋Ƃɏ]���v��
�ꋋ���͍̌@�������Y�n�S�ɕt���K�l�K�Z�Ёi�b�������j�A���Y�O�K�[�و��̎��A�A�Y���̍���Ɉ˂���K�̑������Ȃ�������ׂ�
��b���_��N���͖����O�\�N�����\�����薾���O�\�ܔN�����\�������܃��N�̎��A�A���{�N�����ƗY�ǂ��B�Ə�̓s���Ɉ˂��b���鎖������A���ꍇ�ɖ��S�ăn�O�냖���e����ƒ��K���̕��ϋ��z�E�ܓ������x����
��Z���͍B�Ə�A�������ꌧ��O�������Y�S���R�㑺�厚���A���ҒY�B�̎�
�����{�鍑�̖@�������炵�A���{�l�B�v�S�l���ҒY�B�̏��K���y����ɕ��]���ׂ���
���ꌧ�����Y�S���R�㑺���ҒY�B
�����O�\�N�����\�����@�@�@�B��@�@�@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�㌩�l�����Q�[
�@�@�@�O����b���ݑ�G�d�M�a
�����ł͎葱�o�߂݂̂��Љ�A�E�̌_����e���ɂ��Ă͌�Ɍ�������B�������Ă��̎����������J���҂͕\1�̒ʂ�ł������B�ŔN����18�ˁA�ō��N��36�ˁA���ϔN��25.6�˂ł܂��Ɂu���C�����̑s���v�ł������B�o�g�n�͋���34��
�A���R16���A������2���A���̑�5���ł���B�Ƃ̂悤�ɋ��邨��ъ��R�o�g�҂��������߂闝�R�́A�u�ŏ��̎��Ȃ�ΐ���ׂ����{�̎��Ȃ�A���ꕗ���Ɋ��ꂽ����́A�������{�����n���߂̂��̂�������Ɋ����
�A���ɍ݊؋����{�M�l�̓@��Ɍق͂ꋏ�肵���̏E�]�l����v�Ƃ������Ƃł������B
�`���I�ɂ��T�d�ɓ����������N�l�J���҂ɑ���J���Ǘ��ɂ��Ă͌�ɏЉ�邪�A�ނ�͌o�c�҂���������ɂ߂ėD�G�Ȑ��т��������B1��20���͓�������������B�̒Y��
�A 2��37���͋��~3���ԋx�Ƃ���15���������B�����B
�@�@�@�\1 ��1�����N�l�J����
�@�@�@�J2 ���B�l������ђ���
�\2�͍ŏ�1�����Ԃ̓��B�l���A���ƍ��i�������z�j�A���ϒ��������������̂ł���B���ϒ����͏�����24�K�]���Œ�z�Ƃ��A�ō��z��67�K�]�A1����1�l����47�K78�ł������B���ҒY�B�̓��{�l�B�v��ߗגY�B�̕��ϒ����ɂ��Ă̎j�����Ȃ��̂�
�A�����}�L4�S�̓����̕��ϒ����Ɣ�r����ƁA����S63�K5�ЁA�Ǝ�S54�K6�ЁA�Õ�S62�K7�ЁA�c��S57�K2�ЁA 4�S����59�K5�Ђł��邩��S���̖��o���҂ł��邱�Ƃ��l������Ƃ��̗D�G�����킩��B����������ȏ�ɕ]�����ꂽ�͓̂��B���̍����ł������B
������s�����瓖���̕s���͕��@����A���ҒY�B�͎��X�ƒ��N�l�J���҂��ړ������B���������ꂪ����ɂ킽�����̂��A���l���������ł������̂��K�����������ł͂Ȃ��B�V����f�ނɌ�������O��
�A�nj��̌���j���͂Ȃ��B���قɊւ���L�������ĕ\�ɂ���ƕ\3�̂悤�ɂȂ�B�O�q�̂��Ƃ���1��̓�����2�ǂ�
�����č��v59���ł������B�@�͗\��L���ł��邪�A�A�ɂ��Ɓu���Ă�蔪�\�]���̒��N�J���҂��ٓ��ꋏ�肵�v���Ƃ���A���ۂɌٓ����ꂽ���̂Ǝv����B�A�́u�������N�J���Ҏ��\�������ٓ��ꂽ��R�A���B�匴���ꎁ��葴�ɓ͏o���v���̂ł��邩��
�A�l���͕ʂɂ��đ��ق͎����ł��낤�B�B�ƇC�́A���ِl���A���������قȂ��Ă���B�܂��\�L�ȊO�ł��A��i���璷�ҒY�B�܂ł̌o�H�����͖�s��ԂŇC�́u���d�M�ۂ̍K�ւɂĈꓯ���Ö��C�H�v�Ƒ��Ⴕ�Ă���̂ł��邪
�A�₶�j���[�X������̂ł��낤�B
�@�@�@�\3 �V���ɂ݂鑝�ىߒ�
�ȏ�̂��Ƃ��l���A���V������R�Ȃ����Ă���Ɖ��肷��A���ҒY�B�ٗb�̒��N�l�J���҂́A��1��59���A��2��40���A��3��77���A��4��54�`56����4��ɂ킽�葍����230���ł������ƍl������B����͑O�q�̏������삪�h��2�T�Ԃ̊ԂɁu�J���ғ�S���ٓ��̖o������j �Ƃ���_��
�A��1��̎����̗p�̍D���ʂɂ��A���ׂĎ��s���ꂽ�ƍl���邱�Ƃ��ł��傤�B�V�������̂��Ƃ��L���Ă���B
�i�O���j���������ŏ��ٓ��̖��Ȃ����n��S���Ȃ肵���A�e�Ɋp���]�L�̂��ƂȂ�n�A�����̈��Z�\����g�����邱�ƂƂȂ肵�ɁA�O�L�̔@�����ɂ߂ėǍD�Ȃ���Ȃ�
�A�O��̔@���c���S�l�\���������炸�Ċ锤�ɂāA���蔤�����ɐ��Ћ�����Ȃ�i�㗪�j
�ƁB�܂��Ƃ̐l���́A���w��������������31�N5���ɒ��ҒY�B�J���҂̏���サ�Ė�i�x�@���Ō�����u�ނ̘J���҈�S�\���v�i��q�̖\���ɂ��60�����E����j�Ƃ��قڈ�v����̂ł���B
��2��ȍ~�̘J���҂Ɋւ���ڍׂ͕s���ł���B�����B�́u�S�J���҂͏d���Ɍ��R�n���̂��̂ɂāA�O���̂��́r�@���f���a���ɂ��炸���đS�̂̊ؑ����Ȃ����肽��v�ƋL����Ă���B�����炭��2��ȍ~�����҂���1�łƓ��l��
�A���{�����n���ӂ́A�Y�B�J���҂ɂӂ��킵�������̐s�N�ł������̂ł��낤�B �@ |
��4 ���N�l�J���҂̘J���Ɛ���
���ҒY�B�Ɍٗb���ꂽ���N�l�J���҂̘J���Ɛ������A �����ł���Ƃ��āu���ҒY�B�ɏE���钩�N�J����j�Ɉˋ����ďЉ��B�������̏ꍇ�A����1��J���ғ�����͂�1������̒����ɂ��ƂÂ����̂ł��邱�Ƃɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ǘ��A�����g�D
���N�l�J���҂��Ă���W�����l��������ɂ���ē������ꂽ���A�����͒P�Ȃ��W�����l
�ł͂Ȃ������B�����̖����ɂ��ď�L�͎��̂��Ƃ��L���Ă���B
�ޓ��J���҂͒ʖ�ɂ��ē����Љ���Ȃ����鏬�����쎁����ƂȂ�ĒY�B�������Ƃ̕��Ɍ_����挋�Ђ���Ȃ�A�Ⴕ���݂̍B�v�ɂ��Ď~���鎖�̂���A������l�̏ꍇ�ɍۂ���
�A�������͒����ɑ���[���Ȃ��̐ӔC����A�Ƃ苎�A�݂̂Ȃ炸�S�̂ɏA���ӔC��L����Ɉ˂�A���������͔ޓ��J���҂����X����������K�����̈늄�ܕ��ɑ��������V�����������ɑ��^��
�A�B�v�����͈ꕶ����Ƃ����������炴��|�_����Ȃ���A�ł����~���鎞�͎������̏����Ă�������鎖�Ƃ̖���R
�܂��ʂ̋L����
���N�l�n�{�M�ƌ��ꕗ�����قɂ��������ȂāA�B��ɏE�ăn�ʖ�����˒��N��ɏn�B����ΏB�l���������Y��������Ƃ��A���N�l��̎������������ス���߁A��������20�l���ɓ����݂�
�A����������ĘJ�������̎w�����Ȃ����ނ�R
���Ƃ�ɂ��ƁA�����͒��N�l�J���҂̕�W����т��̕�[�݂̂Ȃ炸�A�S�̂ɐӔC�������Ǘ�����u���j�Ƃ������̂̔[�����ł������B�ނ͒Y�B�o���͂܂������Ȃ������Ǝv����̂ōB���J���̎w�����Ƃ邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ł��낤�B�������啔�������{��������Ȃ��J���҂����ĉ~���ɍB���ŘJ�������߂邽�߂ɂ�
�A�ʖ�Ƃ��čB���ɂ�������A�o�Y��������̂ł͂���܂����B�����Ĕނ͓��{�l�[�����Ɠ��l�ɘJ���Ғ�����1��5���̕�V���̂ł���B
��������̉��ɒ��N�l�J���҂̒�����u��\�l���v�����́u����v�ƌĂ�钆�ԊǗ��҂��C�����ꂽ�B�Ⴆ�Α�1��1��20���ł͗ђ����i���R�o�g�A 26�ˁj���u��\�l���v�����Ƃ߂��B�u����͗��ٓ��{��ɒʂ��������́r�݂Ȃ�n�{�M�B�v�Ƃ̈ӎu���ʂ��܍��X���݂̂Ȃ炸
�A������̎w���ɂ͊F�y����Ő��]����i��ދɂ߂Đ��l�����ɂđ����s�̍ق̏�����v�Ȃ������Ƃ����B�����������͂ł͂Ȃ����{��\�͂ŔC�����ꂽ���悪�A������n�߂Ƃ���Y�B�����{�l�̊Ǘ��g�D�ɑg�ݍ��܂��Αg�ݍ��܂���
�A���N�l�J���ҁe�̒��ł͖����������悤�ł���B
�ނ�͒Y�B���������ɂ͑��������B���̒Y���s�����B�������S�����u�����]�ĒY�B�������������Ȃ��A���ɍB���̌@�̖͗l�ɘc��ăn���z���ɒm�炴J�肵�J���҂ł������B���̂��ߒY�B��
�A�u��\�l���l�ؗt�ɕ����A��ؗt�Ɍܐl���A�Ƃ����߁A����R���O�l�Ƃ���l�͌�R�̋Ɩ��ɏ]�ЂʁA�R��ɊF�Ȗ��o���̂��̂ɂāA�ߖ̈��Зl���֒m�炳����̂Ȃ�A�f���Y���̋ؖڂȂǒm��R�Ȃ�
�A�˂�Ĉ�ؗt���ɏn���Ȃ�B�v��l�Ė����̋������Ȃ����߁v���B
�����̎c�����̒Y�@�ɂ����ẮA��؉H�i�̌@�ꏊ�j�ŁA��R�i�d���ɏn�������A�̒Y��Ƃ̎�v�������s�ҁj��l�A��R�i��R�̕⏕��Ɛ��s�ҁj��l�Ȃ����j�l���ʏ�ł������B�����Đ�R����R���w���w�������B���̏ꍇ
�A��R�ƌ�R���ɋ}���ɗ{�����Ȃ���Ȃ炸�A�������ʖ�҂����Ȃ������̂Łi�t�ɂ����Γ��{���������J���҂����Ȃ������̂Łj��������@���Ƃ�ꂽ�̂ł��낤�B�]���Ă���͓��������̍B�v�{���̂��߂̈ꎞ�I�[�u�ł�������������Ȃ�
���̂��Ƃɗ��ӂ��Ȃ���A �����Ē��ҒY�B�ɂ����钩�N�l�J���҂̊Ǘ������g�D�����Ă����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�Ƃ���ł��̍̒Y��Ƃɂ�����J���ҊǗ��ɂ����āA �����Ƃ����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́u���N�l�Ɠ��{�B�v�Ƌ��ɏ]�Ƃ����ނ�͎��R���ܓ�����N���̋��ꂠ��Ɉ˂�
�A�\�Ē��ӂ��鏈����A�S���Б����قɂ��鏊�ɁH�H�č̌@�����ނ鎖�v�Ƃ��A�����Y�B�ɂ�����J���҂ł���Ȃ���A�J���ߒ��ɂ����ē��{�l�ƒ��N�l�J���҂͋��������Ȃ��ǂ��납
�A��Əꂷ��Ƃ��ɂ��邱�Ƃ��o���Ȃ��悤�Ɋu�����Ă������Ƃł���B
�J������
�J�������͌ߑO6�����ߌ�6������12���ԂŁA�x�Ɠ��͖���3��ł������B���̋K��͓����ʏ�̂��̂ł������B�����Ƃ����ɑ����e�r�E�v�������w�E����Ă���悤��
�A���������K��͒����Y�B�ł͗L�������Łu���o�Y�����œ������Ƃ���j���ʒ����ԍݍB�����ʂł������B���ҒY�B�̒��N�l�J���҂̏ꍇ���܂��ɂ��̒ʂ�ł������B�h��q�͎̕��̂悤�ɋL���Ă���B
�����͌ߑO�O���Ⴍ�͎l������葱�X���B���A�̂ɒ荏��葁�����B��������̃n�v��䂯�������Ƃ��x�݂ďo�B����̎��R��^�������A�R��ǂ�������̑O�Ɏ���A�K���������̌@����Ή����҂ɒB���K��̏ܗ^��Ƃ��ӏꍇ�ɍۂ����
�A�Ƃ���B���Ԃ����グ�čB���ɓ���݂̂Ȃ炸�A�c�ߌߌ�\�Ɏ�����ړI�̍̌@�𗹂�ɂ��炴��B�O�ɏo�Â鎖�Ȃ��ƁB
�J������
�����́A������1�����Ԃ̏ɂ��Ă͑O�q�����ʂ�ł���B���̊�́A��������ɏЉ���u���j�ɂ��ƁA�u��Y�S�҂ɕt���K�l�K�Z�Ёi�b�������j�A���Y�O�K�[�Ј��v�ł������B�����K��͊e�Y�z�Ƃ��ɂ߂ĕ��G��
�A�o�Y���ɉ����Ď�X�̊����̊������A�ܗ^����t�^����̂��ʏ�ł������B�E�́i�b�������j�����������ӂ������Ă���A�S�҂ɕt4�K6�Ђ�4��̊�̕��ς����������̂ł��낤�B
�ނ�͒荏��葁�����B���A���W����T�@���閘�o�B�����A���ɓw�͂����B���̂��ߏܗ^���̎�ܔ䗦�����{�l�B�v�̕S�l�ɕt16�l666�ɑ��A 35�l08��2�{�ȏ�ł������B����͑O�f�u��́v�ł͗b���_��N���͖��܃��N�ԂƂȂ��Ă�����
�A�u���~�䂯���܂�ی̋��ɋA���ŖႢ�����v�ƁA���Z���̏o�҂���]���Ă�������ł��낤�B
���ҒY�B�͒����x�����ɂ����Đؕ����Y�B�D�i���I������`�j���g�p�����B����͏o���邾���Z���Ԃ̏o�҂���ړI�Ƃ��A�u���~���̑���������y����J���N�l�J���҂ɂƂ��Ă͑傫�ȕs���ƂȂ����B���ҒY�B�S��
�A�O�r�Y�B�̍B�v�ƂȂ����J���҂͎��̂悤�Ɍ���Ă���B
�i�O���j���̒Y�B�i�M�Ғ��A���ҒY�B�j�ɂĂ͒������x���ӂ̐ؕ����ȂĂ��A�����N���ɂ��炴��Ό����̖ʂ����鎖�\�͂�����A���n�̒Y�B�i�M�Ғ��A�O�r�Y�B�j�ɂĂ͖������ɂ͕K�������ɂĎx���͂�r�̂ɐ��Ɉ��S���ׂ��Ȃ�
�A�z�̒m���ɂ��ď������p������́A���ҒY�B�ɍ݂�S���l�͖ܘ_�{���ւ��ʐM���ďo������U���ׂ�
�ƁB�������E�̒k�b�͒����Ɏ��̂悤�ɒ������ꂽ���A�ؕ����Y�B�D���g�p����A���N�l�J���҂ɂƂ��Ắi���R���{�l�J���҂ɂƂ��Ă����l�ł������j�傫�ȕs���ł��������Ƃ͖��炩�ł���B�����L���͒��ҒY�B�̒����x�����@�̎��Ԃɂ��߂��Ǝv����̂ŏЉ��B
�i�O���j��}�L�Y�B�ɂł����\�ܓ����Ɍ����ƈ��ււ��Ȃ��A�ޓ����]������Ɖ]�Ӓ��ҒY�B�̔@���n�������⍂�̌܊���蔪���܂ł���p�i�y�я����p�Ƃ��Č������x����
�A������n�ꃖ�����Ƃ��ė������߂ɐؕ��̈��ւ��Ȃ��R�Ȃ�A���납���X�X���ɋL���B
�B�O����
���N�l�J���҂̐������_�Ƃ��Ă̏Z��͂܂����B�̎O���̔[�������Ă�ꂽ�B���̑��B�́u��N�J����������~�n�s�\���̂��߈ꎞ�̌@�𒆎~���v�Ă������߁A���{�l�J���҂̔[���Ƃ͂�������Ă����B�Y�B�v�Ƃ��Ă̊O���l�J���҂̎�����
�A�킪���ŏ��̎��݂ł������̂ŁA�����Q�[����X��S���A�\�Ȍ���̍��Ɠ�������������낤�Ƃ����B�Z��i�[���j�ɂ��Ă����N���̍\���A�����A�u���Ɍ����O�ڗ]�̕���~�l��
�A����Ɂ[�ڈʂɓy��h�肽���A������̍\���ɂāA�������ɂ͐�ւ��ΒY��R��������g�ނ�J�I���h�����ɉ��������B
�H���ɂ��Ă����l�ł������B��1��59�����ɂ�2���̐��������܂܂�Ă������͑O�q�̒ʂ�ł���B�����炭���̌㗈���̐l���̒��ɂ��������������ł��낤�B����理�����ɂ���Ē��N���̐H�������ꂽ�B����������͓��{�l�B�v�Ƃ�����قȂ炸
�A�u���ɂ͑卪�ׁA���`�Ƀn���ނ̎ϕ����������A�ӎ`�Ƀn�K�����X�̏`���ɋ��ޓ���p���v�����̂ł������Ƃ����B��قȂ�Ƃ���͎��̓�ł������B��͌ӕ����ʂɎg�p���邱�Ƃ�
�A��l�]�̌Ӎ����͂�2���ԂłȂ��Ȃ������Ƃɋ����Ă���B�܂����b�̑����H�����D�܂�邽�߁A�̎�����v�悵�Ă���B
�����͌��܂̌����Ƃ������R�ŁA������������i�B������o�鎞�j�Ƃ��đ�^�R�b�v��t�݂̂ɐ�������A����ȊO�͎�����[�����̋����K�v�ł������B
�Y�B�̍B�O�����Ǘ��Œ��ڂ��ׂ����Ƃ́A�u���Ǘ��ł���B����ʼn\�Ȍ���̍��̐������K�d���Ȃ���A�����Ō��������{�l�J���҂Ƃ̌𗬂��֎~�����B���̗��R�Ƃ��ĕ͎��̂悤�Ɍ��Ȃ��Ă���B
���̍B�v�����Č݂��ɉ��������ނ�͌��܌��_����o���̔}��Ȃ�ƂĎ������ɉ��ăn����ɉ���������l���d�Ɏ�����Ȃ������
�܂�
�B�̍B�v���i�M�Ғ��A���{�l�B�v�j���X���Ԃ̖ڂ�ς݂Ĕޓ��̔[���ɗ����X�̔������Ȃ��Ĕޓ��̐S������Ƃ�����̂���A�����ɓ����A���̒Y�B�ɍs���Γ��B����{�̒��K�ׂ�
�A�Y�B�Ƃ͊댯�Ȃ�A�����V��̊ח�����������ꂸ�A�z���鎖�Ƃɏ]�������艼�ߒ��K�̏��Ȃ����̋��ɂē��炭�ɔ@�����t�A�ޓ��̘J����W�Q����Ǝ��ނ���̂���ɂ�
�A�����ɂĂ͎������ɉ��Ă��X��ɒ��Ԃ̐��𑝂��Ĉ�w����������ɂ���
���̂悤�Ɍ��܂̗\�h�A�B�v�����̖h��𗝗R�Ƃ��āA�����ʂɂ����Ă����{�l�J���҂Ƃ̌𗬂��ւ����B������R�́[�ɂ́A���N�l�B�v�����āA�O�ߑ�I���{�l�B�v�̂��܂��܂ȁu�ĕ��v�ɐ��܂炵�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ��������B���̂��߂ɑ����́u����j��u��
�A�B�O�������������Ď������̂ł���B
�@ |
��5 �J���҂̒�R��ꓦ���Ƒ������
����30�N�i1897) 10��12���A 2�l�̍B�v�A���ߖP�Ƌ��牤�����������B���l�Ƃ���l��59�l�̃����o�[�ł���������A���B2������̂��Ƃł���B�u���ҒY�B�ɂĂ͐l��h���Č��d�ɑ{��j������
�A����2�l���ŏ��̓����҂ł��������ǂ����A�����͔����ł������ۂ������炩�ł͂Ȃ��B
���̌�����X�Ɠ����҂����o�����B�V���ɕ��ꂽ���̂����Ă����ƕ\4�̒ʂ�ł���B
��q�̑��������ɂ��31�N1��������ɂ͈�x��60���l�����������B1��27����i�x�@���Łu���t�����ʂ��ˁA���i�V��̑�j���Ȃ����p���i�m�j��A�^�����A���l��
�A�����3����i�`�ɋ߂���������~�S�嗢�t�߂�o���ł����������O�͂��̎��̓����҂ł���B�\4�̑��̓����B�v�̒��ɂ����̎��̓����҂��܂܂�Ă��邩������Ȃ��B
3�����{��蕟�����O��O�r�Y�B�̎��Y�B�Ə����B�ɂ�6���̒��ҒY�B�̓����B�v�����荞��ł���B�ނ炪�����x�����@�����R�Ƃ������Ƃ͑O�q�����B
�@�@�@�\4 �V���ɂ݂铦���B�v
5��4B����i�x�@���t�߂�o�ς��Ă���5���̂���4���́i�����͈قȂ邪���l���Ǝv����j�u�H�ӂ�H�͂��̗���Ȃ铹�����ׂ��āc�c�O�����ꗱ�̔т����ɂ�����Ε��ւā[�����i�ނ��Ɣ\�́v�����Ԃ�
�A ���悻2�T�Ԍ�ɋ��s�{�����ɂ�����A�������ɋ~�����肢�o�Ă���B
�����̑��ɂ����ҒY�B����͑����̓����҂������ł��낤�B���̂Ȃ瓦�������m��ł��Ȃ����N�l�Ɋւ���L������������邱�Ƃ��ł��邵�A�����҂��ׂĂ��V�����ꂽ�킯�ł��Ȃ�����ł���B�Y�B�J���҂̈ړ������ɂ߂č������Ƃ͋ǒm�̂Ƃ���ł���
�A�����͕ʂɒ��N�l�J���҂݂̂ł͂Ȃ��������A�䗦�͓��{�l�J���҂̂�����͂邩�ɏ�����̂ł�������������Ȃ��B�\4��4���̓����҂��F�߂��閾��31�N1���̎�����
�A�V���́u��������������ē��肽�鐼���Y�S�����Y�B�i�M�Ғ��A������ҒY�B�̒����L�����o��j�ٓ���̊ؐl�v�ƕ\�����A�u�ؐl�����ȗ��S�Y�B�̎����w���d�ɂ��āA�ߓ��߂͂ꂽ��[�ؐl�̔@�������Ս��̎戵��������Ƃ̂��Ɓv�Ƃ������Ƃ�
�A�������Ǘ��̉��ł��A ���̌�������҂�h�����Ƃ��ł��Ȃ���������ł���B
�܂������҂��݂�ƁA ���̍����ҒY�B��É͉��R�c�Y�B�ȊO�ɂ������Ȃ��璩�N�l�J���҂��ٗb����Ă�����������Ȃ��B���̂��Ƃ��L��������B
�Y�B�B�v�҂��ׂ̈ߌ����i�M�Ғ��A�������j�ɓn�q������钩�N�l�͑��J���ɑςւ����艝�X���S�������̂��邪�A�����B���̒��N�l�B�v���n�ɖ��З���
�A�}���S�l�Q���ӂ��E���c�L���肽����A���Ȃ肵�È������̔F�ނ鏊�ƂȂ�A�����Ɍx�@���ɘA�ꗈ��Ď�����撲�̏�A �ډ������ɑ؍݂���S���l�p�~�O�Ɉ��n������
���N�l�J���җ�����̍ŏ��̉A����ɂ����閾��31�N�i1898) 1��22���A���ҒY�B�ɂ����đ呈���������u�������B�V���w���ꎩ�Rj�́u�ؐl�B�v�̖\���v���邢�́u���N�B�v�̑����v�Ƃ���
�A�w��i�V��x�́u���N�B�v�̌���J�Ƃ��āA�����̐V���Ƃ��Ă͔��ɋ����S�������ďڍׂȕ������B�����̋L���̕��ɂ͎�̑��������̂ŁA �w���ꎩ�RJ��2��ɂ킽���ďЉ�ꂽ�u�\�R���菑�v�ɂ���Ă��̌o�߂��݂�B
�� 1��22�P�͉A��V���ɑ������邽�߁A�B���蒩�N�l�B�v�ꓯ�Ɏ�H�������Ƃ���A�[���O�ɏW�����������A���_���������B
������������삪���~���悤�Ƃ����Ƃ���A�~�����A�~�g�_�A�~�ߍZ��3���y���������͗\�ď����ɉ��������Ă��āA�ˑR�����ɗ��ł������A ����ɖ{������O�܂ŒNj����Ċ��_�ʼn��ł�
�A���a�x��20���ȏ�Ɏ��炵�߂��B
�����̕Y�B�ɒB����ƁA�~���g�i�����炭�[������1�l�Ǝv����j�͗m�����g����Ɍ����A������Ł~�����̓����A ����ɂ͍����ɐؕt�����a�x��17���Ԃ�
�A �܂��Q���łɂ��n���킵�߁A���a�x��2���ȏ�Ƃ����B
���~���E�O�������g���E��i�u���N�B�v�[���v�j�Ɍ����ہA������ŋ������Ɏ��a�x��20���ȏ�A�������ɓ�����5���ԁA�ފ��A�ɓ�20���ȏ�̑n����^���A�X�ɐi��Ŕ㉻�v�̊ዅ��ؔj��
�A�[���̓����Ő������Ɏa�t�����a�x��20���ȏ�Ɏ��炵�߂��B
���~�����g�������o���̏��������ǖh�~���p�����^�����������悤�Ƃ����Ƃ�������ʂœ��������ł����B�����Ƃ����a�x�Ƃ�v���Ȃ������B
�����̑��ɂ������̓��{�l�����N�l�J���҂ɑn����^�����B
�E�̌o�߂���ߑ�����ƁA���������̐��������Ă������߁A�����ɂ��B�������M�Ɠ�d�̖݂���э悪�U����ꂽ�B�܂��u������Ȃ铯���l�^�v�i����ł��낤�j�����[�M�������B���������܂��n�܂�
�A����N�l����^������߂悤�Ƃ����Ƃ���u�ؐl���͗\�Ė^�����肯��^�Ɍ��Дޓz�ł��E���Ƒ��|��J�ƂȂ�A�X�ɓ�����^��ǂ��A�u�ꓯ���̔@���^�̔[���ɋt��
�A�^�͍X�Ȃ�A�������������đŎE����j�ƂȂ����悤�ł���B
�������삪�U���ΏۂƂ��ꂽ���R�ɂ��āu�\�R���菑�v�͎��̂��Ƃ�2�������A�����F�肵���B
���삪���Y�B�X��̈˗����B�v�ٓ��ׂ̈ߒ��N���Ɏ����A�E�퍐���i�M�Ғ��A���N�l�퍐�j�ɑ����{���ɓn�����͋����̒��K�錩������|�Ì����ȂĊ��U��
�A�퍐����������M�����ɔV���ٗb�ɉ����邱�Ƃɗ����肽�鏈�A�p�œ����̗\�z�ɔ����A���]�����鏈�͖ނ��s�o���Ȃ�̒Y���Ƃɂ��āA���x�����J���Ɋ��֓�݂̂Ȃ炷�A�����鏈�̒��K�����]�ď��z�Ȃ邩�̓ڂɉ}���̏����Ɏ����
�@�@�@�\5 �\�R����ь�������
�Ƌ��U�̕�W���s�������ƁA�����
�����Y�B�X��͔퍐�����J���ɏn������Ɏ���܂Ŏ����̓r�邱�ƍ���Ȃ���@���A����̎���o�ē��ԕ⏕�Ă����^���r���肵���A����͋p�ĔV���̒Y���̎x�r�ɋ�����Ə̂������퍐���ɋ��^�����肵�́c�������ׂ̈����ɑ������ɕs��������Ɏ����
�ƒ�����[�̏�O������肵�����Ƃł���B
���̑��������̌��ʁA 60�������������A�e�n�𗬘Q������A�����͋A�������肵���B���̗\�R�͖���31�N�i1898) 4����������n���ٔ����ɂ����čs���A�����͓��n�ق�6��7���ɍs��ꂽ�B���̌��ʂ͕\5�̒ʂ�ł���B
�@ |
��6 ������
���ꌧ�����Y�S�̒��ҒY�B�́A����30�N(1897) 8�����痂�N2���ɂ����āA 4��ɂ킽�荇�v��230���̒��N�l�J���҂��ٗb�����B���ꂪ�킪���ɂ����钩�N�l�J���҂̏W�c�ړ��̐���ł��������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���̂��Ƃ͕\6�ɂ���Ă����t������ł��낤�B���̎����ҒY�B�͂قڐ��m�Ȑl�����W�������ɕ��Ă����Ǝv����̂�
�A�\3�ɂ�����l���ƕ\6�ɂ��l���Ƃ̍��A���邢�͕\3�ɂ����鑝�ِl���Ƃ��̑��L�ڂ̌����l���Ƃ̑��ᓙ�͐₦�������҂����������Ƃ������Ă���ƍl���Ă悩�낤�B�������\6�ɂ����炩�Ȃ悤��
�A�܂��O�q���蔪�S���̗�̂��Ƃ��A���ҒY�B�̌ٗb�ȑO�ɓn���������N�l���F���Ńg�������킯�ł͂Ȃ��B
���N�l�B�v�̓����͂��Ȃ�T�d�ɍs��ꂽ�B�J���҂͂��ׂĒP�g�j���ł���A�Ƒ�����݂̈ړ��ł͂Ȃ��������A���̎����ɍۂ��ẮA�H�Z����Ƃ��鐶���A�����ɂ����ĉ\�Ȍ��薯�����d�������̂悤�ł���B�����Ƃ��߂ɂ��Ă�
�A��1��J���҂̓��������u�\�z����@���ؐl�͈�l�����ւ����āA���n�̗��߂ɕ����т���߂���s��J�p�ŁA�t�Y�ʖ�҂ɂ��ƁA�u���ꌋ���ɂăn�d����s���R�Ȃ�Ɉ˂�
�A���Ƌ��c�̏�A�m��Ɏ̂ď�D�̍ہA�f�R�A�U���ƂȂ����v�̂ł������B���������āA�B�O�ɂ����Ă����{�l�B�v�Ƃ̎��ʂ͊t��ł������Ƃ����B��4��̏ꍇ�́u�O���i�M�Ғ�
�A 3��j�̂��́r�@���f���a���ɂ��炸���đS�̂̊ؑ����Ȃ��v�ē����������A������͑O�҂̂悤�ɓ��{�l�B�v���l�ƂȂ����ł��낤�B
�@�@�@�\6 ���{���Z���N�i�j�l��
�B���J���ߒ��̘J���g�D�ⓝ�����@�Ɋւ��āA�Ⴆ�P���ߒ��̈ꎞ�I�Ȃ��̂ł������ɂ��Ă��A���{�l�B�v�ɑ���̂Ƃ͈قȂ�����X�̍H�v���݂���B�������Ȃ���
�A�[�����x�̉��ɊǗ����ꂽ���ƂɊւ��ẮA��_�������āA���{�l�B�v�̂���ƈقȂ�Ƃ���͂Ȃ��B���ڂ��ׂ���_�́A��Ɩʂł��B�O�����ł����{�l�J���҂�n��Љ�Ƃ̌������u���̂�ꂽ���Ƃł���B������u����͑��݂̊Ԃɕs�M�ȊO�̉����������݂����Ȃ������ɂ������Ȃ��B���������{�l�B�v���n��Љ�Ƃ͈����x�u������Ă������Ƃ͎��m�̂Ƃ���ł���B��W�ɂ�����V�x
�A�B�v�̖\�͓I�ٔ��A�����̔z���̕s���N�����́A�����̔[�Ґ��x�̉��ł́A�ڐV�������̂ł͂Ȃ��B�Ƃ͂����A�����͒Y�B�Ɋւ���\���m�����F���ŁA���t���ʂ��Ȃ����N�l�J���҂ɂƂ��Ă�
�A���{�l����w�Ս��Ɏ~�߂�ꂽ�ł��낤�B
���N�l�J���҂̕s�M�ƕs���́A���ɓI��R�Ƃ��Ă͓����A�ϋɓI��R�Ƃ��Ă͑��������Ƃ��Č��ۂ����B
����31�N2��8����50�����̘J���Ҏ������Ō�Ƃ��āA�ȍ~���ҒY�B�ł͒��N�l�J���҂̏W�c�ړ��͍s���Ȃ������Ǝv����B����30�N����31�N�ɂ����Ă̒��ҒY�B�̒��N�l�J���ғ����͈�ߓI�Ȃ��̂ɏI�����B�����炭�É͉��R�c�Y�B�����l�ł������낤�B����͉E�̒�R�ɂ��Ƃ������ł������낤�B�܂�����31�N�t�ȍ~�Y����������
�A��]���ĐΒY�Y�Ƃ͒��Y�̎R�ɋ�Y���邱�ƂɂȂ�������ł����낤�B���Íz�Ƒg���ł͓��N9���̉�c�ŁA�ؒ��i�̌@���j��1��5���T��2��5���̒ጸ�ƍB�v���^�ĉ��̒ጸ�����c�����B��32�N�Ă̒}�L�͒�34�Ɏ��������Ƃ��u�Y���̒��Â͍���w�Ǒ��Ⓒ�ɒB���v
�A 220�B�̂��������x�p�Ƃɒǂ����܂ꂽ���ł������B�����Ă��̒ꗬ�ɂ́A���{��15�N�푈���Ɛ�㍂�x�������ȍ~���O�Ƃ��āA�ނ���ߏ�J���͂ɋ�Y���A�₦���J���͂̊C�O�ڏo���ł��������Ƃ�����B������ƌ����ɂ��
�A���ҒY�B�̎����͎��s�ɏI�����B���̎��������ؕ����Ȍ�A���邢��15�N�푈���ɂӂ�Ԃ��A�Q�l�ɂ���邱�Ƃ����������ǂ����͕s���ł���B�������A���Ȃ��Ƃ����̎������\���ɐ������ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ��B �@ |
��
�t�L1�@�����Q�[�̉��ʂɂ������铌�����Y�����Q�[�̗����ɂ��䋳�������B����ɂ��ƗQ�[�͉Éi���N11��3�����A����43�N11��28���c�A����4�N�{�q�ƂȂ茴�����̂�
�A����24�N�������ɕ������B�䋳���ɐS���犴�ӂ���B
�t�L2�@���N��1897�N�i����30�N�j 10���������Ɖ��̂���B�����̓��{�̐V�����͗��������p���Ă��邽�߁A���_�ł͕X�㒩�N�œ��[�����B �@ |
|
�@ |
   �@
�@
|
|
�@���߂��@�@���߂�(�ڍ�)�@�@�@�� Keyword�@�@�@�@  |