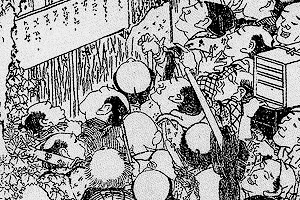|
���ь`�r�@�@�@����s�ԗ͒�
|
���̌`���тɎ��Ă��邱�Ƃ���u�ь`�r(�͂��܂�������)�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł����A�����r�Ɠ��l�A���[��3���قǂŁA�~��̓��J�T�M�ނ�q�œ��키�_�Ɨp���r�ł��B�����r�ƌь`�r�ɋ��܂ꂽ�n�悪���ԗ͑��̒��S�ł��B���݂͎ԗ͒��ƂȂ�A����s�����̎x�����u����Ă��܂����A�����ɑ�R�_�_�Ђ��������Ă��܂��B
�ԗ͒���R�_�_�ЁB���̗R���ɂ��ẮA�u��Ր_�F��R�_���@���J���ۘZ�N (�ꎵ���) ���q����茚���Ƃ��� �������l�̍���؎R�̗���h�������R�̐A�т���삷��ړI�Ō��������Ɠ`������ �X���_�В��v�Ƃ���܂����A���̐_�Ђ��܂��A�ؑ����؍�̎R�_�Г��l�A�����R�̎��_�Ƃ��đ�R�_�_���J��Ђ̂悤�ł��B
�����r�Ɠ������A���̒r�ɂ�������̓`��������܂��B
�u�ь`�̒r�Ƃ����̂�����A�r�̑��ɏ�Ղ�����B�́A���q�ǂ�(������)�Ƃ����l�����̏�ɏZ��ł����B���d�������Ă����s���痈�������A���̒r�Ŏ����̌т���Ƃ����B�Ƃ��낪�A�ǂ��������Ƃ��т͌������݂ɗ���A�������낤�Ƃ��������r�ɗ����Ď���ł��܂����B�����Łu�ъ��v�Ƃ����A�܂��A�r�̌`���тɎ��Ă���̂ŁA�u�ь`�v�Ƃ������B�w�X�̓`���x���v
�u�r�̑��ɏ�Ղ�����B�́A���q�ǂ�(������)�Ƃ����l�����̏�ɏZ��ł����v�Ƃ���܂����A��R�_�_�Ђ̋߂��ɂ́A���āu���q��(�܂�������)�v�Ƃ�����(��)���z����Ă��܂����B
���̏�́A�O����N(1332)���A���q���{�̕����ł��閏�q�e���Ƃ����l�����A�����炱�̒n�ɓ������ċ��قƂ����邾�Ƃ����Ă��܂��B�u���q�ǂ́v�Ƃ����̂͂��̖��q�e���̂��ƂȂ̂����m��܂��A���ꂪ������ɒu��������Ă���悤�ł�(�������A�`���ł���)�B
�]�k�ł����A�u�ԗ�(����肫)�v�Ƃ����n���̗R���́A�u����(�T���L)�v���炫���Ƃ�������A�A�C�k��́u�T���L(�����̎��n��)�v���ꌹ�Ƃ���Ƃ�����������܂����A���̑��ɁA�O�q�̖��q�e�����u���s���狍�Ԃɏ���ė����v���ƂɈ��ނƂ����b���c����Ă���悤�ł��B�@ |
|
���H�c��(����������傤)�@�@�@���Ìy�S�H�c��
|
�傫����قƏ��قɕ�������B��ق́A�H�c��̖k�A10��m2�̍L��Ȗʐς�L���Ă���B����600m��k300m�B���c�Ɉ͂܂�A���͂���i�����A���ؗ��ɕ���ꂽ�ꏊ�ł���B�����{�E�ٓV�����c���Ă���B�k�Ɠ쓌�ɖx���c��A�k���̖x�͒�����300m�E��15〜0m�E�[��3m�A�쓌���̖x�͒���50m�E��2m�E�[��50cm�قǂł���B�َ��ӂ͓ꕶ����̈�Ղł�����A���݂��ꕶ�y���y�t�킪�o�y���A���a47�N�̔��@�����̍ۂ��A�����킪�o�y���Ă�B���ق͓���150m��k150m�B���͂𐅓c�Ɉ͂܂�A�䍂2-3m�قǂ̏ꏊ�ɂ���A�����̕�5m�A�[��3m�قǂ̖x�ɂ�蓌���ɕ������Ă���B���̖x�͖k�̈���ɐ�̐��������Ă���B�C���y�����������A���a46.47�N�ɑ���c��w���w���l�Êw�������̔��@�ɂ��G���Z���Ղ��˂��������ꂽ�B�z�铖���͏��ق݂̂ł������̂��A��k�����ォ�玺������ɑ�ق��z�邳��A������Ɉڂ����Ǝv����B
�����j
�Ò�4�N(��m���N�E1238�N)�Ɉ������G�̒�̒����ʒ傪�z�邵���Ƃ����B��������암�����쒀����ƁA�����������邵�A���������Ȃǂ̖����`����Ă���B���������ދ�����ƁA�����N�Ԃɕ�������8��ڂ̑��n���������邵�A�H�c�z�O�Ɩ�������B���̌�A�����ȂǂƋ��ɑ�Y�אM�ɑR���Ă����悤�ł���B�u�ꓝ�u�v�Ɂu�V�����N�Ìy�O�S�����Y�אM�̎�ɑ�������ǂ��A�O���l�ؕ��ϖ������炸�B����A���c�A�r��A�H�c�A�����̎҂ǂ����ɉ������肵���A�����Ǘ�����ׂ��ƂēV���\�O�N�O���ނ̕\�֎茭����]�X�v�Ƃ̋L�q����A����闎��Ɠ����A�܂��͂��̌�H�c�����Y���̎x�z���ɂ͂���A�H�c���͓암�ɓ��ꂽ�悤�ł���B����ɂ��p��ƂȂ����B
���H�c��Ƒ��n��
�Q���A�k���̗̒n�͊O���l�ɋy��ŁA���̊O�l�َ�͍��ʂ̕��۔V���ƖH�c�َ�̖H�c���O�Y�Ƃ�����B���۔V���̖��͖k����^�̎��ƂȂ��č��ƂƂȂ�A���ꂪ�@���ƂȂ荡�ʔ����{�����c���ꂽ�B�Q�����̐�������Ȃ鎞��ɂ́A�Q����͒Ìy�̉��œ����̔ɏ��Ԃ��Q���������Սl�ɍ��̔@��������Ă���B
�ƘV�ɂ͐ԏ����l�A���R�����A�a�c�ܘY���q�喔����̊قɂ͌��팰���A�����y���ɂ͌y�䌹���q�垻�A���a�����ɂ͋������b�@�сA�k����߉ނ̊قɂ͉��䖜���A���k���q�قɂ͌��q�������q�A��������̊قɂ͋g���퍶�q��A����{�{�قɂ͖{�{�������̌ҁ@�n���w�̕��m��u���Ďl�������ߔ������ށB
�������َ̊卋���͍a��̊قɂ͐��ؖ^�A�v�䖼�قɂ͍��X�ؖ^�A�����قɂ͌��������A�����قɂ͍������Y���q��g���A����@�قɓ���ɓ��A�����قɕ��۔V���r���A�H�c�قɖH�c���O�Y�A����قɓ��茹�ׁA���̊قɋ��ؒe�����A���c�̊قɓy���a�V��@����A���؍݉Ƃɐ��ؕ����т��薔��̎l���ɂ͋_���A�����A���A�t���̎l�Ђ���Ċ����R�@��̕�������[������B
�Ƃ���B���ɖH�c���O�Y�͊O���l�̔����Ŗk�����̗L�͂ȕ����ł������B
�R��ΖH�c��傪�����납��H�c��ُ�ɋ��Z�������s���ł��邪�A���n�Ƃ̌���Ō��ݍO�O�s�c���ɏZ��ł��鑊�n���������������Ă��鑊�n�Ƃ̌n�}�ɂ��ƁA�q���̗����Ɠ����̑��n�����̎O�j���`�l�Y���ꂪ�O���l�ɏZ������Ə�����Ă���B���n�}�ɔN����t���Ă��Ȃ��̂ł����납��ڂ�Z�ނ悤�ɂȂ��������炩�łȂ��B�܂����n�}�ɍ��`�l�Y����̑����n�z�O�����������l�N�ɒÌy�O���l�ɏZ�����A�����瑊�n���Ƃɕ���Ƃ���B���Ƃ��ʂꂽ���R�͏\�]�N�O�̍N����N�Ɉꑰ�̗����Ƃ����Ȃ邱�Ƃ������ł��邩�s���ł��邪�A�_�����A�̂��a�k�������̒험�d�ɏ����ł��Ă���B���̘_�����������ĉz�O�������Ìy�֗��đ���̂��Ƃ��������Z�������̂̂悤�ł���B������ɂ��Ă��ܕS�N�ȑO���瑊�n�z�O���H�c��قɏZ�ނ悤�ɂȂ����̂ł���B
�R��Α��n�Ƃ��H�c�ֈڂ�Z�ޑO�ɂǂ��ɋ��Z���������n�}�ɂ���Ē��ׂ�ƁA���n�Ƃ̑c��͕��e�����傩�甪��̌�����n�����痘�͒}�O���M���S�ɋ���A������N�O���������Ă���B���n�Ƃ͕��E�������Ė����������Ƃƌ����āA�����̗��ɑ��n�����痘�Ǝq�̗����A�������l���������Ă���B��̗����͎蕿�������ĎO�璬�̌�����ɂȂ����B�Z�������S�����̂Œ�̗������Ƃ��k�����B��������������������łł������̂ŁA�����̎q�̗��s�����i�O�N��m�J����œ����������A���j���t�A���j���g����A�d�V�Y�ŌR�����������B�����������N�O���\�Z�������ŖS�ƂƂ��ɑ��n�Ƃ͒����Ɋ���@����������B���������t�̎q���M�͌��ی��N�̘a�c�`���̍���ɉ����璬�̉��������āA�̂����������B
���n�s�V�i���M�̎O�j�ł��闘�v���@���Ȃ鎖��������A���Ó�N�}�O���M���S����암��T������ɈڏZ�����B�@�����n�s�V�i���M���a�c�`���̗��ɉ���蓢���������Ƃ�R��ŗ������암��T�����(����)�ɈڏZ�������̂��A�܂������̑�������@���n���ɂ������ƒ����������]���Ă����邩��A�암�ɕ����̈ꑰ�������Z��ł����̂ŁA�����𗊂��Ĉڂ��Ă����̂��������Ȃ��B
���v�̑��A���n�����V�������͋����̒m���Ă���Ƃ��납��l����ƁA���v����@���ֈڂ����Ƃ�����̗̒n�����łɐ�߂Ă����̂ł��낤�B���̂��Ƃɂ��Č̐X�я����͓�������(���a�ܔN�����\�O��)�Ɂu�O���l�̎j�֖H�c��告�n�ƂɏA�āv�Ƃ����_���\���ꂽ�B
���͒}�O���M���S��m�s�������邪����B������N�O�����������A�j�q��l�A�����A������������������B����Η��̒험���@���p���A����������Ə̂��B��������Ɏ蕿�����������ߎO�璬���������ꂽ�Ƃ��邩�畽�ƕ��ł������낤�B�O�L��l�����Ƃ���@�̂������̗��ɐ펀�����Ǝv����B
�����̎q�}�O�痘�s���ꂩ��q���t�A���M���o�ė����Ɏ���B�ȏケ�̗��������������̂���������B���̌n�}���ꊪ�A�ʂɂ��@�̌n�}���ʂ��X�ɗ����̒험�v���珑���Â������̂��ꊪ����B���v�͗��M�̎O�j�Ő��Ó�N(�k��������������)���B�ɉ����@����T������ɋ��Z�����B�암�Ìy�n���̑��n���̐�c�ƂȂ�B���v�̒��j�����͕��ƕs���̎�������A�O�q�������̌�𑊁@�����A������̂����B
�Ƃ���B�X�����@���Ȃ闝�R�ŋ�B���牜�B�܂ʼn������������Ă��Ȃ��B�n�}�ɂ͖ܘ_�Ȃ��B���v�̒��j���n�}�O�����̓��n�}�ɂ��ƁA���̍��`�l�Y���ꂪ�O���l�H�c�ɏ��߂ďZ���������Ƃ�������Ă���B�Ƃ��낪�n�}�ɋ����̂��Ă������n�����V�������̒��j���Y�Ɨ����̒��j�����Ƒ������Ƃ������Đ��ɗ��Y�����B�����̓����������������ĎO�j���`�l�Y���ꂪ�H�c�ɋ����ڂ����̂ł͂���܂����B
�H�c�Ɉڂ������`�l�Y����̎O���ɑ��n�}�O�����A���̎q�ɉz�O�����A���V�A����������A�����̒��j�������������l�N����̉Ɨ̂��p���ŁA���ꂩ�瑊�n�Ƃ͏�@������ƖH�c�Ɨ��Ƃɕ����ꂽ�̂ł���B����܂ł̌n�}�͓암�ɏZ��ł��������d���F�߁A���ܘY�ɓn�������̂ł���B�������ē��n�}�ɂ͑���Ȍ�A�V���\�O�N�H�c��ގU�����H�c�z�O�܂ł̂��Ƃ��L����Ă��Ȃ��B���̊Ԃ̎����X�я����͍��̔@�������Ă���B
���`�l�Y����̒푥��̎q��}�O�瑥���Ƃ����B���̎q�ɉz�O�����A���V�A�����̎O�l������B�����u�����l�N(�����`������)�@�Ìy�O���l�j���Z�i���v�ƌn�}�ɏ����Ă���B
�����l�N�͂��̉��m�̗����N�����Ă���Z�N�ڂŁA���̗��ܔN�ɂ͎R���@�S�ƍא쏟�V������������a������(����N���͏I���)�B
���悤�ɗ����̎��ł���B�������̊O���l�n���͉����������̗̒n�ł������B������悫�\�]�N�O�N����N�����͈ꑰ�����Ƙ_�@���������A��a�k�������̒험�d�ɂ��̏����ł��ƌn�}�����̏��ɂ���B���ꓙ�ꑰ�����̌��ʑ����͊O���l�ɈڏZ�������̂��A���炭�͑���̉Ɨ̂����������̂ł��낤�B(�n�}�ɑ���̒푥��̎q������̎O���Ə����Ă���)
�Ƃ���B�������Ă��̌n�}�͓암�ɏZ��ł������d���F�߂ď��ܘY�ɗ^�������̂�����A�����l�N�Ìy�ɏZ���������̎q���̂��Ƃ������Ă��Ȃ��ƐX�я����������A����ɓV���\�O�N�H�c����ގU�����z�O�Ƒ����Ƃ̐���͕s���ł���B�L����ʂ͓̂��R�ł��邪�A�Ìy�ɂƂ�Ă͈⊶���̏���Ȃ��Ə����Ă���B
���H�c�z�O�Ƒ��n���
�H�c�z�O�����邵�Ă���암���l�đ��ɏZ�����Ă�������A�����N�ԉ��l�đ����n���Ȃ���̂��Ìy���_�������̂́A�c��̋w����邽�߂ɂ����s�ׂł���Ƃ������j�Ƃ����������B���̂��ƂɊւ��C�R�l(���c������)�����a�ܔN������\�����̓�������ɊO���l�̎j�ցA�H�c�̏隬�̘_���̒��ɍ��̔@���_�����n��삪�H�c�z�O�̌���łȂ��Ɣ��\���Ă���B
���j�Ҏ[�̒����������葊�n���͖H�c�z�O�̖������Ƃ�����ꂽ�̂��āA��{��ꑺ���ƍ�{�`�O����ˌS�̕����@�܂Ŏ��n�����ɏo�������B�������l�đ��̑��̌�͂������Ĕ��\���Ă���A�����̎�l�͉�����鏊�͂Ȃ����ʉƂ̉��^�֕����悭���邾�낤�Ƃ����̂ŁA�������������B
���̉Ƃ͑����̍\�Ŕ�陂̎�l���o�ĉ������B�����ő��n���͖H�c�z�O�̌���ł��낤�Ƃ̎����Đq�˂Ă����|�����ƁA�@�ނ͕��R�Ƃ��ĐF���Ȃ��A�݂�Ȃ��疼�_���鑊�n���̉Ƃ͈אM���Ƃ��ɒǂ����Ƃ����㒎�̖H�c�z�O�Ȃǂ̎q���ł͂�����ʂƌ����z�����̈��A�ł������̂ŕ����ċA�������ȁB
�Ə�����Ă���B�����ʼn��l�Ď��̌n�}����茧��ˌS���������l�ė^���Y�Ҏ[�ő吳�\��N��\�ܓ����s�́u���l�đ����`�v�ɂ��f�ڂ���Ă���̂�������ƍ��̔@���ł���B
�ȏ�͉��l�ĉƂ̌n�}�ł����āA���n�Ƃ����l�ĉƂ����c�͕�����ł���B���������Ƃ��r���đc��͓�������ł��邪�A����͑S�R���Ⴕ�A���Ƃ͌��̂Ȃ��肪����łȂ�����A���n���͖H�c�z�O�̌���łȂ����Ƃ��m�邱�Ƃ��ł���B�O�̂��ߑ��̐l�ƂȂ�����������Ă݂�ƍ��̔@����������Ă���B
���l�đ��́A���������̐l�A���͉��l�āA���͏��^���͎q���A�G�V�i�Ə̂��B
���͌`���A�ʏ̑��A�����ˎm�Ȃ�B�c���͗����ːЂ�E���Ē��R�呠������Y�Ɖ]���A��ɑ��n���Ə̂��B
���͏@���q�A��͈ꑰ���l�ĉE�����̎o�Ȃ�B�O�j����A�������X�A���j����Y�A�����~���A���j�G�V�i�A�O�j���V��B
���ƌn���̏�����ᑊ�n�����Y�t�����o�ÁA�t�������̑������̎l�j�Q�͎���̎q���l�Y�����A���������߂ē암���֗������@�l�đ��ɕS��H�ށB�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| ����茧 |
   �@
�@
|
|
���_��(������)��� 1�@�@�@���B�s����
|
����21�N(802)�A���c�����C�ɂ���đ��c���ꂽ�B ��a����́A���k�̓y�n���x�z���邽�߁A�o�H��E�H�c��E�����E�_���Ȃ�22�̏���z�����B �_���͂��̈�ł���B��Ƃ������A���ɐ����̌����z�u�ł���B�ŋ߂̔��@�����ŁA�R����n�������ɂł��� ���Ƃ����������B����́A����{���R��C�������B�哯3�N(808)�ȍ~�A���̒���{���R�����C����ꏊ�ł�����B ����{���R�̖�ڂ́A�ږ��Ȃǂ̌x�ŁA�ڈ̓����A�����Ď��Ȃǂł������B
�����Α叫�R���c�����C
38�N�푈�ŁA���c�����C(758�`811)�́A����10�N(791)�ɑ唺�햃�C��������g (���Α叫�R�Ƃ�����������)�ɂȂ��ĉڈΐ����ɍs�������ɁA�������g�Ŋ����B
���̊��F�߂��A����16�N(797)�ɐ��Α叫�R�ɂȂ����B���Α叫�R�Ƃ́A�ڈ𐪓����鑍�叫�Ƃ����Ӗ��ł���B ���߂ɒ�߂��Ă��Ȃ��A�ߊO�̊��ł���B
����20�N(801)2���A�c�����C�́A�����V�c����ڈΓ����̖����A�ߓ��́u���������v���������B�ߓ��Ƃ́A�V�c���o�w���� ���R�ɓ��ʂɎ����铁�ŁA���N10���A�C�����I������ƓV�c�ɕԂ����B���̓��u���������v�͌������Ă���B
����20�N(801)�r�����q�ŁA�폟���F�肵�F�_�Ђ����i�����B �����ĈɎ�������_�ɁA�ڈƑΛ������B
������21�N(802)1��9���A�_�������邽�߂ɁA�c�����C�́A�o�������B�z�邪�n�܂���2�������قnjo����4��15���A �ڈ̎E�������V���ׂƔՋ����炪500�]�l��A��ē��~�����B�x�d�Ȃ銯�R�Ƃ̐킢�ŁA�敾���Ă����B
�c�����C�́A �~������2�l�����ɘA��ċA��B8��13���A2�l�͉͓����m�R�Ŏa���B �ڈ͑�Ō����A�Ȍサ�炭�́A�傫�Ȕ����͂Ȃ������B
�O�s�̖k��̋߂��Ɂu���V�S����{�����{�v������A��ȋ�����5�N(1189)9��21�����ɁA�u�����������_����t�����B ���̐_�Ђ́A�c�����C���R���A���̎��A���������h������_�ł���B�E�E�E�v�Ƃ���B
������{������邩��_����
�哯3�N(808)�A����邩�����{�������A�_���ֈڂ��ꂽ�B(���{�͑����Ɏc���ꂽ) ���ꂩ��10���I���܂ŁA��150�N�Ԃقǂ��̖������ʂ������B
������{���R���Ǖ�
�V�c2�N(939)4��17�����痂�N5���܂ŁA���Ǖ��́A���H�ł�������������������邽�� ������E����{���R�C�����A����������Ē_���ɂƂǂ܂����Ƃ����B ���傤�ǂ��̊ԁA�V�c2�N(939)6�����痂�N2���܂ŕ�����̗���������B
������{���R�����`�ƑO��N�̖�
����5�N(1028)�ȍ~����{���R���C������Ȃ����Ԃ��������B���̊Ԉ��{��������{�E�_���̎������������B���{����(���ǂ̕�)����������ł������B ���{���ǂ͗������Z�S(���A�u�g�A�B�сA�a��A�]�h�A�_��)�̌S�i�ł���A�ڈ̒��ł������B
�i��6�N(1051)�����瓡���o�C�͍v�[����[�߂��A�J�����ʂ����Ȃ����{���ǂ��S�ؕ�(�q����S��)�ɍU�߂邪�s���B �O��N�̖��̑O����ƂȂ����B
����������͓��N�����`�𗤉���ɁA�V�쌳�N(1053)����{���R�ɔC�������B������25�N�ԕs�݂ł���������{���R���C�����ꂽ�B ���{���ǂ��߁A�����`�͑���邩�����{�E�_���ɒ��C�����B
���������{���ǂ́A�O�N�̉i��7�N(1052)�̓������q�̕a�C�����̑�͂ɂ���āA�߂������ꂽ�B ����{���ǂ́A���𗊎��Ɖ��߂��B����������ŏI������킯�ł͂Ȃ��B
�V��4�N(1056)�����`�̗�����̔C�����I���A����{�_��邩�獑�{�����֊҂�r���A ���v����ɂ����Č����`�ɐ��s���Ă�����������A ����炪���҂��ɏP���A�l�n���E�������Ƃ����A�����鈢�v���쎖�����N���A�O��N�̖����n�܂�B
|
|
���_���
2 |
�������_��S(���݂̊�茧���B�s����)�ɂ��������{�̌Ñ���B���̎j�ՂɎw�肳��Ă���B���c�����C��802�N(����21�N)�ɒz���A1083�N(�i��3�N)�̌�O�N�̖��̍��܂Ŗ�150�N�ɂ킽�����{�Ƃ��ċ@�\�����B
������̏����́w���{�I���x�ɂ���A���c�����C��802�N(����21�N)1��9���ɗ������_���邽�߂ɐ����n�ɔh�����ꂽ���Ƃ�`����B���Α叫�R�̓c�����C�͂���ɂ�葢�_���g�����C�����B11���ɂ͓�����10�����A���Ȃ킿�x�͍��A�b�㍑�A���͍��A�������A�㑍���A�������A�헤���A�M�Z���A��썑�A���썑�̘Q�l4,000�l��_���ɔz���钺���o���ꂽ�B�����炭�܂����ݒ���4��15���ɁA�c�����C�͉ڈ̎w���҃A�e���C�̍~������B
�V�����n�̏�Ƃ��ẮA���N������k�Ɏu�g�邪�z���ꂽ�B�u�g��̕����K�͂��傫���̂ŁA�����͂���Ȃ鐪���̂��ߎu�g�����v���_�ɂ�����肾�����Ɛ�������Ă���B�������܂��Ȃ������͒��~����A�u�g��͂��т��т̐��Q�̂�����812�N(�O�m3�N)���ɏ����ȓ��O��Ɉړ]�����B����ɂ���Č���ɂ���_��邪�ŏd�v�������悤�ɂȂ����B
9���I���߂ɒ���{�����{�����鑽��邩��_���Ɉړ]�����B���̐��m�ȔN�͕s�������A������Ό��݂Ɠ�����802�N�A�x�����������u�g��ɂ����ꂽ�Ƃ݂�812�N�ƂȂ�B�w���{��I�x��808�N(�哯3�N)7��4��������A���̎����ɒ���{�����{�Ɨ��ꂽ�n�ɂ��������Ƃ��m��邪�A���ꂪ�u�g���_�܂ł͂킩��Ȃ��B�ړ]��̒_���͗������k���A���̊�茧�����������R���E�s�����_�ƂȂ����B
815�N(�O�m6�N)����͌R�c�̕��m400�l�ƌ��m300�l�A�v700�l�����Ԃ��邱�ƂɂȂ����B���m��60���A���m��90���̌���ɂ���ď펞700�̕��͂��ێ������B����ȑO�ɂ͑�������h�����ꂽ����500�l���풓���Ă����B���߂���500�l���������A�ʂ̉������o��500�l�ɂȂ����̂��͕s���ł���B
9���I�㔼�ɂȂ�ƁA���̌��Ђ͌`�[�����Ă������B �@ |
|
������{�����{�@�@�@���B�s����
|
���Њi�͌��ЁB�w��ȋ��x�Ɍ��������_��S����{�ɒ������锪���{�ɎQ�w���������L����Ă���B���Α叫�R���c�����C�����ׂ̈ɉ����������Ɋ��i����A�c�����C�̋|����ڂȂǂ��ɔ[�߂��Ă���Ƒn���̗R�����L���Ă���B����͕������ɔ����{�����i�����ȑO�ɁA�c�����C�ɂ�芙�q�������h���锪���_���_��S�̒���{�Ɋ��i����Ă������ɋ����ċL�q�����B�吳11�N(1922�N)�Ɍ��Ђɗ��B
����Ր_
������_
��_�V�c(�_�c�ʑ�)
�_���c�@(�����ѕP��)
�s�n���P��
���R��
���{�̌�_�͍��Ƃ���삵�w��Y�ƌo�ς�ɂ��A�Г�����ł����l�̈ꐶ����苋��������_�Ɛ\����_�͍̂ŗ�Ƃ�����ł��B��Ր_�͜�_�V�c(�_�c�ʑ�)�_���c�@(�����ѕP��)�s�n���P���̎O���̐_�ɍ����܂��B
����20�N(801�N)�����V�c�@���c�����C�����ē��������̂Ƃ����n�ɒ_����z���A����{��u���A��̖k���̒n�ɖL�O��(�啪��)�F�������_�̐_����������A�_�{���̈������ƂƂ��ɒ���{�����{�ƍ������k�J��o�c�̎��_�ƂȂ��܂����B
�O�m���N(810�N)���Ƃ̐��h�����A����V�c��蛂�M�̔����{��������܂��܂����B
�Ï�3�N(850�N)���{�ʓ��E�~�m(���o��t)�͋{�Ƌ{�����̈������ɂčŏ����o���u���A�C����A�C���A������A���u���̏��Ղ������Ȃ��A������P��Ƃ��܂����B
�V�c3�N(941�N)�����G���͕����吪���̂���A���{�ɐ_�̂Ȃ�ѐ_�����[���폟���F�肵�܂����B
�N��5�N(1063�N)�����`�܂����`�Ƃ͒���{���R�Ƃ��ē��{�ɐ폟���F�肵�܂����B
�������N(1177�N)���B�������͓��{�����\�Z���������͂��ߎГa�̑��c�A�L��Ȑ_�́A�������̐_����[���������h���܂����B
����5�N(1189�N)�������͎�ɋԋ����{���j�a�ƍ����S�_�����Ƃ��Ƃ����q���{�̌��Ƃ��A�����o�H�����̏��ϕ�(��)�������Đ��V���Ղ����s��������P��Ƃ��܂����B�����ɂ͉��B���V�����{�Ƃ��̂��ꉜ�B����s�̊������⊋�����̏d�b�A���R���̐��h�������܂����B����3�N(1336�N)�k�����Ƃ͒���{���R�Ƃ��ċF��Q�q���܂����B
����2�N(1337�N)��k�������̕��ɋ����s����ɂ߂��Гa�Q�⑽���̐_��Y���͂��Ƃ��Ƃ��p�o�ɋA���܂����B
��a4�N(1348�N)�k�����B�T��g�ǒ�Ƃ͒_��A�]�h�A�a��A�C��A�z�g�̌܌S�̓��ʑK�������ē�k���������ɏĎ������Гa�Q��V�ɑ��c�Č����܂����B
�������N(1390�N)�V��@�䓙�R���������C�����ɉ��߂܂����B
�V��19�N(1591�N)�L�b�G�g���������h�����e�����������ĎГa�̑��c�Ƒ����̋����Ђ̏C���������Ȃ��L��ȋ����n�̐_�̂����g���܂����B
���i6�N(1629�N) / ����2�N(1662�N) / �勝2�N(1685�N) / ���\7�N(1694�N) / ��i6�N(1709�N) / ����2�N(1717�N)�@�]�ˎ���ɂ͐��ˈɒB���̌����ی�����˕M���̔����_�Ƃ��Đ��h�����A�˔�������ĎГa�̑��c�C�������܂����B
���i14�N(1637�N)�ɒB���@�̐������P�͌c���^���̂��ߌ��ׂ����Вn�̏C���ƎГa�����ݒn�ɑJ�����܂����B
����8�N(1811�N)�ˎ�A�ˎm�A����Ȗk�����S�l�Z�Z�����̑�̓��A�̓��A���f�A���X�̑�����(��t)�������Č��Гa�c���܂����B���{�͉��B�X�������ɒ������邱�Ƃ������āA�X�����������{�����g����ˎ�A�����ˎ傳��ɖ����ɂ͔��ٕ�s���֕��C���開�{��l���n�ߋߓ��d���ȂǗ��j�ɖ����c���Ă���҂������Q�w���Ă��܂��B
����9�N(1876�N)�����V�c�͓��k�䏄�K�݂̂���A�E��b��q��A�{�������厛�����A���t�ږ�،ˍF������킵�Č��q���点���܂����B
�吳11�N(1922�N)���Ђɗ܂����B
������_��̂Ȃ��œ��ɍ���V�c���M�̔����{����A���c�����C��[�̕ƓL��A���`�ƕ�[�̌�|�A�ɒB����[�̑����Ȃǂ�����܂��B�]�ˎ���̋I�s�Ɛ��]�^�������{���Q�w���ŗ��ƓL���q���A���̊G���c���Ă��܂��B�@ |
|
���ۍ���א_�Ё@���_�Ё@��ː����_�Ё@�@�@��ˎs����
|
�ۍ���א_��(�Ƃ����Ȃ�)�@/�@���_�Ё@/�@��ː����_��(���̂ւ܂�����)
3�̐_�Ђ������Ɉꏏ�ɂ���܂��B�암���̗c�N���vጂ��A�����ɗ������u��ב喾�_�Ȃ�v�ƍ����锒�ߔ����̘V�l�̂������ŕ����������Ƃ���A �ۍ���ב喾�_�Ƃ��������ł��B
���������h�ł��B���̓ۍ���ׂ���Ƃ������O�͂悭�����܂��B���Ղ肪����ȂƂ���ł���ˁB
�u�Έ���(������)(���Њw��)�@/�@����5(1858)�N�A���̏��q����(�ȓ�)(����ǂ�)�����n��K�ꂽ�ہA�a���w�̍u�w��ړI�Ƃ��āA�ۍ���א_���K�����ۓ�����(�܂��肭)�Ɛݗ������̂����Ђł���B����ɖ�����(1860)�N���˂̋g�c�[�ܘY(����)(�Ԃǂ�)��������K�˂��ہA�ЋK��n��������w���A���ЂƂ��Ă̑g�D�𐮂����B�В������ۓ������A��ٖ��̂Ƃ��A���ۓ���g(������)�A�c�����X�V������Ƃ��Ă��̌o�c�ɓ��������B�Έ��ɂ͑����̒����ŁA���Ђ̍u�`�͂����ōs��ꂽ�̂ł���B���Ђ̖��O�̗R���́u�N�q�H�ȕ���F�ȗF��m�v�Ƃ����_��̈�߂ł���B����11(1878)�N�A��g�𒆐S�Ƃ�����ЎЈ��͎��w�Z�ł�����Њw�Z��ݗ����A�ߑ�Љ�w��K�C�ȖڂɂƂ肢�ꂽ�B���̊����͓��n�ɂ����Đ��N�̈琬�ɐr��ȉe���������炵�����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��A��N�����ɐ�ĕ������w�Z�̐ݗ�������Ɏ������̂��A����A�����A�Y�Ƃ̊e����ɂ킽���Ċ����̈̐l��y�o�����̂��A���̑b���������Ђɂ݂邱�Ƃ��ł���B�v
�������������Ă��`�オ��܂��傤�B��x�݂������C����}���Ă̎��z�Ԃ��Y��ł��B���Ђ����h�ł��I�����͂��a���܂��K�����Q�肷��Ƃ��낾�����悤�ł��B�u��Ёv�Ƃ���܂��B
�ۍ���ׂ���E���������܂��Ɓu���_�Ёv�����ɂ���܂����B���������͈�ו��ɂł��B���_�Ђ̂����ł��B�����ɒÌy���P�������������N���������n�����Ղ������_�Ђ������ł��B���̘e�ɂ͏������K������܂����B������͊R�̕��ɂ������K�ł��B�����Ƃ���ꂻ���ł��ˁB�u�k����{���v���a����Q�q�L�O��v�������ł��B�����V�c�̑�7�c�����{�[�q���e���ƌ��������l�炵���ł��B
�����炪�u��ː����_�Ёv�ł��B���傤�Ǒ݂��Ă�������{�����̋�ː����̂��Ƃ���n�܂�܂��B�����ɍs������œǂ�ł܂����A�������{���y�������̂ɂȂ�܂����B�암�ƂƑ������l�Ŕ��t�߂Ƃ��Ă��ׂČ������ꂽ�l�Ȃ̂ł����ɐ_�Ђ�����킯�Ȃ��̂ł��B
�u��ː����_�Ё@/�@��ː������a�ꂽ�O�̔�(�{�錧�I�)�̋�ː_�Ђ��番�삵�ċ�ˏ��m�̊ېՂɂ����_�Ђ���������܂������A�V�������ɔ�������13�N�ɂ��̏ꏊ�Ɉڒz�V�z����܂����B�v
�ׂɈ��{�����������̂ł��������ƂȂ����Ă���̂ł��傤���B��ˏ�́u���̊ېՁv���狫���֑����}�ȐΒi�������ł��B
��א_�Ђ̍����ɕ�����ׂ̂悤�Ȓ�������������̂������܂����B���̒������C���������Ƃ����l�����܂������͑�D���Ȃ̂ł��B���̐�ɉ�������̂��m�肽���l�Ȃ̂ł��B���R����ׂ��܂ł��ς���������܂����B
�u��ו���(���Ȃ�Ԃ�)�@/�@���v2�N(1862)�A�ۍ�(�Ƃ�)��א_�Ћ����ɐݒu���ꂽ�����ˍŏ��̎��ݐ}���قł��B���Ѝw���̂��߁A��ז��s�u(�ނ���)�𗧂āA���̔�p�ɏ[�Ă������ł��B��ו��ɂ́A��˒n���̐l�ވ琬�ƒn��̐U����ڎw�������Ђ̊����̈�Ƃ��ĊJ����A���Ђ̎Ј��₻�̎q�ǂ������ɐ}����݂��o���܂������A����Ɏ��͂̑��X�̐l�X�����p����悤�ɂȂ�܂����B�����͘a�������犪�Ə̂���A���p�҂͔n���d���āA�����͏H�c�����p�n���ɂ܂ŋy�Ɖ]���Ă��܂��B�v
�u�Z�p��`(��������݂���)�@/�@�ۍ�(�Ƃ�)��א_�Ђ͎Г`�ɂ��ƁA����20�N(801)�܂��͏��a�N��(834�`)�̍��A�o�H���̑啨��(�������̂���)�_�Ђ�����(���傤)�����̂��n�܂�Ɖ]���A�V�a��N(1682)�A���ۓ������q�傪�얲�ɂ�茻�݂̒n�ɑJ�������Ɠ`�����Ă��܂��B�ː�����͐����˂̋F�菊�ƂȂ�A��Ղ͐�Ίi���Ő��\���̕��m���O����x�삵�A�_�`�n��(�݂����Ƃ���)(���o����)���s���Ă��܂����B���̐_�`�͕��13�N(1763)�A��34��ˎ�암���Y(�Ƃ�����)������i�����Ɖ]���A�`��I�ɂ��������M�d�Ȃ��̂ł��B�v
�ۍ���א_�Ђ́A�u�Ƃ����Ȃ肶��v�v�n���ł́u�ǂ��v�Ƒ����ŌĂꂽ��A�P���Ɂu���Ȃ肳��v�Ƃ��Ă�Ă邻���ł��B�@ |
|
�����Ό䏊 1�@�@�@���S���Β�
|
���Ώ�(����������-���傤)�́A��茧���S���Β����Êق̕W��200m�ɂ���u��ŁA�䍂��10m�ƁA���ӂ�菭���������ɂ���܂��B�ʖ��Ƃ��ẮA�Â��͓H�Ώ�Ə����A���Ό䏊�E�����قƂ��Ă�܂����B
�ŏ��̒z��͕s�ڂł����A���q����̂͂��߂ɁA�������̑��E���t�����A��a���O�ւ�藤�����֎�S�H�Α��ɉ��������Ƃ���܂��B���t��(������̂Ђ����)�́A���B�U�߂Ő���������A�H�Α��̌ˑɉ��~���\����ƁA�ˑ��̂��܂����B�X�ɁA���̎q�E�ˑ��́A1206�N�ɓ암������U�߂��āA�R���z����ƁA�o�H���̎R�{�S�剮(���ǂ�)�ɐi�o���A�o�H�E���R�c���z���܂����B�������A���̌���A���͌ˑ̗̒n�Ƃ��ĉ����悤�ł����A�ˑ̖{���͖剮�邩��߂邱�Ƃ͂���܂���ł����B
��k������ɂȂ�ƁA�H�Ώ�����C���ꂽ���A�V�z���ꂽ���ŁA���̏ꏊ�ɂ���ƌ������ɂȂ�A���E�ˑ����߂��悤�ł��B���̌�A�쒩�̕����ł���k�����M���A1346�N�`1351�N���A4�N�Ԓ��x�A�H�ɑ؍݂��Ď��ӂ̍����Ɏx������A�w���������Ƃ���A���Ό䏊�ƌĂ�鏊�ȂƂȂ�܂����B�₪�āA�o�H�̌ˑ@�Ƃ́A1423�N�Ɋp�ُ��z�邵�Đ��͂��g�債�܂��B
�퍑�����1532�N�ɁA�ˑ͏��̔z�u�����������Ȃ����L�^������A�H�Ώ�ɂ͎�ˍ��q��т������Ă��܂��B���̍��̎��E�ˑ̉Ɛb�c�͎�ˎ��A���R���A�ؑ����A�c�����A�ڎs(����)���A�p�̑A���ꎁ���m���Ă��܂��B
���̌�A�H�̌ˑ��́A�암�����̏d�b�ł���ΐ���E�ΐ썂�M�ɂ���čU�������悤�ł��B1540�N�A���Ώ�ɂ́A�ΐ썂�M���͂��߁A���m�ɐ��A�����Y�����q��A���ˎ��A�ʎR���A�H�����炪�����܂����B�ˑ��́A��ˎ��A���R���ƂƂ��ɓH�Ώ�ɂĐ킢�܂������s��A��ˎ��͓������A���R���͎���̎�Œ��R����Ă������A�ˑ�\�Y�����ƈꕔ�̉Ɛb�͊p�ُ�ɗ����L�т܂����B
���݂̎��Ώ隬�ɂ��锪���{�́A�H�Ώ��E��ˍ��q��̎��_�ł����B���̏H�c�X���̗��������ނ悤�ɁA���Ώ邪�z����Ă����悤�ł��B�암�̂ƂȂ����H���A��������̎z�g�F�����U�������悤�ŁA��x�́A�ΐ썂�M�Ɍ��ނ���܂������߂��A1546�N�Ɏ��j�E�z�g�F�^(����-��������)�������Ď��ΑF��(����������-��������)�Ə̂�3000�ѕ��ɂāu�z�g�E���Ό䏊�v���J���܂����B���̍��A���ɉ������Ă��܂��B
�܂��A����̗����E���c���E���\�����̈ꑰ�ł��鈻�D�L�M(���D�z�O�L�M)���A���Ό䏊�𗊂��ē���ė����Ƃ��A�R�t�Ƃ��Č}����ꂽ�Ƃ������Ă��܂��B���D�z�O�͑��̒n�ɁA���p����1586�N���Ɋ��������Ă��܂��B
�������A�암�M���̑�ɂȂ�ƁA1584�N�`1586�N�܂ʼn��x�����Ώ邪�U�����āA���ӂ����X�Ɏ����܂��B1586�N�A���Ό䏊��3��ځE���v�F(����������-�Ђ�����)�́A�q�ڎs���E�����o�_���O�ˏ�ɑ����āA�a���������܂����������o�_�͕ߔ�����A�܂��암���ɍU������܂����B���ɁA���v�F�́u�悵���v�̌̎�(��q)���c���A���Ώ���̂ĂČˑ̉Ɛb�E��ˍ����ɏ���ƁA�����E��������ɓ��ꂽ�ƌ����܂��B���̎�ˎ����q�ڎs��ɑދp�������߁A���Ώ�Ɏc�����͕̂S�����肾�����Ƃ���A���Ώ�͗��邵�܂����B�����o�_�͋�����Ďߕ�����A��ˍ����͐�k�p�قɗ����L�т��ƌ����܂��B
1591�N�ɂȂ�ƁA�암�M���͎��Ώ�ɔ��������Y���q�����܂����B�������A1592�N�A�L�b�G�g�̈�̎���̕��j�ɂāA���Ώ�͔j�p����Ă��܂��B�������A�]�ˎ���ɂ͎��Α㊯�����u���ꂽ�悤�ł��B
�x(�₰��ڂ�)�̐ՂȂǂ����邻���ł����A�X�������͑�n������Ă���A��\�͂قƂ�ǎc���Ă��܂���B
���Β��̏j���̐Ȃł͕K���u�悵���v���S���x���Ă��܂����B����́A���Ώ�ɂ͐��̎�Ƃ��āA�����c��㗬����n�����H���g���ėp����~���Ă��������ł��B�����āA���̐��H���암���ɔ�������Ȃ��悤�A������݂��āA���l�̏����Ɍ����点�Ă����ƌ����܂��B�암���͉B�����g���Đ������@���A���ɒ����ɖڂ�t���āA�����ɐ��H�̔閧���o�����Ƃ��܂������A���j���Ă��܂����Ƃ����b���A�̎��ɂȂ��Ă��܂��B���̌�A�x�肪�t�����āA�����|�\�E���悵���ɂȂ�������ł��B
|
|
�����B�z�g��(����)�E���Ό䏊��
2 |
���B�z�g���͎z�g�S������ �ɋ���u���u�z�g�䏊�v���̂��A�V���N�Ԃɂ͎��Ζ~�n�ɂ��i�o�A���Ό䏊���\�����Ƃ����B
���āA�z�g���̑c�͑������̒��j�����Ǝ��ł���B�Ǝ��͒��j�ł͂��������A�������̉Ɠ͖k�@�Ƃ��Ƃ���헊�����p���B�������A�c���̑��������傪���̌㑱�������߁A�Ǝ��͑������̑�\�Ƃ��āA�֓���Ɛl�Ƃ��Ċ���A���������Ƃƌ���� �A�����Ƃ��Ă̊�b��z�����B�Ǝ��͗������z�g�S��̗L�������Ƃɂ��A���̌n���͌�Ɏz�g�����̂���ɂ�����B�Ǝ��̑\�������������Ɠ��N�̑��������獂�o�ŁA��k�����Ɋ����B���o�̒��j�ƒ��͗�����A���B����s�Ƃ��ē�R�Ɖ��B��֓��őΌ���������A�Ⴍ���Ċ��q���{��̐킢�Ő펀����B17�˂Ŗv�����ƒ��ɂ͍Ȏq���Ȃ������Ƃ���A�����o�͑F�o��{�q�Ƃ��Ďz�g�S��̗L�����A�₪�Ă��̌n���͍������������Ƃ��A�z�g���@��(���q��)�Ƃ͕ʂɁA���B�̒n�ɍ݂��āA���R�̈��E�u�z�g�䏊�v�Ə̂���퍑�����܂ʼnh�����B�z�g�䏊�̗��̎��т͏\���ɂ킩���Ă��Ȃ����A�V��14�N�o�F�̑�ɓ암�����ˑ�ǂ��o����̂��Ă��������U�����A��F���z���Ď��Ό䏊���̂����Ƃ���Ă���B
���Ό䏊(���Ώ�)�́A�ˑ̎��Ώ��啝�ɉ��z�����Ƃ��錩�����L�͂ŁA���Ζ~�n�̂قڒ����A���ΐ�̍���(�k��)�̒i�u�ɒz���ꂽ�B�i�u�͒�n����10�����炢�̍���������A��͍��Œi�u���A���[�ɓ��s�A���Ɏ�s�A��̊s�A�O�̊s�Ɛ��ɘA�Ȃ�B�s�Ɗs�̊Ԃɂ͍��ł��[��3�`4���̍��Ղ����o�����Ƃ��ł���B��̖k���́A���}�s�Ȑ��тƂȂ��Ă���B�꒣��́A�o���͕s���ȓ_�����邪�A���숻���̏o�Ŏz�g�䏊�b�ƂȂ��������z�O�L�M�̎�ɂ����̂Ƃ���Ă���B�L�M�͓y�؍H�������ӂł������̂��A�y������A����Ɉ��������Ƃ����B
��s�͓����A��k���ꂼ��70�`80������A���݂͔����{�ƂȂ��Ă���B�e�s���c�f����悤�ɐ������H�������Ă���A��s�܂ŎԂŏ�����邱�Ƃ��ł���B�܂���s�Ղ̔����{�̓쑤�������ɎԂ��߂čs�����Ƃ��e�Ղł���B�i�q�̎��Ήw�����������5�����x�ł���B�����̌��݂̉i���������Ȃǂɂ͉Ɛb�c�̉��~�n���������Ƃ���邪�A���̐Ղ͂͂����肵�Ă��Ȃ��B
���Ό䏊�́A�c�O�Ȃ��炻�������͑����Ȃ������B�F��A�F�M�A�v�F�Ƒ����A�v�F�̑�ɂ�����V��14�N�암���ɂ���ĖŖS�ɒǂ����܂ꂽ�B
�@ |
|
���w�����^�I�_�Ё@�@�@���g�S���g���{��w����
|
�w�����͕W��136���A��k�ɂȂ��炩�ȋu�˂ł���B���͂ɂ͑��̍���Ȃǂ͂Ȃ��A���̐w�����������Ɨ����Ă���B���̒n�`�̂ɁA���̒n�͋�����荬�����܂��܂Ȑ킢�̏�ʂʼn��x���U�ߎ肪�w��~���Ă���B���ɌÑォ�璆���ɂ����Ă��B�X���镐�l������A�˂Ă���A�퍑���㖖���܂ł��̈�ࣂ�����j��D��Ȃ��Ă���B���݁A���n�Ɍf�����Ă���ē��ɂ�����̂���ׂĂ݂��
�ڈΓ����̂��߁A���{�������h�c�B���̒n�ōȂ̔����䔄(�{�ŕP)���Y�C�t���čc�q�����܂�邪�A����3���ڂɖS���Ȃ����̂ŕ��z�����B���ꂪ���n�ɂ��鉤�q�X�Õ��Ƃ����B
�Ė��V�c5�N(659�N)�A�ڈΓ����ɕ��������{�䗅�v���h�c�B
�V�����N(781�N)�A�ڈΓ����ɕ����������������h�c�B
����20�N(801�N)���ڈΐ����ɕ��������c�����C���h�c�B
�N��5�N(1062�N)�A�O��N�̖��̏I�펞�ɁA�����`�E�`�Ɛe�q���{�w�Ƃ��ďh�c�B���̌�A��O�N�̖��̎����ɂ����Đ��X�̈�\���c���B
����5�N(1189�N)�A���B�����������̂��߂ɏo�w�������������{�w�Ƃ��ďh�c�B
�V��16�N(1588�N)�A�암�M������������̎z�g�����U�߂鎞�ɖ{�w�Ƃ����B
�V��19�N(1591�N)�A��ː����̗���������邽�߂ɏo�w���������������h�c�����Ƃ����B
����ő����̕������W����n�ł��邪�A�Ƃ�킯�[���䂩��̂���̂������`�E�`�ƕ��q�ł���B�܂����̒n���g�w�����h�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂́A���̕��q���{�w���\�������Ƃ���n�܂�Ƃ����B���̒n�ɖ�c�����܁A��������ɏƂ炳�ꂽ�����́g�����̊��h�����F�ɋP���Ē�ɉf�����̂����āA���`�Ƃ������̋g���Ƃ��đ傢�Ɏm�C��g�����̎��ɂ��Ȃ�ő��c���ꂽ�u���̗`�v������B����Ɍ��`�Ƃ���]���[����`�����ꂽ�g����ٍb�h�̕��@�����H���ċɂ߂��Ƃ����w�`�̐ՂƂ������̂��c����Ă���B
�����ė��`�E�`�Ƃ����̒n�Ɍ��������̂��A�w�����̒��S�ɒu���ꂽ�I�_�Ђł���B����͑�a�̏t����Ђɂ���O��������芩�����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B���̈���ŁA�G�̈��{��C���U�����鎞���M�̒��̖I�̑�Q�ɔY�܂���Ă����`�Ƃ��A�t�ɖ�̂����ɖI�̑���܂ɋl�߂āA���������G�w�ɓ�������œG�����������ĎU�X�ɓ����ʂ��������߁A�I���J��_�Ђ����������Ƃ����`�����c����Ă���B
�O��N�̖��̏I�펞�ɂ��̒n���{�w�ł��������Ƃ���A���̒n�ɂ͋C���̈������̂��c����Ă���B�킢�ɏ����������`�E�`�ƕ��q�͂����Ŏ�����������Ȃ����B���̎��ɓG�̎�̂ł�����{��C�̎��N���u�����ꏊ�������Ȃ��c����Ă���B���������̏ꏊ�́A�`�Ƃ̒��n�̎q���ł��錹���������B���������U�ߖłڂ����ۂɁA���̍Ō�̓���ł��铡���t�̎��N�����߂ɂ��g���Ă���̂ł���(�w�����̂��ɂ͂��̑t�̎��������˂��c����Ă���)�B
���݂͎j�Ռ����Ƃ��ĊǗ�����Ă��邪�A�Ƃɂ��������鎞��̗l�X�Ȉ�\���Љ��Ă���A���̓��₩���͕��݂ł͂Ȃ��B�@ |
|
���ނ��ŕP�̕�@�@�@��茧�����s���{�쒬
|
�암�����̐����E�����̕��͐�c���ނ��őގ��������Ɏg������̍������Q���Ă������A���̖S���Ȃ������ɁA��̂̉��ɂނ��ł�A�z������͗l�����ꂽ�B�ނ��ł��M������ꂽ�����́A�ނ��ŏ����̖x���߂��点��������悤�ɖ�����(�ނ��ł͐������Ȃ���)�B�����A���̕�֍s�����߂̋���x�ɉ˂����̂����A���ɂ��Ĕj��Ă��܂����B�����ĉ��x���t���ւ��悤�Ƃ���̂����A�ނ��ł�����Ă����j���B�悩��召�̂ނ��ł������o�Ă��邵�A����ɉ����̕��̔����Жڂ̎ւɕω����ĐΊ_�̌��Ԃ���o�Ă����Ƃ����B�����ʼn����̕����g�ނ��ŕP�h�A���̕���g�ނ��ŕP�̕�h�Ɩ��t�����Ƃ����B
���̉����̕��͊��������̗{���A�܂��c�͋ߍ]���łނ��őގ��������U����(�����G��)�ł���B���̂ނ��ŕP�̓`���́A�܂��ɂ��̕U�����̓`�������[�ƂȂ��čL�܂������̂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| ���H�c�� |
   �@
�@
|
|
����鍳�P�@�@�@��k�s(���E��k�S�c��Β�) |
����鍳�P 1
��鍳�P(�����₵��Ђ�)�͕�����(������̂܂�����)�̑�O���ƌ����Ă��܂��B�@����(�ɂ傼����)�Ɠ���l���ł���Ƃ����`��������Εʐl�Ƃ����������A�ޏ�������`���ɂ͗l�X�ȃo���G�[�V����������܂��B
�@����̍��ł������܂������A�@����̕�Ɠ`��������̂���������2�̌b����(���ɂ���)�Ɏc����Ă��܂��B�������떃�S�֒̌b�����ƕ��������킫�s�̌b����(�l�q���ʎR�����1)�ł��B�O�҂Ɏc��`���ɂ��ƁA����ŖS��ɁA�O���̑�鍳�P�����̒n�ɓ���A�����ނ��т܂����B�����ɂ͔@����̕��Ƒ�鍳�̕�肪���邻���ł��B��҂ɂ͑�鍳�̕�Ə̂���y����ƕ�肪�����Ă��邻���ł��B���b�����̓`���ł́A�@����̍ݑ����̖��O���鍳�Ƃ��Ă���悤�ł��B
�Ƃ���ŁA�H�c���̓c��̂��ɂ���c�ɂ���鍳�P�̓`�����c���Ă��܂��B
�u����̈ꑰ�͗��̌�A���U�����B�ɓ������т܂����B��鍳�P�͌ܐl�̉Ɨ��Ɏ��ꒆ���ۓ�(�Ȃ����ڂȂ�)�ɏZ�ނ悤�ɂȂ�A���̑c�ɂȂ����Ɠ`�����Ă��܂��B��鍳�P�������Ƃ����P�˂����݂��c��A�]�ˎ���ɂ́u���c�P�ˁv�̐Δ�������Ă��܂����B�܂��A�P�����{���Ƃ��Ď��Q���������n�����͒����ۓ��_�Ђɕ��ꍡ�Ȃ����h����Ă��܂��B�v
�u�ꏊ�ł����A����341������k�サ�A�c��Ήw���ʂȂ����čs���ΈӊO�Ƃ������茩����܂��B�u�P�ˌ����v�Ƃ������ł��Ȃ�ڗ����܂����̂ŁB���̂܂܁A���֑����Ă����Β����ۓ��_�Ђ�����܂��B�c�O�Ȃ��牄���n�����͔���܂���ł����B�v�Ƃ������Ƃł��B
��L�̓c�̓`���ł́A��鍳�P�͂��̒n��5�l�̎q���Y�݁A���ꂼ�ꂪ���c�ƂȂ����Ɠ`�����Ă��āA��鍳�P�̏o�Ƃ�ޏ���@����ƌ��т���`���͂���܂���B
���āA��鍳�P�`�������I�ȕ��Q����ɕϖe�����̂́A�ǂ����]�ˎ���ɓ����Ă���̂悤�ł��B�֓��̉p�Y�E����̗�͂������č]�˂̋S������Ƃ�������ƍN(���邢�͓V�C)�̔z���ɂ��A�]�ˎ���ɂ͈Ӑ}�I�ɏ���̒n�ʂ��グ���A�܂������̊Ԃ̐l�C�����������킯�Ȃ̂ł����A��鍳�̕ϖe��(�����܂őz���Ȃ̂ł���)���̕ӂ�̎���Ɗ֘A������̂�������܂���B���Q杂ɂ����đ�鍳�P�Ɨ���œo�ꂷ��̂�����̑��q�Ƃ����ǖ�(�悵����)�ł����A�ޏ��܂��͔ނ��o�ꂷ�镨��ɂ͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
•�u�P�m���������`�`(���Ƃ��₷�������イ���ł�)�v(�R�����`/����4�N(1807�N)��)
•�u����R��鍳�P����v(����7�N(1810�N)�Ɋ��s���ꂽ���`�́u�e�G���ƂӔV�݁v�����肵�Ė���19�N�ɍĊ����ꂽ���́B)
•�u�֔��B�q�n(����͂����イ�Ȃ�����)�v(�ߏ��卶�q��/����9�N(1724�N)��)
�ȂǂȂǁB���Ȃ݂Ɂu�֔��B�q�n�v�ɓo�ꂷ�鏫��̖��́u�����v�Ƃ������Łu��鍳�v�ł͂���܂���B�ǂ̍�i�ɂ����ʂ���̂́A����̖����d�p�g���ɕϐg���Ă��邱�ƁB���`�̑�鍳�͂Ȃ�Ɖ�寜߂��������肵�܂��B
�ߏ��卶�q��́u�֔��B�q�n�v���㉉����Ĉȗ��A����̖������镜�Q杂���ڗ���̕���ł����Ύ��グ����悤�ɂȂ��������ł��B������ƋC�ɂȂ����̂��u��ȉԑ��n����(���Â܂̂͂Ȃ����܂̂�����)�v�Ƃ����猩�������̋ؗ��Ăł��B����̖��̘ݕP(���������Ђ�)�����{�����ɗ�����������ǁA�n�Ӎj(�킽�Ȃׂ̂�)�̎�Ɋ|�����ĎE����A���̉��O���ǖ�ɑg���ĕ��Q����Ƃ������b�ł��B
|
����鍳�P 2
������̖��Ƃ����`����̗d�p�g���B�{���̖��͌܌��P(�����Ђ�)�Ƃ����B
�V�c�̗��ɂĕ����傪������A�ꑰ�Y�}�͖łڂ���邪�A�����c�����܌��P�͉��O���点�A�M�D���_�̎ЂɉN�O���ɎQ��悤�ɂȂ����B����̓�\���ڂɂ͋M�D���_�̍r���̐����������A�܌��P�͗d�p��������ꂽ�B�M�D�_�Ђ̍r�_�́u�N�̍��Q��v�̎��f�_�Ƃ��ėL���ł���A�M�D�R�ɉN�̔N�̉N�̌��̉N�̓��̉N�̍��ɍ~�Ղ����_�Ƃ��`������B�M�D�_�Ђ́A�w�h�ԕ���x��w�������q�x�A�\�u�S�ցv�A�F���̋��P�̓`���ȂǂŎ��グ���Ă���B
�r���̂������ɏ]���đ�鍳�P�Ɩ�������܌��P�͉������֖߂�A���n�̏�ɂĖ鍳�ۂ�w偊ۂ�艺���W�߁A����]���̔������N�������B����͑�鍳�P���s�̒������������(�ʏ̑��Y)�ƎR������ɉ����A�����̖��ɉA�z�̏p�������đ�鍳�P�𐬔s�����B���̊ԍہA��鍳�P�͉��S���ĕ�����̂��Ƃɏ��V�����Ƃ����B �Ȃ��A���c�����C���鎭�R�ɂāA��S�l�̌��_�ۂ̎艺�ł���S�l�ɖ鍳�ۂƂ����҂�����B�鍳�ۂ͉��S���A�c�����C�̉Ɛb�ɂȂ��Ă���B���̖鍳�ۂƂ̊W�͕s���B
�`���ł͗d�p�g���Ƃ���邪�A���ۂ͓ɓ�����Ƃ��Đ��U�𐋂��Ă���B����̖��A�܌��P���Ƒ�鐷�P�̕�́A���݂̈�錧���Ύs���ˁA���������琼��200m���ꂽ���̒��ɏ����Ȓ˂�����B�ȑO�͐������ɓ�Ƃ��ďo�Ƃ��Ė鍳�ƌĂ�Ă��邪�A�n���ł͑�鐷�P�ƌĂ�A���ł���������������Ă���B�����������̉h�c�t��������ɂ́A��鐷�P�̐Ί��Ɏg���Ă����傫�Ȉꖇ�������u����Ă���A�ȑO�͏���̋������Ƃ��Ďg���Ă����B
|
����鍳�P 3
�{���͌܌��P�B������̈⎙�Ƃ��ċߐ��̏����E�Y�ȂȂǂɓo�ꂷ��l���B
�j����͓V�c�̗��ňꑰ���ł��ߓ�Ƃ��ė]�����߂������ƌ����邪�A�ꕔ�̓`���ł͕���ꑰ�Y�}���E���������ւ̍��݂𐰂炷�ׂ��A�M�D�_�ЂʼnN�̍��Q����s�������ɍr�_�̉���Ď�p�t�ƂȂ����Ƃ����B�l�X�Ȏ�p��d�p����g���Č��Ƃւ̕��Q����Ă��E�ǖ�����������A�Ŋ��͒���̌��킵���A�z�t�Ƃ̐킢�ɔs��A���V�����B
�̕���╂���G�ȂǁA�㐢�̕��w��i�ɂ��r�F���ꂽ�`�œo�ꂷ��B���ɐ������邪�`�����d���u������ǂ���v�̊G�́A�̐썑�F�̕����G�u���n�̌Ó���(��鍳�P������Ȋ[���̗d������������G)�v�����`�[�t�ɕ`����Ă��鎖�ŗL���B
|
����鍳�P 4
������̈⎙�Ƃ���A���̈�u���p���d���������e�̏����B�j���ɂ͂Ȃ����A�w�O�����L�x�ɖ��O�������閺���w�v�����L�x��w�����ߏ��x�ɂ���@����̋L�q��ʂ��ċr�F����Ă��������̂ƍl�����Ă���B�����L�̐��E�Ŏ�v�l���Ƃ��Ĉ�����悤�ɂȂ����̂́A�R�����`��w�P�m���������`�`�x�Ɏ��グ���Ă���̂��Ƃł���B
�w�P�m���������`�`�x ���o����鍳�P�́A�͂��߂͔@����Ƃ��ĕ����ɗ�ނ��A��寂̐�����Ő傩�犪���𐁂����܂�A��ƂƂ��ɖd������ݗd�p�Œ��Ԃ��W�߁A���n�̌Ó����ɑ������悤�ɂȂ�B���������̉A�d�͑��Y�����ɂ��ł��ӂ���A���Q���ĉʂĂ�Ƃ������������ǂ邪�A���̂悤�ȋr�F���s����ȑO�̑�鍳�P�͓��s�̐l�ł��肻�̉��ς̃M���b�v�Ƃ����Ƃ���ɂ��L�����N�^�[���^�̑�_����������B�܂��A��寂̐�l����d�͂𐁂����܂�鏗���Ƃ����̂́A�@����̃��`�[�t�Ɍ������ނŁA�V�������q�ؔ��̐��E�ɉe�������ہA�G�Ɖ̕���̐��E�����т������̂Ǝv����B
����̖��͑��̍�i�ɂ��`����A�u�����v(�֔��B�q�n�F����͂����イ�Ȃ�����)�A�u�~���v(�p���]��:�䂸��͂������݂���)�Ȃǂ̖��O�œo�ꂵ�Ă���B�{�i���F�͂��̂悤�ȑ��̍�i�ɂ����鏫��̑��������A���Ȃ��炸��鍳�P�̑��^�Ɋւ���Ă��Ă���Ǝw�E���Ă���B
�����G�̉��Ƃ��đ�鍳�P��������ꍇ�́A���ɂ낤������t���A���ɏ����������A���ɋ����|�����X�^�C���Ƃ����̂��悭�����邪�A����͑��̗d�p���g��������(�Ⴆ���P)���������ꂽ�`�ł͂Ȃ����낤���B����͑P�����u���w�E���Ă��鎖�ŁA�l�X�ȗv�f�����ݍ����ďo���オ���Ă���̂���鍳�P�ł���Ƃ��������ł���B����ɁA��寊^�Ƃ�������ɕ`�������̂Ȃǂ������邪�A��ɏq�ׂ��悤�ɁA��鍳�P�̑��^�ɂ͏@����̉e��������B����Ă��̂悤�ȃ��`�[�t�̎����͂����̌��_��A�̂悤�ł���Ƃ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����낤���B
|
����鍳�P 5
�����V�c�̌�������������̖��A�S���P�͏f���̍������E���A�}�g�R�Ɋ≮��z���艺���W�߂ď������ƂȂ�A�����鍳�P�Ɖ��߂Ĉ����̌����s�����Ă����B
�m���Z�Y�G���ΔԒ��̌��ƕɂ��A�u�E�؊ہv��d�p�������ē��ݏo���B���̂��ߎ�N�������̓{��������A�Q�X�̐g�ƂȂ����m���G���́A�O�䑾�Y����̏�������A���ɕT���ׁ̈A�������̗��ɏo��B
����A�m���G���̍ȁA�P������l�̐g���Ă��M�B�}�g�R�}�g�����l�֎Q�q���邪�A���~�̓r����鍳�P�̂͂��育�Ƃɂ��A�≮�ւƘA�ꋎ����B�J�ԍX�[���ɂđ�鍳�P�̎艺�ɂ��h���ڂɑ����Ă���ȕP�����A�m���G���͋~���o���݂̍肩��m��B
�m���G���A�O���������́A�}�g�R�̊≮�ւƏ�荞�݁A���X�̗d�p�A��̑������g����鍳�P�������̖��A�|�����Ƃ̕u�E�؊ہv��D���Ԃ��Ƃ�������ł��B
|
��������̖��E��鍳�P�̗d�p�`�� 6
���̎�˓`���≅��`���̉A�ɉB�ꂽ�����ł͂���܂����A������̖��ł���܌��P�A�ʏ́E��鍳�P���A�ƂĂ����͓I�ȓ`���̐l���ł��B
�܌��P�͌��X�A���p�ɂ��x��ŁA���Ƌ��ɎQ�킵���Ƃ���Ă��܂��B�V�c�̗������肳��ĕ��������ꂽ��������c�����P�́A�M�D�_�Ђōs��ς�ŗd�p��g�ɒ����A�r���̂������ɂ���đ�鍳�P�Ɩ�������Ƃ���܂��B
���̌��x�艺�𗦂��Ē���]���̗����N�����܂������A���삪�h�������d�p�g���̑��������ƎR�������Ɍ����̖��ɔs��A�ʂĂ��Ƃ������܂��B���������ۂ͂��̌���������сA����]���̊肢�͂Ȃ�Ȃ��������̂̈��œ�Ƃ��đ����̐M�҂��W�߂��Ƃ������Ƃł��B
���ꂾ�����I�Ŗ��͓I�ł������鍳�P���ƌ܌��P�Ȃ̂ɁA�㐢�ɂ����Č���邱�Ƃ����ȉ߂���Ǝv���̂ł��B�����ɂ���������A�Ӑ}�I�Ȃ��̂��������ɂ����Ȃ��̂́A�������ł��傤���H
��鍳�P�����̈�u�������p���ŁA����̗��Ɏ��s����������̍l����`�����čs�������Ƃ́A�m����Ƃ���ł��B������̐l�C�������p���ꂽ�̂́A�ޏ��̐s�͂��傫�������Ƃ�����ł��傤�B
������鍳�P���g�������̐M�ҁA�Ǐ]�҂����̂ɂ́A���̎v�������łȂ��A�ޏ����g�̍s���ɂ�����Ȃ�̃J���X�}�������������Ƃ͊ԈႢ����܂���B���̗v���́A�d�p�����������̂ł��傤���H
���Ă����ƁA���c�����C���u�ڈΐ����v�������̂�8���I���ł��āA������ɂ��V�c�̗���10���I�B�ނ̖ړI�ł���u�����{���앜���v�������Ŏ��s�����Ƃ��Ă��A���S�ɂ��̒��삪���ł��Ē��삪�����{�ɓ��ꂳ�ꂽ�̂�12���I�Ƃ���Ă��܂��B����͒x���Ƃ������A������̖v��ɂ܂�200�N�قǁA�S�������ƂɂȂ�܂��B
�����ɑ�鍳�P������ł����Ƃ������Ƃ́A�Ȃ��̂ł��傤���B���傪�����A�L�\�Ȗ��ł��B�d�p�Ƃ����̂͂�������������̂́A���������\������яo���ꍇ�A�������炻��ȊO�̔�тʂ����˔\���B�����߂̏��u�ł���ꍇ�������ł��B
�֓��ł̊����͂��������ƂȂ�����鍳�P�ł����A���k�Ƃ̌𗬂͂܂��\��������������܂���B�ޏ������Ȗk�A���k�ɑ��ĉe�����y�ڂ��A�����{����̑����ɐs�͂��Ă����ƌ���̂́A�ނ��뎩�R�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���������\�ɏo�����Ƃ́A�����{����̑��݂���蕂������ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B
������̗��̐^���Ɠ��l�ɁA��鍳�P�̍s���Ƃ��̃L�����N�^�[�ɂ��Ă��A�o�������ڂ����Č���I�ȏ��u�ł��܂����K�v���������̂��Ǝv���܂��B
|
���P�ˁ@�H�c���c��Β�
��������A�鐝�V�c�̂���V�c�̗�(939)�ɔs�ꂽ������(50�㊺���V�c�̎q��)�̈ꑰ�́A���B�ɓ���ė��U���A����ɓ���ҁA����E��Ő[�R�ɂЂ��ގҁA���邢�͍s���m�ꂸ�ƂȂ����҂������Ƃ����Ă���B���a�����܂ŎG�ؗт̒��ɕ���Ǝv����傫�Ȓ˂�����A�]�ˎ���̍�Ƃ����u���c�P�ˁv�̐Δ肪�����Ă����B���݁A����ꑰ���S�̗��j�́A���̗l�����~�߂Ă͂��Ȃ����A��鍳�P�������Ƃ����P�˂́A�����̕���ł���Ƃ����A�P�˕t�߈�тɂ͓��̑O�A������A�n�������̏̂������Ė��c���~�߁A���ɉ��̂̔ɉh����Ă���B�P�����{���Ƃ��Ď��Q���������n�����́A�����ۓ��_�Ђɕ��A���̒n���~�̒���Ƃ��č������h����Ă���B�܂��A�P�ꑰ�̌Ñ�n�Ƃ�������ӂɂ́A�c�~�n���A���ꗎ���A�n�������Ȃǂ̖̂��b���̂����Ă���B�@ �@ |
|
�������ۓ��_�� (�Ȃ����ڂȂ�����)�@�@�@��k�s�c��ΐ��ۓ�
|
�ʏ́F�����ۓ��̒n������
��Ր_ ��R�_�_(������܂Â݂̂���)/�ΎY�����_(�قނ��т̂���)/����Y�����_(�����݂ނ��т̂���)/�V�䒆��_(���߂݂̂Ȃ��ʂ��̂���)/�_��Y�����_(���݂ނ��т̂���)/���q�_(���������̂���)
���Ђ͑�R�_�_�Ђƈ����_�Ђ̍��������_�Ђł���B��R�_�_�Ђ́A���Â��R�_�Ƃ��āA�_�����ɓĂ��A�쌱�܂������ł���B
���̈���������ƁA���鎞�ØV���A�_��������Ȃ�A����̏��������ɎĂ������ƁA���̎}��}�����Ƃ���A���̐��̖���ƂȂ�\��������������������ƌ����B�����������ƂŁA���̕t�߂̎����u�\���v�Ə̂��Ă���B
�������_�Ђ́A�̉����n�����Ɛ\������c��鍳�P(��50�㊺���V�c5��̑�������̖�)���A������̓����ɉ��ĕ��吷���쉟�̎g�����G���ɖłڂ��ꂽ���A���ĉ��H�ɗ��A���̒n�ɋ��Z���邱�ƂɂȂ�B���̎��������Ă�����{�����J�������̂ŁA�_�����ɓĂ����̂�����B(���ݕP�˂�����)
���̈���������ƁA�̐_�Ђ̑O�͐[�����c�ŁA���N��ғ��́A�d��������̂ɓ�V�����Ă������A���鎞��l�̓��q������ė��Ĕ_�k�̎�`�����n�߂��B����͑�l���y�Ȃ��قǏ��ł������B���ƂȂ�c�ނ������ė����Ƃ���A���q�ɑ����̕g���z�t�������z���Ă���B�������ǂ���A�����Ă��Ă��ƌ������Ƃ���g�͊F����Ă��܂����Ƃ����B���q�͓D���̂܂Гa�ɓ����čs�����̂Ō��Ă݂�ƁA���_�̂Ɉ�ʓD�����Ă���B���̐_�A���̗����܂Ŏ�莒�����_���ł���ƕ����q�̂ł���B
���݂��̒n��̕g�͐l�ɋz�t���Ȃ��ƌ����B
����44�N�H�c���m���̋����A�R�_�ЁA�����_�Ђ������A���a3�N�ď̂𒆐��ۓ��_�ЂƉ��ߍ����Ɏ���B �@ |
|
���Ɗy���@�@�@��k�S�������Z��
|
|
�Ɗy���͐����ɂ́u�@�]�R�Ɗy���v������^�@��J�h�̎��@�ł��B�J��͖@�G�V���j�ŁA��c�͕�����Ƃ����Ă��܂��B�����傪�g�����Ƃ�����w��������A�H�c���w��L�`�������ƂȂ��Ă��܂��B
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| ���{�錧 |
   �@
�@
|
|
����u���@�@�@���s�{����
|
��u���̒ʂ�́A���s�{������A���s��ʋǓ����c�Ə��O�����؊X���ɐڑ�����(���s�n��Ɏ���)�ׂ��⓹�̒ʂ�ł��B
�m�Ԃ�50�N��A�u�����ד����̗V�v�����o�l�k���u�����ւ́A�c�����A����Ȃ��A�т��ɍ�A���s�c�v�Ɠ����L�ڂ��Ă��܂��B�m�Ԉ�s�����̃��[�g��ʂ����Ǝv���܂��B���݂̓��������̂��̂Ɠ������͕s���ł��B��䒆�S�n�A���������o�������݂̍���45�����ɉ��������𓌐i�AJR��ΐ����O���m���w�t�߁E�≺�����_�̎�O�Ŗk��A(���͍≺�����_���K�X�ǂ̒ʂ�Œ��f����Ă��܂����������������NHK���W�I�����ǂɎ��郋�[�g)�K�X�ǑO�𗘕{�X�����܂����ɐi�݁A�r��JR���k�{���E�����w�ɋ߂��u�ē��n��v��ʂ�A��ʋljc�Ə��O����⓹�ɓ���܂��B
����u���̗R��
�����傪�łڂ��ꂽ���A���̖������n�䏊���̂���Ă��̒n�ɂ��ǂ蒅���A��u��ƂȂ��Ĉ������сA���s���l�X�ɊÎ����Ĕ������Ɠ`������B�@���̊Î��́u���l�̂��킳���������v��u��̖��Ƌ��ɂ̂��̂��܂œ`���A�ē��̓������⍡�s�̂��ڂ들���A���s���y�����E�Ƃ��č�������s�������ȂǂƋ��ɉ����X���̖����ƂȂ����悤�ł��B
����u���A������̖���������Î�
�u��u���v�͐��s���S�����痘�{�X���𓌂i�ݓ������z�����������k���ɓ����Đ��F����X����s�c�o�X�����c�Ə��̉���i�ꏊ�ɂ���܂��B�����c�Ə��̗����̓��H��k�֓����čs���܂��B���H������ɂȂ��Ă��܂����B�������u��u���v�ł����Z��X�̒��̕��ʂ̍⓹�ł��ˁB�⓹�͓��փJ�[�u���Ă��܂��B���̋Ȃ���p�ɒҕW������܂����B�u����v�Ɓu��u���v�Ə�����Ă��܂��B��u��Ƃ͏o�Ƃ��ĕ���ɓ����������̂��Ƃœ�m�Ƃ������܂����A�⓹�̖��O�ɂȂ����`�����c����Ă��܂��B�V�c�O�N�ɕ����傪�������N�����Ėłڂ��ꂽ���A����̖������B�ɓ����Ă��ē�ɂȂ��Ă����ɏZ�݂܂����B
��ɂȂ�������̖��͒������J�����l�ɊÎ����Đ������������ł��B���̊Î������������ƕ]���ɂȂ�A�S���Ȃ�������u��u���̊Î��v�Ƃ��Ďp����ĉ����X���̖����Ƃ��Ė�������܂ŊÎ����������������ł��B
����́u�Â̔�v�����ɗ������ɖK�ꂽ�P�����ɂ́A����J�����u��u��ˁv������܂��B�u��u��ˁv�͖����l�N�ɑ��̐l���������Ă����̂ŏ��a�ɂȂ��Ă���P�����Ɉڂ���܂����B����ɂ͌����̎��ɔs�ꂽ�Õ��������Ă����Ƃ����`��������܂����A������̖��������Ă����Ƃ����`���������ł��ˁB�`�����{�����ǂ����͔���܂��A���̌��͎҂ɕ������l�������̍��̉ʂẲ��B�܂œ����Ă���Ƃ������Ƃ͎��ۂɂ����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��̂��ȂƎv���܂����B
�@ |
|
���������@�@�@���s�{���敟��
|
�������̎R��B�������͗ՍϏ@�ŁA�L���ȏ������ގ��̖����ɓ�����̂��Ƃ��B���ގ��͂��Ƃ��ƓV��@�ŁA�ɒB���@�����ɏ���\�������ɗՍϏ@�ɕς���Ă��܂��̂ŁA���̐����������X�͓V��@�������̂�������܂���B
�R��̌������ĉE���ɂ���̂����̍��̖B�G�ߓI�ɏI��肩���Ȃ̂ƁA����̖\���ʼnԂ��U�����̂ƂŐF�Ă��܂����B2�T�ԑO�Ɋ�؏錩�w�������ɂ͍��̋G�߂�������������̂��A���łɐ�����߂��Ă�����ł��ˁc���Ė{��B���̒����̔肪�쒩�̍c�q�̕�Ȃ̂������ł��B
������1m�قǁB���Ȃ薀�Ղ��Ă��邽�ߔ蕶�͓ǂ߂܂��A�Ȃ����Ղ��Ă���̂��Ƃ����ƁA���̐�����Đ����Ĉ��ނƌ��j�H�Ɍ����Ƃ��������`��������������Ȃ̂��Ƃ��B�ɂ���ȗ͂�����͂����Ȃ��̂ł����A�]�ˎ���ɂ͑�^�ʖڂɌ���Ă����̂ł��傤�B
�������̊J�R�͐������N(1346)�B��k���̑����͂��̐��ł������������Ă���A���s�k�����̐�����(���˂���)�œ쒩���R���{�̍c�q���펀�A�����Ő������̘a����������ĂĖ������F�����̂������ł��B�Ȃ����̔�͕�����̕�Ƃ����������邻���ł��B
�R�傩�猩���������̖{���B�����ɂ͐^���ԂȉԂ������ւ̖��B�����ɂ���Z�n���B�Z�n���Ƃ����Ƌ��s�̘Z�n���w���v�������ׂ���͑吨��������Ⴂ�܂����A�Z�n�����̂��̂͑S���ɂ���܂��B�Ⴆ�Ί}�n���̕�����Z�n���ł����B�{���O�ɂ������350�̂��炩���B�����ď��O�B
���̍c�q�A���O�͓`����Ă��Ȃ����߁A�����̌������琳���e���Ɩ��t�����܂����B�R���{���쒩�̌n���̂ǂ��Ɉʒu����̂��s���ŁA�����炭����V�c���猩�đ��ɂ�����̂ł��傤���A����Ƒ哃�{��ǐe���̍c�q�ł���\������ԍ����悤�ȋC�͂��܂��B�k���ꑰ�ƌ�ǐe���͐e�����ԕ��ł���A�c���̎R���{��e�[�E���M�Ȃǂ��{�炵�ĉ��H�̊����ɂ��悤�Ƃ����ƍl���ĕs���R�͂���܂���B�����ē쒩�̒��ł���k���ꑰ�Ɏ���{���Ŋ��Ă����̂ł��傤�B�@ |
|
���������@�@�@�I���s�I���P��
|
�R���@���H�R���ʉ@�@�@�h�@�^���@�q�R�h
�哯2�N(807)�A���c�����C�����B�N�U�̂��߁A���̒n�ɑؐw�����Ƃ��얲���݂ď��R�̎��{���Ƃ��Ċ��ɖ��߂Ă�����腕��h���ƌ����������(5.5�Z���`)�̐��ϐ��������ϐ����J�R�����Ɠ`�����Ă���A�����ߊt�Ə̂��A���k�n���ł͂܂�ɂ݂閼�����ƂȂ��Ă��܂��B
�{���̓����ɂ��������r�𒆐S�Ƃ�����뉀�͏��ƍL�t���̎��R�тɈ͂܂�A�t�ɂ̓c�o�L��\����̃T�c�L���炫����A�H�ɂ͐�����r���^���Ԃɐ��܂�قǍg�t���܂��B
��
�哯2�N(807)�A���c�����C�̉��B�i�U�̂��߁A���̒n�ɑؐw�����Ƃ��얲���݂ď��R�̎��{���Ƃ��Ċ��ɖ��߂Ă�����腕��d���̋�����(5�D5����)�̐��ω������������A���k�ł͂܂�ɂ݂閼�����ƂȂ��Ă��܂��B�{�����ω���F�͔镧�ŁA33�N���ɊJ������܂��B
�剞�N��(1222�`1223)�O���X�َ�핽���G�t�傻�̕v�l�Ƌ��Ɋω���M���A����Ȋ�i�������Ȃ����s�������ɖ͂��đs��ȓ������������A�������ɂ߂����A����6�N�t��ɂ��S�R�Ď������B���Ɏc��뉀�͉������ÂԂ��Ƃ��ł��܂��B
���i2�N(1625)�ˑc���@�����Q�w���ꂽ�L�^���c���Ă��܂��B
���s��������͂�����y�뉀�́A����Ȋ�i���Ȃ����v�l�̖��ɂ��Ȃ�Łu������v�Ɩ��Â����Ă��܂��B
�w�������J�X�ُ��̕��t�傪��i�����Ƃ�����y�뉀�B�t��̕v�l�u����̑O�v�ɂ��Ȃ݁A����̒r�A����̏��̖����c���A�����ɕ������������ł���B�x
��
��P�葺�ł́A���a�N�Ԕˎ吭�@�̌ܒj�@�j���ߊۏ�ɓ���A�Ȍ�̗̎�͊��i���Z�j�@�M�A���̌�A�Ε�c��V�E�c���@�ǁE�Ó���V�E�Β�呠�Ƒ����A���\7�N����������3000��������̎�ƂȂ薾���Ɏ���܂��B�I��R�[�̓��n�͌Â����n�Y�n�Ƃ��ĉh���A�I��R�̋�`�̎c��͐_�n�̂����鏊�ƐM������`���_�Ђ��J���܂����B�V��19�N�˒��c�ƂȂ���n��ɏ�E���n�ꂪ�݂����ˎ�̌�p�n�Ȃǂ������ŋ�������܂����B���n��͓���300�ԁE��k17�Ԃ̍L��ŗ����̓y��ɍ����A�����Ă����Ɠ`���܂��B����͌F��_�ЁA���͍��c�����C�����A���i2�N�ɔˑc���@�̎Q�w���������Ɠ`����^���@�q�R�h���H�R���ʉ@�������A�ɒB�@�j���̂Ƃ����@�����J�R�Ƃ����R�����z�̎R�������y�@���z�h�ێ�R�~�����A��咆���Ƃ̕�����@�����h���{�R�َR���A�ɒB�@�M�E�Ε�c��V�E�Ó���V�E�Β�呠�̕悪���鑂���@�����h�F��R�������A�V�ۋQ�[�̋��{��̂��鑂���@�����h����R�����@�Ȃǂ�����܂��B�@ |
|
���������Ձ@�@�@���s
|
�������ω����@�@�@�{�錧���s�c�K�k����
�u���ω������y���e�җ����v�̂��鏊�ݒn�͑��s�c�K�����n���ɂ���A ���L�҂́u����t�l�������ۑ���v�ł��B����3�̕����͖{���A�ߐ��ȑO�ɔɉh�����������ɓ`��������̂ł����A������������̔p���ʎ߂̍��ɔp�ꂽ���߁A���݂̏ꏊ�ɒʏ́u�����ω����v�����ĂāA�����Ɉ��u����Ă��܂����B����23�N3��11�������̓����{��k�ЂŔ�Q���A��Ѓ~���[�W�A���ċ����ƂŏC������A���ݑ��s���R�ӂ邳�Ɨ��j�قŊJ����Ă�����ʓW�u�k�Ђƕ������v(4/4�`5/17)�ɂ����ēW������Ă��܂��B���ʓW�I������p���W�������\��ł��B
���ؑ���ω������A12�_���@�@�@�{�錧���s�c�K�k����
�����͒n���A�c�K�̎�������Љ�܂��B��̒��̕�ł��B�������A�����̍��������قŏC���A�������̖ؑ����ω�������12�_���̂��Љ�ł��B���̂����c�K�����̏����Ȍ䓰�ł��̕������W���̒��Ŏ���Ă����̂��A�s�v�c�ȕ����ł��B
�������㖖�����ɑ���ꂽ�Ƃ������ω��ł��B����̓���������������������̕����Ƃ������Ă��܂����A�������ڍׂ����ł��B�����������ł��B
�����ω����A�����ɐ��ω��Ə�����Ă��܂��B���������ɔp���ƂȂ������������ł���A�ƌ����Ă��܂��B���̂悤�ȕ����������ɍŋ߂܂ł����ɂ������̂ł��B������11�ʊω��B�s�����������A������V���̎O�������̒����J���Ă����̂ł��B
�䓰�̐��ʁ@�����ȓc�ɂ̌䓰�Ȃ̂ł����A�Ƃ��낪���ɓ����Ă����̂͌��݁A�{�錧�w��̕������A���ω��ł����A���͍��Œ������B�������́u���̕���v�u���{�����Ɋy�I�v�ɋL�ڂ���Ă���u�V�c�S�������v�Ɠ��l�Ȃ��̂ƍl�����Ă��邻���ł��B
�������ω��l�̑���̑�B���̑�̏�ɑ��������A���̏�ɂ���Ɋω��l�������Ă���̂ł����B���̕����A1000�N���O���炱�̒n��̕��X������č��Ɏ���̂ł��B�悭�����ʂ������̂ł��B�ŋ߂܂ł��̂Ƃ�ł��Ȃ��M�d�Ȃ��́A�����g�߂Ɏ���Ă����̂ł��B
����1�̑厖�Ȍ䓰�ł��B��t�@����12�_���̕����B������͐��ω��قǂ͌Â��͂Ȃ��悤�ł����A12�_�������Ă��܂��B�B�ꂽ��ςȕ����ɂ���̂ł��B
�������ω����ɓ`������3�[�̑�
���j�ق܂ł̓��@�ӂ邳�Ɨ��j�ق͏��R���̎{�݂Ƃ���1989�N�ɐݗ�����A2006�N�Ɏ��ӂ̎s�A�����������đ��s�ƂȂ�ɂƂ��Ȃ��A���s���R�ӂ邳�Ɨ��j�قƂȂ����B�����R���͒��̒��S�������k�{���̏��R���w���痣��Ă���A�����₤��ʎ�i�Ƃ��āA���Ĕn�ԂȂ�ʁu�l�ԁv���^�s����Ă����B���̓����͔n�����������l���ق��������オ�肾�������߂Ƃ̂��ƁB���j�ق͂��̐l�Ԃ̓W���A�܂��n���o�g�̃t�����N�i��Ɋւ���W�����Ȃǂ�����B�����{��k�Ќ�A�����ω����Ɉ��u����Ă������ω����A�e���������̗��j�قɊ������A�W������Ă���B
�����̂����@���s���A���j�ق̂��鏼�R�n����10�L�����炢�k�̓c�K�n��(���c�K��)�Ƃ����Ƃ���ɂ��鏬���ω����ɓ`����������ł���B�����ω����́A�w���̕���W�x�ȂǕ�������̎j���Ɂu�������������v�Ƃ��ēo�ꂷ��Î��̌�g�Ǝv����B�V��@�ŁA�̂��ɐ^���@�ɓ]�����Ƃ����B�ߑ�ɔp����A�����͓c�K�̖�t���ׂ̗Ɋω���������A���u�����Ƃ����B�����ɕ������ォ�犙�q����ɂ����Ă���ꂽ���ω����ƕs���A�����呜�����u����Ă����B
���ω����͔�r�I�����������ŁA������1m��B��ؑ��A����B���Ă̎ʐ^���݂�ƁA���݂����Ȃ�i��ł���A���̈�ۂ��������������A�������㍠�̕����ƍl�����Ă����B�C���ɂ���Ėʖڂ���V���A���݂ł͕��������E�����̍�Ƃ���Ă���B���s�E���莛�̐��ω����ɕ��͋C�����āA�s�Ԃ�ȑ��`���牜�B�������W�̑����ł͂Ȃ����Ɛ��������B��i�ŗ��������������ł���B���̎���ɂ悭������ۂ܂�Ƃ�����Ƃ����A�ق��͎��R�Ȃӂ���݂ł���B�ڂ͐꒷�ŁA��d�܂Ԃ��B�݂��ƂȓV��������A�@�̉�����͏����߂ɂ܂Ƃ߂�B�ʔ����̂͌㓪���̔��ŁA��������Ă���B�P�[�X�̑��ʂ��猩����B�������Ō����グ�Ă���̂�����A�㓪���̔��͑S�̓I�ɂ͉������ւƈ��������Ă���͂������A����ʼn��ւ������w�A�X�^�C���ƂȂ��Ă���B�ȂŌ��őׂ͍̂��A����ɓ��ōi���Ă���B�r���͎��R�Ȋ����ŁA�߂̂Ђ��͐[���Ȃ����A��r�I�傫�Ȑ��̊Ԃɏ����Ȑ����͂���ŕω������Ă���B
�e�ɕs�������A������V��2�������B�V��@�ł܂܌�����g�ݍ��킹�ł��邪�A�����Ƃ͍앗���قȂ�A�f�p�ȕ��͋C������B���̎���ɕ��ꂽ���̂��B�قڒ�������s���������Ƒ̂ɂЂ˂��������������V���A�ÂƓ��̑Δ䂪�ʔ����B�@ |
|
����ǐ_�Ё@�@�@�{�錧���s��o�R��ԎR�ԐV�c�@ |
(�����炶��)
�n���ł́u�������ϗl�v�ƌĂ��B�����Ȃǂł���ǐ_�Ђł͂Ȃ��u�J�b�p���_�v�̕����ʂ�(���邢�́u�c�q�J��ǐ_�Ёv�̖��̂����z���Ă���)�B�����ɖʂ����Ƃ���ɒ���������̂ŕ�����₷�����A���ӂɂ͐l�Ƃ͑S����������Ȃ��B�_�ЈȊO�ɂ͂قƂ�lj����Ȃ��B
�́A����̍����E�����G��(���q�̓`���ɂ��)�̔n���ɌՋg�Ƃ������̎҂��d���Ă����B���鎞�ӂƂ������Ƃł��̐��̂��͓��ł��邱�Ƃ��������Ă��܂����B�����ʼnɂ�������Ď�Ƃ𗣂�邱�Ƃɂ����B�Ջg���������Ă����G���́A���̎��Ɏ����̏\��ʊω���^�����Ƃ����B
�Ջg�͊e�n�������ēc�q�J�̏��܂ŒH�蒅���ƁA�������C�ɓ����ďI�̐��ƂƂ��邱�ƂƂ����B���̌�A�Ջg�͑����̎q����������A�q�͓����������̏��̂قƂ�ő��o��������肵�ėV��ł���p���悭��������ꂽ�Ƃ����B
�������Ȃ���悭�������ꂽ�Ђł��邪�A���ƌ����Ă����̉��ɂ��������ۓI�ł���B���͂ɐl�Ƃ��Ȃ������A���̐_��Ȍ��i�͖{���ɉ͓����Z��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��قǂł������B�@ |
|
�������Ձ@�⌳�_�Ё@�@�@�j���S�R����
|
��������A����R�ɒz�邳�ꂽ�⌳��(�⌳�v�Q�A��{��)�B���̕~�n���ɂ́A����̐_�Ƃ��Ċ������ꂽ�������{���J���Ă��܂����B�����ɓ���A��Ƃ��Ă͔p�邳��܂������A���̌�A����42�N�Ɏ��ӂ̑��Г��ƍ��J����A�⌳�_�ЂƂȂ�A���݂Ɏ���܂��B�����͍��̖����Ƃ��Ă��m���A�t�ɂ͍Ղ肪����s���܂��B�܂��A�Ăɂ͛ޏ�����q�ǂ��݂����A�_�y�⑾�ۂȂǂ���[�����čՂ�ł����킢�܂��B
��
��Ր_�@�V�䒆��_
�R���@�{�Ђ͐��e���V�c�A�V��2�N(1574)3��23�����n�����̈ꑰ�j�����Z��̐b�A�⌳�Q�͂������{�ۂɊ��������Ƃ����A�������{�Ə̂����B�ʓ��͐^���@�������A�⌳�Q�͂����c�S���J�Ɉڕ����ꂽ����A���ƂȂ����㓡�A���A�Óc�A�垊�Ɛ��l�ւ肵���A�F����̐_�Ƃ��Č��������J�����B����2�N4���k�C�_�ЂƉ��̂����B����42�N3���A���А_����(�����n�J)���Ј����_��(���i9�n�J)���͂��ߑ��̑��ЂƖ��i�Ђ����J���č⌳�_�ЂƉ��߂āA���Ђɗ�ꂽ�B���a8�N12���A���i�ЂɎw�肳�ꂽ�B�{�a�͓V���N���̑��c�ő���Ȍ��z�ł���B�q�a�͑吳8�N�퍇�J�����_�Ђ̋����̎��̂��đ��c�����B�����n�͐����������Ƃ��ċɂ߂Đ_�X���A����44�N�����ɒB�@���������̐���e��ċ����755����i���ꂽ�B�X�ɑ吳2�N�����S�{�̕�[�����苌���ɔz�A�����̂Ō����̔@���t�͉ԁA�Ă͐���ƕ��i����ǂ��_��ƂȂ����B
��
�⌳�_�Ё@�⌳�_�Ђ͍⌳�O�͂��z���������ՂɌ��Ă�ꂽ�_�ЂŁA����2�N�ɖ����{���k�C�_�ЂƂȂ�A����42�N�ɐ_���ЊO���_�����J���⌳�_�ЂƂȂ�܂����B���Гa�͂��Ė{�ۂ��������ꏊ�Ɍ��Ă��Ă��܂��B���݁A��Ղ͌����Ƃ��Đ�������Ă���A�⌳�_�Ђ̎Гa�̎�����͂��ߍ��̖������A�����Ă��܂��B��N4�����{�`���{�ɂ����ĉԂ���Ăɍ炫���̖����Ƃ��Ēn���̐l�����ɐe���܂�Ă��܂��B
�����@�����(�����)�͖���R�̏�ɂ���R��ŁA���Ώd�@�̉Ɛb�ł���⌳�O�͂����T3�N(1572)�ɒz�������̂ł��B����n��10���]��[����7�`8���̍��Őؒf�����]�ˎ��㏉���̂��̂Ƃ݂��Ă��܂��B�Ï�^�ɂ��@�u�����O�\�O��(��60��)��k50��(��90��)�`�ŁA�����Ԃ�v�Q�̏�n�v�@�ƋL�ڂ���Ă���A�ɍ��Ȃ������̖ʉe���Ƃǂ߂Ă��܂��B���̏�(��)�ɂ́A�ɒB�Ƃ̉Ɛb�垊��(4000��)�A�攪��@�j�����\����@���ɂ�����\��̂���������ƂȂ��Ă��܂����B��Ղ͎R�����̕������Ɏw�肳��Ă��܂��B �@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| ���R�`�� |
   �@
�@
|
|
���ь˖�t��(�ɂ����ǂ₭���ǂ�)�@�ԕ��@�@�@�đ�s
|
�ʖ��u�R������t�v��t���͊֍�����@�Ɉ��u
�����́A�R������t���邢�́u���S�̐�v�ŗL���ȁA�đ�s�ԕ�(����������)�̐Ζ،˂ɂ���A�ь˖�t����K�˂Ă݂܂����B����˖�t���邢�͐Ζ،˖�t�Ƃ�������邱�Ƃ�����܂��B
�ԕ���ʂ�s���e�̎Q�����Ɂu���S�̐�v������A�������琙�ؗ��̒��́A���ɋ}�ȐΒi��o�邱�Ɩ�15���A�藧������Ɉ͂܂�ď����Ȃ����������Ă��܂��B�����h��ꂽ���ɔ����ۂ��`�ǂ����ؕ@����(�т�I�̐�ɕt������������)����ۓI�ł��B���ʂɌ����Ă���k���́A�V��13�N(1842)�������{�n�̎��q��(���������イ)����[�������̂ł����B
�]�ˎ���͕ʓ��̐��A(���傤���ア�R�㑺�E����@����)���Ǘ����Ă��܂������A���A�@�͖��������ɔp���ƂȂ�A�֍��̕���@���Ǘ����邱�ƂƂȂ�܂����B���́A����h�~�̂��ߖ�t���͕���@���Ɉڂ���A5��8����9��8���̗��Ղ̑O��A���q��������`�ɏ悹�Ēn����������A���̖�t���ֈ��u���܂��B
�ь˖�t���̗R���́A�]�ˎ���̒n�������݂�ƁA�{���̖�t���͕U����(�����G��)�� ������̗�����߂�����ɂ��A�ޗǖ�t������J������{���Ƃ������̂ŁA���̌�q���̉��B�������ɓ`���A�����G�t�̒��j����ˍ��t(�����t�ٕ̈�Z)�̎�{���ƂȂ������̂Ɖ]���Ă��܂��B
����5�N(1189)�A�������������t���U�߂����B����̍ہA���B�����R�͈��É�u�R(���� ����܁�������������)�ɎO�d�̖x��z���A����ˍ��t�叫�ɂ��Ď��܂������A�����̗������R�ɔs��܂����B���t�͋��̑m�Ɏ�{���̖�t��������A�m�͏o�H���ɓ���āA���̐ԕ��̒n�ɑ��������сA�R���ɖ�t�������Ė�t�������u�����Ɠ`�����Ă��܂��B �܂��A�G�t�̘Z�j���t����ȎR���z�����̒n�Ɉ��u�����Ƃ��`����Ă��܂��B
��t�@���͂��̖��̂��Ƃ��A�l�тƂ̕a���~�������@���ł����A���̍����炩�A���̋ь˖�t�ɋF�肷��ƁA�ꂵ�ݖ��������ł���Ƃ̕]���������܂����B���̕����ł����u�ՏI���O�v�Ƃ������ׂ��쌱�ɂ��u�R������t�v�Ƃ��Ă�A�������𒆐S�Ɋe�n����Q�q�҂��K��Ă��܂��B
�܂��A�ь˖�t���̎Q�����ɗN���o��u���S�̐�v���A��������ނƓ������u�ՏI���O�v�̌��p������ƌ����A������݂ɗ���l�������₦�܂���B
��
�đ�̐ԕ��ɕ���@���Ǘ�����u�R������t�v������B�ѓ�(�ь�)��t���Ƃ������B�����́u���S�̐�v�u�ڗ����̐����v�ƌĂ����́u�ՏI���O�v�Ƃ������ƂŁA���ނƁu�����v�Ƌꂵ�܂��ɖS���Ȃ�Ƃ������Ƃ����B�~�l�����L�x�ȗ��Ƃ����āA�y�b�g�{�g����|���^���N�Ő������݂ɗ�����������B���ɂ́u���̐��������ɗ��p������q�X���X������M�肪����v�Ə����Ă���B
�ѓ��̗R���͑僀�J�f�ގ��╽���哢�����s�Ȃ����U�������Ɠ����G�����폟�ɍۂ��A���썑(�Ȗ،�)��t������J���A��{���ɂ����̂��n�܂�Ƃ����B������G���̎q���ɂ����鉜�B�������O��ڂ̓����G�t�̘Z�j�ьˑ��Y���t��1188�N�ɌZ�A�����t���������ɐ������ꂽ���A�`�ɕ�����ĈɒB�̂����ȎR���z���o�R���āA�����ɍՂ�悤�ɂȂ����Ƃ����B�ِ��Ƃ��ĉ��B�������O��ڂ̓����G�t�̒��j���،�(�ь�)���Y���t�����É�u�R�̐킢(������������)�Ō������ɔs��A��{���̖�t����m�ɑ����A�m�����̒n�Ɉ������Ƃ������B
������@�@�R�`���đ�s
����@�͐m��3�N(853�N)�p�c�@�l�X�̎����ƕ������F��ׂɑn������܂����B���݂̏ꏊ�ɂ��������Ă�ꂽ�̂́A�đɒB�Ƃ̏鉺������������A��450�N�O�ł��B���̌�A�Ď������݂̌����͊���8�N(1796�N)�ɍČ�����܂����B��������ɂȂ�܂ŕđ�J����ʂ蕟�����ʂ��Ă��������]�˂ɒʂ���B��̊X���������̂ŁA���a�l���Q�Ό��ō]�˂ɍs�����ɋx�e����ꏊ�Ƃ��ĕ���@���g���Ă��܂����B
����@���Č����ꂽ����8�N(1796�N)���̍��䕽�F�Ƃ����w�҂��]�˂���đ�Ɍ������Ă��܂����B���̍䕽�F���㐙��R������@�ɂ��ē����x�e���Ƃ��ĘJ���Ԃ߂�ꂽ�Ƃ�����b���c���Ă��܂��B
��������@�ɂ͂��ڑ҂Ɏg��ꂽ�������Ɠ���c����Ă���܂��B�܂��A���F�搶���L�O�ɐA����ꂽ�ւ̉Ԃ����N�t�ɂȂ�ƁA�Ԃ��Ԃ��炩���܂��B
���̂��Ƃ���A�����Ȃ͏��a�\�N�ɕ���@�����w��̎j�ւƂ��Č㐢�ɓ`������悤�ɂ��Ĉȗ��A����@�̂���֍��͌h�t�̋�(����)�Ƃ��Đ��ɍL���m����悤�ɂȂ�܂����B
�����ɂ͂��̎��̗l�q�����������F�搶�̎莆�̈�߂��A�u�ꎚ��܂̔�v�ɍ��܂�Ă��܂��B
������@�ƃR������t�l
����@�̂��{���̐��ʂɂ͑���@���l���J���A�E���ɂ͍O�@��t�l�A�����ɂ͋�����t�l�����Đ��ʍ����ɃR������t�l�������Ȑ~�q�̒����J���Ă��܂��B
���̖�t�@�����́A�p���V�c�Ƃ��̍c�q�������q���꓁�O�炵�Ă̍�Ƃ���ꕽ�������ɓ���3��(���t〜��t〜�G�t)�Ƃ��ĕ���𒆐S�ɉ��B��~�ɐ��͂�L���Ă������B�������ɓ`���A�G�t�̒��j����ˍ��t�̎��{���ƂȂ�܂����B
����5�N(1189�N)�������̉��B�����ɑ��A�������͍��t�叫�Ƃ��Ĉ��É���u�R(������������)�Ɍ��h�̖x��z���w���\�������s��A4��t�ł��̉h�̖�����܂����B
��t�@�����́A�G�t�̘Z�j���t�����ɕ�����Č�ȎR���z���o�āA�ԕ��̒n�Ɏ��`�����A�u�ь˖�t���v�Ɉ��u���꒷���ԐM����Ă��܂����B��t�@���͖{���A�a��Ȃǂ��琶�����邷�ׂĂ̂��̂��~�����B�E��͎{���؈�����э���ɂ͖������p�ŕ\����Ă���܂��B���̍����炩�肩�ł͂���܂��A���̂���t�l��M���ꂨ�Q������ꂽ�������ʎ��ɋꂵ�܂Ȃ��������Ƃ���b���L����A���̂܂ɂ��u�R������t�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B�܂��a�C����䂾���łȂ��A�����Ă�����ł̕s����ő����Ȃǂ��Ƃ�̂����A�����������S�����߂��܂��B
���݁A����@���J���Ă����t�l�́A��J�^�A���a���Ђ���y���Ȃǂ��肤�吨�̐l�����ɓĂ��M����Ă���܂��B ���X�̌��N�Ɋ��ӂ��A�߂��݂�ꂵ�݂̒��ɂ����Ă��K����̌���������Ƃ������Ƃ������Ă��������Ă��܂��B �Q�q���邱�Ƃɓ��ʂ̌��܂��V���͂���܂���B�S�����߂Ď�����킹�邾���ł��B
���Q�肷�邱�ƂŁA�S���Ȃ�ꂽ�������炩�ɖ��邱�Ƃ��ł��܂��B �R������t�̂��F��ɂ��Ă͂����k�������B
�@ |
|
���H���R�d���@�@�@�߉��s�H�������
|
��Ր_�@�卑�喽
�Њi���@�o�H�_�Ж���
�ʖ��@�H���R�d��
�R�`���߉��s�H�������(�Ƃ���)�̉H���R�ɂ��鎺�����㌚���̌d���B
�R�`���ɂ���R�x�C���̓���ł��錎�R�A���a�R�A�H���R�����킹�ďo�H�O�R�Ƃ����B���̂����H���R�ɂ͎O�R�̐_���J��O�_���Փa������A�����֎���Q���̓r���A�ؗ��̒��ɂ��̌d�������B�߂��ɂ͎���1000�N�A���̎���10m�̋����u�ꐙ�v������B ���k�n���ł͍ŌÂ̓��Ƃ����A���a41�N(1966�N)�ɍ���Ɏw�肳�ꂽ�B���̏��L�҂͏o�H�O�R�_��(���R�_�Џo�H�_�Г��a�R�_��)�ł���B
�������㒆���̏����N��(931�N - 938�N)������̑n���Ɠ`�����Ă��邪�肩�ł͂Ȃ��B�������铃�́A�w�H���R���L�x�ɂ��Ή���5�N(1372�N)�ɉH���R�̕ʓ��E��������Č������Ɠ`������B�c��13�N(1608�N)�ɂ͎R�`�ˎ�ŏ�`��(�����݂悵����)���C�����s�������Ƃ����D�̎ʂ�����킩��B���̓��D�ʂ��ɂ��A�d���͉���2�N(1369�N)�ɗ������A�i�a3�N(1377�N)�ɉ���̑��ւ��グ���Ƃ����B
���͑�����29.2m�A���g��(���ւ�����)��22.2m�B������杮(������)�����A�l���͏��a�l�ŁA���g�ɂ͍ʐF�����{���Ȃ��f�̓��ł���B
��������̐_�������ɂ��A�_���K���̌`�Ԃ������H���R�͏o�H�_��(���ł͂���)�ƂȂ�A�R���̎��@��m�V�͂قƂ�ǔp����A���ꂽ���A�d���͎��ꂸ�Ɏc���ꂽ�����Ȃ����������z��1�ł���B�]�ˎ���͌d���̎��͂ɂ͑����̌��������������Ƃ����B
�ߐ��܂ł͓����ɐ��ω��A�R䶗������A������F�����u���Ă������A�_�������Ȍ�͑卑�喽���Ր_�Ƃ����J��A�o�H�O�R�_�Ђ̖��Ёu��ߎ�(����肵��)�v�ƂȂ��Ă���B
|
|
���o�H�O�R�_�Ё@
|
�R�`���߉��s�H����
��R��
�����{�̌���
�o�H�O�R-�H���R(�W��414�l)���R(�W��1984�l)���a�R(�W��1500�l)-�́u�o�H���v�𓌐��ɕ�����o�H�u�˂̎�v�����߂�R�x�ł���B���Â̑�͉̂ΎR�������J��Ԃ��g�{���R�h�ł������B
_____�����o���A�ĂѐÎ�����߂������A�R�ɂ͑��������A���������菬����b�����ǂ��Ă����B���̎��A�[�̗��l�����͂����ɐ[���s�v�c�ȁg�_��h���������B�u���̎R�����A�䂪�����c��̗썰���h�邨�R���E�E�E�v �u���̐����̗Ƃ��i��R�̐_�A�C�̐_�����܂��Ă��邨�R�ɈႢ�Ȃ��E�E�E�v
_____���ꂩ��X�Ɏ��������ÓV�c���N(593�N)�A�����ޗǂ̓s����͂����{�C�̍r�g�����z���Ĉ�l�̍c�q�������łɂȂ�ꂽ�B��O�\��㐒�s�V�c�̍c�q�E�I�q�c�q�A���̐l�ł���B�C�c�n�̗��E�R��(���)�̔������Y(�₨�Ƃ߂���)�Ɍ}�����A�O�{���̗�G�ɓ�����āA���Ȃ��a�������������ǂ�����̂��H���R�̈��ÒJ(������)�Ƃ����A���Ȃ��Â��鏊____�B�I�q�c�q�͂����ŁA����������������s��s�̌�C�s��ς܂�A���ɉH���̑�_�E�C�c�n�̗��̍����u�Ɏ��g�_(���ł͂̂���)�v�̌�o����q���A���������H���R���Ɂu�o�H(���ł�)�_�Ёv����������ꂽ�B�������邱�ƁA��l�S�N�O�̌䎖�ł���B�o�H�O�R�_�Ђł́A���̎����Ȃāu��J�R�̔N�v�Ƃ��A�I�q�c�q���u��J�c�v�ƒ�߁A�Ă��h���Ă���B�₪�āA��J�c�E�I�q�c�q�̌�C�s�̓��́u�H���h�ÏC����(�͂���͂����グ��ǂ�)�v�Ƃ��Č������A��l�S�N��̍����܂Łg�H���R���h�̌`���Ƃ��āA�u�H�̕�����(�݂˂���)�v(�����Ԃ��イ)�ɑ�\����錵�����C�s�����A�ȂƑ����Ă���B
_____�Ȍ�A���R�̓��O���킸�A�S���Z�\�Z�B�̂������O�\�O�����̖��O�͂��Ƃ��c���A���̕����̓Ă����h�ɗ^��A�������{�M���w�́u��R�E���v�Ƃ��Ă��̒n�ʂ�z���A�l�G��ʂ��o�q�҂̐₦�邱�Ƃ��Ȃ��B
���������A�o�H�O�R�́A�c��̒��܂�g����̂��R�h�A�l�X�̐��Ƃ��i��u�R�̐_�v�u�c�̐_�v�u�C�̐_�v�̏h��g�_�X�̕�h�ɂ��āA�܍��L���A�務�����A�l�����ЁA�������y(���炭)�A���X���F�肷��g���n�h�ł������B�����āu�H���h�ÏC�����v�́g���{����h�Ƃ��āA�u�Î��̌�(������������)�E�h��(��݂�����)�v���͂����R�ł�����B���Ȃ킿�A�H���R�ł͌������v���A���R�Ŏ���̑̌������āA���a�R�ŐV��������(���̂�)�����������Đ��܂�ς��A�Ƃ����ނ��܂�ȁu�O�֎O�x(�����)�̗�R�v�Ƃ��ĉh���Ă������R�ł���B
�o�H�O�R�̐M���E�����ꍇ�A�܂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�����Ȃ��u�_���K���v�̐F�ʂ��F�Z���₳��Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B�×����o�H�O�R�́A���R���q�A�R�x�M�A�Ȃǁg�h�_���c�h���d�����邨�R�ł��������A�������㏉���́u�_���K���v�̋����e�����A�Ȍ�A�������N�́u�_�������v����̎��{�̎��܂ŁA�����𒆐S�Ƃ������R�̌o�c���Ȃ���Ă����B
�����A�o�H�O�R�_�Ђ́u�_���v���Ȃĕ�d���Ă��邪�A�Â�����̍Ղ͓�����A�z�������Ė����𒆐S�Ƃ���u�C�����v�������ĕ�d���Ă���B�܂��ɁA���ꂱ�������̏o�H�O�R�_�Ђ̑傫�ȓ��F�Ƃ����Ă悢�B���j���ӂ�Ԃ��Č���ƁA���q����ɂ͉H���R�����āA�u���@���w�̎R�v�Ə̂��A�S���e�n����C�s�m�������ē��R���A�e�@�����H�C�����Ă������B
���̂Ɂu���@���w�̎R�v�ł���A���X�̏@���E�@�h����������G�ɏK�������̂�_____�B���ꂱ���A�o�H�O�R�̑�_�A�_�X�A�����Č�J�c�E�I�q�c�q�́g��S(�݂�����)�h�����������̂ł��낤�B�M����җ������A�o�H�O�R�̑�_�͉��l�ɂ���������_����������A�̑�ɂ��ĉi�v(�Ƃ�)�ɗL�肪�����_�X�ł���A�Ƃ̖��O�́g�m�M�h������������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�l�Ԃ̋ꂵ�݁E�Y�݂͌����Ĉ�l�ł͂Ȃ��B���l�ɂ��ĕ��G����A��́g�N���E���`�h�݂̂ł͌����ċ~�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�o�H�O�R�̑�_�ƌ�J�c�E�I�q�c�q�͌������Ă���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�o�H�O�R�̐_�X�͊���ł���_____�B
�M�S�́A�܂��A�g�M���邱�Ɓh�Ɏn�܂�B�����̎הO�E�אS���ނȂ������āA�u�_�v��M���邱�ƁA���ꂪ�M���E�ɓ�������ł���B�h�_���c(����������)_____�B�_���h���A�c��𐒂߂邱�ƁA���̈��ɐs����B�o�H�O�R�̐_�X�Ɏd����҂́A��l�S�N�Ԉ�т��Ă��̍��{���_���Ȃđ�_�Ɍ��d�v���A���o�q�ҁE�M�҂̕��X�ɓ������ڂ��A�����ɋ߂Ă����B
�o�H�O�R�_�ЂƂȂ��������ȍ~�����R�͔ɉh��_�Ђ̔��g���}���Ă���B�����ł͓��O�\�O��������̐M�҂ɂƂǂ܂炸�A�S���̒ÁX�Y�X����A�l�G��ʂ��ēo�q�҂̐₦�邱�Ƃ��Ȃ��B�����āA�ŋ߂ł́A���{�͂��납�O����������R�ɂ����łɂȂ�������ڗ����đ����Ȃ��Ă��Ă���B�܂��Ɂg���ۉ��h�ł���B������A���Â���ȁX�Ǝp����Ă����R�[�̏h�V�E�H���R���̑S���Ɍ������o�܂ʁg�z���E���������h���邢�́A�o�H�O�R�_�Ђ̌�_�Ђ́g���g�h������������ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�o�H�O�R�̐M�́A���̎���ɂ��A�e����q�ցA�q���瑷�ւƓ`������u�e�q���`�̂��R�v�Ƃ��Ē����ł������łȂ��A���l�V��Ƃ��Ēj�q�\�܍ɂȂ�ƁA�u���R�킯�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������K���e�n�ɂ����āA�������݂ł���B
���Ɋ֓����ʂł͌Â�����A�o�H�O�R�ɓo�q���邱�Ƃ��u���Q��v�Ə̂��ďd�v�ȁg�l���V��h�̈�Ƃ��Ĉʒu�Â��A�o�q�����҂͈�ʂ̐l�Ƃ͈Ⴄ����(�_�ƂȂ邱�Ƃ���ꂽ��)�Ƃ��Đ��߂�ꂽ�B�܂��A���Ɉʒu���邨�ɐ��l���ӎ�����悤�ɓ��ɑ��݂���o�H�O�R���w�ł邱�Ƃ��u���̉��Q��v�Ƃ��̂����B�܂�u�ɐ��Q�{�v�́u�z�v�A�o�H�O�R��q���邱�Ƃ́u�A�v�ƌ����āg�h�𐬂����̂ƐM�����A�ꐶ�Ɉ�x�͕K�������𐬂������˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����K�����������������B
�����A�o�H�O�R�̂��R���A�u���{�̌����E�E�E�E�v�u���{�l�̐S�̂ӂ闢�E�E�E�v�@�Ƃ����鏊�Ȃ́A�ނȂ���l�S�N�Ƃ������j�����ɂ����̂ł͂Ȃ��A�g����h���z���Ĉ�т��Č��킳��Ă����O�R�̑�_�̌�_�ЁE��_���A���킹�Č�J�c�E�I�q�c�q�́g�O���ϓx(���ザ�傤������)�h�̌䐸�_�A�c���̌�ɉh�Ɩ��O�̑��Ђ��肤��S�́u��m���v�ɂ��邱�Ƃ��A�������͍���x�A����ׂ��ł��낤�B
���o�H�O�R�̊J�c�I�q�c�q�㗤�̒n
�o�H�O�R�̊J�c�ł���I�q�c�q���H���R�֒H�蒅���܂ł̃��[�g�ɂ��Ă͏������邪�A���̈�ɗR�ǂ̔������`��������B���s5�N(592)�̓~�A���ł����32�㐒�s�V�c���h��n�q(�����̂��܂�)�ɂ���ĈÎE���ꂽ�B���̂܂܋{���ɋ��Ă͍c�q�ł���I�q�̐g����Ȃ��ƁA�������q(���傤�Ƃ�������)�̊��߂ɂ��q���̎Ċ_�̋{��o�ĉz�H(�k����)������A�\�o��������D�ŊC���n��A���n���o�ėR�ǂ̉Y�ɒH�蒅�����B�����ɗe�p�[���Ȕ������l���C�̕��������ē��A���������Ă����B�c�q�͕s�v�c�Ɏv���㗤���A�����ɖ₨���Ƃ������F����B��Ă��܂����B�����ɕE�̉���������A�c�q�Ɂu���̒n�͔��ד��P�̋{�a�ł���A���̍��̑�_�̊C�K�̕l�ł���B�������瓌�̕��ɑ�_�̒�������R������B���X�ɐq�˂邪�悢�v�Ƃ��������ꂽ�B�����ōc�q�͂��̋����ɏ]�����̕��Ɍ������Đi�܂ꂽ���A�r�����������Ă��܂����B���̎��A�ЉH����(2m40cm)������3�{���̑�G�����ł��āA�c�q���H���R�̈��v�x�ւƓ������B����ɂ��A�R�ǂ̕l�����̉Y�Ə̂��A�c�q�����G�ɂ��Ȃ�ŎR���H���R�Ɩ��t�����B���̂悤�ɁA�H���_�͔������̉Y�̓��A���قƂ��Ēa�������Ƃ���A���������̓��A�͉H���R�{�Ђ̋{�a�ƒn�����Ō���Ă���Ƃ��������`��������B
�����ד��P�@�[�@�����̖��ł���ʈ˕P��(���܂��Ђ߂݂̂��Ɓ����{�ɂ����Ă͔��ד��P)�ŁA�]�ˎ���͉H���_�Ƃ��ꂽ�B
���I�q�c�q
��J�R�͐�l�S�N�]�O�̐��ÓV�c���N(593�N)�A��O�\��㐒�s�V�c�̌�q�I�q�c�q���A�h�䎁�Ƃ̐����Ɋ������܂�A���邽�߂ɉ�H���͂��Ɩk�サ�A�o�H���ɂ�����ɂȂ�܂����B�����ĎO�{���̗�G(�ꂢ��)�̓����܂܂ɉH���R�ɓo��H�������̌䎦����q���A�R�����K��n������A�����Ō��R�A���a�R�����X�ƊJ����܂����B���̌�A�c�q�̌䓿��炢�A���ꔒ�R���J�����א���C�����̑c�Ƃ���������m�s�ҁA�^���@�̊J�c��C�A�V��@�̊J�c�Ő��Ȃǂ����R���C�s��ςƓ`�����Ă��܂��B
���o�H�O�R�̉��v
�o�H�O�R�Ƃ́A�R�`��(�o�H��)�ɂ��錎�R�A�H���R�A���a�R�̎O�̎R�̑��̂ł��B���R�_�Ђ́A�V�Ƒ�_�̒�_�̌��ǖ�(����݂݂̂���)���A�o�H�_�Ђ͏o�H���̍����ł���Ɏ��g�_(���ł͂̂���)�ƈ�q����(�����݂̂��݂̂���)�̓�_���A���a�R�_�Ђ͑�R�L��(���ق�܂݂݂̂���)�A��ȋM��(���قȂނ��݂̂���)�A���F����(�����ȂЂ��Ȃ݂̂���)�̎O�_���J���Ă��܂��B���R�Ɠ��a�R�͓~�G�̎Q�q���s�\�ł��邱�Ƃ���A�H���R���ɎO�R�̐_�X�����Ղ��Ă��܂��B�܂��L��ȎR���ɂ͕S�����ЂƂ�����Ђ������āA���S��(�₨�낸)�̐_�X���J���Ă��܂��B�o�H�O�R�͌����A���{�×��̎��R���q�̎R�x�M�ɁA�����E�����E�Ȃǂ��K���ɐ��������u�C�����v�̂��R�ł����B����́A�����ېV�܂ł͕����́A�^���@�A�V��@�ȂǑ����̏@�h�ɂ���ĕ�d����A���q����ɂ́u���@���w�̎R�v�Ƃ��̂���܂����B�I�v�̗��j�̒��Ŋ����̕ϊ҂��d�˂Ȃ���A���l�ɂ��Č���Ȃ��[���M���`�����A�u���O�\�O����������v�Ƃ��āA�l�X�̍L���Ă��M�Ɏx�����Č��݂Ɏ����Ă��܂��B
|
|
���H���R�E�o�H�_��
|
���H���R�咹��
��k���̖�������H���R�ɐ��͂���̒n���������́A�����̑�ɉH���R�̕ʓ����̂��A�q���ɂ��̐E���p�����B�����͒��c�V�c�������N�H���R�Ɍd��(����)���Č��A���̋�����(�߉�)�ɒ��������������H���R��̒����Ƃ������A���͂Ȃ����������̖����c���Ă���B���̈�̒����͒߉�����H������n��A�R�X���鏯������������āA�H���X�����H���u�˂ɂ�����i���̒n�ɍ���22.5���̗����̑咹��������B���a4�N�R�`�s�g���S���Y�̕�[�B
���h�V�Ɩ������̈��j
��O�����(�Ƃ���)�́A�ꑺ���C���ŁA�]�ˎ���ɂ�336�V������A�˂��B���Ɋ��ؖ�(���Ԃ�����)���\���A���A�����h�V������A�����h�ߏ���x�z���āA���҂̏h����R�ē�������B���A���ɑ����j���邵�Ă���̂��������邪�A����͏����(�~�̕�)�ɁA����(����)���������ďĂ��̂Ă�_���Ɏg���������j�ŁA�j��������ƈ������ߊ��Ȃ��Ɠ`�����Ă���B
�����_��(�����������)
���_������͏o�H�O�R�̐_��ƂȂ�A�_��͉������R���z���A���a�R�܂ōL����B���_��͂��̍L���_��̕\���ւł���B���̖�͏��ߐm����Ƃ��Č��\�N�ԏH�c��ˎ����i���ꂽ���A�����̐_�������̐܂�A���g�����J�萏�_��Ɩ��t�����B
�����ЉH���R�V�n���_��
���_��̉E��O�ɂ����h��̂��ЂŁA���i4�N�w���@���@���ʂɂ��n�����ꂽ�������̂��ߑ�j���A��ɉH���R�q���@�G�R�ɂ����i8�N(1779)�ċ����ꂽ�B���Ɓu���O��t���v����{���Ƃ��Ă��J�肵���̂ő�t���Ə̂��Ă������A���a39�N�A�{���V�j�������J�肵�A�V�n���_�ЂƂȂ茻�݂Ɏ����Ă���B
���P��Ɛ{��̑�(�͂炢����E�����̂���)
���_����p�q����������P��Ɋ|����_���ɏo��B�̎O�R�w�ł̐l�X�͕K���P��̐�������ɐg�߁A���C�����Ƃ�O�R�ւ̓o�q�̓r�ɂ����B��h��̔������_���͌����ȐZ�I�J�ɂ�����A�������̌��R���痎����{��̑�Ƒ����A���̌i�ς͂܂��Ƃɐ��X�����������B��͏���3�N(1654)���̕ʓ��V�G�ɂ�茎�R�X�[���ۑ����8km�̊Ԃ��������P��̌��R�ɗ����A�s���̑�Ɩ��t�����B���A��ʓI�ɂ͐_��Ƃ͐��_��Ɠ`�����Ă��邪�A�������R��ƎR�[���Ăѕ����A�R��ɂ͈ېV�܂Ŗ{�V���n��30�]���@�̎��@������A���H�ȑт����Ȃ��u���m�C���v���Z�݁A�R�[�ɂ�336�V�́u�ȑяC���v���Z��ł����B
���d��
�H���R�́A��Â╽��Ƌ��ɓ��k���������̒��S�ł����������ɁA���X�̕������ɕx��ł���B�R�[�̉������͏d���ɁA�R���̌d���͍���ł���B�Â��͑됅���̌d���ƌ����A���߂ɂ͑����̎��@�����������A���͂Ȃ��d����������̍�̓o�������ɑf�ؑ���A�`���A�O�Ԍܑw�̗D���Ȏp���ނ藧�������̊ԂɌ����Ă���B���݂̓��͒��c�V�c�̕����N��(��600�N�O)�����̗̎�ŁA�H���R�̕ʓ��ł��������������̍Č��Ɠ`�����Ă���B
���R����������
�Q���̐Βi�̐s����Ƃ����̒���������B���ƍ]�ˍu������i���ꂽ���̒��������������푈�ŋ��o���ꂽ�Ղɏ����̐��k��w���̊�t�ɂ���Č������ꂽ���̂ł���B�����̎�O�̍���\�ܓ���Ƃ����A��̍��ɁA��R�̊ю�̏Z���s���ՁA�E�ɖ{�Ђ̂�������舵�����J��(�����ǂ�)���Ƃ����ꐶ�s�Ƃ̐��m�C���̏Z�\�щ@���݂����B�܂��\�����q���o��̐܁A�x�����ꂽ�ꏊ�Ƃ��A���V�̂Ƃ������ꂽ�̂����̏ꏊ�ɂ������Ɠ`������\�����q�����(���܂�)������B
���I�q�c�q�䑸�e(�����������q�A�E���������q)
�o�H�O�R��J�c�E�I�q�c�q�́A���ÓV�c�̌��ɏo�H�O�R���J���A�܍��̎�q���o�H�̍��ɓ`���A�l�X�ɉҞ��̓��������A�Y�Ƃ������A���a�̖@�������A�l�X�̂������Y���~�������ȂǁA�����̌������c���ꂽ�B���̑S�Ă̋�Y�������Ƃ���������\�����q�Ə̂���A�����V�c��13�N10��20����N91���I�����ꂽ�B�I�q�_�Ђ̌�Ր_�Ƃ����J���A���͉H���R���o�X�����{�a�ւ̎Q���r���ɂ���A���{�����̊Ǘ�����Ƃ���ƂȂ��Ă���B
���I�q�_��(�������́u�����_�Ёv)
�\�Q���Βi�̏I�_�����Ɩ{�a�̊Ԃ̌����_�Ђƕ��ԎГa�B�o�H�O�R�_�Ќ�J�c�E�I�q�c�q���J���Ă���B
���O�_���Փa(���������ł�)
�Гa�͍��Փa����Ə̂��ׂ��H���h�ÏC�����Ǝ��̂��̂ŁA����28��(9��3��)���s24.2��(13��2��)����17��(9��2��4��)�Ŏ�ɐ��ނ��g�p���A�����͑���h��ŁA�����̌���2.1��(7��)�ɋy�Ԋ������̍��s�Ȍ����ł���B���݂̍��Փa�͕������N(1818)�Ɋ����������̂œ����H���ɓ������ꂽ��H��35,138�l�����n�ߖؔҁE�h�t�E���t�E�H�E�����t���̑��̐E�l���킹��55,416�l�A��`�l��37,644�l�A����ɗv������976�]�A���ݔ�5,275��2���ɒB�����B���̊O�ɑ����̓��u��t���n�߁A�R�[�����̎�`�l��56,726�l�����������ꂽ�B���ݓ����͐ԏ����h�ł��������A���a45�N�`47�N�ɂ����J�R1,380�N�L�N��^���Ƃ̈�Ƃ��ēh�֏C���H�����s���A���݂Ɍ���悤�Ȏ�h��̎Гa�ƂȂ����B����12�N�A���̏d�v�������Ɏw�肳���B
���O�_���Փa���ʁ��O�_�Ѝ��z����ї͎m����
�H���R���ɂ���A�O�R�̊J�c�I�q�c�q�́A��s��s�̖��A�H����_�̌䎦����q���A�R���ɉH���R��������������A�����Ō��R�_�A���a�R�_���������ĉH���O���匠���Ə̂��ĕ�d�����Ɖ]����B�����̐_��������A�匠������p���ďo�H�_�ЂƏ̂��A�O���̐_�X�����J���Ă���̂Ō������O�_���Փa�Ə̂��Ă���B
���O�_���Փa����
�O�_���Փa�͈�ʐ_�Ќ��z�Ƃ͈قȂ�A��̓��ɔq�a�ƌ�{�a�Ƃ������Ă���A���R�E�H���R�E���a�R�̎O�_�����J����Ă���Ƃ��납��A���Փa����Ƃ��̂����Ɠ��̎Гa�ŁA�����w�͌�[��a�Ə̂��A�×�17�N���Ɏ��N�̑��c���֍s����Ă���B�܂���{�a�����ɂ́A��\�l�F�̒���������A�O�_���Փa�z�̑莚�͕�����b�̏��ł���B
��
���R�E���a�R�͉����R����k�J�ɂ���A�~�G�̎Q�q��ՓT�����s���邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA�O�R�̔N���P�ᖔ�Վ��̍ՓT�͑S�ĉH���R���̍��Փa�ōs����B�Â��͑哰�A�{���A�{�a�A�{�ЂȂǂƂ��̂���A�H���C���̍��{����ł��������B
���w�͎O�ˑO�̔��ɕ�����A���ʒ����Ɍ��ǖ��A�E�ɈɎ��g�_(��q����)���ɑ�R�_���A��ȋM���A���F�������J��B�{�Ђ͑哯2�N�����ȗ��A�x�X���ւ��s�Ȃ��A�߂��]�ˎ���ɉ����Ă͎l�x�̑��ւ��s��ꂽ�B�c��10�N�A�ŏ�`���̏C�����n�߁A���a5�N�ɍđ��A29�N���o������8�N����A����2�N�Č����ꂽ���A��8�N�܂��܂����サ���B���b�R�ł͍ēx�̉���ɕ���10�N�����@�o�x��ʓ��ɔC���A�{�Ђ̍Č��ɓ����点�A�������N1818�N���������B���ꂪ���݂̖{�Ђł���B
���o�H�O�R�_�ЎQ�W�a
�n��2�K�A�n��1�K�����ʐ�2,179m2���ꉮ���蓺�ꕶ���i���A�]���̒������̋@�\�ɎQ�q�҂̎���{�݁A�_�E�{�����@�\����ɋV���a�������ݑ��ړI�ȏo�H�O�R�ɑ����������h�ȎQ�W�a�����a63�N7��2���Ɍ������H���ꂽ�B
�����r
����38m��k28m�̑ȉ~�`�̂��̌�r�͌�{�a�̌����r�ł���A�N�Ԃ�ʂ��قƂ�ǐ��ʂ��ς�炸�A�_��Ȍ�r�Ƃ��ČÂ���葽���̐M�����߁A�܂��H���M�̒��S�ł��������B�Ï��Ɂu�H���_�Ёv�Ə����āu�����݂̂��܁v�Ɠǂ܂��Ă���A���̒r��_�삻�̂��̂ƍl���Ă��M�̕�����ꂽ�_��Ȍ�r�ł���A�×���葽���̐l�X�ɂ���[���ꂽ�A���������[����Ă���̂ŋ��r�Ƃ����B
�����O�ƌ����̑��
���͋��r�̓��ɂ���A�؍ȑ���̊������ŁA�����������s�Ȍ����ł���B�ŏ�ƐM�̊�i�Ō��a4�N�Č������B�R���ł͍���d���Ɏ����Â������ł���B���͌������N�̖�������A�Ï��ł́A���厛�E�����Ɏ����ŌÂ����傫���B���̌��a1.68��(5��5��5��)�A�O�̌���22cm(7��1��)�A�܂����g�̍���2.05��(6��7��5��)�A�}�`�̍���13cm(4��4��)�A�����̍���68cm(2��2��3��)����A����2.86��(9��4��2��)�ł���B��т̔�_��͐��錩���Ȏ�@�ŁA�悭����̎�����A�r�̊Ԃ́A�_����s�̓V�l��A�r���A�𒒌����Ă���̂́A�H���̏��ɂ̂��鏊�ŁA�S����L�ł���B�܂��V�l�̐}�͉F���P�����̓�������̏��Ɍ���ق��A�₦�Ă��̗�����Ȃ��Ƃ����B���̏��͕��i�E�O���̖ÏP���̍ہA�H���̗��_(�㓪����)�̓����ɂ���āA�G�̊͑D��S���C���ɕ��ł����̂ŁA���q���{�́A�H���R�̗�Ђ������������āA���q�������H�𑗂�A�H���ŏ��𒒂āA�H���R�ɕ�����̂ł���Ƃ����B
�����Ǝ�
���i18�N(1641)�A��50��V�G�ʓ��͓��얋�{�̏@���ږ�ł��铌�b�R�̓V�C�m���̒�q�ƂȂ�A�H����R��V��@�ɉ��@��������̈�ɁA���ƌ����̉H���R�����̎�����\���o���B�V�C�m���͒߉������䒉���ɓ��������A�V��2�N(1645)�ˎ�͎Гa����i�����B�����A���̔ˎ�̐��h��̂��ƈێ�����Ă����B��������ɓ��Ƌ{�͓��ƎЂƉ��߂��A���݂̎Гa(3��5��)�͏��a55�N(1980)�ɉ�̕����������̂ł���B�V�G�ʓ��̊����̂˂炢�́A���ƌ������R�����J�邱�Ƃɂ���ĎR�Ђ����߁A���̍��ْ��̓x�����������������˂Ƃ̊W���~���Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃɂ������B
����œ�(�O��)
��S���\軀�̕�����������u���錚���Ƃ��ĕ���29�N7���ɏv�H�B�Q�W�a�Ɨ�Փa�����Ԗ������S���B���А��h��̏����ˎ���Ƒ�18��䓖����䒉�v����育���|�������Њz���f�����A�V��ɂ͉�Ɖ����ᑋ���|�̓V��旳���������Ă���B
����œ�(����)
�o�H�O�R�͖����ېV�܂Ő_���������Ƃ��Đ��߂�C�����̌�R�ŁA�H���R�́u�H���R������v�Ə̂��A��R�͕����ŕ�d���Ă����B��œ��Ɉ��u����250���[�̕����̑����́A�����ɂ����������⎛�@���J���Ă����Ɠ`��������̂ł���B�����̐_�������ŏo�H�O�R���_�ЂƂȂ�A�삵�����̕�������R������U�킷�钆�A��c�s�ɏZ�ލ����ב��lj��͎����𓊂��ďN�W���A��n�Ɉ��u������������q�����B���a49�N�A�q���̍������i���͕S�N�߂���葱���Ă��������̑S�ĂЂɕ�[���ꂽ�B
����Փa
�o�H�O�R�͉��Â��c������̂��R�Ƃ���A�[���M�����߂Ă���A����c�̌������{���镗�K�����݂�����ɍs���Ă���B�P�w���ꉮ�璹�j���܊ԎБ���̖{�a�Ɏ����A�����Ȍ����ŏ��a58�N�ɍČ����ꂽ���̂ł���B
�����{��
�H���R�ɂ͔j�ړ����O��n���n�߁A��{�V���A��J�Ɨ��ʓ����{�������邪��Փa�e���{���͓ĐM�҂̋��{��������A��Փa�����Ƌ��ɐ��������ʎQ�q�̕��X�̌䋟�{���₦�Ȃ��B
������
�o�H�O�R�ɂ͕S�ꖖ�ЂƏ̂��A�H�����n�ߌ��R�A���a�R�̎R��A�܂��͗H�J�ɑ����̖��Ђ��U�݂��Ă���B�ʐ^�̖��Ђ͍�����嗋�_�ЁA���p�g�_�ЁA��א_�ЁA��R�L�_�ЁA���R�_�ЁA�v���_�ЁA����_�ЁB
�����Ќ��p�g�_��
�H���R�̖��ЂŁA���ƍs�ғ��Ƃ����Ė��s�҂��J��B���̎ア�҂����ʂ������A���r���F�镗�K������B
���V�G��
�H���R�\�����s�ʓ��V�G�@����J��B�����̓��U�͓V�G�@��̕�n�̂��铌���s�V������菺�a63�N6��7���ɕ��ꂽ���̂ł���B
�������ē�
�����܂ł͏H�̕�̓�̏h�ł��������A���݂͑S�Ă��̕����ē������_�ɍs���s���B
�����z�_��
���z�͉H���h�ÏC�����̍��{����ł���B���z�_�Ђ͎O�R�̊J�c�E�I�q�c�q���J��B���a62�N6�����z�����B
�@ |
|
���r��(����������)�@�@�@�߉��s�H�������
|
�R�`���߉��s�ɂ��鎛�@�ʼnH���R�C���{�@�̖{�R�ł���B�R���͉H���R�ŁA���P�@���{�V�ł���B�{���͑���@���E����ɔ@���E�ω���F�B
���̎��́A���s�V�c�̍c�q�I�q�c�q(�\�����q)�ɂ���ĊJ���ꂽ�Ɠ`�����A�o�H�O�R(���a�R�E���R�E�H���R)�ɑ���R�x�M�E�C�����̎��Ƃ��ČÂ�����M����Ă����B���Ƃ͐^���@�𒆐S�Ƃ��鎛�@�ł��������A�]�ˎ���ɓ���ƓV��@�ɑ����邱�ƂƂȂ����B
�������N�̐_�������ɔ�������̖����ƂȂ�A����E�����1946�N(���a21�N)�A���Ó`�����Ɨ����ĉH���R�C���{�@�̖{�R�ƂȂ����B
���H���R�C���{�@
�H���h�C���́A�^���@���R�h�A�V��@�{�R�h��2�h�Ɏ��ʂ��Ă������C����2�h�̂�����ɂ��������A�Â�����̏C�����ƁA�y���̌��R�̑c��M�����т����Ǝ��̏C���ł���B
���̒��ŁA�r�̏C�����́A�n���A��S�A�{���A���C���A�l�ԁA�V�l�A�����A���o�A��F�A���́A���E���`�����Ă���\�E��̌�����u�\�E�s�v�������ɍs�����Ƃ��A�o�H�O�R�_�ЂƔ䂵�������ł���B�\�E�s�Ƃ́A�s�҂����ɁA���̐��E�ŁA�R���̊e�s��ł̏C�s��ʂ��ď\�E�̋ꂵ�݂�̌����A�����ւƓ]������s�ł���B�o�H�O�R�_�Ђ̍s�͕����ł͂Ȃ��_���ł���A�s��ʂ��Ď���̒Ǒ̌����s���͓̂��������A���̓��e�͌×�����̏C���Ɣ�ׂĊȗ������ꂽ���̂ł���B
��
�r�̋����͉H���R�o�R���̋߂��ɂ���B�R���́A���s�V�c�̑�(587�N)�������q�̏]�Z�A�I�q�c�q�̑��n�Ɠ`���A�H���R�̉��m�@�Ƃ��ď��l���̐���ł������B�c�q�́A�\���ƌ����F�Ə̂���A��s���厛�̖@��ɋA�˂��A�@�����O�C�ƍ������B�����C�s�̓r�ɂ����ĉ����Ɉē�����A�H���R�ɓo��A�o�H�O�R���J�����Ƃ����B���̌�A���P�N�Ԃɖ��s�ҏ��p�������A�哯���N�ɂ͍O�@��t���|�����ꂽ���Ƃ�`���Ă���B
��
�R�`���߉�(�邨��)�s�H��(�͂���)���ɂ���H���R�C���{�@(���グ��قイ)�{�R�B�H���R���P�@(���傤����)�ƍ�����B�{���͑���@��(�����ɂ��ɂ�炢)�E�����(���݂�)�@���E�ω���F(����̂�ڂ���)�B�����܂ł͓V��E�^���E�T�̎O�@���w�̏C������ŁA�����͉H���R��R�̉��̉@�ł������B1189�N(����5)������(���Ƃ�)�������t(�₷�Ђ�)�����̂���A�H���R�ɐ폟���F�肵�A���̕��Ƃ��ĎГa�c�A�R�[(����낭)�ɉ�����(�����˂ǂ�)(���̏d�v������)�������A1596�N(�c��1)�ɒ��]�R��猓��(�Ȃ�����܂���̂��݂��˂�)�A�Ô������i�p(���܂����т̂��݂�����)���C�z�B1641�N(���i18)�S�R�͓V��@�ɓ��ꂳ�ꂽ���A1946�N(���a21)�Ɨ����ĉH���R�C���{�@�{�R�ƂȂ�B����ɂ͐m����(�`�^�c(����)��)�A�{���A�ɗ�(����)�ȂǑ����𑠂��Ă���B�@ |
|
���P�����@(���E���؎�)�@�@�@�߉��s����
|
�����B
(�݂傤���A���v�N����)�́A�������㒆���̓V��@�̑m�B�o�H��(���݂̎R�`��)�߉��̗��؎�(�P�����̑O�g)��V�c����V��N��(938�N-957�N)���ɊJ�R�����Ƃ����@�،o�̍s�ҁB�u���̕���W�v�Ȃǂ�955�N(�V��9�N)�A腖��剤����O�����~�����Ƃ����߂��A����7���ڂɑh�����Ƃ����`�����c��B
���m���B�h�����L(�����݂傤�����������イ��)
�o�H�̍��̓c��S�ɂ��间�؎��ɏZ�ޖ��B�Ƃ����V��@�̑m�̒��q�ł���Ƃ����B���̎��S���腖��̉��{��K�˂āA�m�l�B�̎���̗l�q�����������Ă���腖����ɋ������7����ɐ����Ԃ����Ƃ������e��10���I������ɐ��������h��杂ł���B�����ɓo�ꂷ�鎛�@���͂��̓������瑶�݂��Ă������݂̑P�Ƃ���A���̂���̓����ɂ����镧���̏������Ă���B
�����B�Əo�H���c��S
�o�H��(�H�O��)�c��S�́A���݂̎R�`�����c��S�E�߉��s����ю�c�s�̈ꕔ(�T�ˍŏ��ȓ�)�ɂ�����B����S�A�c�͌S�ƕ\�L����邱�Ƃ��������B7���I�ɉz���ɐڂ���ڈ̏Z�ޓy�n�ɍ݂����A�֑D�E�ّ���2�S�̕����ɂ��z�㍑����������ƁA���̖k���ɐ��͂��g�傳��A�a����(708)�N�ɏo�H�S���ݒu����A�o�H��(�R�`�������n��)���z�����ꂽ�B�a��5�N�ɏo�H���ɏ��i���A����������u���S�ƍŏ�S���������č��̑̐����������B����ɁA�����E�k���Ȃǂ̏�������800�ˈȏ�̍�˂��ڏZ�����A��˂�����𒆐S�Ƃ����S���{�s�n���g�傳��A����N��(901〜923�N)�܂łɏo�H�S�암����c��S�����������Ƃ����B
���B�B���v�N���ځB�������㒆���̖@�،o�̎R�x�C���ҁE�m��(�V��@?)�B�o�H���߉��̗��؎�(���݁A�����@�E���V�R�P�����̑O�g)��V�c�E�V��N��(938〜957�N)�ɑ��������сA�J�R�����Ƃ����B���B�R(�z��Ƃ̍����c��S�̓�̎R)�̎R������C���ɏ����������Ζʂ̌E�n�ɂ������\�ʂ����Ȏ��R�̏�ŁA�@�،o����u���A���T����ɂ��Ă����Ƃ����B���B�̍��T�͌��݂Ɏc��B���B�R�̖k���ɒ��C�R���ނ��A���13(871)�N�ɕ��L�^������A�啨���_�Ƃ����J���Ă������A����ł��ق������ď]��ʂ܂ŏ��ʂ���A�啨���_(�ΎR)����߂邽�߂ɁA�@�،o���u��������ꂽ�Ƃ����B�V��9(955)�N�ɖ��B�͖��B�R�ɘU��A�܍���f���A�@�،o���u�̋F���̍s�����Ȃ�����肵���Ƃ����B���B�̑����E���؎��͗��؎O��ɊW���āA���ӂ��������ďO�����~�����ӐM�ƂȂ�A�P�����̖��ӐΕ��Ƃ��Ă̂���B�����w�m���B�h�����L�x�ł́A�����腖��̉��{�Œn���̐l�X�̗l�q�����������A���P�r���ɂ���ďO�����~�����ƁA�s���V�㐶�����n����������A7����ɐ����Ԃ����Ƃ����B�w���̕���W�x�Ȃǂł́A腖��剤�A�K���Ɋy�ɐ��܂�ς���悤�Ɍ���ĕ�������悤������ꂽ�Ƃ��A��y�M�̒蒅�ߒ����f����B
�����N
�������㒆���̓V��@�̑m�A�P�����J��ؖ��B��l�́A�o�H��(���݂̎R�`��)�̏�������̓�̎R�ɓV��ܔN(��܈�)�̏H�A���؎��Ƃ����������J���A�����ς�w�@�،o�x����u���Ă����Ɠ`������B
�V���N(��܌�)�Ɍ܍��f�������āA����C�s�ɓ���A������ɂ��̐��ɑh�����Ƃ����Ă���B�����A���B��l��腖����̓s�ɏ�����āA�u���́w�@�،o�x���悭�ǂ݁A�ϔY�Ȃ��B���₩�ɋA��ׂ��v�Ɖ]���A���̐��ɋA���ꂽ�B
���B��l�͋A��O�ɕ���ɉ�����Ɛ\���グ��ƁA�u����͒n���ɂ���ꂵ��ł���B����̍߂����߂Ɍ�����ς݂Ȃ����v�ƁA腖����͌����A����ɐl�Ԃ̎���̗l�X�ȗl�q�������Ă��ꂽ�B������ς҂͊����V�ɐ��܂�A�߂���肵�҂͒n���ɂ���A����ɂ͑�ցA�㓪���ɐ��܂�ċꂵ��ł�����̂�����B
�n���̋ꂵ�݂̐l�X�������V�ɓn���������������腖����͐\���n�����Ƃ����B
���鎞�A���B��l�̏��ɁA�������ꂽ�B�̂����ė��̐g�ƂȂ����B�w�@�،o�x�̌����������Ƃ����B���͖��B��l�́w�@�،o�x���u���A�肢�����A���B�R�̘[�ɂ���r�ɐg���B�����Ƃ�����B���̒r���u�L��̒r�v�ŁA���̗��́u���_�l�v�ł������B
���̌�A���c��N(��O�Z��)���`������c�A�P�����J�c�̉�R��בT�t�͖��B�R�ɏ������A���B��l�̍��T�ɍ��T�����Ă���Ɨ��_�l�����ꂽ�Ƃ����B
�T�t���u�O�A���v��������ƊL��r�ɏ������Ɠ`�����Ă���B
��R�T�t��莵���̑P�����J�R���N��֑T�t�͕����O�N(��l�l��)���؎������ĉ����������͂����A���V�R�ƍ����A�P�����Ɖ��߂�ꂽ�B���̎����ɍēx�A���_�l����������`�����肤�B
�u��͔��嗴���̈�l�Ȃ�B�Ƃ��Ȃ���͑�O�̗����Ȃ�B�����ɖ��B��l�̊ØI�̖��T�̌������A�X�ɉ�R�T�t�ɎQ���ĉ����A�����ɑ��N�T�t�ɂ͎����Ō������������A�s�ޓ]�̖@�y����B���ő��𗦂��Đs�����ہA���̌�R����삹���B��ɋF��������̂���A�K���S�萬�A�����߂�v�ƌ����I����v���V�n�k���A�L��̒r�ɐg�𑠂����B
���N�T�t�͗����a���������A���̉@�̊L��̒r�ɂ͗��_�����������A���_�l�����J�肵�A�����Ɏ���B
�����؈�(��イ������)
�����F�����ÉE�q���ًg�@/�@���F���R�x�ܘY�@/�@�O�����F�V���P�Z�E�{�Ԗ��g
�P�����̑O�g�ł��间�؎��̖{���ł���A�P�����̗��j��R�����ɏd�v�Ȍ����ł���܂��B�̂͂��̏ꏊ����k�k��2�L���قNJu�Ă��ꏊ�ɂ���A���݂͐������w�Z�̕~�n�ƂȂ��Ă���܂��B���̒n�����u���ԍ�v(��イ������)�ƌĂ�ł��������ł��B���݂̌������O�̒����ƌ����͖���13�N(1880�N)�ɑP�����������̓����u�������g�v�̍�ł���܂��B����12�N�ȑO�̗��؈��́A�d������ē����̊Ԃ̕~�n�Ɍ��Ă��Ă��������ł��B���݂͌ܕS�������C���̂��߂́A��Ə��Ƃ��ė��p����Ă���C���̗l�q�����邱�Ƃ��ł��܂��B
������(��������)
�����F�����ÉE�q���ًg
����3�N(1856�N)�ɍČ����ꂽ�\��x����̂Ƃ���ׂ₩�Ȓ����̑���B���P���L����B���̗D�ꂽ�����͓����̌������g30���̋C���̍��߂�ꂽ��B���Ɏ��q�̑��`�Ɣ��͈͂ꌩ�̉��l����B�펞���ɏ\��x�̓�(�Ƃ�)�����܂�A��x�����Ă��܂��B�C�͗��̎p�ł͒�������Ă��܂���̂ŁA�悭�悭�T���Ă݂Ă��������B
���R��(�������)
�����F�����ÉE�q���ًg(�Z)�@/�@�e�����F���R�x�ܘY(��)
���v2�N(1862�N)�Č��B�c��3�N(1867�N)5��27���ɏ㓏�������s�����L�^������܂��B�\���͕��G�Œ����͎����Ȃ鑍�P���L����A�������̘O��ł��B��������e�ɂ͉E�Ɂu������V�v���Ɂu��ʓV�v��������܂��B��ʂɂ����̖�ɂ͐m���������u����邱�Ƃ������̂ł����A�p���ʎ߂̐܁A�P�����ɔ��Ă������̗����V�������u�����ƌ����Ă���܂��B�R�吳�ʉ~���̓����q�͓����̉ÉE�q��̍�ł���̂ɑ��A����̎��q�͓����̒�x�ܘY�̍�ł���A�Z��ŋZ�����������ė͍삵�����̂ł���܂��B�R���K�O������ɂ͔镧�ł���\�Z�����������u����Ă���܂����A��ʂւ̌��J�͂��Ă���܂���B���Ԃɉ˂����Ă���z���ɂ͑P�����̎R���ł���u���V�R�v�Ə�����Ă���A����͍]�ˎ��㊈���߉��o�g�̔\�M�̖��m�u�s�c�V��(�ӂ悤�낤���)�v�����������̂ł���܂��B�������猩��Ə������A��ɋ߂Â��߂Â��قǖP�����H���L���邩�̂悤�ɑs��Ɍ�����ƌ����܂��B
���d��(�����イ�̂Ƃ�)
�����F���R�x�ܘY�E�������g�E�R�{�����q
����26�N(1893�N)�����B�ޗ��͑��P���L����A�����͓������A����38m�̑哃�́u���؈�ؔV���{���v(�����������̂��悤�Ƃ�)�Ƃ��āA�C�̐������B�̋��{���Ƃ��ċ��t���͂��ߊC�Ɋւ��l�X�̊肢�ƋF����Č�������܂����B�����ɂ͕���5�̒q�d��\���ܒq�@�����J���܂��B���ʁF�߉ޔ@�� �����F��閦(�����キ)�@�� �����F����ɔ@�� ����F�@�� �����F����@��(�c���~���������\��)�P�����ɂ͐̂����ɂȂ�Ɖ�����u��e���v�Ƃ����s�v�c�Ȑ����������A����𓃌����̍ۂɑb�Ƃ��Ē����ɔ[�߂��Ƃ����A����ȍ~���e�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ����ƌ����܂��B���������N�]��㖾��27�N�ɋN�����}�O�j�`���[�h7�D0�̒����^�n�k�ł����c�n�k��̍ۂɂ��A�܂����3�D11�����{��k�Ђ̍ۂɂ��q�r�����Ȃ������Ă���܂����B����@����\���c���͓������ɏォ�牺�֕����̂悤�ɒ݂邳��Ă���A�U�q�̖����Ƃ��ĖƐk�\���ɂȂ��Ă���A��n�k���������肢�������Ă���܂��B���̑��ʂɂ͏\��x��3�́~4�ʂɒ�������Ă���A�����̊��x�������āA���̕��p���������킹��Ƃ悢�ƌ����܂��B����Ɠ������A�C�N�����͗��̎p�Œ����Ă͂���܂���̂ŁA��������T���Ă݂Ă��������B
���ܕS������(���ЂႭ�炩��ǂ�)
�����F�{�Ԋ��� (�����͌����ÉE�q��)
����2�N(1855�N)�����B531�̂��̗������͊�̍��E�\����A�����̖͗l�̃f�U�C������|�[�Y�܂ň�Ƃ��ē������̂͂Ȃ��A�߂̖͗l��f�U�C���Ɏ���܂œ������̂͂���܂���B�k�O�D�ō��𐬂������l�B�̊�i�ɂ���Č��Ă�ꂽ�A�k�O�D�����q�H�̔ɉh������������M�d�ȕ����I��Y�ł��B�u�S���l�̖ʉe���̂ԌܕS�����v�Ɖr����悤�ɁA���Ďʐ^�̂Ȃ�����ɂ͖S���Ȃ����l�Ɏ�������ܕS�̂̒����猩���āA�����Ɏ�����킹���ƌ����܂��B���ʂ͎߉ގO���A�\���q���J���A����ɂ͕��_���_�A���E�����ɂ͓�����k����삷��l�V�������u���ꂵ�Ă���܂��B���ݓ��k�|�p�H�ȑ�w�l�̋��͂̉��A�ܕS�������̏C���Ɏ��g��ł���A��̈�̒��J�ɏC����Ƃ�i�߂Ă���܂��B
�������a(��イ�����ł�)
�����F�{�Ԋ���(�Č�)
�J�R�̑��N���֑�a������������������3�N(1443�N)�Ɏ��_�̗��_�l���J�邽�߂ɑn�������ƌ����A�V��4�N(1833�N)�ɍČ����ꂽ��������̑����ȉ����ł��B�����͌��ݓ������ƂȂ��Ă���܂����A���Ă͊���(����Ԃ�)�����ł���A���̌`�͔g�̂��˂��\�����{�×�����̊����Z�p�̐����W���������̂ł������Ƃ����܂��B���̗����a�͗��̉������ނƂ����闳�{���͂��đ����A�����ɂ͑�o������ė��ɕω����悤�Ƃ�����A�g���Ԃ��������Ă���A���ƊC�Ƃ̌q�����\���Ă���Ƃ����܂��B���������E��ɂ͑P�����̗��Z�E�̈ʔv���A�����̋e�̌��̉��ɂ͗L����{�Ɨl�̌��v���ƂȂ��Ă���A����̋��F�̔��̒��ɂ͑P���������嗴���A�����嗴���̓_���������Ă���܂��B2016�N�ɂ͑P�����J��ؖ��B��l�l�̐��a1150�N���L�O���Ă��̉����̔������J������A�j�㏉�߂ė��_�l�̂����̂���ʂɌ��J�����R�̕��X��������킹�Ē����܂����B�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �������� |
   �@
�@
|
|
�����n�_�Ё@�@�@���n�s�������k��
|
����12�N�@���n���̎n�c�w�t��(�����)�x������Ր_�Ƃ��A������(�n�ˏ�)�{�ېՂɑn������܂����B
�t����́A�ۉ��ܔN(1139�N)�ɁA��t����̎��q�Ƃ��Đ��܂�A���n�������v�t���̉Ƃ��p���܂����B
���n���́A�w������x���̖���ł���A��X�����̑��n�S��т�̂��Ă��܂������A�����ܔN(1189�N)�������̏��ł��镃����ɏ]���ĕ���U�߂ɉ����A�R�����������̂ʼn��܂Ƃ��Ĕ������F�̊�����Ƒ��n�n��������܂����B
�t����́A����̎q���l�̒��ł����ɂ����ꗊ���̐M�]�������A�w���q�l�V���x�̈�l�ɐ������Ă��܂����B�܂��A�M�S�̌����l�ł������̂ŁA���㊙�q�̐l�X�ɂ́w���n�V�c�x�Ƃ����J���A�����Ȃ��䐒�h����Ă���܂��B
����́A���j�ɂ͐�t�n�����p�����A�t��ɂ͗��R�n���Ƒ��n�n����^���܂����B�t������琔���ĘZ��ځw�d���x���̂Ƃ��A�㐙�e���ɒʂ��փ����̖��ɎQ�����Ȃ��������ƂŁA�ꎞ��n��v������܂������w����ƍN�x�͂��̎q�w�����x�������o���ĘZ���̖{�̂����g���A�����ېV�܂ő����܂����B
�����ɂ́A���̖����n�ˏ�(4�����{��)��19��w�����x�����A�������̂Ɠ`������A����l�S�N�Ƃ�����w���x(���n�s�w��V�R�L�O���E���a54�N7���w��)������A�Ԋ�(5�����{��)�ɂ͎Q�q�҂̖ڂ��y���܂��Ă���܂��B�@ |
|
���b���� 1�@�@�@�떃�S�֒� |
���X�́A���������イ (�킫��) �Ƃ��Č����B���\15(1702)�N�A�헐�ɂ��Ď�������/�{�����Ēz�B����37(1904)�N�A��������b�����Ə̂��B���x�R�A�^���@�L�R�h�B�R��́A�����傪��i�����Ɠ`������B���厩�g���d�����ɋA�˂��Ă����Ɠ`�����A���œ������ɂ�����́A��/��鍳�P���g���Ă���B�����t�n�����̖{���͖�t�@���������������Ă��Ȃ��B���c��O�\�O�ω��̔ԊO�l�ԁB
���d������
��Õ��������̔��W�̒n�B�֒�R�A�^���@�B���������̑哯2(807)�N�A�ޗǓ��厛/�@���@�̍��m/�����t���A�ܖ�t��1�Ƃ��ĊJ�n�����B�J����炩�Ȏ��@�Ƃ��ẮA���k�n���ōŌÂ̂��́B6��m2�ɂ��y�ԐՒn�̈ꕔ�́A���w��̎j�ՁB�Ő����ɂ́A���m300�A�m��6,000�A�q�@3,800�𐔂��A18�����^�����Ă����Ɠ`�����Ă���B���̌�A��������ŕ��ƕ��ɕt�������߈ꎞ���ނ������A��������ɂ͕������A�z����ʂƍ������ (��Îᏼ�s) �֕���v�Ղ̒n�ł�������O�����傢�ɉh�����B�V��17(1589�N�A�ɒB���@���̉�ÐN�U�̍ہA�������c���đS�Ă��Ď��E�j�ꂽ�B���̋��������i3(1626)�N�ɏĎ����A�����̔p���ʎ߂ɂ���Ĕp���ƂȂ�B�d�����ɂ��Ă̎����⍑�w��d�v�������Ȃǂ́A�u�֒�R�b���������فv�ŕۑ�����A���J������Ă���B�������ꂽ���݂̎��́A�b�����Ə̂��Ă���B
|
|
���b���� 2�@�@�@�떃�S�֒� |
(���ɂ���)�@�������떃�S�֒ɂ���^���@�L�R�h�̕������@�B���Ă͌d����(���ɂ���)�Ə̂��A�����̔p���ʎ߂ň�U�p���ɂȂ������A1904�N(����37�N)�ɕ�������A���݂̎����ƂȂ����B�������㏉������̎��@�̈�\�́A�d������(���ɂ�������)�Ƃ��č��̎j�ՂɎw�肳��Ă���B
�d�����͕������㏉�߁A807�N(�哯2�N)�ɖ@���@�̑m�E����ɂ���ĊJ���ꂽ�B����͂��Ƃ��Ƃ͓�s(�ޗ�)�̊w�m�ŁA�z�������̂��߉�Â։����ď��펛��~����(���Ë���)���������A��Òn���ɕ����������L�߂Ă����B�܂��A����͉�Â̒n���瓖���̐V���������͂ł������V��@�̍Ő��Ɓu�O�ꌠ���y�_�v�ƌĂ���_�����J��L������A�^���@�̋�C�Ɂu�^���@�������v�𑗂����肷��Ȃǂ����Ă����B�����842�N(���a9�N)�Ɏ������A���^(���s)���Ղ��p�����B���̍��̌d�����͎��m300�A�m������A�q�@3,800�𐔂���قǂ̗������ւ��Ă����ƌ�����B
�����������ɂȂ�ƌd�����͉z�ォ���Âɂ����Đ��͂��Ă����鎁�Ƃ̊W���[���Ȃ�A1172�N(����2�N)�ɂ͏鎑�i���z�㍑�������S���쏯75��������i����Ă���B���̉e���ŁA�������킪�n�܂�ƁA���ƕ��ɕt�����鏕�E���ؑ\�`���ƐM�Z�����c�͌��Ő�����ۂɂ́A�d�����O�k���̏�O�V����Îl�S�̕��������A��ď��E�ւ̉��R�Ƃ��ċ삯���Ă���B�������A���̉��c�͌��̐킢�ŏ��E�͔s��A��O�V���펀���A�d�����͈ꎞ�I�ɐ��ނ����B
���̌�A�����ɓ���Ɨ̎�̔�Ȃǂ����艾���̕������i�݁A�w���{���F�b�����G�}�x���玺������ɂ͕����̉����ƂƂ��ɖ�O�����`������Ă������Ƃ��킩��B�������A1589�N(�V��17�N)�̐��㌴�̐킢�ɏ��������ɒB���@����ÂN�������ۂɂ��̐�Ɋ������܂�A�������c���đS�ďĎ����Ă��܂����B���̋������]�ˎ��㏉����1626�N(���i3�N)�ɏĎ����A���̌�͍Č����ꂽ���̂́A���Ă̑剾���ɂ͂قlj����A1869�N(����2�N)�̔p���ʎ߂ɂ���Ĕp���ƂȂ����B���̌�A�����̐l�̕����^���̐��ʂ��������сA1904�N(����37�N)�Ɏ����g�p��������A�u�b�����v�Ƃ��������ŕ������ꂽ�B�Ȃ��A���݂͐^���@�ɑ����Ă���B �@ |
|
������̎O���@��鍳�P�Ɣ@����
|
���b�����E��鍳�P�̓`���@�@�@���������킫�s�l�q���@
�l�q���̋ʎR�ɂ���r���R�b�����ɍs���Ă��܂����B�����̎R��̓V��ɂ́A�������\��̑傫�ȗ���2�C�`����Ă��āA���́u���r�ܘY�v��Ɠ`�����Ă��܂��B�܂��A�u������̎O���E�@���@�@����A��鍳�P�I���̒n�v�ƂȂ��Ă��āA�@����ɂȂ�����鍳�P���A�ӔN��Â��ɕ�炵�������ƂȂ��Ă��܂��B
��鍳�P�́A���Ƃ̕�����̎O���ŁA�̕���̉��ځu�A�z�t�@��鍳�P�v��A�l�X�ȍ�i�̃��f���ɂȂ����`���̗d�p�g���̂��P�l�ł��B�c���Ȃ݂ɁA���s�̋M�D�_�ЂŃ��[�\�N���u�N�̍��Q��v�̂��ƂɂȂ����̂��ޏ��ł��B ( �d�p����ɓ��ꂽ��鍳�P�́A���̌� ���n�ɂނ����鍳�ۂ�w偊ۂ�̎艺���W�߂ĕ��̓G�Ƃ��Ƃ��邪�E�E�E�B)
�d���Ȃǂ̘b���ł͂���܂����A���ۂɊe�n�ɗl�X�ȐՂ⌾���`��������A������R�茻����������܂��B
��˂̒���`������A���������Ղ肠��܂����B���̈�˂́A��鍳�P(�@����)�������Ƃ��Ă��g�����Ƃ����Ă��܂��B
���R�ɂ���@����ɂ��s���A���Q������Ă��܂����B��鍳�P(�@����)�̂���́A��Â̌b�����ɂ�����A��������l�X�Ȑ�������܂����A�ΖL���ȏ���N�₩�Ȏ��z�ԁc�c�c�W..�@�F�����̉ԁX���A�����āA�Y��ɐ�����ꂽ������݂�ƁA�n���̐l�Ɂ@������ɂ���Ă���P�̗l�q���M���܂����B
���b�����E�@����̓`���@�@�@�������떃�S�֒@
�@����͕������3�Ԗڂ̖��ƌ����Ă��܂��B�ޏ��Ɋւ�����b�́A���̕���(����17�̑�29)�A�����ߏ�(����18 ��G3 ��)�A�n����F�O���쌱�L �̒��Ɏ��߂��Ă��܂��B
�����ߏ��A�n����F�O���쌱�L�ł͔@����͕�����̑�O���Ƃ���Ă��܂����A���̕���ł͕����s�̑�O���Ƃ���Ă��܂��B�܂����̕���ł͑���2���ƈ���āA����̖ŖS�㉜�B�ɗ����ė����Ƃ��������肪�Ȃ���Ă��܂��Ă��܂����A����̊T����3���Ƃ��قړ��l�������ł��B�ȉ��ɍ��̕���̊Y���L���̂��炷�������Љ�܂��B
�́A�����̍��ɓ���Ƃ������m���n�������b�����Ƃ�����������܂����B���̎��̖T��Ɉ�������ŁA�����s�̑�O���ł���Ƃ����ЂƂ�̓M�̓��X�𑗂��Ă���܂����B���������������S�̂₳���������ł����̂ŁA�o�Ƃ���O�͂�������̒j�����狁������܂������A�ޏ��͂���ɑS���������������Ɛg��ʂ��Ă��邤���ɁA������a�ɂ�����͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B����A�ޏ��͖��r��腖����ɍs���A���̒�ő����̍ߐl���������O�̈��s�̂��߂ɔ����ċꂵ�ނ̂����܂����B�ޏ��͑ς��������قNj��낵���v���܂������A���̒��Ɏ�����g���������ȑm�������A�v�킸�o���������܂����B���͂��̏����ȑm�͒n����F�ŁA�ޏ��̐��O�ɍ߂̂Ȃ����Ƃ�m���Ă���A腖����ɔޏ��������ɖ߂��悤�����܂����B�ʂ�ۂɒn����F�͔ޏ��Ɍo���ƋɊy�������邽�߂̗v��������Ă���܂����B�h�������ޏ��͏o�Ƃ��Ĕ@����Ɩ����A�����Ђ�����ɒn����F��M���܂����B���̐M�̂䂦�ɔޏ��͒n����Ƃ��Ă�܂����B�@����͂��̌�80�Η]��܂Ő����A�剝���𐋂��܂����B
���ꂪ���̕���Ɏ��߂�ꂽ�@����ɂ܂��n����F�̗쌱杂ł��B�Ƃ���Ŕ@����̕�Ɠ`��������̂��������̌b����(���ɂ���)�Ɏc����Ă��邻���ł��B�������ɂ͌b������2����A�Е��͕������떃�S�֒ɁA�����Е��͕��������킫�s�l�q���ʎR�����1�ɂ���܂��B�O�҂͑哯2�N(807�N)�ɓ����t�ɂ���ĊJ����܂����B���̎��̎R��͕�����ɂ���i���ƌ����A���厩�g���b�����ɋA�˂��Ă����Ɠ`�����Ă��܂��B����ŖS��A�O���̑�鍳�P�����̒n�ɓ���A�����ނ��Ƃ����`��������܂��B�b�����ł͑�鍳�Ɣ@�����l�Ƃ��Ă���悤�ł��B�����ɂ͔@����̕��Ƒ�鍳�̕�肪���邻���ł��B��҂ɂ͑�鍳�̕�Ə̂���y����ƕ�肪�����Ă��邻���ł��B�����g�͂܂��ǂ���̂������K�ꂽ���Ƃ�����܂���̂ŁA�ʐ^�ł����������Ƃ�����܂��A���Ј�x�s���Ă݂����Ǝv���Ă��܂���
���āA�@���O���Ƃ�������ɂ́A���Ⴀ�A�����Ǝ����͂ǂ�������H�Ǝv���܂��H�����ɂ��Ă͍��܂œǂǂ̕����ɂ�����炵���`���������������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�����ɂ܂��b�͎c���Ă��Ȃ��̂�������܂��A�����ɂ��Ă͂�͂�@����Ƃ悭�����`�����c���Ă��܂��B����ŖS��A��̏t�P�͌��݂̐�t�����쒬���t�߂ɗ����ė��ďo�Ƃ��A�@�t��Ɩ�����ĉB��Z�̂������ł��B��t�����쒬���ɂ͏���_�Ђ�����A���̋����ɂ���n���͔@�t���E����ƈꑰ�̕������߂ɍ�������̂��Ƃ����Ă��܂��B��t�����쒬���t�߂ɂ͏���̏�̂ЂƂ��������Ƃ��������`�������邻���ł��B �@ |
|
�����킫�s�̌b�����E�֒̌b�����@�`��
|
�����킫�s�̌b�����@�@�@���������킫�s�l�q���@
���̎����L���Ȃ͍̂��r�ܘY��������Ƃ����銝���̎R�傪���邱�ƁA�����m�푈�̎��T�C�p�����ŋʍӂ����֏钆�w�Z(���݂̔֏鍂�Z)�o�g�̊C�R�叫�E���ؕ��Y�̕悪���邱�ƁA�X�ɑ�鍳�P�̋��{�肪���邱�Ƃ������ł��B�����A���̍��r�ܘY��̎R�傪�o�}���Ă��܂��B�b�����R��̑O�ɂ͑�鍳�P�I���̒n�Ə����ꂽ���ƁA�b�����ɂ��ď����ꂽ�ē�������܂��B
�w�b�����@�哯���N(806)�N�����t�����B�֗����Ƃ��A�a�B���{�̋{�ɂȂ���Ă��������Ē����������L�߂鋒�_�Ƃ��čċ����A�V�c3�N�A������̎O����鍳�P���b�����ɓ���n����F��M���A����@����Ɖ��߈ꑰ�̖������F��A���̒n���I���̒n�Ƃ��܂����B�x(�ē�������)
��鍳�P�͕�����̖��Ƃ����`����̗d�p�g���ŁA�{���̖��O�͌܌��P�Ƃ��������ł��B�V�c�̗��ŕ�����͓�����A�ꑰ�Y�}�łڂ���邪�����c�����܌��P�͉��O���点�A�M�D�_�ЂɉN�O���ɎQ��A����ɋM�D�_�Ђ̍r���̐����������d�p�����Ƃ����Ă��܂��B���̌�A��鍳�P�Ɩ�������܌��P�͉����̍��֖߂�A���n�̏�ɂāA�鍳�ہA�w偊ۂ�艺���W�ߒ���]���̔������N�������̂ł����A��鍳�P���s�̒����������������ƌ����̖��A�A�z�̏p�������đ�鍳�P�͐��s���ꂽ�����ł��B�����Ď��̊ԍہA��鍳�P�͉��S��������̂��Ƃɏ��V�����Ƃ����v���t�B�[�����ǂ�����ʓI�ɓ`������Ă���悤�ł��B
����A�@����Ƃ������̃v���t�B�[���ׂ�Ǝ��ɋ����[���`�������������܂��B������̎O���͔��ɐS�D�������̍��������Ŏ��̊nj��ɒʂ��A���炩�Ŕ������P�N�ł����������ł��B�����Ă�������̒j�����狁�����ꂽ�ɂ�������炸�����������Ɛg��ʂ����̂ł����B����ȓ��X�̒��ŕ��A���傪������ꑰ�Y�}�Ǔ��̓������邽�ߌb�����Ɉ�������ŐM�̓��X�𑗂��Ă��܂������A������a�ɂ�����͂��Ȃ����������Ă����܂����B����A���r��腖����ɂ����A���̏ꏊ�ő����̍ߐl�B�����O�̈��s�̂��߂ɔ����ċꂵ��ł���̂����ċ��낵���v���������̂ł����A���̒��Ɏ�����������m�������o����������ƁA�n����F�ł��邻�̑m�͕P�̐��O�ɍ߂̂Ȃ����Ƃ��������A腖��剤�ɕP�������ɖ߂��悤�������̂ł����B腖��剤�̗����ĕP�͑��E�ɖ߂邱�ƂƂȂ�A���̍ہA�n����F�͕P�Ɍo���ƋɊy�������邽�߂̗v��������Ă��ꂽ�����ł��B�h�������P�͏o�Ƃ��Ĕ@����Ɩ����A�Ђ�����n����F��M��80�]�ő剝���𐋂����Ƃ����Ă��܂��B
����͌b�����ɓ`���@����`������̃v���t�B�[���ł����A���̌b�����Ƃ͓����������ł��떃�S�֒ɂ���b�����̂��ƂŁA������̌b������807�N�����t�ɂ���ĊJ����A������̌b�����̎R��͕�����̊�i�Ƃ����Ă��邻���ł��B
180�x�Ⴄ�v���t�B�[����2�̌b�����ł́A���ǁA���b�����̓`���ł́A�@����̍ݑ����̖��O���鍳�Ƃ��āA���̗d�p�g���̑�鍳�P�ƐS�D�����@����͓���l���ŁA�֒̌b�����ł͔@����̕��Ƒ�鍳�̕�肪����A���킫�s�̌b�����ɂ͑�鍳�̕�Ə̂���y����ƕ�肪�c���Ă���Ƃ������ƂŔ����ۂ����܂��Ă���悤�ł��B���c�Ɩ{�Ƃ̏X�����������������ǂ��Ƃ��܂����A���ƂȂ��ߑR�Ƃ��Ȃ��͈̂�ʃs�[�v���ł��傤�B�����ł�����x���̃v���t�B�[���̃o�b�N�{�[���ׂ�Ɖ��ƂȂ��[���ł���悤�ȉ��߂������яオ���Ă��܂����B����������鍳�P�̓`���͂ǂ���畨��Ƃ��ē`����Ă�����̂炵�����Ƃ�����܂����B
��鍳�P�͍]�ˎ���A�̐썑�F�̋ъG�ɕ`���ꂽ�菬����Y�Ȃɑ����o�ꂵ�Ă���A���ɗL���Ȃ̂�1806�N�A�R�����`��̏������u�P�m���������`�`�v�Ƃ�������̂悤�ł��B����͕�����v��̌���k�Ƃ��āA����̎q�Ǐ��Ƒ�鍳�P���d�p�������ĕ��̈�t���ʂ������ƈÖ镨��ǖ{�ŁA3��15���ɂ܂Ƃ߂��Ă���̂ł��B�����ď���̎O������鍳�P�Ə��o�����̂����̓ǖ{�������ł��B�����Ă��̎R�����`��́u�P�m���������`�`�v���c�������r�F�����u�P�m�����n���a�������`�`�v���̕���Ƃ��ď㉉����A�ǖ{�Ɖ̕���ɂ���đ�鍳�̐��i���m�����������ł��B���̂悤�ɏ���̈⎙�������e�̖��O�𐰂炳��Ƃ��ė���������A�Ƃ����`�����j���𗣂�Ė��Ԃɐ��܂ꂽ�̂͋ɁX���R�̂��Ƃł��̂ŁA�����܂ő�鍳�P�̓t�B�N�V�����̐��E�Ɗ�����������������₷���Ƃ����܂��B�����āA���̃��f�����`���̔@����ŁA���炩�ɒ��l�I�Ȑ��i�ɏ���������ꂽ(�@����̓`��������̋A���͂���̂ł���)�ƍl����ׂ��ł��傤�ˁB����Ӗ��ł̓t�B�N�V�����ƃm���t�B�N�V����(�`�����m���t�B�N�V�����ƈʒu�Â��邩�ǂ����͕ʂƂ���)�̓�̃v���t�B�[������������鍳�P�Ƃ������ƂƏ���ɗ������Ă����܂��傤�B
��鍳�P�ɂ��Ă͈ȏ�ł����A�O�q�����@����`���͂����܂Ŕ֒̌b�����̓`���Ȃ̂ŁA�ꉞ���킫�s�̌b�������ӂ̓`�����f�ڂ��Ă����܂��傤�A�Ў藎���ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB������̓`���́A�܂��ɑ�鍳�Ɣ@������~�b�N�X�����悤�ȓ`���ł��B
�w��鍳�P�͕��̉e���ŁA�g������̐l���𑗂����l�ł���B������u�����E�V�c�̗��v(931�`940)���N�������A������̎O���Ƃ��Đ��܂ꂽ�B������͍��E�̖쐶���ł������B�̒n�̖��ŁA�f���������̕s���Ȉ������ς���ꂸ�A�f���E�������Ɛ킢�A������펀�����Ă��܂����B���̌�A����͉����������Ɍ䏊�𗧂āA�֔��B���䂪���ɂ��āA����u�V���v�Ə̂����l���ł���B����͌��߂����킯�ɂ͂������A4000�l�̕������������A�֓���~�Ō������킢���J��L����ꂽ�B�����������ł̐킢�ŁA����͗����������Đ펀���Ă��܂����B����̊قɉ�������āA�^���Ԃȉ��ɕ�܂�Ă������钆�A��P�ƌZ�̗ǖ�͂Ђ����ɓ����o�����B�n����F����w��������P�Ɨǖ�́A���n�ɗ������т��B�����āA�̋���ǂ�ꗼ�e���E���ꂽ��P�́A���݂Ƒ����݂���A�S�_�̂��Ƃ����鍳�ɕϖe���Ă������Ƃ����B�����߂��āA�Z�Ɩ��͊���g�������A�����ڂ͂Ȃ��ǖ�͐펀�B���n�ɏ������P���A�������т��悪�l�q���ʎR�̌b�����������̂ł���B��鍳�P�͎��̖T��Ɉ������сA���������藎�Ƃ��A��ɂȂ����B����ɓ������P�͕��ɂ����A���ɔ��g�͂Ȃ��������Ă����n����F��[���M�����B�܂��A���̗��ɂ����ː��Ɏ����̊���f���āA�����~���̐S���ɂȂ��Ă����Ƃ����B��ɒn���̐l�X�́A���̈�˂��u��鍳�P�̋���ˁv�Ƃ����A�܂���鍳�P���u�n���̓�N�v�Ƃ��u�n����v�ƌĂ�Ōh���悤�ɂȂ����Ɠ`�����Ă���B�n�����80���߂��ĂȂ��Ȃ����B�x(�u���킫�ӂ邳�ƎU���v)
���r�ܘY�Ƃ����Γ`���̑�H�ŁA�������Ƌ{�̖���L�ň���L���l�ƂȂ����l�ł��B�ӊO�ƍ�ʌ��ɐr�ܘY��̍�i�͑����A�����_�Ђ́u�Ȃ��̗��v��ȏ����V�R ����@(�F�J�s)�A������(�������s)�A���y��(���S�g����)�Ȃǂ����邻���ł��B���̐r�ܘY��̊����̎R�傪�c�A�ƌ���Ί����̎R��ł����B���Ē����ꂽ�̂ł��傤���ˁB�������ȊO�͌��\�Â����ŁA����Ȃ�ɋÂ����Z�p�������܂����A���ꂪ�r�ܘY��Ƃ�����̂��ǂ����ǂ�����܂���B
���֒̌b�����@�@�@�������떃�S�֒@
�w�b�����J�n1300�N�@��剮���Ў������։��C���L�O��@���R�͓ޗǎ���a��2�N(709)�O�_�@�̎��d�@�t�������q�̋��@���L�߂�דޗǂ�艺�����A���̒n�ɓ��F�����Ď��L�R�d�����ƍ����J�n���ꕽ������哯���N(806)�����t���B�ɕ����z���̋��_�Ƃ��Ē��������B�V�c3�N(940)��������O����P(��鍳�P)���R�ɓ���A����ɋA�˂��@����Ɖ��ߒn����F��M����I���̒n�ƂȂ�B�ȗ������N�ԗ��b��u��܂œƂ��ĉh���A����3�N(1392)���q�ϏC���̐r�b��l���b��u���莛�̗R����@�����x���J���A������ꐢ�̑c�ƂȂ�A�R����r���R�Ɖ��ߖ@���������{�k�тƂȂ薾���ېV�܂ő����̊w�m��y�o�����B������������̔�Ă��A�V��3�N(1534)���n���������d�����U�߂��܁A�����̈˗��ɂ�蓖�R�Z�E���٘a�r���Ȃ��B�]�ˎ���Ɉڂ�֏镽�ˎ�̋F�莛�ƂȂ�A���a5�N(1619)�������������̓��̍ޖE�l�n�E���p�ɔC���A�{���E�ɗ��E���������c��i����A�����������O�����і�t�W�����Ď���̗������ɂ߂��Ɠ`������B���Ɏc�邱�̉��{�̑��͓�������������i���ꍶ�r�ܘY�̍�Ɠ`�����n��̐l�X���猻�݂����ƌď̂���e���܂�Ă���B���E���̑��O�͓��R�̑����w���Ă���̂ł���B�c��3�N(1650)���{������25�����薖��63������i�����i��������{���ł������������ېV��₩�ɗ뗎�A�������Ȃ��疾��6�N(1873)6��15���ʎR���w�Z�b�����ɊJ�Z�����B���a20�N(1945)7��28����Ђɑ������剾���E�ɗ��E�a�E�������ɂ�������u�ɂ��ĊD���ɋA���B�͂��ɐ�Ђ��Ƃꂽ���݂̂����ÂƂ��Đ̓��̖ʉe���c�����R�̈Зe��ۂ��Ă���B����̕ϑJ�����̐��ڗʂ��A����̗����܂������ꂸ�A�J�n�ȗ�1200�L�]�N�̖��A���Ƌ��ɖ���̒��ɖv����A�@�������̈�r��H�肵�����a38�N(1963)�{���Č����Â̖�����o�܂��A�@���b����_���Ď��̋���������Ɏ���B�X�ɒh�M�k�̑��͂Đ�t�c����J��ʔv���̌��݂��n�ߏ����Ƃ��N���������̐��������A����6�N(1994)����88��������76�ԎD���ƂȂ�B����13�N(2001)��剮���Ў��������C���H���ɒ���A�����ɐi�������N11��3���㓏�����c�]��@����C���B���������R�͕���21�N(2009)�J�n1300�N�ɂ�����L�O���ׂ��N��ڑO�ɂ��Đ�Јȗ��̏�Ɗ������ꂽ���Ƃ́A�h�ƈꓯ�̊�тł���A����킭�͖{���ɐ��肵���y�̕����Ɠ��R�̋������W�h�M�k�̏��萬�A����Ƃ��F�O���A�����ɓ��R�̉��v�Ƒ��̗R�����L���i���㐢�ɓ`����Ƃ��鏊�Ȃł���B����15�N11��3���x(�L�O��蕶)
�J�n1300�N�Ƃ����Ε��鋞�J�s�A���̇�����ƌN���̓ޗǂƓ����Ƃ������ƂŁA��鍳�P�����łȂ����@���̂����]�Ȑ܂Ȃ���g���ł��ȗ��j���ւ��Ă����̂ł��B�����Ă��̏ے����R��Ȃ�ʁu���v�Ƃ������ƂŁA�M�d�Ȍ������ł��邱�Ƃ�F���������܂����B�u���v���ĎQ���̐Βi���オ��Ɩ{���̂��鋫���ł��B�b������鍳�P�̋��{��Βi���オ�肫������������ɐΔ肪����܂��B�͂�����ƍ��܂ꂽ������ǂނ��Ƃ��ł��܂��A���̕��ɂ͋��{���ƍ��܂�Ă���̂����Ď��܂��̂ŁA���ꂪ��鍳�P�̋��{�肩������܂���ˁA�����������ɂ����Ƃ����̂�������ۂ��ł����B
���Α��ɂ͉̔肪2����܂��B�b�����̔荶���ɂ́u�@�����P�v�ƍ��܂�Ă���A�u���Ï�ɂ����Ђ�@���_�́@�i���ɂ܂���߁@�V�n�̘a���v�Ƃ���A�E���ɂ� �u�@���쏬���v�ƍ��܂�Ă��āA�u�R���̌\�H�̍���@�z���ʂ�@����̈��́@������Ȃ��݁v�Ƃ���܂��B
�b�����{�����ʂɖ{��������܂��B���a38�N�̍Č��ł�����{���Ƃ��Ă͂��Ȃ�V�����ق��ł��傤�B
�����ɂ͌��w��̕������ł���u�ؑ�����ɔ@�������v�����u����Ă��邻���ł��B����͊�؍��̎������ŁA�Ή��l�̏M�`���w���Ă���̂ł����A���w�̈ꕔ�͔j�����Ă��邻���ł��B���i���N(���Z�l)�ɍ��ꂽ�����ōݖ��ł́A���킫�s���ŌÂ̕����Ȃ̂������ł��B����ʉ��{��ב喾�_�{���̍����ɂ́u����ʉ��{��ב喾�_�v�̌f�z�����钹��������������ł��܂��B����ʉ��{��ב喾�_�����̐�ɂ͉����Ȃ���������Βi������������ɎЂ炵�����̂�����܂����A���ꂪ�{�a�Ȃ̂ł��傤���B
�������đ�鍳�P�I���̌b�����̋����̎U����I���A�Ō�̖ړI�ł����鍳�P�̕悪���R�ɂ���Ƃ̂��ƂŁA����ꂽ�Ƃ���ɐi�ނƍ����ɂ���܂����A��鍳�P�̕�ł��B��鍳�P�̕�͐��_�Ɉ͂܂�A�����ɗ����̂悤�ȏ��������萮�R�Ƃ��Ă��܂��B���̉E���ɂ̓V�_���U�N�����A�����č����ɂ͖��O���킩��Ȃ��̂ł����s���N�̃T�N���̂悤�Ȗ��A�����Ă��܂��B�V�_���U�N���͂����I���Ă��܂��Ă��܂������A�����̃T�N���̂悤�Ȗ͖��J�Ŏ����Y��ɍ炢�Ă��܂��B��鍳�P�̕悻�̎�O�ɂ͏����ɕ������Ԃ���悤�Ɋ�Ȍ`�̏����A�����Ă��܂��B
��鍳�P�̕悻���Ă��̐�̒����ɓy�\���̌`�ɂȂ��Ă���̂���鍳�P�̕�ł��B�y�\���̑O�ɂ͐������A�����č����ɂ́u��鍳�P�̕�@�@���@�@����v�ƍ��܂�Ă���Δ肪����܂��B�����ēy�\���̌�둤�ɂ́u�j�đ�鍳�P�V��v�ƍ��܂ꂽ�Β������Ă��Ă��܂��B�����̐Ղ�A�Ԃ��Y����ꂽ�Ղ�����A�Y��ɐ��|�E��������Ă���̂ŁA�ߏ��̕���������ɂ��Q�肵�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB���f������ljؗ�A�܂��ɑ�鍳�P�ɑ���������ł͂Ȃ��ł��傤���B
�t�̃T�N���̖����̂悤�ł����A��鍳�P�`���Ƌ��ɔ��ɋ����[���b�����ł����B�@ |
|
���o�_�_�� 1�@�@�@�쑽���s |
��Ր_�͑嚠�喽(�I�I�N�j�k�V�m�~�R�g)�A���Y��(�j�j�M�m�~�R�g)�B�Њi�͋��ЁB
�Г`�ɂ��ƁA��Z�\���E�鐝�V�c�̎���A�V�c�N��(938�`946�N)�ɕ�������ŖS��̎c�}�����n�ɓ���H�蒅���A���̒n���A�_�n�̊J��������Ȃ����B��������đ�Z�\�Z��E�꞊�V�c�̎���A����N��(990�`995�N)�ɉA�z�t�E���{���������n�ɉ����B�u���̒n�͏����ɉh����n�������Ă���B���y�J���̐_�A���Ȃ킿�o�_��Ђɍ����嚠�喽���ւ��A���̒n�̒���Ƃ���ׂ����B�v�Ɗ��߂��B���k�ɂ͈ӊO�ƈ��{�����̉����̓`���������āA�����s�̕�����א_�� �ɂ������悤�ȓ`�����c���Ă���B
�����̐l����̐��h���W�߁A���̌�_���сw���А_�Ёx�Ə̂����B�����l�N�Ɂw�o�_�_�Ёx�ƎЍ������߁A���݂Ɏ����Ă���B
|
|
���o�_�_�� 2 |
�������쑽���s����ɒ�������o�_�_�Ђ͑卑�喽���Ր_�Ƃ���_�Ђł���B��R�L�_(�I�I���}�c�~�m�J�~)�Ə��R�P�_(�n�j���}�q���m�J�~)��2�����Ր_�Ƃ������А_�Ђł��������A����4�N(1871�N)�ɏo�_�_�ЂƉ��̂��A�Ր_��卑�喽�Ƃ����B
�Г`�ɂ��A�n���͐���N��(990�N〜995�N)�Ɉ��{�������u���y�J���̐_�v�Ƃ��ē��n�ɑ卑�喽���ւ������Ƃɂ��Ƃ����B
�����ɂ́u���R�����^�����˔V�n�v�̔肪����B
�o�_��Ђ��J����卑���_���J�����_�Ђ́A�X��_�ЂȂǂ��邪�A�o�_�_�Ђ͂���قǑ����͂Ȃ��悤���B�������߂ďo������o�_�_�Ђł�����B�����ɂ�2�{�̎}��������A�����Ă���A�y������̑����������B�܂��A�����̌������ɂ���4�������̓X�܂͗��j����������̂�����̂��B
��
�u�w�V�҉�Õ��y�L�x�ɂ͑��А_�ЂƂ���A��R�L�_(�I�I���}�c�~�m�J�~)�E���R�P�_(�n�j���}�q���m�J�~) ��2�����Ր_�Ƃ��Ă��邪�A����4�N�ɏo�_�_�ЂƉ��́A�Ր_���卑��_(�I�I�N�j�k�V�m�J�~)�Ƃ����B�Г`�ɂ��A���̒n���J�����̂́A�V�c�N��(938�`946)�ɂ����܂œ���Ă���������̎c�}�ŁA �_�Ђ͐���N��(990�`995)�Ɉ��{�������u���y�J���̐_�v�Ƃ��ē��n�ɑ卑�喽���ւ������Ƃɂ��Ƃ����B�����ɂ́A�V���̍��ɒ��c�t(���E�쑽���s�⌎��)���ڂ����s�_���J���Ă���B�v�Ƃ��Ă��B
�u�Г`�ɂ��ƁA���{�����������ɉ����� �u���̒n�͏����ɉh����n���ł���B���y�J���̐_�A�o�_�̐_����Ƃ��ׂ��B�v�Ɗ��߂��Ƃ���B�E�E�E�A�Ր_�́w�卑�喽�A�玌|�� (�j�j�M�m�~�R�g)�v�Ƃ��Ă��B �@ |
|
���V���c�����@�@�@���͎s��H��
|
�V���c�����́A�哯�N��(806�`10)�@���@�̍��m�A�����ɂ���đn�����ꂽ�������ł����B�������A�������㖖���ɎO�\�O�ԓ��Ȃǂ̌����ƂƂ��ɍċ�����A���O���u�唒�R�V���c�����v�Ɖ��߂܂����B���݂̏ꏊ�Ɉڂ����̂́A�O�g���̎���Ƃ���Ă��܂��B
�����ɂ́A���X�̗��j�I�L���l�̕�A�ԗ�肪����A��Òn���̗L���Ȗ��w�u��Ô֒�R�v�ɓo�ꂷ�鏬�������̂��������܂��B�ە��q�̏����炵���A�����̏�ɂ��������W�����Ă���`��͂������j�[�N�Ȃ���ɂȂ��Ă��܂��B�����́A�u�ď`�ۗ��M�m�v�B
��
�哯�N��(806�N�`810�N)�A���݂̎����H�̂�����ɁA�@���O�̑m���������������Ă����������O�g�ł���Ɠ`�����Ă��܂��B���������ɎO�\�O�ԓ��������@�Ƃ��čċ�����A�u�唒�R�V���c�����v�Ɩ��O��ς��܂����B���݂̒n�Ɉڂ����̂́A���얋�{�ɂ��ڕ����ꂱ�̒n�ɂ���Ă����O�H���̎���Ƃ���Ă��܂��B���͌��̐킢�Ő펀�����V�I�g���m�@�e�n���̕��A���w�u��Ô֒�R�v�̚��q���ƂŖ��������������̃��f���ƌ������Óh�t�v�ܘY(����5�N6��10���v)�̕悪����܂��B �@ |
|
��������Ձ@�@�@�쑊�n�s
|
�������쑊�n�s������(�ߐ������F�������s���S����)�ɂ��������{�̏�(���R��)�B�ʖ��u�g�~�R���D��v�B
��k������ɁA�k�����Ɨ�����쒩�̌R���ɑΉ�����ׂɌ��݂���A�������{����1336�N�ɍU�߂���x�ח����Ă���B���N1337�N�ɏ��D�҂��Ă���́A��16�㓖�告�n�`�����{������z��⒆����Ɉړ]����܂ŁA��260�N�Ԃɘj���đ��n���̋���ł������B
��̖k������L�т�䍂10m�قǂ̋u�˂���x�Ő�`�ŏ�����A��̓�𗬂�鏬������O�x�Ƃ��Ă���B��̐�����k�ɂ����Ă͐��c�������Ă���A�x�ł������Ƒz�肳���B���̂悤�ɎO�ʂ𐅈�Ǝ��n�ň͂܂�Ă������߁A���D��ƌĂ�Ă����Ƃ����B���݂͏�̓��ɕٓV�r�ƌĂ��x�Ղ��c���Ă���B
���͓����ŁA���ݍ���Ă���쑤�̎Q���͈�\�Ƃ͖��W�ł���B��̈ꕔ�ɓy�ېՂ��c��A���ɐ_�З��E�k�ʂ̕ۑ����ǂ��B
��̋K�͂͏������A��s�ȊO�̋ȗւ͏����������B�ł��邽�߁A��������Ƃ͌�����B�h��͂̒Ⴓ��₤�ׂɁA�t�߂̋u�˂ɕ����̏o�邪�������Ƃ����Ă���A���̏�n�̋����䂦�ł���Ǝv����B
���n����������{���n�ɂ����v���́A��ׂ̊�鎁(�{���n�F�l�q�A�і약)����������ړI�ł������B�Ƃ��낪�A�k�ׂ̈ɒB��(�{���n�F�đ�A��o�R)�Ƃ̍R������������ƁA���n���͒����ɏ���u���ĈɒB�����ɂݍ������B
1600�N�̊փ����̐킢�ł́A���n���͍��|��(�{���n�F�헤���c�A����)�ɗ^�����ׂɁA�փ����̌��ʂƂ��ė̒n��v�����ꂽ�B�������A�ɒB���@�����n�`����i�삵�ē��얋�{����������ׂɁA���n�`���͋��̂ł���l�ʂ��m�X�Ȗk�ւ̕��A���ʂ����A1611�N�ɂ͖{���n����㏊�ݒn�ł�����������Ɋ��S�ړ]���āA�����˂𗧂Ă��B���̖{���n�ړ]���A���̏�����̋����䂦�ł���Ǝv����B
���݂͖{�ېՂ̕���ɑ��n���̎��_�ł���V�V�䒆��_���J�鑊�n�����_�Ђ������Ă���A���n��n�ǍՂ�̎��ɁA���n��f��Ŏ�艟�����_�Ђɕ�[����u��n�����v�̏ꏊ�Ƃ��Ēm���Ă���B
�Ȃ��A��錧�s���s�����ɂ������́u������Ձv�����݂��邪�A������͍s���@���̎q���Y�芲�ɂ���Ēz���ꂽ�B
|
�����n�����_�Ё@�@�@�쑊�n�s
��Ր_�@�V�V�䒆�喽���߂݂̂Ȃ��ʂ��݂̂���
���n�����_�Ђ́A�����̉��B���n���̋���ł�����������Ղɂ���܂��B������́A���B���n��������������ڂ������q����̏I��肱�납��]�ˎ���̏��߂܂ł̖�280�N�ԁA���B���n���̋���ł���܂����B���B���n���͂��̏�����_�Ƃ��āA��k���̓�����ɒB���Ƃ̍R�����J��L���܂����B������͒����̏�Ƃ��Ă͏��K�͂Ȃ��̂ł����A�y�ۂȂǂ����݂��悭�c���Ă���A���̎p����A�ʖ����u�g�~�R���M��v�ƌĂ�A�Z���ɐe���܂�Ă��܂��B
�]�ˎ���ɂȂ�A���n����������(���n��)�Ɉڂ������Ƃ��������Ղ��Ă���A��������ɏ����_�ЁA���ɑ��n�����_�ЂƉ��̂��܂����B���݂́A���w��d�v���`�����������u���n��n�ǁv��3���ڂ̖�n���̍Տ�n�Ƃ��čL���m���Ă���A���̍]�ˎ���̗l�q�́A���n�����_�Ђɕ�[����Ă��錧�w��L�`�������u���n��n�NJz�v�Ȃǂ��炤�������܂��B
�_�Ћ����ɂ́A���_�ЁE���̉@�E�V���{�E�I�@���Ȃ͂��_�ЂȂǂ������J���A���w�ɂ͑����̎Q�q�҂œ��키�ƂƂ��ɁA���̖����Ƃ��Ă��L���ł��B
|
����ߎR(�����Ђ�)�̐Ε�
�쑊�n�s��������ɂ����t���Ε��E����ɓ��Ε��E�ω����Ε��́u��ߎR�̐Ε��v�ƌĂ�e���܂�Ă��܂��B�����̗l������A���쎞���͕�������O���Ɛ��肳��A1��N�ȏ���O�ɂ��̒n�Ŕ�ނȂ������������ԊJ�������Ƃ������M�d�ȗ��j��Y�ł��邱�Ƃ���A���a5�N�ɍ��j�ՂɎw�肳��܂����B���k�n���ōő�E�ŌÂ̐Ε��Q�ł��邱�Ƃ���A�Ȗ،��F�s�{�s��J���R��������܂����ԂA�啪��������������P�n�s�P�n���R���������܂����Ԃƕ���œ��{�O�喁�R���ɂق��܂����Ԃɐ������A���{�L���̐ΌA���@�ƕ]�������ɂ�������炸�A���̐Ε���������l�B����j�I�w�i�͏ڂ����킩���Ă��炸�A������̑����Ε��Q�ł��B
����t����
��t���Ε��͑�ߎR�̐Ε��̒��ōł��ۑ���Ԃ��ǂ��A�ÊD�����€�傤��������������蔲�����Ԍ�15���A����5.5���̊�A���̕ǖʂɁA���������ڂ��4�̂̔@������2�̂̕�F�����A������2�̂̕�F���Ɣ�V��o���Ă��܂��B�����A��������A�����̍L���A�ʊ��̂���ǂ����肵���@�������̎p�́A��������O���̓���������Ă��܂��B
���ω����Ε�
�ω����Ε��́A���̐Ε��Q�̖{���ł������Ƃ����\��ʐ��ω������ŁA�ۑ��͗ǂ��Ȃ����̂́A����9���𑪂���{�ő勉�̐Ε��ł��B�������ɂ��ɒ���o���ꂽ��������̎�̂���2�{��ɋ����ĉ��������������Ɠ��̃|�[�Y�́A���s�̐������̖{���ł���\��ʊω����Ƌ��ʂ��邱�Ƃ���A�u�����^�v�ƌĂ�Ă��܂��B�ω����̍��E�����ɂ́A�����������ɂ��ڂ�Ő������̉��������܂�Ă��܂��B���̖��R���́A���\���ɉ��B������告�n�����ɂ���ĉ����O�E�O���ω�����߂��A���̒��̑��\���ԎD���ɂ��Ȃ��Ă��܂��B
������ɓ��Ε�
����ɓ��Ε��͌`�����炩�łȂ��قǂɔ����͂��炭���������A���݂͕����Ǝv����c�̕����c���݂̂ŁA����ɕ������܂�Ă����Ɠ`�����Ă��܂��B
����ߎR�̑吙
��ߎR�ɂ���吙�́A��t���Ε��̑O��Βi���ɂ���A�ڒʂ�8�D4���A����45���𑪂錧���L���̑�ł��B����́A��N�ɋy�Ԃ��̂Ɛ��肳��A��t���Ε������ꂽ����ɁA�炿�n�߂��ł���ƍl�����܂��B�������̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B |
|
�����n���c�_�Ё@�@�@�쑊�n�s
|
�������쑊�n�s�����撆���c�ɗ��n����_�ЁB���n�O�����Ђ̈�B���c�_�ЂƂ��Ă�Ă���B��Ր_�͓V�V�䒆���_�ł���B
�����N��(931�N - 937�N)�ɑ��n���̉��c�E�����傪�����������S�牮��ɖ����Ђ�n���������ƂɎn�܂�B
�����傩��\���ɂ����鑊�n�t�킪�������̌R�ɏ]���A���B�������Ƃ̍���ł̌��тɂ�艜�B�s���S�̒n������A�����̐�t�����瑊�n���p���A���B���n�̏���ƂȂ����B
���̌�A����3�N(1321�N)4��22���A��������J���葊�n���ܘY�d�������䍑�����̍ہA���̒n�ֈڂ�Z�݁A���_��������ċ{�K��n�������J�����B
���n�Ƃ͖����M�̐M�]�҂ŁA�ˎ傪�Ă��M���Ă�������E�������������玝�Q���A�~�n���ɒ����������B���̖����������n���c�_�Ђ̗R���Ƃ���Ă���B
���̐_�Ђ͒����ˑ��n���̎��_�Ƃ��đ�X���q����Ă����B �@ |
|
�����h�_�Ё@�@�@�쑊�n�s
|
(�Ђ킵����)�@�������쑊�n�s������ɂ���_�Ђł���B���Њi�͑��ЁB
�V���h�����J��B �u�����u�v�ɂ��A�V���h���A���Ζ�(�V���ގ~����)�A�V�����H�_���J��Ƃ����B
�Ր_�̓V���h���́A�V���~�Ղ̍ہA�����n���ɋ����O�\�̂����̈ꒌ�ŁA�V���ʖ��ɕt���]���_�ł���B���̌�p�͎�ɂ͋|����тё�h�ɏ��A��삯�ƂȂ��ēV�~��Ɠ`���B���̂��߁A�V���h���͋|��̐_�ł���A��̍ۂ͑�h�Ƃ��Č������R��擱����ƐM���ꂽ�B
���h�_�Ђ́A���Â͉������L�c�S���X���ɑ�`�_�ЂƂ������O�Œ������Ă���A�����傪�������ɂ����ۂ��Ă��M���u�h�{�͐_����|��̐_�ŁA�h�͖ҁX�������ł���B�䂪�R���G���ɍU�ߓ���A�V���h���͑�h�̎p�Ō���Ċ������낤�B�䂪�R�ɑ嗘�����炵�ނ�A�䂪�q���͉i���V���h�������_�ƒv���v�ƋF�肵���Ƃ����B�֓��n���肵����A������͓V���h���̉���ւ̕��Ƃ��ĎГa���c��_�c�̊�i�A�т̐_�����s�����B
�����N�ԁA�������͉������́u�h�{(�킵�݂̂�)�v�𐒌h���A�_�c��_�n����i���J�^���F�肵���B���n�����㓖��̑��n�t��͎���4�N(1180�N)��茹�����ɏ]���A�����ΌR�����グ���Ƃ����B����5�N(1189�N)9���ɉ��B����ɎQ�킵���ہA���c�ł��镽����ɂȂ炢�h�{�Ő폟�F����s�����Ƃ���A�傢�ɌM�����������B���n�t��͌��������J�܂Ƃ��čs���S������A�M����͘h�{���C�U���Ă��Ă����h����悤�ɂȂ����Ƃ����B
���h�_�Ђ́A����3�N(1323�N)���A�������n�Ɠ���ł��鑊�n�d����������(���݂̐�t���k��)����s���S�ֈڂ����ۊ������ꌴ���摾�c���J��ꂽ�B���n�d���̉��c�ł����t�������h���閭����(���݂̓쑊�n�s�̑��n���c�_��)�E�㑾�c�̉��}�_�Ђ����̎����ɑ��n�̒n�֊�������A���h�_�Ђ͕��_�E�V���h�����J��_�ЂƂ��Đ��h���W�߂Ă����Ƃ����B�厡3�N(1364�N)�Ɍ��݂̒����n�ł��鏬���揗��ւƑJ�������B�������ꂽ�����́u�h�{(�킵�݂̂�)�v�ƌĂ�Ă������A���ʂ̏(�������{�͍c�c�_�ȊO�Ɂu�{�v�̌ď̂��ւ���)���疾��5�N(1872�N)�Ɍ��݂̎Ж��ł���u���h�_�Ёv�։��̂����B
���h�_�Ђɂ́u�т̎s�_���v�Ƃ����_��������A�_�Ђ��珬���ȍהf(���܂��炢�A�F��)�����������čK�^���F����̂ł���B�הf�́u�ӂ̂��Ƃ��ƍ��E��������R�C�̊l���������W�߂�v�Ƃ����Ӗ��Ŏ��^����A���ł����Ƃɂ��̏K�����c���Ă���B�܂��A����(11��)���߂Ă̓т̓��ɍs����_���ɑ���(�͂�����������)���������Ƃ����B�������Ƃ́A�펞�ɂ����ēG�̎��߂邱�ƂɂȂ炤�Ƃ����B �@ |
|
�����n������Ձ@�@�@���n�s����
|
���������n�s����(�ߐ������F�������F���S����)�ɂ��������{�̏�B�P�ɒ�����Ƃ��������A���́u������v�Ƌ�ʂ���ۂɂ́A���n������◤��������Ƃ����B�퍑���ォ��]�ˎ���ɂ����Ă̑喼�E���n���̋���̈�ł���A�]�ˎ���ɂ͔ˎ告�n���̒����˂̔˒��ł������B�n�ˏ�(��傤���傤)�Ƃ����ʖ������B
�꒣��͒�s���̕��R��ł���B
���̈����G�R�n����L�т�䍂15m���̏��u�˂ɒz���ꂽ��ł���B��ʂɗ����F�����V�R�̊O�x�Ƃ��A���̐��������Ėk�ʁE���ʂɐ��x���z�����B���������̐��ʂ́A�x�Ɛ؊݂Ŗh�䂳��Ă���B�k�ʂɐ��x�𒆐S�Ƃ����n�`�I��V�𑽂��p���A���z�G�ł���ɒB�����ӎ������\���ƂȂ��Ă���B�펞�ɂ͖x����ď�̖k��500m�]�����ʂ̏���n�ɂ��邱�Ƃ��ł����Ƃ�������B�ꏊ�Ƃ��Ă͉F����̓n�͓_�𐧈�����Ӗ������������Ă���B
�����j 1
������̗��j�͌Â��A���n����������ڂ��O�������قƂ��ė��p����Ă��܂����B�Â��́A����20�N(801)���c�����C�̓��ΐ����̂Ƃ����p�����Ƃ���A�����ɂ́A�����������B����̋A�r�A�����̊قɏh�c�����Ɠ`�����Ă��܂��B
��k�������1337�N(����2�N)�ɂ́A���ӂ�z���Ƃ����������������̒n�Ɂu�����فv���\�����B�Ȍ�A�퍑���㏉���܂Œ������̎x�z���������B
�������ɑ����đ��n�������l�ʂ��m�X�Ȗk�Ɍ�����U�邢�A1563�N(�i�\6�N)�Ɏ��j�̑��n���������邵���B���̎����͑��n���ƈɒB���̍R�������������퍑����^�������ł���A���n���͖{��ł��鏬����ɉ����āA���̒�����ɏ���u���ĈɒB�����ɂݍ������B
1600�N(�c��5�N)�̊փ����̐킢����11�N���1611�N(�c��16�N)�A�����̑��ł��闘���́A�{��������邩�璆����Ɋ��S�ړ]���A������͒�����6���̐��{�ƂȂ����B���N�A�����͂������ɋߐ���s�ւ̉��C���J�n���A��s���̏�s�������A�{�ێl�E�Ə̂����E��`���̑O��y�ѝ���(����߂�)��E�k���E�E�V�炪�݂���ꂽ�B�������A1670�N(����10�N)�ɂ͗����ɂ��V����Ď��������A����4��ˎ����͔ː���D�悵�V��Č��ׂ͈���Ȃ������B�Ȍ�A������w�j�Ƃ��ė��ˎ�͓V����Č����Ȃ������B
1868�N(�������N)�̕�C�푈�ł́A������͖������{�R�̍U�����Ċח����A�ח���̒�����͖������{�R�̎x�z���_�ƂȂ����B�����āA1871�N(����4�N)�̔p�˒u���ɂ���Ĕp��ƂȂ����B
�����j 2
������̗��j�͌Â��A�������㏉���̉���N��(800�N��)�ɉ��B�����̂��ߍ��c�����C���ŏ��ɒz�����Ƃ����B
��k������̉�����N(1337�N)�ɂ́A���ӂ�z���Ƃ����������������̒n�Ɂu�����فv���\�����B�Ȍ�A�퍑���㏉���܂Œ������̎x�z���������B
�������ɑ����đ��n�������l�ʂ��m�X(�y����)�Ȗk�Ɍ�����U�邢�A�i�\�Z�N(1563�N)�Ɏ��j�̑��n���������邵���B���̎����͑��n���ƈɒB���̍R�������������퍑����^�������ł���A���n���͖{��ł��鏬����ɉ����āA���̒�����ɏ���u���ĈɒB���ƑΛ����Ă����B
�c���ܔN(1600�N)�̊փ����̐킢����11�N��̌c���\�Z�N(1611�N)�A�����̑��ł��闘���́A�{��������邩�璆����Ɋ��S�ړ]���A������͑��n������6���̒��S�ƂȂ����B���N�A�����͂������ɋߐ���s�ւ̉��C���J�n���A��s���̏�s�������A�{�ێl�E�Ə̂����E��`���̑O��y�ѝ����E�k���E�E�V�炪�݂���ꂽ�B�������A�����\�N(1670�N)�ɂ͗����ɂ��V����Ď��������A���̎l��ˎ����͔ː���D�悵�V��Č��͍s���Ȃ������B�Ȍ�A����ɕ킢���ˎ�͓V����Č����Ȃ������B
�������N(1868�N)�̕�C�푈�ł́A������͖������{�R�̍U�����Ċח����A�ח���̒�����͖������{�R�̎x�z���_�ƂȂ����B�����āA�����l�N(1871�N)�̔p�˒u���ɂ��p��ƂȂ����B
�����\�O�N(1878�N)�ɑ��n���̑c�E���n�t����J���đ��n�_�Ђ��{�ېՒ����Ɍ������ꂽ�B
�@ |
|
�����n�_�� 1�@�@�@���n�s���� |
����12�N�@���n���̎n�c�w�t��(�����)�x������Ր_�Ƃ��A������(�n�ˏ�)�{�ېՂɑn������܂����B
�t����́A�ۉ��ܔN(1139�N)�ɁA��t����̎��q�Ƃ��Đ��܂�A���n�������v�t���̉Ƃ��p���܂����B
���n���́A�w������x���̖���ł���A��X�����̑��n�S��т�̂��Ă��܂������A�����ܔN(1189�N)�������̏��ł��镃����ɏ]���ĕ���U�߂ɉ����A�R�����������̂ʼn��܂Ƃ��Ĕ������F�̊�����Ƒ��n�n��������܂����B
�t����́A����̎q���l�̒��ł����ɂ����ꗊ���̐M�]�������A�w���q�l�V���x�̈�l�ɐ������Ă��܂����B�܂��A�M�S�̌����l�ł������̂ŁA���㊙�q�̐l�X�ɂ́w���n�V�c�x�Ƃ����J���A�����Ȃ��䐒�h����Ă���܂��B
����́A���j�ɂ͐�t�n�����p�����A�t��ɂ͗��R�n���Ƒ��n�n����^���܂����B�t������琔���ĘZ��ځw�d���x���̂Ƃ��A�㐙�e���ɒʂ��փ����̖��ɎQ�����Ȃ��������ƂŁA�ꎞ��n��v������܂������w����ƍN�x�͂��̎q�w�����x�������o���ĘZ���̖{�̂����g���A�����ېV�܂ő����܂����B
�����ɂ́A���̖����n�ˏ�(4�����{��)��19��w�����x�����A�������̂Ɠ`������A����l�S�N�Ƃ�����w���x(���n�s�w��V�R�L�O���E���a54�N7���w��)������A�Ԋ�(5�����{��)�ɂ͎Q�q�҂̖ڂ��y���܂��Ă���܂��B
|
|
�����n�_�� 2�@�@�@���n�s���� |
���n������Ղɕ��ꂽ���������n�s�ɂ���_�ЁB���Њi�͌��ЁB�]�ˎ��������疾�����㏉���ɗ��s�����ˑc���J�����_�Ђ̂ЂƂB�Ր_�Ƃ��Ė�����F���ƓV�V�䒆���_(���߂݂̂Ȃ��ʂ��̂�������)�Ƒ��n���̎��_�ł��镽���傪��������Ă���B
���n�Ƃ̎n�c�t����Ր_�Ƃ��Ė���13�N(1880�N)�Ɍ������ꂽ�B�n�ˌ���(�����隬)�ɂ͑��n�Ƃ̎��_�Ƃ��Ă̖��������_�ЂƑ��n�_�Ђ�2�Ђ�����B���������_�Ђ͑��n�����_�ЂƂ����邽�ߑ��n�_�Ђƍ�������邪�ʕ��ł���B���n�Ƃ͑��n�����˗̓��ɋ��邵�������A�����ɂ����ꂼ�ꖭ�����c�_�ЂƖ��������_�Ђ������������̂����݂��c���Ă���A��ʓI�ɂ͒����_�ЁA���c�_�ЁA�����_�Ђƕ\�������B �@ |
|
�����n�����_�� 1�@�@�@���n�s���� |
���������n�s�����ɗ��n����_�ЁB�ʖ��͖��������_��(�݂傤����Ȃ��ނ炶��)�����A�����_�ЂƏȗ�����邱�Ƃ�����B�Ր_�͓V�V�䒆��_(������F)�B���n��n�ǂ̏o�w���͂����ōs����B
���n�����_�Ђ̋N���́A���n���̎n�c�ł��镽���傪�����N��(931�N�`937�N)�ɉ����������S�ɖ����Ђ������������ƂɎn�܂�Ƃ�����B���n���̑��n�S�����ɔ����������ꂽ�B�퍑�����16���I�㔼�ɂ́A�����邪���n���̖k�̋���ƂȂ�A���n�����⑊�n�����Ȃǂ��������ƂȂ����B
1600�N�̊փ����̐킢�̌��ʂƂ��đ��n���͉��Ղ��ꂽ���A1611�N�ɋ��̂ւ̕��A���ʂ����Ē����˂𗧂Ă��B���̎��A�����˂̏���ˎ�ƂȂ������n����(���n����17�㓖��)���A1611�N�ɒ�������̓쐼�ɑ��n���̎��Ђł��閭���Ђ����������̂��A���݂̑��n�����_�Ђ̋N���ł���B
���݂̎Гa�͊��i20�N(1643�N)�ɒ�����2��ˎ告�n�`��(���n����18�㓖��)�ɂ�茚������A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B
��������ɓ����Ĕp���ʎ߂ɂ��{���̖�����F���p������A���n�����_�ЂƉ��̂����B�܂��A������{�ېՂɂ́A��C�푈���1880�N�Ɍ������ꂽ���n�_�Ђ�����B
�{�i�͏���c��M������n�܂��āA��X�c��Ƃ����P����29��𐔂���B
|
|
�����n�����_�� 2 |
���n�_�Ђ̎n�܂�́A�Г`�ɂ���������]�N�O�̏����N��(931�`937�N)���n�Ƃ̐�c�A���̏��傪�����̍������S�Ƃ������ɖ����Ђ�n�����Đ폟���F��A�����č��ƈ��ׁA�������s�̔ɉh���F�O�������ƂɎn�܂�A�㑷�t������A�����̑��n�S�ɎГa�����Ă��Ɠ`������A�����O�N(1323�N)�ɂȂ��āA�t����Z���̑����n���ܘY�d�������A���q���珉�߂ĉ��B�s���S�Ɉڂ�Ɠ����ɖ����K���c�Ɉڂ��A���c���N(1332�N)�����ɒz�邵�Ĉڂ�Ƃ��_�Ђ��ڂ���܂����B����Ɍc���\�Z�N(1611�N)���n�����������n�����ɏ���ڂ����Ƃ������_�Ђ���������ֈڂ���܂����B���ꂪ���݂̑��n�����_�Ђł��B���n�����_�Ђ́A���n�Ƒ�X�̎��_�Ƃ��Đ��h����Ă�������łȂ��A���n�n���̑�����Ƃ��Ē�����s���̐��ɂ��鏬�����u�Ɍ����Ă��܂��B
���݂̖{�Ќ��z�{�a�E���a�E�q�a�́A���i20�N(1643)�18��ˎ告�n�`���ɂ���Č�������A���n�n���̑�\�I�ȌÌ��z�Ƃ��č��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�p�ނƂ��ğO���ӂ�Ɏg������������ŁA�{�a�y�єq�a���ʂ�富҂ƌĂ�镔�ނ͐_�ЗR�����ے�����悤�ɔn�̒������{����Ă��܂��B�������͔��ؑ���̗l����悵�Ă��܂����A�{�a�͖{���A�ؕ��S�̂Ɏ��h�肳��Ă���܂����B������O�S�\�N�Ƃ����Ό��ɂ�茚���͐^�̎p���B���Ă���܂����A�����Ɏ{���ꂽ���h��A�ʐF�͂悭�c�蓖���̑����������ɓ`���Ă��܂��B���݂̎Гa�́A�ق�20�N���Ƃɓs��10��̏C�����d�˂Ă���A�܂��A����29�N�����C�����s���A�������n�������̂����畘�ɉ��C����܂����B�@ |
�������Ж{�a�@�@�@���n�s����
�����Ђ́A���n�����_�Ћ����ɂ���܂��B���̐_�Ђ́A�f����(�����̂��݂̂���)�Ƒ��n���̑c�Ɠ`�����镽��������킹�čՂ��Ă��܂��B
���n�����s���S(�Ȃ߂��������݂̏������E�����s�E�������E�ъڑ�)�Ɉڂ��Ă������A�������s��(���̓���)�Ɍ�������A���n���̑c�_�Ƃ��ĐM����܂����B
1694�N(���\7)�A�ˎ告�n���������݂̒n�Ɉڂ��܂����B�@ |
|
�����̎�̘b
|
�����o���@/�@�ᏼ����
�ᏼ���ҁF���n�̑�n(���̋��n���w�Z�̂Ƃ���)�Ɏᏼ���҂Ƃ�����x�����Z��ł����B�L���y�n�Ƒ����̂߂��g���������Ă����B��l�̔������������čK���Ȃ��炵�����Ă����B����Ƃ��a�C�ɂ�����A��҂��Ǝ��s�������������߂��Ȃ��B��ɂ݂Ă�������Ƃ���A�����̔N�́A���̓��́A���̍��A�ɐ��܂ꂽ���̐����������܂���Ȃ��釁�ƁA����ꂽ�B���҂̏��g���Ɉ�l����ɂ����鏗�������B�����ł��̏��ɏh������������A���̓r���E�����ƂƂ����B�����E�������ł��A���������̂܂�����A�����ǂ���ɕa�C���Ȃ������B�����ɏh�����肩�珢�g�����A���ė����B�s�v�c�Ȃ��Ƃ��B���҂���{���̂��݂����܂��݂���A���g������������Ǝv����Ƃ���ɓ��̂������������B���݂����܂��g����ɂȂ����̂��B���ꂩ�璷�҂̉Ƃ͖v�����A���҂͓s�֍s�����Ƃ�����B�w�����Y�̖����x
��
���ς�炸�悭������Ȃ��B�����炭�́u�����s���̕a�ɂ����������Ƌ��Ɋւ��鉽���v�̘b������A���ꂪ�����āu�g����{���v�̘b�ɑg���܂ꂽ�̂��낤�Ǝv���B�S�̂�ʂ��ĉ�肷��͓̂���̂ŁA���́u�����s���̕a���v�Ɓu���v�Ƃ����R�[�h�̋��ʂ���b�����Ă݂悤�B
�����������b�������ɂ���̂��B����͗����ɒB�S�E�������ɒB�s�̔��c���ɓ`���k�V�̘b�B���̘b�ɂ͏d�v�ȃq���g�������������Ă���B
|
�������@/�@���c���̎�
�����c���̎�
�ɒB�S�X�]�쑺�ɁA�˖�ڂƂ������m�̈�l���ő��S���Ƃ������������������B���̖����a�C�ɂȂ�A�u���c���̐����݂̂����v�Ƃ���Ԃ��B���c���Ƃ͐̂̋�R�E���c�R�̎R���ɂ���Ï��̂��Ƃ��B���̐��𖺂Ɉ��܂���ƕa�͎������B���̌���a�ɂȂ邽�тɔ��c���̐������܂���Ɩ��͗ǂ��Ȃ�̂������B��������������͎p�������B�F�ŒT���Ɣ��c���݂̊̏��ɒ������������Ă����B�����T��������������͊���ȑ̌�������B���ɐ���Ƌ@�D�鉹�������A��ɂ͗��h�ȉ��~���������B���̊Ԃɂ͑��S��������A��l�ŋ@��D���Ă����B���S���͏��̎�Ɍ����܂�ȂƂȂ����̂ł����߂�Ȃ��A�ƌ����B�������肪�ӂ��܂��ׂ��J���Ď��̊Ԃ�����Ƒ傫�Ȑԋ����Q�Ă���̂������B�w���{�̖��b�x
���@���̏��̎�A�ԋ��Ƃ́A�����̍����`�o������ɏG�t�𗊂�ɂ��̎R�����������A�����w�������ꓪ�̋����A�ɂ킩�ɋ��������A���̒��ɗ������݂܂����B���ꂪ���̎�ɂȂ����Ƃ����`�����Ă��܂��B��N�A���Ƃ肪�Â��ƁA�_���͏��̂قƂ�ʼnJ������܂��B ���܂ł��u���S���ǂ́v�ƁA���̂قƂ肩��A����ɂ�т�����ƁA�K�炸�J���ӂ��Ă���Ƃ����Ă���܂��B
��
���͔��c���̐������ނ��Ƃɂ�����B�������A����͒ʏ�́u�v�ł͂Ȃ��B���X�ɏ��̎�̐ԋ��Ɠ����ɕω����čs���Ă��邱�Ƃ������Ă���Ǝv���B���Ȃ킿�A�ԋ��Ɍ����܂ꂽ���_�Ől�Ƃ��ĕ�炷�̂ɕs�s���ȑ̎�(�a��)�ƂȂ��Ă��܂��A�ȍ~���̐������݃k�V���ő������i�ނ��Ƃʼnu�����悤�Ɍ�����v��Ԃ����炭�������A�Ƃ������Ƃ��B
����͒����Ɂu�o�����n�̎ᏼ���҂̖��������������̂ł͂Ȃ����v�Ǝv�킹��B�ᏼ���҂̖��̌����s���̕a���Ƃ͉��炩�̃k�V�Ɍ����܂ꂽ��Ԃ������B�����̔N�́A���̓��́A���̍��A�ɐ��܂ꂽ���̐����������܂���Ȃ��釁�Ƃ�����̈ٗl�ȑ���Ƃ́A���̃k�V���ő������邱�ƂŐ����Ȃ��炦�邱�Ƃ͂ł��邾�낤�A�Ƃ����b�������̂ł͂Ȃ����B���{���̘b�ɑg���܂��O�ɂ́A���҂̖��͉�����̂̂₪�ĉ����Y�ɂƂт���ł��܂��A���҉Ƃ͖v�������A�Ƃ����b�������̂ł͂Ȃ����B
���ɔ��c���̐ԋ��̏o���B���߂��狍���k�V�������킯�ł͂Ȃ����Ƃ����Ɍ���Ă���B�`�o�̘A�ꂽ�������ɂƂт���Ńk�V�ƂȂ��Ă���B�����ĉJ����W���Ă���B
����͋������V�Ƃ���J��̏K�������c���ɂ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킹��B���V�Ƃ��ꂽ���̂��k�V�������͂܂܌�����B�����āA������o�����n�ɑ傫�������B���n�ɂ͋������Ƃ������˂����邱�Ƃ́u�����Y��n�鋍�̘b�v�ɏq�ׂ��B�����ɁA�����_�{�֕������i���D�㋍��A��Ă����A�Ƃ����ތ^�����邱�Ƃ��q�ׂ��B���̍��i�͋���A��Ă����̂��B���͂�������ϋC�ɂȂ��Ă���̂��B
�����Y�o���̐�́u�O�����v�ƌĂ��B���͂����͌Ñォ�猻��Ɏ���܂ň��́u���̊C��v�Ƃ���Ă������낤�ƍl���Ă���B����A�l���Ă���Ƃ�����肻���������̂��B�o���݂̊Œނ������Ă������ɕ������̂����A���̕��͑D�ނ������邻���ʼn����Y�ɑD���o�����Ƃ�����̂�����ǁA�O�����Ƃ����̂͊댯�������ȁB
���Ɂu�}�g���낵�v�Ƃ����k���������������~����t��́A���l���肩��̔g�ƁA�y�Y���肩��̔g���O�����łԂ���傫�ȎO�p�g���ł��₷���̂������ȁB�����āA����͊e��`���Ƃ����v����B
�u�������̏��v�Ƃ����b�ŐΉ��̏헤������������𓐂ݏo������͂̑�D�_(�ٌc�Ƃ�����)�́A�D�ɏ���ς�ō��l���肩��O�����ւƐi���A�O�����łɂ킩�ɗ����N��A����������M��ƈꂽ�D�_�͏����O�����ɒ��߂��B
�܂��A��~�s�̕����Ɂu�P�{�_�Ёv���������邪�A�����͍��|���ɍU�ߖłڂ����Ƃ������̒n�̈ꑰ�̕P�N�����̂��n�n�Ɠ`���B���̍ہA�͂���E�����P�N�͏��M�ʼn����Y�ɓ����o�������A�O�����ɂ������������Ƃ���啗�Ɍ�����ꂠ���Ȃ��]�����A����ɒ��Ƃ����B
�����炭�����Y�̃k�V�̐_�Ђ͎O�����Ɍ����A�Ƃ���Ă����̂��B������A���i�͋���D��A��Ă����̂ł͂Ȃ����B�O�����ŗ����N�����狟�V�Ƃ��ċ��߂�A�����������Ƃ������̂ł͂Ȃ����B
���̂悤�ɔ�ׂČ��Ă����ƁA�u�ᏼ���ҁv�̘b�����Ƃ��Ƃ́u���c���̎�v�̂悤�Șb�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���̎��ɏd�v�ȓ_�Ƃ��āA���x�͐ԋ��Ɍ����܂ꂽ�˖�ڂ̖����k�V�����Ă���߂�����Ƃ�����肪����(���́u���S���v�ƁA���_�ւ̐l�g�䋟杂̓T�^�Ɍ���u����E���p�P�v�Ƃ̗ގ���������Î����Ă���)���A���邢�͉����Y���ӂɂ��o�v����u��ւ̉��g�̔������v�������ł���̂�������Ȃ��B
���̓_�͌���u���n�v�ɒ�������b�������Ă��Ȃ��̂ł��Ēu�����A������ɂ��Ă��J��������߂��̈Ⴂ�͂��邪�A�u���̋��V�v�Ƃ����L�[���[�h�c������q���ė��邱�Ƃ́A�o�����n�𒆐S�Ƃ���u�����Y��n�鋍�v�̘b��ǂ݉������߂̂ЂƂ̎��_�ƂȂ邾�낤�B�����Ɂu�ᏼ���ҁv�̘b���u�����Y��n�鋍�v�̘b�ڑ����邽�߂̃R�[�h�͂��ꂵ���Ȃ����낤�Ƃ��l���Ă���B
�܂�A�o�����n�����鋍�̘b�͂��邢�́u�����Y�̃k�V�v�̘b�ɒ������邩������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B����͂��̈�_���w�E���Ė��Ƃ��邪�A���͂����ɂ͓r�����Ȃ��傫�Șb���֘A���ė���\��������B�ȉ��֑��Ƃ��Ă��̃A�E�g���C�����Љ�Ă������B
|
���j�[�P�̘b
��̔��c���̐��k��10�L���قǂ̂Ƃ���ɂ͌��݃_���́u�Β���v�����邪�A���Ă͂����̂�����Ɂu�����v�Ƃ������������������ȁB�����ɑ�֓`��������B
�������̑��
�ɒB�S�Β둺�z���ɁA�����Ƃ�������������ւ������B���l�͎O�N�Ɉ�x��ւ��Ղ�A���������������Ƃ��Ă��Ă����B����N�Β둺���������o���ԂɂȂ������A���ɂ͔N���̖������Ȃ������B�d���Ȃ��������o�������Ă悻���班�����������Ƃ��悤�ƌ��܂�A���ܘY�Ƃ����҂����ɏo���B�~����t�ւƊe�n������Ă��ւ��тɖ��낤�Ƃ����҂͂Ȃ��������A���ɓߐ{��̗t�̖�����N�̂��߁A�l�������邽�߂Ȃ�A�Ɛ\���o���B�t�̎�N(�ē�)���ǂ����̈�����ł��@�v�̋����Ȃ������Ă����̂��B���ƕ��ܘY����������A�t����N���ǂɎ��̎����b���ƁA���ǂ͋����A�����ɐ����̑�ւׂ��Ɨ���A��ď��������B
�Β둺�ł͎��ǂ֑̎ގ��̐\���o�ɋ�����Ԃ��A��ւ̎d�Ԃ�������Ęb���܂Ƃ܂�Ȃ������B����ƈ��ׂɈꓪ�̔��ς�����A���H�̖��{�����ǂ̑O�ɒu�����B�l�X�͐_���܂������ł���Ɗ�сA���ǂ͑�֑ގ��Ɍ������B�������݂ɋ����A�Ղ���s���ƕӂ�͈Èłɕ����A��J���ӂ�A�������ւ����g���������B����Ɠ�H�̔��������̏���щ��A�J���~�݁A�_��������Č����˂����B�����������ǂ�����˂�ƁA�����ɑ�ւ̋}���ł������т��A��ւ͐���ɒ��B
��
���̘b�ł͑�ւ͎��ǂɓ����꒾��ł邪�A�ޘb�ł͔��������Łu���c���ւƓ����悤�Ƃ����v�Ƃ������̂�����B���̓����̉ߒ��ŕs�����Ɉ�����n���ꂽ�Ƃ����@�ؑ�Ƃ�������Β�ɂ͂���B�Ȃ��A���c���ւƓ����悤�Ƃ����̂��B
���̑�ւ͂��Ƃ��Ɣ��c���ɂ���A�����苷�ƂȂ����̂Ő����ւƈڂ��Ă����A�Ƃ����`���������Ă���B���c���A�낤�Ƃ����킯���B�����āA���̓`���ł͂��̑�ւ́u�j�[�P�v�̎����Ƃ���Ă���̂��B
������̏�(�ȁE���Ƃ�)�ł���j�[�P���G���ł��铡���G��(�U����)�ɐS���Ă��܂��B�����āA���ɂ͋j�[�P�͏G���ɏ���̔閧(�e���҂̂��ƁA��_�̎�)��R�炵�Ă��܂��A����͏G���ɓ��������B��A���p����Ă����ƒm�����j�[�P�͔������ɂȂ�G����ǂ����c�c�Ƃ����b������B�ޘb�ٌn�͐r�������̂ŁA�����͑�G�c�ɁB
���ꂪ�����ł͂��̋j�[�P�͂��������G�������c�̓����ŏo������ւ̉��g�ł������(�ɗ��܂�ďG���͑僀�J�f��|��)�ƏG���Ƃ̊Ԃɂł������ł������Ƃ����̂��B�j�[�P�͕��ƒm�炸�G���ɗ����Ă��܂����킯���B�G���ɗ���ꂽ�j�[�P�͔������ɂȂ��ďG����ǂ������ɁA���ʂɉf�鎩���̎p����ւɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�����B�����Đg�𓊂����̂������̔��c���ŁA��ɔ��c���������������̂ŖΒ�̐����Ɉڂ����̂��Ƃ����B
����Ŋ��̒n�͌��݂̍Ⓦ�s���B���̒m�点�����j�[�P�͎��s����˂ł͂�������g�𓊂����Ɠ`����Ă���B���̕���͉����Y�o������͓쐼��30�L���قǂ̂Ƃ��낾�B
�����������A���������Y���ӂƔ��c���E�����ɂ͂���B�o���Ɣ��c���̘b���ׂČ����̂́A�P�Ɂu���Ă���v���炾���ł͂Ȃ��A�����炭�͒����̏���`���E���B�������̓`���𓌎R�������Ɍ��`�����l�X�̓���������̂���Ȃ����A�Ƃ����_���W����B �@ |
|
���u��֑ގ��v�`���@�@�@�����s�э⒬�Β�
|
�Β�ɂ́u��֑ގ��v�̓`�����c���Ă���A�`���ɂ܂��n����j�Ղ��A���ɓ`����Ă��܂��B��ւ́A�Β��̐����Ƃ����Ƃ���ɂ���ł��āA���Q���N�����đ��X���P�����̂Ƃ��ċ�����Ă��܂����B���̂��߁A�ߗׂ̑��X����l�g�䋟��I��ŕ����Ă����Ƃ������Ƃł��B
���v3�N(1192)�A�l�g�䋟������閺���~�����߂ɉ��썑(�������̂���)������Ă����֓�����(�����Ƃ����˂悵)���A�_�̌����ɂ���Ď���������ő�ւ�ގ������ƌ����Ă��܂��B���̂Ƃ����l�̊肢�ɂ���Ă��̒n�ɂƂǂ܂����֓����ǂ��A�������߈Ȍ�\�O��ɂ킽���Ă��̒n�����߂�Β���̏���ƂȂ����Ƃ������Ƃł��B
��ւ͎̑̂O�ɐ藣���A���쉺�̓c���ɁA���𒆂قǂ̗����ɁA������̖����ɖ������A���ꂼ��̏ꏊ�ɁA�c���̌�Ԑ_�ЁA�����̌�Ԑ_�ЁA�����_�Ђ����Ă܂����B��A���A���̏��Ƃ��Ȃ������̂́A���ɕ��ׂ�ΐ����Ԃ��čĂъQ���y�ڂ���������Ȃ��ƕ|�ꂽ���߂������Ƃ����Ă��܂��B
��ւ̓��߂���Ԑ_�Ё@/�@��ւ̔��߂������_�Ё@/�@��ւ̎�߂���Ԑ_��
�����_�ЁA�����_���̌��݂ɂ�萅�v���關���n��̐l�������A���̒n�ɎГa���������A��ւ̔��ߋF�����B��Ԑ_�Ђ��͂��߁A�Β���̎��_�ł�������א_�Ђ⏔�X�̍Ր_�����J���A�����_�ЂƂ��܂����B
���Β�̑�֓`��
��(�킴�킢)�̎n�܂�͕������㒆���A���ł����j���x���ꂽ���ɂ��c�������玩�����������Ă��ꂽ��A����������ꂽ����(�j�[�̑O)�͂��̉��O�����ւƉ������̒n�̐����ɏZ�݂����A�Ђ���������l���ꂵ�߂�悤�ɂȂ�B
�����o�����q����̍��A���镐��(���h�a)���V���~�肽�_��(���{�����������喾�_�Ɏp��ς�������)�������������ő�ւ�ގ����A�ꂵ�ޑ��l�������悤�Ɛi��Ől�g�䋟�ƂȂ蔒��ɘU������(���e)���~���܂łɎ���������B �@ |
|
����א_�Ё@�@�@�����s�э⒬������
|
�ʏ́@�@�k�����_
���Ր_�@�q��_
�@ |
|
���Êِ�(������)�@�@�@�ɒB�s���ڒ�
|
�ِՂ́A�l�����J������A�����͖ܘ_�A�|�c�̒��P�R�A�����A��R�̈ꕔ�܂Ō��������i�̒n�ł���܂��B
�֊ق̎x�� �Êِ�(������)
�d�X���m�̐����̎R�A�o�v�R�̎R�����߂����āu�����فv�Ə̂���A���͌Êف��ӂĂƌĂ�Ă���ِՂł��B�o����ɂ͂��܂��Â���˂��c���Ă���A�Â�����̐����Ƃ����āA�����ŋ߂܂Ŏg�p����Ă���܂����B�ق̖��ƌ��т��ē`����Ă��܂��B
�َ�́A�����֊َ�̊�鐭���̐b�A�����^�Ɠ`�����Ă��܂��B�܂��A���������������̋������Ɛ��肵�Ă���(�M�B��S����)���̂�����܂��B���ẮA�L���삪�������𗬂�A�V�R�̗v�Q���������̂Ƃ݂��܂��B
�@ |
|
�����P�_�Ё@�@�@�o�t�S��F�����ω��R
|
|
�����P�_�Ё@�@�@���킫�s���R���c��
�@ |
|
�����P�_�Ё@�@�@���͎s�\���Гc������
|
����[�n�G���E�Гc���P�_�Ќ�_�n��
�\���n��A�Гc�O�R�n��ɂ��鍂�����P�_�ЂƁA�Гc�����n��ɂ���Гc���P�_�Ђ̂ӂ��̐_�Ђɓ`���A�n��̔n�Y�M�f���鎑���Q�ł���B
��[���ꂽ�G�n�E�n�̎ʐ^�▋�A�n���̋F���W�E�u�W�����𒆐S�ɁA�_�ЎГa���A�Α�����_�n���Ȃǂ��w�肳��Ă���B
���P�_�Ђɂ́A���`�o���֎R�Ő폟�F����s���Ă���ԂɈ��n������ł��܂������A��(��`�̐�)�ɔn���f���Ă����̂ŁA�������K�����ď��P�_�ЂƂ��A���n���J�����Ƃ����`��������A����4�N(1174)�Ɍ��݂̕\���Гc���O�R�ɑJ�����A�_�a�A�_�n�ɁA�����A�Βi�������������Ƃ����B�@ |
|
���j�[�P�@�@�@�ɒB�S�K�ܒ�
|
�́A�����̕U�����G���Ƃ������E���o�̕��m������A���c�̓����̂����Ƃɐ��ޑ�ւ̉��g�̔����ɗ��܂�A�O��R�̑�S����ގ������B�G���Ɣ����͈��̌_������сA�����͋j�[�P�ƂȂ閺���Y�B�j�[�P�͎����̏o����m�邱�ƂȂ��A��ɕ�����̏��ƂȂ����B
����͔j�|�̐����œV�����f���Ă������A����͂��̐����ɏG�������킹���B�������A����͏�ɉe���҂�u���Ă���A�{���̌����������Ȃ������B�����ŏG���͐g���U��A����̉Ɨ��ƂȂ邱�Ƃł��̔閧��T�낤�Ƃ����B
�������ċj�[�P�ƏG���͏o��A�j�[�P�͏G���������̕��ł��邱�Ƃ��m�炸�ɐS���䂩��Ă��܂��B�P���G���ɖ��������˂�Ɓu���͔��c�̔����ł��v�ƏG���͓������Ƃ����B�����āA���ɋj�[�P�͏���̔閧���G���ɋ����Ă��܂����B
�閧���o�����G���͏���̂��Ƃ�����A�G���Ƃ��ď�����ʂ������ƂɂȂ����B����A�j�[�P�͏G������炷�邱�Ǝ~�ݓ�A���c��K�˂Ĕ����Ȃ�l��T���������B���������̂悤�Ȑl������킯���Ȃ��A�q�˂鑺�l���˂�߂ĉ���Ă���Ȃ��Ȃ�B
�A���ɂ݂������̂ŁA�P�͔��c���֍~�萅�����������Ƃ����B����ƁA���ɉf�鎩���̎p����ւƂȂ��Ă��邱�ƂɋC�����B�P�͂��͂⎩���͖��_�ɕς�����A�Ǝv���A���c���͏����������̂ŁA�R�ЂƂ������ɂ��鐛���֍s���A�k�V�ƂȂ����B
��
�ޘb�ł͂܂����c���ɐ��݁A�苷�ɂȂ����̂Ō�ɐ����Ɉڂ����Ƃ�����B���̓_�͒��X�d�v�ŁA�����ɂ́u�����̑�ցv�Ƃ����`��������̂����A���̑�ւ��������܂ɂ��Ƃ������c���֓����悤�Ƃ���B�u�����̑�ցv���܂��j�[�ł���̂��B���āA���̘b���̂��̂́A���낢��ȗv�f�����т��ďo���Ă�����̂ł���A�������肷��̂͂܂������Ɛ�̉ۑ�ƂȂ�B�����ł́A�j�[���u����̕�v�ƌ����`(�u�j�[�O�ٓV�v)�ɑ��A�����ł���ւƂȂ�j�[�Ƃ��������邽�߂Ɉ������B�@ |
|
�����ʐ_�Ё@�@�@�o�t�S�Q�]��
|
�Q�]�w����k��1�q�B���Ắu�����_�Ёv�Ə̂��Ă��āA������Ր_�ɂ��Ă��܂����B����̖��E�@����������J�������Ƃ������Ă��܂����A�n���͕s���ł��B���̎Ђ̎Гa�́A�����܂Łu�y��ω��v�̂��̂ŁA�����_�Ђ͊ω����Ɉ��u����ď�����J���Ă����Ƃ����Ă��āA�����ȍ~�A�u���ʐ_�Ёv�Ə̂��č��Ɏ����Ă���Ƃ̂��Ƃł����B
���y��ω�
���݂̍��ʐ_�Ж{�a�̍���́A�������K�̒��ɏ�����J���Ă���Ƃ����Ă��܂��B�i�q�˂̊Ԃ���`���Ă݂�ƁA�����Ȋω����������܂��B����̖��E�@�����̊ω�����w�����Ă��āA������J�����Ɠ`�����Ă��܂��B
|
|
�����ʐ_�Ё@�@�@���n�s�ؓc
�@ |
|
�����_�� 1�@�@�@�␣�S�V�h�� |
|
�ØV����ɞH�����e�����傪��ɔs�ꂻ�̈ꑰ���邩�ɉ��B�̐������𗊂�ׂ����̒n�_�����ꗈ�������x�����d���ɂߋj�[�̑O�͋t���ɂ��S�炸�������Y����̈�q���Y�݂���ꑰ�傢�Ɋ�т�����R���R�̓�R�𑱂�����������̑��ɂ͊���ꂸ�A�ꑰ�̑���܂Ƃ��ɂȂ������j�[�P��(����Âɒn���݂�)�ɉ��Ď��Q����A�ꑰ�j�[�̑O�̈⌾�ɂ���Y����삵�Č��݂̕���Y�J�Ɏ��邪�R����ȏ�̓����͍���ł��邱�Ƃ���茻�݂̌�畽�ɏZ�ݔ邩�ɍċN�ݖ{�_�Ђ��J�肽��͂��̍��Ȃ�R��ǂ��āX�̕s�R�͂̈��V��Ɍ������̎�����Ȃ��H�ƌ��R�O�X�܁X�e�n�ɕ��U�ڏZ������Ɖ]�ӌ��n�ɂ͌�畽�Ɖ]�ӕ��R�n����Ė�K�ΐH��̔j�Г��o�y����B�`���ɏ����̎��_�Ƃ��Đ��h���ꉓ�����w�ł�l�����ɑ������Ƌ��ɐ���Ȃ�B
|
|
�����_�� 2 |
�������1,000�N�O�A��������̒����A�킢�ɔs�ꂽ������̍ȁA�j�[�P�Ƃ��̈ꑰ�Y�}���ǂ����A�����ɂ��̒n�ɉB��Z�Ɠ`������B�j�[�P�͏���̎q���Y���A�c�}��肪�������P���s�͓�݂̂��c���A�p���������Ƃ���Ă���B���̓�����_�̂Ƃ����J���Ĉȗ��A���_�ЂƌĂ��悤�ɂȂ����B
�Ȃ��A�БO�̃T�����̖͎�����42���A�������͖�3.8m�ŁA����12�N�ɗі쒡������100�����̋��A����I�u�X�̋��l����100�I�v�ɑI�o����Ă���B��߂��B
|
|
�����_�� 3 |
�E�E�E���͕������㒆���A�����傪�킢�ɔs��A�����ɓ���ė������̍ȋj�[�P�ƈꑰ�����̒n�ɉB��Z��ł����Ƃ��������`��������܂��B�j�[�P�͌�ɏ���̑��q����Y(�Ɛb�Ƃ̐�������)���o�Y���܂����A�O�r��ߊς��Ď��Q���Ă��܂��܂��B�c���ꂽ�ꑰ�͍ċN���F�肵�A�������玒������(�C)����_�̂ɂ��Đ_�Ђ��Ղ�܂����B���ꂪ���_�Ђ̋N���ł��B�����ɂ́A�_�Ђ�����邩�̂悤�Ɏ���500�N�̓�{�̃q�o(���̕������w��)�������������A�����̖�ڂ����Ă��܂��E�E�E
�Ր_�͕�����A�Ȃł͂Ȃ��ʐ��ł͈����ł���j�[�P�A�����Ďq���Ɖ]����i�䕽��Y�̎O�l�B�����Ȃ��炱�̋j�[�ɂ��Ă͐獷���ʂ̌����`��������A����̎�_�𑊑��铡���G���ɋ����Ă��܂����Ƃ��]���Ă���B
���������Ƃɂ��Ă͋����ꂽ�A�������蒝�����Ƃ�������A�����҂Ƃ��ď���̑����ɂȂ����Ƃ�����������A�X�Ɍ��_�Ђ̌����`���ł͎��Q�ƂȂ��Ă��邪�A�����m��������Ɏ���ꂽ�A��錧�k���n�S���㒬�A�����s�̈���a�ŏ���̎���m���ē��������A���͂����G���Ɍ������̂��ߎE�Q���ꂽ�ȂǂȂǁA����Y�̑��݂��܂ߐ^�U�̒��͒肩����Ȃ��B
���݁A������J��_�c���_�̖��_�Ղł͋j�[��̉Ƃ͎Q�����֎~����A�����M����l�X����͋j�[�̉ԁA���A�F�ȂǂȂǂ��������Ă���B�]�k�������a51�N��NHK��̓h���}����Ɖ_�Ɠ��ƣ�ł͐X���q���j�[�������Ă���A���܂ŏq�ׂ��������Ɛ����̎p�ŕ`����Ă���B
���̌����`���ł́A����ɔs�ꂽ����̈�}�����̒n�ōċN�݁A���p�̓����_�̂Ƃ����J�����Ƃ��]���邪�A��̋j�[�P���l�A�C�M���X�̗��j�w��E.H.�J�[���q�ׂ�悤�ɢ���j�Ƃ͌��݂Ɖߋ��Ƃ̐s���邱�Ƃ�m��ʑΘb��̊i���ʂ�A���j�̒T���Ƃ͈���ɐs���邱�Ƃ��Ȃ��d�Ƃ������Ȃ���A���̓�͂ǂ��݂Ă��炶��Ȃ��Ċ����Ǝv���̂͋������낤���B�@ |
|
�����R (�ӂ��܂����) 1�@�@�@�␣�S�V�h�� |
|
�ߐ{�A��̖k���Ɉʒu���A�V���N�i�Q�̌Q���n�ƂȂ��Ă��钸�ォ��́A�іL�A����͂��ߔ֒�R�A���c��A�ߐ{���������]�ł��A�^���ɉH����]�ށB�́A��j�����̎R���܂������ۂɌҊԂ��R���ɂԂ������߂ɁA�R������2����Ă��܂����Ƃ����`��������B�R�������360�x�̑�p�m���}���y���ނ��Ƃ��ł���R�ł��B
|
|
�����R 2 |
�]�ˎ���ɏo�ł��ꂽ�J����́w���{���R�}��x�ɂ��ڂ����Â�����̖��R�ł���B���قȑo����̎p�́A�����Ɋo�����鑶�݂ł���B���R�́A���x�Ɛ��x���͒j�x�Ə��x�ƌĂ�e���܂�Ă���B�}�ȓo�艺�肪�A�����钆�������̎R�ł��邪�A�R�������360�x�̓W�]�����i�ł���B�R�[�̓��́A��ꂪ����Ƃ�����Â�����̖����ł���B
���r�ꂽ�ѓ���i�ݓ炪���_�̂̌��_�Ђ̐�ɓo�R��������B������ƌĂ��}�₪�҂��Ă���B�����̓A�X�i����~�Y�i���̎��ётł���B�㕔�ɓo��ɂ�Č����ȃu�i�тɕς��B�u�i���̐悩�玟��ɋ}�ȓo��ƂȂ�B�������ƎR���̒j�x�ł���B�R���ɂ͎O�p�_�������āA360�x�̓W�]���L�����Ă���B�ߐ{�A��A�����X�R�A�唒�X�R�A����x���ˊx�Ȃǂ����߂���B�������珗�x���o�R���Ēn����ƌĂ��}����g�����[�v�ɒ͂܂��č~���B���Ƃ͗ѓ�����ڎw���ĉ���B
|
|
�����R 3 |
���H�R���̓암�Ɉʒu���A�������␣�S�V�h���Ɠ��ÌS�������Ƃɂ܂������l�I�ΎR�ł���B�W��1,544.3m�B�O�p�_�u���R�v�ݒu�B���H���������R�����Ɏw�肳��Ă���B
���R�₩��Ȃ鐬�w�ΎR�A�n��h�[���ł���B�ΎR�����̎�����14���`9���N�O�B�k�k�������ɗ��ꂽ�n�◬�n�`(��R�n��)�����ĂɎc���Ă���B�O�p�_�̂���s�[�N�j�x�̖k����0.5km�ɂ�����̃s�[�N���x(�W��1,504m)�����сA�o�q�̂悤�ȓ����I�ȎR�e�����Ă���B
�R���̓u�i�A�A�X�i���̌����т��c��A�u�������̒��v�L�r�^�L�A�I�I�����Ȃǂ��������Ă���B �@ |
|
���嗋�_��(�����炢����)�@�@�@�ΐ�S�ʐ쑺
|
�������ΐ�S�ʐ쑺�ɒ����B��Ր_���vጐ_(�ق������̂���)�A�嗋�_(�������������̂���)�ȂǗ��_�����B�Њi�͑��Ђɗ�i�B
�V�c�N��(940�N��)�A������̖���E���ׂ������ɋ����ہA���ƈ��̎��_�ł���w�Η��V�_�x�������G��t�߂̗��͌��Ɋ��������̂��͂��܂�B���̌�670�N���J���Ă������̂́A�c���\�l�N(1610�N)�̏H�A�����G��̑�^���ŎГa����ѐ_�������B���N�̌c���\�ܔN�Ɍ��݂̒����n�ł��鏬���̒n�ɑJ������B
�]�ˎ���ɂ́w���_�{�x�̏̍���������Ă����B
���������̌�A�����ɓ���Ɛ_�������߂����z�����B����ɂ��A�ʓ����@�ł������^���@�ʎ���p���ƂȂ�A���Ђ́w�Η��_�Ёx�Ɖ��́B���̌�A������\��N�Ɂw�嗋�_�Ёx�ɉ��́B�����E���E�f���̑�����Ƃ��Đ��h���ꂽ�B
���̌�A�g�����̗��_�l�h�Ƃ��ēd�͉�Ђ╟����`�A�q���ЂȂǗl�X�Ȋ�Ƃ�������h����Ă���Ƃ̂��ƁB
�ʐ쑺�͕�����`�̂��鑺�Ȃ킯�ł����A���̑����vጐ_�○�_����Ր_�Ƃ���_�Ђ�����Ƃ����̂͋����[���ł���ˁB��̌��ւł����`����u�a������Ȃ��悤�ɋʐ쑺��I�̂ł͂Ȃ����Ƃ����悤�ȋ��R�̈�v�c�c�I������������`�̊Ŕ̕����F�͐ԂŁA��`���ɂ͑̂ɐ^���Ԃȃ��C���̓������E���g���}���̑��܂ł���Ƃ����c�c�I�u�vጐ_�͐ԐF�����Ƃ���v�Ƃ��������`��������킯�ŁA����͊��S�ɋʐ쑺�ɉu�a������̂�h�����߂̓S�ǂ̃K�[�h�ł���c�c�I
�vጐ_�ЂƂ��͋������ЂƂ��ł悭�������������ł����A��Ր_�Ƃ����vጐ_���J���Ă���_�Ђ͌����ł͒������C�����܂��B���W�̐_���܂ŏ��F�����Ȃǂɒu���������Ă����ł��傤���ˁB
�����Ă����Е��̌�Ր_�́w�嗋�_�ȂǗ��_�����x�Ƃ����̂́A�Î��L�̒��ŃJ�O�c�`���Y��Ŏ���ł��܂����C�U�i�~������̍��ő̂ɐ��������������̗��_�̂��Ƃ��ȂƁB�C�U�i�~�͎���ɉ���̍��ɗ����C�U�i�M�ɁA�u����Ȃ�I��Ό���Ȃ�I�v�ƔO�����������̂́A�C�U�i�M�͂���j���ăC�U�i�~�̎p�����Ă��܂���ł��ˁB���̎��A�C�U�i�~�̑̂ɂ��v��������A����ɂ�
���F�嗋�_ / ���F�Η��_ / ���F�����_ / �A���F�����_ / ����F�ᗋ�_ / �E��F�y���_ / �����F���_ / �E���F�����_
�Ƃ��������̗��_�������Ă�����ł��ˁB����������C�U�i�M�͋��ꂨ�̂̂��ē����o���Ă��܂��킯�ł��B
����ƃC�U�i�~�͌������B�����c�V�R���Ƃ�������̍��̋S���ɃC�U�i�M��ǂ킹��킯�ł����A�C�U�i�M�͌��ނ��Ă��܂��܂��B����ƍ��x�͑̂ɐ��������Ă��������̗��_�ɉ���̌R���𗦂������ăC�U�i�M��ǂ�������킯�ł��B���ǃC�U�i�M�͓������āA�����Ǎ�̑����u�ĂăC�U�i�~�Ƃ̌��ʐ錾�������ł��ȁB
������(������)�隬
�u�嗋�_�Ёv�̊Ŕ�����A���̍��̓��ɓ���Ɩڂ̑O�̎��̖����X���u����隬�v�ł��B�|�т�o���Ă݂�ƁA�M�̒��ɏ隬�炵�����̂���������܂��B���̏�́A�V�c�N�ԁA����̖���E���ׂ�����Ƃ��Ă��܂����B
����隬�̖k���̍���Ɂu�嗋�_�Ёv������܂��B����̖���E���ׂ��A�����G���(�w�����̈����G�엋�쌴)�ɉΗ��V�_(�����̎��_)���������܂����B�c���̂���A���Ђ͑�^���̂��ߎГa���������A���݂̂��̒n�ɑJ�{���ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B�u�����̗��_���܁v�Ƃ��āA�����̐l�����ɐ��h���W�߂Ă��܂��B����ɁA�V�c�̗��̂̂��A���ׂ�͓��n�ɓق�A����ɉ��B��ڎw���O�t���ʂɓ������Ƃ������Ă��܂��B�w�t��L�x�Ɂs����̒폫�킪�����ɓقꂽ�t�Ƃ̋L�q�������A���ꂪ���ׂɕt��ꂽ�Ƃ������Ă��܂��B �@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| ���Ȗ،� |
   �@
�@
|
|
�������s
|
|
�������s
|
���w�x�̖���(�x��)�x
�����s���ł́A�_�c���_������́u��v�A���z�_�Ђ��u��v�A�z�y�_�Ђ��u���v���J���Ă���Ƃ����Ă��܂��B���̂悤�ɁA���̂������Ԃ�����A������r�ꂳ���Ȃ�(�M��Ȃ�)�悤�ɂƊ���āA���̂����Ė������邱�Ƃ��u�x�̖���(�܂��͎x���Ƃ�)�v�Ƃ����܂��B���c�R�Ɠ����悤�ɁA���咲���̎��Ƃ��đ����s�������̌{����������܂��B�{�����Ə���̌��т��́A���̎��ӂɂ�����́u�x�̖����v�̓`�������邱�Ƃ�����M���܂��B�{�����͐������Ƃ����Ă����̂��A�G���ɐ�ꂽ����̎A�����ł��̎��̉����ɂ������������Ƃ�����A�O�{���̌{���n�ɏR���Ƃ������Ƃ���A�������{�����ɉ��߂��̂��Ƃ����܂��B�����́A����ł������̏���ԗ�����Ƃ������܂����A���̓`�����{�������ӂɏW�����Ă���Ƃ������Ƃ́A�{���������咲���ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�Q�n�����c�s����͏���̒��܋j�[�̑O�̏o���n�Ƃ����Ă��܂����A���̑���_�Ђ͂����ē����̋{�ƌĂ�A����̓��̂߂��Ƃ���Ƃ����Ă��܂��B�������A�����s�\�����̑��_�Ђ͏���ŖS�̂Ƃ��ɂ��̎肪���ł����Ƃ���Ƃ����A���s��O���̑匴�_�Ђ͂��̕����������Ƃ���Ƃ����܂��B������Z�߂Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B
�w��ԁx���{����(�����s������)
�w���x���q�̌���(�����s���蒬)
�w��x�����_��(�����s�\����)
�w���x���匴�_��(�����s��O��)
�w���x������_��(�Q�n�����c�s����)
�܂��A���c�R�V�����ƌ{���������Ԓ�����ɁA���傪�����E�o�ρE�R���̖{���n�Ƃ����Έ�̉c���ՂƂ����铇�L�R(���܂Ђ���)������܂��B�V�����ƌ{�������狲�����ɂ���悤�ɗ�I�U�����������Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���̏ꍇ�́A����͊��(�Έ�)�ɂ������ƂɂȂ�܂��B����ɁA�{��������̐��k30�x����ɏ��傪���܂ꂽ�Ƃ����L�c�ٔ��n�̈�ł��錋��S�Ή������Ή��̏������������܂��B
|
�����_�Ё@�@�@�����s�\����
�������n��̖k���ɂ���܂��B�V�c�N�ԁA�G��������Ǔ��F��̂��߂Ɍ��������Ƃ����A���傪�s�������Ƃ��ɂ��̎肪���ł����̂��J�����Ƃ����`��������܂��B�����̈ē��ɂ́A���̂悤�ɋL����Ă��܂����B�s�Ր_�͓V�̊�ˊJ���̐_�b�ŗL���ȓV��͒j���ŁA�l�Ԃ̎�̐_�l�Ƃ��đ��M���A���a�ގ҂܂��͎�̏�B���肤�҂̋F��_�ł���A��̌^��`�����G�n���[����l�������B�Ƃ��낪�A�܂��ʂɂ��̍����炩�A���̍Ր_�͕�����ł���Ƃ��āA���̏��傪�����G���ɎE�Q���ꂽ�̂́A�j�[�P���G���ɏ���̋��ꏊ���w�����ċ��������炾�Ɠ`�����A���̌�A���_�Ђ̓G�͋j�[�P�ł���Ƃ������Ƃ���A���̐_�Ђ̂���V���~���ł́A�j�[�̂��ׂĂ����炢�A���Ƃ��Β����̕��ɂ�����܂Ŏg�p���Ȃ��K��������Ƃ����Ă���B�t
���匴�_�Ё@�@�@�����s��O��
�_�Ђ́A�R�鍑(���s�{)���P�S�̑匴��_�Ђ̎l���̑�_�����������̂��N���Ƃ����A������̕������ł����Ƃ����`��������A�����̕a�C����Y�ɗ쌱���炽���Ƃ����M������Ƃ̂��Ƃł����B���̂��Ƃ́A�����̐_�y�a�̐����ɏڂ����L����Ă��܂����B
���q�̌����@�@�@�����s���蒬����J
���傪�łт��Ƃ��A���̌�(��)�����Ă��āA������J�����Ƃ����Ă��܂��B�q�̌����͑��̐_�l���Ƃ������ƂŁA�K�̉��ɂ͑��܂������݂邵�Ă���܂����B
���n���@�@�@�@�����s�S����
�n���@�́A�����������w�̓�Ɉʒu���܂��B�n���@�̖k50m�̂Ƃ���ɂ����n�̒����ɂ���Â��ܗ֓��́A�������̒n���̌��͎҂ł�������~���Y�̂��悾�Ɠ`�����Ă��܂��B���̌�~���Y�́A����̒�E��~�O�Y�̂��Ƃ��w���Ă���Ƃ����܂��B�ꎚ�������������̂́A���l��݂��ĕ��������Ȃ������Ƃ����܂��B
�����_�_�Ё@�@�@�����s�Β�
���̐_�Ђ́A���ѐ������̑��������ɕ���ł���܂��B�����̈ē��R���ɂ́A���̂悤�ɋL����Ă��܂����B �s���쓂��R���A����瓡�����Y(�G���̕�)�����̂������ɂ��A��ϔN��(859-876)�ɑn�������Ɠ`�����Ă��܂��B�܂��u�Ȗ،��_�Ў��v�ɂ��A���a�V�c�̒��11�N(869)�A�E��b������o���A���Β��ɏ�ЁA5���ڂɉ��Ђ菊�Ƃ��đn�������Ƃ����Ă��܂��B������̗��ɕ���F�萬�A�ɂ��A�����A���c���S�̑�����ƂȂ�A�����V���ƌĂ�L�����h���W�߁A����⍑�{����̎Q�q���s��ꂽ�Ɠ`�����܂��B�t
�����ʉ@�@�@�@�����s�t����
���ʉ@�͓V�c�N��(938�`946)�̂���A�����������C��l�ɂ���ĊJ����܂����B�����̃J���͎��Ŗ�̑O�̈�i�������肠�������Ƃ���ɗ����Ă��܂��B�����͈�i�Ƒ����Ȃ�A�����肪���B���Ă���l�q���悭�킩��܂��B
���{�����@�@�@�����s������������
1,100�N�ȏ���́A��b��l�ɂ���ĊJ�n���ꂽ�����ŁA�^�������̑�{�R�ł��B���߂͐������Ƃ����܂������A�V�c�̗�(939�`940)�̍ہA������������Ƃ��납�璺���ɂ��{�����Ɖ��߂��Ƃ����܂��B�w�{�����̓`���x �����傪����ɔw�������N�������̂��V�c2�N�̂��ƁB���N�A�����G�����V�c�̖��ɂ���ď���Ɛ킢�܂��B���̂Ƃ��������̏�S�@��͏G���̏������F�肵�A�@�͂ŏ����|���悤�ɖ������A�y�ł�����������̎�������ĘA���A��F�葱���܂����B�Ƃ��낪8���ځA�@��͂Ƃ��Ƃ������Ă��܂��܂����B����Ɩ��̒��ŁA3�{���̌{�����܂݂�̕�����̎�݂��Ă���ł͂���܂��B�@�{�̏����Ńn�b�Ɩڂ��o�܂��ƁA�y���̎�ɂ͌{�̑��Ղ�3�A�͂�����ƕt���Ă��܂����B�����āA17���ڂ̖����̓��A�G��������������܂����B�������́A���̂��Ƃ���u�{�����v�Ɖ��߂܂����B�Ȃ��A���̒n�ɏ����������S�@��̒˂Ƃ�����u����ˁv������Ƃ����̂ł����A�m�F�ł��܂���ł����B �@
���ՏƎ��@�@�@�����s���x��
�V�c�N�ԁA���咲���̋F�����s�����Ƃ����B
�@
���O��@�@�@�@�����s�ʎ�
�����ɓ����G���̖���̓����s���ɌW��u�����s���̐Γ��v������܂��B |
 �@ �@
 |
|
�����_�� 1�@�@�@�����s�\���� |
�w��̗͂������������x�w�������ɏ�����悤�Ɂx�w���̋Z�p��������悤�Ɂx�w��̕a�C������܂��悤�Ɂx�c���̐_�Ђ͎�̐_�l�ł��B�����āA�肢�����������炨��Ƃ��āw���x��w��`�x�̊G�n��[�߂܂��B
���_�Ђ̓`���@/�@�V�c�̗�(�Ă傤�̂��A939�N�`940�N)�ŁA������(������̂܂�����)�������G��(�ӂ����̂Ђł���)�ɓ������ꂽ���A�ܑ̂��o���o���ɂȂ��Ċe�n�ɒė����܂����B���̎������Ă����w��x���܂����̂����_�Ђ��Ƃ����Ă��܂��B����Ɋւ���`���́A�ق��ɂ��������́w�{����(����������)�x�A��O���́w�匴�_��(�����͂炶��)�x�A���蒬�́w�q�̌���(�˂̂���)�x�Ȃǂ�����܂��B
��Ր_�@�V��͒j��(�A�}�m�^�a�J���I�m�~�R�g)�@/�@ �V��͒j���́A�V�Ƒ�_���V��˂ɉB�ꂽ�Ƃ��A��˂�͂Â��ŊJ�����_�l�ł��B
|
|
�����_�� 2�@ |
��̕a��Ɗw�|��B
���̐_�Ђ̍Ր_�́A�V�̊�ˊJ���̐_�b�ŗL���ȓV��͒j��(���߂̂������炨�݂̂���)�ł��B���̌̎�����l�X�͐l�Ԃ̐_�Ƃ��đ��M���āA��̗́A��̋Z�p����̐_�l�Ƃ��Ă��Q�肷��l�������̂������ł��B�Ƃ��낪�A���̍����炩�A�Ր_�͕�����(������̂܂�����)�ł���Ƃ�����悤�ɂȂ�܂����B�V�c�̗�(�Ă傤�̂��A939�N�`940�N)�ŁA�����傪�����G��(�ӂ����̂Ђł���)�ɓ������ꂽ���A�ܑ̂��o���o���ɂȂ��Ċe�n�ɒė����A�����Ă���������̎���J�����̂����_�Ђ��Ƃ����Ă��邩��ł��B
�Ȃ��Ր_���Ƃ�����l��2�l����̂ł��傤�B���y�O�d�����^�ɂ��ƁA������͏����̂��߂ɒ���ɖd�����N���������m�ł������̂ŁA�����͎��������̂��߂ɎE���ꂽ�ƍl���A���_�Ђ��J�������A����̖ڂ��떂�������߂ɕ�������Ր_�Ƃ����A�V��͒j����\�ʓI�ȍՐ_�Ƃ����̂��ƍl�����Ă���̂������ł��B�����s�ɂ͑��_�Ђ̑��ɂ��A�������܂��Ă���Ƃ����`�������銒�蒬�́u�q�̌����v�A�܂��A�����~���Ă����Ƃ����`���������O���̢�匴�_�У������܂��B�����s�͎������{����������������˂̒n�ł����A�����ł��镽����̓`��������������Ȃ�ĕs�v�c���Ǝv���܂����B
|
 �@ �@
 |
|
���匴�_�� 1�@�@�@�����s��O�� |
��Ր_�@�V�Z�������E�o�Î喽�E���P�Ɩ��E�䏗�_
������
�R��
�{�Ђ͐l�c��\���i�s�V�c�����{�����������A�H�A��R(�{�Ќ���̑�n)�ɓo��A�O���̖L�ɖ���c������n���ꍑ�ƒ���ׂ̈ɁA�R�鍑(���s)�匴��_�Ђ��������Č��Ă��A�����ȍ~�{�Ђ͍�e���̑�����Ƃ��ĉh�����B�匴�_�Ђ́A�R�鍑(���s�{)���P�S�̑匴��_�Ђ̎l���̑�_�����������̂��N���Ƃ����A������̕������ł����Ƃ����`��������A�����̕a�C����Y�ɗ쌱���炽���Ƃ����M������B
|
|
���匴�_�� 2�@�@ |
�ē��ɂ��Ɓu�i�s�V�c�̌��A���{�����������̋A�H�A���̎Ђ̌���̑�n�ɓo��A�O���̖L���ɖ���c������n���A���ƒ���̂��߂ɎR�鍑(���s)�匴��_�Ђ����������̂��n�܂�Ƃ����܂��B�����ȍ~�͍�e���̑�����Ƃ��ĉh���܂����B�v�Ƃ���A���A�s����ψ���ɂ��Ɓu���̎Ђɂ͏�L�̋N���̑��ɁA������̂��������ł����Ƃ����`�����c��A�����̕a�C����Y�ɗ쌱���炽���Ƃ����M������B�v�ƋL����Ă��܂��B
�R�鍑(���s)�匴��_�Ђ̌�Ր_�Ƃ͌���ꓤ�q���A�ɔg��喽(�S�Î喽)�A�V�V�q�������A������_�̎l���ŁA�����V�c�ɂ�钷�����J�s�ɍۂ��A���������̏��l�ɂ��t���Ђ��R��̒n�Ɋ������ꂽ�̂������ł��B
���A���̑��ɑ����s�ɂ́A����̎肪�������`��������u���_�Ёv�B����̒�̌�~���Y���[���W���Ă���Ƃ�����u��~�_�Ёv�B�������܂��Ă���`��������u�q�̌����v�ȂǏ���ɊW����`������R����悤�ł��B
|
 �@ �@
 |
|
���q�̌����@�@�@�����s���蒬 |
|
�u�q�̌��� (�˂̂���)�v�@�����傪�łт����A������̌�(���邢�͑�)�����Ă��āA������J�����Ƃ����`��������B
|
 �@ �@
 |
|
���n���@�̌ܗ֓��@�@�@�����s�S����
|
|
���(�������)�͂��Ȃ茇���Ă��܂��Ă��܂����A���̂ق��̕����͎c����悭���q����̓������悭�����Ă��܂��B��q�͂Ȃ��A���L���s���ł����A�����ނˌ��`���Ƃǂ߂Ă��銙�q����̌ܗ֓��Ƃ��ċM�d�ł��B���̌ܗ֓��͓����A���̒n���̌��͎҂ł�������~���Y
(����̒�) �̂���Ɠ`�����Ă��܂��B
|
 �@ �@
 �@�����s�� �@�����s�� |
|
�����_�_�Ё@�@�@�����s�Β�
|
���������� �`�� ���_�_��
�`�Д��_�_�Ђ́A���{�������������̓r���A�o�_��Ђ̌�Ր_�����������̂��n���Ɠ`�����Ă��܂��B
���11�N(869�N)�ɐ��a�V�c��������꒺�菊�ƒ�߁A���s�̔���_�ЁA���m�̒Ó��_�Ђ̎O�_�Ђɒ��菊�ƒ�߁A�u�a�ގU�A���ƈ��ׂ��F�点�܂����B
���m3�N(1019�N)����V�c�́A�V���_���ɒ��g������[����h�����Ĉȗ��A���N�ᕼ�g��h������܂����B�܂�����V���y�Ђƒ�߁A�����V�����_���ЂƖ�������܂����B
���\8�N(1695�N)�ɎГa�����z����A�����V�����J��_�ЂƂ��ĐM���W�߂܂����B
����10�N�A�n�ǐ��̔×�������邽�߁A�߂��̓V�_�Ђ̋����ɑJ�����A����22�N�ɎГa�̉��z���Ȃ���܂����B
�������N�A�V�c�䑦�ʋL�O�Ƃ���10�N�̍Ό����|�����z����܂������A����24�N12��9���̖����ɐS�Ȃ��҂̏��Ƃɂ��Ď����Ă��܂��܂����B
���_�_�ЍČ��ɂ�����A�ɐ��_�{(�O�d��)�̎��N�J�{�N(����25�N�E��62��)�̂���A�u�V�Ƒ�_��_�̌�椑��r�䍰�{�v�̖{�a�E���a�ꎮ�Ƃ̈ꕔ�����^����Ƃ����A��ςȂ��������������܂����B��Ђ����̂܂���A�ڒz����邱�Ƃ͋ɂ߂ċH�Ȃ��ƂŁA�V���Ɍ��Ǎr�䍰�{�����J����܂����B
�����āA����29�N12��9���A10����2���ԁA�Ď�����5�N���o�߂��āA�������ꂽ�V�Гa�̏v�H�����s���܂����B
��
869�N(���11�N)���a�V�c���������F�菊�Ƃ��đn������B���s�̔���_�ЁA���m�̒Ó��_�Ђ̎O�_�Ђɒ��菊�ƒ�߁A�u�a�ގU�A���ƈ��ׂ��F�点���B��Ր_�͐{���V�j��(��E������)
939�N(�V�c2�N)�������V�c�̗��B�u������̗��v����̉��̎g�����G�������哢���̂��߁A���_�_�Ђɐ폟�F�肵�A��������B
1019�N(���m2�N)�����~�q�V�_(�w��̐_�l �������^�����J��)�B�������������ƍj������V�c�̋����āA�������^���̗�����̓����̒n�ɏ��߂ĕ��J�����B���m2�N11��25���ɒ��g�Ƃ��Ē�����[�����������A����3�N(1179�N)�܂ŁA���N�ᕼ�g���Q�����ꂽ�B�����~�q�V�_�͓����̓����V�_�̖{�{�ł���A�������瓒���Ɍ䕪�삪�͂���ꂽ�B
1051�N(�i��6�N)/1083�N(�i��3�N)�����������̑O��N�̖�(1051�N)�A��O�N�̖�(1083�N)�Ɍ����`�E���`�Ƃ����_�_�Ђɐ폟���F�肷��B
1084�N(�������N)�������̑c�A���`���������S�E���c�S�Z�\�Z��(�S�Z�\�O�_��)�̑�����ƒ�߂�B�������ɉ����̍ۂɓ��_�ЂɌ䑾������i����B
1695�N(���\8�N)�����V���_�� �Гa���z�̂���A�n������ʂɓޗǁE��������̌ÑK���o�y����B���̗̎� �{�����瓡���@���͋g�˂Ɗ�сA�ÑK����܂̐_���𒒑�������B�ɐ���_�{�E������_�{�E���s��{�����{�E�]�ˌ썑���ɕ��A�c�����������F�菊�̔��_�_�Ђɓ`���A���{�܋��Ə̂���Ă���B
1877�N(����10�N)�n�ǐ��삪�p�ɂɔ×����邽�߁A���ݒn�Ɉړ]�B
2017�N(����29�N)�ɐ��_�{(�O�d��)�̎��N�J�{�N(����25�N�E��62��)�̂���A�u�V�Ƒ�_��_�̌�椑��r�䍰�{�v�̖{�a�E���a�ꎮ�Ƃ̈ꕔ������A�ڒz���ꂽ�B
|
 �@ �@
 �@�����s�ʌ� �@�����s�ʌ� |
|
�������s�̔��_�_��
|
�����s���Ɍ������锪�_�_�Ђ͈ȉ���5�Ђł���B
���_�_��(�₮������) - �����s�Β�1-3776�ɒ����B���_�_�� (�����s�Β�)�ŏq�ׂ�B
���_�_��(�₮������) - �����s����2379-2�ɒ����B���_�_�� (�����s����)�ŏq�ׂ�B
���_�_��(�₮������) - �����s��5-2816�ɒ����B���_�_�� (�����s��)�ŏq�ׂ�B
���_�_��(�₮������) - �����s�c����193�ɒ����B
���_�_��(�₭������) - �����s�\����130�ɒ����B���s�Β��̔��_�_�Ђ��番�J�ɂ��n���B
�����_�_�Ё@�@�@�����s�Β�
��Ր_�@�fᵚj�j��
�Њi���@����
�n���@���11�N(869�N)��
�{�a�̗l���@��������
���_�_��(�₮������)�́A�Ȗ،������s�Β��ɂ���_�ЁB�fᵚj�j������Ր_�Ƃ��A��ȋM���A���F�����A��y����z�J���Ă���B
�Г`�ɂ��ƁA���11�N(869�N)�ɐ��a�V�c�̒���ɂ��fᵚj�j������_���J�����̂��n�܂�Ƃ����B����ŁA���{�����������̍ۂɏo�_��Ђ����������Ƃ����`��������B������̗��̍ۂɂ͓����G�����폟�F�肵�A�O��N�̖�����ь�O�N�̖��̍ۂɂ͌����`�ƌ��`�Ƃ��폟�F�肵�Ă���B�G���͏��哢����ɓ��Ђɐ_�n�Ƒ�������i�������A�����S�ƐV�c�S��_�̂Ƃ��Ċ�i���Ă���B
�܂��A���m3�N(1019�N)���玡��3�N(1179�N)�܂œ��Ђɗᕼ�g���h�����ꂽ�B�������N(1084�N)�ɂ͌��`���ɂ���đ����S�Ɨ��c�S�̑�����Ƃ���Ă���B
1877�N(����10�N)�A�V�_�Ћ����ɎГa���ړ]�����B�ȑO�̒����n�͓n�ǐ���̔×��ɑ������߁A����̓V�_�Ћ����Ɉړ]�����̂ł���B
2012�N(����24�N)12��9���ߑO3��25�����A�o���Гa��S�Ă����B
2015�N(����27�N)2��20���A���_�_�Ђ͓��{�ʋ{�̌�植r�䍰�{���玮�N�J�{�̌Íނ�����Гa���Č����邱�Ƃ\�����B
2017�N(����29�N)12��9���A�Гa�̍Č��ɔ����_�����s��ꂽ�B��椑����V���ɍ��J���ꂽ�B
���_��
���Ђɂ͒��a55�Z���`�A�d��18.7�L���́u�����V���̐_���v���`����Ă���B���\8�N(1695�N)�A�Гa���z�̍ۂɓޗǁA��������̌ÑK���o�y�B���̒n�̗̎�̖{���@���͌ÑK����5�̐_���𒒑������A���̂���4���c��_�{�A�����_�{�A��{�����{�ЁA�썑���ɕ����B�c��1�����Ђɓ`���_���ł��葫���s�w�蕶�����ł��邪�A����24�N�̉Ђɂ��Ď����Ă���B
�����_�_�Ё@�@�@�����s����
��Ր_�@�fᵚj�j���A���c�P��
�Њi���@����
�n���@��i2�N(1705�N)
�{�a�̗l���@����������
���_�_��(�₮������)�́A�Ȗ،������s���ʂɂ���_�ЁB�fᵚj�j���A���c�P�����J��B���Њi�͑��ЁB
��i2�N(1705�N)�ɑn���Ɠ`������B���v3�N(1863�N)�A�Ђ̂��ߎГa���Ď����邪�A���N�Č������B���a4�N(1929�N)�A���s��2���ڂɎГa�c�B��42�N(1967�N)�A�Гa����ʂɈړ]�����B
�����_�_�Ё@�@�@�����s�ʌ�
��Ր_�@�fᵚj�j��
�Њi���@����
�n���@��ϔN��
�{�a�̗l���@��������
���_�_��(�₮������)�́A�Ȗ،������s�ʂɂ���_�ЁB�fᵚj�j�����J��B���Њi�͋��ЁB
�Г`�ɂ��ƁA��ϔN��(859�N�|877�N)�ɓ������Y���Ó��_�Ђ����������̂��n�܂�Ƃ����B�V��14�N(1843�N)�A�{�a�����z�B�吳14�N(1925�N)�A�q�a��V�z�����B����14�N(2002�N)�ɂ͎Ж��������z���Ă���B
|
 �@ �@
 |
|
�����q�R���ʉ@�@�؎��@�@�@�����s�t����
|
�V�c�O�N(940)�ɒ�C��l�ɂ��n��
�~�m��l�A�������㒆���Ɍ��ݒn�̐��̎R���ɖ{�����ċ�
�~����l�A���i�\�Z�N(1639)�Ɍ��ݒn�ɖ{�����Č�
�呸��l�A���۔N��(1716�`1735)�ɎR����
�@�|�@�h�@�^���@�L�R�h
�{���@����ɎO��(����ɔ@���Ƙe���̊ϐ�����F�E������F)
�����ʉ@�̔�@
���q�������`��k������@���ʉ@�̓��̉��z�ɔ����ďo�y�������̂ł��B���Ƃ��Ƌ����Ɍ����Ă������̂��A���炩�̗��R�ňꃖ���ɂ܂Ƃ߂��ďo�y�������̂ƍl�����܂��B���̂悤�ɑ����̔肪�܂Ƃ܂��ďo�y���邱�Ƃ͒������A�N������q���������玺������ɂ����Ă̂��̂��p�����Ă���܂��B�߂��Ɍ{����(����������)������A���ʉ@�͌{�����̉B�����ł������Ƃ̓`�������邱�Ƃ���A�{�����֘A�̑m�═���̋��{���̉\���������A�t�������ӂ̍�����L�͔_���Ɋւ�����̂ƍl�����܂��B
�����ʉ@�̃J��
���� 25.0m�@�ڒʂ� 3.89m�@�J���̑�ŁA�����430�N�Ɛ��肳��A��̑O�̈�i����オ�������ɗ����Ă��܂��B�����͈�i�Ƒ����Ȃ�A�����肪���B���Ă���l�q���悭�킩��܂��B���͍��{���班������悤�ɗ����オ���Ē������A�}�͊��̒��قǂ���l���ɐL�тĂ��܂��B���ł悭�������сA�����̎���ɂ͂�������̎����o�܂��B�R�����鎛�@�ɐ������A�����N����l�X�ɐe���܂�Ă����ł��B
|
 �@ �@
 |
|
���{���� 1�@�@�@�����s������ |
�{����(����������)�́A1100�N�ȏ���́A��b��l�ɂ���ĊJ�n���ꂽ�����ŁA�^�������̑�{�R�ł��B���߂͐�����(������)�Ƃ����܂������A�V�c�̗�(939�N����940�N�܂�)�̍ہA������������Ƃ��납�璺���ɂ��{����(����������)�Ɖ��߂܂����B
���{�����̓`��
�����傪����ɔw�������N�������̂��V�c2�N�̂��Ƃł��B���N�A�����G�����V�c�̖��ɂ���ď���Ɛ킢�܂��B���̂Ƃ��A�������̖@��͏G���̏������F�肵�A�@�͂ŏ����|���悤�ɖ������A�y�ł���������̎�������ĘA���A��F�葱���܂����B�Ƃ��낪8���ځA�@��͂Ƃ��Ƃ������Ă��܂��܂����B����Ɩ��̒��ŁA3�{���̌{�����܂݂�̏���̎�݂��Ă���ł͂���܂��B�@�{�̏����Ńn�b�Ɩڂ��o�܂��ƁA�y���̎�ɂ͌{�̑��Ղ�3�A�͂�����ƕt���Ă��܂����B�����āA17���ڂ̖����̓��A�G������������܂����B�������́A���̂��Ƃ���w�{�����x�ƂȂ�܂����B
���Α��R���V�g��
���~��8��14���A�����ɍs���܂��B�Z�E�̌얀���{�E���S�F��̂̂��A�������̎�ҒB�ɂ���āA�ߑO4���A�z���L�����}��15m�̂����Ɛ�̗]��̞��V��W��486m�̐Α��R�ɒS���g���܂��B�����ĐΑ��{�ɕ�[���A�����ɂ��Ă��鞐�V����҂��o�苣���āA�����������܂��B
|
|
���{���� 2 |
����R�������@�{�����@���N
���n�܂�́u�R�v���琶�܂ꂽ�ꑸ�̐Ε�
���̐́A���͂̎R�X���ˑR�n����N�����ėh�ꓮ���A�ٗl�ȉ����o���͂��߂܂����B�����̌�A���̎R�͐Â܂肩����A��̎R���������܂ł��葱���܂��B�R�������o���n�߂Ď����ځA�R�͋}���ɑ傫���h��A��������ꑸ�̐Ε������܂�܂����B�y�n�ɕ�炷�l�X�͊F�A���̎R���u�R�v�ƌĂ�ŁA���߂Ă���܂����B
���S�N��̑哯�l�N(809�N)�A��������̏����Ɂu�R�v�͗��j�̕\����Ɍ���܂��B�ޗǓ��厛�̒�b(���傤��)��l���A�u�R�v��萶�܂ꂽ���̐Ε����R�̘[�Ɉڂ��A�߉ޔ@�������J�肵�āu���������V�v�Ƃ������������Ă܂����B
�m�����N(851�N)�A��b�R�̉~�m��l(���o��t)�ɂ���āA���̎R���́u����R�v�A�@���́u�������@�v�ƒ�߂��܂����B�����傫���L���A�߉ޓ����n�߂Ƃ������̎��V��R���ЁE�@�r�Ȃǂ�����ꂽ�����ƂŁA�����̍\���������܂����B
��������̗��Ɓu�{�����v�̒a��
�V�c��N(939�N�E�������㏉��)�A������(��t���k��)�Ő��͂��g�債�Ă��������傪�Ⓦ�S�����������K�͂Ȕ������N�����A����ɔ�����|���܂����B�鐝�V�c�̖����A����̉��̎g�E�����G���́A���O��R�𗦂��Ă��̓����Ɍ������܂����B�������A�����A�������ւ�������̌R���͋���ŁA�G���̓����R�͋ꋫ�ɗ�������܂��B�G���̌�����������̏�T�@��(��G�Ƃ�)�́A����ɂ���ď��咲���̖@���C���鎖�ɂȂ�܂����B
�ܑ呸���J��A���̑O�Ɍ얀�d��z���A�����s�������d�ɂ́A�y�ł���������̎�������A�S�l�̑m���]���ď\�����ԁA��T�@��(��G�Ƃ�)�͒����킸�A�C�@�𑱂��܂����B
����̓��A�������ɔ��ʂĂ��@���C�ɏP��ꂤ�Ƃ��Ƃ��Ă���ƁA�O�{���̂ɂ�Ƃ肪�A���ɂ܂݂ꂽ����̎�܂��āA���炩�ɂƂ��̐��������閲�����܂����B�͂��Ƃ��ɂ��������@�d�������ƁA�y��̎O�J���ɎO�p�ɂɂ�Ƃ�̑��Ղ����Ă��܂��B�@��́u�����͐��������v�ƁA�Ȃ�����S�ɏC�@�𑱂��܂����B����ƍ��x�͎��E���̓��q���ǂ�����Ƃ��Ȃ�����āu���A�G�������������v�ƍ��������Ǝv���ƁA�����܂����̎p�������Č����Ȃ��Ȃ�܂����B�������̒ʂ�A���̂Ƃ�����͓����ꂽ�̂ł����B
�₪�ďG���͏���̎𐢑����Ɏ����A��A�폟�̂���Q���������A�����ɗp�����y������낦�āA���s�̒���ɕ��܂����B���̗쌱�ɂ��A�������́u�{�����v�Ɖ��߂��A����E��|���͂��߁A�ܑ喾�����E���E�܂�Ȃǂ����삩�牺������܂����B
�����ɂ̕���������A�����Ė����֓`����
�������N(1243�N�E���q���㒆��)�A�㍵��V�c�����|��������A�{�����͍c�q�a���̂��F����������A�ܑ喾���̊G��(�Ȗ،��w�蕶����)�Ƒ品�͉���(���d�v������)����������܂����B���̂��F���̗쌱�ɂ��A�c�q����(��[���V�c)�������܂�ɂȂ�܂����B
�O���O�N(1263�N)�ɁA������(�q�����a)�̔���ŁA���`��(�f�����J��`���̎q)���̂��߁A����(���d�v������)�������܂����B
���i�Z�N(1269�N)�A�����t�����V����(���݂傤)��l�����̎��Ɍ}�����܂����B����܂ł͓V��E�^�����т̂����ł������{�����́A���̎�����^���@�ƂȂ�A����R����`������^���@���җ��̑S�����{�R�Ƃ��Ė��@��C�̓���ƂȂ�܂����B�S�����́A�R���ɓ�\�l�@�E�l�\���m�[�������A�S���ɎO�S�Z�\�]�̖������������Ɠ`�����Ă��܂��B
�V����\��N(1553�N�E����������)�A�퍑����̑����̒��Ō{�����͕��ɂ�����A���g����������̓��ɂ͂��ׂďĎ����܂����B���݂̖{���͍]�ˎ��㒆���̐����O�N(1713�N)�Ɍ����A�얀��(�ܑ呸��)�͋��ۏ\���N(1732�N)�Ɍ������ꂽ���̂ł��B
���ꂩ�猻�݂܂ŁA����������̈ڂ�ς��ɂ����Ȃ�����A�J�n���S�N�̖@���͐₦�邱�ƂȂ��A���ɁA�ϐ����l�̖@��������������āA���ɂ̕����������Ă���܂��B
|
|
���{���� 3 |
����R�{�����͓Ȗ،������s�������ɋ������\���Ă���^���@�L�R�h�̎��@�ł��B�{�����̑n���͕������㏉���̑哯4�N(809)�A���厛(�ޗnj��ޗǎs�G�i��)�̒�b��l���J�R�����̂��n�܂�Ɠ`�����Ă��܂��B�����͐����R(�W���F259��)�̒���(���̌E)�ɂ���܂������m�����N(851)�ɂ͎��o��t�~�m(3��V�����A��b�R����̍��m)�����ݒn�ɋ������ڂ������̓��F����������Ȃǐs�͂�s�����V��@�̎��@�Ƃ��Đ������܂����B�V�c2�N(939)�̕�����̗��̍ہA�����G��(�c������ �U����)���폟�F��ׁ̈A�����̖@��Ɛ}��A����̓y�l�`���˂��Ƃ��Ė@�͂��{�����Ƃ��떾���ɓy�l�`�ɂ͌{�̑��Ղ�3�t�����Ă��܂����B������A�G���������ɔO�萬�A�����ׁA�{�̑��Ղ��g���ƌ�萢�������V����{�����ɉ��̂��A����ɁA���̌��ɂ��V�c�̒��莛�ƂȂ荮�����D���E��䶗��}�Ȃǂ������Ă��܂��B
���q����̕��i�N��(1264�`1275�N)�ɉ����t���̎��ҏ�l�������ċ��A���̍ہA�^���@�ɉ��@����Ǝ��җ��̑��{�R�Ƃ��Ď��^�͗������Ő����ɂ͎R����24�@�A48�m�[�A�S����310�]�̖�����i����������ɂ��f�����ƂƂ��ɒ߉������{(�_�ސ쌧���q�s)�̕ʓ��ƂȂ�܂����B�V��12�N(1553)�ɏ㐙���M�̕��ɂ�葽���̓��F�A����A�L�^�Ȃǂ��Ď����ꎞ���ނ��܂������V��19�N(1591)�ɓ���ƍN�ɂ���čČ�����Ă��܂��B���݂̌{�������g��͐؍ȁA�����畘���A��Ԉ�ˁA�l�r��`���A�㐙���M�̕��ΈȑO�Ɍ��Ă�ꂽ�B�ꌚ���Ő��a�N��(1312�`1316�N)�Ɍ��Ă�ꂽ(�`)���q���㖖���̌Ì��z���Ƃ��ċM�d�Ȃ��Ƃ��珺�a45�N(1970)�ɑ����s�d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B
�{�����̎���ł���u�{������v�͕�������ɐ��삳�ꂽ���̂Œ������A����7�D5�����A�c5�D5�����A��5�D5�����A1�s2��(�{������)�A�Î���`�����Ƃ��ċM�d�Ȃ��Ƃ��珺�a30�N(1955)�ɍ��w��d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�R��͐؍ȁA�V�������A��Ԉ�ˁA����`���B�{�����{���͖ؑ��������āA���ꉮ�A�V�������A�����A���s7�ԁA����1�Ԍ��q�t���A�O�ǂ͐^�Ǒ�������d�グ�B�s�������͖ؑ��������āA���ꉮ�A�V�������A�ȓ���A�Ԍ�3�ԁA����1�Ԍ����j�����q�t���A�O�ǂ͐^�Ǒ�����B�����Ⓦ�O�\�O�ω����F��7�ԎD��(�D���{���F���ϐ�����F�E��r�́F�L���@�{�̑��Ձ@�W�ɂƁ@���ݕ����o��@��ɗ��̎R)�B�R���F����R�B�@���F�������@�B�@�h�F�^���@�L�R�h�B�{���F�߉ޔ@���B |
 �@ �@
 |
|
���ՏƎ��̕@�@�@�����s���x�� |
���� 363cm�@�]�ˎ���@
�{�������Ɍ����Ă��܂��B�O�i�ɐςݏグ�����`���̏�ɁA���ԍ�(�������)�A�~�֎q�A�@�؍��A��b�A�@�؍��A���g(�Ƃ�����)�A�}(����)�A�I�Ղ��d�ˁA���ւ𗧂ĂĂ��܂��B���g�̎l�ʂɂ͋����E�l���̎�q�����݁A��b�ɂّ͑��E(������������)�l���̎�q�����^���肵�Ă���܂��B���ԍ��ɂ́A�u��⸈v�u�ێ��V�������~�ՏƎ����b�ގ��v�̉A����������܂��B�V��7�N(1787)�̑����ł��邱�Ƃ��킩��A���j�I���l���������̂ł��B
|
 �@ �@
 |
|
���O��@�@�@�@�����s�ʎ� |
��{���@����ɔ@��
�@�h�E���`�@��y�@
���{�R�������B�����ɑ������̋A�˂����������B�������N(1239)�w�q�ɂ���ĊJ�n���ꂽ�Ƃ����B���̌�A����̉Ђɂ��������A�Éi�ܔN(1852)�E�̂Ƃ��ɍČ������B���Z�E�̒��ɂ͋��_�d�R�̂悤�ɖ@�R�̋��Ղ�K�˂Ďl���ɕ����A�i�\�N��(1558—1570)�ɉ��O���������ɗ��}���𒆋����A�V����Z�N(1588)�F����(���쌧���̌S�F���Ò�)�̏���J�R�����҂������B
���s�s��������ɂ���^���@���h���{�R��펛�̎q�@�B�i�v�O�N(1115)�A��펛��l�����o�ɂ��n�����ꂽ�B�{�@�́A��펛�ܖ��(�O��@�E�@�E�����@�E�������@�E���ʎ��@)�̒��ł��A��������ȍ~�A���@�傪��펛����ƂȂ邱�Ƃ��ʗ�ƂȂ��Ă���A���S�I���i��L���Ă��邱�Ƃ��m����B���m�E�����̗��ʼn����̋��p�������������A���Z������`���́A�L�b�G�g�̐M�������A���̎x���ɂ��A�ϘO(���̉Ԍ�)�ɍۂ��ĉ������������ꂽ�B���R�����̐����W�߂�����ƕ\���@�͍���Ɏw�肳��Ă���B�܂��A���c��̖{�����ӕ�F���͍��d�v�������w��B���̋`���̕M�ɂȂ�ʖ{�Q�̒�����A�吳�Z�N(1917)�Ɂw�@�R��l�`�L�x(�w���{�x)����������A�����ɐ�����鎖���̌ŗL������ÑԂ������@�R�`�Ƃ��ďd�v������Ă���B
��
�����ɂ͑����s�w�蕶�����u�����s���̐Γ��v�ƒʏ����J�́u���{���F�@���ߊω��}(�c�葐�_�M)�v������܂��B�����s���͓����G���̖���ŁA�V��2�N(1054)�������R�R�ɋ��邵��������v�������s�̒�s�[�̎q�ł��B�s���́A���j���������c�����ĉƓ��p�����ƍj����������܂ŁA���s�̌�̑����S�i�߂��ƍl�����Ă��܂��B
�������s���̐Γ�(�ӂ����䂫���ɂ̂����Ƃ�)
���� 140.0cm�@�@�@��������(����)
2�i�̑�A��b�A�n��(�����)�A����(�������)�A�Η�(�����)�Ə��^�̋�(�����ӂ����)��ςݏd�˂Ă��܂��B
���ւ͗B��ÊD��ő��̂��̂��Â��A����ȊO�͈��R��ł��B�n�ւɂ͐��ʂɁu���P���a�v�A�����ʂɁu�厡�����ߎ�����\�����v�A�E���ʂɁu�����ܘY�������s���v�̖��L���A�����Ă���A�厡���N(1126)7��27���ɖv���������s��(�䂫����)�̕擃�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B
�s���͓����G��(�Ђł���)�̖���ŁA�V��2�N(1054)�������R�R(��傤��������)�ɋ��邵��������v�������s(�����䂫)�̒� �s�[(�䂫�ӂ�)�̎q�ł��B
�u���P���a�v�͎��`�ɂ����O��@�̑��n�ł��鐳�P���܂��͐��P�����Ƃ����s���̑��薼�ł��B
�ȏ�̂��Ƃ���A�����������̑��Ղ���юO��@�̔��˂�m��ォ����M�d�Ȏ����ł��B
�܂��A���ւ����Ƃ͂����A���̖��L���畽���������Ɛ��肳���ܗ֓��̈ꕔ���������邱�Ƃ��M�d�ł��B |
|
������s |
|
������s
|
���x�U�R�_�Ё@�@�@���������`��
�����G��(�U����)�����c�̓����ŕS����ގ����āA���_���瑡��ꂽ�Ă̕U�́A��ɂȂ��āA�G���̉Ɨ��B���t���ɂ������A�����珬���ȑƂ������A���ꂩ������Ă͏o�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����Ă��܂��B���̎��̑ƂƕU���A���̐_�Ђ̌�_�̂��Ƃ����Ă��܂��B�Ȃ��A�G���͍���s�̓���R�_�Ђ��J���Ă��܂��B
�����{�_�Ё@�@�@����������g
�_�Ђ́A�V�c��N(939)�A�����G��������Ǔ��̂��߂Ɍ��������Ƃ����Ă��܂��B
�����y(�A�h)�R�隬�@�@�@����������g
�����@�̗���̎R���u�A�h�R�v�ł��B���̎R�́A�u���y�R�隬�v�ł�����܂��B�V�c�N�ԁA���ˑ��Y���傪���Z���Ă��āA�V�c�̗��̂Ƃ�������ɑ������Ƃ����Ă��܂��B
�����ΐ_�Ё@�@�@���������L��
�V�c��N(939)�A�����G��������Ǔ��̂��߂Ɍ��������Ƃ����Ă��܂��B
���萬���@�@�@������������
�����G���̊J��ŏG���̕�����߂Ɍ��������Ƃ����Ă��܂��B�܂��A�w�ȁu���̖v�ŗL���ȍ��쌹���q��퐢�̕悪����܂��B
�����h��_�АՁ@�@�@���������R��
�����w����H�R��ɉ˂���V�_����n��Ɓu�������l�L�O��v������܂��B���̍���̓��ɓ���Ɓu���h��v�̐Δ肪����܂��B���̔�̗���Ɂu���h��_�Ёv���������Ǝv���܂��B���̎Ђ͍��͍X�n�ł����A�����G���������ɂ���Č��������Ƃ����Ă��܂��B
�����R�_�Ё@�@�@���c�������c
�_�Ђ́A�����G�������|�̌����_�Ђ��番������������Ɠ`�����Ă��܂��B
�����Εʗ��_�Ё@�@�@���c�������c
�_�Ђ́A�V�c�N�ԂɏG�����Č������Ƃ����Ă��܂��B
�����Εʗ��_�Ё@�@�@���c�����R�z
���Εʗ��_�Ђ͑��c�ƎR�z�̓�ӏ��ɂ���܂��B�R�z�ɂ��邱�̐_�Ђ��A�V�c�N�ԂɏG�����Č������Ƃ����Ă��܂��B
���{�����@�@�@���c�����R�z
�G���̋��ق́A���̎��t�߂̎R�z�̒n(�c���{�h)�ɂ������Ƃ����Ă��܂��B�]�c���E�����������Ƃ��Ċ֓��ɉ��������̊ق́A����s�̍����(��R����)�ł������A�c���E�L��̍��ɂ��̒n�Ɉڂ����Ǝv���܂��B
����r�ˈ�א_�Ё@�@�@���c�����c��
�_�Ђ́A�G�������������֓��Ј�ׂ̈�ЂŁA���吪���̐��A���F�����Ƃ����Ă��܂��B
���������@�@�@���c�����g��
���ɁA�G���v�Ȃ̈ʔv������Ƃ����Ă��܂��B���Ɛ����邪�������Ƃ���ł��B
���G���̕�(�G��������)�@�@�@���c�����V�g��
�g���w�̐���200m�Ɂu�G���̕�v������܂��B���̒n�̉~��(�������Õ�)���G���̕�Ƃ��Đ��߂āA������J���Ă��܂��B���Â��̒n�ɓ������Ƃ������������āA�p������ς�Œ˂Ƃ��A����ɕ��̑���K�̕~�ɂ��āu�c�������v�Ƃ����J�����Ƃ����܂��B���̒n�́u�c���v�́A�U�����́u�U�v�ɒʂ��܂��B�G���̖v�N�́A�u�����N(991)�㌎�v�ƂȂ��Ă��܂��B
���c�������_�Ё@�@�@���c�����V�g��
�G��������ׂ̗ɏ������K������܂��B�Ր_�͏G���B���Ƃ͏G��������̏�ɂ������̂ł����A������ɑJ���ꂽ�Ƃ����܂��B
�����É��_��(���É��隬)�@�@�@���c�����Ȗ{
�Ȗ{���w�Z�̓�500m�Ɂu���É��_�Ёv������܂��B���Ƃ͓���R�ɂ������_�Ђ��A�����ɑJ����܂����B���̒n�ɍ��É��邪����A�G��������ɂ��̎Ђ����������Ƃ����܂��B
���𗈖�̊Z�@�@�@���c�����Ȗ{
�G��������Ɛ�����Ƃ��A�Z�Ɉ�{�̖�������炸�������B�����ł��̊Z���u�𗈖�̊Z�v�Ə̂����Ƃ����B���̊Z�͂��Ă��̒n�́u���Ό����v�̌�_�̂ł������A���͓���R�_�Ђɂ���Ƃ����܂��B
������R�_�Ё@�@�@���c�����E����s���E
����R�̎R���t�߂Ɂu����R�_�Ёv������܂��B���̐_�Ђ́A�G���̖{���n�E����R�R���Ɍ����G���̗���J��Ƃ����܂��B�Ȗ{�̒n����u�𗈖�̊Z�v��J���d�ĕۑ�����Ă���Ƃ����܂��B����R�隬�̖{�ېՂɌ����Ă��܂��B
������R�隬�@�@�@���c�����E����s���E
�V�c�O�N�A�G�����z�邵�܂����B�Ȃ��A�G���ȍ~�Z��ɂ킽�鋏��Ƃ����Ă��܂����A��̍��쎁���v�Q��Ƃ��đ�X����Ƃ����Ƃ����܂��B�����䂩��̒��߂��悩�����ł��B
���H���R�_�Ё@�@�@����s�쌴��
�_�Ђ͓����G�����n�������Ƃ����A�_�Ђ���������Ő����ɂ���u���H���R�v(��R)�́A����R��̉B��邾�Ɓw�c�������x�ɋL����Ă��܂��B�����̍g�t�͑f���炵���A���̎����ɂ͑����̊ό��q��������Ƃ����܂��B
���H�R�隬�@�@�@����s�쌴��
�H�R�ւ̓o�R����o��܂��B�R���ɂ͓���K������A�u�H�R�隬�v�̐V��������������܂����B�����ɂ́A�w���̏�͓���R��̖k�̎��Ƃ��āA�G�����z�邵�G���̒�E�i���炪���Z�����x�Ƃ���܂����B�܂��̖����u�E��v�Ƃ������܂��B
���O�R�_�Ё@�@�@����s�D�z��
�V�c�ܔN(942)�G���̑n���Ƃ����Ă��܂��B
����{�_�Ё@�@�@����s�D�z��
�V�c4�N(941)�n���̌ÎЂŁA�G�������������Ƃ����Ă���A�k�L����(�������q�̕��ł���p���V�c�̂��Ƃł�)�����J�肵�Ă��܂��B�������q���J���Ă��鑾�q�a������A�ʏ́A���q�l�Ƃ������Ă��܂��B
����R�Ԃ�@�@�@���c�����o����
�o�����ٓV�r�̗���̌�R(��R)�t�߂��u��R�Ԃ�v�Ƃ����܂��B�G�����G�ɐ�R�̕����w�������܂������A�R���œ��������������Ԃ����ƂɂȂ����̂ŁA�����Ă��悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B
�����g�_�Ё@�@�@����s�Ԍ���
�G�����Č������Ƃ����Ă��܂��B
�����{�_�Ё@�@�@����s�x�Ē�
�G�����鐝�V�c��[���������āA�n�������Ƃ����Ă��܂��B
�����씪���{�@�@�@����s�x�Ē�
������̗��肵�A�����ɔC����ꂽ�����G�����A�R��̍��̒j�R�����{�����i�����Ɠ`�����܂��B�G���̎q���ł��鍲�쎁���A�S�啕���̐_�ЂƂ��Đ��h���܂����B
����梥(���܂�)�_�Ё@�@�@����s�ޗǕ���
��ԎR�̓�[�Ɂu��梥(���܂�)�_�Ёv���ʒu���Ă���A��ԎR�̓o�R���ł�����܂��B���̐_�Ђ́A�V�c��N(946)�ɏG���̑n���Ɠ`�����Ă��܂��B
����ԎR�̉Ղ�@�@�@����s�ޗǕ���
��ԎR�̉Ղ�(7�����̓y�j��)�́A�G��������R�ɏ��z���A���̕t�߈�тɓ������ꑰ���Z�݂��A�ނ�̐��͂��֎����邽�߂ɎR���ʼn����̂��N���肾�Ƃ����A�Ȍ�A���l�͉����a��ǂ��������Ɠ`�����Ă��܂��B��ԎR���ւ��̔N�Ɏ�ꂽ���������w�����グ�A�_�����s�����̂��ɉ�t���܂��B�R���ɐ�Ԑ_�Ђ̏��K������A����s�X�n�̒��߂������ł��B
���I����(�䂵��)�_�Ё@�@�@����s�x�m��
����R��[�Ɂu�I����(�䂵��)�_�Ёv������A����R�_�Ђւ̓����̑咹���̂����E���ɂ���_�Ђł��B���̐_�Ђ́A�V�c5�N(942)�ɏG�������|�������喾�_�������A�s�n���P��(���������܂Ђ߂݂���)�𓂑�R�Ɍ��J�肵�A��X�����傪�Č����E�C�����Ă��܂����B�{�a�O�ǂɂ͒����̎��ɗR������u�|�т̎����v�݂̂��ƂȍʐF�����������{����Ă���A�ʏ́u���_�l�v�ƌĂ�e���܂�Ă��܂��B
���֓��Ј�א_�Ё@�@�@����s��I��
�n���͓V�c5�N(942)�ŁA�G�������͍�������ב喾�_�����̒n�Ɉڂ��A�{�����݂����Ƃ����܂��B������ׂ͑剻2�N(646)�n�����ꂽ���̂ŁA��Ր_�͈ɜQ�����A�fᵚj���A��ȋM���ł���A�����ɉG�X�A���q�A�V���@�A��I��ׂ�4�Ђ��ڂ��ꂽ�̂ŁA������֓��Ј�ב喾�_�Ə̂���悤�ɂȂ�܂����B�c�����ɒ�������L���Ȉ�r�ˈ�א_�ЂȂǂ��A���̐_�Ђ̕��슩�����ꂽ���̂Ƃ����܂��B
���������@�@�@����s��������
�G���̖��E�x�m�P���Ɛb�̔�������ɖ����~���A�G���������������������B���ꂪ���ƂŁA�Ɛb�����͌�����i�݂��ƂƂȂ�A�����͐g���B���ĕx�m�P�͎��E���ĉʂĂ��B�G���͕P�̕����A���̎���n�������Ɠ`�����Ă��܂��B�����̂тႭ����́A��������A���̐_�Ƃ����܂��B
������隬�@�@�@����s�ᏼ��
����w�̂����k���́u��R�����v���u����隬�v�ł��B�����́A�ʖ��u�t������v�Ƃ������A����N(782)�A�G���̑c���E���������̋u�ɏt�����_���Ղ������ƂɗR������Ɠ`�����Ă��܂��B�����́A����9�N(790)�W��60���̏������u�ɏ�ق����Ă��̂��n�܂�ŁA���͂ɂ͂��̏��R�ȊO�S���u���Ȃ��A���n�����̋ɂ߂Ă悢�ꏊ�ł����B�G�����ꎞ���A���قƂ��Ă��܂����B
������Ƃ̓`���@�@�@����s
����Ƃ̓`���ɂ��A�G���͔��H�̖��p���Ă����Ƃ����A����Ƃł͔��H�̖��Ƃ��Ă����Ƃ����Ă��܂��B
���y�@��(��������t)�@�@�@����s����㒬
�t����(����������)�Ƃ��A�����̐l����e���܂�Ă��鎛�B�鐝�V�c�̓V�c���N(944)3���A�ޗǂ̑m�E�G��(�䂤����)��l���J�������ŁA�ŏ��͓��{�̕����ōł��Â���s�Z�@�̖@���@�ɑ����A�������͏t�����R�]�@�։@�y�@���� (�������� ����܂Ă�ڂ�������イ����)�Ƃ����B�����G����������~���̐���ɂ��A����̏t���� (���݂̏�R����)�̒n�ɁA�t�����_�̎Гa�ƂƂ��ɂ��������Ď鐝�V�c �ɐ\���グ���Ƃ���A�V�c�͑�ϊ��u�t�����R�y�@�����v�̒��z���������Ƃ����Ă��܂��B
�������_�Ё@�@�@����s�ԍ⒬
�y�@��(��������t)�̓삷���Ɂu�����_�Ёv������܂��B�V�c�Z�N(943)�A�G����������Ђ����̒n�Ɋ��������Ɠ`�����Ă��܂��B
���ԏ�_�Ё@�@�@����s�A����
���̐_�Ђ́A�A�쏬�w�Z�̏�����ɂ���܂��B�G�������吪�����F�肵�A��C���ʂ������Ƃ��ł����̂ŁA���̎Ђ��Č������Ƃ����܂��B
�������{�E����ˁ@����s��H�c��
���̐_�Ђ͗��ѐ��x�c�w�̓쓌��2.2�����A��H�c���ɒ������Ă��܂��B�R���ɂ��ƕ����吪���̂��߂��̒n�ɂ����G�����A�폟�F��̂��߉F�������{�������������ƂɎn�܂�܂��B�V�c5�N(942)�A�G���������ɕ���ߒ�(����ˌÕ�)�����A�Гa�����āA�����̗��S�����̎ЂƂ��܂����B�_����n��ƒ����̉��ɂ͌��グ�����̌Ö�(�P���L)�����Ă��܂��B
���厭�_�Ё@�@�@����s�D�Ð쒬
�G����������ɔC�����ہA��Ђ����������̂����̎Ђ̎n�܂肾�Ɠ`�����Ă��܂��B
����c�_��(�V���_��)�@����s�n�咬
�����̐Δ�Ⓓ���ɂ��閼�̂ƈႤ�̂ł���(�����̕����͓V������)��c�_�ЂƌĂ�Ă��܂��B�G��������������ɂ�蕐����ƂȂ�A�[�����ӂ��Ă��̎Ђ��C�������Ɠ`�����Ă��܂��B
�����c�_�Ё@�@�@����s�z����
��c�_��(�V���_��)����k��500m�B�ē��ɂ��ƁA�V�c�N��(938�`947)�����G�t�������������Ɠ`�����Ă��܂��B�]�ˎ��㏉���܂ł͓����喾�_�Ƃ��̂���Ă��܂����B �@ |
|
�������@�@�@����s�ᏼ��
|
���썑���h�S����(���݂̓Ȗ،�����s�ᏼ��)�ɒz���ꂽ���{�̏�(���R��)�ł���B�ʖ��t������E�t����E�W��(�������傤)�B
���쎁�͌��X����̖k���ɂ��铂��R������_�Ƃ��Ă����B���쎁�͖k��������{�q���}���Ă������߁A���c�������̍ۂɂ͖ŖS�̊�@���}�����B�����A�ꑰ�̍���[�j���L�b�G�g�Ɏd���Ă������߁A����ɖ[�j������ɏA�����ƂŒf���Ƃꂽ�B���̌�A�[�j�͖L�b���ߐb�ł���x�c������M�g��{�q�Ɍ}���ĉƂ̈��ׂ�}�����B�L�b��������������]�ˏ�̓���ƍN���������邽�߂Ɋ��p���悤�Ɛ}�����B�Ƃ��낪�A�փ����̐킢�ɂ���ē��쐭���������������Ƃɂ���č��쎁���p���ł�������M�g�̗���͔����ƂȂ����B
1602�N(�c��7�N)���쎁�͓���ƍN�̈ӌ����āA�㐙���M�̍U���������̂����R��̓���R���p���Ę[�ɐV�K�ɍ�����z�邵���B����R��̔p�~���R�Ƃ��ẮA�]�ˑ�ΓW�]���A�R��֗ߐ��A�L�Ɖ��̐��Ȃǂ��o����Ă���B���R�͖��炩�ł͂Ȃ����̂́A���쐭���̖{���n�ł���]�˂̋߂��ɖL�b���ɋ߂��喼���R��������Ƃ����쎁�ɂƂ��ĕs�s���ł��������Ƃ����肳���B
�����͏t�����ɂ������y�@���̐Ւn�ɐV�������쎁�̖{���n�ɑ��������ߐ���s�Ƃ��Ēz�邳��A�z��r����1607�N(�c��12�N)�ɂ͏��ł��鍲��M�g������R�邩�獲���Ɉړ]���ď鉺�����������ꂽ���A��������1614�N(�c��19�N)�ɓ˔@���쎁�����Ղ��ꂽ���߂ɁA�킸��14�N�Ŕp��ƂȂ����B
��̌`���͘A�s���̕��R��ŁA������370���E��k��500���̋K�͂�L����A��ՂƂ��Ă͋ȗւ̐Ղ�x�E�y�ۂȂǂ��c����Ă���B�O�x(���x)�͋�搮�����ɂ����ł����B�삩��O�̊ہE��̊ہE�{�ہE�k�o�ۂƕ��сA�e�����͖x�ɂ���Ďd���Ă���B�ł������{�ۂ̕W���͖�56���ł���B
1988�N(���a63�N)����1998�N(����10�N)�ɂ����č���s�ɂ�锭�@�������s���A���݂͍����R�����ƂȂ��Ă���B�܂��A�z��ɂ���Ĉړ]�𖽂���ꂽ�y�@���͍����ł��u��������t�v�̈��̂ōL���m���Ă���B
��
�����Ղ́A�s�w��j�Ղ̕��R��ł��B�쑤����O�̊ہE��̊ہE�{�ہE�k�o�ۂ������I�ɔz�u���ꂽ�A�s���ŁA�ʖ����t������A�t����A�W�P��Ƃ������܂��B���݂́A�s�w��̖����u��R�����v�Ƃ��Ďs���̌e���̏�ƂȂ��Ă��܂��B
���̒n�͌Â����爮�u�Ƃ����A�����G���̑]�c���̉���瓡��������9�N(790)�ɏ��z�����̂��n�܂�Ƃ���܂��B�V�c3�N(940)�ɏG���������哢�����F�肵�ďt�����R�y�@�������������Ɠ`�����܂��B��������܂����A�c��7�N(1614)�A����M�g�ɂ���āA����R�邩�獲���ւ̒z����J�n�����Ƃ���܂��B����ɔ����A�y�@���͌��݂̏ꏊ�Ɉڂ�܂����B
�j���u����ꍑ�v�ɂ��ƁA��̋K�͓͂�����360���[�g���A��k��580���[�g���ƋL����Ă��܂��B�܂��L��ȊO�x����点�Ă����l�q���L����Ă���A���̂��Ƃ͌����ł͂قƂ�NJm�F�ł��܂��A���u�O�x�v�Ƃ����n�����c���Ă��܂��B
���Ă͖������̂܂ܔp��ƂȂ����ƍl�����Ă��������Ղł����A�ߔN�̔��@�����ŁA�������b�Ό����A�Ί_�Ռ��A�Ώ�Ȃǂ̈�\���m�F����A�������ʂɏo�y���Ă��邱�Ƃ���A�������ꂽ��s�ł������ƍl�����Ă��܂��B�܂������̒z��ƂƂ��ɁA��Ղ̖ڏ�̐��R�Ƃ����鉺���Â�����n�߂��Ă���A���ꂪ400�N��̍����̒����݂Ɏp����Ă���̂ł��B
��
�����́u�փP���̐킢�v��ɍ���M�g������R���p���ĎR�[�ɐV���ɒz������ł��B����R��̔p�~���R�Ƃ��ẮA�M�g���L�b�Ɖ��̂ł��������ߓ���Ƃɔz���������߁A�]�ˋߍx�̎R�邪�֗߂���Ă������߁A���邢�͍]�˂ɉЂ����������ۂɂ����������������M�g�ɑ�����ƍN���u����R�邩��]�ˏ�������낷�͉̂������v�ƈꊅ�������߂ȂǁA�������̐�������܂��B���݂͍����R�����ƂȂ��Ă���A�z��ɂ���Ĉړ]�𖽂���ꂽ�y�@���͍����ł��u��������t�v�̈��̂ōL���m���Ă���A���̎R��͍����̏����ڒz�������̂Ɠ`����Ă��܂��B
|
|
���y�@���@�@�@����s�t�����R
|
�Ȗ،�����s�ɂ���V��@�̎��@�ł���B�R���́u�t�����R�v�A�����͏ڂ����́u�t�����R �]�@�։@ �y�@����(������������� �Ă�ڂ���� �������イ����)�v�Ə̂���B��ʂɂ͍�������t�̒ʏ̂Œm����B�N���N�n�ɂ͊֓��n���𒆐S�Ƀe���rCM��������������邽�ߍL���m���Ă���B
�J��(�n����)�͓����G���A�J�R(����Z�E)�͗G���ł���B����t�A��z��t�Ƌ��ɐ��Z�E���u�O��t�v��B�Ȍ�蒅���u�֓��̎O��t�v�̈�ɐ������邱�Ƃ������A���N�̐����ɂ͏��w�̎Q�q�q�œ��키�B�u�֓��̎O��t�v�ɂ͏�L3���̂ق����j�Ȃǂ�������蕡���̎��@�����ɂ������Ă���B
�E�Ȗ،������s-�����R���O��t(�����R�����t)���y�@���{��
�E�Ȗ،������s-���������t
�����j
�����ɂ���c�������̕�V�c7�N(944�N) - �����G�����t����(���̍���隬�̒n)�ɑn���������̂Ɠ`���B
�c��7�N(1602�N) - ����M�g�ɂ���Č��ݒn�Ɉړ]����B�t�����ɍ�����z�����߂ł������B
1913�N(�吳2�N)10��12�� - �����z�Ŏ����̉����ɐs�͂����c�������̖{�����s���B
����{��
���O��t(�nj���l)
���R���Ɩ��
��������t�y�@���́A�Ȗ،�����s�ɂ���֓��O��t�̈�A�V��@�̎��@�ł��B���N�������w�ł͑����̎Q�q�q�œ��키�֓��L���̎��@�ŁA�܂�����E���ʏ����Ȃǂ��L���ŐV�t�ɂ͋F���Ղ��s���A���N�����̖�N�̐l�A�����]�̎Q�q�q���K��܂��B�N���N�n�ɂȂ��TVCM�ȂǂŁu��͍�������t�A��������t�v�Ɨ���Ă�����A�d�Ԃ̒��݂�L���Ȃǂɏo����Ɩڂɂ��邱�Ƃ������Ȃ鎛�@�ł��B
��������t�ł͌��O��t(�nj�)���J���Ă���A���̌��O��t�����X�̋O�Ղ��N������ɂ��傫�Ȃ����v������Ƃ��āA�u�����t�v�Ƃ��ČĂ�A�M�����߂Ă���A�����@�́u��������t�v�Ƃ��Ă̌ď̂Ƃ��Ȃ�A����ɂ����v�̂��鎛�@�Ƃ��ėL���ɂȂ�܂����B
|
|
������̕��l�@/�@���O��t(������)
|
�������v
���
�����O��t���J�鎛�@
��������t(�y�@��)�E��z��t(�쑽�@)�E����t(������)�[�֓��O��t
�[�厛�E��b�R���O��t���Ȃ�
�����t�Ƃ��čL�����߂���V��@�����̑c�nj������f��
���O��t�̃��f���ƂȂ��Ă���̂́A�nj�(��傤����)�Ƃ�����������V��@�����̑c�ł��鍂�m�ŁA�u���t�v�ȂǓƓ��̐M�Ŗ��O����L�������߂��܂����B
����������3���ł��������߁A���O��t�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂��B�ŋ߂͂��܂�ڂɂ���@��Ȃ��Ȃ�܂������A����̂��D�Ŋp��t�A����t�Ƃ�������D����܂��B
���̗nj���l(�����O��t)���݂����̑n�n�҂ł�����ƌ����Ă��܂��B�����ň����邨�݂������u���O��t�݂����v�Ƃ����^�C�v�̂��݂����ł��邨�������{�S���ɑ�������܂��B
���p��t
2�{�̊p�������A���Ɣ�Ƃɑ�����������S�̎p�B�nj���l���S�̎p�ɉ����ĉu�a�_��ǂ����������̑��ł���Ƃ����Ă��܂��B���D�����Ƃ́A��l���u�a�ɂȂ炸�A�܂��a�C�ɜ���Ă����l�X���A�قǂȂ��S�����āA���낵���u�a���A�����܂��ɏ����������Ƃ����Ă��܂��B���̂��D���p��t�Ə̂��āA���N�A�V�����D���ˌ��ɓ\��ƁA�u�a�͂��Ƃ��A���Ă̖�Ђ������A�܂��A�������̑��A���̐S�����҂́A���̌ˌ�����o����o�����Ȃ��Ƃ����A�L���Ђ�܂�܂����B
������t
33�̂̓����̂悤�ȑ�t���ŕ`���ꂽ�p�B���O��t(�nj���l)�͊ω���F�̉��g�Ƃ������Ă���A�ω��͂�����O�����~�����߂�33�̎p�ɉ��g����Ƃ����u�@�،o�v�̐��Ɋ�Â���33�̂̑�t����\�����Ƃ���Ă��܂��B
|
|
�������_�Ё@�@�@����s�ԍ⒬
|
�ԍ⎭���_�Ђ́A�����G�����������_�{���������ēV�c�Z�N(943)�V���R�������̓�����ɕ��J�A������[���j������t���R�ɑJ�������Ƃ����܂��B���i4�N(1627)���n�ɑJ���A����5�N���Ђɗ�i���Ă��܂��B
��
�Ր_�@���䗋��
���a�@���孁�M���A�ɜQ�ߔ����A�L��P��
�����Ё@����_�ЁA�@�D�_�ЁA�H�t�_�ЁA�O���_��
�R���@�V�c6�N(943)�����吪���̒����Ɏ�����_�ɐ폟�F�肵���U����(��̓���)�G�����́A���������߂���A����̏��E�V���R�������̓�����ɓc���Ƃ̌R��_�Ƃ��Ď����{�{����J���A���̌�t���R�ɈڑJ���܂����B�]�ˎ���ɓ���A�c��7�N(1602)�A�G���̖���E����M�g���ɂ��t���R�z�鎞�ɁA�V�����O�C�ɑJ������܂����B���̌㊰�i4�N(1627)�A���ݒn�ɑJ������A�����Ɏ���܂��B�Ȍ�A���̎Ђ𒆐S�Ƃ��đ@�ێY�Ƃ������ƂȂ�A�ԍ⒬�̔��W�Ɍq����܂����B����11�N(1671)�{�Ђ��Č�����A����3�N(1718)����ʎ����喾�_�Ə̂���悤�ɂȂ�A����5�N�Ɍ��Ж��ɉ��̂���A�����ЂƂȂ�܂����B |
|
���ԏ�_�Ё@�@�@����s�A����
|
�A���ԏ�_�Ђ́A�L����F���̑��A�F���������C���і썑�ɋA���̓r���A�i�s�V�c55�N(4���I)�t������W���I���A�F���������J���ւ����Ƃ����܂��B�����哢���ɍۂ��Ă͓����G�������ЂɋF��A���Ђ��Č�����ۂɏ��ԏ�_�Ђ����J�������Ƃ���ԏ�喾�_�ƍ����āA���ԏ�_�Ђɔ䂵�ē��Ђ����̋{�Ə̂����Ƃ����܂��B����9�N���Ђɗ�i�A����42�N�厚�A�쎚��n�꒬�����{�Ȃ�8�Ђ����J���Ă��܂��B
�Ր_�@�F���������A���{����
���a�@���P�Ɩ��A���헧���A棓c�ʖ��A�s�n���P���A���孁�M���A�f���j���A�������^���A��q�����A���c�F���A�L�Ώ~��
�����Ё@���������{�A�_���{�A�����_�ЁA�D�P�_��
��
�A���ԏ�_�Ђ́A�Q�n���O���s�x�m�����̐ԏ�_�Ђ삵���_�Ђł��B�R���ɂ��Ă͕s�ڂł����A�����G������������A���̒n�Ɍ�M�w�̕�����j�[���ꂽ�ƌ����`�����܂��B�܂��A���{���������̋A�r�A���̒n�Ɉ��h�����ꂽ�Ƃ̓`��������܂��B
|
|
���x�U�R�_�Ё@�@�@����s�`����
|
�n���͕�����܂��A����40�N4���Ɏ����_�ЁA���J����_�ЁA����_�Ђ����J���܂����B��Ր_ �͑喼�����A����喽�A�c�S�P�� �A�z�_�͕��P�Ɛ_�A���F�����A�f���j���A���ǖ��A�e���Ɩ��ł��B
��
���J�L�O��B����_�ЂƔ����_�A����R�_�A�b�q��_�A������_�A�O�����_�Ђ��l�\�O�N�ɍ��J�����悤���B��Ր_�͑喼�����Ǝ���喽�A�c�S�P���̎O���ŁA�z�J�_�͕��P�Ɩ��Ə��F�����A�fᵚj���A���Ǒ��A�e���Ɩ��ł���Ƃ̂��ƁB����_�ДV��B�Ր_�͏����F�ߖ��ƕ��P�ƔV���̓ł���A���Â͉��N���Ă����̂œ��J�����Ə̂��B
|
|
�����{�_�Ё@�@�@����s��g��
|
|
�V�c2�N(1947)�����G��������������̎��A�c�_�ɋF���̈��������̂��n�܂�Ƃ����܂��B��Ր_�͓V���������A�z�_�͑fᵚj���A���[�]���A�F�����X�n���A�喼�����A�ʏ̌����l�ł��B
|
|
���L���ՁA���y�R��� 1 |
�L����(�Ƃ悵�낶�傤����)�͖L�㒬�Ɏc���ِՂŁA�ʖ����쌹���q��퐢�ِՂƌĂ�A������110���[�g���A��k��150���[�g���ɂ킽���āA����1.5�`2���[�g���̓y�ۂ������c��܂��B����������ِՂ͈��50�`100���[�g���̋K�͂���ʓI�ł��B�{��Ղ͋K�͂̑傫�Ȃ��̂ł��B���݁A��Փ��ɂ��鐳�_�������قɂ͏퐢�Ƃ��̕�̈ʔv����сA��t�@���ƒn���������u����Ă��܂��B�܂��A�k���ɂ͏퐢�̎��_�Ƃ������z�_�Ђ��܂��Ă��܂��B
�L���Ղ̖k���Ɉʒu���鈢�y�R���(���ǂ�܂��傤����)�́A��g���Ɏc�錘�łȎR��ł��B�W��371���[�g���̎R������́A��g����A�������ʂ���łȂ��A����R���]�߂܂��B�{��Ղ́A���i���N(1206)���ˎ����z�邵���Ƃ���A�i�\2�N(1559)�Ȍ㍲�쎁���g�p���A�c��3�N(1598)�ɂ͓V������(�ق�����)�����邵���Ƃ��`�����Ă��܂��B�R���ɑ��������Ȃǂɑ傫�Ȗx�����J���ŔF�߂��A�ΐς݂��c����Ă��܂��B
���̗���Ղ́A��g��ƏH�R��̍����n�_�t�߂ɗ��n���܂����A���ӂ͓Ȗؖk�����ʂƁA�������ʂւ̕���_�ɂȂ�ꏊ�ł�����܂��B����ՂƂ��A���������������ʂɂ�����v�Ղ̒n�����������ڂ��ʂ������A����ɂ�����k�����_�̏�Ƃ�����ł��傤�B
|
|
�����_����ՁA���y�R��� 2 |
���_�����(�L���ՁA���쌹���q��퐢�ِ�)�A���y�R���
���_����Ղ́A�ʖ��L���ՁA���쌹���q��퐢�ِՂƌĂ�A������110m�A��k��150m�ɘj���āA����1.5�`2m�̓y�ۂ������c��܂��B����������ِՂ͈��50�`100m�̋K�͂���ʓI�ł�����A�K�͂̑傫�ȏ�ق������ƍl�����܂��B���݁A������ɂ��鐳�_�������قɂ͏퐢�Ƃ��̕�̈ʔv�y�сA��t�@���ƒn���������u����Ă��܂��B�܂��A�k���ɂ͏퐢�̎��_�Ƃ������z�_�Ђ��܂��Ă��܂��B
���y�R��Ղ́A���_����Ղ̖k���Ɉʒu���A�R���ɑ����������ɕ����̑傫�Ȗx��A�ΐς݂��c����錘�łȎR��ł��B�W��371m�̎R������́A��g����A�������ʂ���łȂ��A����R���]�߂܂��B�z��́A���i���N(1206)���ˎ��ɂ��Ƃ���A�i�\2�N(1559)�Ȍ㍲�쎁���g�p���A�c��3�N(1598)�ɂ͓V������(�ق�����)�����y�R�ɋ��Z�����Ƃ��`�����Ă��܂��B
���̗���Ղ́A��g��ƏH�R��̍����n�_�t�߂ɗ��n���܂����A���ӂ͓Ȗؖk�����ʂƁA�������ʂւ̕���_�ɂȂ�ꏊ�ł�����܂��B����ՂƂ��A���������������ʂɂ�����v�Ղ̒n�����������ڂ��ʂ������A����ɂ�����k�����_�̏�Ƃ�����ł��傤�B
|
|
���L���A���y�R�� 3 |
�����쌹���q��퐢�̊�
�여����H�R�썶�݂̒i�u��ɖL���͈ʒu����B����113���[�g���A��k259���[�g���̋K�͂��������ِ̊Ղł���B���݁A�ِՂ̑啔���͔��n�ɂȂ��Ă��邪�A���͂ɂ͏��2���[�g���A����5���[�g���A����1.5�`2���[�g���̓y�ۂ��̂�����Ă���B�ِՂ̐����ɂ́A���쌹���q��퐢�̎��_�Ɠ`�������z���_���܂��Ă���B
�܂��A���쑤�ɂ́A�퐢�Ƃ��̕�̈ʔv�A�����Ď��{���̖�t�@���ƒn���������u��������@���������Ƃ����B���݁A�ʔv�ِ͊Փ��ɂ��鐳�_�������قɕۑ�����Ă���B���쌹���q��́A�w�ȁu���{�v�̓o��l���Ƃ��Ēm���Ă���B�w�Ȃł́A���q���{�̎����������k���������������s�r���Ă���r���A���̂��߂Ɍ����q��̉��~�ɓ��̏h�����߂��B���̂Ƃ��A�����q��͑�Ɉ�Ă����̐����āA���������ĂȂ��B�뗎�����g�̏�Ȃ�����A���{�ւ̕ς��ʒ����S�������Ɍ���������q��́A�̂��ɖ��{�̏��W�ɉ����Ċ��q�ւƒy���Q���A�������牶�܂�^����ꂽ�Ƃ����B
���쌹���q��̎��݂ɂ��Ă͏������邯��ǂ��A��ʓI�ɂ͏�썑����(�Q�n������s)�̕��m�Ƃ���Ă���A���͖L���ƒ��ڂ̊W�͂Ȃ��B�Ƃ͂����A���ِ̊Ղ����݂���L�ォ�A�����ł͍��쑑(����s)�ɑ����Ă���A���ɖL����܂ޏH�R��㗬��т��㍲��Ƃ��Ă������ƂƁA�w�ȁu���v�̗��z���A���̒n�ƍ��쌹���q��Ƃ����т����Ƃ݂���B�������ɖL���́A���쑑���x�z�������쎁�̗L�͈ꑰ�ł���m���쎁�̋��ق������ƍl�����A���ӂɂ͒������쎁�Ɋ֘A����j�Ղ��Z���ɕ��z���Ă���B�K�͂̓_�ł��A����y�̉Ƃ̋��قƂ���鐴����(��������)�𗽉킵�A���쑑���ɂ̂���ِՂƂ��Ă͍ő�ł���B
���퐢�̕�ƕ��
���쌹���q��퐢�̕�Ɠ`������̂́A�ِՂ̓�ɗאڂ��铯�s���ؒ��̔~�G�R�萬��(�ՍϏ@)�����̐Γ��ł���B�O��̕擃�̂����A�����č����̔�́A�퐢�̕�̋��{���Ƃ����B�㕔�ƉE�������������Ă��邪�A����86�Z���`�A��61�Z���`�̔�r�I��^�̔�ł���B�ނ͗ΓD�Њ�ŁA�E�e���Ƃ݂��鐨����F�̎펚���̂���A���Ă͈���ɎO�������肾�����Ƃ݂���B���a�l�N(1315)�̔N�������B
�����̕�⸈́A�퐢�̕��Ƃ����B���ւƓ��g���������A����ł�������150�Z���`�𑪂�B���R��ŁA��^�̓��ł���B�����ĉE���́̕A�퐢�̖��̕��Ƃ����B�ÊD��Ō��������������A�킸���ɓ��g�̈ꕔ�Ɗ}�����̂���݂̂����A�ޗႩ�炷��ƈ�O���I�㔼���̂��̂ƍl������B�萬���̑O�g�́A�����R���S�@�@�ؖV(�V��@)�Ə̂��Ă���A���쎁�̐�c�����G���̊J��ŁA�G���̕�̕_���������Ƃ����B����������N��(1249�`56)�ɏ퐢���ՍϏ@�ɉ��@�����āA���쎁��X�̕�ɂ����Ƃ����B
���l�߂̏�E���y�R��
���쑑��여����H�R��Ƒ������k�Ɋт��X���Ƃ���������L��̒n�́A�܂��ɐ�����ʂ̗v�Ղł���A�㍲��̏d�v���_�������B�������Ȃ���A�L��鎩�͕̂���ł���A��������v�Q�̒n�ɐ�n���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̂��߁A�헐�̎�����}����ƁA���̂����ɗ��Ă�����v�Q�A������l�߂̏邪�K�v�ɂȂ��Ă���B�L���̋l�߂̏�̖������͂������̂��A�L���̖k�����@�E�܃L���Ɉʒu���鈢�y�R�邾�����Ƃ݂���B
�A�h�R�́A�W��371���[�g���A�䍂��210���[�g���ŁA�u���y�R�v�u���ˎR�v�Ȃǂ̎������Ă��Ă���B���y�R��́A�V�c�N��(��O���`��l��)�Ɉ��ˑ��Y����̒z��Ɠ`�����邪�A�m�͂Ȃ��B���̌�A����(�㍲��Ƃ�)�A�؎��Ȃǂ̏����ւāA�퍑���㖖���ɂ͍��쎁�̈��V���������N�ԋ��Z�����̂��A�p��ƂȂ����Ƃ����B
�R�[�����ɂ́A����R�����@���@��(�^���@)������B���쎁��X�̋F�菊�ŁA�c���N��(1596�`1615)�ɂ͓V�������B�������Ƃ̓`��������B����R��̔p��̎����́A���̂ɓV�����݂̍��l�͂ɂ�����̂�������Ȃ��B���݁A�A�h�R�ɓo��ɂ́A�����@�O���琼���̔�����o��̂���ʓI�ł���A�����Ă̓o�郋�[�g����͂萼�����炾�����ƍl������B���ɁA�o�郋�[�g�ɂ͎O�̖x�ƐΊ_�̈�\���݂���B�R���̎�s���̖ʐς͋����A
����R��͂����܂Ŕ��̂����̗v�Q�������B
�������獡�{�_��
���y�R��̎R�[�𗬂���g����A�k���ɖ�j�L���قǂ����̂ڂ�����g�n��ɂ́A���쑑�̑����炾�������{�_�Ђ�����B���{�_�Ђ̍Ր_�͓V�Î��������ŁA�����G���������吪���̂��߂ɓV�c�O�N(940)�Ɋ��������Ɠ`������B�Гa���͍̂]�ˎ���̍Č��ɂȂ邪�A�����Ă̑����ȕ��͋C�����܂ɂƂǂ߂Ă���B
�����́A���쑑�̑�����Ƃ��āA���쎁�������߁A�ꑰ�E�Ɛb����̏Z�������̐��h���W�߂Ă����B���ڂ����̂́A���{�_�Ђ���k�ɖ�j�L�����ւ��Ăďo���R���@���莛(�^���@)�����邱�ƂŁA���莛�͏�����l���V���_��O�N(767)�ɊJ�R�����Ƃ����B�����́A�R�x�M�̗������R���J�������Ƃł��m���A����������̊J�R�Ƃ���閞�莛�Ɠ����R���T���͂Ƃ��ɍⓌ�O�O�D���ł��������B�@
�Ⓦ�O�O�D���̐����͈�O���I�O������Ƃ���Ă���A���łɂ��̂���ɂ͈ꎵ�ԎD���̖��莛�ƈꔪ�ԎD���̓����R�͊ω��M�̏���H�Ō���Ă����B�����āA��Z�ԎD���ł����쐅��(�Q�n���a��s)���疞�莛�ɓ������钼�O�ɁA���쑑���̖L���A����R��A���{�_�Ђ̕t�߂�ʉ߂����̂ł���B�܂�A�L��邪���݂���㍲��́A���q����ȗ��̌�ʂ̗v�Ղł���A���A�@���I�ɂ��d�v�ȏꏊ�������B�L���́A���̏㍲����x�z���鋒�_�̖������ʂ����Ă����Ƃ�����B
|
|
�����ΐ_�Ё@�@�@����s�L�㒬 (���E���h�S�������L�㒆��) |
��Ր_�@�卑�喽�@
�z�_�@��龗�_�A�ɜQ�ߊA����喽�A�s�n���P���A��ȒÌ���
�V�c��N(939)�ɕ������j���������G���ɂ���đn������A�V�����N(1,573)�ɍ���@�j�ɂ����C�B�����ܔN(1,872)�ɏ�Ց����ЂƂȂ�A���̌�A�_�Ѝ��J�߂ɂ�薾���l�\��N(1,909)�\���\�Z���ɔ����_�ЂƕۘC�H�_�ЁA���R�_�ЁA�����_�ЁA�����_�Ђ����J�����B
|
|
���萬���@�@�@����s���ؒ�
|
�~�G�R�萬���@�ՍϏ@�������h�@�{��/�߉ޔ@����
�萬���́B��T�N��(770�N)��m�s�q�J�@��̊J�R�ŁA�哯�N��(806�N)�͌��̐��̂قƂ�ɑn������A�V��@�ɑ����Ă��܂����B�V�c�N��(938�N)�����G�����A�R�{�̗����̓��̏�Ɏ������āA�����R�����@�@�ؖV�Ƃ��̂����B�̂ɏG�������J��Ƃ��Ă��܂��B
�i���N��(1381�N)�ƂȂ�B�ÓV�T�t�����J�R�ƂȂ�A�V��@���ՍϏ@�ɉ��@�A�~�G�R�Ə̂����B�O��2�N(1556�N)���Ƃ�蔭�����Ђׁ̈A��������ɋ����B�c��6�N(1601�N)�悤�₭�ċ��ƂȂ邪�A����7�N(1795�N)�ɂ͎��ɂ�莵���������̑��A�Õ����E�ËL�^���͂��ߊ����̓�������������B
�Éi3�N(1850�N)�{���ċ��̍H���N�����A�Éi4�N�v�H�吳4�N(1915�N)��\�ꐢ�`���a���A�{�������A��5�N�������C�s�B
�����̖ؕ���
����̖���̏h���Ə퐢�̌����ɗ��������m(�����k������)��e�Ɍ}������āA�g���Ƃ点�邪�r���ŕ����������Ȃ�A���̂Ƃ��퐢�͗��h�Ȗ~�͂�ɂ������������ׂĒg���Ƃ����Ƃ�������̕���̎�l�����쌹���q��퐢�̕�Ƃ��ėL���ł��B
|
|
�����h�V�_�Ё@�@�@����s�R���� (���E���h�S�c�����厚�R��) |
��Ր_�@�ʗ��_
�z�_�@��龗�_�m���������݂̂��݁n�A��{�����A���g�T����
���썑�̍ݒ������ł����������G��(���ÒJ���V���c������)���얲�ɂ�蕐�^���v�A�̓y�����F��̂��ߊ����B�V�����N1787�Гa�����z�B�R������Ƃ��đ�������Ă����B�G�����������������̐_�Ђ̂ЂƂB
|
|
�����R�_�Ё@�@�@����s���c��
|
|
�i��6�N(1434)�ɑn������A�@���O���_�̈ꒌ�ł���s�n���P����Ր_�ł��B�s�n���P�͔��l�̂ق܂ꍂ���A�ٓV�l�Ɍ����Ă��Ă���_�l�ŁA�C���ʁA��̐_�ł���ƂƂ��ɁA���̌�_���ɂ��q���̎��_�Ƌ���Ă��܂��B�����̐_�Ђ́A�����_�Ђ̌�Ր_���J���Ă���ׁA�̂͌����喾�_�Ɖ]���Ă����̂ł��傤�A���ł��ʏ̖��_�l�ƌĂ�Ă���悤�ł��B
|
|
����Εʗ��_�Ё@�@�@����s���c��
|
�ʏ́@���d�l(�炢�ł�)
���Њi�@����
��Ր_�@��Εʗ���(�����킯�����Â��݂̂���)
�z�_�@�H�H�n��(�ɂɂ��݂̂���)/��Ό��p�g��(���������ʂ݂݂̂���)/�ʈ˕P��(���܂��Ђ߂݂̂���)
�����_�Ё@�Y�א_��(����)�A�@�P�_��(����Ђ�)�A����_��(�₳��)�A�H�t�_��(������)�A����_��(���Ԃ��킳��)�A����_��(��������)�A��Ԑ_��(����)�A�[���X�V���{(�䂤�Ђ���V���{)
���R��
���_�Ђ̌�Ր_�́u��Εʗ��̐_�v�Ɛ\���܂��B���s�̏��̒n�Ɂu���͂�Ԃ�@�킯���R�ɋ{�����āA�V���邱�Ɛ_���肳���v�Ɠǂ܂�A�����̂��A�R�̐_�A�_�Ƃ̐_�Ƃ��ĕ���āA���������A�������A�܍����A�A�V���ו��̐_�Ƃ��Đ��h����Ă܂���܂����B
���_�Ђ͓V�q���N(669)�A�u���̐_���J��A���̓y�n�͕x�M���ÂȂ�ށv�Ƃ̐_��ɂ��A�e��R�̒����ɎГa�����āA��_����Վ����s���Ă܂���܂����B
���̍L��Ȃ��_���ɂ�萳���ܔN(1715)�A�@����|�ɂ�萳��ʂ̐_�K������܂����B
���݂̖{�a�͕��\��N(1761)�̌��z�ŁA���̒����͏�B�ٗт̏Z�l�ē��r���A�r���A���l�̍�ŁA�|�т̎����l�A�e�̉ԁA���ȂǁA�߂ł������������������܂��B
���̌�A���q�̔O��ɂ��A�����l�\�O�N���n�ɑJ�����A�Ɠ����S�A���������A��ʈ��S�Ȃǂ̋F����s���A���N4��15���ɂ͑�Ղ��֍s���āA�����l�N(1739)�V���̌�`�̎��q�����K���s���Ă���܂����B�_�I�ՁA���_�ՁA�n���ՁA�㓏�ՁA�Ԃ̂��P���Ȃǂ��v���Ă���܂��B
�������_�Ђɂ���
�Y�א_��(�q�a����)�@���w�l�̎��_�Ƃ��ČÂ��̂���M�����A�D�w�����̔O��ɂ�蕶���\��N(1815)�Гa�����đ�_���ւ������܂����B���Y�A�q��Ă̐_�Ƃ��Đ��h����A���Y�F��A�Ɠ��ɉh�A�q�����v�ȂǁA�F��̐M�҂���������Q�q����Ă���A���̌�_���͍L�喳�ӂł������܂��B������I���̂����k�������Ă���܂��B
����_��(�q�a��O���A������ׂ̐{)�@����̐_�Ƃ��Đ{���V�j�����ւ��A���N7��15���Ɍ�`�̏��K�����āA�Վ����s���Ă���܂��B
��Ԑ_��(�q�a�E���̃T���̓��A�E�[�̐{)�@���a���Ђ̐_�Ƃ��Ė؉ԍ��P�����ւ��A���N8��21���ɉՂ���s���A�Վ����s���Ă���܂��B
����R�_��(�q�a�E���̃T���̓��A�����̑傫���{)�@�R�̎��_�Ƃ��đ�R�_�����ւ��A���N11����3���j���ɋΘJ���ӂ̍Վ����s���Ă���܂��B
���̂ق��@��א_�ЁA�[���X�V���{�A�@�P�_�ЁA�H�t�_�ЁA����_�ЁA�����_�ЁA�Õ��_�ЂȂǁA���Е���Ă���܂��B |
|
���喾�R�{�����@�@�@����s
|
�{���@�߉ޔ@���@�@�|�@�h�@�����@
�����́A���T��N(1502)����Ƃ̕�Ƃ��đn������܂��Ĉȗ��A�ꑽ������S�l��㔐���V�c���璺�莛�̏ق����蓿���O�㏫�R�ƌ�������͌���n��q�̂��A�h�Ɗe�ʂ̌䉇���E�䋦�͂̉��ɁA�Z���̑��邱�Ǝl�\�ܐ��A�l�S���\�N�߂��ɂȂ�܂��B�E�E�E
|
|
����r�ˈ�א_�Ё@�@�@����s�c����
|
������
��Ր_�@�L��P��_ ���c�F��_ ��{�\�̑�_ �v�X�\�q��_ ����P��_
�{�a�́A����O�N(1675)�A�����O�N(1791)�̉Ќ�ɍČ�����A���{�a�͊����\�N(1798)�̍Č��ō���s�w�蕶�����B�����E��ɂ��鐼�{�_�Ђ��{�a�Č��̍��̌����ō���s�w�蕶�����炵���B
��
�ʏ̂́A�c����א_�ЁB
�Г`�ɂ��ƁA����{���R�����G��(�U����)���A�V�c�ܔN(942)�A���B���q���P����ב喾�_���w�Ŋ֔��B�Ǘ̂̒n�Ɏl�Ђ��������֓���ЂƏ̂�����ЁB���̎l�ЂƂ́A��������X�A���������q�A��썑�V禞�@�Ɖ��썑�x�m���B
���̌�A������N(1186)�܌��\�ܓ��A�G�����፲�쑑�i�]��琬�r�������ċ��̍ہA�c���̒n�Ɉ�u��z���A���썑�x�m���̈�ב喾�_�����������̂����ЁB���쑑�S���\���̑��ЂƂ��Đ��h���ꂽ�ÎЁB
���Ђ���r�˂Ə̂���̂́A�ߋ��ߍ݂̐l�X�͋����ĕr�ɓy�����Ă��̒n�ɉ^�сA�˂�z�����̂ł��̒˂���r�ˁA���̒˂̏�Ɉ�ׂ��K�������������߂��ƌ����Ă���B
��L�̑��B���q���P����ב喾�_�́A���P�������{�Ƃ��̂��ꂽ�߉������{�̒n�ɂ������ێR��Ђ̂��Ƃ��Ǝv�����A�m�F�͂��Ă��Ȃ��B
�܂��A�����Ɋ������ꂽ��������X�́A���G�X�_�ЁA���������q�́A�����q��ׂ��Ǝv�����A��썑�V禞�@�͂ǂ����낤�B�Q�n�����c�s�̊���Ђ��낤���B
���Ђ̌��Ђł��鉺�썑�x�m���̈�Ђ́A��I�����̊֓��Ј�א_�ЂƂ���Ă���炵������I�ƕx�m�͕ʂ̒n�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�܂��A����s�̎����ɂ��ƁA�֓��Ј�א_�Ђ̌Ђ͊֓��Ј�ׂ��������ꂽ���ɁA�����ɉG�X�A���q�A�V���@�A��I��ׂ̎l�Ђ��������ꂽ�̂Ŋ֓��Ј�ׂƏ̂���悤�ɂȂ����Ƃ���B���̐�����������A���̋����n��Ɋ֓��Ј�ׂƑ�I��ׂ̓�Ђ����݂��邱�ƂɂȂ��a���B
�w�Ȗ،��_�Ў��x�ɂ́A�V�c�ܔN�p�Ќ܌��\�ܓ��J���䂦�ɌЂƏ̂���Ƃ���B
���n�̏ڍׂȋ��y�j�Ȃǂ��Q�Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂Ő��m�Ȃ��Ƃ͔���Ȃ����A�x�m���̈�Ђ��c���֑J�����ꂽ���ɑ�I�Ɋ֓��Ј�א_�Ђ����J���ꂽ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B�����܂ł��G���I���������ǁB
���Ȃ݂Ɂw�����_�Ў����x�ɂ��ƁA��r�ˈ�א_�Ђ́w���썑�u�x�ɂ͎R���ז��_(������ׂ��H)����̊����Ƃ���A�܂��A�����������n�������Ђ��A�����A���A����ɑJ�������Ƃ����`��������O�P���y�ЂƏ̂��ꂽ�Ƃ��B
�Гa�̘e�̋����Ђɂ́A�ȉ��̖��O���L����Ă����B���Nj{�A�W���_�ЁA�V���{�A���a�_�ЁA�s�D�_�ЁA���q�_�ЁA����_�ЁA��Ԑ_�ЁA���d�_�ЁB�w�����Ճf�[�^�x�ɂ́A���ЂƂ��Ĉȉ��̖����ڂ��Ă���B�ꕔ�͋��O�ɂ���̂�������Ȃ����A�m�F���Ă��Ȃ��B���{�_�ЁA�����{�A�D�P�_�ЁA�������O�ƈ�ׁA����_�ЁA�_���{�A���X��א_�ЁA�����_�ЁB
|
|
����������@�@�@����s�g����
|
��\�@�y�ہA�x�@/�@�`���@����@/�@�z��ҁ@���썑�j�@/�@�z��N��@����2�N
��������́A���쎁�̖{�铂��R��̓�[�̕��암�ɒz����A�ʒu�I�Ɍ��Ă��d�v�Ȏx��ł������ƍl������B�����ɂ��A��������͌��݂̋����������ƂȂ��Ă���n�ɖ{�ۂ��u����A�k��̊ہE���̊ہE�O�̊ۂƔz���A���ꂼ��̋ȗւ�x�ň͂݁A�X�ɏ��S�̂��O�x�ň͂꒣��ł������Ƃ��B���݂ł́A�ȗցE�x�̂قƂ�ǂ��Z��n�␅�c�ƂȂ��ď��ł��Ă��邪�A�{�ۂɂ��鋻�����̎��͂ɂ́A�y�ۂƋ�x�������悭�c����Ă����B
��������́A�ʖ�������ƌĂ�A����2�N�ɍ��썑�j���ꑰ�̊��`��ׂ̈ɒz�����Ɖ]���Ă���B�i���N�ԂɊ��d���͎O�D���Ɉڂ�A��i���N��荲��G�j�̋���ƂȂ����B�@�������A�G�j�͋������������Ƃ����A�Ɛb�̏��c�E���]��E�͓c�E�V���E�����E���{�炪���ŏ�Ԃ߂��B�@���̌�A���Ƃ��ĎR�c�ዷ�炪�ݏ邵�A���쎁���ՂƋ��ɔp��ƂȂ����ƍl�����Ă�B
|
|
�������G��������@�@�@����s�V�g����
|
�����G���͕��吷�Ƌ��͂��A�V�c3�N(940�N)�ɗ����N��������������Ƃ�A����ɂ��]�l�ʉ��ɏ������A�����A����̍���ɔC�����܂����B
�G�����͓V��2�N(991�N)�ɖv���A�������ɑ���ꂽ�Ƃ����Ă��܂����A�p���ƂȂ�p��2�N(1705�N)�n���L�u���c�����������Ă܂����B
�������Õ��Ⓦ�����u�Ƃ��Ă�Ă��܂��B
|
|
�����É��_�Ё@�@�@����s
|
�̒����ɂ́u����ʁ@�𗈖�喾�_�v�ƍ��܂ꂽ�z���|�����Ă����B���V�R�_�Ђ̔𗈖�R�ɍ��É��_�АՂ�����������A�R�̏ォ��ړ]�����_�ЂȂ̂��낤���B��Ր_���������̑c�_�ł���V��������(�A���m�R���l�m�~�R�g)�ł����邵�A�����G�����ɉ��̂���_�Ђł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B
���v�J�R��ՁA���É��ِՁA�V�R���
�v�J�R���(�悤�������傤����)�A���É��ِ�(�˂���₩������)�A�V�R���(���Ȃ���܂��傤����)
�v�J�R��Ղ͔��Ɏc��W����400���[�g���̎R��ł��B�R���t�߂͓�����16���[�g���A��k��17���[�g���̋K�͂Ŏ�s��݂��A��s�̎��͂ɂ͋ȗւ��z�u����Ă��܂��B�܂��A���݂���s�̎��͂ŐΊ_���F�߂��܂��B����́A�V�����N(1532)�̍��A����z���`�Ƃ����邵���Ƃ��݂��܂��B���̌�A�������������̏��]���}�O��ɂ���ė��邵���Ƃ����Ă��܂��B
�����āA�v�J�R�̖k���R�[�ِ̊Ղ����É��ِՂŁA������43���[�g���A��k��37���[�g���̋K�͂ŋȗւ�����܂��B���ق͗v�J�R�邪���邵����ɏĎ������Ƃ����Ă��܂��B���̎R���t�߂̎�s�ƎR�[�ِ̊Ղ���̂ƂȂ��Ďc���Ă��邱�Ƃ͑��ɂ��܂�Ⴊ�Ȃ��M�d�ȏ�Ղł��B
�V�R��Ղ́A�˓ޗǒ��Ɏc�镽�R��ŁA�����ɂ͊��삪����Ă��܂��B����́A������31���[�g���A��k��56���[�g���̋K�͂̎�s��݂��Ă��܂��B�z��ɂ��Ă͊��q����ɍ�����j�̎q�˓ޗnjܘY�@�j���z�����Ƃ����A���̌�A���N(1247)�p��ƂȂ����Ƃ����Ă��܂��B���݂͎�s�̂Ƃ���ɐΔ肪���Ă��Ă��܂��B�ꑰ���z������Ƃ��č��쎁�ƊW�̐[����ՂƂ�����ł��傤�B
|
|
�������@�@�@����s��
|
|
�V���N�ԏ����ɍ��쎁�ɑ����Ă������앺�����㍂�g���A�����������ɔ����邽�ߓ���R��̎x��Ƃ��Ēz�����Ƃ����Ă��܂��B������1584�N(�V��12�N)�A���g�͒�ƂƂ��ɒ��������̉Ɛb�E���\���}�O�ɖd�E����A���̌�͏��\���������ƂȂ�܂����B���ݏ隬�́u���É��X�ь����v�Ƃ��Đ�������Ă���A�{�ېՂ́u�v�J�R�W�]�L��v�ƂȂ��Ă��܂��B��\�Ƃ��Ă͐؊݂Ɩx�Ȃǂ��m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B
|
|
������R��@�@�@����s�x�m���A�Ȗ{��
|
���{�̏�B���ݒn�͓Ȗ،�����s�x�m���A�Ȗ{���B�ʖ��͓Ȗ{��A���É���A������B �u�֓���̎R��v�Ə̂����B��Ղ͍��̎j�ՂɎw�肳��Ă���B2017�N�ɂ͑����{100����(114��)�ɑI�肳�ꂽ�B
�֓�������̈�B����s�X�n�̖k����5�L�����[�g���̓���R(247���[�g��)�R����{�ۂƂ��Ĉ�тɋȗւ��z���ꂽ�A�s���R��ł���B�퍑����ɂ����āA���쎁��15�㓖��E���쏹�j�ɂ�铂��R��̐킢�ŗL���ŁA�㐙���M��10�x�ɂ킽��U��������A�x�X���ނ��Č��M��Y�܂����B�֓��n���̌Ï�ɂ͒����������Ί_���z����Ă���̂������ł���B�����{100����ɑI�ꂽ�B
���݂͓Ȗ،������R�����̈ꕔ�ƂȂ��Ă���A�{�ۂɒz���Ɠ`�����铡���G�����J�铂��R�_�Ђ���������B���s�Ղɂ͓Ȗ،�����N�̉Ƃ����Ă�ꂽ���A����19�N(2007�N)3��31���������B��\�Ƃ��ĐΊ_�A���e�`�A�y�ہA�x�A�y���A�ߐ��ɕ������ꂽ��˂Ȃǂ��c���Ă���B
�����j�E���v
�z��͕�������̉���5�N(927�N)�ɁA�����G�����]�܈ʉ��E���썑���̎g�����C�A�֓��ɉ���������R�ɏ��z�����̂��n�܂�Ƃ����B �V�c3�N(940�N)������ɂ��V�c�̗����N���������A�G����̊���ŗ�����������B���̌��тɂ��G���͏]�l�ʁA�����E���염������{���R��q�̂����B �܂��A����ɂ͂��̗�����������V�c3�N����z�邪�J�n����V�c5�N(942�N)�Ɋ��������Ɠ`������B���̌�A5��ɂ킽�肱���ɋ��邵����A6�㐬�s�͑������Ɉڂ�ꎞ�p��ƂȂ����B
�������㖖���̎���4�N(1180�N)9��r�j�̒퐬�r�͍Ăт����ɏ���ċ����A���쎁�𖼏�����B���q����ɓ��������ی��N(1213�N)���r��30�]�N�̍Ό��������ď�������������B
�ȏ�̂悤�ȓ`�����������ŁA�ŋ߂̌����ł͓���R��̋N����15���I�㔼�܂ł����k��Ȃ����Ƃ����炩�ɂ���Ă���B�G���z�邪�`�����ꂽ�w�i�ɂ́A����R���̍��쎁�̐�c�������G���ł��邩��ł���Ƃ�����B
�������㒆���̉���3�N(1491�N)�ɂ͍��쐷�j����̏C�z���s�����B
�퍑����̍��쎁�͑��̖͂k�����A�z��̏㐙���̓�吨�͂ɋ��܂�ǂ���ɕt������Y�����B�����A�z��̏㐙���M�ƌ����쏹�j�́A�i�\2�N(1559�N)�k��������3��5��̑�R�������ď���͂��ꂽ�B���M�͑����ɉ��R�����������k���R��P�ނ������B
����R��(����)�͌��M�ɂ����Ă͊֓��ɂ����鐨�͌��̓��[�ł���A���|�����͂��߂Ƃ���k�֓��̐e�㐙�h�����̐��͌��Ƃ̋��E���ł����������߁A���ɏd�v�����ꂽ�ƍl�����Ă���B
���j�̎q�E�@�j�͒�ŏ㐙���̗{�q�ɓ������Տ��ۂƕs�a�ɂȂ�A�ꑰ�ԂŁu����R�V���̗��v�ƌĂ�鑈�����N�������B����ɂ�荲�쎁�͏㐙���ƌ��ʂ���Ɏ������B�V��4�N(1576�N)�Տ��ۂɉ��������㐙���M��1��5��̕��������Ă��̏���U�߂����A�ꑰ�̌��鎁�E���R���E�F�쎁�Ȃǂ̉����ɂ��㐙�R��P�ނ������B����܂ł�9�x�ɂ킽��㐙�R�̍U����A���E���j�͉��x���~���������̂́A���M��傢�Ɏ�Ԏ�点���B���̌��ł��͕]���ƂȂ�֓���̎R��Ə^���ꂽ�B
�㐙���ƌ��ʂ��Ǘ����������쎁�́A�V��15�N(1587�N)�ɖk�����N�̌ܒj�E������{�q�Ɍ}���k�����Ƙa�c�����B
�V��18�N(1590�N)�L�b�G�g�ɂ�鏬�c�������ł́A����̍���[�j�͖L�b���ɕt������̖k�𐨂���|�����B���\2�N(1593�N)�L�b���Ɛb�x�c�ꔒ�̓�j�E�M���{�q�Ɍ}���A�G�g�̕�恂����荲��M�g�Ɩ�������B
�c��5�N(1600�N)�̊փ����̐킢�ł͐M�g�͓���ƍN���ɕt��3��5��̋��̂����g���ꍲ��˂����������B�c��7�N(1602�N)�[�ɍ���邪�z���ꕽ�������葱��������R��͂��̗��j�ɖ�������B�p��Ɏ��������Ƃ��āA�]�˂ɉЂ��������Ƃ��A�R��ɂ��铂��R���肱��������n�ō]�˂ɋ삯�Q�������A�]�˂������낹�鏊�ɏ���\����͉����邱�Ƃ��ƉƍN�̕s�������ƌ����b������B�܂��A�]�˂���20��(80�L�����[�g��)�ȓ��̎R��͋֗߂���Ă����Ƃ̐�������B
����16�N(1883�N)�L�u�ɂ��{�ېՂɓ���R�_�Ђ��������ꂽ�B
���a30�N(1965�N)�Ȗ،������R�����J�݁B���a38�N(1963�N)�Ȗ،�����N���R�̉ƊJ���B
����26�N(2014�N)3��18���A��Ղ����̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B
����29�N(2017�N)4��6���A�����{100����(114��)�ɑI�肳�ꂽ�B
�������G���Ɠ���R���
����R�̏�ɂ́A�����G�������܂铂�V�R�_�Ђ��������Ă��܂��B�G���͕�������A������̗��̕���Ɍ��т����������ƂŒm���Ă��܂����A���̈���Łu�U�����v�̒ʏ̂Łu�S���ގ��v�̓`�����͂��߂Ƃ��āA�����̕����G�����Ɏ��グ���A�e���܂�Ă���l���ł��B
����R��̒z��́A�G���ɂ���ĂȂ��ꂽ�Ƃ����`�������̈�ł��B�������Ȃ���A�M���ł���j���Ɍ�����G���Ɋւ���L�^�́A�f�ГI�Ȃ��̂ł���A�z��Ɋւ�����̂͊m�F���邱�Ƃ��ł��܂���B�܂��A����܂łɎ��{����Ă��锭�@�������ʂȂǂɂ���Ă��A�z���N��́A�����Ă�15���I����ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B���w��j�Չ��̂��߂ɂ́A����R��Ղ̗��j�I���l�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B
���̈���A�G���̌n���ł��鍲�쎁�Ⓜ��R��ɓ`���A�`����`������ɂ��Ă����������̂ł��B
|
|
������R�_�Ё@�@�@����s�x�m��
|
�Ȗ،�����s�̓���R�R���ɂ���_�ЁB�����G�����J��B���Њi�͕ʊi�����ЁB
�Ր_�̓����G���͕U����(�c������)�̕ʖ��ł��m���A���썑���̎g�Ƃ��ē���R�ɓ���R���z�邵�A�G���̎q���̍��쎁�����邵���B�G���͕�����̗���������Ē���{���R�ƂȂ������Ƃ��璉�c�̐b�Ƃ���A�G���̌���⍲�쎁�̋��b�炪���S�ƂȂ��ďG�����J��_�Ђ̑n�����n�߂��A����16�N(1883�N)�A����R��̖{�ېՒn�ɑn���E�������ꂽ�B����23�N(1890�N)�ɕʊi�����Ђɗ�i�����B
���Ђ�萼2km�̍���s�V�g�����ɂ���G���̕揊�́A��n�����ƂȂ��Ă���B
|
|
���H���R�_�Ё@�@�@����s�쌴��
|
|
�c�����j�ɂ͓���R�̉B��邾�Ƃ����Ă���悤�ȁA�����A�[�R�H�J�ɂЂ�����ƌ�������Ă���悤�ł��B�������c�����̖H���R�͓��{�O�H���̈�Ƃ����A��1,200�N�O�A������r�R�J�R�̏�����l���J�����Ƃ���Ă��܂��B��Ր_�͎s�n���P���ł��B
|
|
���H�R��Ձ@�@�@����s�쌴��
|
|
��ː�Ə��ː�̍���������ƂȂ鐼�̕W����385��(�䍂��140��)�̔����̓�[�H�R�R���Ɉʒu����B�o���čs���Ǝ�s(�L��60��)������A�ΐς�����A��k��2�����A�ΐς��K������B�쐼���ɔ�A���������Ă��Ă���B�k���������ɖx������B���������Ղ̋K�́A�`��Ȃǂ��瓂��R��k���̎��Ƃ��Đ퍑����ɒz�邳��A����ƖŖS�Ƌ��ɔp��ƂȂ����Ǝv����B
|
|
���O�R�_�Ё@�@�@����s�D�z��
|
��Ր_�͓V�������������A�z�J�_�Ƃ��Đ��D�ÕP�����J���Ă���B�Ȗ،����Ő��D�ÕP�����J���Ă���_�Ђ͊�M���̉דn�_�ЂƂ��̎O�R�_�Ђ݂̂ł���Ƃ̂��Ƃ����A���̂��̓��݂̂Ȃ̂��낤���B���Ȃ݂ɁA���D�ÕP�����J��_�Ђ͑�T�߂��ɐ삪����Ă�����̂����A���������ɉk�ꂸ�A�����쑤�Ɋ��삪����Ă���B
�V�c�ܔN(942)�ɓ����G�����ɂ���đn������A�V���\���N(1,590)�ɑD�z�Z�Y�Ȃ�l���ɂ���čČ����ꂽ�̂��������B
|
|
����{�_�Ё@�@�@����s�D�z��
|
|
�V�c4�N(941)�n���̌ÎЂŁA�k�L����(�������q�̕��ł���p���V�c�̂��Ƃł�)�����J�肵�Ă��܂��B�������q���J���Ă��鑾�q�a������A�ʏ́A���q�l�Ƃ��]���Ă���悤�ł��B���̌Ö������ɂ��������̍ʂ��Y���Ă���悤�Ɍ����܂��B
|
|
�����g�_�Ё@�@�@����s�Ԍ���
|
|
�_�Ђ̑n���́A�����V�c��N(698)�Z���\�ܓ����������Ɠ`�����A�����G���������c��N(946)�Ɍ�{�a�y�єq�a�����Č������Ƃ����Ă���܂��B���̌�A������N(1200)�Ɍ�{�a�A�q�a���C�����A���a���N(1615)�Ɍ�{�a�̉��z���s���Ă���܂��B���۔N�ԂɎ���q�a�́A�Ђɉ�������Ă���܂������A�V�ۏ\��N(1831)�����\����ɐV�z����܂����B���̓x�A��{�a�A�q�a���V�����r�����A���C�̕K�v�ɂ��܂��A���q�A���h�ґ��v��A�Гa�̉��C�A�Ж����̐V�z�����邱�ƂɌ��肵�A�Гa���C�́A���a�\���N(1983)������\�ܓ����J�{���тɉ��C�Ղ����s�A���N�\��\�ܓ��C���A�Ж����̐V�z�͏��a�\���N�N�H�����s�Ȃ��A���\��N�O����\����H�����C���������܂����B�lj��H���Ƃ��āA�������тɐ_�y�a�A���Ђ̐������s�Ȃ��A�����ɑ��ׂĂ̍H�����������邱�Ƃ��ł��܂����̂ň���N���L�O����j�Ղ����s�������܂����B
|
|
����R�Ԃ�@�@�@����s�o������(���E�c�����o����)
|
|
�o�����ٓV�r�̗���̌�R(��R)�t�߂��u��R�Ԃ�v�Ƃ����܂��B�G�����G�ɐ�R�̕����w�������܂������A�R���œ��������������Ԃ����ƂɂȂ����̂ŁA�����Ă��悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B
|
|
���u���邵����E�����v�@�@�@����s�o������
|
�o�����ٓV�r�ɂ́A�ƂĂ��₽���A�����ꂢ�Ȑ������킫�o���Ă��܂��B���̒��ɂ́A�傫�ȂЂ�����ɂ������������C�ɉj���ł��܂��B���̒r���������Ă���̂��A��R�Ƃ����ΊD�̏o��R�ł��B���̎R�̓�������R�Ƃ����܂��B���̌�R�ɁA�����Ƃ��Ȃ������̂Ȃ����c���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@���邵����@����
�@�@�@�@�@�������@�������
�@�@�@�@�@�����ɉf���@�[�������₭�J
�@�@�@�@�@���̎O���ǂ蔼�́@���ɂ���
�ƁA�����̂��A�̂��瑺�l�̊Ԃɓ`����Ă��܂��B���ꂪ���̂Ȃ��̕���ł��B���̉̂́A���̂����肫���Ă̑�������A�������҂�������������ꏊ���Ƃ��u�����v�Ɠ`�����Ă��܂��B���̒��҂̉Ƃ̂��Ƃ́A���܂͉����c���Ă��܂��A�̂́A����̂悤�ȍL���ƂŁA�����ւ��Ɉ͂܂ꂽ���ɁA�傫�ȉƂ�����A�܂��ɂ͂�������̂��炪�����Ĕ������ׂ����ɂ����₢�Ă����Ƃ����܂��B�����ۂ��A���̉~��@�R�ɂ͗[�����҂��Z��ł��āA�������҂ɕ����Ȃ��قǂ̑�������ł������Ƃ����܂��B
�������҂ɂ͎q�ǂ�������܂���ł����B�q�ǂ����ق������ҕv�w�́u�ǂ����q�ǂ��������������������܂��悤�ɁE�E�E�E�E�v�ƕٓV�l�Ɉ�S�ɂ����̂�����܂����B
����ӂ̂��Ƃł��B���҂͕s�v�c�Ȗ����݂܂����B����́A���̂ƂĂ����ꂢ�ȔӂɌ��������Ă���Ƃ��ł��B�}�Ɉ�R�̏オ�܂Ԃ����قǂɌ���ƁA��������̒����Ƃ�ŗ����̂ł��B���̒��̑傫�Ȓ��A����͂�ł������A���̂��Ȃ��ɂ��킢�����P�l���̂��Ă��܂����B
���҂́A���ꂵ���Ȃ��Ă��P�l�Ǝ���Ƃ��Ă��ǂ�܂����B���̂����A���҂͖�����o�߂�ƁA�s�v�c�Ȗ��������̂ōȂɘb���܂����B
�u����́A�s�v�c�Ȃ��Ƃ�������́A�킽�������������݂܂����B�v�ƁA�Ȃ��s�v�c�Ȏv���ł����ς��ł����B�����āA��l�͂Ȃ����A�q�ǂ����������邱�Ƃ����̂葱����̂ł����B���炭����ƁA�{���Ɏq�ǂ�����������܂����B����͂��킢�����킢�����̎q�ł����B���҂͊��ł�P�Ɩ��Â��܂����B
�����āA�������ɂ������Ɉ�ĂĂ����܂����B�Ƃ��낪�A������A���҂́A���{��l�Ƃ����������݂������V�l�ɘA���A���_�̂Ƃ���֘A��Ă�����܂����B����́A���Ƃ������Ƃ����Ȃ��ł����ł������A���ǂ��ė��Ă��A���̎�����ꂽ�s�V�����̖�(�N���Ƃ炸�����������)����P�Ɉ��܂��邱�Ƃ����͂킷��܂���ł����B
���҂́A�ƂɋA��Ƃ����������̖����P�Ɉ��܂��܂����B����ƁA�܂������Ȃ������P�́A�����܂��A�\���A���˂̔��������ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�P�́A�������R�ŗV�Ԃ��Ƃ��A���̏���Ȃ��y���݂ɂ��Ă��܂����B�Ƃ��낪������A�V�тɏo���P�́A�R����A���Ă��܂���ł����B���҂͐S�z���A�R�����܂Ȃ������������ɐl�𑖂点�Ă��������̂ł����A���Ɏ肪���肪����܂���ł����B
���ҕv�w�́A����قǂ��킢�����Ă����P�����Ȃ��Ȃ������ƂŁA������]�݂������Ȃ��Ă��܂��܂����B����ƁA�����A���҂̂˂Ă��閍���Ƃɐ_�l��������܂����B
�u���O�̕P�́A���̒��Ō�ƂȂ��āA�����яオ�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B�����A���܂ł̕�l�X�ɂ������A���ꕶ�ɂȂ��Ė����_�l�╧�l�ɂ����̂����������A�P�͗��̐_�l�ɂȂ��ēV�ɏ��ł��낤�B�v�ƁA�����A������o�߂܂����B
�����ŁA���҂́A�P���킢���̂��܂�A���邵����@�����@�������@��������@����R�̐�R�Ԃ�ɂ����߂܂����B
�����
���̎�̘b�́A�x���̉h�͐��ނ����b�ŁA���ғ`���Ƃ��S���e�n�ɕ��z���Ă��܂��B�Ȗ،����ɂ��A�������z���A���R�s�A�����s�̂��̂Ȃǂ��m���Ă��܂��B�b�̒��ɓo�ꂷ�钩�����҂́A���̎�̘b�ɍD��ŗp�����閼�ŁA�����̓����R�̉��N�`���ɂ����̖��������Ă��܂��B
�{���́A�Ȗ،��A�������ҁu����`���W�w���邵����E�����x�v���Q�l�ɂ��܂����B���̘b�́A�`���҂ɂ���āA�������҂ɕC�G���邱�̒n���̑�������[�����҂̂ނ������A�ߕP�ɗ����������Ƃ��A�������҂Ɨ[�����҂��A���������̉̂̂Ȃ����������߂ɑ������Ƃ��A�㐢�A�̎��ɑ|�����̏�n����R�ɂ܂��ꂱ���A�Ђ��߂Ɏ�����ċA�����Ƃ����b������܂��B
�܂��A���Ƃ̔n���u��R�Ԃ�v�ɖ������ݑ��Ɏ�����Ă����Ƃ����܂��B���̉Ƃɂ͂��̎�œh�肠�������킪�c���Ă���Ƃ������Ă��܂��B�������҂Ɨ[�����҂̋��������́A�u��v�ہv�̘b���Q�Ƃ��ĉ������B
|
|
�����{�_�Ё@�@�@����s�x�Ē�
|
|
�����G�������鐝�V�c�����đn���������̂ł���炵���B
|
|
����Ԑ_�ЁE��Ԃ̉Ղ�@�@�@ ����s�ޗǕ����@ |
����192���̐�ԎR�̎R���ɂ����Ԑ_�Ђ̂��Ղ�ŁA�n���ł́u��Ԃ������グ�v�Ƃ������Ă��܂��B
�Ղ�̓��̗[���A�n���̐l�������R���̐_�ЂɎQ�q���A���a���ЁA�܍��L�����F�肵�A���̔N�ɂƂꂽ150���̏������(�n���ł̓J���ƌĂ�)�ɉ��Ƃ����u�_�̋V�v���s���܂��B�����āA�K�ꂽ�l�������A��Ɏ�Ɏ����������ɂ��̉����炢�R������܂��B
������ԎR��]�ނƁA�R���܂ł̎Q���́A�̋��̂��Ƃ��Èłɕ����o�āA���̔������������o���܂��B
���悻1,000�N�̗��j�����Ƃ����`�������邱�̉Ղ�́A�����G��������R�ɏ��z���A���̕t�߈�тɓ������ꑰ���Z�݂��A�ނ�̈А����������߂ɎR��ʼn����̂������肾�Ƃ����A�Ȍ㑺�l�́A�����a��ǂ��������Ƃ����܂��B
|
|
���I�����_�Ё@�@�@����s�x�m��
|
��Ր_�@�s�n���P��(���������܂Ђ߂݂̂���)
�n���E�����@�V�c5�N(942�N)
�R�� �@�����G���������|�������喾�_���V�R�Ɋ����B��i���Ɋ}���R�̒����ɕ�ڂ��A�c�����Ɍ��݂̏��ɑJ�����ꂽ�B����5�N�A�I�����喾�_��I�����_�ЂƉ��̂����B
|
|
���֓��Ј�א_�Ё@�@�@����s��I��
|
|
�n���͓V�c5�N(942)�ŁA�����G���������͍�������ב喾�_�����̒n�Ɉڂ��A�{�����݂����Ɖ]���܂��B������ׂ͑剻2�N(646)�n�����ꂽ���̂ŁA��Ր_�͈ɜQ�����A�fᵚj���A��ȋM���ł���A�����ɉG�X�A���q�A�V���@�A��I��ׂ�4�Ђ��ڂ��ꂽ�̂ŁA������֓��Ј�ב喾�_�Ə̂���悤�ɂȂ�܂����B�c�����ɒ�������L���Ȉ�r�ˈ�א_�ЂȂǂ��A���̐_�Ђ̕��슩�����ꂽ���̂Ɖ]���܂��B�~���Ė���6�N�ɎЍ����֓��Ј�א_�ЂƉ��̂��A���݂Ɏ���܂����B
|
|
���������@�@�@����s��������
|
�{���@����ɔ@�����@�@�h�@��y�@
�����ɂ͓V���{������A�t��W�ɂ������������^�����J��A���t���Âь������̎��_�Ƃ��Ă��܂��B�J�c���荂���̂���A���ł���u�тႭ����v�̖͎���800�N���Ă���A����s�̕������Ɏw�肳��Ă���܂��B����̐���(1703- 1775)���r�u���������́@�l�̂��Ƃ߂Ɂ@��������v�̔o�́A���̖��������������̌������̗l�q���r���ŁA����̒��M�̊|�������ۊǂ���A�����ɂ��Δ肪���Ă��Ă��܂��B
������ �c�������G���̉Ɛb�A���荂���������B���荂���͐������^(844�N〜903�N)�̎t��ł�����B
���10�N(1760�N)���{�����B
����5�N�@�V�����̐i���{�����Č����܂����B
����18�N�@�ɗ��E�q�a��V�z�B
|
|
����H�c�����{�@�@�@����s��H�c��
|
����6�N(936�N)�c�������G���A���G����ׂ����������ē����܂ŏo�n�Ȃ肵�����ɂ��������G�Ȃ�ƂĉF�������{��폟���F��B���̗i��ɂ�萋�ɑ��炰�ē�����z������B
�V�c5�N�������ɕ���ߒ˂�ċ{�a�����āA�Ȃė��S�����ƂȂ葦�����{�Ђ̌��������������˂Ƃ����Ē���Ȃ肵����A���\8�N�{�a�Č��̍ی��݂̏��֑J����������̂ɂ��ē����ދ����K�тĐ��f�ƂȂ����̒n���蔭���������Ƃ���B
|
|
���厭�_�Ё@�@�@����s�D�Ð쒬
|
�����G������������ɔC����ꂽ�ۂɌ��������Ɠ`�����Ă���B����s�ɂ͏G�������n�������Ɠ`������_�Ђ�����������̂��A�_���ւ̐M�S���Ă��Ƃ������Ƃ��B
��Ր_�͕��P�Ɩ��ŁA�V�c�O�N(940)�ɓ����G�������]�l�ʉ����앐����ɏ��ʂ��ꂽ���ɓV�����̏t�����R�Ɍ��Ă�ꂽ���A�i���Z�N(1509)�Ɍ��ݒn�ɑJ�����A�厭�_�ЂƏ̂����Ƃ̂��ƁB��i�N��(1704�`1711)�ɖ{�Ђ��Č��A����ʂɎ������ė����������V���Z�N(1786)�ƌc���N(1866)�ɉЂ����Ă��邻�����B
|
|
����c�_�Ё@�@�@����s�n�咬
|
�Ѝ��W�ɂ́u���і썑�@�V�����Ёv�Ƃ���A�܂������̊z�ɂ��V�����ЂƏ�����Ă���B
�������������ĉE�葤�ɔ���_�ЁB���葤�Ɉ����_�ЁB�Q���E�葤�ɐ匳�_�ЁB�Q�����葤�ɂ͌�ԎR�_�Ђƛԕ�����_�B���̍����Ɉ�������匠���B�q�a�z�ɂ͓V���y�А�c��_�Ƃ��邪�A��Ր_�͂ǂȂ��l���낤�H�@�i�s�V�c�\�Z�N(126�N)�Ɋ������ꂽ���̂ŁA�Â��͓V�����Ђ∢�\��_�{�Ƃ��̂��Ă����������B���\�͂��̕ӂ肪�ȑO�͈��h�S���������炩�B
��Ր_�͑�ȋM���Ǝ���喽�A�L�閽�̎O���ŁA�ڈΐ����Ɍ��������{������������ɐ_�߂�����(630�N�̂��Ƃł���炵��)�A��A���̚��ɐ_�Ђ����ĂēV�����̑�����ƂȂ����̂��Ƃ��B�܂��A���݂̎Гa��1854�N(�Éi�Z�N�`���N)�Ɍ��Ă�ꂽ���̂��������B
|
|
�����c�_�Ё@�@�@����s�z����
|
|
�V�c�N��(938�`947)�����G�t�����������ĂƓ`�����Ă��܂��B�]�ˎ��㏉���܂ł͓����喾�_�Ƃ��̂���Ă��܂����B
�@ |
|
�������s |
|
�������_�Ё@�@�@�����s��a��
|
�Ր_�͑啨�喽���a�V�ƍc��_�fᵚj�������F�������{�����_�c�ʖ��Ȃ�B
�{�Ђ͐l�c��\��㕽��V�c �̌䎚�哯�l�N(���Z��)�㌎�\����̑n���ɂĉ����@�� �̊����Ȃ�B���Â͉����̋��Z�\�Z�����i�������c���u�ɂɜ��Ď�����ґ��� �����@�ۂ͑�a���O�֑�_�f���M������̖��ɑ�_�������܂͂�������J����Ήu�����ނׂ��ƍ����o�ސ��ɉ��Đ���̒n����ѐb���̉��ɗ��K�����đ啨�喽���Ă��B�u�a�������ݔN����ɖ����B�����ĉ������̑y���牟�����{�喾�_�Ƒ��h���čG�s�̎Гa�����z����B������_�a�����i�ւ��邪���a���Ə����Ɏ������̂͐_�Ə�Ƃ̓��P�ɂ��T��邩�B
�{�Ђ͍���~�g��[�����h�̎ЂȂ�B��V�c��N(��Z���)������ �����̎����吷 �����G�� �����{�Ђɐ폟���F�葬�ɒǓ����Đ폟�������ȂĖ{�Ђɋ|�����������[����B�����Еo���肵���ɂ����Ƒ��\��㕚���V�c �̐���ܔN(��j���)�������R�̍Ђ��ɜ��Гa�����G�L�ɋA�����B�����l�N(��l�Z�O)�㌎�얓�����v�Ɏ���{�Ђ��Ēz����B�c���_�͈�˂��@�邱�Ƃ����Ћ��В勝�ܔN(��Z����)�O��������_�_���̒���g�����A�ɐ����Đ_�ʏ@����|���ȂĐ���ʂ����͂苏���̈��ׂ��F�肵����˂��@�邱�Ǝn�܂肵�Ɖ]�`�ӁB������N�l���_�_����艟���_�ЂƐ��ߕ��B���݂ɉ]�Ӊ��Î����_�a�͈ꕔ���Ȃ�Ɩ����̎��������w�Z�̏��ɒŒJ���Ƃ������Ƃ���Đ_�ЕӖ��y�n�����L���_�Ђ̍ՓT�ɂ́W�Ƃ��̎Q�q��҂��Č�s�ւ��Ƃ�����Ɏc���B
�������̕������L����
�����_�a�@�c��B�ȋv�ە����ʓc���㏬�q�@�����L
�����B�������B�����c�B�����[��x���B�É�u�B���ъ⁖
�艪�B���B���V�B�����s�B���ˁB�o�������B���a�c���B�Ζ�c�B���r�B�R���B�Бq�B�����B�юR�B��g�B��K�����B�\�X�Z�B��h���V�B�y�V�B�����V�B�ڏ��B�X�F�B���q�B���쁖���B�到�B�����B�ԉ��B�������C�B��n�B�r�j�B�ѓc�B�얀�B�I��B���J�B����B��R�B�ޗǕ��B�[�ÁB�����B�������B�ԉ��B���c�B�v��B
���a�l�\���N�㌎�\�Z���@�g��
�����s��a�����l�Ԓn
���V�`�Y�@��i
�����s��ޗǕ�����Ԓn
�F��_�A��@�ޏ�
��
�Ր_�͑啨�喽(�������̂ʂ��݂̂���)�A���a(�����ǂ́F��ȏ�̐_���J�邱��)�V�ƍc��_(���܂Ă炷���߂����݁F�V�Ƒ�_�Ɠ���)�A�fᵚj��(�����̂��݂̂���)�A�����F����(�����ȂЂ��݂̂���)�A���{����(��܂Ƃ�����݂̂���)�A�_�c�ʖ�(�ق킯�݂̂��ƁF���_�V�c)�Ȃ�B�{�Ђ͐l�c��51�㕽��V�c �̌�F(����E���F�鉤���V�������߂Ă������)�哯4�N(809)9��19���̑n���ɂĉ����@�ۂ̊����Ȃ�B
���Â͉����̋�66�����i����(�̂���)���c(��)���u�(�����ꂢ�F�u�a�̂���))�ɜ���(�������)������ґ����A�����@�ۂ͑�a���O�֑�_�f���M���A����(�����)�̖��ɑ�_�������܂͂��A������J����Ήu�(�����ꂢ)����(��ށF�~��)�ׂ��ƍ���(�����܂�)�o��(���ށF�o�߂邱��)���ɉ���(�����ɂ�����)����̒n�����(�����)�b��(���݂����H)�̉��ɗ��K�����đ啨�喽���Ă��B�u�a��������(�����܂����)�N��(�˂��H��N�̍����H)��ɖ����(������)�B
�����ĉ������̑y����A�������{�喾�_�Ƒ��h���čG�s(���������F�L��ł���ςȂ���)�̎Гa�����z����B������_�a�����i�ւ��邪��A��a���Ə����Ɏ������̂͐_�Ə�Ƃ̓��P�ɂ��T��邩(����܂��邩�F�Ԉ����)�B�{�Ђ͍���O�g��[�����h�̎ЂȂ�B��V�c2�N(1015)������ ����(�͂�͂�F�d������)�̎��A���吷�A�����G�������{�Ђɐ폟���F�葬(���݂₩)�ɒǓ����Đ폟�������ȂāA�{�Ђɋ|������(�|�E��E���E��)�����[����B�����A�Еo���肵���ɂ����ƁA��92�㕚���V�c �̐���5�N(1292)8�����R(�����낭�F�Ύ�)�̍Ђ��ɜ��(������)�Гa�����G�L(���Ƃ��Ƃ�����)�ɋA�����B����4�N(1463)9���얓�����v�Ɏ���{�Ђ��Ēz����B�c���_�͈�˂��@�邱�Ƃ����Ћ��В勝5�N(1688)3��21���_�_���̒���g�����A�ɐ����Đ_�ʏ@����|���ȂĐ���ʂ����͂�A�����̈��ׂ��F�肵����˂��@�邱�Ǝn�܂肵�Ɖ]�`�ӁB����2�N4���_�_����艟���_�ЂƐ��ߕ��B���݂ɉ]�Ӊ��Î����_�a�͈ꕔ���Ȃ�Ɩ����̎��������w�Z�̏��ɒŒJ���Ƃ������Ƃ���Đ_�ЕӖ��y�n�����L���_�Ђ̍ՓT�ɂ́W�Ƃ��̎Q�q��҂��āA��s(���������F���Ƃ���s������)�ւ��Ƃ�����Ɏc���B
|
|
�����g�_�Ё@�@�@�����s���얀��
|
���g�_�Ђ́A�`���ɂ��ƓV�c3�N(940)�ɓ����G���������������ɂ�����A�ߍ]���}�_�ЁE���g���(���ꌧ��Îs��{)����������7�Ђ̂����̈�Ƃ����Ă���A�]�ˎ���ɂ́A���c���E���E���얀��(�V�c��)�̎Y�y�_�Ƃ����J���܂����B
���̐_���Q��24��̐_���ƕ������琬��A�ꕔ�ɂ͍O��3�N(1557)�A���T3�N(1572)�A�c��13�N(1608)�Ȃǂ̖n�������m�F����Ă��܂��B���Q��l�Q�ɂ�錇���A���w�E����̖S���ȂǕۑ���Ԃ͗ǍD�Ƃ͌�����܂��A���}�R���M�ɌW��24��̐_�����ꊇ���ď��݂��邱�Ƃɉ����āA�����ۂ�ȂǑ��`�ɂ��D��A�܂��L�ڔN�ォ��p�����Ƃ̊֘A�����������ȂǁA�n��̋M�d�Ȏ����Ƃ��ĕ������Ɏw�肳��܂����B
|
|
�����g�_�Ё@�@�@�����s�r�m�X
|
�����̊z���Ɂu������ᡖ������������g���v�ƍ��܂�Ă���B������̐_�Ђ͊�����N(1461)�ɉF�s�{���j����r�m�X�ɑ���悤������ꂽ���䍶�����A�r�m�X���J���ɒ��肷��Ǝ��������ē��g�_�Ђ����������̒���Ɠ`�����Ă���̂��������B1461�N����Łu��ᡖ��v�ƂȂ�͓̂V����N(1533)�A������N(1653)�A���i��N(1773)�̎O�����A�z���̕����ƌ`�����Ă���͈̂��i���ȁB
��Ր_�@��R��_�A���孁�M���A�fᵚj���@���Ђ̑n���́A������(1461)�N��ꌎ��ܓ��B������(1737)�N�A����ʎR�������ƍ����A�c����(1866)�N�㌎�A����ʓs����g�_�ЂƉ��̂����B�����O��(1906)�N�A�_�a���嗿���i�ЂɎw�肳���B���݂͎��q���������A�r�̐X����삷��ЂƂ��Đ��h����A���₩�ȗ��Ղ��s�Ȃ��Ă���B
|
|
�����g�_�Ё@�@�@�����s���g��
|
�_�Ђ͕W��328.2���̊�R�n�C�L���O�R�[�X�̓o�R���ɒ������Ă��܂��B�n���͉����E������E����{���R�̖������C���A����R(���݂̍���s)�ɏ��z���A�P�����{���������G�������������Ƃ����Ă��܂��̂ŁA�������㒆���Ǝv���܂��B�����Ɂu����ʁ@�R���匠���v�A�u��Ր_�@��R��_�v�̐Β��������܂��B
�V��5�N(1834)���܂�̍����B���͊p��t���A�݂ɂ͓������Ɍ�������܂��B
|
|
�����}�_�Ё@�@�@�����s��
|
��Ր_�@��R��_
�A���o�l�ׂ͔̑吙�_��(���}�_��)�̂��ƂŁA���u�ގU�A�n����̈��S�̐_�A�܂����_�Ƃ��Ēn���̐M���W�߂Ă��܂��B�Ղ�ł͐_�Ђ��o�������_�`���n������������A��V��E���V�炪���q�������A��ĉƁX��K��A���������Ət�̎��G(���ƂԂ�)���s���܂��B�V�炪�擱����_�`�̂��Ƃɂ͉��䂪�����A���̏�ő吙���q��l�X�ɉ��������āA�Ղ��グ�ĕ����܂��B�A���o�l�́A�ׂ̑吙�_��(���}�_��)�̂��ƂŁA�u�A���o�v�Ƃ͑吙�_�Ж{�Ђ̂����錧��~�S�u���g�v�̒n���ɗR�����Ă��܂��B
|
|
�����R�s |
|
�����������{�@�@�@���R�s����
|
�_�Ђ͓V��3�N(1534)�ɕ������Ɣ������̋��𗬂��b�g��Ɋ����~�̐[��A�z�J�C(�����ł́u�O���v�A�u�s��v�Ə����A�ؐ��̊ۂ��e��̎��B�؍ނ𔖂����H���A������Ȃ��Ďd�グ�鎖�ŋ��x�𑝂������̂ł����A�d�����y���e��Ȃ̂ōs�y�ٓ̕����A���s�E�g�s�H��Ƃ��Ďg���܂����B�H�c���ŗL���ȁu�܂�����ρv���v���o���Ē�������A�z���ł���Ǝv���܂��B)�ɓ��������_�̂����ꒅ���A�n�����ꂽ�͗l�ł��B�����{�Ȃ̂ŁA��Ր_�͗_�c�ʖ��Ǝv���܂��B
���������{�̌Î���Ƃ�����A�������̖��c�肪����������M�d�ȍՂ肪�L���Ȃ悤�ł��B����͋߂��𗬂��b�g��Ő[��̎ᐅ���݂���n�܂�A���̐��ŐԔт𐆂��_�ւ̋����Ƃ��܂��B���̌㋟�����������s��͓��ԑg�̏h���甪���{�ւƌ������_���̌�A�����ɒ݂邳�ꂽ�S�̖ʂ�I�ɋ|����˂�B����͋S�A���Ȃ킿���삪���ɓ���̂�h�����Ƃ���s���ł��B���̏o�����}�ɁA�����̍s�Ղ�̓��ԏh���o������̂Łu���̏o�Ղ�v�Ƃ��]���Ă��܂��B
|
|
�����v���@�@�@���R�s���v��
|
�ʖ��F������A�T��A����
�z��N �������㖖���@�z��ҁE��� ���R��
�v����(1155)�N�ɏ��R�������A��c�����G�����V�c�̗����莞�ɕ����咲���̂��߂ɋ����V�����J�����n�ɒz�邵���Ƃ����B�i����(1381)�N�A���R�`������x�ڂ̋����Ŋ��q�{�E���������R�ɔj��A���v���t�߂̖k�R���N���ʼnB�����āu�i���v�ƍ������Ƃ����B���̌�A�`�����L��������Ă��ĎO�x�ڂ̋������������A��s��Ŏ��n�����B
�퍑�����̓V���N�Ԃɂ́A�L�����E���R�G�j�Ƃ��̎���̌�����E���鐰�����k�������Ɣ��k�������ɕ�����čR�����J��Ԃ����B����������˂����|�`�d�E����J�d�o������ƂȂ�A��l��k�R�̒n�ʼn�����Ęa�k���A������L�O���Ėk�R�̒n���u���v��v�ɉ��߂��Ƃ����B�܂��A�V����(1581)�N�̖k�����Ə���A�V���\��(1584)�N�̌��鐰������Ȃǂɂ��A���v�����ӂ��k�𐨗͂Ɣ��k�𐨗͂́u����v�ł��������Ƃ��킩��Ƃ����B�V���\�l(1586)�N�ɖk�������炪�L����ɓ������ۂɂ́A���k�𐨗͂͌����E���v���Ŕ������ł߂Ă����B
�V���\��(1590)�N�̏��c���̖��Ŗk�������łԂƁA���鐰���͉ƍN���j�̏G�N��{�q�Ɍ}���Č����𖾂��n���A����͒��v���ɉB�������B�c����(1603)�N�̌���G�N�̉z�O�]���ɔ����p��B
��
���R���̑���B�߂��ɂ͌���Ə��R�����ԊX��������A���Ƃ��Ƃ͂��̊X�����Ď����A���R�̂ƌ���̂��q���u�q���̏�v�������Ǝv���܂��B
���������v��邪�傫���N���[�Y�A�b�v�����̂́A�ނ��댋�鎁���猩���u���ڂ̏�v�Ƃ��Ă̖����ɂ���܂����B�V���N�Ԃɂ��L���邪�k�����ɐ�̂���A�L����͖k�����Ƃ̖k�֓��U����n�ƂȂ�܂��B����ɋ��Ђ�������̂�������̌��鐰���B�����͏��R�G�j�̎���ɂ�����܂����A�k���Ə㐙�̊Ԃ��s�����藈����A�����c��̂��߂Ȃ�ΌZ�̋�������U������Ƃ����A�`�U��\��ʘI���ȁu�����c���v���������l���ł��B�k�����L�����D��ꂽ�Z�E�G�j���A�������ɂ��̒�𗊂�C�͂��Ȃ������悤�ŁA����̂�ʂ�z���č��|���ɔ�����߂Ă��܂��B
�Ő����A���悢��k���������ׂ��L����ɐw���Ɏ����āA�u����̓}�W�Ń��o�C�v�Ǝv�������A��������͔��k�𐨗͂ɏ�芷���A�F�s�{���j����{�q�܂Ŏ���āA�k�����Ɍx���ɂ�����܂��B���̍őO���ƂȂ����̂����̒��v���ł����B�����ēV���\��(1590)�N�A�k�������łсA����ɘA�����Ď��Ƃ̏��R�����ł�ł��܂��ƁA�����͗{�q�ɖL�b�Ƃɗ{�q���肵�Ă����ƍN���j�̏G�N��{�q�Ɍ}���A�����͂��̒��v���ɉB�����܂��B�F�s�{���̗{�q�́u�ԕi�v�A�����Ď��ƂƂ́u���ڂ̏�v�ł��������̒��v���ʼnB���E�E�E�}�����_�o���Ă܂���A���̐l�B
|
|
���{��_��(��������)�@�@�@���R�s�{�{��
|
���Њi�͋��ЁB�Ր_�@�fᵚj��(�����V��)/��ȋM��/�_�c�ʖ�(�����_)�B
���̐_�Ђ͎Г`�ɂ��A940�N(�V�c3�N)�����G�������݂̏��R�s���v��ɑn�������̂Ɏn�܂�Ƃ���A���ݒn�Ɉڂ����͕̂����N��(1159�N – 1160�N)�Ƃ����B�����ɂ͏��R���̐��h���Ă��A���R��̎��_�Ƃ��ꂽ�B���͏��R����ɂ������Ƃ���邪�A�]�ˎ��㏉���A���R�˔ˎ�ƂȂ����{�c�����ɂ���Č��ݒn�Ɉړ]���ꂽ�Ƃ����B
���R��̕ʖ��ł���_����̖��͂��̐_��(�_����)�ɗR�����Ă���B���R�s�S��A��ؒ��A�������n��A�����A���c�ђn��Ȃǂ��܂ށA���R�Z�\�Z���̑�����ł������B1605�N�ɂ͏��R���{���������v50����i����A�̂���15�̎��n��F�߂�ꂽ�B
�Q���͋������X���ɖʂ����ʂ肩��n�܂��Ă��邪�A���݂͓��H�ɂ���ĕ��f����Ă���B�����ɂ͏��R���₻�̑c�ł��铡���G���̌����肪����B�܂��A�V��}�ɑ��������؏t�Y�͂��̐_�Ђ̐_�E�̎��j�ł���A�ނ̌���������Ă��Ă���B�Гa�̓쑤�ɂ͎��c������B���̎��c�͖{���_����ɂ������ł���Ƃ̂��ƂŁA���R�̓`���ɓo�ꂷ����́B�܂��A�Q���e�ɂ���Β�����1653�N�ɑ������ꂽ���̂ŏ��R�s�ł͍ł��Â����̂ł���A�����ł���ԖڂɌÂ������ł���B
|
|
�����R��@�@�@���R�s��R��(���썑�s��S���R)
|
���{�̏�B�ʖ��͋_����(�����傤)�B�n���ł͎�ɋ_����ƌĂ�Ă���B��Ղ́A�_����Ղ̖��̂Œ��v���ՁA�h��ՂƂƂ��ɏ��R����ՂƂ��āA���̎j�ՂɎw�肳��Ă���B
���R��́A1148�N(�v��4�N)�ɏ��R�����ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ̓`��������B���R���͕������ɖ{�̂�L�������G���̌���Ə̂������c���̏o���ŁA�������͂��߂ĉ��썑���R�ɈڏZ���ď��R���𖼏�����B
���R��͒��v���A�h��ƂȂ�сA���q����ɉ��썑���߂����R���̎�v�ȋ���ł������B�����͘h��̎x��ł��������A��k������ɏ��R�ג�������Ƃ��Ĉȗ��A���R����X�̖{��ƂȂ����B1380�N(�N��2�N)����1383�N(�i��2�N)�ɂ����ċN���������R�`���̗��ł́A���R���̋��_�Ƃ��ĕ��������ɋL���ꂽ�h��A����A�V�X��A�_����A�h��̂����u�_����v�����R��ƍl�����Ă���B���R���͋`���̗��Ŋ��q�{�ɂ��Ǔ�����f�₵�����A�����̌���Ƃ���{�q���}���čċ������B
���̌�́A��X���R���̋���ł��������A�V��4�N(1576�N)�ɏ��R�G�j���k�����ɍ~�����ĊJ�邵�A�k�����̎�ɂ���ĉ��C����A�k�֓��U���̋��_�ƂȂ��Ă���B
���c�������̂̂��A1602�N(�c��12�N)���A�{�����������͍��ʓ�������������A������1619�N(���a5�N)�ɉF�s�{�ֈڕ��ƂȂ�A���R��͔p��ƂȂ����B
��������ɂ͑���O�c�@�c���ł����������̕ʓ@�����Ă�ꂽ���A�������Ă͂��炸�A���@�����őb�Ǝv������̂��m�F���ꂽ�B
�ʖ��ł���_����͏��R���̎��_�ł���_����(���{��_��)����Ƃ������̂ł���B
|
|
�����@��(�����ڂ���)�@�@�@���R�s�{����
|
�V��@�̎��@�ł���B
849�N���o��t�~�m�ɂ���Ĉ�F����������A���y�@�ƍ������̂��n�܂�Ɠ`������Ù��ł���B
940�N�ɓ����G�����_�����z�邷��Ə���Ɉړ]���A�����R���y�@���@���ƍ������Ƃ�������B���̌�͏��R���̋F�菊�ƂȂ����B
�]�ˎ���ɂ͖��{����9�̎��̂��F�߂�ꂽ�B�܂��A�����ɂ͕�C�푈���̗���e�̍����c��Α���n����������B
|
|
�����ߎ�(������)�@�@�@���R�s�{�{��
|
|
�V�c�N��(940�N��)�����G�����̊J��ŁA�����͖@���@�ɑ����Ă��܂����B�i�m5(1297)�N�A���@��c�����^����l�����̒n���������������A���@���@(���R����)�ƂȂ�܂����B
|
|
���Ԍː_�Ё@�@�@���R�s�Ԍ�
|
�����Ё@���욠����S ���`�_��
�����i��
��Ր_�@�c�S�P��
�z�J�@��R�_�_ �V�Z������
�n���N��͖��ځB�}�O�̏@��(�ނȂ���)�_�Ђ���̊����Ɠ`�����A�����E���`(�ނȂ���)�_�Ђ̘_�ЂƂȂ��Ă���B�Ж��̓ǂ݂́A�����ɂ���ẮA�u�A�W�g�v�u�A�~�g�v�Ȃǂ��������B�n���̖Ԍ˂́A�u�A�W�g�v�ƓǂށB
�����ɂ́A�傫�ڂ̋����Ђ��A��ׂƔ���̓�B�������K�ɂ́A�����A�c�{�A�k���V���{�B���̑��ɂ�����̐��K������ł���B
|
|
���u�t�����r�v�`���@�@�@���R�s����
|
�����̖k�̂͂���ɁA�t�����r�ƌĂ��A��1�D5���[�g���l���̂��ڒn���������B���ẮA�F�쌠���̋����ŁA�_���Ȓr���������A���̂��납�Гa�͋����ʂāA�r�����߂��Ă��܂����B
����Ƃ��A���l�����̂��ڒn�ɌL����ꂽ�Ƃ���A�����܂��|��Ă��܂����B�ʂ̐l���������Ƃ�������A���_���Ă��܂����B���ꂩ��A�������k���Ĕ��ɂ��悤�Ƃ���l�͂��Ȃ��Ȃ��āA���܂ł��n�Ƃ��Ďc�����Ƃ����B�t�����r�̖��O�̗R���ɂ��ẮA
�����G���̉������j�q���o�Y�����ۂɐԎq�������Ƃ������ƁA���̒r�̂قƂ�Ŗ��N��l�̒t�����тɂ����Ƃ�����������B
|
|
���ԁX�c�����{�@�@�@���R�s�ԁX�c
|
��Ր_�@�_�c�ʖ��@�����ѕP���@
�Њi���@������
�n���@�@729�N�`749�N(�V���N��)
�n���͓V���N��(729�N�`749�N)�Ɠ`������B
939�N(�V�c2�N)�A�����哢���ׁ̈A�����G�����폟���F��B���肵���̂��A���̂��_���ւ̉��Ԃ��Ƃ��Đ_�c���[�����B�ȍ~�A���̈�т͔ѓc(�܂�܂�)�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����B
1189�N(����5�N)�ɂ́A���B�����������Ɍ��������������Q�q�B�����ɏ���A����B���̏��́u������A���̏��v�Ƃ��Ď��q�Ɏ���Ă������A1905�N(����39�N)�Ɍ͎������B
�]�ˎ���ɂ͒���������Ɍ��킳�ꂽ�ᕼ�g�������K���Q�q����K�킵�ƂȂ��Ă����Ƃ����B
|
|
�����[�_�Ё@�@�@���R�s���{
|
�Ր_�@�V���ʖ�(���߂̂ӂƂ��܂݂̂���)�@�p���t�Y�q��(�����̂킫������݂̂���)
�Њi���@������(��)�@������
�Г`�ɂ��ΐ��_�V�c��̑n���ł���A�m���V�c��ɍČ����ꂽ�ƌ�����B�w���쎮�x�ɂ́u���[�_�Ёv�Ƃ��ċL����Ă���B
939�N�A�����G���������哢���ɍۂ��Đ폟���F�肵�A�З̂���i�����Ƃ��`������B�����ɂ͈��{�ƌĂ�A���R���E���쎁�E���鎁�E�É͌����Ȃǂ̐��h�����B
|
|
���h�_�Ё@�@�@���R�s�O��
|
�h��Ղɒ�������h�_�ЁB
���j�Ձ@�h���
�N���N(1380)����i�����N(1382)�ɂ����ď��R���\��̋`���́A�O���ɂ킽���Ċ֓�����(�������R�Ƃ̕���)���������̌R���Ɛ킢�܂����B�u���R�`���̗��v�ƌ����܂��B���̗��̌����́A���͂��g�債�����R�`����}�����悤�Ƃ��鎁���̍��d���������Ƃ���A���̎w�߂����֓��e�n�̕��m�������A���R�ɍU�ߊ܂����B�ŏ��̖I�N�Ŋ�(�_���J�̋ȗւ�)���U�߂�ꂽ�`���́A��x�ڂ̖I�N�ƂȂ�N��O�N�ɂ͘h��ɗ����Ă����Đ킢�܂��B�������`���͌��ǔj��A���̗��N����(���쒬)�Ŏ��E���܂����B�h��͎v���J�n�E�Ꮌ�n�Ɉ͂܂ꂽ�v�Q�ŁA������400m�A��k��600m�ŁA����ƊO��̓�̊s����Ȃ�A�����Ƃ��Ă͍L��ȏ�s�ł����B����̋�x�E�y�ۂ����ĂɎc�����A�h��̖��̗R���ƂȂ����h�_�Ђ��������Ă��܂��B��k������̏�s������قǂ悭�⑶���A�֘A���镶�������������`�����Ă���̂͂���߂ċH�ȗ�ŁA�M�d�Ȏj�Ղƌ�����ł��傤�B
��
�w��Ր_�@��ȋM���@�V�c�N��(938�`47)�̑n���B�����G�������������̐܁A�������h�{���_�ɏ��哢�����F�肵�A���̌�A����ɉ������A���썑���R�ɘh�{���_�����������̂��A���Ђ̑n���ł���Ɠ`�����Ă���B���̌�A�ߋ��ߍ݂̐l�X���q���̕��ׁE�S���P�������ȂǁA�a�C�����̌�_������M����A��Փ��ɂ͗��̎��^�ƕ�[�������āA��ɓ�����Ă���B�����ܔN���ЂƂȂ�x
�Ȗ،��_�Ў��ɂ͏�̂悤�ɋL����Ă���A���������c���̘h�{�_�Ђ��珬�R�`�������̏�Ɋ������A����ɂ��Ȃ�Řh��Ɩ��t�����Ƃ�����̂ŁA�����Ƃ����R�`�����������̌���p��������E�ƂȂ������a�l�N(1335�B�쒩�̌����ł͐����\�N)�ȍ~�B�����ܔN(1372�B�쒩�̌����ŕ������N)���̒z��ł��낤�Ə�����Ă���Ƃ�����������̂ŁA������̘h�_�Ђ̑n�������̂�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B���Ȃ݂ɕ��������c���͓����G���̌���ł��鑾�c���̖{���n�ŁA���R���͂��̑��c������h�������ꑰ�ł��邱�Ƃ���A�h�{�_�ЂƂ̉����������̂��낤�B
|
|
���h��(�킵���傤)�@�@�@���R�s�O��
|
���썑���R���ɂ��������{�̏�B��Ղ́A���v���ՁA�_����ՂƂƂ��Ɂu���R����Ձv�Ƃ��āA���̎j�ՂɎw�肳��Ă���B
�z��N��͕s���B���R���́A���q����ȗ����썑�̎��ɔC�����A������ʂ��ĉ��썑�ő�̍����ł������B
�h��͒��v���A�_����ƂȂ�сA���R���̎�v�ȋ���ł���ƂƂ��ɁA1380�N(�N��2�N/�V��6�N)����1383�N(�i��2�N/�O�a2�N)�ɂ����ċN���������R�`���̗��ɂ����Ė{��Ƃ��Ă̖������ʂ������B���ɂ����鏬�R���̋��_�Ƃ��ĕ��������ɋL���ꂽ�̂́A�h��̂ق��A����(���v���)�A�V�X��A�_����A�h�邪����B
�����A�E��A�y�ہA�x�̍��Ղ��c���Ă���B�{�ۂɂ͖��̗R���ƂȂ����h�_�Ђ�����B�O��͑�n������A�n���ƂȂ��Ă���B���R�����������אڂ��Ă���B
|
|
�������_��(�Ƃ���)�@�@�@���R�s�厚�쏬��
|
��k������ɁA���R�����c��ł��铡���G��������`������Ƃ��������[���Đ폟�F������������瓌���_�ЂƌĂ��悤�ɂȂ����ƌ������Ƃ����A����Ƒn���͍X�ɌÂ����ƂɂȂ�̂��낤�B�����A�R�����v���Ր_�͕s���B
��
�����_�Ж{�a�@���K�͂Ȉ�ԎЗ����̖{�a�ŁA�����͖؉H�����A�����t���̉����܂킵�ė������ɘe��q�𗧂āA�O�ʂɌ��q��݂���B�����{�͕̂�����N(�ꔪ���)�Ɍ��݂��ꂽ���Ƃ��������铏�D�ɂ���Ēm���邪�A���̖{�a�̑傫�ȓ����́A��\�N�قnj�ɕt��������ꂽ�ƍl������L�x�ȑ��������ɂ���B
���Ȃ킿�A���H�ڂƘe��q�ɂ͒����̌̎����ނɂ����������������͂ߍ��܂��ق��A�ؕ@�̏ۂⓂ���q�A���q������̗��Ȃǂ��ے������ƂȂ�A���ԁA�ȏ��A�����A�������ǂɂ��Ԓ���g�A���A�T�Ȃǂ�����������������������{����Ă���B��������O�ނ�f�̂܂ܗp���Ă���A���I�Ő��������Ƃ����\���́A�����e�n�̂��̎����̐_�Ќ��z�̒��ł��������z���������ւ��Ă���B
�Ȃ��A���H�ڒ����̍�҂́A�w�ʂɍ��܂ꂽ���ɂ���āA���쐏��̒�����H�W�c�Ƃ��Ēm��ꂽ��粈ꑰ�̖��H�u�㓡�������G�v�ł��邱�Ƃ��m�F�ł���B
|
|
����쓇�_�Ё@�@�@���R�s��쓇
|
�����G���������哢���̍ۂɑn�����A�����ɂ͑y�匠���ƌĂ�A���R�s�����A�啽���Ȃǂ�̈�Ƃ������̑��ЂƂ��Č������h����Ă��������ł��B�����͌����Ђ������荡�����ĎВn�͍L���̂ł����A�E�������Q�[�g�{�[����ɂȂ�A���̓������������n��̕��B�����K�ɗ��ł�������Ⴂ�܂����B���A�����ɂ͍]�ˊ��̍�����������Гa�̒���������������Ə[�����\�����Ă��炢�܂����B
��
��Ր_�@��ȋM���@
�z�_�@��龗�_�m���������݂̂��݁n�@���̔z�_�ɈɎדߊA�Ɏדߔ����A�ΎY�˖��A�؉ԍ��P��
�_�Ђ̓�𑖂铹�H�͎��́u�����ᕼ�g�X���v�ł���B�Q�n����̑q���h���N�_�Ƃ��A��쓇�̐��k�サ�ď��R�h�A�p���h�A�����h�Ɣ����Č��݂��c������ЂƂ̐����̓������X���E�ᕼ�g�X���ɂȂ���B�L���ȕ��̐����E�����X���Ƃ͍��s�ō�������B
�����������j��w�i�ɁA�����̖��_�����́u���\�l�N�v1691��320�N�O�̌Â����̂ł���B
�����G���̊����œV�c�O�N940�ɏ��R���A���A���䏯�̑y�ЂƂ��A�u�y�����v�Ə̂������A�]�˖����Ɂu�y�_�Ёv�A�������N�Ɂu��쓇�_�Ёv�Ɖ��́B
�u��i�Z�N1709�v�Č��̖{�a�B�萅�͂����ƌÂ��A�����{�݂Ō����ɂ������u������ȓэ�1669�v�Ɠǂ߂�B
�{�a�@�������Ε��@�q�a�@���ꉮ��������
|
|
���͌��c�_�Ё@�@�@���R�s���͌��c
|
|
�@ |
|
�����o�@�@�@�@���R�s���
|
|
���Y�̌䗘�v������u����������v�ω��́A33�N��1�x�A���J������܂��B
|
|
�������x�V�ˌÕ��@�@�@���R�s�厚�ђ�
|
�Ȗ،����R�s�厚�ђ˂ɂ���Õ��B�`��͑O����~���B���̎j�ՂɎw�肳��Ă���B�Ȗ،��ł͑�3�ʂ̋K�͂̌Õ��ŁA5���I��(�Õ����㒆��)�̒z���Ƃ����B
�Ȗ،��암�A�v��E�p��ɋ��܂ꂽ��n��ɒz���ꂽ�Õ��ł���B�Õ��͑O������쐼�Ɍ�����B���u�͎��R�̔����n�𗘗p���Ēz����Ă���A���u��ɂ͉~�����ւ�����Ȃ��đ��݂��Ă���B�z�������ɂ��ẮA�Õ��̌`���o�y���ւ���5���I���Ƃ����B
�{�Õ��̖k���ɂ͓�������K�͌Õ��ł�����i�ˌÕ�������A�Ƃ��ɉ��і�n����\�����Ƃ����B���Õ��z������A�v��E�p��Ԃ̑�n�̖k���ł́u����^�Õ��v�ƌĂ��Ɠ��̑O����~���Q���c�܂�Ă������B
�Õ����1978�N(���a53�N)7��21���ɍ��̎j�ՂɎw�肳��A2002�N(����14�N)9��20���Ɏj�Ք͈͂��lj��w�肳�ꂽ�B
|
|
�����h���@�@�@���R�s����
|
|
����ω������ÂɘȂނ����ł��B�s�w��L�`������(����)��ۗL���Ă��܂��B
|
|
�������{�@�@�@���R�s������(�����Ȃ܂�)
|
���n���@�����䎚����
��Ր_�@棓c�ʖ��@�����Ё@�����_�ЁE���_��
�v��Ɣb�g��ɋ��܂ꂽ�L��ȓc���n�тɂ���傫�ȓm�ɒ����B������̉͐��������œn�ǐ���ɍ�������B
�V�c�l�N941�R�鍑�j�R�����{���䕪����������đn���B
�Ѝ��W���u���w��v�ƌ����Ă��܂����A���́u���v�Ƃ́u�_�a���嗿�v�̗��B
�������N1796��������ɏ��a�Z�N1931�����{�Q���L�O��B���̍��̊ۂ��́u�͐v�ƌĂ�A�����\���q1828�B�u�O�\��Y�ځv�͏d�ʂ��B
�吳�l�N1915�Ѝ��W�B�����O�N1806�����B�����\�V1827�萅�B
�q�a���Ɂu�����_�{�v�z�A����ɔG�B
|
|
���F�s�{�s |
|
�����g�_�Ё@�@�@�F�s�{�s�É�u��
|
��Ր_�F��R��@�����ЁF�镔�_�ЁE���Ð_�ЁE���a�_�ЁE�����_�ЁE�P�a�_�ЁE���c�F�_�ЁE�����_�ЁE��א_��
��J�X���E��R�����w�Z�̓��A��J�X�������ɐ����l�N1714�̌É�u�ΐ����������X���镗��ŗ����Ă���B��b�R�̍�{�R�����������������N1104�ɑn���B�]�ˎ���ɂ͎R���匠���Ə̂������ېV�ɍۂ��ē��g�_�Ђɉ��̂����B�����e�̗R�������ɂ���Ր_�͓��ɂȂ��Ă��邪��R��Łw����_�Љ��v���x�ɍ��v����B�w�Ȗ،��_�Ў��x���a39�N�ł̑�R�_���͌�A���B
�w�Î��L�x�ɂ��Α�R�Ì��_�̖��̐_��s���̂��ނ��ق����Ђ߂��{���V�j���Ƃ̊Ԃɑ�N�_�ށB��N�_���V�m�ޗ��������̂��߂�����݂ÂЂ߂�W���đ�R�����܂��А_�ށB�܂��R�_������܂ݐ_(���{���I�̕\�L)�̑�����R��_�A�ʖ��R���V���_�ł���B�w�Î��L�x�ł͑����āu���̐_�͋ߒW�C���̓��}�̎R�ɍ����A������̏����ɍ����āA�L��p�_���v�Ƃ���A����������}�_�ЂƏ����_�Ђ̍Ր_�Ƃ����J����B��O�܂œ��g�́m�Ђ��n�Ɠǂ�ł����B�m�Ђ悵�_�Ёn�ɂ�������Ђ����邪�A�m�Ђ��_�Ёn�̂܂܂̎Ђ������B�w�Ȗ،��_�Ў��x�̓ǂ݂́A�����́m�Ђ��_�Ёn�B
��
��Ր_�@��R��@/�@�������N(1104)�F�s�{���E�@�j�̎���ɁA��b�R�̍�{�R�����É�u�R�[�̍��É��Ɋ������A���̌�A�V�����N(1573)�F�s�{�Ɛp�����̍���ɂ��Гa���Ď������̂ŁA���ݒn�ɑJ�����ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�����ɂ͌É�u�̒n���̗R���̓`�������u�Â��~�̖v������A���q�a�͑吳����ɍZ��ɂ������ω������ڒz�������̂ł��B�@ |
|
���F�s�{��r�R�_�Ё@�@�@�F�s�{�s�n��ʂ�
|
��Ր_�@�L����F��
�Њi���@������(���_��)�_��/���썑��{/����������/�ʕ\�_��
�n���@�@(�`)�m���V�c41�N
(���݂̂�ӂ������܂���A-�ӂ����܂���)�@������(���_���)�_�ЁA���썑��{�B���Њi�͍������ЂŁA���݂͐_�Ж{���̕ʕ\�_�ЁB�_��́u�O�b(�e�ɎO�b)�v�B�������͓̂�r�R�_�Ђł��邪�A�����̓�r�R�_��(�ӂ��炳��)�Ƃ̋�ʂ̂��߂ɒ����n���������āu�F�s�{��r�R�_�Ёv�ƌĂ��B�Â��͉F�s�{�喾�_�ȂǂƂ��Ăꂽ�B���݂͒ʏ̂Ƃ��āu��r����v�Ƃ��Ă��B
�F�s�{�s�̒��S���A���_�R(�P����A�W����135m)�R���ɒ�������B
��������߂��Ƃ���L����F�����Ր_�Ƃ��ČÂ���萒�h����A�F�s�{�͓��Ђ̖�O���Ƃ��Ĕ��W���Ă����B�܂��A�ЉƂ��畐�ƂƂȂ����F�s�{�����m����B�Гa�͑n���ȗ����x���Ђɑ����Ă���A���݂̎Гa�͕�C�푈�ɂ��Ď���̖���10�N(1877�N)�̍Č��B
�������Ƃ��āA���F��̏d�v���p�i�ł���O�\���Ԑ����A�S�������Ȃǂ�L���Ă���B
��
�F�s�{��r�R�_�Ђ́A�S�ݓX�Ȃǂ��������Ԓ��S�n�́A�W����135���̐_���R�R���ɒ������Ă��܂��B
����܂ʼn��x���Ђɂ����Â��j���̂قƂ�ǂ��������Ă��܂����A�ЋL�ɂ͍������1600�N�O�ɖі욠���㉺�̓ɕʂ����A��Ր_�L����F���̎l�����ޗǕʉ�(�Ȃ�킯�̂���)�����і욠�̍����ɔC����ꂽ���A�c�_�ł���L����F�����r����(���V�{)�ɍՐ_�Ƃ����J�����̂��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B��̏��a5�N(838)�Ɍ��݂̒n�P����ɑJ���ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B
���쎮�E�_�����ɂ́u���욠�͓��S��� �� ��r�R�_�� ���_��v�Ƃ���A�F�s�{�̓�r�R�_�Ђ����욠��V�{�Ƃ����Ă��܂��B���݂͒ʏ́u��r����v�ƌĂ�Ă��܂��B
|
|
�����{�_�Ё@�@�@�F�s�{�s�V����
|
��Ր_�@��ȋM��(�����Ȃނ��݂̂��ƁE�卑�喽)
��������A������̗������������G���̎l�j�A������킪���̋��ɓy�����A����3�N(992)������r�R�_�Ђ���Ր_���������A���{�_�Ђ�n�������B
|
|
���S�ڋS(�ǂ��߂�)�ʂ�@�@�@�F�s�{�s
|
�S�ڋS�ʂ�́A�����O�ʂ�̈�{��Ɉʒu���܂��B�ʂ�̒�����150���[�g���قǁB�F����́A���̕S�ڋS�ʂ�̖��O�̗R�����������ł����B�F�s�{�̖��b�Ȃǂł́A��������b���c����Ă��܂��B��������A�F�s�{�ŕS�C�̋S�̓��ڂł���u�S�ڋS�v�������G���ɂ���đގ�����܂����B����400�N��A�������c�ɂ������{�莛�̏Z�E�q����l���M�S�ɐ��������Ă���ƁA���̐����ɖ����p����������������������܂����B���̐��̂͂��́u�S�ڋS�v�ŁA�̂̈З͂����߂����ƁA�����ŗ����������z����邽�߂ɗ��Ă����̂ł��B�������A��l�̐����������ɉ��S���A�p��܂�A�܂����������A�Ƃ������̂ł��B
�܂��A�n���ɂ͕ʂȌ����`��������܂��B�́A���̋ߕӂ͔����R�Ɠ�r�R�̎R�ԂŁA�R�ɂ͂�������̎R��������ł��܂����B�R�������̖ڂ�����Ɍ���S�̖ڂ̂悤�Ɍ������̂ł��傤�B�S�̌���S�̖ڂ���A���̕ӂ���u�S�ڋS�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ������̂ł��B
�I���́A���̒ʂ肪��������r�W�l�X�X�ɋߐڂ��Ă������Ƃ���A�������Ȃǂ�����A�˂�悤�ɂȂ�A�ߋA��̐l�X�ł��Ȃ�̂ɂ��킢�������Ă��܂����B�����͎��������̏�A�Ƃ��đ��������ʂ������̂ł��B�������A���݂͓X�������ĐՒn�͒��ԏ�ƂȂ�i�F�͕ς���Ă��܂��܂������A�܂������̂悤�ɐԒ��������A�ɂ��킢��������S�ڋS�ʂ�ɂȂ��Ăق����Ɗ���Ă��܂��B
�u�S�ڋS�v�̖����c���Ă���͍̂��ł͂��̒ʂ�Ǝ�������ł����A�ƂĂ�����������܂��ˁB�S�ڋS�Ƃ����`���I�Ȓn���͒m���x������A�݂������L���ł��B���S�s�X�n�ɂ��z���̍ۂ́A���ЁA���̕S�ڋS�ʂ�ɗ�������āA�`���Ɏv�����͂��Ă݂Ă͂������ł��傤���B
���u�S�ڋS�v�`��
�������N���́A������Ƃ����������A���̒���ɔ�����|���āA����������(���݂̈�錧�̉���)�ɂ����āA�����V�V�c�Ɩ�����đ��ʂ��悤�Ƃ������Ƃ�����B�����������͒ʂ�Ȃ����̂ŁA����͒��삩��h������Ă������������G����̐s�͂ɂ���āA�����łڂ���Ă��܂����B���̓��������G���́A�Ⴂ���́A���������ȗ��\�҂ł��������A�ߍ]�ɂ����đ�S��(�����ނ���)��ގ����Ĉ������y���������ŁA���̘r�͂����҂���āA�����̕�����̗��ɔh�����ꂽ�̂ł���B���̏G�����A���썑(���݂̉F�s�{�s��\������)�ɍ����|���������A�ˑR�����̘V�l������āA�G���ɂ����������������B
�u���Ȃ��́A�����̂��߂ɁA���S��ގ�����ɂ����ƕ����B��\���ɂ��̈��S���������B�����ł����҂����v
�G�����A���̏ꏊ�܂ōs���ƁA�����Ȃ�ʉ_�s���ƂȂ�A���������āA���̕S�ڋS�Ƃ������S�����ꂽ�̂ł������B�g�̏��3������B��ɂ͕S���̖ڂ������āA�������A���łɑ�S����ގ������G���ɂƂ��ẮA���̐��ł͂Ȃ������B�����Ƌ|�������āA�����ƁA�S�ڋS�̐S�̑��ɓ˂��h�����āA�ꂵ�݂Ȃ��瓦���Ă������B�G���̕����B�́A���̌��ǂ��āA���_�R�̕ӂ�܂ōs�������A�S�ڋS�͍Ō�̗͂�U��i���āA�̂���Ή���f���A�߂Â����Ƃ��o���Ȃ��L�l�ƂȂ����B
�����ɖ{�莛�̒q����l�Ƃ����m��������Ă��āA�@�͂������āA�u���A�䂪�@�͂ɂ�蓾�x����v�Ǝ�����������ƁA�S�ڋS���甭���Ă������͏����āA�l�̎p�ƂȂ��āA����ł������B�ȗ��y�n�̐l�X�́A���̒n��S�ڋS�ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����̂ł���B
|
|
���������ˁ@�@�@�F�s�{�s��������
|
���s�ŎN����ɂȂ��Ă�����������̎���̓��̂����߂Č̋��ł���Ⓦ�ɔ�ї����A�͐s���ė������ꏊ����˂��ƌ����`�����Ă��܂��B������̎�˂��Ƃ�����j�ւ͋��s����֓��n���ɂ����ď\���ӏ��͂���̂ł����A �ł��k�Ɉʒu����̂�������̎�˂ƂȂ�܂��B�����͏�����̎������ꏊ�ł͂Ȃ��A������̉��҂ɂ���Č��Ă�ꂽ���{���Ȃ̂ł����Ȃ����u��ˁv�ƌ����K�킳��Ă����B
��
���̏��叫��͍��]���̑��ŁA���ǎ��͉������L�c�S�Ɋق��\���A����{���R�ɂ��Ȃ����B����̎x�z���鉺���O�S�̊O���ɂ́A�ނ̏f�����������͂��͂��Ă����B�N�Ⴂ����͖S���̈�̂̂��Ƃ⌋�����ő������N��A�ꑰ���m�̗��킢�����N���������B�V�c��N�A����͏헤�֍U�ߓ���A�X�ɏ��𗎂��֓��̑唼�����������B��������͏���ɏ̍����āu�V�c�v�Ƃ������B�V�c�O�N�A����͐����R�������A���吷������̓����G���̋��͂āA�����̊��Ő���ď�����n�����B�ނ̎���ɂ͔ނ�炢�ނ����ގ҂������A�֓���~�ɂ͒˂��Ղ������B�����ɂ��鏫��̎�˂̔�́A���̂̎҂����̒n�ɓق�A����̉�������߂Ɍ��Ă��{��ł���B
|
|
����龗(������)�_�Ё@�@�@�F�s�{�s��ˍՒ�
|
��Ր_�@��龗�_
�Ȗ؊X��(���ʂ�)�����������ɓ����O�̐��B����̓�B�J������ēc���͏��������̒��̐_�ЁB50�N�O�͓c���n�т������B����18�N���́w�Ȗ،��_�Ў��x�ł́m�����݁n���̍�龗�_�ЂƂȂ��Ă���B���v������龗�_�ЂŋL�^�B�{�a�z�́u�����_�Ёv�ɂȂ��Ă��܂����B���ɎЖ����������̂͌�������Ȃ��B
����ɍ�����16�̕ۑ����Ă���B
�u���n�����F���{���v�u���g���Y�q�獂�n�����v����������ɁB
�Â��Γ����z�R�̏�ɁB�u�����l���K����x���v�Ɠǂ߂�B�k���̉Ìc���N�Ɏ������d�Ȃ��Ă����1387�N�Ȃ̂Ō����̍����_�Ђ̒��ł͓ǂݎ���N��Ƃ��ẮA�����ς݂̂Ƃ���ł͍ŌÂ̐Γ��ɂȂ�B�u�������Ŏq�@������T�v���ǂݎ���B
�����Ђɐ��g�T�����̐��_�ЁA�f���j���̔���_�ЁA��R�_���̓��a�_��
|
|
����龗�_�Ё@�@�@�F�s�{�s���ˍՒ�
|
��Ր_�@��龗�_�@
�F�s�{�s�̒��S���A�����̐��A�������̖k���ƂȂ�B�����̒����z�͕������������ǂ݂ɂ������A�u��龗�R�_�Ёv��3�t���Ă���悤���B�u�R�v���t���̂͂������n�߂āB�q�a�̕�[�z�́u�J+罒+���v�ō�龗�_�ЁA�R�Ȃ��B
�u�ˍՎY�Γy��@������\��N�O���@���c���`��v�̒��قǂɁu��龗�_�v�̕���(�ԓ_��)�A���Ȃ��B
�u�V�ۏ\�܍b�C�\�ꌎ�g���v1844�̓�̒����B�u�����O���C�N�l���g���v1856�̒j铎R�Γ��āB������N�̌�_���B�吳�Z�N�̍����B�����O�\�O�N�\�ꌎ�g�˓��̓��c�f�����́u�q�a�V�z���[�v��B�u�吳�ܔN�����ܓ��v�̊}�Γ��ȂǁB�q�a�����ɐΒ����t���̐��K�Q��5��B�Ԃ�������������̂��Ɏדߊ̎O���_�ЁB���̉E�����ɑ卑�喽�̑吙�_�ЁA�{���V�j���̔���_�ЁB���E���[�͕s���B
��̒����Ɍ������č���͂���ɋ��O�ЂƂ��č�龗�_���J��u���_�Ёv������B�吳��N5��6���Ɉ�א_�Ђ����J���Ă���B�R�����v�ɂ��ΓV�c�O�N940�F�s�{��z��̍ۂɑn���B���{�O�ɒ������Ă������A�����ېV�Ŏ��ˍՂ��������߁A����6�N9��29���Ɍ��݂̒����n����ɑJ�������Ƃ���B���݂̎Гa�͏��a56�N�̂��́B���v���̍Ր_�\�L���獂龗�́m�^�J�I�n�ƌĂ�ł������Ƃ�������B�Ȗ،����ł́u���ɉ����v�u���������v�̕\�L�̕��������B��龗�����͒������B
|
|
����龗�_�Ё@�@�@�F�s�{�s������
|
���Ђ́A���m���N(��l�Z��)�ɑn������A�u��龗�_�v����Ր_�Ƃ���B
�S�{��E�ݍL���鐅�c�n�тɂ���A��鯎��ɂ́A�J�F���A�������ɂ͍^���������s���A�H�̖L���Ȏ����������J��ꂽ�B
����500�N�ȏ�Ɠ`�����鐙��3�{��A�Î�̒��ɐ����Ȑ_�Ђ�����w���߂Ă���B
|
|
�������_�Ё@�@�@�F�s�{�s�V�_
|
�Ր_�@�������^�A���孁�M��(�����Ђ�߂ނ��̂���)
�V��N��(1053〜1058)����������ł����������`�����̎q�`�ƂƋ��ɁA�������B�ɏ���\�����G�ƂȂ��Ă������{��C(���ׂ̂����Ƃ�)���U�߂܂������A�Ȃ��Ȃ����肷�邱�Ƃ��o���܂���B���̎��A�ߍ]��(�����ꌧ)�ΎR���̍���ŁA��ɉF�s�{����(�F�s�{�Ƃ̑c)�ƂȂ����@�~(���c�֔������̎O�㑷)�����G�����F�������A���̖{������J���C�R�̕s�������Ƃ����Ă��܂��B
���̏@�~�̗͂ɂ���Ē�C�����n���肵���Ƃ����A���̌��ɂ�艺�썑���E�ɔC�����F�s�{�ɋ����z���܂����B���̐܁A��̎l���ɓV���V�_���܂�A�������^�̒��v���F�肵���Ƃ����A���̓����ɓ�����Ђ����̐_�Ђł��B
���\���N(1688)�ɂ́A��剜������珹�K���Гa�A�����̑��c�A�����ĉÉi2�N(1849�E����ƌc(�����悵))�˓c�ƂɎ���160�]�N�̊Ԃɂ́A11��ɂ킽���ĎГa�̑��c�C�����s���A�����̓��D����������Ă��܂��B
����O���ڂ̓V���{���F�s�{��̐��̎��_�ɑ��āA������͓��̎��_�B
|
|
���V���{�@�@�@�F�s�{�s���
|
�Ր_�@�������^
�V�_�ڂ̐����_�Ђ��F�s�{��̓��̎��_�ɑ��āA������͐��̎��_�B
�@ |
|
���F�s�{��(�T������) 1�@�@�@�F�s�{�s�{�ے� |
��s�@�֊s��s����������
�z��@�������㖖���A�����G���܂��͓����@�~
�p��@1868�N
��ȏ��@���F�s�{���A�{�����A�������A�˓c��
�����j
�F�s�{�ɂ͉F�s�{�喾�_(��r�R�_��)���������A�O��N�̖�(1051�`62�N)�ɍۂ��A�����@�~(�F�s�{���̑c)�͌����`�E�`�Ƃɔ����ĉ��B�����ɕ����A���̌��ɂ���ē��_�Ѝ���̒n�ʂƖі��(�S�{��)�����̂̎x�z����^����ꂽ�B�N���Z�N(1063�N)�����@�~�ɂ���ĉF�s�{�邪�z�邳�ꂽ�B
�ȗ��A���q���ォ�玺������E���y���R����܂�530�N�ɂ���э��i�E���E�֓������`�ɗ��A�F�s�{��͉F�s�{���̋���(����)�ƂȂ�A�k�֓��x�z�̋��_�ƂȂ����B���̍��̉F�s�{��͒�����s�������Ƃ�����B
�퍑���㏉���ɂ͉F�s�{���17�㓖��F�s�{���j���������������邽�߂ɁA�F�ꍂ����d�E���A�F�s�{�����Ƃ���傫�ȓ������N���肻�̐��ƂȂ����Ƃ����B
�퍑�������ɂ͌�k������Ɛb�ł���p�����̐N�U���ꎞ�͂��̈�h�ɂ���Đ苒���ꂽ�B�V���\���N(1590�N)�̏��c�������̂̂��G�g�ɂ��F�s�{�d�u���s�Ȃ�ꂽ���A���̂Ƃ��ɉF�s�{��͈��g���ꂽ�B
�������c����N(1597�N)�G�g�ɂ��ˑR�̉��Ղɂ��A��\���F�s�{���j�͔p���ꂽ�B
����A��쒷��������A�c���O�N(1598�N)�ɂ͊����G�s��18���œ������B���̌��͓����A�������Ƒ������B
���a�ܔN(1619�N)�{������������A�F�s�{��Ə鉺�̉��C���s�����݂̉F�s�{�̑b��������B�V��͑��炸�A��d��K�̐����E�Ő������s�������A�����̈ӂɔ����ĉF�s�{����C�ɂ܂�鐳���d���̉\�����z����A���a���N(1622�N)�ɐ����͉��Ղ��ꂽ(�F�s�{��ޓV�䎖��)�B
���̌㉜�����A�����������A�{�����A�������A�������A�˓c���A�[�a�������ƕ���喼������ւ�����B�]�ˌ�����i�l�N�˓c����������A�ȍ~�˓c��7�オ6�`7���Ŏ��ߖ������}�����B
�c���l�N(1868�N)�l����C�푈�̐�n�ƂȂ�A�F�s�{��̌������͏鉺�̒���(3��˂̂���2��˂��Ď�)�Ƃ��ǂ��Ď�����(�F�s�{�푈)�B
|
|
���F�s�{�� 2 |
�Ȗ،��F�s�{�s�{�ے��ɂ��������{�̏�B�֓�������̈�B�]�ˎ���͉F�s�{�˂̔˒��ƂȂ����B�ʖ��A�T������(���߂��������傤)�B
��������ɓ����@�~����r�R�̓�ɋ��ق��\�����̂����߂ł���B�ߐ��E�]�ˎ���ɉ��C����A�֊s�ƒ�s�`�������킹���y�ۑ���̕���ł������B�{�������̍��ɂ͓V�炪�������Ƃ����Ă��邪�A������E��������̓V��Ƃ��Ă����B�܂��A���쏫�R�̓������Ƌ{�Q�q�̍ۂɏ��R�̏h���{�݂Ƃ��ė��p���ꂽ�B
���������̕�C�푈�̍ۂɏĎ����A��2�����E����ɓs�s�J�����s��ꂽ���߁A��\�͂قƂ�ǎc���Ă��Ȃ����A�{�ۂ̈ꕔ�̓y�ۂ��������A�{�ۂ̓y�ہA�x���O�ϕ����A����(������A�x�m���E�A�y��)���ؑ��ŕ�������A�F�s�{�隬�����Ƃ��Ĉ�ʂɌ��J����Ă���B����A�{�ی䐬��a�A�{�ې�����A�{�ۈɉ�������v�悪����B
�����݊m�F�ł����\
�Z ��ʌ�����s�{���̎��ɖ���41�N�ɉF�s�{��̖�̂���́A�ڐݍČ����ꂽ�Ɠ`���R�傪�����B
�Z �Ȗ،��F�s�{�s���J���ݏ����̎R��͖�������ɉF�s�{��̖���F�s�{�s���c�̐������ֈڒz����ݏ����̎R��Ƃ��čĈڒz���ꂽ�Ɠ`���B���������͑��������ߔN�����������̖�ɉ��C���ꂽ���́B
�Z �����H�傪��������ɏ�s��т����ԕ��������ɂȂ����ۂɈڒz���ꂽ�Ɠ`���傪�F�s�{�s�k���̖��ƂɌ����B
�Z �O�̊ېՂ̓y�ۏ�Ɉ����̑傢���傤�������̈ʒu�̂܂܂Ō�������B
�����j
����E����
�z��N��͕�������ɑk��B�����G���������͓����@�~(�F�s�{���̑c)���z�邵���ƌ�����B���Ƃ��ƉF�s�{�ɂ͉F�s�{�喾�_(��r�R�_��)���������A�@�~�͑O��N�̖��ɍۂ��Č����`�E���`�Ƃɔ����ĉ��B�����ɕ����A���̌��ɂ���ē��Ѝ���̒n�ʂƖі��(�S�{��)�����̂̎x�z����^����ꂽ�B�ȗ��A���q���ォ�玺������E���y���R����܂�530�N�ɂ���э��i�E���E�֓������`�ɗ��A�F�s�{��͉F�s�{���̋���(����)�ƂȂ�A�k�֓��x�z�̋��_�ƂȂ����B���̍��̉F�s�{��͒�����s�������Ƃ�����B
���ߐ�
�퍑���㏉���ɂ͉F�s�{���17�㓖��F�s�{���j���������������邽�߂ɁA�F�ꍂ����d�E���A�F�s�{�����Ƃ���傫�ȓ������N���肻�̐��ƂȂ����Ƃ����B�퍑�������ɂ͌�k������Ɛb�ł���p������F�쎁�̐N�U���ꎞ�͂��̈�h�ɂ���Đ苒���ꂽ���Ƃ����������A���c�������ɑ����F�s�{�d�u�ł͂��̕���ƂȂ�A�L�b�G�g�ɉy�����邽�߉��B�̑喼�炪�F�s�{��ɎQ�邵��(�Ȃ��A�����̉F�s�{���͌�k�����̐N�U��h�����߂ɑ��C�R��ɋ��_���ڂ��Ă���)�B�F�s�{���͏G�g���珊�̂����g���ꋏ������̉F�s�{��ɖ߂��悤�ɖ�������B���̌�H�Đ���������ȂǁA�G�g�Ƃ̒��͗ǍD�ł��������A�c��2�N(1597�N)�ɓ˔@���Ղ��ꂽ�B�F�s�{�����Ռ�̌c��3�N(1598�N)�A�F�s�{��ɂ͊����G�s��18���œ���A���쒬�⍮���������ĉF�s�{�鉺�̏��Ɛ�����i�߂��B
���]�ˎ���
�c��6�N(1601�N)12��28���ɂ͊փ����̐킢��̋��x���Ō���F�߂�ꂽ�����Ə���10���œ���A���ĉF�s�{���̕�̈�ł������c��Ί݂ɂ��鋻�T�����ċ�����ȂǏ鉺���̋@�\�������B
����Ɍ��a5�N(1619�N)�A����ƍN�̉����ƌ���ꂽ�{��������15��5��ʼnF�s�{�ɓ���A�F�s�{��Ə鉺�̉��C���s�����B�꒣����g�����ĐV���Ȋs��݂��A�{�ۂȂǏ�s���͂��@�킵�N�����Ċ�d�̐����Ƃ��A�@��Ő������y����������グ�ēy�ۂƂ����B�������Đ����͉F�s�{����ߐ���s�Ƃ������A�鉺�̓����X���Ɖ��B�X�������Ē������s���A����̎��ЌQ(�����@�A���y���Ȃ�)���X�������ɍĔz�u����ȂǏ鉺�̖h��\�����コ����Ɠ����ɁA����ɏ��R�h�����ƂȂ�{�ی�a�����݂��A�܂��F�s�{�h�̏h�@�\�E�w�@�\������ȂǓ����ЎQ�Ɋւ���ݔ�����𑣐i�����B���̑���C�H���̌��ʁA�F�s�{�鉺�͏鉺���A��O���A�h�꒬�̊e�@�\�����s�s�ɍĕ҂��ꂽ�B�F�s�{����C�ɍۂ��A�����͖��{�̈ӌ��ɏ����F�s�{��ɓV��݂͐���2�w2�K�̐�����E��V��̑���Ƃ������A�����̈ӂɔ����ĉF�s�{����C�ɂ܂�鐳���d���̉\�����z����A���a8�N(1622�N)�ɐ����͉��Ղ��ꂽ(�F�s�{��ޓV�䎖��)�B
���������3�N�Ԃ͉F�s�{�鉺�ɑ傫�ȕω��������炵�A�����ɂ���čĕ҂��ꂽ�s�s��Ղ͋ߑ�s�s�E�F�s�{�s�̑b�ƂȂ����B���̌�A�������A�����������A�{�����A�������A�������A�˓c���A�[�a�������ƕ���喼�����Ƃ��Ă��܂߂ɓ���ւ�����B�]�ˎ������ɂ͌˓c����6-7���Ŏ��߁A�������}����B
���ߑ�
�F�s�{�͌c��4�N4��(1868�N5��)�ɂ͕�C�푈�̐�n�ƂȂ�A�F�s�{��̌������͔ˍZ�C���قȂǂ��c���ĉF�s�{�̒������X�Ď�����(�F�s�{�푈)�B���̎��A�F�s�{�鉺�ː���3,000�˂̂���8���ȏ�̖�2,000���S�˂��Ď����A�܂������Q��48���@���S���Ă����Ɠ`������B�F�s�{��ɂ͈ꎞ�咹�\��狌���{�R�����邪�A�����ɉ͓c���v�n�A�ɒn�m�����A��R�폕�A��Î����A�L�n�����痦����V���{�R(�F���ˁA���B�ˁA����ˁA��_�˂Ȃǂ̔˕���)�ɒD�҂���A�F�s�{�˕�s�̌˓c�O���q��Ɉ����n���ꂽ�B��A��Í`�ɗ}������Ă����ˎ�˓c���F���A�ҁB����ȍ~�A�F�s�{��͓��R���R�̑Ή�Ð푈�̋��_�ƂȂ�A�_�ޏ����͂��ߓ��R���R�̊����������ԁA�F�s�{�˕��͐V���{�R�̈ꕔ���Ƃ��ĉ��썑�����甒�́A��ÂƓ]�킷��B�O�ˎ�̌˓c�����͓��N5��27��(1968�N7��16��)�ɉF�s�{�ɋA�邷�邪�Ԃ��Ȃ����E�����B����(���N6��)�A�F�s�{����ɂ͉���������{���É͂���ړ]���Ă����B�܂��A1871�N�ɐ^���V�̂��p����^�������o����ƁA�瓇�����Y���^���m�����ɑI�C����A�w����^������F�s�{����Ɉڂ����B���N�A����ɓ��������4���c��7�ԑ�������Ԃ��邱�ƂƂȂ����B���̕����͂��̌��1874�N�ɓ������������2�A����2����ɖ��̂�ς���B������1884�N�ɂ��̕��������������q�Ɉڒ��ƂȂ�ƁA�F�s�{����͐Â��ɂȂ�A�₪�Ė���23�N(1890�N)�ɂ͏�s��т����Ԃɕ��������ƂȂ��āA����ɂ͌�{�ی�������������A�s���̌e���̏�Ƃ��ėl�X�ȍÂ����s��ꂽ�Ƃ����B����A���Ȃǂ̍��Ղ͕��������ɂ���Ď����A��s�̖ʉe�͏��X�ɏ����Ă������B�܂����͐��ٍ��A�n�����Ȃǂ̓��x�����܂Ŏc����A��̗{�B��@�͔̍|������Ă����ƌ�����B
���A���{���{�ɂ���Е����s�s�v��̍���ɔ����A���a21�N(1946�N)10��9���ɂ͉F�s�{�s����Гs�s�Ɏw�肳��A��Ղ̈�\�͓P������s�X�n�ւƐ��܂�ς�����B���a30�N��(1955�N - 1964�N)���܂ł͌��݂̓����F�s�{�S�ݓX�ߕӂɂ��傫�Ȑ������c�����Ă����B�������q����̎���𗝗R�ɁA1972�N(���a47�N)�܂łɂ��ׂĖ��ߗ��Ă�ꂽ�B
������
�F�s�{��{�ۂ̈ꕔ���O�ϕ�������A�F�s�{�隬�����Ƃ���2007�N(����19�N)3��25���ɊJ���A��ʌ��J���ꂽ�B�������ꂽ�͖̂{�ۓy�ۂ̈ꕔ�Ɠy�ۏ�Ɍ��x�m���E�A������E�A����ѓy���ŁA�y�ۓ����͉F�s�{��Ɋւ��鎑����W�����Ă���B�������ꂽ�E�Ɠy���͖ؑ��{�������Ŕ����h�ĂŎd�グ���Ă���B�����Ɏg�p���ꂽ�؍ނ́A�y���̒��Ɨ����X�Y�̃q�o�ނȂ̂������A�Ȗ،����Y�̕O�E���E�����p�����Ă���B�y�ۂ̍\���̂Ɍ����Ă͓S�R���N���[�g���ł���B�s�s�h�Ќ��������˂邱�Ƃ���A�{�ېՂ͎Ő����L����݂̂ŁA�������͂Ȃ��B
������̓����ɓ��邱�Ƃ͂ł��邪�A�ʏ�2�K�����ɏオ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�j���ɒ����ɕ����������߁A�K�i���}�œ��ݖʂ��������A���z��@�����Ă��Ȃ����Ƃ����R�ł���B
�������
�������㒆���������ɒz�邳�ꂽ�Ƃ����F�s�{��́A��X�����@�~��c�Ƃ��鉺��F�s�{���ꑰ�̋��_�Ƃ��Ďp���ꂽ�Ƃ�����B�Ȃ��A�퍑���ɂ͈ꎞ�A���J����p���j�[�Ȃǂ̐p�����ꑰ�A�F��r�@�ɐ苒���ꂽ���������������A�ȉ��̈ꗗ�ɂ͂�����܂߂Ă��Ȃ��B
�����@�~(�N��6�N �| ) / ���c�@�j / �F�s�{���j / �F�s�{���j / �F�s�{���j / �F�s�{�j / �F�s�{�i�j / �F�s�{��j / �F�s�{���j / �F�s�{���j / �F�s�{��j / �F�s�{���j / �F�s�{���j / �F�s�{���j / �F�s�{���j / �F�s�{���j / �F�s�{���j(����9�N �| �i��13�N) / �F�s�{���j(�i��13�N �| ��i3�N) / �F�s�{���j(��i3�N �| �V��5�N) / �F�s�{���j(�V��5�N �| ��18�N) / �F�s�{�L�j(�O��3�N �| �V��4�N) / �F�s�{���j(�V��4�N �| �c��2�N) / ��쒷��(�c��2�N �| ��3�N) / �����G�s(�c��3�N – ��6�N) / ��͓��G�j(�c��6�N – ��7�N) / �����Ə�(�c��7�N – ��19�N) / ��������(���a���N – ��5�N) / �{������(���a5�N – ��8�N) / ��������(���a8�N – ����8�N) / �������\(����8�N – ��9�N) / �������O(����9�N �| �V�a���N) / �{������(�V�a���N �| �勝2�N) / ��������(�勝2�N �| ���\8�N) / ��������(���\8�N – ��10�N) / �������M(���\10�N �| ��i7�N) / �˓c���^(��i7�N �|����14�N) / �˓c���](����14�N �| ����3�N) / �˓c���m(����3�N �| ����2�N) / �������_(����2�N �| ���12�N) / ��������(���12�N �| ���i4�N) / �˓c����(���i4�N �| ����10�N) / �˓c����(����10�N �| ����8�N) / �˓c����(����8�N �| ����6�N) / �˓c����(����6�N - �Éi4�N) / �˓c����(�Éi4�N - ����3�N) / �˓c����(����3�N - �c��4�N) / �˓c���F(�c��4�N - ����4�N)
|
|
���Ȗ؎s |
|
��������@�@�@�Ȗ؎s�������厚����
|
�ʖ� �ԉ��فA�����
�`�� ����
����2�N(932�N)������ɂ���Ēz���ꂽ�ԉ��ق����̑O�g�Ɖ]����B
���m2�N(1018�N)�������s���Č����Ē����Ə̂��A�ꑰ�̍��ё��Y�d����u�����B ��ɑ����r�j�̎O�j���s�����ƂȂ�A�[�s�A�[�j�Ƒ�X�������B
���̌�A�����������̈ꑰ�����ƂȂ��ē��������̂���X���������A�V��5�N(1577�N)�������n�琴�[�̂Ƃ��A����R��卲��@�j�Ƃ̑����ɔs��Ď��n�����B�������̌�͉ƘV�̖ΘC�e���v�d�����ƂȂ������A�V��18�N(1590�N)���c���k�����Ɖ^�����Ƃ��ɂ��Ĕp��ƂȂ����B
��
������͓��������������w�̖k������тɒz����Ă����Ƃ����B ��n�̐��[�ɂ���O���_�Еt�߂��{�ۂŁA�������瓌�ɓ�̊ہA�O�̊ۂ��������悤�ł��邪�A���݂͑�n��c���ȂǂɂȂ��Ĉ�\�͂قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��Ƃ����B
|
|
�������_�Ё@�@�@�Ȗ؎s����������
|
��Ր_�@�@�V�Ƒ��_
�z�_�@�@�ʓV�_ / �_�㎵�� / ���ǖ� / �����{���V�j�� / �v���_ / �Ɏz�����x���� / �ʑc�� / �V������ / �z���ʖ� / �V�F�� / �V��͒j�_
���R�����v
�V�c�O�N(940)�̑n���ɂ��ēV���ܔN(1577)�l���{�a�q�a�Ƃ��Ď��ɂ����\���N(1590)�Гa�Č��̏㓡������Ɛ��ށB
���̍@���\���N(1694)�{�a���ցA������N(1712)�g�c�Ƃ�萳��ʂ̐_�ʂ̋�����B�����������_�ЂƉ��ߖ������N(1875)�����_�ЂƉ��̂��B
���a�\�Z�N(1981)�ꌎ�A�x�m�R�{�{��Ԑ_�ЁA�H�t�R�{�{�H�t�_�ЁA������ב�ЁA�z�K��ЁA�o�_��ЁA�������Ƌ{���{�Ђ̏��F�ď��a�ɕ�Ղ�
��
��Ր_�@���孁�M��
�z�_�@�ɜQ�����A���ǖ��A�V���������A�V�F��
�V�c�O�N(940)�㌎���n���Y����ŖS�̐܁A�������������̉Ɛb�Z���A�]�Y�������������~�[�A�����ĔɌj�A���G��@���A���V����A�~���@����A�헤�̐����s�k���A��U�{���̕����ւƋA�������A�����D�ɂčⓌ����t�サ�A���\����A�����ւƋA�蒅��������̂�������ɏ㗤�A�r��ʂĂ���߂��̔����{�����ɂĎ��Q�A�₪�Ĕ����{���ɑ����Z���喾�_�Ƃ��ĕ��J���ꂽ�Ƃ��A�܂����m���ߔN(1018)�O���A�헤���}�g�R���J�������_�Ƃ��`���B�V���ܔN(1577)�l���A���ɂ�����Ď��A���\���N(1590)�Č��A���\���N(1694)���F�𗧑ցA������N(1712)�g�c�Ƃ�萳��ʂ̐_�ʂ��B�����l�N(1821)�����_�ЂƐ_���̍����A�����ܔN(1878)���ЁA���Z�N(1879)�����꒬�ܒi�ܐ��O���A�����N(1875)�����_�ЂƉ��ߍՐ_���\�L�̘Z�_�Ƃ����B�����_�ЂɈ�א_�ЁA���Ƌ{
|
|
�������@�@�@�@�Ȗ؎s���������� (���s��S����������) |
�^���@�L�R�h
����2�N�A���傪���̒n�ɏ�y�����������A�₪�Ĕp���ƂȂ�����ɍČ�����āu�����@�v�ƍ�����悤�ɂȂ����Ƃ����B�����̖�t�����J���Ă����t���́A����̎��{�����Ƃ����Ă���B
|
|
����O�_�Ё@�@�@�Ȗ؎s��������O�����{
|
�����Ё@���욠�s��S ��O�_��
������
��Ր_�@���J�S�P���m��(�������Ȃނ��݂̂���)�@
�z�_�@�_���{�֗]�F�X�o����
�L�閽 / �匊���� / �喼���� / ��ȋM�� / ���J�ߕ��m�� �_���{���P�F�X�o��
��
�n���N��͕s�ځB�Ր_�́A���J�S�P���m��(��ȋM��)�B���썑�ɂ͂������O�_�Ђ�����A���������ȋM���B���Ђ́A���{�ƍ����Ă��������ŁA�Ր_���L�閽(�L����F�������_�V�c�̍c�q)�Ƃ����������B�L�閽�́A���і�N�̑c�Ƃ���Ă���A�L����F���ɂ܂��`���������B���Ў��ӂɂ́A�u�^�^���v�Ղ��c���Ă���炵���B�Ж��̓ǂ݂́A�{���́u�I�I�T�L�v�Ȃ̂����A�ߔN�ȍ~�́A�u�I�I�}�G�v�Ɠǂ܂�Ă���B
|
|
�������@�@�@�Ȗ؎s�������s�ꎚ��
|
�`���@�@���R��
�z��ҁ@�ђˎ���
�z��@�@����5�N
�Ȗ؎s�A���������̐����A�s�ꎚ�قɏ��݂��܂��B���k�����ԓ����쓡���C���^�[�̓쑤�A�萬��������ꏊ��тɂȂ�܂��B���݂͎�v���͕�n�ƂȂ���ς���Ă���A���̑��͑�n�y�ѐ��c�ƂȂ��Ă���܂��B�萬���R�Ɏ�v����݂��A�����ɋȗւ�A�˂�A�s���̓꒣��ŁA�K�͓͂�����400���A��k��100���ɂȂ�܂��B�{�s�͕�n�ƂȂ���ς���Ă���܂����A�{�s�����͎O�i�ɍ핽����A�k���ɂ͓y�ۂ������܂��B�쑤�ɂ͓�����100���ɂ킽���ċ�x�������܂��B�{�s�̓�������m�s�Ǝv���A�����ɂ͖x�ՂƎv���鐅�c�������܂��B����ɂ��̓������O�m�s�Ǝv���A�O�m�s�͓�i�\���ŁA�����ɂ͓y�ۂ������܂��B�쑤�͋��͐�𗘗p�����x�������A�k���ɌՌ����݂����Ă���܂��B
�u�Ȗ،��̒�����ِՁv�ɂ��Γ���͕���5�N�ɔђ˗����Ȃ���̂��z�邵���ƌ����Ă���A�������̐��͉��ŁA����2�N�܂ő������Ă����悤�ł��B
|
|
����_�_��(�����݂킶��)�@�@�@�Ȗ؎s�y�В�
|
������(��)�_�ЁA���썑���ЁB���Њi�͌��ЁB�Â��́u����y�Б喾�_�v�u�y�ИZ���喾�_�v�u�����喾�_�v�Ȃǂ̕ʏ̂��������B�����m�ԁw���̍ד��x�ɓo�ꂷ�鋫���́u���̔����v���m���Ă���B
���Ր_
��Ր_�@�`�啨���𤭖�ʖ� (��܂Ƃ������̂ʂ������݂����܂݂̂���) �啨�喽���w���B��_�_��(�ޗnj�����s)����̕���B
�z�J�_�@�؉ԍ��P�� (���̂͂Ȃ�����Ђ߂݂̂���)�@/�@���X�n�� (�ɂɂ��݂̂���) - �؉ԍ��P���̕v�_�@/�@��R�_�� (������܂݂݂̂���) - �؉ԍ��P���̕��@/�@�F�X�o���� (�Ђ��ققł݂݂̂���) - �؉ԍ��P���̎q�B�Ή������ɓ���
�����j
���n��
�Г`�ł́A���_�V�c�̎���ɖL����F��(���_�V�c�c�q)����������̐܂ɐ폟�Ɛl�S�������F�肵�A��������L������m��ꂽ���̔���(�ނ�̂₵�܁A���̔����Ƃ��L��)�ɁA���_�V�c���s�Ƃ�����a����鐐�ߋ{(���݂̓ޗnj�����s����)�ɍ�������O�֑�_(��_�_��)�����������̂��n���Ƃ���Ă���B
���T�j
�������㒆���́w���쎮�_�����x�ɂ́u���썑�s��S ��_�Ёv�̋L�ڂ����邪�A���Ђ�����ɂ��Ă�������肻�̘_�ЂƂ���Ă���B
�܂��A�Ñ�̍��i�͊e�����̑S�Ă̐_�Ђ���{���珇�ɏ��q���Ă������A��������������邽�߁A�e���̍��{�߂��ɍ����̐_�����J�������Ђ�݂��A�܂Ƃ߂č��J���s���悤�ɂȂ����B���Ђ͂��̂����̉��썑�̑��Ђɂ�����Ƃ����B���Ђ̓����2.8km�̒n�ɂ͉��썑���Ղ����@����Ă���B
������̗��ɂ���Q�������A�����G����̊�i�ɂ��Č�����A��������܂ŎГa�͍L�����h�ł������Ɠ`����B�������퍑����ɁA�F��L�Ƃ̎c�������ЂɘU��A�k�������̌R��������������߂ɏĎ����A�r�p�����B���̌�A����ƌ��ɂ��З�30�Ə��̕c1���{�̊�i�Ȃǂɂ��A1682�N(�V�a2�N)�Ɍ��݂̌`�ւƕ��������Ƃ����B
�������Ȃ���A���ۂɂ͖���������ȑO�̎j���œ��Ђm�Ɂu��_(�����݂�)�v�܂��́u��O�ցv�ƌĂ��͔̂�������Ă��Ȃ��B�u���ۂ̂Ƃ���́A�s���猭�킳�ꂽ���i����a���̑�_�_��(��O�_��)��ʂ̏ꏊ���J���Ă��āA���ꂪ����y�Б喾�_�ɍ��J���ꓯ�������v�Ƃ�������������ȂǁA���̗��j�͕K�������ڂ炩�Ƃ͌�����B
�����ېV��A����6�N�ɋߑ�Њi���x�ɂ����ċ��ЂɗA����40�N�ɐ_�a���嗿���i�_�ЂɎw��A����44�N�Ɍ��Ђɏ��i�����B1924�N(�吳13�N)�ɎГa�̑���C�A1993�N(����5�N)�Ɏ��̔����̑���C�Ȃǂ��s���Č��݂Ɏ����Ă���B
|
|
���t���_�Ё@�@�@�Ȗ؎s��v�ے�
|
|
�����Z�N(936�N)�㌎���쉟�̎g�A�����G���̑n�݂ł���B��A���i���N(1182�N)���Ђɂ�����A��j�����B���̎��A�A�����A�݂Ȏ����Ă��܂����B���̌�A�N�����o�ĉ��i�O�\�O�N(1426�N)�㌎����z�O��t�j���Č��������A�V���N���A�Ђ̂��߁A���Ƃ��Ƃ��Ď������B�c����N(1597�N)�u�����v�\�����Č������B���݂̖{�a������ł���B�����ܔN(1872�N)�\�A�\�ꃖ���̋��ЂƂȂ蓯���N�Z���q�a�c���A�\�N��������ɕ��ʂ���Ɏ��苽�Ѝ����~�߂��B�����l�\�N�l���w�葺�ЂƂȂ�B���a�l�\��N(1966�N)�㌎�A�䕗��\�Z���ɂ��Жؓ|���ɂ��A�_�a�y�єq�a�|�ׂ���B���z�̌�A���a�l�\��N�J�{���A�������̐��h�̒��S�ƂȂ��Ă���B
|
|
���z�܉���@�@�@�Ȗ؎s�s�꒬�[�v�Q�R
|
�z�܉�(�قĂ�������)��́A��`�ԎR�Ƃ����Ԗ؉��̓����̔�����тɒz����Ă���B
�R�������琼���͏�L�̉Ԗ؉��̕~�n���ƂȂ��Ă��邪�A��炵����\��������̂́A�R�����ł͂Ȃ��A�ނ��낻�����瓌���ɒ������тĂ��镝�L�̎Ζʏ�ł���B�Ƃ����킯�ŁA�o�邷�邽�߂ɂ͑�`�ԎR������荞�ނ����A�����ɓW�J���Ă�������Ɏ��t�������������B
�Ƃ����킯�ŁA�����ɓ˂��o�����A�k����1�{�ڂ�1�{�ڂ̔����̊Ԃ̔��ɂȂ��Ă���J�˂�i��ł����āA�r���߂����ӂ肩�獶��(�쑤)�̔����Ɏ��t���Ă݂邱�Ƃɂ����B�}�s�ȎΖʂ���������10���܂ł͂Ȃ��̂ł����ɓo���B����Ƃ����Ȃ��K�͂ȉ��x�̏��ɏo�āA���łɂ��������ł��邱�Ƃ��͂����肵���B���x�̋K�͂͑傫���A���҂����Ă����ȋC���ɂȂ�B
��̍ő�̓����́A�R�����ł͂Ȃ��A�R�[�Ɍ������Ζʂ̓r���ɏ�̎�v����u���Ă���Ƃ����_�ł���B���Ր}�����Ă��炦�Ε�����ʂ�A��̎�s�ɂ�����͎̂R�̒����ɂ���1�s�ł���Ǝv����B���̊s�𒆐S�Ƃ��āA�����̗��e�ɂ͉��x��i�K�I�Ɍ@��A�R�[���ɂ����āA��ۂ�x�A�y�ۂȂǂɂ���ċ�悳�ꂽ��K�͂Ȋs��i�K�I�ɔz�u���Ă���B�R�̎Ζʂ𗘗p���Ēz���ꂽ��ɂ��ẮA���Ȃ��K�͂ȏ�s�ł���B
�ʏ�Ȃ�ΎR��������s�ƂȂ�ׂ��ł���A���ۂɎR���̔����̖k�[�ӂ�Ɂu�z�R��{�ېՁv�ƕ`���ꂽ�ē����ɂ���������Ă����B�������A�R�����͍ה��������Ȃ��̂ŁA�����Ɋs���c�ނ̂͂�����߂��悤�ł���B����ɓ����̕��L�̔����ɒi�K�I�Ɋs������Ƃ�����@��p���Ă���B���������āA���㕔�͊s�ł͂Ȃ��A��ۂƂ������@�\�Ō��Ă����������悢�B
�R������1�s�܂ł̊Ԃɂ͒i�X�̏��s���������z����Ă���B����t�߂͎Ζʂ��}�s�Ȃ̂ŁA��K�͂Ȋs�����邱�Ƃ͊���Ȃ������̂ł��낤�B�ʘH�̓W�O�U�O�Ƃ��Đ܂�Ȃ����Ă���A�r�����ӏ��ɁA�Ռ���̐ꂪ������B
��̂�������̗��e�ɂ͉��x���@���Ă��邪�A�R������R�[�܂ň꒼���ɉ��тĂ���̂ł͂Ȃ��A�r���ŁA���s�̕���ƂȂ��ĕ��f����A�܂��r�����牡�x��ɂȂ�Ƃ������ϑ��I�ȍ\�������Ă���B����͈꒼���ɖx���ʉ߂ł��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł��낤���B
��L�̒ʂ�A��s�Ƃ����ׂ��s�͐}��1�ł���A30���~60���قǂ̂܂Ƃ܂����L��������B���̗��e�ɂ͓y�ۂ������A���ʕ��͍���7���قǂ̋}�s�Ȑ؊݂ƂȂ��Ă���B��k�̏�ۉ��ɂ͍��ȗւ��z����Ėh����ł߂Ă���B�쑤�͎Ζʂ����ɂ₩�������̂��A���ȗւ͂���ɉ��Ɉ�i�z����Ă���B1�s�̓����ɂ͖x��������Ă��邪�A���ꂪ�܂����[�Ȃ��̂ŁA�쑤�̕����Ɩk���̕����Ƃ͐ڑ����Ă��炸�A�Ԃɔ����Ȓi���ŋ�悳�ꂽ����������B
1�s�̌Ռ��Ǝv������͓̂쐼���̕t���������ɂ��邪�A���̑��ɂ��A�����̐��ʂƁA�k���[�ӂ�ɂ�����B�������A����ɂ͌㐢�̉��ς����邾�낤�B�{���̌Ռ��͂�͂�쐼���̂��̂ł������Ǝv���B�����̂��͖̂{���̓o�铹�ł��������ǂ����͂����肵�Ȃ����A���݁A�n�`���s�����ɂȂ��Ă���2�̖k���������A�����Ƃ�������Ƃ������̂��̂ł������Ȃ�A�n�o����̋@�\��F�߂Ă��悢��������Ȃ��B�܂��A1�s�̖k���[�ӂ�ɍ���1���قǂ̓y�d���u����Ă���B���̓y�d�̏㕔�͌E��Ă���A�T����̂悤�ɂ���������̂ł��邪�A�T�����u���ɂ͏ꏊ�����[������B��̎��_�Ƃ����K�ł��u���Ă������ł��낤���B
1�s�̓쑤�ɂ�2�C3�Ƃ��������ꂪ�`������Ă��邪�A����ɂ��̐�ɂ�4�C5�Ƃ������A�ő����ɂȂ��Ă���L��ȕ��ꂪ����B�����̊s�����킹��ƁA�S�̂Ƃ��Ă͂��Ȃ�̖ʐςƂȂ�A�������̌R���𒓓Ԃ����邱�Ƃ��\�ł���B�F�s�{���ɔ����āA��R�����e���Ĕ����邱�Ƃ��ӎ����Ă����̂ł��낤�B4�s��5�s�Ƃ̊Ԃ͖x�؏�̒ʘH�ƂȂ��Ă���A5�s�̑��ɂ͓y�ۂ������Ă���B�܂��A���̊Ԃ̐�ʂ��ʘH�́A5�s�̑��ʕ������n���ɑ����Ă���悤�ł���B�������Ă݂�ƁA5�s�����ƓƗ����̍����s�ł��������Ƃ�������B
���̐�ɂ�����͒i�X�ɑ����Ă���悤�ł��邪�A���������͖��Ƃ̕~�n�ƂȂ��Ă���悤�Ȃ̂ŗ�������͉������Ă������B�R�[�����猩��ƁA��ԎR�[�ɋ߂��傫�Ȃ���̂�������A�����ɂ����ِՂ̂悤�Ɍ�����̂����A�ǂ��܂ŏ��ł������̂��A������Ə����͂��Ă��Ȃ��B
�z�܉���́A�R������R�[�ɂ����ĎR�̎Ζʏ�ɉ��X�Ɗs��z�u����Ƃ����Ɠ��̍\���̂��̂ł���B�F�s�{���ɔ����ĊF�쎁���z������ł��邾���ɁA�����̖h��݂̂��d��������s�ł������A�Ƃ����邩������Ȃ��B�R�����͕�����A���邢�͘T����Ƃ��������x�̂��̂ł������B
�z�܉���́A���Ƃ��Ƃ͓����G�����z������ł������Ƃ����B�����G���Ƃ����A��������̓V�c�N�Ԃɕ�������������ƂŗL���Ȑl���ł��邩��A�����Ƃ��Â�����̒z��Ƃ������ƂɂȂ�B
�����������悤�ȍ\���ɂ����̂͊F�쎁�ł���ƌ�����B16���I�O���̉i���N�Ԃ̂��Ƃł������Ƃ����B���̈ʒu�́A�F�쎁�̎x�z�̈�̓��[�ɓ������Ă���A�����̉F�s�{�����ӎ��������ڂ̏�ł������B�F�쎁�͉Ɛb�̔��q�������q������̏�ɓ���āA�F�s�{���ɔ��������Ă����Ƃ����B
�z�܉��闎��̋L���́w�F�쐳���^�x�Ƃ����L�^�ɍڂ��Ă���B����ɂ��A�V��16�N(1588)�A���|���̎x�������F�s�{���j�́A�k����̊F�쎁�����|���ׂ��A1��5����̌R���𗦂��āA���ɐi�R���Ă����B�F�s�{�����A�����s���Ɛ�����ɐw��u���ƁA�F�쐨�͎����̐z�K�R��܂Ői�o���Λ������B�������A�F�s�{���̖ҍU�ɂ���Đz�K�R��͗���A�F��L�Ƃ́A�^���q�邩��A�z�܉���ւƑދp�����B�F��L�Ƃ́A�z�܉���ɕ����Ă߁A�S�C�E�|�𑵂����ď邵�A�u�����œ����̊o��v�Ǝv�������߁A�F�s�{����҂����B�F�s�{���̐����͌������A���❎�ߎ肩��ǂ�ǂ�U�ߍ��܂�Ă��܂��A��̈ێ��͓���Ȃ����B�����ōL�Ƃ́A����̂ĂĊF���Ɍ������đދp�����B
���̏�U�߂ɂ���āA��͉��サ�A���邵���Ƃ����B�z�܉���́A����Ȍ�p��ƂȂ������̂Ǝv����B1�s�̏�ӂ�̕��R�n����́A���݂ł��Y�������Ă��Ă��o�y���邻���ŁA���サ�ė��邵���Ƃ����`���𗠕t���Ă���B
|
|
���O�}�R(�݂������)�@�@�@����s�E�Ȗ؎s
|
�Ȗ،��ɂ���R�B���h�R(��������)�Ƃ��Ă��B�֓�����̖k�[�Ɉʒu���A��k��3.5 km�ɂ킽���ĘA�Ȃ�ג����R�ł���B�ō���͐����x�ƌĂ�A�W����229 m�ł���B
�Z ���Đ����R�[�ɂ͈��h��������A�����݂̂��ق̍肩��Â��͊�M�̌Í](�� ���h�S�Í])�t�߂܂ŐL�тĂ������悤�B
�Z ���t�W��̐l�Ȃǂɂ���ĉ̂ɉr�܂�Ă������R���̋����E�����ۃm�ւ̓����͈̌��h���ł��������A���s�̓V�����̓��C�͈��h�C�ł���B
�Z ���앗�y�L�ɂ́A���h�쌴�������۔T�ւƂ���B
�Z �����Ɠ����R�[�ɂ͔��R�_�Ђ��������悤�����A���݂̖��͕̂ύX����Ă�����悤�B
�Z �쓌���R�[�ɌÓ��u���R���v�̐ՂƐ��肳��Ă��铹������B�܂��A���̓��ɌÑ�̊֏����������Ƃ����B
�Z �������`��������L�ɕ`����Ă���A�����o������э�㐋���炪���̎g����ѓ����G���Ƒΐw�����u���R�V���v�͈��h�R(�O�}�R)���w���Ƃ̐�������A��O�̒Ⴂ�R���A����(������)�m�R�A�����ۃm�R�Ƃ����B
|
|
�����w�_��(���O�_�ЁA�ނ�Ђ���) �@�@�@�Ȗ؎s |
���Њi�͎����ЁB
��Ր_�@�_�c�ʖ�
�n���@�@(�`)646�N(�剻2�N)
�Г`�ɂ��Α剻2�N(646�N)�A�F���_�Ɠ��}��_���}�����J�����Ƃ����B �哯2�N(807�N)�A���J�����F�쑺������̔����{�̍Ր_�u�_�c�ʖ��v�Ђ̎�Ր_�Ƃ��Č}�����B�܂��A���a�V�c�̑�(858�N - 876�N)�A�F�쑺������Ɋ�������������_�����F�V�c�̑�(884�N - 887�N)�ɍ��J���� �B �V�c2�N(939�N)�A����������铡���G���������Ő폟�F�肵���Ɠ`����B �����ȍ~�A���쏬�쎛���Ⓜ��R��̏��⍲�쎁������M���B �]�ˎ���ɂ͓Ȗ؏h���u���ꂽ�Ȗؒ��̏��l������A�˂��ꂽ�B
|
|
�����}�_�Ё@�@�@�Ȗ؎s�啽�����F��
|
|
�V����N(825)�Ɏ��o��t(�~�m)�ɂ���đn���B�����͓��g�R�R���匠���Ə̂��Ă����̂��������B�܂��A��ɏ�����l�������R�{�{�����Ă��Ƃ��`�����Ă���Ƃ̂��ƁB��Ր_�͑�R��B
|
|
�����F�쏫���_�Õ��@�@�@�Ȗ؎s�啽�����F��
|
�Õ����㒆�������̍\�z�ƍl�����A�A��(�Ύ��⌺���ƊO���Ƃ����ԒʘH����)�͉��F��}�K�L��ꍆ�Õ��Ɏ��������ł��B������̕�ł���Ƃ����`��������܂��B
���K�͂ȉ��炵���~���ł����A�Ύ��̒�����6m�����邻���ł��B����ɐΒi������Ă����Ɛ_�Ђ��J���Ă��܂��B
|
|
���������@�@�@�Ȗ؎s�啽�����R�c
|
�V��@�̎��@�ł��B�������̑n���͓ޗǎ���̓V�����N(739)�ɖ��m�Ƃ��Ēm����s���F������\��ʐ��ω���(���݂̑��͑ٓ����ɂ��1265�N��Ɣ������Ă��܂��B)�荞�݊J�R�����Ɠ`�����Ă��܂��B�哯�N��(806�`810�N)�ɂ͉��썑�̍��i�����F�̑��c���s���A�V�c10�N(947)�ɂ͓����G��(�c������ �U����)�������ɏ��啽��o�������Ɋ��ӂ����F�̑��c�A����4�N(1180)�ɂ͕��ŋ������傫�Ȕ�Q���Ă��܂��B
�\��ʐ��ω����͕ʏ́u��̊ω��v�ƌĂ���͂̐M�̑ΏۂƂȂ艺����O�\�O�ω������\�Z�ԎD���ɑI��A���a53�N(1978)�ɓȖ،��w��d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B�e���ł��鏟�R�n���Ɣ�����V�����͌��\9�N(1696)�ɐ��삳�ꂽ���̂œȖ،����ɐ����Ȃ��]�ˎ���̕����Ƃ��M�d�Ȃ��̂Ƃ��đ啽���w��L�`�������Ɏw�肳��Ă��܂��B
�������{���͖ؑ��������āA���ꉮ�A�V�������A�����A���s7�ԁA����4�ԁA����1�Ԍ��q�t���A�O�ǂ͐^�Ǒ���A������d�グ�B�������ω����͕�`���A�V�����A���s3�ԁA����3�ԁA����1�Ԍ��q�t�A���ʍ��E�̊J�����͉ԓ����A�O�ǂ͔��A�ٕ��F�Œ��F����Ă��܂��B������O�\�O�ω������\�Z�ԎD���B�����Ԃ̎��Ȗ�4�ԁB�@�h�F�V��@�B�{���F����ɔ@�������B
|
|
���W�ΐ_�Ё@�@�@�Ȗ؎s���䒬
|
���̐_�Ђ́A�����R�_�Ђ̐�2km���̍W�ΎR���߂��ɒ������Ă���܂��B�R���߂��ɂ���A�L�����H���������̏ꏊ�ɗǂ����Ă��Ǝv�����̗��h�ȎГa�������Ă��܂��B
�W��(�Ă邢��)�_�Ђ͉����́A�R�x�M�ɂ���Č��Ă��܂����B�����A����(�_��)�������āA���霒�X�ƋP�������Ƃɂ��A���s��V�_�Ə̂���ĎR�c�̗��l�ɐ��߂���܂��邱�ƂƂȂ�܂����B
�V�c2�N(825)8��1���A����b�����~�k�����Њz������]�܈ʉ��ɏ������܂����B
�V�c�̗��̐܁A�����G�����K�����F�肵�ď��������̂ŁA���̗쌱�Ɋ��ӂ��V�c10�N(947)�Ђ��Č�����i���܂����B
����R�Ύ��ɂ�艽�x���Ď����܂������A���̌����͕���8�N(1825)�ɍČ����ꂽ���̂ƌ����Ă��܂��B�{�a�͟O�ތ������`���ő��������͓��n�x�c�̈�Ӗ}���M�G�̍�ł��B
|
|
���������R�@�ӗ֎��@�@�@�Ȗ؎s�啽��
|
�{���@�@�ӗ֊ϐ�����F
�@�h�@�^���@�L�R�h
�������R�@�ӗ֎��́A�����ɂ͋������R����V�i���@�@�ӗ֎��Ƃ����܂��B�������R�@�ӗ֎��́A�����������u�V�啽���w�v�̋߂��ɂ���A���ẮA�����ᕼ�g�X���x�c�h�̘e�{�w�������Ƃ̂��Ƃł��B
�V�c���N�A�����G�����F�쑺�Ɂu�����R�߉ޑ����v(����)���������A�p�e���̌��ɏ��咲�����F��A�^�|�Ƒ���̏�������t���J����Ɠ`����B |
|
���z�K�_�Ё@�@�@�Ȗ؎s�啽������
|
��Ր_�@���䖼����
�n���͕s�ځB�u�啽�����v�ɂ́A�����G���������咲���̂��߂ɐM�Z�̐z�K�_�����������Ƃ��邪�A���c�����C�̓`�����c��B�����O�Z�N(1903)�A�������̉H���_�ЁE���i���c�̉i���_�ЁE���R�m���̈��i�_�Ђ��A���l��N(1909)�A�������̈����_�Ђ����J�B�吳�ꁛ�N(1921)�ɎГa�c�����B�z�_�Ƃ��ď��F�����E����C�얽���J��A�����Ђɑ吙�_�ЁE�����_�Ђ�����B
|
|
���z�K�_�Ё@�@�@�Ȗ؎s�啽���^�|
|
|
���Ђ́A�����G����������̔�������̐܁A�M�B�z�K�喾�_�ɐ폟�F����Ȃ��A�V�c3�N(940)�_���ɂ�菟����������ɔC����ꂽ���Ƃɂ��A��R�̎R��ɍՐ_�����������̂�n�n�Ƃ���B�_�Ђ̒��炷���R�́A�C��51m�̌����ŏ��̎R�ƌ����A�R��ɓV���A�䗳��A�T�m�q��̊�₪����A�V���ɂ́u�V��̑���(��������)�v�Ƃ����鑫�`�̉�������B�V��₩��͑����A�W�̗��R���]�܂�A�Гa�O����͒}�g�R�̗E�p�ƒ����̏o��q�ނ��Ƃ��ł���B
|
|
������_�Ё@�@�@�Ȗ؎s�啽���^�|�|�{
|
��Ր_�@�����fᵖ�
�����G����������Ǔ��̍ہA�R�鍑�����S���⋽�̋_���Ђ폟���F��B�_���ɂ�蕽�肵�����Ƃ���A�����Z(936)�N�ɁA���̒n�Ɋ��������̂����Ђ̎n�܂�ł���B�V����(1580)�N�A�u�a���s�̐܁A�_�`������ď��s�����Ƃ���A�u�a�����܂����Ƃ����B���͋_�������V���Ƃ��������A�������N�A����_�ЂƉ��̂����B
��
�����Z�N(936)�R�鍑�����芩�����ꂽ�Ɠ`���B�V�����N(1580)�u�a���s����`�n��ɂ���Ē��������̂ŁA���䏯�|�{��܋��̑�����ƂȂ����B�ʐ��ɂ��ƁA�����G���͕�����Ǔ��̑�肪���Ȃ����̂ŁA���R�A����A�|�{�̎O�����ɋ_���O�Ђ��J����(940�N��)�̂��A���̐_�Ђ̎n�܂�Ƃ����Ă���B
|
|
�������㔪��_��(�ɂ��݂�����₳������)�@�@�@�Ȗ؎s�啽��������
|
��Ր_�@�fᵚj��
������̒���B�������͒P�Ɂu����_�Ёv�ł��邪�啽�n����ɂ͕����̔���_�Ђ����邽��(�|�{����_�ЁE�x�c����_�ЂȂ�)�n���������ČĂ�邱�Ƃ������B���Њi�͑��ЁB
940�N(�V�c3�N)�ɓ����G���������哢���ɍۂ��폟�F��̂��߉��썑�s��S���ʋ��_����(���݂̓Ȗ؎s�啽��������_�����A���Ƃ̐����㑺�_����)�Ɋ����A1581�N(�V��9�N)�Ɍ��ݒn�ɑJ�K�A1711�N(�������N)�ɋ��s�̐_�_�����u�V�����v�̎Ѝ�������B1868�N(�������N)�Ɂu����_�Ёv�Ɖ��́A1906�N(����39�N)�A�Гa�����z���A�咹���������A1909�N(����42�N)�ɐ�������̐z�K�_�Б�4�Ђ����J����B |
|
�� |
|
�����_�_�Ё@�@�@�G�R�s
|
�G�R�s�X�n�̒����ɒ������锪�_�_�Ђ́A�����炱�̏ꏊ�ɂ��������̂ł͂���܂���ł����B�ߐ{�����������V���ɋF�肷��ɂ�����A�剱�����犩�������ƌ����Ă��܂��B�ꏊ�����̂����a�̒u�����Ƃ���ŁA���̂��u�����V���Ёv�ƌĂ�Ă��܂����B
�����V���Ƃ͌��̓C���h�̋_�����ɂ����傤����̎��_�Ƃ����Ă���A�f���j�������̂��݂̂��ƂƓ���_�Ƃ���A�܂���t�@���̉��g�ł���ƌ����Ă��܂��B�u�a�悯�̐_�l�Ƃ��ē��{�S���̊e�n�ōՂ��Ă���A���s�̋_���ՂŗL���Ȕ���_�Ђ����̐_�l���J���Ă��܂��B�Â��͎R�����Ղ����V������A�V���ՂȂǂƌĂ�A�V����������ɗR�����܂��B����3�N(1870�N)�A���̂_�_�ЁA�Ր_��f���j���ɁA�����đ吳3�N(1914�N)�ɎЗL�n�g���̂��ߌ��݂̏ꏊ�ɑJ������܂����B
�����͐M���ՓT������܂���ł������A���̌�_���h���Ƃ����v�z������n�߁A���̒����Ɉʒu���A��t���܂Ɠ����悤�ɕa�C�̐_�l�ƌ���������M������オ���Ă��܂����B�i�\6�N(1560�N)�ɂ͊����炪���߂čs��ꂽ�悤�ł����A�ڂ����L�^�͎c���Ă��܂���B���ꂩ���80�N��̐��ی��N(1644�N)�ɁA�G�蒬�A������c��(���c��)�A�r��(���䒬)�A�ԍ⒬(��)�A������5�������߂Ē����\�����ō���s�����Ɠ`�����Ă��܂��B
����6�N(1666�N)�A�x�����e���ق�݂܂����̂��݂����܂��͐_�a��V�z��[���A�l�X�͉G�R���Y�̘a����p���Ģ�R������A�x�����J�݂��ĕ�[���A����3�N�����肩��R�����̓����ƌ����颏��싶��(�̕���)�����I����A�x�肪�ō����ɒB����Ɖ���(�_�ʗ͂�L�����)������ϏO�����܂����B���ꂪ��R��ɍ~�Ղ��ꂽ���_��_�Ɛ_���}�������q�����h�҂��֔Ԃɕ�[���ꂽ��R������̎ŋ����ӏ܂����Ɋ�т����p�ł���A�{���̎p�ƌ����܂��B
�_�Ђ̍Ղ͉Ă����ł͂���܂���B�ʏ�ɂ�����_�Ђ̎O��ՂƂ́A�F�N�Ղ��˂�(�t��)�A����(�č�)�A�V���Ղɂ��Ȃ߂���(�H��)�������A1�N�Ԃ̌܍��L�����F�肷�邨�Ղ�̂��Ƃł��B
�F�N�Ղ͂��̔N�̌܍��L���Ȃǂ��F�肵�A���Ղł͎��n�O�ɓV�Џ������A�V���Ղł͏t�̋F�������Ă�����������_�l�ւ̊��ӂƊ�т�`���܂��B�G�R�̔��_�_�Ђ͂��̗��Ղ��������Ģ�R�����գ�Ƃ��đ�X�I�ɍs���Ă���̂ł��B���̑��ɂ��ǙT�Ղ��Ȃ���(�ߕ�)���̍s��������A�����͂��ׂē��Ԓ��̎�O�B�����d��܂��B
|
|
���ԎRⴍ��_��
|
���ԎRⴍ��_�Ѝ�����(ꡔq�a)
�ԎRⴍ��_�Ѝ�����(ꡔq�a)(��������ق����˂��Ⴝ�����݂��悤�͂��ł�)
�n���͑哯���N(806)�Ƃ���Ă��邪�A�肩�ł͂Ȃ��B�_�Ђ̉��N�ɂ��ƁA�F�s��(�ߐ{�����s)�������_�����̂��Ƃ���������A���P���Ȃ��疶�J��֓n���čs�����̂����āA�������匠���Ɛ��߂��K�����āA�������_�ЂƂ����Ƃ����B
���̌�A�ԎRⴍ��_�Ђ̕ʓ��Ƃ��Ė{��(���̉@)��̎��ɂ́A�ߍ݂̔_���������L����j���A�u���S���͖{�Е��тɌF��Ђ̑O�ɍ����A�g���͓����R�_�Ђ̑O�ɍ���v�A�ՓT���s�Ȃ��Ă����B����2�N(1790)�ɍČ�����A���̌�吳5�N(1916)�A�{��(���̉@)�ƍ������A�ԎRⴍ��_�Ђ̗y�q�a�ƂȂ����B
���ԎRⴍ��_�Љ��̉@(�{�a)
���_�V�c�̌��A�����ɔh�����ꂽ�L����F�����A���R��|���R�Ɩ��t�����Ƃ����Ă��܂��B�_�Ђ̑n�������͕s���ł����A���c���N(877)�ɏ]�܈ʉ��̈ʊK���������Ă��܂��B
���̌�A�Гa�͔����X���̋F�菊�ƂȂ�܂������A�V��12�N(1543)��c�����ɔs��A�ȍ~��c�����̋F�菊�ƂȂ�܂����B
���݂̎Гa�́A���v2�N(1862)�ɐV���Ɍ������ꂽ���̂ŁA�F��_�Ђ͓V��4�N(1784)�A�����R�_�Ђ͕��3�N(1753)�ɍČ�����܂����B�吳5�N(1916)�F�s��̍������_�Ђ����J���Aⴍ��_�ЂЛԎRⴍ��_�ЂƉ��̂��܂����B
|
|
�����}�_�Ё@�@�@�����s���
|
�����}�_�Дq�a�V���L�O�V��
�}�A���Ђ́A���������S�]�N�O�A�Ïˌ��N(848)�����ܓ��A���o��t�~�m������̎��_�Ƃ��č��̒n�A��������ɎR���������J��Ɏn�܂�B�����A���Ђ́A�ߋ��������̑�����Ƃ��āA�_�Ђ��܂˂���d�̑m�V��\�]�������щ��߂̎��q���W���Ĕɉh���ɂ߂����A�퍑�̐��A�L�b�A�k�𗼎��̑����ɍۂ��A���Ђ́A�m�V�Ƃ��ǂ������D���ɋA�����Ɠ`������B�����N���A���q�����Č��Гa���ւ��Ȍ㍡���ɋy�B��A���a�l�\��N�����F�s�{���H�̊J�݂ɂ�肻�̕⏞���̈ꕔ������Ƃ��Ď��q�ꓯ������A�����ɋ����̐������s���q�a��V�z�����̂ł���������ċL�O�Ƃ���B
��
�~�m�͂������썑��D�̐��܂�ƌ����Ă���(�p�����ƌ�����������悤�ł�)�A���k�A�k�C���ɂ����̑��Ղ��c���Ă���ʂł�����A�̋��̂��̒n�ɉ~�m�̊J�R�ɂ��V��̎��@�������Ă�����s�v�c�ł͂���܂���B�������~�m�̋A���͏��a14�N�B�Ïˌ��N�Ɠ���848�N�B�`���b�g��������C�����܂��B�`���Ȃ̂ł��傤���B���ݒn�}���݂邩���莛�@�͖����A���炭�����̏��߁A�{�a���ɐΕ����c���A�p���ƂȂ����Ǝv���܂��B
�����}�_�Ж{�a
���}�_��(���̐����R����)�́A�Ïˌ��N(848)���o��t�̌����Ɠ`������B�]�ˎ���ɂ́A�����R�����Ђ̈�ɐ�����ꖔ�A�ߋ�������(����E����E�a��E�����E����E���S�E������E�g��)�̑�����Ƃ��̂��ꂽ�ÎЂł���B���݂̎Гa�͈�ԎЗ����ŁA���D����勝���N(1684)�̌����Ƃ���B�O���̓h���������͌㐢�̏C���������Ă���A�������͌��������ł��������̂��ߔN���C�������̂ł���B���q�̋��@�A富҂̒����Ȃǂɍ]�ˎ���̓������悭����Ă���B�K�͂͏��������A�����̌ÎЂɂӂ��킵���Гa�ł���B
|
|
�������_�Ё@�@�@���s�s���q
|
|
����940�N(�V�c3�N)�B�����傪���Ƃ������͂���Ђ���ĐH�ׂ��Ƃ���Ɠ`�����Ă��܂��B���̌̎�����ł��̒n���̔ы�(���̂���)�����q�̖����t�����Ƃ����`��������܂��B
|
|
�������쉷��@�@�@�����s������
|
|
�d�m�Y�̍���ɔs�ꓦ��Ă������Ɨ��l���A�͌��ɗN���o�鉷�����������������Ɠ`��������j�̌Â�����ł��B����n���̗R���Ƃ��Ȃ���������(�ꋉ�͐엘���쐅�n)�̌k�J�����ɗ��ق▯�Ƃ��������т܂��B���ʖL���ȉ�����y���ނ̂͂������̂��ƁA�싛��R�̍K�A�쒹�E���E�F�E�R�����̒����Ȃǎl�G��������n��������S�䂭�܂Ŋ��\�ł��܂��B���X�ׂ瓙���͘F���ł�������Ă��Ē������l�������L���ł��B�܂��A1�����{�`3����{�̂��܂���Ղł́A����͐�~�ɖ�800���̃~�j���܂��炪����A��ɂ͒��Ƀ��[�\�N�̂����肪����A���z�I�ȕ��i���L����܂��B
|
|
����ؐ_�Ё@�@�@���s��S��ؒ�
|
���Њi�͋��ЁB���_�V�c�̍c���q�ł���䷓��t�Y�q������Ր_�Ƃ��A�_�c�ʖ�(���_�V�c)�A�������P��(�_���c�@)�A�@���O���_��z�J����B
�m���V�c�̎���A�ޗǕʉ������썑���Ƃ��ĉ��і썑�ɕ��C�����Ƃ��A䷓��t�Y�q���̈�[��ē��n���J�����̂Ɏn�܂�Ɠ`����B���̌�A����N��(��������)�ɍ��c�����C���ڈΐ�������̋A�r�A���Ƃ��Č��ݒn�ɎГa�c���J�������B�O���N��(���q����)�ɔz�Ղ̌ܐ_���J��ꂽ�B
���썑����S�����̑�����Ƃ���A�]�ˎ���ɂ͌É͔ˎ�y�䎁�̐��h���ČÉ͔˂̒���E�F�菊�Ƃ��ꂽ�B����5�N�ɋ��Ђɗ��B
���Վ�
12��2�`4���ɂ́A����S������_�삪���s����Վ����s����B�|�Ƃ̐�ɒ����ĉ��A������݂��ɂԂ��ĉ����������Ƃ����ՂŁA��ʂɂ͒��ݍՂ�ƌĂ�Ă���B���m�N�ԂɎn�܂������̂Ɠ`�����A���X�͐_��̏��s�̍ۂɁA�_��������ł������̑��Ɍ}���悤�ƁA���ꂼ��̑��̎�҂��������Ō��������ݍ��������ƂɗR������Ƃ���Ă���B��ɂ��ꂪ���Ԃ������Ղɕω������B
���M��
�����ɂ́A�c�����C�̎�A���Ɠ`������C�`���E�̖�(�������1200�N)����������B�o�Y�����������A���̏o���ǂ��Ȃ�悤�ɂƊ���āA���z�ɕĂʂ������ē��[��͂������̂����̃C�`���E�ɕ�[����Ƃ������ԐM������B���R�叫�T�؊�T���A���Ɠ����ǂ݂ł��邱�Ƃ�����ʂȐ_�Ђƍl���A���x�����ЂɎQ�q���A�w�H�D�Ȃǂ��[���Ă���B�Ȃ��A�T�؊�T���Ր_�Ƃ���T�ؐ_�ЂƂ̒��ڂ̊֘A�͂Ȃ��B
|
|
�����h���@�@�@�^���s��{��
|
���h���́A�Ï�3�N(850)���o��t�ɂ��n�����ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B��������̐M�Ă��A�����G���������吪���̋F��ɕ��^�揟���F�����Ƃ���A�ȗ��A�F�菊�Ƃ��ē`���܂��B���̌�A�v���c��吅�J崗������������̊ω���M���A���̑��̐��J�ɐ��珟�������i9�N(1632�N)�Ɋω����A������A�O��A�{���A�ɗ����Č����܂����B���݂ł͘O��݂̂��c���Ă��܂��B
�O��͊��i9�N�ɍČ����ꂽ�����̂��̂ŎO�Ԉ�ˁA���ꉮ�A�������A2�w�ڂɂ͍������Ă��܂��B���h���O��͍]�ˎ��㏉���̋M�d�Ȍ����Ƃ��ď��a42�N(1967)�ɐ^���s(����{��)�w��L�`�������Ɏw�肳��Ă��܂��B���A���l�Ɋ��i9�N(1632)�ɍČ����ꂽ�ω���(��蓰�F�{�����ω��A�A�����A���s5�ԁA����5�ԁA���݂͓��ɕ����ւ����Ă��܂��B)�����蕶�����w�肳��Ă��܂���������10�N(1998)�Ɍ��R��(��錧����s)�Ɉڒz����Ă��܂��B
|
|
���ؔ��_�Ё@�@�@��s�ؔ�
|
��(1) �ؔ��_�Ђ̎n�܂�ƍ��c�����C
8���I�̖��A�����V�c�͐������������߂悤�Ƃ��āA���� 13(794)�N�A �s�����s�Ɉڂ��܂����B���̂̂���������Ƃ���悤�ɂȂ�܂����B ���c�����C(758�`811)�����Α叫�R�ɔC������A���k�n���ɕ����o���ĉڈ� ���݂� ���A����̐��͂�k���̒�����܂ł̂��܂����B ���썑�͉ڈƐڂ���Ƃ���ŁA��a����̌��Ђ��s���n���Ă��܂����B
�ؔ��_�Ђ̗R���ɂ��ƁA���c�����C�͂��̒n�����ŏh�w���A�u������Έ��K����������v�Ɠ����됒�h���Ă����R�鍑���g�� ���͂� �_��(�����s�{�F�� �s)�Ɍ������Đ폟���F�肵�܂����B����14(795)�N�A��ɏ����Ă̋A�� ���A�����ɎЂ����������̂��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B �Ր_�͋��g���_�ЂƓ����V�E�䎨��(���߂̂����ق݂݂݂̂���)�ł��B
���Ր_�͐����ɂ͐��ƌᏟ�������V�E�䎨���œV�Ƒ�_�̎q(�_�b����̐_)
�����c�����C���������鎛�Ђ����{�S���ɕ��z���Ă���B���k�n���� 53����(���� ���E���c�����C�E�V�e�ł��)����Ƃ����B
�����k�̗Y�A���V�����Ă�ׂ��ƕ��̍~���́A����21(802)�N�̂��Ƃł���B
��(2) �����E���q���m�ɂ�鐒�h
10���I�̑O���A�����̍��������傪�����������A�֓��n����}���Ă��܂� �����A����̕��m�����G����ɂ���Ă悤�₭���߂��܂����B�G���͏��� �ۂɖؔ��_�ЂɋF�肵���Ƃ����Ă��܂��B ����ɁA�����̓������������n�߂� 11 ���I�̌㔼�ɂ́A�������{�ɑ� �锽����ꑰ�̓�����������A�O��2��ɂ킽���ė����������܂����B(�O ��N�̖� 1051�`62�A��O�N�̖� 1083�`87)����ɂ��A�����̕��m�� �������`�Ƃ�ɂ���Ă����߂��܂����B���̌��ʁA�֓��n���̕��m�c�ƌ� ���̌��т������܂�܂����B
�����`�E�`�Ɛe�q�́A�����̈��{��C ���ׂ̂����Ƃ� �ہA�ؔ��_�ЂɋF�肵���Ɠ` �����Ă��܂��B����̍��͐�͂𐮂��ďo������O����n�ł������Ƃ��� �܂��B
��(3) ���J�����̂⎁�̎��_�Ƃ��Ẳ��J�y�Ђ�������喾�_
��������̖����A���썑�̉��J�n�������߂��̂͌��`�Ƃ̑����� ��肸�� �ł��B ���̌�A�F�s�{����{�q�Ƃ��Č}����ꂽ���J���� �Ƃ��Ȃ� �������z���F�s�{ �ꑰ�̖k�̎����ł߂��Ƃ����Ă��܂��B ���q���ォ��퍑�����400�N�Ԃɂ킽���āA���J�n�����x�z���鉖�J�� �̑y�ЁE����̐X�Ƃ��Č�������܂����B ���q����̌�Ɛl�ʼn̐l�ł����������J���Ƃ́u�M���@�t�W�v�ɂ͖ؔ��_ �Ђƍl���Ă��悢�Ǝv����̂��c����Ă��܂��B
���̂₵��(��)�ɂ�݂ĕ��
�����݂�������炵�ɂȂ�ʂׂ��͂͂���͂Ă�����̖̂���
��(4) �����ŌÂ̐_�Ќ��z�ƍ��̏d�v�������u�O��E�{�a�v
�ؔ��_�Ђ̘O��Ɩ{�a�́A�Ȗ،��ŌÂ̐_�Ќ��z�ō��̏d�v�������Ɏw�� ����Ă��܂��B���a35 �N����36�N(1960�`1961)�ɂ����āA��K�͂ȉ� �̏C�����s���܂����B(�J����̊��Ԃ��������H�j�����i�݁A�����ɌX���Ă��邱�ƂȂǂ����������B)�����̓������玺�����㒆���̌������Ƃ� �����Ƃ��͂����肵�܂������A���D�E�n���͔�������܂���ł����B
��������̒����́A���n���₦�����ƉƖ����ċ��������J�F�j(�F�s�{�� 17�㐬�j�̎q)�̎���ł��B�F�j�͉i��11(1514)�N�ɖ�t�@������(�s �w�蕶�����E����蔽����t��)����i���܂����B�܂��A�q�̗R�j�͕��̎� ���� 3 �N�o�����V�� 18(1549)�N�Ɍ�O������ɂ��������Ēn�����Ղ�� �����B���݁A�u�͂����n���v�ƌĂ�l�X�̐M���Ă��܂��B���̂悤�ɐM�S�[�������ł���A���J�Ƃ̍ċ��Ɖ��J�y�Ђł���ؔ��_�Ђ̍Č��ɗ� �𒍂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
��(5) �ؔ��Г����喾�_�� �]�ˎ���
�V�� 18(1590)�N�A���J���̖ŖS�ɂ��L�b�G�g�ɎЗ̂�v������A�� �����������̂̓��쎞��ɓ����ē�����r�R�̍Ր_�����J���܂����B �O�㏫�R�ƌ��̎���A�c����(1648)�N�A�������Ɍ���n2 �S����i ����܂����B �����R�։����̎x�z���̂��ƁA�u�ؔ��Г����喾�_�v�Ə̂��Đ_�������� �Ȃ�A�O��ɂ͐m���������u����܂����B
|
|
�����쎛��
|
�o�H���ɂ����Đ��͂��ւ��������ł���B�{���͓������Ƃ���邪�畔���Ƃ������B�ƌn�͏G�����ŎR�����̏����ɂ�����B���Ȃ葁���������瑽���̕����ݏo���A���k�n���𒆐S�ɍL�����z�����B�����̏��Ƃ̒��ł��o�H����k�O�S�Ɋ��������퍑�喼�ƂȂ�����k���쎛���̉ƌn�������Ƃ��L���ł���A�{���ł͎�ɂ���ɂ��ďq�ׂ�B
���쎛���͕�������㔼�ɉ��썑�s��S���쎛(���E�Ȗ؎s��M�����쎛)���u�ꏊ�����v�̒n�Ƃ��Ă����̂��n�܂�ƌ����Ă���B����5�N(1189�N)�̉��B���������łɏo�H�Y���S�Ȃǂ̒n���E���B�ʍj�͏��R�������̐M�C�����A�ȍ~����㏫�R�ɋߎ����Ă���B���ׁ̈A�e�n�̏��̂ɂ͏����̎q���㊯�Ƃ��Ĕh�����A�y�̂͊��q�ɏ풓���o�d���Ă����ƌ�����B��k������ɁA�y�̉Ƃ������Ȗ{�̂���L��ȏ��̂ł���o�H�Y���S���ɈڏZ�����ƌ�����B���쎛���͓����쒩���Ƃ��Ċ����悤�ł��邪�A��Ɏ������{�ɍ~��B�������R�Ɗ��q�����̘a�r�ɂ��A�����A�o�H�͊��q�{�̊NJ��ƂȂ�A���쎛�������q�{�ɏo�d����B�������A���q�����̎x�z�ɔ����������̗L�͍��l�Ɠ������A�������{�̋��s��}���O�ƂȂ�A���q�{�ɑR�����B�܂��A��㓖��͏��R����恂������Ă���B
���̌�A���쎛���͐��͂��g�債�A�e�n�ɏ��q�Ƃ���������B�������A���̎����̏��쎛���̌n���ɂ��ẮA�j���I���t�����Ƃꂸ�A�s�ڂȓ_�������B
�퍑����ɓ���ƁA���쎛��13��ɂ�����i���̂Ƃ��ɁA�Y���S���͂��ߕ����S�A��k�S�̐�k�O�S����R���S�E�͕ӌS�E�ŏ�S�ɂ܂Ő��͂��L����L�͂ȑ�g�ƂȂ�A�u�Y�����`�v�Ə̂���čŐ������}�����B
�i���̎q�E�`���̑�ɂȂ�ƁA�ˑA�{�����A�Z�����Ȃǐ�k�������������A�V��18�N(1590�N)�̉��B�d�u���ɂ�5��4,000�Η]�Ɋ��Z�ł��鉡����ł��������A���B�d�u�ŏ���3����1�����ꂽ�B�c��5�N(1600�N)�̊փ����̐킢�ŐΓc�O���A�㐙�i����̐��R�ɖ����������߁A�c��6�N(1601�N)�ɂ͉��Ղ��ꂽ�����A�Ό��Øa��ɗa����ꂽ�B�����ɐ퍑�喼�Ƃ��Ă̏��쎛���͖łB
�`���Ƃ��̎q���͒Øa��ˎ��莁�A�̂��T�䎁�Ɛb�ƂȂ��Ė������}�����B �܂��A�`���̖�����͗����암�˂Ɏd�����B�`���̎��j�ۓ��͉���Ɏc���Ă������A���ẲƐb�ł���o�H�V���ˌˑɒm�s400�̋q���̏d�b�Ƃ��āA�̂��ɖ������R�����Ɖ��ߖ����܂ő������B����ɁA�ԕ�Q�m�̈�l���쎛�G�a���`���̎q���ƌ����Ă���B |
|
�����̌䏊����(����̂�����悱����)�@�@�@ �ߐ{�S�߉ϐ쒬 |
�a���E�k���c���珬���Ɏ��鐼�����ɉ�����Q���U�݂��Ă��܂��B���̒��ł������Ȃ��̂��A���̌䏊�ł��B
�����͂قڐ^��Ɍ����ĊJ�����A�����͉������Ύ��Ɠ��l�Ɍ����⌺��A�A���Ȃǂ�����܂��B�����̒�����2.75���A�����ł̕���2.34���A�����͉��ǑO����1.9���ŁA�����S�̂�����������˂̏Z����v�킹��悤�ȍ\���ł��B�V��͒����ɓ�������o���A���E�ɐ؍Ȃ̉����Ɏ��������z���������A����̊O���Ɍ˂��͂ߍ��ނ��߂̒��荞�݂��{���Ă���A���I�ȓ_�ł͑S���I�ɂ݂Ă����w�̗�ł��B
���ӂɂ́A�������A�P���Ȃǂ̖��̂ŌĂ�鉡���悪����܂��B
��
����ŖS�̌�A����̏������̒n�Ɉڂ��ďo�Ƃ����O�����E�������ǂ𗊂��ė��āA�Õ��̒��Œj�̎q���o�Y�������A����݂��ē��y�鉤�̍@��槌��ɂ���ĉ��������ꂽ�ƌ����ӂ炵���B����ŁA���̉������u���̌䏊�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B �܂��A���ǂ𗊂��Ă����͎̂O���̔@����ŁA�ޏ����g����������������������Ƃ����`��������B�����Đ��܂ꂽ�j�q�́A���R���Y�ǖ�ŁA�ނ͏\�Z�̂Ƃ��A���̒n��o�āA���̕�d�����Ƃ������Ă���B �@ |
|
����O��(����܂�����E������)�@�@�@�ߐ{�S�߉ϐ쒬��R�c����
|
|
����m���_��(�����̂�₳������)�@�@�@���Ύs�ʎ�
|
�ߑ�Њi���x�Ɋ�Â����Њi�͋��Ђł������B�j���j�N�Ղ�ƒʏ̂����A�_���Ղ��Ís����B
���a�V�c�̎����A��ό��N(859�N)�ɑn�����ꂽ�Ƃ����B���̐��ł́A�R�鍑�����S(���E���s�s)�̔���_�Ђ��犩�����ꂽ�Ƃ���B�������w��䒬�j�x�ł́A�m������̂͐_�ЂɎc��̐���N�ォ���k������܂łł���A����ȑO�ɑ��݂������ǂ����ɂ��Ắu�Ȃ�Ƃ������������v�Ƃ��Ă���B�V�c�N��(938�N - 947�N)�ɂ͓����G�����Q�q�ɖK��A�����哢���̂��߂̐폟�F��Ƃ��Ė��[�߂��Ɠ`������B
���c�����������ւ��Ă������ɂ́A�����̐��h���u�ʎ�̗���ԉ��v�ƌĂ�A���������т��ї��V�����ق��A�|��̕�[���Ă���B���̂��ߏ��c��̗���ɔ����A�V���N��(1573�N - 1593�N)�ɕ��ɑ����A�Гa���Ď������B(�_�Ђ̂���ʎ摺�͏��c��ւ̐N�U�H��ɂ������B)�܂��헤���ɂ���Ȃ��牺�����ɐ��͂����������鎁�̐��h�����W�߁A�����̊�i��̒��ɔ���_�Ђ��K���Ƃ݂���u�Z�Y��v�v�̖���������B
���̌�A�n��Z���ɂ���ĕ��\�N��(1593�N - 1596�N)�ɎГa���Č�����A�ʎ�ˎ�̖x�ʎ�������4�N4��(�O���S���I��F1676�N5��)�ɖ{�a�̑��c���s�����B�܂��x��������i8�N3��(�O���S���I��F1711�N4��)�ɔq�a�c�����B�]�ˎ���̈�m���_�Ђ͈�ʂɓV���ЂƌĂ�A�ʓ��̓V��@�@�̎x�z���ɒu����Ă�������������A�H�X�ł͂Ȃ����m�����̕ʓ��E�����J���s���Ă����B���۔N��(1716�N - 1736�N)�̓͏��ɂ��A�����n�̖ʐς�2�A552��(��8436m2)�ŁA�n����E����(�r)�E�䗷���сE�V���Ɠc�������L���A�ł�Ə�����Ă����B�܂���ɏW���l�X��ړ��Ăɒ��X�������A���ӂɖ�O��(�����O��)���`�����ꂽ�B�������Ē������B�������Ƃ����m��̑��l30�l�͋ʎ摺����̕����Ɨ�����}���ĕ�������o����Ɏ��������A�]�菊�͕�����F�߂���m��͋ʎ摺�Ɏc�������B
��������ɂȂ�ƁA�ߑ�Њi���x�Ɋ�Â����Ђɗ�ꂽ�B1994�N(����6�N)���_�̋����n�̖ʐς�3�A746��(��12�A383m2)�A�ЗL�n��5��5��12��(��5�A494m2)�ł������B
����m��̒n���`��
�Ж��ł�������n���ӂ̒n���ł�����u��m��v�ɂ́A���̂悤�Ȓn���̗R���Ɋւ���`��������B
�u�́A���̒n��ɔ����J���X���_�앨���r�炵�A���l�͍����Ă����B�����ŃJ���X��ގ����悤�Ƌ|�̖��l���W�߂�ꂽ�B���̏ꏊ���u�V���v(�Ă���)�Ƃ����B�|�̖��l�̓J���X�ɖ������A1�ڂ̖�ŃJ���X���˗��Ƃ����Ƃ�����u��m��v�A2�ڂ̖�ŃJ���X���˗��Ƃ����Ƃ�����u��m��v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�A���ꂼ��V�����J�����B�˗��Ƃ����J���X��6�{���ŋʂ������Ă������߁A�ȗ����̑��̖��͋ʎ摺�ƂȂ����B�v
����A�Г`�ł͔����ɓ`���̓��e���قȂ��Ă���B
�u�́A3�{���̃J���X�����̒n��ɔ����B�|�̖��l�ł���F�i�͌�Ɂu�V���v�ƌĂ��n�ɘE�����āA�J���X�Ɍ����Ė��������B1�ڂ̖��2�ڂ̖�͎ˑ��������A3�ڂ̖�ŃJ���X���˗��Ƃ����B���ꂼ��̖�������Ƃ���ɂ͈�m��A��m��A�O�m��̒n�����t�����B�˗��Ƃ����J���X�͋ʂ������Ă������߁A�ȗ����̑��̖��͋ʎ摺�ƂȂ����B�J���X�́u���܂��̍�v�̒˂ɖ��߂����A��ɖS��ƂȂ��ăE�V�̎p�Ō��ꂽ���߁A����ӂɗF�i���ގ������B�J���X�������Ă����ʂ͒}�g�R�����ɕ�[�����B�v
���M�E��
�Ր_�͑f���j��(�����̂��݂̂���)�ŁA���Ж�a�E�C����S�̂����v������Ƃ��ĐM����Ă����B���̂��ߊC���痣�ꂽ�������ɒ���������̂́A���ƊW�҂̎Q�q�������B��錧�ɂ����鋍���V���M��(�_���M��)�̒��S�ł���A��m���_�Ђ̓V���l(�j���j�N�Ղ�)���I���Ȃ������͂ق��̐_�ЂœV���l(�_����)�͂��Ȃ��ƌ����Ă���A���Ђ̍Ղ�̌ォ�狌��6���̌����܂ł̊ԂɈ�錧�̑����̐_�ЂœV���l(�_����)���s����B����ŁA�n���E�ʎ�n��̎Y�y�_�Ƃ��Ă̐M������B1990�N(����2�N)�̒����V���ɂ���ނɂ��A�����̎Q�q�҂͌�����̒n��Z�������}�g�����w���s�s�ɂ��錤�����̐E�����w���������������Ƃ����A��w�@�����������������邱�Ƃ��������B
����̎��^�͍s���Ă��炸�A�Q�q�҂��e�����^���̑O�Ɍf���Ă���QR�R�[�h��ǂݎ���ĕۑ�����Ƃ����`�����̂��Ă���B
��Ƃ��Ă͉��L�̃j���j�N�Ղ�̂ق��A���U�ՁA�ߕ��ՁA�ܘZ��(5��6��)�A��Z��(9��6��)�A�V�����Ӎ�(12��21��)������B �@ |
|
���Ή��s |
|
�������䗅�_�Ё@�@�@�Ή��s���{
|
���_�Ђ͒������j�̉ߒ��̒��ŁA�u�X�̐_�Ёv�Ƃ��Ă̗��j�A������䂩��̐_�У�Ƃ��Ă̓`���A�����Ģ����҂�M�ɗR������_�У�Ƃ��đ��l�ȑ��ʂ������Ă��܂��B
���X�̐_��
�w�헤�����y�L�x�ɂ��ƁA�헤�������ȑO�̑��Âɂ͐V���E�}�g�E���E�߉�E�v���E���ς̘Z���ɕ������Ă����Ƃ����܂��B�@���n���͈�鍑�Ƃ����A�����Y���^�̗v�Ւn�ɂ����āA�����̑�a�����猩�ē��̊C���u�Ă�����(�����܂̂���)�̊J��̒��S�n�Ƃ��čł���������J�����Ƃ���ł�����܂��B���_�Ђ̌Ï̂ł���u�X�v�u�X�v�u��v�͐_�ЁE�_�E�_�_�̈ӂ�����킵�A�Ñ�_�؍��J�̎��ォ��̗R������_��ł��������Ƃ�`���Ă��܂��B
�������䂩��̐_��
�������㒆���ɁA�����V�c�̑\���ł��镽���](������̂�������)�����獑��(���ɂ�)�E�吷(��������)�炪�헤�坁(�Ђ����̂������傤)�Ƃ������E�č��{�ɒ��C���Ĉȗ��A���̂܂ܓy�����Đ��͊�Ղ�z���グ��ƁA�����䂩��̐_�ЂƂ��ĐX�̍��J���p�������悤�ɂȂ�܂����B�X�́u��X�����_�v�Ƒ��̂���A���̕����̎q�����Վ�ƂȂ��Đ_���ɋΎd���Ă����Ɠ`�����܂��B�@�܂��X�ɂ́A�X�̍��J�ɏ]�����镽���̌�a�u�X�ؓa�v������A�_�������ł��������̎���ɂ͐X�؎��┪�厛�Ƃ������@���t�����Ă��܂����B�@�V��18�N(1590)�A�헐�ƕ��̒��Ɋ������܂�āA�X�͉�ł��A�Z�S�L�]�N�̒����Ԃɂ킽���ē��n���x�z���Ă����헤�������ŖS���܂����B���̌�A�����̌���ł���ʓ�����@�ɂ���Đ_�Ђ���������Ă���܂��B
������҂�M�ɗR������_��
�]�ˎ���ɂȂ�ƁA����(���݂̐Ή��s���S��)�̒���Ƃ��ĕ{���ˎ叼���Ƃ̐M�͎�̂ق������A���_�ЂɎ������Ƒ���̐��h�����܂����B�܂����̍��ɂ́A�啨��_�͕����̎��_�ł���{����(���т�)�叫�Ɠ���_�ł���A�����ōł��쌱���炽���Ȑ_�l�ł���ƍl����u����҂�M�v���S���ɓ`�d�g�債�܂����B���_�Ђ��u�������匠���v�Ƃ��ĐM���W�߂�悤�ɂȂ��Ă��܂����B����10�N(1827)�ɁA���炽�߂Ď]�ۓ��R(���쌧�Օ��R)�̋������匠��(�����䗅�{)�̌䕪����������A����҂�M�̂��ǂ���ƂȂ��đ����̐l�X�̎Q�w���W�߂č����Ɏ����Ă��܂��B
������_�Ђ̗��j
����_�Ђ́A�Â��͈��Í��{��Ή��O�邪�������Ƃ����Ή��s���̈��J���h���̒n�ɒ������Ă����Ɠ`�����Ă��܂��B���q����ɐΉ��O�邪�z�����ƁA�R�_�Ƃ��čՂ��܂����B���̍��͐X�ؓa�̒m�s�Ђł�����܂����B�퍑���㖖���̓V���N�ԂɐX�̓V�����n�ɑJ�����ꂽ�Ɠ`�����܂��B�V�����n�͌��݂̋����䗅�_�Ћ����̓쑤��2�Ԕ��B�Гa�̑傫����1�Ԏl���������Ƃ����܂��B�]�ˎ���ɂ͕{�������̓V���Ղ̐_�`�̐�������䗷���ɂȂ��Ă��܂����B����39�N(1906)�ɋ����䗅�_�Ђƍ������A��Ր_�ł���o�Î�_(�ӂʂ��̂���)�͋����䗅�_�Ж{�a�ɍ��J����܂����B����_�АՒn�ɂ́A���݁A�m����א_�Ђ��������Ă��܂��B �@ |
|
���헤���`社�{�@�@�@�Ή��s����
|
�헤���`社�{(�Ђ����̂��ɂ������Ⴎ��)�́A��錧�Ή��s���Ђɂ���_�ЁB�헤�����ЂŁA���Њi�͌��ЁB�Ж��ɂ͐V���̂́u�헤�����Ћ{�v�̕\�L���p������ق��A�ʏ̂Ƃ��āu�`社�~社(�������Ⴖ��)�v�Ƃ��̂����B�Ή��̎Y�y�_�ł���A�n��Z������́u���_���܁v�Ƃ��Ă�Ă���B
�Ñ�A���i�͊e�����̑S�Ă̐_�Ђ���{���珇�ɏ��q���Ă����B��������������邽�߁A�e���̍��{�߂��ɍ����̐_�����J�������Ђ�݂��A�܂Ƃ߂č��J���s���悤�ɂȂ����B���Ђ͂��̂����̏헤���̑��Ђɂ�����B
���Ђ͐Ή��̒��S�s�X�n������u�˂̉��ӂɒ������A�������ɂ����ė�����̒�n��]�݁A�Вn�͋��헤���ɂɗאڂ���B���q��1994�N(����6�N)���_�Ŗ�2�A500�˂ŁA�e�����ƂɎ��q��g�D����Ă���B
���N9���ɍÍs������Ձu�헤���`�Ћ{���Ձv�́u�Ή��̂��܂�v�Ƃ��̂���A�֓��O��Ղ��1�ɐ�������B
���Ր_�@
�ɜQ���� (�����Ȃ��݂̂���) / �嚠�呸 (�������ɂʂ��݂̂���) / �f���j�� (�����̂��݂̂���) / ���X�n�� (�ɂɂ��݂̂���) / ��{���̑� (�����݂�Ђ߂݂̂���) / �z�����~ (�ӂ�̂����݂���)
����3�N(1791�N)�́w���А_�{��]�c�x�ł́A�Ր_�͑�ȋM��(���قȂނ��݂̂��ƁF�卑�呸�ɓ���)�ł���A�u���̖̂ؑ��ɂāA���Z�͉̂��~(���₵��)�`�v�ł���Ƃ��Ă���B
�����j
�Г`�ɂ��A�ޗǎ���̓V���N��(729�N - 749�N)�̑n���Ƃ����B�������w�Ή��s�j �����x�ł́A���Ђ̐��x���m�������̂��������㖖���ł��邱�Ƃ���^���悵�Ă���B
�����̎Ж��́u���{�̋{�v�ł��������A����N��(901�N - 923�N)�ɓV�_�n�_(�Ă�)��6���̐_���J����悤�ɂȂ��āu�Z���̋{�v�ƂȂ�A����Ɂu���Ёv(�Ñ�̓ǂ݂́u��������v)�ɖ������߂��B�܂��n�������͌��݂̏헤�����Օt�߂ɂ������Ƃ���邪�A�V�c�N��(938�N - 947�N)�ɑ坁��(���F��)���헤�{��(�Ή�)�ɒz�邵���ۂɒ���̂��߂Ɍ��Вn�ɑJ�����Ƃ����B�_��͑�X�����������P���Ă����B
���Ȃ��Ƃ�����3�N5��(�����E�X��F1179�N6��)�Ɂu���c�����āv���o����A�{��̐������Ȃ��ꂽ���̂Ɛ��肳��Ă���B���c�ɂ͋g�c�_�Ђ�}�g�R�_�ЂȂǂ̏헤�������Ђ⋽�����q���㖖���܂Ō��܂��Ă������A14���I�����ɂȂ�ƁA��X���̔C��S���Ă����n���炪���c�����ۂ��A�_�Б��͊��q���{�ɒ�i�A���{�͑��c���S�𖽂���ƂƂ��ɒn����ɑ��c�̐��̗L�����L�ڂ��������̒�o��v�������B���̎��̐������u���Ћ{�����v�Ƃ���6�ʂقǎc����Ă��邪�A��������u���c�̐��͂Ȃ��v�Ƃ��Ă���B����͎Ў��ی쐭������߂Ă������{�ɑ���֓���Ɛl�̔����̒�����1�Ɉʒu�t������B�܂����Ђɑ��錠�Ђ̔ے�A���ɋ@�\�̕ώ��E��̂Ƃ��Č��邱�Ƃ��\�ł���B����Ɋ��q���㖖���ɂ́A�坁���̈ꑰ���Вn�̓c���ɂ��Ēm�s�����s�g���Ă����B
�����ɂ͍��i��ɂ��̍��J��3��3����7��16���ɍs���Ă����B�܂��A���Ȃ��Ƃ��퍑����܂ŏ헤�����̐_�������s�E�哱���闧��ɂ���A�����ɑ��Ă��֗^�ł���قǂ̌��͂�L���Ă����B�����āA7���̑��Ћ��m�ƌĂ�镧���m���_�Ђɕ�d���Ă����B
�i��12�N5��(�����E�X��F1440�N5��)�ɂ͑��c�����B�������ɂ������ĕ��^���F�邽�ߎQ�q���A��ɏ����Ė߂����܂ɌR�z�c��1���ƒZ��2�t����i���A�ȉ��̂悤�ȒZ�̂��r�B
�u���̘I�͒u�������_�_�� ��t�����Ă̖�̌��v
����̎q���ł��鑾�c���@�͐�c�E����̊�i�����R�z�Ɋ������A�R�z��[�߂���̗��n���(�͂�)�����A���̊W�ɗR���������Ċ���8�N4��(�O���S���I��F1668�N5��)�ɐ_�Ђ֕�[�����B
�]�ˎ���ɂ́A�{�a�ɉ����A���a�E�q�a�E�_�{����L���A���ЂƂ��č��[���_�ƈ�ז��_���NJ����Ă����B���i4�N(1627�N)�A�헤�{���ˎ�̊F�엲�f�����݂̎Гa���Č�����B���̔N�ɍ]�˖��{�ɂ���ĎЗ̂�25�ƒ�߂�ꂽ�B���̌�A�����M�肪�V�a3�N(1683�N)�ɔq�a���C�z�A1886�N(����19�N)6���Ɏ��q��Ŕq�a�_��̏C�z�Ɩ{�a�̊����ɕύX�����B
�����ېV��A�ߑ�Њi���x�ł͎n�߂͋��Ђɗ����A1900�N(����33�N)9���Ɍ��Ђɏ��i�����B������L�O���ĐΉ������͊�t���W�߂Đ_�Ђ̊�������A�O�������ɎГa��z�̎Ѝ��̕M���˗������B1978�N(���a53�N)�A���А_�Ў��ӈ�ɐV�����u���Ёv���ݒ肳��A�꒚�ڂƓڂ�������A�_�Ђ͑��ГڂƂȂ����B���̎��A�n���Ƃ��Ắu���Ёv�̓ǂ݂́u��������v�Ƃ��邱�Ƃ���c�Ō��肳�ꂽ�B
2005�N(����17�N)4��14���A�{�a���Ή��s�w��L�`������(������)�ƂȂ����B �@ |
|
�����̋{�@�@�@�Ή��s���̋{
|
�Ր_�@�V���X�w�j��
�R���͓ޗǎ���̓V���N�Ԣ�{���O���̋{��̂ЂƂƂ��Č��Ă�ꂽ�B���{�̒n���͐���k�̕��ʂɑ����A���{�̖k�ɢ���̋{����J��A��ɢ���V�l��Ƣ���V�l����J�����B
����̋{��ƍ��ɂ����ԂƁA����k�̐���ɂȂ�A���ɂ��猩�Ģ�k�ɐ���̈ʒu�Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����A�k�ɐ��M�̂�����ł���B
�����͍��{�ݒ��̊��������J���s���Ă������A��ɍ��ے��̎��_�Ƃ���A���N�Վ����s���Ă����B���݂͏헤���`�Ћ{�ɍ��J����Ă���A�����̏ꏊ�ɂ͂Ȃ��B�@ |
|
���؈�א_�Ё@�@�@�Ή��s�{��
|
�Ր_�@�q���
�؈�א_�Ђ̗R���́A���@�Ƃ������@�̋��ɂ������Ɠ`������B�c���N��(1596�`1614)�A�̎�Z�����ɂ�荑�ƈ��S�E�܍��L���E���^���v�ׂ̈ɐ[���M����Ă����B�����N��(1818�`1829)�ɕ��@�͔p���ƂȂ�؈�א_�Ђ������c�����B�Č��͍O��2�N(1845)�B�ؒ��̖��́A�{���Z�̈�¢��أ�ɗR�����A���i2�N(1625)�A�����ɢ��أ����ӂ���̌ď̂��L����Ă���B�@ |
|
������@�@�@�@�Ή��s���{
|
����@�͗��}�R����@�Ɋy���ƍ����A51cm�̈���ɔ@������{���Ƃ���V��@�̎��ł���B�{���̌�O���ɁA�n�����F�s�������������u���Ă���B
�`���ɂ��A��鐝�V�c(�݈�1036�`1045)�̌��A�O���w�����̑n���B�܂��u�헤�坁����(�`935)�̋F�菊�Ƃ��āA�q�ޗ��ǖ��J��v�Ƃ����L�^������A11���I���߂܂łɊJ�R���ꂽ�Ɛ��@�ł���B
�܂��A�����ɂ͔_��\�̍l�ĎҁA��ؖ��\�̕悪����B�ނ����\�삵�Ă����Ƃ��������́u�A�c�o�C�v�̒n�ɂ́A�ނ̋Ɛт��������āu���\�ˁv�����Ă��Ă���B�@ |
|
����ڗ��R�����@�@�@�@�Ή��s����
|
�@�h�@�V��@
�헤���{(���݂̐Ή����w�Z)�̐��Ɍ�������Ă��܂��B
�n���͕s�ڂł����A�V�c2�N(939)�A�����傪�헤���{���U�߂����ɏĎ����܂������A��������̍ő�̌��J�҂ł��镽�吷���Č����ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B���吷�͕����]���̎q����������ɎE���ꂽ���Ƃŋ�����헤��(��錧)�ɖ߂�V�c3�N(940)�ɉ��썑(�Ȗ،�)�̍��������G���𖡕��ɂ� �����łڂ��܂����B���Ɖ������ւȂ���ɐ������̑c�A���ۍt�̕��ł��B �@ |
|
���t�юR�������@�@�@�Ή��s���{
|
�Ή��s���{��6���������ɂ���t�юR�������́A�������㒆���̕����ŏ헤������ɐ������̑c�Ƃ����镽����(���ɂ�)�ɂ���1000�N�O�Ɍ������ꂽ�B
�@�ӗ֊ϐ�����F��{���Ƃ��A���Ă͐^�����@���������헤�坁���ŖS��͑����@(�T�@)�Ƃ��č����܂ő����Ă���B
�u�����͕��ƈꑰ�̊�Ղ��ł߂��w�͂̐l�B�������Ƃ������ɂ͉Ƒ��⎟����̍K���╟���肤�C���������߂��Ă��܂��v�Ƒ]���c�G���Z�E�B
�����͊����V�c�̂Б��E�����](��������)�̒��j�ŏ���̏f���ɂ�����B�}�g�R���[�̋��^�njS���Γc(���}���s)��{���n�Ƃ��A�헤�����{�̊��E�u�坁�v���p�����B
���j�E�吷�͒���{���R�ƂȂ�A�吷��4�j�E�ۍt�͈ɐ����ɒn�Ղ�z�����ɐ������̑c�A���̌�͐��x�A���t�A�����A��̕����������x�������͂ƍ��͂��ւ��������A�����Ă��̒��j�E���������m�ŏ��߂đ�����b�ƂȂ��Đ����̎���������A�u�����ɂ��炸��ΐl�ɂ��炸�v�ƌ�����Ő������}�����B
����A�헤�坁�͍����̎��j�E�ɐ����p�����A���͂����߂��F��(��������)���z�邵���{��������_�ɕ����ꑰ�ɂ�钆���̏헤��(���Ή��s)�x�z����700�N�ԑ����A���|�`��̐N����1590�N(�V��18)�ɖŖS�����B
�������͏헤�坁���̕�Ƃ��Ēm���A�坁����X������u�헤�坁���揊�v(�s�w��j��)�ɂ͌܂̐�ςݏd�˂��ܗ֓�14��ї����A�{���O�ɂ͍���3.2m�̋���ȁu�헤�坁����v������B�@ |
|
����ؓ��q�@�@�@�Ή��s
|
���Ή��s������J���@
���_�R�ɂ́A��银�q���Z��ł����B���q�͖�A���ɏo�Đl��������ċВ��ɓ���A�����H�ׂĂ����B�������������琪�����ɂ���ė���҂�����ƌ����\���A���낵���Ȃ����̂ŋS�z�R���z���ē����A�В��܂�����o���Ă������B(�w���̖����x31���@1992�N)
���Ή��s�@
��ۓ��q���ő��ł����ؓ��q�����ꂽ�B�����̕��P�Ɩ��������ǂ������������A���܂̋S�z�R�ł���B(�w���̖����x11�� 1972�N)
���Ή��s
��银�q�Ƃ����S�����āA���̐l��������Ă������B�l�X�͕s���������������狭���S���ގ����Ă����Ƃ����\���������B����������q�͓��������Ă������B���̎��R���щz���čs�����Ƃ����B(�w���̖����x6���@1967�N)
�@ |
|
����ؓ��q�`��
|
���V����
���V�����Ȕ��s�@���F�u��O�Y�k�v(�J��@����)�A�w�Ȕ��s�j�E�j���W�����ҁx��
�Ȕ��s�y���n��́A�S55�˂̂�����ؐ��𖼏��Ƃ�34�˂ɏ��B���݂̈�ؐ����ƌĂ�鏊�Ŏ�ۓ��q�ƈ�ؓ��q�����o��������A��ؓ��q�����̑����J�����Ƃ�����B���̎q���̉Ƃ�����B�܂���ؐ��̉Ƃł͊������ł���Δj�������Ƃ��̉Ƃł͕s�ǂ��o��̂ō���Ă͂����Ȃ��Ƃ����B
(���c�a�v�u�z��̎�ۓ��q�v�w�`�����w�����x51���@�`�����w������@2001�N)
���V�����Ȕ��s�@���F�J�쌒��u��O�Y�k�v�A�w�Ȕ��s�j�E�j���W�����ҁx��
�Ȕ��s��V�L�n��ł́A�ߕ��ɂ��Ȃތ����`���ŁA�u���̓��n�Ӑ��͎�ۓ��q�̘r��������̂ŋS�͕|���Ȃ��B��ؐ��͈�ؓ��q�̎q���Ȃ̂ł��̗����͓��܂������Ȃ��Ă��ǂ��v�Ƃ����̂�����B
(���c�a�v�u�z��̎�ۓ��q�v�w�`�����w�����x51���@�`�����w������@2001�N)
���V�������z��S�g�쒬
���_�̒���l�̉��̊≮�ɂ́A�́A��银�q���Z��ł����B��银�q�̑��ՂƁA33�̂̕��l���c���Ă���B
(�u�V�������z��S�g�쒬���v�w�����̖K�x���a31�N�x�� ���{�@��{�����w������@1957�N)
|
����錧
����錧�Ή��s������J���@
���_�R�ɂ́A��银�q���Z��ł����B���q�͖�A���ɏo�Đl��������ċВ��ɓ���A�����H�ׂĂ����B�������������琪�����ɂ���ė���҂�����ƌ����\���A���낵���Ȃ����̂ŋS�z�R���z���ē����A�В��܂�����o���Ă������B
(���c���u���̐Ɋւ����l�@�v�w���̖����x31�� ��閯���w�̉�@1992�N)
����錧�Ή��s�@
��ۓ��q���ő��ł����ؓ��q�����ꂽ�B�����̕��P�Ɩ��������ǂ������������A���܂̋S�z�R�ł���B
(����`���u�j�ւƓ`�����`�����_�R���Ӂv�w���̖����x11�� 1972�N)
����錧�Ή��s
��银�q�Ƃ����S�����āA���̐l��������Ă������B�l�X�͕s���������������狭���S���ގ����Ă����Ƃ����\���������B����������q�͓��������Ă������B���̎��R���щz���čs�����Ƃ����B
(����`���u�Ή��s�n���v�w���̖����x6���@��閯���w�̉� 1967�N)
|
�����s�{
�����s�{���m�R�s�@
�R�Ɉ�ؓ��q���Z��ł����B���̓��A������B��ۓ��q�̏o�邾�����Ƃ����B��ؓ��q�͕�����̎q�ł������Ƃ��`�����Ă���B
(�{�{���́u�u��]�R�`���v�����l�v�w�ߋE�����x48���@�ߋE�����w�� 1969�N)
|
�����{
�����{��؎s��ؒ��@�b�F�ØV
�������E�����q�͉��p�����ٖe�ł��������A�����ŐS�D�����F�Ɉ�����Ă����B�Ƃ��낪�A�ӂƂ������Ƃ���l�̌���~����悤�ɂȂ�B�����̋S����`���ɋC�t������͉Ƃ��o�ĐX�ɐ��݁A�l��߂炦�Ă͌�����H���悤�ɂȂ�A�㐢�Ɉ�ؓ��q�ƌĂꂽ�B
(���_���сu��ؒ��Ɏc��`���u��ؓ��q�v�̈�ցv�w���y��������x������y������ 3��29���@1933�N)
�����{��؎s�@���F�w�ےÖ����}��x�A�w�ۗz�����x
���{��ؒ��ɂ͈�ؓ��q��������Ƃ����Ƃ̌オ�c���Ă��邪�A����ɂ��ƁA��ؓ��q�͐�粌S�������̓y���̎q�ł��������A���܂�Ȃ���ɉ傪�����A���������A����������ċ����ł��邱�Ɛ��l�ȏ�ł������̂ŁA�ꑰ�͂����|��ē����Q��ؑ��̕ӂ�Ɏ̂Ă��̂��Ƃ����B���̎q�͎�V���q�ɏE���ė{�炳��A���̑��k�ƂȂ��đ�]�R�̊ތA�����A�ތA�̂������n�����Ȃ��Ĉ�ؓ��q�ƍ������̂��B
(���_���сu��ؒ��Ɏc��`���u��ؓ��q�v�̈�ցv�w���y��������x������y������ 3��29���@1933�N)
�����{��؎s�@
���锯�����̕v�w�͉|�̖̉��Ɏ̂Ă��Ă���Ԃ�V���E�����B����s���傪2�{������l�ԗ��ꂵ���ٌ`�̐Ԃ�V�ł��������A�v�w�͎����݈�Ă��B�Ƃ��낪������Ƃ������Ƃ��炨�����ȉ\���L�܂�A���q�͉Ƃ��o���B���ꂪ��̈�ؓ��q���Ƃ����B
(�b�]�Ȑl �u����`���s�r(�O)�v�w���y��������x������y������ 1��5���@1931�N)
�����{��؎s�V����
���{�O���S��ؒ��V�����ɁA������̋S�A��ؓ��q�o���`��������B
(�R�c���v�u�j�����J���ʉƁv�w���Ɠ`���x10��5���@�O���� 1937�N)
|
�����Ɍ�
���w���^���L�x
�O�g����]�R�Ɏ�ۓ��q�Ƃ����S�������B���̗R���B���㑺�ɍ��n���l�Ƃ����l�������B�q�����Ȃ��̂ŌˉB�R�ɐ��肵�A�j�q�����܂ꂽ�̂ŊO���ۂƖ��Â����B7�˂��獑�㎛�ɂ͂��������A17�ɂ͔��l�������̂ŕw�l�ɂ��ĂāA����̎R���֓����������ł����B�l�X�͎�ۓ��q�Ƃ������B�O���ۂ͐M�B�ˉB�R�֔�ѓ���A���l���Â�H�������A���l���ˉB�匠���ɋF�O����]�R�ɔ�ы������B���g�̒��Ɉ�������B��͎אS�ł��ɋS�ƂȂ肻�̉Ƃ̔j������яo���A14�A5�N�O�����]�R�ɏZ��ł����B��ۓ��q�ƈ�͑����A��ۓ��q��������
(���c�a�v�u�z��̎�ۓ��q�v�w�`�����w�����x51���@�`�����w������@2001�N)
|
���L�ڂȂ�
���n���L�ڂ͂Ȃ����A���e�I�ɂ͋��s�̎��Ǝv����B
���w���^���L�x
����3�N3��26���ɑ�]�R�ɓo��B�S�傪����A��c�������ł��j��B�s���玝�Q�����������S�Ɉ��܂���B��ۓ��q�͍�ɐl�Ԃ̘r�����o���B��ۋS��17�A8�Ɍ�������j�ł������B�����ĉ��̈�Ԃɓ���A���̂������ĐQ����B���9��8��������B�e�X���������ڂ��o�܂��A�ꌾ���̉��݂ƌ������ł����B���̓��͓V�ɔ�я��A�����̓��ɐH�����B�n�Ӎj�͈�S�̕����ɓ���B��S�͍j�̎p�ɂȂ�B�吨�������������ǂ��炪�{�����킩��Ȃ��B�������s�̍j�ɂ͊z���{������Ƃ����A�}�ɔ��Ԃ̏���{�̏o���ق���ގ������B�O�̋S������
(���c�a�v�u�z��̎�ۓ��q�v�w�`�����w�����x51���@�`�����w������@2001�N)
���w���^���L�x
�s���鐼�̕��A������œn�Ӎj����S�Əo��A��S�̍��r��������B��͂ǂ����ɔ�ы������B�s�ɘr�𑗂������A���̘r��7��7��̊�5�w���J�����Ƃ����B
(���c�a�v�u�z��̎�ۓ��q�v�w�`�����w�����x51���@�`�����w������@2001�N)
��
�����ɏZ�݂��B��ؓ��q�ɂ��Ă̘b����B
(�S�䓄�J �u�������M�v�w���{���M�听��2���x12�� �g��O����1974�N)�@ |
|
�����_�R�̋S(��银�q)�@�@�@�Ή��s |
���_�R�͐̂��炱�̒n���̐M���W�߂Ă����B�����n��ƐΉ��s���̋��ɂ���A�R�̌������Ƃ����瑤�ł͒����ԋC����قȂ��āA���ꂼ��ʁX�̋C��ɕω����������Ă����B�̂͒��オ1�̎R�ł��������A���Ԃ̍̐Ǝ҂ɔ��p����A�������肻�̎p���ς��Ă��Ă��܂����B���ł͂������ė��_�̖��̒ʂ�A�Ή��̎s���̕�����݂�ƉE�����ō������̂ł��闳�̌`�Ɍ�����B���̑��̐��̖����̃q�Q�̂悤�ɂ�������B�������A������ߔN�͎�̕���(���̎R�̒��̂������t��)�̍̐��i�݁A2�̎R�Ǝv����悤�Ȏp�ɕς��Ă��Ă��܂����B�R�̑O��̋C��̕ω������������Ȃ����炢�ɕ����ʉ߂��Ă��܂��V�̌b�݂̉J�Ȃǂɂ��e�����o�Ă���悤�ł���B�삩�痬��o���ł���R��������������̒r�ɒ�����A�Ή��w����ʂ��ĉ����Y�ɒ����ł��邪�A�̂̂悤�Ȃ��ꂢ�Ȑ�͖]�߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��낤���B�M��[�߂Ă����R�ł���A�̂̂܂܂̎p���c���ė~�������̂ł���B
���̗��_�R�ɂ́A��̂��痳�_�̕v�w���Z��ł���A���_�l�̂������łӂ��Ƃ̈�˂��͂�邱�Ƃ��Ȃ��A�ۓV(���Ƃ�)�������ƁA�l�X�͉J��̋F��𗳐_�ɂ������A���ɂ������|���Ɉ�˂̐������݁A�x�܂����A�����Ƃ����B�����r���ŋx�ނƁA�x���ɉJ���~���Ă��܂��ƐM�����Ă����B
���̗��_�R�ɂ́A���_�v�w�ȊO�Ɂu��银�q�v�Ƃ����S���Z��ł����B���q�́A�O�g�̑�]�R�̎�ۓ��q�̌Z�핪�ƌ����A��������l�Ԃ�����傫�ȋВ��܂������A�̍����߂ŕR��������A�邲�Ɨ��l��������Ă͐H�ׂ��Ƃ����B���̂��߁A�l�X�͓��q������A�q���Ȃǂ́u��银�q�v�ƕ����������ŋ�����ނقǂł������B
�܂��A���̂Ƃ��A���q�����ɉ����Ă����В��܂̍����ߐ��A�ז��ɂȂ��ē����o���Ă��܂����B���ꂪ�͂邩���̖������̐��ɗ����A���̒��ɂ߂荞��ł��܂����B���ꂪ���Ɏc��В��ł���B
���ɂ��A�������琪�����ɂ���ė����(������)������ƌ����\���A���낵���Ȃ����̂ŎO�p�R���z���ē����A�В��܂�����o���Ă������Ƃ̘b������B���̖�����O�p�R�́u�S�z�R�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B
��
�ǂ��ɂ��A�S���ӂ��Ƃ̐l��������Ă����b�������c���Ă��邪�A���̈�银�q�ɂ��ẮA���̈�Ɉ�ؓ��q�̘b���`����Ă��ċ����[���B������̘b�͗L���ŁA��ۓ��q�̉Ɨ��ł���A���s�̗������ �n�Ӎj �킽�Ȃׂ̂� �ɕИr������A�̂��ɍj�̔���ɉ����Ă��̕Иr��D���Ԃ����Ƃ����b�͉̕���̉��ڂɂ�����L���ł���B�܂��A���q�̏o���n�͐ےÂ̍�������(��؋߂�)���A���̕x���������邪�A�z��(�V����)�̓Ȕ�(����)�Ƃ����b������A�Ȕ��̌y���Ɉ�ؓ��q���Ղ��K������B�V���ł����̘b�͓`����Ă��āA�����́A�V���̒����őc��ɗǂ��������ꂽ�B��ۓ��q�ɂ��Ă��z��o�����ƈɐ��R�o�����Ƃ�����B �@ |
|
�����c��א_��(���������Ȃ肶��)�@�@�@�Ή��s�L�n |
�Ր_�@�F��䍰�_
����6�����̊L�n�����_�����̋u�˒n�Ɍ�������Ă��܂��B ���̒n�͐Ή���(�O��)�ՂŐ_�Ђ̑O�Ɉē��Ŕ�����܂��B
�u����2�N(1214)�헤�坁(�Ђ����������傤)���p�����āA�헤���q�ɂ����Đ������Ƃ��Ă����坁����(��������)�� ���q���{����{���̒n���E�����������A���̒n�ɋ��ق����܂����B���ꂪ�Ή���̋N����Ƃ�����B ���̌�A�坁���̋��_�Ƃ��ď�s����������u�Ŗ�����(�����������)�v�ɂ́A��k���������� �坁����(��������)�̋���Ƃ��āu�{���Ή���v�̖��O��������Ă���B
�����̎q�F��(��������)�̑�ɂ́A�坁���͏헤���q���g�����ĕ{����(���݂̐Ή����w�Z��)��z�� �{��������Ɉڂ������߁A�Ή���́u�O��v�ƌĂꂽ�Ƃ����B�ߐ�����ɏ����ꂽ�n���ނɂ́A�坁�����{����Ɉڂ������Ƃ́u�O��v�̏��Ƃ��� �Ή��^�E�D�|�����V���E�c����w�Ȃǂ̖��O������A�V��18�N(1590)�̑坁���ŖS�ƂƂ��� �O����p��ƂȂ��Ă���B���݂́A�����Ă̏��ł������D�|�����J��D�|�_�ЂƖx�E�y�ۂ̈ꕔ���c���݂̂ł���B�v
�D�|�_�Ђ͓V��18�N�ɍ��|���ɂ���Ėł坁�����Ă�ꂽ���̂ł��B��א_�Ђ͂��Ƃ͊O��̋S�叜�Ƃ��čՂ��A�ً{��ב喾�_�Ƃ������A�V��6�N(1835)�ɉ��c��א_�ЂƉ��߂�� ���D�|���̈�ނł��鉪�c�Ƃ��K��(������)�����Ă��܂��B �@ |
|
������������_��(���傤���傤��������)�@�@�@�Ή��s�����
|
�������
������Ƃ������O���o�Ă���͕̂����傪1000���ʂ̕���3000�l���������{�̕���������A�헤���{��D������������̎��ł���B����1000�N�ȏ���O�̑厖���ł��B
���傪�������N�������������ɂ��Ȃ����u��������(�͂邠��)�v�u��������(�ӂ����͂����)�v�����̈ꑰ�̏Z��ł����̂ł͂Ȃ����ƌ����邱�̐�����ɂ���u�����_�Ёv�����Ă݂��������̂ł���B
����L�ł��别�l�̂悤�ɏ�����Ă��铡�������Ƃ͂ǂ�Ȑl���������̂��B
������͐Ή�����}�Ԃ�������355���A�}�ԊX��(�}�Ԃł͍]�ˊX���Ƃ��)��Ή����猧��7�����̉���������Ƃ��납���ɂ���B
�����_�Ђ͌��c�A�p�[�g�̏������355��������������������獶�ɏ����������Ƃ���ɂ���܂����B�K���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��炵���A�����͂���Ă��܂������A���Ղ͂Ȃ��A�����������Ղ������c��܂����B�_�Ђ�����قǑ傫���͖����A�e�n�̕����Ɏc���ꂽ�Ƃ����悤�ȕ��ʂ̐_�Ђł��B
�O�ɏ��������|�`���̎�˂̂�����͖ڂƕ@�̐�ł��B
������̖��O�̗R���͏헤����(���傤���傤)���Z��ł����Ƃ���Ƃ����Ӗ��ł����n�����ƌ����Ă��܂��B�헤�̍���(���Ή����w�Z�̕~�n)�ɂ͏헤�坁(�������傤)���Z��ł��܂����B
��(���傤)�Ƃ����͖̂�E�ʼn�̉��̈ʂł����A�i�X�ƔN�オ�i�ނƁA�헤��͓s�ɂ��Ă���Ă��Ȃ��Ȃ�܂�����A������̌��m���̂悤�ȃg�b�v�̖�E�ɂȂ��Ă����܂��B�����Đ��P�̂悤�ɂȂ薼�O�܂Łu�坁���v�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ă������̂ł��B
���傪�헤���ɂ�D�����Ƃ��A�����헤���ɂɂ͂�������̌����ۊǂ���Ă����Ƃ����܂��B�����͑�ϋM�d�ł��������z��1��5����������Ɠ`�����Ă��܂��B�@ |
|
���s���@�@�@�@�Ή��s��{ |
�����͖����R�����s���@�B�@�h�͐^���@�A�{���͕s������(�s��̍�Ɠ`������)�ł���B
����ɂ�15���I�A���`������ƍN�̑��E��慌o�ɎQ�����ĉ������ꂽ�u���@�@�،o�v������헤�{���̎R�����Y�q��̊�i����������V�c�̏��Ȃł��雂�˂�����B
�܂��A�����Ǝ��̖@��̂ЂƂŁA���w�蕶�����̕��A�s�w�蕶�����̖ؑ��s�������y�ѓq�����A�ؑ�����ɔ@������������B�@ |
|
�����g�R�_��(������)�@�@�@�Ή��s��ˁ@���g�R�R��
|
�}�g�R�ȂǂƂƂ��ɘA����`��������g�R�ɑ�����g�R�M�Ɋ�Â��_�Ђ������B���Њi�͋��ЁB���g�R�R��������k�Ɋu�����������ɖ{�a���������A�X�ɂ��̖k���ɔq�a������B�܂������̗��R�[�ɂ��ꂼ��y�q�a�Ƃ��Ă̗��{������B�����n�ɂ͋ߐڂ��ĉ��g�R�{�{�Ɛe�{�������A���̗��{���ĉ��g�R�����Ƒ��̂���A���{�ɑ��Ē��{(���イ����)(���g�R�_�В��{�E���g�R���{)���̂��A��ɒ��V�{(���イ�Ă�)�Ƃ��̂��B
�Ր_�@���헧���@�Ɏדߊ@�Ɏדߔ���
�������N(19���I��t)�܂ł͕���@(���ア��)�Ƃ����{����̂̐^���@���@�ŁA���g�R���[�̐Ή��s�k�����ӂɋ����̐M����L����헤���L���̏C�����̗��ł��������B
�Г`�ɁA�i�s�V�c�̎���ɓ��{���������݂̓��k�n���肷��ɍۂ��ĉ��g�R�ɓo�q�A�_���ɂ��V�䒆��_�A���̐_�A���̐_��3�_���J��A�Гa�����Ă��̂��n�J�ŁA����20�N(800�N)�ɂ͐��Α叫�R�A���c�����C�����k�n������ɍۂ��ē��_�Ђ폟���F�肵�A�哯���N(806�N)�ɎГa����i�����Ƃ����A���n�֖K�ꂽ�O�@��t�ɂ���āu���g�R�匠���v�ƍ����ꂽ�Ƃ��A�m��2�N(852�N)�T����3�N�̑n�J�ł���Ƃ������B�܂��A���g�R�����͒��17�N(876�N)�ɏ]�܈ʉ���������ꂽ���j���ݎЂ̏헤���O�}�_�_�ɔ�肳��Ă��邪�A�u�O�}�_�Ёv�Ǝ����ꂽ���D���c����Ă��鎖����A3�{���̓��ɓ��_�Ђ�����ł���Ƃ����������B
���g�R�����͌��݁A���_�ЂƖ{�{�A�e�{��3�_�Ђɕ�����A�x���Ƃ��ߐ��ɂ͂��̌`�Ԃł��������A�А��Ɉ˂����͘a�̎R���F��O�R�̍Ր_����������Ė{�{�E�e�{��2�{���V���ɑn�����ꂽ���߂ł���Ƃ����B�܂��A��R�x�z�ł͂Ȃ��O�R�C���̌��ۂ����ꂽ�͈̂����͉��g�R���}�g�R�̎}��ł��鎖����}�g�R�_�Ђ̉��ł��̒n�ʂ��Ⴍ�A�Ǝ��̐M��W�J����܂łɎ���Ȃ��������߂ƌ����A�����M���e�������ʂ���̂ł��邪�A�Ƃ܂�ߐ��ȍ~�͕���@��ʓ��Ƃ���{����̂̌`�Ԃ��̂�A��ˑ�(���Ή��s���)���J���Ă����_�Е��t�̖w�ǂ̕ʓ��E�����т���ƂƂ��ɓ����̖ōߎ�(���V���s����)�Ƃ��ď@���I���S�Ƃ�����A�����ČÂ�������g�R���C�s��Ƃ����C����(�R��)���{�ɏ��������Ď�p������F�����s���u�R��B(��܂���)�v�Ƃ��đg�D�����Ă����B�܂����{������n5��^�����Ă������A������(19���I����)�ɖ{�ЍČ��̂��߂̍u����������Ă���A����͈ێ��o�c�̂��߂̍����m�ۂ�ړI�Ƃ�����̂Ǝv���邪�A���̍����_�@�Ƃ��ĎR��B�̏@���s�ׂ�}��Ƃ��Ď��ӕ����ɐ_�`�����K��������(�����݂����n��Ղ̋N��)�A����(18���I��)�����ɎR���̏C�s�����u�T���(���傤��)�v�Ƃ��Đ�������ƂƂ��ɓo�q�𑣂��g�D�Ƃ��đT��u(���傤����)�������������肷�铙�̐ϋɓI�ȕz��������W�J���A���ꂪ�n���I�ɂ��旒����B�Y�Ƃ������L�͂ȐM���l������v���ƂȂ����Ǝv����B
�������N(1868�N)�ɐ_�����R�߂��o�����ƈ�U�_�ЂƂȂ������A���������đi�ׂ��N���������߁A��2�N5���ɉ��߂Ď�ɂ߂��s���Đ_�ЂƎ��@(������@)�����A��6�N(1873�N)�ɋ��З�i�A�Ж����u���g�R�_�Ёv�Ƃ��A��11�N(1878�N)�ɎQ�q�҂̕X��}���ē��[�̑�ˑ�(���E�Ή��s���)�ɔq�a������(�����q�a)�B����16�N(2004�N)�ɂ͐��[�̐^�ǒ�(���E����s)�ɔ�����V��R�_�Ђ̎����ŐV���ȗ��{(�^�ǔq�a)�����������B �@ |
|
���y�Y�s |
|
�����˔ʎ�ƌ��E�@�@�@�y�Y�s����
|
�����˔ʎ
�y�Y�s���˂̗����R�ʎ�́A���쉺���̓�݁A���ˋu�˖k�[�̕W����m���̔����n��ɗ��n����B���ݐ^���@�L�R�h�ł��邪�A���O�Ɏc�銙�q���㞐���̖�������̌��E�Ȃǂ��A�헤�ɂ����鐼�厛���^�����@�̋��_�ł��������Ƃ��������Ă���B
�����߉ޓ��ɂ͖ؑ��߉ޔ@���������u����A���̐���N��͊��q����〜��k�����Ɛ��肳��Ă���B
�y�Y�s����ψ���ɂ���ď��a61�N�Ɋm�F�������s���A�����̍a�E�y��A���������܂ފ����A�핽���ꂽ�Õ��̎��a�Ə��ւȂǂ����o���ꂽ�B�����̈╨�ł́u���d������v�̗��������^��������������b�䌬�ۊ��E����̌������A�����y��A�����فA����炯�Ȃǂ̊T�v������Ă���B���̂ق��̏o�y�i���݂�ƁA�f�Փ�����ł͐����~�r�E����q���L�B�ٕ��q�E�m���Ԑ��E���F�A�����l���فA�V�ڒ��q�A�S�����l�A���Y����ł͐��˓S�����O���r�q�D�����H�E�l���فE�r�q�A�튊�����E�k�E�فA���Z����(�D�����M�E�ՁE���E���q�E���F�E���ؕr�E�r�q�A�V�ڒ��q)�ݒn�y��ł͓�����E����炯�E�����M�E�فE�X�E�����A�Δ��A�������i�ł͎�〜�j�ЁA�n�����Ȃǂ��o�y���Ă���B��O���I�O����̏튊�P�������邪�A������͈�O���I�㔼〜��l���I�O���ƈ�ܐ��I�O���̂��̂���̂Ƃ��A�������ɑޓ]�����Ɛ��肳���B���l�ȓ�����g���́A��h���厜�����ł�����������B
�E���̍s�����L���w�����哿���x�ɂ́u���@���E���\��v�u�E���֒f�Z�\�O�v�Ƃ���A�w�{�����m�`�x�ɂ��u�x�ғl�\�l�A���@���E����ӏ��A�����C�c���O���A����������\��A�呠�o�[���\�l���A�ˋ��ꔪ�㏊�d�v�ƋL���B�}�g�R��[�Ɏc���ꂽ�u��E�O���v�E�A�u�s�E���E�v�ɂ͔E���~�Z���Əd�Ȃ���̂������A���̂��[�v����_����E������Â������E�̕W�ƍl�����Ă���B�����ܔN(���O)�̎��������ɂ܂����˔ʎ�����E����A���ŋ㌎�����ɎO���R�Ɋy���ŎE�����֒f�A����ɋ㌎�����ɐV�����鎛(�߉މ@�������͒n���@)�Ō��E�������Ƃ��m����B
�����ł����u���E�v�Ƃ́A�_�Е��t�ȂǂE�Ɖ悵����Ƃ��邱�Ƃ��������A���ɗ��@��T�@�Ȃlj������d��@�h�̎��@�ň��̋������肵�A���̋����őm�����Z�ݐ����ɋ߂邱�Ƃ������B
���������ɂ�����m���̌��E�ɂ͑傫����E�A����A���E�̎O��ނ�����A�ł���{�I�ȁu��E�v�Ƃ́A�͈͂��傫���ʏ팋�E���鉾���̋��������A�O���͂��̊O����\�킵�Ă���B����͑m���������ꏏ�ɏZ���ꏏ�ɕz�F�̋V�����Ȃ����߂Ɍ������̈�������B
�z�F�Ƃ́A�������Ƃɑm�����W���ĉ��o������A�����Ԃ̎��Ȃ̍s�ׂ������������邱�Ƃ𐾂������V���ŁA�u��E�v���̑m���S�����z�F�ւ̎Q�����`���t�����Ă���B����đ�E���E�͗��@�����_�@�ɍs�Ȃ���@(�����@�����)�B
�Ȃ��C���h�ł͕z�F���\�ܓ��@(����)�ƎO�\���@(����)�@�ɁA���{�ł͏\�l�E�\�ܓ��Ɠ�\��E�O�\���ɍs�Ȃ����B�ʎ�E���鎛�́u��E�O���v���Ƃ��ɓ�\����ƍ��ނ̂͂��̂��߂炵��(���@�����)�B�R�鑬���A�@�̌��E�V��̎�ẤA������̎������厛���V�I�o�̈Ӌ`�������Ă����Ƃ̎w�E������A�E���������Ԃ��Ȃ��헤�ŕp�Ɍ��E�V����s�Ȃ������Ƃ́A�����ɂ����闥�@���d�̎w���҂Ƃ��Ă̒n�ʂ������Ă���B�܂��z�F�̎��{�͓��S����m�������̎��@�ւ̎Q�W�𑣂��A�����͂����ڋ��w�̏�ƂȂ�A���w�������J�͉��̘A�т����肾�����B���厛���̊֓��z���̏����Ɏ��{���ꂽ���@���E�́A�L�͂Ȑl���`���ɑ傫�Ȗ������ʂ������ƍl������B
�ʎ�͈�i�┭�@�̏�����������e���������̂͊��q�O���ȍ~�Ɛ��肳��A����͌����ܔN(���O)������\����̑�E���E�ȍ~�̂��Ƃł��낤�B
���O�ɂ���Ï��͍������Z�Z�p�A�a��Z�Z�p�ŁA�Â��w�W�Ï\��x�ɑ�e�����^���ꂽ�B�����ɂ��A�������N (���)�����̐���ŁA��H�͓����������̂��ƂŊ��q�啧�����ɎQ�����������t�O���v�F�ł���B�O�����͕������ƂƂ��Ɋ��q������\���钒���t�ŁA�k�𐭌����Ō��H�I�Ȉʒu�ɍ݂����B�O���v�F�ƕ��L���ꂽ��H���d���͒n�������t�Ɛ��肳�ꋤ������������������B�L�͒����t�Ƃ����ǂ��A�������Y���蒅���Ă��Ȃ��n��œƎ��ɞ����̂悤�ȑ�^�����̏o�������s�Ȃ��̂́A�v����ޗ��̎�z�Ȃǂ�����ł���A�n���̒����t�W�c�̋��͂̂��Ƃɏo�����ɂ��������Ƃ݂���(�\��@�����)�B���q�啧�̒����H���ʎ�����̒����ɎQ�悵�Ă���̂́A�E�������q�啧���̕ʓ��ɏA�C�������ƂƊW����悤�ł���B
�ʎ�̓����ɒ���ЂƂ��Ď����Ђ��J���Ă���A�E���痥�m�̎������q���������킹��(�e�r�@��㔪�Z)�B
|
���ʎ�d���ƍ���q�̉͊�
�ʎ�ł́u�ʎ�d������v�̗��������^��������������A�O���R�n�̌��������o�y���Ă���A���q������ɂ͊����̌d�����������Ɛ��肳���B�w�����哿���x�O�����N(���)���ɂ͔E�����^�ǒŔ��R�@�ɕc�����L��������A�O�������{(���?)�Ƃ��킹�A���여��̗��@�ł͊��q�������ɓ��̌��݂��������ł���A�����͈�A�̓����ƍl������B�����������l�N(�����)�N�ɔE���E�t�C�炪���c���{��������̖������ł����O�d���ɂƂǂ܂�A���c�̂��ߍL��Ȋ��i���s���Ă���A�����̒h�z(�����E�{��)�����ƂȂ�B���˂̒n�́A�����ɂ͐M�����̑���Ɋ܂܂�A���q�����ɂ́A�b���ɉ���������ꂽ�k�𐭑��̈ꑰ�̏��̂ł���A�d���̑��c�́A�k�����̋��͂Ȍ㉇�̎Y���Ƃ��l������B
�܂����C�ɒ����͐�ƌd���̐����闥�@�Ƃ����W�́A�L�������R�s���c�여��̋����厛�����A���Ï핟��(�����@)���霂Ƃ�����B�핟���d���͒�a�l�N(��O�l��)�ɖ��O�Ɩ�Ε�F�Ƃ̌������肢�A���嗊�G���ꕶ���i�̏��������Č����������̂ŁA��O���ł��鑐�ː猬���Ƃ̂�����肪�z�肳��Ă���B�܂����n���㍑���a���̒n���͖k�����ƊW�̐[�����䎁�ł�����(�u�c�������)�B
�ł͓�������ׂ�Ɍd�����W����ʎ�̋߂��ɂ́A���ː猬���̂悤�Ȓ���͂Ȃ������̂��낤���B
�ʎ��1km�㓌�k�A����x���̔��O��̖T��ɁA����q������n������B��n�̒����̍��܂�ɑ�����Z��Cm�𑪂鍲��q�ܗ֓������т��Ă���A��k�����玺�����㍠�̂��̂Ɛ��肳���B����Ȍܗ֓�����芪���ď��^�ܗ֓��E��肪�т�����ƒ˂��A�u�U���}�C�v�ƌĂ�Ă���B���͂̐Γ��ɂ͎������ɑk����̂��܂܂�邪�A�����͈�Z���I�ȍ~�̂��̂ŁA�܂��Ɋ��n���̑y��̕��i���v�킹��B
�ʎ�����ɂ��悭�����`�œ���قǏ������ܗ֓����ڒz����Ă���A���҂̊W�����肳���B�����͂��܂ł������c�̒��ƂȂ��Ă��邪�A�����Ɏ����Ђ̗������邱�Ƃ��܂ߎ��˂��璎�|�ւ̓n���̓r��ɂ�����A�]�ˊ��̍���q�ׂ݂͊͗̔ѓc�݂͊ƕ���Ő��^�̗v�Ղł�����B�ܗ֓��͍���̒����݂͊ɉc�܂ꂽ�L�O��I�ȓ��Ǝv����B�אڂ��钥���n��ɂ́A�Õ�〜��������̓y��ɂ܂����āA���������킪�݂��A��O���I�ȍ~�̐��ˁE�튊����̔j�ЂȂǂ��U�z���Ă���B�k���ɂ��˂⒆���Γ��E�ߐ��Ε����c��A�ߐ��Ɋ����̓����������ƍl������B�t�߂ɎU�z���钆�ߐ�������ɂ͑�����̂ق��A���́u��v�̏�����ɂ��������̂��܂܂�Ă���悤���B
�X�ɓ����̔���(������)����ɓ��ɂ͓�k�����̏�Z����ɔ@��������䐳铂�����B����q��n�E���т̓��͉i�\���N(��ܘZ��)�J��ɂȂ鍲��q���������Ǘ����Ă������A����ȑO�͔ʎ�ɂ���ĊǗ����ꂽ�A�u�����v�̋�Ԃ������̂ł͂Ȃ����낤���B
|
���ʎ�J��`���̐���
�����R�ʎ�͓V��N(��l��)�ɕ�����̎��j�����̖������P���J����Ɠ`����B
�Ƃ���Ŕʎ�Ɠ��l�ȊJ��`���́A�ʎ�̖k�����E��km�ɏ��݂��鏼�˓������ɂ��`���B�������͌����l�N(���ܓ�)�@�O���E���̊J�n�Ɠ`���`�E����̈���ɔ@�������c��(�w����}�x)�A�܂�����ł͊��q�Ɋy���̏�C�������N�Ԓ��ɊJ����Ƃ��`����B���`�ɂ͋^�₪���邪�A���厛���̗����ŋɊy�������ł������\�����w�E����Ă���B�������͓�k�������̐�ŏĂ��Č��ݒn�Ɉڂ����Ɠ`���邪�A�����ɂ͈ȑO���畽����̖���鐷(��)�P�@����̔O���������n������{���Ƃ��铌��������(�u�������q�䐳�쉄���n���������N�v)�A�����̌Õ���@����̕�Ɠ`���Ă����B�Õ��͍핽������ł������A���݂�����ȐΎ��ނƓ�˂̎������c����Ă���B�����ɂ͈�l���I〜��Z���I���̌ܗ֓������W���Ă���A�@�����Ƃ����Õ����j�Ɍ`�����ꂽ�O���ƍl������B
�ʎ���A�����t�߂ɂ͂��ė����R�Ƃ����O����~�����������B�������ݒn�ɐ�n�����_�@�́A����Ɩ��W�ł͂Ȃ��悤�ŁA�Õ��������P�̕���ɉ������A�@���I�Ȋj�Ƃ��Ă����\��������B
�Ȃ������P�E��鐷(��)�P�@����`���́A���Ƃ��Ə\�I�ɐ��������@�w���̕���W�x�ɏ���̎q���Ƃ��ēo�ꂷ��@����̓`�������`�Ƃ���B
���哢����ɉ��B�ɉ߂ꂽ��O���́A�b�����̖T�Ɉ������ĂďZ��ł������A�a�����Ċt���̒��ɍs���B�������n����F�ٌ̕�őh��A�o�Ƃ��Ĕ@���ƍ������B�Ȍ��S�ɒn����O���A�l�X����u�n����N�v�Ƒ���āA�Δ��\���߂��Ē[�����ł����Ƃ����B
�����n�}�ɂ͔@������L�����̂����邪�A����Ƃ̊W�͖��E�ÂȂLj�肹���A���݂͋^�킵���A�n���M�ȂǂƂ���߂đn�����ꂽ�l���ƍl������B
���������`���͖��O�̑f�p�ȗ��j�ςɑi����_�ŁA�����̐擪�ɗ������i�����s��������t�����ɂ���Ă������Ɍ���鉿�l��L���Ă����B�l�Êw�I�ȏ�������݂āA�����̎��@�̑n�����Ñ�ɑk��\���͖R�����A�����ɂ����̎��@�̑��c�Ɋ֗^�������@�̊��i���������A�n���̌Ó`�����I�݂ɍĕҐ��������̂ƌ���ׂ��ł��낤�B |
���ʎ�̑m���Ƒ��c����
�w���厛�����^�������ߋ����x�́A���厛�L���̑m�����v���Č�A�����^����Ɍ��������ۂɋL������A���m�̖v�N�̖ڈ���������D�����ł���B���厛�l�㒷�V�ǐ�(��O�O��)�ƌܑ㒷�V�o��(��O�l�Z)�̊ԂɁu�����[�@�헤�ʎ�v�u�@��[�@�����v�u�����[�����v�Ə헤�ʎ�̑m�O���������ċL�ڂ���A��㒷�V�ł������ƍl������B
�ʎ�̌������N(���)�������Ɍ�����u�助�i���C�v�͐��厛�b����q�̌𖼂ɂ݂���헤���l�̛����[���C�ŁA�ʎ�̎�����̊J�R�Ɛ��肳��Ă���B
���C�͓����V�������鎛�ɂ������Z�[�ʋŁ@(����Z〜��O���)�̎t�ŁA�E���ƂƂ��ɏ헤�ɉ��������Ɛ��肳���B���Z�́w�G�k�W�x�Ɂu��\��A�����V��l��~�ω{�V�B�v�u��B������[�m��l�m�\�V�V��m�w���m�~�σm�u�m���A���C�K�~�ύu�W�����v�Ƃ���A���V�䌓�w�̑m�ł��邱�Ƃ��킩��B���Z���~�ς̍u�`�����͔̂E�����ʎ�����E���ĊԂ��Ȃ����܌ܔN���̂��ƂŁA���E��Ԃ��Ȃ��~�ς̍u�`���n�߂��炵���B�ʎ�͑�E���E�Ȍ�A�z�F(�ӂ��Ƃ́A�����ɂ����āA�m��(�m�c)�ɏ�������o�ƏC�s��(��u�E��u��)�B���A��2��A�V���Ɩ����̓�(15���E30��)�ɏW�܂�A���(�g����؍�)�̉��{��ǂݏグ�A��G���Ă��Ȃ����m�F�A���ȁE��������V��)�ɍۂ��Ċe�n�̑m�O���W�������̂𗘗p���A���܂��܂ȍs�����s�Ȃ�ꂽ�͂��ŁA���̈�Ƃ��Č��C���~�ς��u�������̂ł��낤�B
�܂����ɌÕ���3581�ɁA�u�u�X�ˁv(���ʎ)�̎~�ςƌ�����̂��A�����炭���C�ɂ���ču����ꂽ���̂ŁA�u�v���������Ă��Ȃ������p�����łĂ��āA�O������A�u�X�˂ɂł����邱�ƂƂȂ�܂����B�~�ς�����Ƃ��ŁA����[�͘A��Ă������ƁA�ߍ��A����������Ă����܂������A��w��A�䐸�i�̂��ƁA�{���ɂ�낱�������Ƃł��B�Ƃ���ŁA�w�~�ρx�̌܊���������ɂ���܂��B���ł̂���ɂł��v�Ƃ���B
���̏��Ȃ́A�̖������V�̖����[�R�C(����〜�O�Z�l)���@�w���N�M�_�ȕ��x�@�̏��ʂɗp�������w���ł���B���(�@��)�[���T�͈��N�܂łɖv���Ă���A�R�C���E���̐����ŏ̖����ɓ��������i�l�N(���Z��)����Ԃ��Ȃ����̎莆�Ɛ��肳��A���˔ʎ�ɗL���̑m����o���ꂽ���̂ł���B���̑m�́A�R�C���ʎ�ɏo������܂ɂ́A�⍲���̗��T���ꏏ�ɂ�Ă���悤���߂Ă���B�����̗����ł͓V��w���C�߂�l�����������悤���@(���Ɉ���l)�B�R�C�E���T�͉����t���E�O���R�E�ʎ�E�����_�{��������p�ɂɉ������Ă���A�̖����ɋ߂��Z�Y����D�ɏ��A��芷���Ȃ��ŊȒP�ɓy�Y�܂ł��ꂽ�炵���B
��O���I�㔼�̔ʎ�͊֓��e�n���痥�m���}���~�ς��s�Ȃ������̎��e�𐮂��Ă������Ƃ͋^���Ȃ��B�d���̑��c���������N(���)�̞����̎{���A�O���ܔN�@(���)�Ɠ`����߉ޑ��̑����Ƌ߂������Ǝv����B�����������c���Ƃ𐄐i�������C���܂��A�w�m�ɂ��đ助�i�Ƃ�����ʐ������Ȃ��闥�m�ł������B
�����̐����ɂ͌��C�̕擃�Ɛ��肳���ܗ֓����������Ă���A�������O�p�A���ւ͂��Ε��ʼnP�`�ɋ߂��^�}�l�M�`�ʼnΗւ͌��z���₩�Ō����͔����A��������ɂ��B����ɂ͔��ԍ��E�e�ʓ̞y��(���܂���)������A�i����(�����͂���)�̈�(����)���ȗ�����މ������^���������Ă���B
�O���R�ܗ֓��Ɠ��l�A��������厛�b����q�̕�ɍ̗p���ꂽ��^�ܗ֓��̂ЂƂŁA�{�̍��͌ژZ���ŏ̖����J�R�̐R�C�̕擃�Ƃقړ��K�͂ł���B
���C�Ɏt���������Z�͉Ø\��N(����Z)���܂�ŁA�t�̌��C�͂�����N��ƍl������B���C���@�w�ߋ����x�Ɍ���(��������E�����ɓ��鉏�����Ԃ��ƁB�����ɋA��(����)���邱��)������O�O�Z〜�l�Z�N���ɖv�����Ƃ���ƁA�S�Η]�̔N��ɒB���s���R�ł���B����Č����͉�����{�ɔ������̂ŁA�ܗ֓��͉�����{���Ɛ��肳���B
���V�Ɛ��肳���@��[�q�˂͉b���̒�q�ʼn͓��o�g�ł���B���ɌÕ������Z�l�̎������ڏ���́A�O�щ������̚����[�̎���(��܍�)���O���̏��ȂŁA���T�̑ݗ^�Ɋւ���L�q�̒��Ŕ@��[�̖���������B�u�������n���v�̑�\�O�\�ɂ��Ί��q�o�����J�R�̓��Ɩ[�S�d(���q�C�A��O�Z�Z�v)−�{���[�q��−�@��[�q�˂Ƃ����u�q�v��ʎ��Ƃ��錌�����L����A�k�����{�����ɘA�Ȃ�m�ł������ƍl������B
�O�����V�Ɛ��肳���暢�[���C�͉b���̒�q�ő�a�o�g�ƍl������B���ɌÕ����Z�c�͉��c��N(��O�Z��)�ȑO�ɏo���ꂽ�a���������ׂ̏���ŁA��~��[�𐄑E������e������B���C�͉i�m�ܔN(���㎵)�ɕ������{���ŋ����E�E�ّ��E�̔�@��`������Ă���B�܂��×�l�N(��O���)�ɒ�q�̌��C�ɔ�@�̓`�����s���Ă���B���̕����̐^�ɂ́u�N�i���N(��O�l��)�K��������ȍ����{�v�ƌ��C�����̏������݂�����A���̂���v�����炵���B
�܂��@�w���ɌÕ����x�@�ɂ͐����O(��O�Z��)����l�Ɏ��˔ʎ�ʼn_���@(�܈��)�ɔ�@��`���������Ƃ�������ʂ̕���������B���̕����������@������݂ĉ_���͏暢�[���C�̌Z��q�ɂ�����ƍl������B
|
�����@�ƌ��E��
�����̌��E�̕��z�͑S���I�ɂ������A�ޗǖ~�n�쐼���ƒ}�g�R�[�ɏW������B���݂ł����̖�O�Ɂu�s���͎���R��v�ƍ��肪�݂��邪�A��������E�̈��ł���B�u��E�O���v�Ƃ͔�u�̍s���͈�(�L���E)������(���E)����W�ŁA��E���E��㹖��t(���܂�)�E�����t�E���@�t�̎O�t������������L���L���Ȃ���s����(��X�@��㎵��)���Ƃ���A�헤�������̔E����s�͏��Ȃ��Ƃ����`�ɒʂ����O�l�ȏ�̐��厛�m�ō\������Ă����ƍl�����A�@���[�����A���M�[��w�ƂƂ��Ɏ����[���C�����ƂȂ邾�낤�B
�ʎ�����ɒ}�g�R�_��Њ�̓��̌��E������A�\�ʂɂ͂Ƃ��Ɂu��E�O���v�̍���������B�����y�Y�s�������قɈڂ��ꂽ���͍�����Z���p�A�����̕��Z�Z�p�A������O�p�ŁA���̕������Ɏw�肳��Ă���A���ʂɁu�����ܔN(���O)���N������\����v�̓��t������B�ʎ���E�Γ��́A���łɏ�����M�ҁw�W�Ï\��x�ɑ�e���̘^����Ă��邪�A����đ�a�ʎ�̂��̂Ƃ���Ă����B���̗Ⴉ�琄���ē����͎l〜�܊�ō\������Ă��������̓��ƍl�����A���̌��E�̔��������҂����B
�V�����鎛�͓���̓`��������A�Ő�����̍Ő�̊J���`����B�n�������͌o�ˌQ�̂��铰���ɖ�t�����������Ɠ`���A�{�����ɔ镧�Ƃ����J����\�ꐢ�I�����̖�t�O���͂��̋��{���炵��(��錧�@��㔪��)�B�E���헤�����̍��A���̎��ŏC�ƒ��ł��������Z�ʋł́w���ΏW�x�w�G�k�W�x�ɂ́A���鎛�Ɋւ���L��������������B���E�͖{��������萼���̎R�����{���̏��ݒn�ł���B�u��E�O���v�͎������c���߉މ@���ӂɎl�������ق��A���鎛�����Ɉڒz���ꂽ���Ɂu�����ܔN�ˉN�㌎��\����v��������A���̗̂ގ�����E���ɂ�錋�E�ɔ������̂Ɛ��肳���B�����̌��E�́A�ł���^�ŋI�N���̂�����̂��̈�̓�����ɗ��Ă��A���͂��ꂼ��l�����悵�Ă����Ɛ��肳��Ă���(����@��㎵�Z)�B�t�߂̎Ζʂɂ͒����ܗ֓��̌Q�݂��݂��A�n���@�ƒʏ̂���_��������鎛�̕掛�Ƃ��Ă̖������l������B
�|�ю��́A�ޗǖ~�n�̐����A����R�[�̏������u�̏�ɂ��鎛�@�ŁA�s���F�̕�_�Ƃ��Ė������B�V����N�@(��O�l)�@�Z����\�l���ɒ|�ю��m�b���ɂ���čs��̈⍜�����@���ꂽ���A�Ⴋ���̔E�������̏�ɗ���������Ɛ��肳���B�s��ɗ��̔����͓�s�����E�ɑ傫�ȏՌ���^���A�s��啧���i�ɋ��͂����W���瓌�厛�ł͉~�Ƃ�ɂ���ēx�X�s���F�ɗ����{���s��ꂽ�B�~�Ƃ͈ꎞ�|�ю��ɏZ�݁A��ł��ċ��������ς����A�ÑR���ĎO�|�ю��ɐg���A�w�|�ю����^�x�ꊪ���q�����B
����s���y�����قɂ́u��E�O���v�u��E�쐼�p�W�v�u��E����p�W�v�@�̎O��W������A�|�ю����铌�k���ɂ́@�u��E���k�p�W�v����������B�{������̎l���ƎR��̌v�܃J���Ɍ��E�W�����������Ɛ��肳��A�����̔����ʒu����݂āA���E�͍s���𒆐S�Ƃ��Č����ɐݒ肳��Ă������Ƃ��킩��B�R��t�߂ł݂��������̂́A���ʂɁu��E�O���v�u���i����l���v�w�ʂɁu����V����\���@���މ������@���⍑�V�͈͉v���p��V���@�����V���Ď��ꓙ���������x�v�Ƃ���A�u���x��v�Ƃ͍s����̕������A��������j���ɍs���ւ̌h������߂Ă���B
���E�����������̖��͉Ì���N(�ꌾ�l)���̖��ʎ��ܗ֓��n�ւɂ݂��A�L���`�Z���̍s�������ނ̑����Ɛ��肳��Ă��邪�A�Ì��O�N(��O�Z��)�́w�|�ю����^�x�@�ɂ����̖����L����Ă���B���́w�|�ю����^�x�ɂ́u�����E�A��l���W�ȁA�����n�s���ɉF�v�Ƃ��邱�Ƃ���A�E���v��̉Ì��O�N�@(�O��)���̌��E�ƍl������B���̎����E���s�Ȃ����͓̂����o�g�Ŏ������̒����J�R�ł��闥�m�̋�q�[�E��ł���(�ɓ�����l�A����s����ψ������n)
�������ł͉ԛ���ō����R�`�E��i�荞�݂Łu��E�O���v�ƃo����q�����ޑ�E�O����ƁA�荞�݂̂Ȃ��u��E���k�c�v�Ȃnjv�l��̑��݂��������A�{���R��Ǝl���̌܊�Ɛ��肳���@(�� �@�����)�B
���̑n���͕�T���N(������)�ɑk��A�Ӑ^�ɉ����������������m���i�̊J�R�ŁA�C�~�͓���̎t�Ƃ���`��������B���i��N(�O����)�@�ȍ~���ɋ�q�[�E�����J�R�ƂȂ�A������N(��O�Z�O)�E���ی��N(�O�O)�ɓ`�@���s���ȂǕ������Ă���A�|�ю����E�Ƃ̗ގ�������A���������E�͔E��̈�i�Ƃ݂���(�ɓ��@����l)�B�������ܗ֓����A���厛�l���̌`�ԂƓ��e�������E��̕擃�ƌ���̂��Ó��ł��낤�B
���������ӂ̏\�֎��E���R�R���E���q�ω����ɂ����E�̑��݂��m����B
�ȏ�ޗnj����̌��E�́A��������}�g�R�[�̂��̂��V�������A�|�ю��ł͍s���̑����A�������ł���������Ƃ������i�������������B�Ȃ����{��͓��S���q���b�����̐������q��ł́A�Õ��̕��u�̐����߂���A�O�����ɖ��ڂ��ĕ����q��(���i〜�O����)�̔��ɂƂ�܂��A�X�ɂ��̉��i�ɂ��ߐ��̔�߂����i�̊_���Ȃ��Ă���B����͐������q��@�ӗ֊ω��̉��g�Ƃ���M�Ɋ�Â��c�܂ꂽ���E�̈��Ƃ���(�c���@��㎵�Z)�A�Õ����̂��̂����E���Ă���A�|�ю��s�����͂ތ��E�Ɠ��l�ȈӖ��������̂ł��낤�B�̖������E�}�̕��͂ł́A���E���ɂ͕擃�E������݂��Ȃ����Ƃ��w�E����Ă�����(�O���@�����)�A�Ñ�̐��l��c�t�̕�͂��̌���ł͂Ȃ��A�ނ��뒆�j�Ɉʒu���Ă���@(�ɓ��@����l�A����s����ψ�������)�B
�����ɐ��������闥�@���@�̒��ł��A�����̌��E��������̂͒}�g�R�[�Ɍ�����B���n���̒������E���A�Ñ㕧���̑c�t�E���l�Ɩ��ڂɊւ���Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�}�g�R�[�ɂ��Ă��A�����m����䂩��̒n�ł��邱�ƂƖ����ł͂���܂��B�@ |
|
���y�Y��@�@�@�y�Y�s
|
�헤���V���S(���F��錧�y�Y�s)�ɂ��������{�̏�B��������ɒz����A�]�ˎ���ɒi�K�I�ɑ����z����Č`�𐮂����B���̍L����d�̖x�Ŏ�镽��ł���B�V��͍���Ȃ������B���ۘE�傪�������A�������̘E����������Ă���B�y�Y�͓x�X���Q�ɑ����Ă��邪�A���̍ۂɂ����v���邱�Ƃ��Ȃ��A���ɕ����ԋT�̍b���̂悤�Ɍ��������Ƃ���T��(�����傤)�ٖ̈������B
��������A�V�c�N��(938�N����947�N)�ɕ����傪�Ԃ�z�����Ƃ����`�������邪�A������m���Ȃ͎̂�������A�i���N��(1429�N����1441�N)�ɏ헤���A���c�m�Ƃ̌���A�����̏��c���ɑ�������(����)�O�Y���z�邵���̂��ŏ��ł���B�퍑����ɓ���i��13�N(1516�N)�A���ܘY���q�傪���̎��A���c���̕����E���J����ɂ���ď�͒D���A�ꎞ�A�M���͒傪���߁A��ɐ��J����̋���ƂȂ�B�������A���c���͏㐙�E���|���ɏ��X�Ɉ�������A���c�����͏��c���ēy�Y��ɓ������B���̌�A�x�X���c���D�邪�i�\12�N(1569�N)�̎蔇��̐킢�Ő^�njR�ɑ�s���Đ��͂������A���T���N(1570�N)�ȍ~�͍��|���̍U���ڎ�悤�ɂȂ�A���J����E�͐��e�q����N���c����⍲�������A�V��13�N(1583�N)�A���ɏ��c�����͍��|���̌R��ɍ~��B�V��18�N(1590�N)�A�L�b�G�g�̏��c�������̍ۂɐ��J�͐��͌�k�����ƌ����ߍ��|���⓿��ƍN�̌R���ɍU�߂��A��N���c���ƂƂ��ɖŖS�����B
�֓��ɓ���������ƍN�́A�y�Y�����j�Ō��鎁�ɗ{�q���肵������G�N�ɗ^���A�y�Y���̓��̎x��Ƃ���B�G�N���z�O���k�m���Ɉڂ�ƁA���䏼���Ƃ̏����M�ꂪ3��5��œ��������B���̌㏼���M�g�̑��5��̉�������B���a3�N(1617�N)�A�M�g����썑����ɓ]���ƂȂ��Đ������i��2���œ��������B�Ȍ�A���͐����ƁE���؉ƂƑ���A����9�N(1669�N)�A�y��������4��5��œ��������B�y���Ƃ́A�V�a2�N(1682�N)�A�q�̐����̂Ƃ��V�a2�N(1682�N)�x�͍��c���Ɉڂ������A�����ď��ƂȂ�����͓������Ƃ̏����M����5�N��̒勝4�N(1687�N)�ɑ����ɓ]����ƁA�y���������Ă�6��5��œ��������B���̌�A3�x�̉�������9��5��ƂȂ�A�헤���ł͐��˔˂Ɏ����ő傫�ȗ̒n���x�z���A�Ȍ�y���Ƃ�11��A��200�N�Ԑ��P���Ė����ېV�Ɏ������B
�����j
����������ȑO
��������A�V�c�N��(938�N����947�N)�ɕ����傪�Ԃ�z�����Ƃ����`�������邪�A������m���ł͂Ȃ��B
���������ォ����y���R����
������m���Ȃ͎̂�������A�i���N��(1429�N����1441�N)�ɏ헤���A���c�m�Ƃ̌���A�����̏��c���ɑ�������O�Y���z�����̂����߂Ăł���B �i��13�N(1516�N)�ɏ��c���̕����E���J���傪���ܘY�E�q���łڂ��A���̉Ɛb(���J�^�܂��͐M���͒�)����ɓ������B��A���J��������A����A�͐��̎O��ɂ킽���ēy�Y���������B�퍑����ɍ��|�������͂��L����ƁA���|�ɂ���Ė{���̏��c���ǂ�ꂽ���c�玡�����邵���B
�퍑���オ�I���ƁA�y�Y�͌����̌���G�N�̂��̂ɂȂ�A���c���͂��̉Ɛb�ɂȂ����B�����đ���J���L�����߂�B�c��6�N(1601�N)�ɏG�N���z�O���ɓ]���ɂȂ�ƁA���䏼�����̏����M�ꂪ�y�Y��ɓ������B�M��Ǝq�̐M�g���A���݂̏�̂��悻�̌`��������ƍl�����Ă���B
���a61�N(1986�N)�̔��@�����ŁA�퍑����ɖ{�ۂő傫�ȉЂ����������Ƃ����������B�Ή����镶������������Ă��Ȃ��̂Ŏ����⌴����m�邱�Ƃ͍��̂Ƃ���ł��Ȃ��B
���]�ˎ���
���a3�N(1617�N)�ɏ����M�g����썑�̍���ɓ]����ƁA�y�Y�ɂ͐������i���������B���i�̎q���Ƃ͌��a6�N(1620�N)����7�N�����Đ��E�Ɠ��E����点�A���a8�N(1622�N)�ɂ͖{�ۂ̐����E��ɉ��߂��B����ɂ��{�ۂ͐��x�ƍ���̓y�ہA�O�̘E�Ŏ����悤�ɂȂ����B
�c��2�N(1649�N)�ɐ������Ƃ͏x�͍��̓c���Ɉڂ����B������ċ����e�j�����ƂȂ�A����2�N(1656�N)�ɘE������݂���`�̑��ۘE��ɉ��z�����B�������N(1658�N)�ɁA�p�ɂƉ��ɑq�����������B�������N�A���ߎ��A�O�L����������ɂ����B���؎폹�̑�ɁA�y�ۏ�̕������ׂĊ����ɉ��߂��B
����9�N(1669�N)�ɓy���������������B�y���Ƃ͌������c�Ƃ̉Ɛb�ŁA���c�Ƃ̖ŖS��ƍN�Ɏd���A�����̑�ɑ喼�ɂȂ����B��q�̏����M���̎���������āA����Ȍ�]�ˎ����ʂ��ēy�Y��̎�͓y���Ƃł������B����6�N(1678�N)�ɓ�̊ۂɕđq�����Ă�ꂽ�B
�����M������̒勝2�N(1684�N)�ɂ͑���C�����{����A�����Ɛb�E�R�{����(4��A����)����s�߂��B���������͐퍑���̍b�㕐�c�Ƃ̉Ɛb�R�{����(����)�̎q���ŁA�����E������͕��c���̒z��p�ɂ�蕁�����Ă���B
�V�a2�N(1682�N)����勝4�N(1687�N)�܂ł́A�����M�������ł������B�M���͒勝2�N(1685�N)�ɕ��Ɍ��ƕs�j�������A������Ă��B�܂��A�{�ۂ̉�������z���A���N�ɂ����Đ��ˌ��̌Ռ������ǂ��ē�d�۔n�o�Ռ��Ƃ����B
���ߌ���
�p�˒u����2�N��A1873�N(����6�N)1���ɁA���������ߑ�84���œy�Y��͔p�~���ꂽ�B�{�ی�a�͐V�����̌����A��ɐV���S�̌S�����Ƃ��Ďg��ꂽ�B�{�ۂ̑��̌��������قƂ�ǎc���ꂽ���A�y�ۏ�̕��͎��ꂽ�B��̊ۈȉ��̌����͊O�ی�a����������A�x�����߂�ꂽ�B
1884�N(����17�N)�ɉЂŖ{�ی�a������ꂽ�B���̂Ƃ����������{�ۓ��E�Ə��O���P�����ꂽ�B11���ɌS�����̌�������a�ՂɌ��Ă�ꂽ�B1899�N(����32�N)�ɖ{�ۂƓ�̊ۓ쑤���T������ɂȂ����B
1949�N(���a24�N)�A�L�e�B�䕗�̔�Q�������E�́A1950�N(���a25�N)�A��������Ƃ����������ʼn�̂��ꂽ�B��̎��̕����\��͒����������Ȃ��������A1992�N(����4�N)�ɕۊǂ���Ă������ނ�p���ĕ������ꂽ�B
1998�N(����10�N)�ɂ͓��E���y�Y�s�������ق̕t���W���قƂ��ĕ������ꂽ�B
2011�N(����23�N)3��11���ɔ����������k�n�������m���n�k(�����{��k��)�̉e�����A���ۘE��A���E�A���E�Ƃ��ׂĂ̌��������j�������B�Ƃ��ɓ��E�A���E�͔��ǂ̌����ȂǑ傫���j�����A���E�W���ق��ق�]�V�Ȃ����ꂽ�B
2012�N(����24�N)6��22���܂łɁA�E��A���E�A���E�A�y���Ȃǂ̏C���H�����I���B��30�����珇���A��ʌ��J���ĊJ���ꂽ�B
2017�N(����29�N)4��6���A�����{100����(113��)�ɑI�肳�ꂽ�B �@ |
|
�����|�_�Ё@�@�@�y�Y�s���|��
|
�n���N��s�ځB�����`���ɂ��A�V�c�̗��̐܁A�������s�����Ă��̎Ђ̖��ɂ�����Ċ���Ƃꂽ�Ƃ����B���L�ɕ��6�N�Č��Ƃ���B����15�N4�����Ђɗ�i�B�吳���N12���A������א_�ЁA�������Ђ��������āA�L�{�����Ж��ɉ��̂����B�吳2�N3��27��(��164��)���i�w��B���a27�N8��15���@���@�l�ݗ��B���Y�̐_�Ƃ��Đ��h����A���݂��[���ċF�肷��B
�����͕��nj��A���ɐ�(�������̓�j)�ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B
���Ր_�@�_���V�c�̕��ʼnL�������s����(������ӂ��������݂̂���)
�@ |
|
�������R�ʎ�@�@�@�y�Y�s���˒�
|
�^���@�L�R�h
���`�ɂ��A��������̓V��N(974)������̎��������P(�@����)�ɂ��Ƃ��Ď��˂̑�n�ɑn������A���������Ɍ��ݒn�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ����B���q����ɂ́A�k�������̕ی���A���ɔE����F���O���R�ɗ��Z�������߁A���@���@�Ƃ��ĉh�����Ƃ����B�퍑����ɂȂ�Ɛ�ɂ���ē��������������A�]�ˎ���ɁA�n���o�g�̎O�����Z���]�ˌ썑���̊ω������ڒz���Ċ�i���Ă���B
�����́A�������N(1275)�m���C���助�i�ƂȂ�A���q�啧�̒����ɂ���������O���v�F�A���d���������������Ƃ��m���߂�� �ݖ��Ï��Ƃ��đS���I�ɒm���Ă��܂��B�����ɂ͂��̑��A����5�N(1253)�̌������������܂ꂽ�u���E�v��u�Α��ܗ֓��v�u�Z�n���Α����U�v�ȂǑ����̕�����������܂��B
���E�Ƃ́A���@���̐���ȋ���W�����邽�߂̕W�ŁA���ɉ����̌��������@�ł́A����̍s�@�ɓ������ĕK�� �������肷�邽�߂Ɍ����������̂ł��B �@ |
|
�������_�Ё@�@�@�y�Y�s������
|
�]�ˎ���͈��������ƌĂ�Ă����B���Њi�͑��ЁB
�����ˊX��(���݂̍���354������)�����ɂ���_�ЂŁA����E�݂̑�n�Ζʂɒ�������B���Ă͉����Y����]�ł��镗�����Z�ȏꏊ�ŁA�����_�Ђ̌�_��������̋@�\���ʂ����Ă����Ƃ����B
�Q���͋����ˊX�������铌�����ɖʂ��A�肷��t���̊K�i���t���Ă��邪�A����̏핟�����璼�ړ��邱�Ƃ��ł���B�Гa�̂�������܂Œ��ԏ���n�������Ă���B�����_�Ђ̎Q�q�җp���ԏ�͋����ˊX���̓��������ɂ���A���ׂ̗ɂ͋���18�N(1733�N)�����́u�����Â̓��W�v(�y�Y�s�w��j��)������B
�]�ˎ���A�����Ñ��̒���ł���ƂƂ��ɁA�y�Y��̕\�S��̎��Ƃ��ꂽ�B����ɂ�����K�T���̐�ɂ���咬�����_�̕t�߂ɁA�y�Y�鍂�Ì�(���)���ʒu���Ă����B
�Ր_�@�e���˒m���@/�@�_�̂��e���˒m���̖{�n���̏��R�n���ł���B�Ε����̐_�Ƃ��ĐM����Ă���B�_�А������ɂ�鍇���̗L���͕s���ł���B
���R��
�n���͓V�c�N��(938-947�N)�A���吷���폟�F��̂��߂��e���˒m���̐_������������Ƃ����B
�퍑����A�y�Y���ƂȂ������J�ɘ��珟�傪���h���A����s�����B
�]�ˎ���A����9�N(1669�N)�ɓy���������y�Y���ɂȂ�ƁA�����_�Ђ�\�S��̎��Ƃ��邽�߂ɕ�ւ��A�Гa�������z�����Ƃ����B�y�������̕�ւ�����7�N(1679�N)�Ƃ��鎑��������B
���\12�N(1699�N)�ɎГa���Ď����A����8�N(1811�N)�Ɍ����̎Гa���Č������B�哏�ɂ͓y�����̉Ɩ�ł���O�c�Ζ䂪�z����Ă���B
����15�N(1882�N)4���A���Ђɗ�i�����B �@ |
|
����~�s |
|
�����P���@�@�@��~�s����
|
�V�����n�揬��Ɍ��u���P���v�͏���̊ω��l�Ƃ��ČÂ�����e���܂�Ă���A���i�ϕS�I�̈�ɂ�������ꌧ�̗L�`�������ɂ��w�肳��Ă���]�ˌ���̑�\�I���t���z�ł��B
���P���̗��j���Ђ��Ƃ��ƁA�������N�ȏ�ނ����̕�������̓V��3�N(828)�A���P���l�����ω���{���Ƃ��Ď��@��n���B�~�a�V�c�̒��莛�Ƃ��Ĕ��W���܂����B����3�N(1713)�ɂ͓V��@�̊֓����h�т̈�ɒ�߂��A�m���{���̂��߂̊w�⏊�Ƃ��ĉh���܂����B
���̊ԁA���P����2�x�̉Ђɑ����A���݂̖{���͓V��13�N(1842)�ɍČ����ꂽ���́B���a56�N����7�N�����Ă̏C���H�����s���A�������̏d���Ȃ���ɓ����̔ɉh�Ԃ���������܂��B�܂��A�{���̓V��ɂ͎����o�g�̓��{��ƁA���{���ɂ��V�����ؗ�ɕ����G�u��V�̐}�v�����邱�Ƃ��o���܂��B
���̑��A�����ɂ͌��w��̕������Ƃ��āA�m����A���@�E�ɗ��A�����̖ؑ������͎m�����A�H�|�i�̌܌ؗ�ƌ܌؋n�A�o���̖��@�@�،o�ȂǑ�R�̕�����������܂��B�@ |
|
��������@�@�@��~�S���쑺����
|
�����N��(931�`938)������̗^�}�A�������狻�������ق�z���Đ��V�����Ɠ`������B�������A���̖v��A�V��N��(956)�����M���A����A�������Y���L���C�z���ċ���Ƃ��A���ᑊ���������A���T�A�V���̍�(1570�`1590)���̖�����e�������|�ɖłڂ���p��ɂȂ����Ɠ`������B���A���̊Ԃɕی��̗��ɔs�ꂽ���`�L(�`��3�j)��20�]�N�ɘj�蕂���ɐ�������(1156�`1180)�Ǝj���Ɍ�����̂ŁA�������̔�̉��ɂ������̂ł͂Ȃ����Ƃ��v����B�`�L�͐M���O�Y�搶�ƍ����A���q�ׂ����������������ɔs��ؑ]�`���ɓ������Ɖ]���Ă���B
��
�����̓��̑�n(�W��20m)�S�̂ƌ����Ă��邪�A����Ƃ������m�͂Ȃ��B������}���Ɂu�l���̒ˁv����Ղ̈�p�ɂ���ƋL��������F�s�\�ł���B�����A�������ɐl������4�Ƃ���B�܂��A���a�����܂Ŏ������̏�Պ��̒n�_�Ɂu�Ƃ����̏��v�Ƃ������̑�����������͎������B���̕ӂ肪�n�o���ł͂Ȃ����Ɛ��肳��邪�A�����̂��ߓy���(�ؓy)���ꂽ�̂Ō�������͕s���ł���B���ݑ�n��͔��n�Ƃ��čk�삳��Ă���A����̈�\�������Ȃ��B
�@ |
|
�����c�_�Ё@�@�@��~�s���c
|
���c���ɂ��鍂�c�_�Ђ́A�����N��(931�`937)�ɁA�I�ɍ�(���݂̘a�̎R��)�̌F���Ђ̕�����������A������̗��̕�����F�肷�邽�߂ɑn�����ꂽ���̂Ɠ`�����Ă��܂��B���̎��A13�l�̋��m�����̒n�ɗ��Z���Ă��܂��B�Ր_�͈ɎדފȂ�8���ł��B
��k���̎���ɂ́A����3�N(1338)9���̖k���e�[�̐_�{���ď�̍ہA�_���Ȃǂ��쒩���ɖ������A�_�̂��k�����ɖv������Ă��܂��܂����B
����18�N(1733)�ɍČ����ꂽ�Гa�́A����2�N�ɏĎ����܂������A����9�N�ɍČ����ꌻ�݂Ɏ����Ă��܂��B
��140m�̎Q���̗����ɗ������Ԑ��̋��͑s�ςł��B���̐����ɂ������Ղ�ꒋ�ł����Â��Q������ƁA�ˑR�A�����ȎГa�����̂Ȃ��Ɍ���܂��B���l�ȋC���ɂ�������u�Ԃł��B
�܂��A���c�_�Ђ��܂߂����̎��ӂ́A���R�тƐl�H�т��D��Ȃ��A���ƁA����̃A�Q�n�ނ��������邻�̖L���Ȏ��R���ɂ��A���̎��R���ۑS�n��Ɏw�肳��Ă��܂��B
�@ |
|
���������Q�@�@�@��~�S������
|
���Õ��Q�́A���Ď����W���̐��k�̏������q�t�߂ɁA7��̉~�����琬���Ă��܂������A����7�N�Ɍ�������c�ɂ��4����@��������A����3��c����Ă��܂��B1�����́A���a23���[�g���A����3 .6 ���[�g���ŁA����(�ӂ傤)�ɐΓ�������܂��Ă��܂��B2�����́A���a18 .5 ���[�g���A����4 .5 ���[�g���ŁA�����ɂ͓V���{���܂��Ă���A�܂�����20�`30 ���[�g���A�ڒʂ�4���[�g���̍��̑���ɖ��Ă��܂��B3�����͒��a14 ���[�g���A����2���[�g���Ńs���~�b�h�^���Ȃ��Ă��܂��B
���@�������ꂽ�ȊO�̉~��4��̂����A4�����̎�̕��͕������ɐ݂���ꂽ�S�y��(�˂�ǂ���)�œ�l�̖����Ղ�����A�����i�Ƃ��Ē���5�{�A�S���A���q�A�K���X�ʓ����o�y���A�Õ��������̍����̐��������̂��܂��B���ɁA�Õ����㒆����6�̏Z�����A6�����̕��u��������ܗ֓�(�\����)���o�y���Ă��āA�S�̂Ƃ��ċ��Ί펞�ォ�璆���܂ł̕�����ՂƔ��肳��܂����B
���ݎc��1�����A2�����̂�����́A��������̍���������̔�������(���ɂ�)�̕�ł���Ƃ����`�����c����Ă��܂��B
1�������ɖ����ꂽ�Γ����(�ܗ֓��̒n�ւ�)�Ƃ����A�ŋ߂̔��@�ŏo�y�����ܗ֓��Q�Ƃ����A���̈�Ղ́A�����̌Ñ����łȂ��A�������̑����������M�d�Ȉ�Ղł��B
�@ |
|
�����\�_��(���݂���A����_��)�@�@�@��~�S�������|��(���M���S�|����)
|
���������܂ł͋��M���S�̓�̋{�Ƃ��āu��̋{���_(��{���_)�v���̂����B�܂��A���a�ƍ��킹�āA�ʐ��ɂ͎���_��(�������厺)�y�я\���_��(���������)��2�Ђƍ��킹�āA�u�|���O�Ёv�Ƃ��Ă�Ă����B�����������ɂ��铯���̈��\�_�ЂƂƂ��ɁA���쎮�_�����̏헤���M���S����̈��(����)�u���\�_�Ёv�̘_��(������)�ł���B�ߑ�Њi���x�ɂ�����Њi�͋����ЁB
��Ր_�@���䗋�V�j���@/�@�z�_�@�o�Î喽�A�V�Z������
�_�͉̂~���ł���B���s�_�b�ɗR�������߂闈����A��Ր_�s��_�Ƃ����������B
���R��
���n��
�n���̔N��͕s�ڂł��邪�A
�w�����_�Ў����x�́u�n���N��ڂȂ炸�A�`���ɋ���Ό����V�c�a���N�ԂȂ�Ɖ]�Ӂv(708-715�N)�Ƃ��Ă���B
�w��錧�_�Ўʐ^���x�́u�n���s�ځv�Ƃ��Ă���B
�w�V����n���x�́u�W���a���̍��Ȃ�ׂ��Ƃ��ւ�v�Ƃ��Ă���B
�����ɂ���u����_�Ў��p(�|��)�v(����������ψ���)�̈ē��ł́u���ÓV�c15�N(607�N)�v�Ƃ��Ă���B
���헤�����y�L�̋L�q
�|��(������)�́A�헤�����y�L�̐M���S�̏��ɂ���u������(�����̗�)�v�̈�̒n�ł���B�����̗��ɂ��Č���鋌��(���s�_�b)�̑嗪�́A�ȉ��̒ʂ�ł���B
�u�V�n�̌��`(�����)�A�������t������Ă������A���s��_�Ƃ������̐_���V����~�Ղ����B��_�͈����̒���������A�R�͂̍r�Ԃ�_(�r�[)�肵���B������(����)�𐬂���������_�́A�V�ɋA���Ǝv�������A�₪��(����)�A�g�ɂ܂Ƃ������(���̂�)�A�b�A���A�|�A���A�ʌ]�����Ƃ��Ƃ��E���ŁA���̒n�ɗ��ߒu���A�������_�ɏ���āA���V�Ɋ҂菸�����B�ȉ��V�𗪂��B�v
���̋L���ɂ��A�����͕��s��_�̓o�V�̐��n�ł���B�����_�Ў����́u�_��̗�n�v�ƕ\�����Ă���B�Ì�́u��(��)�v�ɂ́u�s���v�̈Ӌ`������A���{���W�u�e�́u�����v���u���s�v�̈ӂł���Ƃ��Ă���(����{�n������)�B�V�ҏ헤�����́u���V�����~�����ӂ��o�ł���Ȃ�v�Ƃ����A�u�A�ʂɋ`����ׂ��v�ƒ��߂��Ă���B�܂��A�S���l�Ɂu�������|�ʂ��R�Ɖ]�ӂ�����v�Ƃ���A���s��_���|��E�������ƂɗR������n���ł͂Ȃ����Ƃ��Ă���B���́u�|�E�R�v�́A�Гa�̗���ɂ���u�˂̂��ƂƂ���Ă���B�����n���͏|�D�_�Ђ̎Вn�ɂ�����B
�헤�����y�L�ɂ́A���s�_�b�ɂ܂��Ђ̑��݂͎�������Ă��Ȃ����A�u�߉��V���v�ɂ�藪���ꂽ�\��������B
�|�����u�������v�̈�̒n�Ƃ��邱�Ƃɂ́A�V�ҏ헤�����ȗ��A����Ɏ���܂ň�ʂɈ٘_�͂Ȃ��B�������A����{�n�������͂��̒ʐ���ے肷��Ǝ����𗧂āA���̊֘A�Ŏ����̈��\�_�Ђ𒆋����\�_�Ђɔ�肵�Ă���B
�����s��_
���s��_�́A�u�ӂv�̉��̗ގ�������A�o�Î�(�ӂʂ�)�_�Ɠ���_�i�Ƃ���邱�Ƃ�����B
���V�ҏ헤�����́u���s��_�Ƃ́A�o�Î��_��\�����邩�A���͕��P�Ɩ��̐_��\�������A�ڂ��Ȃ�˂ǁv�ƁA�̂����ꂩ�ł��낤�Ƃ�����ŁA�u�Î��L�ɁA���䗋�V�j�_�A�����z�s�_�A�����L�z�s�_�Ƃ���āA���䗋�_�����z�s�_�Ƃ��\������A���s��_�͂��̐_�̔@���ɂ�����A�R��ɓ��{�I�ɂ́A�o�Î�_�ƕ��P�Ɩ��ƁA�e�X�ʐ_�ɂ��āA�o�Î�͑叫�̔@���A���P�Ƃ͕����̔@���ɂ������A���Â�̐_�Ƃ���߂Ă͉]�������v�Ƃ��Ă���B
���W���Õ��y�L�́u���s��_�v�̕����Ɍo�Î�_�̒������A���쎮�_�����ɋL�ڂ�����M���S����́A�Ƃ��ɕ��s�_�b�Ɋ�Â����J��ꂽ���̂ł��낤�Ƃ��Ă���B
������{�n�������́u���y�L�ɋ���A�����_�Ƃ́A���s��_�A�������_�̈ꖼ�Ȃ�v�Ƃ��Ă���B���ۂɂ́A���s��_�������_�̈ꖼ�Ƃ��閾�炩�ȋL�q�͂Ȃ����߁A���̗ގ����Ɋ�Â����f�ƍl������B
���|�D�_�Ђ́A�����ē��Ŏ��Ђ̍Ր_���u���s���_�v���́u���s�喽�v�ƕ\�L���Ă���B
������̎������A���s��_���J��ЂƂ����_�͈�v���Ă���B�V�ҏ헤�����A�_�_�����y�ш�~�S���y�j�́A�P�Ɂu���s��_���J��v�Ƃ����L���Ă���B���̑f���ɂ��Ă͌o�Î�_�Ƃ����P�Ɛ_(���z�s�_)�Ƃ�����Ă���A���̗ގ������痣��ĖL����F���Ƃ���ʐ�������B�������A���Ђ��Â����猒�䗋�V�j�����J�鎭���Ђł������Ƃ����T������������B
�����\�_�Ђ��|�D�_�Ђ���Ր_�̍s�K����Î��Ղ��A�|�D�_�Ђɂ����Ắu�����_���v�Ə̂��Ă����B
���y�Y�s���������ɂ��鉞�i2�N(1395�N)�n�J�̕��Ђ́A���P�Ɩ����J�鎭���_�Ђł���B���Ђ��܂߁A��~�S���ӂɂ́u��{�����_�Ёv���̂���Ђ����������݂����B
���������|�n�ɁA�哯�N��(806-810�N)�̑n���Ɠ`�����鎭���Ï��q(���Ȃ�)�_�Ђ�����A������q�_���J���Ă���B������q�_�͒|�����\�_�Ђ̎q���Ƃ���A���Ђ����鐼�k���������J���Ă���B
���u�|���O�Ёv�̊���ɂ����ẮA���Ђ͕��P�Ƒ�_���J�鎭���_�{�ɑ�������ʒu�Â��������B�������A���̓_�ɂ��ẮA�S���l�ɕʂ̉��߂��\�ƂȂ�L�q������B
����_�Ђ̎Г`�ł́A���4�N(864�N)���͐m�a3�N(887�N)�A�|�����\�_�Ђ̑��a�O���̂����A�V�Z��������_���ɂ��厺�ɕ��J�����Ƃ��Ă���B��錧�_�Ўʐ^���ł́A���(�͂��܂�)�̏\���_�Ђւ̌o�Î�_�̕��J���܂��A�������ɍs��ꂽ���̂Ƃ��Ă���B���̐_���ɂ�镪�J���A���s�M���玭���M�ւ̕ω��Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B
���|���O��
�S���l�Ɂu�����K�v�̋L�q�Ƃ��āu���a�O�_�ɂĒ|���O�ЂƏ̂��v�Ƃ���A�Â��͎O�����J�邱�Ƃ���u�|���O�Ёv�̏̂��������B
���V�ҏ헤�����y�і����_�Ў����ɂ́A���̏̂ɂ��Ă̌��y�͂Ȃ��B
������{�n�������́u�S���l�]�v�Ƃ��Č��y���Ă���B
����錧�_�Ўʐ^���ɂ́u�����J�����_�͒��2�N(���]�m�a3�N)�e�X�l�ɜ�(��)���˂̗W�y�ё厺�̗W���J���B���̓�ЂƓ��Ђƍ����Ē|���̎O�ЂƂ��Ӂv�Ƃ���B
��錧�_�Ўʐ^���̋L�q�́A�u�|���O�Ёv�������K�̕ʏ̂Ƃ���S���l�̋L�q�ƈقȂ�A�厺�ЂƉ�ˎЂ����킹���O�Ђ̑��̂Ɖ�������̂ɂȂ��Ă���B
�S���l�ɂ́u����N�������Ƃ��Ӓn�̍r�Y���J������Ƃċ{������̑b�Ό�����������đ������(���)����Ɖ]�ӗ��̖��ɋ��͕��P�ƓV�Z�����̓�_�Ƃ���ɔz�Ղ����ɂ�v�Ƃ�����A�����́u���v�Ƃ����r���n�ɐ_�Ђ̑b���������ꂽ���Ƃ���A���s��_(�o�Î�_)�͓��ЂɁA���䗋�V�j���͂��́u���v�̒n�ɁA�V�Z�������͂܂��ʂ̒n���J���Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ��Ă���B�����K�̂ق���2�̎Ђ�����A��������J���đ��a�O���ɂȂ����Ƃ���A�u�|���O�Ёv�̕ʏ̂��������R�Ȃ��̂ɂȂ�B
�|���O�Ђ̑��̂́A�헤�����y�L�̍����S�̏��ɂ���u�����V��_�v(�V�V��_�ЁA��ˎЁA������)�ɗގ������\�}�ł���A���Ȃ��Ƃ��_���ɂ�镪�J�Ȍ�ɂ����ẮA���Ђ́u�V�V��_�Ёv(�����_�{)�ɑ�������ʒu�Â��������B���ЂƎ���_�Ђ����ԂƁA��������ɉ�ˏ隬�̑�n������A�\���_��(�������ɒ������\�_�Ђɍ�����A�P���ЂƂ��Č���)�Ɏ���B���̎O�Ђ́A�Гa�̌����Ɏ���܂Ő��R�Ƃ����z�u�ɂȂ��Ă���B�u�����V��_�v�̔F���͉��쎮�_�����̍��ɂ͌�ނ��A�����ȍ~�͓����O��(�����_�{�A����_�{�A�����_��)�̊��肪�D���ɂȂ�B�×��́u�����V��_�v�̎O����(�t���_�Ƃ��Ăł͂Ȃ�)�����_�Ƃ����J��Ђ́A��錧���ł͒|�����\�_�Ђ̂ق��A���c�_��(���v�s���c��)�A���l�_��(�Ή��s���l)�A���R�_��(�g�c�s���R)���ɂ����c���Ă��Ȃ��B
���O���|���ЂƂ̊W
�헤�`�Е����̍ŌÂ̋L�^�ɂ����鎡��3�N5��(1179�N)�t���́u�헤���y�Б��c�����āv(�Гa��������)�ɁA�u�}�a��F�O�ԁv�̑��c���Ƃ��āu�O���|���Ёv�̖�������B�O���Ƃ́A��ʂɏ��}�g�S�O�����ɔ�肳�����Ύs���c�t�߂̌Ï̂Ƃ���Ă���B�������헤�`�Е����̕���2�N5��4��(1318�N)�̏��c��@�����Ɂu�}�g�ЎO�������A�S�����c�V���v�Ƃ���A�u�O���|���Ёv�̖��͏����Ă���B
�ŏ��̎Гa���������ɗ�L����Ă���u�}�g�ЁA�g�c�ЁA���s�ЁA�Ós�ЁA��c�ЁA�卑�ʎЁv�́A�Ǔ����Ђł͂Ȃ��{�{���w�����߁A�u�O���|���Ёv�͏헤�����\���鎮�����Ђɕ��̂�����Ђ̈����ƂȂ��Ă���B�������A�O���|���ЂƂ́A�{�{�|���Ђ��ʂɂ��邱�Ƃ�O��Ƃ����ď̂ł��邩��A���̎Ђ����͕��Ђł������ƍl������B���̑�Ђɂ��ẮA������p�ЂƂ�����Ђ͂Ȃ��A���ӂɁu�������v�ɒʂ���n�����Ȃ��B���q����̎O�����ɂ͎O���R����@�Ɋy���Ƃ����L�͂Ȏ��@�����������A���݂͍��Ղ��܂�ɂ����c���Ă��Ȃ��B���̎��@�Q�Ɂu�O���|���Ёv���܂܂�Ă����\��������B
�헤�`�Е����́A���Ȃ��Ƃ��������ɂ́u�|���Ёv�܂��́u�|���_�v�Ƃ������肪���݂������Ƃ������Ă���B������u��̋{���_�v�����Â��ď̂Ƃ���(���\�_�Ђł͂Ȃ�)�u�|���Ёv���������Ƃ������������镶�������Ƒ����邱�Ƃ��ł���B
���ߐ��Ȍ�
�ߐ��ɂ����ẮA�M���S��ŏ|�D�_�ЂɎ����i���̎ЂƂ��āu��̋{���_�v���̂��A�M���S������45�����̑��ЂƂȂ����B�i�a���N(1375�N)�̐M����������Ћ��m�������(�~���@����)�ɂ́A���Ɂu�A��(�Ȃ���)�A�،��A�|���A���Ўҏ������V�y�_��v(�W���Õ��y�L)�Ƃ���B����2�Ђ́A���s�_�b�̐��n�Ƃ��āA���쎮�_�����̐M���S����̔���(������)�Ƃ��āA�M���S�ɂ������{��{�Ƃ��āA����ɋߑ�Њi���x�ɂ����鋌���ЂƂ��āA��Ј�ΓI�Ƃ������闈���������Ă���B
���\4�N2��(1691�N)�{�a�����̓��D���������Ă���B�O�ԎЗ����̖{�a�́A��������ł͍ŌÂ̌������ł���B
���6�N(1756�N)�A��ɐ_�y�a�ƂȂ�_�{�����������ꂽ�B
�]�ˎ���ɒ������\�_�ЁA���̍��F�쌠��(��ɒ������\�_�Ђɍ���)�Ǝ����̈��\�_�Ђ������Ę_�����s�����B�����_�Ў����́u���Ж��ג����n�߁A��\���Ѝl�A�_�_�u�����͓��I�_�������̔@���͓��Ђ��ȂĎ��̐M���S���\�_�ЂƂ��A�R��ɌS���l�A���Ѝl���V��ƌ������قɂ��A���Ѝl�A�n�������̔@���������̈����_�Ђ��ȂĎ��̈��\�_�ЂƂ���A�R�ċL���Č�l��ւv�Ƃ��Ă���B�Ȃ��A�|���ƈ����́A�Ƃ��ɘa�����ڏ��̍������ƈ��\���ɗR������Â��n���ł���A���A�����̒������ɂ����Ă��|����(��ɏM����)�ƈ������ŕ����ꂽ���x�ɂ͕��������قɂ���n�悾�����B
����6�N10��(1873�N)�A�M���S��{�̏|�D�_�ЂƂƂ��ɋߑ�Њi���x�ɂ����Č��Ђɗ�i���A�|���𒆐S�Ƃ���8�����̒���ƂȂ����B�܂��A���̎��ɎЖ������\�_�Ђɉ��̂����B�Ж���Ɂu���Љ��쎮����{���\�_�Ёv�A�����_�{��{�i��[�̔q�a�G�z�Ɂu�p�Ј��\�_�Ёv�Ƃ���B�����Ђ͈�錧���ɂ����Ă�16��(������b�w��썑�_�Ђ��܂߂��17��)�����Ȃ��A�헤���̎������ЂƂ��Ă͐M���S��Ђ݂̂���i���Ă���B���Ђ͑��̒n��̋����Ђɔ�ׂ�ƒm���x�͒Ⴍ�A�ό��n�Ƃ��Ă̗v�f�͐△�ɋ߂��B���̗����ɑ��������d���Ȏ��p�y�юГa��i�����A����Ɏ���܂Ő�捂ȋ�Ԃ�ۑ��������Ă���B
���a52�N(1977�N)�A���p���������w��V�R�L�O���ƂȂ�B
���a57�N(1982�N)�A�Вn����錧�w��Βn���ۑS�n��(20�A����)�ƂȂ�B
�{�a�̗��ɂ͋��������Ă���B���p�ɑ��A����̒|�т͍r��Ă��邱�Ƃ�����B�Вn�͉����Y�Ɍ���������n�ɂ���A�Гa�̎��ӂ���L�т鏬���͂�������}���ȉ���ɂȂ��Ă���B�Гa���̉���(���ԃm��)�͒����̒|���ِՂł���A�����ɓꕶ�����̍��c�L��(�|���L��)�A����̒|�����w�Z��т��܂ޒn��ɂ͒|����Ղ�����B �@ |
|
����{��ف@�@�@��~�S���Y����{��Á@���}�@
|
|
�����`���ɂ��ƁA������͕�����̍���œ����ɂ��钼�O�ɁA�g�������Ă������̊���(������)�P�����A�P�͎�����{����L���F�̂��Ƃ֓��ꂻ���Œj���݁A���̎q�͌�ɐ��a�����𖼂����Ƃ����B���̑�{����L���F�̍ݏ�����{��قł������悤���B���Y����{��Â̂��̏ꏊ�ɂ͌��ݗ��}�@(���T2(1571)�N�����̓V��@�̎�)������B�@ |
|
���������@�@�@��~�S���Y��
|
|
����N�ԍ��c�����������ɍۂ����u���Ă�����g���������̍��̍^���ŗ�����A����2�N���傪���L��ł�����E���グ���������J�����Ɠ`���B �@ |
|
���|�D�_�Ё@�@�@��~�S���Y���M��
|
�|�D�_��(���Ăʂ�����)�B�������̓����̐_�ЂƋ�ʂ��āA�ʏ̂͐M���S�y�Џ|�D�_�ЁA���͐M���|�D�_�ЁB�ꏊ�͈�錧��~�S���Y���M��1830�Ԓn�B
�Г`�ɂ��A��12��i�s�V�c�̌��(71�`130�N�H)�ɑn���A��T���N(715�N)�Č��Ƃ����B��Ր_�͌o�Î喽�B�헤���M���S�̎����Ёu�|�D�_�Ёv�̘_�ЂƂ���邪�A��ʂɁA�������Y�������ɒ�������u(��{)�|�D�_�Ёv(�O��)����肳��Ă���A�����Ђ��Љ��{��E�F�u�T�C�g���ł��G����Ă��Ȃ����Ƃ��w�ǁB�������A���̒�������n���ł��킩��悤�ɁA���̕ӂ肪�Ñ�u�M���S�v�̒��S���ł������炵���A�u�M���S��(�S��)�v�̑z��n�ł�����Ƃ̂��ƁB����āA���_�Ђ������Ёu�|�D�_�Ёv�̌�g�ł����Ă��ǂ��A���邢�́A�Ñ�ɒn���̗L�͎�(����)�ɂ���ČS�Ƃ̎��_�Ƃ��Ċ������ꂽ�Ƃ������Ƃ��l������B�@ |
|
����{�_�Ё@�@�@��~�S���Y���y�Y
|
��{�_�Ђ́A���M����������\�l�����̑�����ŁA��Ր_�͓V�ƍc��_�A���{�����A�V���ʖ��̎O�����J���Ă��܂��B
�`���Ƃ��Ă͔�賌�(650)�N�̑n����`���A���c���Җ��������_�Ƃ��đn�����A�ɐ���Ђ̕�����ւ������ƁA���̌�ޗǎ���ɁA���̐����������Ƃ����n���̗R���ɂȂ����Ƃ���������{�������A����̒����Đ����Ɋ������A������\�l�����̑�����ɂȂ������ƂȂǂ��`�����Ă��܂��B
�L�^�ɂ��ƁA�V����(1575)�N�ƁA���\�l(1691)�N�ɎГa�̍Č����s�Ȃ��Ă��܂��B���̌�A�吳��(1920)�N�̑䕗�ɂ��Гa���|�����߁A���\�N�ɍČ�����Ă��܂����A���݂ł��Íނ��܂ߍČ��O�̋�����悭���߂Ă���Ƃ����܂��B�����̖{�a�͌��s�O�ԁA���ԎO�Ԃ̖{�̂ɉ��݂���ꂽ�K�͂̑傫�Ȃ��̂ŁA�����ő���ւ�܂��B���ɖ{�a�̍ȏ���͓Ƒn�I�Ȃ��̂œ����̓��������⓪�іؕ@�E�g���̌��@�Ȃǂ̒����́A���\������L�̂��̂ł��B���̂悤�Ȍ��z�ו��̗l������A�]�ˎ���ɏ헤���𒆐S�Ɋ������A���c�R�V�����̎O�d���Ȃǂ��������䂪�����\����{��H�E���䎁���̍쎖�ɂ��ƍl�����Ă��܂��B�@ |
|
���ٓV�ˌÕ��@�@�@��~�S���Y����ˎ��ٓV
|
|
�ٓV�ˌÕ��͏헤�����y�L�ɋL����Ă��鍕�▽����Ɠ`������Ă���B�y�Y�o�g�̍��w�ҐF��O���̏������u���▽����l�v�ɂ��ƁA�O��4�N(1847)�ɕ�����Ί����o�y���A������b�h�A���A���Ȃǂ��o�y�����Ƃ���B �@ |
|
������㒬 |
|
������N��O�@�@�@����㒬�M�ˁE�Z��
|
������U�߂�G���E�吷�@�M�˂��畽�ˁA�Z���ƍL���鐅�c�́A���Ƃ͖��X�Ɛ�����������я��ƌ������̍L��ȏ��ł����B���̔я����܂��u�L�͂̍](�Ђ납��̂�)�v�ƌĂ�Ă��������̂̂��Ƃł��B
����7�N(937)�A�f���nj������̂��悤�Ȍ����点�⒧���ɑς����˂�����́A���ɏo�w���A�������т��̐킢�ɏ������܂����B�������A���̎��͈���Ă��܂����B���(�����A���݂̖�܂�����)�̐킢���͂��߁A����܂ł͏������Ă�������ł������A�q���̓n(���쑺�~�t��)�ŗnj������̘A���R�ɔނ͎�ɂ��s�k�������܂����B�����ēˑR�r�C���킸�炢�A����͈ӎ��������낤�Ƃ��A�������Ƃ����܂܂Ȃ�܂���B�킸���ȉƗ��ƉƑ��������A��āA����͑D���g���čL�͂̍]�̂قƂ�A���Í](�������A���݂̈��P�J�M��)�܂œ���Ă��܂����B�u����҂�J�Áv�Ƃ��Ă�A�ܕ����ɕ��ˏ�ɓ��肭���]�́A����܂ł����傪���т��ѐg���B�����ꏊ�ł�����܂����B�܂�����҂�J�Â̂ЂƂɂ͏���̒������鏗���Z��ł���A�����́u�R�̐_�v(������⏗�[�̕ʏ�)�ƌĂ�Ă��܂����B���̏��[�𗊂��ď���Ɛ��ȁu�N��O�v�A�����ėc���q�ǂ������͏M�˂܂œ���A�u�z�K�_�Ёv�̂��Ђɐg���B���܂����B�������A���܂藈��nj��R�������邽�߁A�₪�ČN��O�Ǝq�ǂ������͔��z�̑D�ɏ�荞�݁A�z�K�_�Ђ𗣂�܂����B�����ɎR�̐_�ƌĂꂽ�������R�[������܂����B���������������ؗl���J���Ă���_�R�W���ł��B�R�̐_�����ꂽ�R�u�_�̎R�v����A����Ȓn�����c�����̂��낤�ƌ����Ă��܂��B
���đD�ɏ�荞�N��O�����́A�G���牓�����邽�߁A����ɏ���k�サ�܂����B���̕ӂ��u���ԁv(�������)�A���݂̘Z���t�߂ł����B���������������ĉ߂��܂����B��Ɉ������Ȏq�������炸������Ă�������ł������A���̖݂ɂ�������Ȏq�̎p���������Ă��܂��܂����B�����āA����قNJ݂ɋߊ���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����܂߂Ă����̂ɂ��ւ�炸�A�N��O�����͊ݕӂɑD���Ă��܂����̂ł��B�����nj��̌R�����������͂�������܂���B�����ɌN��O�Ǝq�ǂ������͑D�����������o����܂����B�����Ď��X�ɏ���̋��ꏊ��₢�߂��܂������A�N��O�͊�Ƃ��Ă��������܂���B�������ł͗c���q�ǂ����������|�ɂ��т��ċ�������ł��܂����B���ɏ���̋��ꏊ�𔒏��邱�Ƃ�������߂����m�����́A�N��O�Ǝq�ǂ����������Y���邱�Ƃɂ��܂����B��E����钼�O�A�N��O�͗c���䂪�q�����������A�����̌N��O�K�����Ǝ�����킹�ċF��܂����B
�u����l�A�Z�������ł��������͍K���ł����B�e�P�����ƂƂ��ɂ��̐��ɗ������܂��B�v
�������Ė��S�ɂ��N��O�Ǝq�ǂ������́A�f���nj��̕��m�ɂ���ĎS�E����܂����B�}���ď��傪�삯�����̂͂��ꂩ�炵�炭�o���Ă̂��Ƃł����B�₽���ނ���Ɖ������Ȏq��r�ɕ����A�ނ͋������悤�ɋ������сA�܂�ŋC���ӂ�Ă��܂����悤�ł����B
���̌�N��O�Ɩ��A�e�P�̎���������l�́A���̏ꏊ�ɒ˂����܂����B���ꂪ�́A�O�a�������̔я��ׂ�ɂ������u�N��O�ˁv�ł��B�����ĔߎS�ȍŊ����Ƃ����N��O�������ŁA���l�͂������u���v�Ɩ��t���܂����B�������A��ɂ���͌��݂��g���Ă���u�����v�ɏ����������܂����B���������̂́A�߂������Ƃɋt���Ƃ��Đ������ꂽ����̊����Y��������邽�߂ł����B
������ɂ��Ă��A�N��O�Ƌe�P�����͂����ɑ����܂������A���a40�N��A�y�n���ǎ��Ƃ̂��ߒ˂͐������Ă��܂��܂����B�������̏ꏊ���NJ������Ǝ҂ɂ��A�@��N�������˂̒��ɂ͑召���܂��܂ȓ��╛���i����������Ă����ƌ������Ƃł��B�����Ē˂̂����������J���Ă����u�N��O�v�̏������K���A���������n��̕ʂ̊ω����Ɉڂ���܂����B�ω����̕Ћ��ɂ���Âڂ����D�F���K�ɂ͍��ł��u�N��O�v�Ǝ�n�ŏ����ꂽ�Âڂ������D������Ă���܂��B�@ |
|
���ϑ��̋����r�@�@�@����㒬���m�J
|
�ނ����A�V��̖k���A�㉺�c�̐쑺�Ƌ���ڂ��邠����ɂ�10�A�[���قǂ́u�����r�v�ƌĂ��r������܂����B���͂�V�����������A���Ȃ��Â��r��K��鑺�l�͂قƂ�ǂ���܂���ł����B�ΐF�̐������������r�͒�Ȃ��̂悤�ɐ[���A��ւ��Z��ł���Ƃ������킳����Ă��܂����B���āA�����V�c�̗��ŏf���̍����A����̑��q��ɏP��ꂽ����́A�悤�₭�̂��Ƃł��̋����r�̂قƂ�܂œ���Ă��܂����B�������A�X�̂܂��͓G�����܂����͂�ł���A���₷�����Ƃł͒E�o�ł������ɂ���܂���B�����ŏ���͈�v���Ă��܂����B����ɂ͂������l�̉e���҂��t���]���Ă��܂������A���ꂼ��ɖ����Ĕn����r�̂قƂ�ɍ~�肳���܂����B�����ċ��̂悤�ɓ₢���r�ɂ߂��߂������̎p���f���������A���ꂼ������傻������ɕϑ��������̂ł��B
�܂��Ȃ������ł��S�������������Ȃ����炢�Ɏ����A���l�̉e���҂��ł�������܂����B������m���߂�Ə���͍Ăєn�ɂ܂�����A�G���҂���X�̊O�֔�яo���܂����B�������̎q�ǂ������ɂ͒N���{���̏��傩������܂���B�����������Ă��邤���ɏ���͖��������̗̒n�֖߂邱�Ƃ��ł��܂����B
�����r�ɂ͂��̑��ɂ��s�v�c�ȓ`���������`�����Ă��܂��B���鎞�ЂƂ�̒j���[���߂�����(�ߌ�5��)�����A���̒r�̂قƂ��ʂ�߂��悤�Ƃ��܂����B����ƓˑR��w�̎������X�𐁂������܂����B�������Ǝv���r�̒[�ő����~�߂��j�́A���C�Ȃ��r���̂����܂����B����ƌΖʂɂ͐�����������ɏƂ炵�o���ꂽ�傫�Ȍ�����U��A���X�Ɖf���Ă���ł͂���܂��B�����ڂɂ����j�́u����[�v�Ƃ������ѐ���������ƁA��ڎU�ɓ����A�����ƌ������Ƃł��B
�܂����鎞�A��͂�ЂƂ�̏������̒r�̂���ʂ肪����܂����B���łɋ����r�̕s�C���Ȃ��킳�͎��ɂ��Ă��܂����̂ŁA�����ɒʂ�߂��悤�Ƃ����Ƃ���A�����C�Ȃ��r�̐��ʂ��̂����Ă��܂����̂ł��B����ƌΖʂɂ͂Ȃ�Ƒ傫�ȋ����f���o����Ă��܂����B�т�����V�������͂��̏�ō������A�ւȂւȂƍ��荞��ł��܂��܂����B
����ȕs�v�c�Ȍ����`�����c���Ă��鋾���r�ɂ́A�吳����܂œ��݂ɓy�˂�����܂����B���̒˂̒��ɂ͌�����E��������E���킴��̎O���̔肪�����Ă��������ł����A���̂܂ɂ����̒˂��Ȃ��Ȃ�A��������␅�c�ւƎp��ς��܂����B�����č��ł͕ӂ��т͍L�X�Ƃ����S���t��ɂȂ��Ă��܂��B
�@ |
|
���I�R�ω��̞����@�@�@����㒬�I�R
|
�I�R�ω��̑���@�I�R�ω��E�Ő����̂���ꏊ�ɂ́A�����̏���̉Ɨ��ł������ʓ��E�����o��(����)�˂��������߂Ă����I���@��H��X(���邷�����݂͂̂܂�)������܂����B�����͏���̗͂̌��ł������R�n�̎�������Ă��܂����B�������N(937)8��6���A�s����A�����ċސT���Ă���������̗nj��E�ǐ��̑�R���P��������܂����B���̔��ƓˑR�r�C���킸���������͂��Ƃ��Ƃ���ɕ����A�Ȏq�ƂƂ��Ɉ��Í](���̈��P�J�M��)�ւƓ��ꂽ�̂ł��B���Í]�̐z�K�_�Ђɐg���B���������s�͌I���@�̕��p�����߂܂����B��ڂɂ��͂�����Ƌԍ����R���Ă��܂��B�c�E�ȗnj��̌R���͖��Ƃ��Ă������A�l�X���E�C���܂����B������̉ʂĂɂ͊ω����ɂ����������̂ł��B�K���{���̊ω���F�͉Ɨ��̉����Ƃ����҂����̒��J�Ɉڂ��܂������A���͂��Ƃ��Ƃ��Ă������܂����B�����ċ��~�ȌR���͊ω����̞����ɖڂ����܂����B�ނ�͏���D�ɐς�Ŏ����A�낤�Ƃ����̂ł��B���ČI���@�͔я��̒J�Âɖʂ��Ă���A�D�̉��������R�ɍs�����ł��܂����B�₪�ď���ςݍ��D�����c�J�ÂƌĂ����̍ł��[��������ɂ��������������A�ӂ��ɞ������u�����[��v�Ɖ��������܂����B��荇�킹�����m�����͓ˑR�̏����Ɋ�������킹�܂����B�u�ւ�ȉ����o���̂͒N���v�ƈꓯ���Ԃ���܂������A�N���S������͂���܂���B����ǂ��납�����͂��悢�挃�����剹���������܂��B����͎���������̂����܂������ł����B���m�����́u�����Ă���[�v�ƌ��X�ɋ��т܂������A�[���J�Â̐^�ł͔�э������ɂ���э��߂܂���B�₪�Ğ����͗��̂悤�ȉ����グ�A����Ɠ����ɑD�͂ǁ[��Ƃ����������グ�āA���c�J�Â̒��قǂœ]�����Ă��܂��܂����B�u����[�v�Ƃ������ѐ������������ʂɏ����܂����B
���ꂩ�牽�S�N���̔N�����߂��܂����B�������т��̕���������ʂ��A��F���͂��Ȃ�����܂����B�i�\9�N(1566)����J���o�̒��j�d�o�́A���̕s�v�c�ȗ쌱�Ɋ������Ċω������Č����܂����B����Ȏ������N����n�߂��̂͂��̍��̂��Ƃł��B�����������c�J�Â��疈�ӂ̂悤�ɉ̋ʂ������яo�āA�I�R�ω��̋����ɓ��荞�ނƂӂ��Ə����Ă����܂����B�����̑��l�����̋S��ڌ����A�s�g�Ȃł����ƂɊF���т��܂����B�����ď��ɒ������̉��O�ł��낤�Ƃ��̂������|�ꂽ�̂ł��B�����ŌI�R�ω��̏Z�E�͊ω���F�ɋF�������A�����̋��{�̂��ߑ�@�v���Ƃ肨���Ȃ��܂����B���̍b�゠���Ă��ꂩ��͋S������Ȃ��Ȃ����ƌ������Ƃł��B
��R�ɋ߂����c�J�Â͍��ł͍L�X�Ƃ������c�ɕς���Ă��܂��B�������A�������̍L�����c�̂ǂ����ɌI���@�̞����͖��܂��Ă���̂����m��܂���B�@ |
|
���É͎s |
|
�������_�Ё@�@�@�É͎s�����J
|
�Ր_�@�@�@����ˋM���A���ǖ�
�����_�Ё@�����_�ЁA��א_��
�R�����v
�V�c�̗�����̒���������썑�Z�U���������G���A�����Ən�c�����炵�R��i�߂����ɖ{�w���ߋт̌�������ĂēV�_�n�_���܂��Đ폟���F�肵���Ƃ���A�_���̂���������܂��A���ɕ������n���̑�C���ʂ������Ƃ��ł����B������L�O���т̌���̓������Ƃ��ĎЖ��Ƃ��đn�������B
�����ɂȂ��đ��Ђɗ�i�A�����l�\�N�Z�������_�Ђ������B�@ |
|
���\�ˌÕ��Q�@�@�@�É͎s���R�c
|
�\�ˌÕ��Q(�����Â����ӂ�)�́A�É͎s���R�c��KDDI�������M���~�n���ɂ���܂��B�͉̂~���\����E�O����~��2�����܂������A���݂͉~��2��A�O����~��1��c���Ă��܂��B
�\�˂́A�u���\��(�₻��)�v�A�u���(������)�v�Ƃ��Ăꂽ�����ł��B50���邢��80����̌Õ��Q�A�̑������ӁE��ɂ���Õ��Ƃ����Ӗ������ł��傤�B
�����ɂ͂ǂ�Ȑl����������Ă���̂ł��傤���H�@�Õ������锪��(��܂�)�Ƃ����n�����A�q���g�ɂȂ邩������܂���B
�����͕������ɂ����̂ڂ�Â��n���ł��B������(����)�ɂ́A���݂̎R�c�A���R�c�A�k�R�c�A�J�L���܂܂�܂��B�����āA�S�ύ�(���N�����쐼��)����̓n���l�����̂Ȃ��Ɂu�������v�����邱�Ƃ���A���n�Ƃ̊֘A���z�肳��Ă��܂�(�w�n���u���x)�B
�����Ȃ�A�Õ��̎�͓n���l��������܂���ˁB���@��������Ƃɂ�镪�͂�����ɐi�߂Ζ��m�ɂȂ�ł��傤�B
���̌Õ��͔я��ɖʂ����n�̉��ɒz����܂����B�я��͓�k�ɍג����A��[�ŋS�{��ƍ��̗����쉺���Ƃ̍������ɂȂ���܂����B�]�ˊ��̋��۔N�ԁA�V�c�J���̂��ߊ���܂������A�Õ����z���ꂽ���ɂ́A���ӂŕ�炷�l�X���W�܂�A���Ƃ�������ŁA�M�̉������p�ɂ��������Ƃł��傤�B���������l�X�̎������Ă���Ƃ��l�����܂��B
�я��̎��͂ɂ́A�ˎR�Õ��E�H�t�_�ЌÕ�(�ǂ��������㒬)���A�����̌Õ�������܂��B����͉���܂����A�Ⓦ�s�t��̋t�����A�я��̂قƂ�ł����B�\�ˌÕ��Q�̔w�i�ɂ��ẮA�я����߂�����j�S�̂���Ղ��Ȃ���A�l�������Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁA�Ñ�̒n���u�����v�́A�̂��Ɂu�R�c�v�Ə������悤�ɂȂ�A�]�ˊ��ɂ͎R�c��(��R�c��)�A���R�c���A�k�R�c�����蒅���܂��B���̂��߂ɎR�c�́u��܂��v�ł͂Ȃ��A�u��܂��v�ƌĂ�܂��B
����22�N(1889)�A���̒n��̑��X�����������Ƃ��A�Ñ�̒n���u�����v�������B�����ď��a15�N(1939)�A���������R�c�ɑ��M���̌��݂��n�܂�܂����B
�����ƎR�c�A�ǂ�����u���}�^�v�ƌĂсA�n�����n��̗��j���@�肨������|����ƂȂ��Ă��܂��B�@ |
|
�����씪���{�@�@�@�É͎s����
|
|
������̐_�Ђł͕�������̎���J���Ă���B������̎��ŗ����Ƃ��A������̎Гa����ӂœ����G�����̗̒n������k�̕������������Ȃǂƌ����`�����c���Ă���ƌ������Ƃ����A������̎�͂������������ɔ��ōs���˂��B�������炻�������������K��s�̏��ɂ�������̎�˂����邵�B�@ |
|
������s |
|
�������@�@�@����s�卑�ʎO��
|
(�݂��ǂ��͂�)
������̋��{���Ƃ����4��̌ܗ֓�������B����ꂽ�̂͊��q���㏉���B�y�n�Ɏc��`���ł́A���Ă��̒n�ɏ���̋��ق�����A����̗��e���ɂ�����M�肪����ƐM����ꂽ���߂ɑ���ꂽ�Ƃ����B�g�����h�Ƃ������̂́A���傪�����N�������ۂɁg�V�c�h�Ə̂����Ƃ��납��t����ꂽ���̂ł���A����Ɂg�O��h�Ƃ����n������������h���������ł���ƌ����邾�낤�B
���̕ӂ�́A������̗��̍��A���^��(������̂܂���)�̎��߂�y�n�ł������B����̍Ȃł������g�N�̌�O�h�̕��ł���A����̓����҂ł���B�����̕��K�ł͒ʂ������ʗ�ł���A�����炭���ɂ��ʂ�����̂��߂Ɋق��݂����Ă������̂Ɛ����ł���B
���̕t�߂ɂ͌N�̌�O���J��@�_�Ђ����邪�A����4��̌ܗ֓��͂��傤�ǂ��̐_�Ђƌ����������`�Œu����Ă���B��������̌ܗ֓�������ɂ܂��`���������̂ł���Ƃ���؍��Ƃ���Ă���B�@ |
|
���^�ǒ��H�����@�@�@����s�^�ǒ�
|
�����t�̗��E�H��
�u����L�v�ɂ��ƁA����7�N(937�N)�ɕ����傪�U�ߓ������ꏊ���A���D(�͂�����A�͂Ƃ�)�̏h�A�Ƃ��Ă���B���ꂪ���݂̉H���n��ł���B�H���ɂ́A�^�ǂƒ}�g�R�̒j�̎R�����ԉH����������A�Â��͏C�o�҂̎R�x�C�s�̓��ł��������A�]�ˎ����������ʏ����ɍL�܂����Ў��Q�w�̐M���ƂȂ����B�������ɂ͓����̖ʉe���Â���앧��Δ�Ȃǂ��������c���Ă���B�܂��A�H���ɂ́A�t�ƏH�ɖ��t�тƂ��W�܂�̂��r���킵�ėx��u�������v�̓`���n������A���t�̗��E�H���̉��[��������Ă���B
���H���V�_�ˌÕ�
�����̓��^�̈⍜�̈ꕔ���A�O�j�̌i�s�����������`��������Õ��B�}�g�R���،i�ɐ�N�̗��j�����ɓ`����B
���̕P(�����Â�)���_
�H���W���̐����̏������u�ɂ��肱�̒n�Łu�������v���s��ꂽ�Ƃ����`�����c��B
�@ |
|
�����@���@�@�@����s�{��
|
|
���g���̂��鎛�Ƃ��ėL���ł��B�]�ˎ���A�w�`��l�����̎��ɓ���A1686�N2���ɓ��₵���Ɠ`�����Ă��܂��B�@ |
|
���F��_�Ё@�@�@����s�^�ǒ�����
|
����͐́A�F��ۂƂ����ċI�ɌF��_�Ђ̎З̂ł������Ƃ����B�F��_�Ђ͎���̏W���̉��A�������ƖX�ɕ���ꂽ�u�̏�ɒ����B�Вn�܂ł�70�i�قǂ̋}�ȐΒi���̂ڂ�˂Ȃ�Ȃ��B���̐_�Ђ͗�̑ւ��ɞ���������A����̖ؕ@�Ȃǂ̒����������������Ă���B
��Ր_�@�ɜQ�e��
�R���@�n���͍]�ˎ���Ƃ����Ă��邪�ڂ炩�łȂ��B�@ |
|
���Ŕ��R�@�@�@�@����s�^�ǒ��Ŕ�
|
�}�g�R�����ɂ���Â��Ȃ����̒Ŕ��R�@(����������₭��������)��1200�N�̗��j������A���w�蕶�����V�R�L�O���ł���X�_�W�C(�ł̖�)�̋��،Q���n�ł�����܂��B
�����ɂ͖���H������̎�ɂ��O�d��(���w�蕶����)��m����(�s�w�蕶����)�Ȃǂ���������A�×����a�C�����̗��Œm���Ă��܂��B
�����ɂ���d����1�g���̑傫�Ȟ����͂ǂȂ��ł��ł��Ƃ��ł��܂��B���̞����͐^�ǒ��̓`�����鏬�c�������ő���ꂽ���̂ł��B
�����ɂ͎���300�N�`500�N�Ƃ�����X�_�W�C�Ȃǂ��Q�����u�Ŕ��R�@�̎��p(���セ��)�v�Ƃ��Č��̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B�@ |
|
���ܑ�͓��ƒr�T���@�@�@����s
|
���_�R�̓��[�A�r�T�W���ɂ���ܑ�͓��́A���c��N�Ɋ��̒n�ŎE���ꂽ������̎c�}���������炩���Ă��������Ɠ`�����A�����ɂ���ܑ�͑��́A�����l�̎�ɂ���Čܑ̂̑��������܂�A�t���ǂ̈��C�@���s�����Ɠ`������B
�������A���ݎc���Ă���ܑ呜�́A���ꂩ���S�O�\�]�N��̎�����N�ɒ��蒼���ꂽ���̂ł͂Ȃ����ƌ����A�ٓ��̖����ɂ́u���ܑ�͕�F���[�E�E�E������N������V��v�ƋL����Ă���ƌ����A�����l�N�ɂ́A�s�Ŏ��m���̗ߎ|�ɂ�茹���������������F���̗�������A�������Ō������A�ؑ]�`���������A�悤�₭�S�����ɂ߂��������ɉA�肪�o�n�߂�����̍�ł������B
�܂��A��̂̑��ɂ́u���̂̉́v���L����Ă����ƌ����A�F���C�̒����ɂ��A���̗��̌_���Ȃ��̂������̂������ł���B
���ܑ̌�͓��́A���݂������C������A���H���ׂ��ۂނ������̂���L���ܑ����ꂽ���̂ɕς��A�Â����������̂̂܂c��R���ł���B
�ܑ�͓��̓��ɂ���W���̒��獁��_�ЁB���̐_�Ђ̓��k�ɒJ�삪����A���̋߂��ɓ��������̕�̌����A���e���l�Ƃ��Ă�鑽������B
���ɂ͌����̔~�ƌ�����V�~�����j�̏d����`���Ă���B
���̐́A��������̒����A����������̒n�œ|�������吷�Ɠ����G���́A����R�ł�����̕����ł���������������ǂ��Ē}�g�E���g���z���A���_�R�̂ӂ��Ƃɂ���r�T�̒n�ɂ��ǂ蒅�������A�����̌����R���U�߂����ˁA�@�͂ɂ����낤�Ƃ��č��ꂽ�̂��ܑ�͑��ł���B
���̌�A�����l�ɂ�鑯�k�����̑�C�@���x��t�������A����J�ƂȂ��Č����R�̐w�n���P���V�����������s�́A���̈�̒J���Ŋ��̌����Ƃ��ĉX�����������ɂ����Ɠ`������B����ɁA�ܑ�͑��̑ٓ��ɋL����Ă����u���̂̉́v�⌺������̊G�n������ɂ��A�����̎R��Ɉ������������N�������ꐢ�̉p�Y�A������Ƃ��̔��ށA����������s�̉��O���Â��B
���ꂩ����S�N��A�����������吷�̎q���ł��鐴���Ǔ��̊��グ�����āA�����𐼊C�ɖłڂ��A���q���{���J�������Ƃɂ���ē������l�Ƃ��Ă̏���̔O����ʂ����ꂽ���̂Ǝv����B
��
�ܑ�͓��͕�������A������̗��̍ہA�U���������G�����쑜5�̂����u���ď��哢�����F�������A������͏���̑P�S��m�����Ԃ߂����ƌ����Ă��܂��B������삷���͂̂���y������z�@�y������z�@�y���؏\�͙�z�@�y���d��z�@�y���ʗ͙�z�ܑ̌�͑��͞w���̊�ؑ���ƂȂ��Ă���B�@ |
|
���r�T��@�@�@����s(���␣��)�r�T
|
����s(���␣��)�̖k���[�A�r�T�n��ɂ���B�␣�w����͖k��6�q�̒n�_�ł���B�k�ɓȖ،��Ƃ̋��ƂȂ�W��519.6���̍���������A���̓�ɉ��т�������[�Ɍܑ�͓�������B���ܑ̌�͓��̂��������400����̔����̖��[������ł���B���̉��̖k���ȊO��3�����r�T�̏W���ł���A�W�����������ł������Ǝv����B���̏��͓쑤�����ɂȂ��Ă��邪�A��k300���A�����ő�100���قǂ���B
�r�T�̏W���쐼�Ƀ|�c���Ə隬�̕W��������A�������k500���̎R���Ə����Ă��邪�A���ꂶ�Ⴓ���ς蕪��Ȃ��B�����Ɠ����̌����ق̗�����Ƃ̂��ƁB���̌����ق̗��R�A�����猩��Ə���ۂ������Ȃ̂ł���B�䍂��10�����x�ɉ߂��Ȃ��B�����ق̗��ɂ͉��x7�������B���̏�͔��Ȃ̂ł��邪�A�i�X��ɂȂ��Ă���B�̐S�̏�́H�Ǝv���A��5�ɂ���l�ɕ����B�u�����A��R���H���̎R����B�v���Ă��Ƃňē����Ă��������B���̕��̖��͋e�r����A�ē����Ă��������k�ɍs���ƁA�x4������A�y��������B
����͈�\�ł͂Ȃ��A�g���b�R���Ȃ̂��Ƃ����B�������A�x���ۂ��B���̐�ɋȗևU�A�k�ɓy�ۂ�����A�x3������B
���̖x�͋ȗևT(1)�̓�Ɛ�2���Ă���B���̖k�̋ȗևT����R�ƌĂ�Ă���B��k35���A����20���B���͂���͍�����3,4������B�����͍��ȗւɂȂ��Ă���B�k���ɓy�d������B���̖k���x�ł���B��������̖k�[�ł���B
������k�ɍs���ƌܑ�͓��ł���B�]������w�E���Ă���悤�ɏ�R�Ƃ����ȗւ͖k���͖x1�{�����Ȃ��B�����͖{�s�ł͂Ȃ��B��̖k�����ȗւł��낤�B
�{�s�͋e�r����̔��ł���ȗևV�ł��낤�B���̓쑤�͒i��6�ɂȂ��Ă���A�x���������̂�������Ȃ��B����ɓ�ɂ��i���̂��锨�������B���̔����S�ċȗ�(�W�A�X)�Ȃ̂ł��낤�B
�}�Ԏ��ɏ]���������ɒr�T���̖��������邪�A�ǂ̂悤�Ȏ҂ł��邩����Ȃ��B�����炭���̒n�̓y����������������Ȃ��B
�Ȃ��A���̏�A300���~100���قǂƍL���A4�̋ȗւ��������Ɛ��肳���傫�Ȃ��̂ł���B�Z���̔��{�݂Ƃ������������邪�A���{�݂ɂ��Ă͗��ɋ߂��ꏊ�ɂ��肷����B��͂�A�r�T���̋��ق�����A�đq���쑤�ɑ��݂��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
1�ȗևT�����A�k�ɓy�d������B 2�ȗևT�̐����̖x�A���Ȃ薄�܂��Ă���B 3�ȗևT�쑤�̖x
4�ȗևU�A�V�Ԃ̂��̍a���ۯ����Ƃ������B 5�ȗևV�A�������{�s�ł��낤�B 6�ȗևV�쑤�̐؊�
7�ȗևV���̉��x �k�ɂ���ܑ�͓� �ܑ�͓���F�B���Ȃ�ς�������ł���B
���̑��A���Ȃ�ς�����\��ł���B���j�͐������A�������ɂ͎w�肳��Ă��Ȃ��悤�ł���B�������I�ɂ͏������l�����̂��H
�@ |
|
���H���R��Ɠ����@�@�@����s(���␣��)�H��
|
����50�������␣�s�X����H�����Ċ}�ԕ��ʂɑ���Ɛ��ʂɑ傫�ȎR������B���̕W��245���̎R�̎R����тɓW�J����̂�����R��A�H���R��ł���B�[����̔䍂��170������B���̎R�͖k������U�Ⴍ�Ȃ�A�܂������Ȃ�B���̖k���̎R���W��263���̓���R(�����݂�)�ł���A�R��ɉH���R��̏o��ł��铏��邪����B�@
�ʐ^�͐������猩���H���R(��)�Ɠ���R�ł���B����Ƃ����㕔�ɒz����Ă���B�H���R��ɂ͓_�Ђ�����A�_�Ђւ̎Q���������̎R�[���牄�т�B���ꂪ���Ă̓o�铹�A��蓹�ł������炵���B���ʂ͂��̓����s�����A���Ⴂ������1�{�k�̎R����o���Ă��܂����B���\�������ꂽ���ƕ����Ă����̂����A�|����ŏ��X���������Ă���s���Ɏv���Ȃ��炻��ł���ɐi�ނ���30���B20���l���̕��R�n�ɏo��B
��ŕ����������Ƃł��邪�A�������H���R�Ɠ���R�̊Ԃ̈ƕ�(�W��230��)�ł������B(���̋�Ԃ�2�̏�̒��p�n�ł�����A�[����̓o�蓹�̏I�_�ł�����d�v�ȏꏊ�ł���A��Ȃǂ��������ł��낤�B)
�H���R�邪���̍���ɂ���Ǝv���A100���قǁA���x��30���قǓo��B�x������A����10���ʂ���؊݂��s�����j�ށB�₪�����o���̋}�X�̐؊݂�o��ƕ��R�ȏꏊ������B�������{�s�ł��邪�����B�r���ɐx������B40���قǐ�ɓ�d�x������B�x�̐����ɍ��ȗւ�����B
�x���z���A�k���̕��R�n���s���������Ȃ��B�u���������B�v�����ŊԈႦ�����ƂɋC�t���A�ł��������̂́A����������ǖ��炩�ɏ�ł���B�u���������ꂪ����邩�v�Ƃ������Ƃœ���߂�B(���̑O�ɂ�����ȈՑ��ʂ������E�E�B���̂悤�ȏ�������͑��ʂ��₷���Ă��肪�����B)�������̓꒣�}�ł���B
�쑤�̖x��{�s�����猩���낷�B ��d�x�؊O���̖x�B ��d�x�ؖ{�s���B
�ƕ��܂Ŗ߂�A�������Ɍ��������A�����Ȃ��B�}��~��������100���قǐi�ނƁA�b�ɕ��������̒[�ɂ���Ƃ�����x�ɏo���B�x�Ƃ����������f����剡�x�ł���B
�[����10���A����20���͂���B������80���ʂ��H�쑤�͒G�x������B�y����ʂ�A�x���z���A�ȗ�6��ɏオ��ƁA�y�ۂ��x���ɂ���B�y�ۂ̐�����20���ɓn�蕽�R�ɂȂ��Ă���B���̐��͊ɂ₩�ȓo��ł���B��ʂ̍��|�̒��̏�����i�ނƓr�����牺��ɂȂ�B100���قǐi�ނƁA�x������A��������Ƃ܂��x������A�O�ʂɍ���4���قǂ̐؊݂�����B
���̕����͓�d�x�̂悤�ɂȂ��Ă���B(�x�Ƃ������t���^�̉��x�ɋ߂��B)�������炪��s���ł���B�؊݂̏オ�ȗ�5�ł���B�x�ɖʂ��O�ʂɍ���2���ʂ̓y�ۂ������A�����͈�i�����Ȃ��Ă���B40���~30���̍L��������B
���̐����{�s�ł���A�ȗ�5����͓y�ۏ�܂�6���قǂ̍���������B�{�s�̓����͈ӊO�ɏ������B���a30�����x���B���͍͂���2.5���̓y�ۂ�����B���̓y�ۂ��������ŕ⋭����Ă���B
�Ռ��͐��Ɠ�ɊJ���Ă��邪�A�쑤�̌Ռ��͏o����}�Ζʂł���B�������ȗ�5�ւ̒ʘH�ł������悤�ł��邪�������Ă���\��������B�����̌Ռ������������Ȍ��ł���B�o���5���قlj�����ȗ�2���i�X��ɓW�J����B�ȗւ�20���قǐ����ɓ˂��o���A5���̗������Ȃ��āA�ȗ�3�ɂȂ���B���̊Ԃ͖x��ɂȂ��Ă��邪�A�ȗ�3�ւ̌Ռ������˂Ă����悤�ł���B�܂��A�쑤���Q���������Ă��邪�A����͖{���͑ыȗւ����˂Ă����̂ł��낤�B�ȗ�3��30���l���̋ȗւł���A3��������3���̓y�ۂň͂܂��B�����͂�ԏ�Ԃł���B�����͐[��6���̖x���o�ċȗ�4�Ɍq����B�ȗ�4�͖k���ɋȂ���Ȃ��牄�т�70���~30���̍L���������A��X���Ă���B���̐�[�͓y�ۂň͂܂�A���ɓy�ۂ����x������B(�y�ۂŎՕ����ꂽ�ʘH�Ƃ����ׂ����H)���̂���̐��̊O��ł���B���͖k���猩��Ɓu�ցv�̌`�����Ă���A�S����400���ɋy�Ԓ����A�s���ł���B
�H���R�Ɠ���R�Ԃ̈ƕ��̕��R�n�B �ȗ�6�k�̓y�ۏォ�猩����x�B�[����10m���邪�M�Ž��ق�������Ȃ��B �ȗ�6�k�[�̕��R�ȌE�n�B�E�ɖx�ɖʂ����y�ۂ�����B
�ȗ�5�k���̐؊݂Ɩx�B �{�s�����B���͓͂y�ۂɈ͂܂�邪���a30���قǂƋ����B �{�s�̓y�ۂ͓������Ί_�ŕ⋭����Ă���B
�{�s�����̌Ռ����ȗ�2���猩��B �ȗ�3�A4�Ԃ̖x�B�M���Ђǂ��B �ȗ�3�̌Ռ��͖x�����˂�B
������ł����邪������̕������邽�߁A���\�L���X�y�[�X�����A���Ȃ�̐l�������[�ł���B��S�̂̋K�͂ɔ�ז{�s�͂����ɂ��������B�������n�߂ɒz���ꂽ�I���W�i���ȕ����ł��낤�B���ɌÕ��ł�����B
�퍑����ɓy�ۂ������ς��A�n�`��A����ȏ�g���͕s�\�ł������̂ł��낤�B���̋ȗւ͐퍑���Ɋg�����ꂽ�����ł��낤�B���̏�͊��q����ɉH�����ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ������A�����͖{�s�̕����݂̗̂Վ��̍Ԃ������̂ł͂Ȃ����낤���H��k������́u���S��v�������邪�A���̏�̂��Ƃł͂Ȃ����낤���H���ɂ����n�͂��邪�A�����@�ŏ����Ă����Ƃ��̏�݂̂��c���Ă��܂��B
�퍑����͊}�Ԏ��̏�Ƃ��ċ��{��ƂƂ��ɉv�q���Ƃ̍R���̍őO���Ɉʒu���邪�A��͂蕺�͈ȏ�ɋ��傷����B�������Z�����p�̏�ł͂Ȃ��������Ǝv���B���ɋȗ�6�̋��傳�Ɗs���̒P�����͑����̐l�Ԃ����[����ȊO�l�����Ȃ��B�ȗ�6�w��̑�x���S�z���̗̖��̗͂����グ�����̂ł��낤�B�@ |
|
���N��镔��_�Ё@�@�@����s�镔
|
�V�ƍc��_�A�؉ԍ��v��P���A�V��͗Y���Ȃǂ̏��_���J��_�Ђł��B
�i�s�V�c�̎���ɓ��������̕�����ڂ����J�����Ƃ����`��������܂��B
��X�ˎ�̐��q�����ق��A��������̎Q�w���܂����B
�ؑ��̍����͌��̕������Ɏw�肳��Ă��܂��B
���̐_�Ђ́A���̎Q����_�Ђ���������u�̎Ζʂɑ����̎R���������A���̖����Ƃ��čL���m���Ă��܂����B
�����̎R���͓��k�n���ɎY���锒�R���ŁA�W�g�F�̉Ԃ���łȂ���Ԃ��̎����̐ԉ�������ŁA�w�p�I�ɂ��M�d�ȑ��݂Ƃ���Ă��܂��B
���ɂ���镔����������܂��ӈ�т͍��́u�����v�Ɏw�肳��Ă���A�܂��A�_�Ћy�ь����ɂ���������̓V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B
���̒n�́A�×������̖����Ƃ��Ēm���Ă������Ƃ���A�]�ˎ���ɂ͗�㏫�R�ɂ����c���A�ʐ�㐅�ȂǍ]�˂̉Ԍ��̖��������ۂɐA������܂����B
���ˎs���𗬂�����́A���̐��ˌ����������n�̍����C�ɓ���A���̕c�𐔕S�{�ڐA�������Ƃ��@�ɍ���Ɩ����������̂Ɠ`�����Ă��܂��B
���w�ȁu����v
�w�ȁu����v�͍��̖����n�Ƃ��Ė������镔��т�����ł��B���������1438�N�ɟN��镔��_�Ђ̐_��镔�S�s(�����ׂ����䂫)���A�����̊֓�����((����Ƃ�����ꂢ)���ۂ͊��q����(���܂��炭�ڂ�))�ł�������������(����������������)�ɁA�Ԍ����u�N������v(�����炱���̂�����)�ꊪ�����サ�܂����B���̕����ڂɂ�����Z�㏫�R�����`��(���������悵�̂�)���A�����팳���ɍ�点���̂��w�ȁu����v�ł��B�헤�Ɖ����̍��i�ɂȂ���������̎q�A���q�̎�̕���ŁA��q�̈����Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B
�`���炷���`
��B�̓�����(�{�茧)���̔n��̐��ɁA��ЂƂ�q�ЂƂ�̕n�����Ƃ�����܂����B���̉Ƃ̎q�E���q�́A�����̐l���l�ɂ킪�g��A�����Ǝ莆���ɓn���Ă���Ƃ��̂ݍ��𗧂��܂��B���̎莆��ǂ�́A�Q���߂��݁A�q�̍s����{�����ɏo�܂��B���ꂩ��3�N�A�����헤��(��錧)�ō��q�͈镔���ɒ�q���肵�Ă��܂����B�t������̍��̋G�߁A���q�͏Z�E�Ƌ��ɉԌ��ɏo�����܂��B���x���̍��A����̂قƂ�ɂ́A�������H�̖��A�����ƂȂ������q�̕�e�����ǂ蒅���Ă��܂����B����ɎU��Ԃт���������āA�������L�l�������鏗�����邱�Ƃ����Z�E�������Ăяo���Ė���ƁA��B����͂��䂪�q��T���ɗ������Ƃ����܂����B����M���邢���A�䂪�q�̖������q�ł��邱�ƂȂǂ����A�z�����点�ċ����̋ɂ݂ƂȂ��Ă����̂ł��B�Z�E�́A�A��Ă�����q���������킹�܂��B��l�͊����܂ɂ���A��͐��C�ɖ߂�A�A�ꗧ���č��ɋA��܂��B��ɕ���o�Ƃ��āA���̌b�݂����Ƃ���A�e�q�̓��͖{���ɗL��Ƃ������P������܂��B �@ |
|
�����c�_�Ё@�@�@����s���c
|
�Â��͌o�Î�_�ƕ��P�Ɛ_�A�C���ˎ�_�̎O�����J�荁��_�ЂƏ̂��Ă������A�����_�Ђ����J���Č��c�_�ЂƉ��̂����Ƃ̂��Ƃł���B�܂����B�����Ɍ��������`�Ƃ����_�Ђɗ���������Ƃ̌����`�������邻���Ȃ̂ŁA�i�ێO�N(1083)�ɂ͊��ɂ������ƌ������ƂɂȂ�̂��낤�B��q�����_�̈ē��ɂ͌��`�Ƃ�����������̂�1090�N(�����l�N)�ƋL����Ă��邪�A��O�N�̖���1083�N����1087�N(�������N)�܂ł̊ԂȂ̂ŁA1090�N�ɗ������ƌ������Ƃ͖����Ǝv���̂����ǂ��Ȃ̂��낤�B
����_�u�O�v
��_�u�O�v�́A�������Z�Z�N�Ɠ`������B��Z��Z�N�A���`�ƌ������̓r�����ЂɋF��A���̐܁A���̟O�߂āu��������o�肵�O�̎O�̞��ɁA�݂̒X�̋v������ׂ��v�Ɖ̂��r����ꂽ�B�܂����������̋L�^�ɂ��A�u������O�\�āA���r����O�}�ɂȂ��ē�����A���������ցw����x�ƌĂԁB�����V�F�J�̍ہA���̐������݂����ƌ��K������B�v�Ɨ��l�ɐ��߂�ꂽ�B(�ȏ�Г`�A���_�Ўj�ɂ��)�������A�ϔN�̕��J�ɑς��Ē��ÖƂȂ���ߔN�����₩�ɐ����A�������N�t�����S�Ɍ͂�ʂĂĂ��܂��A䢂ɐ��h�҈ꓯ�����荪������Ă�ۑ����A�㉮�ɂĕ����A��_�u�O�v�̗��j�𖢗��i���㐢�ɓ`��������̂ł���B�@ |
|
���_�Ё@�@�@����s�������H���R
|
�Ր_�@�q���(�����݂̂��܂݂̂���)�@�_�c�ʖ�(�ق킯�݂̂���)
�H���_�Ђ͎鐝�V�c��㕽�萷�A�����哢���ɑ���Ȃ�������ӂ��ĕ��J�����Ɠ`������B�����{�͋Ԗ��V�c��㗢�l�����J�A����6�N4�����Ђ��������ē_�ЂƂȂ����B
�@ |
|
�������_�Ё@�@�@����s�^�ǒ���J�L
|
����2�N(1162)�A���P�Ɩ�(�����݂��Â��݂̂���)���Ր_�Ƃ��đn�����ꂽ�Ɠ`������ÎЂł��B�V���N��(1573�`92)�̓��D�ɂ��A�^��17������Y��v���E18���厁�����q���[���������A��j���Ă����Гa���ċ������Ƃ������Ƃł��B
���Гa�́A�����������炵�āA�]�ˎ��㒆���E���\�N��(1688�`1704)�̍Č��Ƃ݂��Ă��܂��B
���z�l���́A�D���Ȉ�ԎЗ����ŁA�d���Ȋ��������ɓ���������܂��B�@ |
|
���卑�ʐ_��(�������ɂ��܂���)�@�@�@����s
|
�Ր_�@�卑�喽
���͖̂��_���܁B�����͎����喾�_(�������_)�B������(�헤���^�njS�A����)�B���Њi�͋��ЁB�����̂ő嚠�ʐ_�ЂƂ��\�L����B
�n���͕s�ځB�Г`�ł͗{�V�N��(717-724�N)�̑n���Ƃ��Ă���B����ɓV���N��(824-834�N)�Ƃ�������B
�Z���j�y�щ��쎮�_�����ɋL�ڂ�����ÎЂł���B
�������{��I / ���Z�B�m���V�c�̑�A���a4�N(837�N)3���A�V���S���u�\�_�ƂƂ��Ɂu���njS�嚠�ʐ_�v�Ƃ��āu���a���ЁB�Ȕ�N���L��鄖�v(�쌱�r����ł��������߂Ɋ��Ђɗa��)�Ƃ���B���\�܁B��12�N(846�N)�A�u����헤���وʑ嚠�ʐ_�n�܈ʉ��v(�]�܈ʉ���������ꂽ)�B
�����{�O����^ / ���܁B���a�V�c�̑�A���3�N(861�N)9���A�u���헤���n�܈ʉ���ʐ_�n�܈ʏ�v(�]�܈ʏ�ɏ���)�B���j���̂����A�B����{�O����^�͐_�����u��ʐ_�v�Ƃ��Ă��邪�A���̐_���嚠�ʐ_�Ɠ���_�ł��邩�͂͂����肵�Ȃ��B��錧���ɂ́u��ʐ_�v�̔��Ђ��̂���_�Ђ�3�Б��݂��邽��(�g�c�s�̎�ΐ_�ЁA����s�̊���_��q�_��ʐ_��)�A���{�O����^�̌��ݎЂƂ��Ă͘_�Ђł���B
�����쎮�_���� / ����5�N(927�N)�A�헤���^�njS������u�嚠�ʐ_�Ёv(�헤��28�Ђ̈��)�B
���\12�N11��(1699�N)�A���ˌ������A�l�_�̔��A�����̔��g���[�B
����6�N4��(1872�N)�A����i�B
����4�N10��(1992�N)�A�Гa���C�B
�Â��n���ɂ͖����u�卑�ʎ���v�Ƃ��āu�{�O�̈�A�v�X�È�A�M�\�O��A�@�̈�A����A����Ĉ�A�������v�̏Љ����B �@ |
|
���@�_�Ё@�@�@����s�卑��(�؍�)
|
�Ր_�@�{�����������@�N�̌�O
��_�́@�ؑ����l��
�@�_�Ђ̌�_�̂̌܈ߐ����̏��l�ؑ��͍����_�Ђ̏��呜�Ƒ��Ȃ������H
����s�卑�ʒn��̑卑�ʐ_�Ђ̎�Ɏ҂́A���̒n���ɐ��͂����^���ŁA���̖�������̍ȁu�N�̌�O�v�ł��B��������V�c�����̂����̂ŌN�̌�O���@�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B
�����ɍ@�_�Ђ̂��_�̂́A���t�̏��u����̍ȁv�Ȃǂł͂Ȃ��A�卑�喽�̍@�u�{�����������v�ł͂Ȃ����Ɛ��˔ˎm�R�������f�肵�A�؍�̒n���ڂ��卑�ʐ_�Ђɍ��J�����悤�ł����A���̔N�A���ɉu�a�������A�؍�S�˂ɋy���߁A���l�͏��傳�܂��M��Ƌ���A�@�_�Ђ����ɖ߂������߂��Ƃ���A�u�a�͂����ǂ���ɐ₦�A���ɕ��a���߂����Ƃ����܂��B
�卑�ʐ_�Ђ͒j�̋{�Ə��̋{�ɂ���Ј���������A�����̏��߂ɂ͒j�̋{�����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����̂́A���J�������@�_�Ђ����ɖ߂�������Ȃ̂�������܂���ˁB
�؍�̒n���͍@����̂悤�ŁA�����t���̂��镽�̒n���͕����J����������B���ۖɂ͏�����̏o�邪�������Ƃ̓`�����B�����̂���O��n��́A�邩���傻���ĎO��ɂȂ����悤�ł��B�@ |
|
�������_�Ё@�@�@����s�^�ǒ��R��
|
�����_��(�����傱�܂���������)�́@�Г`�ɂ��A�������㖖���Ɏ����_�{�̌�Ր_�A���P�Ɩ�(�����݂��Â��݂̂���)�̕�����J��A�^�ǎ��̎��_�Ƃ��đn�����ꂽ�ƌ����Ă��܂��B
�^�Nj_���Ղ͕��������A�L�^�쐬���̑[�u���u���ׂ����`�̖����������ɑI�����ꂽ�A400�N�̗��j����Ղ�ł��B���N7��23������26���܂�4���ԁA�����������Đ���ɍs���܂��B�܂��A8��31���͂������čՂ肪�J�Â���܂��B�܍��L�����F�肷�邨�Ղ�ł��B�@ |
|
���^�Ǐ�(�܂��ׂ��傤)�@�@�@����s�^�ǒ��Ï�
|
�헤���^�njS�A���݂̈�錧����s�^�ǒ��Ï�ɂ������퍑����̓��{�̏�(����)�B�坁���̈ꑰ�ł���^�ǎ�����X�x�z�����B���̎j�ՁB
�^�ljw�Ղ̓��Ɉʒu���A���g�R�n�̑����R���[�ɂ����n��ɒz���ꂽ�A�s���̕���ł���B�܂��A�Ñ�̐^�njS�Ƃ����݂����Ƃ������A�^�njS�̒��S�n�Ɉʒu���Ă����B
�����̖{�ۂS�~��Ɉ͂ޓ�m�ۂ�����ق��A��m�ۂ̓����ɎO�̊s(����)�E�l�̊s(�O�s)�������A�O�s�쓌�[�ɂ͎����_�Ђ��Ղ��Ă���B
�z��͏���2�N(1172�N)�Ɠ`���B�坁�����̎q�E�������^�njS�ɓ����Đ^�ǎ��𖼏��A�S�Ƃ̏ꏊ�ɒz�邵���B�ȗ��^�ǎ��̋���Ƃ��đ������B
������Ő^�Ǐ邪���o����̂͋���2�N(1341�N)12���ŁA�k���e�[�́u�����X�v�Ƃ��āA�^�Ǐ邪�݂��A�쒩���̏�ł������B�̂��k�����ɗ����ς��A�^�ǎ��͒n���E��L���Ă���B���i30�N(1423�N)�A�^�njc���̂Ƃ����I���d�̗��ɏ��I���ŎQ���������ߑ��������R�ɂ���ė��邵�����A���̌�̍����̒��Ōc���̏]�Z��E�������^�ǂɕ��������B
17��v���̂Ƃ��Ɏ��j�`�����`����ɕ��Ƃ��A18�㎁���Ɏ����ĉ��̊`�����[��(�`���̎q)�ɉƓ����������߁A�^�Ǐ�͐^�ǖ{�Ƃ̏�ł͂Ȃ��Ȃ����B���̌�A�c��7�N(1602�N)���|���̏H�c�]���̍ہA���|���̉Ɛb�c�����Ă����^�ǎ����o�H�p�قֈڏZ���A�^�Ǐ�͋��ƂȂ����B���̂̂��c��11�N(1606�N)��쒷�����B�����Ƃ��Đ^�ǔ�5����^�����A��16�N(1611�N)�ɒ����̐Ղ��p���Ő^�Ǐ�ɐ�쒷�d�����邵���B���a8�N(1622�N)�A��쒷�d�͉�������A�^�ǂ̗͗L����������̂̏헤�}�ԏ�ֈړ��ƂȂ�A�^�Ǐ�͔p��ƂȂ����B
���̂������傪�e�X��A�y�@������(����a���A�`����)�E�l��\��(�����a��)�Ƃ��Ĉڒz���ꌻ�����Ă���B�꒣��͖{�ۈȓ��͗ǍD�Ɏc�邪�A��̊ۂ̐����Ȑ��͂قڎs�X�n�������ł��Ă���B�{���͐^�ǒ��Ï�n�悪���̐������ɓ�����B�Ï�n��̐��ɑ��O�̒n�����c���Ă���A���n�ߕӂ���肾�����Ɠ`����Ă���B�{�ېՂɂ͋��^�ǒ����̈�ق�����A��̊ېՂɂ͑̈�ٌ��݂ł̎c�y�������Ă���Ȃǒ������̕ۑ���Ԃ͗ǂ��Ȃ�(��̊ۂɂ͘E��̂悤�ȍ��������邪�A�c�y�̎R�ň�\�ł͂Ȃ�)�B
1934�N(���a9�N)�ȗ��A�{�ۂ̈ꕔ����錧�w��j�ՂƂȂ��Ă������A1994�N(����6�N)10��28���ɍ��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B
1997�N(����9�N)�ȍ~���@�������������Ă���A���ʂɊ�Â��O�ȗւ̓y�ۂ⍈����������Ă���B�܂�����̔��@�����ł́A���H��r����K�͂Ȓ뉀�̈�\�Ƌ��ɁA������\����Ǝv���錚���Q�̍��Ղ����o����A���̋K�͈͂�錧���ł��ő勉�ƌ����Ă���B �@ |
|
���J���珟�_��(���܂т���������)�@�@�@����s�{��
|
�n���͑哯2�N(807)9��29���A�珟������㓡�����肪������芩��
���O3�N(1333)�A��ؐ����͑�Q�𗧂Ăĕ��^���v�̋F��������Ƃ���A�쌱�����芙�q���{��łڂ������o�����̂ŁA�{�a�C�����e���̒��������
����3�N(1646)�A�Ђɂ��Гa�Ď�
���\9�N(1696)���_�ł̎З̂�3��
�]�ˊ��ɂ͊}�Ԕˎ�E�q�쎁�ɂ�萒�h����A��X�����閈�ɕ��^���v���F�肵���Ƃ���܂��B
����6�N(1873)�A���܂Ő珟�喾�_�Ə̂��Ă������J���珟�_�Ђɉ���
�܂��A���N�ɑ��З�i
��Ր_�͉��c�F��
���̏헤�������A�쒩���̏邪����������܂��Ă�������̐^�ǂɂ͐^�Ǐ邪����A�쒩���̊֓��Z���1�Ƃ���܂��B�֓��Z��́A�헤���֏�(�}���s)�E�헤������(���Ȏs)�E�헤���ɍ���(�}���s)�E�헤�����S��(����s)�E���썑��������(�v�q��)�ƂȂ�܂��B
�܂��A����3�N(1336)�ɓ�ؐ����͏헤���Z�A(�߉ώs)��̒n�Ƃ��ė^�����Ă���A�����̒�Ƃ�������ؐ��Ƃ��㊯�Ƃ��Ĕh�����ꂽ�����ł��B�����ʼnZ�A���z���k�����ł��������|����1�N�]�������Ƃ���܂��B���̎�����A�쒩�̐��͌��ł������^�ǒn��Ə헤�ɉ������Ă�����؎����q����A�R���ɂ��镐�^���v���肢�e����̂����肪�M�ߐ��������̂ł͂Ȃ����ƁH
�珟������オ�������犩���ƗR��������܂����A�헤���ł��Ǝ����������_�{�Ȃ̂ł����c������̌�Ր_�͉��c�F���A�����_�{�͕��P�Ɩ��ƈႢ�܂��B�����_�{�ɂ͍��J������Ă��炸�ۖ��Ђɂ����c�F�����J��_�Ђ͖����c�ł����A�����̗R���Ŕɂ͓��ē��̐_�Ƃ��ĉ��c�F�����Љ��Ă��܂��B
�����n��œ��ē��̐_���J��_�ЂƂ����A�_���s�ɒ������Ă��铌���O�Ђ�1�ł��鑧���_�ЁA������͊�_����Ր_�Ƃ��Ă��܂��B���̊�_�A���̐_�Ƃ��ĉ��y�V���_�≎�c�F�_�Ɠ������̂Ƃ���鎖������܂��B
�Ƃ�����Œf��͂ł��܂������_�Ђ��犩�������\���͑傢�ɂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@ |
|
���}�Ԏs |
|
���H���R�_��(�͂Ȃ���܂���)�@�@�@�}�Ԏs�㋽
|
�Ր_�͖؉ԍ��P���B�헤�����S�̎������ЂŁA���Њi�͋��ЁB
�Â��͉H���R�̒����ɒ������Ă����B �V�q�V�c3�N(664�N)�A���̑����H���R�̒����ɖ؉ԍ��P�����J���K�������������ƂƂ����������ɁA�u�Ԕ��R�_�Ёv�ƌĂ��悤�ɂȂ����B
����22�N(803�N)�ɂ͍��c�����C�����������̐폟�F�肵�A�Гa����i�����B
������̗��ł́A���吷���|��A�������[���A�����吪���̐폟�F��������B
��������ɂ͌����`�A���`�Ƃ����A�����A�Z�A�_�n���[�����B�_�n�̓��̂�������B ���q����ɂ͊��q����ڂ�Z���ˉƐ����Гa�����đւ���B
�V��11�N(1542�N)�ɂ͕��ɂ��H���R�̒����̎Гa���Ď����A���݂̒����n�ƂȂ�R�[�̌F�쌠���ɍ��J���ꂽ�B����8�N(1668�N)�ɂ͎Гa���V�����ꂽ�B ���\16�N(1703�N)�ɂ͌��݂̖��_�Β����A����4�N(1747�N)�ɂ͌��݂̎Гa�����������B
��������̐_�������߂ɂ��A�ʓ����̕����@�̊Ǘ����痣���B �@ |
|
����c�_��(���Ȃ�����A�j�c�_��)�@�@�@�}�Ԏs��c
|
������(���_���)�ŁA���Њi�͌��ЁB
��Ր_�@���c�P�� (�������Ȃ��Ђ߂݂̂���)�@���J�_�@�z�s��_�A�������^���A��R��A���孁�M���A����1�� 5���Ƃ��A����6�N(1873�N)�ɍ��J�B
���n��
�n���͕s�ځB�w��c�P�{�_�Љ��N�x(�]�ˎ���)�ɂ��ƁA���n�̗W�������̉Ɠ�����c�D��̐����������Ƃ���ƁA��̖T��ɏ��������ꂽ�B�Ɠ��̒m�点�ŕ������q�˂�Ɓu�����͊��c�P�œ��n�̒n��_�ł���v�Ɠ����A�P�̕���̋{�E�v�w�̋{�����āA�D��̐��ň������J��悤�_�����������Ƃ����B���Ђ̖k��300���[�g���̈�c�R�����ɂ͖{�{(���̉@)���������邪�A�{�{���K����ɂ͋����˂��o�Ă���A���̔֍�����c�P�̍~�Ւn�Ɠ`����Ă���B
�܂��A���Ђ͐V����������ւ����_�Ђƍl�����Ă���B�V�������͗��ߐ��ȑO�ɐV���S�n������߂��Ƃ���鍑���ŁA�w��㋌���{�I�x�u�����{�I�v�V���������ɂ͔��s�C�̎q�̔�ޗ��z�������㍑���Ƃ���|�̋L�ڂ�����B���s�C��(��s���ꖽ)�͓V������̔������ŏo�_�����Ɠ��c�ɂ��邪�A���Ў��ӂɂ͎����ЂƂ��č��u�\�_�ЁE����_��q�_��ʐ_�ЁE�卑�ʐ_�Ђ�����A��������o�_�n�̐_�X���J�邱�Ƃ��當���Ƃ̊W���w�E�����B
���T�j
�Z���j���̐��j�ɂ͓��ЂɊւ���L�ڂ͂Ȃ��B�������㒆���́w���쎮�x�_�����ɂ͏헤���V���S�Ɂu��c�_�� ���_��v�ƋL�ڂ���A���_��ЂɗĂ���B
���q���㏉���A�̎�̊}�Ԏ����͓������r�E�j��8�l�������ē��Ђŕ�[�̉���Â��Ă���A�w�V�a�̏W�x(�F�s�{�V�a�̏W)�ɂ��̉̂̋L�ڂ�����B
�������㖖���ɕ��ɂ��Гa���Ď��A�c��7�N(1602�N)�Ɉɓޒ��������n�����n�����ۂɖ{�a�����Č����ꂽ�B����8�N(1668�N)�ɂ͔ˎ�̈�㐳�������n4��^�����B���\7�N(1694�N)�ɂ͓�����������ЂɎQ�w���A�ÎЂ̐�������l�q��Q���A���N�����[����(�Е�̎l�_���͌��\11�N(1698�N)�̕�[)�B�Гa�͍O��2�N(1845�N)�ɏĎ����A�Éi���N(1848�N)�Č�����Ă���B
�����ɓ���A�ߑ�Њi���x�ł͌��Ђɗ��B �@ |
|
�������s |
|
�������_�{(�����܂����A�����_�{)�@�@�@�����s�{��
|
������(���_���)�A�헤����{�B���Њi�͊�����ЂŁA���݂͐_�Ж{���̕ʕ\�_�ЁB�S���ɂ��鎭���_�Ђ̑��{�ЁB��t������s�̍���_�{�A��錧�_���s�̑����_�ЂƂƂ��ɓ����O�Ђ̈�ЁB�܂��A�{���̎l���q�ŗy�q������Ђł���B
��錧�쓌���A�k�Y�Ǝ�����ɋ��܂ꂽ������n��ɒ�������B�Â��́w�헤�����y�L�x�ɒ������m�F����铌������̌ÎЂł���A���{�_�b�ő卑��̍�����̍ۂɊ��镐�P�Ɛ_(���䗋�_�A�^�P�~�J�d�`)���Ր_�Ƃ��邱�ƂŒm����B�Ñ�ɂ͒��삩��ڈ̕���_�Ƃ��āA�܂����������玁�_�Ƃ��Đ��h���ꂽ�B���̐_�Ђ͒����ɕ��Ƃ̐��Ɉڂ��ĈȌ�������A���̕��Ɛ�������͕��_�Ƃ��Đ��h���ꂽ�B���݂������ł͓Ă��M�����_�Ђł���B
�������̂����ł́A�u韴�쌕(�ӂ݂̂��܂̂邬)�v�Ə̂���钷��Ȓ���������Ɏw�肳��Ă���B�܂����������̎j�ՂɁA�{�a�E�q�a�E�O��ȂǎГa7�������̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���ق��A�����̕����������݂ɓ`���Ă���B����_�g�Ƃ��邱�Ƃł��m����B
����
�_�{�͏헤�������S�̒n�ɒ������邪�A���̒n���u�J�V�}�v�́A�w�헤�����y�L�x�ł́u�����v�ƋL�ڂ����B���y�L�̒��ŁA�u�����S�v�̖��̂́u�����̓V�̑�_�v(�����_�{���w��)�Ɋ�Â��Ɛ�������Ă���B�u�J�V�}�v���u�����v�ƋL���������͗{�V7�N(723�N)�ł���A8���I�����ɂ́u�����v����u�����v�ɉ��̂��ꂽ�ƌ����Ă���B���̕ω��̗��R�͎j������͖��炩�łȂ����A�_�{���ł͐_�g�̎��ɗR������Ɛ�������B���́u�J�V�}�v�̗R���ɂ͏���������B��Ȑ��͎��̒ʂ�B
�u�_�̏Z���v���Ȃ킿�u�J�X�~�v�Ƃ����
���؊Ԗ�(���������܂݂̂���)����u�J�V�}�v��������Ƃ���� ���؊Ԗ�(���ؔn��)�́A�w��㋌���{�I�x�����{�I�ɏ��㒇����(�߉ύ���)�Ƃ��āA�܂��w�헤�����y�L�x�ɋL�q��������l���B
�u�D���~�߂�Y��łꏊ�v���Ӗ�����u�J�V�V�}�v�Ƃ���� �w��O�����y�L�x�Ɂu�n��(������)�v�̗R���Ƃ��Č�����L�q�Ɋ�Â����́B
�Ȃ��A�_�{�ł͌��ݎЖ��Ɂu���v�̎���p���Ă��邪�A�����̂̈�錧�����s�͍��ꌧ�����s�Ƃ̋�ʂ̂��߁u���v�̎����g�p�����B
|
���Ր_
�Ր_�͎���1���B
���P�Ƒ�_(�����݂����̂�������/�����݂��Â��̂�������) �w�Î��L�x�ł́u���䗋�_�v�A�w���{���I�x�ł́u���P�Ɛ_�v�ƕ\�L�����B�ʖ����u���z�s�_(�����ӂ̂���)�v��u�L�z�s�_(�Ƃ�ӂ̂���)�v�B
��L�̂悤�ɁA�����_�{�̎�Ր_�̓^�P�~�J�d�`(���P��/���䗋)�ł���Ƃ����B�^�P�~�J�d�`�̏o���ɂ��āA�w�Î��L�x�ł́A�Ɏדߊ�(�ɜQ����)���ΔV�ދ�y�_(�e���˒q)�̎��藎�Ƃ��A���ɂ���������ɔ�юU���Đ��܂ꂽ3�_�̂�����1�_�Ƃ���(���{���I�ł͂����Ń^�P�~�J�d�`�c�̃~�J�n���q�����܂ꂽ�Ƃ���)�B�܂��A�V���~�Ղɐ旧������������ɂ����ẮA�A���m�g���t�l(�V���D�_�F�Î��L)�܂��͌o�Î�_(���{���I)�ƂƂ��Ɋ����Ƃ����B���̌�A�_�������ɍۂ��ă^�P�~�J�d�`�͈ɔg�����(�_���V�c)�ɐ_��(�z�s�䍰)���������B�������w�Î��L�x�E�w���{���I�x�ɂ͎����_�{�Ɋւ��錾�y�͂Ȃ����߁A�^�P�~�J�d�`�Ǝ����Ƃ̊W�͖��炩�łȂ��B
����A�w�헤�����y�L�x�ł͎����_�{�̍Ր_���u�����̓V�̑�_(�����܂̂��߂̂�������)�v�ƋL���A���̐_�͓V���̓����ȑO�ɓV���牺�����Ƃ��A�L�I�̐��b�Ɏ����`�����L���B�������Ȃ���A���y�L�ɂ����̐_���^�P�~�J�d�`�ł���Ƃ̌��y�͂Ȃ��B
�u���V�̌����~(����)�藈(����)�肵��_�A��(�݂�)�������V�̑�_�Ə�(�܂�)���B�V�ɂĂ͂��Ȃ͂����̍����̋{�ƍ�(�Ȃ�)���A�n(��)�ɂĂ͂��Ȃ͂��L�����̋{�Ɩ��Â��B �w�헤�����y�L�x�v
�_�{�̍Ր_���^�P�~�J�d�`�ł���ƋL���������̏����́A�w�Ì�E��x(807�N����)�ɂ�����u���P�Ɛ_�]�X�A���헤�������_����v�Ƃ����L�q�ł���B�������A�w���쎮�x(927�N����)�́u�t���Տj���v�ɂ����Ă��u����������ꓤ�q���v�ƌ����邪�A���́u�t���Տj���v�͏t����Ђ̑n���Ƃ�����_��i�_2�N(768�N)�܂ł����̂ڂ�Ƃ�����������B�ȏ�Ɋ�Â��A8���I����̉ڈΕ��肪�i�ނɂ�Ēn���_�ł������u�����_�v�ɒ����_�b�̌R�_�ł���^�P�~�J�d�`�̐_�i��������ꂽ�Ƃ����������ق��A�����̍�����_�b���̂��헤�ɉ������u�����_�v�����b���ɂ���Ċ��荞�܂�č��ꂽ�Ƃ�����������B
�_�{�̍Ր_�́A�^�P�~�J�d�`�����y����Ɋ����Ƃ����L�I�̐��b�A������������Ƃ������y�L�̐��b����A���_�E�R�_�̐��i�����ƌ��Ȃ���Ă���B���ɕʏ́u�^�P�t�c�v��u�g���t�c�v�Ɋւ��āA�u�t�c�v�Ƃ����ď̂͐_���̃t�c�m�~�^�}(�z�s�䍰/韴��)�̖��Ɍ�����悤�Ɂu�����̉s���l�v��\�����t�Ƃ���邱�Ƃ���A�������ے�����_�Ƃ����������B�����_�{���R�_�ł���Ƃ����F����\�����̂Ƃ��ẮA�w���o�鏴�x(�������㖖��)�́u�ւ�蓌�̌R�_�A�����E����E�z�K�̋{�v�Ƃ����̂��m����B����A�D��[�߂������Ƃ������y�L�̋L�q����q�C�_�Ƃ��Ă̈�ʂ�A���J�W�c�̖m��������@�����Ƃ������y�L�̋L�q����_�k�_�Ƃ��Ă̈�ʂ̎w�E������B�ȏ����Ղ��āA�R�_�E�q�C�_�E�_�k�_�Ƃ����������I�Ȑ��i�������Ă����Ƃ����������B
|
�����_�{�́A��������{�̍���_�{(��t������s�A�ʒu)�ƌ×��[���W�ɂ���A�u�����E����v�ƕ��я̂�����̑��݂ɂ���B
�����E����̗��_�{�Ƃ��A�Â���蒩�삩��̐��h�̐[���_�Ђł���B���̐_�Ђ́A���_�{���R�_�Ƃ��ĐM���ꂽ���Ƃ��w�i�ɂ���B�Ñ�̊֓������ɂ́A���݂̉����Y(���Y�E�k�Y)�E����E�������܂ވ�тɍ���C�Ƃ������C���L�����Ă���A���_�{�͂��̓������N����n���w�I�d�v�n�ɒ�������B���̍���C�̓��}�g�����ɂ��ڈΐi�o�̗A����n�Ƃ��ċ@�\�����ƌ����Ă���A���_�{�͂��̋��_�Ƃ���A���_�{�̕���͒���̈Ђ������_�Ƃ��ē��k���ݕ��̊e�n���J��ꂽ(��q)�B�����_�{�̎Гa���k���������Ƃ��A�ڈ��ӎ����Ă̔z�u�Ƃ�����B
���삩��̏d�v�����������̂Ƃ��ẮA���Ɏ����悤�Ȏ��Ⴊ��������B
�Z �_�S�@�����E���旼�_�{�ł͂��ꂼ��헤�������S�E����������S���_�S�A���Ȃ킿�S�S�̂�_�̂Ƃ���ƒ�߂��Ă���(�ߏW���≄�쎮�ɋL��)�B�_�S��L�����_�Ђ̗�͏��Ȃ��A��������R����E��ʏ�̏d�v�n�ł������Ƃ����B
�Z ��������g(�����܂��Ƃ�Â���)�@���_�{�ɂ́A���N���삩�璺�g�Ƃ��Ď����g(�����܂Â���)�ƍ���g(���Ƃ�Â���)�A�܂��͗����Ď�������g�̔h�����������B�ɐ��E�ߋE�������n���̐_�Ђɂ����āA����I�Ȓ��g�h���͗��_�{�̂ق��͉F���_�{(6�N��1�x)�ɂ����Ȃ��A���N�̔h���������������E���旼�_�{�͋ɂ߂Ĉٗ�ł������B
�Z �u�_�{�v�̌ď́@�w���쎮�x�_����(��������̊��Јꗗ)�ł́A�u�_�{�v�ƕ\�L���ꂽ�̂͑�_�{(�ɐ��_�{���{)�E�����_�{�E����_�{��3�Ђ݂̂ł������B
�܂��A����������̐��h��������1�ł���B�����ɂ͓������O�g�̒��b���Ɋւ���`���������c�邪�A�������c�̓����������܂��헤�Ƃ̊W���[���A�w�헤�����y�L�x�ɂ��Ə헤�����ɂ͊���(��������b)�̕��˂��݂����Ă����B�܂��w�勾�x(����������)�������Ƃ��Ċ����̏헤���o����������A�_�{���O���Ђ̒Ó����АՋ߂��ɒ������銙���_��(�����s�w��j�ՁA�ʒu)�͂��̏o���n�Ɠ`������B�������̎��ЂƂ��đn�����ꂽ�ޗǂ̏t����Ђł́A�����_�����a�A����_�����a�Ɋ���������J���A�������̑c�_����V��������(��O�a)������ʂɈʒu�Â���ꂽ���A�V���������̕������䗋�_�Ƃ����������A����ɏ]���Ό��䗋�_�͒��b���̏�c�ƂȂ�B
���̌�A�����ɕ��Ƃ̐��ɓ����Ă�������_�{�͕��_���J��_�ЂƂ��ĕ��Ƃ���M���ꂽ�B����ł����p���ʂ���M�͋����A����ɂ́u�����喾�_�v�E�u����喾�_�v�Ə����ꂽ2���̊|�����Ōf�����邱�Ƃ������B
|
�������̎O�ԑ��q
�X�́A�q�̂ق��ɂ��A�{���̋ȗւ𒆐S�Ƃ��āA�������̂��A�����ɂ������B���ł��A��ɉ�������悤�ɁA�Ƃ��������A�|�q�▵�q�̋߂��ɂ���A��������̉X�Ƃ��ł����B
���̌I�т́A�v�͂₢���A��▵�̌��ɂ��A�����낢�����͂Ȃ��B���n�̑������邼�A�e����₷�ȁ\�\�ƁA���̗ǎ����A�\�N�̗]�����悵�Ă����Ĕn�̔w�ɁA�����Y�́A�Ȃ�̊������Ȃ�������B
�Ƃɂ́A���̐H�Ƃ��Ă��A�J����A�S�i�̗���ə�Ƃ��߂�ꂽ���Ɏ����ːЂ̌����A�ꑩ�ЂƂ��̋|���������킢���āA�L�c�̊ق������o��Ƃ����̍⓹�ցA�ӋC�g�X�ƁA�~��čs�����B
�ǂ����ŁA�ڈΔ��̊炪�A�������������Ă���悤�ȋC���������A�U�����Ă��A���ł��A�s���ĂɓW�Ђ炯���K�����Ȃ��߂Ă��A�ǂ��ɂ������Ȃ��B
�\�\�E����܂���B�������ʂ�ƁB
�ƁA����ȂɔM�����ł����₩�ꂽ�̂ɁA�ނ̓��ɂ́A�����̎����A�����Ƃ��A�l���o����ė��Ȃ������B���X�����ʕ��̂悤�ȓ����т��́A�������k������Ă��钖���̍������́A�L���L���ƑO���������܂������̎��̐O���Ƃ��́A����Ȃ��̂����]���Ɏʂ��ė��Ȃ��B
���A��A�܂����A�������̎��n�B�D��̓��ł���Ȃ��̂́A���������B�����̉��������܂���A�����̊����������A��ʂ������܁A�����������̕��p���Ƃ��ĕ������Ƃ���A��͂⏬�����͂́A�c�����s�Ƃ����Ă����B�Ⓦ���Y�ƌh�̂���嗘���̓����𒆐S�Ƃ��āA���͐Ö��̂悤�ɗ���Ă���Ƃ������́A���̑嗤���A�\��܂���Ă���Ƃ������������ۂ̑��������ɋ߂������B
�u�������B�L�c�̓��A�ǂ��ցA�������H�v
���̓���ځB
�����Y�́A�N���ɁA�ĂтƂ߂�ꂽ�B
�ނ́A������̐l����������ƁA�ނ炵�����Ȃ��A����ĂĔn���~�肽�B�����V�������B
�u�i�s�����䂫���܂ŁA�������܂������v
�u�a�q�킱�B������l�ŁA�ǂ��֍s���v
�u��f���̂������ŁA���̌I�т��A�^�l�t���Ɏ����čs���܂��v
�u�ǂ��̖q�ւ́v
�u���R�m�q�܂Łv
�u���A���R�ցB�a�q�ЂƂ�ł��v
�u�͂��v
�i�s���A�n�ゾ�����B������ɂ͎��A�����̏]�҂���Ă����B�c�c�s���ӂт�ȂƁA�����Y������悤�ɁA���������ƁA�n�̔w����Ȃ��߂Ă������A
�u���R�Ƃ́A��������B�����b�ォ���ɋ߂����q�R��������܂̂Ă܂��ɂȂ�B�킵�͔��Ђ��̌S�i�̒��܂ōs���Ƃ��낾����A���̋߂��̐����������m�q�ŁA�ǂ��n�ɁA��t�����Ă��炤�������v
�u�����܂��B�f���䂽���Ɂv
�u������A���R�m�q�̎҂ցA�قǂ悭�A�������킵�Ă����悤�ɁA�g�����o���Ă����Ă��B�坁�̍����ǂ̂ւ́A�m��ʂ悤�ɂ��Ă�邩��A�킵�̋��ɁA�������ė����v
�u�͂��B���Ⴀ�A�������܂��v
�����i�s�́A���h���Ă���l�������B�ނɂƂ��āA�ǂ�������ۂ�����킯�ł��Ȃ��������A�S���̗ǎ����A�܂߂Ă����l������ł���B���̖S���̂͂Ȃ��ł́A���̐l�́A���ł����A����ȓc�ɂ֗����ė��ď헤�̑坁���������Ⴂ�g���̒n�������߂Ă��邪�A�ق�Ƃ́A����ŁA�E��b����������ɂ܂ŏ���A�w��ł́A�����m�ł��y�Ԏ҂��Ȃ������B�������^�݂����ˌ��́A�O�Ԗڂ̎��q���Ƃ������Ƃ������B
�����̖��́A����ȉ����n���ł��A�m��Ȃ��҂͂Ȃ������B������\�O�N�O�A�}�������̔z���Ŏ���ňȗ��A�Ȃ��Ȃ̂��A�_�i������āA���߂˂A�ނ��닰�낵�����̂̂悤�ɁA��Ƃǂ낢�Ă���B
�}�g�R�̘[�ɂ́A�킸���Ȑ��Ƃ��̑������������B�i�s�́A���̈⍜�������āA�}�g�̂ӂ��Ƃ��J�܂�A���̂܂܁A�Z�݂��āA�n�������̗]���𑗂��Ă���҂��Ƃ����B
�ꎞ�A�����ς炢��ꂽ�����Ƃ̉\���A�����Y�́A����o���ɁA�L�����Ă����B�\�\�����������̂��A���R�ƁA����̌h�炯���炢�ɂȂ�A����̌��t���܂ł��A�Ă��˂��ɂ������̂������B
�i�s�Ƃ��ẮA�����Y�̗��s���A�͂āA�����������ƁA�����ɁA�^��ꂽ���̂��������̂ł���B�ǎ��̎���A�L�c�̊قɂ͂��肱��ŁA�㌩���Ă���O���̏f���������A�Ȃɂ��A�Ӑ}���Ă��邩�A�@������Ƃł͂Ȃ��B��Ɏ����̏㊯�ł͂��邪�A�坁�̕������Ȃ�l�����A�ǂ�Ȑ��i���Ƃ������Ƃ́A�����̂���������A�悭�����Ă���B
�u�킵�ɏo����āA���܂��́A���т낢�����Ă���̂����v
�i�s�́A����ƂȂ��A�����Y�ɂ����������A�����m�q�܂ŘA��čs���āA�����ł��A
�u�킵�́A���ꂩ����p�ŁA���̒��֍s���āA�̋����ɂA�邪�A���܂��́A�ǎ��ǂ̂̑��̂�����傤�A��ɒ�n�̉Ƃ̌�q�Ȃ̂�����A�g���A�厖�ɂ��˂������B�������ˁv
�ƁA���ꂮ����A�@���Ƃ����B
�u�����B�c�c����B�c�c����v
�����Y�́A���x�������Ȃ������B�����A�ǂ̒��x�A�ۂ݂��߂��̂��͋^��ł���B�ނƕʂꂽ�����A�����̌�~�̉��i�������A�ނ̎����ė����I�т̖ĂƁA�鑠�̂��˔n�Ƃ��A�_����������ƁA�����Y�́A����킷��Ē��ߓ���A�I��܂ŁA�����������A���g���A���Ԃ���݂����ɁA�M�����Č������Ă����B
|
���x�m�܂��Ⴕ
�q�ŁA��������V�сA���R�֍s�����قǓ������킴�Ƃ����āA�ނ́A�ȂɐH��ʊ�ŁA�L�c�̊ق̖{���A�����B
�u�c�c�����́A�������ɁA���R�֍s�����̂��v
��f�����A�����f�����A�������āA�ςȊ�������B���J�Ƃ��A����Ȃ������B
�헤�}�Ԃ̖k���̎R�x�ŁA�˂ɁA����̍��������ɔ��R���Ă���ڈ���̍�̎҂��A�����N�����Ƃ������n�����A�����A�ǐ������́A���ꂩ���\���قǁA�����Ȃ������B
���N�̏t�ɂ��A�H�ɂ��A�����������������B
�f���ǂ����A���Z���ƁA�����Y�́A�H��L�����B������ɁA�ڈΔ��Ɖ�@��ɂ��A�߂��܂ꂽ�B�Ɛl�����́A�ޏ��̌����˂��₵�ނ��A�ނɂ́A�Ȃ�̋�ʂ��Ȃ��B���R�A���̐^���ɔޏ��̏n���ꂽ���̂��ӖڂɂȂ����B�ڈΔ��́A�z�X�ȗւ���A�댯�ȋ��킽��A��������A���āA�^�钆�ɂȂ�ƔE��ŗ����B������q���Ă��邱�Ƃ́A�����Y�݂̓Ȑ_�o�ɂ��킩�����B�ޏ��̔������₩��ẮA�v���m�炳���ɂ����Ȃ��B
�����A���̔N�̓~�̈�邠���\�\�B����A��͖����āA���ɂ܃b���ȓ��n���Ă��̒����B
�̒�ɗ����āA�G�̎��[�݂����Ɏ���ł�������������B�ڈΔ��ł������B
�u�����Y�B���ė����v
�����f���ɓ˂��̂߂���āA�����Y�́A���ЂȂ��`���ɍs�����B�R�ۂ���A�����t���ɐA�����悤�ȕX�����̗�������̉��ɁA��Ђ̎G�Ђ�������݂����Ȃ��̂��������B�ނ́A��܂ŁA�����ɂȂ�A�O�̂ӂ邦�����܂܁A���̑��ŁA�匋�m�q�̕��ցA�z�n�݂����ɁA�����čs�����B
�������A�q�̔n�ƈꂵ��ɁA�n�[�̘m���̏�ŐQ���B
�ނɂ́A�l�Ԃ̉Ƃ��́A�n�̒��Ԃ̂ق����A���������������B
�ł���B�坁�̍����́A�ق̉��ŁA�є�̏�ɍ��肱�݁A�nj��A�ǐ��̗��f�������A���E�ɂ����āA�����Y�ւ����n�����B
�u�s�ցA�V�w�ɍs���B�l�Ԃ炵���Ȃ�悤�ɁA�w��ŗ����v
�����Y�́A�ރb����A�����ނ���ł����B�s���ƁA�Ƃ������̂��A�����f���܂ŁA�������������āA
�u�ȂA�M�l�́B�����V�c����̌���J�͂������߂₪���āA�ڈ̓z�X�ƁA���܂����ȂǂƂ́A�����ꂽ��s�҂������̂��B�\�\���A�Z�Ґl���ɂ���ЂƂɂ��A�����܂ʁB�Ƃ̂��߁A�M�l�̂��߁A�s�֏o�āA�����ė����B���h�ɁA���l���āA�l�炵���Ȃ�܂ŁA�A���ė��Ă��A�Ƃɂ͓���ʂ��v
�������ɁA����̍����A�����ƁA������ʂ�ƁA�����āA��ʂ̏���Ƃ��A�����Y�̊�̂܂��ɒu���ꂽ�B
����������Ȃ��B�����Y�́A����������āA�ނ��肩�����B
�u�҂đ҂āv�ƁA��������тƂ߂��B�u�\�\���̏�����A�r���ŁA�������܂�����B���̉E��b�A���������ӂ����̂����Ђ���ցA���ɁA�����g������������ƁA�킵����̂��肢�̏Ⴜ�B�悢���A���N�ł��A�h�����āA�����̖S�������ǎ��ցA�킵�炪������̂Ȃ�悤�ɁA�ꂩ�ǂ̒j�ɂȂ��ċA���v
���̍��́A���̎O�f���̕��̂Ȃ��́A�����Y�ɂł��A�������ǂ߂Ă���B�����Y�́A���܂���ł��@�������������A���s�֕�����邱�Ƃ́A�ӊO�Ȋ��т������̂ŁA����������]�T���Ȃ��B
��l�̖�̎��R���́A�������āA�Ƌ��痢�̑z�������鋞�s�ւ̏������A���������������ė������B����\���N�B�����Y���\�Z�̏t�ł���B
�f���ǂ��́A����قǂ���ꓪ�̔n������Ȃ������B����ǔނ́A�Ȃ�̕s�����v�킸�������B������̒[����[�֏o��܂ł��A�O�����l�����������ĕ������B�l�̒ʂ����Ղ����H���ǂ�A��X�̔���̑����ɂ�����Ȃ������B
�߁X�ƁA�x�m���������A����͊����ɔR�����B�s�֏o����A������A���炭�Ȃ��ƁA�x�m�̕����ɁA������C�������B
�x�m�́A�ߔN�A�܂������N���A������ɁA�����������Ă����B�����āA�������ɂ��A������̑��������Ȃ�قǁA�D���~�炵���B�����Y�́A���̖т̍��ɗ������D���A�܂ő~���āA�s�v�c�Ȃ��̂�����悤�Ɍ��߂��B
���C�̒�Ȃ����ɏo��A���Ă�������A���t�̐������A���������̕ӂ�Ƃ́A�����̂������������������B�x�͘H���邪���ƂȂ�A���������Ȃ���������A���@������B�����āA��ƂȂ�A�x�m�̂��ނ�́A���̉͂ȂƂ������A�C���R��邩�Ƃ���������B
�����̓s�́A����ȏ�A�������ɂ������Ȃ��B���䂭�l�X�́A�ǂ�ȂɋC�������낤���B�܂����`�ǂ����傤�����ނ̖쐫�́A�l�̂͂Ȃ������ɒm���Ă��铡�����S���̋{���J��\�z���āA���������֗������������㵒p�͂ɂ��݂ɂ���A�������Ă����B |
�����܂��̉䂪�V��
����\���N�̔ӏt�̈������ЁB���n�̏����Y�́A�������傤�����̉�������A�\�]�����₵�āA����ƁA���s�̂����Ă܂��́A����R����������܂܂ŁA���ǂ�����B
�u�����́A�Ⴂ�R���z����A������̉��������̓s����v
�u�ꎛ�̉��ŁA�����������A�ނ́A���ӂ���܂��āA���̎���̓W����܂ŁA���̊��^�b�����Ɏ������܂܁A�����o����A�o��߂��B
�u�c�c�����v
�ƁA�₪�Ĕނ́A�_������V�O�ɂƂ����悤�ɁA䩑R�ƁA�܂���������ʂ��������ŗ��������B
���m�̐��E�Ɋė����ނ̂悢���ۂ��傤�����́A�z���ȏ�Ȓn��̓W�J�ɏV����ꂽ�B���R�X�̂��₩�Ȑ��ɂ����܂ꂽ�L���~�n��т̎��������ׂĂ����Ȃ�ʌ��ʂ����тĂ���悤�ɁA�ނɂ͌������B�X����ʂ��Ă�����ΐ���A�����̐�������Ă��邽���̐�Ƃ͎v���Ȃ������B���Ď��@�̉��Ŕq���Ƃ̂���g��y�֑ɗ��}���傤�ǂ܂炸�h���̂܂܂ȍ����������̂�ɂ��������̂��Ǝv���B
�u�����B�c�c�s�֗����B�c�c�s���v
���܂��₷�����N�̏��^�́A�����j���ʂ炵�Ă����B�������A��������́A�s�l�̂����ɗ���������A���̑����ȎЉ�̒��ɐ�����̂��Ƃ��銴�������ӂ邦�������B�����āA�O�����ƂȂ��A���ق̎��E�Ɋ������Ă����B
�����ꗢ�ܒ��A��k�ꗢ�\�Ƃ���ꂽ���̍��̕����̓s�{�́A�^�얖����܂����͂����悤�Ȓ����̒�Ɉ�]���ꂽ�B�s�X�̒������ɂ́A��������ł����炩�ɍc���̑��������������\���̈�c�Ƃ킩�銯�ɓa�����A�E���F�����Ⴍ������O���炩��O�h�ɂʂ�̖�L�Ƃ��ڂ����s�����₫����b�āA����ڗ�����炭���Ȃ��Ă���A�鐝�����Ⴍ�A��{�Ȃǂ��n�߁A����������܂ł̑�H��������A���c�O�\��̓��H�́A��Ֆڂ̂悤�ɁA�s�V���悬���Đ��R�ƌ������B�܂��A�����̒҂�a�̕ӂقƂ�̂��̂ł��낤�A���X�́A���A���ɐ��߂��āA�����ɂ�A���t�̎������������p���ŁA�Í�������̒��ׂ��r�����l�����̉����́A�����ɂ�������ׂ��͂��\�\�ƁA�����ɗ����l�݂͂Ȉ�l�Ɋ��������ɈႢ�Ȃ��B
�܂��Ă�A�Ⓦ����̖��J�y�ɐ���A���ɓߐ{���Ԃ̕��������A���́A�q�̖�n��F�Ƃ��Ĉ炿�A���炢�y�A���炢���A���炠�炵���l�Ԃ�������̒��ɁA���悻�����炵�����̂̓������m�炸�A�\�Z�̓���ƂȂ��Ă������n�̏����Y���A�����������l�Ԃ̂��ޒn�ォ�ƖY��̂��₵�݂ɑł��ꂽ�̂������͂Ȃ������B
�u�a�q�́A�ǂ��̘a�q��́B�ǂ����痈�āA�ǂ��ցA������邩���v
�ӂƁA�N���ɁA���������A�ނ́A�悤�₭�A���ɕԂ����B
�����́A���N���ł���B��͂蓯�������⓹��o���ė������̂Ƃ݂��A���𗧂ĂāA�ނ̂������ɋx��ł����B
�ǏD�����イ�̏��N�́A�������̓�̐e�����ɓ�ꂽ�B�����āA�͂�铌���������痈�����Ƃ��́A���ꂩ���f���̓Y�����������āA�����������̂��ق������ˁA���l�̓��܂ŗ��܂��āA�w��C�{�ɐ�O���A�ꂩ�ǂɂȂ��ċA���������ł���ȂǂƁA�����������܂ł�b���b���A���Â�ɂȂ��āA�����A���s�̊X�Ȃ�������Ă����B
|
���ЂƂ̕���
�u�܂������B�������̂��Z���́B�\�\���ꂳ��́A�ق�ƂɁA���ق̂��鏊���A�m���Ă�낤�ˁv
�����Y�́A���s���ɂȂ��āA��ɂ����˂��B
�u�����B�S�z�����łȂ��B�����̌��O�܂ŁA�A��čs���Ă�����v
��́A���߂ɁA�����Ƃ���A���R�Ƃ��āA���Ȃ������B
����ǁA�c�Ɏ҂̏����Y�ɂ��A���������x����������A�����NjȂ������҂ւ܂��o�ė����肷��A�^�킸�ɂ����Ȃ��Ȃ�B
��́A�悭����ׂ����B�u�a�q�����ꂩ��K�˂Ă䂭�E��b�Ƃ́A������̂��ق�����ǁA����ɂ���ʑ������邵�A�͌��̐ΐ������A���Z���̂ЂƂȂ�B���̂����́A�ǂ��֍s�������������A���́A�ЂƂɐe��������ɂ��A�e��s���Ȃ��ƁA�C�̂��܂Ȃ���������������A�������āA�������������Ă��܂����̂���v�\�\�����Ă܂��A�����Â����B�u�a�q��B���̕ӂŁA�ЂƋx�݂��悤�B�������O���߂�����ǁA���A���܂��A�E��b�Ƃ����K�˂���̂ɁA����ȁA����甯�����čs���ẮA���Ă��܂��c�c�v
�ق�ƂɁA�e�ȓ�ł���Ǝv���A�����Y�́A�ޏ��̂����Ȃ�ɁA�������낵�āA�ӂ�Ɍ��Ƃꂽ�B�Ȃ�Ƃ������@���m��Ȃ����A�R�傪���蓰�t���������A�d�̓��̍�����S�������̍������n�𗎉Ԃ̔��ӂɐ��߂Ă���B�����S�ڂ����̂́A�[�ł̉A�e���A�����̉e�ɂ��A�Z���Ȃ肩���Ă������Ƃ������B
�u�˂��A�a�q�c�c�v�ƁA����ő����x�߂�ƁA��͂��������o�����B�u���܂����A�w�ɕ����Ă��闷��݂́A�c�ӂ����Ō����邪�A�����ƁA�܂��H�ׂȂ����ٓ����͂����Ă���̂���Ȃ����B������������A��̂��ʒ��ɁA���ٓ̕������ɂ������B���������ƁA���́A�������ւ��āA�����A�ЂƑ��������Ȃ�����v
���Ƃ������Ɏ���o���Č�̂ł���B
�����ŁA���̓�́A���߂��玩���̗���݂ɂ������������ł������Ƃ�A�Ə����Y�����ɂ��āA�v�����킹���B����������āA�H�ׂ����������Ƃ́A�ނ̋��ς�Ȃ��������A�A��̓�ɂ������āA�ނ���䖝���ė����Ƃ��낾�����B�ŁA�ނ͂�����������݂��炻����o���āA��̎�ɓn�����B
��́A������킸�ɁA�H�ׂ͂��߂��B���Ƃ�荡���A�ؒ��ł����炦�Ă��ꂽ�n�����邤�邿�̔���������܂�����c���������ɂ����Ȃ����A��͂��̒|�̔�Â݂�G�֕�������ŁA���F�������ނ��o���ɁA�����H�ׂ��B�܂̐L�т��A�����w�̌҂ɂ��b�����ꗱ�܂ŁA���܂����ɐ�œ[�ߎ���ẮA�������̂�H�ׂɂ�����A���ɁA�����Y�ɂ́A������ꂸ�ɁA�݂ȐH���Ă��܂����B
�u���̎҂ɁA���Ȃnj�āA�Ђƌ��A����ŗ���قǂɂȁB�a�q�́A�����ő҂��ċ�������v
��́A�����������B
���ꂫ���̉e�͌������A�ӂ�͈Â��Ȃ����B�ނ͑҂������т�āA�̂����Ă��܂����B����Ƃ��������異�����т̌����ԁX�Ƃ������Ă����䓰���݂ǂ�����̂ق�����傫�Ȓj���̂��̂������ė����B�����ď����Y�̑O�ŏ��@���N���N���炵�A���̃q�Q�ʂ�˂����Ă������B
�u�����A���̓��B�����̑̂́A���܂̌�H��A���ꂪ�����Ă�������B�Ă߂��́A�Ȃ����B���ꂪ�����Ă��Ȃ���A������͉����̓z��ЂƔ����ɓn�����ɂ��܂��Ă���B�����A�������́A�~���ɁA����Ɨ~���A����A���̂Ƃ���A�����ɂȂ��Ă��܂������B���������A���A�������֗����v
�䓰���̕��ɂ́A�Ȃ����l����̒j�ǂ��������B�ΎG�킢���Ȑ��ʼn���炰�炰���肠���A�݂��֖҂ǂ������Ȋ�ƁA�����Ė��A�쑾���Ȃǂ̋���������A�܂�ŐԋS�̂悤�Ȋ�����낦�āA�������Ȃ��A���̂܂��ɁA�Q�܂��ł���̂������B
�u�ǂ����A�݂�ȁA���̓��́A�E�������낤���v
�����Y�̘r������ŘA��ė����j�́A���Ԃ̎҂Ǝv����j�������������āA�厩���ŁA�����������B
�u�����b�āA���J���낾�ɂ̗~����肾����A�������̂��낶��A�����b���˂��B���Ă��낲�߈��ЂƂ����ɁA����̓����ꖇ�悱���ƁA���b�����₪�������A�l�ł́A�����Ղ�ƌ��āA�����Ă�����B�c�c�ǂ����A���̓��́v
�ނ��ނ��ƁA�݂ȋN���o���āA�����Y�̊�����A���������A�S�p���A�W���W����ŕ��ł܂킵�āA
�u�����B����₠�A�������̂����v�ƁA�ЂƂ肪�����A���̎҂��A���������Ƃ������͂₵�āA���X�ɔl�̂̂������B
�u�ȂA���ꂶ�Ⴀ�A���������A���J�̓�ƁA�����Ŏ������肵�Ă����̂́A���̎���������̂��v
�u���̒����Ă����߂��肬�ʂƑ��������ł��A������̂���ȏ�̒l�͂ӂ߂�v
�u�ӂĂ��z�B�ЂƂ�ׂ��́A�悭�˂����B���ꂽ������g�₳�����݂̝|�����Ă���Ԃ���̂��v
�u�����₢�v
�u�������B�₢�A�s���l�ӂ��ƁB�����āA�݂ȂɐU�����B�����Ȃ��A����g�̒��ԝ|�͗v��ʂ��ƂɂȂ�v
���ԂƂ����A�g�Ƃ����B��́A����͂ǂ������ނ������̓k�}�Ȃ̂ł��낤���B���Ƃ�菬���Y�ɁA�����̗͂͂��蓾�Ȃ��B�ނ͖��݂�悤�Ȋ炵�āA�����̕s�v�c�ȉ��̐F�ƁA�s�v�c�Ȓj���̉�b�̂Ȃ��ɁA�ۂ���ƁA�����g��u���Ă��邾���������B�����A�r���ɕ�ꂽ�e�q�͌��������A��g�̕s���ȂǂƂ͏����������Ă��Ȃ��炵�������B
|
���\���̖���
���n�̏����Y���A���A���߂āA����R�̍������璭�ߒm���������̓s�́A�����āA�ނ̌��o�ł͂Ȃ��B�����v�ɂ��l�Ԋy�y�̌����ł���A����搂������铡�������̒n��ɂق�����݂̂������ł��������ɂ܂������͂Ȃ��B
����Lj���A���̎s���ɁA�����ӂݓ���Ă݂��Ƃ��́A�]��ɂ��A�\���̂������̐r�͂Ȃ͂������̂ɁA���̍��̗��s�҂ƂĂ��A�݂ȈӊO�Ȏv�����Ȃ������Ƃł��낤�B
���������A�������A�ޗǂȂǂ̎������o�A�����ɑJ�s�������߂ɁA���̋K�͂�����A�����Ƃ����傤�嗤�̕����܂˂�ɋ}�ŁA���悻�A�����̍��͂Ƃ͕s�����ȁA�����L��ȗ��z�ɂ�������������炢������B
�\�\�Ƃ��������A�M���������A�M�����������̐����v�ƁA�ɉh�̈Ӑ}�̂��Ƃɑn�Ă��āA��ׂȏ����̐��ԂƁA�傫�ȗ͂̍�p�Ȃǂ́A�l���ɂ���Ȃ��������̂Ƃ������ق��������B
������A�N���ӂ�ɏ]���āA�����̓s�Ȃ���̂́A���ɂւ�Ă��Ȕ��W��`���Ă����B
���Ƃ��A�{��⑾�����A���Ȃ͂����傤�Ȃǂ̌����Ƃ��̒n��́A�ؔ��s��Ȃ��ƁA�@�������Ƃ��̊G��ɂł�����悤�ł��������A�����𒆐S�Ƃ����Ֆڂ̓������������������ƁA�����D�^�ʂ���݂́A����ɐ₵�A�����A���̕��ӂA���ق��肾���A�����č����̎l���̈�A�E���͂Ȃ��S��̎O���̈ꋭ���A�c�ł���A���ł���A���n�ł���A�ӂ�����ȏ���ł���A��䩁X�����Ւn�ł���A�Òr�ł���A�X�ł���A�܂��A������݂��߂ȕn�������̌������ނ��������Ԃ��̒�����كb���ď����������B����A���ɂ͂܂��A�����̏K���������Ă���ꕔ�̋ɕn�҂���A��������ɏZ��ł����B
���������n��ɁA�܂��A��屼�Ƃ����Ƃ��āA���������ɁA�G��ȏ�y�̑������ق����Ă��铰�����������̕��t���U���ł���B�����ɂ́A�����n���ȗ��A�{���ƕ_���ɁA�S�Ƃ��Ĕ����ׂ��炴�鍪���������m���������A�ˑR�A�傫�Ȑ����͈͂��������āA���������I�ɂ킽������̒��ɂ킪�܂܂�U�����Ă����B
�u������B����q�ނ̂��v�ƁA�����ɂ������āA����҂́A�V��̌��܂˂���āA�����������B
�u�\�\�ߑ����Ⴍ����͗\�����Ă���B���̋������A���͂��肫�̌�����������̂́A���������܁X�S�ɂ������A���@��N�A���@��N�������A���悻���N�ŁA�ł���ł��낤�\�\�ƁB���Ƃ͓������s�̖��@����ɓ���\�\�Ɩ��炩�Ɍ������Ă���ł͂Ȃ����B�������Ă݂�ƁA���쉽�N�Ƃ������́A�������@�ɓ����Ă���̂��B���́A�����N�ォ��A�����܂����Ȃ̂ł���A�����̐��݂̂�����l�Ԃ̑����A���̂ӂ����ł�����͂��Ȃ��v
�����������́A���X�ɁA�J�ɕ��������A�㗬�w���������A�Ђƍ�����݂�A��قǎ��Ȃ̐M�ɁA���^���o���Ă͂�������ǁA����ł��Ȃ��A�f�p�Ȃ�m�I�����ɂ��邱�̍��̏�ł́A���悻���ɂ̏��̉��݂����ɁA�������ɏO���앚�����Ă��܂��قǂȖ��͂�����̂́A���ɂȂ������B
|
�����ƍ��̒n�E
�V�q�A�V���A�����A�����V�c�Ȃǂ̗𐢂�ʂ��āA�����̋������̂����A�S���ɑn�����ꂽ���@�̐��͂����ւ�Ȃ��̂ł���B�����J�������A���͂́\�\����݂͂ȉ��w���̊��Ɛłɂ����̂��\�\����Ȃ��������Ă����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�����A���̒����̐M�҂ł��鉤���M�������́A����̐����⎄�I�����̒��ɁA���̕������}���ɕ��s��������o�H�����ǂ��Ă����B�������̂����ꐢ�I�]�ɂ킽��h�Ɛꉡ�́A���̗��j�ł�����B
����ł��A�剻�̊v�V�Ȍ�A�����S����������njp�悵�������̌��b�����ɗ����āA������ɁA�y�n���v��f�s������A���x�̓K����A���������̒������v�����肵�Ă����Z�����Ԃ́A�ǂ��ɂ��A���{�̏������傱���݂����Ȑ��V�����A�����̐F�ɂ����������A�₪�Ĕޓ��̐ꉡ���Â��A�c���A��{�A�݂ȓ������̌�������Ď��ɂ������A�����̊��ɂ�����n�����̎�Ȃ�E�܂ŁA���̌n�ނłȂ��҂́A�قƂ�ǁA�ߊ�������ɂ�����Ȃ����オ�����\�N�����������ʂ́\�\���܂␢�͂��₵���Ȃ闼�ʎЉ�R�Ɏ��ɂ�����\�\���܂��܁A���n�̏����Y�����������悤�ȁA�����̈����Ȃ������̓s�ƁA�S�S��s�̈ł̐��Ƃ��A�ЂƂn��ɁA�ǂ������A���Ƃ��āA���݂���悤�ȏ�ԂɂȂ����B
�����āA���̂ǂ������ɋ�����Đ����Ă����̌Q�́A���ƍ��̂悤�ɁA�ɂ߂Ė��ĂȐ��ԕʂ������Ă����B�㗬�M���K���ƁA�n�����Q�ґw�Ƃ́A�ӂ��F�ł����Ȃ������B
�����K���Ƃ����w�́A���̍��܂��A���{�ɂ͌�������Ȃ������B����炵���m���l��A���Y�����l�̋ɂ��������A���邱�Ƃ͂��Ă��A����ƂĂ݂ȁA�{���ߊ����܂Ƃ��A�����Ƃ����̌��͉��ɂ��钩�����傤�ǂ��̔��ȂɁA������̏o�d�����邩�A�ۊցA��b�ƂȂǂɘ\�d�낭�����āA�ق��ڂ����������߂邵���A�Љ�́A�ޓ������@�\���]�n�������Ȃ������B�Љ�\���ɑw�𐬂��قǂȒ����l�m�ƂĂ͂Ȃ������̂ł���B
�\�\������A���n�̏����Y���A�����̑����ɐڐG�����҂݂͂ȁA���̈���̍����w�ɏZ�ސl�Ԃ������������Ƃ́A�����Č�����܂ł��Ȃ��낤�B�����A����ɂ��Ă��A�Ö�̎���ɁA�S�̂��Ƃ��Ό���������ŁA�X�ӂ�����ӂƂ����A����C�܂܂Ț������킲�Ƃ𓊂������Ă��邱���̒j���́A�������������ɋ��߁A����E�Ƃ��Ă��邩�Ƃ����^��ɂȂ�ƁA����́A�����Y���Ȃ������̔N�����A���ۂɁA���̓s��ɂ����Đ������Ă݂���łȂ���A�����ȒP�ɁA����Ƃ����܂ł́A�����ɒB����܂łɂ͂䂩�Ȃ��B
|
�����l��
����U�����A����������A�ƒ��Ԃ������点�т��āA�s���l�ƌĂ�Ă�����j�́A���̊v�Ԃ��납��A�K���������āA�����Ă�����B����ƁA��l�͂����܂��ǂ����֑����čs���A�₪�đf�Ă̎�r�������߂��������ė��āA
�u�����A�L�y�a�ق��炭�ł�́A���������������Ƃ��悤���v
�ƁA����Ɏԍ����A�r�ݍ������B
�u�҂đ҂āA���������A�s�i�C�ɂȂ����B�d�܂��͂˂����v
�u�ȂɁA�d���B�d�ȂA����Ȃɂ�����v
�������w�������ꖼ�̎҂́A�����ǂ���ɁA�����̉��L�֏オ���āA���łɉ��Ă�������������̈ꕔ���������A�܂����w����A�o�����́A�ؒ����̓����̂�����ė��āA�蓖�莟��ɁA���̌Q�ցA����������B
�u�ق��B�܂����邪�v
�u�����A��������A��������v
�����đf�Ă̕r����A�ǂ�ǂ낵���t�̂��A�ނ����킵�A���݉Ă�����ɁA�悤�₭�A�C�ɂ��Ԃ�ꂽ��r�̂����ɂ܂ŁA�����܂��n�߂��ƂȂ�ƁA�ޓ��̔��ɖO�����b�Ԃ�́A��]���āA�����̟T�������Ղ�炵�ɂȂ��Ă����B
�����Y�́A�s���l�̂��ɁA�҂�����Ɗ����āA�������������ł��Ȃ��悤�ɒu����Ă����̂ŁA�����ۂ���ƁA���̌��i�����Ă������A�ނɂƂ��āA���ɂуb���肳����ꂽ���Ƃ́A���̘A�����A���̑�b���Ƃǂł��낤���A�e���A�ۉƂ������̍��M�ł��낤���A�Ѓb�ς�����A�������Ԃ��́A���\�Ă�肵�āA�܂�ł�����̖}���ڂ������n���Ҏ����āA�l���܂Ȃ����Ƃ������B
����A�������ゾ���̈����Ȃ�܂������A�͂ẮA�V�q�̈Ë��ɂ���сA�������̏������聖�ɂ���āA�������̔�]���Ƃ������������A���コ���A�~�a�����ȁA�z���悤�����ȂǗ��V�c�̌䖼�܂ł����ɂ��āA
�u���������A����Ȑ��̒��ɂ����ꑰ�߂�́A�Ɉ��}�Ƃ����Ă�����˂����A�������҂��܂��������҂ŁA�V�q�l������d�����˂��Ƃ����@�͂���܂��B�ނ����ނ����A���ꂽ���̑c�X���₨�₩����p����ė����V�c�Ƃ������̂́A�m���V�c�l�������o���܂ł��Ȃ��A����Ȃ͂��̎҂��Ⴀ�Ȃ��������v
�ƁA���l�������߂Ă�����C�́A���Ȃ����������̂��̂ł͂Ȃ��B
�����́A�c�X����̊��킵�ŁA�V�q�Ƃ������A����Ƃ������A���������̂��̂Ƃ������Ӌ`�ɍl���Ă����B������A�q���e�Ɉ�������������ꍇ�����肤��悤�ɁA������̓V�c��@�c�̌䖼�ɂ������Ă������݂��Ɉ����������Ĝ݂͂���Ȃ��̂ł������B
�����A�����Y�������Ă���K���ł́A����́A���̂ւ��ꂫ�ɂ��тꂽ�悤�ȋ������傤�����������B�����̌��t�̂���Ɏ��V�c�Ə����Ƃ̐e���̕ό`���A����Ȍ���ɂȂ��ďo��̂ł��낤�\�\�ȂǂƂ����l�@�̂��Ƃ܂͂Ȃ��B�ނ̐�������Ⓦ�n���ɂ����ẮA�V�c�̂��͂��납�A���i�A�S�i�̒m�����ɂ������Ă���A����A�����тɂ��A���������t�ł͂Ȃ��B���Ƃ��A�s�̐ۊ։Ƃ�A�������̖����Ȃ����āA�n���̒��Ɋ����������炷�g�҂Ȃǂɑ��Ă���A���炢��A�q�}�͂������A�����ǂ���A�������Ԃ�̍��������A�y�������āA�˂Ȃ�Ȃ��قǁA��ΓI�ȁA�ډ��ƍ��M���A���炩�ɂ���Ă���B
�u�Ȃ낤�H�@���̐l�����́v
�ނ́A�����̑���ɁA���̋^��ɂԂ������B
�����A�Ă�Ō��������Ȃ��̂ł���B�悤�₭�A������������������Ďe�ׂɘA���̕��������Ă��A�����̎q�킩�Ƃ��v����悤�ȁA�l�i�����̎�҂����邵�A�t���A�������������̐e�����Ǝv����j���́A�@�t������ɈႢ�Ȃ��҂��́A�앚�̂Ԃ���p��陖ʂ��́A�ǂ��ɂ��푰�I�Ȉ�v�͂Ȃ��B
���ԓ��m�ŌĂт����Ă��閼�O�ɂ��Ă��A����₳���̕s���l�ӂ��Ƃ��n�߂Ƃ��āA�Ñ�͂��������́A�ђ��Y���ނ��낤���́A�ۋ����ق��˂��́A���F���́A�w偑����������̂Ƃ��������ŁA����ɂ��E�Ƃ̂ɂ����͂Ȃ��B�����A���̕����̒��ɂ́A�܁X�A�}���ł͂����Ȃ��m�I�Ȕᔻ���������肵�āA��ɁA���b�̂�����炵������̕s���l�̌��ɂ́A�����Y���A���������Ă��B
|
���
�s���l���A�ꓯ�̎G������������A�����Ă����ɂ́A
�u�V�q�̑����́A��ւ��Ƃ����̂́A����Ȃ��B�m����́A�\�������������B�����V�c�́A���ꂽ���̐��̍��A�������������Ă��������悤�Ȗ��V�q�ł������B�܂�́A���̂Ƃ��̒��b�y���傤�����ɂ����B�����S�����Ă���A���������A�V�����C���т��n�߂��������B���������A�s��ꂽ�剻�̊v�V���A�ł���ߐ��x�ɑ��A�l�����c���ł�⎄�����ւ��������Ƃ͋ւ��Ƃ������{�̍������A�Ă߂������̉h�B����肷�邽�߂ɁA�߂��Ⴍ����ɂ��Ă��܂₪�����v
�ƁA�Â܂Ȃ���������Ēɔl���A�Ȃ��A�����ݎ����������Ă����Â����B�u���c�c�B���ꂩ��́A�n���̍����ƁA�s�̕�������B��b�A�֔����炵�āA�y�n���L�����A�����Ɏ��c��~���߂���ŁA���킽�����ɑd�ł����ڂ����Ă�̂��B�n���̌S�i�⍑�i�ȂǁA����������ɂ��āA�܂˂��邳�B�������āA�_�Ђ����āA���Ȃ���Α��Ƃ����C�ɂȂ�͓̂���߂����B����A�s����n���֔h�����ꂽ��l�ł��A�����ł��A�e���ł��A�܂����̈�ނ̒n�����ł��A�������A�c�ɂɂ��āA�������܁A���c�������A�����������A�d�������������āA�ꐶ��邵�������������ƂȂ邩��A�݂�A���̎g������傤�����́A���炲��̂��݂��̂Ȃ́A���̂ƁA�C������āA�C�n�։����čs������l���́A�݂�ȁA��������Ăт������Ă��A����������āA�s�A���ė��˂��̂��A�啔�����Ƃ�������˂����B�\�\���̌��ʂ́A���\�₯�ƕs���̒��Ԃ�A�y�n�������A�̋���ǂ��āA��������S����A������������A��肽���������đ���ƁA����������V�����́A�������́A�Րł̖Ԃ̖ڂ������肻���˂Ă��܂�S���̌Q���́A�����āA���ꂽ������g�̒��Ԃ̂悤�ɁA�����ƒm��A���̒��ɏ|���āA�����ł��蓐��ł��A�����Z���A����Đ�����ƁA�����������傤����̖{���ɋɂ߂���ł��܂��l�Ԃ��A�����Ⴄ����o�ė����Ƃ������ƂɂȂ����܂����̂��v
�s���l�̗Y�ق́A�}�ɁA�Ղ�ƁA�������B
�u�ȁA�Ȃɂ��H�v�ƁA����������ŁA���������Ă钇�Ԃ������A�ނ͏��āA�������̏����Y�̓��̏�ցA�����̑傫�ȏ��Ă̂Ђ���ڂ��āA���ނ悤�ɁA�h�肤���������B
�u���B�Ă߂��͍��A�傫�Ȋ�����āA����̊�������ȁB���ꂽ���̎d����m���āA�������̂��낤���B�c�c�������A�d����ł�邼�A�Ă߂��ɂ��B���������牴�̎��ɂȂ��āA���̓����A�o���邪�����B��b���Ƃǂ��֔���������̂��A�����̈�傪�A���̐����䂪���̊�̉h�����Ȃ�A���������A�ÈłɁA�X���������̈�������āA�z��ɁA�A���ӂ����Ă��B���a�ʘO����ł傭�낤�̉h���y�������A�y�𑃂ɂ��āA���������܂݂��傤��傤�̐��n�肪�y�������A���ꂽ���́A�y�����ׂ����Ă݂�C�ȂB�����ŁA�d���̏d��ɁA�Ă߂����炢�ȓ����ЂƂ�v��p�ȂB�����͂���܂��B���������Ă��݂ȁA�ق�Ƃ́A��������������肾����A�����W���W���ЂƂ̊�����邱�Ƃ͂Ȃ���v
�ނ��܂��A�����I������Ȃ������������B�^�����ɂ����Ñ邪�A����b�ƁA�˂��グ��ꂽ�悤�ɂЂƂ�N���オ���āA
�u�ς��B����ς�c�c�A�����A���������H�v
��Ԃ₭�̂��A�݂Ȍ��グ�āA
�u�Ñ�B�Ȃɂ��A���Ԃ������v
�u����̊��́A�v�����͂�Ă݂݂��B�c�c�������ɁA��������A���n�̒��ЂÂ߂̉������Ă���v
�u�悹�₢�A�����B���₾���A���ǂ��Ȃ�A�Ñ�v
�u����I�@�����߂��B�������v
�u�����B�ق�Ƃ��v
�u�����\�\�����g���������v
�ꂹ���ɁA����ƋN�����Ƃ���ɁA�˂��̂߂���āA�����Y�́A�R���c��̕��̏�ɁA�K�����������B
�u����Ă�ȁB�����̎R�̌��ցv�ƁA�s���l�́A��ꂪ���ɓ����܂ǂ����Ԃ֎��B���������Ȃ���A����̘r�ɁA�����Y�̂��炾�����b�邵�A�m���u���b�邵�A�v�͒�{�ł́u���b�邵�A�A�v�n�R������ɁA�R���̒n�������āA�킯�o���Ă䂭�ƁA�ނ���\�������Ȃ�������������A��w�̐l�e���A��������߁A���ƁA����ɂ͉H���Ȃ���A�n�ɂ͋������̉��𗧂ĂāA�����̖���A�ˏW�����߂Ă����B
�u�����B�����˂��v
�ƁA�g���Ђ邪�����āA���p���X�������Ƃ��A�����Y�̑̂́A�ނ̘r����U��̂Ă��A��n�ɕ��ւ��������Ă����B
�r�ɓ�{�A���̂�����ɂ���{�A��������B�����Y�͂��̌�A�Ȃɂ��m��Ȃ������B�C�������Ƃ��́A���B��������̂悤�ȁA�L���A�����A�܃b�ÂȁA�S�i�q�̒��ɂ����B
|
���傩����
�����́A�������ɂ̔��Ȃ̂ЂƂA�Y���Ȃ��傤�Ԃ��傤�̖���ɂ������Ȃ��B
�ȓ��ɂ́A���i�������̂����A�������ゲ���i�A�܉q�{���̂��ӁA���E���傤�����A�����i�Ȃǂ̕��ǂ��A�e�\���ɂ킩��A�e��(��̎��_�A1-2-22)���̂��́A���ɂ����܂��āA�ߊ��̊������A�������Ȃ�������h��h��̓������ȕ��L���A�̂�т�ƁA���ނȂǂ������āA���������Ă���B
���ẮA�e���䂾�傤���������������A���͔p����A���ɁA�����g�����A�݂����A�ߍ��ɂȂ��ẮA�Y���ȍs���̂����ŁA�����Ƃ������Ȉ�@�ւƂȂ��Ă����B
�����܂ł��Ȃ��A�����̊lj��ł́A���@�A���e�A����A���i�A�Ǖ߁A�����A�f�߁A�Ǝ��ȂǁA�Y���ƌ��@�s���̂��ׂĂɘj�킽���Ă���B�\�\�֖�O�̋����͂������A�E�����Ȃ��A�S���̎i�@�����݁A�n���ɂ͒n���̌����g��C�����Ă���B
�u������́A�ߐl����Ȃ��B�����A�������͂��Ă��Ȃ��v
�����Y�́A��邩��A�C�����Ɠ����ɁA�����̕s���ɁA�����ł����������Ă����B
�u���ɂЂƂ₾�v�Ƃ������Ƃ́A�ނɂ��A�ЂƖڂł킩�����B�ނ̂ق��ɂ��A�S�̂��݂ɂ́A�L�������݂����ɁA�C�͂Ȃ��A���낲�낵�Ă�����l���A���l���������B
�u���B���߂����A�Ε����������A�������������̂��v
�ƁA�����̎҂���u���ꂽ�肵���B
�����Y�́A���X�A�ۂ�ۂ�ƁA�܂����ڂ����B�Ȃɂ��A���O�Ȃ̂ł���B���S�̌��Ȃ��A�S�O���ɁA�����̂̂��̂ł������B
�u������́A�����V�c����A�Z��ڂ̌�q���B�Ⓦ���m�̕�������̗ǎ��Ƃ��������̎q���v
�݂�����̏������������邽�߂ɁA�ނ̋��́A�ӂ���ɂ͈ӎ������ĂȂ����t�̂��Ƃ��A�����������A�ꂩ��Ă���B
�u��l�̑O�֏o����A���������āA�В����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�O������ŁA���ɂɁA�҂������Ă����B
����ƍ��A�����Ɂg�C�����h��ۂ܂��Ă��ꂽ�ʼn����̕ߗ����A�`��������A��������āA
�u�����A���C���ȁA���B���܂��́A�����ɏo������v�ƁA�����Ă��ꂽ�B
�Ԃ��Ȃ��A�ߊ��̎��������A�ߎj�ꂢ���A�{���ӂ��傤�A���������Ă��Ȃǂ̉��������������āA�O�ɂ������݁A
�u�o�����v
�ƁA�{�Ŗ������B
�����āA�����Y���A���i���傤����̒�ɂ����A�ǂ������킯�ŁA����̌Q�����̒��ɂ��������撲�ׁA���R���Ƃ�ƁA�ނ��������Njy�͂����A�ނ̏����i���A��̂܂��ɁA�Ԃ��Ă��ꂽ�B�����āA
�u�����A���āA��낵���v�ƁA�����n�����B
�����i�̒��ɂ́A��f���A�헤�̑坁��������A���������ɂ��Ă��厖�ȏ��ނ���ł���B�ނ́A�����āA�������ɁA����̂���낱�сA���x�́A�����ӂƂ���ɂ���������āA���F���炷���������B
����ƁA���i�́A��܂ő����ė��āA������ƁA�����Y�̕��������Ă������A
�u���������A�����̏����҂�����B���ʂ��́A�ق�ƂɁA�������̂��ق֍s���̂��v
�ƁA�u�˂��B
�u�����A�Q���ł��B�ǂ����֍s�����炢���ł��傤�v
�u���Ⴀ�A���̏���Ɍ����A�坁�����ǂ̂́A�R���䂩��Ȃ̂��B�ق�ƂɁA�����Ȃ̂��v
�u�͂��B�����́A���̑�f���ł��B���́A�����̍����A���ǎ��̎q�A���n�̏����Y�Ɛ\����ł��v
���������A���i�ɂ��A��n�̌�q���Ƃ������Ƃ��炢�́A����Ȃ��Ă����邾�낤�ƁA�����Y�́A�Ђ����ɁA�����܂�������j�ɂ̂ڂ����B
�Ă̂��傤�A���i�́A�ԓx�����炽�߂��B�����āA���߂ēs�̒n���ӂނ̂ł́A��b�̂��ق���Ƃ��A���p�ɖ������B����(�����̒㗙�Ă���A�㐢�̖ږ��߂�����)����l�A���ē��ɂ��Ă�낤�\�\�ƁA�e����������ŁA
�u�����A�����Y���ҁB�����ȁA���̂��Ă��݂��A���X�ɁA�������֏o���܁A�����A�r���̎��ǂ����A���̂������炽���˂�ꂽ��A�]�X���������̗��R�킯�ŁA�Y���Ȃ̍��i�A���{���ʂ����̑P�k�悵���ɁA���A���������S���������Ȑe�ɂ悭���b���Ă��낤���Ɓc�c�����́A�������悭�A�b���Ă�������B�c�c�̂��B���ނ��B�킵�̖����A�Y�ꂸ�ɂȁv
�ƁA�I���ȁA���Ȑ�`�̈˗����A���C�Ȋ�ł������B
|
�������n��
���Ƃ́A�C����Ȓj�������B
�u�����b�Ă����ƁA�����Ԃ�A�������낤�ȁB�悭��l�ڃb���ŁA�������ˁB�䂤�ׂ݂����ȖڂɁA���x���A�����ő����₵�Ȃ����������v
�u������v�ƁA�����Y�́A���Ԃ��U��\�\�u����Ȗڂɑ������̂́A���߂Ă���B�鎭�R��������܂ɂ��A�C���ɂ��A�����Ԃ�D�_�͂������邻��������ǁA��l�̌�ɂ��肭�b���ĕ����ė�������v
�u�����ȁA���܂��́B�s�֏o�āA���ɂȂ����Ȃ��v
�u�w�₵����A���낢��A��l�O�̒j�̓����A�������肵�āA�A��������v
�u�Ƃ�ł��Ȃ������B�����l�ԂɂȂ낤�Ƃ����Ȃ�A�s����c�ɂցA���K���ɍs���������ق�Ƃ��v
���r��������܂��A�O���痈���B���H�ɗh��āA�r�̗����A�������ĂĂ���B�D�^���悯�A����ƁA���ꂿ�������A�����Y�́A���̂����Ԃ���A�`���ƌ�������l�̔����e�e������ƍ����ɁA�����A�ǂ����Ƃ����B�����āA���g�~�����������ɁA����������̑ň߂������ʂ��P�˂��ւ��������炱�ڂꂽ���Ȃ�ʌO�肪�A���܂ł��A�����̂��Ƃ�ǂ��Ă���悤�ȋC�����ɂƂ��ꂽ�B
�u�˂��B���Ƃ���v
�u�Ȃ��B�����ҁv
�u�ւ�Ȏ��A�u���悤������ǁA�ǂ����āA�s�̐l�́A�����c�c���ꂩ�玞�X�̒j�ł��A����ȂɁA�F�������낤�H�v
�u�͂͂͂́B���������낢���A�m��Ȃ��̂��낤�A���܂��́v
�u�������āA���v
�u���ςɁA��֓h������̂��B����������A���������߂̕��Ő������炦�����̂�����v
�u�ȃA�B��ւ��b���Ă�̂��v
�u���܂��Ă��邶��Ȃ����B�����A���������n�߂��̂́A�������S�]�N���ނ����́A�����V�c�̍����炾�Ƃ����̂ɁA�܂��A�����ւ́A�s���Ă��Ȃ��̂��Ȃ��v
�u�������Ƃ��Ȃ���B���߂́A�ق�ƂɁA�F�������l�Ȃ̂��Ǝv�����v
�u���Ⴀ�A�g�ׂɂ��m��܂��B���Ò����������傤�̍��A�m�̓ܒ��ǂ傤���������炦�o���������ƕ����Ă��邪�A�������Ȏ��ɂ́A�������A�ϐ����傤�Ƃ����m���A���̓V�c�Ɍ��サ���̂��n�߂��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�c�c���̉��ςɂȂ��ĂȂ�Ȃ������A�ǂ������A�V����̔������Ƃ�������A�������낢����Ȃ����v
�u���������B����́A�����g���A�x�߂��Ȃ���D�ŁA�����ė����v
�u�فB�Ȃ��Ȃ��A���܂����A�m���Ă�ȁB����ǁA�A�����ė����̂͂���ς�V�傾�����ɂ������Ȃ��B�ǂ����āA�m���Ƃ������̂́A����łȂ��Ȃ��@�˂̂Ȃ����̂��B��ʎ�o�����͂�ɂႫ�傤���̊��Ђ݂����ȕ����莝���ė����̂���A�F�C���Ȃ��߂��āA���@�O�ʂԂ��ۂ������̕��ւłȂ��ƍl�����ɂ������Ȃ����v
�u���Ƃ���A�܂������B������́v
�u���B���������Ă���B�c�c���ꂾ��A����Ɍ����钷�������z�y�����A���A����̑剮���A�z�R�̎��X�A����������͂�s���A�̂��炸������@�̂��ق��v
�����Y�͂����A��ւ̕Ԏ����킷��Ă����B�߂Â��ɂ�A�ނ̂ЂƂ݂́A���̍G�s�ƗD��Ȃ�Q�a����̓@��̔��ɑł���āA�����������قƁA���������ɁA�g���ق��܂��Ă��邾���������B
�u���B�c�c�����͂܂��A���q�l�܂낤�ǂ������āA�䉃�y�̐܂Ƃ݂���B�c�c�ȁA�ق�B���̕��y�̋Ȃ��A�k�ꕷ���Ă��邾�낤���v
��O���A��◣�ꂽ���ŁA��l�́A�ӂƘȂ������B�\�\�Ȃ�قǁA�A��̕��Ƃ̂����Ƃ���A�z�y�����̎��X���āA♂��傤�A�a�Ղ킲��A�U�ۂӂ�Â݁A�J�Ȃǂ̎U�y�������ӂ��A�V��̉_�Ԃ���ł��~���Ă���悤�ɁA�����Y�̗��C���炯�Ȏ��̌��ւ��A�t���ƂƂ��ɁA�E�т₩�ɁA���ꂱ��ł����B |
�����K
�S�~���T�����̑�{�l���ق݂�тƂ́@���Ƃ܂����
������}�������č�������炵��
����̐������A�����r�ւ����l�X�����傤���ĂяW�߂āA������̑����m���₩���a�����݂ǂ̂̂�����ɂ́A�t�y����ނƁA��̒����̑傫�ȏ������A�q�̛g�ΎG��̈�ꂪ�A��\���v��Ȃ�������A�_�ɂ�����̂قƂ�܂ŁA�߁X�Ɖk�ꕷ���Ă����B
�u�����ҁB���ꂪ��ɁA������ƁA�掟�𗊂�ł�邩��A������ɁA�҂��Ă��ȁv
���Ƃ́A�v����͂����āA�����̂����߂Ă���L�O������Ƃ���ƌ��܂킵�A������d�ЂƂ�����E���̕�����̂���������ƁA����̎G�ɂ�������̂�������A������������p�̏��҂��A�ς��ƁA�킯����āA
�u������B�����Ȃ����B�\�\�o��A�o��v
�ƁA�������ǂ����B
���Ƃ��A�����Y�ɂȂ����āA�͂��K�˂ė����킯���A�䂤�ׂ���̎e�ׂ��A�܂т炩�ɁA�q�ׂ��ĂĂ���܂ɁA�T�S�l�낤�����ɂ�Ƃł��܂����������̂��A����ɉ�����A�Ǝi�������A���A�G�F�������������܂ŁA���ӂ�o�ė��āA���X�������Ƃ���肩���݁A���āA�猩��������A�u����������A����ɋc�����������A����ƕ��ƂɁA�����Y���A�Ăѓ��ꂳ�����B
���Ƃ́A�o�߂����e�؋C���A������悤�ɁA
�u���Ⴀ�A�Ă܂��́A����Łc�c�v�ƁA���V�ЂƂc���āA���X���������ɁA�����������B
�����A��ɂ͈ˑR�A�����Y����͂�ŁA�͂Ȃ��ɂ̂ݕ����A�ڈ̎q�ł�����悤�ɁA�D��Ȋ�ƁA�^�f�Ƃ��A�I���ɂ��т��Ȃ���A�Ȃ����X�ƁA���͂��荇���Ă����B
�����āA���ǂ́A
�u��V���̂��Ȃ��B���q�l�����������鏊�ցA�Ђ��Ȃ��掟�́A�����߂̂�����������悤�B�܂��܂��A���́A������ɗ��߂āA�l�ڂɂӂ�ʂ悤�ɂ��Ă������������v
�ƁA�Ǝi(�V�E)�̂������������āA�����Y�́A��������X�ɁA�O�����������A
�u�����ŁA�҂��Ă���v
�ƁA�G�F�̎w�������֓����ꂽ�B
�����́A�@�����r�h����܂�ǂƂ�ԋ��҂Ƃ��܂������ł������B
��������ȋ��r���A������g������ł���A���X�́A���̕����A�R���Ȃ��Ă���B
���Ɵ��悾��ƁA���̐K���b���ۂ̂������ł́A����Ƃ����Ă��A���鏊���Ȃ��B�ӏt�Ȃ̂ɁA������墂��A����ė��Ă���B�����Y�͗��������т�āA�r�h�̉��̓����̂����Ă݂�ƁA�����ɂ́A���ꂼ��̎�l�ɋ����ė����������ɐl�Ƃ˂肽�����A�\�l�ȏ���A�Ԃ��ނ낵�Ă��āA�Ȃɂ��A������ЂƂ�䭂ނ���Ɋ����Ă����B
��������������B
�g���K���ɂ����h�Ƒ��ɂ�������ŁA���̍��̏������M�����Ă�������̂ł���B�����̒j���A�������̌������K�𗼂̏��ɓ���A�U�艹�����āA���ƁA��ɓ�����B�����̑K�ʂ��ɂ߂�ƁA���l�̑K�ʂƂ��A�ǂ��o�邩�Ƃ����_�ɓq�������̂ł������B
�����Y���A�`������ł����B����́A�Ⓦ�n���ł�����ł���B����ǁA�����ƌ��n�I�Ȕ��Z�ŁA����ɁA����Ȃɂ����炴��ƑK���ɂ�q���邱�Ƃ͂Ȃ��B�q����̂��A��́A�є炾�́A�z���̂Ƃ����������肾�B
�����ł��A�ނ́A�������߂������B�K���܂�Ő���݂����Ɉ����Ă��邱�Ƃ������A�����Ɣނ��V�����������̂́A�ԗ��Ȑl�Ԃ̗~�S���悭�`�����ނ瓯�m�̊���ł���A���̌�C�ƌ�C�̉���悤�Ȍ���D��ł���A�܂��A�E�C������ȓ����̌��i�������B
|
���E��b����
��l�����̂���̂��A�T�ς��Ă��邾���ł��A�����Y�͏[���ɁA����V���āA�ދ����킷��Ă����B
�\�\���A�₪�āA�K�̎���Ƃ��[�łɂ܂���ē����~�����Ȃ肩�������B
�u�����̏O�B���q�l����������A���������ƌ����܂��邼�B�r�ցA���낻��A�����Ȃ�ьv
�ƁA���̎҂���G��ė����B
����Ƃ���A�������҂��A�������ҁA�ꂹ���ɏo�����āA���̂��̂̋��r���g���o���čs�����B���킽�������Q�킾���̚e�Ȃ��a�����݂ɁA�܂��狍�̔��ӂ����ł��悬��߂������Ƃ́A����墂����������Ȃ��B�ǂ����畴��Ă���̂��A�x���̕ЁX���A�ӏt�̈�e���A�킸���ɕ`���Ă��邾���ŁA��a�̂�����ł��낤���A�^�̐�������������B
�����Y�͈Â���ŁA�����ނ���ނ���j�b�Ă����B�@�����狟�l�����֏o���ٓ��̗]����E�������̂炵���B����ȂɁA���̂����˗��������Y���Ȃ̍��i�ł���A�H���Ȃǂ͎��l�ɂ���銟���䂵���^���͂��Ȃ������B�܂��A�����ł��A���������Ƃ��m��Ȃ������̂ŁA��}���ŁA���������B
�����A�S�z�͂Ȃ��B�������̉Ǝi���G�F���A�ނ�u���Y��Ă͂��Ȃ������B���C�̉e���h��ė��A�ӂ����сA�ȑO�̕���O�̑O�͂����܂ŘA��čs���ꂽ�B
���łɁA�ނ������ɏq�ׂ�����ƁA��f����������̏���Ƃ́A�Ǝi����掟����āA�E��b�����̋����Ƃɒʂ����Ă������Ƃ͊m���炵���B
�����āA�q�炵�������ł͂Ȃ����A���g��������A�ꕔ�̌����̂����ɁA�܂��オ�邱�Ƃ���邳��A���܂�炶�Ȃlj��������Ă���ƁA������u�Ă����Ȃ��̍Ȍ˂܂ǂ̈��ŁA
�u�₢�A�₢���B�Ǝi�̐b�ꂨ�݂��́A�ǂ��ɂ���邼�B�b��ꂶ���A�}���ŗ������v
�ƁA�s������ȋC�F�����߂āA�劫������߂��ɌĂт��ĂĂ���l�e���������B
���ɁA�����̈ӎu�̍s���ʂ��Ƃ�m��ʓ������̒��҂����l�̐��Ȃ��A�Ǝi�̐b��́A�����ł�����V���̎��ł��A��������܂邱�Ƃ͂Ȃ������B
�u�͂����A�͂����B�b��߂́A��O����܂��ł�����܂��B�����́A�Ȃ�̌�ӂ��傢�ɂ�����܂������v
�u�����ȁA�s���҂�B�悢�N���������āv
�u�����A�ȂA���S�ɂ����܂��ʂ��v
�u���ǂ��҂�A��́B�Ȃ�ځA�q�̂��Ƃ����Â��ɖZ�����낤�ƁA������A�����������������A�Ȃ����낻���ɂ�����������v
�S�Z�̓����������A�����ȑ吺�ŁA�悭�a��̘_���ɂ��A�������^�Ƃ������l���̐��q���A���̐��ł��߂����Ƃ����b���̂����Ă��邪�A���̒�̒������A�L���ȓ��̂̎�����ł͂���A���Ƃ��O�\���Ƃ����s�N�ł����邹�����A�Z�ɕ����Ȃ�����߂������X���̂ł������B
�u��������łɁA�܂����ǁA��������܂��B��߁A��͂��Ԃ�A�N�V�Ƃ�܂������̂��A�����̂悤�ȖZ�����ɂ����܂���ƁA���A�ӂƁA���̖Y��Ȃǎd���܂�܂��āv
�u�����̉�S�̂��Ƃ����B�����̏���������ė����Ƃ������������B�܂��A�킩��ʂ��v
�u�́A�͂��B���̏����҂��A�ǂ������ƁA���������ł�����܂������v
�u�������A�₭�������Ȃ���������낭���B�c�c�킵���������̂́A�����A�ꂸ�A�������ЂƂ�ŁA���������֒ǂ���������B�ǂ����A�낭�Ȏ҂ł���͂��͂Ȃ��B�\�\����ɂ�A�����̒��ӂ́A������������̓����A�ǂ���q������ɐG�ꂽ���ב̂��������m���B���₢��A���ɁA���́A���ɂɐQ���ˁA���傤�͖�O�܂ŁA�s��҂̕��ƂȂǂɁA�����ė����ƁA��ꎩ�g�A������������Ƃł͂Ȃ����B�c�c������A������B�q���ɐG�ꂽ�l�Ԃ��A�ق̉��̓��́A�ǂ��ɏグ�Ă��悭�Ȃ����B���ꂱ���A�厖���B�_�H�X����˂������ŁA�q�ꕥ�������܂��܂ŁA�y���O�ǂ����Ƃ́A�������ւł�����Ă������B�c�c�����������̂���B�c�c������ȂA��A���낻���ɂ��A�ޕ��ł́A�����グ�悤�Ƃ��Ă���ł͂Ȃ����v
�u��A��B����́A���������v
�u�����x����B�q��҂��グ�����́A������߂�B�����āA���̑̂��A�������ɏ�ߕ������āA���C���݂�������Ƃ点���v
�ʂẮA�������ӂ邦�������قǁA�����́Aᒂ�������Ă��B
���̈ٗl�ȓ{�肩���́A�a�I�ɂ��猩�������A�b��ł����̏��g�ł��A������A�s���R�Ȋd�{�����ǂƂ́A�N�����Ȃ��l�q�Ȃ̂��B
|
�������M���w
�Ȃ��ł��낤���\�\�Ƃ����ɁB�ЂƂ肱���̓����Ƃ����̒��҂���łȂ��A�֒��ł��A���b��ʂ̂������ł��A�g�G�q���傭���h�Ƃ����A�����т��ӂ���āA�q�ꕥ���ɁA�����ł��A�����A�ߊ���p���āA�Q���������x��߁A�q���ӂ��Ƃ�������A�N�����m���Ă��邩��ł���B
����ȐM�́A���ʂɁA�ɒ[�Ȃ܂ł̖��M�����������Ă����B�։}�܂��Ȃ��A�Տj�������キ�A�P���͂炢�悯�A�A�z���A�������̂��݁A�S�삫��傤�A��⬂����ȂǁA���l�Ȗ��ς̈Ԉ��������Ȃ��ẮA�����Ă����Ȃ��㗬�w�̐l�X�������B�킯�Ă��A�q�̎v�z�́A���Ԃ����A�_���Ƃ������Ƃ�����ݍ����āA�������̈�ʂɁA�[���ȕa�I�S����I�ނ��܂��Ă����B
���Ƃ��A���q�����ɐG�ꂽ�ƂȂ�ƁA�O�\���̊����݂��ŏ�Ƃ��A���Ȃ����A�����́A�P�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Y�w�ɂӂꂽ�ҁA�ƒ{�̎��ɂӂꂽ�ҁA���o�����Ƃ̎ҁA�݂ȁA�G�q�̎҂Ɗ��܂��̂ł���B
���̈�l����łȂ��A���͂̎ҁA�Ɛl�A���ɂ́A�o����̒m�l�܂ł��A���l�Ȗڂɑ������ƁA���Ȃ��Ȃ��B
�j���ɁA����������Ƃ߂�A�����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��قǁA���ł��A�������o�Ă���B��A�O����E���Ă݂�\�\
���鐝��m�V��e�������N���N�B���߉q�{�m�����m�����K�A���҃m���Ѓ����w�e���^�g�C�t�m�f�A�{�n�A�O�\���m�q�g�i�c�e�僒�Y�B
�������A�{�m��˃��A�\���g�m���Y�A�C�@���m���K�����f�p���^�g���C�f�A��������A�����m�q�j���X�B
�����F��m����A��ϓa�m��j�A�����m���������o�f�A���i�V���V�ߓT�V���N�e�����V�e�A�O�\���m�P�n���w���X�B
���̂ق��A�Y�����`�����Ȃ������Ă����Ƃ����̂ŁA�҂̒ʍs�~�߂���������A�Ђ̏o���ꏊ�̓y���ӂ�킹�āA�̐_���J�܂�����A���悻�C�a����܂��̖�_�₭���݂��A�㗬�w�̐S�ɁA����قLj��Y��U�����ʂ�������͂Ȃ��B
����́A�q�Ƃ͂����Ȃ����A�����ؚ̉��ɍʂ�ꂽ�����̋M���������A������ɂ́A�����M�肾�́A���삢����傤���̎��삾�̂Ƃ������̂̎�����M���āA�قƂ�ǂ��A�_�o���I�Ȑ��i�����сA���ɂ́A�����ɂ��猩����҂��������̂́A�h�̓Ɛ肪�A�K�������A�K���݂̂ł͂Ȃ��������̈�Ƃ����Ă����B
������ɁA���̊K����遚������́A�e�l�̐������A�݂ȒZ�����Ă����B�O�\�A�l�\�𑽂��o�ʂ܂ɁA��킩���ɂ���҂����������B�\�\������܂��A�������̂̂����M��Ƃ��A�������^�̉��삪�Ȃ��Ƃ���ł���Ƃ��������A�����͖{�C�ŐM�����̂ł���B
����̓���A���̍ł��A�T�Ȏ���́A���݂̋{���ɂ������B���̑���́A���^����݂����˂����傤�����A�S����M���āA���ɕs�\�ɂȂ��A���̍c���q�A�����Ђ날����e���Ȃǂ��A����Ĉȗ��A�O�N�̊ԁA��������z�̌��ɂ��킷���ƂȂ��A��������A�����ɓ����Ƃڂ��A�q�m��O���コ���āA���������������������̂����Ȑ����̏����A�Ђ�����|�����Ă����Ƃ����������炠��̂������B
|
���n������҂��ޖ܂�
�s�������ȕ���o�Ɏ����킸�A�D�_�ŌƑ��ŁA�킪�܂܂țg���ɂ����Ȃ��������A�����ƂƂ��ẮA�E��b�̌��E���l�A���̒��҂Ƃ��ẮA���ȏ�A�Z�ȏ�Ȑ����̌��h���Ă��A�S�̂ǂ����ɂ́A�������ア���ςƋ������������Ă������Ƃ́A�@����ɂ�������Ȃ��B
�������������A�q�������āA�ӏt�̉A�T���A��|�������������Ǝv�����̂ɁA�����̑坁�����ȂǂƂ������[���܂�����肩��A�������낭���Ȃ����҂�Y�����Ԃ݂��Č����Ă悱���A��ł������炵�����Ƃł͂��������A���ǎ��̎q�Ƃ����̂ŁA�����f�C�Ȃ��ǂ��������ł��Ȃ������B�ǎ��́A���O����A�����ɂ��A�����̖�ɁA�b�������A�ނ̗i���铌���̎��c�̎����ł��߂������Ă����j������ł������B
�����A���̈⎙�̂������ɂ܂ŁA�ǂ������l���Ă��قǂȍD�ӂ͂Ȃ��B���ɁA�ӂƓ��������߂��̂��A��������ނ̍ł��������Ă����q�̐S�z�������B����A�͂��Ⴌ�ʂ�����J�̔������A����Ɏ�`���A�����Ȃ�A�b���ւ́A�劫���ƂȂ����̂ł���B
�b��͐b��ŁA�܂��A�G�F�����֗��āA�ǂȂ藧�ĂĂ����B���ʂ́A�����ǂ����܂ŁA�����グ��ꂽ�����Y�̐g�֕Ԃ��ė����B�����Y�́A���̓y���傩��A�͌��֘A��o����A�܂闇�ɂ���āA���ΐ�̐��̒��ւƁA�˂��̂߂��ꂽ�B
�u�\�\�q��̂���A�q���B���̂��z���܂��A���̕����珸��܂ŁA���x���A����ł́A�P���āA�q����߂��܂��ƁA���V�ɂ��F�肵�Ă���̂����B�悢���B���́A�����Ă肵�āA��͖�ŁA�������P�����˂Ȃ��v
�b��́A���т����������āA�G�F�����Ƌ��ɁA�@���ւ��ǂ��čs�����B
�����Y�́A���āA�Ȃ�̎����A����Ȃ������B
����ǁA���ꂪ�E��b�Ƃւ́A������߂̈���Ǝv���A�ۂ����ƁA�}���̒�����A�����o���Ă����B
���͂܂��A����䂫���������Ǝv����قǗ�Ђ�������B������ƁA����̒��ŁA�l���̍����A�]������Ɍ����ċÌ������B�\�\���A�ق����ƁA�傫���x�C����ɓf�����Ƃ��A�O���ڂ�Ȍ����A�������̖��̂܂ɂӂƌ������B
�u�c�c���̌����A�s�ɗ��Ă���B�����A��������A�s�ɂ���v
�ނ́A��������ȁA�n�̊���A�O�_�̏�ɕ`�����B�̋��̑匋�m�q�̔n�[�ɁA�������A���܂�m�܂��A���a�ɖ����Ă���ł��낤�n�����ɁA�S���獐���Ă����B�\�\������̗F�B������A�҂��ނȂ���B������͍K�����B�s�l�ɂȂ邽�߂ɁA���ΐ�̐������܁A������̗��̍C���������Ă���Ă���B
|
�����҂����k
����́A��\��N�܂łŁA���̗��N����A�������傤���N�ƁA�������ꂽ�B
���n�̏����Y���A�͂��\��ł���B�ނ��A�E��b�ƂɎd���Ă���A�����A�ܔN�͂������킯���B���ӋC������̔N���Ƃ����Ă����B
�������A���������A�ѓ�����邳��A������l�O�̒j�ł���B�����b�ς�ƌ������āA�C�̂��Ȃ��z���߂ʂ̂Ђ�����Ȃǒ��Ă���ƁA�悭�A���������܂̂��т��̎q�ƁA���炩���Ă����ނ��A�߂���ł́A�ǂ����A��b�@�̏��ɐl���Ƃ˂�Ƃ��āA���ԂȂ݂̏��g�ɂ͌�����悤�ɂȂ��Ă����B
�@���ł́A�ނ̖�����́A�ԎG�F����܂��������Ƃ�ԏ��҂̂ЂƂ肾�����B��l�̊O�o�ɂ������āA������܂��g���o���A���̂����ɂ��ĕ����A�܂��A�A���Ă���ƁA��������A�Ԃ̗ւ�A�v�Ȃ����̋���܂Ńs�J�s�J�����āA�ӂ�Ȃ������Ă����B
���傤���ނ́A�Q���̋��ɂ��āA�鐝�傷���Ⴍ������r������܂��܂���r�����A��l�̒������ނ���̂��A�I���Ђ˂����A�҂��Ă����B
�ق��̔[���A�Q�c�ȂǁA����b���r���A�v���Ȃ�ׂāA���҂����Ă���B
�����ł́A���Ƃ̎G�F����肠�܂�̂ŁA�s�̂Ȃ��̏o�����́A��Ƃ��ĉ\����k��邱�Ƃ͂Ȃ��B
�u�Ȃɂ����̑�b���Ƃǂ̌�Ƃ̋��ցA�䂤�ׁA���钩�b���������̂悤�ɔE��ōs�����B����Ƌ߂��둽���Q���̈�ނ������āA�������딼���ɁA�j�����A聂˂�ނ݂̍����͂����Ď����P���A�Ɛl���݂Ȕ��肠������A����͂������A�j���̈ߏւ܂Ŏ��F���������A�Ԃɂ�Ŏ��������Ă��܂����B���̂��߁A�E�ђj���̒��b�́A����ɒ��镨���Ȃ��A����ƂāA���ł킪�ƂA����Ȃ炸�A�G�F�̕z�Ђ�������肤���āA�������邪����ł���A���������A���čs�������A�قɂ́A�L���Ȃ₫�����i�₫�̉����������邵�A���̉����͔D�P���ŁA�ق��ɂ���������Ȏq�������邵�A���Ƃ̑������v������A�����ɂ��܂��A��������������ł͂������B�\�\�Ƃ��낪�A���̒��b���A���傤�̋{���W�c�ɂ��A�Q�c�̈ߊ������āA�����߂炵�イ�Q�����Ă���B�Ȃ�ƁA�_�c�т傤���̐Ȃ��A�������āA���̂����āA�ς�����Ă��킷���Ƃł��낤��\�\�v
�ȂǂƁA�ЂƂ肪���A�܂��ЂƂ���B
�u���₢��A�F���ƌQ���̂͂Ȃ��Ȃ�A�s�ɂ́A�����A�|���قǂ�����B����͂��������ɂȂ��Ă��邪�A�����̂����ɂ����āA����Ȏ����������B���Ƃ��̌܌��J���݂��ꍠ�������B�O�J�a�����ł�̍X�߂������Â��́A���鏗�����A����̂ЂƂ̂����Â��������ŁA�ЂƂ�̊��l�ƁA��Ђ����������̂���ł����B����ƁA�܂�邭�A���̔ӁA�Y���Ȃ̉����̂��̂��A����a������傤�ł�ɉ������܂��p�������āA���̂��łɁA������`�����B���́A���ǂ낢�āA�߂��ʂ����킩�����Ă����ꂽ���A�j�͍Ȍ˂��R���ē����o�����Ƃ�������A��l�͐��������āA�l�X����ы��߁A�Ƃ��Ƃ��A�j�����܂������c�c���ꂪ���ƁA����a�̋�������A���钩�b�̈ߏւ𓐂݂����āA����𒅂���ł܂�܂Ɗ��l�ɂȂ肷�܂��Ă��������������Ƃ����̂����炠�����ł͂Ȃ����B�������A�����́A�����炪��ŁA���ꂪ�A�쓐�Ƃ͒m�炸�ɔ�����邵���̂��낤���A���킢�����ɁA�X�߂̂����ɂ��������Ă��܂����̂ŁA�a�C�Ƃ����āA�h�ւ��Ƃ܂��Ƃ��āA�ނ����Ă��܂������������c�c�v
�G�k���킭�ƁA��������Ȃ��A���������݂���ƁA�����Ȃ͂Ȃ��́A�����玟�ցA�������A���o�����̂ł���B
���t�����s����Q���́A���܂�A�s�������炷�����ł͕�����Ȃ��Ȃ�A�܁X�A�{������������āA��{�̏���X�߂��������A���т₩������łȂ��A����Ƃ��ȂǁA�^���A�É��������邫�ɂȂ�O�J�a�̋��L���̂����ɐ��������Ă����̂��A�É����g�������ɂȂ��āA�����ƂȂ������Ƃ�������B
�\�\���������A�����Ȃ��̂̏o�v�����тɁA�����Y�́A���ď\�Z�̏t�A���̓s�̓y�����߂ē����̏��ɁA���R�̂ӂ��ƂŌ������̌Q�������L������Ăт��ǂ��ꂽ�B�����Ă��̒��Ԃ����̊��A�܂��A����̕s���l���́A�Ñ邾�́A���F���̂ƌĂь��킵�Ă����ނ�̖��܂��܂Ŏv���o���ꂽ�B
�@ |
���f�p�ȓǏ��q
�����߂����A���ȏ\���̂����ɂ́A�����Ȃ�����A�Y���Ȃ�����A�܂��s���ɂ́A�����g������̂ɁA�ǂ����Ă���ȌQ���ǂ��ɉ��s����Ă���̂��A�����Y�ɂ́A�ӂ����łȂ�Ȃ��B
����ǁA���҂����Ԃ́A���Ƃ̓z�l��ɐl�����̕��k��������Ƃ���ɂ��ƁA
�u�����Ȃ�̂́A������܂����c�c�v�ƁA�݂Ȃ����āA�݂�Ȃ������B
�u�䐭������邢�̂��B�c�c����A�����ɂ��A�����ɂ��A���́A�䐭���ȂȂ�����A�Q�������ɂ́A����Ȃ��肪�����䐢�݂�͂Ȃ��v
�b�肪�A���̗��R�ƁA�����Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�����Y�́A�����A���g�����܂��Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�A�ނ̎d���Ă����l�\�\�E��b�����������A��������A�����݂��ɁA�����̑ΏۂɂȂ邩��ł������B
�����́A�������̒��҂Ƃ��āA���܂ⓡ���Ƃ����̈����A�v���܂܂ɂ�����������g���ł���݂̂łȂ��A����̒��ł��A����̈�т��́A�f�R�A�d�����Ȃ��Ă���B
����́A�����ɁA�Ⴍ�ĖS���Ȃ����A����b�����̈ʒu�ƌ����Ƃ��\�\��̔ނ���������p���ł��邩��ł��邪�\�\�Z�̎����Ƃ́A���̐����I�ȍ˘r���A�������A�������A�l�Ԃ��̂��̂��A�܂�Œi�������ɁA�i�������Ă���̂��A���܂̉E��b�Ƃł���Ƃ����̂��B
�����Ȃ����A�O�����̍���b�����́A�������^���A���G�Ƃ��āA�h煂����Ȑ�����A�����{�ʂȖd���������Ԃ��������A�܂��A�n���̔_�n���v���́A���S�̈�V���́A�����ƕ����̖ʂɂ����āA���Ȃ藝�z�������Ă����B���ꂪ�A�ɂ������A�O�\��Ƃ����Ⴓ�ŁA�a�����Ă��܂������߁\�\�����̍ˊ��́A�܂��A�����̂����Ɏ����͂���Ȃ��������\�\������A�l���́A�F�߂Ă����B
�Ƃ��낪�A��̒����Ɨ��ẮA��ׂ�ɂ��A���͂Ȃ��ɂȂ�Ȃ��B
�g�{�������������h
�Ƃ����]���A�����s���Ă���B
�D�_�ŌƑ��B�킪�܂܂ŁA�ؚ����������ق����B�D��Ă���̂́A�nj��Ɖ悾�����A�Ƃ݂Ȃ����̂ł���B
��́A�����ŁA���Đ�ɁA�����قƂƂ������悢���̂��A�����Ȃ�������e���ɂ����������B�e�����A�Ȃɂ��Ȃ��A����J�����ƁA�v���Ȃ߂��A�L�L�Ɩ����̂ŁA
(���B���̎������e�����\�\)
�ƁA�Y��ɋ���������B������܂��A���x�b���Ȍ����������A������A
(�������́A���M�̖��A����̂��邵�A�����͉悢�Ă��A�e�����܂ł��悫����킵���҂́A�Í��A�����̌N���ЂƂ�ł��낤)
�ȂǂƏ܂߂��Ă��B
����𒉕��́A�����ŁA�����Ȃ��ɂ�����A�̂̑��e�Ȃǂɂ��A����g�����̑�b�h�ȂǂƏ������Ă���B
�܂��������̓֒��������́A�nj��̖���Ȃ̂ŁA����������ĂɁA�a�ՁA�J�ȂǂɗJ���g������A����̒��镨�́A�@���ɐD������߂������āA�ӏ��A���F�A���ԂɂȂ����̂��āA������A�ւ�Ƃ���悤�ȕ��������B
��������A�{��̂������A�ۂ����āA�ؔ��ɂȂ�A�ނ����́A�V�c�̂ق��ɂ͒��Ȃ������悤�ȕ����A���������̎j�������傤�①�l��������������A�я����˂߂⏗�[�������A����X�߂ɂ��������ɉ��������������A�]���āA���I���݂���A�Ȃ����A�_�c����ɂ������ẮA�Ă�ŁA�ӂ����ȗL�l�ł���B
���������劯��{��̂��ƂɁA�ЂƂ�Y���Ȃ╺���Ȃ̊��l�����������A���Ƃ܂�������ȂāA�������łĂ���͂����Ȃ��B�\�\�����͔ނ�̗̖�ɂ����āA��͂蓯���^�̈�y�Ɩ��������Ď����ɓ������Ă���B�Q���ɂƂ��Ă��肪�����䐢���鏊�Ȃ̂ЂƂł���B
����Ȃӂ��ɁA�����r����̋��҂��ŁA�����Y���A�����A���邱�ƕ������Ƃ́A�ȂɈ�Ƃ��āA�낭�Ȏ��ł͂Ȃ��B
�u���i�����́A�������Ȃ����̂Ƃ������A�܂������A���邳���������傤�����߂��B���̐l�����́A�l�Ԃ̏X�݂ɂ����Ƃ���ƁA���̒��̉����Ƃ������ɋ����������Ă���B����ȗ��`�����肵�Ȃ��ŁA�����ƁA�l�Ԃƍ������̂�́A�������A�����������A�����́A������ǂ����낤�v
�����Y�́A���ɂ́A�ЂƂ̕��k�ɁA����Y��āA�������낪����������A�܂��A�܂ɂ́A���������āA�Ȃɂ��A���R���Č��������Ȃ����B
�Ȃ��A�Ƃ����܂ł��Ȃ��B
�ނ́A���ł��A���̕����̓s���A�������Ԃ̓s�Ƃ��āA�����Ă����B���߂āA�s�т̍Ⓦ�D�삩��㗌�̂ڂ��ė��ā\�\���s�ɓ���������A���̍������ɂ����āA���ΐ��A�������A�����́A�܂ӂ��t�̓s���A��]���āA
(�����A����ȓV�����A�l�Ԃ̂��ޒn��ɂ������̂��H�@�c�c)
�ƁA�����Ƃ��āA���ۂ�������̖����ɗ܂����炵���\�\���̓��̈�ۂ��A���܂��͂����莝���Ă���B���́A���e�łȂ��A�������A�ނ͂��܂ł��M�������B
�����āA�������A���̔������s�l�̂Ȃ��̈�l�ƂȂ蓾�����Ƃ��ւ��Ă����B�������������Ȃ��B��߁A���������Ȃ��̂ł���B
����ɂ́A�܂��A
�̋��̐l�X���������ꂽ�ʂ�A�����ɗV�w�����������������āA�s�̕����ɏK�܂ȂсA�悢�l���ɂȂ��āA�ЂƂ��ǂ̒j�U����A���̓����ɂ́A�̋������̖L�c���ɂ������ċA�肽���B�\�\
�u�����A���̂ق��́A�܂�ł��߂��B�������̎q���ƁA���w�@��������ɂ����w�ł��邪�A��������̏��ɐl�ł́c�c�v
�ނ̑f�p�́A�܂��㋞�̏��u���A�킷��Ă͂��Ȃ������B������A��ԁA�Ђ����ɖ�w������A�����A�����r����łԂ������̎��Ԃ��A�Ȃ�ׂ��A�Ǐ����邱�Ƃɂ��Ă����B
�\�\�ŁA�����A�v���v�̂������ɁA�ЂƂ����ŁA�߂���̊w�҂Ƃ�����O�P���s�݂悵�����̉Ɛl����肽�����̏������A�ӂƂ��납���o���āA�ǂݒ^���Ă����B
����ƁA�����炻�̑��֗��āA���܂��āA�����Y�̎�̏������A���ɁA�����낵�Ă���҂��������B
���ߎp�̂����������́A�g���̂Ђ������������ނ炢�ŁA�N�����A�����Y�ɂ���ׂāA���������Ȃ��\�\�O�c�l�c�ォ�\�\���炢�ȐN�ł���B
|
���ӂ���̏]�Z
�u�c�c�H�@�₠�v
�ӂƁA�C�����āA�����Y�́A�����������͂Ȃ����B
�����āA�p���������ɁA����ĂāA���ق���ӂƂ���ɂ��܂����݁A
�u�\�\�܂��A�z�������悤�ł��ˁB�����̂��ނ���ɂ́A�����ԁA�Ԃ�����܂��傤�ȁv
�ƁA�Ăꂩ�����ɁA�ߌ�̗z���A�ӂ�����B
���l�h�̛��Ђ����̈��ł́A��ɂ���āA�Ȃɂ��A�ΎG�Ȃ������������܂����B�O�́A�˂̉Ԃ̉��ŁA�������Ă���̂����邵�A���̂�������̐����悻�ɁA�Ђ����ɁA���K(����)������Ă��镨���̈�Q������B
�u�悭�w�����ȁB�������Ƃ́v
�������A���߂āA�ɂ��Ə����B�����Y�́A���������߂��B�����A�������ǂ�ł����̂́A���̏����ł͂��邪�A�������w�҂̓ǖ{�ɂ����Ȃ��E�q�̈꒘���ł��������炾�B
�u�c�c�����B�w�Ȃ�āB�c�c����قǂȂ��̂��Ⴀ��܂���v
�u�ł��A�S�����́A�Â�݂��ׂ�����B�\�\�Ƃ���ŁA���g�́A�킵���A�m���Ă��邩�H�v
�u�����B�ǂ����ŁA����������Ƃ��A����ł��傤���H�v
�u����������u���������v
�u����ł����c�c�o�����������܂���v
�u�������낤�ȁB�n�n�n�n�v
�u�ǂȂ��l�ł������܂����B�����������Ȃ��A���������������v
�u�������Ƃ̐����́A�����ł��낤���v
�u�����ł��B���Ȃ��́v
�u�킩�邾��B���Ƃł��B�c�c�킵���������B�������A���g�̐��ꂽ�����̖L�c������������Ȃ��헤�̊}�Ԃ��v
�u��B�c�c�v�Ȃ������ɁA�����Y�́A�����Ȃ藧���オ�����B
�u�c�c���Ⴀ�A�헤�̑坁�����ǂ̂��A�䑶�m�ł��傤�v
�u�m��Ȃ��ŁA�ǂ�������̂��B�킵�́A�����̂����ꂾ���́v
�u�����B���Ⴀ�A���̎��Ƃ��Ȃ��Ƃ́A�]�Z�킢�Ƃ��ɂ�����킯�ł��B�v���o���܂����B��f�������ǂ̂̂����q�\�\�핽���吷���傤�ւ�����������ǂ̂��A�������炱�̓s�ցA�V�w�ɗ��Ă���ƕ����܂����B���Ȃ��́A���̒吷�ǂ̂ł����v
�u�������B�吷�́A�킵�̒��Z�B�킵�͒�̔ɐ���������Ƃ������̂���v
�u�ł́B��Z�킨�ӂ���ŁA�s�ɂ���������̂ł����B����́A�A�܂������Ƃł��B������A���̋��s�ɂ����łȂ̂Łv
�u���g���A�L�c������A���s�֏o���A���X�N�̂��Ƃ��B�����Ƃ��A�Z�̕��́A�����肸�b�ƑO�ɁA���Ă��邪�c�c�v
�u�ŁA���́A�ǂ���ɁA���Z�����܂��ł��v
�u�Z�̒吷�́A�����Ƃ��ɁA���w�@�𑲋Ƃ��āA�䏊�̑��l�����낤�ǂǂ���ɁA�߂Ă���B�c�c���A�킵�́A���捠�A�O�P���s���m�̖���o�āA���ł́A�E��b�Ƃ̌��q�A����t����낷�����܂̂��قɁA�����Ƃ��āA�d���Ă���̂��B�c�c���傤���߂āA�{��̂����ɂ��ė����̂�����A���g�Ɖ�̂��A���߂ĂȂ킯���v
�u��ɌZ�̒吷�ǂ̂́A�����A������̉E��b�Ƃɐg���悹�Ă��邱�Ƃ��A�䑶�m�̂悤�ł����v
�u�c�c�����B�m���Ă���炵�����A���킵�����́A���������Ȃ������B����āA�b�������Ƃ����邩���v
�u�����B�����c�c�v
�����Y�́A�ӂƗ҂�������������B���́A��������x�A���V��̏Ě��₯���Ƃ̕��߂ŁA�l����A���ꂪ�핽���吷�ł���A���܂��Ƃ͓����炵���\�\�Ƌ�����ꂽ���Ƃ�����A�߂Â��āA���߂āA���A�ł����悤�Ǝv�����Ƃ��낪�A�����A�悪���������ł������̂��A�Ղ��ƁA�����ނ��āA�吷�́A�w���������܂܍s���Ă��܂����c�c���������L�����A�ӂƁA���������߂��̂ł���B
�����B�\�\����ɂ͐G��邢�Ƃ܂��Ȃ��A�ނ́A�ɐ����獡�A���Ƃ�������ꂽ�̂����ꂵ�������B�]�Z��Ƃ����A���͑��l�����Z���A����A���l�ɂ��Ă��A�ً��痢�̂��̋��s�ŁA���߂āA�����̋��́A�����Ⓦ����̓y�Ɉ�����l�Ԃɉ�����̂ł���B�Ȃ������A���ꂵ���A�����Y�́A�W�����D�Ɠ����ɁA�傫�ȗ͋������������B
�ނ̂��̋C�����́A�����āA�֑�Ȋ����ł͂Ȃ��B���̍��\�\�l�c��Z�\��A����̍c�I��܋�Z�N�Ƃ�������̓��{�̂����ł́A�E�����Ȃ��̂��Ƃ͂����g�O���h�Ƃ��������̂ł���B�����Ƃ����Ⓦ�Ƃ����A�܂�Ŗ��J�l��̍��Ƃ��������Ă��Ȃ������B
���Ƃ��A�z����悤�����Ă��̌��c�����̌ܔN�܌��ɂ́A���s��������̂䂫�Ђ炪�A���w�@���傤��������Ƃ����w�Z��V���ɋ������������A���̂Ƃ��ɁA�����z�g���ׂ̂̂̂��Ȃ݂ƘA�i��ނ炶�̂Ȃ��̂Ƃ����̎j�����A�܂���㗌���̗����݂��̂��̖��̑�\�҂���ė��āA�u���ŁA���k��̑Ζ�����āA���������肵�Ă���\�\�����āA���̓�l�́A���k��̒ʖƂ��Ă��A����Ɍ����������Ƃ����̂ŁA���N�A�e��(��̎��_�A1-2-22)�A�]�܈ʂ�������ꂽ�قǂł���B
���ً̈��̋�ŁA�����Y���A���܂��܁A�����Ⓦ�҂ɁA�o������̂ł��邩��A�ɐ�������ނ̊Ⴊ�A�]�Z�ȏ�ȁA����A������̐e���݂ƂȂ��������������̂́A�����Ăނ�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
|
�����傫��
�u�����Y�A���g���A���������̂��v
�u�������v�ƁA�����Y�́A�����ɁA�ɐ��ɓ������B
�u���w�@�ւ��A���w�@�ւ��A����Ȃ��ŁA�G�F�Ȃ��ē����Ă��Ă͂��߂��B�̂����āA�w�ȂǁA�v�������ʁv
�u�ł��A���w�@�ւ́A�����B���w�@�ւ́A�������̎q��łȂ��ƁA����Ȃ��̂ł��傤�v
�u�Z���́A�����Ȃ��Ă��邪�A�E��b�Ƃ���A�������ꌾ�A�����������Ă��炦�A�Ȃ�ł��Ȃ����B���m�������A�w�҂݂͂ȁA�n�R������A���̉����~�������Ă��邵�A���@�͂����������v
�u�����ł��傤���c�c�H�v
�u�܂��A���ʂ��炢���Ă��A��������Ȃ����B���������́A�Ⓦ�̒n�������̎q�ɐ���A�����ł��A�����ꑰ�ł��Ȃ����A�n�}���炢���A�������A�����V�c����Z��߂̑��������\�\��n����Ȃ����A�������v
�u�������B�Ȃ�قǁc�c�B����ǁA�E��b�ƂɁA�g�������Ă��A�܂���x���A���������炨����������ꂽ���Ƃ���Ȃ��\�\�ǂ����ė��炢�����낤�v
�u�킵�̂����q���̋���t�コ�܂̂��قւ́A�܁X�A�킵�̌Z���A�nj��̂������Ăɏ�����邩��A���̂Ƃ��A�Z�ɘb���Ă����Ă�낤�B�Z����A�t�コ�܂ցA�t�コ�܂���A���̌N�̒������ւƁA���ނ悤�ɂ���A�����ƁA�����ɒB���邾�낤�v
�u���˂������܂��B�܂��A����������܂��ʂ��A�Z��̒吷�ǂ̂ɂ��A�ǂ�����낵���A��������Ă��������v
�u�悵�A�悵�B�S�z����ȁc�c�v�ƁA�ɐ��́A�̂ݍ���ŁA�ʂꂩ�������A�܂��ӂƁA�������ǂ��ā\�\
�u�����A�����Y�B�߂������ɁA���ЂƂ�A�Ⓦ�҂��A�����ƁA�E��b�Ƃ֊���o�����v
�u�ւ��B�N�ł����v
�u����Ƃ̎҂��畷�����̂����\�\���썑�������̂��Ɉ��h�S����������c���̓y���ŁA�U�����G�������̂Ƃ����Ђł��ƂƂ����̂��A�Ȃ�ł��A����m�q�̔n���A��������ȓy�Y���������āA����ɏ���Ă���Ƃ������͂Ȃ����c�c�B����Ƃւ��A�E��b�Ƃւ��v
�u����̏G���̖��́A���̋��̂ق��ւ������Ă��܂��B����ǁA���̏G���́A�����܂��L�c���ɂ������ɁA�����A�傫�ȑ������N���āA���߂邴���ɂȂ����Ƃ������]���ł������v
�u���ꂪ�A���N���ƂƂ��A�͖ƂɂȂ��āA����ɋA���Ă����̂��B��N�́A�ސT���Ă������A�����A�悩�낤�Ƃ����̂ŁA�s��݂₱�̂ڂ肳�B�c�c�������A���̂���̂��߂ɂ���v
���̓��́A����ŕʂꂽ�B
�������A�ɐ��Ɖ�������Ƃ���A�ނ̊�]�́A�ꂻ���傫���c�ӂ����ł����B�ق��̎G�l�����ƈ�ɁA�ɐl�̉������̔����ɁA�f�ނ����~���A��ɋ���A�z�l�����̕n�������ɂ����Ă��A�����Y�̖��ɂ́A���������R�ɕ`���ꂽ�B�w������A�l�Ԃ�����A�͂₭�̋��ɋA���āA�틤�������S���������B�����̔y�ɂ��A��낱�������B�����āA�����₵�Ă��ꂽ����ȓc�Y�ł�ƉƖ�Ƃ��o�c����g�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����A�킸���ɁA�s���������̂́A
(�]�Z�����́A�������Ċw�Ƃ��I���A�݂ȁA�Ⴍ�Ă��A�ʒu�Ă���̂ɁA�ǂ����Ď����̂݁A���܂ŁA����ȋ������ׂ̗ɏZ�݁A�w�@�ւ������ꂸ�ɁA���傤�܂ŕ��b�Ă����ꂽ�̂��H)
�Ƃ����s�R�����ł������B
�������A�ނ͌����A���̎����A�P�ӂɂ����Ƃ�f�p�Ȗ{���ƁA�l��M���鏃��Ȑ���悢�B�ŁA���������^�₪�킢�Ă��A�ނ��ނɂ��铚���́A
(�����ƁA��f���̍������A����Ɏ������Ă��ꂽ�Y����ɁA����Ȏ��܂ŁA�ׂ��ɏ����͖̂Y��Ă�������ɂ������Ȃ��B�\�\�����āA���������A����Ȓ��C�̂Ȃ���������A���ꂪ�d���Ă��邱�Ƃ��A�I���b���肵�Ă����łɂȂ�̂����킩��Ȃ��B�c�c�����A����ǂ́A�]�Z�̒吷����A�b���Ă����A�����������ƁA���C������鎖���낤)
�Ђ�����A�ނ́A���̋g����A�҂����˂��B�\�\�ɐ�����A���������ė��Ă����B���邢�́A�ˑR�A����������A
(�\�\�����Y�B�낳���֗���)
�Ƃł��A�Ǝi��ʂ��āA�����Ƃ��A�����邩�ƁB
�҂ĂA�����B�Ȃ��Ȃ��A�Ȃ�̋g�����Ȃ��B
�����B�\�\�H�̏��߂ł���B
������A������̂₩���ɁA��Q�̖K�q���������B
�K�q�����́A��������̐l�X�炵���A�����A�s�V���ڂ��̗��قɁA�������Ƃ��āA���炩���߁A�g���������āA�E��b�Ƃ̓��ӂ����������A�ߑ��A���������A���l�Ȃǂ��S�ɂ̂��ė����y�Y�̕i�X�܂ŁA���������肽�ĂāA���Ƃ��̂��̂�����֘Ȃݕ����̂������B
�u����́A��������̝��A�U�����G���ɂ�����܂���B�z�����A���������̌䍃���ɂ��A�����āA�e���イ������\���������A��s�����������˂Ă���܂����́A���������A���y�Y���ɂƂȂƁA����ڂɂ�����ƁA�܂���o�Ă�����v
�ЂƂ�A�G�������A���ւ͂����āA�ق��̘Y�}�́A����ɂ̂����A�����A��b�Ƃ̏�B�������߂ցA�\�����ꂽ�B�@ |
�����l�G��
�G�����A�����Y�̖S�����A���ǎ��ƂЂƂ����A�Ⓦ�n���̖k�ӂɁA���ォ�������˂Ă���y���̑����ł������B
����̋��ق������A����̓c���ɋ߂��c���ɂ���Ƃ��납��c���m�����Ƃ������A�U�����Ƃ�������Ă���B
����͐��������̍Ⓦ�y�������A��n���������̉����Ђ��Ă���Ƃ��납��A��������������Ă����B����������āA���E�A�������狞�s�ւ��o�āA��Ԃ��߂���A�܂��ߔN�A����m����C�����A���̌n�}�A���́A���s�Ƃ̐ՂȂǂɂ����āA���悢��n���I�Ȑ��͂������Ă����B
�Ƃ��낪�B�\�\���鉄��\�Z�N�̎��ł���B�G���̕��S�̔z�����A���i�Ƀ^�e���Ղ��āA�������J�߂�ꂽ�B�@�K�Ƙr�͂̍R���ƂȂ�A�ʂẮA��������悤�Ȏ����ƂȂ����B�����̂������J�߂ɂ́A������Č������邱�Ƃ̋����̂��A�ޓ��̓����ł���A�܂��A���������������҂̎��R�Ȑ��Ԃł��������B
�G���́A�܂��A�l�\�O�́A���C�����ł���B�����ł��ʼn߂݂���������Ƃ����Ƃ��낾�B�ނ́A�Ɛl�Y�}���������イ�������āA���i�̒����P�������B�����č����Ђ炢�āA�����̎��Ƃ���Ă���҂�D���Ԃ��A�M�̂������āA�킪�قւЂ��������B���̍ہA���l���̎i���̖�l���E�����A�܂��A������āA���q���Ă�����A�R�Ղ̂��������Ƃ͂����A�����ȗ��\�����̂ł���B
����́A�����ɁA�����ɑ��ł�����A����A�ۊւ�������Ƃł��A�R�X��䂵�����Ƃ��A��߂̌R���A�����������悤�Ƃ����B�G���ꑰ���A����ɂ������āA������ƂƂ̂��A���d��ɂȂ邩�ƌ��������A�����A�s�ɂ��āA�����̒n�Ɍċz���A�܂��A�������̂��ꂩ�ɁA���̂Ȃ��������ނƂ��ẮA���d�͋��ƁA�����o���Ƃ����B����͌����A�����ɂƂ݁A�����̈Ӓn�ɂ̂��āA�`���̍��A�c�n�A���E�\�\�܂������ΐ����܂ł�q������悤�ȉI�������ł͂Ȃ������B����܂ł́A�����ɂ������߂Ȃ��A������̍s���ɂ��A�v�Z�����j�ŁA����ǂ̎������Ђ��N�����@����́A���ĂȂ��������A�ނƂ��ẮA���ɁA�����̂炳�Ƃ��������A��C�̂������Ƃ���Ƃ��������A�傢�ɉ����Ă����̂ł���B
(�ÂāA�߂ɕ����A�����Ȃ����A��̌v�Ƃ��ׂ��ł���)
�ނ�������ŁA���߂����̂ŁA�ꑰ���݂ȁA������̂āA���������m�������傤�����Ɉ˂��Ė�߂̎g�߂Ƃ��ĉ������ė������R�̎�ɂȂ���A���N�����\����b�߂��̂����܁A�����̌��L���˂���A�����������ƁA���储���������\�\���ׂď\���l�A�d�߂ɂ��z���͂���Ƃ����n����A�ɓ��̓�[�ցA�����ꂽ�̂ł������B
�����āA�z���̍ߐl�ƌ��������������ƁA���悻�O�N�B
���̂������ɂ́A�ނ̍Ȃ̉���������āA�s�̑劯�����̊ԂɁA������͖Ɖ^�����s���Ă������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�O�N�ɂ݂����A�͂�邳�ꂽ�̂́A�܂��ɁA���̌��Ƃ����Ă悢�B�������A�A�����ċސT��A��N�̗]�ŁA�����̊��E�ɂ����������̂́A�Ȃ݂Ȃ�Ȃ����̐��Ɖ����̗͂ł��������B
�����ŁA�G���́A�����̂��߁A�܂��A���̐܂ɂ��������Ĕ���������E��b�����ցA�����˂āA����ȉ�������������������āA�͂��㗌�����킯�ł������B�\�\�n���y���Ƃ͂����A���������K�q����낱�ʑ�b�Ƃł͂Ȃ��B�������A�ނ��}����ɂ��A�قƂ�ǁA�s�̏����Ƃ����Ȃ����������B
������̂Ђ�₩�Ȓ뉀�ɂ́A�����̂���������A���R�̏���̂悤�ɂЂ��A���������̐�̂قƂ�ɂ́A���ĂƂ��낤���u����A���Ă̗���́A�����̋q�̂��߁A�����镗��ƁA��������������Ă����B�����āA��̎�Ƃ���nj��y������Y���A�y���G���̓c�ɚ����Ȃ�������Ƃ́A�_�D�̍�������Ƃ���������������B
|
���������낵��
�u���ɐl�A���ɐl�B�c�c�������̌����Ђ炫�A�ޓa��ǂ̂̂���O�ցA�����̋q�l���A���ق���̔n���A�g���Č������Ƃ̋��ł��邼�B�\�\���́A�p�ӂȋ}���v
�E��b�Ƃ̘V�Ǝi�A���ꂨ�݂��́A�悭�����Ɏ������Ă���̂ŁA���̎҂ցA����ʂ��邱�ƁA�����A���̂悤�ɁA���ǂ��ǂ����B
����̌꒲���܂˂āA�G�F�����̎҂��A
�u�S���Čv
�ƁA���Ȃ���A���������A�Ȃ��b��V�l���A�����������̂ɁA�Ăѓ����āA
�u�䌣��̉��쎭�сB�������܁A�ޓa�̂���O�ցA�g�Ђ��ĎQ�낤����ɂČ�B���炭�A����҂��v
�ƁA�ǂ��Ə����B
�b��́A����ɁA���̏��҂ɁA����������A��ɕ������āA�I�ł̉����ɁA�Ђ��܂����Ă����B
�u�����Y�A���ւ������Ă��ꂢ�B�c�c�����Y�A���ւ��v
�G�F�����́A���̂��ŁA���������Ă����B�r�C���̂悢�n�Ƃ݂��A������ƁA��ɂ����Ȃ��炵���̂ł���B
��������A���g�����̊Ԃł��A�n�ɂ����Ă͑��n�̏����Y�\�\�ƁA���ꂾ���́A�ʂ�҂ɂȂ��Ă����B���ہA����̎�ɂ������āA���ƂȂ����Ȃ�Ȃ��n�͂Ȃ�����ł���B
�����Y�́A�����A�n���D�����B�n������ƁA���e�̎҂�����悤�ȋC�������B���́A�̋��̂Ђ낢�V�n���A�n�̂ɂ����Ɋ�����B�܂��A�匋�m�q�̔n�[�ŁA�n�ƈꂵ��ɁA�Q�m�̒��ŐQ������������A�n�̕��ɖ����āA���������������߂������̂������o���t���Ȃł��Ă���B
�u�������B�S�����B�\�\�����Ă悢�v
�����Y�́A��������A���ւ������Ƃ��āA��������A���B
�����Ĕn���r�C���A�Ȃ��߂Ȃ���A���������ƁA�M�l�̂܂��ɗՂޕ������Ƃ点���B
�q�̏G���ƁA��̒����́A�L�̊Ԃ֏o�āA�����Ă����B
�u�c�c�فB���̔n���B�Ȃ�قǁA������ȁv
�����́A������ق��߂āA������ɏ܂߂��B���̑�b�́A�r�̏���ɂ́A�Ђǂ��Â��Ă��邪�A��n�ɂ́A�܂�Ŏ�͂Ȃ��B�������A�����J�߂�̂́A�n�́A�ݕ�������ł���B��ɁA���n�Ƃ��Ȃ�A����͋����ׂ��������Ƃ������Ƃ́A�悭�m���Ă��邩�炾�����B
�G���́A���蕨���A�C�ɓ������ƌ��āA����ɁA�����Œ�֍~��Ă����B�����āA���̔n���A�����ɖ��n�ł��邩�Ƃ������I�m���������ނ��āA��ォ����������B
���̂��Ƃ��́A�ǂ����J�ɏq�ׂĂ��A������Ⓦ�Ȃ܂�̑e��Ȍ�ł���B���ꂪ�A���Ȃ������A�S���Ђ���āA�����Y�͔n���킷��āA�G���̊���茩�Ă����B
�N�̍��́A�O�\���A�ォ�B�畆�̐F�����A�����Y�ɂ́A�̋��̂ɂ��������������ޓy�F����������̎��傾�����B���́A�e�ŁA��͂��꒷�ł���A�ʒ��Ȋ{�����Ƃɋ߂�������ɁA���q�ق��낪����B���̍��q�ɁA�т������Ă������߂��A�����Y�̊�ɂ́A���܂ŖY��Ȃ��L���ɂȂ����B
�u����c�c���ɐl�B�Ȃ�ł����́A�킵�̊���茩�Ă��邩�v
�G���́A�ނ̂Ԃ����Ȏ����ɁA�s�������ڂ����̂��A�₪�āA�n�̐������I��ƁA�����������B
�u����A���s�����ł͂���܂��ɁB�W���W���ƁA�s�C���ȓz���v
�����Y�́A���ꂪ�A�����̎��ւ��͂������Ǝv�����̂ŁA�͂��ƁA�g�������߁A���ɂ����炸�A�n�ցA�ʂ������Ă��܂����B
�u�����A�ǂ����ꂽ�̋q�l�c�c�v�ƁA�ʂ����āA�����́A������߂ā\�\�u���́A���ɐl���A�䑶�m���v
�u����A�����m��܂��ʂ��c�c�v
�u�Ȃɂ��A�e�������������B���̏��g�́A�������Ƃ̍����Ƃɋ߂��A�����̗ǎ��̎q���Ⴊ�́v
�u�ǎ��H�@�c�c�ƁA�������ƁA�����̖L�c�̋��ɂ������ǎ������Ƃł������܂����v
�u���������B�m��́B�헤�̍�������Y���莆�����āA�����A�s�݂��ǂ�ȓ��A�̂����āA�����ɂ����Ƃ܂�A�Ƃ����A���e�͂炩�炽���Ƃ��A�܍����̂ނ��������Ҍ́A�����A���Ƃ̉��l�̂����ɂȂƁA�������낵�ɁA���g���Ă��ꂢ�Ƃ������̂Ł\�\���̂܂܊قɂ����Ă���v
�u����́A�S���ǎ��́A���Ԗڂ̘�ɂ������܂����v
�u�����āB�O�j���A�l�j���A���̂قǂ͕ق킫�܂��ʂ��A�ǎ��̎q�Ƃ́A�����̏�ɂ��������B�����A�O���Ƃ̏�����Ȃ̎q�ł����낤���B�Ƃ�����A�݂Ȏq�ƁA�����̓Y����ɂ��A���Ƃ��̂������҂���B�����A�e���������Ȃ�A��邵�Ă�ꂢ�v
�����Y�́A�n�ɂʂ������Ă��鎨�ցA���̂܂����Ȑ����A�����A��������ƁA�n���Ȃ�̂悤�ɕ�����S�n�ŁA�����ɂ́A�����Ƃ�Ȃ������B
�����̂��Ƃ̓r������A������ƁA�����t��̂ڂ��Ă������߂ł���B�M���A�[�������ʂƂ͔��ɁA�̂͂��ނ��A�ł̖�I�ɁA�g���ς��Ȃ��قǁA���������ƁA�ӂ邦�ɏP���Ă����B
�@ |
���V����
�핽���吷�́A�����N�̊�ɂ��A�Ⓦ�҂Ƃ́A�����Ȃ������B���̍����Ɏ��āA�w��������A�ʖe������������i�����A�s�̒m�����A�g�ɂ��āA�����^�������܂˂́A�D����˂ɖY��Ȃ��B
�g�����Ȃ݂������B�������܂��߂ł���B�L�ׂȐN���\�\�ƁA����ɂ��A���S����Ă���B
�߂Ă��鑠�l�����낤�ǂ̂�傤�ɁA�]�ɂ�����ƁA����́A���쓹�����݂̂̂������̉ƂցA�������K���ɒʂ��Ă����B
�����́A�I�єV���̂�䂫�ȂǂƂȂ��ŁA���㐏��̖��M�ƂƂ����āA���̓��ɂ����ẮA��������l���������A�Ƃւ����˂Ă݂ċ��������Ƃɂ́A���̉��~�̂Ђǂ��n�R���ł������B�\�\���A�l���Ă݂�ƁA����̊��ɂ�����g���́A�����L���傤�Ȃ����ɂ����Ȃ��̂ł���B�j���⏑�L���ɁA�т������������̂��̂ł���B
����ł��āA�N�͂����Z�\�������A�q�������A������������B���ւ̔��͕����Ă��邵�A�����Ƃ݂�Ȍ˂��K�^�K�^�Ȃ̂��B�����āA�@���̑�䩁X�������ɂ́A�c�������Ȃ��̂��ނ������Ă�������A�c�q���A�H�����˂����ċ����ʂ��Ă��鐺�܂ł��\�\�₵���͍L�����\�\���ƂȂ������ɁA�����ꂵ��ɒʂ��Ă���B
�����A�����́A���Ƃł���B�M���̂��ɁA�����Ǝ��̓V�n���y����ł���ӂ����B�������A���̘V���Ƃ́A�s�V����邭�A�ĂȂǁA�������͂��Ԃ��Ă��邪�A���������̂̒��߂̂����̑��Ȃǂ����������āA�b�ɋ�����ƁA�������ĕG�ɂȂ�A�тԂ��������˂�r�����L�o���ɒk����̂ł���B
�͂Ȃ��D���ŁA���w�̂��ƂɂȂ�ƁA�����M���邪�A���ȏ�A�����ɂȂ�̂́A�������ӂ�ł������B���ǂ���ɂ��āA�ǂ����畷���̂��A�Ȃ��Ȃ�����ʂł���B�����āA���_�́A�����A�u���������́A�s������v�\�\�ł���B���ꂩ��A�܂��A
�u�N�����A���V�ɂ��Ȃ�����߂��B���������́A������ł́A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�������������𗣂��Ȃ������́A����������݂͂Ȃ��B�c�c���A���܂Ɍ��ċ������B����Ȃ��Ƃ��A����Ă��邤���ɁA�����A�N�邩������B�V�������ꂴ����r�������B���́A�E�W������Ȃ��A�l�Ԃ�����ˁB���̐l�Ԃ��A�n�̒�ɁA���݂��ӂ��ނ��Ƌv�����ƁA�₪�āA�n�M�ɂȂ�A�n�k���A�h��o����B�n�k�Ȃ����ȁA��n�k������Ă���B�\�\���^�̎����A����Ƃӂ邦�オ���������ɁA�܂��A���R�����Ȃ��A�����ɂ����݂��Ă���B����ǂ́A�����P����Ă��邩�����B�킵�ɂ͕���ȁB���ꂪ�ǂ�ȉ��삩�͕���Ȃ����A�P��b�Ă��邱�Ƃ����͂���������v
�Ƃ����ӂ��ɁA�����킷��A��Ђ������̓���m��ʂ��ɁA�c����墂��A墒@���ŁA�@���Ȃ���A�������ؚ̉���~���̂̂���o���̂ł���B
�����Ȃ�ƁA���ʂׂ��Ƃ������Ȃ��C�����Ȃ̂ŁA���傤���A������K�˂Ă����핽���吷�́A
�u�搶�B�c�c���́A������ƍ����́A���邨���̋��ցA��蓹���܂��̂Łc�c�v
�ƁA�����������������B�\�\����ƁA�����́A
�u�A�A�����c�c�v�Ƃ��낭��N�������߂āA�������A���������̊W�ӂ������Ȃ���A
�u��蓹�H�@�c�c�ǂ��̂��فB�̂̉�ł����邩�́v�ƁA�����˂��B
�吷���A�������ڂ������Ă���E��b�Ƃ̌�q���A����t�コ�܂̏��ց\�\�Ɠ�����ƁA�}�ɁA����Ŏv���o�����悤�ɁA�����́A���ĕG���グ�āA�������̏��I����A�꒟�̏��̎�{�����A������ɁA�ނɑ���B
�u�������ƁA�����܂ꂵ�Ă����̂��Ⴊ�A�C�������܂�̂łˁc�c�����Ƃ������A���ł��������̂ŁA�����Ƃ�����B������A�t��N�ɁA���������Ă��ꂢ�B�c�c�����Ă������Ƃ���ŁA�ǂ����A�낭�Ȏ�K�������܂����ˁv
�u�������܂�܂����B�ł́c�c�������ɁA���������肵�āv
�ƁA�吷�́A���X�ɁA�����̂��牮���R�Ȗ���������B
|
���₽����l
���̗[�ׁA�t��ɉ�A���̎�{���A�n�����B�����āA�����̂��Ƃ��A�a�Ղ��������킹�A�������Ă���A�A�낤�Ƃ���ƁA�����Ɏd���Ă����̔ɐ����A
�u�Z��B������ƁA������c�c�v�ƁA�����̏������ւ܂˂��āA�����������B
�u���n�̏����Y���A�s�֗��āA�E��b�ƂɎd���Ă��܂����A�܂��A�䑶�m����܂��v
�u�c�c�����Y���v�ƁA������ƁA����Ȋ�����ā\�\�u���܂��́A������̂��v
�u���B������A�{��̌��r����ŁA��܂����v
�u���܂�e��������ق��������ȁv
�u�Ȃ��ł����v
�u�헤�̕��ォ��A���������ė��Ă���B�킵���A��x���܂��ɁA���ӂ��悤�Ǝv���Ă����̂����c�c�v
�u�͂āB�ł��A���̕��オ�A�E��b�ƂցA�Y����������āA���ɏC�w�����Ă���ƁA��˗��\�����̂ł͂Ȃ��̂ł����v
�u�C�w�Ȃ�āA���̒j�ɁA���m�Ȗ]�݂���B�c�ɂɂ����Ƃ�����A�e��Ŗ\�ꁦ�m���������Љ������A83-14�n�ڂŁA�l�ɂ��A�����Ă��������Y���B�ǎ��ǂ̖̂S�����Ƃ́A���オ�A����̑�f���Ƃ��āA���Ƃ��ƁA�Ƃ̂Ԃ�ʂ悤�A�ꑰ�⏢�g�̏��������Ă����Ȃ���Ȃ��ɂ���c�c�B���������_����A�����Y�̐��i�́A�������낭�Ȃ��Ǝv���Ă�����炵���ȁv
�u���Ⴀ�A�����Y�ɁA�L�c���̐Ֆڂ͌p�����Ȃ�������Ȃ̂ł��傤���B�������A�����͂����Ă��A�����Y�́A�܂�����Ȃ��ǎ��ǂ̂̒��j�����A���̌���Ƃ���ł́A�������������قnj��ׂ̂��鐫�i�Ƃ������܂��v
�u�ɐ��A�ɐ��c�c�v�ƁA�吷�́A�Z�Ƃ��āA�����Ȃ߂�悤�Ȋ�Ł\�\�u�߂����ȉ������A�݂���ɁA���֏o�����̂���Ȃ��B�������A����̂��|�ނ˂ɂ���āA�킵�͂����Ă���̂��v
�u���l�ЂƂɂ́A����Ȃ��ƁA�\���͂��܂���v
�u�����тɂ��c�c�B�悢���v
�吷�́A�����������B
������A�����Y�Ɩ������ƂȂǁA�����A�����o���Ȃ������Ɂ\�\�ł���B�ł��A�ɐ��́A�����Y�ւ̕Ԏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���A�Z�𑗂��āA�@�O�܂ŕ������B�����āA����ƂȂ��A�����Y�̊�]�������Ă݂�ƁA�吷�́A�j�x���Ȃ��������B
�u����Ȃ��ƁA�t��l�ւ��A�E��b�Ƃւ��A�����݂ł��邷���̂��̂���Ȃ��B�悹��A�悯���ȁA�����b�����́v
���ꂩ��A�������������B
�u�킵�����āA�����A���V��̕��߂ŁA����ɉ���Ă����B���̎��A�����Y���A���~�������ɁA�������������ė������ɂ�������A����ĂāA�g�����炵�����ȂB�E��b�Ƃł��A�G�F�̒��֓���āA���ɐl���炢�ɂ������p���ɂȂ��Ă��Ȃ�����Ȃ����B��������Ă��A�킩�邱�Ƃ��B����Ȏ҂ɁA�e�ފ炳�ꂽ��A���ɁA�e�����Ȃ��ė���ꂽ��A����܂ŁA�����悤�ɁA���͂��猩���Ă��܂��B����́A�o���̏Ⴓ���ɂ����Ȃ�A�Ȃ�̉v�ɂ�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���܂��ɂ����āA���邾��v
�ɐ��́A�Z�̂�����p���A�閶�̂Ȃ��Ɍ������ā\�\�Ȃɂ��A�Z��Ȃ���A�₽���l���Ȃ��Ǝv�����B
�������A�ނɂ́A�Z�̈ӂɂ��ނ��Ă܂ŁA�����Y�̂��߂ɁA�P�Ƃł������E�C���Ȃ��B
�����A���ꂩ��́A�w�߂āA�����Y�ɉ��Ȃ����Ƃ̂݁A�S�����Ă����B
|
�������̔n��
�����Y�́u�s�ւ̗��v�́A�悤�₭���^�ɂ�����Ă����B
�s��m��Ȃ������߂̓s�ւ̗��́A���Ȃ����̎q���A�݂ȁA�����ǂ͂ЂƂ������키�Ŏ��̋�t�ł͂������B�����Y�ƂĂ��A�����ނˁA�����̐��̖��̎q�����ƁA���Ȃ��Q���ӂ�ł����킯�ł���B�����ގ��g�ɂƂ�A�Ƃ莩�������Ɍ����Ă��锖���݂����ɂ����Ƃꂽ�B
�u�E��b�Ƃ́A������A�ꐶ�U�ł��A�r�h�̏��ɐl�̂܂܁A�������낵�ɂ��Ă������肾�낤���H�v
�Ⴂ�O�r���A�����������������̕s���s���́A�ȗ��A�����Y�̋��ɁA�������������[���ӂ��łƂȂ����B
�����̋q�A�G�����A�E��b�Ƃ�K�ꂽ�����A��̒������G���ɂ��炵�Ă������ƂɈ˂��āA�ނ́A�����̉^���̑O�r���\�\����A�O�r�������Ȃ��A����b����Ȃ��̂��Ƃ����^�����\�\���߂āA�g�ɒm�����̂ł������B
�u��f���̍������A�ق��̏f���߂���A�Ă��悭�A������̋�����ǂ����̂��B�c�c�E��b�Ƃւ́A���ݏ�́A�����s�֎̂Ďq����A�g����ؕ������Ȃ��������̂��v
���ɂ��āA�����m�������̂́A�����̉����A���݂̋����B�\�\����݂́A�Ƃ�̒��Ŗ�X�ƁA�Ƃ��R�₷�����ɉ߂��Ȃ��B
�\�\�̋��̏�������ǂ��́A�ǂ����Ă��邩�B�q�̔n�́A�ǂ��Ȃ����낤�H
���D���A�܂��A�s����������B
��ɁA��f���̍����́A�ꂮ�낢���d���A�����炩�ɁA�ǂ߂Ă������ł́A�s�ɂƂǂ܂��āA��ނȂ�����]�ɂ�������́A���b���A�����A�낤���\�\�Ƃ́A���x���l�������Ƃ������B
�u�����B�A������A�f���������A�ǂ�Ȋ炷�邩�B��f�������̐��͂��ނ����ɂ܂킵�āA�����̏������͂��A�ǂ�قǂɑR�ł��邩�H�v
�K�R�ȁA�����킢���̂��\�z����Ă���B�����炭�A�����̋A����҂��̂́A��ƁA�n���炢�Ȃ��̂��낤�B��������ȓz�X�A�Ɛl�ƂāA�M�����Ȃ��B������A��f��������|��Ă���ꑰ�������炵�Ď������}����͂��͂Ȃ��B�\�\�����ӂ肩����ƁA�A���̓r�Ƃւ̕s�C�����́A�s�ɂƂǂ܂�����A�����ƈÂ��\���ƁA���݂Ƃ��A�����̂ł������B
�u�c�c����A���͋A��܂��B�A���Ă����߂��B���ꂳ���A��l�O�ɐ�������A���R�A������������B�c�c�܂��A�����́A���������A�����m���ĉ����邾�낤�B�h���̂��ǂ��낾�v
�����Y�́A�v���������B
�����āA�ЂƂ���r�ɐl�́A���b���ƁA�r�̗ւ�A���������A�����ƁA�Q�������l���v�ɏ]���āA�Εׂ��|�Ƃ����B
�����āA������̋��҂ł́\�\
�u�ɐ��ǂ̂́A���Ă��Ȃ�������B���̗��݂́A�ǂ��Ȃ����낤�v
�ƁA�����̖ɂ��ނ̕Ԏ����y���ނ��Ƃ��v�����������A�ɐ��̎�l����t����r�������Ɍ�������ł��A�ɐ��̂������́A���ꂫ�茩�����Ȃ��B
�N�͕��āA������N�̏t�A�����́A����b�ɏ������B
�C�������A���Ƃ̉�̎Q����A�t���ЎQ���������Ⴓ����A�ЂƂ�̑�b�̏��i�ɁA������������A�܂�ō��Ƃ̌c���݂����ɑ����ł������B�\�\����b�Ƃ̌��ւցA�g���w�@�̕��݁h������ׂ̂邽�߂ɁA�����ė����B
�g���݁h�Ƃ����̂́A�s��̈Ӗ��ł���B
���w�@�o�g�҂́A�����N���炢�Ȋw������B���A���̂��������ɁA���̉Ԃ�}�������A���߂̐F��B���܂ł������낢�ŁA�X�Ɨ������A�j���ق̌��ւ֗��āA�ꎌ��悵�A������̂��āA�Ђ������Ă䂭�B
�������̒N�����A���������Ƃ��A����ɂ�낱�т�����Ƃ�����ƁA���Ȃ炸���́g���w�@�̕��݁h���A�����̖�Ɍ���̂��A��ł������B���Ƃ��Ɠ��������n���āA�������̕ی�̂��ƂɁA�w�@�o�ς��ێ�����Ă��邽�߂ł���B
����͂Ƃ�����A�����Y�́A�����A���́g���݁h�̒��̈�l�ɁA�ɐ��̎p�������B�܂��A�ɐ��̌Z�\�\�吷�̎p�������B
�u���B�c�c�]�Z����������v
�ƁA�C�Â����Ƃ��A�������ɁA��l�Ƃ��A�����̕��������悤�ȋC���������A�Ȃ����A�吷���ɐ������������Ă��܂����B�����炩�ɁA������l�q��������ꂽ�B
���̎��ɂ��Ă��A�ނ́A���Ȃ莞�������Ă���A����ƌ�����悤�Ȋ�������B
�u�c�c�������B�l���Ă݂�A��l�Ƃ��A�����̑��q���B��f���̕����炢���Ă��A������悭�v���Ă���킯�͂Ȃ��B����́A�����邨�߂ł����j���낤�B����ȓz����A�]�Z�ƕ������A���ݎ��̋g����A�����ɁA�҂������ꂽ��c�c�B�����A����͍����̏���ɏ����ꂽ�Ƃ���A�ق�ƂɁA��݂Ȑ��ꂩ������Ȃ��v
�ނ́A�����̔n���ɂ��A�C�����ė����B
|
�����z�Ԃ̌N
�����͂悭����Ă���B�Ԃ�Ԃ�Ȗݔ������͂��������B�����ŁA������̍���b�́A�Ă܂��̂��������Ƃ����A�{���̒�]�ɂ��Ȃ��Ă���B���l��������悢���Ƃɂ��A��قǂȐ����ł��Ȃ�������A�^�Ă̎Q���͂߂����ɂ��Ȃ��B
�������A������̊ق̊nj��́A���ӂ̂悤�ł������B���y�ɂ́A�����ނ��Ƃ�m��Ȃ��炵���B�����Ƃ��A���ΐ�̏㗬����O�\�Z��͒�̂����̂悤�����A��a��ޓa�̉��ɂ́A�����炬�𗬂��āA�����ł́A����������硂��Ƃ܂����낤�͂��͂Ȃ��B��ɁA���z�Ԃ��������̚�́A�����m���₩�璷���n��L�����ւ��āA�����̍O�J�a���y�Ȃ��\���Ƃ����Ă���B
�ނ����A�͌�����b���Z�݂Ȃ��Ƃ̂Ƃ���́A������\�̒�����肩��^�������A���̘Z���̓@�ɂ������A�����̉����������܂̌i�������āA�s�̂�����߂��A�����������݂̊C�����܂ɋ[���A遚��̐�����ւ����Ƃ������A�����ɂ́A����قǂ����ȋC�����Ȃ��B�ނ���A������`�ł���B���z�Ԃ̚�ɂ́A�������ЂƂ�̉��l�����A�����܂��Ă��Ȃ��B
���l�̖��́A��(��A�����̏�)�̖����Ƃ��āA���z�Ԃ̌N�Ƃ��Ă���B�V�c���͂��߁A�����āA��v���Ȃ͂�����܂��Ȋ����Ƃ���Ă��鐢�Ȃ̂ŁA���̌N���A�����ɂƂ��āA���Ԗڂ̕v�l�Ƃ����ׂ����Ȃǂ́A�F���̂�����łȂ��B����ǁA���Ԃ���ׂ��́A����ɂ��A���߂���b�̈��l�ł�����̂��A���̂܂ɂ��A�����炱���ɏZ�ނ悤�ɂȂ����̂��A�@���ł��m��҂��Ȃ��̂������B����݂̂��A���f���������₩�܂��������K���ɂ����āA���̌N�̐g���ɂ��Ă��A�N�m��҂��Ȃ��̂ł���B
���̕s�R���A�����Ƃ��I���ɂ����₩��Ă���̂́A���i�����̉A���Ƃ�����ʂ�A���Ƃ����Ă��A���������ׂ̎d���l�тƂ����ł���B
�u�c�c�������v�ƁA�����A�u�c�c����A���ʁv�Ƃ����B
�u����́A����ƁA�_�Ԃ����܌������v�Ƃ����̂�����A�u���Ⴀ�A��������Ƃ��A�����ǂ͔`���Ă݂Ȃ��Ắv�ƁA�鉑�̉Ԃɖϑz�����̂ł������B�ȂׂāA���M�ȏ���Ɉٗl�ȁA�ϔO�ɂ������͖̂}���ڂ̂˂ŁA���̂����₫�́A��S���ǂ��ւ��ĂāA�ׂ̐H���̂ɂ����ɔ�����z������̂ƈقȂ�Ȃ��B�������q�\�q�\�����A�������܂����̉��́A����������Ȃ��B
���̎��z�Ԃ̚�ւ́A�V�Ǝi�̐b��̂ق��́A��|���̎ɐl�ł��A�j�́A��邵�Ȃ��͓���ʂ��ƂɂȂ��Ă��邪�\�\��l�������Ƃ����K�^�Ȃ��l�̎G�F�̂͂Ȃ��ɂ��ƁA�u���N����͎v���̂ق��A��\�l�A�܂Ɍ���ꂽ���A����͂����A���̐��̂ЂƂƂ͎v���Ȃ��B�ĂȂ̂ŁA�����������ɂ������W�F����������݂������ɁA���߂������̂̏P�ːF��݂ɂ̂������A���₩�ȍ����́A���̐l�̐g��قǂ����邩�Ƃ����v��ꂽ�B�����������������A���ɂނ����Ă���ꂽ�̂��A�Ȃ��Ό����ꂽ����݂������Ɍ����̂����c�c�v�ȂǂƁA�R���������̌`�e���ł͂Ȃ��Ȃ���������Ȃ����ɁA������Ȃ邳�܂��A�������ĕ������̂ł������B
�����Y���A����͊т����ɂ��āA�ЂƂ������D�݂̌����A�ނ��l�m�ꂸ�~�������Ă��Ă����B�Ƃ��낪�A�͂��炸���\�\����́A�Z������������C������قǐQ���邵�������y�p�̐^�锼�A�����������Ȃ��A���z�Ԃ̌N�̂��������A�����ɁA�������ڂ܂̂�����Ɍ�����悤�ȁA��̎����ɂԂ������̂ł������B
�ނ͎��X�A��������ƁA�ق̗��֔����o���āA���ΐ�̒��ɐg�߁A�Ƃ�W���u�W���u�Ɩ�𐅂ɗV�ԏK���������Ă����B���炾�̍C�⊾�𗬂�����łȂ��A���R�Ȃ鐅�̈ӎu��C�ƋY�ꂠ���āA�{���̖쐫�ƁA�Ⴂ�̔M�ɁA�v���̂܂܂Ȍċz��������y�������A���Ƃ������ʂ�낱�т������B
����́A�ނЂƂ�łȂ��A���̑����̉����ł��A��������߂��ɂ́A�F��鐅���ł������B�������ނ̂����́A�a�̂��l����݂ɐQ��������锼���́A�����̍��Ɍ����Ă����B�l�m�ꂸ�A�Q�ǂ����o���A���ΐ�ƈ�V�̗�����킪���̊�ɁA�͎��������Ƌ��ɂ��邱�Ƃ��A�Ђ����Ȗ��x�ł������̂ł���B
�\�\���̔ӂ��B����A�����܍X�����̍��ł������B��̂��Ƃ��A�܂����ɂȂ��āA�����ɐg���ȂԂ点�Ă���ƁA�Ί݂����������m�X�̉����������肩��A��Q�̐l�e���쌴�̕��֍~��ė����B�������A�����́A�������āA�������֓n���ė���l�q�B�\�\�͂ĂȁH�@�ƌ��Ă���܂ɁA�����̎҂̉e�́A������̊ق̗���ɁA�ӂ���قǂ̌������̂����A���Ƃ݂͂ȁA���z�Ԃ̚�̒z�y�������āA���֑~�������Ă��܂����̂ł���B�c�c�����Y�́A�I�n�A����܂낭���Č��Ă������A�₪�āA���R�ƁA�C�������B
�u�����c�c�B�Q�����B�c�c�Ƃ��Ƃ��A�����ւ�����ė����v
|
����̐��E�l�̐�
���悻�A�����̒����Ԃ�́A���܁A�����Ȃ�M�a�̑��ł��A���̏o�v�̓y���ɁA�܂ʂ���Ă���ق͂Ȃ��B
���̉ẮA�����̕ʑ��̂��т�́A��́A���̋��Ђ��Ƃ����Ă���B���܌��J����ɂ́A�����̌䑧���݂₷��ǂ���ɂ����A�s�G�ȉ������A����s�ׂ��̂����ċ������Ƃ������ł���B
�\�\���A�������ɁA���߂��A������̍��������傤�̓@�ɂ́A�܂����̑������A�����܂ł͂Ȃ������B�l�̐���Ȃ�Ƃ��͂����������̂��Ɛ��Ԃł������Ă����B
�������A���܁A�����Y����Ɍ����̂́A�������ɁA�ӂ��̐l�Ԃ̌Q�ł͂Ȃ��B�܂ӂ��A�������N�������݂������āA�܍X�ɂ������A�����������炵���e�́A�Ί݂̐쌴�ɂ��A�ꂩ���܂�c���Ă��邵�A�z�y�̉��ɂ������Ă���B�O�i���܂��̔E�т��݂ł���B�����ɂ��Ă��A�l���ł͂Ȃ��B����b�����̎��z�Ԃ̚��ڂ����āA�g�D�I�ɁA������݂��ʂ����ɂ��������Q���ɂ܂������Ȃ��B
�u�����ւ��c�c�B�������ł͂Ȃ��v�����Y�́A�������яo���������B
�����A���݂ɁA����������B�����ɁA����������ЂƂ�ł��낤�B�ނ́A���������������܂ŁA�אS�ɁA�����čs�����B�����@�킸�A�g�ɂ܂Ƃ��������B��u�ЂƂƂ��̂܂Ɏv��ꂽ���A���̊ԂɁA�Q�������́A���łɁA����Ԃ�ȍs�����d���������̂Ƃ݂���B�������̖���������ƁA�Ȃ������Ȃ��āA�쌴�̓y���y���~��ė����B
�����Y���A������̂܂��ɁA���z�Ԃ̌N�������̂́A���̂��Ȃł���B
�v���ɁA�ߖ��Ȃ������̂ŁA���z�Ԃ̌N�́A�C�������Ă������̂ɂ������Ȃ��B�ЂƂ�̒j�̏��e�ɕ�����ꂽ�ޏ��̊�́A��܂���ӂ����A����Ƃ��āA���̋��̂��܂��Ȃ��B��������A�����ƍ����Ɋ�����Ă��������ł���B�����Ĉꖼ���֖҂����Ȓj���A�ޏ��̗�����������������ݎ����Ă����B��l������ŁA�Ђ������čs���̂��B�ق��̒��Ԃ��A���ꗣ��ɁA�������ŁA�U�u�U�u�ƁA���Ƃ̑Ί݂ցA�n���čs���\�\�B
�u�҂Ă��v�Ƃ������̂��u�D�_���v�Ɠ{�����̂��A�����Y�ɂ́A�킫�܂����Ȃ������B�ӎ��ɂ������̂́A�u�ԂɌ������z�Ԃ̌N�̔����炾���������B���̔��������A�ނd�ɂ������Ƃ����悤�B�����Ȃ�A���̖����ւ����݂��A�͂����ς��A�����グ���̂��B���łɁ\�\�ޏ��̑��̕��������Ă����j�̉�������A�o�Ȃ���Ƃ����B
�����ƂɁA�����͎��͂��Ă��A�܂����l�Ԃ����悤�Ƃ́A�����A�v�������Ă��Ȃ������B�\�\����ƁA�����Ȃ���A���z�Ԃ̌N��������܂܁A�̂��Ԃ��ցA���߂����B�����đ吺�ŁA�������ւ䂭���Ԃ̎҂ցA�����{�����B
�܂���ɁA���֗����̂́A������ɁA�ق�����������Ă������̓��ڂ炵���j�������B
�u���𑛂��B�����������Ȃ��v
�Ɠ��ڂ͎������B�������ɗ��������������̂ŁA���������Y�̂�����։���āA�݂��݂�����ł��܂����B�����āA
�u����ȏ��ɐl��C�B���ꂪ�ЂÂ��邩��A�Ă߂������́A�������ƁA���������ŁA���n���Ă��܂��v
�ƁA�����ւ��������B
�����Y�́A��������āA�ޓ��̍s�������悤�Ƃ������A��������̌����Ԃ����݂��݂��痣�����Ƃ��ł��Ȃ��B�c�c���A�ӂƌ���ƁA���ڂ͍��̎�ɁA�g�ق��Ɏ��������̓��������Ă���B�����Y�́A���̕��������B
����ɂ́A���ڂ̒j���������炵���A
�u�����������z�b�v
�Ɩi���āA�傫���U��������Ƃ����B�Ƃ��낪�A�����Y�͗���������Ă��܂������A�j�́A���肾�����̂ŁA�����́A�����Y�𗘂��A�����Y�̂��炾���A�Ԃ�݂����ɉ�������ɁA�����́A�ނ̎�Ɉڂ��Ă��܂����B
�u�������E�������v
���ڂ̒j�́A�������ɁA�쑾�����Ђ������āA�x����̂��Ƃ�����A�ނɂ��������B�����Y�͑傢�ɕ|�ꂽ�B�߂��āA�������ɓ������Ƃ�������悤�ɁA�������̂ĂāA�����������B
����ƁA���ڂ̒j�́A���炩��Ə��āA
�u�����҂āB���n�̏����Y�B�������o���Ȃ��̂��B����̕s���l���v
�ƁA�����āA�܂������B
�@ |
����ɔ�������b�̔�
�u�����H�@�c�c�B�I�I�A�o���Ă���B�c�c����̉��ŁA���ɂ������Ă������̈�l���v
�u���ʂ��́A�܂�ʼnڈ��т��̎q�݂����ȁA�s���̓��������B���ꂩ�牽�N�������낤�B�c�c�������A����́A���ʂ������ǎ��̒��j�A���n�̏����Y���Ƃ��������A���ʂ����A�헤�̑坁�����̏���������āA�����̊قւ���ė������Ƃ��A���̎莆�̒��̕���܂ŁA�����ƁA�o���Ă��邪�ǂ����B���̊o�����������낤�v
�u�����B�ǂ����āA����Ȏ��܂ŁA�m���Ă���̂ł����v
�u�͂͂͂́B�^�l����������A���ʂ����A���̗����A�Y���Ȃ̍��ɂ���A������̊ق܂ŁA�����Ă��ꂽ����(�ږ���)�����邾�낤�B���̕��Ƃ��A����̎艺���v
�����Y�͈��R�������ł���B�s���l�̘��݂�������A���}�������A�����A�p�Y�̂悤�Ɍ������������B�\�\�ƁA�s���l�́A�}�ɐe���݂��݂��A
�u�c�c���A�����Y�B���ʂ����A�����ԓs��m�����낤�B������҂ɂȂ����Ƃ�����B�����ǁA�ǂ����ŁA���������ݍ���������Ȃ����B�������c�c���������āA���ʂ��Ɉ�蕿���Ă����Ă��B�܂��A�����̓y��̉��ւł������Ęb�����v
������ɋ}�ł���͂��̑�������������ł����̂ł���B����ǁA�e�ׂ��Ă݂�A��������ĂȂ����R���킩�����B�s���l�́A����b�����́A�ɂ��㖡���A�����Ă���B�\�\������́A������A�ǂ��ɂ��ǂ����A�����x�\�������āA�Ƃ�������Ă��邾�낤��B�ނ́A�������āA�����Y�ɘb���̂������B
���z�Ԃ̌N�Ƃ����̂́A���Ƃ��ƁA���̖{���ł͂Ȃ��A�������A�ޏ���D���āA���̏�����ɁA�����܂��Ă����A���ɌĂъ��킹�Ă���ɂ����Ȃ��B�܂��Ƃ̖��́A����������̗��q�������Ƃ����A��y��������傤�̖���A�����P���˂Ȃ�̍Ȃł���A�����āA�܂��A��N�Ƃ������Ȃ������ɗǐl��S���������Ƃ̌N�ł���B
�����́A���˂Ă���A���q�̗e�p�ɁA�H�w�����������Ă����̂ŁA���܂��܂Ȏ肾�Ă������āA�˗������Ǝ��݂����A���q�́A���邳���v�������A�������āA�I�єV���̂�䂫�̉��ŁA�I�j���ӂ݂݂˂Ƃ����A���Ƃ��n�����꒩�b�̉ƂցA�ĉł�Ă��܂����B�\�\�ƒm���āA�����������́A�܂��~�̍��̐�̈��A����̕��m�������āA���q���P���A�ꎞ�A���O�ɉB���Ă����āA���₨���Ȃ��A���̎��z�Ԃ̚�ցA�₪�Ĉڂ��Ă������̂ł���B�\�\������A�����������ł��Ȃ���A�썇�₲���ł���Ȃ��B�\�͂ƌ��͂ŁA�ЂƂ̍Ȃ��A�D�������̂��B��������ꂪ�A�܂��D���̂́A�s�`�ł͂Ȃ��B�s���l�́A�������ꂵ�āA�͂���Ȃ��̂ł���B
�u�Ƃ���ŁA�����Y�c�c�v�ƁA�ނ͐��𗎂��ā\�\�u���ʂ��́A����b�̏��g���B�����łЂƂA�肪��𗧂Ă�B�ȁc�c�������āv
�ƁA���������A�����₢���B
�����āA�₨�痧���オ��Ɓ\�\
�u���Ⴀ�A�҂��Ă��邼�B����̓��Łv
�s���l�́A�������ɁA�O�������ƁA���ꂱ���A��������C����悤�Ȑv�͂₳�������āA�����܂��A���̌����֓n���čs�����B
�C�����ƁA��掛�̕�̂ӂƂ��납��A�����_���A��邬�����Ă����B���̕ӂ�̔��_����炬�o���ƁA������̌��ɁA�閾���̌����ق̔��ނ̂��߂������邵�ł���B�\�\�����Y�́A������߂āA�����������o�����傩��A���z�Ԃ̚�ցA�킯����ōs�����B
�u�\�\��b�B��b�v
�J��������Ă���Ȍ˂̂ЂƂ�������āA���܂�����Ԃ̂����ցA�����ĂԂƁA���߂��������A�����āA�N����H�@�c�c�ƁA���X���킲�킢����������B���̊Ԃ����肩��A�����Y���A
�u�����Y�ł��B�r�h�̏��ɐl�A�����Y�ɂ�����܂����A�����̂قƂ�ŁA�����������āA����ė��܂����B�\�\�����A������͂������܂��ʂ��v
�Ƃ����ƁA�����́A���ɋ������炵���A�������āA���炭�́A���������������Ȃ��������A��₠���āA
�u����ł��悢�B�͂₭�A�N�݂̔����܂��߂��A�����Ă��ꂢ�B�݂炢�ł������B����c�c�����v
�ƁA�����ӂ��������B
�ނ́A�܂����ɂ���āA���ɂ����������Ă����B���������A��ɂ���ꂽ���Ƃ��A���������قǁA��͂�Ă���B���悢�݂̂́A���̑�b���A�킪�����Ȍ����A��̊����Ɏ{���Ă����̂ł���B
�u�������������Ȃ�A��̌N���A��������čs�����̂��A�����ł��낤�B�c�c�ޏ�����́A�ǂ������B�ޏ��̐g�́v
�u���q���܂̂��s���ł����v
�u�ȂɁc�c�v�ƁA��������������\������ā\�\�u�ǁA�ǂ����āA�����́A�ޏ��̖����A�m���Ă���̂��v
�u���̓��ڂ��A�����Ăт܂����v
�u�����A���̈����߂��H�@�c�c�B���āA�����́A�a�荇�����̂��v
�u�͂��A���傤�ǁA���ӂ́A������葁���ɖڂ��߁A���ɓy��̑��������Ă���܂����B�����ƌ��āA�ǂ��܂����Ƃ���A�吨�́A���q���܂������ŁA��ɁA��̔ޕ��֓n�肱���A���ƂɎc�������̓��ڂ��A�����\���̂ł������܂����v
�u�ǂ��������c�c�B�ǂ��H�v
�u���q�̐g���A���Ƃ�����������A����̂����ɁA������܂��������������āA�����Ƃ�ɗ����B���̓����߂�����A���̑̂́A���ꂪ���R�ɂ��Ă���Ǝv���B�O������A�Q�ԍ]�Ȃɂ킦�̗V���ɔ���Ƃ�����A�T���āA�������ǂ�����悩�낤�B�c�c�ƁA���悤�ɂ��������ē��������܂����v
�����Y�́A��������ׂ��Ă���҂��A�����ł͂Ȃ��悤�ɁA�ꑧ�ɂ��܂�����ׂꂽ�B
|
�����B
����ɂ������Ȃ�B�\�\�����Y�͂��������ǂ߂��ꂽ�B���Ƃ���b�̂���ׂɈ����悤�Ȏ��A�����Ɍ��O�������܂��傤�B�����Y�͓������B�������ɁA�ނ́A�M�����B
�́A���X���̗[�����ł���B
�ނ́A�������炠�������������̈�X�����̂����g���A����̓��̉��֍s�����B
��������Ȃ��B�s���l�����Ă��Ȃ��B
��������������������ӂƂ���Ɍ��������イ����Ă��A���̂�����͖�ɓ���ƁA���������傤�̉H�������悤�ȗ҂����ł���B�V���낤����̏�ɁA�[���������B��ԉႪ�P���Ă���B�ʂ�m�����Ȃ��B
�u�₠�A���Ă����̂��v
�҂������˂āA���S���Ă������A�����Ȃ�؈�����s���l�̐��������B�����Y�́A���ƂƂ��́A���ʂ������āA
�u���̕��ł��v�ƁA�����A����n�����B
�s���l�́A������āA���ƁA������ɂ����艺�̒j�ցA
�u�Ñ�A�a�����Ă����v�ƁA�E���獶�֓n���āA�Ȃ�����炢���̂����ƁA�����Y�����āA�����U�����B
�u�����܂ŁA�ꂵ��ɗ��Ȃ����B�d���͂��܂��s�������A���₩�Ȕӂ��B�ǂ���A��������A����́v
�����Y�ɂƂ��Ă��A������Ɏd���Ĉȗ��A�����鎩�R����͏��߂Ăł���B��ɂ́A���܂��l�̒������A�����ɕ��Ђ��ڂ������Ă���B���ꂾ�ɁA�����łȂ�Ȃ��Ƃ���ցA�ނ́A�s���l�Ƃ����l�ԂɁA���ȗ��A�r���S���Ђ���Ă����B���ꂪ�A���Ƃ��鈫�l���낤���B�M�����Ȃ����A�����A���������Ȃ��̂������Ă����B�\�\�������A���N�̓��A�匋�m�q�̔n�ɂ��A����������������Ă����B�ނ́A���悻���Ǝ��ɕʂ�Ă���A�����������̂ɁA�Q���Ă����B�n�ɂ���A�����ɂ���A�����������ƁA���ꂪ�����������ɂȂ�B
�ӊO�������B�s���l�ɗU���ė����Ƃ́A�l��Z�p���̖ؗ������ɂ����傫�Ȍ����₵���ł���B���̂�����A���������ɁA��˂݂̂�������A�݂ȑR��ׂ�����̌����������B�\�\�s���l�́A�傫�ȕ���Ђ����̑������łƂ��������A�܂�ł킪�Ƃ̂悤�ɂ͂����čs�����B����ɏo�}�������ɂ��A��˂����ׂ����ꂽ�����ŁA
�u�����邩�B���F���݂Ƃ��́v
�Ƃ��������B
�͂��鏬���Y���A�ӂ�ނ��āA
�u�F�����̉Ƃ���B�オ�苋���v
��ɗ����āA�����n�a�킽�ǂ̂��䂭�B�L�̊ԁ\�\�₪�đm���̍L�ԂƂ��ڂ����C��������ƁA�吨�̏����������ɕ������B
�u�₠�B����Ă����̂��v
�u�����s���l���B�悢�܂ցv
�ǂꂪ��l��番��Ȃ��B�����Y�ɂ́A����������������̌��B�������A�ǂ����̌䑂�q�����Ɍ�����B
�e��(��̎��_�A1-2-22)�A�~����~���A�L���Ђ�䂩�����܂��Ƃ���A�t�Ղ��A�Ƃ藐���Ă����B�M���̎q�킽���ɂ��ẮA�E���Ȍ��i�ł�����B�������A���̕����A�l�X�̕����́A���E�̂Ƃ���ɂ��Ă��A���b�ȊO�Ȏ҂����ł͂Ȃ��B
�u����́A����b�Ƃ̏��ɐl�A���n�̏����Y�Ƃ����ҁc�c�B����́A���������A���͖S�����ǎ��B�ʂ��܂������Ă��炢�����B�Ȃ��Ȃ����̂������Ȏ�҂��낤���v
���ꂪ�A�s���l�̏Љ�̂��Ƃł������B
�\�\���������s���l���A�v�������ƁA���߂āA����̕��̒��ԂŌ����Ƃ����A����̎p���A�܂���Ȃ��A����������ɂ������Ȃ������B�s�䂵�����̖������Ƃ́A����قɂ��Ă���B
�u���B�c�c�����v�ƁA���ʂɂ��Ĉ���ł����N�́A�������������āA�����A�C����ɔt���A�����Y�ւ������B
�u���́A��C�̊C���Ƃ����铡�����F�ł��B����ɂ���̂́A���쎁�F���̂̂����Ђ��A�I�H���̂��������A�Î����Ƃ������ȂǂŁc�c�ǂ���u�ӂ̂Ȃ��F�l����B���C�҂̏W���B�C���˂Ȏ҂͂ЂƂ�����܂���B�N���C�y�Ɉ�����Ă��������v
�\�\�C���Ƃ́A��Y���傤����ł��낤�B�����Y�́A���������āA���Ă����B
�����A�傠�邶�͂��̐l�ɂ������Ȃ��B���̂����Ƃ����e���݂Ԃ�́A�ނ��돬���Y���A�܂��������B�ނ́A�����������E�ɂ���悤�ȋC�������B
�����̎q��Ƃ����A�J�ł��ӂ����A�̂̈����邵���A�ق��ɔ\�̂Ȃ����B�y�ł��A�݂Ȉߊ�������A���r�ɂ��܂��A�l�����邱�ƊH�̂悤�Ȃ̂��A���ׂĂł���B�Ƃ��낪�A�����ɂ́A��̏��F�n�߁A����ɂ��A����ȏL�C���Ȃ��B
�����⌠�͂̂��ꂪ�Ȃ����ɁA����C�̂ɂ����́A�N�ɂ�����B���߁A��߁A�z�����ȂǁA�܂��܂��̕��𒅁A�������肠���āA�Ă̖�炵���A�k�_�����ł���B�������ɂ͊F�A�����������Ă����B
���̂͂Ȃ����A�����Y�ɂ́A���߂��炵���A�܂��A���X�ɁA���m�ւ̋��قł������B |
����䑡��
���܂͖��l�ŁA���ƍr��ÂтĂ͂��邪�A�����̓@���A�G��Ȃ̂́A�ӂ����ł͂Ȃ��B���F�̑c���A�������o�ӂ����̂Ƃ��˂̑�Ɍ��Ă�ꂽ�قł���B
���o�́A�z���悤�����A���F�̓��̒��Ɍ��Ђ��ӂ���āA�厁�������̔ɉh���Ђ炢���֔���o����ς����Ƃ˂̒�ł���B
��o�̎��j�A�����Ƃ��Ђ�́A����b�̉h�E�ɂ̂ڂ�A�������^�ƁA�_���Ɍ��𑈂��āA���ɓ��^���쒀�����قǂȐ����I��r�̒j�ł������B
���܂́A������̍��������́A����Z�̗]�����p�������̂ɂ����Ȃ��B���\�Ƃ́A�����Ȃ�����A���̒��ҁA�{��̌��^�A�ӂ��Ȃ���A�������A�ނ̂��̂��B
�\�\�Ƃ��낪�A���Ȃ��ۊ։Ƃ̑��ł��Ȃ���A�������F�́A���ǔ͂悵�̂�̑ォ��A�n�����ɒǂ�����Ă����B����ł��ǔ͂͂܂��A��ɏ������̂��傤�ɂ��炢�܂ł́A�߂����A���F�ɂ������ẮA�ɗ\�̕ƒn�Ł\�\�Z�ʃm���Ƃ����Ⴂ���ʂ̂܂̂Ďq�݂����ɁA�s����Y����Ă���B
���F�́A�s���ɂ����Ȃ��B
�u�ȂA�������Ƃ����v
�ɗ\�ɂ��Ă��A�����̐��߂Ƃ����A����̔��R�S��������āA�f���ɁA���]����C�ɂȂ�Ȃ������B
��ɁA��C���ʂɂ́A�����̈Ђ��A�Ƃǂ��Ă��Ȃ��B�ނ͂˂ɁA
�u����̕��́A����b�����̏]�Z���B�ނ̖��\�́A���͂悭�m���Ă����B���nj��́A��p�����A�ƂĂ������Ȃǂ̂ł���j����Ȃ��Ƃ����Ă����v
���͂̎҂Ɍ���Ă����B�����āA���߂�ᔻ���A�������A�l�|���Ă����B
���������ނɁA�����A�ꖡ�̓}�������ė����̂��A���R�ł���B
�������āA���[�ł���肽�Ăɂ��������̒��őD���P���āA�ŕ��̒D��Ԃ���������肵�o���āA���悢��A���F�̖��́A�l���ł́A�p�Y������Ă����B
�̂ĂĂ��������A���ł́A�悲��A��ߎg�����������āA���F�ȉ��\�\�܁A�Z���̋��Ǝ҂��A�s�֝f���ė����̂ł���B
�u������A������Ƃ����̂��v
���F�́A�����傤�ɏo�āA��ł�Y�����������A�ւ����������B�ۊ։Ƃ̑��ɂ�����A����b�����Ƃ́A�����炩�ȁA���ɂȂ���ނł���B���Ă��܂��āA���ł����ɁA����ނ�ɂ��Ă��܂����B���@�́A���F�̕�����A���������قǂ����āA�ނ����������B
�u�ǂ����B���̂��ƂŁA����ɁA�ɗ\�̝������ցA��K���قǁA���i�̎��߂������Ă悱�����B�c�c�������A������ɂ����āA����̗G�Ȃ��ߗ��Ƃ�������Ȃ̂��낤�B���悻�A�����̐���Ƃ́A����ȂƂ��낾�B���m�Ƃ��A���炵���Ƃ��A�����悤�͂Ȃ��v
���悢�A�s���l��A�ق��̐l�X�̑O�ł��A�ނ́A���������āA���ʂ��̂ł������B�����āA
�u�ǂ����A����ŏ㗌�̂��ł��B�Ȃ��A�؋����āA�H�܂ł́A�V��ōs�����v
�Ƃ��A����Ă���B
�_�̑����A�l���Ȃ��ȑ匾�A�����Y�́A����������������ł���B
����A�����Ə����Y���A�������̂́A���z�Ԃ̌N�̗��q���A�s���l�����ɁA���܂����̂��A���̒��Ԃ����́A�I�H�̓���q�b�������Ƃ������ł���B���̏H���A���쎁�F���A�Î������A�܂�����̕s���l�������āA���ׂĂ����ɉ�Ă����\�l�A�܍���O�\�O�̌��B�ǂ��́A���̏��݂ƁA���c�∫�s�Ԃ肱���A�e��(��̎��_�A1-2-22)���������A����̉��́A��A�̕s�����A���R���ł��邱�Ƃɂ͕ς肪�Ȃ��B
�\�\����X�����B�����Y�́A��l���A�v���o�����B
�u�A��̂��v�ƁA�s���l�́A�ނ̗e�q�����āu�\�\���́A��A�O�������ɁA���z�Ԃ̚�A���Ă�邩��A�D�����̑�b�ɁA���������āA���ʂ����A�J������������������B���̒��҂Ȃ�Ă����z�قǁA��͙債�݃b���ꂾ����A�悱���ƁA�����Â悭�A����˂��߂��B���ʂ��́A�C���ア�B�����Ȃ�A�����v
�ƁA�����������B
����ƁA���F��H�������A���������s���l�̉�����Ȃ��߂Ȃ���A�Ӗ����肰�ɁA���������B
�u���́A�Ԃ����낤���A���̂��炾�́A���̂Ƃ���ł́A�Ԃ��܂��B�s���l�̂��Ƃ��B����A�y���������A��䂤���݂݂����ȏ��̂ʂ��k���A�����čs���ɂ������Ȃ��B�����ɁA���̂��Ƃ悷��̂͂������낢�B�c�c�����Y�A���ʂ����A���̑�b�̊���A���X�A�Ȃ��߂邾���ł��A�������낤���A�������A�����Ȃ�A���̎��́v
�����Y�́A�ӂ������A������ցA�A�����B
���̒��A�ނ݂̂����ƁA���z�Ԃ̚�Ăꂽ�B�����ЂƂ�ŁA�낳���ɁA�������܂��Ă���ƁA�����́A�a�l�݂����Ȋ炵�āA�L�ɂ����ꂽ�B
�u�ǂ���������H�@�c�c�����Y�B�ޏ�����́A�Ԃ��Ă悱���ł��낤�ȁv
�u���ɂ����A�����ł���B�������A�����Y�̕Ԏ��āA�����́A�傰���ɁA�����Ђ炢���B�܂�ŁA�悭������ł��̂悤�ɁA�@�����悭���āA
�u�������B�c�c�C�������ł��������B��V��V�B��A�O�����ƂɂȂ��Ă��A���Ђ͂Ȃ��B���g��������B�ޏ��̑̂����A�߂�Ƃ킩��v
�����āA�Ȃ��A�����������B
�u�������A���ƂɎd���āA�͂�Z�N�قǂɂ͂Ȃ�̂��B���ƂŁA�Ǝi�̐b��ɁA�\���Ă������B�c�c���傤���́A�����Y���A���������ނ炢�ɂƂ肽�ĂāA�����Ƃ����ނ炢�̊Ԃɂ����āA���������Ɓv
����́A�v���������Ȃ��A�����ł������B�����Y�Ƃ��āA���ꂪ�����A���z�Ԃ̌N�̎������Ȃ��O�ł������Ȃ�A�n�ɂʂ������āA����������������Ȃ������B����ǔނɂ́A�䂤�ׂ̏��F�����̂��Ƃ��v���o����āA���܂��́A�����������A���݂����Ă����B
|
���ډ��Ǝ㖡
�ނ́A��Ƃ���A����߂��A�����܂�����B
������A�����߂����̎m�ɁA�旧�Ă���ƁA�݂ȁA���̐F�̕��𒅂�̂ł���B
���F�ɂ���āA�l�̈ʊK��g�����A��ڂŕ��鎞��Ȃ̂��B�F�K���̎᎘�́u���v�Ƃ��Ă�Ă����B�㐢�́A�g��ˁh�h��g�����͂܂����h�ȂǂƂ������t�̋N�����Ǝv����B
���ɁA���n�̏����Y�́A��\��B�\�\�㋞�V�w���Ă���Z�N�ځA�Ƃɂ����A�����ɂ���ƒm���A���̈�l�ƂȂ����̂ł���B�[���A�܂������������ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B
�\�\���̔N�B�H�����鍠�ł���B
����b�Ƃ̗��̉͌��ŁA���J���������B�����Y�́A�����@���������o�����B
�����A�l�͌����Ȃ��������A�����̏��ɁA�����ꂪ�A���̕�ɁA�����Ă���B����̕s���l����̘A���ł���B�\�\�ނ́A����ȗ��A���̕s���l�Ƃ��A�������F�����Ƃ��A������������̌������Â��Ă����B
(��������A����m���܂ŎQ����)
���ʂ͊Ȃɂ��Ė����B�ނ́A������������A�o�����čs�����B�艺�������Ă���B�����āA�ق��āA�ނ��A���₩������Ɖ��́\�\�_�ɗт������̈ꎛ�@�܂ŁA�A��čs�����B
�ނ����́A�_���̖����ł������炵�����A���܂͔p�����l�ɍr��͂āA�s���l���̏Z�ނɂ��������ȁA���ƂȂ��Ă���B��Ƃł���B
�u�₠�A�����Y�v�ƁA�s���l�́A�ނ��}���\�\�u�ق��ł��Ȃ����A���悢��A���F�������A�ɗ\�m���A��Ƃ����̂Ł\�\���̑��ʂ��A�ǂ����悤���A�Ƃ������k�����v
�s���l�́A�܂��A�����Y�ɁA�����ނ������B
���̒��ԂƐe�����Ȃ��Ă���A�����Y�́A�}�Ɏ��̎肪�オ�����B���̖��Ƌ��ɁA�l�ԓ��m�̔��������o���A�s�ɒm�Ȃ���A�Ǝv�����߂��B
�u����̍l���ł́A�����A�������ŁA�F�C���Ȃ��A����ł��Ă��A�Ȃ��傭���Ȃ��B�ЂƂA���F�̋A���𑗂�Ȃ���A�ꂵ��ɁA������M�ʼn���A�]���������̗V���������ĂɁA����ȑ��ʉ����낤�Ǝv���̂����c�c�ǂ����A�ꂵ��ɁA�s���Ȃ����v
�u����́A���ł����v
�u������������Ă̒��A�����ɗ��������A�M�̒��ł����݁A��������ɂ́A�]���ɒ������Ƃ����킯�����v
�u����ƁA�A��́A���̗����̔ӂɂȂ�܂��ˁv
�u�܂��A�O��������Ǝv�������v
�u���܂����ȁv
�u�ǂ����āH�v�ƁA�s���l�́A�ނ̓��f�����āA���������B
�u���������B�܂����A��l�̒����ɋC���˂��Ă���킯���Ⴀ��܂��ȁv
�u�ł��B�c�c��͂�A���g���Ă���g�ł́v
�u�l���ǂ��ɂ��A��������B�\�\���������A���ʂ��ɁA�C���˂��Ă���������Ȃ����B�����A�����B����b�������Ƃ��A�������̒��҂Ƃ��A�v�����炢���Ȃ��̂��B�\�\���z�Ԃ̚�ɁA�������������ӁA�����̒��ɂ������āA��ɐH���Ȃ���A�D��ꂽ���̍s���ɁA�x�\��~���Ă����Ƃ��̗��̒j���v���o���Ă݂�B�\�\�����A����ɂ����āA��b�̑O�֏o�邪�����B����ƂȂ�ł��y�ɂ����邾�낤�v
�u����B�s���܂��傤�B�\�\��l�ɂ́A�Ȃ�Ƃ������āA�ɂ����炢�A���ЁA���s���邱�Ƃɂ��܂��v
�����Y�́A���A�Ă��܂����B�\�\���т��сA�y���ɂȂ�����A�Ȍ�A���낢��ȓ_�ŁA�F��������Ă��鏃�F�ւ̋`��������A���̑s�s�ɁA������ɂ́A�E�тȂ������B
��������B�\�\�����̎��ŁA�����ɏ����ꂽ���łɁA�����Y�́A�O���̋x�ɂ��A����Ă݂��B
����ƁA�����́A�����ɁA
�u����Ȏ��́A�Ǝi�̐b��ɂł������v
�ƁA�Ђǂ��s�@���ɁA�����������B
�����Y�́A���Ԃ������܂܁A�������Â��Ă��܂����B�R���A�o�Ȃ��̂ł���B�l���Ă����������A�ɂ킩�ɁA���֏o�ė��Ȃ��B
�u�c�c�c�c�v
�����A���̒��ق̊ԂɁA�������A�v�����������Ă����B�\�\�Ǝi��ʂ����ɁA�����ցA���ڐ\���o�邩��ɂ́A�����Y�ɂ��A�ꂪ�����Ă̎��ɂ������Ȃ��B�c�c�Ƃ���ƁA����ȓz���A�w�^�ɁA���z�Ԃ̌N�̂��Ƃ��A�����ӂ炳��Ă��A���Ԃ����邳���B�����́A���S�̕����ڂɁA�����u��������āA
�u�c�c�O���̂��������A�ǂ��։����ɁA�Q��̂���B�����́A�悤�߂Ă��邵�A�ɂ�����ʂł��Ȃ����v
�ƁA�����̕�����A�����������B
|
�����̘Q�V
�J�X���傤���傤�ƁA�ڂ̂�����̐��A�ڂ̂�����̈������Ƌ�B
���̂ނ����̗���́A��̐������A�͕����Ђ낭�A�����āu���v�ȂǂƂ������̂́A�܂��A�n��ɑ��݂����Ă��Ȃ������B
����ǁA�s����A������I�B�֍s���ɂ́A���ЁA���̏M�q�Ɉ˂����̂ŁA���D�⏬�M�́A�����̋����ɁA���������A�ςƂ܂┿������A���ׂĂ����B
�u�\�\�]���́A�܂����A�]���́v
�u�E��݂̊Ɍ�����̂��A�����Ƃ肩���̗�������A�����A��������Ȃ��B�\�\�_���ƁA����������̎O�c�҂ɁA������̏F���B�������A�]���̌N�����̂��܂�������v
�u�v���̂ق��A�v�������ȁv
�u�V�ђj���̐S���悹��ɂӂ��킵���}�����B�\�\����ǁA�㒩���ʂ��ʂ��A�܂��A�s�ւ��ǂ���́A�M�������x�����A����̂������������v
�u����A��������܂��B�������������v���܂��B���ꂪ�A�V�тƂ������̂��v
��͂������c�̏��M�ɁA���l�قǂ̒j������Ă����B
�ɗ\�A�铡�����F���n�߁\�\���쎁�F�A�I�H�A�Î����̎l�l�ƁA������̌�����l�́A����̕s���l�A�艺�̓Ñ�A�����đ��n�̏����Y�̎O���B
���A�M�̒��ւ݂�����ٓ����A���݂����H�������A���̘N��ɁA�����Ԃ��A�ʂẮA�M��ɁA�v���v���A�Ђƒ��Q���āA���܁A�Ⴊ���߂������Ƃ���ł���B
�u�c�c�₠�A���ꂪ�]�����B�݂ɁA���������A�Ƃ����������A��ӂˏ��ӂ˂��A���т������������Ă���\�\�v
�u�����A�]���̗����B�������ʂ����A�͂₭�������B�c�c�I�I�A�������̏M������v
��R�A�ދ��́A������сA�V�ѐS�ɁA����̊���A�Ⴆ�Ă���B
��ɁA�����Y�ɂ́A����ɂ傲�m���ւł������v���������B�\�\�ނɂ́A�l�X�̂悤�ȏ�Y���傤��������ɏo���A�����ڂ��݂͂��āA�߂Â��݂̉ƁX�ƁA���z���́A�V�������̑D�ɁA���Ƃ�Ă����B
�̐l�Œn�������������I�єV���A�C�n�̎l������s�A��r���A������ʂ��āA�����̗V���̔ɏ����A�u�y�����L�v�ɏ����Ă���B�\�\�܂��ƂɁA�R�z�A��C�A�����ɂ킩�ꋎ�闷�l�����ɂƂ��āA�]���̈��̔��肱���A�Y�ꂦ�Ȃ�������c�����̂������B
�u�����A���₩�܂������v
�u�܂�ŁA���ׂ݂��Ƃ�̚��������肾�c�c�v
�M���A�݂߂Â��ɂ�A�҂��������Ă����V���D���A�q���Ƃ炦�邽�߂ɁA�ꂹ���ɑ����Ă����B�ޏ������́A�G���P�Ɏ��������Ȃ������\�\���X�ɋq�̏M�։��������т�����̂������B�\�\�g���A���ɂЂт��A�������ӂ�g���ʂ�\�\�Ǝ��l�̉̂����ʂ�ɂł���B
�@ |
����̔�
���܁A���̗V���ɂ́A����Șb���A�l�X�Ɍ��p����Ă���\�\�B
���A���ƂƂ��́A�Ă̍��B
�������牓���Ȃ��A��͂蓯������݂̊ɂ��钹���̉@(���{)�ցA�����ɂ����łɂȂ��Ă����F����c���A������A��Â�̂܂܁A�]���̗V�����A��������ɁA�@�֏����ꂽ�B�����āA
�u���̒��ɁA�悵����l�̖������邩�v
�ƁA�u�˂�ꂽ�B
�ЂƂ肪�A�����āA
�u����A�]���̌N�����ɂ́A���N�Ȃ��̂��݁A��a�Ƃ̂��A���F������A���ω��A�E���ȂǂƂ������l������܂������A�ߍ��ł́A��]�ʕ��������̂��܂Ԃ��̖��A��������߂̌N�ɋy�Ԃ��̂͂���܂���v
�ƁA�t�����B
��]�ʕ��Ƃ����̂́A��]���l���Ƃ�ǂ̎q�ł��邩��A���̑����ɂ�����킯�ł���B
���l�́A���a��Ɏd���A�]�O�ʍ��q���������̂��������ˁA�����g�̕ʓ��܂ŋ߂��l�ł���A���̒�̐痢�����Ƃ́A�̐l�Ƃ��Ă��A�L���ł������B
��́A���������A������������āA
�u�����̒n�����r�ݓ���āA���r�߁v
�ƁA���̉̍˂��A���݂�ꂽ�B
��݂ǂ肩�Ђ���t�Ɉ��Ђʂ��
���Ȃ�˂Ǘ����̂ڂ肯��
�������A�����A�����r�̂ŁA�F����c�́A�ޏ����A�ȑO�̉Ƃ����g��p���Ă���S�����@���āA
�u�悵�Ȃ����Ƃ��A�v���o�������v
�ƁA���������������A�Â��ꂽ�B�������݈߂������ƏP�����˂��A�^�����̂ŁA���������c�q�⒩�b�������A�v���v���ɁA����^���A
�u�����A�������炵�ɂ炢������������A�����Ȃ��@�֑t����������v
�ƁA�Ȃ����߂ċA�����Ƃ������Ƃł���B
��c�́A���ꂩ����A���т��сA���������ŁA���K���傤�����A�����Ȃ�ʂ��̂����������A�����̗��{�ɂ́A�ق�̉Ă̈�Ƃ��������������ł��Ȃ��̂ŁA��@�̎��Y�Ƃ����҂ɂ������āA����ɂ������̐������A������ƂȂ��A�㌩���������\�\�����̊Ԃɂ����Ȃ��l����������ɂȂ����Ƃ����B
����́u��a����v�ɂ��ڂ��Ă���b�ŁA�����A���̗V���́A��葐�ɂȂ������Ƃł��낤���\�\���F�A�s���l�A�����Y�Ȃǂ��A�܂݂����V�������̂����ɂ́A��c�̌䊴�ɓ���قǂȂ����⏗�߂́A�ǂ����Ă��A��������Ȃ������B
��������A���������낢�܂���ŁA�����������A�����āA���z�̋q�ɁA���ȂƂ��āA���Ă�����ʂĂ��\�\���ꂩ�炵�̗������Ɉ��D�̉e�̂���\�\�������łȂ��҂͂Ȃ��B
�����Ƃ��A�q���q�������B
���F��A�H�Ȃǂɂ��킹��ƁA
�u���˓��́A�ۂƂ��m�Â�A���ނ�m�`�Ȃǂ̏��́A������́A�����ƁA�i��������B�c�c��͂�A�]���̌N�����ɂ́A�ǂ����܂��D��݂�тȂƂ��낪����\�\�v�̂������ŁA��������A���̖�́A���x�̂Ă��������B
���l�́A��O�ɏオ���āA������锼�܂ŁA���݂Â����B
�x������A�̂������A���悻�V�Ԏ肾�Ă��s����قǁA�V�ѕ��������B
�u�����������B����ȂɁA�����Ƃ͂Ȃ��\�\�v
�����Y�́A��܂����o���āA�ԃb���ꂽ�B���̂܂ܑO��s�o�ɐQ�������B�c�c�����āA�ӂƊ�����܂������́A���C�ɋ߂������̏�Ƃ��āA������̕ǂ�A��̋���̂܂ŁA�����Ƃ�ƁA���C���ӂ��݁A�����̂��ɁA���ЂƂ荕�����݂��������̂��Q������Ă����B
��͔���ł��邪�A�J�^�Ƃ������A�Ƃ̒��͂܂���ł���B�\�\���̂Ȃ��A���ɐQ�Ă��鏗�́A�䂤�ׁA��Ȃɂ����V���̂ЂƂ�ɈႢ����܂��B���A�����Y�́A���߂āA���鏗�̂悤�ɁA������ƁA�Q��Ɋ���݂͂����c�c�B�����āA�Ȃ����A�ʖт܂��ɗ܂�����A�ɂ��܂����B
�u�c�c�ڈΔ��B�c�c���ڈΔ��ƁA�Z����B����́A�ޏ�����̐���ς�ł͂Ȃ��̂�����H�v
�����v����قǁA�����Y���\�l�̂Ƃ��ɏ��߂Ēm�����A�������z��̖��ƁA�悭���Ă����B
�ނ́A���R�ƁA�Q���߂̂��ɁA�Ⓦ����̖q�̔n���ɂ��v���o�����B�n�̐Q�����̒��ŁA�N��̓z��̉����Ɉ������ꂽ�Ƃ��̓������A���̏�������k�����o����Ă����B��������A���̎��̂悤�Ȍ��z�Ɩ쐫�������āA�����Ȃ�Q��̐O�O�����������B���́A�A�c�c�ƌy�������āA������������A�j�̉����Ԃ����l�����A�����Ȃ�ӂ��Ԃ��ƕ��i�����B�����ď����Y�́A�ߋ��Ƃ������A���Ƃ����ʁA���o�Ɩϑz���A��̂т̂悤�ȏ�ŏĂ��������B
|
�������L
�����ӂ����A�����������Ă��Ȃ��̂ŁA���̖X�́A���������������A��͂̐����܂��������ŁA�]���݂̊ɁA�g���Ȃ݂��������ĂĂ��Ȃ��B
�u�c�c�ǂ��H�@���ꂽ���́v
�����Y�́A���ƂȂ��ŁA�U�肩������̐��ۂ��A�����Ă����B���������̏h���܂��Q�Ă��邵�A�����悤�ȉ�����̗V���h���A�����Ƃ��A���܂��锼�̂悤�ɁA�Ђ��܂��Ă���ł������B
�u�c�c�����ł��́v
���́A�������B�N�́A�\���Ƃ����B�\�\�����āA�ʖт̍�����A�����F�̑e���炢�畆�B���ƁA���̐I�����Ă��閡�X�b���̌�����O���Ƃ܂ł��A�ڈΔ��ƁA��������ł���B��͂�A�����̉ڈ̌��������Ă����̂��ƁA�����Y�́A�����ɁA�R����悤�Ȋ�����āA���������B
�u���Ⴀ�A�����ė����ˁB�\�\��������v
�u�����B�c�c�����ꂳ�v
�u���B�������B���܂��́A�����m��Ȃ��A�q�ǂ��̂����ɂ��v
���́\�\�ƁA�����˂�ƁA
�u���J�Ƃ����܂��c�c�v�ƁA�����������B
�����Y�́A�����ɁA������A�Ⓦ�̐��ꂾ����A�������A���܂����D�����B�܂��A�����ƁA�ʂ��ė���\�\�Ƃ������肵���B
���J���A�����̂�����A�����Ȃ�ł͂Ȃ��炵���A�����A���ƂȂ��A���Ȃ����D���ł��A�����ƁA�Y��Ȃ��Łc�c�ƁA�Ȃ�����ɁA�������B
�c�t�ȋq�ɏo����āA�ޏ����A�c�t�Ȗ��̂Ƃ��߂����A�^���A���Ɏ��������̂�������Ȃ��B���́A�c�t�ȂقǁA���l�����ɂ́A�y�������ł���B
������́A���邭�Ȃ�ɂ�A����ق�A�M���������A�l�e�����������ė����B��l�́A���Ƃ̏h�̕��ցA�A�肩���ė����B
����ƁA�ꌬ�̐�������A��͂��l�̗V���ɑ����āA�M�ɏ�肩���Ă���s�l�炵���q���������B�j���́A�݂ƁA�M�̏�ŁA�㒩�̐ɂ��݂��A����Ԃ��Ă������A�₪�āA�q�̏M�͉͒��ɁA���́A�݂ɗ����c�����B
�u���B�c�c�H�v
�����Y�ƁA���̋q�ƁA�v�킸�A���������킹�Ă��܂����B�\�\����́A�]�Z�̏핽���吷�ɁA�������Ȃ��B
�吷���A�����Y�̎p���A�����ƁA�����悤�Ɏv����B�����Y�́A���R���Ȃ��A�����킬���A�o�����B
�u�䑶�m�Ȃ̂ł����v
���J�ɂ�����āA�����Y�́A
�u�����A���̈����A�]�Z�ȂB�c�c���̒j�A���т��сA�����֗���̂����v
�u�W�H���킶����̂��q���܂ł��B���ɁA��x���A�O�x���炢�́A�����ƁA�����Ă���悤�ł���v
���J�́A�����Y���A�吷�̏]�Z�Ƃ����āA�Ȃ��A�M�����܂����悤�ł������B
�h�ւ��ǂ�ƁA���F���n�߁A�䂤�ׂ̒��Ԃ́A�݂ȋN���Ă����B�s���l�́A������ɁA��������A�����ŗV�ڂ��Ƃ��������咣�������A����ł́A�Q����l���ւ̑D�ւɁA�܂��������҂��˂Ȃ�ʁB������܂��A�㗌���邩��\�\�ƁA���F�����́A�����ŗ���������A�₪�āA���z�̑D�ɏ��ʂ�A��͂̂����ŁA���Ɠ��ցA�Ԃ������B
�V���������F�A�D�̏�ɁA���P���������ׂāA���̗���̒��قǂ܂ŁA��s�𑗂�ɏo���B���̒��́A���J�̊��c���������A�����Y�̊�ɂ́A�c��Ȃ������B
|
������̉���
�u����B�����Y�\�\�v�ƁA����܁A�����́A�ނɂނ����ę�ߏo�����B
�u�����Ƃ���Ɉ˂�ƁA�����͋ߍ��A�����A�����������āA������A�ق��邻�����́B�\�\���ꓹ�f�ȁv
�R�ł͂Ȃ��B�����Y�́A��������āA�z�ʂ������Ă��܂������������B
�u���������A�ǂ��̒N�ƁA�]���ւȂǁA�ʂ��n�߂��̂��B�V�т̕�����̂���ȂǁA�ǂ�����o��̂��B���Ԃ������ł͂��邼�B������A���炳�܂ɏq�ׂ˂A�̂Ă�����ʁB�c�c����̂܂܂�\���B����̂܂܂��v
�u�\���܂���B�c�c���A��b�ɂ́A���ꂩ��A����Ȏ��������ɓ���V���܂������v
�u���l�Ȃ��Ƃ́A�u�����ł������B�����̂������������B�����́A�g�̖������v
�u���́c�c�v�ƁA�����Y�́A�R���l�������A�ʓ|�������Ȃ��Ă��܂��āA���߂���ʂ�A���������Ă��܂����B
�u��̌��A���߂āA�]���֗U���܂����B����́A�e�����F���A�ɗ\�m���A��̂ŁA���ʂ̂��߁A�ޏ��������̐����ɁA�W�܂����̂ł������܂��v
�u�ȂɁB�e�����F�H�@�c�c�����ɁA�ǂ�Ȑe�����F������̂��v
�u�͂��B�ɗ\�̘Z�ʃm���A�������F�ł��B�܂��A�I�H�⏬�쎁�F�����Ƃ��A�؋����A���ӂɂȂ�܂����v
�u�����A���́A���F�Ɓv
����́A�Ռ��ł������Ƃ݂��A�����́A���̂������A�����Y���A���܂������B
�����Y�́A�S�̂����ŁA�Ȃ�قǁA���F���������̂́A�R�ł͂Ȃ��ƁA���S�����B
���F�́A�����Y���A��l�ɂ������A��ɜ��X���傤���傤����Ă������āA�����A���̏��S���������Ă��������Ƃ�����B
(����ǁA������������A����̖��������Ă݂�B���F�ƁA�F�B���Ƃ����A���̒������A�����ƁA��𔒍������āA�Ȍ�͋M�l�ɂ��A��ڂ����[�����ɁA�������Ȃ�����\�\)
�����Y�́A���A���̌��t���v���o���āA���̌��̓K�m���ɁA�����������A����������Ȃ������B�ނ̂��������e�q���A�����ɂ́A�Ȃ��Ӗ����肰�ɁA��ꂽ���̂��A
�u�悢�قǂɐT�߁B�ق��̐����́A�Ă܂�������Ɂv
�ƁA����ނ�ɁA��������߂Ă��܂������A�Ȍ㉽�������Ă��A�����Y�Q��\�\�ƁA�g�߂��ւ́A�ĂȂ��Ȃ����B
���̂����ɁA�ˑR�A�ނ́A������̊ق���A����̉q�{���ӂցA�ߑւ����A������ꂽ�B
�q�{�́A�֖�̕��̋l���ł���B
���q��{�A�E�q��{�ɁA�e�A�Z�S�l���̏����������B
�ق��ɁA����Ȃ��Ă��ɁA�߉q���̂��B�O��ɁA���q�Ђ傤���̊e�������������B
����ɂ��A�Â�����A�h�l��������Ƃ��A��������ł��Ȃǂ́A�����̑s�����l�߂Ă����B�䏊���̑���ɕ��ɂ�����̂ŁA����̉q�m�����Ƃ��A����̕��҂ȂǂƂ����̌Ă����ꂽ�B�\�\�����Y���A�����֗��Ă���A����̏����Y�ƁA�Ă�o�����B
�ŋN�̓_�āA�ߑO�ߌ�̌P���⒲�n�ȂǁA�������ɁA�c����̕��������ɁA���т��������т������A���A�O�o���₩�܂����B
�Z�q�{�̒����́A���[���ŁA�q�������̂��݂ł���A���̉��ɁA����A��v�A�т��傤�A�ѓ������͂��Ȃǂ̏���������B
�u�͂͂��A������A�������߂��ȁv
�����Y�ɂ��A�����̂�����͓ǂ߂��B������������ɂ�����́A�͂邩�ɁA�H�����L����āA�����āA�s�����ȓ��X�ł͂Ȃ������B�����A���Ȃ����̂́A�ӂ����э]���֒ʂ��@��̂Ȃ��Ȃ����������ł���B
�x�ɂ͂��邪�A�킸���A����ɉ߂��Ȃ��B�����̂���҂́A�����ւ��A��邪�A����͎O�N�Ɉ�x�����A���ɂ�������Ȃ��K���ł���B
�u���ɂ��āA����ƁA�킩�����B������̑�b�ցA����̍]���ʂ����A���������̂́A�핽���吷�ɂ������Ȃ��B�c�c�{���A����ɂ�����A�ڂ̂������ɂ��₪��v
�ނ��A�����o�����̂��A����ֈڂ��Č�A���R�A���n���̖�O�ŁA�ނƂ��ꂿ�������̂ŁA�͂��Ǝv�������̂ł���B
���̎����A�吷�́A
�u���B�c�c�v
�ƁA��������A�y���A�����Y�̉�߂��A��ł���������ŁA��e�����悤�ɍs���Ă������܂܁A�����Ă��܂����B
�Ȍ�A�֖�̓��ł́A���R�A�吷�ƍs������Ƃ������������A�吷�͂˂ɁA�M���q�R�ƍ\���āA����̕����҂Ђ�ނ���ȂǂƁA�e���݂̂��邱�Ƃ́A�p�݂����Ȋ���������B
|
���N������
�q�{�̕��Ґ����́A�����Y�ɁA��ɂł͂Ȃ������B�D��̖쐫�ɁA�ނ��т��āA�ނ̑̋�́A���悢��痂����܂����Ȃ����B
����ɁA�c����̐����́A�ނ̐S�ɁA�V���Ȗ�]���߂��߂������B��������ɂ��A�ʊ������̍��ʂ�����B���R�A�����Y�̈Ӓ��ɂ��A�h�B�̗~�]���A���𝪂������o�����B
���サ���A�w�������B�������Ă��A���̕��ɂ́A���܂��Ƃ����B
���ɁA���n�\�\�n�������킹�ẮA���n���A�E�n����ʂ��Ă��A����̏����Y�ɋy�Ԏ҂͂Ȃ��Ƃ���ꂽ�B
�l�N�̌�A�ނ́A���ʃm�傤�ɂ܂ŁA�o�����B
���̎l�N�ڂ̏t�B
�v���Ԃ�ɁA�܂��A�ɗ\�̓������F���A�㗌�����B�\�\�����āA���F������֗U���ɗ����̂ŁA�A�ꗧ���āA�V�тɏo���B
����̈�Ƃ��Ȃ�A�O�o���A���R�ł������B�����A�]���̑��J�́A���ӂ��ʂ��������Ɏ��āA�����A�Ƃ��ɂ����ɂ͂��Ȃ������B
�u�ǂ��֍s�����c�c�H�v�ƁA���F�͂����B�����Y�ɂ��A���Ă͂Ȃ������B
�u�܂��A����̕s���l��U���Ă݂悤�B�\�\�q�{�ɓ����Ă���A���́A�s���l�ɂ��A���ꂫ���x������Ă��Ȃ��̂����v
�u��B�c�c���Ⴀ�A���ʂ��́A�s�ɂ��Ȃ���A�s���l�̍Ŋ����������A�m��Ȃ��̂��v
�u�s���l���A�����āv
�u�\�\�ƁA�����Ă��邪�v
�u�R���낤�B���킳�ɂ��A����͎��ɂ��Ă��Ȃ��v
�u�߂܂��āA�������ꂽ�������́A�R�ł͂Ȃ��B����́A�����֓����U�����艺�̈�l����A�����ɁA���������Ƃ�����v
�u���̐_�o�S�v�Ȓj���A�ǂ����āA�����g�ȂǂɁA�߂܂����낤�v
�u����A���̎�ł͂Ȃ��A�핽���吷�Ƃ������j�̎w���ŁA�ˑR�A����̑����A�Q���݂ɏP���\�\�Y���Ȃ̍����֓������܂ꂽ�Ƃ����͂Ȃ����B�c�c���ł��A����͍���b�ƂɎ�����Ă���吷���A�����Ɍ�āA�i��ł�����d�����ƁA�����Ă���v
�u�c�c�m��Ȃ������B���̎����낤�H�v
�u���A���̐����̂��Ƃ��Ƃ����B�M�l���m��Ȃ����ł́A���Ԃւ��A��قǁA��Ђ����ɂ��Ă�����̂Ǝv����B�c�c�@����Ƃ���A�����Ƃ��ẮA���z�Ԃ̌N�̎d�Ԃ����A�吷�ɁA��点�����̂ɈႢ�Ȃ��v
�u���ꂪ�A�ق�ƂƂ���A�₪�ẮA����̐g�ɂ��A�����A�~�肩�����ė��邩���m��ʁv
�u�����A�ǂ�ȍ���������悤�ƁA�s���l���A�M�l�Ƃ̊W�܂ŁA��������Ƃ͎v���Ȃ��B���̕ӂ́A�S�z����ɂ�����܂����A�吷�ɂ́A�O���܂ŁA�C�����Ă��邱�Ƃ��B���������ނ��A�\���͂ł��ʁB�\�\�����A���ʂ��̐g�̏�Ȃ��ɁA�̋����̎�������������v
���݂̊��A�����A�オ���āA
�u�����A�b�R��������ցA�s�������v
�ӂ��ɁA���F���A�����o�����B
�[�ŁA�����A������g���āA��l�́A�l�����x�֓o�����B
�t���̉��ɁA�����̉����ƁA�c���̏��傪�A�]�܂ꂽ�B
�u�c�c�����A�����̓s�A�l�Ԃ̓s�v
�����Y�́A���S�ɂ����Ȃ��B
�\�Z�A�͂��A�Ⓦ���삩��A�s�֏���āA���߂āA���s���������̔����������]�ƁA���A���Ă���v���Ƃł́A�]��ɂ��A������������B
���傤�̒V���́A�s�ւ́A�}�������B�܂��A�l�Ԃ̒n��ւ́A�{�肾�����B
�u�����Y�A�Ђǂ��A�l��������Ȃ����v
�u�����c�c�B���炵���ɁA���R�Ƃ��Ă���̂��B����́A�����҂������v
�u����A���̋́A����܂���B�\�\���݂��ɂ��v
�u�N�́A�����v
�u�͂͂͂́B������A�Ȃ�ŁA��C�̕Ћ��ɁA���܂ŁA�Z�ʃm�n�����Ȃǂ��āA�����ԃb�Ă�����̂��B�Ƃ��ɁA�s�֏o�āA����b�������Ƃ��ɁA�傫�Ȋ�͂����Ă����Ȃ��B�\�\����̑c���́A�֔���o�̒킾�B�\�\�z���A���F�̓��̒��Ɏd���A�������̔ɉh���Ђ炢����o�̌������Ȃ̂��v
���F�̌�C�́A�ߒ������сA�[��������ɁA�܂��������B��C�̋����ƁA�����A���}���Ă����A�����܂��̂��̂������B
�u�ɗ\�ɂ���A���i�̕��s��A�S�i�̎ア�҂����߂��A�ڂɂӂ�āA�ق��Ă����Ȃ��Ȃ邵�A�s�ɏo��A������h�Ԃ̑��ɂ��āA�������̗��A��������Ȃ����y�A�����H�����ė�����鏬�l�y��槑i�����́A�����́A�����́c�c�B���̋C�����́A�u���ꂪ�Ȃ��v
���F�́A�t�ŁA�ʂ����������B�r���̎��@�Ō�ė����t�B������A�����Y�ɁA�����āA
�u���܂B�\�\���ʂ����A�����V�c����Z���B�������A��n�̌�q�ł͂Ȃ����B�������肵�����v
�u�������B������c�c���̐����Ă������܂ł́A�̋��ł́A��q�Ƃ��Ă����v
�u����̉������낤���炢�ɂȂ��āA�o�������ȂǂƁA���Ă��Ăǂ����邩�B�\�\��ɂ��A���Ȃ����v
���F�́A�܂܂ŐԂ���ŁA�ޕ��Ȃ镽���̓s���A�w�������B
�u�\�\���̉����̉��ɁA�ǂ���Ȑl�Ԃ��A���傤���A�y�����A�邵�Ă��邩�B�����ނ˂́A�h�Ԃ̑���̉������A�ɂЂ�����Ă���G�����B���̒��҂Ƃ����A���̒N�ނƂ����A�������������A�L�邱�Ƃ�m���āA�����̋Q�����A�n�Ɍ��悤�Ƃ����Ȃ��B�����Ē���܂ł��A��������I�����Ă���B���ǂ낭�ׂ��A���݂��B������A�ӂ����Ƃ����Ă��Ȃ��A���̏t���̂���炩�Ȓ����ɁA���ʂ��́A�����A�܂��A�킢�ė��Ȃ����v
�u����ɂ́A���������̂��Ƃ́A����Ȃ����A���N�̉u���������^���ł��A�s�̋����́A�݂��߂Ȃ��̂��B�\�\���̏o���̐��������Ȃ������ɁA�������������̊قł́A�nj��̉��˂��A������o���̂Ɂv
�u����A�V�Ђ́A�܂������B�l�Ђ��������Ă���@�͂Ȃ��B���������ׂ����B����́A�����Ă�낤�Ǝv���v
�u�ł��A���ꂽ���A�g���̂Ȃ��҂��A�ǂ��v���Ă��A���܂�Ȃ�����Ȃ����v
�u���Ă������A����ǁA�ɗ\�A������A����͕K���A�������B�\�\�����Y�A�������N�̂����ɁA��C�ɕς���ƕ�������A�����ɁA�������F����ƁA�v���Ă���B���A����́A�ǂ����Ă����v
|
���A��
���F�́A����ǂ̏㗌�́A���ׂ̈��������A�킩��Ȃ��B�ގ��g���A���̎��́A�����Y�ɁA�������Ȃ������B
�܂��Ȃ��A�ނ́A�ӂ����сA��C�̔C�n�ցA�A�����B
�u�s���l�̐�������������A���莟��A�ւ������c�c�v
���ꂪ�A�ނ̎c���čs�������݂������B
�����������Y�̕����T�肮�炢�ł́A�Y���Ȃ̓���͕���͂����Ȃ��B
�ނ́A��Ă��v�������B������A��y�Y���āA���˂ɁA�Y���Ȃ̍��i�A���{�P�k���ʂ����̂悵�����A�K�˂čs�����B
�u�����Y��ŁA�������܂��傤���c�c�v�ƁA�����Y�́A��������낭���Ă���悤�Ȃ��̘V�T���ցA�y�Y���o���Ȃ��炢�����B
�u�����A�\�N���O�ɂȂ�܂��B���́A��������㗌�̂ڂ��ė�������ŁA����̕ӂŁA���ɏo�����A���̖�A���̏��߂�ƈꂵ��ɁA�����A���̍��ɂɁA��ӁA�u���ꂽ���Ƃ�����܂����B���̎��́A�c�ɏo�̏����҂ł����v
�u���B�c�c�����\�N���O�ɂƂȁH�@�c�c�B�ӃE�ށA���āA���Ƃ�����́A���́A�����́v
�u���n�̏����Y�Ƃ����A������̑�b�ւ��Ă��f����������̍����̏���������Ă����҂ł��v
�u�����c�c�v���o�����B���̂Ƃ��́A�����҂ł��킷���B�v���o���ʂ͂���B�]��ȁA���ς�ł͂���v
�u���̐܂́A���ɂ̓��ł��A�܂�������܂ŁA�������ɁA�ē��𖽂��ĉ���������A���e���A�Y��ʂ���ł������A���A�����������Ă���܂����v
�u����A�悤������ꂽ�ȁB�c�c�����āA�����A����b�ƂɁA���d�����́v
�u�ߍ��́A����̕��ҏ��ɁA�d���Ă��܂��B���́A���傤�́A���ƁA���f���������V�������āA�o�����܂������v
�����Y�́A�����Łu����̕s���l�v�̖��������o�����B�\�\�ߍ��A�����̍X�ߓa��`����������������A����́A�s���l�̎d�ƂƂ����҂����邪�A�����A�s���l�́A�Y���Ȃ̍��ŁA�Ƃ��ɍ��������Ƃ������Ă���B�ʂ����āA�ǂ������^�ŁA�ǂ������R���B�M���Ȃ�䑶�m�ɂ������Ȃ��B�����ł͂��낤���A�����ƁA���炵�Ă������������\�\�ƁA�I�݂ɁA���܂������Ă݂��̂ł���B
�u�����A�X�ߓa�ցA�s���l�炵�������͂������ƂȁB��������ȑ�_���A�������邩�c�c�v
���{�P�k�́A����܂邭���āA�������炵��ׂ�o�����B
�u����A�������ɁA�s���l�̐g�́A����b�Ƃ��獷����A�����ǂ́A���֓��������A��ӂƁA�����ɂ����A����j���ē����Ă���������B�c�c���̂��߁A�킵���S���̐T�݂������A���l�A�ܓ��O����o�d��������łȁv
�E�Ђ��̒�����A���������āA�������A�}�ɂ܂��A�^��ɕԂ��āA
�u�\�\���A��A����Ƃ������ɂȂ��Ă���̂ɁA���ɂ́A�ǂ����畷���ĎQ��ꂽ���B����b�Ƃ���A�����A���������Ă̂��z�����́H�v
�ƁA�s�R�������B
�����Ƃ̖��邢�����ɂƁA�����Y�́A�������܂��炵�āA�����A�����B�\�\�����Ă������Ɉɗ\�̏��F�ցA����𑗂����B
�ǂ������̂��A���F����́A���ꂫ�艽�̕ւ���Ȃ��B
���A�������N�́A����ɁA���������A����Ȃ������B
�O�N�́A�ߋE��т̐��Q�ŁA�t����A�s�̗����́A�H�T�ɁA�쎀�҂̋�[�Ȃ����炪�݂����B
�����Y�n�߁A����̕��́A�����A���[�ЂÂ��ɁA�Z���������B���[�̃c�x�J���Y�\�\�̐��D�ȂǁA���̂����߂��Ȃ��A�邪������ƁA���������ɁA�܂��A�̂ĂĂ������B
���E�́A�a�l��Q��̎҂��A���O�̎{��@���₭����Ɣߓc�@�Ђł�ɁA���e�������A�������ꂫ��Ȃ��Ȃ�A����ɁA�ւ������āA�n���̋Q���܂ŁA�s�ɂ͂��荞��ł���B
�����A�H���̂��鏊�́A���@�ƁA�����ƁA�֗�����肵���Ȃ��ƁA���������ꂽ�B
���̏�A�āA�u���̗��s������A�����a�ɗ����������āA����N�����B
�l�S�A���X���傤���傤�ȂǂƂ������A���납�ł���B�\�����N��Ȃ��̂́A�\�����N���قǂȐ����݂ȁA�Q���炵�Ă��邩��ŁA���C�Ȏ҂́A�Q���Ɖ����A��X�̗������A�r��������B
�����������Ԃ̂����ɁA���V�c�́A���䂹���A�܂����̎鐝�邪�A�c�ʂɂ��ꂽ�B�\�\����b�A����������ې��Ƃ��āB
�������āA�������N�B�\�\�t�ɂȂ��Ă��A���t�̌Q�����s�͂�܂Ȃ������B
���̒��ɁA�s���l��A����̈ꖡ�����A�����Ȃ��������Ȃ��B���킳�Ɉ˂�A�������b�̉Ɛl����A�����̒��Ԃɂ���Ƃ����B
�ɂ��ւ�炸�A������̑�b�̊قł́A����ȁA�ې��A�C�̏j�����A�O���ɂ킽���čÂ���A����������ɁA���Ƃ̌���ł��A�t�̒W��ɁA�܂��A�t������̉ԂɁA�J���悻�Ȋnj��̉�������͂��߂��B
�u���̒����A����Ȃ��Ȃ����B�����ǁA���̍Ⓦ����A���āA�킽���̊��������A���̈�Y���������āA���y�ŏI�邩�A�Ȃ��s�Ő����邩�A�l���Ă���A�l�����o�������v
����̏����Y�́A���N�ɂȂ��āA�������S�����B
�����ŁA���������A�s��Ƃ���������āA�\�O�N�Ԃ�ŁA���������̖L�c���ցA��\��ŋA���ė����B�@ |
�����R��
�x�m�͕x�m�̂܂܂ł���B������͕�����̂܂܂ł���B�܂��A�Ⓦ�̕�����A�u���A��͂��A������A�\�O�N�O�ɂ킩�ꂽ���R�͂́A��������A�ނ̋L���̂܂܂������B
�u�c�c���ЂƂA�ς��Ă��Ȃ��v
�����Y�́A�߂Â������̋�ցA�Ԃ₢���B
���]��Ă�̗�͂������s����A���̖��ω��ȁA���n�̌��e���������܂܂̓V�n�A���ė��āA�ނ́A��ڂ̂Ȃ����������A�s���Ɏ����⛌������傤�ɂƂ��ꂽ�B
�������A�������ɁA�L�c���ɋ߂Â������́A���ꂽ�����Ƃ̓y�̂ɂ������A���������ƁA�������ĂB
�u�����B�Z���B�\�\�Z���������v
�u�����Y�l�ɂ������Ȃ��B�����Y�l��v
�䂭�Ă̓��ɁA�ꂩ���܂�̐l�Q�ꂪ�����A�ނ��w�����āA���₪�₢���Ă����Ǝv���ƁA������O�A�l�l�̎�҂��A�킯�o���ė����B
�u�Z��B���}���ɏo�Ă��܂����B��̎O�Y�����܂����ł��v
�u�l�Y�����܂��Ђ�ł��v
�\�\���ꂩ��A�����܂��ӂ݁A�����܂������Ȃǂ́A����܂ŁA�݂ȗ��Ă����B
�u���[���B�傫���Ȃ����Ȃ��A�݂�ȁv
�����Y�́A���̒킽���́A�ǂ̊�����Ă��A�\�O�N�̋�Ԃ��A�悭�o�����B�c�ɕ��҂ɂ͂������Ȃ��Ă��A���ꂼ�ꗊ��������痂����܂������B�ނ́A���ɁA����̉Q�Ɏ��܂���A
�u�ǂ����B������ς����낤�B������A��\�ゾ����ȁB�����ԁA����ɂ��āA���܂��B�ɂ��A���낢���J�����������ɂ������Ȃ��B�\�\���A�A���ė������B���ꂩ��́A���ɓ����āA���̈�̂������̖��A���悭�Ɩ�̔ɉh�ɓw�߂悤���B�悭�A�݂ȑ����āA���C�ł��Ă��ꂽ�B�������A�������A�������萬�l���āA���������������B�悩�����Ȃ��v
�\�\���肪�������肪�����ƁA�ނ́A������ɂ����̂ł���B�������Ăł��Ȃ��B�������b�ς��Ȋ��ӂ������B��l��l�̌�������A�������A�ق��炠�ӂ��܂��m�炸�ɂ���B
�ق��́A�o�}���́A�Ɛl�����ł���B�f�����̊�͈�������Ȃ������B�l�X���g���ė����n�̔w�ɏ��A�킽���Ɍ��ւ�c���A�K���̖�}����ꂽ�悤�ɁA�����Y�́A���̓��A�����̐��ꂽ�ƁA���Ȃ킿�A�L�c�̊قցA�������̂ł���B
�����̖����A���̓��́A�Ƃ��x��ŁA
�u�ق̌�q���A���l���āA�s����A��ꂽ�����ȁv
�ƁA�j�������Ă����B�Â�����Ȗ�̊O�ɂ́A���̘V�c���A�ނ炪���āA����`������ł���B�[�����Ȃ�c�V�ł�낤���A�݂��́A�˗ނȂǁA����ɗ��邵�\�\�܂�ŁA�Ղ̓��݂������B�É�ȑ��ۂ�J�̉����A�ǂ����ŁA���Ă���B
�����������l�X�A�������������t�A�����������ƒ��̎����B�����Y�́A�S�����̂��A�����ƘJ�������ɐZ�Ђ��肫���āA����ɂ����B
�����A�����B�\�\���̋���ȍ\���̒��̈ꕔ���ɍ����āA���炽�߂āA
�u���ꂪ�A������₳��āA�������ƒ��Ƃ��āA���ꂩ��c��ł䂭�Ƃ��\�\�v�Ƃ����A�o��ƁA���S�����������A�����Y�́A�Ȃ����A��������Ȃ��A���ƁA�ǂ�т������A���ق�̂悤�Ɋ������B
���̗ǎ����������̊قƂ́A�܂�ňႤ�B���̕������ɁA�\�Z�ŋ��𗣂ꂽ���̊قƂ��Ȃ��������B��������Ȃ͉̂����낤�B
�ς�Ȃ��͎̂R�͂������B�܂��A�Â�������͂��傾���ł������B�ς肷������A�������ς��Ă���B
|
������̊�
�N�������ɁA�ނ́A�L���ق��傳��������A�ꏄ�����B��������ȓy�q���̂������B����ǁA�ȑO�͂����ɏ[���Ă�������Ȃ��A������قƂ�ǎ����Ă���B
����Ȃɑ����������g�������A������قǂ������Ȃ��B������F�A�ق��֍s����̂Ȃ��悤�ȘV�����X�����a�҂���ł���B
�u�ڈΔ��̂悤�ȏ��z�����Ȃ��B�c�c�v
�ނ́A�z�꒷���̑O�̋���ڂ���̂������B������z��͂��Ȃ��̂ŁA�����́A�H�̂��݂��ď�ɂȂ��Ă���B
�\�\�~�́A�R�X���������̉��ɁA�����֒Ă����Ď��ڈΔ��̂��Ƃ��A�͂�����A���N�̓��̎v���o�̈�ꑂЂƂ��܂Ƃ��āA������ł���B�Y�꓾�Ȃ��ޏ��̐O�̔M�����z���B�����Y�́A�ڂ��肵�Ă����B
�u�Z��B�����ɂ����łł������B�܂��A�����肩�Ǝv���Ă��܂����v
�u�����A�O�Y���B�悭�Q����A�䂤�ׂ́B�\�\�ق��́A�킽���́A�ǂ������H�v
�u�����A���������āB�\�\�l�Y�́A�Γc�̊ق����̑�f���̋��ցB�ܘY���A�Z�Y���A�ق��̏f����̋��ցA���ꂼ��A�蕪�����āA�Z�Ґl����ЂƂ̂��A����A�m�点�ɁA�������܂����v
�u�ȂB���b�Ă��������Ɂv
�����Y�́A���ӎ��ɂ��A����Ȋ炢�낪�A�o�Ă��܂����B
�u����̋A������A�ǂ����āA��ɁA�����Ă����̂��v
�u���̏f���䂽������A�点������܂����v
�u���E�ށc�c�B���Ⴀ�A���ꂪ�s�𗧂ƁA�ǂ������ɁA�吷����e�̍����ցA�����͂�Ԃ݂ł��A�o���Ă������ȁH�v
�u�����A�m��܂��A�����点�ė��܂����B�����āA�����Y���߂�����A�������̎|���A�͂��ɗ����ƁA���������Ă��܂����̂Łv
�u�ȂɁB�͂���ƁB�c�c�܂�Ŋ����݂������ȁB�ߍ��A�f�����́A����������̂��v
�u�����B��f���́A�]��Q��܂��A�nj��l�ƁA�ǐ��l�Ƃ́A���������ɁA�悭���܂��v
�u���Ⴀ�A����̗���A���܂��B�̐��b�́A���̏f����l���A���Ă��ꂽ���v
�u�c�c�����v�ƁA�悭������ɐU��ƁA�O�Y�����́A�n�Ђ����Ȃ��āA�܂̊�����������B
�u�O�Y�B���������c�c�B���ꂪ�A���y�𗧂Ƃ��A����������Ȃ����B���܂��́A����̂��Ȃ���ł́A�������Z�풆�́A�������炾���ƁB�\�\���̍��͂܂����܂����A�\��A�O�̟����͂Ȃ��炵���������A�����A����Ɏ����A������l�B���������B�����ʂȂǁA�����Ă����ȁv
�u���������A���A��ɂȂ�������̌Z��ɁA�x�\�́A���������܂��ƁA���̂�����A�����ƁA�C��߂Ă����̂ł��B�\�\�Z����B���̊قɂ́A�����A�����₵�Ă��ꂽ��Y�͉�������܂���v
�u������B��q���Ȃ�����A����q���A�c�c���A���������A����Ȏ����낤�Ƃ́A������s�ɂ��邤������A�@���Ă����B�ӊO�Ƃ͎v��Ȃ��v
�u�������́A�����ɂ��Ă��A�f���䂽���́A���g�����l�ł����B�����A�����������Ă���́A�s����������ɂ����܂���ł������A�����A�������Ɂ\�\�B(����\���A���킢��͈�́A�N�Ɉ�Ă�ꂽ�Ǝv���B�c���ɐe�͂Ȃ��A�Z�̏����Y�����̋�݁A�������̏f�����������Ȃ�������A�Ƃ��̐̂ɁA�L�c�̋����A���̊ق��A���S�̓y���ɍU�ߒD���A����́A���Ƃ̓z�l�ɔ����Ă��邩�A�������邩�ۂ��A�m�ꂽ���̂ł͂Ȃ��B������A�������l���Ă����̂́A�N�̉����\�\)�ƁA�肢�����A�ɂ߂����ẮA�ق��āA�܂��̂�ł��܂������A�Ȃ������̂ł��v
�u�������B�c�c���܂������ɂ́A���𒅂��A�����āA���܂��B�ׂ̈ɁA�����₵�Ă��ꂽ�����́A�݂ȏf�������A���������^�ы������̂��낤�v
�u�����B���̊ق́A��Ɠ��R�ł��B���������c���Ă��܂��ʁB�Z��A���������A�������̂ł͂���܂���A��邵�ĉ������v
�u���B���ꂪ�A���܂��B���A�^�����̂��B�C�̎ア��B�����Ȃ����c�c�v
�u�́A�͂��v
�u��������Ȃ����A�O�Y�B�ƍ��A���x�A���q�̍��A����q�̕��킪�A�݂�Ȏ����Ȃ낤�ƁA�����ɁA���ꂪ�A���ė����B�Ȃ��A���̑�ɁA�����J���L��ȓc���A���������āA�����킢����ė������`�̓y�n�́A���������킽���ɔЂ��^���Ă��A�]�肠����Ȗʐς��B�C����蒼���āA���������B���̈����A�������ǁA���ꂽ�����g���A���ɂȂ��āA��蒼�����Ƃ��B�c�c�Ȃ��ɁA�y��������A�����A�Ȃ������āv
�u�Ƃ��낪�A���̌Â�����̑������A�V�c����ł���A�Z�オ�\�O�N��������̂܂ɁA�݂ȎO�Ƃ̏f�����A�e��(��̎��_�A1-2-22)�߂��߂��A�����Ă��܂��܂����v
�u����ɁH�@�c�c�B����̕��Ɂv
�u�f��������A�f�������̑��q�̕��Ɂv
�u�A���ȁv�ƁA�����Y�́A���o�������Ɂ\�\�������A������ƁA�s���Ȕ����Ȃ�������Ȃ���A�f���o���悤�ɁA�����֔ے肵���B�u����Ȏ����A������̂���Ȃ��A����Ȏ����B�\�\�Ƃ̌�p���Ƃ��̂���͂��Ȃ����A���܂��B�́A�c����������A�f�����O�ƂŁA����̋A��܂ŁA�a�����Ă��Ă����̂���B���������ɂȂ��Ă���̂��B���ꂪ�A���ė�������ɂ́A���R�A����ɕԂ��Ă悱�����v
�u����ǁc�c�B�����ł͂Ȃ��ƁA�l���A�����܂��B�݂ȁA�ܑ̂Ȃ����Ƃ��B�Ђǂ����̎�������傤���Ƃ��Ɓv
�u����́A���l�̓i�˂��݂��낤�B������A�L��ȓc�̂�����A���֑d�ł�[�߂Ă��A�]������݂���́A����Ȃ��̂�����ȁB����́A�\�O�N�̊ԁA�f�������A���܂��B�̗{�痿�Ƃ��āA�ӂƂ���ցA����Ă͂����낤��B�c�c�����A���b�ς炩��A�܂�Ȃ��b�ɗ������B����́A�匋�����䂤�֍s���Ă����v
�u�匋�m�q�ł����v
�u�ށA�ށB�q�̔n�ǂ��ɂ��A����̋A���ė�������A�����Ă��̂��c�c�v
�u�n�ƂĂ��A�ȑO�̂悤�ȁA�ǂ��n���A�n�����A���͂���܂���B�V�n�A�p�n���A�킸���Ɏc���Ă��邾���ł��v
�u�n�܂ŁA�����čs���Ă��܂����̂��v
�u�z�X�A�z�l�܂ŁA�A�ꋎ���Ă��܂������ł�����v
�u�������A�y��������B�\�\�Ƃɂ����A�s���ė��邩��ȁv
�ƁA�����Y�́A����o���B
�̋��A������A���N�̓��̑������߂������A���̖q�̋u�֍����āA�������A�s���_�߁A�ߐ{�A��ԁA�x�m�̎O�������]���Ă݂����\�\�ƁA����́A�s�ɂ���������̊肢�ł������B�����ł������B
|
���Y�l�̈⏑
���܁A�]���̓��́A�����͂Ƃ����B
�����Y�́A��̋u�̏�ɍ���A�ۂ˂�ƁA���N�̓��̂Ƃ���̊��D�ŁA�G��������B
�\�\���B�[������Ă���Ȃɂ��̂��Ȃ��B
���V�n�B�n�̂��Ȃ��q��܂��B
�ǂ����āA�c�����A����Ȏ⛌�̒��ɁA�I���A�Ƃ�ł���ꂽ�̂��낤�B�܂��A�s�ɂ��Ă��A�܂ɂӂ�A���ɂӂ�A�����������o����āA�����̂��낤�B
��������ɂ��ς��Ȃ������B
�������A������߂悤�B���̐Â��ȓV�n�̒��ŁA�\�\���̋u�ɕ����Ă������Ƃ́A�܂������ׂȌ����̒��ɁA�����Y�́A�l���^���Ă��܂����B�\�\�����́A��l�O�̒j�Ƃ��ċA�����ȏ�A���ꂩ��A����ł��A�����̑o���ɂ������Ă���ƒ��̐ӔC�������B
�u�\�\�s�֏o���̂́A���_�ł͂Ȃ������B���͊w�Ȃ��Ă��A����͐l�Ԃ��ςĂ����B�s��m��Ȃ��킽���Ƃ͏������������B����́A�f�����ɁA���܉�����͂��Ȃ��B�܂��A�|������Ȃ��v
������ɁA�ނ́A�����ւނ����āA�ꂫ�o�����B���y�̑厩�R�́A��͂�A���e�̕��Ɏ����ł́A�����̎����ł������B�������E�C�ƁA�ǐS�Ƃ��A������ɁA�ނ̎Ⴂ�̂��܂����̂Ƃ݂���B
�u�������B�l�Ԃ�Ɏv���܂��B�s�ɂ��Ă��A�l�Ԓ��Ԃ́A���̒ʂ肾�B�����藧���āA������A���F��s���l�̂悤�ȍl���ɂȂ��Ă��܂��B�������������B�f�������ꂮ�낳�ɂ́A�Ƃ������ς��āA���܂�Ȃ����A�߂������ɂ́A���Ƃ���܂��B�\�\�����A�y�������ĂɁA�فX�ƁA�o�������B���̗ǎ��̂������U���A���̑��q���A�f���ɕ�Ȃ���āA�s���Ƃ��悤�B��݂Ƃ����Ȃ炢���B���l�悵�Ə��Ȃ���B����ɂ́A���̂̔C������B�y��������A���ꂾ���āA���̈�ギ�炢�ȉƖ�ɂ́A�����ƁA����Ԃ��Ă݂���B����A����ȏ�ɂ����āA�f�������A���Ԃ��Ă��v
�A��r�ɁA�ނ́A���̑ォ��q�̔Ԃ����Ă�����~�̉Y�l�̏Z�����̂������B�X�͋����A�n�̉e�������Ȃ��B�����A�j��˂̓��̓y�ԂɁA�����̛[�����Ȃ���l�A���Ԃ��āA�Ƃ�A����a�ނ��ł����B
�\�\����́A�ς�ʂĂĂ������A�Y�l�̍Ȃ������B�ޏ��́A�܂��Ȃ����āA�ǐl�̉Y�l���A�������ɂȂ����Ƃ�����āA
�u�₪�āA�a�q�l���A�s�̋炨���ǂ�ɂȂ�����A�����ƁA������������\��������Ƃ����āA���̐l�́A�����Ђ��Ƃ�܂����B�c�c����́A�����A���ƂƂ��̏H�̂��ƂŁA�������܂��邪�v
�ƁA�⏑�炵��������o���āA�����Y�ɓn�����B
���̖�A�����Y�́A�Y�l�̈⏑��ǂ�ŁA���ɁA�����苃�����B�Y�l�́A�Ђ�����A�����Y�̋A����҂��A�����锗�Q�ƁA�n���ɑς��A�������̍Ŋ��܂ŁA�q������Ă����̂������B�⏑�̏I��ɂ́A�����������B(�\�\�O�����́A�q�̂����B�ق����́A���łɁA�nj��A�ǐ��l�����́A�Ɛl���Ɏ�����Ă��܂��B���̂ق��A���`�����ł�̌䑑�������傤�����J�c�n�����łȂǂ��A�ǂ����A���₵���ȏ����ɂȂ��Ă��܂��܂����B���O�Ȃ���A�Y�l���Ƃ��V���̗͂ɂ͋y���A����܂��������Ȃ���A�a�ɉʂďI�邱�Ƃ́A���Ƃ��S�c��ł��B�ǂ����A��A���̏�́A�[���ɁA���͂�{���āA��Ɖ^���A����Ԃ��Ă��������B�Y�l�̍�鮂���ς��́A���������Ă��A�a�q�l���A����܂���\�������Ă���ł��傤�c�c)
�X���閖���܂��̕�������ˁA�Ȃ��A�c�����ɁA���Ƃ𗣂ꂽ�����Y�̂��߂ɁA���R�A�����Y���������ׂ��ǎ��ȗ��̏��̂̒n��ƁA���̌S���Ȃǂ��A�ׁX���܂��܁A�I��ɏ����Ă������B
�������A���̌�ɁA�܂��A
(���ꂾ���́A�m���ɁA��Ɩ�ɕt���Ă��鑊�`�̌�̒n�ɂ���������܂��A�������̒n���̉�����A���i�̏Ȃǂ́A�ǂȂ��̎�ɂ����A�����Ă���܂���)
�ƁA�NjL���Ă���B
�����Y�́A�傫�ȁA�s���ɏP��ꂽ�B����ł��Ȃ��A�����H�@�����H�@�c�c�ƁA�ł����������C�����̕��������Ă����B�f���Ƃ����A���̌Z�킽���ł���B���������Z��ɂ��A���̔Z���l�X�ł͂Ȃ����B�N���݂ȁA�\�A�Z�\�Ƃ�������̔N�z�ł���A�������A���ꂼ��Ɛl�Y�}��������������A����Ƃ����ƕ��ł͂Ȃ��B����������Ƃ����y�����肾�B���ŁA���������A�e�̂Ȃ��ǎ��̈�Y�ȂǁA�������ߒD�Ƃ낤�B���l�̂Ђ��݂��B�א��ł���B�\�\�ƁA�����Y�ɂ́A�ǂ����Ă��A�^������Ȃ��Ł\�\�������܂��A�ꖕ�̕s�����A�@������Ȃ������B
|
�������̒퓙
��A�O������ƁA�l�Y������A�ق��̒킽�����A���X�ɁA�A���ė����B
�����Y�́A�����ցA�����˂��B
�u�헤�̑�f��(����)�́A�Ȃ�Ƃ��������B�\�\���ꂪ�A�A���������Ƃ��v
�u�������c�c�ƁA�����������ł����B�����āA���̂̌Z���A������́A�����킵�B���A���܂ŁA�����Ă��Ă͂����Ȃ��B�e�ʂȂǂ́A�Ȃ����̂Ǝv���āA������A�Ƌ����Ⴂ�܂����v
�u���܂��́A�Ȃ�Ɠ������̂��B���A�����v
�u�c�c�����A�͂��A�ƈ��A���āA��ӁA���߂Ă�����Ė߂�܂����v
�u���ɂ��Ă��₪��v
���R�ӂ���ƁA�ނ̐S�́A�Ԃ₢���B�Ӓn�̂Ȃ���ɂ��A���������Ă���B�������A���������Ă��A���̉��̏����A���������Ă��A�݂Ȃ܂��A��\�͂������������̎�҂ł����Ȃ��B�V�Ԃ낤�����ȏf�������̊Ⴉ��́A�܂�ŁA���������Ԏq�ɂ��������܂��B�������Ȃ��C�͂���̂������B
�u�����́B�c�c�}�g�̏f��(�ǐ�)�̏��ցA�s�����킯���v
�u���A��낵���A�����܂����v
�u��낵���H�@�c�c�B���ꂾ�����v
�u�����B�Z��ɂ��A����������A�V�тɗ����B�킵���A���̂����ɍs���Ɓv
�u�����B�\�\�nj��f���́A�ǂ������v
�u������ł����B���ł����A�V���ɂ���̊قɁA����낱�т́A���ꎖ�������āA���o�������Ƃ��A�Ɛl���\���܂����v
�u�V���̊قƂ́A�N�̂₵�����v
�u���㌹���������́A����݂Ȃ��Ƃ̂܂���ǂ̂ł��B�\�\�Z��̂�����̂����ł������A�nj��f���́A�܂��̍Ȃ�S������Ă���A���̌�ǂ̂́A�䑧���̂ЂƂ���A���W���炢�ɂȂ�܂����B�j���̉��́A�����Â��ŁA�������Z����A��`���ɁA�Q��܂����v
�u�f���̉śW��߂Ƃ�Ȃ�A���܂��B�ɂ́A�f��}������Ȃ����B���ꂪ�A���ɂ������ꂸ�A��Տ�������ǂ���̎�������v
�s�@���ȁA�Z�̌�C�ɁA�킽���́A�ق��Ă��܂����B
�\�\��𗧂ׂ��ł͂Ȃ��B���̌ǎ������́A�����ӋC�n�Ȃ��A�������ė����̂��B�����Y�́A�����v���������B
�u�j���ł͂Ȃ����A�킪�Ƃł��A�l���т��A���˂Ȃ�ʁB���ɂ��悤�ȁB�\�\����̋A����I�ڂ��v
�z�C�ɁA�������B�킽���́A��������킹���B�V�l�݂����ɁA�����A��p�̎v�ĂȂǂ���炵���B
�u����B�������A�f�����ւ��B���̂ق��A���̋��m�A���Ƃ̘Y�}�A�Ў��̑m��_�H�X����˂��A�S�������̒N�ނւ��v
���Ă������āA�ނ́A�킽���֓n�����B
�\�ׂ������̎�r�������߂�p�ӂ��A�����A���L�ق������A�싛�A�����A�ʎ��A�������イ�炭�A�؍��ȂǁA�����钿�������āA�����̐��`��������ɂ��Ȃ����B�\�\�����炭�A���̊ق̌Â��~�[���n�܂��Ĉȗ��̎ϐ����ł������낤�B
�����̍ޗ��́A�唼�A�s�ŕ����Ԃ��������ė��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Y�́A���̂��߁A�S�����g�ɂ��Ă����╨�܂Ŏs�֎����čs�������B�~�����̒������A�������̂����āA���̉������݂���A�s���Ȋ�Â������A�������肵���B����b�ƂŔ`���Ă����܂ˎ��ɂ����Ȃ����A���y�l�̊�Ɛ���A�������Ă�낤�Ƃ���A�c�t���ȋC���A�͂��炢�Ă����B
�\�\���A�P�Ȃ��ȋC����ł͂Ȃ��A�l�̂�낱�т���낱�тƂ��鐫���́A�������ɁA�ނ̒��ɂ͂���B���̓��́A�ׂɁA�݂������A�L�c���̘V�c�ɁA�݂��T�����B��O�ɂނ炪�����y���ɂ��A�����́A�َq���̂��A�U�������B
�q�͎��A���\�l���������B
�S�������̒m�Ȃ́A�����͌̐l�ɂȂ�A�]�Z�́A�Â̂Ƃ����҂��A�����Y�ɂ́A�݂Ȋo���̂Ȃ�����肾�����B
�ނ����A�d���Ă����Y�}�����́A�q�ɗ��Ă��A�ˑR�A�����ɂ��āA��`�����B���̐l�X�̊Ⴔ����A����ɁA�����Y�͂������āA���e���������B��f���̍����́A���ׂ��݂Ƃ����ė����A�}�g�̏f�����A���s�Ƃ����āA�p�������Ȃ��B�㑍��ǐ��������A�f���g�̑�\�݂����ɁA�ȂɌ����A�l�X�ցA��������̂������߂�t�̂��Ƃ���A�Ђ������Ă����B
���̋q�̒��ŁA�����Y�ɂƂ��āA�����Ƃ��A���ꂵ���l���A���Ă��Ă��ꂽ�B����͐^���A�Y���l�Ȃ̂ł���B
�u���v���イ�������܂����v
�����Y�́A���̐l�̑O�֍����āA���܂ŁA�ق����A������݂Ȃ������B
�u�䐬�l�Ԃ肾�́c�c�v�ƁA���̐l�́A���������ƁA�ނ����āA���a�ȐO���ƂɁA�t�������Ă����B
�����i�s�������̂����䂫�ł���B
���N�̓��A���̐l�ɁA���₤���ꖽ���A������ꂽ���Ƃ�����B�\�\�������^�݂����˂̎O�Ԗڂ̎��q�Ɛ���A�w�˂�����A�l�����悭�Ă��A���ɁA����ȉ����̒n�����Ƃ��āA�ꐶ���A���ɂ��m��ꂸ�A�������s�������킸�A�فX�ƁA�I��l�����邩�Ǝv���ƁA�����̌�������̑��݂��A���Ȃ��̂Ɏv���Ă���B
�u�ǂ��������ˁB�c�c�s�́v
�u���p���������Ƃł����A����A�K��������������܂���v
�u���ꂩ��́A�����ƁA���������́v
�u���̂ł�����v
�u�ǎ��ǂ̂��A�����Ă����ł���Ȃ��B�c�c��낱�Ԃ��낤���A�������A�Ȃ��̂����v
�f���̗ǐ����A���낶��A���Ă��邹�����A�i�s�́A���������A�����Ȃ������B�����āA�����̐����A�̂�A�蔏�q�ɁA����o�����A���̂܂ɂ��A�����ƁA��ɋA���Ă��܂����B
���̖�́A�A����I�ڂ��A�������ɁA�����Y�́A�Ȍ�A����܂����ǂƁA���̂邱�Ƃɂ����B
�����̂Ƃ�����A����Ƃ������̂�͎����Ă������A�s�֏o���̂ŁA���ƂȂ������̂܂܁A���߂����̂ł���B�킽������A�����͂����Ă��Ȃ��B�ނ́A���̍��́A��Ƒ����x�̂��ƂɁA�ƒ��ƂȂ�A�܂��A����ƂȂ����B
|
�����H
����̋A�����m��킽��ƁA���ƂȂ��A�ȑO�A�g���Ă����Y�}��Ɛl���A�ڂڂA�L�c�̊قցA���ǂ��ė����B
�����͊F�A�坁������A�nj��A�ǐ��Ȃǂ̏f���g���A������킹�āA�����̓c�Y��������A���傪�����ɁA�����D�肵�Ă��܂����Ȏ������A�m���Ă���B
�u����Ȕ�l��Ȏ҂��A��l�Ƃ���̂͂��₾���A��q�����A��ɂȂ����ƕ������̂ŁA�߂��ė����̂��v
�������킹���悤�ɁA���ԓ��m�ŁA��肠���Ă���B
����́A���ꂵ�������B�����ɁA�悵���A�Ɖ����A�͂Â悢�A���M���������B
�ނ������ɂ͂䂩�Ȃ����A�s�ŁA�z�X�z�l���w���A�n�������A���߂̍k���A���J���n�ւ��A������o�����B
���A�l���B����A�����H�Ƃ�����B���̈����A��q�ɂȂ��B
�u���H�ނ��������B�і��̉͌����́A�����^�b���F���B�����ꂵ�ė����v
�������āA�����A�l�A�ܓ��ɂ킽��A���邻����A�����̎R���A�L�c�̊قցA�^���Ă����B
���̓��A����́A�z�l�ƈꂵ��ɁA����̏�ŁA�y�q�̏�h�������Ă����B
�Ă����������Ƃ肪�A���̒n�����L�ȓy�̍��������Ă���߂��낾�����B���X�����l���ɁA���傪�A�ӂƁA����̏ォ��A���̊O���̂����ƁA�і��֊����݂ɂ�����Y�}��z�l�������A����l�������ŁA�ォ��ォ������ė���B
�u�ǂ��������H�v
����̐������ŁA�Y�}�̈�l���A
�u����܂����B�\�\����܂����v�ƁA�q���e�ցA�i����悤�ȁA���𓊂����B
�u���܂��B�����ẮA�ǂ��́A���ꂾ�v
�u���܂͂��܂���B�����Ȃ�A��������A�吨���āA�����Ă������ė����̂ł��B�\�\���́A����ɒf����Ċ�����邼�B�����̉͌����́A�ǂ��̏��̂��A�m���Ă��邩�Ɓv
�u�����u���Ă���̂��B������v
�u�}�g�̘Y�}�����ł��v
�u�ȂɁB�ǐ��̉Ɨ����Ɓv
����́A������~��āA
�u�ǂ̕ӂ��B���ꂩ�A�ē�����v
�ƁA�����������đ��肩�����B
�u�Z��B���悵�Ȃ������c�c�v
�O�Y������A�ق��̏������킽���́A�������āA�Ђ��~�߂��B
�u�і��̉͌����́A���N�̕�A�f����̏��g���A��q���˕t�������̂ł�����\�\���Ƃ��Ƃ�����������̂́A���������A�����̂ł��B�Z��́A�䑶�m�Ȃ�����v
�u�����A�����B�m��Ȃ��̂́A���܂��B���B���̉͌��n�͂ȁA���オ�����Ă������A���N���N�̏o�����A����ƁA���~�����ǂ߂��āA���ꂱ���A�\�N������ŁA���ł�����悤�ȓy�n�ɂ����̂��B�\�\����́A���������A��������āA�o���Ă���B�����Ɛl��A��������ȏ��g�́A���Ɗ��ƂŁA�y�炵�����ɂȂ������n�Ȃ̂��B�\�\������A���̌�p���̂��ꂪ�������̂ɁA���́A�ӂ���������v
����́A�킽���̎��ɕ������ɂ́A�K�v�ȏ�̑吺�ŁA������߂����B�ǂ����Ă��A�����ǂ́A�V�ւނ����āA��߂��������Ă����悤�Ȑ��������B
�u������A���قɁA���čs���B����́A�吨���v
�z�l���A�Y�}���A�����������āA�ނ̋킯�o�������ƂɂÂ����B�������A�і��ׂ�́A�������ɂ́A�ǂ��߂Ă��A���łɁA����̉e�́A�����Ȃ������B
�����A�����ɁA���D�������Ă����B����ƁA���������Ă������B
�͌��n�A����A��\�����A���e�A�}�g����m�Z�A���ǐ��^�C���m���V�}�T�K���̃m��n�^���B���~�����������ҁA���t�P����A�i�l�A���x�L�R�g�B�@�@�@�ǐ��Ɛl�i�v
�u�킷�ȁB���l�̍��D�������Ƃ́v
����́A������A�R�������������B
�Ȃ��A���������Ȃ��悤�ɁA�c�Ƃ��āA�і��̗���ɁA�����̂Ă��B
�ނɂÂ��ė����\�����̊�́A������A���C���悵�ƌ�������A�����A�����ƁA���̐F���Ђ����悤�ɁA�������B��ɁA���i�̂��ƂȂ����O�Y�����́A
�u�c�c�A�v�ƁA�����̐���������āA�܂����Ȋ�������B
�u�������v
�u�͂��v
�u�Ă���ȁB�����͂ƁA����́A��̂����ŁA�����o������҂��Ă����̂��B�\�\���傤�ǂ����B����͂��ꂩ��A�f�����ցA�k�͂Ȃ��ɍs���Ă���v
�u�ȁA�Ȃ�́A���b���ɂł����v
�u�m��Ă���B�\�\�f�������A���ꂩ��a�����Ă���L��ȓy�n���A����ɕԂ��Ă��炤�̂��B����ȁA�L�̊z�Ђ����݂����ȁA�͌��n�Ȃǂ̊|�����ł͂Ȃ��v
�u�ł��B�c�c�A�����Z��B���ƂȂ��āA������������Ă��v
�u���܂��Č��Ă���B����́A�f�������A�]�݂ǂ���ɁA�s�֏o�āA�����́A����ċA���ė����B�����ǁA�Γc�̑�f���ɂ��A�����������A��������������B���������A�a���������A�Ԃ��Ă��炤�����̎����B�s���ė���B�c�c�ȂɁA��l�ł����B�����͋A��Ȃ��Ă��A�S�z����ȁv
�����o���Ă���A����́A�Ȃ��A�J���C�Ȓ��Y�}�������A�U�肩�����āA���������B
�u���܂�ʂ���A�Â��āA��������A�����ق̓y�q�ցA�ǂ��ǂ��^��ł��܂��B�Ȃɂ��A���l�ЂƂ̕�����Ȃ����B�V�n���Ɨ�����A����́A���܂������ɁA�P�`�ȓ��݊��ȂǍ������̂������̂��B����ƕ邷�Ȃ�A�����M����v
�@ |
���s�X�q
�C�̌����܂܁A�S�̐��ނ܂܁A�V�Ԃ܂܁A���������܂܁A�����������͂��Ȃ��ŁA���̓V�n�ԂɁA���قǁA�̖�������̕��ɂ������āA���R�ɕ邵�Ă����͂Ȃ��B
�u�\�\�A�܂����p���B���̐S���B�ᛂ��Ⴍ�Ȃǂ́A�������p�������ȁv
����́A�ׂ̂A��҂ɁA���������ĕ����Ă������A�ӂƂ���ȍl�����N�����B
�\�\�Ƃ����̂́A�����Ε����قǁA���ɁA���̒n���́A�����炯�ŁA���悻�A���E�⑫���Ƃ���A���Ɖ��̐�邱�Ƃ͂Ȃ���������ł���B
�]���āA�͌����炯�ŁA���������̐����Ă���y��ł��X�ł��A����͉͌��̒��̓��ɂ����Ȃ��B�����ĉ͌��𑖂�c�����s�ȁA�����̐������A�₪�Ē��S���ɑ�����āA���݂̂悤�ȕ��ɂȂ�B����������Ǝ嗬�ŁA������A�����A�헤�̍������Ȃ��і��(���̋S�{��)�̑�͂ł���A�V���ɂ���A�헤�̕���ƁA�}�g�̎R���A�ޕ��Ɍ�����B
�u�c�c�͂ĂȁB���ꂪ�q���̎����ɂ́A�������A���̕ӂɁA�n�M�킽�����������͂������v
����́A���Ԃ����܂̊�ɍ������낵���B�������ɁA�L�c�̊ق�������A�y���ʂ��A�܂��A�����Ƃ������̂ŁA������ꂽ���̂Ƃ݂���B��䩂т傤�ڂ������]���������̐���O�ɁA�����A�s�X�q�悵����̚e�����ɂ܂�Ă����B
���̍s�X�q�̐��ɁA�ނ́A�������܂��A�c�����A���e�ɔ����A������Y�}�ɘ�����������A�헤�̕�����A���̑�͂��M�œn���ċA�������̂��Ƃ��v���o���ꂽ�B�L���ɂ����������A�����̎O�c�̏j���ł͂Ȃ��A���ȂȂ̏j���ł������낤�B������A�s������ł��A�M�̒��ł��A���ꒅ��ꂽ��q�݂��l�̎������j������钆�S�ł������B
�����ꂽ��́A�헤�Γc�̑�f�����A�H���͂Ƃ�␅��݂���̗��f�����A�݂ȉƐl�Ƒ�����āA�킴�킴���̐�݂܂ŁA������ɗ������̂������B�\�\���̍��́A�����̕��ǎ��̈А��Ɠ��]�́A�債�����̂������ɂ������Ȃ��B�ނ�́A���̌Z�킾���A���̑O�ł́A�����l�A���̂�����҂͂Ȃ������B�ꑰ�̒���Ƃ����߂āA���n�̘J�����Ƃ�Ȃ������B
���̓��A���̑�͂�n���ċA�邽�߂ɂ��A�f�����́A��X�A�V�����D��p�ӂ��A�Ⴂ���B�ɁA�傫�ȊG���P���Ȃ��������āA�������悳���Ȃ܂ŁA�����Ă������B���̏j�����ɏ���ꂽ�����́A���̐^�ɁA���q�l�̂悤�ɁA�s�V�悭�A���点���Ă����B�c�c�����āA�D���A�͐S�ɂ܂ŏo�Ă��A�Ȃ��A�헤�݂̏f�������̌Q��́A���Ԃ݂����Ɍ����Ă����B���U���āA�Ⓦ�̍����A�D��̉��҂��镃�̗ǎ��ƁA��k�̌�q����c���������A�j�����Ă����\�\�B
�����A���ʂƂ��A���̏f�������̗ǐS���A�M�������̂������͂Ȃ��B�����_�ł͂Ȃ��B�����̏f�������A���̂Ƃ��̐l�ԂƓ����҂������Ƃ������Ƃ́A�_�ł��Ȃ���A���낤�͂��͂Ȃ��B���R�A���́A���Ƃ̏������q����ƁA���ɊJ����Y�̓c�̂ł��傤�Ƃ��A��������A�f�����̗ǐS�ɑ�Đ����Ă��܂����B
�c�c�����A�삪��������A���́A�����ɂ������Ėі��̐������Ă��鍡�̏����Y������A�ǂ����߂Ă��������邾�낤�H
�u�R�ڂ���ƁA����́A�܂�������A�V���ɂ��Ă����B�c�c�{���ƁA�v��������A�܂��G�ɂ��ڂ�ė����B
�u�������������Ă�����A�z�����A�����������̂ł͂Ȃ��B���̕������ɂ��Ȃ��̂����߂ɏ���Ȃ܂˂����Ă���f�����Ȃ̂��B�悤���B���ǎ��́A�܂������Ă���Ƃ����������A���f���߂�ɁA�v�����炵�Ă�낤�B�ǂ��ɐ����Ă���Ƃ������B�c�c�₤��������B����͕��ǎ��̎q���B����̒��ɁA��������̂͂�����܂����v
�ނ́A�ʂ��ƁA�˃b�������B�����ɏՂ��グ��ꂽ�悤�ɁB�\�\�����Ĉ�����Ă��̊Ԃ����܂킵�A�Ί݂ɓn��M��T�����߂Ă���ƁA�ꓪ�̔n���g�����j���A
�u�������B���ق��܁B�͂̏�ɂ��A�ݕӂɂ��A���p�������Ȃ��̂ŁA�ǂ��������ƁA�����Ԃ�T���܂�����v
�ƁA�v�������ʐ��������ċ߂Â��ė����B
�j�́A�L�c�̊ق̘Y�}�̂ЂƂ�ŁA���v�������̗��ۂȂ��܂�Ƃ����܂��\���A���̏����҂ł���B�ނ����ƂɎd���Ă�������̖��q�ł������B���傪������A���ė����ƕ����ƁA���v�̗��ɂ܂������Ă�����ꂪ�A���ЁA���g���Ă���ĉ�����ƁA�ނ�����Y�ꂸ�Ɍ����ė����҂Ȃ̂��B����Γ��Z��ł�����B����́A����̈╨�����݂Ǝv���ĉ������Ă���B���ۂ��A���Ɋ����āA���U����l�Ƃ��ē����Ă����B
�u�\�\���ۂ��B�����ɗ����H�@����́A�헤�֏o������̂��v
�u�ł�����A�n���Ȃ��ẮA��s�ւł��傤�B������A����̏f���䂳�܂��A�H���ւ��A�����ł��傤�v
�u�����B�c�c�����Ԃ�ȁA�����݂��̂�ł͂���ȁv
�u�͌����ŁA�����ƁA�䗧���Ȃ����āA���̂܂܁A��U�ɁA�������ɂȂ��Ă��܂����ƁA�ق��̎҂��畷���܂����̂Łv
�u�ق̔n���A�g���āA�ǂ������ė��Ă��ꂽ�̂��v
�u�����āA�����A���Ќ�ꏏ�ɁA�������������Ǝv���ė��܂����v
���ۂ́A����̊���A�����ƌ��āA���肷��悤�ɁA�����������B�����ɁA�헤�֓n�邩���A�ނ͒m���Ă���ӂ��ł���B����́A���܂��āA���Ȃ������B����Ȗ����̂����ɂ��A��ɂ͂����܃b�ۂ��Ȃ�̂��A�ނ̂����ł������B
|
���쑚�̏h
�u�n�M���́A����ȏ��ł͂���܂����v
���ۂ́A��l�������n�̔w�ɂ̂��āA��������܁A�Z���������ւ�čs�����B
�n���悹�A�������������A�n�M�́A�݂𗣂�āA�͐S�֕Y���o�����B�͕��͂����낵���L�����A���X�ɁA������A���̂��тɁA�M�ꂪ�A�K���K�������B�M�́A�����֗����ꗬ����A�߂ɁA�Ί݂������悹�Ă䂭�B
�u������A�ق��̎҂́A���ꂩ��A�قA�������v
�u���A��ɂȂ�܂������A�݂ȁA���s��̎���S�z���āA���Ȃ��A�A���ĉ�����悢���ƁA���g���C�����Ă����łł��v
�u�������B�c�c����������ƁA�܂��A�܂�Ő��Ԍ����Ȓ킽�����肾����Ȃ��v
�M�̏ォ��U�����ƁA�L�c�̊ق�A�X��A�܂��ق̂���ӂ�̏������n�`���A�ĂׂA�����ė������ȁA�ޕ��Ɍ�����B
(�\�\�����āA�ӂ����сA������n�邾�낤���H)
�ނ͂ӂƁA�^���ς݂����ȁA�����A�������Ă��m��ʐl�ԂƎv���v���ɂƂ���Ă����B���̔��ʂɂ́A����قNJ댯�ȓ{�肪�A�꒩�łȂ������̊킪�A�������Ƃ������Ƃ������Ă����B
(�Ί݂֒�������A���ۂ́A�A���Ƃ��悤�B�s����ŁA����ɖ��ꂪ���낤�Ƃ��A����̎q�܂ł����Ȃ��Ă͂��܂�)
�����l�������܂��A
(����A����̍��ȂǏE���ĖႢ�������Ȃ����A���ۂł����Ȃ���A�N���A�L�c�̊قցA������点�悤�B��͂�A��Ă䂭�Ƃ��悤�B���ۂɂ́A������������킹�Ȃ��悤��)
�n�M���w�݂悵���A�݂��������ŁA����́A�傫�����߂����B�����������Ƃ�����ɕԂ����B
�n�̔w�Ɉڂ��āA���ۂɌ��ւ�c�Ƃ点�Ȃ���A���֓��ւƓ����Ƃ����B��H�̂��͂����������˂ɐ��܂�A�n�Ɛl�̍ג����e���n�ɘA�ꂾ���čs���B�����āA�s����̒}�g�R�́A���A�e�������āA�N�����炩�ɁA�߁X�ƌ�����̂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ������Ă͉����̂ł���B�ǂ����ɁA����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ǝv���B
��ɓ���ƁA�\���A�����Ȃ��������L���ł̉ʂĂɁA�u���ق��邭���̂悤�Ƀ`�J�`�J�Ƃ܂������Ă��铔�̂����܂肪�]�܂ꂽ�B���ۂɐu���ƁA����͗�����̓��]�ɂȂ��Ă���y�Y�̎s�������Ƃ����B
�u�s������̂��B���Ⴀ�A�����֍s���Ĕ��낤���v
�u����ȉ����֎Q��قǂȂ�A�܂��܂��A����̗ǐ��l�̂��₵���֍s���������A����ۂNj߂��������܂���v
�u�������Ȃ��B����Ȃ��͂�A�ǐ��f���̓@�֍s������B�Ȃ��ɁA�锼�ɂȂ��Ă����܂����̂��B�c�c�����A�����ւ邼�A�����B�c�c���ہA�����H�����͎��������v
�u�����܂��ʁB����ɂ́A������܂����v
�u���̉k��Ƃ��݂���K���Ƃ̂��Ă݂��B���Ƃ��Ȃ낤���v
�u�Ȃ�܂��傤�Ƃ��v
��]�͕\�ʁA�C���邾�����B�ǂ������Ⴂ�����̂ł���B�s���R�łȂ��A�����A�ǂ�Ȋ����A�����̎�������͂܂��S�̂����Ŋ�Ԃ�ł��V�Y���Ă�����̂������B
�u���B�c�c�Ƃ������܂��B����Ă݂܂��傤���v
�u�S���Ƃ��v
�u�\�\�ł��Ȃ��悤�ł��B�y��������A��������܂��B�͂͂��A�v���o���܂����B�����́A�쑚�̕����ł��B�܂��A���������ɁA�����ȉƂ���������v
�u�쑚���B�c�c�Ƃ���ƁA�����ɂ́A�ނ����A��������Ȃ�Ƃ������Â��Ƃ��������͂������B�����̕����́A�|�t�A�b��A���v�t�A��낢�t�A�Ǝt�B�݂�ȕ���n��������Ă���҂����̕������v
�u�Ƃ�����A�����̓y������A�K���Ă݂܂��傤�B�\�\���ق́A������ƁA�����ł��҂����������v
���ۂ́A�ЂƂ�ŁA���@���ɍs�����B�Ȃ��Ȃ��߂��ė��Ȃ��������A�₪�āA���������������Ĕ��ŗ����B
�u�傪�o�ĎQ��܂��āA���́A���������ƁA��������܂����Ƃ���A�\�\�ȂɁA�L�c�̌�q���A����艺���ꂽ�Ƃ��B����́A�܂��Ƃł����邩�B�\�\�ƁA�܂�ŁA�o�q�ɖK��ꂽ�悤�Ȋ��т����ł��v
�u�����A�����A���ہB���܂��́A�Ƃ̎�ցA���ꂾ�Ƃ������Ƃ��A�G�ꂽ�̂��v
�u�����G�炷�قǂɂ͐\���܂���ł������A�]���Őu���܂��́A�L�c�̏���l���ƁA���\���܂����B����ƁA��́A�ɂ킩�ɁA�d�����𒅍X������A�Ƃ̎҂ɁA������𐴂߂�Ƃ������肵�āA�ǂ����ƁA��}���ǂނ����ɏo�ė��āA�������ɁA�����Ă���܂���B�c�c�ł�����A���قɂ��A�m�炸�ɂƂ͂���Ȃ��ŁA�}�g�ւ̒ʂ蓹�ɁA�킴�킴����������Ƌ�������ĉ������v
�u�ł��A����́A�����̎�Ȃǒm��Ȃ����v
�u��ł́A�悤���A�����グ�Ă���܂���B�\�\�Ƃ�����A����A���������肢�����܂��傤�v
�ƁA���ۂ́A��n���炤�܂̎�j���g���Ȃ���A��l�̂��Ƃɏ]���āA�����̓y����܂Ŕ����čs�����B
|
������
�헤�A�����𗼊݂ɂ��āA�����֗���鑼�̏��삵�傹��ƁA�㑍�̊C�֓f����Ă䂭������ƂɁA���̖і��̖��́A�����݂Ȃ���(���̐��C���̕�)�̂�����Ō��т����Ă���B
���̑吅����ㅂ߂����āA����䂤���A�V���ɂ���A�}�g�A�L�c�A���������܁A���n�A�M�����̂��A�^�ǂ܂��ׂ̏��S������A���̓c�̂ł��傤�̑����́\�\�Ƃ������́A�قƂ�ǂ��A���̒n���̌����̕���ɂȂ��Ă����B�ꔼ�́A����̏f�������\�\�헤�̑坁�����A�H���͂Ƃ�̏㑍��nj��������̂����悵���ˁA����̏헤�Z�Y�ǐ��ȂǁA�����镽���̑��������Ă����B
�������A���̒��ɂ́A�s�̐ۊ։Ƃ������̂�A�Ў��̑�����A�����̒��ڊǗ����Ă���y�n��A����̗̂Ƃ��m��Ȃ����J�n�Ȃǂ��A���G�ɁA���ݓ����Ă͂��邪�A�v����ɁA���͔͈͂Ƃ�����`�ɂȂ��Ă���\�\�܂��A�����܂ł��Ȃ��A����̖S���ǎ����A��Y�Ƃ��āA����ȉ��̈�q�����̂��߂ɁA�O�f���ɑ�Ă������c�̖̂ʐς��A���Ȃ��炸������Ă���B�����āA���ꂪ�A���ł͂�������A�f���O�Ƃ̕��ƂȂ��Ă��܂��A���F���傹��A�ق��Ă����Ђɂ͂��܂ŁA�Ԃ��Ă��ꂻ�����Ȃ��B
����́A�����ꔼ�͂Ƃ����ƁB
����́A�V���S����ɏZ�ތ���ɑ����鏊�̂�Ǘ��n�ł������B���̔Ő}�͂�Ƃ́A�����ɂ��������S�̂����̎l�S�ɂ킽��A�����Ƃ��Ă��A���ЁA������������Ƃ����ꑰ�ł���B
�ꑰ�݂͂ȁA���㌹���̂悤�ɁA��Ɩ��������Ă���B��̎q�A�}�������A���������A�ɂ�����ȂǁA���ꂼ��A�̓y���āA��˂������A���̂��āA���̈��̂��Ƃ��g�헤�����Ђ������h�Ƃ��������Ă���B
����̕��ǎ��̌��݂��������ɂ́A�܂��ɁA�헤�����ɉ�����g�Ⓦ������ǂ��ւ����h�̊T�������ȂāA���X�A���䂸��Ȃ��Λ��������Ă������̂ł��������A���̂܂ɂ��A�ǎ��S�����Ƃ́A�f���O�ƂƂ��A��̖�ɋ���Ȃ��ŁA�헤�����̉��ɏ]�����Ă��܂����\�\�����炭�́A�������Đh���炭���A���勌�̂��A�ۂ����Ă������̂ɂ������Ȃ��B
��́A��̂ӂƂ��A���͂�����A�������䂽���Ȓj�ɂ������Ȃ������B�헤�坁�Ȃ銯�E�́A���́A�ނ������Ă����������A�����͑ނЂ��āA�������ɑ�点�Ă��܂����B�܂��A�����̏��q���A�ǐ��ɉł����A���̂ނ��߂��nj��̌�Ȃɗ^���A����ɁA���̕P�܂ŁA���܂͓s�ɂ��鍑���̎q�A�핽���吷�̉łɂ���Ă���B
�������āA�����ƁA��������̗��ʂ���A��́A�����̎O�Ƃ��A����Ȃ��A�헤�����̑��}�ɉ����Ă��܂��A�����Ă��܂�A���̒n������̍������̒��V�Ƃ��āA������A�Ќ�������ׂ���҂��Ȃ��B
�\�\����ȁA����̒��ɁA����́A�����m�炸�ɁA�A���Ă����̂��B�\�O�N���A�s�ɂ��āA�����A�e�̂̂������L��ȓy�����͂���ƐM���ċA���ė����̂ł���B�Ƃ��낪�A�c���Ă����̂́A�����Ȃ��L�c�̌Êقӂ�₩���ƁA�������ꂽ�悤�Ȓ킽�������������B���̐��ڂƗ��݂������l�S���A�s�ł́A����Ƃ����قnj��ė������A�ނ͂܂��A����̋��ł́\�\�I�X�Ƃ��ĕω��̂Ȃ��厩�R�ɂ��܉�����ā\�\��Ɍ���قǂɂ́A�Ɋ��ł��Ȃ������B�ǂ����ɂ܂��A���y��M�������C�������������B���̔���������c���R�ɒ��[���߂��ďZ�ސl�Ԃɂ́A�s�l�̂悤�Ȍy���∫���͂Ȃ��Ƃ����M�O�������Ȃ������B�\�\���������邢�f�������ł��A���ꂩ��s���āA���ӂ�i����A�ĊO�A�͂Ȃ��͂킩��ɂ������Ȃ��B�Ȃ��A�~�͒����Ă��A���Ƃ������ł��A�Ԃ��Ă���Ȃ��Ƃ����b�͂Ȃ��B�\�\�ǂ����Ă��A�����v�����������B
�������A�ǂ����Ă��A�Ԃ��Ȃ�������A�ǂ����邩�B
����́A�������A���̏ꍇ���A�r�X�A�����Ԃ�l�����B���A�������������Ă��A�Ƃ����悤�Ȍ����̓{�肪���ɕ��������Ă��܂������ŁA���O�ɁA���̏ꍇ�̍l���������ėՂނ��Ƃ͕s�\�������B�����A�����̐��i�̎�_���A�����Ƃ��A�댯�ȉH�ڂɂԂ���̂��Ƃ������Ȃ́A�[���ɂ��Ă����B�O�����Ă̔��ȂȂǂ��A���ɂ����Ȃ�A�Ȃɂ��A��_�Ƃ͂����Ȃ����A���傪�A�|��Ă���̂́A�ނ��둊��ł͂Ȃ��A�����ł������B
�u�c�c�����B�������āA�����ŗV���ƁA�܂��ƁA�悤���Ă����łȂ���܂�����B���S���Ȃ�V�����ǎ��l�ƁB�c�c���͂��炻���ʁB�Z������v
������̖쑚�̉������Ȃ́A�q������ɂ����āA����������A���Ƃ�Ă��肢��B���Ƃ�Ă͂܂��A�ꌾ�ꌾ�A�������Ă��肢��B�~���ɍ����āA����́A�������̂��悤���Ȃ������B�]��ɁA�����̎���A�Ƒ����A������q���āA���d�ɂ��邩�炾�����B�s�ŁA���r�̗ւ�������A����߂Ă�����A�֖�ŏo��ߊ��̐l�ɂ́A�������������艺���Ă����Ȃ��܂������Ă��Ȃ��B�܂�ŁA����ł́A���������̒�����b�ɂȂ����悤�ȋC����������B
���̂Ƃ���A�����ւ��Ă��Ă��܂�Ȃ��̂��B��V���́A�т�H�������B�����āA��̖铹���}�����B
�u�Ȃ��A���ہv
����́A���イ�������ɁA���֘b���������B
�u���ł������B�����ƁA���ł��B�Ђ��ł��A�y���ɂȂ��āA�ɂ��Ƃ܂��悤����Ȃ����B�\�\�A��r�ɂł��A�܂��A��点�Ă��炤�Ƃ��āv
|
������
���́A�ȂĂ̂ق��Ȋ�������B
�u�ǂ����Ăł�����܂���B���������A������얖�̂��牮�ցA�킴�킴���K�������ꂽ���̂��v
�����Ă��炤���肾�Ƃ����B
���̂��߁A�����A���a�ł͕��C�����A�~�ł́A�V�Ȃ►�܂ł��A���̒ʂ�A���������̂��ނ�������āA���͂Ȃ��Ƃ��A��̖��A��̖��A�^�S����ׂĂ����������Ƃ��āA�呛�������Ă�����B
�u�����A�������Ƃ́A�]����A���C�̂��������܂��邼�B�L�c�̌���ɂ́A�ǂ���A���ڂ������Ă������������m��܂��ʁB���������A�Ă܂����A�s�����q���ł��ǂ����Ђ���āA�����ɕ������J�����̂��A�ǎ��l�̂������Ɉ˂�̂ł��B���̒n���ɂ́A�悢�Z�t��낢���ЂƂ肢�Ȃ��B�����A���E��A��čⓌ�։���Ȃ�A���A�d���͌����Ď肠���ɂ͂��ʁB�ǂ̂悤�Ȑ��b�����悤�ƁA���̂��a�̌�e�ɂ��ق�����A�܂��A�s�ɂ��Z�ݖO�����S�n�Ȃ̂ŁA��q�A���E�̎҂���낤�āA�����ɏZ��ł��������\���N�ɂȂ�܂����B�c�c���̗ǎ��l�����������A�ӂƁA�H�ɗ҂��ނ��Ƃ�������܂����Ƃ���A�v�������Ȃ��A��q�̌䐬�l�����A��܂̂�����ɔq���āA���̖ꂶ���́A�v������X�����ɁA�ނ����������イ���������Ă���܂����̂��v
�\�\�܂��A�@���̂ł���B
����́A�������˂Ă��܂����B�����ւ����ȂǂƂ��A�����o���Ȃ��B
���̖��́A�������ӂ��݂̂��傤�Ƃ����A�R���܂���̐��ꂾ���A���̒n���։���H�������݂Ƃ��ĈڏZ���Ă���́A�P�ɖ쑚�̉��Ƃ��A�쑚�̋�t���������Ƃ��Ă���B
�B��̌㉇�҂ł������ǎ��̖v��́A�ꎞ�A�����̏��E�Ƃ��A�d���������āA�r���ɂ��ꂽ���A���̌�A����̌��삪�A����ɑ��ȏ�̒������o���n�߁A�ȗ��헤�����̏��Ƃ̕�����Ђ������āA�N���A��̂������Ƃ͂Ȃ��ȂǂƂ��A�b���o�����B
�u����̗ǎ��l�ɂ��[�߂����A���X������Z���A�G������A�|�A���ق��A�����Ȃǂ��A���т����������ł�����܂������A�����̕i�X�́A�܂�����q�ɁA��������A���`���ł�����܂��傤�ȁB�����ǁA���Ȃ��̂��̂ɍ���������A���ЁA��点�Ă��������������̂Łc�c�v�Ƃ��A�������肷��B
����́A���҂�����������B���ۂ��A�����������ƁA�����Ɍ������B�n���̍����̗��݂Ƃ���̂́A�y�̎��ɂ́A����Ȃ̂��B�����̎�l�ɂ́A���̓�Ƃ��A���͂Ȃ��B
�u�����̒��́A�ǂ�������āA�������ł������܂��ȁv
���́A����������̂ƁA�Ƃ肬�߂��āA�����u�����B�\�\�}�g�̏f�����̂₵���ցA�Ə��傪������ƁA
�u�͂͂��A�����H���ւ�������Ⴂ�܂����B�����A����́v
�ƁA�Ȃɂ������Ȃ���������B
�쑚�̉����A����̍��̋����́A�m���Ă���炵�����������Ԃ�ł���B�����̔[�߂�����A�����q�ɂ���܂����Ɛu�����̂́A�킴�ƁA����̌���U�����߂ɐu�˂��̂�������Ȃ��B
�ǎ��̈�q�����֕Ԃ��ׂ��L��ȓy�n���A���̏f������������ĉ��̂��Ă���Ƃ��������́A�����A�ߋ��̓y���ɂ܂Œm��n���Ă�����Ȃ��\�ɂȂ��Ă���炵���B�\�\�쑚�̉��̊��҂́A�����A�ނ������������Ƃ����݂̂ł͂Ȃ��A���́A��������������A���ꂪ���Ă���̂�������Ȃ������B
����A���ꂩ��A��X����܂ŁA�y���ɂȂ�Ȃ���A����ɑł������Ęb������ł݂�ƁA�����̉Ƒ����F�A�������āA������A�C�̂ǂ��ȁA�����ȁA��s�^�Ȍ�q�Ƃ��āA����Ă�����̂ł��������Ƃ��A�Ȃ��A�͂����肵���B���̍Ȃ́A�����\�ȏ�Ƃ݂���[���o�ė��āA���d�ɘ����������Ȃ���A�b�̂��ŁA�Ⴂ�������Ă���̂ł���B
�u�H���ւ��o�łȂ���Ă��A�Γc�̍����l�̂��قւ������Ȃ���Ă��A��߁A�����������ĂȂ���܂��ȁB�ЂƂ͊F�A�m���Ă���܂�������B����ɁA����A���g�ɉ���Ȃǂ����Ă͂Ȃ�܂��ʁB���ꂱ���A�S��������ǎ��l��������܂��ʁc�c�v
�[�������B���������B
���������Ȑl�S�ɂ���܂�A���������ȐH���ɕ����݂����A����́A���ɂ��̔ӂ́A�쑚�̋�t�̉ƂɐQ���B�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��L���A��q��珢�g���������A�䂽���Ȋ����ł���B�����āA�Q���˂�ɓ������Ƃ��A�ǂ����ŁA�Ⴂ���̐��������B���̔��������̂ʂ���z�����Ȃ���A����́A��������ɂ������B
�閾���ɗ��������A�Ƃ����Ă������̂ŁA�܂��A�����̂ӂ��������ɋN���ꂽ�B�H�������A�ٓ�������Ă��炢�A�Ƒ������ɑ����āA����o��Ƃ��A�ӂƁA����͔n�̏ォ��[�̂��ɂ���\�Z�A���̖��������B�܂�ŕ����̓s�Ō����悤�Ȗ��������B����̎������䂭�ƁA���͕�̌��̈��ցA�g�����������B���̗z���A�܂䂰�Ȕޏ��̊���A�N�炩�ɁA�������Ă����B
�u�c�c���A�肪���ɂ��v
�ƁA�Ƒ��������������B����͂��Ȃ��������A���͎��M���Ȃ������B�y����̕��ցA�n�̔����߂���ƁA���ۂ͂������ւ�c�����B���ۂ��A���̓����A������x�ʂ�ł��傤�Ƃ͒N�ɂ�����Ȃ��B
�u������v
�ƁA�n�������o���Ă���A����͐U��ڂ��������B�\�\�ƁB�܂������Ă���Ƒ������̎������A�݂ȁA�ׂȕ��ւ���Ă����B������A�n�ォ�猩�܂킵���B�ޕ��̐�䊂������̏�Ɍ܁A�Z���̏㔼�g���������B���̂ЂƂ�́A�R�n�ł���B
���݂���߂Â��قǂɁA���R�A���̎҂����Ƃ�������������B�R�n�̎Ⴂ���m�́A����̊���A�������ɁA����Ō����B��߂Ƃ����A�ƂƂ����A�����Ƃ����A���̒n���ł́A�r�������ڗ����ȑ����ł���B�]�҂����ł��A������͗��h�ł���B���ۂ́A���b�ۂ������Ēʂ�ʂ����B
���߂����Ă���A���傪�u�����B
�u���ہB���܂̂��A�m���Ă邩�\�\�B�N�����A����́H�v
�u���ꂪ�A���}�ł���B����̌���̒��j�Ƃ������v
�u�헤�������B�c�c�����A�h��₩�Ȃ��̂��ȁv
�u���q�����͂����A�䑂�q�������Ƃ��A��a�Ƃ��Ă��āA���ɂ��A�X�ɂ��A�o�܂���ˁB�c�c����ǁA���ۂ̌��l�̕����A�͂邩�ɏ헤�����Ȃǂ��A�Ƃ���͏�ł��B�����V�c����Z���̌䑷�ł��傤�B���̎҂ł��A���̐l�������A��q�Ƃ͒N���Ăт͂��܂���v
���ۂ́A�ЂƂ�ł���ׂ��Ă����B���傪�������U�����Ă���̂�m��Ȃ��̂ł���B����̊�́A�������A�������ʂ�ė����y����̑O�ŁA���̏헤�����̌䑂�q���A�n���~��āA�Ɨ������Ƌ��ɁA�ЋV�Â���Ȃ���A�Ƃ̒��}�����Ă���̂��\�\�n�̔w�ɗh���h���Č��Ă����̂������B |
�������炬�̌N
�}�g�R�̐���̂ӂ��ƁA�}�g����ƁA�і��̕������āA����̏��A�Γc�̏��A�H���̏��Ȃǂ��A�����A�O�������ɂ���B
�ǂ���F�A�}�g��w�ɂ����[�̐l�����B
���̓��A����́A�܂�����̗ǐ��̂₵���֍s�������A�f���͂��Ȃ������B������������Ă���l�q�ł��Ȃ��B
�������A�Ɨ������̊���ɂ́A����������Ƃ���ɁA�����ƁA�������F������A
(�����ȁI)
�Ƃ������悤�Ȕ������A�����炩�Ɍ���ꂽ�B�����āA���傪�����҂��ЂƂ�A�ꂽ�����ł���Ă������ƂɁA�ނ���A�C������H�����قǂȋْ��Ԃ肪�M��������ꂽ�B
�u�����炾�B���ق́A��邩���s�݂��B�����A��p���v
�ƁA�Ɛl�Y�}�́A���l���A�傫�ȘE��₮��������o���āA�ʂ��������A�����ł��������������B
�����炭�͍���A�і��̉͌����ŁA�킪�Ƃ̓z�l��Y�}���������߂����̂́A���̘A���ɂ������Ȃ��B���Ƃ���A�͌��̔����ցA���̐錾�݂����ȍ��D�𗧂Ă��Ɛl�i�v���ɂ��Ђ��Ƃ�炢���ǐ��̉Ɨ������̒��ɂ���̂�������Ȃ��B�������A����́A���������G�l���������ĂɌ��܂���C�ɂȂ�Ȃ������B�����̕s���ȑԓx�ɂ́A���͂��������A�������āA�����͗����������B
�������炢���A�坁�����������傤���ɂ��̋��فA�Γc�̗��̕����A��������͋߂��B�������A���̑�f�������́A������̉����ł���A�����ł���ƁA����͊ςĂ���B���łɁA�s�ɂ����Ƃ�����A����͍����̎q�A�핽���吷�̍s���ł��ǂ߂Ă������A�܂��A�㋞�̏��߂���A���܂��܂ŁA�����ɂ������鍑�����q�̑ԓx�́A�D�ɗ����Ȃ������炯�ł���B
�u�c�c��ɂ��悤�B�������̑Ό��Ƃ��āv
����́A�����ɁA�H���̏㑍��nj���K�����Ƃɂ��߂��B
���̏f�����A�H�킹�҂�������Ȃ����A�ꑰ�̒��ł͈ȑO����A������M�Ƃł������B���@�ɋA�˂����ӂ����A�ق̓��ɂ��A���̂悤�Ȏ����������ĂĂ���Ƃ������B���������l�Ȃ�A�����炩�̕��S�͂��������Ă��邾�낤�B������A�苭�Ă��킻���ȑ�f���ւԂ�����́A�܂��A���̐M�S�Ƃ̏f���Ƙb���Ă݂�̂��A�Ǎ�Ƃ������̂��B����́A�Ȃ��A�����āA��Â���������A���ʂ���������͂��Ă��Ȃ�����ł���B
�H���̏f���̊ق́A�R���������B�[���炷�����R�H�������������ɍ\���A���܂����Βi�̎R�ɁA���Ȃ���厛�@�̂悤�Ȗ傪�A���R�̘V���⏼������������Ԃ��Ă����B
�n�́A�[�ō~��A���ۂ��A���ɑ҂����Ă����āA������l�ŁA����͂������B�区�ւ����܂킵�Ă���ƁA���̉Ɛl��������A���m���o�ė����B���߂́A�܂ݏo�������Ȍ��܂����������A�ނ��A�B�R�Ƃ��āA�����Y���傾�ƍ�����ƁA�������ɋC���������ꂽ�C���ŁA���Ƃ����߂������B
�掟���ɋ������܂܁A�Ɛl�́A�Ȃ��Ȃ��o�ė��Ȃ��B�[����߂��z���A�j�t������̂悤�ɓ����āA�������̎R�ӂ������ł́A哂Ђ��炵���e���Ă����B�ǂ����ɁA�ӂƁA���̂����炬�������A����́A�A�̊����킫���o���o�����B
�u�x���Ȃ��B�������Ă���̂��낤�H�v
�掟�ɂ����ꂽ�Ɛl�́A�傪�A����Ƃ����킸�A���Ȃ��Ƃ�����Ȃ������B�����ɂ��A����̖і�쌴�̎����A�����Ă�����̂Ƃ݂���B�Ƃ���ƁA����o��͂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�f���̊ق֗��āA�댯���ȋ^����������C�����ɓw�߂�̂́A����̐��i�ɂ́A���̐܂�邱�Ƃ������B����ǖ쑚�̕���t���A����ƂȂ��A���ӂ�^���Ă���Ă����B�\�\�������A���Ȃ��́A�܂����Ⴂ�łȂ��A�Ƃ����ɂ��S���ƂȂ��悤�ɁA���������Ǝ��������ĂԂ₢�����Ƃ������B
�u�悵�B�����A�ˑR�N���Ă��A����͌����āA�����͂��Ȃ����B������Ȃ�A�і���n���ė��͂��Ȃ��v
����́A�����ւނ����āA���������Ă����K�v���o�����B��҂ɁA�L�O�Ђ�܂����߂ɕ����o���Ă����B����ɁA�R��ւ͂��肱�B����������A�A�̊��������߂Ă��鐅���\�\�ǂ����ɁA����̗����Ă��鉹���\�\�T���ɍs�������̂炵���B
���ꂢ�ɁA��̂Ƃǂ��Ă�����A��ۂ�A���̋��́A�ڂɂ����A���́A�ǂ���ʂ��Ă���̂��A������Ȃ������B���̂����ɁA�ނ́A�v�������Ȃ����̂��A�ӂƁA�ޕ��̖؈��Ɍ��o�����B
��ł��A���Ԃ���悤�ɁA��������Ă����B
�u���B�c�c�H�v
����́A���R�Ȃ��A���������߂��B���܈ȂāA�ނ́A�����������Ɗ�����ƁA���R�̐����Ȃ��O�ɁA��͂�������A�̂��イ�ɔ��˂��N�����B
�ނ��A�������藧���������Ƃ���́A���̏Z���̂����ł����������m��Ȃ��B�s�̒�������b�̏�����̚₪�v���o���ꂽ�B��b���A�����ɔ邵�ĉ������Ă������z�Ԃ̌N�ɂ悭���Ă��āA������͂�⏬�Â���ŔN���Ⴂ�������A�����ƁA�Ȃ��܂��؈�����A�ނ̎p���A�����܂��Ă���̂������B
�@ |
���ʒ�
�u�����͒ʂ�܂��ʁv�\�\�ޏ��͍D�ӂ̂��钍�ӂ�^���ĂقُB�u�����A��p�ł��́H�@�c�c�B�،˂��ԈႦ���̂��Ⴀ��܂��v
�e�����ɂ����u����āA����́A�܂��A�ǂ��܂������B���R�̂Ȃ�㵒p���A�����ł́A���b�Ƃ��Ȃ��Ǝv���Ȃ���A�v���قǁA�Ȃ��A���Ԃ������B
�u�����A���ł��B������ς��A�~�����Ǝv���āv
�u����������ɂȂ鐅�ł����v
�u�����B������A��������������̓����A�n�ŏ��ʂ��ė����̂ŁA�����ɂ��Ƌ}�ɁA�̂ǂ̊������o�����Ƃ���ցA������ɁA���������������̂ł�����v
�u�z�z�z�z�B����Ȃ�A������֗��āA��������Ȃ����܂��B���₷�����Ƃł��v
�ޏ��́A��̖̊Ԃ�D���A�������n�����傤����ȉƂ̐����ւ����ꂽ�B
��ɐ����������A����ǂ́A�L�̍Ȍ˂��痧�������āA����̑O�ւ����߂��B����́A�ł��̎q(��)�̒[�ɍ��������B�����āA�\�����Ȃ������������ɂ܂ꂽ�悤�ɁA������̂������܂������܂킵���B
�u�������Ă���ƁA�ǂ����A�s�̂��Z���̂悤�ł��ȁv
�u�s�B�c�c���̕����̓s���A���Ȃ��́A�����Ȃ̂ł����v
�u���B�i�����ƁA������ցA�s���Ă���܂����v
�u�܂��v�ƁA�����́A�傰���Ȓ��A�Ȃ����ޕ\������āu�s�́A�ǂ���ɁA�����łł����́v
�u������̍���b�Ƃɂ�����܂������A��ɁA�䏊�̑���ɂ��A�߂���Ȃǂ��āv
�u�ł́A���Ȃ��́A�L�c�̌�q�́A����l�ł͂���܂��v
�u�����ł��B�����Y����ł��v�悤�₭�A�ނ͔ޏ��𐳎����邱�Ƃ��ł��ā\�\�u�����A�䑶�m�ł����v�ƁA�S�̋������}�ɂ̂������B
�u�������B�������̂́A���߂Ăł����A�����킳�́A�����Ă��܂����B����Ɏ����A���́A�s�̎҂ł�����v
�u�����ł����B�ǂ����A�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂����v
�u�ǂ����Ăł��H�v
�u�ǂ����A�s�̕��ӂ���������ɂȂ邵�A����ȁA�y���e�������r�������̉ʂĂɁA���Ȃ��̂悤�Ȕ������l���c�c�Ɓv
�u����A����Ȃ��Ƃ��A��������āv
�ޏ��́A���̂�������A�ς��Ɛ��߂āA�����̊���A�����̌��̂�����։B�����B���炾�̎p�Ԃɂ�āA���₩�ȍ������₳�����Ȑ���`�����B����́A�ޏ����݈߂������݂̋�������A�v�����킷��Ă����s�l�̔����̍���k���Ƃ��āA���������A�Y��Ă����B
����ƁA���������֎掟�ɂ͂������nj��̉Ɛl�����ɈႢ�Ȃ������O�A�l�l�̐������āA������ɏ����T������Ă����B�����ĂӂƁA���̈�l���A�����̛��̉����A�̊Ԃ����ɉM���āA
�u��B������B�����ɂ���B�ʒ��ǂ̂̋ǂɗ��āA�b������ł����v
�ƁA�����ꂽ�悤�ɁA�ق��̎҂��A�Ăт��Ă��B
����́A�e�͂����ꂽ�悤�ɁA���𗣂�āA��������Ɛl�����̕��ցA���݂������B�nj��̉Ɛl�����́A�ނƋʒ��̂��������A�����Ɍ�����ׂāA�u�ԁA���Ȋ�����Ă������A
�u�L�c�̏��a���Ƃ́B�\�\�nj��l����Ă��Ƌ���ꂽ�B������ցA�n��ꂢ�v
�ƁA��ɗ������B�����Ă��Ƃ̍L�O�ɖ߂�A��������ق̓��ցA�ē����čs�����B
|
���Y���_��
�����̌��z���܂˂��̂ł��낤�B�Q�a�A�m���Â���ł���B�������A���̒n���̕���ɑς��邽�߂ɂ́A�����ӂƂ��A�ǂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���R�A��łł���A�e��ł���A���Â����Ȃ�B�\�\��̊��q���z�Ǝ���Ƃ��낪���������B
���̒�(����)�֖ʂ����L���̊ԂɁA�a����~���A�~���ɍ����āA�����ނ݂����Ă���q�Ǝ�l�Ƃ́A����������A���������ɒk���Ă����B
�㑍��nj��ƁA����̘Z�Y�ǐ��ł���B
����̕��ǎ��̒킽�����B�܂�f�����ł���B�����ɂ͂��Ȃ����A�헤�̑坁�������A�������ŁA���̉�������̕��A�����nj��A�ǐ��̏��������B
�u�ǐ��B�\�\���傪����֗��Ă��A�]��j�ȂԂ�������B�j��҂ɂ��āA�{�炵�Ă��n�܂�ʁv
�u�ł����A�����ǂ́A��̍����Ƃ����߂Ă��������������Ǝv���ȁB�c�c�����ɂȂ�v
�u�܁B��������邪�A����ɂ��Ă��v
�u���̂��A�͌����ŁA����̓z�l�ƁA�킪�Ƃ̉Ɛl�Ƃ��A���܂̉ʂāA����ɓ{���āA�ގ��g�A�����܂ł���ė����Ƃ�����݂�ƁA�܂��ȑO�̏��̒n�ɂ�������āA���ꋤ�̏��u���A�ӂ����A�⍦�ɂ��Ă���ɂ������Ȃ��v
�u���̎����́A�꒩�ɂ́A�����܂���B��������i�������A�C���ɁA���߂����ɂ�����v
�u���Ȃ��́A�悭���������邪�A������A���ł́A�ނ����̕@���炵�Ƃ������A�s�̂����ɂ�������ė��āA�����̈���o�����낤���A���܂����̂����N�ł��Ȃ��B�\�\�͂ŗ}������Ɍ���܂���B�����ƁA��x�A�����瑤�́A�͂̂قǂ��A�v���m�炵�Ă����ʂ��Ƃɂ́v
�L�̒[�ɁA�����������B��l�́A��܂��Ƌ��ɁA�ނ��������������āA�������B
����́A�ʂ��ƁA���̊O�ɗ������B�����āA�f�������̎����Ɏ����������Ă��������B�������A�w�߂�悤�ɘa�Ȃ��܂��āA
�u���ז����܂��v�ƁA����ɍ������B
������ē����ė����Ɛl�����́A�t���l�݂����ɁA�ނ̔w���ɂ�܂����܂܁A�L�̊Ԃɂ������܂��Ă����B
�u�₠�A���傩�B�����ƁA���ʂ��B����ȉ����ɁA�������܂��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��v
�nj��́A���肰�Ȃ��A����������B�\�\���A�ǐ��́A���̂�����̎������邵�A�R�ɂ��A������������Ă���nj��Ƃ������A����ł��A���E���ȂāA�ߋ��ɖ��Ă���j�ł���B�Ă�ŁA���̏���ȂǁA��̂����ɂ��Ȃ��悤�ɁA���������āA�����̂�ł������A
�u�����ɗ����̂��B�����ɁH�@�c�c�v
�ƁA�����Ȃ菫��̕������Ă������B
����̑S�g���A����ɂӂ���āA�ۂ��Ȃ����悤�Ɍ������B���A�ނ́A��������āA�����̗��ʐF���B���悤�ɘ�����ނ����̂ł������B
�u�A���ȗ��A���A�����������Ă���܂����c�c�ŁA�����ǂ́A���������ɏo�Ȃ���ƁA�v���܂��āv
�u��ɗ����̂��B���N�̗�Ɂv
�u�c�c���B�c�c�܂��A�����ł��v
�u�܂��Ƃ͉����B�g�Ƃ��ɁA�Γc�̑�f���ւ��A���������Ɏf���͓̂��R���B�s���ė����̂��v
�u�����B�܂��A�Q��܂���v
�u�Ȃ��s����B�����֗���Ȃ�A�ʂ蓹�ł͂Ȃ����B���ׂĂ̂������A�a���ʂ��̂́A��b�������Ă���B�p�ł��Ȃ��S�i��ߋ��̗L�ۖ��ۂ������ނ������A�A����I�ڂɁA�L�c�֏������肵�āB�\�\����Ȍ������A�Ȃ��A���`�̂����f���̊قցA�i�X�A���璆�ɂ́A���炢�����b�ɂȂ�܂����ƁA�����ĕ����Ȃ����v
�u�c�c�Ƃ́A�v���܂������v
�u������v
�u�́v
�u�����ɕ��̂͂��܂����悤�Ȃ�����������ȁB�M�l�́A�����A�v�����������Ă���ȁB�ւ�Ɂv
�u�c�c�c�c�v
�u��낵�����B�悭������B�\���N�Ƃ����i���ԁA�Ƃ܂�A�����ȉ��́A���ĂĂȂ��q�A���l���A���̂悤�ɁA�����A���l�����ė����̂́A����̏���v
�u�c�c�c�c�v
�u������肶��Ȃ��B�����܂��A����f�����̔삪�Ȃ�������A�Z�ǎ��̈₵���y�n�Ƃ����A�قƂ����A�q��Ƃ����A���̒ʂ�ɁA��Ȃ�Ȃ��A�����܂ŁA�M�l�����Z��̎�ɁA�c���Ă���Ǝv���̂��B�\�\�Ƃ�ł��Ȃ�����v�ƁA�ǐ��́A��ɂ��Ă����t�̒��֑�����悤�ɂ����āA�������������A�܂��������B
�u����ȊÂ��l����������A�Ђ��ẮA���`�͖Y��āA�t��������݂ȂǕ����悤�ɂ��Ȃ�B�\�\���̍L���Ⓦ�̞D��ł́A�����A������z���o�āA���ɗz������ł��邾���̂悤�ɁA�M�l�Ȃǂ̊�ɂ́A�����邩������ʂ��A�ǂ����āA�Ԃ܂��Ȍ��������ȁA�ߐ{�A�{��݂€�Ȃǂ́A���k�̘؎��ӂ��イ��A�l�ׂ̍������A��ڂ̓y�n�ł��A�\�H���悤�ƁA�M�������Ă���̂����B�\�\������\���N�̊ԁA�h������Ă��ꂽ�̂͒N���B����A���Ƃ��A�ȑO�̂悤�ȍG��ȓc�́A�����͂��������������ɂ��Ă��A�s����A���ė��āA���������A�Z�މƂɂ����炸�A�k���y�n������A�Ɩ������y�ɑ������Ă���Ƃ����剶�́A����̂��������v
�u���A������A������ƁA�҂��ĉ������v
�u���܂�B���ꂩ�瓚���Ă݂�B����̗͂��A�l�ׂ̘T����A�y�n��ق��A�h���A����Ă��Ă��ꂽ�����v
�u��A�킩���Ă��܂��B�c�c����ǁv
�u�킩������A����ł����B�������Ƃ����Ȃ���A�����A���̗܂́A�c�c�ڂ�ڂ�A���ŗ܂��o���̂��v
�u�����A�������Ȃ�A�����A�\���܂��v
�u�Ȃɂ��v
�u����̉����A����̏���ƁA�����Ⴂ�܂����A���̎��́A���ǂ��Z�킪�c���ł��������߁A���̗ǎ����A���e�̂��Ȃ�����M���āA���c�c���ʂ܂��Ɂc�c�����A���̂ނƈ⌾���c�c���Ȃ����́A����ł䂭�҂ɁA�S�z����ȁA���Ȃ炸�A�q�炪���l�̌�ɂ́A�������A���y�n���A�Ԃ��Ă��ƁA�����āA���a�艺���ꂽ���̂ł͂���܂��v
�u�������B�c�c������A�����A�M���܂́A�L�c�̊قɁA�Z��ł���ł͂Ȃ����B�ق��̒�ǂ����A�Q�����ɁA�����Ă���ł͂Ȃ����v
�u����B�܂��A�Ԃ��ė��Ȃ����̂�����܂��B�\�\�����A���������Ă�����y�n�A���ɂ���Ď���������`�̑����B�����ɕ������Ă��鑾�����̒n���A�����A���i�̏ȂǁA��Y�̑啔���́A�Ԃ��Ă��������Ă���܂���v
�u��������ȃb�v�ǂ����āA�ǐ��́A�t�̎����A�Ԃ������悤�Ƃ������A�nj����A����ĂāA�肭�т�}�����B
�u���ꂱ��A����B���e�����炢���悤�Ȃ��̂́A����ȓ��菟��́A�������̂ł͂Ȃ��v
�u���菟��ł��傤���B�\�\�f���䂽���łȂ����̕����H�v
�u���B�����ƁB����c�c���܂��͂ȁv�ƁA�nj����A�����A���Ȃ̗����̖h���ɗ�������Ȃ��Ȃ����B����A���������ŕ������̂����y�n�̐��������A�����ŕق��Ă����K�v�ɔ���ꂽ�̂��B
�u�Ԃ��́A�Ԃ�ʂ̂ƁA�P���ɁA�����Ă��邪�A�L��ȓc�̂𑽔N�A����Ă���ɂ́A���ꂾ���́A�]��������̂����B�����a�ł��A�����ɂ���ǐ��ł��A���ׂ̈ɂ́A���x�A�S�̐N���҂�A�؎��̑����ȂǂƁA�����Ȃ����āA���܂�A�������������m��ʁv
�u����́A����ł��B���Ԃ�������ȏ�́A����n�߁A�틤���A�I���A����͌䉶�Ɋ����A�܂��A�f���䂽���̂��ƂɁA�꒩�A�ϗ��̂���Ƃ��ɂ́A���ł��A�|���т������āA�܃b��ɋ킯���悤�Ƃ������̂ł��B�\�\�s�K�A����͗c���Ŋo���Ă��܂��A����̐e�ދ��̂͂Ȃ��ł́A���āA���Ȃ������A���̏헤�A�����̒n�ɁA���͂ŗ����A���܂��̓G��A�؎��̐��͂̒��ŁA����ꓬ����Ă������ɂ́A���̕��ǎ����A�����̕��g�Ƃ��v���āA���Ȃ����������āA���ɂ��̒}�g�R�ȓ��Ȗk�̂Ђ낢������A���Ȃ����̗̖�ɂ����̂��ƕ����Ă���܂��v
�u���A���ꂪ�������A����Ȏ����v
�u����ł��A���Ԃł́A�m���Ă��܂��B�\�\�����A���Ȃ����Ɉ�ǂ��������̂��A���ꂪ���邩��ł��B����A�ԈႢ�͂���܂��ƐM�����̂ł��傤�B�����A�Y���Ƌ������Ȃ�A���̑O�ɁA���Ȃ��������A���҂̈��𗠐����Y���̓k�ł͂���܂��v
�u���ӋC�Ȃ��v
����ǂ́A�Ԃɂ���Ȃ������B������̂́A�ǐ��ł���B�nj����Ƃ߂邷�����Ȃ��A�˂������āA�nj��̂�������ׂ��A
�u�Y���Ƃ������ȁB�f���ɂނ����āA���l�����ȁB���̐�˂߁v
����̍��̌��ցA�ނ̑傫�ȑ����A�R���Ă����B����́A���̑����A����ł��܂����B�����āA�ނ����𗧂Ă�̂ƁA�ǐ����A������̍����������Ⓐ�q���傤����Â��āA�����ɁA�Ђ�����Ԃ����̂ƁA�ꂵ��ł������B
�u������Ȃ��A����v
�ǐ��́A�i�����B�������ǐ����A�N���オ��܂��ɁA�L�̊ԂɂЂ����Ă���Ɛl�������A���ǂ肩�����āA�����납��A����ɁA���݂��Ă����B
|
�����Ă̏��l
���ȋȗ֑���̉Ƃ��A��u�A�Ɩ�Ɏ��������ƁA�b���݂��l�Ԃ̙ɁA�h���Ԃ�ꂽ�B
�\�\���B��u�ɂ���́A�n�^�Ƃ�B
���̂��Ƃ́A���Ƃ��������Ȃ����܂̉��ɁA����̂��߂����������B����A�f�����Ă��Ⴍ�苃���ނ̈ٗl�Ȑ��������B�܂��A���̎���ɁA���O���A�����炯�ɂ�����A����т͂��܂��A�ق�����Ă�����l���\�\�܂����Ȋ���������܂܁A���炭�A�傫�ȑ����A���ł������Ă����B
�u�c�c���A�{���߁B�c�c�����Ƃ������āA�悢�قǂɂ��Ă����v
�ǐ��́A����ƁA���������ė����悤�ɁA�ꂢ���B�����āA�吨�ŖŒ��Œ��ɖo������R�����肵�āA���E���̖ڂɂ��킹������̎p���A���̂��������A���܂ŁA�ɂ�݂��Ă����B
�u���Ă��B���B��������āA���݂����Ȍ��������Ă݂�B�\�\������B�ǂ������B���ĂȂ��̂��v
�ǐ��A�nj��A�͂��߁A�l�X�͂悤�₭�A������̔t�Ղ̕��X�ɂȂ��Ă���̂�A����Ă���Ǒォ�ׂ���ȂǂɋC�����ā\�\�����̕@���Ő@�����肵���B
����́A�g�𝆂�ŁA�܂��A�L�Ȃ��ނ���ł����B
�u���킯�҂��v
�nj��́A�Ɛl���ɂ�ցA���������B
�u���������̎�������A�����Ȃ����B�܂ݏo���Ă��ꂢ�B���̉����v
�����ɋ킯�W�܂��Ă����Ɛl�Y�}�́A�\�l�������Ă����B������A�����������B��قǁA�r���ۂ��A�ܒ@���ɂ��ꂽ�Ƃ݂��A����́A���������Ȃ��B���O���A�����������������B
�u�܂Ă܂āA�܂��v
�ǐ��́A�ނ������ŁA�����o���Q����Ƃ߂ā\�\
�u����B�킷���Ȃ�B���傤�̂Ƃ���́A��邵�ċA�����A���ꂪ�A��̉����ƁA�����炭�A�������̂��͂Ȃ������͂����B�c�c���̂����A�͌����ɁA�Ɛl�̌i�v�����ĂĂ��������D���A�Ђ������āA�і��֝e�ق���̂Ă��Ƃ��B�\�\���̈���ł��A�ق�Ƃ́A�L�c�̊قցA�킪�Ƃ̘Y�}���A�����P�悹�Ă䂭���R�͂���B�P�������������A���S�R�Ƃ����r���҂��A���̏f�������A�~���Ƃ����Ă��A�~�܂�ʂ��B�c�c�悢���B���̌�Ƃ��A�����ʂ͂��܂��߂�B�܂�ʂ܂˂��āA���̒틤�ɁA�����������ʂ������v
�ƁA�l���̎��R�������Ă���ނ̎����Ƃւ����Ă��������B
������A�����A���͂��ӂ���āA�������Ƃ������A�Ƃ���ɁA�����L�̋��������āA�ˊO���Ƃ̍L�O�ցA�����o����Ă����B
�u�ǂ�����c�c�H�v�ƁA�����ŁA�Y�}�����̑��k���������A�₪�āA�ʓ|���Ƃ���A�ق̖���o�����̊R�ۂ������킩��A�������āA������A�e��̂Ă��B
�R�͋}�����A���������Ȑ����A�������Ă���̂ŁA�ނ̑̂́A�����r���̖̍��ɁA�Ђ����������B
�u�c�c�������Ă���B���ɂ͂��Ȃ��v
��ŁA�Y�}�������A�����ċ������̂��A����ɁA�����Ă����B���A�ӎ��̂��̂ق��̉����̂��Ƃ炦���Ȃ��B�����������Ă���悤�ȋC�͂��邪�A���̎�ɂ��m�o���Ȃ��B
��̖̍����玟�̖̍��փY���Y���Ɠ]�������B�ɂ��ƁA�v���A����������邱�Ƃ��ł����B
�u�c�c�������Ă͂��߁B�������Ă͂����܂���B���́A����ł�����v
���ꂩ�A�ǂ����ŁA�����Ă���B�܂������A���Ԃ̌o�߂m�o�ł����炵���B�^���Ԃȗ[�A�����̏��̂����܂�N�炩�ɂ��Ă���B�[�I���A���ɟ��ށB
�u���܁A�s���܂�����ˁc�c�B�������Ȃ��Łv
�����߂��B����߂Â��Ă���B����́A�Ƃ��Ƃ��������������B
�ꏊ�����ɁA�������A���������̖`���ɗՂ�łł�����悤�ɁA�ォ��~��Ă���҂�����B�������A�݈߂̐l�ł���B�nj��̘Y�}���A�ʒ��ǂ̂Ƃ���̏����ɂ������Ȃ��B
�u���c�c�H�v���R�Ƃ��A�����킸�A����͉�����A
�u���ԂȂ��v�ƁA�����B
�����Ԃ܂łɁA�ӎ����͂����肷��ƁA�S�g�̒ɂ݂��A�M�����тāA�ނ��A�X���߂������B�傫���A���x���X���Ȃ����B�X��ƁA�y�ł���B
�ʒ��́A���ɂ��܂ŁA�~��ė����B�ޏ��́A�ނɋC�͂������āA��������オ��悤�ɂ����߂����A���߂������B�Ƃ����āA�ޏ��̛]�Ȃ�₩�Șr�ł́A����̑̂��A�ǂ����悤���Ȃ��B
�u��ė������ۂƂ��������҂��A����̐Βi�̉��ŁA�҂��Ă��܂��B���̗��ۂɁA�m�点�ĉ������v
����́A����Ƃ��������B�ޏ��́A�������ǁA�݈߂̏ւ����A�]�ق���Ԃ̂����Ƃ킸�A�R���̂ڂ��čs�����B�����āA�₪�ė��ۂ���ė����B��̈��͂�����āA�[���������o���Ă����B
�悤�₭�A������A�A��グ�āA���ۂ́A��l�̂��炾���A�w�ɂ������B�����A�Â��A�����A�ʒ��́A�r���܂ł��ė��Ȃ���A����������B�����āA���̏��܂�����]�̉e���A�[�̗[�łƈ�ɂȂ�܂Ō������Ă����B
�\�\�ӂƁA�l�̋C�͂��������āA�ޏ��́A������A��ցA�߂����B�Ƃ��낪�A�����ɂ́A�ޏ��ɂƂ��āA�Ђǂ��C�܂����l�����a�ʂ������ĘȂ�ł����B�������A�ޏ������L���Ă�����̂̎�l�ł���B���̗nj��́A�����M�҂ł����邪�A�܂��A�ȈȊO�Ɋ��l���̏�������ẮA���̎R���̋ǂɎ����Ă����̂��A����ȓ��y�ł�����l���������B
�ʒ��́A���Ĕނ��A���r�̌��p�ŁA�㗌�����Ƃ��A�����̏핽���吷�̈ē��ŁA�]���̗V���ɂ��悢�A���ɁA����ȕ���ƌ��Ղ��āA�����ւ�A�������Ȃ̂ł���B
�Ɛl���畷���ƁA�����A���̋ʒ��̋ǂɁA���傪�A�b������ł����Ƃ������A�����A�ǂ�`���Ă݂�ƁA�ʒ��̎p�������Ȃ��B�����āA�����̂��̗L�l�Ȃ̂ł���B
������A�s�ɂ����̂����A���̏���̂��������A�]���̗V���ŁA�����������Ƃ�����Ƃ����͂Ȃ����\�\���āA�吷����A�����Ă������̂ŁA�nj��́A���V�̒j�̋���₷���A�Ђ��݂Ǝ��i�ɁA�ނ���ƁA�R�����B�������A������������ɏo���āA�����ȋC�₷�߂��}���悤�Ȕނł��Ȃ������B
�u�����Ă���̂��A����ȏ��ŁB�c�c�܂��A�ǐ��Ɠ�l���āA���Ȃ��̔��i�ł��������Ǝv���āA����������T�����Ă����̂Ɂv
�u�c�c�c�c�v
�ʒ����A���������������ɁA�������ŁA���݂܂���Ƃ��A�����͂��Ȃ��B�ޏ��ɂ͏[���ޏ��̎��M�݂����Ȃ��̂�����A������Ȃ炢�ł��s�A��܂��A�Ƃ����̂��������Ȃ̂ł���B
�u�������B�ǂ��֍s���̂��A�ǂ��ցv
�������ƁA�ޏ����A�ЂƂ肵�āA��ɁA�����o�����̂ŁA�nj����A�ǂ�������悤�ɁA�����ƁA�ʒ��́A�������ɁA������֓������B
�u�����āA���ɂ́A�����ς�����܂��̂�B����Ȋ��D�Ŕ��i���Ђ��́A�܂��A�����̂Ƃ����Ă��A���ނ�ł��傤�v
�nj��́A�ɂ����������A�ޏ����A�ǂɓ���܂ŁA�ޏ��̒��Ăł���Z���̏���ɂ����납������čs�����B
|
�����Ɛ�
�쑚�̉��\�\��t�̕������ӂ��݂̂��傤�́A��Ƃ�Ȃׂ����Ă����B
����̒��j�A�}����A�o���炦���Ă�����̂̊Z���A���̂����A�傰���ɁA�Ñ�����Ă������炾�����B
�O�����ɁA���M�Ђ�����˂��A���̖R�������̉����ƂɁA�w���܂낭���āA�V������Ȃ�A����A��l�̒�q�Ȃǂ��A�P�ɂ��킲�Ă��g������A���ǂ��̎���ԂÂ�����A�݂ȁA�����o�������Ă����B
�u�c�c�ǂ��Ȃ������낤�́B�L�c�̏��a�́v
�ӂƁA�v���o�����悤�ɁA���������A�Ԃ₢���B���̂��̒��A�閾���Ƌ��ɁA�����𗧂�������̂��Ƃ��A���傤�́A�Ƒ������̌��ɁA���x���A���킳�ɂ̂ڂ����B
�u���傤���A�����̓����A�܂��A�ʂ��͂��Ȃ̂��B�\�\���ꂩ�A���p���A�������̂́A���邩�v
�[���������B��q�����́A���U�����B�n���ǂ��̐��ߎ����A�������ɁA�����ẮA�Ԃ��ɂȂ�ׂĂ����������́A���S�̂悤�ɁA���킳�́A�O�ɂ����B
�u�����̓����A�����Ȃ��A�邨�p������܂ł́A���ƂȂ��A�C�ɂ����邱�Ƃł͂���B�c�c���̏f���䂽���́A�ꂮ�낢�邽����݂��A���a�̕��ɂ��A�������������Ă���炵�������ɂȁv
���̂��Ƃɂ��āA��q�B���A����̗ǐ���A�H���̗nj��̈������A�s�����ɁA�����o�����B�z�X���A���n�̂��Ƃ��A���`�Œǂ��g�����Ƃ��́A���̉Ɨ������܂ŁA�s�����֗��Ă��A������ʂ��Ă��A���ŕ�����āA���邢�Ă���Ƃ��A�܂��A�����̕�����A�[�߂ɍs���Ă��A��x�ł��A����Ȃ��ɁA��������Ƃ͂Ȃ��B�H�������݂̗ǐS�Ȃǂ́A�킩��Ȃ��ŁA���̈����������肢���Ƃ��c�c�����o���ƁA������Ȃ����A��q�����́A����ׂ����B
�u���₢��A���̓�l�́A�܂��ǂ����Ȃ̂���v
�ƕ������͂������B�[��A��q���A�ӊO�Ȋ��������ƁA���́A�u�������Ƃ��c�c�v�ƁA���⎩�����āA�d���̎���Â��A�₪�Ă܂��A�����������B
�u�\�\�ق�ƂɁA����̈����̂́A�Γc�ɏZ�ޏ헤�坁�������܂���B�L�c�̗ǎ��l�̑傫�Ȍ��Y���A����A�ۂ�ł����܂��ɂȂ��āA�ق�̋͂킸�����A�nj��A�ǐ��l�ցA����Ă����ɂȂ��Ă���ɉ߂��ʁB�c�c�����A�䎩�g�́A���m��ʊ炵�āA���������A�nj��A�ǐ��̂���l�ɂ�点�Ă���Ƃ������B�悭�����ÒK�Ƃ����̂́A�������������̎��ł��낤��v
�����ŁA������ɁA�����i����B�쓐�̂��Ȃ��ɁA���̕����ł��A���������Ă����B�\�\���́A��������A���M���Ȃ����ɁA�ӂƉ����āA�����т���悤�ȁA�ƂЂƂ݂������B
�u�d������B���낤����A�����v
�H����A�ЂÂ��A���������A�L���Ƃ̌˂��܂���A�蕪�����āA���͂��߂Ă��鎞�������B
�y������A�������҂��������B
��q���A��l���āA�`���ɏo���B�n�̂��ȂȂ���������B�J�C���������Ⴂ�_�ԂɁA�����锼�������������A�ڂ���ƁA�ق̔����B
�u���ꂾ���B�c�c�ǂȂ��H�v
�u���ۂł��B�\�\�L�c�̏���l�̏��g�ŁA���ƂƂ��̖�A�����b�ɂȂ�܂����A���̎�]�ł��B��X���ɁA�����ꂢ��܂����v
�u���B����l�ł����āv
�u�����ł��B���̂Ƃ��́A�����Ƃ��v���o���A����܂ŁA�}���ŁA�߂��ė��܂����v
�u���B�悤�����v�ƁA���́A�K���݂��Ă����q�����ɂނ����A
�u�͂₭�A����������āA���ʂ��\���ʂ��v
�ƁA�������B
�₪�āA���ۂ��A������A�w�ɕ����āA�͂����ė����̂����āA�����[���A���߂āA�炢����A�������B�c�c���́A䩑R�ƁA�Ђ��݂ɁA���������B
���ۂ́A�n�̔w�ɁA��l���̂��āA���炭���A���ꂩ�琅�����܂��ɁA��H�����H���A����܂ň����Ԃ��ė����̂ł���B�������Ăނ�����Ƒ������ɁA����܂����A���O�����Ɍ���āA����̑̂̂����݂��A��������܂ŁA�ǂ����A�ꎺ�������ĉ�����܂����ƁA���ނ̂ł������B
���Ƃ��A�����̉Ƒ��ɁA�ۂ�͂Ȃ��B�����āA�����]�ɁA������悹�A���̖邩���a�₭���A�蓖�ɁA������������قǂł���B
�u�ȂɁB�����������͂Ȃ��B�����ԁA�S���������܂������v
���ɂȂ�ƁA����́A�Ƒ������ɁA���ӂ��āA���̓��̂����ɂ��A�L�c���A��悤�Ȏ��������o�����B�������́A�ȂĂ̂ق��Ȋ�������B
�u���C���˂Ȃ���̂ł������܂��傤�B�Ƃ��낪�A�����ɂ́A��낱�тȂ̂ł��B�����A������肢�������ʂ�A���a�̂�����ǎ��l�ɂ́A�ǂ�ȂɁA�����b�ɂȂ������Ƃ��m��܂���B���N�����Ƃ��̌�A�͂��炸�A���̂���h��\��������̂��A�s���ʌ䉏�ł��B�ǎ��l�̂킷�ꂪ���݂ł��݂킷���Ȃ��ɁA�����A�����������\�������邱�Ƃ��A�l�̐��̂�낱�тłȂ��Ăǂ����܂��傤�v
���̂��Ƃ́A���̂܂܁A�����̉Ƒ��́A�^�S�Ȑ��b�Ԃ�ɏo�Ă����B����́A�C�����������A���̓�����A��M�����B���̓����A�����ȁA�e�Ԃł������B
�������A�ӎ��Â��ƁA�ނ́A���O�����ɁA�����Ă��肢���B�������ƂɁA�����A�l�O���͂���Ȃ������̂́A���̎���\�\���������̓��{�l�̂��ׂĂł��������A�c��������ɁAᒂ������āA�������ȏ���ł������B���̏��傪�A���܂��܁A����Ȋ�Ђ̂��ƂɁA�v�������Ȃ��D��̉Ƃ̐l��ɂӂ�āA��������A�c���̂悤�ȐS���ɕԂ��Ă����̂�������Ȃ������B�܂�������ɁA��������A����ɋQ���Ă����ނł��������ɂ������Ȃ��B
����ǔނ́A�O���ڂ��납��A�ӎ��I�ɁA�����̂���߂��B�ƁA�����̂́A�����ނ̖����ɁA�Ō�݂Ƃ肵�Ă��邱�̉Ƃ̏������A�ނ������ƁA���X�����āA�ʂẮA���キ���キ�A�Ԃ����ƂɁA�j�����ނ���ł���B
���̖��́A�j�[�����傤�Ƃ������B�������܂���\�͂����������Ă��Ȃ��B��q�����́A�j�[���܂ƌĂ�ł���B
�u�j�[�ǂ́B�Ȃ��A�������ɂȂ��ł��v
����́A����܁A�ޏ��ɂ����������B�a�l�ƊŌ삷��҂̊ԂقǁA�S�ƐS�Ƃ̐ڋ߂��A�}���ɂ�����̂͂Ȃ��B
�u�����āA����l���A�������ɂȂ��ł����́v�ƁA�j�[�́A�͂ɂ��݂Ȃ��瓚�����B
�u�ЂƂ������̂ɁA�����A�������āA�ꂵ��ɋ����Ȃ��ł�������ł���v
�u���������ł͂���܂����B�����������狃���̂ł����́v
�u�ǂ����āA���������Ȃ�̂ł����v
�u�ł��c�c�B���Ȃ����A�������ɂȂ邩��v
�u�ł́A���ꂪ�����Ȃ�������v
�u�����A�����܂��܂��B����ǁA����l�́A�S�̂����ł́A���X�A�������ɂȂ炸�ɂ����Ȃ��̂ł��傤�v
�u���������A����Ȃ��v
�u����������A�������X�A�S�̂����ŁA�������ɂ����Ȃ��Ȃ邩������܂���v
�u���B�ǂ����āv
�u�Ȃ��ł��傤�B���Ȃ��̂��S���A���܂��Ă��Ă��A���ɂ́A���������A���Ɛ��̂悤�ɁA�����f������A�h�ꂽ�肵�܂��v
�u�j�[�ǂ́B�c�c�ق�ƂɁv
�u���B�ق�ƂɁv
�u�ق�ƂȂ�B�c�c�v�ƁA�ނ͎���̂����B�����ċ}�ɁA�ނ����ƁA�g���N�����������A
�u�c�c�ɂ��v�ƁA��������߂āA���炾���A�܂�Ȃ����B
�u����B�����܂���B�}�ɂ��N���ɂȂ��Ắv
�j�[�́A�ނ�����āA�Q���������B����́A����������o�̂悤�Ȃ������ł������B
|
���{
�͉̂��悭�Ȃ����B�����A�g�������ɁA�s���R�͂Ȃ��B
��������Ă���L�c�̒틤���A�����߂��A�Ă��Ă��邱�Ƃ��낤�B�A��Ȃ���Ȃ�܂��Ǝv���B���A�A�肽���Ȃ��v��������B
�����e�q���A�j�[�ɂ�������B
���������A�m���Ă��邩�̂悤�ɁA�쑚�̋�t�̘V�v�w�́A�Ȃ�����ɐe�ł������B�q�l�Ƃ��ĂłȂ��A�Ƒ��������́A�������ł���B
�u�����̊قł��A���̂悤�ɁA���[�A�����āA�ю��߂��ǂ��ɏ�����v
�A�܂������ƂɎv�����B�c�R������̒��ł��A�ނ͂ӂƁA���͂��������킷�ꂽ�܂܁A�j�[�̉�������Ă��܂����Ƃ�����B
�L�c�ւ́A���ۂ��g���ɏo���āA�S�z����ȂƂ����Ă���Ă��̂ɁA���̗��ۂɂ��āA��̏����A�����́A��l���}���ɗ����B
����́A������@�����ɁA��������Ƃ̎҂ɁA����ׂ̂āA��ƈꂵ��ɁA�쑚�̕����𗧂����B
�u�킴�킴�A��l�������āA�}���ɂȂǗ��Ȃ��Ă��A�悩�����̂Ɂv
�і��̓n�M�킽���̏�ŁA����́A�������B
�j�[�̖ʉe���A����������Ȃ��B��̂܂��ɒ킽����u���Ă��A�ޏ��̊炪�A�d�Ȃ��Č�����B��������͂����������̂ɁB�\�\
�����̕s�@�����A���킹���̂ł���B
�u�\�\���A���璆�ɂ��A�����ς�͂Ȃ��������v
�u���B�ׂɁB�c�c�����璆�́v
�킽���́A�Z�����킩�����B�s����A���ė������̌Z�ɂ́A���������ɂ́A�ʂ͂���m��Ȃ��V�m���������A�[���Ȑl���̌��ƁA�����̕�����������̂ƁA�r���傤���Ă����B���ɑ�鑾���ӂƂ��炪�������悤�ɁA�͂Ƃ��Ă����B
�u�����́A�ǂ����Ă���H�@�c�c�C�̎ア�������B�S�z�������Ă����낤�ȁB�\�\���A����͂��̒ʂ�A���Ƃ��Ȃ��B�f�������炢�A�����ɂȂ��Ă��A�|��͂��Ȃ���v
�f���̎����A���ɂ���ƁA����̊�́A��̒ꂩ��A���ӎ��ɔR���������B�}�g�̎R�e���A�͂邩�ɁA�U��ނ��āA���炭�A���̂�����Ȃ������B
�ӂƂ܂��A���ɕԂ��ā\�\
�u�܂����r���ŁA���ꂪ�����Ă͂ƁA���ۂ�����̂ɁA���O�����܂ŁA�}���ɂ悱�����̂́A�����̂��������낤�B����Ȏ��z����J�͂���ȁB���O�����܂ŁA�����݂����ɐ_�o���ׂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ����v
�u�����B�������܂��v
�u�����A�������v
�u�������ɁA�Z����A�����A��ė����Ƌ���������̂́A�s���痈�Ă��邨�q�l�ł��v
�u�s�̋q�l�H�v
�u���B�����ƁA�����āA�Z�Ґl�̂��A����A�L�c�̊قŁA�҂��Ă����łł��v
�u���B����Ȃ�A�����ƁA�Ȃ���������Ȃ��̂��v
�u������A�уb���肳���Ă��̂�����A��܂ł́A�ق��Ă���ƁA�ł��A���q�l����A���~�߂��ꂽ���̂ł�����v
�u���������̂��A�n�������ƁA�s�ł͂����̂��B��Y���܂ɂ�������������̂��B���āA���̂��l�̖��́A���ƁA���������v
�u�����́A�f���Ă���܂���v
�u����������A�����Ă��Ȃ��̂��v
�u�����A�����Z���A�m��Ȃ��悤�ł��B����ǁA�̂��l�炵���Ƃ����Ă��܂����v
�u�N����́A����炢�v
�u�l�\���炢���Ǝv���܂��v
�u��l���H�v
�u���B����l�ł��B����ǁA���������h�Ȃ̂��������A�s�̐l�X�ł��A����b�Ƃ̒N�ނł��A���̒n���̍��i�A�S�i�ł��A�݂ȌĂю̂ĂɂȂ����܂��B�\�\�����āA�������D���ŁA���������ł́A�����Z�����܂��āA������A�t�𗣂��܂���B�s�͂��납�A��B�̉ʂĂ���A���̍Ⓦ�n���̎��܂ŁA���ɂ悭���ł��m���Ă���ƁA�����Z������܂��āA���h���Ă���܂�����v
�u�͂ĂȂ��B�N���낤�v
����ɂ́A�v�����肪�Ȃ��B����b�̎g���Ȃ�A���̎l�A�ܖ��͘A��Ă���͂��Ǝv���B
����ɂ��Ă��A���������f��������Ȃ����̐l�Ԃ��A�ق֔��߂Ă������肩�A����������o���āA�����Ă��鏫����A���̒킽���́A���ᔻ�ƁA���Ԓm�炸�ɂ́A���R�Ƃ����B����ł́A���̏f�������A���S���N�����̂��A�ނ�͂Ȃ��ƍl����ꂽ�B�ނ́A�������A���Ԓm�炸�̂��l�D���Ƃ͎v��Ȃ��B����ǂ��납�A�]��Ȃ��l�悵�́A����ɁA���l�������̂��Ƃ����C���������������B�����āA�����䂢�틤�ɁA�������Ƌ��ɁA
(�s���s�����A�c�ɂ����ꂾ�B�����҂������ɏZ�߂�n��ȂǁA���肻�����Ȃ��B�\�\���̒����A���̒�ܐl�������āA���ə������Ă䂭�ɂ́A�f�����̏�����ꂮ�낳���A�����˂��߂��B�悵�A���ꂾ����)
���ꂾ���͂ƁA����́A��ɂ��������B
�L�c�̌ǎ��Z�l�ŁA���̏f���������Ԃ��Ă��ׂɂ́\�\�ƁA�����̐���ɂ͂Ȃ���������Ƃ��Ƃ����B�\�\���낤�Ǝv���A�f�����ȏ�Ȗ����߂Ȉ��l�ɐ���Ȃ����Ƃ͂Ȃ��ƁA�v�����߂��B
�nj��A�ǐ����A�}�g�ɖK�˂āA�ނ���ɂ����ċA�������̂́A���ꂾ�����B����A����ƁA���̊�̉��ɁA���������c�����o�������݂��{�����ł������B
�@ |
���G�q
�L�c�̊قցA�A�����ӁB�ނ́A��낱�ь}����Ɛl��z�l�ɁA��킽��A�����Ȋ�������Č�A�����ɁA
�u�s�̋q�l�Ƃ́A�ǂ��ɂ���̂��v
�ƁA�����ɂ����˂��B
��߂Ă���ނ̊�����o�炸�A�����́A���������ƁA
�u�����A�l���������āA�����A�҂���тĂ����܂��B���̋q�a�Łv
�ƁA������ւ����֑��낤�Ƃ���B
�u�҂đ҂ď����B���ꂪ�A�ʂ�����Ƃǂ��Ă���ɂ���B����ȗy���܂ł����K�˂ė���s�̒m�l�ȂǁA�S������Ȃ��B�ǂ����A������L���v
����́A���֍s���āA�L�낤�̊Ԃ܂̕ǂɐg���A�����ƁA�q�̐l�Ԃɂ�Ă����A�`���Ă݂��B
�\�\�Ȃ�قǁA�����Ȃ��z������B
�������A����ň���ň��ݖO�����Ƃ������ɁA�t�Ղ�A��̐ܕ~���������A�݂����Ȃ��A�U�炩�����܂܁A�̂��̂��ƁA�薍�ŁA���ɂȂ��Ă���̂������B
�u�c�c�H�v
����́A�s���ƁA���b���Ԃ���ɁA�v�킸���̎�ŁA�����̂�����������B�C�́A���ɂ��܂������Ă��邪�A���������ɂ��ƁA�����Ă̐Q�炪�����Ȃ����߁A���������ƁA�j�̂��܂ŁA�����čs�����B�����āA���̐}�X�����Q����A�^�ォ��`�����B
�u�c�c����H�v
�Ǝv�����Ƃ��A���˓I�ɁA�j������������B
�n�`�̂悤�Ȋ�̊�́A�܂��A�����ԂA�Ƃ��Ƃ��Ă���B���A����́A������݂����Ɍ����܂����B�����āA�ނ���ɁA�v���o�������̂炵���B���̐��ɂ́A�������������߂Ă����B
�u�����A�s���l�ł͂Ȃ����B�\�\����̕s���l�v
�u�����A�A�����̂��B�����Y�v
�j�́A�ނ�����A�N���オ�����B����̎�ցA���L�����B�����Čł����肠�����B�Ӎ�������ƌӍ���ނ��������A��Ɗ���������A��l��䩑R�ƁA�����Ă��܂����B
�u���炭�Ԃ肾�Ȃ��B�����Y�B����߂���́A����Ƃ����Ă��邻�������v
�u�����B���v���Ԃ肾�B�܂����A�q���a���ʂ��Ƃ́A�v��Ȃ������v
�u�������낤�v
�u�����B�������v
�u���͂͂͂́B�܂��A���݂ʼn���肾�B�Ȃ�قǁA�s�ł������Ă������A�M�l�̊ق́A�債�����̂��ȁB�������A�Ⓦ�̍����A�����V�c�̌�q�A�����e������͂炵��̂��̖��\�\���ǎ����������̐��͂�����������B�M�l�͂��̑��̑��q����Ȃ����B�\�\�������A�������肵���v
�u�������B��������A�������v
�u�����������B�\�\���璆�A�킽���ɕ����A�e�̗ǎ�����̂�����������ƎY�́A����܂��f�����ɕ����D�Ƃ肳��Ă��܂����Ƃ����ł͂Ȃ����B�������܂��A�����O�A�H���̗nj��̊قŁA�M�l�A�ܒ@���̖ڂɑ������Ƃ������Ă���v
�u�m���Ă������B�@���Ă���B�c�O�Ŏc�O�Ŋ���Ȃ��B���̖��O���ǂ����Ă͂炻�����B�������l���ċA���ė����̂��c�c�����Ƃ���֖K�˂Ă��ꂽ�B�������A�����A�����ǂ�����ЂÂ������āA���߂āA�����^�ׁB��������݂����v
�킽���ɂ́A�Z�Ƌq���A�ǂ������W�Ȃ̂��A����Ȃ������B�����̐e�F���낤���炢�ɑz�������B�Ɛl�́A�C����A�Ȃ𐴂߂āA�����Ⓐ�q��V���ɁA�����o�����B
���̊Ԃ��A�s���l�Ə���́A�Ѓb����Ȃ��ɂ���ׂ��Ă����B�b���������A�������������A�R�قǂ����āA������A�Z�ȂĂ�߂�̋���������ׂ����A�ǂ������A�v���ɋ}������Ă���p�������B
|
���b�R�̖�
�܂��A���傪�s�̍���b�Ƃɂ������B�\�\��N�ЂƂƂ��A�������F���A�ɗ\�m���A��Ƃ����̂ŁA�F�l�ǂ��吨���A��M�������イ���������A�]���̗V���ŁA����ȑs�s�̉����Ђ炢�āA���������嗐�s�C���������ĕʂꂽ���Ƃ�����B
�s���l�ƁA���Ȃ��̂��A����ȗ��́\�\�v�������Ƃ������B
�ЂƂɂ́A���傪�A����b�Ƃ������̉q�m�ցA��ւ����ꂽ���߂ł�����B
���̊ԂɁA����b�Ƃɂ�����������̒��Ԃ���������A��@�̕s���l�͌Y���Ȃ̘S�ō��������ƁA�\���ꂽ�B
���̌�A���F����x�ڂɏ㗌�����Ƃ��A����́A�ނƉb�R�̈�p�֓o�����B�����ނ݂Ȃ���A���ɁA�N�q�C�������̖��ɐ����A�����̓s���A�ቺ�Ɍ��āA
(�݂ċ������B���܂ɁA��C�̈������A�厖��������V�������邼�B�M�������̕��s�̕{��h��ׂԂ��A�V���̋����ɁA���J�Ɗ�]��^����҂�����ꂽ��A����͈ɗ\�̏��F���Ǝv���Ă���B�\�\�N���Ⓦ�̞D��ɐ���A�������A��n�̉Ƃ̌�q�ł͂Ȃ����B���F�A���ɗ��ƕ�������A�N���A���ɗ���)
�����A��M�̕��ӂ��̂��āA������A
(����B�N�̂����ʂ肾�B�N�̂��������Ă���ƁA���ɁA�����ɂȂ��)
�ƁA�������B
���F�́A�Ў�ɔt�������Ȃ���A
(���Ⴀ�A�����̐������L�O���悤�B�N���A�t������)
�Ƃ����A��l���āA���t�����B�����āA��X�����A������B�\�\�s�̏t�̈���ɂ́A����̏����Y�ɁA����ȋL������������ɂ͂������B
(�s���l�̐���������Ȃ��B��������A�ɗ\�ցA�m�点�Ă���)
�Ƃ́A���̂Ƃ����F���珉�߂ĕ����A�܂��A�˗������ꂽ���������B���̂��ߏ���́A�Y���Ȃ̍��i�A���{�P�k�������˂āA�T���Ă݂����Ƃ�����B�������A����̒��ԂƂ��A�A�����₦�A�s���l�̏������s���̂܂܁A�ȗ��A�Y���Ƃ��Ȃ��Y��Ă����B�\�\��ɁA�A���̌�́A������������ς��Ă����B����ǂ���łȂ����X���X�ɒǂ��ʂ��Ă���B
�u�c�c���ɁB����̎�����A���ꂽ��b�����肵�Ă��邪�v�ƁA����́A���i�̈�V�����Ƃ���ŁA���炽�߂āA�q�ɔt��悵�A�b����A�s���l�̐g�̏�Ɍ����X�������B
�u���������A�a��́A���̌�A�ǂ����Ă����̂��B�\�\�����������A�����Ă������Ƃ́A���A��Ɍ��Ă��邪�A���̍Ⓦ�̉����ւ܂ŁA�����K�˂ė����ɂ́A�����A�e�ׂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��v
�u����͂���Ƃ��B���ꂪ�A�I���ĂȂ��A����ȉ����֗�����̂��B�����ɁA�����Y���傪�Ȃ������Ƃāv
�u�������ł͂Ȃ����B�܂�������c�c�v
�u�Ђƌ��ɂ����A�������F�̎g�҂��B���́A���̏t�A���˂̎��ނ�m�Âŏ��F�Ɨ��������A�����Ǔ����։����āA�����Y����ƁA���N�̖���A���낻����s�Ɉڂ������ɂ������Ă���ƁA�����ė����v
�u���N�̖�Ƃ́v
�u�a��Ə��F�Ƃ��A�t�������Đ������Ƃ������\�\�b�R�̖v
�u�҂��Ă���B�ׂɁA����͉����A�͂��Ȃ����v
�u����A���F�́A�ł��������B���ꂾ���ɂ͂ƁA���̔閧���v
�u�������Ȃ��c�c�B�������Ȃ��H�@���̎��v
����́A������������B
���ɁA�𒆁A���̂悤�ȋC��f�������͊o���Ă���B���F���A���s�M�����̂̂���A�S�����������̊�܂Ȃ���������āA�h�Y�̖����~���Ƃ��A�~���̎��������Ƃ��A�����������悤�ɂ������̂��A�L���ɂ͂Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B
����ǁA����́A���F�̏\���Ԃ��͂��Ȃ̂��B�����ΕK���o���C�⟶�܂Ă��邢�ł����āA�b�R�̓��ƌ��������Ƃł͂Ȃ��B�ЂƂ̜ˊS�Ȃ��������ւ����낤���炢�ɏ���͎Ƃ��Ă����B�����A�����̕��ɂ��A���ɂ������āA�ނƓ��l�ȁA�s���╮�S������̂ŁA���ނɂ��A�̂��ɂ��A�{��ɂ��A���t�I�Ȋ��t�͂������A�V���^���Ă�Ղ��̖����Ȃǂ��A����Ȑ����ɁA�������茋�Ԃ킯���Ȃ��B������u�b�R�̖�v�ȂǂƁA���X�����A�����뎝�����܂�ẮA�܂�������Ȃ������B����́A�Ԏ��ɍ������B
�u�ނށB�c�c���������A���F�́A��]�߂��������悭�����Ă������A���˓��ŊC�������O�Ȃ����邩��A����́A���̎����ƕ����Ă����̂��B�b�R�̖�Ƃ́A���������̂��낤���v
�u���͂͂͂́B�B����ł��悢�B������ꖡ�̐l�Ԃ��v
�u�ł��A����ɂ��āA�g���ɗ����Ƃ����̂́H�v
�u�܂��A�������}�ɁA�ЂÂ���ɂ��y�Ԃ܂��B���������A����Ȍv�����g���B�����́A���ɂȂ���肾����A�܂����āA�܂��ĂƂ��ƁA�k�����悤�B�c�c��������A���̌�͂ǂ����B�c�c���A����B���̍]���̗V�h��ǂ̑��J�݂����ȌN�ɂ́A���̌�A�o���Ȃ��̂��B���͂͂͂́B�܂��A�Ɛg�ЂƂ�݂��Ƃ�������Ȃ����B�ӋC�n���Ȃ��ȁA���܂ł��v
|
���T�F
���Ȃ�Ȃ��B�ǂ��ɂ��A�ܕ��Ɏ�g�߂Ȃ��B�s���l�ƔނƂł́A��l�Ǝq�ǂ����B
�����Ƃ��A�\�Z�̏t�A���傪�s�̓y���̓��A�ւ�ȓ�ɁA�U�����ǂ킩����āA�_���̐X�ɁA�A�ꂱ�܂ꂽ�Ӂ\�\���̂Ƃ����łɁ\�\����̕s���l�́A���������ށA��������̐l��̂����ł��A���ڂƗ��Ă��Ă��������̑�l�ł������B
(���Ȃ�Ȃ��̂��A�ނ�͂Ȃ��c�c)
����́A��͂�̒��ŁA���ԂƂ�E�����B�Ɠ����ɁA�s���l���s�ɂ����Ă̐_�o�S�v�Ԃ���v���o���āA�}�ɁA�������C���ނ��ɕς����B�\�\�s�ɗV�w�����ŏ��̓�����̖��ȋ@���ŁA���̒j�ɁA���̖����������A���̒j�́A��I�Ȉ�ʂɁA�e���ݓ��āA�����A�������Ȃ��A�܂��Ȃ��F�݂����ɁA������ė������A�l���Ă݂�ƁA����͑�ςȒ��q�ł���B
�틤�ɁA�ނ��܂��A�f���𖼏���Ă��Ȃ��̂́A�������B�ނ̑O�g�́A�m�炷�ׂ��łȂ��B�܂��āA�w�G�̏f�����ɒm��ꂽ��A��䂵�����ɂȂ낤�B�����𑒂鈫��`�ɂ́A��D�Ȏ������B����́A�Ƃ����A���������Ȃ��v���ɂȂ����B
�u�c�c�������B�ǂ������B�����Ȃ����A�����ς�v
�s���l�́A�ЂƂ�t�������˂āA
�u���C���Ȃ��ق́A�Ȃɂ��҂����B�Ȃ��A�k�̕��������Ȃ��̂��v
�ƁA��������āA����Ȃ�����̊�����߂��B
�u����A���̂����ɁA�W���炤��v
����́A������҂�����B�j�[���A���ɑz���o���Ă����B
�u�W���Ă�A�����B�t�͒Z���B�����̑�]�ɂł�������ƁA�n��A�Ԃ�������݂�Ԃ��Ȃ����B�c�c���ꂩ�A���Ă͂���̂��B���l�́v
�u�Ȃ������Ȃ��v
�u����₠�����B���S�����B�\�\���S�����Ƃ���ŁA����͐Q�悤�B�������ɁA����́A�v������Y��Ă����B�a���ʂ��͔��Ă����낤�ɁB���ق���A���ق���v
�n���̂����q�ł͂������B����ǁA�ǂ����ɁA��T���낤�̕��e������B���������オ���Ă��镠�̒��ցA���{��e���Âނ��ڂ����悤�Ƃ��邩�m�ꂽ���̂ł͂Ȃ��B
����́A�����A�킽���ցA�����������B
�u���̂����́A�r���ۂ����A�������낢���l���낤�B����ł��A�s�ł́A�܈ʑ��l�Ƃ������h�Ȓ��b�̌䎟�j�Ȃ̂��B��������ƕ����ق���̂��߁A���r���܂�Ȃ��ŁA����������������݂����ɐg�����������Ă��܂�ꂽ�炵���B�c�c�����A����̗V�w���́A�e�ɂ��ĉ��������B�F���A��ɂ��Ă����Ă��ꂢ�B�����A������������ċA����肾�낤����v
�킽���́A�^��Ȃ������B
����́A������̖������A���̒킽�����A������������Ɍ����B�������ɁA�Z��M���Ă��邻�̏]�����ł���B�Z�ȏ�A���Ԓm�炸�̑f�p�����B�ӔC��������B�ނ́A���̊�̈��̏�ɍK�����������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƁA�d�ׂ��v���B
�u�Z�Ґl����ЂƁB�c�c���q�l�́A�����܂��́v
���̎��Y���ׂ��A�ӂƁA�u�����B
�u���B���������B�����́A�����s���l�B�\�\�V��ł��邩��E���͂Ȃ��v
�����Ȃ���A�ь��̂ǂ������A���B
���̕s���l�́A�������������ł���B����́A�܂����܂�ƁA�������Ȃ��C�������̂ŁA
�u���̂����ɁA�����������傤�܂ōs���ė��邼�v
�ƁA���ۂƎq�t�ۂ������܂�́A���l�ӂ���ɁA�n�̌���c�点�A�����O�̎���������̂ŁA�ق��ɘY�}�\�l�قǁA���ɘA��A���i�̒��ցA�o�����čs�����B
�����m��Ȃ����A���璆�ɁA�o������悤�ɂƂ́A�ʒB�����Ă����̂ł���B���̏��ݒn�܂ł́A��锑��̉����������B��������ƁA�坁������ǐ������肩��A�������āA�i�ׂł��o�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���A����́A���X�Ƃ��Ȃ�����A����̋��\�������j�邱�Ƃ��A�r�X�A�����ɗp�ӂ��Ă����B
�\�z�͊O�͂��ꂽ�B�����A�g�������̂ق��Ɉ���Ă����B
�����������������Ԃ݂̎��B�������āA��������ނɂ������A���߂��͂��Ă����̂ł���B
���ʈ�V�`���m�W���E�A�O�T�L�m����m���^�q���m�����Y���僒�ȃe�A���n��~�~�N�����m���i�Q�X�j���W���X�B
�ƁA����B
����́A�ӊO�Ȃ����ɁA���т��A�傫�������B
��~�Ƃ́A�n���n���̌䗿����傤�̑����ł���B�����Ŏ��鋛���̗ނ�A�ʎ��A�A�����A��Ȃǂ̑�V���p�̒����傤�������Ǘ����āA�l�G���ƂɁA����֑���E���Ȃ̂��B
�s�̒��b�����ɂ���ׂ�A���X����n���̈ꏬ�������A�n���ɂ����ẮA�ǂ�ȂɒႭ�Ă��A���E������ƂȂ��Ƃł́A�Z���̐M�����d�����������B����́A���N�A���g���ꂽ����b�Ƃ̍��݂��Y��āA�͂邩�ɁA������̒������ցA�S�������A�S���牶���ӂ��āA�ӑR�ƁA�L�c�ɋA�����B
�킽�����A�ӂB�Ɛl�z�l���A�����ďj�����q�ׂ��B�������ƂÂ��̌Êقӂ�₩���ɁA���ɁA����A���ȗ��́A������̋g���������B���ꂾ���ɁA���g�́A�����Ƃ̏Z���ɂ��A���������ӂ����傤���Ă��邫�A�S�����̂�낱�тƂȂ��āA��O�́A���킢�������B
�����A������āA�ЂƂ�}�������̂́A���ɂ���T�F�������B
�u�Ύ~�����A����B����A���̐����̔Ԑl�����t�����āA��������ȂɁA�߂ł����̂��B�����Ƃ��A���d�̌v�Ȃ�悢���A�������킢�ẮA����܂ł��A�����ɂ������A�ꌾ���炢�A�j�����q�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�v�@ |
���ނ����Ȃ���
���y�͍Ղ�D���ł���B�������������A�}�g�⌋����A���̖L�c�S���A�����Ƃ����Ղ肾�����B
�ق̌�q���A���������������������A��~�̐E��������ꂽ�ƕ����A�ܕ��\�J���ӂ����イ���̊�J�Ƌ��ɁA�y�����͂����A�Y�y�_���Ԃ��Ȃ��݂ɏW�܂����B���n�I�Ȋy��≼�ʂ����������A��\�܍��̐_�y��t���A�ƁX�ł��݂����A�������ނ�ʼn̂����B��͖�ŁA�������ꎞ�ɏ����������ʼn̊_�̏W�����Ȃ��A��������A�l�Ȃ��A���Ƃǂ낭�ÈłɁA�j�̎��҂��������B�悻�̗ǐl�ƁA�悻�̐l�ȂƁB�m��ʎ�l�ƁA�m��ʖ��ƁB�ǂ��r�ނY��Ă��A�Ղ̒�ł́A�l����邵�_����邵�A�߂Ƃ͂��Ȃ����̍��̏K���ł������B���ÁA���̕ӂ̖��тɁA���b���Ⴆ�Ă������̐l�Ԃ̈�K���A�Y��ʂ܂܂ɁA�Ȃ����Ă��邾���̂��Ƃ������B�����Ă��ꂪ����̊y���݂ŁA�s�̋���A�y�ɂ��炷�����A���s���v��Ȃ��y�������ł������B
�u���Ⴀ�A����B���d���Ă���B�\�\�����݂��̂��̋A��ɂ́A�܂��A�����Ɗ��B�~���z���āA���N�ɂȂ邾�낤���A�K���A����邩��v
���̔ӁB
�s���l�͋}�ɁA�ʂ���������B
���k�̉��n�\�\�܂��ڈ����l��̐��͂������ɋ����\�\������܂ŁA�s���̂��Ƃ����B
�ړI�͋��B������������ɂ͋����B�������˂���ɓ���ė���Ƃ����̂��B����ɂ́A�n���I�Ȓm�����Ȃ��B����ӂ݂͂��ĕ�������ł���
(�\�\���݂ɂł��s���̂�)
��قǁA�u���Ă݂��������B�\�\���A�����܂ł͂����Ȃ��ł���ƁA�炢�낾���ŁA�s���l�́A����̐S��ǂݎ�����悤�ɁA���o�����B
�u�s�̉������A�s��ǂ��Ă���́A���痎���������B�c�ɂ́A����ɓ����ɂ����B�ό��o�v�̂����Ȃ������B����܂����ǁA�w���Ȋ������Ȃ�B���݂ɍs���킯�ł͂Ȃ��A���h�ɕ�����̂�����g���āA�����ƁA���Ղ��ė�����肾�v
�u����Ȃ�悩�낤���A�������A����́v
�u����́A�悻�̊قɒu���Ă���B���ĂĂ݂�B�������v
�u������̂��B�ЂƂ̊قɂ��镨�Ȃǂ��v
�u�Ƃ��낪�A�a��́A���Ă���͂����v
�u���ꂪ�B�͂Ăȁv
�u�H���͂Ƃ�̗nj��̊قɁA���ꂢ�Ȃ̂������낤�B�s�Ԃ�́A�������N�͂Ƃ��Ă��邪�A��\�܁A�Z�̏����v
�u���B�c�c�ʒ����v
�u�������B�����̔N�A�吨���āA���F��A�I�H���̂���������A�Î����̂Ƃ��Ȃ�Ȃǂ��A�ɗ\�ɋA��̂��A�]���̗V�����Ƃ܂ŁA�����čs�������Ƃ�����B�a����ꂵ��ɂ�v
�u����B���邪�c�c�ʒ��Ƃ��̎��ƁA���̊ւ肪����̂��v
�u�ł������邪�A�ޏ�����͂���̓邶�݂������B���F�Ƌ��Ɉ�鑛�����ƂƂ́A�ׂȗV�h�̏������A�핽���吷���傤�ւ�����������́A�悭�ʂ��Ă����B���̒吷���A����܁A�㗌�����nj����ē������̂����ŁA�����g����������čs�����B���ꂪ�H���Ɉ͂��Ă���ʒ����v
�M�����Ȃ��B�ނ̂������@�������Ƃ͏���ɁA�v���Ȃ��̂��B���M�ȁA�����ėD�����e�ȏ����ł������C������B���Ȃ��Ƃ��ނ̈�ۂƊ����ł͂����ł���B
�u������A�킩��B�Ƃɂ����A���N�܂��K��悤�B������c�c�v
��Ƃ����̂ɁA�ނ́A�L�c�𗧂��čs�����B�n�̔w����ł��Ȃ��A�ǂ��֔�����肩�ƁA�D��Ɉ��������ł���A�ނ̐����̎d���ɂ́A�������o�����B���ӂ���̂悤�ɁA�ÈłƁA�����������Ă���B�ނ����A�_���̐X�̈Â���ɁA������̕��������āA���������ނ��܂��ɂ����Ă����ނ̑��݂��v���o���ꂽ�B�܂��A���������Ђ獶��b�𗇂ɂ��A���l�̎��z�Ԃ��������̌N�𓐂ݏo���āA�������A�ǂ����ɉB���Ă����A�F����قǂɂ��āA�܂��A��b���Ƃǂ�聂˂�֕Ԃ��Ă�������ƂȂǂ�����B�����j�Ƃ����ق��͂Ȃ��B�ʂ����āA���N�܂����邩�ǂ����B����́A������A���̒��q�𑗂�o���āA�ق��Ƃ����悤�ȐS�n�������B
�Ƃ��낪�A�����قǂ��ƁA����ȉ\���A���ɂ͂������B
�헤�̉��Ȃ����Â܂܂ŗp�B�ɍs�������ۂ��A�捠�̗�ɁA�쑚�̋�t�A�������̉Ƃ֊�����Ƃ���A�����ł��\�ɏo�����A�ق��ł��A�������Ƃ����̂ł���B
�\�\�Ƃ����̂́A�nj��̒������Ă����Ȃ��ǂڂ˂̋ʒ����A���R�ƁA�H���̊ق���p���������B�蕪�������ĒT�������A�F�ڒm��Ȃ��B���̌��ʁA
(����͂Ă�����A����̋��ցA�����čs�����ɂ������Ȃ��B�����ނɏ[���ȗ��R�͂���)
�ƁA�H���̐l�X���A�����G�ꂽ�̂����@�ŁA�܂����̉������������ɁA���q�������A
(�������낤�ɁA�L�c�̌�q�́A�f����̈������A���D��Ȃ��ꂽ)
�ƁA�����ς�A�����������������ŁA�捹������Ă���Ƃ����̂������B
�쑚�̋�t�̉Ƃ֗��āA���������̍s�ׂƂ��߁A�l��l���Ɣl�����̂́A����݂Ȃ��Ƃ̂܂���̒��q�̕}�������ł��邱�Ƃ��A���ۂ͕����Ă����B���̒ʂ���A����ɍ�������A���ۂ́A�Ȃ��������B
�u����ȁA���Ȏ��͂Ȃ��B�܂�ŁA�R�b�ς����B�H���̓z�炪�A����قNj^���Ȃ�A�Ȃ��L�c�̊ق��ɗ��Ȃ����B���ɂ����Ȃ��ŁA�����������B�\�\�ƁA���͎v�����܁A�쑚�̉ƂŁA�{���Ă��܂����B���A�����̉���[���A�����ł���A�����ł���ƁA���X�{���Ă���܂����B������́A�j�[���܂������Ă��܂����B�c�c�c�O�ł��B���̊Ԃ��A���O�ł������A���傤�́A����ɂ��܂�����ɂ��܂��̂�ŋA��܂����v
����́A�ّR�ƕ����Ă��邾���������B
�\�\�]��C�ɂ������Ȃ��̂��ƁA���ۂ́A�ؑ��̂悤�Ȏ�l���ӂƌ��グ���B�{�C�Ƃ��A������Ƃ����Ȃ��ʐF���A�����ɂ������B���ۂ́A������āA�����Ƃ����B�����ė܂�}���Ȃ���A��l�̑O�ɘ�����ނ��ƁA�ؑ��̗��Ⴉ����A���炽��ƁA���̗܂����ꂽ�B
|
���ّR�l
������ԁA���������ɐ����āA�فX�Ɣn���݂����ɂȂ��ē����\�\�Ƃ������Ƃ́A�^�ʖڂȐl�����悭�v�������Ƃł���B
���̎��s�����Ⴍ�����A���l�ɂ́A�l�̉M���m��Ȃ����x����������B
��Y�����̂��̂܂ܔN�͕�ꂽ���A�N�����炽�܂��āA�������傤�ւ���N�̐������}����ƂƂ��ɁA����́A�|�R�ق�ƍl�����B����Ɏ���������Ƃ苹�ɂ����B���Ȃ������ł���B�n���ɂȂ낤�A�n���ɂȂ낤�A�ł���B�����āA���ɂ݂�A�Ƃ����ڕW�����Ă��B
�u����́A�C���y�ɂȂ����v
����́A�������A��@����~�����Ǝv�����B�n���łȂ��������A�n���݂����ɂȂ��āA���̎��A�y�X�����ƁA�ړI��簉��܂��������Ă䂭�B�\�\�₪�ČܔN���\�N��ɂ́A�n���n���Ƃ���v���Ă����������A�͂�����ƁA�n���łȂ����т������āA���̏f�������A���Ԃ��Ă��B
�u�������낢�B�ّR�l�����˂�ɂȂ邱�Ƃ��B�������A����b�Ƃ̎Ԏɐl�ƂȂ����Ǝv���A�Ȃ�ł��Ȃ��v
�ނ́A���ԂɎ����ӂ������B�Ɛl��z�X���A�O���牽���ė��č��������悤�ƁA���Ă��邱�ƂɌ��߂��B
�J��������A�V���Ȕ_�c�̂��ł�́A�����Ɋl����ꂽ�B�R�т�A���߁A�����ɗ�݁A���̂Ƃ���N�����ł��A�L�c���̖ʐςƔ_�Y�́A�ʖڂ��A���炽�߂��B
�܂ӂ��A������N����O�N�ɂ����ẮA�S���I�ȑ�Q�[�����A���{�̈ܓx���A�������Ă����B
�H�ɂ́A���₪�Â��A���N�܌��ɂ́A�ljԂ��傤���̌�Ƃ����̂ɁA�e�n�ō~�������A���̉Ăɂ͂܂��x�����Ȃ��E���̏P���ƁA�^���̏o���������B
���̂��߁A��N�ڂ̏H�ɂ́A�n���̒��v���傤����(�ŕ�)���A�܂������s�֑����Ȃ������B
�V�c�́A�ق݂��Ƃ̂肵�āA��̌�V���̗ʂ��A�l���m��Ɍ�����ꂽ�B
(�\�\�X�j�A����t�N�M���m��V�W���E�[�����A�l���m��j���[��)
�Ƃ����A����̂��߂ɏ����֔͂͂�������ꂽ�ق́A��N�ɓ�x�܂ŁA������ꂽ���ł���B
���܂��ɁA��r�I�A��Q�̂Ȃ��l���A��B�Ȃǂ̐��C�n���ł́A�C���̖I�N�ق������A�p�X�Ƃ��āA�������B
���C�̊C���́A�s�̊��ɂ֗A������Ă��钲�v�D��_���ẮA�P�����B
�u�ɗ\�̏��F���B�c�c���F�̂��킴���v
�ƁA������A�s�̕s���ɁA�ւ��������B
���q�@�̍ɍ��́A�����̋����ɁA�{��������̐����o�������邾���ł��A���X�A�C���Ђ���قnj����Ă���B�吆����������傤�̜H�@���ł́A�������������A���Ȃ��āA�S���̏��Ƃ��傤��(��������)�ɂ������A���c�A���c�����ł�̒��łƗA���Ƃ��A������̂ɁA��̂����ς��Ă����B
���R�A�e�n�Ƃ��A�����g���傤����(���ŗ�)�̎旧�Ă��A����ɂ߂��B
�R����ɂ��A�i����ɂ��A����A�@�̔�������Ȃ����̎���̖��̖͂��́A�ǂ�ȉ՝��n������イ���イ�ɂ����������Ȃ��B�p�������������ڂ��Ă��A�o���˂Ȃ�Ȃ��B
�������̖��́A���̍��̖��w�ɁB
�}������������
�\�]�Ƃ��܂莵��
���肵����
�������Ӄm�����傤��
���������Ɏ��A��悳����A
��肵����
�}�������Ȃ�
�킸���Ȑŕ��̑��ɁA�����肷��A�n���̝��̉����Ɏ����čs���ꂽ�ƒQ���Ă���y���̍Ȃ̊炪�ڂɌ�����悤�ȗw�����ł���B���̂���݂��A��X�܂ŁA�n���̎q���́A���S�ɁA�w���Ă������̂Ƃ݂���B
���A���͂��납�A���������̘I�����Ȃ��A��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ƁA�ނ�́A�Ō�̎�i�Ƃ��āA�������̂āA�����̂āA��Ɨ��U���āA�v���v���ɁA�����̐g���A�z��ɁA�������B
���@�ł���A���Ƃł���A�����̉Ɛl�ł���A�ǂ��ł��A�͂̂��鏊�ցA�z�X�z�l�Ƃ��āA�������̂ł���B���������A���Ђ̖��ɂ́A�ł͕��킹���Ȃ��B�܂�A�g�����ĂāA�ł̕��S����ق̂����̂ł������B
�����������U���傤����̗�����݂A����̖L�c���ɂ��A���т��������A���肱��ŗ����B
����́A�ǂ�Ȃ������B�ނ���A�K���Ƃ��āA
�u�H���Ȃ��҂́A����Ɠ����A�����Ƃ���ɁA�Q�[�͂Ȃ��v
�ƁA���������B���̂��߁A�ق̑�Ƒ��`�Ԃ́A�c���ڂ����傤���邵�A�����͐B�������ł��������A�}�J��̉Γc�@���ł�ق��Ȃǂ��p���āA���悻��N���A���ɂ��̋����ɁA�������ē������B
���́A�����̑�Q�[�Ƃ���ꂽ���Ȃ̂ɁA�L�c���́A���̊��ԂɁA�������āA�x�𑝂����B
���삩��C�����Ă������n��~����̌䗿�̔[���̂����́A�t�H�Ƃ��A������Ɠs�֑����Ă������A�d�ł����[�ł����B
�܂��A���������A������n�߂��q�̖Ĕn�Ђ�́A�݂Ȏe�݁A�����ĎO�̏t���A��A���Ύe�Ƃ����������A�匋�m�q�ɁA�Q��V�сA�ނ����ɋ߂��i�ς�悵�n�߂Ă�����B
����A�����ƁA�傫�ȗ͂����������Ƃ́A�S�̌���≎���̏��������A��n�����Ă���������ނ̖����Ƃ������͂ɂЂ���A�܂����ۂɁA�ނ̓w�͂��A�L�c���̖u�������āA����̊قցA�����ƁA�b�悵�݂�ʂ��Ă������Ƃł���B
����ɂ������Ă��A�ނ́A
�u���ށA��ɂȂ邩�B�悩�낤�B�������A���������A�荇�����́A���ƂȂ��āA�͂��ނ��сA�[�������āA��ƂȂ낤�v
����҂́A���܂��A�N�Ƃł��A�t�������킵���B�ނɂ͂ǂ����A����ȕ��ɕ����e�����Ȑl���炪�������Ƃ݂���B�R���A�֓����B�́A�㐢�܂ŁA��������ƁA�t�ɂ���ċ`����k�̕��K�����̂��A�����A�����̐��̍Ⓦ�D�쎞��A���̕ӂ̌��n���x�̒��ŋ��������邽�߂Ɏ��R�Ɏd�g�܂ꂽ���}�����̖��c�Ƃ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B
�@ |
���j�[�Ђ炭
����A�O�l�̏f���ɉ��̂��ꂽ��Y�̑�ɂ́A�y�т����Ȃ����A����ł��A����͂ЂƂ܂��A�Ɖ^��҉�������B
����ł̎��ɁA��������Ƃ��Ȃ�A���c�ȗ��́A�L�c�̊ق��A���肩�������B�f�����̎肩��́A�ˑR�A�ꖇ�̓c���Ԃ���Ă͂��Ȃ����A�D��ꂽ�ƎY�c�̂̉��\���̈ꂩ�́A�����̓w�͂Ɗ���������ǂ����B
�u�\�\�V�͂�������ł���Ă���B����ɂ́A��݂�����A�l�m��ʊy���݂�����v
�فX�O�N�̊ԁA�ނ����X�j�^�j�^�����Ă��������̔閧�́A�����ܔN�̐����A���߂āA�ꑰ�Z��ɁA��I���ꂽ�B
�u���Ƃ��́A������A�Ȃ������B�c�c�N���H�@���ĂĂ݂�v
�ƁA���t�̉���̖�ł���B�����Ȃ�吨�̑O�ŁA�����A�ނ炵���A�����o�������̂ł���B
�u�ق�ƂȂ�A�ꑰ�̊��тł��B���ق₩���ƂāA����O�\�܍ɂ����Ȃ�ł����́v
�݂ȁA�ǂ�߂��āA�t���グ���������A���āA���傪�����Ƃ��Č}���悤�ƌ��ӂ����قǂ̏����́A�N�ł��낤���H�@�N�ɂ������͂��Ȃ������B
�����A�����̕��́A�����̓s����łȂ��A翂ЂȂł��A�\�O�A�l�A���邢�͏\�܁A�Z�ōȂ����҂́A�����������B������ܘ_�A���傪�O�\�܍܂ŏ����𑤂ɂ����Ȃ������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�ȂȂ�ʍȂ́A�����ɂ������Ă����B�ق̓��̂��������ɏZ��ł��������킩��Ȃ��B�������A���Ȃ͂܂��W�߂Ƃ��Ă��Ȃ������B
�u�Z�Ґl����ЂƁB���͒m���Ă��܂��B�c�c���ĂĂ݂܂��傤���v
�������̂́A��̏����ł���B
�����́A������ɂ������ۂƁA����������ď����B
�u�ȂɁB�m���Ă���ƁH�v
�u�����Ă��܂��Ƃ��v
�u���ĂĂ݂�v
�u������A����������H�v
�u���܂��ɂ́A��~�̌䗿�n���ӂ��ށA��J�ꋽ����₢�����������v
�u���B�c�c�܂����A�Z�Ґl�A����ȁA���˂���͂��܂���v
�u�悢����A�����B���ĂĂ݂�v
�u�쑚�́c�c�j�[�����傤�ǂ̂ł��傤�v
�u�������v
����́A���ł����B�������Ƃ����������A�r�����Ȃ��吺�������̂ŁA�݂ȁA�����C�ɂƂ��āA������A���܂������B
����������́A����ĂĔt��O�։^�сA��ɗ܂����߂Ă����B�����āA�����ɁA�t��^�����B
�u����������A�����B�����Ă��Ă��ꂽ�̂��ȁA���ꂵ�����B�c�c�ǂ����A�������A�������A�������A���ׂ��v
�����ƁA�킽���A���ׂĂ̊�����킽���āA
�u�j�[�ǂ̂��A���ꂪ�A�W���Ă��������A�ǂ����B���ꂪ���������B�Ɛl�����A�����Ă���A�����Ȃ������Ă���B���̊ق̖k�̕��Ƃ��Ă悢���A���������v
�ƁA�����낵���^���ɂȂ��Đu�˂��B
�������n�߁A�ނ̒킽���́A���X�ɂ���֓������B
�u�悢���������������܂���B�Z�Ґl���A���D���ȕ��Ȃ�v
�u�Z�Ґl���A�䌈�ӂȂ̂ł������܂��傤���v
�u���������́A�����Z����A�����Ă��܂����B����ȁA���D���ȕ�������̂ɁA�����W���炢�ɂȂ邨���肩�ƁA�����������A�҂������v�������Ă������ł��v
�u�c�c�c�c�v
����́A�傫�Ȗ������悤�ɁA�킽���̈������A���Ȃ����ŎẮA���炵�Ȃ��A�@�̂����܂̗܂��A�����݂��Ȃƈꂵ��ɁA�������Ă����B
�u�������A���O�������A�������������v
�u�Ȃ��A���̂悤�ɁA�������ցA���C���˂Ȃ���̂ł����v
�u����B�����W���ɂ́A���O�����̗͂�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B��b���₭�A�����������Ȃ�A�j�[�ǂ̂̐e�A�쑚�̉��̂��Ƃɂ́A����āA�œ��炷�Ƃ����킯�ɂ͂܂���ʒ��ɁA�������Ă̋��Ȃ�A�����A����ŋ����\�\�Ɛ\���̂��v
�u���A�����ł����B�]��ɐg�����Ⴂ������ƁA���̎����Ȑe���́A�ډ����Ă���킯�ł��ȁv
�u�c�c�Ƃ��A�������B���R�́A�܂������A�ׂɂ���v
�u�ł͂Ȃ�ŁA����ȌÕ��Ȏ����A�]�ނ̂ł��傤�B�����̂ɂ́A�]�ނƂ���̉Ƃ̖����A�ۂƁA�ۂ̈ꑰ���s���āA�������ߒD�Ƃ��ė���̂�����ł������K���������ɂ͕����Ă���܂����v
�u������A����̖]�݂�����d�����Ȃ��B����ɂ́A�j�[�ǂ̂̐e���̋ꂵ���C�����͏[���ɂ킩���Ă���̂��B�����āA���O�����ɂ��A���̋ꂵ�݂��A�₪�ẮA�݂邢���Ȃ��čs�����Ƃ���������Ă���B�c�c�����A������߂��Ȃ��̂��B����́c�c���̌Z�́v
����́A�w�Ŕ���~���������B���̎�́A���܂ŁA���̍������܂܁A�ނ炵�����Ȃ����ߑ��ɂȂ��Ă����B
�����ɂ������ɂ��A�ӂ�������͂킩��Ȃ��B�����A�Z�̗����A�l�N�����A���̒��ɂ�����Ă������Ƃ����͒m���Ă���B�����āA���̌Z���A�����ł͂Ȃ��A�吨�̂܂��ŁA������シ��̂����A���ł����ɔۂ₪���낤�A�ƈꂹ���ɁA�Z�̗����܂��悤�Ȕ��F�т��傭�����������B
�Ɛl�Y�}�����ɂ���A����́A�����ōX�ɏj�t���d�˂Ă��������Ȏv����������A�ًc�̂���ׂ��͂��͂Ȃ��B�₪�āA�ٌ������ɁA
�u�g���͑��������B�ԂɉJ�A���ɉ_�̂��Ƃ�������܂����v
�ƁA�M�̂̂悤�ɂ������͂₵���B
�ꑰ�̎҂ɁA�����j������A��܂���āA������A���悢���`�ق��������߂��炵���A
�u�ł́A�����炬�܂łɂ́A�Ō䗾���A�����Ɍ}���悤�B�����ƁA���̐S�������Ă����₢�v
�ƁA�錾�����B
���̋����̂́A���̎���́A��ɁA���̌���̐l��̓��F�ł���B�\�₶�����̍������낫(�o�����т���)����ɂ��ĂȂ�����ʂقǂ������B���A�D�T�̂悤�ɐ������B�����āA����̗��ƁA�����āA�����̖���A��ʂ��ɁA�j�����B
�Ƃ��낪�A�����ЂƂ�A�s�������ɁA����߂Ă����V�l������B����̕��ǎ��̑ォ�炢�鑽���o�������̂˂����Ƃ����V�b�ł���B
�o���́A������������݁A�����Ȃ����āA���̖��ɂ͗����Ȃ��V��Ȃ̂ŁA��~�̌䗿�̒r�̔ԏ��ɋl�߁A�߂����ɁA�قւ����Ȃ��������A���܂��܁A�V�N�̉��ɉ�āA�������ĂЂǂ��J����ɒ���ł����B
�����A�ނ��ꌾ�A���������ł��������A���̎�҂��낢�́A痂����쐫�Ɏ��C�������������͋C�ɔ����ނ��悤�Ȏ��́A�ƂĂ��V�l�̖R�����ӗ͂ł́A�悭�ׂȂ����邱�Ƃł͂Ȃ��B
�\�\�ƁA������悤�ɁA�ނ݂̂́A�Ƃ�A�ƂڂƂڂƁA�Â����������A��~�̌䗿���A���čs�����B
|
���헤����
�������́A��q�����Ⴍ���A�₦�Ȃ��B
����́A����������A�q�ɐڂ��āA�ׂ̂����Ă���悤�Ȋ��D�������B
���傤���A�����i�s�����Ă����B
�u�悭���悭���A����܂łɗ�܂ꂽ�B�S���ǎ��ǂ̂����݂킵����A�������芽��悤���B�\�\�������́A������̖���܂��������q����ǂ̂�B�킵���A�ǂ�Ȃɂ��A���ꂵ�����m��ʁB�悢���t�͂���A�̂Ȃ��������̊قŁA�j�킹�đՂ����v
�i�s�́A�����ɂ߂āA�������N�́A����̍��Ȃ��܂ق߂��B
���̋ޒ��ȌN�q�l������̂܂��ł́A������A���Ă̟����ꓶ�q�̍����̂܂܁A�����A�܂��āA���N�̉��`���ӂ�����A���ꂩ��̋ΕׂƁA�Ɖ^�̔҉�����������炢���A�ւ̂�܁A���ɏo��b��ł������B
�u���̂ނ��B���̏�Ƃ��Ɂv
�܂�ŁA�^�̕����A�^�̑��q���A��܂��悤�ɂ����ċA��i�s�ł������B
���̐l���A�ق̒���܂ŁA����o���āA�ӂƓy�q�̕�������ƁA�܁A�Z���̉בʂ������Ă���B�킽���ƁA�Ɛl���A�n�̔w���牺�낵������̌ԍ�����������A����q�ցA�^�т���ł���̂������B
�u�����A�܂��A�쑚����A�o���炦�Ă������o���Ă����̂��v
�u�͂��B�Ȃ��g�ق���|�̗ނ��A�ߓ��A�o����������A���X�ɓ͂��ĎQ�邻���ł��v
�u�n����A�������A�|���A���������A�ʂ͗������낤�ȁv
�u�����ԁA�����ĎQ��܂����B�����ǁA�O�̓y�q���A�䗗�Ȃ����܂����v
�u����A���傤�͎~�����B�c�c�����菫���Ə����́A������ƁA����̋��Ԃ܂ŁA���Ă���Ȃ����v
����́A�₪�āA�ォ��]���Ă�����l�̒���A�O�ɂ����āA�����������B
�u���ƂƂ��̔ӂȁB���t�̖鉃�₦��̐ȂŁv
�u�͂��v
�u����́A��قǁA�S�������Ă������̂Ƃ݂���B���m�炸�A�j�[�ǂ̂̎����A���ɏo���Ă��܂����B������߂���ʏ����ł͂���A�����āA���߂悤�Ƃ��A�v���Ă͂��Ȃ��������A����Ƃāc�c��������������Ȃ������̂��v
�u�悢�ł͂������܂��ʂ��B�z�����A�z���̂܂܁A���܂ŁA���ݗV���Ă�����́v
�u���������ĖႤ�āA����́A�܂����ڂꂽ��B�\�\�����A�����B�c�c�ł������邪�A���́A�j�[�ǂ̂ɂ́A����̂ق��ɂ��A���̂���q���āA�����Ă���j������B����ɂƂ��ẮA������A�苭�Ă��킢�����������v
�u�ǂ��������Ƃł��B�Z�Ґl�A���ɕ����ĂȂ���̂ł����B���肪����ƕ����A���������A�Z�Ґl���A�����̐l�ɂ͂������܂���B�ȃA�����v
�u�����ł��Ƃ��B����ł��A����́v
�u���ꂪ��B����̑��q�������v
�u���q�����Ƃ́A���������ł͂���܂��B��̒��j�A�}�ł����B���j�̗����B����Ƃ��A�O�j�ɂł����v
�u���ɂ��A�Ύ~�Ȃ��Ƃ��B���̕}�ƁA���j�̗��Ƃ��A����܂��A�ЂƂ�̋j�[�𑈂������Ă���킯���B���̂��߁A�ނ�Z����A�����ނ��ɂ́A�j�[�ǂ̂���ɂ��ꂩ�˂Ă��邵�A�j�[�ǂ̂̐e�����A����𗝗R�ɁA�ǂ����̋��߂ɂ��A�I�݂ɁA�f������������ė���ꂽ�̂����c�c�������������́A���̌������A�����Ȃ��ؔ������ς��ɒǂ��߂��Ă���炵���v
�u�\�\�ƁA�������̂́v
�u�}�Ɨ��̌Z�킪�A��͂�Z�킾���ɁA�b�������āA���̗��A�ǂ����ɍK�����邩�A�܂����������āA�j�[�̏��L�����߂悤�ƂȂ����炵���v
�u�A���ɂ��Ă���B�����鏗�����A�q�����ɂ���Ȃ�āc�c�v�ƁA�C�̗D������������A�`�������炵�āA�u�\�\����ŁA�쑚�̕������́A�����A���̂ǂ������ցA�^�������Ȃ̂ł��傤���v
�u����A���̉��́A�E�͋�t�ł��A�S�͍d�����B�������A���C�͂Ȃ��B����͂���ɂ������Ă���v
�u���A����ł����v
�u�����֗��ẮA�l�ڂɂ��B�����ł����A��~�̌䗿���ցA�����ƔE��Ō�����B���̌o���̏Z��ł���r�珬�ɂ������育��̂����ŁA�тƂȂ��A����Ă����B�\�\�����܂Ȃނ��߂̋j�[�ǂ̉����ɁA�����A�쑚�̉����A�q�䂦�ɖ�����̒߂Ƃ��������Ƃ킴�ǂ���A�����ɂ��āA�����K�˂ė���v
�u����ł́A�e��̕��������A�Z�Ґl�ցA�łƂ��������ƊA�j�[�ǂ̂��A�Z�Ґl���A�z���Ă���킯�ł������܂��傤�Ɂv
�u�܁B�c�c�����Ȃ̂��v
����́A���Ԃ������B�킽���ɁA�������ʂڂ�Ə������܂����ƁA�����������������������B
�u�\�\�Ȃ�A�����A���́A���S�O�����イ����Ȃ��邱�Ƃ�����܂��傤�B�}�◲�ցA���܂��A�����킯�̂��悤�ɁA�����A�l�����ʂ�̎�i���A�Z�Ґl���A���������A���s���Ă����܂��ɂȂ�A����܂ł̎��ł��傤�v
�u����A����̜����̂́A���ꂩ��悾�B�\�\���Ƃ����Ă��A�����Ƃ́A�V���A�^�ǁA�}�g�O�S�ɂ킽��헤�����̏@�����B�Ⓦ��тɂ��A�����Ȃ��呰�ł͂���A���㌹���̗^�}���e�n�ɂ����Ă���v
�u�����āc�c�Z�Ґl�B���ł��傤�A���́B�����獵�㌹���̒��j�ł��A���ЂƂ�ɁA����ȕ\���������͂�U�������܂��܂��v
�u�c�c���A�Ȃ���B�����ɂ��ƁA���̌�̏��ނ��ߓ�l�܂ł��A���ꂽ���̏f�����ցA�ł����Â��Ă���B�ЂƂ�͗nj��ǂ̂̎��B�ЂƂ�͗ǐ��ǂ̂̓����ցv
�u���́A�ǂ��Ȃ����Ă��悤�Ƃ��ł��B�\�\�ł́A�Z�Ґl�́A�j�[�ǂ̂��A�z�����̂ł����v
�u����Ȃ��c�c�v
����́A����ނ����B
�u���Ⴀ�A���Ƃ̋���A�����̂���Ȏv���́A���o��̏�ł��A�v������ʂ������Ȃ��ł͂���܂��v
�u��邵�Ă���邩�v
�u����Ȃ��C�̎ア���Ƃ��v
�u����ɋ��Ђ�݂͂Ȃ��B�����̗����B����q���Ă���ʂ������킳�B�\�\�ł͏����A���܂��́A���ƂƂ��̖���A�������悤�ɁA����ƕ��Ƃ��āA�߁X�ɁA��~�̕��֏Z�߁B���̕ӁA��J��т̓c�̂́A���܂��Ɍ����B�܂��A�����́A�����̊��������悢�v
�u���̎��ɁA�������̐g�܂ŁA����Ȃɂ��l��������Ȃ��Ă��v
�u�����́A�����A�����ɂ��A�ǁX�A�������Ă��˂Ȃ�Ȃ��N���ɂ݂ȗ��Ă���B���̖S���Ƃ�����A���ꂪ���̎d�c�����d�����˂Ȃ�܂��킳�B���͂͂́c�c�B������A���ɂƂ���āA���܂��B�ɂ܂ŁA�S�z�����Ă��鍢�����e��肾�B�����̂������Ȃ��͎v�����낤���ȁv
���l�́A���キ���キ�A��������B���ɁA�c�������Ȃǂ��̈��D���ĂыN���ꂽ�B����́A�������Ĉ��������悤�Ȋ�������B
����ƁA��ɂ͋C�̎ア�_�o���ȏ����Ȃ̂ɁA���R�ƁA�܂��āA�����o�����B
�u�킩��܂����B���C�������A�䎖����A�悭����܂����B���������̂悤�ɁA���́A�������ɁA��~�֕ʂ�܂��B�������A���������B�\�\�Ƃ���ŁA�Z�Ґl�B�Z�Ґl�̗��l�́A�����}�����܂����B�쑚�ցA�j�[�ǂ̂��A�����炢�ɂ܂����́A���Ў����A�A��čs���Ă��������v
�u�Z�Ґl�B�\�\�����v
�ƁA�������܂��A�Z�֔������B
|
�����D
�܂��A����u���A�~�͂�̂܂܂������B�@�������炬���߂̕��́A�Ђ傤�Ђ傤�ƈ��̕�ɖ�A�[���A���ڂ��قǗ������ł���ꂪ�A��H�ɂ��A�����̉����ɂ��A����̂悤�Ȕ���������߂����Ă���B
�\�\���̓��B�������̉Ƃ́A�I���Ђ˂����A�Ђ��₩�������B������q���A�d���ɂ����l�q���Ȃ��B
�[�M�䂤���̈ꍏ�ЂƂƂ��ɂ́A�e�����₱���āA�����ƁA�y�킩��炯�Ŕt���ނ݂��킳��A�j�[�̕�Ȃ�[�����Ȃ́A�ق��ʂ����ʂ��Ă����B
�ޏ��́A���ς����B������ꂽ����A�т��A���ɂނ����Ē������B
��q�����́A���\���A�������Ă���B
�\�\�₪�āA������̒��ŁA���������܂�U��̂��������B
�u�c�c�ł́v
�ƁA�ɂ킩�ɁA�����[���A�ƒ����āA����߂����B
�u�������ɁB�c�c�Â��ɂ�v
�܂Ȃ���A�j�[�̎p���A�y����̏����Ȃ����肩��A����o���̂������B�j�[�́A�����g�~�A�A���A���ƋݐF���d�˂����݂��������𒅁A��₩�ȍ�����������ɉ����Ă������A�e�̉Ƃ̖���A�������A�o��ƁA���̍��������݂̑����A��֕�����������悤�ɁA�ԏ��C���������낵�ɐ�����Ă����B
�����A���̕ӂɁA�g���Ă������̂��낤�B�����ƁA�؈���ނ炩��A�\�l�]��̐l�e�������A�j�[�̂��߂Â����B
�������ɁA�j�[���A�A�\�\�ƁA���낢���𗬂����B�Ƃ����A�ޏ��́A�n�̔w�ɁA�����������A�Ƃ���ɁA�z�ł������A���̕��ցA�킯�������B
������A�y���ő҂��Ă���҂̍��}�炵���A�������������������A�܂�������ɁA��ʂ̂Â�̂����ŁA�������Ă����B�\�\���悤�ɂ���ẮA�쑚�̉��ƛ[�ցA�������A���Ō���Ă���Ƃ���������B
�[�Ɖ��́A�Ƃ̂����֖߂�ƁA���������ɁA�V���̗܂̂Ƃ߂ǂȂ����A�Ԃ߂������B
�u�����A�₵���B��̂����̎삽�܂��������悤�ȁB�c�c����ǁA�ނ��߂̖]�݂��A���̂����̂��B���Ȃ����悤�ȉœ���ł͂��邪�A�j�[�̐g�ɂȂ��āA����ł��B�j�[�̐S�́A�����A�L�c�֍s���Ă���ł���B����A�y����ʂɌ����������́A�ۓa�ނ��ǂ̂��݂�����U���Ă����x�Ђ�������ʁv
���������A���̘V�v�w�́A�j�[�����܂ꂽ������A���傤�܂ł̑z���o���A������b���Ă��b�����Ȃ��悤�ɁA��肠���ẮA��������ł����B���̓����A���̋�t�̂₵���́A��̂悤�ɁA�Ђ��܂�Ԃ��Ă����B
��q�����́A�����̓��E�̐l�X�ւ���A
�u�j�[���܂��A���̂��̗[������A�s���m�ꂸ�ɂ��Ȃ�Ȃ��ꂽ�v
�ƁA�������B���Ă����B�����āA
�u����̐l�����ɁA�U�����ǂ킩���ꂽ���A�쓐�̌Q��ɁA����ꂽ���v
�ƁA�킴�Ƒ�ɐ��������B
����������͂Ȃ��ł͂Ȃ��B�����̘؎�(���ڈΗ�)�̐��͒n�֍s���ƁA���������������ɔ��������Ƃ����B�܂��A�͂��s���������A�����Ă䂭�l�����͂悭�k�̕��֒ʂ��čs���B
���ɁA���N�O�ɂ́A�H���̗nj��̋ǂɂ������Ă����\�\����Ȍ��łȊق̂����̏��l����A���R�ƁA�p�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ⴓ������B
����������́A���i�̒���A�S�i�̖����֑i���Ă��A�ǂ����悤���Ȃ����������B���̉H���̗nj��̐��͂��ȂĂ����A���ɁA�����̋ʒ��́A���ꂫ��A�ǂ��֍s�������A���炸�d�����ł���B�ꎞ�́A���傪�B�����̂��ƁA�����ς猙�^�������āA�T�����ꂽ���A�^���A�L�c�ɂ��A�ǂ��ɂ����Ȃ��ƕ����āA�悤�₭�A������A��N�O�ɁA�\���Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ��낾�����B
|
�����呧�q
�u���A���B�\�\�j�[���s���m�ꂸ�ɂȂ����Ɓv
����̒��j�A�}�́A���̓��A����̗ǐ��̊ق֗V�тɏo�����A�܂��ǐ��ɂ����Ȃ������̖�O�ŁA�ǐ��̉Ɨ���������A���̎������ꂽ�B
�u����́A�̂Ă�����B��厖���v
�ނ́A�����܂��A�n�������āA�쑚�̕��ցA�킯�čs�����B
���̍��㌹���̒��q���A�N�͂����������ł���B���Ȃ������������Ă����B�����A���́A�ׂȓ��Ƃ��Ă���炵���B�n���ɂ߂��炵�������҂������̂ŁA�Y���₩�ȑ����A��߂̑�����A�n��̏���̔��X�����́A�˂ɑ��[���̉��̓y���̊�����������Ă����B�����āA�������l�┪�l�̋��͘A��Ă���B
�u�͂₭�����B�����B������ȁA�Y�}���v
�ǂ�����Ȃ��Ɨ��������A���X�A�n�ォ��U��Ԃ��Ď���Ȃ���A�܂�ŁA���ւł��}���悤�Ȍ�C�ł���B
�u���̎d�Ƃ��ȁH�@�c�c�B�������B��������ƁA��߁A���ꂭ�炢�Ȏ��͂�肩�˂�v
�[���ɁA�^���āA�쑚�̋�t�A�������̕������~�ցA�킯���B
�Ƃ��낪�A�ǂ��ŕ��������A��̗��̕����A������ɂ����֗��Ă����B�����[���A���̗[����A���ɂ��āA�Q������ł���Ƃ����ĉ��Ȃ��B��q������A�����̏��E�̎҂��W�߂āA�ׁX�A�u���������Ă����̂������B
�u�ǂ����A�悭�킩���B�\�\�j�[�����Ȃ��Ȃ����̂́A�����炵�����A�O��̂��������A�҂܍���ʁv
�u���B�����A�肪����́A�Ȃ��̂��v
�u�₠�Z��B����͂��ƁA����B�̕s�o�������B�@����ɁA�L�c�ł͂Ȃ����Ǝv���v
�u���傩�B�c�c�����A��x�́A�������l�������A���̏��S�҂ɁA�傻�ꂽ�܂˂͏o���܂��B�j�[�̐g�ɂ́A����̑����������Ă���ƁA�ޓz�́A�S�����m�̂͂����v
�u�����l���Ă������������A�ƂтɁA�o�������ꂽ�����Ƃł͂���܂����B���v���ɁA�����ꗼ�N�A�쑚�ŏo���镐��Ȃǂ��A�唼�͖L�c�̕��֔�������Ă���B���̂܂ɂ��A����ƕ������Ƃ̊ԂɁA�b���������o���Ă����̂����m��ʂ��v
���́A����Z���̂�U���āA������ɁA���Ȃڊ���A������֓��������B�����̚k�o�ɁA�m�M�������āA��������̂ł���B
�}�́A���߂��B���{����Ƃ����Ȃ鐫���炵���B
�u�����A���B�������v�w���A���܂��̔n�̔w�Ɉ������������āA�ォ��قցA�������Ăė�����B��낵�����v
�����������āA�����́A�s�����X���������ƁA��Ɏ��@�ցA�A���Ă��܂����B
�܂��Ȃ��A�����A�ォ�痈���B�������A�쑚�̘V�v�w�́A�f�v�炿���ė��Ȃ������B�ǂ��������Ɛu�˂�ƁA���ƛ[�́A��Ԃ𐴑|���A�����Ȃ�ׂāA����悤�ɁA���Q���Ă����Ƃ����̂ł���B
�u�L�c�̂ցA���Ƃق��߂�(����)�����Ă݂�A�����킩��B�����^���]�n�Ȃǂ������ł����v
���̌����������Ă������Ƃ́A�����̌�ɁA�����ꂽ�B���ɁA���ӂƂȂ��Ă݂�A���̌Z��́A����ނ��Ƃɉ����āA�܂��A�������ړI�ɉ����āA�ǂ��̌Z�풇�����A�}�ɁA�����悭�Ȃ����B
�u�ޓz�ɂ��A�Ɛl�Y�}�͂���B�����ɂ́A�肪�o����B�ǂ����Ă�낤���v
�s�����犮�S�ɏ���̒v����N�₭���悤�ȍ�łȂ���Ȃ�Ȃ��ƁA��l�͒q�b�����ڂ肠�����B�����A���S�N�E�ƂȂ�ƁA�ɂ킩�ɖ��Ă�������ŗ��Ȃ��B
����ƁA�̖����ł���B
�Γc�̑坁��������A�g�҂������B������Ђ炢�Ă݂�ƁA�����������B
�\�\���炭�����̂�����핽���吷���A�ˑR�A�A�Ȃ������܂����B
���̂��т̋A�Ȃ́A�V���ɁA�E�n�܂̂����ɔC���������т����̘V���ɍ����邽�߂ƁA���t�̌�n�エ�܂̂ڂ��̍v�n�݂����܂��A�����̊e�n�̖q�ɁA���������݂��邽�߂̌��p�̓r���Ƃ̎��ł��B
�����킸�����O���قǁA���Ƃɗ��̐g���x�߂�ɂ����݂̂Ƃ��B���Ђ��̊ԂɁA�v�X�Ԃ�A��������āA�l������̂������ȂǁA�����̎v��̑z����s�������ƁA�O���Ă���܂��B
���҂��\��������B�ǂ����A�����낢�ɂāA�������z���̂قǂ��B
|
���x�M�Ɛύ�
�헤���k�Ɠ�ł́A���Ȃ�G�߂��������B
�Γc�̊ق́A��헤�ɂ������B
�B�}�g�̕��͂܂��₽�����A�G��Ȋق̒z�y�ɂ��A������߂܂����ɂ��A�g�~���~�������]�ق����ł����B
�坁�����́A������@���ł���B�H���ق��炢�̉������Ȃ̂悤�ɁA�����Ȃ��炫�ꂢ�ɋ������Č��������A���߂̂����̋��ɂ������a陂�����𐂂�Ă���B�G�X�q���ڂ��A�ߖ䂦��������������ɁA�Ȃɂ��ƁA�q�҂��̂����������Ă����B
�₪�āA�ƐE�⎘���������āA�����̏o�������Ƃ�������ƁA
�u�������B�q��̕ӂ����łȂ��A�q�l�܂낤�ǂ̋���Ȃ��X���܂�Ȃǂ����߂��낤�ȁB�X�̕s���b�����̂́A���Ȃ��̂��v
�u�m��U�炵�ĂȂ��悤�ɁA���|���Ă����܂����v
�u�悵�A�悵�B�c�c�����₪�Ă��������낤�v�ƁA�K�������ɘV���ᰂ���߂Ĝ��������Ƃ�ƒ뉀�̏t�����Ƃ��ׂ߂��\�\�B
�u�E�n�ǂ̂ɂ́A�����Ă����邩�v
�u�������A�����a���o���A�䑕���X�����傤����������V���Ă�������Ⴂ�܂��v
�u��������A�s����́B������Ȃ��Ȃ������҂ł͂���B�x�x������A�q�l�����̂������ɂȂ�܂ŁA����֗��āA���Ƙb���ʂ��Ƃ����Ă���v
�E�n�ǂ̂Ƃ́A�����̒��j�A�����̏핽���吷�������̂ł���B�V���ɁA�E�n��ɏ��������̂ŁA���̘V���́A����Ǝ������āA�ӎ��I�ɁA�Ɛl�����ɂ́A�ߍ������Ă��Ă����B
�u����A����ɂ����łŁv
�u���A�吷���B�܂�����B���a�Ђ��ɂ߂��܂�Ă悢������������v
�u���傤�̋q�l�́A�N���ǂȂ��ƒN���ł����v
�u���q�́A����ǂ́B����݂���̗ǐ��A�H���̗nj��ȂǁA�������ւ����ɂ��Ă��������v
�u��ǂ̂̌�q�������́v
�u���邾�낤�B�ē��͂��Ă���������v
�u�s�֏o���܂܁A�v�����A�������܂���ł������A�ȑO�Ƃ́A��r�ɂȂ�ʒ��A�������g�܂�A�Ɛl�Y�}���B���A���̂��قȂǁA���Ⴆ�����ؗ�ɂȂ�܂����ȁB������Ȑ������炵�́A�s�ł���b�����݂��炢�̒n�ʂłȂ��Əo���܂���v
�u�������A�킵�̊��ʂȂǂ́A�ˑR�Ƃ��āA�坁�Ɏ~�܂����܂܂��B���Ƃ����Ă��A�c�ɂɂ��ẮA���Ԃ���邢�B�������Ƃ́A�E�n��ɂȂ�A�₪�ẮA�q�{���ӂ̓����݂ɂ��Ȃ�悤�B���E�ł́A���̘V�����͂邩�ɏザ���v
�u������ł́A�m�a���ɂ�Ȃ��̎������{�����Ԃ��傤�݂̂₾�́A�E��b�Ƃ����t��l�ȂǂɁA�Ȃ�Ƃ��A�����Ă������Ă���܂��B�����ł́A���Ƃ����Ă��A�ۊ։Ƃ�e�����Ȃǂɂ��߂Â��Ȃ���Η��g�͐���܂���B�c�c���A����Ŏv���o���܂������A�����Y����́A���̍��A�ǂ����Ă��܂����v
�u���傩�B�c�c�ӂӂӂӁv�ƁA�����͉��O�炵�ď����B�吷������Ƃ��́A��̓��ւ�����Ă��܂������悤�Ȉ���ɗn�Ƃ낯�邱�̘V�����A����Ƃ��������������ŁA�Ƃ̒ꂩ��������セ�̌���������̂������B
�Ⓦ�ɂ��āA�s�ɂ������Ȃ����ق�A�Ɛl���ɂ��ő������̜Е����傤�ӂ��̏�ɍ����A�L�����Ƃ��Ȓ��҂̕��������Ă���坁�������A���̒n�ɁA�����̑���Ȃ��܂łɂ́A���̔����U�ɁA�M�`���̎��߂��̏�ȂǂƂ������̂́A���ׂĎ����̂����ɒ��ߎE���āA�O�ɂ͊��āA�h煂����Ȏ�i����@���A�����̔錍�Ƃ���сA���~�̎�����ݐς��Ă����ɂ������Ȃ��B�N�́A���\�]��A���܂ł͐[����ł���ߋ��̂�����������̕��~�̖鍳�₵�Ⴞ�����З��A�ǂ�������Ɨe�e��ᰂ̒ꂩ��ɂ��ݏo�Ă���B
�u����A����A���̏���ɂ͂ȁB�c�c��������ƍ��ł��A�ǎ��̈⌾���́A�����̌Ïؕ��Ȃǎ����o���Ě����킮�B��قǁA���Ԃ����⍦�Ƃ��Ă���炵���B���̂��߁A�����A����������������Ă����ʁB�nj����ǐ����A�ꑰ�ɉh�̒��ŁA�������A�Ђ����Ɛ\������v
�u�ݕ��ǂ�Ԃ̈�O�ł��傤�B���I�肱���łȂ�����A�Ȃ��A�n�����������ɂ������Ȃ��B�͂͂͂́v
�u��������吷�B���������́A�������������Ӗ��ł��������v
�u�z�B���ɂ��߂�����܂����v
�u���邼��B�\�\����A���̂悤�ɁA�Y���ł͂Ȃ����v
�u�͂āH�@��������Ă݂ĉ������v
�u�߂��������������A���傪�܂��s�ɂ��邤���A�����ւ̖����̂����ɁA�������Ă������ł��낪�B�c�c����߂��A�����֖����A���ė��Ă͖ʓ|�ɂȂ�B�s�ɂ��邤���ɁA���Ƃ��A��������悤�ɂƁv
�u���A�Ȃ�قǁB�v���o����܂��B�\�\�ނ̍����A�܂���ƁA�������Ђ����ɁA�����_���Ă݂͂��̂ł����B�������w�^�Ɏd���������ςł�����ȁB���A�E���܂��Ȃ������킯�ł��B�܂��A���̍ˋC���Ȃ��D�݂�ǂ�Ȑl���́A�A�������Ƃ���ŁA�����f���䂽���ŁA�ǂ��ɂł��Ȃ낤�ƁA������A���ǂ��������Ă�������ł������v
�u����A�݂͓݂ł��A�ޓz���A���������̂́A���������A�s�̟B����ɒǂ��������b�̎q���A�s�ň�ĂāA�܂��킴�킴�Ⓦ�̖�֕����Ă悱�����悤�Ȃ��̂��B�����̔������A���ꂾ���́v
�u����́A���߂��Ă���A�v��ʂ���������Łv
�u�Ȃɂ��A���܂��Ă����ł͂Ȃ����A�����ꂫ�傤�̉��ɂ́A�ǐ��A�nj��Ȃǂ�����K�����̘b���ނ��Ԃ���ďo��ɂ������Ȃ��B���炩���߁A�e�S�ł����Ă����̂��B�����f�������ӂ߂���A�悢�悤�ɂ���������v
�@ |
�����v
�吷�̋A���̕ʉ��Ƃ͂Ȃ��Ă��邪�A���˂Ă͔ނ��E�n��ɏ���������I�ڂ̈Ӗ������낤�B��ɓ���܂ł̐����������B
��o�̌���́A�V��Ȃ̂ŁA������Ɗ�͌��������A�`�����ɏ���āA���邢�����ɋA�����B�ꑰ�̂قƂ�ǂ��A���ꂼ�ꍠ���͂����ĎU�����B�\�\�c�����̂́A�nj��A�ǐ��A����ɂ������x��ė�����̎q���̕}�A���A�ɂ̌ܐl�������B
�L�Ԃ̐C���A����ɏk�߂āA�����𒆐S�A���ւ������Ȃ�������ݍX�����Ă���̂́A�b�肪�A����̎��ɂȂ�������ł���B
�u���傤�́A���̌Z�̒Q���������Ă���ĉ������v�ƁA��̗��́A�����̉�����͒I�ɏグ�ā\�\
�u���N�A�����Ă��������A�Z�́A����ɒD���āA�ߒQ�����Ȃ��c�c�Ƃ������̍��Ȃ̂ł��B����ƈ��܂��āA���C�����Ă��������Ȃ��ƁA�����ʂ����m��܂���v
�ȂǂƐ����ɂ܂����Ă������B
�吷�́A�������āA�������炩�������ɁA
�u�������A�}�ǂ́B�\�\�����ŕ����ʊ��B�������A�����́A���ł͖������ʂ��c�c��t���������������𓊂��悤�Ɂv
�ƁA�������������B
����Ǘǐ��A�nj������́A�킴�Ɛ[���ȕ\��������ď�Ȃ������B���̎��́A�����O���畷���Ă������A���肪�A����ƕ����āA��������ɁA�p�J�������Ă����Ƃ��낾�\�\�ƁA�����������B���傸��ɁA���Ԃ���ẮA���Ȃ��̒j�����܂����A����ƂāA�̂Ă�����Ȃ��B���O�ł���B���Ɋ��X���܂��܂������肾�A�ƁA��N�ł��Ȃ���l�̔N�z�҂ɂ��Ă����A�{���܂������̂������B
���̊ԁA�������A�ނ��������炵�āA�a陂�������w�ł܂�����Ȃ���A�`���A�`���ƌZ�킽���̊��������A�ǐ��̐����I�Ȍ�C�ցA�傫�������Ă݂����肵�Ă����B
����łȂ��Ă��A�T���ɂ���܂�Ă����A�}�A���̌��C�́A�킯���Ȃ��U���o���ꂽ�B�����āA���z�Ȍ�C�̂��Ƃɓ����̑�_�ȍl�������ɂ��o�����B
�u���Ƃ��A���̂܂܁A����������������ł͂��Ȃ��B�ǂ������珫����A�K�E�̒n�ցA���т��o���邩�\�\�ƁA���͂��̖d�͂�������̊Ԃ��イ����l���Ă���̂ł��B�����A�悢��������A���q�b�������ĉ������v
�����𑓔��Ȃ��̂ɒ��߂đi����̂ł���B���̎�C�킩�����A�ЂƂ܂��͗G�Ȃ��߂Ȃ���A���́A�s���Ȉӎu�ɂ����߂����Ă���悤�Ȍ��t���A������nj������̘V�I�ȑԓx�Ɍ�����B
�吷���A�����Ɏ����̎�ł�蓾�Ȃ����������A�}�◲�̎�ōs����A����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��Ǝv�����B������A��������҂̔@��������ɂ���邪�A�헤�����̒��q���j�O�j�炪��������Ȃ�A���͂�ߍ��ł��A���̐��s�������ɁA���������o���҂͂���܂��B���i�m���Ȃǂ́A�ǂ��ɂł������B�\�\�܂��A�����̕����́A�������A�s�A������A����ł��āA�\���H��ɂ�����悢�B
�吷���A����Ȉӌ����o�����B�m���I�ȑԓx�̔ނ��炻��������ƁA�}�����́A���Ȃ̍l���ɁA�Ȃ��m�M���������B��ɁA�����̍H����A�吷�������Ă����Ƃ���A�\�\�ƁA������傫�ȗ͂Ƃ����B
�Ƃɂ����A���̖�A��̖��d���A�����߂�ꂽ���́A�m���ł���B�\�\�v�����s�ɂ��āA�߂����ɋA�Ȃ��Ȃ��吷���A�����������Ƃ��A��Ɏv���A�h���I�ł������B
���̒吷�́A�₪�āA�s�A�����B
�O������l���ւ́A�Ⓦ��т̏t�̖�̗키��炩���͌���ɐ₦��B���R���̋ɒv���A�ۊU���������Ȃ��D��̏\���ɓW�Ђ炭�̂ł���B
����́A�����������R�ɐg�܂Ő��܂��āA���ς炸�A�Ɛl�z�l��サ�āA�����Ă����B
�킯�āA���l���ȂƂ��āA�ق̈�ɁA���̋j�[�̑O�ƁA���̂悤�Ȋy�����V�ƒ��t���ȂłĂ���́A�Ȃ��悭�����A�悢�ǐl�ɂȂ낤�Ƃ��Ă����B
����ƁA�܌��̏��{�͂��߁B�����X�����Ƃ����̓��ł���B
�Γc�̑�f���A�坁��������A����Ȏg�҂������B�����āA���制�ɁA���ʂ��������B
��Ђ炢�Č���ƁA����̕��ǎ��̖@�v���c�݂����Ƃ���������B
�u���B�c�c�����S�������̏\���N�����v
�ނ͂ӂƁA䩂Ƃ��āA������ڂɂƂ��ꂽ�B
�\�\���́A�܌��l���B�ꏊ�́A�V���S�̑�B
�ꑰ������āA�ǎ��ǂ̖̂@�v���c�ݐ\�������B�ق��Ȃ�ʌ̐l�̂��ƁA�����������Ƃɂ��A�����ߏ�͐��ɗ����āA���Ќ�ՐȂ��肽���B
�Ƃ����Ӗ��̕��͂ł���B
�u�c�c�Q��܂��B���͑[�����Ă��v
����ɗ܂��������B�Ԏ����������߁A�܂��A�g�҂��ł����ƂÂ����B
|
���K���ȕS��
�j�[�́A�l���̎����āA�ʖт܂����Ȃ����ɁA�J�킵�������Ƃ߂��B�V�Ȃ炵���A�܂��A�ǐl�ɂ��A�ǂ����C���˂��������Ă���B
�u����������Ȃ���A�����Ȃ��̂ł��傤���c�c�v
�낵�ڂɂȂ��āA���ꂾ���������A�ǂ����������Ȃ��p�Ԃ��Ȃł������B
�����ƂȂ����B
�j�[�́A�܂��A
�u�ǂ����Ă��A�����łɂȂ�Ȃ�������܂���́c�c�H�v
���ƂƂ��ƁA�����悤�ɂ������B
����́A������ƁA�����d����߂ā\�\
�u����Ȏ����A�V������߂��肬�ʂ́A�D�킵�Ă������̂��B�т��v
�u�����c�c�B�䑕���́A�݂ȁA�����Ă��܂�����ǁv
�u�Ȃ��A����ȗ҂����������̂��B�\�\�j�[�A�悹��A����Ȕ߂������ɁA�ʖт��ӂ�킹��̂́B����܂ł��A�߂����Ȃ��āA�������A�s�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��v
�u���˂����ł�����c�c�v
�j�[�́A�����ꂽ�ǐl�̎�̍b�ցA�G�ꂽ�ʖт��A�Ђ��ƁA��������B
�u�\�\����������Ȃ��ʼn������B�l���̌�@���ɂ́v
�u�ǂ����Ă��B�Ȃ��v
�u�ł��c�c���A�S�z�łȂ�܂���B�������A��ɒ킽�����A�����A���Ă��\���āA���ցA�������āA���~�߂��Ă���Ƌ����Ⴂ�܂��v
�u���������H�v
�u�������B�����l���A�����l���v
�u�V���̑�Ƃ����̂ŁA�G�n�֍s���悤�ɈĂ���̂��낤���A�헤�����̑��q�����́A���̖@�v�ɂ͊ւ�͂Ȃ��B�H���␅��̏f�����͌����邾�낤���A���ꂳ���A�����ɂ������炦�Ă���Ύ��͂��ށB�\�\������A�]�l�̔N���Ȃ�����A�S���ǎ��̂Ɛ\����ẮA�ǂ����Ȑl�Ԃ��W�܂��Ă��Ă��A�s���ʂ킯�ɂ͂䂩�ʁv
�u�����l�̌��Q�ł͂����܂��v
�u���̂̂��ꂪ����̂ɁB�c�c��ɂ́A�ق�ƂȂ�A�@�v�͂���̖��������ĉc�܂˂Ȃ�Ȃ��Ƃ��낾�B�c�c�ȁA�����ł��낤���v
�u���A���v
�u���̓�A�O�N�́A����͂����A�Ɖ^�̔҉�ɁA���䖲���������B�N����A�c��֏o�āA�z�l�Ƌ��ɁA�y�ɂ܂݂�A��ꂽ�g���A��������Ɓc�c�j�[�A���܂��̖�����݂Ă�����B�c�c�����A���̓������܂��A���̂�����A��̖����y���݂ɁA�����O�N�͕邵�Ă����v
�u�c�c�����B�c�c�����ł��v
�u��l�̖����A�������ꂽ�B���̓����炬�̖邩��̍K�����B�c�c����͍��A�����A�����ς��Ȃ�A���̍K���Łv
�u�ł�����A���̈����������A���܂ł������Ă䂯��悤�ɁA�����Ǝ���Ă������̂ł��v
�u���Ƃ�肾�B�c�c�����A����ȍK���ɁA�����S�����A�b�܂�Ă������̂�����A�܂������A�S���̏\���N�̔N���ȂǁA���̂����ɁA�v���o��������Ȃ������̂��B�s�F�Ƃ����Ă��d�����Ȃ����A�������A������́A�m���Ă��Ă�����B�c�c��邵�ĉ������Ă���ɈႢ�Ȃ��v
�u�c�c�c�c�v
�u����́A��Ƃ́A����m��Ȃ������ɕʂ�A�������N�̓��Ɏ��Ȃ�Ă��������B���������ُZ���������܂��ł́A���̕��ւ��A�Â�����͂Ȃ��ĕʂꂽ�B����ł���Â��Ă��������낤�Ǝv���Ă���̂��B�ȁA�j�[�v
�u�ł�����A�����̌�@�v�ւ��v
�u�s���ȂƂ����̂��B�����A���ƂȂ��ẮA���ƒx���B�s���ƁA�ԏ������Ă���̂ɁA���̓��ɂȂ��āA���ꂪ�p�������Ȃ�������A���a�������т傤�����ɂӂ��ꂽ���ƁA�����ŏ��ǂ�߂����낤�B�S�������ǎ��悵�����̒p���B����͍Ⓦ�����̑��̂��B�s�����ł��v
�j�[�͂����~�߂邱�Ƃ��������B�܂��A��������������ǐl�̒j���炵���ɂ���Ђ��ꂽ�B�����悤�Ȗ��͂ɜ����ƂȂ��Ă��鎩���ɂ͂��ƋC�������B�����Ă��̖��͂���r�̂Ȃ��ɁA���̖���A�K���Ȗ���A�����̂܂܂ɖ������Ă��܂����B |
������
�u�s���ė��邼�v
����́A�n����A�Ə゠�傤�̐l�ƂȂ��āA�ق��o�čs�����B�n�̏ォ��U������āA�Ɛl�̒��̐V�ȂցA���邢�ꌾ���c�����B
�����ғ�l�ɁA�Y�}�\�l���肵���A��Ȃ������B
�����ܔN�̌܌��l���������B
�����̐V�̕����A�u�₩�ł������B�\�\�L�c�̒��Ƃ�ʂ��čs���B���̘V�c���A����ĂĔn������A���̂��������A�Ă��˂��ɂ���B�\�\����́A
�u���Ƃ܂���̌˖������Ƃ��A�Ђƍ����́A�悭�Ȃ����B�F�̂ӂƂ���H�����A�����͕x��ł������ȁH�v�ƁA�Ȃ��߂��B
��ւ́A�L�c���牺�삵�����X�����A�і�삯�ʂ���ɉ����čs���B�\�\�ƁA�ǂ̕ӂ���]���ė����̂��A�����납��b�h�������イ�𒅂�����������B��ɏ���̋��݂����ɂ��ė����B
�u�͂͂��A�틤�̎蕺���ȁv
�������A�������A�������B����Ƃ��݂ȑ����Ă��B�Ƃɂ����A�������S�ɈĂ��āA���c�̌��ʁA����ė����ɂ������Ȃ��B���肪�����A���ꂵ���z�炾�B����܂ł̐S���Ɏ����Ēǂ��Ԃ����Ƃ��Ȃ��B�\�\����͒m���Ēm��Ȃ��U������Ă����B
�Ƃ��낪�A�쐼�̖�܂̂Â߃����͂�ɂ�����ƁA�т悵�∰������A�܂��Ⴂ�u�̋N���̔ޕ��ɁA��������ȋ|�̐悪�������B�g�̐������߂��Ă���B
�u�͂ĂȁH�@�c�c������A�킩����v
�Ƃ̏ォ��A�L�яオ�������A���̂����A�Ђ���ƁA�ւ�ȉ����������߂��B�V���b�A�V���b�\�\�ƁA������̑��ނ�ւ��A�����̖�A������ڂ��A��ɐ킻�悬�������B
�u����A�g������Ȃ����v
����́A�V���āA�ǂȂ����B
�u�ȁA�Ȃ�B���̐l���́A�����A�l�Ⴂ���Ă����Ȃ����B�����[���A�L�c�̏��傾�B�ԈႦ��ȁA����͏��傾���v
�ނ͂܂��C�����Ȃ��B�g�́A�����̎�߂ł���B��̈���������炻��܂łȂ̂ɁA�ނ́A�܂��A�킴�ƕW�I�ɂȂ�悤�ɁA��������U��ʂ��Ă���B
�������݂ȌZ�B���l�悵�ȌZ�B
�ނ���A�G�̕��������A����ɕ����������悤�ɁA�����납��A�S�b���҂���R�A
�u�Z�Ґl����ЂƁA���ԂȂ��b�v
�ƁA��ǂȂ�Ȃ���A�ނ�ǂ��z���āA�ޕ��̋|�̌Q������Ď������čs�����B
����ƁA��R�̉�������āA
�u�����A�����A�����v
�ƁA�ݏd�Ȕނ��悤�₭���Ԃ̂������łȂ��̂�m�����B
����Ƃ܂��A�����ォ��A�������n���Ƃ��ė����B�����āA
�u�Z��A�Z��B�����A������������Ȃ����v
�ƁA��̂̋������āA�n���Ƃэ~�肽�B������A���Ē��э~�肽�B
�u�����B������������͉��҂��v
�u�m�ꂫ���Ă���܂��B�\�\����̑��q���ł��B����A���̌R���̑����������Ȃ����v
�u�ȂɁA�}��A�����Ɓv
�u�����A�ǂ����āA����Ȃɋh���т�����Ȃ���̂ł��傤�B�j�[�ǂ̂��A�قւ��}���ɂȂ�O�ɂ́A�Z�ケ���A�������ցA�����鎖�����邼�ƁA�o����������ɂȂ����ł͂���܂��v
�u���B�c�c����́A���̏�̎��B�c�c���傤�̓r���́A�ق��Ȃ�ʕ��̖@��ق����̓��ł͂Ȃ����v
�u�Z���_���Ă���G�ɁA�����A����Ȝ݂͂��肪������̂ł����B���������A�l������āA�T�点���Ƃ���ł́A���̖@�v���R�ł��B�Z���ۂ�Ȃ��U���o���āA�ꋓ�ɁA�����Ă��܂����Ƃ��������̖d�v�ł��B�Ȃ��A�����^���]�n�Ȃǂ���܂��傤���B�\�\���A�Z��v
�����́A��̒����݂���`���āA�Z�̑̂��A���̈Ƃ̏�ցA�����グ��悤�ɋ}�������Ă��B
��͔��ŗ��Ȃ��Ȃ����B�������A�ޕ��ł́A���������ɑ������L�c�̘Y�}���A�G�Ƃ̊Ԃɔ�������N���Ă����B
����́A�Y�}�̒�����c�Ƃ��āA
�u�����A�䖝���Ȃ����B����́v
�ƁA�D��ւނ����āA�ꐺ�����߂����B
|
����܍���
�ЂƂނ�̂��₫�т�����B
�������т̂��鏊�ɂ́A���Ȃ炸�Ƃ�����A�������Ȃ��Ă���ƌ��Ă܂������͂Ȃ��B����͌���̏Z�������߂ɖh���тƂ��ĐA�����W�c�����̚Ԃ����ł���A����ȊO�̎G�ؗтƂ́A�����̂�����p���������Ă��邩��ł���B
���n�̈��̊Ԃ�D���A�܂��A�L���쌴���킯�A�����킯�A�ꂷ���̓y���ނ���g�����R���̌Q�ꂪ�A���A�z�����܂��悤�ɁA�����̟O�т��₫�₵�̈��ɂ����ꂽ�B
�u���邼���A���邼�B���傪�v
�u�₪�āA�쒖�̂����̂悤�ɁA�P����ė��悤���v
�u�������B�\�\�p����v
�і��̓����A�������̈�w�Ƃ��A�����̟O�т��w�Ƃ��āA���}�A�������Z��̕��́A��i���܂��ɁA�����܂��ӂ����Ă����B
���̑�������߂��ė��������̋R�n�����́A���������̖����ւ������Ȃ���A�����̒��̈�ԑ傫�ȉƂ̑O�֗��āA�y���̒��ցA�n�����������ꂽ�B
�u�ǂ������A����́v
�����ɂ́A�}�Ɨ����A���X�������������āA��҂��Ă����B�����̘Y�}���A��\�����܂��ɏ]���A�܂�ŁA�叫�̖{�c�߂����������ł������B
�u���܂��s�������B�ޓz���A�܂Â݂ɂ��āA�퓬�����v
�Z�ƈꂵ��ɁA��̗����A�����̎҂ցA���������˂��B
�܁A�Z�l�̕����̒������l���������B
�u�͂��B����͍��A��܂̂Â߂̏��Ƌu�̊ԂŋN���Ă��܂��B�\�\���A����́A�v���ڂƂ͐\����܂���B���Ԃ�A����̕��ɂ��A�p�ӂ��������悤�ł�����v
�u�ȂɁB��ɂ��A����̔������������ƁB����͂ւȁH�@�c�c�B�܂����A�������̌v����A���ʂ����҂��Ȃ����낤�Ɂv
�u�ǂ����A����܂��A�Ƃɂ����L�c�̘Y�}���A����̎p���A��������āA���Ƃ�������Ȃ��ď]���ė��܂����B�\�\�ł�����A�����̏����ł́A����Ƃ���������Ă��A�܂Â݂ɁA����ȂǂƂ������͂ł��܂���v
�u���܂����B����ł́A��͂肠�����ꃕ���ɁA��������ŁA�����Ă���悩�����̂��B�\�\���āA��̂��悤�́v
�u������A���傪�A�{��o���܂����̂ŁA�L�c���̋����Ƃ������炠��܂���B����ɁA�����A�����ȂǁA����̒킽������ɂȂ�A�������́A�킯���炳��Ă���L�l�ł��v
�u�ł́A����ȁA�������ցv
�u�K��Ђ��傤�A�������̕��ꗧ���ė�����ցA�ǂ��炢�A�ǂ��炤�āA�P���Ă���Ǝv���܂����v
�}�́A���炦�Ă���ӂ������A��̉��ɁA�ӂ邦�������A����A�d�����Ă����B
���́A�������āA���������B
�u��������Ȃ����B�������̍��ǂ��肾�B�����ɂ���w�̕����͂Ђ��߂Ă���B�킴�ƁA�����ւ炵�āA�ޓz���A�����ɂ���������A�l�����������āA�Ă��E���Ă��܂������v
�����̉�����荂����ř��҂��������B�O�j�̔ɂł���B�ɂ́A�O�̑����爂��ׂ�~��Ȃ��炢�����B
�u�і�ׂ�̕�����A�^�����ȂقǁA�y�ڂ��肪�A�����������āA�킯�ė��邼�B����ƁA�L�c�̓z��ɂ������Ȃ��v
�y���̒��́A���R�ƎE�C�������B�}�����́A�n�̔w�ɒ��т��ƁA�����܂��ǂ����ցA���苎�����B�Y�}�������A��ɂÂ��A�c�����҂́A�I���ɁA�ƁX�̈��ɁA�g���Ђ��߂��B
�₪�ēy�������ނ��̉^��ŗ����l�����n���̉����A�O�т̒��ɂ����ނ�o�����B����Ƃ��̉Ɛl�ɒǂ��ė����}���̕��������A������e��Ƃ̂悤�ɁA�������������֓����܂ǂ��̂ł������B�����Ă��ɂ́A�G�̈�e���������A����̂́A����ɂÂ��ė��������⏫���A���̂ق��A�L�c�̘Y�}�����ł����Ȃ��Ȃ����B
|
���������閡��
�������ɊF�A�킢����āA���Ɠy�ɂ܂݂ꂽ�p���A������ݍ������B����̋�ɂ��A������Ă���B
�u�����ǂ��ȁB���ꂭ�炢�ɂ߂Ă��A�����肽�낤�B���̍L���D��A�ǂ��܂ŁA�ǂ����܂����Ă��A�ʂĂ͂Ȃ��v
����́A�n���~�肽�B�������݂��������̂ł���B�ƁX�̊Ԃ��A���̔�Ƃ����ʂ��Ă���B������⨂����Ђ̗������ցA����悹�Ă����B
�������A�Z���܂ˁA�Y�}�������A�r�̂܂��ցA���ݍ������B
����ƁA�������A���ӂ����B
�u�₠�A�Z�Ґl�B����ɂ��A�n���~��Ă͂����܂��B���ԂȂ����ԂȂ��v
�u�Ȃ����B�����v
�u�����Ȃ����B�ǂ��̔_�Ƃ��A�Ƃł��B�������B�@����Ƃ���A���܂ŁA�G�������ɂ������Ȃ��B�l�������������|�ꂪ����܂��傤�v
�u��A�������v����́A�}���ŁA�n�����B�����́A�ӋC�n�̂Ȃ��A�C��ȏ����Ǝv���Ă������A���̏������A���傤�͎��������A�������Ă��邵�A�悭�����ɋC�����̂ɂ́A�������ꂽ�B
�u�����A��֏o�܂��傤�B�������ǁX�A����ė��܂��傤���A�����̒��ɂ����܂�̂́A�����ł��B�����������Ȃ����v
�u�I�I�A�����ʂ肾�v
�}�ɁA�l�����܂Ƃ߂āA���肩�������A�������s�������Ă����悤�ɁA�������̍s���́A�x�����Ă����B
�ƁX�̋����Ԃ��獕���������A�����킯��A�ǂ����֏o�Ă��A���̂܂ɂ��A�R�̂悤�ɁA�Ă��ς�ł���A�Ă̓p�`�p�`�ƁA���͂��Ă���B
�̊ԁA���ނ�ւ����A�������o�����B�܂��A�̊Ԃɂ́A���n������A�����肵�Ă��鏊�������āA�n������̂͂��납�A�k���ŋ킯��̂��A�낤�����Ƃ��̏���Ȃ��B
�u�C������B������ɂ��A�܂��G�̕�����������炵�����v
����ɓ�����悤�ɁA�����邨�Ƃ��Ȃ肪�A�l���ɋN�����B����D���A���������߂āA�ԁX�ƌ�����l�e�ɁA����ł���B
�u���A�Z�Ґl���v
�u����B����v
�Ăт����A�Ăт����A�����ʓG�Ɛ키�f�r�ق��������J�Ԃ������������B���ɂ��̖�ܑ��̊��v�́A�Ȍ�̏���̐��i�ɑ傫�ȕω��𗈂������߂��قǁA�ꂵ���Ղ����Ȃ݂Ɗ�@����v���ɒǂ��߂�ꂽ���̂������B�����Ĕނ͊��S��㩂�ȂɊׂ����`�ɂȂ����B���܂͂���܂łƁA�ϔO�����ɂ����Ȃ������̂ł���B�Ɠ����ɁA���傤�܂ŁA���Ɋ邽�����ł����}�����́\�\�����f���̍����̖����ȂāA���₨���Ȃ����������т��o���ɂ������ޓ���A�̐l�ԋ��ɂ������āA�{���̓{��ɔR�����̂����̓��������B�{���ǂ͂V�Ă�����Ƃ����`�e�͉Β��̔ނ̌`�����傤�������̂܂܂ł������낤�Ǝv����B
������ނ͂����Ŏ��ʖڂɂ������킯�����A������̙F�������B����́A�і�ׂ�̗����ŁA�Z�̎p���������A���̂��߁A���֖z�͂����āA��̂����̏�����l���A���̉Β��ɂ��Ȃ��������ł���B
�����́A�ׂȓG��ǂ��āA���p�������킯�Ă������A���������̂ŁA��U�ɂ����킯���ė����B�����ē��̏�V�����傤�����Ԃ�A�̎Ă������āA�����̒��̌Z�������A�Β�����~���o�����̂ł���B
�u�������B���₤���A����͎��ʂƂ��낾�����B�悭���Ă��ꂽ�B����͐������v
�u�ǂ��ɂ��A�������Ă����́v
�u��̓��O�A���̂��Ƃ͂Ȃ��B�\�\����͐������B�킽���A���Ă���B���ꂪ�ǂ����邩�v
�u�\�\���A�Z��B�����͈�x�A�L�c�ֈ����g����������낵���ł��傤�B���Ƃ����Ă��A�G�́A�[���A�p�ӂ������ďP�������Ă���B�������́A�����̂Ȃ���ł�����v
�������|�����߂��A����̓{����Ȃ��߂�ɂ͑���Ȃ������B�ނ́A�f���āA���̂܂܁A�L�c�ɂ͋A��Ȃ��Ƃ�������A�Ɛl�Y�}���W�߂āA�ꂽ�Ƃ�ۂƂ�A���̊ԂɁA��@������āA�}�◲���̂��鏊��˂��Ƃ߂��B
�}�A���A�ɂ����̏헤�����̕��́A�������甼���قǓ��̖쎛�̂ł�ɐw���Ă��邱�Ƃ��������B�܂��A�����ɂ́A�헤���̎O�Z�����łȂ��A����̏f������̗ǐ����A�萨����ĉ�����Ă���Ƃ������B
�u�݂�B�z��́A����̏f�����ƁA�^����ł���̂��B�ǂ�Ȏ�i�������Ă��A������E�����ɂ͑[���Ȃ��C�ł���ɂ������Ȃ��B���ꂪ�ނ��A�z��́A�L�c�܂ł��A�ǂ��������ė���ɂ��܂��Ă���v
����́A�ߑs�Ȍ꒲�ŁA������̈ꑰ�����ւ������B
�u�قցA�|�Ă��Ă���������A�������̕������B��������A����́A�L�c�̕S���⋽���Ƃ̖����A�z��ɁA�����ꂽ��A���D��Ⴍ������āA�����܂ǂ��̂��A���Ă͂����Ȃ��B�\�\�������ƂȂ�A����������U�ߍ��߁B�z��̓y�n�̊قł����Ƃł��A�Ă������Ă��܂��v
�ނ͂����n��ɂȂ��āA���C���������̎p���A��ɐi�܂��Ă����B���߂́A�S�܁A�Z�\�l�̏����ł��������A�і�ׂ�̎����������L�c�{���֒m��n�����̂ŁA�ォ��ォ��A����̐g���Ă��ċ킯���ė���҂��₦�Ȃ������B
�ق̉��l�����ׂ���A�����ƂɏZ�ޒn�������ނ炢�Ƃ������ނ̎҂܂ŁA���悻��������헤�����̈ꑰ�ɁA�����������Ă��邩�A���邢�́A�툳���I�ȗ���ɂ�����Ă���҂ȂǁA���݂��ɁA�Ăт��������āA
�u��܂֍s���B����a��������v
�ƁA�̎�����āA�W�܂��ė����B
����ɁA���Ƃ�肱�̒n�����A���ẮA����̕��ǎ��̋��̂ł���������A�坁������A�ǐ��A�nj������̑��N�ɂ킽�鈫�s��ŁA�Ђ����ɏ���ɓ�����悹�Ă����҂����Ȃ��Ȃ��B
�����̐l�X���A���ׂāA
�u��܂ɁA���킪���邼�v
�ƕ����ƁA�j�����܂Ƃ�����A�T�r��������������A�܂��A�Ƃ��Ȃ���n�̔w�ɂ܂������āA���ŗ���҂����������B
�����āA�₪�ď���́A�G�̓Ԃ��ނ�ƌ����쎛���߂����Ă��悢��U���ɂ����������A���̎��A�ӂƐU������āA���߂��͓��R�A�����Ă��Ă悢���̐l�����A�������ĉ��{�ɂ��B���Ă���̂ŁA����ɂ͏��厩�g���A
�u����A�ǂ����āA����ȂɁA����̂�����ɖ���������̂��v
�ƁA�傢�ɋ������Ƃ������Ƃł���B
�@ |
���R��
���傪���߂ɋ������̎�ł͂Ȃ��B
���㌹���̂�����B���A����̏f���̑坁������ǐ��A�nj��ȂǂɁA���܂��������̂�����āA��܂ɑ҂������������́\�\���s����傫���Ȃ�����ł���B
�܌��l���Ƃ����Ă����ߍ��̐^���܂��݂̋�ɁA��������n���ނ�≊���������̂����āA�Ⓦ����ɏZ�ށA�����Ɍ��n�I���i�����l�Ԃ������A
�u������A���킾�v
�ƁA�����藧���āA����ڂ��ĂɁA��̏\������A�킯�o�������Ƃ́A�������ɁA�����̍L���y��ɂ��߂����ɂȂ���ٕςł������B
�������A���̋킯�o���҂̂قƂ�ǂ��A�D���ȏ헤�����̂�����B�̐w�n�֍s�����A�L�c�̓a�ׂ̈Ɂ\�\�ƁA������ւ����Ƃ��������A�ނɂƂ��āA�K���A�s�K���A�킩��Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A���̂��߁A��R�A����͗D���ƂȂ�A�قƂ�ǁA�ނ̎v���܂܂ɁA��͏����Ă��܂�������ł���B
���̏��������܂��A���ɂЂǂ������B
�}�����̖쎛�̐w�́A�₪�ď���ɂ��ĉ����P�悹���Y�}�Ɠy���R�̍U���ɉ���āA���x��������̉��ɂ���Ă��܂��A�ב�����}�����̕��������\�l�ƂȂ������ꂽ�B
���̒��ŁA�C�̂悢�������A��ɂ������āA�����������A�܂��A�O�j�̔ɂ��A���������Ȃ��āA���������B
�����Ȃ�ƁA��b�������ҕ��́A�Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ����A���A���厩�g���A���{�ӂ�ʂ̌��������̔@�����̂ł���������A�����A�헤�̂։z�����A��܈�т���łȂ��A����A��Ȃǂ̋����Ă����āA�헤�����̗^�}�̑�ɂ���A��������o������A���q��j���āA���Ƃ��l�����肵�āA���ɗ��������X�����A�G�n���r���Â��A���͈̔͂́A�}�g�A�^�ǁA�V���̎O�S�ɋy�B
�������A���̏P���ŁA����̑���̊ق����A�Ă������A���̂����A���ɁA��̒��q�}���A�Β��̐킢�ŁA�����Ƃ��Ă��܂����B
����B�_�@����т́A���ꂾ���Ɏ~�Ƃǂ܂�Ȃ��B
�坁�������A���Ă���킯�ɂ䂩�Ȃ��̂ŁA����։����ɒy������r���A����̂��߂ɁA�Ԃ蓢���ɂȂ����B���̏�œ��������̂ł͂Ȃ����A�������āA�ꂽ��Γc�̋��ق܂œ����A��A���̔ӁA�ꂵ�݂ɂ������˂āA���Q���ĉʂĂ��̂������B
���̂ق��A����̑O��j�͂߂���A�G�����肵������������̏��₵�����́A�ЉƂ��Ⴏ���́A���Ƃ��́A�����q���́A�Ă����Ă����͂����m��Ȃ������B�u�ËL�v�ɂ��ƁA�œy���傤�ǂƂȂ���̌ܕS�ˁA�l�{�̎��������т��������A�D��̋�������Ԃ邱�Ǝ�������ɋy�Ƃ����B
�ȂāA�����ɁA�{��鈢�C���̂��ꂩ�����A�Ђǂ����̂ł��������A�z���ɓ�Ȃ��B
�����炭�́A�����̂��ƁA��J��������߂��������āA�������A���Ԃ�R���Ă����D��̉����������ꂽ��ł́A������A�M����������̌ւ�����߂āA
�u�c�c���ƁA��肷�������ȁH�v
�ƁA�����̂������Ɏ�����䩑R�Ƃ�����������Ȃ������B
����ǁA����Ȍ�A�L�c�̊ق́A�Ɛl�Y�}�ŁA�[�����Ă��܂����B�ނ�͂�������ɏ���̌ҍn�������ł���A�Y�}�ł���Ƃ��߂āA��̉Ƃɂ́A�߂�Ȃ������B����ɐb�����邱�ƁA���ǎ��̂悤�ȗ���Ƃ��āA
�u�킪�A���فv�Ƒ��̂����B
�����Ƃ��A�헤����M������Ƃ��ɁA�G�n�̔n�́A���S�����g���ė������A���̔n�̔w�ɂ́A�����A�H�ƂȂǁA�ς߂邾���ς�ł����B�ނ�ɂ��킹��A
�u���N�A�킪���ق̐��ǎ����܂̑����c�̂��A���ǂ肵�Ă����l�Ԃ̕����B���ꂭ�炢�́A�N�v�Ƃ��Ă��A��グ�Ă��̂�����܂����v
�ƁA�����̂ł���B
��܂̍���̌��ʂ��A�₪�Ďl�ׂɂ܂ŕ����킽��ƁA�v�������₦�Ă������������̉��ނ܂ł��A���̂��̖L�c�̈ꑰ�Ɩ��̂��āA���g�������K�˂ė����B�����Č����ɂ߂āA
�u��������̂��A���R����B����́A�a�a��ǂ̂��܂���S���ǎ��ǂ̂̌v���ł���v
�ƁA�폷���傤���j�����B
����牏�ނ̉Ƒ����A�܂������A�L�c�̊ق̕��߂ɁA�����ׂďZ�ݎn�߂��B�L�c�̋��͂����̔N�̂��тꂽ�����݂ł͂Ȃ��A���˂��s���ɏ��������n�߁A���̒n���̏���s�炵���u�������悵�Ă����B�Z���̑��h���܂��A����̈�g�ɂ��܂�A���܂�ǎ��̂��肵�������̂܂ܖL�c�̊قɂ͂߂���҂��ė��邩�Ɍ������B
�헐�̌��ʂ́A�����܂��A�L���y��̈ړ��ɂȂ��āA����ꂽ�B�헤�����̑唼���A�������̎x�z���͂Ȃ�āA����̉��ɋA�����ė����̂ł���B
�y�Ɛl�̗����́A������������������A�`��ς��Ă䂭�B�܂��āA���ẮA���X�A�L�c�̂ł������y�n�������A�l���܂��A�ǎ��ɉ��̂̔y�Ƃ����炪���������̂ł��邩��A���̋A���́A���R�ȍ�p�ł���Ƃ����Ȃ����Ȃ��B
�������A�헤������}�g�̗ǐ��A�nj��Ȃǂ��猩��A���Ԃ͍����ł��Ȃ����̂ł������B��ɗǐ��̂��������_�I�ȑŌ��́A�Ђƒʂ�ł���܂��B�ނ́A���̑厖�����Ђ��N�������̐����҂Ƃ��āA���ɁA����̉��ق���₩���ցA�Ӎ߂ɏo�������B
�u���Ȃ炸�A���̏�����āA��q�����̂�����݂��͂炵�܂��B����߂��A���c�ɂ��āA���̓��������˂A���̋��������܂�܂���v
�\�Ղ��S�Ղ��A�ǐ��͏��ɂЂ�����������āA��ɎӍ߂����B������A�l�т́A�����Ƃ����B
��́A�ق��Ă���邵�A���q�����O�l�́A�ꎞ�ɁA��v���Ă��܂������A����ɘV��Ȃ̂ŁA�Ă��o����̉���������Ԃ���̒��ŁA���̂Ƃ���A�ڂ��ƁA���E���Ă����B
�u�킵�̐g�ɂȂ��Ă��ꂢ�B���O����B�������O����B���㌹���̕��������āA��ʂ��Ɉς��Ă��������A���̏��傪���Ă邩��A���̏��傪�v
�u���ǂ̂��ꂽ���̂ł��B�����ߓ��́A��q���������A�]��ɂ��A�ނ����܂����߂������߂̕s�o�ł����v
�u����ɂ��Ă��A�ǂ����āA�Ȃ��A������B���A����ƁA���̂悤�ɁA����˂Ȃ�Ȃ������̂��B���܂́A���X���Ƃ��ƁA�������Ƃ����f�����̎��Ƃ���v���Ă����ɂ�B�c�c���ꂾ�����A�킵�ɂ͂Ȃ��A������l���Ă��A�������ʂ��v
�u����A���A���̎��͂ł��ȁv�ƁA�ǐ��́A�ꂵ�����Ȋ�����āA�z��}���\�\�u������܂��A�܂����āA����ƁA���͂Ȃ��������܂��B����ɂ́A�[���e�ׂ�����A��Ж�́A���Ƃ��A���@������܂����v
���ǂ���ǂ�ɁA�������낢�A���X�A��̑O�𗧂��������B
����B�\�\�ނ͋��s�ցA���n�𗧂āA����������āA���x�̎����ƁA�坁�����̉������A���܂��܂ƍ����̒��q���Ⴍ���吷�ցA��点�Ă������B
�吷�̋����́A�����܂ł�����܂��B
���捠�A�ʂ�ė�������̘V���̎��B
�܂��A�����̉E�n�i���A����Ȃɂ��A�L���V�ɁA��낱��ł����V���B
�\�\�����A�l���Ă݂�ƁA�]��ɂ��A�g���g���̂����Ȃ���A�v���������āA�l�̐��̒����A������̈ӂ̂܂܂ɁA���܂����߂��Ă������ʂ̉Ђ��ł������Ƃ��A�吷�́A���Ȃ����ɂ������Ȃ������B
�Ȃ��Ȃ�A�s�A�鐔���O�̕ʂ�̉��ŁA�V���̍�����A����̏f���nj��A�ǐ��Ȃǂ�����Ă������Ƃ́A�]��ɂ��A���菟��Ȗ]�݂ł��舫�邾���݂ł������B�����瓯���̕���ޓ����������Ă��鏫��ł��A���������傪�s���ӂт�ɂȂ邭�炢�A���ӂɂ݂����A�A�d�̉�ł������B
�u���̂Ƃ��A�悭�A����Ȋ�݂́A�~�߂Ă����悩�����B�\�\���A���������������B�������A�E�n��C���ɁA�܂����������C�ł����Ƃ��낾��������v
���͂Ƃ�����A�s�A��������ł��邪�A�ӂ����ыA�����Ȃ���Ȃ�܂��ƁA�ނ́A�q�c���������ƁA���֎��Ɋ肢���o���āA�܂�����A������V���ɂ����B
����̗ǐ��́A�s����吷���A�����ɂ��ł���ė����ƕ������̂ŁA���������A�Γc�̊قցA�ނ������˂��B�����āA���Ƃ��C�̂ǂ������ɁA
�u�c�c�ǂ����A���̂��т́v
�Ƃ���������ŁA������ƁA�Ȃ����߂錾�t���o�Ȃ������B
�吷�́A�����Ŕ��Ă������낤���A�ǐ��ɉ�ƁA���Ƃ������Ȃ��s�����Ȋ�����߂��A
�u�f����B���炢�������܂����ȁB���Ƃ��A���Ȏ����\�\�B���������A�ǐ��ǂ̂́A�V���̂��ɂ��Ȃ������̂ł����B����ȘV�l���A�擪�ɂ������āA���Ȃ���nj��a�́A�ǂ����Ă�����ł����v
�ƁA�܂��������āA���˂������肬�݂ɂȂ������B
�u������Ă͂��܂�v�ƁA�ǐ��́A�����̂��悤���A�Ԃ��ɐ������āA�u�悹�����̂ɁA����ǂ̂̑���̊ق����₤���ƕ����āA���̌�C�����c�c�~�߂���������ɔn��y���A����߂ɁA�˂�ꂽ�̂��v
�u�˂��̂́A����ł����B�������Ɂv
�u�������B����́A�f���E��������B�\�\�h�����ȁB�����Ȃ�̂��v
�u�ǂ����āA�h���ł����v
�u�l���Ă��݂邪�����B���傪�A�܂��A�s�ɂ��邤���ɁA�т��A�����ɁA�������s���Ă����ł��낤���c�c���ꂪ�A�����֖����ɋA���ė��ẮA���Ȃ炸��ɉЂ����Ȃ��ɂ������Ȃ�����A���Ƃ��A��i���߂��炵�āA�����ɁA������E����߂Ă��܂��悤�Ɂc�c�Ɓv
�u����́A�V������������Ă������A��������A��x�A���Ȃ��̂��莆�ɂ�����܂������A�s�̂����ł́A�����₷�₷�ƁA�ނ��E���悤�ȋ@��Ȃǂ͂�����̂ł͂���܂���B�c�c�܂��āA����́A����b�ƂɎd���Ă������Ƃł����A��ɂ́A�֖�̑���ɂ����āA���͂ł́A�߂����ɁA���̒吷�̎�ɂ�������҂ł͂���܂���v
�u����A�Ȃɂ��A�������A������ʂ��Ȃ��������Ƃ��A�������s������A��߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����A�����܂ŁA�s�������l���Ă��Ă������Ƃ��A�����A�����������ʂɂȂ������Ƃ��A�h���Ƃ͂������܂ł��c�c�v
�u���̕s�K�̒��ŁA�����A���X�A�f����ƌ��܂�����������܂���B�ǂ������ł��n�܂�Ȃ����Ƃ��B������́A��X���Ƃ��Ƃ����v
�u���B���̌�X���A�e�ՂłȂ��B�������A���������̑����₨�Ƃ̎��c�܂ŁA�L�c�̏���ցA�D���Ă���B���Ƃ��A��܂�����̕S�����A�ȗ��A�܂������A�헤�����ɂ́A�w���ނ��āA���ɂ��Ă��A�L�c�֑����ނ��Ă䂭�v
�u����́A���������ł��ȁB������܂ʂ�����c�c�v
�u�������A���O�N���o�Ȃ��܂ɁA�Γc�̗̂́A�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B���Ƃ��Ă����Γc���N�����A����̐����H�����A����߂ɁA��������Ă���͓̂��R�B�吷�ǂ́A�������肵�Ă���v
�����̌�B�\�\�吷�̖��������āA��ł́A�坁�����̑��V���s��ꂽ�B�������A����͗��Ȃ����A����ɐS���悹��҂́A�݂Ȋ�������Ȃ������B
���̑��V�̎Q��҂̊�Ԃ�ɂ���āA���悻�A�G�����̕��ނ��͂���������B����́A���R�����A���V�̂����炵�����ʂƂ�������̂������B
�吷�́A�l�����B�Ȃ��Ƃ����̂ɁA����ȋ��ȂƁA�s�ł͎v���Ă�������ɁA�ĊO�A��������҂̑������Ƃ�����������ł���B����ł́A�����ɁA�ނɂނ����ĕ��͂��[�����������Ă��͂��ł���Ƃ��v�����B�����ɂ���ԂɁA���������ǁA�ނ̎��͂Ƃ��̐l�Ԃ��\�\�����Ă܂��܌��l���̂��������A�[���A���ׂĂ݂�K�v������Ǝv�����B
|
�������̉�
�ǂ������̂��A�吷�́A���������ɁA�ϋɓI�łȂ��B
����̘Z�Y�ǐ��́A�Ƃ������ɂ₵�āA
�u���߂��A�s�l�݂₱�тƂ̕��ӂ��ɐ����݂���́B�ЂƂ�̉��ȂǁA�����݂̂ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�悵�A����ЂƂ�ł��A�ʂ��Ă݂���v
�ƁA����ǂ́A�Ɨ́A�L�c�U�߂��v���āA�Ђ����ɁA�����ɁA�V�₶������Ƃ����Ă����B
�Ă������A�����ܔN�̏\����\����ł���B
������o����l�������y���ƋR�n�����A�L�c�����čs�����B
����̕��ł��A�˂ɕ�����z���Ă����̂ŁA���������m�����B
�u�����Ă����ȁv
�ƁA����́A�V���܂ŁA�킯�o���āA�w�������B
�Z�Y�ǐ��́A��������āA
�u�f�����낵�̏���āv
�ۂ���炵�āA�����ɁA���m�����B
����́A���Ђ�ނ�����Ȃ��A����̒��ɁA��n�����ĂāA
�u���������B���������낵���̂́A���炾�B���ꂪ��ɂ����ē������̂ł͂Ȃ��v
�ƁA�����Ԃ����B
����ȏꍇ�ł��A����́A�����A�����̐��������A�吨�ɁA�����J�������Ă����悤�ȋC�������̂Ă��Ȃ��̂ł������B���̋�݂��A�}����������Ȃ���A�ǐ��́A
�u�����A���܂ŁA�������ė����Ă���v
�ƁA�������A������āA�ނ�I�܂ƂɁA���A�������ڂ����B
�u�������A����ȃw���w����ɂ������Ă��܂邩���v
����́A���������Ɏ����āA�n���Ƃ��ė����B��A�ނ̑̂��睛�͂ˁA�ǐ��Ƃ̋������A��C�ɁA�������B
�ǐ��́A����ĂāA�����̒��֓������B
���̓��̍�����A���ɁA���琨�̑�������ɏI��A��������ɁA�L�c�̏����}�ɁA�ēx�̌ւ���������Ă��܂����B
�ǐ��́A����Ȗڂ����āA����̂₵���A��ƁA�����}�g�̌Z�nj��̏��֍s���āA����݂��������B
�u���ƁA���Ђǂ��ł͂���܂��v
�u�Ȃ��A�����A�����̂��v
�u���X���Ƃ��ƁA����������Â��悤�Ƃ����v�́A���݂��̖��_�݂������ł��傤�B���ЂƂ�ɁA�����܂ŁA��S�����āA�����ɏ���������Ă���̂ɁA�ꕺ���������o��������ʂƂ́v
�u���̎����B�c�c������́A�Ȃɂ��A�����|��Ăł͂Ȃ����A�킵�ɂ́A�������D�ɂ����ʎ�������̂ŁA���̉H���̍ԂƂ�ł��A�߂����ɗ���ɂ����˂Ă���̂��v
�u�\�\�ƁA���������̂́H�v
�u��̒吷�̍s�������v
�u�Ȃ�قǁB�s�R�ł��B����A�s���ł��A�����v
�u���̍�������Ă���̂��B�N�����A�����{��A�܂���ɁA�`�������āA�N���˂Ȃ�Ȃ��͂��̒吷����c�c�v
�u�ЂƂA�䓯�����āA�ނ̐^�ӂ�@���Ă݂悤�ł͂���܂��B�����A���S�傢�ɁA��������Ȃ��v���Ă���Ƃ���Ȃ�Łv
��l�́A�����̌�A�ꂾ���āA�E�n��吷��K���A���̗�Â����l�₵���B
�吷�̓�����Ƃ���́A�����������B
�u�c�c�ǂ��������̕����́A�ЂƂ��A�����ɁA�������͂Ȃ��B��������������Ă��A����ɁA����܂��B����ł́A������V���̎������Ă��A�����ɂ́A�E�C���o�Ă܂���܂���B���d�̎��s����A��������ނ̂́A�t���݂��ƁA�I���ɂ����Ă���҂�������B�c�c�V�������̎����A����ł́A���狁�߂��Г�Ƃ�����߂邵���Ȃ����ƁA���낻��s�֊҂����鏀�������Ă���Ƃ���ł����v
�ǐ��A�nj��́A���������āA���R�Ƃ����B����ł́A�����̓�����A��������o���悤�Ȃ��̂ł���B���܂���A�܂����m�������B�����ŁA��l�́A����|�����āA���̔��������B
�u�����남���́A�s�ɂ��āA������̋��y�̎����m��Ȃ����炾�B�����̎��́A�݂ȏ��傪���킹�Ă���L�c���̗����ɂ����Ȃ��B�܂肨�����炵�āA�G�̗����̍�ɏ���Ă���B���A���̊Ԃ܂ł́A�����܂łł��Ȃ��������A�ЂƂ��сA���傪�A�����ւ��āA������������Ƃ݂��̂ŁA�}�ɁA�S�����܂ł��A����Ȏ��������o�����̂��B�c�c���͂܂��A�E�n��吷�Ƃ��������������Ƃ������j������Ȃ���A������āA���R�ƁA���߂��Ă����肵�āA�����́A�ǂ̊炳���āA�Ȍ�A�����̗̖��ɂ܂݂�����肩�v
�V�Ԃȏf����l�́A����邪���A�������܂��āA�͐������B�ӂ߂���A����������ł���B�吷���A���ɂ́A�������Ǝv�������āA���炽�߂āA���吪���̉��S����B
�������A���ɂ̓��������܂������A�܂��A�����I�ɁA�����ɂ����Đ���ł��Ă����H����A�傢�ɕK�v�Ȃ̂ŁA�ЂƂ܂��A�ނ͂܂��A���s�ւЂ��Ԃ����ɂȂ����B
�������āA���̔N�͕��A���A�����Z�N�̉Ăł���B
�ǐ��A�nj��̕��͂ɂ��킹�āA����ɐΓc�̒吷�̉Ɛl��A�헤������������������̌R�����A�Ă����悤�ȉĖ���킯�āA�O���сA������P�����B�\�\���߂́A�f�������܂���v���ƁA���ɁA�v�������ʖ{�i�I�Ȑ푈��ԂɂȂ������̂Ƃ��������Ȃ��B
��͋����B
�����������͉ʂĂ��Ȃ��Ђ�܂��Ă䂭�B
�l�ׂ̉\���悤�₭���̐퓬�ɂ��������āA��g�͖��g�A���������A���������A�����ȓ��h�����������n�߂��B
�\�\�ƁB���̍��A�ԏ邠�����R�̐����牓���Ȃ����h�����m�����傤�c���ɁA���R���Ƃ�����ǂ��̉w�H���܂₶��N���āA�ق����A�ԂƂ�ł����܂��A�͂邩�ɁA�Ⓦ�̖�ɂ������o���A���₩�Ɍ��Ă����V�y��������B
���̒n���̉��̎g������傤���A�c�������G�������̂Ƃ����Ђł��Ƃł���B
|
���i�ו�
���̍��A�Ⓦ�n�����狞�s�ւ̉��҂�������ɂ́A���C���Ɠ��R���̓������ƂȂ��Ă����B
���R���́A�O�X���������z���āA�M�Z�������o�āA�ؑ\�H�֏o��̂ł���B������̕��������͂����邪�A�E�n��吷�́A�r���A�K���ׂ��l���������̂ŁA����ǂ̋A���ɂ́A���R��������B
�u�܂悭�A���ĉ�����悢���ȁv
�吷�͔n�̏ォ��A���̘Y�]�����ցA���x���������B
�u����A�����܂��傤�Ƃ��B�ʂ�w�H�Őu���Ă݂Ă��A�ߍ��͓c���̊قɂЂ��Ă�������ŁA�߂����ɁA���������Ȃnj������Ȃ������ł�����v
���̂ЂƂ�A�吷�̎��b���l����������������B
��s�͎�]�\�A�R�n�͒吷�ƒ��������ŁA�ق��͓k���������B����A������l�A�i���ׂ̉�ςn�ꓪ���A���ɐl����j�ʼng���čs���B
�܂����ɁA�ԏ�̒����R�����A��������Ɖċ���c���Č������B�c���̏h�́A���R�����牡�����A�k���ɂ͂��肱��ł���B���̎g�A���������G���̖�@�������ɂ���A���������ꂽ�c���ɂ͋��ق�����B�����ŁA�c�������G���Ƃ��l�͏̂�B
�u�ق��B�E�n��吷�B���̒吷���A�K�˂ė����Ƃ��B�܁A�ʂ��ʂ��B�c�c���������͗��邾�낤�Ǝv���Ă����Ƃ��낾�v
�c���̊ق̍G��Ȗ�ɁA���l�����̔n�͌q�Ȃ���Ă����B
��̏G���́A�����Z�\�ɋ߂������B�n���l�ŁA�����̐����̂ƂȂ��Ă���҂́A�߂����ɂȂ��B������A�������̐��́A�����I�ȁA�܂��M���K���I�ȓ����ƁA���������ӂ���ł����B
�������G���́A�s�l�ł��A�M���̗���ł��Ȃ������B����Ȃ���̍Ⓦ����ǂ��ڂˁ\�\���J�n�l�̖쐫痂����܂����j�ł���B
�����Ƃ��A��͓���������o���҂̏��ł��邩��A����̉ƌn��H���āA�s�̑劯�Ƌߐe���ނ��сA�ꐩ�̓������𖼏�邱�Ƃ͏o�����ɂ������Ȃ��B
������݂Ă��A�Ⴂ��������A�����ȍ�m�ł�����A��S�̂悢�����ŁA�n���l���L�ȁg�炫���h�ɐ���ׂ��A��������S�����Ă������Ƃ�����B�����Ĕނ́A�܂�܂Ǝu�𐋂��������҂ł���Ƃ����Ă悢�B
���̒n���ɂ�����ނ̊��E�́A���̎g�����삵�����m�����傤�ł���B
���̎g�̔C�́A�����A�x�@�A�i�Y�Ȃǂ̐E���������A���́A���ł��Ď@����ɂ������B�܂�㐢�̔��B�\��a��̊����z���ɂ����A�����āA�ŗ�����ʒu�ɂ������̂ł��邩��A����ȏ���ɂɂ�݂͂Ȃ��B���̏�A�����̘Y�}��{���A�ő��������݂ȁA�y�n�A���͂�~���A���R�������Ȃ����R����������ɂ��āA�Ⓦ�̑啽���ɁA��ʂ��Ă���`�ł������B
�u���ɁA�v�������ƁA���ڂɂ�����܂���ł������A���悢���s���̂悤�Łv
�q�a�ɒʂ��ꂽ�吷�́A����̗���Ƃ��āA��ցA�����������B
�u����A���Ȃ����A�����������h�ɂȂ�ꂽ�́v
�G�����܂��A�A�d�ɁA�ނ��}�����B�����āA
�u�c�c����\�������ꂽ���A������̍����a�̌䎀���B�͂邩�ɁA���\�͂������B�����䖳�O�ł��킻���B���������ݐ\��������v
�u�s�ɂāA��点�������A�܂������V�������܂����B���V�̂��߁A�A���������܂������A���̐߂ɂ́A�˂�Ȍ䒢�g�������������A�܂��A��O�֎�X���������̂��������ނ����Ȃǎ����A�ꑰ�A���S�̂قǂ��A�݂Ȃ��肪���������Ă���܂��v
�u�Ȃ�́A�S���肶���B�\�\���A���������̂��́B���̌���A�����͂�܂��A����̎q���O�l�܂ł��A����ɓ����ꂽ�Ƃ��A���̒n���܂ŁA���炢�\�����v
�u���������A�������y�тł��傤���A���́A�h�����キ����ɏh�����ς���A���������������ƂȂ�܂����B��������ƁA����́A�嗐�̒������݂��܂���v
�u�ǂ����āA�ЂƂ�̏�����A���㌹���̗͂�A���Ȃ���A�܂��nj��A�ǐ��a�܂ő����Ă��āA�}�����ʂ̂��v
�u�����ɂ��ƁA�������N�ԁA�Q�[���Â��܂����B�����̋Q���╂�Q�̓k�������A�ǎ��a����̋��̂̒n���ނ炢���A�݂ȁA�L�c�̋��ɏW�܂�A����������Ă����āA���ɂ���āA����H�����Ƃ��Ă��܂��B�ł�����A���̋��\�Ȃ��ƁA����ׂ��炸�ł��v
�u�����ŁA���Ȃ��́A�ǂ��������l���ł�����̂���v
�u�ȂɂԂ́A�E�n��̊��E��A�s�ɍ̐g�ł�����A�������̑��V�����ȏ�́A�ǂ����Ă��A�ꂽ��A���������˂Ȃ�܂���v
�u�����B�������Ƃ����v
�u����̗��\�A��ɗ]����̂�����A����ȏ�A���̔g�y���������Ă͂����܂��ʌ́A�A���̂��łɁA����ǂ̂̑i��ƁA�f���nj��A�ǐ��̏�i���傤�������g�т��āA�����̕{�ɑi���o�ŁA�������������傤����̉����������Ԃ݂������āA���������������Ȃ��Ǝv�����߂Ă���܂���v
�u�Ȃ�قǁv
�u���������킯�ŁA�s�}���r���ł͂���܂����A��ɁA�䒢�g���������܂܁A�������܂ł��A�����ɕ��āA�䉹�M�������Ă���܂����̂ŁA�r�݂��̂��łƐ\���ẮA����ł����A����ɎQ���o������ł������܂��B���Ȃ����Ƃ��A�ǂ����A�ȑO�ɂ����Ȃ��A�����Ə�����܂���v
�ƁA�吷�́A�n�ɉg�����Ă������X�Ȓ���̕ԕ��Ǝ�݂₰�Ƃ��A���̎��ɐς܂��āA�G���֑������B
|
������ď㋞
�吷�́A���҂��ꂽ�B�ނ̍l���ɂ���O��I�ȈӐ}������A���̖K��́A�[���Ɍ��ʂ��������B
�G�����܂��A���̋q���Ƃ炦�āA�����ɁA���Ȑ��͂̊g�[�ɁA���p����̂�Y��Ă��Ȃ��B��͓��ɁA�����Ђ炢�āA�吷���˂��炢�A�V�n�����l�������̂����ɁA�吷������������āA
�u���Ȃ�ƁA�܂��䑊�k�ɂ݂��邪�悢�v
�ƁA�͂Â����B�����ĂȂ��A
�u��J�������āA�����炾���A���킵������Ȃ�B�����a�̂Ȃ���́A�Ȃ�����厖�ȁA���Ȃ����v
�ƁA����������肵�āA�吷��܂��܂����B�Ǝv���Ƃ܂��t�������ẮA�����ɋC��ς��āA���̌������܂����肵���B
����ǁA�G���́A����l�ɂ��ẮA�������ǂ�������Ȃ������B�吷�Ȃǂ��A�͂邩�ɔN��̔ނł���B����̕��ǎ����܂������Ă������ォ��̏푍�n���̎�����A�e�Ƃ̐��͕��z�̂������ɏA���Ă��A�吷�ȏ�A�Â������ƁA�y�Ɛl�̗��j��m���Ă���̂������B���������A���̘V�Ԃ́A�m���Ă��镗���]���ɂ͏o���Ȃ������B
���̕ӂ��A���ƂȂ�������Ȃ��C�������̂ł��낤�B�吷�́A�ӎ��I�ɁA�ނ��A������ǂ��l���Ă��邩�A�Ђ��o�����Ǝ��݂��B
�u�G���l�B���Ȃ��́A����Ƃ����l�ԂƁA����ɂȂ������Ƃ�������ł����v
�u����B����ɂ́A�K�˂�ꂽ���Ƃ��Ȃ��A��������Ƃ��Ȃ��v
�u�ނ����A�����\�O�A�l�N�O�ɂȂ�܂��傤���B��������x�A������ł����ȁv
�u�ǂ��Łv
�u�s�̉E��b�Ƃ̂���Łv
�u�c�c���B�������v
�v���o��������ł���B�������A���̍��̏����Y����̎p�����A�G���ɂ́A�ׂȎ����v���o���ꂽ�B
����͉������N�A�G���́A�܂��O�\�䂾�����B���i�̉��̖�l�ƁA�化�܂��N���A�������Ă�����A�������E�����A���߂邴���ɉȂ����A�ꑰ�\���l�A�쐔���ジ�Ȃ��ɁA�z���֑���ꂽ���Ƃ�����B
�S���A�^���̎���A���̉E��b���������Ђ�ɂ��A����ȑ��蕨�������肵�āA�O�N�Ŏ͖Ƃ���߂�ɂȂ����B���̗�ɁA�㗌�����̂ł���B�\�\���̎��A�ނ��瑡�������n���A�������A����̂����ցA�g�����Ă݂��B��̂����ցA���ւ��Ƃ��ďo�Ă����̂��A�Ⓦ�����ǎ��̎q�A�����Y���傾�ƁA���̎��A�������畷�����ꂽ���Ƃ�����B
���Ƃɂ���ɂ��A�G�����A����������̂́A���̎�������ł���B���͉����ނ����ł���B�ߍ��A�p�X�Ђ�҂�Ə���̂��킳�����ɂ��Ă��A�v���o���Ȃ��قǁA�L���͂������Ȃ��Ă����B
�u�\�\����b�ƂցA�Q��ꂽ��A�������ցA��낵�����`���\�������Ă��ꂢ�B�t�H�̎��݂̂蕨��A�l���̂��ւ�́m���u�l���̂��ւ�́v�̓}�}�n�������Ă��Ȃ����v
�G���͂����b�����炵���B�������A�O�Ȏ҂������悤�ȋL���ɂ͂ӂꂽ���Ȃ��̂��B�吷���A���Ƃ��āA
�u�A���̏�́A���������ɂ��A�Q�シ�����ł��B�ق��ɁA�䏑�ʂł�����Ȃ�A���Q���āA���掟���������܂��傤�v
�ƁA�������B
�����A�吷���A�c���𗧂����ɂ́A�G���́A�����Ȏ����O���A�ނ̋��ɉ��������āA
�u������A�O�X�z���͕����ł��B���v����������܂ŁA���A�ꂭ�������v
�ƁA�ق̊O�܂ŏo�āA���������B
�吷�́A�₪�āA�s�֒������B
�ނ́A�������ɁA�������ɏo�����āA���f�������̑i�����o���A
�u��낵���A���W���傤���イ�ɂ����āA�����̋c���������܂��v
�ƁA�Ȃ�����������A�ׂɏڍׂȈꕶ��F�߂āA�o���Ă������B
���A���ꂾ���ł͂ƁA�ނ́A�m�邩����̍��M��劯��K�˂āA����̔�������ӂ炵�ĕ������B
�吷���A��N���爤�ڂ������������Ă���m�a���̎������{�����Ԃ��傤�݂̂�̋��ւ��f�����B�܂��A��̔ɐ����d���Ă��钉���̎q������t����낷���ɂ�����āA�b�����B
�������A���̋��a�̕��N�ł���A�܂����ẮA�����Y���傪�d���Ă�������b�Ɓ\�\�{�������̌��E�ɂ��铡�������̎��@��K�����Ƃ͑ӂ�͂����Ȃ��B
�Ƃ��낪�A�ǂ����s����X�ł́A�ނ̑i�����A������]��M�S�Ɏ��������ނ��āA�����Ă���Ȃ������B
�u�ق��B�قفc�c�H�v�ƁA�s�l�炵���A�����Ȃ���́A�O�����Ƃ��ɂ��Ƃł������悤�ɁA�̂ǂ��Ȋ���A����������傫�����邾���������B
�u������邢�v
�ƁA�吷�͂��Ƃ����B�\�\�Ƃ����̂́A�����ɂ��A���̉č�����܂��A��C�ə����Ђ傤�Ƃ����I�N���A�����̔�Q�n�́A�ɗ\�A�]��A�܂����˓��̊e�n�ɂ킽��A���c�ł��A�̂Ă����������ƂȂ��āA�ɗ\��I�i�l�̑i����e��A���D�\���ǂɁA���ڂ��āA�C�������ɂ����ނ��A���������e�Ȃł��A���̎��ł��������Ă���Ƃ���ł���B
����łȂ��Ă��A�s�l�̋������ƁA�܂������S�́A���J�y�̓����Ȃǂ��́A��g�ÂȂɂ�Â��琣�˂̊C�ɂÂ���C���ʂ̂ق����A�͂邩�ɁA�g�����Ȃ��̂������B
�H�ɂȂ����B
�Ȃ��܂��i���ɂ������鍹���͂Ȃ��B
���̏H�A���������́A�ې������˂āA������b�ɏ����傹��ꂽ�B
�ꂵ����́A���̏��C�̏j���牽���ŁA�܂��A���������̎Ԕn�͊nj���ꉃ�̎����ɂ��艝�����A��C�̑��������A�s�̕\��ɂ́A�e�������Ȃ������B
�u�����A���̂܂܁A�����Ă����ꂽ��A�����̗����܂��A�ǂ�ȑ厖�ɂ�����������܂���B�Ⓦ�̏��n���ɂ͐ۊ։Ƃ̑����A���c����ł���������邱�Ƃł����A���������A�����ɂ͂܂��A�����̗߂ɕ����ʘ؎��ӂ��イ�̑����A���͂ȌR���ƕx�͂������āA�Վ�����ƁA�䐭�����C�݂�������������Ă���܂��B���Ƃ̂��߁A�吷�́A�J���ɂ����܂���v
�t���������ƁA���x������Ȃ��B�����ւ͍ēx�̏�i�������B�Ȃ��A���܂��܂Ȕނ̉^�����A���ɂ��̂����������A���̔N���\���ɂȂ��āA����ƁA
�\�\������~�V���t�T�~�N�����m���i�Q�X�A������B�������i�V�A�d�����z���m��A���J�i���B�g�V���h�V�e�A�R�����߃w�A�����V�N���m�@��j���e�A�w�e�V�_���A��Ӄ����Z�L�A���x�L��B
�Ƃ��������F�c���̋c�肪�A�������ꂽ�B
�������ɁA�����̏���ցA�����������A����́A������������ƁA�܂��Ȃ��A��������y���̂ڂ��ė����B�����đ������ɁA�������Ƃǂ��A���炭�A�ނ͊X�̗��ɂɔ����Ă����B
�ނɂƂ��ẮA��x�߂̏㋞�ł���A�Z�N�Ԃ�Ɍ��镽���̓s�ł������B�@ |
���Ό�
�u�t���ł��ꂽ�B���������A�i�l�Ƃ��āA�o�����Ƃ�����v
����́A�o�������ꂽ�ƒm���āA�S�O�ɂȂ����B
�u�c�c�����A���͔��A���͍����v
�ނ́A�{����Ȃ��߂��B�����ɏo�āA�@���̑O�ɁA����𑈂��̂́A�ނ��낢�����ł͂Ȃ����B���`�̎҂ɗ^����ꂽ�D�@�ł͂Ȃ����B�����A�v���������B
�u�ڋ��ɂȂ�܂��B���X�ƁA�����Ƃ�����q�ׁA�����ȑ��̉����́A�����珔���ցA�������ɕ������Ƃ͂��܂��v
�������A�ނ́A�s��ɂ��݁A�i�ނ�������B
�ْ��̒��ɁA�����𑗂��Ă����B
����ǁA���̊���яo���́A���̔N�̂����ɂ͂Ȃ������B�������N�̐��������Ă��܂����B
�j�̎O�\�܂ƂȂ������U���A�ނ͑i�ג��̗��ɂŁA��т����}�����B
�Ȃ̋j�[����A�ւ肪�͂����B�Ȃ������ޏ��̕����B�ꎚ�ꎚ���A���̂悤�ɁA����ɂЂт��B����́A�܂����߂āA�ǂݏI�����B�������A���Ȃ������͉���Ȃ��̂��B����݂͂Ȗ������Ƃ���B�����āA�ޏ��́A�I��̕��ɁA
(���A��̂���ɂ́A���Ȃ��Ǝ��Ƃ́A���߂Ă̘a�q�킱���A�L�c�̊ق����ɁA����Ă��邩������܂���)
�ƁA�����Ă������B
�ޏ��́A�ނ��㗌�̂܂�����A�D�P�݂������Ă���炵�����Ƃ��A�ǐl�̎��ɂ����ƍ����Ă����B
�\�\�ƁA�����ЂƂA�p�������邵�Ă������B����₳���̕s���l�ӂ��Ƃ��A�����̗��̋A��ɗ�������āA�l�A�ܓ��ؗ����Ă���Ƃ������璆�̎����B
���b�ƁA�S�̉��Ő�ł��Ɏ����C���������������B���̖����Ȓj���A�܂������⏫���Ȃǂ��A�肱���炵�Ă���̂ł���܂����B�킪�Ƃւł��A�A�����悤�ɁA�����o���́A�ǂ�����̂ƁA�j�[�ɂ��A��V�������Ă��邱�Ƃ��낤�B�c�c�����Ԃ킪�܂܂����Ȃ�悢���A�j�[�́A����Ȍ��B�҂��ĉ���Ȑl�Ԃ͌������Ƃ�����܂�����A�����A�ނ̋����Ȃ�邳�ɂȂnj�������˂悢���A�ȂǂƖ��ȕs���ɂ��P��ꂽ�肵���B
�ꌎ�̖��B����ƁA���߂āA�������̂�яo���������A�ނ́A���ƂƂ��ȗ��́A�e���Ԃ̑����̂��������A�ڂ����\�����Ăďh�A�����B
�A���Ă���A�Ƃ�ŁA���܂����ƁA���̂����łԂ₢���B
�u�o���Ȃ��ꏊ�֏o�����߂��A����ȂɁA�l���Ă����̂ɁA�����킷�ꂽ�B���ƂƂ�����́A���܍��������ł͂��߂��B���������A���ǎ��̎���A���ꂽ���A�c���݂Ȃ��q���A�f�����̎�ɁA�䂾�˂��A�����āA���ꂪ�\�Z�ŁA�s�֒ǂ����ꂽ���̎��̑坁�����̂����݂��́A�������A�吷�ɂ������āA������A�s�ɂ��邤���h���E���Ă��܂��Ƃ������Ă������֎��܂ŁA�܂��ł������˂A�킩��܂��v
�v���A�ނ́A�Y�������́A�����g���т������́A�ʓ����́A�咆�������Ȃǂ̌������ߊ�����˂Ă���O�ł́A�v���̔������A�q�ł��Ȃ������B
����Ƃ��A�ԕ����䂰���̂��傤�̖@��ŁA�E�n��吷�ƔނƂ��A�Ό����ꂽ�B�吷�́A�䂽���Ȏ��X���̂��ƁA�����߂������ȓ��ƁA�����ĕِ�Ƃ������āA��X�Ƃ��Ƃ��A���猾�ɘj�킽���āA����̂��̓��܂ł̒q���A���Ƃ��Ƃ��A���������������āA
�u�]�Z�킢�Ƃ��̊Ԃł�����A��傤�ɂ����ẮA�f����ɔE�т܂��A�v����ɁA����́A�f�������̌��ӂ��A�݂Ȉ��ӂɉ����A�܂��Q���╂�Q�̐����ɂ̂�A�ގ��g���A��ɂ͂т����肷��悤�ȏf���E���̑�߂�Ƃ��A���ɁA�傻�ꂽ�����I�Ȉ��v�z���������ɂ����������̂ł��B����ނׂ��ǎ��̂Ђ��݂ɔ����A�����̋��\�����A�n���̈����ɁA���p���ꂽ���̂Ȃ̂ł��B�\�\�ł�����A�s���ӂт�ɂ́A�v���܂����A���������������u���Ă����Ȃ�A���́A�Ⓦ�Ɏ~�܂炸�A�l�ׂɋy�сA�Ђ��ẮA��C�C��̙����Ђ傤�����ɂ����������āA���Ƃ̉Ђ��ƂȂ�ʌ��������܂���v
�ƁA�ق����B
����́A�吷�٘̕_�ɕ����ق�āA�G�Ȃ��犴�S�����B���X�A�Ȃ�قǂƂ��Ȃ�����ɂ����Ȃ����B�唻���́A����ނ悤�ɁA�ނ����āA
�u����B���܂��̐\���Ԃ���A�����A�\�����ĂĂ݂��v
�ƁA�������B
�����A����A�ނ̙�X�ǂǂȂǂ́A�����Â炭�āA�吷�̂܂��ɂ́A�n�������Ȃ������B�������A�吷�̗�R���鉡��̔�������ƁA�������ɁA���R�ƁA�D��ɔR�����{�C�����̂܂܌���瞂��āA�吷�̃E�\�ƁA�����炦���������Ă��B
�������A����̌��́A�����قǁA�ނ̑e�\���؋����Ă��B��Ɍ����ė��Ȃ���A���Ƃ���X�Ɠf�͂��Ȃ������Ȃ̂ł���B�����炻��͙�ق�����A����Č����邾���̂��̂Ƃ��Ă��������Ȃ������B���_�͎x���ŗ�߂�ɂȂ�A�ʂẮA�܂��ɂ��܂��A��������ɁA�����ɂ����Ă��܂��̂ł���B
�u���傤�́A�ނ���v
�ԕ������o��ƁA�ނ͂����A�n��Ő�����Ƃ��̂悤�ɔ��Ă����B
��яo���͎���A������x�́A�吷�ƁA�Ό����ꂽ�B�����āA���炭�܂��A�������Ȃ������B
����ƁA�O���̖��B�������̔������A���c�̖��A��������̏�A�����n���ꂽ�B
�u����̍߂́A�����ɒl���邪�A�܂ӂ��A�V�c�䌳���̑�͂������Ⴀ��ɂ���āA�͖ƁA��������B�A�����āA�ސT�������������v
���߂ł������B����́A���݂邲�Ƃ��A�������āA�ۂ���Ƃ��Ă����B
�吷�ւ̐\���n���ɂ́A
�u�ꑰ�����Ȃ��ӂ�̈��ɂ́A�������A���ǎ��̌��̂��A�����̈��ɂȂ��Ă���ƒf����B��낵���A����ɓn���ׂ������̒n����A�c�̂̏؏��ȂǁA����A���̂����ԋp���āA�a���������悤�Ɂv
�ƁA�������B
�吷�ɂ͈ӊO�������B���_��́A�����܂ł��Ȃ��B���ȕs���ł���B�������A�Ԃ����Ƃ��Ȃ��A����āA���̓��͑ޒ삵���B
����́A���֑��n�𗧂āA
�u�i�ׂ́A�������v�ƁA�Ȃ�ꑰ�ցA�ւт�������āA��ɕ��B
���ꂩ�珉�߂āA�ނ́A�����̐g�ɂȂ����悤�ȐS�n�Ŏl�A�ܓ��A����������܂�����B�Ȃ̋j�[�ցA�s�݂̂₰���ƁA�s���b���ׂɂ��́A�������́A�߂��炵���D���Ȃǔ����āA���������A�邵���B
���傤���ނ́A����₳���A�_���т�����₵�ȂǁA�x������������̎U��ʂ������A�h�̕��ցA�߂肩���Ă����B����ƒN���A���叫��ƁA������ŌĂԎ҂�����B�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�E���̂ԑ������𐠂��������F�̎�߂��肬�ʂɁA�������������A���Ђ����Ԃ�A����ɓ��Ђ̏ォ���}�����Ԃ��Ă��闷�l�ł������B
�߂Â������āA����ƕ������B����́A����̕s���l�ł���B
�u�����B�c�c���A�ǂ����āA�s�ցv
�u��ʂ����A�㗌�ƕ����āA���Ƃ�ǂ��ė����̂��B�Ƃ��낪�A���ɂ�ǂ��킩��Ȃ��B�ԕ����ŕ����āA����ƒm��A���ꂩ��s�ӂɋ������Ă�낤�Ǝv���āA�K�˂ė����Ƃ��낾�v
�u�������B�c�c�����A�s������Ă��Ă��A���܂�ʂ̂��v
�u���܂�ʂ��Ƃ́v
�u�ߕ߂����ق̗߂������āA�������̂�ł���g�ł͂Ȃ��̂��B�����A�������A�ԕ����ցA�����ōs���Ƃ́v
�u�͂͂͂́B�l�̂��킳���A�����Ƃ�����B��C�̊C�������ŁA����ǂ��납�A�����g���A�����Ȃ��A�肢���ς����B�ނ�͂Ƃ����ɁA�킷��Ă���B�������̍��̎��́A�����Ƃ������̂��v
�s���l�́A�����s���l�ł���B�ς�Ȃ����A�܂��A������炸�A�������Ǝv���Ă��Ȃ����A�l��l�Ƃ��A�v���Ă��Ȃ������ł���B
�u���ɂ֍s�����B�ǂ����A�ق��ň��ނ��v
�u�����́A���֗����肾�B�Ƃ����p�������邩��v
�u�͂͂́B����Ƃ�����҂��A�Ђǂ��A�^�ʖڂ���Ȃ����B�����Ƃɔ������Ȃ��҂��Ă��邹�����낤�B�������ʔt���炢�́A��������B�܂��A����ɂ��ė����B�����B��V�т̉Ƃ�����v
|
�����̓s
�s���l�ƁA���߂ĉ����������A�ނ͂��łɑ�l�ł��������A�Ȍ�S���������Ȃ��B���N�����Ă��A������V���䂤�Ƃ����l����B�ق��ɔ\�͂Ȃ����̂悤�Ɍ�����j�ł���B
�������A�܂���Ȃ�ɂ��A����́A�������Ă���B���e�̕ω�������B�ǂ����A���̒j�Ƃ́A����ȏ�A����������Ȃ��C������̂������B
���̂����A�ނ͂�͂�A���݂��ꂸ�A�s���l�ɂ��āA�����̗V���h�ցA�͂����čs�����B
���̍��ɂȂ�ƁA�s���l�́A�ꂾ��s���l�炵���A�Ⴆ�Ă��āA
�u�܂��A�N�̑i�ׂ̏������j�����v
�ƁA�����A�t���A��̍����ɏグ���B
�u���B�m���Ă���̂��B�吷�Ƃ́A�i�ׂ̂��Ƃ��B���₻��́A�L�c�̗���̎҂ɕ������낤���\�\���ꂪ�����������A��́A����ɕ������̂��v
�u���������A����B���ʂ��́A�����̗͂ŏ���������ł���̂��B����ǂ̑i�ׂ��v
�u�������҂́A���ɏ����v
�u���͂͂́B�A�n�n�n�v�s���l�͂��悢����ā\�\�u�܂��A�����B�܃A�����v�ƁA�ЂƂ肵�āA�������B
�u�����A�܂������̂��v
�u�]��A���m�����炾�B���܂ł����Ă��A�N�́A��l�ɂȂ�Ȃ��B�V�R�̓��q���v
�u�������Ȏ�����������Ȃ����v
�u���Ⴀ�A���𖾂������B�\�\�吷���i�����ƕ���������A����͂�����A�M�l�̕����ƌ��܂��Ă���B��������ƁA���߂�������Ȃ��B����́A�������������B�\�\���ʂ��̖L�c��K�˂����A�}���ŁA���Ƃ�ǂ��悤�ɁA�㗌���ė����̂����̂��߂��v
�u�����āv
�u�M�l�͒m��܂����A����́A�������玝���ė����������˂̑唼���A���ׂ̈ɁA������Ă��܂����B�Y���ȁA�ԕ����̎�Ȃ���ǂ���̌�����A�a��̎Q�c�����ɁA����āA�������瑡���Ă������B�\�\�M�l�̏����́A���̌����ڂ���B�������Ǝv���Ȃ�A���܂ɕ���B�܂��A���ނ������B����ł���A���܂ɕ���v
�����Ă���Ƃ���ցA
�u�₠�A�s���l�B�����n�߂��̂��v
�Ђ������A�ꖼ�̌������͂����ė����B�ǂ����ŁA�����悤�Ȍ��������ƁA����́A��������������B�����āA�₪�Ĕt�����킵�n�߂Ă���A���R�Ƃ����B
����́A�ԕ����̖@���̂ЂƂ肾�B�������ɁA�����̍ق��ɗ����������̈ꖼ�ɂ������Ȃ��B
�u���܁A�e�ׂ��A����ɑł������Ă���Ƃ��낾���A���̒j�A�ǂ����Ă��A����̂������Ƃ��A�^���Ǝv��Ȃ��̂��B��������A�b���Ă���Ă���v
�s���l�́A�˂������悤�ɂ����ď����B�����āA����̂��Ƃ��A���̌����ƁA�����ނ݂����A�����āA���ʂɂƂ��Ă��ꂽ�����̘J���A�ӂ��Ă���ӂ��ł������B
�₪�ĂȂ��A�O�l�A�l�l�ƁA�����������A����ė����B�ނ�́A�s���l�̑O�ł́A�q��͂����������A�ڋ��������B�݂ȍ����̕����O�ɂ��������Ă���ҋ��ł��邱�Ƃ����킸���Ď������Ă����B
�u���������A�n�������Ȓj�ł�����ȁA����Ƃ́v
�ʂƂނ����āA�s���l�͂������B�܂�ŁA����̉I���������A�F���A���̂����Ȃɂ��āA����ł���悤�Ȍ��i�ł������B
�邪�X����ƁA�ނ�͂��ꂼ��V��������āA�ق��̐Q���ւ����ꂽ�B�����Ă䂯�ƁA������ɂ����̂��A�f���āA����́A���ɂA���āA�Ƃ�ŐQ���B
�u�Ȃ�قǁA����́A���������v
����́A�����̋����A���݂͂Ƃ߂Ă����B
���{�̕��s���A��{�l�̕n�������ʂ��A�s��̂ǂ�Ȃ��̂��Ƃ��������A���āA�����V�w���ɁA�����Ԃ�A�m���Ă����͂��Ȃ̂ɁA����������A�Y��͂ĂāA���������͕̂K�����ƁA�M���Ă����قǂȂ��ł����������A����o���Ƃ炸�ɂ����Ȃ������B
�u�\�\�����́A���̂��v
�s���l�́A�����ɂ���ė��āA�ނ̋A�������������B�����āA�ʂ�ۂɁA���ꂾ���́A�����A�Ђ��߂āA�^�ʖڂɂ������B
�u��C�̓������F���A���悢��A�\��͂��߂��B���ɂ̍������A�o��ŁA�̎Ԃ��B�����̊��������́A�����瑝�h����Ă��A�������܂�܂��B�\�\�Ƃ���ŁA����A��ӂ̕����A���낻��A���@�����v
�u���@�Ƃ́v
�u�܂�����Ȏ��������Ă���c�c�v�ƁA�������Ɂu���F�Ƃ̖���ʂ������Ƃ��B�ĉ����āA�����A���k�̒n�ƁA��C�ŋ����邱�Ƃ��v
�u����ɂ���ȗ͂͂Ȃ��B�b�R�̖Ȃ�A����͂������Âق��ɂ��Ă���v
�u�����͂Ȃ�܂��B�V���̑厖��Ă����āv
�u�g���̌��܂ɂ����A�������ς����B�V���ɁA�����]���悤�B����́A�����тꂽ�B�����A���A���āA���a�ȐC�̂��ŁA�Ȃ̊炪�������v
����́A�n��ɂȂ��āA���ꂫ��U��Ԃ�Ȃ������B�O�l�̏]�҂���A�R�ク�����ւ����āA��𑁂߂��B�s���l�͂Ȃ��A������܂ł��ė��āA
�u������A���F�ɉ���Ă���A�H����ɂ͂܂��A�����։����Ă䂭�B�Ȃ��A����ƁA���̂Ƃ��b�����v�ƁA�����ĕʂꂽ�B
�Ƌ��𗣂�Ă���A�������N�͂������B�ȑO�̋A���Ƃ������āA����ǂ́A�͂�����A�L�c�̉Ƃɂ́A������҂��Ă��Ă����Ȃ�����B�s�C�A�ǓƂ̍��A�ӂƓ������F�Ɖ���āA���̂��̑������Ƃ���肠�������ƍ��Ƃ́A�܂������A�S�̂��肩�����A����Ă����B
�܂��āA�i�ׂɂ��������B���̑i�ׂ��A��ɂ́A�����̐��`�ɂ���ę����Ƃ������̂łȂ������̂�m�����̂́A�҂������Ƃ����A�������A�S�̕��S�ɂ����Ȃ����A�������A���������Ƃ́A�����ł���B�ԈႢ�͂Ȃ��B
�V�̖L�c�̊قł́A������ɁA�ނ̕ւ�Œm���Ă����̂ŁA�ނ������ɒ������ɂ́A�ꑰ�Y�]���o�����āA��ɁA�M���̎��҂��Ă����B
�j�[�́A�Y�����Ԃ�𗣂ꂽ����ł������B�ł����̓��́A���ς�V���ɂ��āA��ƂȂ����r�����ȂɁA��̂悤�Ȓj�̎q������āA���̕v�܂��A����̂قƂ�ő҂��}�����B
�@ |
�����̒���
���̔ӏt�قǁA�Ȃ̋j�[���A�ǐl�����Ƃ̊�ɔ����������Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B
�����₩�ȏ��Y������������Č�A�ꂵ�����F������A���傤�ǂ��̔N�����̂����̊J�Ԃ����S�Ɏ����Ă�������ł���B�܂̂��������ƂЂƂ݂̉��ɂ܂ŎY����̏n��������Ƃ���قǏے����Ă���V�Ȃ������B
�u�킽�����͌ł��B���Ȃ��͈����Ă������邵�c�c�B����ǂ���܂�K���ŁA����ȍK���ȓ����A���܂łÂ����Ǝv���āv
�ޏ��͂܂������K���̖��܂�̒��ɂ����B�������A�L�c�̊ق̉��ӂ������ɂ��A���ƂȂ��A���Ԃ̂��킳�͒����Ă���B��ɂ́A����܂ł̐��N���A�������ޏ��̐S�������т₩���Ă��������ł���������A���̒��Ɏ���Ă��Ă��A��������A����������Ԃ̂悤�������̂̂��̂������B
�u����Ȏ�z����J�͂��Ȃ��������B�ǂ����A���܂��͂��Ƌ�J���������v
����́A�������āA���āA
�u���������s���́A�����ւ���A���ꂪ�]��ɗ���ɂȂ�Ȃ��ǐl���ƁA���܂��������Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ邼�B�Ȃ��A����̘r�ɂ��܂��Đ����Ă䂭�̂������s���Ȃ̂��v
�u���������Ȃ��B���͖����������Ă��܂��B�\�\���Ă��������B��̎��̘r�ɁA����ȂɁA���S�������ĕ�����Ă��邱�̓��̂ݎq�̂悤�Ɂc�c�ł��v
�u�����B�悭�Q�Ă���ˁv
�u�₪�āA���Ȃ��́A�����k����ł��̂�v
�u�������Ȃ��ȁB����������A���ƂȂ������v
�u�c�c�ł�����A�ǂ��������A���S����˂��āA���Ԃ��ǂ��������ƁA�Ȃɂ����ŗ��悤�ƁA���h���Ă��A�����ƁA���E���Ă��������܂��ˁv
�u�������B���܂��͂܂��A�H���̏f����吷�Ȃǂ��A�������o���ė��₵�Ȃ����\�\�Ƃ����S�z���Ă���̂��ȁv
�u�܁X�A����ȉ\�������܂��̂Łv
�u�����Ε������ŁA��������ɂ́A�ނ������A�������A�z���������������悤�ƁA�捠�̏㗌�ɂ��A����͐������A�������̖@��ŁA�i�ׂɏ����Ă���̂�����ȁB�����̐��{�����łɂ���̐�����F�߁A�@���ɏƂ炵�ā\�\�f���������̂����킾�Ă��̓c�̒n���́A�������A����ɕԂ��\�\�Ɣ����������Ă���̂��B�z��Ƃ��Ă��A����ȏ�A�ǂ��ɂ��Ȃ�܂��v
�u����ǁA�l�̐S�͗ʂ͂���܂���B����łȂ��A�f���䂳�ܒB����Y��Ԃ��Ă悱���Ȃ��Ă��A���������Ă����𗧂Ăĉ������܂��ȁB���́A�����v��Ȃ��Ǝv���܂��B����ȏ�ɂ́v
�u�������A����ȏ�ɂ͂ȁv
������A���ɁA�v���B�Ȃ̂��Ƃ́A�����ł���A�܂�������������҂̐����Ǝv���B
�����A���قǍK���ɉm�݂�����Ă��鎞�͂Ȃ��B�i�ׂɏ����āA�ނ��A���y�ɋA���Ĉȗ��A�ނ̐l�]�́A���}��������A���₪��ɂ����߂��Ă���B
(�ǎ��a�̂��Ƃ��k���ŁA�ǎ��a�ɂ��܂���Ⓦ�����̓����Ƃ���傤��B�䂭���A�����̏��B����߂�����l���́A���Ȃ���[���Ă͂���܂���)
�l���̏��n���n���́A���������āA�L�c�̖�ɔn���q�Ȃ��ɗ��A���낻��A����̎��ɂ́A�Â�������A�ނ����������鈢�����˂肪�A�W�܂肩���Ă���̂ł���B
�������A���������C�ɂȂ�ނł��Ȃ��B�ނ́A�����̎҂̂����Ăɂ͏��܂��Ƃ��āA
(����A�ƂĂ��A����͕��̗ǎ��ǂ̂ɂ́A�������Ȃ��A�s�т̎q���B����͂���̔n�����悭�m���Ă���̂��B����ǁA�����҂��s�����������āA���q�b�̂���z���A�В��肿�炵����A���x��ς�ŁA������������̂��A�Ƃ�邵�Ă͂����Ȃ�����ȁB�����������͂Ƃ́A�키��B�����܂Ő���āA�Ⓦ�̓V�n���A�ق�Ƃ̕��a�ɂ��āA�Z��������Ȃ����B���ꂾ���̎����A����̂��Ă܂���)
�ƁA�N�ɂ���l�ɂ����̂ł���B�������A���̒P���ŊJ�������Ȑl���炪�A�������āA���͂ł�����悤�ɁA�l�ׂ̋q�́A�悯���ɐ₦�Ȃ��B
���������l�ׂ̋q�͂܂��A���Ȃ炸�A�L�c�̊ق̓�������A�̉���ʂ̋ΕׂƘa�y�����点�Ă���ɏ������ċA�����B
�{�\���_����A���Y���ыƂ��A���̒n���̐i���͂��ɖڂ��܂����B�s�͏����ɗ����A��ʂ��悭�Ȃ�A�_�Ƃ̈���`���Ă��A�Q���Ă���悤�Ȋ�͂Ȃ��B�Ղ�Ƃ����A�ǂ��̒n�����A�������A�����āA�y�����S���̂��A�S�ɂ܂ŁA����̓����A�����Ă���B
���厩�g���A�悢�ȂA�悢�q�݁A���܂͉��̕s�����Ȃ��̂��B�\�\������ނ͂���ȏ�A�ނ�ȍ�悳�������̉��̕S���ɋ��߂͂��Ȃ��B
�܂��ނɂ́A���N�̍��A������M�����Ă��ꂽ���z�߂̂�����̉ڈΔ��̎����A�����v���o�����̂ŁA�z��ǂꂢ�����Ɏ����Ă���j���̂�������Ȏg�p�l�ɂ��A��ɂ�����������l�������B
�u���B�킩������B�����N���Ă��A���E���悤�B�������������Ȏ�z����J�͂��悵�v
�q�ǂ��̐Q����̂����ɗ������łɁA�ނ́A�Ȃ̐O�ɂ��A�O���ȂāA������^�����B
���ɁA���x�ƂȂ��A����Ȃӂ��ɁA�ق̖k�̓a�������˂āA���̒��̕��a�ƈ���ɐZ��ɗ���̂��A���̂Ƃ��됔�����́A�ނ̗B��Ȋy���݂ł������B
����ǁA���̊ق̕��a���A�t����H�����܂ł́A�킸�����N�قǂ̊Ԃł����Ȃ������B�j�[�̗\���́A�s�K�ɂ��������Ă����B
|
���y�Ɛl
�����B
�u��������傤�ȏH���K��͂��߂�������̑��łł���B
����̒�\�\���N�A���Ƃ��āA�����������Ɉ�@�������Ă����刯���l�Y�����́A
�u�Z�Ґl���B�������ł͂Ȃ��v
�ƁA�n�����āA�L�c�֕�点�ɗ����B
�u�ȂA���킽�������v
���̒����A����́A�����̂ɂ����̂���Ȃ̕����ɂ����B�O�̏����̉��ƁA�j�[�̖��邢�����A�����̒��̂悤�ɁA�ǐl�̏Ί���݁A���ꂩ��߂��̗̉��������݂ɏo�����悤�Ƃ������������A��O�ɑ҂������܂܁A����Y��Ă����̂ł���B
�u�䂤�הӂ������A�}�g�̎҂��A���@���āA�����ɗ��Ă��ꂽ�̂ł��B�\�\�H���̗nj����A�R�ɕ����W�߂āA����̗ǐ��̕��ƁA������ɁA���n�������킵�ĉ����ڊ�������ł���l�q���Ɓv
�u�܂��A�f�����̃J���������B���݂����ʂ̂ɁA�킴�킴�A���������ƁA��点�ė���̂����邩�獢��ȁv
�u���邱�Ƃ͂���܂���B���ق₩����厖�Ɏv���A�Z�Ґl�ɁA�D�ӂ��Ă�������c�c�v
�u���A�Ȃ��l�Y�B����͂����A���܂ŁA�f���������������m�ŁA��܂������݂ǂ댖�܂͂������Ȃ��v
�u����́A�������ł��A���l�ł����A�f�������́A���ł��A�L�c�̂���Z����A�����܂œG�Ƃ��āA�₶������Ƃ��ł���̂�����d��������܂���v
�u����ɂ���ȁB�ǂ���������Ƃ��ƁA�邽�������Ɓv
�u�[���A�������͔����Ă��܂��B�������A�H���␅��̏O�́A���̔��N�A���悢�敐��n����W�߂āA����ɑӂ�Ȃ��A�������A�������̑i�ׂł́A�������̕����A�������������ƁA�����G��Ă��܂��v
�u���Ƃ��������A����̎�ɂ́A����̏��i�ƂȂ����������傪����B�����āA�H���␅��̏f���B�ւ́A�킪�Ƃ̐����Ȉ�Y�ł���c�̂̒n�����A�������ɁA����ɕԊ҂���Ƃ������̒ʒB���͂��Ă���͂����v
�u����ȕ��́A�ނ�ɂƂ��āA���̈З߂ł�����܂���B�\�\�ނ���A�����܂ŁA�ǂ��߂�ꂽ�̂ŁA�Ȃ�����A���d�ƕ��͂ɁA�אS���W�����A�ꋓ�ɁA�L�c��j���āA�����̔s�i���A����ނ�ɂ��Ă��܂����Ƃ�����Ȃ�ł��B����ɋɂ܂��Ă��܂��v
�u�c�c�܁A�҂Ă�B�l�Y�v
����́A��̕�������܂Ȃ��̂ŁA����}����悤�ɁA�ӂƁA��C��ς����B
���ɂ��āA�����߂Ȃ��畷���Ă���Ȃ̊�ɁA�͂��ƁA�����������Ȃ��v������������ꂽ����ł���B
�u����́A�o������Ƃ��낾�B�Y�}�������A�n�������đ҂��Ă���B�b�́A�������ŕ�������B���X�A�����ׂĕ����Ă��悢�v
�j�[�̊�́A�����܂����ɂȂ��Ă���B��̋��|�͂������B�ɂЂт��āA������Ă���q�܂ł��A���̖��ɂ����m��̂ł���B�}�ɁA�ޏ��̂ӂƂ���Ń��Y�J���n�߂��B�\�\�l�Y�����̋��͂��̒��A���������Ă���v�����������A�Z�̋C�����A���ɂ�߂̐S���o���Ƃ��āA
�u���B�����ł������B�ł́A�Ƃ��������̕ӂ܂ŁA���ꏏ�ɏo�����܂��傤�v
�ƁA���肰�Ȃ��A�j�[�̕������ɏo���B
����A�����̂ӂ��肪�A�ق̕\�́A�Ɛl�������ɂ�ׂ�̘L�̂�����܂ŏo�ė���ƁA����������̉Ɩl�⏗�������퉹���A�����̂悤�łȂ������B
�u���𑛂��ł���̂��v
���傪�A�Y�}�̂ЂƂ���A����ƁA
�u�����A���̎҂��A�����̂ŁB�����āA����������z�≺�l�ǂ����A����ʎ����A��������̂ł�����v
�u����ʎ��Ƃ́H�v
�u�����A�L�c��ʂ��Ă䂭���l���\�\�L�c�͉��ƒ��̂�т肵�Ă���킢�B���ɂ��A�헤����}�g�����A�������֗���̂��m��ʋC���Ɂ\�\�ƁA�������ɁA���̕ӂ��A���Ēʂ����Ƃ��\���܂��v
�l�Y�����́A������ƁA
�u����A�����Ȃ����B���l��S���܂ŁA���������`���Ă���ł��傤�B�\�\�@����Ƃ���A�H���̏f���́A���̂����ɁA�}�g���A����̕��������āA���̖L�c�ւ����ċ}���ł���ɂ������Ȃ��v
�u���₾�Ȃ��A���茖�܂��v
�u�Z�Ґl�I�@�����Ă��������v
�u�l�Y�v
�u�͂����v
�u���Ƃ��A�����킷�@�͂Ȃ����B��킸�Ɂv
�u�A���Ȏ�����������āB�\�\����Ȃ�A�L�c���̂Ăē����邵������܂���v
�u���������������v
�u��k���Ⴀ��܂���B���Ȃ����A�L�c�̎傠�邶�Ƃ��A�y�n�̐e���Ƃ�����ŁA�������ő���������Ċ�荇���������̎ҁA�܂��A��������ȋ��̎҂��A�ǂ��ɂ��Ȃ�ƁA�U��̂ĂāA�������܂����v
�����ցA��J�ɏZ��ł����~�݂����O�Y�������A�n�Ƀ��`��ł��āA�킯���ė����B
�����́A���̒�̎l�Y�������́A�C���₳�����A�Z�̏�������A�߂����ɁA�����Ȃ��������ł���B�\�\���A���̏�������A�����������āA����A�|���Ђ������Ă����B
�u�nj���叫�ɁA���ȏ�̑啺���A�q���̓n���������āA���X�ƁA�������ė��邻���ł��B�\�\�nj��A�ǐ������́A���N�̔s��ɒ���āA���̂��т����ƁA�R�������˂��Ă���Ƃ��������́A�g�͂₭���畷���Ă��܂������\�\��͂�{���������Ƃ݂��܂��v
�O�Y�����́A�����͂��܂��āA��������A
�u�����A�q���̓n�����A�ނ�ɒf�����ƁA������́A�L�R��S�ɁA�ǂ��߂��A�키�ɁA�s���ƂȂ�܂��B�Z�Ґl�A�����킯�����Ă��������B�ꍏ���A�����܂��傤���v
�u�c�c�������B���Ђ��Ȃ��v
������A������߂��B
�������A�ނ̖��߂�҂܂ł��Ȃ��A������ɂ����Y�}�́A�فA����̖����ւނ����āA���Ԃ��ǂȂ�����Ă����̂ŁA�n���g���o���A����������Ƃ�A�O�サ�āA�b�h�̖z���ق��イ���A���傩�牝���ցA���o�Ă����B
������A��}���ŁA���g�ɒ������B���̊ԂƂāA�ނ̐S�̂ǂ����ł́A
(���₾�Ȃ��A���݂ǂ�́A�������Ȃ����c�c)
�ƁA��������u��������C���������B�Ȃ̔������A���̂ݎq���A��ɂ����āA���ɂȂ��A�Z�̏d�����A�g�ɂ��������B
���̊ԂɁA�ܘY�����A�Z�Y�����Ȃǂ��A�匋�m�q��A���߂̓@����A�킯���킹�A�܂������܂Ɏ��A���S�R�B
�u�q���̓n�����ւ䂯�v
�u�q�������v
�ƁA�܂����ɁA�킯�o�����B
�ォ��ォ��A�Ȃ��킯�������������B�D��̕��́A���̍��܂��A�݂ȁu���_�����v���A�u���_���v���A�Ƃɂ����A�ق̘Y�}����U�݂��Ă���n���ɂ�����܂ŁA���R���镐�m�Ƃ����҂͈�ʂɂ������Ȃ������悤�ł���B�u���̕���v�Ȃǂɂ́A�g���탒���c�e�A�ƃg�i�X�\�\�h�l��̂悤�ɂ͏����Ă��邪�A�ّ��Ђ����̂悤�ɁA����݂̂��ړI�ł͂Ȃ��B����Ƃ����ǁA������J����A�y�̌o�ς̏�ɁA�����Ă����B���ꂾ���ɂ܂��A�y�̑��D�ɂ́A����ɂ��܂��A�����̑������A�����Ȃ������킯�ł�����B
�����������c�B�����������n�I�ȕ��́B�\�\�]���Ă܂��R����A��������w�@���Ȃ��A�����ɂ߂ėc�t�ȍ��m���ƁA�傴���ςȊK���ʂƂ����邾���������B
�Ƃ͂����A�ؕv��Ղ̗E�ɋ߂��������_�ƁA�쐫���̂��̂̌��́A�������łɁu�Ⓦ�Ҏ҂�ǂ������v�ƓV���ɒ����Ȃقlj�������ł������B���̎��R���ɂ������������A�j��A���傪��ыN�������̂Ƃ����ė���������g�V�c�Ă傤�m�����h�Ȃ���̂��A�Ђǂ����S�Ȃ��̂ɂ����ɈႢ�Ȃ����Ƃ́A�^���̗]�n���Ȃ��B
�@ |
���ؑ��w
�u���B�x���������v
�u���܂����B�����x���v
�q���֎E�����Ă݂�ƁA�G�͂����̓n�������A�������S�ɁA�N�₭���Ă����B
�H���̗nj���叫�Ƃ�������ǂ̊�P�́A���ɁA�ނ�ɂƂ��ẮA�l�x�ڂ̗��U�ł���B
�n�̗����A����̐킢�����A�o���ɂ���āA�ނ�́A�����A��������ŗ����炵���B
�܂��A�O������A�ϑ������U��������A���̕ӂɁA�B���ȗ\���H����Ƃ��Ă���A�ꋓ�ɁA����������D��A�܂��A�����߂āA�����n���Ă��܂����̂��B
����́A��������A�G���̂����������āA
�u�{���v
�ƁA�̂��イ�ɁA�����܂��A�ނ炵������������������B�����āA
(��͂肨��́A���C�̂����Ă����̂��낤���B�ǂ����Ă��f�����́A����̎�����Ȃ������́A�~�߂Ȃ����肾�낤��)
�ƁA�ߗ܂��āA��������������B
��������Ђт����A������āA���E�𗩂����߂Ă䂭�B
�ނ̒킽���͂��������ƈꂵ��ɁA�G�̂܂��������ցA�������Ă����B��Ƃ�������āA�[���ɁA�҂��������Ă����G�̋|�́A����ɂ����āA�����̋]�����A�L�c���ɕ��킹���B
�u���A�G�́A���������ł͂Ȃ����v
����́A�������T�������B�Ƃ����̂́A���{���悤�A�c�������A�@�������ǂ��Ȃǂ̕��߂̕�������A���������n�߂����炾�B�����̏������́A�ː��͑債�����̂ł͂Ȃ��Ă��A�݂ȖL�c���̓��ł���B���[�ɁA��������Ă��鉮�������A����ɂƂ��ẮA��Ɏ������A�u�͂Â悢���ٗl�v�Ɨ��݂����āA�L�����������A���Ƃ��Ȃǂ�����Ă���A�������炵���̖��Ȃ̂��B
�u������ȁB���f���߂�v
�ς��Ă���E�J�ɂ�ɂ��̉�����A�����Ȃ�o�͂�Ƃ��ꂽ�悤�ɁA����͕��R�ƁA�܂Ȃ�����グ���B
�u�ЂƂ��сA���ꂪ�{������A�ǂ�Ȏ��ɂȂ邩�A�z��͂܂��A�v���m���Ă��Ȃ��̂��v
�ނ́A���n����ƈ�ɂȂ��āA�G�O�ɔ���A
�u�nj����A�o�ė������B���������́A����ƁA����������v
�ƁA��R�����B
���Ƃ��nj���ǐ����A�ނ̋��߂ɉ�����킯�͂Ȃ��B�ނ���A�g��ɂ����ꂽ�勛�̔w�����ċC�������t�̂悤�ɁA
�u������A���傾���v
�u������˂炦�B������˂�v
�u������������āA�킷��ȁv
�Ȃǂƌ��X�ɂǂ�߂��n���āA��u�A�ނЂƂ�ɁA������߂��B
��̊O�֏o��̂��d�v�ł���B����͈�S�s���̋S�_������ɂȂ����B�����āA���ځA�G���ɐG��A���n�̋r�������ƂɏR���炵�Ȃ���A�����̐n�����œ݂Ȃ܂�قǁA�c�����s�ɁA��Ȃ��ōs�����B�����āA���ɁA�叫�̐w�ցA���肩�����B
�������A�����炩�ɁA�nj��̂���w�̒��j�ƕ������킯�́A�����߂�Ȑ�䊂����������ɕ����Ă����n�ցA����ɁA�|���Ă��͂��A�ꕔ�ɁA���Ƃ��ㅂ߂��炵�Ȃǂ��āA�����ƁA��茘�߂Ă��镐�҂��A�G���Ƃ͂������A���邩��ɊF�A�����߂����b�h�═��𑵂��Ă�������ł���B
�u�nj��́A�ǂ��ɂ��邼�B�ǐ��͂��Ȃ��̂��B�����Y���傪�A�����͂����܂ŗ����̂ɁA�Ȃ��A����̎�����ɏo�Ȃ����v
�u�������A����A�������v
����́A�N�̐��Ƃ��A��l�Ƃ����ɂ́A����Ȃ��������A���ƁA����̏|�͂����J���ƁA䊂̔g�̏�ɁA���A���ƁA�ٗl�Ȃ��̖̂ؑ����A�_�`�݂����̂悤�ɁA�l�����グ���A���E�ɐ��\�l�̍b�h���҂��]���āA
�u�c�c�������A����A�������v
�ƁA���̂̂悤�ɁA�������낦�āA�ǂȂ����B
�u��A��H�@�c�c������v
����́A�v�킸�A���n�̎�j�����ڂ����B
�ؒ��̐l�ԑ��́A��̂Ƃ��A�����ł���B�ߊ����т̂������ŁA����̉��ɂ́A�����炩�ɁA���������Ă���B
�Ƒc���]���������������A����
�̂��A���ǎ���������̂悵���������A����
�\�\�܂蕽���̐�c�ƁA����̖S���̖ؑ��Ƃ��A�ǂ����炩�����o���āA�w���ɉ����i�߂ė����킯���B
���傪�A������ƁA�����낢���l�q������ƁA�ؑ��w����Ȃ��ė������̈�Q�́A�܂��A�������낦�āA
�u�������A���B���m��ʂ��v
�u���]���̑����Ɂv
�u�����̗ǎ����̑O�Ɂv
�u�˂��A����v
�u�����A�s�G�Ɂv
�u���A������v
�ƁA����̎�����ڂɂ��Ă��܂����ƌv���Ăł�����悤�ɁA�����߂����͂₵���B
�����āA�U�b�U�A�U�b�U�ƁA���̔g���āA�����i��ŗ���̂����āA����́A�}�ɔn��ނ����āA�ӋC�n�Ȃ��A���߂炢�o�����B
�\�\�ƌ��āA�ؑ��̑O�ɂ����O�A
�u����A��������v
�ƁA�}�ɁA�����炵���B�l�A�ܖ{�̖�A����̐������I�܂ƂƂ��āA�т���Ɣ�B
���ƁA����́A�n�̂��Ă��݂ɑł��������B�v���������B�n�͐K�͂ˏグ�āA�����ƁA������B�Ƃ���ɁA����́A���`�������Ă����B�\�\���ꂱ���A��ڎU�Ƃ����Ă悢�ނ̎p�ł������B
��騂����ǂ��Ƃ��A���̗��Ƃ����Ȃ������A������ŕ������B
�u������A�ǂ������ɂ�����v
�u�Ă����Ă�A�U�߂Ɉڂ�v
�nj��̕����́A�]��������āA����ɁA�L�c���̐[���ɐi�U���A���A���D�A���J��傤���傭�ȂǁA���S�̒�����ق����܂܂ɂ��āA���̓��̖锼���A�}�g�ւЂ��������B
|
���r�C��a�݂�
���̂����ɁA�L�c�S��т́A�����̏œy���A�����������ɁA����Ă����B���̂ݓ�l�̐��̕��a�����悤�ɁA�]���̂��ނ肪�A���̓����A���������ƁA���������߂���A���炭���Ă����B
�u�����m��Ȃ��S���̏����ׂ�V�l�Ƃ����ɂ܂Łc�c�B�����A�C�̂ǂ��B����́A����̂������v
����́A�n�ŁA���������A�������Ă��邢���B���̎S����A��Ō��A���ɕ������B
���N�B�\�\�G�n�킯�������Ƃ��A���傪�G�֗^�����ʂ�ȎS�Q���A�����́A�ނ̗̉��ɁA�������Ă����B
�K���ɁA�L�c�̖{���́A�����������B�قɂ��A��O�ɂ��A�܂��ނ̍Ȏq�ɂ��A�������Ȃ������B
����ǁA����́A�h�������B�������A�����̐��_�Ɠ��̂ɁA�ɑł������������ł���B
�~��������̏��ꏄ���āA�قA��ƁA�ނ́A���ɂȂ��A��J�̐F���������Ă����B���ŁA�ꐇ�͂��Ă���̂ɁA�Ȃ����Ђǂ��C�͂��ӂ��Ȃ��B
�u�ǂ������̂ł��A�Z�Ґl�v
�����������A�����A�������A�ނ��͂�ł������B
�u����A�ǂ�������B�������������тꂽ��A����́v
�u���ɂȂ�����F�ł����v
�u�������c�c�v�ƁA����́A�����̖j���Ȃł��B�m�o���ɂԂ��A�������A��̕����{������悤�ȋC�������B
�u�Q�s���Ƃ݂���B�Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B���̂��́A�܂����������Ă��܂������c�c�Ȃ��ɁA�������ɁA���f���Ȃ���A����Ȃ��ȕ������͂��ʁv
�u�ނ���A�������́A�悩�����Ǝv���܂��B�\�\�]��ɂ��Z�Ґl�́A�����̋C�����ŁA����ʂ肷����B���ꂩ��́A�������̂��Ƃ��A�����ƁA�����ĉ�����ł��傤����v
�u�c�c���������v
�f���ł���B����́A����ȑf�����A�킽���ɂ���A�������āA�ǂ��������Ƃ��ƁA�S�ڂ����B
�u�����A�����āA�Z�Ґl���A�������������āA���ӂ߂���킯�ł͂���܂���B�\�\�����A�����Ɋ댯�ȑ��苤���A������A�������_�ɒm���Ă����Ă��������Ȃ��Ɓv
�u�킩�����B�����A�s�o�͂Ƃ��B���������ǁA����̖{���̗͂��A�v���m�炵�Ă����K�v������B�O�Y�A�l�Y�v
�u�͂��v
�u�߂������ɁA���Ă����B�������A�[���ɁA�Y�}��n���x�܂��Ă����Ă���v
���ꂩ��A�\���قnj�ł���B
����́A��������ނƁA������Ȃ�Ɛl��킽�����āA���S�Ȗ��c�����炵�A�锼�A�L�c�̕����]���������āA�q���̍]���n�����B
�����́A�l���̑�́A�]�������킹�Ă��A�ǂ���萅��n��ŒZ�����ł������B
�Ȃ��܂��œV���Â������ɁA�ނ́A�G�̂ɋ߂�������ق������x�z�̓n�����߂ɖ����܂��ӂ������B
����䊂��H�����L�т邾���L�т����Ă���G�߂ł���B�����ɂ͎��Ă����B�����āA�g�Ђ�ɋ��ꂽ�胄�u��ɂ����ꂽ��̒��ق������Ɯ����炦�āA�₪�Ă̐�@��҂��Ă����B
�u�c�c�����ʂ��A�܂��v
�u�͂āA���Ȃ��Ȃ��v
���̓��A�H���̗nj����A����̊�P�ɖ������߂āA�ӂ����сA�L�c�֏P���Ă���Ƃ������A�O���ɒT���Ă����̂ł���B
�\�\�ƁA�ʂ����āB
�z�������Ȃ������A�}�g�A�헤�A����̕������킹����R���A����ƁA���ւ̉e�������Ă����B
�n���ցA���������B
���ɂ̂�A�n���A�ɉg���A����w���A�݂��ꂽ�����v���āA���傪�A
�u�˂�v
�ƁA�}�ɖ��߂��������B
�G�́A�T�������B�]�̐��́A�Ԃ��Ȃ����B
�������A�nj��̕����́A�捠�ɂ��܂���啺�ł���A���炩���߁A�r���̕����ɂ́A�v�S�����Ă����炵���A�����܂��A�������A����Ԃ��āA
�u������Ȃ�B���傤�����A����������ǂ�ɂ���v
�ƁA�������Ă����B
�ǂ������̂��A���̓��A����́A��������ƁA��������Ă����B
�u�͂āB���Ԃ������v
�u�����������A�Z�Ґl�̗e�q�悤���́v
�ނ̒킽�����A���ꂪ�A�ꖕ�̗J���ƂȂ��āA�[���ɁA�킦�Ȃ������B
�\�\���R�́A��ɂȂ��āA���������Ƃ����A����́A���łɂ��̉č�����A���̐����n���ɑ������y�a�Ƃ�������g�r�C�������h�ɂ������Ă����̂ł���B
���̑O�́A�q���̓n���̍���ł��A���ƂȂ��A�S�̂����邭�A�����āA�����Ⴆ�Ȃ��S�n�����Ă����̂��B
�\�\��ɁA���̓��́A�Â���������A���n�̈��␅����̑������n�ɔ������Z�����Ă����̂ŁA�}���ɗe�Ԃ������Ȃ��Ă����B�����ɁA���C���ɂȂ낤�Ǝv���Ă��A�C���҂������Ȃ�Ȃ����A���A���n�����R�ɂȂ�Ȃ������B
���̂��߁A�ϋɓI�ɁA�����܂œG���}�������ɏo�w���Ȃ���A�ނ̌R�́A�ӂ����сA�݂��߂ȑދp���A�]�V�Ȃ����ꂽ�B
�u����̗E�҂��A�ꂪ�������B�����ނ̍��͂������Ă��邼�v
�nj��́A�����ς��B
�u���傤�����́A�������̂Ƃ���܂ŁA�L�c���U�߂�B�����炭�A��ɂ́A����̎A�킵�̑O�ɂ������邾�낤�v
���������āA���X�ƁA�ێ肱��������āA�ۂ�炳���A���������A������̌R�̓���̂悤�ɁA�L�c�֔������B
�����āA���̑O�̂悤�ɁA�s�����̖��Ɠԑq�Ȃǂ��Ă����āA���ɏ���̖{���ɂ܂Ŕ������B�����͌S�̒��S�n�ł���A����ق̖�O���Ȃ̂ŁA�l�Ƃ����č���ł���B���̉����A�����܂ǂ����q���̔ߖ��A�����܂��A���@�������т��傤��������o�����B
��m��ɁA�������B
��m�����A�ق̐�����A�͂≊�ɂ���܂�A�̉��̉���ɂƂǂ܂炸�A����̍Ȏq���Z��ł���k�m�a�܂ŁA���́A�]���Ȃ������o�����B
�@ |
���a��
�u�ǂ��������Ă����B���肾�B��B�L�c�̊ق̉^�����A�������I��Ƃ݂���v
�G�̍U�������ނƁA�������āA������C�����ޗl�q�������B�H�T�̖؈��ցA����������A�����A��ꂫ�����悤�ɁA�n�̔w�œf���Ƃ����������B
�u�Z�Ґl�B�撣���Ă��������B�����̌Z�Ґl�炵�����Ȃ��v
��̌ܘY�����܂��Ԃ݂́A�Z�̖��C�͂ɁA�ՁX���炢�炵�Ă������B��̍��ɕt���Ă����v�̐����������āA�n�ォ��n��ցA
�u��������܂����A�Ђƌ��A������������ɂȂ�܂��v�ƁA��n�����B
�u���A���肪�����v
����́A�����A�����A�ƍA�̂ǂ�L���Ĉ��݂��������B�ق��Ƒ��������B�����āA���̎���������炶�イ�̊����A�Z������낢�������̑��ʼn��ɂ��������B
�u�����B�\�\�O�Y��l�Y�����́A�ǂ��������B�p�������Ȃ��Ȃ������v
�u�ق��̌Z�B�́A���킵�āA���납�܂ɂ�̊O�ւƁA�G��ނ��Ă��܂��B�����A����S�Ȃ����܂��v
�u����A�G�͐V�肠��Ă������Ă���B�����܂ŁA�U�ߓ����Ắv
�u�ǂ����āA�����Ɍ����āA����Ȏ㉹���˂����ӂ��ɂȂ��ł��B�Z�Ґl���炵�āA���C����������ł́A�m�C�͂ǂ��Ȃ�܂��傤�v
�u�����A����B������̊ق��A��O�����A��~�݂����̌������A�݂ȉ≌�ɂ���܂�Ă���B�ނЂ��Ă͏P�悹�A�ނ��Ă͏P���ė���G�ɁA�����h�����Ă��܂��Ắc�c�v
�u�ǂ����A���̂ł��A�������̂ł����v
�u�ȂɁB�́H�v
�u���炪�A��̓�{�ɂ��A�c�ӂ���Ă��܂��B���܁A�C�����܂������v
�u�������B�c�c����A����́A���Ƃ��Ȃ����B�̂́A��̒ʂ肾��v
������܂ł��Ȃ��A����͎��o���Ă����B�����̊�łĂ��A�܂������m�o���Ȃ��A�S�g�͏d���A�E�C�̌��@���A���Ȃ���A���ǂ����������B�������A�a�C�̂��Ƃ����́A�܂��A�킽���ɂ͔邵�āA�����A������ʑԂ����̂������B
����B��~�O�Y�����A�刯���l�Y�����A���̂ق��Z�Y�����Ȃǂ̒킽���́A����ɐ���āA�G���A�Ƃ����������܂Ō��ނ����̂ŁA
�u���ǂ��́v
�ƁA���܂��ߍ����A
�u�Z�Ґl�̂��g�̏ケ���A�Ă�����v
�ƁA����������āA����̎p���A�����������߂ė����B
�����āA�����ɒ��Z�̖��������āA��낱�э������̂��A���̊ԁA�G�͂܂��A�������̕Ԃ��悤�ɁA�V��𗧂ĂāA�P���ė����B
�u�����́A���炵�āA�h���܂��B�Z�Ґl�́A�قɂ��閡�����܂��ĉ������B�ق��Ă��āA���q������A����肭�������v
�킽���̂����߂ɏ]���āA����͘Y�}��A�O�\�R����āA�������̍ԂƂ�łƜ����̂ޖL�c�̖{�@�ւЂ��Ԃ����B
�������A�����̍�傩��A��Ɖ����܂ŁA�̎�͑傫������Ă���B�Ɛl��z�X�����̒j���܂ŁA��������ŏ��ɓw�߂Ă�����̂̉��̖h���ɂȂ낤�Ƃ������Ȃ��B�����K���Ȏ��́A�́A��щɂ����̂炵���A�G���̉e�́A�܂������܂ł͐N�����Ă��Ȃ������B
�u�j�[���B�c�c�j�[�͂ǂ������B�j�[����c�c�v
����́A�L��������A������A������A�������ČĂтʂ����B�ޏ��̂���k�̓a���A�����Ԃ��Ă�������ł���B
�u�������A���ق��v�\�\���̒�����j���悤�ɁA�Y�}�̗��ۂȂ��܂邪�A�ނ������āA�킯����ė����B
�u�k�̕��l���n�߁A���[�O���V�c���A�݂ȁA�匋�����䂤�m�q�ցA�����ނ���܂����B���̗L�l�ł��B�����A��������A�h���͂��܂���B�\�\�a�ɂ��A�匋�ւ������������܂��悤�Ɂv
�u���ɁA���߂��v
�����́A���������藧�ĂāA��̋y�Ԃ�������A�̊C�Ƃ��Ă���B�������A�G�e�͌����Ȃ����A�ǂ�����ƂȂ��A�G�̖�́A����Ȗ����ڕW�ɏW������Ă����B
���̗ǎ����A���U�������āA�y�Ƃ��������A�l�ׂƐ���āA�z���̂����������A�����Ƃ��ɊD����������ɋA�����Ǝv���ƁA����́A�������قƋ��ɊD�ƂȂ�̂��A���������ɕ��݂����Ɏv��ꂽ�B
����ǁA�j�[���v���A���̂ݎq�̊���������ƁA���̂܂܂ɂ́A���ɂ���Ȃ������B
|
�����Q�̑�
�L�c��т̉́A��ɂȂ�ƁA���悢�悻�͈̔͂��A������傤����̂������ɁA�g���Ă����B
�j�[�́A���̂ݎq������āA�q�̔n�����̒��ɁA�g���Ђ��߁A
�u�킪�ǐl�܂́B����l�́v
�ƁA���ɏ]���Ă���V�b�̑����o�������̂˂����ɂׂ̂u�˂Ă����B
�o���́A�܁X�A�u�ւ̂ڂ��āA�Ԃ������Ȃ��߁A�����̐��U�ƁA�������d���ė����O��ǎ�����̔����I�ɘj�킽��y�̗��j���ӂ肩�����āA
�u���������N���������B�܂��A�Z�����̊Ԃ̖��ł��������B��̐������́A�����m��ʂ��ɁA�I�v�ƁA�܂������Ă��邱�Ƃ�B�\�\���S�N�A����N�A����̂悤�ȋƉ�����������Ԃ��āA�����̓y���A�ق�ƂɁA�Ђ��Ȃ����y�ɏZ�߂�y�ɂȂ邱�Ƃ��H�@�c�c�B����A���肠�閽�ł́A����͌��ɂߓ��Ȃ����̂��A�킵�͗]��ɒ����������߂����悤���v
���\���������V�b�́A�����ė�͂���������ɏՂ���邱�Ƃ��Ȃ��A�܂��A�܁X�ɁA�j�[�̂��֖߂��ė��āA
�u�܂��A���ٗl�́A�K���ɁA�䍇��ƌ����܂���B�G��ǂ����肼���Č�A���Ȃ炸�A�������V���܂��傤�B�]��ɁA���C�Â����Ȃ����ƁA�a�q���܂́A�������̏o�ɂ��Ⴓ���܂��傤���B�������^���ɂ��܂��������āc�c�v
�ƁA�����������꒲�Ŕޏ��̖\���̂悤�ȕs�����Ȃ��߂Ă����B
���̂����ɁA���������������A�h������j��ꂽ�l�X���A�����������悤�ɁA���̑匋�m�q�ցA�����ނ��ė���B
�₪�āA������B�܂������A�����������A�u�c�O���v�u���O���v�ƁA���X�ɂ����тȂ���A����Ȃ��ꍇ���ė����B
�u�����Ȃ��ẮA�ꎞ�A�������ɐg����߂āA�ċ���}�邵������܂���B�Z�Ґl�́A���̂�������ʌ�l�q�䂦�A�ǂ����A�����𗎂��āA��{���ɓw�߂Ă��������v
�ނ̒퓙���A�V�b�̌o�����A�܂���Ȃ�Y�}�ɂ��Ă��A���ׂĂ��A�������ʂ������傤�̋}�Ƃ��āA
�u�j�[���܂��A��ꂵ��Ɂv
�ƁA���≞�Ȃ��A���Ă��Ȃ��n��I��ŁA�n�̔w�ցA�����������B
����ƁA�o���̂������ŁA�����܂ŁA�Β�����^�яo��������̕i�X���A�\�����̔n�ɐς�ŁA
�u�ꍏ�������v
�ƁA�匋�m�q�̋u����A��̞D��ցA�}�������B�o���͂��̌�ŐS�Â��Ɏ��n�������B
����ɂ͋����ȘY�}���l�A�\�R�قǏ]���čs�����B�ނƋj�[���悹���̔n���܂ɂ��āA�s�����Ă��Ȃ��A���̖�̊�n��E�����̂ł������B
���́A�킸���ȘY�}�ƁA�Ȏq����ď���͐����̂������A�ޕ��������Ȃ����Ȃ��A�����܂�����B
���߂̎l�A�ܓ��́A���������J��(���Ñ�)�̋��v�̉ƂɁA�Ȏq���B���āA�߂����x�����Ȃ���������Ă������A��@�ɏo�������ۂȂ��܂��A���艺�������ׂ̎q�t�ۂ������܂�Ȃǂ��A�����A���ė��āA
�u�������A�����ł��B�nj��̕����A���������A�_�Ƃ̈ꌬ�ꌬ�܂ŁA�L�c�̎c�}�͂��Ȃ����A��������܂��Ă͂��Ȃ����ƁA�i�������Ȃ���A���ו����Ă���悤�ł��v
�ƁA�����B
�����B�܂��Z�Y�������A�\�R�����āA�����։����A
�u�O�Y�Z��l�Y�Z�́A�����������āA�����֗����čs���܂����B�Z�Ґl���A����ȋ߂��ɂ��ẮA�����ł��B�\�\�G�͖L�c���̂��āA�����ق���A���̍����Ă��A����ǂ́A����̎�������ċA��ƍ��ꂵ�Ă���̂Ɂv�ƁA����̖��f�������߂��B
������A������A�o���Ƃ�Ȃ��ł͂Ȃ��B����ǁA���̂ݎq��������j�[������܂Ƃ��Ȃ̂ł���B����ƁA�����̕a������̂����A�Ȃ��A�Ȏq�Ƃ̕ʂ��C��������`���B
���A�댯�́A���̂ق��ɂ��A���낢��A�g�߂ɁA�������Ă����B
�u���������Ȃ��B�����̊ԁA���т����v����E��ł���B�����ƁA�~�̏������~��ʂ܂ɁA�ȑO�ɂ܂��閡�����̂��āA�H���͂Ƃ�A����݂���̓G�ɁA�t�P�����悹�����킹�A�����āA���Ȃ����}���ɗ��邩��c�c�v
�j�[�́A�ǐl�̂��̌��t�ɁA�܂Ȃ���A���Ȃ������B����A���̍��ӂ����A�ӂƂ���ɖ����Ă����c�q�����Ȃ��ցA��̖j������悹���܂܁A�܂̖ʂ��グ�Ȃ������ޏ��̂ق�Ƃ̈ӎu�́A
�u���ł��B�c�c����ł��A�����̂́c�c�v
�ƁA�悭�ʂ�U���Ă����̂����m��Ȃ����A����̊���A������ɁA�[���Ȋ�����ނ��Ă����Y�}�������A�ޏ����A�����̍Ȃ炵���o��̂��ƂɁA���Ȃ��ɂ��A�����Ȃ��������̂ƁA�F�A���Ă��܂����B
�O�z�̋��D���p�ӂ��ꂽ�B
���D�̏�́A��������A�ςƂ܂�~���Ȃ�ׁA���ɁA�H�Ƃ�A����A�����ĖL�c����^�яo�����d��̈ꕔ���́A���ׂĂ�ς݉B�����B�������z�ɂ́A�j�[�Ə����߂̂��ׂ⏗�[���������A�ׂ̓��z�ɂ́A�\�]���̘Y�}���悹���B�����Ĉ����J�̓��]����A�C�̂悤�ȌΏ�ւƁA��ɁA�����̂тčs���ƁA���������B
�ނ̍Ȏq���̂����O�z�̓ϑD�Ƃ܂Ԃ˂́A�Ȃ�ׂ��A�����т悵�̖݂��������āA���a�Ȑ����̂悤�ɁA�܂�ꒋ����A�k�֖k�֓����k��A�₪�čL�͂Ђ낪��̍]���̂�����ɁA�[���D�e���Ђ��߂āA�ЂƂ܂��A�������B��ꏊ�Ƃ��Ă����B
����́A���H�����ǂ��āA�Ȏq�̗��������A���Ƃǂ�����B
�u�킸���̊Ԃ̑D�Z�������B�����́A�҂����ʁB���Ȃ��A�a�C�����ʂ悤�A���Ă����v
��������F�����B���̕ӂ�̏H���b����Ă��ɂ��Ȃт����̎⛋�������ɐɕʂ̊���A�Ă������B�����Ĕގ��g�́A�萨���Ђ���ė��Ղނ֊�(�����鑺)���߂̎R���ւ����ꍞ�̂ł������B�@
�@ |
���H���J�E
���Ƃ��ƂƁA�����H�J���Â����B
�R���ɁA�������@��A���̌��ɁA�ۖ�g�݁A�̔�ʼn����ӂ����悤�ȏ������A�ނ̓����̉B��Ƃ������B
�����悤�ȕ����A���̕��߂ɁA�y�I�ǂ��̑��̂悤�ɍ���āA��]�Z�A���\�R���A���̎R�˂������\�����A������ɁA������������A���U���������Ƃ̘A�����v������A�܂��H�Ƃ̗�W�߂ȂǁA�c�X�Ƃ��āA�Ƃɂ����A�ċN�̈ӋC�����́A�����ς��Ă����B
����Ǐ���́A�����֗�������������A�܂������A�a���d���āA�Q��������A�g���������ł��Ȃ��Ȃ����B
�r�́A�M�̂悤�ɑ����A�w�ň����ƁA�ӂ��������ڂށB��̂ނ��݂��A���������ނ��Ȃ����A�S�g�̂��邳���A�C�������Ă����Ԃ͂܂������A�R�ւ�����Ă���́A�킪�g�������A���ė]�����肾�����B
�u�j�[�́A�������B�c�c�a�q���A�ς�͂Ȃ����v
��߂��Ȃ�����A�������́A���ɉ��x���A�u�����Ƃ�Y��Ȃ��B
�u�������������Ȃ��c�c�v
����̏����́A�Y�}�������A�Ђ��Ђ����ŁA������Ԃ₭�̂��A���x���������B�\�\�ق��̏����A�����Ȃǂ̌Z�ƁA���Ƃ��A�A�����Ƃ肽���Ǝv�������A�ւ��ɁA�ӓ�����ƁA�Ȃ��L�c���߂ɏ[�����Ă���G�̖ڂɂӂ�āA�����̎R�˂��A���Ƃ��霜�����ꂪ����B
�u�����A�����ցA�G�ɏP�悹��ꂽ��\�\�v�ƁA�l����ƁA�����́A�g�̖т��悾�����B���Ƃ��A���Z�̕a�C���A�ꍏ�������\�\�ƁA�������F����̂́A���̖�a����A��ɓ����B
����ƁA�ǂ����āA�m�������̂��B�S�������ǎ��̗F�l�ŁA���Ȃ���A����̐g�ɁA���ȓ���������Ă��������i�s���A������A�����ɗ��āA����̕a������A
�u����́A���Ȃ���ʕa�ł͂Ȃ��B�킵���A���ē����a�ɂ����������Ƃ�����B���̖��͂��Đi����v
�ƁA�����ċA�����B
����́A���̐l�̂�����p���q��ŁA
�u�����A�\���킯���Ȃ��B���̐l�ɂ́A�����������炦�Ƃ����ƁA�����A���E���厖���Ƃ�����ӌ����悭�f���Ă����̂Ɂc�c�B���ɁA����Ȃ݂��߂Ȏ����̎p�������āv
�ƁA�a���ɁA�܂𗬂��Ă����B
�����̌�A�i�s�̎g�����A���͂��Ă悱�����B�܂��ςẮA�������x�ƂȂ��A���̖�����݂Â����B�����قǁA�A���悭�o��B����ɔ�Ⴕ�āA�C�����ۗ����킾���đu���ɂȂ��Ă����B
����́A�ЂƂ��ɁA
�u����͖���I�v
�ƁA�吺�ł������B����ƁA�̖ؗ삱���܂��O������(����́A�Ȃ����)�ƁA����ɘa���悤�ɁA����������B
���̂ɁA���N����ѕԂ���A���̌��N���A�ނ̔ނ炵���ӎu�C�͂��A�������Ă���ƁA
�u�͂āB����͂ǂ����āA����Ȗڂɑ������Ă���̂��B���n�����Y����Ƃ�����҂����B����́A�����āA���܂ɕ����ĉ��ւ��ނ悤�Ȓj�ł͂Ȃ��B�c�c�������A����͍���ɔs�ꂽ�̂ł͂Ȃ��A����͂��̂�̕a�C�ɕ������̂��v
�ނ�ނ�ƁA����ȍl���������A���𝪂������Ă����B�g�݂̂��߂����A�N�����炩�ɁA���ɂ��A�ň��̍Ȏq�́A�����ȑD�Z�����v���ɂ��A�ނ́A�S�ɁA�⍦�̋|���A�Ђ����ڂ��āA���������悤�Ȕ����������B
�u�ǂ����A����̊�́B�c�c�������������͂���Ђ����낤�B�Ŗ@�A�������܂��Ȃ��ė����B��������Ă��A��S�̂悤�ɔ������܂��v
�\�\���̒��́A�킯�ď���́A�C�������������B���Z���ɂ͑ς��Ȃ��Ȃ�A���łɒ��̉��̒�������ċA�����B�����đ吨�̘Y�}�����Ƌ��ɁA�G����̎������������ٗl�Ȋ��ɁA�����̓��Ȃ��t���Ԃ��āA���₩�ɁA�H�ׂĂ������ł���B
�N���A�[����A�킯����Ă���B�{�\�I�ɁA�݂ȗ������B�������A�����̕����̎҂Ƃ킩�����̂ŁA�����ɂ܂��A��������������ƁA�߂Â��ė��������̂��̕����������A���X�ɁA�����ւ��\�\�Ƃ����Ȃ芫���߂����B���̐��ɂ��A�\��ɂ��A�������ɁA�ꓯ�R��������Ƃ�����\�\�����Ȃ�ʂ��́\�\���������B
�u�k�̕��̑D���P��ꂽ�v
�u�G�ɒm���āA�j�[���܂�A�a�q�l�܂Łv
�オ�Ѓb��āA�������A�������A�����Ȃ��̂ł���B���X�̐��݂͂ȁA�Ƃ������́A�����֗��āA�Ƃ���ɁA������ƈꂵ��ɓf�����⋩�ł������B
�u�Ȃɂ��v
����̂���ɂ������鐺���A�ӂ邦���g���āA���Ƃ́A
�u�j�[��A�a�q���v
�ƁA����������ł���B
�O�̂ق��A���̂�����Ȃ�����A�����ƁA�����ς��Ȃ���A
�u�����ƁA�ڂ��������B�G�Ɍ������āA�ǂ������̂��H�v
�ƁA����Ǝ��̌��f�����B�����āA�����̎O�����A�ɂ݂����B
�u���c��A���p�������܂���B�c�c���ɂ��D��A���Ȃ����Ȃ��ɁA��߂��̑����A�����̘Y�}�̎��[�́A�̂Ă��Ă���܂������v
���ׂĂ��I��Ȃ��܂ɁA����́A�R���킯����Ă����B�������A���ׂĂ̔ނ̕������A�R�Ȃ݂̂悤�Ȑ������Ȃ��āA�ނɋ킯�Â������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�[�ɋ߂����n�ɁA�����̔n�\�������B���Ă���B�ނ́A���̈ꓪ�ցA�Ƃт̂����B������ɁA���������ė��悤�Ɨ��܂��ƁA���ł͂Ȃ��炵���B�ނ͂����A�ނ̍����Ă����������ցA�킯�Ă���B
���Պ݂���A�ނ̍Ȏq�̑D�̂���Εӂ܂œ�A�O���͂���B���̊ԁA����́A������Ɍ����Ȃ������B
�b���ƁA�����߂Â����B
�ӏH�̑�C�́A��������A�ЂƂ̕��݂����ɁA������ƁA���݂����āA�����ɁA���������������A�^�킹��B�]��ɂ��A���R�́A���a�ł��������A����������قǁA�������H��[�߂Ă���B
�u�c�c�j�[���v
�n���~�肽����̐����A���ւЂт����B�������т��A�ނ́A���s�̎��̂悤�ɁA���x���A���ւނ����āA�J��Ԃ����B
�u���A���c�c�j�[�c�c�v
�₪�ẮA������ނ��сA�����܂ƂȂ�A�����āA���남��ƁA��������A�s����ꂽ�悤�ɁA��������āA�ˑR�\�\
�u���ꂾ���B���傾�B�c�c�j�[��v
�ƁA���̒��ցA���Ԃ��ԁA�����͂����čs�����Ƃ����B
���łɁA�ォ��킯�ė����ʁX���A������̒n����A���F������A�����āA���ԂɁA���ɐ����݂āA���݂����Ă���j��D���������肵�āA�n����ŁA��s�o���A�������Ă����̂ł���B
�u�����B�ǂ��ցB�c�c���ٗl�A�ǂ��ցv
����̈ٗl�ȍs�������āA�Y�}�̂ЂƂ肪�A�����Ƃ߂��B�������������āA������܂����B
�u�������A�������B�c�c�����ʂ��v
����́A���낵���͂ŁA��l�͂˂Ƃ����B
�����́A���ɁA�����݂��āA
�u���A���Ԃ̂��������܂��B�Z�Ґl���A���̑D�ɂ́A�N���A����܂���B�j�[���܂��A�N���c�c�v
�u����B�c�c����c�c�B����ɂ́A������B�c�c�j�[���A�a�q���v
�u���������B�݁A�݂�ȁA�����֗��Ă���v
�ƁA�����͐⋩�����B
�u�\�\�Z�Ґl���A�����Ȃ��ꂽ�B�c�c���A�Z�Ґl���A�ǂ����A�悻�ցA�S���ōs���Ă���v
|
���S�L
���ꂩ�A���������҂��A�������̂����m��Ȃ��B
�H���̗nj��́A����̍Ȏq���A�Ώ�̓ςƂܑD�ɁA����ł���̂��A���ɁA�����̎茜�肩��A�m���Ă��܂����B
���łɔނ́A�L�c�S�̖{�����A��̂��āA�T�S�낤�����A���D��Ⴍ���A�j��A��肽������Ȃ��Ƃ͂�����B
�������A�ނ̖{���̖ړI�́A����ɂ���̂ł͂Ȃ��A���ɏ���̎�����邱�Ƃɂ���̂��B
����ȏ�����킵�����Ƃ́A�nj��ɂƂ��āA�Ȃ��ꖕ�̕s�C�����̂����Ă���B���ނ��A�����������イ�������āA�ɏo�Ă��邩����Ȃ����A�����́A�}�g�H���̎����̗��炪�A�s���ɂȂ����B
�u���������B����Ԃ�A���͖������B�ЂƂ܂��A�H���ֈ��g���悤�v
�M���̓r���Ŕނ́A����̍Ȏq�̋��ꏊ��m�����̂ł���B�ŁA���̂��ߋ}�ɁA����ς����̂��B���삱���́A����A��ԖA�����J�Ɛ��H�ɓY���ė��邤���A�ӂƁA�̓��݂ɋ߂����̒��ɁA�O�z�̓ϑD���A�w�݂悵�����Ă���̂��������B�������A���̈��z�̓ςɂ́A�d������������ނ��������Ă������B
�u����ցA�ˍ���ł݂�v
�nj��́A���ɁA�|�𑵂��������B
���S������̖�����A�ꂹ���ɁA�ςւނ����āA�����ꂽ�B������̂ł͂Ȃ��B�ς̉��ɂ́A���Ƃ��A���������l�Ԃ̔ߖ��N�����B
�j�[�̎��ɂ��Ă����\�����̘Y�}�́A�����ǂɁA�D����o���āA
�u����܂Łv�ƁA�D���߂Â��A���C���ɂȂ��āA�a�肱��ŗ������A�����́A��ɂ������āA�����ɗ����A�݂҂��A�ȂԂ�a��ɂȂ��āA�����ɂ����B
���̈��z�ɁA�nj��̕���������āA�������̓��z���A�݂։g���ė����B���z�́A���[�⏗������Ȃ��ׂ���ł���B�nj��́A
�u�j�[����߂�B�Ђ�����グ�āA���������v
�ƁA��߂��Ă����B�������A�D���A�߂��ցA�g����ė���܂łɁA�j�[�́A����Ƃ̒��ɐ������\�\���̏t�A������̈������\�\����قǕv�w�ӂ��肪�삽�܂Ǝ���������ł������̂��A����Ƃ��āA��̎�Ŏh���A���������̐n�ŁA���Q���Ă����B
�nj��́A�����A�ޏ��̍s�ׂ��A���ɖʑ���ɂ����C�������B�\�\�ނ͂Ȃ����ł��v������ł���B���āA�����̈����ʒ����p�����������̂́A���傪�����̂Ƃ��Ă��邠�̂Ƃ��̊���B���̕��Ȃ��ׂ����̂����������߂̋ƕ������͂�ł������ɂ������Ȃ��B�j�[�̎��[���A����ɏR�����A�Ȃ��߂̂Ȃ�����������������̏��[�����܂ŁA�����̎c�s�ȏ��u�Ɉς��āA�H���ֈ����g���čs�����̂������B
�\�\���ꂪ�A���̂��́A�[��ł������B
�_�@����т�����߂��ӂ�̏�́A�Ȃ����̂܂܂ŁA�]��̐��X�����ɁA�납�炷���߂Â��Ă͂��Ȃ������B
����́A�ꂽ��́A�������ɁA�����ɂ����������������B�L�Ȃ��Ƃ������߂��Ƃ����Ȃ��{�����Â��Ė\�ꋶ�����B�X�ԂƂ����ΏX�ԂȂقǒQ�����B����ǁA���̎���̞D��̐l�Ԃ́\�\����A�����Ȃ݂���s�l�݂₱�тƂ̊Ԃł��A��{���y�̊���𐳒��ɂ���킷���Ƃ́A�����������̐l�Ԃ̉��l�����܂����Ȃ������B����̕����́A�ނ���A���傪���炵�̂Ȃ��قǁA�L�Ȃ����苶�����肷��̂����āA�S��ł��ꂽ�B�����Ĕނ���܂��A���������Ǝ�����ŋ����A�����͂Ȃ݂��������肠���A�����ėy���ɒ}�g�̎R�e��]��ŁA
�u�݂�A�݂�A���̂�S�{�������߁B�킷���ȗnj��v
�ƁA����U�������A�Â܂Ȃ����Ĕl��҂��������B
�ނ�̂悤�Ȕ����n�l�̂������ɂ��A�Ȃ�������c���҂ւ̈����Ƃ��݂͂������B����キ�Ĕ������ƂȂ��҂��s����������s�ׂފ���́A�����T�O�ł͂Ȃ��A�{�\�̂܂܂ȋ�����ттĂ����B�]���Ă��̌��ʂ́A���N�̎j����`����B��̌��T�Ƃ�����u����L���傤���v�̋L���ɂ��A
�\�\ৃR�R�j����A�{�y���G�m�n���j���W�\�N�����T���A�����t���������������m���Y�A�\�m�g�n���L�i�K���A�\�m���n���Z���K�@�V
�Ƃ�����A����ɂƂ��ẮA�v���I�ȈÍ��U�ɖꂽ���̂ł͂��邪�A�������A�ނ̕������A�ނƋ��ɚL���A�ނ̈�g�ɁA�S���������������Ƃ́A���Ȃ��̂ł������낤�B������]���Ɠ�������߂āA����̏������傤������������Ԃ߂��ł��낤���Ƃ́A�z���ɓ�Ȃ��B
|
���x�m�R����
�����ǁA�p�����������O�Y������l�Y���������́A�f���̗nj������A�}�g�A��ƁA�������ɂ܂��A�L�c�̏œy�ցA�A���ė����B
�����̔s�k�ŁA�����͔����ȉ��ɂ��A�����Ă������A���ꂪ���n���ɕ�����ƁA�������āA�ȑO�̐��ɔ{����قǂȐl�����A�R�쑐�܂ŁA�Ă����Ԃ��Ă���L�c�S�֏W�܂��ė����B
�u�ЂƂ܂��A�Έ�m����Ђ낰�āA�Έ�ɂ��Ă����낤�v
�Έ�́A�L�c�̗S�ŁA�����S�̓��ɂȂ�B
������₪�āA�����ɋA���ė����B
���̐Έ䎞�ォ��A�ނ̐��i�A�ނ̐l�Ԋς́A�������Ɉ�ς𗈂��Ă���B���̌������A���̏H�̌Ώ�̔ߌ��ɂ��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�ۂ���ƁA�n���݂����ɁA���ق�����������A����ɂ��Ă��邱�Ƃ����邩�Ǝv���ƁA���ׂ������Ȃ��Ƃɂ��A���{������A�܂����������傤�����肵���B
�u�Z�Ґl�́A���̓�����A�܂��������ςł����v
�ƁA�����́A��̏����⏫���ɂ����₢���B
�킽���ɂ́A�v�����[�����Z�ł��������A���̍��́A�ǂ�������ƁA���̒킽������A�����Ȃ��ɁA�ǂȂ���鎖������B�����āA�Ƃ�����ƁA
�u�������v�ƁA�����o���̂ł������B��ʂ́A�ȑO�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�同��~���Ȃ���A���������ł��A�����Ȃ��ӂ��ł������B
�u�{���Ă��A�{���Ă��A����͂܂��A�ق�ƂɁA�̂Đg�œ{�������Ƃ͂Ȃ��B����͂���ɁA�������̂���ɂ��܂��鈤�����҂����������炾�B�c�c�����́A�����Ȃ��B���E�Ԃ�����Y�^�Y�^���B�����܂ł́A�g�ɉ���Đ���Ă������A���ꂩ��́A���ꂩ��킢��z�����Ă��B�\�\�����ȂĎ��ɏV���\�\�v
�ނ́A������A���x���������B
�C�̂������A����̑��e�܂ł��A�O�Ƃ́A����ė����悤�ɁA�N�ɂ��v�����B���Ƃ������������A�������A�������������A�����Ă���B�Ƃ߂����łȂ��A�����A���킵���A�O�́A�����̂����������сA�j�[�Ɍ����Ă������̔���A�킪�q�����₵�Ă������̘a�₩�ȕ��̏��ڂ́A�����i���ɁA�ނ̖ʏ�ɉ����ė��Ȃ����̂ł������B
�~�̏��߁B�����A�~�̏��߁B
�ނ́A����������ƁA�v���o�����B
�j�[�ƁA�ʂ�āA������Ƃ��ɁA
(���т����Ă��A���炭�̑ς��炦����B�����̍~���܂łɂ́A�����ƁA�}���ɗ��邩���)
���������ĈԂ߂����̍Ō�̂��Ƃ��\�\�ł���B����́A�Έ�̉c���𐔂����B�����͓��������Ă���B�Ȍ�A�܂������ϋɓI�ɒb���Ă������s�ł���B
�u�悵�A�����͂ł����B�Ȏq�̂Ƃނ炢���킼�v
����́A���甪�S�l����āA�}�g�֗������B�Ȃ��Z�A���S�̕����A�Έ�̉c�Ɏc���āA�킽���ɂ́A��������̂B
�H���̗nj��́A�����m��ƁA
�u���������g��ق������́A���킷�Ɍ���v
�ƁA�ꑰ����A�푁�����͂₭�A�}�g�������āA�|�R�֓����Ă��Ă��܂����B
�u�����A�����ɐ���āA�Ĉȗ��̎v�����������ł�낤�Ƃ����̂Ɂv
����́A�H���֗��Ă݂āA���O�������B�������i�������āA�nj������т��o�����Ƃ������A�����͘V�Ԃ낤�����ł���B�����āA���������ꍇ�́A����ɂȂ�Ȃ��B
���ЂȂ��A�ނ́A���ꂪ�ړI�ł͂Ȃ����A�L�c���̊ق⎩���̗̖��ɗ^����ꂽ�ʂ�ȁA�T�S�A���A���D���A�nj��̗̉��ɐU�����Ċ҂��ė����B�܂��ɁA�����ȂĎ��ɏV�����̂ł���B
�������āA���̔N�́A��ꂩ�����B�������N���A�\�ꌎ�ɂ͂������B�Ⓦ����́A�ԏ��C���������낵��A�ߐ{�Ȃ��̐ᕗ�ɁA�~���Ă����߂��钩�[�ƂȂ����B
����ƁA�˂Ƃ��āA���삩��A��������Ղ������āg����Ǖ߃m�߁h���֓������ւ������āA������ꂽ�B���̓��e�́A
(�������Y���厖�A�k�}�����A�\�ӂ邢�A�̂Ȃ��A���c����ł�������ɗ�������A�ǖ��Q�ӂ����A���q�𗩒D���A�l���E�����Ɩ����B�\�\���Ȃ킿�A�����nj��A����܂���A�E�n�܂̂����吷�A�Ȃ�тɁA���낫�݂܂��A���A���݂�A�`�����͂��̂���Ԃݓ��ɋ��͂��āA�\�k������A��@�����߂��A������A�����傤�ɂ����̂ڂ��ׂ����̂Ȃ�)
�ƁA�����̂ł���B
�Ƃ��낪�A�����̌S�i�≟�̎g�́A���̊����������Ȃ���A���������������l�q�͂Ȃ������B�����̖��Ȃ���̎��̂��A����قǂ܂łɁA�n���ɂ͍s���Ȃ������؋��ł����邪�A�܂���ʁA
�u�ǂ����āA����ɁA�Ǖ߂��������āA�nj��₻�̑��ɂ́A���̉ȂƂ����Ȃ��̂��B�\�\�܂��āA���̏t�̑i�ׂł́A���傪�A���i�ƂȂ��āA�A�����Ă���̂ɁH�v
�Ƃ����^�����A�����ɂ���A���݂����A���̏o�����܂����Ă���Ƃ����ԓx�ł������B
�����̒ʒB���ꂽ�͈͂́A�����A���[�A�㑍�A�헤�A���삵�����̍��X�ł���B�Ƃ��낪�A���R�ɂ��A�������̔N�\�ꌎ���ɁA�x�m�R�̑啬���N�����B���̂��߁A���傤�NJ��������������n�̒n�k���A���ƂȂ��A�n�k�Ȃ��̂悤�ɖ������B�V�n�����߂�A�ӂ����Ȕ��u�������т��A�������߂��ɂ܂�A�Ⴉ�Ƃ܂����~�D���A�����ƂȂ��~��Â����B
�������N�́A�V�c�Ă傤���N(����)�ł���B������V�c�m���́A���ꂪ�O���ł�������ƁA��ɂ݂͂ȁA�v�����������ł������B
|
���~�̊C
�E�n��吷�́A���ʂ̉Y(�]�ː�K)�̉����s���֑D�̏�ɁA�����Ă����B
�ق��̑�R�ȗ��q�Ƃׂ͂ɁA䃂̈ꕔ���͂��A�]�҂̒��c�^���������̂܂��Ƌ��l�����̓�l��ɁA�ٓ����Ђ炢�āA���ނ����킵�Ă���B
�y���I�Ȓn���l�́A���̎�]�ɁA��������Ă����A
�u�s�̓���l���A���������܂����肵�āA�̗̂��ł����Ă���̂��c�c�H�v
�ƁA�������悤�Ȋώ@�������ĂȂ������B
�֑D�́A�����A�㑍�̕l���o�āA�����̎ō葺(��̐���)�����Ă����B�\�\�ŁA�D�����܁A���ʂ̉Y���悬�鍠�ɂȂ�ƁA���q�݂͂�ȑ��R�ƈ���̓V�����Ďw�����������B�\�\�͂邩�����ɖL���Ƃ��܃�����ёq��������̋u��(��̎Ō������߂̍���)�������̂悤�ȉe���g�Ђ��Ė]�܂�A���̕��p�ɁA�x�m�̕������A�����炩�ɒ��߂�ꂽ�B
�u�����A���̋�A���炢�������B�����O����A�x�m�R�����������Ƃ����\���������A���ꂪ���̉����낤���B�c�c�܂�ŁA��_�̂悤�ȊD�ł͂Ȃ����v
�吷�́A�t��Ў�ɁA�ӂ����ȓV�ς̑��e���A���グ�āA�������B
�]�ҁA��l���A
�u�����Ȃ����B���̕ӂ̊C�܂ŁA�����A���̂悤�Ȃ��̂��A�������߂Ă��܂��v
�u��B�c�c�t�̎��̏�܂ŁA�D���~���Ă���B����ł́A���́A�����Ȃǂ́A�D�ɖ��܂��Ă��܂������m��܂���ȁv
�u�܂����c�c�v�ƁA���āA�u�x�m�̕��́A���߂Ăł͂Ȃ��B���������̂��̂��グ�A�R���邾���̂��̂�R�₵�Ă��܂��A����A����ނ��낤�v
�吷�́A�t��`���Ȃ���A�Ђƌ��Ɉ��݂ق����B�����č��A�Ȃɂ��Ȃ��o�������̂��Ƃ��A�푍����ɑ嗐�������N���Ă��鏫��̖҈Ђ��A���ӎ��ɁA�\�������悤�Ɏv�����B
�u�c�c�������B����Ă邱�Ƃ͂Ȃ��v
�т����݂Ȃ���A�ނ́A�����ւ����ĕ������Ă����B�����̂Ƃ���A�ނ́A���傪�z���ȏ�A�����Ȃ����A�܂����ł��A�ނւ̖������o�Ă���̂ŁA�捠���A����ĂĂ����B
���s�֏���ẮA�����I�H��ɖz�����A�헤�A���ẮA���X�̌S�i��A�����̖�l�������A��������āA
(���łɁA�����ł́A����̍߂��݂Ƃ߁A����Ǖ߂̗߂��A�������Ă���B�\�\�l�ׂ̏����́A���͂��Ă���ׂ��\�\�Ɗ��������ꂼ��͂��Ă���͂����B�Ȃ��A�����o���āA�}�g�ɋ����A�nj��a�������Ȃ���)
�ƁA����̓��ɁA�헤�A����A�㑍�A���[�A�����Ȃǂ��A��K���Ă���ނł������B
�Ĉȗ��\�\����Ɨnj��Ƃ̐퓬�͂��Ɍ�����ɂ߂Ă����̂ɁA�����āA���ɂ͒吷�̖����畷���Ȃ������B�\�\�ӎ��I�ɁA�ގ��g�A�\�ɗ��̂��A�����Ă������̂ɂ������Ȃ��B
�ނ́A����Ƃ͐����ȁA�����Ƃł���A�ǐ��A�nj��ȂǂƂ����V�Ԉȏ�ɁA�Ⴂ�����I�҂Ȃ̂��B��Ȍ��܂�E�������́A�nj��ɁA�������āA���Ȃ̎p���I�݂ɂڂ����Ă������̂Ǝv����B
�����A���̂Ƃ���A�����Ȃ͂��̔ނ��A���X�A�Q�ċC���������B�܊p�́g�����m�߁h���A���������З߂��s���Ȃ��B���X�̍��i��S�i�́A�݂ȖT�ϓI�ł���B�吷�Ƃ��āA����͝�@���傽�蓾�Ȃ��B�\�\�₪�āB
�D�́A�ō�̓��]�ɂ͂������B�D���~���ƁA�ނ̑O�ɁA
�u�₠�A���a���悭�āA�������������ł����ȁv
�ƁA�����A����g���āA��Q�̘Y�]�Ƌ��ɁA�吷���A�o�}���ė��Ă����l��������B
������o��ނ����̂����˂��Ƃ������B
|
�������ƕa��
�o��́A�H����A�s���炱�̕����֕��C���ė�������́A�V�C�́u����v�ł������B
�O�����̕�������ۖ��ꂵ�����A�헤�֓]�C�����̂ŁA���̌�ց\�\�吷�̂������Ł\�\�C�����ė����҂ł���B
�u�����ł��傤�B�Ƃ�����A���悢�́A���̏a�J�̊ق����ւ����肭�������v
�u��D�ӂɊÂ��悤�B��ɏo���Ă��������ʂ́A�����A���苖�֓͂��Ă������ȁv
�u�q�����܂����B�c�c�o���̋V���A����a����̂��݂ǂ̂ƁA�����A���k�͂��Ă���̂ł����v
�ƁA�o��́A��������āA
�u�e�ׂ́A��ł����ɓ���܂��傤�B�������n������Ƃ������̂́A�n���������Ă݂�ƁA�z���O�Ȃ��̂ł��ȁB���C���N�ŁA�قƂقƂ��̓�����A����ƕ����ė������炢�ȂƂ���ł��v
�ƁA����Ȃ�ׂāA�Q�������B
�Y�]�����́A�r���ŏ��������܂�_�Ƃ������B�����āA�a�J�R�̌o��̓@�ւ����̂́A������X���ł������B
�吷�͐Q�V�����B�\�\������A�N���o�Ă݂�ƁA�����ق����̕ꉮ������ɁA�q�����Ă����B
�u���ڂ��߂ł����B����a���A�������痈�āA�q�a�ł��҂��������Ă���܂��v
��̌o��ɁA�Љ��āA�吷�͂₪�āA���̐l�ƁA�q�a�őΖʂ����B
�u�\�\�������狻�����ނ����̂���̂��݂����您���ł��v
�ƁA�ނ́A��������B�吷���A�s�l�炵���ԓx�ŁA
�u�E�n��吷�ł�����B�����܂��́A���͂₭�ɁA�������̏ȓ��ł��A�悭�f���Ă���܂����v
�ƁA�Ќ��ɂ��A�����������낱���悤�Ȉ��A�������B
�����ƂȂ����B
�s�̊��l���}����A�K���A�����ƂȂ�̂́A���̎��ォ��́A�n�����̕��K�������B
�������A�������Ƃ����j�́A�ǂ����A�Ȃ̑����A���݂�������Ȗʂ��܂������Ă����B�����A���͂Ȓn�����𒎃P���̂悤�Ɍ������Ă���y���������͌^�̐l���ł��邱�Ƃ́A�������ݍ����Ă���ƁA���������Ă���B
(�D�������Ȃ��l�Ԃ�)
�吷���A�����v���������A�������̕��ł��A
(����ȁA����B�s���𐁂����₪����)
�ƁA�ςĂ���炵���B
����ǁA�V�C�̌o��́A�吷�����E�����҂ł��邵�A�������̎����ł���B�\�\�ŁA�吷�́A�o��̂��߂ɁA
�u�ЂƂA��낵���A�Ђ����ĂĂ������������v
�ƁA�S�ɂ��Ȃ��@�����Ƃ��Ă����B
���̌�ŁA�ނ́A
�u���ɁA�������܂��A�o���̌�l�q���Ȃ����A�����A�����̖��ɔ����ނ��悤�Ȏ��������ẮA����A�R�X��������߂����낤���m��A�䏊���́A�ǂ��Ȃ̂ł��낤�v
�ƁA����́A�������̖��ɂ����Ăł��邩��A�吷���A���������A��l�̐^�ӂ������������B
�u����A�����āA�������y��킯�ł͂Ȃ����c�c�B�܁A�e�ׂ́A�o��炨�����Ƃ艺���ꂢ�v
�ƁA�������́A��������ނ̕��ցA������ƁA�{�����Ⴍ���āA�����́A���Ԃ��Ă����B
�o��A����āA������ׂ̂��B
�\�\���̗��R�Ƃ����̂́B
�o����V�C�����A���������܂��A��N�قǑO�ɁA�u����v��q�����āA���̕����֗����n�������Ȃ̂ł���B
�Ƃ��낪�B
���̕����̍��ɂ́\�\���u�T�������T�V�m�N�j�m�~���c�R�\�\�ȗ��̎q���ł��荋������A�y�ɍ����Ă����Z������B
�����S�i�����゠�����̂��ق������A�������łނ����̂������Ƃ����l�����B
���ꂪ�A�V�C�́u����v��u��v���A
(����́A�F�߂Ȃ�)
�ƁA���ۂ��āA�Ŗ����̑��A��̍s���ɁA�{���������e���ꂳ���Ȃ��̂ł���B
���ł̂������́A�����Ȃ̂��B
(�\�\����̎��тƕ����Ԃ݂�̌��́A�꒩��[�̂��̂ł͂Ȃ��B�ݑ�邢�����A�n���̂��߂ɁA�v�����ė����̂��B�R��ɁA���̗��x���Ȃ��A�܂����v���傤�����A���ł��ӂ��Ă��Ȃ��̂ɁA�����Ȃ薯����m��ʐl�Ԃ��A�����̎��߂Ȃǎ����āA�u����v���́u��v���̂ƁA��ʂ����Â炵�ĕ��C���ė����Ƃ���ŁA����ȓz���ɁA��������ƁA�����ꍑ��C��������̂��B�\�\���̕��ł��A�ӂ݂��ɂ������������)
���ł́A�S�i�B
�������́A���炾����A���i�m�ゾ���ł���A�S�i���A����ł���B
������A�C�ɐH��Ȃ���炵���B
�Ƃɂ����A���ł́A���낢��������āA�V�C�́u����v�Ɓu��v���ɔr�˂��Â��Ă����B������������ɂ���̂ŁA�����̖��ɂ��o���̎��s�Ȃǂ́A���̂����A�v�������ʂ��Ƃł���\�\�Ƃ����o��̎ߖ��ł������B
�u�͂͂��B�c�c����Ȃ킯������̂��v
�吷�́A�ꉞ�́A���Ȃ������B
�Ƃ͂����A����܂��������A�ƕ�������Ȃ������B
�㐢�̍��Ƃ̂���������ς�A�����ׂ����Ƃւ̔��R�����A�������Ȃ͂Ȃ��ł��邪�A�ЂƂ蕐���ꍑ�Ɍ��炸�A���u�̒n���قǁA�����̐��߂́A�܂��܂��s���Ă��Ȃ������̂ł���B
���������ɁA�s���̂������߂Ȃ�A�邪�A�s���Ȑ��߂Ȃ�A��������A���邢�́A��������B
�܂��āA��Ђ̑��������߂Ȃǂ́A�Â�����n���ɍ������낵�Ă���҂ɂƂ��ẮA���Ђł������̂ł��Ȃ��B������A���Ȃ̒n�ʂ�`�������Ȃ��҂Ȃ�A�e�F���邪�A�V�~���܂����莮�ɔC������Ă���㊯�Ȃǂɂ́A�����āA�ՁX�Ƃ��āA���̉����ɂ͏]��Ȃ������B
|
�����Ό�����
�u���ɁA�s���ӂ炿�ɂ܂镐�łł��B�㖽�����A�����̎��߂Ȃǂ́A�Ă�Ŏ��債���ɂ������܂���v
�o��́A���S���āA�吷�����̒n���֗���̂�҂��Ă����悤�ɁA��������i�����B
�吷�́A�ق��ɁA�������B
�����̖ړI�́A����ގ��̏o���̓��ł���B�������������̒��ւƂт���ŁA�i�������Ƃ͎v��Ȃ������B
�u�e�ׂ��A�����֏�\���A���ł֑��A���炩�̑[�u���Ƃ��Ė���Ă͂ǂ��ł��B�\�\�ۊ։Ƃ̌䖼���ȂāA�ēx�A���ł��B���Ă��������Ȃ�A�����Ȃ��A���c�ɂ����āv
�u����A���߂ł��B���������葱���́A���x�A����Ԃ������m��܂���B�Ƃ��낪�A����ł��A�������ł��A�������āA���ł�������āA���̂��������Ԃ��ė��Ȃ��B���R�́\�\����A��C���ʂɂ́A�ɗ\�̏��F��ނ̊C�����A�p�X�Ɨ����N���Ă���A�܂��A�Ⓦ����ɂ́A����̔��ނ�邢���A�l�ׂ𑛂����Ă���܂���A���̏�A�����Ɏ��[���Ђ��N���Ắ\�\�Ƃ������ソ���́A���ɓI�ȍl�����낤�Ǝv���܂��v
�u����A�����A��C�̑��́A�N�X�A�҈Ђ�痂����܂��イ���Ă��܂�����ȁv
�u�c�c�Ƃ����āA����ꗼ�����A���̎��߂������Ȃ���A���A�s�A��܂��傤���v
�u���Ƃ��A�������łƁA�����̐܂荇���́A���ʂ��̂��v
�u����������Ԃ�A����Ⴄ���āA���݂܂������A�{���̍����֎Q���Ă��A�����ȂāA���������݁A���������Ȃ��̂ł�����A�Ë��̂��悤������܂���B�\�\�������̏�̈��́A������́A�������C���̎��߂������Ă���̂ł�����A�������̂��āA���ł��A��x�A���͂Œ@���Ă��܂����Ƃł����v
�u���͂́A�ǂ��Ȃ�ł��B�[���A�ނ���������͂�����ł����c�c�v
�u����́A�[���ɁA���ڂ�����v
�������́A���߂āA�����Ō����������B�\�\����ȊO�ɁA���@�͂Ȃ��̂ŁA�Ђ����ɁA�捠���畐�͂͏������Ă���Ƃ����̂ł���B
�u�������A�k��������ɁA���͂�p�����ƕ����ẮA�������āA���������\�k�̉����𒅂�����S�z������B�����A�吷�a���A�����֑��āA����̐��`�ɁA�ؐl�Ƃ��Ă�����������Ȃ�A���̂����A�v�����āA���ł��������Ă��܂��܂��傤�B�\�\�����āA���吪���̏o���ցA�K�����͐\���グ�邪�v
�u�Ȃ�قǁB�\�\���̏�Ȃ�Ƃ����邩�B����A�ނ����Ƃ����B�悩�낤�B�����Ȃ����B���ӂ�ۊ։Ƃɂ������ẮA�吷���ؐl�ɗ����A�㗌�̂����ɂ́A�ύׂ���\�������Ă����v
�ނ́A�������B
�����ɂ܂��A���̕������ꌈ����A����ގ��ɁA�����̕����A�K���A���͂�����m���������B
�吷�Ƃ��Ă��A���������Ȃ���A���̊����ɂ������āA�����A�����������悤�ɁA�ꕺ���o���Ȃ��Ƃ����ẮA�����ɂ������āA�ʖڂ����������łȂ��A���g�̗�����낤���Ȃ�B
����ɂ́A�����A���𒅂��Ă���o��Ɏ���킹�āA�������ɁA���ꂭ�炢�Ȗ`���͂�点�Ă��d�����Ȃ��B�o�����m���ɂ�����ׂɂ́A�ޓ��̓����ɂ���ٕ��q�̈�|���������́A�ނ���A�}�����ׂ��ł���Ƃ���l�����̂ł������B
�������ƌo��́A
�u����A����ŁA���������A���łɂ������錈�ӂ����܂����B�吷�ǂ̂��A���ӂւ̏ؐl�Ƃ��āA��������������ƕ����ȏ�v
�ƁA��ɂ킩�Ɍ��C�Â��āA���ݎn�߂��B
�����̊ԁA�吷�́A�a�J�̊ق֑؍݂��āA�ޓ��̖��c�ɂ��������Ă����B�\�\���ł̓@�����P���āA�������̂��A���ł��ċւ��Ă��܂����\�\�Ƃ����蔤�����̊Ԃɐi��ł����B
�������A�吷�͂Ȃ����ꂩ��A���삵�����A��삱�������̏��������A�c���̓c�������G���ɂ���\��ł���Ƃ������B�Y�]�̋��l�����A���c�^���̓�l��A��A�₪�Đ����̌�A���̏a�J�R���瓌�R���֗����čs�����B
�ȗ��A�ނ̏����́A�܂��A���悤�Ƃ��āA���������ė��Ȃ��B
�吷�̐��i�ƁA���̍s���́A�����܂ŁA�A���ł���A�f���̂��Ƃ����̂ł������B
����ǁA���������Ԃɂ��A����𒆐S�Ƃ���푍�̖�ɂ��A�܂���g�p���N���Ă���A�X�ɁA�吷�̋���������ɂ́A�����̍����ɁA�\�肳��Ă����Ƃ���̑������\�ʉ�����Ă����B
�x�m�R���́A�������āA�����鏊�̒n�\�ƁA�����ɏZ�ސl�Ԃ̐����ɂ��A�����A�����I�ȍ�p���A�X���X�A�`�d���Ă����̂����m��Ȃ������B
|
���ނ����쌖��
�����S�i�����㕐�ł̂₵���́A�㐢�A�]�ˎ���ɂ͎O�c����Ƃ������ł̍���ɂ������B
�Õ����ɂ́A���ł͂܂��A�|�đ��Ƃ�������A���̕ӂ̍��n�́A�����f�R�̐^�����A�Ŋ铌�C�̔g������Ă����B
�����āA����A���Ńm�Y�Ƃ�сA���u�T�����ȗ��̍����\�\�����坁�ނ����̂������傤���ł́A�����炵�̂悢�R�̏�ɁA�G�s�ȋ��ق����܂��Ă����B
�����B
��������A�ނ̊Ǘ̂��Ă��镐���ꍑ���A���Ղ��傤���Ă݂�Ȃ�\�\�B
�܂��A���܂̓����s�̉�����т́A�قƂ�ǁA�C�ł������ƊςĂ悢�B
�̐X�A���ÁA�{���ӂ̌��n�сA�����āA���₩�ȑ�͂��A���n�̟T�т̊Ԃ���A�C�֓f���o���A���͕̉ӂɉ����āA���X�A���R�ɓy���������ďo�����F���ޕ��������т∰���点�Ă����ł��낤�B(�����̏F����⎩�R�Ȃ�D�y���A��̐��c��A������Ȃǂł���)
�����́A�]�ˎ���œ�\��S�Ƃ���ꂽ���A���Âł́A�����\�S�ɕ���Ă����B�����āA���̓��̒������́A�k��L���S�Ƃ����A����`������S�Ə̂��A�ł̐ԉH������̋��E�Ƃ��Ă����̂ł���B
�ŁA���ł̋��ق́A����I�Ɋς�ƁA��͂肻�̍��ɂ����ẮA�̉��̑������Ǘ�����ɓs���̂������v�n�ɂ��������̂ɂ������Ȃ��B
�����āA�ނ͐܁X�A��������A�����̕{���ɂ��鍑�{�m���ցA�ʂ��Ă����B
�u�ߍ��A�s����A�E�n��吷�����āA�o��̊قɁA�������Ă���悤�ł��B�\�\�����ǁA���K�˂Ȃ���Ă͂ǂ��ł��傤�v
���ł̉Ɛl�́A�s�ŕ����ė����\�Ƃ����̂��A��l�ɂ����āA�������߂��B
�u���������A���ꂩ��o�������Ƃ�������̂��v
���ł́A�����̍���������āA����C���Ă����̂ŁA
�u�\�\�E�n��A��������ƂāA�Ȃɂ����ꂩ��G���Ȃ��āA��@���f���ɏo�������Ƃ͂Ȃ��B�p������Ȃ�A�ނ̕��������ė��邳�v
�ƁA�قƂ�ǁA�������Ă��Ȃ������B
�Ƃ��낪�A��͂�C�ɂ͌���̂ŁA���X�A����Ă��閧�����ъāA�T�点�Ă݂�ƁA�吷�̑؍ݒ��A��������������āA���т��сA���c���Ђ炩��A�܂��A�Ђ����ɁA�������i�߂��Ă���炵���Ƃ����B
�u�c�c�͂ĂȁH�v
�ƁA���ł��A�x�����o�������́A�����x�������̂ł���B������̑��ŁA����قǂ̕����A�������}�P���ė����B
���łɂ́A����̔������Ȃ������B
�ނ́A�`���̉ƕ������A�������苏�قɎc�����܂܁A�Ȏq���A�邩��D�ŗ����A�����́A�킸���ȘY�}����āA�u�Â����ɁA�����͌���H���āA���z�ɂ̂���A�{���̍����ɂ́A�ٕς͂Ȃ��ƒm�����̂ŁA�{���֓����čs�����B
�������A�����ɂ͂����A�{���ւ��A�������ƌo��̕����P���ė���ƕ������̂ŁA
�u�悵�B�����ɂ����Ă��āA�������܂ŁA�킨���v
�ƁA��ɁA�����G��o�������A���̒n���������́A��������ނ̖\����ł������A�̖����܂��A���N�A���łɔ������������Ă����̂ŁA�i��ŁA�ނƋ��ɁA��ɓ��낤�Ƃ����҂��Ȃ��B
�u�����A�ӂ����Ȃ��z�炾�B���Ɍ��Ă���v
�ƁA�̂Ă���ӂ��c���āA���ЂȂ��A���ł͂܂��A�����𗎂��̂т��B�����āA�͂邩�����̐��k�n���\�\���R����܂̕ӂ�ɁA�g���B�����B���R�ɂ́A�ނ̕ʓ@���������炵���B
�������ƌo��̎��Љ^���͐��������B
��l�́A���ł̋��ق̍�����v�����A���{�ɌN�Ղ��āA�P�߂��A���łɑ���āA�V���Ɏ������������B
�u���ʁB�ǂ����āA����悤�v
���ł́A�T�������Ȃ��A����A���l�����B
�����̓��ɂ́A�Ȃ��ނ̕��ւ��A��҂����āA�F�C���������������B
�����𑀂��āA�����̎�����ӂ点�A�O������́A��������₳�܂��܂ȕs�����N���āA�������������v�����B���ł̂��̋t��@�����������B���ǁA�����͖I�̑��̂悤�ȑ��݂ɂȂ�A�吷���Ӑ}�����}�g�ւ̏o���Ȃǂ́A����A�]�݂�����Ȃ��Ă�����Ɋׂ������Ă��܂����B
|
��������������
�}�g�̘[�̍�ɁA�������������āA�H���̗nj��́A�Έ�m��̏���ƁA���̓~���A�Λ����������Ă����B
�u���������������Ȃ����A��́A�吷�͂ǂ��������H�v
�ނ��҂��̂́A�����̉����ł���B�\�\�吷�̉��Ɉ˂��Ĕ�����ꂽ�����̌��ʂ������B
�����ɂ́A����̕��Q�ɉ���āA�|�R�֓������݁A���炭���ނ̏P������قꂽ���A�A���Ă݂�ƁA�H���̊ق��A���߈�т̖��Ƃ���ԑq�܂ŁA���ɁA�Ė쌴�Ɖ����Ă���B
������ɁA���̑O��A�ނ������݂̂Ƃ��Ă�������̗ǐ����A�a�����Ă��܂����B������傫�Ȑ��_�I�Ō��������B
�u�����͍~�������A�����Ƃ��A���͏o���Ȃ����A�吷�͐w���ɗ��������Ȃ��B�\�\�������āA���̐g��l���A����̖ڂ̋w�������ɗ����Ă��܂����B�c�c�l���Ă݂�ƁA�����̔����l����坁�����͎��ɁA����������A���̎q�̕}�A���A�ɂ��������Ő�f���A���܂��ǐ����a�������B�c�c�����c�����҂̍Г�Ƃ͂����A����ȑ呈����������ɂ����p���ŁA��́A�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��낤�v
�nj����A�����A�����V�N�Ƃ��ł���B
����ɁA�[�����łȐM�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���X���Ƃ��ƁA���������ɋA�˂��āA���̒n���Ɏ��̈�����������イ�������Ƃ̂���j�����ɁA������������ς��āA�����l�����ɂ������Ȃ������B
�u�吷�����A��������ʁB�\�\�{���A�N�����A�吷���g���A��\�ɗ��ׂ��ł͂Ȃ����v
���̕s�����ɂ��v�������āA�悤�₭�A�E�n��吷�����錫�����������ɂ��A�C�����Ă����B
�������A���ɂ��āA�����C�Â��Ă��A���łɒx���B
�ނ̕����́A����̖L�c���ɐN�����āA���q�A��~�A��O���A���Ƃɂ�����܂ł��Ă������A���ɂ́A���傪�����̐����Ƃ����Ă���ň��̍Ȏq�܂ł�{���o���āA�݂Ȃ��낵�ɂ��Ă��܂��Ă���B�\�\���ׂĂ���͗nj��̏��ƂƂ��āA���傩��I���̍��݂������Ă���̂��B������A�����̌��݂ǂ�ƁA�̓y�̍r���������}����ɂȂ��Ă��A����̕��ŁA���̂܂ܖ��ق������߂�͂��͂Ȃ��B
�������A�|�R���痢�֏o�ė����ނ��ő��┺�ނ����́A���傪�Έ�ւЂ��g�������ƂŁA�����݂��������A
�u���Ă���A����ǂ́A����������A�ЂƖA�ӂ����Ă�邩��v
�ƁA�ċ��A���������ӂ�͂Ȃ��B
���ɂ��A�����ȃe���j�V�E�\�\�̕�����Ԃ��A�l�Ԃ̖�b���Ǝc�E�Ȏ�i�́A�Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��Ȃ�B���Q�ɑ��āA���Q��Ԃ��A���̕��Q�ɂ܂����Q���v���̂ł���B
�����ɁB
������̑��艺�������ׂɁA�q�t�ۂƂ��������オ��̘Y�}�������B
���ƁA���畍�߂́A�S���̏���ł���B
�nj��̉Ɛl�i�v���A���̎q�t�ۂ�U�f���āA����H��킹�A�Έ�m�����コ�����B
�u��́A�蔖�ł��B�債�����͂͂���܂���B���傤�ǁA�N�邭��̎O�\���ɂ́A�Y�q��U�̒Y�𑗂����܂�����A���̎��A�n�q��S���̒��Ɍ������āA��̓��֒}�g�̕���������ɂȂ�A���ƊO�Ƃ̗��U�߂ɉ�킹�āA��Ȃ��A�Ԃ��j�邱�Ƃ��ł��܂��傤�v
�q�t�ۂ́A�~�ɖڂ������ŁA�H�����ɓ��ʂ��A���ɁA����Ȍv���̎������ƂɂȂ����B
�ނ̊��͗p����ꂽ�B
�ׂɁA���̎��̍s��ꂽ�[���A�Έ�m��́A�Y�q������A�����ɁA�������������҂ƁA�O�����P�����}�g���ƂɈ͂܂�āA�܂������A�ꎞ�́A��}�Ɋׂ��������B
�������A����́A���̔N�̉Ă���H�ւ����Ă̂悤�ȋr�C���҂ł͂Ȃ������B�����ނ̌��N�́A���������ӂ����Ă������A���͍Ȏq�������A�L�c�̖{���������Ă���A��O�A�S�̂��Ƃ����Q�ɔR���Ă����B
�u������Ȃ�A�nj��v
�Ƃ����ӋC�ł���B
�Q�Ă͂������A�����ǂ���ɁA�c���̘Y�}����Z�킽�����c�����āA����ɓ������B����͓��A�U�ߊ��G��s�ł���߂��āA�������āA�nj��̒}�g���ɁA��ɂ����Q��^���āA�����A�ǂ��Ԃ��Ă��܂����̂ł���B
�u����҂́A�q�t�ۂł��v
�ނ��悭�m�钇�Ԃ̗��ۂ��A���̌�ł�������ɑi�����B
�u�c���̎�����A��������Ă���Ă����̂ɁA�������߁v
����́A��̏����ɂ������āA�������ɁA�ނ������߂��A���ł��āA�H���̗nj��ցA�킴�ƁA����͂��Ă�����B
�q�t�ۂɂ́A�V������ꂪ�������B�H���m��ցA���̎��Ⴂ�ɗ��āA�nj��̑O�ŁA�������ĜԚL�ǂ����������B
�u�킵�̘���A���̂悤�ɂ����̂͒N����B�N���A�킵�̎q���c�c�킵�̎q���I�@�c�c�v�ƁA�V��́A��������ł��邤���ɁA�ˑR�A���������炵���A�킪�q�̎�̂��Ƃǂ������ŁA�����낵���`�������Ȃ��痧�����߂��ƁA�nj������āA
�u���܂������B���܂��ɂ������Ȃ��B�킵�̎q���A���̂悤�ɂ��ĕԂ��I�v
�ƁA�����Ȃ�A�����Ă����킪�q�̎���A�e�ق�������B���̎A�nj��̋��ɂԂ������B�����āA�ނ̕G�̏�ɁA�ǂ���ƁA�d���������č��肱�B
�nj��́A���̔ӂ��甭�M�����B
���ɐ��������A�����グ���Ȃ������B
�u�c�c���Ȃ�������A�o�Ƃ������v
����Ȏ��������o�����̂��A�C�̎��ł��낤�B�ɓ���ƁA�a�͂Ȃ��d��A�ނ��ǐ��̂��Ƃ�ǂ��Đ������Ƃ����v��ꂽ�B
�u���̏�́A�ǂ����Ă��A�E�n��ǂ�(�吷)��\�ʂɗ��Ă˂Ȃ�ʁB���́A���̂��l���A���ɁA���ɂ���B��Ă���̂ŁA�l�ׂ̍��X���A�A�����ė��Ȃ��̂��v
�nj��ɂ��A�������q������B
�������낵�����̂������݂܂��A���[����̏��i���A���݂�Ȃǂ��B�\�\����ƁA�q���ł͂Ȃ����A���[�̗v���ɁA�`�����͂��̂���Ԃ݂ȂǂƗL�͂Ȗ����������B�Ɛl�i�v�A��s�˂䂫�A�����܂������Ȃǂ̏d�b�������āA���c�̖��A��Ɏl���֎g����h���āA�吷�̋�����T���܂�����B
|
�����ւ�ǂ�
�吷�̏��݂������˂Ă����̂́A�H�����̗nj��ꑰ�����ł͂Ȃ��B
������܂��A�����A����킯�āA
�u��f���̑坁�����ȗ��A�����S���҂ɂ��悤�ƁA�c���A�s�ɂ���������A����̈ꖽ���˂���Ă����̂́A���̔��ʘY�͂��߂�낤�吷�Ƃ����H�킹�҂��B�ޓz�����A����̐��U�̋w�A�吷��q�ˏo���v
�ƁA�����̎҂ցA�������Ă����B�ނ̒킽�����A�Ⓦ����̑��̍����Ă��ƁA����ɂȂ��āA�s����k�����邢�Ă����B
���[�A�㑍����A�����֓n��A�����ė��т�p�j���āA�c���̓c�������G����K�����Ƃ������Ƃ܂ł́A�������������Ă����B
�������A�G���̏��ł́A�Ă��悭������f���āA�ǂ����֗����������Ƃ����\�Ȃ̂��B����́A�ǂ����^���炵���B
�����A���̈Ȍオ�A�킩��Ȃ��B�܂������A���Ƃ��ĕ���Ȃ��B
�u�\�\�����A�܂��A�ӂ����сA�s�֏�������̂Ƃ���ƁA���Ɩ��B������A�ۊ։ƂȂǂ𗧂����A�낭�Ȏ��́A�ӂ�����܂��B����Ȃ炻��ŁA����Ƃ��Ă��A���Ƃ��A�s�֎��ł��˂Ȃ�ʂ��v
�ƁA����́A����݂̂��A��ɂ��ł����B
�ނ́A�s��m���Ă���B�\���N�̐������A�s�l�̒��ő���A�ۊ։Ƃ̉�������̂��A����̂ǂ��������̂����A�n���l�Ƃ��ẮA�m���������Ă���l�Ԃł���B���ꂾ���ɁA�������{�Ƃ������̂ɁA�n���̍����炵�����Ȃ��A�]�v�ȋC�������̂������B
�V�c���N�̓��\�\�R������t�߂��Ă�������ł���B
�u�Z�Ґl�I�@�m��܂������B�吷�̋��ǂ��낪�v
�ƁA��̏����A�����̂ӂ��肪�A�Έ�m��삯����ŗ��č������B
�u�헤�ɂ���ނ̎o�̗ǐl�A�����ۖ��ꂵ���̉ƂɉB��Ă�����ł��B�����č��A�}�ɁA�����𗧂��āA�Y�}�l�\�R�قǂɎ���A�R�z���ŁA���R������O�X���z���A�s�A���čs���������ł��B�\�\�ǂ��A�ǂ�����ɂ���������܂���v
�u�ȂɁA�O�X�z���ɏo�āA�s�����čs�����Ɓv
�u�܂������Ȃ��A�������Ɍ��Ƃǂ����҂̒m�点�ł��B�\�\���̂Ƃ����킵�ẮA�ĂсA�ޓz���A��߂�ɂ���@��͂���܂��܂��v
�u���߂����\�\�v�ƁA����́A���ł��Ă����B
�u�V�̗^�����B�吷�̉^�̐s�����B�����ǂ������v
��𒅂��݁A����A�n���g���A����́A�L��ɗ����ėE���B
���������Ɛl�Y�}�́A�S���ɑ���Ȃ��B
�u��́A���ɂȂ��Ă����܂�ʁB��l�̂��炸�]���ė����v
���ڂ����g���āA���̓��A��傩��o�������B
���́A������q���Ȃ��Ȃ����̊قƂ����A�������H���̓G�ɖ��������Ă��A������̒吷�����܂��Ƃ���ނ̌��ӂł������B
���̈ӋC���݂��猩�Ă��A�����ɔނ��A�吷�Ƃ��������ĉA���ȓG�ɂ������āA��������A����s�Ɏɐl�Ƃ˂������Ă����㊥�̂ނ�������A�S���̓{���}���Ă������A�܂��A�ߔN�̕��{����Ŗ����ɍ����̋@���҂��Ă������Ƃ����A�@������B�@ |
����Ȑ�
�����̓́A�܂��c��̍��������B
�t�́A�����Ƃ̎ᑐ�ɂ��������邪�A�������E�̎R�X�́A�����x�ł��A��Ȃ����R���ł��A��̂Ȃ��e�͂Ȃ��B
�u�\�\�ȂɁA���傪�ǂ�����ė����ƁH�v
�E�n��吷�́A���������Ă��A���߂͂ق�Ƃɂ��Ȃ������B
����ǁA�䂤�O�X��������������̋����ɁA���̏���A�����A�����Ȃǂ̎萨���A�h�c�����Ƃ����\�́A�r�X�A���x�����ɂ����������A�܂����v�����m��q�݂܂��ł����A
(���悻�S���\�R�̕����A�����́A���v�������珬��������������������A����猌��ɂȂ��āA���{���Ă���l�q�ł�)
�ƁA�����̖q�v�������畷�����ꂽ�̂ŁA���́A�^���]�n���Ȃ������B
�u�\�\�^���܂��B�ǂ��������̂��낤�H�v
�吷�́A�n�ォ��U��������B���c�^���A���l���������͂܂̂��イ�����n�߁A�]�҂͂��悻�l�\�R�����A��Ă��Ȃ��B
�u�ޓz�ɁA�ǂ�����Ă͑�ς��B�\�\�Ƃ����āA���̐M�Z�H�A�R�z�����Đz�K����֔����邩�A��Ȃ����܂̐쌴��n���āA�X�����炵�ȁA�����݂̂�����z��H�֖z�͂��邩�A��̂��������c�c�����͂ǂ��l���邼�v
�u���B�R�ɐႳ���Ȃ���ł����v
�^�����������A���W�ƁA�s����ꂽ�悤�Ȋ���ł���B����ƕ����������ł��A�ޓ��́A�_�̂����ގv��������B�܂��Ė����͂��̏����A�������s�����āA�헤���炻���Ɨ����̂тė��������̂܂܂��B�����듦�����邾��������ɔ@�����͂Ȃ��Ǝv���B
�吷�ɂ��A���v�s����ՂӂƂ��̗E������킯�ł͂Ȃ��B�^���A�����̍l�����́A���̂܂ܒ吷�̕��ʂł��������B
�u����A�P������������������ւ����āA�Ђ�����ɁA�}�����B���Ƃ́A��̓���Ƃł���������̎v�ĂƂ��āv
�R�n�A�k�m�����A���킹�Ďl�\�l�قǂ̎�]�́A���̓��A���������땍�߂��珬���̍��{(��c�ߖT)������܂ŁA�����}���ł����B
�����āA��Ȃ͔̉ȂقƂ�֏o���Ǝv���ƁA�����v���A�n�D�����炵�����𒆐S�ɁA�ꂩ���܂�̐l�n���A�����������āA��ɁA�|�ɖ����������A���ق��A�����̓��Ȃǂ��\���āA�����A�^�������������n�߂��B
�u��B����̖L�c���炵�����v
�u����ɂ��ẮA���l���ł����v
�u���肵�đҕ����Ă����ꏬ���ɂ������Ȃ��B��̐l�������ʂ����Ɂv
�u�������B���傳�����Ȃ���A���̂��炢�ȏ��l���̓G�́c�c�v
�}�ɁA�吷�������A������ƂƂ̂����B
�܂��������̐w�`�̗p�ӂ���@���Ȃ��ɁA�ˑR�A�o���̊ԂɁA�җ�Ȗ�킪�n�܂����B�\�\�\�܁A�Z�l�̖L�c���̒��ɂ��āA�w�����Ă���Ⴂ�R�n���҂́A�������ɁA����̒�̏����������ɂ������Ȃ��B
�u���Ђ���A�G�́\�\�v�ƁA�吷�́A���߂̗D���ɁA�����o���āA�u���̌������ɁA��Ȃ��킯�n���Ă��܂��B���ǂ̂��ꂽ�����̎萨�A����邱�Ƃ͂Ȃ��v
�ƁA���g�A�^����ɁA���Ԃ��������āA�ցA�킯�������B
�Ƃ��낪�B
��������قǏ㗬���A��Q�̋R�n���A��ɑΊ݂֓n���Ă䂭�̂��]�܂ꂽ���A�܂������̕�������A���X�ƁA��w�̕��n���������֏P�悹�Ă���B
�u�����B�����Ȃ����B�\�\���傾�v
�吷�́A�������ԂƁA�V�̂��܂�A���₤���n����͒��֗��������ɂȂ����B
|
���R�����Q
�R�x�n�т́A�܂���Z�ǂ������Ă��Ȃ��Ƃ݂��A��Ȑ�̐��͏��Ȃ������B�ۂт傤�Ƃ��čL���͌��ɁA�����Ö��̂悤�Ȑ����̂��˂�����邾���ł���B
����̎萨�́A�O�����ɕ���Ă����B����ɂƂ��āA���̓��قǁA���������������Ƃ͂Ȃ������낤�B�吷�͂����Ԃ̒��ɂ͂����������B���Ƃ͖Ԃ����ڂ��āA��Â��݂ɕ߂��邾���̂��̂ł���B
�������A�吷�ƂāA�����Ȃ�A��݂�ݍ����ēG��ɂ�����قNj��҂��傤����ł��Ȃ��B
�u���܂����v
��x�͐�]�I�ȋ��т����炵�����A���Ƃ��G�̔����ȉ��ɂ���A�l�\�l�̘Y�]�͘A��Ă���B���ꂾ���̎҂�����������\�\�Ǝv���������B
�ނ́A��ɂ��A�E���͒q���������B
�u���̓n�D�����ɋ����Đ킦�B�����̈���k�������Ȃ����|�ɂƂ��āA�߂����ɏo��ȁB�������炽�������āv
���̉��앨���Ȃ����ł́A����͗L���ɂ������Ȃ��B�������A������͐�����ė����������A�吷�����́A�����ł���B�܂��������A�����Ă����̐��ɂ����x������B
���R�A��s�������B
���͂悵�ƁA����̕��́A�n�D�����𒆐S�ɁA��芪�����B����A�����A�����A�����ƁA�Z��A������낦�āA
�u�吷�B�o����v
�ƁA�Ăт������B
�u�������\�\�v�ƁA�����̈�����A���n���点�āA�o�ė����҂�����B
�吷�ƌ����̂ŁA���傪�A
�u��߂�ɁA��߂�Ɂ\�\�v
�ƁA�킽���֒��ӂ����B
���̈�R�͂Ȃ��Ȃ��E�҂������B�ނ̂��߂ɏ����҂����Ȃ��Ȃ��B
���₱������łȂ��A��������A���Ȃ����b�Q�̙��K�ق������ƂȂ����B�N����l�������։���B���̉��ƍ������o���̎E������藧�Ă��B
�₪�āA�������������B�����k�炳�ꂽ�吷�̘Y�]�́A�w偂̎q�݂����ɁA�R�n�̕��֓����U�����B����͌��Ԃ邢���Ȃ���A�G�̎r��ӂ�Ɍ��āA
�u�����A�������B�c�c�ǂ������A�吷�̐g�́v
�ƁA�킽���̎p�ւ������B
�u�ɂ������Ƃ����܂����v�ƁA�����������Ȃ���n���ė����B�u�\�\�����߂�ɂ��āA�����։g���Ă����Ǝv���܂����̂Ɂv
�u�ȂɁB���������̂��v
�u����A���Q���Ă��܂��܂����v
�u���Q�������\�\�v�ƁA����͜��R���傤����ƒV���̔����g���Ȃ���A
�u�����z�����A�������́A�p��m���Ă���B���Q�������̂Ȃ�d�����Ȃ��B�����v
�u�͂����v
�u���������v
�u�S���܂����v
�����͔n�̔w�����э~�肽�B
����ȉ��A�L�c�̏����́A���̂Ƃ��A�l���キ�Ƃ��āA�S�ɁA�M�̗̂p�ӂ����Ă����B
�Ƃ��낪�A���̏u�Ԃɂ́A���Ɍv�炴�鎖�����N���Ă����B
�u��I�@���A����͒吷�ł͂Ȃ��v
�ƁA��������Ă݂������������A�܂��A���͂̎҂��A�����o�����̂ł���B
�u�����A��ȂǁA�吷�̕��𒅂��Ă��邪�A�吷�̘Y�]�A���c�^�����\�\�B���c�^�����A�g���ɗ����A�吷�炵���U�����Ă����̂��v
�u�ł́c�c���̒吷�́H�v
�ƁA����̊�ɂ́A�܂����ڂꂩ���ė����B
�u���̘Y�]�����̒��ɂ܂���ē������������B����Ƃ��H�v
����̂��Ƃ��v���o���Ă݂�A������������f�����Ƃ��A���ɂ����n�D�̘V�ꂾ�́A�y���炵���҂����l���A�����]�܂�т����čs�����B
�Ђ���Ƃ�����A���̒��ɁA�p��ς��Ă�����������Ȃ��B
���₢��A����Ȍ����������Ƃ��v���ʁB���邢�́A�S�[�Ȃ�����ɂȂ��āA�ׂɂ�����ɘ�������Ă���̂ł͂���܂����B
�����A���������́A�Z��䩑R����ʂ�����ɑς��Ȃ��悤�ɁA�ӂ�̓G�̎��[��������čs�����B���A�����ɂ��̓k�J���o���Ƃ����B
�u�c�O���B�������A���_���Ă�������łȂ��B�c�c���̏�́A�蕪�������āA���Ƃ��A�吷���ǂ��������ƁA�q�ˏo�����ɂ����Ă������̂��v
����͖ʂ𑓔��ɂ��āA�킽���֖��߂����B�S�]�l�����g�ɕ���A���A�얖�A�R�x���ʂȂǁ\�\�v���v���ɑ{���Ɍ������B
���A���̓��͂��Ɏ茜����Ȃ���ꂽ�B
���������̗������A�R���̕����⓹�Ƃ�������{��������B�����Ȃ�ƁA�s���Ȃ̂́A�������đ�l���̕����Ƃ������ƂɂȂ�B���������̍s���������ّ��҂ɂ͊o���Ă���ɂ������Ȃ��B����ƁA�y�n�̌S�i�́A�u�����̏���̎萨�炵���\�\�v�ƕ����ƁA�ז��͂��Ȃ��܂ł��A�����Ԃ��W�ȑԓx���������B�ނ���A�E�n��Ƃ��������������A�������{�ɂ��A�����Љ�ɂ��W�̂���吷�̕��ցA�ÁX���Ȕ삪�������Ă����B���R�A�吷�����̕��ʂ̎�ɉB��āA��n��E���Ă����ɂ������Ȃ��B
����ɂ��Ă��A�吷�́A�S�邽���J���������̂̂悤�ł���B
�����炭�A�g��Ŗؑ\�H�ւ̂���A�₪�ċ��t�ɒH��������̂ł��낤�B���������A�A���͂Ƌ��ɁA����̖\����A�������ɑi���o���B���̏�i���̈ꕔ�ɁA�ގ��g�A��Ȑ�̓�����������Ă���B
�\�\�J���V�����t�j�ナ�i�t�����A�����g�A��{�A���R�������X�B����A�d�V�m�r���V�e�A��K�㋞���m���A�y���S�]�R�A�����m�@�N���Y�c�C�f�t�V�����B��\����A�M�Z�����V�i�m�`�q�T�K�^���������ʃX�O���j�A���j����A��Ȑ샒�у^�C�V�e�҃`�A�O�ヒ���̓X�B��n�����j�V�e��s�X�����A�吷�i�z�V���A���A�R���ƃg�V�A�d�^�L�M�j���V�A䅓�J���i���Q�N�s�j�A�����N�R�g�����^���c�c�B
|
���l�S��
���̔N(�V�c���N)�̍��A���s�ɂ́A�m�̋�炭����Ƃ����҂�������āA�҂ɗ����A�O�����ƂȂ��A�O���������߁A�O������y�̐��������n�߂Ă����B
���́A����������āA�n�҂��������A�a�l��}�������A�����˂��A�������낢�A�܂��n�������邱�Ƃɒ����Ă��āA�ǂ�Ȑ��̕s�ւȏ��ł��A��炪�s���āA��˂��@��ƁA�������琅���N�킢���Ƃ����B
�s�̒��ɂ��A���̌@������˂���������āA���̈���A�X�̐l�X�́g��ɂ݂��̈䂢�h�ƁA���Â����肵���B
�Ƃɂ����A�ނ́A�����̒��̏����̗F�l�ł������A�t�ł������B
������A�X�̐l�X�́A�ނ��ĂԂ̂ɁA
�u�s�����̂���l���傤�ɂ�v
�Ƃ����āA�e����ł���B
����A�������̐l���A���������̗͂ł���悤�ɁA��炪��̒҂ɗ��ƁA�݂Ȕނ̂܂��ɏW�܂����B�����āA�����Ɏ��������ނ��A�O�������a���A�₪�ĒN�Ƃ��Ȃ��Â��ɒ@���ނ��˂̉����ɂ��킹�āA�Q�W�̗ւ́A�s�̏�l�̂܂���x�邪�@�����肠�邢���B
���O���\�\���x��\�\
�t�̐����A�s�̋���A�d���₵�����ɐ��߂Ă���B���O�̒��ɁA�����������ۂ��N��Ƃ��́A���O�̒��ɁA�����A�s��������Ƃ��������B�\�\���x��̗ւ́A�O���Əނ̉��̉����́A���������Ă����B
�u���傤���A���̑��n���A�������̖�ւ͂������v
�u����A���̂������v
�u�ɗ\�̏��F��ނ��A��C����łȂ��A�ߍ��́A���W�H��Â̊C�܂ŁA�r������Ă���Ƃ������v
�u���������A���̒Ǔ��́A�����Ă���̂ł���H�v
���������s���Ț����́A�₦�������B
�������N�A�������{�́A���F��ނ̊C�������ɂ́A�܂������A����₢�Ă���B
����ۊ��A�I�i�l�Ȃǂ́A�������ѐ�|�������������āA���F��ނ̊C�������ɁA���˓��C��쉺���čs�������m��Ȃ����A�s�l�͂����̈�x���A�M���R���������Ƃ͂Ȃ��B
�u�s���s���قNJC�̂�������v
�N�Ƃ͂Ȃ��A�s��͒m�����̂ł���B���ɂ́A�����Ă��A������s�������Ă����Ȃ��悤�ȗL�l�ł���B
���̍ł��Ђǂ����́A�V�c���N���炢���A����N�O�̏����Z�N�O���A
��C�m���A�D�A��]�z���ȃe�A���m���v�e�E�R�E�������w�E�����N�V�A�׃j�A���C��уm�C�H�}�c�^�N�ʃ[�Y
�Ƃ��������������̈ꍀ�����Ă��킩��B�v�ł̕������ڂ������D���A�C�������ɑ_��ꂽ��́A��x���x�̎��ł͂Ȃ��B�r�����������́A�D����݁A�Ǔ��։^�ы����A���ɂ��ꂽ���l���A����ɂȂ��āA�s�֓����A���ė����Ƃ����R�̂悤�Șb���炠��B
�V���̗����́A���F��h�̊C������łȂ��A�R�z�k���n���ɂ́A���i��y���̑������ׂ̂����A��ɁA�o�H�̘؎��m���u�؎��v�͒�{�ł́u�؈��v�n(�ڈ̋A���l)���A���i�̏H�c����đł������Ƃ����悤�Ȕ��́A����������̐_�o�������B���܂��ɁA���������̕�������Q���̉��s�͖��ӂ̎��ŁA����͂��������������Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă���B
�������������B���������㉺�̕s���������Ă����Ƃ���ցA�E�n��吷���\�\�R���ƃg�V�A�d�j���V�A䅓�Q�N�s�j�A�����N�R�g�����^���\�\�Ƃ����p�Ŋ֓����瓦���A���ė����̂ł��邩��A
�u����A����������H�v
�ƁA���u�̎���ɂ��Ƃ���b�A�Q�c�������A�ނ̏㍐���Ȃ���̂��A�d�������̂��ނ�ł͂Ȃ��B
�㍐���ɂ́A�Ⓦ��т̑���́A���ׂĂ���A�ނ̖�]�ƁA���������̔��ӂɂ����̂ł���ƂȂ��\�\�׃j�A�����n�͊��R�J�c�V�A�_���n�œy�j�������S�L�t�e�C���o�E�V�A�\�m�\��n�S�{�����N�׃i�X���j�A���Y�\�\�ƁA�֒����������ŁA����̔����I�s�ׂ��A���鎖�Ȃ����A�j���_��ɏ����o���Ă���B
�u���ĂĂ͂����Ȃ��v
�������́A��������グ���B
�������A��N�A����㋞�̂Ƃ��A�吷�Ƃ̑i�ׂ̑Ό��ł́A����̐\�����Ă𐳂����Ƃ��āA�u�ނɍ߂Ȃ��v�Ƃ��������������Ă������łȂ��A�u���傪���ȗ��̈�Y�c�̂͂�����ɁA����̎�ɋA���ׂ��v�Ƃ����鍐��吷�\���n���Ă���B�v����ɁA���̂Ƃ��̊��̍ٔ��́A����𐳓��Ƃ��A�吷�̑i�����A�s���Ƃ����̂��B
�\�\��������܂��A�s�i�̒吷�̏㍐�������グ�āA�y�X�����A�����̍ߐl������̂́A�ǂ��������̂ł��낤�B�������w���Ȃ��̂ł͂���܂����B�\�\�Ƃ����悤�Ȑ��_���A�����̈ꕔ�ɂ����Ă����B
�u�ꉞ�A�吷�������āA�Ԃ��ɁA�吷�̌�����A�Ⓦ�̎�����A�u������Ă݂�ׂ��ł��낤�v
����̈ӌ��́A����Ɉ�v�����B�吷�͂��̓��A�ߊ����āA����̓��Ɉ܂����B
�a��ɂ́A�O���ȉ��̑劯���A������āA�ނ̌�����A�����̎�����m�낤�ƁA������ł����B
���̒��ɂ́A������b����(�O����b)�̎q���\�\��[���������˂��A�����[���t����낷���Ȃǂ̎p��������B
�吷�́A��ォ����ŁA
(���B�����Ă�����ȁc�c)
�ƐS�Â悳���A�Ђ����ɕ������B�����[������t��́A��̔ɐ������N���d���Ă����l�ł��邵�A�܂��A���̌Z�N�̎������A�����ɍD�ӂ������Ă��邨�l�ł��邱�Ƃ��A��X�A�ɐ����畷���Ă����B
�u�㍐���́A���̒ʂ�ɈႢ�Ȃ����B����ɂ������A�E�n��́A�d���l�ނق�ɂ�Ȃ�ƒf���Ă��邪�A����ɁA����Ȃ��̂��v
�������A���₵���B
�u����������܂���v
�吷�́A�����₩�ɁA�������B
�����������ŁA�v���̂܂ܒq�ق��ӂ邤���Ƃ́A�吷�Ƃ��āA���Ӓ��̓��ӂł���B�܂��āA����������ɓ����Ă����ȂǁA����Ă��Ȃ������Ǝv�����B
|
����m����
�吷�̒n������̐����́A�O���O���Ă��Ƃ��ĂсA�ގ��g�̂��߂̍I�݂ȕٌ�ł������B�����ɁA����ɂƂ��ẮA�@�����Ƃ̂ł��Ȃ��u���t�ҁv�u���\�ҁv�Ƃ�����ۂ��A��������̓������₫���Ă��܂������̂ł������B
���Ƃ͑u�₩�ŁA���O�͂悭�ʂ��Ă��邵�A���A�吷�̑ԓx�������炵���B����������ۂɂ́A�킯���Ȃ��A�D�������̂��A�����S���ł��������B
�u�c�c�Ȃ�قǁv
�u���������킯���v
�a��̏����́A�݂ȁA�吷�̐����ɁA�m�肵���B�����́A�������ɁA�u�˂��B
�u�������吷�B�������Ƃ́A���łɐ�ɁA����Ǔ��̊����𐿂��āA���̗ߎ|�����������ē����։����Ă����̂ł͂Ȃ����v
�u���l�ł���܂��v
�u�Ȃ��A�ߎ|��āA�����߂��ʂ��\�\�O�ɂ́A�v���������A�����ɂ����ẮA�����̏��݂��m��҂Ȃ��A���̂��߁A��������āA�ق����܂܂ɁA�\�Ђ�U�킹���Ƃ������y�Ԃ��v
�u���̋V�́A�\���킯������܂���v
�吷�́A�f���ɁA���ւʂ������āA�߂��ӂ����B
�u����ǁA����ɂ́A�e�ׂ��Ȃ��킯�ł͂������܂���B�\�\���R�́A���łɁA���̕������A�f���ǐ��A�nj��A�܂�����̈�Ƃ܂ł��A�قƂ�Ǐ���̂��߂ɁA�ł���Ă���܂��B����́A���⏫���l���A���Ђ��߁A�l�ׂ̍��X���A����̎d�Ԃ�������āA�����̗ߎ|���S�ɂȂ�Ȃ��̂ł��B���ׂāA����������Ƃ��납�痈�Ă���܂��v
�u����ǁA���̊Q��������ׂ́A�����̗߂ł͂Ȃ����B�Ȃ��A�w�߂ʁv
�u����A���Ƃ��ẮA�����A����A�헤�A���[�A�㑍�ƁA���X���K���āA�����ɂ������A�e��(��̎��_�A1-2-22)�A�o������ƁA�����ĕ����܂������A���̂����A�g�ӂɊ댯�������āA��ނȂ��헤�ɉł��ł���o�̗ǐl�A�헤��ۖ̋��ցA���炭�g����߂Ă�������ł����v
�u���Ԃ������ʂقǂɎn�I�A���傪�_���Ă���̂��v
�u�h�q�A���������āA���̒吷�����A�܂���ƁA�������ǂ��ł���܂��́A��ɁA�����邻�������܂���B�c�c������ɔs�c�̏f���A�H���̗nj����A����̂��߁A���فA�̓y���Ă�������A���ɁA�ߕ��̗]��A�a���ɘ���c�c�������Ȃ��c�c�v�ƁA�吷�͂����ɂ�����ƁA���������܂点�\�\�u���Ȃ����A�捠�A�a�f�������܂����B�����ɂ����āA���ɂ���̋㑰�͖S�ы���A�c��́A�吷�ꖼ�ƂȂ�܂����B�c�c���́A�ʂĂȂ������ɐ������āA�����̂܂܂������͂ƁA�ۖƌv���āA�Ђ����ɓ��R�����M�Z�H���o�ցA�s�ցA�ď㍐�̂��߁A�}������ė����悤�Ȃ킯�ł������܂��v
�u�ށB��Ȑ�̓�́A���̓r���̎��ł�������ȁB�����A����̎��O�̗���v
�ƁA�����͒V���Ƌ��ɁA�u����I�����B�\�\�������āA�吷�͂��̓��A�܂��Ȃ��ޏo�������A�a��̔����ɂ������āA�ނ́A
�u�܂��́A�����v
�ƁA�S�̂����ŁA�Ƃ薞�����ċA�����B
�����Ă܂��A�����̌�A�ނ͑�[�������̎��@��K�ˁA�܂�����̌����[���t��̓@��ւ��f���āA
�u���܂⎄�́A�����̋����ł́A���c�ȗ��̉Ɖ�����������X���イ���A�܂������ǓƖ����̐S�ׂ�����ɂȂ�܂����v
�ȂǂƎG�k�ɂ܂��点�āA�Ⴂ�t��̓�����Ђ��悤�Ȏ����������B
�Ⴂ�Ƃ����Ă��A����t��͎O�\��B���Z�̎����͂����l�\�ł���B
�ނ����A���傪�d�������������́A���łɘZ�\����̘V��ł���A������b�̌��E���傭�ɂ��邪�A�����ʂ���͂������ۓI�ɂ͐g��ނ��Ă����B����̐��_�ŁA�����������Ă���̂́A�q���̎����Ǝt��Ȃ̂ł���B
�u����A���͈Ă���ȁA�����̒�ɐ��ɁA�킵�̓��ӂ͐\���Ă���B�����A���̒��������ǂ����A����ɂ������āA�����A���������݂������Ă�����B�c�c�����A�ނ����킪�ƂɎd���Ă������҂Ƃ�������������т�ł͂��낤���c�c�e�ՂɁA�ނ�̖d���l�Ƃ���V�ɂ́A�䓯�ӂ��Ȃ���ʂ̂��B�������A������A�����̑i���ɋU�肪�Ȃ���A���Ǝ������A�؋����Ăė���ɂ������Ȃ��B�������炭�A����҂āv
�t��́A�吷��͂Â����B
�吷���A�\�����̑i���◠�ʉ^���ɂ���āA���ɋ��߂Ă�����̂́A����G�Ƃ��āA����Â��鎖�ɂ���B�\�\����ǁA���G�̏ق���������A���R�A���ꂪ�����ɂ́A�����Ȑ������R��C�����A�܂��s���犯�R��h�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�u���Ƃ��A�吷�̏㍐���̒ʂ�ł��낤�ƁA���G�ƒf����̂́A�R�X�������Ƃł���B��������₩����Ă��A�ȋ^���������ď㗌���ʂƂ���ΐ���g�����������������āA����̐^�ӂƁA������A�������߂Č���ׂ��ł͂���܂����v
�_�c�͍��A���������Ƃ���Œ�����Ă���Ƃ��t��͒吷�ɉk�炵���B�\�\�吷�Ƃ��ẮA���̕_�c�̋A�����A��������@�̂��ƂɁA�����ɗL���ɗU�݂��т��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
����A�ނɂƂ��āA�����̕��j�̔@�������A���U�̉^�����Ђ炭�����邩�̕���ڂł��������̂ł���B
|
����X�̒�
�V�c��N�̉Ē��́A�閈�悲�Ɩ閈�A���O���̖̏����傤�݂傤�̐��ƁA�����ł������ނ̉��ƁA�d�����܂łɗx��X�ӂ���l�e�ɁA�s�̒҂́A�ٗl�Ȗ�i���������Ă����B
�u�킪����v
�u�嗐�̒�����������v
�u�{��̜��傢�ʂ��ɁA�����������v��̐l�o�ɕ��܂��ꂱ��ŁA�����������҂�����B�ނ�������A�{���̐X�ɓ������Ɛ킪����Ƃ������Ƃ��A�����̖��͐M���Ă����B
�H�̍��ɂ́A�O���̐������A�����̕������������o���ė����B
�u�ɗ\�̏��F�ƁA��������ȊC�����́A�������˓�������āA�ےÁA��g�m�Â�����Ɏ����M���������Ă���v
�܂��A���������҂��������B
�u�\�\����́A�����̏��傪�A�U�ߏ���ė���̂�҂��Ă���̂��B���F�Ə���Ƃ́A�\�N���O����A���������������сA�V������āA�������ɂ���ٌ_���������܂ŏo���Ă���v
���������A�N���A����Ȏ������������̂��B
�V�Ɍ��Ȃ��A�l�����Ă��킵�ށ\�\�Ƃ�������Ȃ̂��낤���B
�u�c�c�Ȃ��A��B�܂�ŁA�킵�����ׂ̈ɁA�N���A��ق��Ă���Ă���悤�Ȃ��̂���Ȃ����v
�吷�́A����[�ׁA��̔ɐ��Ƌ��ɁA�҂̋��O���̌Q��������ɏo�����Ȃ���A�r�X�A���������āA�����������B
�\�\�����āA���ɜ߂���ėx���Ă���悤�Ȑl�e�̗ւ߂Ă����B
����ƁA�G�X�q���ڂ��̉��ɁA�܂��A�ʂ�z�ŕ��ł����߂��肬�ʎp�̒j���A�ӂƁA�Z��̂��Ɋ���ė��āA
�u������A���Ȃ��l�́A�E�n��吷�ǂ̂ł͂���܂��v
�ƁA����ꂵ���b�������ė����B
�u�H�@�c�c�B���������A���ʂ��͒N���v
�u���N�O�܂ŁA�����̌���a�̂��قɎd���Ă����҂ɂ������܂��v
�u�����B��a�̉Ɛl���ɂ����̂��v
�u��ꑰ�A�݂ȁA���̒ʂ�ɂȂ�܂����̂ŁA���Q�̖��A�s�֗��Ă���܂������A�v�������Ȃ����ŁA���p�����������������A���Ȃ������ɂ����܂��ʁB�c�c�����A�����A���Ȃ��l�ɁA���u������A�m���Ȏ�������Ǝv���܂����v
�u�킵�ɁA����u�������Ƃ����̂��v
�u�����A������l�����łȂ��A������ɍ��X�Ɨx���Ă���҂�A�s���イ�̖��́A���ꂪ�R���ق�Ƃ��A�m�肽�����Ă���܂��傤��B�\�\���������A�݂�Ȋ���ė����v
�吷���A�т����肵�Ă���܂ɁA�j�͗����U�肠���āA��������Ă����B
�u�����ɂ���������̂́A�E�n��吷�l���B�����̎���Ȃ�A���̂����قǒm���Ă��邨�l�͂Ȃ��B�c�c�݂�Ȃ��āA���u�˂��Ă݂�B���̍��̂��낢��ȉ\���A�R���A�ق�Ƃ��v
�u����A�����������B���̗����ȂǁA�吷�̒m�������Ƃ��v
�u�����āA���Ȃ��l�́A���̏t�A���������A���ɂȂ�₢�ȁA�������֒����㍐���������o���āA����ɖd����������Ƃ������i�����o���Ă���ꂽ�ł��傤�v
�u��B�ǂ����āA����Ȏ����A���ʂ��@�����m���Ă���̂��v
�u������A��ڂɂ���Ă������ꉺ���ł��A���ꂭ�炢�Ȏ��́A�����A�����������Ă���܂���B�c�c���������Ƌ�����邪�A���̗����A�����v���A���������o�Ă����ł���B����A���{�l�́A���Ȃ��l�Ȃ�ł��B�c�c�����A�吨�ɓ����Ă���ĉ������v
����ƁA�Q�W�̒�����A�p�͌����Ȃ����A�吷�ցA��������̐����Ƃ�ŗ����B
�u�����̏��傪�A�헤�̑坁������A�f���̗ǐ��A�nj��Ȃǂ�łڂ��āA���̒n���ɁA�}�ɖ҈Ђ�U���o�����Ƃ����̂́A�\�����ł͂���܂��v
�u�c�c�c�c�v
�u�R�ł����v
�吷���������Ă��܂����B
�u�����āA�R�ł͂Ȃ��v
�u���Ⴀ�A�ق�ƂȂ�ł��ˁv
�u�ق�Ƃ��Ƃ��v
�u����ƁA�������߂āA���n�����ĕ�������A���\�T�S���Ă��鎖���v
�u�ނށc�c�v
�u����A����́A�����炩�ɁA�d���l�Ȃ�ŁH�v
�u�������B�����̗ߎ|�ɂ��A�����ʂ���v
�u���ɁA��R�������āA�s�֏���ė��܂��傤���v
�u�����Ă����A�����̉A�ǂ��܂ŁA��]���ق����܂܂ɂ��ė��邩�킩��ʁv
�u����Ƃ�͂�A�C���̏��F�ƁA�\�̂悤�ȁA�������킹������̂ł��ȁv
�u�m���B����Ȏ��́v
�u�܂��A�͂�����A��������ĉ������B�}���ڂ̎������́A�S�z�Ȃ�ł��B�C�Ɨ��̗�������A���̓s�ցA������āA�ǂ��Ɩ\�ꂱ�܂�Ă͊���܂���v
�u�܂�ʗ�����\���ȁv
�吷�́A�Q�O�������āA�ɐ��Ƌ��ɁA�������瓦����悤�ɁA�҂̈Â���Ȃ��肩�����B
����ƁA�ꕔ�̐l�e���A
�u�₢�҂Ă��B�\�\���̗����́A�N�������o�����̂��v
�u�n����Y���v
���ƁA�ނ̉e�����āA�I�ԂĂ���сA�����ɁA�w偂����̎q�̂悤�ɓ����U���퉹�������Ƃ��A��̊X�֎U������B
�u��͂͂́B���͂͂́B�c�c����A����͂��܂��ޓz�𗘗p���Ă�����ȁB����Ȃ������낢�ڂ������̂͋v���Ԃ肾�v
������̎��B
�Z��V�啍�߂̏��Ƃ̑����������Ȃ����čs���Ȃ���A�T�ᖳ�l�ȍ����ł����b�������Ă䂭�l�A�ܐl�̗V�����炵���j�������B
���̒��̔N��Ȉ�l�́A�������ɁA����̕s���l�炵���������A�܂������̂���ނ̂���ǂ���ł������B
|
�����̎�
���̘Z��V�啍�߂́A���Ƃ̑��ł������B�߂��Ɏs������A�ז������̐���������B����̕s���l�́A���̕ӂ�������ɁA������|�M�ق�낤���Ă����B��肽������A�s�̒����𗐂��Ă���B�������A�ނ̉��ɂ́A���⎞��̎艺���O��葽���W�܂��Ă����B�����Č����g���e�R���点����A���̂Ȃ��������T�܂����炵����A��������h�����Ắ\�\�܂������A�s�⏩�Ƃ̎G���X�ցA�A�Ԃ̂悤�ɁA�������ނ̂ł���B
�Ă̖����B
�s���l�́A�C�̒��Ԃ���A�A���������Ƃ����B
(�����̉���A�]���ł�邩��A�]���܂ŏo�ė��Ă���)
�Ƃ������F�̎莆�ł���B
�����֏o�������A�s���l�͎艺�̌��F�A�ۋ����ق��ˁA�Ñ�͂������Ȃǂւ��������������B
�u�\�\�ʂ���͂���܂����A��̉E�n��(�吷)�̖�̌����肾���́A�ӂ�Ȃ�B����ɒ�̔ɐ��̕������B���̂Ƃ���A�z��Ɗ��ӂ̂������ɁA����牝���������悤�����v
�s���l�́A���F�ɑ����āA�����珬�M�ŁA�ےÂ։����čs�����B
�]���̈�O�ɂ́A�����吨�̗F�l�����Ă����B�\�\�������F�A���쎁�F�A�Î����A�I�H�A�唺�\�ǂ����Ƃ��̂���A�ɗ\����ȂǂƂ�������Ԃꂾ�B
�����̉ʂĂ�A�n�����̂�����ł���B
�����āA��C�̔C�n�ŁA�C���ɕς��A���N�O����A���R�ƁA���˓��̊C���A�킪���̊�ɉ��s���Ă���A���ł���B
��������߂́A�ɗ\�̓��U���ЂԂ肶�܂𒆐S�ɁA������E���o�Ȃ��������A�C���̌o�����A�P�����o�Ă������A���ӂ̖��͂��������Ă����̂ŁA�ߍ��́A�l���̖k������A�W�H�A�ےÂ̋ߊC�܂ŁA�I�X�Ɖ��s������A�����Ď��ɂ́A���̗���K�́A�]���A�I���A�_�肠����ւ��A�������̎������݂ɏ���Ă����B
�ޓ��́A�]���A�_��̏�q�������B�����̗��l��A�����ȂǂƂ́A�U���Ԃ肪�܂�ł������B
�����A���c����������Ƃ́A�W����Ȃ������������Ē�ʂ��̑�V�т������B���������┼��ł͂Ȃ��B������O�����Ԃ��ʂ��āA���A���ɖO���̂ł������B
����ƁA���M�ɏ���āA�Z���̗���̑�����A�Ñ邪�A�m�点�ɗ����B
�u�吷���A�}�ɁA�����֗����܂�����B����ɁA�������ł́A���悢��A����t�҂Ƃ݂Ƃ߂āA�����̗߂��o���Ƃ��A�����叫�R��N�ɂ���Ƃ��A�]�c���n�܂��Ă��邻���ł����v
�s���l�́A�����ƁA
�u�����͑�ς��B�������Ă͂����Ȃ��v
�ƁA��ɁA����Ă��B
�u���Ⴀ�A�s�ł́A���哢���R���A�����o������ƁA�����ł���ȁv
�u����A�܂��A�����܂ł͍s���Ă��܂���B���炵�̂Ȃ������]�c�ł�����A�������܂��A���A���������ɂȂ邩�m��܂��ˁA�܂��A�T���Ă݂��Ƃ���ł́A����t����[�������Ȃǂ��A�����^�ڂ��Ƃ��Ă���Ƃ������ƂȂ�Łv
�u�吷�́A���̖������āA�����։������ȁv
�u���ꂾ���́A�m���ł��傤�B�\�\�Ƃ��낪�A�����������ɂ́A�N���A���哢���̑叫�R�ɂȂ�Ă��Ȃ����Ă����\�ł��B�����덡�A�������Ⴀ�A����ƕ����ƁA�ӂ邦�オ���āA���������z���Ȃ��قǂȐ������Ɓc�c�����������F�A�����Ă��܂�����ˁB�������A�E�n��吷���A����O�������悤�Ƃ��āA�]�肭���肪�����߂����܂����`�Ȃ�Łv
�s���l�́A���̂܂܂������A���F�ɘb�����B
���F�́A���������ƁA�t�̖����Ђ��āA
�u�@�́A�n���ė����ȁB�\�\�O�j�����v
�ƕs���l�ɁA�ނ����āA
�u���Ⴀ�A���ʂ����A�吷��ǂ������āA�����։����Ă���v
�ƁA�������B
���Ƃ��s���l�����̋C�炵���B�����ɂ����ẮA����ɑ嗐���N�����A�C�ォ��́A���F��}���A�ےÂɏ㗤���āA�{�i�I�Ȋv���s���֎����čs�����Ƃ����̂��A���̒��Ԃ̑_���ł������B
|
������ȍv��
�u����Ƃ���Ƃ́A�b�R�̖���B�\�\���܂�A���̐������A�ق�ƂɌ�����������̂��B�ނɉ������A���������Ă���B�c�c���������ɁA�s�֍U�߂̂ڂ��āA�u���Ƃ����������ɂ́A���̎v���o�̉b�R�̏�ŁA������낤�ƁB�c�c���F�������\�����ƁA�Y�ꂸ�ɂ����Ă���v
���F�́A���傪��n�̌�q����Ƃ���ɁA���͂��Ă���B�܂藘�p���l�Ȃ̂��B����ǔނ͌����ȑŎZ�Ƃł͂Ȃ��A����Έ��̋����ł���B���ނƁA���̋������Ƃ́A�����A�����A�����̂��悤�Ȍ꒲�ɂȂ�B
���������ƁA�s���l�̐S�̂����ɁA�܂��s�����������B
���́g�b�R�̖�h�Ȃ���̂��A����̕��ł́A�Ă���ɂ��Ă��Ȃ��̂��B�������A���ɏo���Ă݂����Ƃ����������A�قƂ�ǁA�Y�ꂽ�悤�Ȋ�����������A�܂������ꎞ�̎����̌��t�Ƃ������Ă��Ȃ��B
�\�\�����A����ȋȌ��t�̏�����A�^���͏�������āA�v���ڂɁA�܂��v�����p�ցA�ނ��Ƃ炦�Ă���B�s���l�͂����������݂̂������B
�܂����A���F�ւ́A�ނ��b�R�̖�Ȃǂ́A��ɕ����Ă���Ƃ��A�����Ȃ��̂ŁA
�u�����́A���I���B�����������ɂȂ�A���炵������ł��B����ɉ������A���������Ă����܂��傤�v
�ƁA�������B
�u�����B�b�R�̖�́A����̗��ȂB������������āA���I�ȍĉ���Ƃ������B�\�\�������B�ނ����ł́A�ނ����̑���̏����Y�Ƃ͂������B����ǁA���ʂ���������łɁA���F����̍v���݂����̂��Ƃ����āA�����̋W���l�A�ܐl�A��čs���Ă���v
�u���B�c�c���̑��J�����Ԃ��ł����v
�u���J�������\�\�����ƎႢ���ꂢ�Ȃ̂��O�l�قlj����čs�������������B�P�`�ȂƎv���ẮA����̟���������ɂ�����邩��ȁv
���J�́A�����̋W�ł���B
�����O�\�ɂ��������A���X�����������Ă��Ȃ����A�f�p�Ƃ����Ă悢�قǁA�s���ꂪ���Ă��Ȃ��B
���A���Â��̎��̂������ɁA���̒��Ԃ��A�ӂƁA����̂ނ����b�����Ă���̂��A
(���̐l�Ȃ�A�킽���A�悭�m���Ă��܂��B�����ɂ���̂Ȃ�A��ɍs�������B�����A�ǂ�ȉ����ł��A�s���܂��Ƃ�)
�ƁA���̏����Y���A�܂�������̉E��b�ƂɁA�ɐl�Ƃ��Ă������A�����̋��֒ʂ��Ă����g�D�܂������S���ԂȂ��q�h�ł��������Ƃ��A�����ɂ܂��炵�āA����̂낯���炵���̂ł������B
�s���l���A�����̈��F�̂ЂƂ�B�����Ă݂�A�Ȃ�قǁA����Ȏ����������\�\�Ǝv���o����͂���B
���F�́A���̗��ɁA�����Y�̌Ó���݂������������A���[���������āA�ЂƂނ��������Ă�낤�ƁA���J�̐g��݂̂�����A�O�̎�ɂ킽���āA�s���l�Ƌ��ɁA�����֘A��čs���Ă�邱�ƂɂȂ��Ă����̂ł���B
�����A���ꂾ���ł́A�����Ȃ��B���J�́A������ނ����̔ނ̗��l�ł��A�O�\�Ƃ����Ă͔N���Ƃ肷���Ă���B�\�\�ǂ����̎��A�����O�l���A�Ⴂ�̂��A�A��Ă䂯�B�ނ����͒m�炸�A���͓�C�̏��F���A�����̕�����֍v�݂�����̂ɁA(�����c�c)�Ǝv���ẮA����̖ʖڂɂ��������A�ƂȂ����̂��B
���l�̍v�Ƃ��A���l�̑�����̂Ƃ��A���������镗�K�́A���̍��̐l�g�������펯�Ƃ��Ă������Ԃł́A�ӂ��̎��Ƃ��Ă����̂ł���B���F�́A����ȕ�����āA�]���̋W�O���Ƒ��J�̐g���A�s���l�ɑ�A�����ď���ֈꏑ���������߂āA�������Ă�����B
���ꂩ��������̌�B
�s���l�́A�W�������A��ɏ悹�A�������n�̔w�ɂ܂�����A�����݂��̂��̏��l�����イ�ǂ����A����̂Ə̂ƂȂ��ā\�\�艺�̓Ñ�A�w偑��A���F�Ȃǂɔn�̌��ւ��������A�s���瓌�C���������čs�����B
|
�����c�֓���
�W������s���l���A���̖ؒ����d�˂āA���傤�ǁA�x�m�̍~�D������������̂悤�ɍ~�肵����H�̕����m�����s�����\�\�܂ӂ�����́A���ցA���ɏo�Ă��āA�Έ�m��ɂ͂��Ȃ������B
�����m���̕{���֏o�����Ă����̂ł���B
��̏����A�����𗯎�ɂ����A���g�͏����ȉ��A�ꑰ�Y�}�𐔑����܂��Ђ���āA�[�厛�̋����ɁA�h�c���Ă����B
���̕��X�����s���́A�܂�ŏo�w�̂悤�ȕ��n�����A����Ƃ��Ă��A���ꂾ���̗p�ӂ������Ȃ���A�o������Ȃ��댯�������Ă̎��ł���B�\�\������A���̖ړI�Ƃ����̂��A�푈�̒��ق����邱�Ƃł��������A�����������m���́A�ނɂƂ��āA����ΓG�n�ɂЂƂ����y�n�ł���B
�u���̏���̊�ŁA���܂��a���������ǂ����B�܂��A����̕��ł������ɉ���Ă݂悤�B�\�\�b�́A���̏�̎��Ƃ��āv
�ނ́A�[�厛�܂Ō}���o�ė�����������ނ����̂���̂��݂̋����������您���Ɖ���m�o��˂��ƂցA�����������B
�u��낵�����肢�\��������B�\�\���ł̕������A�����Ђ��A������͂��Ƃ��A�����D�ނ̂ł͂Ȃ��B���ł��A�ނ������ɂނ����āA���ɁA�����ɓw�߂銰�x�͂����Ă������Ȃ̂Łv
�u��낵���B����ɂ��ς܂�������Ȃ�A�ЂƂA���ł��A�����Ă݂悤�v
�u���Ƃ��A���o������������ȏ�A���̂��̂ƁA�����߂������́A�������Ăʁv
�u�ł́A�{���A���āA�g���E���A���҂��Ȃ����v
����́A�����ۂ݂���ŁA��l���A�����B
���͏������Ȃ��B
�������A�����̍��́A�ȒP���B
�u�\�\����́A�������܂�v
����́A�������z���Ă����B�܂��\�\�m�M���������̂ŁA���������Ђ������āA�G�n�Ƃ������Ƃ�����ʕ����֏o�����ė����킯�ł�����B
���̕����n���ɂ́A��N�A�ނɂƂ��ẮA�s��ՓV�ӂ������Ă�̋w�G�Ƃ�������E�n��吷���A��������Ă����`�Ղ�����B
���������A�ނ��A����͒�m���Ă���̂��B
�Ƃ��낪�B
���̌�A�����n���𒍈ӂ��Ă���ƁA�吷���A���͂����߂āA�o��������ĉ�����ɂ�������炸�A�����̍����𒆐S�Ɂ\�\�����A�܂��������Â����������A�ߍ��ł́A���ɁA�����̏�����ɁA�o���A�܂��������Ă��܂����炵���B
�o���Ƃ����̂́B
��́A�����S�i�����゠�����̂��ق������Ƃ��������̂��镐�����łƁA�V�C�̌��狻�����A��m�o��Ƃ̑Λ��������ł���B
���̘A���̂����ݍ����́A�����ɁA�吷�����̒n���֗����Ƃ��A�吷�̍�ƁA���S�ɗ�܂���āA���������́A�|�đ�̕��ł̋��ق��P�����A���̂Ƃ��A�ꉞ�́A�ނ�̏����ŁA�I���Ă����B
����ǁA���ł��A���u�T�������T�V�m�N�j�m�~���c�R�\�\�Ƃ����Â��Ƃ���̍����ł���B���̌�A�������ɂȂ����ꑰ�����肠�߁A�����̋��R����܂ɁA�ԂƂ�ł����܂��āA���ɗ[�ɁA�{���̍��������т₩���A���A��ܗ�A�����̐肭�����A�̖��̐����A���r���A�ÎE�A�����\�\�Ȃǂ��s���A�����Ă͂���ƕ��������Ċ�P���Ă���̂ŁA�ȗ��A�����ł́A�������p������A�ŕ����オ�炸�A�܂����������{��ԂɊׂ��Ă��܂����B
�ŁB���̍��ނ���ς��̂�����������������A����ցA
(�ЂƂA���ق̘J���Ƃ��Ă�����������)
�ƁA�������މH�ڂ�]�V�Ȃ����������̂������B
����́A�����������Ƃ��A���������Ċ���Ȃ������B
�{���́A�吷���n��������̂��B
�吷���A���Ƃ̎���ۏ��A�吷�ɃP�V�������āA���ŒǕ���������悤�ȋ������ƌo��̓�l�Ɣނ͒m��ʂ��Ă���B
�����B���̒吷�́A�����Ɏ������A�M�Z�̐�Ȑ�܂ŁA�ǂ��������A���ɁA���ւ͈킵�����A�����炭�A���g�ɟ��ނ悤�ȋ��|��^���āA�s�֒ǂ�����Ă��܂����B�����炭�͂�����x�ƁA���̏��傪���铌���ւ́A���Ԃ݂��o���Ȃ��͂��\�\�ƁA�ނ́A�Ђ����ɁA���ʂڂ�Ă����B
����A�吷���痣��āA���痎�������݂����ȋ����ƌo��B�\�\���������̂ŁA���̓�l���A�����𗊂��ė������Ƃ��A���Ƃ��A��������������A����ɂ������A
(�悵�B���ꂪ�A�b�����Ă��)
�ƁA���C���Ƃ������o���āA��肱���̂ł���B
�v����ɁA���ꂪ����̐��i�������B
�ނ̊Â��ł���A�ނ̐l�̍D���ł�����B
�����A����ɁA�����������A�l�̂�邳������Ȃ�A���̋@��ɏ悶�āA�����ꍑ�ۂւ��ǂĂ��܂��͉̂��ł��Ȃ��B
��ɁA����ł���ꂽ���Ƃ��A�ނɁA�S����Ȗd���C�ƁA�傫�Ȗ�]������Ȃ�A����Ȑ�D�ȋ@���A���܂Ȃ��łǂ����悤�B���ɂ��Ȃ�Ȃ����ٖ��ɁA�댯��`���Ă܂ŁA�̂߂̂߂ƁA�G�n�ɂЂƂ��������֏o�ė���Ȃǂ́A���������A��قǐl���^�킸�A�܂��A���������ė��܂��A���Ƃ����Ȃ��l�Ԃ̂��邱�ƂŁA�܂��ƂɁ\�\������㐢�̊֓��ҁA�]�˃b�q�l��̑c�悽��ɒp���Ȃ����i�̎���ł͂������B
|
���n��
�����̌�B
����́A���łƁA������B
������㗬�̎R�x��������ɂ��A�����̌����A�����тɌ��킽������u�˂ɁA���ł́A�ʑ��������Ă��āA���̕��߂��A�ԑ���ɁA�����߂Ă����B
(�Ȃ�قǁA���̓V�ӂĂ�ƁA�n���ɍ\�����Ă��ẮA�����Ȃǂ��A�肱����̂́A�ނ���Ȃ�)
�ƁA���傷��A���Č��āA���������������B
�u�悭�A���H�����Ƃ킸�A���ĉ��������v
�ƁA���ł́A��H���������āA���҂����B
�u����A�����̘J�Ȃǂ́A���ł��Ȃ��B�����M�����A��x�ʂ��ȂāA���̏���ɁA�܂�����Ƃ����Ă��炦��\�\�����v
�u���܂������Ă��悢�B�c�c����ǂ��A���n�a(�ނ͏���������Ă�)�\�\���̕��ł��A������o��̂��߂ɁA�c���X�̋��ق��������A���F��������A�Ă�����ꂽ���Ƃ͌䑶�m�ł��傤�ȁv
�u����́A�����y��ł���v
�u�\�\�ƁA����������A���̏����Ȃ��́A�ǂ����Ă�������B�����ނ�Ǝ������Ƌ�������Ă��A�ނ肾���A�܂������̈ꑰ���A���m����͂����Ȃ����v
�u���Ƃ��A���̍����⋏�ق́A���킹�悤�ł͂Ȃ����B�c�c���݂ɁA�����Ă����Ă��A���̂悤�ȓD�������荇���āA�đł����̓c���̓��ݍr�����Â��������Ƃ��v���A�����̑����͂����ւ�Ȃ��̂��B����A���킢�����Ȃ̖̂͗����B�\�\�M�������A����Ƃ����Ȃ�A���̂��炢�ȏ����́A���قǂ̎��ł��Ȃ��B�����ƁA�������ƌo��ɁA���m�����悤�v
����́A������������ɁA
�u�����̐g�ɑウ�Ă��A���̋V�́A�Ђ��������v
�ƁA�f�������B
��O�҂���ނɁA�����܂Ő^�S���ȂĂ����ẮA���ł��A�a���Ă͂����Ȃ������B
�u�R��A���n�a�ɁA���C���������v
�ƂȂ����B
�u���肪�����v
�ނ́A�ق�ƂɁA���B���̏���ɂ́A���̂�������Ȃ��B���S�R�����債�����̂��̂ł���B�\�\���������Ă���A�傢�Ɉ��ݏo�����B
�����āA�{���̍����ŁA���������߂āA�a���̎��������悤�ƂȂ����B���̓��ǂ�Ǝ��������āA�₪�ċ��R�̍Ԃ��������B
�x��̋���͂ł����B
�������ɁA�����̋��֒m�点�Ă��B
�������ƌo��̕��ł��A�ًc�̂��낤�͂��͂Ȃ��B
���傪�A�w��̓���҂��A���̓��́A�����̂���{���̘Z�����_�낭����݂傤������A��Ŏ��̒�Ƃ��āA����̕��łƁA���َ҂̏�����A�҂����B
�����芽�삵���̂͏Z���ł���B
�u�����A����ŏ������ł��A����Q����v
�ƁA���̓��́A�Ղ̂悤�ȓ�����悵���B
����́A���ނ�����āA���ւ͂������B�����āA�����͒����̒҂ɓԂ��ނ낳���A���g�͒�Ǝ�Ȃ�҂�������āA�Z�����_�̎���̐X�ւ͂����Ă䂭�B
�����߂��ɁA���ł�����ė����B
�햋��ł����_�O�ŁA���嗧��̉��ɁA�o�݂̎҂����Ȃ���A�H�X�˂��A�_�E�̏j���̂�ƁA�t�y�A�_�a�̋��䂭���Ȃǂ���������A�_���݂����ނ݂킯�āA�߂ł����A�a�r�����B
�u�悩�����v
����́A�ꓯ�ւ������B
�ꓯ�̎҂��A
�u���������Ȃāv
�ƁA�ނ̘J���A���ӂ����B�����āA�Ȍ�̐e�a�𐾂����B
���āA���ꂩ��̎��ł���B
�������j�����A��j���̎����肾�B�ꎞ�ɁA�S���قǂ����ɂ������Ȃ��B
�����ł́A�ޏ��݂��̗邪��A�J��ۂ��A���ɕx�ޓc�ɉ̂��Ȃ������ɍ����ĕ����A�����̕��ł��A�_�y�����Ɏ������ۂ��Ƃǂ낭�B
�D�������́A������l��̂��݂��ɍD�ނ��Ƃł���B���ꂠ�邪���߂̐l���݂����Ȃ��̂������B�������A���a�������̂��B�\�\�E�������Əđł�����������̂��B�\�\���������͈��ނׂ��肯��A�Ǝނ��݂����A���������A�D�ӂǂ��傤�̂悤�ɁA�������ꂽ�B
�\�\����ƁB����������������ɋ߂��B
�����̂���������A�����̒҂ɂ��A������̉��A�ق̂��ɁA���Ԃ�n�߂����B�ǂ����ŁA
�u���܂����v
�ƁA���������A�����ꂽ�B
�}�J�̂悤�Ȑl���퉹�A�Â��ē{���B
�u���܂����A���肠�����b�v
�u����A���܂���Ȃ��B�a�荇�����B����A���킾�v
�u���ł̕��ƁA�������̎҂Ɓv
�u�\�\���ŕ����A�s�ӓ������d���������B���f����Ȃ��v
���ꂬ��ɁA����ȑ吺���A��ї����B
�u�\�\�f�j����v�ƁA�Z���_�Ђ̂����ł��A�������ɂȂ����B
������A�����Ă��Ȃ��҂͂Ȃ��B���܂��ɁA�z�����͂��߂��[�ł��B
�u�����ȁv
�ƁA����́A�������炵�āA���������A���܂�����ł���B
����Ă��l�e�́A���̏�����A��납��˂��Ƃ��āA��������e�ɁA�킯�o���Ă䂭�B
�u�����B�\�\���ė����v
�Z�̂������ɁA�����́A���ōs�������A�͂�X�̂��������ł́A��b�g�݂�����A���n�̂Ђ�߂���A���S���̓�����������悤�ȗ������A�n�܂��Ă���B
�N���A������̂��A�����̈�p�ɂ́A�����̎肾�B
���J�y�̏Z�l�̏K�ȂƂ��āA�������̎�i�Ɏg���B�����A���Ƃ�������Ȃ��B
�u�������B���邩�v
����́A�Ă�ł݂��B
�u�\�\�o��ǂ́B��m�o��ǂ̂́A�����邩�v
������A�Ԏ��͂Ȃ��B
�u���łǂ́B���łǂ́v
����������āA�ނ́A�����O�����A����������Ăщ���Ă������A��������A�������Ă��āA�킯�o���čs�������̂��A�����������悤�ɁA�݂Ȍ����Ȃ��B
�������A����ƁA�A���ė����B
�u�Z�Ґl����ЂƁB�����A�肪�����܂���v
�u�ǂ������킯���B��́v
�u�悭����܂��A���ł��A��������o��̉Ɨ����A�����̒҂ŁA�j�������݂̂Ȃ���A��͂��Ⴌ�ɁA�����ł����炵���̂ł��v
�u�E���B�c�c���ł̉Ɨ����A�ꂵ��ɂ��v
�u�������A���ł̐g�����A�܂��A�������̘Y�}���A���̕ӂɁA�������āA����������Ă������̂ł��傤�B�\�\�Ƃ��낪�A�������ɂȂ��āA�܂��A�b�h�ɐg�������߂��S�l����̕��ł̘Y�}���A���R����\�\��l���ł̋A����Ă��āA�}���ɗ����炵���̂ł����\�\������A�o��̉Ɨ����א����āA���̓����ŗ����j�͂߁A��������Ȃ��A�Ƃ������悤�Ȏ�����A���\���n�܂�A���ɁA�{���̂̐퓬�ɂȂ��Ă��܂������̂ł��v
�u�A�n���ȓz���߁I�@����ȂɁA����܂��āA����Ƙa�r�̂ł������Ɂv
�u�n���ł��B�܂������A�n���҂��낢�ł��B�\�\�Z�Ґl�A��������Ȕn���Ҍ��܂ɗ��������āA�����̗x������Ă���̂͂�߂܂��傤�B�ꕺ�ł������Ă͂܂�܂���v
�u�������B�������������Ȃ��v
�u�����āA�n������Ɋւ������炤�ȂƁA�������̘Y�}�́A���̊O�ցA�����ނ����Ă����܂����B�\�\�Z�Ґl�A���A�艺�����v
�����́A���������s�����悤�ɁA�Փ�A�Z�����������āA�Z���̐X����A�O�֘A��o�����B
�����ĕ{���̉Ό��Ƌ��������̂ĂāA��ǂ����n���}�����A�����̗̓������ċA���Ă��܂����B
�܂��B�\�\���Ƃ̕{���̕��ł��A���̔ӁA��֎����������A�Ȃ�������Ă����B
�������ɁA�֎��Ƃ����Ă����B
�V�C�̕�����o��́A�ǂ��l�������A�C�n���̂ĂāA���̖邩����A�s�֓����A���Ă��܂����̂ł���B
�ނ́A���̖�̕������m�̑������A���ł̌v�����g�s�ӓ����h�Ƃ������v�����݁A�܂��A���̕��łƏ��傪�ꂮ�낢������ނ���ŁA�����������E�����Ƃ����g�v��h�ł������̂��ƁA�����ʂ�邸����傤���܂킵���̂��B
���ꂪ����ł��������Ƃ́A�ނ����������������Ă�����A�[���A���������ɂ������Ă����͂������A������A��قNjV�������A�Q�Ď҂������ɂ������Ȃ��B
����A�����炪��A�C�n�S���Ă��܂����̂ŁA�s�֒����₢�Ȃ�A�������֏o�āA
�u����̖�]�́A���ɁA�����m���܂ŁA������̂��Ă��܂����B���łƐS�����킹�A�����ǂ��āA�����̒D���������݁A�{���͂��ɍ����Ɋד���̂ق��Ȃ��L�l�ƂȂ�ʂĂ܂����䂦�A���͑厖�ƁA��ɏ㗌��������ɂ�����܂���v
�ƁA�����̕s�Ă��������B�����߂ɂ��A�ɗ́A����̖�]�����Ƃ��A���łƂ̕����͓�`�I�Ȃ��̂Ƃ��đi���A�܂�����̏������ɂ��A�����ӂ����傤���ĉ�����B
��R�B�\�\����ɂ������钆���̋^���́A���̎����ɂ��A�֖����������ꂽ�B���܂⏫��d���̍����́A�m��I�Ȃ��̂Ƃ���āA���Ƃ͂����A�����̑�d���l���A�ǂ����ē��������邩���A���c�̏d����Ƃ��āA�㋨���傤���������̔Y�݂ł������ɉ߂��Ȃ������B |
�����Ă��鑐�J
���Ƃ̏o�����Ȃǂ́A����́A�����m��Ȃ��B
���Ƃ��ނ́A��Ђ̋`������A���o�����܂ł̎����B
�u�n����������B�Ȃ��A�����v
�u����͂�������܂��ł��B�n����ɂ���A�����Ɣn�������܂���v
�u��ɂ͏�̂�����̂��B�c�c����������Ԃ�n���̕����Ǝv���Ă������v
�u������A����Ȕn�����Ԃ́A�������Ƃ�����܂���B�����ɂ́A�������w�ɂȂ�܂����v
�u�ɂ����������Ȃ�B����͂��̌Z�̂��Ƃ��B���ꂪ�\�N�]��̏㗌���Ȃǂ��A���v���A�n�����E�̌��w���B���̖��ɂ������Ă��₵�Ȃ��B�c�c���͂͂͂́A���������ƁA��͂莩���͔n���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��悤���ȁv
�n�̔w�ƁA�n�̔w�ƂŁA�Z��͂���ȋC�y���b��r�X�ɂ��Ă����B
�u�������A�r�̂��łɁA�L�c�̕����ӂ���ł����čs�������v
�L�c�́A�H���̗nj��ɁA�đł����ꂽ�p�Ђ̋��@���B���̌�A��H���������Ă���B�ȑO�ɂ܂����ق����₩�����A���������ǂ���v�H������������Ă����B��O�����A�������Ă����B
�ނ́A��������āA�Έ�m��A��A�����ɉ���āA���Ȃ���������A���ւ̉����~�ւ͂����āA�������������B
����ƁA�Ɛl���̏������A
�u�����璆�ɁA�s���炨�q�l�����āA�ׂȓ��ŁA���A���҂��܂��ƁA�����A���₩�ɑؗ����Ă����܂��v
�ƁA�������B
�u�ȂɁA���₩�ɁB�c�c�N�ƒN���B���������v
�u���N�O�ɂ�������ꂽ����̕s���l�a�ƁA�����č��x�́A�������̉��Y�ƁA�Ȃ��l�l�̏����ɂ債�傤�����A��ɂȂ��āA�����A�\�l�قǂ��������܂��傤���v
�u�ӂ��ށH�@�c�c���̕s���l�����v
�s���l�ƕ����A���ɁA�Ȃ�����������A�d���邵�������������Ă���B�\�\�N���A�s�֗V�w�ɏo�����̑��邩��A����̈ÈłŒm�Ȃ����ƂȂ������̗F�B�j�K��Ƃ��������������Ȃ��̂��B
�u�ǂ̚₩�v
�ƁA�ނ́A�������ē��ɁA���̓��֍s���Ă݂��B
�Ȃ�قǁA�L��n���Ă䂭�܂ɁA���������ւ�Ȑ���������B�s���l��A��̎҂̂��ݐ��Ɍ������āA�L���b�L���b�Ə��������̛g����牽���A�܂�Ŋ����̈ꎺ�Ƃ������悤�ȑ����ł���B
�u�����A�s���l�B���Ă����̂��v
�ނ��A�����Ɍ�����ƁA�j�����̊�A�������̊�A�ꂹ���ɁA�ނ�U������āA�����Ă�⋏���܂������B
�u�₠�A�߂������B����傠�邶�v
�ƁA�s���l�́A���������A�t�����āA
�u�܂��A�����ցv
�ƁA�Ȃ������߂āA�ꉞ�̎��V���A��ʈȗ��̋�����ׂ̂Ă���A���āA�ɂ�ɂ�Ƃ������B
�u�Ƃ��ɁA���n�a(�ނ��A�ȑO�̂悤�ȌĂю̂Ă���߂āA���Ԃł����悤�ɁA�����Ă�)�\�\�����ɂ��鏗���������Y��͂���܂��́B�c�c�����A����ق��āA�͂ɂ���ł���̂��B�͂��A��ė��Ă�������̂��v
�ƁA���J���w�������B
����́A����������ޏ��̉�����A�܂��܂����Ă����Ƃ���ł���B�Ƃ��������B���̊�́A�ς��ƍg���Ȃ����B
�u�����A���܂��́A�]���́c�c�v
�u���o���ł������܂����ł��傤���B�]���̑��J�ł������܂���v
�u�����B����͈ӊO�ȁv
����́A�S����A���������ď\�]�N�̉߂��������A�v�킸�r�V�����B
�u�\�\���͂��܂ŁA�ς�Ȃ����̂��Ȃ��B�킪�g�̕��́A����Ȃɂ��ς������v
�u�������B���Ȃ��l���A�����������ς�ɂȂ�܂��ʁB�ق�ƂɁA�������ς�ɂȂ��Ă�������Ⴂ�܂���v
�u����B�����ł�����܂��B�܂��s�ł́A���̍��A�E��b�Ƃ̏��ɐl���A����̏����Y�ł������͂����B�ȗ��A�Ⓦ�̖�ɋA���āA�߉J�S���Ђ�����Ղ��ɑł��@���ꂽ����B����S���A�ނ����̂悤�ł͂Ȃ��v
�u���S���ς�ꂽ�Ƌ������Ȃ�A����͎��ɂ͕���܂��c�c�v
���J�́A�ӂƁA�X���˂��悤�ȁA�����āA�҂����ɋ��������悤�Ȋ�ɂȂ����B������A��ɂ�ɁA���ɂ��������Ƃ�����̂̂悤�ɁA�t���Ƃ肩����ƁA�s���l���A
�u���������B���������̒s�b�������킭���͂悵�Ă���B�t���A���n�a�ɂ��������ʂ̂��B�\�\����A���⑊�n�a�B�Ȃ������Ȃ��A�]���̗��́v
�u�Y��Ă��܂����B�����c�c�܂������������̂悤�ł����Ȃ��v
�u�����ł��낤�B���́c�c���������A�҂������݂킳�߂ƁA���F�a����A���̑��J�ƁA�ق��O�l�̗V�N�������A�����ւ́A�v�݂��Ƃ��Ă�����ɂȂ������̂��B�ǂ����Ƃ��Ă������������v
�u�v���Ƃ́A���������ł͂Ȃ����B���蕨�Ȃ�A�����Ă��悢���v
�u����B���F�ǂ̂́A���Ȃ����A������n�̌�q�݂��Ƃ��āA���h���Ă�����B�����ł�����Ȍ��t������ꂽ�̂ł��낤���A���蕨�ɂ́A�������Ȃ��̂��B�ǂ��ł��A�Ⓦ�ɂ́A��̉ԁX�́A㇗���傤���ł��傤���A����ȓs�̉Ԃ��A�����ɂ����Ē��߂�̂��A�܂爫���͂���܂��܂����v
�u����A���肪�����B�����������蕨�Ȃ�A�܂ӂ��A����̐g�̂܂��́A�~�r�ӂ䂴��̂悤�ɗ҂����Ƃ���B���������A���̔t���܂킵�Ă��炨���B�c�c���J�A�����ł��ꂢ�v
�ƁA����́A�ޏ��̕��֎���̂����B���J�́A�N���߂����ԉł̂悤�ɁA�p���炢�Ȃ���A���q�̕���c�����B
�\�\���̎p�Ԃ��ȂɁA���̉���ɁA����͂ӂƁA���N�̉����������A�X�ɘm���܂���̏����Ȃ��ŁA����̔��ɏ��߂Ēm�����ق̓z��̏��z�\�\�ڈΔ��̂����������A�S�Ɏv���o���Ă����B
|
������g
�R���A������l��͐����I���i�ɂ͂܂����������Ă���B��V�I�ɁA��̕��E�ӂƂ���쐫�̖��ŁA����̕����Ԃ݂�͗e�Ղł͂Ȃ��B
���̌���\�\
�����ꍑ�́A�����̂܂��܂肪���Ȃ������B
�����������傪���قɏo�����āA���ł������A�����������您���A�o��˂��Ƃ̎O�҂̂������ɁA�a�r���ł��A��ł����ɂ܂łȂ�Ȃ���A���̓��̕��a�𐾂������肩��A�܂��化�܂��Ђ��N���A���Ƃ̓D����֕Ԃ��Ă��܂��n���ł���B���傳�����A����������āA
�u����A�����ꂽ���̂��B�����Ăт���Ȕn�����̔n������ɗ��������āA���ق̌��������Ȃǂ͐^�b�����B�܂��A���Ƃ���܂ł���Ă�����A�Ⴊ���߂邾�낤�v
�ƁA�ȗ��A�ǂ������璇��𗊂݂ɗ��Ă��A���đ���ɂ��Ȃ����������B
�������A���̕����̓������A����̉^���ɂƂ��ẮA�������Č��Ă�����Ί݂̉Ђł͂Ȃ������̂��B
�C�n�̊��E�Ȃ������āA���s�֓����A���Ă��܂������o��́A
�u�܂������A����̖d������݂Ɉ˂���̂ł��v
�ƁA�����̊��ӂցA�������ĉ�����B
�u�\�\�a�r�̒��قɗ��Ə̂��āA���͂��悢�挖�܂�傫�������A���̋��ɏ悶�āA�������r�炵�A�Ђ��Ă͕��������Ȃ̐��͉��ɕ����������Ƃ������̂ɂ���������܂���v
�ƁA�������������傤����̓��\�ɂ��A�����ɂ߂āA�q�ׂ��ĂĂ����B
������A�����ɂ́A�吷�̑i�����������Ƃ��낾���A����̐l�C�͔��ɂ�邢�B������������܂ɂ�����������A������[�������Ȃ��ŁA
�u�c�c��������Ȃ�B�����������v
�ƁA�m�肵�Ă��܂��悤�Ȍ�����ʂ̐����ł������B
���u���Ă͂����Ȃ��Ƃ������c�ł���B
�u�����։����������i�ɂ́A�N���A��قǕs���Ȑl�������������˂Ȃ�܂��v
�Ƃ��āA�V���ɑI�ꂽ�̂��A�S�ϒ�A������̂�����ł������B
���̒�A���A�����̐V�C�m���Ƃ��āA�����։������Ă��琔�����̌�ɁA����̋��傽�鑾����b�Ɓ\�\���������́A�]��ɕ��X���鏫��̈��]�ƁA�����Ē��c�����łɔނ�d���l�����Ă��鎖������A
�u���Ă����܂��v
�Ƃ����āA�����͓��ɁA���{���l�����^�l���イ�����̂��낤�ǂ����̂܂тƂɁA�������������āA
�u�Ȃ��ꉞ�B���̎��ۂ�����������������Ă܂���v
�ƁA�����֗��������B
�^�l���A����g���イ���Ƃ��āA���������ƕ������Ƃ��A�����̎q���̋���t����[�����������́A�������낦�āA
�u�����炭�́A�^�l�������Ă��A���̉v�ɂ��Ȃ�܂��܂��B�����ɂ́A�吷�̑i�������鎖�ł��B�ނ��A�������E���āA���̂��Ђ낰�����ʁA�����Ɍւ��āA���ɍ����ł́A������݂炸�A���ɍR���Ă��A�Ȃ����̖\�~���ق����܂܂ɐL�����Ƃ��Ă��鎖�́A�]��ɂ������ł��B�\�\������A�䋳���݂��傤����Ȃǂ������āA�������������ɂȂ�Ȃǂ̎��́A�������āA��������āA���������邾���̂��̂ł��傤�v
�ƁA�������B
����ǁA�����̐S�̉��ɂ́A�܂������Y����̏��傪�c���Ă����B�\�\���̏����Y���Ƌ^����̂ł���B
�u����A�O�̂��߂�B�����ɂ��A�O�����߂��Ĉ����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��v
�����͊��U���āA���߂̍l����ς��悤�Ƃ͂��Ȃ������B�ނ����ł́A�����Y���d���Ă������̐F�D�݂ȕ�����b���Ƃǂł͂Ȃ��B�N�����\�ɋ߂��A�������̒��҂Ƃ��āA�܂�����̌��V�Ƃ��āA�����ɂ܂�A���̊낤�������A�ǂ������牸�₩�Ɏ��ߓ��邾�낤���ƁA�������́A�J���ɂ����Ȃ�����ɂ������B
|
���ڈΔ��ƌĂׂ�
����g�̑����^�l�́A����قǂɘj���āA�����A�����A���̑��̒n�������@���A�����ď���ɂ������ẮA���ځA�ʒk���āA���̎ߖ����A���߂��B
����ɂƂ��ẮA���ׂĂ��c�Ȃ킢���傭���ꂽ�����ł���B
�吷��槑i���ł���A�o��̋��\�ɂ����Ȃ��B
�ނ́A���������Ɋm�Â��邽�߂ɁA�����A���A����A�헤�A�����ȂǁA�܃����̍��ɂ���������A���Ԃ�(�����̏ؖ�)�����āA
�u�����̂��Ƃ��A�����͒m�炸�A�Ⓦ�n���ł́A�������Ȃ�ƔF�߂Ă���҂͂���܂���B���ׂĂ�槎҂���̍�莖�ł��B�����Ă���槑i�ɂ��Ԃ炩����āA��������ʌ��e�ɔY�܂�Ă���̂��A����̏����ł͂���܂��܂����v
�ƁA���g�̔F�߂��ٖ��̕\�Ђ傤�Ƌ��ɁA����𑽎��^�l�ɒ�o�����B
�u�_���ł��v�ƁA�^�l�́A�ނ��D�ӂɌ����B
�\�Ɖ��g���āA�₪�Ĕނ́A����̂܂܂𒉕��ɕ��ׂ��A���s�A���čs�����̂ł���B
�����܂ł́A�܂��A�����ł������B
���̖N�قǂ̒Z�������̊��Ԃ����A����̈ꐶ�U��ʂ��Ă����Ȃ��g�����̓��h�ł�������������Ȃ��B
�L�c�̐V�@���A�v�H���Ă����B
�ނ͂����Ɉڂ�A�l���̈ꕔ�́A���փm��Ɏc�����B�܂��Έ�m��ɂ��A�刯�����������͂�ɂ��A��J�����̌�~�݂����ɂ��A�ނ̒킽�����A�Ɛl�Y�}�����āA���ꂼ��ɒ�Z�����B
���߂́A�q���Ƃ��āA����̊قɐg���Ă�������̕s���l���A��������̉Ɛb���l�ɁA�ނɎd���A
�u���n�a�\�\�v�ƁA�ނ𐒂����߁A�܂����ɂ����Ă��u���فv�ƌh�̂��āA�����ȑO�̂悤�Ȉ��F�Ԃ����͌����Č��킳�Ȃ��Ȃ����B
���厩�g�̊ј\���܂��A����ȑO�Ƃ͂������ė��Ă���B
����A�ނ̏O�]�́A�����ւ�Ȃ��̂ł������B���Ă̏헤�坁���́A���삾�́A�H���␅��̏f�������̉��ɂ������y�n�Ɛl�ԂƂ́A���������āA���̂Ȃт��悤�ɁA�ނ̖�ցA�ނ����āA�W�܂��ė����B
��̉��҂ł���A��l�̒��̐e���ł������B
����ǁA�������������ȁA�����ė��^�̓��������ė��Ă��A�ނɂ́A�ǂ��������I�ȉe���@������Ă��Ȃ������B�\�\���������ς�����ނ̐l�ԂɌ����o���Ă����̂́A�ň��̋j�[�ƁA�ޏ��Ƃ̒��ɐ��܂ꂽ�m���u�ޏ��Ƃ̒��ɐ��܂ꂽ�v�̓}�}�n��q�Ƃ��A�f���̗nj��̕��̂��߂ɁA�����J�̓��]�ŎS�E���ꂽ������̌��ۂł���B
���̂Ƃ��́A�ނ̐�]���ƁA�l�Ԃ̎c�s���ւ̗����{�Ƃ́A�������āA�w�݂̂Œ��肱�悤�ɁA�ނ̑��e�ɁA�[���A�e���Ƃǂ߂Ă���B
�����łȂ��A���̉A�e�́A�������A�S�̕ǂɂ��A�J�r�݂����ɁA�����݂��Ă����B
���́A�N�Ƌ��ɁA�ʂ𑝂����B���܂ł͑���̕��ł���B�~����������ƁA�S�̑����Ђ炯�A���R�A�����ƋC�������炵���B
�u�����A�ڈΔ��B�c�c���܂��͂����s�A���Ȃ����B����Ƃ��]���A�肽�����v
����́A���J�̂ق����r���т������Ă������B����[�ׂ̐����̒��ł������B
�u�܂��A�����A�ڈΔ����Ȃ�āc�c�B���͍]���̑��J�ł���B����Ȗ��ł͂���܂���v
�u�X���˂��̂��v
�u�����āA�ق��̏��ƊԈႦ��ꂽ�肷��A�ǂ�ȏ������ē{��ł��傤�v
�u�{��Ȃ�{��B�c�c�s�ɂ������A���߂āA���܂��Ɠ���Ȃ���ŁA�S�����ǂ点���̂��A���܂������̉ڈΔ��ƉZ��Ƃ����Ă悢���A�悭���Ă������炾�����B�\�\����ɂƂ��ẮA�Y�꓾�Ȃ����߂Ă̏��B���ꂪ�ڈΔ��Ȃ̂��B�����Ă��Ă���v
�u�Ђǂ����قł����ƁB���͎��łȂ���ł��ˁv
�u����A���܂��́A�ڈΔ����v
�u�������A���J�ł���A�킽�����́v
�u���������B����ł��ڈΔ��łȂ����v
���������߂āA�����܂���A���J�̐O���ނ��ڂ����B���������ӂ�킹�A�����Ђ��߂āA�O�����`�Ȃ�ɐg�炵�����̎p���A����́A�������Ɏ��ɕʂ�Ă��܂����ڈΔ����A�����݂�p�ƌ���̂ł������B
�u�c�c��A����́c�c�B�����܂ł������ȁv
�L�̊O�ɁA�s���l�̉e���A��������ł����B
�u�����A�s���l���B�ׂɌ����Ĉ����قǂȎ�����Ȃ��B�����͂�������ǂ����A�������ցv
�u�ł́A���掟������������\���Ă����܂����v
�u���ށA�����H�v
�u�����̋������Ƃ����҂��A���A���O�ցA������\�R����Ō����܂������v
�u���A�܂��D����̖��A���ɂ͂����Ă���Ƃ��Ȃ�Ƃ��A���َ��̗��݂��낤�B���ʂ�������āA�p������u�������Ă���v
�u�ł́A��N�A�{���֏o������āA�a�r�ɂ܂Ő��肩�������̂��A����̌��܂ŁA�܂��Ԃ��Ă��܂������̈���̎҂ł��ȁv
�u��������B�O�����̕������狻���Ƃ����j���v
�u�S���܂����B����\������ė������A����Ă��܂��傤�v
�s���l�݂͂̂���ŁA����������ނ����čs�����B
�q�Ƃ����Ă��A��\�R�̓����ł���B�n�͉X�ɗa����A�l�Ԃ͍T���ɒʂ��A�����ċ������������A�q�a�Ɉē������B
�u�Ă܂��́A���n�a�̌���݂����̎ҁA����̕s���l�ł����v
�ƁA�ނ́A����ɑ���āA���ɏo���B�����Ă��������A���ӂ������˂��B
|
�����҂̖�
�������́A�S�����ė����̂ł���B
���ɕ����ɂ������܂ꂸ�ɁA�ꑰ����āA���O�֓����ė����̂ł������B
�O����s�a�ȕ��łƂ��A�Ȃ��R�����Â��Ă����Ƃ���ցA�s����V���ɕ��C���Ă����S�ϒ�A�Ƃ�����Ȃ��ŁA
�u�������肪�V�n�ł͂Ȃ��v
�ƁA��A�ɏ悶�āA�����𗧂��ނ��ė����̂ł���B
�\�\���A�Ђ낢�V�n�Ƃ͎v�������A���Č��܂킷���A�Ⓦ�\�B�̕���ł́A���ޖ؈��������͂Ȃ��B
�u�ǂ��֍s���Ă��A�����A���n�a�̖����ʂ��Ƃ͂Ȃ��B����a�Ƃ́A���˂Č�ʎ������Ă��邵�A�m�������Ȃ����Ƃ́A�g�ƂɁA���炢�\���Ă���B�r�����������܂������A�����ȉ��A�ꑰ����݁A���ق̒[�ցA�g���̎҂Ƃ��Ă�������������܂����B�c�c���Q�\�������肢�̋V�Ƃ́A���͂���Ȃ킯�ł����邪�v
�������́A������������ŁA�����˂āA
�u�ЂƂA��ӂ�����A���n�a�ւ����Ȃ��𗊂ށB�����̒ʂ肨�˂����\��������v
�ƁA������������B
�s���l�́A�l�����B
����͂������낢������������ŗ����B�\�\���������l�Ԃ́A�ǂ��ǂ��P���ɏW�߂Ȃ�������Ȃ��B
�s���l�̉�炢���ƁA���̊ق̗]��ɖ����Ȃ͖̂{�ӂɜ����Ƃ�B�Ȃ��Ȃ�A�����ẮA��C�ɂ��������̂낵��҂��Ă��鏃�F�Ƃٌ̖_���A���悢���ނȂ������̂ɂȂ���Z���傫������ł���B
�x�m�͕�����f���Ă���B
�Ⓦ�̕�����A���̔@���r���A�Ɣނ͎v���B
�ނ͉����A�@�������ŁA�_�Ζ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA����̐g�ӂ���ł��閳���ƈ��Ղ𐁂�����Ă��܂����Ƃ��l���Ă����B���������Ƃ���ւ̋q�ł���B�S���ҋ���������������������ŗ����̂ł���B
(����͊��}���ׂ��������B���Ƃ��A���������Ă��A���Ԃɉ����Ă�낤)
�s���l����͂������܂������A���������Ɏ掟���ł݂�ƁA�ނ̏����Ȃǂ͕s�K�v�ł������B�Ȃ��Ȃ�A�������̎�����ƁA����́A�������Y��āA�����ɂ��̋����ɁA����āA
�u����́A���������v
�ƁA�����̂ł���B
�u�ЂƂ��т́A����܂ŋ߂Ȃ���A�ꑰ����āA�����֗��S��ڂ����A����̖�ɗ����ė���Ƃ́A�悭�悭�Ȏ����낤�B���m��̓��ɁA��\���̉��~���Ă���͂����B����ւł�����Ă��v
�����̌�ɂ́A�������̍ȁA���A���A���Y�������H����āA�ނ̈�Ƒ������ł��\�l�߂��l�Ԃ��܂��A�L�c�ȗւ����̂����ɏZ�ނ��ƂɂȂ����B
�����镗�����ďW�܂�Ƃ������̂ł��낤���B���n�a�̖�֗����Ă䂯�A���Ƃ����Ă����\�\�Ɠ`���������ҋ����A�������̂ق��ɂ��A���g���������B
�������A���������ނ̎҂́A��������H���t���ɋɂ܂��Ă���B�����Ƃ��A��������m�ŁA�Ђ������ɁA�Ђ��������ƁA�ۂݍ���ł��̂��A�㐢�̂�����m���̐e���ł���A���̐���́A������l��̂������ɂ́A���厞�ォ�玝���O�̂��̂ł������炵���B
�V�c��N�̏H�A�\�����߂̍��������B
�헤�̍�����A�܂��A���̉����L�c�ցA���S���ė����l�Ԃ�����B
������������߂��Ƃ����āA�헤�̊��ɂŁA�����̐E�ɂ������j�ł���B
������吨�̍Ȏq�⏢�g��A��\�\
�u�ǂ����A���������܂��˂��������v
�ƁA��������ŗ����̂ł������B
�����͏헤�̉����Ƃ��āA�]��]���̂����j�ł͂Ȃ��B
�ނ��A�����̂����ɁA�˂ɏ�i�ɔ��R���A�e�\�ŗ⍓�Ȋ������Ƃ������Ƃ͏�������˂Ă����������ɂ��Ă����̂ŁA
�u�������E�𗣂ꂽ�̂́A�����ꎩ�Ǝ����Ƃ������̂��낤�B����ȎҁA���܂��Ă��킯�ɂ͂䂩�ʁB�ǂ������Ă��܂��v
�ƁA�ނ����ɂ́A�����̊��x���m���������Ȃ������B
�u�����ɂ��A�������ʂ�A�q�������ɒ������������������j�ł����c�c�����ޓz�́A�헤�̓�����悭�m���Ă���͂��ł��傤�B�����ł��낢��Ɛu���Ă݂�ƁA���قɂƂ��ẮA��邪���ɏo���Ȃ���厖���ӂƌ�����܂�����B���ɈӊO�Ȏ����v
�s���l�͂��������āA�l��������悤�Ȋ�������₩�����B����́A���������܂�āA
�u�ȂB����ɂƂ��āA��邪���ɂȂ�ʈ�厖�Ƃ́v
�ƁA�����ɐu���Ԃ����B
�u�E�n��吷���A�Ƃ�����헤�A���āA���X�ɁA�܂��������߂��炵�Ă���炵���̂Łc�c�v
�u�ȂɁA�吷�̂���H�v
�吷�Ƃ����ƁA����͂����S�������������킵���B����������������ݏo���Ėʂɂ�������ނւ̑����ƁA�x���ƁA�����ĖY�����݂ɔR�����́A����A�s���l����������ɓw�߂Ă�������̊�ȂǂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ����̂ł���B
|
�������̈�l��
�����̍Ȏq�⏢�g���A�܂��A�L�c�̓��ɓ��܂�ꂽ�B
�����ɁA���̐l���̖������A����������������Ƃ͈�ʂ�łȂ��B
����L�c�A��~�A�刯���A�Έ�Ȃǂɂ���ނ̈ꑰ�����āA
�u���f�͂Ȃ�ʂ��B�c�c���̂܂ɂ��A�吷�߂��A�܂��헤���肱��ł���Ƃ������v
�Ƃ���A���ׂĂɁA�����Ȃ�ʋْ������������B���펞�̐��ɓ������悤�ɁA�삷���ɂ͏����𗧂āA��͖�x�̕���z���āA
�u�\�\������Ȃ�A�吷�v
�Ƃ��������̊���ł������B
�ł́A�����������A�ǂ����������������������炵���̂��Ƃ����A����͂����A�E�n��吷���헤�ɂ���Ƃ��������̂��Ƃł����Ȃ��B
�������A�헤�Ƃ̍����́A��ߑѐ������������������B����ɂ���A���ꂾ���ł��A�����������Ă͂����Ȃ��B�x���̗��R�́A�[���ɂ���B
����ɁA���̌�A�����̎�ɂ���āA�吷���헤�ʼn������ł��邩�Ƃ����֊s�́A�ǁX���������ɁA���炩�ɂȂ����B
�헤�̍��i(����)�����ۖƁA�吷�Ƃ́A���Ă���Ȃ��Ԃł���B�\�\�吷�̎o�͈ۖ̍Ȃ������B
���̋`�Z�̎q���ɁA�����߂̂�Ƃ����҂�����B�吷�Ƃ́A�f���������B
���́A�����̕��e�ɂ͎����A�|�n�̒B�҂ŁA��ɁA�����̕����A�����̂悤�ɂ悭�������A�킪�Ƃɂ��A�q�����̕��҂���������ɗ{���Ă���B�\�\�����̂��Ƃɂ��A���������w�����Ƃ�A���Ȃ����Ă��A�O��̕��n�͂��ł����R�ɋ�g����͂�����Ƃ����B
�吷�́A���ς炸�������B�����āA�\�Ɏ����͗����Ȃ��B
�����āA�����A�������݁A
�u�����A���Ȃ����A�킪�Ƃ̒p�J���������ŋ����Ȃ�\�\�����đ傫���́A�����ƕ��a�̂��߂ɁA���\������A��������Ă����Ȃ�A�S�������̓c�̂ł��傤�̈ꔼ�́A����Ƃ��āA���Ȃ��Ɍ��サ�悤�B�c�c�܂��A���Ƃւ̌��J�Ƃ��ẮA�����瑾�����\�����āA���Ȃ炸�����Ȋ��ʏ��M���傭��̂��邱�Ƃ��A���\���Ă��悢�v
�ƁA���ƂI�݂ɁA�������Ă����B
���Ȃ����ɁA�|�n�ɂ����ẮA���M�̂�����ł���B�S�����Ȃ��͂��͂Ȃ��B
�u���̌��́A�����āA���炲�Ƃł͂���܂���B�\�\�����̔@���A���ɂĂ�����A���哢���̊����͂��邱�ƂɂȂ��Ă���̂ł��v
�ƁA�吷�͂Ȃ����A�����̎ʂ���A�i��Ɋւ��鏑�ނ������A�܂������ɂ����铰��̋�C�Ȃǂ��A�܂т炩�ɁA���Ɍ���āA
�u���܁A����𗧂Ă悤�Ƃ���Ȃ�A������āA�������̉Ï܂������������ł��傤�v
�ƁA���̌��C�Ȃ�n�����҂��A���������B
�u���Ƃ��v
�ƈ��́A���ɔR�����B
�u�킵�ɂƂ��Ă��A����́A���ɂȂ���l�X�̋w�G���c�c��炢�ł��A���̓��ɂ��v
�u�������A��֍s���قǁA����̕��͂́A����ɂȂ�܂��B���̓��ɂ��Ƃ����Ă͂����܂���v
�u�����́A�N�ƒN���v
�u�Q���̑��₩��́A���ނɑ���܂���B�������Ȃ����A�����������Ȃ�A���́A���ꂱ���Ǝv�������̈�l�����A�O���sࣂ���ӂ��̐㓪�����Ƃ��ɂ����Ă��A�����ƋN�����Ă݂��܂����v
�u�ӃE�ށc�c�B����ȑ�l�����A�ǂ��ɂ���̂��v
�u�������牓���Ȃ�����̓c���ɂ���܂��B���Ȃ��Ƃ́A���������������ł����A���̖����̂��āA�c�������G���Ђł��ƂƂ��Ă���l�ł����v
�u�����c�������a���B�c�c�����A���̂悤�Ȑl�����A�����ɋN���낤���v
�u�������q�Ƃ��ĎQ�邩��ɂ́A���Ȃ炸�N�������ɂ͑[�����܂���B�c�c���͂܂��A�G�����g�ɂ��A�[���A�F�C�͂���̂ł��B�ނ��~�������̂́A���ł��邩���A�吷�͒m���Ă��܂�����v
�u�ǂ����āA���ꂪ����H�v
�u���āA�c���̊قɁA�����߂�������������B���̐܂̔ނ̌�C�ŁA�ނ͌����āA���̉���̉��̎g���炢�ŁA�������Ă�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă��܂��B�ނ���A��]���X����l���ł��B����ǘV�Ԃł�����A����̂悤�ȉ���͂��܂���B�\�\����ɁA����Ă����A�������点�Ă����āA�ォ��A���▃�ł��A���悤�ƍl���Ă���̂��A�����G���ł���Ɓ\�\���͌��܂����v
�u�|�낵���l�����ȁB���ƁA���C���̈����c�c�v
�u������Ȏ҂łȂ��ẮA�����ɊĂ�����������܂��܂��v
�u����͂������c�c�B����͏��傾���v
|
���헤����
���Ԃ́A���������Ƃ���܂ŁA���X�ɐi��ł����̂ł���B
�����Ē吷�́A�헤����R�z�������ẮA�т��A����̓c���։������Ă����̂ł��������A������ɂ́A�܂�����܂ł̋@���͒T�蓾�Ă��Ȃ������炵���B
�����ɂ��Ă������ł���B
�ނ������炵����̂��̂��A�ɂ߂ĕs�[���Ȃ��̂��������A����Ɍ������g�A������߂������̂�����̂ŁA���̂������낢�ɁA�����āA������c�Ȃ��Ă���X��������B
�����A�s���l�ɂ���A���͂Ƃ�����A�������낭�Ȃ��ė����B�v���ڂ����ė����Ƃ����Ă悢�B
�u�s�ӂ����āA����̘T���̂����ɁA����������A�Ƃ����v���ł��傤�B�ЂƂ헤�֏�荞��ł݂悤�ł͂���܂��v
���̔N�̓~�A�\�ꌎ�̂��Ƃł���B
�s���l�́u�������v�ƍl�����̂ŁA��������ցA�����B
�u���B�c�c�捞�ށH�@���ʂ����헤�֍s���Ƃ����̂��v
�u����A����ȃP�`�ȏ���ł͂���܂���B���X�ƁA���n�𗧂āA�w�e������āA���n�a�����i�ۖɌ��Q����\�\�ƌ������čs���̂ł��v
�u�������Ȃ��ł͂Ȃ����A�������v
�u�\�ʂ̗��R�́A������ł�����܂��B�\�\���������Ȃ�҂��A�L�c�ֈ��i���ė����ɂ���āA����������Ă���ė~�����A�����̒Ǖ߂��~�߁A�ނ��A���E�ɕ����Ă��炢�����Ɛ\���A����ւ̕������悢�ł��傤�v
�u��낤���B�s���l�v
�u���ׂ��ł��B�����āA����ꂪ�헤�ɓ���A�ނ�̘T���Ԃ肪�ǂ����A��������B�܂��A�吷���Q�ďo���āA�K�������o���ɂ������Ȃ��B�\�\�ꍇ�ɂ���ẮA���̓r�[�ɁA�吷�߂��A�����߂�Ȃ�A��ɂ��ĊM����������悤�Ȏ��ɂ��Ȃ�Ȃ����������܂���v
���̍�ɂ́A���������A�����ɂ߂āA�^�������B�����A�����A�����Ȃǂ��A
�u�����A�����I���s�����낤���H�v
�ƁA�����̓�̑����ӂ��A�܂������s�^���ł��Ȃ��B
�����āA���̔N�A�\�ꌎ��\����̂��ƁB
����͂���������߂��B�����̏�����疼���]���A�L�c����헤�����ďo���ƂȂ����B
��Ɏv��������A���̈�������A�ނɂƂ��āA�v���I�Ȃ��̂ł���A����܂ł̎����I�ȑ�������A�V���̗����ƌĂ�鋫�݂��������̂ł��������A���̒��̔ނ̍s����l�n�́A�ӋC�g�X������̂ł������B�\�\���ׂĂ̏ꍇ�A�l�Ԃ����ׁ̊������m���u�����Ƃւ�{��v�AU+9631�A402-1�n�ɗ����������O�Ƃ������̂́A�����������ӂɖ����Ă�����̂ł���B
|
�����A���
�헤�̍����ɂ́A�捠���瑾�����̏��@�g�����Ă����B�����Đ����ԁA�����Ƃ̍s���̑ō������A�v�ł��������̏Ȃǂ��A�{������u��������肵�Ă����B
�e�������傤�̂��イ�����艓�����Ƃ��ƁA���̐��������ł������B
���̒e�����艓�́A���A���i�̓����ۖ̓@�ɏ�����āA����ȋ����̎�o�ɂ�����ꂽ�B
���������āA���ɂɂЂ��������̂́A���Ȃ�[�X�̂��Ƃł������B�������A�ނ̐����������A���ꂼ���H�̋����������A�݂ȖO�����Ė���ɂ����B
�����́A�I�����̂ł���B
�䂤�ׂ̉��́A���ʂ̈Ӗ��ł��������B�������A�킸���Ȏc���Ɨ��x�x�̂��߂ɁA������͋x�{���Ă����B
����ƁA�בʂɎR�Ɛς܂����y�Y���������āA�ۖƂ��̏]�҂��A�����ɔނ̗��ɂ�K�˂ė����B
�u���́A�����ł����낤�B�낭�Ȃ����ĂȂ����Ȃ��āv
�u����A����ǂ���ł͂Ȃ��B����Ȍ�����ɂ́A�s�ł��ő��ɏo��܂���v
�u�₪�āA��̈��ƁA�����č���ꂵ��ɂȂ����吷���A������ƁA�䈥�A�Ɏf�������Ƃ��\���Ă��܂����B�����ƁA���̂��x�x�ɁA���S��������Ȓ��ł������܂��傤���v
�G�k���Ă��邤���ɁA���̈��ƒ吷���A�A�ꗧ���āA�܂������֗����B�\�\���̓�l���A�S�ʂ̕i�X���A�艓�̑O�ɋ����āA
�u�����܂��A�����c���s���ʋC�����܂��ȁB����͂ЂƂA���C�y�ɁA���̉Ƃ֗V�тɗ��Ă��������v
�ƁA�����������肵���B
�u�f���܂��傤�B���̎x�x���������A�����p�̂Ȃ��̂ł�����B�c�c�������ۖǂ̂�吷�ǂ̂���ꂵ��ł��傤�ȁv
�u�o�����܂��v�ƁA�吷�͓����ā\�\�u�����̓@���A�ȑO�̂悤�Ȃ�A���Ј��͔����Ă������������̂ł����v�ƁA�������B
�u���������B������̑坁�����ǂ̂��S���Ȃ��A�Ȍ�̌�Г�ŁA���قȂǂ��Ă���Ă����܂��ɂȂ����Ƃ��v
�u�����߂��A�X���\���肪�����ɂ͂����Ă��鎖�ł��傤�B���₨�p����������ł��v
�u���āA���Z���͋ߍ��H�v
�u�߉όS�Ȃ�������̂��鏊�ɁA���ɍȎq�ƉƐl���͒u���Ă���܂��B�\�\���A�����͋��s�Ƃ��̒n�����������Ă���̂Łc�c�܂��A�ʂ��������̂悤�ȋ����ł��ȁB�͂͂͂́v
�吷�̎��}���Ă�����ɂ́A���G�ȉe���������B����ɍ�邩�瓯�Ȃ��đł��������ӂ��͎����Ă��Ă��A�����̏Z���ɂ���A�ߍ��̐i�ނɂ��Ă��A�ǂ����b�ɖ��Ă������Ă����B�閧�����l�Ԃ̂悤�ȁA�N�ɂł��אS�ȋC�������ĕ��������Ă���ӂ���������B
�������A�e�����艓���A��������Ȋώ@���������Ă����킯�ł͂Ȃ��B�ނ��A�吷�Ə���Ƃ̌����Ȋ�����A�܂����̒n�����܂߂��Ⓦ��т̐ϔN�ɂ킽�铬���Ȃǂ��A�����𗧂Ƃ����玨�ɂ��Ă����B����ǁA����ɐG�ꂽ����Șb�ɂȂ�̂��悭�ق킫�܂��Ă����̂ł���B�n���Ȃ���A��k�ɂ͋����Ă��A����ɂ͐G��Ȃ��Ɍ���Ƃ��߂Ă����B�\�\�����č��́A���p���ʂ����A�ʉ��ɂ��Ղ݁A����̋��Y���̑��蕨�����̂ŁA�����A���肰�Ȃ��h�𗧂��A�����s�̍Ȏq�̊�ł����悤�Ƃ����~�]��]���Ă��邾���ł������B
�Ƃ��낪�A���̓��B
����吷�������A�܂����̗��ɂŒ艓�Ƙb������ł���ԂɁA�����̑��n���A��������ۖ��A�����܂ŁA�T�����Ăė��āA
�u���ςł��B���̐N���ł��B�����̏��吨���A�勓���āA�헤�̍����݉z���ė����Ƃ̕�点������܂����v
�ƁA��R�O�R�ƁA�������ŁA�}�Ɉۖɑi���ė����B
�\�\�܂��A�ꌣ�A�Ɨ��ɂ̎҂ɖ����āA����̎x�x�������A�艓��������ɁA�O�����Ђ��~�߂Ă����܂ł��������A�r�[�ɁA����Ȏ�q�̂��났�͏��������Ă��܂����B
�u�ȂɁA����̌R�����Ɓv
�ƁA�܂��吷�������Ȋ�����āA�������𗧂Ă����A���́A�\������Ƃ�����������̂ŁA
�u�����ȁI�@�@��𐧂��āv
�ƁA�Â܂Ȃ�����グ�āA�˂��������B
����ǁA�N�����A�ӔC��A�V�����̂́A�ۖł���B�ۖ́A���q�̈��ƒ吷�Ƃ��A�����������ɂ킽���āA�����A����������������ׂ��A�R���̏[�����͂����Ă��邭�炢�Ȃ��Ƃ͒m���Ă������A�����܂ŁA������h�����Ă������̂Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B���Ƃ�藼���Ԃɐ퓬���N�낤�ȂǂƂ́A���z�����Ă��Ȃ��l�������B
�u�ǁA�ǂ��������Ȃ̂��B����͈�́v
�吷�����A���q�̊�����A�ނ͂��̘T���Ԃ���B�����Ƃ��Ȃ��T�����āA��l�ɐ������B
�u�����A�ԈႢ�ł͂Ȃ��̂��B�c�c���̈�O�҂̏����ɁA�����N������A�K����܂��A���̍����␅��̗ǐ���H���̗nj��Ɠ����Q�ނ��낤�B�\�\�\���đ���ɂ���ȂƁA���܂��B�ɂ��ł������Ă������v
�吷�́A������炵���B���ԂɁA�ނ炵���_�o������Y�킹�āA�������ɁA�\�ꌎ�̋�����Ă����B
�ۖƈ��Ƃ̕��q�̊ԂɁA������Ɗ���̂��ꂪ�I���ɂȂ肩�����B���̕�����`�Ƒ��q�̔e�͎�`�Ƃ̐H�����������A�͂��Ȃ����\�ʂɏo���̂ł���B
�u�܂��A�䕃�q�ł���Ȃ���̋c�_�͂���߂Ȃ����B����ȏꍇ�ł͂Ȃ��ł��傤�v
�艓���������̂͂����Ƃ��ł���B�������ɂ���Ȏ��Ԃł͂Ȃ��B�����Ē艓���܂��A�}�ɍ��𗧂��Ă����o�����B
�u�����Ǝv���Ă������A�������ꂩ�璼���ɏh�𗧂��܂��B�\�\�吷�ǂ̂ɂ́A�s�ł������܂����낤���A�䕃�q�ɂ́A���܂�����o�����番��ʁB�c�c�ǂ�����@���悤�B�c�c���ɍ\�킸�A�ǂ��������̕��ցA�������킯���������B�ꍏ�������A�ǂ����v
|
���r��̓�
�����̂܂ɁA�����́A��ǂ̂悤�Ɍł߂�ꂽ�B
�헤�̍s���Ȃ߂����A�͓��A�߉όS�Ȃǂ̏���������A�Ȃ����X�A�����̕ς��āA���{�̊��ɂ⊯�q�����ׂ��A���n���킯���Ă���Ƃ��������B
�ꎞ�A���R���C�݂��Ꚅ���킢���Z�����A����Ɨ��������B���i�����ۖΈȉ��A���ׂĂ��b�h�ɐg�������߂āA
�u����������B�ЂƖA�������Ă����v
�ƁA�|��A�|����ׂāA�҂��\�����B
��R���牓���o���āA�n�I�A�������������A�n�̋r���炵����A���u���X����ӋC�������Ă����̂́A�����܂ł��Ȃ����ŁA
�u����ꏫ����A�����֔���ΖԂ̋����B���̈��̉��ɁA�헤�ɂ͏���̋����O�炪�A���ł����ɔ����ĘB���Ă���̂�ނ͒m��ʂƂ݂���v
�ƁA������̖����ցA������Ă����B
�������A����ɂ��ƁA����̌R���́A���悻�l�A�ܗ�����ɕ��n���~�߂āA�ǂ���炻��ȏ�ɂ͑O�i���ė�����悤�Ȃ��A��c�̏����܂ł��Ă���Ƃ����B
�u�����́A�ǂ�����ȁv
�ƁA���͕����ւ����˂��B
�u�����ƁA��R�����ƌ����܂��v
�u�ȂɁA��l�B�Ȃ�̎����v
�ƁA���͑傢�ɏ����B�����N�U����ɂ́A���Ȃ������̍��̏���ȏ�ȕ��͂��ȂČ����̂��펯���B���������ȁ\�\�ƎႢ���́A���ꂾ���ŁA��������̗͂��A�[���Ɍ��o�݂��т��Ă����B
�Ȍ�̕����́A�[���ɔ����Ă��A���̕ω��������ė��Ȃ��B
�ނ́A�����āA�v�n�v�n�ɖ����܂��ӂ������A�₪�ĘY�}���R����āA�����̖{�c�A���ė����B
����ƍ����̍L��ɁA�J�������̐l�n����Q��A�[�ł̒��ł܂��܂����Ă����B����ƁA���̒��ɁA�������ɂŕʂꂽ�e�������傤�̂��イ�艓���A�ڂ��肵��������ĘȂ�ł���B
�u�₠�A�e�����a�B�ǂ��Ȃ������̂ł��v
�u���B���ǂ̂��B����̂��悤�́A�ǂ��Ȃ̂ł��v
�u����B����Ȃ��̂́A�ǂ��ɂ��N���Ă͂���܂��ʂ�B��������A��o���͂ǂ��Ȃ��ꂽ�̂Łv
�u����A�����̔@���A�בʋ��l�������������āA�h�͗����Ă͗����̂ł����A�r���A��Ɋ������܂�Ă͑�ς��Ǝv�����A�ۖǂ̂��吷�ǂ̂��A�����͕ۏ̌���łȂ��A�댯�͏[���ɍl������ƁA������ɂ��������߉�����̂łȁv
�u�͂͂́B���߂̋������傫�������̂ŁA�������ƘT�����Ă���̂ł��傤�v
�u�X���͖����ɍs���܂��傤���v
�u�܂���{�̖���˂Ă͂��܂���B�����̎��͒m��ʂ��A�����͕����ł��B�������������}�����S�Ȃ�A�r���A���S�ȏ��܂ŁA�����̕������ɂ��đ��点�܂��傤�v
���ɂ����Ă���A�}�ɒ艓�͕����ɂ߂��B���R�̖���������Ȃ������ɁA������A�헤�𗣂�Ă��܂��Ɍ���ƁA�C���}�����ꂽ�̂��B
�吷�́A���Ԃ��獑���̓��ɂ����āA�ۖ�{���̒��ɗ���������A������疋�����̓��̏��������Ă����B�{���A�ނ͂����̗��ł͂Ȃ����A���ɂ��A�����Ɋւ��Ƃ����C���͑ттĂ���킯�ł��Ȃ�����A���ɂ̓����Ɏp�����킵�āA���i�֏���������w�}���܂����U�������Ȃ��ȂǂƂ������́A��@�ł����邵�A�z���ȍ��������A���Ԃ����ԂȂ̂ŁA�N�������ގ҂͂��Ȃ��B
�u�e�����l�ɂ́A��͂��ɂ����Ă����̂����ɁA��o���ɂȂ肽���Ƌ����܂����v
�{���̈�l���A�ۖɒm�点�ė����B
�吷���A�����āA
�u����́A���������H�v
�ƁA�Ђ��~�߂����ŁA�Q�ĂĒ��̒�֏o�ė��Ă݂�ƁA�艓�͂����n�ɏ���āA�]�҂Ɍ��ւ���点�Ă����B
�u���v�ł���B��S�z�͂���܂���c�c�v
�����������̂́A�o�����čs�����l�ł͂Ȃ��A���Ɍ��Ă������ł���B
�u���̕����ɂ������āA�r���܂ŁA���点�܂�����v�\�\�ƁA����吷�̞X�J�����Ă����̂������B
���ЂȂ��A��l���A
�u�ł́A���C�����āv
�ƁA�艓�̈�s���A���̖�O�܂ŁA���������B
����ƁA���̖�������Ȃ������ɁA�e�����艓�Ƃ��̐����𑗂��čs���������̕����A�����A���ė��āA
�u��厖�ł��B�r���A����̕��Ɏ�͂܂�L�������킹���A�e�����l�ɂ́A�ߗ��Ƃ��āA�G�̎�ɒD���Ă��܂��܂����B�\�\���̑��̐������A�݂ȓ�ڂ������āA����̐w���ֈ������Ă�ꂽ�l�q�Ɍ����܂��v
�ƁA�ӋC�n�̂Ȃ��ł������B
�������A��\�����t���Ă�������̂����A�A���ė����͎̂l�A�ܖ��ɂ����Ȃ��B
�u����A���傪���킵�ė���O�Ԃ�Ƃ݂��邼�v
���́A�ł̂����ɁA�w���ɗ����A���{�̓����A�F�߂������Ă����B
�\�\�ƁA���̒��B���������A�R�n�b�h�̈�c���A�i��ŗ��āA
�u����́A�����̕����傪�g�҂ł��B�헤�̍��i�ۖǂ̂ɕ��\�����̂����Đ��Q���Č�B�\�\�ۖǂ̂̉c�֓��������v
�ƁA���̐w�O�Ɍ����A�܂�܂�Ɗ�荇���Ȃ���A�吺�ɂ����Ă����B |
 �������q�̕���3�E����L
�������q�̕���3�E����L



 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@ �@�����s��
�@�����s�� �@
�@ �@�����s�ʌ�
�@�����s�ʌ� �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
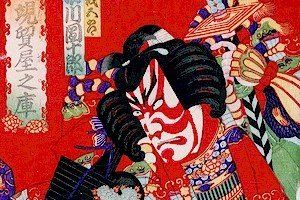 �@
�@ �@
�@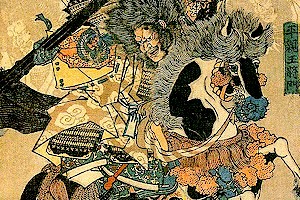
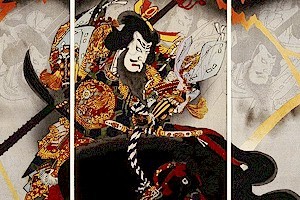 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@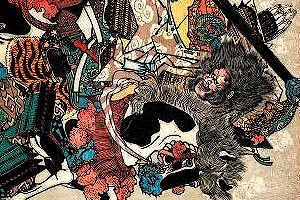 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@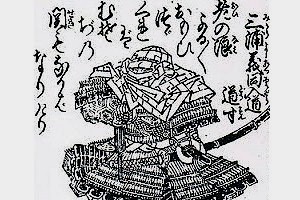 �@�@
�@�@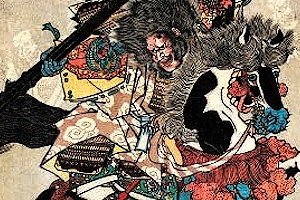
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@