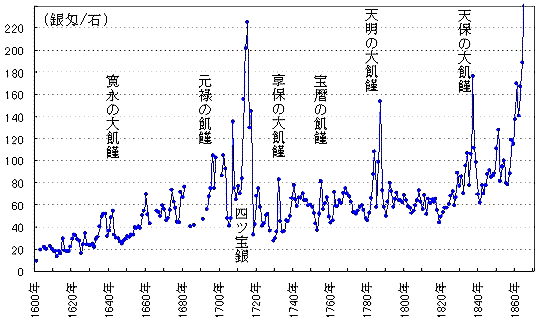| �����̐��ޏ� |
�@ |
����|�}�@�u�����̂��ނ���v�ƓǂށB�c���ӎ��̐��U��`������i�ŁA���̐l����c����݂̂��k�A��q������炪�x����B�܂��A���̍�i�͎O�l�̐t�Q���Ƃ����Ă��ǂ���������Ȃ��B����͂����ƁA����ƔN������Ă���͂��Ȃ̂ɁA���̎O�l���Ⴂ�܂܂̂悤�Ɏv���Ă��܂����߂��낤�B���̎O�l�ɉ����āA�����\���q�Ƃ����َ��Ȑl��������ł���B�c���ӎ��̐̂���̈�ʓI�ȕ]���͎��d�����ʼn��E�ɂ܂݂ꂽ�l���ł���Ƃ������̂ł���B�]���͈����ł��邪�A�ŋ߂͐����̎��_����c���ӎ���]���������������A�{����������������ɂ���B���̗���ōs���ƁA�c���ӎ��̓K�^�̗��Ă��開�{�̉��䍜���Č����邽�߂ɗl�X�ȕ����ł��o�������A�u���Ő����������Ƃ������ƂɂȂ�B�����āA���̌�ɗ��鏼����M�͓c���ӎ��̐�����S�ے肵�����߁A���{�Č���䖳���ɂ����Ƃ������ƂɂȂ�B���̏�����M�́A�ŏ��������҂��ꂽ���̂̂����Ɍ�������킸���Z�N�ł��̌��͂̍����炷�ׂ藎�����B�c���ӎ��Ƃ����l���𐳊m�ɕ]������̂́A�o�C�A�X����蕥��Ȃ���Γ���B���̃o�C�A�X����菜���̂��A���r���[�ɂ�����͖{�����炢�ɂ������������̂�������Ȃ��B�łȂ��ƁA���̎��ՂƂ������̂ɏœ_������ɂ����Ȃ邩�炾�B�c���ӎ��Ə�����M�Ƃ��������Ƃ̕]���Ƃ����̂́A�����������獡��ς���Ă������̂Ȃ̂�������Ȃ��B�c���ӎ��̈�̕s�K�́A���̍ݐE���ɓV�ϒn�ق��N�������Ƃł��낤�B���̒����ǂ��Ȃ�ǂ��납�A�����Ȃ����̈�ۂ�^���Ă��܂����̂́A�^�̈����Ȃ̂�������Ȃ��B������̕s�K�́A����オ����̂ł��������Ƃ��B�����Ȃ��Ƃ�����A�Ƃ��ɓ���@�ƂɘA�Ȃ��O�Ƃ��O���ɑ��܂�Ă����߂�����B����ɂЂ����瑫����������ꂽ�Ƃ������������邾�낤�B�{���ł́A�c���ӎ��̑��q�E�Ӓm���a��������P���q��������̂������̂͏�����M�ł���Ƃ��A���ɂ͌�O�Ƃ�����Ƃ������������Ă���B������������A�����Ȃ̂�������Ȃ��B�����āA������������A�c���ӎ��̕]���̈����Ƃ����̂́A���������c���̉h�B�ގҒB�ɂ���č��ꂽ���̂������̂�������Ȃ��B���āA�薼�ɂ��ẮA�{���̒��œc���ӎ��ɉ��L�̂悤�Ɍ��킹�Ă���B�u�킵�́A���̏�Ɩ����Ȃ��A���̂܂܁A��C�ւȂ������̂��B�C�̔ޕ����炳�܂��܂̑D�����Â���B�C�������ė��鋛�B�̂��ǂ���ƂȂ�悤�ȏ�Ɏd�グ�����v�����ЂƂ���B�u���̓����A���܂��܂̋������̖��֓����ė���Ƃ悢�ȁB�킵�͂��̎��A���̏�ɂ��āA���܂��܂ȋ����}���A���̘b�Ɏ����X���悤�B�C���z���Ă���ė���҂ɂƂ��āA���̏�͋������̂��낰���ł���Ƃ悢�̂����ȁv
�@
��
�@
�{����|���̗���̐��Ƌ߂��ł��k�ɏo������B���k�̐��Ƃ��߂����B���k���œ��肵�Ĉȗ������甪�N�Ԃ肾�B���̑O�ɗ���͂̂��܂�đ��O�̍�q���ɗ{�q�ɍs���Ă���B���ɗc����݂ɂ�����l�̗����Ƃ��u��������B
�@
�O�l�Ƃ����{�̉Ƃ��B����̑����Ƃ͓�S�A���k�̐ē��Ƃ���S�A�c���������O�S���B
�@
���̓��A���u�����œ��肷�邱�Ƃ�m�����B����͖{���̊��{���Ƃ����B
�@
�\�\�c�������͉Ɠ𑊑����Ĉӎ��Ɩ����A���݂���Ď�a���ƂȂ��Ă����B����A����{�q�ɍs������q���͍����̒��ɓ���D���������B���k�͕H�_���D�≮�E�����K��Y�̂��Ƃɉł��ł���B�����͕i���a�R�̘[�ɂ���B
�@
�\�\�ł������u�����߂��ꂽ�Ƃ����B�D���Ă����̂��B����̖�������Ȃ����A�\�ɂȂ��Ă���͓̂c���ӎ��B
�@
�����A����͐M���Ȃ������B�\�͂��u�����c���Ƃɏ���������Ă��������ɈႢ�Ȃ������B��������A�c�������ׂ̗Ɏ������̂͂��k���Ƃ����Ǝv���Ă����B
�@
�����v���Ă���ƁA���u���̉Ƃ���j���o�Ă����B���̌��p�ɂ͌��o��������悤�ȋC�������B
�@
�\�\�c���Ƃ̑��Ă̌�p����q�Ƃ������ƂɂȂ����B�c�������͋�㏫�R�Əd�̏�������ƂȂ��Ă���B
�@
���̓c����������q���𑠏h�ɂ��悤�Ǝv�����̂́A�����ꗴ���q���̓���ƂȂ������ɁA������M���ċ���p���ĂĂ����Ǝv�������炾�B�䂪�F����Ȃ玩����M���Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@
���u�������̂͏��̎q�������B
�@
�\�\��㏫�R�Əd�͌���s���ĂŐ��m�ɕ�����邱�Ƃ��ł���̂͑��d���̑剪���������������B�����ēc�������͂����Ə��R�Əd�̌��t���낤�Ɠw�͂����B���R���ǂ�قNJ������A���������v�������Ƃ��B
�@
�\�\�c�������͍�q������狎�N�̌܌����甒�R�������ӂŋN���Ă���Ҏa��̘b�����B���̌���A���s�͑������B�����āA�c�������͒Ҏa��̔Ɛl���m�M�����B
�@
�\�\���k���g���Ă���Ƃɓc���������ɂ��ʂ��Ă���Ƃ̘b�𗴉�͕������B��l���q���̍�����D�������Ă��邱�Ƃ𗴉�͒m���Ă����B
�@
�\�\��䏊�ƌĂꂽ�g�@���̒�������Ă���B�悤�₭��������㏫�R�Əd�Ɉڂ낤�Ƃ��Ă����B�����Q�ɋꂵ�݂Ȃ�����Əd�͋����ȏ��R�ł͂Ȃ������B
�@
��������̓c���ӎ��ɂ͔������͂Ȃ��������A���t���W�܂�Ȃɂ͉Əd�����ɌĂB�ۉ��Ȃ��ɐ������w����Ȃ������B���{�̖ډ��̉ۑ�͕Čo�ς������B
�@
�Čo�ς����藧�̂́A�ĉ��Ƒ��̒l�i���ύt��ۂ��Ƃ��������A�ܑ㏫�R�̍�����ĉ��͉�����͂��߁A�t�ɑ��̕����͉�����Ȃ���Ԃ������A���m���������邱�ƂƂȂ����B���㏫�R�g�@�͕ĉ��̈����グ����ɋꓬ�������̂̎v���悤�Ȑ��ʂ��オ��Ȃ������B
�@
���Əd�̎���A�ĉ�����ƕ�������ɖ|�M����Ȃ���A�Ȃ�Ƃ������������Ɏ������Ƃ����ł���B�낤���Ɠc���ӎ��͍l���Ă����B
�@
����̑䏊�͂ڂ�ڂ�ŁA�y������ꂩ���Ă���Ƃ����Ă悩�����B
�@
�\�\���̊ۂ̑�䏊�g�@�̗e�Ԃ����������B����܂ŋ�㏫�R�Əd�̎����͒Z���ƌv�Z���Ă������t����͘T�����B���Ȃ������B��ɏ��R�̑��߂Ɋ�F���M���������B�c���ӎ��ɂ��Ă݂�Εs���̈ꌾ�ɐs�����B
�@
�ӎ��͏��R�ɑ��ėǂ��Ɛb�ł���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������o�����܂ňȏ�ɋ����Ȃ��Ă����B��䏊�g�@�����������B�c���ӎ��O�\�O�B
�@
�\�\����̋���ŁA���k�͉Ƒ��ƂƂ��ɒM���D�̋����\���q�̂Ƃ���ɐg���Ă����B����̍K��Y�������������A�����\���q���ʑ����Ă��ꂽ�̂��B�I��������Ă���āA�悤�₭���ʂ������n�߂Ă���B���k�̎q�A�V���Y�͋�ɂȂ��Ă����B
�@
�����āA�]�˂ɖ߂邱�ƂɂȂ����B�]�˂𗯎�ɂ��Ĕ��N�B�]�˂̓X�͖����{�Ƃɏ������Ă����B
�@
�\�\�c���ӎ��͈ꖜ�̑喼�ɂȂ��Ă����B�͂��߂ė̒n�̑��ǂɍs�����ƂɂȂ����B����ɍ�q����������s���邱�ƂɂȂ����B
�@
���C���f�q�̏h�ɂ͂��k�̈�s�������B�����\���q�����s���Ă����B�����āA���̋f�q�̏h�ł��k�͓c���ӎ��Ƌv���Ԃ�̍ĉ���ʂ������B
�@
����A�c���ӎ����狛���\���q��K�ˁA���k�����̐��b�����Ă��ꂽ����q�ׂ��B��������������Ƃ��āA�ӎ��Ƌ����\���q�Ƃ̌𗬂��n�܂����B
�@
�\�\����N(�ꎵ�܋�)�͓c���ӎ��ɂƂ��Ẳ^���̏���ł������B�����N�A��̓c���Ӑ�����O���E�ꋴ�Ƃ̉ƘV�ƂȂ����B
�@
�\�\��㏫�R�Əd���B�������j�E�Ǝ����\�㏫�R�ƂȂ����B���R�̌�ւ͎��R�ɏ����ɉ^�ꂽ�B�����āA���\��N���Əd�����E�����B
�@
�V���R�Ǝ��͕Ă⌐��̑��ɖ��{�̍������v�͂ł��Ȃ����̂��Ɛu�˂��B���t�̗��ɂ͕��l�N�ɋN�����S��Ꝅ������̂��������B�ĈȊO�ɗ��v�𑝂₻���Ƃ���̂Ȃ�A�Ƃ肠�����́u���v�ł���B
�@
�ӎ��͍�q������ɉƍN�̎��ォ��S�N�̊Ԃɋ��₪���т��������C�O�ɗ��o�����b�������B��͎l���̎O�A���͎l���̈ꂪ���o���Ă���B���������肾���炻���Ȃ�...�B
�@
�c���ӎ��͉�������Ĉꖜ�ܐ�ɂȂ����B
�@
�\�\�����\���q���ٍˑD�Ƃ͂��Ȃ�قȂ�O���̑D�ō]�˂ɂ���Ă����B�m�D�̒������������ꂽ���̂������B
�@
�\�\���a�l�N(�ꎵ�Z��)�B�c���ӎ��͑��p�l�ɂȂ����B�l�\��ł���B�ɉ������ꂽ�B
�@
�ؔҒ��ɉ��~�������A���������I�ȏ��W�߂̐ȂƂ��Ă����B���~�̎�͂��k�������B
�@
���̂��k�����u�������̓o�����Ƃ��Ȃ��Ă���Ă����B�����đ剜�ւ̕����������B�c���ӎ��̎������A���o���̑剜�ւ̕�������Ȃ����B
�@
���̎����ӎ����͂𒍂��ł����̂́A���{�����ɒʗp����ʉ݂������B����͋⊨��A�]�˂͋⊨�肾�����B�ӎ��͂�����d���ɊW�Ȃ��ݕ��ɕ\�����ꂽ�ʗp���l�Ŏg�p�ł���ʉ݂ɓ��ꂷ�邱�Ƃɂ����̂��B
�@
���a�Z�N�B�c���ӎ��͓ܐ�ɉ�������A�V���i�Ƃ��Ė����̕\����ɗ������B
�@
�\�\���肪���₩�ɂȂ����B�����\���q�͎v�����B��̗A�o���~�߁A�������~�������Ă������Ɏ�͂�ς����B�����ɂɂ��x�����͂��ׂċ��݁A��݂Ƃ������ƂŁA���Ď���ꂽ����ȏ�̋��₪�W�܂��Ă��Ă���B���Ղɂ���ė͂����߂��Ă����B
�@
�\�\�c���̖����ɂ�苛���\���q�̎����ۂ��]�˂����B�ڈ��������̂��B����܂łɂȂ����Ԃ������炳�ꂽ�B
�@
�\�\�剜�ւ����������o�����ꋴ�Ƃ̎��ςɌ����߂��A�ꋴ�Ƃɕ�����邱�ƂɂȂ����B
�@
���t�͌�O�����ɐ�Ƃɂ��Ă��܂��Ă��ǂ��Ƃ����l�����������B�Ƃ����͉̂Ǝ��ɂ͉Ɗ�Ƃ������q���������炾�B��O���̑��݈Ӌ`�͔����B
�@
�\�\���a��N(�ꎵ����)�B�ӎ��͎O���ɉ����ƂȂ�A�����ɘV���ƂȂ����B���p�l�͌����ł���B���̔N�A�ڍ��s�l��̑���]�˂��P�����B�\�ꌎ�ɉ������A���i���N�ƂȂ�B
�@
���i��N�B���o�����j�����o�������B�ꋴ�L���A��̓���ƐĂł���B���̒���A�c���Ӑ������B�Ӑ������O�ɓ���̈ꋴ���Ă͍��d�D���ƌ����Ă����̂��v���������B
�@
�\�\���i�O�N�B�c���Ƃ����B���͏����Ƃւ̗{�q���g��f�����B���B���͏����Ƃ���c���Ƃɒ�M��{�q�ɂƊ肢�o�Ă���̂�c���ӎ��͏��m���Ă����B
�@
���̌��Ɋւ��ď��R�Ǝ����畷�����b�Ɉӎ��͐�傷��B����͓c����M���A���͂֒f������ꂽ�̂́A���j�̉Ɗ���ꂪ����Ύ����͂���ɂ������̂�����Ƃ������̂������B�Ǝ��͌��{���Ă����̂��B
�@
���������c���Ƃ͐��̉Əd�̎��ɂ����R�̍��������炳�܂ɑ_���āA�Əd�����ɂ܂�Ă����Ƃł���B�Ǝ��͂��̕��̐S��m���Ă���B
�@
�����������A���o�����剜�̎��͎҂����ƍ��ӂɂ��Ă���Ƃ����b���`����Ă����B�ꋴ���Ă̈ӂ��Ă̂��Ƃ��낤�B
�@
�c����M�͏��R�Ƃ̂����|����Ƃ��āA���͔˂ɗ{�q�ɍs�����ƂɂȂ����B
�@
�\�\�Ɗ����ɂ����ĕ��ׂ��������B�����ċ}�����Ă��܂��B
�@
�\�\���i��N(�ꎵ���Z)�B�c���ӎ��͏��R�Ǝ��̋����ē�\�]�N�Ԃ�ɑ��ǂ֍����肵���B���R�̂����|����Œz��̖�������Ă��玞�Ԃ������ď����点���B�̖����ꂵ�߂č��悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����炾�B
�@
�\�\�c���ӎ��͉ڈ��ڂ������ׂ����邱�Ƃɂ����B���̍��̖��ɗ����ƂȂ牽�ł����錈�ӂ��B���h���̂ĂāA�������B��p�D�����������ĉ������������B����ɂ́A�C�̌���������̌��Ղ̑D������Ă���̂����҂��Ă����B
�@
�����āA�ڈł͉䂪���̏��l�����낵��̏��l�Ɣ��ׂ��Ă��邱�Ƃ����������B
�@
�\�\�c���ӎ������ǂɍ����肵�����N�A��������ēV���ƂȂ����B�������A���c����Ă������R�Ǝ��̌�p�҂Ƃ��Ĉꋴ�Ƃ��L��オ�}�����邱�ƂɂȂ����B���̊ۂɈڂ��ĉƐĂƖ�������B
�@
�\�\�V���ƌ������ς���Ă���C�s���ƂȂ�s�삪�����Ă���B�����������A�V���O�N�ɐ�ԎR���啬���N�������B�Q�[���L�����Ă����B�@�@
�@ |
| ���c���ӎ��E��a�̐� |
�@ |
��������@���\�N(�ꎵ�Z�Z�N)������́A���悻�l�����I����ʂɓc������Ƃ����B���d�����̌����ƌ�����c���ӎ��ł��邪�A���̔��z����Ƃ���́A���Ȃ�̐挩�̖��̎�����ł��������Ƃ���������e�ƂȂ��Ă���B���{����̉�����̂́A����X��قǎ����Ă��鏤�l������肵���ŋ������Ȃ��������Ƃɂ���B���������肵�Ă��钆�ŁA�o�ς����W����A�s���ɋ������܂�͓̂�����O�̂��Ƃł��邪�A�����ɖڂ����Ȃ�������X�̖��t�̑Ӗ������얋�{�̕�������Ƃ����悤�B���̖��t���@���ɖ��\�ł��������́A�c���ӎ����R�藎�Ƃ���������M�̉��v�ł�������ł��낤�B������M�́A�i�C��₦���܂��邱�Ƃɂ͓V����i�̓��������������A����ȏ�̔\�͎͂������킹�Ă��Ȃ������B�����l����ƁA�V�ϒn�ق��N����Ƃ����s�^��A�c���ӎ��̔N��I�Ȑ��Ȃ���A�c���ӎ����l���Ă������Ƃ́A����I�Ȃ��̂������͂��ł���B��������̍l����悤�ɁA�c���ӎ��̕]���͂��܂�ɂ��Ⴗ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@
��
�@
�c���ӎ��́A���R�̓������Ƌ{�Q�q�̂��߂ɁA�Ȃ�Ƃ����ē�Z�������Ђ˂�o�����ƍl���Ă����B�₪�āA���̖ڏ��������A���{�����Ă̌����������A�]�˂̊X���Ύ����P��������B�����āA����ɗ��\�������Ђ̂��߂ɏ����悤�Ƃ��Ă����B
�@
�c���͏����悤�Ƃ�����Z������P�o���邽�߂ɁA��O���̎��Ԃ��ɂ��������B�c���Ƃ����Ԃ����Ƃɂ���ď\���������o���邱�ƂɂȂ�Ƃ����킯���B�c���̎v�f�ʂ�Ɏ��͉^�сA�c���Ƃ̏\���͎�������A�������Ƌ{�Q�q��p�̔P�o�ɐ�������B�������A���̎��œc���͌�̐��G�ƂȂ鏼����M�̍��݂����ƂɂȂ�B
�@
�������Ƌ{�Q�q��p�̔P�o�����̘_�����s���A�c���͏o���̊K�i�𒅎��ɏ��n�߂�B
�@
�₪�Ė��{�����ł̌��͂��������c���͔��{�I�Ȑ���̌��������l���n�߂�B�������㐢�ɂ����ĕ]�������悤�Ȃ��Ƃ��������ƍl���n�߂��̂��B
�@
���̂��߁A����ߗ��Ă��l������A�ڈ̊J�����l�����肷��B�����āA����܂Ŗ��{���l�������Ȃ������A�u�ŋ��v�̒������l���n�߂�B
�@
�������A�܂舫���A�V�ϒn�ق������A���Ԃ͈̏����Ȃ����ł������B�@�@
�@ |
| �����R�����̋��ɔ� |
�@ |
��������@�u�]�˂̐łƒʉ݁v���u�]�˂̌o�ϊ����v����B�{���ł͂��ď��������j�o�Ϗ����̒��̌��𐳒��ɔF�߂Ē������Ă���B���������p���͍D�������Ă�B�{���͍]�ˎ���̌o�ϒʎj�ł���B�Ȃ������Ƃ��H�Ƃ����^�₪���邪�A���͂��̕���̐��Ƃ��قƂ�ǂ��Ȃ��̂��Ƃ����B�Ƃ��Ɍo�ώj�̗������Ղ��錤���͐△�̂悤���B�w�҂ɂȂ肽����A���������������������̂��悢�Ǝv���B�l������Ă��Ȃ����Ƃ����̂��w�҂̈�̎p�ł���B���҂́u��N�̒ʉ݁v�u�F���ˌo�ϊ����v�u�����Z�F������v�u��a�̐Łv�Ƃ��������j�o�Ϗ����������Ă��钆�ŁA�]�ˎ���̌o�ρA�Ƃ�킯�ʉ݂�ŁA�������킩�����̂��Ƃ����B�]�ˎ���̌o�ϊ��������͌o���Ɗ��𗊂�Ɍo�ς̂�����������Ă��Ă���B���s�����������B�g�@�̒ʉݏk����Ȃǂ�����ł���B�����A�v��ʂ��Ƃ����Ă̂��Ă���B����Βʉ݂̘B���Ƃł������ׂ����̂ŁA�u��݂̋��݉��v�ł���B���E�ł����Ă̂������͂Ȃ��B���́u��݂̋��݉��v�ւ̃v���Z�X���ׂ���������Ă���B���{�ʐ��̂��Ƃŋ���̌����䗦���Œ艻(�בփ��[�g�ł����Εϓ�����ł͂Ȃ��Œ葊��Ƃ�������)���A���{�����̔䗦�̕ۏ������Ƃ������̂ł���B��{�I�ɂ͙[�������̍l�����ł��邪�A����{�̕ۏ݂̂ɏœ_�Ă�ƁA�s�������̍l�����ɂ��Ȃ�B�܂��A�ߔN���̊T�O����������Ă��邪�A�]�ˎ���͈�ʓI�ɍ����̐���������B�����A�C�O����̏��͗l�X�Ȍ`�ł����炳�ꂽ���A�C�O�̑D�����{�ɗ��Ȃ���Ώ�������Ă��Ȃ��B�I�����_�����{�ɂ���Ă����͓̂��{�Ɂu���v�����������炾�Ƃ����B���̓_�����ɏd�v�ł���B�����āA�]�ˎ���̉ݕ��o�ς�����ɂ́A���₾���łȂ����̓����ɂ����ڂ���K�v������B
�@
�ȉ����Ɍ��Ă����B
�@
����ƍN�̎���A���{�̓S�[���h���b�V�����}�����B���̂��߂��킩��Ȃ����A�O�㏫�R�ƌ��́A�����̘g���Ŏx�o���l���邱�Ƃ������A�����ɂ��݂Ȃ��������B���O��̘Q��Ƃ������B�����A���̍��ɂ͋���̎Y�o���}�����Ă���B
�@
���̉ƌ��̘Q��́A�o�ϊϓ_����͑傢�Ƀv���X�ɓ������B�\�����I�㔼�ɏ��i�o�ϊ���������������̂����A���̑O�i�K�ł��̘Q����������炱���ł���B
�@
����ł��l�㏫�R�ƍj�̎���ɂ͘Z�S�����c���Ă����B�����A�ƍj�������A��Y�͕S��������Ă����B
�@
�ܑ㏫�R�j�g�͈�࣍��ȕ������ԊJ�������\����ł��邪�A���̂���̖��{�̋��ɂ͂�����ۂɂȂ��Ă���A������Ɏ��]���|���n�߂邱�ƂɂȂ�B
�@
�j�g�̎���A����ᖡ��(�̂��̊����s)�ɉ����d�G������B
�@
���ꂪ�l���o�����̂��A�E���g���b���̍��������̔P�o���@�ł������B�u�ݕ��̉����v�ł���B
�@
�ݕ��̉����͋���݂̉��l(�i��)�𗎂Ƃ����Ƃł���B�܂����̊ܗL�ʂ����炷���Ƃł���B
�@
�{���̉��l�ł����A���ݕ��ƐV�ݕ��̌����䗦��3�F2�ł��邪�A�����2�F2�ɂ����̂ŁA���z��1���������{�̉��ɓ���B���ꂪ�ܕS�����قǂɂȂ����B
�@
���̌ܕS�������V�Г��ɂ�肠�炩���g���Ă��܂��B�����A���̌���ōD�i�C�ɕ������B
�@
�Z�㏫�R�Ɛ�E���㏫�R�ƌp�̑�͐V�䔒���哱�����������B���͉����d�G��ڂ̓G�ɂ��āA�ݕ��̉��l�����ɖ߂����Ƃ���B���̎��ɁA�ݕ��_�����N����B
�@
�����d�G�̎咣�͂������B�u�ʉ݂Ƃ������̂͐��{�̕ۏ�����A�ގ��Ȃǂǂ�Ȃ��̂ł������̂ł͂Ȃ����v�B�s�������̍l���ɋ߂��B�M�҂́u���{�̈_�v�Ɩ��Â��Ă���B
�@
�����A���͕��������������A�ݕ����l�����ɖ߂����B���������ɖ߂邱�ƂŃf�t�����N����B
�@
�x�c�������V���ɂȂ�������A�\�Z�Ƃ������̂��g�܂��悤�ɂȂ�B���z�\�O�����痼�ł���B
�@
�Γ��͕S���\���������������A���b�ւ̕�Ȃǂ̗}���ł��Ȃ��x�o������A���������d�����̍�����ڈȊO���W�߂�ƁA�\�O�����痼�قǂ����Ȃ������B���{�̍����͍d�������Ă����̂ł���B
�@
���ŁA�M�҂͓c���ӎ��ɂ��āA���ď������{�u��N�̒ʉ݁v�̌���F�߂Ă���B
�@
�ґP�V�����̏������u�c������v�ɏ�����Ă�����e���L�ۂ݂ɂ��Ă��܂��A�����������c������������ƂƂ��āA�c���ӎ����o�ϒʂ��Ǝv���Ă��܂����̂��B
�@
�c���ӎ��́A�����ꂽ�o�σe�N�m�N���[�g�Ƃ����]����A�ݕ��o�ς����������d����`�҂Ƃ����]���̍����͂ȂɂЂƂȂ��B
�@
�J���u���������Ă����Ƃ����̂����ł���B���̓����ǂ̍������{�ɂ͂���Ă����A�J�������܂鍑���Ȃ��B����������Ȃ����ŁA�J�����u�����闝�R���Ȃ��B
�@
���a�̈�A�̉ݕ����v�͐��v�h���s���Ă���B���̐l���̍s�����ݕ����v�������u��݂����݂ɉ��������Ă��܂��v�Ƃ������̂������B�u���`����v�ł���B
�@
����܂ł̋�݂͏d�������ł͂Ȃ��A�ʂ��Ďg�p����u���ʉݕ��v�������B
�@
���͓��`����ɁA���݂ł���Ƃ����u���{�̈�v���������̂��B�u�ȓ��`���ЁA�������ꗼ�v�B�u��ʉݕ��v�̑n�o�ł���B
�@
��ʂ�����g�����肪�����B���X�Ɏg����悤�ɂȂ�A��݂����݂ɉ������B
�@
������M�́A���ݓc�����o�ςɖ��邢�Ƃ����]�����Ă��邽�߂ɁA���ΓI�ɕ]���������Ă���B
�@
�o�ς̑��ʂ��炢���ƁA���̒ʂ�ŁA�o�ςɂ͖��邭�Ȃ������B�G�ɂ������悤�Ȗf�L�Q�_�҂ł���A����������Ƃ����ɖf�Տk�����ł��o���B�܂��A�ґ������̌����Ǝv�����݁A���ʋ֎~�߂���B
�@
�c������̌o����x�̓g���g���������悤�����A�V�Ђɂ���ĎO�S�����������̂���S�\�����Ɍ����Ă���B�c�����r��A�킸����N���J���œV�Ђɂ��S�O�\������������B
�@
������M���V������ɂȂ��āA�V�����N�B��]���͔��\�����Ɍ����Ă���B
�@
��M�͍����Č��ɂȂ�̎��������o�����A���r����B���������̈�V�������u����v�̃X���[�K���݂̂Ŏl�����I�����������B
�@
��]���͘Z�\�ܖ����Ɍ������B
�@
�\��㏫�R�ƐĂ̎��̘V�������쒉���ł���B
�@
�������Ƃ�����ƌ����āA��������̂��ݕ��̉����ł������B�����ɂ͓�ʂ肠��B�i�ʂ𗎂Ƃ����̂ƁA�u���{�̈_�v�����p�������̂ł���B����͂��̗������s�����B
�@
���ʂƂ��āA�ݕ��̉������s�����N����l�\�N�ԂŐ玵�S��\�Z�����ܕS���]�A�N�ŕ��ώl�\�l������S���̉v�����Ƃ����B
�@
�d�v�Ȃ̂́A�u���{�̈_�v�����p���������͐��l�ɉݕ������ƌ���Ȃ������B�����̏r�ˁE��H��敂ł��炻�̂��Ƃ�m��Ȃ������B
�@
���{�̗B��̐����������v�E���ۂ̉��v�ȂǑ����ɂ��y�Ȃ����ʂ��グ���̂��B
�@
�����Z�N(�ꔪ�܋�)�B���{�͕ė��I�p���܃J���ƒʏ��������юO�`���J�`����B���̎��A�����̗��o�������N����B�����͋���䉿�̂������ɂ������Ɛ��������B
�@
�M�҂́A�����������̂��낤�Ǝv���Ă������A���͓V�ۈꕪ��Ƃ�����݂������Ă������ƂɌ������������Ƃ����B
�@
�V�ۈꕪ��́u���{�̈_�v�����������ʉ݂ł���B�܂�A�����I�Ɉꕪ�̉��l��L���Ȃ��₾�����̂ł���B
�@
�������{�̌��҂��m��Ȃ��������߁A�����̒ʉ݂͑卬���̏�ԂɊׂ�B
�@
�����A�V�ۈꕪ�₪�����I�ɂ��̉��l��L���Ă��Ȃ��Ƃ����̂͒��肪�c�����Ă����B�����Ă��̂��Ƃ��]�˂ɓ`�������A�]�˂̌��҂͗����ł��Ȃ������悤�ł���B
�@
���ʂƂ��Č�����בփ��[�g�ŏ���ꂽ�B�{���A���L�V�R�h��4�F�ꕪ��4�F����1�̂͂����A���L�V�R�h��4�F�ꕪ��12�F����3�ƂȂ��Ă��܂����̂��B
�@
���̌��͂����ɓ��{�����C�������B�����A���肪�n���X�������̂��s�K�������B
�@
�M�҂̓n���X���u�j�ケ��قǂ��������O�����͂��Ȃ��Ƃ����Ă����������ł͂Ȃ��O�����v�ƕ]���Ă���B
�@
�����Ȑl�i�҂ŁA���l���g�̘b�Ȃǂ��肤�ׂ��炴��b�Ƃ������������Ƃ���Ɗʼn߂ł��Ȃ��B
�@
���̃n���X�͎������~�̂��߂ɁA���{�̒ʉ݂ƌo�ς�卬���Ɋׂ�Ă���̂�����B
�@
�n���X�͘V��̒~�����c��������S�ł���Ă����u���̂����A�䂩���ȊO�����v�������̂ł���B�M�҂�����������ĕ`���Ă���̂́A�܂��Ɏ�K�z�n���X�̎p�ł���B
�@
�����������{�͊J�������Ƀ~�X��Ƃ��Ă���B�S��������ł����錠�����m�ۂ��Ȃ������̂��B
�@
���̌��ʁA���{�Ɍ��炸���喼�Ƃ����ɍ����Ԃ������A�������鑤�̑S���������ɋꂵ�݁A��������鑤�̏��l�������Ƃ�����ŕs�v�c�ȎЉ�\�����o���オ�����B
�@
���{�͏��l�ɐł������邱�Ƃ�z�肵�Ă��Ȃ������B�����A����ł���O�I�ɉېł����B�O�ɕ�������B�^����A�������A�����ď��i������F�߂����ɔ[�߂��ނ̐łł���B�@�@
�@ |
| �����{�̐��� 2 |
   �@
�@ |
|
�@ |
|
�����{�̐��� 2 |
���͂��߂�
�@
���c�̐��̐����⒆����s�̐ݗ��A�@�B���E�H�Ɖ��̐��i�ȂǁA��ʓI�ɓ��{�̋ߑ㉻���n�܂����͖̂����ېV�ȍ~�A�܂薾������Ƃ���Ă���B�m���ɖ����ېV�͉��ėɗ}������Ă����A�W�A�����ɂƂ��ċߑ�v���̖͔͂ƂȂ����B�܂��A���̌�A����E���Ŕs�퍑�ƂȂ������{�����x�o�ϐ����𐬂������A���E�̗̒��ԓ��肵�����Ƃ́u�A�W�A�̊�Ձv�Ƃ��Ă�Ă����B���̋N�_�͖����ېV�ɂ���Ƃ��������ł���B
�@
�������A�����ېV�����̔w�i�ɁA���̑O�i�K�ł���]�ˎ���ɖڂ������Ă݂�A�J�����Y���⋳�琅���̍���������A�s�ꌴ����`�̐Z��������A�}�j�t�@�N�`���[��M���h(�g��)�̐���������A��(���{)��(���l��E�l)�̎d���m�ɕ������������Ƃ̐��i�Ɩ��c��������ȂǁA���łɋߑ�̍����I�ȍl�����������f�n��������Ă������Ƃ͌������Ȃ��B�܂�A�u�ߑ㉻�ւ̏����v�́A���łɍ]�ˎ���Ɏn�܂��Ă����̂ł���B
�@
���T����X�^�[�g���邱�̃R�����ł́A�]�ˎ���ɐ��܂ꂽ�ߑ㉻�̖G��𐭎��E�o�ς̗��ʂ����̓I�ɏЉ�Ă������̂ł���B���ړ_�́A�ߑ�I�Ȕ��z�A�Ȋw�I�E�����I�Ȏv�l�̊�Ղ��]�ˎ��ォ��E���グ�邱�Ƃɂ���B
�@
18���I�����A���łɐl������100���l�ł������Ƃ����]�˂͓������E�ő�K�͂̓s�s�������B�����h����p����50���l�O��ł��������Ƃ�����ƁA�K�R�I�ɐ����ʂł��Y�Ɩʂł��s�s�����̊�Ղ��z����Ă����Ƒz���ł���B�����炭�s�s�����𑗂邽�߂̍Œ���̃C���t�������͂ł��Ă����ł��낤���A��������Ƃ����Ő����~����Ă����ł��낤���A�������Ƃ▯�Ԏ��Ƃ��i�߂��Ă����Ǝv����B�܂��A�e��̐��x���~����A����𐄐i������A���{�����肷��S���҂������ł��낤�B�������A�����̌���@�ցA�g�D���������͂��ł���B
�@
�܂��A���l��E�l�����S�ȓs�s�����𑗂邱�Ƃ��ł���x�@�@�ւ͕s���ł��邵�A���S�Ȑ������������҂�s���ȍs���������҂ɑ��ČY���������@�ւ��s���ł���B
�@
���Ƃ��Γs�s�����̃C���t�������̈��Ƃ��āA��������������B�_�c�㐅�A�ʐ�㐅�A�R�㐅�A�O�c�㐅�A�T�L�㐅�A���㐅��6�㐅�ɂ��u�]�ː����v�͋K�͂����ɃX�|�b�g�Ă�A���E��ł������Ƒz���ł���B�]�ˎ���ɒa�������_�c�㐅�Ƌʐ�㐅�́A17���I�����ɂ͒n�����㐅���Ƃ��ẮA����150�L���Ƃ������E�ő�̏㐅���ɂ܂Ŕ��W�����B����͒N�����s�s�����҂ɖ𗧂��߂ɍs�������ƁA���Ȃ킿�������Ƃł���B����قǂ̌������Ƃ𐄐i����ɂ́A���{�̐���Ƃ��Ď��Ƃ����肷��@�ւ��������ł��낤���A����Ȏ����Ƒg�D�I�ȘJ���͂��K�v�ł��������Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B
�@
�܂��A����ƍN�����{�̋���v���x����Ό���R�{�����̂Ƃ������Ƃ������[���B��R�J���̔�p�E����(�R���Ȃ�)��d�����߁A���ӂ̋����ɒ����̂ł���Ό���R��(��5����)���ݒu���ꂽ�̂ł���B���{�͋�R�̃}�l�W�����g��S����R��s��h���B���̋�R��s�͎R�t(�z�R�o�c��)����g���ĐΌ���R�J�����}���ɐi�߁A�ƍN�ɔ���ȋ��[�߁A���D�f�Ղ̌���ɂ��Ȃ����B�Ό���R�̊J���͖��{�̎������̊m�ۂ����łȂ��A���ԘJ���҂̌ٗp���i�̖ʂ�����ߑ�I�ō����I�Ȑ���ł���A�d�v�Ȏ��Ƃ������̂ł���B
�@
���̂悤�ɍ]�ˎ���ɂ͂��łɋߑ�I������`�����܂�A�}�l�W�����g�̂����݂��@�\���A���{�����������x���ғ����Ă��Ƃ��킩��B�����ʂ���]�ˎ���ɂ͊w�Ԃׂ����Ƃ�����B�����͌����Ė��ɗ����Ȃ��G�w�ł͂Ȃ��A�o�ς�������������ՓI�ȑ��ʂ������Ă����ł��낤�B���̒m�V�́A�ӊO�Ȃ��ƂɐV�������z��u���C�N�X���[�ɂ��Ȃ��邱�Ƃ�����B���̃R�������������������z�̓˔j���ɂȂ�K���ł���B�@ |
�������x�z�̐��̊m��
�@
�u�փ����̍���v�ɏ������ēV���̔e�҂ƂȂ�������ƍN�́A1603�N�ɐ��Α叫�R�ƂȂ�A�����x�z�̐��̊m�����߂������B����ƍN�͒�������������ƁA�������Ƃւ̈��́A�喼�����A�g�����x�̓O��A���l�Ȑl�ނ̓o�p�A�]�˂̐����Ȃǎ��X�ɑ傫�ȉ��v���肪���Ă������B�ƍN�E�G���E�ƌ��O��̂ق�50�N�ԂɁA����Ƃ��S���x�z�̑̐����ł߂����A�����铿��O�S�N�̑����̊�Ղ�z���Ă������̂ł���B
�@
���얋�{�́A�喼�E����Ƃ�ΏۂƂ������Ə��@�x�A�V�c�Ƃ���Ƃ̍s���𐧖�֒������Ə��@�x�A�������c��m�������鏔�@���@�@�x�ƁA�������Ŋ�{�I�@�x�z���A��������{�����B�����̌��Ă͂��ׂē���ƍN���l�������̂ŁA�ƍN�͍���ɂ�����m���Ƃ��Ă݂̂Ȃ炸�A�����ƂƂ��Ă���z�������]�������̂ł���B���喼�A����ƌ��ƁA���@�Ƒm�����]�˖��{�̎x�z���ɒu���Ďv���܂܂ɃR���g���[������B����͓���ƍN���o�ꂷ��܂ŁA�ǂ̐퍑�喼���������Ȃ������̋Ƃł���B
�@
���ڂ��ׂ��_�́A���얋�{���R���͂ł����B�������̂ł͂Ȃ����Ƃ��B���{�̒����R��3���ȉ��������Ƃ���Ă���B�փ����̐킢�ʼnƍN�������铌�R�ɎQ�������͖̂�10���B���R�ɎQ���������喼��������R���̂ق������쒼���R�������������Ƃ������Ƃ��B���{��������������A���{�̌R���͂͂ƂĂ��R���p�N�g�ł������悤���B
�@
�]�ˎ���̑喼�ɂ́A����喼�ƊO�l�喼�̕��ނ��������B����喼�́A�L�b�����̂��ƂʼnƍN���֓��n���Ɉڕ����ꂽ�ۂɎ�v�ȕ����ɗ̒n��^���A�喼�i��^���ē���Ƃ��x�����������ƂɗR������B�փ����̍���ȑO���瓿�쎁�ɏ]���A��藧�Ă�ꂽ�喼�ł���B�O�l�喼�́A�փ����̍��풼�O�A���邢�͈ȍ~�Ɏx�z�̐��ɑg�ݍ��܂ꂽ�喼�ł���B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�������O�l�喼�ł���B
�@
�փ����̍�����I�����ƍN�́A���R�̏��喼�̏��̂̏�����O��I�ɍs�����B�F�쑽�G�Ƃ̏��́A���O���R57�����v�����ꂽ�悤�ɁA���R�ɑ������喼�́A�Ƃ��Ԃ��ꂽ��A�̒n��v�����ꂽ�肵���B�ƍN�͖v�������y�n���ĕ��z�����B�܂��A���Ȃ̒����̂𑝂��A����̂������喼�ɉ������A�̒n��啝�Ɉړ������B��Ɏ���{�����瓿�안��̉Ɛb�́A������@�ɓƗ��̑喼�Ƃ��Ĉ�����悤�ɂȂ����B
�@
�R���p�N�g�ȌR�����������Ȃ����얋�{���A�S���x�z�̐����m�����邽�߂ɂ́A����˂̑O�c�ƁA�F���˂̓��ÉƁA���B�˂̖ї��ƁA�y���˂̎R���ƁA�đ�˂̏㐙�ƁA���˂̍א�ƁA���˂̈ɒB�ƂȂǁA���̑傫�ȊO�l�喼�������Ɏx�z���邩���d�v�ł���B�����ő喼�����̂��߂Ɂu���Ə��@�x�v�߂����̂ł���B�喼��@���ł���B
�@
2�㏫�R�E����G���̖��ŏo���ꂽ�ŏ��̕��Ə��@�x�ɂ́A1�D�喼�͗̒n�ƍ]�˂Ɍ��݂ɋ߂邱��2�D�V������Â���͋֎~3�D�d������Ă邱�Ƃ̋֎~4�D�喼�͖��{�̋��Ȃ�����Ɍ������Ă͂����Ȃ�5�D����Ɋ֏���݂��Ă͂����Ȃ�6�D500�ΐς݈ȏ�̑D�����L���Ă͂����Ȃ��|�Ȃǂ��L����Ă����B�Q�Ό��z�����̂́A3�㏫�R�E�ƌ��ł���B
�@
���얋�{�́A�喼�ɗ̒n��^���A�e�̒n�ł̓Ɨ��̎Z�̌����Ɨ̒n�̊Ǘ��E��^��������ŁA�I�݂Ȗ@���ɂ���Ďx�z�����̂ł���B�傫�ȌR���������Ȃ��]�˖��{���u�����Ȑ��{�v�Ƃ��ċ@�\�����ЂƂ̗��R�́A�O�l�喼�����ɃR���g���[�����鐧�x������������ł���B�喼�͔˂̒m���ł���A�В��ł����邪�A���ׂĂ�����O���[�v�ɏ�������Ƃ������Ƃł���B�O�l�喼�́A���Ă͓Ɨ�������Ƃ̃I�[�i�[�ł��������A�u�փ����̍���v���_�@�ɓ���O���[�v�ɋz������A���̃O���[�v�K��ɏ]�킴��Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł���B�����Ă��̓���O���[�v�́A�����͉ƍN�Ƃ����ˏo�����n�ƃI�[�i�[�̃}���p���[�ɂ��Ƃ��낪�傫���������A�₪�Čl����g�D�ւƕϖe�𐋂���̂ł���B�@ |
�����ˑ̐�
�@
�]�˖��{�̎x�z�̐��́u���ˑ̐��v�ƌĂ�A�������{�ł��開�{�ƒn�����{�ł���˂̓�d�x�z�ɂȂ��Ă����B�n���͏��R���C���E���F�����喼���˂��`�����A�x�z���Ă����B�Ȃ��A���R�̒����n(�V��)�ł͑喼�̑���ɑ㊯��u�����B���̖��{(���R)����(�喼)���R���g���[�����開�ˑ̐��́A�����Ɂu�����Ȑ��{�v��z���Ă���B
�@
�e�喼�́u���Ə��@�x�v�̏���͂�����̂́A���ꂼ��̗̒n�ɂ����Ă�����x�Ɨ����������@�\���`�����Ă���B�x�z�̐��̊�{�ƂȂ��Ă���̂́A�ĂȂǂ������Ŕ[�߂����ĔN�v�Ƃ���������B�]�ˎ���O���̔N�v�����́A�c�����@���āA���̔N�̎��n�ʂ�������Ŗ��N���ƂɔN�v�������肷����@�ł������B
�@
�c���≮�~�Ɏ���܂ŁA�ʐςɐΐ��Ƃ������̌v���������ĕĂ̐��Y�͂Ɋ��Z���A�ΒP�ʂŕ\�����邱�̐��x�́A�킩��₷���u�ېŐ��x�v�Ƃ�����B�����Đ��́A���̂܂ܑ喼����{�̎�����\���_�ɂ����ẮA����O���[�v�e�x��(��)��Ɛb�ƌĂ�铿��R���c�F���������́u���㍂�v�u�N���v�u�N���v�Ƃ��ǂ߂�B�{���@�\�������{�́A����O���[�v�e�x�ЁA�����́u���㍂�v�u�N���v�u�N���v���`�F�b�N�ł���Ƃ��������I�Ȃ����݂ł���B
�@
�܂��A��͑�l��l����N�ɐH�ׂ�Ă̗ʂɑ������邱�Ƃ���A����m�����ɗ^�����V�Ƃ݂Ȃ��A���~�N�v���Ɠ��������̕��m��{���邱�ƂɂȂ�B�܂���͑喼�́u���́v�����ł͂Ȃ��u���́v�����Ӗ����Ă����̂��B
�@
�]�˂ɒz���ꂽ���{�̉��~�����f�ł������̂ɑ��āA�]�ˏ����Ɍ��Ă�ꂽ��O��(�����A�I�ɁA����)����ё喼���~�͂���������ł������B������������������炱���B���~�̍����Ő����ւ����̂ł��낤�B
�@
���āA���얋�{�̏ے��Ƃ����]�ˏ邾�B�z��H���́A�ƍN�̏��R�C���̗��N�A1860�N�ɒ��肳�ꂽ�B��n�߂́A��̊�b�ƂȂ�ނ��^�ԑD�̌����ł���B���̑D�̌����S�����̂́A���Ò��P(����F���ˎ�)�A���K��(����I�ɘa�̎R�ˎ�)�A���c����(����}�O�������ˎ�)�ȂǗL�͂ȊO�l�喼28���ł������Ƃ����L�^���c���Ă���B���̑D���ɓ����狐��Ȑ���x�ɐ����ς�ŁA���ɓ��A�]�˂Ƃ̊Ԃ����������Ƃ����B����������喼�ɉۂ���ꂽ�~�b�V�����ł������B
�@
�܂��A���̑O�i�K�̖��ߗ��čH�������喼���S�����Ƃ����B���Ƃ��Ώx�͑�̐_�c�R��������y�ŁA����J�̓��]�͖��߂�ꂽ�B�����͓���Ƃɑ��钉���S�������ɂ��A�Ɛb�̘J���͂��g�킸�ɏ�̊�b��z����_�ł��A�����I�Ȏ�@�ł���B����u��V���o���Ȃ��A�E�g�\�[�V���O�v�ł���B
�@
�֑������A�]�˂̒�����߂ɖ����Ă�ꂽ�y�n�ɂ́A�V���Ȓn��������ꂽ�B���̕����̍H����S�������喼�̍������Ƃ��Ĕ������A���꒬�A�o�_���Ȃǖ��Â���ꂽ�Ƃ��������B���Ȃ݂ɁA����œh��ł߂�ꂽ��̕ǂ̌����ƂȂ����ΊD�́A�]�ː����ɂ��鑺�ɖ����ĐΒY����Ă����āA�n�ʼn^�������̂����A���̓������݂̐C�X���ł���B
�@
���喼�͎����̗̒n����_�����]�˂ɘA��o���A�����s���͉Ɛb�ɂ��S���Ă��炢�A�܂���������؋������Ăł������Ȃ�������Ȃ������B����͌R���Ƃ������邾�낤�B�̒n���x�����Ă�����Ă���A�܂����������Ă��铿��Ƃɑ������Ȃ̂ł���B
�@
�]�ˏ�̌��݂ƕ��s���āA1604�N�ɂ͋ߍ]�̕F������A���̋ߗ�7�J���̑喼�ɖ����Ēz�����A1612�N�ɂ͏x�͏���A1615�N�ɂ͖��É���̌��݂𖽂���ȂǁA�喼�ւ̉ۖ��͂����Ԃ�傫�������悤���B�]�˖��{�̎x�z�����̖{���́A�I�݂ɑ喼�𑀂邱�Ƃɂ������悤���B����͖��ˑ̐����z�����c�Љ�̂��̂ł���B�@ |
�����{�̊�������
�@
�ƍN�𐪈Α叫�R�ɐ������]�˖��{�̊����������A�ˎ���g�b�v�ɒu���e�˂̎x�z�������A�����I��]�W���x�[�X�ɂ��Ă���_�ł͓����\���ł���B
�@
1590�N�A�ƍN�͏G�g�̖��߂ŁA�x�́E���]�E�O�́E�b��E�M�Z��5�J���̗̎傩��A�k�����̋��̂ł��镐���E�ɓ��E���́E���E����E�㑍�E������7�J���Ɉڕ����ꂽ�B150������250���ւ̉����ł��������A�ƍN�ɂƂ��ĉ��̐[���O�͂̓y�n�������A�܂��Ă��Ȃ������֓��Ɉڂ��ꂽ���Ƃ͐h�_���Ȃ߂�v���ł��������Ƃ��낤�B
�@
�֓��ɓ������ہA���쎁�̒����͍̂]�˂̎��ӂ����������B�������A���̍�����ƍN�͗L�͂ȉƐb(�㋉�Ɛb)���]�˂��牓���̏d�v�Ȏx��ɔz�u�����B���Ƃ��匴�N��(10����)����B�ٗтɁA��ɒ���(12����)����B���ւɁA����G�N(10����)����������ɁA�{������(10����)���㑍�命��ɁA��v�ے���(4����)�𑊏B���c���ɔz�u�����B�ނ�͖d������ĂȂ��ł��낤�x�X���N���X�ł���A���ꂼ�ꂪ�R���𗦂��郊�[�_�[�ł������B
�@
����A���悻100���̒����n�ɂ́A�ɓޒ������v�ے����Ȃǂ̗L�\�ȉƐb���u�㊯�v�Ȃǂɐ����A�������Ă������B���̑㊯�N���X�́A��ɕ��c�E����E�k���̋��b��o�p�����B�܂�A���Ă̓��C�o���O���[�v�ɂ����r�����Ђ̗D�G�Ȑl�ނF�����̂ł���B����ɈӋC�Ɋ������r�����Бg�͓���R���c�F�����ɒ����S�𐾂������Ƃ��낤�B
�@
���̓����̎d���́A�ƍN�Ǝ��̐l�ޓo�p�@�̌����ł���B�ƍN�͈�ɂ�{���ȂǁA������u���������v�̕����ɂ���ċ��͂ȌR�c���`�����A�r�����Бg�̂����L�\�ȍs�����E�������߂ɕ����A�̍������ƍ������ł߂��̂ł���B�L�b�������ōő�̗̒n��������O���[�v�͍ł����͂ȌR���ƖL���ȍs���E������z���Ă������̂ł���B�ƍN���₪�Ĕe������������b�́A�����������֓��̒n�o�c�̐���������������ł��낤�B
�@
���āA�]�˖��{���J�����ƍN��1605�N�A���R�̐E���O�j�E�G���ɏ���A���̌�͑�䏊�Ə̂�����悤�ɂȂ�B�����̎����͑�䏊������A���������̖@�I�Ȏ匠�҂͏��R�Ƃ������ƂɂȂ�B�ƍN�́u�����̎匠�҂͑�X����̖{�Ƃ����P����̂��v�Ƃ����`���𑁂��ɂ��肠���Ă��܂����̂ł���B�l�̎����łȂ��A���R�Ƃ�����E�����Ђ������A�܂�����Ƃ���ΓI�Ȍ��͂������Ă��邱�Ƃ����喼�ɒm�炵�߂邱�̎�@�́A�����̎d���Ƃ��đ�z���Ă���B����͓���Ƃ̑��߂����喼�����R�̑オ�ւ���Ă������I�ɓ���Ƃɐb�]����Ƃ����V�X�e�����B�؉ƂȂ����I�Ɍ_��X�V�葱��������A�v���싅�I��Ȃ����I�ɋ��c�Ƃ̌_��X�V���s���邪�A����ƂƉƐb�A���喼�̊W�͔��i�v�I�Ɍp�������̂ł���B������u�����Ȑ��{�v��z�������ŏd�v�ȃt�@�N�^�[�̂ЂƂł���B
�@
�]�˖��{�ݗ������ɌR���E�������ʂŃL�[�}���ƂȂ����̂́A���䒉���A��ɒ����A�{�������A�匴�N���Ƃ������u�l�V���v�ł���B����瑤�߂ɂƂ��āA����Ƃ͑�X�̎�N�B����Ďl�V���̎q������������ƂɎd���邱�ƂɂȂ�B���Ƃ��Ζ{�������̑��q�A�����͈ɐ��K���˂̑���ˎ�ƂȂ�A�̂��ɔd���P�H�˂̏���ˎ�A���̕P�H���ƂȂ�B�܂�A�Ɛb����������Ƃ���^����ꂽ�̒n�̗̎�̒n�ʂ������p���ł������̂ł���B����͉Ƃ̌p���E�ɉh�̂��߂ɂ���ꂽ����Ƃ̃V�X�e���Ƒ������Ă���B
�@
����ł́A�{�����M�̂悤�ɉƍN�̑��߂Ƃ��Ė��������ۂɎ哱���闧��̎҂��o�ꂷ��B�ƍN����ƌ��Ɏ��铿��O���`�������㌀�ł́A�{�����M�ɑ�\�����u�����h�v�Ɩ{�������ɑ�\�����u�����h�v�̌��͍R�����悭�`����邪�A����͂ނ��떋�{�ɗL�\�Ȑl�ނ������Ă������Ƃ���Ă���Ƃ����悤�B����͑O�q�����ƍN�̓��������l�ވ琬�ɑ傢�ɍv���������Ƃ��ؖ����Ă���Ƃ����悤�B�ƌ��ɂ���đ�V�Ɋi�グ���ꂽ�y�䗘���A���䒉���Ȃǂ����{�̎x�z�̐����m�����Ă����B�@ |
�����{�̐E���̓���
�@
�]�˖��{�͊O�����A�s�����A���Ō�������������łȂ��A�i�@�E���@�������������B�V��������ʂ��������쎁�ɂ͂��͂⍇��̕K�v�͂Ȃ��Ȃ�A���ɖڎw���͈̂��肵�������ł���B��������{����ɂ͑g�D������B���얋�{�́A�ƍN����ƌ��Ɏ���O��̊ԂɃR���p�N�g�ō����I�ȑg�D�����肠���Ă������B�ȉ��ɏЉ��E���̗v�E�ɂ͎�ɕ���E���{�������B�������������Ԑ��E���c���ł������B
�@
�ō��i�ߊ��́u���R�v�́A�������Ƃ̒j�q���A�C�B��Ђł����u�В��v�����A��䏊�ƂȂ����ƍN�Ȃǂ͂������ߎ��������B��펞�ɒu���ꂽ�ō��E�ł���u��V�v�́A�x�c�A����A�y��A��Ɋe�Ƃ���I�ꂽ�B�ނ�͂��ׂ�10���Έȏ�̕���喼�ł���B������͑�\���������В��ɊY�����邾�낤�B��ʐ���������u�V���v�ɂ͕���喼4�`6�������A�����͔N��ƌĂꂽ�B��u�����ō��E�ŁA��ԓ��E��ڕt�E����s�E�����s�E������s�Ȃǂ��x�z�����B
�@
���{�̊����@�\������ƁA�喼���Ď@����̂��u�V���v�A����ȉ��̊��{�E��Ɛl���Ď@����̂��u��N��v�A�喼���Ď@����u��ڕt�v�A���{�E��Ɛl���Ď@����u�ڕt�v�A����E�������Ď@���邽�߂Ɂu���s���i��v�Ƃ�����E�����Ă����Ă��邱�Ƃ���Ď@�@�\���������肵�Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@
�V�����x�z�����E���̂����u��ԓ��v�͍]�ˏ�x�������B���{����C�������R������̃g�b�v�ŁA�]�ˏ�ƍ]�ˎs���̌x����S�����B�u��ڕt�v�͑喼���Ď@�����ځB����ɘV���̉��ɂ͍s���E�i�@�̒S���҂����ԁB�u�����s�v�͓V�̂̍����E�s���A�֔��B�̌����́E�֔��B�ȊO�̖��̂̎i�@��S���B�V�̂̌o���E�����S���҂ł���A���łƎi�@��S������u�S��v�Ɓu�㊯�v���Ǘ������B
�@
�u�]�˒���s�v(����s)�́A�]�˂̍s���E�i�@�E�x�@��S���B�쒬��s�Ɩk����s��1������ւ̌��Ԑ��ŁA���{���C�����ꂽ�B
�@
�n���ɂ��開�{�̒����s�s(���s�A���A�x�{�A����Ȃ�8��)�ɂ͋��s����s�A�����s�Ȃǂ́u������s�v���u����A����ȊO�̖��{�̗̒n�ɂ͊����s�z���̌S���㊯���h�����ꂽ�B���Ȃ݂ɕ�s�̏o���R�[�X�����㌀�u�剪�z�O�v�ŗL���ȑ剪�������ɋ����Ă݂悤�B
�@
���ڂ������̂́A�ЂƂ̖�E�������̐E�������˂Ă������Ƃ��B�]�˒���s�͎O����x�������قǂ̍��������ŁA���{�����@�\�ł���ʂ̖�l�ł���B�ނ炪�Ǘ������k���E�쒬��s���́A���݂̓����s���ƌx�����ƍٔ����̖�ڂ������Ă����Ɨ\�z�����B�S���s�s�E�]�˂̎���������Ă����̂́A����̌x�@�Ɩ��ɓ����钬��s���̓��S�����A����قǑ傫���Ȃ��g�D���x�@���ƍٔ����ƍs�����̂ق��ɏ��h��h�u�ȂǗ��@���܂Ō��˔����Ă������Ƃ́A���̃R�����̃e�[�}�ł���u�����Ȑ��{�v�Ԃ����Ă���B
�@
�V����⍲�����u��N��v������喼����C������A���{���Ɛl���Ď@�����B��N��̉��ɒu���ꂽ�u�����g�ԓ��v�͏��R�̎G�p�W�A�u���@�ԓ��v�͏��R��q���̑����ł���B
�@
�V�����N�Ǘ����������̐E���̂ق��ɁA���R�����̐E��������B���ЁE���З̂̊Ď@�߂����Е�s�́A�@���s���@�ւł���B�ꖜ�Έȏ�̑喼���A�C�������Ƃ���A�O��s�̒��ł͊��{����C������钬��s�E�����s���i���͏�ł���B���s���i��E���������R�����ŁA�O�҂͓����ɂ����ĘV���Ɏ����v�E�B�u���R�̑㗝�v�Ƃ����j���A���X�ł��낤�B�������喼�̊Ď��߂��B��҂͑���ɂ����đ��Ζ��{����l�����A�ً}���ɂ͏��R�ɑ����ČR�����茠���ł����B�o���R�[�X�Ƃ��āA����ォ�狞�s���i����o�ĘV���ɏ��i����̂��ʗ�ł���B
�@
���Ȃ݂ɕ�s�̏o���R�[�X�����㌀�u�剪�z�O�v�ŗL���ȑ剪�������ɋ����Ă݂悤�B���@�ԁ�����s��������s(�ɐ���s)���]�˒���s��������s�����Е�s���喼�B����������s����喼�ɂȂ����̂́A�]�ˎ����ʂ��đ剪�����݂̂ł���B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
�������n�̉^�c
�@
���{�̎������̂ЂƂɒ����n�̋��R���R�̌o�c����������B�������u���Ԃłł��邱�Ƃ͖��ԂɁv�̃X���[�K������肷�邩�̂悤�ɁA�z�R�ɕK�v�ȎR�t�̎�z�Ə�[���̏W�������͕�s���s���A�̍z�̎d���͖��ԂɈϑ����Ă����Ƃ����B���ł��L���Ȃ̂����n�E�Ό��E�ɓ��Ȃǂ̍z�R(���R�E��R)�̌o�c�ł���B���{�̎x�z�����͒����n�̉^�c�ƓK�ޓK���̐l�ނ̗̍p�ɂ���Ď����ł������Ƃ��킩��B
�@
���n���R��1601�N�ɎR�t3�l�ɔ�������A�������ܓ��얋�{�����̓V�̂ƂȂ�A���̖L�x�ȎY���ʂ�300�N�ɂ킽�開�{�̍������x�����B�ƍN�͓��N�A�ї����̋��̂ł������Ό���R�������̂Ƃ��Ă���B�Ό���R����Y�o���ꂽ��́A�L�b���̒��N�o���̌R�����ɂȂ����قǂŁA�����ԓ��{�ő�̋�R�ł������B���̐Ό���R�̕�s�߁A�̂��ɍ��n��s���o�Ċ����s�ɔC�����A�N��A�V���ɏ��i���A�ɓ���s�����߂��̂���v�ے����ł���B���ĕ��c���̉Ɛb�ł������������ƍN����S���̋���R�̓����𖽂���ꂽ���R�́A�ނƂ��̔z���̎R�t�������N�����̔r�����R���g���[������Z�p�������Ă�������ł���B�����͕��c��(�b��)�ɂ����鍕����R�̍z�R�J����Ŗ��Ɍg����Ă����̂ł���B
�@
�Ό���R�̍̌@�Ɍg����ʂ̋���Y�o���������̃}�l�W�����g�͍Ⴆ�Ă����B���n���R�ɂ͓�l�̉Ɛb��h�����A��l�ɂ͔_���������A������l�ɂ͋�R�̊Ǘ����������B���n�ɂ͖��{���c�̒��R(�������)�ƁA�R�t�������̎����ō̌@���Ĕ�����̉���������[���鎩���R(���Ԃ���)�Ƃ��������B�����͐Ό���R��ɓ����R����D�G�ȎR�t���W�߁A�ނ�ɕĂ�Y�A���[�\�N�Ȃǂ��x�������Ƃ����B����A�����R�̎R�t�ɂ́A�B���̍��ɂ���ėǎ��̂Ƃ���ɂ͎Y�o��5���A����ȉ��̍B���ɂ͎Y�o��3����1�A4����1�Ƃ������̏�[���ۂ����B�t���[�����X�̎R�t�ɂƂ���5���̃}�[�W���Ƃ����Α傫�Ȋz�����A�ނ�͒��l�ɋ`���Â����Ă����u�l�����v��u�`�n���v�Ƃ�����������Ə�����Ă����̂ŗD������Ƃ����Ȃ����Ȃ��B
�@
�܂��A�z�R�̎Y�o������ɂȂ�ΑS�����瑽���̍R�v�����ɏW�܂�̂ŁA�����͒��̓����ɖ�����݂��A�H���i�����i�Ȃǂ̕�����ꔄ�ɂ��A���グ��1���̏�[�����ۂ����B�������č��n���R���㐙�����x�z���Ă�������Ɣ�r���āA�Y�o�ʂ�����I�ɑ������Ƃ���Ă���B
�@
�Ό���R�⍲�n���R����Y�o���ꂽ�����͉��H����Ēʉ݂ƂȂ�A�|���g�K���f�Տ��Ⓦ�C���h��Ђ�Ƃ̊����Ȗf�Ղ𑣐i���A�܂��ƍN�����i�������D�f�Ղ̎����ɂ��Ȃ����B���̍��ɓ��{�ɂ����D�f�ՉƂ��o�ꂵ�A�������n�܂�܂ŃA�W�A�𒆐S�ɖf�Ղ������������̂ł���B
�@
���c�������̗p���ꂽ�̂͒n���������L�x�ȓy�n�����ł͂Ȃ��B�֓�����Ƃ��钼���n����̔N�v���͕x�ɑ傫�������B�V�̂̐��́A�փ����̐킢�ȑO��100�����炢�ł��������A�փ����̐킢�̌�A���R�ɑ����������̗̒n��v�����������璼���n�ɕғ��������̂������A�ƍN�̔ӔN�ɂ�200�����炢�ɑ��������B�����Ė�1���I��̌��\����ɂ�400���ɒB����̂ł���B�ŏ����瑽���̒����n�������̂łȂ��A���������₵�Ă������̂́A�V�X�e�����@�\���Ă��������ƂƊǗ��҂̏K�n�����������炾�낤�B
�@
����ɖ��{�͍]�ˈȊO�ɋ��s�E���E����E��Ȃǂ̏d�v�s�s���ɂ��āA���H�Ƃ�f�Ղ����A�ݕ��̒��������ɂ������B�o�ϓ�����i�߂邱�Ƃŗ��v��Ɛ肵�悤�Ƃ�������ł���B�]�˖��{���a�����Ă����Ƃ̒��S�����s����ł��������Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B����ċ��s�E���E�������K�v���������̂ł���B
�@
���̂悤�ɍ]�ˈȊO�̓y�n���ɂ��A�D�G�ȕ�s��h�����Ďx�z�����A��������m���ɗ��v���グ�Ă����̂́u�����Ȑ��{�v�炵�������I�ȕ��@�ł���B����ɖ��{�͔_������ɂ����肷��B1648�N�Ɏ{�s���ꂽ�u���n�v�̏�߂ł���B�@ |
���N�v�Ƃ����d�Ő��x
�@
�喼�̎x�z�����ƍz�R�Ȃǒ����n�̃I�y���[�V�����̎��ɐ������Ă����Ȃ�������Ȃ��̂��A�_�������ł���B�_�������Y�����Ă�喼���N�v�Ƃ��Ē������A�喼�͖��{�ɐ���\�����A��[����[�߂�B�N�v���������{�̍����̊�Ղł��������Ƃ��ӂ݂�Ȃ�A���̐��x�������]�˖��{�̎x�z�����̉��䍜�Ƃ����悤�B
�@
���̃x�[�X�ɂȂ�u���n�v�́A�퍑�喼�������̎x�z�n��ʼnېł��s�����߂̎����Ƃ��ēy�n�̒������s�����̂��N�����B�D�c�M�����̍����Ō��n�����{���Ă������A���߂đS���K�͂Ō��n���s�����͖̂L�b�G�g�ł���B������u���}���n�v�̑����́A�喼�̎��Ȑ\���ł������B����ɂ���đS���I�ɐ������F�m�����悤�ɂȂ�B
�@
���}���n������I�ł������̂́A�y�n�̏��L�҂łȂ��A�k���(�_��)�����A�_���ɉېł������Ƃł���B����ɂ���Ē��Ԃō�悷�镐�m����|���ꂽ�B���ʋƂł����Ζ≮���Ȃ������悤�Ȃ��̂��B�_���o�g�̏G�g�炵������ł������B���̑��}���n�����~���ɂ������̂��A�]�˖��{�̏����̍v�d(�N�v)�ł���B����͌���������A���{�̑d�Ő��x�ł���B
�@
���{�͂��ׂĂ̓y�n�̉��l��Ă̐��Y�͂ɂ���������u�����v���̗p���A�S���I�ȗ��ʂɂ�鏔�N�v�̊����A�̎�o�ς̈ێ���ۏ��A�̎�͌��n�ɂ���Đ����v�Z�����̂ł���B���n�ɂ͂���ɂ����ЂƂ̑傫�ȖړI���������B���̓y�n�̍L�����������łȂ��A�_���͌��n���ɋL������A�E�Ɓu�S���v�Ƃ��đd�ł̕��S�҂Ƃ��ꂽ�B���n���Ƃ������́u�ېő䒠�v������ꂽ�̂ł���B
�@
�]�ˎ��㏉���̔N�v�����́A�c���ώ@���A���̔N�̎��n�ʂ�������Ŗ��N�N�v�������肷����@���̗p����Ă����B�N�Ԃ̐�����v�Z��������Ȃ̂ŁA���݂̐ŋ��̎�ނł����u�����ېŁv�Ƃ����悤�B���̃V�X�e����S���ŋ@�\����悤�ɐ��i�����̂́A�喼�ƑS���ɔh�����ꂽ��s�A�㊯�ł���B���{�͂������l���Ŋe�n�ɐŖ����ɂ�����g�D���������̂ł���B���������������݂�����O�S�N���x�����̂ł���B
�@
�N�v�̃V�X�e���͂������B�̒n�̐��X�ɐU�蕪���A���S�̂̐��Ƃ��Ċ��Z���A�N�v�[���͑������ꊇ�[���̋`�����B�����Ė��{����h�����ꂽ�㊯���s�A�̒n�̑喼�̐Ŗ��S���҂����̑����̑�\�҂��璥�����A���{��喼�ɔ[�߂�̂ł���B
�@
������������߂邽�Ƃ��Ƃ��āu�������N�v�̔[�ߎ��v�ƌ������A���̗��ɂ͓����̔_���́u�Ȃ�Ƃ��N�v�[��������������v�Ƃ����ԗ��X�ȐS������B�ꂵ�Ă���B�܂��A���P�ʂŋ������ĕĂ�����Ȃ�������Ƃ����p����_�k�����́u���Љ�v�̍\�}����������ƕ����т������Ă���B�_��Ƃ����ڂ�Ƒ��S�̂ɖ��f�������邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�@
���������N�v���ɑ傫���e����^����̂��A���̗̒n�����{�����̂��ۂ��ł���B�喼�̂ł͌܌��ܖ��A�܂�50���̎��[���B����ɑ��Ė��{�����̂̏ꍇ�A����N�v���͎l���Z���A���Ȃ킿���{�̒�����40���ł������B
�@
���������ۂɂ́A�}�l�W�����g��S���㊯�̐������Ȃ菭�Ȃ����߁A���Ŋ����̐Z�������Ⴍ�A40���̒������ɒB���邱�Ƃ͓�������Ƃ���Ă���B���{�̒����n���u�V�́v�ƌĂԂ̂́A�V(���{)�����߂�̂Ƃ����Ӗ������łȂ��A�N�v�����Ȃ��Ă��ނ���_���ɂƂ��ėL�����Ƃ����j���A���X�����߂��Ă���悤���B
�@
���n�ɂ��N�v�������x�ɂ̓����b�g�ƃf�����b�g������B�����b�g�͔_���̊Ǘ������₷�����ƁA�ېŐ��x���z���邱�ƁA�����̊Ǘ��҂ł��ނ��ƂȂǂ�����B�u�����Ȑ��{�v���ғ�����ɂ́A��͂肱���������ېŃV�X�e���A�x�z���x���K�v�ł������Ƃ������Ƃ��B�f�����b�g�͍^���⊱�A�䕗�Ȃǂł��̔N�̎��ۂ̐����傫�����E���邱�Ƃ��B�喼���_�����N�ɂ���Ď������傫���ς�郊�X�N��w�����Ă����̂ł���B���̂��Ƃ���]�˒����ɂ́A�L��E�s��ɂ�����炸���̔N�v���ɂ����(���傤�߂�)�@���̗p�����悤�ɂȂ�B�@ |
�����H�̐����Ɠ`�n���x
�@
���T���琔��ɂ킽���č]�˖��{�̐�s�I�Ȑ�����Љ�Ă������B���{�̐���Ƃ����A�Q�Ό��̎��{�═�Ə��@�x�E���Ə��@�x�̔��߁A�����A�唻�E�����̉����Ȃǂ��v�������Ԃ��A�܂����̑O�ɍ]�˂ƒn���s�s�����ԃC���t���������K�v�ł���B�]�˂͖��{���J�����܂ŕӋ��ł������̂ŁA�]�ˎs�X�̌��݂ƌ�ʖԂ̕Ґ��͓���Ƃ̏d�v�Ȏ��Ƃł������B�Ɠ����Ɍ�ʖԂ̐����́A�o�ς̔��W�𑣂���s�I�Ȑ���ł��������B
�@
�]�˂ւ̌�ʁE�A���H�͗����ʂ���ɐi�݁A�̂��ɏ���|�]�˂����ԉ��D�ȂNJC���ʂ����܂��B1603�N�A�ƍN�͏��喼�����Đ_�c�R������A���݂̓��{������V���Ɏ���n��̎��n�ߗ��ĂĎs�X�n�����B���̍ہA�]���͐�����n��ʉ߂��Ă������C�������̎s�X�̒����ɒʂ����̂ł���B���ꂪ���݂̋���ʂ�A�����ꍆ�ł���B
�@
�V���ɉˋ��������{�����N�_�ɁA��������36�����u�ꗢ�v�Ƃ��A�ꗢ���ƂɌ܊Ԏl���̈ꗢ�˂点���B��A���ė��l�̋x�e���A�e���̏�Ƃ����̂ł���B���l�͈ꗢ�˂�ڈ�ɂǂꂾ���������̂����m�F�����̂ł��낤�B���˂��]�˂ɂȂ炢�S���Ɉꗢ�˂��݂���ꂽ�B
�@
���C���E���R���E�b�B�X���E�����X���E���B�X���́A������܊X���̂����A�ŏ��Ɋ��������̂́A�]�˂Ə�������ԓ��C���E���R�����B�ƍN�͈ꗢ�˂ɉ����A�e�I�_�܂ł̓����ɖ�2�`3��(8�`12km)�Ԋu�ŏh�꒬(�h�w)��݂����B�����̗A���̎�͔͂n�ł���A���p�̕������^�Ԃ��߂ɐ݂����̂��`�n(�Ă��)�ł���B�`�n�Ƃ́A���̈ړ��╨���̗A���ɔ����āA�h��ɏ��p���p�̔n��l����u�����ƁA���邢�͂��̏��p���p�̔n�̂��Ƃ��w���B���p�̗��s�҂�ו����h�w����h�w�ւƑ��邱�̓`�n���x�́A���ɍ����I�ȕ��@�ł���B
�@
�����ɏڂ����l�Ȃ�A���݂̍���}�ւ�}�g�^�A���s���Ă���V�X�e���Ɠ����ł��邱�ƂɋC�Â����낤�B���Ƃ��ΑS�����瓌���s���Ɍ����đ���ꂽ�ו��́A��x�i��̋���ȑq�ɂɏW�܂�B�����͓͂���ɂ���ďa�J��A���c�J��Ȃǂɕ��ނ���A���̃G���A�̒S���҂��i��̑q�ɂ܂Ńg���b�N�ŋ삯�A�g���b�N�ɉו����ڂ��A�����̒n��֖߂�B����͉ƍN���l�Ă����`�n���x�P���������V�X�e���ł���B
�@
�e�h��ɂ́A���̔n�Ɛl�����������≮(�Ƃ��)���u���ꂽ�B���C���ł͓����A�≮�̐���36�ł��������A������p�̗A���E��ʗʂ������A1616�N�ɂ�75�A1638�N�ɂ�100�ƂȂ������A����ł����肸�ɏh��̋ߏ��̔_������l��n����o���ꂽ�B���̂悤�ɏh�w���ӂ̑��X�ɉۖ��킹���̂�����(��������)���x�ł���B�������ɂ͕�V�Ƃ��Ē��K���x����ꂽ���ʏ���K�̔������炢�ɂ����Ȃ炸�A���������牝����1�A2���������Ă����̕��͖����ł������B�܂��A���{���p�̗��s�҂͔_�Ɋ��ɑ����A���ł͏������ɍ����o���_�����Ԃɍ��킸�ɑ���ɋ��K�������o�����Ƃ�����A���̍����͈������ꂽ�Ƃ����B
�@
�����[���̂́A���p�̉ו��͖����ł��������Ƃ��B�����炭�n���̑喼������Ƃɑ������莆�╨���̂��Ƃł��낤�B���p�ł��邱�Ƃ��ؖ����邽�߂ɖ��{�͎���(�`�n���)�s�����B������g�т��Ă��Ȃ��҂ɑ��āA�e�≮�͌��p�̓`�n���o�����Ƃ��ւ���ꂽ�̂ł���B���Ƃ����B����܂ł́A�������H�ł͌��p�̉ו��̗A������ł������悤���B
�@
�ł́A�����������ו��̑S�H���̊Ǘ��ƌ�����N�������Ă����̂��Ǝv���Ē��ׂĂ݂�ƁA�]�˂̒��N�S���Ă������Ƃ��킩�����B����ɗA�����Ǘ����Ă����`�n���́A���݂̍c���O�ɓ����鑺�̗L�͎҂ł������悤���B�܂�A���ԂɔC�����̂ł���B�ނ�͍]�ˏ邪���������ۂɖ����n�ɗ����ނ��������l���B������ł��낤���A�`�n������z����㏞�Ƃ��ĐV���ȓy�n��^�����A���̖���ɂȂ��Ă������B�`�n�����ڂ�Z���́A��`�n���A��`�n���A���`�n���ƌĂꂽ�B�������Ă��̎��ӂɈɐ����l�Ȃǂ��i�o���ēX���J���A�≮�����`������Ă����B���ꂪ��������{���Ɏc���Ă���u��`�n���v�u���`�n���v�̒����̗R���ł���B�@ |
�����H�E�����H���Ȃnj�������
�@
�]�˂͓��{�̏鉺���Ƃ��Ă͓���ȗ��n�ł������B�ƍN���]�˂ɓ����Ă����Ƃ��ɂ́A��̖ڂ̑O�܂œ��]�����荞��ł����B�܂�A�_�Ƃɂ��鉺����z���ɂ��K���Ȃ��E�H�[�^�[�t�����g�������̂ł���B
�@
���̓y�n�ɑ喼�̉��~��݂���ɂ͓y�n�����K�͂������̂Ŏ��n��C���āA���̓y�n�Ɏ�s�@�\���������邱�ƂɂȂ�B�ƍN�́A�ŏ��͏�̋߂��ɑ喼�A���{�����̕��Ɖ��~��U�v���A���{������C�����Ă̈�т��ɂ����B���ƒn�͎�ɑ�n�ɁA���l��E�l�̏Z�ޒ��l�n�͒�n�Ɍ������čL�����Ă������B��n��ʏ́u�R�̎�v�A��n���u�����v�ƌĂB�]�k�����A����J���]�ߗ��Ăł������������{���⋞���A������u�����v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
�ł́A���ߗ��čH�����K�v�ȓy�n�ɂ킴�킴����\�����̂͂Ȃ����낤���H����͐��^�𗘗p�ł���Ƃ��������b�g�����������炾�B�]�˂̐��x�͐��H�̖������ʂ����A�o�ϖʁE�����ʂő傫���𗧂����̂��B
�@
�ƍN�́A�]�˂ɒ��������ɍ]�ˏ�{�ې�ƍ]�˖������ԑD����x�u���O�x�v�̌��݂ɒ��肵���Ƃ����B�]�ˏ錚�݂̂��߂̎��ނ�������邽�߂̐��H�ł���B�g���b�N�̂Ȃ������A��̌��z�ɕK�v�ȋ���Ȑ�؍ނ͗��H�ł͉^�ׂȂ������B�܂��A���H��萅���ʂ̂ق����A���ʂ��傫���A�R�X�g�͒Ⴂ�Ƃ��������b�g���������B�ɓ��Ő�o���ꂽ�ނ�A�x��(���É���)�A���](���É���)�A�O��(�����m��)�Ŕ��̂��ꂽ�؍ނ́A�O�l�喼���������D�ɍڂ����A���̂܂�֎������܂ꂽ�̂ł���B����ɏ����ؐ���J�킵�āA�s���̉���D���̖�A�ĂȂǂ̐H�����m�ۂ��邽�߂̐��H��z�����B����͍]�ˏ錚�݂Ə���j�ɂ����C���t�������Ƃ����悤�B
�@
�����̍]�˂́A��n�䂦�ɐ��Q�Ɏキ�A�J���ɂł��Ȃ�ƁA��ɍ^���ɂȂ�܂���Ă����B�ƍN�́A�����𐅊Q�����邽�߂ɁA�̂���̕���Ə��ΐ�����J���]�ɂ͒��������ɁA�ЂƂɂ܂Ƃ߂ē����ɗ���Ă�����c��ɗ��Ƃ��H���ɒ��肵���B�{�����������Ƃō^����h����ł���B�����H���͐����͂��Ȃ���Γ���ł��Ȃ����̂��B�ƍN�̎��s�͂͂����������̂ł���B
�@
����A�����ł͎��R�̉͐�����Ƃɖx���߂��点�A�����̗A���ɗp����ꂽ�B���݂͊����{���ɐ��܂ꂽ�̂́A���{�����ˋ����ꂽ���ゾ�B����Ƃɋ�����邽�߂ɐےÂ̍�(�����{�E���Ɍ�)���痈�����t�����́A�ƍN������c��̉͌��̐ꏊ���đ������邱�Ƃ������ꂽ�B�ނ�͋��Q��ǂ�����ň�ԑŐs�ɂ�����@�ɂ���āA����Ƃɒ��Ă��܂��]��قǂ̋��l�ʂ��ւ����B�]��������l�ʂ�̑������{���ʂ�Ŕ̔����鋖�{������炢�A���ꂪ���݂͊̎n�܂�ƂȂ�B�����́A�����̋����ׂĂ����{�����D�ʼn^��ĉ݂͊ɉחg������A����ꂽ�Ƃ����B���{����Ƃ��̎x���̖x�A�e�X�݂͍̉͊]�˖��̓��`�̖������ʂ����A�]�˂̕����̒��S�ƂȂ��č]�˂̌o�ς��x���A���W���Ă������B
�@
�����������n�ɂ͖����������B��˂��@��ƊC�����N���o�邽�߈�������̂���������̂��B�����ʼnƍN�͐����p���̕s����S�z���A�Ɛb�̑�v�ۓ��ܘY�ɏ㐅���̌��݂𖽂����B�܂��A���ΐ�t�߂̗������]�ˏ���ʂɈ����ď��ΐ�点���B����W�����A�_�c��̏�Ɂu�����v��n�点���̂��u�_�c�㐅�v�ł���B�����̐����͖ؐ��̐����ǂɐ^����ʂ������̂����A���ꂪ���{�ŏ��̐������Ƃł���B��̓��r(���݂̕�����s)�𐅌��ɂ��A���ΐ�̊��ŕ������A���̌�A������_�c�̑�n�ɉ����ė���Ă����Ƃ����B
�@
���̌�A�]�˂̐l�����}�������̂ŐV���ȏ㐅���K�v�ƂȂ�A������̐���������A���݂̐V�h�܂Ŗx�Ƃ��ė����A��������Ë��ƂȂ��č]�ˏ�Ճm��ɒB����u�ʐ�㐅�v����������B�ʐ�㐅�͍]�˂����łȂ��A�r���̑��ł���������_�Ɨp���ɗp����ꂽ�B
�@
�z��Ǝ����ƕ����̂��߂ɐ��H���J���A����ł͈��p��_�Ɨp���̊m�ۂ̂��߂ɏ㐅�������ƍN�B�]�˂͔ނ̎�r�ɂ���ďZ�݂₷���s�s�ւƕς���Ă������̂ł���B���H�E�����H���A�㐅���H���Ȃnj������Ƃ̎��{�́A�����ƂƂ��Č����Ȑ���ł���B����Ȃ�ƍN�́u�s�s�J���v���f���[�T�[�v�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B�@ |
�����������x�Ǝ��D���x
�@
�ƍN�����{�����O���E�f�Ր���̂ЂƂɁu������(���Ƃ����)���x�v�Ɓu���D���x�v������B�ƍN������A�W�A�����Ƃ̐e�P�O����i�߂�Ɏ���ɂ́A�������̕z���������B1600�N�A�I�����_���C���h��Ђ̃��[�t�f�������݂̑啪���ɕY�������B�D���̓C�M���X�l�E�B���A���E�A�_���X�B�����ܑ�V�̎���������ƍN������Őڌ��������̂́A�A�_���X�̋A���肢�����ꂸ�A�ނ��Ɨ��ɂ��邽�߂ɍ]�˂֘A��čs�����B
�@
�A�_���X�͉ƍN�ɊO���̖f�Ղ̂����݂�̏����������Ƃ���O���g�߂̖ʒk��ʖ�Ƃ��ďd��A���m���̔��D�̌������S���悤�ɂȂ�B�ƍN�̓A�_���X�ɏo��A�f�Ղɋ����S��������̂��낤�B�̂��ɃA�_���X�͑��͎O�Y�S�̒m�s�n��^�����A���{�E�O�Y�j(����)�Ƃ��Đ���Ȑl������B���̃��[�t�f���̕Y�������������ɁA�I�����_�A�C�M���X�����{�f�Ղɉ���邱�ƂɂȂ�B
�@
�ƍN��1601�N�ȍ~�A����(���݂̃x�g�i��)�A�X�y�C���̃}�j���A�J���{�W�A�A�V����(���݂̃^�C)�A�p�^�j(�}���[�����ɑ��݂����}���[�l����)�Ȃǂ̓���A�W�A�����Ɏg�҂�h�����A�O�����n�߂��B������1604�N�ɃX�^�[�g�����̂����D���x�ł���B����͓��{���o�`���鏤�l�̑D�ɊC�O�n�q������������^���A�f�Ղ𑣂����̂��B����́A���Ƃ���Ȃ�u�f�Ճr�W�l�X�}���ɗ^����p�X�|�[�g�v�ł���B���݂Ȃ�O���Ȃ̋Ɩ��Ƃ����悤�B
�@
�����A���{�̖f�Ց��荑�Ƃ����Ύ�Ƀ|���g�K���ƃX�y�C���B���Ƀ|���g�K���̓}�J�I�ɋ��_��z���Ĉȍ~�A�����Y�������ꊇ�w�����ē��{�ɗA�o���A���v��Ɛ肵�Ă����B�����͓����̓��{�ɂ����čł��d�v�ȗA���i�ł��������A�|���h�K���l�����i���茠�������Ă����̂��B�����ʼnƍN���l�Ă����̂��A���s�̍����E�����l�Y���Y�����[�_�[�ɔC�����A���s�A��A����̗T���ȏ��l�Ɂu���������ԁv��g�D�����A�l�i���Ɛ����̈ꊇ�w����������u���������x�v�ł���B���Ԃňꊇ�w�����������͏��l�ɕ��z�����A���ꂪ���s�E���E�]�˂ɓn�����B���Ԃɉ��i���������A���̉��b�Ƃ��ď��l�ɗ��v��^����Ƃ������Ґ��x���B�u�փ����̍���v�ɂ���č����̌o�ς��������A�̔��s�U�Ɋׂ��Ă����͂̂��鏤�l�Ɍ����āA�ƍN�͋��͂ȃr�W�l�X�̃l�^������̂ł���B����͌o�ϊ���������Ƃ�������B
�@
�ƍN������̏��l�ɓƐ�I�A�����ƓƐ�I��������^�������R�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B���͂̂��鍋�����L�b�h�̎c�}�ɌR���������Ζd�����N����B�������x�z���ɒu���ɂ͂܂��ނ�ɗ��v��^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������Ӑ}���������̂��낤�B
�@
�����ē��N�A���D���x���X�^�[�g������B���D�͒��肩��o�q���A����ɋA�`�����B���D�f�Ղ͖��{�Ɛ[���Ȃ���̂��鏤�l�Ɍ����Ă������A�喼�═�m�ɂ�����͗^�����Ă����悤���B�A���i�́A�����A���D���A�����A����Ɏg����L��⎭��ȂǁB���{����̗A�o�i�́A��A���A�S�A�����A���Ȃǂł������B���ɐΌ���R�ō̌@���ꂽ��́A�����₪�s�����Ă��������}�[�P�b�g�Ɋ��}���ꂽ�B����A�W�A�ł͌��ώ�i�Ƃ��ċ₪�g��ꂽ����ł���B
�@
���D�f�ՉƂƂ��Ė������̂��A�O�o�����u���������ԁv���W�߂����[�_�[�̒����l�Y���Y�ł���B����͑�X���̖��𖼏��A���オ����Ƃ̌�p���l�̈�l�ƂȂ�A���ڂ����{��p�B���l�ɏo�����A�O��ڂ����D�f�Ղł̓������������Ĕ���Ȏ��Y���B�O��ڂ͒���㊯�⍲�������߂��A����ΉƍN�̖f�ՃG�[�W�F���g�ł���B
�@
�����ď��l�Ɩ��{�̊Ԃɗ����Ď���̔��s����莟�����̂��A���݁E��ݔ��s�̑��ӔC�҂̌㓡���O�Y�ł���B�����ɐݗ����ꂽ�u����v�̉^�c�Ǘ���C����Ă����㓡�́A�f�Ֆʂł��d�v�Ȓn�ʂɂ����B���D�f�Ղŋ�̗A�o���ƍN�ɐi�������̂͂����炭�㓡�ł��낤�B�ނ͂������ߖ��{�̍��������Ƃ������Ƃ��납�B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
���V�c�J���Ɣ_�Ɛ��x
�@
�]�ˎ���ɔN�v�̑�����}��ړI�Ŗ��{��e�˂͐V�c�J�������サ���B�s���T�C�h���炷��ΊJ������E�_�ƐU����A�����������u�_�n�J��v�����A�k�n�ƂƂ��ɏW�����`������A���H��X���̐������Z�b�g�ɂȂ��Ă���̂Łu�n��J���v�ƕ\�����Ă��悢���낤�B�V�c�͋��z�̗��v(��)�ݏo���ƂƂ��ɁA�l��������܂��Ȃ����߂Ɏ�H�̕Ă��K�v�ɂȂ����Ƃ����������ł��邾�낤�B�V�c�J���́A���Ǝ����̂������ɍs�����H�Ƒ��Y�v��Ƃ��������������ꂻ�����B
�@
�V�c�J���́A�]�ˎ��㏉���A���ۂ̉��v���s��ꂽ1720�N���A�������O�ɂ�����1840�N����3�̃s�[�N������B�]�ˎ��㏉���ɂ͖�l��_���̎哱�Ō⊃�A�Ȃǂ̖��ߗ��Ă⊱���{����A���n�������čk�n�ƂȂ����B���������]�˂̒��̑����������n�ł��������Ƃ��ӂ݂�A�e�˂͍]�˂ɂȂ�����Ƃ������悤�B�܂��u�˒n�т��n�ȂǓ����n�ł��J���͐i�߂�ꂽ�B���������V�c�J���ɂ���č]�ˎ��㏉���ɑS����1800����������(�܂荑�������Y)�́A�]�ˎ��㒆���ɂ�2500���A����ɂ�3000���Ɣ{���ɋ߂����ʂ������߂��B���Ɋ֓��A���k�A�����A��B�Ȃǂł͌Ώ��⊃���J������A�_�n���������B
�@
���̂悤�ȑ�K�͂ȐV�c�J���́A�J���\���҂Ɋ����s�������A�H�����n�߂�ꂽ�B�V�c���������Đ��N�Ԃ͔N�v���Ə������Ƃ����������������Ƃ����B
�@
�����[���̂́A���c�̐V�c�Ɩ��c�̐V�c�������������Ƃ��B���{�̒����̂�˂̏��L�n�̊J��͓��R�������Ƃ����A�_���������Ǝ��ŊJ������͖̂��Ԏ��Ƃł���B�u�͖��̂��߂ɓy�n���k���B�_�Ƃ��������҂͎��͂ŊJ������v�Ƃ����]�ˎ���̓y�n�J���́A�ƂĂ��킩��₷�����B���{��˂����ׂĂ̒n��J�����v��I�ɐi�߂�A����͖������������Љ��`�Ɋׂ�B���`�x�[�V�����̍����_���͂��C���Ȃ������낤�B
�@
���c�̐V�c�́A���{�V�̂̑㊯�������čs����u�㊯�����V�c�v�ƁA�˂��哱�ōs���u�ˉc�V�c�v���������B�O�҂͓V�̂Ȃ̂Ŗ��{���I�[�i�[�ł���B�_���͌ق��闧��ɂ���A�㊯�͔N�v��10����1�̎������B�u�ˉc�V�c�v�͔˂��_���ɔ_�n�J���ɕK�v�Ȏ��ނ���ĐV�c���J�������邩���ɐ��N�Ԃ̔N�v�̖Ə���ۏႵ���B���c�̐V�c�Œ����Ȃ̂��A����Ǝ������܂ޗ����쐅�n�J�����B�����ɂ���65�N�̍Ό����₵���Ƃ����B
�@
���c�̐V�c�ɂ́A���ʂ̕��m�ł���y���������������o���A���ӂ̔_�����ق��ĊJ�������u�y���J���V�c�v�A�_�����������S�̂Ŏ����ƘJ�͂���ĊJ������u�����V�c�v�A�����͂̂����s�s�̏��l���J�����A����_���ق��čk������u���l�����V�c�v���������B
�@
���{�̍�����@����E�p���邽�߂ɓ���g�@�����{�����u���ۂ̉��v�v�ł́A���{�͎��̂悤�ȐV�c�J���𑣂����B�V�̂̓��ő喼�̂Ɠ���g�ޏꏊ�ł����Ă��V�c�ɂȂ肻���ȓy�n������Ό܋E��(�ےÁA�͓��A�a��A��a�A�R�鍑)�̏ꍇ�͋��s����s�ɁA�����E�����̏ꍇ�͑���s���ɁA�k���E�֔��B�͍]�˒���s���Ɋ肢�o��悤�Ɂ\�\�B
�@
���̐���́A���{�������S���邱�ƂȂ��A���Ԏ��������邱�ƂŔN�v�n�̊g���ژ_�ނ��̂ł���B���̂����ɊJ���n�̈ꕔ���o���҂����L���邱�Ƃ������A�J���҂͒n��Ƃ��ď��엿���ł���B�܂�_�n�̃I�[�i�[�ɂȂ��Ƃ������Ƃ��B���̂����݂́u�ŋ���Ⴍ�ݒ肷�邩��A���̒n�Ɏx�Ђ��o���Ă���v�u�y�n���i���Œ��邩��A���̒n�ɍH������ĂĂ���v�Ƃ����������݂���u�o�ϓ���v�Ƃ�������ł���B
�@
���̎���ɊJ�����ꂽ�̂��A�֓����[���w�n�тɂ���A���ɖR�����������Ƃ���_�Ƃɂ͂���߂ĕs�K�ł�����������̑�n�ł���B���{���L�\�Ȕ_�ƋZ�p�҂�h�����A������̓y�����J�������B�������Ċ֓����삪��Ă������̂ł���B
�@
�������Ȃ��畾�Q�����Ȃ��Ȃ������B�V�c�J���u�[���ɕ֏悵�����v��ȊJ���ɂ�鐅�Q�ł���B���������H�������Ƃō^�����N����A�V�c������P�[�X���e�n�Ō���ꂽ�Ƃ����B�]�ˎ���̎��Ƃ��傫�ȃ��X�N���������Ƃ������P�̂ЂƂł���B�@ |
���ݕ������@�ւ̐ݗ�
�@
���얋�{���m�������ݕ����x�̊�{�́A���݁E��݁E�K�݂�3��ނ̉ݕ����߂�O�ݐ��x�ł���B�f�Ղɂ���Ă����炳�ꂽ�l�X�Ȓ����K�̍������ʂɉ����A�]�ˎ�����O�͉ݕ�����������Ă����̂ŁA���̈����ݕ��ȂǗl�X�Ȏ�ނ̉ݕ����o���A����炪���ʂ��邱�ƂŎ���ɖ�肪�����Ă����B
�@
�܂����R�E��R�ō̌@���ꂽ������Y�n���ƂɎ��I�ȍ�������A���������Ɏx����������v���ł������B��������������ƍN�͓V������̋��̂ЂƂƂ��āA�S���ǂ��ł��ʗp����ψ�̎��̉ݕ��ɓ��ꂷ��K�v���������̂��B������ς���Ζ��{�ɂ��u�ݕ��̔��s���v�̓Ɛ�ł���B
�@
���{�͋����A����A�K���ƌĂ��ݕ������@�ւ�ݗ����A���ꂼ��̉ݕ��𒒑��������B�����͖����ɒa���������c�̑����ǂƂ͊T�O���قȂ�B�����A����A�K���́A���{���������^����ꂽ���l(�������l)�ɂ���č\������鐿���������Ƃ��������炾�B���݂ł����Ƃ���̃A�E�g�\�[�V���O�ł���B
�@
�����{�̖�l�ł��銨���s���������ē��A�������ꂽ�ݕ��͌����Ƃ��Ė��{���菊�֏�[���ꂽ�B�}�l�W�����g�͖��{�̖�l���S���A���ۂ̍�Ƃ͖��Ԃ����������Ƃ����d���̂����݂́A���{�����̂̋��R�E��R�̉^�c�V�X�e���Ƃ悭���Ă���B���ꂼ�u���Ԃɂł��邱�Ƃ͖��ԂɁv�����H���鏬���Ȑ��{�̐���ł���B
�@
�ƍN��1601�N�A�S�����ʂ�ړI�Ƃ����c������𐧒肵���B���ݒ����̒��S�ƂȂ����l���������H�|�t�E�㓡���O�Y�����ł���B�㓡�́u���~�̐w�v�œ���R�̐땺�Ƃ��Ċ����l�����B���ݒ����ƊӒ�E������s���������́A�ƍN��1595�N�A�]�˂Ɍ㓡���ĂсA�����𒒑����������Ɏn�܂�B���{�ݗ���͊����s�̎x�z���ɒu����A�]�˖{�Β��ɖ��(���݂ł������@)���ݒu���ꂽ�B
�@
�����͏x�́A���s�A���n�ɂ������͒u���ꂽ���A�����܂ő������̂͋��s�ƍ]�˂݂̂ł���B�ƍN�ɔ��F���ꂽ�㓡���O�Y�͌������(�����炽�߂₭)�Ƃ��ċ��݂̊Ӓ�ƌ�����s���A���ۂ̒����͏����t�ƌĂ��E�l���S�������B���{������ݐ����̋��������t�����͌㓡�Ƃ����Z����������̎��ӂɎ�����\���A�i����[���Ȃǂ��ׂČ㓡�Ƃ��}�l�W�����g���A����ō�Ƃ����B�����t���������������̂͌��������B���ꂪ�㓡�̖��Ō��肳��A�㓡�Ƃ̋Ɉ�(�O�˂̑ō�)���Ȃ��ꂽ���̂������ݕ��Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�̂ł���B
�@
�㓡���O�Y�����͒P�Ȃ�����ł͂Ȃ��A���{�̌o�ϐ����S���҂̂悤�ȑ��݂ł������B�������������̒������Ă����̂͌㓡�ł������B�ȑO��葾�}�G�g���g���唻�͋��z���傫�����A�����Ŏg���ɂ͕s�ւł���A�唻��1/10�̉��l�ɂ����������g���Η��ʂ��h����ƒ�Ă����̂ł���B���{�͏��O�Y�̃v�����������ɗ������A�㓡�Ƃɂ��V�ݕ��̐������X�^�[�g�����B����̔��s���㓡���ƍN�Ɏ�莟�����Ƃ���Ă��邱�Ƃ���A�f�Ղɂ����邢�ːl�ł������̂��낤�B
�@
�����[���̂́A�������̒����ɕK�v�ȍޗ��͏����t���������g�Œ��B�������Ƃł���B�t���[�����X�̏����t�����͎��ȐӔC�ŋ��E�⏤�l�����������邩�A���{�����̋��R������D���ē��肵���Ƃ����B�₪�ĊǗ��̓O��Ə����t�̕��U����h�����߂ɁA1698�N�ɂ͌㓡�Ƃ̕~�n���ɒ����{�݂��ݒu����A�ȍ~�]�˂ł̋��ݐ����͂��̋����݂̂Ŏ��{�����悤�ɂȂ����B
�@
�ݕ������@�ւ̒��ŋ����͓��Ɍ������Ǘ��A�������Ă����B�����̍�ƈ��ɂ�鑊�݊Ď��̐��A�E�l�̗p���̐��̒�o�A�ƕ��̌���Ȃǂł���B
�@
����A��݂̒������s��ꂽ����́A�ƍN��1601�N�ɋ��s�E�����ɐݗ������̂��N���ł���B��݂͍�̗��֏��E����앺�q�����P�Œ��������B����͓���Ƃ���单�퐥�Ƃ���������^�����A��݂ɂ͑单�Ƃ̋ɈL���ꂽ�B
�@
���Ƃ͂Ƃ����u�������������Ă���̂͋�݂��s���肾����B�ǎ��̋�݂s���ė~�����v�Ƌ�ݔ��s���Ă����̂́A�ےÍ�����̍����ő�Ñ㊯�̖��g�����q�ł���B�����̋���͑单�Ƃ��d��A�O�o�����㓡���O�Y���Ɩ��g�����q�ꑰ�����[�_�[�ƂȂ��ĊǗ������B����������s�̎x�z���ɂ��������A�������l�A���l�ɂ�鐿���������Ƃł������B�@ |
������ɂ��ݕ������@�ւ̊J��
�@
�]�ˎ���ɋ@�\���������E����͉ݕ��̒�����S�����ԋ@�ւł���Ɠ����ɔ��s�@�ւ̖����A�����ɂ��ʉݒ����������˂Ă����B���݂ł����Ȃ瑢���ǂƓ��{��s�̈ꕔ���̋@�\������炪�S���Ă����̂ł���B���ɃR���p�N�g�Ɏd�オ�����g�D�Ƃ����悤�B
�@
�����͏����t�̒��������������̊Ӓ�ƌ�����s�����ݐ����E�Ǘ��Z���^�[�A����͋�ݐ����E�Ǘ��Z���^�[�ł���B����͓����A�����A�x�́A���ɐݒu���ꂽ���A�����̋����1608�N�ɋ��Ɉڂ���A�x�͂̋���͂̂��ɕ������B���̋���͐����Ό��Ȃǂ̋�R���璒���p�̋���W�߁A���ɑ��������S���Ă����悤���B�₪�ċ���͍]�˂Ƌ��s�̓��݂̂ƂȂ�A�̂��ɍ]�˂݂̂ɏW������悤�ɂȂ�B�����E����Ƃ������s���������Ǘ��������̂́A���Ԃ̐����������Ƃł���B
�@
����A���𒒑������K�݂̊��i�ʕ��S���ɍL�߂邽�߂�1637�N�A���{���S���ɐݒu�����ݕ������@�ւ��K���������B�����E����ƈقȂ�A�K�݂�K�v�Ƃ���ꍇ�Ɍ���ꎞ�I�ɊJ�݂��ꂽ���̂ŁA�����͖��{����K�ݒ����Ɋւ���Ɛ�I�ȓ�����^����ꂽ���l�őg�D���ꂽ�B�����E������l�A�����s�̎x�z�������A�J�݊��Ԃ��Z���A���������l����������ւ����̂ŁA�����܂�͉��₩�ł������悤���B�ʉݒ����̂��߂̒Z���W���̐����������ƂȂ̂ŁA�����E����قǏd�v������Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤�B
�@
�K���͍]�˂ł͊��i�ʕ�̒�����Ǝłōs���A���̌�͖{��(���݂̖n�c��̈ꕔ)��[��ɂ��ݗ����ꂽ�B���������x�ɂ���ă|���g�K���D�̗A��������Ɛ�I�Ɉꊇ�w���������̏��l�������K���̐ݗ���\�����A1700�N�Ɋ��i�ʕ�̒������s�����Ƃ����L�^���c���Ă���悤�ɁA�K���̌o�c�͌���ɂ����̂������B���{���Ǝ҂�T���đŐf�����̂łȂ��A����ł��������Ƃɒ��ڂ������B
�@
���{�͐��������Ǝ҂��ʼn_�ɒT�����X�N������ł��邵�A���l�ɂƂ��Ă͑K���o�c�̋@��ϓ��ɗ^����ꂽ���ƂɂȂ�B��������ɂ����ĉ���I�Ŗ���I�ȕ��@���B�Ƃ͂������̂́A�����������̂́A���R�o�c�ҁA�f�Տ��ȂǑS���̗L�͏��l���قƂ�ǂŁA���̔w��ő����Ă����̂͊e�n�̑喼�ł������悤���B�K���̗��v�̈ꕔ�͖��{�ɏ�[���ꂽ���A�K���o�c�̗��v�͑喼�̎������ɂ��Ȃ��Ă����̂��B
�@
�������A�₪�č��Y���̌��ނ������ɂȂ�A�f�p���̊m�ۂ̂��߂ɓ����Y���R���g���[�������悤�ɂȂ�B�������������ꂽ���a��(1764�`1771�N)�ȍ~�́A���{�̖��ɂ������E������K�݂̒��������˂�悤�ɂȂ�B1772�N�ɂ́A�����E����ȊO�̑K�ݒ����͌����Ƃ��ċ֎~���ꂽ�B��������{�ɂ��ʉݓ�������ł���B
�@
�������Ēʉݒ������s���A���݁E��݁E���݂ɂ��O�ݕ����x���蒅���Ă������킯�����A�����ɑ傫�Ȗ����ƂȂ鐧�x�����܂ꂽ�B���{�͏���ŗ��ʂ��Ă����G���ȋ���A��݂̈�肵������E���ʋ�ɓ��ꂵ���̂ł���B����E���ʋ�Ƃ͋�̔��ʂɂ��ݕ��ŁA�d����ʂ��Ďg���ݕ��ł���B����̋��݂͂��̖����ɂ���Č������l���v��\�L�ݕ��B���̔��ʉݕ�(���)�ƌv���ݕ�(����)�̕��p���]�ˎ���̉ݕ����x�̃��j�[�N���ł���A�܂����_�ł��������B
�@
���E��E�K(��)�݂Ƃ����A�P�ʂ����i���܂������قȂ�ݕ��������������ƂŁA��݂��d�p���Ă�������Ƌ��݂��d�p���Ă����]�˂Ƃ̎���ɍ����������������Ƃ��痼�֏������W���A�₪�ĎO���Z�F�Ƃ��������������܂��v���ɂ��Ȃ����̂ł���B
�@
���{�ʁE��{�ʂ̎��_���猩��A���{�͑f�މ��l�̍��������ݕ����x�̒��S�ɐ����悤�Ƃ����悤�����A���ی��ώ�i�Ƃ��čL���F�߂��Ă����̂͋�ł������B���{�ʐ��Ƌ�{�ʐ��͂܂������قȂ�p���_�C���ł���B�����ɑ�ʂ̋��݂��C�O�ɗ��o�����̂́A�����O�̉ݕ��ɑ��鉿�l�̃M���b�v�ɂ���Đ������Ƃ����������ł��邾�낤�B
�@
���Ȃ݂Ɍ��݁A�]�ˋ����̐Ւn�Ɍ����Ă���̂����{��s�ł���B�����ē�����܂������E������l�A���{����Ɨ������@�l�ŁA���I���{�Ɩ��Ԏ��{�ɂ���Đ��藧�g�D�ł���B�@ |
�������̐E�������˂�����s�Ɩ��Ԃւ̈ϑ�
�@
���{�ōs����S�����̂́A�V�����V�A��ڕt��O��s(����s�A���Е�s�A�����s)�Ȃǂ̐E�ɏA���������̕��m�����A����疋�{�����ōł������������̂��]�˒���s�ł���B��s�����ݒn����k����s�E�쒬��s����s�ƌĂꂽ��l�̍]�˒���s�́A���݂ł����Ȃ瓌���s�m���A�x�����āA���h���āA�����s�n���ٔ������������C�����悤�Ȗ�E�ł������B��s���͌�ԏ��A������Ƃ��Ăꂽ�B�s���������Ƃ������n���ٔ����ɋ߂��ꏊ�ł���B
�@
�]�˒���s�̓T�����[�}���̂悤�ɖ����o�邵�A�V���̎w��������A���̊����ƐՂ����肵���ق��A�]�˂ɂ�����E�l����ȂnjY�������̑i�������s���A�����1������ւō]�˒��l����̑i�ׂ������B������͖����i�ׂ̎ł���B
�@
�����̏d�v�����̌����ٔ����s�����A�]�菊�ƌĂꂽ�ꏊ������B�V���A��ڕt�A�ڕt�A�O��s�Ȃǂ�����6��o�Ȃ��A���̓s�x�Č������������ꏊ�����A�����Œ��S�ƂȂ����͎̂O��s�ł���B�]�˒���s�͕]�菊�̃����o�[�Ƃ��č����ɂ��֗^�����̂ŁA�i�����ƍs�����������Ȃ��A�ٔ��������߁A����ɖ@����b�����˂������Ƃ������ƂɂȂ�B�]�˒���s�Ƃ��Ė������̂́A�쒬��s�̑剪�z�O�璉���A�k�E�염��s�߂����R���q��ьi��(���R���l�Y�i�����u���R�̋�����v�̃��f��)�A�����̗D�ꂽ�����E���I����(����)�Ȃǂ�����B�ނ炪�����ɃX�[�p�[�}���I�Ȏd�������Ȃ����̂��͑z���ɓ�Ȃ��B
�@
���\����ɍ]�˂��l��100���l�s�s�ł��������Ƃ�����ƁA�l�X�Ȗ�肪�������Ă����Ƒz���ł���B����s�ɂ͂��ꂼ��^�́A���S�������Ƃ��Ĕz�u���ꂽ�B�^�͓͂s�s�s���̊e����̒��ԊǗ��E�B���S�͗^�͂��i���̖�l�ŁA���݂Ȃ��ʂ̌x�@���Ƃ������Ƃ��납�B
�@
�]�˂̓s�s�s����S����s���̃X�^�b�t�͗^�́E���S�����킹�Ă�300�l�ɖ����Ȃ������Ƃ���Ă���B����ɍs���̈ꕔ��ł��鎡���A��̓I�ɂ͎s���̎����܂�ɂ��������̂�20���قǂɉ߂��Ȃ������悤���B����ł�100���l�s�s�̎���������͂����Ȃ��A���ۂɂ͓��S�̉��ɉ������A���̎q���̉��������]�˂̎����ێ��ɑ傫���v�����Ă����B
�@
�����ċ����ׂ����ƂɁA��s���͊e���ɒu���ꂽ����(����l)�Ɋe���̍s�������̏������ϑ����Ă����̂ł���B�]�˒���s�𓌋��s�m���ɒu���ς���Ȃ�A�m���͈ꕔ�̍s�������ԂɈϑ����A�s�s�s���𐋍s�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
����͈�l������A����7�`8���A��2000�l�ȏ�̒��l��S�����Ă����悤���B�ނ�͖𗿂����炢�A��s������̓`�B�A�Ύ���ł̉Ώ��l���̎�z�A��s���ɒ�o�����i���͏��̃`�F�b�N�A�����̂��߂��Ƃ̒���ȂǑ���ɂ킽��d���������B����撷�⒬���̂悤�ȑ��݂��B����̏��3�l�̒��N����A��s���Ƃ̃p�C�v�����ʂ����Ă����B����͊e��g���ɓ���A�g�����̖�����Ď����A�`�B������`�����B�s���𖢑R�ɖh�����߂ɂ��݂��̒��̍s���������`�F�b�N�������̂ł���B�]�˂̍s���͂��̂悤�ɖ��Ԑl���g���Ă����̂Ŋ����g�D���R���p�N�g�ɂȂ��Ă����Ƃ������悤�B
�@
�܂������p�ƌĂ��s���ɂ������p�͖��{�łȂ��A�������S���Ă����B���̃V�X�e���͐ŋ��ɋ߂����̂ŁA�n�傪��������Ɖ��~(�s���Y)�̋K�͂ɉ����Ē������ꂽ���������p�Ɏg��ꂽ�̂ł���B����̖𗿂������p�ɂ���Ęd��ꂽ�B�y�n�������Ă���s�����s���ɂ������p�S���Ă����Ζ��{�̎����o���͂Ȃ��B���{�ɂƂ��ăx�X�g�ȑI���ł���B
�@
���̂悤�ȓs�s�s���̂�������ӂ݂�ƁA�]�˂̒��l�������ɍs���ɎQ�����Ă����Ƃ������Ƃ��킩��B�����Ė��{���I�݂ɒ��l���R���g���[�����Ă����Ƃ����\���������Ă���B���݂ł����Ԑ��Ŗ�����s���Ă��钬������邪�A����͍]�ˎ��ォ�瑱���s���̎��q��i�ł���Ɠ����ɁA�s���̎d�����s��������I�ɒS���Ă����Ƃ�������B�Ƃ�����A�]�˂̍s���͒���s���������Đ��藧���Ă����Ƃ������Ƃł���B�@ |
���]�� �Z��ƃS�~���
�@
�]�ˎ��㒆���ȍ~�̍]�˂̐l���\���́A���Ɛl��50���A���l�l��50���Ƃ���Ă���B�]�˂̖ʐς̖�70�������ƒn�ƌĂ�镐�Ƃ̋��Z�n�ł������B50���l�̒��l���c��30���̓y�n�ŕ�炵�Ă����Ƃ������Ƃ́A�K�R�I�ɒ��l�̉Ƃ͏������Ȃ炴��Ȃ������̂ł���B�]��(����)�̈�ʎs����400�N�O����u�����������v�ɏZ��ł����Ƃ������Ƃ��B
�@
�l���̑��������łȂ��A�]�˂̒n���͍��z�ł��������Ƃ�����A�ƒ��̑ؔ[�⋤���{�݂̕K�v���Ȃǂ��܂��܂Ȗ�肪�������悤���B�l�����x�̍����]�˂̒��S���ƁA�_���n�ł�����Ӓn��̓X���̊i����4�`5�{�ɂ̂ڂ��Ă���A���S���ł͋X�܂������A�܂��X���̑ؔ[�����Ȃ��Ȃ������悤���B���̂悤�Ȗ�肪�����������ƂŁA�������x��s�s���i�Ɛ����ł���B
�@
���l�������Z�܂��T�^�I�ȏZ��Ƃ��Ď��㌀�◎��ɓo�ꂷ��̂�����A�˂��������B�����y�n�Ȃ��炱�̒����ɂ͓s�s�������c�ނ��߂̑����̍H�v���قǂ�����Ă���A��������邱�Ƃ������B�n��͕\�ʂ�ɖʂ��������̓y�n�����X�ɑ݂��A���̗��ɂ͗����������āA�����Ƃ̂Ȃ��l�X�ɑ݂��t���钬���o�c���s���Ă����B
�@
�ЂƂ̓y�n��p�r�ɕ����đ݂��o���Ƃ����A���݂ł͓�����O�ƂȂ��Ă���s���Y�Ƃ̔��z�́A���̍��ɐ��܂ꂽ�̂��낤�B�܂������ɂ͋����̙�(�g�C��)���ˁA�����̏Z�l���g�������Ȃǂ��݂����Ă����Ƃ�������A�W���Z��̊�b�ƂȂ�C���t���������s���Ă������Ƃ��킩��B
�@
���m�ƒ��l����炷�]�˂́u���Y�n�v�ł͂Ȃ��A����ȁu����n�v�ł���B�e�n����^��Ă���H���A����ށA�����Ȃǂǂ���Ƃ��Ă�����ړI�̕i���肾�B����ɑ�������Ύ���n�k�ɂ���đ�ʂ̌��z�p�ނ��r�o����Ă����Ƒz���ł���B100�����̐l������炷�Ȃ��ʂ̃S�~�������Ă����ł��낤�B�ł́A�S�~���͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă����̂ł��낤���B�]�ˎ���̏����̕�炵���L���������������Ă݂�ƁA�]�˂ł̓S�~���������閄���n���݂����Ă������Ƃ��L����Ă���B
�@
���{���s���ɏo�������G��(���{�̌���)�Ɂu�S�~�������Ɏ̂Ă邱�Ƃ��ւ���v�Ƃ������̂�����B�S�~�̂ċ֎~�̏ꏊ�ɂ́A�����E��E��Ȃǂ��������Ă���B1648�N�ɔ��߂��ꂽ���G�ꂪ�ł��Â����������A����ȑO�̋L�^����������Ă��Ȃ�������������Ȃ��B�Ƃ�����A���{���S�~���̉����Ɏ��g��ł������Ƃ̏ؖ��ł���B1655�N�̂��G��ɂ́A�u�S�~�͑D�ɏ悹�ĉi�㓈�֎̂Ă邱�Ɓv�u�S�~���^�ԑD�̉^���͒��X�ŏ��������S���邱�Ɓv��u�n�悲�ƂɃS�~����D���܂��������߂�v�Ƃ��������Ƃ��L���Ă���B
�@
�D�������S���邱�Ƃ͕ʂɂ��āA���X�̃S�~��D(����͉����)���W�߂ăS�~�̂ď�ɉ^�ԥ������͎����̂����{���Ă��錻��̃S�~����Ɠ����V�X�e���ł���B���{���S�~���Ɛ��ʂ�����g�݁A����グ���s�s��������{���Ă������Ƃ������Ă���B���m��50���l���Z��ł������Ƃ��玩�������̂��߂ɂ��������������K�v�������̂��낤�B
�@
�Ƃ���Łu�S�~�͑D�ɏ悹�ĉi�㓈�֎̂Ă�v�̂��G��ɂ���u�i�㓈�v�Ƃ͌��݂̓����s�]����ɊY������n��̂��ƂŁA�����͋��c��ɉ����đ����̏F������A���ꂪ���̂悤�Ȓn�`�����Ă������߉i�㓈(��)�ƌĂ�Ă����Ƃ����B�n���̒��l�����{�ɐ��肵�A�i��Y�����ɃS�~�̂ď��ݒu���A���ߗ��Ă��n�߂��̂��n�܂肾�B
�@
�����������������Ђ˂肾���s��̃A�C�f�B�A�}���͂ǂ��ɂł������Ƃ������Ƃ��B�������A�킸��3�N��6���̃S�~�����n�ƂȂ�A�S�~�̂ď�͐[��z����(�]����)����Ɉڂ���Ă���B�֑������A�i��Y�����̖����n�ɂ͂̂��ɐ[�썲�꒬�ɂ������ޖؖ≮�̑������ڂ�A�u�؏�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�B
�@
��]�˃E�H�[�^�[�t�����g�ł́A���̂悤�ɖ҃X�s�[�h�ŃS�~�̂ďꂪ���܂�A�����n�ƂȂ��Ă������̂ł���B���{�ɂƂ��Ă̓S�~�̏����Ɠ����ɐV���ȗ̒n���l�H�I�ɒa���������ƂɂȂ邪�A�s�s�ɂƂ��ăS�~���͐������x���ł̑���ł��邱�Ƃ͍]�˂��������{���I�ɂ͓����ł���悤���B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
���]�� ��҂̃Z�[�t�e�B�l�b�g
�@
100���l�s�s�E�]�˂͋���ȏ���s�s�ł��������Ƃ���A�]�˂ɍs���u�d�������邩������Ȃ��v�u�����������L���ɂȂ邩������Ȃ��v�ƍl���A�����̐l�X���������A���̈ꕔ�����h�҂╂�Q�҂ƂȂ�P�[�X������ꂽ�Ƃ����B�ނ����ݓI�ƍߎ҂ƌ��Ȃ��Čx�����開�{�́A���т��сu�����A�_�߁v����ƂƂ��ɁA1790�N�ɂ͐ΐ쓇(���݂̒�����)�ɒ���s�Ǘ����́u�l�����v��ݒu�����B
�@
�����A�_�߂Ƃ́A������M���V���ݔC���ԂɎ哱���Đi�߂��u�����̉��v�v�Ŏ��{���ꂽ����ŁA�n���o�g�̔_�������Ɏ�����^���ċA�_�����A�]�˂���_���ւ̐l���ړ���_�������̂��B�]�˂��N�_�Ɍ���u�����Ȃ��҂͓c�ɂA��v�Ƃ���������Ȑ����A�n�����N�_�Ɍ���Ȃ�Ήߑa��A�l�ފm�ۑ�ł�����B���݁AU�^�[����]�҂�]����]�҂ɏ������Z�܂�(�؉�)��^���鐧�x��݂��Ă���n�������̂����邱�Ƃ��ӂ݂�A���ɂ��Ă݂�����A�_�߂͉���I�Ȑ���ł������Ƃ����悤�B
�@
����̐l�����Ƃ́A���h�l�A���Q�l��ΐ쓇�ɐݒu�����h��ɏW�߁A�X�������鎩���x���{�݂̂��Ƃ��B�u�S���ƉȒ��v�Œm����Εt�������������E���J�약�����V���E������M�ɒ��Ď����������̂ŁA������u�����̉��v�v�Ŏ��{���ꂽ����ł���B����̊Ǘ��҂ɂ͕������A�������A�ȍ~�͒���s���S�����B300�`400�l�̌y�ߐl���3�N�Ԏ��e���A�ނ炪�V���Ȕƍ߂ɑ���O�ɐg�����S�����A�Ȑ������ł̏d�J���������邱�ƂŁA���h�l�ł��邱�Ƃ̕s�������o�����A���h�l������������ړI���������B
�@
�����x���̃v���O�����́A��H�A�����̌P���A�P���y��Ƃ�y�؍�Ƃ̎w����u�`�Ȃǂ��B���݂̌Y�����ōs���Ă���A�H�|�i��Ƌ�Ȃǂ̌Y����ƂƂ悭�����V�X�e���ŁA�J���ɑ���蓖���x�����A�蓖�z�̈ꕔ�������������A3�N�̎��e���Ԃ��I���ďo������ۂɂ͂��̒�������t���čX�������ɏ[�Ă������B�܂��A���e���Ԗ�����A�]�˂ł̏�������]����҂ɂ͓y�n��X�܂��A�_���ɂ͓c���A��H�ɂȂ�҂ɂ͓�����x�������Ƃ����B���̐��x�͌��݂ł����Ƃ���́u��҂̃Z�[�t�e�B�l�b�g�v�ł���A������܂�����I�Ȑ���Ƃ����悤�B
�@
�]�k�����A�l�����͖��{����̉^�c�������s���������߁A���J�약���͖��{���玑������đK����ɓ���������A�喼���~�Ւn��L�͏��l�Ɏ��ޒu����Ƃ��Ē��݂����肷��Ȃǂ��ĉ҂������v��l�����̉^�c�����ɓ��������Ƃ����B�{�݂̉^�c�����ݏo����@�́u�S���ƉȒ��v�ł͕`����Ă��Ȃ����A�����ɂ͕ߕ������łȂ��o�c�҂Ⓤ���Ƃ̎�r���������悤���B
�@
�u�����̉��v�v�ł́A���ݕ}���̐��x�����܂�Ă���B����𗿂�㉺�����̈ێ��o��A����(����@���Ď�����m�点��d��)�A�،˔�(�����ɐ݂���ꂽ�،˂̔Ԑl)�A�S�~����A��ȂǂɎg���Ă��������ߖA����7���ɖ��{����̉�����1����������������u�����ϋ��v��݂��A�ЊQ���̋~�ς�n�V�S�A�艱�Ȃǂ̍w����p�A���H�⋴�̏C�U�ȂǂɎg��ꂽ�̂��B
�@
�����p�ߌ��z��10����7��ϋ��������Ƃ���u�����ϋ����x�v�ƌĂԁB�����݂���������A���X�̐ϋ��Ɩ��{�E�x�T���l(��ɒn��)�̏o���������{�Ƃ��A���̎��̋~�ςɏ[�Ă�Ɠ����ɁA������̐\���ɂ�薼��A�n��A�q�̒n��(����)�֒ᗘ�őݕt������ɐ��x�Ƃ�������B���̑ݕt���x�͂��̗��q�����ɂ���ċ~�ώ����̑������͂�����̂ł��������A�����ɔq�̒����~�̒n��(�������m)���܂ޏ��n��w��ی삷�邽�߂̂��̂ł������B
�@
���{���炷��u���ɐ��x�v�����A���l�����炷��ΖړI�͕ʂɂ��Č��݂́u�ݏ���v�̃V�X�e���Ɏ��Ă���B�����̎��������s����Ă����u����v�ł́A�ǎ��A���S�l�A�����҂�ɕđK���x�����Ă����Ƃ����B����͋~�ϖړI�̌����قƂ������Ƃ��납�B���̒���̐ݗ��ɂ���č]�˂̎s���͕s���̍ЊQ����~��ꂽ�Ƃ����L�^���c���Ă���B
�@
�܂����{�ɂ��~�ς����x���������̂Ƃ��ẮA�Ђ␅�Q�A�n�k�Ȃǂ̔�Q�҂ɕĂ��x��������A�u���~�������v�����āA�Z�܂�������肵�����Ƃ���������B����Ȃǂ͒n�k�ɂ������n��ɒn���s���⍑�����ݏZ������Ă�A���݂̕������x�̋N���Ƃ����悤�B�]�ˎ���ɐ��܂ꂽ�D�ꂽ����̂ЂƂł���B�@ |
���]�� ���h���x
�@
�u�Ύ��ƌ��܂͍]�˂̉v�Ƃ́A���㌀�⎞�㏬���ł悭�������t�����A��100���l����炷��s�s�E�]�˂ɂƂ��āA�Ύ��͓s�s�@�\���}�q�����A�����̐l����D�����˂Ȃ��d�厖�������B���ƂɂƂ��Ă��喼���~���Ă���ƁA�����ɔ���Ȕ�p��������̂ő傫�ȋ��Ђ������B1657�N�̑�ł͍]�˂̒��̖�60�����Ď����A�]�ˏ�̖{�ہE��̊ہE�O�̊ۂƓV����Ă��A�V��͂��̌�A�Č�����邱�Ƃ͂Ȃ������B���҂�10���l�ɋy�Ƃ���Ă���B
�@
3�㏫�R�ƌ��́A6���Έȏ�̑喼16�Ƃ�4�g�ɕҐ�(1���ɂ���30�l�̐l��)����u�喼�Ώ��v�ɏ��h�������s�킹�Ă����B����͎�N��̔z���ɑ�����g�D�ŁA�]�ˏ��喼���~���Ǝ�������A����Γ���Ǝ��݂̏��h�����B4�㏫�R�ƍj�́A1657�N�̑�̔��Ȃ���ŏ��̌��ݏ��h�u��(���傤)�Ώ��v��ݒu�����B4�l�̊��{�Ɂu�]�˒蒆�ΔV�ԁv�𖽂��A�ѓc���A�s���J�A�����̐��A�����ɉΏ����̉��~������A�^�͂⓯�S��t�������A�Ώ��l�����풓�����ĉΎ����N�����炷���o���ł���悤�ɏ��������̂��B���ꂪ���݂̏��h���̌��ł���B
�@
����ł��喼���~���S�̏��h�g�D�ł��������߁A�������Ǝ�������܂łɂ͎���Ȃ������B�����ŁA1718�N��8�㏫�R����g�@�̖������]�˓쒬��s�剪�z�O�璉�������l�̂��߂̖{�i�I�ȏ��h�g�D�Ƃ��đn�݂����̂��u���Ώ��v�ł���B���ꂪ���㌀�ɓo�ꂷ��A�������̔��Z��g�ɂ����u�����48�g�v���B
�@
����s�����h�c�̐ݗ��𖽗߂��A����s�x�z���̌x�@�g�D�u�Ώ��l�����v(�̂��ɉΕt�������Ɠ����B�u�S���ƉȒ��v�̒��J�약��������)�̗^�́E���S�̊Ǘ����ɂ������Ƃ͂����A���Ώ��͖��{����u�����ߋ��v�Ə̂���A�킸���ȋ��z���x������邾���ŁA���Ԃ͒��l����p�����ȕ��S���鎩�q�I�ȏ��h�c�ł������B�u�����ߋ��v�Ƃ́A�Ύ��͂��N���邩�킩��Ȃ��̂ŁA�Ώ��l���͏�������g�̋߂��ɂ���悤���o���֎~����Ă������Ƃ��疽�����ꂽ�Ƃ���Ă���B
�@
���Ώ��̔�p�l�����S�����ƑO�q�������A�������ˈ�˂��܂���ďW�����������łȂ��A�ǂ�����X�̎�l���X�|���T�[�ƂȂ�A�ی��̂���Œ��Ώ��̓��ɂ�����n���A����I�ɔނ�̐����̖ʓ|���݂Ă����悤���B���l��n��ɂƂ��Ď����̓X��݂��Ă��钷�����Ǝ��ŏĎ����邱�Ƃ͑傫�ȒɎ肾�B�Ύ��ɂȂ����Ƃ��ɏ����Ă���钬�Ώ��Ɠ����납��e�������Ă������Ƃ����X�N�w�b�W�ɂȂ������̂��낤�B���݂Ȃ�x����ЂɎx�����K�v�o��̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@
�������Č��Ă݂�ƁA�]�˂̏��h�ʂł̓s�s����́A�傫�Șg�g�݂͊���������A�^�c�͖��ԂɈς˂�Ƃ��������ł������悤���B�܂����l���炷��u�����̐g�͎����Ŏ��v�Ƃ����ӎ��������������̂��낤�B�s�s�����ɂ͍s���ɂ��C���t�������̂��ƂŁA�K�����̃V�X�e�����ێ����郉���j���O�����E�����e�i���X���������܂Ƃ��B���{�����߂��Ȃ��Ă����v�Ƌ��������܂�A��������������Ƃ������Ƃ��B
�@
�Ƃ���ŁA���Ί��������A�����̂���͕����ɂ�����Ƃ�Ό���h�҂Ƃ���������ʼnA���Ă�h���Ȃǂ̔j����h����ł������B�����̏�ɏ�邱�Ƃ����������̂ŁA�Ώ��l���ɂ͓��H�Ƃ��������E���A�����B�]�˒����ɃI�����_����u���f��(��傤�ǂ���)�v�ƌĂ�鏬���ȃ|���v���`���������A�������Ⴍ�����ʂ����Ȃ��������ߏ��ɍv�����邱�Ƃ͏��Ȃ������悤���B
�@
�����͂���Ώ��h�̃\�t�g�ʂ���̃A�v���[�`�����A�n�[�h�ʂł��H�v�͂������B1657�N�̑�����������ɖ��{�́A��������y������Ƃ������h�\�������サ�A��˂̊J���␅�����̐ݒu�𖽂��A�h�ΖړI�̋n�ł���Ώ�(�Ђ悯)�n��ݒ肵���B1723�N�ɂ́A�u�̌��₮��v�̐ݒu���`���Â����A2�l���Ԑl��u�����ƂƂȂ����B
�@
��������y����������シ�邽�߂ɖ��{�͕��ƁE���l�̐g���ɉ����Ė�������10�N�����ŋ���݂����ق��A�����ɑ��Ă�5�N�ԑd�ł�Ƃ����B���݂Ȃ�ȃG�l������n�k�������A����Ή��������ɗL���ȗZ�����s���Z��x�̂悤�Ȃ��̂ł���B����Ȃǂ͋ߑ㍑�Ƃɕs���Ȑ��x�ŁA�]�ˎ���̉���I�Ȑ���Ƃ����悤�B�@ |
���]�� �u���̏��v
�@
�������k���ɏo�Ă���u��������N�O���v�B�N�O���́A�]�ˎ���̎��Ԃ̕\�L���B���x�Ɗ��x�̊Ԃ�2���Ԃ�����ɂ���ɍׂ���4�ɕ����A�N���(2:00�`2:30)�A�N���(2:30�`3:00)�A�N�O��(3:00�`3:30)�A�N�l��(3:30�`4�F00)�Ɛ������B�N�O���͌ߑO3������3�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
���������u���̏��v���s�s����̈�Ƃ��Đݒu���ꂽ�̂��]�ˎ���ł���B���R�̂��ƂȂ����͎��v�Ƃ����T�O���Z������O���瑶�݂����B���{�ł͒�������`�������@���ԗp���Ă������A�]�ˎ���ɓ��{�Ǝ��̂��̂ɂȂ����B�����̎����̎����́u�s�莞�@�v�ƌĂсA���̏o�Ɠ��̓������ɒ��Ɩ�̂��ꂼ���Z�Ɋ����Ĉꍏ(�����Ƃ�)�ƒ�߂��B
�@
���������Ĉꍏ�͋G�߂ɂ���Ē��Z�����܂ꂽ�B
�@
1626�N�A�]�ˏ邩��߂��{�Β�(���݂̓��{��)�ɏ��O�����Ă��A����������炵�Ď�����m�点���̂��u���̏��v�̋N���ł���B�Ί_�̏�Ɏl�{���̘O�����Ă��A��^�̞�����݂邵�A���̎����ɂȂ�Ƃ��̎����̐��̏�(���Ƃ��Ό��݂̌ߌ�6���ɊY��������Z�Ȃ�6��)��@�����̂��B
�@
�悭�����������Ȃ̂��̌��₮��B������͏��h�⎩�q�̂��߂ɒ����Ƃɒu���ꂽ�l��(�ԉ�)�ɏ풓����Ԑl�����S�̂����n����悤�A�ԉ��ɘE��g��ň�i�����ꏊ�ɒu����������ŁA�Ύ���^�������������Ƃ��ɔ�����炷�ꏊ�ł�����B���O�͏��h�ɂ͎g��ꂸ�A�����܂ł��u���̏��v��@���ړI�̂��߂����ɐݒu���ꂽ���������B����ڔ��s���ɂ��ݒu���ꂽ�̂ŁA�����̞����ɂ������邪�A���@���Ǘ������킯�ł����l�̎���Ǘ��ł��Ȃ������B����͌�q����B
�@
�{�Β��ɏ��O�����Ă���ȑO�͍]�ˏ�ő��ۂ�炵�Ď�����m�点�����A�������ɍ]�ˎs���ɂ͓͂��Ȃ������悤���B���̌�A�A���A�łȂ�9�����ɏ��O�����Ă��A�������̉��������[���Ď���m�点���Ƃ����B�]�˂̊X��g��ƂƂ��ɁA�u���̏��v�̐��������A�ŏI�I��15�����ƂȂ����B���Ŏ�����m�点�鎞�v����]�˂�15�ݒu���ꂽ�Ƃ����킯���B
�@
�u���̏��v�͍]�ˈȊO�̏鉺���⋞�s�A����Ȃǂ̓s�s�ɂ��ݒu���ꂽ�B
�@
���O�̉^�c�͈ӊO�Ȃ��Ƃɒ��l�ł͂Ȃ��A���{�̊Ǘ����ɒu����Ă����B���O�̐ݒu�ꏊ�A�u����K�v�̒����z�A�����͈́A���O�̌��݁E�C���A����炷�����̌��ȂǁA���ׂĊNJ��̕�s���̋����K�v�ł������B����K�Ƃ́u���̏��v�̉^�c��̂��ƂŁA���̏�����������͈͂ɂ��钬�̏Z������1���ь��z�K4���������B�����Ȃ�u����Łv�Ƃ������Ƃ��납�B�����͖��Ց����ɂ�鐢�P���ŁA���{���������҂����̎d���ɏA�����Ƃ����B���P���̌������̂悤�ȐE��ł���B
�@
�������Ė��{�́u���̏��v�Ƃ����s�s�����Ɍ������Ȃ��V�X�e��������A�Ǘ������Ƃ����B�]�˂̐l�X�͂��̐���̂��ƁA���ꂵ��������m�ɂ���Đ������c��ł����̂ł���B����͕��Ƃ⒬�l�ɓ��ꂳ�ꂽ���Ԃ̔F�����K�v�ɂȂ������Ƃ���Ă���B�������ɏ����������͂Ȃ����A���̋ߑ㉻�ɕK�v��OS�̂悤�Ȃ��̂ł���B����R���c�F�����₻�̎x�В��̂��Ƃœ����T�����[�}���ł��镐�Ƃ́A�]�ˏ�֓o�邷�鎞�Ԃ����߂��Ă��������ɐ��m�Ȏ��Ԃ�m�邱�Ƃ͕s���ł������B�܂����l�ɂƂ��Ă��[�i�̎��Ԃ�d���̏I���̎��Ԃ�m�点�Ă����u���̏��v�͏d�v�ł������Ƒz���ł���B
�@
�]�˂ł͖،˂�߂鎞�Ԃ����{�ɂ���Č��߂��Ă����B����͋�������ɑ���h�Ə�̐��B�����ɖ،˔ԂƌĂ��{�݂��݂����A�،˂̌�����������B�s�R�҂ɓ���Ȃ����߂̍H�v�ł���B�،˂͖�̎l��(�ߌ�10��)��m�点��u���̏��v���ĕ�����A�ȍ~�͍��E�̐��˂���ʍs�������B���̍ۂɂ͕K�����q��ł��āA���̖،˂ɒʍs�l�����������Ƃ�m�点���Ƃ����B������u���̏��v�V�X�e�����@�\���Ă��Ȃ���ł��Ȃ��d���ł���B�@ |
�������s�����d�G�̉ݕ�����
�@
�]�ˎ���̌o�ϐ���Ƃ����A�܂������ƔN�v���̃A�b�v���v�������Ԃ��낤�B�O�҂͉ݕ����x�A��҂͐Ő��̕���ƂȂ邪�A���҂͕����̕ϓ��A�D�s���ƘA�����Ă���B�]�ˎ���̕����́A��ɕĉ��ƘA�������B�N�v�Ď����Ɉˑ����開���Ƃ��Ă͕ĉ����ő�̊S���ł������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B�ĉ�����������Ə����͍������邪�A�Ă��������Đ�����ɂ��Ă镐�m�͏����B�ĉ���������Ə����̐����͊y�ɂȂ邪�A���������ቺ����̂ŕ��m�̐����͋ꂵ���Ȃ�B�ĉ���������A�������オ��ƁA���m�ɂƂ��āu�����͌��邪�A�x�o�͑�����v�Ƃ����ň��̎��ԂɂȂ�B�܂�A�ĉ��͕��m�Ə����̈בփ��[�g�������̂ł���B
�@
�ĉ����ᗎ���͂��߂��̂́A�u���ޗ��݂̗߁v�Ŗ������ܑ㏫�R�j�g�̍����B�l�㏫�R�ƍj�̎���ɁA�]�ˏ�V��t�Ǝs�X�̂قƂ�ǂ��Ď����A���҂�10���l�ɂ��y�u����̑�v���N�����B���̂��ߍ]�˂̕������Ƃɔ���Ȏ�����������ꂽ�B�܂��A�O�㏫�R�ƌ��܂ő������A�e�n�̋��R�E��R�ɂ�����u�S�[���h���b�V���v���������������ł��������B����ɉƍj�̑����A�j�g�̏��R���ʂŏo������݁A�����čj�g�̕�E�j���@�ƍj�g�����Ђ̐V���z�ȂǂŘQ������ƂŖ��{�̍����͐Ԏ��ɓ]�����Ă����B
�@
�����ō������Ē����̂��߂ɉݕ��������s��ꂽ�̂��B�����̊����s�͉����d�G�B�����Ԏ��s����Ă��Ȃ��������n���l�㏫�R�ƍj�̑�ɍs���A���P�㊯���̕��Q������l�����B���R�̍��ɂ�������̍j�g�͉����̒�����A���P�㊯����|���A������@�ɑ㊯�̊��������n�܂�B�o���X�����̂ڂ�͂��߂������́A���ɍ��n��s�ɔC�����A���Y�ʂ���������ł������n���R��r���a�̌@��ɂ���čĐ�������B�܂����n�̑�K�͌��n�ɂ����肵�A�N�v������8���A�b�v������B����������r���F�߂��A�����͊����s�ɏo�����A�j�g����o�ϐ������C���ꂽ�B
�@
�����͑啝�ȍ����Ԏ�����E�o���邽�߂ɁA�s���ɗ��ʂ���ݕ��ʂ̑����ڎw���āA1695�N�A�c��������������A���ܗL�ʂ����炵�����\������������B�������炷��ΓV�˓I�Ȕ��z�ł���B�ƍN�̂��������݁A��݂�������āA�����̊ܗL�ʂ����炵�ĉݕ��𑝂₹�A���₵�����͖��{�̎����ɂȂ�B���̎��̍��v�͋���450�����A���456�����B���v��1000����(2���~)�Ƃ�500����(1���~)�Ƃ������Ă���B�c�����������s����Ă����100�N��̂��Ƃ�����A�o�ϋK�͂͑傫���Ȃ�A������Ɏg����ʉ݂̎��v�͍��܂��Ă����Ƒz���ł���B��������z���ė��ʂ���ʉ݂̗ʂ𑝂₷�̂́A�o�ς���蔭�W�����邽�߂̂ЂƂ̕���ł���B�������C���t���Ƃ�������p���������Ƃ́A�o�ςɐ��ʂ��������Ȃ猩�ʂ��Ă������Ƃ��낤�B
�@
���̌o�ϐ���̕]���͓�ɕ������B�ЂƂ͉����ɂ��o�ς��������A���������������̂Łu�����͎���v�Ƃ��������B�����ЂƂ́A�C���t�����͂��قǃA�b�v�����A�����̐����ւ̉e���͏��Ȃ��������̂́A���Ǝ��{�ƕx�T�w���X�g�b�N���Ă�����ʂ̌c������̎����w���͂��ቺ���A���{�͉������v���ɂ���č����Ԏ����k���ł����Ƃ����]�����B
�@
���j���ɂ́A���\����͐퍑����ȗ��̌o�ϔ��W�����Ƃɏ�������������������𐋂��A�l�X�ȕ���(���\����)���ԊJ��������ƋL���Ă���B���̈���ŁA�o�ϐ����̎����猩��A���x�o�ϐ������Ђƒi�����A�ᐬ���ւƈڍs�����]�����Ƃ�������B���\�̉����́A������Ƃ�����薋�{�̍����Ԏ���₤���߂ɗp����ꂽ�o�ϐ������B
�@
���������A���{�͌o�ϊ�������Ƃ��Ď��Б��c��y�ؕ����ȂǁA�l�X�Ȍ������Ƃ�W�J���Ă���B�P�C���Y���_����肷��悤�Ȍo�ϐ��B���̔g�ɏ�����̂��A���̗L���ȋI�ɍ��������q��(�I��)�ƍޖ؏��E�ޗlj����q��(�ޗǖ�)���B���ɋI�ɍ����͓����̘V���E����g�ۂ⊨���s�����d�G�ɘd�G���Đڋ߂��A�p�������]�˂̉Ύ��ɂ��Č��H���������Ƃ���Ă���B�ނ�͖��{�̌������Ƃ𐿂��������Ƃŋ��z�̗��v���̂ł���B����͌��݂ɂ��ʂ���A�o�ϐ���̕��̑��ʂł���B�@ |
���]�˒����̉ېŐ��x�ƕ����㏸
�@
�ܑ㏫�R�j�g�̎���ɕĉ����ᗎ���͂��߂��v���͕Ă̐��Y�ʂɂ������B���{�⏔�˂́A�ā��u���v���ێ��A���邢�̓A�b�v���ׂ��V�c�J���ɗ�݁A�܂��_�ƋZ�p�����サ�����ƂŕĂ̐��Y�ʂ������Ă������B�]�ˎ��㏉���ɐl�������������Ƃ͂����A�����v������������ΕĂ͗]��B
�@
�Ă��]��Εĉ��͉�����B���{�̍����̂����傾���������́A�Ă��ċ��Ɋ����邱�Ƃ������̂ŁA�ĉ���������Γ��R�����͋ꂵ���Ȃ�B����ɕĈȊO�̏��i���l�オ�肷��A�C���t���ɂ����������͌����߂Ȃ��B
�@
����ɒǂ��ł���������悤�ɁA�]�˂ő�A�֓��Ō��\�n�k�A����C�ŕ�i�n�k�A������̍^���ȂǑ�ЊQ�������A���{�̐Ԏ������͌���Ȃ������B�j�g����̊����s�E�����d�G�́A���{�V�̂̍��n���R�̃e�R������S���̎𑠂�50���̉^����������Ȃǂ��Ď����̑����ɓw�߂��Ƃ����B
�@
�^���Ƃ͔_�ƈȊO�̏����ɂ�����ŋ��A�c�Ɛł̂��Ƃ��B�E��ɂ���Ċz�͌��߂��Ă����B���Ƃ��ΐ��Y���̉^����S���D���ĉ^���Ƃ��n�߂�ꍇ�A���̑D���łȂ��A�^���ƂƂ����E�펩�̂Ɍ��߂�ꂽ�c�Ɛł��K�v�������Ƃ������Ƃł���B����͏������c�ނ��߂̊ӎD���ƍl����Ƃ킩��₷���B���Ƃ��Ə��X�͓X�̊Ԍ��ɉ��������ʑK������Ă������A���l����Ǝ҂͂���ɉ����A���D(���ƊӎD)�����Ƃ����X�^�C���ʼn^����[�߂��B
�@
�L�^�Ƃ��Ďc���Ă�����̂����ŁA��X���D�A���X���D�A���X���D�A���≮�D�A�����D�A�ݖ��葢���D�A�ݖ��ה��D�A�����D�A�����D�A�D�A�b��D�A���X�D�A�P�D�A���ԉ��D�A�|�؏��D�A�|�H���D�A�����D�A���ĎD�A�Y�������D�A�ޖؖ≮�D�A�|�葢�D�A���菤�D�A�����l�h�D�Ȃǂ�����B����|�A���ȂNJ�������Ǝ�E�ƑԂ��@���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
�@
�^�p��͏��˂ł��̗p����A���Y���̐��Y�ɂ������҂��ېł��ꂽ�Ƃ����L�^���c���Ă���B���Ƃ��]�ˎ���ɔ엿�Ƃ��ďd�p���ꂽ����(�ق���)���B������ʂ����J�X�ŁA������(���݂̑啪��)�̕l�Ő��Y���ꂽ����͓��Y�i�������B�Ȃ͔̍|�Ɍ��ʂ�����ƕ]�����ĂсA���S���s��Ŕ̔������悤�ɂȂ�ƁA�����˂͂����ɖڂ����A���Y�Ɨ��ʂ̗��ʂ��痘�v�悤�Ƃ����B����Y���銱�l�ɉ^���������A�����̈���l��ԁA���D�ɂ��ŋ����ۂ��A����ɋ��l�ʂɉ����ĉېł����Ƃ����B�����˂ł͑D�ɑ��Ă��u�D���v�Ƃ����ł��ۂ��Ă���B
�@
�e�˂̉^���̒����̎d���͂������B�˂̎w�肷�锻���ɐŋ���[�߁A�����Ŏx�����ς݂ł��邱�Ƃ��L�������Ђ����炤�B�[�ł������Ƃ��ؖ����邽�߂Ɂu���v�����������Ƃ��画���ƌĂꂽ�悤�����A���̔��͎����̂悤�ȑ��݂ł������Ƒz���ł���B�����͌��݂Ȃ�Ŗ����h�o���Ƃ������ʒu�Â����낤�B
�@
���āA�]�˒����̕��������A���\���ォ�畨���͏㏸�𑱂��Ă���B���\�������ԊJ���A�ŋ��╂���G�A�s�y��ԉȂǂ̃G���^�e�C�����g������ɂȂ������Ƃ��l����ƁA�����̐������������サ�����Ƃ��킩��B���Ƃ����������A�����̏������o�ϊ����Ɋ֗^����悤�ɂȂ�ƁA�ݕ��͊����ɗ��ʂ���B�����Ő����֘A���i�̎��v������������悤�ɂȂ�B
�@
�����������͂܂��@�B��Z�p�͓�������Ă��Ȃ��̂ŁA���Y�ʂ͋}�ɂ͑����Ȃ��B�i�s����������B����ɏ悶�ĕs���ȗ��v�悤�Ƃ��ĉ��i�̒l�グ��}�铮�����n�܂������Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B����͏��l�����������Ȃ������Ƃ����߂ł��邪�A���l�������g���ĉc�Ɗ������J�n�����Ƃ����͂ł���B�������������Ƃ͗����������邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă���̂ŁA�����K���i���s����������̏��i�������̔����悤�ƍl����͓̂��R�̗���B�����畨���͏オ��B
�@
�����㏸��}���邽�߂̐V���Ȑ��o�ꂵ���͍̂j�g�̎���A��10�N��̂��Ƃ��B�u���\�o�u���v���e���A���{�͂��͂☥����ō������^�c�ł��Ȃ���@�ɖʂ��Ă����B�����ɓo�ꂵ���̂��I�ɔˎ傩�珫�R�ƂȂ����g�@�ł���B�g�@�����s�����u���ۂ̉��v�v�͖������v�ł���Ɠ����ɏd�v�Ȍo�ϐ��܂܂�Ă����B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
���V�䔒�̌o�ϐ���ƋI�ɔˎ�E����g�@�̎���
�@
�]�ˎ��㒆���A�ܑ㏫�R�E�j�g���玵�㏫�R�E�ƍj�Ɏ��鎞��́A���{�������Ԏ��ƕ����㏸�ɋꂵ�߂�ꂽ�������B���{�ŏ��̉���(���\����ƕ�i���₠�킹��2500����)�ɂ���Ĉꎞ�I�ɍ��v�{�ɂ����炵�������s�E�����d�G�͘Z�㏫�R�Ɛ鑤�߂̐V�䔒�ƃ\�������킸�A�V��́u�������㏸�����͉̂����̖���v�u���l����d�G��������Ă���v�Ƃ��������e�̏�\����Z�㏫�R�E�Ɛ�ɒ�o�����Ƃ����B�����͎��Б��c��y�ؕ����Ȃnj������Ƃ̔����ɂ�����A�I�ɍ��������q��(�I��)����d�G��������Ă����Ƃ����L�^������̂ŁA�V��̎w�E�͂��Ȃ����ԈႢ�ł��Ȃ������悤���B������ǂ����Ƃ����V�䔒�́A�ݕ��̊ܗL�ʂ����ɖ߂��悤�咣���A�j�g�̎���ɔ��s���ꂽ����(���\����)��������A��������s����B�s��̉ݕ��ʂ����炷���߂ɉݕ��̏��x�����ɖ߂��Ƃ������B�������A�����ʂ�21�����Ə��Ȃ��A�s��ւ̉e���͂͂Ȃ������B
�@
�V�䔒�����s��������Ɂu�C���ݎs�V��v������B����͍��ۖf�Ղ𐧌����邽�߂ɐ��肵���@�߂��B�V��͍����ʉݗʂ̂�������25���A���75�����C�O�ɗ��o�����ƌv�Z���A����f�Ղɂ�����A�o�K�������{�����B���̐���̈Ӑ}�͋���̗��o�ɑ���h�q��ł���ƂƂ��ɁA���Y�i�̐��i�܂�Y�Ƃ̊������ɂ������B�A���i�̃��C���́A�ȕz�A�����A�����A���D���Ȃǂ������B��������Y�i�ł܂��Ȃ��悤�ɓ]�����悤�Ƃ�������ł���B�܂��j�g����̕����ȍ������o���������߂�ړI���������̂��낤�B����ł��A�����㏸����É����錈��I�Ȍo�ϐ���Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ������B���R�̌��͂͐��ނ��A���b�ɂ����镈��h�ƐV�Q�h�̑Η�������A�������v�͐i�܂Ȃ������B
�@
�₪�Ă܂��c�����㏫�R�E�ƌp���a���B�㌩�l�ł������g�@�����㏫�R�ƂȂ�A�V�䔒�����J���A�u���ۂ̉��v�v�����s����킯�����A���̑O�ɋI�ɓ���Ƃ��珉�̏��R���}����ɂ�����A�g�@�̉��������]�����ꂽ�̂��A���̎�r�����Ă������B�I�ɔ˂́A�����O�Ƃ̂ЂƂI�B����Ƃ��ˎ�Ƃ��Ď��߂�e�˂��B�ƍN��10�j�E���邪����ˎ�ŁA�ނ̑��ɂ�����g�@�͋I�ɔˌܑ�ˎ�ł���B�̂��ɔ��㏫�R�ƂȂ�A�u���{�����̑c�v�Ƌ���邪�A�g�@�͋I�ɔˎ厞�ォ�琭����r�����Ă����B������ς���A�I�B�˂Ő���������@���ł��g�����Ƃ������Ƃ�������B
�@
�Z�ł���O��E�l��ˎ傪�������ŖS���Ȃ������Ƃ���A�g�@��22�ŋI�ɔˎ�ƂȂ����B�����̋I�ɔ˂́A�]�˂̑�ŏĎ������]�ˉ��~�̍Č��A���R�̖K����}���邽�߂̐V��a�̌��݁A�������ő��E�������ˎ�̑��V��p�Ȃǂ��d�Ȃ�A������ɒ��ʂ��Ă����B����ˎ嗊�邪���{�������ꂽ��10�������������̂܂c���Ă����B�ǂ��ł���������悤��1707�N�ɂ́A�n�k�ƒÔg���I�B��݂��P���A�傫�Ȕ�Q�����܂�Ă����B
�@
�g�@���I�ɔˎ�Ƃ��Ď��s���������̗��Ē�����́A�ː��@�\�̊ȑf���Ǝ��f����̓O��ł������B�ƕ��ɂƂ��ꂸ�L�\�Ȑl�ނ�o�p���A�����̈ꕔ��˂ɍ����o���u������v�ƌĂ��X�^�C���ɂ���ĉƐb�̋�����������J�b�g���A���X�g��(��80�l�̉Ɛb������)�ɂ���Đl�����ߖ��B���������������J�b�g��X�g�������s����ƁA�Ɛb�̕s������������̂����̏�Ȃ̂ŁA�g�@�͘a�̎R��̖�O�Ɂu�i�ה��v��݂��A�s�����z�����A�����ɉ��v�̒�Ă������B���ꂪ�̂��́u�ڈ����v���x�̋N���ł���B
�@
���̈���ŁA�g�@�͐������Ƃ�V�c�J���ɂ���ĕĂ̑�����}��A���Y�i(�݂���A�ޖA�ݖ�)�̘̔H�̊g������݂��B�������Ė��{����ؗp���Ă���10������ԍρB���݂ɒu��������Ȃ�A�V�m�����{���⌧���Ƀ��X�����A�E���̃��X�g�������s���A�����̎��v�A�b�v�ɐ��������Ƃ������Ƃ��B�����������ˎ�Ƃ��Ă̎��т������ċg�@�͏��R�ɂȂ�A�u���ۂ̉��v�v�����s����̂ł���B�@ |
���u���ۂ̉��v�v����Ƒ���
�@
���㏫�R�E����g�@�͍ݔC����(1716�`1745�N)�ɑ����̐����ł��o���A�]�˖��{�n�܂��Ĉȗ��ł��傫�Ȗ������v�𐋍s�����B�N������u���ۂ̉��v�v�ƌĂ�Ă���B�ڂ������ׂĂ݂�ƁA�u���ۂ̉��v�v�͑O��(1716�`1730�N)�ƌ㔼(1730�`1745�N)�Ƃł͓��e���قȂ�B�O���ɐ��s�������v���邢�͎�����Ȃ�����������㔼�ŏC�����A�]�������݂��̂ł���B���̒����������@�ɒ��ʂ��Ă������{���~�����߂Ɏ��s���ꂽ��������𒆐S�Ɍ��Ă������B�����͍j�g���Q���ĉ��̉����Ő������u���\�o�u������̌�n���v�Ƃ������ʂ������Ă���B
�@
�g�@�̍�����������O�ɐl�ޓo�p�ɂ��Đ������Ă������B��������v�̂ЂƂŁA�����v�����s����ɂ�����g�@�͑O�������ʼne���͂̂������V�䔒����C���A�V���Ȑl�ނ�o�p�����B������ς���Ώ��R�̑��߂��������i�鎞�オ�����A���R�����\�Ȗ��_�E�ƂȂ��Ă����̂������Ƃ������Ƃ��B���݂ɒu��������Ȃ�A������b�ł͂Ȃ��A�e�Ȃ̖�l���A�ő�����b�𑀂��Ă����悤�Ȃ��̂ł���B�g�@�͏��R�A�C�̗��N�A�������������鏟��|�V���ɋ��s���i��̐��쒉�V��C���B����́u���ۂ̉��v�v�̑O�����x���������b�ł���B���N�A�剪����(�剪�z�O)��s�ɔ��F���A��s�]�˂̉��v�Ɠs�s����ɒ��肵���B�剪�͂��������蓌���s�m�����ō��ٔ����������@����b�Ƃ������|�W�V�������B
�@
�g�@�̐l�ޓo�p���x�́u����(��������)�̐��v�ƌĂ��@�߂Ɍ����ɂ�����Ă���B�]���̊e��E�͊�̐������Ă��Ȃ��ƏA�C�ł��Ȃ��������A��̘\��(���^)�ȉ��̎҂���E�ɏA�C����ۂɍݐE���̂ݕs�����Ă����(��)��₢�A���̐E��������Ό��ɖ߂��Ƃ�������I�Ȑ��x�ł���B�\�͂͂��邪�ƕ����Ⴂ���߂ɗv�E�ɏA���Ȃ��Ƃ����l�ނ̃~�X�}�b�`���������邱�ƂƁA��E��ޔC����ΐ��͋����̊z�ɖ߂邽�ߖ��{�̍������S���y���ł��邱�Ƃ������b�g�ł���B���݂Ȃ�u�\�͎�`�v�̗̍p�Ɛl����A�b�v�̗}�����Ɏ��s����悤�Ȃ��̂ł���B
�@
�����������g�@�̍l�����ɂ���ėv�E�ɓo�p���ꂽ�l���Ƃ��Ė������̂��剪�����ƁA�g�@�������Ɋ����s�Ƃ���煘r���ӂ邤�_���t��(�͂�Ђ�)���B�܂��A�g�@����ɋI�B�˂̑��y������{�ɓo�p���ꂽ�c���ӎ��́A�\�㏫�R�E�Ǝ��̎���ɘV���܂ŏo������B���Ԑl�ł́A������p���̉��C�H���ō˔\�������c���u��������B�c���͉͐�Ǘ��̐ӔC�ҁu�쏜�䕁����p(����悯���ӂ��悤)�v�Ƃ��Ė��{�̎������ƂɌg������B���ԓo�p�́u������b�v�ł���B
�@
�ł́A�g�@�����s����������������Ă������B�܂���������̂��u����߁v�߂��ď����}���邱�ƂƑ��ł��B������@���������邽�߂Ɂu�x�o�����Ȃ����A�����𑽂�����v�Ƃ́A����������O�̂��Ƃ����A����𐧓x�������̂͋g�@�̎�r���B���������f����͗��n�̌��ŁA������ӎ����邱�ƂŖ��{�̘�����͐����ł��邪�A�����g��ɂ͂Ȃ���Ȃ��Ƃ����}�C�i�X�v�f������B����ӗ~�����ނ����鐭��́A�g�@�����݂����v�̂�����ʂɂ�����Ă���B
�@
�g�@�͔N�v�����̑����}�邽�߂ɉ͐�~��R�т܂ł��܂ދ����ȐV�c�J�����J�n��������ŁA�N�v�����u�l���Z���v�u�O�������v����u�܌��ܖ��v(���n�̔�����N�v�Ƃ��Ĕ[�߁A�c��̔�����_���̂��̂Ƃ���)�Ɉ����グ���B���Ńv�����Ƃ��Ĉ����ԔN�v���Œ肵���X�ɐ芷���đ��z����u���(���傤�߂�)�@�v�����s�B����ɂ͏o�����̂������N�̍Đ��Y�������c���Ă��ׂĔN�v�Ƃ��Ē�������u�L�ь�����(���肰���݂ǂ�)�@�v�Ȃǂ̐V�Ő����̗p���A���{������啝�ɑ��傳����B
�@
�g�@�����s�����u�ɂ݂��\�����v�v�͂܂��_�����]����������ꂽ�悤���B�������V�c�J���ɂ���ĕĂ�������Εĉ�������ɉ�����A���m�͐������ꂵ���Ȃ�Ƃ���������������B�g�@���ĉ���ɒ��肷��̂͏��R�A�C���Ԃ̌���̂��ƁB�ĉ���͉��߂Đ������邪�A�g�@�����łɗ͂𒍂������Ƃ���A���v�̗D�揇�ʂ͍��������ɂ��������Ƃ��悭�킩��B |
���u���ۂ̉��v�v��Ă̐��ƒ�Ɩ@
�@
�g�@�����߂Ď��{�������Ńv�����u���(���傤�߂�)�@�v�́A���{�̎��������肳���邽�߂̔N�v�����@�ł���B�]���͔N���Ɏ��n�ʂ����Ă��炻�̔N�v�ʂ����߂Ă������A��Ɩ@�͉ߋ����N�̎��n���̕��ς���N�v�������߂�V�X�e���Ȃ̂ŁA�L��E����ɂ�����炸���̔N�v��[�߂邱�ƂɂȂ����B����̔N�͔N�v�̑啝�����F�߂��邱�Ƃ��������Ƃ����B�ߋ����N�̕��ς��L��ł���Δ_���͔N�v�ʂ�����̂Ń����b�g�����邪�A���ۂɂ́u���ۂ̋Q�[�v�������A�L��͊���Ȃ������B�Q�[�͔���Ȃ��Ƃɖ��{�ɂƂ��Ă͈��肵�������������炷���ʂƂȂ����B
�@
���̐���ɂ͓�̑��ʂ�����B�ЂƂ͔_���ւ̍�悪�������Ȃ������ƁB���̎����ɈꝄ�������Ă��邱�Ƃ���_���̕s�����������Ƒz���ł���B����͗��j�̋��ȏ����L�������ł���B�����ЂƂ͎��n���𑝂₷�w�͂�����A�_���̗��v�͑�����Ƃ��������b�g�ł���B���Ɏ��n�̔�����N�v�Ƃ��Ĕ[�߂��Ƃ��Ă����Y�ł���Ă̐�Ηʂ������Ă����Η]�肪������Ƃ������ƂɂȂ�B�s���ޗ��́A���Ƃ�E���E�^���E�䕗���B�_�Ƃ̓��X�N�ɖ������E�ƂƂ����邾�낤�B
�@
���̂ق��g�@�����݂����x�Ɂu���(�����܂�)�̐��v������B����͕Ă�[�߂錩�Ԃ�ɑ喼�̎Q�Ό��̍]�ˍݏZ�̊��Ԃ������鐧�x���B���{�͑喼�Ɉꖜ�ɑ��ĕS�̕Ă�[�߂������B�e�n�̑喼����W�߂��Ă͖��{�̑����ɍv���������A���{���ꂽ�̂�1722�`1730�N��8�N�Ԃɉ߂����A�蒅����ɂ͎���Ȃ������B�喼�ɂƂ��Ă͏�[�Ă������o���]�ˑ؍ݔ�����ƂȂ�̂ŁA�]�˂ł̑؍ݔ�����������͂��B���̎��x���v�Z���Ă݂�A�����̉Ɨ���A��č]�˂܂ōs�����n���̑喼�ɂƂ��Ă͑؍ݔ���������ق������肪�������Ƃ������̂�������Ȃ��B
�@
���ۂ̉��v�̎d�グ�����ɂ́A�N�v�����𐄐i���������s�̐_���t����煘r���ӂ�����B�u�Ӗ��̖��Ɣ_���͍i��i��قǏo����̂Ȃ�v�ƌ��������ƂŖ������l�����B1744�N�ɂ͎��璆���n���ɕ��C���ĔN�v���̋����A�o�L���ꂸ�N�v�ݒ肪����Ă��Ȃ��B�c�̓E���Ȃǂ��s�����B�_�������Ă����u�L�ь�����(���肰���݂ǂ�)�@�v���̗p����˂��������B����͖��N�̍앿�A�o�����ׂĔ_���̗]�\���������Ȃ������Ō^�̉ېŖ@���B����ɉېł̑Ώۂł͂Ȃ������͐�~��R�т��u�V�c�v�ƌ��Ȃ��ĔN�v���ۂ����Ƃ����L�^���c���Ă���B
�@
����߂Ƃ����������ߍ��ȉېł����킳��A���{�̔N�v������167���ɑ������B����ɋQ�[����Ƃ��ď��喼�ɑ݂��t�������������1742�N�ɂ͊��[�������B�������������A����ɂ���āA���ۂ̉��v�̖����ɂ́A���{�̎�����180���ɂ܂ŏオ�����B���̐��͍]�ˎ����ʂ��čō��L�^�ł���B���{�̍������Č�����Ƃ����ڕW�͒B������A�g�@�͖����R��搂�ꂽ�킯���B
�@
�������A�����ЂƂ̑傫�ȉۑ�ł���ĉ��̈���A�܂蕨���̒����E����͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă����̂ł��낤���B�ĉ��ܑ͌㏫�R�E�j�g�̎��ォ�牺���������A�ĉ������̂܂����ɔ��f���镐�m�͑傢�ɍ������Ă����B
�@
1730�N�ɔ������ꂽ�u����(���킹�܂�)�߁v�́A���{���s��̕Ă��グ�Ē������A�ĉ��̈����グ�𑣂��@�߂��B���˂�L�͏��l�������I�ɏ]�킳�ꂽ�B����͎s��ɗ��ʂ���Ă̗ʂ����炵�ĕĉ��������グ�A���m�K�����~�ς��邱�ƁA�ނ�̍w���͂����߂Či�C��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�܂��A�Q�[�ɔ����Ă���~���Ă����͕Ă����サ�A�s��ɕĂ��o�܂��Ȃ��悤�����A���˂ɑ���]�ˁE���ւ̉��āE�����~�̕Ĕ��p�̐����E�֎~�Ȃǂ̑[�u�����ꂽ�B�Ă̗��ʗʂ�����Εĉ��͏オ��B����ĕ��m�K���̎����͏オ��B�Ă̗��ʗʂ��R���g���[�����悤�Ƃ������{�̑_���́A���̈�_�ɏW�����Ă����B�@ |
����������̂��߂̊����Ԃ̌��F�Ɛݗ����i
�@
�ĉ������ƕ������ɑΏ����邽�߂ɓ���g�@�����s�����̂������Ԍ��F�Ɗ����Ԑݗ��̐��i�ł���B1721�N�A���{�͍]�ˎs���̂����鏤�l�E�E�l�ɓ��ƎҒ��Ԃ�ϋɓI�Ɍ������邱�Ƃ𑣂��@�߂����B�����A�k���ɂ�鉿�i���삪�����㏸�̂ЂƂ̌����ɂȂ��Ă������炾�B
�@
����̒��g���Љ��O�Ɋ����Ԃɂ��ď����������Ă������B���Ƃ��Ƃ͓��Ƃ̖≮�ɂ�邲�����I�ȃO���[�v�ł������B�����̂ڂ�A�M����G�g�����i�����u�y�s�y���v���N���ƂȂ�B�e�n�̐퍑�喼���L�����鉺���ɂ́A�V�����Ǝ҂��琬���A�o�ς̊�������}��ړI�ŁA�ł̌��ƂȂNjK�����ɘa���ꂽ�u�y�v�Ȏs�ꂪ���܂ꂽ�B����ΐ퍑�喼���z�����u�o�ϓ���v�ł���B�M�����z�����ߍ]���̈��y�Ƌ��X�̊y�s�y���́A�̂��Ɂu�ߍ]���l�v�ݏo���y��ƂȂ����B
�@
�]�˖��{���y�s�y���H�����p���������̂́A�≮�Ǝ҂����������ƂŁA���Ǝґg�������R�������A�₪�Ĕނ炪�J���e�����`�����A���i������s���悤�ɂȂ��Ă����B�������L���邱�ƂŃ����o�[�Ƃ��ĔF�߂�ꂽ���Ƃ��犔���ԂƌĂꂽ�B���͋��K�ɂ���Ĕ������ꂽ�B�]�k�����A�͎m�����ތ�����{���o����Ɏc���āu�N��v�ƌĂ��g���ƂȂ�A�告�o�̔��W�̂��߂ɓ����ۂɕK�v�ƂȂ�؏����u�N�v�ƌĂԁB�������i��1���~�Ƃ�2���~�Ƃ�����Ă��邪�A���̃V�X�e��������܂Ōp������Ă��銔���Ԃ̂ЂƂƂ����悤�B
�@
���āA�]�ˎ���̏��Ƃɖڂ��ڂ��Ă݂�A�≮���C�j�V�A�`�u�������Ă���A��ɗA���E�ۊǂ�S���Ă����B�嗬�́A�傩��ϑ����ꂽ�ו���̔����Č��K(�̔��萔��)�Ƒq�~��(�ۊǗ�)���≮�ł���B
�@
����ɑ��Ď��Ȋ���Ŕ�������d���≮�����W���A�ޖA�āA�d�A�Y�A���A�|�Ȃǎ戵���i�ʂɕ������Ă������B���ł́A���i�̎Y�n���Ƃɐ�剻������≮�ł��鍑�≮�����܂�A����𒆐S�ɏ��i�ʂɐ�剻�����d���≮���S�̗��ʑg�D�ւƓ]�����Ă������B�����̖≮�����Ǝґg��������A�����o�[�̐��E���A�������ƂŒ��ԂɎQ�������̂ł���B
�@
�����Ԃ͋��K���̕ۏ̋@�\�����悤�ɂȂ�B�≮�̎���̑������M�p����A�܂菤�i�������n������A�u�ߋG�����v��u��G�����v�ȂLj����Ԃ��o�Ă������͌��ς��ꂽ�B�����Ԃ̖≮����ƒl�i�����߂čw�������ו����͂����Ȃ������ꍇ�A�����ԑS�������̉�Ƃ̎�����~�����B���̂悤�ɖ≮�𒆐S�Ƃ��ď��Ƃ́A�}���ɍ��x�ȃV�X�e�������肾���Ă������̂ł���B
�@
�����Ԃ̔��W�ɂ��A�ނ炪���ʋ@�\���x�z���Ă������̂ŁA���{�͋��ЂɂȂ邱�Ƃ�����A�K���̑ΏۂƂ��Ă������A���ۂ̉��v�ł́A�����Ԃ�����Ε����������ł���Ƃ��������ɓ����A�����Ԃ����F�����̂ł���B
�@
1723�N�A�g�@�̋��߂ɉ����č]�˓쒬��s�剪�����́A�k����s�z�K���ĂƘA���Ŏ�������Ȃ�u�������������Ɋւ���ӌ����v���o�����B�]�˂̌o�ϐ����S���剪�́A�����㏸�̌����̂ЂƂł���A�����Ԃ̒k���ɂ�鉿�i������Ď����A����ɃR���g���[���ł��銔���Ԃ����������A�o�ϓ��������悤�ƍl�����̂ł���B
�@
���{�͐M�p����̈����}�邽�߂Ɏ���I�Ɍ������ꂽ�����Ԃ��u�芔�v�A���ʓ����̂��߂ɖ��{�ɂ���Č����𖽂���ꂽ�����Ԃ��u��Ɗ��v�ƌĂ�ŋ�ʂ����B����Ċ����Ԃ̌��F�Ƃ́u�芔�v�̌��F���w���A�����Ԃ̐��i�Ƃ́u��Ɗ��v�𑝂₷���Ƃł���B���F���ꂽ�����Ԃ́A��[����[�߂邩���ɔ̔����̓Ɛ�Ƃ�����������F�߂�ꂽ�B
�@
�剪�́A����ݖ��Ȃǐ����K���i���������l�ɖ≮�E�����E�������Ƃ̌�Ɗ������������A���ꏑ(���i���i�\)���o�������B���i�����������ۂɂ͂��̗��R��������B�]�˂̌�Ɗ��ł͗��R���킩��Ȃ����́A���s����ɒ�������h�����A���ׂ�����Ƃ����܂ł���B�@ |
���剪�����̕���������
�@
�쒬��s�E�剪��������Ă��A�g�@�����������A�����Ԃ����p�������������́A���s�A���A�ޗǁA��Ȃǂ̓s�s�ł������Ɏ��s���ꂽ�B�]�˂̕���������ɂ́A���s���₩����镨���̗����c�����Ȃ�������Ȃ��B�����ő剪�͉Y���s�ɍ]�˂ɓ���ςׂ̗݉ʂ��������B�C�H�ō]�˂ɉ^��镨�����A���̒ʉ߃��[�g�ł���Y��Ń`�F�b�N�������̂ł���B�܂��A����s�ɂ͏����ƍ]�˂֑������S�������X�g�������ĕ���悤�˗������B
�@
����������s���u�ώG�����Ăł��Ȃ��v�ƕԓ������̂ŁA�剪�͎�v11�i�ڂ̍]�˂ւ̏o�חʂɌ��肵�A���X�g���t�����߂��B�剪�������ɗD��Ă���̂́A�ςׂ݉̋N�_(���)�ƒʉݓ_(�Y��)�ƏI�_(�]��)�̐�����c�����悤�Ƃ������Ƃ��B�]�˂̑D�≮�ɓ��������ςׂ݉��`�F�b�N����A������߂┄��ɂ��݁A�Ђ��Ă͕��������𐅍ۂŖh����ƍl�����̂ł���B
�@
�剪�̎a�V�Ȓ�Ă͑�ؔF�߂��A�V�������⒬��s�ƉY�꒬��s�Ɂu�����̏o�א��������v�Ƃ������߂��������B�剪��1725�N�A�֓�����]�˂ɓ����Ă��鐶���K���i�̒����ɂ����肷��B���������ʂ̊e�i�K�ł̃f�[�^��c�����������ł́A���������̑�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ǂ����Ă����l�̎����܂肪�K�v�������B
�@
���̉ۑ���������邽�߂ɑ剪���ڂ������̂��A�]�˂̖≮���l�����\����Ɍ��W���Č��������ʏ́u�]�ˏ\�g�≮�v�B�����I�ɂ́u��\��g�≮�v�ŁA���̓���͎戵���A�C�e�����Ƃɋ�ʂ���Ă����B���Ƃ��ΖȔ����≮�A���≮�A�]�ˑg�іȎd���ϖ≮�ȂǂŁA���Ԃ̑��l����347���ɋy�B��\�l�g�≮�ɂ͎�����A�y�s���A��s���A�ʘH�l�Ȃǂ̖���������A���Ԓ�@���߂đS�̂��Ǘ����Ă����B
�@
����Ɍĉ����đ��ł��u��\�l�g�≮�v���������Ă����B���̏\�g�≮�Ɠ�\�l�g�≮�̊W�́A������Ɣ����l�̊ԕ��ŁA���̏��i���^������̂����D�≮�Ƃ����\�}���������Ă����̂ł���B����ɂ�����ƍ]�˂����ԉݕ��D�̕H�_���D�́A�\�g�≮�E��\�l�g�≮�̒�ّD�Ƃ����ʒu�Â��ɂȂ��Ă������B�剪�͔ނ���Ǘ��E�����ł���Α傫�Ȑ��ʂ�������ƍl���A�≮�ɑ䒠���o�����A�������Ď������B�֑������A���̑��ƍ]�˂����Ԓ���D�̉^�c��S�������l������z���A��������ɍ�_�����ւƐ������Ă������B���ɓ�̎����]�˂ɉ^�Ԏd���́u�h�����v�ł������B
�@
�剪�̎����܂�ɂ͂���ȃG�s�\�[�h���c���Ă���B1724�N�ɖ��̒l�i�����������B�剪�͖��≮���s���ɌĂяo���A���i�����̗v����₢�l�߂��B���̌��ʁA���≮�����i��������ĉߕ��ȗ��v�Ă������Ƃ����������̂ŁA���̕���v�������B���������̂�41���B���{�͍���Ǝ҂������ɏW�����A���ʉߒ��œƐ萫�����܂�A���ꂪ���i�����e�Ղɂ��Ă���Ƃ݂āA�֓��ߍx�ł̍؎�̍�t�������サ�A�������m�ۂ����B
�@
�剪�͕Ė≮���Ԃ��ĕҐ����āA�ĉ������ɂ�����ł���B����҂��炷��Εĉ��͒Ⴂ�ق������肪�������A�]�˂̏���o�ς͈�N���Ƃ̎Q�Ό��ō]�˂ɂ���Ă��đ؍݂��镐�Ƃ̖c��Ȏ��v�Ɏx�����Ă����B�ĉ����㏸����ΕĂ��������Đ�����ɏ[�ĂĂ��镐�Ƃ̏���͂��A�b�v���A�Ђ��Ă͒��l���̗��v�ɂ��Ȃ�Ƃ����l�������B
�@
1730�N�ɂ́A�������̕Ă�8�l�̕Ė≮�ɓƐ�I�ɉ���Ƃ������G����o���B�剪�͍ĕҐ����ꂽ�Ė≮�g�D�����p���āA�ĉ��������グ�悤�ƌv�悵���̂ł���B���̂悤�ȓw�͂ɂ���ĕ�����͈����Ǝ҂̓E���Ƃ������ʂ͂����������̂́A�ĉ��̈����グ�͊��҂����قǂ̐��ʂ������炸�A�s��̗��ʗʂ����邾���ł͌��E���������B�ĉ��̈����グ�ɂ͋��Z����̓]�����K�v�������̂ł���B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
���剪�����̃��[�g����
�@
�쒬��s�E�剪�����������Ԃ𐄏����A�≮���l�ɑ䒠���o�����A�Ă╨���̗��ʗʂ��R���g���[�����Ă������㏸�ɑ傫�ȉe���͂Ȃ������B���̗v���ɂ͊֓��Ɗ��Ŗ{�ʉݕ����قȂ��Ă������Ƃ���������B
�@
�]�˂𒆐S�Ƃ���֓��o�ό��͋��݂��d��̂ɑ��A���E���s�𒆐S�Ƃ�����o�ό��͋�݂��d��o�ςł������B�����̌o�ς̒��S�n�͑�₾�����̂ŁA���݂���݂������A��݂̋��݂ɑ���������[�g�����������B���̌��ʁA�������z�̕������]�˂̕����͍����Ȃ����̂ł���B
�@
���݂͗��A��݂͖�(�����)�A����(�K��)�͕�(����)����{�P�ʂƂ��Ă���A1700�N�ɖ��{����߂����葊��́u��1�������60��v�ł������B�����������ɖڂ�ʂ��Ă݂�ƁA�剪���쒬��s�߂Ă�������(1717�N�`1736�N)�ɂ́A�u����1�������43�`50��v�ŗ��ʂ��Ă������Ƃ��킩�����B��݂͌��背�[�g��2���ȏ�������A���̏��l���]�˂ɏ��i���^�ׂA���i�̑e���ȊO�Ɍ������z�Ƃ������v����ɂ��Ă������ƂɂȂ�B
�@
�����痼�֏����x��~�����킯�����A���ɍ]�˂̏��l�͑�⏤�l���珤�i���Ɨ��v�����Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃ��B�]�˂̏��l���K���ȗ��v�悤�Ƃ���A���背�[�g��2������3���A�b�v����̔����i�ɏ悹����Ȃ��Ȃ�B�܂�A�]�˂̕����͏㏸����B���ɋ��݂������Ȃ�A�]�˂Ŕ̔����鏤�i�͈����Ȃ�A�]�˂̕����͈��肷��B���̋�ɑ��鉿�i���[�g�̐�グ�́A�]�˂ɑ����̈����ȕ����������Ă��āA���������肷�邱�Ƃ�z�肵���剪�̔ߊ�ł������B
�@
�����k���Č��\����ɓ����̊����s�E�����d�G�ɂ���Đ��s���ꂽ�u���\�����v���v���o���Ă��炢�����B���݁E��݂̎��𗎂Ƃ��āA���̕����s�ʂ𑝂₵�A���z�������{�̉��ɓ���Ƃ�������I�Ȏ�@�ł���B�����͖��{�̎x�o�����債�A�N�v���������ł��ɂȂ��Ă�������B
�@
�܂��ݕ��̌����ƂȂ����̐��Y�ʂ��L�єY��ł����̂ŁA�ݕ��̋���̊ܗL�ʂ����炷���Ƃ͓���ł������B�܂��A���܂�m���Ă��Ȃ����A�o�ϒʂ̉����d�G�͋�������̉��l�̉������̕���傫�����邱�ƂŁA���̋�ɑ��郌�[�g���グ�悤�Ƃ����悤�ł���B
�@
�u���\�����v�ɂ���Ė��{�̗��v�͑������B���ꂪ�ő�̖ڕW�ł������̂Ő��ʂ͂������Ƃ�����̂����A���𗎂Ƃ������Ƃœ��R�̂��ƂȂ���ݕ��̉��l�͉�����A���ƊE�͍��������B�����̋��Z������������ᔻ���A�����{����ǂ��o�����V�䔒�́A���Z�����ߐ����f�s�B
�@
1714�N�A���{�͐V��̒�Ă�����A�u���\�����v��������A�ݕ��̎����c������̃��x���ɂ܂Ŗ߂����u��������v�s�����B�ǎ��ɂȂ������A�s��̗��ʗʂ͕s���C���ɂȂ����B��������Ƃ��Ƃ��Ƌ��������₪�Ăѐ����𑝂��A�]�˂̕����͏㏸�����B
�@
�]�˂̕������㏸���邱�Ƃɑς����Ȃ��剪������1718�N�A�]�˂̗��֏��ɑ��āA���葊��(1�������60��)�ɂ���悤�w�������B���������֏��͎s�ꉿ�i�����Č��背�[�g�ɂ����2���ȏ�������邱�Ƃ��킩���Ă���̂Ō������������A��ĂɓX��߂��Ƃ����Ă���B
�@
�����ő剪�́u1�������55��v�Ƃ������[�g����đË��_�����o�����Ƃ������A���֏��͔[�����Ȃ������B�剪�͎d���Ȃ�����̓����ɔC���邱�Ƃɂ����B�܂�ŃA�_���E�X�~�X�̌����Ƃ���́u�_�̌��������v�ɔC����Ƃ������f����x�͂����悤���B���̍�����o�ϐl�����S�Ɏs��o�ς����[�h���鎞��ɓ˓������Ƃ����悤�B
�@
���������V���s�s�ł������]�˂̗��֏��ɂ͏����{�X�Ƃ���҂������A�⑊�ꂪ������Ζ{�X�����łȂ�����̖≮�A���ʋƎ҂��ׂĂ����v�Ȃ����ƂɂȂ�B���֏��͏�����l�S�̂̊������v�Ǝ��R�o�ς���邽�߂ɒ�R�����̂ł��낤�B�@ |
���w���x�_�x��葁�����Z����u���������v
�@
�u���ۂ̉��v�v�̑傫�Ȗ���̂ЂƂ́A�ĉ��������A���������肳���A���m�̐�����L���ɂ��邱�Ƃł������B�������Ă╨���̗��ʗʂ��R���g���[�����Ă������㏸�̗}�����ʂ��Ȃ��A�܂��쒬��s�E�剪���������֏��ɍm�背�[�g�u��1�������60��v�ɖ߂��悤�˗����Ă����܂ꂽ�w�i������A���{���Ɂu���\�����v����{�Ƃ����ݕ������Ă����サ���B
�@
�ݕ������ɂ��⑊��̋����I�Ȉ��������ɂ���č]�˂̕��������肳���悤�Ǝ��݂��̂ł���B1736�N�ɍs��ꂽ�u���������v�́u���ۂ̉��v�v�̌���ɍs��ꂽ�d�v�Ȍo�ϐ���ł���A�ߑ�o�ϊw�̊�b�ɂ���}�l�[�T�v���C���w�ԍŗǂ̃T���v���Ƃ����悤�B
�@
�剪�����͎��̂悤�ɍl�����B���𗎂Ƃ��ĉݕ��̗��ʗʂ𑝂₵�A���݂�����݂̉��l�̉�������傫�����邱�ƂŁA�⒆�S���̏����������S�̍]�˂ɉ��i�̈����ȏ��i�������Ă���悤�ɂȂ�A���������肷��B�܂������̂��߂Ɏs��ɕ��o�����Ă̗��ʗʂ�����A�ĉ������̑傫�ȗv������菜�����Ƃ��ł���A�ƁB����������������Ă����ƁA�剪���g�@�ɒ�Ă��A�悤�₭���s���邱�Ƃ����܂���1736�N�́u���������v�́A���{�̎����A�b�v�̂��߂̕���łȂ��A�����܂ł�������ł��������Ƃ������Ă���B
�@
�]�ˎ��㒆���ɂ��łɐ��̒�(�s��)�ɏo��邨���̗�(�ʉ�����)�߂��āA�����̈�����͂���A�o�ς̓�����������Z����̗��_�������Ă������Ƃ͂ƂĂ������[���B�o�ϊw�j�ł́A�o�ϊw���ЂƂ̊w�╪��Ƃ��Ċm�������悤�ɂȂ����̂̓A�_���E�X�~�X�́w���x�_�x(1776�N���s)�Ɏn�܂�Ƃ���Ă���B���������ɓ��{�ł̓C���t����f�t���s���Ă����Ƃ������Ƃ��B
�@
1736�N�A�剪�͉����������钬�G�����B�c������̎���100�Ƃ���ƁA�������݂̕i�ʂ�60�A��݂�58�Ɉ���������ꂽ�B��������̕i�ʂ����������邱�Ƃő��ΓI�ɋ����������悤�Ƃ����̂ł���B�������đ�ʂ̐V�ݕ������s���ꂽ�B������������A��̃��[�g��49��ɏ㏸�����B����������ꂽ�V��݂����s���ꂽ���ƂŁA�ǎ��ȋ��d�݂��ޑ��A���Ȃ킿�^���X�a���ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B
�@
���݂����Z���Y�Ƃ��ĕۗL�����ƐV��݂Ƃ̈��������͐i�܂��A�s��ɏo���Ȃ��Ȃ�B���̌��ʁA���ʂ����݂����Ȃ��Ȃ�A��݂̉��l���オ�����Ƃ������Ƃ��B����͗��������A�o�ς͂��炭���������B�剪�͗��֏����⑊�ꍂ���𑀍삵���ƌ��āA�����̗��֏��𓊍������B���͂̍s�g�Ƃ�������܂ł����A�����Ȏ�@��I����Ȃ��Ƃ���܂ő剪�͂��炾���Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B
�@
���́u���������v�����{���ꂽ1736�N�A�剪�͓ˑR�A���Е�s��"�h�]"���Ă���B���Е�s�Ƃ����E�ʂ͎O��s�̕M���i�Ȃ̂ŏ����Ƃ�����̂����A���֏��ɑ���e�������̖��b�̖ڂɗ]��A�����ɂ���đŌ��������֏������̏��l���������b�ɑ剪��s����O���悤���͂��������̂ł͂Ȃ����A�Ɨ��j�Ƃ͕��͂��Ă���B�剪�͋g�@�����F�����D�ꂽ�s���}���Ŏ��т������A�ȒP�ɃN�r�ɂ��ł��Ȃ��B�܂�A"�h�]"�Ƃ����`���Ƃ������J�ł������̂�������Ȃ��B
�@
���āA�u���������v�̌��ʂ��������̂�1741�N�����B�����炭�V�ݕ������ʂ���̂ɂ���Ȃ�̎��Ԃ��K�v�������̂ł��낤�B���{�̋����p���������ċ⑊��͎���ɉ������A�悭�₭�u��1�������60��v�Ƃ������背�[�g�ɗ��������A�ĉ��╨�������肵���B���̎���ɂ�1737�N�Ɋ����s�ɏA�C�����_���t���������i�s�Ő��i�����N�v���Ő�����t���A���{�̍����ɂ���Ƃ肪���܂�Ă����B��������͂��̌�1818�N�܂�82�N�ԉ�������邱�ƂȂ����ʂ����B���ʂƂ��Č��������͍]�ˊ��̉����ōł�����������ɋ������Ă���B |
���u���ۂ̉��v�v�̓s�s���� �ڈ����̐ݒu�Ə��ΐ�{�����̐ݗ�
�@
�u���ۂ̉��v�v�͍����ƕ����̈��萭��A�ĉ��̏㏸�����������[�g�̐����ȂNj��Z�����ł��������A�ق��ɂ��������̉���I�Ȑ����{����Ă���̂ŁA�܂Ƃ߂ċL���Ă������B
�@
���R�E����g�@��1721�N�A�����̗v����s���Ȃǂ��������������邽�ߍ]�ˏ�̕]�菊�̖�O�ɐݒu�����u�ڈ����v�́A�u���i���v�u�i�v�Ƃ��Ă�A�s�s����╟������ɑ傢�ɖ��������B���Ƃ��Ƌg�@���I�B�ˎ厞��Ɏ��{���A�傫�Ȏ育������������̂ЂƂ��B
�@
���b�̓����͓���������Ă������A�Ԃ��Ȃ��֎~����A���l��_�����������������B�����ɑ���ӌ����W�߁A�Љ������W���鐧�x��݂������R�͋g�@�ȊO�ɂ͂��炸�A�ނ������ɏ����̐������o�ɕq���ł��������A����������}�[�P�e�B���O���o�ɒ����Ă����̂����킩��B
�@
���������̃V�X�e�����^�c����̂ɃR�X�g���g�D���K�v�Ȃ��B�g�@���g���ڂ�ʂ��A�����Ή�����u�����Ȑ��{�v�Ȃ�\���@�\����B�Ƃ���ŁA�����̓��e�́A�قƂ�ǂ���l�̕s����i������̂ł������炵���B�����̂���l�͑��d��g�����݂����Ă����Ƃ������Ƃ̏ؖ��ł��낤�B
�@
���āA���̖ڈ�����ʂ��Ēa�������̂������̈�Î{�݁u���ΐ�{�����v�ł���B����҂̏���♑D���]�˂̕n���҂�g���̂Ȃ��҂̂��߂Ɏ{�Ï��̌��݂����߂�ӌ����𓊏����A�����ǂg�@���쒬��s�E�剪�����Ɏ{�݂̌����𖽂��A�剪������Ɩʒk���āA���ł��������ΐ����ł̐ݗ������肵���B���̏ꏊ�͌��݁A������w���w���̕t���{�݁u���ΐ�A�����v�ƂȂ��Ă���B
�@
�{�����̎��e�l����40���B���ݔ�̋�210���{��12��Ɩ����̉^�c��͖��{�̍�������P�o����A��t�͏����7���̈�t���S�����A�^�́A���S�炪�X�^�b�t�Ƃ��ĎQ�������B�J�ݓ����͖̎�����ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����s��������A�����͗{���������܂藘�p���Ȃ��������A�剪���]�˒����̖�����Ă�Ŏ{�݂����w�����A���]�@�������Ƃœ��@���҂͋}�������B
�@
�u���w��v�����{�����Ƃ��낪�ނ̗D�ꂽ�_�ł���B���ΐ�{�����͉��w����Ƃ��ċ@�\���A�����܂Ŗ�140�N���܂�]�˂̕n���~�ώ{�݂Ƃ��ė��p���ꂽ�B�u�i���Љ�v�����{�ɂ��u�Љ���s���v��u�Z�[�t�e�B�l�b�g�v�Ƃ����T�O���]�ˎ��ォ�瑶�݂��Ă����Ƃ������Ƃł���B
�@
�Ƃ���ŁA���ΐ����̖�150�̓y�n�ƁA���ΐ�{�������̖�180�̓y�n���Ŏ�ăT�c�}�C���̎���ɗ�̂��A���̐؍��z�ł���B�����x�̗^�͉��~����Ď�w���u�`���Ă�����剪�����F���A���{�̊̂���ŃT�c�}�C���̎���𖽂����̂ł���B�剪�͋��ۂ̑�Q�[�ɂ���ĕĂ����n�ł��Ȃ��������P����A����̎��⑉�����y�n�ł����n�ł���앨�̊J���ɖڂ������Ă����B
�@
���z�̓T�c�}�C���̌��p��剪�ɓ`���A���̕K�v�����������剪�����{�̓y�n������̂ł���B�����œ���ꂽ�c�́A�͔|�@�ƂƂ��ɍ]�ˎ��ӂ̔_���ɍL���z���A�e�n�ɍ��t���A���쎞�ɑ����̐l�X�̖����~�����ƂɂȂ�B�u���ΐ�{�����v�ƃT�c�}�C���͖����~���Ƃ����_�ɂ����ċ��ʂ��Ă���B�ǂ�����u���ۂ̉��v�v�̒��Ŗ����ꂪ���Șb�肾���A�s�s����Ɛ[���Ȃ��鐭��Ƃ����悤�B
�@
�Ƃ�����A����s���n��Y�ƁA���ɔ_�ƈ琬�ɋ��͂��A���{���x���������Ƃ͕x�ɋ����[���B���������l����100���l���鐢�E�ő�̓s�s�ł������]�˂Ȃ�ł͂̎��g�݂Ƃ����悤�B���Ȃ݂ɐ؍��z�̓T�C�}�C���͔̍|�ɂ��Q�[�̉�����F�߂��A���b�ƂȂ�A�̂��Ɏ��Е�s�ɏ��i�����剪�̔z���Ƃ��������B���̐؍��z�̒�q���w��̐V���x�Œm����O��Ǒ�ł���B�@ |
�������Ԃ̏���ɂ��@�l�Ŋl��
�@
�]�ˎ���̎O����v�u���ۂ̉��v�v�u�����̉��v�v�u�V�ۂ̉��v�v�́A�Ă𒆐S�Ƃ���q�d�_��`�r�I�����A�]�ˎ��㒆���ɘV���Ƃ��Ė������哱�����c���ӎ��́A�ߋ��ɗ�����Ȃ��q�d���Ǝ�`�r�I�o�ϐ�������{�����B�u���ۂ̉��v�v�Ɓu�����̉��v�v�̊Ԃ��Ȃ��c������(1767�`1786�N)�ƌĂ��20�N�Ԃ́A�܂��16���I�̉��B�̂悤�Ɏ��R��`�o�ς̔��W�𑣂����̂ŁA���{�̌o�ώj�̗���̒��łَ͈��Ɍ�����B���̌�Ɂu�����̉��v�v���哱���鏼����M�ɐ���A�l�i�Ƃ��ے肳��A���{�j�ł́u�c�������l�v�u�d�G�����Ɓv�Ƃ����C���[�W�����܂Ƃ����̂́A���͓c���͌��݂̎��R��`��q����`�ɂȂ��鑽���̐V�����o�ϐ�����s���Ă��̂��B
�@
�c���ӎ��͖���o�g�ł͂Ȃ����A�ٗ�̏o�����ʂ������H�L�Ȑl�����B���͋I�B�˂̑��y���������A8�㏫�R�E����g�@�����R�A�C�ɍۂ��ēo�p����A�]�˂̖��b�ɉ�����ꂽ�u�I�B�g�v�̈�l���B�c���͂̂���9�㏫�R�ƂȂ�Əd(�g�@�̒��j)�̌䑤��p�掟(���݂Ȃ狳��E�G�p�S�����鏑)�ɔ��F����A�Əd�̏��R�A�C���1���̏��̂�^������B�Əd�͕��E�g�@�Ƃ͔��ɕa�ゾ�������߁A��䏊�ƂȂ����g�@�́A���̉Ǝ��Ɋ��҂��������B1751�N�ɋg�@���S���Ȃ�ƁA�}�f�ȉƏd�͘V���ɐ�����C�������A���R�A�C���Ԃ͒Z���A1760�N�A�Əd���B�����A���j�̉Ǝ����Ɠ��p�����B
�@
10�㏫�R�E�Ǝ����d�p�����̂��c���ӎ����B�Əd�̎�����A�Ǝ��͓c����M�����A�c���͔j�|�̐����ŏ��i�B1767�N�ɂ͉��]���ǔ�(���݂̐É����q�V���s)�̏���ˎ�ƂȂ�B�Ǝ��͓c���̐V�����������o�������]�������悤���B�c����1769�N�ɘV���i�ɂȂ�A���{�̊t���Ƃ��Ė������v���肪����悤�ɂȂ�B���̔ނ��̗p�����̂͏d���Ǝ�`�o�ϐ��B
�@
��̓I�ɂ́A�����Ԃ̐ϋɓI�Ȍ��F�A����̐ꔄ���̎��{�A�ݕ����x�̌������A�z�R�̊J���A�O���f�Ղ̊g��A���V�A�̋��ЂƖf�Ղ��Ӑ}�ɂ����ڈΒn�̊J���v��A����������̊���̒���Ȃǂ��B���̌��ʁA���{�̍����͉��P���A�i�C�͏㏸�����B���̑�G�c�ȃ��C���i�b�v����ł��A�ނ��u�_�Ɓv�łȂ��u���Ɓv�Ɏ�����u���Ă��邱�Ƃ��悭�킩��B���s�ɏI�������������邪�A�܂�ŏ������{��`�o�ς̊�ՂÂ�������邩�̂悤�Ȃ��̂��肾�B
�@
�ł́A�c���̐�����ЂƂ����Ă������B�����Ԃ̌����́A�u���ۂ̉��v�v�ɂ����ĕ����㏸��}������ړI�ő剪���������i�������̂��B����ɑ��c�������Ǝґg���̐ݗ������サ���̂́A���{�̌����������Ə��Ǝ҂̋����͂����߂邽�߂ł������悤���B�����Ԃł����{�̔���銔���Ԃł͂Ȃ��A���l������I�Ɍ�������u�芔�v�����サ�A����ݖ��A����ȂǓ���̎Y�Ƃɂ́A�ꔄ���Ȃǂ̓�����^����Ƃ����u�A���v�������ċ����S�����������B���̌��Ԃ�Ƃ��āu���`�v���������B�^����A������(��[��)��łƂ��Ē��������̂��B�u���l�̎s��ւ̎��R���������}���悤�B�w�͂���Ύs��͓Ɛ�ł���B
�@
�������A�ŋ��͂������蕥���Ă���v�Ƃ����A�ƂĂ������I�Ȑ��B�g�@�̎���ɐV�c�J���͂قƂ�ǏI�����A�N�v�𑝂₻���Ƃ��Ă����E���������B�_������̑d�ŁA�܂�N�v���������łȂ��A�傫�Ȑ��͂ɂȂ��Ă������l����@�l�ł����A�����͂����Ə����͂��B����������Ə��Ƃ��d�A���l��������悤�Ȑ�������{����B����͗��ɂ��Ȃ��������B�܂��A���l���炷��A���f����A�䖝����������Љ���A�w�͂�����Α傫�ȍ���z�����Ƃ��ł���Љ�̂ق������͓I�ɉf�����͂��B
�@
���̂悤�ɏ��Ƃ��d�����ƂŁA���l���l�̔q����`���i�ށB��������d�G�����s����悤�ɂȂ������Ƃ���A�c���ɂ́u�d�G�����Ɓv�Ƃ����C���[�W�����܂Ƃ��B�܂��A�s�s���ɂ����ď��Ƃ��������������ƂŔ_�����s�s���ɗ��ꍞ�݁A�_���̍r�p���i�ނƂ����u���v�̖ʂ�����B�d�G�ɂ܂݂ꂽ�V���ł��������Ƃ����ΐ��͂̃f�}�������̂��A�����������̂��͒肩�ł͂Ȃ����A�c�����挩���ɕx�o�ϒʂł��������Ƃ����͊m�����B���炭�ނ̐���������Ă������B�@ |
���ꔄ�̐��̐����ƒ���f�Ղ̊g��
�@
�c���ӎ������{���������Ԃ̐����́A���ڐŒ��S�̐Ő��ɁA�Ԑڐł◬�ʐł������Ƃ����_�ɂ����ĉ���I�ł������B�����Ċ����Ԍ��F����͓s�s�̏��H�Ǝ҂݂̂Ȃ炸�A�_���̏��l�ɑ��Ă��ݕ���(�_�����̊�����)�̌��F�Ƃ����`�Ői�߂�ꂽ�B�]�˒����ɂ͔_���̒����珤�Ɗ�����W�J����҂��o�ꂵ�A�ނ�͍����l�ƌĂ��悤�ɂȂ��Ă����B����Ό��Ɣ_�Ƃ����A�ނ�������Ԃ�����n�߂��̂��B�s�s�Ɣ_���ɓ���̑d�ŕ��@��K�p�����_���c���̖ڐV�������B
�@
����ɓc���́A��p���l�ɓ��A�S�A�^�J�A���N�l�Q�A�V���E�m�E�A��ȂǃA�C�e���ʂɖ��{���c�̍��������������B���������Ɠ����悤�ɁA���{�哱�œ�����S�������点���̂ł���B�����ԂƂ̌���I�ȈႢ�́A�����Ԃ��ŋ������̑ΏۂƂȂ�g���ŁA��{�͎��R�����A�^�c�͊����ԂɔC���Ă����̂ɑ��A���͖��{�ɂ�鐻���E�̔���Ɛ肷�鐧�x�ł��邱�Ƃ��B�܂���͖��{���c�̃r�W�l�X�ŁA���v�͖��{�̍����ɒ��������Ƃ����킯���B���Ă̂����ꔄ���ЁA���{���L�S���A���{�d�M�d�b���Ђ��ƍl����킩��₷���B
�@
�c����1780�N�A�^�J�����A�����ő��ɓS����V�݂��Ă���B�Ƃ��ɍ]�˂���ɂ������Ɠ��������Ƃ��A�ꔄ���ł������B�������Ă݂�ƁA�ꔄ���͎Y�ƈ琬�Ƃ����������{�̎����A�b�v�̈Ӗ��������������Ƃ��悭�킩��B
�@
���Ƃ���1782�N�A���{�͎��(���)�ȊO�ł̎�(�ԐF�̊痿)�̔������₦�Ȃ����߁A�A���i�͒��肩��A�����Y�͎F���������֑���悤���߂��A����ł̐ꔄ���������Ă���B�u����͖��{���c�̃r�W�l�X������A���߂�ꂽ���Ŕ̔�����̂����K���[�g�ŁA����ȊO�͔F�߂Ȃ����v�Ƃ����x���ł���B
�@
���ꂼ��̍��͐����E�̔���Ɛ肵�����A���{���c�̔̔������_�ɂ́A�u��v�ƌĂ�鎖�������̔������������B���Ƃ��ΐΊD�̎Y�n�ł��锪���q���썑(�Q�n��)�Ɂu�ΊD��v������A�ΊD�̓Ɛ�̔��������B�̂��炠��H�i�Y�����ŁA�Е���A�N�����Ȃǂ̗p�r�Ŏg���A�Ђ�����ؐ��߂Ȃǂɗp����ꂽ���H(�݂傤��)�́A�]�ˁA���A���s�A���4�J���ɐݗ����ꂽ�u���H��v���Ɛ�̔������B���������{�͉������ŋ��������Ƃ����B
�@
�e�˂������̂����݂��܂˂āA�˂̒��c�r�W�l�X���J�n�����B���Ƃ��ΐ��˂́A���A�C����A�Ί��Ɂu���Y��v��ݒu���A���˂̓��Y�i�̓Ɛ�̔����s���Ă���B�x�R�˂͔���̐ꔄ���J�n�A���B�˂͉Γ�̑����������֎~���Ĉ������l���w�肵�A�ꔄ�����n�߂Ă���B
�@
�Ƃ���ŁA���{�̃r�W�l�X�Ƃ��ă��j�[�N�Ȃ��̂ɁA����ȋL�^���c���Ă���B1765�N�A���{�����������A�o�i�̃t�J�q�����Y�̂��߁A�V���ɃT�������n�߂�҂ɂ͓����̊ԁA�ŋ���Ə�����Ƃ������̂��B�����͍������ł͂��������A�����̌��F�D�ƃ|���g�K���̖f�ՑD�͒���ɏo����ł����B����ɂ��Ă��A�t�J�q���Ƃ����Β������{�Ƃ��Ǝv������ł�������A�]�ˎ���ɖ��{�������Ƀt�J�q����A�o���Ă����Ƃ͋������B
�@
����Ȓ��c�r�W�l�X�̂ЂƂ̑����ƂȂ��Ă����ꏊ�����肾�B�c���͒���`���g�����A�`�ɏo���肷��D����H������������蒥�����Ă���B�����Ē���f�Ղ̊g��ɂ��͂𒍂����B���{�̖f�Ր���͍����̐��̊m���ȗ��A���Y�̋���̌����ɑΉ�����`�ŁA�K�͂��k�����Ă����B�������A�c���͂��̕��j��傫���]�����A�f�Ղɂ�����̗A���A�܂�O�݊l����}�����̂ł���B
�@
���̂��߂ɗA�o�i�ƂȂ铺��C�Y��������������U���(�C�Y����舵��������)��݂��A���R�̊J����C�Y���̑��Y�����サ���̂��B�L�^�ł͕x�R�˂ɒ����ւ̗A�o�p�H�p�N���Q�����点�A����܂œ͂������Ă���B������O�q�����悤�Ƀt�J�q�����Y�̂��߂ɐŋ��Ə��܂ōl�Ă����̂ł���B�㐢�Łu�d�G�����Ɓv�u�����V���v�ƌĂ��c���ӎ������A����قǂ̌o�ϒʂb����T���͓̂�����낤�B�]�ˎ���ɊO�݊l����}��A���Y���̑��Y�𐄏������Ƃ͋����ł���B�Ȃ��Ȃ�A�����16���I����18���I�ɂ����ďd����`�������������̒����Ȍo�ϊw�҂̗��_���̂��̂��������炾�B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
������ʉ݂ւ̕z��
�@
�c���ӎ��͉ݕ����v�ɂ�����ł���B�ނ͋g�@���i�߂��u���f����v����͏����₦���܂��邱�Ƃ�m���Ă����B������ݕ��o�ςy�����A�đ���̗��������������A�����Ɏs���ɗ����ݕ��̗��ʑ��x�����āA�o�ς����������悤�Ƃ����̂��낤�B����ɓ����ňقȂ�ݕ��̌n�̓�������݂悤�Ƃ��Ă����悤���B���Ƃ̔��W���d�A�����g���}�����c�������݂��ݕ����v�́A���̂Ƃ��肾�B
�@
�]�ˎ���̉ݕ�������ƁA���݂͑唻�⏬���̂悤�ɂ����Ɖݕ��̌`�����Ă��邪�A����̋�݂͉���������̂��̂ł��邱�Ƃ��킩��B����͑��ŗ��ʂ��Ă�������ⓤ�₪�A�`�ɊW�̂Ȃ��d����ʂ��Ďg���ݕ�(���ʉݕ�)���������炾�B�u�]�˂̋��A���̋�v�ƌĂ��悤�ɁA���ꂼ���Ɏg����n����قȂ��Ă����B���������Ƃ̒��S�n�ł�����Ŏg����₪����苭�����ƂŁA�������C���Ɏg���Ă���]�˂̕����͍����Ȃ肪���������B�剪�����͕ϓ����ꐧ�̈בփ��[�g�����ė��֏��Ɍ��背�[�g����点�A���Ƌ�̈ב֑�������肳���悤�Ƃ����B����͈قȂ�ݕ��̌n�����邱�Ƃ�O��Ƃ�������ł���B
�@
����ɑ��c���͋��݂𒆐S�Ƃ���ݕ����x���l���Ă����B�Ђ���Ƃ����瓝��ݕ��̔��s�܂ł������ł����̂�������Ȃ��B1765�N�A���݂Ƃ��ďd����5��(��18.75�O����)�ɌŒ肵���u�ܖ��v�s�����B�u�ܖ��12������1��(����1��)�v�ƌŒ肷�邱�ƂŁA�⑊��ɂӂ�܂킳��Ȃ��悤�ɂȂ�ƌ����悤���B�܂��K�̑�p�ɂ��Ȃ�B���ꂪ���݂Ƌ�݂̈בփ��[�g�̌Œ��_�����ŏ��̋�݂��B�����������̎������[�g�́A����1���ɑ����63��(��236.25�O����)�O�ゾ�����̂ŁA������C���Ɉ����҂ɗL���ƂȂ�A���֏������̔��ɂ���čL�����ʂ��邱�Ƃ͂Ȃ������B���֏������������R�́A�z�ʂ��Œ肳���ƁA��݂̔��ʎ萔�������Ȃ��Ȃ邩�炾�B���������������A�ܖ��͂قƂ�Ǘ��ʂ��Ȃ��܂܁A1768�N�Ɏg�p����~���ꂽ�B
�@
1768�N�ɂ́A�S�K�̕s�l�C��ŊJ����ړI�Ő^�J���̑�`�K�u���i�ʕ�l���K�v�s�����B������1772�N�A�]�˖��{�n�܂��Ĉȗ��̉���I�ȉݕ������s���ꂽ�B�u�����v�Ƃ����Ă��������낤�B����ɖ����Ă��点���u���`����v�́A��łł������݂ł���A���݂̓��ɑ��������݂ł�����B�₪�܂܂�Ă��邪���ډݕ��ł���B���`�Ƃ͗ǎ��̋�Ƃ����Ӗ��B2.7��̏d�������Ȃ����A�u�d�v�Ȃ͉̂ݕ��̉��l�ł���v�Ƃ������b�Z�[�W�������̂��낤�B
�@
�܂��A�ܖ�₪���y���Ȃ��������Ȃ�����A��̏��x���グ�����ŁA�ݕ��Ɂu8���ŏ���1���Ɍ����ł���v�ƕ\�L�����B����͏d���ł͂Ȃ��A�������l���̂��̂�\���������̂ŁA���֏�����舵���₷���B����������݂Ƌ�݂̈בփ��[�g�͌Œ肳���B�܂�A�܂��EU�ɂ����郆�[���̓���̂悤�ɉݕ��̌n�͓��ꂳ���B���ꂪ��������A�]�˂̕������͉����ł��A�����̗��ʂ͂����Ɗ���������c�c�B���������c���̃r�W��������A�ނ������ƂƂ��Ă��o�ϊw�҂Ƃ��Ă���z�����Z���X�������Ă������Ƃ��킩��B
�@
���`����͔��ʉݕ��ɂȂ���ł������ɂ����X�ɐZ�����A����ⓤ��Ƃ��������ʉݕ����������쒀���Ă������B�c���́u���ݖ{�ʐ��v���̗p�����̂��B������_�@�Ƃ��ċ�݂̋��݂ɑ���⏕�ݕ������{�i�����A���̌㖋���܂ł�7��ނ́u�v����݁v�����s���ꂽ�B���̂܂ܐi�߂Ζ����ɂȂ�܂łɓ���ݕ����ł����͂��Ȃ̂����A�c����ǂ����Ƃ���������M�́A���`�����ɉ����������ƂŁA�c���̉ݕ����v�͋������Ă��܂��B�K���Ȃ��Ƃɓ��`����͂̂��ɔ��s���ĊJ���ꂽ���A���������c���̉ݕ����v�������p���҂͓o�ꂹ���A����ʉ݁u�~�v�̓o��͔����I��ƂȂ����B�@ |
���ڈΒn�̊J��
�@
�c���ӎ��͉ڈΒn�̊J���ɒ��肵�悤�Ƃ��A���{�̎����Œ������𑗂荞�ނȂǔ���ȓ��������Ă���B�ڈΒn�Ɩ{�B�͂���܂ł܂������𗬂��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B����n�ł��邱�Ƃ���Ă̎��n���ł��Ȃ��������O�˂��ˍ������ێ����邽�߁A�ڈΒn���������ɕ������A�u�ꏊ�v�Ɩ��Â��A�傾�����Ɛb��m�s(�Ǘ���)�ɔC�����A�A�C�k�Ƃ̌��Ղ�F�߂Ă����B�u�ꏊ�v�̐������͏��O�˂��s�Ȃ��A���ۂ̃r�W�l�X�͏��l�̎�Ɉς˂�ꂽ�B���O�˂͏��l����ŋ�������Ƃ��������݂��B������u�ꏊ�������v�Ƃ����B���Ƃ��Ƃ͉ƍN�����O�˂Ɍ��Ղ̓Ɛ茠��^�������Ƃɂ���B�������Ă݂�ƁA�ꏊ�������͏��O�˂ɂ��"�A���n���x"�Ƃ�������B
�@
�����̖��{�̓A�C�k�̐l�X�����ڃ��V�A�l�Ɩf�Ղ��J�n����̂ł͂Ȃ����ƌ��O���A�ڈΒn�����̂܂��O�˂ɔC���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl���Ă����悤�����A�c�����ڈΒn�ɒ��ڂ������R�͂���Ƃ͈قȂ�B�傫��������ƁA���V�A�̓쉺����ւ̑Ή��Ɠy�n�̗L�����p���B�����̓��{�͍������ł��������A�|���g�K���ƒ����D�����͒���ɏo����ł����B���V�A���A���n�����߂ē쉺�������낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A����ɂ���Ă��鉢�B���l��ʂ��Ė��b�̎��ɓ����Ă����B
�@
�����A�������V�A�D�͕p�ɂɓ��{�C�܂ł���Ă��Ă����B������^����Ƀ��V�A���������Ă���͂��̉ڈΒn�����h�̂��߂ɊJ�Ă������Ƃ����Ӑ}���������̂��낤�B1771�N�ɃA�C�k���E���b�v���̃��V�A�l���U�����Ēǂ��������Ƃ����L�^���c���Ă��邱�Ƃ���A���V�A�l�͌��݂̖k���̓y�ɏ㗤���Ă������Ƃ��킩��B�ނ�̓��V�A���{�̐l�Ԃł͂Ȃ��A������ߊl���Ėє�悤�Ƃ���n���^�[���������A����n�Ŕ_�앨���炽�Ȃ����V�A������Ƃ��Ď����̂���y�n�����߂ē쉺���Ă���͎̂��Ԃ̖��ł������B
�@
�c���͉ڈΒn�ׂ邽�߂�10�����琬��T���`�[�����������A���荞�B���̒������ɎQ�������̂��T���Ƃ̍ŏ㓿���ł���B�ނ͒n����A�C�k�̕��������A�瓇�⊒���܂ŒT�����Ă���B�𑨂�E���b�v���ւ��n��A���V�A�l�Ƃ��ڐG���A��F��z���Ă���B�ԋ{�ё����ڈΒn�̑��ʂɒ��̂́A����20�N��ł���B
�@
���āA�c���̉ڈΒn�J���A�d����`����͂����ɂ��F�Z�����f���Ă���A�ނ͖h�q�����łȂ��A�A�o�����̊C�Y�����ڈΒn�ŗʎY�����悤�ƍl���Ă����Ƃ����Ă���B���V�A�ƍ��������сA�f�Ղŗ��v�������A���ʂƂ��ă��V�A�̋��Ђ�����{����낤�ƍl���Ă����悤���B�����������ЂƂA�c���͏��O�˂Ǝ��g��ʼnڈΒn���J�A�k���f�Ղ̗������m�ۂ��A�������₻���Ƃ����ɉ߂��Ȃ��Ƃ�������������B�m�b�̓����c���̂��Ƃ�����A���ꂭ�炢�͍l���Ă������낤�B
�@
�ǂ���ɂ��Ă��C�O�Ƃ̖f�Ղ��k�����Ă�������ɁA���Ƀ��V�A�Ɩf�Ղ����悤�ƍl�����c���́u�t�]�̔��z�v�́A�ێ�h����͂܂����������ł��Ȃ������͂��B���ɓ��ďC�D�ʏ����O�ɓ��I�C�D�ʏ���c���̂��ƂŌ���Ă����Ƃ�����A���̌�̓��{�j�͑傫���ς���Ă������낤�B
�@
�c�����r��A������M�͉ڈΒn�J���𒆎~�������A�ڈΒn�ߊC�ɕp�ɂɃ��V�A�͑D������ꂽ���Ƃ���A�ڈΒn�̌x���ɖ{������ꂴ��Ȃ��Ȃ�B1799�N�A���{�͓��ڈΒn�����O�˂��珢���グ�A���{�̒����n�Ƃ��A����1807�N�ɂ͐��ڈΒn(�k�C���̓��{�C�E�I�z�[�c�N�C��)�������n�Ƃ��āA���O��s��u���A�ڈΒn�̊Ǘ����n�߂�B���ʘ_�����A�c�������ڂ������Ƃ����Ƃ���Ȃ������悤�ȓW�J�ł������B�@ |
���c���ӎ��̏I���Ƃ��̈�Y
�@
�����Ԃ̏���A���𒆐S�Ƃ���ꔄ���̎��{�A�����A����f�Ղ̊g��A�A�o���Y���̈琬�A�ڈΒn�̊J���ȂǁA�c���ӎ����s�Ȃ����������v�͂قƂ�ǐ������Ă���B1770�N�ɂ́A���{�̔��~����171��7529���Ƃ����A5�㏫�R�j�g�ȗ��̍ō��l���L�^�B�i�C�͉��A�c����������ی삵�����Ƃŗ��w���ԊJ�����B
�@
�c���̖������v�́A�_�ƒ��S�̎Љ�珤�ƒ��S�̎Љ���n�������ƂɈӋ`������B���ɉݕ��̏d���łȂ��A�z�ʂ̋��z�������ݕ��̉��l���Ƃ���ݕ����v�́A���B�Ő��܂��o�ϊw�̊�b�Ɠ������_�ɂ���B�C�O�Ƃ̖f�Ղ��d�A�C�Y���Ȃǂ̉��H�i�Ƃ������t�����l�̍������i��A�o���A�O�݂��҂��Ƃ�������Ȃǂ͍����̓��{�o�ς̂��������肵�Ă������̂悤���B���{�ɂ����鏉�����{��`�̌`�Ԃ����̍��ɐ��܂ꂽ�ƌ���ׂ����낤�B����͑傫�Ȉ�Y�ł���B
�@
�c�������r�����ő�̗v���́A��؎R�A��ԎR�̕��Ɏn�܂�u�V���̑�Q�[�v(1782�`1788�N)�ɑ��A�L���ȑƂ�Ȃ��������炾�Ƃ���Ă���B��������������ɁA�}���ȉ��v���D�܂Ȃ��ێ�h�̔��������������Ƃ����킯���B�u�d����`����ɂ���Ĕ敾���Ă����_�������A����ɑŌ��������ނ����̂́A�c���̐������������炾�v�Ƃ����_���ł���B�Q�[�͎��R�ЊQ�����A�_�������敾���Ă����̂͊m���ɏd����`���v�����B���{�ɏ��Ƃ��蒅���A�ݕ����͂����悤�ɂȂ�A�o�ύ\�����傫���ω����鎞���Əd�Ȃ����̂ł���B
�@
�u�V���̑�Q�[�v�Ƃ́A�]�ˎ���ɋN�������ő�̋Q�[�B�����A���k�n���͓V��s�ǁA���ɗ�Q�ɂ��_�앨�̎��n���������Ă����B����ɔ��Ԃ�������悤�ɁA1783�N�Ɋ�؎R�Ɛ�ԎR�������A�e�n�ɉΎR�D���~��A�_�앨�ɉ�œI�Ȕ�Q���������B�d����`�����ڂɏo�āA�Q�[�͑S���K�͂Ɋg�債���B
�@
��Q�͓��k�n���𒆐S�ɁA����Ő����l�̉쎀�҂����܂�A�u�a�����s�B�ŏI�I�Ȏ��Ґ��͑S����30���l�Ƃ�50���l�Ƃ����肳��Ă���B���݂̊��o�ł�����300���l����500���l�̋K�͂��B�_�������瓦���o�����_���́A�e�s�s���֗������A�����������B�]�˂���ł͕ĉ��̑ł��������u�������B
�@
���̂Ƃ��c�����Ƃ�������́A�S���̕Ă��]���Ă���n��Ɍ����A�u���k�n���ɕĂ�ɂ��݂���ȁv�Ƃ������̂������B����Ȃ��Ƃɕĉ��͍������A������߂⍂�l�ł̔������͂т������B����͕Ă����Ȃ��Ȃ������牿�i���オ��A��������v����đ�ׂ����悤�Ƃ���҂��o���Ƃ����A�����V���v���Ȏs�ꌴ�����B���˂͍����ێ��̂��߁A�Ă���̎s��ɑ������B���Ƃƕ����̒��S�n�E��₪��������߂�ꏊ�ŁA���l�Ŕ�������Ă��ꂽ���炾�B�c���̃��C�o���A������M�͂��̋@�ɑ��ŕĂ̔�����߂��s�Ȃ����B�ނ͋g�@�̑������A�{�q�ɏo����A1783�N�A�܂�u�V���̑�Q�[�v�̍Œ��ɗ����E���͔˔ˎ�ƂȂ����B
�@
�Q�[�ɒ��ʂ��A�H���~�ϑ[�u��v���ɍs�Ȃ��A���͔˂ʼn쎀�҂͏o�Ȃ������Ƃ���Ă���B���j�̋��ȏ��ɂ͏�����Ă��Ȃ����A������M�͉�Ô˂̏����Ƃ����1�������A���Ŕ�����߂��ĂƂ��킹�āA���k�n���ɂ͕Ă𑗂邱�ƂȂ��A���͔˓������ŏ�����B�̓������l�̉쎀�҂��o���Ȃ����������͖��N��搂��A��@�Ǘ��\�͂������]������A���ꂪ���t����̕z�ƂȂ�B
�@
�c���ӎ��Ə�����M�͐����̎����������Ă���B�c���͊J���h�ŁA�g���ɂƂ���Ȃ����͎�`�Ɋ�Â��o�p�����݁A���c������O��Ǒ�ȂǗ��w�҂╽�ꌹ���Ȃǂ̍˔\���d���B�����ɂ͌���łȂ��A����𐄏������B���̓����ɕq���ȁu�����ۂ��v�ɂ��ӂꂽ�o�ϒʂł���B����A�����͐g�����x���q�w���d�����A���f����𐄏������B�d�_��`�Ɏ�����u���ێ�h�ŁA�C�O�Ƃ̖f�ՂȂLjӎ����Ȃ��l���ł���B�]�ˎ���̍�����`�Ƃ����������炷��A�c���͂܂��ɂ�������H�����l���B�d�G�����ƂƂ������b�e���͏����Ȃ����A�ނ̐���͐挩���ɂ��ӂ�Ă���B�@ |
���u�����̉��v�v�̌o�ϐ���
�@
�c���ӎ��̎��r��A����g�@�̑��Ŕ��͔ˎ�̏�����M���V������ƂȂ�B���͔ˎ�Ƃ��ċQ���ɐ����������Ƃ��A���F���ꂽ�傫�ȗv�����B���̐������́A�c���̏d����`��ᔻ��������������ێ�h�̃N�[�f�^�[�Ƃ�������B
�@
������M�͘V���ݔC���Ԓ��Ɂu�����̉��v�v�ƌĂ�開�����v��i�߂��B�c���E�g�@�����i�����u���ۂ̉��v�v�P�������̂ŁA���݂ɒu��������Ȃ�ُk�������B�o�ϐ���Ƒ���͂Ƃ��Ɂu�o�Ɂv�Ɓu�ْ��v���J��Ԃ��Ƃ������A�c���̏d����`����ɂ̏d�_��`�Ɉڂ������Ƃ́A���̒���ǂ���ł���B����ɂ��Ă����f�E����Ɣ_�Ƃ��d�鐭��́A���オ�t�܂�肵�����̂悤�ȗl�����B�c���̎a�V�Ȑ���̂��ƂŐi�������{��`�o�ς́A�����ł��炭�����B���������{���������v�����҂������ʂ������邱�Ƃ��Ȃ������̂́A���łɏ��Ƃ��傫�ȗ͂��l�����A�s�ꌴ�����@�\���͂��߂Ă������炾�B
�@
�����͊����Ԃ�ꔄ����p�~���A�������l��}�������B�ꌩ�K���ɘa�Ɏv���邪�A���Ǝ�̒��Ԃɂ�鋤���d����◬�ʐ��������ɂ����Ȃ�A���l�ɂ͂ނ���K���ƂȂ��Čo�ς͒����B�܂��c�������w���d���̂ɑ��A�����͎�w�̂����_�ƂƏ㉺�̒������d��������q�w�ȊO�F�߂��A���{�̖�l�̓o�p����q�w���w�҂Ɍ������B������u�����يw�̋ցv�ƌĂԁB����ɏo�ł��������������A���̖̉��̕����G�𐢂ɍL�߂��Ō��̒Ӊ��d�O�Y�͔���������Ă���B
�@
���̈���Ŕ_���ƌ�Ɛl�~�ςɂ͈��̌��ʂ��������B��Ȑ���Ɋ��o�߁A�����A�_�߁A�͕ĂƎ����ϋ�������B���o�߂́A������Ɋׂ������{���Ɛl���~�ς��邽�߁A6�N�ȏ�O�̍��j���Ǝ؋��̗��q�̈��������𖽂���Z�[�t�e�B�l�b�g�@�߂��B�]�ˋ��Z���`���Â����Ă������{�E��Ɛl�́A�y�n�⌻�āA������������Ă���Ƃ͂����A�]�˂ł͉������Y���Ȃ�����ҁB�������オ��ΐ����͋ꂵ���Ȃ�B�����̉��v�Œ������ɂȂ������{���Ɛl�̎؋��̊z�͖�120���B
�@
���݂̋��z�Ɋ��Z����Ɩ�1���~�B���{�̔N�Ԏx�o�Ƃقړ��z�������悤���B���̐��x�ɂ���đ傫�ȑŌ������̂��A���m�Ɏx�������Ă̒�����d���Ƃ����D�����B�ނ�͕Ă̒���ɂ��萔�������A���Ă�S�ۂɍ����݂����c��ł����B����u�Ă̗��֏��v�ł���A�u���Ɛ��̊X���v���B�D���́A���̐��x�ɂ���ė��v�����������̂ŁA���{���Ɛl�ɑ݂��t�����s��Ȃ��Ȃ�B
�@
�����A�_�߂͍]�˂֑�ʂɗ��������n���o�g�̔_�������Ɏ�����^���ċA�_������t�^�[������B�͕Ă͏��˂̑喼�ɋQ�[�ɔ����邽�߁A�e�n�ɑq�ɂ�z�����A�����̔��~�𖽂������̂ŁA���炪�̌������Q�[�̋��P���瓾�����X�N�w�b�W�ł���B�����ϋ��͒��P�ʂŐςݗ��Ă鋤�ς̂悤�Ȃ����݂��B�����p�̌o���ߖ��l�����̎����ɁA���{���x������1�����������Ċ���Ƃ����B����͎�ɐ�����n�V�S�̔�p�A���̊|���ւ��C�U��ȂǃC���t�������Ɏg��ꂽ�B����͋g�@�����R����ɓ쒬��s�E�剪���������{��������̉����ɂ�����̂��B
�@
����A���o�߂ɂ���đŌ��������ނ����D�����~�ς��邽�߁A���{�͐E�������Ɂu��������ݕt����v��ݒu�����B����͍��������D���Ɍo�c������Z�����開�{�̋@�ւŁA��ݗ��ɏo�������͍̂]�˂̍����������B���{�E��Ɛl���~�ς���@�߂̎��ɁA�D�����~�ς���@�߂��o���ꂽ���Ƃɂ͖�������_�����邪�A�D�����|�Y����ƕ��m�ɋ���݂����ԋ@�ւ��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������̍�Ƃ����悤�B
�@
���������̐���̓q�b�g�����B�D������������ƕ��m���������A�ő�̏���҂ł��镐�m���n�����Ȃ�ƁA���l�����|��ƂȂ邱�Ƃ���A��͎D���ɐϋɓI�ɑ݂��o���������̂��B���{�ɂƂ��ẮA�������������A�����̎����ŎD�����~�ςł��A����Ɋ��{�E��Ɛl���~����Ƃ����čD�s���̐��x�ƂȂ�A��������ݕt����͖����ېV�܂Ōp�����ĉ^�c���ꂽ�B������M�̌o�ϐ���̒��ł́A�ő�̃q�b�g��Ƃ����悤�B�@ |
���đ��
�@
�]�ˎ���̖��ˑ̐��́A���얋�{�Ɛe�ˁE����E�O�l�̏��˂ō\������Ă���B���{�̉��v�͑喼�̉��v�ł���A����Ƃ̒����n�ł���]�˂̉��v�ł��������B���˔ˎ�̈ʒu�Â��́A�S�������쎁�̎P���ł��邪�A�]�ˏ�Ζ���������ꂽ���b�ȊO�́A����Ύ����̂̒��Ƃ��Ċe�˂̌o�c�ɐ�O�����B���{��300�N�����������R�̂ЂƂɁA���˂��N�v�ƎQ�Ό��Ƃ����`���𐋍s���Ă���A����ȊO�͔ˎ�ɔː����ς˂����Ƃɂ���B�����n�͕�s��㊯�����������Ƃ��Ĕh�����ꂽ���A����ȊO�́u�n���̐����͑喼�Ɉ�C����v�Ƃ������������d���̂��B���ꂪ�u�����Ȑ��{�v���������������̂ЂƂł���B�ꕔ�̔˂ɂ͖��N�▼�ƘV������A���̔˂̎�{�ƂȂ����B
�@
�ł́A���N�E���ƘV�̔ˍ������v�����炭�̂������A�Ђ��Ƃ��Ă݂悤�B�܂��A�đ�˂���n�߂悤�B1767�N�A�㐙��R(�悤����)��17�Ŕˎ�ƂȂ����Ƃ��A�˂̍����͔j�Y���O�ł������B�Ɛb�������A�ނ�̐l����傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă����B�܂��O�ˎ�E�㐙�d�肪���Ƃ̌ւ肩���ґ�Ȑ����𑱂������Ƃ����Ԃ��������B��R�͏㐙�d��̗{�q�ł���B�ˎ�ƂȂ�����R����|�����̂��A�Y�ƁE�����ɋ��������̏d�p(����Ή��v�u���[���̔��F)�A����A�A�_�̏���A���Y���̈琬�Ȃǖ������Ƃ��B
�@
�����́u�V���̑�Q�[�v�̍Œ��ŁA���k�n���ɂ͑����̉쎀�҂������B��R�́A���H�Ƃ��ă^���m�L�A�R�V�A�u���A�n���M���A�`���E�Z���j���W���A�g�`�o�j���W���A�E�h�Ȃǂ��H�ׂ��邱�Ƃ�˓��ɃA�i�E���X�B������y�n���k�����B�����A�đ�̖��Y�ƂȂ��Ă���R���B����ɕđ�˂̓��Y���ł������R�E�]�A���A���E��10�N�Ԃ�5�{�ȏ�̐��Y�ʂɂ���v��𗧂Ă��B�R�E�]�͘a���̍ޗ��A���͎��h�Ɍ������Ȃ��������B�܂��^����J�ɋ����K�͔̍|�𐄏����A�K���G�T�ɂ��Ĉ�{�\��ɂ��A�D���̕��y�ɗ�B
�@
�����ɋQ�[�̍ۂɌ������N�v�̎�藧�Ă͔_���̃��`�x�[�V�����̒ቺ�ɂȂ���Ƃ��āA�N�v�̎�藧�Ă��ɘa�������ŁA���Y���̑��������_�n�̑�\�҂ɖJ�܂�^�����B���̈���ŁA�Q�[�ɔ����A�Ă̔��~���s�Ȃ����B�܂��A�ߗ܌����ܐl�g�Ƃ��đ��݂ɏ��������A���S�̂������̂Ƃ��ċ�y���Ƃ��ɂ���u�Y�g���v�ƌĂ��_�����݂̕}���g�D�������������B����ɔ_�n�̕����̂��ߗ��������҂��Ăі߂��A�_�ƈȊO�̎����Ƃ��āA��H�ƋZ�p�̓����ɂ��͂𒍂����B
�@
�ނ͊�@�Ǘ���ƎY�ƐU�����ɍs�Ȃ����̂ł���B���ɍ������v�ƃ��X�g���ɒ��肷��B�܂�ő��{�̋����m���̂悤�ȓW�J���B�]�˔˓@�̈�N�Ԃ̌o��1500����200���ɐ�l�߁A�l�������V�����B���̍ہA���߂����Ō��f�������ƂɈ٘_�����������Δh���������A���X�g���ɂ������B�����Ċw�⏊��ˍZ�E�����قƂ��čċ����A�ˎm�E�_���Ȃǐg�����킸�w����w�����B����͋�����v�A�l�ވ琬�̕��B�V�c�̊J���A�͐�̉��C�A���̊|���ւ��Ȃnj������Ƃ́A���m���擱���čs�Ȃ����B
�@
�V�l��a�l�A�D�w�Ȃǂ̎�҂��d�����镟������̏[�������H�����B��R�͔˓��e�n�Ɋ��I�̈�t�������A�ނ�ɑ�n��^����ƂƂ��ɗD�������B�܂��玙����������o���A�q������Ă��Ȃ��n�����_���ɂ����^���邱�Ƃɂ����B����ɓ����Ȃ��Ȃ����V�l�́A�u�����炵�v�̂��߁A�����Ζ�R�Ɏ̂Ă�ꂽ���A��R��70�Έȏ�̘V�l�͑��ŐӔC�������Ă�����萢�b����悤�N�����x��҂ݏo�����B
�@
�����̐���ɂ���āA��R���ӔN�̍��ɂ͍����ƂȂ�A�j�]���O�̔ˍ����͗�������A�؋����ԍς����Ƃ����B�㐙��R�͐����ƂƂ��Ĉꗬ�ŁA�����܂Ŗ��N��搂��Ă���B�������������v�ɖ��{�͌����o�����Ƃ��Ȃ������̂́A����Βn���������m�����Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B��R�������ɎQ�悵�Ă���A�������v�͂����Ƒ�_�ɐi��ł�����������Ȃ��B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
�����R��
�@
�u�փ����̐킢�v�Ő��R���瓌�R�ɐQ�Ԃ�A���R�����̂��������ƂȂ���������G�H�����˂������R�ˁB�G�H�͎q���Ɍb�܂�Ȃ��������߁A���R�̕����Ƃ��đ傫�Ȍ��т��������r�c�P����{���Ƃ���r�c�������R�ˎ�ƂȂ�B���N��搂�ꂽ�r�c�����́A�d���P�H�ˑ�3��ˎ�A��������ˎ�A���O���R�ˏ���ˎ�߂��啨�O�l�喼�Ő����Ƃ��B
�@
�������喼�̏h���Ƃ��āA���{����^����ꂽ�˂Ɂu���ւ��v�𖽂�����A�]�킴��Ȃ��B�喼�͓���Ƃ���ˎ�ɔC������A�e�˂ɔh�������`���B�������O�̔˂Ŕˎ�߂������Ƃ͒������B���݂Ȃ畺�Ɍ��A���挧�A���R���̒m���ɑ����ďA�C�����悤�Ȃ��̂ł���B
�@
�r�c�����͉��R�ˎ�߂�10�N�ԂŔ˂̉��v�𐬌������A�����܂ő����r�c���x�z�̐����m�������B�����̐����̊�{�́A���f����A����̏[���A�V�c�J��A�Y�ƐU���A�L�\�Ȑl�ނ̓o�p���B�ł��L���Ȃ̂��A1641�N�ɑS�����̔ˍZ�u�Ԕ�����v���J�Z�A�����ɏ����̂��߂́u��K���v��˓����S�J���ɂ���A�̂��ɓ��ꂵ��1670�N�ɓ��{�ŌÂ̏����̊w�Z�u�ՒJ�w�Z�v���J�Z�������Ƃ��B
�@
�ՒJ�w�Z�͔˗��̊w�Z�Ƃ��ăX�^�[�g�������A�ˎ傪�������ꍇ�ł��w�Z����������悤���ʂɁu�w�Z�́v��݂��A�ˍ������Ɨ��������B�w�Z���L�̓c����т��瓾�������Ŋw�Z�̉^�c���܂��Ȃ���悤�ɂ����̂ł���B�{�݂̌��z��Ɛl�ޕ�W�͔˂��s�Ȃ��A����u�����w�Z�v�Ƃ��ăX�^�[�g�����A�O���ɏ��Α�O�Z�N�^�[�̋@�ւ��u�����w�Z�v�Ƃ��ēƗ��̎Z�ʼn^�c���Ă����Ƃ����������B����͐��E�I�ɂ�����I�ȃV�X�e���ł���B
�@
�����͊w��D���̑喼�������̂ŁA�w��̑���𗝉����Ă����̂��낤�A�����̎q����ɕw�������߁A��l��x���̎q���ɂ͌�15���͊w�Z�ɒʂ����Ƃ��`���Â����B�ˎ�̖��߂ƂȂ�A���`������ł���B�]�ˎ��㏉���ɂ���قNj���ɗ͂𒍂����喼�͂��Ȃ��B�]�˖��{���ˎ�̌��⎩�����d���Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B
�@
���݁A���R�����u���猧�v�ƌĂ��̂́A���q���A���m�A�������w�Z�̐���������葽���A��w�E�Z��̐ݒu��(�l��10���l������)���S����6�ʂƍ��������ɂ��邩�炾���A���͂��̊�Ղ�z�����̂������Ȃ̂��B�ނ͉ƕ��͖������A�L�\�Ȑl���F�����B�z���w�ҁE�F��R��ԓ��ɏ����A��ה_���̋~�ς⎡�����ƕ���ƔˍZ�u�Ԕ�����v�̉^�c��C�����̂������̎�r���B
�@
�����̐����ɂ���ĉ��R�˂̔ː��͈��肵�A���W�������A��˂Ƃ��Ȃ�Ύx�o���傫���A�����̒��j�ő�2�㉪�R�ˎ�ƂȂ�r�c�j������������Ɠ��p�������ɂ́A������Ɍ������Ă����B�j�����肪�����̂́A�_���Č����B�����A���R�˂͍^�����������A�Ă̎��n�ʂ��������Ă����B�����ōj���́A�����p�����A�S�Ԑ��q����̎����H���Ȃnj������Ƃ��肪�����B�����̌������Ƃ��˓��Ōٗp�ݏo���A�^���̔�Q������ł���V�c���_�����Đ��Y���ʂɓw�߁A�_������͐��������B�ϋɓI�Ȍ��������ȂǂŌo�ς��x����P�C���Y���_�Əd�_���~�b�N�X�������̂��B
�@
�j���͑��c���Ƃɂ��M�S�ŁA1700�N�A�̂��ɓ��{�O�喼���ƌĂ��u��y���v�����Ă���B�����E�j���e�q�̕⍲���Ƃ��ďd�p���ꂽ�Óc�i�����y�؎��Ƃō˔\�����A�S�Ԑ�̊J���ՒJ�w�Z�̌��݁A�V�c�J�����Óc���ӔC�҂Ƃ��Ď��{�������ƁB�Óc�͂����̐������F�߂��A�S��(�\���Έȏ�̑㊯)�ɏo�����A�O�o������y���̑����ɒ��肵���B�@ |
���F�{��
�@
�F�{�˂́A�u�փ����̐킢�v�Ő��������������������52���Ēz�����ˁB����̗_�����F�{���z�邵���̂��������B���̌�A�����Ƃ̒f��ɂ�菬�q�˂���א쒉�����������A�p�˒u���܂ōא�Ƃ��ˎ�߂��B
�@
�F�{�˂̍����͏�Ɋ�@�I�ɂ������B�Ђ炽�������u�n�R�ˁv���B����4�㏫�R�א��I�̎���ɁA�Q�[�A�C�i�S�̑唭���A�^���A�u�a�A�䕗�����đ����ɋN����A40�����߂��؍���������B���݂̋��z�Ɋ��Z����Ɩ�320���~�B���Ȃ�[���s�̂悤�Ɂu�����Č��c�́v�Ɏw�肳��邾�낤�B
�@
���̂悤�ȋٔ�������Ԃ̒��ŁA���Z��5��ڔˎ�̏@�F���}���������Ƃ�6��ˎ�ƂȂ����א�d���́A�u���̉��v�v�ƌĂ��ː����v�𐋍s����B��ɖ��N��搂���d���́A�đ�˔ˎ�㐙��R�̎�{�ɂȂ��������Ƃł���B
�@
����g�@���剪�����F�����悤�ɁA�d���͂܂��x������M����s�ɔ��F����B�x�͔��Δh��}����6�l�̕�s�Ɍ������W���������B�g�D���v���s�Ȃ��A����ʃ}�l�W�����g����~���A���ߌn���̍č\�z�����݂��̂ł���B
�@
��s�ɔC�����ꂽ�x�́A���Ɍ������A�����̍����ő�̍����E���r�ƂɎؓ���\���o��B���������r�͗v�������ہB�F�{�˂ɕԍϔ\�͂͂Ȃ��ƌ������炾�B�x�͂������ܕĖ≮�Ɨ��֏������Ƃ���������Ɍ�����B�]�ˎ���́u�喼�݂��v�́A�\�����M�p�݂��ł��������A���ۂɂ͑��Ă��S�ۂɂȂ����B�x�͌F�{�˂̔N�v���������ɓn�����Ƃ������Ɏ�����B�x�͍����Č��̎�r���F�߂��A�̂��ɉƘV�܂ŏo������B
�@
�d���͎��f����𐄏����A�]�˔˓@�̔�p�Ɍ��x�z��ݒ�B�Ă����Ɉˑ����邱�ƂɌ��E���o���Ă����d���́A�B�Y���Ƃ𖽂���B�����A���E�\�N�̌����ɂȂ锥(�͂�)�A�a���̌����ɂȂ�R�E�]�Ȃǂ�ꔄ���ɐ�ւ��A�˂������I�ɔ����グ���B�����̌������d���ꂽ�˂́A����������肽���������ɂ��Č��݂����ˉc�H��Řa����E�\�N�Ȃǂɉ��H���A���̉�������ʂ��ĔˊO�ɗA�����A�傫�Ȏ������B�d���́A�����Ƃ̐U���Ɨ��ʐ���������Ă̂����̂ł���B�˂����[�J�[�ƂȂ�A���������u���[�J�[�ƂȂ��āA���i�𗬒ʂ�������@�͉���I���B���̉��v�ɂ���č����͍D�]���Ă����B
�@
�d���͍������v�݂̂Ȃ炸�A�����@�����v�����{�����B�F�{����ɔˍZ�u���K�فv���J���A����������ΐg���ɊW�Ȃ����Z�ł���悤�ɂ����B����Ɍ��݂ł����u���w�����x�v�����A�l�ވ琬�ɗ͂𒍂����B�܂��A��w�Z�u�ďt�فv���ݗ������B�̂��ɌF�{��w�Z���o�ČF�{��w��w���ƂȂ�B���Ȃ݂ɌF�{���̖�i���[�J�[�u�ďt�ِ��v�́u�ďt�فv�ɂ��Ȃ�Ŗ�������Ă���B�܂��A1883�N�ɌF�{���Ő��܂ꂽ�A�u���{�ۊw�̕��v�k���ĎO�Y�͌F�{�ˍZ�u���K�فv�A�F�{��w�Z���o�āA���݂̓����w���ɐi��ł���̂ŁA�d���́u���{�ۊw�̕��v�̕��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
����ɏd���͍s���Ǝi�@�����A�Y�@�����肵���B����܂ł̌Y���́A���Y���Ǖ��Y�����Ȃ��������A������݂��Č��Y���x������A�ߐl�̎Љ�A��e�Ղɂ����B���́u�Y�@�p���v�͖������@���̌Y�@�̎�{�Ƃ���A�F�{�����瑽���̐l�ނ��@���E�ɍ̗p���ꂽ�B
�@
���̂悤�ɕ��L������ʼn��v�����{���A�n�R�˂��ċ������א�d���̐����ƂƂ��Ă̎�r�͌��݂������]������Ă���B�א�Ƃ͖����ɓ���A��݂̈ʂɂ��ؑ��ƂȂ�B���Ȃ݂ɁA��79����t������b�̍א��ꤎ��́A�א�Ƒ�18�㓖��B�F�{���m������u���{�V�}�v��\�Ƃ��ďO�@�I�ɗ���₵�ē��I�B�t�����o���ɎɂȂ����B���E���ތ�́A���|�ƂƂ��Ċ��Ă���B���̈炿�̗ǂ�����u�a�l�v�ƌĂꂽ���A�p�˒u�����Ȃ��A�א�Ƃ��ˎ�̂܂܂ł������Ȃ�A�ԈႢ�Ȃ��{���ɓa�l�ɂȂ��Ă����l���ł���B�@ |
���F����
�@
�O�l�喼�̒��ʼn����(102����)�Ɏ�����90����z�����̂��F���˂��B�F���˔ˎ�́A���q����ɓ��n�̎��ɔC����ꂽ���Î����B���Î��͍]�˖��{���J����Ĉȍ~�ɗ��������������A�������������Ƃ̖f�Ղ��J�n�������Ƃ���A���Ƃ��Ɩf�Ղ̃Z���X���������悤���B�����Y�̍����ŗ��v�������Ă����Ƃ����B
�@
�������A�˓��̓y�낪�_��Ɍ����Ȃ��ΎR�D�w�ł��������߁A���ۂ̐��͔������x�������Ƃ����Ă���B�F���˂قǂ̑傫�Ȕ˂̍������ꂵ���������R�́A�䕗��ΎR�̕��ȂǍЊQ���₷�����n�ł���������łȂ��A���{�̑�K�͂Ȍ������Ɓu��`�����v�ɋ��o����A�傫�ȏo����܂�Ă������炾�B����R���c�F�����̖��߂ŁA���쎁�̗̓y�̓y�؍H����������ꂽ�̂ł���B�������A����͊O�l�喼�������═�͂�~�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̐헪�ł���B
�@
���͑傫�����A���Ԃ́u�n�R�ˁv�������F���˂̔ː����v�ɒ��肵���̂́A10��ˎ哇�Ðċ�(�Ȃ肨��)�ƁA11��ˎ哇�Ðĕj(�Ȃ肠����)���B�ċ����ˎ�ƂȂ��������A500�����ɂ��y�Ԕ���Ȏ؋�������A�j�]���O�������B���݂̋��z�Ɋ��Z����Ɩ�4000���~�B
�@
���S�Ɂu�����Č��c�́v�ł���B�ċ��̕����ł���ƘV�̒����L���́A���l���������Ď؋����q��250�N�̕��������Ƃ�������ŁA������ʂ��Đ��Ɩ��f�Ղ��s�Ȃ��A���v���������B�哇�⓿�V���Ŏ��n�ł��鍻����ꔄ���ɂ��č������v��i�߁A250�����̒~�����ł���܂ō����͉���B�����L���́A�����̋~����ł���Ȃ���A�f�[�^�B�[�ȑ��ʂ����������Ă����悤���B
�@
���̐ċ��ƒ��������r�������̂��A�ċ��̒��j�Ƃ��č]�ˎF���˓@�Ő��܂�A��������Ðĕj���B11��ˎ�ƂȂ����ނ��ł��o��������́A�����ꔄ���̋����A�����f�Ղ̊g��ɉ����A�����Ƃ��Ă͉���I�Ȏ��ƁA�H��Q�̌��݂������B�������~����������m���̔ˉc�H��̐ݗ��ɓ������A�������鉺�̈�n��ɍH��Q��z�����̂��B�̂��ɢ�W���َ��Ɓv�ƌĂꂽ���B
�@
���݂��ꂽ�H��́A���D�E���S�E�e�C�E�d�́E�a�сE�K���X�E�H�i�E�o�ŁE��ÂȂǑ���ɂ킽��B�����̍H��͒n��Y�Ƃ̈琬�Ƃ������ʂƁA�u�x�������v������ɋ���������̂Ƃ�������B�����ׂ��́A���D��n�z�F�A�K���X������K�X�������ȂǓ����̉Ȋw�Z�p�̍Ő�[���W�܂��Ă��邱�Ƃ��B�����Â����Ƃ������A�������鉺�̈�n��́u�V���R���o���[�v�̂悤�ȗl���������̂��낤�B
�@
�ĕj�͌R���ɂ��͂����A�I�����_����R�́u���Պہv���w�����A�C�h�̋�����}�����B�܂��A�Ǝ��ɐ��m���D�u�ɘC�g�ہv�A���m���R�́u�����ہv���������A���얋�{�Ɍ��サ���B���ꂾ���̐�����ЂƂ̔˂����s�����̂�����A�]�ˎ���͐����ʂł͔˂̎���������A�ˎ��̂��u�����Ȑ��{�v�ł��������Ƃ����������m���B
�@
���m�K���o�g�̐����������v�ۗ��ʂ�o�p�����̂��ĕj���B���Ȃ݂ɁA�u���ۣ̊����{�D�͂ɂ��悤�Ɩ��{�ɒ�Ă����̂��ĕj�ł���B����ɐĕj�͌��݂ł����Ƃ���́u�m���l�b�g���[�N�v������A����ˁA�F�a���ˁA�y���ˁA���˔ˁA�����˂�Ə�ɏ��������A�����ɂ��ϋɓI�Ɍ������B���̃g�����h���̂��ɓ|���̓����ւȂ����Ă����̂ł���B
�@
�ĕj�͍�������̔p�~�ƂƂ��ɍ��h�̈ӎ������������悤���B����ɂ��Ă��A�ˎ傪�H�ꌚ�݂ɓ�������Ƃ́A��������ʂ���͂ɗD��Ă����l���ł���B�����ɎF���˂��V�^�̏��C�D��S�C�A��C���ʂɕۗL�ł����̂́A�ĕj����W���َ��Ɓv�ɂ���Đ��i��̔����A���͂�~��������ł���B�@ |
���y����
�@
�y���˂́A�u�ւ����̐킢�v�̍ۂɓ��R�ɂ����R����L�����쎁����^����ꂽ�̒n���B�ː����m�������̂́A���ڔˎ�E�R�����`�̎���B��s�̖쒆���R�ɖ����āu���i�̔ː����v�v�𐄐i���A���ꂪ�����������ƂŔ˂̍����V�X�e�����ł����������̂��B
�@
���R�̕]���́A��ɕ������B�ЂƂ͔�ނ̂Ȃ������ƂŁA�y���˂̌o�ϓI��Ղ��`���������ƘV�Ƃ�����́A�����ЂƂ͔ː����x�z���ė̖��̔������������Ɉ��l�Ƃ������̂��B
�@
�O�l�喼�ł���y���ˎR���Ƃ́A���쎁�����K�͂Ȍ������Ɓu��`�����v�ɋ��o����Ă����B�܂��A�n���I�ȏ�������Q�Ό��ɂ������p������ł��������߁A������ɔM�S�ł������B�F�{�˂�F���˂̂悤�Ɏ؋��̑����u�n�R�ˁv�ł͂Ȃ��������A�x�o�����������̂��B
�@
���R�̔ː����v�Ō��ʂ��������̂́A�܂��V�c�J�����B�y���˂͐��c�����Ȃ��A�R�ԕ��͔��Ő�߂��Ă����̂ŁA�Ă��s�����Ă����B���R�́u�ւ����̐킢�v�ȑO�̋��̎�E���@�䕔������̍����m�Ŕ_�������ɂȂ��Ă���W�c��V�c�J���Ɏ�藧�āA�N�v�̒����ɓ����点���B���Ԃ���̖�l�o�p���B����͐V�����̎�ƂȂ����R���Ƃ������ނ�̕s�����������邱�ƂƁA�_���x�z�A�V�c�J���ɂ�鑝������x�Ɏ����ł�������B
�@
���Ɍ��ʓI�������̂��A�`�p�̉��C�A��h�̌��݁A�p���H���݂Ȃǎ������ƂƖ؍ނ̈琬�E�̔����B�z�`�ɂ���Ĕ˓��̓��Y����D�ŏ��˂ɉ^�Ԃ��Ƃ��\�ɂȂ�A�܂��ˊO���珤�i������邱�Ƃ��e�ՂɂȂ����B���ɒ��肩����������́A�y���˂ɂ͋M�d�i�������B
�@
�X�ьo�c���瓾�����v�́A�˂̍����ɂ��Ă��B���R���D��Ă����̂́A�؍ނ��`�ɏW�߂邽�߂ɐ�ɉ͐�����C�������ƂƁA�ނ�݂Ȕ��̂ɂ��R�̍r�p��h�����ߍޖ؋Ǝ҂Ƀ��[�����߂����Ƃ��B�g���b�N�̂Ȃ��]�ˎ���A���̂��ꂽ�؍ނ͏㗬���牺���ɗ����ꂽ�B�삪�A�����[�g�������̂ŁA�͐���C����ɍs��ꂽ�̂ł���B���R�͓����ɐA�т𐄏������B�䕗�̑����y���ɂ�����A�т͖h���тƂȂ�A�C�݂̓y������h�~�̂��߂ɂ��K�v�ł������B���m���Y�̍ޖA���Ƀq�m�L�Ǝ������݃u�����h�ɂȂ��Ă���̂́A���R�����������u�X�т̊Ǘ��v�Ƃ����l�������Z����������ł���B
�@
�܂��A�ߌ~�A����A�{�I�A���߂Ȃǂ̋Z�p�̈ړ���ϋɓI�ɐi�߁A�ꔄ�������������B�y���̕ߌ~�͍]�ˎ��ォ��L�������A���͋I�B�̑��n�Ő��܂ꂽ�g�D�I�ȕߌ~�@����{���B�~�̓r�W�l�X�ɂȂ�ƌ������R���A�ߌ~�@��"�Z�p�A��"�����̂��n�܂�ł���B�{�I�́A�~�J���A�����Q�A�r���Ȃǖ������L�x�Ȓn��ɓK���Ă���A�y���̒g�����C��͗{�I�ɍœK�������B���݁A���m���̗{�I�͓��Y���ƂȂ��Ă���B�ق��ɒ��A���A���Ȃǂ�ꔄ���ɂ��Ĕ˂Ŕ����グ�A�]�����ė��v���������B�����̐���ɂ���Ĕˍ����͍D�]���A�����ېV�ɂ�����܂œy���˂̌o�ϓI��ՂƂȂ����B
�@
���̈���ŁA���R�ɂ͑����̔������W�܂����B�ߍ��Ȑł̒����A�ĉ��̓����A�Ă̔���ɂ��݂̋֎~�A�ґ�̋֎~�Ȃǂ̐��̖��ɕs����A�������̂��B�܂��A���⊏�߁A�����̐ꔄ���̋��s�ɂ���āA�����E���l�E�E�l�̂���������ꋫ�ɗ�������邱�ƂɂȂ����B
�@
���ڔˎ�E�R�����`���B����A���R�͔ނɕs�������ƘV�ɂ���Ēe�N�����B�ː����v�͐����������A�l�I�ȍ��݂����Ƃ������Ƃ��B���̎�����{���I�ȕ����͕ς��Ȃ��悤���B�@ |
�������Ɩf�� �Èɖ���
�@
�]�˖��{�̊O�𐭍�Ƃ����A�O�㏫�R�ƌ����|���g�K���D�̗��q���֎~�����������L�����B���{�����Ԃ̎��R�f�Ղ��K�����邱�Ƃ́u�����Ȑ��{�v�̕����ɔ����邪�A���E�f�Ջ@��(WTO)��FTA(���R�f�Ջ���)�̂Ȃ�����A���B�ɂ��f�ՖړI�̐N�������s���Ă������Ƃ��l����ƁA�����̈Ӗ��͕ς���Ă���B�|���g�K����C�M���X�A�I�����_�A�X�y�C���ȂǓ����̗̐A���n�ɂȂ�Ȃ������͍̂��������������炾�Ƃ���ӌ�������B
�@
�܂��A��������܂ł̓��{�͗A���卑�ŁA���₪��ʂɊC�O�ɗ��o���Ă����̂ŁA�f�ʂ��K�����ė��o��j�~���邵���p�͂Ȃ������Ƃ�������������B�����̓��{�͐��E���w�̋���̎Y�o���ł��������߁A����̏��x�̍����ݕ��𒒑����Ă����B�f�Ղ��s���A���₪���o����͓̂��R�̂��ƁB
�@
����ɁA���R�͂��Ƃ�薋�b�ɊO��\�͂��Ȃ���A�]�v�ȊO�������Čo�ς�����������A�O�������Ȃ��������s��ւ̉�������Ȃ��������ł������Ƃ�������B�]�ˎ���ɍ��Ƃ̑��S�ɂ������悤�Ȏ������Ȃ��A���a�������������̂ŁA�Y�ƂƋ��Z�����W���A�ߑ㉻�̊�ՂƂȂ����͎̂����ł���B
�@
�f�Ղ��K�������Ƃ͂����A���ۂɂ͈ȉ���4�̃`�����l���Ŗf�Ղ͍s���Ă����B1.����E�o���|�I�����_�D�A�����D�̑����B���{�̒����n�Ŗ��{�̊Ǘ��Ŗf�Ղ��s��ꂽ�B2.�Δn�|���N�Ƃ̑����B�Δn�˂̏@�����Β��N�O���E�f�Ղ̒���҂ƂȂ����B3.�F���|�F���ˁE���Î����������x�z�������ƂŁA������ʂ����f�Ղ��s��ꂽ�B4.�ڈ|���O�˂ɂ��ڈΒn�ł̖k���f�Ղ�����ł������B
�@
�Ȃ��ł�����E�o�����[�g�́A���{�̓��Y�������O���ɓ͂���M�d�ȃ��[�g�������B���Ƃ��]�ˑO���ɔ�O��(�����ꌧ)�ŏĂ��ꂽ�Èɖ����̎M�̔j�Ђ��A���L�V�R�Ō������Ă���B�Èɖ����̌����Ƃ������������ʁA���̕��l����1660�N�`1680�N���ɗL�c�Ő��Y���ꂽ����ł��邱�Ƃ������B�ł́A�Èɖ����́A�ǂ����č����̂Ȃ��������L�V�R�܂ł���ė����̂��낤���H���͂��̓�ɂ́A�����Ƒ�p�ƃt�B���s�����[���������A��������J�M�̓X�y�C���l�������Ă����B
�@
���̔��������烈�[���b�p�Ő��Ȑl�C���ւ�������̐��Y���ł��钆���́A�����琴�ւ̈ڍs���ԁA���Ԗf�Ղ��ւ���C�֗�(1656�N�`1684�N)�߂����B�����Ŕ�O���̎���̎Y�n�ł́A�������i�̑�p�i�Ƃ��ėA�o�������i������ꂽ�B�����̓��{�͍�����Ԃ��������A�I�����_�D�ƌ��F�̒����D�̂ݒ���ւ̗��q��������Ă����B1647�N�ɂ́A�������l�ɂ���ăJ���{�W�A�ւ̈ɖ����̗A�o���n�܂�A��p�o�R�Ńt�B���s���ɂ��^�ꂽ�B1659�N�ɂ̓I�����_���C���h��Ђ��n�m�C(�x�g�i��)�ɔ[�߂��B���ꂪ�l�C���ĂсA1659�N���璆����[���b�p�֑�ʂ̓��{�����킪�A�o���ꂽ�B
�@
�������{�ƃX�y�C���͒��ڂ̌��Ղ͂Ȃ��������A�t�B���s���ƃ��L�V�R�͂Ƃ��ɃX�y�C���̐A���n�������B���F�̒����D�����肩���p�܂ŌÈɖ������^�сA���ɃW�����N�D����p����}�j�����i��͂���B������w�������X�y�C���l���}�j�����烁�L�V�R�܂ňɖ������^�̂��B
�@
�X�y�C���̖f�ՑD�͓����A�}�j���ō��h���⌦��ς݁A�����m���[�g�Ń��L�V�R�ɉ^��ł����B���̑D�ɌÈɖ������ڂ����Ă����̂��낤�B�����ă��L�V�R�̃X�y�C���l���A�������i�̑�p�i�Ƃ��ČÈɖ������g�p�B���̔j�Ђ����߂�ꂽ�B���L�V�R�Ō��������Èɖ����̔j�Ђ́A�����������f�Ճ��[�g����Ă���B
�@
������Ԃł������Ƃ͂����A���E�̖f�Ղ͊�����悵�A���{�̐��i���C�O�ɗA�o����Ă����Ƃ������Ƃ��B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
�����N�ʐM�g�ƒ��N�O���E�f��
�@
���N�������]�˖��{�ɔh�����������̊O���g�ߒc���u���N�ʐM�g�v�Ƃ����B�G�g�̒��N�o���ɂ���Ēf�₵�Ă������������A�ߗ���Ԋ҂����̂��ƍN�������B�ƍN�͊O���ɐϋɓI�ŁA����(��)�⒩�N�Ƃ̖f�Ղ͕K�v�s���Ɣ��f���Ă����悤���B�܂��A�f�ՖʂŒ��N�ւ̈ˑ��x�̍����Δn�˂ɂƂ��ẮA�����͔ߊ肾�����B�Δn�˂�����A�ƍN�͒��N�̎g�҂Ɩʒk�B���N�ʐM�g������邱�Ƃ����肵���B1607�N�ȍ~�A1811�N�܂Ŗ��{�͌v12��A���N�ʐM�g������Ă���B
�@
���N�ʐM�g�͏��R�̌��␢�p���a���̍ہA���R�Ƃ��j�ꂷ�邽�߂ɂ���Ă����B���[�g�͊��R-�Δn-���˓��C-���-���ƍq�s���A�����痤�H���s��B���s���瓌�C�����킽���čs�����Ƃ���A�s�̂������̌�y�ƂȂ�A�Ђ��Ă͏��R�̌��Ђ��֎����邽�߂ɗ��p���ꂽ�B���������~���Ă���́A���ڒ����嗤�����ɂӂ�邱�Ƃ�ł���M�d�ȋ@��ƂȂ����B
�@
�����̓��{�l�́u�Ăђ��N�������U�������ƍ���̂ŁA���N�ʐM�g���v���������ď��R�̋@�����Ƃ�ɗ���v�ƍl���Ă����悤�����A�؍��ł͒��N�ʐM�g���u���{�͊؍��̐�i�w����w�Ԃ��߂Ɍ����������̂ŁA�g�ߒc�͊O���g�߂Ƃ��Ă݂̂Ȃ炸�A��i��������{�ɓ`�d����������ʂ������v�ƈʒu�Â��Ă���B�����A�����A�A�����A���n��A�ՁA��A���z�A�����A���|�ȂǁA���N��������`����Ă������̂��肾�B
�@
���͒��N�o���̍ۂɓ��{�ɘA�ꋎ��ꂽ�Ƃⓩ�H�́A���{�ł͎�����ҋ����Ă����B����ⓩ������肾�����H�͑喼�ɂ���ĕی삳��A�e�n�ɏĂ����̗q���J���ꂽ�B���N�ʐM�g���������A�ߗ��̕Ԋ҂����߂��ہA�f�v����Ă��铩�H�̑������A���{�ɗ��܂邱�Ƃ�]�Ƃ����B���N�ł͎v�z�ɂ��g�����x�ɂ���ē��H���ʼn��ʂɈʒu�Â����A�z��̂悤�ȘJ�����������Ă������炾�B
�@
����A�Δn�˂͊��R�Ɍ��݂����u�`�فv�ƌĂ����{�l�����n�ŊO���ƒʏ����s�Ȃ����B���{���狖���ꂽ�������ő���Ɋ��p�����̂��B�O�����Ə��l�����݂��Ă������Ƃ��`�ق̓������B�`�قɋ��Z�������ꂽ���{�l�́A�Δn�˂���h�����ꂽ�َ�A�㊯�A���L���A�ʖ�A�ނ�̎g�p�l�A�d�����A�����A��w���w���Ȃǂ��B�َ�A�㊯�A���L���́A�Δn�˂̖f�ՒS����l�����A����ȊO�͖��Ԑl�ł���B�펞400�`500�l�؍݂��Ă����Ɛ��肳���B���̘`�ق��O���ƌ��Ղ̏�ƂȂ����B
�@
�]�ˎ���O���A���N�́A���N�l�Q(����l�Q)�A�g����ɉ����A�����Y�̐����A���D���Ȃǂ���{�ɗA�o���Ă����B�����̃V���N�͍����i�Ƃ��ē��{�̋M���A�喼�ɍD�܂�Ă������A���{�D�͒���(��)�ւ̓��`�����ۂ���Ă������߁A���N����w��������Ȃ������B�Δn�˂͘`�قŒ���-���N-���{�Ƃ������[�g�̒��p�f�Ղ��c�݁A���z�̗��v���B
�@
�������A18���I�ɓ���Ɠ��{�����Ō����Y�̋Z�p�����サ�A�����Y�̌��̗A���͌��������B�܂��A���N������O�s�o�Ƃ��Ă������N�l�Q�̎킪�����ɓ��{�Ɏ����o����A�����Œ��N�l�Q�͔̍|���n�܂������߁A���N�l�Q�͓��{�ɗA�o����Ȃ��Ȃ����Ƃ����B�Δn�˂ɂƂ��Ă���͑傫�ȒɎ肾�����B����ɒʐM�g�ڑ҂̔���ȕ��S�������āA�Δn�˂̍����͋��R�����B
�@
���āA���{���Δn�˂̌��Ղɂǂꂾ���֗^���Ă����̂��Ƃ����A���͐[���^�b�`���Ă��Ȃ������B�Δn�˂�`�ق͖��{�̒����̂ł͂Ȃ��̂ŁA����u�o�ς͎��R�ɂ���v�Ƃ�����ԁB�Δn�˂́A���{�Ƀ����b�g�ƂȂ钩�N�ʐM�g�̑����Ƃ������̎d���ƁA�˂̍��������肳���邽�߂̌��Ղ��Ɏ������Ă����̂ł���B�@ |
���x���s
�@
�]�ˎ���Ƀu�[�����}�������̂ɕx���s������B�x�����A�x�D�A�x�˂Ȃnjď͈̂قȂ邪�A�������e���B�������邽�߂̎����W�߂̕��@�Ƃ��čs��ꂽ���̂��Ƃł���B���Ђ����Е�s�ɏo�肵�A�����ĊJ�����B
�@
�����́A�]�ˁA���s�A����3�J���Ɍ����A���K�����ꂽ���A1820�N����1830�N���̍Ő����ɂ́A�]�ˎs���ł̋��s��15����20�̎��Ђɂ܂ōL����A���s�͔N��120����J�Â���Ă����Ƃ����B
�@
�x���s�̃V�X�e���͂������B���s��(����)�����疇���琔�����̖ؐ��̕x�D������A����ɔԍ�������B�x�D�X(�D��)�����s��(����)����A�ԍ����L���ꂽ�x�D�����B�x�D�X�͂��̎d����l�ɐ����̗��v���悹�Ďs���Ŕ̔�����B���Е�s�ɐ\������K�v�����������߁A�艿�͂���ꂽ���A�܋��z�Ǝ��v�ɂ���ĕx�D�͏㉺�����B
�@
�ꓙ�܋��́A1000��(�痼�x)�A500��(�ܕS���x)�A300��(�O�S���x)�A100��(�S���x)�Ȃǂ��܂��܂ȃ^�C�v������A�D�����c��Ȑ��ɂ̂ڂ�Ƃ��́A�ԍ��ɁA�ߋT�A���|�~�A�ጎ�ԁA�����_�Ƃ������g�����A���ꂼ��ɔԍ��������B���Ƃ��u�~��267�ԁv�����������Ƃ��́A���ƒ|�̓��ԍ��̎D�ɂ������炩�̖J�����������邱�Ƃ��������B
�@
�w���҂́A�s���ōw�������x�D(�؎D)��ؔ��ɔ[�߁A�����ԍ����L�������D�����炤�B���I�ԍ������߂�u�x�ˁv�̓��ɁA�m�������̎D�������܂��A���ʂ̌�����L���Ŗ؎D��˂��A�h�������؎D�̔ԍ���ǂݏグ��B���I�������D�������o���A���̐l�����I�҂Ƃ��������݂ł���B
�@
�x�D�͍��z�ŏ������C�y�ɔ�������̂ł͂Ȃ������B���Ƃ��A�痼�x(�ꓙ�܋���1000������1��2000���~�̂���)�ł́A�x�D�̗�����1��1��(��3���~)�������B���̂���1���̎D�𐔐l���������čw�������B����́u���D�v�ƌĂ����̂ŁA�w���҂͉��D�����炤�B2�l�ōw���������D�́u�����D�v�A4�l�ōw���������D�́u�l�l���v�ƌĂꂽ�B
�@
���ۂɂ́A���Е�s�����F�����痼�x�͏��Ȃ��A�S���x���嗬�������悤���B�������A���F�̕x�D�ȊO�ɔ@�̕x���s������ɍs���A�����ł͐痼�x���������ꂽ�Ƃ����B���{����������������̂͌����܂ł��Ȃ��B
�@
���I�҂���ɂ�����́A���Ƃ��ΐ痼�x�����������Ƃ���A100������Ƃ��ċ��s��(����)�ɐi�悵�A100����x�D�X�ɂ���Ƃ��č����o�����B���̂ق����o��Ə̂��āA40�`50�������s��(����)��x�D�X�ɓn�����B��������ۂɓ��I�҂̂��Ƃɓ���̂�700���قǂ��B�����炭�ł������������̂͋��s�傾�낤�B
�@
�����͉Ђ����������̂ŁA�Ď��������Ђ��Č��̔�p��P�o���邽�߁A�x���s���J���P�[�X�����������Ƃ����B�����̖ڍ��s���ⓒ���V�_�́A���ɗL���ł������B���̈���ŁA�x�D���w�����邽�߂Ɏ؋����d�˂鏎���������A�����h�~���邽�߁A�ŏ��ɐ痼�x�̂֎~���ꂽ�B�����āu�V�ۂ̉��v�v����1842�N�A���쒉�M�ɂ���đS�ʋ֎~�߂��o���ꂽ�B
�@
�x�D�̋֎~�́u���ł̋֎~�v�Ǝ���d�����A����͂ق��ɂ��ŋ�����(�������A�s�����A��c��)���]�ˍx�O(��)�ֈړ]������A��Ȃ�������肷��ȂǁA�����̌�y�ɂ��������������B���ɉ̕���ւ̒e���͌����������B
�@
���{�́A��肪�Ȃ���Ώ����̍D���Ȃ悤�ɂ��������A���ƕ��I�������悤�ȌX����������ƁA���ډ�����A�K�������悤���B�@ |
��������`�Ƃ����Q��
�@
�]�ˎ���A��ʏ��������s����ۂɁA�K���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��u������`�v���B���݂̃p�X�|�[�g�ɑ���������̂ł���B����ɁA����Ƃ͕ʂɊ֏���ʂ�ۂɂ́u�֏���`�v���K�v�ŁA�ʉ߂��邲�Ƃɒ�o�����B
�@
������`�s����̂́A��ʏ����̏ꍇ�A�����̕�A�����̏Z�ޒn��̖���A�����A�g���Ȃǂ��B��`�ɂ́A���L�҂̏Z���E�����A�����̏ꍇ�͌ˎ�Ƃ̑����A���s�������̒h�Ƃł��邱�Ƃ�A���̒n��ɍݏZ���Ă��邱�ƁA���s�̖ړI�Ȃǂ��L����Ă����B�܂��A�r���ōs���|�ꂽ���͗��h�̐��b���A�a���̏ꍇ�́A���̓y�n�̏K���ł̏��u���˗����A���ł̐܂ɘA�����Ă����悤�L���Ă������B
�@
�܂��A�]�˂���o�鏗���͐g���ɂ�����炸�A�u������`�v�Ƃ͕ʂɁu����`�v�ƌĂ��֏���`��K�v�Ƃ����B�܂��A�]�˂̊e�˓@�̏��������ɏo��ۂɂ́A���̏���`�{���狏�ɔ��s���Ă��炤�K�v���������B���{���狏�Ƃ́A���{����я��˂ɒu���ꂽ�E���̂ЂƂB���{�̗��狏�͘V���̔z���ŁA�剜�̎����܂��ʍs��`�̊Ǘ��A���R�s�ݎ��ɂ͍]�ˏ�̗����S�����B���݂Ȃ獂�������ł���B
�@
����A���˂̗��狏�́A�ˎ傪�]�˔˓@�ɕs�݂̏ꍇ�ɔ˓@�̎��ɂ��������ق��A�]�ˏ�ɂ߂Ė��{���玦�����l�X�Ȗ@�߂���肵����A���{�ɒ�o����㏑�̍쐬���s�Ȃ����肵���B�ނ�͖��{���F�̗��狏�g���������ď����������Ă����Ƃ����B�e�˂̊O�����̂悤�ȑ��݂Ƃ����悤�B
�@
�����̗��l�́A���̖��{���狏�����s������`�ɋL�ڂ��ꂽ�g�̂̓����Ƒ��Ⴊ�Ȃ����A�����Ƃ��Ă܂Œ��ׂ�ꂽ�Ƃ����B�������������`�F�b�N���ꂽ�̂́A�����āu��m��v(�����E��)��߂��邽�߂łȂ��A�l���Ƃ��č]�˂ɋ��Z���������喼�̍ȏ���̓��S��j�~����̂��ړI�������B�]�ˎ���́A�ˎ�̍Ȃ��A�����e�˂̍]�˓@��ɏZ�ނ悤��������Ă����B������u���{�̐l���v���B�ˎ�͖��{�ɐl�����Ƃ��Ă��邽�߁A�N�[�f�^�[���N�����Ȃ������B�������A�ޏ��������ɔ�ɍ]�˂�邱�Ƃ��ł���A�ˎ傪�d�����N�����\���������Ȃ�B�����ŁA�]�˂̊e�˓@�̏��������ɏo��ɂ́A���{�͌������`�F�b�N���s�Ȃ����̂��B
�@
�����������֏��́A�����̂悤�ȗv���Ɍ��炸�A��v�X���ɐ݂����A�S����53�𐔂����B�܂��A�����ړI�ŊC�H�̃`�F�b�N���s���Ă���A�����͈ɓ��E���c�̔ԏ��A�]�˒����ȍ~�͑��͂̉Y��ԏ����u�C�̊֏��v�̖�����S�����B���̂悤�ɋK���͂��������̂́A���̓��W���[�����Ă������B
�@
�]�ˎ���ɓ���ƁA�܊X�����͂��߂Ƃ����ʖԂ����B���A�����ɂƂ��ė��s���傫�Ȍ�y�ƂȂ����B�ł��L���Ȃ̂��u�����Q��v�ƌĂꂽ�ɐ��_�{�ւ̎Q�w���B����Ɗό����ꏏ�ɂȂ����悤�ȗ��ł���B�����̗��ɂ͑O�q�̂悤�Ɍ������K�������������A�ɐ��_�{�Q�w�Ȃ狖����镗���������̂ŁA�u�����Q��v����u�[���ɔ��W�����̂ł���B�����̏����ɂƂ��Ĉɐ��܂ł̗���́A�����ȕ��S�������̂ŁA�u���ɐ��u�v�Ƃ�������Ȑϗ��Ă��l�Ă��ꂽ�B
�@
�u�̏����҂͂������o�������A��������킹�ė���ɓ��Ă��B��\�Ƃ��ĒN���s�����́u���������v�Ō��܂������A�u�̑S���������͓�����悤�z������Ă����B�_���̏ꍇ�A�u�����Q��v�͔_�Պ������p���ꂽ�̂ŁA���������ɑS������ɐ��_�{�ɐ����l���̗��l���W�܂����Ƃ����B
�@
���́u�����Q��v�̌o�ό��ʂ͑傫���A�X�������̕��������������ق��A���s�⏼��ȂǓs�s�̗��s��̒�����y�Y�ɂ��闷�s�҂��}�����A���Ƃ���C�Ɋ����������B�܂��K�C�h�u�b�N�◷�s�L�ɊY������{����������A�u�����Q��v�͍]�ˎ���̏������u�ꐶ�Ɉ�x�͌o���������v��僌�W���[�ւƐ��������B�@ |
���������܂���(�����Q��)�̈Ӌ`
�@
�n�߂Ɂu�������܂���v�Ƃ͂��������������l����K�v������Ǝv����B�ꌾ�ł����Ă��܂��u�ߐ����{�ɂ����Ď����I�ɂȂ�ǂ��J�肩�����ꂽ�A�ɐ��_�{�ւ̏W�c�I�ȏ���^���ł���v�B����́A�ق�60�N�����ɌJ��Ԃ���Ė����Ɏ���܂��B�ȉ��ɂ��̍s�Ȃ�ꂽ�N���L�ڂ��Ă݂܂��B
�@
�O��
�@
(1)�@1650�N�@(�c��3�N)
�@
(2)�@1705�N�@(��i2�N)
�@
(3)�@1718�N�@(����3�N)�|�|�|�ꕔ�n���̉^���ɂƂǂ܂�B
�@
(4)�@1723�N�@(����8�N)�|�|�|�ꕔ�n���̉^���ɂƂǂ܂�B
�@
����
�@
(5)�@1771�N�@(���a8�N)
�@
���
�@
(6)�@1830�N�@(����13�N�E�V�ی��N)
�@
����
�@
(7)�@1867�N�@(�c��3�N)�|�|�|�A���@����́u��������Ȃ����v�ł����āu�������܂���v�ł͂Ȃ��B
�@
���̂悤�ȑS���I�ȉ^�����N���������R�E�����ɂ͑����̐������邪�A�����u�x�m�u�v�Ƃ����x�m�R�ւ̓o�R�����������Ɠ���̂��̂ƍl����B�ꂵ�����X�̐����̂Ȃ�����A�u�ꐶ�Ɉ�x�͈ɐ��_�{�̎Q�q���v�ƍl�����̂ł��낤�B���ꂪ60�N���ɔ������Ă���Ƃ����̂��d�v�ŁA���O���u��������c����c��ɕ����Ă����w�������܂���x�̎������ȁB�v�Ǝv���Ă��鎞�ɂ���n���Łw�������܂���x�����������Ȃ����ɎQ�����悤�Ƃ���C�����ɂȂ��Ă��܂��̂͒v�����Ȃ��B���X�̎d������̋�J���瓦��A�ǂ������u�����̋�J�𗣂�A�����̍K�����肤�v�C�����𐬏A�������������u�����V�R�E�����ŗ��s�ł���v�@��^������B�Q�����Ȃ����R�͌��N�ł���Ȃ�Ζ����ł��낤�B�u�ɐ��_�{�֎Q�q�ł���v���̈Ӌ`���������Ȃ��B���ʂ̏�Ԃł���A�u�n��v��u�����v�Ȃǂ̗T���ȉƒ�łȂ���ΎQ�q�ł��Ȃ��E���̊y�����b���������Ă�����ʂ̐l�X�ɂƂ��āA�u�����ɂ��Q���ł���v�Ƃ��������ǂ�قǖ��͓I�����������̉�X�ɂ͑z���ł��Ȃ����ł������낤�B
�@
�������{�͕�������ȏ@���Ƃ��Ă����B���̂Ȃ��ł����ɂ��āu�w�ɐ��_�{�x�ւ̎Q�q�v�����܂�Ă����͔��ɋ����[���B���O�̂Ȃ��ł́A�_�������قړ����ʒu���߂Ă����悤�Ɏv���B���̒�����_�ɑ���w�ɐ��_�{�x�|�������܂��肪�䓪���Ă����̂͂��́w�������܂���x�ɂ��Ƃ��������ł��낤�B���̕����ɂ��Ă͈ȉ��̕��͂��Q�Ƃ��Ă݂����B
�@
�u�Ƃ͂������̂́A�w�M��������x�Ƃ͂����Ă��A����͂��Ƃ��瓯���ł������Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�L���w�_�x�̐M�Ƃ��Ă͋��ʂ�����̂��������Ƃ͂����A�w�ɐ��M�x�Ƃ��Ė��m�ɓ��ꂳ�ꂽ�����M���ŏ����瑶�݂������̂łȂ��A�J�肩�������w�������܂���x�̏W�c�^���̂Ȃ��ŁA���ꂳ��������̂ł���B�^�@�̑m����M�k�ɂ�������U�����A���̉^���̈�Ƃ��Ă���킳�ꂽ���̂ł���B�_�����ザ��G���ȐM�ɐ����Ă��閯�O�̂Ȃ��ɁA�ɐ��_�{�́w���ӂ��x���~�邱�Ƃɂ���āA���O�̐M���A���ꂵ�������I�@�����`���������֓��т���Ă����̂ł���B���������̓���𐄐i������̂́A�������āw�V�c�̑c��_�x�Ƃ����_�i�̑����ł͂Ȃ��B���O�̌��������̓���������Ă��閯���I��������Ƃ߂�͂ł���B���O�̐�����j��ɂ݂��т��Ă���A���˕��������̖����ɂ������閯�O�̒�R�̃G�l���M�[���̂��̂ł���B�c���w��������Ȃ����x�̂���ɗ��s�����A�w������������ǂ��߁x�́A���̂悤�Ȗ��O�ӎ��̐������悭����Ă���B�v
�@
���O�̐M�̑ΏۂƂ��Ắw�_�x���A�w�������܂���x�̂悤�ȓ����̔˖��̐����Ă����Ȃ�ꂽ�e�n�̖��O�̌𗬂ɂ���č��߂��Ă����Ƃ����ӌ��͔��ɂ����ꂽ���̂ł���Ǝv���Ă��܂��B�����āA�w���ꂳ�ꂽ�����I�@���x�̑��݂��ߑ㖾���ȍ~�̖��O�̒��ɖ��X�Ǝp����Ă����̂ł���B���ꂪ�A�����^���̊��ɂ������ł��낤�B
�@
����ł́A�Ȃ����̂悤�Ȗ��O�ɂ��^���͍������A�������������͂�(������)�Ȃ�Ȃ������̂ł��낤�B����́A���Ƃ��w�S���Ꝅ�x���l����킩��₷���B�ʂ̒n���I�ȁw�Ꝅ�x�́A�����܂ł��̒n���݂̂ł̊����ł���A���ꎩ�̂ł́w�˖��̐��x����邪���悤�Ȃ��̂ɂ͂Ȃ肦�Ȃ������̂ł���B���{�͊�{�I�ɂ͂��̍\���v�f�ł���l�����ꂼ��̔˂��甲���鎖���֎~���Ă���ᔽ����҂��d�ߐl�Ƃ��Ď�舵���Ă���B����ȂȂ��ŁA�w�������܂���x�́A�w�˖��̐��x�����@�I�ɔ����o������ł������B(�A���A���{�́w�������܂���x���m�肵�Ă����킯�ł͂��B������K�������ꍇ�ɋN����ł��낤�w���O�̗́x�����ꂽ�ׂƎv���邪)�m���ɁA�������������O�^���𗘗p���āw�˖��̐��x�ɑ��Ă̔�������Ă鎖�͉\�ł������낤�B�����A����ɂ́w�w���ҁx���K�v�ł������B���̕����ɂ��ẮA�ȉ��̕��͂��Q�Ƃ��Ă������������B
�@
���{��������̏@�����������ƁA�����͍L�����O�̂������ɕ��y���Ă�������ǂ��A����͑����̏@���ɕ��Ă���A�܂��������c���̂��̂��A�S�̂Ƃ��ċ��������x�z�@�\�ɑg�݂��܂�Ă�������A�������L�͂Ȗ��O�̉���v����I�ɕ\�����邱�Ƃ͍���ł������B�Ƃ��낪�_���ɂ��ẮA���˕����x�z����������Ȃ炸�����\���ɐ����I�ɏ������邱�Ƃ��ł����A���ꂪ�����{�I�v�z���ӂ���ł������Ƃ́A�̂��ɐ_���Ƃނ��т������w�v�z���A�|���̗��_�ƂȂ������Ƃ����Ă������炩�ł���B�Ƃ��Ɉɐ��M�́A�܂��ɂׂ̂��悤�ɁA�������炢������������ՂƂ���_�_�M�̓`���Ƃނ��т��Ă���A�ߐ���������L���_���A�s���̂Ȃ��Ɋg����������B���̂悤�Ȉɐ��M���A���O�̕������̑�������̉����v�����铬���̐S���I���ǂ���ƂȂ������Ƃ́A���R�̂��邱�Ƃł������B�킽���͍��w�v�z�́A�ނ��낱�̂悤�Ȗ��O�̐S���f���āA�������Ă������̂ƍl��������Ǝv���B���������疯�O��������邽�߂́A�Ȃ��̎v�z�����_���ق��ɗ^�����Ă��Ȃ�����ɁA���O�����̂悤�ɁA�x�z�K���̎��_��ς��āA����ɉ����^����_�Ƃ��邱�Ƃ��l���o�����̂́A���炵���n���ł������Ƃ����ׂ��ł��낤�B���́A���̂悤�Ȗ��O�̎����I�ȏ@���I�J���^�����A���ꂪ�A�ǂ̂悤�ȕ����Ɏw�����Ă��������Ƃ������Ƃł���B
�@
�����ŁA�c��3�N(1867�N)�́w��������Ȃ����x���l���Ă݂�B���́w��������Ȃ����x�́A���̍s�ׁA���O����̂ɂȂ��Ă����_����́A����܂ł́w�������܂���x�Ɠ����悤�ɂ������邪�A�ǂ������̉^���́w�c�̎u�m�x�B�ɂ��Ӑ}�I�ȉ^���ł�������������������B�ڂ����́A���J�r�Y���́u�������܂���v�Ɓu��������Ȃ����v���Q�l�ɂ��Ă��炢�����B���̎��́w��������Ȃ����x�̍����ɂ̂��āw�吭��ҁx�ւƎЉ�������Ǝv����̂ł��邪�A�������w�c�̎u�m�x�B�ɂ��^���̗��p�̎d���͒P���ɎЉ�����������邾���ɂƂǂ܂��Ă��܂����B�w���҂����Ȃ��������Ȃł��낤�B���̎��A�剖�����Y�̂悤�ȕ��m�K���ł���Ȃ��疯�O�̗͂𗘗p���悤�Ƃ��鐨�͂����݂����Ȃ��(�剖�����Y���^�ɖ��O�𗝉����������ǂ����͕ʂƂ���)�����̂�������̂������ƈ�������̂ɂȂ����ł��낤�B
�@
�������A�w�������܂���x�̑��ݗ��R��ے肷��̂͌�����l���ł��낤�B���O�͂��݂̂�����̍s���ɂ���Ă͎Љ������\�������o�������A�˂̘g���Ċ�������p�����w�B������A�Љ�����鎩���B�̗͂Ŋ���������B���̊��o�ɊO������̗l�X�ȕ������Z�����鎖�ɂ����10�N��́w���R�����^���x�����O�̊Ԃ���������Ă����ƍl����̂ł���B�@ |
���������x�ƗV�s
�@
�]�ˎ���̌������x�̓����̂ЂƂ��A�U�݂���V���������n��ɏW�����������Ƃ��B�܂�A�V�s�̐ݒu�ł���B���ꂪ����ɂ܂Ŏ���u�\�[�v�����h�X�v�̋N�����B
�@
�������x�́A�]�˂���s�s�ɕϖe����ۂɔ����Ēʂ�Ȃ�����琶�܂ꂽ�s�s����̈�ł������B�ƍN�͍]�˂ɖ��{���J���ɂ�����A�O�͂���吨�̉Ɛb�c�������A��Ă����B�ނ�̏Z�ޏꏊ���m�ۂ��A��������������A�����|�����肷��C���t���������}�s�b�`�Ői�߂邽�߁A�֓���~����l�����W�܂����B�܂�A�S�[���h���b�V���̂悤�ɑ����̒j�����]�˂ɏW�܂����̂ł���B�]�ˏ����̐l���̒j����́A���|�I�ɒj���������������Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B��y�̂Ȃ�����ɁA�ނ炪�������ɋ��߂�̂́A���R�u���ށv�u�łv�u�����v���B�����������j�[�Y�ɑΉ�����悤�ɁA�����̍]�˂ł͗V�������_�݂��ĉc�Ƃ��n�߂��B
�@
����A���{�͍]�ˏ�̌��݂ƕ��Ɖ��~�̐�����i�߂��B���̂��߁A������V���������т��шړ]���������ꂽ�B�s�s�J���������̐������D�悷�邱�Ƃ́A�ߑ㍑�Ƃ̏Ƃ������悤�B�������A���܂�ɂ��p�ɂɈړ]�𖽂���ꂽ�V�����̌o�c�҂��������{�ɗV�s�̐ݒu���B���N�������Ă悤�₭���ꂽ�̂ł���B
�@
���{��1617�N�A���{���������E�G�ɗV�s�̐ݒu�������A�u�g���v�Ɩ��������B�����͓����̊C�݂ɋ߂��n��ŁA���̖�ƒn�������B�����錴���ς́u�����v���]���āu�g���v�ƂȂ����悤���B
�@
���̂Ƃ����{�́A�������̋K�����o�c�҂����ɉ������B��̓I�ɂ́A�]�ˎs���ɂ͂��������V������u���Ȃ����ƁA�V���̎s���ւ̔h���̋֎~�A������V���̒�����n���ɂ��邱�ƁA�c�Ƃ͓����Ɍ��邱�ƂȂǂ��B�����̏�����V���g�����F�߂����ƂŁA�]�˂̌������x�̓X�^�[�g�����B
�@
���{�́A�V�s�����F���錩�Ԃ�Ƃ��Čo�c�҂��疻����(��[��)����邱�Ƃ��ł��A�܂Ƃ߂ĊǗ����邱�Ƃ��\�ɂȂ����B����A�V�����̌o�c�҂͎s���Ɛ�ł��郁���b�g���������B�܂��A��䏊�ƍN�̏I���̒n�A�x�{��鉺�ɂ������V�s���ړ]���ꂽ�Ƃ����L�^���c���Ă���B�܂�ŎY�ƈړ]�ł���B
�@
�₪�č]�˂̒��S�n�͂ǂ�ǂ�x�O�Ɋg�債�A���ĕƒn�ɂ������u�g���v�ɂ܂Ŕ���悤�ɂȂ����B�����ŁA���{��1657�N�A���{�Ɉړ]�𖽂����B���̍ۂɁu�V�g���v���c�Ƃł���y�n��5�������ƂȂ�A��̉c�Ƃ������ꂽ�B�g���́A�]�˂̈��Y�ƂɂȂ��Ă����̂ł���B
�@
�g���́u1���ɐ痼������v�Ƃ���ꂽ���Ƃ���A���݂̉��l�ɂ��Ė�1���~���̋������������ƂɂȂ�B�ޖr�W�l�X�ŋ��z�̕x��z�����I�ɍ��������q��◼�֏��Ȃǂ̍��V�Ԃ�͍]�˂̘b����W�߂�قǂŁA�g���̎s��K�͂ƈ��H�⒅���Ȃǂ��܂߂��o�ό��ʂ͑����Ȋz�ɒB�����Ƒz���ł���B�������č����ő�K�͂��ւ�V�s���a�����A�]�ˎs���̍ő�̊��y�X�ƂȂ����B�܂��A���s�A�����A���ɁA��ÂȂǂɂ����F�̗V�s���ݒu���ꂽ�B�g�����ɐ����邱�ƂŁA���{�ւ̏�[�������������A�s��j�[�Y�����邱�Ƃ������F�̗V�����������������B
�@
���ɐl�X�������W�܂銽�y�X��h�꒬���傫���Ȃ�ɂ�A����F�̗V���r�W�l�X�͍L������������B�g���ȊO�̔���F�V�������W�܂銽�y�X���u���ꏊ�v�ƌĂсA���{�ɂƂ��Ă͑傫�Ȗ��ƂȂ��Ă������B������肩�Ƃ����́A������(��[��)�����Ȃ����ƂƁA���I������邱�Ƃ��B�܂��A���{���F�̋g�����炷��Ήc�ƖW�Q�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�g���̌o�c�ґg���́A����s���ɕp�ɂɎ����܂�̋��������߂��B
�@
���̂悤�ɂ��Ė��{�Ɣ���F�r�W�l�X�̒ǂ������������{�i�I�ɂȂ�B�ł��������Ȃ�̂��u���ۂ̉��v�v���ԁB����s�̑剪�����͏��R�g�@����̖��߂ŁA�g�D�I�ȓE�������J�n�����̂ł������B�@ |
���]�˂́u���c�@�v���ꏊ�̎����܂�
�@
���{�͋g���ł̂ݗV�������������A����ȊO�ł̉c�Ƃ��֎~���Ă����B�]�ˏ����̑K���ɂ͐��I�ȃT�[�r�X����铒��(���)���풓����u�������C�v���@�ʼnc�Ƃ��A�ꎞ���͌��g���Ƌ������鐨�͂ɂȂ��Ă����B�V�g���̊����ȍ~�A�֎~�߂����߂��ꂽ�B
�@
����A�l�X�������W�܂銽�y�X��h�꒬�ŁA�V�������͍L���s���Ă����B���������ꏊ�́u���ꏊ�v�ƌĂꂽ�B�u���v�́A�e�A�O��\�킷���t�Ȃ̂ŁA�g���̊O�A�g�����猩�Ęe�̏ꏊ�Ƃ������Ӗ����������悤���B�g�����u�����v�Ƃ���Ȃ�A���ꏊ�́u�����v���B
�@
�g���́A�i���������A�ʑオ�����ق��ɁA���낢��Ȃ������肪���������A���ꏊ�́A���قǗD�ꂽ�V�������Ȃ����߂ɁA����������A�C�y�ɗV�ׂ�ꏊ�Ƃ��ė��p����Ă����B�g���ŗV�Ԃɂ́A���݂̉��l�ł�����10���~�ȏ�K�v���������A���ꏊ�Ȃ�1���~�ŗV�Ԃ��Ƃ��ł����B�܂�A��O�̃j�[�Y�ɍ��킹���s��o�ς����R�ɐ��܂�Ă����̂ł���B���������Ӗ��ł́A�S�ݓX�ƃX�[�p�[�A�R���r�j�A�f�B�X�J�E���g�V���b�v���������Ă��錻�݂̍\���Ɠ������B�������A�g���̌o�c�҂������炷��A���ꏊ�͉c�ƖW�Q�ɂ�����B�g������ŋ�������Č��F�̗V�s�Ƃ�����O�A���{�͌��Ђ�ۂ��߁A���ꏊ�̎����܂�����������B
�@
���㏫�R�E�g�@�́A�쒬��s�̑剪�����ɍ]�ˎs���̗V�������܂�̋����𖽂����B���{��1718�N�A�u�]�˓��{�����甼�a40�L���ȓ��̊e�X���̏h��ł́A���ĉ��ꌬ�ɂ��ѐ����̐���2���܂Łv�ƒ�߂��B�ѐ����Ƃ͐H�����܂��Ȃ������̂��Ƃ����A�����̗��ĉ��͔ѐ����ɂȂ肷�܂����V���̐E��ł������B�܂�A���ꏊ�ł���B���{�́A�V���̐������肷�邱�ƂŁA�h�꒬�ɂ�����V�������܂�����������̂ł���B���݂Ȃ�u���c�@�v�̉��肾�B
�@
�ΏۂƂȂ����h��́A�]�ˎs���ł͕i��h�A�����V�h�A���A��Z�Ȃǂ��B�b�B�����̓����V�h�Ɏ����ẮA�������߂̖ړI�Ŕp�h�ɂ܂Œǂ����܂ꂽ�B
�@
�剪�����́A���G�ŕ�s�����A���ꏊ��E������ƌx�����Ă���B�E���̑Ώۂ́A�V���A���ƎҁA�h���ƎҁA�V�����Z�܂킹�Ă���Ǝ�A�ꏊ����钃���Ȃǂ��B�W�҂���̖��������サ�A�O�o�����W�҂̖����ɂ��Ă͖{�l��ƍ߂Ƃ���u������v�Ƃł������ׂ����Ꮘ�u���L���Ă���B����s���x�@���ƍٔ��������˂Ă������炱���ł������Ꮘ�u���B
�@
�剪�����́A�{�����⒬(���E�n�c��)��O�c������(���E�`��)�ŗV����E�����A���Ǝ҂������B��������ēs�s�͂��Ƃ��Ĕ������ۂ���ꂽ�B�����1722�N�ɂ́A�V�������̋Ǝ҂����̉Ɖ���ƍ���v������|�̒��G���o�����B
�@
�܂�u�����������v�ł���B�����č]�˗L���̉��ꏊ�Ƃ��Ēm��ꂽ�썑����O�̉��H��(���E������)��E�����A�V���������c��ł���Ɖ��̓P���𖽂����B������͗v����Ɂu�����P���v���B���̂悤�ɖ��{�́A�킸���Ȑl���Łu���c�@�v�����肵�A�����������A�����P���Ƃ�������@�Ŕ@�r�W�l�X��E�����Ă������̂ł���B
�@
�]�k�����A�̂��ɐ[�쒇���Ɍ|�����I����|�҂��o�ꂵ�A�g������q��D���Ă䂭�B�|�҂͖�������ɔɐ����邪�A�吳����Ɂu�_���X�z�[���v��u�J�t�F�v�𖼏��X�̏����ɋq��D���A�����͂₪�ăo�[�̃z�X�e�X�ɂ���ċ쒀�����B1946�N�A�f�g�p�ɂ���Ă��ׂĂ̌������֎~�����B1957�N�ɔ��t�֎~�@�����߂����܂Ŕ@�Ŕ��t���s���Ă����n��́u���v�u�Ԑ��v�ƌĂꂽ�B���̑�\�ɂ́A�V�h�S�[���f���X�A���l�E������������A���݂��킸�������A���̖ʉe���c���Ă���B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
�����������ƑK���̉c�ƌ��Ɗ�
�@
�]�ˎ���ɔɐ�������������(���݂̗�����)�ƑK���́A�Ƃ��ɖ��{����c�ƌ���^����ꂽ�T�[�r�X�Ƃł���B���ʂ��Ă���̂ɂ́A�c�ƌ������Ƃ��Ĕ������ꂽ���Ƃ��B
�@
�G�p�����Ȃ����g������Ă������m�ƈقȂ�A�����͎����Ŕ��𐮂��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�������A�}�Q�������A�q�Q�����邱�Ƃ���̐E�l�Ɉ˗�����悤�ɂȂ����̂́A�ߐ��ɓ����Ă��炾�B
�@
�]�˂ɒj���̔����������o�ꂵ���̂́A�ƍN�̓��{���炷���̂��ƁB�]�˂͒j���̔䗦�������A�܂������͎����Ō���(�O�z�����瓪�����ɂ����Ĕ����`�ɂ��肨�Ƃ������l�j���̔��`)�𐮂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A���̐E�l��������������Ďd��������悤�ɂȂ����̂��B�n���ł͑��ŕ������A�u���v�ƌĂ�鉼�X�ʼnc�Ƃ��s�Ȃ����B
�@
��������u�����v�Ƃ����Ăі������܂ꂽ�B�]�˂ł́A�����͍��D��(���G����f������A�@�߂̔��߂����m�����肷��{��)�̔ԏ��Ɋ肢�o�ĉc�ƌ��Ă����B�����Ė��{��1659�N�A���������ɊӎD�s���A�꒬�Ɉꏰ�ƒ�߂��B�ӎD�Ƃ͉c�ƌ��������D�̂��Ƃ��B���݂�����̐�ł́A�ނ������ۂɊӎD���K�v�Ƃ���Ă���B
�@
���������ɂ͓��ނ���A����������ē��Ӑ�ɏo�����Ďd��������E�l�́u��蔯�����v�ƌĂꂽ�B�ނ�͓��Ӑ�ƔN�G�_�A�����ɑ�X�ɕ������Ă����B�܂�A�X�|���T�[�����Ă����̂ł���B��l�̗�������1��S���O��A�]�ƈ��̗������͂��̔������x�̗�����������B���ꏡ����S�\�����������ƂƔ�r����A�����Ȃ������ł���B
�@
����A�s���̉��X�܂ŏ���������E�l�̂����A�ԏ����ʼnc�Ƃ���҂́u�����v�A���̂���҂ʼnc�Ƃ���҂́u�o���v�ƌĂ�A���̌�����Ԃ�o�̍ۂ̖����ւ̋삯���݂Ȃǂ����Ƃ��ĉۂ���ꂽ�B����A�ނ���u�������������̂ɍD�s���̏ꏊ�ł��鋴�l��҂œX���J���Ȃ�A�c�ƌ���^���悤�v�Ƃ��������ł������悤���B���j�[�N�Ȃ͉̂c�ƌ���^���Ă��炤�����ɁA���̌��̎d�����S�킳�ꂽ���Ƃ��B���{���炷��A���{�̊�@�Ǘ�����ɋ��͂��Ă����{�����e�B�A�ł���B��l���g���̂łȂ��A�������^�_�Ŏg���Ƃ́A�u�����Ȑ��{�v�Ȃ�ł͂̔��z�Ƃ����悤�B
�@
�Ƃ���ŁA���������̎����͗��v���������A�ƂĂ����肵�Ă������߁A�c�ƌ������Ƃ��č��z�Ŕ������ꂽ�B�������̂ł͎��S�`���S������ꍇ���������B��l�Ő��������L����T���Ȓ��l�������Ƃ����B���۔N�ԂɂȂ�ƁA�]�ˎs����1000�ȏ�̔����������������Ƃ����B�����炭�]�˂̐l���������I�ɑ��������߁A�c�ƌ����������s���ꂽ�̂ł��낤�B
�@
�]�ˎ���̑K�����܂��c�ƌ��ēX���J�����B�]�ˎ������ɂ͈꒬�ɓقǂ͂������Ƃ������A����ȑO�͑K���̐��͂����������Ȃ������B���̗��R�͉Ǝ��̐S�z�ƔR����̍��������������炾�B���ɍ]�˂͖ؑ��Z��̖��W�n�������A�o����L���͈͂ɔ�Q���y�Ԃ��Ƃ���A���{�͌���ꂽ�҂ɂ����c�ƌ��s���Ȃ������B�������A�ꕔ�̕��Ɖ��~�������A�قƂ�ǂ̉Ƃɕ��C�͂Ȃ��A�h���ł���q�͑K���ɒʂ����قǂ������B�j�[�Y�͂��邪�A�X���̂͏��Ȃ��B���̂��ߑK���̉c�ƌ��́u�������v�ƌĂ�A�]�˂̍����̓����ΏۂƂ��Ă��D�܂ꂽ�Ƃ����B�������͋����̔��z���x�̗����ł��������A�q�������������߁A���肵���o�c���c�߂��悤���B
�@
�����[���̂́A�����������K�����c�ƌ������Ƃ��č��z�Ŏ��������ꂽ���Ƃɂ���B���{�͗\�z���Ă��Ȃ��������Ƃ�������Ȃ����A�A�_���E�X�~�X�̂����Ƃ���́u�_�̎�v�ɔC���Ă����A�o�ς͏���ɂ悢�����ɓW�J���Ă����ƍl���Ă����悤���B�����������Ӗ��ł́A�]�ˎ���͏��Ƃ𒆐S�Ƃ������{��`���������������o��������Ƃ����悤�B�@ |
�����̏��� �����~�Ƒ����A�|��
�@
�L�b�������S���x�z������������������A���ɂ͗L�͏��l���ݏZ����悤�ɂȂ����B�]�˂ɖ��{���������A�����̒��S�͍]�˂Ɉړ]�������̂́A���Ƃ̒��S�͂��̂܂ܑ��ɗ��܂����B���{�͑��ɉ�����s��u���A���ו��̊Ď@�▋�̂̔N�v�������s�Ȃ����B
�@
���͐��^�֗̕������畨���̏W�U�n�Ƃ��ĉh�����B�e�˂͑����~����ɐݒu���A�����Y�i�����≻�����B��ɑւ����̂́A������̂ق������l�������A�܂����͋₪��v�ݕ����������炾�B�����~�Ƃ́A���{��喼�E���{�Ȃǂ��N�v�Ă���Y�i�肳�����߂ɍ\�����q�ɂ����˂����~�̂��ƁB
�@
�]�ˁA����A��ÂȂǁA��ʂ̗v���ł��鏤�Ɠs�s�ɐݒu���ꂽ���A��͂菤�Ƃ̒��S�n�E���ɏW�������B1670�N��ɂ�80�A1840�N��ɂ�125�̔˂̑����~������A���˂�喼�ȊO�̂��̂��܂߂��600�߂��͂������Ƃ���Ă���B
�@
�����̑����~�ŔN�v�Ă̔��p���s�Ȃ�ꂽ���߁A�]�ˎ����ʂ��đ��͕Ă̏W�ϒn�ƂȂ����B�����A�����~�͗L�͏��l��\�����̖��`�l�Ƃ��Ă������A�����I�ɂ͊e�˂̔ˎm���Ǘ�����`�Ԃ����������B�����~�̉^�c�͔˂���h�����ꂽ����l���S�������A���X�Ɏw�肵�����l�ɊǗ��𐿂����킹��悤�ɂȂ����B�܂�A�Ɩ��ϑ��ł���B
�@
�������������l�́A���`�l�ł��閼��A�����A�|���Ȃǂɕ��ނ����B���オ���������˂�ꍇ���������B�����Ƃ́A�����~�̕i���̊Ǘ��E���p���s�Ȃ������ӔC�҂̂��Ƃ��B����̂ق��A�Ė≮�◼�֏��ȂǗL�͂ȏ��l���C����邱�Ƃ����������B�|���́A���p����Ȃǂ̊Ǘ��E�o�[���s�Ȃ���E�ŁA���Z�E�בւ��������֏����C�������P�[�X��A���������˂�P�[�X���������B
�@
�����E�|���͔����̍ۂɎ萔������邱�Ƃ������ꂽ�B�܂��A�˂ɑ��Q��^�����A�K�v�ȏo�[�ɂ��ł������邱�Ƃ������ɁA�˂���a���������������R�ɉ^�c���邱�Ƃ������ꂽ�B���������ɓ��@���s�Ȃ��Ĕ���ȗ��v�������鏤�l�������B���̍\���́A�ڋq����a���������������Ђ̍ٗʂō�������A�����������肷��Ȃǂ��ĉ^�p����A���݂̏،���Ђ��s�Ɠ����ł���B
�@
�ł́A������|���̎�r�͂ǂ��Ŗ����̂��B������������ɂ́A��ɑ��Ă̔����̎d���Ɨ��ʂ�m���Ă����K�v������B�����́A�܂����D�̊����ƕ��������ʂ��������ĕĒ������W�߂ē��D�������B���D�҂͕ۏ؋���[�߁A���̌�A7�`10���ȓ��Ɋ|�����邢�͑����Ɏc�������āA��̏��ɂ������؎���������A�����30���ȓ��ɑ����~�ɍ����o���A�Đ؎�ƌ��������B���Q�l���Đ؎�����A�����~�͋L�ڂ��ꂽ�ʂ̕Ă�n���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@
�������A�����~���ɂ�30���`1�N�̗P�\���^�����Ă����B�Ē����́A�Đ؎�����n���邱�Ƃ��������邱�Ƃ��ł����B���؎�⏤�i���Ɠ����ł���B�����͂��łɕۏ؋�����ɂ��Ă���̂ŁA�˂���a�����������ƂƂ��ɉ^�p���đ傫���𑝂₷���Ƃ��ł����B�܂��A�ĉ��͂������㉺���Ă����̂ŁA���������ɔ̔����A�ĉ����������Ă��鎞�ɓn���A���̍��z���͑����̗��v�ƂȂ����B�]�����Ă����甄�����邱�Ƃ��ł������A�������邱�Ƃ��ł����B�܂�A������|���ɂ͈בւ�ǂޗ͂Ƒ���t�̍ˊo���K�v�������̂ł���B
�@
�D�ꂽ���l�̂Ȃ��ɂ́A�����̔˂̑�����|������������҂������B�L���ȑ������u�����v���B�����͍ޖ؏����琶���f�Տ����o�đ����ƂȂ����B�|�������ˁA�������������Ă���喼�ɋ���݂��t����喼�݂��ō��𐬂����B�u�喼���Z�v�ł���B
�@
�喼�݂͕\�����͐M�p�݂��ł��������A�����͑��Ă��S�ۂƂȂ��Ă����B����͔˂̔N�v�Ăł���B�喼�݂��́A���N���ׂ̕Ăƈ��������ɁA����݂����ƁB�˂��Ԃ�邱�Ƃ��Ȃ���Εԍς͂����킯�����A�傫�ȃ��X�N���������B������|���Ƃ��Ă̌_���ł�����\������ɕ����Ă����̂��B�܂��A����I�ȍ��̌J�艄�ׂ��s�Ȃ�ꂽ�B���ɎF���˂̂悤�ɍ�����@�Ɋׂ��Ă���n�R�˂ɑ喼�݂�������A�؋��ݓ|����郊�X�N�����܂Ƃ����̂ł���B�@ |
�����̏��� �������ꂽ�敨������u�����ĉ�v
�@
1697�N�A�Ί݂̒��V�����瓰���ɕĎs�ꂪ�ړ]���A����ȍ~�A�����܂œ����Ƃ����ΕĎs����Ӗ�����悤�ɂȂ����B�����́A�V���̐��s��A�G�A��(������)�̋��s��ƕ��ё��O��s��̈�Ƃ��āA���l�̑䏊���܂��Ȃ��Ă����B������1730�N�ɂ́A����܂ŋ֎~����Ă����ĉ�������ɊJ�݂��ꂽ�B
�@
�ĉ�Ƃ́A�Ă̎�����̂��Ƃ��B���{�́A����܂Łu�Đ؎�v�̔�����u�������v�ɂ�������ĉ��̍����ɂȂ���Ƃ��āA�ĉ�̊J�݂����F���Ă��Ȃ������B�Đ؎�Ƃ́A���˂̑����~�����Ă̏��L�҂ɔ��������Ă̕ۊǏؖ����ŁA�Ă̏��L���������؏��ł���B�ۊǂ��Ă��鑠�∵�����l�̖��O�A�Ă̗ʂȂǂ��A�U����h�����߂ɓ���Ȏ��̂ŏ�����Ă����B
�@
���̗p�r�͂������B�Ē����l�͗��D�������Ă𑠉��~�ɕۊǂ����A�Đ؎�����B�����ő��Ă̏��L�����ړ]����B�����͔��s��30���ȓ��ɕĂ̑��o�����s�Ȃ����Ƃ��`���Â����Ă����B�������A����ɗ��ʏ،��Ƃ��Ă̐��i�����悤�ɂȂ�A�בւ̑�p�i�Ƃ��Č��ςɎg����悤�ɂȂ�A�]�������悤�ɂȂ��Ă������B����̉������Ƃ́A�����_��̍ہA����������ɕ��킸�ɁA������Ԍ�ɕ������Ƃ��B���{�́A���̕Đ؎�Ɖ������ɂ�������֎~���Ă����̂ł���B�������A���ۂ̉��v���������A�ĉ������������̂����āA���{�͊J�݂�F�߂��B�v����ɋK���ɘa���B
�@
�ĉ�̔���┃���̒����́A��w�ɂ�镄���ōs�Ȃ�ꂽ�B���̓`���͋ߔN�܂ŏ،�������ɂ������p����Ă����B�ĉ�ōs�Ȃ�ꂽ����́A����(���傤�܂�)����A������(���傤�����܂�)����A�Ό���(�������Ă܂�)�����3��ށB���Ď�����A�Đ؎�����錻������ł���B���F�̕Ē�������L�����(���݂ł������)�̂ݎQ���������ꂽ�B�Ē����l�́A�Ė≮�̒����Ⓤ�@�ړI�ŕĐ؎�������B
�@
1�N���t�E�āE�~��3���ɕ����A�˂̑����~�����s����Đ؎��Ē����̊ԂŎ������B���ς͋�ɂ�鑦��(�̂���4��)�x�����ł��������߁A���̎�����Z�ʂ������(���ꂩ��)���ւƌĂ����Z�Ǝ҂��o���肵���B���֗��ւ́A�Đ؎��S�ۂɍ������ŕĒ����Ɏ�����݂��t�����B���́A�ĉ����オ��ƒS�ۂɓ���Ă���Đ؎�p���A�؍���ԋp�����B�܂��A�ĉ����������A�Đ؎�𗬂��Ă��܂����ɑ��āA���֗��ւ͎��Ɏ�����Đ؎���s��Ŕ��p���A����Ō������ς����B
�@
�����Ď���́A�}�O�A�L���A�����A����Ă̂����A�ЂƂ�Ώۂɂ����敨����ł���B�~��Ƃ����؋�����ςނ����ŁA�����܂łɔ�����Ɣ��������ŏ��̔����Ɣ��̔������s�Ȃ��A�������ςɂ����������ゾ���ōs�Ȃ�ꂽ�B���ꂪ���݂̊�{�I�Ȑ敨�s��̂����݂�������u���E���̐敨����s��v���Ƃ����Ă���B
�@
���Ƃ��A����≮�����Ď���ŕĐ؎����ɂ����ꍇ�A���Ă���ɂ���܂łɕĉ�����������Ƒ������Ă��܂��B�����ŁA�Đ؎���Ɠ����ɁA���ʂ̒����Ă��Ă����B����A�ĉ����������Ă��A�����Ă��߂��Α������o�Ȃ����ƂɂȂ�B���������敨����̂����݂ݏo���������ĉ�́A�������E�Ő�[�̎s�ꃁ�J�j�Y���ł������Ƒz���ł���B
�@
�����Ď�����傫�ȒP�ʂŎ�����ꂽ�̂ɑ��A�Ό��Ď���͏��K�͂Ȓ����Ď���Ƃ�����B�ĉ�ł́A�Ό��Ď���͂��قǏd�v�Ȏ���ł͂Ȃ��A�����Ă����S�ƂȂ��Ď������Ă������A�����ɋ߂Â��ɂ�ĕĂ̐敨����̒��S�͒����Ă���Ό��Ăւƈڂ��Ă������B
�@
�����ĉ�́A���{�̌o�ϐ���Ɠ������炢�A����A����ʂł͂���ȏ�ɍ]�ˎ���̌o�ς����[�h����d�v�ȑ��݂ł������B�ĉ�ɏW�܂鏤�l�����A���Ȃ킿�����A�Ė≮�A�Ē����l�A���֗��ւȂǂɂ���ēƎ��̎s�ꃁ�J�j�Y�����ł�������A���Ƃ̂����݂����肠���Ă������̂ł���B�@ |
�����̏��� �N�v�Ă�S�ۂƂ������Z�u�喼�݂��v
�@
�e�˂̑����~���W�܂�A�����ĉ���敨����s����J��L�������́A���˂̎������B��ł��������B��₪�]�ˎ���́u���Z�Z���^�[�v�̖�����S�����̂́A���ɔN�v�Ă��W�ς���A������|���A���֏��Ȃǂ��W�܂��Ă������炾�B�喼�ɑ��čs�Ȃ�ꂽ�A�N�v�Ă�S�ۂƂ����݂������u�喼�݂��v�ƌĂԁB���݂Ȃ�n�������̂����ԋ��Z�@�ւ���؋�������悤�Ȃ��̂ł���B
�@
�喼�݂��́A�̔��\��̔N�v�Ă�S�ۂƂ����Z���Ȃ̂ŁA�喼����̎��ۂ̕ԍς͑��ɓ͂�����N�v�Ă��邢�͔N�v�Ă̔��p����ōs�Ȃ�ꂽ�B�������A��鑤�Ƒ݂������҂ɑ傫�ȃ��X�N���������B�喼�ɂƂ��ẮA�ĉ��̒ቺ�Ƌ��삪�ő�̃��X�N���B����̏ꍇ�A���v�Ƌ����̃o�����X������A�ĉ��͏オ����̂́A�̔��ł����Ηʂ���������̂ŁA�ԍϊz�ɓ͂��Ȃ��Ȃ�B���̕s���z�͕����Ŏx�����v����L�����u�ؕ��݂��v�ŌJ��z������A�喼�͌��������N�ɂ킽���ĕ����ԍς����B����̓����Q�[�Ɍ������Ă��A���̔˂̑��̑����~�ɂ͕Ă����~����Ă����̂́A�Q�[�ɋꂵ�ޔ_���ɔz�����邱�ƂȂ��A�ԍςɂ��Ă�ꂽ����ł���B
�@
�݂��t���鑤�̃��X�N�Ƃ́A�喼�̍��j���A���Ȃ킿���ݓ|���ł���B�����������̔˂����d���Ɋׂ�A���j�������肵�Ă���B�˂̍�����N�v�Ăł܂��Ȃ��Ă������A�Q�[���N����ΕĂ̎��n�ʂ�����A�ԍς��邱�ƂɂȂ�B�喼�����~�Ă�_���ɔz�����Ȃ���A�_�����쎀���čk��҂̂��Ȃ��c�������܂�A����ɍ�����������������B�����ĕԍς���Ƃ������z�Ɋׂ�B
�@
�����������Ԃ�������邽�߁A���Z�Ǝ҂̂Ȃ��ɂ͔ˍ����̍Č��ɋ��͂��鏤�l�������B�܂�Ő���Ƌ��Z�̃R���T���^���g�ł���B�˂̎��Y�^�p�܂Ŏ肪�������l�������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�]�ˎ���ɂ��������E�Ƃ����R�����I�ɐ��܂�Ă������Ƃ́A�ƂĂ������[���B
�@
�Ƃ���ŁA���̑喼�݂��Ƃ������Z���Ƃɂ���đ��ő�̗��֏��ƂȂ����̂����r���B���r�͑�����|���̋Ɩ������Ȃ��痼�֏����c�B���̗��v�ő�a�여��ɍ��r�V�c���J���A��n��ɂ��Ȃ����B���݂Ȃ�A�s���Y���Ƃւ̐i�o�ł���B�����̍��r�Ɂu���Y�^�p�v�Ƃ����T�O�͂Ȃ������Ǝv���邪�A���ɗD�ꂽ�����̎d���Ƃ����悤�B�n��ɂȂ�A�V��ł��Ă���������������邩�炾�B
�@
�喼�݂��̂ق��ɂ́u�l����[�v�ƌĂ��Z�����s�Ȃ�ꂽ�B����͓����ĉ�ɏ�������Ē����◼�֏����A�喼���L�̕Đ؎��S�ۂɎ��{�����݂��t���ł���B���l���炩�炷��A�N�v�Ă�S�ۂƂ����喼�݂����A����Ƀ��X�N�̍����Z�����B�Đ؎�͕Ă̏��L�����������ɉ߂����A�܂��ĉ����\������Ή���ł��Ȃ��Ȃ邩�炾�B����ĕl����[�͍������ł������B
�@
�����ɂ����č�����@�Ɋׂ����������̔˂́A����������܂܁A�����ېV���}�����B���̍ہA�������{�͋��˂̎؋��̂������z�߂������ɂ���悤���l�ɔF�߂����A�������ԍς��̌��ɂ�镪���x�����Ƃ����B���̐���ɂ���āA���̑����̗��֏����o�c�s�U�Ɋׂ����B�������{�ɂƂ��Ă͔p�˒u���ɂ���Ēa�������n�������̂ւ̋~�Ϗ��u�ł��������A���Z�Ǝ҂ɂ͔��̌��ʂƂȂ����B���ꂪ�Ȃ���A���Z����ՂƂ�����_�����̐��͂����Ƒ������܂�Ă������낤�B�܂��A�����ł͂��邪�A���֏��Œ~���������ƃm�E�n�E����s�Ƃɒ������l���a�������B�@ |
�����̏��� �T�u�v���C���喼���x�z������⏤�l
�@
�喼�̍����́A�N�v�Ă��������Ă�����⏤�l�Ɏx�z����Ă����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���j�̋��ȏ��ɂ́u���q���{�̐����ȍ~�A�����ېV�܂ŕ��m���������i�鎞�オ�������v�ƋL����Ă��邪�A�]�ˎ���̑喼�̍��������E�����̂́A�܂�����Ȃ���⏤�l�ł������B���̑��̏��Ǝ��{�́A���S�ۂ́u�喼�݂��v�ő��z�̗��v�Ă����B
�@
���̂��Ƃ́A�]�ˎ���̍\���I�ȓ����������ɕ\�킵�Ă���B�퍑����̑喼�́A����(�N�v�Ă���E��A���Y���Ȃ�)���g�傳���邽�߂ɁA���ɍU�ߓ���A�̓y���g�債�A���̍��Y��D�����B�������A�����Ɏ���܂Łu�y�n�����Y�v�ł��邩��A�y�n�𗪒D���邱�Ƃ����Y�𑝂₷���Ƃł���A�܂������𑝂₷���߂̑喼�̊�{�I�Ȏd���ł������B����͐퍑�喼�̃V���v���Ȑ�������Ƃ����悤�B
�@
���c�M�����D�c�M�����L�b�G�g�����ׂĂ��̐�����т����B�������A�ƍN���]�˂ɖ��{���J���A���ˑ̐����ł܂�ɂ�A�喼�͗��D�Ƃ����{���̐��Y��i�Ǝd���������A�̓y�̐������s�Ȃ������d���͂Ȃ������B�喼�▋���ɂ͐����Ƃ��l�Ƃ��Ă̖��������������A�命���̕��m�͒P�Ȃ�u������ҁv�ɉ߂��Ȃ������B
�@
���\���ɓ���ƌo�σV�X�e���������A�܂��l���������I�ɑ����A�x�o���������Ă�������ŁA�N�v�����͓��ł��ƂȂ��Ă������B���m�ɂ����A�N�v�����͈�肾���A�x�o�������Ă������̂ł���B�v���C�}���[�o�����X���ύt������ɂ́A�Ώo��ŋ��ł܂��Ȃ��������@�͂Ȃ��B�����ŁA���{��˂́A���l����ŋ�����邱�Ƃ��l�����B�܂�A���łł���B
�@
�������A�喼�̓��[�J�����{�����ł͍������^�c�ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B�����͗\�����ʋQ�[���N�X�������A�Ă��s��ɂȂ�A�N�v�Ď��������������ق��A���{����̓V�������ƌĂ��������Ƃւ̎Q���A�������Ղ�V���ȏ��R���a�����邽�тɎx�o�������Ă����B�����ŁA�喼�͎�ɑ��̏��l����؋������č������^�c���邱�Ƃ�����I�ɂȂ��Ă����B���Ȃ킿�A���˂́u�����Ԏ��v�������̂ł���B�������������L�тȂ��܂؋����J��Ԃ��A����͉i���Ɋ��ςł��Ȃ��B�����������ł��x�����}�V�ȕ��ŁA�����̕ԍςɂ͎肪�܂��Ȃ��喼�����������悤���B
�@
�؋����ݓ|���Ŗ������̂��A���F�{�̍א�Ƃ��B�A�����J���̋��Z��@���ɋ�����Ȃ�A�א�Ƃ͊m���Ɂu�T�u�v���C���v(�M�p�x�̒Ⴂ�w)�ł���B�M�p�x�[���̑喼�̉\�́A��⏤�l�̊ԂōL�܂�A�N���݂��t�������Ȃ��Ȃ����B�U�v���C���喼�ւ݂̑��a�肪�n�܂����̂ł���B�Ȃ��ɂ͑喼�̍��҂ł��鏤�l�����̗̓y�ɏo�����A�_������N�v�ڎ�藧�Ă���A�㊯�ɔN�v���������������肷�邱�Ƃ��������Ƃ����B�U�v���C���喼�͊��S�ɑ�⏤�l�Ɏx�z����Ă����Ƃ����悤�B
�@
�喼�̐M�p���������A�喼�݂��̃��X�N��������ɂ�āA���l�͕ĂȂǂ̌������Ȃ�����A�喼�ɋ���݂��Ȃ��Ȃ����B���m�͂���ɂЂ������Ȃ�A���l�̎����͑���]�˂ȂǑ�s�s�̋��Z�s��ɏW�܂�悤�ɂȂ�B
�@
���Ƃ��ΎO������̎n�c�E�O�䍂���͏���ŋ��Z�Ƃ��c�݁A�喼�݂��ō��Y��z���A���̎��{�����Ƃɍ]�˂ɐi�o�����B�u����������|�l�Ȃ��v�̌������u�O������X�v�́A���l���^�[�Q�b�g�ɂ��������ƂƂ��đ傫�Ȑ��������߂��B�喼�ւ̔̔��͔��|���ł��������A�܂��ł��t�����Ƃ��\�z���ꂽ�B�����炻�̔��|���̏ł��t���͌����ɉ��Z����Ĕ̔�����A���z�ɂȂ��Ă������A���l����̒����̔̔��������݂̂ɂ������ƂŁA�X�����i�����������邱�Ƃ��\�ɂȂ����B
�@
�����������_���I����͓I�ȃ}�[�P�e�B���O�v�l�́A�����̏��l�͂����Ԃ钷���Ă����悤���B�����ĉ������Y�����A��������邾���ƂȂ����]�ˎ���̕��m�́A���l�ɂƂ��đ傫�ȓ�����ł͂Ȃ��Ȃ����B���l�͎��g�̐V���ȃr�W�l�X�ɓ�������悤�ɂȂ��Ă������B�����m�̂悤�ɁA�����Ɏc���ꂽ�ő�̓�����́A�]�˖��{�Ɗ��R�̂ǂ��炩�ł������B���͂łȂ��A�o�ς�������������鎞�オ���������̂́A���R�̐���s���ł������Ƃ����悤�B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
����p���߂̗���
�@
�����̖��{�̍����́A�����̈�r�����ǂ����B���̊C�O�����A�O���l�̎E�Q�ɂƂ��Ȃ������A���D���q�ɔ������R���̑����A���ݖh���A�x�d�Ȃ�]�ˏ�̉ЁA��x�ɂ킽�钷�B�����Ȃǂ����̌����������B�]�ˏ�̉Ђ́A�����h�ɂ����ł������B
�@
�����I�ȍ����s���Ɠ˔��I�Ȏx�o���U���邽�߂ɖ��{�����߂����̂��A��p���߂��B��p���Ƃ́A���{�⏔�˂�������̕s����₤���߁A���l�E�_����ɑ��Վ��ɏ�[�𖽂�������̂��Ƃ��B����Ζ��{�⏔�˂́u���ʉ�v�v�ł���B���߂̖��ڂ́A���{�����Z�ʁA�ĉ����ߔ�A�]�ˏ�Č���A�C�h��A���B�����R��̒��B�ȂǗl�X���B
�@
�N�v�Ƃ͈قȂ�A�{���͗��q�t���ŔN���ԍς���؏���ł������B�܂�A���Ԃ���̎����ł���B���̗��q�͔N��2�`3���Ƃ������ᗘ�ŁA�ԍς������̔N���ԍς������B�����݂͍��Ǝ��Ă��邪�A�قȂ�̐M�p�x���B���q���x����ꂽ�͍̂ŏ��̐��N�Ԃ݂̂ŁA�����ɂȂ�ɂ�A���q�͂������A�������قƂ�Ǐ��҂���Ȃ��Ȃ��Ă������B
�@
�����́A�������I�Ȍ����ł���B�����͑���]�˂̍����ɑ��ĉۂ���ꂽ���A�₪�đ��̕x�T���l���ʒ��l�A����ɂ͔_���̕x�T�w�ɂ���������悤�ɂȂ����B���̐Z���Ԃ�́A�ݕ��o�ς̔��B�ɂ��A��������Ȃ����ƊK�����A�o�ϊ����̃v���C���[�Ƃ��Ď���������w�ƂȂ������l�����̎x�z���ɒu����Ă��������Ƃ���Ă���B
�@
�L�͏��l���W�܂���ł̌�p�����������Ă����̂́A����������s�������B��s���͕��i�����⒬�l�̎��Y�E�����̏�c�����Ă���A���̃f�[�^�Ɋ�Â��ČX�̒��l�ւ̌�p���z�����肵�Ă����Ƃ����B��s�����A�x�@����ٔ����݂̂Ȃ炸�A�Ŗ�����s�����̖������ʂ����Ă������Ƃɂ͋����ł���B�ЂƂ̑g�D���W�������̈قȂ镡���̋Ɩ�����s���Ă��Ȃ��Ă������Ƃ��킩��B�܂��Ɂu�����Ȑ��{�v���B
�@
�₪�č��������́A�ԍς���Ȃ�������[�������Ă����A�����ɔj�]���Ă��܂����߁A��p�������ɐ���ɒ�R����悤�ɂȂ�A���{�̌��Ђ͎��Ă��Ă����B���{�ɏ�[���邭�炢�Ȃ�A���R�ɓ������āA���R��������������łɂ͐V������p�B�̋Ǝ҂Ɏw�����Ă��炨���ƍl���鏤�l���o�ꂵ�Ă����������Ȃ��B����A�헪�ƂƂ��ē��p������킵���̂��O��Ƃ��B���{�ւ̌�p�������z���ĕ��[���邱�Ƃɐ������A�Ȃ������l�f�Ղ̊Ŏ����̈ꕔ�����i�S�ۑ݂��t���ɉƖ��{���珳�F���Ă�������̂ł���B
�@
�Ƃ���ŁA�C�M���X�Ǝ��g�F���ˁE���B�˂̍����͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��Ƃ����A�]�˂��痣��Ă��邱�Ƃ��K�����A���f�Ղɂ���č������x���Ă����B�C�M���X���l����R�͂═����w�������p�́A���f�Ղœ������v�ł���B����A��p�������ɂ���Ă������̗��Ē������ł��Ȃ����{�̓����ɂ́A�t�����X����̊O���R����ɂ��Ă悤�Ƃ��铮�����������B�������A�ŏI�I�ɂ͊O�ŌR����B���Ă����҂�����ɂȂ�Ɣ��f�����̂ł���B
�@
�]�k�����A�]�ˏ�̖����J��̑O�ɁA�����ɒn���ɖ������ꂽ�Ɠ`������u���얄�����v�́A���{�����l���璥��������p���������Ƃ���Ă���B�吭��ғ����A�����s�߂Ă������I��������ӔC�҂ł��������Ƃ���A�u���I�����{�̋��������ē����A�ԏ�R�ɖ��߂��v�Ɖ\���ꂽ�Ƃ����B���������ނ������I�͏�썑(�Q�n��)�ʼnB�ِ����𑗂�Ȃ���A���������@��N�����`�����X�����������Ă����B���̋��Ŗ��{���ċ�����v��������Ă����������ƁA���̂悤�ȓ��얄�����`���Ƀ��}����������l�͌��݂����Ȃ��Ȃ��B�@ |
�������̌o�Ϗ�
�@
�T�u�v���C�����[����肪�\�ʉ�����O�N��2006�N1���܂�FRB�c����18�N���߂��O���[���X�p�����́A�T�u�v���C�����[���ɒ[���鐢�E���Z��@���u100�N��1�x�̐M�p�̒Ôg�v�ƕ\�������B���̌��t�����Ȃ�A400�N���������]�ˎ���̖����Ƃ́A�܂��Ɂu400�N��1�x�v�̑�]�����ł������Ƃ�����B�ł́A�����̍����͂ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ������̂��H���{�̎�ɕ����Ȃ�������@����Z��@���N�������̂��낤���H
�@
���������Ă�������̓��{�́A�K���ɂ��f�Պz�����傫���Ȃ��������̂́A�A�����ߏ�Ԃɂ������B������������������������A�]�˖��{�̍����������������Ă����B�����������{������������n�߂�����ɁA�����̋��⓺�̗��o�j�~�Ƃ����ړI���������킯�����A���{�̈Ӑ}�ɔ����āA�����̋��͍��O�ɗ��o���A�C�O�ւ̏����ړ]���N�����Ă����B����ɕĉ��̉������d�Ȃ�A���{�͉ݕ��̉������J��Ԃ����B���̉ݕ�����̎g�p�ʂ����Ȃ��������������߁A���{�̐M�p���ቺ�����Ƃ���Ă���B
�@
���C�M�͉�z�^�Łu�������ɂ͖��{�̋��ɂ͒�����Ă���A�V���ȍ���������Ȃ��܂܁A�j�]���O�ɂ������v�ƋL���Ă���B������@�́A�����I�ȊJ���ɂ����鉡�l�`�̊J�`���瓾������v�ɂ���Ă������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł���B
�@
�J������Ɠ����ɁA���{�̗A�o�͔����I�ɑ��������B���ɐ����́A���̕i���̍�������O�����l���������������B����ɕč��œ�k�푈���u�����āA�ȉԂ̍��ۉ��i���}�㏸���A���{�̖ȉԂ�������߂�ꂽ�B�����A�������A�o�K�������Ă������߁A�����Y�̑�p�i�Ƃ��ē�����⎽�킪����ɗA�o����Ă������B
�@
�����̓��{�͍����Ŋ��S�����̐����ɂ���A��H�Ƃ̐��Y�͂ł͑ΊO�I�Ȏ��v���}�ɂ܂��Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ������B���i���A�o�p�̂��̂���ɂȂ�ƁA�����̗��ʕ����͌�������B���̂��ߏ������͍��������B���ɁA���Ăő�ʐ��Y���ꂽ�����ȖȐ��i�������ɓ����Ă���悤�ɂȂ�ƁA�����̖ؖȉ��H�Y�Ƃ͉�œI�Ō������B����͍������Y�̖��蒆�����Y�̖�̂ق��������ł���̂Ɠ������ۂ��B
�@
�����̐��Y�_�Ƃ́A���i�����ł͒����Y�ɏ��ĂȂ��B����Ɠ����\���ŁA�J���O�ɖȐ��i�͌����i�Ɏ��������i�ł��������A�J����ɂ͂��̉��l�͈�C�ɖ\�������B��������ƁA�����̔_�ƁA�����ƁA���ʋƁA�����Ƃ͂��ׂĂ��Ō������Ƃ������ƂɂȂ�B���ɋ��Z�Ƃ́A�喼�݂̑��|��Ƃ������X�N�͂�����̂́A�ƊE�Ƃ��Ă͊��������Ă������Ɨ\�z�ł���B
�@
���������ɂ����āA����̍��ۃ��[�g�Ƃ̍����A�����̍����ƃC���t���ɔ��Ԃ��������Ɠǂނׂ����낤�B�J���O�̓��{�����̋���[�g�́A��1��5�������̂ɑ��āA���ۑ����1��13�������B�܂�u�⍂�����v�ł���B���̌��ʁA�O�����l�́A��ʂ̗m��(���L�V�R�h��)�œ��{�̋��݂�������A�C�O�Ŕ��蕥���ė��U�����҂����B�܂��A���{�̓����i�����ەW�����͂邩�Ɉ����������߂ɁA���{�̐��i�͂��Ƃ��ȒP�ɊO�����l�ɔ�����߂��Ă��܂����B�J�`�n�t�߂͊J�`�����ɂ��₩�邱�Ƃ��ł��Ă��A����ȊO�̂قƂ�ǂ̒n��̓C���t���ɋꂵ�߂�ꂽ�̂ł���B
�@
�����̍����A�n��Y�Ƃ̒���A����ɕĂ̕s�삪�d�Ȃ�A���˂̑喼������̂Ȃ��s��������͓̂��R�̂��ƁB�����牺�����m�⍋�_���邢�͏��l�܂ł����A�|���̎�̂ƂȂ��Ă����V�i���I�����̍��ɂ��łɂł��Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B���Ɏ����ł���o�ϊ�Ղ��\�z���Ă����F���ƒ��B�ɂƂ��āA���{�̐���͒n���o�ς�����������̂ɉ߂��Ȃ������B�F���́A���f�Ղ◮���̐A���n���ɂ���āA�f�Ղ̂��ܖ��ƌo�ς̃O���[�o�����̗�������łɎ@�m���Ă����B����̒��B�́A���˓��C�̗��ʖԂ�`�̐����ɂ���Ĕ˂̍������܂��Ȃ��Ă������A��������l�J�`�ɂ���đ傫�ȑ��Q�������ނ��Ă����B�@ |
���C���t����Ɩ≮�ی�
�@
������@�Ɋׂ��Ă������{�́A�f�Ֆʂł��傫�Ȗ��ɑΛ�������Ȃ������B1859�N��������Ƃ̖f�Ղ��n�܂����B�����Ƃ��Ė��{�̖�l�͊֗^�����A���{�l���l�ƍ`�ɋ�������O���l���l�Ƃ̊ԂŎ��R�f�Ղ��s�Ȃ��A���Ղ�9���͉��l�`�������B���l�`�̌��^�ƂȂ����_�ސ얩�ɂ́A���C���̏h��E�_�ސ�h������A���{�̒����n�������B���̑Ί݂̉��l���ɍ`���J���ꂽ�̂́A���{���Ď����₷���Ƃ������R���������̂��낤�B
�@
���|�I�ȗA�o���߂Ŏn�܂������Ղ�1866�N�ɂ͗A�����߂ɓ]����B���̗��R�́A�A���i�̐ŗ����A20������5���Ɉ���������ꂽ���炾�B�܂�ł����������̂ł���B�ł́A���j�I�ɂ͌Ñ�s�s���Ƃɂ�����萔���Ɏn�܂�A���[���b�p�ł͓����ŁA�����łƂ����悤�ȕϑJ���o�āA�����ł͈�ʂɁu�A���i�ɉۂ����Łv�Ƃ��Ē�`����Ă���B����͗A�����鍑����߂��@���ɏ]���ĉ^�c�����B
�@
���{�������ƌ����ɂ͊Ŏ��匠���Ȃ��A���O���Ƃ̋��c�Őŗ������߂�V�X�e�����Ƃ��Ă����B�������A���{��1866�N�A���ɂ̊J�`�������������邩���Ɋŗ��������A���R�f�Ղ����܂����鏔������P�p���邱�Ƃ��L�������Ŗɒ����̂ł���B�\�����v�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�o�[�^�[���B
�@
���̊ň��������ɂ���ĊO�����i���ǂ��ƈ��������ɗ��ꂱ��ł����̂ł���B�����Ĉ������i����ʂɍ����ɗ��ʂ������Ƃŋ}���ȕ���������������B�C���t���̔w�i�ɂ́A�A�o�̗��ʃV�X�e���̕�����B�����⒃�Ȃǂ̗A���i�͐l�C�������������߁A���l�͔_�Ƃ��琶���⒃���t���A�≮��ʂ����ɂ��̂܂܉��l�֒��������B�����̗��ʂ́A���i���≮�ɏW�܂����i�K�ň�x���i�̗��ʗʂ͒��������B���i����ʂ�����Ɖ�������̂ŁA���ɕۊǂ��Ē����֓n���ʂ��R���g���[������B
�@
�������A�A�o�Ɋւ��Ă͗��j�����߁A�������������K�͂Ȃ��A���l�͖≮��ʂ����ɉ��l�֑������B���ꂪ�ǂ�ǂꂽ�̂ŁA���l�͑S���̎Y�n�ɏo�����A�A�o�p�̐����⒃������A�܂��ǂ�ǂ�A�o�����B��������Ɛ����ƒ��̋������n�ł���]�˂⋞�s�A���ł͕i����ԂɂȂ�A���i�������B����ɘA�����Đ����K���i�����{�ɒl�オ�肵���̂ł���B
�@
����A�C�O��������ȐD����ѐD������ʂɓ����Ă������ƂŁA���ΓI�ɒl�i�̍��������̖ȐD���͂܂���������Ȃ��Ȃ�A�ȐD���ƁA�a�ыƁA�ȉԂ͔̍|�_�Ƃ͑傫�ȑŌ������B
�@
�������オ��A�����̖ȐD���֘A�͉�ŏ�ԁB����ł͏����̐����͋ꂵ���Ȃ����B�����ɍ]�˂̖≮���傫�ȑŌ����Ă����B�����ŁA���{��1860�N�Ɂu�ܕi�]�ˉ����߁v�߂���B�C���t����ƍ]�˂̖≮�̕ی��ړI�Ƃ����f�Փ����@�߂ł���B(1)�G��(2)����(3)�X(4)����(5)������5�i�ڂ́A��������]�˂̖≮��ʂ��Ȃ��ƗA�o�ł��Ȃ��Ƃ�����̂��B
�@
�G���␅���A�X�ȂNJC�O�����ł����Y�ł���i�ڂ����X�g�ɋ������Ă���̂́A�����A��(����)�Ŗu����������Ȕ����u�����V���̗��v�ɃC�M���X�ƃt�����X������������ƂŎ��v���}����������ł���B�����̐��Y�҂��炷��A����u�����v�����A����ɐ��Y�������ǂ������A�����̕����������グ��傫�Ȉ��͂ƂȂ��Ă����B
�@
�ܕi�]�ˉ����߂́A�C���t���}����Ƃ��Ă��]�˖≮�̕ی�Ƃ��Ă����ʂ͂����ɕ\���邱�Ƃ͂Ȃ������B�e���̏��l�́u���R�f�Ղ�W����v�Ƌ����������A���{�ɓP��悤�v�������B����A�����̏��l�͖@�߂����A���ډ��l�`�֏��i�𑗂葱�����B��������u���{�E�]�˖≮�v�u�O�����l�E�������l�v�Ƃ����Η��\���������Ă���B�@ |
������Ƃƒ���E���Ƃ̃X�|���T�[
�@
�����̍����A���̊C�O���o�Ȃǂɂ��A�����̓��{�͑�s���Ɋׂ����B�����Ė��{�̍����͊�@�ɒ��ʂ����B��15���l�̕��m�𑗂����Ƃ���钷�B�����̎����́A�_���⏤�l�ɉۂ����u��p���v�ł܂��Ȃ�ꂽ�B�܂薋�{�̎������B�́A���ԗ��肾�����̂ł���B
�@
����A�����̕\����͋��s�̒���Ɉڂ��Ă������B���j�w�҂͒N���w�E���Ă��Ȃ����A�����̓���Ƃƒ���E���Ƃ̎��Ȏ��{�����r���Ă݂�Ƌ����[�����Ƃ��킩���Ă���B�����炭�o�ϓI�Ɉ��肵�Ă����̂́A����E���Ƃ̂ق��ł��낤�B�ނ�͕����̍�������̗��o�Ƃ͖����̐��E�Ő������Ă������炾�B
�@
�F�������ɂ��|���̎����������܂����Ƃ��A�ނ炪�����I�x���Ƃ��Đ������̂����삾�����B����̐����ɂ������Ă����̂́A�V�c�A�ۉ�(������)�A���؉�(��������)�Ȃǒ��c�o�ȃ����o�[�ł���B�ۉƂƂ́A���q����ɐ������������������Ō��Ƃ̉Ɗi�̒��_�ɗ������܉�(�߉q�A����A����A����A��i)�̂��Ƃ��B�ނ�͓V�c�Ƃɕ�d���邱�Ƃ�E���Ƃ���M���ŁA���{�̎x�����Ă����B���؉ƂƂ́A�܉ƂɎ����Ɗi�ŁA���(�v��A�O���A�����A���厛�A�ԎR��A�吆���A���o��A���A�L��)���Y�������B
�@
�ނ�͖��{���炻�ꂼ��300�`1700�̉Ƙ\��^�����Ă����B���q����̌��Ƃ͑����Ǘ������o�ϓI��Ղł��������A�]�ˎ���̌��Ƃ͖��{����^����ꂽ�Ƙ\�������ł������B�܂��A��X�`���ƋƁA���Ƃ��Ή̓��E�����Ȃǂ�������Ƃ́A�ƌ��Ƃ��đS���̒�q�ɖƏ��^�������������A�������甜��Ȏ����������߂��B
�@
���Ƃ��Ζ����̒��쌠�͂̕�����w�i�ɖ����ېV�Ɍ��т��c������q���O�������͌��Ƃł���B��q�͉������Ƃł��������A����Ɏd���Ă����B����{�����̐E���ł���B�}�i�h�̌��Ƃł���O���ɂ��Ă����{����^����ꂽ�y�n������A���肵���������������B
�@
����̓���Ƃ͒��������n��ł���]�ˁA���A���Ȃǂ��璥�����������Ȏ����ł������B�������A��������\��(����)���x����˂Ȃ�Ȃ��������߁A�ĉ��i�̗������͍����ɑ傫���e�������B�܂��A�e�˂̍������ꂵ���������߁A���{���x������ǂ��납�A���g�̎؋��ԍςŋ��X�Ƃ��Ă����B
�@
1867�N�ɓ���c�삪������֕ԏシ��吭��҂\�B������Ė����V�c���V�����̎�����錾�B�����̌`�Ԃ͗Y�˘A�����B���̎��_�ł�����Ƃ͓��{��̑�喼�ł��������A�c��͐V���{�̃����o�[���珜�O���ꂽ�B���̎��_�ŋ����{�͔��ΐ��͂ƂȂ����킯�����A�R���̐��͂܂������Ă����B���s�����̂͌R�����̑����ł���B�������B�\�͂ƌ��������Ă��������낤�B
�@
�����ېV�̍ۂɊ��R�́A���l����؋������ĕ���B�������A�݂������炷��ΐM���ł��钩�����Ƃ��w��ɂ���Ƃ������S�����������̂��낤�B�܂��A���{�ɑ���s�M���A���]���̑傫�������R���x�����铮�@�Â��ɂȂ����Ƃ�������B1868�N�A���R�͓��C���A���R���A�k�����ƎO���ʂɕ�����č]�˂�ڎw�����B�F���𒆐S�Ƃ���22�˂̔˕��A���悻5���l���s�R�����̂�����A�h��A�H��A�����ȂǑ����Ȍo����������Ƒz���ł���B
�@
�����B�����̂́A���A���̏��l��130�l�ł������B���̍��v�͂��悻300�������B�O��͒P�Ƃ�25000���������Ƃ���Ă���B�������{�̎����I�ȃX�|���T�[�́A�O����͂��߂Ƃ��鏤�l�ł������B���喼�����R�ɐQ�Ԃ�A�]�ˍU���ɗ��悵�ĕ����^�ςԂ�B�����{�̐����c��ł��铿��Ƃ́A�������č]�ˏ�ɌǗ����A���ɖ����J��ւƂȂ����Ă����̂ł���B�@ |
�������ېV�Ŋ������w�o����
�@
�吭��҂ɂ���Ė�������]�˖��{�B�V���{��1867�N�A�������Â̑卆�߂߁B����ɂ�蕐�Ɛ�����p�~���A����ɐ������߂��Ă������Ƃ�錾�����B���N�A�����V�c���u���ʂ̗�v�������A�����͌c�����疾���ւƉ��߂�ꂽ�B
�@
��q���}�i�h���ƂƎF���̓����h�ɂ���ē���Ƃ͐V���{�̉^�c�����o�[���珜�O����A�F���o�g�҂��V���{���i�̎哱�������邱�ƂɂȂ����B
�@
�����Œ��ڂ������̂��A�����ېV�Ŋ����l���ɖ������疾�������ɉ��Ăɕ����A������H�Ƃ̔��W��ڂ̓�����ɂ��ċA�������҂��������Ƃ��B
�@
���{�⏔�˂́A���{���i���Ă̏����x���z�����悤�Ƃ��āA�����̗��w�҂�h�����Ă����B���{�̏����̊J���h�ɂ͐挩�������������A�F���E���B���˂̕��m�����͓��{��ς���ɂ͊C�O�Ƀq���g������Ɗm�M���A����̈ӎu�ŊC��n�����B�����͊v�V�ƕێ炪�����ĐV���ȃV�X�e���Â����͍����������Ƃ����悤�B�܂������̂Ȃ��ʼn����̕��m�����ɂ������̕\����ɗ��`�����X���^����ꂽ����ł��������B
�@
���B�ˎm�̋g�c���A���u�`���������m�u�������m�v�̖剺���ł������ɓ������́A���B�˂̉������m�o�g�ł���B���������B�˂̈��]��ƂƂ��ɁA1863�N�ɔˎ傩�痯�w�̖������B�m�s��͔ˎ傩���l200�����x������A�s�����͎؋��ŕ�����B�����I�ɂ͖��q�ł��������A�ɓ�����Ȃǒ��B�˂�5���̎�҂͏�C�o�R�ŃC�M���X�ɓn�����B�ɓ��͂̂��ɏ�����t������b�ɏA�C�B���͑�ɓ����t�ŊO����b�߂��ق��A�a�ыƁE�S�����ƂȂǂ������ĐB�Y���Ƃɍv�������B�܂��A�O������Ɛe�����A�u�O��̑�ԓ��v�Ƃ��Čo�ϊE�ł������B
�@
1865�N�ɂ́A�F���˂̐X�L�D�ƌܑ�F�����C�M���X�֗��w�����B�X�͂��̌�A�A�����J�ɂ����w���A�A����A���㕶����b�ɔC�����ꂽ�B100�N�ȏ�O�Ɂu�p�����{�̋��ʌ�Ƃ��č̗p���悤�v�ƒ�Ă������挩�h�ł��������B�ꋴ��w�̑O�g�ł��鎄�m�u���@�u�K���v���J�݂���ȂNj��番��ŋP�������Ɛт�����B�ܑ�͉��B�A����A�������{�̎Q�^�E�O�������|�ƂȂ�A��l�Ƃ��đ��ɕ��C�B�����ǂ�U�v���A������Ŋ֒��ɏA�C�B������ՂƂ��鑽���̊�Ƃ̑n�Ƃɂ������A��㏤�H��c�������߂��B
�@
����ҁA�v�z�ƂƂ��Ė���������@�g�́A�L�O�����Ô˂̉������m�̎��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�ނ͍]�ˎ���ɂ͊���ł��Ȃ������l���̈�l���낤�B1860�N�A���Ďg�ߒc�̐��s�D�E���Պۊ͒��̏]�҂Ƃ��ď�D���A���߂ēn�āB���̋A�H�ɍ��`�A�V���K�|�[���A�}���Z�C���A�������A�p���A�����h���A���b�e���_���A�x�������A���X�{���ȂǂɊ��A�������L���Ă���B1867�N�ɍēn�Ă��A�A�����J�ő����̂��Ƃ��w�B�A����A���犈���ɏ�M�𒍂����B�܂��A����4�N�ɂ͊�q��������q���@�c�����Ăɔh�����ꂽ�B���{�̗v�l�Ɨ��w�����琬�鑍��107���̒��ɂ́A�،ˍF��A��v�ۗ��ʁA�ɓ������̂ق��A�̂��Ɏv�z�ƁA�W���[�i���X�g�Ƃ��Ċ��钆�]������A�O������̑����ƂȂ�c�����������B
�@
���̂悤�ɓ����̖����ɉ��Ăɗ��w�����҂������c��⌛�@�̐ݗ��A������v�A�B�Y�Y�Ƃɐ[����������Ă������B�]�ˎ���̍Ō�ɔނ�̂悤�Ȑl�������܂ꂽ���Ƃ����{�ɂƂ��čK���������Ƃ����悤�B400�N���������]�˖��{�͕������x���x�[�X�Ƃ��A����R���c�F�������I�݂ȓ�����~�������Ƃň��肵�����オ�����������B����͔˂̎�����F�߂鑽�l���ɕx����ł������Ƃ�����B�������A���̖����ɂ��������C�O�Ɋw�Ԃׂ��������������̂́A�c�O�Ȃ��瓿��ƂłȂ��A���B��F���Ƃ������n���̕��m�Ɨ��w�������ł������B
�@
�������A���{�ɂ͊w�Ԃׂ��������v�͑����������B�����͌��݂ł������ČÏL���͂Ȃ��B�ނ��땁�Ր��ɕx�����Ăɐ�삯�A�]�ˎ���̓��{�Ŏ��{����Ă������Ƃɑ傫�ȈӖ�������Ƃ����悤�B�@�@
�@ |
| �����{�̐��� 3 |
   �@
�@ |
|
�@ |
|
�����{�̐��� 3 |
|
�������d�G�̉ݕ������ƊǗ��ʉݐ��x�@ |
���͂��߂�
�@
�Ē�������E�����d�G�E�V�䔒�E�c���ӎ��E������M�E�C�ېˁE�R��崓��E�{�������E���ꌹ���E���c�����B�]�ˎ���͖ʔ������ゾ�Ǝv���悤�ɂȂ��Ă����B1640�N����1853�N�܂ō��������Ă��āA�قڊ��S�Ɏ��������̎���B�����Ă���́u�R�����R�����v���咣����u���_���v�M�҂������A���������̎Љ�����B���̎��������̎���ɂ����āA1600�N����̐l����1�A000����A1720�N��2�A600����Ƃ����120�N�Ԃ�2.6�{�̑���������A���ꂪ�����ɂ͖�3�A000���l�ɂȂ��Ă���B���{�ł��̂悤�ɐl�������������Ƃ������Ƃ́A��G�c�Ɍ������������Y�f�c�o��3�{�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃ��B
�@
���ˑ̐��Ƃ́A�e�˂��Ɨ��匠���Ƃ̂悤�Ȑ����̐��������B�u�n���̎���v�Ƃ��u���B���x�v���咣����l�ɂƂ��Ă�����̎���Ȃ̂��낤�B�������R���̗��ʐ��x��c���ӎ��̌o�ύ\�����v�͌���ł��A����𗝉��ł��Ȃ��l�����邭�炢�i���̂������B�܂��܂��T���Δ閧������ɈႢ�Ȃ��B���̎���Ɍo�ϋK�͂�3�{�ɂ����閧�Ƃ���ɔ����Љ�E�����̕ω����B���̂悤�Ȏv������u��]�ˌo�ϊw�v�Ƃ̃^�C�g���𗧂��グ�Ă݂��B�]�ˎ�����^�e�Ƀ��R�ɐ��Ă݂悤�Ǝv���B����Ɛ�����̏����������ɂȂ�B�u��̌o�ϊw�v����{�Ƀ��j�[�N�Ș_�@��W�J���悤�Ǝv���B�����Ȃ���A���̌l�I�Ȏ�ւ̂��t�������A��낵�����肢�v���܂��B
�@
�������d�G�̉ݕ�����
�@
�]�ˎ���ɑ傫�Ȍo�ω��v��2�x�������ƍl����B����͗��j�̋��ȏ�����������v�Ƃ͂܂�ňႤ�B�]�ˎ����3����v�Ƃ��āA(1)8�㏫�R�g�@�w���́u���ۂ̉��v�v(18���I�O��)�A(2)������M�w���́u�����̉��v�v(18���I��)�A(3)���쒉�M�w���́u�V�ۂ̉��v�v(19���I����)�����グ���邪�A�����ł͈�����ʂ���]�ˎ���̌o�ω��v�����Ă������Ƃɂ���B�悸�g�b�v�o�b�^�[�͒ʉݐ���Ő�i�I�ȍl���������Ă��āA���̐�������s�������b�o�ϊ����̊���g�������d�G�̓o�ꂩ��B
�@
�����d�G(1658-1713)(������-����3)����5�㏫�R�j�g�̎���A���\�̉₩�Ȓ��l�������炫�ւ��Ă������A���������{�̍����͐Ԏ������Ŕj�]���O�������B���̎��䑤�p�l����g�ۂ̖����āA����g�������d�G�͍����Č��֎��g�ނ��ƂɂȂ����B�����ŏd�G���l�����͉̂ݕ������������B�c�������̋��ܗL�ʂ����炵�A�o�ڂ��҂��A�ʉ݂��g�傷�邱�ƁB�܂菬��10����������āA�������������15���Ƃ��ė��ʂ�����B����Ŗ��{�̍����͏����ƍl�����B���������ݕ����������4�㏫�R�ƍj�̎���ɂ����{���Ō������ꂽ���A���̘V���y�������̔��u��(�悱����)�Ȃ�킴�v�Ƃ��đ����Ă���B���������̎��́A�d�G�̂���܂ł̎d���Ԃ肩�����g�ہE���R�j�g�̐M���������Ď��{����邱�ƂɂȂ����B���ꂪ1695(���\8)�N�B
�@
���{�͂��̉����̖ړI���u���Â��Ȃ��Ė��ł������߁v�Ɛ��������B�������{���̖ړI�͕i�ʂ̍����c��������������ĕi�ʂ𗎂Ƃ������̂ɉ������A�o�ڂ̊l����_�������̂������B�c��������86���̋��i�ʂ��������̂��A56���Ɍ��������́B����ŏo�ڂ͑傫���A��̉����ƍ��킹�āA�S�̂�500�����ɂ��y�Ǝ��Z�����B
�@
���ꂪ���{�̍����Č��ɑ傫���v������̂����A������̌��ʂ��������B����͒ʉݗ��ʗʊg��ɂ��i�C�h���������B���얋�{���������A�퍑�̂������������֕��݂����A�Ă̐��Y���L�сA�L���ɂȂ�n�߂Ă����B�j�g�́u���ވ���݂̗߁v�������������̒��̈�������琶�܂ꂽ���̂ŁA�P�ɍs���߂�����������ł͂Ȃ������B
�@
����ȑO�͎E���Ƃ�������ŁA�����ɍ����Ďq�����̂Ă���A�C�ɓ���Ȃ��q�����̂Ă��肷�邱�Ƃ����������A�l�Ԃ⋍�n���N�V������a�C�ɂȂ����肷��ƁA�܂����̂��邤���ɖ�R�ɒǕ����Ď��R�Ɏ��ʂ̂�҂悤�ȕ��K�����������B�r���살�炵�̂܂܂������B�j�g�͂����������܂낤�Ƃ���B���̎����͐l�Ԃ��܂߂��u���ށv�A�܂萶���Ƃ���������̑S�Ă��ɂ��A���a��z�����Ƃ̎��ゾ�����B���{�l�S�Ă������́u��v�����悤�ɂȂ�̂͂��̎��ォ�炾�����B������������́u���ވ���݂̗߁v�ł������B
�@
�������Đ��̒������肵�A�������L���ɂȂ�A�o�ς��g�債�Ă���Ƃ���ɔ������ʉ݂������K�v�ɂȂ�B�����̌o�ϗp��Ō����u�����ʉ݁v���K�v�ɂȂ�B�d�G�̉ݕ������͂��́u�����ʉ݁v�̖������ʂ������킯���B
�@
�������Ė��{�̍�������������A�o�ς������ɐL�т邩�̂悤�Ɍ��������A�����Ŏv��ʕ��Q���o�Ă����B����͍]�˂̏�������ُ�ɍ������Ă������Ƃ������B
�@
�����E��E�K�̎O�ݑ̐�
�@
�����ō]�ˎ���̒ʉ݂̓��ِ��ɂ��Ēm���Ă����K�v������B�]�ˎ���̒ʉ݂͎O�ݑ̐��Ƃ����āA���E��E�K��3����Ȃ��Ă����B���͑��ɏ����ƌĂ����̂ŁA������̂Ƃ��������ʉ݂ł���A1����4���A1����4��Ƃ���4�i�@�̒ʉ݂������B�Ƃ��낪��͋��ƈ���āA���̏��x�̋�̂��̂����扽��(10�i�@)�Ɣ��Ōv���Ďg����A���ʉݕ��ł������B���Ƌ₪���z�ݕ��ł���̂ɑ��āA�K�͓�(�̂��ɂ͓S�̏ꍇ��������)����ނƂ��鏭�z�ݕ��ŁA�сE��(��т�1�A000��)�Ƃ����P�ʂŐ������Ă����B������u���i�ʕ�v�Ƃ����̂�����ł���B
�@
�Ƃ���őK�͑S���I�ɒʗp�������A���Ƌ�͂����ł͂Ȃ������B���͍]�˂𒆐S�Ƃ���֓��E�����o�ό��ŁA��͋��E���𒆐S�Ƃ������E�����o�ό��Œʗp�����B���������č]�˂̏���ҕ���������E�������甃���Ƃ������Ƃ́A������{�I�Ȓʉ݂Ƃ���o�ό��������{�Ƃ���o�ό����畨�������ƂɂȂ�B���̏ꍇ���̏��������Ƃ���A�ʉ݁���ɑ��āA�ʉ݁����������Ȃ�Ȃ�قǁA�]�˂ɂ͑����̕������������ė��邱�ƂɂȂ�B�t�ɒʉ݁���ɑ��āA�ʉ݁������キ�Ȃ�]�˂ɂ͕����̗��������Ȃ��Ȃ�A�]�˂̏�������������邱�ƂɂȂ�B�����ō]�˂ɂ�葽���̏�������W�߂āA�s�����������肳���悤�Ǝv���A�ʉ݁���ɑ���ʉ݁����̃��[�g���グ������B���邢�͒ʉ݁����ɑ���ʉ݁���̃��[�g��艺��������B����͍����̍��ۖf�Ղɂ�����בփ��[�g�̌����Ɠ����ł���B�����d�G�����̂��ƂɋC�Â����B
�@
���E��E�K�͖{���Ɨ������ʌ̒ʉ݂ł����āA���݂̃��[�g�͓��X���ꂪ�����āA�₦���ϓ����Ă����B���̑��ꂪ��̂��̒��x�ň��肵�ė~�����A�Ƃ������葊��{���ŏ��Ɍ��߂��̂�1609(�c��14)�N7���̂��Ƃ��B����ɂ��ƁA��1���͋�50��A�K4�тƂȂ��Ă���B���炭�͂���ɋ߂�����̓������������A�_���E�������L���ɂȂ��Ă��銰���E����(1661-1681)����ɂ́A��1������60��Ƃ����̂����葊��ɂȂ��Ă����悤�������B�d�G�̉ݕ������͏����̉����Ɠ����ɁA����������Ă���B
�@
�d�G�̉ݕ������A���߂͑傫�Ȓ�R���������B���{������I�ɒʉ݁���ɑ���ʉ݁����̕i�ʂ��������̂�����A���{�̌o�ς������Ă���������l����R�����B�d�G��1700(���\13)�N11���A���{�̎x�����ɂ������Ă͋�1�����]���̂悤�ɋ�50��̌��葊��ł͂Ȃ�60��̌v�Z�ɂ���̂ŁA���Ԃ�����ɏK���悤�ɁA�ƐG��Ă���B����ɂ���ċ⍂��������������悤�Ƃ����B����͒ʉ݁����20���̐艺���ɂȂ�B�ʉ݁����̕i�ʂ��������������ɁA����ɋ�̐艺���ɂȂ�̂ŁA������l�͔[�����Ȃ������B�d�G�͊��x�ƂȂ����{�̐����O�ꂳ���悤�Ǝw�����邪�A������l�̒�R�͎��܂�Ȃ��B�����ō��x�͒ʉ݁���̉������s���B
�@
��̊ܗL�ʂ�50���A40���A32���Ɖ����Ă����A���ɂ�20���ɂ܂ŋy��ł���B���̂��Ƃ͓��R���⑊��ɂ����f���A�]�˂ɂ����ẮA��i6�A7�N�ɋ�1���ɂ��₪60��ł��������A�������N�ɂ�64-55��A����2�N�ɂ�76-81��܂łɒᗎ�����B���̏ꍇ�������ŁA����2�N�ɂ͋�1���ɂ���80��]�ƂȂ��Ă���B�]���̌��葊����60�������艺�����̂�����A����E�����o�ό��͑傫�ȑŌ������B
�@
���̂悤�ȏd�G�̐���ɑ��ĐV�䔒���U�����Ă����B���͏d�G���u�V�n�J蓈ȗ��̊��ׂ̏��l�v�Ƃ��߂��A6�㏫�R�Ɛ�ɏd�G�̔�Ɨv������������3�x�B�u�������̗v����������Ȃ��ꍇ�́A�����͏d�G��a���Ŏh���E���ł��낤�v�Ƃ܂ŋl�ߊ���āA1712(����2)�N9��11���A�d�G��Ƃɐ�������B
�@
�d�G�̎��͂�F�߁A���̐����M�����ĔC���Ă�������g�ۂ͂��łɉB�����A���R��6�㏫�R�Ɛ�ɑ����Ă���B�����ɂ����ĉ����d�G�̐�i�I�ȋ��Z����͏I��邱�ƂɂȂ�B���ɂ���Ċ����s���Ƃ��ꂽ�d�G�͂��̗�1713(����3)�N���v�B�E�Q���ꂽ�Ƃ̉\������B
�@
�V�䔒��(1657-1725)(����3-����10)�͏d�G�̐����ᔻ���Ă����B1712�N�A�d�G�����r����������āu���v�v���s���B���̕����Ƃ́A�d�G�̋t���s���������B�����͈ȑO�̊ܗL�ʂɖ߂��B�c�������Ɠ����ɖ߂����̂�����ʂ͌������B�ʉݗ��ʗʂ����炵���̂�����f�t�����s���ɂȂ����B���̐���̊�{�́u����v�B���Ō����u������f�m�o�v���B���߂͒��l�����}�������A�i�C�������Ȃ肷���ɐl�C���Ȃ��Ȃ����B�o�ϐ���Ɋւ��ĐV�䔒�͖��\�ł������B1716(���ی�)�N4�����R�ƌp�v�B���N5�����Δ�ƁB���̌�g�@�́u���ۂ̉��v�v���n�܂�B
�@
���f�p�ݕ��@
���얋�{�͒��N�ƃI�����_�����Ɛ����ɖf�Ղ��Ă����B�����Ėf�Ղ̌��قɂ͒����p�������A�d�G�̉ݕ������ɂ��i�ʂ�������ƁA���N���璚��̎������ۂ����B���̂��ߏd�G��1710(��i7)�N�A���N�l�Q�A���̂��߂Ɂu�l�Q�㉝�Ë�v�ƌĂ��A���N�f�Ր�p�̋��(�i��80��)�𒒑������B
�@
�l�Q�㉝�Ë�͂��̌�1714(����4)�N�̉����ŕi�ʂ������グ��ꂽ�ׁA�������~�ɂȂ�B���������̌�1736(������)�N�̉����ɂ��i�ʂ�����������ꂽ���߁A�Ăђ������ꂽ���A18���I�㔼�A�ӎ��̎���ɂ́A�����⒩�N�l�Q�Ȃǂ̍��������̐������������߁A�u�l�Q�㉝�Ë�v�͂��̖������I���A�������~�ƂȂ�B
�@
�������d�G�̐�i��
�@
�ʉݗ��ʗʂ𑝂₵�o�ς𐬒������鐭��́u�����ʉ݂͓���̔����I�y�ɂ���ċ�������v�Ƃ��������̋��Z����ƈ�v����B����ȏ�ɐ�i�I�Ȃ̂́A�u�c����������������́A�ׂȂ�킴�v�ɑ���d�G�̓����u���Ƃ����I�̂��Ƃ����̂Ȃ�Ƃ��A����Ɋ��{�̓����{�����Ԃɒʗp�����߂ȂA���Ȃ킿�ݕ��ƂȂ�͓��R�Ȃ�B���Ȃ�������B�v
�@
����͏������M�����Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�u�M�p�ɗ��t����ꂽ�ݕ��v�ƍl���Ă������ƂŁA����́u���{�ʐ��v�ł͂Ȃ��u�Ǘ��ʉݐ��x�v�̍l�����B�d�G�ȍ~�����{�ʐ��͈ێ�����Ă����B�����ېV����[���������s�Ƃ����`�ŋ��{�ʐ��͑����B���{�����{�ʐ����̂Ă�̂́A1931(���a6)�N12�������������呠��b�ɂȂ����Ƃ��B�������̌���A�����J�̃h���́A1�I���X35�h���Ō��������B���ꂪ1971�N8���܂ő����B����200�N�ȏ���O�ɏd�G�͊Ǘ��ʉݐ��x���l���Ă������ƂɂȂ�B�A�_���E�X�~�X���u���x�_�v���o�ł����̂�1776�N�A���{�Ŗ|�ꂽ�̂�1882�N�B���[���b�p�Ōo�ς̖�肪�u�ϗ��w�v����Ɨ�������Ɓu�o�ϊw�v���ł��������B�d�G�̐挩���ɂ͋����ق��͂Ȃ��B�V�䔒�Ƃ�����R���͂ɂ���Ă��̉��v�������ӂ��ꂽ�A�Ƃ͂����d�G�̂悤�Ȑ挩�����������o�ϊ����������A�Ƃ������Ƃ͌o�ϊw��������n�߂��҂Ƃ��ĂƂĂ��������B�o�ϊw�Ɋւ��Ă͓��{�l�����s�I�ɂȂ�K�v�͑S���Ȃ��B
�@
���\����̊���vs��������̊����d�G�͏��߂���ʉݐ���̒m���������Ă�����ł͂Ȃ��B���s������d�˂Ȃ���[���������Ă������B�w�ҁE�G�R�m�~�X�g�̂悤�ȃu���[�������Ȃ��B���̂悤�ɏ��R��3�x����Ɨv�����o����R���͂ȂǁA�킸���ɖ���g�ۂƍj�g�����C�Ȃ����͂���ł��d���ɐ�O�ł����ł��낤���A���̌�̋C��J�����A�z����₷����̂������낤�B��������̊����͂ǂ����B�Ȃ��ɂ͉��v�����݁A�e�̒�R���͂ƌ��сA���v�҂̑�����������A�Â��g�D�̂���邽�߁A�����̃g�b�v�����v�҂ƍ����Ⴆ�邱�Ƃ�������B�u����őg�D��������v�Ƌ��銯���ɔ�ׁA�d�G�̏�M�Ɋ��������ɂ͂����Ȃ��B�@ |
|
���c���ӎ��ƁA���̋��͎҂����@ |
   �@
�@ |
�������ʂɂ킽����v
�@
�c���ӎ�(1719-1788)(����4-�V��8)�����d�G�̉��v�����܂��āA���I��V���ȉ��v�҂��o�ꂷ��B�u�c���ӎ��ƁA���̋��͎҂����v���B���j�̖{�ł́u�c������v�Ƃ����\������������B�u�c���ӎ��ƁA���̋��͎҂����v�Ƃ̃^�C�g���ɂ����B����́A���̉��v�͊m���ɓc���ӎ������S�ɂȂ�A�ӎ����������炱���i���v�Ȃ̂����A�ӎ��͓ƍَ҂ł��d�G�����ł��Ȃ������B�������ӎ��̐l���̂������A�����̋��͎ҁE�u���[���������̂����������炾�B
�@
���y�̏��䂾�����c���ӎ������̎��͂�F�߂��āA�䑤�p�l�Ƃ��āA�V���Ƃ��đ����̉��v��i�߂�B�ӎ��̎��͂Ƃ��̋��͎҂����̒m�b������Θd�G�ȂNJW�Ȃ������B��ɔ��c�������h�������������ɘf�킳��邱�ƂȂ��u�c���ӎ��ƁA���̋��͎҂����v�̎��g���v��U��Ԃ��Ă݂悤�B
�@
���X�̉���I�Ȑ���A����������ƁA(1)�ʉݐ���A(2)�Ő����v�A(3)�ڈΒn�J���A(4)����J���A(5)�o����x���P�A(6)�\�Z���x�m���A�ƂȂ�B�����̔�d�͌����ɂ���Ă��낢�날�낤���A�����ł͉����d�G����̗���Ƃ��āu�ʉݐ���v������グ�邱�Ƃɂ���B
�@
���@
���a�ܖ��̔��s1765(���a2)�N�A�䑤�p�l�c���ӎ��͊���ᖡ���̐��v�h�������A����܂Œ���Ɠ���Ɍ����Ă�����݂ɉ����A�܂������ʂ̐V�����ݕ��s�������B�u���a�ܖ��v�ƌĂꂽ���̉ݕ��́A���{�̉ݕ��j�����I�ȈӖ��������Ă���B�����ɏ��߂Ċz�ʂ������W���ݕ��Ƃ��Ă̋�݂����܂ꂽ���炾�B���̋�݂͕\�ʂɁu��ܖ�v�Ƃ���悤�ɁA���Ōv�邱�ƂȂ��ʗp�����邱�Ƃ�ڎw�������̂������B����܂ł̋�݂͓��X����Œl�������A���݂Ƃ̌������[�g�͕s�肾�����B���Ɛ��̌o�ς���r�I�Ɨ����ċ@�\���Ă��邤���́u�]�˂͋������A���͋⌭���v�ł����Ă����܂�x��͂Ȃ������B�Ƃ��낪�]�˂̌o�ϊ����������ɂȂ�A�S������̎s��ƂȂ�X���������A�����̌o�ό𗬂��[�܂��Ă���ƁA���̂܂܂ł͕s�ւł������B
�@
�ʉ݁����ʉ݁����Ƀ����N�����A���̃��[�g���Œ肳����A����ɂ���Ď����p��ጸ���悤�Ƃ���̂��ړI�������B�ʖڂ�5��(18.75g)�A�i�ʂ͌�����Ɠ���460/1�A000�ŁA�\�ʂɂ́u������ܖ�v�A���ʂɂ́u�퐥�v�̕������A���ʂɂ͏��^�`�ł��ꂽ�������̋�݂������B������Ƃ͌������N�ɒ������ꂽ��̈Ӗ��ŁA�ܖ��̖��̂悤�ɁA���{����߂�����̌��葊��A��1����60��ɂ��������āA����12���ŋ�1���Ƃ��Č�������悤�Ɏw������Ă����B
�@
�u���a�ܖ��v���L�����ʂ���Γ��{�����ł̏���������ȏ�ɉ~���ɍs����͂��������B�����������ɑ傫�Ȓ�R���͂����݂����B�]�ˁE���E���s�Ȃǂ̗��֏��������B���Ƌ₪�Ɨ������ݕ��ł���A���X���ꂪ�������Ƃɂ��A�ʉ݁����ƒʉ݁�������������̎萔���������Ƃ��闼�֏��A�o�ϋK�͂��傫���Ȃ�ɏ]�������ʂ������Ȃ�A���v��~�ς��Ă������B�����u���a�ܖ��v�����y����A�萔������������͖̂ڂɌ����Ă����B���֏����������R��́A���́u���a�ܖ��v�ɑ��Ă�����E����Ɠ�������𗧂āA�ӎ����Ӑ}�����A�u���a�ܖ��v12������1���Ƃ̑�����̗p���Ȃ������B���̂���1772(���i��)�N�܂ł�8�N�Ԃ�1�A800�іڂ̒����������݂̂ł��̐����͏I������B
�@
���a�ܖ��ɂ����Ƌ�̌������[�g���Œ艻���A���Ƌ��1�̒ʉ݂ɓ������悤�Ƃ́A�ӎ��������b�o�ϊ����̖��͂����ӂ��ꂽ�B���������v�ɔR�������������͒��߂Ȃ��B���s�͂��V���ȉݕ��s����B
�@
���@
���a���`��锻�̔��s1772(���i��)�N9���A�V���ȉݕ��s����B���i���N�̔��s����9���͂܂����i�Ɖ�������Ă��Ȃ������B���̂��߁u���a���`�v�ƌĂ��B���̉ݕ��A�\�ʂɁu�ȓ��`���Њ������ꗼ�v�̕�����2�s�ɑō����A���ʂɂ́u����퐥�v�̕��������A���̏�Ɏq���������A����ɂ��̍����Ɂu��v�Ƃ������̋Ɉ������ł���B�����đ��ʂɂ́u���a�ܖ��v�ɗp�������Ԍ`�ł���Ă���B�\�ʂ̕����́A���`��锻���Ђŋ�1���Ɍ�������A�Ƃ����Ӗ��ŁA����͋�łł��Ă͂��邪�A���Œ�������Ă�������Ɠ���ʉ݂ł���A���̂́u���a�ܖ��v�̗��O������ɐi�߂āA����́u��ő��������݁v�ł������B���Ȃ݂ɖ�������̙[�������́u���ō�������݁v�ƌ����悤�B
�@
���́u���`�v�Ƃ������t�́u�����̗ǎ���v�Ƃ����Ӗ��ŁA�����ܖ��(�i��46��)�ɔ�ׁA98���Ƃ���߂č����A����ƌ����Ă������x���Ȃ������B����������ł����֏��͂��̕��y�ɑ��Ē�R�����B���{�͂��̎g�p�𖽂������A���֏��B�͎���Ȃ������B�����Ĉӎ����r��A������M�͗��֏������̎咣�����A���̒������~�����B�������u��锻�v�͎���̗v���ɍ������̂������̂ŁA������M����C���ꂽ��A����12�N�ɒ������ĊJ���ꂽ�B
�@
�ӎ��͋��古�l���{�ƌ������Ă��邩�̂悤�Ɍ����邪�A�ʉݐ���Ō������A���古�l�̗��v��i�삵�A����ƌ������Ă���̂͏�����M�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
���b�o�ϊ����������ڎw�����A�ʉ݁����ƒʉ݁���̓����A�u���a�ܖ��v�̎��s����w�сu���a���`��锻�v�ł��̓����J�����ƂɂȂ����B���v�ɔR�������b�o�ϊ���������������M�ɂ���Ď��r�������Ă�����A��M�Ȍセ�̈Ӑ}�͎p����čs���B�u��ő��������݁v�͖����܂ł�7��ޔ��s���ꂽ�B�����Ă��̌W����݂̒����ɂ͑�ʂ̒��₪���ׂ��ꂽ���߁A1830�N��ɂȂ�Ƌ�݂̖�9�����W����݂���߂�悤�ɂȂ����B�o�ϊ��������̎��݂͖��ʂł͂Ȃ������B
�@
�Ƃ���ł���͍]�ˎ���̒ʉݐ���Ȃ̂����A�����̖��Ƃ��čl����Ƃ����ƕ�����₷���B�Ⴆ���[���b�p�ŁA�C�^���A�l���h�C�c�̉�ЂɏA�E���p���x�X�œ������ƂɂȂ����ƍl���Ă݂悤�B�����̓h�C�c�̃}���N�ŋ�s�ɐU�荞�܂��B������͂�����t�����X�̃t�����ɑւ���B�̋��ɋA��Ƃ��̓C�^���A�̃����ɑւ���B�����͉Ƒ������[�}�ɂ����Ƃ�����A��͂�C�^���A�̃����ɑւ��đ�������B�ƂĂ��ʓ|���B�N���������v���B��̒ʉ݂ɂȂ�����֗����낤�ƍl����B���{�Ԃ���Z�S���҂̊Ԃŋ��c���i�ށB�W�҂̓w�͂������Ă���ƃ��[���b�p�̒P��ʉ݃��[�����a�������B�傫�Ȋ��҂̖ڂ������B���[���b�p�̌o�ώj�̈��G�|�b�N���B21���I�̓��[���b�p�o�ςɑ傫�Ȋ��҂�������B
�@
���ꂪ21���I�̂��ƂȂ�A���v�ɔR�������b�o�ϊ������������킵���̂�200�N�ȏ���O�̂��ƁB�A�_���E�X�~�X(1723-1790)��}���f���B��(1670-1733)�̎���ƌ����邾�낤�B�u�I�̋��b�v�\�����̂�1714�N�Ȃ̂�����B����ɂ��Ă��������ꂽ���{�ƃ��[���b�p�A���̎��オ�o�ϊw�̑傫�ȓ]�����������Ƃ́B�o�ϊw�ɂ����Ă͓��{�ƃ��[���b�p�̐�i���C�M���X�Ƃ������i�s�������̂��B���{�͖{���Ɂu�����v�����Ă����̂��낤���H
�@
�����d�G(1658-1713)(������-����3)
�@
�}���f���B��(BernarddeMandeville)(1670-1733)
�@
�c���ӎ�(1719-1788)(����4-�V��8)
�@
�A�_���E�X�~�X(AdamSmith)(1723-1790)�@ |
|
���������E�^����ȂNJԐڐŏd���̐Ő����v�@ |
   �@
�@ |
���N�v�ā����ڐł̑����͊��҂ł��Ȃ�
�@
���{�̍����͔N�v�ĂƓV�̂ł̋��E��ȂǍz���̎Y�o�ł������B�N�v�Ă͓���ƍN���u�N�v�͕S�������ʂ悤�A�E���ʂ悤�A���肬���t�܂Ŏ��̂����z�ł���v�ƌ������Ɠ`������悤�ɁA�S���̂��̔N�̎�����70����藧�Ă�̂���ʓI�ł������B���ꂪ�����O���̐ŗ��B
�@
�������A�����H���A���H���݁A�鉺�����݂Ƃ������C���t���������I����������N��(1661-1673)���납��N�v���͋}���ɒቺ���n�߁A�V�䔒����������������i�N��(1704-1716)�ɂ͎O�������ɋt�]�����B
�@
�����O���̔N�v�����O�������ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A�N�v��[�߂����Ɖ����c���Ă��Ȃ������S���̎茳�ɁA�N�v��[�߂����ƂɁA�Ȃ��u�l�v�Ƃ��������������c��悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B���̂��ߏ����̐����͒������L���ɂȂ����B4�㏫�R�ƍj�̎��ォ��A5�㏫�R�j�g�̌��\����ɂ����Ă������������̐�������A�܂茳�\�̔ɉh�͂��̂悤�ɂ��Ă��������B
�@
����͏����̌o�ρB���{�̍����͋t�������B
�@
�ꎞ�I�ɉ����d�G�̉ݕ������ɂ������Č����V�䔒�̂��߂Ɍ��ɖ߂�A���{�͍����ێ��ɋꂵ�ނ悤�ɂȂ�B
�@
8�㏫�R�g�@�̉ۑ�͖��{�����̌��Ē����ł���A���̎�@�͔N�v�̑����ł������B�����ĔN�v�����̋�̍�́A(1)�V�c�J���𑣐i���A�ېőΏۂƂ��Ă̍k�n�𑝂₷�B(2)�N�v�����@���u������@�v����u��Ɩ@�v�ɕς��邩���A�����̔N�v��[�߂�悤�ɁA���ꂪ�s���Ȃ�u�L�ь����@�v�ɂ���B�Ƃ������̂������B�Ƃ���ŐV�c�J���͐퍑�������犈���ɂȂ������A����L�]�ȏ��͏I����Ă����B�ނ��덡����c���̂ĐV�c�J���Ɍ������_���������A�N�v�����͒Z���I�ɂ͖]�߂Ȃ��Ȃ��Ă����B�����āu��Ɩ@�v�ւ̕ύX���_���̒�R���傫�������炱����ňꝄ���N����n�߂�B
�@
�g�@�̎q�Əd�̏����Ƃ��Ă̈ӎ��͂�������Ă���B���{�����Č��͔N�v�����ł͌��E�����邱�Ƃ����B
�@
�u������@�v���N�H�̎��n�����ɖ�l���������A���̂����̃T���v���ɂ����n������B�o���̈����ꍇ�͔[�߂�N�v�̗ʂ���������B�ꌩ�S���ɂ͊�ꂻ�����������͋t�B��l�̂���������Ŋ��蓖�Ă����܂�̂ŁA���ł͖�l�̐ڑ҂ɖZ�����B�܂���l������܂Ŋ����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@
�u��Ɩ@�v���n�̏ɊW�Ȃ����̗������߂Ă������@�B���R�g�@�́u���̕����S���ɗL���Ȃ͂����A�v�Ƃ������ƂŔ[�߂闦�����߂悤�Ƃ����B
�@
�u�L�����@�v��l�����ۂɓc������M��M���ׁA����ɉ����ĉېł�����@�B�u������@�v�ȏ�Ɍ��������肷��B���ꂾ�ƌ����Ɏ��Ԃ������邾���łȂ��A��ɊJ�����ꖳ�Œn(�B��c)���������Ă��܂��A�ȂǕS���ɕs���ɂȂ�B
�@
���S��Ꝅ�ɑ��鏫�R�Əd�̂��ق�
�@
�L�����@�͉ߍ��ȐŖ@�ŁA�u�S���ƌӖ��̖��́A�i��i��قǏo����̂Ȃ�v�ƕ��������Ƃ����開�j�_���ዷ��t�����ďo�������̂��Ƃ���Ă���B�g�@�͂������{�C�ł��̐Ŗ@���̗p����A�Ƃ��������̋����Ƃ��Ďg�����肾�����B�Ƃ��낪���̗L�ь����@���̗p���悤�Ƃ����˂����ꂽ�B�S�㔪���ˎ���X���т������B�S���͂����j�~���悤��1754(���4)�N8��10���A�����鉺�ɋ��i���������B�������ˑ��ł�3�l�̉ƘV���P������A�o�����o���ĕS�������U�������B
�@
�������˓����d�h�ƍ]�˂̔˓@�͔[�����Ȃ��B���b�ɓ��������A�˂̔N�v���ɖ��{���������ނ��ƂɂȂ�B�����m�����S���͂���ɋ��d�ɂȂ�B�ˑ��͕S���̐�����Ɏ�肩����B�S�����͖��{�ɑi����B���̌���x�����Ƃ肪����A1754(���4)�N8���Ɏn�܂藎������̂�1758(���8)�N12���B���ɗ�̂Ȃ����������ɂȂ����B
�@
�����9�㏫�R�Əd�̎���ŁA�c���ӎ���1751(��)�N�ɑ��p�\���Ƃ�����E�ɂȂ�A1758(���8)�N9����������1���ƂȂ�A�喼�̗�ɉ����ƂƂ��Ɂu�]�菊�̎����ɂ��̐Ȃ�Ȃ�ׂ��ނˁv�������A���܂��ܐi�s���Ă����u�S��ꌏ�v�̐R�c�ɎQ���B���̏����R�Əd�ɕ����ڂ𖽂����Ă���B
�@
���{�]�菊�ł̐R���̌��ʁA�̎���X���т͗̒n�v���̂������B�암��V��v�̂Ƃ���ɉi�a���B�S�����͎���13�l�����������B����ɑO�㖢���Ƃ������ׂ����ƂɁA�V���ȉ��̖��t�����X�ː��ɂ���Ƃ��ď������ꂽ�B����͘V���A��N��A��ڕt�A�����s�ȂǂŁA��N��{������璉��(���B����1��5���)�̒n�v���A��B�ÎR�����z���։i�a���B�����Ă��̑��ǂ͓c���ӎ������炤���ƂɂȂ�B
�@
���̂��ق��̈Ӗ��́A���ڐő����h���t��Ǖ����A�c���ӎ������[�_�[�Ƃ���ԐڐŔh�̓o��Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
�������ԂƂ����]�ˎY�Ɛl�̒m�b
�@
�ȒP�Ɍ����Γ��Ǝґg���B���̓��Ǝґg���Ƃ��Ắu�����ԁv���]�ˎ���Y�Ƃ̃L�[���[�h�ɂȂ�B�]�ˎ��㏤�Ƃ̎���͖≮�ŁA�A���E�ۊǁE������Ȃǂ̋@�\��L���A���Ȋ���̔����͍s�킸�A�����ς�傩��ϑ����ꂽ�ו���̔����Č��K(�̔��萔��)�Ƒq�~��(�ۊǗ�)���≮���嗬�ł������B
�@
17���I�����A�]�ˎ��㏉���Ɏ��Ȋ���Ŕ�������d����≮�����W���A�����≮���ޖE�āE�d�E�Y�E�|�E���Ȃǂ̎戵���i�ʂɕ��������B������ł�17���I�O���ɁA���≮(���ɂǂ���)�Ƃ����ƑԂ̖≮�����܂ꂽ�B���≮�͏��i�̎�ޕʂ��͂Ȃ��A���i�̎Y�n���Ƃɐ�剻������≮�ł������B��O���≮�E���g���≮�Ȃǂ����̗�Ƃ�����B17���I�㔼�A���\����ɂȂ�Ƒ��ł����≮�𒆐S�Ƃ��闬�ʑg�D���珤�i�ʂɐ�剻�����d���≮���S�̗��ʑg�D�ɓ]�������B�����̖≮���W�܂蓯�Ǝґg�������B�����ԂƏ̂��A����̐��E���������Ƃɂ�芔���ԂɎQ������B
�@
�]�ˎ���ɂȂ�Љ�͈��肵�Ă���B����s���Ȃǂ̎i�@�@�ւ��ł���B����ł����݂̑���Ɋւ��ẮA���ϗߔ��߂ɏے������悤�ɁA���{�ɂ����K���̕ۏɂ͌��E���������B�����Ŋ����Ԃ�������ۏ���@�\�������ƂɂȂ����B�≮�̎���͑����̏ꍇ�M�p����������B���i�������n������A�����Ԃ��o�߂��Ă����������ς��ꂽ�B�x�������Ԃɂ́A3���A10���A�ߋG��(�����炢)�A��G���Ȃǂ��������B�x�����͌����̂ق��A�f�l��`(��`)�A����ї��֏�������U��`(���؎�)�E�ב֎�`���p����ꂽ�B������������Ŗ�����Ȃ��ꍇ�͂ǂ��Ȃ邩�H
�@
�u��O�ƒ��i�拆������ו��s���n�m�L�V��͂Β��Ԉꓯ����v�\�ԕ܌v
�@
���ԓ��̕č��≮����ƒl�i�����߂čw�������ו����͂����Ȃ������ꍇ�A���̉�Ƃ͒��ԑS����������~����Ƃ����K�肾�B
�@
���Ǝ҂������̐��`����邽�߂Ɏ���I�ɍ�����u�芔�v�Ɩ��{�⏔�˂����ʓ�����x�@�I������s�����߂ɁA�ォ�犔���Ԃ�ݒ肷��u��Ɗ��v���������B
�@
�]�ˎ��ォ��o�ς́u�M�p���v�ł������B�����d�G�̉ݕ��������u�M�p���v�B�����Y���Ɛ��H�i�ł����c�Ƃł��Ȃ��Ȃ�B�����R�������R������敨������s��ꂽ�ꍇ�A�����̏���җD��Ŗ����Ȃ��A�o�ƎҁE���{�@�ւ���������A����ȍ~���ێs��ł͎���ł��Ȃ��Ȃ�B����͓��{�ł͍]�ˎ��ォ��m�����Ă������A�����ł͓��{�̊����Ԃ̂悤�ȁA11���I���_�����l�W�c���}�O���r���l�̌���������B���X�u���_���v�M�҂̌����u�H�����ہv�_�ɂ͂��̊ϓ_�������Ă���B�����̐��`������Ȃ��Ƃǂ��Ȃ邩�H�]�ˎ���̏��l�Ɋw�ԓ_�͑������낤�B
�@
����������̂��߂ƍl�����剪�z�O�璉��
�@
�剪�z�O�璉���͍]�˂̕�������̂��ߊ����Ԃ𗘗p���悤�Ƃ����B1678(����9)�N5���ɐ^�ȁE�z�E�ؖȁE�āE�ݖ��E���E���E���Ȃǐ����K���i22�i�ڂ������e�폤�l���W�߂āA�g�������悤�����Ă���B����͍]�˂̏�����������������悤�Ƃ̍l�����炾�����B���̌㓯�N11���ɂȂ��āA�����E�����E�J�ȁE�^�ȁE���E�d�E�ؖȁE�ݖ��E���E�āE���X�E���X�E���X�C�E���E�Y��15�i�ڂɂ��Ă̖≮�A����Ǝ҂̓o�^���I���B
�@
���������E�^����Ƃ����ԐڐŁ@
�≮�E�����E�����Ƃ������{�Ɠ��̗��ʐ��x�͊����Ԃ̔��W�Ƌ��Ɋm������B�c���ӎ��͂��̑g�D�������ƌ����B���{�������ԂƂ����r���I�ȑg�D��F�߁A���ԈȊO�ɂ͏����������Ȃ��Ƃ������Ƃ�ۏ��邱�Ƃɂ��A�u�������E�^����v�Ƃ������Ƌ��ł���邱�Ƃɂ����B
�@
����͎��Ƌ��ŁA���ʐł܂��͊O�`�W���ېł̂悤�Ȃ��̂������B���ʐł܂��͏���ł̂悤�Ȑł͉����d�G������50���̗��ʐł����������Ƃ����������A�V�䔒�ɂ���Ēׂ���Ă���B���������s��{�����������߂ċ�J���Ă���A����Ɠ�����J�����Ă����킯���B
�@
�����Ԃ͏��l���Ɛ�I���v����낤�Ƃ��A���{�͍����ƌ��ė��҂̎v�f����v�������Ƃɂ���Ĕ��W�����B�������ӎ��ȍ~�͂��̑Ή������܂炸�A1841(�V��12)�N���쒉�M���u�V�ۂ̉��v�v�̈�Ƃ��āA�����ԉ��U�߂���B������1851(�Éi4)�N�A�≮���ԍċ��߂���B�����ېV�ɂȂ�A���ˑ̐��ɓK�����������ԑg�D�͂��̑��݊�Ղ��������B�@ |
|
���������ł��f�ՐԎ��H�@ |
   �@
�@ |
���ʉݗ��ʗʂ̑����ƌi�C
�@
�ʉݗ��ʗʂƌi�C�͖��ڂȊW�ɂ���B�o�ς���������ɂ͒ʉ݂������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������u�����ʉ݁v�ƌ����B�Ƃ��낪����������ƃC���t���[�V�����ɂȂ�B�u�C���t���͂������Ȃ�ꍇ���A�ݕ��I���ۂł���v�͌o�ϊw�̏펯�ɂȂ��Ă���B�Ƃ���Œʉݗ��ʗʂ�������ꍇ�A���ꂪ�����ɏ\���m���Ă��邩�H���邢�͂قƂ�ǒN���m��Ȃ����H�ɂ���Ă��o�ςɑ���e���͈���Ă���B���Ƃ��w���R�v�^�[�ʼnݕ�����܂����Ƃ��悤�B(1)�E�����l���N�ɂ����킸�A�F�������������Ǝv���Ă���ꍇ�A(2)�E��Ȃ������l���܂߁A�F���m���Ă���ꍇ�E�E�E(1)�̏ꍇ�͏E�����l���������̂������g���A�i�C���ǂ��Ȃ�B���������̂����C�Â��n�߂�u�����������A�i�C�͗ǂ��Ȃ�������ǁA�������������B������������ݕ��������������Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���H�v�ƁB���̂����ɃC���t���ɂȂ�B�����Ă��̌��ʂ́A���Ԃ��o���Ă݂�ƒP�ɃC���t���ɂȂ�A�ݕ����l���������������ɂȂ�B�F���C�Â��܂ł̂ق�̏����̎��Ԍi�C���ǂ��Ȃ����悤�ȋC�ɂȂ��������������B
�@
����ł��u���炭�͌i�C���ǂ������̂����炢�����Ƃ��v�ƌ����l������B�����Č����u�i�C�K�v���B�����o�����ׂ��B���Ƃ����ڂ����ł��D���ɂȂ�����B�����Ԏ��͌i�C���ǂ��Ȃ��Ă���l��������v�ƌ����B�ł�(2)�̏ꍇ�͂ǂ����H�u�ݕ����������̂Ŗ��ڏ���͐L�т邪�A�C���t���ɂȂ�̂Ōi�C�ɂ͒����B�܂�i�C�͕ς��Ȃ��v�ƂȂ�B
�@
�ʉݗ��ʗʂ��������茸�����肷��A���̌����͂���������B�]�ˎ��㉬���d�G�͏����̋��ܗL�ʂ����炵�ĉݕ��𑝂₵���B�c���ӎ��͐V�����u��̏����v������ĉݕ��𑝂₵���B
�@
�������ւ̓��@
�����Ƃւ̓��͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��낤���H���̌o�܂����Ă݂悤�B
�@
1609�@�c��14�@�G���I�����_�Ɩf�Ղ��J�n
�@
1612�@�c��17�@�G���V�̂ɋ���
�@
1613�@�c��18�@�G���S���ɋ���(�o�e�����Ǖ���)
�@
1616�@���a2�@�@�G�����D���`�ˁE����ɐ���
�@
1623�@���a9�@�@�ƌ��p���A���{����ދ�
�@
1624�@���i���@�ƌ��C�X�p�j�A�D���q�֎~
�@
1633�@���i10�@�ƌ��D�ȊO�̊C�O�n�q�֎~
�@
1634�@���i11�@�ƌ��C�O�����E�ʏ�����
�@
1635�@���i12�@�ƌ����{�D�̊C�O�n�q�֎~�A�A���̑S�ʋ֎~
�@
1636�@���i13�@�ƌ��|���g�K���l�Ƃ̍�������Ǖ�
�@
1637�@���i14�@�ƌ������̗�(�`38)
�@
1639�@���i16�@�ƌ��|���g�K���D���q�֎~(�����̊���)
�@
�����E���A�o���������{
�@
�]�ˎ�����{�͍��������Ă����B�������S���f�ʂ��[���������킯�ł͂Ȃ��B�����œ����̖f�ʂׂĂ݂悤�B�]�ˎ��㏉���̗A�o���i�ڂ͎��̂悤�ɂȂ��Ă���B
�@
�A���i�������D����v������퍻��
�@
�A�o�i���E�����i��E��i���E�����i���]
�@
�Ƃ���œ����̑ΊO�f�Ղ͐Ԏ��������̂��H�����������̂��H����͋����������i�E��i�Ɠ����M�����ƌ��邩�A���邢�͉ݕ��ƌ��邩�ɂ���Ĉ���Ă���B�����ł͐悸�M�����Ƃ��Ă݂Č��悤�B��������ƗA���ƗA�o�͋ύt���Ă������ƂɂȂ�B�܂�ΊO�f�Ղ͐Ԏ��ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ������A�ƂȂ�B
�@
�ł͂��ꂼ��̕i�ڂ̊������ǂ��������̂��H�A���Ɋւ��Ă͈��|�I�ɐ�������ь��D�������������B���z�I�Ɍ�������2�i�ڂł킪���̗A���͂قƂ�ǑS�Ăƌ����Ă��������炢�������B����͍]�ˎ���ɂȂ�A�Љ���肵�A�������L���ɂȂ�A���m�𒆐S�Ɉꕔ�L�ՊK�����ґ���y���ނ悤�ɂȂ�A�����Y�̐����⌦�D���������I�ɏ���ꂽ���炾�B���{�×�����������͂��������i���̓_�Œ����Y�ɂ͗���Ă����B���̂��ߓ��{�̌��������L�ՊK���ɗp���Ă����̂͘a���ł͂Ȃ��A�����ƌĂ�钆���Y�̗A�������������Ƃ������̂������B
�@
���̔����f�Ղ�Ɛ肵�Ă����̂��|���g�K���l�ŁA����ȗ��v�Ă����B���{�͂���ɖڂ�t��1604(�c��9)�N�������̖@���߁A���s�E��E����̏��l�Ɏ��������Ԃ����点�A����ɐꔃ����^���Ĉꊇ�w�����������B���̌��ʗ��v�͓��{���l�̎�Ɉڂ������A�O�����l����̒�R���悭1655(���)�N�ɂ͎��������x���~�߂đ��Ύ���Ƃ����B�������܂����拣���̂��ߗ��v�̑啔�����O�����l�̎�Ɉڂ��������A�����̉��i�����������̂�1672(����12)�N�ɂ͎s�@�����Ƃ����āA������肪���炩���ߕ]�����D�̂����K�����i�����߂�Ƃ������@���̂����B���������̕��@�����낢���肪�������̂�5�㏫�R�j�g�̎���A1684(�勝��)�N�ɂ���ǂ͗A�����z���ߐ������������ŁA���������@�������Ă���B
�@
����A�o�͂ƌ����ƁA���E�����i����ɋ�E��i����v�A�o���i�ƂȂ�B���ꂪ�Ȃ��Ȃ���ʂȂ��̂������B�����ł͗A�o�i�ڂƏ����������ۂ͗A������Ƃ��Ă̂��̂������B�܂萶���E���D���̑���������킯���B���ꂪ�ǂ̈ʂ��������H�V�䔒�͂��̒��u�܂肽���Ă̋L�v�̂Ȃ��ł��̂悤�Ɍ����B
�@
���m�ɂ͒m�肪�������A1648(�c����)�N����1708(��i5)�N�܂ł�60�N�Ԃɋ�139��7600���]�A��37��4229�ї]�A�ł���ƌv�Z���A����ɂ��̑O��1601(�c��6)�N����1647(����4)�N�܂ł�46�N�Ԃɂ���2�{�͂������Ɛ��肵�Ă���B����ł�����1601(�c��6)�N����1708(��i5)�N�܂ł�108�N�Ԃɗ��o�������{�̋M�����̗ʂ͋�719��2800���Ƌ�112��2687�тƂȂ�A����͌c���ȍ~�̑��Y�o�ʂ́A���͂���1/4�A��͂���3/4�ɂ�����A���̂܂܂ق����Ă�������100�N������Ƌ��͔����ɂȂ��Ă��܂��A��ɂ������Ă͂����܂ł����Ȃ������ɗ�ɂȂ��Ă��܂��A�ƐS�z���Ă���B
�@
���ӎ��̐ϋɓI�Ȏ��x���P��
�@
�����������E�◬�o�Ƃ������Ԃɑ��ĐV�䔒�͖f�ʂ𐧌����đΏ����悤�Ƃ����B1715(����5)�N�ɏo���������V�߂Ŗf�Ղ̑�g�����̂悤�ɋK�肵���B�܂��f�Ց��z�͑I�����_5�����A�Β���6��т����A����ȊO�ɕU�����ɂ��㕨��3��т�F�߂������ŁA���㕨�ւ͔p�~�����B�܂����̗A�o�ɏ����݂��A�I�����_150���ҁA�Β���300���҂Ƃ��A����͂��̉��i����f�Ց��z���獷�������Čv�Z����Ƃ����B
�@
���̂ق��f�ՑD�̓��`���ɂ����������A���N�I�����_�D��2�ǁA�����D��30�ǂ܂łƂ����B�I�����_�͂���܂�4�|5�ǂ����`���Ă�������傫�ȒɎ�ɂȂ����B����������͍��{�I�ȉ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����ɑ��ēc���ӎ��͐ϋɓI�Ȏ��x���P����Ƃ�B
�@
���N�l�Q���N�l�Q�́A�a����̃G�[�X�Ƃł������ׂ����݂ŁA���N�f�Ղ̒��S�ł��������B�ӎ��͂�������Y�����邱�Ƃ���Ă�B�����ŁA���N�Ǝ������y��T���ď�썑�̍��s�t�߂�I�肵�Ď���܂��A�͔|���Ă݂��Ƃ��낻��ɐ������A��������N�Y�̂��̂ƈقȂ�Ȃ��A�Ƃ������_���o��B�����ŁA����{�̐ꔄ�Ƃ��āA�l�Q����������B���ꂪ1763(���13)�N�̂��ƁB�����͊��菊�̖�l�������ŏ������Ă������A�Ɩ��ʂ������A�ƂĂ������Ƃ������ƂŁA1766(���a3)�N����́A���ɒS������E���������悤�ɂȂ�B������1819(����2)�N�ɂ͍��Y�̒��N�l�Q�𒆍��ɗA�o����Ƃ����Ƃ���܂ŁA�A�o�Y�ƂƂ��Đ���������B����̗��o�������������N�l�Q���A�t�ɊO�݂��҂��Y�Ƃɂ܂Ő������Ă������킯���B
�@
�����Ă��̒��N�l�Q���Y���ɂ͕��ꌹ���̍v�����傫���B1757(���7)�N��7���A�����̒ɂ��c�����Y��Â̑�1���i����Y��]�˂̓����ōÂ����B�S���ɓ��u�����߁A���i�������������A�����ɑ����Ēm�����������������A�Ƃ��������ɂ��u�摖��v�̌����炵���A�C�f�B�A�����s���ꂽ�B�]�ˎ���u�ؑ��w�v�Ƃ����̂������āA���Ō����u�A���w�v�̂悤�Ȃ��̂ŁA�Ȃǂ������ΏۂɂȂ��Ă����B�ƌ����Ă����D�̎m����������������x���������̂��A�����͍L���S���ɌĂт����A�h���I�Ȃ��̂����z���ĊJ�Â��ꂽ�B���̉�Ō����́u���N�l�Q�͓��{�ł��͔|�ł���͂�������A���̂悤�ȏ��������m�点�ė~�����v�ƌĂт����Ă���B���̍��܂������͓c�����~�ɂ͏o���肵�Ă��Ȃ��B
�@
���N�l�Q���Y���͌����̎t�A�c�����Y�����g��ł����B���Y�����R�g�@�̖��Œ��N�l�Q�̎�20����S�ԊX�Ə̂��鎩���̖Ɏ��A�����̂�1737(����2)�N�B���̌�1743(����3)�N�ɂ����N�l�Q�̎�100���]�������Ŕ|�{���Ă���B���N�l�Q�����Y������Ă����̌��p�͂��܂�M�p����Ă��Ȃ������B����Ɋւ��ĕ��Y�W�̏o�i���܂Ƃ߂��{�ɓc�����Y�̒��j�A�c���P�V���d�v�ȃG�s�\�[�h�������Ă���B�����1760(���10)�N2���A�_�c���Ē�����o�����{���A�A�{���[��܂łЂ낪��������������B���̑�̂��ƁA������12�A3�˂̏��N���Q���ƕa�C�ő����₦�₦�ʼn�������Ă���̂����������Ƃ����B�����ł��������c���P�V���~�}�H�������Č����ƈꏏ�Ɍ���ւ����Ă݂�ƁA���N�͂��������₦�����ɂȂ��Ďl���͗₽���Ȃ肩�����Ă����B���̂Ƃ������͉�����T���Ē��N�l�Q�����o���A���ݍӂ��ď��N�̌��ɓ���Ă��ƁA�܂��Ȃ����N�̕�����A�l�����g�܂��Ă����B�����Ō����͋}���Ől�Q1�{������āA�₩��̌����班�N�̌��ɒ�������ł�����B����ǂ͖����߂��āA����Ƃ��Ȃ萺���������̂ŁA������̂ƐH�ו���^���c���Ƃ̎g�p�l��t���Y�킹���N�̉Ƃ܂ő���Ԃ��Ă�����B�ƌ����̂ł���B
�@
�U��1764(���a��)�N�ɁA�ӎ��͒����A�o�����̐���C�l(�Ȃ܂�)�y�ъ����(�����)�Y����悤�ɁA�����ɖ����Ă���B���̊C�l��鸂̋��ƂɂȂ�Ă��Ȃ�������A�����������̊C�l��鸂��̂��Ă��Ă��A�����l�̍D�ސ������@��m��Ȃ����߂ɁA���H���Ă��Ȃ����������Ȃ肠�������炾�B�����ŁA�������������͋ߗׂ̂��������Z�p�������Ă��鋙�����炻����K���āA���Y�ɓw�߂�悤�ɁA�Ɩ��������́B��1765(���a2)�N�ɂ́A��h(�ӂ��Ђ�)�̐�����������ƂȂ���Ă��Ȃ����߂ɏ��i���l�𗎂Ƃ��Ă���Ⴊ����̂ŁA�������@�ɒ��ӂ���悤�ɁA�Ƃ������G����o���Ă���B�A�o��ɂ��邽�߂ɁA����ɂ��Ă͑d�ł�Ə�����A�Ƃ����������Ă���B���̂悤�ȗA�o�U����ɂ��o����x�͉��P����Ă������B��������̐����E���D�������Y�i�ɑ�����{�̎�v�ȗA�o�Y�ƂɂȂ�̂͂����ƁA�����ƌ�̂��Ƃ������������ӎ��̗A�o�U������������A�����̎Y�ƐU���ɗ͂��������悤�ɂȂ����ƌ�����B
�@
�����E��̗A�o
�@
1639(���i16)�N�A���R�ƌ��̓|���g�K���D���q�֎~���A����ɗ��ē��{�Ɩf�Ղł���O�����I�����_�ƒ�����2�J���݂̂Ƃ��A�����ɓ��{�̍�������������B��������������ΊO�f�Ղ͌p������B���{�����ŋ��E��̎Y�o�����Ȃ��Ȃ�A����ɓ����A������̎x�����ɗp������B���̎������{�ł́u�����v�ƌĂ�ŁA���E����u�����Ă����悤�Ɍ����Ă���B���̎�����O���ł͂ǂ̂悤�Ɍ��Ă����̂��낤���H
�@
���{����̗A������̎x���������ɂȂ������́A�I�����_�ɂƂ��ē��ʂȈӖ����������B����͋��E�₪�]�߂Ȃ��Ȃ�A���{��������o����Ō�̎������Ƃ����Ă悩�����̂��B���C���h��Ђ͓��{�̓������[���b�p�ɉ^�сA���C���h��ЂŘJ�����Ɏx�������K�ɒ����������A���̑����s��Ŕ��p�����B���{�̓������[���b�p�̎s��łǂ�قǂ̃E�F�C�g���߂Ă������́A�A�_���E�X�~�X�́u���x�_�v�Ɏ��̂悤�ȕ������邱�Ƃ�����z���ł���B
�@
�M�����̏ꍇ�ł��A���E�����Ă̑��Y�I�ȍz�R�ɂ����邻�̉��i���A���E�̑��̂�����z�R�ɂ����邻�̉��i�ɑ����Ƃ��e������������Ȃ��̂ł���B���{�̓��̉��i�́A���[���b�p�̓��R�ɂ����邻�̉��i�ɂ��������e������ɈႢ�Ȃ��B(�A�_���E�X�~�X�u���x�_�v1776�N)
�@
�����E��̗A���@
1763(���13)�N�A�����s�ΒJ�����������s�����C���Ă��������A���̔N�̋L�^�ɁA��������u���ԋ��A������A�㐯���v�����ꂼ��146��4���A�u���������v��117��179��A�u���^�����v��37��752��9���A�u���N��v��240��73��2��2��6�їA�������Ƃ̋L�^������B�����ɂ��Ă���ς�������̂̈Ӗ��͂悭����Ȃ����A���ꂼ��̉�̌`���Ӗ�����Ǝv����B�����P���ɍ��v����ƁA��͌v395�тƂ������ɂȂ�B���̒���V��ɂ��Β����f�Ր����z���N3000�т�����A����1�����x�ŁA�����I�ɋ����C���p�N�g��^����قǂł͂Ȃ����A���{�n�݈ȗ��̗��ꂪ�t�]���A���₪�C�O�ɗ��o�������ɗ�������悤�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃ̈Ӌ`�͑傫���ƌ�����B���̔N����ɁA�Ȍ�A���N�̂悤�ɂ��Ȃ�̋���̗A�����n�܂�B���N����1782(�V��2)�N�܂ł�10�N�Ԃ́A��������̗A�����ʂ͋���88��474��A�₪6374��772��]�ɂȂ�B���̂���3829��919��9��9��9�N��n�����āA���a���`��锻��126��650�Ђ𒒑������ƌ�����B�z�ʋ��z�ɒ����A15��7581�����܂�B���̂ق��A1765(���a2)�N����A�I�����_�������͂��̗A�����J�n���Ă���B�I�����_�̏ꍇ�ɂ͓����̋�݂��̂��̂�A�����Ă��邩��A����͗A���Ƃ������A���荑�ʉ݂ɂ��f�Ղ̌��ςƂ����������������낤�B�����̃I�����_�̋�݂́A�f���J�b�g�Ƃ����P�ʂŁA1770(���a7)�N�ɂ́A�A�����x�z��1��5000�f���J�b�g�ƌ��߂Ă��邩��A��̂��̒��x�̗A���z���������ƍl������B�����̓��{�l�ɂ́A�f���J�b�g�Ƃ����������������Ȃ������炵���A�e�J�g���Ƃ����\�L�ɂȂ��Ă���B1782(�V��2)�N�܂ł̏W�v�ł́A1417��068��]�ƂȂ��Ă���B
�@
�����͖��a���`��锻�����̂��߂ɗA�����ꂽ�̂����A�A�����ꂽ�̂͂��ꂾ���ł͂Ȃ������B��������A�n����A��q��Ȃǂ̋���n���A����Ɠ������n�����l�ŗ��ʂ��Ă����X�y�C���̃h����݂�A�`�x�b�g�����̋��E����A������Ă���B�I�����_�l�͎����̋���݂̂ق��A�L�����Ռ��𗘗p���āA�C���h�A�W�����̋�݂������炵���B�S�������a���`��锻�����̂��߂ɉꂽ�킯�ł��Ȃ����A�ݕ��p�ɊO���̋����p���邱�Ƃ��ӎ��Ƃ��̋��͎҂ɂ���Ďn�߂�ꂽ�킯�ł���B�@ |
|
���ڈΒn�J���̎u�͕����J���ɂ���Ă���Ǝ����@ |
   �@
�@ |
�����O�˂͂܂�œƗ��匠����
�@
�ڈ�(�k�C��)�͍]�ˎ��㏼�O�˂��x�z���Ă����B�x�z�̓��e�͎��̂悤�Ȃ��̂������B
�@
��
�@
��A���������O�֏o���V�ҋ��A�u����s���f���A�ΐm�^���ɏ����d��V�A�Ȏ���
�@
��A�u����ɖ��f���ߓn�C�A�����d��ҁA�}�x�v���㎖�t�A�ΔV�V�ҁA�����։��s���A���Ύ��掖
�@
��A�Έΐm�\���Ҍ���~��
�@
�E���X���w�V�y�ҁA�����ȎҖ�A�˔@��
�@
�c����N��������������
�@
���O�u���Ƃ̂�
�@
�����1604(�c��9)�N����ƍN���珼�O�u����ւ̍����B����̈Ӗ�����Ƃ���́A��1�������{���珼�O(�ڈ�)�֏o���肷��҂͏��O�u����ɒf��Ȃ��Ɉΐm(�A�C�k)�Ə��������Ă͂����Ȃ��B��2�������O���ɒf��Ȃ��ɓn�C���Ĉΐm�Ə�������҂�����A�K�����{�Ɍ��シ�邱�Ƃ𖽂��A��3�����ΐm�ɑ��Ă͌����Ĕ̐\���������Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��Ă���B�܂�ڈΒn�ł̌��Ռ��́A���O���̓Ɛ肷��Ƃ���ŁA�������]������{�l�́A�K�����O���̋��čs���ׂ������A���얋�{�̖��ɂ����Ē�߂�ꂽ�B�Ȃ���2�����u�t�v�ł́A�ΐm���A�C�k�͂ǂ��֍s�������ނ�̏���ŁA���{�̐�����Ȃ��A�ƒ�߂��Ă���B
�@
���O�˂͖{�B����̗��K���������������Ă����B���ˌ�����̎҂�h�����������A���O�˂ł͓K���ɂ�������Ēǂ��Ԃ��Ă��܂����B����͏��O�˂��ڈΒn��A���n�x�z���Ă��āA����{�ɒm���Ȃ��悤�ɂ��Ă������߂������B���̂��߉ڈΒn�ւ̊S�͖��{���ł������B�������c�����������Ƃ͂Ȃ����R�ȕ��͋C�̒��ŁA�ڈΒn�ɑ���S���o�Ă����B���Ƀ��V�A��1689(���\2)�N�A���E�I�̃l���`���X�N���ɂ���ē�i�����߂��Ă���́A���i�𑱂��x�[�����O�C���A�瓇�A�����1767(���a4)�N�ɂ͑𑨓��܂ŗ��Ă���B
�@
���̎��オ�ǂ��������ゾ�������E�E�E�X�y�C���̖v���M���̏o�ł���R���e�X�������̖ړI�������ă��L�V�R�̃��J�^�������ɏ㗤�A���L�V�R�E�V�e�B�[�ɐi��Ń����e�}�X��łڂ��A���̒n�ɉh���Ă����A�X�e�J�鍑��łڂ��A�X�y�C���̐A���n�ɑg�ݍ��̂�1521(��i��)�N�B1532(�V����)�N�A�s�T���̓C���J�鍑�𐪕��A���݂̃y���[��т�A���n�Ɏ�荞��ł���B�C�M���X���C���h��Ђ͊�]��ȓ��̃A�W�A�n��̖f�Ղ�Ɛ�I�ɍs�������ЂƂ���1600�N12��31���ɐݗ��B�I�����_�A�M�c���1602�N3���ɘA�����C���h��Аݗ�������B1780�N�ɂ̓C�M���X���C���h��Ђ��C���h���Ђ̖f�Ռ����l���B
�@
�V�嗤�ł�1763�N���N�푈(�A�����J�̂�����t�����`�E�C���f�B�A���푈)�̏I���ƂƂ��ɃC�M���X�{���ƃA�����J�A���n�̊W���Η����Ă����B1773�N12���{�X�g���ɂ����ăT�~���G���E�A�_���X���w���҂Ƃ���A���n�l�̈�Q���A�C���f�B�A���ɕ����đD��̒������{�X�g���p�ɓ����̂Ă�Ƃ����A�u�{�X�g��������v���N�����B1775�N4���Ɏn�܂����A�����J�Ɨ��푈��1783�N9���ɍu�a��p���Œ���A1776�N7��4���A�����J���O���͓Ɨ�����B���[���b�p�ł͂��̐푈�ɊW�������X�̌o�ς��j�]�������Ă����B�����1783(�V��3)�N�A��ԎR�̑啬�ɂ���ĕ����オ�������o���ΐ����ɂ̂��āA�t�����X�܂ōs���A�C��s���̂��ߔ_�앨���s��ɂȂ�A�_���̕s���E�s�����̂�A���ꂪ1779�N7��14���̃t�����X��v���������N�������������ɂȂ����A�Ƃ̐�������B
�@
���@
�H������(1734-1800)(����19-����12)�́u�ԉڈΕ����l�v���ˈ�H�������͗��w�҂̑O��Ǒ�E�юq���E�j�����E��Ό���A�I�����_�ʎ��̋g�Y�k���A�����O�ˊ����s�̖������q��A���O�ˈ�t�ēc���O��Ɛe�������сA1781(�V����)�N�Ɂu�ԉڈΕ����l�v���Ėk�����̏d�v����������B
�@
�u�ԉڈΕ����l�v����
�@
����{�̗͂𑝂����A�ڈɂ������Ȃ��A�܂��A���̂܂̂Ēu���A�J���T�X�J�̎ҋ��A�ڈΒn�ƈꏊ�Ȃ�A�ڈ��I���V���̉��m�ɏ]���́A���͂�䂪���̎x�z�͂����܂��B�������͉���݂Ă�����ʎ��Ȃ�B�����ɗl�X�̕������ɁA���k�ڈ̕��́A�i�X�I���V���ɉ����]���Ə���B���̔@�������ɂāA��U�I���V���ɏ]���Ă͗͋y�ʎ��Ȃ�A�����̗l�ɂ��Ă͍����u�����������Ǝv�����B�����܂ł̒ʂ�ɂāA�ʘH�Ȃ���Ή�����������m��ʎ��Ȃ�A�O�Ɍ������̉䂪���̗͂��v���Ƃĉڈɂ������Ȃ��A����Ɉ˂�S��s�����ׂ����Ȃ�B�@���l�ɍ��v���l����Ƃ��A�䂪���̓�����ɂĂ̎�i�A�H�v�ɂẮA�͂����������L��܂����Ȃ�B�����Ďz���̂��Ƃ��i�X�̎��悠��A�ł��̂Ēu������߂Ƃ����ׂ����B���˂Ĕ������̈ꌏ�͖l�����N�H�v���鏊�Ȃ邪�A������I���V����̔����ׁA�������̎d���ɂĂ͋�������Ȃ�v
�@
�H���̌������Ƃ���̂́A�A�C�k�����̂܂ܕ����Ēu���Α��ă��V�A���ɂ��Ă��܂�����A�ꍏ�������A�C�k������������A���{�̌����ŁA�ڈΒn�̋���A���Y���Ǘ����A���V�A�ƌ��Ղ��ׂ��Ƃ������ŁA�A�C�k�����ɑ��镏��͍��h���ɕK�v�ł���Ƃ������ł���B
�@
�����͓c���ӎ��̗p�l�O�Y����ɂĂ����߂�����ӎ��̖ڂɓ���悤�Ƃ���B������1784(�V��4)�N5��16�������s���{�G���͂��́u�ԉڈΕ����l�v��Y���ĉڈΒn�����ɂ��Ă̎f�����o���f����������ӎ��͖��t�ŕ]�c���鎞�̍��̂��߂ɁA���炩���ߏo�H��ɂ�����������Ă����悤�ɂƎw�����Ă���B�o�H��Ƃ͐��쒉�F�̂��ƂŁA�ނ͈ӎ��̎l�j������{�q�ɂ�����Ďk�q�Ƃ��Ă���A���̎��V���i�ŏ��Ôˎ傾�����B�����ċI�B����Ƃ̑��y�̑��q�Ƃ����y�y�̏o�ŘV��(���p�l����)�܂łɂȂ����ӎ����A����唴�w�̂Ȃ��Ɏ����Ă��鐔���Ȃ��������肾�����B���̂悤�ȉ��H�삪����t�����̂��A�u���ʎf���ʂ�ɂ���v�Ɛ\���n���ꂽ�̂�5��23���A�f����o���猈�ق܂ł�����7���Ƃ����\�z�O�ɑ������f�������B�����������f�̑����������ɂ����v�ɔR���開�b�������Ɗ���������B
�@
�������璲�������̂��߂̊����s���{�G���̎��q���v�̑劈�n�܂�B
�@
���@
���{�G���Ƃ��̋��͎҂��������s���{�G���͑�X��V��Ԃ��Ƃ߂開�b�̂Ȃ��ł��y�y���̌y�y�ɑ�����ƕ��ł������B1779(���i8)�N�����s�ɉh�i��500�̒m�s��ƂȂ�A1782(�V��2)�N�ɂ͓c���Ƃ̉ƘV�����˂Ă���B�ڈΒn�T���ɂ͐悸�l�I����n�߂�B
�@
�G���͌䊨��g���̓y�R�v���Y�F�V�ɑ��k����B���̂���v���Y�͕a�C�ň����������Ă������A����������ܘY��ʂ��ĕ������o���Ă���B�ڈΒn�ɏڂ����҂Ƃ��Ď��̖��O�������Ă���B��щ����E�q��A�����q��A�ؑ��g�E�q��A��������\�Y�B����ɉڈΒn�̊T�v�A�Y���A�{�y����̓n�����������������Ă��邱�ƁA�Ȃǂ���Ă���B
�@
�y�R�v���Y�̕������{�G����������̂�1784(�V��4)�N5���B�����ɏ��O�˂Ƃ̌��ɓ���B�G���͂������O�˂ōs���Ă��锲���ׂ��I��������A�˂̑��S�ɂ�������邼�ƁA�����ז�����������ď��O�˂��䂳�Ԃ�Ȃ�������d�ˁA���N10��21���ɂ͒������̋K�͕Ґ��ɂ��Ė��{���ǂ̋�����B
�@
�ڈΒn�����̂��ߕҐ����ꂽ���{�̐w�e�́A�䕁����5�l�A������5�l�A���D2�z�A�Ƃ������̂ł������B
�@
�䕁�����Ƃ��Ďw�����ꂽ�͎̂R���S��Y�A������Z�A�������Z�Y�A�F�쉫�E�q��A���r����5�l�B���̑���ɉڈƐ[���ւ������悤�ɂȂ�ŏ㓿�����A�{�������̏Љ�ʼn����Ƃ��ĎQ�����Ă���B
�@
1785(�V��5)�N4��29���A���ڈΒn�������Ɛ��ڈΒn�����������̂��̏��O���o�������B
�@
1786(�V��6)�N2��6���ɂ́u�ڈΒn�̋V�A���������d��\��t�v�Ƒ肷�钷���̕����ӎ��ɒ�o����Ă���B����ɂ́u�ڈΒn�͍L��Ȃ����n�����悭�_�k�ɓK���Ă��邪�A���O�˂͉ڈΐl(�A�C�k)��_�k�������Ȃ����߁A�ނ炪��������邱�Ƃ��֎~���Ă���v�Ƃ���A����Ɂu���̖ʐς�1166��4000�����B����10����1���k�n�ɂł���Ƃ��āA116��6400�����ƂȂ�B�������n�̌Óc���̕���1��1�̔���ł���1��5�l�Ƃ��Čv�Z����ƁA583��2000�̍k�n�ƂȂ�B�v�Ƃ���B���ꂾ���L��ȍk�n���ǂ����čk�����A�����ɂȂ�B�ڈΐl�ɔ_���^���A��q��n���A������������B���ꂾ���ł͔_�k�҂��s������B�ǂ����Ă����n������A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��E�E�E�ƉڈΒn�J���̖��͍L�����Ă����B
�@
���@
���̍��܉ڈΒn�J���̖��ɂ������M�͈ӎ��E�G�������łȂ��A�������Z�Y�ȉ��ڈΒn�֏�荞�ʁX�������ł������B���̔M�ӂ��疳���������]���҂��o�邱�ƂɂȂ�B
�@
���������܂ő����̂������ڈΒn�������́A�~���߂Â��H�Ƃ��R�����Ȃ����̂ŁA�ŏ��̌v��ǂ���ЂƂ܂��{���̂��鏼�O�܂ň����Ԃ����ɂ����B���������N�ȍ~�̂��Ƃ�����̂ŁA�ڈΒn�Ŗk�[�̃\�E��(�@�J)�܂ŋA�����Ƃ���ŁA�u���C�����v�̂��߉z�~���邱�Ƃɂ����B�������Ɋ��n�ł̐ݔ����������m�����Ȃ����߁A�u���C�ɂ�����v�����͂����ɓ|��Ă������B���O�˓S�C���y���c���^���Y�A�ʎ������E�q��A���ڈΒ������������V�䕁������������Z�A���O�ˎm���H�������q��A���O�ˎm���ēc�����A���S�B
�@
�����]���҂��o���Ȃ�����A��2��̒���������������B���������n�ł̔M�C�Ƃ͕ʂɍ]�˂ł͏�����M�̋{��N�[�f�^�[���N���Ă����B1785(�V��5)�N12��1���ɗ��V�ԋl�ɂȂ���������M��1786(�V��6)�N8��15���ӎ��̂����낾�ĂɂȂ��Ă������R�Ǝ������a����ƈӎ���V���E�����Ƃ���B�ӎ����i�߂Ă����v��������ƒ��~����B�����ē��N10��28���ɂ͉ڈΒn�������S�ʓI�ɒ��~���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B
�@
��M�̔��ӎ�����͓O�ꂵ�Ă����B�R���S�ܘY�A�������Z�Y�͂���܂ł̒������ʂ��Ƃ�܂Ƃ߁A���ɂ����ĂĊ����s�܂łɒ�o�������u�ڈΒn�̈ꌏ�͂��łɍ����~�߂ɂȂ��Ă���̂Ŏ��Ȃ��v�ƂȂ�B����݂̂����l�͂��͂�p�͂Ȃ�����u����ɋA�_����悤�Ɂv�Ƃ����ď����͕����ɂȂ��Ă��܂��B�����悤�ɊF�쉫�E�q����A���r�����ꌾ�̂˂��炢���Ȃ����������ɂȂ��Ă��܂����B���̂悤�ɓ��{�k���T���j��A�ŏ��̋P���������ʂł���u�V���ڈΒn�����v�́A���̂悤�Ȏv�������Ȃ��S�߂Ȍ��ʂɏI���B
�@
���@
��M�̎d�ł�1786(�V��6)�N10���ӎ��͉B���𖽂����A�̒n�̂���2����v�������B���̊ԏ��R�Ǝ������S�A�ƍς�11�㏫�R�ƂȂ�A���N7��6��������M���V���ƂȂ�B��M�̎d�ł��͈ӎ��ɂƂǂ܂�Ȃ��B
�@
�ӎ��Ƌ��ɉ��v��i�߂Ă��������s���{�G���͉ڈΒn�����E�J���Ȃǂ��i�鏟�����s����A�ՐE�̌������ɂ܂킳��A����ɐE��D��ꏬ�����g�ɗ��Ƃ���A����ɉz�㔃�Ď����ŐӔC����炳��100��v������Ă���B
�@
�G���Ƌ��Ɉӎ����v��i�߂Ă��������s�Ԉ䒉���͂Ƃ����ƁA1750(����3)�N�ɕ��̈�Ղ��p���ł���́A���\�l���A���|������1774(���i3)�N���s����s�A1782(�V��2)�N�ɂ͊����s�ƂȂ��Ĉӎ��Ƌ��ɉ��v��i�߂邪�A�ӎ������r����Ɛ��̊ۂ̌䗯�狏�ɉ�A����ɗ��N�ɂ͉z��Ĕ��Ď������N����ƁA���̊ē��s�\���ł���A�������̎�d�ғy�R�@���Y����؋����Ă����Ƃ������R�ŁA�̒n���v�����ꏬ�����g�ɗ��Ƃ����B
�@
���{�������ẲڈΒn�ʂƌ����A�ڈΒn�����̐��i�ɑ傫�Ȗ������ʂ��������{����g���y�R�@���Y�A��M�ɂ���ĕx�m���ԓ��Ƃ����ՐE�ɉꂽ���A�u�z�㔃�Ď����v�Ŏ��߂ɏ������Ă���B���̎����͍���͂����肵�Ȃ��̂����A�y�R�@���Y���߂��n�߁A���{�G���A�Ԉ䒉���ȂNJ֘A�z����l�A�s�����l�Ȃǐ��\�l������A���߁A�����Ȃǂɏ�����ꂽ�����ŁA��M�̘V������A�C����ł��邾���ɁA���c��������Ƃ����M�̈Ӑ}���������鎖���ł������B
�@
���ڈΒ��������̖������ʂ��������r���̉^��������ł������B��M�o��Ƌ��Ɉꌾ�̂˂��炢���Ȃ����������ꂽ�̂����A1789(������)�N�A�C�k�̔���������ƁA�Ăя����o���ꂽ�B���������K�Ƃ�����E��^���A�u�ڈΒn�����������v�̂��ߌ��n�ɋ}�h����B���̂Ƃ��ŏ㓿�������s����B��s��7���A���O�ɒ��������̋N���������n������11���]�˂ɋA���Ă���B���̕��ł́u���̎����͏ꏊ�����l�̉��\�Ɍ���������A���V�A�l�͊W�Ȃ��v�Ƃ��Ă���B�Ƃ��낪�A�u�����̔w��ɐԉڈ��������v�Ƃ��ĊC�h�����i�߂悤�Ƃ��Ă�����M�̓{��ɐG�ꂽ�B1790(����2)�N1��20���A�B���Ƃ��Ĕh�������������O�ˎm�ƌ��R�ƐڐG�����A�Ƃ̗��R�œ�������A�ƍ��v���̂��������Ƃ����\���n�����邪�A���s�O�ɍ������Ă���B
�@
�ŏ㓿��(1755-1836)(���5-�V��7)�͂��̌���ڈΒn�ƊW��ۂB�ނ��뉺���Ƃ����y�����������̂��K�������̂��낤�B���̌�����т��щڈΒn�E����(�T�n����)�E�瓇��T���B�D�ꂽ�ώ@�ɂ�葽���̒��q���c���Ă���B�ӔN�̓A�C�k��̎��T��Ҏ[����ȂǁA�w�������ɐ�O�����B
�@
���{�̉ڈΒn����͂��̌�ϋɓI�ȑΉ���͑ł���Ȃ��B1857(����4)�N�A�����͈ꋴ�c��(���15�㏫�R)�Ɂu�ڈΒn�J���_�v����悵�Ă��邪�A�ڈΒn�J�����������Ƃ��Ē��肳���̂́A1869(����2)�N5��21�������V�c����ڈΒn�J��̂��Ƃɂ��Ď��₪����A����Ɋ�Â��ē��N7���A�u�k�C���J��g�v��u���ĊJ��ɒ��肵�Ă���ł������B�c���ӎ��Ƃ��̋��͎҂����A�G���E�����E�r���E�@���Y�E�����E���������̎u�͕����J���ɂ���Ă���Ǝ����Ɍ������̂ł������B�@ |
|
���܂��܂��������c������̉��v�@ |
   �@
�@ |
������J���v��
�@
�퍑���㖖������]�ˎ��㏉���ɂ����đ�K�͂ȍk�n�J�����s��ꂽ�B���̎����ɓ��{�̍k�n�ʐς�2�{������3�{�ɂ܂ő��������ƍl������B���������̍k�n�J����17���I���Ńu���[�L��������B(1)�J���ɓK���Ă��Ȃ��疢�J���Ŏc���Ă��鏊�������Ȃ����B(2)�����ɊJ���������ߏ����̉J�ł��сE���Ȃǂ̕ې����ʂ��Ȃ��Ȃ�A��J���~��ƍ^���ɂȂ�A�c���l�{�ɔ�Q���o��悤�ɂȂ����B(3)��R�ɐ�����ᑐ����c���ɕ~�����ށu���~�v�Ƃ����_�@���c���n�͍Đ��Y�̎�v��i�ł��������߁A�J���ɂ��̑��n�����Ȃ��Ȃ�A�����I�ɂ݂�Ɣ_�Ɛ��Y���Ƀ}�C�i�X�ɂȂ�n�߂��B(4)�J�����}�����������ߍk�삷��S���̎蓖�������A�����ɍD�����ŗU�����߁A���k�n���������ꂽ�B
�@
���������̂��ߐV���ȊJ�������A������_�n�̐��Y�����グ��ׂ����A�ƂȂ�B1666(����6)�N2���A4�㏫�R�ƍj�̎��o���ꂽ�u�����R��|�v�����̓]�����ł��낤�B���̂��߈ꎞ�̔_�n�J���u�[���͋���A���{�E�e�˂͐V�c�J���ɏ��ɓI�ɂȂ�B1687(�勝4)�N�A5�㏫�R�j�g�͒��l�����V�c���֎~���A1721(����6)�N6���A8�叫�R�g�@�́u�V�c�̂ł��邱�Ƃ͂悢���Ƃ����A��T�{�c�����a��̂����ɂȂ邩��A���̂悤�Ȏ��͋����Ȃ��ق����悢�v�Ƃ̐G���o���Ă���B
�@
8�㏫�R�g�@�̐V�c�J��������������̒���8�㏫�R�g�@�͐V���ȐV�c�J��������Ƃ�B����͖��{�̍������Ē�������v�Ȑ����ڕW�Ƃ��A���̃R���̑����ɂ��N�v�đ�����ڎw�����B���̔N�v�đ����̂��߂̍k�n�����̂��߂ɐV���ȐV�c�J��������Ƃ�B
�@
1722(����7)�N7��26���]�˓��{���Ɂu�V�c�J���Ɋւ��鍂�D�v���f����B����͐V�c�J�������シ�鍂�D�ł���A�s�s���̏��l�ɒm�炵�߂悤�Ƃ������̂������B�܂�J���̔�p�����l�̎����Ɋ��҂��Ă����킯���B���D�f���̏ꏊ���]�˓��{���ł���A�菑�̎�t�ꏊ���A�܋E���͋��s����s���A�����E�����͑�㒬��s���A�k���E�֔��B�͍]�˒���s���ƁA���菊�ł͂Ȃ�����s���ł��鏊������A���炩�Ɏ����͂̂���s�s���l�̐V�c�J���ւ̐i�o�����҂��Ă���B
�@
�g�@�̐���ɉ�����悤�ɑ����̊J�����v�悳���B���̒��ɂ����āu����̊���v�͍ő勉�̃r�b�O�E�v���W�F�N�g�������B
�@
1724(����9)�N�A��t�����ˑ��̐��J���E�q�傪����J����\�����A���{�͂���������A6�A000���̕⏕����^�����B�����������̌����݂ƈႢ��H���̂��߁A���E�q����͂��ߔj�Y����҂����o���A�H���͍��܂����B
�@
�c������̈���J�����^���ɂ�蒆�f�E����1780(����9)�N�A�㊯�{�������q�傪����J��̌v�揑���쐬���A��1781(�V����)�N���̓V���������ܘY�A�]�ː̒��J��V�ܘY��2�l������Ƃ��A�����v�揑���쐬���ꂽ�B���ꂪ�����s���ŋ��c�̂����A1782(�V��2)�N7�����{�ƌ��肳�ꂽ�B�Ȃ��ł����������V�c����̗��v�z���́A���傪8���A�n�����b�l��2���ƌ��߂�ꂽ�B
�@
��S���s�ꑺ�Ɍ��n����(���s��)���݂����A�����Ɋ��菊����h�����ꂽ�䊨�蒖���v�E�q��A��������Y�E�q��ق������̕��������l�߁A�H���̎w���ēɂ��������B�������A�s�^�Ȃ��ƂɁA�S�s����3����2�قǂ��I�����1786(�V��6)�N7���A�֓��n�����^�����P�����B�����1783(�V��3)�N�̐�ԎR�啬�ɂ���Ċ֓���~���Ă����y�����A�͐�̐�����Đ��͂����������Ă������߂������B�����Ă��̍^���̂��ߍH���̓X�g�b�v����B����ɂ��̒���̏�����M�̋{��N�[�f�^�[�ɂ��A����J���v��͒��~�����B
�@
���@
�k�n�����ł͂Ȃ��^�͍�肾��������J�����k�n�J���Ƃ��đ����Ă������A�c������̌v��͗����삩������ʂ��āA��������^�͂ō]�˂ɓ���悤�ȊC�㗬�ʘH�낤�Ƃ����v�悾�����B���ꂪ��������A�]�˂Ɩk�������ԍq�H�͑啝�ɒZ�k����āA���i���ʂ͊����������͂��ł������B����͌v�揑�Ɂu����V�x���䕁���ژ_�����v�Ƃ��������t���Ă��邱�Ƃ�����킩��B
�@
����J�����^�͍�肾�����A�Ƃ̌����͖{�������Ƃ̊W�ł��̂悤�ɐ�������B
�@
�{������(1743-1820)(����3-����3)�咘�u�o�����v�u���敨��v�u�o�ϕ����v�B�]�˂̐��w�m�̏m���B�V���̑�Q�[�́u�l�Ёv�ƌ����B�u���{�͖��\(�Ђ�����E�쐼)�̋����N��(�����Ƃ�E�k��)�̋��ցA�}�\�x�]�A�����܁A�Z�S���ɏ��݂��čג������Ȃ�A���ۑ�(���Q�⊱�Q�̔�Q)�Ƃ���Ă��A�����c�鏊�Ȃ��A�s�n���邱�Ƃ͌Í��Ȃ����ƂȂ�E�E�E�v�u�L��̍���若��̍��֓n�C�E�^���E���Ղ��ėL����ʂ��A�����̋Q�����~���́U�A���N�̖����ɕ��ꂽ��V�E�ɂ��āA����Ƃ����Ŋ��͂ʂ��ƂȂ�v�����͗��ʌo�H�m�ۂ̂��߉Ζ���g���āA���H���J���`�����ƌ����Ă���B����ɂ͊e�˂̎��Ȗh�q�I�E���������I�Ȑ퍑�̈���ז����Ă���A�Ǝ咣����B����ɉڈΊJ�����咣���A�m���������ŏ㓿���͗����̐��E�ɂ���ĉڈΒ������ɉ����Ƃ��ĎQ�����Ă���B����ɗ����̎咣�́u���[���b�p�̎�v���̎�s�͈ܓx�̍����Ƃ���ɂ���B���{�̎�s�������Ɩk�ɂ����Ă������B�]�˂ł͂Ȃ��ĉڈΒn�Ɏ�s���ړ]���Ă������B�v�Ƃ܂Ō����Ă���B
�@
�ڈΒn�����E�J���ɂ͍H�������́u�ԉڈΕ����l�v�����ڂ̂��������ɂȂ��Ă���̂����A����܂łɗ����̍l�����ӎ��ɓ`����Ă����A�ƍl������B�ӎ������㔼�̐���ɗ����̍l�����e����^���Ă����A�Ƃ���Ȃ�Γ��R����J���ɂ������̍l�������f����Ă����ƍl������B����ɉ^�͂�A���k�n���ƍ]�˂Ƃ̈��S�ȍq�H���m�ۂ���A����͗����̎咣�ƈ�v����B����ɌS�㔪���Ꝅ�ɑ��鏫�R�Əd�̂��ق��Ō����悤�ɁA�ӎ��͒��ڐłɑ傫�Ȋ��҂͂��Ă��Ȃ������B�����Č����Δ��Δh��������邽�߂Ɂu�k�n�J���v�ƌ����������m��Ȃ����A�{���̖ړI�͉^�͍��ɂ������ɈႢ�Ȃ��B�����Ă��̂悤�ɍl����ƁA�c���ӎ��Ƃ��̋��͎҂����̉��v�h�A�]���̖��{�̐���傫������A���\�����߂Ă����ƌ�����B�����Ă�����������狌�h�E��R���͂���@���������A������M��S���A����P���q�吭���������̂����A�{��N�[�f�^�[���N�����A����𐳓������邽�߂ɋ��͎҂�������|���A�����𗬂��A�����̐��Ԃƌ�̗��j�Ƃ���点���A�ƍl����ׂ��ł��낤�B
�@
���͎҂����ɂ�������l��1786(�V��6)�N8��27���A�c���ӎ����V�����Ƃ����Ƃ����Ɉ���J���H���̒��~�ɂȂ�B�ڈΒn�����Ɠ��l��M�̓c���������@�̍s���͑��������B�����Ĉ���J���ł����͎҂����͏��������B�H�����i�̐ӔC�҂ł���������g���������A���蒖���v�E�q�剷���A��������Y�E�q��s���͔�Ƃ̂����������ƂȂ�A���n�ŊJ���v��𐄐i���Ă����㊯�{�������q��́u������a���Ă������s�l���ޓ]���ď��݂��m��Ȃ��v�Ƃ������R�ʼn����𖽂����Ă���B�ڈΒn�����E���J���v��̏ꍇ�Ɣ�ׂ��킹�Ă݂�ƁA�c���ӎ��̐���ƊW�̂������҂́A���҂Ɏ���܂œO��I�ɒǕ���������Ƃ����̂��A������M�̕��j�������悤���B
�@
���V���ȗZ�����x
�@
�]�ˎ��㍑�������Y�������Âł��L�тĂ��鎞��A�����ĕ��z�͂ƌ����ƁA�u�����O���v����u�O�������v�ɕς��n�߂Ă����B�u�Č����o�ς���������o�ρv�ɕς��A�S���E�����̐����ł͕Ă��u�[�ł̂��߂̉ݕ��v�����ɂȂ�A�������ł͉ݕ��o�ςɑ傫���ς��Ȃ���A���m�͕Ăŋ�����������Ă����B���{�l�̏����͕S���E���l�͑��������������m�͕ς��Ȃ������B�l�X�̐������L���ɂȂ�Ȃ���A���m�����͎����������Ȃ������B���̂��ߕ��m�y�єˍ����͐Ԏ����������l����̎؋��ɗ��邱�ƂɂȂ�B�����������Č��̋�̍������߁A�����g���A���E�f�t�H���g����������B�����Ȃ�ƕ��m�K���ɑ�����ґ�����̊i�t���͉��������ɂȂ�B�s�Ǎ�����������Ȃ����߁A�݂��o���R���͌������A�����������Ȃ�B����͖��{�Ƃ��Ă������Ă����Ȃ��B���炩�̑��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�c���������ł��o��������͂����������B�喼���]�ˁE���s�E���̎O�s���l����؋�����ꍇ�A���{���ۏؐl�ɂȂ�A�d�Œ�����(�N�v�����錠��)��S�ۂɂ��A������N7���Ƃ��邱�ƁB�������A���̂���1���͖��{�����[����A�ۏؗ��Ƃ����ׂ����̂������B
�@
���̍\�z�́A���̌�p���߂ɔ�ׂ�Ό��O��ɍ�������������̂ł��܂��������Ǝv��ꂽ���A���l���͐M�p���Ă��Ȃ������B���ꂪ1785(�V��5)�N�̂��ƁB�����ŗ��N�ɂ͐V���ȏ�����������B
�@
����͑S���̕s���Y�ɑ��Ď����I�ɌŒ莑�Y�ł��ۂ��A���ꂩ��̎�����喼�ɑ�����Z�̌����Ɏg�����Ƃ������́B��̓I�ɂ́A�S���ɂ͎������S�ɂ��ċ�25����A���l�ɑ��Ă͉Ƃ̊Ԍ���Ԃɂ��ċ�3����A���ꂼ��5�N�Ԍ�p���Ƃ��ďo������悤�ɁA�Ƃ̐G����o�����B�����ł̑S���Ƃ́A�P�ɖ��{�̒����x�z�̂���ł͂Ȃ��A�喼�́A���{�̂��܂ށA�����ʂ�̑S���������B����́A��{�I�ɂ́A�j�g��1708(��i5)�N�ɁA�x�m��i�R�̕��ɂ���Q�����̂��߁A�Ə̂��đS���̔_�n�ɉۂ����Վ��s���Y�łƓ���̔��z�������B���̎��́A�_�n�S�ɑ���2���̊��ʼnۂ��ꂽ�B����́A��25��Ȃ̂ŁA5�N�ԂŌv125��ƂȂ�A���{�̌��背�[�g�ł����1������60��Ōv�Z����ƁA�قړ��z�̉ېłɂȂ�B�C���t�����i��ł��邱�Ƃ��l����A������͂��Ȃ��z�̉ېłƂ����������B�������A����͂قƂ�ǂ��ׂĂ̑喼���������B����͍�����ɂ������S���̔˂͐ŋ������邾����낤�Ƃ��āA�����ېł̗]�n�͖����������炾�B�����ɉېł��悤�Ƃ���ΈꝄ�̋�����������B���̂��߂��̋��Z����ɔ�������Ȃ������B
�@
�ǂ��ł������x�ł͂��������A�����o�ς͂���قǂ܂łɈ������Ă����B����ɂ�����H�v���K�v�Ƃ��ꂽ�B���̎���̐���͎��s����̘A���������B��̐����s���Ă�����ɍH�v���ăg���C����B���������p�����炳��Ȃ�H�v���������͂��������B�����������Ă��o���ꂽ3�����1786(�V��6)�N8��27���V���c���ӎ��͘V���E����C�����B�����ɂ����ĐV���ȑ喼���[���E���m����҃��[���̍\�z�͏�������B���̌�x�z�K���E���m�K���̍����Č��ɗL���Ȑ���͌��ꂸ�A���{�̍�����̉��͐i�݁A�������}���邱�ƂɂȂ�B
�@
�������Z�ƉƎ�����(��������������)���z������͂�����̎��s����̗Ⴞ�B�������Z�̈�ł��鎿�́A���ʂ͒S�ۂɓ���镨�̐�L�������҂Ɉڂ��čs���S�ە����̂��Ƃ��B�܂�S�ە��������Ɏ������ނ̂����A�s���Y�͎������ނ킯�ɂ͂����Ȃ��B�����ŏ��L���������ɗa���A�g�p���͂��̂܂܂ɂ���B�����ł����Ǝ�(������)�Ƃ́A�]�ˎ���̒����ōs��ꂽ�Ɖ��~��S�ۂƂ�����̂̂��ƂŁA�����̖��@�w�ł������n�S�ۂ̂��Ƃ��B�Ƃ�S�ۂƂ��ċ��Z�邽�߂ɁA���̉Ƃ����ɓ���Ă͋��Z����ꏊ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA���҂͍��҂ɔ���(�������p�ؖ���)�Ǝ؉Ɛ���(�������傤)�������Z�b�g�ō�������ĒS�ۂƂ���B�����͉ƒ��̎x�����Ƃ����`�����Ƃ��Ďx������B�����܂łɎ؋��̕ԍς��ł��Ȃ��Ƃ��́A�����ɒ���(���傤���聁���`�̏�������)���s����B���i�o�ς̔��B���Ă������ŁA�ᗘ�Ŋm���ȏ������Z�Ƃ��Ĕ��B���Ă������x�������B
�@
���̂܂܂ł͌��������Ⴂ���߁A����̈��S���m�ۂ��邱�Ƃ�����B�����ŁA���R�g�@���㋝�ۂ̉��v�̈�Ƃ��āA�Ǝ��ؕ��ɂ͌ܐl�g�ƒ��N��肪�������鎖�ɂȂ����B�������A�����҂����̒n�ʂ����p����悤�Ȏ��Ԃ����ꂽ���߁A���q�ϐ���������@�ւ̐ݒu���K�v�ƂȂ�B
�@
������1767(���a4)�N�ɁA���ɒ��l�̏o��ɂ��Ǝ��(��������������)���݂����鎖���F�߂�ꂽ�B����͉���ؕ��ɉ����^���āA���������m�ۂ���Ƃ�����@�B�����ɒS�ŗ͂̑��݂�F�߂����{�́A��1768(���a5)�N�ɂ�����Ǝ����z���ɐ�ւ���B���z���ł́A�Ǝ��ؕ��ɉ����^����ɍۂ��Ĉ��������B����͍����̌��t�Ō����Β���̐ݒ�ɓ������ēo�^�Ƌ��ł�����Ƃ�����@�ɂȂ�B�������A����͉Ǝ��ɂ�鎑���^�p�̔閧�����ׂĖ��{�Ɉ����邱�Ƃ��Ӗ����邽�߁A��㒬�l�͋��������A���ǁA���z������̎����z�Ɠ��z�̐쟲��������ɉۂ����ƂŁA1775(���i4)�N�ɔp�~�����B���̒����ɉۂ����쟲�����́A���z9950���Ȃ̂ŁA��̂��̒��x�̊z�����N���{�̍Γ��ɏオ���Ă������ƂɂȂ�B���{���菊�̓����ׂ̍��ȍΓ����e�ɂ��Ă͐��m�ȋL�^���Ȃ��B���̂��߂��̖�������^�オ�A���{�����̉��P�ɂǂ̒��x��^�������͔��f�ł��Ȃ��B�������A���������^�������Ƃ����Ő��́A�c���������n�߂����������B�������{�����얋�{����p��������������(�����̂Ȃ聁�c���ɉۂ����{�N�v�ȊO�̎G�ł��Ӗ�����)�A�^�㓙�́A���v��1500�`1600�ɋy�Ԃƌ�����B����炪�������́A�����łȂǂ͂قƂ�ǖ����ɓ�������������ɂ�����d�ł̒��j�ł������łւƔ��W���Ă������ƍl������B���̐Ő����c����������������Ȃ�H�v�������ꂽ�ł��낤�B
�@
���\�Z���x�̓���
�@
���얋�{���������������A�u�\�Z��g�ށv�Ƃ������Ƃ͖��������B�������L���őO�����ė\�Z��g�܂��ɁA�K�v�Ȍo��͂��̓s�x�x�o����Ηǂ������B����������̑��1657(����3)�N�ȍ~�͍]�˂̓s�s�����H���Ɏn�܂�A���������喼�E���{�ւ̎x�����d�Ȃ薋�{�̍����͈��������B�����āu�����O���v����u�O�������v���ς�����悤�ɏ����ĕ��z���ω����A���{�̍��������ɔ��Ԃ��������B
�@
�ӎ��̍̂�������́A���{�̊e�������ɗ\�ߎx�o�̊z�����߂Ă����\�Z���x�̗̍p�������B�Ⴆ�]�˒���s���͂�����A�Ƃ����悤�ɂ��ꂼ��̕����̗\�Z�����������ݖ��{�S�̂̌o��ߌ���ڎw�����B�Ƃ��ɏ��R�̐g�̉��Ƃ��剜�Ȃǂ́u��[��(���Ȃ��)�v�W�̗\�Z�͑啝�ɍi�荞��ł���B1750(����3)�N��2��4600���������u��[�ˁv�W�\�Z�́A1755(���5)�N�̂�2�����ɁA�����1771(���a8)�N�ɂ�1��5000���ɍ팸����Ă���B���̂悤�Ɉӎ��̗\�Z�͑剜�ɂ͌����������B����ł����R�̐M���Ă����Ƃ������Ƃ́A���R���剜���ӎ��̐���ɐM�����A���҂��Ă������炾�낤�B
�@
���̑��̗\�Z�ɂ��ڂ������Ă݂悤�B
�@
1750(����3)�N�\�Z(�P�ʗ�)1771(���a8)�N�\�Z�䗦
�@
��[�ˊW�@�@24,000�@�@�@15,000�@�@�@62.5��
�@
��d���@�@�@�@�@19,000�@�@�@10,000�@�@�@52.6��
�@
��쎖���@�@�@�@7,500�@�@�@�@6,000�@�@�@80.0��
�@
���������@�@�@�@9,000�@�@�@�@8,416�@�@�@93.5��
�@
������s�@�@�@�@�@150�@�@ �@�@�@150�@ �@100.0��
�@
���̂悤�Ɉӎ��̗\�Z�͖��ԕ���̗\�Z�������u���ł͂��邪�A�D������Ă���̂ɑ��āA���R�E��������̗\�Z�͑啝�ɍ���Ă���̂�������B
�@
�ߑ�\�Z�̎n�܂�ߑ㍑�ƂƂ��Ă̓��{�����ŏ��ɗ\�Z�����\�����̂́A1873(����6)�N�����̑呠����G�d�M���u������v�\�v�����z�������������B���̌�@������������A1881(����14)�N�ɂȂ��Ă���Ɨ\�Z�E���Z�Ɋւ���n���I�Ȑ��x��@����������v�@�����肳�ꂽ�B����܂ł͖������{���������Ă��u�\�Z���x�v�͂Ȃ��A�e����������ɕK�v�ɉ����Ďg���Ă����킯���B�c�������̐�i���͂��������u�\�Z�쐬�v�ɂ�����Ă���B�@ |
|
��������A�e�����A�ϋq�܂ŔR�������v�h���}�@ |
   �@
�@ |
���c���ӎ��̗�����
�@
�ӎ��̕��Ӎs(���Ƃ䂫)�͋I�B�ˎ�g�@�Ɏd��1716(���ی�)�N�A�g�@���R�A�C�ɔ����]�ˏ�ɓ���B�g�@�̌䏬������A1724(����9)�N�]�܈ʉ���a��(�Ƃ̂��̂���)�ɁA1734(����19)�N�䏬�[��(���Ȃ��)����ɂȂ��Ă���B�ӎ���1719(����4)�N�A�]�˂Ő��܂��B�Ȍ�̌o���ɂ��Ă͑�c�쐤�́u��b�ꌾ�v������p���悤�B
�@
�c����a��(�Ƃ��̂���)�ӎ�
�@
����19(1734)�N3��13�������Z�݂�萼�ی䏬��(�Əd�Â�����)��t(�����������)�A�O�S�U�퉺(��������)�B����\�N�O���ՖژZ�S�ɂČ䏬������B����2(1737)�N�\�\�����C���A����3(1746)�N����������䏬������A���l�N�㌎�\�ܓ���p��掟���K�A��l�S�U�䑫��(����������)�B������(1748)�N�\������䏬���g�ԓ������сA��l�S�Ό�����Ɏ����Ɛ��A���l�N�����������䑤�O��p��掟���K�A������ܐ�B������(1755)�N�㌎�O���ܐ�Ό�����A���떜�ɐ��B�]�菊�֗���o�ȉd�|(���܂�ׂ��ނ�)�A���N�\�ꌎ�\�������B���ǔ퉺(��������)�B���\��N(1759)�\�ܓ��ܐ�Ό�����B���a�l�N(1767)��������ܐ�Ό�����ɐ��A�䑤��p�l�A���l�i���B���Ǐ��B���Z�N(1769)�����\������V���i�ܐ�Ό�����C���]�A�����������V�ʖ�(���)��{���|��n�B����N(1772)�C�N�����\����ܐ�Ό�����A���O���Ή����V��t�Ԗ��V�B���i�Z��(1777)�l�����������Ό�����B�V���l�C�N(1784)����������ꖜ�Ό�����A���ܖ�����B���Z��(1786)���������������ƁA��V�ԐȔ�t�B���N�[�\���ܓ��v���L�V�A������Δ폢��(�߂��������)�A���T�B���N�\���Z����ƁB�������N(1787)�\�������a���Ζ𒆕s���V��v���L�V�i�A�ǁX�B�䒮�d�X�s���V���ɔ�v����B�����a�C���B����������L�V��ɕt�A���Ύ���Δ폢��A�B����t�����~��z�A��孋��T��C�|��t�B�V�����N(1788)�������l�����A�N���\�B
�@
�ӎ��ސw1784(�V��4)�N3��24���ӎ��̎q�A��N��c���Ӓm(�����Ƃ�)���u�V�ԏ��v�̔Ԑl�ł��鍲��P���q�吭��(�܂�����)�Ɏa������A���ꂪ���Ƃ�4��2��36�˂̎Ⴓ�Ŏ��S�B�ȍ~�ӎ��̐��͂��}���ɐ����A2�N���1786(�V��6)�N8���ӎ��̎��r�œc������͏I���B����P���q��͎�������̔ƍs�ƌ����Ă��邪�A���̂܂���ɂ͂����Ȃ��B�I�����_�̒���ْ��ł���`�`���O�͂��̒��u���{�����}���v�ł��̂悤�ɏ����Ă���B�u���̎E�l�����ɔ������낢��̎���琄������ɁA�����Ƃ����{�̍����ʂɂ��鍂�����l�����̎����ɂ��������Ă���A��Ŏ��������Ă����^��������v�B���̍����̈�l�͏�����M�ł���A����ɒ�M���t�����l���������ɈႢ�Ȃ��B1786(�V��8)�N8��26�����R�Ǝ��a�C�̍������Ɉӎ��̘V����Ƃ����܂�B�Ȃ����͎҂����̏������I���A��M���������ɂ���܂łɂ�2�N��v�����B
�@
���]�˒����ɐl�C�̑剪�z�O�璉��
�@
���v�ɔR�������b�o�ϊ����̈�l�Ƃ��đ剪�z�O�璉�������グ�Ă݂悤�B1677(����5)�N���{���{�剪���Z�璉���̎l�j�Ƃ��Đ��܂��B1700(���\13)�N24�˂ŗ{���̈��1920���p���B1712(����2)�N�ɐ��̎R�c��s�ɓ]���A�I�B�ˎ�g�@�̖ڂɂƂ܂�B1717(����2)�N�䕁����s����1736(����21)�N���Е�s�ɂȂ�܂ō]�˒���s���߂�B���̊ԋg�@�]�˂̕�������Ɏ��g�ށB�d�G�̂悤�Ȑ�i���͂Ȃ����s�������������A�����̖����ɂȂ��ĔM�S�Ɏ��g�p�����]�˒����Ɏx�����ꂽ�B�d�G�̐Ղ��p�����⑊��������������B1730(����15)�N8����㓰���̕ĉ�����F���A����܂Ŗ����F�������R���敨������A���{���F�̕Ē�������Ƃ��čs����B�����́u�Ĉ����F���v�ɑ��āA�R���̎���������u�č��v�ɂȂ�ƍl���Č��F�����B�u�s��̃��J�j�Y���͎����̗L�����p�ɖ𗧂v�ȂǂƂ������Ƃ͗������Ă��Ȃ������B���̓_�͊C�ېˁE�R��崓��E�{�������Ȃǂ̂悤�Ȑ挩���͎����Ă��Ȃ������B�ƌ����Ă����鎖�͏o���Ȃ��B21���I�̍����ł��敨����̎d�g�𗝉��ł��Ȃ��l��������������B�敨����E��E�w�b�W�t�@���h�E�f���o�e�B�u�Ȃǂ̌��t�́u�r�X�������{��`�́v�A�u���邢�͎�����H�̃A�����J���O���[�o���E�X�^���_�[�h�́v�A�u���{�ɂ͓K���Ȃ����x���v�Ƌ��ۂ���l����������悤�����炾�B���R�g�@�ƒ����̌�����琶�����u�ĉ���F�v�ł͂��������A���ꂪ���E�ɐ�삯���敨����ɂȂ�A�Ȍ�R���̉��i����ɖ𗧂��ƂɂȂ�B
�@
���Ȃ�ƂȂ����邭�A���R�Ȏ���
�@
�c���ӎ����]�菊�ɏo�āA���̎�������R�Əd�Ɉ�l�ŏ�\����悤�ɖ�����ꂽ1758(���8)�N����A�V�����Ƃ����1786(�V��6)�N�܂ł̊Ԃ��u�c������v�ƌ����B���̉��v�̎�����ꌾ�Ō����Ȃ�u�Ȃ�ƂȂ����邭�A���R�Ȏ���v�������B�c���ӎ��Ƃ��̋��͎҂�������A���̂��ɂ��ĉ��v���i���T�|�[�g���Ă����e�������A�����Ē��ڂ͊W�͂��Ȃ�����������������v��������Ă����ϋq�܂ł��A���̎���R���Ă����B����Ȋϋq�̈�l(������������ϋq�ł͂Ȃ��A�e�����邢�͎��)�Ƃ��ĕ��ꌹ���������B���b�o�ϊ��������v�ɔR�������̎���A�V�˂ł��苶�l�ł��������ꌹ���Ƃ����u���̐l�v�ɐG��Ă݂悤�B
�@
���ꌹ��(1728-1779.12.18)(����13-���i8)�����˂̏��j���Ζ��q��̎O�j�Ƃ��Ď]��u�x�ɐ��܂��B1749(����2)�����q��v�B�Ɠ��p���A���ꐩ�𖼏��B�����ˎu�x�䑠�Ԉ�l�}���A�ؕĎO�B1752(���2)����V�w�B1754(���4)8���˖��ޖ��肢���B1756(���6)�����o�č]�˂ցB�]�˂̖{���Ɠc�����Y�ɓ���B1757(���7)�t���Y������đ����i����ŊJ�ÁB���咆��~�����o�i�B���c�����I�����_���O�Ȉ����{���ʎl���ڂɊJ�ƁB1760(���10)�܌������V��i�ƂȂ�A�����ˎ嗊���ɐ��s���A���B1761(���11)�u�\�d�q����v��o�B12�������ɂ��ɓ��ʼn��܌����S�ɂ��̎�B1762(���12)�����ő�܉s��i�����ÁB1763(���13)������i��̐��ʂ��o�ŁB�㌎��ΐ^���ɓ���B�\�ꌎ�u����u��v�u�����u�����v���s�B1764(���a��)1�������ցB���Ð�R���ŐΖȔ����B1765(���a2)�u�����z�����v�B���S����u���̉����v�ɏ��B�u�召�G��̉�v�ɎQ���B���̔N�����_�c���ǒ��̗�؏t�M�ъG��n�n�B1776(���a3)�������Ð�ŋ��R���Ƃɒ���B1767(���a4)��c�쐤��m��㌎���́u�Q���搶���W�v�ɏ����B1768(���a5)�g�������C�g��(���g�v)����B1769(���a6)�u��������ҁv���B�쐤�u�����y���`�v�ɏ��B���Ð���R�x�R�B1770(���a7)�u�_�����n�v�����B�Ȍ㑱�X������ڗ��㉉�B�����ɖ|���p�Ƃ��Ē���ցB1771(���a8)���c�����u�^�[�w���E�A�i�g�~�A�v����B3��4����Z���ˌ��̌Y�r�D�����ɗ�����B1772(���i��)1���c���ӎ��V���ƂȂ�B2���ڍ��s�l��̑�Ō�����ޏāB�e�n����R���B�H�]�˂ɋA��B1773(���i2)�t���Ð�S�R���ƒ���B6��������čz�R�ĊJ���̂��ߏH�c�ցB�H�c�ˎ卲�|���R�Ɣˎm���c�쒼���ɗm���`����B10�����A�r�ɂ��B12�������]�˂ցB�i�n�]��(��؏t�d)��Ɛe���B1774(���i3)�����S�R���s�A�x�R�B7���u���̂������]�v�u���ݘ_�v���s�B8��������u��̐V���v���A�����̑}�}����B1775(���i4)�r��ʑD�H�������B�����ؒY�̍]�ːςݏo����}��B1776(���i5)��������o���B3���c�����Y�v�B11���G���L�e���̕����ɐ����B12���u�V���鐊Ӓ艏�N�v���M�B�A�_���E�X�~�X�u���x�_�v�B�A�����J�Ɨ��錾�B1777(���i6)5���u���ݘ_��ҁv�B�G���L�e�������q�����B1778(���i7)8���u�����V�فv�A9���u��\�̕]�v����B���H���e�[���A���\�[�v�B1779(���i8)(52��)2���u���̐��v����B���{���́u����v�ɓ]���B11��21���������V���Đl���E���B12��18�������Ɏ����B�S�[�͐�ꓹ���E���L���q�A���S�����F�l�̎�ŋ��ꑍ��(���䓌�拴��2����)�ɑ���ꂽ�B
�@
���n���ǂȂ炸�A�K���ׂ�L��B�ڂ̊�鏊���܂����
�@
���ꌹ���͑�c�쐤�̊����W�u�Q���搶���W�v�̏��ŁA����Ȃӂ��ɏ������B�u���ǂȂ炸�A�K���ׂ�L��v������҂͌Ǘ����Ȃ��A�K�������ނ̗L���̎҂��o�Ă����������A�Ɓu�_��v�Ɍ��Ƃ���̃p���f�B���B������҂����܂邾�낤���A�n�����܂����܂�B�V�������́A���l�Ȃ�ʔn������肠�܂��ďo�����������A�Ƃ����B���ł������B(�c���D�q���u�]�˂̑z���́v�}�����[����)
�@
���̎��㗬�s�����o�~�́u�A�v�Ƃ������@�ɂ���Đ��藧�B�o�~�͌��܂̔���Ɏ����̕t������A�܂����܂̑�O������āA�Ō�̋���܂ő����Ă䂭�B���̐�҂̍�����O�̋�ɂ́A�t�������������ꂷ���������Ȃ��悤�A�אS�̒��ӂ��Ȃ���t���Ă䂩�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������đ����Ă����ƈ�̂ǂ����̕����������Ă����̂��A�N�ɂ�������Ȃ��B����ł��Ȃ�������������͎Q���҈�l�ЂƂ�ɂ������Ă���B
�@
�A���L�����y���A��O�����u�V�����́v�����܂��B��c�쐤�Ђ�����u�R�̎�A�v���n�߁A��y�A(������)�A�l�J�A�A���I�A(��������)�A�ŘA�A�{���A�A���y�A�A�X�L���A�A�g���A�A�䒬�A�A�݂܂��A�Ȃǂ����܂ꂽ�B�A�ɎQ�����鋶�̎t�͋����������Ă���B�������V���̋��̎t�Ɏ����ċ����̈Ӗ�����ς��Ă���B����܂ł̋����͔o����덆�Ɠ����悤�ɁA���̒��ɍ�҂������B�������V�����̎t�����͖��̒��ɍ�҂����Ȃ��B�����l�i�ł���A�ǐl�s�m(��݂тƂ��炸)�ł���B�u�������ӂ����Ă��ƁA�Ђ��ς����Ă݂Ă��A��҂͂����ɂ�Ȃ��v�\�\�\�ƁB���Ȃ݂ɁA�ǂꂾ���ӂ����Ă��邩�A���������ƁE�E�E����s��(�����̂����̂ӂ炿)�A�����H�l(�͂炩��̂�������)�A��M���s(�ЂƂӂł̂Ȃ�䂫)�A��W��(�Ȃׂ̂ӂ��܂�)�E�E�E�C���^�[�l�b�g�̃n���h���E�l�[���Ƃǂ��炪�ӂ����Ă��邾�낤���H�����A�l�b�g�̌f�����u�A�v�Ȃ̂��B
�@
�����ƘA�o�~�ɂ��Ă����̂ɂ��Ă��A�A�Ƃ������@�Ő�������B���X�Ƌ傪�����������Ă����B�ǂ�����������킩��Ȃ��B�����̐������́u�A�v���̂��̂������B���邢�̓A�W�e�C�^�[�ƌ����ׂ���������Ȃ��B�����͎��s���肵�Ă����B�����������ɐG�����ꂽ�����̐l���u�����d�������Ă���v�B
�@
��؏t�M(1725?-1770)(����10?-���a7)�����Ɠ����_�c���ǒ��ɏZ�݁A�����Ɏh������G�������Ŋ��A���F���ؔʼn�u�ъG�v�̒a���Ɏ哱�I�Ȗ������ʂ������B
�@
����~��(1739-1786)(����4-�V��6)�{���w�҂Ƃ��Č����ƒm�荇���A��ɐ��c�����Ɖ�̐V���̖|��ɎQ������B
�@
���c����(1733-1817)(����19-����14)�u��̐V���v��|��A���s�B�������ł��悭�������Ă�����l�ł������B
�@
��c�쐤(1749-1823)(����2-����6)1767(���a4)�N19�˂̎��u�Q���搶���W�v���B�����������������B�V�����̂̃��[�_�[�ƂȂ�B�ӎ����r���M�̕������㐭�����n�܂�A���|�E�Ɛ≏�����B�u���̒��ɉ�قǂ��邳�����̂͂Ȃ��Ԃ�ԂƂ��ӂĖ���˂�ꂸ�v�Őg�̊댯�����������߂ł������B
�@
���c�쒼��(1749-1780)(����2-���i9)�H�c�ˎm�Ƃ��Ċp�قɐ��܂�A��������u���݂��ォ�猩�āA�����Ă����v�ƁA���m��@�������A�Ȍ�u��̐V���v�̑}�G����Ȃǂ��A�i�n�]���ɂ��e����^�����B
�@
�i�n�]��(1747-1818)(����4-������)�m��Ƃł���A�v�z�Ƃł������B�n�ߗ�؏t�M�剺�ƂȂ�A�t�M���̊��ҁA��؏t�d�Ƃ��Ċ���B��ɏ��c�쒼���ƌ����̉e���ŗm��ƂƂȂ�B
�@
�����吧�x�E�s��o�ς����ĘA
�@
�����d�G�����āA�剪���������̉ݕ�������p���A����Ɉӎ������g�ށB���̈ӎ��𒆐S�ɖ��b�o�ϊ��������v�Ɏ��g�ށB���̎��ゾ���炱�������̂悤�ȁu���̐l�v�����鎖���o���A�h�����ꂽ(���邢�͐U��ꂽ)�l����������B�ǂ���̕����������̂��H�J���X�}���c�͂��Ȃ��B�Q���҈�l�ЂƂ�̗͊W�ŕς���Ă���B�T�ώ҂̒��ɂ͕s���������҂��o��B�u�r�W�������Ȃ��v�u���ߓI�E�ꓖ����I���v�ƁB
�@
�����̎Љ�E���{�ɑ���ᔻ�ɂ��������̂�����B�u�K���ɘa����������Ă��̂��Ⴀ�Ȃ��B�s�ꂪ�ǂ̂悤�ɂȂ�̂���̓I�Ȑ��������ׂ����v�u�����Ƃ��������̗��R�őI�Ԑl������B����҂͌����Ȃ�ׂ����v(�����͐��������f���o���邪�A�����̏���҂͂��ꂪ�o���Ȃ��A�Ƃ����v���オ��)�B��������������O�����ƌ�����悤�ȁA�������������邩������Ȃ��댯�����߂Ă���A���吧�x�B�����̌��_�������Ȃ��������ɑւ����ǂ����x�͍l�����Ȃ��B���吧�x�ɂ͑����̌��_���L��A�A�}�`���A�ł��w�E�o����B���������̂��Ƃ��u���吧�x�ɑւ�鐧�x���K�v���v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B
�@
�s��o�ςł͏�Ɏ����M���b�v�͂��邵�A�����̌��_�������Ă���B�������u�s��̎��s�v�ƕ\������ꍇ������B
�@
�����̐��x�͔M���I�Ȑ��q�̑ΏۂɂȂ�悤�Ȋ��S�����Ȏ�`�Ȃǂł͂Ȃ��A���s������J��Ԃ��Ȃ���悭�Ȃ��Ă����A�����I�E�o�ϓI�Ȍl�̎��R��ۏ��邽�߂̌����I�Ȑ��x�Ȃ̂��낤�B
�@
����ȑ傫�ȃ��_�������Ă����̐��x�ɏ�����̂͂Ȃ��B���l��c���M���Ȃǎx�z�҂����P���ł���Љ�A����҂����������Â���悤�Ɍo�ς̕a�������Âł���Ɛ��ƂɊ��҂���Љ�A�v�����^���A�ƍقƂ������̊��������A�@���ł͂Ȃ���O�̊���ōق����v����̐l���ٔ��A�c��̌�������s���^���̎咣���d�����钼�ږ����`�A�Ǘ��ӔC�ҕs�݂̃A�i���R�T���f�B�J���Y���A�}�l�[�Q�[�����ɒ[�ɋK�����鍑�ƎЉ��`�A���Ƃ����艿�i���߂Ă����ۂ̓��~���i�����s���铝���o�ρA�l�Y�~��߂�̂������L�������L�������Ȃ̂ł����č��ƃC�f�I���M�[����邽�߂ɂ͍����ɉ쎀�҂��o�Ă����܂�Ȃ��Љ�A��ɖL���ɂȂ��҂���L���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��������ׂĂ������ɕn�R�ɂȂ錋�ʕ�����`�A�b���Ε�����P�ӂ̐l��������̎Љ�Ǝv������ł����z���a��`�A���������ē��������Љ�ۏ�⑼�l�̔����S�ɗ����������y���ƍl����l�������Ȃ镟�����ƁE�E�E�E
�@
���吧�x���s��o�ς��A���̌��_��⏞���A����ɐ��x�W������ɂ́u�A�v�̕��@���̗p���邱�ƂɂȂ�B
�u���v�ɔR�������b�o�ϊ����̖��v���犴����̂́A���̏�M������������ʂ��Ė��Ԑl�̂��e����^���A�u�A�v�̕��@�Ŕ��W���Ă������A�ƌ������ƁB�����Ă���͍���21���I�̎������������炩�̕s���E�s�����q������Ȃ�����u���吧�x�v�Ɓu�s��o�ρv����ĂĂ������ƁB���������ɑ����̃��b�Z�[�W���c���Ă���A�Ƃ������Ƃ��낤�B�@ |
|
�����{�̍��e�N�͔N��1���̒��l�������Z�@ |
   �@
�@ |
�����N�Z��������S��
�@
���v�ɔR�������b�o�ϊ����͒m�b���i��A����̐V��������ɒ��킵���B�����ł͂��̈�A���{�̎莝�������^�p��Ƃ��Ă̒��l�������Z�ɂ��Č��Ă݂悤�B�����ɓo�ꂷ��̂͘V�������E�ߏ��ĕ����E�c���ӎ��E��N��o�H�璉�F�E�k����s�ȕ��b��炻��ɒ��l�����璬�N�o�ꂷ��B�����ł́u�]�˂̌o�ϐ���ƌ���v(��؍_�O���E�r�W�l�X����o�ŁE1993�N12������)���炻�̎��̂�ǂ��Ă݂悤�B�悸��1771(���a8)�N12���̎��{���ꂽ���l�������������Ƃ��Ė��{�����N��ɑ݂��t����5�����ɂ��Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B
�@
�Z������܂ł̌o�߂���͖��{�̎������u�ݕ���蓖���v�Ƃ������ڂŒ��N��ɑݕt�Ď����^�p�����A�������痘�q�����悤�Ƃ������̂������B1771(���a8)�N11��20���ɁA�k����s�ȕ��b���͎�N��o�H�璉�F���ɁA�����^�p���s���ꍇ�̗����A�S�ہA�M�p�ۏȂǂ̗Z�������ɂ��Ē��N�̏�\�����o���A���������ꂪ�Ó��ł���|�̈ӌ���(���\)���o���Ă���B������12��10���ɂȂ�ƁA�����̘V���M���ŏ���W�V���Ƃ��Ė����E�����̐ӔC�҂����������E�ߏ��ĕ���������s�ɑ��āA���{�����N��ɑ݂��t���Ď����^�p���s�����Ƃ̌���ƁA���̎����̎n�����@�ɂ��Ċ����s�ƒ������邱�Ƃ𖽂����B����s�͑�����11���ɂ͎O���N��ɂ��̎|�̓������s���Ă���B
�@
�Z�����������N��̎咣�ǂ��茈�܂�ƁA12��13���ɂ͎O���N��̘A���ŁA���̍ݕ���蓖��5�����̑ݕt���@�◘�q�A���N��̎敪�Ȃǂɂ��āA�ׂ��Ȏ����葱���̐\�����Ă��s�����B���̌�15������18���ɂ����āA���N��A����s�A�����s�̊ԂŁA�ݕt���̎�n���@��A�u�Z�����z���������ߐM�p���������؎�l����x�ɑ�����̂�����A��x��5���������̂͑�ς�����2��ɕ����Ď�̂���v�A�Ȃǂ̂��������Ȃ���A20���ɂȂ�ƗZ�����钬�l83�l���m�肷��B�����ē�k������s��12��29���ɏ����E�ߏ��ĂɁA5�����̍ݕ���蓖���̗Z�������������|�̕��s���Ă���B
�@
���{���ƒ��l���̂����͂��߂ɗZ���b���������������{���́A�N��10���ő������̉Ǝ��������o�����邱�Ƃ�ژ_��ł����B����ɑ��Ē��N�́A�u�Ǝ�������đ݂��t�����s���ꍇ�A�s���̗����͔N4-7���ł���A���{���̏����ł͎�肪������Ȃ��v�Ǝ咣���Ă���B���̌��ʖ��{�͒��N�ɉ������āA���ǒ��N���̎咣��������Ō������Ă���B����ł�12��10���ɂ��ׂĂ̗Z�����������肳��钼�O��12��7���̒i�K�ɂȂ��Ă��A����o�H��́u5�����͂��ĂȂ��قǂ̑��������A�ݕt�ɍۂ��Ă͉Ǝ������ׂ����v�Ǝ咣���Ă���B���ꂩ�番����悤�ɁA���̌��Ɋւ��Ă͑o���A����������肪�������ɈႢ�Ȃ��B�Ɠ����ɑo�����{���Ō����������o����قǂ̐M���W���������̂��낤�A�Ƃ������ł���B
�@
�Z���̓��e1771(���a8)�N12��11���ɏ����E�ߏ��Ă��猎�Ԃ̒���s(�k����s�ȕ��b���)�o�R�ŁA�쑽���F�E�q��A�ޗlj��s�E�q��A�M���^���q��̎O���N��ɑ��āA���{����(�ݕ���蓖)5�����̑ݕt�����̂悤�ȏ����Ŗ������邱�ƂɂȂ����B
�@
����5����
�@
�����N10��(�N�ԗ���5�痼)
�@
���Ҋ���5�N
�@
�S�ۖ��S��
�@
���̑����N���ɑ��ĔN�Ԃ̗���5�痼�̂Ȃ�����250��(�����ɑ���0.5��)���G��p�Ƃ��ė^����B
�@
�܂�A���N���ʂ��������^�p���Ȃ�Ƃ��������������{�����A�Ǝ��͎��Ȃ����ƁA�Z����̊ɘa��F�߂�ȂǁA���N�̌����������ׂĔF�߂����ʁA5�����̒��l�����Z�������܂����̂������B
�@
��ȗZ���悱���̗Z����́A�������Ǝ��̔d�����V�E�q��̂悤�ȗ��ցA�����Ǝ��̈ɐ����l�Y���q���V���U���Ǝ��̈ɐ����l�Y���q�̂悤�ȎD���Ȃǂ̑古�l���傾�������̂������B�����ėZ����͉Ǝ�74���A�n��7���A�n��1���A�Ǝ�1���ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɖ��{�̎��������N���ʂ��ė��֏��A�D���Ƃ����������̒��l�����ƕ��ƌ����̋��Z�@�ւɗZ������A�Ƃ��ɉ^�p����邱�ƂɂȂ����B����5�����̗Z���b��1771(���a8)�N11���Ɏ����オ��A12�����{�ɂ͎s�����������������B���̂悤�ɓ����̍]�ˎs���̎������v�͉����������B
�@
�����đ��������N�����ɂ͖��a8�N12�����̗��q�����{�ɕ������܂ꂽ�B
�@
�������������^�p�͂���ȑO������������B1771(���a8)�N12���̎��_�ŁA���N�^�p���˗�����Ă������{�����́A���a3�N����1�����A���a4�N����1�A294���A���̖��a8�N����5�����A�剜�����ł����L�~��p����1�痼��2����2�痼�A���ˉ@������600���A��^�@������3�痼��2�痼��2���Ōܐ痼�A�̍��v68�A894���ƂȂ��Ă���B�����Ă����������{�̎����^�p�͓c���������㑱���A���������ɂȂ�ƐV�K�ݕt�͂Ȃ��Ȃ�B
�@
���N����ӎ��̋��͎ҍ]�˂̒��N��Ƃ́A�]�˂̒������邤���ł̊ԐړI�Ȏ��s�@�ւł���A�]�˒��l�̎����g�D�̍ō��@�ւł��������B���N��͂��NJe���̖���A�Ǝ�̒��_�ɂ����Ă����̂Ɠ����ɁA�Ǝ�ʂ̓��ƎҒc�̂��������āA����ɑ��開�{�̖��߂���`�B����Ƃ����@�\�������Ă����B���㕗�Ɍ����A�������ł͂Ȃ����u�����v�̖����ƁA�u������v�̖�����S���Ă����A�Ɨ�������������낤�B�]�ˎ���A���얋�{�Ƃ������{�̐��{�͌���̏펯�ł͂ƂĂ��l�����Ȃ��قǁu�����Ȑ��{�v�������B���̏ꍇ�̗Z�����s�Ɋւ��Č����u���N��v�͓��쐭���́u������s�v�̖������ʂ����Ă���B
�@
�u���N��v�����������ڂ����������悤�B�悸�]�˂̒��n����ђ��n���Z�҂��x�z����@�ւɂ��Ą������̂��߂̍ō��@�ւ͊��{�̂Ȃ�����C�����ꂽ��E�k����s�B����͌���́u���ƌ������v�A������L�����A�g�B����s���͂��̂��߂̑g�D�Ƃ��Đݒu����A���̍\�����Ƃ��āA�^�́E���S���z�u���ꂽ�B�����܂ł����{�@�ւł���A���ƌ������B
�@
���̐��{�@�ւ̈ӎu���]�ˑy���ɓ`�B���A����ɔ����������s���s�����ԑ��̋@�ւƂ��Ē��N�u���ꂽ�B����́A���Ƃ����ڒ��l�ɐڐG����̂�h�����߂̋@�ւł��������B
�@
�]�˂̒��N��ɂ͒M���E�ޗlj�(�̂���)�E�쑽���̐��P�O�Ƃ�����A�@�߂̓`�B�A����s����̒����˗��A�s���̓y�n�̒n���E�n���^����Ȃǂ̒����Ə�[�A�e���̖���̔C�ƁA�����Ԃ̓����A�����݂̑��t���Ȃǂ���ȔC���Ƃ��Ă����B���̒��N��͍]�˒��l�̑�\�Ƃ��Ē���s�Ɓu���v�̊Ԃ̘A�����ł���s�����ɁA�����Ȃǂ̓s�s�{�݂̒��Ȃ��Ă��Ȉێ��Ǘ��@�ւł��������B
�@
�����Ē��N��Ɗe���̊Ԃɂ����āA��Ƃ��Ē��̎����I�Ȋ������s�����߂̋@�ւ��u����v�������B��������P���������������A����Ɂu���v�I�ȑ��݂ɂȂ��Ă������B
�@
����ɂ��̖���̔z���ɂ͐E�\�c�̂Ƃ��ẲƎ�̏W�c���������B�Ǝ�́u�ܐl�g�v���������đ��݂ɘA�������Ȃ���A���Ԃł���u���s���v�������ɂ������Ă����B�]�˂̉Ǝ�ܐl�g�́A���{���S���_�����ɑ��݊Ď��̖ړI�őg�D�������u�ܐl�g�v�Ƃ͂܂��������i���Ⴄ���̂ł���A���ꎩ�̂������Ȏ����I�\�͂����������@�l�I�Ȃ��̂ł������B
�@
�����̑g�D�E�������A�u�]�˂̌o�ϐ���ƌ���v�̒��ҁA��؍_�O�͎��̂悤�ɕ\�����Ă���B
�@
�����ŁA�g���ʊK�����x����̎x�z�@�\�ƌ��݂̍s���@�\������������̂ł͂Ȃ��ƒf���������ŁA�����Ē��N��E����E�Ǝ�W�c�̖�������₷�������ƁA���N��͌��݂̓����s���m���A����͓���23���ʋ�̋撷(�������N�̍s����搧�x���������̋撷�̑����͖���o�g�҂�����)�A�Ǝ�W�c�͋撷�̕⏕�@�ւł��������E���ɂ�����B����͍s�������g�D�̌`�̏ゾ���̔�r�Ȃ̂����A���ǂ낭�ׂ����ƂɎ����Ƃ��Ă̓s�s�s���̑Ώۍ��ڂ��݂�Ƃ��̓��e�͌��݂ƂقƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��B
�@
�������Ԑ��x������o�ϐ����ɖ𗧂���
�@
��]�ˌo�ϊw��3�����v�ɔR�������b�o�ϊ����̖�(3)�������E�^����ȂNJԐڐŏd���̐Ő����v(2002�N2��25��)�Ŏ��グ���u�����ԁv�A�ӎ������͊Ԑڐł̉ېőΏۂƂ��čl���Ă������A����ȏ�ɕ�������ƌo�ϐ����ɖ𗧂��Ă����B�����Ԃ͓c������ɑ��𒆐S�ɂ��̌������}���ɐi�B���̎��㌋�����ꂽ�̂͐�56�ŁA�ؖȁE���E�Y�Ȃǐ����K���i�W�̊����Ԃ������B�����͏��Ȃ����Ԃ�2(������≮)�A�������̂�190(�V�����s��≮����)�ł���A�����s��̒��Ԃ�9�������B
�@
���̂悤�Ɋ����Ԃ͖��{�ɂ���Č��F����A���̖������E�^����͖��{�̍�����Ղ̈ꕔ�ɑg�ݓ������܂łɂȂ����B������1840�N��Ɏ��{���ꂽ�V�ۂ̉��v�ŁA���{�͈�]���Ċ����Ԃ��֎~����B1841(�V��12)�N�A��O�Ƃ̈���˔˂̓���ď��́A�V�ۉ��v���哱�����V�����쒉�M�ɑ��Ċ����Ԃ����U����悤�i�����Ă���B������1841(�V��12)�N12���Ɋ����Ԓ�~�߂��o�āA1851(�Éi4)�N3���ɖ≮�ċ��߂��o��܂Ŋ����Ԃ͒�~�����B�����Ŋ����Ԃ��������Ă��������ƁA���̒�~���ԂƂŌo�ϊ����ɕω������������ǂ����H������u�]�˂̎s��o�ρv(����N�u�k��1999�N4����)���甲���o���Ă݂悤�B
�@
�o�ϐ�����1842-1850�N�̌o�ϐ������̓}�C�i�X2.29���ƂȂ�B���̊��ԑ傫�ȋQ�[�͂Ȃ��B�����Ԓ�~�ȊO�̂�蒷���I�Ȍ����ɂ����̂�������Ȃ��B�����ŁA���̓_���`�F�b�N���邽�߂Ɋ����Ԃ���~���ꂽ9�N�Ԃ��A��~�O�̓���9�N��(1833-1841)�Ɣ�r����B�����Ԓ�~�ȑO�̌o�ϐ������̕ϓ������������A�������ς���ƔN��0.571���ƂȂ�B���̂悤�Ɋ����Ԓ�~���Ԃ̕��ϐ��������}�C�i�X2.29���ł���������A��~���Ԃɂ͒��O�̎����Ɣ�r���Č����Ɍo�ϐ��������ቺ�����Ƃ������ƂɂȂ�B��������~�O�̋@�ւɂ͓V�ۋQ�[��2�N�Ԃ��܂܂�Ă����B���̓_���l������ƁA��~���Ԃ̌o�σp�t�H�[�}���X�̑��ΓI�Ȉ����͈�w�m���Ȃ��̂ƌ�����B
�@
���Y�E���ʋ@�\�̍��������Ԓ�~�ɂ���ė��ʋ@�\���������A������̗��������������B�����N�Ԃɍs��ꂽ�Ɛ��肳��钲���Ɋ�Â����P�[�X������Ă���B����Ɉ˂�Ɠ����E�C�Y���E���E���E�a�k�D�E�ΊD�E���E�C�^�E�ޖؓ��̊����Ԃ���~���ꂽ�̂ŁA�T�[�r�X���s���Ȃ��Ȃ�����A���i�̗���������������A���ʁE���Y�V�X�e�������ꂽ�B
�@
���܂��܂Ȋp�x���犔���Ԓ�~���Ԃ̓��{�o�ςɂ��Đ��ʃf�[�^��p���Č�������ƁA������̕��͂���������Ԓ�~���Ԃɂ́A����ȑO�̊������ɔ�ׂČo�ς̃p�t�H�[�}���X���ቺ���A�s��@�\�̋@�\�ቺ���������Ƃ������ʂ�������B
�@
���]�ˎ���ɂ�������݁E��݂̗��ʗʂ̕ϑJ
�@
�P�ʐ痼(���݊��Z)()���͍\���䁓
����(�N)����ݍ��v�N���ϑ�����
�@
1695(���\8)�N�@�@10,627(76%)�@�@�@3,333(24%) �@ 13,960(100%)�@----
�@
1710(��i7)�N�@�@15,050(58%)�@�@10,755(42%)�@�@25,805(100%)�@4.2%
�@
1714(����4)�N�@�@13,570(43%)�@�@18,120(57%)�@�@31,690(100%)�@5.3%
�@
1736(������)�N�@ 10,838(52%)�@�@10,204(48%)�@�@21,042(100%)�@-1.8%
�@
1818(������)�N�@ 19,114(65%)�@�@10,141(35%)�@�@29,255(100%)�@0.4%
�@
1832(�V��3)�N�@�@23,699(52%)�@�@22,165(48%)�@�@45,864(100%)�@3.3%
�@
1858(����5)�N�@�@28,315(54%)�@�@24,438(46%)�@�@52,753(100%)�@0.5%
�@
1869(����2)�N�@�@74,321(57%)�@�@55,904(43%) �@130,225(100%)�@8.6%
�@
��]�ˌo�ϊw�ʼnݕ����������グ���B�����ō]�ˎ���̒ʗ��ʗʂ��ǂ��Ȃ��Ă����̂��A���̐�����\�ɂ��Ă݂��B1695(���\8)�N�A�����d�G�̌��\�ݕ������͌o�ς̐����ɑ��āA�ݕ��ʂ����ΓI�ɕs�����Ă������Ƃ�����A�^�C�~���O�̗ǂ������������B�����E���ۂ̉����ł͓����ɋُk�������̂��A���m�E���l�w�̏���x�o�̒ቺ�������A�o�ς͒�������B���ꂪ1736(������)�N�̉����Ōo�ς͎��������B�����������ɂ͐ߓx�������A�ݕ�����͔j�]���A�����ېV���}���邱�ƂɂȂ�B�@�@
�@ |
| ���]�ˎ���̐� ���� |
   �@
�@ |
|
���]�ˎ���̐�1�@ |
��1.�]�ˎ���̐�
�@
�]�ˎ���́A���얋�{���S���ꂵ�Ă�������ł����B�����č����́A���{�́E���{�́E�˗́E���З̂Ȃǂɕ�����Ă���A�ł̎�ނ�ŗ��͂��ꂼ��قȂ��Ă��܂����B
�@
�]�ˎ���̐ł́A�傫���N�v(���{�N�v�A�{�r����)�Ə���(�������E���|���E�v���E�����Ȃ�)�ɕ�����܂��B
�@
�N�v�͓c���ɂ�����łŁA�������͓c���ȊO�ɂ�����łł����B�܂��A���|���͑���(�����̐�)�⎝��(���S�����k�삷��y�n�̐�)�ɂ��������łł��B
�@
���̑��ɁA�]�ˎ���ɂ́A����̎d���ɉېł����^��E�����A�܂��A�Վ��̎��Ƃ�����̌����߂̂��߂ɕ��ۂ�����[��������܂������A�]�ˎ���̐ł̒��S�͖{�r�����A������u�N�v�v�ł����B
�@
��2.���n
�@
���n�Ƃ́A�̎傪�����̗̒n�ɑ��čs�����y�n�����̂��Ƃł��B
�@
���n�̎��ɂ́A�y�n�̎�ށE�L���E���n���Ɠy�n�̍k��҂���������A���̌��ʂ͌��n���ɋL�^����܂����B���n���ɓo�^���ꂽ�k��҂́A�y�n�̍k�쌠��F�߂������ɐłS����`��������܂����B�܂��A���n�ɂ���Ē�߂�ꂽ�y�n�̐�(�Ă̎��n��)�́A����Ȍ�N�v�⏔���Ȃǂ��ېł��鎞�̊�ɂȂ�܂����B
�@
���n�́A�S���I�ɂ́A���\����܂ōs���A����ɂ���đ��̓y�n�̊�{�I�Ȑ����m�肵�܂����B�������A�Ȍ�����n�́A�V�c�J���Ȃǂɂ���ĐV���ɉېőΏےn���������ۂɍs���Ă��܂����B
�@
��3.�N�v�̉ېŁE�[��
�@
�N�v���ېł���ɓ������āA�̎�͎����̗̒n�̑��Ɉ��Ăāu�N�v���t��v���o���A���̔N�̔N�v�̊z��ʒm���܂����B
�@
�u�N�v���t��v���āA���ł͗̎傩��ʒm���ꂽ�N�v�̕S�����Ƃɍk��n�Ƃ��̐�(�Ă̎��n��)���܂Ƃ߂��������ƂɊ��蓖�Ă����߂܂����B
�@
�܂��A�N�v�̉ېŕ��@�ɂ́A��Ɍ����@�ƒ�Ɩ@�̓�̕��@������܂����B
�@
�����@�́A��N���ƂɎ��n����������ʼnېł�����̂ŁA�N�v�̊z�́A���̔N�̎��n���ɑ傫�����E����܂����B����ɑ��Ē�Ɩ@�́A�ߋ��̎��n�������Ƃɂ��Ĉ����ԓ��z�̔N�v���ېł���Ƃ������̂ŁA�N�v�̊z�́A���̔N�̎��n���ɍ��E����邱�ƂȂ����̊z���m�ۂ���܂����B
�@
�]�ˎ���ɂ́A�̎�́A�N�v�̎��W�ߋy�є[���ɔC���Ă��܂����B������u�������v�Ƃ����܂��B
�@
���ł́A�N�v�����W�߂���A�̎�ɔ[�߂܂������A���ɕ����Ĕ[�߂邱�Ƃ�����܂����B�����āA���ׂĔ[�����I���Ɨ̎傩��u�N�v�F�ϖژ^�v�����Ɉ��Ăďo����܂����B����͗̎傪���̔N�̔N�v���m���Ɏ�������Ƃ�ʒm�������̂ŁA����������ĔN�v�Ɋւ����N�Ԃ̎葱�����I�����܂����B�Ȃ��A���{�̂̏ꍇ�A���������ʒm�́A���얋�{�̒��b�ł���㊯��S�オ�o���܂����B
�@
�܂��A�N�v�Ȃǂ̎��W�߂ɂ��������o��͑��ŕ��S���Ă��܂����B���ɂ���Ă͏W�߂��N�v�ĂȂǂ��߂��̒���`�܂ʼn^�ԑ�������܂������A���������N�v�ĂȂǂ̗A���ɂ��������o����܂����ŕ��S���Ă��܂����B
�@
��4.�N�v�ȊO�̏���
�@
�]�ˎ���ɂ́A�N�v�ȊO�ɂ��l�X�Ȗ����ۂ����Ă��܂����B
�@
�Ⴆ�A���H�Ǝ҂ɂ͉^��E�������ۂ����܂����B�܂��A���̒n��̓��Y�����������������̑ΏۂɂȂ�܂����B���̓��A�Ƃ́A�Ă��ʂɎg�����ߕđ���ɑ傫�ȉe���͂��y�ڂ��܂����B���̂��ߓ��얋�{���S���Ɍ����Ď����߂��o�����Ƃ�����܂����B�̐����́A���i�͗̎傪�Ǝ��ɍs���Ă��܂������A���{���琧���߂��o���ꂽ���ɂ͂���ɏ]��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B
�@
�܂��A���{�͍�������S���܂��͓���̍��ɑ��č��ƍs���A�Ⴆ�Β��N�ʐM�g�����������v�ȉ͐�̕������s�����ɕ��ۂ��Ă��܂����B�܂��A�S���̌�ʖԂ��ێ����邽�߁A��v�ȊX�������̑��X�͊e�h��̏���(��)�Ɏw�肳��Ă��܂����B�����Ɏw�肳�ꂽ���ł́A�h���⏕���邽�߂ɐl�n�̋������s�����Ƃ��`���Â����Ă��܂����B
�@
��5.�ېł̖Ə��E����
�@
�̎�́A��{�I�Ɏ����̗̒n�̂��ׂĂ̓y�n���ېőΏۂƂ��邱�Ƃ��ł��܂������A�ېłł��Ȃ��y�n������܂����B�Ⴆ�A���З̂ɂ͎��n�E���n������A��{�I�ɗ̎�͔N�v���ېłł��܂���ł����B���̑��A�ꏊ�ɂ���ẮA�̎�Ƃ̗R������ʂȖ���C����Ă������ߔN�v���Ə��ɂȂ��Ă����Ƃ��������܂����B
�@
�V��s����ЊQ�Ȃǂɂ���ċQ�[�⋥��Ɍ�����ꂽ���A���ł͗̎�ɔN�v�̌��Ƃ��肢�o�܂����B�̎�ɂƂ��Ē�Ɩ@�́A���̔N�v���m�ۂł�����̂ł������A�Q�[�ȂǂŎ��n�������������ɂ͌����@�ɕύX����Ȃǂ��ĔN�v�����Ƃ��邱�Ƃ�����܂����B�@ |
|
���]�ˎ���̐�2 / ���l��E�l�ɑ���ŋ� |
�w�ŋ��x�Ƃ����l�����͖����ȍ~�̋ߑ�Љ�ł����Ȃ�ꂽ���̂ł��邩��A�]�ˎ���Ɍ���̐ŋ��ɂ�������̂����o�����Ƃ͑�ϓ���B
�@
�ł́A���l�͖��{��̎�A�n��W�c�⓯�ƎҏW�c�ɑ��āA���S���Ă������̂��Ȃ������̂��Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��A���l�����l�ł��邽�߂ɂ͉�������̕��S��S���Ă����B
�@
�܂����ɒ��l�͏����Ƃ��c��ł�������A�������E�^����E��p���S���Ă����B
�@
�������́A���{��˂���c�Ƃ������ꂽ���H�Ǝ҂��A���v�̈ꕔ�������������̂ŁA�l�P�ʂƓ��ƎҏW�c(������)�P�ʂ̂��̂Ƃ��������B
�@
�^����͏��H�Ƃ����Ɍ��������̂ł͂Ȃ��A�A���ƁE���ƁE��E�z�R�ƁE�����ƂȂǍL���Ǝ�ɂ킽��A���v�̒�������̊����Ŕ[�߂����̂ł���B
�@
��p���͖��{�⏔�˂��������₤���߂ɗՎ��ɒ����ᗘ�ŁA�x�T�ȏ��H�Ǝ҂����グ�����̂Ȃ̂ł���B
�@
�����ɂ́A�������I�Ȍ����ƌ����������ǂ��B
�@
���ɁA���l�͓s�s�ɋ��Z���A���Ƃ�����(�Ǝ�)�A���Ƃ����n�������̂̐��K�̍\�����ł������B
�@
���̍\�����ł��邱�ƂŁA���l�͉ƁE���~(�n)�E���Y��ۑS���A�����̐M�p�A�Ƒ���g�p�l�E�؉Ɛl(�X�q)�E�ؒn�l�̐������x���Ă����̂ł��邩��A���̐e�r��}���A�����̂��߂̕��S��S���Ă����B
�@
�����p�Ƃ����`�ŋ��K���W�߂��A���̏o��ɂ�蒬�̉^�c���Ȃ���Ă����̂ł���B
�@
�Ō�ɁA���l�����Ƃ�̎�ɑ��ĕ����Ă�������(��)������B
�@
���̓��e�͓`�n���ƒ��l�����ł���B
�@
�`�n���Ƃ́A�̎�̊X���ʍs�̍ۂɔn��l������邱�ƂŁA���l�̉��~�̊Ԍ��ɉ����Č��߂��Ă����B
�@
���l�����́A�����H���A�|���A�h�A�h�ЂȂǂ̎�X�G���ȓ���̌����I�Ȑ����Ɍ����ׂ��炴�镉�S�ł������B
�@
�ȏオ�A���l�����l�ō݂邱�Ƃ��畉���Ă��������S�ł���B
�@
�����ď����ł̂悤�Ȃ��̂�������Ƃ���A�l�P�ʂ̖������ƂȂ�ł��낤���A�N�v���_���l�ɒ��ڕ��ۂ��ꂽ�킯�łȂ��A�̎傩�瑺�֕��ۂ���A�����Ŋ������킯�ł��邩��A����̂悤�Ɍl�����ڐŋ����x�������Ƃ͍]�ˎ���ɂ͂Ȃ��������̂ƍl������̂ł���B�@ |
|
���]�ˎ���̐�3 / ���l����ł���藧�Ă�
|
�n�ʂɐ�����앨��A�����ɌQ���鋍�n�ƈ���āA���Ɗ����œ�����x�͂ǂꂾ�����v������ꂽ�̂��O����͌v�������ɂ�����_������܂��B����ɓy�n�͌��͎҂ɂ���ď��L�ɋK���������₷���̂ɑ��ď��Ɗ����͏ꏊ��I�Ȃ��̂ŋK�������ɂ����ʂ�����܂��B
�@
���Ɗ����́A���Y�҂��珤�i���d����ď���҂ɔ��邱�Ƃŗ��v��킯�ł����A���̏��i���x�z�҂̗̈�̊O���玝�����ꍇ�A�x�z�҂͏��i�ɑ��ď��L�����咣�ł��Ȃ����߁A���l�������ɂ���ē������v�ɐŋ��������邱�Ƃ��ł��܂���B
�@
�̂̐l�Ƃ����͈̂ӊO�ƌ����W�Ɍ��i�ł���̂ł��B��낤�Ǝv���Ȃ�ɂł��ŋ��������邱�Ƃ��ł���ߑ㍑�Ƃ̕�������Ӗ�����ۂlj��\�ł���̂ł��B
�@
���ď��l���O���玝���Ă������i�������Ƃœ������v����ŋ�����藧�Ă锄��ł̍l�����͌Ñ�͂��܂�Ȃ������̂ł�(�S���Ȃ������Ƃ͌����܂���)�B
�@
�x�z�҂��咣�ł���̂͋�Ԃ̐�L�������ł��̂ŁA���l����ł���藧�Ă�Ƃ���ƁA�����̒��ݗ��A���邢�͏��i�̗̓��ʉߗ�(�֑K)�̌`�ƂȂ�܂��B���ݗ��͔̔��ݔ��ɑ���O�`�W���ېłƂ�����ł��傤�B�ʉߗ��͂���ΊԐڐłł��B����Ə����ϑ��I�Ȑŋ��Ƃ��ĔF���Ƃ����̂�����܂��B
�@
���B�̋���͓s�s�Z���̏����ɏ\���̈�ł������Ă��܂������A����͑S�Ă̕��͐_�̏��L���Ƃ�����_���̋����������ƂȂ��Ă��܂��B������ӁA�S���I�����@�\�Ƃ��ċ�����p���������B�̋ߑ㍑�Ƃ͏����ɐŋ��������₷�������̂ł��ˁB
�@
���ߍ��Ƃ͎s�̏��l�ɂ͔����������c�Ɠ����悤�ɔz�����āA��������g�p�������`�����Ƃ�܂����B����͖�K�ɋ߂��B�����ɂȂ�Ɗ֑K����ɂȂ��Ă��܂��B��藧�Ă₷������ł��傤�B�������̎���ɂȂ�ƌ���⎛�Ђ����l�ɕی�(�c�ƌ���֏��̎��R�ʍs�̌���)��^����ւ��ɏオ�������P�[�X���o�Ă��܂��B�F���E�Ƌ����ł��B����͐�Ή����̉��B�����ł͐Ŏ��̑傫�ȕ������߂Ă��܂����B�D�L�����͒ʍs���ړI�̊֏���A���Ǝґg������Ƌ����̒���������̂��~�߂邩���ɁA�s�s�̏Z������ƒ�����藧�Ă�悤�ɂȂ�܂��B
�@
�ƒ��͊Ԍ�(�X�̒ʂ�ɖʂ��������̕�)�ł�����ꂽ�̂ŁA���s�ł͉V�̐Q���ƌĂ����ɐ[�����������B���܂����B����͋��s�̒��l�̐ߐő�Ȃ�ł��ˁB
�@
�������͗��ʋƎ҂������炵���A���s�ɂ������Ƃ͎������{��ɋ��Z�Ƃ������肵�Ă��܂��B����Ɋւ��Ă�����W(�����̐��^�Ǝ�)�̈���������L�b�G�g�Ƒ��ʂ��镔��������܂��B�ł��̂œ���ƍN�͏��Ƃ̏d�v���͏\���ɔF�����Ă����͂��ł��B
�@
����������Ƃ̏��Ƃɑ���m���͏��l����ł���藧�Ă�����ɂ͎g��ꂸ�A���l�̐ŋ����y�����ď��Ɗ���������������������ɐi�݂܂��B����ɂ���āA�]�ˎ���̑O���ɓs�s�͑唭�W�𐋂��܂��B�]�˂͐l���S���̐��E�L���̓s�s�ƂȂ�B���������\���l������鐢�E�I�s�s�ƂȂ�܂����B�s�s�͂���܂ʼn����퓬���ɂȂ邵���Ȃ������_�Ƃ̎��j�V�O�j�V��Q�l�����Ɗ����ɂ���ċz�����Đ��̒������肳�����̂ł��B���얋�{�͌��łɂ���ēs�s�Ɏ��Ƃ��z���������̂ł��ˁB
�@
���������Ɗ��������������A�����K���i���s��Ŏ�ɓ����悤�ɂȂ��Ă���Ɖݕ����K�v�ɂȂ��Ă��܂��B�]�ˎ���̏����̐l����1�A500���l���x�ł������A���̌�̌\�N�Ԃɑ唚������3�A000���l�܂ő������܂��B�ł��̂ŒP���ɍl���Ă��f�c�o�͔{�������͂��ł��B���������얋�{��喼�́A������܂��Љ�̈���̂��߂ɂ��܂茟�m�͂��܂���ł����̂ŐŎ��͔{�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B�������ł�Ă̌`�Œ������Ă��܂����̂ŁA�Ă̐��Y���ɂ���ĕĉ�����������ƂƂ��Ɏ��������͌��葱���܂����B���H��ߗނ�Q�Ό��ɂ�����ʍs���A�]�˂ł̑؍ݔ�(���R�s�s�̕�������������)�͉V�o��B����`������(��������)�ɂ������p���l����̏㏸�ɂ���ďオ��܂��B
�@
�������Ė��{�Ɣ˂͖����I�ȍ�����Ɋׂ�̂ł��B
�@
���喼�݂�
�@
�茳�̎����Ő��l���`�F�b�N���Ă݂܂��B�u��ڂł킩��]�ˎ���v(���w��)�ɂ��܂��ƁA�c���O�N(1598)�̑S���̐���1�A851���B���ۓ�N(1645)��2�A455���B50�N�Ԃ�30�������B���̌�͋C��̊��≻�ɂ���Ē���A2�A500���ΑO��𐄈ځB�V�ۂɍĂѐ�������3�A000����˔j���܂��B
�@
�]�ˊJ�{�̍��̑��l����1�A200〜1�A800���l�̊ԁB���߂đS���K�͂̐l���������s��ꂽ���ۘZ�N(1721)�̒����̐l����2�A600���l�B���̌��2�A400〜2�A600���l�̊Ԃ𐄈ڂ��Ă��܂��B���̂ق��ɕ��m��300���l���炢����̂ő��l���͖�3�疜�l�ł��B
�@
���یܔN(1730)�̖��{�̍Γ��͖�80�����ŁA���̂���64�����N�v�A�^���(������ȂǓ��菤�i�̔����ɂ�����ꂽ�ŋ��A�����ł��͏���łɋ߂�)��7���A��p��(�������I�Ȏ�グ)��4���A�ݕ������v��1�D3���ƂȂ��Ă��܂��B
�@
�S�N��̓V��14�N(1843)�ɂȂ�ƁA�Γ���154������2�{�ɂȂ�A�N�v��39���Ɣ䗦�����A��p����10���A�ݕ������v��26���Ɗg�債�Ă��܂��B
�@
���Ȃ킿�]�ˎ���̒�����100�N�ԂŔN�v������51��������60�����ɂ����������B���̂����Ɍ�p����3��������15�����ɁA�ݕ������v��1��������40�����ɑ����Ă��܂��B(�����ێ���̓f�t�����Ƃ��Ă����̂ʼnݕ������v��������)
�@
���ˑ̐��͏��l����ł���藧�Ăɂ����悤�ɂł��Ă��܂����B���������얋�{�͗��ߍ��Ƃ⎺�����{�ȂǂƔ�ׂĒ������{�Ƃ��Ĉ��肵�Ă��܂����̂ŁA�����ɂ͂Ȃ���������������܂����B
�@
�܂���ꂪ�ݕ������v�ŁA����͋��݁E��݁E�K�̌����Ɗz�ʉ��i�Ƃ̍��z�ł��B��������܂œ��{�͎x�߂̓��K���g���Ă����̂ł����A�]�ˎ���ɂȂ��Đ��̒������肵�A�z�R�̐��Y�ʂ����������̂ŁA���{�͈���I�ɒʉ݂s�ł���悤�ɂȂ�A�ݕ������������ł���悤�ɂȂ�܂����B
�@
����͎��������Ɛ��E�I�ɂ͒��������ƂŁA�����̉��B�͐V�嗤����A��������ɗ����Ă��܂����B��݂��ʂɔ��s�ł����̂͐V�嗤���x�z���Ă����X�y�C�������ʼnp����t�����X�Ȃǂ̓X�y�C���ɖѐD���⍒�����ĉݕ���Ȃ���Ȃ�܂���ł����B���ɂ��z�R�͂Ȃ������ł����A���̍��̎x�߂͋Z�p�͂����E��ł����̂ŁA���D���₨���Ȃǂ����B����{�ɔ����ċM������A�����Ă��܂����B����ɑ��ē��{��400�N�ԉݕ��������ŋ������邱�Ƃ��ł����H�L�ȍ��Ȃ̂ł��B���E�̑命���̍��ł͉ݕ��͋�J���Ȃ��Ǝ�ɓ�����Ȃ����ł����B
�@
������������Ή�����قljݕ������v�͑�����̂ŁA���ێ���ȍ~�͏����̋��ܗL���͉����葱���܂����B���ۏ�����86���A20�N��̌���������65���܂ʼn������Ă��܂��B�ܗL�ʂƓ����ɁA�����̎��ʎ��̂��������Ȃ��Ă��܂��B���ۏ�����18���ł���������������13���ɉ������Ă��܂��B
�@
�������e���ȏ��������ŏ��̂����͖��{�̖ڂ������Ă���̂Ŋz�ʉ��l�ŗ��ʂ��܂����A�₪�ĉ��l��������܂��B�����C���t���ł��B���������ۂ���100�N��ɍ��ꂽ�V�ۏ����͋��̊ܗL�ʂ������ɂȂ��Ă���ɂ�������炸�A�ꉞ�ꗼ�Ƃ��ė��ʂ��Ă��܂��̂ŁA�]�ˎ���̓�S�N�Ԃ�ʂ��āA���X�ɓ��{�ɂ�����ݕ��͋M�����̉��l�ɂ�镨����A�������{�̐M�p(����)�ɂ�镨�ւƕω����Ă��������Ƃ��킩��܂��B
�@
�������ݕ��邱�Ƃ��ł����͖̂��{�����ł����B�喼�����ɗ��������Ƃ����ƃY�o���؋��ł��B
�@
�l���p��(�g��O����)�́u�ї��d�A�v�ɂ��ƕĂƋ₪�ʉ�v�Ȃ̂ł�₱�����̂ł����Ăɒ����āA���l�N(1754)�̎�����17���A�Ώo��28���A�����̕��ϓI�ȕđ���Ōv�Z�����10���̕s���ł��B������؋��Ŗ��߂Ă��܂����B���˂̎�����82���ł��̂ō����Ԏ��f�c�o��12���ł��B���̐Ԏ��͋��Z�Ǝ҂���̎؋��Ō����߂���܂����B
�@
�u�㐙��R�v�ɂ��ƕđ�˂̎���4���ɑ��āA�����Ԏ���2�D5�����A��2�D5���̐Ԏ��ł��B������؋��Ō����߂��邵������܂���ł����B�đ�˂�15���ł��̂ł�͂�f�c�o��13���̍����Ԏ��ł��B
�@
�u���Ïd���v�ɂ��Ƃ��̎����̎F���˂͔N�Ԗ�2�����̃y�[�X�Ŏ؋��𑝂₵�Ă��܂��B�˂̋K�͂��炷��Ɣ��ƕđ���܂��ł����A�F���˂͂��̌�����o�c�Ǝ؋��̌J�艄�ׂ̎��s�ɂ��؋���5�{�ɑ��₵�Ă��܂��܂��B�@ |
|
���]�ˎ���̐�4 / �]�ˎ���ɑ��ł͍s��ꂽ���H |
�R�����Łu�M�v�����A�]�ˎ���̍����Č�����A��Ɠ�������̍�i���ɂ��āA(1)���ŁE�؋���A(2)���ō�ɕ����A(1)���ŁE�؋���͈ꎞ�I�ȌГh�ŁA�ˍ����̈����������A�R��͍r�p���A�����͔�剻���A�i���͊g�債�Ĕ_���Ꝅ�E���U�������B����A(2)���ō�́A�����������������A�����ŋ��d�h�̓w�͂ŁA�ˍ������Ē������B�����ŋ��d�Ȑl���Ƃ͒N���H����ł��傤�ˁA�Ō���ł���B�����]���ĕM�҂͔���Ȃ��̂ŁA���Ă��������l���������Ȃ�A�����̎���́A�ǂ̔˂́A���Ƃ������O�ŁA���̌�̔ނ̉^�����A��̓I�ɋ����Ă���������K���ł���B���_���]���A����͑��̃^���S�g�ł���B���������͖`���ɋ������A���������i��������Ȃ��B�������A�����͏��F�����ł���B�l��������鍪���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���������]�ˎ���̐ŋ��́A�_���A������{�S���Ɖ]����A�y�n�����_���݂̂����S���Ă����B����l�␅�ۂݕS���͊W�Ȃ������̂ł���B
�@
���N�v�͗̎�̔C�ӂŕύX�o���邩�H
�@
�]�ˎ���̌o�ϑ̐��́A�_�{��`�E�Ė{�ʐ��ł���B�N�v�́A�č�y�n�ʐςƁA�[�ŕ��S�҂̓y�n�Ɖ����O����Z�肳���B����̎Z���b�́A���n�ɂ��m�肳���̂����A�]�ˎ���A�S�����ꌟ�n�́A���\�����n���Ō�ŁA��͍s���Ă��Ȃ�(�u�n�_�j�ς��������v�����P�v�A��ΐT�O�Y�A1995�A�u�k�Ќ���V��)�B�Ȍ�A�喼�́E�V�̂ŕ����I�ɍs��ꂽ���A���̓s�x�A�Ꝅ�E���i���N�����āA���������������Ȃ��B�܂�A�N�v���͍]�ˎ����ʂ��āA�ς��Ȃ������̂ł���B�N�v���́A�������̔˂̖��ڐ��ɒ�������B�喼�̔C�ӂŐ����ς�邱�Ƃ́A���ˑ̐��̊�b��h�邪�����̂�����A���{���F�߂�킯���Ȃ��B���A���ł���ƁA�˂̖��ڐ���������̂ŁA�˂̌��I���S�������A�ǂ����Ƃ͏������Ȃ��B
�@
�u�M�v�����]���l�ɁA�d�����m������āA�̖��ɑ��ł����v�����Ƃ���ŁA�{�S������A�ˑc�⌠���l�̂��n�t���������ꂽ��A�O�[�̉����o�Ȃ��B�{�S���Ƃ����̂͒m���K�w�ł���A����ȕ��m���w��������B����ł����d����A�m���ɈꝄ�ɂȂ�B���̏ꍇ�A���{���ق��Ă��Ȃ��B�ː��s�s���͂��ɂ��A�˂����������B���ł������o�����Ɛb�E�ƘV�͐ؕ��A�ˎ�͗ǂ��ĉB���B��͘V������㌩�l�������o����āA�˂͖��{�Ǘ��ɂȂ�B���肷��A���Ղ��B������A�����������Ƃ͂��蓾�Ȃ��B
�@
���؋��ŎR��͍r�p�������H
�@
����͍����̖����ϑz�ł���B�܂��������Ⴄ�B�؋�����������R�삪�r�p����̂ł͂Ȃ��B�����Ă����A�R�삪�r�p���A�y�n���n������������B�����h�����߂ɁA�؋����Ď��R�������Ƃ��s�����̂ł���B���̌��ʂ́A�y�n���n���̑���Ƃ��āA�ˎ�E�_���ɕԂ��Ă���B�X�ɁA�������ƂɎ��Ǝ҂��z���o���邩��A�_���̎����͗ǂ��Ȃ�A�n��o�ς͊���������B�ނ���A���R�C�Y�~�����̍s���Ă���A�������Ƃ̍팸�A�X�����c���̕���ꡂ��Ɋ댯�ł���B�����̐���́A�m���ɒn���̉ߑa���������A�s�s�ƒn���̊i�����L����B���ꂪ�R��̍r�p�������A����͓s�s�ւ̓ЊQ�Ƃ��ďP���������Ă���B�X�Ɏ��������A�l�X�ȎЉ�X�N�̔������\�������B�����̎Љ�I�R�X�g�́A���ݍs���Ă���R�X�g�팸���ʂ�ꡂ��ɏ�����̂ɂȂ邾�낤�B��N�A���z�n�k�Ŕ�Q�����V�����암�n���́A���Ƃ��ƑS���L���̒n���ׂ�n�тŁA����܂Ŕ���Ȓn���ׂ����p���������Ă����B����ł����̏�Ԃł���B��H�����s���Ă��Ȃ���A��Q�͂���Ȃ��̂ł͍ς܂Ȃ��������낤���A����Ƃ�}�����Ă����A�S�̂Ƃ��ĕs���艻���i�s���A����������ɐr��Ȕ�Q���y�ڂ����낤�B
�@
���喼���؋����Ĕ_���͕n�R�ɂȂ������H �o�ϊi�����L���������H
�@
����������̖������z�ł���B���喼���؋����d�˂Ă��A�N�v���グ���Ȃ��̂�����A�_�����n��������킯���Ȃ��B���A�Ă̕i����ǂ�y�n���ǂɂ���āA����������n�ʂ́A�]�ˎ����ʂ���2�`3�{�ɂȂ��Ă���B�܂�A�_���K�w���x�T������B�n�R�ɂȂ����͉̂������m(���ʼn]������������)�ł���B����ΎЉ�̊��Ƃ����Ă悢�悤�ȘA���B���Ȃ�ߎS�ȏɒu���ꂽ�炵���B���̂��߁A�ޓ�����̈ېV�v���̌����͂ɂȂ����B�������A���������ޓ����o�ϓI�Ɏx�������̂��A�x�T�������_���K�w�������̂��B����͑喼���؋������Ă��ꂽ�������A�Ƃ��]����B�x�T�������_���Ɏ��{���~�ς���A���ꂪ�ېV�̌����ƂȂ�A�O���Ɏ؋����Ȃ��Ă悩��������A���{�����Ă̐A���n�ɂȂ�Ȃ��čς̂ł���B���̎d�g�݂��炢�͔���ł��傤�B
�@
�]�ˎ���㔼�ɍL���������s�ɁA�u�������Q��v�Ƃ������̂�����B����͈ɐ��Q��ɂ��������������s(�����V�R)�ŁA�S���̔_���E����������ɎQ�������B�܂�A�]�ˎ���㔼�ɂ́A�����̉��������́A�������x���܂Ō��サ�Ă����̂ł���B�X�ɁA�����ɂ͔_�����A���m�g�������Ŕ������Ƃ�����ɍs���Ă����B�ޓ��̑����͕��m�g���ɂȂ�����ŁA�����ɎQ���������A���̔�p�͖w�ǎ��O�ł���B�M�҂̈�����͕̂��Ɍ��ɒO�s�ŁA���Ƃ̑��ɁA���߉q�Ƃ̑㊯���~�Ƃ����̂������āA���������͂��ꂪ�ɒO�ň�ԑ傫���������Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪�A�������āA���ӂ̔_���n��ɍs���Č���ƁA�㊯���~�ȂǕ��̐��ł͂Ȃ��A���h�ȕS������������ׂĂ���̂ł���B��̑S�́A�����Ōo�ϊi�����L�������Ɖ]����̂ł��傤���H
�@
�����́A�喼�͎؋������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������H
�@
�喼���؋����闝�R�̓��A�ő�̂��̂́A�Q�Ό��ł���B�܂��A�]�ˁE�����Ƃ�����d�����E��d�s�����傫�ȕ��S�ł���(�s�K�v�ɑ����Ɛb�c���A�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�)�A�X�ɉ������̚��ʂ����S�ɗւ�������B11�㏫�R�ƐĂ�50���l�̎q�����������A���q�͂ǂ����̑喼�̉łɉ�������B���R�̖��ł���A�喼���f��Ȃ��B���{����́A�����炩�̉��ϗ����x������B��������������Ȃ�ƁA���{�����ɂƂ��Ă����ނɂȂ�Ȃ��B�������A���ƈ���āA�g��ʼnłɂ���킯�ł͂Ȃ��B���t���̏������A���\�l�ƈꏏ�ɂ���Ă��āA����炪�]�ˏ�剜�Ɠ����ґ�����邩��A���ϗ������X������Ƃ���ŁA�喼�ƂƂ��Ă�����Ă����镪�����Ȃ��B�v����ɖ������̍Ώo(�����ƘI���ɉ]���ƁA�Z���u���ƁA���������ق₷��n���a�̖��ʎg���E�E�E����̉������̍��Ɏ��Ă��܂��˂�)���A�����̃N�r����߂Ă����̂ł���B
�@
���喼�͎؋���Ԃ������H
�@
����͐r���^��ł���B�O��ƉƌP�ł́u�喼�݂��͕Ԃ��Ă��Ȃ����̂ƐS����v�Ƃ����ꕶ������炵���B�����̎؋����ݓ|�����������̂ł͂Ȃ��낤���H�����A���ݓ|�����d�Ȃ�ƁA���l������݂��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���V��p������ƍ��邩��A���������͕Ԃ������낤�B
�@
���ǂ����������Č����s�������H
�@
�]�ˎ���̍����Č���ɁA���łƂ����͕̂��������Ƃ��Ȃ��B�悭�s��ꂽ���͎̂��̂悤�Ȃ��̂��B
�@
��1 �Ώo�팸
�@
�剜�̏��팸�B�s�v�����̃��X�g���B�ł̃N�r�͐�Ȃ�����A�v����Ɏ����E���ɂ���B�Q�Ό��̌o��팸�B�����̍팸�B���H����C�H�ւ̕ύX(�{�w�h����ߖ�o����)�B���^�팸�B��������@���g���āA�ˎm�ւ̋��^���팸����B�Ȃɂ�������t���ă��X�g������͓̂�����O�B���l�X
�@
��2 �V�c�J��
�@
���R�E��������(��������)�ɂ��A�V�c���J�����A�Ă̎��n�傳����B���ƂɎ��Ǝ҂��z���ł��邩��A������ɂ��s�����悢�B�a�̎R���L�c��̒����ɁA���e����ǂɂȂ����}���ӏ�������B����͎��R�k���ł͂Ȃ��A����g�@���I�B�ˎ傾�������ɍs�����A�͐���C�̌��ʂł���B����ɂ��A�L�c�여��ł͍^���������Ȃ�A�I�B�˂̍����Č��Ɋ�^�����B�g�@�͂��̌��тɂ��A���㏫�R�̍����ˎ~�߂��B����̌����͋��E���̏��l����̎؋��B
�@
��3 ���Y�i���Y�̐U���E����
�@
�]�ˎ�����㔼�ɂȂ�ƁA�Ăɂ�钼�ڔ[�ł��́A�����ɂ��Ԑڔ[�ł��嗬�ɂȂ�B�̎���N�v�̌����Ȃǂ̎�Ԃ��Ȃ���̂ƁA�Ă̏o���s�o���ɍS��炸�A�Ŏ����m�ۏo����̂ŁA����̕����s���悢�B�_���ɂ́A�Ă̍�t���ɊW�̂Ȃ��A��ېł̓y�n����R����B�����֊����앨�͔̍|���n�܂����B�Ⴆ�A��B�E�M�B�̖��A�R�`�̍g�ԁA�d���̖ȉԁA���g�̗��A�I�B�̐��E�����Ȃǂł���B����ɂ�茻�������āA�[�ł��ς܂��A�Ă�đ���ɂ���������Ǝ�����������B����ɉېł���Δˎ����͂����Ƒ�����B�Ɖ]���킯�ŁA�����������Y�i�̐��Y�{���喼�����サ���̂ł���B�Ȃ��A�ĈȊO�̐��Y���͌�����ېł�����A����ɂ��ˎ������������Ă����ڐ��͕ς��Ȃ��B�˂��L���̂ł���B
�@
��4 ����
�@
���Y�i�̗��ʂɂ͖������Ƃ��^���(�ƊE�g���ۋ�)�Ƃ����A���̊ł����ۂ���邱�Ƃ�����B������ˎ����ɂȂ邪�A�s���߂���ƃ}�C�i�X�ʂ�����B���鎞�A�P�H�˂��P�H�Y��v���i�ɑ���^�����P�p�����B����Ƒ��Ŕ�v���ꂪ�������A���̔�v�����Ǝ҂������āA�P�H�˂Ɲ��߂��Ƃ����������������B����Ȃǂ́A��v�����Ƃւ̉ېł����炵�A�P�H���i�̔���グ�����_���A�X�ɏo�Ă������v���v�����̍�������A���Y�Ƃւ̓�����ژ_���߂��낤�B
�@
��5 ���A
�@
�����Ԏ���U�̂��߂́A��O���v���ƂƂ��Ă̔ˉc���A�ł���B�F���˂��L�������A���ɏo�_�˂����˂��^�킵���B�A���A����͊J���ɂ���ĈӖ����Ȃ��Ȃ����B
�@
���܂Ƃ�
�@
(1)�˂���������Ɋׂ������R�́A�Ŏ��\�����ς��Ȃ��ɂ��S��炸�A�Ώo�����ɑ��₵���B
�@
(2)�����Č��̃|�C���g��1�ɍΏo�팸�ł���A2�ɐV���ȐŎ����̍H�v�ł���B
�@
(3)���łȂǂƂ������Ղȕ��@���̂�喼�́A���Ȃ��Ƃ��]�ˎ���ɂ͂��Ȃ������B�^�ʖڂȑ喼�́A��L�̂悤�ȕ��@����g���č����Č��ɓw�߁A�����͐��������B���Ȃ��Ƃ��V�ۋQ�[�ȗ��̊�@���A�����܂łɂ͏������̂ł���B�������A��ԑʖڂ������̂����얋�{�������B�c��ȉƐb�c�A�剜�̚��ʂ����̂܂܂ɂ������߂ɁA���ɐ�����ǂ�ꂽ�̂ł���B
�@
���x���]���Ă������A�]�ˎ����ʂ��āA���{���喼�����ł͍s���Ă��Ȃ��B���̌��ʁA���{�����Ԃɒ~�ς���A���ꂪ�����ېV��̐��{�����ɓ]�����A�ߑ㉻�ߒ��ŊO������؋������Ȃ��čς̂ł���B
�@�@
�@ |
| ���剜�Ƃ��V���� |
   �@
�@
|
���剜�ƕ���
�@
�ŋ߁A�e���r��f��Ȃǂő剜�͑�l�C�ł��B�]�ˏ�̉��[����̋�Ԃł́A���R�l�̂��������߂����āA��������������Ȑ킢���J��L�����Ă��܂����B
�@
�剜�̃h���}�����Ă���ƁA�K���o�ꂷ��̂��A���V����ł��B������A���Ȃ�d�v�Ȗ����������Ă��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@
�剜�̏����ƌ����ƁA�N���v�������ׂ�ł��傤�H�����ɂ���5�㏫�R�j�g�̕�E�j���@�́A�e���r�ɂ��ǂ��o�ꂵ�܂��B
�@
�G�����������Ƃ����剜�̑�X�L�����_���Ƃ��Ēm���鎖��������܂����B����4�N(1714)�ɋN���������ł��B�剜�̎��͎ҊG�����ł̑��㎛�ɎQ�w�����A��ɉ̕�������āA�l�C���Ґ����V�ܘY�Ɩ��ʂ����ƌ����̂ł��B���̎����̔w�i�ɂ́A6�㏫�R�Ɛ�̐����V�p�@�h�ƁA�����Ŏ���7�㏫�R�ƌp�̕�ł��錎���@�h(�G���͌����@�h�̒��S�l��)�̑������������ƌ����܂����A2�l�Ƃ������@�Ƃ������O�ł����B
�@
���R����������ƁA����(��䏊)�⑤�������͗������ĕ���ɓ���܂��B�j���@��3�㏫�R�ƌ��̑����ł����A�ƌ��������������߁A�j���@�Ɩ����܂����B�V�p�@�ƌ����@��6�㏫�R�Ɛ邪�����������߁A�V�p�@�A�����@�Ɩ�������킯�ł��B�����ɌW���̂͂��V����ł����A�@�������^����̂���ڂł����B
�@
�����E�����Ɍ��炸�A�剜�ɋ߂鉜���������̓��X�̐����ɂ́A�������[���W����Ă��܂����B�剜�ƌ����ƁA�Ȃ��Ȃ��O�ɂ͏o���Ȃ��C���[�W�������̂ł����A���ۂ͉����Ɨ��R��t���āA�����Q������Ă��܂����B�����Q��ƂȂ�ƁA��̊O�ɏo�₷���Ȃ����悤�ł��B
�@
���R���a�C�ɂȂ�ƁA���̕����̂��߁B�����⑤�������D����A���̈��Y�F��̂��߁B���邢�́A���R�̕��^���v�A�V���ו��ȂǁA�l�X�ȗ��R��t���āA�����������͂����ɂ���ė��܂����B
�@
���V����̑����A�������������Q�w����̂�傢�Ɋ��}���܂����B�Q�w���Ă��炤�ƁA���낢��ȃ����b�g���������̂ł��B����́A�剜�Ƃ��V����̐[���W�����낢��݂Ă����܂��B�@ |
���剜�̒��̂��V����
�@
�剜�́A�]�ˏ�̖{�ی�a�̒��ł���ԉ��ɂ���܂����B�{�ی�a�͌��݁A�c�����䉑�̈ꕔ�ƂȂ��Ă��܂����A��a�̌���1��1300�قǂ���܂��B����ȋ�Ԃł��B
�@
��a��3�̋�Ԃ���\������Ă��܂����B���{�������l�߂Đ���������\���A���R�����퐶���𑗂钆���A�����ď��R�̐Q���ł���剜��3�ł��B���̂����剜�͖�6300������A��a�̉ߔ����߂Ă���v�Z�ɂȂ�܂��B
�@
���̌��ɓV��t������܂������A����3�N(1657)�̖���̑�ŏĂ������Ă��܂�����͍Č�����Ȃ��܂܂ł����B�ł�����A�Ȍ�]�ˏ�ɂ͓V��t�͑��݂��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���㌀�ł́A�]�ˏ�̃V�[���ł��̂悤�ɓV��t���f��܂����A���ۂɓV��t�����т������Ă����̂́A�]�ˎ���ŏ���50�N�قǂɉ߂��܂���ł����B
�@
�����ɂ͏��R�̐g�̎���̐��b�����鑤�߂������l�߂Ă��܂������A�剜�ɓ���開�{����(�������j���ł���)�͌�������������Ă��܂����B�e���r�ɂ��o�ꂷ�鑤�p�l���炢�ł��B
�@
�����A�剜�̌o���������l��x���̖�l���l�߂Ă����Ԃ�����܂����B������A��L�~(���Ђ낵��)�ƌĂт܂��B���̋�Ԃ����͗�O�ł����B
�@
���ɁA�剜�ɂ�3000�l���̏������Z��ł����Ə�����邱�Ƃ��ǂ�����܂����A����Ȃɑ����͂���܂���B��ԑ������ŁA1000�l�قǂł����B
�@
�������Ƃ́A����Ζ��{�̏��������̂悤�ȑ��݂ł����B���R�̐Q����Ɛ肵�Ă���킯�ł�����A���̈А��͂����ւ�Ȃ��̂ł����B�g�b�v�N���X�̉������ƂȂ�ƁA���{�̊t���l���܂ł����E����͂������Ă��܂��B���g�o���������T�����C�����́A�����悤�ɘd�G���������ɑ����āA�O��̃|�X�g����ɓ����̂ł����B
�@
�������̃g�b�v�́A��N��ł����B���̈А��͘V���܂茻�݂̑�b�Ɠ����Ƃ��ꂽ�قǂł����B�����V�ܘY�Ɩ��ʂ����Ɠ`������G�����A����ɓ�����܂��B
�@
�剜�̃h���}���e���r�Ō��Ă���ƁA�K���o�ꂵ�Ă���̂��A�䒆�d�ł��B�䒆�d�Ƃ́A���R�̐g�̉��̐��b�����鏗�����w���܂����A���R�t�̌䒆�d����A���R�̂��肪�t���đ����ƂȂ�܂����B�䒆�d�͍��������Ȃ̂ł����A�����胉���N�������鉜�����ł����Ă��A���R�̖ڂɗ��܂��āA���肪�t���ƌ䒆�d�ɏ��i����V�X�e���ɂȂ��Ă��܂����B
�@
���R�̂��������߂���o�g�����A�剜�h���}�̃e�[�}�Ƃ��Ă悭���グ���܂��̂ŁA���R�ƁA�䒆�d�Ƃ������t�͎��Ɏc���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B
�@
���āA�������̂Ȃ��ɁA�u��V��v�ƌĂꂽ���������܂����B���O�̂Ƃ���A�䔯�p�ł����B���̌�V����剜�̊����Ȃ̂ł����A�剜�Ɍ��炸�A�]�ˏ���ɂ͒䔯�p�̊����͑吨�����̂ł��B�@ |
�����V����͐��E�����
�@
���܂�m���Ă��Ȃ����Ƃł����A�]�ˏ�ɂ́A��V�傪��������l�߂Ă��܂����B�剜�ɂ���V��͂��܂������A���ƌ����Ă����{��l���l�߂�\���A����Ō����Ǝ��@�E�i�c���ł����A�����ɂ͒䔯�p�Ŗ@����g�ɂ܂Ƃ�����V�傪�Z�������������Ă��܂����B�a���̃V�[�������Ă���ƁA���V���悭�s�������Ă��܂��B
�@
�����������V����͉��̂��߂ɁA�]�ˏ钆�ɂ����̂ł��傤�H�]�ˏ�̗�������Ƃ��Ă̂��߂����Ă����̂ł��B
�@
���R�̈ߑ����Ǘ�������A���R�����̂���������W���߂邨�V���������A�钆�̎G�p�����Ȃ����V��������܂����B��a�ɂ����邨�a�l�����̐��b��������A�ē��W���߂邨�V��������܂��B�̕���ɂ��o�ꂷ��͓��R�@�r�́A�䐔�V��B�䒃���o���i���W�̌�V��ł����B���V����́A�l���͗ǂ�������܂��A���̐��͌y���S�l�͉z�����ł��傤�B
�@
��V��́A������Ƃ������m�ł����B�����A���R�l�Ɏg����T�����C�Ƃ��Ă͐g���͒Ⴉ�����̂ł����A�A�̎��͎҂ƂȂ邨�V��������܂����B
�@
���a�l(�喼)�����͍]�ˏ�̌�a�ɓ�������A��l�ōs�����Ȃ���Ȃ�܂���B���ƌ����Ă���a�͍L�����������������̂ŁA�ē��W�̌�V��ɐ擱���Ă����Ȃ��ƁA���H�ɓ��荞��ł��܂����悤�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ł�����A���炩���߁A����̌�V��Ɉē��𗊂�ł����Ȃ��ƁA��ςȂ��ƂɂȂ�܂��B�����s�n�������ł����Ă��܂��ƁA��Ƃɏ����t���̂ł��B���̂��߁A���a�l�Ƃ������A���̉Ɨ����爥�A�Ƃ������̋��i���͂����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
�܂��A�ނ�͌�a���E��Ȃ̂ŁA�钆�̎���ɂ͎��R�Əڂ����Ȃ��Ă��܂��܂��B���a�l�����́A���E����ʂ̔ނ�ƍ��ӂɂȂ邱�ƂŁA�V�[�N���b�g�Ȑ��E��������ɓ���邱�Ƃ��ł��܂����B���̌��Ԃ�Ƃ��ċ��i��͂��Ă��܂��B���̎���ɂ��Ă��A���𐧂���҂����҂ƂȂ�܂��B�������āA�A�̎��͎҂ƂȂ�A�ґ�Ȑ��������邱�Ƃ��ł����̂ł��B
�@
���āA�剜�̕��̌�V��ł����A�N���50�ˑO�ゾ���������ł��B���R�̎G�p�|���߂܂����B���̎p������ƁA���͒䔯���Ă��āA�H�D�т𒅗p���Ă��܂����B
�@
���Ƃ��ٗl�Ȏp�ł����A���̌�V��̂݁A�����Ƃ������R�̑��߂��l�߂�ꏊ�ɓ��邱�Ƃ��ł��܂����B�剜�͒j�q���ƌ����܂����A�t�Ɍ����ƁA�剜�̏��������͑剜�ȊO�̏ꏊ�ɗ������邱�Ƃ͋�����܂���ł����B�剜�ȊO�̏ꏊ�܂蒆���E�\���͏��l���������̂ł����A�B��A�H�D�юp�̌�V��͓���܂����B���V����̎p����������ł͂Ȃ��ł��傤���B�@ |
������҂�������V����
�@
�剜�ɓ����҂͌����Ă��܂������A��O������܂����B����́A����҂���ł��B�]�ˏ�Ζ��̂���҂�����T�����C�ł������A��҂ɂ��K��������܂����B
�@
�ォ��A�T��(�Ă�₭�̂���)�A����t�A�\��Ԉ�t�Ƒ����܂��B�T�͈�t�̃g�b�v�ŁA�喼���݂̊��ʂ�^�����܂����B�@��ɏ������܂��B
�@
����t�Ƃ����̂́A���R�̂������������A�����ł����䏊�⑤���A�����������̐f�Â������Ȃ�����҂���ł��B�u�����v�ƌĂ�܂����B����t�ɔC�������ƁA�@��ɏ������܂����B
�@
�@���@��ɏ�������Ƃ������Ƃ́A�����ւ_�Ȃ��Ƃł����B�@���@��Ƃ͑m���̈ʂ̂��Ƃł����A���̎���ɂ͑m�������łȂ��A��t�A�����ĕ��t��G�t�ɂ��^��������̂ɂȂ��Ă��܂����B
�@
���X�͑m���ɗ^����ꂽ�ʂł�����A�@���@��ɂȂ�ƁA�����ۂ߂Ȃ���Ȃ�܂���B�ł�����A�剜�ɓ��邨��҂���́A�䔯�p�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�{���̂��V����́A����������̌����M�����Ă����̂ł����A�������ɑ剜�̓����ɂ͓���Ȃ������悤�ł��B
�@
���̂ق��A���N�Ȃ�Α剜�ɓ��邱�Ƃ��ł��܂����B���N�ƌ����Ă��A��˂܂ł̒j�̎q�����ł��B
�@
������ɂ��Ă��A�剜�͂���������O�������A�j�q���̋�Ԃł����B���̂��߁A�{���̂��V���������ƃR���^�N�g�����ɂ́A�ޏ������ɑ剜(�]�ˏ�)�̊O�ɏo�Ă��炤�K�v������܂����B�����Q������Ă��炤���ƂŁA���̐M�C�����������̂ł��B
�@
�ޏ���������O�ɏo�鎞�̖�͌��܂��Ă��܂����B�����ƌ����܂��B���̖�͕s���Ƃ��Ă�܂����B���҂�ߐl����̊O�ɏo�����Ɏg�p���ꂽ��ł����B�Ⴆ�A�ԕ�Q�m�ŗL���Ȑ��������͐n����A���̖傩���̊O�ɏo����܂��B
�@
���̖���o�āA�����������͂����Ɍ��������킯�ł����A���ł́A�ޏ������̂����Q��̗l�q�����Ă����܂��傤�B�@ |
�����R�l�̕��
�@
���R�l����������ƁA�ǂ̂����ɑ�����̂ł��傤���B
�@
����Ƃ̏@�|�͏�y�@�ł��B�ƍN�͓����R�ɑ����܂������A2�㏫�R�G���͎ł̑��㎛�ɑ����܂����B���㎛�����R�̕�E�h�ߎ��Ɏw�肳�ꂽ�킯�ł��B���̏��R�l�͑��㎛�ő��V������s���A��_�����������͂��ł����B
�@
�Ƃ��낪�A3�㏫�R�ƌ��͓V��@�̑m���V�C�������M�����Ă��܂����B�V�C�̂��߂ɏ��ɑ������������A���i���ł����A���̃��f���͔�b�R����ł����B
�@
�`����t�Ő��͋��̋S��(�k���̕��p)�ɔ�b�R�����n�����A���s����삷�������S�킹���킯�ł����A�V�C�͍]�ˏ�̋S��ɂ�������̂��R�ɁA����ɂȂ���Ċ��i���̌������肢�A������܂����B�R���͓��̔�b�R�Ƃ������ƂŁA���b�R�B�����́A�n�����̌��������i�ł����̂ŁA���i���ƂȂ�܂����B����n�����̌���������ł��������ƂɂȂ�������̂ł��B
�@
���̂��߁A���R�̑��V����ł��鑝�㎛�ł����Ȃ���͂��ł������A�ƌ��͊��i�����w�����A���̌�A�����ɑ����܂����B�����R�����łȂ��A���i���ɂ��ƌ��̗�_����������Ă��܂��B�����āA�ƌ��̑��q�ł���4�㏫�R�ƍj�A5�㏫�R�j�g���A���Ɠ��������i���ő��V���s���A��_����������܂����B
�@
����Ɋ�@�����������̂��A���㎛�ł��B���{�ɋ��͂ɓ������������ʁA6�㏫�R�Ɛ�͑��㎛�ő��V������s���A�����܂����B7�㏫�R�ƌp�����㎛�ɑ����܂������A���x�͊��i���������Ԃ����͂���A�\���V���R��8��g�@�͊��i���ɑ����܂����B�g�@���g���A���i���ɑ����邱�Ƃ�]�悤�ł��B���̌�́A�����̃����c�𗧂Ă�`�Ō��݂ɑ����܂����B9��Əd�͑��㎛�A10��Ǝ��͊��i���ɗ�_����������܂��B
�@
�������A�K���������Ԃ����ꂽ�킯�ł͂���܂���B11��ƐĂ͏��Ԃ��猾���ƁA���㎛�̂͂��ł������A�W�������Ă݂�ƁA���i���ł����B���i�����剜�ɋ��͂ɓ������������ʂ̂悤�ł��B12��ƌc�͑��㎛�ɑ����܂������A���̗��ɂ͊��i���Ƃ̌������������������̂ł��傤�B�@ |
����_�̒D������
�@
���i���Ƒ��㎛�́A���R�̑��V�������̏��Ŏ���s���A��_����������邱�Ƃ������]��ł��܂����B���R���h�ƂƂȂ��ė�_����������邩�ǂ����ŁA���̌o�c���傫�����E����Ă��܂��̂ł��B���R���h�ƂƂȂ�ƁA�����ɓ����Ă��邨���̃P�^���Ⴄ�킯�ł��B
�@
���R�̑��V�Ƃ́A���{�̈АM�����������ƓI�ȍs���ł�����A���̔�p�͔���Ȃ��̂ł����B�������A���V�̔�p�����łȂ��A��_�̌���������Ɨ\�Z����x�o����܂����B��������������ƍ�������x�o����܂����B
�@
���������i�����͖̂��{�����ł���܂���B�O�S����Ə̂��ꂽ���喼���A���������i���Ȃ�������܂���ł����B���{�̕�������z���w�肳��Ă��āA60���Έȏ�̑喼�͔���30���A25���Έȏ�60���Ζ����̑喼�͔���20���Ƃ����悤�ȋK��ł����B
�@
���܂�o�ϗ͂ɉ����āA������͌��߂��Ă��܂����B����͌���z�ł���A�����͂��ꂾ���̏o��ł͍ς܂Ȃ������ł��傤�B���ꂾ���A�����ɂ͂�����������킯�ŁA���V�̎������ł�����Ȃ����������Ă���l�q��������܂��B
�@
����ꂽ���R�̏ˌ������ɂ́A����̏��R���Q�w���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B��������ƓI�s���ł����A���̎��Ɍw�ł�̂͏��R�����ł͂���܂���B�]�˂ɂ���喼�͂��ׂāA���̓��͌w�łȂ�������܂���ł����B���Ƃւ̋`���Ȃ̂ł��B
�@
���̍ۂɂ́A���R�̂��ƂȂ���A�����̋��i���݂܂��B���̂悤�ɁA���R�̗�_�����������ƁA����Ȃ���������������킯�ł�����A���i����㎛�����D��ɑ���͓̂��R�̂��Ƃł��傤�B
�@
�ǂ���̂����ŏ��R�̑��V�������Ȃ��A��_���������邩�����߂�̂͘V���̉�c�ł��B�t�c�̂悤�Ȃ��̂ł����A�剜�̈ӌ��͖����ł��܂���ł����B�剜�͏��R�̉ƒ�ł���A�Ƒ��̈ӌ��͖����ł��Ȃ��Ƃ����킯�ł��B
�@
�剜�Ƃ́A���R�����܂��Ă��A�����đ����������ꏊ�ł��B���V�܂ŁA�S�[�͑剜�Ɉ��u����Ă��܂��B���̂��Ƃ�����A�剜�̈ӌ�����_�I��ɉe���͂������Ă������Ƃ͖��炩�ł��傤�B���������A���i����㎛�͑剜�H��ɑ���̂ł��B
�@
����ɂ͕��i����剜�̂��@��������Ă����K�v������܂����B�������āA�剜�Ɗ��i���E���㎛�̊W�͂����ւ�[�����̂ƂȂ��Ă����܂��B��������́A����̈��A�Ȃǂ̌`����邱�Ƃŗl�X�ȕi���������܂��B�����āA�������������Q�w�����܂�ɂ́A�S�s�����̂����ĂȂ������邱�ƂɂȂ�킯�ł��B�@ |
����̑傫�ȃ����b�g
�@
���R�̕�ł��銰�i���E���㎛�́A�]�˂̂����̒��ł͕ʊi�ł����B��ł�����A�ق��Ă��Ă��A�剜�����㏫�R�̕�����Q�̎g�҂�����ė���킯�ł����A����ȊO�ɂ��A���R���䏊���a�C�Ɋ|���������Ȃǂ́A���̕����̋F�����˗����邽�߁A���������o�����Ă��܂��B��ł��邾���łȂ��A���R�̋F�����ł�����܂������A���̍ۂɂ́A���R�Ȃ����Ԃ�ł���ė���킯�ł͂���܂���B
�@
���̂ق��A��E�F�����ł��邱�Ƃ̃����b�g�͉��ł��傤�B�Ⴆ�A�����̏C�������鎞�ɁA���{����C����x������Ă��܂��B���̗��R�͕�A�܂菫�R�Ƃ̗R���������Ă��邩��ɑ��Ȃ�܂���B���������A��_������킯�ł�����A���̈ێ��E�Ǘ���͖��{�������I�Ɏx������Ă��܂��B�C���͂������ł��B
�@
��ł��邪�䂦�ɁA���i���E���㎛�͓��ʑҋ����Ă���A������ی삳��Ă����̂ł����A����ɊÂĂ����̂ł͂���܂���B���i���牜�����̊��S���߂�悤�A���X�c�Ɠw�͂��d�˂Ă��܂����B���������ςݏd�˂��A�����ƌ������̏C����Ȃǂ̋��z�ɁA�����ɒ��˕Ԃ��Ă��܂��B���㏫�R�������������̗�_�������Ɍ�������邩�ǂ����̑傫�ȗv���ɂ��Ȃ�܂��B
�@
�����̊ē����͎��Е�s�ł��B�C������͂��߁A�_�Е��t�ɑ���⏕���z�����肷�銯���ł����A���i���E���㎛�Ɍ��炸�A�������C����̎x���Ȃǂ����Е�s�Ɋ肤���ł́A�剜�ւ̍������s���Ă����Ȃ��Ă��܂��B
�@
�剜�Ƃ����߂̈ꐺ�ŁA�ʂ肻���ɂ��Ȃ��Č����ʂ��Ă��܂����Ƃ�����܂������A���̋��z�̏�ς݂��\�ł����B������������͂�������܂��B�剜�͊t���l���܂ō��E����قǂ̐����͂������Ă��܂�������A���Е�s�����̈��͂��Ēʂ��Ă��܂��̂ł��B
�@
���ɏ��R�̕�ł��銰�i���E���㎛�Ɍ����Ȃ̂ł����A�����̌o�c��Ղ́A�����̉ƌv�͑剜(���{)�������Ă����Ƃ�������̂ł��B�@ |
���剜�̌�����
�@
���i���E���㎛�͑剜�̃o�b�N�A�b�v���邱�ƂŁA�o�c��Ղ��ێ��������Ă����܂����B�剜(���R�l)�Ȃ����āA���i���E���㎛�Ȃ��ƌ����Ă��A�����Č����߂��ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@
�����Ƃ���ɑ����āA�]�ˈȗ��̓��Ђ͂��Ȃ莸���܂������A����ł������̌������́A�����̏��R�ƕ�Ƃ��Ă̗̈e�����ɓ`���Ă���܂��B���̌��z��E�ێ���E�C�z��̂��ׂĂ����Ɨ\�Z�Řd��ꂽ�̂ł͂���܂��A���Ȃ�̊������߂Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B����ɁA���R�̕�̏C�z�ƂȂ�A���喼���X���[���邱�Ƃ͂ł��܂���B���R�A�����̋��i�͊�i����ł��傤�B���ꂪ���R�ւ̒����S�̏ɂ��Ȃ�̂ł��B
�@
���R�ƗR���������Ƃ̋��݂�������Ȃ���������Ă���Ƃ����킯�ł����A�ƂȂ�ƁA���R�Ȃ���A���̂��������R�Ƃ̌��ѕt�����͂���܂��B���R���Q�w���Ă����A���R�̑㗝�Ƃ��ĒN�����Q�w���Ă���邾���ł��A���邢�́A�q�̕i������Ƃ������������ł��A�����̊i�����܂�̂ł��B
�@
�����Ɍ��炸�A���̎���͕��m�ɂ��Ă����l�ɂ��Ă��A���R�Ƃ̂Ȃ���������ƂŁA�����̃X�e�[�^�X�����߂悤�Ƃ��܂��B���쏫�R�Ƃ̏ے��ł��鈨�̖䏊�́A�V����Ƃ̍ŋ��u�����h�ɑ��Ȃ�܂���ł����B���l�Ȃǂ́A���R�ƌ�p�B�ɂȂ邱�ƂŐM�p�𑝂��A�o�c���g�傳���܂����B����u�����h�ɖ������āA�r�W�l�X��W�J�����̂ł��B
�@
�����̏ꍇ�ł݂�ƁA����͌��Ǖ�[���̊z�ɒ��˕Ԃ��Ă���̂ł��傤�B���R���Q�w���Ď��i���A�b�v����A���܂ł̊z�ł͍ς܂Ȃ��Ȃ�ł��傤���A�����Ƃ��Ă͎����̓A�b�v�̐�D�̃`�����X�ł�����܂����B
�@
���R���Q�w�����Ƃ����]���ɂ��A�V���ȐM�҂��l�����邱�Ƃ��ł��܂��B���i�̕�[�҂̐����A���̊z���}�㏸���Ă����Ƃ����킯�ł��B��ʂ̎Q�w�q��������̂͂������ł��B���R�Ƃ̗R���������̗R���ɉ���邱�ƂŁA�����̃u�����h���l���㏸���A�o�c��Ղ����������Ƃ����V�X�e���ɂȂ��Ă��܂����B
�@
�������A���C�o���͑����킯�ł����A�����ȒP�ɏ��R�▋�{�̗L�͎҂Ɛړ_�������Ƃ͂ł��܂���B�����Œ��ڂ��ꂽ�̂��A�剜�Ȃ̂ł��B�����̋@��𑨂��ĉ������̊��S�����߂A��������剜�ւ̑������肪�ł��܂��B�剜�ւ̑������肪�ł���A���R�Ƃ̋������i�i�ɋ߂��Ȃ�܂��B���̌������ɂ��A�ē���(���Е�s)�ւ̍H����L���ł��B�剜�Ƃ̐l�������邱�Ǝ��̂��A���Е�s�Ɍ��炸�A���{�L�͎҂ւ̖����̈��͂ƂȂ�킯�ł��B
�@
���̂��߁A�����ɂ��đ剜�Ƃ̐l������邩�ɁA�ǂ̂������m�b���i�邱�ƂɂȂ�܂��B�����ƌ������A�剜����̌��������s�\���\�ɂ�������͐��m�ꂸ����܂��B�������āA�����̉c�Ɛ헪��A�剜��͌������Ȃ����̂ɂȂ��Ă����܂��B�@ |
���j���@���܂��܂̂���
�@
�����ɂ́A�剜�Ƃ̗R���Ō������ꂽ��������������܂��B
�@
����ƍN�̐���E����̕��́A�@����`�ʉ@�ƌ����܂��B����̕��́A�剜�Ƃ͒��ڊW������܂��A���̕��������������揬�ΐ�ɂ���܂��B�����́A�@������`�ʉ@�Ɩ��t�����܂����B�`�ʉ@�ɂ́A���̗L���Ȑ�P�A��ɂ�����ƌ��̌�䏊(��i�F�q)�̂��������A���{��������ی���Ă��܂����B
�@
�剜��n��グ���ƌ��̓���t���ǂ́A�@����ُˉ@�ƌ����܂����B���̂��߁A�t���ǂ��J��ƂȂ��đn�����������̖��O�ُ͗ˉ@�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�����V�_�̋߂��ɂ���܂����A���̑O�𑖂�t���ʂ�́A���̏t���ǂɂ��Ȃ�ŕt�����܂����B
�@
�剜�Ƃ̂Ȃ���ɂ��n������A���{��������ی삳�ꂽ�����͑��ɂ�����܂��B�Ȃ��ł��A�썑���͂��̃V���{���̂悤�Ȃ����ł����B
�@
���R�ɂ��A�썑���͓`�ʉ@�E�ُˉ@�Ɠ������A�����s������ɂ���܂��B�����̒n���S�̉w�̂Ȃ��ŁA�����̖��O���w���ƂȂ��Ă���̂́A�썑�������ł��傤�B�����~���A�V���~���Ƃ����w��������܂����A���~�����̂܂܂ł͂���܂���̂ŁA�썑�����B��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@
�썑���͐^���@�L�R�h�̂����ł����A�J�R�͗����Ƃ������V����ł��B���X�́A�Q�n���̌썑���Ƃ��������̏Z�E�ł����B����3�N(1646)�ɁA���R�ƌ��̑�������������(��̌j���@)�͍j�g���Y�݂܂����A�����̋F���ɂ��A�j�̎q�����������ƌ����Ă��܂��B���̂��߁A����(�ƌ��Ɏ��ʂ�����A�j���@�Ɩ����܂�)�͗����ɐ[���A�˂��Ă��܂������A����8�N(1680)�ɁA�j�g��5�㏫�R�ƂȂ�܂��B
�@
�{���A�j�g�͏��R�ɂȂ�闧��ɂ͂���܂���ł����B�Ƃ��낪�A4�㏫�R�ƍj�Ɏq�����Ȃ��A�ƍj����������O�ɁA�j�g�̌Z�E�j�d(6�㏫�R�Ɛ�̕�)�����łɎ������Ă������߁A�͂��炸�����R�ƂȂ�܂����B
�@
�j�g�����R�ƂȂ�ƁA�j���@�͗����̂��߂ɖ��{�����A���݂̌썑���̒n��p�ӂ��A�������J�R�Ƃ��邨���E�썑����n�����܂����B�j���@�͍j�g�ƈꏏ�ɁA���x�ƂȂ��Q�w���Ă��܂��B���Ɨ\�Z�ɂ���ċ����̓��Ђ����������ȂǁA�j���@�ƍj�g�̋��͂̃o�b�N�A�b�v���āA�썑���͋��剻���Ă����܂��B�썑��3���̉����́A���ɑ�m���ɂ܂ŏ��܂��B
�@
�剜�̍ő���͎Ҍj���@�̐M������������āA���{�̃o�b�N�A�b�v���邱�Ƃ��A�ǂ�Ȃɑ傫�����������A�썑���̐��藧���͋����Ă����̂ł��B�܂������A�썑���͑剜�����o���������Ȃ̂ł����B�@ |
���������̖��O���n����
�@
�썑���ɎQ�w�����͍̂j�g��j���@�����ł͂���܂���B�剜����A��������̉��������Q�w���Ă��܂��B�썑�����剜�Ƃ̐l��������ɋ��߂Ă����͎̂��R�̐���s���ł��B���R�Ƃ��̕ꂪ�����A�˂��Ă��������ł�����A���喼���Q�w���Ă��܂��B�]�˂��q���A�e���̏��R�l���Q�w�����Ƃ������Ƃ��A�Q�w�������C�����������オ���Ă������Ƃł��傤�B
�@
�������āA�j�g�̎��ォ��A�썑���͎Q�w�q�ő傢�ɓ��키���ƂɂȂ�܂����B�ƂȂ�ƁA��O�ɎQ�w�q��ɂ������X���������Ԃ̂́A�قƂ�ǖ@���̂悤�Ȃ��̂ł��B�썑����O�́A���y�X�Ƃ��đ傫�����W�𐋂��܂��B�剜�͔���Ȍo�ό��ʂ������炵���̂ł����B
�@
���݁A�썑�����ӂ͕����批�H�ƌ����܂����A���H�Ƃ����X�̋N�������ǂ��čs���ƁA�剜�ɂ��ǂ蒅���܂��B���H�Ƃ��������̗R���ɂ͏�������܂����A�剜�ɂ䂩�肪����Ƃ�����������̂ł��B
�@
�썑����O�̒n���́A���l���̉������ɗ^����ꂽ�ƌ����܂��B�n��ł���ޏ������́A���̒n����݂����ƂŒn������ɓ���Ă��܂����B�̂悤�Ȃ��̂ł����A���̈�l�̖��O�����H�ƌ����܂����B���̂��߁A��O�������H���ƌĂ��悤�ɂȂ����ƌ����̂ł��B
�@
���H���q�̂����n���ɂ͎��X�ƒ��������݂���A�Q�w�ґ���̏��������悤�Ƃ����҂������������Ă����܂��B�썑���̓��킢�ɔ�Ⴕ�āA�����������āA�썑����O(���H��)�͊��y�X�Ɖ����Ă����̂ł��B
�@
�썑����O���̒n�傪�������Ƃ���A�剜�������������̖�O�̏������炠�����Ă�����v���A�Ăё剜�ɗ��ꍞ��ł������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�썑���ւ̎Q�w�҂������A���̖�O�����키�قǁA�������̎������������Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B
�@
���i����㎛�����łȂ��A�剜�Ȃ����Č��݂̌썑��������܂���ł����B����Ȃ��������Ė�O����a���������剜�̗͂͐��ł����B���R�l����돂�ɂ����͂ł�����܂������A���̎����́A�]�˂̕����E�ɑ傫�ȏՌ���^�������Ƃł��傤�B�剜�̗͂�ڂ̓�����ɂ��������͌썑���ɑ����Ƃ���ɁA�剜�Ƃ̐ړ_�����Ƃ����Ƃ��ƒm�b���i��̂ł��B��������́A�������̊��S���������ƁA�����v�̂��邨���₨�D�A�������i�Ȃǂ��A���낢��ȃ��[�g��ʂ��đ剜�ɑ����Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł����B�@ |
�����u�����h�̊�i����
�@
�����Ƃ��ẮA�剜��ʂ��ď��R�����A�Q�w���Ă��炤�̂��x�X�g�ł����B�������A���R��1�l�ł�����A���̂Â���Q�w���邨���͌����Ă��܂��܂��B�������s��ł�����A���R���߂��鑈�D��͌����������悤�ł��B
�@
��Q�Ƃ������@������܂����B���R�̑㗝�Ƃ��ĎQ�w���邱�Ƃł����A���R�̌�䏊�̑㗝�Ƃ��ĎQ�w������@������܂����B���R�̑�Q�͘V���Ȃǂ̊t���N���X���Ƃ߂܂������A��䏊�̑�Q�͑剜�̖�ڂł����A�剜�̔��f�����łł��܂����B��䏊�͏��R�̐����ł����A�����̑㗝�Ƃ��Ă̎Q�w���\�ł����A���R�̖��̑㗝�Ƃ��ĉ��������Q�w���ė���Ƃ����`������܂����B
�@
�������A�����͌����Ă��Q�w���Ă��炢���������̐��͑����킯�ł�����A�������s��ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B�����ŁA�����̑����͏��R�̏ے��ł��鈨�̖䏊���������i�̊�i�����߂܂����B���R���̐l�A�Ƒ����Q�w���Ă��炤�̂�����̂ŁA���̕��g�ł��鈨�̖䏊����ɓ���悤�Ƃ����킯�ł��B���R����A�˂��Ă���ؖ����̌�t���肢�o���ƌ�����ł��傤�B
�@
���̖䏊����̕i�Ƃ��ẮA������J���̎��ɗp���開�A���邢�͌˒��A�����A�A�U���A�{���ɒ��p������ߕ��Ȃǂ�����܂��B�����̑��́A�����̕i���ǂ̂悤�Ɋ��p�����̂ł��傤���B
�@
�M�d�i�Ƃ��āA�l�Ɍ����Ȃ������̂ł͂���܂���B�ނ���A���̋t�ł��B
�@
���̖䏊����̕i��q�̂���̂́A�{���ɑ�ςȂ��Ƃ������悤�ł��B�����̂����ɂ́A���̖䏊���������i�����ݐ������c����Ă��܂��B�����̃u�����h�i�́A�����̉c�Ɠw�͂̎����ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@
�ł�����A��ɕۊǂ��ĊO�ɏo���Ȃ��܂܂ł́A��J���Ď�ɓ��ꂽ���R�̌��̎�������ł��B�������������͉�����A���v���グ��K�v������܂��B���̂��߁A������J���Ƃ������C�x���g���ɁA�����̕i��ϋɓI�Ɍ��J�W�����A���R�Ƃ̗R�����L���A�s�[�������̂ł��B�����̃��f�B�A�헪�̈�ł��B
�@
���Ԃ́A���R�l�{�l����̊�i�ł͂Ȃ��A�剜�����i���ꂽ���̂ł����B���R�̐����E�����A���邢�͖��ɂ���A���R�̉Ƒ��Ȃ̂ł�����A���̖䏊����i����i���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��B
�@
�ł����A���Ԃ͂ǂ�����A��i�Ƃ͐M�̏ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B���̖䏊����̕i���W������Ă���A���̂��������R����[���A�˂��Ă���Ƃ����C���[�W���A����҂╷���҂ɃC���v�b�g�����邱�Ƃ��ł��܂��B���R�ƌ�p�B�Ƃ����킯�ł͂���܂��A�u�����h���l��������܂����A�����ɂ��ĎQ�w�q���W�߂邱�Ƃ��ł��܂����B���ʉ��̃c�[���Ƃ��Ĉ��̖䏊���t���Ɋ��p����C���[�W�헪��W�J���A�o�c��Ղ��������Ă������̂ł��B�@ |
���S���ɍL���邨�����
�@
�����ɂƂ��āA�剜�Ƃ̊W�͂����ւ�厖�ł����B�剜��́A�o�c�헪�ɂ�������Ƒg�ݍ��܂�Ă��āA���������Q�w���Ă���A�����������Ă̎����s������̐ڑ҂ƂȂ�܂��B
�@
�剜����̎Q�w�ƌ����Ă��A���R�̐����E�����E��(�P�N)���g���Q�w���邱�Ƃ͂��܂肠��܂���B�d���鉜�������㗝�Ƃ��Ă���ė���̂ł��B���̉������ɂƂ��ẮA��̊O�ɏo����M�d�ȃ`�����X�ł����B
�@
���R�̐����E��������̊�i�ƌ����Ă��A���������l�ɒ��ڃA�^�b�N�������ʂł͂���܂���B�ޏ������ɂ́A��������̉���������芪���Ă��܂������A���̂����N����l�Ƃł��ړ_�������A�M�C�邱�Ƃ��ł���A�����Ƃ��Ă͑听���ł��B���̉������𑋌��ɁA��l�ł��鐳(��)���E�P�N���A�˂��Ă��炦��A���̖䏊����i�̊�i�Ƃ������[�����������킯�Ȃ̂ł��B
�@
�剜�̒��ŁA���̂������b��ɂȂ�A�ǂ�ǂ���R�~�Œm���x���オ��܂��B�剜�Řb��ɂȂ�ƁA��a�̒����E�\���ƁA���{�����̋l���ɂ��̏�L�����Ă����܂��B
�@
�{�ی�a�Ƃ́A���{�̒����@�\���W�����Ă�����@�Ɗ����X���ꏏ�ɂȂ����悤�ȋ�Ԃł��B�����Řb��ɂȂ�A�]�ˑS�̂ɍL�����Ă����܂��B�]�˂ɂ͏��喼�̉��~������܂�����A���̃X�s�[�h�͌���Ƃ͔�r�ɂȂ�܂��A�S���ɓ`����Ă������Ƃɂ��Ȃ�ł��傤�B��a���ɑ剜�̘b��ƂȂ�ƁA�݂�ȋ����S�������܂������A���̕ӂ�̎���͌���������ł��傤�B
�@
�����̑����A��i���ꂽ�Ƃ��������͎����̃u�����h���l���グ����̂ł�����A�ϋɓI�ɂ��̏��𗬂��܂��B�����ɂ����̂ł��B
�@
���̎���́A�R�~�j���P�[�V�����E�c�[���́A��{�I�Ɍ��R�~��������܂���B���łȂǍ��蕨�Ƃ������f�B�A������܂����A�C�x���g�̏W�q�́A���R�~�ɗ��邵������܂���ł����B�ł����A���Ղ�₲�J���Ȃǂ̗l�q��`�����ъG������ƁA�{���ɓ�����Ă��܂����A���A���^�C���ŏ����ꂽ����������A���̎����͊m�F�ł��܂��B�t�Ɍ����ƁA���R�~�����ł��A���ꂾ���̏W�q�͂�����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���R�~�ŁA�����͒m���x���グ�Ă������̂ł��B�@ |
���L�������Ȋ�i����
�@
�������A�����ň�傫�Ȗ�肪����܂����B����������̋��߂ɉ����đ剜�����i���ꂽ���̃u�����h�i���A���܂�ɑ��������̂ł��B
�@
���{�̑����猩��ƁA���̃u�����h�i���o���߂���ƁA����(���R)�u�����h�̉��l�������茓�˂܂���B���Ȃ����炱���A�L���݂��o�āA���R�l�̌�Ќ����ۂĂ�̂ł��B��i�����Ȃ�ǂ��̂ł����A��������X�ƌ��J�W�������ƁA�u�����h���l�̒ቺ�ɒ������Ă��܂��܂��B
�@
����A�����̑��́A�剜�Ƃ̐l�����������A���̃u�����h�i�������Ɗ�i���Ă��炨���Ɖ�܂��B���J�W�����邱�ƂŁA���R�Ƃ̗R��������ɃA�s�[�����A�o�c��Ղ��������悤�Ƃ����킯�ł��B
�@
�����Ŋē����ł��鎛�Е�s�́A�����ւ̃u�����h�i�̊�i�A���̌��J�W���𐧌����悤�Ƃ��܂��B���R�u�����h�̉��l�̒ቺ��h���������̂ł��B
�@
�������A�����ɂƂ��ẮA�����������j�͂܂��Ɏ������ł����B�u�����h�i��q�̂ł����A�����Ă���u�����h�i�����J�W���ł��Ȃ��ƂȂ�ƁA�܂�������̎�������ł����B������������������ł����A�o�c�ɂ���Ō��ƂȂ�̂ł��B�ނ���A�����ƃu�����h�i�𑝂₵�āA���R�Ƃ̗R�����A�s�[���������Ƃ���ł����B
�@
���̂��߁A�����͑剜�ւ̍H����������܂��B���Е�s�ւ̉^���Ƃ������U�@�ł͚��������܂���A�剜���爳�͂������Ă��炢�A�K���ΏۊO�Ƃ��āA���Е�s�Ɍ��J�W����F�߂����Ă����̂ł��B���������A��i���邱�Ƃ��ł��܂����B�������A�剜�ւ̉^������|�������ł��傤���A�w�ɕ��͕ς����܂���ł����B
�@
�����̌o�c�́A�剜�Ƌ������ѕt�����ƂŐ��藧���Ă����̂ł��B���̗��ł́A���{�����̗͊w�������Ă��܂����B�@ |
���剜�ɓ�������{��
�@
�剜�ƌ��ѕt�����ƂŁA�̂��������Ă����������́A�]�˂̂��������ł͂���܂���B�n���̂������]�˂ɏo�Ă��āA�剜�Ƃ̌��ѕt���q�ɁA�m���x���グ�Ă����܂��B�]�˂ł̏o�J���́A�������g�傷���ł̕K�{�̃R���e���c�ƂȂ��Ă��܂����B
�@
�]�˂͑S���̂������o�����ė��āA��{�����J�����郁�b�J�ł����B�S���s�s�����ɑ����̎��v���グ���܂������A���̖��O�荞�ސ�D�̃`�����X�ł�����܂����B�J�����͑剜���͂��߁A���喼�̉�����������A�������������Q�w�ɖK��܂����B�����Ŗڂɗ��܂�A�剜�Ƃ̐l����������킯�ł��B
�@
�剜����̎Q�w��҂����łȂ��A���̋��߂ɉ����āA�剜�ɓ��邱�Ƃ�����܂����B���̎��́A���{�������łȂ��A���V���������邱�ƂɂȂ�܂��B�剜�ƌ����Ă��A�S�Ă̕������j�q���ł͂���܂���A�ǂ����̕����Ɉ��u����A�ޏ������̗�q�����̂ł��B
�@
�썑�������͂Ƀo�b�N�A�b�v�����j���@�́A�_���ɂ͂����ւ�S�����鏗���ł����B�j���@�̗�q�����_���̈�ɐ��c�s��������܂��B�썑���̏ꍇ�Ɠ������A���c�R�̗��j��U��Ԃ��Ă݂�ƁA�j���@�������ʼnʂ����������͖����ł��Ȃ����̂�����܂��B
�@
���c�s���͐��c�R�̖{���ł����A���̌��\�̍��܂ł́A����Ƃ͈���āA���c�R�͑S���ɂ��̖���m��ꂽ�����ł͂���܂���ł����B���̍��A���c�R�͎؍��̕ԍςɂ��ꂵ��ł��܂������A���̋����ŊJ���邽�߁A�]�˂ł͂��߂Ă̏o�J���������Ȃ��܂��B
�@
���̏o�J���͑听�������߁A���̎��v�ɂ��؍���ԍς��܂����A���c�s���̒m���x���S����̂��̂ƂȂ�܂��B�j���@�̗�q���邽�߁A�]�ˏ�ɓ������̂ł��B���\16�N(1702)7��4���̂��Ƃł����B
�@
���̎��A�j���@��10�����[���Ă��܂����A��i�҂̖��������ƁA���喼�̉�������̊�i���ڂɕt���܂��B���\�̍]�ˏo�J����ʂ��āA���c�R�͌j���@�܂�剜�����łȂ��A���喼�̉���������̐M���������̂ł��B���������]�˂ł̉c�Ɗ����̐ςݏd�˂��A���w�̐l�o�x�X�g3�̒n�ʂ��l������傫�ȗv���ƂȂ��Ă����̂ł����B�@ |
���ΑK���A�喼���~�܂���ʂ�
�@
���c�R�ƕ���ŏ��w�ł̃x�X�g3�ɐ����������t���A�剜�Ƃ̊W���[������������1�ł����B����t�́A���݂������t�Ƃ��Ēm���Ă��܂����A11�㏫�R�ƐĈȌ�A�O�E���̔N�ɏ��R���Q�w���邨���Ƃ��Ĉʒu�t�����܂��B
�@
����t���]�ˏo�J����ʂ��āA�m���x���A�b�v�����Ă����̂ł����A���c�s���Ɠ������A�]�ˏ�ɓ���A�ƐĂƂ��̌�䏊�ΕP�̗�q���Ă��܂��B���̐܂ɂ́A����̂����ƌ���Ă��̂����サ�Ă��܂��B�]�ˏ�ɓ��������Ǝ��́A�傫�Șb��ɂȂ����ł��傤���A���̌���i�Ȃǂ��A�����t�̉c�Ɛ헪�ɑ��Ȃ�܂���B�ƐĂ̍���1000�l�O��̉������������ƌ����܂����A�ǂ���`�ɂȂ������Ƃł��傤�B
�@
�剜����́A�����̂悤�ɁA�����������̐���t�Q�w������܂����B�c�Ɛ헪�̎����Ƃ����킯�ł����A�ޏ������ɂƂ��Ă��A���܂ł̓����͓��A�藷�s�Ȃ悤�Ȃ��̂ł�������A���̏�Ȃ��y���݂ɂȂ������Ƃł��傤�B
�@
���āA���c�R�����t�Ɍ��炸�A�������]�˂ɂ���Ă����ہA���{���͍]�ˏ��J����̂���(����@����Ȃ�)�����ɂ����̂ł͂���܂���B���R�̖����ł������喼�̍]�ˉ��~������Ă��܂��B
�@
���R�̖������喼�ɉł��ƁA��a�����݂���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B��������a(������ł�)�A��Z��(�����܂�)�ƌĂт܂��B������w�̐Ԗ�́A�ƐĂ̖��n�P������ˎ�O�c�đׂɉł����ۂɁA�O�c�Ƃ��{�����~���Ɍ��݂�����a�̖�Ȃ̂ł����A�]�˂ɂ͂���������a���A�ł������R�̖��̐l����������܂����B��{���́A���̗v���ɉ����Ă����̌�a������Ă������̂ł��B
�@
��a�̎�ł��鏫�R�̖��Ɏd���鉜���������́A�剜����o�����Ă��������ł����B�ł�����A�]�ˏ�Ɍ�{��������Ƃ������́A�O�����ăL���b�`���Ă������Ƃł��傤�B�剜�̉��������q�ƂȂ�A�����������q�݂����Ƃ������ƂŁA�����悤�ɗU�v����킯�ł��B
�@
�����ɂƂ��Ă݂�A���̑喼�Ƃɑ��������ƂƂ��ɁA�a�l��Ɛb�����ɂ����O��m���Ă��炦���D�̃`�����X�ł����B�]�ˏ�ɓ��������Ɠ������A�����Ȃǂ����サ�Ă��܂����A���̎��́A�ΑK�����ꏏ�ɉ���Ă��܂��B���V����A��{���������ΑK���܂ŁA�Ԗ���������Ă����킯�ł��B���������͂ݎ�낤�Ƃ��������̂������������A�����������ɂ��\��Ă��܂��B�]�˂̂����͑剜�Ȃ��ɁA�o�c�헪�𗧂Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��B�@ |
|
�@ |
   �@
�@ |
|
�@���߂��@�@���߂�(�ڍ�)�@�@�@�� Keyword�@�@�@�@  |



 �@
�@ �@
�@ �@
�@