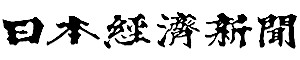|



|
�R�c�^�M�q�E-2/28�E3/1�E3/2�E3/3�E3/4�E3/5�E3/6�E3/7�E3/8�E3/9�E3/10�E3/11�E3/12�E3/13�E3/14�E3/15�E3/16�E3/17�E3/18�E3/19�E�E�E
�����̌������E�g���L���E���{�u�����@�����v�E�E�E
���u�}�X�R�~�v���b / ���チ�f�B�A�Ɩ@�I�����E���f�B�A�̎g���E�}�X�R�~�̖����E�}�X�R�~�ƃ}�X���f�B�A�̈Ӗ��E�e���r�̖����E�}�X�R�~���j�P�[�V�����_�E�����̖����E�V���̖����E�W���[�i���Y���̖����E�}�X�R�~�ϗ��E�}�X���f�B�A�̖����E���a���̃��f�B�A�ƎЉ���E���f�B�A�͂Ȃ�����̂��E���f�B�A�̖������т��E���������̂܂ܓ`�����E�}�X���f�B�A�����_�`���ɉʂ��������Ƃ��̗h�炬�E�}�X�R�~�̏��ƍ����匠�E�R���i�ŕs������郏�C�h�V���[�E�}�X�S�~1�E�X�e�}�ɕΌ����E�}�X�S�~2�E�}�X�R�~�͔����E�̃^�u�[�E�V���e���r�̊������E�����ܗ֒��~���X���[����}�X�R�~�E�e���r���������E�W���[�i���Y�����v�E���f�B�A�Ď��E�W���[�i���Y���̖����E�W���[�i���Y���̂�����E�l�b�g����̃W���[�i���Y���E�f�W�^������̕��E���W���[�i���Y���̎v�z�E�R���i�ً}���Ԃ̃W���[�i���Y���E���_�s�ꉻ�E�����W���[�i���X�g�������E���X�́u��́v�E�V���L�҂�����1�E�u�����v�̎Љ�j�E�u�����v�̐����E�V���L�҂�����2�E�V���А��Ɍ���u���f�v�E�j���[���[�N�^�C���Y�̓Ƒ��E�W���[�i���Y��������j�E��������L���E�����Ȃ��L�҂����E�E�E
�@ |
|
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@ �@ |
|
�����������Ȃ��}�X�R�~�@���ł̏ؖ� |
������@���[�́u���t�v
�ǐ�����
��ޗ͂Ȃ� |
�������M���[�����̔���
�u�����v�͂����Ă��@
�u�������e���莋�v�����͂���܂���
�ᔻ�͂Ȃ� |
�����@�L�҃N���u�@�����Љ�
�����삯�@�X�N�[�v�͂��@�x
�����ɂԂ炳����@�C�y�Ȃ��d���̂悤�ł� |
���ʂ��猩�܂��@���������Ƃ���܂�
�e���猩���肵�܂���
�܂��ā@���ɉ�荞��Ł@�`�����肵�܂���
���ʈȊO�@���t�@�V���@���C�����Ă��܂� |
 |
|
�����c��b�@�uNTT�Ƃ̉�H�v �� �@ |
�u�ʂ̎��Ăɓ�����͍̂T���邪�A
�@�@�@�����̋^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v
�u�ʂ̎��Ăɓ�����͍̂T����B
�@�@�@�����̋^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v
�u�ʂ̎��ĂЂƂЂƂɂ��ĉ͍T����B
�@�@�@�����݂̂Ȃ���^�O��������H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v
�u�ʂ̎��ĂɈ�������͍̂T�������B��������^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ����A���������A�݂�����𗥂��A�E���ɐ�O���Ă��������v
�u�ʂ̎��Ĉ��ɂ���������͍̂T�������Ă������������Ǝv���܂��B�������A���͍����̊F����^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂������܂���v
�u��������^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v
�u��������^�O��������悤�ȉ�H�A��ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v
�@ |
����ȑ�b�������@�܂���ʂ鍑�ɂȂ�܂���
�}�X�R�~���@����܂� |
�r�߂��炠����@
���t�I�����C����17�����B����ɂ��ƁA���c���͑������A�C��̍�N11��11���A�����s���̃z�e���̓��{�����X���V�c�A�����A�����e���Ƃ̉�H�ɓ��Ȃ����B |
3/18�@���c��b�@�O�c�@�����ψ���
�u�������_��Ƃ̉�H�ɓ��Ȃ������Ƃ͎������B���������琺���������蓖���܂łق��̏o�Ȏ҂�m��Ȃ������B�ʂ̗\�肪���������߂����݂̂��������Ē������A��p�Ƃ���1���~���x�������v�@�u�o�Ȏ҂������̋��F�ȂǂɊւ���v�]�A�˗��������Ƃ͂Ȃ��A��b�K�͂ɒ�G�����H�ł͂Ȃ������Ǝv���Ă���v |
|
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
|
���R�c�^�M�q�@�O���t�L�̏����Ɍ���V�@�� |
 |
|
�@ |
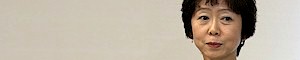 |


 �@
�@ |
|
���R�c�^�M�q
|
|
(��܂��܂����A1960 - )�@���{�̌��X���E���������B�ːЖ��͋g�c�B���t������b�鏑���A�����ȏ��ʐM���ې헪�ǒ��A��b���[���A��ʍs���ǒ��A�����R�c��(���ےS��)�߂đފ����A���t�L�߂��B���`�̂̑��q���߂�A���k�V�Ђɂ�����ڑҖ��ɂ��A2021�N3��1���Ɏ��E�B
|
�������j����̈�@�����ڑҖ��
���`�̎̒��j���߂�������Ɖ�ЁA���k�V�Ђɂ��ڑҖ��ŁA�����R�c���ł������R�c�^�M�q�E�O���t�L��2019�N11��6���ɒ��j�Ɖ�H�����Ă���A1�l������̈��H�P����7��4203�~�ł�������2021�N2��22���ɑ����Ȃ��������ʂ�����B�����Ȃ͒��j��ɐڑ҂���13�l�̂���11�l�ɂ��āA���ƌ������ϗ��K���́u���Q�W�҂���̐ڑҁv�ɊY�����邩�A���̉\���������ƔF�肵�A���������ȂǂƂ�����j���ł߂��B�R�c�͓��ʐE�̍��ƌ������̂��߁A�����Ώۂ���͊O��Ă��邪�A�ڑғ����͑����R�c��(��ʐE)�ł������B
�����j��ɐڑ҂���20���Ɏ�����X�R���ꂽ�H�{�F���̌�C�ƂȂ����g�c���j�����R�c���́A�R�c�̕v�ł������B
2��24���A�R�c����7��4203�~�̋����̓��e�́A�a���X�e�[�L�A�C�N�����Ȃǂł���Ɩ��炩�ɂȂ����B���Y��H�̔�p�́A�R�c���Ƒ����Ȋ�����4�l�A�v5�l��37��1,013�~�ł������B
2��25���A�R�c�͏��߂ĎQ�l�l���v���ꂽ�O�@�\�Z�ψ���Ŗ�}�̒Njy�����B�R�c�́u(�����j��)���������܂Ƃ́A���h�����͂��̉�ȑO�ɂ��Ă����Ǝv���Ă���܂��v�Ɠ����Ă����Ȃ���A��������}�̍����l�c�����u��H�ɍs�������ɒ��j������ƔF�����Ă����̂��v�Ƃ������ƁA�R�c�́u�𗬂��قƂ�ǂȂ��������̂ŁA���O�ɂ�����ƔF�����Ă������Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����v�Ɩ������铚�ق������B5�l�̉�H���̔F���́u�����т������Ǝv���̂ŁA���b�����Ă���܂���̂ŁB�ǂ������������������A�ɂ킩�Ɏv���o���Ȃ������Ƃ������Ƃł��v�ƎR�c�͖������ق𑱂����B���䂪�u5�l�ʼn�H���āA�����Ɏ̑��q���������ǂ���������Ȃ��A�Ȃ�Ă��Ƃ�����̂��v�ȂǂƂ������ƁA�R�c�́u�����g�A�d���A�v���C�x�[�g�ł��A�����������ǂ����������̂��q���ł��邩�Ƃ��́A���܂肨�t�������ɊW���Ȃ��Ǝv���Ă���v�u�����܂��������Ƃɂ��āA���������������͓K�����ǂ���������܂��A���ɂƂ��đ傫�Ȏ������������Ƃ����ƁA�K�����������ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɓv�Ɠ������B���قł́A6���O�ɑ����Ȃ̏�ʍs���ǒ��ɏA�C�����A�R�c�̕v�̋g�c���j�������D���o����ʂ��������B�R�c�͌�����6���ɑ�������70��5000�~������Ԕ[�������A���C�͔ے肵���B�������A���N3��1���A�̒��s�ǂɂ����@�𗝗R�Ɏ��E�͂��o�����B�R�c�̑ސE���ɂ��āA�������M���[�����́u���T����v�Ƃ̓��ق������B�����ƐE�ł͂Ȃ��A����ސE�̂��ߑސE���͖��z�x���������̂ƌ�����B�����̎������t�c�ɂ�莫�E�����肳�ꂽ�B
�Ȃ��A����2006�N�̑�����b�A�C���A�����̃o���h�}���ŎЉ�l�o���̂Ȃ����E�̐��̒��j(����25��)���b�鏑���Ƃ��Ĕ��F���A2007�N�܂ő����̑��������Ƃ̐ړ_���������Ă����B |
��NTT�ɂ�鋟���ڑҖ��
2021�N3��3���A���������̒J�e�N�F�ƎR�c�^�M�q���ANTT���V�c���В���A�q��ЁENTT�f�[�^�̊�{�q�j�O�В���������z�Ȑڑ҂��Ă������Ƃ��T�����t�����BNTT�͑�����b���玖�ƌv��Ȃǂ̔F���Čo�c����Ă���A�����Ȋ�����NTT�����狟���ڑ҂��邱�Ƃ́A���ƌ������ϗ��@�ɒ�G����^��������B
2020�N6��4���A�R�c�͑����Ȃ̊����p�i���ې헪�ǒ��ƂƂ���NTT�O���[�v�̊֘A��Ђ��^�c���郌�X�g������K��Ă����B�ڑ҂����̂�NTT���V�c���В��Ɩk���������s�����ŁA4�l�̈��H��͑��z�Ŗ�33���~(�����O)�������BNTT������Ƃ�100���~�P�ʂ̔N����X���Ɏx�����Ă���A�����Ƃ̏ꍇ�A�����4�������ɂȂ�B
���������R�c���������R�c�^�M�q���ANTT�В���Ƃ���H�����Ă����ƏT�����t�ŕ�ꂽ���Ƃɂ��āA���{��2021�N3��4���̎Q�@�\�Z�ψ���ŎR�c���Ɏ����m�F�����Ȃ��l�����������B���`�̂́A�R�c��3��1���Ɏ��E�����ۂ�NTT�В���Ƃ̉�H��m��Ȃ������̂��Ɠ��{���Y�}�̓c���q�q�ɐq�˂��u���m���Ă��܂���ł����v�Ɠ������B�c�����u�R�c���ւ̎����m�F�͓��R�s���܂��ˁv�Ɛq�˂�ƁA�������M���[�����́u���ɑޔC����Ă���̂ŁA�������玖���m�F���闧��ɂ͂Ȃ��Ǝv���Ă���v�Ɠ��ق����B�c�����u�Ȃ������m�F����Ȃ��̂��@�v�Ǝ��₷��ƁA�������[�����́u���ɑޔC����Ĉ�ʂ̕��ɂȂ��Ă���킯�ł�����A���{�����m�F���闧��ɂ͂Ȃ��v�Ɛ��������B�c�����u����ł͐������͐ڑҖ����������闧��ɂȂ����ƂɂȂ�v�ƒNjy����ƁA���́u�����̓��[���Ɋ�Â��Ă�������Ή����Ă���v�Ǝ咣�����B
3��5���A�����p�i���ې헪�ǒ��́A�ڑ҂ɎR�c�����Ȃ��Ă������Ƃ�F�߂���ŁA���Ƃ���NTT�����狁�߂�ꂽ1���~���x�������Ɛ��������B�@ |
 �@-2/28 �@-2/28 |


 �@
�@ |
|
���m�g�j���u�����Ȑڑҁv���ɐ�X���X�@2/23
|
�u���`�̎̒��j�������Ȃ̍���������ڑ҂��Ă�����肪����ŒNjy����Ă��܂����A�݂��y�Ԃ̂ł͂Ɛ�X���X�Ȃ̂��m�g�j�Ȃ�ł��v(�m�g�j�����E��)
�T�����t���X�N�[�v�������̒��j�A���������̑�������4�l�ւ̐ڑ҂͏��Ȃ��Ƃ��ߋ�12���炩�ƂȂ����B�����́A�����Ȃ̋��F���q���������^�c���铌�k�V�Ђ̕����E�ɂ���A���̎q��Ђ̎�����������B�����ȃi���o�[2�̒J�e�N�F�A�g�c�^�l�������R�c���犲�������z���H�ڑ҂ƃ^�N�V�[�`�P�b�g�������Ƃ͍��ƌ������ϗ��@�Ɋ�Â��ϗ��K��ɒ�G����^��������A�܂����k�V�Ђ͐��̈Ќ��𗘗p���āA�A�Ő��E�H�삵�Ă����^����������Ă���B
���k�V�Ђ͊O���f��̓��{��Ő���ŗL�������A�e���r�̐����ЂƂ��Ă��ƊE�ő�肾�B
�u���k�V�Ђ͂m�g�j�ƌ��т����[���A�w�r�v�h�s�b�g�C���^�r���[�@�B�l�B�x��w�A�i�U�[�X�g�[���[�Y�@�^���̕���_�x�ȂǑ����̔ԑg����𐿂������Ă���A�q���ԑg�w�I�g�b�y�x�̏��i�����C����Ă��܂��B�q���n�C�r�W�����S���ǒ����������쒼�H����2005�N�ɗ����ƂȂ�A���̌�m�g�j�G���^�[�v���C�Y�В��A�m�g�j����ɏA�C���܂������A2015�N�ɓ��k�V�Ђ̎ЊO������E�č����ψ��ɂȂ肢�܂����E�B�q����������̉���������Ă��܂��v(���O)
�m�g�j�̗����͊֘A��ЂɓV���肷��̂��킾���A�Ǔ��œ��k�V�Ђ͂��̎��́g��2�̓V����h��Ƃ��Ă݂��Ă���B
�u�m�g�j���������������ŗv�E���C���A��̃j���[�X�ԑg�̃L���X�^�[�����߂����Ƃ����钘���Ȃn�a�����݂͓��k�V�Ђ̌ږ�̌����������ł��B�ނ��}�������ꂽ�̂��A�ē����̑����Ȃƌ��������m�g�j�̐l����o���A�������҂���Ă̂��ƁB���̋K�͂̉�Ђŕ����̂m�g�j�̌��������}��������Ă���̂́A�ٗᒆ�̈ٗ�Ƃ����܂��v(�m�g�j�W��)
�v�͂m�g�j�l���̏���ʓI�ɁA���k�V�ЂƐ��������̑Α����ȍH��ɗ��p����Ă����Ƃ������Ƃ��B
�u22���̒��Ԕ��\�ő����Ȃ��犯���ڑ҃��X�g���o��\��ł����A4�l�ȊO�����7�l������Ƃ����Ă���B�܂����k�V�Ђ́g���E�H�샊�X�g�h�����݂���炵���A�e�Ђ͂��ܕK���ł����ǂ��Ă��܂��B�����n���ɍ����o�����Ƃ����b������A����ڂ������Ȃ��v(�������L��)
�g��͍L���肻���Ȑ������B�@ |
|
���u��ɒf��Ȃ����݉�v�̋��|�@2/26 |
�w�S�`�L�x(�[���t�W)�@�������o���ł��B
�������Ɂu�S�`�ɂȂ�܂��I�v�̐V�����o�[���\�݂����ɑ����ȃS�`�����o�[�����X�Ɣ��\����đs�ρB�ł�11�l���u�o��v����Ȃ�Ĕ������߂���B�����j�A�X�^�[������B
�����ȑ��́u�����s�����䂪�߂�ꂽ�����͊m�F����Ă��Ȃ��v�Ƃ����B���������͂Ƃ�ł��Ȃ��R�����g�������Ă��܂����B
�����2��25���̖����V���B�������������Ȃ�11�l�́A�ʐM������s���̒�����S�����X���ȏo�g�̊�������ŁA�s�����ȓ�����́u�����s���ɉe�������˂Ȃ��v(����)�Ƃ̌��O��A�u���������͎̂d���̂ł���l���肾�v(�ʂ̊���)�Ƃ����������R���B�t �����A�����Ȃ̎d���Ɏx�Ⴊ�o�����ȂقǕ����s�����䂪�߂�������B����ς萛���j�X�^�[������B
���u�����ȑ��o�Őڑ҂��ɂ����܂��ˁv�Č��̏Ռ�
�����ĐV���ȃX�^�[�������ꂽ�B�R�c�^�M�q���t�L�B�w�S�`�L�x�ł��B�ڑҊz�͌Q���Ă�1�l������7��4203�~�B���̋��z�͒N���\�z�ł��Ȃ������B��ނł���B
�R�c���͂��Ď�Ҍ����̃��b�Z�[�W����Łu���݉����ɒf��Ȃ����Ƃ��Ă���Ă����v�ƌ����Ă����̂Ńl�b�g���V�����吷��オ��B
�����������͒��ӂ��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B�u���݉���ɒf��Ȃ����v�̓C�W�������Ȃ邪�A���k�V�Ђ̈��݉�́u��ɒf��Ȃ��v���炱�����o���̂ł́H�@�������{���ł͂Ȃ����B�g���������o�ł��܂��ˁh�Ȃ�ʁA�����ȑ��o�Őڑ҂��ɂ����܂��ˈČ��̏Ռ��B���̈Ӗ��B
�R�c�L�ɂƂ��Ă͂ǂ�قNj�ɂ��������낤�B��������ł͈��݉��f��Ȃ����R���u�K�^�ɏo�����@��������Ă����܂��v�Ǝ�҂ɐ����Ă����B����ł����Ɛ����j�̐ڑ҂�������͎R�c���͑��̈��݉�ɏo��`�����X���ׂꂽ���ƂɂȂ�B�K�^�ɏo�����@��m���Ɍ������̂��B�l���𑝂₵�����^�C�v�Ƃ��Ă͒ɂ������͂����B
����ł��o�Ȃ��Ă͂����Ȃ��ڑ҂Ƃ͉��Ȃ̂��H
���ꂾ���ł����Ɖ����[�����k�V�ЂƐ����j�̈Ќ����v���m��̂ł���B
�����Ɉ�{�ނ肳��č��͓��t�L��
�����炢���Ă����ƁA�����Ȃ͒ʐM���Ǝ҂�����ǂւ̋��F�������B�q�������Ɏg������g���ɂ͌��肪�����Đ��{�����̊��蓖�Ă����߂Ă���B����Ȑ�ΓI���҂̑����ȑ����Ȃ����k�V�Ђ̐ڑ҂͑��o�Ŏ�̂��B���Ђ̐ڑ҂͎Ă��Ȃ��Ƃ����̂ɁB������b�߁A���ł��鐛���͒��j�́u�ʐl�i�v�ƌ������B�����R�c�^�M�q���t�L�̃L�����A���݂�Ɩʔ������Ƃ��킩��B�R�c���͑�2�����{���t�ŏ������̔鏑���ƂȂ�A�����Ȃł͎������i���o�[2�̑����R�c���ɏA�����B
�s�͊��[�������ォ��R�c���������]�����A��N9���̐����t�����ɍ��킹�A���t�L�ɋN�p�����B�t(�ǔ��V��2��25��) ������(�����ƊE�ɑ��đ��݊����傫��)�Ńi���o�[2�������l���A���Ɉ�{�ނ肳��č��͓��t�L�ɂȂ��Ă���B����l�����B���̕��݂␛���j�̃L�����A(��������b�����̔鏑���A���̂��ƕ������ƎЂ֏A�E)�ƍ��킹���̂悤�ɂ��݂���B
�����������̈��݉�����̂Ɂc�����j��F�����Ă��Ȃ��H
���͒��j�����k�V�Ђɓ��Ђ���ɂ������āu�����ȂƂ͋�����u���ĕt�������悤�Ɂv�Ə��������Ƃ����������͎R�c���Ƃ͋�����u���Ă��Ȃ��B�����ȂƂ��J�̐[���̏ے��B���k�V�Ђ��炷��Α��̐l��肨���������đ_�����낤�B
����ȁu���v�̔閧���S�`�L�͉�X�ɋ����Ă����̂��B���̍L��A�킩��₷���B
�R�c���́A25���̏O�@�\�Z�ψ���̎Q�l�l���v�ł͐����j�Ƃ̊W�ȂǏڍׂ�����Ɓu�o���Ă��Ȃ��v�ƌ��t�������(�����X�|�[�c)�B����̓w�����B�R�c�������݉�ɏo�闝�R�́u�ǂꂾ�������̐l�ɏo��A�����̃`�������W�����Ă��邩�v�������͂��B���������̈��݉�����̂ɑ����F�����ĂȂ��Ȃ�ă`�����X���킵�Ă���B����Ƃ������j�́u�K�^�ɏo�����@��v�ł͂Ȃ��A��X�������݂������̂��B
����ׂ��͐����j�̃X�^�[���Ղ�ł���B�T�����t�͎��X�Ɛ����j�̎ʐ^���ڂ��Ă���B�܂�ŃO���r�A���B�ڑ҂̂��ƋA��鑍�������Ɍ������Ď�����킹�Ă��鐛���j�B�������肢���Ă�B�t�H�g�W�F�j�b�N������B
���X�^�[�����j�ɂ͏\���Ԃ̌|�����݂��Ă����c�������I
����ȂȂ������Q���_�C�́u��X�N�[�v�v��������B
�w����|�ł����̈Ђ���鐛���j �S�l�^�́u�ߘa��������v���m�}�l�x(2��26���t)
���k�V�Ў�Ẫp�[�e�B�[�ɏo�Ȃ����l���ɂ��ƁA�����j�̓S�l�^�́A���e�ł���g�ߘa��������h�̃��m�}�l���Ƃ����B
�s�_���Ȋ���Łw�ߘa�x�Ə����ꂽ�F�����f���A�w�V���������͗ߘa�ł���܂��x�ƌ����܂ŃR�s�[���Ă���܂��B�t
�X�^�[�����j�ɂ͏\���Ԃ̌|�����݂��Ă����B�������I
���Ȃ݂ɃQ���_�C�t���͐����j���u��Ɂw�ߘa�x�̐F�������������Ă������͕�����܂���v�Ɩ��ȍו��܂ŏ،��҂Ɋm�F���Ă����B
��������Ȃ����Ƃ����̍��̋C������`����u�L��v��
�z�C�Ȑ����j�����A���e����͉A�C�ȃj���[�X���B�w���A�}����������� �R�c�L�̖����e�����x(�����V���f�W�^��2��25��)
26���ɗ\�肵�Ă����ً}���Ԑ錾�̐�s�����ɔ����L�҉����������j�ɂȂ����Ƃ����B
�R���i�Ή���S�����{�W�҂́u������Ȃ����R�͍L���낤�v�B
�͐錾����������2��2���̉�ł́u�����̊F����ɂ�����Ə�M���A�����ӔC���ʂ��������v�ƌ���Ă����̂ɁB��̐i�s���߂Ă����͎̂R�c�^�M�q���t�L�B������Ȃ����Ƃ����̍��̋C������`����u�L��v�ɂȂ��Ă���B�ƂĂ��킩��₷���B�����j����̈�A�̗���͕ʐl�i�ł͂Ȃ���͂��S���̗̂��ꂾ�B
�����Ȃ�����X�^�[�����j�ɕ��e�̃��m�}�l�ʼn���Ăق����B
�u�����ł��邱�ƂƂł��Ȃ����Ƃ�����v(��N10��NHK�u�j���[�X�E�H�b�`9�v�o�����̌��t)�B�X�^�[�`�����l���Œ��p���Ăق����ł��B�@ |
 �@3/1 �@3/1 |


 �@
�@ |
|
���R�c�^�M�q���t�L�����E�@3/1
|
�q�������֘A��Ђɋ߂鐛������b�̒��j�Ȃǂ���ڑ҂��Ă����R�c�^�M�q�E���t�L�́A28���̒��s�ǂ𗝗R�ɓ��@���A1�����E���܂����B
��������b�́A����ŁA����̐ڑҖ������߂Ēӂ��܂����B
�R�c�^�M�q�E���t�L�́A�����R�c�������A�q�������֘A��Ёu���k�V�Ёv�ɋ߂鐛������b�̒��j�Ȃǂ���1���1�l������7���~������H�̐ڑ҂��Ă��܂����B
�挎25���ɂ́A�Q�l�l�Ƃ��č���ɏo�Ȃ��u�������̐M�p�Ȃ����ƂɂȂ�A�[�����Ȃ��Ă���v�ƒӂ����ƂɊւ��铭�������͂Ȃ������ȂǂƐ������������ŁA���E��ے肵�Ă��܂����B
�܂��A��������b����T�A�u����Ƃ��A�撣���ė~�����Ǝv���Ă���v�Əq�ׁA����������ӌ��������Ă��܂����B
�������A��}���͎R�c���̍���ł̐����͕s�\�����ȂǂƂ��ē��t�L�����E����悤���߂Ă��܂����B
�����������ŁA�R�c���́A28���̒��s�ǂœ��@����1���t���Łu�E���𑱂���͍̂���v�Ƃ��Ď��\���o���A�������̊t�c�ŔF�߂��܂����B
���̉e���ŁA�ߑO9������\�肳��Ă����O�c�@�\�Z�ψ���̏W���R�c�́A30���x��Ďn�܂�A��������b�́u���̉Ƒ����W���āA���ʂƂ��Č��������ϗ��@�Ɉᔽ����s�ׂ��������Ƃ́A��ϐ\����Ȃ��A�����ɐ[������ѐ\���グ��B�s���ɑ��鍑���̐M����傫�����Ȃ����ԂɂȂ������Ƃ́A�[�����Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƒӂ��܂����B
�R�c���́A���X���ȏo�g�ŁA��2�����{�����ŁA�����Ƃ��ď��߂Ă̑�����b�鏑���߂܂����B
�����Ȃ�ފ��������ƁA���N9���ɓ��t�L�ɋN�p���ꐛ������b�̋L�҉�Ői�s���߂Ă��܂����B
|
|
����������]�A�����Ӂc�R�c�^�M�q�L���d�����E�@3/1
|
���̒��j�炩�獂�z�Ȑڑ҂��Ă����R�c�^�M�q���t�L�����E�����B3��1���A�L�Ғc�̎���ɓ��������͑Ή��ɂ��Ė���u�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ��v�Ɠ������B
���������]�c�Q���̎R�c�^�M�q���t�L��3��1���A�d�����E�����B3��1���ߌ�5���O�A������ނɉ������B
����:����R�c�̋ɂ߂ďd�v�Ȏ����ɁA�L���E�������B�����������ԂɎ���A��ϐ\����Ȃ��v���܂��B
�[�[�Ή��������Ƃ̔ᔻ�����邪?
����:���͂��̂悤�ɂ͎v���Ă��܂���B
�����Ȃ̊�������ɁA���̒��j�炩��7��4000�~�̍��z�ڑ҂��Ă����R�c�L�B���͐�T2��24���A�u�����̍L�Ƃ��Ċ��҂��Ă���v�Ƃ��āA�����̕��j��ł��o�����B26���ɂ́A�ً}���Ԑ錾�̈ꕔ�������߂����������������ƂɁg�R�c�B���h�Ƃ̔ᔻ���W���B����ł����p���ɕς��͂Ȃ������B
�[�[�Ȃ��L�҉���s��Ȃ������̂�?���z�ڑҎ��R�c���t�L�̖�肪�e����?
����:�܂��R�c�L�̂��Ƃ͑S���W������܂���B
���ꂽ���̎R�c�����A��T�܂ł́g�����̈ӎv�h�������Ă����B
�R�c���t�L��:����E���𑱂��Ă������ŁA�����̐g��������݂āA�ł�����莩������P���Ă��������B
2��25���̓��قł͓����A�͂̂Ȃ��\����������ʂ����������̂́A��}�̒Njy�ɂ͂�ǂ݂Ȃ����ق����B�������A����3�����28���A�R�c���͑̒��s�ǂŖ�2�T�Ԃ̓��@���K�v�Ɛf�f���ꂽ�Ƃ��Ď��ӂ�`�B�B3��1���A�u�E���𑱂��邱�Ƃ͓���v�Ƃ��Ď��E�����B
���{�W��:�u���@��������Ƃ����̂͌��O�ŁA���{�l���ӔC��Ɋ����Ă���Ƃ����̂��ő�̗��R�B�����^���͂���Ȃ�Ƀ_���[�W�Ă���Ǝv���܂��v
3��1���ߌ�5���O�̎��@�ɂāA
�[�[�C���ӔC�ɂ��Ăǂ��l����?
����:�R�c�L�ɂ��Ă͍s���o���L���A���҂��C�����܂����B�����������ł��̂悤�Ȍ`�Ŏ��C����邱�Ƃ͑�ώc�O�B
3��1���̗\�Z�ψ���ɏo�Ȃ���\�肾�����R�c���B���̒��O�̎��E�Ɏ����}�����������Ȑ����オ���Ă���B
�����}�c��:�u����ȏ㓚�����Ȃ�������@�Ȃ�āA�_�B��̏퓅��i�ł���v
��������}�@�}���\:��T�̒i�K�Ŏ��߂Ă��������Ƃ��肢������ׂ��������̂ł͂Ȃ����B�x���Ɏ������Ǝv���܂��A�����B
����:2�T�Ԓ��x�̓��@�A���Â�v����Ɛf�f���A�����g�͂��������ł���A��ނȂ��Ɣ��f�������Ă��������܂����B
��������}�@�R��a���c��:�����̑��q���������������Ƃő���ɂȂ�A�̒����Ď��߂���Ȃ��Ȃ�B�����͊W�Ȃ��Ƃ����̂�?
����:���̎���ɓ����闧��ł͂Ȃ��B���ʂƂ��āA���������ϗ��@�Ɉᔽ����s�ׂɎ��������Ƃ́A��ϐ\����Ȃ��S���炨��т�\���グ��B
��������}�E�Ҍ�����\:���ǂ͑�����b�̐g���ɐU��ꂽ�Ƃ������A�������܂��Ԃ��ꂽ�̂�����Ƃ������ʂ�����Ǝv���B
�R�c���̌�C�ɂ��ẮA���������Ă���Ƃ����B
|
|
���R�c�^�M�q���t�L�̎��E���ɂ��Ẳ�@3/1
|
(�R�c�^�M�q���t�L�̎��E�ɂ���)
����R�c�̋ɂ߂ďd�v�Ȏ����ɁA�L���E�������A�����������ԂɎ���A������n�ߊF�l���ɁA����f�����|�����Ă��܂����Ƃ��A��ϐ\����Ȃ��v���܂��B��C�ɂ��܂��ẮA���������ł���܂��B�Ɩ��Ɏx��𗈂��Ȃ��悤�ɂł�����葁��������������A���̂悤�Ɏv���Ă���܂��B
(�Ή������ɉ���Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ᔻ�ɂ���)
���͂��̂悤�ɂ͎v���Ă���܂���B
(�R�c���t�L�̔C���ɂ���)
�R�c�L�ɂ��ẮA�s���o���L���A�����Ă܂��A�O�����̍L��̔鏑��������Ă��܂����̂ŁA���������Ӗ��Ŋ��҂��A�C�����܂����B���̒��ŁA���̂悤�Ȍ`�Ŏ��C����邱�Ƃ͑�ώc�O�Ɏv���܂��B
(�����ł��邱�Ƃ������������R�ɂ���)
���ɁA�����̂��ߍׂ����Ƃ��A���邢�́A���{�̊����ɏ����̐������ɏ��Ȃ��ł����A�������������Ƃ��ē����Ă����A���������o��������܂��B�s���ɂ������Ă��܂��B���������`�̒��Ŋ��҂��ēo�p�����Ă����������A�����������Ƃł��B
(������b����ɒ��j��鏑���ɔC���������Ƃɂ���)
12�N�O�̘b�ł���B12�N�Ԏ��͒��j�Ƃ��̖��̌`�̒��ŁA�A�E�A�����̉�Ђ̂��ƂŘb�������Ƃ��Ȃ������ł��B�����Ȃ��Ƃ������܂�����ǁA�����͂��̂悤�Ȃ��Ƃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�@ |
 �@3/2 �@3/2 |


 �@
�@ |
|
�������ȂƓ��k�V�Ђ̈�@�ڑҖ�� �^�f�̖{�ہ@3/2 |
���̒��j���߂铌�k�V�Ђɂ�鑍�������ւ̈�@�ڑҖ�肪�����h�邪���Ă���B�^�f�̖{�ۂ́A�ڑ҂ɂ���āu�s�����䂪�߂�ꂽ�v�\�����B���̈�[���c���v�|���炤��������̂��A���k�V�Њ�����ڑҊ������Q�����������Ȃ̗L���҉�c�B���́g������c�h�ɒ����̃��X������ׂ����B
���̗L���҉�c�́A2018�N2���ɐݒu���ꂽ�u�q�������̖������Ɋւ��郏�[�L���O�O���[�v(WG)�v���B4�j�A8�j�����̊J�n�ɍ��킹�A�q�������̏����I�Ȃ�����Ȃǂɂ��Č������邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����c�̂ł���B���k�V�Ђ̎ЊO���������߂�u�q����������v�ȂNjƊE�W�҂�L���҂ɉ����A���k�V�Ђ���ڑҍU���ɂ��������������������o�[�ɖ���A�˂�B
�u�������哱�����͓̂����A�������������������v�h�̏��юj���E�����}�O�@�c���ł��B���̒��j�Ɖ�H�����H�{�F���E�O��ʍs���ǒ��ɁA�w��s�n�ɂ܂݂�Ȃ��Ɓx�Ɲ������ꂽ�l���ł��v(�����֊W��)
�v�f�͓��N5���̑�5���c�ŕ��Ă��܂Ƃ߂�ƁA�x����ԂɂȂ����B�x�����͐����j�瓌�k�V�Ђɂ��ڑҍU���������BWG�����o�[�̂����ڑ҂����̂�19�N7���܂Ŗ�2�N�ԁA�����s�������ǂ����ʍs���ǒ��������R�c�^�M�q�����܂�9�l�B���̊Ԃ�����19����̐ڑҒЂ����B
����ƁA�x������2�N���20�N4����WG�͓ˑR�A�ĊJ�B�r�[�ɕ��������u���k�V�Њ��v�̃y�[�X�ɂȂ��Ă����̂��B
�����Ȃ�HP�Ɍ��J���ꂽWG�̋c���v�|����́A�R�X�g�ጸ��_�������q����������́u�v�]�v�������Ɍ��Ď���BWG�ĊJ�㏉�̉�c�ł́A����q�������s�����߂ɂ́A�X�Ȃ�Œ��̍팸���K�v�ɂȂ�r�ƋL���ꂽ������z�z�B���N9���ɒ�o���������ɂ́q�q�������̌Œ��S�͑傫���r�q�Œ��̒�����Łc���R���e���c�ɓ������I�@������Ȃ�T�[�r�X�����̒l�����Ƀt�B�[�h�o�b�N���I�r�ƁA�Œ��̒ጸ���������߂镶���������Ă���B
������WG�̋c���v�|�ɂ��ƁA����L���҂��u(�q�������֘A��Ђ�)�q����������A�g���āA�Œ���蓙���������邱�Ƃ��d�v���v�Ɣ����B���̐l���͋���̗����߂Ă���B
�܂�A�v�f�ĊJ������k�V�Ђ̐ڑҍU���͉ߔM���A���Ђ̖����Ɗ֘A�̂���L���ҁA�ڑҊ�����3�҂Ō������s���Ă����킯���B���ʓI�ɁA���N12���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���Ăɂ͋���̖]�ݒʂ�q���p�����ጸ�Ɍ��������g�݂�ϋɓI�ɐi�߂�r�q�����Ȃɂ����Ă��K�v�ȑΉ����s���r�Ƃ̕������������B18�N5���̕��Ăɂ͂Ȃ������u���Ǝ҃R�X�g�̒ጸ�v�����荞�܂ꂽ�̂ł���B
��͂�A�s���͂䂪�߂�ꂽ�̂ł͂Ȃ����B�d�g�s���ɏڂ����W���[�i���X�g�̏����v�����͂��������B
�u����̈ꌏ�́A���v�h�̏��ыc����18�N5���Ɉ��̕�������������A�x����ԂɂȂ���WG�����������Ⓦ�k�V�ЂɁg�����D�فh�Ƃ���ɗ��p���ꂽ�悤�Ɍ����܂��BWG���s���Ă��邳�Ȃ��̐ڑҍU���ł�����A���k�V�ЂɗL���Ȍ��_�������ꂽ�\���͔ے�ł��܂���B�����Ȃ̌��؈ψ���͍���A�O��I�ɓ˂����������K�v�ł��v
���ڍׂȁu�c���^�v�����J���A�g�^�f�̖{�ہh�ɐ荞�ނׂ����B�@ |
 �@3/3 �@3/3 |


 �@
�@ |
|
����l10���~�����@NTT���R�c�O�L�ƒJ�e�����R�c���ɍ��z�ڑ� 3/3 |
���`�̎̒��j�E�������������E�߂铌�k�V�Ђ���ڑ҂���A�����̒������������J�e�N�F�E�����ȑ����R�c���ƁA���^�̎���Ԕ[�Ɠ��t�L���E�Ɏ������R�c�^�M�q���B2�l���ANTT��������z�Ȑڑ҂��Ă������Ƃ��u�T�����t�v�̎�ނŕ��������BNTT�͑�����b���玖�ƌv��Ȃǂ̔F���Čo�c����Ă���A�����Ȋ�����NTT�����狟���ڑ҂��邱�Ƃ́A���ƌ������ϗ��@�ɒ�G����^��������B
2�l��ڑ҂��Ă����̂�NTT���V�c���В���A�q��ЁENTT�f�[�^�̊�{�q�j�O�В�(�����k��)��ANTT�O���[�v�̊����B
�R�c�����ڑ҂����̂́A��N6��4���B�����R�c���͑����R�c��(���ےS��)�̔C�ɂ���A�����ȍ��ې헪�ǒ��̊����p�i���ƂƂ���NTT�O���[�v�̊֘A��Ђ��^�c���郌�X�g������K��Ă����B�ڑ҂����̂�NTT���V�c���В��Ɩk���������s�����B4�l�̈��H��͑��z�Ŗ�33���~(�����O)�������BNTT������Ƃ�100���~�P�ʂ̔N����X���Ɏx�����Ă���A�����Ƃ̏ꍇ�A�����4�������ɂȂ�B
����A�J�e������N7��3���ɓ����X�Őڑ҂��Ă����B�ڑ҂����̂�NTT�f�[�^�̊�{�O�В��B�����A�O���R�c������������������(���C���h�l�V�A��g)�����Ȃ����B�v4�l�̈��H��̍��v�͖�19��3��~�B
�܂��J�e����2018�N9��4����9��20���ɂ����X�Őڑ҂��Ă����B
9��4����NTT�В���ޔC��������̉L�Y���v���k����3�l�ʼn�H���A���z30��2��~�ƈ�l10���~����ڑ҂����B
9��20����NTT���V�c�В���3�l�ʼn�H���A���z8��7��~�B
�J�e���ɑ���NTT������̐ڑ҂́A3�v�̑��z��58���~���A�J�e�������ڑҊz�͌v17���~����v�Z�ɂȂ�B�܂������Ȃɑ��āA�K�v�ȓ͏o���o���Ă��Ȃ����Ƃ����������B
�R�c���ɂ͓��t�L���A�J�e���ɂ͑����Ȃ�ʂ��Ď��₵�����A�͓����Ȃ������BNTT�L�́u�������T�������Ē����܂��v�Ƃ����B
�J�e���͂���܂Łu���k�V�ЈȊO�̉q�������e�ЁA������NHK�A���邢�͒ʐM��Ђ̎В�����ڑ҂������Ƃ͂���܂����v(3��1���E�O�@�\�Z�ρA�X�R�_�s�c���̎���)�Ɩ���A�u�������ϗ��@�Ɉᔽ����ڑ҂����Ƃ������Ƃ͂������܂���v�ȂǂƓ����Ă����B�ߋ��̍���قƂ̐����������ꂻ�����B
|
|
���R�c�^�M�q�����m�s�s������ڑҕɁu���@�A���E�������R�����������v 3/3 |
�R����Y�@����w������3���A�c�C�b�^�[�ɐV�K���e�B���`�̎̒��j�E���������߂�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv�����7��4��~�̐ڑ҂������Ƃ���莋����A���t�L�����E�����R�c�^�M�q���炪�m�s�s��������z�Ȑڑ҂��Ă����ƕ����t�I�����C���̋L�������p���A���̃̕^�C�~���O����u���@�A���E�������R�����������v�Ɛ��������B
�R�����́u�m�荇������R�s�[�𑗂��Ă�����ēǂ�ŁA�т�����V�v�Ɛ�o���A�u�R�c�L�����@�A���E�������R�����������B�������ł͎��E�����������ȁA�Ԗ؎��̉�����̎�L���v�ƂÂ����B���̏�ŁA�����́u�s���̕��s�𑼐l���̂悤�ɕ��u���鐭�������ɂ́A�l�ԂƂ��Ă̗ǐS��i�������@���Ă���v�Ƌꌾ��悵���B
�u�T�����t�v�̕ɂ��ƁA�R�c�����m�s�s�̐ڑ҂����͍̂�N6���ŁA�����A�����͑����R�c���߂Ă����B�܂��A���k�V�Ђ���̐ڑ҂Ō����̒������������J�e�N�F�E�����ȑ����R�c������N7���ɓ����X�Őڑ҂��Ă����ƕ��Ă���B�@ |
|
������݉���ɒf��Ȃ�����@3/3
|
�����́u�̒��s�ǂȂ��ނȂ��v�Ɠ˂�������
�R�c�^�M�q����3��1���A���t�L�����߂��B2��25���̏O�@�\�Z�ψ���ł͓��k�V�Ђ���̐ڑ҂͔F�߂���ŁA�u�E���𑱂��Ă������ŁA��������P���Ă��������v�Ǝ��C��ے肵�Ă����B����Ȃ̂ɁA�u�̒��s�ǁ����@�����\��o���v�ƈ�]�B���k�V�ЂɋΖ����鑧�q�̕��ł��鐛�`�̎��u�����̍L�Ƃ��Ċ��҂��Ă���̂ŁA���̂܂ܐ�O���Ăق����v(24��)�����]�A�u�̒��s�ǂȂ��ނȂ��Ɣ��f�����v(1���A�O�@�\�Z�ψ���)�Ɠ˂��������B
���������u�L���C�v�Ɣ��f�����̂́A�u�����̑��q�̂����ŁA�����̔��F�����L�����߂�v�Ƃ������Ƃ������������������Ȃ��������炾�Ǝv���B26���ɗ\�肵�Ă����L�҉������߂��̂́A�قƂڂ���܂����肾�����낤�B���A�u�R�c�L�B���v�Ɣᔻ����A�����́u�Ԃ牺����v�ł����ǁA�ڑҖ����ꂽ�B�ǂ����Ă��u���q���R�c�v�ƂȂ�Ƃ������Ԃɂ��痧���A����͈�C�Ɏ��C�ցB����Ȃӂ��ɑz������B
�����ǁA����ȓW�J�A�f�l�̎������đz���ł���B���Ƃ����l�́A�ǂ݂̊Â��A�����Z���X�̂Ȃ��ɉ����A�₽���������Ă��܂����B�u���Ȃ��Ȃ�A�ŏ����玫�߂����Ă��v�Ǝv���B�̒��������Ȃ�قǁA�ǂ��l�߂�ꂽ�R�c����B�ڑ҂������Ƃ͏\���ɖ�肾���A�����ƕʂȖ��������ł����͂����B
���Ȃ��u���݉��f��Ȃ����v�Ƃ����b����o�����̂�
�X��N��������������ɍL�܂������t�ł����Ȃ�A�R�c����́u�킫�܂��Ă��鏗�v�ɈႢ�Ȃ��B�����炱���A���t�L�ɂ܂ŏ��l�߂��B�����āA���ɐ헪�I�ɏ���Ă������l���B�u���݉��f��Ȃ����v�Ǝ��������Ęb��ɂȂ�������́A���ݔ���J�ɂȂ��Ă���B���A���ׂĂ�����ƁA���ɉ��̐[���u�R�c���헪����v�ɂȂ��Ă����B
���߂Đ�������ƁA�R�c�������R�c��������20�N6���A�u�����狦��v(��E���{�R�G�����呍��)�̋��߂ɉ����Ċ����̂��B���ꂩ��̎�҂�3�̃��b�Z�[�W������ƌ����A�ŏ���2���u�j���[�m�[�}���v�u�O���[�o���Љ�v�ƌ�����B�ǂ�����u�l�b�g�Љ�ƃl�b�g���p���������A�����������Ƃ����Ȃ����v�Ƃ������e�ŁA�����狦��́uIT���琄�i�v�Ƃ����ݗ���|�ɓY�������̂��B
������3�ڂ́u�K�^��������́v�ŁA�����Ɂu���݉�v���o�Ă���B����Ƃ܂�ŊW�̂Ȃ����e�ŁA�ޏ��ɂ��Ă݂�T�[�r�X�Ƃ������e�ؐS�Ƃ������A�u�Ō�ɁA�������Ƌ����Ă��[����v���������낤�Ƒz������B
�ŁA�Ȃ����ꂪ�u�K�^��������́v���������Ƃ����A���M������������ɈႢ�Ȃ��B
�������u���݉��f��Ȃ����v����������悭�킩��
�R�c����́A�u�������v�̃|�X�g�����X�Q�b�g���Ă������l���B2013�N�A���{�W�O���t�Łu�������̓��t������b�鏑���v�ɂȂ�A15�N�Ɂu�����ȏ��̏����ǒ�(���ʐM���ې헪�ǒ�)�v�A16�N�Ɂu�S�ȏ��̏�����b���[��(�����ȑ�b���[��)�v�ɂȂ����B�����R�c���Ƃ������Ȃ̏������̎������|�X�g�ɂ����̂́A���̓���̑O�N�B���݂��݂Ƃ킪�g��U��Ԃ�A�u���͍K�^�������Ă����v�Ƃ������ȍm�芴�ł����ς��������낤�B
�ł́A�ޏ��̎v���u�K�^��������́v�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��B�ŏ��Ɍ������̂��A�u���т���������v���W�F�N�g�v�u�`�����X�������l�v�ɏ����K�^���݂Ȃ���肤�Ǝv���܂��A�������B�K�^����֍s�����Ă����u���Ɓv�Ɓu�l�v�ɏo����ƁB�����R�c����͒�`����B
���������̘b�������Ă��������ƁA���͎R�c����Ɠ��w�N���B�R�c����1960�N���܂�A���͑����܂��61�N���܂�B����83�N�A�R�c�����84�N�ɏA�E�����B�V���L�҂ƍ��ƌ������B�E��͈Ⴄ���A86�N�{�s�́u�ٗp�@��ϓ��@�v�ȑO�Ɏd�����n�߁A�������璷���������Ƃ����_�ł͓������B�����u���݉��f��Ȃ����v����������A�R�c����̃��b�Z�[�W�͂悭�킩��B
���u�`�����X�������l�v�������ɂ����ēw�͂���
�����A�قƂ�ǂ̐E��ɂ͒j���������Ȃ������B���ł͂��������j�����m�������߂��Ă��鐢�E���A�u�z���\�[�V�����Љ�v�Ɛ������\������悤�ɂȂ����B���A�����͂����������t���Ȃ��A�����ɓ����Ă����������͂Ƃɂ�����T��Ői�ނ����������B
�z���\�[�V�����Љ�́A�j���m�ŕ]�������肳�ꂽ�肷��̂��f�t�H���g���B�R�c����̃��b�Z�[�W�ɂȂ炦�A�����Ɂu�`�����X�������l(���j��)�v�͔��ɒ������B�����āA�`�����X�������j�������Ȃ��ẮA�u���т���������v���W�F�N�g�v�ɂ����Ȃ��B������A���������l�ɏo������璴���b�L�[�B������]������j���́A���ꂾ���Ō���ڂ�����B������A���̐l�ɂ��Ă������A�I�[�B�Ⴂ���̎��́A����Ȃӂ��ɐ����Ă����B
�����āA�������炪�R�c����̎R�c����䂦��ɂȂ�B�R�c����̓r�f�I�̒��ŁA�����������B�u�������A�ǂ��v���W�F�N�g��l�ɏ����m���Ƃ����̂́A�l�ɂ���Ă����Ⴄ�͂��͂���܂���v�B�Ⴂ�́A�u�����̐l�ɏo��A�`�������W���Ă��邩�v�ł���A�Ǝ咣���Ă����B
�܂�R�c����A�u(������)�`�����X�������l�v�ɉ���߂ɂ́A�o��̉𑝂₳�˂Ȃ�Ȃ��A�ƌ����Ă���̂��B�u�o����烉�b�L�[��������Ă����v�����Ȃ�A�u�����ɂ����ēw�͂���v���R�c����B����͂܂�ňႤ�B
���u�f��Ȃ��v���|���V�[�Ƃ��Ă����Ƃ���������
�ޏ��ɂ͂��̎�@�ŏ��l�߂��Ƃ�������������B������A�����A�h�o�C�X����B�u�C�x���g��v���W�F�N�g�ɗU��ꂽ���ɒf��Ȃ��B�܂����݉���f��Ȃ��B�f��l�͓�x�ƗU���܂���A�K�^�ɏ����@��������Ă����܂��v�B�����āA��̃Z���t�ɂȂ�B�u�܂������g�A�d�����������Ȃ�ł����ǁA���݉���ɒf��Ȃ����Ƃ��Ă���Ă��܂����v�B
��قǏ������悤�ɁA�������݉�͒f��Ȃ����������B�]�v�Șb�����A���Ђ��čŏ��ɖJ�߂�ꂽ�̂��A���̑傫���ƃA���R�[���̋����������B�P���ɂ��ꂵ���������A�܂������o�Ɉ������̂��Ƃ��B�������A����͎������łȂ��A������Łu���v�����E���ɂ��������ɂ́A�ĊO�u���ނ��Ƃ���ɂ��Ȃ��v�^�C�v�����������悤�Ɏv���B
�Ƃ��낪�A�R�c����͈Ⴄ�B�u���ށv�ɂ��헪���Ƃ������A���͂����ӂ�Ă���B�����ƌ����Ȃ�A�u��Ɂv���B�u��ɒf��Ȃ����Ƃ��Ă���Ă����v�Ƃ͂܂�A�u�f��Ȃ��v���|���V�[�Ƃ��Ă����Ƃ������Ƃ̕\���B���w�N�Ƃ��āA����A�������Ǝv���B
���Ȃ��ޏ��قǂ̏������\���䂩�狎�邱�ƂɂȂ����̂�
�u�ٗp�@��ϓ��@�v�Ȍ�̌�y�����ċ������̂��A�u�ϓ��������̂́A�ٗp�@�������Ȃ����v�Ɠ{���Ă������Ƃ��B
���Ќ���j���W�Ȃ��A���C���X�g���[������߂�Ǝv���Ă����B����Ȃ̂ɁA�����̓S���S���̒j�Љ�B�ƈႤ����Ȃ����Ɠ{���Ă����B�ޏ����������āA�����̓��C���X�g���[���̎�O����O�A�u��Ђɓ���Ă��������������ł��肪�����v�Ǝv���Ă������ƂɋC�Â����B�����āA���قǂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�ϓ��@�ȑO�̏����ŁA�ŏ����烁�C���X�g���[��������C�܂�܂�Ƃ����^�C�v�͏��Ȃ������悤�Ɏv���B������A�R�c������Ă������ȁ[�A�Ƒf���Ɏv���B
����Łu���݉�v�����R�c��������āA���̓���A���炩���Ă��܂��̂������Ȃ��Ȃ��A�Ǝv������������B�����Ƃ��Ă̐T�d���������t�����̌���������A���Ȉ��Ƃ������S�\���Ƃ������A�����������̂������Č�����̂��B�u7���~�������������ꂿ������̂ˁ[�v�Ƃ����ڂŌ���ƁA���ꂪ��l�̂�����̂悤�ɂ���������B
�J��Ԃ����A�R�c����͂������������B����n�}��`���A���X�ƕ����Ă����B����Ȃ̂ɁA�ǂ��l�߂���`�ŕ\���䂩�狎�邱�ƂɂȂ����B���ꂪ�j�Љ�̌����������Ƃ���ƁA�Ȃ��ޏ��قǂ̏����������������ƂɂȂ��Ă��܂����̂��낤�Ǝv���B
���ޏ��́u�����Ȃ̏펯�v�ɏ]�����̂��낤
�ޏ��ɂƂ��āA���{�W�O�O�Ɛ��́u�`�����X�������l�v�������B����̂��Ƃʼn��߂āu���@�ɂ�銯���x�z�v�̖��_����������ɂ��ꂽ�B���A�ޏ��l�ɖڂ����A2�l�������炵���u�v���W�F�N�g�v�Ń`�������W���A���ʂ��o���������Ƃ������邾�낤�B
���G�ȋC�����ɂ�����̂́A�R�c����Ɂu�ߏ�K���v�����邱�Ƃ��B���̒��j����������A���k�V�ЂƂ������Q�W��Ƃ̉�H�B�͂��������A������x���킸�B�\�Z�ψ���ŎR�c����́u�C�̊ɂ݁v�Ɣ��Ȃ�������B
�v���ɔޏ��́u�����Ȃ̏펯�v�ɏ]�����̂��Ǝv���B�u�̑��q���o�Ȃ���̂��A�f��Ȃ��v�Ȃ̂��u�s���Ă����đ��͂Ȃ��v�Ȃ̂��u�s���Ȃ��ᑹ�v�Ȃ̂��A����͂킩��Ȃ��B�����炭��������̏펯�ɏ]�����B���Ȃ�̍����X�Ƃ킩���Ă���̂Ɂu�܁A�������v�Ǝx����Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��ł���̂��A���ꂪ�u�펯�v�Ǝv���Ă������炾�낤�B
���u���l�͗����v�ƌ�����͂��̗��ꂾ�����̂�
�}�C�m���e�B�[�̋��݂Ƃ́A�u���l�͗����v�ƌ����邱�Ƃ��B�ڑ҂���Ă�������ł����H�@��������Ȃ��Ă����ł����H�@�u���l�v�ɑ��Ă��A����������B�z���\�[�V�����Љ�ŁA�����͂��̖������ʂ�����B���ꂪ�s���l�܂����Љ��ς���B��̎�i�B����Ȃӂ��ɂ����A�v���Ă���B
�R�c����́A�}�C�m���e�B�[�ł͂Ȃ��}�W�����e�B�[�̘_���ɓK�����Ă��܂����B�����甲�F�����̂��A���F����邩�炳��ɓK������̂��B�j�Љ�ɒn�}��`���A����������l�Ȃ̂ɁA���ꂪ�������c�O���B
�ޏ��̎��C���A���߂ċC�̊ɂ݂������������ւ̓��勉�̌x���ƂȂ��Ăق����B���w�N�Ƃ��č��A�v���Ă��邱�Ƃ��B�@ |
 �@3/4 �@3/4 |


 �@
�@ |
|
���R�c�O�L�̐ڑҁA���[�����u���ɑޔC�A�m�F���Ȃ��v�@3/4
|
4���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA���Y�}�̓c���q�q���́A�����Ȃ̒J�e�N�F�����R�c���畡���̓��Ȋ�����NTT�O���[�v�����獂�z�Ȑڑ҂��Ă����ƏT�����ɕ�ꂽ����Njy�����B
�ɂ��ƁANTT������ڑ҂��ꂽ�̂́A�J�e���ƁA�����Ȃ̊����p�i�E���ې헪�ǒ��ƎR�c�^�M�q�E�O���t�L��3�l�B�R�c���́A���`�̎̒��j���߂�����֘A��Ёu���k�V�Ёv���獂�z�ڑ҂��Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�A3��1���t�Łu�̒��s�ǁv�𗝗R�Ɏ��E���Ă���B
�c�����́A�R�c�������E�������ɁANTT������̐ڑ҂̎�����m���Ă������ɐq�˂����A�́u���m���Ă��܂���v�Ɠ��فB�c�������d�˂ĎR�c���Ɏ����m�F���邩�₤�ƁA�������M���[�������u(�R�c����)���ɑޔC����Ă���܂��̂ŁA�������玖���m�F���闧��ɂ͂Ȃ��v�Ɠ��ق����B
�ψ�������u���[���v�Ƌ^��̐���������Ȃ��A�c�����́u�������͐ڑҖ��̋��������闧��ɂȂ��̂��v�Ɛ��{�̑Ή������������B�����A�́u�����̓��[���Ɋ�Â��āA��������Ή����Ă��܂��v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂��B
�c�����͑����āA�J�e����NTT������̐ڑ҂̎����W��q�˂��B�Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��Ă����J�e���́u�܂������āA�����݂̂Ȃ��܂ɂ���Ȃ�^�O��������邱�ƂɂȂ����_��[�����Ȃ��A����т�\���グ�����v�ƒӁB
���̏�ŁA���ꂽNTT���Ƃ�3��̉�H�ɂ��āu���̂悤�ȉ���������ƔF�����Ă���v�ƔF�߂��B����A�o�Ȏ҂��̓I�ȋ��z�ɂ��Ă͊m�F���Ƃ����B
|
|
���R�c�O�L�̂m�s�s��H�@�������u��ʂ̕��v�����m�F�͍s��Ȃ� �@3/4 |
���`�̎̒��j�炩�獂�z�ڑ҂��Ď��E�����R�c�^�M�q�O���t�L���A�m�s�s�В���Ƃ���H�����Ă����ƏT�����t�ŕ�ꂽ���Ƃɂ��āA���{��4���̎Q�@�\�Z�ψ���ŎR�c���Ɏ����m�F�����Ȃ��l�����������B���Y�}�̓c���q�q���̎���ɓ������B
���́A�R�c����3��1���Ɏ��E�����ۂɂm�s�s�В���Ƃ̉�H��m��Ȃ������̂��Ɛq�˂��u���m���Ă��܂���ł����v�Ɠ������B�c�������u(��H���)�T�����t�͓��t�L����Ȃ�ʂ��Ď����m�F�̎�����������A���Ȃ������Ƃ��Ă���B���k�V�Ђɂ��ڑ҂�����̍Œ��ɑ����̎��ɓ����Ă��Ȃ������̂��v�Ɗm�F����ƁA���́u���m���Ă��܂���ł����v�ƌJ��Ԃ����B
����ɓc�������u�R�c���ւ̎����m�F�͓��R�s���܂��ˁv�Ɛq�˂�ƁA�������M���[�����́u���ɑޔC����Ă���̂ŁA�������玖���m�F���闧��ɂ͂Ȃ��Ǝv���Ă���v�Ɠ��فB�c�������u�Ȃ������m�F����Ȃ��̂��@�v�Ǝ��₷��ƁA�������[�����́u���ɑޔC����Ĉ�ʂ̕��ɂȂ��Ă���킯�ł�����A���{�����m�F���闧��ɂ͂Ȃ��v�Ɛ��������B
�c�������u����ł͐������͐ڑҖ����������闧��ɂȂ����ƂɂȂ�v�ƒNjy����ƁA���́u�����̓��[���Ɋ�Â��Ă�������Ή����Ă���v�Ǝ咣�����B
|
|
�������ȁE�J�e�N�F�R�c���@NTT�Ɖ�H�F�߂�@�Q�@�\�Z�ςŒӁ@3/4
|
�����Ȃ̒J�e�N�F�����R�c����4���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA���g��NTT������v3��ɂ킽�荂�z�ڑ҂����Ƃ����T�����ɂ��āu���̂悤�ȉ�H�͂������ƔF�����Ă���v�Əq�ׁA��H�����ƔF�߂��B���`�̎͗\�Z�ςŁu�����Ȃɂ����ēO�ꂵ�Ē������Ă���v�Əq�ׁA�����Ȃ������W���m�F���Ă���Ɩ��炩�ɂ����B
���Ȃ͒J�e����ɂƂǂ܂炸���̐E�����ΏۂɁA�u���Q�W�ҁv�ɂ���������A�ʐM���Ǝ҂����@���̂���ڑ҂��Ă��Ȃ���������������B8���̎Q�@�\�Z�ϗ������k��ŁA���ԕ����錩�ʂ��B
�J�e���͗\�Z�ςŁu�����ɂ���Ȃ�^�O��������邱�ƂɂȂ������Ƃ�[�����Ȃ��A����т������v�ƒӂ����B��H�����ړI�ɂ��Ắu���e�Ə��ʐM�W�S�ʂɂ킽��ӌ������������v�Ɛ������������ŁA�u����̒������z�ɂ��ĕ��S���s�����B(���ƌ�����)�ϗ��@�ɂ͒�G���Ă��Ȃ��ƔF�����A��b���[�ɕ��Ȃ������v�Əq�ׁA�����Ȃɂ͓͂��o�Ă��Ȃ������Ɩ��炩�ɂ����B���Y�}�̓c���q�q���ւ̓��فB
4�������̏T�����t�ɂ��ƁA�J�e����2020�N7��3����18�N9��4�A20�����ANTT�O���[�v�̊֘A��Ђ��^�c���铌���s���̃��X�g�����ŁANTT�f�[�^�̑O�В���NTT�̎В��炩��ڑ҂����B�v3��̈��H��͑��z58���~���A�J�e����20�N7���̐ڑ҂ł�5000�~���u���v�Ƃ���NTT���Ɏ�n�����Ƃ����B
�܂��A�̒��j������ڑ҂��ē��t�L����������ӎ��E�����R�c�^�M�q���Ɠ��Ȃ̊����p�i���ې헪�ǒ�����N6��4���A�������X�g������NTT�̎В��炩����H�㑍�z33���~�̐ڑ҂��A�����͊e1���~���x�������ƕĂ���B�R�c���͓����A�����R�c���������B
�����Ȃ�4���̖�}�����q�A�����O�ŁA����������H�̎�����F�߂��Ɩ��炩�ɂ�������ŁA�R�c���ɑ��Ă͎����m�F�����Ă��Ȃ��Ɛ��������B����Ɋւ��������M���[�����͗\�Z�ςŁu(�R�c����)���ɑޔC���Ĉ�ʂ̕��ɂȂ��Ă���A���{����m�F���闧��ɂȂ��v�Əq�ׂ��B
���ƌ������ϗ��K���́A���Q�W�҂��狟���ڑ҂��邱�Ƃ��ւ��Ă���A��}�́u�ϗ��K���ɔ�����ڑ҂��v�Ƃ��ĒNjy�����߂Ă���B
|
|
�����ANTT�ڑ҂̒����O�ꂵ�Ώ��@�J�e�����R�c���A��H�F�ߎӍ߁@3/4
|
���`�̎�4���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA�����Ȃ̒J�e�N�F�����R�c���炪NTT�������獂�z�̐ڑ҂������ɂ��āA���Ȃ����肵�������ɐG��A�u�����W�̊m�F��O�ꂵ�A���[���ɂ̂��Ƃ��đΉ����Ăق����v�Əq�ׂ��B
�Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ����J�e���́u3��ɂ킽���H�v��F�߁A�u�����ɂ���Ȃ�^�O��������邱�ƂɂȂ����B�[�����Ȃ��A����т������v�ƎӍ߂����B
�J�e���̐����ɂ��ƁA��H��2018�N��2��A20�N��1��ŁA�ړI�́u���e�Ə��ʐM�W�S�ʂɂ킽��ӌ������v�������Ƃ����B18�N��NTT���A20�N�͋��ʂ̒m�l����ē����������Ƃ������ANTT���̏o�Ȏ҂���H��̋��z�́u��b���[�Ŋm�F���Ă���v�Ƃ��Ė������Ȃ������B
���Y�}�̓c���q�q���́u���ƌ������ϗ��K���ɔ�����ƌ��킴��Ȃ��v�ƒNjy�B�J�e���́u���ꂽ���z�̕��S���s���A��G���Ȃ����̂ƔF�����Ă����v�Ǝߖ������B
�J�e���Ɠ��l��NTT��������ڑ҂����Ƃ����R�c�^�M�q�O���t�L�Ɋւ��A�������M���[�����́u�ޔC���A��ʂ̕��ɂȂ��Ă���v�Ƃ��āA�����m�F�͍s��Ȃ��l�����������B�͈�A�̐ڑҖ��ɂ��āu���[�����������菇�炵�āA�����ȐE�����s��O�ꂵ�Ăق����v�ƌ�����B�c�����A��������}�̑����M�玁�ւ̓��فB�@
|
|
���J�e�����m�s�s�̐ڑҔF�߂�@���U���ً^���Ɏߖ��@3/4
|
�����Ȋ����ɂ��V���Ȑڑҋ^�f�����o�����B4���̎Q�@�\�Z�ψ���ŋ��Y�}�̓c���q�q���́A�ʐM���Ƒ���NTT��c���В���ƁA3�x�̉�H�������Ƃ����J�e�N�F�����R�c����Njy�����B�J�e���́A�u��H�ł͐�����������z�S�����v�Ƃ�����Ŏ����ł��邱�Ƃ�F�߂��B
�J�e���瑍���Ȋ����́A���`�̎̒��j���Ζ�����������Ǝ҂���ڑ҂��A2��24���ɓ��ȐE��11�l�ɒ�������������������B����܂ł̍���قŒJ�e���́A�������ƎЈȊO�̐ڑ҂�ے肵�Ă����B�c�������A���U���ق̋^�����w�E�������A�J�e���́u���ƌ������ϗ��@�ɂ͒�G���Ȃ����́A�Ƃ��ĕ��Ȃ������v�Ǝߖ������B
�c������NTT�O���[�v���獂�z�ڑ҂����A�ƕ�ꂽ�R�c�^�M�q�O���t�L�ɂ��āu���t�{���A�ǂ��Ȃ��Ă���̂��v�Ɣᔻ���A�����W�̊m�F�����߂����A�������M���[�����́u���łɑޔC����āA��ʂ̕��ɂȂ��Ă���킯�ł�����A���{�����m�F���闧��ɂȂ��v�Ƃ����B�@ |
|
��NHK��u���肢�͐��X���X�Ɓv�@�����ȐڑҖ��@3/4
|
NHK�̑O�c�W�L���4���̒���ŁA�����Ȋ������������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv��NTT�̐ڑ҂��Ă������Ɋւ��A�u��A�C�ȗ��A�ڑ҂��ĉ�������Ă��炤�Ƃ������Ƃ͈����Ȃƌ����Ă���A���肢����Ƃ��͐��X���X�Ƃ��肢����v�Əq�ׂ��B
�O�c��́ANHK�����̌��۔��N�x�A12�l�̑��v�Ŗ�1200���~�������Ƃ��A�u���g�����\����̂́A������̂��Ƃ�����̂Łv�ƏڍׂȐ����͔������B�����A��O�҂ł���NHK�o�c�ψ���Ɗč��ψ�����e���`�F�b�N���Ă���A�u�s�K�Ƃ̎w�E�������Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ����B
��A�̖��ł́A�����Ȋ�����NHK�����Ɖ�H���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B�O�c��́A���g����ɂȂ��Ă���͂��肢�͐��X���X�Ƃ��Ă���Ɛ������A�u������������Ă��������v�Ƙb�����B
|
|
���R�c�^�M�q���@���\����{�C�R�b�g 3/4�@ |
�R�c�^�M�q���������ȏ�ʍs���ǒ��̐E�ʂɂ����������ɁA���k�V�Ўq��Ђ̉q���������Ɖ�Ђ��s���R�ȔF���B����������������߂铌�k�V�ЃO���[�v�̎q��Ёu(��)�͌鏫���`�����l���v��2018�N�ɑ����Ȃ���u���o110�xCS�����ɌW��q��������̋Ɩ��F��v�����B���̔F���ɂ߂ĕs���R�ł���B
�����A�����Ȃ̓n�C�r�W��������i�߂邽�߂ɉq��������̑啝�ȑg�ݑւ����s���Ă����B�F��ɂ����Ă̓n�C�r�W���������ł��邱�Ƃ��d�����ꂽ�B���ہA���̂Ƃ��F�����12��16�ԑg�̂����A11��15�ԑg���n�C�r�W���������������B
�Ƃ��낪�A�u�͌鏫���`�����l���v�ԑg�����A�n�C�r�W�����ł͂Ȃ��W���掿�����ł���̂Ɋ�����̋Ɩ��F������B���̔F������肵����ʍs���ǂ̃g�b�v���R�c�^�M�q���������B
���̎R�c���������ȐE���i���o�[2�̑����R�c���̐E�ʂɂ������A�^�f�F�̗��N�ɓ��k�V�Ђ���ߏ�ڑ҂����B1�l7��4,000�~�̈��H�����ڑ҂����B���k�V�Љq���������Ǝq��Ђ̖����͗��Q�W�҂ł���A�������ϗ��K��Ɉᔽ����B�������A7��4,000�~�̍��z�ڑ҂͎��d�߂���������\���̂�����z���B
����ɏ��v���Đ��������߂Ă��A�����ȏ؋����Ȃ�����A������ł܂����̖��ɂȂ�Ȃ����ق��s�����Ƃ͖ڂɌ����Ă���B
TBS�̏��ԑg�ɏo������R�����e�[�^�[���R�c�^�M�q���̐������^�������ATBS�͍H����܂����̒��V��̂悤�ȃR�����e�[�^�[�N�p����߂�ׂ����B���j���̏��ԑg�ł��A�i��҂�o���҂��H����ł��邱�Ƃ���������悤�Ȑ����i�씭�����J��Ԃ��B
�d�g���f�B�A�̐��E�^�D�̌����ȏ�ʍs���ǂ������Ă���B���̎x�z���ɒu����Ă��邩��A�e���r�ǂ͐����H����I�Ȑl����ԑg�̗v���ɔz�u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���A���ɂ����ł���Ȃ�A�o�b�W�Ȃǂ�t�������āA�����҂ɂ킩��悤�Ȕz�������ׂ����B
�u��p�o�b�W�v�̂悤�Ȃ��̂삵�āA��p�R�����e�[�^�[�A��p�i��҂ɂ͂��̃o�b�W��t��������B���ꂪ����A�����҂͌�p�����������Ă��A�u����͌�p�l�̔����v�ƔF�����Ď~�߂邱�Ƃ��ł���B
�C���^�[�l�b�g��̃j���[�X�|�[�^���T�C�g�ɁA�j���[�X�L�������L�����U��߂��Ă���B�������A�悭����ƁuPR�v�̕\�������Ă��邩���ʂ̋L���Ƌ�ʂł���B�e���r�ɓo�ꂷ��u��p�l�v�ɂ��ẮA���̑������킩��悤�Ɂu��p�o�b�W�v��t�������Ď����҂ɔz�����ׂ����B
�e���r�ǂ�����I�ɑΉ��ł��Ȃ���A�s�����R�����e�[�^�[���̑�����]���A���f����i�t�@�֓I�ȑ�O�ҋ@�ւ𗧂��グ�āA�L���s���ɏ������m������K�v�����邾�낤�B���̈���ŁA�������͂ɑ��Ă��������ᔻ��W�J����ǎ��Ȏ��҂���ʂ��牓�������Ă���B���̃}�X���f�B�A�ɂɂ�݂𗘂�����̂������ȏ�ʍs���ǁB
���`�̎��͐����ɋ��z�̎����x�����s����Ƃɒ��j����Ђ������B�e�̃R�l�œ��Ђ������Ƃ͋q�ϓI�Ɍ��ĊԈႢ�Ȃ��Ǝv����B
�o���h�}�������ĂԂ�Ԃ炵�Ă��������������A�������������ɏA�C�����ۂɑ�b�鏑���ɋN�p�����B���������͑�b�鏑����ސE������A���k�V�Ђɓ��Ђ����B
��b�鏑������ɑ����Ȋ����Ɩʎ����B���k�V�Ђɓ��Ђ��A�q���������Ǝq��Ђ̖������������āA�����Ȋ����ɑ����@�ڑ҂�簐i�����̂������������B
�����瓌�k�V�Њ����ɂ�鑍���Ȋ����ɑ����@�ڑ҂̏�ł́A�q���������Ǝq��Ђ̋Ɩ��ɂ�������b�����Ă������Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B
�����Ȋ����͍���ɏ��v����ĒNjy����Ă��E�\��˂��ʂ��Ă����B�������A�����f�[�^�Ƃ�������I�ȏ؋���˂��t������ƁA�������e��ς��Ď�����F�߂��B����ɏ��v���Ă��A����I�ȏ؋����Ȃ���E�\��˂��ʂ��l�������Ȃ̂��B
�����ȏ�ʍs���ǂ͋ɂ߂ĕs�����ȔF���s�����B���̎����̋ǒ��ɑ��ė��N�ߏ�ڑ҂��s���Ă���B���̊W��˂��l�߂�A�����d�����ɔ��W����\��������B
����ł��������ȓ��ق��s���A�����������Ȃ��A���t�L�X�R���Ȃ��A�Ŗ�������}�낤�Ƃ���Ȃ�A�匠�ҍ������ق��Ă��Ȃ��B����1�_�𗝗R�Ɏ��̐��_�����œ��t�s�x�����L���鍑���^���̓W�J���K�v���B
���͓��k�V�Ђ��琭������500���~����̂��Ă���B�����͑�����b�߂���A���t���[�����ɏA�C�����B���t���[�����ɏA�C���A���t�l���ǂ�ʂ��Ċ����l���ɓƍٌ����s�g�����B���̓ƍِl���ɂ���ĎR�c�^�M�q�����ȏ�ʍs���ǒ��ɋN�p�����ƌ��Ď���B
���̎R�c�������k�V�Љq���������Ə���Ђɑ��ĕs���R�ȔF��t�^���Ă���B���k�V�Ђɑ��Đ��`�̎����X��}��A���̌��Ԃ�ɐ��������k�V�Ђ��猻������̂����Ƃ̐}����`�����Ƃ��s���R�łȂ��B���`�̎��Ɠ��k�V�ЂƂ̊ւ�肪��������500���~�����Ȃ̂��B�O�ꂵ���{�����K�v�ł���B
���@�ł̎���R�c�^�M�q�����d�邱�Ƃ��ɂ߂ĕs�K���B�R�c�^�M�q�L�͑����ȍݐE���ɏ�ʍs���ǒ��̒n�ʂɂ������B��ʍs���ǒ��͓d�g�Y�Ƃ��x�z���ɒu���B�d�g�Y�Ƃ̐��E�^�D�̌������镔�ǂ��B�����������̋ǂ�n�݂��āA�d�g�Y�Ƃ̎x�z�����l�������邤���Ŏ哱�I������S�����̂����`�̎����B
���@�ł̋L�҉�ł͋L�҂��玖�O�Ɏ�����o������B���@�͂��炩���ߎ���ɑ��铚�ق������ɗp�ӂ�����B����҂ł���L�҂̒N���w������̂������炩���ߌ��肳��Ă���悤���B�ɑ��Ď��O�Ɏ�����o�����A������������Ԃ���L�҂͎w�����Ȃ��B
�̓������Ă���A���₪�����Ɏc�����Ă���̂ɁA����I�ɉ��ł���B����Ȃ��̂��L�҉�ƌĂ�ł͂����Ȃ��B�u�����\��v�Ƃ��ׂ����B
���������L�҉�͋L�҃N���u����Â�����́B���@�̑��p�l������d�邱�Ǝ��̂����������B���O�Ɏ�����o�������A�t���[�Ɏ��₳����ׂ����B�L�҃N���u�̊����Ђ��i��߂�����ɉ�̕�����ς���ׂ����B
�����鎿��Ƀy�[�p�[�Ȃ��ʼnł���͗ʂ��ɋ��߂���B�������p�ӂ������e��ǂނ����Ȃ�A��ȂNJJ�����A�L�҂���̎���Ɗ������쐬���铚�ق����@HP��Ɍ��\���邾���ł悢�B���̕����Ȃ�A���ׂĂ̎���ɉ��������邱�Ƃ��ł���͂����B
���������e��p�ӂ��Ă��A�������ǂނ��Ƃ���ł��Ȃ��̂�����A�������쐬�������ق�HP�Ɍ��J��������A�ԈႢ���Ȃ��ėǂ��B
�R�c���́u���݉���ɒf��Ȃ����Ƃ��Ă���Ă����v�Ɩ������Ă���B���̂��Ǝ��́A�ɂ߂ĕs�K���B���Ђ̐l��������݉�ɗU���Ă��u��ɒf��Ȃ����v�ł���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B
�������ϗ��K������݂���B�u��ɒf��Ȃ��v�ł́A�ϗ��@�Ɉᔽ����P�[�X���o�Ă���B�u��Ɋ��芨�ŎQ������v���Ƃ�����Ă��Ă��Ȃ��̂�����A���k�V�ЂƓ��l�Ɉ�@�ڑ҂͖����ɑ��݂���Ɛ��@�����B�R�c���ɕK�v�Ȃ��Ƃ́u������ɒf��Ȃ����Ƃ��Ă���Ă䂭���Ɓv���B
���@�ł̎��3���E5���̔��\��B���O�Ɏ�����o�����A���������ق��쐬���čs�����\��́A����ȍ��Ƃ����{������́B�L�҂ɑ��ăy�[�p�[�Ȃ��œK�ɓ��ق���\�͂������Ȃ��Ȃ�ɂȂ�ׂ��łȂ��B�����Ȃ�ƁA�^�}�ł͊Y���҂����݂��Ȃ��Ȃ�̂��낤���A���̏ꍇ�́u�Y���҂Ȃ��v�̂ق����܂��܂����B
���@�̋L�҃N���u�̃����o�[�͍��c�̂����A���@�L�҉�̕����ύX�𐭕{�ɐ\�������ׂ����B�L�҃N���u��Ẩ�ł���Ȃ�A�L�҃N���u������[����K�ɒ�߂āA�L�҃N���u������d��ׂ����B���������Ȃ��Ȃ�A���@���Ǝ��Ɂu���\��v��݉c���ׂ����B
���s�����Ȃ�ǐS���郁�f�B�A�͉���{�C�R�b�g���ׂ��B���{���{�̑O�ߑ㐫�A���f�B�A�̖����̎��A�o���̍��V���K�v�s�����B�܂��́A�R�c�L���d��u���\��v���₩�璅�肷�ׂ����B�@ |
|
�������ȐڑҖ��łȂ������ƂȂ����}�X�R�~�e�Ђ������u����u�[�������v�@3/4 |
���Ȃ��Njy���g�[���_�E���H ���̒��j�����ޑ����ȐڑҖ��
���̒��j�ɂ�鑍���Ȋ����ڑҖ��t���X�b�p�����Ă��炨�悻1�J���A�e���r���V���������������ăg�[���_�E�����Ă����B
�����Ȋ����A���k�V�Ќo�c�w�̏����ɑ����āA���t���̎R�c�^�M�q�������@�E���C���������Ƃ��āA�u����ɂĈꌏ�����v�Ƃ����S���[�h�������o���Ă���̂��B
���Ƃ��A���̖�������Ȃ�ɑ傫�������Ă����e�ǂ̏��ԑg�ł��A�����̃R���i�l�^�A�d�Ԃ̉^�s��~�A5�Ύ��̉쎀�����Ȃǂɒ������Ԃ������悤�ɂȂ��Ă����B�܂��A�����Ȃ�u�^�f�͐[�܂����v�u�[���̂����������v�Ƃ��������ŁA�������H�炢���u�����V���v���A�w�����ȓ�������u�ꂵ��������v�����̎ߖ��A4�̋^��x(3��2��)�ƁA�₯�ɂ��D�����B�u�W�҂̏����Ŗ������v�Ƃ����T�^�I�ȉΏ��������������Ă��A�u�^��v���������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�u��������ȏ�A�Njy����C�͂Ȃ������v�Ɣ��Ă���悤�Ȃ��̂��B
�ƕ����ƁA�u�����҂������ے肵�Ă���̂Ƀl�`�l�`�ƒNjy���Ă��Ă��s�тȂ�������v�u�}�X�R�~�ɂ͓`���Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ����ɂ�����̂��v�ƃ��L�ɂȂ�}�X�R�~�l�����������邾�낤���A����͂��܂�ɂ���Ƃ������A���s����`���߂���B
�^�f��������ꂽ�l�������ǂ�ȂɎߖ������Ă��A�u�^�f�͐[�܂����v�u�[���̂����������v�ȂǂƂ��������ň�؎�荇�킸�l�`�l�`�ƒNjy��������A�Ƃ������Ƃ�����܂Ń}�X�R�~�͓�����O�̂悤�ɂ���Ă����ł͂Ȃ����B
������ƑO���A��������u���̒��ɂ͂����Əd�v�ȃj���[�X���������A���̋^�f��������グ��ȁv�u�i�W���Ȃ����A�����������v�Ƃ����s���̐����������Ă��A�u���ꂼ�W���[�i���Y�����v�Ƌ���Ȃ���A1�N�ȏ���^�f��Njy�����������Ƃ�����B
�����A�X�F�w���E���v�w����肾�B
���u�Ό��v�Ƃ܂ŝ������ꂽ �����J�P���Ƃ͖��炩�ɈقȂ镵�͋C
���{�O���ߕ߂���Ă��Ȃ����Ƃ�����킩��悤�ɁA�����2�̋^�f�ɂ͎̒��ړI�Ȋ֗^�������m����؋����Ȃ��B�܂�A�������ꂸ�A�����҂��ے�������炨��グ�Ȃ̂��B�������A�}�X�R�~�͌����ĒNjy�̎���ɂ߂Ȃ������B
�u�����V���v�̎А�(2017�N9��17��)�ɂ��A�Ƃ̋����ɂ���āA�s�����c�߂��Ă��邩������Ȃ��Ƃ����^�f�́A�u�����`�Ɩ@�����Ƃ̍����ɂ������A�ɂ߂ďd���e�[�}�v(�����V��2017�N9��17��)�����炾�B
�����A�����҂�ǎ҂̊S������Ă��A�e���r��V���͒�����ӂ܂Ń����J�P�A�����J�P�Ƒ����������B���ߖ�������u�M�p�ł��Ȃ��v�u��������v�Ƒe��T�����B���C�h�V���[�ł͓���p�l���Ől�����}��������A�i��҂�R�����e�[�^�[���u�܂��܂���͐[�܂�܂����v��2���ԃh���}�̂悤�ȃZ���t��f���Ă����̂́A�F������悭�o���Ă���͂����B
���̂��܂�ɏ�O���킵���^�f�Njy�L�����y�[���ɁA�ꕔ����́u�Ό��v�u���ő�̕ƍ߁v�ȂǂƂ����ᔻ���N�������A�}�X�R�~�́u�s�����c�߂�ꂽ�v��1�N���������������B���ꂪ�ނ�̍l����u�Љ�`�v���������炾�B
�������A�ǂ������킯������́u���̒��j�ɂ�鑍���Ȋ������z�ڑҁv�́A�킸��1�����ۂ����ő�l�����Ȃ��Ă���B��d�l�i�̂悤�ȕ^�ςԂ�Ȃ̂��B
��������̒��ړI�Ȋ֗^���������͂Ȃ��B�������u�v����������A�����J�P�������͂邩�ɍs�����c�߂��Ă��銴�������͖̂��炩���B
�܂��A������b�������p�p�̗͂ő�����b�鏑���ɏ����グ��ꂽ���q���A�����Ȃ����F����������Ƃ��肪�����Ƃ̕����ɂ����܂��āA�p�p�ɍ��J����Ȃ����Ƌ����鑍���Ȋ��������ɍ��z�ڑ҂����Ă���A�Ƃ����\�}������ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�����J�P�̂Ƃ��ɂ��U�X�w�E���ꂽ�A�l����������ꂽ����������Ɏ̊�]�𗶂�A���肵�āA����̎��Ǝ҂�D������A�Ƃ����u�u�x�v�������N������邩�炾�B
���ہA�����Ȃ̗L���҉�c�u�q�������̖������Ɋւ��郏�[�L���O�O���[�v�v��2018�N�̕��ŁA�E���ш旘�p�g�ɂ��āu���傷�邩�A�V�K�Q�����K���v�Ƃ��������̂��A20�N�̕��Ăł͓��k�V�ЂȂNJ������Ǝ҂̗v�]�ł���u4K���Ǝ҂Ɋ��蓖�Ă�ׂ��v�ɕύX����Ă���B���ꂪ�ڑҍU���ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�f�́A2��25���̏O�@�\�Z�ψ���œ��{���Y�}�̓���ێj�c�����Njy�����B�������A�����J�P�ŕs�m��ȏ��ł���قǑ呛���������}�X�R�~�́A�Ȃ�������́u�Êρv���Ă���B
���ڑ҂́u���v�Ɓu�����v������� �����J�P������قLjł��[��
�܂��A����ɉ����ă����J�P�����u�Łv�̐[����������̂́A�s��ꂽ�ڑ҂̐��Ǝ������B�����Ȋ�����13�l�̐ڑ҂́A2016�N7������20�N12���ɂ����āA�̂�39���B�u����͂������o����Łv�Ƃ��u�������芄�芨�ɂ��Y�ꂽ�v�Ƃ������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u����v�u������v�̊W���r�^�b�ƒ蒅���Ă������Ƃ�����������B
�������A�����J�P���ō����Ȃ̍�������������Œ݂邵�グ��ꂽ���悻���N��ɂ́A���̒��j�炩�瑍���ȑ����ʐM��Ջǒ�(����)���A���H�P��2��4292�~�̐ڑ҂��Ă���B�}�X�R�~���A���̂悤�Ɂu�̉Ƒ��E�F�l�ɜu�x���銯���v��ᔻ���Ă������Ƃ��A�����Ȋ����ɂ����̒��j�ɂ��܂����������Ă��Ȃ������̂��B
����ɁA�ނ�̏�K���E�������������̂��u���U���فv���B�����m�̂悤�ɁA���t�C�ɃX�b�p�����ꂽ�ہA�������������́u�������ƂɊւ���b�͂��Ă��Ȃ��v�ƍ���Ō��������āA�������Ԃ��ăV�����V�����Ɩ�������}�낤�Ƃ����B�������A���̉R�ɑ��āu�҂��Ă܂����v�ƌ�������ɕ��t�������f�[�^�𖾂�݂ɏo���A������n����Ă��܂����̂ł���B
����Ȍ��������̉R�����l�������A�ǂ�ȂɁu���F�ɉe���͂Ȃ��v�ƌ��������Ă��A�M�p�ł���킯���Ȃ��ł͂Ȃ����B
�������A�ǂ������킯���e���r��V���́A���̂�����̂��Ƃɂ܂������˂����܂Ȃ��B�����J�P���̂Ƃ��̂悤�ɕ@���r���A�u����ȖŒ��ꒃ�Șb��M�p�ł��܂����I�v�Ɠ{���Ă���R�����e�[�^�[�͂قƂ�ǂ��Ȃ����A�����J�P���̂Ƃ��̂悤�ɋ���p�l���������āA�������������̌o����f����ڍׂɐ������A���t�@�~���[�Ƃ̐e���x��������������Ȃ��B
�F����A�����J�P���̂Ƃ��Ɍ������u�^�f��Njy���鐳�`�̃W���[�i���X�g�v�Ƃ͂܂�ŕʐl�̂悤�ŁA��Ă����L�̂悤�ɑ�l�����̂��B
�ł́A�Ȃ�����́u�s�����䂪�߂�ꂽ�v�Ƃ����^�f���}�X�R�~�͑����������ăX���[���Ă���̂��B�����J�P���ł���u�������v�u�Ό����v�Ȃǂƒ@���ꂽ���ƂȂ��āA�u�{�l���^�f��ے肵����A����ȏサ�����Njy����̂͂�߂܂��傤�v�Ƃ�����ރK�C�h���C�����ł����\�����[���ł͂Ȃ��B�������A�l�I�ɂ́A�u����u�[�������v������āu���Ȃ����R�v���s�g���Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă���B
�܂�A�u�̑��q�v�u�����̐ڑҁv�Ƃ��������������Njy�������قǁA���̌������Njy���u�[�������̂悤�ɂ��ꂢ�ȕ�������`���āA�}�X�R�~�e�Ђ̌㓪���ɓ˂��h�����Ă��܂��̂��B
���}�X�R�~������K�����X�g�̒��ł� ���ɋC�������u�����ȁv�Ƃ�������
���ǂ��A�}�X�R�~���Ȃ�ł�����ł��D���Ȃ悤�ɕ���Ǝv���Ă���l�̕������Ȃ��Ǝv�����A�e���r��V���ɂ̓^�u�[���������݂���B���z�̍L���o�e��������Ƃւ̔ᔻ�͂������A�L���㗝�X�A������A�V���̔����Ȃǐg���ւ̔ᔻ����S�������邵�A�L�҃N���u��y���ŗ��Ƃ����������v�͊�{�I�Ɂu���݂��Ȃ��v���̂Ƃ��Ĉ����B
����ȃ}�X�R�~������K�����X�g�̒��ł����ɋC�������̂��A�u�����ȁv���B
�������̂悤�ɁA�����Ƌ����K�v�ȃe���r�͑����Ȃ̊ē��ɂ���B����͗���Ԃ��A�����Ȃ̓d�g�E�����s���̂��A�ŁA�V�K�Q���ɋ�������邱�ƂȂ��A�d�g��Ɛ肵�ď������ł��Ă���킯�Ȃ̂ŁA�����Ȋ����ւ̃��r�C���O���ɂ߂ďd�v�ȃ~�b�V�����ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B
������ے�����̂��A�u�g���L�ҁv���B
����͏��a�̎���A�e���r�L�҂̒��ɂ����A�L�����������ɓd�g�E�����s���̃��r�C���O������l�������w�����t�����A���������悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���l���������݂���B�܂�A���x�͈Ⴆ�ǁA���k�V�Ђ́u�������v�Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ����Ă���Ǝv�����l�����́A�e���r�ǂȂǂ̕������Ǝ҂̒��ɂ̓E�W���E�W������Ƃ������ƂȂ̂��B
�������A���̂悤�Ɂu���͂̊Ď��v���f���Ĉ̂����ɂ��Ă���e���r���A���ł͌��͂ɂ��ݎ�ŋ߂Â��Ă���Ƃ����������A�����ɒ��ڂ���Ă��܂��ƁA��V���ɂƂ��Ă���낵���Ȃ��B��V�����e���r�Ɠ����悤�Ɍ��͂ɎC�����āA�y���ŗ��������V���@���u�������v�v����郍�r�C���O�����Ă��邩�炾�B
�������ȐڑҖ�肩�猩���� �}�X�R�~�́u���s����`�I�Ȑ��`�v
�킩��₷���̂��A�ƐV�������̉�H���p�ɂɊJ�Â���Ă��邱�Ƃ��B��N12���̎��Â�����A�V�^�R���i�Ŏ��l���Ȃƌ����n�߂Ă����ɂ�������炸�A���͓��{�o�ϐV���̉��В��A�t�W�e���r�̉�A�В��A�ǔ��V���̊����A���{�e���r�̎��s�����ȂǂƉ�H�����Ă���B
�������A������҂����́u��ށv�u�ӌ������v���Ɛ�������B�������A�������������k�V�Ђ̎��Ƃɂ��Ęb��ɂ̂ڂ��Ă��Ȃ��ƍ���Ō��������Ă��Ȃ�����A���͗��ł��������q���������Ƃɂ��Ęb�������Ă����悤�ɁA������̒��œd�g�s����V���ւ̗D���[�u�Ȃǂ��b��ɂ̂ڂ��Ă��Ă����������͂Ȃ��B
���k�V�ЂƑ����Ȃ̊W��@���Β@���قǁA���������}�X�R�~�ƊE�ɂƂ��Ď��̒ɂ��b�ɂ����ڂ��W�܂��Ă��܂��B���́u����u�[�������v������邠�܂�A�e���r���V�����������̖����������Y��Ă����悤�ɁA��l�������Ă���̂ł͂Ȃ��̂��B
������ɂ���A�u�����j�ڑҖ��v�������J�P�������ł��[���A�����J�P�������s����c�߂Ă���\�����������Ƃ́A�N�̖ڂɌ��Ă����炩���B���̖��ɑ��ċ^�f��Njy���Ȃ��Ƃ��������X�^���X�́A�u���s����`�I�Ȑ��`�v����掂���Ă����傤���Ȃ��B
�u�Ό��v�Ƃ���������ԏシ�邽�߂ɂ��A�S����}�X�R�~�l�ɂ͂��Ћ^�f�̓O��Njy�����肢�������B�@ |
 �@3/5 �@3/5 |


 �@
�@ |
|
�������O���A�R�c�^�M�q���߂��鐭�{�Ή��Ɏ��] �@3/5 |
�����{�m���ŕٌ�m�̋����O��(51)��5���A�t�W�e���r�n�u�o�C�L���OMORE�v(���`���j�O11�E55)�ɐ��o�����A�����Ȋ����炪NTT���獂�z�̐ڑ҂��Ă������ɂ��Č��y�����B
���t�I�����C�������Ƃ���ł́A���t�L�����E�����R�c�^�M�q����A�������������J�e�N�F�����R�c�����܂ސ��l����N6���ANTT���V�c���В��炩�獂�z�Ȑڑ҂��Ă����B�R�c���ւ̎����m�F�ɂ��āA�������M���[������4���A�u�������ɑޔC����Ă���܂��̂ŁA�������玖���m�F���闧��ɂȂ��v�Ƃ��A�s��Ȃ��l�����������B
�������́u���{�̌������Ƃ����͍̂����̐M�p���ǂ�ǂƂ��v�Ǝ��]���������ɂ����B�R�c���ւ̎����m�F�ɂ��Ắu�@�I�ɂ͊m���Ɍ���������Ȃ��̂ŁA���{�������Ƃ������������Ƃ�@�I�ȋ����͂������Ă�邱�Ƃ͂ł��܂���B�����A�C�ӂŕ������Ƃ͂�����ł��ł���v�Ǝw�E�����B
�R���i�Ђō����ɖ@�I�����̂Ȃ��v���𑱂��Ă������{�����ɁA��ŕԂ����悤�ȑԓx�B�������́u��N��2������n�܂�R���i�Ђɂ����āA���X�ɋx�Ƃ�v�����Ă����̂́A�@�I�ȍ���������ӂ�Ȃ��肢�x�[�X�ł���Ă�����ł���H�v�Ɛ��������B����Ɂu�����ɂ͂��肢�ŁA�X(�̉c��)����߂�ƁB�⏞���������͏\���Ȃ��̂͂Ȃ������ł���H����ł��X����߂����āA�����ɍ�������l�������o�Ă����B�S���g���肢�h�ł���Ă����̂ɁA�Ȃ�ō���A�R�c����Ɂg���肢�h���Ȃ���ł����H����Ɠ������炢�́B�@�I�������Ȃ��Ƃ��A����ʂ̐l�����猠�����Ȃ��Ƃ��A����͂��������v�ƌ����������B
�������͂���ɁA�R�c���ɂ�����̏�Ő�������ӔC������Ƃ��w�E�����B�u�R�c����͍���ŃE�\���Ă���킯�ł�����B�w����(���k�V�Ђɂ��ڑ�)1���x�ƌ������ł��傤�H�w���ɂȂ��x���Č������ł��傤�H�v�Ƃ��A�uNTT(�̖��)���o�Ă���B�����(�R�c���ւ̎����m�F��)��߂Ă��܂����B�������u���Ă���ƁA�����͐��{�ɑ��ĐM�p���Ȃ����v�ƁA�Ăѐ��{�ɓ{��̖�����������B
|
|
���g�m�s�s�ڑҁh �R�c�^�M�q���̓��Ȃ��Ȋ����F�߂�@3/5 |
�����Ȋ����ւ̐ڑҖ����߂����āA�u�m�s�s���獂�z�̐ڑ҂����v�ƕ�ꂽ�����Ȃ̋ǒ������F�߁A�R�c�O���t�L�����Ȃ��Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B
�Q�c�@�\�Z�ψ���ɏo�Ȃ��������Ȃ̊������ې헪�ǒ��́A�u�T�����t�v���u���N6���A�m�s�s���V�c�В��炩��ڑ҂��Ă����v�ƕ����Ƃɂ��āA��̎�����F�߂܂����B
�u�����Q��������H�ɂ����鎖�Ăɂ��A�����̊F���܂̋^�O���������ԂƂȂ��Ă��邱�Ƃɂ��āA����ѐ\���グ�܂��B��������̂���܂������Ȏ҂ł����A�R�c�A�����̑����R�c���ł����v(������ �������ې헪�ǒ�)
�������́A�R�c�O���t�L�����Ȃ��Ă������Ƃ��F�߂���ŁA���Ƃ��Ăm�s�s�����狁�߂�ꂽ1���~���x�������Ɛ������܂����B�@ |
|
���m�s�s�����������ڑҁ@���[�������\���̉𖾂��@3/5�@ |
�����Ȋ����炪�ƊE�W�҂���A�܂������z�Ȑڑ҂��Ă����^�f�����炩�ɂȂ����B�J�e�N�F�����R�c���炪���x�́A�m�s�s�̎В���Ɖ�H���A���H��S���Ă�����Ă����B�m�s�s�͑��������玖�ƌv��Ȃǂ̔F���Ă���A���Q�W�҂���̐ڑ҂��ւ��鍑�ƌ������ϗ��K���Ɉᔽ����\��������B���Ȃ͒������n�߂��B�J�e����2018�N�ȍ~��3���H�������Ƃ�F�߂��B�����p�i���ې헪�ǒ��͍�N6���ɉ�H�������Ƃ��A���Ȃ̒����ɔF�߂Ă���Ƃ����B
�ŏ��ɕ��T�����t�ɂ��ƁA���H��̑��z�͒J�e����3��Ōv58���~���������Ƃ����B��N6���̉�H��33���~�ŁA����ɂ͑����R�c���������R�c�^�M�q�O���t�L���Q�����Ă����Ƃ����B�J�e���ƎR�c���́A�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv�ɋ߂鐛�`�̎̒��j�炩����A���H��Ȃǂ̐ڑ҂��Ă����B
����ŒJ�e���́A�m�s�s���玦���ꂽ���z���x�����Ă���A�ϗ��K���ɂ͒�G���Ȃ��ƔF�����Ă����Ɛ��������B���̂��߁A���k�V�ЈȊO�̕�����ʐM�̎��Ǝ҂Ƃ͗ϗ��K���Ɉᔽ�����H�͂��Ă��Ȃ��Ɠ��ق��Ă����Ƃ����B�����A���Q�W�҂Ƃ̉�H�́A���芨�ł����Ă����ȕ��S����1���~����ꍇ�͎��O�͂��o���K�v���B�J�e���͓͂��o�����Ă��Ȃ������B�ϗ��K���̎�|�𗝉����Ă���̂��^�킴��Ȃ��B
�J�e���́A�����Ȃɋ����e���͂����ɋ߂����ƂŒm����B�����̊Ŕ���ł���g�ѓd�b�������������̊��U������B�͊��[��������Ɂu�g�ї�����4���l�����ł���v�Ɣ������A�ʐM���Ǝ҂ɒl�����𔗂����B��A�̐ڑ҂��n�܂��������Əd�Ȃ�B�W�͂Ȃ��̂��낤���B
�m�s�s�͐������̔�����A�m�s�s�h�R�������S�q��Љ�����Ɣ��\���A�В�����コ�����B�g�ї����l�����ɉ�����l�����������B���͂⊯���̗ϗ����ɂƂǂ܂�Ȃ��B���Ƃ̈ٗl�Ȗ����̍\���Ƀ��X�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A�́u�����Ȃ��O�ꂵ�Ē����������Ǝv���v�Ɠ��ق��邾�����B�^�f�̑S�e�𖾂ɓw�߁A�����̐����s�M�@���ׂ����B�@ |
 �@3/6 �@3/6 |


 �@
�@ |
|
�����������̐ڑҁ@�g�������̌��E���������@3/6
|
���`�̎̒��j���������߂�u���k�V�Ёv����J��Ԃ��ڑ҂��Ă��������Ȃ̊������A�m�s�s��������z�̐ڑ҂��Ă������Ƃ����������B
�m�s�s�͎��ƌv��������̑I�o�ɂ��āA�����Ȃ̋��F���K�v���B���ƌ������ϗ��K�����ڑ҂��֎~���闘�Q�W�҂ɓ�����B
�ڑ҂��Ă����J�e�N�F�����R�c���́A���k�V�ЈȊO����̈�@�ڑ҂�����Ŕے肵�Ă����B���U���ق̋^�O���傫���A�ʼn߂ł��Ȃ��B�ӔC�͏d���B
�����Ȃ͓��k�V�ЈȊO����̈�@�ڑ҂͂Ȃ��Ƃ̒������ʂ����\�������肾�B�g���ɂ��Â��������������Ƃ͖��炩���B
�����Ȃ͍���̖��ł́A�������ٌ̕�m������������������{���āA���Ԃ̔c�����}���Ƃ��Ă���B����ł������Ȃ��哱���钲���ɂ͌��E������B���_���o���Ă������̐M���͓����܂��B
�K�v�Ȃ̂́A�ڑҖ��S�̂�ΏۂƂ����O�Ғ����ψ��������A�O�ꂵ�Ď������𖾂��邱�Ƃ��B��@��Ώۂ͈ψ���Ɉ�C���āA�����Ȃ͒����ւ̋��͂����ɓO����ׂ����B
�m�s�s�Ⓦ�k�V�Ђ̐ڑ҂ŁA�s���͂䂪�߂��Ă��Ȃ��̂��B�ق��̒ʐM���Ǝ҂Ƃ̐ڑ҂͂Ȃ������̂��B�������Ă��銯���ȊO�����ׂ�ׂ����B���̒��j�����k�V�ЂɍݐЂ��邱�Ƃ̉e�����A�u�x(����)�Ȃ����ׂ�K�v������B
�_�_�͑����B�܂��g�ѓd�b�����̈��������ւ̉e�����B�J�e���͐������[�������ォ��f����g�ѓd�b�����̈����������哱���Ă����B�ڑ҂̎����͂�������m�s�s�����ǂ��闧�ꂾ�����B
����ւ̉e���͂Ȃ������̂��B������肾���łȂ��A����ߒ��Ȃǂ���������ȂǂɊ�Â��ďڍׂɌ�����ׂ����B
���k�V�Ђɂ��ڑ҂ł́A�q�������̏�������b�������L���҉�c�Ƃ̊W�����B
�ڑ҂̑Ώۂ͑����ȑ��̏o�Ȏ҂ɏW�����Ă���B��c����N12���ɂ܂Ƃ߂����͓��k�V�Ђ̗v�]�ɉ������`�ɂȂ����Ƃ����B�ڑ҂Ɗ֘A������̂��B���߂����Ȃ����ł���B
�[���ł��Ȃ��̂́A�R�c�^�M�q�O���t�L�𐭕{�������Ώۂɂ��Ȃ����Ƃ��B�R�c���͓��k�V�Ђ����łȂ��A�m�s�s��������z�ڑ҂��Ă���A�����̑����Ȃł̖�E�͕�����ʐM�����ǂ��Ă����B���ׂ�͓̂��R�ł���B
�u���ɑޔC���A��ʂ̕��v(�������M���[����)�Ƃ������R��U�肩�����悤�ł́A���{�̖��𖾂ɑ���^���x�������B�@ |
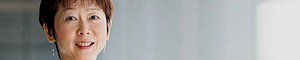 �@3/7 �@3/7 |


 �@
�@ |
|
�����������̐ڑҁ@�����\���̉𖾂��K�v���@3/7
|
�V���ɂm�s�s�ɂ�鑍���Ȋ����̍��z�ڑ҂�����݂ɏo���B���ƌ������ϗ��K���������܂Ō`�[�����Ă��邱�Ƃɋ������ւ����Ȃ��B
�����Ȃ́A���`�̎̒��j���߂�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv���獂�z�Ȑڑ҂����Ƃ��Ċ�����̏�����挎���{�A���\��������ł���B�u�ق��ɗϗ��K���ᔽ�͂Ȃ��v�Ƃ��Ă����ɂ�������炸�A�킸��1�T�ԗ]��Œ����̂�蒼���𔗂��邱�ƂɂȂ����B
�����Ȃ͂m�s�s���܂ޒʐM���Ǝ҂Ƃ̉�H�̗L���ȂǁA���Ԕc�����}���Ƃ��Ă���B�������ٌ̕�m�������ɉ����Ƃ����B�����̔[���邽�߂ɂ͓������������A���i�Ȓ��������߂��悤�B
�m�s�s�͖��c���O�̋��d�d���Ђ̓d�b����ԂȂnj����̎��Y���p���ł��邱�Ƃ���A����������3����1��������劔��ł���B���ƌv��̍��������̈ٓ��Ȃǂ������Ȃ̔F���K�v�ƂȂ��Ă���A�����Ȋ����ɂƂ��āA�m�s�s�̊������ϗ��K���̒�߂�u���Q�W�ҁv�ɊY������͖̂��炩���B
�T�����̕ɂ��A�m�s�s���V�c���В��炪�J�e�N�F�����R�c�����܂ޑ����Ȃ̊������l��ڑ҂��Ă����B�J�e����2020�N7���܂łɌv3���H���A�v17���~�ȏ�̐ڑ҂����B
����ŒJ�e���͉�H�̎�����F�߁A�u������������z�v�Ƃ���1��5��~���x�������Ƃ��A�ϗ��K���ɒ�G���Ȃ��ƍl���Ă����Ǝߖ������B�������A�l���@�͐ڑ҂ɂ��āA�{���̔�p�ɔ�ׂĎx�������s�\���ŁA���z���������S�����ꍇ�͗ϗ��K���Ɉᔽ����Ƃ̌����������Ă���B���S�Ɋ��芨�ɂ���ꍇ���A1���~����ꍇ�͎��O�̓͂��o���K�v�����A�J�e���͂��������͂��o�����Ă��Ȃ������B���������ϗ��K���̎�|�𗝉����Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����ƌ��킴��Ȃ��B
�m�s�s����̐ڑ҂́A20�N6���ɓ��������R�c���������R�c�^�M�q�E�O���t�L����A������ꕔ��������Ȃ������ƕ��Ă���B�̒��s�ǂ𗝗R�Ɏ��E�����R�c���ɂ��āA���{�͎��E�ς݂ň�ʐl�ɂȂ����Ƃ��čĒ������Ȃ����j�������Ă��邪�A�����m�F�����Ȃ��Ƃ͓���A�[���ł��Ȃ��B
���͂��đ����������߁A�����Ȃɋ����e���͂������ƂŒm����B�A�C��͌g�ѓd�b�̗����l�������Ŕ���̈�Ɍf���Ă����B���Ɏ̐M�C�������Ƃ���Ă����̂��J�e���ŁA���璼�ڎw�����A���������d���Ă����Ƃ����B
�ڑ҂���ԉ����Ă����Ƃ���A�����ɂ���Đ������f�ɂ䂪�݂��Ȃ������̂��Ƃ����^�O��������B�������A���́u�����Ȃ��������n�߂��Ə��m���Ă���v�Ȃǂƌ�邾�����B���擪�ɗ����A���݂��o�������œO�꒲�����Ȃ���A�����̕s�M�͕�����ł���B�@ |
 �@3/8 �@3/8 |


 �@
�@ |
|
�����g������ �J�e�����R�c����̐ڑҖ�� �\���Ȓ����K�v�h 3/8 |
�����Ȃ̒J�e�����R�c���炪NTT�̎В��Ȃǂ���ڑ҂��Ă��������߂���A��������b�͎Q�c�@�\�Z�ψ���ŁA�����Ȃ��\���Ȓ������s���K�v������Ƃ����F���������������ŁA���{�Ƃ��Ă�����̗���ŁANTT���ɃR���v���C�A���X�Ȃǂɂ��ĕK�v�ȑΉ������߂Ă����l���������܂����B
���̒��ŁA��������b�́u�����Ȃɂ����钲���ŁANTT���ɂ��q�A�����O���s���ƂƂ��Ɏ�����o�̋��͂Ď����W�̊m�F��i�߂Ă���B�\���Ȓ������s���K�v������v�Əq�ׂ܂����B
���̂����ŁA���{��NTT�̊�����3����1�ȏ��ۗL���Ă��邱�Ƃ܂��u�K�o�i���X��R���v���C�A���X�Ȃǂɂ��āA���呍��̋@����Ƃ炦�A�����ȂŕK�v�ȑΉ������߂邱�ƂɂȂ�Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A�J�e�����R�c���́A��}�����A���NNTT���s����NTT�h�R���̊��S�q��Љ����A��H�Řb��ɏo���̂��Ƃ��������̂ɑ��A3���̉�H���ׂĂɂ��āu�o�Ȃ������Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
���̂����Łu�g�ѓd�b�����̈��������́A10�N�قǑO������g��ł��������ŁA����30�N��2��̉�ł͘b��ɏo���Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
����ANTT���h�R�������S�q��Љ�����ۂɌ����ȋ��������j�Q����邨���ꂪ����Ƃ����ӌ������o�����AKDDI��\�t�g�o���N�Ƃ������ق��̒ʐM���Ǝ҂Ɖ�H�����̂����ꂽ�̂ɑ��A�J�e���́u�ӌ������o�������Ǝ҂Ɖ�H���������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���v�Əq�ׂ܂����B
|
|
��NHK��NTT���c�����������Ȋ����u��H���v�@3/8
|
�����X�Ƌ^�f������
��T�̖{�R�����u�����j�u��@�ڑҖ��v�ŁA�e���r�E�V���̎��ꂪ��������u�E������v�v�́A�����̃}�X�R�~�W�҂��������Ă��܂����悤���B���낢��Ȑl����A�ǂƕ������B�Ȃɂ���A�}�X�R�~�̃^�u�[�ł���u�g���L�ҁv�������Ă��܂����̂��B
���낢��ƕ������̂ŁA�l�b�g�ł͎�����youtube�`�����l�����܂߂āA�u���J��K�m�ƍ����m���NEWS�`�����l���v�u�����l�����ǁv�Ȃǂ������̔ԑg�Řb�����B
��T�̖{�R�����ŁA���k�V�ЈȊO�ɂ��ڑ҂������Ƃ���͂���͂��Ȃ̂ŁA�����ȑS�̂ł̐ڑҒ��������Ў��{�����炢���Ə������B����Ɛ�T�ANHK��NTT�Ƃ̉�H�̖��܂ŕ��サ�Ă����B(�����ȐڑҖ��ANHK�����Ƃ���H�����@�O�c��u�K�Ɗm�M�v)(������ �J�e�����R�c�� NTT�Ƃ̉�H���F�ߒ� �Q�@�\�Z��)�B
NTT�В���Ƃ̉�H�ɂ��ẮA8���ɍ���ɒ��ԕ����Ƃ������A���̍ہA�����ȑS�̂œO�ꂵ���������������������B
NHK��NTT�Ƃ���ƁA���}�X�R�~�����͂܂������Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ����낤�B�}�X�R�~�́A����̂Ƃ���Ȃ̂����璲�ׂ�̂��ȒP�Ȃ͂��ŁA���Њ����Ƒ����Ȋ����Ƃ̉�H�A�ڑ҂��u�X�N�[�v�v�ł��邾�낤�B
���Ȃ݂ɁA�����Ȃ́A�������ȁA���X���ȁA�������������킳�����Ȃł��邪�A����͂����ς狌�X���Ȃ̗����Ɋւ��镔���ō��ƌ������ϗ��@�ɔ�����s�ׂ��������B�������ȁA���������ł������蓾��Ƃ���A������u�����ڑҁv�ł���B
���ƌ������ϗ��@��A�n�������̂⍑�̋@�ւ��u���Q�W�ҁv�ɂȂ蓾��̂ŁA���̍ۑ����ȑS�̂œO��I�ɒ��ׂ�̂��A���ƌ������̐M���m�ۂɕK�v�Ȃ��Ƃ��낤�B
�����t�l���ǔᔻ�ɂ������ȃ��W�b�N
1998�N�ɔ��o�����呠�Ȑڑ҉��E�������o�āA1999�N���ƌ������ϗ��@�����肳��2000�N����{�s���ꂽ�B
����Ɠ������s�I�ɁA�����Ȓ��ĕ҂ƌ��������x���v���i�s���Ă����B�����Ȓ��ĕ҂�2001�N����X�^�[�g���A���������x���v��2007�N���ƌ������@�����A2008�N���ƌ��������x���v��{�@�Ő��x�����ꂽ�B
���̍��ƌ��������x���v��{�@�̒��ŁA���t�l���ǂ����荞�܂�Ă����B�������肭���p�����̂��A2013�N�Ő�����������{�����������B
����{�������������2013�N�ɍ��ƌ������@�����Ă��o���A2014�N�ɓ��t�l���ǂ��X�^�[�g�������B
���t�l���ǂ́A2008�N���ƌ��������x���v��{�@�ɐ��荞�܂�Ă���A����ɂ͖���}���^�����Ă����B�������A�ēx���{�����ɑ���ƁA��}�͔��ɉ�����B�ꕔ���������̐��x�ɔ��������B
���̉ߒ��ŁA���{�����ᔻ�Ƃ��āA�u���t�l���ǂ����邩��A�����������Ƃɜu�x���Ă���v�Ƃ�����ȃ��W�b�N�����ݏo����A���Ɏ����Ă���B
�呠�Ȑڑ҉��E�����̌�A���ƌ������ϗ��@���ł��āA���ƌ��������x���v��{�@���o�āA���t�l���ǂ����ꂽ�o�܂��q�ׂāA���̓��t�l���ǂɂ��u�x�������ɓI�O�ꂩ���������B
�Ȃ����Q�W�҂�������ڑ҂���̂��Ƃ����A�����͋��F�A�⏕���Ȃǂɂ����čٗʌ������邩�炾�B
���ڑ҂Ɛl���D���Ƃ����u�A���ƃA���v
��ʓI�Ȑ}���͈ȉ��̂Ƃ��肾�B���Q�W�҂͌���������(1)�ڑ҂��A���Ԃ�(���F�A�⏕���Ȃ�)�����҂���B
���������́A���Q�W�҂�(2)���Ԃ��^����ہAOB�����̓V����̎�������߂āA���Q�W�҂́AOB������(3)�V����������B
����AOB������(4)���������̐l���ɉ������B�������Č��������́A���Q�W�҂���̐ڑ҂�OB��������̐l���D���Ƃ��������b�g����B
�����ɂ͂����܂ŒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�����悻�̃��J�j�Y���͎����悤�Ȃ��̂��B
�����ŁA(1)�����ƌ������ϗ��@�A(2)���葱���̓������A(3)�����ƌ������@(�V����K��)�A(4)����t�l���ǂŁA���ꂼ��Ή����悤�Ƃ������̂��B
�v����ɁA���t�l���ǂ́A����܂ŁA�����l����OB�����������㋍�����Ă����B�܂�A�����l���ɂ��āA�����Ƃ͈�،������ł����ɁA�������炪�l�����s���Ă����Ƃ����Ă������B���̍ہA���������̃g�b�v�̎��������ɂȂ낤�Ƃ���AOB�����Ɂu�u�x�v���Ă����킯���B
���t�l���ǂł́A�@����̔C�����҂ł��鐭���Ƃɖ@���ʂ�̖������ʂ����Ă��炤�Ƃ����������BOB�����Ɛ����Ƃ��r����A�����Ƃ̂ق����I�����o�Ă��邾���A�܂��}�V�Ȃق����낤�B
���}�X�R�~�ɑ����Ȗ���鎑�i�͂Ȃ�
���Ȃ݂ɁA���{�̊e�Ȏ��������́u�������������v����ł���A��i���̒��ł͒������قǐ����Ƃ��l�����s���Ȃ��B���{�ȊO�̐�i���ł́A�e�Ȏ��������̈�芄���́A�O���o�p�E�����C�p�Ȃ̂Ő����Ƒ�b���l�������s�g�ł���̂���ʓI���B
���{�́A���t�l���ǂ�n�݂��Ă��A��i�����A�����Ƃ̐l�������ł��ʂ�ɂ������ł��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��B
���́A���Q�W�ҁA���������AOB�����̊W�ɂ����ẮA(1)�ڑ҂̗v�f�͂���قǑ債���b�ł͂Ȃ��B(1)�Ȃ��ł��A(2)���F�E�⏕���ɑ��A���Q�W�҂�(3)�V����ꂵ�āAOB����������������(4)�l�����s���A�����̊W�͐��藧�B���̈Ӗ��ŁA�����T�C�h�ɂƂ��ẮA(1)�ڑ҂Ȃ��ł����܂荢��Ȃ��Ƃ�������B
���̈Ӗ��ŁA(4)�l���͌��������ɂ���ăL���ł���B���̂��߁A���t�l���ǂ̔ᔻ�����āA(4)�l�������b�g�������̂������̖{�����B��Ȃ����ƂɃ}�X�R�~�́A����𐂂ꗬ���Ă���B
�Ȃ��A(1)�ڑҁA(2)���F�A(3)�V�������A(4)�l���Ƃ����A�\���̓}�X�R�~�ł��T�ː��藧���Ă���B
�����Ƃ��A(3)�͂���قǒ��ړI�ł͂Ȃ��A���܂茩���Ȃ��B�������A�����Ȋ����͋��Z�@�ւɁA�����Ȋ����̓}�X�R�~�ɓV���肷��Ƃ����u�N���X���ہv������̂͋����[���Ƃ��낾�B
���̈���ŁA(2)���F�ɂ��āA�d�g�I�[�N�V�����Ȃǂœ��������m�ۂł����i�͎c����Ă���̂́A��T�̖{�R�����ł����y���Ă���B
������ɂ��Ă��A�}�X�R�~�́A����̔g���L�҂̑��݂�ڑ҂̎������Ȃ��ŁA�d�g�I�[�N�V�������Ŋ������i��ɋ��X���Ă���̂ŁA����̑����Ȑڑ҂��܂Ƃ��ɕ鎑�i�͂Ȃ����낤�B�@ |
|
�����C�����R�c���L�A�����ւɐ�̂Ă�ꂽ�u��Q�ҁv�@3/8�@ |
���u�]���ҁv�Ɍ������R�c�^�M�q��
�u�ʑł��v�Ƃ������t������B�i�n�ɑ��Y�̗��j�����ɓo�ꂵ�A�l���ɂӂ��킵���Ȃ��ʊK�����X�Ɨ^���A���ɂ͐l�i����уo�����X���o�����킹�A���ł����Ă�����@�A�Ƃ����B
�����ȏo�g�̓��t�L�A�R�c�^�M�q�������k�V�Ђ���7���~���̍��z�ڑ҂��Ă������Ƃ����o���A���ɂ͎��C�Ɏ������^���ɁA�M�҂́u�ʑł��v�Əd�Ȃ��ۂ��������B
�f���Ă������A�R�c���͏������̓��t�L�A�鏑���A�����ȋǒ����C�����D�G�Ȑl�ނ��B�����A�l�̔\�̖͂��ł͂Ȃ����������܂��g�����Ȃ��Ȃ������g�D�������A�Ƃ����̂��A���N�A�S�����̌o�ϋL�҂Ƃ��ĉ����ւ���ނ��Ă����M�҂̗����Ȋ��z���B
���������u1�l������7���~���v�Ƃ����̂͘a���X�e�[�L���̐H�ނ̒P���ł͂Ȃ��A�������C�������O���[�v�ŋ�����ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B�Ƃ͂����A�������o�Ƃ͂������ꂽ���H�Ƀo�b�V���O���W�������B
�{�l���A�����E�ɂƂǂ܂�ӌ��������Ă������A�R�c���͏O�c�@�\�Z�ψ���ł̓��ٌ�Ɉ�]���đ̒��s�ǂ𗝗R�ɓ��@�A���C��\���o���B������ɓ��Ȃ��������Ȋ����͏�������Ă�����̂̐E�������Ă͂��Ȃ��B�ɁX����������������^���ɁA���C��͓���鐺���o�Ă����̂́A�R�c�����g�D�ɖ|�M���ꂽ�u�]���ҁv�Ɍ����邩��ł͂Ȃ����낤���B
�����Ƃ��Ƃ͖@���E�u�]������
�R�c���͋��X���ȏo�g�ő���c��w�@�w�����B���ł�������o�g�҂������Ă�������ւ̊����Ȃ���A1984�N���Ȃ̎R�c���̔N��ł͓��呲���������߁A���呲�͋ɂ߂ď��Ȃ��B
�R�c���͂��Ƃ��Ɩ@���E�u�]�ŁA�u�w�i�@�������Ė@���E�œ��������x�Ƃ�����������A�@�w���ɓ��w���܂����B�������̉����F�N�搶�̃[�~�ɓ���A���t�̓��X�ł����v�Ƒ���c��w���s�́u����c�E�B�[�N���[�v�Ō���Ă���B
�����݊w���ɍ��ƌ��������������������B�u���V�ŁA���̓����̕����y�̊F����Ƃ��b�����Ă��������@�����v�u����������肪���̂���d�����ȁA�Ɛi�H�ύX�����f���܂����v(�u����c�E�B�[�N���[�v)�B
�o�c�C�`�ŁA���X���Ȃł�3�N��y�̋g�c���j���ƍč��A���q��1�l����B�����Ȃ�2013�N�x�ɔ��s�����u��y����̃��b�Z�[�W�W�v�ł́u(���q��)�c��ق̑O���ȂǑ�Ȏ��Ɍ����č��M���o���A�钆�ɂ��Ԃ��ċ~�}�ɋ삯���ނ��Ƃ��v�������ƐU��Ԃ��Ă���B
�R�c���Ƃ͕W�҂�L���҂��͂���ʼn��x��������킹�Ă���A���e��ł͂�����ƈꗥ�̉����Ă������Ƃ��o���Ă���B���ċx���ɁA�R�c���Ƌg�c���ƒ��j�̈��3�l�ɓs���̉f��قł������������Ƃ�����B�e�q�ňꏏ�ɉf�������Ƃ����A���ނ܂����l�q���`����Ă����B
���u�������v�鏑���ɔ��F�������c
2013�N�A�R�c���͈��{�W�O���ɔ��F����鏑���ɏA�C�����B����͏������ł���Ɠ����ɑ����ȏ��̎鏑���ŁA�����A�傫�Șb��ɂȂ����B
�����ւ̊e�Ȓ�����I��鎖���S���̎鏑���́A�ʏ�͎�v�����Ƃ����O���ȁA�����ȁA�h�q�ȁA�x�@���A�o�ώY�ƏȂ�5�Ȓ�����1�l�����A�C����B�������̔N�͐V���ɑ����Ȃ��A�n���n���Ə������p������ɎR�c�����������E���A1�l�����ƂȂ����o�܂��������B
�����A���[�����������������̐l���ɂǂ��܂Ŋւ�����̂��͂����肵�Ȃ��B������2009�N�ɑ����Ȃŏ��ʐM�ƗX���S���̕���b�ɏA�C���Ă��鐛�́A�R�c���Ƃ͂��̍��ȗ��̕t�������������Ƃ����B
�鏑���́A�������銯���́u�ȉv�v���ő���������邽�߂ɁA���Ȓ���i�c���Ƃ̍��������\�͂����߂���B�����Ȃ�M���ɁA���������m�E�n�E�͏ȓ��Ŗ��X�Ǝp����Ă����B���������Ȃɂ͂��ꂪ�Ȃ������B�܂��Ă⏉�̏����A�R�c�����鏑���̎d���ŋ����𐿂����y�͂��Ȃ������͂����B
�����A�����Ȃ̂��銯������u�R�c���ɓ{���Ă��܂����v�Ƃ����b�����B�ڍׂȃe�[�}�͊������邪�A���ٗp�̌��e�̓��e���s�\���Łu���̂܂ܑ������b������呛���ɂȂ��Ă����v�Ƃ������R�������B����͖{�l�̎����Ƃ������A���������ǖʂɓ����邽�߂̋������Ȏ�����Ă�����������ƁA�K�����������ł͂Ȃ����������́A���̈Ⴂ�����������̌����ł͂Ȃ����낤���B
�����ȑS�̂̊��҂�w�����A���{���̒��ڂ��W�܂钆�A�R�c���̜ܜ����������l�q��ڂɂ��邱�Ƃ��������B�����͖���2�`3���Ԃƕ������B����I�ɏo�Ȃ��Ă���������x�݂����ɂȂ�A�R�c�����v���Ԃ�ɎQ�������ۂ́A��H���őސȂ������Ƃ��o���Ă���B���{��(����)�̊O�V�ɓ��s���邽�߂̏���������A�Ƃ��������R�������B
2015�N�A�R�c���͎鏑����ޔC�A�����Ȃɖ߂���ʐM���ې헪�ǒ��ɏA�C�����B�����ȏ��̏����ǒ��A�Ƃ����X�����]�g�������B���������Ȃ���鏑���̌�C�͔h�����ꂸ�A�l�I�͍ĂъO���A�����A�h�q�A�x�@�A�o�ώY�Ƃ�5�Ȓ��̑̐��ɖ߂����B
�R�c���̌�C�̏����鏑���Ƃ��ẮA�o�ώY�ƏȂ���A�̂��ɓ����������߂��@�����q�����h�����ꂽ�B���̐l���������Ӗ����邩�B�܂葍���Ȕh���̎鏑���Ƃ��Ă̎R�c���̕]���́A�K�����������Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤�B
����͎鏑���Ƃ��Ă̋���A����юx���̐��������Ă��Ȃ������̂ɂ��ւ�炸�����������Ȃ̐ӔC�A�����m���Ă��m�炸���A�������̔鏑���Ƃ��Ă��Ă͂₵�����{�̐ӔC�ł͂Ȃ��������B
�����t�L�Ƃ��Ă̗͗�
�R�c���͑����ȓ��ŏ����ɏo�����A���t�Ō������[�����ɓ����銯�[���A���������Ɠ���́u�����R�c���v�܂ŏ��i���č�N7���ɑފ������B�قڂ��ׂĂ̌o���Ɂu�������v�����B�����Ȃ̏����E���̊ԂŎR�c���́u��]�̐��v�ł���A�����������i�����҂��鐺�������������A�������������Ȍږ�ƂȂ����B
���Ȃ������t���������A���t�L�ɉ����肷��B��������������A����b���ォ��R�c����m�鐛�������X�̔��F�������̂��낤�B�����Ȃ̂����菗���E���́u����������肠��Ӗ��Ŋi��A���x���W���ʂ������v�Ǝ�����Ŋ�B
�ފ����������̍ďA�E�͈ӊO�ɓ���B����V����ɑ��鍑���̖ڂ͌������A���������Ȓ����ʓ|������̂����E������A���͂ŒT�����Ƃ���{�ƂȂ����B
�m���x�̂��鎖�������N���X�ł���u�����萔��(���܂�)�v��������Ȃ����A����ȊO�͓�q����Ƃ����̂������̏Ȓ��̐l���S���҂̔������B�R�c���̂悤�ɁA�ďA�E���T���Ă������Ȃ��ł̓��t�L�A�C�́A���Ȃ胉�b�L�[�ȃP�[�X�Ƃ�������B
�����A���t�L�̎d���́A�L�҉�̎i��߂邾���ł͂Ȃ��B�@�ւ��܂߂����Q�W�̒�����͑���ɓn��B�ő�̎d���͊�@�Ǘ��ł���A�����ɓ�ǂ����邩�̎�r�������B
�^�u�[�Ȃ͕̂@�ւɈ��͂������邱�ƁB�R�c���̏ꍇ�A�A�C���J���ŐE���ɂ܂�����Ă��Ȃ������Ǝv���A��������낤�Ƃ��邠�܂�A�����猩�ăo�����X�������Ή��͂������̂�������Ȃ��B
���u��s�ˎ��v���o�����Ȃ�����������
�����āA�ᔻ���W�����Ă��铌�k�V�Ђ�NTT�ɂ�鑍���Ȃ̐ڑҖ��B�����֑S�̂̏Ȓ����u�����̎��v���Ƃ����ƁA�����̏Ȓ��Ɏ�ތo��������M�҂���݂�ΕK�����������ł͂Ȃ��B��K�͂ȕs�ˎ����o�������Ȓ��ƁA�����łȂ��Ȓ��ő傫�ȈႢ�������ۂ��B�@
�Ⴆ�����ȁE���Z���̊����Ƃ̈��݉�́A�قڗ�O�Ȃ��u�����J���v�ł������B�����1998�N�ɔ��o�������呠�Ȃ̐ڑ҉��E�őߕߎ҂⎩�E�҂��o���A�����ȂƋ��Z���ɉ�̂��ꂽ�ꂢ�ߋ������������Ă��邽�߁B
���̎������@��2000�N�{�s�̍��ƌ������ϗ��@�Ɋ�Â��K�肪�ł��A���F�̑���ƂȂ闘�Q�W�҂���̐ڑ҂��ւ����A���ȕ��S�̉�H��1���~��������ꍇ�͎��O�̓͂��o�����߂���悤�ɂȂ����B
�@�ւ͋��F�Ƃ͊W�Ȃ����A����䂦���Ȓ��̎�ނł́A������u�����ē�����O�v�ƍl���Ă���炵���ǖʂ��Ȃ��ł͂Ȃ������B
���Z���̂��銲���́A�ē�ł�����Z�@�ւƂ̏������̏�͊�{�I�ɓ����A�E��ł̖ʒk�������J���ł̃����`�A�Ƙb���Ă����B����ŋ��呠�ȋ��̕s�ˎ����o�����Ă��Ȃ������Ȃ́A�ڑ҂���ԉ����Ă������Ƃ��f����B����ȑg�D�Ŗ��ӎ��������A���ƌ������ϗ��@�Ɋ�Â����������s�Q���A�Ƃ����s���́A���Ƃ����_���Ƃ��Ă����ɂ����̂ł͂Ȃ����낤���B
NTT�̐ڑҖ��ŁA�������M���[�����͎R�c���ɂ��āu���łɑޔC���Ĉ�ʐl�ł���v���Ƃ𗝗R�Ɏ����m�F�����Ȃ��ӌ����������B�ސE���̗L������̉ۂɂ��Ă��u�v���C�o�V�[�Ɋւ��邱�Ɓv�Ƃ��Ė��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B
�����Ƃ���K���@���͂���̂��낤���A�u�����̐ŋ��Ōٗp����Ă���������Ȃ̂Ɂv�Ƃ�����a���͂ʂ�����Ȃ��B�R�c���̎��C�ɊāA���{����A�̖����łɑ��苎�낤�Ƃ��Ă��邩�ɂ�������B
�u�������v�Ƃ��Ă͂₵�Ă����Ȃ���A��������ΐ^����ɐ�̂Ă�B����ȎR�c���̏��������Ă���ƁA�ƂĂ���邹�Ȃ��B�����܂Łu���ڗ����v���Ă��܂����R�c���̍ďA�E�́A�����ȑފ���������͂邩�ɓ���Ȃ��Ă��܂������낤�B���{�͂܂��܂��j�Љ�Ȃ̂ł���B�@ |
|
�������Ȋ����ANTT����̐ڑҔ�A�A����@3/8
|
�����Ȋ����炪NTT������ڑ҂��ꂽ�ƕ�ꂽ���ŁA�����Ȃ�8���A�����̒��ԕ����\�����B�J�e�N�F�E�����R�c���Ɗ����p�i�E���ې헪�ǒ����A���Ȃ��Ƃ�2018�`20�N��4��ɂ킽���Čv15���~���̐ڑ҂��Ă����BNTT������̐ڑ҂̈��H��Ƒ���A���ȕ��S�̗L���̈ꗗ�͎��̒ʂ�B
���J�e�N�F�E�����R�c��
18�N9��4��:1�l���̈��H��6��480�~(���ȕ��S�Ȃ�)�A��H�����NTT���k����2�l
18�N9��20��:1��7431�~(���ȕ��S�Ȃ�)�ANTT�V�c���В���2�l
20�N7��3��:2��8941�~(5��~)�ANTT�f�[�^���k����2�l�ƊO���Ȋ���
�� ��b���[�t�ɍX�R
�������p�i�E���ې헪�ǒ�
20�N6��4��:4��8165�~(���ȕ��S1���~)�ANTT�V�c�В���2�l�ƎR�c�^�M�q�E�O���t�L��(���������R�c��)�A3��~�̓y�Y�t��
�� �R�c���͑ސE�ς݂Œ����ΏۊO�@ |
 �@3/9 �@3/9 |


 �@
�@ |
|
���m�s�s�����Ȑڑҁ@��Ȃ��̖�����O��𖾂���@3/9
|
�����Ȃ́A�m�s�s�ɂ�铯�Ȋ����ւ̐ڑ҂Ɋւ��钲���̒��ԕ\���A���z�ڑ҂��Ă������Ȏ������i���o�[2�̒J�e�N�F�����R�c����������X�R���܂����B�J�e���͕����֘A��Ёu���k�V�Ёv����ڑ҂���Ă������Ƃ����o���Ă��܂��B�Ǝ҂���̐ڑ҂́A�_�ѐ��Y�Ȃł����炩�ɂȂ�A���������炪��������Ă��܂��B�����͂��悢��[���ȗl���ł��B�����E���ɑ���ُ�Ȑڑ҂��������ł�����́A�������ϗ��K���Ɉᔽ���邾���łȂ��A�s�����䂪�߂������d�^�f�Ƃ��Ă��O�ꋆ�����s���ł��B
�m�s�s�ɂ�鑍���Ȋ����ڑҖ��́A4�������́w�T�����t�x���X�N�[�v���܂����B�J�e�����R�c����2018�N�`20�N��3��A�m�s�s�֘A�̉�����������X�g�����ŁA���z�̐ڑ҂��Ă����Ȃǂƕ܂����B�����R�c���������R�c�^�M�q�O���t�L�Ɗ����p�i���ې헪������20�N6����1��ڑ҂����Ƃ���܂��B�J�e���̐ڑ҂ɂ́A���������O���R�c�������Ȃ��Ă��܂����B
�����Ȃ�8���̒��ԕł́A�J�e���̐ڑґ��z�͖�10��7000�~�ŁA�R�c���Ɗ������̐ڑҋ��z�͖�5��1000�~�������ƋL�ڂ��܂����B�J�e���Ɗ������͂��ꂼ��5000�~����1���~���x�������Ƃ����܂����A�ڑ҂ł̈��H�P���͂��̊z��傫�������Ă��܂��B
�m�s�s�͎�����̑I��Ȃǂő������̔F���鑍���Ȃ̗��Q�W�҂ł��B���ƌ������ϗ��K���ɔ����Ă������Ƃ͖����ł��B
�J�e���͐挎�̍���ŁA���k�V�Ђ̂ق��ɂ͋K���ᔽ�̐ڑ҂͂Ȃ��Əq�ׁA�����Ȃ����l�̐��������Ă��܂����B�����Ȃ̒����������Ȃ肾�������Ƃ͏d��ł��B�ē��闧��́A���c�Ǒ��������̐ӔC�͖Ƃ�܂���B
�J�e���炪�m�s�s����ڑ҂����̂́A�����Ȃɋ����e�������鐛�`�̌����M�S�ɐ��i����g�ѓd�b�����̒l�����Ƃ̊֘A���^���܂��B�J�e���͑����R�c���ɏA�C����O�͂m�s�s�����ǂ��鑍���ʐM��Ջǒ��Ȃǂ��C���Ă���A����Ȃ钲�����K�v�ł��B
���̒��j�E���������߂铌�k�V�Ђɂ��ڑ҂��A�S�̑��͕s���̂܂܂ł��B�q�������̎��g�����蓖�Ă�F��X�V�Ȃǂ��߂���^�f�����܂��Ă��܂��B
���d�߂ōݑ�N�i���ꂽ�����߂̋g��M�����_�����ƂƂ��Ɍ{�����Y��Ёu�A�L�^�t�[�Y�v�ɐڑ҂���A�������ꂽ�_���Ȏ���������̖��������܂��ɂł��܂���B�����d�ɒ������܂��B
�e�Ȓ��̊����E����̊�ƂƂ̖��������s���Ă���̂́A�s���̎���������ԉ������Ă����A���{�W�O�O�Ɛ���2��̐����ɂ킽�銯�@�哱�̋����I�ȁg�����֎x�z�h�Ɩ��W�ł͂���܂���B�������̂̐ӔC������������܂��B
���_�����œ��k�V�Ђ��瑍���Ȋ����E�����ڑ҂��Ă������Ƃɂ��āu��肪����v�Ƃ�����8�����܂��B
���͕��c�������C���ł͂Ȃ��A�������ڑҖ��̑S�e�����璲�����A�����ɖ��炩�ɂ��ׂ��ł��B�m�s�s�Ⓦ�k�V�ЊW�҂̍���v���������A�^�����𖾂��邱�Ƃ����߂��܂��B
|
|
��NTT�̍��z�ڑҁA�h�R���u�A�n���v��������Č�����I�@3/9
|
NTT�O���[�v�ɂ�鑍���Ȋ����̍��z�ڑ҂ŁA�g�ѓd�b�����l�������哱���Ă������������i���o�[2�̒J�e�N�F��(60)��2021�N3��9���A�����R�c�����X�R���ꂽ�BNTT�Ƒ����Ȃ́u�Y�u�Y�u�̖����v�����炩�ɂȂ�A�h�R���̐V�����v�����u�A�n���v(ahamo)���r�[�ɐF�����Ă݂���B�g�ѓd�b�����̒l�����͂��ꂩ��ǂ��Ȃ�̂��\�\�B
���u�ʐM�s����10�N�x���v�قǃf�L�銯��
NTT�������獂�z�ڑ҂��čX�R���ꂽ�J�e�N�F�E�O�����R�c��(60)�́A���Ƀf�L��j�������悤���B�g�ѓd�b�����̒l���������łȂ��ANHK�̎�M�����ȂǁA���`�̐����̖ڋʐ�������Ɏd���Ă����B
�����V��(3��9���t)�u���������ڑҁA�����ʒ�@�����A����̐��i�������v�́A�����Ȋ����̂���ȒQ���̐����Љ�Ă���B
�u�J�e���́A���ɂ��߂����ƂŒm���A�̂���̌g�ѓd�b�����l�����̐��i���������B�J�e���̍X�R�Ő����̒ʐM�E�����s���ɉe�����y�Ԃ͕̂K�����B�����Ȋ����́w�ɂ��B�ʐM����łȂ������s�����܂߂�10�N�͒x��邩������Ȃ��x�Ǝw�E����v
��l�̐l�����|�X�g���狎�邱�ƂŁA���̑厖�ȍs����10�N���̒��]�V�Ȃ������قǂ��Ƃ����̂��B�ǂ�قǃf�L��j�������̂��\�\�B���{�o�ϐV��(3��9���t)�u�g�ђl�����E6G��� �J�e���X�R�A�i�ߓ��s�݂Ɂv���A�����`����B
�u�J�e�N�F����NTT���������ȂǂɊւ��A���N�Ă̎����A�C���L�͎�����Ă����B�J�e���͂���20�N�A�Œ�d�b��g�ѓd�b�ȂǒʐM����Ɉ�т��Ċւ�����B����������������2007�N�ɂ́A�ے��Ƃ��Čg�ѓd�b�����ƒ[�����i�̕����v�����̓������哱�����B�g�ђl�����̌���������A�����͋ƊE�Łw�J�e�s���x�Ƃ̌��t�܂Ő��܂ꂽ�B�J�e����m��W�҂́w�s�����Ƃ��Ẵr�W�����Â���ƁA�i�c���ւ̍��𗼕��ł���l���x�Ƙb���v
�u�J�e�s���v�Ƃ������t�����܂��قǁA�ƊE�ɂ͌������������Ă����l���������悤���B���{�o�ϐV���́A����������B
�u�����Ȃ͌g�ї��������������߂��鋣�����̐�����A2030�N��̎��p����ڎw��������ʐM�K�i�w6G�x�̌����J���Ȃǂ̏d�v����������B���c�Ǒ�������b�́A�����R�c���͋�Ȃɂ���Ɛ��������B�ʐM����̎i�ߓ��͈ꎞ�s�݂ɂȂ�B�ڑҖ��ő����̊������������Ă���A�����E�ʐM�s��������鋰�ꂪ����v
��C����Ȃɂ�����Ȃ��̂́A�܂������ȓ��́u�ڑҖ��v�̒����������Ă���A�����Ɍ�C��I�сA���̐l�����܂��ڑ҂��Ă����ȂǂƂ������Ԃ��N����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂������B
�J�e���́A���Ɍg�ѓd�b�����̒l�������ł́A�ǂ�Ȏ��т�����l���Ȃ̂��B�����V��(3��9���t)�u�J�e���w�̉����x�w�~�X�^�[�g�сx�v���A�ڂ����Љ�Ă���B
�u�J�e����1984�N�A���X����(��������)�ɓ��ȁB�����ɂ��������鍠����ʐM������ނ悤�ɂȂ����B�ȓ��ł́w�~�X�^�[�g�сx�w�ٔ\�̑��݁x�Ȃǂƌ����A���݊�������Ă����B���ȊW�҂́w�g�ѓd�b��C���^�[�l�b�g����̑������I���݁B�ȓ��ł͉E�ɏo��҂͂��Ȃ������x�Ƙb���v
�J�e���̖����g�ѓd�b�ƊE�ɍL���Z�������̂�2007�N�B�����Ȃ͎s��̋����𑣂����߁A�g�ђ[���̉��i�ƒʐM������u�����v�����v�̓������Ă����B�ړI�͍��ۋ����͂̋����ŁA���̒��j��S�����̂��g�ѐ����S���ے��E�߂��J�e���������B���̂��߁A�[���̔̔��䐔���ꎞ�ቺ���A�ƊE������u�J�e�s���v�Ɣ��𗁂т��̂��B
���̂悤�ɒJ�e�������x�������Ɏ��g��ł����Ƃ��A���`�̎��͑�������b�A�������������B�ȑO����O�ᓥ�P��������v�̑Ŕj��i���Ă��������ɂƂ��āA�J�e���͌g�ыƊE�Ƀ��X������u���v�h�����v�ɉf�����B���Ȋ����͒����V���L�҂ɁA�u�J�e���͂Ƃɂ����s��ɋ��������悤�Ƃ���Ă����B���ꂪ����b�A��b����������(�̐S)�Ɏh�������Ƃ������Ƃ��v�Ƙb���̂������B
���h�R���q��Љ��Ɓu�A�n���v�̓M�u���e�[�N�H
�����V��������������B
�u�w��ҁv�Ŗ炵���J�e�������A�ȓ��ł́w���邭�A����Ȃ����i�������x�Ƃ̕]������B�C���^�[�l�b�g����ŕ����̒������o�ŁB�����Ńc�C�b�^�[��u���O���J�݂����B�c�C�b�^�[�̃v���t�B�����ɂ́A�w��l�����nj����Ȃ������x�ƋL�����B�ŋ߂ł́A���{�ɏ㗤���ĊԂ��Ȃ������^SNS�w�N���u�n�E�X�x�����������Ƃ��Љ�Ă����v
���Ȃ݂ɒJ�e���́A���Q�����R�s���܂ꂾ�B�n�����E���Q�V���̌o�ϖʂɁu�r�Ye���Q�v�Ƃ����R������A�ڂ��Ă����B2013�N6�����獡�N2���܂�2�T�Ԃ��Ƃ�182����������B�u�C���^�[�l�b�g�̎��R���߂����āv�u���猻��ɏ��ʐM�̌����v�u���q����ƒʐM�Z�p�v...... �Ə��Љ���e�[�}�ɂ��Ă���A�Ō��182��̃^�C�g�����u�g�ѓd�b�l�����Ɍ���������Ȃ���g�݁v�������B
�����̌o�ϖʂ̖��O�́uE4(���`���)�o�ρv�B�J�e���͎����̃R�����ɂ��āA�u�C���^�[�l�b�g�̐��E�Ƃ����ƁA����������A�ꕔ�̐��Ƃ̂��̂Ǝv����������Ȃ��B�����o�ς̃G���W���ł�����A���̌o�ϐ������x����d�v�ȃ}�[�P�b�g�ł�����B�V�N�ł킩��₷���e�[�}�ł��낢��Ȃ��Ƃ��Љ�Ă��������B���Ƃ��A��ʂ̃f�[�^����͂���r�b�O�f�[�^��I�[�v���f�[�^�A�C���^�[�l�b�g�̐i����X�}�[�g�t�H���̕��y�Ő������ǂ��ς��̂��ȂǁB�\�[�V�����ƘA������E4(���`���)�́A���p�҂��ӌ��������L�ł���R�~���j�e�B�[�̏�ɂȂ��Ăق����v�Ə����Ă���B
�d���̓f�L�邪�A���\���������l���̂悤���B |
|
��NTT���z�ڑ҂ōX�R�̒J�e���A�������Œ�N�ސE�@3/9�@ |
�������M���[������9���̋L�҉�ŁA�m�s�s���̍��z�ڑ҂��đ����R�c�����X�R���ꂽ�J�e�N�F��(60)�����[�t�����������Œ�N�ސE����Ɩ��炩�ɂ����B�ސE���ɂ��Ắu���ƌ������ސE�蓖�@�ɂ̂��Ƃ�Ή�����v�Ɛ��������B���c�Ǒ��������͋L�҉�ŁA�ڑҖ��Ɋւ��钲���ɂ��āu�\�Ȍ���ΏېE�����L����B�����W�̊m�F�𐳊m�ɁA�O��I�ɍs���K�v������v�Ƌ��������B
���ƌ������@�͈�ʐE���̒�N��60�Ƃ������ŁA�ꕔ�̊����E���͐l���@�K���Ɋ�Â��ʓr�K�肵�Ă���B�����R�c���̒�N��62�ŁA�J�e���ɂ��K�p�����͂����������A8���t�Ŋ��[�t�Ɉٓ������B�������́u���x�I�ɂ͌����Œ�N���}����v�Ɛ��������B
����A�����Ȃ�9���ɍ�����ŊJ���ꂽ��}�����q�A�����O�ŁA�����͑����Ȃ̌���E��������ΏۂƂ��A�ڑ҂ɓ��Ȃ����R�c�^�M�q�O���t�L��(���E)��O���Ȃ̋��������O���R�c��(����)�ւ̕������͌����_�Ŏ��{���Ȃ��Ƃ����B�@ |
|
�������� �ڑҖ�蒲�� �ʐM�E�����S���̌���E���ȂǑΏۊg��� �@3/9 |
NTT�̎В��Ȃǂ��犲������@�Ȑڑ҂��Ă��������Ȃ́A����A���������ɂƂǂ܂炸�A�ʐM�������S�����錻��̐E���Ȃǂɂ��Ώۂ��L���Ē�����i�߂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�����A�E���̋��͂��O��ƂȂ邽�߁A�ǂ��܂Ŏ������̂��钲���ɂȂ邩���œ_�ɂȂ�܂��B
�q�������֘A��Ђ���̐ڑ҂ŁA�����������������Ȃ̒J�e�E�����R�c���́ANTT���V�c���В��炩�獇�킹��3���E���z10���~�]��̈�@�Ȑڑ҂��Ă������Ƃ��m�F����A8���t���ŁA��b���[�t�Ɏ�����A�X�R����܂����B
���c������b�́u�J�e���ɂ́A�O��̒����ŁA�ق��ɗϗ��@�߂Ɉᔽ����s�ׂ��Ȃ��������A�ĎO�m�F�����ɂ�������炸�A�V���Ȉᔽ���^����s�ׂ��m�F���ꂽ���Ƃ͐r���⊶���v�Əq�ׂ܂����B
�����Ȃ́A����A�J�e���犲�������ɂƂǂ܂炸�A�ʐM�������S�����錻��̐E���Ȃǂɂ��Ώۂ��L���āA���Ǝґ������@�Ȑڑ҂����P�[�X���Ȃ������ׂ邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
���������́A�����܂ŐE���̋��͂��O��ƂȂ邽�߁A�ǂ��܂Ŏ������̂�����̂ɂȂ邩���œ_�ɂȂ�܂��B
����A����ł́A���T15���ɎQ�c�@�\�Z�ψ�����V�c�В����Q�l�l�Ƃ��ď��v���A�W���R�c���s���邱�ƂɂȂ�܂����B
��}������́A����S�̂Ő^�����𖾂��ׂ���肾�Ƃ��āA�O�c�@�ł��V�c�В��̏��v�����߂鐺���o�Ă��āA����A�������s���錩�ʂ��ł��B
�@ |
|
���ڑҖ��̎R�c�O�L�@������Ƃ�A�ސE��5000���~�͖��z�x���@3/9
|
�u���݉�͒f���Ȃ��v�Ɓg�ڑҏ㓙�h�����ꂵ�Ă����R�c�^�M�q�E�O���t�L���a�C�𗝗R�Ɏ��C�����B���@�͌�C�ɏ�����q(�Ђ��肱)�E�O���������N�p���A�g�R�c�B���h���}���ł��邪�A�������{���Ă���͔̂ޏ��ɑ���g�߂Ɣ��h�̃A���o�����X�Ɂu�㋉�����v�ł��銯���̓����A�����i������������Ă��邩�炾�B
�R�c���͑����ȃi���o�[2�̑����R�c�������A�u�����܁v�ƌĂԐ��̒��j�E�������瓌�k�V�Њ�������7���~���܂�̃X�e�[�L�ڑ҂��A���܂���NTT������ڑ҂���Ă������Ƃ��T�����t�ɕ��Ă���B
���̓��k�V�Ђ���̐ڑҖ��ő����Ȃ́A��ʍs���NJ�����11�l�����ƌ������ϗ��@(�K��)�ᔽ�ŏ��������B�R�c�����{���Ȃ珈���Ώۂ̂͂������A�����͂��łɑ��������ł͂Ȃ��̂��|�C���g�ƂȂ�B��N9���Ɂu�����������v�̃|�X�g�ł�����ʐE�̓��t�L�ɏA�C����O�A�����Ȃ�ފ�(��N7��)���Ă������Ƃ���A�u������ސE�����҂������ł��Ȃ��v�Ƃ������R�Ŕ���Ƃꂽ�B
���Ԋ�Ƃł���A�s�ˎ��Œ����ƐE�ɂȂ����Ј��͑ސE�������z����邱�Ƃ������B�����A���ԃT�����[�}�����s�ˎ��őސE�ɒǂ����܂��Ƃǂ��Ȃ邩�B�l���R���T���^���g�ŎЉ�ی��J���m�̓��C���l�������B
�u���Ԋ�Ƃ́A�{�l�̐\���o�őސE����ꍇ�ł��A������������ΑސE���̌��z���A�ƋK���ɐ��荞��ł���P�[�X�������B�܂��Ă�A�s�ˎ��Ŗ��O����ꂽ�ƂȂ�ƁA�ސE��̍ďA�E������Ȃ�ƍl�����܂��B
���݂̃R���i�s�����ł͂Ȃ�����ł��B���J�Ȃ͉��ق�ق��~�߂�9���l�����Ɣ��\�������A����͕X�R�̈�p�B�E�������čďA�E���܂܂Ȃ�Ȃ��A�Z��[�����c���Ă���悤�Ȑl���ƁA������藣���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ɒǂ����܂�邱�ƂȂǂ��l�����܂��B�V��̐l���v���č\�z������Ȃ��ł��傤�v
����̎R�c���͑O�q�̒ʂ��N7���ɑ����Ȃ�ފ����Ă���B�������̑ސE���͖�5000���~�ɂ̂ڂ�B�ڑҖ�肪���o����ƁA���t�L�̌�����6���ɑ�������70��5000�~������Ԕ[���A���K�I�y�i���e�B�����悤�Ɍ����邪�A����͌����������B
�������͍���̐ڑҖ��ōX�R�����H�{�F���E��ʍs���ǒ��̌�C�ɁA�R�c���̕v�ł���g�c���j�E�����R�c���F�����B���ƌ������w��E�̕�\�Ȃǂ��玎�Z����ƁA�g�c���͌���81.8���~(�N����1500���~)�̑����R�c��(�w��E��\3����)���猎��96.5���~(�N��1770���~)�̋ǒ�(��5����)�ւ�2�K�����i�ŁA�N����250���~�A�b�v�B�v�w���Z�̎����ōl����ƕԔ[�������Ԃ���ǂ��납�A���ނ肪����B
���Ȃ݂ɎR�c���̑����R�c������̌���(��\7����)��110.7���~(�N����2190���~)�ŕv�ƍ��킹3500���~���鐢�єN�����������v�Z���B�v�w��2005�N�ɐ��c��́g���V�����h���w����5�N�ԂŃ��[����ԍς����ƕ��Ă���B�s�ˎ��őސE���Ă��A���[���n���̐S�z�Ƃ͖������B����ł́A7���~�ڑ҂̐Ȃł̂��Ƃ����A�u�o���Ă��Ȃ��v��A�������R�c�������A���ꂾ���́g�h������A7���~��H���x�̂��Ƃ��L���ɂȂ��͖̂������Ȃ����ƂȂ̂�������Ȃ��B |
|
���u�ސE��5000���~�v�g�����h���� �R�c�^�M�q�߂���ᔻ�̐��@3/9 |
���`�̎�(72)�̒��j�炩��́g�ڑҖ��h�����サ�A�̒��s�ǂ𗝗R�Ɏ��C���������������̎R�c�^�M�q�O���t�L��(60)�ɂ���9���A�ސE��5000���~�����z�x�������Ƃ̈ꕔ���A�c�C�b�^�[�ł́u�ސE��5000���~�v���g�����h���肷��Ȃǔᔻ�̐������������B
�c�C�b�^�[�ł͍��z�ȋ��z�ɂ��āu����ȂɑސE���������R����́H�v�u�������㋉�����v�u�߂����ፋ�Ȃ�������H�ׂĂ���������������v�Ǝw�E�����鐺�����������ق��A�u�ސE��5000���~�ق������A���ׂĂ̈��݉��f��j�Ȃ̂Ŗ����v�u���B�����ɑ��Ĉꗥ���t����z���Ă��������v�Ƃ��鐺���������B�@ |
|
�����ّI�O�ɒl���������肩�HNTT�����Ȑڑ҂ŕ��サ�����̋^�O 3/9 |
�T�����t�����ANTT�ɂ�鑍���Ȋ����ւ̐ڑҖ��B�J�e�����R�c����������̍X�R�����ƂȂ�܂������A��}�y�у}�X�R�~�͒Nj��̎���ɂ߂����͂Ȃ��悤�ł��B����̃����}�K�w�ΐ쉷�́u�X�}�z�ƊE�V���v�x�ł͒��҂ŃP�[�^�C�^�X�}�[�g�t�H���W���[�i���X�g�̐ΐ쉷���A�ʐM�ƊE�W�҂̊ԂŚ�����Ă����ANTT�Ɗ��@�Ƃ̊Ԃ��^���u�Ƃ���\�v���Љ�B����ɓ��Č�����X�L�����_���ɔ��W����\�����������Ă��܂��B
��NTT�Ƒ����Ȋ����ɂ���H�̔g��\�\�g�ї����l��������ɉe�����y�ڂ��Ă��Ȃ��̂�
�T�����t���R�c�^�M�q�O���t�L�ƒJ�e�N�F�����R�c����NTT�Ɖ�H�����Ă����ƕ��B���ł�NTT�A�J�e���Ƃ��Ɏ�����F�߂Ă���B
��H��NTT��NTT�h�R�������S�q��Љ����悤���Ă��������Əd�Ȃ�B
�����ЂƂA�^�O�̖ڂ���������Ȃ��̂��A�l������������a������NTT�h�R���̐V�����v�����uahamo�v���B
ahamo�́ANTT�h�R���Г��ł͍�N1�������A���N3���̊J�n�Ɍ����Ċ�悪�X�^�[�g�����ƌ����Ă���B
����A��N9���ɐ���������������̂����A�����͑��ّI�ɗ���₷��i�K�Łu�g�ѓd�b�����̒l�����v�𐭍�ɂ���ƌf���Ă����B
�Ђ���Ƃ���ƁA���ّI�̑O����ANTT�h�R���������ȗ����ݒ�����邱�Ƃ�7���̐ڑ҂ɎQ�������J�e�R�c���o�R�ŁA�������͒m���Ă����̂ł͂Ȃ����B
NTT�h�R�����l�������邱�Ƃ��킩������ŁA�g�ѓd�b�����̒l�����𐛑������d�v����Ƃ��Čf���Ă����Ȃ�ANTT�Ƒ����Ȃɂ��s��ȏo�����[�X�������\�����o�Ă����B
�ʐM�ƊE�W�҂̊Ԃł́A��N����uNTT�h�R���̊��S�q��Љ���ahamo�̓����́ANTT�Ɗ��@�Ƃ̌��������������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����₩��Ă����B
�O���[�v�ĕ҂����s���A���ۋ����͂����āA���E�ɐi�o������NTT���A�������̌g�ї����l�����̐���������������ɁA�����Ȃ�NTT�O���[�v�̓Ɛ��A��F�߂������̂ł͂Ȃ����Ƃ����킯���B
�܂��ɍ�N7������9���ɂ����Ă̖��k�́A���@��NTT�ɂƂ��ēn��ɑD���������ƂɂȂ�B
���������A���������g�ї����ɂ��āu4���l�����ł���]�n������v�Ɣ��������̂͊��[�����ł�����2018�N8���̂��Ƃł���B
�J�e���������ʐM��Ջǒ��ɏA�C�����̂�2018�N7���ł���A�T�����t�ɂ��A2018�N9���ɂ�NTT�ō������ƒJ�e������H���Ă���Ƃ��Ă���B
���ł�NTT�Ƒ����ȂŁA�����l�������������A���̒i�K�Ō��킳��Ă����\��������B
NTT�Ƒ����Ȃ͉�H�̏�łǂ�Șb�����Ă����̂��B���c�Ǒ�������b���A�₽���KDDI�ɑ��č����I�Ȕ��������Ă����̂́A�w���NTT������m�b�����Ă����̂ł͂Ȃ����BNTT�Ƒ����Ȃ̊W������݂ɂȂ������ƂŁA�����ȋ^�O�������Ԃ悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�����Ȃ�NTT�̉�H�ɂ����NTT�h�R�����l���������[�h���A�\�t�g�o���N��KDDI��l���������Ɋ������݂AMVNO�s���ׂ��悤�Ȃ��ƂɂȂ���A���ꂱ����X�L�����_���ɔ��W����B
�J�e���ɂƂ��Ē��N�̔ߊ�ł������g�ѓd�b�����̒l��������������钼�O�ŁA�J�e���͎���D��h���Ă��܂����悤���B
�������ȁE�g�ѓd�b�|�[�^���T�C�g�͐E���̎���\�\�A�N�V�����v�����u�ڑ����l�����v�͑O�|���ŒB��
3��5���A��ʎВc�@�l�e���R���T�[�r�X����MVNO�ψ���ɂ��u���o�C���t�H�[����2021�v���I�����C���ŊJ�Â��ꂽ�B
��u���ɑ����ȑ����ʐM��ՋǓd�C�ʐM���ƕ����̍����Y���A�p�l���f�B�X�J�b�V�����ɂ͑����ȑ����ʐM��ՋǓd�C�ʐM���ƕ������T�[�r�X�ۊ�抯�̑���N�������o�d�B�����̋�������ɂ��Ă̎��g�݂����ꂽ�B
���������A�����ȂƂ��ē��{�̌g�ѓd�b�����͂ǂ��݂Ă���̂��B���쎁�́u���ۓI�Ɍ��āA���{�̌g�ѓd�b�����������Ƃ����ł͂Ȃ��B�����A��e�ʃv�����ł͉��B�̈��������ɑR�ł���v�������Ȃ��v�Ƃ����B���e�ʃv�����ɂ����Ă�MVNO�Ƃ����I���������邪�A20GB�v�����ȏ�ɂ����Ă̓L�����A�����I�ׂȂ��̂���莋���ꂽ�悤���B
12���ȍ~�A3�L�����A����������3,000�~�ȉ��̃I�����C����p�v�������o�����BMVNO����́u�̎Z���ꂵ�Ă��Ȃ��̂��A�X�^�b�N�e�X�g�����{���ׂ��v�Ƃ����ӌ����o���ꂽ�B�����ŁA�����Ȃ����ׂ��Ƃ���uahamo�Apovo�ALINE�ɂ��Ă͓����ō̎Z�����m�F�������A�Ԏ��ł͂Ȃ����A�e�ЁA�M���M���̂Ƃ�����U�߂Ă���v(�����)�Ƃ̂��Ƃ������B
2���̒i�K�ŐԎ��X���X���Ƃ������Ƃ��l����ƁA�ʂ����āA3��1����2,980�~��1����ɓ�����280�~�̒l����������ahamo�͑��v�Ȃ̂��C�ɂȂ�Ƃ��낾�B�܂��A500�~��1��5���܂ł̂�������I�v�V������1�N�ԁA�����ɂ���Ƃ����L�����y�[�����d�|���Ă���LINEMO�́A��͂�̎Z�M���M���Ƃ������ƂŁA�l�����ł͂Ȃ��L�����y�[���ŏ��낤�Ƃ����̂��A�ȂǑz���͖c��ނ��肾�B
3�L�����A���I�����C����p�v�������o�������ƂŁA�ڑ����̎Z��ɂ��e�����y�ڂ��A�u3�N�ԂŐڑ�����������Ƃ����A�N�V�����v�����̖ڕW��1�N�O�|���Ŏ������錩�ʂ��v(���쎁)�Ƃ����B
MVNO�e�Ђ́A3�L�����A�̃I�����C����p�v�������āA����Ȃ�l�����v�����𓊓��B�o�c�I�ɂ���Ɍ������ɒǂ����܂��\�������������A�ڑ��������������ڏ������������Ƃ�����A�Ȃ�Ƃ���̔�ꖇ�A�Ȃ�������������B
��N�A�A�N�V�����v�����ɂ��f�����Ă��������Ȃɂ���芷���𑣂��|�[�^���T�C�g�ɂ��āA���쎁�́u�g�ѓd�b�|�[�^���T�C�g�͑����ȐE���̎���B�Z���X�����܂����Ǝv���邩���m��Ȃ����A���ꂩ��������ꂽ�f�U�C���ɂ��Ă����v�Ƃ��Ă����B
���ꃌ�x���ł́A�n���ɋ��������i�߁A���ʂ��o�n�߂悤�Ƃ��Ă��钆�A�����̕s�ˎ��ɂ���āA�����ȑS�̂��^�O�̖ڂŌ����Ă��܂��̂́A�Ȃ�Ƃ��s���łȂ�Ȃ��B�@ |
|
�����@�Łg�ߘa��2�E26�����h�u���I�@3/9
|
�ŋ߂̕s�v�c�ȗ���������܂��B
�u�͌鏫���`�����l���v������E�����j�̊���̂����ŁA���e�ł��鐛�̂�邱�ƂȂ����Ƃ��������p�݂����ɂ݂���̂ł��B �����j�����Ȃ��A���z�Ȑڑ҂����R�c�L�̎��E���߂���e���̌��o���ł́u���v�Ƃ��u�ǂ��v�B�܂�Ő��̈͌�E�����`�����l�����B
���u����B���v���u�R�c�B���v�ɕς��������
�ǂ�肾���ł͂Ȃ��B�R�c�������E���钼�O��2��26���ɂ͂Ƃ�ł��Ȃ����p���������B
��������ƁA�{���Ȃ炱�̓��ً͋}���Ԑ錾�̈ꕔ�����ɍ��킹���L�҉�����\�肾�����B�������u�Ԃ牺����v�ɕύX�����̂�(���@����o��Ƃ��r���ŗ����~�܂��Ęb������Ƃ����X�^�C��)�B
���@�͓��t�L�҉�̊����Ђɂ���̐\����������ۂ����B�L�҉�̎i��߂�L�ł���u�R�c�B���v?
���@���̐����ł́A��N�ً̋}���Ԑ錾�ł̊��O�{�������������ۂ̈��{�O�̑Ή����u�Ԃ牺����v���������Ƃ�傫�ȗ��R�ɋ����Ă����B�����������͓��������������̓q���}�[�W������肪�u���C�N���Ă����Ƃ����B����B�����R�c�B���ɕς���������Ƃ����O�ᓥ�P�B
���u�Ԃ牺����v�ɂ��c���Ȑ����p
����Ȃ킯�Ő��ɂ���A�肪���ɗ����~�܂��Ĕ������A�K���ȂƂ���ł��J���Ƃ������S�ȓW�J�Ȃ͂����������c�B
�Ƃ��낪���̈͌�E�����`�����l���͎c���Ȑ����p�����Ă��܂����̂ł���B
�L�҂�������u���������炸�Ƃ������̋��͂���Ǝv�����v�u���z�ڑ҂����R�c���t�L�̖�肪�e�������̂��v�u�Ȃ����傤�L�҉���s��Ȃ������̂�?�v�Ȃǎ��₪���X�ɗ��т���ꂽ�̂��B
�R�c�^�M�q���L�@�Y�o�V���Ё@�����Ȃ�u��l���v�Ȃǂƌ����R�c�L�����Ȃ��B�C��������͎���ƌ������킴��Ȃ���ԂɂȂ��Ă����B�܂�ŋl�����̐����p�B�̐����̖R�������N�����K�`�ȓW�J�ɂȂ��Ă��܂����B
�R�c�B�����B�����B
���̓��͗��j�I�ȉ���ǂ��ɂȂ����B���͗ߘa��2�E26�����Ɩ��t�������B
�����������u�`����Ȃ��ł��傤���v�̈Ӗ�
���č����2�E26�����ł킩�������Ƃ�����B���̕s�v�c�Ȍ��Ȃ��B
�u�`����Ȃ��ł��傤���v�Ƃ��������𗐔�����̂ł���B
�E�R�c�L�̂��Ƃ͑S���W����܂���B���ɍ���A����œ��ق���Ă������Ƃ���������Ȃ��ł��傤���B
�E�����������āA�u�Ԃ牺����v�����Ă��Ȃ��ł��傤���B
�E�K�v�Ȃ��Ƃɂ͓����Ă��Ȃ��ł��傤���B
���̂��Ƃɂ��ď㐼�[�q�E�@���勳���́u�������m�F�����Ƃ���A13����������v�Ƃ��āu�Ȃ��������ӔC�������āA�͂�����ƌ�����Ȃ��̂��낤���v�Ǝw�E�B����Ɂu����́A���痧����}���Ȃ��甽�_����ꍇ�ɗp�����錾���ł͂Ȃ����낤���v�ƍl�@���Ă���B(�w�n�[�o�[�E�r�W�l�X�E�I�����C���x3��1��)
�����̓��ٔ\�͍͂���u�ł͂Ȃ��ł��傤���v
������Ȃ�������ɉ����t����b�@�B�����������̎����g���Ă����B
�u5000�~�łł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ���Ȃ��ł��傤���v(2019�N11��14���E���[�����)
���{�O�̍��������O��Ղ́u���5000�~�v�^�f�ɑ��Ă̐����̃R�����g�ł���B���̂��ƈ��{����������U���Ă������Ƃ����������B��͂�5000�~�ł͂ł��Ȃ������̂��B
���̂��Ƃ���l����Ɛ����ƁE���`�̂́u�`����Ȃ��ł��傤���v�͉����}�Y���Ƃ��⋇�n�ɒǂ����܂ꂽ�Ƃ��ɏo��悤���B
�ł�2�E26��������x�U��Ԃ��Ă݂悤�B����܂œS�ǂ̃Z�R���h�Ɉ͂܂�Ă��������A��������ۍ��ŋL�҂Ɉ͂܂ꂽ�狩��ł����B�u����Ȃ��ł��傤���v�u����Ȃ��ł��傤���v�u����Ȃ��ł��傤���v��13����B���݂��݂��Ă��܂��B
�����S�z����̂͂��̘b�@�͍����Ȃ�ʂ��Ă��A���v�𑈂���ł͑����̃��[�_�[�ɒʗp���Ȃ��ł��낤���Ƃ��B���̓��ٔ\�͍͂���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�u�����悤�Ȏ��������v�Ǝ͌������A�����悤�Ȃ��Ƃ����āA�����悤�Ȃ��܂������������Ƃ��Ă邩��ł͂Ȃ��ł��傤���B�@
�u�e���r�j���[�X�v(���쎟�Y�E��w�̗F��)�Ƃ����{�ɂ̓A�����J�哝�̂̋L�҉�ɂ��Ă���Ȃ����肪����B
�s�u�Ȃ肽���ĂȂ������l�ɂ́A�ǂ̂悤�Ȏ�����Ԃ��Ă����܂�Ȃ��v�Ƒ����̃W���[�i���X�g�������l���Ă���B�o���ɂƂ��Đ^�������̏�ł���B�t
��30�N�O�̖{�ł���B���͂Ȃ肽���Č��l�ɂȂ�A�Ȃ肽���ĎɂȂ����B�u�����悤�Ȏ��������v�ƃL���闧��ł͂Ȃ��͂����B
���R�c�O���t�L�́u�ސE������ʂ̕��v
�u�����悤�ȁv�Ƃ����M���b�Ƃ��邱�Ƃ�������������B
�������[�����͎R�c�^�M�q�O���t�L�ɂ��Đ��{�Ƃ��Ă��炽�߂Ē�������l���͂Ȃ����Ƃ�\���B�u�ސE������ʂ̕��v�Ƃ������R�ŁB
�c�b�R�~�ǂ���͂������邪1�_�ɂ��ڂ�B
�R�c�^�M�q���͂���1�T�Ԃōł����ڂ��ꂽ�l�����B����Ȃ��Ȃ��ł����R�Ƃ��̂悤�ȐU�镑��������̂��B�����������Ƃɂ��Ă��܂��̂��B�ł͉�X���m��Ȃ��ċC�Â��Ȃ��Č��ł͂ǂꂾ������̂��낤���c�B
���́u�͌鏫���`�����l���v���炽�߁u�l�����`�����l���v�B���ǂ��낪�������ă��o����Ȃ��ł��傤���B
��3��7���͐Ԗ���̖���
�Ō�ɂ����Ƃ������Ƃ������Ă����B
�w�X�F�������A�Y��Ȃ��� �Ԗ���̎�����3�N �ȁA�����V���Ɏ�L�x(3��6��)�B
�s�Ԗ���́A������̌o�܂��ڂ����L�����t�@�C�����c�����Ƃ���邪�A���̓t�@�C���̗L�����܂߂Ė��炩�ɂ��Ă��Ȃ��B�u�v������N�Ɏw������A�ǂ���R���A���������A���ɋꂵ��ł����̂��������Ă���͂��ł��v�B��q����͍��ւ̊J�����߂�n�قɐ\�����ĂĂ���B�t
3��7���͐Ԗ���̖����������B���{�͖Y��悤�Ƃ��Ă��邪���͖Y��Ȃ��B�@ |
 �@3/10 �@3/10 |


 �@
�@ |
|
���J�e�������R�c���A���z�ڑ҂̎��́u���z�ސE���v�@3/10�@ |
�������M���[������9���̋L�҉�ŁANTT���̍��z�ڑ҂��đ����R�c�����X�R���ꂽ�J�e�N�F��(60)�����[�t�����������Œ�N�ސE����Ɩ��炩�ɂ����B
�����������̑����R�c���͍��ƌ������@�Ɛl���@�K���Ɋ�Â��A��N��62�Ƃ�����Ⴊ����B�J�e�����E�ɂƂǂ܂��Ă���A��N���}����̂�2�N�ゾ�����B�������A�ڑҖ��ōX�R����A8���t�Ŋ��[�t�Ɉٓ��B����ɂ���ē��Ⴊ�K�p���ꂸ�A�ʏ�̒�N�ƂȂ�60�ŔN�x���ɑސE���邱�ƂɂȂ����B
�ސE���ɂ��ĉ������́u���ƌ������ސE�蓖�@�ɂ̂��Ƃ�Ή�����v�Ɛ��������B��́A�ǂ̂��炢�ɂȂ�̂��B�l���@�̃��f���P�[�X�Ȃǂɂ��ƁA�e�Ȓ��̎��������N���X�őސE���͖�7500���~�A�R�c���ł�5000���~����B�J�e���͐ڑҖ��ő����Ȃ��猸��10����2(3�J��)�̒��������������A�ސE���͋Α��N�����E�ȂǂŌ��܂�B������No�E2�̑����R�c���������J�e���̏ꍇ�A���z�Ȃ�6000���~�O��̑ސE�����x�������\��������B
������N�⎫�C�őފ��������ƌ������ɑ��ẮA�ݔC���̍s�ׂ��u�������������v�ƔF�肵�đސE�����z�Ȃǂ̃y�i���e�B�[���Ȃ����Ƃ��ł���B�����Ȋ����́u��N�œ�����̂͐��Ԃ������Ȃ��Ɩ{�l���������Ă���͂��v�Ǝw�E�B�ߋ��ɂ͏����L�҂ւ̃Z�N�n���������������������C�������c�~�ꎁ�ɑ��A�����Ȃ��ސE����5300���~�̎x��������������ۗ��B���̏�Łu�����̒��������ɑ����v�ƔF��A������(6�J���̌���20���ɑ���������z)�����������Ďx�������P�[�X������B
���k�V�Ђ��班�Ȃ��Ƃ����z11��8000�~�ANTT���瓯����10���~�̍��z�ڑ҂����J�e���B���o�ώY�ƏȊ����Ōc���w�@�����̊ݔ��K���́u�ސE���������łȂ��Ȃ����v����`���͂Ȃ��B�قƂڂ肪��߂�ΓV������\�ł��傤�v�Ƃ����B�ʂ����Ăǂꂾ���̑ސE�������̂��B���̊z�ɂ����ڂ��W�܂�B
�������ȐڑҖ�� / �J�e����3���Ōv��10��7000�~�A�����p�i���ې헪�ǒ�����5��1000�~�̍��z�ڑ҂�NTT������B�J�e����1������5000�~�A��������1���~�������S���Ă��Ȃ��B���Ȃ������Ă͐��`�̎̒��j���������߂�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv�����@�ڑ҂������Ƃ����o���A�挎�A�J�e����9�l�̒������܂ߌv11�l�����������B11�l�Ƃ͕ʂɁA�R�c�^�M�q�O���t�L�������R�c��������7���~���̐ڑ҂����B�R�c���͍L�����E�BNTT�͎����W�̉𖾂⌴��������ړI�Ƃ������ʒ����ψ����ݒu����Ɣ��\�����B �@ |
|
�������� �ڑҖ�� ��O�҈ς͎R�c�O���t�L�������Ώۂ� 3/10�@ |
�����Ȋ�����̉q�������֘A��Ђ���̐ڑҖ��ŁA�����Ȃ́A��O�҈ψ���ɂ�钲���ł́A�����A�����Ȃ̒S���ǒ��Ȃǂ߂Ă����R�c�O���t�L���ΏۂɂȂ�Ƃ������ʂ��������܂����B
�����Ȋ�����̐ڑҖ����߂����ẮA�R�c�^�M�q �O���t�L���A�����Ȃ̍ݐE���ɁA�q�������֘A��Ёu���k�V�Ёv�ɉ����āANTT���V�c�В��炩����ڑ҂��Ă������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B
����ɂ��āA10���̏O�c�@���t�ψ���ŁA�����Ȃ̒S���҂́u�R�c���́A���łɑ����Ȃ�ސE���Ă��āA�����ȂƂ��āA���ƌ������ϗ��@�ᔽ�̋^���ɂ��Ē������s������ł͂Ȃ��v�Əq�ׁA�����ȓ��Ői�߂Ă���ANTT�������@�Ȑڑ҂��Ȃ��������̒����ł́A�R�c���͑Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����F�����d�˂Ď����܂����B
����ŁA���k�V�Ђ���̐ڑҖ��ŁA�s�����䂪�߂�ꂽ���Ƃ��Ȃ��������������邽�߂ɏȓ��ɐݒu����\��̑�O�҈ψ���ɂ��āA�����Ȃ̒S���҂́u�R�c���̍ݐE���Ԓ��̂��̂��܂߁A�ߋ��̉q��������̔F��v���Z�X�Ȃǂɂ��Č����i�߂���ƍl���Ă���v�Əq�ׁA�R�c�����A�����A�����Ȃ̒S���ǒ��Ȃǂ߂Ă������Ƃ��璲���ΏۂɂȂ�Ƃ������ʂ��������܂����B
���k�V�Ђ��߂����ẮA4�N�O�ɊO���K���Ɉᔽ������ԂŁA�q��Ђɉq���������Ƃ��p�����Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�A�����Ȃ́A��O�҈ψ���œ����̌o�܂ׂ邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�@ |
|
���R�c�O�L�������Ώہ@�ڑҖ��̌��؈ρ\���c������ 3/10 |
���c�Ǒ���������10���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA�����Ȋ��������Q�W�҂�����ڑҖ��̌��؈ψ���Ɋւ��A�R�c�^�M�q�O���t�L�������Ȏ���Ɍ��ق������F�������ΏۂƂ�����j���������B���؈ς͌����o���҂��O�҂ō\�����A�ڑ҂��s���ɉe���������ׂ�B
�R�c���͓��Ȏ���ɕ����֘A��Ёu���k�V�Ёv���獂�z�ڑ҂��Ă����B�̒��s�ǂ𗝗R�Ɋ��Ɏ��C���Ă��邪�A�s���ɑ��鍑���̕s�M�̍��܂���A���ԉ𖾂�i�߂�B
���c���́u�����ɑ�O�҂ɂ��ψ����������q�ϐ����ł���v�Ƌ����B�u�R�c���̍ݐE���Ԃ��܂߉ߋ��̉q��������̔F��v���Z�X�Ȃǂ�������v�Əq�ׂ��B
����A�J�e�N�F�O�����R�c���炪�m�s�s���獂�z�Ȑڑ҂��������߂����ẮA���Ȃ͌����o���҂𒆐S�ɑ�O�҂̋��͂Ȃ��璲��������j�B�������Œ�N���}����J�e���́u�ސE����\�Ȍ��苦�͂������v�Əq�ׂ��B
���k�V�Ђ�2017�N1���A�a�r�`�����l���u�U�E�V�l�}4�j�v�̎��Ǝ҂Ƃ��đ����Ȃ̔F��������A�O���䗦�����N3������21�����ɏ㏸�B�O���䗦��20�������ƒ�߂������@�Ɉꎞ�ᔽ�����ԂƂȂ����B
���k�V�Ђ͂��̌�A�u�U�E�V�l�}4�j�v���q��ЂɎ��Ə��p�����B���Ȃ����p��F���������̏�ʍs���ǒ����R�c���������B�@ |
|
������������NTT�E���k�V�Ђ��u�ڑ҂��鑤�v�������ƍl������[���̗��R�@3/10�@ |
NTT�Ⓦ�k�V�Ђɂ�鑍�������̐ڑ҂�����ƂȂ��Ă��邪�A��A�̐ڑҖ��ɂ͑傫�ȓ䂪����B���F�ɉe���͂��������NTT�Ⓦ�k�V�Ђ���ڑ҂��邱�Ƃ́A���������Ƃ��Ă̓��X�N���傫�����ă����b�g�ɑS��������Ȃ��B����Ȃ̂ɂȂ��ڑ҂����̂��A�Ƃ����䂾�B�������A�����I�ɂ͑��������̑����ڑ҂����̂��ƍl����ƌ��ʂ����ǂ��Ȃ�̂��B
���S�Ă̐l���C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ� �O�́u���v
����̂���l�́A�O�́u���v�ɂ��ꂮ����C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���́u���v�́A�u�Z�N�n���v(�Z�N�V���A���E�n���X�����g�B���I�����点)�́u���v���B��Ƃ����������Ԃ��Z�N�n���ɂ͋ɂ߂Č��������A���̌��������N�X��������Ă���B�����āA�Z�N�n���͂ǂ��ɂ��i�D�������B
�Z�N�n���ŗ�����������l�͐����ƁA���������A��Ɛl�ȂǕ�������ő����v�������ԁB�{�l�ɂ��̈ӎ����Ȃ��ꍇ�ł��Z�N�n���ƔF�肳���ꍇ�����邵�A�Z�N�n�����g���ă��C�o���Ȃǂ��Ӑ}�I�Ɋׂ��P�[�X������B
�M�҂��r�W�l�X��Œm���Ă���l���ł�2�l�قǁA���l���d�|�����Z�N�n����㩂Ɉ����|�����ĐE�Ə�̃|�W�V�������������B�u�Z�N�n�����^����\���̂��鑊��Ƃ́A������2�l�����ŐH���ɍs���Ȃ��v�Ƃ������炢�̗p�S�[�����A����r�W�l�X�p�[�\���̏펯���B
���́u���v�́A�����Ƃ��B�����ƂƂ̕t�����������ԈႦ��Ǝ��������d�Ȃǂ̍߂ɖ���邱�Ƃ����邵�A�����Ƃ̑��ɖ��f���|����ꍇ������B�����ƂƂ̕t������������l�́A�\���Ȓ��ӂ������ēK�ɕt������˂Ȃ�Ȃ��B
�����āA�O�Ԗڂ́u���v���A�ډ��b��́u�ڑҁv�́u���v���B���`�̎̒��j���ւ�����Ƃ����q�������֘A��Ђ̓��k�V�Ђɂ�鑍�������ڑ҂ɑ����āANTT�ɂ��J�e�N�F�����R�c��(���݂͍X�R����Ċ��[�t)�ւ̐ڑ҂����ɂȂ��Ă���B��������������̗ϗ��K��ɔ�����̂ŁA����Ȃ�̒n�ʂɂ������l���������āA��E�����C������o���ɉe�������肵�Ă���B�������̐l���ɂƂ��Ă͑�ςȂ��Ƃ��B
�Ȃ��A����̂���l���C��t����ׂ����̂́A�O�́u���v�ɉ����Ă��������B���_���t���̂Ŏl�́u���v�ɂł��Ȃ��������A�u�ŋ��v�́u���v�ɋC��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�t�������Ă����B
�Ƃ���ŁA�u����̂���l�v�Ƃ͒N�̂��Ƃ��H�����Ƃ�g�D�̊����A���邢�͗L���l�ł͂Ȃ��Ă��A���ʂ̃T�����[�}���ł��t���[�����X�ł������Ă��Ȃ��l�ł��A�ǎ҂̂قڑS�Ă��u����̂���l�v���B�Ƃ����̂��A��L�̂����ꂩ����艻����ƁA�o�ϓI�ȗ��v�����łȂ����_���������ƂɂȂ邩�炾�B
���ڑ҂��Ȃ������Ƃ͂ł��Ȃ� ���R�́u���ȃ��o���b�W���ʁv
���āA�ډ��z�b�g�Șb��ł���u�ڑҁv�����A����͂Ȃ������Ƃ��ł��Ȃ��̂��낤���H
���_���ɏq�ׂ�ƁA�ڑ҂��Ȃ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv����B����́A�ڑ҂ɂ͐��ȃ��o���b�W����(�Ă��̌���)�����邩�炾�B
���o���b�W���ʂƂ͋��Z�̐��E�ł悭�g���錾�t�����A���̏ꍇ�u�ڑ҂̑Ώۂł��鑊�葤���瓾���郁���b�g�v���u�ڑ҂Ōl������邽�߂ɕK�v�Ȕ�p�v�̉��{�ɂ��y�Ԃ��Ƃ��w���B
�u���F�v�ɂ���A���̎��ɕK�v�ȁu���v�ɂ���A���̌o�ϓI���l�͔��傾�B����A�ڑґ���l�����ĂȂ���p�Ǝ�Ԃ̃R�X�g�͍����m��Ă���B
���łɎ����̑����̂Ȃ��̘b�����悤�B
1980�N��̌㔼����90�N��O�����炢�́A������o�u���̎����̘b���B�����A���{�̑����̐����ی���ЁA�M����s�A�^�p��ЂȂǂ̃t�@���h�}�l�[�W���[�̒��ɂ́A�،���Ђ̐ڑ҂��P��I�ɎĂ��āA�ڑ҂ɑ���ԗ�Ƃ��Ċ�����O�����Ȃǂ̔������،���ЂɉĂ����҂����������݂����B
���u�C���g���ł�������A�J�l�g���Ă���v �u���̊̑��͕���Ȃv
�����̕M�҂̓����ɂ́A���j��������j���܂ŘA�����H�̐ڑ҂��āA�y�j���ɂ̓S���t�Őڑ҂����悤�Ȑl���������B�ʂ̉�Ђɓ]�E���Ă��p�ɂɐڑ҂��Ă��āA�u�C���g���ł�������A�J�l(��)�g���Ă���v�Ə،���ЂɌ����Ȃ�����l���������B���̐l���̂��Ƃ�ʔ����������G���̌��e�ɏ�������A�u���̂��Ƃ������₪�����ȁv�Ɠ{�����l�����Г���3�l�����A�Ƃ������Ƃ�����B
���Ȃ݂ɁA�ڋq�̂������^�p���邢����@�֓����Ƃ̐��E�͂��̌�A�N������Ȃǂ̃N���C�A���g�̖ڂ��ӎ�����悤�ɂȂ��ď،���Ђ���̐ڑ҂ɑ��Č������Ȃ����B�^�p�S���҂��،���Ђ̎Ј��Ɖ�H����ꍇ�A���O�ɓ͂��o���s���ď�i�̏��F�ĉ�H���A��v�͊��芨�������Ƃ���A�Ƃ��������x���̃��[����݂��Č��i�Ɏ���Ă����Ђ���������B�^�p�ƊE�̖��_�̂��߂ɕt�L���Ă����B
���̌�A�M�҂͊O���n�̏،���Ђɓ]�E�����B�ȑO�Ƌt�̗���ɉ�����킯���B�����̃Z�[���X�}���̎d���Ԃ������ƁA�m���ɐڑ҂͔����A���Ȃ킿�萔�������ɒ������镪����₷����i�������B�ڑҔ�̐��Z�����ς����i�̔��f��́A�u�|������p�ȏ�Ɏ萔��������Ȃ�A������ł����Ȃ��v�������B
�Z�[���X�}���̒��ɂ́A���̓����`�ŋ@�֓�����A��ڑ҂��A��͑O���ɋ@�֓�����B���A�����Č㔼�ɋ@�֓�����A�_�b�V��(A�Ђ̒��Ƃ͈قȂ�l�I)��ڑ҂���悤�ȖҎ҂������B�O�H��������A���R�[���t�����B�u���̊̑��͕���Ȃv�Ƃ����ނ̂���ӂ��������Ɏc���Ă���B
���āA�u�|������p���������闘�v�̕����傫���v����A�ڑ҂����鑤�ɖ��m�ȓ��@������ȏ�A�ڑ҂��Ȃ������Ƃ͓���B
��Ђ̔�p�ŐڑҔ����������邱�Ƃ��x������ڋq���������A���������ڋq�ɂ͎����Őڑ҂��ė̎���������킸�ɍς܂���Z�[���X�}���������B�ڋq���瓾����f�B�[�����ނɂ����炷�{�[�i�X���ڑҔ�����傫���̂ł���A�ނɂƂ��Ă͍����I�Ȃ̂��B
�ڑ҂��鑤�ł͌v�Z�ƍ������������Ă���B�ڑҔ���o��Ƃ��ĔF�߂Ȃ����Ƃɂ��Ă��ڑ҂͂Ȃ��Ȃ�Ȃ����낤���A���H���֎~���Ă��ʂ̌`�Ԃ́u�ڑҁv���J�������͂���(�Ⴆ�I�����C���łł���ڑ҂̕��@���W����ƁA�����̃A�C�f�A���W�܂邾�낤)�B
��ʓI�Ɍ����Đڑ҂́A����鑤�������鑤�̕������|�I�ɂ���������̂��B
���ڑ҂��������邽�߂ɕK�v�� �ڑ҂���鑤�̍������Ƃ́H
�Ƃ���ŁA�ڑ҂��鑤�ɂƂ��č����I�ł��邾���ł́A�ڑ҂͎������Ȃ��B�ڑ҂���鑤�ł�������������ƍl���Ȃ���A�ڑ҂̏�ɏo�����Ȃ������̂��Ƃ��B�u��H�͒f��Ȃ���`���v�Ǝ����ɕ��j���ۂ���K�v���Ȃ��B
���Ẵt�@���h�}�l�[�W���[�Ə،���Ђ̐ڑҊW�́A�u�J�l(��)�g���Ă���v�����Ȃ̐l���̏ꍇ�A���H��S���t�̔�p�������ŕ��킸�ɍςނ��Ƃ������b�g�ŁA�����������ɏ،���Ђɒ������o����Ԃ������R�X�g�Ƃ����ȒP�ȑ������肾�����̂�������Ȃ��B
�������A�ނ̂悤�ɒP���Ȑl�ł��A���������������u�a�t���v����Ă��邪���Ƃ��W�ɂ͖������Ă��Ȃ��������낤�B�ڑ҂�ʂ��đ��肪�ւ肭���邱�Ƃւ̐��_�I����������������������Ȃ����A�ڑ҂̐ȂŌ��킳����b�Ɂu���v�̉��l������ƐS�̒��Ŏ��ȕٌ삵�Ă�����������Ȃ��B
���Ȃ݂Ɂu���邱�Ɓv�́A��������Ƃ����Ԑl�Ɖ�H���邱�Ƃ̌�����Ɏg���₷�����ڂ��B
�ڑ҂̊���ʂɂ��ĒNjL���Ă����ƁA���H�������ɂ�������炸�A��������p�S���Ă��Ȃ����Ƃւ́u�ꖕ�̂�܂����v�̊���ڑ҂��ꂽ���ɂ͐�����B�ʏ�̖��ԓ��m�̐ڑ҂ł��A�u���炩�̌`�ł��Ԃ������Ȃ��Ắv�Ɛڑ҂���������������N�����Ƃ���ɁA�ڑ҂̑傫�ȈӖ�������B
�����͑��������́u�ڑ҂��鑤�v������ �ƍl�����闝�R
���āA�ڑ҂��邱�Ƃ́u�ꖕ�̂�܂����v�ɐG�ꂽ���A���̓_�܂ōl����ƁA����̈�A�̑����Ȋ����ڑҖ��̓��ِ��������яオ��B
�͂����茾���āA���F�ɉe���͂�������œ��k�V�Ђ̐ڑ҂�����A�g�ѓd�b�̒ʐM�������傫�Ȗ��ƂȂ��Ă���Ƃ���NTT�̐ڑ҂����肷��̂́A�����ɂƂ��āu���܂�ɂ��A��܂�������v�B�H����C���������ɍ����ȕ��ł������Ƃ��Ă��A����A�ނ��덂���ȕ��ł��������̂ɁA�ʏ�̓��X�N���傫�����đ��������Ƃ��Ă̓����b�g�ɑS��������Ȃ��B
�����ɏo������悤�Ȍ������ɂ��������v�Z�ƔF�����Ȃ������Ƃ͍l���ɂ����B�ނ�̓��[���ƃ��X�N�ɂ͑�ϕq�����B
����ɁA�������C�������݂��������Ȃ�A�O���Ȃ̗F�B�ɂł����ނƖ��Ԃ̐ڑ҂��������Ƃ������̂����߂��̂ł͂Ȃ����B
���k�V�Ђ�NTT�̑��������ɑ���ڑҖ��̖{���́A�P�ɘe�̊Â��������u��������I�v���Ă��܂����Ƃ������ł͂Ȃ��B
�ꌩ�A�����������Ȉ��H�ŃT�[�r�X���Ă��邩�̂��Ƃ����B�Ƃ��낪���Ԃ́A����ĉ�H���鎞�Ԃ�^���A��H�ł�(���Ԃ�)�L�v�ȏ���`����Ȃǂ́u�{���̃T�[�r�X�v�A�܂�����I�Ȑڑ҂��s�����̂͊����̑��Ȃ̂��B��A�̖��́A�����I�ɂ͑��������̑������k�V�Ђ�NTT��ڑ҂����̂��ƍl����ƌ��ʂ����ǂ��Ȃ�B
�ނ炪�l�I�ȃ��X�N��`���Ă܂ŋ��߂��u���o���b�W���ʂ̂��郁���b�g�v�����Ȃ̂��́A�܂����m�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�����A�ނ�ɂ̓��X�N��`���Ăł����悤�Ǝv���Ă��������b�g�Ȃ����͎�肽�������������������͂����B
����͉����H�ނ�͊����Ȃ̂�����A�ŏI�I�ɂ͐l�����낤�B���Ԃ�ԈႢ�Ȃ��B
�����Ȃɉe���͂�����Ƃ���鐛�ɗǂ���ۂ��������(���邢�́u������ۂ�������邱�Ƃ�������āv)�����̐l���Ɋւ��郁���b�g���������̂��B�����ɔ����Ē��ꋉ�̓V�����Ƃ̐l�ԊW������Ă������������̂��B�����I�ȍ������܂���肽�������̂��B
����A�ނ炩�猩�Ĕނ�l�l�ɂƂ��đ傫�ȃ����b�g������Ƃ������ƂȂ�A�u�ڑ҂�f��Ȃ��v�ȏ�̃����b�g�𓌖k�V�Б���NTT���ɗ^���Ă��Ă����������Ȃ��B�u�s�����䂪�߂�ꂽ�v�\���͑傢�ɂ���B
�Ǝ҂Ƃ��̊W��(�����Ƃ��܂�)�ƁA�����Ċ����̖����̎��Ԃ����𖾂炩�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A�����Ƃ⊯���Ɠ��k�V�Ђ�NTT�Ǝ�����ނ̖����W�������Ă���ɈႢ�Ȃ��}�X�R�~�́A���̖��ɂ��ĉʂ����Ăǂꂾ���͂����ĕ���̂��낤���B
�������Ȃ̐ڑҖ��̋��P �������l���ɂ́u�����ӔC�v���K�v��
���x�̖��Ƃ��āA���������鍡��̂悤�ȍ\���̖��������S�ɉ�������̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�����A�������̂́u���͂Ƃ��Ă̐l���v���u���b�N�{�b�N�X�������Ȃ����Ƃ��̐S���Ƃ������Ƃ��B
���t�l���ǂ�ʂ��Ď��@���������̐l�����R���g���[�����邱�Ƃ́A�u�����哱�v�̎�i�Ƃ��Ă͂����Ƃ��悤�B�������A�������̐l���ɂ��Ă͍����ɂ��e�����傫���̂����A�����{�l�̐l���ɂ��e����^����̂�����A���̌o�܂◝�R�Ɋւ��ċɗ͏������J���A���u�����ӔC�v����������ׂ����B
���{�w�p��c�̉�����̔C�����ۂɊւ��āA������u�l���̖��Ȃ̂Ő������T����v�Ƃ������ق��p�ɂɂȂ��ꂽ���A����������������������ׂ��ł͂Ȃ��B�厖�Ȑl���̖�肾���炱���A�{�l�ɂ������ɂ��\���[���̂����������I�[�v���ɍs�����Ƃ��K�v�Ȃ̂��B�l���̕ی�����͂邩�ɏd�v�Ȗ�肾�B
���R�����ɍs�g�ł��錠�͕͂��s�̂��Ƃ��B���������ڑҖ��̖{�������ǂ�ƁA�����炭��{�͂����ɂ���B�@ |
|
�����s���c�@�w�T�����t�x�̋L���͉����߂���I 3/10 |
�����A�����ɂ͏��X�ɕ��ԁw�T�����t�x�̋L�����i�c���ŏo����Ă���A��ǂ��܂������A�{��S���ł��B
�^�C�g���́A�uNTT�ڑҕ�������@������b�A����b���Y�u�Y�u�̉��v�Ƃ��āA�����c���q����b�̊�ʐ^���f�ځB
�L�����ɂ́A�uNTT�̑�����b�A����b�ւ̐ڑҁv�Ƃ����\���o�Ă��āA��c���q��b2��A���s���c��b2��A�e��b�ƂƂ��ɓ����ĉ�����������b2�����e1��̐ڑ҂����Ƃ���Ă��܂��B
���́A�u�ڑҁv�͎Ă��Ȃ��|�A��ގ҂ɑ��āA���m�ɕ����ʼn��܂����B�����̎x���̗̎��ⓖ�Y�X�܂̗�������������鎑�����Y�t���đ��t���܂����B
�������A�L�����Ɂu(NTT�O���[�v��)�ʐM���Ƃ̋��F�ɒ��ڊւ�鑍����b�A����b�A�������̐����O���A����т��̌o���҂��^�[�Q�b�g�ɐڑ҂��J��Ԃ��Ă����̂ł��v�Ƃ܂ŁA������Ă��܂��B
��b������b���u�ʐM���Ƃ̋��F�ɒ��ڊւ��v���ƂȂǁA����܂���B���������A���B�́u���فv�����Ă��Ȃ��̂ł�����B
�wNTT�@�x��w�d�C�ʐM���Ɩ@�x�Ɋ�Â��F�̒��ŁA���ƂɌW����̂́u�ŏI���فv������̂͑�b�╛��b�ł͂Ȃ��A�ǒ��ł��B
��L�̏��ǖ@�߂Ɋ�Â����I�ȔF�ȊO�́u�ʈČ��ɌW��y���ȔF�v�ɂ��Ă��A�S�ċǒ��ȉ��̐E�����ŏI���َ҂ł���A��b�╛��b�͌��َ҂ł͂Ȃ��A�Č��̐�������Ă��܂���B
���̍ݔC���ɁA�B��A��b�ɔF����������̂Ƃ��Č��ق����̂́ANTT������Ђ̊��呍��Ō��肵���u������E�č����̑I��C���c�v(�l���Č�)�݂̂ł��B
NTT���A�֘A�@���x�͂悭�������ł�����A��c����b�⎄�ɑ��Ď��ƔF�ȂNjƖ��ɌW�闊�ݎ����Ȃ���͂�������܂���B
�V�c�В��Ⓡ�c���В��Ƃ���������ɂ��A���̌l�I�ȊS�����ł���T�C�o�[�Z�L�����e�B(��Ɏ����Ԃ��Ë@�ւ̃T�C�o�[�Z�L�����e�B���������̊S��)�ɂ��āA�y�l�g���[�V�����e�X�g�ȂNjZ�p�ʂł̐��m���������Ă��������Ă��܂����B
�������A�����Ȃ̔F���ɌW�闊�ݎ��̘b�肪�o�����Ƃ͊F���ł��B
�ȉ��A�w�T�����t�x����̖₢���킹�ɑ��āA3��9���ɕ����ʼn������̂��f�ڂ��܂��B
���w�T�����t�x�ҏW���@�_�c�m�q�l�@3/9
�@�@�@�O�c�@�c���@���s���c
�Ⴒ����1�ɂ��ā�
�Z����1�́A������b�ݔC����2019�N12��20����2020�N9��1����NTT���V�c���В�����ڑ҂��Ƃ������͎������A�Ƃ������e
• ������b�ݔC���ԂɁA�����Ȋ֘A�c�̋y�ю��Ǝ�(�n�������c�́A�ʐM�A�����A�X���A�s�����k��)����A������u�ڑҁv�������Ƃ͊F���ł��B�u��H���ӌ������̋@��v�ɂ��܂��ẮA�u�s���̌������v�ɋ^�O��������邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�S�āu���S���芨�v���́u�S�z�������S�v�őΉ����邱�Ƃ�O�ꂵ�Ă��܂����B
• �[���܂ňψ���ق�ȓ��⊯�@�̉�c�Ȃǂ̌��������Ȃ��ƁA�W�c�̂⎖�Ǝ҂̂��ӌ�������f���@��͖�ԂɂȂ邱�Ƃ������A�ޒ����Ԍ�ɑ�b�����g�p���邱�Ƃ͐E���̎c�ƂɌq���邱�Ƃ���A�ȊO�ŗ[�H���ӌ��������s�����Ƃ͓x�X����܂����B����̎���𗝉�������Ő�����l�Ă�����{��̎g�������ǂ������肷�邱�Ƃ́A����3���Ƃ��Ė����ɓ��鐭���Ƃ̋Ɩ��ł���ƍl���܂��B
• ��H���ꍇ�́A���O�Ɏg�p�X�܂̌����T�C�g�ŋ��z��c������ƂƂ��ɁA����Ƙb�������A����ł��܂ވ��H������ܔ��ɂȂ�悤�ɉ������肵�Ă��������A�x����͗̎�������Ă��܂��B�X�ɁA��������ʼn����郊�X�N���������y�Y��p�ӂ��郊�X�N�����Ă��A�����1��������5,500�~�̂��y�Y(����)�����Q���Ă��܂����B
• ���w�E��2019�N12��20����2020�N9��1���́A�������NTT���V�c�В��A���c���В��A�鏑������3���Ɖ�H�����Ă���܂��B�u���S���芨�v�ȊO�ł̉�H���o���Ȃ��|�͐���ɓ`������ŁA�鏑�����ɉ������߂Ă��������A�y�Y�t����1�z�̒ʂ�A�w�肳�ꂽ10,000�~�����x��������ƂƂ��ɁA�����16,500�~(3����)�̂��y�Y�����Q�v���܂����B2��Ƃ��A�����̕��S�z��26,500�~�ł��B
�Z�y�Y�t����1�z�́A2���̓����x�������̗̎��̃R�s�[
• �w�肳�ꂽ��ꏊ�̓X�܂ɂ��܂��ẮA�����T�C�g�����t����Ȃ������ׁA�y�Y�t����2�z�̗��������Q�Ƃ��A�K�ȋ��z�̉����x�������ƍl���Ă���܂��B
�Z�y�Y�t����2�z�́A�l�b�g��Ŋm�F�ł������Y�X�܂̗������(NTT�O���[�v�d�F��{���̃T�C�g�F�t�����X����8,000�~�ˉ��������6,400�~)
• ���A�����ȏ��ǂ̓���@�l�ł���NTT�����ENTT�����́u�Ɩ��ɌW�鋖�F�����v�̍ŏI���ٌ��́A��b�ɂ͂���܂���(�ǒ����قő�b�ւ̐����͖���)�̂ŁA��H�̐Ȃ�NTT���狖�F���Ɋւ���˗��������Ƃ͊F���ł��B
�Ⴒ����2�ɂ��ā�
�Z����2�́A���H���S�z���S�����̂�NTT �������Ƃ��������B2019�N�̎��x���ɂ͓��Y�̋L�ڂ��������ANTT�������S�����͎̂������A�Ƃ������e
• 2020�N���̎��x���͍��N5������o���ł����A2019�N�̎��x���ɂ́A2019�N12��20���̉����v�サ�Ă���܂��B�@���ɑ���A10,000�~���̎x�o�ɂ��Ă͎x�o��(�X��)���L�ڂ��܂����A10,000�~�̏ꍇ�́u���̑��x�o�v�̔�ڂɓ����Ă��܂��B
• ���A��b�ݐE���́A�x���̏؋����m���Ɏc�����߂ɁA�u���v�ɂ��Ắu�����}�ޗnj����I����x���v����x�o���邱�Ƃɂ��Ă���܂����B�O�ׂ̈ɕt�L���܂��ƁA�ŋ��ɂ��u���}�������v�����H��Ɏg�����Ƃ́A�����}�ŋ֎~����Ă��܂��B�u���}�������v�̎g�r�ɂ��ẮA�}�x���̎��x���Ƃ͕ʂɁA�u�g�r�����v��1�����܂łɓ}�{���̃`�F�b�N�������2�����܂łɓ}�{���ƑI�ǂɒ�o���Ă���܂��̂ŁA���H��̎x�o���������Ƃɂ��ẮA�u�g�r�����v���{�����Ē�����ƍK���ł��B
��
�ȏオ�A�{��c��c���A���̉���T���Ē����p����������A�����̎��Ԃ��g���č쐬�������ł��B�̎���T���ׂɁA�ޗǎ������̉�v�ӔC�҂ɂ���J�������܂����B
��b�ݔC���ɂ́A�����ȊW�c�̂�W���Ǝ҂ƁA��H���ӌ�����(�S�āu���芨�v���u�S�z�������S�v)�͓x�X����܂����B
�A���̂悤�ɏO�Q�ňψ���ق������Ė�Ԃ͑̂��x�߂��������ł��A���������đΉ����Ă��܂����B������A����3���̎d�����ƍl��������ł��B
�ʎZ4�N�Ԃ̑�b�ݔC���́A�w��b�K�́x�����i�Ɏ��ׂɁu����p�[�e�B�[�v(��K�͂Ȑ��������p�[�e�B�[)�̊J�Â����܂���ł������琭�}�x����������c�̂̎c�����R�����A�����{��k�Д�Вn�ւ̎x���Ƃ��ċ��^�̍��ɕԍς�����Ƒ��̍���c�����������̎���z��5���~�����Ȃ��Ȃ�܂����炨�y�Y��p�ӂ��镉�S���傫���A�u���芨�v��u�S�z�������S�v��O�ꂵ���������Ƃ́A�����ɋꂵ�����̂ł����B
�֘A���Ǝ҂̘J���g���Ƃ̈ӌ�������ɂ������Ă��܂������A���芨���z�������ɍ��z�ŁA�b��͑����Ȃւ̕s������Ō������ӂߗ��Ă��A�����o�������قǂɐh���Ȃł����B����ł��A�����f���̂�����3���̎d�����Ǝv���đς��Ă��܂����B
NTT�ɑ��ẮA����Ǝ�茈�߂��u���芨�v�̉�����悤�ȐH������ݕ����o����Ă����Ƃ�����ᔽ�ł��̂ŁA���}�ɖ��גP���ׂĂ��������A���Ɂw�T�����t�x�̋L���ɂ���悤�ɍ��z��������̂ł���A�������ɂ��x��������|�����`�����Ă���܂��B
����̋L����ǂ�ŁA�u�s���̌������v�ɓ��ɒ��ӂ��Ă����҂Ƃ��āA�������ĂȂ�܂���B�@ |
 �@3/11 �@3/11 |


 �@
�@ |
|
�����s�O�������A���F�Ɂu���ق͋ǒ��v�Ǝ咣�@�����ȁu�@�I���`�l�͑�b�v�@3/11�@ |
�m�s�s������̐ڑҖ��ŁA���s���c�O�������͎��g�̃z�[���y�[�W(�g�o)�ŁA�m�s�s�����Ƃ̉�H�͐ڑ҂ł͂Ȃ������Ƃ̌�������������Łu��b������b���w�ʐM���Ƃ̋��F�ɒ��ڊւ��x���ƂȂǂȂ��v�Ǝ咣�����B�m�s�s�Ɋւ�鋖�F�̑����͑������ł͂Ȃ��ǒ����قł��邱�Ƃ����������`�����A�����Ȃ̒S���҂͖{���̎�ނɁu���F�̖@�I�Ȗ��`�l�͑��������v�Ɛ��������B
���s���͂g�o�Łu�w�ŏI���فx������̂́A��b�╛��b�ł͂Ȃ��ǒ����v�Ǝw�E�B�������ݔC���Ɏ��g�����ق����̂͂m�s�s�̖����l����1���݂̂Ƃ����B
�����Ȃɂ��ƁA�ʐM���ƂɊւ��鋖�F�̑����͋ǒ������ق��邱�ƂɂȂ��Ă���B����A�d�C�ʐM���Ɩ@�ł͋��F�̑����͑��������s���ƒ�߂Ă���B�����Ȃ̒S���҂́u�K���ɏ]���ċǒ�����b���`�Ō��ق��Ă���v�Ɛ�������B
���s���̎������́A�������̋��F���Ɋւ���{���̎���Ɂu�@�I�Ȗ��`�l�͑������ł����Ă��w���F�ɒ��ڊւ�邱�Ɓx�͂Ȃ��v�Ɖ����B�@ |
|
����c���⍂�s����A��H�F�߂�@NTT�ڑҖ�� 3/11 |
�����Ȃ̐����O���ݔC���ɂm�s�s������ڑ҂����ƏT�����t�ɕ�ꂽ�����}�̖�c���q��������s��4���́A���������H�̎�����F�߂��B���̏�ŁA�����̐M������I�������̊m�ۂ�ړI�Ƃ����b�K�͂ɂ͒�G���Ă��Ȃ��Ƃ����F�����������B
��c����11���A�}�{���Ŏ�ނɉ����A������������2017�N11���ɂm�s�s�h�R���̗���h�В��ƁA18�N3���ɂm�s�s�����{�̑����a�r�В�(����)��Ɖ�H���A����͔�p���x����Ȃ������Ɛ����B2��Ƃ����g�̑I����ł�����W�҂̏W�܂肾�����Ƃ��āu�d���̘b�͂قƂ�ǂ��Ă��Ȃ��v�Ƌ��������B
���肪�����̌o�c����������18�N�̉�H�Ɋւ��ẮA��b�K�͂ɒ�G����Ƃ����^�O���������˂Ȃ��Ɣ��f�B���H��ɓ������2��6000�~��ԋ������Ɩ��炩�ɂ����B
���s����10���A���g�̃z�[���y�[�W�ŁA�����������19�N12����20�N9����2��A�m�s�s���V�c���В���Ɖ�H�����ƌ��\�B�u�w���S���芨�x�ȊO�ł̉�H�͂ł��Ȃ��|�͐���ɓ`�����v�ƋL���A���ꂽ���1���~���x�����A1��6500�~���̓y�Y���n�����Ǝ咣�����B�u���F���Ɋւ���˗��������Ƃ͊F�����v�Ƃ��A���ƂɊւ��錈�ق͋ǒ��܂łŊ������Ă���A���g�͊ւ���Ă��Ȃ��Ǝw�E�����B
��������b���������w���[�������Ǝ��c���O�@�c����11���A���ꂼ��̋c����������ʂ��A���ȕ��S�Ȃ���H�������Ƃ�F�߂��B�����Ƃ��X��}��悤�˗����ꂽ���Ƃ͂Ȃ��Ɛ����B���c���͈��H���2��4000�~��ԋ������B�@ |
|
���g�����������NTT�Ɖ�H�h�� ��c����ڑ҂ł͂Ȃ��ƔF�� 3/11 |
�����Ȃ̐ڑҖ��Ɋ֘A���āu�T�����t�v�́A������b�߂������}�̖�c���q��������s�⍂�s������������炪�A�ݔC������NTT�̎В���Ɖ�H���Ă����Ȃǂƕ܂����B��c���ƍ��s���͂��������H�̎����͔F�߂�����A�ڑ҂͎Ă��Ȃ��Ƃ����F���������܂����B
11���A�������ꂽ�u�T�����t�v�́A�����Ȃ̐ڑҖ��Ɋ֘A���āA������b�߂Ă��������}�̖�c���q��������s�ƍ��s���c������������A�܂���������b�߂Ă������w���[�������Ǝ��c���O�c�@�c�����A���ꂼ��ݔC������NTT���V�c���В���Ɖ�H���Ă����ȂǂƕĂ��܂��B
����ɂ��Ė�c����11���ߑO�A�}�{���ŋL�Ғc�ɑ��A2017�N��2018�N��2��ANTT�̊�����Ɖ�H�������Ƃ�F�߂�����A�u�d���̘b�͂��Ă��炸�A�����Ɛ蕪���Ă����̂ŁA�����ȂƂ͊ւ��Ȃ��v���C�x�[�g�̉�Ƃ����F���������v�Əq�ׁA�ڑ҂Ƃ����F���͂Ȃ������Ƃ����l���������܂����B�����āA��H��p�̈ꕔ��NTT�������S���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ��āA���̕��̔�p���x�������Ɛ������܂����B
�܂��A���s���͎��g�̃z�[���y�[�W�Ɍ������f�ڂ��A��H�������������͔F�߂����A�u��b�ݔC���͊֘A���Ǝ҂ȂǂƂ̉�H�́A���芨�ɂ��邩�S�z�����g�����S����Ή���O�ꂵ�Ă����v�Ƃ��āA�w�肳�ꂽ�����x�����������y�Y�����Q���Ă���A�ڑ҂͎Ă��Ȃ��Ɣ��_���Ă��܂��B�����āA��H�̏�ŁANTT���狖�F�ȂǂɊւ��˗��������Ƃ͂Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B
��䕛�����́u2018�N6��29����NTT���Ɖ�H�������Ƃ͎������B���O�������w�m�l���Љ��x�Ƃ����U�����ĉ�H�����B���H��͑��葤�̎x�����ŁA���z�͕����Ă��Ȃ��B���̏�ł͑����Ȃ̋Ɩ��Ɋւ���v����v�]�͑S���Ȃ������v�Ƃ���R�����g���o���܂����B
���c���͎��g�̎�������ʂ��āuNTT�̊W�҂Ɖ�H�����͎̂����ł���A���H��͑��葤���x�������B���łɕ���b��ޔC���邱�Ƃ����܂��Ă��������ŁA���̈ԘJ��Ƃ����F���ŎQ�������BNTT���ɂ́w���H����x���������x�Ɠ`���Ă���v�ƃR�����g���Ă��܂��B
NTT�́u��������ӌ������̂��߂ɂ��܂��܂ȕ��Ƃ̉�H�͍s���Ă���Ƃ���ł͂��邪�A�ʂ̍���c���Ƃ̉�H�ɂ��Ă͉������T����v�ƃR�����g���Ă��܂��B�܂��A�В���Ɛ����ƂƂ̉�H�����邩�ǂ����ɂ��Ắu�ӌ�������ړI�Ƃ��Ă���̂ŁA��b���܂߂Đ����ƂƂ̉�H�ɂ͖@�I�Ȗ��͂Ȃ��ƔF�����Ă���A���̂Ƃ��뒲���̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��B
�������[�����́A�ߑO�̋L�҉�Łu��䊯�[����������́ANTT�̎�������䎁�̊w�Z�̐�y���Љ�Ă���������Ƃ����b������A��H�������ƕ����Ă���B���̍ۂɂ́A�E���Ɋ֘A����˗��Ȃǂ̘b�͂Ȃ������Ƃ̂��Ƃ��v�Əq�ׂ܂����B�܂��L�Ғc���uNTT������p�S�����Ƃ̂��Ƃ����w��b�K�́x�ȂǂɏƂ炵�ēK�ƌ�����̂��v�Ǝ��₵���̂ɑ��u�w��b�K�́x�́A���E�ɂ�����̂Ƃ��Ă̐�������ێ����A�����ƍs���ւ̍����̐M�����m�ۂ���ϓ_�����߂�ꂽ���̂��B�X�̍s�ׂ������̋^�f�������悤�ȍs�ׂɂ����邩�ɂ��ẮA�e������b�Ȃǂ���̂̎��Ăɑ����A��|�܂��K�ɔ��f���ׂ����̂ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B�܂��u�P�����d�߂ɂ͂�����Ȃ��̂��v�Ƃ�������ɑ��Ắu�X�̎��Ăɉ����Ĕ��f�����ׂ����̂Ə��m���Ă���v�Əq�ׂ܂����B
�����}�̊ݓc�O����������́A�L�Ғc�ɑ��u����c���̉�H�́A���ƌ������ϗ��@�Ƃ͕ʂ̎��_�œK���ǂ������厖�ŁA��b�ł���A��b�K�͂ɏƂ炵�Ăǂ��Ȃ̂�������K�v������B����������Ȃ��悤�����ӔC���ʂ������Ƃ��厖���v�Əq�ׂ܂����B
�Q�c�@�\�Z�ψ���̗�����ł́A��}�����A��ꂽ���e�̎����W���������K�v������Ƃ��āA������b�߂������}�̖�c��������s�⍂�s��������������12���̈ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v����悤���߂��̂ɑ��A�^�}���͎����A���đΉ�����������l���������A�����������c���邱�ƂɂȂ�܂����B
�܂��O�c�@�\�Z�ψ���ł��A�����Ȋ�����NTT���V�c�В���ɂ��ڑҖ����߂����ė^��}�̕M����������k���A���T16���̌ߑO���ɗ\�Z�ψ�����J���A�V�c�В����Q�l�l�Ƃ��ď��v�����^���s�����Ƃō��ӂ��܂����B
����A��}���́A�q�������֘A��Ёu���k�V�Ёv�̎В���u���k�V�Ёv�ɋ߂鐛������b�̒��j�̎Q�l�l���v�����߂܂������܂荇�킸�A���c���������邱�ƂɂȂ�܂����B
�����}�̖k������\�́A�L�҉�Łu�E���̎��s�ɋ^�O��������Ȃ����Ƃ��ɂ߂đ厖���B�s�����̐E�ɂ���l�͑�b���܂߁A�^�����w�E���ꂽ�Ȃ�A������������ӔC���ʂ����Ă��炢�����v�Əq�ׂ܂����B
��������}�̋ʖؑ�\�͋L�҉�Łu�����Ƃ͂��낢��Ȑl�Ɖ�H���邪�A��@���ǂ����ɂ��ẮA�E���������H�̏A�x�����������ǂ����Ȃǂő����I�ɔ��f����K�v������B�܂��͖{�l���������ׂ����B���̂�����NTT��������ǂ������Ӑ}�ŒN�ɑ��Đڑ҂������A���������߂����v�Əq�ׂ܂����B
|
|
����c���u�v���C�x�[�g�ȉ�v�A���s���u���芨�v�c�u�ڑҁv�͔ے� 3/11 |
�m�s�s�ɂ�鑍���Ȋ�����ւ̍��z�ڑҖ��́A���̑�������ɂ��g�債���B�T�����t�̕ɑ��A�����}�̖�c���q��������s�ƍ��s���c�O�@�c���͑������ݔC���ɂm�s�s���Ɖ�H�������Ƃ�F�߂����A�u�ڑҁv�͎Ă��Ȃ��Ɣ��_�����B
�Q�@�\�Z�ψ���œ��ق��镐�c������(11���A�����)�Q�@�\�Z�ψ���œ��ق��镐�c������(11���A�����)�L�Ғc�̎���ɓ����鎩���̖�c��������s(11���A�}�{����)�L�Ғc�̎���ɓ����鎩���̖�c��������s(11���A�}�{����)
��c����11���A�}�{���ŋL�Ғc�ɑ��A2017�N�Ɍ��m�s�s�h�R���В��̗���h��ƁA18�N�ɓ����m�s�s�����{�В������������a�r����Ɖ�H�������Ƃ𖾂炩�ɂ��A�u�����Ɛ蕪���Ă����̂ŁA�����ȂƂ͊ւ��Ȃ��v���C�x�[�g�ȉ�Ƃ����F���������v�Ɛ��������B2��̉�H�̂����A�x�����Ă������1��ɂ��Ă͉�H���2��6000�~��ԋ������Ƃ����B
���s����11���A�ǔ��V���̎�ނɑ��A19�N12����20�N9���ɂm�s�s���V�c���В��A���c�����В���Ɖ�H�����Ɛ����B��������A�m�s�s���Ɏw�肳�ꂽ���1���~���x�����A1��6500�~���̓y�Y��n�����Ƃ����B�x�슯�Ɖ^�]��ٓ̕���ȂǁA���ۂɂm�s�s�������S�������z�Ƃ̍��z�ɂ��Ă͂��łɕԋ������Ƃ����A���s���́u���F�Ɋւ���˗��͎Ă��Ȃ��B���芨�ɂȂ�悤�Ή����Ă���A�ڑ҂����Ƃ͗������Ă��Ȃ��v�Ƌ��������B
���̂ق��A���w���[�������Ǝ����}�̎��c���O�@�c������������b�ݔC���ɂm�s�s���ƐH�����������Ƃ�F�߂������ŁA�ʐM�s���ւ̓���������ے肵�Ă���B
����ɑ��A��}��11���̎Q�@�\�Z�ψ���̗�����ŁA��c�A���s������̎Q�l�l���v�����߂��B
�܂��A��}�͂��̓��̎Q�@�\�Z�ςŁA���c���������m�s�s����ڑ҂��Ă������ǂ�����₢���������B�O���̎Q�@�\�Z�ς́A���c�����m�s�s�Ƃ̉�H�̗L�����Ȃ��������ƂŁA�R�c�����f���A���̂܂U��Ă����B���c���͂��̓����u�ʂ̎��Ăɓ�����͍̂T���邪�A�����̋^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Ɩ�����������B�����A��O�҂ɂ�錟�؈ψ���̒����ɂ��Ắu�����O�����܂߂Ă������蒲������v�Əq�ׁA�������o���҂��㐭���O�����ΏۂƂ���l�����������B
����A�O�@�\�Z�ψ���̗^��}�M��������11���A16���ɗ\�Z�ς��J���A�m�s�s���V�c�В����Q�l�l�Ƃ��ď��v���邱�Ƃō��ӂ����B
|
|
�������� �����O���̉�H���� �g��O�҈ςɗv�]�`����h ������ 3/11 |
�����Ȃ̐ڑҖ��Ɋ֘A���āA�Q�c�@�\�Z�ψ���ŁA��}�����A�����Ȃ̐����O���ƁANTT���Ƃ̉�H�̗L���Ȃǂ𖾂炩�ɂ���悤���߂��̂ɑ��A���c������b�́A�ȓ��ɐݒu����\��̑�O�҈ψ���ɗv�]��`����l���������܂����B
11���J���ꂽ�Q�c�@�\�Z�ψ���ŁA��}���́A�����Ȃ̐ڑҖ��Ɋ֘A���āA���c������b��NTT���Ɖ�H�������Ƃ����邩�������܂����B
����ɑ��A���c��b�́u�ʂ̎��ĂɈ�������͍̂T�������B��������^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ����A���������A�݂�����𗥂��A�E���ɐ�O���Ă��������v�Əd�˂ďq�ׂ܂����B
���̂����ŁA��}�����A�����Ȃ̐����O����NTT���Ɖ�H��������A��H���s��ꂽ�ꍇ�̔�p���S�Ȃǂ𖾂炩�ɂ���悤���߂��̂ɑ��A���c��b�́u��O�҂̃`�F�b�N�@�ւł��钲���ψ���ɁA����ł̎w�E��`���A�����͈͂��܂߂āA�w�������������Ȃ���i�߂Ă��������v�Əq�ׁA�ȓ��ɐݒu����\��̑�O�҈ψ���ɗv�]��`����l���������܂����B
�������[�����u�܂т炩�ɂ���͓̂K�ł͂Ȃ��Ɣ��f�v
�������[�����͌ߌ�̋L�҉�ŁA���c������b�̎Q�c�@�\�Z�ψ���ł̓��قɂ��āu���ꂼ��̐����Ƃ����낢��Ȋ��������Ă���킯�ŁA��������܂т炩�ɂ���͓̂K�ł͂Ȃ��Ƃ������f���낤�v�Əq�ׂ܂����B
�܂��L�Ғc����u�^�O�������邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����v�Ǝ��₳�ꂽ�̂ɑ��u�c�_��˂��l�߂�ƁA�S���b�����邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����ŁA�������^�O��������Ȃ����Ƃ͑厖���v�Əq�ׂ܂����B
|
|
����c����H�F�߂� ������b����� �ڑ҂͔ے� 3/11 |
|
�ڑ҂ł͂Ȃ��A�v���C�x�[�g�ȉ�������Ƌ������܂����B�����} ��c��������s�u�����A�����Ɛ蕪���Ă����̂ŁA���R�A�����̑����ȂɑS���ւ��Ȃ��v���C�x�[�g�ȉ�Ƃ����F���v�����}�̖�c���q��������s�́A�ꕔ�T�����ő�����b�ݔC���ɂm�s�s������ڑ҂��Ă����ƕ�ꂽ���Ƃɂ��āA2��̉�H��F�߂���ŁA�ڑ҂Ƃ̔F���͂Ȃ��A��p�͕ԋ������Əq�ׂ܂����B�܂��A��������b����ɂm�s�s�̊�������ڑ҂����ƕ�ꂽ��䊯�[���������A��H�̎�����F�߂���ŁA�u�Ɩ��Ɋւ���v����v�]�͑S���Ȃ��v�Ƃ̃R�����g�\���܂����B����������A�̐ڑҖ�������A���c������b�͂��傤����ŁA���������łȂ���b�╛��b�A�������̐����O�����ΏۂƂ��đ����Ȃ̌��؈ψ���Œ�������l���������܂����B
|
|
�����c�������A�m�s�s�Ɖ�H�������@��㐭���O�������ؑΏ� 3/11 |
���c�Ǒ���������11���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA�m�s�s�Ƃ̉�H�����������ǂ��������u�ʂ̎��Ăɓ�����͍̂T����B�����̋^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Əd�˂ďq�ׂ��B�����Ȋ����ւ̈�@�ڑ҂Ɋւ��錟�ł́A�������o���҂���̐����O�����ΏۂƂ���ӌ���\���B��O�҂ɂ�錟�Łu�O��I�ɐ^��������i�߂�v�Ƃ��āA��Ƃ̌����������������B
�����Ȃ͈�@�ڑҖ����āA�����o���̂���ٌ�m��L���҂ō\�������O�҈ψ����ݒu����\��B��}�́A�m�s�s�Ƃ̉�H�Ŗ��O�������������ɁA���؈σg�b�v�A�C�\��̕���b������Ǝw�E�����B�@ |
|
���������A�m�s�s�Ƃ̉�H�̗L���������u�^�O�����悤�ȉ�ɉ����Ă��Ȃ��v 3/11�@ |
���c������b��11���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA�m�s�s���Ƃ̉�H�����������ǂ��������A�u�ʂ̎��Ăɓ�����͍̂T����B�����̋^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Ɠ��ق��܂����B
�u�Ȃ��A��b�͂m�s�s�Ƃ̉�H�����������ǂ����̎��������ł������ł��Ȃ��̂ł��傤���v(���Y�} �⟺�F�Q�@�c��)
�u�ʂ̎��Ĉ��ɂ���������͍̂T�������Ă������������Ǝv���܂��B�������A���͍����̊F����^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂������܂���v(���c�Ǒ�������)
���c������b�͖�}�̎���ɌJ��Ԃ��������ق��A�m�s�s���Ƃ̉�H�̗L���ɂ��Ă͒��ڂ̌��y������܂����B�܂��A�����Ȃ̊����ւ̈�@�ڑ҂Ɋւ��錟�ł́A������b�o���҂���̐����O���������̑ΏۂƂ���Ƃ̍l���������܂����B
����A�m�s�s��11�������̏T�����t���A�m�s�s���J��Ԃ��A���̑�����b�������b�E��������ɐڑ҂��s���Ă����ƕ����Ƃɂ��āA�u��������ӌ������̂��߂ɂ��܂��܂ȕ��Ƃ̉�H�͍s���Ă���Ƃ���ł͂��邪�A�ʂ̍���c���Ƃ̉�H�ɂ��Ă͉������T�������Ă��������v�ƃR�����g���܂����B�m�s�s�́A�u����c���Ƃ̉�H�͖@�I�Ȗ�肪�Ȃ��Ƃ̔F���ŁA�������K�v���ƍl���Ă��Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��B�@ |
|
���ڑҖ�萭��3���������@��H�L�����������A���C�͔ے�\���c������ 3/11 |
���c�Ǒ���������11���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA�����Ȋ����ɑ���m�s�s����̐ڑҖ��Ɋւ��A�t���A����b�A�������̐���3�����ΏۂƂ��ďȓ��̌��؈ψ���Œ�������l�����������B�ݔC����ޔC��ɐڑ҂�������3���o���҂���������ƏT�����t�ɕ�ꂽ�̂܂����Ή��B���Y�}�̊⟺�F���ւ̓��فB
���c���͎��g���m�s�s�̐ڑ҂������ǂ����ɂ��āu��������^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Əd�˂ē��������A10���̎��^�Ɠ��l�ɗL�������Ȃ������B
��A�̐ڑҖ����߂����}�Ɏ��C�����߂��Ă��邱�Ƃɑ��ẮA�u����擪�ɗ����A�Ȉ�ۂƂȂ��ăR���v���C�A���X(�@�ߏ���)��O��I�Ɋm�ۂ��A�����̐M���ɓw�߂�v�Ƌ������A�����Ɉӗ~���������B��������}�̔��^�M���ւ̓��فB�@ |
 �@3/12 �@3/12 |


 �@
�@ |
|
��NTT�Ƃ̉�H�u���W�҂̏W�܂�v�u�L���ɓ{��S���v��c�E���s���� 3/12 |
����c���u�����ȂƊւ��Ȃ��v���C�x�[�g�ȉ�ƔF���v
�\�����W�́B
�u2017�N(�̉�H)�͊��l��L�u�̐�y���������k������悤�Ƃ������ƂŁA�m�s�s�h�R�����В�������1�l�������B����20�N���炢�O�̎В��ŁA�����͊��Ɉ��ނ���A�m�s�s�̐Ђ��Ȃ��B�x�������X�l�A�ʁX�������B�b�̓��e�͌��l��̘b���肾�����v
�u18�N�̉�H(����)�͏����I�ȗ��A30�N�߂��F�l�Ƃ��ĕt�������Ă���m�s�s�����{�В��B(�I�����)�̎x�X������シ�邽�сA�������킹���ꂽ�B�d���ɂ��Ă͂قƂ�ǘb���Ă��Ȃ��B�В����N���Ƃ������ƂŎx�����Ă�����Ă������Ƃ�������(���)���z��₢���킹�A���̕���2��6150�~��U�荞�v
�\18�N�̉�H�ł́A�����X��}��悤���܂ꂽ���B
�u�����B���(��)�x�X�������邽�тɏЉ��Ă����v
�\�W�Ǝ҂���̋����ڑ҂��ւ��鍑����b�K�͂Ɉᔽ���Ă��Ȃ������Ƃ����F�����B
�u�����Ɛ蕪���Ă���A���R�A�����ȂƑS���ւ��Ȃ��v���C�x�[�g�ȉ�Ƃ����F���������v
�����s���u��b������b�����F�Ɋւ�邱�Ƃ͂Ȃ��v
�T�����t�̋L������ǂ������{��S�����B���́u�ڑҁv�͎Ă��Ȃ��|�A��ގ҂ɖ��m�ɕ����ʼn����B��b������b���u�ʐM���Ƃ̋��F�ɒ��ڊւ��v���ƂȂǂȂ��B���������u���فv���Ă��Ȃ��̂�����B���ƂɌW����̂́u�ŏI���فv������̂͋ǒ��B�Č��̐�������Ă��Ȃ��B
�m�s�s���V�c(��)�В���Ɖ�������ɂ��A���̌l�I�ȊS�����ł���T�C�o�[�Z�L�����e�B�[�ɂ��āA���m���������Ă��������Ă����B�������A�����Ȃ̔F���ɌW�闊�ݎ��̘b�肪�o�����Ƃ͊F�����B
��b�ݔC���ɂ́A�����ȊW�c�̂�W���Ǝ҂ƁA��H���ӌ�����(�S�āu���芨�v���u�S�z�������S�v)�͓x�X�������B������A�����O���̎d�����ƍl�������炾�B�m�s�s�ɑ��ẮA����Ǝ�茈�߂��u���芨�v�̉����Ă�����ᔽ�Ȃ̂ŁA���}�ɒP���ׂĂ��������A���z��������̂ł���Ύx�����|��`���Ă���B����̋L����ǂ݁A�u�s���̌������v�ɓ��ɒ��ӂ��Ă����҂Ƃ��ĉ������ĂȂ�Ȃ��B�@ |
|
�������e���r�ǂƂ͗ϗ��@�ᔽ�Ȃ� 3/12 |
���{��12���̊t�c�ŁA�����Ȃ������ڑҖ������荑�ƌ������ϗ��R����ɕ��������̉ߒ��ŁA�����e���r�ǂƂ̊Ԃł͍��ƌ������ϗ��@�Ɉᔽ���鎖�����m�F�ł��Ȃ������Ƃ��铚�ُ������肵���B���{�ېV�̉�̗�؏@�j�Q�@�c������o���������ӏ��ɓ������B
��������}�̉��{�[���O�@�c���̎����ӏ��ɑ��铚�ُ��ł́A���E�����R�c�^�M�q�O���t�L�̑ސE�蓖�ɂ��āu�x������邪�A�z�͌l���̂��ߍ����T�������v�Ƃ����B�@ |
|
���m�s�s�ڑҁA�����Ɋg��@��c�E��䎁���H�F�߂� 3/12�@ |
�m�s�s�ɂ�鑍���Ȋ����̍��z�ڑҖ��ŁA�����}�̖�c���q��������s�A���w���[�������A���c���O�@�c����11���A�������������b�̍ݔC���ɓ��Б�����ڑ҂��ꂽ�Ƃ̏T�����t�̕��A��H�͎����Ƃ��ꂼ�ꖾ�炩�ɂ����B���s���c�O�������͊��ɉ�H��F�߂Ă���B�s���ւ̐M����h�邪���ڑҖ��́A���}�̐���3���o���҂ɂ��g�y���A��Ȃ��̗l����悵�Ă���B
�t���A����b�A�������̐���3���̋K�͂́A�ڑ҂Ɋւ��u�����̋^�f�������悤�ȍs�ׂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƒ�߂Ă���B��}�͖�c����̍���v��v�����A�s�����䂪�߂��Ă��Ȃ����O��Njy����\�����B
��c����11���A�}�{���ŋL�Ғc�̎�ނɉ����A������������2017�N�ɗ���h��m�s�s�h�R�����В���A18�N�ɓ����̑����a�r�m�s�s�����{�В���Ɠ����s���̃��X�g�����ʼn�H�����Ɩ��������B�����A2��Ƃ��u�d���̘b�͂قƂ�ǂ��Ă��Ȃ��B�����Ȃ��S���ւ��Ȃ��v���C�x�[�g�ȉ�v�Ǝ咣�B2��ڂ͔�p�S���Ă���������A��2��6000�~�����ɕԍς����ƌ�����B
��������b�߂Ă�����䎁�̓R�����g���o���A18�N�Ɏ��O���m�s�s��Ɖ�H�����ƕB�u���H��͑��葤�̎x�����B�Ɩ��Ɋւ���v����v�]�͑S���Ȃ������v�Ɛ��������B��䎁�͐��`�̎̑��߂Ƃ��Ēm����B����������b���������c���̎������͎�ނɁA20�N���V�c���m�s�s�В�����̐ڑ҂�F�߂���ŁA��p��2��4000�~�͕ԍς���Ɛ��������B
���s����10���A19�N��20�N���V�c���Ƃ̉�H��F�߁A���芨�ƔF�����Ă����Ƃ��ĕs�������x�����l�����z�[���y�[�W�Ŗ��炩�ɂ��Ă���B
��������}��11���A��c�A���s��������Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ď��v����悤�v���B�����}�͑�����������B���}��15���̎Q�@�\�Z�ςɑ����A16���̏O�@�\�Z�ςł��V�c���̎Q�l�l���^���s�����Ƃł͍��ӂ����B
����A���c�Ǒ���������11���̎Q�@�\�Z�ςŁA���@���o���҂���ψ��ɋ߂����������錟�؈ψ���ɑ��A�m�s�s�Ɛ���3���̉�H����������悤���߂�l�����������B�u����3�����܂߂Ă�������ƒ�������悤(���؈ς�)�������v�Əq�ׂ��B���g�̉�H�̗L���Ɋւ��Ắu��������^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v��10���̐������J��Ԃ��A������������B �@ |
|
���R�c�����t�L���������u�㋉�����v�����@3/12
|
�������j�����]���Ď��C�ցB���`�̑����̒��j�E���������獂�z�ڑ҂��Ă������Ƃ����o�����R�c�^�M�q�����t�L�̏����������ĉ�����ꂽ�h�^�o�^���B�\���䂩�狎�邱�ƂɂȂ����ޏ����������A�u�㋉�����v�����ƁA�ؗ�Ȃ�u����c���]�g�v��v�\�\�B
�w���҂ɋ��߂���d�v�Ȏ����̈�Ƃ��āu��ɑבR�Ƃ��Ă��邱�Ɓv���������悤�B�p�ɂɊ����I��ɂ���u��v�A�Ⴆ�Ή�Ђ̏�i�̌��t�ɐ����͂������͂��͂Ȃ����A���g�������Ă���ł��s�����B�����Ƃ��ł��Ȃ���i�ɂ͒N�����Ă����Ȃ��͂��ł���B�u��v���ł��s�����B���Ȃ���A�u���v�͍���������肾�B
���������_���猩��ƁA�u�Ԃ牺�����v�̏�ł��痧�����B�����Ƃ��ł��Ȃ������������́A�w���҂Ƃ��Ă̎����ɂ͋^�╄��t������Ȃ��̂ł͂Ȃ����BNHK�̒��p�f���ɂ���āu���痧�����v�̎p�����A���^�C���Ŗڌ����A���G�Ȋ����������������������ɈႢ�Ȃ��B
����������̏�Ŏv�킸�����I��ɂ��Ă��܂����w�i�ɁA�����̒��j�E���������߂�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv�ɂ�鑍���Ȋ�����ւ̐ڑҖ�肪����̂͊ԈႢ�Ȃ��B���̖��́u�T�����t�v�̕ɂ���Ĕ��o���A10�l�ȏ�̊�������������鎖�Ԃɔ��W�B���ł��A�����Ȃ̒����ɂ����2019�N�A�����R�c������ɐ������炩��ڑ҂��Ă������Ƃ����������R�c�^�M�q�����t�L��(60)�̃P�[�X�́A�������̗v�f�Œ��ڂ��W�߂��B
��́A1�l������7��4203�~���̍��z�ڑ҂��������ƁB������́A�ޏ����u�������v�Ƃ��Ēm���Ă������Ƃł���B�������������e���͂��ւ鑍���Ȃŗv�E���C���A13�N�A��2�����{���t�ŏ������̎鏑���ɔ��F���ꂽ�R�c���B���������a������ƁA���t�́u��v�ł�����t�L�Ɏ�藧�Ă�ꂽ�ޏ��́A�ڑҖ��̔��o����2��25���̏O�@�\�Z�ψ���ɏo�ȁA��}�c������ᔻ�̏W���C�𗁂т��B���̏�ł́A�ޏ����ȑO�A���惁�b�Z�[�W�Łu���݉���ɒf��Ȃ����Ƃ��Ă���Ă����v�ƌ���Ă������Ƃ܂ł��ʂɋ�����ꂽ�̂ł���B
�����Č}������26���A�ً}���Ԑ錾�̈ꕔ�n��̐�s�����ɔ����A���t�L�҉�͑����̋L�҉��v�]�������A�����͂�������ہB����ɍs��ꂽ�̂��`���ŐG�ꂽ�u�Ԃ牺�����v�ł���B�L�҉���J���ƂȂ�A�R�c�����i��߂���Ȃ��Ȃ�B����䂦�u�Ԃ牺����v�ɂ��āu�R�c�B���v��}�����̂ł́A�Ƃ�����ꂽ���A��ő����́A�u�R�c�L�̂��Ƃ͑S���W�Ȃ��v�ƒf���B���̌�A�L�҂���̎���ɓ����邤���ɂ��痧�����B���Ȃ��Ȃ�A���Ԃɂ�����A�����r�炰���ʂ��B�����čŌ�́u�����悤�Ȏ�����肾�v�Ǝ̂đ䎌��f���ė����������̂ł���B
���������������Łu�בR�v�Ƃ͐����̑ԓx���N���Ă��܂����킯�����A��͂�w���҂ɋ��߂��鎑���ł���u���f�́v�Ɋւ��Ă͂ǂ����B��ł͎R�c���𑱓���������j�ɕς�肪�Ȃ��|���q�ׂĂ����������B����������3�����3��1���A�}篁A�ޏ��͓��t�L�̐E�������邱�ƂƂȂ����̂��B
�u�O����2��28���A�R�c����͐�������������M���[�����ɘA�����A�̒�������ē��@�����̂ŐE�ӂ𑱂����Ȃ��A�Ɠ`���Ă��܂��B�����́g��ނȂ��h�Ƃ��ė������������ł��v�ƁA�����}�W�ҁB
�u�R�c����͉ߋ��ɑ�a�������Ă��܂��B�ŁA�̒������S�ł͂Ȃ����A��}����̏W���C�𗁂тċ����X�g���X��������A���@���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǑ̒���������B�R�c����Ƃ��Ă͂����Ƒ������߂��������悤�ł����A���@�O�̒i�K�ł͐�������c�ɐU��Ȃ������悤�ł��ˁv
�ǂ���炻�́u���f�́v�ɂ��^�╄��t������Ȃ����������A�S�����̐������f�X�N�ɂ��A�u�̒��s�ǂ����R���Ɗ��@�͌����Ă��܂����A���_�̔������A�T���ɂȂ��đ����͖������Ƃ������f�ɌX�����̂ł��傤�B�̒��s�ǂœ��@�Ƃ������Ƃɂ���A��}���ᔻ���Â炭�Ȃ�܂�����ˁv�������L�҂������B
�u�̒��s�ǂ��{���Ȃ̂��ǂ����͂��Ă����A�L�҂������瓯��鐺�͑S���������Ă��܂���B�ޏ��͍L�Ȃ̂ɑ����ԋL�҂ȂǂƐϋɓI�ɃR�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ͂Ȃ��A�����Ă��܂����v
�R�c���͓����w�|��w�������Z���o�āA����c��w�@�w���𑲋ƁB���X���Ȃɓ������̂́A1984�N�̂��Ƃł���B
�u�R�~���j�P�[�V�����\�͂������A�C�z�肪�ł���l���Ƃ��Đ�����ȂǂɈ����グ���A���ɓ��t�L�Ƃ����|�X�g�ɂ����l���ł��B�d���ɂ͌������A���ɍׂ����Ƃ���܂ŕ������g���l�߁h���邱�ƂŒm���Ă��܂��v�ƁA�����ȊW�ҁB
�u�����Ȃ̖{���ł��鋌�����ȏo�g�ł͂Ȃ��A�܂��A����o�g�Ƃ����g�n���f�h������Ȃ���A�T�^�I�Ȓj�Љ�̒��������A�i���o�[2�̑����R�c���Ƃ������_�ɋ߂��Ƃ���܂ŏo�������B�\�͂����������ł͂Ȃ��A�㏸�u���������l���ƔF�����Ă��܂��v
������OB�͂����b���B
�u�ޏ��͐V�l�̍������̐l�Ԃɂ������������ɓ��X�Ƃ��Ă��āA�D�G�ł����B�������A������D�G������Ƃ����āA�ŏI�I�ɏ�ʍs���ǒ�����R�c���ɂ܂ŏ��i����Ƃ͎v���Ă��݂Ȃ������ł��ˁv
�v���C�x�[�g�ł�20��̎��Ɍ���������A�����B���̌�A���X���Ȃ�3�N��y�������g�c���j���ƍč����A���j�����������B���Ȃ݂ɕv�̋g�c���́A�ڑҖ��Ŋ��[�t�ɔ���ꂽ�H�{�F�����̌�K�}�Ƃ��Đ悲��A��ʍs���ǒ��ɏA�C���Ă���B
�u�R�c�����04�N�ɑ����Ȃ���o�����ē����E���c�J��̏����ƂȂ�A07�N�ɂ͈ꎞ�A���撷�����߂Ă��܂��v(��)
08�N�ɖ����V���Ɍf�ڂ��ꂽ�A�ޏ����Љ��L���ɂ͂�������B
�q���j���͏��N�싅�ɏo�����鑧�q�̂��߁A���N�����Ă��ɂ��������B��e���m�̌𗬂��M�d�ȏ������̏�B�u�����҂ł��邱�ƂƁA���̒��ɖ𗧂d�������邱�Ƃ͖��ڂȊW�ɂ���v�r
�ł́A�ޏ��͂����Ȃ�u�����ҁv�������̂��B
�u�ޏ���05�N�ɓ����̂ǐ^�A���c����ɐV�z���ꂽ�����}���V������v�Ƌ��L�ōw�����Ă��܂��B�̔������i��8600���~�B1250���~�̃��[����g�݁A�����5�N�Ŋ��ς��Ă���B���̕����̌��݂̉��i��1��1�疜�~���Ă��܂��v(�s���Y�ƊE�W��)
�g���݉��f��Ȃ��h�͎̂����������悤�ŁA�u���鐭���Ƃ��Z�b�e�B���O�������݉�ɔ�ѓ���ŎQ�����Ă���̂��������Ƃ�����܂��B�}�ɗU���āA�g�s���܂��h�Ɖ������悤�ł��v(�i�c���W��)
�܂��A�R�c�����Q�������ʂ̈��݉�ł́A�u�r���Łg�������C���J�����Ⴈ���h�Ƃ����b�ɂȂ��Đ����~���鍂�����C�������ނ��ƂɂȂ����B���ʂȂ�`�����ł��g���₢��h�Ɖ�������Ƃ���ł����A�S������ȑf�U����������Ɉ���ł����B�ޏ��̓��C���ɏڂ����̂ŁA���ꂪ�ǂꂭ�炢�̒l�i�̂��̂����������Ă����͂��ł��v(���Ȏ�)
�Ȃ�قǁA�����������ށu�㋉�����v�̂悤�Ȑ����𑗂��Ă����킯�ł���B
�u�R�c����͂��Ȃ葁���i�K���琛����ɖڂ��������Ă����悤�ł��B��2�����{��������ɏ������̎鏑���Ƃ��Đ��E�����̂��A���������ł����v�ƁA��̑S�����f�X�N�B
�u�������A�ޏ��͔鏑���A�C��A2�N���������ɑ����Ȃɖ߂���Ă���B���̗��R�́A���@���A�ŋ������Ă������䏮��(������)�O�鏑���Ɍ���ꂽ���炾�Ƃ����̂͗L���Șb�B�����A�L��̂����������ė��҂̈ӌ����H����������Ƃ����[�������悤�ł��v
�R�c�����g�A�������Ɉ������Ă��Ă���A�Ƃ̔F���͎����Ă����悤�ŁA�u(��������)�j�炵���l�B���f������Ԃ�Ȃ��A�Ƃ��Ƃ���v
��N�A�e�����m�l�ɑ��Ă���ȁu���]�v���J���Ă���B�������A�K�������u����v�ł͂Ȃ��A��̉i�c���W�҂ɂ��ƁA�u17�N����18�N�ɂ����Ė�c���q��������b�߂Ă������́A��c����̂��Ƃ��o��̂悤�ɕ���Ă��܂����v
����ȎR�c�����傫�ȓ]���_���}�����̂́A��c�������ɒ�����s�����Ă��������̏����O�̂��ƁB
�u���c�J��̏����A���撷�߂��o������A15�N�ɍs��ꂽ���c�J�撷�I�̌��ɐ��������オ�����̂ł��B�I���̑���́A�Ж��}�̏O�@�c������撷�ɓ]���Ă����ۍ�W�l���ł��v�ƁA���{�W�ҁB
�u�����}����́g���̌�̍����i�o�܂݁h�őŐf���Ȃ���A�ޏ��͑傢�ɔY�悤�ł��B�������A�ŏI�I�ɂ́A�����}����g��ɏ�������h�Ƃ̊m�����Ȃ��������Ƃ𗝗R�ɁA�o�n��f�O���܂����v
���������ߋ������邽�߁A�u�R�c���͐������ł��炭���t�L�߂���A�����}�̌��Ƃ��č����I���ɒ��ނ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����������������v(��)
�������A����ȁu�ؗ�Ȃ鍑���]�g�v��v���A����̈ꌏ�ŏ��ŁB���t�L�̌��z��V117��5��~�A2�疜�~�͒�����ƌ�����N���������ȂǁA�u7��4��~�ڑҁv�̑㏞�͂����Ԃ������̂��B
�u����̌��́A�g�����ȂŐl������U�肩���������|�����̘c�݁h�ȊO�̉����ł��Ȃ��B���������ɊÂ����������̂͊ԈႢ����܂��A�ނ炪������̒��j�̐ڑ҂�f���͂����Ȃ��̂ł��v(��)
�����A�i���X�g�̈ɓ��Օv���������B
�u�������������͓��k�V�Ђ̐ڑ҂�f��Ȃ��ǂ��납�A���ʼn����Ă�����������܂���B����ɂ���Đ������̊o�����߂ł����Ȃ�A�ȂǂƎv�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���v
�������������|�Ŏx�z���A��ł͋L�҂ɂ��痧���A�x�X���f�����B�R���i�Ђ̐��Ԃɏ[������u����v�ɂ�������C�͉ʂ����āA�{�i�I�ȁu�����낵�v�Ɍq����̂��ۂ��\�\�B
�@ |
|
���u7���~�̘a���X�e�[�L�v�ڑ҂��b��@��Ƃ́u���۔�v 3/12 |
�����Ȃ𒆐S�Ƃ����ڑҖ�肪�傫�Șb��ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�R�c�^�M�q�E�����t�L�́A�����R�c��������2019�N�ɁA���k�V�Ђɋ߂鐛�̒��j�炩��A1�l7���~�̘a���X�e�[�L��C�N�����Ȃǂ̐ڑ҂��Ă����B
�ڑ҂��ꂽ���̘b�ɒ��ڂ��W�܂肪�������A��ʘ_�Ƃ��āA�ڑҔ�͊�Ɠ��łǂ���������Ă���̂��B�����Ȃ�Ȃ�قǁA�ߐłɂȂ���̂��B�y�c���ŗ��m�ɕ������B
�ڑ҂Ȃǂ̌��۔�͂ǂ̂悤�Ȉ����ɂȂ�̂��B
�u��Ƃ̎x���������Ƃ̉���E�����i���A�w����̔���l���̂��߂̕t�������̕��S�x���ł�����۔�́A���Z��ł́w�҂��̊l���̂��߂̋]���x�ł������p�Ƃ��Čv�シ�ׂ��ł��B�������A���۔�s���Ɂw�ŋ��v�Z��̌o��x�A�܂�A�w�����x�Ƃ��ĔF�߂�Ɓw�ŋ��𑽂������ʂȂ�A�����B�̉���ɍD������Ɏg���������悢�x�ƍl�����Ƃ�����܂��B����ł͐^�ʖڂɊ撣���Ă����ƂƔ�וs�����ł��̂ŁA���۔�͌��Z��ł͔�p�ƈ�������Őŋ��v�Z��ł́w�����Ƃ��Čv��ł���͈̂����x�z�܂Łx�Ƃ���A���x�z���镔���́A���Z��̉҂�����Ŗ���̉҂����v�Z���邽�߂̒������ڂ̈�Ƃ���܂��B���́A�w�@�l�̌��Z��̉҂��Ɉ��̒��������Đŋ��v�Z��̉҂����Z�o���A�@�l�œ��̐Ŋz���v�Z�������́x�������@�l�Ő\�����Ȃ̂ł��B�ł��̂ŁA�@�l�̌��۔�̒����͖@�l�Ő\������łȂ���܂��v
���x�z�͂ǂ����܂�̂��B
�u�w�����̎��{���̊z���͏o�����̊z��1���~�ȉ��ł��铙�̖@�l�x���ۂ��ň������قȂ�A�Y������@�l��1�N���̐\���̏ꍇ��800���~�ȉ��ł���ΑS�z�����ɂł������ŁA�Y�����Ȃ��@�l�͈��̎Z���Ōv�Z���ꂽ�z�͑����Z���ł��Ȃ����A�����Z���ł�����x�z�͊�ƋK�͂ňقȂ�܂��B�܂��A���ɂ͌��۔�ƌ����邩�������Ȏx�o������܂��̂ŁA��������ŗ��m�ɑ��k����Ƃ悢�ł��傤�v
����̐ڑҖ����ǂ��l���Ă��邩�B
�u���k�V�Ђ��K�Ɍ��۔�Ƃ��Čv�サ�\�������Ȃ�A�w�Ŗ���̊ϓ_�x����͖��͂���܂���B�܂��A��Ђ����S������۔�Ƃ��邩�͓��K�Ɋ�Â��������鎖���ʏ�ł��傤�B�����Ƃ��A�Ŗ@�I�ɂ͓K�ł��A�Љ�I�ɋ�����邩�͕ʖ��B���̂悤�ȕs�ˎ��͌��������e�����ׂ��ł��傤�B�����A����𐭑��̋�Ƃ��Đ����������鎖�����ł��B�L���҂Ƃ��ẮA�s�ˎ��ɖڂ����点���A���݃A�s�[���̂��߂ɉߏ�ɚ������đ��ł͉��̍v�����ł��Ă��Ȃ��ꕔ�̋c���ɂ��������ڂ�������ׂ��ł��傤�v
|
|
�����k�V��NTT�̎��̓e���r���f�B�A 3/12 |
�u��������^�O��������悤�ȉ�H�A��ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�u�R�c�L����R�c�̓d�b���������͂Ȃ��v���{��̌����ɒ��ӂ��K�v���B
2012�N3��9���Ɏ����}���gThe Fax News�h�ŁuTPP�ɂ��Ă̍l�����v�\�����B
���̂Ȃ��ɁA�u���̎匠�Ȃ��悤��ISD�����͍��ӂ��Ȃ��B�v�Ɩ��L���ꂽ�B�������A�����}�����i����TPP�ɂ�ISD���������荞�܂ꂽ�B
ISD�����Ƃ́A�O�����{�̍��ʓI�Ȑ���ɂ�艽�炩�̕s���v���������ꍇ�A������(Investor)�ł��铖�Y��Ƃ����荑���{(State)�ɑ��A���ʂɂ���Ď����Q�ɂ��Ĕ��������߂�(Dispute)������^���邽�߂̏����B
���ْ̍�͐���P���̒��كZ���^�[���s���A���ƂƂ����ǂ��A���̌���ɕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�]���āAISD�����͍��̎匠�Ȃ����̂��B�����}�����ISD���������̎匠�Ȃ����̂�����A���ӂ��Ȃ��Ɠǂݎ���B�Ƃ��낪�A�����}�͂����ے肵���B
�u���̎匠�Ȃ��悤��ISD�����v�ɔ����邪�A�u���̎匠�Ȃ�Ȃ��悤��ISD�����v�ɂ͍��ӂ���Ǝ咣�����B���ǁATPP��ISD�������������܂ꂽ�B
�u�l�̖���D���悤�ȎE�l�������Ȃ��v�Ƃ��āA�u�l�̖���D��Ȃ��悤�ȎE�l�v�͋��e����Ƃ����̂Ɠ����B
�����Ȋ���������@�ڑҖ�肪�g�債�����Ă���B�J�e�O�����ȑ����R�c����NTT�Ȃǂ���̐ڑ҂������Ƃ̗L���ɂ��āA�u���k�V�ЈȊO�����@�Ȑڑ҂͎Ă��Ȃ��v�Ɠ��ق��Ă����B
�Ƃ��낪�ANTT������ڑ҂��Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B�R�c�^�M�q�O���t���������B�����Ȃ͈�@�ڑҖ��ɂ��Ē������s���A���̌��ʂ�����ɕ��Ă������A���̒��������U�ł��������Ƃ��������Ă���B
����͍����̍ō��@�ւ��B�������A����ɂ����锭���A���قɋ��U���U��߂��Ă���B����R�c���̂��̂��`�Ƃ�����Ă���B
����ł̎��^�ɂ����Ắu�C�����t���������m�F�v����߂�ׂ����B�u�����A���͂��H�ׂ����v�u�����A���͂�͐H�ׂĂ��Ȃ��v�ł͎������m�F�ł��Ȃ��B�u�����A�H�����������v�ł����߁B�u�H���͂��Ă��Ȃ��v���u�p���Ƌ����͌��ɂ����v�Ƃ�����������Ȃ��B�u�����A���炩�̂��̂����ɓ��ꂽ���v�ƕ��������Ȃ��B
���c��������3��10���̎Q�c�@�\�Z�ψ���Łu��������^�O��������悤�ȉ�H�A��ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Ɠ��ق������A��������}�̔��^�M�����u�����ɋ^�O��������Ȃ��Ă���H���������͂��邩�v�Ɩ₤�ƁA�u�ǂȂ��Ɖ������������Ă��ׂē�����̂��������Ȃ��̂��v�Ƃ��ē��ق����₵���B
�d�v�Ȃ��Ƃ͎��Ǝ҂Ɖ�H�܂��͖ʉ�̎���������̂��ǂ������B�u�^�O���������v�Ƃ����C�����t����ǂ��ɂł���������ł���B���c�Ǒ������Ȃ����C�ɒǂ����܂����͉����Ȃ����낤�B
���������̌������܂ł����A����ŋ��U���قR�ƍs���悤�ɂȂ��Ă���B�i�c���̑��A�����ւ̑��͖ڂ�����B���̔w�i�Ɉ��{���t�̑����������B����ŕ��R�Ƌ��U���ق��J��Ԃ����B���������O��Ղɂ�������H�͎Q���Ҋe�l�ƃz�e���ɂ���Č_���킳�ꂽ�B���{�������͈�؊֗^���Ă��Ȃ��B���{�W�O���͌J��Ԃ����B�Ƃ��낪�A���ۂɂ͈��{���������z�e���ƌ_�A�x�������s���Ă����B�O��Ղ̔�p�͎Q����Řd�����ꂸ�A���{���̎����Ǘ��c�̂��s�����S���Ă����B���������K���@�ᔽ�A���E�I���@�ᔽ���Ă��B�������͂Ɩ������錟�@�͈��{�W�O����s�N�i�ɂ������A���@�R����ɐR�����\�����Ă�ꂽ�B
���@�R����͓�x�̋N�i�����c���ň��{�W�O�����N�i���ׂ����B���{���́u����f���悤�ɉR�����v�ƌ���ꂽ�B
���t������b�����C�ʼnR�����ʂ��p�����āA�������͈��S���ĉR�����悤�ɂȂ����B�������������ȗ����ǒ����R�����ʂ����B���̉A�ŁA���̍߂��Ȃ��O���̐E�������ɒǂ����܂ꂽ�B
���{�̕a�����������Ɗ����@�\�̊����ɏh��BNHK�ɍR�c�̓d�b�����Ă��Ȃ���������Ȃ����ANHK�W�҂ɉ��炩�̘A������ꂽ�\���͔ے肳��Ă��Ȃ��BNHK��́u�R�c�̘A���͎Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ����A�A���������Ȃ��������ǂ����ɂ��ē����Ă��Ȃ��B
�����Ȋ����͉q�������ɂ��ĉ�b�������ǂ����ɂ��Ė���āu�L���ɂ������܂���v�Ɠ����Ă����B���ۂɂ͉q�������Ɋւ��鐶�X������b���Ȃ���Ă����B�����f�[�^�Ƃ�������I�؋����˂��t������܂Ő^�������Ȃ��B�u�L���ɂ������܂���v�͉R�ɂȂ�Ȃ����肬��̓��������B����ł��u����f���悤�ɉR�����v���͂͂邩�ɂ܂����B
����ɂ����锭���ɂ��āA���U���ق�e�F���錻�݂̖@�̌n���C�����ׂ����B����ɂ����鋕�U���فA���U�����ɔ�����݂���ׂ����B�����łȂ���A����͖��@�n�тɂȂ�B
?�̏�ɉR��h��ł߂ē��ق��Ȃ����B�^�f�͐��ꂸ�A��}�͒Njy�𑱂���B
�������ɒ����Ԃ�������̂͂��������Ǝ咣����҂����邪�A���������̂́A�R����������c���A��b�A���������B�@�����Ɏ��Ԃ�������Ȃ�A���U���ق�������Ȃ��ؐl����𑽗p���ׂ����B�ؐl������y�X�ɗp����ׂ��łȂ��Ƃ̎咣�����邪�A����R�܂݂�ɂȂ��Ă���̂�����A����̂��߂ɏؐl����̑��p�͂�ނȂ��B���������ؐl����ŏ��v���ׂ����B
�Njy�����鑤���A�C����Ȃ��̎�������A�C����Ȃ��̓��ق����߂�K�v������B���ق��鑤�́A�C����Ȃ��ŁA����������̂܂܂ɏq�ׂ�ׂ����B�����̋^�f�͏T����������I�؋�������ł��邱�Ƃɂ���Ė��炩�ɂ���Ă���B
�T�������Ȃ���A���̒Njy���������Ă��Ȃ��Ƃ����ʂ������B�d���肪���炩�ɂȂ�A����ŒNjy���邱�ƂɂȂ��Ă��A�e���r�������s���Ȃ����Ƃ�����B�\�Z�ψ���R�c�͂��ׂăe���r���p���s���ׂ����B�^�}������c�ɐU��Ȃ��Ȃ�A��}�͐R�c���ۂőR���ׂ����B�^�}���ᔻ����Ȃ�A�����ɁA�u�^�}���e���r���p�����₵�Ă���v����R�c���ۂ��s���Ɛ������ׂ����B�����̓e���r���p�����₷��^�}��ᔻ����B���k�V�Ђɂ���@�ڑҖ���NTT�ɔg�y�������A����NHK�ƃe���r�A�V���̃}�X���f�B�A�ɂ���@�ڑҖ��Ɉڂ�B
�e���r�NJ����ɂ���@�ڑ҂̎���������݂ɏo��Ήe���͐r�傾�B
|
|
�����k�V�Ўq��Ђ̉q���������Ƃ�F��������ց@ 3/12 |
|
���c������b��12�����̉�Łu���k�V�Ёv�̉q���������ƂɊւ��A�O���K���ᔽ�ɂ��F����������l���������܂����B �@���c������b�F�u���Y�F��̎������Ɍ����ĕK�v�Ȏ葱����i�߂Ă������Ƃƒv���܂����v �@2016�N10���ɓ��k�V�Ђ��F���\�������ۂɊO���䗦��20���ȏ゠��A�����@�Ɉᔽ�������Ƃ����R�ł��B �@���̐\����2017�N1���ɔF�肳��Ă��āA���c��b�͂��̔F����u�d������r(����)���������v�ƔF�߂܂����B �@�������̎葱���Ɍ����č���17���ɁA�q��Ђ̓��k�V�Ѓ��f�B�A�T�[�r�X�̏���В��ɑ��钮���������Ȃōs����\��ł��B�@ |
|
�����k�V�Ђ̋��U���ف@�ڑҎ������Ȋ����A�R�c����֗^ 3/12 |
���`�̎̒��j���������߂�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv���̊O���K���ᔽ���́A�q���������Ƃ̔F��������ɔ��W�����B���z�ڑ҂����R�c�^�M�q�E�O���t�L�畡���̑����Ȋ������A�F��̌��قɊւ���Ă������Ƃ������B�s���R�Ȍ`�Ŏ葱�����i�w�i�Ɋ����́u�u�x�v���������Ƃ��������́A�^��}�ɍL����B
���k�V�Ђ�2016�N10���ɍs�����q���������Ƃ̐\���ŁA�O���䗦���K�������20���������Ƌ��U���A�����Ȃ̔F������t�����B����ɁA�ᔽ��Ԃ̂܂ܐV�ݎq��Ђ̓��k�V�Ѓ��f�B�A�T�[�r�X�ւ̎��Ə��p��\�����A17�N10���ɔF������B���̍ۂ̍ŏI���ق������̂��A���{�W�O�O�̔鏑���Ȃǂ߂���A��ʍs���ǒ��ɏA�����R�c���������B���̌��قɂ́A�ڑҖ��Œ��������ɂȂ������̕����̊������֗^�����B
���k�V�Ђ̊O���䗦�͍ŏ��̐\���i�K��20�����Ă������A�����Ȃ����m�Ȕ䗦���ڂ����m�F�����`�Ղ͂Ȃ��B���̌�̎��Ə��p�����l���B���c�Ǒ���������12���̋L�҉�Łu�`�F�b�N�A�R�����\���łȂ������v�Ǝߖ��������A�^��}�Ƃ��z�ʒʂ�~�߂Ă͂��Ȃ��B
�����}�̐��k�O���Q�@�������́u�����Ƃ��͂����Ȃ��v�Ǝ�����������B�ʂ̊t���o���҂́u���ɉ����Ȃ��ƁA����Ȃ��Ƃ͐�ɋN����Ȃ��v�Ǝw�E����B
��}�́A�������̑��݂ɂ��s�����䂪�߂�ꂽ�^�f��Njy����B�����Ȋ��������k�V�Ђ̈�@�\����m��Ȃ���A�ڂ��Ԃ��Ă����Ƃ��������Ă��B
����𐄎@�����鎖����12���̎Q�@�\�Z�ψ���Ŕ��������B�����Ȃ̋g�c���j��ʍs���ǒ��́A���k�V�Ђ��u17�N8���ɊO���K���ɒ�G����\��������ƔF�����A�����Ȃ̒S���҂Ɍ����œ`�����L��������v�Ɛ����������Ƃ𖾂炩�ɂ����B����A���Ȃ̒S���҂́u�����o���͂Ȃ��v�Ƙb���Ă��邱�Ƃ��⑫�����B
���c���́u�������A����Ȃ��̘b�ɂȂ��Ă���v�Ƃ��āA�߂��n�߂��O�҂̌��Ɉς˂�ӌ����������B�@ |
|
�����z�ڑҖ��ő�u�[�C���O�̖�c���q���Ɂu���}�����}�V�i���I�v���� 3/12�@ |
�������ɍݔC���A�m�s�s(���{�d�M�d�b�������)���獂�z�ڑ҂������Ƃ�F�߂������}�̖�c���q��������s(60)���A���_�����u�[�C���O�Ɍ������Ă���B
��c����16���A�}�{���ōs������Łu�T�����t�v�������e���ŔF�߂���Łu(�m�s�s����)�d���ɂ��Ă͂قƂ�ǘb���Ă��Ȃ��B�ڑ҂łȂ��A�v���C�x�[�g�̍��k��Ƃ̔F���������v�Ɣ��_�����B
1��ڂ̎x�����͊��芨���������A2��ڂ͂m�s�s�������S�B���t������A���Б��ɕԍς����Ƃ����B
�Ƃ��낪��}���ɂ��ƁA��c���̖��͐����O�����W�Ǝ҂��狟���ڑ҂��邱�Ƃ��ւ���ꂽ�u��b�K�́v�ɒ�G����Ƃ����B
�l�b�g�ł͖�c���ɑ��āu�����ł����킸�Ɉ��ݐH�����邱�Ƃ�ڑ҂��ꂽ�Ƃ�����Ȃ��́H�@��c���ɂ��킹��ƈႤ�炵���v�u��b�K�͂ɒ�G���Ă���B�����ɃA�E�g�v�Ɣᔻ�̏������݂��E�����Ă���B
���Ԃ̔ᔻ���A�����}���̈ꕔ����͖�c���̗��}�������₩��Ă���B�����Ȃ�ً}���Ԑ錾���̓����E����Ő[��܂ŃN���u��K��Ă������Ƃ����o�����}��������������Ə��{���O�@�c��(70)�Ɠ����p�^�[������邱�ƂɂȂ�B
���鎩���}�c���́u��c���͗X�����c���@�Ăɔ��Ȃǂ��āA���̏������痣�}�������o����Ĉ�x�A���}���Ă��܂��B���̌�A���{�����ŕ��}���A���܂��ኲ������s�|�X�g�B���̖��̎����Ɍ����čĂї��}���A���̏O�@�I�œ��I������A�w�݂����͍ς܂����x�ƕ��}����̂ł͂Ȃ����v�Ɩ�c���̇����}�����}�V�i���I�����������B
���������Ȃ����ꍇ�A�����}�x���҂͖�c��������Ȃ�Ǝ����̂��B�@ |
|
����c���q�E���s���c������NTT���ɕԋ��B�Ƃ��Ɂu�ڑҁv�͔ے� 3/12�@ |
NTT�������������������������}�̖�c���q��������s�⍂�s���c�O�@�c�����ڑ҂��Ă����ƏT�����t�������Ƃ��߂���A��c�A���s�������11���܂łɎ��g�̈��H���NTT���ɕԋ������B�����A��H�ɂ��Ắu���k��v�u�ӌ������v�ȂǂƂ��Đڑ҂ɂ͓�����Ȃ��Ɛ����B��}���͖�c�A���s������̍���ւ̎Q�l�l���v�����߂Ă���B
�����́ANTT����2017�N11���`20�N9���ɂ����āA��c�A���s�����̂ق��A������������b���������w���[�������A���c���O�@�c����4�l������6��ڑ҂��Ă����ƕB��c�A���s�����ɂ�2��A�����E�`��ɂ���NTT�֘A�̉�������X�g�����Őڑ҂��s��ꂽ�Ƃ��Ă���B
��c����11���A�}�{���ŋL�Ғc��2��̉�H��F�߂������Łu�v���C�x�[�g�ȉ�Ƃ����F���������v�Ɛ����B��H�́A��c���̒n���E���́u���l��L�u�̍��k��v��ANTT�����{�̎x�X����゠�������ړI�������Ƃ��A�u�ڑҁv�ł͂Ȃ������Ƃ̔F�����������B����A2��̂����A1���NTT���̎x�����������Ƃ���11���A����̈��H��2��6150�~��ԋ������Ɩ��炩�ɂ����B
�܂��A���s���̎������ɂ��ƁA��H�̑O��NTT���ɉ���q�˂��Ƃ���1���~�Ɠ`����ꂽ�Ƃ����B���s���́A���Ƃ͕ʂɈ��ݕ���Ȃǂ��z�肵�A2��Ƃ�5500�~�̂��y�Y����H�����3�l�����Q���Ă����B����̕���NTT����2��̉�H�̉�v�z���m�F�B���ۂɂ̓R�[�X����������1�l2��4��~�������Ƃ����A�x���������Ƃ̍��z���Ƃ��Čv7��3885�~��10���Ɏx�������B
���s����10���Ɏ��g�̃z�[���y�[�W�ő�b�ݔC���́A�����Ȃ̊W�c�̂�W���Ǝ҂Ɖ�H���ӌ�����������ۂ͑S�āu���芨�v�Ƃ��邩�A�S�z�S���Ă����Ƃ��āu�w�ڑҁx�͎Ă��Ȃ��v�Ɣ��_�B�u����Ǝ�茈�߂��w���芨�x�̉�����悤�ȐH������ݕ����o����Ă����Ƃ�����ᔽ���v�Ƃ��č��z�������Ă����ꍇ��NTT���ɕԋ�����ӎv�������Ă����B�@ |
|
�������e���r�ǂƂ͗ϗ��@�ᔽ�Ȃ��@�����Ȑڑ҂Ő��{���ُ� 3/12 |
���{��12���̊t�c�ŁA�����Ȃ������ڑҖ������荑�ƌ������ϗ��R����ɕ��������̉ߒ��ŁA�����e���r�ǂƂ̊Ԃł͍��ƌ������ϗ��@�Ɉᔽ���鎖�����m�F�ł��Ȃ������Ƃ��铚�ُ������肵���B���{�ېV�̉�̗�؏@�j�Q�@�c������o���������ӏ��ɓ������B
��������}�̉��{�[���O�@�c���̎����ӏ��ɑ��铚�ُ��ł́A���E�����R�c�^�M�q�O���t�L�̑ސE�蓖�ɂ��āu�x������邪�A�z�͌l���̂��ߍ����T�������v�Ƃ����B�@ |
 �@3/13 �@3/13 |


 �@
�@ |
|
����H�͂��o�A5�N�ł킸��8���@�����ȁA�u�ڑ҉B���v�� 3/13 |
�����Ȋ������m�s�s�Ȃǖ��ԋƎ҂��獂�z�ڑ҂��Ă������ŁA���Q�W�҂Ɖ�H����ۂɕK�v�ȓ��ȓ��̓͂��o���ߋ�5�N�ԂŌv8�������Ȃ��A���l�ɖ��ԋƎ҂Ƃ̐ړ_�������Ȓ��Ɣ�r���Ĕ��ɏ��Ȃ����Ƃ�13���A���������B���ۂɂ͊�������H���J��Ԃ��Ă���A�Ӑ}�I�ɓ͂��o�������ڑ҂��B���Ă����\���������ԁB
�����Ȃ�15���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA�m�s�s����ڑ҂������R�c�����X�R���ꂽ�J�e�N�F�������[�t����Ɋւ���lj������̌��ʂ����\��B�V���ȐڑҎ��Ă����o����A�s�M�̐�������ɍ��܂�͕̂K�����B�@���ƌ������ϗ��@�́A���Q�W�҂���̐ڑ҂��ւ���B
|
|
���v���C�x�[�g�ȉ�c��c���q�c���Ɂu�����Ђǂ��v�̐� 3/13 |
3��18�����́w�T�����t�x�ŁA�����������NTT���獂�z�ڑ҂��Ă����ƕ�ꂽ�����}�̖�c���q��������s(60)�B
�L���ɂ��ƁA��c�����ڑ҂����̂�2��B17�N11����NTT�h�R���В��Ȃǂ��C��������h����A18�N3���ɂ�������NTT�����{�В������������a�r��������Ƃ����B
�e���f�B�A�ɂ��ƁA��c���́g�ڑҋ^�f�h��ے�B3��11���ɕw�Ɍ����āA�u�d���̘b�͂قƂ�ǂ��Ă��Ȃ��B�����Ȃ��S���ւ��Ȃ��v���C�x�[�g�ȉ�v�Ǝߖ������Ƃ����B
�܂���c���͗��쎁�Ƃ̉�H�ɂ��āu���l��L�u�̉�̐�y���������k������悤�Ƃ������ƂɂȂ����v�Ɛ������A�u���쎁�͂��łɈ��ނ��Ă����v�u�x�������l�����������v�ƃR�����g�B
�����ۂ��������Ƃ̉�H�ɂ��ẮA�u30�N�ȏ�F�l�Ƃ��Ă��t�����������Ă����v�Ɛ����B�܂����������ޔC���邱�ƂȂǂ���u�F�l�Ƃ��đ��߂ɓ`���Ă������������Ƃ����b��A���s�̘b�������v�ƃR�����g�B����ɉ�H��p��26,150�~�́A�ŋ߂ɂȂ��ĕԋ������Ƃ����̂��B
�uNTT�@�Ɋ�Â��Ď��ƌv�������̑I�C�Ȃǂ́A�����Ȃ̋��F���Ă��܂��B���ƌ������ϗ��K���ł́A���F�Ȃǂ��Ď��Ƃ��s���Ă��闘�Q�W�҂���ڑ҂��邱�Ƃ͋ւ����Ă��܂��B
�����18�N�Ƃ����A�����̊��[�������������`�̎��g�ѓd�b�����̒l�����Ɍ��y���n�߂������B�ł����A��������������c���́w�����Ɍ���ꂽ���瓮���̂ł͂Ȃ��A��������瑍���Ȃ͎��g��ł����x�Ɛ����������鐨���ł����B
��c���͂������ȂɁg�ڑҁh��ے肵�Ă��܂����A��H���s��ꂽ�ꏊ��NTT�O���[�v��Ђ̉�����Q�X�g�n�E�X�wCLUB�@KNOX ���z�x�B�������Ƃ�������ł���A�^����悤�ȍs���͐T�ނׂ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���c�c�v(�S�����L��)
�u��H�͂������ڑ҂ł͂Ȃ��v�u���͕ԋ������v�Ɖ����ʂ���c���B�����ANTT�O���[�v��Ђ̃Q�X�g�n�E�X�ł킴�킴�g�v���C�x�[�g�ȉ�h���Â��K�v�͂������̂��낤���B�ޏ��̎ߖ��ɔᔻ�̐����E�����Ă���B
�s�����Ȃ�NTT�̓v���C�x�[�g�ȊW�A�܂�g���炵���B����ł́A�������Ȃ̂���������Ȃ���ȁt �s�܂��܂��V��̌����I�@�d���̘b�͂Ȃɂ��Ȃ��A�v���C�x�[�g�Ƃ�����NTT�͖��ʂȋ����g���Ă���Ƃ������ƁH�t �s�ォ��ԋ��������ōςނ̂��B���������ĕ߂܂��Ă���A��������ƌ����Ă������Ă��炦�Ȃ����낤�B����c�����@���Ă���t �s���̌������܂�ɂЂǂ��B ���ꂪ��l�̌������Ƃł��傤���t�@ |
|
���m�s�s�����Ɛڑ� 3/13 |
�m�s�s�ɂ�鑍���Ȃ��߂��鍂�z�ڑ҂́A�����E���ɂƂǂ܂炸�������╛��b�玩���}�̐����Ƃɂ܂ŋy��ł������Ƃ�11�������́w�T�����t�x�̕Ŗ��炩�ɂȂ�܂����B���O�����������������o���҂�͉�H�̎�����F�߂܂����B�^�f�͕����ʂ��Ȃ��ł��B�t���Ȃǂ��W�Ǝ҂���ڑ҂���邱�Ƃ͑�b�K�͂ɔ����܂��B�ڑ҂̐ȂŐE�������ɂ������b���o�Ă���A���d�߂ɂȂ��肩�˂Ȃ����ł��B�ʐM�s�����䂪�߂�ꂽ�^���͈�w�[�܂�܂����B����ł̓O��𖾂��}���ł��B
�w���t�x�ɂ��A�������ݐE���ɐڑ҂��ꂽ�͖̂�c���q�E�����}��������s(2017�N11����18�N3����2��)�A���s���c�O�@�c��(19�N12����20�N9����2��)�ł��B�ꏊ�͂�������m�s�s�O���[�v�̌}�o�قł����B��������b�o���҂ł͍��w���t���[������(18�N6����1��)�A���c���O�@�c��(20�N9����1��)�ł��B
�ߋ�7�N�Ԃł͓��}�o�قŐڑ҂��ꂽ�����Ȑ����O��(��b�A����b�A������)�o���҂͏\���l�ɂ̂ڂ�A1�l�̔�p�͎�㍞�݂�3���`5���~�ɐݒ肳��Ă����Ƃ����܂��B�ʐM�s���ɊW���鎩���}�����Ƃ��m�s�s�ڑ҂ɂǂ��Ղ�Ђ��������Ԃ������т܂��B
��c���́u�d���ɂ��Ă͂قƂ�ǘb���Ă��Ȃ��v�Əq�ׁA���s���́u(���F�ȂǂɊւ���˗���)�F���ł��v�ȂǂƎ咣���܂��B�������A�W�Ǝ҂ƐڐG����ہA�u�����̋^�f�������悤�ȍs�ׂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����b�K�͂ɏƂ点�Έ�E�͖����ł��B��c����1�̈��H����x���킸�A���A���c�̗����͑S�z�m�s�s���̕��S�ł����B���c�Ǒ��������͎���̂m�s�s�ڑ҂̗L�����������܂���B�^�O�͖c��ނ���ł��B
���߂����Ȃ��̂́A18�`20�N��3�N�Ԃ̐����O���ւ̐ڑ҂�26��ƁA���̑O��3�N�Ԃ�3�{�߂��n�C�y�[�X���Ɓw���t�x�������Ƃł��B���`�̎����[���������A�g�ѓd�b�����̑啝���������������o�����̂�18�N�ł��B���������ŗ��v�����ƊE3�ʂɓ]�������h�R�����A�m�s�s�����S�q��Ђɂ��ăe�R���ꂷ�铮�������߂������ɂ��d�Ȃ�܂��B
�m�s�s�ڑ҂ōX�R���ꂽ�����Ȃ̒J�e�N�F�O�����R�c���́A�ڑ҂̐ȂŌg�ї����l�������b�ɏo�����Ƃ�F�߂Ă��܂��B�̊Ŕ���ƌ��т����^�f�������܂��ɂł��܂���B
�m�s�s�͐��{��������ۗL���A������̑I�C�Ȃǂő������̔F����܂��B���{�Ɩ��ڂȊW�ɂ���m�s�s�̐����Ɛڑ҂̏�ԉ��̑�{�Ƀ��X�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�����Ȃ́A�̒��j�E�����������Ζ���������֘A��Ёu���k�V�Ёv�̉q���������Ƃ̔F����ꕔ�������葱���ɓ���܂����B�\�����ɖ@���ᔽ���������Ƃ������R�ł��B�����Ȃ͂Ȃ��ᔽ���������Ȃ������̂��B���Ђ���J��Ԃ��ꂽ�ڑ҂␛�ւ̜u�x(����)�͂Ȃ������̂��B�䂾�炯�ł��B�F��������ł͍ς܂���܂���B
�T�����̍���ɂ͂m�s�s���V�c���В��A���k�V�Ђ̒����M��В������v����܂��B�ڑ҂̑S�̑���_���A�s���ɗ^�����e���Ȃǂɂ��ė]�����ƂȂ����ӔC������܂��B���͉𖾂��ȔC���ɂ���p�������߂鎞�ł��B
|
|
�������ȐڑҖ��@�s�M�̔O���c��ވ���� 3/13 |
���z�̔�p����������H�ɁA���������łȂ��A��b�琭���Ƃ��Q�����Ă����B�ڑҖ��͂ǂ��܂ōL����̂��B�����̕s�M���͖c��ނ��肾�낤�B
�����Ȃ̐ڑҖ�肪�A���̂悤�ɐ��Ԃ𑛂����Ă���B
�m�s�s�����瑍���Ȋ����ւ̍��z�ڑ҂Ɋւ��钲���̒��ԕ�8���A���\���ꂽ�B�J�e�N�F�����R�c����3���v10��7��~�A�����p�i���ې헪�ǒ���1��5��1��~�̐ڑ҂��Ă����ƔF�肳�ꂽ�B
����������ƌ������ϗ��K���Ɉᔽ����^���������Ƃ���A�J�e����8���t�Ŋ��[�t�ɍX�R�ƂȂ����B
�J�e���͐挎�A���`�̎̒��j���������߂�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv����̈�@�ڑ҂Ō����̒������������B����������Ȃǂœ��k�V�ЈȊO�Ɉ�@�ڑ҂͎Ă��Ȃ��Ɛ������Ă����̂ɁA���ꂪ�������B
�����A�ʐM�s���ւ̐M�������Ă������J�e���̐ӔC�͋ɂ߂ďd���B�X�R�͓��R���B
�V���ȋ^�f�����������B
���T�����̏T�����t�́A�m�s�s���V�c���В��炪�����������̖�c���q�E�����}��������s�⍂�s���c�O�@�c����ڑ҂��Ă����ƕ����B����b������2���̐ڑҋ^�f����ꂽ�B
������b�K�͂́A�W�Ǝ҂��狟���ڑ҂��邱�Ƃ��u�����̋^�f�������悤�ȍs�ׁv�Ƃ��ċւ��Ă���B
��c���A���s���Ƃ���H�̎����ɂ��Ă͔F�߂����A�u���k��v�u�ӌ������v�ȂǂƂ��Đڑ҂ɂ��Ă͔ے肵���B
��H�̒��ŗv�]�◊�ݎ��͂Ȃ������Ƃ����B�J�e���犯�������v�U���ɂȂ���b�͂Ȃ������ȂǂƂ��Ă���B
���v�U���Ȃǂ��������Ȃ��B����ŁA�Ǝґ��ɍ��z�Ȕ�p�S���Ă��炤��H�ɎQ�����Ă����Ƃ������g�̍s�ׂ��̂��̂���莋����Ă���Ƃ̔F���͂���̂��낤���B
���������W���A�����Ȃ��Ƃ���Ŗ�����Ȃꍇ���݁A�s���̌���������������䂪�߁A�����ɕs���v�������炷�̂ł͂Ȃ����B����Ă���̂͂������낤�B
������ɂ��Ă��s���Ȃ̂͑S�e�̓O��𖾂��B
�J�e�����m�s�s����ڑ҂���2018�N9���͐��{�����߂�g�ѓd�b�������������ւ̑Ή����œ_�ƂȂ��Ă����B�m�s�s�ɂ��ڑ҂������������͌o�c�̏d�v�Ȑߖڂɏd�Ȃ�B
���k�V�Ђ͕����@�̊O���K���Ɉᔽ���Ȃ���q���������Ƃ̔F����Ă������A�ڑҖ��Ƃ̊֘A�͂Ȃ��̂��B
���c�Ǒ�������������łm�s�s�����Ƃ̉�H�����������ǂ������ĎO����A��������������Ă���̂��C�Ɋ|����B
�����Ȃ͈�@�ڑҖ��ɂ��đ�O�҈ψ���Ō�������j�������Ă��邪�A���܂��܂ȋ^��ɂ��č�����܂߉𖾂ɓ�����K�v������B
�T�����̍���ɂm�s�s���V�c�В��Ⓦ�k�V�Ђ̒����M��В������v�����B�ڑ҂̑_���⑼�̑����Ȑڑ҂̗L���Ȃǂ��A�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@ |
 �@3/14 �@3/14 |


 �@
�@ |
|
��NTT�ڑ҉����́g�V�̂̎�h���ɔ�щI ���c�������Ɠ������� 3/14�@ |
NTT�ɂ�鑍���Ȑڑ҉��������̑�����b�ɔ�щB���s���c�E�O��b���c���q�E����b�炪�ߖ��ƕԋ��ɒǂ��钆�A�ς���Ȃ��̂����c�Ǒ��E����b���B�܂��Ă�A��b�o���҂Ƃ��đ����Ȃɐ��ȉe���͂��ւ鐛�ɂ��̕����y�ԂƂ݂�͎̂��R�ł͂Ȃ����B
�u�ʂ̎��Ăɓ�����͍̂����T����v�u�����̋^�O������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v
�Q�@�\�Z�ψ����NTT�����Ƃ̉�H�̗L�����J��Ԃ�����Ă����c��b�͔��ʼn������悤�ȓ��قŋ��䍂�ɂ͂��炩���B���̂��тɖ�}���R�c���A�R�c�͒��f�B���c��b�̍���y���͐r���������A�挎16���̏O�@�����ςł́u�ʂ̎��āv�ɂ����ς蓚�ق��Ă����B
���̒��j�E�������Ƃ̉�H�̗L������A�u�������܂���v�Ɩ��������̂��B�z����1�J���O�̓��قɕ���āA���c��b��NTT�����Ƃ̉�H�̗L�����n�b�L��������A�厖�ȗ\�Z�R�c���������邱�Ƃ͂Ȃ��B
���̓_��12���̎Q�@�\�Z�ςŁA��������}�̏����m�V�c���ɕ������ƁA���c��b�͓����Ȃ����R���u�����I���f���v�ƊJ���������B�����čĂѐR�c�̓X�g�b�v�c�c�B����ł͉�H�̎������B���Ă���Ƃ݂��Ă��d�����Ȃ��B
������b��NTT�ȂǒʐM���ƂɊւ��鋖�F���������Ă���B��N9��29���ANTT���h�R���̊��S�q��Љ��\�B��11��11���A�ʐM���Ǝ�28�Ђ��u�����ȋ��������j�Q����鋰�ꂪ����v�ƈًc��������ӌ��������ɒ�o�B�������A�����Ȃ̓h�R���q��Љ��ɂ��n�t����^���ANTT��TOB�͓���17���ɐ����B����2�T�Ԍ�A�h�R���͐��̂���̌g�ѓd�b�����l�����v�����\�ƁA����������c��b�̍ݐE���̏o�������B
���̊ԁANTT�����Ɖ�H���Ă���u��S�v���^��ꂩ�˂Ȃ��B����ɁA���c��b�̓��z���ɑ����ł��鐛����NTT�����Ɖ�H����A�܂��܂��^�O�͐[�܂�B�s���ϗ��ɏڂ����_�ˊw�@�勳���̏�e���V���������B
�u�������A�g�ю��Ǝ҂Ɂw�l�����x���͂����������{�l�B�������A��1�����{�����̑�����b�o���҂Ƃ��āA���Ȃ��w�V�́x�ƌĂ��قǑ����Ȃɋ����e���͂����B���̗͂����邩��A�����ȏ��ǂ̌g�ї����l�����������ł���Ɠ��킯�ł��B�w�h�R�����S�q��Љ��x�Ɂw�g�ї����l�����x��2��ۑ������Ă���NTT�ɂ���Γ��R�A���̕���T�肽�������ɈႢ����܂���v
12���̎Q�@�\�Z�ς͎����Ŏ��{�B�������[�����͐��̎A�C���NTT�����Ƃ̉�H�̗L������A�u�Ɋm�F�������A�����̋^�O��������H���͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������v�Ɛ��������B���c��b�̓��قƂ܂邫��ꏏ���B
�u�^�O���������ۂ��f����͍̂����ł���A�����҂̎��ȕ]���͔F�߂��܂���v(��e���V��)
�����Q���_�C�͐��������Ɋ��[����������܂߁ANTT�W�҂Ƃ̉�H�̗L�������ʂŎ��₵�����A���ߐ�܂łɉ͂Ȃ������B�T�����ɂ�NTT���V�c���В�������ɏ��v�����B��}�c�����琛�ƕ��c��b�{�l��O�ɉ�H�̗L�����ꂽ��A�ǂ�������̂��B���ڂ��B�@ |
 �@3/15 �@3/15 |


 �@
�@ |
|
��NTT�V�c�В��@���═�c�������Ƃ̉�H�̗L�������� 3/15 |
�����Ȋ�����ւ̐ڑҖ���15���ANTT���V�c���В����Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l���v���ꂽ�B�V�c���́A����܂łɍ���c�������I�ɍ��k�����Ă����ƔF�߂���ŁA�u�Ɩ���̗v����A�X����b�͂��Ă��Ȃ��v�Ɠ����|����ے肵���B
�����}�̑�ƕq�u�c������ڑҖ��ɂ��Ė��ꂽ�V�c�В��͖`���A�u�W�̊F�l�ɑ傫�Ȃ����f�ƁA���S�z���������B�S��肨�l�т�\���グ��v�ƎӍ߁B�����납��A�^��}�̍���c����e�E�̗L���҂ƍ��k���s���A�����̎Љ�⍑�ۏ�ɂ��Ĉӌ������̏��݂��Ă���Əq�ׂ��B
��H�̖ړI�ɂ��āA�u����c���̐搶�́A�ǂȂ��������Ȃ�ł����A���Ɍ�����m���A���L�����X�ł��B���ǂ��ɂƂ�܂��ẮA���Ɏh���ɂȂ�ǂ����ɂȂ�����Ē����Ă�v�Ɛ����B�u�Ɩ���̗v���ł���Ƃ��X����Ƃ��A���������悤�Ȃ��b�͂������Ă���܂���v�Ƌ��������B
2018�N6���̎В��A�C�ȍ~�ɁA�����Ȋ�����18�N�H��2�x�A20�N6����1�x�̌v3�x��H�����Ƃ�����Łu�����̎Љ�A�`�h�������Ă����܂̎Љ�̃v���X�ʁA�}�C�i�X�ʂɂ��čL����ʂ̘b���ӌ����������v�ƌ�����B
�܂���������}�̕��R�N�Y�������́A�V�c�В��ɐ��`�̎═�c�Ǒ��������Ƃ̉�H�̗L�������₵���B�V�c�В��́u�m�s�s�͏���ЂŁA����Ђ̎В����ʂɂǂȂ����Ɖ�H�������ۂ������̏�Ō��J���邱�Ƃ͎��Ƃɉe����^����B�ʂ̉�H�ɂ��ẮA���̕�����͍T�������Ă������������v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂��B
���R�����u�T�����ɏo�Ă������Ƃ͎������v�Ƃ������ƁA�V�c�В��́u�T�����ɏo�Ă������ƂŁA�c���̕��X�����\���ꂽ���͎�Ɏ����ł��B����ȊO�̌ʂ̈Č��ɂ��Ă͍T�������Ă��������܂��v�Ɛ����B�����Ȋ��������b�琭���O���Ƃ̉�H����ԉ����Ă������ɂ��Ắu��ԉ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B��{�I�ɂ����Ȏ��҂ƈӌ��������Ă���v�Ƃ����B
�V�c�В��Ƃ̉�H�̗L���ɂ��āA�������Ă��Ȃ����c�������͂��̓��̓��قł��u�ʂ̎���1��1�ɂ���������͍̂T�������Ă��������������A��������^�O��������H���ɉ����邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƌ�����B�@
|
|
���m�s�s�V�c�В��@�R�c�O�L��Ƃ̈ӌ������A�����ȑ����玝���|�� 3/15 |
�m�s�s���V�c���В���15���̎Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��A�����R�c���������R�c�^�M�q�O���t�L��(���E)�Ƃ̍�N6���̉�H�ɂ��āA�����ȑ�����ӌ������������|����ꂽ�̂ɑ��A��H�`�����Ă����Ɛ��������B
��������}�̍֓��×����́u�R�c�����1�l������5���~�߂���H������Ă��āA�R�c����͉����̕��S�Ƃ���1���~�S�����Ƃ������Ƃ����A���z�͂m�s�s����������̂��v�Ǝ���B�V�c�В��́u�m�s�s����������v�Əq�ׂ��B
������V�c�В��́u�ӌ����������Ȃ����Ƃ����̂́A����(�����ȑ�����)�����|�����܂��āA���̔F�����Â����̂ł�����A�ł͉�H���A�Ƃ��b�������Ă����������v�Ɛ����B�u�ӌ��������������B�����������B���̈�Ԃ̓��e�͏����̂`�h���������܂̃}�C�i�X�ʁB���邢�͎��ǂ����l���Ă���f�W�^���c�C���Ƃ������E�����ꂩ�痈�邪�A���̐܂ɎЉ�w�I�ɂǂ����Ƃ��b�������Ă����������B���ɑ����̈ӌ��������������̂ŁA�L�p�������ƍl���Ă���v�ƌ�����B
|
|
���@�u���u�������^�f�������邩�͑�b�̔��f�ł͂���܂���v 3/15 |
��������}�̘@�u�Q�c�@�c����15���A�c�C�b�^�[�ɐV�K���e�B�����ȐڑҖ�������A���c�Ǒ����������m�s�s���V�c���В��Ƃ̉�H�̗L���ɂ��āu�����̋^�O��������H�͂��Ă��Ȃ��v�ƍ���قŖ�������������Ă��邱�Ƃɑ��A���́u�^�O�v��������̂́u�����̔��f�ł����đ�b�̔��f�ł͂Ȃ��v�Ǝw�E�����B
�@�u���́u�w�����̋^�O��������H�͂��Ă��܂���x�m�s�s�V�c�В��Ƃ̉�H�̗L���ɑ��镐�c������b�̓��قł��v�Ɛ�o���A�u�w�����̋^�f�������Ȃ���H�͂������̂��x�Ɩ���Ă��w�����̋^�f��������H�͂��Ă��܂���x�Ƃ̌J��Ԃ��v�Ɛ����B�u���c��b�A�^�f�������邩�ǂ����͍����̔��f�ŁA��b�̔��f�ł͂���܂���v�Ƌꌾ��悵���B
�u�����̋^�O�v�̓c�C�b�^�[�̃g�����h�ɂȂ����B
|
|
���m�s�s�В��A���E���c�������Ƃ̉�H�̗L���������@�Q�@�\�Z�� 3/15 |
�����ȐڑҖ�������15���̎Q�@�\�Z�ψ���ɏo�Ȃ����m�s�s���V�c���В��́A���`�̎═�c�Ǒ��������Ƃ̉�H�̗L���ɂ��Ė�����������B���c������������܂łɈ��������������T�����B���R�N�Y�ψ�(����)�ւ̓��فB
���R�����V�c�В��ɑ��đ����Ȋ������b�琭��3���Ƃ̉�H�͏�ԉ����Ă����̂�����B�V�c���͑����Ȋ����Ƃ́u2018�N��2��A20�N��1��v�ƉB�u����3���Ƃ̉�H�͏�ԉ����Ă���킯�łȂ��v�Ɖ����B������Ƃ̉�H�L���Ɋւ��Ắu����Ƃ̎В��Ƃ��āA�ʂ̉�H�̗L���͍T����v�Ƃ����B
���c���������u�ʂ̎��ĂЂƂЂƂɂ��ĉ͍T����B�����݂̂Ȃ���^�O��������H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�V�c���͈ψ���`���A��ƕq�u�ψ�(����)�ւ̓��قŁA�ڑҖ��Ɋւ��u�傫�ȐS�z�Ɩ��f�������v�ƒӁB�u�����납��^��}�̍���c���ȂNJe�E�̗L���҂ƍ��k������݂��Ă���B�Ɩ���̗v����X����b�͂��Ă��Ȃ��v�Ɛ��������B
|
|
���J�e���̑ސE�����ۂ��@�ڑҒ�����Ɍ��z�̉\���\���c������ 3/15 |
|
���c�Ǒ���������15���A���Q�W�҂���̐ڑҖ��Ŋ��[�t�Ɉٓ������J�e�N�F�O�����R�c���̑ސE���̎x�������A�{�l�̓��ӂ���ŗ��ۂ���\�������������B�s�ˎ����N�������E�����ސE��ɏ��������Ɣ��f���ꂽ�ꍇ�A�ސE�����珈�������������z�������Ⴊ����A���c���͓����̎Q�@�\�Z�ψ���Łu���l�̎�舵�����s�����Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��B�����}�̕��ؑ�쎁�ւ̓��فB
|
|
�����c��b��́u��^��v�������قɁu�����ۂ��o���Ȃ���ꂽ���R�[�h�v 3/15 |
�]�Ȋw�҂̖Ζ،���Y����15���A�c�C�b�^�[�ɐV�K���e�B�����ȐڑҖ�������A���c�Ǒ����������m�s�s���V�c���В��Ƃ̉�H�̗L���ɂ��āu�����̋^�O��������H�͂��Ă��Ȃ��v�Ƃ̍���ق��J��Ԃ��Ă��邱�Ƃ��A�u��ꂽ���R�[�h�v�Ǝw�E�����B
�Ζ؎��́u���R�N�Y�c���w�m�s�s�В��Ɖ�H�������Ƃ͂Ȃ��̂ł��ˁx(�l�H�m�\�|��)�w�R���Ƃ��ƂłЂǂ����x�v�u���c������b�w���͍�������^�O���������悤�ȉ�H�����邱�Ƃ͂���܂���x(�l�H�m�\�|��)�w���͏T�����t�ɂ����ۂ�͂܂�Ȃ������H������������F�߂邱�Ƃ͂���܂���x�v�ƍ���ł̂��Ƃ���g�l�H�m�\�|��h�t���Ŕ�������߂ĕ`�ʂ����B
���̏�ŁA�Ζ؎��͘A�����e�B�u����p���ꕔ�����Ă����ǁA���{���̓��ق́A��^�����ꂽ���R�[�h�̂悤�ɌJ��Ԃ��A���ʂ��ɏ������ĂƂɂ��������ۂ��o���Ȃ��悤�ɂ���Ƃ����X�[�p�[�~�j�}���Y���U�|�p���ȁv�Ǝw�E�B�u��}��������i�H�v���ăn�c�N���Ȃ��ƁB���������t���݂��ᖳ���Q�[���ˁv�ƕt���������B
|
|
���g�ڑҁh���k�V�ЂƂm�s�s�В�������Œ� 3/15 |
�����Ȋ�����̈�@�ڑҖ��ŁA�m�s�s�̎В��Ɖq�������֘A��ЁE���k�V�Ђ̎В���15���A����ɏo�Ȃ��A�ӂ��܂����B
�ڑ҂����������A����Ő�������̂͏��߂Ăł��B�m�s�s���V�c�В��͈�@�Ȑڑ҂ɂ��Ă͒ӂ������ŁA�ʂ̉�H�ɂ��Ă͓���������܂����B
��������}�E���R�������u�V�c�В��́A�������������ɂȂ�O�A�Ȃ��Ă���A������炸�A���H�������ꂽ���Ƃ�����܂����v
�m�s�s�E�V�c�В��u�ʂ̉�H�ɂ��ẮA���T������������Ɓv
��������}�E���R�������u�����O���ƁA���ꂩ��A�ʐM�W�̊����ƐH�������邱�Ƃ��A��ԉ������Ă����̂��v
�m�s�s�E�V�c�В��u18�N��2��A20�N��1��Ƃ������ƂŁA����͑�ϐ\���킯�������܂���B����������ƁA����ς�F�����Â��Ƃ����Ƃ��낪�������Ƃ������ƂŁA����т�\���グ�Ȃ��Ƃ����Ȃ���ł����A��ԉ����Ă���킯�ł͂������܂���v
�m�s�s���V�c�В��́A���c������b�Ƃ̉�H�ɂ��Ă��u�ʂ̉�H�͍T�������Ă������������v�Əq�ׂ܂����B���c��b���u��������^�O�������悤�ȉ�H�͂Ȃ��v�ƌJ��Ԃ��܂����B
�܂��A�ڑ҂ōs�����A�䂪�߂�ꂽ���Ƃ��������̂��ɂ��āA�V�c�В��́u�Ɩ���̗v����A�t�ɕX����悤�Șb�͂��Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A���k�V�Ђ̒����В����A�ڑҖ��ɂ��Ēӂ��܂����B���̏�ŁA��}���������̒��j�ɂ��āu�ڑ҂ŏd�v�Ȗ�����S���Ă����̂��v�ƕ������̂ɑ��āA�����В��́u�ڑҗv���̂��߂ɂ����̂ł͂Ȃ��v�Ɣ��_���܂����B
|
|
��NTT�В� �v����X��ے�@������ �ڑҖ�� 3/15 |
�Q�c�@�\�Z�ψ���ŏW���R�c���s���ANTT���V�c�В��Ɖq�������֘A��ЁE���k�V�Ђ̒����В����Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ����B
�����Ȋ����ւ̐ڑҖ���A�����@�Ɉᔽ������Ԃł̎��Ɛ\���Ȃǂɂ��Ď��^���s���Ă���B
NTT�E�V�c���В��u(�ڑҖ���)�傫�Ȃ����f�Ƃ��S�z�����������A�S��肨��ѐ\���グ��v
NTT���V�c�В��́A��H�ł́u�Ɩ���̗v����X���߂���b�͂��Ă��Ȃ��v�Ƃ��������ŁA�ڑ҂͏�ԉ����Ă��Ȃ��Ƃ̔F�����������B
��������}�E���R�������u�V�c�В��͕��c��b�Ƃ��H�����ꂽ���Ƃ�?�v
NTT�E�V�c�В��u��قǂ��\���グ���悤�ɁA����Ƃ̎В��Ƃ��āA�ʂ̉�H�̗L���ɂ��Ă͍T�������Ă��������܂��v
���c�������u�ʂ̎���1��1�ɓ�����͍̂T�������Ă������������Ǝv���܂����A�����̊F����^�O�������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂������܂���v
����A���k�V�Ђ̒����M��В��́A�O���K���Ɉᔽ�����Ԃ������ɂ�������炸�A�q���������Ƃ̔F��\�����s�����ق��A�s�K�ȉ�H�ŋ^�O���������Ɏ������Ƃ��āA�u�[������ѐ\���グ��v�ƒӂ����B
�����В��́A2016�N�̐\�����_�ŔF�����Ă��Ȃ������ᔽ��Ԃɂ��āA���N�A�����Ȃɕ��s�����Ƃ��炽�߂Đ����������A�����Ȃ́A�����̒S���҂́u�����o�����Ȃ��v�Ƙb���Ă���Ƃ��Ă���B
|
|
��NTT�В��A�ڑҖ��Ӂu�Ɩ���̗v���͂����v�Q�@�� 3/15 |
NTT���V�c���В���15���̎Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��A�����Ȋ������ڑ҂������ɂ��Ēӂ����B�u�W�݂̂Ȃ��܂ɑ傫�Ȗ��f�ƐS�z���������B�S��肨��ѐ\���グ��v�Əq�ׂ��B
�V�c���́u��������^��}�̍���c�����͂��ߊe�E�̗L���҂ƍ��k������݂��Ă���v�Ƙb�����B����c������Ȋ����Ƃ̉�H�Łu�Ɩ���̗v����X����b�͂��Ă��Ȃ��v�Ƌ��������B
���Ԑl�̍���v�͈ٗႾ�B�V�c������H�̎����W��ړI�ɂ��Č�����̂͏��߂āB�Q�@�\�Z�ς͑����Ȋ����ւ̐ڑ҂����ɂȂ����������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv�̒����M��В����o�Ȃ����B���������}���Q�l�l���v�����߁A�^�}�����ꂽ�B
�V�c���͎��g�Ƒ����Ȋ����Ƃ̉�H��2018�N��2��A20�N��1��̍��v3�����ƌ��������B18�N�ɂ͊��ɖ��炩�ɂȂ��Ă���J�e�N�F�O�����R�c���ɉ����A���������R�c����������ؖΎ��O����������Ƃ���H�����Ɛ��������B
���`�̎═�c�Ǒ��������Ɖ�H�����������Ɓu�ʂɂǂȂ��Ɖ�H�������ۂ������J����Ǝ��Ƃɉe��������v�Ɗm�F��������B�́u�����̋^�O�������悤�ȉ�H�ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Ǝ咣�����B
�V�c�����J�e����Ɖ�H����18�N�͓������[�������������g�ѓd�b�����̈��������Ɍ��y���������Əd�Ȃ�B�J�e���͂���܂ł̍���^�ŁA�V�c���Ƃ̉�H���Ɍg�ѓd�b�����̘b�肪�o���ƔF�߂��B��}�͒ʐM����̓������ɋ^�O������Ƒi�����B
�����}�̖�c���q��������s�畡���̋c�����������������b�ݔC����NTT�W�҂Ɖ�H�����B��}��NTT�Ɛ��{�E�^�}�Ƃ̊Ԃɕs�K�ȊW���Ȃ��������ƒNjy�����B
���k�V�Ђ������̑����Ȋ�����ڑ҂��Ă���A���ЂɋΖ�����̒��j���֗^���Ă����B�������́u�^�O���������Ɏ��������Ƃ�[������т���v�Ɠ����������B���c���͐ڑҖ��Ɋւ��đ�O�҂ɂ�錟�؈ψ�����T���ɗ����グ����j��\�������B
���k�V�Ђ�17�N�ɑ����Ȃ���q�������̔F������ہA�����@�̊O���K���Ɉᔽ���Ă������Ƃ����������B�������́u�\���i�K�ŊO���K���ᔽ��F�����Ă��Ȃ������v�Əq�ׁA�ӂ����B���c���́u�����Ȃ̐R�����\���łȂ������B���Ԃ��d���~�߂Ă���v�ƌ��y�����B
��������17�N8�����_�ŊO���K���ᔽ�̉\���ɋC�Â��A�ᔽ������邽�߂ɉq���������Ƃ��q��Ђ֏��p����[�u���Ȃɒ�Ă����Ɩ��������B�����Ȃ̋g�c���j��ʍs���ǒ��́u�����̒S���҂ɂ��ƕ����o���͂Ȃ��v�Ɣے肵�A�������H��������B
���c���͑�O�҈ψ���őo���̈ӌ��̑���ɂ��Ă��R�c����ƌ�����B��}�͐ڑ҂��F��ɉe����^�����\�����w�E����B
15���̎Q�@�\�Z�ς͒ʐM�s����V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���Ȃǂ��e�[�}�ɂ����W���R�c�ŁA�ƊW�t���炪��������BNTT���V�c���Ɠ��k�V�Ђ̒�������16���̏O�@�\�Z�ςɂ��Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ���B
|
|
�����Ɖ�H�������������@�m�s�s���V�c�В� 3/15 |
�m�s�s���V�c���В���15���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA���`�̎Ƃ̉�H�̗L���ɂ��āu����Ƃ̎В����ǂȂ��Ɖ�H�������ۂ������J���邱�Ƃ͎��Ƃɉe����^����B�ʂ̉�H�ɂ��Ă͍T�������Ăق����v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂��B��������}�̕��R�N�Y���ւ̓��فB
�Ƃm�s�s�����̉�H���߂����ẮA�������M���[������12���̗\�Z�ςŁA�u�Ɋm�F�����Ƃ���A��������^�O�������悤�ȉ�H���Ȃǂɉ��������Ƃ͂Ȃ��Ƃ̂��Ƃ������v�Ɩ��炩�ɂ��Ă���B
�V�c���́A���c�Ǒ��������Ƃ̉�H�Ɋւ��Ă����l�ɓ��ق�������B���c���́u�ʂ̎��Ĉ��ɓ�����͍̂T�������Ăق����v�ƌ�����B
|
|
��NTT�Ɠ��k�V�Ђ̎В� �ڑҖ��Œ� �Q�@�\�Z�� �W���R�c 3/15 |
�Q�c�@�\�Z�ψ���̏W���R�c���J����NTT�Ɠ��k�V�Ђ̎В����o�Ȃ��A�����Ȋ�����̐ڑҖ��Ȃǂ��߂����Ď��^���s���܂����B2�l�̎В��͈�A�̐ڑҖ���ӂ��܂����B
�W���R�c�ɂ́ANTT���V�c���В��Ɠ��k�V�Ђ̒����M��В����Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��܂����B
���̒��ŁANTT���V�c�В��́u��������}�X�R�~��^��}�̍���c�����͂��ߗL���҂ƍ��k���A�����̎Љ�⍑�ۏ�ɂ��Ĉӌ�������������݂��Ă���v�Əq�ׂ܂����B
�����āA�����Ȋ����Ƃ�3�N�O�̎В��A�C�ȍ~3���H�������Ƃ�ӂ��A���̂������N6���ɓ��������R�c���������R�c�E�O���t�L��Ƃ̉�H�͑����ȑ�����ӌ������������������A��H�`�����Ă����Ɛ������܂����B
���̂����ŁA�����Ȋ����⍑��c���Ƃ̉�H�ŋƖ���̗v�����s������A�X��}���Ă�������肵�����Ƃ͂Ȃ��A��ԉ����Ă���킯�ł͂Ȃ��Əq�ׂ܂����B
�܂��A�����Ȋ�����ւ̐ڑ҂�NTT�h�R���̊��S�q��Љ����b��ɂȂ���������u�������n�߂��̂͋��N4���ŁA����ȍ~�A����O�ꂵ�Ă���B�C���T�C�_�[��̂��̂ŁA�����Ȃւ̎����I�Ȋm�F�������N�ɂ��b�����Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
�����āA�ڑ҂ƑO�サ�Ċ��S�q��Љ���g�ї����̒l�������s��ꂽ�Ǝw�E����u�����������Ɍ�����Ƃ����ӌ��������邪�S�����������b���o���Ă��Ȃ��B�l�����͎��Ǝ҂̐헪�Ŏ����痿���̘b���o�����Ƃ͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
����ɁA��������b�Ɖ�H�������Ƃ����邩�ǂ����́u�ʂɒN�Ɖ�H�������ۂ������J���邱�Ƃ͎��Ƃɉe����^������̂ƍl���Ă���A�T�������Ă��炢�����v�Əq�ׂ܂����B
���c������b�́A�V�c�В��Ɖ�H�������Ƃ����邩����u�ʂ̎��Ăɓ�����͍̂T����������������^�O�������悤�ȉ�H���ɉ����邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƌJ��Ԃ��܂����B
��������b�́u�����̐M����傫�����Ȃ����ԂɂȂ������Ƃ͐[�����Ȃ���ׂ��ŁA�M���������҂ɉ�������悤�w�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������Ƃ��Ă��܂��܂ȕ��ƈӌ��������Ă��邪�A��������ׂ����̂ł͂Ȃ��B��������^�O��������悤�ȉ�H���ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
����A���k�V�Ђ̒����В��͉q���������Ƃ̔F�����ɂ������Ă̊O���K�����߂�������@�̈ᔽ�Ƒ����Ȋ�����ւ̐ڑ҂ő���Ȗ��f���������Ƃ��Ēӂ��܂����B
�����āA�F��̐\���i�K�ň�@���͔F�����Ă��Ȃ��������̂́A���̌�A�S���҂��ᔽ���Ă��邨����ɋC�t�������Ȃ̒S�������ɕ����Ɛ������܂����B
�܂��u�S���҂��K���̓��e������ė������Ă����Ƃ����A��ς݂��Ƃ��Ȃ����Ă���B�{���ɂǂ����悤���Ȃ��o�c���������Ă����Ԃł͂Ȃ������v�Əq�ׂ܂����B
����Ɂu��������ɒ��ځA�Ȃ�����Ȃɂ��������H���Ă���̂��ƕ��������A��Ȃ����ƌ����Ă��ĖړI�܂ł͒Njy���Ȃ������v�Əq�ׂ܂����B
����ɁA��������b�̒��j�͑����ȂƂ̉�H�ɓ��Ȃ���������������̂ł͂Ȃ����Ɩ���u�D�G�Ȏ�҂����A�����ȂƂ̐ڑҗv���̂��߂ɉ�H�ɌĂ�Ă����̂ł͂Ȃ��A��H�ɏo�Ȃ������������v���������߂��B���j�����̖�����S���Ă����Ƃ͍l���Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A���c������b�́u���k�V�Ђ̃~�X���傽�錴���Ƃ͂��������ȑ��̐R�����\���łȂ��A�R���̐��̋����������������B�܂��A��O�҂̌��؈ψ�������T���ɗ����グ��\�肾�v�Əq�ׂ܂����B�@ |
|
��15���̎Q�@�\�Z�ς̎�Ȃ��Ƃ� 3/15 |
��NTT�ڑҖ��
��ƕq�u��(����)NTT������c���Ɖ�H���Ă����͎̂������B
�V�c��NTT�В��@�傫�Ȃ����f�Ƃ��S�z�����|�����A�S��肨��ѐ\���グ��B�����납��^��}����c�����͂��߁A�e�E�L���҂ƍ��k������݂��Ă���B�Ɩ���̗v���A���邢�͕X����Ƃ����b�͂��Ă��Ȃ��B
��Ǝ��@�����Ȋ����Ƃ̉�H�̎����W���B
�V�c���@��H��2018�N�H��2��A��N6����1�����B�L����ʓI�Ȉӌ������������B
���R�N�Y��(����)���`�̎═�c�Ǒ��������ƐH�����������Ƃ����邩�B
�V�c���@�ʂɂǂȂ��Ɖ�H�������ۂ������J����Ǝ��Ƃɉe��������B
���R���@�����Ȋ����Ƃ̉�ł́A�R���v���C�A���X(�@�ߏ���)�J�ɂ��ׂ����B
�V�c���@�Ɩ���̗v���A���邢�͕X��}���Ă������������Ƃ͂Ȃ��B
�֓��×���(����)�R�c�^�M�q�O���t�L�瑍���Ȋ����ւ̐ڑ҂͎��Ƃ̐i�W�̂��߂��B
�V�c���@�����ȑ�����ӌ������������|�����u�ł͉�H���v�Ƙb�����B���̔F�����Â������B
�֓����@�ڑ҂Ōg�ѓd�b���������������b��ɏ�������B
�V�c���@�l�����͎��Ǝ҂̐헪�ŁA������b�����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�֓����@�����R�c�����X�R���ꂽ�����Ȃ̒J�e�N�F���͐ڑ҂ŗ������b��ɏo�����Ƃ�F�߂��B
�V�c���@�b�͏o����������Ȃ����A���Ԃ��Ŏ~�߂��Ƃ������A���̘b��ɕς����Ǝv���B
�֓����@��N6�A7���̉�H��NTT�h�R���̊��S�q��Љ������グ�����B
�V�c���@�C���T�C�_�[��̂��̂��B��N4���ȍ~�͎���O�ꂵ�Ă���B�ǂȂ��ɂ��b���Ă��Ȃ��B
���ؑ�쎁(����)��H��ڑ҂͎Г����[���ɏƂ炵�ēK���������B
�V�c���@���ƌ������ϗ��@�Ɋւ��鍀�ڂ̃��[������̓I�ɏ�����Ă��Ȃ��Ƃ�����肪�������B��ϔ��Ȃ��Ă���B
��c�t�q��(����)���ƌ������ϗ��@�{�s��������̕s�ˎ��������Ă���B�S�Ȓ��ɑ��_�����|���邱�Ƃ��K�v���B
�@�����A�_�ѐ��Y���ȂŒ�������B���ʂ�����ɂ�����x������K�v������B
�R�Y��(���Y)�g�ѓd�b�����̈�������������A���������䂪�߂��\�����������̂ł͂Ȃ����B
�@(�����Ȋ�����ւ̐ڑ҂ƁA�����̈������������)���ѕt����͔̂�߂���B
�R�Y���@�Ȃ���H���d�˂�ꂽ�̂��B�����l�������ŔɌf����A�O���[�v�ĕ҂�_��NTT�̎v�f����v��������ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̕\�ꂪNTT�h�R���̊��S�q��Љ����B
�����k�V���
�i�������q��(����)���k�V�Ђ͉q�������̎��Ɛ\���i�K�ŁA�O�����{�K������������@�ᔽ��F�����Ă����̂��B
�����M�瓌�k�V�ЎВ��@�����ȊW�҂Ƃ̕s�K�ȉ�H�ŋ^�O���������Ɏ��������Ƃ�[������т���B�����Ȃɉq�������̎��Ƃ�\������16�N�̎��_�ł́A�O���K���ւ̒�G��F�����Ă��Ȃ������B
�i�����@�\�����R�����A������ł͂Ȃ����B
�������@�\�����̃~�X���傽�錴���Ƃ͂����A�����Ȃ̐R�����\���ł͂Ȃ������B���Ԃ��d���~�߂Ă���B�R���̐��̋����������������B
�i�����@�ǂ̂悤�ɖ��̌�����}��̂��B
�������@�ڑҖ����������O�҈ψ�������T���ɗ����グ��\�肾�B
���R���@�����������ڑ҂��Ă����B�̎q�����ւ���Ă��鑍���Ȃ͋��U���ق��肾�B
�@�Ƒ����W���A���ʂƂ��č��ƌ������ϗ��@�ᔽ�ƂȂ������Ƃ͑�ϐ\����Ȃ��A����ѐ\���グ��B
�֓����@�͉��킸�Ǝ҂Ɖ�H�������Ƃ͂��邩�B
�@�����̋^�O�������悤�ȉ�H�A��ɉ��������Ƃ͂Ȃ��B
���؎��@��H��ڑ҂Ɋւ���Г����[���ɏƂ炵�ēK�������̂��B
�������@���ɞB���ȓ��e�ŁA�������Ƃ̉�H�̃��[���͑��݂��Ă��Ȃ������B���F�⎖�ƂɊւ���v�]�͂Ȃ��A�Љ���ƊE��ʂ̘b�肪�������ƕ��Ă���B
���؎��@�O���K���̈ᔽ���������悤�����Ȃɓ����|�����̂��B
�������@�����|�������Ƃ͂Ȃ��B
�R�Y���@17�N8�����_�œ�{�������k�V�БO�В����O���K���ᔽ��F�����Ă����̂��B
�������@�F���������B�@ |
|
���h�R���q��Љ��A�g�ї����l�����͢�ڑ҂ƑO�サ�Đi� 3/15 |
3��15���̎Q�@�\�Z�ψ���̏W���R�c�ɁANTT���V�c���В����Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ����B��}���͑����Ȋ����Ƃ̐ڑ҂ƑO�サ�āA�g�ї����̒l������NTT�h�R���̊��S�q��Љ����i�������Ǝw�E�B����ɑ��ANTT���V�c�В��͢�b�͏o���Ă��Ȃ���Ɣے肵���B
�R�c�ɂ͕����֘A��Т���k�V�У�̒����M��В����Q�l�l�Ƃ��ďo�ȁB���Ђɋ߂鐛�̒��j�E���������Ƒ����Ȋ����Ƃ̐ڑҖ��⓯�Ђ̊O���K���ᔽ�Ɋւ��鎿�^���������B
�R�c�̒��ł�NTT���E���k�V�Б��Ƒ����ȑ��Ƃ̓��ق̐H���Ⴂ���ڗ������B
���Y�����H�̕B�����Ȃ̒����Ţ2��ANTT�В��̓��قł͢3��
�����}�̑�ƕq�u���̎��^��NTT���V�c�В��͖`���A�����Ȋ����ւ̐ڑҖ��ɂ��Ģ�W�̊F�l�ɑ�ςȂ����f�Ƃ��S�z���������B�S��肨�l�ѐ\���グ�����Ă���������ƎӍ߂����B
�����Ȋ����ւ̐ڑ҂ɂ��Ģ�������}�X�R�~�A���邢�͗^��}�̍���c���̕��X�͂��ߊe�E�̗L���҂ƍ��k���A�����⍑�ۏ�S�ʂɂ��Ĉӌ������������Ă��������悤�ȏ��݂��Ă��飂Əq�ׂ��B
����c���Ƃ̉�H���R�ɂ��Ă͢(�c����)�����A�m�������L�����B���Ɏh���ɂȂ�A���ɂȂ�����Ă��������Ă��飢�Ɩ���̗v����A�X����悤�Șb�͂��Ă��Ȃ���Əq�ׂ��B
�V�c�В��͂��̓��̓��قŁA�����Ȋ����Ƃ̉�H�����v3��(2018�N�F2��A2020�N6���F1��)�������Ɩ��炩�ɂ����B�����Ȃ́A3��8���Ɍ��\���������Ȋ������V�c�В��̉�H�Ɋւ��钲�����ʂł͢2��Ƃ��Ă����B
��������}�̕��R�N�Y���������V�c�В��ɐ��Ƃ̉�H�o���ɂ��Ď��^�B�V�c���͌ʂ̉�H�ɂ��Ẳ͍T��������A�ʐM�s���Ɋւ�銯������O���Ƃ̉�H�͢��ԉ����Ă���킯�ł͂Ȃ���Əq�ׂ��B
�NTT��3����1�̊����𐭕{���ۗL���Ă�������ЁB�����ɏ���ЁB����Ђ̎В����ʂɂǂȂ����Ɖ�H���������ۂ������̏�Ō��J���邱�Ƃ͎��Ƃɉe����^����B�ʂ̉�H�ɂ��Ă͍T�������Ē��������(NTT�V�c�В�)
�����Ȃ�3��15���A�H�{�F���E�O��ʍs���ǒ�(���E��b���[�t)�Ɨ�ؖΎ��E�O�����������A���ƌ������ϗ��K���Ɉᔽ����^���������H��NTT���Ƃ��Ă������Ƃ����\�����B
�H�{���͓��k�V�Ђ���ڑ҂����Ƃ��Ď�����X�R�B��؎��͎�������������2019�N���ɂ���ې����ی��̕s���_������߂���A�s�������̌�������{�X�����ɘR�k�����Ƃ��čX�R����Ă���B
�������̗����l�����A�h�R���q��Љ��c��ߖڐߖڂʼn�H���ڗ��£�w�E
NTT�Ƃ̑��������̐ڑ҂ŏœ_�ƂȂ�̂́A���ƌ������ϗ��K��ւ̒�G�ƂƂ��ɁA�ʐM�s���ɉe����^�������ǂ������B
��������}�̍֓��×����́A���̂���̌g�ї����̒l������NTT�h�R���̊��S�q��Љ��̌o�܂ɂ��Ď��^�����B
�֓����ɂ��ƁA2018�N8���ɐ��`�̊��[����(����)��4���̌g�ї����̒l�������u���Ŗ����B����ɑ����Ȃ̐R�c��ŗ����l�����̋c�_���n�܂�A���̍��ɂ͒S���ǒ��������J�e�N�F�E�������R�c����NTT�����������ʼn�H�����B�܂��A2020�N�ɂ�NTT�h�R���q��Љ��̋c�_���n�܂������A������NTT���Ƒ����Ȋ����炪���đ����ɉ�H���Ă���B
�֓����͢�ߖڐߖڂʼn�H���ڗ��£��J�e�������R�c���́A��H�̏�Ōg�ѓd�b�����̒l�����Ɋւ���b���o��͎̂��R�Ȃ��ƂƓ��ق��Ă��飂Ǝw�E�B��H�ł̂��Ƃ�̏ڍׂ�₤���B
NTT���V�c�В��͢���������͂��q�l�̕��ՓI�ȃj�[�Y�B�����������̐헪�Ƃ��đ����A�l��������B�����ɏ����ƂƃZ�b�g�ƍl���Ă���B�����l�����͎��Ǝ҂̐헪�B���̕����痿���̘b���o�����Ƃ͂Ȃ���Ɣے肵���B
���̏�Ţ�J�e���w���������b���o����������Ȃ��x�Ƌ����Ƃ���A�o����������Ȃ����A���͂��Ԃ���(�b��ɂ���̂�)�����~�߂��Ǝv����Əq�ׂ��B
NTT�h�R���q��Љ��ɂ��ẮA�V�c�В��͢TOB�̌�����2020�N��4������B2018�N�H�̒i�K�ł̉�H�ł́A�܂��l���Ă��Ȃ��B�b�Ƃ��ďo�Ă��Ȃ��B2020�N6���ɎR�c����(�R�c�^�M�q�E�O���t�L��[���������R�c��])�Ɖ�H���Ă���B2020�N7���ɂ�NTT�f�[�^�ƒJ�e����H���Ă��飂Ə،������B
����Ţ2020�N4���ȍ~�́A�O��I�ɊW�ґS��������O�ꂵ�Ă���B�܂������C���T�C�_�[��̂��́B�ǂȂ��ɂ����b�����Ă��Ȃ���Ƌ��������B�������A������I��2020�N7���ɑ����ȂɊm�F�����Ă��飂Ƃ����B
�֓����͢�ٖ��ɐڑ҂��鎞���ƑO�サ�Čg�ї����l�����A�q��Љ����Z�b�g�Ői�����Ă���B(�ڑ҂�)NTT�Ƒ����Ȃ������A�ӎu�a�ʁA�ӎv�m�F�������ł������̂ł͂Ȃ�����Ǝ��₵���B
�V�c�В��͢���ʓI�ɂ��������ӂ��Ɍ�����Ƃ������ӌ����킩�邪�A�������Ƃ��Ă͑S�����������b�͏o���Ă��Ȃ����ʕ���Ɣے肵���B
����K�ͣ�ɒ�G���BNTT�Ɛ����O���̉�H���Ƃ́H
NTT���߂����ẮA�ē����ł��鑍���Ȃ̕��������̂ق��A�����O��(��b�E����b�E������)�o���҂��ݔC����NTT������ڑ҂��Ă����Ƣ�T�����t����B
�����}�̖�c���q��������s(����������)�A���s���c�O�������A���w���[�������A���c���O�@�c��(�������������������b)�́A����܂łɉ�H�������������ƔF�߂Ă���B
�����O���̋K�͂ł́A��W�Ǝ҂Ƃ̐ڐG�ɓ������Ă͋����ڑ҂��邱�ƁA�E���Ɋ֘A���đ�����X���^���邱�Ɠ��ł����č����̋^�f�������悤�ȍs�ׂ����Ă͂Ȃ�Ȃ���ƒ�߂��Ă���B
• ��c���c2��̉�H�B����̐M���ł������ł�����ǂ��A�d���ɂ��Ă͂قƂ�ǘb�����Ă��܂���B�����̑����Ȃ̑S���ւ��Ȃ��A�v���C�x�[�g�ȉ�Ƃ����F���ł�����BNTT�������S����2��ڂ̔�p��2��6000�~��ԍς����Ǝ咣�B
• ��䎁�c2018�N��NTT�̎��O����Ɖ�H�B����H��͑��葤�̎x�����B�Ɩ��Ɋւ���v����v�]�͑S���Ȃ�������ƃR�����g�B
• ���c���c�������͎����ʐM�̎�ނɑ��A�V�c�В�����̐ڑ҂�F�߂���Ţ��p��2��4000�~�͕ԍς��飂Ɛ����B
• ���s���c3��10���A�V�c����2019�N��2020�N�ɉ�H����������F�߂��B��p�͢���芨��̔F���������Ƃ��A���z��������s����������Ύx�����ƌ����T�C�g�Ŏ������B
���O���K���ᔽ�A���k�V�Т��@������������Ȣ���o���͂Ȃ��
���k�V�Ђ��߂����ẮA�����@�̊O���K���Ɉᔽ���Ă������ɂ��Ď��^���������B
�����@93���Ȃǂł́A�O���@�l�Ȃǂ��c������1/5(20%)�ȏ�̊�����ۗL����ꍇ�A��������Ǝ҂ɔF��ł��Ȃ��ƒ�߂Ă���B
2016�N10���A���k�V�Ђ�100%�q��Т���k�V�Ѓ��f�B�A�T�[�r�X���4K�q��������U�E�V�l�}4K��̎��ƔF���\���B2017�N1���ɔF������B�Ƃ��낪�A�\�����̊O���䗦��20.75%�������B�����Ȃ͢�U�E�V�l�}4K��̔F������������j���B
���k�V�Ђ̒����В��̓��قɂ��ƁA���Ђ��O���K���̈�@����F�������̂�2017�N8��4���B4K�q�������̔F��擾����N�ゾ�����B
�����В��́A���Ђ̈�@���ɂ��Ģ2017�N8��9������ɑ����Ȃ̒S�������Ɩʒk�A������Ɠ��فB����͑����Ȃ̏�ʍs���Ǒ����ے��������Ə،������B
���k�V�Ђ͂��̒��O��2017�N7���A���Ђ���CS�������Ƃ����p����Ɣ��\���Ă������A�̂��ɓP��B���̒���̓��N9���A�V�݂���100%�q��Ђɉq�������̔F������p�������B
�����В��͢�q��Ђւ̏��p�ŁA(�O���K����)��@��Ԃ������ł���ƍl�������������炱�̃A�C�f�A��(�����ȑ���)�o������Əq�ׂ��B
�����A�����ȑ��͒����В��̓��ق�ے肵���B
������̒S���҂ɂ��Ɓw�O���K���ɒ�G����\������|�̕𓌖k�V�Ђ�����o���͂Ȃ��B���̂悤�ȏd��Șb�Ȃ�o���Ă���͂��B�����ł��ޘb�ł͂Ȃ��̂ł́x�Ƃ̂��Ƃ������(�����Ȃ̋g�c���j�E��ʍs���ǒ�)
���c�Ǒ��������͢���k�V�Ђ̃~�X���傽�錴���Ƃ͂����A�����Ȃ̐R�����\���ł͂Ȃ�������Ƃ��āA���@���o���҂��܂ޑ�O�҂ɂ�錟�؈ψ�������T���ɗ����グ��Ƃ����B
|
|
���u�����ւ̓u���b�N�E��v�c�L�����A�����̐l�C���� 3/15�@ |
�����Ȋ����̐ڑҖ��ł́A���E�����R�c�^�M�q���t�L�����u1�l7��4203�~�v�Ƃ������z�ڑ҂����ڂ��W�߂��B�a���X�e�[�L��C�N������U�镑��ꂽ�R�c���́A2��25���̏O�@�\�Z�ψ���Łu�S�̊ɂ݂��������v�Ǝߖ������B�Ƃ��낪�A���E��ɂm�s�s����̍��z�ڑ҂����o���A�u�ɂ݂ǂ��납�A�ڑҒЂ����v�ƈ�w�ᔻ���������B
�����ڑ҂ƌ����A1998�N�ɔ��o�����u�呠�Ȑڑ҉��E�����v���v���o�����B���Z�@�ւ�����H��S���t�ȂǑ��z�̐ڑ҂��A100�l�ȏ�̐E�����������ꂽ�B���ꂩ��20�N�]�B�u���ς�炸�����̈́����v�Ƃڂ₫�������Ȃ邪�A��芯���́u����͈ꈬ��̊����̘b�B��X�Ƃ͕ʐ��E�ł��v�Ɣ��_����B
�L�����A�ƌĂ�鍑�ƌ����������E�̐l�C�́A�����傤���炭���Ă���B2020�N�x�̑����E�̐\���҂́A�O�N�x��3.3������1��6730�l�ŁA4�N�A���Ō��������B�����E����������12�N�x�ȍ~�A�ߋ��ŏ����B
�Ȃ��L�����A�l�C�͒ቺ���Ă���̂��B�v���̈�́A�u�����ւ̓u���b�N�E��v�Ƃ����C���[�W�����ԂɐZ���������Ƃ��낤�B�������J���ȃL�����A�E�琳�N�T���́u�u���b�N�����ցv(�V���V��)�ɂ́A������Ƃ��������̖{�����炩������A����Ή����ʂ̃R�s�[�Ȃǂɒǂ���p���ԗ��X�ɕ`����Ă���B�[��c�ƁA�����ԘJ���͓�����O�B�u7�F00�d���J�n�A27�F20�ޒ��v�Ƃ�����芯���̈���͉ߍ����̂��̂��B
���t�l���ǂɂ��ƁA19�N�x�Ɏ��ȓs���őސE����20�Α�̑����E��87�l�ɏ��A13�N�x��21�l����6�N�ԂŖ�4�{�ɑ������B30�Ζ����̒j���E����7�l��1�l���A�u3�N�ȓ��Ɏ��߂����v�Ɖ����Ƃ�������[�����B�@�E�E�E�@ |
|
�������ȐڑҖ��A�̐����u�[���ł��Ȃ��v7���@�����^�}�ɉe�@3/15 |
�����O�@�I���H�܂łɔ��钆�A���k�V�ЂɋΖ����鐛�`�̎̒��j�̐������炪�����Ȋ����ւ̐ڑ҂��J��Ԃ��Ă�����肪�A�̉��U�헪�ɉe�����y�ڂ��\��������B
��������}�̕��R�N�Y�������u������w�����͂�������m��Ȃ��x�ƌ����Ă������͂����Ȃ��v
���u���j�Ƃ͉ƌv���ʂ��B��Ђ̂��Ƃɂ��Ęb�����邱�Ƃ��Ȃ��v
��15���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA���j�̖��̐ӔC�킹�悤�Ƃ��镟�R���ɔ��_���A���j�Ƃ́u�ʐl�i�v���Ƃ���]���̓��قɉ����咣��W�J�����B
�Ƃ͂����A�Y�o�V���ЂƂe�m�m�̍������_�����ł͎̐����ɂ��āu�[���ł��Ȃ��v�Ƃ̉�70�E3���ɒB�����B�u�[���ł���v�Ƃ̉͂킸��17�E4���ɂƂǂ܂�A�����ɗ������L����ǂ��납�A�^�O�����������Ƃ���������ɂȂ����B
�����}�����́u���t�x�����͉������Ă��Ȃ��v�Ƌ������A���j�̖�肪���U�헪�ɗ^����e���͌���I���Ƃ̌����������B�����A�����̋^�O�����̂܂ܐ���Ȃ���A���ǂ̎哱���������\�����ے�ł��Ȃ��B�@ |
 �@3/16 �@3/16 |


 �@
�@ |
|
��NTT�ڑҖ��œ��ً��ۂ�A���A���܂��ɂ͋t�M���������c������b�B 3/16 |
�����ڂ��W�߂�3��12���̏����m�V�c���̎��^
2021�N3��12�� �Q�c�@�\�Z�ψ���̗�������}�E�����m�V�c���ɂ�鑍���ȁENTT�ڑҖ��̎��^�͑傫�Ȓ��ڂ��W�߂��BNTT�V�c�В��Ƃ̉�H�L���ً��ۂ��Ă������R���J��Ԃ����ꂽ�����}�E���c�Ǒ�������b���܂����Ă����ً��ۂ�A��������A���̋��ۗ��R�����܂�ɂ��x���ŗ������炾�B
�����Ŗ{�L���ł́A���c��b�̋��ۗ��R�ɂ����閵��3�_�𖾂炩�ɂ�����ŁA�����̖�8���Ԃ̎��^���m�[�J�b�g�ŐU��Ԃ��Ă����B
�܂��A���c��b�͓����̎��^�̒��ŁANTT�V�c�В��Ƃ̉�H�L���ً��ۂ������R�Ƃ��āA�傫���ȉ���3�_�������Ă����B
�����c��b�̎咣��
1 �ʎ��Ă̓��ق͍T����
2 ����ʍ�������Ă��Ȃ�
3 (���k�V�� ���������Ƃ̉�H�L���͓��ق������Ƃɑ���)�l������肵�����₾���琛�������̌��͉���
�����A����3�̎咣�͑S�ċU��ł���A�咣�Ƃ��đS���������Ă��Ȃ����Ƃ��A���ꂩ��Љ��킸��8���Ԃ̎��^�̒��ŘI�悵�Ă���B
��������
1 ���c��b�͌ʎ��Ăق��Ă���(2��16���̏O�c�@�����ψ���ŗ�������}�E�����ꐳ�c���ɓ��k�V�ЂƂ̉�H�̗L�������A�u�������܂���v�Ɠ��ق����������c���^�Ɏc���Ă���)
2 ����ʍ��͂���Ă���(�����c���́uNTT�����v�Ɩ��L������ʼn�H�L���ɂ��Ă̎����ʍ����Ă���B���������A����܂ʼn��x���_�_�ɂȂ��Ă������ł���A�ʍ��̕K�v�����̂��ɂ߂ĒႢ)
3 �uNTT�V�c�В��v�ƌl������肵�Ď��₵�Ă����c��b�͓��ً��ۂ��Ă���(���^�̏I�ՁA�����c���́uNTT�V�c�В��Ɖ�H�������Ƃ͂���܂����H�v�Ǝ��₵�Ă��A���c��b�́u�ʂ̎��Ă͉��T����v�Ɠ��ق���)
�܂�A���c��b�͂Ƃɂ���NTT�V�c�В��Ƃ̉�H�L�������A���ق����ۂ��闝�R�Ƃ��ăf�^�����Ȏ咣���J��Ԃ��Ă����B���^�S�̂�����ƁA����ɂ��̈������������Ă���̂ŁA��8���Ԃ̎��^�����ꂩ��m�[�J�b�g�ŐU��Ԃ��Ă��������B
��NTT�V�c�В��Ƃ̉�H�̗L���ق��Ȃ����R�́H
�܂��A�����c����NTT�V�c�В��Ƃ̉�H�L���ق��Ȃ����R�ɂ��āA���c��b�ɖ₢�����Ă����B���̎��^�͈ȉ��̒ʂ�B����ȍ~�A�����(�����c��)�A���َ�(���c��b)�ȊO�̔����A�ψ���̗l�q�Ȃǂ͕����̒���(��)�ŕ⑫����B�܂��A�M�Ҏ��g�̃R�����g�����킹�Ē���(��)�ŕ⑫���Ă����B
�����c���F �u���c������b�Ɏf���܂��B�U�X���ً��ۂ���Ă��܂����ANTT�̂ł��ˁA�����Ƃ̉�H�̗L���ɂ��āA���ق��Ȃ����R�͉��ł����H�v
���c��b�F �u���ق����Ƃ��Ă܂���B�����ɋ^�O�������悤�ȉ�H�E����A����ɉ��������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������m�ȓ��ق������Ƃ��Ă܂��B���������������B�v
�����c���F �uNTT�̊����Ɖ�H�������Ƃ�����̂��ǂ����Ƃ����Ȋw�I�������Ă��邾���Ȃ̂ŁA������ĉ������B�v
���c��b�F �u����A���͓��ق����Ē�������ł����ǁA�ʂ̂ł��ˁA���̎��Ăɂ��ăR�����g�͍����T�������Ē��������ƁB���̏�ō����ɋ^�O�������悤�ȉ���H�ɉ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ɖ��x�����ق������Ē����Ă���܂��B�v
���M�҃R�����g�F�咣1�u�ʎ��Ă̓��ق͍T����v1���
�����c���F �u��������������A���̌ʂ̎��Ăł��ˁA�ʂ̉�H�̎��Ă̗L���ɂ��Ă͓��ق��T������Ă����̂́A����ɑ����b�̐����ӔC�̉ʂ������Ƃ��Ă̓��قƂ������Ƃł�낵���ł����H�v
���c��b�F �u���A���ꍑ��̈ψ���œ��ق��Ă�킯�ł�����B�v
�����c���F �u�ʂ̎��Ăɓ����Ȃ��Ƃ������ق͍���ւ́A�܂������ւ̐����ӔC�̉ʂ������Ƃ��Ĕ��ɏd�������ӔC���Ƃ������Ƃł�낵���ł��ˁH�@�v
���c��b�F �u���͉��x�����ق������Ē����Ă���܂��B�ʂ̎��Ĉ��ɂ��Ă͓��ق������T�������Ē��������B���̏�ō����ɋ^�O�������悤�ȉ�H��ɂ��Ă͉����邱�Ƃ͖����ƁB�����������Ƃł���܂��B�v
���M�҃R�����g�F�咣1�u�ʎ��Ă̓��ق͍T����v2���
�����c���F �u��b��2��16���̏O�c�@�����ψ���ŗ�������}�̉����ꐳ�c���̎���ɑ��āA���k�V�ЂƂ̉�H�̗L���ɂ��ē��ق���Ă��܂��H�v
�����c��b�̓��يJ�n�܂łɖ�40�b������B�X�T�q�����́u�����œ��ق�����ł���B���������Ă�B����������ʂ̎��Ăɂ͓��ق��Ȃ��ƌ���������Ȃ��ł����B�����œ��ق��ĂȂ��ƌ����Ă����A���ق��ĂȂ���ł���B�����������������Ȃ����B3���4����ʂ̎��Ăɂ͓��ق��Ȃ��ƌ���������v�ƍR�c
���c��b�F �u�ʂ̎��ĂɈ����ق͒v���܂���B�v
���M�҃R�����g�F�咣1�u�ʎ��Ă̓��ق͍T����v3���
�����c���F �u���Ⴀ�A���k�V�Ђ̉�H�̗L���œ��ق��Ă������b���E���邱�Ƃł�낵���ł����H�v
���c��b�F �u����̘b�ɖ��m�ȓ��ق́A����͖������Ǝv���܂���B�v
�����c���F �u����ł͂Ȃ��āA�����c�^��̎����Ɋ�Ď��₵�Ă���܂��B�������k�V�ЊW�҂Ɖ�H���Ă���Α�b�����E���邱�Ƃł�낵���ł����H �v
���c��b�F �u���x�����ق��Ă��܂��B�����̘b�ɓ��ق͂ł��܂���B�v
�����^�����f�B�����݂��ًc�����u�����ɓs���̈������Ƃ����^���ʂ��瓚���Ȃ��̂͂��������ł���B�v�ƍR�c
���˔@�A�u����ʍ�����Ă��Ȃ��v�Ƌt�M�����镐�c��b
�����܂ł̂����ŁA�咣1�u�ʎ��Ă̓��ق͍T����v��3����A�����āA���ق����ۂ������c��b�B�������A2��16���ɕ��c��b���g���܂��Ɍʎ���(�����k�V�ЂƂ̉�H�̗L��)�ɂ��ē��ق��Ă����Ƃ��������������c�������߂��������ƂŒǂ��l�߂��Ă����B���̏ɉ������̂��A���c��b�͋����ׂ��s���ɏo��B
�咣��2�u����ʍ�������Ă��Ȃ��v�ƌ����o���āA�����c�������������Őӂߎn�߂��̂��B���������ANTT�V�c�В��Ƃ̐ڑҗL���ɂ��Ă͂���܂ʼn��x���_�_�ɂȂ��Ă������ł���A�܂�2��16���̕��c��b�̓��قɂ��Ă͎������g�̂킸��1�����O�̓��قł���B��������ʍ��̕K�v�����̂��ɂ߂ĒႢ�ƍl������B����ɂ�������炸�A���c��b�́u�t�M���v�ƌ`�e���č����x���Ȃ������ŏ����c���ɑ��Đ����r���Ă��邱�Ƃ����L�̓���ł��n�b�L���Ɗm�F�ł���B
���̎��^�͈ȉ��̒ʂ�B
���c��b�F �u�ψ��ˁA���ꐳ�m�����ɂ߂邽�߂ɒʍ����ĉ�������I �ψ��A�ψ��A�����ψ��I �ʍ��A�����Ƃ��ĉ�������I�v
�������c���́u�ʍ����Ă܂��I�v�Ƒ����ɍR�c
���c��b�F �u���Ⴀ�A������ƌ����Ă�B�ʍ����A�����Ă�B�v
���X�T�q�������u�����ʍ��ł����B���Ȃ��̓��قɂ��ĕ����Ă��ł��v�ƍR�c�B���^��1��20�b�قǒ��f�B���̊ԁA�R�{���O�ψ����═�c��b��2��16���̋c���^��{���̎���ʍ��Ǝv���鎆�̓��e���m�F�B
���c��b�F �u�����A�@�l�Ƃ�����Ȃ��A�������l�̖��E�E�E�A���l�̖����Ԃ���ꂽ��ł��傤�H�@�����ł���H�v
���M�҃R�����g�F�咣3�u�l������肵�����₾���琛�������̌��͓������v1���
���X�T�q�������u���������Ă��ł����H�ʂ̖��ɂ͓����Ȃ��ƌ���������Ȃ����v�ƍR�c�B���^��40�b�قǒ��f�B
���c��b�F �u�l����肳�ꂽ�킯�ł��傤�H �����ψ��́A�l���B�v
���M�҃R�����g�F�咣3�u�l������肵�����₾���琛�������̌��͓������v2���
�����c���F �u���c������b��2��16���ɗ�������}�E�����ꐳ�c���̎���ɂł��ˁA�w���k�V�Ђ́A����W�҂Ɖ�H�������Ƃ�����܂����x�Ƃ����₢�ɑ��āw�������܂���x�ƁA�ʂ̉�H�̗L���ق��Ă��܂��B�ɂ�������炸���́A���̎���́ANTT�����Ƃ����ӂ��Ɏ���ʍ��œ��{��ŏ����Ă���܂��BNTT�����Ɖ�H���������Ƃ����邩�̎���ɁA�Ȃ����ً��ۂ������ł��傤���B�Ȃ��A���ꂪ��������ł��傤���B�����ĉ������B�v
���M�҃R�����g�F�����c���̏�L�����ɂ���āA���c��b�̎咣1�u�ʎ��Ă̓��ق͍T����v��2�u����ʍ��͂���Ă��Ȃ��v�͂���������R�Ƃ��Đ������Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�
���c��b�F �u�����A��̓I�Ȍl���̂�������ꂽ��ł���B�l�́B�ǂ��̉�ЁA�ǂ��̒c�̂��āA�l�́A��̓I�Ȍl�̖��̂�������ꂽ��ł���B�v
���M�҃R�����g�F�咣3�u�l������肵�����₾���琛�������̌��͓������v3���
���l������肵�Ď��₵�Ă����ً��ۂ���Ƃ����������[�v
�����܂ł̂����ŁA�咣1�u�ʎ��Ă̓��ق͍T����v�Ǝ咣2�u����ʍ��͂���Ă��Ȃ��v�𑱂���̂͂������ɋꂵ���Ɣ��f�����̂��A�咣3�u�l������肵�����₾���琛�������̌��͓������v���J��Ԃ��悤�ɂȂ������c��b�B
����ɑ��āA�����c���͒��J�ɁuNTT���V�c�В��v�ƌl������肵����ʼn�H�̗L�������߂Ď��₷��B�����A���c��b�͂܂����Ă������ׂ����ق��s���A�ꓯ�����R�Ƃ�����B���̎��^�͈ȉ��̒ʂ�B
�����c���F �u���Ⴀ�A���c������b�͑�b�A�C��ANTT���V�c�В��Ɖ�H�������Ƃ͂���܂����H�v
���c��b�F �u�ʂ̎��Ăɂ��Ă͂������������T�������Ē����܂��B�v
���M�҃R�����g�F�咣1�u�ʎ��Ă̓��ق͍T����v4���
�����c���F �u���k�V�Ђ̐��������Ƃ̉�H�ɓ����āANTT�V�c�В��Ƃ̉�H�̗L���ɂ��ē������Ȃ����R�ق��ĉ������B�v
���M�҃R�����g�F�l������肵�Ď��₵�Ă����c��b�͓��ً��ۂ𑱂��Ă���A�咣3�u�l������肵�����₾���琛�������̌��͓������v�ɂ��Ă����R�Ƃ��Đ������Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ���
���c��b�F �u�ʂ̎��Ăɂ��Ă͈��������͍����T�������Ē��������Ǝv���܂��B�v
���M�҃R�����g�F�咣1�u�ʎ��Ă̓��ق͍T����v5���
�����c���F �u�ψ����B���c��b�̓��ق͍����̍ō��@�ւł��鍑��ɑ���R�c�W�Q�ł���A���ً��ۂł��荑������M����s�ׂł��B�ψ������猵�������ق���悤�Ɏw�������肢�������܂��B�v
��8���Ԃɋy���^�̓��e�͈ȏ�ł���B���̌�A�^��}�̗������W�܂��ċ��c���邪�A���ǁA�����}�E�R�{���O�ψ����͕��c��b�ɓ��ق���悤�Ɏw�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�x���ŗ�ȓ��ق�e�F�B���̌�������c���́uNTT�V�c�В��Ɖ�H�������Ƃ����邩�H�v�ƌl������肵����Ŏ��₷�邪�A���c��b�́u�ʂ̎��Ăɂ͂������������T����v�Ɠ��ً��ۂ𑱂��āA���^�͏I�������B
����܂ł������}�c�����ψ����߂�ψ���ɂ����āA�������������^�c�͓��풃�ю����������A�����܂ŋ��ʂ�Ȃ����ً��ۂ��J��Ԃ��t���ɑ��āA�ψ������ꌾ�����ӂ��Ȃ��Ƃ����̂́A�������ɒꂪ�����Ă��܂�����������B
|
|
�������ȐڑҖ��@�[�܂�^�O����ɉ𖾂� 3/16 |
�����Ȋ�����ւ̐ڑҖ��Ɋւ��A�Q�@�\�Z�ς���H���Â��Ă����m�s�s���V�c���В��ƕ������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv�̒����M��В����Q�l�l���v�����B�Ȃ����Ђ͏��ʐM����������ǂ��铯�ȊW�҂Ɖ�H���d�˂Ă����̂��B����ɂ���čs�����䂪�߂��邱�Ƃ͂Ȃ������̂��B�������猩��Γ��R�̋^�O�����A���̓��̂��Ƃ�Ŗ��̊j�S���𖾂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
��3�N�O�ɎВ��ɏA�C�����V�c���́A���g�Ƒ����Ȋ����Ƃ̉�H������܂�3�����Ɛ����B�ӌ��������ړI�ŁA�Ɩ���̈˗���������A�X�����肵�����Ƃ͂Ȃ������Ɣے肵���B���`�̎═�c�Ǒ��������Ƃ̉�H�ɂ��Ă������ꂽ���A�u�ʂɂǂȂ��Ɖ�H�������ۂ������J����Ǝ��Ƃɉe��������v�Ƃ��Ė������Ȃ������B
���ƌ������ϗ��K���Ɉᔽ���銯���ڑ҂��J��Ԃ��Ă������k�V�Ђ̒����В����A��H�ړI���u��Ȃ��������B��̓I�ȖړI�ł͂Ȃ��A���������b�ɂȂ��Ă��邩��U�����v�Ɠ������B
�������A�m�s�s�͎��ƌv�������I�o�ɂ��āA�����Ȃ��狖�F���闧��ɂ���B�g�ѓd�b�������������Ȃǂ������Ă��A�s���Ƌْ��W�ɂ������B
����A���k�V�Ђ��q���������Ƃ̊O���K���Ɉᔽ���Ă������Ƃ��������Ă���A���̑�������đ����ȂƂ��Ƃ�����Ă����Ƃ����B
�����̏ƍ��z�ȉ�H�ڑ҂̊W�ɂ��āA�\���ɋ^�O���@��ꂽ�Ƃ͌����Ȃ��B
��A�̕s�ˎ����o��A�����Ȋ�����͕ŕ\�ʉ���������������F�߁A���̑��̐ڑ҂������ƂȂǂ�ے肵���B�Ƃ��낪�V���ȏ؋����������ƑO����|���F�߂�Ή����J��Ԃ��Ă���B
�����Ȃ͓����������n�߂����A15���ɂȂ��Ă�����ɑO���������ƑO��ʍs���ǒ����m�s�s����ڑ҂��Ă������Ƃ������B�����玟�ɑΏێ҂��g�債�A�����̌��E�������ɂ��Ă���B
����͊���144�l��ΏۂɁA����2�ЂɌ��炸�A�L�����ԋƎ҂���ڑ҂��Ă��Ȃ��������߂Ē�������Ƃ��Ă���B����Ƃ͕ʂɁA2�Ђ̐ڑ҂ɂ���čs�����䂪�߂��Ȃ����������������O�҈ψ�����A�T���ɔ���������B�q�ϐ���S�ۂ�������i�߁A���ʂ��܂т炩�ɂ��Ă��炢�����B
���߂����Ȃ��̂́A���c�����������g�̉�H�̗L���ɂ��Ė���������Ă��邱�Ƃ��B���̓��̎��^�ł��m�s�s�W�҂Ƃ̉�H�����A�u�����̋^�O�������悤�ȉ�H�A��ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�ƌJ��Ԃ����B�����ɗL�������Ȃ���A�^�O��������Ă��d���Ȃ��B���̂܂܂ł͍����̐M���͓����Ȃ����낤�B
16���ɂ͏O�@�����В��������A�Q�l�l���^�𑱂���B��}�͈�@�ڑ҂��Ă����R�c�^�M�q�O���t�L�̏ؐl����Ȃǂ����߂Ă���A������������ł̓O�ꂵ���𖾂����߂���B
|
|
�������Ȃ̐ڑҖ��@�^�O���炷���m�Ȑ����� 3/16 |
�����Ȋ����炪�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv�Ƃm�s�s����ڑ҂��Ă������ŁA�Q�@�\�Z�ψ���ɗ��Ђ̎В����Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ����B
���k�V�Ђ́A�����@�̊O���K����ɒ�G�����܂܉q���������Ƃ̔F����Ă���A�����Ȃ̐R���̐��Ɛڑ҂̊W���^���Ă���B
�����Ȃ͂��łɔF��̎����������߁A�O���L���҂ō\�����錟�؈ψ����݂��ċ߂��������n�߂���j�����A�œ_�͐ڑ҂�ʂ��čs�����䂪�߂��Ă��Ȃ��������̈�_�ɂ���B
�Ƃ��낪���c�Ǒ��������͈ψ���Łu�\�����̃~�X���傽�錴���Ƃ͂����A�����Ȃ̐R�����\���ł͂Ȃ������v�ƁA�~�X�Ɠm��(������)�ȐR���ɖ����⏬(�킢���傤)�����Ă��܂����B�����Ɂu�ڑҁv���ǂ��ւ�����̂��B���؈ψ���������ׂ��ŗD��ۑ�ł���B
�����@�ł͉q���������Ǝ҂̊O���o���䗦��20�������ƒ�߂Ă���B4�N�O�ɔF��������k�V�Ђ͓����̊O���䗦��20�������@��Ԃ������B���Ђ̒����M��В��͗\�Z�ςŁu�F�肩��N��Ɉ�@����F�����A�����ȒS�������Ɩʒk���ĕ����v�Ɛ����������A�����ȑ��͕��������͂Ȃ��Ɣے肵�Ă���B�^���͈ł̒��̂܂܂��B
�m�s�s���V�c���В��͑����Ȋ����ɑ���ڑ҂̉Ȃǂ͎��������A����c���ɑ���ڑ҂ɂ��Ă͖�����������B�u�ʂɂǂȂ��Ɖ�H�������ۂ������J����Ǝ��Ƃɉe��������v�Əq�ׂ����ŁA�u�����납��^��}����c�����͂��߂Ƃ��č��k������݂��Ă���B�Ɩ���̗v���A�X����Ƃ����b�͂��Ă��Ȃ��v�Ƃ�������B����͖������Ă���B���̂Ȃ����k�����Ƃɉe�����闝�R��������Ȃ��B
���`�̎A���c�������́u�����̋^�O�������悤�ȉ�H�A��ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Əq�ב����Ă���B�m�s�s���̏،��ƍ��킹�Đ����ʂ�A��H�̎����͂������̂��낤�B�����ے�Ƃ��m��Ƃ����ʓ��ق��J��Ԃ�����A�^�O��������̂��B
�����I�Ŏ��������鐭���ł��o���ɂ͖��Ԏ��Ǝ҂Ƃ̈ӌ��������K�v�ȏꍇ������B���ƌ������ϗ��K���̑ΏۊO�ł��鐭���ƂƊ������ꗥ�ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�^�O�������S�z���Ȃ��Ȃ�A�܂������m�ɐ�������Ƃ��납��n�߂Ă͂ǂ����B�@ |
|
�����c������7��u�^�O��������H�Ȃ��v���قɃ��W�u���������Ă�v 3/16 |
�m�s�s���V�c���В���15���̎Q�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��A�����Ȋ����ւ̐ڑ҂⍑��c���Ƃ̉�H��ʂ��ċƖ���̈˗���X�ɂ��Ĕے肵���B�ڑҖ��ɂ��Ēӂ������A���c�Ǒ��������Ƃ̉�H�̗L���ɂ͐��ʂ��瓚���Ȃ������B�������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv�̒����M��В����o�Ȃ������A���`�̎̒��j�������ɂ��ē����ɋ������ʂ��ڗ������B�����Ȃ́A������v144�l��Ώۂɐڑ҂̎��Ԓ��������{����Ɣ��\�����B
���c�Ǒ��������́A�V�c���Ƃ̉�H�����u�����̋^�O�������悤�ȉ�H�ɉ��������Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ̓��ق����Ȃ��Ƃ�7��J��Ԃ����B��}�́u�v����ɉ�H�͂������Ǝ~�߂�̂����R�B���ق������قǍ����̐M���͎�����v�Ɣᔻ�B���c���́u�^�O�������悤�ȉ�H�v����̓I�ɉ����w���̂������Ɓu�܂��ɓǂ�Ŏ��̂��Ƃ��A�����̋^�O���������Ƃ̂Ȃ���H�v�ƉB�u���������Ă�v�Ƃ₶����B�@ |
|
���܂��u�����v�A�����Ȑڑ҂̊j�S��˂��Ȃ������͂Ȑl�����ց@3/16�@ |
�����Ȋ����ւ̐ڑҖ����߂���A3��15���̎Q�@�\�Z�ψ���ɓ��k�V�Ђ̒����M��В��Ƃm�s�s���V�c���В����Q�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ����B
�����Ȃ͒����Ȓ��ĕ҂Ŏ����ȁA�X���ȁA����������������2001�N�ɒa�������B�����Ȃ̕s�ˎ���`����ł́A����ې������̏������e����{�X���̗�؍N�Y�㋉���В�(����)�ɘR�炵�����ƂŁA19�N�ɗ�ؖΎ��O����������������X�R���ꂽ���Ƃ��L���ɐV�����B�Ȃ��A�������e���������������[�N�����̂��B
�����ŗX�����c���������������A����}�����ɂȂ��Ď�����́u�č��L���v�ɂȂ��Ă��܂����B�{���͊��S���c���ŁA���͕ۗL���鋌�X���O���[�v�̐��{�ۗL����S�����p���邱�Ƃ�ڎw���Ă����B�������A����}��������̖@�����ŁA���̊������p���u�`���v����u�w�͋`���v�ɂ��ꂽ���ƂŁA�����������X���O���[�v�̍ő�̊���̂܂܂ł���B
���̌o�ϓI�ȁu�����v�́A����ɐl����̖����B��̓��{�X�����̗�؎��͌������Ȃ̎��������ł���B�܂�A�T�^�I�ȓV���肾�B�X�����c���̍Đ��i�Ɠ����ɁA�V����K���̌��i�����K�v���낤�B
�ł́A����̖��͂ǂ����낤���B��͂葍���Ȃ̍ٗʌ������ڂ���Ă���B�ʐM�E�����Ɋւ��鋖�F�̍ٗʂ��傫�����邱�Ƃ���肾�A�ƕ]�_�Ƃ̌��p�j����Éx�勳���̍����m�ꎁ��͌������w�E���Ă���B
���ɓd�g�̊��蓖�Ă�����̖��̔w�i�ɂ�����B���k�V�Ђ������@�̊O���K���Ɉᔽ���Ă���ɂ�������炸�A�q���������ƂɔF��������͒��ڂ��ꂽ�_�������B�Ȃ��Ȃ瓌�k�V�Б��͍���Łu�����Ȃ̒S�������Ɩʒk���A�����v�Ɣ������Ă���B�����ł���Ȃ瑍���ȑ������r�����A�ڑҖ��ȊO�ł��A���҂̓����납��̂Ȃꍇ�����u�������v�Ɏ������\��������B
���{�X���ւ̃��[�N�����v���o���Ăق����B�����Ȃ͎���̍ٗʌ��̑傫���Ɉ��Z���A�K������鑤�͕��i����́u�𗬁v�ň��ՂƂ��Ă����̂��낤���B�����͂��ЁA�����̉𖾂����Ăق����Ƃ��낾�B�܂��A���ƌ������ϗ��K��ᔽ�̋^���̂���ڑ҂ɂ��ẮA������k�V�Ђ�m�s�s�͐^���ɔ��Ȃ���ׂ����낤�B
����̘_��ł́A��т��Ė�}�͐��`��(�����E�悵�Ђ�)�̒��j���N���[�Y�A�b�v���邱�Ƃɖ�N�ł���B3��15���̎Q�@�\�Z�ψ���ŗ�������}�̕��R�N�Y�������́u�{���̓R���i�̂��Ƃ���肽���Ă����ς��������Ă���ł��B�����{��k�Ђ���10�N������G�l���M�[�̂��Ƃ���肽���āA�������������Ă���ł��B�����(�ڑ�)���N���邩��ł��Ȃ�����Ȃ��ł����I�c�R���i���Ă��f�����܂��v�Ǝւ̎���Ő����r�炰�����A�������ɖ����⏬(�킢���傤)���������Ă���B
�܂��A���ƌ������ϗ��K���j�����ƂȂ�Ζ�肾���A���В��ւ̎�������Ă���ƁA������H�������邾���ł��u�ڑҁv�Ƃ������t�ŋ^�f���������Ă�悤�ȕ��͋C������Ă���B
��@���̍��������������P�Ɂu�����̋^�f�v����������Ƃ����A�X�F�E���v�w�����Ȃǂł��Ȃ��݂̎�@�ł���B�ނ���A�{�ۂ͑����Ȃ̋��F�݂̍�����Ǝv���̂����A�Ȃ��Ȃ������ɂ܂ŋc�_�������Ȃ��B�����܂Łu�����V���[�v���B
�����A���̒��x�Ȃ�A���R��������F�߂Ă���悤�ɃG�l���M�[����V�^�R���i��ɂ�莞�Ԃ�������ׂ��������B���ς�炸�̃e���r�̃j���[�X�ԑg��C�h�V���[�E�P��_���A�����̖�}�̎p�ɂ͂�����邵���Ȃ��B
�������A�^�}�A�����}�ɂ́A��荪���I�Ȗ�肪����B�����Ȃ̕����E�ʐM�̍ٗʌ������炷���߂ɂ́A�������D�����ōł��������i��������Ǝ҂Ɏ��g���������ԗ^����u���g���I�[�N�V����(�d�g�I�[�N�V����)�v�̓������]�܂����B
���́A����}�����̎���Ɏ��g���I�[�N�V�����̓������t�c���肳�ꂽ�B�������A�����}�����ɂȂ��Ă���u�����͂̂���҂����g����Ɛ肷��v�Ƃ������R�Ŕp�ĂƂȂ����B(�Q�ƁF�o�ϊw�҂̈��c�m�S���̃u���O)�B�����̗��v���悻�ɁA����}�����͗X���������A�����}�͕����E�ʐM��������낤�Ƃ����킯�ł���B
����̖��ł����������A�������̕s�ˎ����o�Ă���ƁA�Ȃ������܂��ē��t�l���ǂ��ᔻ�����B���t�l���ǂ����邹���Ŋ��������{�ɜu�x(����)���A��肪�N����Ƃ����̂ł���B���������K�Ɏw�E���Ă���悤�ɂ����������t�l���ǂ������̓������K�����邽�߂ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ������\�_�ł͂Ȃ����B���t�l���ǂ�ᔻ�������������̗������}�X�R�~�A��}�A����ɔ����炢�����͎u���̐l����(�����C�h�V���[��)�����v�l�Łu�����v���Ă���̂��낤�B
�ł���Ί����g�D�̗����̉����𖾂�݂ɏo���Ăق������A���_����������ƁA�ǂ������_�͖�����̕����ɊS�������Ă���悤���B�����V���̐��_�����ł́A�Ȃ�Ɩ��̐l���A���̒��j�̐ڑ҂ɂ��āA�ɐӔC������Ǝv���Ă���Ƃ����B����ł͂܂�ň������A�ѐӔC�ł���A�ǎ�����ӌ��Ƃ͂����Ȃ��B
�����A�j���[�X�ԑg��C�h�V���[�����Ă���ƁA���̂悤�Ȉӌ������悤�ɍ������U������Ă���̂�������Ȃ��B�̃��x���̒Ⴓ�͐[�����낤�B�e�ǂɂ́A�����ȂȂǂɁu�ڑҁv���������Ƃ��Ȃ����A��O�҈ψ���Œ��������邱�Ƃ��������߂������B�g�߂ȂƂ���Ŏ��Ђ̃��C�h�V���[�l�^�����@�ł��邩������Ȃ����炾�B�@ |
|
���J�e�O�����R�c�������E�@�ڑҖ��Œ�E3�J�������� 3/16 |
���c�Ǒ���������16���̋L�҉�ŁA���Ȋ�����ւ̐ڑҖ�������O�����R�c���̒J�e�N�F�����t�Œ�E3�J���̒��������ɂ����Ɣ��\�����B�J�e���͎��E����o���A���ꂽ�B�J�e���̓��ӂ����ߑސE���̎x�����͗��ۂ���B���l�ɐڑ҂��������p�i���ې헪�ǒ��͌���10����1(2�J��)�Ƃ����B2�l�����Q�W�҂���̐ڑ҂��ւ��鍑�ƌ������ϗ��@�̗ϗ��K���Ɉᔽ�����ƔF�肵���B
�J�e���ɂ��Ă͓��k�V�Ђɂ��ڑ҂����钲���̍ہA�m�s�s����̐ڑ҂�\�����Ȃ��������Ƃ����ƌ������@�̐M�p���čs�ׂȂǂɓ�����Ƃ����f�����B���c���́u�[������ѐ\���グ��v�Əq�ׂ��B�@ |
 �@3/17 �@3/17 |


 �@
�@ |
|
�����c���ANTT�����Ɖ�H���@���t 3/17 |
���c�Ǒ���������NTT���V�c���В���ƍ�N11���ɉ�H���Ă����\�����������Ƃ�17���A���������BJR���C�̊����h�V���_��≓���T�qNTT�h�R���Ɨ��ЊO����������ȁBJR���C�͋����ʐM�̎�ނɑ��u��H�͎������v�Ƃ̃R�����g�\�����B���c���͎��ӂɁu����o���������ʼn�H�͂��Ă��Ȃ��v�Ƙb���Ă���Ƃ����B
���c����18���̏O�@�����ψ���ɏo�Ȃ���\��ŁA�����W���������Ƃ݂���BNTT�́u�����W�����v�Ƃ��Ă���B
���c���́A����܂ł̍���قŁu�����̋^�O�������悤�ȉ�H���ɉ����邱�Ƃ͂Ȃ��v�ƌJ��Ԃ��ANTT���Ƃ̉�H�̗L���ɂ��Ė���������Ă����B��H�������ł���A��p���S���b�̓��e�Ȃǂɂ��Đ��������߂�ꂻ�����B
���t�I�����C����17�����B����ɂ��ƁA���c���͑������A�C��̍�N11��11���A�����s���̃z�e���̓��{�����X���V�c�A�����A�����e���Ƃ̉�H�ɓ��Ȃ����BJR���C�͊�������3���Ɖ�H����������F�߂���ŁA�F���֘A�̈ӌ������������Ɛ��������B
��H������NTT���h�R���̊��S�q��Љ��Ɍ������������J�����t��(TOB)�����{���ŁA�I����Ƀh�R�����ł��o���g�ѓd�b�������������̓��e�ɒ��ڂ��W�܂��Ă����B
���c���͍�N11��20���A����܂ŕ]�����Ă���KDDI�A�\�t�g�o���N�̊i���u�����h�ł̒l������ᔻ�B�h�R����12��3���A���c�������߂�{�̃u�����h�Ƃ��Ă̒ቿ�i�̐V�v�����uahamo(�A�n��)�v�\����ƁA���`�̎ƕ��c���͍����]�������B
NTT�͎��ƌv����������I�C�ɑ����Ȃ̔F���K�v���B�����}�̖�c���q��������s�A���s���c�O�@�c�����������ݔC����NTT���Ɖ�H���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B
|
|
�����c��������NTT�V�c�В�����H���Ă��� 3/17�@ |
���c�Ǒ�������b���A��b�A�C��̍�N11��11���ɁANTT���V�c���В��Ɖ�H���Ă������Ƃ��A�u�T�����t�v�̎�ނŕ��������B�ꏊ�́A�����E�p���X�z�e�����ɂ�����{�����X�u�a�c�q�v�B�V�c�В���NTT�h�R���Ɨ��ЊO������̉����T�q���A���c��b��JR���C�̊����h�V���_������Ȃ��Ă����B
NTT�W�҂��،�����B
�u2019�N12��18����NTT�O���[�v���^�c����}�o�فwKNOX�x���V�c�В��Ɖ��������AJR���C�̊������Ə����r�ꕛ�В���������A�ڑ҂��Ă��܂����B���̓��̘a�c�q�ł̉�́A�ԗ�Ƃ��Ċ����������Z�b�g���Ă��ꂽ���̂ł��v
�����A�Ȃ������ɕ��c�������ꂽ�̂��B
�u���c��b��A��čs�����̂�NTT���ł��B�������͏T���_�C�������h���ҏW�����o�āA2016�N6����NTT�h�R���̎ЊO������ɏA�C�B�V�c���̊o�����߂ł�������ŁA���c��b�Ƃ��ȑO����W���[���ƕ����Ă��܂��B�������ƕ��c��b�͖ʎ����Ȃ����������ł��v(���O)
����܂ō���ŁA���c��b�́u���͍����̊F����^�O�������悤�ȉ�H�ɉ����邱�Ƃ͂���܂���v�A�V�c�В����u����Ƃ̎В��Ƃ��ẮA�ʂ̉�H�̗L���ɂ��Ă͍T�������Ă��������v�Ɠ��ق��A��H�̎����m�F�ɉ����Ȃ��p�����т��Ă���B���ł��A���c��b�́A���l�̓��ق��ĎO�J��Ԃ��A�u�ł͋^�O�������Ȃ��H���͂����̂�?�v�Ɩ���Ă��u�^�O�������悤�ȁc�c�v�Ɠ������t���q�ׂ�ȂǁA�x�X����������Ă����o�܂�����B����̉�H�̗L���ɂ��āAJR���C�ɐq�˂�Ɓu�����ł������܂��v(�L�����L��)�Ɖ����B
��H��11��11���́ANTT�ƃh�R���̖��^�����E����TOB(�������J�����t��)�̍Œ��B9��29�����V�c�В��̓h�R���̊��S�q��Љ��\���A��������TOB�𐄂��i�߂Ă����B�j��ő�ƌ�����4�E2���~�K�͂�TOB���������ꂽ�̂́A��H��6����A11��17���BNTT�̃g�b�v�A����ɂ͎q��Љ��̉Q���ɂ������h�R���̎ЊO�������TOB�̍Œ���NTT�̎��ƌv��Ȃǂ�F���闧��̑�����b����H�ɓ��Ȃ����Ă����̂��B�V�c�В����A���E�l�̉�H�ɕ��c��b��A��čs�������Ƃ������������ƂŁA�V�c�В��ƕ��c��b�Ƃ̊W���ɂ��Đ��������߂鐺���オ�肻�����B�@ |
|
�����X�Ǝ��E�ʼn��̂������Ȑڑ҂̐^���@���߂��u���Ԑl�v���v�ɔے�I �@3/17 |
�m�s�s�Ⓦ�k�V�Ђ���J��Ԃ����z�ڑ҂��A16���t�Ŏ��E���������Ȃ̒J�e�N�F�O�����R�c���ɂ��āA�^�}�͍���A��}�����߂鍑��v�ɉ����Ȃ����j���B���{�Ƃ̊W���ꂽ�u���Ԑl�v�ł��邱�Ƃ𗝗R�ɂ��邪�A���`�̎̒��j���������������s�ˎ��ւ̒Njy�����킵�����v�f��������B��ɓ��t�L�����߂��R�c�^�M�q�����ȓ��k�V�ЊW�҂�A���̊j�S��m��L�[�p�[�\���ɂ��Ă����l�̑Ή��ŁA�^�������Ɍ��������ɓI�Ȏp�����ڗ��B(��c�Ďu)
�J�e����15���܂ō���ɎQ�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ��Ă������A�����}�����͎��E���@�Ɂu������ʐl������A�ĂԕK�v�͂Ȃ��v�Ɩ����B���k�O���Q�@���������L�҉�Łu�����Ȃ����ݍ����������A�J�e�����g�����Ȃ�̉A���ق��Ă���v�Əq�ׁA����̏��v�ɔے�I�Ȍ������������B
�Q�l�l���v�́A���@62���́u�����������v�Ɋ�Â����x�B�l�I�⎞���͗^��}���ӂŌ��߂邽�߁A���ŏ���^�}�̗����Ȃ��ɂ͎������Ȃ��d�g�݂��B
����̐ڑҖ��ŁA�^�}�����v���ۂ̂��ǂ���ɂ���̂́A����̉ߋ��̑Ή����B�O�@�����ǂȂǂɂ��ƁA���ɕs�ˎ�������R�c�ł͎Q�l�l���u�Ɛl�����v����A�s���v���鋰�������Ƃ��āA�T�d�ɔ��f����X��������Ƃ����B��������ɁA�^�}�͐ڑ҂��Ă������k�V�Ђ̎O��`�V�O��������s������ؓc�R�I�v�O���s�����A���������ĂԂ��Ƃ����ݑ����Ă���B
�����A���Ԑl�̗���d���邱�Ƃƈ��������ɁA�^�������͉��̂��B���̓����҂���d�v�،��������o���@��Ȃ��Ȃ邩�炾�B16���̏O�@�\�Z�ψ���ł́A��������}�̌㓡�S�ꎁ���J�e���ɂ��āu����ɌĂׂȂ��Ȃ�B(�����ɂ��)�������ł͂Ȃ����v�Ɣᔻ�������A���c�Ǒ��������́u����Ō��߂邱�Ƃ��v�Ǝ������B
|
|
�������ȐڑҖ��ANTT�������ɉ�H���[���Ȃ��u�Ȃꍇ���v�����Ɂ@3/17
|
�u(�����Ȋ����ւ̐ڑ҂�)���ƌ������ϗ��@��A���Ȃ��ƍl���Ă����B��ϔF�����Â��\����Ȃ��v���Ă���v�\�\�B
2021�N3��16���̏O�@�\�Z�ψ���ɎQ�l�l�Ƃ��ďo�Ȃ���NTT���V�c���В��́A�O���̎Q�@�\�Z�ψ���ɑ����A���̂悤�ȕٖ����J��Ԃ����B�����Ȋ����i���o�[2�̍X�R�E���E�ɂȂ���������̐ڑҖ��B2���ɂ킽�鍑��^���猩���Ă����̂́ANTT�A�����Ȃ̑o���Ń��[�����y�����Ă������Ԃ��B�����̐M���Ɍ��������̂�͉����B
NTT�ɂ�鑍���Ȋ����ւ̐ڑҖ��̘_�_�͑傫��2����B1�́A�Ȃ����ƌ������ϗ��@�ᔽ����ԉ������̂��B����1�́A��A�̐ڑ҂ōs�����䂪�߂��Ă��Ȃ������B
���ƌ������ϗ��@�Ɋ�Â����ƌ������ϗ��K���ł́A���F�̑ΏۂƂȂ�悤�ȗ��Q�W�҂���̐ڑ҂��ւ��A���ȕ��S�ł�1���~�����H�͎��O�̓͂��o���`���Â��Ă���BNTT�ɂ�鑍���Ȋ����ւ̐ڑ҂ł́A���F�Ώۂ���1���~��D�ɒ����鍂�z�ȉ�H�����������B�ɂ�������炸�A�ڑ҂������̑����Ȋ����̎��O�͂��o�͂Ȃ������B
3��16���̎��^�ł́ANTT�V�c�В��ɑ��u���z�ȉ�H�ꏊ���w�肵�����Ƃō��ƌ������̃��[���ᔽ��U�������̂ł͂Ȃ����B�Г��ō��ƌ������ɑ����H���[���͂Ȃ������̂��v�Ƃ̎��₪��B
NTT���V�c�В��́u�O���[�v�S�̗̂ϗ����͂͂�����̂́A�����В��߂�NTT�̎�������Ђɂ́A��H�Ɋւ����̓I�ȃ��[�����Ȃ������B���ꂪ�傫�Ȗ��ł���A���ꂩ�璼���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƌ�����B
NTT��������Ђ͊Ǘ���Ђł��莖�Ƃ��c�Ƃ����Ȃ��B���̂��ߍ��ƌ�������ΏۂƂ�����̓I�ȃ��[�����Ȃ������B��������ЎP���̎��Ɖ�Ђł́A���ƌ������ȂǂƂ̉�H�Ɋւ����̓I�ȃ��[�����߂Ă���P�[�X�������Ƃ����B���̓_���ANTT�Ƒ����Ȃ́u�Ȃꍇ���v�̉����ɂȂ����\��������B
���z�ڑ҂̏ꏊ�ɂ��Ă�NTT�̔F���̊Â����o���B��A�̐ڑ҂̏�ƂȂ����̂́ANTT�O���[�v���o�c�����������X�g�����u�N���u�m�b�N�X���z�v���B�V�c�В��́u����Ђ��o�c���Ă���A��������Ђ̃R�X�g������Ђ̎����ƂȂ�A�A�����Z��ł��������B�Ⴆ��2���~�̃R�[�X���ƁA3����1�قǂ̌�������������Ƃ����ӎ��ɂȂ��Ă����B(���[���ᔽ��)�U������f�n��1�ɂȂ����Ɣ��Ȃ��Ă���v�ƕٖ������B
NTT�Ƒ����Ȃ̊W���A1990�N���NTT����������S�ʑΌ����疨���ւƈڂ�ς�����_���A���[���y�����������w�i�ɂ��肻�����B���ʐM�����̉ۑ�́A���Ă̍����s��d������A���݂�GAFA���܂߂����ۋ����ւƃV�t�g������B���̓_�ɂ���NTT�V�c�В��ƁA2021�N3��16���Ɏ��E�����J�e�N�F�O�����R�c���̖��ӎ��͈�v���Ă����B
NTT�V�c�В��ƒJ�e���́A���X���Ȃ�NTT���S�ʑΌ����Ă���1990�N�ォ��ʎ�������A�Â�����ӌ��������d�˂Ă����߂�����B�s��������ς��A�݂��̖��ӎ�����v���钆�ŁA���[���y���̍\�������܂�Ă������\��������B �E�E�E
|
|
��NTT�В��̘V�ԓ��قƓ��k�V�ЎВ����c�����u�Ύ�v�@3/17
|
3��16���A���c�Ǒ���������NTT����ڑ҂��Ă����J�e�N�F�O�����R�c�����E3�J���̒��������Ƃ��A�J�e���͓����t�Ŏ��E�����B�T�����t����NTT�O���[�v�ɂ��ڑ҂ɂ��āA�Q�l�l�Ƃ��ď��v���ꂽNTT���V�c���В��́u�����ނˎ����ł���v�ƍ���ŔF�߂��B�V���ȁu���t�C�v�ɂ���āA���c��������NTT�В��ƍ�N11��11���ɉ�H���Ă����V����������BNTT�O���[�v�����W�҂ɂ�郊�[�N�������N����������͍��Ȃ������Ă���A�����ȒʐM��(���X���ȓ��ȑg)���ւ����u���v�̊���v���E�������Ă��Ă��A���ƂȂ�C�z�͌����Ȃ��B
3��15������16���ɂ����ĎQ�c�@�ƏO�c�@�̗\�Z�ψ���ōs��ꂽ�Q�l�l���^�ŁANTT���V�c�В��́u�������}�X�R�~���邢�͗^��}�̍���c�����̗L���҂ƍ��k���s���Ă���v�Ƃ��肰�Ȃ��q�ׂ��B�u�}�X�R�~�v��u��}�v�ɂ��Ċ����Č��y����K�v���Ȃ��������������A������āA�d�g�I�[�N�V�����̓����c�_�Łu�������v�v��ᔻ���������ǂȂǑ�胁�f�B�A��ANTT�J�g�E���J�A�o�g�̋c����������}�ւ́u�u�[�������v�̉\����z�N�����l���������낤�B��A�̐ڑ҂������s���́u�c�݁v�������炵���̂��A����NTT�h�R���̎q��Љ��ƊW������̂��\�\�Ƃ������^������킷�u�������v�𓊂����̂��Ƃ�����A�����ɘV���ȓ��ُp���ƌ��킴��Ȃ��B
����ɑ��ē��k�V�Ђ̒����M��В��́A�u�ڑ҂̖ړI�͊�Ȃ��������Ƃ������Ƃ����A���̊�Ȃ��̖ړI�͉����v�Ɩ���A�u��Ȃ��̖ړI�͊�Ȃ����v�Ɠ��ق��Ă���B
��Ȃ��̖ړI�͊�Ȃ��|�|�B
������������́u��x����̓ڒq�v���A�͂��܂��u�[���Ȃ�T�ⓚ�v���B�v�͑����d���^����悤�ȋ�̓I�Ȑ����������̂ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�l�ԊW�̈ێ��̂��߂ɐڑ҂������ƌ��������̂��낤�B
�������A��Ȃ������ȖړI�����āA����Ȃ��̂悤�ɁA�ē����̓���|�W�V�����̊����ɑ���ڑ҂��p������Ă����Ƃ���A���ꂪ�ނ����肾�B�������l�Ƃ̋����I�E�ʓI�Ȑl�ԊW�ł͂Ȃ��A�E��������L���Ă��銯���Ƃ̊W����Ɉێ����悤�Ƃ��Ă����Ƃ������Ƃł���A�E���Ƃ̊֘A���͋��܂�B
���u�U���v�����������Ȃ̐R����
������ɂ���A����ł̎Q�l�l���^�͐^���𖾂ɂ͒��������̂��������A���ڂ����̂́A�������Ǝ҂ɑ���u�O���K���v�̖�肾�B
���k�V�Ђ�2016�N10���A�m����BS�`�����l���u�U�E�V�l�}4K�v�̎��ƔF����Ȃɐ\���������A���̎��_�Ŋ����20.75%(�c�����x�[�X)���O���������B�����@�́A�u���{�̍��Ђ�L���Ȃ��l�v�u�O�����{���͂��̑�\�ҁv�u�O���̖@�l���͒c�́v���c�����̌ܕ��̈�(20%)�ȏ���߂Ȃ����Ƃ��A�q��������̎��ƎҔF�����v���Ƃ��Ă���B��@���͖��m�����A2017�N1���ɓ��k�V�Ђ͎��ƎҔF������B�����ȑ��̐R���́u�U���v�������B
�������A�{���̖��͂��̌ゾ�B�����В��ɂ��A���k�V�Ђ�2017�N8��4���ɊO���K���Ɉᔽ���Ă��邱�ƂɋC�Â����B�����ŁA�u�ᔽ���B���v���߂ł͂Ȃ��A�u���퉻�v���邽�߂ɁA�����ȂɕE���k������ŁA�q��ЂɎ��Ƃ����p�����Ƃ����B���̉�Ђ������A���k�V�Ђ�100���q��ЂƂ���2017�N9��1���ɐݗ����ꂽ���k�V�Ѓ��f�B�A�T�[�r�X�Ђł���A�������[�������������`�̎̒��j��������ɖ���A�˂Ă�����Ђł���B
�����k�V�ЎВ��́u�V���فv��
���u�����������Ă��ĂȂ��̂œ������Ȃ��v��
�O���K���ᔽ���Гh���邽�߂̎��Ə��p�������̂��ۂ��́A�����_�ł͕s���ł���B���k�V�Ђ��E���k�����Ƃ��������ł���A�����Ȃ̏�ʍs���Ǒ����ے�(���d�g����)���\�Z�ψ���Łu�L���ɂ������܂���v�Ƃ������ق��J��Ԃ����B�����Ȃ��ݒu������O�҂ɂ��u���ʐM�s�����؈ψ���v��17������n���������A�ǂ��܂Ŏ��Ẳ𖾂ɐ荞�߂邾�낤���B
�����@�̊O���K���́A�����I���Y�ł�������d�g�̗L������A���������_��S�������̏d�含���狖�e����Ă���A�킪���ł͒n��g�����łȂ��A�q�������ɂ��Ă���������Ă���B���ۂɂ͊O���ɂ�銔���ۗL����20�����Ă�������ǂ����邪�A���喼��ւ̋L��(���`����)���ۂƂ�����@�ɂ���āA�c�����x�[�X��20�����Ȃ��Ƃ������[�������炳��Ă���(���Ȃ݂ɓ��{�헪�����t�H�[���������ψ��̕���G�����̎w�E�ɂ��A���̃��[����2017�N9��25���t�ǒ��ʒB�ɂ���ē������ꂽ�Ƃ����B���k�V�ЈČ��̏����Ɠ����^�C�~���O�����A�֘A���͕s���ł���)�B
�ߔN�ł́A���S�ۏ�̊ϓ_������A�������f�B�A�ɑ���O���̉e���͔r���͏d��ȉۑ�ɂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�C�M���X�����ʐM����2021�N2��4���A�����̍��c���f�B�A�ł��钆�������d����(CCTV)�����L�E�^�c���鑽����e���r�u�������d����v(CGTN)�������I�ɂ͒������Y�}�Ɏx�z����Ă���Ƃ��āA�����Ƌ����������Ă���B����ɑ��Ē�����2��11���A�C�M���XBBC�̒��������ł̕��f���֎~����[�u�ɏo���B�E�C�O���⍁�`�Ȃǂł̐l�����������āA���v�̏Փ˂������Ƌ��̕t�^�ɒ������鎞�ゾ�B
�O���ɂ��y�n�擾����莋����Ă���B���{�͍�����Łu�d�v�y�n�������@�āv�𐬗������悤�Ƃ��Ă���B����́A���q����n�̎��ӂ⍑���̗����ȂǁA���S�ۏ��d�v�ȓy�n���O�����擾���邱�ƂɈ��̐������������̂ŁA�y�n�擾�҂̎����⍑�ЁA���p�̎��Ԃ����錠���𐭕{�ɕt�^������̂��B�L�͂ɋy�Ԏ����������Ƃ��Ĕ�����ӌ����������A������Ő������邩�s�����ȂƂ��낪���邪�A�����n�𒆍����{��������߂�̂ł͂Ȃ����ƌ��O���鐺�����܂��Ă��钆�A�����ꐬ�����邱�ƂɂȂ낤�B
�����ɂ�����O���K���������悤�ɏd�v�Ȗ�肾�B�����ȏ�ʍs���ǂɂ�����C�̊ɂ݁A����������̃~�X�ōςޖ��ł͂Ȃ��B
15���̎Q�c�@�\�Z�ψ���Łu�ǂ��̍��̊�ƁE�l(������)�Ȃ̂��v�Ɩ��ꂽ���k�V�ЁE�����В��́u�����������Ă��ĂȂ��̂ŁA�������ł��Ȃ��v�Ɖ����B���̏d�含�𗝉��ł��Ă��Ȃ��A����Ƃ̎В��Ƃ��Đ^���𖾂Ƀn���O���[�ɍv������ӔC���������Ă���ƌ����Ă��d�����Ȃ��B�ǂ����Ă����������Ȃ��A�������Ȃ�����������̂�������Ȃ����B
|
|
���u�������Ƃ��ă��[�Y�v�����Ȃ̊����ڑҁ@3/17
|
�����Ȋ����ɑ���m�s�s������֘A��Ёu���k�V�Ёv�̐ڑ҂��A�s���ɗ^�����e���ׂ��O�҂̌��؈ψ��17���A�����Ȃŏ�����J�����B�W�҂���̒���Ȃǂ�ʂ��A��H�O��Ɉӎv���肳�ꂽ����Ɍ��������m�ۂ���Ă�������������B�Ĕ��h�~���������j���B
��O�҈ς͑�w������4�l�ō\������A�����͌������̋g�쌷���ٌ�m�B�����ȐE����ڑ҂��s�����m�s�s�Ȃǂ̖��Ԋ�Ƃɉ����A��H�O��Ɍ��肳�ꂽ����̌��قɊ֗^���������O��(�t���A����b�A������)������̑ΏۂƂȂ錩���݁B
�g�쎁�͏I����A�L�Ғc�Ɂu�������ⓧ�������������ӎv����v���Z�X���Ȃ����A�������O��I�Ɍ�����v�Əq�ׂ��B�l�I�Ȍ����Ƃ��������ŁA����̐ڑҖ��ɂ��āu�������̂�����Ƃ��Ă̓��[�Y���B�ڑ҂����鑤�́A��p���S���邾���̎v�f�͂���͂����v�Ƃ��w�E�����B
��A�̖��������ẮA�s���ւ̉e���ׂ鍡��̑�O�҈ςƂ͕ʂɁA�����Ȃ��ڑ҂̗L���ׂ钲�����s���Ă���B�g�쎁�́A���̒����̏����������߂Ă���A�A�g���đS�e�𖾂�i�߂�l�����������B
|
|
�����k�V�Ђ̔F�����Ƒ����Ȑڑ҂͊W������̂��H�@3/17
|
���k�V�Ђ̎q��Ђ��p�������q���������Ƃ̔F�肪��������邱�ƂɂȂ肻�����B���̎����ł́A���k�V��(���`�̑����̑��q�����)�������Ȃ�ڑ҂������ƂƖƋ��F��̎��������֘A������ۑ����_�����悤�ȋL����ӌ����U�������B�������A�����ŎU�������L����ӌ��́A�����@�̊O���K�����[����m��Ȃ��A������A�d�_�̗ނɉ߂��Ȃ��B�{�e�ł́A���k�V�Ђ̔F��������̗��R��������A�����Ȃ̃N���[���q�b�g�ł���V�O���K�����[���Ȃǂɂ��Đ�������B
�������ƊE�ւ̊O���K���͐��E�̏펯
�킪���ł́A�d�g�@������@�ɂ�������Ђ̊O���l���c����������5����1���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƒ�߂��Ă���(�\1)�B���������_�ɋy�ڂ��e�����l���������S�ۏ��̗��R����A�����Ǝ҂ɑ���O���K���́A�킪�������łȂ��A�A�����J���O���ł����B�ł��ގ��̐������݂����Ă���B
�����Ȃ́A2005�N4��14���ɏ��ʐM����ǂ��쐬�����u�����ǂɑ���O���K���ɂ��āv�̒��ŁA�����ƊE�ɊO���K�������闝�R�ɂ��āu�n������́A�����I���Y�ł�������̓d�g���g�p������̂ł���A���̗L�����������B�����A�����A�Љ�ɑ傫�ȉe���͂�L���錾�_�@�ւƂ��ďd�v�Ȗ�����S���B�ЊQ����͂��߂Ƃ��鍑�������ɕs���ȏ���B�v�Əq�ׂĂ���B
�������������_�ɗ^����e�����l����A�O���K�������邱�Ƃ͍����I���B
�������ƊE�ɂ�����O���l����䗦�̎���
�O���l���c�����䗦���A�S�Ă̋c������5����1���Ă����Ƃ́A���k�V�Ђ����ł͂Ȃ��B�\2�Ɏ����ʂ�A�{�e���M���_(2021�N3��12��)�ɂ����āA�t�W�E���f�B�A�E�z�[���f�B���O�X�Ɠ��{�e���r�z�[���f�B���O�X�̊O���l���c�����䗦�́A�S�c������5����1���Ă���B
�@�@�@�\2�@��������Ƃ̊O���l���傪��߂銄��
�����`�������ۂƂ���������
�Ȃ��A���k�V�Ђ͔F����������A�t�W�E���f�B�A�E�z�[���f�B���O�X�Ɠ��{�e���r�z�[���f�B���O�X�͕����Ƌ�������ɂȂ�Ȃ��̂��B
�d�g�@��5��4����A�O�́A�����ǂ̖Ƌ��̌��i���R�Ƃ��āA�O���l���̋c�����������S�Ă̋c������5����1���Ȃ����ƂƂ��Ă���B�܂��A�����@116���ł́A�O���l���̋c�����������A�S�c������5����1���A���i���R�ɊY�������ꍇ�́A���̎����y�яZ�������喼��ɋL�ڂ��A���͋L�^���邱�Ƃ����ނ��Ƃ��ł���Ƃ��Ă���(�ȉ��A�����ǂł͔���ɂ����̂Łu��������Ɓv�Ə���)�B�Ȃ��A�q���������n��g���O���l���̋c�����������A�S�c������5����1����ƌ��i���R�ɊY�����邱�Ƃ͓����ł���B
�t�W�E���f�B�A�E�z�[���f�B���O�X�Ɠ��{�e���r�z�[���f�B���O�X�́A2017�N9��25���t�̑����ȒʒB(�ʒB���͔̂���\)�Ɋ�Â��O���l���̏��L�����̂������喼��ւ̖��`���������ۂ��������ɌW��c�����𑍋c�������Z��̊�b���珜�O���ĊO���l���̋c�����������v�Z���Ă���B
���̌v�Z�̌��ʁA�O���l���̏��L�����̂������喼��ւ̖��`�������s��������(���ۂɊ��呍��ōs�g�����S�Ă̋c��������19.99��)�����ɋc������^���Ă���B�܂��A19.99�����������̊O���l������ɂ͊����̖��`�������ۂ��s���A�O�q�̕����@�y�ѓd�g�@�ɒ�߂錇�i���R��������Ă���(�ڂ��������͌�q����)�B
�Ƃ��낪�A���k�V�Ђ́A�W�v�~�X�ł��̊����̖��`�������ۏ������s��Ȃ������B�s�����Ȃ����k�V�Ђ̔F����ŏ��ɍs�����͕̂���29�N1���B�����A�O���䗦�̊�����Ă���Ɛ\���������A���ۂ�20.75���������Ƃ����B�����Ȃɑ��A���k�V�Ђ�1���ȏ��ۗL���銔��𑫂����킹�Đ\�������~�X���Ɛ������Ă���B�t(2021�N3��12���w�Y�o�V���x����)
���k�V�Ђ̖Ƌ��F�肪��������闝�R�͖��炩���B�O���l������̏W�v���ԈႦ�����ʁA19.99������O���l������֖��`�������ۂ����Ȃ������B���̌��ʁA���k�V�Ђ����i���R�ɊY�����邱�ƂɂȂ������炾�B���k�V�Ђ������Ȃ�ڑ҂������ƂƂ͖��W�ł��邱�Ƃ͖��炩���B�u�������̎q���͐ڑҗv���B�����Ȃ͊O���K���ᔽ��m��Ȃ���u�x���ĔF���������Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�ڑ҂��邱�ƂŔF����j�~��ژ_�v�Ƃ����ނ̋L���͑z���ɉ߂��Ȃ��B�^�}�ւ̈�ۈ�����ړI�Ƃ�����̂��B�@�ւ͔F�������̗��R�𐳊m�ɕ��A���̖��𐭋ǂɗ��p����悤�ȑԓx�͌��ɐT�ނׂ��ł͂Ȃ����B
�@�����Ƃł���킪���ł́A�@���Ɉᔽ����A�@�ɏ]���Ƌ������������B�����c���̎w�E�ɂ��A���k�V�Ђ̖@�I���r�����炩�ɂȂ������ʁA�@���ɏ]���āA�F�����������B���̎����́A����ȏ�ł�����ȉ��ł��Ȃ��B
���N���[���q�b�g�������u�����ȒʒB�v
���k�V�Ђ̔F�����������ŁA������Ђɑ���O���K�����[���Ɍ������������B�����ŁA�����Ȃ��O���K�����[���ŃN���[���q�b�g����������Ƃ��Љ��B
2017�N9��25���t�̑����ȒʒB(�ʒB���͔̂���\)�ɂ��A�O���l���̊���ɖ��`�������ۂ��s���Ƃ��ɐ����Ă����d��Ȗ��_���������ꂽ�B�M�҂������ȂɊm�F�����ʒB�̓��e�Ƃ́A�O���l���̏��L�����̂������喼��ւ̖��`���������ۂ�������S�c�������Z��̊�b���珜�O����悤�ɂ�����̂ł���B���̒ʒB�̎��Ӗ��́A�o�ψ��S�ۏ�̊ϓ_������傫���B�����Ȃ��A�O���K���̃��[�������P�������Ƃ�]���������B
2017�N9��25���̑����ȒʒB���o��O�́A�O���l�������Ƃ����呍��ōs�g���邱�Ƃ��ł���c�������́A�S�c��������19.99�������������̂Ƃ���Ă����B���̌��ʁA���呍��ōs�g�ł���O���l�������c�����̌����A�S�c��������5����1����ُ�ȏ�Ԃ������Ă����B
���呍��ōs�g�ł���O���l�������c�����̌����A�S�c��������5����1���闝�R���A���p���Đ�������B
�O���l�������Ƃ��S�c������1���̏�������Ƃ̋c������3000�L���Ă���Ƃ���B���`�������ۑO�̋c�����̏�Ԃ͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�B
�@�@�@�O���l������̎��c�������@3000��
�@�@�@���{�l����̎��c�������@7000��
�@�@�@�S�c�������@�@�@�@�@�@�@ 1����
���̏�Ԃ̂܂܂ł́A���̏�������Ƃ́A�O���l���̋c�����������S�Ă̋c������5����1����̂ŁA���i���R�ɊY�����邱�ƂɂȂ�B���̏�������Ƃ͖Ƌ��̌��i���R��������邽�߁A�O�q�̋K��ɏ]���A�O���l���̎��c�����̂���19.99���̂��̂ɋc������F�߁A�c���10.01���̊O���l���̎��c�����ɂ͊��喼��ւ̖��`���������ۂ���B���`�������ی�̋c�������͈ȉ��̒ʂ�ƂȂ�B
�@�@�@�O���l���̊���̎��c�������B1999��
�@�@�@�O���l���̊���̎��c�����̂������`�������ۂ��ꂽ���@1001��
�@�@�@���{�l����̎��c�������B7000��
�@�@�@�S�c�������@�@�@�@�@�@�@ 1����
���`�������ۂ��ꂽ�c����1001�̋c���������O���l���̊���ɂ́A��������Ƃ��犔�呍��ւ̏��W�ʒm�͔�������Ȃ��B����A�O���l�֊��p��������ɂ��A���呍��ւ̏��W�ʒm�͔�������Ȃ��B���̌��ʁA���̏�������Ƃ̊��呍��͈ȉ��̏�ԂŊJ�Â����B
�@�@�@�O���l������̎��c�������@1999�@(22.21��)
�@�@�@���{�l����̎��c�������@7000�@(77.79��)
�@�@�@���呍��őS���傪�s�g�\�ȋc�������̍��v�@8999�@(100.00��)
���̏�������Ƃ̊��呍��ł́A�O���l���s�g�\�ȋc�����������A22.21���Ƃ������ʂɂȂ�B�O���l�c�����������v�Z����ۂɁA�O���l�̎��c�����̂������`�������ۂ��ꂽ��1001���v�Z�̕���ɉ��������Ƃ��������B���Ȃ݂ɁA���̌v�Z���@�ł́A�O���l�����傪���c��������8002�ȏ�ɂȂ�ƁA�O���l���̊��傪�o�c�������邱�ƂɂȂ�B
�@�@�@�O���l������̎��c�������@1999��
�@�@�@�O���l������̎��c�����̂������`�������ۂ��ꂽ���@6003��
�@�@�@���{�l����̎��c�������@1998��
���̂悤�ɁA2017�N9��25���t�̑����ȒʒB�O�̊O���K�����[���ł́A��������Ƃ̊O���l����ۗ̕L�䗦�@���ł́A�O���l���ӎv��ʂ����Ƃ��\�Ƃ��Ă����B
|
|
�������ȐڑҖ������@�����u���������u�x�����v�@3/17
|
�s�����䂪�߂�ꂽ�����͂Ȃ������̂��B�����Ȋ�������@�Ȑڑ҂��Ă������ŁA��O�҈ψ���ɂ�錟���n�܂�܂����B
��@�Ȑڑ҂ɂ́A�ǂ�ȖړI���������̂��B�����Ȋ�����ւ̈�A�̐ڑ҂ɂ��Č����s����O�҈ψ��������J���܂����B
�������̋g�쌷�������́A�����Ȃł͂Ȃ���O�҂ō\�����ꂽ�����b�g�ɂ��Ă����b���܂����B
���ʐM�s�����؈ρE�g�쌷�������F�u���������A�ނ��u�x(����)�������A��������ƌ����ł��邱�Ƃ��傫�ȃ����b�g���Ǝv���Ă܂��v
����ȂȂ��A�ڑ҂����Ă������k�V�ЂƐڑ҂�����鑤�����������Ȃ��O���K���ᔽ�̕������č��A�^�����Η����Ă��܂��B
���k�V�Ђ�2017�N8���ɑ����Ȃɕ����Ɛ����B
���k�V�ЁE�����M��В��F�u(2017�N)8��9������ł������܂��B�ؓc�R�I�v(������)�������Ȃ̗�ؐM�瑍���ے�(����)�ɖʒk�����Ɓv
����A�����Ƃ����{�l�͍���17�����A�����ے肵�܂����B
�����ȑ����ʐM��ՋǁE��ؐM��d�g�����F�u�O���K���ɒ�G����\��������|�̕�������Г��k�V�Ђ���������Ɋւ���L���͂������܂���v
�����17���A�V���ȐH���Ⴂ�����炩�ɂȂ�܂����B
���k�V�ЁE�����M��В��F�u�䔦�ے����x�ɒ��ł��������߁A�Ή�������ؐM�瑍���ے�(����)�ɂ��`�������Ɓv
�����Ȃ̒S���ے����x�ɒ����������߁A�����̗�ؑ����ے��Ɩʉ���Ɛ������Ă��܂������B
�����ȁE���M�����[���F�u�䔦���̏o�Ε�A���ꂩ��{�l�ɂ��m�F���܂����Ƃ���A���k�V�Ђ������Ȃɑ��A�����ŕ����Ƃ����8��9������́A���k�V�Ђ̐����Ƃ͈قȂ�A7������11���܂ň䔦�͏o���Ă����Ɓv
���c������b�͑����ȂƓ��k�V�Ђ̐������H������Ă��邱�Ƃɂ��Ă���O�҈ψ���Ō�����Ƃ��Ă��܂��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����c��b�ɂ����₫�^�f�c�{�l�ے���f���Ɏc�鐺�� 3/18 |
��H���̉Q���ɂ��镐�c������b�ɂ����₫�^�f������ł��B�g�L�����Ȃ��h�Ƃ��������������č��A�g�䂪�L�����Ă��܂��B
�u�L�����Ȃ��ƌ����v�Ǝw�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����w�E��18�����A�u�w�������L���͂������܂���v�Ɣے肵�����c��b�B���ƂȂ����̂�16���́u�L���͂������܂���v�B
���k�V�Ђ̊O���K���ᔽ������c�_�œ��ق����߂�ꂽ�����Ȃ̗�ؓd�g���������ّ�֕����o�����Ƃ���ŁA�ǂ����炩�u�L�����Ȃ��v�Ƃ��������₫�����c�B
���̉����ɂ��āA��}���͕��c��b�̐����Ǝw�E�B���̗l�q�̓e���r�Ő���������A�c�C�b�^�[�ł��g�U����܂����B
���c��b�͔������ꕔ�A�F�߂������Łc�B
���c������b�F�u�ǂ��������������Ƃ����悤�Ȏw���������L���͑S���������܂���v
���̕��c��b��18���ANTT���V�c�В���JR���C�̊������_��Ƃ̉�H�ɂ��ē��Ȃ����ƔF�߂܂����B
�����A�����܂ŋ��F�Ɋւ���v�]��˗��͎Ă��炸�A��b�K�͂ɒ�G�����H�ł͂Ȃ������Ƃ��Ă��܂��B
|
|
�����c������b�u�L�����Ȃ��ƌ����v���َw���͔ے� 3/18 |
���c������b�͓��k�V�Ђ̊O���K���ᔽ�����鍑��R�c�ő����Ȃ̗�ؓd�g�����Ɂu�L�����Ȃ��ƌ����v�Ǝw�������̂ł͂Ȃ����Ƃ�����}�̎w�E�ɑ��A�u���ق��w������悤�ȈӐ}�͑S���Ȃ������v�Ɣے肵�܂����B
��������}�Ȃǂ̖�}��16���̏O�c�@�\�Z�ψ���ł̕��c��b�̔������莋���Ă��܂��B
���c������b�F�u�L�����Ȃ��Ɓc�v
18���̏O�c�@�����ψ���Ŗ�}���͑����Ȃ̗�ؓd�g���������ق����钼�O�ɕ��c��b�������|���A�u�L�����Ȃ��ƌ����v�Ǝw���������^��������Ǝw�E���܂����B
��������}�E�R�ԏO�@�c���F�u�w�L�����Ȃ��ƌ����x�ƌ����Ă���悤�ɂ��������鉹�����m�F�ł��܂����A���������w�������Ƃ����F���͂������܂��ł��傤���v
�����ȁE��ؓd�g�����F�u�ړ��̍ۂ̎��͂̐��Ȃǂ͑S���������g�̎��ɓ����Ă���܂���ł����v
��������}�E�R�ԏO�@�c���F�u��b�A�������������������ꂽ��ł��傤���v
���c������b�F�u(���^�̂Ȃ���)�w�L�����Ȃ��x���Ă������t�������ČJ��Ԃ��̂��Ƃ肪���������߂ɁA���̌��t�����̕�������ɏo���̂�������܂���B���ق��w������悤�ȈӐ}�͑S���������܂���v
���c��b�͔����������Ƃ͔F�߂܂������A���ق̎w���ɂ��Ă͔ے肵�܂����B
��}���́u�^�O���������悤�ȍs�ׂŋɂ߂Ė�肾�v�Ƒi���A���������Njy����l���ł��B
|
|
�����c������b�u��b�K�͂ɒ�G�����H�ł͂Ȃ��v 3/18 |
���c������b�͏T�����t����NTT���V�c�В���JR���C�̊������_���Ƃ̉�H�ɂ��āA���Ȃ������Ƃ�F�߂������Łu��b�K�͂ɒ�G�����H�ł͂Ȃ������v�Ƌ������܂����B
���c������b�F�u��H�ɓ��Ȃ������Ƃ͎����ł���܂��B�����܂�(JR���C��)�������_��Ǝ��ȊO�̏o�Ȏ҂͑����グ�Ă���܂���ł����B�o�Ȏ҂������̋��F���Ɋւ���v�]�E�˗��������Ƃ͂Ȃ��A��b�K�͂ɒ�G�����H�ł͂Ȃ������v
���̂����ŁA���c��b�́u�Z���Ԃ̏o�Ȃł������������݁A��p�Ƃ���1���~���x�������v�Ɛ������܂����B
���c��b�͂���܂ł̍���ق�NTT���Ɖ�H�����̂��ǂ����ɂ��ĒNjy���Ă��u�����̋^�O�������悤�ȉ�H�ɉ����邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ɩ���������A��}���������Ă��܂����B
|
|
�������� NTT�В���Ƃ̉�H�F�߂� �g��b�K�͂ɂ͒�G�Ȃ��h 3/18 |
���c������b��NTT���V�c�В���Ɖ�H���Ă����Ƃ���u�T�����t�v�̕ɂ��āA�O�c�@�����ψ���ʼn�H�̎�����F�߂������Łu����̋��F�ȂǂɊւ���v�]�������Ƃ͂Ȃ��A��b�K�͂ɒ�G�����H�ł͂Ȃ������v�Ƌ������܂����B
18�������́u�T�����t�v�́A���c������b�����N11���ANTT���V�c�В���JR���C�̊������_��Ɖ�H���Ă����ƕ܂����B
���c��b�́A�O�c�@�����ψ���Łu�������_��Ƃ̉�H�ɓ��Ȃ������Ƃ͎������B���������琺���������蓖���܂łق��̏o�Ȏ҂�m��Ȃ������B�ʂ̗\�肪���������߂����݂̂��������Ē������A��p�Ƃ���1���~���x�������v�Ɛ������܂����B
���̂����Łu�o�Ȏ҂������̋��F�ȂǂɊւ���v�]�A�˗��������Ƃ͂Ȃ��A��b�K�͂ɒ�G�����H�ł͂Ȃ������Ǝv���Ă���v�Ƌ������܂����B
�܂��u��H�����́ANTT��NTT�h�R���̊��S�q��Љ��Ɍ�����TOB�������̌��J�����t�����s���Ă����^�C�~���O�ł���A�����ɋ^�O����������H�������̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E���ꂽ�̂ɑ��A���c��b�́uNTT�h�R���̊��S�q��Љ��͖@�ߏ�A�����Ȃ̋��F���K�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ANTT���̌o�c���f�Ŏ��{���邱�Ƃ��\�Ȃ��̂��v�Əq�ׂ܂����B
NTT���V�c�В��炪���c������b�Ɖ�H���Ă����Ƃ���u�T�����t�v�̕ɂ��āA��H�̎�����F�߂������ŁA�u��H�͖��Ԃ̕����F���Ɋ֘A����c�_�̂��߂Ɋ�悳�ꂽ�Ə��m���Ă���B���c��b�����Ȃ��Ă������ANTT�����畐�c��b���ĂƂ��������͂Ȃ��A��H�̏��NTT������Ɩ���̗v���������������Ȃ��v�ƃR�����g���Ă��܂��B
���c���[�������͋L�҉�Łu�����Ƃ����������̈�Ƃ��āA�L����Ƃ̕��X�ƈӌ��������s�����Ƃ͂��肤��Ə��m���Ă���A��b�K�͂̎�|�܂��A�K�ɔ��f���邱�Ƃ���{���B���c������b�́A����܂ł������Ɋ�Â������ɓ��ق���w���U���ق��������Ƃ͂Ȃ��x�Ɠ��ق���Ă���Ə��m���Ă���B���������A�����̊F�l����^�O���������Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��Ă������Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ܂����B
����A�L�Ғc���ڑ҂Ɖ�H�̈Ⴂ�����₵���̂ɑ��u�ڑ҂Ɖ�H�̈Ⴂ���@���I�ɖ�������Ă��邩�͑����Ȃ����A�L�����ɂ͐ڑ҂Ƃ́w�q�����ĂȂ����Ɓx�A��H�Ƃ́w�W�܂��Ĉ��H���邱�Ɓx�ƋL�ڂ���Ă���Ƃ������Ƃ��v�Əq�ׂ܂����B
��������}�̐�������́A�L�҉�Łu�ǂ��łǂ�Șb���A�ǂꂮ�炢�̎��Ԃ������Ă����̂��ɂ��Ė��m�Ȑ������K�v�ŁA��������Ȃ����獑���ɋ^�O��������B�����ɋ^�O��������悤�ȉ�H�����Ă��Ȃ����ǂ����͖{�l�����߂���̂ł͂Ȃ��A�q�ϓI�ɐ�������悤�A���߂ċ��߂Ă��������v�Əq�ׂ܂����B
���Y�}�̎u�ʈψ����́A�L�҉�Łu�T�����ɏ����ꂽ���H�̎��������Ԃ��ԔF�߂�Ƃ�����������̂������̋^�O��ł���B�Ȃ��ŏ����猾��Ȃ��̂��B�����Ȃ̖��𐳂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����c������b���A�����̋^�O������悤�ȑΉ������Ă���A�܂��܂����Ԃ͐[�����v�Əq�ׂ܂����B�@ |
|
�������ȐڑҖ��Ō��؈ς�����@��Ƃ̎v�f�A�s���e���� �@3/18 |
�����Ȋ������m�s�s�ƕ������Ɖ�Ёu���k�V�Ёv����ڑ҂��Ă������ŁA�����Ȃ�17���A��A�̐ڑ҂��s�����䂪�߂����ǂ�����_�������O�҂ɂ��u���ʐM�s�����؈ψ���v�̏�����J�Â����B���؈ς̍����Ō������̋g�쌷���ٌ�m�́u�ڑ҂����鑤�͔�p���S����̂Ŏv�f������v�Ƃ�����ŁA���ꂪ�s���ɗ^�����e���ׂ�l�����������B�����O���̊֗^���܂߁A�L�����Ă���^�O�@���邽�߁A�����W��O�ꌟ����B
���؈ς͋g�쎁�̂ق��A���������s���w�̐��ƁA��ƌo�c�҂̌v4�l�ō\������B�ʐM����ɏڂ����L���҂̒lj����������Ă���B����ł́A���c�Ǒ����������u�����̋^�O���������ԂƂȂ�A�[������ѐ\���グ��B���m�ɓO��I�Ɍ���i�߂Ă������������v�Ƃ����������B
��̓v���C�o�V�[�ی�Ɠ������̊m�ۂ��l�����A��������J�����A�c���v�|��������\����B�����O����A���E�����R�c�^�M�q�O���t�L��J�e�N�F�O�����R�c�����܂ޑސE�҂Ɋւ��钮�������s���B�ڑ҂̑S�e�͖��𖾂ȕ����������A�����܂Ƃ߂鎞��������Ƃ����B�ŏI�ɂ͍Ĕ��h�~�Ɍ����������荞�ށB
��A�̖��ł́A���k�V�Ђ̐ڑ҂ɐ��`�̎̒��j�̐��������Q���B���k�V�Ђ͉q�������̔F��ŕ����@�̊O���K���ᔽ�����߂����ꂽ�ق��A�m�s�s�͌g�ѓd�b�̗�������������m�s�s�h�R���̊��S�q��Љ��̑O��ɐڑ҂��s���Ă���B
�������E�ʐM�s���@/�@�����Ȃ͂m�g�j�▯���Ȃǂ̕����ƊE��A������Ȃǂ̒ʐM��g�ѓd�b�Ƃ��������Ƃ����ǂ��A����⎖�Ƃ̋��F�̌��������B�����ǂ͕�ԑg��ʂ��Đ�����Љ�ɑ傫�ȉe���͂������߁A�O�����{�̏o���䗦��20�������łȂ���Ȃ�Ȃ��ƕ����@�Œ�߂Ă���B�m�s�s�͖��c���O�̉���ԂȂnj������Y�������p���ł��邱�Ƃ���A����������3����1�ȏ��ۗL���A�����̑I�C�⎖�ƌv��̍���Ȃǂɂ͑����Ȃ̔F���K�v�Ƃm�s�s�@�Œ�߂Ă���B
|
 |


 �@
�@ |
|
���uNTT�������ȁE�����O���Ƃ���H�v���t 3/19 |
���T�A�T�����t��NTT�����Ƒ����ȁE�����O���Ƃ���H���Ă����ƕ��B��c���q���������A���s���c���������A���w������b�A����ɂ�NTT�h�R���o�g�̏��юj�����������̖��O���������B
��T�̒J�e�N�F�����R�c������̐����O���Ƃ������ƂŁA���T�̕��t�C�͂���ɋ����ׂ��l���^�[�Q�b�g�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă���B
���k�V�Ђɂ�鑍���Ȃւ̐ڑҕł́A�T�����t�̋L�҂����H�X�ɐ������A��b��^���B����ɋA��ۂɐ������̒��j�������Ȋ����Ƀ^�N�V�[�`�P�b�g��n���V�[�����B�e����Ă���B
�����炭�A�����Ȋ����Ɠ��k�V�Ђ���H����Ƃ�����A���O�ɏT�����t�ҏW���Ƀ��[�N����A�L�҂����荞�݂������̂ł͂Ȃ����B
����ANTT�ɂ���H������ƁA�T�����t�ҏW�������荞�݂����Ă���L���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B����������Ƀ��|�[�g�������e�����A���ۂ̓��j���[����z�Ȃǂ̗���ƂȂ��Ă���BNTT�����Ƒ����ȊW�҂Ȃ�тɐ����O���Ƃ̉�H�ɂ��āA�N���u�m�b�N�X���z�ł̘b�����o�Ă��Ȃ��ƍl����ƁA�����炭�ANTT�}�o�قƂ����Ă���N���u�m�b�N�X���z�̑䒠���T�����t�ҏW���Ɏ������܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����B
�V�c���В��ɂ���āANTT�h�R����NTT�̊��S�q��Љ��ƂȂ����B���̓�����ʔ����Ȃ��Ɗ������A����l�����N���u�m�b�N�X���z�̊W�҂���䒠����肵���\�������������B�N���u�m�b�N�X���z�͊�����Ѓm�b�N�X�g�D�G���e�B�������^�c���Ă��邪�A���̉�Ђ�NTT�s�s�J���̃O���[�v��Ђł���B���Ƃ��ƁA�d�d���Ђɓ��Ђ����l�������ANTT��NTT�h�R���ANTT�s�s�J���ɎU����Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�䒠�̂悤�Ȃ��̂��W�҂̊Ԃł��Ƃ肳���͕̂s���R�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B
����A�C�ɂȂ�̂�NTT�̌o�c�̐����B
���k�V�Ђ̎В��͂�������Ǝ��C�ɒǂ����܂ꂽ�B�V�c���В��́A15���ɎQ�@�\�Z�ψ���̏W���R�c�A16���ɂ��O�c�@�ŎQ�l�l���v�����B�J�e�����R�c���݂̂Ȃ炸�A�����O������������ł̐ڑҖ��ƌ������ƂŁANTT�̎В��𑱂����邩�͂��Ȃ茵������ƌ����邾�낤�B
�V�c�В���IOWN�\�z���f���ANTT�O���[�v��GAFA�ɑR�ł���悤�A���ۋ����͂����߂悤�Ɛs�͂��Ă����͂����B�����炱���ANTT�h�R����4���~�������Ċ��S�q��Љ������̂ł͂Ȃ����B
�������V�c�В���NTT�O���[�v�̐w���w��������Ȃ��Ȃ�Ƃ���A��C�͒N�ɂȂ�Ƃ����̂��B
NTT�O���[�v�̍��ۋ����͂���������ǂ��납�A�V�c�В��������邱�Ƃ�NTT�O���[�v�̂����鋁�S�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B
�����Ȃł����������r����Ȃ��A�u���{�̒ʐM�ƊE�ɂ����関���Ɍ������r�W�����v��`���l���N�����Ȃ��Ȃ�Ƃ������낵�����ԂɊׂ肻�����B
|
|
�������Ȑڑ҂��A����ɂȂ�Ȃ����R 3/19 |
���L���葱���鑍���ȐڑҖ��̔g�� �呠�Ȑڑ҉��E�����Ə͂ǂ��Ⴄ��
���A�����͎g���̂Ă̎���ł��B�R�c�^�M�q���t�L�ɑ����āA�����Ȃ̎�������������₾�����G���[�g���̃G���[�g�A�J�e�N�F�O�����R�c�������C���܂����B���t�C�ő_���������ꂽNTT�Ƃ̐ڑҖ��ŁA�u�����ɖ��f�������A�s���ɑ���M�p�����Ă������v���Ƃ����C�̗��R�ł��B
���ꂩ�����A�����ȐڑҖ����߂��鑛���͑����Ǝv���܂��B�w�^������ƕ��c�Ǒ�������b�̎��C�܂ł�����������܂��A���̏ꍇ�������܂ň�g��̗��R�ł����āA�ڍׂ͐�������Ȃ��܂܁A���̖��͖������ł��傤�B
�����̐ڑҖ��Ƃ����A1990�N��ɑ���ƂȂ����呠�Ȃ̐ڑ҉��E�������v�������т܂��B�o�u�������ɐςݏオ����100���~�K�͂̋�s�̕s�Ǎ����B���A�ŏI�I�ɍ����̐ŋ��𒍓����Ă������������w�i�ɁA��s���呠�ȋ�s�NJ������m�[�p������Ԃ���ԂȂǂŐڑ҂��u���肢�v�����Ă������Ƃ��������A�����̓{�肪���_�ɒB���܂����B�ŏI�I�ɂ��̎����́A�`������呠�Ȃ̖��O�������邱�ƂŖ������ƂȂ�܂��B
�J�e���قǂ̎��͎҂��A�����Ŋ����Ƃ��ẴL�����A���I���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ǝ��̂́A�����ȂɂƂ��Ď��ɏd���������ŁA���ꂾ���d�厖���ł���Ƃ����F���͂���킯�ł��B����ō�������Ƃ��ẮA���̎��������ĂقǑ傫�Ȗ��ɂȂ��Ă��Ȃ��悤�Ɍ����闝�R�͉��Ȃ̂ł��傤���B
���̈Ⴂ�́A����̑����ȐڑҖ��ɂ́A90�N��̑呠�ȐڑҎ����Ɣ�ׁA�����ɂƂ��đ傫�ȕs���v���Ȃ����Ƃł��B
��萳�m�Ɍ����A�����ɑ��鍑������ɂ�2��ނ����āA1�́u���ł��낤�ƕs���͋����Ȃ��v�Ƃ������`�̊���ƁA����1�́u�����ƂȂ��瑽���̕s���͂���̂��낤���A����ł��������₵�č������]���ɂ��邱�Ƃ͋����Ȃ��Ɓv�������Q�ɂ�����銴��ł��B
�����Ƃ������l������ڂɂ����킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���܂��܂Ȑ��_������w�i�ɑ����Ă݂�ƁA�O�҂́u��ΐ��`�h�v�͂ǂ��炩�Ƃ����Ə����h�ł��B�R���i�Ђ̃}�X�N���ł��c�_�ɂȂ�܂������A�}�X�N�x�@�̂悤�Ȋ����Ƃ͍����S�̂ł��������܂ŏ����h�B�u�����������`�����邾�낤���ǁA���܂萳�`��U�肩�����߂���̂͂ǂ����낤�v�ƍl����l�̕����A���ۂɂ͑����h�ł��B
����ŁA�����̖{���͗��Q�����ɂ���܂��B�����̖ړI��B�����邽�߂ɁA�N���ɉ䖝�������邱�Ƃ������̖{���ł��B���H�邽�߂ɏZ���ɗ����ނ������肢����Ƃ��A�����������炷���߂ɓ���̉��w�i�̐�����g�p���֎~����悤���[�J�[�ɓ`����Ƃ��A���@���s�����ǂ�����A�u�ő命���̍ő�K���v�̂��߂̗��Q�������d���Ƃ��܂��B
�������A�����u�ő�K���̂��߂ɂ͎d���Ȃ��v�Ǝv���ė����ނ���������ꂽ���̍������A���H�����݂��邱�Ƃňꕔ�̐����Ƃ⊯�����������₵�Ă����ƒm������A����͍����̓{�肪�������錴���ɂȂ�܂��B�����������s���ɑ��ċ����{��������鍑���́A�����h�Ȃ̂ł��B
�������ȐڑҖ��͍����̗��v�˂Ă͂��Ȃ�
���̊ϓ_�Ŏ����𑨂���ƁA����̑����ȐڑҎ����͗��Q�̍\�}�Ō���ƍ����ɂƂ��ĕs���v���������悤�ɂ͎v���Ȃ��B�����܂ō����������Ă���̂́A�X�}�z�̗����̍����ɖ������������̑�����b���A�����Ȃ̊����Ɏw�����o���āA�ʐM�e�ЂɃX�}�z�̊�{������l����������悤�Ɉ��͂����������Ƃƍ���̎����ɂ́A���炩�̊W������̂��낤�Ƃ����א��ł��B
�^���͂��Ԃ�𖾂���Ȃ��Ǝv���܂����A�����𖾂��ꂽ�Ƃ�����A�s���v�������͎̂��v�������邱�ƂɂȂ�����Ƃ̑��ł����āA�����̑命���͓������邱�ƂɂȂ�͂��ł��B
���Ȃ݂ɁA���̍\�}�����Ă͂܂�Ɖ��肵���ꍇ�A�u�Ȃ����肢�����鑤�̑����Ȃ��ڑ҂���Ă���̂��H�v�Ƌ^����������ǎ҂����������邩������܂���B���͂���A�u�����ڑ҂��邠��v�ŁA���ō����ȗ���������邻�̏\�����~�̐H����~�����ɁA�o��������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B�{���́A�����Ƒ傫�Ȑ��牭�~�̗��Q�������āA�삯�������s���Ă���B�o���ɂƂ��Đڑ҂͂����܂Ō��̕K�v�o��Ƃ����̂����Ԃł���A��X��ʐl�ɂƂ��Ắu�ڑ҂���E�����v�Ƃ������o�Ƃ́A�قȂ鎟���̘b�Ȃ̂ł��B
����ŁA��������Ƃ��ĉ��サ�₷���̂́A����̌l���ł��B����̓��J�j�Y���Ƃ��Ă�SNS�̉���Ƃ悭���Ă��܂��B���̊ϓ_�ł́A�s�ϖ��̓n���������ʼnc�Ɩ��̋{�����V����Ɠ����ŁA���̒��j�����ڑ҂̕����ANTT�����Љ���Ƃ��ăo�Y�������Ƃ͎����ł��傤�B
�������Ƃ̋�Ƃ��Ċ�������̂Ă���Ƃ����u�^�̖��_�v
���āA���̎������Ȃ����Ă̑呠�ȐڑҎ����̂悤�ȑ���ɂȂ�Ȃ��̂��Ƃ������J�j�Y���̘b�́A�����܂Ő��������ʂ肾�Ƃ��āA����̑������Ӗ�����ʂ̖��_�ɂ��Ęb�����܂��傤�B
�O�q�̂悤�ɁA�u�R���v���C�A���X�d���h�v�ɂƂ��ẮA�������W�����Ƃ���ڑ҂����ɂ�������炸�A���̎������B���Ă����Ƃ������Ƃ����ł��B����Łu���v�d���h�v�ɂƂ��ẮA���̎����͈ꌩ���āA�����̗��v�Ȃ��Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��B�����瑽���̍����́A�傫�Ȗ��Ɋ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���������̎����A���͑傫�������̗��v�Ȃ��Ă��镔��������܂��B���ꂪ�`���ŏq�ׂ��u�����̐�̂Ė��v�ł��B��}�͘A������Ŗ���Njy���A�^�}�͂����K���ł��킷�B���̍U�h������邽�߂́u��v�Ƃ��āA�������g����悤�ɂȂ�n�߂��B�������������̌��Ў��Ă���ԗ������Ă���͎̂�҂ł��B
2019�N�̃j���[�X�ł����A���̔N���߂ē�����w�̓����ŁA�����̊����ւ̓o����ł��镶��I�ނ̍��i�҂̍ō��_�ƕ��ϓ_���A�x���`���[�N�ƉƂւ̓o����ł��镶��II�ނ̂���������܂����B
����܂ŁA���т̂�����҂��@�w�����o�Ċ�����ڎw���A�����܂Ő��т��悭�Ȃ��҂��o�ϊw�����o�Ė��Ԃ�ڎw���Ƃ����̂��A���70�N�ԁA���啶�n�ɂ�����펯�ƂȂ��Ă��܂����B�Ƃ��낪���A�܂��ɖ{���ɗD�G�Ȑl�ނ͖��Ԃ�I�юn�߂Ă���̂ł��B����������A�����ɂȂ邽�߂̃n�[�h�����������Ă���B���̂����\���Z�̍L�����A�u�Ȃ�Ŏ��������Ȃ�!?�v�ւƕς�邩������܂���B
�������ւ�ڎw���Ȃ��G���[�g�w���@�m���������u�����̗v
���̖��̖{���́A�����ߒ��w���{�o�ϗ\���̏��x�ŏڏq�����Ƃ���A����}�����̎���Ɋ��@�������̐l����������A���̌�̎����}���������̌��͂�֗��Ɏg���Ă���Ƃ������Ƃł��B������^�}����}���A��������ɖ߂��Ƃ͌����o���Ȃ��B����������́A���{�����ɂƂ��Ắu2060�N���v�Ƃ����܂��B���܂���40�N��ɂ�������{�̊����̗��A�m���ɗ\���ł���̂ł��B
�����Ď��������I����c�����d������̂́A2060�N�̖����̓��{�ł͂Ȃ��A2021�N�̑��I���ł��邩�̂悤�Ɍ����܂��B���ۂɍ���p�͂܂�Ȃ����A��҂͂�������Ȃ���YouTube�Ŏ��Ԃ��Ԃ��A�����ւ�I���ɘZ�{��ڎw���Ă��܂��B
�s���ɑ���M�p�����Ă������Ƃ������R�ŒJ�e�������E��������̎����A���͓��{�̖����ɂƂ��āA�ƂĂ������[������Ȃ̂�������܂���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�������̌�����
|
|
��1�@�{����b���܂�
|
���̐E�Ƃ́A�^���������̍��ƌ������ł��B����㈵�펎���ɍ��i���č̗p���ꂽ�A������L�����A�����ł��B�{���͎��ȏЉ��Ƃ��ɂ́u�L�����A�����ł��v�ȂǂƂ͂����܂��A���̃R�����ł͊����Ă��̂悤�ɂ����Ē����܂����B�Ȃ��Ȃ�A����͎������̃R�������������Ǝv�������R�ƒ������邩��ł��B
����́A�����ł������̕��Ɋ����̎��Ԃ�v����m���ė~��������ł��B�����Ƃ����E�Ƃ̃C���[�W�́A�c�O�Ȃ���D�ӓI�Ȃ��̂���������܂���B�e���r�ł̓��_�ԑg�A�V���ł̔ᔻ�L���A�����ƂƊ����̑Η��𝈝�����G���L���B�w�G���[���o���N�x�ł��A�}�X�R�~�Ƃ̓�ꍇ���̒��ŁA���������ɓs���̈����Ƃ���͉B���ă��[������������(���邪����)���z�Ƃ��Ċ����͕`����Ă��܂��B
�������A�����ᔻ�̈ꕔ�͐������Ǝ����v���܂��B�l�X�ȎЉ���ւ̑Ή���摗�肵����A�����̕s�ˎ���V����ɑ��ẮA�ꍑ���Ƃ��ĕ���������܂��B�������A���ɂ́A�����ᔻ�Ƃ��Ă͑S���̌����������A�A�d�_�I�ł��܂�ɂ������Ƃ�������Ă�����̂����Ȃ�����܂���B�u�ǂ�����Č����𑝂₵�ēV����������ċ��ׂ������悤���v�A����Ȃ��Ƃ���l���Ďd�������Ă���l������Ȃɂ�����̂ł��傤���B�����������ׂ����ړI�Ȃ�A�������ɂȂ���������Ȋ�ƂɏA�E���������قǍ����I�ł��B
���́A�������ᔻ���ꑱ���闝�R�́A���������_���Ȃ�����ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����}�▯��}���ᔻ�����A�c���̓e���r�̓��_�ԑg�ɂłĔ��_���܂��B�������A�����͂����������܂���B�����Ƃ́A���������߂̓����̍��q�ł���A�ӎv�������Ă��Ȃ��Ƃ����O��̂��߁A�ǂꂾ�����s�s�Ȕᔻ���Ă��Ă��A��Ɩ��O���o���Ĕ��_���邱�Ƃ͂��܂���B�����āA���_���Ȃ��͔̂��_�ł��Ȃ�����Ǝ~�߂��A�����̂����łȂ��o�����܂ł����ׂĊ����̂����̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȕᔻ�́A�����ɂȂ낤�Ƃ�����҂����炵�Ă��܂��A���{�Ƃ��������キ���邾���ł��B�������ᔻ�́A���̖����̂��߂ɂȂ�܂����A�������X�P�[�v�S�[�g�ɂ����ᔻ�͓��{�������ւƊׂ�܂��B
���s�s�Ȕᔻ�ł����Ă����_����A�}�X�R�~�ɖʔ����������������B��������A�䖝���č������Y���̂�҂A�Ƃ����̂����܂ł̊����̂����ł����B�������A����ł́A�����ւ̕s�M���∫���C���[�W�͕��@����Ȃ����肩�A�܂��܂��傫���Ȃ�܂��B�����ɑ��鐳�����ᔻ�̂��߂ɂ��A�����̎��ԂƖ{���𖾂炩�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���́A���[�j���O�ҏW���ɘA�����Ƃ�A�Ȃ�Ƃ������Ƃ��Ă̌��������ڂ��Ă��炦�Ȃ����Ƃ��肢���āA���̊�悪�������܂����B�������ǂ�Ȃ��Ƃ��l���Ďd�������Ă���̂��H�����̈����Ƃ���͂ǂ����H�@�����āA�����Ƃ���͂ǂ����H�@�ǂ̂悤�ɂ���A��������M�����������Ŋ��͂��鐭�{�ɉ��v�ł��邩�H�@���́A���̃R�����Ŏ��̎v���𐳒��ɓ`�������Ǝv���܂��B
�{���Ȃ�A���̖��O�A������Ȓ��A�N��ȂǂȂǂ����\���āA���X�Ƙ_�������Ƃ���Ȃ̂ł����A��������ƕ��i�̎d�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B���Ɂu�E�����v�ƌ����Ă��钆�ŁA���{��ᔻ����悤�Ȃ��Ƃ͏����܂���B�ł�����A�����̂܂܂ł��邱�Ƃ��������������B
���āA�������������Ƃ͂Ȃ�ł��傤���H�@���́A�������x���̂ɂ͗ǂ����������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B���Ƃ�����Ƃ��A�����ɂ͕K�����������܂��B����Ɛ��x�ɂ���āA�Ăі����Ⴄ���Ƃ͂���܂����A���j��A�S�Ă̍��Ɋ����͂��܂����B���Ƃ��A���������āA���ׂĂ̌����������Ă����Ƃ��Ă��A���������߂̎�����Ƃ͊������S���Ă��܂����B�����č��Ƃ��ߑォ�猻��ɂȂ�ɂ�A�o�ϖ�������ȂǍ������g�ނׂ��ۑ�͑傫���Ȃ�A�����ɐ��I�ɂȂ��Ă��܂��B�����Ƃ́A����ɋ��߂���ۑ���������邽�߁A�����^�c���邽�߂̎������(�s��)���s���G�L�X�p�[�g�Ȃ̂ł��B
������Ƃ́A�\�͂�����l�������������I���Ǝv���܂��B���{�̃��[�_�[�ł��鐭���Ƃ͍����̑�\�Ƃ��Ė����`�I�ɑI���ׂ��ł����A���̎葫�ƂȂ銯���͔\�͂Ɋ�Â��đI���ׂ��ł��B�\�͂�����l���W�߂邽�߂ɂ́A��������肪���̂���d����^���邱�Ƃ��{���ł����A������x�̋��^���K�v�ł��B�����̋��^���Ȃɂ��Ɩ��ɂȂ�܂����A���̔N���͏��蓖�E�c�Ƒ�ȂNJ܂߂Ċz�ʂ�600���~�ł��B����𑽂��Ǝv�����A���Ȃ��Ǝv�����́A�l�ɂ���Ă��ꂼ��ł��傤�B
�������A���M�ߏ�Ɏv���邱�Ƃ��o��Ō����������Ƃ������܂��B�������Ԋ�Ƃɍs���Ă���A���Ȃ�̊m���ł����Ƃ��������œ������Ǝv���܂��B���Z�A���ЁA�}�X�R�~�ɂ�������w����̗F�l�̋����͂��łɎ��̌��ɓ˓����Ă���悤�ł��B����Ȋw������̗F�l�����ƁA�v���Ԃ�ɉ�������ɁA���X�̐����̘b������ƁA�����̉�����ɎS�߂Ȏv��������A�����̋��^��������߂���̂ł͂Ȃ����Ƃ����s�����ǂ����Ă������Ă��܂��܂��B���w������ł����Ă�����������A���K�I���͂Ɏ䂩��āA�O���ɓ]�E���铯�������Ȃ��킯�ł͂���܂���(������w��p�̏��ҋ`���������܂�)�B�������w���������ɊO���n��Ƃ���U���܂����B����ǂ��A���͊����̎d�������߂悤�Ǝv�������Ƃ͂���܂���B
�Ȃ��Ȃ�A�d�����y��������ł��B�u���̂��߂ɂȂ�v�d���ɂ�肪���������邩��ł��B��x�����Ȃ��l���������Ďd��������킯�ł�����A�s��ȃX�P�[���ňӋ`�������镑��Ŋ������B�����Ƃ��Ĕᔻ����邱�Ƃ����m�ʼn����ւɔ�э��ގ�҂́A�����ĊO������̗U�f�ɂ������Ȃ��E���́A���������u������Ă��܂��B
�������A������Ƃ����āA�u������̂Ȃ�����ƈ��������ׂ����A�ƌ����邱�Ƃɂ͕�����o���܂��B�����̎d���͍��ƂɂƂ��ďd�v�ł��B�����낤�A�����낤�ł͌��Ǎ������������܂��B�ނ���A��d�̐��_���������l�Ԃ����Ȏ����̂��߂ɂ��̂ł͂Ȃ��A�D�G�Ȑl�Ԃ��W�߂Ă������萬�ʂ��o������A�����Đ��ʂɉ����Ė��Ԃ̃g�b�v�N���X�ɂ��������Ƃ�Ȃ���V���B���������x�̂�����͂��ꂭ�炢���{�I�ɕς���K�v������܂��B
�}�X�R�~��F����̔ᔻ�̑唼�́A�V����Ɍ������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ł��鎄���݂Ȃ���Ɠ���������������l�Ԃł��B������V�Ɍ��������Љ�v�������Ă��Ȃ��l�����ɂ͕���������܂��B���́A30�N��ɑ�������炦�邩������Ȃ��A�Ƃ����Ă��A�撣��C�ȂNjN���܂���B�撣��̂́A�d���ɂ�肪�������邩��ł��B�V������l�����ă��[����g��ł��܂����N�z�̊����͍���ł��傤���A�����܂߂������̎�芯���́A���������ւ̓I�O��Ȕᔻ���Ȃ��Ȃ��Ă��̕��������Ǝv������X�Ƒł��o������������Ȃ�A�������ƓV���肪�p�~���������Ǝv���Ă��܂��B
���̂���4��ɂ킽���āA�������x�̕�������_���A�����̎��_����������܂��B
|
|
��2�@���������ăT�����[�}����
|
�u�����Ɣ�ׂĎ������o���ł���̂��C�ɂȂ�v
�u�[�����ĂȂ��Ă���i�ɂ͏]���v
�T�����[�}���Ȃ�悭���邱�Ƃ��Ǝv���܂��B�����ł��鎄�ɂ��悭���邱�Ƃł��B�����Ƃ����ΐ��Ȍ��͂����G���[�g��z�����邩������܂��A���Ԃ̃T�����[�}���Ƃ����܂ňႢ�͂���܂���B�����͂����ƓD�L���Ēn���Ȏd���ł��B
�����̏o���Ȃnjڂ݂��A��i����Ƃɔ��R���Ăł����{�̂��߂��v���čs������̂����z��������܂��A�Ƒ�������Ζ����̐���������܂��B�����[�̂��� �ɂ��Ă��ƁA���J�ƂȂ��Č��lj����ł��܂���B
�����ɂ��Ă̕�ᔻ�́A�ǂ�������������������ȑ��݂Ƃ��ĕ`���܂��B�����������l���Ă���̂�������Ȃ�����A��l���������C���[�W�ɂ�銯���ᔻ���o�Ă���̂ł��傤�B�����Ƃ��}�X�R�~���A�N�������҂ɂ���Ƙb��������₷���Ȃ邤���ɁA�����҂Ⓤ�[�҂̎x�����邽�߁A�����o�b�V���O�ɏ�������Ă��܂��B
�����������l���Ă���̂��H�@�����̎v�l��H�́A���͐��Ԉ�ʂ̃T�����[�}���ƂقƂ�Ǔ����ł��B���̎��Ԃ�����͓`���܂��B
���Ȃ��Ȃ̗��v��D�悷��̂�
�������������Ƃ͒N���w���̂ł��傤�H�@���͖��m�Ȓ�`�͂Ȃ��̂ł��I�@��ʓI�ɂ́A���ƇT�펎���ɍ��i���Ē����Ȓ��ɍ̗p���ꂽ�������̌������A������L�����A���w���Ă��܂��B�����Ȓ��ɂ́A�L�����A���������ł͂Ȃ��A�呲�ŇU�펎���ɍ��i���č̗p�����E����A�����ŇV�펎���ɍ��i���č̗p�����E�������܂��B����ɁA�����ւ̒����Ȓ��ɂ́A�n���o��@�ւ���̏o���҂��������܂��B���������L�����A�����ȊO�̌������̓m���L�����A�ƌĂ�Ă��܂��B��Ђł̎d���ɗႦ��ƁA�L�����A�������E�ŁA�m���L�����A��������E���邢�͈�ʐE�Ƃ��������ɂȂ�܂��B�Ȓ��œ����Ă���l�́A�݂�Ȋ������Ǝv���Ă�����������܂��A���ۂɂ́A�����̃L�����A�Ƒ����̃m���L�����A�������Ă��܂��B
�L�����A�́A�{�Ȃ̊������Ƃ��Ă̗̍p�ł��B�������A�������Ƃ����Ă��A�R�s�[�Ƃ肩��d���͎n�܂�A�ے��ɂȂ�̂�40�㔼�Έȍ~�ł��B���Ԃ��z������悤�ȃX�s�[�h�o���Ȃǂ���܂���B
���Ԃł��q��Ђ�����������Ƃɓ��Ђ���ƁA�����I�Ɏq��Ђ̖����ɂȂ�\���������Ȃ�܂��B���Ƃɑ����E�œ��Ђ���Ƃ��ɁA���̃O���[�v��Ђ̊������ɂȂ��Ă���Ƃ����F�������l�͏��Ȃ���������܂��A�����I�ɂ͓����悤�Ȃ��̂ł��B���ہA���̑�w�̓������̑����́A���ƂɏA�E���Ă��܂����A�ނ�Ǝ������̎v�l�@�⓹���ςɂ���Ȃɑ傫�ȍ��͂���܂���B�������Ƃ������t�̋����̂��߂ɁA���Ԃ�m��Ȃ����Ԃ̕��̒��ŁA�Ⴍ���đ傫�Ȍ����������Ă��邩�̂悤�Ȍ�������܂�Ă���悤�Ɏv���܂��B
������������莞�ɂ͋A���Ă��Ďd�����y���A�ƍl���Ă������������������܂���B�������A����������Ǝs�����̑����œ����������̃C���[�W���������Ă��܂��Ă��܂��B�����́A������[��܂œ������Ƃ������A����̐R�c���͉ƂɋA��Ȃ����Ƃ��悭����܂��B
���v�̂��߂Ɋ撣��Ƃ����Ȃ���A�����̏Ȃ̗��v�̑�َ҂ɂȂ銯���������ł͂Ȃ���?�Ƃ������_�������������ł��傤�B�c�O�Ȃ���A���̔��_�́A�������Ǝ��͎v���܂��B�Ȓ��Ԃ̐l���ٓ��́A�o���͂悭����܂����]�Ђ͂قƂ�ǂ���܂���B�܂�A����Ȓ��ɓ��Ȃ��邱�Ƃ́A�����ЂɏA�E����̂Ɠ����ł��B�����̏Ȓ��̗��v���l���邱�Ƃ́A�����̉�Ђ̗��v���l����悤�Ȃ��̂ł��B��Ј����A�����̉�Ђ̗��v�ɂȂ邯�ǁA���{�S�̂̂��߂ɂȂ�Ȃ������߂Ă������Ƃ͍l���Ȃ��̂Ɠ����悤�Ȏv�l��H�ŁA�����������̏Ȃ̗��v�̂��߂ɍs�����܂��B���Ђ̂ق����A��������Ђ����Љ�I�C���p�N�g�̂���d�����ł��܂��B���l�ɁA�傫���Ȃ̂ق����A�Љ�I�C���p�N�g�̂��鐭����s���邽�߁A�����͎����̏Ȃ��傫���Ȃ邱�Ƃ�]�݂܂��B�t�ɁA�����̏Ȃ̐��ނ́A�����̃L�����A�̒����Ɠ������̂ł��B�ł�����A�K���Ɏ��̂ł��B
�����Ȃ�A���ʂ̃T�����[�}���ƈႤ�v�l�@������ׂ����Ƃ����Ă��A����͗��z�_�ł��B��������A�����������̏Ȓ��̗��v���l�����A���v�̂��Ƃ������l������悤�A�l�����x�Ƒg�D�\����ς���ׂ��ł��B�����āA�����ɂ͕ς����Ȃ����x��ς��邱�Ƃ������A�^�̈Ӗ��ł̐����哱�ł��B�����āA�����ł��ł���d���𐭎��Ƃ�����肷�邱�Ƃł͂Ȃ��͂��ł��B
���ǂ�Ȏ��Ɋ����͊撣��̂�
��������肪���������ĐϋɓI�Ɋ撣�鐭��Ƃ́A���ł��傤���H�@�����ɂ��傫�Ȍ��������܂��B����ɂ͂��������A�����F�̋������̂ƁA�����F�̎ア���̂�����܂��B�����F���������̂ł́A���I�Ȑ����_���������I���Q�����̖ʂ������Ȃ�܂��B���Ƃ��Γ��H���݂ł����A�l�����W�����Ă��ĕ���������Ȏ�s���S�ɐ�������ق����A�n���̒N���g��Ȃ��Ƃ������������o�ϓI�ɂ͍����I�ł��B�������A���H����������֗��Ƃ����L���҂̊��҂ɂ�������ׂ������Ƃ͂ł��邾�������̒n���ɑ����H������������悤���������܂��B���ꂪ���Ɍ����o���}�L�ł��B���̂悤�Ȑ����F�̋�������ł́A�����I�Ȍ��茠�͗^�}�̗L�͐����Ƃɂ���܂��B�����ɂ́A���ɂ̏�i�ł��鐭���ƂɍŌ�܂ōR�����Ƃ͕s�\�ł���A�ނ������Ęb���܂Ƃ߂Ȃ��Ǝd�����Еt���Ȃ����A���̂ق����o���ʂł��v���X���Ƃ����ŎZ������̂ł��傤�B���Ԃ́A���̂悤�ȗ����̓����d���������͊��ł���Ă���Ǝv���Ă��邩���m��܂��A�����ȂƂ���A�����͐���̃v���Ƃ��Ă̖��͊��������Ȃ���A�d���Ȃ���Ƃ����Ȃ������ł��B
�����A�����F�̎ア����ł́A���݂��ł��邽�ߊ����͊撣��܂��B���Ƃ��Ί�����Z���̍��ی��ł��B���ۉ�c�ł́A�����I�ɐ����傫�������Ƃ��o�ꂵ�Ă��A���ی������{�ɂƂ��ėL���ɐi�ނ킯�ł͂���܂���B�����̐�含�������鍑�ی��̂悤�ȕ��삱�����A�����ɂƂ��Ă�肪��������̂ł��B
�u���������݂�����v�ƕ����ƁA�u�����ɂ��܂����̂ł͂Ȃ����H�v�ƕs���Ɏv���l������ł��傤�B�����g���e���r��V�������Ă��āA�����������m��Ȃ����Ȓ��̖��ŁA�u�{�����Ƃ�����Ђǂ��v�Ǝv�����Ƃ�����܂��B�������A�����Ă��鑤�̎������炢���ƁA���܂����Ƃ��Ďd�������Ă��銯���͂قƂ�ǂ��܂���B��������g�D���P�������ċN���Ă���s�����ȏo�������A�u��������������낤�Ɖ�Ă���v�Ƃ������A�d�_�Ƃ��Đ�������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�����āA�����̊����̍l�����ɂ���肪����܂��B���������͐��������Ƃ������̂��߂ɂ���Ă���̂�����A�����ƕ������Ă����͂����Ƃ����Â�������܂��B������A���ԂɌ�����͂т����Ă��Ă��A����𐳂����߂̓w�͂��قƂ�ǂ��܂���B�������A�����܂Ŋ����ւ̕s�M�����傫���Ȃ��Ă��܂��ƁA�ǂ̂悤�ȉ��v���s�����Ƃ��Ă��A������������������̂ł͂Ȃ����Ɗ��J���āA���܂������܂���B�����������ł��o�������ł̓_���Ȃ̂ł��B�����̕s�M���͐���̓y��ɂ���A��̌����Ȃ������g�D�ɑ�����̂Ȃ̂ł�����B���̕s�M�����ׂ��w�͂��邱�Ƃ��A�����ɂƂ��Ă̋}���ł��B
|
|
��3�@�����ɂ͓V������������Ȃ�
|
����͊����ᔻ�̒��j�ł���V������ɂ��Ęb���܂��B
������ސE������ɁA�Ɨ��s���@�l�ȂǂɊ����Ƃ��čďA�E���A�����Ŗ@�O�ȕ�V�E�ސE����A�Ƃ����̂��V����̈�ʓI�ȗ����ł��B���������V����c�̂ɂ͋��z�̕⏕��������Ă���A�����������ł����ƂɊ������Â��`���z���Ă��邱�Ƃɍ����̓{��͏W�����Ă��܂��B�����������ƓV���肪�p�~���������ƁA1��ڂ̘A�ڂŌ����܂����B
�u����Ȃ�A�V����p�~�̂��߂ɁA�Ȃ����O���g�⑼�̊����͊撣��Ȃ��̂��H�v�Ƃ����^��̐����������Ă������ł��B�������o��ŁA�����Ɏ��̈ӌ��������ƁA��������芯�����V����p�~�̂��߂ɗ����オ���āA�w�͂���C���Z���e�B�u�͂���܂���B
�����ʂȓw�͂͂������Ȃ�
���̂悤�ȓw�͂����Ȃ����R�̈�́A�O����������ʂ�A���������T�����[�}���̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�����炻�̂悤�Ȕ��R�����Ă����������A���J�����\���̂ق�����������ł��B�܂��A���������A�����܂ߑ����̊����́A�V����̎��Ԃ��\���ɗ������Ă��܂���B�Ƃ����̂��A���������ł͐l���͈ꌳ�I�ɐl�����̏����̊������R���g���[�����Ă���A�������V����̑ΏۂƂȂ�͉̂ے��ȏ�̃N���X�ł��B�ł�����A������ƑO�܂Ŋ��������Ă����l�̎p�����X�ɖ{�ȂŌ��Ȃ��Ȃ��āA��X�A�ސE(�V����)���Ă����A�ƋC�Â��܂��B�l�I�Ȃ��������Ȃ���A�V����悳��������܂���B�������S�����c�������Ă��Ȃ������A�����������̐l���v�Ɋւ��b���A������˂��グ�ĉ��v����Ƃ����̂͏����ڂ̂Ȃ��킢���ł��B
���V����͕K�v��
������̗��R�B����́A�����g�D�̐V��ӂ̂��߂̓V����͕K�v�����Ƃ����l���������邩��ł��B���{�̏d�v�Ȑ���𗧈Ă��Ă��銯���́A����A30�A40��ł��B50��ł͑ސE��������āA�����Ƃ��Ď���c��݂̂ł��B�������V���肪�Ȃ��Ȃ�����A�͈�ς��܂��B���A����}�ŋc�_����Ă���V����p�~�ƒ�N�����̕��j���ƁA���܂łȂ�ސE�����Ă���50��̐l�X���A�S��65�܂Ō���Ɏc��̂ł��B�P���ɍl����Ύ����������ɂȂ�̂��A10�N�ȏ�x��܂��B���{�̐E��ł́A��肪�咣���鐳�����ӌ������A�N���҂̈ӌ����D�悳�ꂪ���Ȃ��Ƃ́A�N�����o���Œm���Ă���ł��傤�B��������������ꂪ�N�����Ă��܂������A�����_��ő̗͂�����Ⴂ�����ɏo�����āA�������Ă����[�h�����ق����A���{��ǂ��ł���B����Ȏ������Ⴂ�����͎����Ă���̂ŁA�V���肪�p�~����ė~�����Ǝv���Ă��Ă��A���̂��߂ɂ͊撣��Ȃ��̂ł��B
�V����̎d�g�݂͖����Ɍ���܂���B�����ސE�����́A���Ԃł��I�g�ٗp���x�E�N������̐��x�������Ƃł͂悭����܂��B�܂��A�����̓V����͓��{���L�Ǝv���Ă��邩������܂��A���ď����ł��V����͂���܂��B���Ă̊����̓V�����́A�Y�ƊE����Z�E�̃g�b�v�A�ƊE�c�̂�r�C�X�g�A�R���Y�Ƃ�F���J���Y�ƂƂ��������{���ڋq�̎Y�ƁA�@���������Ƒ��푽�l�ł��B�ǂ�����{�Ǝd����̂�����肪���邽�߁A����ƂƂ��Ă�����������邱�ƂɃ����b�g������̂ł��B
���������ƁA�u���Ԋ�Ƃł���Όo�ύ������̂Ȃ����Ƃ�����Ă��������|�Y����̂ɑ��A�Ɨ��s���@�l�Ȃǂ̐��{�@�ւ͎s�ꌴ���������Ȃ�����A�����̓V����͖��Ԃ̓V�����茵�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�O�����������Ƃ����̂͌�����ɂȂ�Ȃ��B�v�Ƃ������_���������Ă������ł��B
���O���[�]�[�����ǂ����邩
�S�����̒ʂ�ł��B�����ŁA�V����̔p�~�Ɍ����ē����o���ƁA���̏�Q�������͂�����܂��B�V�����`���ł��B
�u�S�Ă̓V����͖��ʂ��v�ƓV�����S�ʋ֎~����̂́A���\�����܂��B�Љ�ɂƂ��ėL�Ӌ`�ȓV���������Ɩl�͎v���܂��B�Ⴆ�A�u�F���Z��v�ł�����݂�JAXA���Ɨ��s���@�l�ł��B�����ɉȊw�Z�p����ɐ��ʂ����������ďA�E����A����܂ł̐�含��o�������������Ƃ͉\�ł͂Ȃ��ł��傤���B�V�����p�~����Ƃ��ɑ�Ȃ̂́A�u���ʂȑg�D�v�Ɂu�s�K�C�Ȋ����v���V���邱�ƂŁu���ʂȍΏo�\���������v�����u�����ȓV����v�������Ƃł��B�������A�ǂ����炪�����Ȃ̂��̐������́A����l�̗���ɂ���Ă��ς�邽�ߑ�ϓ�����ł��B
����ɁA���v�@�l��ƊE�c�́A���Ԋ�Ƃ̒��ɂ́A���ڍ�����⏕�����Ă���킯�ł͂Ȃ����A�����̐��{�ł̌o����m���𗘗p������A���{�Ƃ̃R�l�N�V����������Ă��������Ƃ����Ӑ}�������āA�V���������Ă���Ƃ��낪��������܂��B���������V����悪���ʂň����Ȃ̂��̋c�_�͕ʂƂ��āA�P�Ɍ����������Ă�������Ƃ������R�ŁA�]�E���̂��Ă��܂����Ƃ́A���@�����ׂĂ̓��{�l�ɕۏႵ�Ă���E�ƑI���̎��R�ɔ����Ă��܂��܂��B�V������ɂ́A�R�̂悤�ɃO���[�]�[��������̂ł��B
�V��������������鎞�ɁA���������O���[�]�[�������ߍׂ����������āA�ꕔ�̓V������c���Ȃ��瑼�̈����ȓV�����p�~���悤�Ƃ���ƁA�u�Ȃ������̑g�D��p�~����̂��v��u�Ȃ��������̓V����͋������̂��v�Ƃ�����������݂Ȃǂ��A�荞�܂ꂽ�Ȓ��₻�̏Ȓ����������鑰�c���̒����琶�܂�A���̉��v�����悤�Ƃ����l�ւ̔ᔻ�⒆���ŁA���v���̂��ז������\��������܂��B�}�X�R�~�́A�V���聁�����ƕ���̂ŁA�ꕔ���c�����v���悤�Ƃ��Ă���l�܂œV����i��҂��ƃo�b�V���O���A���Ԃ�����������ꂩ�˂܂���B�V������𗝉����Ă���l�́A�S�Ĕp�~�Ƃ������\�ȗ��_�͐U�肩�������A���Ƃ����Ē��J�ȋc�_�͗������ꂸ�A���X�N�̑O�ɗ���������ł���̂�����ł��B
���������܂�̊������قʼn��Ɋ������Ƃ��Ă���Ǝv��Ȃ��ʼn������B�����`���������ƁB����́A�V������͌���̕��G�Ȏ��Ԃƃ}�X�R�~�̈�ʓI�ȕ����܂�ɘ������Ă��āA���͂⊯���ɂ�錻���I�ȉ����ł͍����̐S�ɓ͂��Ȃ��B������A�����̃{�g���A�b�v�����҂���̂ł͂Ȃ��A��������̃g�b�v�_�E���ő����ϊv���Ȃ��Ă����Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ̂ł�!!
|
|
��4�@�u8��31���v�͖ڑO��
|
�V������͊������g�ł͂Ȃ��A�����Ƃ����[�h���ĉ��v���邱�Ƃ̕K�v����O��咣���܂����B����́A�u�����哱�Ƃ͂ǂ�����ׂ����v���e�[�}�ł��B
2009�N9���ɖ���}�͐����哱��W�Ԃ��ďO�@�I�ő叟���A���������������܂����B�������A�����哱�Ƃ������t�́A�ǂ������Ӗ��Ȃ̂ł��傤���H
������c�̔p�~�⊯���̍���ق̋֎~�Ƃ������`�Ő����哱���������ꂽ�A���邢�͊������쐬�����z��ⓚ��ǂ��琭���哱�ł͂Ȃ��A�Ƃ����悤�ȕ������Ό������܂����A�����ɂ̓}�X�R�~�œ����l�̒m���s���ɂ�����������܂܂�Ă��܂��B���Ƃ��Ύ�����c�B������c�Ƃ́A�u��b���W�܂�t�c�̈���O�ɁA�e�Ȃ̊����g�b�v�ł��鎖���������W�܂��ċc�_������������I�Ɍ��߂Ă����v�ƌ����Ă��܂��B�������A���ۂɂ́A������c�ł���`���I�Ȃ��̂ł��B�����I�ȋc�_�́A������c�ɏオ��O�ɁA�S������Ȓ����m�̐Ղ�ʂ��čs���܂��B�����āA���̋c�_�͐ߖڂ��ƂɒS����b��ɕ���܂��B���������āA�`���I�Ȏ�����c�̔p�~�́A�^�̐����哱�̊m���ɂƂ��Ă��Ȃ��Ƃɂ����܂���B���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�����d�v�Ȃ��Ƃ̂悤�Ƀ}�X�R�~���`���Ă��A�����哱�̌㉟���ɂȂ炸�A�������~�X���[�h���邾���ł��B
�����Ƃ��āA���͐����哱���������邱�Ƃ�S�����Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA�⏬�ȃ��x���ł��������哱���c�_�ł��Ȃ��}�X�R�~�ɁA�����������肵�Ă��܂��B�����Ɠ��ݍ��c�_�𑣂��A�^�̐����哱����������ׂ��ł��B�����哱�ɂ���Ċ������d�������グ��ꂽ�Ƃ��C���Ȃ������Ƃ��Ȃ��A���{�ɂƂ��Ė]�܂����A�^�̐����哱�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��傤���H
�������Ƃ̖�ڂ͂����������Ȋw���ψ���
�����哱���������邽�߂ɂ́A�u���������v�Ɓu���������v�̓�p�^�[���̎{�K�v�ɂȂ�܂��B�������₷���Ȃ�悤�A������Ђɚg���čl���܂��傤�B
�܂�����͍����ł��B��Ђ̌o�c�w�������Ƃł��B�o�c�w�ɑI�o���Ă��炦��悤�Ɋ���ɖ���o�c���j���u���������v�̎{��ł��B�Ј��͊����ł��B����ł��鍑���̖������ő剻���邽�߂ɁA�o�c�w�ł��鐭���Ƃ͊����Ɏw�����o���܂��B���ꂪ�u���������v�̎{��ł��B���̓�p�^�[���ɒ��ڂ���A�����哱�̂���ׂ��p�Ɩ���}�����̂���܂ł̎��т����炩�ɂȂ�܂��B
�܂��u���������v�̎{��B����́A�����Ȃ��A�Ƃ����̂����̕]���ł��B���X�g�����A�O�����痈���o�c�w�łȂ��Ɠ���̂Ɠ����ŁA�����}�ɂ͂ł��Ȃ��������Ƃ�}�͂��Ă��܂��B�m���ɁA�V������͂܂��܂��ł����A����������c�̔p�~�⎖���������X�R�ł��鐧�x���v���}�t���߂ł��B�������A���Ǝd�����Ƃ��������ݒu���A�]���̖����I�ȗ\�Z����v���Z�X�ł͂ǂ����Ă��荞�߂Ȃ������\�Z���J�b�g���A���e�Ƃ��Č��v�@�l�̌������ɂ����肵�����Ƃ͕]���ł���Ǝv���܂��B�����A�����̐l�C���̂��߂́u�����������v�̖ʂ������A�Ј�(����)�����܂��g���Ƃ������z�̉��v�����Ȃ��̂��C������ł��B
�����ŁA�u���������v�̎{��́A��]�I�ȕ]���ƂȂ�܂��B����}�́A�I�����̃}�j�t�F�X�g�ŁA�����֖������△�ʍ팸�Ŏq�ǂ��蓖�⍂�����H�������Ȃǂ̍������P�o�ł���Ƃ����o���F�̋����������A���̌��ʁA����ȍ����Ԏ��ƂȂ�܂����B����}�́A�Â����z������������Ƃ��O�����˂Ȃ�܂��A�c�O�Ȃ���A���̃c�P�́A���ǂ͍����ɒ��˕Ԃ��Ă��܂��B
���A�u���������v�̎{��ōł��d�v�Ȃ̂́A�I�����I�ȃo���}�L��Â����z�����Ƃł͂Ȃ��A�u�����ɍ��������s���Ȃ��Ȃ��Ă��錻��𖾂炩�ɂ��A�����ɗ����Ƌ��͂����߂邱�Ɓv�ł��B���̈Ӗ��ŁA�����Ƃ̖�ڂ́A8��31��������O�ɁA�u�ċx�݂͊y�������Ƃ�������Ȃ��āA�h������Ȃ��Ƃ����Ȃ���v�Ƃ������Ƃ�F�B�Ɍ��������������Ȋw���ψ����ɂȂ邱�Ƃł��B8��10�����炢����v��I�ɂ��ΊԂɍ�������ꏏ�Ɋ撣�낤�I�Ɩ����̃r�W�������������Ƃł��B�u���O�A������Ɛ^�ʖڂ����邾��[�A�܂����v����v�Ɨ�₩����Ă��A�u�ł��A���ǂ���ĂȂ��đ�Q�Ă���̂́A�N����B�Ԃɍ���Ȃ�������ǂ�����́H�v�Ƃ����Ċ�@�����������邱�ƂȂ̂ł��I
���ꂪ�ł��鐭���Ƃ͓��{�ɒ��N���܂���B������A���c���ƌ������ĊÂ��`���z���Ă������������܂������A�����̊����́A�����}�����߂�����A���߂Ď����������������肵�Ȃ��ƁA�Ɗ撣���Ă��܂����B�������A���ǂ̂Ƃ���A�������ǂꂾ���撣���Ă��A�����Ƃ̑���͂ł��Ȃ��̂ł��B�Ԃꂻ���ȉ�Ђ𗧂Ē����ɂ́A�Ј��̊撣�肾���ł͐�ɖ����ŁA�o�c�w���������o�c���j�������K�v������܂��B
�ċx�݂̗V�т̌v������Ă�̂́A�N�ł���Ԃ��琭���ƂłȂ��Ă��ł��܂��B�������A�ċx�݂̏h��v��A�܂荑���ɔ��肭���@��`���A�ǂ�����ĉ������邩���j�������Đ������邱�Ƃ́A�������畉�����������ƂłȂ���ł��Ȃ��d���ł��B
���C�M���X�̐����哱�Ƃ�
��Ђ𗧂Ē������A�Ј��̈ӎ����v�͐�ɕK�v�ł��B���������Ӗ��ŁA�C�M���X�����f���Ƃ��āA���Ɗ��̊W��ς��悤�Ƃ��Ă��閯��}�̕��j�́A�ǂ��������Ǝ��͍l���Ă��܂��B
�C�M���X�Ɠ��{�ł́A�����̈ʒu�t�����قȂ�܂��B���{�̌������͌��@�Łu�S�̂̕�d�ҁv�ƋK�肳��Ă��āA�^��}��킸�����Ƃ���Ă��Ƌ삯���邱�Ƃ����R�Ƃ���Ă��܂����B���̂��߁A�����̖�ڂ́A�����̂��߂ɂȂ鐭����ł͂Ȃ������I�Ȓ����ƂȂ�A�W���鐭���ƑS���̊�𗧂Ă鑍�ԓI�ȈĂŁA���̎����摗�肪�J��Ԃ���Ă��܂����B
�����A�C�M���X�ł́A��������Ȓ��̑�b�̂��߂̃X�^�b�t�Ƃ����ʒu�t���ł��B�����ɂƂ��ĕ�d���ׂ�����͑�b�����B�w�����ߌn����Ӗ������m�ŁA�����̎d���̖ړI���͂����肵�Ă��܂��B�C�M���X�ł́A�����͑�b�ȊO�̐����ƂƂ͐ڐG���������A�^��}�̐����ƂƂ̗��Q�����͑�b�̎d���ł��B
����ɂ����A�C�M���X�̑�b�K�͂ɂ́A�u�����̐�含�d���A��������̃A�h�o�C�X�Ɏ����X���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ܂Ŏ�����Ă��āA�����̌������ƂɎ����X���悤���̂Ȃ�A�����Ƀ}�X�R�~����u�����̑���l�`�v�Ɛ����Ǝ��i����������������{�̐^�t�ł��B
���{�Љ�́A�l�X�ȍ\������������ɒ��ʂ��Ă���8��20���ł��B���܂��o�ϓI�ɗ]�T��������̂́A8��31���͂��������ɂ���Ă��܂��B�Ј��̋��͂��Ȃ���Ђ̗��Ē����Ȃǂ��肦�Ȃ��̂ł�����A������r������̂ł͂Ȃ��A���������܂��g���������哱�𐭎��Ƃ͎������ׂ��ł��B
|
|
��5�@���̓Z�~�ɂ͂Ȃ�Ȃ�
|
�����ɐ����Ƃ̑���͂ł��܂���B���������܂��g�����C�M���X�^�̐����哱���������ׂ����ƑO��A�咣���܂����B�ł́A�Ȃ��u�����哱�v�͂����|���������ɂȂ�̂ł��傤���H�@�����Ƃ��Ď�����͍̂����ł����A���ۂɂ͐V����e���r�Ȃǂ̃}�X�R�~�̕ɗ����Ă��܂��B�������W���[�i���Y���̌��@�������A���{�̐����̂���܂ł̒�̌������A�Ƃ����̂����̈ӌ��ł��B�ŋ߁A���ʂɋ�����L�҃N���u���A�����ł��傤��?�@�}�X�R�~�̖����̍l�@�́A����̎咣�̍Ō�ɂӂ��킵���A�����`�ɂ�����d�v�ȃe�[�}�ł��B
�����{���\�𐂂ꗬ���}�X�R�~
���{�̃}�X�R�~�́A�Ώd�̎��ł��B�e�Ђ̒S���L�҂́A�����̌������̈ꎺ�ɋL�҃N���u��݂��āA�����ɋl�߂Ă��܂��B�ނ�́A�ȓ��ōÂ�����b�L�҉�ł̎����A��l����̃v���X�����ŏ������W���܂��B�L�҃N���u�Ƃ����r���I�Ȓc�̂ɏ���������}�X�R�~�́A���{�̌������\���̃j���[�X�Ƃ��ĕ���Ύd���ɂȂ�̂ŁA���{���Ď�����Ƃ������͐��{���\�����@�ւɂȂ��Ă��āA�l�b�g�n���f�B�A�ɂ��L�҃N���u�ᔻ�́A�I���˂Ă���Ƃ����̂������Ȏ����ł��B
���Ăł́A���������������\���̂ł���A�ʐM�ЂƌĂ�鎞���ɓ����������f�B�A���Ή����܂��B�����Ȃnj��n��ނ͒ʐM�ЂɔC���āA�W���[�i���X�g�͐[���������͂����ċL�������Ƃ����������S�����Ăɂ͂���܂��B
�Ƃ��낪���{�ł́A�����ʐM�Ђ⋤���ʐM�ЂȂǂ̒ʐM�Ђ݂̂Ȃ炸�V���L�҂��e���r�̕L�҂��������ɋl�߂Ă��āA�������͂͑a���ł��B�ʐM�Ђ����V���Ђ̂ق����l��������̂���ʓI�ŁA���{�̐V���Ђ͐l����ʂł��W���[�i���Y���̎��̖ʂł�������ȑg�D�^�c�ƌ����܂��B�����������R�X�g�\�����A�L�҃N���u�Ƃ����Q����ǂ�݂��邱�ƂŁA�J�o�[���Ă���Ɣᔻ����Ă����_�ł��Ȃ��ł��傤�B���{�ɃW���[�i���Y���͕s�݂ł��B
���ǎҎ���R���e���c���o�b�V���O
�}�X�R�~�Ƃ����Ă��A�e���r�A�V���A�G���A�l�b�g�Ɨl�X�ȃ��f�B�A������܂��B���f�B�A���Ƃ̓ǎґw�̈Ⴂ�ɍ��킹�āA�L���̓��e��X�^�C�����l�X�ł��B�������A�S�Ẵ��f�B�A�ɋ��ʂ��Ă���}�X�R�~�̖���A����́A�u���ڂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ł��B�}�X�R�~���c����Ƃł���ȏ�A���v���グ�Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɁA�W���[�i���Y���ɓO��������A�ǎҎ���R���e���c�͉�����ǂ����߂邱�ƂɂȂ�܂��B
�ǎҎ�����́B����́A������₷�����̂ł��B���Ԃ����������͂��K�v�ȕ�����ɂ��������_�ł͂Ȃ��A�����Ɂu���������҂��v�Ɣ��f�ł��镪����₷���B���ہA���̃R�����̎��M�ł��A���m�ȋc�_����������₷���c�_��v������܂����B
�}�X�R�~�ɂ́A�u���ҁv���K�v�ł��B���Ɉ��҈������Ă��ʓ|�����Ȃ����҂��B�����āA����́u�����������̂����R�v�ȎЉ�I���͎҂ł��B������A�����ł��邱�Ƃ����R�Ȑ����ƁE�����A�Љ�I�ӔC�������ƁA�u���E�ҁv�ł����ҁE���t���A�}�X�R�~�̃^�[�Q�b�g�ɂȂ�܂��B
����l�l���Ƃ̓Z�~�̈ꐶ�̂悤�Ȃ���
���͋^��Ɏv���܂��B�}�X�R�~�͐��{��ᔻ����̂��ړI�����Ă͂��Ȃ����H�������A���͂ɑ���ᔻ�̓W���[�i���Y���̖{���ł��B�������A�W���[�i���Y���s�݂̓��{�̃}�X�R�~�́̕A�P�Ȃ�o�b�V���O�ɂ��������܂���B
���s���ȋL�҂������ɂ���ăR���g���[������Ă���Ƃ����ᔻ���^���ł����A�����Ƀ}�X�R�~�ɂ��g�������̃o�b�V���O������āA�������u���ƂȂ����`�v�Ɋׂ��Ă���̂��^���ł��B�}�X�R�~�ɂ�������@����n�߂�Ɛ���s�\�ƂȂ�A�����̖ړI���ʂ����Ȃ��Ȃ�̂ŁA�ŏ����猄�������S�̗��_�������Ă������Ƃ���Ԍ����I���ƍl���A������I�Ƃ����v���Ȃ������Ȗ��ʋl�ߍ�Ƃ�簐i������Ȃ������̎p��[��̉����ւł͂悭�������܂��B
�u���ƂȂ����`�v�̊����ɂł��邱�ƂȂǒm��Ă��܂��B���͎�������l���u�����Ƃ��ɁA�^�Ȓ��̖ʐڂŌ���ꂽ���t���Y����܂���B�u��l�l���̓Z�~�̈ꐶ�̂悤�Ȃ��̂��B�Ⴂ���납��A���[���Ǝ������E���āA�Z�~�̗c���̂悤�ɂЂ�����҂��Ċ撣��B�����āA�Ō�Ɏ��������Ƃ��āA�c��2�T�Ԃ̖��Ŏv����������v
���̏����p�͂������Ɏ��������ɂȂ�̂��ړI�̐l�ɂ͐������̂�������܂���B�������A���[���ƃZ�~�̗c���Ƃ��Ă����Ƃ��Ă����l���A�Ō�ɖ����ƂȂǖ{���͂ł��Ȃ��ł��傤�B���v���u���Ċ����ɂȂ����l�Ԃ͎Ⴂ���납������K�����ׂ��ł��B�ڗ����ĂȂ��Ă��A�����Ƃ��Ă��銯�������܂��B�����āA���������Ɠw�͂��Ă��܂��B
�}�X�R�~���A��������낤�Ƃ���l�̗g�������ł͂Ȃ��A�ېg�ɑ���l�̕s��ׂ�Njy����A�����Ƃ��銯���͑�����͂��ł��B
�����C�������`�Ƃ̌��ʂ�
�u���������̉āv�̂悤�ȌÂ��ǂ�����ɂ́A�����Ƃ�}�X�R�~�ł͂Ȃ��A�������g���l���鍑�v��M���čs�����邱�Ƃ�������Ă��܂����B�����������ɑ���M�����������ł́A�����Ƃ́u���Ӂv��}�X�R�~�́u���_�v�ɔ����銯���́u��R���́v�Ƃ݂Ȃ���܂��B������A�ŋ߂̊����̑����́A�I����}�X�R�~�ɁA���ӂ␢�_�͕\������Ă���ƍl���A�s���̎w�j�Ƃ��Ă��܂��B
�����̍s���ɉe����^������@�B����́A�����Ƃ̌�����}�X�R�~�̎咣���A�{���ɂ݂Ȃ���̋C�������ق��Ă���̂��`�F�b�N���邱�Ƃł��B�����āA�����������A�u���O��c�C�b�^�[�ŁA�����Ƃ�}�X�R�~�Ɉق�������̂ł��B
�����������ɊS�������A����̗��v�݂̂Ȃ炸���{�̏������l����B����𐭎��Ƃ��~�߁A���邢�͍����ɕ��j�������Đ������A�������������̉�����B���̐��{�̊������A�}�X�R�~���W���[�i���Y�������A�����̊Ď��ɖ𗧂悤�ɕ���B���ꂪ�����������`���Ƃł��B�����āA�����`���Ƃɂ����ẮA�����̈�l��l�̈ӎ����v�ł��B���̓��{�̗L��l�́A�����Ƃ̂����ł��Ȃ��A�����̂����ł��Ȃ��A�}�X�R�~�̂����ł��Ȃ��A������l��l�����߂Ă���(���邢�͂�������ƍl���Ă��Ȃ�����)���ʂł��B
���č��������E�B���A���E�T�C�����́u���������Ƃ����V���g���֑���o���̂́A���[���Ȃ��P�ǂȎs���������v�Ƃ������t���c���܂����B�悢�����A�悢�����ƁA�悢�}�X�R�~�A��������^��������̂ł͂���܂���B�݂Ȃ����l��l���A���{�̏����̂��Ƃ��l���čs������������������ɓ���Ȃ��̂ł��B������オ�N�����������A�u���C�������`�v�ƌ��ʂ��A���o�ƐӔC�����������s���ɂ��u���n���������`�v���m�����܂��傤�B����́A�����݂̂Ȃ����l��l�ɂ������Ă��܂��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���d�g�����u�g���L�ҁv�̋���ׂ������́@2019/3
|
���{��2��12���A�d�g�@�����Ă��t�c���肵�A����ɒ�o�����B�����㖳�������u5�f�v�ȂǂŁA�d�g�̊��蓖�ĐR���ɉ��i�����̗v�f�����邽�߂��B
�S�ʓI�ȓd�g�I�[�N�V�����̓����ł͂Ȃ����A�����I�ȃI�[�N�V�������Ƃ�������̂ŁA����肶���ƈ���O�i�ł���B�Ɠ����ɁA�d�g���p���̈����グ�����荞�܂�Ă���B
�M�҂́A�d�g�I�[�N�V�������x�X�g�ƍl���Ă���B�����Ȃ�A�d�g���p���͍����1�A2���������邾�낤�B���������d�g�́A���̂��鍑�����L���Y�ł���B�����s���Ɉ����g���Ă���̂����̃e���r�E�ł���A���̐����̂��߂ɂ́A���������O�i���B
�������x���v�͋}����Ă��邪�A���̕����ƊE���������v�ƂȂ��ĂȂ��Ȃ��i��ł��Ȃ��B
�M�҂͊��������2006�N�����A�|������������b�⍲���߂����Ƃ�����B���̂Ƃ��A�M�҂͂����ς�X�����c���ƒn��������S�����Ă����̂ŁA�����s���͒S���O�������B�����́A�ʐM�ƕ����̗Z���ɂ��킹���������x���v���c�_����Ă����̂ŁA������Ƃ̂����������Ă������炢���B
�����̖�O�����猩��A�����@�ŋK������Ă��邱�Ƃ��A�ʐM�Z�p�̔��W�ɂ���ėL������������̂ŁA�������x���v���}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����u�펯�I�v�Ȃ��̂̂悤�Ɋ�����ꂽ�B�Ƃ��낪�A���ۂɂ͕����̊����������������A�S�����v�͐i�܂Ȃ������B
�����ȍݐГ����A�M�҂̎d�������͑�b���ׂ̗ɂ���鏑�����������B�M�҂Ƃ͖ʎ��̂Ȃ������̕����鏑�����ɖK��A���h��z���Ă����B�M�҂��鏑�����̈���ł���̂ŁA���h�����B���������ƁA���f�B�A�W�̕��X���B���̒��ɂ́u�g���L�ҁv�ƌĂ��l���܂܂�Ă����B
�u�g���L�ҁv�́u�g�v�Ƃ͓d�g�̂��Ƃ��B�u�g���L�ҁv�Ƃ́A�L�����������ɓd�g�����m�ۂ̂��߂ɓd�g�s���̃��r�C���O������l�������B���������l�͐V���ƊE�ɂ������B
�ނ�̐����p���[�͋��͂ł���A���̌��ʂƂ��ď�ɏq�ׂ��悤�ɉ��v���S���i�܂Ȃ������̂��B����́A���{�̓d�g�E�����s������i���ōł��x�ꂽ�����ł���B
�{���ł���A10�N�ȏ�O�ɂ���Ă����ׂ��ł������B���ꂪ�ł����ɁA���Ԃʂɂ��Ă��܂����B
�Ƃ��낪�A�Z�p�̐i�W�͖ڊo�܂����A�C���^�[�l�b�g���g���Ắu�����v�͈����ɒN�ł��ł���悤�ɂȂ����B
�M�҂����m������Ă���B���Ă͍u�`���e���e�L�X�g�ɂ��Ĕz�M���Ă������A���ł̓r�f�I�z�M���B���̕����R�X�g�������A���ɂ��D��Ă���B�����Ȃ�A����d�g�̊����āA�N�ł��u�����v���ł���悤�ɂȂ����킯���B
�������A���́u�����v�͕����@�͈̔͊O�ł���B�����@�ł́A�d�g�Ɋ�������̂ŗ^������Ώۂ����Ȃ��Ȃ炴��Ȃ��B���̂��ߗ^����ꂽ�����̊������҂͌����̂��߂ɕ����@�����炵�Ȃ�������Ȃ��B
�Ƃ��낪�A�u�d�g�̊��v�Ƃ��������I�Ȑ��Ȃ���A�����@�̋K���͍ŏ��K�v���x�ƂȂ�A���܂��܂Ȏ�̂̎Q����F�߂āA���̋����Ɉς˂�Ƃ������\�ɂȂ�B
���ɓ��{�ł͐�i���̒��ŗB��̓d�g�I�[�N�V������F�߂��A�����ł͐V�K�Q�����Ȃ��u�g���L�ҁv�̂悤�Ȑl���������炢�́u��i���v�Ȃ̂��B
�`���Łu���̕����Ǝ҂́A�d�g���w�s���Ɂx�����g���Ă���v�Ə������̂́A���̓d�g���p���͖�l�����߂����������炾�B�{���ł���A�d�g�Ƃ����������L���Y�́A���D(�I�[�N�V����)�Ƃ�����������ȕ��@�ʼn��i�����߂Ȃ�������Ȃ��B���̖�l���d�g�����蓖�Ă��āA���D�Ō��߂�ꂽ�͂��̐�������������u�s���Ɂv�����Ə������̂��B
�悤�₭�@���n�����Ƃ����邾�낤�B���Ȃ��Ƃ����̈��{�����͂��������K�����v�ɁA���̐������M�S�ł���B���̔w�i�Ƃ��āA�}�X�R�~�ɍ��h�X��������Ƃ����ӌ������邪�A���{�̃��f�B�A�����ۓI�ɂȂ�̂ł������͍��v�Ɏ����邾�낤�B
�d�g���p���͖{�����D�Ō��߂Ȃ�������Ȃ��B���̏펯�́A��i���ł܂��ɏ펯�ł���A��i��35�J���̏�����ƁA���ł͓d�g�I�[�N�V�����ł͂Ȃ��̂́A���{�����ɂȂ��Ă���B
2017�N�x�̓d�g���p����646�E8���~�B���̓���́A�g�ѓd�b550�E9���~�A�e���r�ƊE60�E1���~�Ȃǂł���B
����2017�N�x�̓��{�e���r�z�[���f�B���O�X(�g�c)�̔��㍂��4237���~�A���������v374���~�ł��������A���S�����d�g���p����4�E5���~�ɂ����Ȃ��B�e���r�����g�c�����㍂3025���~�A���������v158���~�ɑ��A�d�g���p����4�E4���~���B
�����A�d�g�I�[�N�V��������������Ă���A���Ȃ��Ƃ��d�g���p����1���ȏ�傫���͂��ł���B���̈Ӗ��ł́A�����ƊE�́A�d�g�I�[�N�V�����Ȃ��ł̊������҂ł���B
�e���r�ԑg�ŁA�������Ƃɂ��āA���D�ł͂Ȃ����ӌ_�Ă���̂ōH���P���������Ȃ�A���ł��]���Ɏg����Ƃ����ᔻ���悭���グ��B�������A����͓d�g���p���ł������邱�Ƃ��B
����̓d�g�@�����ɂ��A������ɒ�o�\��̋����[���@������������B�����@�����ł���B���̓��e�́A�m�g�j�ɂ������ԑg�̃C���^�[�l�b�g�펞�����z�M��e�F���邱�Ƃ��B�����Ȃ́A�m�g�j�ɏ펞�����z�M��F�߂�����Ƃ��āA��M���̈��������▯���Ƃ̘A�g�����A�q��Ђ��܂߂����������A�Ɩ��̌������Ȃǂ�v�����Ă���B
�����̕��́A���x����ɃC���^�[�l�b�g�펞�����z�M���\�ł��邪�A�s�����Ƃ��S�O(���イ����)���Ă���B�X�|���T�[����Ȃǂ�S�z���Ă���悤�����A���́A�C���^�[�l�b�g�펞�����z�M�ɂȂ�ƁA�Ǝ��R���e���c���������A�����̃e���r�ǂ���̔z�M�Ɉˑ����Ă���n���e���r�ǂ��[���Ȍo�c�ꋫ�Ɋׂ�Ƃ����Ƃ��낪�{�����낤�B�n���e���r�ǂɂ͒����̃e���r�ǂ���̓V���肪��������A���������l�����̎������ɂȂ�B
���������ɁA�C���^�[�l�b�g�펞�����z�M����肽�����Ă���m�g�j�𗘗p����Ƃ����A�u�łɂ͓ł��v�Ƃ��������Ȃ��헪���Ȃ͍̂����̂��낤�B
�����ɂ͑傫�Ȏ������K��Ă���B�L�[�ǂɑ��Ă�5���ɂ��Ȃ�d�g���p���̈����グ�A�d�g�̊��蓖�ĐR���ɉ��i�����v�f����(�ꕔ�I�[�N�V������)�A�m�g�j�ɂ��C���^�[�l�b�g�펞�����z�M�ƁA��͖Ԃ������Ƌ��܂����悤���B�M�҂������Ȃɂ����Ƃ�����10�N�ȏ�o���āA�x����Ȃ���A�����o�����悤���B
|
 |


 �@
�@ |
|
���Ό��e���r�ɃC�������{�u�����@�����v�̖{�ۂ͂m�g�j�������I�@2018/6
|
���{�W�O�������������ł����������x�́u�����v���A�ڍ�������B2018�N3����{������V�������ۂ�ۂ���͂��߁A4����{�ɔ����������{�����́u�������x���v�āv�́A�����ނˎ��̎O�{���������B
1�@�����@��4�����͂��߂Ƃ���������K��(�ԑg�����A�ԑg��̍���A�ԑg�R�c��̐ݒu�A�}�X���f�B�A�W���r�������A�O���K���Ȃ�)�̓P�p
2�@�����ɂ�����n�[�h�E�\�t�g(�m�g�j�ȊO�̕����ݔ�����Ɣԑg���암��)�����̓O��
3�@�m�g�j�ȊO�̕����ƒʐM�̈ꌳ��(��{��)
�ȏ�̈Ӗ�����Ƃ���́A�m�g�j�Ɩ��ԕ����Ƃ����u�̐��v�̏I���ł���B����������A�m�g�j�ȊO�̖������C���^�[�l�b�g�Ȃǂ̒ʐM�Ɠ����A������u�����v�ł͂Ȃ����Ă��܂��B
���́u�����v���ѓO�����A1950(���a25)�N�̓d�g�O�@�����E�{�s������70�N�߂������Ă������{�̕������x�́A���{�I�ɕς�邱�ƂɂȂ�B�܂肱��́A���{�̑�D���ȁu��ヌ�W�[������̒E�p�v�̕����łȂ̂ł���B
���{�������Ό��ɂ���u��ヌ�W�[������̒E�p�v�́A�{���ł���A��̑���ɓ��{�ɂ����炳�ꂽ���̐��̂����A��O�̐����悢���̂Ɛ�O�̐����悭�Ȃ����̂Ƃ��s��(�����ׂ�)���A�悭�Ȃ����̐��������A���̐����悢���̂ɕς��邱�ƁA�ł���͂����B
�Ƃ��낪�A���{�́A���������s�ʂ��D������ƂȂ��ɁA�A�����J�̉������⍶�h�E�i���I�����l�̐������ڗ����̐��̂����A�������ς������Ǝv�����̂����ɂ��āu��ヌ�W�[������̒E�p�v�ƌ������Ă��܂��B����������͂��Ȃ��A���j�ς��������ȗ��j�C����`�҂ƌ��Ȃ���邱�ƂɂȂ�B
���������{�̌��s�̕������x�́A���{�̎葫�ƂȂ��{�c���\���������Ȃ�������O�̈������������x(���W�I)�Ȃ��A�A�����J(�f�g�p)�̎w�����ɂ���ꂽ�A�܂��Ɂu��ヌ�W�[���v���̂��̂ł���B�������A��O�̐����͂邩�ɂ悢���̐����B
�������A�ǂ������{�́A�����������o�����������x�́u�����v���A�u�m�g�j�����̐��̕���v��u�����ƃl�b�g�̔��I�ȗZ���v���Ӗ����A��ヌ�W�[�������{�I�ɕς��Ă��܂��傲�ƂƂ́A�悭�킩���Ă��Ȃ������悤�ł���B
���̌�̊e�Еɂ��A4�����{�ɊJ�������t�{�u�K�����v���i��c�v�ł��̃e�[�}�����グ�A���{���������������Ƃ���Ă����B���̌�A����c��5���������h�ɂ܂Ƃ߂铚�\�ɕ������v�̕��j�荞�݁A�������18�N�H�̗Վ�����Ɋ֘A�@�Ă��o�B20�N�ȍ~�̎{�s��ڎw���A�Ƃ����i���Ƃ݂�ꂽ�B
�������A68�N�������������x�����{�I�ɕς��悤�Ƃ�������v�ɂ��ẮA�ȏ�̃X�P�W���[���́A���������قǐّ��������B��ځA�b�ɂȂ�Ȃ������ł���B
�����A(���{���ԕ����A��)��3�����u�����̉��l����Ɋւ��錟����v�𗧂��グ�A�R���������B��������͑�v�ۍD�j�E���{�e���r�����ԎВ�(6���Ɉ��O�E�s�a�r�e���r���_��̌���Ė����A��ɏA�C�\��)�������A���L�[�ǖ�������v�����o�[�ƂȂ�A���������ēO��R��̍\�����Ƃ����B
�e���r�ƌn��W�̋�����V�������A���x����͎��ꂪ�����Ƃ������ƂŁA���{���킭�u�ǂ�ǂ��V���v���Ɠǔ��V������3��8���Ɂq���{�u�����v���v�ɐ��ޗ��Ƃ����r(���������烁�f�B�A�ǂɈڂ�����������Y�L�҂̏����L��)�A17���ɂ́q�A�ᔻ�ɕs�����r�Ƃ������o���L�����f�ځB���̂ق��̐V���������ނˁu�ّ��ɂ����Ȃ����v�Ƃ̘_���ł���B
���������ǂ��鑍���Ȃ��ˑR�Ƃ��Ĕ��M���^�B��}�͂������A�^�}�ɂ����Θ_���������B����Ȓ�4��16���ɊJ���ꂽ�u�K�����v���i��c�v�����\�����u�ʐM�ƕ����̗Z���̉��ł̕����̂�����ɂ��āv�ł́A�`��1�`3�̒��g�́A�����������Ă����B
����c����̓I�Ȍ����ۑ�Ƃ��Ď������̂́A(1)�ʐM�E�����̗Z�����i�W���鉺�ł̃r�W�l�X���f���̓W�J�̕������A(2)��葽�l�ŗǎ��ȃR���e���c�̒ƃO���[�o���W�J�A(3)��L�̕ϊv�܂����A�d�g�̗L�����p�Ɍ��������x�̂�����A��3���ځB��ŕ������x���v�ɂ��ĕ����ꂽ��c�O�q�E����c�c�����u�ɂƂ܂ǂ��Ă���B���������c�_�͂܂��������Ă��Ȃ��v�ƁA���ʉ��Ō������ꂽ�����@4��P�p���Ȃǂ̉Ώ����ɂ�����ƂȂ����B
���{�́A��c�ŕ����@��4���́u�فv�̎����o�����A�u�����ƒʐM�̊_���͂Ȃ��Ȃ��Ă���A�R���e���c�̐��E�̓O���[�o�������̎���ɓ˓����Ă���B���{�̃R���e���c�͐��E�Œʗp���Ȃ��Ƃ�����߂Ă̓_���v�ȂǂƔ��������B1���̎{�����j������2���̐��{�u����������c�v�ŁA�А��悭�����́u��_�Ȍ������v��錾���Ă����̂Ƃ͑�Ⴂ���B�e���ʂ���̔��ɉ����āA���t�x�����̒���������A����̌y���v������P��������Ȃ������킯�ł���B
����ɂ��Ă��A�Ȃ����{�́A�|�V����ɈႢ�Ȃ�����Ȗ����̘b�������o���Ă����̂��낤���H
����̂悤�ȁu�������x���v�āv�́A���ɖڐV�������̂ł͂Ȃ��B�Ⴆ��2006�N�ɂ́A�����̒|������������b�̎��I���k��u�ʐM�E�����݂̍���Ɋւ��鍧�k��v�ŁA�m�g�j�E�����E�m�s�s�̉��v���c�_����A�u�ʐM�E�����̖@�̌n�̔��{�I�������v�u�}�X���f�B�A�W���r�������̊ɘa�v�Ƃ������L�[���[�h���o�ꂵ�Ă���B
�A�����J�ŁA�����̂�����u�t�F�A�l�X�E�h�N�g�����v(��������)���P�p���ꂽ�̂�1987�N�ƁA30�N���O�̂��ƁB�����ǂ������I�ȓ}�h�����f���Ă��悢�̂ł́A�Ƃ����c�_�́A���{�ł��������炠�����B
����ȌÂ��b���o���Ă����ő�̗��R�́A�X�F���(�����Ȃ̕�����������)����{���b���ɃC�������{�́u�ł�v���낤�A�ƕM�҂͌���B�����Ɂu�s���ȂƂ��͐���g��v�Ƃ����i��������B��}�̎���U���A�}�X���f�B�A�̐��{�ᔻ�A����ɉe�����ꂽ(�Ǝ��v���Ă���)���t�x�����̉����Ȃǂ��āA�V�������_���f���Đ�����g�債�A�ǖʂG�������������킯���B
���̃l�^���������v�Ȃ�A�e���r�̓r�r���Đ����ᔻ�ɓ�̑��ނ�������Ȃ��B���Ɉ��{�́A�V���ł͒����V���A�e���r�ł͂s�a�r�ƃe���r�������A�̂�����(������)�̂��Ƃ������Ă��邩��A�ނ�Ƀ_���[�W��^���邱�ƂɂȂ�D�s���B�m�g�j�͊�{�I�Ɉӂ̂܂܂����A���{�e���r�ƃt�W�e���r�͎^�����Ă����ɈႢ�Ȃ��A�Ƃ��������f���������낤�B�����̏��[���疞���ɃR���g���[���ł��Ȃ������ɁA�����ԑg���R���g���[���������Ƃ����̂��ӂ������b���A�ƕM�҂͎v�����B
������̗��R�́A�����Ȃ̉��v�̒x��ł���B2017�N6���ɏo�����{�����̌o�ύ�������́u�o�ύ����^�c�Ɖ��v�̊�{���j�@2017�`�l�ނւ̓�����ʂ������Y������`�v�ŁA�ڋʂ́u���������v�v�������B���ǂ͌����J���ȂŁA���Ȃ̘J�����Ԃ̎��Ԓ����f�[�^�ɋ^�`��������Ȃǂ������Ⴍ���x��ɒx�ꂽ���̂́A3���ɂ͓��������v�֘A�@�Ă̍����o�Ƀ��h������(4��6���ɒ�o)�B
���đ����Ȃ́A����͂Ƃ������v�Ă��o���Ă��Ȃ��B������������b�́A9���̎����}���ّI���ɂ��ŁA���}�h�u�}�}�p�p�c���A���v�̉�ɏA�C�A�n���ŗ����グ���u���������m�v�̑S���W�J�Ƃ����������������͂��߂���c���q���B���̑����Ȃɉ��v�Ă��܂Ƃ߂����A6���ɏo���o�ύ�������̖ڋʂɂ����������悤���B
���@�̓����ɏڂ��������E�̎���ʂ́A�������ߑ������B
�u�ǂ������{����́A�����@��4���́w�����I�Ɍ����x�K�肳���Ȃ����A�������������Ă����e���r�ǂ�ԑg��������A�Ɩ{�C�ŐM������ł����悤�Ȃ̂ł��B�������v�ɂ���āA�����̈ӌ����ق��A��^��������ǂ��ł���ƁB�ł��A�����������ƌ������ᔻ����ǂ��ԑg�������邾�낤�A�Ƃ͎v���Ă��Ȃ�������ł���v
����ʂ́A�u�ᒠ�̊O�����������Ȃ́w�ł���͂����Ȃ��x�Ƃ������ꂾ���A����̑����ψ���(���E���M�ψ���)�ψ������ɂ��w���z���ɂȂx�ƕs�]�������B�M�S�Ȑ����Ƃ͈��{�����ŁA���{�����䏮�ƁE�鏑��(�o�ώY�Əȏo�g)�����p�j�E�K�����v���i��c�ψ�(2016�N9���`�A�o�ώY�Əȏo�g�A������А���H�[�В�)�̃��C���ȊO�́A�@����ł����v�Ƒ������B
�{�l�́A�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������悤�����A�����͓���Ǝv���Ă���X�^�b�t�́A�傫�ȉԉ�ł��グ�č����̎��ڂ��W�߁A���Ȃ���ʍ��ڂ̂������ł������Ɍ����Č������n�܂�悢�A�ƍl���Ă����̂�������Ȃ��B
�ł́A���{���������ʉ��Ō������A���ǂ͈������߂��������x�u�����v�̉������Ȃ̂��H�@�܂������@��4�������A���̂悤�ȓ��e�ł���B
(�����������̕����ԑg�̕ҏW��)
��l���@�@�������Ǝ҂́A���������y�ѓ��O����(�ȉ��u�����������v�Ƃ����B)�̕����ԑg�̕ҏW�ɓ����ẮA���̊e���̒�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��@�@�����y�ёP�ǂȕ������Q���Ȃ����ƁB
��@�@�����I�Ɍ����ł��邱�ƁB
�O�@�@�͎������܂��Ȃ��ł��邱�ƁB
�l�@�@�ӌ����Η����Ă�����ɂ��ẮA�ł��邾�������̊p�x����_�_�𖾂炩�ɂ��邱�ƁB
2�@�@�������Ǝ҂́A�e���r�W���������ɂ�鍑���������̕����ԑg�̕ҏW�ɓ����ẮA�Î~���A���͈ړ����鎖���̏u�ԓI�e�������o��Q�҂ɑ��Đ������邽�߂̉������̑��̉��������Ƃ��ł�������ԑg�y�щ������̑��̉����o��Q�҂ɑ��Đ������邽�߂̕������͐}�`�����邱�Ƃ��ł�������ԑg���ł�����葽���݂���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�w�I���x2018�N4�����L���q���{�����u�����@�����v�̐^���r�ɂ��ƁA���{��3��9����ɑ�v�ۍD�j�E���e���В��Ɖ�H��(����鏑���Ɣ��J���V�E���e������ψ���������)�A�u4���͌����ɂ͎���Ă��Ȃ��̂ŁA���̍ۓP�p����ׂ����v�Ǝ咣�����Ƃ����B
�������A�u�����y�ёP�ǂȕ������Q���Ȃ����Ɓv�����{�̕����Ŏ���Ă��Ȃ��Ƃ́A���ꂢ���Ȃ��B�u�����I�Ɍ����ł��邱�Ɓv�ɂ��ẮA���{�͎�����Ȃ����{�ᔻ���肷��e���r�́u�����łȂ��v�Ǝv���Ă���悤�����A���f�B�A�����͎҂⌠�͂�ᔻ����͓̂�����O���A�Ƃ��������悤���Ȃ��B
���{�͓��t���[������������2001�N1��29���A�����O���̂d�s�u2001���W�w�����펞���\�́x�Ɋւ��Ăm�g�j��������ĂсA���e�����m�ɕ��Ă���Ƃ��Ĕԑg�ɒ������������Ƃ�����B�܂�A�����O�̔ԑg�ɐ��{�����Ƃ��Đ����I�ȉ�������A���ʁA�ԑg�̓M���M���h�^�o�^�ʼn��ς̂����������ꂽ�B
�����Ƃ�{�������A�����NJ����ɉ�A�����O�Ő��쒆�̓���̔ԑg�ɂ��āA���m�ɕΌ��������e�Ɣ��f���������ŁA�u�`���ׂ��ł͂Ȃ����v�ƈӌ����q�ׂ邱�Ƃ��A���{���͂��ߖ����`�Љ�ł́u�����ԑg�ɑ��銱�v�ƌĂԁB�����āA�����Ƃ�{�����������ԑg�Ɋ����邱�Ƃ��A���{���͂��ߖ����`�Љ�ł́u�����������v�u�����I���͂�������v�Ȃǂƌ����K�킵�Ă���B
������A�����̈��{�W�O������������Ƃ́A�����@�̑�2��(���F�����͑�1��)�u�����ԑg�̕ҏW���Ɋւ���ʑ��v�́u(�����ԑg�ҏW�̎��R)��3���@�����ԑg�́A�@���ɒ�߂錠���Ɋ�ꍇ�łȂ���A���l�����������A���͋K������邱�Ƃ��Ȃ��B�v�Ƃ����ɒ�G��������@�ᔽ���B���łɂ����A���{�����@�u��21���@�W��A���Ћy�ь��_�A�o�ł��̑���̕\���̎��R�́A�����ۏႷ��B�v�ɂ���G���錛�@�ᔽ�ł�����B
�������̎Љ�́A�k���N�⒆���ł���O�̓��{�ł��Ȃ����R�ȎЉ����A�����ǂ��܂��������炵�Ă��Ȃ��ԑg�𐭕{�������Ό��ƌ��߂��A�������낱������ƒ������邱�Ƃ��������͂����Ȃ��B�Ƃ��낪�A���{�͕��C�ł��̂悤�Ȓ��������Ă��܂��B
�悤����ɁA���_�̎��R�▯���`�̎葱���Ƃ��������Ƃ��A�S�R�킩���Ă��Ȃ��̂��B
�Ȃ��A�M�҂́w�����펞���\�́x���ɂ߂ăG�O�����e�̔ԑg�ƍl���Ă���A�悢�ԑg�Ƃ͂܂������v��Ȃ��B����ł����{�����̎��O����̓_�����A�Ǝ咣����B���{�́A�����ԑg�����琭�{���������O�������͓̂��R���A�ƍl���Ă���B���R�A�ԈႢ�ł���B����������A���{�������ԑg�̂悵���������߂邱�ƂɂȂ邩��_���Ȃ̂��B
�e���r���V���ƈ���āA�����@�œ��Ɂu�����I�Ɍ����v�����߂��Ă���̂́A����ꂽ�҂������]����������ǂ�����ꂽ�����̋��L���Y�ł���d�g��Ɛ�I�Ɏg���A���������ԑg�����ډƒ�̃e���r�@�ɉf���o����đ傫�ȉe���͂�������A�ł���B
�˂��l�߂Ă����Ε����@��4���́A���@��21���������������u��̕\���̎��R�́A�����ۏႷ��v�Ɩ������邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��A���͊낤���K��ł���B��������A�q�g���[�����̂悤�ȓƍِ������o�ꂵ�A��4���u�����I�Ɍ����ł��邱�Ɓv�ᔽ�Ƃ��ĕ����d�g���~�߂�悤�Ȃ��Ƃ�����A�ƍَ҂��������x�z����c�[���Ɖ����Ă��܂��B�����炱���A�����@��4���͈��̗ϗ��K�͂ł���A����������Ƃ��ĕ����d�g���~�߂邱�Ƃ͋�����Ȃ��A�ƍl�����Ă���B���ꂪ����̌��@�w�҂̌������B
�܂��A����ʂ̔ԑg�����������ŕ����@��4���u�����I�Ɍ����ł��邱�Ɓv�ᔽ�ƌ��߂���l�����Ȃ��炸���邪�A������ԈႢ�B�����̐����I�Ȍ����́A�����Ԃ���`�����l�����p�����Č��Ȃ���Δ��f�ł��Ȃ��Ƃ����̂��A���\�N���O���琭�{�̌��������ł���B
�����āA���̃e���r�́A���͑I���̎����ɂ͐��{�L��b�l��f��A���_�ԑg�Ő����Ƃ̘I�o���Ԃ������ɂ���A���������_�L����ȂǁA�����҂��l����ȏ�Ɍ����⒆���ɋC��z���Ă���B�����K��̓P�p�Ő����ᔻ�����܂�Ƃ������o�J�������Ƃ͍l���ɂ����A�P�p���Ă悢���Ƃ�������Ƃ��v���Ȃ��B
�u�͎������܂��Ȃ��ł��邱�Ɓv���A���E�I�Ƀt�F�C�N�E�j���[�X��w�C�g�X�s�[�`�����s���邢�܁A�Ȃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��K��ł͂Ȃ��낤�B�u�ӌ����Η����Ă�����ɂ��ẮA�ł��邾�������̊p�x����_�_�𖾂炩�ɂ��邱�Ɓv�́A���{�̕����ł͑S�R�A����Ă��Ȃ��B�M�҂�2011�N�ȑO�ɁA�n��f�W�^�������̐i�ߕ��͂悭�Ȃ��Ǝ咣�������A���̂悤�Ș_�_�����グ������ǂ͊F���������B�������A����Ă��Ȃ�����P�p���ׂ��Ƃ͕M�҂͎v��Ȃ��B���A�Ƃ����ق��͂Ȃ��B
���{��K�����v���i��c�̈ψ������́A�ȏ�̂悤�Ȏ���������ς�킩���Ă��Ȃ��A�ƍl����ق��͂Ȃ��B
�u�}�X���f�B�A�W���r�������v�u�O���K���v�̊ɘa�Ƃ������o�ϓI�E�Y�ƓI���ʂɂ��ẮA������x�A��������]�n�����邾�낤�B
���{�ł̓e���r�����Ƒ��V�����̎��{�n���݂��Ă���A���łɏW���r���������������ƂȂ�A�`�[�����Ă��鎖��������B���q������i�݁A�n�����敾���Đl����������ɐ[���ɂȂ�A�n���ǂ�W�I�ǂ̍ĕ҂͕K���ŁA���̓_������W���r�������̌����������߂��鋰�ꂪ�����B
�����ǂ̎��{��100���O�����������邱�Ƃ́A�d�g�����ۓI�Ȏ�茈�߂œ��{���Ɋ��蓖�Ă��A���ꂪ�e�Y�Ƃ��ƂɊ��蓖�Ă��Ă��邱�Ƃ���A�����������Ⴄ�B�����ǂ͏d�v�C���t���ł����āA���S�ۏ�ȂNJ�@�Ǘ������肾�B�������A�O���K��(���݂͍��������ǂւ̊O����Ƃ̏o��������20������)��������x�ɘa���邱�Ƃ́A�O���[�o�����̐i�ތ��݂ł͔������Ȃ��悤�Ɏv����B
�������Ƃւ̐V�K�Q���������Ƃ����Ă悢���A�����ɂ�����n�[�h�E�\�t�g(�����ݔ�����Ɣԑg���암��)�������A�������悭�Ȃ���̂ł���Ό�������悢�B�M�҂́A�����͌���ێ�����̂������Ƃ��悢�A�ȂǂƂ͂܂������l���Ă��Ȃ��B
�����Ƃ��A�d�͂����d�Ƒ��d�ŕ�����������A�����悤�ɕ�����ʐM���n�[�h�E�\�t�g�����ׂ��A�Ƃ������r���ۂ��c�_�͊肢�������B�d�C�͒N�����d���Ă����d���ɏ悹�đ��邱�Ƃ��ł���d�C�����A�ԑg�͒N�����삵�Ă��d�g�ɏ悹�đ��邱�Ƃ��ł���ԑg�Ƃ����b�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B������O�ł���B
�Y�ƊE�E���E�̌o�c�҂�A�o�ώY�Əȏo�g�̋K�����v���i��c�ψ�������ɂ́A�����̌o�ϓI�E�Y�ƓI���ʂ����ɒ��ڂ��A�����l�p����ʂɕ\�������̂���������ƒʐM(�C���^�[�l�b�g)�͊_�����Ȃ����Ĉ�{������悢�Ǝv���Ă���l�����\����B�����A����ȍl�����ɕM�҂́A�����ɂ͎^�������˂�B�����ƒʐM���ꏏ�����ɂ��A���܂��܂Ȏ��Ǝ҂Ɏ��R�ɂ�点�Čo�ό�����Nj�����A���݂̕������ʐM���ǂ�����悭�Ȃ�A�Ƃ����b�ɂ͂Ȃ肻�����Ȃ����炾�B
��1�ɁA�o�ό�����ӓ|�ł́A�����ł��ʐM�ł����܂�ׂ��肻���ɂȂ����삪���̂Ă��Ă����B�Ⴆ�A�n���ɏZ�ޏ����̎����ҁE���[�U�[�A��Q�҂Ȃǐ�ΐ������Ȃ������ҁE���[�U�[�A����I�Ȓn��Őr��ȍЊQ�Ɍ�����ꂽ�����̎����ҁE���[�U�[�A����҂��N�ҁE�c���ȂNj@�B�ɂ���e���V�[�ɂ��ア�����ҁE���[�U�[�Ȃǂ�ΏۂƂ��镪��ł���B�����ƒʐM���ꏏ�����ɂ���A�ނ�ɂƂ��Č��݂��悢�������Ƃ����ۏ͂Ȃ��A�ނ����̂Ă��鋰�ꂪ�����B
�Ⴆ�A���o��Q�҂ނ��̉��������⒮�o��Q�҂ނ��̎��������͂ǂ��Ȃ�̂��H�u�`���������s�u�v�Ȃ�ʂ`���������s�u(2017�N�̏O�@�I���O�ɏo�����Č�����������ł����̂ŁA���{�̑�̂��C�ɓ���)���̃j�R�����̂��A�ǂ�ǂ�������Ƃɓ����Ă���̂͂悢�Ƃ��āA�ނ�͂܂Ƃ��Ȑ�����ЊQ��ً}�x����ǂ��܂ł��p�ӂ�����̂��H
��2�ɁA�����ƒʐM�̈ꌳ���ɂ���ēd�g����C���^�[�l�b�g�ւ̓]�����i�݁A�����Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�d�g�ɗ]�T���ł��A���̗��p�҂��I�[�N�V���������Ō��߂�Ƃ������������A�d�g����l�b�g�ւ̓]���́A�ꌾ�ł����قNJȒP�ł͂Ȃ��B
���������A�Ȃ������̓��W�I��d�g�Ŏn�߁A���Ƀe���r��d�g�Ŏn�߂����Ƃ����A�d�g���g�����Ƃ��A�s���葽���̉ƒ�⎖�Ə��ɓ͂���ɂ͂����Ƃ������A�����I���������炾�B
���݂ł��A��K�͍ЊQ�Ȃǂ̔������̓l�b�g��(�d�b��)�Ȃ���ɂ����Ȃ�B����l���l�b�g���g����Ƃ������Ƃ́A���̐l(�̒[��)�Ǝ��Ǝ҂��L���ł��ꖳ���ł���o�����łȂ��邱�Ƃ����A�啔���̐l�͑啔���̎��ԁA����ʍs�ł悢�B���������ʍs�̕����ɖ������Ă���B
�����o��������ɂ���Γ��R�A����������R�X�g���ɂȂ�B���̃R�X�g�́A������ƒn(�ւ���)�Ȃǒn��ɂ���đ傫���Ⴄ�B�K�����v���i��c���A�ʐM���Ǝ҂ɂ���ĈقȂ�R�X�g���A�ǂ��܂ł܂Ƃ��Ɍv�Z�����̂��A�����_�ł͂悭�킩��Ȃ��B���[�U�[���A������������Ԃ�ɂ͖����������̂ɑ��āA�ʐM�̓C���^�[�l�b�g�ɐڑ����邾���ŗL���ƂȂ�B���܃l�b�g���g���Ă���l�тƂ͂��Ă����A����҂�n���w�������ȒP�ɔ[���ł���b�Ƃ͎v���Ȃ��B
��3�ɁA�����̂Ƃ�킯�ԑg�́A�ʏ�͂��܂�ׂ���Ȃ����A���������N����Ɛl�X���W���I�ɒ��ڂ��A���ɐl�̐����Ɋւ��悤�ȏd��ȑI�������������Ƃ��炠��B�Ƃ��낪�A���ʂ͉������N�����Ă��Ȃ�����A����ꏊ�ɓ��h���Ȃ�N���u�L�҂Ȃ�ʐM����z�u����̂͂�߂Ă������A�Ƃ������Z�ʂ������Ȃ��̂��Ȃ̂��B�܂�ɂ́A���i����l���J�l��������B
�������炳�܂��܂ȋK����P�p���A���{�E�E��y�Ȃǔԑg�W�������̒��a�����߂�K����P�p���Ď��R�ɂ�点�A�ׂ��肻���ɂȂ����傪�k�����Ă����ƁA���{�̌��_��Ԃ��̂��̂��k��ł������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
���{������́A�̓R���g���[���̌����m�g�j�����ɔC����悢�A�Ǝv���Ă����悤�ł���B�Ƃ����̂́A��������������ƁA�����@�͂m�g�j�ݒu�@�ƂȂ�A��3��(�ړI)�u��15���@����́A�����̕����̂��߂ɁA���܂˂����{�S���ɂ����Ď�M�ł���悤�ɖL���ŁA���A�ǂ������ԑg�ɂ�鍑����������s���ƂƂ��ɁA�����y�т��̎�M�̐i�����B�ɕK�v�ȋƖ����s���A���킹�č��ە����y�ы���ۉq���������s�����Ƃ�ړI�Ƃ���B�v�̎�������ɁA���E��4���̓��e���}�������Ǝv��ꂽ���炾�B
���݂̂m�g�j�̕�����A�����ɑ��Ĝu�x(����)���J��Ԃ��A���S�ɍ�����������Ȃ����̂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B����Ȃm�g�j�̕����ł悢�̂��A�Ǝv��Ȃ������́A�ǂ����Ă������h�ɈႢ�Ȃ��B
�m�g�j�����̐����ƁA�m�g�j�Ɩ����̓̐����d�v�Ǝv���Ă���̂́A�m�g�j��Ɩ���(����)���炢�B����ł́u�������Ȃ��Ȃ邾���Ȃ�A�����ɂ͊W�Ȃ��b�v�Ǝv���Ă���悤�ł���B
�����A���{�����̕������x�u�����v�ŁA�����ꖯ�����Ȃ��Ȃ�(���l�b�g���Ǝ҂Ƌ�ʂ����Ȃ��Ȃ�)�̂ł���A�����ƃo�����X������Ă��錻�݂̂m�g�j�̋K�͂́A��������ē��R���B����ƁA���N�̗\�Z�K��7000���~�Ƃ�������������ǂ͕K�v�Ȃ��Ȃ�B���R�A��M���͉�����B���z1000�`1200�~�ł��܂������A�Ƃ����b�ɂȂ肩�˂Ȃ��B�������m�g�j�E���̐������邾�낤�B
�ȏ�̂��Ƃɂm�g�j�E���̑啔�����C�Â��Ȃ��܂܁A���{�����́u�������x���v�v�͂�������ڍ������B�������A���܂������悤�ȃv���������サ�Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B����͐V���������ʉ��̓�����`�����Ƃ���ŁA�h��ȑł��グ�ԉ������Ă��܂�������A�m�g�j�▯���͖�肪�������ƕ��炵�Ă��炸�A����ɂ͊�@���������B
�������A�J��Ԃ����A�����͌���ێ��������Ƃ��悢�킯�ł͂Ȃ��B�����W�҂́A����̂悤�Ȗ��������Ɛ؎��ɁA���������ɓ˂�����ꂽ���ƂƂ炦�A�Ή����l����K�v�����邾�낤�B�@ |
 �@�@ �@�@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 |


 �@
�@ |
|
���u�}�X�R�~�v���b |


 |
�@�@�@ �}�X�R�~����` �}�X�R�~����`
�@�@�@ �j���[�X�L���X�^�[�������� �j���[�X�L���X�^�[��������
�@�@�@ �}�X�R�~ �}�X�R�~
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����チ�f�B�A�Ɩ@�I���߁@ |
|
���͂��߂Ɂ@ |
���݁A�����̊ԂɁu�}�X�R�~�s�M�v�̋�C����������Ă���B���̔w�i�ɂ�1980�N��ȍ~�ɂ݂�ꂽ�ɂ��l���N�Q�ւ̎s���ӎ��̍��܂肪��̗v���Ƃ��Ă������Ă���B�����ɂ�����e�^�҂̐l���i��Ƃ����`�ŕ\��A�}�X�R�~�����Ăю̂Ă���߂ėe�^�Ҍď̂��̗p�����B����ɁA90�N��ɓ����āA�ƍߔ�Q�҂̐l���i��A�}�X�R�~�̎�ނ���v���C�o�V�[����낤�Ƃ�������ւƑ����Ă������B�ƍߔ�Q�ҒB�̉�ŁA���ɂ��ƍߔ�Q�҂̋~�ύ��߂���Ɠ����ɁA�}�X�R�~�ɂ���Q����̋~�ς��傫���咣������ʂ��J��Ԃ���Ă���(����A2002)�B
�܂��A�����͂Ɠ�������A�Љ�I�e���͂̋����l�ɐ��ʂ���Ԃ������肷��̂ł͂Ȃ��A�߂�Ƃ����Ƃ͂����ア����ɂ���l����|�\�l�̃v���C�o�V�[���ߓx�ɖ\�����Ƃ���ɕ\���̎��R�𗘗p����ꕔ�̃��f�B�A�̎p�����s���̔��������������ƂȂ��Ă���B
����ɁA�ŋ߂̏d�厖��(�u���{�T���������v�A�u�_�ˎ����A���E�������v�A�u�a�̎R�ŕ��J���[�����v�Ȃ�)�ɂ����ẮA�{���@�ւ������{���ɏ��o���O�̒i�K�ŁA�@�ւ�����̎s���ɋ^�f�������Ď�ޥ����X��������A���ƂȂ����B
������������w�i�ɁA�s�����m�肽���ƍl���Ă���A���邢�͎s�����m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƃ��f�B�A���l���I���e���ޕ��@���A���ۂɎs���Ɏ�����Ă���̂��^��Ɋ������B�����ŁA�ŋ߂̏d�厖���̒���1998�N7���ɋN�������a�̎R�̃J���[�����ɂ��Ď��グ�A�s�����m�肽���Ǝv���Ă��邱�ƂƁA���f�B�A���m�錠���ɉ����邽�߂ɂƍl���A��ނ��邢�͕��Ă��邱�ƂɈႢ�͂Ȃ��̂��������邱�ƂƂ����B
���̎����ɒ��ڂ������̗��R�͂���������B�܂��A2002�N��12���A�ѐ^�{���퍐�Ɏ��Y�����������n����A���̎����ւ̊S�x�����܂������Ƃł���B�����āA��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�ŋ߂̍����̒��ɂ���}�X�R�~�ɑ���s�M���̑���ł���B�ߔN�A�����̖����ł���͂��̃}�X�E���f�B�A�������ƓG�ΊW�ɓ]���Ă��܂����Ƃ��p�ɂɋN�����Ă���B�J���[���������l�̏����ꂽ�����̂ЂƂ��낤�B�Ȃ����̂悤�Ȏ��Ԃ��N�����Ă��܂��̂��B
���̎����̒̕��Ŏ��̖ڂɏĂ��t���ė���Ȃ��f��������B����́A�ѐ^�{���퍐���w�Ɍ������ăz�[�X�Ő��������Ă�����̂������B�������є퍐�̂��̍R�c�̎d���ɂ����������A�����̕w���͂����ɓo��A�퍐��̗l�q���̂����Ă���l�q�ɂ��������炢�������B���l�̉Ƃ��͂���������ē��X�Ƃ̂����v���C�o�V�[�N�Q���܂���ʂ��Ă����̂��A�^����m�邽�߂ɂ����܂ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��낤���Ƌ^��Ɋ������B�}�X�R�~�̎�ޕ��@����e�ȂǂɎ��Ɠ����悤�ɋ^����������l�͂��Ȃ������̂��ƍl�����̂ł���B
��ނ��鑤�̈ӌ��Ƃ��āA��ޗ̈�̌���͎��������̗ǎ��ɔC���Ăق����Ƃ������̂�����B�����̃}�X�R�~�ւ̕s�M���̑���Ƃ����������l����ƁA�ނ�̂����u�ǎ��v�Ƃ����̂́A�͂����č����Ɏ�����Ă���̂��^��Ɏv���B�������A���҂̊ԂɈӌ��̑��Ⴊ����ꂽ�Ȃ�A���f�B�A���́u�ǎ��v�Ƃ������̂��A�B���ȑ��ʂ������Ă���Ƃ������Ƃ����̑��Ƙ_���͊��S�ł͂Ȃ��ɂ���A�L�����Ƃ��ł���ł��낤�B�����āA���������f�B�A����̏������̂܂���Ă��܂�Ȃ����߂ɁA���f�B�A�E���e���V�[��g�ɂ��邱�Ƃ̏d�v���������Ă��邾�낤�B�}�X�R�~�̍s����ޕ������s���͂ǂ̂悤�Ɋ����Ă���̂��A���̈�[���̂�������ƍl����B�@ |
|
��1�D���f�B�A�̎g��
|
���f�B�A�͌���Љ�ɂƂ��āA�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ł���B�@���f�B�A�Ƃ́u�l�ԎЉ�ɂ����āA�l�Ɛl�Ƃ����сA�l�̖ڂƂȂ�A���ƂȂ��ē������}�́v�̂��Ƃł���A�l�X�̒m����l���Ɍ���I�ȉe���͂������Ă���B���f�B�A�́A���܂⎄�B�̒n���I�K�͂̎Љ�ρA���E�ς�����Ŏx���Ă���Ƃ����Ă悢�قǂ̋���ȑ��݂ƂȂ���(�n�ӁA1997)�B
���Ƃ��A�Љ�����Ă���̂͐�����o�ς̗͂ł��邪�A���̐�����o�ς̊�{�ƂȂ�����^�сA�l�X�ɂ��̓s�x�̔��f���������ƂȂ��Ă��������Ă���̂����f�B�A���B���������āA���f�B�A����������𑗂�ΎЉ�͍������A����Љ�̊�{���̂��̂�����Ă��܂����ƂɂȂ�B
���f�B�A�Ƃ́A���̎g�����ЂƂŁu�Љ�̋���v�ɂ��Ȃ邵�A�s���匠�̌����ʼn^�p�����Ȃ�A�y�������a�ȁu�Љ�̉^�c�⏕��i�v�ɂ��Ȃ���̂��B
���̂��Ƃ��l����ƁA���f�B�A���s���ɒ�����̓��e�Ɠ����́A���̂܂Љ�̎��Ɠ����A�s���匠�Љ�̍s���ɂȂ���Ƃ������A�܂��ǎ��̃��f�B�A���A���ǂ��s���Љ�����肦��Ƃ�������(�n�ӁA1997)�B
���̈Ӗ��ŁA���f�B�A�́A�܂��s���̗���ɗ������A���͂ƎЉ�ɑ���Ď��҂łȂ���Ȃ�Ȃ��g���ƐӔC��S���Ă���B
���͂ƎЉ�ɑ���Ď��҂Ƃ��Ă̎g���ƐӔC���ʂ������߂ɂ́A�������f�[�^�ƎЉ�I�^���ɂ���āA�匠�҂ł���s���Ɋ�b�����ƂȂ���𐳊m�ɓ`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@
�n��(1997)�ɂ��ƁA���f�B�A���{���S���ׂ������Ƃ͈ȉ��̂悤�ɑ�ʂł���B
�u1���������̒�(�ԑg�͂������ԑg�����܂�)�͂������̂��ƁA2�]�_�Ɖ��(�Ȋw�I�Ő�[�̖�肾���łȂ��A���������Љ���Ղɉ������)�A3�s���ւ̋c�_�̏�(���_�ƈӌ������̂��߂̃v���U�̒�)�A4�Љ��@�\�Ɛ��U����(�S�ԑg��ʂ��ĎЉ�̉��P�Ɖ��v�ւ̃L�����y�[����W�J����)�A5��y��(�����̔�������A�����ւ̊��͂ƂȂ�u�Љ�̏������v�Ƃ��Ă̊y���݂̎��Ԃ̒�)�A6�L���}�̋@�\(�D�ꂽ���i�̎Љ�ʂ̕ۏ�)�A7�Ԉ��E�����@�\(���N����q�ǂ��A�O���l���Q�҂ɂ������ł��A�y����ł��炦����e�̍H�v)�v(�o73)�@
���̂����W���[�i���Y���Ƃ��Ă����Ƃ��厖�Ȃ̂́A1�́u�v�A�܂萳�������̒��Ƃ����B�����A����ɊW������̂Ƃ��āA2�̘_�]�Ɖ���A����юЉ���ɂ��Ă̎s���̈ӌ������̏�Ƃ��Ẵ��f�B�A�̖����́A�ƂĂ��d�v�ł���B�@
�������A���{�̃��f�B�A�͂��������W���[�i���Y���I���ʂ������炩�]���ɂ��āA���̕������A5��y��6��`�}�̂Ƃ��Ă��傫�����p����Ă���̂�����ł���B
�܂��A���f�B�A���S���ׂ������ɂ��Ė��(2001)�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�p���̃��f�B�A�����ҁA�u���C�A���E�}�N�l�A�ɂ��A���ɁA���f�B�A�͎s���̎��ӂō������N�����Ă��邩��m�点��@�\������(���Ď��̋@�\�A�Ȃ����͊� �]���̋@�\)�B���ɁA���f�B�A�͎����̈Ӗ��ƈӋ`�ɂ��Đ���(����@�\)�B��O�ɁA���f�B�A�͌��̐����I�Θb�̂��߂̘_�d����Ă����B����́q���_�r�`���𑣐i���A���O�ɐ��_���t�B�[�h�o�b�N����@�\���������A���̋@�\�ɂ͔��Έӌ���\�������Ԃ���邱�Ƃ��܂܂��B��l�ɁA�W���[�i���Y���̔Ԍ��I�Ȗ����Ƃł��ĂԂׂ��������͂�o�ό��͂̍s���𖾂炩�ɂ��Ă����@�\�ł���B�~�n�G���E�S���o�`���t�̌��t�����A���_������ɉ��炩�̉e����^���Ă����ɂ͐������͂̍s���𖾂炩�ɂ���Ƃ������ƂŁA�u���J���v���ۂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��܂ɁA�����`�Љ�ɂ����郁�f�B�A�͐����I�����̎咣�̂��߂̓`�B��H�Ƃ��Ă��@�\���Ă����B���}�͎��������̐����v���O�����\�����Ƃ��ă��f�B�A�����p���A���f�B�A���܂��A�e�X�̐��}�ɊJ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v(�o137)
��ނ������Ƃ����R�ɕ\���ł��Ȃ���Ώ\���Ȏ�ޕ����͑��݂��Ȃ��B���E�ōŏ��ɕ\���ƕ̎��R�����@�Ō����Ƃ��Ė��m�ɕۏႵ���̂́A1791�N�̃A�����J���@�C�������ł���B���{�́A�����A�A�����̐�̉��ō��ꂽ���s���@�ɂ���āA�A�����J���@�Ɠ����̌��_�̎��R���m�����邱�Ƃ��ł����B���@21���͂����Ȃ闯�ۂ��Ȃ��Ɂu��̕\���̎��R�́A�����ۏႷ��v�ƋK�肵�Ă���B�������A�ō��ق́A���_�E�\���̎��R�������̕����ɂ���Đ��������Ƃ���������Ƃ��Ă���B�Љ�̍K���◘�v���d��������ꂾ���\���̎��R�͎�܂邱�ƂɂȂ�B�܂�A���f�B�A�̕\���̎��R��荑���̗��v���D�悳���Ƃ������Ƃ��B�@ |
|
��2�D�u�}�X�R�~�s�M�v�̔w�i
|
�`���ŏq�ׂ��悤�ɁA�s���̒��ɗ����u�}�X�R�~�s�M�v�̋�C��1980�N��ȍ~�ɋN�����ɂ��l���N�Q�ւ̎s���ӎ��̍��܂肪�ЂƂ̂����������Ƃ���Ă���B�ł́A�Ȃ��s���́u�}�X�R�~�s�M�v���傫���Ȃ����̂��A1980�N�ȍ~�̔w�i��U��Ԃ��Ă݂����B
1980�N��ɁA�}�̂̑�����A�ߓ��������ڗ����n�߁A���̒��ł����ɏT�����̔��s�����������������Ƃ�����(���{�ٌ�m�A����A1987)�B1980�N��͎ʐ^�T�����̃u�[���Ƃ������A81�N10���ɂ͐V���Ђ���wFOCUS�x���n������A�ꎞ��200�����ɒB�����B���̌���A83�N�Ɂw�t���C�f�[�x(�u�k��)�A�w�t���b�V���x(������)�A�w�G���}�x(���Y�t�H)�A�w�^�b�`�x(���w��)�ȂǂƑ�����(�R���A2000)�B
����(2001)�ɂ��ƁA���ɔ����̂������}�X�E���f�B�A�֘A�̃v���C�o�V�[�N�Q�����ɂȂ����Ǝv����i�ׂ�137������A���̂���100���ł͌����A�܂��Q�ґ������i�����Ƃ����B�N��ʂŌ���ƁA���̂悤�ɂȂ�B
�@�@�@�@�@�@50�N��@�@�@60�N��@�@�@70�N��@�@�@80�N��@�@�@90�N�ȍ~�@
���������@�@9���@�@�@�@6���@�@�@�@�@10���@�@�@�@22���@�@�@�@75��
�Y�������@�@8���@�@�@�@5���@�@�@�@�@1���@�@�@�@�@1���@�@�@�@�@�\�@
1980�N��̃v���C�o�V�[�N�Q�Ɋւ���i�ׂ̑����́A�ʐ^�T�����̓o��ɂ����̂Ƃ����Ă��邪�A90�N��̌����́A����ɉ����ă��X�^�f�̔�^�҂������O�Y�a�`������l�ő����̃}�X�E���f�B�A��ɑi�ׂ��N�����A���̒��Ƀv���C�o�V�[�i�ׂ�20���܂܂�Ă������Ƃ��傫���e�����Ă���Ƃ����B
�u���X�^�f�v�́A�v�ȂŃ��T���[���X�𗷍s���ɏP���A����������������O�Y�����A���͍Ȃɑ��z�̕ی����������Ēm�l�ɏe���������̂ł͂Ȃ�����1984�N1���́w�T�����t�x���A�ڋL���u�^�f�̏e�e�v�ō����������Ƃɒ[���Ă���B����Ƀe���r�ǂ���Ăɔ�т��đ呛���ɂȂ��������ł���B�Ȃ��ł������e���r�̃��C�h�V���[�̋����Ԃ肪�ڗ����A�ꎞ�͂ǂ̃`�����l�����Ă��A�u���X�^�f�v������Ă���Ƃ������������B�u�����͂���ȐV�������v�ƎO�Y���̉ߋ���v���C�o�V�[�����X�Ɩ\����A�O�Y���̉Ƃ̑O����u�������ܖ{�l���S�~���̂Ăɏo�Ă��܂����v�ƒ��p����قǂ������̂ł���(���E�ēc�A1996�G�쓈�E�V��E�O�c�E�����A1993)�B
���̂悤�ɁA�wFOCUS�x��w�t���C�f�[�x�Ƃ������ʐ^�T�����̕����������s���̃}�X�R�~�ւ̕s�M��������Â�������Ƃ��Ă������悤�B
�܂��A�s���̃v���C�o�V�[�N�Q�ւ̊S�����߂邫�������ƂȂ����ł��낤�o����������������B1987�N�ɁA���{�ٌ�m�A�����Â̑�30��l���i����ɂ����āu�l���ƕ|�̎��R�Ɛl���i��Ƃ̒��a�����߂ā|�v�Ƒ肵�āA�l���ƕ��߂��邳�܂��܂Ȗ��ɂ��Č������Ȃ���A�u�l���ƕɊւ���錾�v���̑����ꂽ�B�܂��A1997�N�ɂ́u�����Ɛl���Ɋւ���ψ���@�\(BRO)�v�Ƃ�����O�ҋ@�ւ��ݒu����A�ۑ�͑������̂́A�s������̃}�X�R�~�ւ̋����t����@�ւ��ł������Ƃ��v���̂ЂƂł͂Ȃ����B
�a�q�n�́A�u�]�c�ψ���v�Ɓu�����Ɛl���Ȃnj����Ɋւ���ψ���(�a�q�b)�v������ɐݒu���Ă���A�]�c�ψ���5���ȓ��A�a�q�b�ψ���8���ȓ�����\�������B�a�q�n�̐ݒu���ꂽ�ړI�ɂ��ċK���3���ɂ́A�u�����ɂ�錾�_�ƕ\���̎��R���m�ۂ��A���A�����҂̊�{�I�l����i�삷�邽�߁A�����ւ̋��ɑ��āA�����҂̗��ꂩ��v�����L���ɑΉ����A���m�ȕ����ƕ����ϗ��̍��g�Ɋ�^����v�Ɩ��L����Ă���(�n粁A2001)�B
�����āA�s���́u�}�X�R�~�s�M�v��w�i�ɁA2001�N3��27���A�u�l���ی�@�āv���t�c���肳�ꂽ�B�l���ی�@�́A�l���ی�@1���̒��ŁA�d�q�v�Z�@���������l���̎�舵���ɂ��Ă̊�{�I�ȃ��[�����߂邱�Ƃɂ���āA�l�̌������v��ی삵�A�����čs���̓K���E�~���ȉ^�c��}�낤�Ƃ�����̂��ƒ�߂��Ă���(�r�c�A1993�AP155)�B���̖@�č��̑����i�K���烁�f�B�A���u���f�B�A���K�����A�\���E�̎��R��N�����˂Ȃ��v�Ɣᔻ���Ă����ɂ�������炸�A���{�����_���������Ȃ��܂ܖ@�Ă̐�����ڎw�����Ƃ��邱�Ƃ��l����ƁA�����Ɂu�}�X�R�~�s�M�v�̌㉟�������͂ł��邩������������ł��낤(����A2002)�B
���ɁA1980�N�ȍ~�ɋ�̓I�ɂǂ̂悤�Ȏ������N�����̂��܂Ƃ߂Ă݂����B
�܂��A��Q�̒��ڂ��ꂽ���������������グ�Ă݂邱�Ƃɂ��邪�A1980�N����\���鎖���Ƃ��āA�u���X�^�f�v������B���̎����́A��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA81�N�ɕč����T���[���X�s�ŋN�����u���X�e�������v�ŁA�O�Y�a�`�����E�l�Ȃǂ̍߂ɖ��ꂽ���̂ŁA���{���ɐ�s����ٗ�̓W�J�����ǂ�A�ߔM�����ƂȂ���(�����{�V���ЁA2000)�B�O�Y�����}�X�E���f�B�A�e�Ђɑ��ċN���������_�ʑ������i�ׂ̌�����300���ȏ�Ƃ�500���ȏ�Ƃ������Ă���B���̂��������Ŋ��p���ꂽ���̂Ȃǂ������ƁA�ٔ��́u�����v��8���߂��ƂȂ���(����A2001�G�l���ƕE�A����A2003)�B
1990�N��ɓ���ƁA80�N��ɔ�ׁA��Q������ɖڗ��悤�ɂȂ�B
1994�N�ɂ́u���{�T���������v���N����B���̎����ł́A�u���X�^�f�v�Ɠ��l�ɁA�x�@�̌�����{���ƁA�x�@���ɗ��肫�����}�X�R�~�̎v�����݂ɂ���Ď����ɖ��W�ȉ͖�`�s�����u�Ɛl�v�Ɏd���ďグ���Ă��܂����B�}�X�R�~�̊��S�ɉ͖쎁��Ɛl�������́A���N��3���܂ő�����(�����A2002)�B
1997�N3���́u�����d�͏����Ј��E�l�����v�ł́A��Q�҂͍��w���ŁA���͓����d�͂̊Ǘ��E�Ƃ��ċΖ����A��͊X���Ƃ��ďa�J�̒��p�ɗ��Ƃ�����ʐ��������Ă����Ƃ��ꂽ���Ƃ���A���̎��������傫�Șb��ƂȂ����B�����̃}�X�R�~�́A�������̂��̂Ɨ��ꂽ��Q�҂̃v���C�o�V�[�̖\�I�ɏW�����A�ƍߔ�Q�҂Ƃ��̉Ƒ��̐l����N�Q�����ށA�̖�肪�V���ɐ����������ƂȂ���(���{�ٌ�m�A����A1999�G�����A2000�G�R�A�����V��ЁA2000)�B
������1997�N5���ɋN�������u�_�ˎ����A���E�������v�����ڂ��ꂽ�B���̎����́A��Q���N�̈�̂̈ꕔ�����w�Z����O�Ŕ�������A��^�҂Ƃ��đߕ߂��ꂽ���N��14�̒��w���Ƃ����Ռ��I�Ȏ����ŁA�ʐ^�T���������̎����̔�^�҂ł���Ƃ��ꂽ���N�̎ʐ^�ƉƑ��ɂ��Ă̋L�����f�ڂ��A���N�@�̐��_�݂ɂ������Ƃ��Ė��ƂȂ���(���{�ٌ�m�A����A1997)�B
1998�N7���ɋN�������u�a�̎R�J���[�ŕ����������v�ł́A�ꕔ�̕@�ւ̎�ނ���ѕ́A����̌l�̏Z���𒋖�ɂ킽��Ď����A���̎q�ǂ��̎ʐ^���B�e����ȂǁA�l�̖��_�E�v���C�o�V�[�₻�̉Ƒ�����ыߗZ���̐����̕�����N�Q�������肩�A����̌l�̌��^�����X�ɒT�����A���ƂȂ���(���{�ٌ�m�A����A1998)�B
���̂悤�Ƀ}�X�R�~�����s���Ƃ����Η��W�͂��������ɉ��P���ꂸ�A�v���C�o�V�[�N�Q�����i�ׂ͑��������ł���B�����ŁA�ȉ��ł̓v���C�o�V�[�̌����▼�_���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�����������I�S�͈̔�(���l�����l���Ȃ�)�͖@���ł͂ǂ̂悤�ɉ��߂���Ă���̂��ȂNJ�{�I�Ȏ����ɐG��A���_�ʑ���v���C�o�V�[�N�Q�ɂ��čl���Ă݂����B�@ |
|
��3�D���_���ƃv���C�o�V�[
|
��(1)���_���Ɩ��_�ʑ�
�u���_�v�Ƃ́A��ϓI�Ȗ��_����ł͂Ȃ��A�l���Љ��Ă���q�ϓI�ȕ]���������B�l���Љ�̒��ŕ�炵�Ă���ƁA����̐l����Ȃ�炩�̕]�����邱�ƂɂȂ邪�A���ꂪ���_�ʑ�����ɂ���Ƃ��́u���_�v�Ƃ���Ă���B���������āA�u�����͂��������l�Ԃ��v�Ƃ�������ϓI�ȕ]���́A�u���_�v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A���_�ʑ��Ƃ́A�l�̎Љ�I�ȕ]����ቺ�����邱�Ƃ��Ӗ����Ă���(�c���A1998�G��c���A1999)�B
�����ŁA�܂��A�Y�@�̒��ł̖��_�ʑ��̈����ɂ��ďq�ׂ����B
�}�X�E���f�B�A���s�Ȃ������l�̖��_��N�Q�����ꍇ�A���_�ʑ��̐ӔC��������B�Y�@230���ɂ����āA�ȉ��̂悤�ɋK�肳��Ă���B
��1���@���R�Ǝ�����E�����A�l�̖��_��ʑ������҂́A���̎����̗L���ɂ�����炸�A3�N�ȁ@�@�@�@�@ ���̒����Ⴕ���͋�������50���~�ȉ��̔����ɏ�����B
��2���@���҂̖��_��ʑ������҂́A���U�̎�����E�����邱�Ƃɂ���Ă����ꍇ�Ł@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�Ȃ���A�����Ȃ��B
�������A���Ƃ��A�����Ƃ̊����ɑ���ᔻ�Ȃǂ͂ƂĂ�����Ȃ�B�����ŁA�Y�@�͑�230����2�Ŏ��̂悤�ɒ�߂�B
��1���@�O���1���̍s�ׂ������̗��Q�Ɋւ��鎖���ɌW��A���A���̖ړI�������v��}��@�@�@�@�@���Ƃɂ������ƔF�߂�ꍇ�ɂ́A�����̐^�ۂf���A�^���ł��邱�Ƃ̏ؖ����������Ɓ@�@�@�@�@���́A������Ȃ��B
��2���@�O���̋K��̓K�p�ɂ��ẮA���i����N�����Ɏ����Ă��Ȃ��l�̔ƍߍs�ׂɊւ���@�@�@�@�@�����́A�����ɗ��Q�Ɋւ��鎖���Ƃ݂Ȃ��B
��3���@�O���1���̍s�ׂ����������͌��I�ɂ��������̌��҂Ɋւ��鎖���ɌW��ꍇ�ɂ́A�@�@�@�@�@�����̐^�ۂf���A�^���ł��邱�Ƃ̏ؖ����������Ƃ��́A������Ȃ��B
�܂�A�����̗��Q�Ɋւ��(�����̌�����)�A���v��}��ړI�ł̕\���ł����(�ړI�̌��v��)�A�w�E���ꂽ�������^���Ȃ�(�����̐^����)�A�������Ȃ��Ƃ����A����u�ƐӖ@���v����߂��Ă���(��A2001�G�l�c�A1993)�B
����A�����ł́A���_�ʑ��͕s�@�s�ׂƂ݂Ȃ���A���@��709�E710���ɂ��A���Q�����ӔC�̑ΏۂƂȂ��Ă���B���@�ɂ����Ă��Y�@�Ɠ������A�������ی삳��Ă���ƍl�����Ă���A���̂��߁A�^�������\���邱�Ƃ����_�ʑ��ɂȂ�ƍl�����Ă���B�����ł��������Ƃ́A������Ȃ��\�ʂ����̖����E�]���̂��Ƃł���B�������A�Y�@��͌��R�Ǝ�����E�����邱�Ƃ����_�ʑ��̗v���Ƃ���Ă��邪�A���@�Ŗ��_�ʑ����������邽�߂ɂ́A���̗v���͕s���Ƃ͍l�����Ă��Ȃ��B���������āA�ӌ��̌��\�ɂ���Ė��_��������ꂽ�Ƃ��Ă�������̖��_�ʑ��͐�������(����A1994�G�����A1999)
�Ȃ��A���@�͖��_�ʑ��ɑ���~�ϕ��@�Ƃ��ď]���̑��Q��������(�Ԏӗ�����)�ɉ����āA��723���ł́u���l�m���_���ʑ��V�^���҃j�V�e�n�ٔ����n��Q�҃m�����j�������Q�����j��֖��n���Q�����g���j���_���X���j�K���i�����������X���R�g�����v�ƋK�肵�Ă���B���̋K������ƂɁA�ٔ����͎ӍߍL���Ȃǂ��ꂼ��̃P�[�X�ɉ�������������𖽂��邱�Ƃ��\�ł���(��A2001)�B
��(2)�v���C�o�V�[�̌���
�v���C�o�V�[�̌����Ƃ������̂́A��r�I�V�����l�����ł���B���̌����́A19���I�̃A�����J�ŁA�u�ЂƂ�łق��Ă����Ă��炤����(right to be let alone)�v�Ƃ��Ĕ��W���Ă����B�܂�A�������̒��ő��l�ɒm��ꂽ���Ȃ����Ƃ��A���̂܂ܑ��l�ɒm�点�Ȃ��ł��錠���Ƃ������ƂɂȂ�B
�v���C�o�V�[�̌������A���{�̍ٔ����ŔF�߂�ꂽ�̂́A�u���̂��Ɓv�����Ɋւ��铌���n�ٔ���(��39�E9�E28����385��12��)�ł���B�����́A�����s�m���I���̌��҂ƂȂ����l���Ƃ��̍Ȃ̊Ԃ̈������`�����A�O���R�I�v�̏����u���̂��Ɓv���߂���A�����̃��f���Ƃ��ꂽ���O���ȑ�b���A�O���R�I�v�Əo�Ō��̐V���Ђɑ��āA���Ȃ̃v���C�o�V�[��N�Q���ꂽ�Ƃ��ĈԎӗ��ƎӍߍL���𐿋��������̂ł���B�����́A�v���C�o�V�[�����u���������݂���Ɍ��J����Ȃ��Ƃ����@�I�ۏ�Ȃ��������v�ƒ�`���������ŁA���́u�s�@�ȐN�Q�ɑ��Ă͖@�I�~�ς��^������܂łɍ��߂�ꂽ�l�i�I�ȗ��v�v�ł���Ƃ��A�Ԏӗ��̎x�����𖽂����B
�v���C�o�V�[�̌����N�Q�̗v���Ƃ��ĕK�v�Ȃ̂́A���J���ꂽ���e���A1��������̎����܂��͎�������̎����炵������邨����̂��邱��(��ʂɂ͕v�w�E�Ƒ��W�A�����W�Ȃǎ������Ɋւ��鎖�����v���C�o�V�[�ƍl�����Ă��邪�����Ɍ��肳��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�O�ȂȂǂ��v���C�o�V�[�ƔF�߂��Ă���B)�A2��ʂ̐l�X�����J��K�v�Ƃ��Ȃ��ł��낤�ƔF�߂��邱�ƁA3��ʂ̐l�X�ɖ����m���Ă��Ȃ������ł���Ƃ������Ƃ��B�������A����n��ł͌��m�̏��ł��A�S���I�ɂ͂����łȂ��Ƃ������ꍇ�ɂ́A�v���C�o�V�[�̐N�Q�ɂȂ邵�A���Ԃ��o�߂��邱�Ƃɂ���āA�ȑO�͌��m�̎������������Ƃ��v���C�o�V�[�ƂȂ邱�Ƃ����肤��(�l�c�A1993�G�c���A1998�G��c���A1999�G�����A1999�G�r�c�A1993�G����A1994)�B
�v���C�o�V�[�N�Q�ɂ́A����f���閾�m�Ȋ�͂Ȃ��A�P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�Ŕ��f���邵���Ȃ��Ƃ����B���\���邱�Ƃ������̗��v�ɊW���邱�ƂȂ̂��A����Ƃ��P�ɋ����{�ʂɂ����Ȃ��̂��A�܂��ΏۂƂȂ�l�������l�����l���Ȃǂɂ���āA���̌��ʂ͈���Ă���B�����Ƃ�������̏ꍇ�́A�v���C�o�V�[�̋y�Ԕ͈͂�����ȊO�̐l��苷���ƍl����ׂ��ł���(�q��A1991)�B
��(3)�ߏ��ނƃv���C�o�V�[
�ߏ��ނƂ����̂́A���肪���ۂ��Ă���̂Ɂu���܂Ƃ��A�҂������A���H�ɗ����ӂ�����A������A�����|���A�d�b�����ԑтɂ�����炸������v�Ȃǂ̍s�ׂ��p���I�ɔ���������A����̐����̕��������Q�����肷�邱�Ƃ�(�ю��A2002)�B�����́A�d�厖���ŋL�҂����ʏ�̎�ލs���Ǝ���d�ł���B�u�ɂ��v���C�o�V�[�N�Q�v���u�ߏ��ށv���̕K�v���A����������Ύ����̌������A�ړI�̌��v���Ɩ��ڂȊW������B�{�l�ɂƂ��ẮA���炩�ɂ������Ȃ������A�ߏ�Ɗ��������ލs�ׂł����Ă��A�����̂��߁A�����̂��߁A�����̒m�錠���̂��߂Ɏ�E���ׂ��ꍇ������Ƃ���(�ю��A2002)�B�@ |
|
��4�D���I�S��
|
��(1)���l
�܂��A�v���C�o�V�[���ł������A���I�S���͈̔͂��ł��L���Ƃ炦���邱�ƂɂȂ�̂��A�����Ƃ�������Ƃ��������l�ł���B�Ƃ��ɁA����c���Ȃǂ̐����Ƃɂ����ẮA�c���ɂӂ��킵�����f�����ŁA���̐l�̐l����m�邱�Ƃ͏d�v���Ƃ��Ƃ���Ă���B�ǂ̂悤�Ȑ����𑗂��Ă��邩�́A�l����l�i�f����ޗ��ɂȂ邽�߁A���I�Ȓj���W�������ȊS���ɂȂ�A�ނ�������ׂ����̂��Ƃ�����߂�����(�c���A1998�G��c���A1999)�B
�܂��A���l�̏ꍇ�ɂ́A���̐l���ǂ̏@����M���Ă��邩�Ƃ������ƂɊ����邱�Ƃ̓v���C�o�V�[��N�Q����Ƃ�������B�������A�����̕���ł͏@���Ɛ����̊W���ǂ�����ׂ����Ƌc�_������Ă��邽�߁A�����Ƃ��ǂ̂悤�ȏ@����M���Ă��邩����邱�Ƃ́A���l�̂��邱�Ƃ��Ƃ�����(��c���A1999)�B
��(2)���l
���l�̏ꍇ�ɂ́A���҂̐l������ɐ��_�I�ȉe����^���A���̂̍l�����Ɏw�j��^����悤�Ȑ����ƂȂǂ̌��l�Ƃ͈قȂ�A�����̎s���ɉe����^����n�ʂɂ͂Ȃ��̂ŁA���������p���ꂽ��A����ėp����ꂽ��Ƃ������Ƃ��Ȃ��B�܂��A����i��Ō��l�Ƃ��Ă̒n�ʂ������ƂƂ͈Ⴂ�A���l�͂��̗����I�ׂ�킯�ł͂Ȃ��B���������āA���l�Ƃ��Ă̒n�ʂɂƂǂ܂��Ă������́A�Љ�I�Ȕᔻ���邱�Ƃ�\�����Ă����Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��Ȃ��B
���Ƃ��A�����ꍇ���������Ƃ��Ă��A����͔ƍ߂̗e�^�҂ł�������A�ƍ߂⎖�̂Ɋ������܂ꂽ�肵���Ƃ��ɂ́A�{�l�̎�����N��Ȃǂ����邪�A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�ƍ߂⎖�̂��Ƃ����Љ�I�ɐ����ȗ��R����ł���A���̂悤�Ȏ�������邱�Ƃ͕K�v���Ƃ���Ă���B�������A�ꍇ�ɂ���Ăǂ��܂ŐG��邱�Ƃ�������邩�Ƃ�����̓I�Ȋ�͞B���ŁA��肪�����邱�Ƃ�����(��c���A1999)�B
��(3)�L���l�^�|�\�l�@
�|�\�l��A�X�|�[�c�I��ȂǂƂ������L���l�̃X�L�����_�������C�h�V���[�ȂǂŎ��グ��ꂽ�ꍇ�ɁA���ꂪ��Q�ɓ����邩�ǂ����̔��f�͂ނ��������B
�A�����J�ɂ����ẮA�f��o�D��X�|�[�c�I��̂悤�ȎЉ�I�ɗL���Ȑl�����́A��ʂ̐l�Ƃ͕ʈ�������邱�Ƃ������B�������A���{�̍ٔ��ł́A�P�Ɍ|�\�E�ȂǂŊ��Ă��Ė�������Ă���Ƃ��������Ō��I���݂ł���Ƃ��ꂽ�l�͂��Ȃ��Ƃ���(����A1996)�B���I���݂Ƃ��Ĉ���ꂽ�l�ƈ����Ȃ������l�Ƃ̍��́A�Љ�I�Ȍ������Ǝ����I�ȉe���̗͂L���ɂ���Ƃ����B��Ƃ�|�\�l�A�X�|�[�c�I��ɂ͂��낢��Ȑl�����āA���̐l�����������x��L���x�̈Ⴂ�ŕ����邱�Ƃ͕s�\�����A�Љ�I�Ȍ�����������l�Ȃ��l�̍��͂͂����肵�Ă��邩��ł���(����A1996)�B
���������u�|�\�l�v�Ƃ́A�u�f��A�����A���y�A�̗w�A���x�Ȃǂ́w��O�I�x�Ȍ|�\���s�Ȃ��l�v(�L����)�̂��Ƃ��w���B
���āA�|�\�l�͑�O�Ƃ͕ʐ��E�̐l�ŁA���҂̐����͂������ꂽ���̂������B���̂��߁A��O���|�\�l�̃v���C�o�V�[�ɋ����������Ƃ͂Ȃ��A����̑Ώۂł����Ȃ������B�������A���|�\�l�́A�e���r��T������ʂ��đ�O�ɐg�߂ȑ��݂ƂȂ�A�|�\�l�ƈ�ʂ̐l�Ƃ̋��E�͞B���ƂȂ����B�|�\�l�Ƃ��Đ�������ɂ́A��O�Ɉ�����A�b��̑ΏۂƂȂ邱�Ƃ��d�v�ƂȂ����̂ł���(1987�A�O��)�B���̂��߂ɁA�|�\�l�̒��ɂ́A���f�B�A�Ɏ��グ���Ă��炤���ƂŐl�C���l�����A�ێ�����l������A���ʂ̐l�Ȃ猙����悤�ȃv���C�o�V�[��������\���邱�Ƃ�����B���̂悤�Ȃ��Ƃ��l����ƁA���I�S���͈̔͂���ʂ̐l���L���Ƃ炦���Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ�������(�c���A1998�G��c���A1999)�B
��(4)�ƍߎ���
�Y�@230���̓��͌��i��N�O�̔ƍߎ����̎w�E�ɂ͌�������������̂Ƃ݂Ȃ��Ă��邪�A���̏̓K�p���邽�߂ɂ́A�ƍ߂Ƃ��Ďw�E������������Ɏ��ۂɔƍ߂��\�����邩�A����ɋ߂���ԂɂȂ邱�Ƃ�K�v�Ƃ���B�ƍߎ����̎w�E�́A���X�ɂ��Ď��I�����ɓ��ݍ���Ńv���C�o�V�[��N�Q�����������A�w�E���ꂽ�ƍߎ��������ۂɔƍ߂��\�������Ƃ��́A��Q�҂͔ƍߗe�^�҂ƂȂ��ăv���C�o�V�[�N�Q����@�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ꍇ�������̂ɑ��āA�ƍ߂��\�����Ȃ������ꍇ�́A��Q�҂͎��l�ɂƂǂ܂�A�v���C�o�C�V�[�N�Q�͂قڊm���Ɉ�@�ƂȂ�(����A1996)�B
�ƍߏ���I���ł���ׂ����R�͐���������B�܂��A�Y�������E�Y���ٔ��ł͌����͂��s�g����A�������邢�͍ٔ������I�ȏ��ƂȂ邱�Ƃ��w�E�����B���̂悤�Ȍ��I���Ƃ��Ă̔ƍߏ��́A�݂�Ȃɋ��L����邱�Ƃɂ���āA�����͂ɑ���ᔻ�I�Ď����L���ɂȂ����Ɠ����ɁA�{���ɑ��鍑���̋��͂��\�ɂȂ�B�܂��A�ƍߏ��́A�Љ�ɂƂ��ċً}�̎Љ�h�q���l����ƕK�v�ȏ��ł����āA�܂��A�ƍ߂̌��������Ƃ߁A�ꍇ�ɂ���ẮA�Љ���̐ӔC�̈ꕔ�����L�����Ȃ���@�������A�Ƃ����Ӗ��ł������I�S�̑ΏۂƂȂ�ׂ���Ƃ���(��A2001)�B
��(5)�A�����J�Ɠ��{�ɂ�����ƐӖ@��
�A�����J�ɂ����āA���f�B�A�͌��l����I�l���ɂ��Ă͖��_�ʑ��̐ӔC�����邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��B�Ȃ��Ȃ�A���l�A���邢�͌��I�l���ɂ����āu�����̈��Ӂv�Ƃ����@��������Ŋm������Ă���Ƃ������R���炾�B�u�����̈��Ӂv�Ƃ́A�@�ւ����̕��e�����U�ł��邱�Ƃ�m���Ă������A���邢�͐^�U�ɂ܂������S���悹���ɕ��A�����̕�����ɑ��Q��^���邱�Ƃ�F�����Ă������Ƃ��w���B�܂�A���l���́A���_�ʑ��ŏ��i�����邽�߂ɂ́A�u�����̈��Ӂv�����������Ƃm�ɗ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�Ӑ}���Ȃ��łȂ��ꂽ���U�́̕A�̎��R�S�̂���邽�߂ɂ͊ÎȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����l�����炾�Ƃ���(��c���A1999�G�ю��A2002)�B
�������A�u�����̈��Ӂv�����������ǂ����́A�����܂ŕ@�ւ̎�ςɂ���Ĕ��肳���B�܂�A������ꍇ�ɁA�@�ւ��ʏ�ł͍l�����Ȃ��悤�ȕs���ӂɂ���Ă��̓��e��^�����ƌ�M�����Ƃ��Ă��A��ϓI�ɂ͂��̕��������ƍl���Ă����̂ł��邩��A�u�����̈��Ӂv�͑��݂��Ȃ��̂ł���(��c���A1999)�B���������āA��������l���������邱�Ƃ͑�ϓ�����Ƃ��Ƃ������Ƃ�������B
���̂悤�ɂ��āA�A�����J�̃}�X�R�~�́A���l����I�l������̖��_�ʑ��i�ׂ̋���ɂ���āA������邱�Ƃ͂܂��Ȃ��Ƃ�����B
����ɑ��ē��{�͂ǂ����B���_�ʑ����������Ȃ����߂ɂ́A���������Ɍ����������邱�ƁA�͌��v�ړI�ł��邱�ƁA���e�Ɍ��͂Ȃ�����(��肾�Ƃ��Ă��^���ƐM���Ă�ނȂ��������������)�����ׂĕ@�֑��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��c��(1999)�ɂ��ƁA���������ǂ̂悤�Ȑl�ł���A�@�ւ����̗v�����ؖ�����Ƃ�������́A���ׂĂ̐l���Ɏ�舵���Ƃ����_�ŁA�ꌩ�u�@�̉��̕����v�ɓK�����̂悤�Ɍ����邪�A���ۂɂ͌��l�ɑ���ߑ�ȕی�Ǝ��l�ɑ���ߏ��̕ی�Ƃ������ʂ݂����Ă���Ƃ����B
�����āA���l�́A�e��̌��͂⌠����L���A�����̎s���̐����ɉe����^����n�ʂɂ���A�ނ炪�^����ꂽ�����𐳂����s�g���Ă��邩�ǂ����`�F�b�N���邱�Ƃ͕̂����Ƃ��d�v�Ȗ�ڂł���B���̖�ڂ��\���ɉʂ�������̂��̎��R�ł��邩��A���l�Ɋւ���́A��{�I�Ɏ��R�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@ |
|
��5�D�ƍߕ�
|
��(1)�ƍߕƂ�
�܂��T�^�I�Ȕƍߕɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂����B
�ƍ߂̎�ށE�́A�x�@�A���@���A���̑��̑{���@�ւɑ�������A������̎�ނɂ���Ďn�܂�B�܂��A��Q�҂̍��i�⍐���Ƃ����s�ׂɂ���āA��ނ��J�n�����ꍇ���悭����B����ɁA�V���̓Ǝ���ނɂ���ĕ��n�܂�A�r������{���@�ւ��W����ꍇ������B���̓x�����͂��낢�날�邪�A�ǂ̏ꍇ�������͂̑{���Ɉˑ����Ĕƍ߂Ɋւ�������}�X�R�~�������肷��̂ł���B�ʂ̂�����������A�{���̔ƍߕ́A��ԏ��߂̏���{���@�ւɈˑ����A���ǂ̓����̐ߖځA�ߖڂɍ��킹�Ĕƍ߂Ɋւ���j���[�X����Ă���B�{�����ǂƂ̖����A�����Ƃ����ᔻ�́A���̂����肩�琶�܂����̂��Ƃ���(���{�V����������A1990)�B
�ƍߕɂ́A��̖���������B�ЂƂ́A����������̂܂ܕ��邱�Ƃł���A�����ЂƂ́A�{���ɂ���������͂̍s�g���ÂȎ��_�ł�����Ɗώ@���邱�Ƃł���Ƃ����B����������A�{�������������s�g����Ă��邩�ǂ������Ď����邱�Ƃł���B�ƍ߂̍����҂͑{���@�ւɌ���Ȃ��B�����Ɋ������܂ꂽ��ʐl���ƍ߂����i�A���邢�͍�������B�ǂ̏ꍇ�ł��A����̓����҂̌�������咣�A�ߕߎ����A�N�i�����A���i�����Ȃǂ݂̂ɗ���̂͊댯�ł���B���̓_�Ɋւ��ĕ��̌��ؔ\�́A���邢�͎�ޔ\�͂�����Ă���(���{�V����������A1990)�B
��(2)������
���݁A���{�̕@�ւł́A���������A�K�v�ɉ����ē����͈̔͂��g�傷��Ƃ������j���Ƃ��Ă���A�������̗p���Ă��Ȃ��B
�ƍߕɂ������^�҂̌��������̍����͂ǂ��ɂ���̂��낤���B�����V���Ђ�1990�N8���ɂ܂Ƃ߂��A���ψ���u�V�����������߂����āv�ɂ��ƁA���������Ƃ��鍪���͎��̂悤�Ȃ��̂ł���(���c�A1994)�B
1�@�s���������������ƍ߂̔�^�҂���肷�邱�Ƃ́A�ƍߎ������̂ƂƂ��ɏd�v�Ȍ��� �@�̊S���ł���A�����邱�Ƃ͏\���Ɍ��v��������B
2�@�����̕��Q�ɂ��ẮA�l����N�Q���Ȃ��̎d���A�L���̏������ɂ���đ@�����l����ׂ��ł���B
3�@���{�ɂ�����u�v���X�̎��R�v�͌��͋@�\�Ƃ̊W�ł܂��\���ɕۏႳ��Ă��炸�A�@�����ɕύX���邽�߂ɂ́A�����J���x�̎����ȂǑO���������������邱�Ƃ��@�K�v�B
4�@�����ł́A�u�N���v�u�N���v�u�ǂ������v�u�Ȃ��v�Ȃǂ̓ǎ҂��K�v�Ƃ���f�[�@�^�A�����ׂ̍��ȕ����𐳊m�ɓ`���邱�Ƃ�����ɂȂ�B
5�@������O��Ƃ���A�{�����ǂ���^�҂̎������Ƃ��邨���ꂪ����A�s���@���{�����s�g���`�F�b�N���邱�Ƃ����ނ��������Ȃ�B
6�@�����́A�n��Љ�����̐E�Ƃ̐l�����̊ԂŁu�Ɛl�{���v�����Ȃǂ̎��Ԃ����@�������ꂪ����B
7�@�����������Ƃ����ꍇ�A��ނ͊Â��Ȃ�A�\�����B���ɂȂ邨���ꂪ����B
8�@�����͂Ƃ������A�����_�ł́A�����̓ǎ҂����������ւ̓]�������߂Ă���Ƃ͍l���@�ɂ����B
���̑��ɂ��A�����ɂ��ƍߗ}�~�͂̌��ʂ���܂�A���������l�߂��~�����Ƃ��ł���A�Ȃǂ̈ӌ����������Ă���(����A1993)�B
��(3)������
������`�́A1980�N�㔼���琷��Ɏ咣�����悤�ɂȂ�A�}�X�R�~�̔ƍߕɂ�閼�_�E�v���C�o�V�[�N�Q����l����邽�߂̗L�͂ȕ��@�̂ЂƂ��Ƃ��ꂽ�B����́A�}�X�R�~����^�ҁE�퍐�l�E�݊Ď҂ɂ��āA�����E�N��E�Z���E�E�Ƃɂ���Ă��̐l���{�l�ł���Ɛ����ł���L����ʐ^����Ȃ����Ƃ���e�Ƃ�����̂��B���݁A�}�X�R�~�́A�����N�҂�_��Q�҂̔ƍ߂ɓ�����`���̗p���Ă��邪�A�����̂���Ԕ͈͂��L���ē����������Ƃ��A�����ɂ����O�I�Ȃ��̂ɂ��Ă����̂����̕��@�ł���(����A1993)�B
������`���咣����闝�R�Ƃ��Ă͎��̂悤�Ȃ��̂��������Ă���(���c�A1987�G����A1993)�B
1�@�����ɂ����Ƃ��Ă��A�x�@�̋L�Ҕ��\�̒i�K�ł̓����������킯�ł͂Ȃ��A��ނ��� ���ōs�Ȃ��邽�߁A���A���̓`�F�b�N�@�\��������Ƃ͎v���Ȃ��B
2�@�����̔ƍߗ}�~�͂�l�ߖh�~�ɂ��āA���݂̔ƍ߁E�l�ߔ����̏��l����� �@ �@ �^�⎋����������Ȃ��B
3�@�����ɂ���Ă����A�ƍ߂̊j�S�ɔ����ނ��\�ƂȂ�A������̌��ɂ������@�@�@�邱�Ƃ��ł���B�@
4�@�����ɂ�����ƍߕ́A��^�ҁE�퍐�l���g�����łȂ��A���̉Ƒ���ɂ��l���@ �@ �N�Q�������炵�A���Ԃ��̂��Ȃ����̂ƂȂ�B
5�@�����ł́A�ߕ߁A�N�i�A�������̒i�K�ł́u���薳�߁v�͂Ȃ��ꂸ�A�s���ɔ�^�@�@�@�ҁ��^�Ɛl�̎v�����݂������A���ꂽ�҂ɑ��郊���`�ɂȂ邨���ꂪ����B
����܂ł��A�V���E�́A1�����N�҂̔�^�ҁA2���_��Q�̂����^�ҁA3�Q�l�l�A�ʌ��ߕߎҁA4�w���\�s�����̔�Q�ҁA5���E�A�S�������ҁA6��^�҂̉Ƒ��A7�Y�������ҁA�Ȃǂɂ��Ă͌��������ŕ��Ă����B
���̂����A�w���\�s�����̔�Q�҂ɂ��ẮA���̔�Q�҂��E���ꂽ�ꍇ�́A�]���͎����ŕ��Ă������A1990�N1���ɋN�������q�����R���N���[�g�l�ߎE�l�����̕ŁA��Q�҂̏��q���Z���̎����A�ʐ^���V����T�����A�e���r�ŕ��ꂽ���ƂɊ֘A���āA�����ٌ�m�A�����c���A�w�l�����ƂȂǂ��瓯�N5���A�A���ŋ����R�c���}�X�R�~�e�ЂɊ�ꂽ�B�@���������ᔻ���āA�����V���͓��N8�����烌�C�v�����ł͔�Q�҂��E���ꂽ�ꍇ�������Ƃ�����j�\�����B�܂��A���߁E�y�ߎ������̔�^�҂ɂ��Ă��A����������Ђ����������Ƃ����B
���̂悤�ɁA�V���E�͐l���N�Q��[���Ɏ~�߁A����I�Ȕ��f�Ŕ�^�҂�W�҂̐l����z�����������͈͂̊g���i�߂Ă��邱�Ƃ������ł���B(���c�A1994)�B
��(4)�u�e�^�Ҍď́v�����܂��܂�
�ƍߕ̂�������߂����āA�d�v�ȃe�[�}�Ƃ��Ă���������̂ЂƂƂ��āA�e�^�҂́u�h�́A�ď́v������B���{�̃}�X���f�B�A�ł́A1984�N3���܂ŁA�ƍߎ����őߕ߂��ꂽ�e�^�҂̖��O�́A�����ꕔ�̗�O�������A���ׂČĂю̂Ă������B�e�^�҂ɑ��鍑�������z�����āA�������Ă������̂ł���B
���̌Ăю̂Ă���߁A�u�e�^�ҁv�Ƃ����ď̂����悤�ƌ����o�����̂�NHK�ł���B���N4������NHK�P�Ƃł����{����Ɣ��\�����BNHK�́u�ƍߕƌď̊�{���j�v�\���A�ߕߎҁE�퍐�l�ɂ͌����Ƃ��āu�e�^�ҁv�܂��́u�������v��u�퍐�v�̌ď̂����邱�Ƃɂ����B�����āA�Ǔ��Ɂu�Ɛl�Ɋւ���ψ���v��ݒu�����̂ł���(����A1993)�B
NHK�̔��\�ɂ��ƁA�e�^�҂̐l���i��Ƃ����ϓ_�ɗ����āu�Ăю̂Ĕp�~�v���1�N�O���猟�����Ă����Ƃ����B�Ƃ��ɓ����̙l�ߎ����̑����ƁA�O�N9���A���{�L���s����ψ���̎w���厖���s�X�g�����A�����ɂ����őߕ߂���A���̌�A�x�@�̑��̊ԈႢ���������Ƃ��킩�������ƂȂǂŁA��C�Ɏ��{�ɓ��ݐ錈�f�������Ƃ����B
NHK�̐����ł́A�������f�B�A�ƈ���ĕ����ł́u�Ăю̂āv����苭�������̂ŁANHK�����ł���s���Ď��{���悤�ƍl�������ƁA�ٔ��ɂȂ�u�퍐�v�Ƃ����ď̂�����̂ɁA�ߕ߂���N�i�����܂ł̊Ԃɂ͓K���Ȍď̂��Ȃ��A���ǁA�u�퍐�v�ɑ���u��^�ҁv�Ƃ������t���g�����Ƃɂ����������ɂ������Ƃ��瓯�`��́u�e�^�ҁv���ď̂Ƃ��邱�Ƃɂ����Ƃ����B(���E�ēc�A1996)
NHK�ɑ����A1989�N4���ɂ̓t�W�e���r�n�A1989�N11���ɂ͖����V�����A������12������͑��̑S�����A�n�����A�ʐM�ЁA�����e�Ђ��Ăю̂Ă�p�~���A�e�^�Ҍď̂��}�X�R�~�E�ɒ蒅���Ă�����(���c�A1994)�B���̂悤�ɁA�Ăю̂Ĕp�~���蒅����悤�ɂȂ����w�i�ɂ́A�ߕߎ��ɌĂю̂Ăɂ��邱�Ƃ͔�^�҂�Ɛl����������̂��Ƃ���l����̖���z���������߂��B�@ |
|
��5�D�����ƌ���
|
��1�D�����̖ړI
���͂ł́A��s�����Ƃ��āA�}�X�E���f�B�A�̎g����}�X�R�~�s�M�̔w�i�A�����Ăǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����_�ʑ���v���C�o�V�[�N�Q�ɂȂ���̂��Ƃ������@�I���߂�ƍߕƂ���������ɂ��Ă݂Ă����B�{�͂ł́A�O���[�v�f�B�X�J�b�V�����Ƃ����`���Ƃ�A�w���̈ӎ��������s�Ȃ��B�O���[�v�f�B�X�J�b�V�������s�Ȃ���ŁA���̑�ނƂ��āu�a�̎R�J���[�ŕ����������v�����グ���B���͂ł��q�ׂ��悤�ɁA���̎��������グ�����R�́A���̎����̐l���N�Q����莋���ꂽ���ƁA�ѐ^�{���퍐�֎��Y�����������n���ꂽ���ƁA�s���̃}�X�R�~�ɑ���s�M���̑���Ȃǂ���������B�ł́A���������s���͎��ۂɍs���Ă���}�X�E���f�B�A�̎�ޕ��@�₻�̓��e�ɂ��Ăǂ̂悤�Ɋ����A���邢�͍l���Ă���̂��낤���B�����ł́A�}�X���f�B�A������̎g�����ƍl���s�Ȃ��������ۂɎs���Ɏ�����Ă��邩�ǂ����𖾂炩�ɂł�����ƍl����B
��2�D�����Ώ�
���̃O���[�v�f�B�X�J�b�V�����́A�L���s����w��2003�N11��17��(��)�ɍs�Ȃ����B���Ԃ́A�ߌ�1���߂�����ߌ�4���߂��܂ł̖�3���Ԃ��Ƃ����B�Ώێ҂͍L���s����w���ۊw���w���ŁA����͏���3���A�j��3���̌v6���ł���B�����́A6���Ɏ����������v7���Ńf�B�X�J�b�V�������s�Ȃ����B
��3�D�������@
6���ɂ́A�����O�Ƀf�B�X�J�b�V�������e�Ǝ����̊ȒP�ȊT�v�ɖڂ�ʂ��Ă��炢�A�����f�B�X�J�b�V�������e�ɂ��Ď��R�ɘ_���Ă�������B�����ɁA��z�����₷���悤�ɁA�ʐ^�����Ă��炢�Ȃ���i�߂Ă������B��b�̘^���́AMD�ōs�Ȃ����B
��4�D�f�B�X�J�b�V�������e�̑I����@
�܂��A�����V���Ɩ����V���̏k���ł���a�̎R�J���[�����Ɋւ���L����I�сA�Q�l�Ƃ����B�L���́A�����̋N����1998�N7��25������12��31���܂ł̖�5�����Ԃ̂��̂��B���̒�����V���Ў��g���l���ƕɊւ��ď����Ă����L���ƁA���̎�ςŖ�肾�Ɗ������L����ʐ^�𒊏o���A���⍀�ڂƂ����B�������A���ꂾ���ł̓f�B�X�J�b�V�������e�����f�B�A��ے肷����̂���ɂȂ鋰�ꂪ���������߁A���ɖ�肾�Ƃ͊����Ȃ��L���Ɋւ��鎿�⍀�ڂ��������B
��
�����ł́A�������ʂ̒����炢������Ƃ��Ď��グ���B����ɊW�̂Ȃ��ԓ�����e�̗ގ��������̂Ɋւ��Ă͏Ȃ����ƂƂ��A���e���ގ����Ă����荀�ړ��m�����ڂɊW���Ă����肷�鎿�⍀�ڂɊւ��ẮA�����ɓ����Ă��炤�`���Ƃ����B�܂��A���⍀��15�A16�A17�Ɋւ��ẮA���̑I����⎞�Ԃ̊W�Ȃǂɂ�蓚�����Ȃ������B
������1�D�V���ɃJ���[�����̔�Q�҂ł���J���F������(64��)�̈�̂��ƂւƉ^���ʐ^���ڂ��邱�ƂɊւ��āB
�E���̎ʐ^�͂��܂�Ӗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�E�������Ƃ͎v��Ȃ��B
�E���̂��������Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�������Ǝv���B
�E�������Ƃ����ϓ_�ł����������Ƃ��Ȃ������B
�E�������ڂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ�����K�v���Ǝv���B�Ƃ̎ʐ^���ڂ��Ă��Ӗ��̂Ȃ����Ƃ��B
�E���̎ʐ^�ɈӖ����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B
�E�ʐ^�́A�����̐l����Q���A�Z���Ԃ�4�l�̕����S���Ȃ������Ƃ⎖���̔�Q�̑傫�@�������A���ɓ`���Ă���B������l����ƕK�v���Ǝv���B
�E���鑤�̋�����������A���邢�́A�D��S����藧�Ă�Ƃ����悤�Ȉ��ӂ͊������Ȃ��@�B
�E���̎ʐ^�͊炪�o�Ă���킯�ł��Ȃ��A�ꉞ�V�[�g�ɕ����Ă���킯�ŁA���̐l�̑����@�����t����悤�ȎB����͂���Ă��Ȃ��B
�E�ςɋr�F�͂Ȃ�������v�ł͂Ȃ����B
�E��̂������Ă���킯�ł͂Ȃ�������v���Ǝv���B
�E�Ƒ��̃v���C�o�V�[���ǂ��Ȃ邩�Ƃ������ƂɊւ��Ă͂킩��Ȃ��B
�E���̂̃v���C�o�V�[�܂ōl�������Ƃ͂Ȃ��B
�E���ꂪ���R�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��킩��B
�E�ߎS�Ȏ������Ƃ������Ƃ�`�����������̂ł͂Ȃ����B
���̍��ڂ����Ɍ��������Ƃł͂Ȃ����A�Q���҂͕��i���܂�l���Ȃ����Ƃ̂��ߔY�݁A�ӌ����ς���Ă��܂����Ƃ����Ȃ��炸�������B�ŏI�I�Ɉ�̂��ƂւƉ^���ʐ^��K�v�Ƃ����l��3���A�s�K�v�Ƃ����l��2���A��{�I�ɂ͕K�v�������̕K�v�����s�K�v�ɋ߂����̂��Ƃ����l��1���������B�܂��A�ʐ^�̓��e�͕ʂƂ��āA�ʐ^�̑��݂��d�v���Ƃ����l��2�������B�Q���҂炪�ʐ^����m�肽���Ǝv���Ă���̂́A�����̔ߎS���⎖���̏d�傳���Ƃ������Ƃ��B�܂�A�ʐ^�͎��������g�߂Ɋ����邽�߂ɕK�v�ȗv�f���Ƃ��Ă���B�����āA��̂��������Ƃ����悤�ȋ�������ł͂Ȃ��悤���B�܂��A�u�v���C�o�V�[�Ƃ͂ǂ��������̂��B�v�Ƃ�����b����A�v���C�o�V�[�Ɋւ���m�����Z�����Ă��Ȃ����Ƃ��_�Ԍ������B
������2�D�S���Ȃ������̊�ʐ^���f�ڂ��邱�ƂɊւ��āB
�E�S���Ȃ������̎ʐ^�����Ă��ǂ��ɂ��ł��Ȃ��B
�E�K�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�E�Ƒ��̏����Ȃ��ɁA�e�ʂ�F�l�Ȃǎ���̐l������ɂ��̎ʐ^�����̂͂��߂��Ǝv�@���B
�E��̂��ʂ����ʐ^����́A���̂��낢��ȃ��b�Z�[�W����邱�Ƃ��ł��邪�A�S���ȁ@�������̊�ʐ^�����Ă��A���b�Z�[�W�͎��Ȃ��B
�E���̎ʐ^���ڂ��邱�Ƃ��v���C�o�V�[�N�Q���Ƃ����Ă���Ƒ�������Ȃ�A�Ƒ��̋C�������Ȃ�������ɂ��Ă܂ŁA���B�ɓ`���Ă����Ȃ��Ă������C�͂���B
�E����ł͌f�ڂ���邱�Ƃ�������O���Ɗ����Ă��܂��B
�E�ʐ^�͂����������킩��₷���B
�E�m�荇���ł���\�������邩��ڂ��Ă���̂ł͂Ȃ���
�S���Ȃ������̊�ʐ^���f�ڂ��邱�ƂɊւ��ẮA�K�v���Ƃ����l��2���A�K�v�Ȃ��Ƃ����l��3���A����1���������B�������A�K�v���Ƃ����l�Ɋւ��Ă��A�ꍇ�ɂ���ĕK�v�Ȏ��ƕs�K�v�Ȏ�������A�Ƒ����痹�����Ȃ��Ȃ�A���̏ꍇ�͍ڂ���K�v�͂Ȃ��Ƃ��������t���������B���̂��Ƃ���A�ǂ����Ă��S���Ȃ������̊�ʐ^���K�v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����Ƃ��킩��B���̍��ڂɊւ��ẮA��Q�҂ւ̔z���̋C��������������ꂽ�B��
����3�D���V�̎ʐ^���f�ڂ�����A�f���𗬂����肷�邱�ƂɊւ���
�E���킢�������ȂƎv���Č������Ǝv���B
�E����Ȃɔ߂���ł���̂��Ƌ�������������B
���V�̎ʐ^��f���Ɋւ��Ă͌������Ƃ����ӌ��̂ݏo���B���V�ɂ������ޕ��@�ɂ��Ă͋^��������Ă������A�e���r��V���ő��V�̕��i�𗬂����Ƃɂ͖��������Ă��Ȃ��悤���B
������4�D8�����{�A�ѕv�Ȃɕی������\�^�f�����サ���Ƃ�(���̎��_�ł͂܂��є퍐�����̎����Ɋւ���Ă��邩�ǂ����͂͂����肵�Ă��Ȃ�)�A�uH�v�ȁv�Ƃ��Ėڂ������B�����ʐ^���f�ڂ���s�ׂɊւ���
������5�D�ѕv�ȂƓ��肷�邱�Ƃ�����A�uA���v�Ƃ����ď̂��g�������ƂɊւ��āB
�E���߂��Ǝv���B
�E�ߕ߂���Ă��Ȃ��ɂ�������ꂸ�A�C�j�V�������o���Ă��܂��̂͂ǂ����낤���B���ۂɂ��̎����ł́A�Ɛl�������Ƃ������Ƃ��킩���Ă��邪�A�������l�߂������Ƃ�����A���@�{�T���������̓�̕��ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�E�є퍐�̓��f�B�A�ɔ��_���s���Ă���B����i��Ń��f�B�A�ɏo�Ă���̂ŁA�C�j�V�������o�����Ƃ��Ă����͂Ȃ��Ǝv���B
�E�����l�߂������ꍇ�́A���Q�����Ȃǂŏ��������Ǝv���B
�E��ʐ^��Ƃ��o�Ă��邩��A�C�j�V�������o�Ă������悤�ȋC������B
�E���̎������N����������l����ƁA�uH�v�Əo�����Ƃ͕ʂɂ��܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���̎��������N�������Ȃ�A����͖�肾�Ǝv���B�Ⴆ�A���݂Ȃ�A�uH�v�ƃC���^�@�[�l�b�g�Ō������������x�̏��͓����Ă��܂��B
�E�}�X�R�~�̗e�^�҂���肵�Ă����s�ׂ͂��߂Ȃ��Ƃ��Ǝv�����A���������悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���Ȃ�A��炴��Ȃ������Ǝv���B
�E�T�����͌��o���ŏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������uA���v���́uH���v�̕��������Ɣ��f���Ă��܂��̂��Ǝv���B
�E�T�����ɁuH���v�Əo��A�������Ǝv���B
�E�����������Ȃ����ōl����A����͈����Ǝv���B�������A���������������Ȃ����ł���A��͂茩�����Ǝv���̂��{�����B
�E���i�͂���Ȃ��Ƃ��l���Č����肵�Ȃ��B
�E�������Ǝv���ĕ��i���猩�Ă���B
�u�g���v�ƌf�ڂ��邱�Ƃ�ǂ��Ƃ����l��2���A�Ԉ���Ă���Ƃ����̂�4���������B�������A4�����u�g���v�Əo�Ă���Ό��Ă݂����ƌ����Ă���B��͂�A�S�V�b�v�ւ̍D��S�Ɠ����I�ȊϔO�̂ǂ��炩��������Ƃ����ɘ_�̌��_���o�����Ƃ͍���Ȃ��Ƃ��Ċm�F�ł���B
�܂��A���̖��Ɋւ��Ă��A���i������ӎ��������Đڂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������������B���̂��Ƃ���A���ł��邩�����łȂ����ƍl����@����܂�^�����Ă��Ȃ��Ƃ�������������������B
�܂��A�����ł͏T�����ƐV���ւ̈ӎ��̈Ⴂ�����邱�Ƃ�����ꂽ�B�Ⴆ�A�u�V���Ɂu�g���v�ƂłĂ�����A����͂��߂��Ǝv���B�v�Ƃ����ӌ�����́A�V���ւ̐M���Ɗ��҂����߂��Ă��邱�Ƃ��킩�邵�A�u�T���������狖����邱�Ƃ�����v�Ƃ����ӌ�����́A�o���̖�����ނ�̒��őo���̈�������ʂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B�������A�T����������Ƃ����ďT����������e��M���Ă��Ȃ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��悤���B
������6�D�w���є퍐��t�߂Ńr�[�`�p���\���̉��Ńp�C�v�֎q�ɍ���A�b�����Ȃ��瓹���ӂ����ł���s�ׂɊւ��āB
�E�����Ȃ��s�ׂ��B
�E�є퍐�͈�ʂ̐l�ł���A�ߗZ���̂��Ƃ��l���Ă���肷�����B
�E�����܂ł��Ă���������Ȃ����炢�Ȃ�A��ނ����Ȃ��Ă������B
�E�Ⴄ��ރ��[�g����A��ނ���ׂ���
���̍��ڂɊւ��ẮA�S����v�Ŕ��Έӌ����o���B��͂肱�̎�ޕ��@�́A�s���̕s�M���ɂȂ���A�M�����Ȃ����s�ׂ��Ƃ�����B
������7�D�S�~�o���Ɍ��ꂽ�є퍐�̎q�ǂ��������J�����}�������͂݁A�ʐ^���B��s�ׂɊւ��āB����8�D�O�o���邽�߉Ƃ���o�Ă����є퍐��w���͂�Ŏ�ނ�����s�ׂɊւ��āB
������9�D�є퍐�̎q�ǂ��̒ʂ��w�Z�ɍs���Ďq�ǂ��Ɏ�ނ�����s�ׂɊւ��āB
������10�D�n��Z�����āA�d�b����������K�₵���肵�Ď�ނ����邱�ƂɊւ��āB
�E�ߏ�ł͂��邩������Ȃ��B
�E��ޑΏۂ����f�����Ă���Ƃ������_�Ŏ�ނ���߂�ׂ����Ǝv���B
�E�ߗׂ̏Z���Ɏ�ނ��邱�ƂŁA�V�������͏o�Ă���̂��B���܂�o�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B������l����Ǝ�ނ͕K�v�Ȃ��̂ł͂Ǝv���B
�E�q�ǂ��ւ̎�ނ͕K�v�Ȃ��Ǝv���B
�E�Z���������₾�Ƃ������b�Z�[�W���Ă��鎞�_�ŁA��肷���Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�E��l�Ɉ͂܂�Ď�ނ��ꂽ�q�ǂ��̏��̐M�p���ɋ^���������B
�E�Z�������₾�ƌ��������Ă���̂ɂ��̎�ނ𑱂���͖̂�肾�B
�E�q�ǂ��Ɋւ��ẮA�є퍐�̎q�ǂ��Ƃ��Ď�ނ���̂͂��߂��Ǝv���B
�E���߂Ȃ��Ƃ��Ƃ͎v�����A24���Ԓ���t���Ă��o�Ă����A����Əo�Ă����̂��q�ǂ��ŁA���������Ăق����Ǝv���Ď�ނ���̂������͂Ȃ��B
�E���_�l����邽�߂ɁA�ꌩ�W�̂Ȃ��Ƃ���A�܂肱���ł����Ύq�ǂ��ւ̎�ނ����邱�ƂŁA���_�l�ւ̎肪����ɂȂ��邩������Ȃ��Ǝv�����̂ł͂Ȃ����B
�E24���Ԓ���t���Ă��Ȃ���A����������ނ͂ł��Ȃ����Ƃ��l����ƁA�q�ǂ��ւ̎�ނ��֎~���ׂ��Ƃ���Ȃ�퍐�ւ̎�ނ����������ׂ��ł͂Ȃ����B
�E�є퍐�ȊO�̐l�ւ̎�ނ͂��߂��Ǝv���B
�E�є퍐���ߗZ���̂ЂƂ肾����A�ߗׂւ̎�ނ͋������̂ł͂Ȃ����B
�E�Z���̎����I�ȏ��̒ɔC����ƁA���̐l�̎�ϓI�Ȋ���ɗ����ꂽ���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����邾�낤�B
�E�є퍐�ɏœ_���������Ă���i�K�ŁA����̐l����̏������ɓ���Ă��܂��ƁA�P�Ȃ镗�]�ɂȂ��Ă��܂��A�є퍐�{�l�̔��_����@��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����l����ƁA�є퍐�ւ̎�ނ͕K�v���Ǝv���B
�E���_�Ƃ��ẮA�q�ǂ��ւ̎�ނ͂�߂�ׂ����Ƃ������ƂƁA�ߗZ���ւ̎�ނ͂�肷���Ȃ����x�ɂ���Ƃ������Ƃ��낤���B�@
�����ł́A�є퍐�ւ̎�ނ�e�F����Ȃ�A24���ԉƂ̑O�ɒ���t���Ă��邱�Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����悤�ɁA����6�̖��Ƃ��̖��Ƃ͐藣���Ă͍l�����Ȃ����̂��Ƃ��A��ύ��f���Ă����B�q�ǂ��ւ̎�ނɊւ��Ă��A�ӌ����ʂꂽ�B�܂��A��ނ��ǂ��܂ł����肷���Ȃ̂��Ƃ������E���ɂ��Ă��ӌ����ʂꂽ�B���E�����������Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����̂�2���A�Z�����������Ă��邩�ǂ����ŋ��E���͌��܂�Ƃ����̂�2���������B���̖��Ɋւ��ẮA�͂�����Ƃ����������o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B
������11�D�J���[�����̌���ƕv�w��̋�B�ʐ^���ڂ��邱�ƂɊւ��āB
�E�є퍐���ߕ߂��ꂽ��̂��Ƃ�����悢�̂ł͂Ȃ����B
�E���̎ʐ^�������������������l����ƁA�є퍐�̎���������ꂩ��߂��̂��ȂƂ������Ƃł͂Ȃ����B���ɉƂ̒����B�����肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����̂ł͂Ȃ����B
�E��a���͊����Ȃ��B
�E�r�F����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂Ŗ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
����ɂ��ẮA��肾�Ƃ����l�͂��Ȃ������B�ߕ߂��ꂽ��̂��Ƃ�������Ȃ��Ƃ����ӌ�����́A��͂�ߕ߂��ꂽ�l���Ɛl�Ƃ����ӎ�������Ƃ������Ƃ�����������B
������12�D�x�@�ɑߕ߂��ꂽ���_(�ѐ^�{�����Ɛl���Ƃ܂����܂��Ă��Ȃ����_)�ŁA���f�B�A���g�ѐ^�{���h�Ɨe�^�Җ����������邱�ƂɊւ��āB
�E�ƍߎ҂͎������o��A�o�Ȃ��Ŕƍ߂�����킯�ł͂Ȃ��B���������āA�������߂̌��ʂ͈Ӗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�E�}�~���ʂɊւ��Ă͈Ӗ����Ȃ��Ǝv���B�}�X�R�~�ɐ��ٔ\�͂��������邱�Ƃ͂��܂�悭�Ȃ����Ƃ��Ǝv���B�������ǂ̂��炢�̑傫���ŕ邩�̓}�X�R�~�����f���邱�Ƃ��B�������A��Q�҂ɂƂ��ẮA�ǂ̎����ł������ꂵ�݂𖡂���Ă���Ǝv���B������l����ƁA�}�X�R�~�����ق̓x�������߂Ă����̂��Ƃ�����肪����Ǝv���B
�E���{�́A�ٔ��řl�߂͂قƂ�ǂȂ��Ƃ����C���[�W������B���ꂪ�{�����ǂ����͂킩��Ȃ����B�A�����J�ł́A�l�߂����{���͑����āA���{�̌x�@�͂��ꂾ�Ƃ����؋����o��܂ł͓������A���̐l���Ƃ����l��ߕ߂���Ƃ����C���[�W������B
�E���\�����Ȃǂ͎������邱�ƂŁA���������\�ɂ����Ă������Ƃ��킩��Ƃ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B
�E�������o�ĔƐl�Ɗm�肵�Ď��������Ƃ��Ă��A���̎��_�Œ����N���o�߂��Ă���̂ŁA�Ӗ��̂Ȃ����Ƃ��Ǝv���B
�E�����v���ɁA���������ɃA���P�[�g��������Ƃ��āA�����炭�����Ɏ^������l�̕��������̂ł͂Ȃ����B
�E�}�X�R�~���������邱�ƂŁA���Q�҂Ƀ_���[�W��^����ׂ����ƍl���Ă���l�͐��̒��ɂ͑����̂ł͂Ȃ����B���������l����̃}�X�R�~�ւ̐M������҂�����Ă��܂��ƁA�}�X�R�~�̗̑͂͗����Ă��܂��A��ޔ\�͂��ቺ���Ă��܂���������Ȃ��B���������āA���݂̏��l����Ǝ������Ȃ��ƃ}�X�R�~�͂���Ă����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���̓}�X�R�~���̗���ɗ����Ă��܂�����A�}�X�R�~�̗̑͂̒ቺ���l����Ǝ������邱�Ƃ͎d�����Ȃ��Ǝv���B
�E�l�߂������ꍇ���l���ē����ɂ�������A�l�߂������Ƃ��ɔ��F�߁A�Ӎ߂�����Ȃǂ̃}�X�R�~�̑Ή��̕����l��������̂ł͂Ȃ����B
�E�ߕ߂��ꂽ���_�ł̎����Ɏ^�����B�x�@�ɂ͂��T�d�ɑ{����i�߂Ă��炢�A�l�߂��Ȃ��Ȃ�悤�ɂ�����Ă��炢�����B
�E�l�߂ɂ��āA�������N�������_�ł̎��グ���̓x���ɉ����āA��ʂŕ�Ȃǂ̑����������̂ł͂Ȃ����B
�E����܂ŁA���O���o�邱�Ƃ���O�Ɋ����Ă������A���ꂪ�������ƂȂ̂��ǂ����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
��͂�A���{�̌x�@��ٔ����ւ̐M�����͍����悤���B�����Ɏ^���Ƃ����l��4���������B�ނ�̈ӌ��Ƃ��ẮA���̂܂����𑱂��A�l�߂������ꍇ�̃A�t�^�[�P�A���l����ׂ����Ƃ������̂������B�������A�����̔ƍߗ}�~���ʂ�ٔ\�͂ɂ��Ă͔��̈ӌ������������B���̎�������́A�����^���h�̈ӌ��Ƃ̑��Ⴊ����ꂽ�B�����ł̈ӌ��ł́A�S�̂Ƃ��Ă��܂�l�߂̏ꍇ���Q�҂G�����̂͂Ȃ������B
������13�D�ꕔ�̏T�������f�ڂ���є퍐�Ɋւ���ߋ��̎���(�Ō�w�ł��������ƁA�s�A�m���D�����������ƁA���C���������ƁA�Ȃ�)�ɂ��āB
������14�D�V�����f�ڂ���є퍐�Ɋւ���ߋ��̎����ɂ��āB
�E���͂��̂悤�ȉߋ�������������A���̂悤�Ȕƍߎ҂����ꂽ�Ƃ������ʊW�͐M�p���Ă��Ȃ��B
�E���Ȃ̂́A�ُ�Ȏ�ȂǂƂ������̐l�̃}�C�i�X�ɂȂ鎖������邱�ƂŁA�Ⴆ�C���^�[�l�b�g����ɂ��Ă���ƁA�Â��ă}�j�A�Ȋ����Ƃ����悤�ȃX�e���I�^�C�v������Ă��܂��댯������Ƃ������Ƃ��B
�E�����ɂǂ̂悤�Ɋ������邩���l�����ŁA�K�v�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B
�E���������ߋ����猻�݂̗e�^�҂͂��邱�Ƃ͈Ӗ����Ȃ��C������B
�E�є퍐���������Ă���̂ł���A�ڂ��Ă������Ǝv���B�������A�����ɂƂ��Ă͕K�v�Ȃ���B
�E���́A�ߋ��̎������f�ڂ��邱�Ƃ͏T�����ɂ���V���ɂ���K�v�Ȃ��Ǝv���B���́A���̎������ǂ̂悤�Ɋ�����̂����킩��Ȃ��B
�E�e�^�҂̈炿��m�邱�Ƃ͕K�v���Ǝv���B���̐l���ƍ߂Ɍ��ѕt���܂łɌo�܂Ȃǂ��킩��̂ł͂Ȃ����B
�E�ߋ��̏�ƍ߂�l�Ԑ��ɂǂ̂悤�Ɍ��ѕt�����Ƃ������Ƃ��Ǝv���B
�E�є퍐���ی��O�����ɂȂ����Ƃ�����������A�]�߂�����̂ł͂Ȃ����Ɛ����ł���B
�E�Ⴆ�A�^�����g�ł��u�m��ꂴ�遛���v�ȂǂƂ��邪�A�����������̂��T�������o�ł����Ƃ�����A�������Ƃ͎v�����낤�B
�E���̃}���V�����̊Ԏ�肪�o������Ƃ����Ăǂ��Ȃ�킯�ł��Ȃ��B
�E�V���̃��]�[�g�}���V�����̋L�q�͋^�f�̗��t���ƁA�є퍐�̔h�o�D�����̗��t���ł͂Ȃ����B
�E�}���V�����̏����ׂ����������ƂŁA�S�[�W���X���͓`����Ă���B
�E�����ǂ���ł͗є퍐�̑�����N���Ă���悤�ɂ͊������Ȃ��B
�E�V�����f�ڂ���ߋ��̎����Ɋւ��ẮA���͂Ȃ��C������B
�E�T�����Ɋւ��ẮA�����Ă��炦��̂������猩�悤���ȂƂ������x���B
�V����T�����Ƃ������}�̂ɂ͊W�Ȃ��A�e�^�҂̉ߋ��̎����ɂ��Ă̋L�q��K�v�Ƃ����̂�3���A�K�v�Ȃ��Ƃ����̂�2���A����1���������B�������A�K�v�Ƃ����l�̒��̂ЂƂ�͐V���ɂ��ߋ��̎����̌f�ڂɂ��Ă̂ݕK�v�Ȃ��̂��Ƃ��Ă���B
�����āA�T�����ɉߋ��̎������o��Βm�肽���A�������Ǝv���A���邢�͂����v���Ă���l�͂�������Ƃ����ӌ���2������o���B�������A�u�킴�킴�����Ă܂ł͌��Ȃ��v��u�u���Ă���Ό���v�A�u�����Ă��炦��̂Ȃ猩��v�Ƃ������ɓI�Ȉӌ������������B
�܂��A�u�T�����̕��e�ł��A�������o���ēǂނ̂�����A����͐^�����낤�Ƃ����l�������ɂ���v�Ƃ����ӌ�����A�������r�F������A�Ⴆ�ł���߂Ȃ��Ƃ��������Ƃ��Ă��A����͓ǎ҂ɂ͎����Ƃ��Ď���Ă��܂����Ƃ��킩��B
�V���ɂ�郊�]�[�g�}���V�����̋L�q�ɂ��āA�ߏ肾�Ƃ����̂�1���A���Ȃ��Ƃ����̂�3���A����2���������B
������18�D����܂ł̈ӌ������āA�ǂ��������Ȃ����ׂ����������낤���B
�E���@���ߏ肷����Ƃ����_���ЂƂ�肾�Ǝv���B�����āA���ӏZ���ȂǂƂ�������O�҂����f������Ȃ����Ȃ�A����͂܂����ł͂Ȃ����B
�E����̎����ōs��ꂽ���@���l����ƁA�����Ƃ����Ή����ł�����������Ȃ����A���������l����Ƒ��҂�葁�����邽�߂ɁA�Ƃɒ���t���Ȃǂ̍s�ׂ��s�Ȃ����Ƃ͎d�����Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���z�_�ƌ����͈Ⴄ�Ǝv���B
�E�Ƃ̑O�ɒ���t���Ă��������ȊO�͎d�����Ȃ������̂ł͂Ȃ����B������͈͂��B
�E�V���͕K�v�ȏ�����Ǝv�����A�T�����ɂȂ�Ƌ����{�ʂȓ��e�������B
���̎���ɂ����Ă�4���̎Q���҂����ꂽ�B�@ |
|
��6�D�܂Ƃ�
|
�{�e�ł́A�O���[�v�f�B�X�J�b�V������ʂ��āA��w�����a�̎R�J���[�����Ŏ��ۂɍs��ꂽ�@�ւɂ���ނ₻�̕��@�ɂ��Ăǂ̂悤�Ɋ����A���邢�͍l���Ă���̂��������Ă����B�\�z�Ƃ��āA���f�B�A�ɔᔻ�I�ȓ����������̂ł͂Ȃ����Ƃ����l�������������A���̗\�z�ɔ����ă}�X�R�~�̗�����l�����ӌ��A���邢�͂��܂���@����e���肾�Ƃ͊����Ȃ��Ƃ������ӌ������������悤�Ɏv���B�t�ɂ����ƁA�}�X�R�~��i�삵����A���Ȃ��Ƃ��鐺������������Ƃ����X�����������A���f�B�A��ᔻ������A��Q�҂̋C���������ݎ�����肷�鐺�͂��܂蕷�����Ȃ������Ƃ������Ƃ��B���̌��ʂ��l������ƁA���͂�1�ŐG�ꂽ�n��(1997)�̂����Љ��@�\�Ɛ��U����(�S�ԑg��ʂ��ĎЉ�̉��P�Ɖ��v�ւ̃L�����y�[����W�J����)�����f�B�A�̖{���S���ׂ������ł���Ȃ�A���f�B�A�́A�ɂ��l���N�Q�Ƃ������ɂ��Ďs�����l�������\���ɒł��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�������̂ł͂Ȃ����낤���B
����ŁA�����ɔƍߗ}�~���ʂ�ƍߎ҂ւ̐��ٔ\�͂����߂邱�Ƃɂ͔��̈ӌ������������B���̌��ʂɌ���A����5�|(2)�ŏ���(1993)���������m�肷�闝�R�Ƃ��Ď����ɂ��ƍߗ}�~�͂̌��ʂ������Ă��邪�A����͎������m�肷�鐳���ȗ��R�Ƃ��Ă͎�����Ȃ����Ƃ��킩��B
���}�̂Ƃ��Ċw�����V���ƏT�����ɋ��߂���̂��قȂ��Ă���͖̂��炩�������B����́A�\�z�ʂ�̌��ʂƂȂ����B�V���ւ̐M���Ɗ��҂͑�ϑ傫���B�u�T�����ɋ������ł��A������V���������Ȃ����͋�����Ȃ��v�Ƃ����ӌ���������̂��Ƃ�����������B�w�����V���ɋ��߂���̂́A�n��(1997)�̂����Ƃ���̐��������̒�]�_�Ɖ��(�Ȋw�I�Ő�[�̖�肾���łȂ��A���������Љ���Ղɉ������)�Ƃ��������ł���A�T�����Ɋւ��ẮA��y�̂��߂̏��}�̂ł��邱�Ƃ�]��ł���̂��낤�B
�܂��A�v���C�o�V�[�Ƃ����m�����s���ɐZ�����Ă��Ȃ����Ƃ��킩�����B����Ɋւ��Ă��A���f�B�A������@�\�����@�\���\���ɉʂ����Ă��Ȃ��\���������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�������A���f�B�A�����łȂ��s�����ɂ����͂���B�s���̃v���C�o�V�[���܂߂��Ɛl���Ɋւ���m���̏��Ȃ��A���邢�͞B������I�悳���Ă���Ƃ�������B�@ |
|
��������
|
�{�e�ł́A�܂��}�X�E���f�B�A�̖{���S���ׂ������ɂ��ĐG��A���Ɂu�}�X�R�~�s�M�v�̔w�i��T�邽�߂ɁA1980�N��̎ʐ^�T�����̑�����A�s���̃v���C�o�V�[�N�Q�ւ̊S�����߂邫�������ƂȂ����ł��낤�o�����A������1980�N��Ɏ��ۂɋN�������������̕ɂ��l���N�Q�ɂ��ĐU��Ԃ����B
�����܂��A�v���C�o�V�[�̌����▼�_���A�����������I�S�͈̔�(���l�����l���Ȃ�)�͖@�I�ɂ͂ǂ̂悤�ɉ��߂���Ă���̂��Ƃ�������{�I�Ȏ�������������B
�����āA�T�^�I�Ȕƍߕ��Љ�A�����E�������ꂼ��𐳓��Ǝ咣���鍪���A�����āu�e�^�Ҍď́v�����܂ꂽ�o�܂ɂ��ĐG�ꂽ�B
�����̖ړI�Ƃ��āA�a�̎R�J���[�����Ŏ��ۂɍs��ꂽ��ނ₻�̕��e�ɂ��ăO���[�v�f�B�X�J�b�V�����Ƃ������@���Ƃ�A�w���̈ӎ��������s�Ȃ����B���̒��������{�����̂́A�s�����m�肽���Ǝv���Ă���A���邢�͎s�����m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƃ��f�B�A���l���I���e���ޕ��@�����ۂɎs���Ɏ�����Ă��邩�ǂ��������邽�߂ł���B���̌��ʁA���̂悤�Ȃ��Ƃ����炩�ɂȂ����B
�܂��A�\�z�ȏ�ɘa�̎R�J���[�����ɂ����郁�f�B�A�̎�ޕ��@����e���m�肷��ӌ��������A�t�ɁA���f�B�A�ɑ���ᔻ�����鑤�ւ̔z���̐��͏��Ȃ������B
�܂��A���f�B�A�Ɗw���Ƃ̎����̎�ނ��ޕ��@�ւ̈ӌ��̈�����_��A���ɑo���̍l������v�����_�������Ă����B�܂��A���҂̈ӌ��̑���_�ɂ��Ă����A�����ɔƍߗ}�~���ʂ�ƍߎ҂ւ̐��ٔ\�����߂邱�Ƃɂ͔��̈ӌ��������������Ƃł���B�܂�A�������m�肷�闝�R�Ƃ��āA���̌��ʂ͐����Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�����āA���f�B�A�Ɗw���̍l���̈�v�����_�����A�����������Ƃ��鍪���̒��́u�����̕��Q�ɂ��ẮA�l����N�Q���Ȃ��̎d���A�L���̏������ɂ���đΉ����l����ׂ��ł���v�Ƃ����l���ƁA�u�����͂Ƃ������A�����_�ł́A�����̓ǎ҂������ւ̓]�������߂Ă���Ƃ͍l���ɂ����v�Ƃ����l���ł���B
�����āA���_�������������Ă����B�܂��A��ɂ��q�ׂ�����鑤�ւ̔z���̐������Ȃ������Ƃ������Ƃ���A���f�B�A�͖{���S���ׂ������ł���Љ��@�\�Ɛ��U����(�S�ԑg��ʂ��ĎЉ�̉��P�Ɖ��v�ւ̃L�����y�[����W�J����)���ʂ����Ă��Ȃ����Ƃ�����������B�܂�A���f�B�A�͎s���ɕɂ��l���N�Q�Ƃ������ɂ��Ďs�����l������ł��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B������l����ƁA�s���ւ̋c�_�̏�(���_�ƈӌ������̂��߂̃v���U�̒�)�Ƃ��Ă̋@�\���ʂ����Ă��Ȃ��\�����l������B�����āA�w���Ƀv���C�o�V�[�Ɋւ���m�����Z�����Ă��Ȃ����Ƃ��킩�����B���̃v���C�o�V�[�Ɋւ���m���̕s�Z���́A�Ɛl�������l�����ł̕��Q�ƂȂ��Ă���Ǝv����B
����̃O���[�v�f�B�X�J�b�V�����ł́A���ڂ̑I���O��W���l�������ڂ̏��Ԍ��������Ă��܂��A�ӌ��������ł��Ȃ����ڂ��o�Ă��܂����B���̎��s�́A�p�C���b�g�E�X�^�f�B���s�Ȃ����Ƃɂ���Ėh�������Ƃł���B
���ケ�̌����W������Ƃ���Ȃ�A��g�݂̂̃f�B�X�J�b�V�����ł͂Ȃ��A���g����f�[�^�����A�w�������łȂ��A�N��ʂɃf�B�X�J�b�V�������s�Ȃ����ǂ����ʂ������邾�낤�B
�O���[�v�f�B�X�J�b�V�����̎Q���҂́A��{�I�Ɍ��݂̃}�X�E���f�B�A�������x�����Ă���A��ނ��鑤�́u��ޗ̈�̌���͎��������̗ǎ��ɔC���Ăق����v�Ƃ����咣�͎s���Ɉꉞ������Ă���Ƃ����邾�낤�B�������A������l����N�Q���Ȃ��̎d���ɂ���ĕ�Q�ւ̑Ή����l����ׂ����Ǝ咣���Ă��A�ɂ��l���N�Q���s�Ȃ��A����ɋꂵ�ސl�X������̂͌����̖��ł���A���f�B�A�̂����u�ǎ��v�Ƃ�����`�͞B���Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�܂��A�s�����̕�����m���s���ȂǂƂ������������サ���B���ʂƂ��āA���f�B�A���̊�Ō��肳�ꂽ���e�Ǝs���̒m�肽���ƍl������͈�v�������A���̌���ɊÂĂ��Ă͂����Ȃ��̂ł͂ƍl����B���f�B�A�Ɍ����͂��Ď�����`��������̂Ɠ��l�ɁA�������s���ɂ����f�B�A�����ɂ��čl���A�c�_���Ă����K�v������B���̂��߂ɁA���f�B�A�͎s���Ƃ̋c�_�̏����A�s���͋c�_�����邽�߂̊�{�I�Ȓm���������Ȃ���A���f�B�A�Ɍ������ڂ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����f�B�A�̎g���@2013/6
|
���u����Ή����A���ۋ����͂̂����ނ��ł��Ă��邩�B�K�ȃr�W�l�X���f����z���Ă��邩�v(�ߓ�)
���a�ꎁ(�ȉ��A�h�̗�)�F���A���f�B�A�͐F�X�ȉۑ������Ă���B���i�A�ᔻ���鑤�ɗ����Ă����X�����A�����͊����Ĕᔻ���悤�Ƃ������ƂŁA���̃Z�b�V�����̊��ƂȂ����B�\�[�V�������f�B�A�Ȃǂ̓o��Ōo�ϓI��Ղ��h�炮����A���ΓI�Ȕ����͂��ቺ���Ă���B����IT�𐄐i���闧��Łu�\�[�V�������f�B�A���v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃi�����Ă��邪�A�J�j�o���͑��݂���B�����A�����}�X�R�~�ƐV�������f�B�A�������W������A���̂Ȃ��Ő��_���`�����Ă����̂��{���̎p�ł͂Ȃ����Ǝv���B�]���č����̓\�[�V�������f�B�A�ȂǂƂ̘A�g�ɂ��Ă��c�_�������B�܂��̓p�l���X�g�̊F���܂ɏ������f�B�A�̓����Ɋ�Â��A���ꂼ�ꍡ���l���ɂȂ��Ă��郁�f�B�A�̉ۑ�E�g���Ƃ��������̂ɂ��Ďf���Ă������B
�ߓ��m�(�ȉ��A�h�̗�)�F���f�B�A�ɂ͈�����������v��������Ă���B�����Љ�l�ɂȂ����̂�1988�N�����A���Ђ������o�V���ł�11�N�ԁA��ސ����������Ė�����B�ŏ���5�N�Ԃ͎Y�ƕ��Ŋ�Ƃ̎�ނ��A����6�N�Ԃ͌o�ϕ��œ����o�ϐ���̎�ނ������B�����ƂƂ��Ẵx�[�X�ɂ�����11�N�Ԃ�����Ǝv���Ă��邵�A�����u���ǎ��͓��o�V���ł��v�ƁA�R�ł������Ă���(����)�B�w���o�r�W�l�X�x���w�v���W�f���g�x�����T�ǂ�ł���B�����g�͊����ƃ��f�B�A����D���Ȑl�Ԃ��B
�����č��͋c�Ȃ�a�����č��N��11�N�ځB�O�������ł͌o�Y����b�̐E���܂ߗ^�}�c����3�N�Ԕ����߂��B��ނ���鑤���o�������B�ǂ��炪�y�����������ƌ����A��ނ�����ق����y���������Ƃ����̂��U�炴��S�������A�Ƃɂ������f�B�A�̎g���Ƃ����͔̂��ɑ傫�ȃe�[�}���B���f�B�A�ƌ����Ă��A�V���E�G���E�e���r�E���W�I�ƕ��L���B���̓C���^�[�l�b�g�������ŁA�ЂƊ���Ɍ��̂�������A�܂��͎��������Ă���͈͂Ń��f�B�A�����ݕ����Ă���Ǝv����ۑ�����������B
�܂��A�V���A����Ȃ�̔��s���������G���A�����ăe���r�Ƃ������A������僁�f�B�A�Ɋւ��Ċ����Č����A����̎�ޗ͂Ɋւ���ۑ肪����Ǝv���B���߂��l�Ԃ�����Șb������̂��ǂ����Ǝv�����A����Ƀ}�b�`������ނ��o���Ă���̂��ƁB�u���{�̃��f�B�A�ɍ��ۋ����͂����邩�v�Ƃ����\���ł��ǂ��Ǝv���B���܂œ��{��Ƃ�����ŏ�ǂɎ���Ă����僁�f�B�A�����A���̓l�b�g��ɂ��܂��܂ȃ��f�B�A���o�ꂵ�Ă����B�N�����L�҂Ƃ��������ŁA���擊�e���o����悤�ɂȂ����B
�僁�f�B�A�͂��������̕ω��ɂ����Ă��\���킦��قǁA����ł̎�ޗ͂�[���@�艺����悤�ȕ��͗͂��������Ă���̂��B��������������15〜16�N�O�Ɣ�ׂ�ƁA���݊��Ă���L�҂̂ق����ނ���D�G��������Ȃ��B�����A����Ƀ}�b�`�����̐����ޗ͂Ƃ����_�ł͂ǂ����B
�����A���ɐ������f�B�A�ł͋��ԈˑR�Ƃ�����ޓ����ڗ��Ɗ�����B��ϔM�S�ŗD�G�ȋL�҂���͂���B�����A���Ƃ��u�����Ƃ����͒��ǂ��v�Ƃ��������E���b���肪�����b��ɂȂ��Ă���B����͂���ő厖��������Ȃ����A����Șb����ɗD�G�ȖʁX��������������Ӗ�������̂��Ǝv���B���̕ӂŎ���̃j�[�Y�ɂ�����Ȃ��Ȃ��Ă���ƁA��ނ��鑤�Ƃ��Ă͊�����B
����Ƃ����ЂƂB��͂�o�c��̂Ƃ��Ă��r�W�l�X���f���̕ǂƂ������A�u�僁�f�B�A�͍�������ςȂ̂��ȁv�ƁA���Ă̓����Ƙb�����Ă��Ă�������B���ɁA�����A�V���A�����ĎG���ƊE�͂��ꂼ��K���Ɏ���Ă���B����͓��{�̃��f�B�A���炢���B�C�O�ɔ�ׂĖ��炩�Ɏ���Ă��镔��������Ǝv���B
���Ƃ��ΐV���Ђ͏���ł̘b�ɂȂ�ƁA�u�V�������͗�O�ɂ��Ă���B�����͕������v�ƌ����B�����������Ǝv���B�����A�V���������O�ɂ���̂͂������Ȃ��̂��B������o�c�҂͕������Ă��锤�Ȃ̂ɁA�������킴��Ȃ��B���ꂾ���o�c����ςȂ̂��낤�B����̎�ރ��x���ł��o�c���x���ł��A�僁�f�B�A�͑傫�ȉۑ�ɒ��ʂ��Ă���B���ɍ��ۋ����͂ɂ��Ă͑�ϐ[���ł͂Ȃ����Ƃ�����N�����Ă��������B
��������(�ȉ��A�h�̗�)�F�w����r�W�l�X�x�̓E�F�u���f�B�A���B���}�̂��������A�f�W�^�������ŏ��M���Ă���B�܂��A�ߓ������Ă����y���ŗ��̘b�͏ے��I���Ǝv���B����܂ő����̐V���Ђ͍����Č��̂��߂ɑ��ł��K�v���ƌ����Ă����B�������A�G���⏑�ЂƂ������o�ł��܂ޗ̈�͕���������y���ŗ���K�p���ė~�����Ƃ����v�]���o���Ă���B
������x������ǎ҂��ǂ�قǂ���̂��B�V���E�G�����������邢�̓W���[�i���Y���Ƃ��Ė{���ɕK�v�ł���ƁA�Љ�I�ɔF�m����Ă���Ȃ�x�������Ǝv���B���ہA�C�M���X�ł͂����Ȃ��Ă���B���������{�ł͎x������Ȃ����낤�B���ɂ��炵�Ă�����̂قƂ�ǂ��u���������̂ł́H�v�Ɗ�����Ǝv���B
���f�B�A�ɂ̓W���[�i���Y���̖����ȊO�Ƀ}�[�P�e�B���O�c�[����R�~���j�P�[�V�����c�[���Ƃ��Ă̖���������Ǝv���B�ŁA�W���[�i���Y���Ɋւ��Č����A���E�I�Ƀf�W�^�������L����Ȃ��A�]���̃r�W�l�X���f�������ꋎ���Ă����Ƃ�����@������B�����Ă����ЂƂ��A���\���������悤�Ɂu�����̐M���������Ă���̂ł́H�v�Ƃ�����@���B�Љ�狁�߂��Ă���������ʂ����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƁB�\����̂��Ǝv�����A����������̊�@������Ǝv���B
������������˂��l�߂����ʁA�w����r�W�l�X�x�ŐV�����r�W�l�X���f�������肽���ƍl�����B��X�͎�ɐ����E�o�ς������Ă��邪�A���Ƃ��ΐV���ɂ�邱��܂ł̐����͐��Ǖɕ��Ă����B��ʂ̏���łɊւ���͓T�^�I�ȃP�[�X���Ǝv���B�����Y���}�����邩�ǂ����ɂ���œ_���u����A�u���ł����{�ɕK�v�Ȃ̂��v�A�u���ł����̒��ɂǂ�ȉe�����y�ڂ��̂��v�Ƃ������c�_�����܂�s���Ă��Ȃ������Ɗ�����B
�V���͂�������襘H�ɂ͂܂��Ă��邵�A�G�����X�L�����_���ɒǂ��Ă��肾�B�w���Y�t�H�x�́u�ԍ⑾�Y�v�V���[�Y�̂悤�ȁA�u���͂��̐l�Ƃ��̐l�����ǂ��āc�v�Ƃ��������֘b�����A�̐S�̐���c�_���Ȃ���Ă��Ȃ��B����������c�_���s�����f�B�A�͕K�v���ƁA���͎v���B���Ɍ��݂̃��f�B�A�̓A�W�F���_�ݒ�Ƃ������A�����{���{���ɋc�_���ׂ��ۑ��ݒ�o���Ȃ��Ȃ��Ă���Ɗ�����B
�����������������w����r�W�l�X�x�Ƃ����E�F�u���f�B�A�ŕ₢�����ƁA����܂�2�N�قlj^�c���Ă����B�ŁA���̓E�F�u�̍L�������Ƃ������ƃ��f���Ɉ��̎艞���������Ă���B�����A����͗L���̃��f�������肽���Ƃ������ƂŁA�V���ȉۋ����f���Ƃ��āw���݃r�W�l�X�u���C�u�x�Ƃ����L�����[���}�K�W�����͂��߂��B
���f�B�A�ƊE�ɂ��V�K�Q�����K�v���Ǝv���B���C�̂Ȃ��Y�Ƃł́A���X�ɂ��ĐV�K�Q�������Ȃ��B���{�̃��f�B�A�ƊE�����l���B���[���}�K�W���͏������`�ł͂��邪�A����܂łɂȂ����f�B�A�̌`�Ԃ��Ǝv���B�R���e���c�Ɋւ��Ă����l�̍l�����Ői�߂Ă���A���͂��Ƃ��w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x�̖|��L���Ȃǂ��Љ�Ă���B�|�[���E�N���[�O�}����W���Z�t�E�X�e�B�O���b�c�A���邢�̓��`���[�h�E�u�����\����n���[�h�E�V�����c�Ƃ������o�c�ғ��A�C�O�ňꗬ�Ǝv���Ă���l�X�̘b��ʂ��ē��{�ȊO�̉��l�ς��ǂ�ǂ�Љ�Ă��������B
�l�I�Ȃ��b����������ƁA���͏��a63�N�A���o�}�O���E�q���Ƃ������o�̎q��Ђɓ������B���݂̓��oBP�Ђ����A����͌��X�A�w�r�W�l�X�E�B�[�N�x���o���Ă���A�����J�̃}�O���E�q���Ƃ����o�ŎЂƓ��o�V���̍��قŁA�u���{�Ńr�W�l�X�E�B�[�N�����낤�v�Ƃ������Ƃł͂��߂���Ђ��B
�����A�������Ђ���1988�N�A�A�����J�̃}�O���E�q���o�c�҂́u���ꂩ��͓d�q�̎��ゾ�v�ƌ����āA�{�Ɓw�r�W�l�X�E�B�[�N�x�ȊO�̊����قڔ��蕥���Ă��܂����B���o�}�O���E�q���ׂ͖����Ă������A������P�ނ���ƁB����œ��o�V�������ׂĂ̊��������A���o�V����100���q��ЂɂȂ����B�����̓C���^�[�l�b�g���Ȃ��A�w���oMIX�x��w�j�t�e�B�T�[�u�x�Ƃ������p�\�R���ʐM�̎��ゾ�B���̎���ɂ���Ȍ��f���o�����A�����J�̌o�c�҂͂������Ǝv���B�����A�����͂҂�Ɨ��Ȃ��āu���̐l�͂ǂ������Ă���̂ł́H�v�Ǝv�����قǂ��B
���ہA���̌��f���̂͂��܂�ɂ����߂��ď�肭�����Ȃ��������A����ł��A�����J�̌o�c�҂͌��f�͂������Ă����ƁA���͎v���B�A�����J�ł͐V�����`�Ԃ̃��f�B�A�����X�ƃx���`���[�ł��肠������B�������f�B�A��M&A����ʂ��č��]�A�t���A�l�b�g���f�B�A�Ƃ��g�݂Ȃ��玎�s������J��Ԃ��ĐV�����`������B���̃_�C�i�~�Y�������{�Ɍ����Ă���B���̕ӂ��Ȃ�Ƃ��������B���[�����f���������Đ��̒������Ă��������Ƃ����C����������A�����������`�ł͂��邪����Ă����Ԃ��B
|
���u���L���Y�̓d�g���g���g�������h�ƍL���傩��̎������g���g���Ɛ��h�B���̓w���Ǝ������̃v���b�V���[�v(�O�H)
�O�H�����A���h���E��(�ȉ��A�h�̗�)�FG1�ɂ͏���Q�����Ă��邪�A���f�B�A�͖��҂ɂȂ��Ă����̂ō���̂悤�ȃZ�b�V�����ł��Ћc�_�������Ǝv���Ă����B�����͐V���A�E�F�u�A�����A�G���ƃo�����X�悭�p�l���X�g�����Ԋi�D�ɂȂ����B���e�ʂɂ��Ă͎����g�͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA�W���[�i���Y���łȂ��G���^�[�e�C�������g�ɒ����ւ���Ă���B�ɂ����̂͂킸��2�N���x���B���Ȃ݂ɂ��̊ԁA��t�����ɏ㗤�������Ƃ�����B���ǂ͋�̉f�����������Ă��Ȃ����A�������̉f���͗B��̗���f�����B�����ɍ����20�L���������C�P��������̎����f���Ă����肷��(����)�B
�����ƊE�Ƃ����͓̂��ꂾ�B�����������߂���B����ꂽ���Y�ł���d�g�������犄�蓖�ĂĂ��������������Ƃ�����Ă���ȏ�A�^S�V���Ђ̂悤�ȕ����͕����ł͍s���Ȃ��B�������̈���A�L���傳�܂��炢�����������ʼn^�c�����Ă����ŁA�������Ə��Ɛ��̂��������s�����藈���肵�Ȃ�������Ȃ�����ɂ���B
����Ƃ����ЂƂB�����ǂɂ́g�������h�����Ȃ��B�V����G����E�F�u�ł���Ή{�����┭�s�����Ƃ������������Ōo�c�����藧�Ǝv�����A�����͈Ⴄ�B�n��g�ł͎������A��������BSS�ł͐ڐG���A�����ă��W�I�ł͒��旦�ɍ��E�����B���ꂪ���������ۂ��͂��Ă����A�����܂Ő����ɍ��E�����B
�V���Ј��̍��A�f���炵���ԑg��������Ă��镔���ׂɂ����āA�����̓X�|���T�[���u�����������Ă��x����v�ƌ����Ă����B�����A�ŏI�I�ɂ͂�͂萔���������Ƃ������R�őł���ɂȂ����B�����������邽�߁A��ɑ�O�}�������߂���Ƃ����W�����}������B�]���ĉۑ�͎O�B�������Ə��Ɛ��̂��������s�����藈���肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�A�������̂ɑ�O�}�������߂���_�A�����Čo�c�̊�@�B�����������ۑ�̂Ȃ��ŁA�ǂ̂悤�ɕ������f�B�A�Ƃ��Ă���Ă����������͍l���Ă���B
���V�~�s��(�ȉ��A�h�̗�)�FG1�����o�[��1/3�O��͎�ސ�Ƃ��Ă����b�ɂȂ��Ă�����X�Ȃ̂ŁA�܂��͔}�̂̏Љ���������B�w�v���W�f���g�x�̓r�W�l�X�G�����B�ҏW�����ɋƊE�S�����͂Ȃ��B�S�����L�҂Ƃ�����ł��Ȃ��A�ǂ��炩�Ƃ����ƕҏW�ɂ���ĉ��H���ꂽ2�����Ő��藧���Ă���B�ێ�{���̈ꎟ���f�B�A�Ƃ͈قȂ�j�b�`���B���s�͌�2��ŕ�����20�����B�傫���ƌ����Α傫�����A�V����e���r�ɔ�ׂ�ƒ��ړx��e���͂͌���I���Ǝv���B
�ҏW��̓����͑���W��`���̗p���Ă���_���B���悻50�y�[�W�ɓn��A���O����傫�ȃe�[�}��I��œ��W��g��ł���B�܂��A���W�ł͌o�ς�o�c�̂��b�ƂƂ��ɁA��������l���ςɂ��Čo�c�҂╔���N���X�̕��X�Ɍ���Ă��������Ƃ����̂���{�I�ȃX�^�C�����B���Ƃ��Γ��{�d�Y�̉i��d�M�В��ɂ͋ƊE�␢�E�o�ς̌��ʂ��ɉ����A�����g�̃L�����N�^�[��l�̈�ĕ��Ƃ������l�Ԗ����邨�b���f���Ă���B���̕ӂ͂ق��̃��f�B�A�Ɣ�r���Ă����j�[�N�ȂƂ��납�ȂƎv���B
���W�ȊO�͂�����W���[�i���Y���I�R���e���c�����A������ɂ����{�I�ɂ͊�Ƃ�r�W�l�X�p�[�\������������悤�ȓǂݕ��������Ă���B�����̖ړI�́u���{�Ɠ��{�l�����C�ɂ���v���B�܂��A�u�ʔ����Ă��߂ɂȂ�v�Ƃ����_���厖�ɂ��Ă���B��͂菤�Əo�ł��B���f�B�A�͎Љ�̌��킩������Ȃ����A��ɂƂ��ēǂ�ł����������߁A�܂��͖ʔ������̂ɂ��Ȃ�������Ȃ��B���̂����Łu���߂ɂȂ�v�Ƃ����ړI������B�ǎ҂ɐ��̌��ʂ������炷�悤�A���C���o���ĖႢ�A���̍s���Ɍq���Ă�����悤�Ȋ������ʂɔ��f�����Ă��������B
�����������ʂ̊��ɂ�����A������3�̌���������B�ЂƂ́u���S�R���A��������̂܂܂����Ă��邩�H�v�B�ӊO�Ƃ���̂܂܂ɂ͌��Ă��Ȃ��̂��l�Ԃ��Ǝv���B�C�f�I���M�[�␢��_�ŊȒP�ɕ��������ߕt���Ă��܂��������B������Ƃ肠�����O���āA���R�ɕ������l����B��ڂ��u�g�o��Y��L���h�����ł��邩�H�v�B�o��Y���ł���邱�Ƃ̑����Љ���A�L�����Ƃ��ӎ����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B�ǂ��炩�Ƃ����Ə��Əo�ł͖ʔ������邽�߁A�l�X�̎��i����ɑi�������A�o��Y�̑����������肪�����B���N���[�g��������ʐM�A���邢�̓��C�u�h�A�����������������B�������������Ƃ��Ă͏������߂��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�ŁA�����Ă����ЂƂ��A�u�q�������̖����̂��߂ɗǂ����Ƃ��H�v�B������������ƌ��Ă������ƍl���Ă���B
������O�̘b�����A���f�B�A�̎g���́A�Љ�̌��S�Ȕ��W�ɍv���o����悤�L�����m�ɁA�킩��₷������`���邱�Ƃ��B������߂��č������Ă��錻��Љ�ɂ����āA���̏�����ł͑�ς��B���@���A�������A�����t�����s�������҂��K�v���ƍl���Ă���B�����Ŕ}��Ƃ��Ẵ��f�B�A�͊Ԑږ����`�ɂ�����d�v�ȃc�[���ɂȂ�Ǝv���B
�ŁA����̂�����ɂ��Ă����A�l�b�g�Ɏ������ڂ�Ƃ��Ă����f�B�A�̒��g�͂��܂�ς��Ȃ���������Ȃ��B���邢�͕ς�邩������Ȃ����A���̕ӂ͂܂�������Ȃ����A���͐F�X�ȕ������s������Ȃ����Ă���Ǝv���B�ŋ߂͋C�ɂȂ��Ă���̂́A����������\���߂Ă���������wHONZ�x�Ƃ������]�T�C�g���B��ʎВc�@�l�̉^�c�����A�{�D���ȕ����W�܂�A�u�{���ɍD�������珑���Ă���v�Ƃ����X�^���X���Ƃ��Ă���̂ŐM����������B�r�W�l�X�Ƃ��Ăǂ��Ȃ��Ă��邩�͕�����Ȃ����A�����A�o�ŎЂ⏑�X�ł͑т�POP�ɓ��T�C�g�̏��]���g���Ƃ�����o�Ă����B
���]�������Ă�����������X�͂��������Ă����ł͂Ȃ��������A�l�̃u�����h�͂�������C���Z���e�B�u�͏o��Ǝv���B���ہA���т���̖{�͔���Ă��邵�A���̏��]�����o�[���ŋ߂͘I�o�������Ă���B�ނ�̖{������Ă���̂��ǂ����͕�����Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��l�̔��M�͂ƂƂ��ɂ��{�l�����̉��l���オ���Ă��邾�낤�B���Ƃ��ẮA�����������Ƃ����̕���ł��N���Ă���̂��ȂƎv���Ă���B
|
���u�����L����\�[�V�������f�B�A�ł̌l���M�ɂ��A�W���[�i���X�g�X�l�ْ̋��������߂�ׂ��v(����)
���F���b���f���A�傫���͓�̖�肪����Ɗ������B�܂��́u�M�����������Ă���v�A�u�A�W�F���_�ݒ肪�o���Ă��Ȃ��v�A�u��ޗ͂������Ă���v�Ƃ������A���f�B�A���g�̗̑͂����ނ��Ă����肾�B�����Ă����ЂƂ��o�c���B�܂��͑O�҂ɂ��āA�l�Ƃ��āA�����đg�D�Ƃ��Ăǂ��l���Ă����ׂ������c�_�������B�����́A������僁�f�B�A����������Ƃ͂ǂ����������̂ɂȂ�̂��낤�B
�����F��قNjߓ��������u��ނ���鑤���猩�����f�B�A�̖��v�́A�ǎ҂���������ӎ��Ƃ�����قǕς��Ȃ��Ǝv���B�V���L�҂��G���ҏW�҂��猩���ۑ���قړ������B��X�Ƃ��Ă��A�u�W�F���V�[�����L����\�w�I�Ȃ��̂łȂ��A�����Ɛ[���L�������邱�Ƃ��o���Ȃ����v�Ƃ������b���������Ă���B
�ł́A�ǂ����Ă��̉ۑ肪�������Ă���̂ɉ����o���Ȃ��̂��B����̃W���[�i���X�g�́A��Ƃ���ьo�c�_���͈̔͂ł��Ȃ�������Ȃ������ƁA�W���[�i���X�g�Ƃ��Ď����̔��f�ł��ׂ����Ƃ̂��������s�����藈���肵�Ă���B���ɉ�X�̂悤�ȃT�����[�}���W���[�i���X�g�͎�ނ��d�˂邤���ɒn�ʂ��オ��B����Ɖ�Ђ̌������Ƃ������Ȃ�������Ȃ��Ȃ�A�����������Ƃ������Ȃ��Ȃ�P�[�X��������B
�����A�������������i�͂���Ǝv���B���͍K���ɂ��ă\�[�V�������f�B�A���L����A�l�ŏ��M�o����悤�ɂȂ��Ă����B�A�����J�̐V���ł͏������e�������B�����������ł́A���Ƃ��ΎИ_�ƈ���Ă����Ƃ��Ă��ǎ҂̂ق������āA���̒��ɕ]�������L�����������Ƃ��o����Ǝv���B�W���[�i���Y���Ƃ��Ė{���ɕ]�������L�����������Ƃ��o������A���Ƃ��u���̉�Ђ͋��S�n��������������ǂ��A���̉�ЂŎ����̃|�W�V��������邱�Ƃ��o����v�ƍl���邩������Ȃ��B
���̈Ӗ��ł��l�̖��O�ōs���o���鏐�����e�𑝂₷�ׂ����Ǝv�����A�����͊e�Ђ̕��j�ɂ��̂ŁA�Ȃ��Ȃ��c�A��Ђ��ς�邩�ǂ����͕�����Ȃ��B�����A���̓\�[�V�������f�B�A�Ōl�����M���s����B�����ŁA���Ƃ��Ύ�މߒ����ނւ̔������A�L���ɏo���Ȃ����������𐢂̒��ɖ₢�|���Ă����B�����Ɏ����̋L���ɑ��鐢�̒��̕]����m�邱�Ƃ��o���邾�낤�B�����Ŕ��_���o����B���̂Ȃ��ʼn�X�̓\�[�V�������f�B�A�ƕ⊮�I�ȊW�����邱�Ƃ��o����Ǝv���B�E�F�u���f�B�A�ƃ\�[�V�������f�B�A�͓G�ΊW�ł͂Ȃ��B
�������\�[�V�������f�B�A�ɂ����͂���B�t�F�C�X�u�b�N��c�C�b�^�[�Řb��ɂȂ�̂��A�ǂ��炩�ƌ����ΐl�̗g���������悤�Șb��A�N���̈����A���邢�͂��ܒ��Ղ̊����b���B���̕ӂ̓e���r��G���Ɠ����B�����A�ǂ���������肭�g�����̃��f�B�A��������悤�ȁA�l�Ɗ�Ƃ̋��Ԃ��s�����藈���肷�镔���߂Ă������Ƃ͏o����Ǝv���B
�O�H�F�A�����J�ł͑S�L�҂Ƀc�C�[�g��F�߂Ă���V��������B��������ƋL�҂Ƀt�@�������āA�V���w���ɂ��q����Ƃ����B�܂��A�c�C�b�^�[�ʼn��S���Ƃ����t�H���A�[���������L�҂��A����Ƃ��u�����哝�̂���ނ���v�ƁA�s���Ɏ�������������Ŏ�ނ��s�����Ƃ������Ƃ��������B
�e���r�ǂɂ͉���{�Ƃ����{�������������ē��Ђ������ʁA�ォ��ڐ��ɂȂ�悤�ȋL�҂�����Ɗ�����B�����������ɊÂȂ����߂ɂ��A�F�������v���Ă��邩���u���ɕ�����\�[�V�������f�B�A����ނɔ��f������͖̂ʔ����Ǝv���B
���F�ŋ߂͉�ʂ̉��Ƀe���b�v�̂悤�Ȍ`�ŁA�\�[�V�������f�B�A����̐��𗬂��ԑg���ڂɂ���B�����̓\�[�V�������f�B�A�����Ȃ�̂����Ă���̂��낤���B
�O�H�F�Ɋւ��Ă��G���^�[�e�C�������g�Ɋւ��Ă��A���A���^�C���Ń\�[�V�������f�B�A�����p����Ƃ����l�����́A���͑S�ǂŐi�߂Ă���Ǝv���B
�����F�ォ��ڐ��ɂȂ��Ă���Ƃ������w�E�͑厖���B���{�ł̓W���[�i���Y�������������ƍs����w����@�ւ��قƂ�ǂȂ��B�ŋ߂͑���c��J-School�ł����������Ƃ�������悤�ɂȂ������A�A�����J�ł͑����̑�w�ɃW���[�i���Y���̃R�[�X������A��ނ̕��@�_����u���f�B�A�Ƃ͉����v�Ƃ����l�����܂ŋ����Ă���B
���������{�͂ǂ��炩�Ƃ�����OJT���B�Ƃ肠�����L�����������A��y����ނ����Ȃ��狳���Ă���B���͐V�l����A�u���ɔᔻ�L���������Ƃ��Ă��A���肪�[���o����悤�ȋL���������v�ƌ����Ă����B����͈�ʐ��������A�Ƃ�����Ǝ����̋L���ɑ��锽��������c�A���Ƃ��Όo�ϋL���ɑ���ƊE�̔���������C�ɂ��Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ�B�����ł͂Ȃ��A�|�s�����Y���ɂȂ�̂ł��ƊE�̔������f���̂ł��Ȃ��A���������L���Ƃ���Ŏ����̋L�����ǂ��ǂ܂�Ă��邩�ɖڂ�������K�v������B���̈Ӗ��ł��\�[�V�������f�B�A�͖𗧂Ǝv���B
���́w�T������x��S�����Ă������������邪�A�L���Ɋւ��ĕҏW���ɍR�c�ɂ�����͂������A�ꍇ�ɂ���Ă͑i�ׂ��N�������������B����͂���ʼn�����B��������ԉ�����͖̂��w���Ō����邱�Ƃ��B�Ƃ��ɂ͎��������_���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���̈Ӗ��ł������L���������Ƃ��ɂْ͋��������܂��B��������f�B�A�Ɏ������ނ��ƂŎ�ގ҂̔\�͂͑�ύ��܂�Ǝv���B
���F���V����̂Ƃ���͂ǂ����낤�B
���V�F�\�[�V�������f�B�A�Ɋւ��Ă͂Ȃ�̔�����Ȃ��B����Ȃɂ����������Ă����ł͂Ȃ����B
|
���u�撣���Ă���҂���������Ɠ����ɁA�E�H�b�`�h�b�O�Ƃ��Ă̋@�\����͂苁�߂���v(�ߓ�)
���F���o�V���͌l�̔��M���֎~�ɂ��Ă���B�u���M����̂Ȃ珊�����f�B�A�ł��悤�Ɂv�ƁB���������R�͂��邪�A�܂��ǎ҂���̑i���ɑ��ĉ�ЂƂ��Ďė����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����w�i������B�l�����R�ӎu�ł�������ƂɊւ��ĉ�Ђ���Ƃ����̂��ςȘb���B����Ɠ��o�ł̓R�����������ŏ����Ă��邪�A����ȊO�͉�ЂƂ��ċL���������Ă���B�]���Ă����ɏ�����Ă��Ȃ����̂𑼂̃\�[�V�������f�B�A���ŏ���ɔ��M����̂͂�낵���Ȃ����낤�Ƃ������R������B�ߓ�����͂��̕ӂɂ��Ăǂ����l�����낤�B
�ߓ��F�ْ����͑厖���B�����ɂ��Ă͐�قǂ̂��b�ɏW�邪�A��͂荡�̃e���r��G���ł́u�N�ƒN�̒����ǂ����v�Ƃ������ْ����̂Ȃ��g���b����ɂȂ��Ă���B���������̂ł͂Ȃ��A���Ƃ��ЂƂ̖@���Ɋւ��Ĕw�i�ׂ����A�u�����������l�X�����݁A����Ȃ����̓������������v�Ƃ����L���������ė~�����B�����Ƃ̎��������̂��ς����A���̂ق��������ƂƂ��Ă��ɂ����A���̒��ɂƂ��Ă��厖���B
�[���@�艺���Ă��������Ɗy�����Ȃ�Ƃ������A�Ӗ��̂����ނɂȂ�B�b��͂������锤���B���������Ɛ������̊F����ɓ{���Ă��܂����A���̐����ʂɂ͂��������j���[�X���������Ă���B���V�����Ă������C�t��������邱�Ƃ����f�B�A�̑傫�Ȗ������Ǝv�����A���̈���ł́c�A�L�������������A���͂����҂ɑ���`�F�b�N�@�\���厖�ɂ��ė~�����B���̗��������̓��{�ł͒��r���[�B����ő����̐l�X���t���X�g���[�V�����𗭂߂Ă���̂ł͂Ȃ����B
�����F�[�@��͑厖���B�r�W�l�X���f���Ƃ��čl���Ă��A���̕ӂ��\�[�V�������f�B�A��u���O���f�B�A�Ƃ̍��ɂȂ�Ǝv���B�u���̐���̗��ɉ����������̂��v�Ƃ��������Ɋւ��āA���Ԍo�߂�l�ԊW���܂߂����܂��܂Ȃ��Ƃ��A�����̐l�X�ɂ������Ď�ނ��Ă����B���������������I�Ȏ�ނ��l�̃u���O���f�B�A�ōs���͓̂�����A�V����G���ł���Ή\���B
��ƃ��f�B�A�͂�����ɓ������Ă������ق����ǂ��Ǝv���B�����ƌ����A�����Ŕ��\����悤�ȏ��͒ʐM�ЂɔC���Ă��܂��Ηǂ��B�����ʐM�⎞���ʐM�ł��ׂĔ����Ă��ǂ��Ǝv���B�ŁA���o��Y�o�Ƃ��������̃��f�B�A�͐[�@��ɓ������Ă����Ƃ����̂��A�r�W�l�X���f���̖ʂōl���Ă����ꂩ��i�ނׂ����ł͂Ȃ����B
���F�O�H����͂ǂ����낤�B�����͑�O�}���I�ɂȂ炴��Ȃ��Ƃ̂��b���������B�����邨���̊ԃW���[�i���Y���Ƃ����͎̂����ǂ����Ǝv���Ă������B
�O�H�F���f�B�A�ɋ��߂��Ă�����̂Ƃ��āA���͂��`�F�b�N����@�\�A�������������@�\�ɉ����A�L���������@�\������Ǝ��͎v���Ă���B�������ɂ����̊ԃW���[�i���Y���Ɋւ��Č����A���Ƃ��u����Ȃ�Ɍ���ꂽ���Ȃ��v�Ƃ������ᔻ�͂���Ǝv���B�����A�L���������@�\�Ƃ����_�Ō����������ق����ǂ��̂ł͂Ȃ����B�����̊ԃW���[�i���Y���Ƃ����̂͂����������̂��Ƒ����Ă���B
���F���V����̂Ƃ���͑���W�Ƃ������Ƃł܂��ɐ[�@�肾�Ǝv�����A���̂����ŏ�肭�����Ă���Ƃ������Ƃ��낤���B
���V�F�����I�Ȃ��̂̓`�[����g��ł���Ă���B���ꂪ�ǂ�قǂ̎���e���͂��������Ă��邩�Ƃ����ƁA�܂�������Ȃ��Ƃ���ł͂��邪�B
�����F����̃��[�N�V���b�v�ŁA�u���{�̃��f�B�A�̓x���`���[��L���C���Ȃ��̂ł́H�v�Ƃ������w�E���������B���ہA���N���[�g�����ł����C�u�h�A�����ł��A���f�B�A���Ƃɂ����o�b�V���O�ɑ���Ƃ�����肪����B���̕ӂ͌��@�ƈ�̂ł���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������邪�A�����������������@�̑ߕ߂����f�B�A���������������B���̗�������������������̂ЂƂɁA�����D����̒����w���Ƃ��—�O���Ȃ̃��X�v�[�`���ƌĂ�āx(�V������)���������Ǝv���B�u���@�Ƃ����̂͂��������\���ŁA���ƂɓG����Ƃ����Ȃ�v�Ƃ������b�������ꂽ�����́A�u���@�ɑߕ߂��ꂽ���Ɓ����ł͂Ȃ��v�Ƃ����\�}���������B�������������ŁA���Ђ�G�����܂߂����f�B�A�̖��������Ǝv���B�����ɏ�����Ă���悤�Ȃ��Ƃ͕\�w�I�Ȏ�ނ����Ă������o�Ă��Ȃ��B������[�@���āA���̒��ɒm�点���߂�̂̓��f�B�A�̎g�����Ǝv���B
|
���u�������ƁA���͂���Ȃ�������҂��o�c���Ȃ��̂Ƃ���Ńn���[�V�������N���Ă���v(��)
���F�ł͂��̕ӂʼn��̊F���������₲�ӌ��������B
���(�k���L��E���ۑ�w�w��)�F�������x��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B55�N�̐��I�������{�I�ɓ����g�[�����B�u���������ׂ�Ă��A�ǂ������̐����͎����}�B������ǂ�ǂ���ς���v�ƁB���͂���Ȏ���ł��Ȃ��̂ɁA�����悤�ȕ𑱂��Ă���B�܂��A���͂��Ă̔h�����[�_�[�قNJm�ł���V�i���I�⌠�͂������Ă����ł͂Ȃ��̂ɁA�L�͎҂ɂ��肭�����Ă���_�ł��������B����Ɍ����A���Ƃ��Α������C�O�֍s���Ƃ��������̐������L�҂��t���čs�������B�C�O�ɑ��锭�M���Ȃ���ΊC�O����̎�M�����Ă��Ȃ��B����Ȃ��Ƃ����܂ő�����̂��B
���͕قǖʔ����d�������Ȃ��Ǝv���B���h�ꖇ�ŒN�ɂł���邵�A�F�X�ȋc�_���o����B�������A�W���[�i���X�g�ł���Ύ����ŕ����f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂̕������Ă���̂��B����OJT�ɔ����B�K�v�ȏ�ʂ����邪�A��w����Ɋ�b��������������Ă��Ȃ������l�ԂɃW���[�i���X�g�͖��܂�Ȃ��Ǝv���B����@�g�A���X�R�A�n��P��A���A���邢�̓E�H���^�[�E���b�v�}����E�H���^�[�E�N�����J�C�g�̖{��������Ɠǂ�ł���̂��B���j�����n���ΐF�X�Ȃ��Ƃ�������B�����̍\���Ƃ������̂��͂����肵�Ă��Ȃ��Ƃ������l�̗͗ʂ������̂��Ǝ��͎v�����A���̂��߂ɂ����j�������Ƃ�������{�ɋA�邱�Ƃ��厖���B
�܂��A�T�������ōs���鐿������肾�Ǝv���B�����������l�Ԃ��A�u�R�ł��ǂ�����ʔ����b�������Ă��������v�Ƃ������Ƃŕ����ɗ���B����ł�������R�������ꂽ�o�������ɂ�����B���ʂ̐l�Ԃ́u�ʓ|������v�ƁA�R�c�����Ȃ����A�������������ɌӍ��������Ă͂��܂����B��Έ�ł��̐l�Ɖ���ē��X�Ɣ��_�o����̂��B�������������ł��l�̗͗ʂ������Ǝv���B
����ƁA�ŋ߂͐V���L�҂ł����x���ɍ����o�Ă���Ɗ�����B���͍ŋ߁A����k�b�����Ɍ��L�͐V���̕ҏW�ψ��N���X�̕���1���Ԃقǘb���������Ƃ�����B�������o���オ����1�y�[�W�̌��e�����Ă݂��20�J�����ԈႢ���������B�u�����Ă����̂��v�ƁB�����ɂ͂��̂悤�ȍ����o�Ă��Ă���Ƃ������Ƃ��w�E���Ă��������B
���(�����M�Y�E���������R���v���C�A���X�@����������\�ٌ�m)�F�w����r�W�l�X�x�Ɓw�v���W�f���g�x���牽�x����ނ������Ƃ��ẮA�������𗼎��͏o���Ă���Ǝv���B�����A�V����e���r�͂ǂ����Ă��F�X�ȃo�C�A�X��������B�o�c��̖�������A�L�Ҍl�̕p�����c�߂���\��������B���̔w�i�ɂ͖k���搶�̂��b�ʂ�A�\�͂�f�{�̖�肪����Ǝv���B�����A����ɉ����āu���������ϓ_���v�Ƃ������Ƃ��F������Ȃ��܂�ށE���Ă�����������̂ł͂Ȃ����낤���B
���̓R���v���C�A���X�����Z���^�[�ō�N�t�܂ł�200��߂����L�҃��N���s�Ȃ��Ă��āA�ꎞ���͑����̋L�҂��W�܂��Ă����B�����ŁA���Ƃ��Ί�Ƃ̃o�b�V���O�Ɋւ��āA�u����Ȏ��_�ōl���Ă݂Ă͂ǂ����v�Ƃ����悤�Șb�������ԂĂ����B�ŁA���ɐ������ݎ����̍ۂ͑����̋L�҂��W�܂��Ă��ꂽ���A�����͊F�A���@���̌��������荞�܂�Ă����B�����������̎����ɂǂ�Ȗ�肪����̂���������Ȃ���Ԃ������B����Ŏ����F�X�Ƙb�������̂����A�L�҂̕��X�͂�������܂��܂Ȕ}�̂ŃA�E�g�v�b�g���Ă����������B
���������@������ƕK�v�ł͂Ȃ����Ǝv�����A�c�O�Ȃ��炻�̋L�҃��N�ɏW�܂��Ă���������͂��Ȃ��Ȃ��Ă������B����Ƃ��AIWJ(Independent Web Journal)�̊����g����Ƃ���������u���L�҃��N�𒆌p�������v�Ƃ̂��b���A�����u�����̘b�M�o����̂Ȃ�v�Ǝv�����̂ŗ��Ė���Ă����B�������l�b�g�Ō��邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�ƋL�҂͗��Ȃ��Ȃ�B�ŁA�������ĉe���͂������Ă��܂����Ǝv���B�]���āA���i�̃r�w�C�r�A�ł͋L�҂̕��X���A�v���[�`�o���Ȃ��悤�ȏ����A�ǂ����ł܂Ƃ߂Č����ׂ��l��������悤�ȏ��݂��Ă͂ǂ����낤���B
���(�X�_���E�X�r���ꖱ�����)�F���̒��̐l�X�̑����́A�����������ɂȂ����Ƃ��A���ɂ��ꂪ�R�ł��u�����ɈႢ�Ȃ��v�Ƃ�����ۂ����B���������e���͂̑傫����F�����ė~�����B�����L���͑厖���Ǝv�����A�u����������Ƌْ������o��v�Ƃ������Ƃ́A�����łȂ���ْ����Ȃ����ӔC�ɏ�����̂��Ƃ����b�ɂ��Ȃ��Ă��܂����炾�B�܂��A�ӔC���闧��Ő��������s�����߂̃W���[�i���Y��������d�v���낤�B�d��̊F���܂͍����u�������Ă�����Ǝv�����A�����ł͂Ȃ��L�҂̕��������Ɗ����邵�A����ȕ��Ɏ���Ă��邱�Ǝ��̂��傫�Ȗ�肾�Ǝv���B
���(����������E�O���[�r�X�E�L���s�^���E�p�[�g�i�[�Y�p�[�g�i�[)�F���{�̃��f�B�A����������́A�o�c�T�C�h�̃P�C�p�r���e�B���Ⴂ�_�ł͂Ȃ����Ɗ����Ă����B�u�n����Γ݂���v�ŁA������̔\�͂��Ⴂ�ƍ��𗎂������Ē����Ɏ��g�ނƂ��������Ƃ�����Ȃ�Ǝv���B���A�l�b�g���f�B�A�̂قƂ�ǂ͕ҏW�҂�W���[�i���X�g�̕��X�ɉ^�c����Ă���A�o�c�ɂȂ��Ȃ��肪���Ȃ��B��X�͂����������f�B�A�����A�c�Ƃ�V�X�e���^�p�������������ŕɏW�����ĖႦ��悤�ȓ������s�Ȃ��Ă���B���̈Ӗ��ł��o�c�҂ƃW���[�i���X�g�����݂��������K�v������Ǝv�����A�o�c���ɑ��郊�N�G�X�g������������f���������B
���(����x�j�E�t���L���X�g�z�[���f�B���O�X����𑊒k��)�F���ɂ�����X�̑����͑�Ȃ菬�Ȃ胁�f�B�A�ɒ@���ꂽ�o���������肾�Ǝv���B�������ق��h���̉�ЂŁA���ăO�b�h�E�B���E�O���[�v(���e�N�m�v���E�z�[���f�B���O�X)�̐܌��딎����ƂƂ��ɂ���@���ꂽ�B�܌�����̓��f�B�A�ƌ��J�Ȃɒׂ��ꂽ�ƍ��ł��v�����A����4�N�O�͓|�Y���O�܂ōs�����B�ٔ��ł��R�ق����͗^�����邪�A��x�o�b�V���O���͂��܂�Ƃ��ꂷ�犐��Ȃ��B���������Ă��u���Ȃ��Ă��Ȃ��v�ƌ�����B
�ŁA���͓����A�u���f�B�A�͉�X�Ɏ��i�S������āA�����Ă���̂��ȁv�Ǝv���Ă������A���͂����ł��Ȃ��悤���B���@�ɂ́u���I��@���v�Ȃ�l����������Ƃ����B�Љ�`�Ɋ�Â��ĕK�v���Ǝv���Η�������Ƃ������Ƃ����@�ł͂��邻�����B�ŁA���f�B�A�̕��X������Ɠ����悤�ɍl���Ă���Ɗ��������Ƃ�����B�u��X�̓W���[�i���X�g������Љ�`���B������������v�ƁB�����A���f�B�A�̐l�Ԃ����������ƕΌ��Ɍq����Ȃ����낤���B�����A�{�l�����͑������������Ă��������Ȃ��āA���������Ƃ𐳂����`�������ŏ����Ă���B���ꂪ���������Ƃ��A�u����͑����ɍ����[����肾�ȁv�Ǝv�����B���̕ӂɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɂ��l�����낤���B
���(���̓�Y�E�c��`�m��w��������w������)�F���̓��f�B�A�ƃW���[�i���Y���̑g�ݍ��킹���ǂ�ǂR�ɂȂ��Ă���B���f�B�A�Ƃ��Ĉꊇ��ɂ����A�����ƃg�[�^���ōl���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������z���������B
���F�L�҂̃��x�����ቺ���Ă���Ƃ������b�ɉ����A�o�c���f���̂܂����Ƃ������w�E���������B�o�c���Ȃ�������Ȃ����A����Ō�����������Ă����ŁA���͂��́g�Ȃ��̈����h���F�X�ƃn���[�V�������N�����Ă���悤�Ɋ�����B
|
���u���O�̎��i�S�����A�������ɓ������f�B�A�͌��R�Ƃ���B���̂Ƃ��t���̐����قł��邩�v(���V)
�ߓ��F���삳���Ă�����C�Ƃ����̂͂���Ǝv���B�����L�҂��������́u�Г��ǎҁv�Ƃ������t���������B�T�^�I�ȋƊE�p�ꂾ�B�u�����͂��������v�ƕҏW�ǒ��������A�u�����@���Ă��v�Ƃ�����C���ҏW�Ǔ����x�z����B��j���[�X�ł������قǂ����Ȃ��Ă����Ɗ�����B���͐�������Ă���ƐM���������B
�܂��A���ʂ̊�Ƃł͉c�Ƃ�o���̐l�Ԃ��g�b�v�ɂȂ��Ă�������A�僁�f�B�A�ł͕ҏW�Ǐo�g���В��ɂȂ��Ă����B���ꂪ�ʂ����Č��S�Ȃ̂��Ƃ����^�������B�A�����J�̃��f�B�A�ł͏�Ɍo�c�w�ƕҏW�ǂ��Η����Ă���B���{�͂�������̂ł��邽�߂ɋْ������Ȃ��A�o�c���o���������Ȃ������ʂ͂���Ǝv���B�l�ވ琬�����̂Ȃ��ōs���Ă����B���������������������ł́A���͂����Ȃ��Ȃ��Ă����B�����L���ɂ���^�����B����ȏ㌾���ƐV���E����Ǖ�����Ă��܂���(����)�A�Ƃɂ����ْ����̂Ȃ����͕ς��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B
�O�H�F�e���r�ɉ����@���ꂽ�Ƃ��A��l�͓d�g���g���Ĕ��_�o���Ȃ��B�]���ĕ��삳��̂��w�E�͑傫�Ȗ��Ƃ��đ�����ׂ����Ǝ����v���B�X����̂��w�E�ɂ��Ă����l���B���̓e���r�ǂɓ����������A���C�Łu���������̉e���͂̑傫����F�����Ȃ����v�Ə�Ɍ���ꂽ�B����͓��ЂŎ��ۂɂ������b�ƕ����Ă��邪�A����A�i�E���T�[���ԑg���Łu�����ȗE�C�����Ƃ��v�ƌ������������B�ŁA���������������d�ԓ��Ń��[����j�����l�𒍈ӂ����牣���Ă��܂����B�u�����̌��t�Ŕ�Q�҂����܂ꂽ�v�ƁA�{�l�͗��������������A���̂Ƃ��ɔނ̏�i�́u����ł��M���͂����������Ƃ��������ق����ǂ��v�ƌ������Ƃ����B���̘b���������S�Ɏc���Ă���B���������̌��t��ԑg�������҂ɗ^����e���ɂ��ď�Ɏ��⎩�����Ȃ�����A����ł��Ȃ������Ă����̂���X�̎g���Ƃ����C������B
���F���{�̃��f�B�A�́A�ЂƂ̕������o����ƊF�����̕����ŋ������͂��߂Ă��܂��B���̕ӂ͖�肾�Ǝv���B���X�^�f�̎�ނƂȂ�ΊF���J���t�H���j�A�ɍs���āA�����čs���Ă��܂��������߂Ɂu����ʼn���������Ȃ���v�ƁA�������e�����ׂă��X�^�f��F�ɂȂ�B�o�ϕł����l�ŁAIMF�E�������V���g���ŊJ�Â����ƂȂ�Ɠ��n�ɂ͓��{����R�̂悤�ɋL�҂��K���B�������A���Ƃ��h�C�c�͐��l��������x�B������F�ŃV�F�A������d�g�݂�����B
�����F���@�I�Ȑ��`���ɂ��Č����A�V���Ђ̏ꍇ�͂������ɂ�����������Ȃ��B�����A�e���r�ƏT�����́u���̂ق�������邩��v�Ƃ����C�������ǂ����ɂ���̂ł͂Ȃ����B���삳��̂��w�E�ʂ�A���`�Ƃ����͈̂�ʂł͊댯���B�������̓W���[�i���Y���Ƃ������t���̂����Ɏg�����A��{�I�ɂ͂ǂ̎d�����Љ�̖��ɗ����Ă����ł��邵�A�N�������̂���ł���Ă���B�W���[�i���Y�����������ʂł͂Ȃ��̂�����A���̕ӂ͎������������Ɏ~�߂Ȃ�������Ȃ��B
����Ɩk���搶�́u���s���ł́v�Ƃ������w�E�ɂ��Ă����A��͂��b���炪�o���Ă��Ȃ��͖̂�肾�Ǝv���B���͑���c��J-School���A�F�X�ȋ���V�X�e�����o���Ă���B��b����͑傢�ɍs���ׂ����B�܂��A�O�̐��E�̕�����A���Ƃ��Ίw���o���҂�e����Ő��I�Ɋ��Ă���������W���[�i���X�g�Ƃ��Ă��}������A���邢�͓����Ă��Ă���������悤�ȓy������邱�Ƃ��d�v���Ǝv���B
���R�A��X�͕����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���Ƃ��u�铢�����삯�Ŏ�ނ�����v�u�N���ƈ���Œ��ǂ��Ȃ�v�Ƃ��������Ƃ��X�N�[�v���Ƃ�錍�Ɗ��Ⴂ������͑������A���ۂɂ͈Ⴄ�B�厖�Ȃ͎̂�ސ�̕��X���������邮�炢�̋C�����Ŏ�ޑΏۂƌ����������Ƃ��B�����đ���̌������Ƃ����ׂė������悤�Ƃ��āA�u�搶�͂�����������邯��ǂ��{���͂�������Ȃ��ł����H�v�ƁB���̂Ƃ��Ɂu����A������������ǂ��A�Ⴄ��v�Ƃ����������ɂȂ��āA�����ŏ��߂Ė{�������Ƃ��o����B
�J��Ԃ��ɂȂ邪�A��͂胁�f�B�A�ƊE�ł͐V�K�Q�������Ȃ��B�A�����J�ɂ�NPO���f�B�A��n�t�B���g���E�|�X�g���A���l�Ȍ`������B������A���ɂ���������悤�ȊF���܂ɂ����АV�K�Q�������Ă������������B���������{�ł����ꂩ�炻���������������N�������Ƃ��Ă���l�Ԃ͂���B�����A�t�ɂ��ꂾ���ۑ������Ă���Ƃ������Ƃ́A�r�W�l�X�`�����X����������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B�����ō����̕s���������o����悤�ȃ��f�B�A���o������A����͑傫�ȃr�W�l�X�ɂȂ�Ǝv���B
���V�F���O�̎��i�S�����A���������ɓ������f�B�A�͎����Ƃ��Ă���Ǝv���B�����炻���Ńu���[�L�������郁�f�B�A�������Ă��ǂ��Ǝv�����A��X�͂��������Ă��������B���N���[�g�����ł͖����J�����������Ԃ̕��X����������p�[�W����Ă��������A�����́u�����܂ň����Ȃ��̂ł́H�v�Ƃ������������Ă����l�������B���̂�����̐����������グ��Ƃ������A����傫�����Ă����K�v�͂���Ǝv���B�僁�f�B�A�ɂ͂Ȃ��Ȃ��o���Ȃ��Ǝv�����A���������j�b�`�ȕ������G���Ƃ��Ă���Ă��������B
���F���ɓ��{�̑僁�f�B�A�͏I�g�ٗp���̗p���Ă���B�����ŃT�����[�}���Ƃ��Ă���Ă����Ȃ�������Ȃ����߁A��̐l�ԂɌ}�����Ă��܂��ʂ͂���Ǝv���B�A�����J�ł̓��[�J��������X�^�[�g���A�����L���������Ȃ��炻�̕���̃v���Ƃ��Ė����グ�邱�Ƃő傫�ȉ�ЂɈڂ��Ă����Ƃ������A�L�����A�Ɋւ��郂�r���e�B������B���̕ӂ����{�ł����߂��Ă���̂Ɗ������B���́g�ꉭ���W���[�i���X�g�h�Ƃ��������ゾ���A����͗ǂ����Ƃ��Ǝ��͎v�����A���̂Ȃ��ʼn�X�����ׂ����Ƃ�����Ă����Ȃ�������Ȃ��̂��ȂƂ��v���B�����͂��肪�Ƃ��������܂���(��ꔏ��)�B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���}�X�R�~�̖���
|
|
���܂��A�}�X���f�B�A�Ƃ́H
|
�}�X���f�B�A�Ƃ́A�u�}�X����O�v�ɑ��ď��`�B������u���f�B�A���}�́v�̂��ƁB ��̓I�ɂ́A�V���E�G���E�e���r�E���W�I�Ȃǂ̔}�̂��w���܂��B
�}�X���f�B�A�͕s���葽���̐����҂�ΏۂɁA���l�ȏ���`�B����u�}�X�R�~���j�P�[�V�����v�̖�����S���Ă���A���̂Ń}�X�R�~�ƌĂ�邱�Ƃ������ł��B�}�X���f�B�A�́A�A����E�[�ցA����A��y�A�L���ȂǕ����̖������ʂ����A�Љ�I�e���͂��傫�����Ƃ������ł��B
|
|
���}�X���f�B�A�̎��
|
��ʓI�Ƀ}�X���f�B�A�Ƃ́A�V���E�G���E�e���r�E���W�I��4�}�̂��w���܂��B�{���ł�4��}�̂����ꂼ�������������ŁA�}�X���f�B�A�ɕC�G����قlje���͂��g�傳�������Ă���C���^�[�l�b�g���Web���f�B�A��SNS�ɂ��Ă��������܂��B
��4��}�̂̓��������
��1. �V��
�V���Ƃ́A�j���[�X�A�ӌ��A���W�ȂǁA��O���S����������������T���Ȃǂ̒�����s���ł��B���Ŕ��s����邱�Ƃ���ʓI�ł����A�ߔN�̓X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�ōw�ǂł���d�q�ł�AWeb��œǂނ��Ƃ��ł���l�b�g�z�M�����y���Ă��܂��B
�V���͑傫����ʎ��Ɛ�历�ɕ��ނł��܂��B��ʎ��̒��ł����s����Ă���n��̍L���ɂ��S�����A�u���b�N���A�n�����ƕ��ނ���܂��B�n��ɂ�葽���ǂ܂�Ă���V�����قȂ邽�߁A�L��S���҂͂��̒n��ł̉e���͂�ǎґw�Ȃǂ��Q�l�ɃA�v���[�`���ׂ��}�̂����߂Ă����܂��傤�B��历�ɂ́A�o�ώ��A�X�|�[�c���A�ƊE���ȂǁA����̕���ɓ������������f�ڂ�����̂����ނ���܂��B���̑��A�@�֎���_���V���Ȃǂ�����A�V���͑��푽�l�ł��B
�V���̓�����1�ڂ́A�n�斧�����ł��B�n�����͒n���Ő��Ȏx���Ă���A���ɂ���Ă͑S���������n������ǂ�ł���l�̂ق����������炢�ł��B�S�����ɂ����y�[�W�̒n��ʂ�����܂��B2�ڂ̓����́A���L���̍����ł��B�w�������V�����ǂ݂�����A�蔲�����f��������ƁA�����l�Ƌ��L���₷������������܂��B3�ڂ̓����́A�����ł��邱�Ƃł��B�O���̃j���[�X�𗂒��ɂ͏ڂ����m�F���邱�Ƃ��ł��邤�����i�������A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����}�̂ƌ�����ł��傤�B
��2. �G��
�G���Ƃ́A����̎����������A��X�̋L�����f�ڂ���������s���ł��B�T���A�������嗬�ł����A�u�T���A�G���Ȃǂ�����܂��B��ނ��L�x�ŁA�����G���A���G��(���|�G���A�r�W�l�X���Ȃ�)�A��y�G��(�t�@�b�V�����G���A����G���A�X�|�[�c�G���Ȃ�)�A����G���A�e��c�̂̋@�֎��A�l�G���A�L�Ȃǂ̕��ނ�����܂��B�w�Ǒw�ɂ���Ĉ�ʎ��A�j�����A�������A�e�B�[���Y���Ȃǂɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B�L��S���҂͏��`�B�����������҂̎u����S�ɍ��킹�āA�A�v���[�`���ׂ��G���}�̂�ς��Ă����܂��傤�B
�G���͏��X��R���r�j�G���X�X�g�A�ȂǂŔ̔����Ă��邱�Ƃ������ł����A�O�q�̐V�����l�A�X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�œd�q���ЂƂ��Ĕ̔�����`�Ԃ����y���Ă��܂��B
�G���̓����Ƃ��āA���}�̓��L�̌܊��ւ̑i�����������܂��B�ҏW�҂͔}�̂��ƂɎg�p���鎆�̎������������Ă���A�G��S�n�����Z�@�ɂ���ēǂݎ肪��C���[�W���قȂ�܂��B�N�₩�ȃr�W���A���œǎ҂̎��o�ɂ���苭����ۂ�^���邱�Ƃ��ł���}�̂ł��B
��3. �e���r
�e���r�Ƃ́A�d�g��p���āA���u�n�ɉf����`�����A�@�ɂ��̉f�����Č�����Z�p�̂��Ƃł��B���邢�́A���̂��߂ɗp�����鑕�u�A���Ƀe���r�f���@���w�����Ƃ������ł��B
�e���r�̕����ǂɂ́A��������(NHK)�Ɩ�������(���{�e���r�����ԁA�e���r�����ATBS�e���r�A�t�W�e���r�W�����A�e���r�����A���{BS�����Ȃǂ��܂ޑS���Ɨ��������c��)������܂��B
�e���r�ԑg�̎�ނɂ́A�ԑg(�j���[�X�A�V�C�\��A����p�Ȃ�)�A��y�ԑg(�X�|�[�c�A�e���r�h���}�A���y�ԑg�A�g�[�N�Ȃǂ̃o���G�e�B�ԑg�A�e���r�A�j���Ȃ�)�A�h�L�������^���[�ԑg�A���C�h�V���[�A����ԑg(�q�ǂ������ԑg�A��w�ԑg�Ȃ�)������܂��B
����4��}�̂Ƒ傫���قȂ�̂́A�f���Ɖ����ŏ���`�����邱�ƁA�����đ����̎����҂�L���邽�ߕ��f�̃C���p�N�g���傫�����Ƃ��������܂��B�������������ɓ���ŏ��邱�Ƃ��ł��A�����������͎�������������܂���B�܂����[�J����(�n����)�ł͒n���ɖ��������ԑg�������ł��B
�ߔN�͓���z�M�T�[�r�X���䓪���e���r�̎������ቺ�Ȃǂ���荹������Ă��܂����ATVer(�e�B�[�o�[)��Paravi(�p���r)�Ȃǂ̃|�[�^���T�C�g�ŏꏊ�⎞�Ԃ�I���ԑg�������ł���̐����������Ă���A�ˑR�Ƃ��ăe���r�͑傫�ȉe���͂��������}�̂ł���ƌ�����ł��傤�B
��4. ���W�I
���W�I�Ƃ́A�d�g�𗘗p���ĕ����ǂ��瑗��E���y�Ȃǂ̉��������̂��Ƃł��B�����`���Ń��A���^�C���ɏ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A���̓�������^�]����A�����Ȃǂ̍�Ƃƕ��s���Ĕԑg���y���ޒ���҂������̂������ł��B�p�[�\�i���e�B�ƃ��X�i�[�̑o�����R�~���j�P�[�V�������Ƃ�邱�Ƃ����W�I�Ȃ�ł͂̓����ł��B
�܂����������A��ʏ���j���[�X�S�ʁA�ЊQ���̏�M�ɗD��Ă��܂��B�e���r�Ɣ�r����Ƒ��M�V�X�e�����ȒP�ȍ\���ɂȂ��Ă��邽�ߍЊQ���ɂ������𑱂��₷���Ƃ��������b�g������A��d�Ńe���r�������Ȃ��ł����W�I�Ȃ��M���\�ł��B
�ߔN�ł̓C���^�[�l�b�g�z�M�T�[�r�Xradiko(���W�R)�Ŏ�N�w�ւ̃A�v���[�`��SNS�ł̊g�U���̌����ڎw���Ă���A���[�J���ǂ̃R���e���c���S���֔z�M����d�g�݂��\�z����Ă��܂��B
���C���^�[�l�b�g��SNS�̓}�X���f�B�A�Ɋ܂ނ́H
�����܂ŐV���E�G���E�e���r�E���W�I�Ƃ���4��}�̂ɂ��Đ������Ă��܂����B�ł́A�}���ɔ��B���Ă����C���^�[�l�b�g��SNS���}�X���f�B�A�Ɋ܂܂��̂ł��傤���B�{���ł́A����Љ�̃C���t���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��C���^�[�l�b�g��̃��f�B�A�ɂ��Đ������܂��B
�l�b�g��̃��f�B�A�͑傫��Web���f�B�A�ƃ\�[�V�������f�B�A��2�ɕ��ނ���܂��BWeb���f�B�A�Ƃ́A�C���^�[�l�b�g��łȂ�炩�̏��M���Ă���Web�T�C�g�̂��Ƃ��w���A��̓I�ɂ̓j���[�X�T�C�g�A�L�����[�V�����T�C�g�A�R�[�|���[�g�T�C�g�Ȃǂ����ނ���܂��B�\�[�V�������f�B�A�Ƃ́A�l�ɂ���M�A�l�Ԃ̂Ȃ���Ȃǂ̎Љ�I�ȗv�f���܂��f�B�A���w���܂��B��̓I�ɂ́ATwitter�AInstagram�AFacebook�AYouTube�ATikTok�A�j�R�j�R����Ȃǂ��Y�����܂��B
�C���^�[�l�b�g������Ƃ���Web���f�B�A��\�[�V�������f�B�A�́A���łɃ}�X���f�B�A�ƌ�����ׂ�قǂ̉e���͂������Ă���A��5�̃}�X���f�B�A�ɂȂ����܂��B�d�ʂ�16�N2���ɔ��\�����w2015�N�@���{�̍L����x�ɂ��A�C���^�[�l�b�g�L�����1��1594���~�ŁA�V����5679���~�̔{�ɒB���A�e���r��1��9323���~�Ɏ������̂ɂȂ��Ă��܂��B��eMarketer�Ђ̒����ɂ��A���łɕč��s��ł�16�N���Ƀf�W�^���L����720��900���h���ɒB���A�e���r��712��9000���h��������Ƃ���Ă���A�l�b�g�L�����߂������Ƀe���r���Đ��E�ő�̍L���}�̂ɂȂ邱�Ƃ͊m���ȏł���ƌ����܂��B
�C���^�[�l�b�g���Web���f�B�A��\�[�V�������f�B�A�͂��̊g�U���̍����������ł��B���ɂ��D��Ă���A�c��ȏ��̒����玩�������߂Ă�������u���Ɍ����ł���_�����݂ł��B����ŁA�l���e�Ղɏ�M�ł��邽�ߌ����t�F�C�N�j���[�X���o����Ă��܂��Ƃ����f�����b�g������܂��B
|
|
���}�X���f�B�A�̖����Ƃ́H
|
�}�X���f�B�A�̋@�\�ɂ��āA�R�~���j�P�[�V�����w�̕��Ƃ��Ă��A�����J�̊w�҃E�B���o�[�E�V�������́A�u������̋@�\�v�u���_�̋@�\�v�u���t�̋@�\�v��3�ɕ��ނ��Ă��܂��B
�܂��u������̋@�\�v�́A�Љ���̌����ω��ɑ�����`���x����������ł��B������o�ς̓������}�X���f�B�A�����M���邱�Ƃɂ��A��O����@���⎩�g�̍l���������������ɂȂ�܂��B��Ƃ�c�̂ɐ��Ԃ��猩���Ă���Ƃ����ӎ���^���邱�ƂŌ�����Ƃ��ċ@�\���܂��B
���Ɂu���_�̋@�\�v�ł��B����͎Љ���Ɋւ��č\�����Ԃ̈ӌ��������_���`������������ł��B�]����4��}�̂ɉ����ߔN�͑�5�̃}�X���f�B�A�ɂȂ����Web���f�B�A��\�[�V�������f�B�A�Ōl���ӌ���\�����邱�Ƃ��e�ՂɂȂ�A���f�B�A�������_�̋@�\����芈�������Ă��܂��B
�Ō�́u���t�̖����v�́A���l�ς�Љ�I�K�́A�m���Ȃǂ����̐���ւƌq���ł��������ł��B���ɐV���͋��L���A�G���͕ۑ������������f�B�A�ł���A����ւ̏��`�B�Ɍ����Ă���}�X���f�B�A�ł��B
�܂��A�����J�̊w�ҁA�n�����h�E���X�E�F�������ꂼ����u���̊Ď��v�u�\�����̑��ݍ�p�v�u�Љ�I��Y�̐���I�`�B�v�Ƃ��ĕ��ނ��Ă��܂��B�����̖��͈̂قȂ�܂����A���e�͑O�q�́u������̋@�\�v�u���_�̋@�\�v�u���t�̋@�\�v�Ɠ��l�ł��B
|
|
���}�X���f�B�A���^����e���Ƃ́H
|
�s���葽���̑�O�ɏ��`�B�������Ȃ��}�X���f�B�A�B���Ԃɋy�ڂ��e���ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����̂ł��傤���B����́u�����ւ̉e���v�u�o�ςւ̉e���v�u�����E���{�Ƃ��Ẳe���v��3�̊ϓ_�ʼn�����܂��B
��1�D�����ւ̉e��
�}�X���f�B�A�������I�Ȏ�����E������邱�Ƃɂ��s���͏��āA�����֘A�̃g�s�b�N�X�����炩���f����ۂ̊�Ƃ��܂��B�V���̌��o���E�j���[�X�̃e���b�v�Ȃǂ̃}�X�R�~���^����C���[�W��A���C�h�V���[�ɏo������R�����e�[�^�[�̈ӌ��ȂǁA�ЂƂЂƂ����_�̌`���ɉe����^���܂��B���̉e���͂͑傫���A���@�E�i�@�E�s���ƕ��ԁu��l�̌��́v�ƌ����邱�Ƃ�����܂��B
��2�D�o�ςւ̉e��
�}�X���f�B�A���痬�����͐l�X�̌o�ϊ����ɑ���ȉe����^���Ă��܂��B�}�X���f�B�A�Ŗڂɂ��鏤�i��T�[�r�X�̏��́A��Ƃ��o�e�����L���̏ꍇ������A�L���̌��ʂ̘I�o�̏ꍇ������܂��B
�L���̋�̗�́A�e���rCM�A�G���̍L���y�[�W�A�V���̍L�����A���W�ICM�Ȃǂł��B���퐶���ŕp�ɂɂ��J��Ԃ��ڂɂ�����̂ł���A��������҂̈�ۂɎc��܂��B
�L���̌��ʂł���A�j���[�X�ԑg��o���G�e�B�ԑg�Ŋ�Ƃ⏤�i���Љ�ꂽ��A�h�L�������^���[�ԑg�ɎВ����o��������Ƃ������P�[�X���������܂��B
�}�X���f�B�A�œ���̎��ۂ���������グ���邱�ƂŁu���ꂪ�l�C�Ȃ̂��v�Ƃ������ʔF���ݏo���A�o�ό��ʂɌq����܂��B�e���r�E�G���ŏЉ�ꂽ�X�|�b�g�ɐl���W�܂�����A�Љ�ꂽ�����������邱�ƂȂǂ�������₷����ł��B
��3�D�����E���{�Ƃ��Ẳe��
��q�̒ʂ�}�X���f�B�A�ɂ́u���t�̋@�\�v�A�܂艿�l�ς�m���Ȃǂ����̐���q���ł�������������܂��B�e���r�ł���Ό���w�K�̔ԑg�A�q�ǂ������̋���ԑg�A��b�⏫���Ȃǂ̎�̔ԑg�Ȃǂ�����܂��B�G���ł���Ηl�X�ȃW�������̐�厏(�V���͐�历)������A�����E���{�̓y����ɉe����^���Ă��܂��B
����Ƀ}�X���f�B�A�ɂ͌�y�Ƃ��Ă��傫�ȑ��݈Ӌ`������܂��B��̓I�ɂ́A�f���h���}�A�X�|�[�c���p�A�]�ɂ�W���[���y���ނ��߂̌�y�������ԑg�A�g�[�N�₨���Ȃǂ𒆐S�Ƃ����o���G�e�B�ԑg�Ȃǂ�����܂��B�����̌�y�R���e���c�͐l�X���L���y���ޑ�O�����𐬗������A����Ώۂɑ���l�C���m�������邱�Ƃŗ��s�ݏo���Ă��܂��B
|
|
���L���ɂ�����}�X�R�~�̖����@
|
�L���̖ړI�͊�ƁE�g�D�̑��݈Ӌ`�����o���A�o�c���������A�Љ�ɑ��鉿�l�����߂Ă������Ƃł��B������B�����邽�߂ɂ͎��ЁA���i�A�T�[�r�X�̔F�m�g�傪�������܂���B���̍ہA�s���葽���ւ̏�M���\�ȃ}�X���f�B�A�͍L��S���҂ɂƂ��ċ��͂ȑ��݂ƂȂ�܂��B
�}�X���f�B�A�����Ԃɗ^����e���͑z���ȏ�ɑ傫�����߁A���J���T�d�A�����Đv���ȃR�~���j�P�[�V���������߂��܂��B���Ƃ��ΔF�m�x�̍����e���r�ԑg�ł���ΐ����Ԏ��Ђ��Љ��邾���ł��A�z�[���y�[�W�̃A�N�Z�X���W��������A�₢���킹���������ēd�b�����܂Ȃ��ɂȂ�����A���i�̐��Y���ǂ����Ȃ��Ȃ����肷��قǂ̔����������N�����ꍇ������̂ł��B
�V���E�G���E�e���r�E���W�I�Ƃ�����4��}�͍̂L���Ƃ��ă��f�B�A�����[�V�����Y�������Ȃ��ۂɕK���A�v���[�`���邱�ƂɂȂ郁�f�B�A�ł��B�L��S���҂͓�������}�̌�����ӂ�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
|
|
���}�X���f�B�A���^����e���͂̑傫���𗝉����Ă�����
|
�{�L���ł́A4��}�̂ƌĂ��}�X���f�B�A�ɂ��Ă�A�}��������5�̃}�X���f�B�A�ɂȂ����Web���f�B�A��\�[�V�������f�B�A�ɂ��Đ������܂����B
�V���E�G���E�e���r�E���W�I�Ƃ������}�X���f�B�A�͐l�X�̕�炵�Ɩ��ڂȊW�ɂ���A���������̒��ɗ^����e�������ł��B���Ԃ̐M�����傫�����f�B�A�ł��邽�߁A�|�W�e�B�u�ȏ����l�K�e�B�u�ȏ�����C�ɍL����܂��B�}�X���f�B�A���^����e���̑傫����O���ɁA�v�������J�ȃR�~���j�P�[�V�������Ƃ�A�������炫�ߍׂ��ȃ��f�B�A�����[�V�����Y��S�|���܂��傤�B
�܂��A���ꂼ��̔}�̂�Web�ł�d�q�ł�W�J����ȂǁA����ɍ��킹�ď������ω����Ă��܂��B�L��S���҂͓����𒀈�`�F�b�N���܂��傤�B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���}�X�R�~�ƃ}�X���f�B�A�̈Ӗ� 1 |
�}�X�R�~��}�X���f�B�A�Ƃ��������t�i����悭���ɂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����2�̌��t�͓����悤�Ȏg���������Ă��邽�߁A���t�̈Ӗ��̈Ⴂ���킩��Ȃ��Ƃ����l��������������܂���B�ł́A�}�X�R�~�ƃ}�X���f�B�A�͖{���ǂ̂悤�ȈӖ��ŁA�ǂ̂悤�ȈႢ������̂ł��傤���H
���}�X�R�~�Ƃ�
�}�X�R�~�Ƃ̓}�X�R�~���j�P�[�V�����̗��̂ŁA��O�`�B�Ƃ���܂��B��ɐV���A�e���r�A���W�I�A�C���^�[�l�b�g�Ȃǂ�p���āA�s���葽���̑�O(�}�X)�ɑ�ʂ̏���`�B���邱�Ƃ��w���܂��B�}�X�R�~�̓����͑����̐l�ɁA��ʂ̏��𑬂��قړ����ɓ`���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł��B�������A���̏��̗���͔��M�ґ������M�ґ��ւ̈���ʍs�ƂȂ�܂��B�������A���M�����ŁA�������A�`�B���A�o�������ȂǂɗD��Ă���C���^�[�l�b�g�����B���������Ƃɂ���āA�}�X�R�~���ω������Ƃ����܂��B
���}�X���f�B�A�Ƃ�
����}�X���f�B�A�Ƃ́A����`�B���邽�߂ɗp������V���A�e���r�A���W�I�A�C���^�[�l�b�g�̂��Ƃł��B�܂�A�}�X���f�B�A(�}��)��p���邱�Ƃɂ���āA�}�X�R�~�Ƃ����`�ŁA�����̐l�ɏ�`�B�����Ƃ����܂��B�}�X���f�B�A��p�����\�I�ȃ}�X�R�~�@�ւƂ��ẮA�V���Ђ�e���r�ǂȂǂ��������܂��B
�܂��A�}�X�R�~�@�ւ��w���ă}�X���f�B�A�Ƃ������Ƃ�����܂��B�}�X���f�B�A�͕s���葽���̐l�ɏ���`���邱�Ƃ��ł���}�̂ł��邽�߁A�L�p�ȏ��𑽂��̐l�ɓ`�����܂����A����ŊԈ���������`���Ă��܂��Ƃ����댯��������܂��B
��ʂ̏���`�B���邱�Ƃł���}�X�R�~�́A�}�X���f�B�A�Ƃ�����i��p���čs���Ă��܂��B�܂��A�}�X�R�~�ƃ}�X���f�B�A�́A�}�X���f�B�A�����M�ҁA�}�X�R�~�̓}�X���f�B�A����̏�������M�҂Ƃ��Ă��l���邱�Ƃ��ł��܂��B
���݂ł́A�C���^�[�l�b�g�Ȃǂ�ʂ��ĒN�ł����M�ł��邽�߁A�}�X���f�B�A�̓}�X�R�~�ɂ����肦��Ƃ�����ł��傤�B
|
|
���}�X�R�~�ƃ}�X���f�B�A�̈Ӗ� 2 |
�}�X�R�~�Ƃ́A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̂��ƂŁA�V���E�G���E�e���r�Ȃǂ�ʂ��Ĉ�x�ɑ吨�̐l�ɏ���`���邱�Ƃł��B
���f�B�A�Ƃ́u�}�����́v�Ƃ����Ӗ��ŁA�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̔}�̂Ƃ��Ă̐V���E�G���E�e���r�Ȃǂ���ȑΏۂł��B�܂��A1990�N��㔼����́A�C���^�[�l�b�g����v�ȃ}�X���f�B�A�ɉ����܂����B���Ȃ݂Ɂu�}���`���f�B�A�v�Ƃ́A�������A���o���A�������Ȃ�1��ނ̏���łȂ��A�����̏����ɂ��Ƃ�ł��郁�f�B�A���w���܂��B �@ |
 |


 �@
�@ |
|
���e���r�̖���
|
���i���𑱂����j���[�X�̗��j
�����m�̒ʂ�A�j���[�X�͐��̒��̏d�v�ȓ����𐢊Ԃɒm�点�邽�߂̂��̂ł��B�]�ˎ���ɂ͊��łƂ����V���̌��ƂȂ���̂������A������Ő����グ�ēǂ�ł͔�������u�ǔ��v�Ƃ����l�����܂����B����Z�p���i������ƁA��������ɂ͐V������ʓI�ɂȂ莞���j���[�X�͑����̐l�ɒm����悤�ɂȂ�܂����B����ɁA�吳�ɂȂ�ƃ��W�I�����y���A�j���[�X�͂�葦�����𑝂��܂����B�����Ď���͏��a�ɐi�݁A�f���Ɖ����œ`����e���r���j���[�X�̒��S�ƂȂ�܂����B������������w�i����A�e���r�ǂ̒��S�I�ȎЉ�I�����͕ɂ���ƌ����܂��B����ł̓C���^�[�l�b�g�����y���A�j���[�X�͂�葦�����Ƒ��l�������܂�A������ϓ_����̕��������ł���悤�ɂȂ�܂����B�e���r�͂��̂悤�ȃ��f�B�A�̒��ł��ł����p����郁�f�B�A�ł���A���̎Љ�I�����͔��ɑ傫���ƌ����܂��B
���u�m�錠���v��m��
�e���r�̕��y�ɔ����}�X���f�B�A�̔��B�ɔ����A���{�̂悤�ȍ����匠���Ƃł́A�}�X���f�B�A�ɑ��āu�\���E���_�̎��R�v�Ɋւ���u�̎��R�v�Ƃ����������F�߂��Ă���̂Ɠ����ɁA�����́u�m�錠���v�Ƃ����������F�߂��Ă��܂��B2001�N�Ɏ{�s���ꂽ�����J�@�͂��́u�m�錠���v��ۏႷ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ����@���Ƃ��Ēm���Ă��܂��B
�����������Ӗ��ł��A�e���r�ǂ͍̕����̒m�錠����ۏႷ�邽�߂ɂ��d�v�Ȗ�����S���Ă��܂��B�Ⴆ�A�����Ɋւ���Ȃǂ́A���ɐ��Ԉ�ʂɒm�炵�߂�K�v������ƍl�����A���̕ɂ���Đ����Ƃ�s���Ȃǂ��Ď������O�̖ځA�`�F�b�N�@�ւƂ��Ă̖��������S���Ă���A�̌�������q�ϐ����ۂ���邱�Ƃɂ���āA�s�������̒�����S�ۂ���Ƃ�������������܂��B
���W���[�i���Y���̈Ӗ�
�u�W���[�i���Y��(journalism)�v�Ƃ������t�͓��{�ł́u�̎p���v�u�̐��_�v�Ƃ������Ӗ������Ŏg���邱�Ƃ�����܂����A���ۂ̓��{���Ƃ��ẮA��ނ����ăe���r��V���A�G���Ȃǂŕ��銈���A�܂��͕@�ւ̂��Ƃ��w���Ă��܂��B�uism�v�ƕt�����ƂŁu��`�v���w���悤�ȃj���A���X������悤�ɕ������܂����A������v���_�N�g�Ƃ����̂��{���̈Ӗ��ŁA�P�Ɂu�v�Ɩ��ꍇ������܂��B
�܂��A�̎p���ɕK�v�Ȑ��_�ւ̋q�ϐ��ɂ��Ę_�����̂��A�č��̃W���[�i���X�g�ł���E�H���^�[�E���b�v�}���ł��B���b�v�}����1958�N��1962�N��2��ɂ킽���ăs���[���b�c�@�܂���܂����W���[�i���X�g�ŁA�}�X���f�B�A�́u�Ӌ`�v�Ȃǂ��e�[�}�ɂ������ҁu���_�v�́A�W���[�i���X�g�̃o�C�u���I�Ȗ{�Ƃ��Ċw�p�I�ɂ��]���������{�ł��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���}�X�E�R�~���j�P�[�V�����_
|
|
����Љ�ɂ����ẮA�e���r��V���A�C���^�[�l�b�g�ȂǑ��l�ȃ��f�B�A�ƐڐG����@���������A�����̘_�����܂ރj���[�X�������Ă���B�������A�����̃j���[�X���S�������ł���A�����̗���ŕ���Ă���Ƃ͌���Ȃ��B�ނ���A����`�B���闧�ꂩ��́A�C�f�I���M�[�Ɋ֘A������`��咣�������܂܂�Ă���A��M�҂ɂƂ��čD�܂����ƂȂ�悤�ɁA��O�։e�����y�ڂ����Ƃ��Ă���ƍl������B�}�X�E�q�R�~���j�P�[�V�����͐g�߂ȑ��݂ł���A�傫�ȉe���͂�^���Ă���ƍl������B
|
��1�@�C���g���_�N�V����
�u�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����v�Ƃ������20���I�������p�����A�Љ�ۂ�ߑ�Љ���L�q����ړI�Ŏg�p���ꂽ�B�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����́u�}�X�v�͑�ʂ��O�Ƃ������Ӗ��ł���A��ʍ����Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������w���B�������A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̑����ł͂Ȃ��A���̏ꍇ�A��Ƃ�g�D�Ȃǂ̏W�c�ł���A�����̎肪���݂��Ă���B�܂��A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̓����Ƃ��āA���ڑΘb�ɂ���ē`����̂ł͂Ȃ��A�傫�����G�ł���A�@�B�I�Ȕ}�̂���݂��Ă��邱�Ƃł���B�@�B�ɂ���đ�ʂ̃R�s�[�������A�e���r��ʂ��ĕ�������A�C���^�[�l�b�g��p���ď���`�B���铙�A����ȋZ�p���p������B����ɁA�����̏ꍇ�A�R�~���j�P�[�V�����̗��ꂪ����肩���ɑ��Ĉ���ʍs�ł���A���ݍ�p���قƂ�nj����Ȃ��B
Lasswell (1960)�́A�}�X�E���f�B�A�̎Љ�I�@�\�ɂ��āA1���ւ̊Ď��A2�\�����̑��ݍ�p�A3�Љ�I��Y�̓`�B��3�_���w�E���Ă���B1���ւ̊Ď��Ƃ́A�Љ�̕ω��ɑΉ��ł���悤�Ƀ��f�B�A�������Ɍx�����邱�Ƃł���B�������ւ̒m�������f�B�A�ɂ���ė^�����邱�ƂŁA�����͂ǂ̂悤�ɍs��������ǂ����Ƃ����ӎv��������邱�Ƃ��\�ƂȂ�B2�\�����̑��ݍ�p�Ƃ́A���_���Ӗ����A�Љ�̔����𑊌ݍ�p�����邱�ƂŐ��_���`������@�\�����B�Љ�ɂ�����d�v�ȑ��_�Ɋւ��āA�l�X�̋�̓I�Ȉӌ�����ĂĂ����@�\���}�X�E���f�B�A�͎����Ă���B3�Љ�I��Y�̓`�B�Ƃ́A�Љ�̍���ɂ��鉿�l�ς�K�͂��}�X�E���f�B�A���`�B���Ă��邱�Ƃ��w���B
���̑��ALazarsfeld and Merton (1957)�́A�}�X�E���f�B�A�̎Љ�I�ȋ@�\�Ƃ��āA���X�E�F���ƈقȂ闧����A1�Љ�I�n�ʂ̕t�^�@�\�A2�Љ�I�K�͂̋����A3�����I�t�@�\������B1�Љ�I�n�ʂ̕t�^�@�\�́A�}�X�E���f�B�A�����グ��l��o�������Љ�I�ɏd�v�ł���Ƃ�����ۂ�l�X�ɗ^���邱�Ƃ��w���B2�Љ�I�K�͂̋����́A�Љ�I��Y�̓`�B�ɋ߂��A�Љ�̋K�͂�l�X�Ɉӎ�������@�\�����Ƃ���B3�����I�t�@�\�́A�^���̂悤�ɏ���^���邱�Ƃ��������Đl�X�C�͂ɂ�����Ƃ������ł���B
��2�@�R�~���j�P�[�V�����̗��_
�m�`�B���f���E�\�����f���n
�`�B���f���Ƃ́A���̏��ʂ̓`�B�ߒ��Ƃ��ăR�~���j�P�[�V�����𗝉�������̂ł���B�`�B����郁�b�Z�[�W�͑����(���̔��M��)�ɂ���Č��肳���B���̃��f���ł́u�N���A�����A�N�ɑ��āA�ǂ̃`�����l����p���ē`�B���A���̌��ʂǂ̂悤�Ȍ��ʂ����������v�ɒ��ڂ����BWestley and MacLean (1957)�́A�R�~���j�P�[�V�������Љ�ɂ����镡���̏o�����ƕ����̐��A�`�����l���E�`�B�҂̖����A���b�Z�[�W�A��Ƃ�����A�̉ߒ��Ƃ��đ������B
����ɑ��āA���`�B���ߒ��Ƃ��đ����Ă̓��f�B�A�@�\���⏬�������Ă��܂����Ƃ���ACarey (1975)�͐M�O�ɒ��ڂ��A�\���ł���Ƒ������B�܂�A�R�~���j�P�[�V�����͋��L�A�Q���A��g�A���Ԉӎ��A���ʂ̐M�̕ێ��Ƃ������p��ƌ��т��A���鎞��ɂ�����Љ�̈ێ��Ƃ������ʂ����݂���B��`�B����邾���łȂ��A���L���ꂽ�M�O��\�����Ă��邱�Ƃɒ��ڂ����̂ł���B
�m�������f���E��e���f���n
�������f���́A�}�X�E���f�B�A�̏��`�B��M�O�̋��L�ł͂Ȃ��A���ڂ����Ƃ����������d�v�ł���ƍl���郂�f���ł���B�}�X�E���f�B�A�͐l�X�̒��ڂ��W�߁A������������āA�S���h�����邱�Ƃɂ���ƍl����B���̂��߁A���b�Z�[�W�̓��e�����A�����Ȃ��@��p���Ē��邩�Ƃ������`�����@���D�悳���B
��e���f���́A�`�B����郁�b�Z�[�W�̈Ӗ��͎�̑��ōs����ƍl����B���f�B�A�̃��b�Z�[�W�����`�I�ł��邽�߁A�����芪�������╶���ɂ���ė��������B��̓��b�Z�[�W����e����`���͂Ȃ��A�C�f�I���M�[�I�ȉe���ɑR���邱�Ƃ��\�ł��邵�A���ۂɂ������Ă���B�܂�A��̗����͑����̈Ӑ}�Ƃ͈قȂ�ߒ������ǂ�ƍl����B
��3�@�}�X�E���f�B�A�̗��_
[���ق̗������_]
Noelle-Neumann(1973)�́A���f�B�A��������Ԃ�����ɂ��Ĉ�т����p���������ƁA�l�X�̈ӌ������̕����ɏ]���X�����o�Ă���Ƃ������ق̗������_������B�l�͌Ǘ����邱�Ƃ�����邠�܂�A�����h�ӌ��ɏ]���悤�ɂȂ�B�����̈ӌ��������h�ӌ��ƈقȂ��Ă���ꍇ�A�����̈ӌ��𐺍��Ɍ������Ƃ͂��Ȃ��B���f�B�A�̈ӌ��ƈႤ�ӌ������l�͎��R�ɖق荞��ł��܂��B���f�B�A�̈ӌ��Ɏ^���ł���Ȃ�A�����Ɉӌ����q�ׂ�B���̂��߁A��ʂ̐l�X�����߂͉����l���Ă������͊W�Ȃ��A�����̃��f�B�A�̗���Ɍ������Ĉӌ������܂��Ă����B�l�X�͑��̐l�X���ǂ������ӌ��������Ă��邩�m���i���Ȃ����߁A���f�B�A��琄�����邱�ƂƂȂ�B���ꂪ���_���`�����Ă����ۂ̎Љ�I�S����\���Ă���B
[�c��ݒ藝�_]
McCombs and Show(1972)�͐l�X���ǂ̂悤�Șb��A���A�e�[�}�ɂ��čl���邩�ɂ��ă}�X�E���f�B�A������ڂ��e���͂ɂ��ċc��ݒ茠������B�}�X�E���f�B�A��������ɂ��Ď��グ��ʂ�������Α����قǁA�l�X�͂��ꂪ�d�v�ȃe�[�}�ł���ƍl����悤�ɂȂ�B�Ƃ��ɑI���ȂǏd�v�ȏo�����ɂ��āA�V���𒆐S�Ƃ����}�X�E���f�B�A�̏��ʂɂ���Č`�������B
[���̑��̗��_�F���f�����O���_�E�o�����_�E�F�m�I�s���a���_]
���f�����O���_�́A�q���̓}�X�E���f�B�A�̒��ɓo�ꂷ��l�����܂˂��悤�Ƃ���Ƃ��낪����Ƃ�����̂ł���B�j�̎q�͒j�̓o��l�������邱�Ƃɂ���Ēj�̎q�Ȃ�̓����^�����A�������Љ�ɓ��Ă͂߂Ă������Ƃ���B
�o�����_�́A�K�x�̊o���͊w�K�𑣐i���������ŁA�ߓx�̊o���͔ے�I�ȉe�����y�ڂ��Ƃ�����̂ł���B�o���ɂ́A�s�����������銈�����x���ɉ����āA���낤���Ċo�����Ă����Ԃ���ɓx�̋����̏�Ԃ܂ŗl�X�Ȓi�K������A������o�������ƌĂԁB���̊o����������������ƁA�l�͏��ɔ��A��������悤�Ƃ���B
�F�m�I�s���a���_�Ƃ́A�l�͐₦���ԓx�A�M�O�A�s������ѐ��̂�����̂ɂ��邱�Ƃ�~���Ă��邱�Ƃ������B�s���Ȃ��Ƃɒ��ʂ����ꍇ�A���������悤�Ƃ��邪�A�������Ȃ��ۂ́A�����̍s����ς��悤�Ƃ���B
[�t���[�~���O����]
�t���[�~���O���ʂƂ́A�I�[�f�B�G���X�̓W���[�i���X�g�����鏀���g�g�݂��̗p���A�W���[�i���X�g�Ɠ����悤�ɐ��E������ƍl������B�Љ���������j���[�X�̃t���[�~���O�̎d�����A�I�[�f�B�G���X�ɉe�����y�ڂ����ۂ��Ƃ�������������(Iyenger 1991)�B�p�ݐ푈�Ɋւ��錤���ł́A�j���[�X�̃t���[�~���O���O�������R���I�������x����������ւƃI�[�f�B�G���X�������Ƃ������ꂽ(Iyenger and Simon 1997)�B���̑��A�哝�̑I���ŁA�W���[�W�E�u�b�V���ɒ��킵���A���E�S�A�̎��s�́A���_�̃t���[�~���O��@�Ɍ���������ƍl�����Ă���(Jamison and Waldman 2003)�B
[�v���C�~���O����]
�v���C�~���O���ʂ̊T�O�́A���f�B�A�����璍�ڂ����Ώۂ�]�����鉿�l�������s�ׂ��w���B�v���C�~���O�Ƃ����l���͑I���L�����y�[�������ŗ��j�������Ă���B�����Ƃ��ł������]�����鑈�_�Ɋ֘A���čs���L�����y�[����ΏۂƂ���B�ł����ڂ𗁂т������I���_���A�����I�s�҂̐��ʂɑ����ʎs���̕]���ɂ����Ĉ�w�d������邱�Ƃ������ꂽ(Iyenger and Kinder 1987)�B����䂦�A���}����Ƃɑ���S�ʓI�]���͍ł����o�����������_���߂����Ĕނ�̍s�����ǂ��F������邩�ɍ��E�����B
���Ƃ̎w���҂͓����̎��s����l�X�̒��ӂ����炷���߂ɊO�𐭍�̐����A�������͎v�������R���s���܂ł����݂�̂ł͂Ȃ����Ƃ����^����������邱�Ƃ�����B����̓v���C�~���O�̋ɒ[�ȗ�ł���B
[��O�Ҍ���]
��O�Ҍ��ʂƂ́A�����̐l�������̓��f�B�A�̉e�����Ȃ��ƍl������̂́A���҂ɑ��郁�f�B�A���ʂ͔F�������ƍl������̂ł���(Davison 1983)�B���҂Ƀ��f�B�A���ʂ��y�Ԃƍl����X���ɂ��ẮA�����̌o���I�f�[�^�ɂ�闠�Â����Ȃ���Ă���B���������f�[�^�̓��f�B�A�̌��͂ɑ���L�͂ȐM�O���������̂ɖ𗧂��A���̏ꍇ�ł����f�B�A���ʂ����t����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B
��5�@�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̎j�I���W�ߒ�
[���f�B�A�̒a���ƃ}�X�E���f�B�A�̔��W]
�O�[�e���x���O��15���I���Ɋ��ŋZ�p�������l���Ƃ��ĔF�肳��Ă���B�}�X�E���f�B�A�̔��W�͗��p�ړI�A�Z�p�A�Љ�g�D�̌`�ԁA�����`�Ԃɂ���Đ��������B���I�ȑ̐��̂��Ƃł̓R�~���j�P�[�V�����Z�p�̗��p�E�J���͐��������B����Z�p�̓��V�A�ł�17���I���߂܂ŁA�I�X�}���鍑�ł�1726�N�܂œ�������Ȃ������Ƃ����B
�菑���ɑ��镶���̕������@�Ƃ��āA����Z�p�����p���邱�Ƃ�15���I�����ɐ��������f�B�A���x�a���̑����ł���B����͏��X�Ɏ�H�ƂƂȂ�A�d�v�ȏ��ƕ���ƂȂ����B1500�N�܂ł̖{�̔��s������1��5000�ł��������A16���I�ɂȂ�ƃ��^�[�̖|�������̔��s������100���������B
[������f�B�A�Ƃ��Ă̐V��]
�V���̌��^��16���I�㔼��17���I���߂̃j���[�Y���^�[�Ƃ����`�Ŏn�܂����Ƃ����B�����̊S�́A���ێ�w�ȏ�����Ɋւ���j���[�X�ł���A���݂̃j���[�Y���^�[�Ƃ͈قȂ���̂ł���B�����̐V��������Â�����̂Ƃ��āA������s�A���ƓI��ՁA�����I���i�A���l�ȖړI����������B�V�����}�X�E���f�B�A�ƂȂ����̂�20���I�ɂȂ��Ă���ł���B�V���̎�v�`�ԂƂ��ẮA���}���A�������A��O���ɕ������邪�A�����鎞��ƍ��ɓK������V���̌`�Ԃ͈���Ȃ��B
[�������f�B�A�E�j���[���f�B�A�Ƃ��ẴC���^�[�l�b�g]
���W�I�A�e���r�͓d�b�A�d�M�̋Z�p����`�B�Ǝ�M��ړI�ɐv���ꂽ�B���W�I�ł�70�N�ȏ�A�e���r�ł�40�N�ȏ�̗��j�����B���W�I�ƃe���r�ɂ��ẮA���I�@�ւɂ��K���ⓝ���A�Ƌ��t�^���Ȃ���Ă���A���ꂪ�������f�B�A������t���Ă���B�ԑg�̑啔���͉f��A���y�A�����A�j���[�X�A�X�|�[�c�Ő�߂��Ă���B�e���r�̓����́A���A���^�C���Ő����p���Ȃ���邱�ƁA�܂����O�Əo���҂̊W���e���ł���A�l�X���ԑg�Ɋ֗^���Ă��邩�̂悤�Ȋ��o�����܂�邱�Ƃł���B
1990�N�ȍ~�A�j���[���f�B�A�Ƃ��ăC���^�[�l�b�g���L�͂ɕ��y���Ă����B�C���^�[�l�b�g�͑ΐl�R�~���j�P�[�V�����̑�֎�i�Ƃ��Ẳ\��������A���̐��i���܂����W�r��ł��邽�ߒ�`��������A�o�����R�~���j�P�[�V�������\�Ƃ��A���I�����I�ȗ��p���Ȃ���邱�ƁA�n��ɊW�Ȃ��l�����p�ł��铙�̓��������B
|
��6�@�W���[�i���Y���̓���
[�W���[�i���Y���Ƃ�]
�W���[�i���Y���ƃ}�X�E�R�~���j�P�[�V�����͑����Ӗ��������قȂ��Ă���B�}�X�E�R�~���j�P�[�V���������̂����A�S�Ă��W���[�i���Y���Ƃ͌����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�W���[�i���Y������ʂɃR�s�[�������̂�s���葽���̐l�X�ɓ`����_�ł̓}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̍s�ׂł͂��邪�A���̓��e�������I�Ȃ��́A�����I�Ȃ��̂ł���B�W���[�i���Y���̓��e����̃f�B�E���k�X(diurnus)�Ƃ������t���痈�Ă���A�u1���́v�Ƃ����Ӗ������B���ꂪ�u�����t������L�^�v�Ƃ����Ӗ��̃W���[�i���ɓ]���A18���I������͓����V���Ƃ����Ӗ��ɂȂ�A���̊����S�̂��W���[�i���Y���ƌĂԂ悤�ɂȂ����B
[�W���[�i���X�g�̎g��]
�W���[�i���X�g�̎d���͑傫����ނƋL���쐬��2�ɕ�������B���̗����ɏG�łĂ���W���[�i���X�g�͈ӊO�ɏ��Ȃ��A���́A�Е��͋��Ƃ����P�[�X�������B�L�҂́A�l�ɉ���Ƃ��d���̎�ȗ̈���߂�B�m���ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�E�l�����̗e�^�҂ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l�ɉ�A���̐l����b�������o���̂��d���ŁA�����ŋc�_���n�߂Ă͂Ȃ炸�A������ɂȂ邱�Ƃ��K�v�ł���B���i����F�X�Ȑl�X�ƂȂ���������A���̃A���e�i��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�W���[�i���X�g�͐��`���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���G�ȎЉ�������ق����ɂ́A�Ȗ��Ȓ������Âȕ��͔\�͂��K�v�ƂȂ�B
[�W���[�i���Y���Ǝ�]
�W���[�i���Y���̋c�_�ɂ����ẮA�肪���������邱�Ƃ�����B�������A�W���[�i���Y���̃��x�������߂邽�߂ɂ́A��̎��o��Q�悪�K�v�ł���B�����̏�Љ�ɂ����āA��͏��ɑ��Ď�̓I���ᔻ�I�Ȏp�������K�v������B1�̎����ł����Ă��A���̐V���A���W�I�A�e���r�A�G���Ȃǂ�ʂ��đ��p�I�Ɍ��āA���e���r���邱�Ƃ������Ă��邱�Ƃ�����B�o����A���ۂɕ���Ă��邱�Ƃ������̖ڂŊm���߂邱�Ƃł���B���ꂽ���ƂƎ����Ŋm���߂����Ƃ̊Ԃɂ͑����̍���������B�����ɂ���ăA�v���[�`���قȂ邱�Ƃ�m�邱�Ƃ͎�Ƃ��Ă̎�̐����m�����邱�Ƃɖ𗧂B
��7�@�����W���[�i���Y���ƃ}�X�R�~
[�e���r����]
1990�N�ȍ~�A�e���r�̓��_�ԑg�Ő����������Ƃ����悤�Ɏw�E�����قǁA�e���r�͐����ɑ��ċ���ȗ͂�L���Ă���(������, 2007)�B�����1990�N��ɂ����ẮA���j���̒�����A�t�W�e���r�́u��2001�v�ANHK�́u���j���_�v�A�e���r�����́u�T���f�[�v���W�F�N�g�v�Ɛ����Ƃ��Q�X�g�Ƃ��ČĂ�铢�_�ԑg���A���������ԑтɕ�������A�����Ƃ������I�R�~�b�g�����g�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɖ₢�l�߂��Ă�������ł���B
[�����Ƃ̃e���r����]
1998�N7��5���A���{�����Y�̓e���r�����́u�T���f�[�v���W�F�N�g�v�ɏo�������B7��3���̌F�{�s�ŋL�҉�̓��e���u�͏����ېł̍P�v���Ŏ��{������������j��\�������v�ƕ�ꂽ���Ƃɑ��āA���{�́u���͍P�v���łƂ͈ꌾ�������Ă��Ȃ��B�P�v�I�ȐŐ����v�ɂȂ�ł��傤�Ɛ\���グ���v�Ƃ��A�P�v���ł̓}�X�R�~�̉��߂ł������Ǝߖ����� �B�i��ғc������̓I�Ȍ�����������߂Ă��A�u������Ȃ��B�����ɂȂ邩������Ȃ��v�Ƃ͂��炩����ʂ�����ꂽ�B����ɓc�����u�����邩�����Ȃ����A�͂����肷�ׂ����v�Ɣ���ƁA�u�����������������Ő��̋c�_�������������Ă��܂��v�Ɖ��A������������B���̋��{�̃e���r�o�����̃R�����g�͐V���e���Ŏ��グ���(1998�N7��6�������V���A1998�N7��6�������V���A1998�N7��8���ǔ��V��)�A���������Ă���C���[�W�����o���ꂽ�Ƃ�����B�������ėL���҂̎x�������ቺ���A�Q�c�@�I���ɂ����ċc�Ȑ������炵���Ƃ�����B
[�f�����̃C���p�N�g]
�e���r�����b�@�͍���ł̋c�_�Ƃ͈قȂ�A��ʂ̎����҂�����ł�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B����Ȍ��t�₠���܂��Ȕ����𑨂��āA������₷���`����̂̓L���X�^�[�̔C���ł���B�V���ł͗^��}�����Ə����Ƃ�����A�b�����t�ʼn����ق����Ă��������ɁA���݂̖����_�𖾂炩�ɂ���B�e���r�ł͉f��������邽�߁A�b����̕\��畞�̐F�܂ŁA�l�X�ȉf����g�[�^���Ƃ��ē`���A�X�l�̎����҂���������Ƃɉ��l���f�������B
��8�@���Љ�ƃ}�X�R�~
[���̈Ӗ�]
�����u���̎��X�̒��ʂ����ɂ����āA�l���Ή����邽�߂ɕK�v�Ȓm���v�ƋK�肵�Ă����B����͏��̍��x�Ȕ��B�ɂ����̉��l�̍��܂�A���ꂪ�命���̐l�X�ɋ����e�����y�ڂ��Ă���Љ�\���Ɋ֘A���Ă��邽�߂ł���B�܂�A���G�ȎЉ�Ől�X���I�m�Ȕ��f���s���ɂ́A��d�v�ł��邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃł���A��̂��̂͒m�������������Ƃɂ��q�����Ă��邩��ł���B
[��̃X�e�b�v]
�Љ�̏�A���̐�ɂ�����Љ�̐����ɂ́A�ߑ㉻�ƂƂ��ɋ}���ɍ��܂��Ă�����̃X�e�b�v�ɂ݂邱�Ƃ��ł���B���̃X�e�b�v�ɂ�1�X�ցA2�d�M�E�d�b�A3�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����A4�R���s���[�^�Ƃ�����A�̗��ꂪ����B���܂�A�j���[���f�B�A�̊g��́A�R���s���[�^���g�p����l�X�̑����ƁA�}�p��ً}���ԁA�ЊQ�p����r�W�l�X�⌤���A��A�]�ɂɊւ��L���̈�ʼn��p����A���Ȃ�̌��ʂ������Ă���B���̔��ʁA�����������f�B�A�̕��y�ɂ݂���͓̂s���̗ǂ��ł���A�l�ԊW�������Ȑl��l�ԊW��s���ӂƂ���l�����ɂƂ��Ă͎��ɕ֗��ȓ���Ƃ��ė��p�͈͂��L���邱�ƂƂȂ����B����������Љ�̋t�@�\���w�E����Ă���B
[���Љ�̋t�@�\]
�R�~���j�P�[�V�����E���f�B�A��}�̂Ƃ��āA�����Ǝ�̑��݂ɓ������̂��l�X�̏W�܂肪�o�ꂵ���B���̌��ʁA�s���葽���̐l�X�̊ԂŁA������Љ�ɐZ�����邱�ƂƂȂ����B���̏��̔��M�҂̐ӔC�͞B���Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�������̑���́A�l��W�c�A�g�D���U��������A��@�ȓ��e�̏�p�ɂɃl�b�g��������߂���A�l�����Ȃ��ƍ߂𑣐i�������B����ɑ��āA�R�~���j�P�[�V�����E���f�B�A�̈ꕔ�K���܂ł����悤�Ƃ�������������B���x�ȋ@�\�����}�̂��A���Љ�̋t�@�\�ɂ���ĐV���ȎЉ�a�����ۂݏo���Ă��܂����B
��9�@�����ƃ}�X�R�~
[����]
�R�~���j�P�[�V�����E�l�b�g���[�N�������炵�������̂Ȃ��ł��A�p�[�\�i���ȕ������������Ă���̂��A�����R�~���j�P�[�V�����Ƃ����X�^�C���ł���B�����͐l���畷���đ��l�ɘb���Ƃ����`�B�E�g�U�̌`�������R�~���j�P�[�V�����ߒ��ł���B�����͂˂ɁA���������A���̕s���E�o���s�ڂ̃j���[�X�ł���Ȃ���A�N���ȃC���[�W�������l�X�̊Ԃ𑖂�悤�Ɋg�U������̗���ł���B�����́A���̔×��I�g�U���ۂł���A���f�}�ɔ��W���邱�Ƃ����肤��B�ЊQ���̗�����f�}�ɂ���āA�[���ȃp�j�b�N���N���邱�Ƃ�����B
[�����̕���]
Allport and Postman(1947)�͗�����4�ɕ��ނ��Ă���B1�����݂Ɣ����f���Ă���u����E�s�������v�A2�R���֘A�̎c�s�s�ׁA�G�̔閧�s���A�X�p�C�����������u���|�����v�A3�푈�����ȂǘN����ċC���ɂށu��]�����v�A4�����ɑ���s���̊댯�⋺�ЂƂ��āu�s�������v�ɕ�������B�܂������`���ɂ���āA�ǂ̂悤�Șc�݂������邩�ɂ��ẮA���ω��A�����A�����Ƃ���������������邱�Ƃ��w�E����Ă���B�b�̓��e�͓`�B����Ă��������ɒZ���Ȃ�A�Ō�͗v��A���ՂƂȂ�B�܂��A����v�f�������I�яo����ċ��������B����͑傫�Ȃ��̂�ڗ����́A�����I�ȃg�s�b�N�������B�����ē`�B�҂̂����Ă���m�I�A����I�ȏ����̉e���ɓ��������B
[���������̏���]
���������ɂ́A�Љ�I�����ƐS���I���������݂���Ƃ���Ă���B�Љ�I�����Ƃ��āA1�Љ�I��@�����邱�ƁA2�}�X�E���f�B�A�̕s���A3�ӌ����\�̐����A4�l�I�l�b�g���[�N�̑��݂��w�E����Ă���B�܂��A�S���I�����Ƃ���1�命���̐l�X������ʓI�ȕ����I�E���_�I�ȗ~���s���A2�命���̐l�X������ʓI�ȕs���A3�命���̐l�X���������̋��|���w�E����Ă���B����ɑ��đ���(2002)�͍ЊQ��Љ�ϓ����ɗ����������邱�Ƃ����邪�A�u�����I�ȏŐ�������̂��Ƃ����F���͌����ɑÓ����Ȃ��v���Ƃ��w�E���Ă���B
��10�@���_�ƃ}�X�R�~
[���_�Ƃ�]
���_�Ƃ́A�����̐l�X��������Ɋւ��ċ��ʂ��ĕ����Ă���W�c�I�ӌ��ł���B�����l�X�̕\������ӌ��̏W���̂Ƒ����Ă��ǂ����A�K�������X�l�̈ӌ���P�ɎZ�p�I�ɉ��Z���ē�������̂ł͂Ȃ��B�ނ���A�l�X�̊Ԃ̑��ݍ�p��ʂ��ĐV�Ɍ`�������Љ�I���ۂł���ƍl��������K���Ă���B����ł́A���_�͂ǂ̂悤�Ɍ`�������̂��B�傫�ȗ���Ƃ��čl����ƁA���_�̌`���́A���鑈�_�����f�E���_�Ƃ������J�j�Y����ʂ��āA�܂��͌l�̎����ɂ�����ӌ��Ƃ��Đ������A���ꂪ�l����W�c�̎����ցA�W�c����Љ�̎����ֈڂ�A����ɖ��m�Ȍ`�𐮂��A���͂Ȃ��̂Ƃ��Č��������Ă����ߒ������ǂ�ƍl������B���̉ߒ��́A�ĂяW�c�̈ӌ����l�̎����ɁA�Љ�̈ӌ����W�c�̎����Ƀt�B�[�h�o�b�N����A�����ōĂє��f�E���_����A�⋭�E�C��������Ă����B
[���_�ƃ}�X�E�R�~���j�P�[�V����]
�}�X�R�~�͑��_�Ɋւ������l�X�ɓ`���A���_���w�����Ă��̌`���Ɋ֗^����Ɠ����ɁA�`�����ꂽ���_�𐢘_�����ɂ���Ĕc�����A����B���̂��Ƃɂ���Ă���ɐ��_���������Ă����������}�X�R�~�͒S���Ă���B���_�`���ɂ����ă}�X�R�~�̉ʂ��������͑傫���B���̃}�X�R�~�̉e���͂̑傫���𗘗p���悤�Ƃ��A���_�𑀍삵�悤�Ƃ��鎎�݂����ɂȂ���Ă���B�Ⴆ�A���}�́A�I���̂Ƃ��ɒm���x�̍����^�����g����i�����邱�Ƃ���Ƃ��e���r�o������B����ɂ���Đ��_������̓s���̗ǂ������ɑ���E�U�����悤�Ƃ���B
[���吭���Ɛ�`]
�����`�I�������͂͐�`���s���A�����̐l�X�̑ԓx��s���ɉe�����y�ڂ����Ƃ���B�Ⴆ�A�A�����J�͑�ꐢ�E���̂Ƃ��ɍL��ψ�����A����E���̂Ƃ��ɐ펞���ǂ�ݒu�����悤�ɁA�펞�ɂ����Ă͎������̎m�C�����߂�ƂƂ��ɁA�G�w�c�̑@�ۂ�r�������邽�߂ɐ�`���������������B���l�ɕ����ɂ����Ă��A�ΊO��`�͂�����̍��ł��i�߂��Ă���B�����̐������p�𑼍����ɏЉ����A�����Ώےn��̐l�X�����i�ڂ��Ȃ��悤�ȏ�������肷�������S���Ă���B�܂��A���������ɂ����{�̐�`�����͍s���Ă���B���{�������ɑ��ď���������A����������ӌ������ݏグ�A�����ɔ��f������o�����̍s���L�����W�J����Ă���B
|
��11�@�V��
[�V���̑���]
�C���^�[�l�b�g���͂��߂Ƃ�����`�B�̊����傫���ϖe���钆�ŁA�V�����S���ׂ��Ӗ��A������@�\�͂ǂ��ɂ���̂��B�V���͎��̔}�̂Ƃ��đ��݂𑱂�����̂��B�����Ɏ葤�ɁA�V����ǂ܂Ȃ��Ă��l�b�g�̃j���[�X�ŏ\���Ƃ̈ӎ����L�܂��Ă���B���{�V�������2006�N�̐V�����Łu�V���́A���������̒S����Ƃ��āA���ߍׂ��Ȏ�ނƕ��́A��ÂŐӔC����ɂ��A�l�X�Ɋm���Ȏw�j�ƓW�]�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̌��c���̑������B
����̐V���́A�ǎҐ��ɂ��Ă͂قږO�a��Ԃɂ���A�Œ肳�ꂽ�p�C��D�������ߓ��������������A����Ŏ�҂𒆐S�Ƃ����V������ɔY�܂���Ă���B
[�V���̉��l]
�V���̉��l�̈�́A�Ǝ��̎�ޗ͂ʼnB���ꂽ�����@�����邱�Ƃɂ���āA�������K�v�Ƃ������I�m�ɓ`��������ł���B��������}�֎���(1992�N)�ł́A���ېM�����}�����ق�5���~����̂��Ă��������𖾂�݂ɏo���������V���́̕A���{�����ɑ傫�ȕϊv�������炵���Ƃ�����B
�V���̉��l�̓�ڂ́A���ߑ��Ƃ����鍡���̎Љ�ŁA����̗����I�m�ɂ��ݓǎ҂ɒ������͂ł���B�ꗗ���̋��݂����V���́A�Љ���G���E���ۉ�����ɂ�A�K�v���𑝂��Ƃ�����B���ł̓C���^�[�l�b�g��e���r�Ɉ������Ƃ��Ă��A�V���������Ă��������ŁA���o���̑召�Ȃǂœǎ҂ɕ�����₷������@�\�͏d�v�ł���B
[�V���̏�����]
�����V����2004�N�A�z�[���y�[�W��ʂ��ĉ���ɗl�X�ȃT�[�r�X�����u�A�X�p���N���u(�����V���f�W�^���֓���)�v���X�^�[�g�������B�����V���ł́u�܂��܂��N���u�v�A�ǔ��V���ł́u������(�T�[�r�X�I��)�v��2005�N�A2006�N�ɊJ�n���Ă���B�����V���́u�܂��܂��N���u�v�������Č��݂̓T�[�r�X�̌`�Ԃ�ς��Ă��邪�A����̓C���^�[�l�b�g��ʂ��Ă̓ǎ҂̈͂����݂ł���ƍl������B�������������́A���}�̂ł̐V����O��Ƃ��A�C���^�[�l�b�g�Љ���ӎ������헪�Ƃ�����B�V���͐₦���Z�p�v�V�ɂ��`�Ԃ�ύX���A�l�b�g�Љ�Ƃ̋������ӎ�����Ă���Ƃ�����B
��12�@����
[NHK�Ɩ���]
�������Ƃ̌o�c�`�Ԃ́A�O�̃^�C�v�ɕ�������B���́A���Ƃ����炻�̌o�c��̂ƂȂ鍑�c�����A���͌����I���i��L�����Ƒ̂ɂ���Čo�c�������c�����A��O�͖��Ԃ̎��l�A�c�́A����ƂȂǂ��c���I�ȖړI�Ōo�c���s�����c�����̎O�ł���B���{�ł�NHK�̑O�g�Ƃ���1925�N�Ƀ��W�I�̑S�����y��ڎw�����߂ɎВc�@�l�ɖ{��������ݗ����ꂽ�B1950�N�̐��A����@�l���{��������ɉ��g����A1953�N���NHK���e���r����������邱�ƂƂȂ����B�����́A�����@�Ɠd�g�@�̐����A1951�N��16�Ђɗ\���Ƌ����o����A�������W�I���J�n���ꂽ�B1953�N8���ɂ͓��{�e���r������(NTV)���e���r�������J�n�����B
[����]
�����@�̏̑啔����NHK�Ɋւ���K��ł���A�����ɂ��Ă͂��܂葽���̂��Ƃ��K�肵�Ă��Ȃ��B����͕����@���莞�A�������ǂ̂悤�Ȍ`�Ԃ��Ƃ�A�ǂ̂悤�Ɋ������ׂ����ɂ��Ė��m�ȍ\�z���Ȃ��������߂ł���B�܂��ANHK�������@�Ă̐R�c�ߒ��ɂ����āA���������̋]���ɂ����ď��ƕ��������������悤�Ƃ�����Ă�A�������������_�ɔ����A�ے�I�Ȍ�����ł��o�������Ƃɂ����B�����́A��Ƃ��čL�������̎����ɂ���Ă܂��Ȃ��鎄��ƂŁA�قƂ�ǂ�������Ђ̌`�Ԃ��Ƃ��Ă���BNHK�������@�ɂ���đS���������K�肳��Ă���̂ɑ��āA�����͍s�����j�Ƃ��Č����o�͂������Ƃ���{�ݖƋ��ɂ���ă��[�J�����������{����Ă���B
[�q�������ƃP�[�u���e���r]
�q�������͊e�ƒ�ʼnq����M�p�̃p���{���A���e�i��ݒu���邱�ƂŒ��ڂɉq�����瑗���Ă���f���≹���A�f�[�^����葽�l�Ȕԑg���y���ނ��Ƃ��ł���B�܂��A�P�[�u���e���r�͗L���̃T�[�r�X�ł��邱�Ƃ���A�n��g��q���̖��������T�[�r�X�Ƃ͎���قɂ���B���{���̎��p�����q���Ƃ��āu���2��a�v��1984�N�ɑł��グ���A������g����NHK�q���������n�܂����B�܂�1991�N�u���3��b�v���ł��グ���A���{�ŏ��̃y�C�E�e���r�Ƃ���JSB��WOWOW�̕������J�n���ꂽ�B�P�[�u���e���r�͌��X�R�Ԓn�̓���n��̉�����ړI�Ƃ��������A���e�i�ɂ�鋤����M�{�݁A�L���ɂ��e���r�����̍đ��M�{�݂ł������B�P�[�u���e���r�͋����A���e�i�Ɗe�ƒ�̃e���r�@�Ƃ����ԃP�[�u���̋`�����l���𗘗p���Ď���ԑg�����o�ł��邱�Ƃ���A�傫�Ȓ��ڂ��W�߂��B
��13�@�o��
[�o�ŎY�Ƃ��o�ŋƂ�]
�o�ŋƊE�́A�o�ŎЁA�掟�A���X�̎O�҂��琬�藧���Ă���A�o�ł������w�����͖��m�ł͂Ȃ��B�o�ŕ��Ƃ��ẮA�G���A�R�~�b�N�X�A���|���A��发�A���ȏ��A���T�A�Y�Ƃɂ܂ōL�����Ă���B�o�ŎY�ƂƑ�����ƁA�����ɗ������グ�邩�A�������̂������ɂ��邩�Ƃ����o�c�I���ʂ��O�ʂɏo�Ă���B�o�ŋƂƑ�����ƁA�������L������������Ă����u�ł���ƍl������B
[�o�ŊE]
30�N��U��Ԃ����Ƃ��Ă��A�o�ŊE�͐₦����@������Ă����B73�N�u�p���s���ɂȂ�A���\�L�̊�@���}����v�A92�N�u�o�u������ŋx�����o�A�o�ŎЂ̑�^�|�Y���b��Ɂv�A05�N�u�Ăу}�C�i�X�����A���ЁA�G���Ƃ��ɑO�N����v�Ƃ��������Ƃ���������B����ɂ��ւ�炸�o�ŊE�̓W�������̍L���ƓƎ��̍\���ɂ�萬�����Ă����B1956�N���w�T���V���x���n������A�e���r����ɑΉ������G���ɂ��o�ŊE�̍��x�������n�܂����B1973�N���G�������l�����A�ו�������Ă����B�������A�������𒆐S�ɑn���͑����Ă��邪�A��O�������Đ������Ă���Ƃ͂����Ȃ��B
[�o�łƂ͉���]
�o�ł̓����Ƃ��ẮA1���i�폭�ʐ��Y�A2�ϑ��̔��A3�Ĕ̐��x����������B�{���A���̓������������āA�����̓`�B���s�����Ƃ�����Ƃ���ׂ��ł��������A�����͎����ʁA���Ђ��G���ɂ�闘�v�D�悪�Ȃ���Ă���B���앨�̍Ĕ̐��x�́A1953�N�ɓƐ�֎~�@���������ꂽ���Ƃ��n�܂�A�����܂Ō������̌��������x�ƂȂ��s���Ă����B2001�N�Ɍ���ς́u�Ĕ̐��x�͓��ʑ��u���Ó��v�ƌ��f�������Ă���A���݂Ɏ����Ă���B2001�N�A�o�ŋƊE�ɑ��|�C���g�T�[�r�X�����⎞���Ĕ̑Ώەi�ڂ̊g������߂�ӌ������������A���{���X���Ƒg���A����͂�������ۂ����B�������A2004�N�A�����A�͂���܂ł̎p����]�����ă|�C���g�T�[�r�X�̎����\�������B�A�����J�E�C�M���X�ł͎��R�����ł��邪�A�t�����X�A�C�^���A�A�h�C�c�Ȃ�10�J���͉��炩�̌`�ōĔ̐��x�����{���Ă���B
��14�@�C���^�[�l�b�g
[CMC]
Computer mediated communication�́A�R���s���[�^��}��Ƃ���R�~���j�P�[�V�����ł���BCMC�̓����͕����I�ɗ��ꂽ�Q���ғ��m�̑��ݍ�p���A�l�X�Ȍl����铽���A�����ŃR�~���j�P�[�V�������s����B�R�~���j�P�[�V�����ɂƂ��ď�Q�ƂȂ�Љ�I���E�╨���I���E��CMC�ɂ���č������邱�Ƃ��ł���B�������ACMC�ɂ���đ����̕s�K�v�ȏ��Ɛڂ��邱�ƂɂȂ�B�R���s���[�^��}��Ƃ��邱�ƂŁA�l�I�s�ׂƂ��Ă̌o�������ނ���B�܂��A�T�C�o�[��Ԃ̃R�~���j�e�B�͌��z�������ꂸ�A�l�X�Ȍ`�ԂŊĎ������\��������B
[���@�[�`�����R�~���j�e�B]
���@�[�`�����R�~���j�e�B�̓C���^�[�l�b�g�����p���ĒN�ł��`���ł���R�~���j�e�B�ł���B��̒�`�Ƃ��āu�ގ������S�����L����l�X���A�Ӑ}�I�ɒz�����R�~���j�e�B�ł���v�Ƃ����B�������A���������S��CMC�Ƃ͈قȂ郁�f�B�A�Ő����邱�Ƃ�����A�h���}�̓o��l�����p�������t�⌾�������̒��S�ƂȂ邱�Ƃ�����Ǝw�E�����B�C���^�[�l�b�g��̃R�~���j�e�B�͐l�X�ɂƂ��ďd�v�ł͂Ȃ��P�[�X�����X���邱�ƁA�o���ɂ�鐬���Ԃ̌������ړI�������������I�ł��鎖�������݂��邱�Ƃ��w�E����Ă���B�܂��ACMC�ɂ���Č`�����ꂽ�W�c�ɂ͓������ƐM���������@���Ă��邽�߁A�R�~���j�e�B�̈Ӗ�����Ă��܂����Ɣᔻ����邱�Ƃ�����B��ʂ̃R�~���j�e�B�ŕK�v�ȐӔC��`�����A���@�[�`�����R�~���j�e�B�ł͕K�v�Ƃ͌���Ȃ����߂ł���B
[���吭���ƃC���^�[�l�b�g]
�C���^�[�l�b�g�������ɑ��āA�v���X�̉e����^���邩�A�}�C�i�X�̉e����^���邩�ɂ��Ă͗l�X�ȋc�_���Ȃ���Ă���B�v���X�̉e���Ƃ��ẮA1�C���^�[�l�b�g�̑o�������A2�����I�R�~���j�P�[�V�����Ɛ����I�R�~���j�P�[�V�����̋����A3�}��g�D�̖����̌��ށA4���̔��M�A��M�R�X�g�̒ቺ�A5���`�B�̑����A6�l�X�ȋ��E���z���邱�Ƃ��������Ă���B����ɑ��āA1���̋����ߏ�ɂ���ėL�����p����Ă��Ȃ����ƁA2�^���ȓ��c��W����G���Ƃ�������ӌ������݂��邱�ƁA3�����̕����ӌ��̐l�X�ɂ�闘�p�Ȃǂ����p�҂Ɣp�ҊԂ̊i���ނ��Ƃ��w�E����Ă���B
��15�@���̑��̃��f�B�A
[�f��]
�f��Y�Ƃ͔�r�I�Â����j�����B���Ƃ��Ɖf��́A���̓��̎d���̔�������A�����̋ΘJ�ւ̊��͂�^����݂̂Ȃ炸�A�l�X�̕���������L���ɂ��A�Љ�I�E����I�e�������^������̂ƍl�����Ă����B�������A�e���r�̓o��E���y�ɂ���āA����܂Ō�y�̉������߂Ă����f��͐r��ȉe�����邱�ƂƂȂ����B�f��Y�Ƃ́A����A�z���A���s�̎O����ɕ�����Ă��鑼�A�t�B�����H�ƁE�f��@�B�H�ƂȂǑ����̊֘A�Y�Ƃ�����Ă���B�f��قւ̓���Ґ���1958�N��11��2700���l���s�[�N�ɗ����n�߁A1981�N�ɂ�1��4945���l�ɂ܂ŗ������B2000�N�ȍ~��1��6000�|7000���l���1970�N��㔼�����ɂ܂Ŏ��������Ă���B
[�L��]
�L���Y�Ƃ��ꎩ�̂̓��f�B�A�}�̂�L���Ă��Ȃ����߁A���f�B�A�Y�ƂƂ͂����Ȃ��B�������A�L����̈ϑ��ɂ��A�L���v��̗��āA����A���{�Ȃǂ̌�L�����s����L���㗝�s�́A�L���̍���Ƃ��āA�܂����f�B�A�Y�Ƃ̎������Ƃ��ă}�X�R�~�Y�Ƃ̍��Ȃ�v�����鎑�i�������Ă���Ƃ�����B�L���Y�ƁA�L���㗝�X�͂��Ƃ��ƒP�Ȃ�X�y�[�X�E�u���[�J�[�ɉ߂��Ȃ��������A�L����ƍL���}�̂̊Ԃɂ����āA�o���̊e��T�[�r�X����A���̃T�[�r�X�ɑ����V���萔���Ƃ��āA�L����̈ꕔ����邱�Ƃɂ���Đ��藧���Ă����B�L���㗝�X�́A�P�Ȃ�㗝�Ƃɗ��܂炸�A�}�[�P�e�B���O��v�����j���O�A�L�������v�����[�V�����E�C�x���g�̊��E���s�A�R���T���e�B���O��C�Z���X���C�c�Ǘ��A�l�ޔh���܂ł��̋Ǝ�̍L����������Ă���B
[���y]
���y�̘^���ƍĐ���1880�N���Ɏn�܂�A�u���ԂɍL�܂����B���̔w�i�ɂ́A�|�s�����[�\���O�ƃ|�s�����[���y���L�͂Ȗ��͂�����Ă������Ƃ��������B�}�X�E���f�B�A�����鉹�y�ƁA���O���l�I�Ɋy���މ��y�Ƃ̍��͂قƂ�ǂȂ��Ȃ����B����E����A�g�����W�X�^�v���ɂ���āA���W�I�͉ƒ납��l�̃��f�B�A�ɕς�����B���̕ω��́A��҂Ƃ����s����J�A�e�[�v���R�[�_�[�A�E�H�[�N�}���ACD�Ƃ��������W������ꂽ�B
|
��16�@�}�X�E���f�B�A�̍\���Ɗ����̐���
[�}�X�E���f�B�A�̍\��]
�}�X�E���f�B�A�̍\���̓V�X�e���Ɋ֘A���鎖�ۂ����ׂĎw���A����ɂ͑g�D�`�ԁA�����A���L�A�K���`�ԁA�C���t���A���`�B�{�݂��܂܂��B�����͑g�D���x���ł̍s���l�����w���A����ɂ͏��̑I����Y�̕��@�A�ҏW��̌���A�s��ł̕��j�A�����̑��̋@�ւƂ̊W�A�ӔC��L�����Y�҂��܂܂��B�����̐��ʂ͏����Ӗ�����B���Ȃ킿�A�����Ȃ����ۂɃI�[�f�B�G���X�ɓ`�B����邩�����ƂȂ�B
[�}�X�E���f�B�A�̋̕q�ϐ�]
�q�ϕɊւ���I�[�f�B�G���X�̗����͊T���č����B�q�ϕɂ���ď��ɑ���l�X�̐M���x�͑�������B���f�B�A���M�A�q�ϐ��ɂ���Ď����j���[�X�̎s�ꉿ�l�����߁A�s�ꂪ�g�債�Ă������Ƃ�m���Ă���B�q�ϐ��̊���L���Љ�ɍL�܂������ʁA�̕Ό���s�����Ȉ����ɑ���ًc�\�����āA��������߂鐺��������悤�ɂȂ����B�q�ϐ��͎����ɉ����ĉ��l�̖��������K�v������A�����ɂ͉��l���܂܂�Ă���(Westerstahl 1983)�B�������A�q�ϐ����̂��̂��s���m�ł���Ƃ�����肪�w�E����Ă���B�q�ϐ��Ɋւ��ẮA�K�v���A�ϗ��I���ʁA�B���\���Ɋւ��ċ��ʂ̌����͑��݂��Ă��Ȃ��B�u��X�����E�𗝉����悤�Ƃ���ꍇ�A�q�ϐ��̉\���Əd�v�����������A���̍�Ƃ�i�߂邱�Ƃ͕s�\�ɂȂ�(Lichtenberg 1991)�v�Ƃ����咣�ɂ͐����͂�����B
[�Љ��]
�}�X�E���f�B�A�ƒ����Ɋւ���l�����́A�N�̒������A�����Ă����Ȃ��ނ̒������Ƃ����_�Ɉˑ�����B�Љ���ƕ��������Ƃ�������܂��ȋ敪�́A�ォ��̎��_���A������̎��_���ɂ���ĕ��ނ����B
�@�@�@�\.�����̕���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ォ�� �@�@�@�@������
�@�@�@�Љ�� �@�@�����E���] �@�@�A�сE����
�@�@�@�������� �@�@�����E�K�w�� �@�����E�A�C�f���e�B�e�B
��17�@���f�B�A�̌o�ςƓ���
[���f�B�A�̌o��]
�}�X�E���f�B�A���L����Љ���I�ȈӖ��𗝉����邽�߂ɂ́A�L�����������I���o�ϓI�ȗ͂�`�ʂ��邱�Ƃ��s���ł���B���������͂̓��f�B�A���x���`������ۂɍ�p����B�}�X�E���f�B�A�̊����͍��ƃT�[�r�X�̐��Y�Ɗւ��B�����̐��Y�����̑����́A���I�ȗ̈�ƌ��I�ȗ̈�̑o���ɂ܂������Ă���B���f�B�A�̐��Y����T�[�r�X�͏���Ҏs��ƍL���s��ɕ�������B�L���s��ł́A�L����ɃT�[�r�X���̔������B����Ҏs��́A���ЁA�e�[�v�A�r�f�I�A�V���̂悤�ɏ���҂ɒ��ڔ̔�����������̎s��ƁA�P�[�u���e���r�A�I�����C�����f�B�A�̂悤�Ɍp���I�ɒ����T�[�r�X�ɕ�������B
[���f�B�A�̃R�X�g]
���f�B�A�o�ς����E����R�X�g�́A���Y�ɗv����Œ��ƕϓ���ɕs�ύt�������Ă���B�Œ��Ƃ́A�y�n�A���I�ݔ��A�{�݁A���ʃl�b�g���[�N�ł���A�ϓ���Ƃ͍ޗ��A�\�t�g�E�F�A�A�J���҂��w���B�ϓ���̊����������ƁA�s��ω��ɑ��ĐƎ�ȃr�W�l�X�ƂȂ�B�`���I�ȃ}�X�E���f�B�A�͒ʏ�͕ϓ���̕����������߁A�̔�������L�������ɂ���đ��z�̎��{�����ߍ��킹��K�v������B�u�ŏ��̃R�s�[�v�̃R�X�g�����ɍ������̂��A�ʏ�̃��f�B�A�̐��Y���ɔ��������ł���B�����V����f��̏ꍇ�A�ŏ��̔ł��c��ȃR�X�g�ƂȂ�A����ȍ~�̃R�s�[�̃R�X�g�͑啝�ɉ�����B�����������R����V���Ȃǂ̓`���I���f�B�A�͏���҂̎��v��L�������̕ϓ��̉e���������A�K�͂̌o�ς��d�������B
[���L�Ǝx�z]
���f�B�A�\���𗝉����邽�߁A���f�B�A�̏��L�Ƃ���ɔ������͂��ǂ̂悤�ɍs�g����邩���݂�B�u���f�B�A�̓��e�́A���f�B�A�Ɏ��������҂̗��Q����ɔ��f����v�Ƃ����W���[�i���Y���̖@��������B���f�B�A���L�̎�v�Ȍ`�Ԃ͉c����ƁA���Ԃ̔�c���c�́A�����@�ւł���B�����@�ւ��L���郁�f�B�ɂ��Ă��o�ς̘_���͖����ł��Ȃ��B�܂��A���ԃ��f�B�A�̑啔�������{��`�̐��̒��Ŋ������v��L���Ă���A���̑啔�������m�ɕێ琨�́A�ێ琭�}���x������X������������������B
��18�@�O���[�o���ȃ}�X�E�R�~���j�P�[�V����
[�O���[�o���[�[�V����]
�R�~���j�P�[�V�����v��������t����̂̓��f�B�A�̏W�����Ƃ����V���Ȍ��ۂł���B����͍��Ƃ��z���A�l�X�ȃ��f�B�A�Ő����Ă���B���̌��ۂ͏����̐l�X�ɂ�鋐��ȃ��f�B�A��Ƃ̎x�z���Ă����B�j���[�X�A�l�C�f��A�|�s�����[���y�A�V���[�Y�����ꂽ�h���}�A���ЂȂǂ̃R���e���c�̓��f�B�A���L�̃O���[�o���[�[�V�����Ɛ��Y�E���ʂ̎x�z�Ɋ�^���Ă���B�����̃��f�B�A�R���e���c�͗e�Ղɍ��ێs������Ɍv�悳��A�����I�ɂ͎s��◬�ʖʂł��Ȃ�_��ɑΉ������B�j���[�X�͎�v�ȍ��ےʐM�Ђ���āA���i�����ꂽ�ŏ��̐��Y���ł���B�����̃j���[�X�E���f�B�A�ɂƂ��Ď���C�O�j���[�X�����W��������A���ےʐM�Ђ���d���������͂邩�ɕ֗��Ōo�ϓI�ł���B
[�O���[�o���ȃ}�X�E���f�B�A]
�V���⏑�Ђ̊C�O�̔��A�q���e���r�̃`�����l���A���I�@�ւ��x�����鍑�ۃ��W�I�����Ȃǂ́A�����̃I�[�f�B�G���X��Ώۂɂ������鍑�̃��f�B�A�ɂ�钼�ڂ̔z�M�A�o�ŕ��̒��ڂ̋����ł���B�܂��A�������f�B�A�R���e���c��⊮���邽�߂ɗA������鑽�l�ȃR���e���c�����݂���B�O���[�o���ȃ}�X�E�R�~���j�P�[�V�����͑��l�Ȍ`�Ԃ��Ƃ��Ă���B���ɃA�����J�̃R���e���c�̐���ʂ͗A���ʂ����|���Ă���B�A�����J�̃R���e���c�̑����͍��ێs����u�����Ă��邱�Ƃ���A�A�����J�̃��f�B�A�������ԐړI�ɃO���[�o��������Ă���B�������A�O���[�o���[�[�V�����ɑ��āA����╶���Ƃ��������R�̏�ǂ����݂��邱�Ƃ��w�E����Ă���(Biltereyst 1992)�B
[���ۓI�j���[�X�̗���]
�����̊C�O�j���[�X�͂����ς琭���A�푈�A�O���A�f�ՂɏW�����Ă������A���͈̔͂͊g�債�A���ɃX�|�[�c�����������グ����悤�ɂȂ��Ă����B�܂��|�\�A���Z�A�ό��A�L���l�̃S�V�b�v�A�t�@�b�V�����̃j���[�X���������悤�ɂȂ����B���ۃj���[�X�̑I����Ƃł́A�����Ό������Ȃ����݂��Ă���B���̗��R�̓j���[�X�̗���A�e�j���[�X�E���f�B�A�̃Q�[�g�E�L�[�s���O�ɂ���ĕΌ��͐�����B�ʐM�Ђ͎����̃I�[�f�B�G���X�����ɋ����������Ƃ������ϓ_���獑�O�Ńj���[�X�����W����B���̌��ʁA�h���}�����Ȃ��A�j���[�X��M���ƒ��ڊW���Ȃ������̃j���[�X�̂قƂ�ǂ͍폜�����B
��19�@�}�X�E���f�B�A�g�D
[�}�X�E���f�B�A�g�D�̊K�w]
�}�X�E���f�B�A�g�D���l����ꍇ�A�}�X�E���f�B�A�g�D�������I�łȂ��A���̐����I�E�o�ϓI���͂�ێ�����g�D�ɋ����e�����邱�Ƃ�O��Ƃ��čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�}�X�E���f�B�A�ƃ��f�B�A����芪���O�Ƃ̊W�́A�قȂ郌�x���̊K�w�������ƍl�����Ă���(Dimmick and Coit 1982)�B����́A���Ƃ������ۃ��x���A�Љ�x���A���f�B�A�Y�ƃ��x���A�}�X�E���f�B�A�g�D���x���A�l���x���Ƃ����悤�ɏ����t������B���̃}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̑����Ƃ������芪�����̊W�́A�Ɨ����Ă���Ƃ��������A���ݍ�p�I�Ō��\�ƍl������B
[�}�X�E���f�B�A�g�D]
�}�X�E���f�B�A�Ɉ��͂�^����O���҂Ƃ��āA1��������A�L����A���L�ҁA�J���g���A2�@�I�E�����I�����A���͒c�́A���̎Љ�@�\�A3�I�[�f�B�G���X�̗��Q�E�v���A4�o��������ьp���I�ȏ��A�����̋������w�E�����B�܂��}�X�E���f�B�A�g�D���ɂ͊Ǘ��E�A�Z�p�E�A���E�Ƃ���3�̐E�ƕ���������B���̃}�X�E���f�B�A�g�D�̑������܂��āA�}�X�E���f�B�A�g�D���A�Љ�A���͒c�́A���L�ҁA�I�[�f�B�G���X�A�g�D���Ƃǂ̂悤�ɊW���Ă��邩���݂邱�ƂŁA�}�X�E���f�B�A���Ă���e���𗝉��ł���B
[�}�X�E���f�B�A�g�D�����̖ڕW�̑��l��]
�}�X�E���f�B�A�g�D�ɂ͑��l�ȖڕW�����݂���B����́A�}�X�E���f�B�A�̊����ɑ��鈳�͂𗝉����A�X�^�b�t���̗p����d���̑I���������ɂ߂�ۂɏd�v�ł���B�V���E�������n�C�u���b�h�g�D�Ƒ�����B�n�C�u���b�h�Ƃ́A�����ƁE�T�[�r�X�Ǝ����ƁA���Y�Z�p�Ƃ��̗��p�̑��l���̎����̂ǂ��ɂ����m�Ɉʒu�Â����Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł���B�V���ЁE�����͐��i�����Ɠ����ɃT�[�r�X������B�܂��A�P���Ȃ��̂��畡�G�Ȃ��̂܂ő��l�Ȑ��Y�Z�p�𗘗p����B���m�Ȉʒu�Â����ł��Ȃ����Ƃɉ����A�}�X�E���f�B�A�g�D�ɂ͈قȂ�J�����������݂��A�قȂ�ڕW��E���ɂ���Đ���������Ă���B
��20�@�}�X�E���f�B�A�����̐��Y
[�����̐��Y�ƑI��]
�����ł́A�l�X�̏o�����𗝉��\�ȏ��ւƌ����I�ɕϊ�����V�X�e���A�A�C�f�A�����݂̂��镶���I�p�b�P�[�W�ւƕϊ�����V�X�e���������B�܂�A���f�B�A�����ɂ����čs���鐶�̑f�ނ̑I�����犮���i�̒Ɏ����A�̉ߒ��ʼn������I�����w���B�������̃j���[�X���j���[�X�E���f�B�A�̕����̃Q�[�g��ʉ߂��ăj���[�X�E�`�����l���ɓ��B�ł��邩�ۂ����������ۂɃQ�[�g�E�L�[�s���O�Ƃ����l�����Ő��������B
[�j���[�X�o�����[]
�j���[�X�o�����[�Ƃ́A�I�[�f�B�G���X�ɂƂ��ċ����[���X�g�[���[�ւƕϊ������o�����̓������w���B�j���[�X�o�����[�͑��ΓI�ɔ��f����邽�߁A������o�������l�X�̊S�������Ă����Ƃ��Ă��A���S���������o�����ɂ���Ă��̍���D���邱�Ƃ�����B�j���[�X����ɍ�p�����v�ȗv���́A�g�D�I�v���A�W�������Ɋւ���v���A�Љ���I�v���ł���Ƃ����(Gultung and Ruge 1965)�B�g�D�I�v���͉��炩�̃C�f�I���M�[�I�ȉe�����y�ڂ��B�W�������Ɋւ���v���́A�I�[�f�B�G���X�̊��҂ɓK������o�����ł���B�܂��Љ���I�v���͉��l�ςɗR�����A�l�Ԃɏœ_�����Ă���B
[���ԂƑI��]
���Ԃ̓j���[�X�̑I���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���B���Ԏ��͗\�肳�ꂽ���́A�z��O�̂��́A�\��Ɩ��W�Ȃ��̂�3�ɕ������A����ɉ����ăj���[�X�̓n�[�h�j���[�X�A�\�t�g�j���[�X�A�X�|�b�g�j���[�X�A�W�J���E�p�����̃j���[�X�ɕ��ނ����B�\�肳�ꂽ�j���[�X�͎��O�ɒm�炳��Ă��邽�߁A�v��I�ȕ��ł���B�z��O�̃j���[�X�͏o�������\�z�O�ɐ��������ɕ���K�v������j���[�X�ł���B�\��Ɩ��W�ȃj���[�X�͎��Ԃɑ�������Ȃ��A�ۑ��\�Ȃ��̂ŁA�啔�����\�t�g�j���[�X�ƂȂ��Ă���B
|
��21�@�}�X�E���f�B�A�̓��e
[���e���������闝�R]
�}�X�E���f�B�A���e���������闝�R�́A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�������ʂ̉\���Ɋւ���S�A�������̓I�[�f�B�G���X�̋������Ђ����e�ɂ��Ēm�肽���Ƃ������@���痈�Ă���B1�������̃��f�B�A��`�����l���̓��e�̓����m�ɂ��邽�߁A���f�B�A�̐��Y����������A��r����B2���e���Љ�I�����f���Ă���̂��A���f���Ă���Ȃ�A����͂ǂ̌����Ȃ̂��A�N�̌����Ȃ̂��Ƃ������f�B�A�ƎЉ�I�������r����B3�������̎���Əꏊ�A�Љ�W�c�̉��l��M�O�Ɋւ��鎑���Ƃ��ă��f�B�A���e�𖾂炩�ɂ���B4���f�B�A�e���͂Ƃ����ϓ_����A���f�B�A�̓��e�����߂���B���f�B�A���e�����ł͌��ʌ������s�����Ƃ͂ł��Ȃ����A���f�B�A���e���Q�Ƃ��邱�Ƃ͌��ʌ����ɖ𗧂B
[���e����]
���e���͍͂ł��Â��A�`���I�ŕ��͂̒��S�Ɉʒu���Ă���A���Ȃ��L�����H����Ă���B���e���͂ł́A���e�S�ʂ��邢�͓��e�̃T���v����I�����A�����ړI�ɂƂ��ėL�p�Ȏw���Ώۂ̃J�e�S���[�Ɋւ���t���[����ݒ肷��B�w���ΏۂɊւ���e���ڂ̏o���𐔂��邱�Ƃōs���A�o���p�x�ɂ���ē��e�S�ʂȂ����͑I���������e�̃T���v���̑S�̓I�ȌX���𖾂炩�ɂ���B�������A���e���͂ɂ����E�◎�Ƃ���������B���̈�Ƃ��āA�J�e�S���[�Ɋւ���t���[����ݒ肷��ہA������J�e�S���[�͑I��I�ƂȂ炴����A���e�̈Ӗ��̌n������Ƃ��������A����J�e�S���[�������t���郊�X�N������B
[�ʓI���͂Ǝ��I����]
�ʓI�ɖ��炩�ɂ�����e���͂Ɖ��ߓI�A�v���[�`�̊Ԃɂ͂������̈Ⴂ������B1�\����`�ƋL���_�ɂ͗ʓI�Ȗ��͊܂܂�Ȃ��B�Ӗ��̖��ɉ���ۂɁA�v�Z��p���邱�Ƃ͔��������B�Ӗ��͒P�ɐ���o�����X�̖��ł͂Ȃ��A�e�N�X�g��̊W�A�Η��A�R���e�N�X�g���瓱����邽�߂ł���B2�����I�ȓ��e�����َ��I�ȓ��e�̕��ɒ��ӂ��������A�َ��I�ȈӖ��̕����d�v�ł���Ƃ݂Ȃ����B3���I�ȍ\����`�͓��e���͂Ƃ͈قȂ���@�ő̌n������Ă���A�T���v�����O�̎菇�͏d�������A���e�̑S�Ă̒P�ʂ��Ɉ����ׂ��Ƃ����l����ے肷��B
��22�@���f�B�A�̃W�������ƃe�N�X�g
[�W�������̗ތ^]
�W���������͂́A���e�m�ɋ�ʂ���J�e�S���[�����ɓK�p�ł���ƍl�����Ă����B�������A������郁�^���͂����݂�ꂽ�B����́A�e���r�ԑg������̒��x�Ƌq�ϐ��̒��x��2�̎����ɂ���ĕ��ނ��鎎�݂ł���(Berger 1992)�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q�ϐ��̒��x������ �@�q�ϐ��̒��x���Ⴂ
�@�@�@����̒��x�������@�@�@���Z�@�@�@�@�@�@�@�@�h���}
�@�@�@����̒��x���ア�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@����
���Z�́A���ۂɍs���鋣���ł���A�X�|�[�c�ԑg�A�N�C�Y�Ȃǂ��܂܂�A��������߂�ԑg�ł���B�������ɂ̓j���[�X�A�h�L�������^���[�ԑg���܂܂�A�q�ϐ��̒��x�͍������A����I�ł͂Ȃ��B�h���}�͂قƂ�ǂ��t�B�N�V�����ł���A�q�ϐ��̒��x�͒Ⴂ�B�����͐������s�������̈Ӑ}�����f����A�L���A�̔����i�A��`���܂܂�A����E�q�ϐ��͂ǂ�����Ⴂ�B
[�e�N�X�g]
�e�N�X�g�Ƃ����p���2�̈Ӗ��ŗp�����Ă����B��́A��ʂɕ����I�ȃ��b�Z�[�W���ꎩ�̂��w���B������́A�e�N�X�g����e�Ɠǂݎ肪�o��������ʐ������Ӗ��Ƒ�����B�Ⴆ�e���r�ԑg���e�N�X�g�ɂȂ�̂́A���ꂪ�ǂ܂ꂽ�Ƃ��ł���B�e�N�X�g�Ƒ����̃I�[�f�B�G���X�̂�����l�Ƃ̑��ݍ�p�ɂ���āA�e�N�X�g�͊���̈Ӗ�����y�̊�������^������B�t�B�X�N�́u�ԑg�͋ƊE�ɂ���āA�e�N�X�g�͓ǂݎ�ɂ���Đ��Y�����(Fiske 1987)�v�Əq�ׂ��B�܂�A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̐��Y�́A�����ƃI�[�f�B�G���X�̗��҂̊����ɂ���Đ��܂�邱�Ƃ��w�E���ꂽ�B
[�J���ꂽ�e�N�X�g�ƕ����ꂽ�e�N�X�g]
���f�B�A���e�̈Ӗ��͂�����x�J����Ă���A���邢�͕�����Ă���ƍl������B�J���ꂽ�e�N�X�g�Ƃ́A�e�N�X�g�̌������ǎ҂��������̈Ӗ�����߂ɍS�����悤�Ƃ��Ȃ����̂ł���B�Ⴆ�A�A���҂̃h���}�͂��̈Ӑ}�����m�ɕ\������邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ӑ}���̂����l�ȓǂݎ�Ɉς˂���B�e�N�X�g���J�������x�͈�̃W�������̒��ł����Ȃ葽�l�ł���B�e�����Y���Ɋւ���e���r�̕`�ʂɊւ���c�_�̒��ł́A�J���ꂽ�`�ʂ���֓I�Ȍ������X�����������ŁA�����ꂽ�`�ʂ��x�z�I���邢�͍��ӂ��ꂽ��������������X���������Ƃ��w�E����Ă���(Schlesinger et al 1983)�B
��23�@�I�[�f�B�G���X�Ɋւ��闝�_�ƒ����̓`��
[�I�[�f�B�G���X�̊T�O]
�I�[�f�B�G���X�Ƃ������t�́A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����ߒ��̒P���Ȍp�N�I���f���̒��ł́A��̂���p��Ƃ��čL���蒅���Ă���B�I�[�f�B�G���X���͉̂����w��������̂��s���Ăł���A�B���Ȃ܂ܗp�����邱�Ƃ�����B�I�[�f�B�G���X�͑��l�ŁA�d��������@�Œ�`�Â������B���Ȃ킿�A�ꏊ�A�l�I�ȍ\���A���f�B�A��`�����l���̃^�C�v�A���b�Z�[�W���e�A���Ԃɂ���ăI�[�f�B�G���X�͒�`�����B
[�I�[�f�B�G���X�����̖ړI]
�I�[�f�B�G���X�����̖ړI�͑��l�ł���A�����Έ�ѐ��������Ă���B�I�[�f�B�G���X�Ƃ͈�ʂɌ`����܂炸�A�ω��������A���������������݂ł���B�������A�I�[�f�B�G���X�����́A�����������݂��\�����A�ʒu�Â��A���m�ɂ���̂ɖ𗧂B�ړI�Ƃ���1����グ�⎋�����̂��߂Ɏ��ۂ̏�B���𑪒肷��A2�V���ȃI�[�f�B�G���X�s���T���A3���f�B�A�̐��Y���̌��ƗL�����̌����ړI�Ƃ���A4�I�[�f�B�G���X�ɂ������ăT�[�r�X���s���A5�I�[�f�B�G���X���s���Ӗ����߂m�ɂ���A6���f�B�A���p�̃R���e�N�X�g�̋���������������B
[�I�[�f�B�G���X�̔\�����ƑI��]
�e���r�͑�l�Ɠ��l�A�q���̎���������ƍl����ꂽ���Ƃ���A�I�[�f�B�G���X�̔\�����ƑI�𐫂��d�v�ȊS���ƂȂ����B�I�[�f�B�G���X�͂ǂ̒��x�\���I�ŁA�I��I�Ɋ������Ă���̂��A5�̗ތ^������Ă���(Biocca 1988)�B1���f�B�A�Ƃ��̓��e�Ɋ֘A���đI�����s������x�������ꍇ�A�I�[�f�B�G���X�͔\���I�ł���Ƃ����B2�I�[�f�B�G���X�͎��Ȃ̗��Q�S�Ɋ�Â�����҂̌����ł���A���炩�̌`�̃j�[�Y������B3�\���I�ȃI�[�f�B�G���X�́A�l�X�Ȍ`�Ń��f�B�A�։�������Ȃǎu���������B4���������������e����w�K�ɑ��ăI�[�f�B�G���X�͎��狫�E����݂���B5�e���r�ɑ��鎋���ҎQ���Ƃ����`�ԂŁA�I�[�f�B�G���X�͐i�s���̃��f�B�A�ɔM�����A�v������悤�ɂȂ�ƁA�֗^����@���������B
��24�@�I�[�f�B�G���X�̕Ґ��Ǝ����o��
[���f�B�A���p�̍\��]
�I�[�f�B�G���X�̃��f�B�A���p��������邽�߂̃��f���Ƃ��č\�����f��������Ă���(McQuail 1997)�B�\�����f���ɂ��ƁA�Љ�ƃ}�X�E���f�B�A�\���Ƃ�����̗v�������т��A�K���I�ȍs���̃p�^�[�������łȂ��A���f�B�A�u�����ƌĂ�鎝���I�ȓ����A�X���A�p�����������B�Љ�́A����l���ʒu�Â���Œ艻���ꂽ���̂ł���A�l�X�͂��̎Љ�̒��Ńj�[�Y�����B�}�X�E���f�B�A�\���́A�������̏ꏊ�A���^�̌o�ϊ��A������ɂ����郁�f�B�A�̗��p�\���ɂ���č\�������B���̃��f���̓��f�B�A�\���ƌX�̃I�[�f�B�G���X�̎Љ�I�ȗ�������ѕt���Ă���Ƃ��낪�D��Ă���B���f�B�A�\���͎Љ�ɂ����鏊�^�̎����A�o�ϓI�E�����I�����f���A�I�[�f�B�G���X�̗v���ɂ��Ή�����B�I�[�f�B�G���X�̗v���͎Љ�I�w�i�Ƃ����v���ɂ���Č��肳�����́A�����I�ɐ�������̂�����B
[���f�B�A���p�Ɩ���]
���f�B�A���p�́A�I�[�f�B�G���X���m�o���閞���A�j�[�Y�A��]�A���@�ɍ��E�����Ƃ��錩��������B���̌����́A�Љ�I���S���I�ȗv������j�[�Y�����܂��ƍl������B�T�^�I�ɂ͏��A�������A�C���炵�A�����Ƃ������j�[�Y�ł���B����ɉ����āA���f�B�A�����闘�v�Ɋւ���m�o�ƁA�X�̃I�[�f�B�G���X�����̗��p�ɑ��čs�����l�t���̑g�ݍ��킹�ɂ���ă��f�B�A���p�������������҉��l���f�������ꂽ(Palmgreen and Rayburn 1985)�B���̃��f���ł́A���f�B�A���p�̓��f�B�A���瓾���邱�Ƃ����҂����[��������������B�����ă��f�B�A�𗘗p���ē���ꂽ���������҂��������ꍇ�A�I�[�f�B�G���X�͍����[���āA�]���⒍�ړx�����߂�B
[�I�[�f�B�G���X�̒f�Љ�]
��萔�̃I�[�f�B�G���X�����l�ȏ�Ɉ�w���ӂ������邱�ƂɂȂ邱�ƂŁA���̕��U�����i�ނ��Ƃ�f�Љ��Ƃ����B�ŏI�I�ɂ͂قڑS�Ă̑I�����l�P�ʂōs���A���̌��ʁA�Љ�I�W���̂Ƃ��ẴI�[�f�B�G���X�͏I������B�h�C�c�̉ƒ�f�[�^�ł́A�T�^�I�ȉƑ��������������Ă���B�e���r�����͈��|�I�Ɉ�l�Ȃ����͓�l�ōs���Ă���B�܂��A�q�����N�w�ł́A�p�ɂŒZ�����Ԃ̃e���r�����`�Ԃ���ʉ����Ă���B�����đ����̎����҂̓`�����l���������������ɂ�������炸�A�Ō�ɍs�������z�[���x�[�X�ƂȂ�`�����l���������Ă���B�I�[�f�B�G���X�͌���ꂽ�`�����l�������I�������Ȃ��A�S�ẴI�[�f�B�G���X�Ƀ��f�B�A�o�����L�����L����Ă����ꌳ���f������A���l�����i�������f���ɕω����A�I�[�f�B�G���X�̒f�Љ����i��̃��f���ɕω�������B
��25�@���f�B�A�E���e���V�[
[���f�B�A���e���V�[�Ƃ�]
���f�B�A���e���V�[�Ƃ́A���f�B�A�̒�����𐳂����ǂ݉����A���f�B�A���g�����Ȃ��\�͂��w���B���f�B�A�̍\���A�����A��o�̎d�g�݂���A���̎Љ�I�@�\��ӔC�A���̓�������l�X���ǂꂾ���m���Ă��邩���܂ށB�s���̑������f�B�A�����͂̈�����L���傩��̈��͂Ȃǂɒ��ʂ��A���f�B�A�g�D�����ł����Ȃ铬�����������Ă��邩�A�܂����f�B�A�ϗ��ƌ��E���ߒ���ԑg�E���ʂ̓�����m��Ȃ���A�s���E�����͎匠�҂ł���Љ�̌��݂͊ȒP�ł͂Ȃ����Ƃ����Ӗ�����B
[���f�B�A���E�ᔻ�̍��]
���f�B�A�̕��e�������邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B���f�B�A�ɑ��čו��ɂ킽��m�F�����߂�Ǝ�ތ��̔铽�𗝗R�ɂ��āA�قƂ�Ǐ��͊J������Ȃ��B��������ƁA��ƂȂǎ�ނ��ꂽ���́A���f�B�A�Ƃ̒������I�ȊW���l�����ă��f�B�A�ᔻ�����ɂ͔����A�T�d�ɍs������B��ނ���鑤�ƃ��f�B�A���̔Z���ȊW�����f�B�A�ɑ��錚�ݓI�Ȕᔻ��}�����Ă������Ƃ��A���f�B�A���ɂƂ��ėL���ɓ����Ă����Ƃ�����B
[���f�B�A���e���V�[����̂��߂�]
�ᔻ�I�u���͏��̌��▵���ɋC�Â��A�����I�Ɉӎv��������A�����̐������⎩�Ȃ̐��_�ߒ����ӎ��I�ɋᖡ���悤�Ƃ���v�l�̂��Ƃ������B���̔ᔻ�I�v�l�ɂ͓�̑��ʂ�����A��͔F�m�I�ȑ��ʂł���m����X�L���ł���A������͏�ӓI���ʂł���ԓx��X�����Ƃ���Ă���(Ennis 1987)�B�m����X�L���Ƃ������F�m�\�͂͒����N���������ČP�����邱�Ƃɂ���Č��シ��B�����ŁA�v�l�E�ԓx�͈Ӑ}���x���̖��ł���A�����̎d���ɂ���ĕϗe�\�Ȃ��̂ł���B���f�B�A���e���V�[�����߂邽�߂ɂ́A���Ȃ̃C�f�I���M�[���ʒu�m�Ɏ��o���������ŁA�ᔻ�I�Ƀ��f�B�A�̓��e���ᖡ���邱�ƂɂȂ�B
|
��26�@�v���p�K���_
[�v���p�K���_]
�v���p�K���_�Ƃ́A�����̐l�X�̐����l����s���l���A����ɑԓx�E�ӎv����Ȃǂɑ���ȉe����^���A�����̈Ӑ}���邠����̕����ցA��������킹��g�D�I�Ȏ��݂ł���B���鑤�͎��Ȃ̓s���̂悢������\�o�����A�l�X�ɋ��������i��p����B�܂��A����〈���̑Η�������Ɋւ��āA���t�₻�̑��̃V���{������g���A�l���邢�͏W�c�̑ԓx�ƈӌ��ɕϗe��^����悤�Ȋ�������B�����ĈӐ}���������ɐl�X�̑ԓx��ӌ���ω������A�����̍s���ւƗU�����Ƃ�ړI�Ƃ��������ł���B
[���Ɛ�`]
���Ɛ�`�ɂ͓�̑��ʂ�����B��́A��Ƃ̃}�[�P�e�B���O�����̈�Ƃ��āA���i�E�T�[�r�X�ɑ�����v�����N���邱�Ƃɂ���Ĕ̔��𑣐i����o�ϓI�Ȗʂł���B������͏��i�E�T�[�r�X�Ɋւ���\���ȏ�����ݓI���v�҂ɓ`�B����R�~���j�P�[�V�����Ƃ��Ă̖ʂł���B���̓�̑��ʂ͏��i�E�T�[�r�X�ɂ��������̓`�B��ʂ��Ă���ւ̎��v�����N����A�̔����i���������锽�ʁA���i�E�T�[�r�X�̎��v�̊��N���Ӑ}���邪�䂦�ɂ����Ɋւ����l�X�ɓ`�B�����Ƃ����A�\����̂̊W�ɂ���A���҂m�ɋ�ʂ��邱�Ƃ͓���B
[������`]
������`�̖ړI�́A�����E�Љ���Ɋւ��Ď�̐l�X�̍s���E�ԓx�ɑ��āA����肪�L���ȕ����ɗU�����悤�Ƃ�����̂ł���B�Ⴆ�A�I���������ɂ����āA�Η�������Ƀ_���[�W��^���邽�߂ɁA������f�}�𗬂��A�}�C�i�X�̈�ۂ�A���t���邱�Ƃ�����B�ŋ߂ł́A�p�\�R���E�l�b�g�ɂ��I���ȕ��@�ɂ���Ē�����f�}�𗬂����Ƃ������A������`�̃X�^�C�����ω����Ă��Ă���B�Ⴆ�ΐ�`�҂́A��҂��O�̖����ł���Ƃ�����������Ƃ�A�����̐l�Ɏx������Ă���Ƃ������o���s�����肷��B
��27�@��O�����Ɛ��_����
[��O�����Ƃ�]
��O�����Ƃ́A�命���̐l�X�ɘ_���I�E��I�Ȏ�i��p���A��O�̈ӌ��E�ԓx�E�M�O�ɑ��đ�O�𑀍삷�鑤���L���ȏɂȂ�悤�ȕ����ɈӐ}�I�ɒ�߁A��O�ɂ�����̍s�����N�������錾���ł���B��O�����́A������m�������ނ����⊴��ɑi���ċ����Ȃ�����Ƃ����X�^�C����p���āA�I�݂ɑ����U������B�����Ȃ�����͍U���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A����̊���ʂɒ��ړI�E�ԐړI�ɓ��荞�ނ��̂ŁA������Ƃ���ł��̎�@����������Ă���B
[���_����]
�}�X�E���f�B�A���_���Ȃǂœs���̂������߂�֒������A����̈ӌ��𗬂����ƂŁA��������ɐ��_���U������邱�Ƃ������B�V���Ђ̃C�f�I���M�[�����̌X�������ҏW�L�ҁA�_���ψ��A�e���r�ԑg�Ґ��A�L���X�^�[�̔����E�U���A����ɉ����ē���̃^�����g�g�p�ƃv���_�N�V�����̊W�Ȃǂɂ��Ɛ�̉e�����v��m��Ȃ��B
[���[�j���ƃq�g���[]
���V�A�v���̑�\�I�w���҂ł��郌�[�j���̓A�W�e�[�^�[�ł���Ƃ����B�A�W�e�[�^�[�Ƃ́A�������s�����̂��w���A��O�S���ɑ��ė�߂��ԓx�����B���[�j���̐����͈�̊ϔO�𑽂��̑�O�ɓ`���L�߂��B���̌��ʁA���V�A�Ƀv�����^���A�v�������������A�鍑��`�_���\�Ƃ���}���N�X��`�̗��_�Ǝ��H�̎w�j���������ƂƂȂ����B
�q�g���[��1919�N�ɍ��Ǝ�`�h�C�c�J���ғ}���������A1929�N�̐��E���Q�ɂ���Đ������Љ�s���ɏ悶�Đ��͂�L�����B�P�Ȃ�E�����}�ɂƂǂ܂炸�A����̐���O�ʂɉ����o�����A�W�e�[�V�����ő�O�s���I�Ȑ��}�ł��邱�Ƃ������ɐA���t�����B�q�g���[�͌��Ў�`�┽���_����`�Ȃǂ��f���đ�O�W���e�����Y�����J��Ԃ����B�i�`�Y���̓A�W�e�[�V�����������ɐZ���������j�I����ł���Ƃ����B
��28�@�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̎Љ�I�ӔC
[�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̐ӔC]
�}�X�E���f�B�A�ɂ͕̎��R������A�m�錠��������B�}�X�E���f�B�A�̕ɂ͊O���ɔ��\����ɂ�����A������̊����邱�ƂȂ��A���{�����݂��Ă��Ȃ��B�܂��A���̓����`�B���W�����邱�Ƃ��Ȃ��B�}�X�R�~�ɂ́A��ނ̎��R�A�E�]�_�̎��R�A�}�́E���ʂ̎��R���m�����Ă���Ƃ�����B�����ɂ́A����莩�g�̎���K�������߂���Ƃ�����BSchramm(1949)�́A�}�X�E���f�B�A�ɐӔC����s�ׂ������邽�߂ɗp�������i�Ƃ��āA�s���@�ւɂ������܂�A���f�B�A�̌����E������c�́A��ʂ̌��O���w�E���Ă���B�u���{�A���f�B�A�A���O�v�̎O�҂̃o�����X���d�v�ł���A�ӔC�͕��S����Ă���Ƃ����B
[�}�X�E���f�B�A�̎̕��R�����ތ����̗��v]
�}�X�E���f�B�A�̎�ށA�̎��R�͌����̗��v�ɂ��Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B1���O�����͎҂��Ď����A���͎҂Ɋւ���M���ł����K�ɒ����B����̓}�X�E���f�B�A�̔Ԍ��@�\��ᔻ�I�����ł���B2��L�x�ɒ���A�����Ȗ����`�̐���Љ�������i�����B�������Ƃɖ����`�̐�����������A�l�X�̎Љ���̊�Ղ��`�������Ƃ�����B3�\���̎��R�Ƃ�����������A���O��M�O�A���E�ς�\������@�����Ă���B
���f�B�A�����R�ł��邱�Ƃ��Ƒn���A�n�����A���L�����l���ݏo���Ă���B���R�ȃ��f�B�A�͓�����`�Ɋׂ�ׂ��łȂ��A�ӌ�����̑��l�������ׂ��ł���B�܂��A���f�B�A�͌��O�ɑ����ďo���������A�Ԍ��@�\��S���B������Ƃ����ă��f�B�A������̗���ɗ����Ƃ��W������킯�ł͂Ȃ��B���l���������Ƃ��J���ꂽ�����`�ɂƂ��čD�܂����Ƃ�����B
[���f�B�A�̃A�J�E���^�r���e�B]
���f�B�A�͌��\�������̎��A�Ȃ����͏������\�������ʂɊւ��āA�Љ�ɑ��Ē��ځE�ԐړI�ɉ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�A�J�E���^�r���e�B��������ꍇ�́A���f�B�A�̊����ɑ��ĉ��炩�̔������������ꍇ�ł���B�A�J�E���^�r���e�B�̓��f�B�A�����炩�̖��ɂ��ĒN���ɂނ����ĉ��邱�Ƃ��Ӗ�����B�A�J�E���^�r���e�B�ɂ͓�̃��f�������݂��A���I�Ȓ�������������铙�Љ�I�Ȉ��e��������ꍇ�A���@����@�̉Ȃ��������܂܂��@�I�ӔC���f���ƁA���f�B�A��ᔻ����l�ƃ��f�B�A�̊Ԃɐ��܂�鍷�ق߂邽�߁A�Θb�ⓢ�_�ɂ���ĎӍ߂�����A�������Ȃ���鉞�����f��������B
��29�@�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̏���
[�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̕K�v��]
�}�X�E���f�B�A�͏W�c�ƌl�̑o���ɗ��v�������炵�Ă����B�l�ɂƂ��Ă͌�y��C���炵�ɂȂ邤���A��R�X�g�ŃA�N�Z�X���\�ł���A�����̎����ɂ��ėL�p���M�p�ɑ����{�I�ȏ�����肷���i�ƂȂ��Ă���B�܂����҂Ɠ���������������L���邱�ƂŁA�W�c�̗��v�ɂȂ���B�������A�}�X�E���f�B�A�̒�����̎��ɂ͒Ⴂ���̂�����A���̌��ɂ߂��K�v�ł���B�X�l��������̑I�����A�}�X�E���f�B�A�̒���������p���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�}�X�E���f�B�A�̌��ׂ�����Ƃ��Ă��A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����͂��ǂ��Љ��ڎw�������ŕK�v�s���ł���Ƃ�����B
[�����w����݂�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̏���]
�����Q���ƃ}�X�E���f�B�A�̗��p�͋������т��Ă���B�������A�}�X�E���f�B�A�͐����̎���ቺ�����A��ʎs���Ɏ���ʂ����ׂ��`������ڂ����炳����悤�ȕ����Ă����Ɣᔻ�����B����ɑ��āA�j���[���f�B�A�ɑ傫�Ȋ��҂����A�����Q���𑣂��\��������Ƃ����B�j���[���f�B�A�͐V���ȃA�N�Z�X�`���l���⑼�҂ƌ��т����߂̉�H���J���Ă����B�������A�j���[���f�B�A���}�X�E���f�B�A�����S�ɑ�ւ��邱�Ƃ͂Ȃ��A�������Ă����ƍl������B
[�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̏���]
�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̕K�v���܂���ƁA���ł��邱�Ƃ͍l�����Ȃ��B����Ȃ�A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����͂ǂ̂悤�ɏ����ϖe����̂��B�}�X�E���f�B�A�͍��{�I�ɑ傫���ϗe���邱�Ƃ͂Ȃ��ƍl������B�}�X�E���f�B�A���͂͐ӔC�����Ƃ��قƂ�ǂȂ����߁A���݂̌`�Ԃ�ϗe������K�v���͂Ȃ����߂ł���B�������A�V����e���r�Ƃ������I�[���h���f�B�A�̗��p�͏��X�ɒቺ���A�V���ȏ���̃^�C�v�����ߍ��킹��悤�ɂȂ��Ă����B�����ŁA�C���^�[�l�b�g�ɂ͑����̏������̂́A���̓��e�͍U���I�ł���A���ʓI�ł���A���p�ȏ��������B�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����͑傫���ω����邱�Ƃ͂Ȃ����̂́A�I�[���h���f�B�A���j���[���f�B�A��K�Ɏ�荞�悤�ɁA�A���I�ɕω����Ă����ƍl������B
��30�@����
[�e���r�ԑg]
�����ł͎��ۂ̐������_�ԑg���������A���̐���̈Ӑ}�A�ԑg�̎����l�ρA�����R�~���j�P�[�V�����̂�����ɂ��ċc�_���s���B
���䑼(2002)�ł́A�������_�ԑg�ł���u���j���_(NHK)�v�Ɓu�T���f�[�v���W�F�N�g(�e���r����)�v�ɏœ_�āA2001�N�Q�c�@�I���̓��e���͂��s���Ă���B�����䗦�y�уJ�����V���b�g�̎��Ԃ��v�����ANHK�ł͗^��}�̔����̃o�����X���l�����Ă������ŁA�e���r�����ł͖�}�̔����䗦�������Ȃ��Ă��邱�ƁA����o������NHK���_�ԑg�ł̎����}�̔����䗦�������邱�Ƃ������Ă���B�܂��A�J�����V���b�g�̕��͂ɂ����ẮANHK�ł͗^��}�̌��������S�ۂ���Ă�����̂́A�e���r�����ł͖�}�ɑ���V���b�g�̕����^�}�������Ă��邱�Ƃ������Ă���B�����ŁA�����I�ȃJ�����V���b�g�Ɋւ��ẮA�������Ă����}�o���҂̔w�ォ��^�}�o���҂��B��Ƃ����J�����A���O�����u���j���_�v����сu�T���f�[�v���W�F�N�g�v�̗��ԑg�ɋ��ʂ��Č���ꂽ�Ƃ��Ă���A��}�ɑ��ĕs���ȉf���\���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B
���(2006)�ł́A2005�N5��16�������́u���j���_(NHK)�v�Ɓu�T���f�[�v���W�F�N�g(�e���r����)�v�����グ�A�u���҂̔������ւ̊��荞�݁v�A�u�����̈ӌ��������v�A�u�����Â��v�Ɋւ��āA�T���f�[�v���W�F�N�g�����j���_�������Ă��邱�Ƃ��m�F���Ă���B���̏�ŁA�u���҂̔������ւ̊��荞�݁v���ɑ��āA���ꂼ��̈�ە]����s���Ă���B���q���͂̌��ʂ܂��A�T���f�[�v���W�F�N�g�ɂ����ẮA�u���_��e���݈Ղ��A�y�����A������������Ȃǂ̍D��ۂ�^���Ă������ŁA�U���I�A����I�A���������A�}���I�Ƃ��������ے�I�Ȉ�ۂ��^���Ă���v�ƌ��_�t�����Ă���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�������̖���
|
�u�����́A�����`�̐��_�ɂ̂��Ƃ�A�����̌��������d�A�@�ƒ��������A��{�I�l���d���A�����̒m�錠���ɉ����āA���_�E�\���̎��R�����B�����́A���܂⍑���ɂƂ��čł��g�߂ȃ��f�B�A�ł���A���̎Љ�I�e���͂͂���߂đ傫���B�����́A���̂��Ƃ����o���A���������������A�Ƃ�킯�����E���N����щƒ�ɗ^����e�����l�����āA�V��������̈琬�ɍv������ƂƂ��ɁA�Љ���ɖ𗧂��ƌ��S�Ȍ�y����A�����̐�����L���ɂ���悤�ɂƂ߂�B�v
����́A1996�N�ɓ��{���ԕ����A��(�����A)�Ɠ��{��������(�m�g�j)����߂��u�����ϗ���{�j�́v�̈�߂ł��B�����ɕ����ǂƂ��Ă̎g���E�������Ïk����Ă��܂��B
�������f�B�A�́A�f���E�����ł��܂��܂ȏ����_�C���N�g�ɓ`���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�ق��̃��f�B�A�ɔ�ׂāA��ɗ^����C���p�N�g(�Љ�I�e����)�������ƌ����Ă��܂��B�܂��A�����ǂ́A�������ł���u�d�g�v�𗘗p���āA�ԑg�E�b�l�����ƒ�ɑ���͂��Ă��܂��B���̂��߁A�������f�B�A�ɂ́A����߂č����g�������h�����߂��Ă��܂��B
�������f�B�A�́A�ԑg�E�b�l��ʂ��āg���h�𑗂�͂��邱�Ƃ������̒��S�ƂȂ�܂��̂ŁA���@�ŕۏႳ�ꂽ�u�\���̎��R�v�𐳂����s�g���邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B����́A�����ǂ��\���������s�����߂̎��R�Ƃ������Ƃ����łȂ��A�葤�ł���A�����ҁE�����̊F���܂́u�m�錠���v�ɉ����邱�Ƃ��܂�ł��܂��B
���X�̏o�����⎖���E���̂������A�ЊQ�����������ۂɁA�����������ɍL���`�B����Ƃ��������g�݂�����ɓ�����܂��B�܂��A�h���}��o���G�e�B�Ƃ������A���S�Ȍ�y�����͂�����Ƃ������Ƃ��A�������f�B�A�̂ƂĂ��厖�Ȏd���ł��B
����ɁA�u�\���̎��R�v�����A�������҂̊F���܂���M�����Ă��炦�郁�f�B�A�ł��葱���邽�߂ɂ́A�������e�ɂ��āA�����ǂ�����l���A����𗥂��Ă������Ƃ����߂��Ă��܂��B
�u���̔ԑg�����ɗ������v�u���̂b�l���ĉ������C�����ɂȂ����v�Ƃ�����������������������悤�A�����S�̂œw�͂𑱂��Ă����܂��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���V���̖���
|
�������́u�m�錠���v�����
�V���̑��̎g���́A����̂�����ꏊ�ŋN���������푽�l�ȃj���[�X�𐢊Ԉ�ʂɓ`���邱�Ƃł��B����Ɂu�Љ�̌���v�Ƃ��č����́u�m�錠���v����邽�߁A���������ȗ���Ő��������s�Ȃ����Ƃ����߂��Ă��܂��B�e���r������o�łȂǂ̐�����}�X���f�B�A�̒��ŁA���Ƃ���V���ɂ��ꂪ�������߂���̂ɂ́A���������R������܂��B
�e���r�E���W�I�Ƃ������������Ƃ͕����@�ɂ��K������A�����Ȃ�����肠����g���̊����Ă���Ƌ����Ƃł���A���F���Ȃ���Γd�g���邱�Ƃ��ł��܂���B�G���͔��s�T�C�N���̖ʂ���V���قǑ����Ȃ��A�߂܂��邵���ω����鎖�ۂɂ��ē`����ɂ͕s���ł��B�o�ł͂����ɓ��e���D��Ă��Ă��A���v�����d�����邽�߁A����錩���݂������Ȃ���Δ��s����܂���B�܂��A�����߂��܂������𐋂��Ă���C���^�[�l�b�g�́A�N�ł������ŊȒP�ɔ��M���\�Ȃ䂦�ɁA���������̎��ƐM�����ɂ��Ă͉ۑ肪�����̂������ł��B
�����ɑ��ĐV���́A�P�Ɏ�������邾���łȂ��A�[����ނɊ�Â��A���̔w�i�⍡��̉e���ɂ��Ă܂ł����y����̂��D�ʐ��ł���A�s������̋��F���s�v�ł��B
���B���ꂽ�������@��N����
�u�����v�Ƃ́A�L�҂���ѐV���Ђ��Ǝ��ɁA���܂��܂ȏ��\�[�X�����ނ�ςݏグ�Ă������Ƃɂ���ĐV���Ȏ�����˂��~�߂Ă����`���ł��B����ɑ��āu���\�v�́A�s�����Ƃ����J����L�҉��v���X�����[�X�ȂǁA������甭�M���ꂽ�������̂܂܃j���[�X�ɂ���ł��B
�����́A�܂��Ɂu�Љ�̌���v�ł���V���炵���X�^�C���ł���A���ɂ͌��͂������Ă����ޑΏۂ��\�ɏo��������Ȃ��������A�n���Ȏ�ފ����ɂ�萢�ɔ��\���邱�Ƃ�����܂��B���������ƁA�Â��̓A�����J�́u�E�H�[�^�[�Q�[�g�����v�������ł��B���V���g���|�X�g�Ȃǂ̒Njy�ɂ��ƍ߂�����݂ɏo�āA����哝�̂����C�ɂ܂Œǂ����܂�܂����B���{�ł��u���N���[�g�����v�A�u�����ڑҁv���Ȃǂ��v���N������܂��B
���L�����y�[����A���_���`������
�V���Ђɂ����钲���ł́A�Љ�ɉQ���������⍑���̕s����킾���܂�ȂǁA�Љ�ɑ傫�ȉe����^����悤�Ȗ����A�����ԂɘA�����ċL���f�ڂ��s�Ȃ����Ƃ�����܂��B�������ɂ��ď��\�[�X��p�x��ς��Ď�ނ����A�V���Ȏ����������яオ��x�ɌJ��Ԃ��Nj����čs���܂��B������L�����y�[���Ƃ����܂��B��Ђ��n�߂������ɑ��Ђ��ǐ����A���̉B����F�߂Ȃ��C�^�����߂āA����݂ɏo�������̐���𐢂ɖ₤���߁A���_�`���ɑ傫�Ȗ������ʂ����܂��B�����ł悭������̂́u�����߁v�u�̔��v�ɂ��Ă̕�A�����{��k�Јȍ~�̓d�͉�Ђւ̐ӔC�Njy�Ɋւ���ł��B���̃L�����y�[���͍ŏI�I�ɂ́A���̎��ۂ��B���Ă������������ƔF�߂�����قǂ̗͂������܂��B�@ |
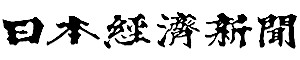 |


 �@
�@ |
|
���W���[�i���Y���̖���
|
���X�������鐢�̒��̏o�����⎞���I�Ȗ���A����A�_�]����̂��W���[�i���Y��(Journalism)�ł��B�����O�̐����A�o�ρA�Љ�ۂ���X�|�[�c�A�Ȋw�A���������Ɏ���܂ŁA���܂��܂ȕ���̌���j���L�^�������Ă��܂��B�V���A�e���r�A���W�I�A�G���̂ق��A�ŋ߂̓C���^�[�l�b�g�������A��l�ЂƂ�̋L�҂�|�[�^�[������Љ�̑�����`���A�g�߂ȎЉ�ɐ����_��ۑ���@��N�����Ă��܂��B
���{�Ŗ����ȗ�100�N�ȏ�̗��j�����V���́A�吨�̋L�҂������Ŏ�ނ��������O�̕��G�Ȏ������킩��₷���L���ɁA����Ζ|�ēǎ҂ɓ`���܂��B�e�V���Ђ́A�L�x�Ȏ�ޖԂ���g���ē��肵���j���[�X�̉��l�f���A�ǎ҂���ڂł킩��悤�ɑ召�̌��o�������Ď��ʂɊ���t���A���Ԃɒǂ��ĖZ�����ǎ҂������ƌ��������ł��A���e���Â��݂ł���H�v���Â炵�Ă���܂��B
���ڂ���������j���[�X���������A����̂��߂ɍ��O(����)�s���Ċe�n�̊X���Ŕz��ƁA�ŐV�j���[�X�����߂đ吨�����O�Ɏ��L���܂��B
���{�V�����54�N�Ԃ�ɉ��肵���V���ϗ��j��(2000�N6������)�́A�V���̐Ӗ��Ǝg���ɂ��āA�u���т��������ʂ̏��т����Љ�ł́A�Ȃɂ��^�����A�ǂ��I�Ԃׂ����A�I�m�Őv���Ȕ��f���������߂��Ă���B�V���̐Ӗ��́A���m�Ō����ȋL���ƐӔC����_�]�ɂ���Ă��������v�]�ɂ������A�����I�A�����I�g�����ʂ������Ƃł���v�ƋL���Ă��܂��B
�D�ꂽ�ɑ�����V������܂ɂ́A�S���ɍL�����Ă����u���Z�K�C�Ȗڂ̖����C�v�̏���(2007�N�x)�A�u���a�V�c��A����Ƃ̖����_�Ѝ��J�ɕs�����v���L�������{�����������L�E�蒠�̕�(2006�N�x)�A�u���q����W�̂��߂̏Z����{�䒠�����W�v(2003�N�x)�ȂǁA�B����Ă����A���邢�͖�����Ă��������𖾂炩�ɂ��ĎЉ�ɖ���N�����������A���̒��̎d�g�݂����P���錋�ʂɂȂ���ꍇ�����Ȃ�����܂���B���ꂱ���W���[�i���Y���̐^�����ł��傤�B
21���I�̏�����肤�n�����g�����ɑ���e���̎��g�݂��A���E�̌����҂Ɛ����ƁA�s���Ɗ�ƁA��ʎs���܂Ŋ��������L���������p���I�ɕ��Ă����W���[�i���Y�����������@�\�������ʁA���ʔF�������܂�A���ԉ��P�֓����o�����Ƃ�����̂ł��B
�ۑ�������Ă��܂��B�傫�Ȏ����⎖�̂̍ہA�����҂�W�҂Ƀ}�X�R�~���E������W�c�I�ߔM���(���f�B�A�X�N����)�ɑ��āA���{�V������͎�ސw���Ƃ�ׂ��s���K�͂���A��ނ����l��������������瑁�}�Ɏ��ԉ��P���邽�߂̋��c�@�ւ�S�s���{���ɍ��A�K�Ȏ�ޑΉ��ɓw�߂Ă��܂��B�܂��A�l���ی�@�̎{�s(2005�N4��)�����������ɁA�������\�������A�^�������ɔ�������⌟�ؕ�W���Ă�����ɑ��������g��ł��܂��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���}�X�R�~�ϗ��@/�@�����ƐӔC�̏d�����߂�
|
�u�`����̂́A���̂��߁A�N�̂��߁v�����C���e�[�}�ɁA���m�s�Ń}�X�R�~�ϗ����k��S�����c��̑�63��S�����J���ꂽ�B
�����c��͐V��������A�o�łȂ�200�ȏ�̃��f�B�A�ō\���B�N1��̑��ŐM���m�ۂɌ������ۑ����b�������Ă���B�{���ł�1987�N�ȗ�2��ڂŁA���̍ۂ̃e�[�}�́u�\���̎��R�ƐӔC�v�B�����͕ɂ��l���N�Q���N���[�Y�A�b�v����Ă����B
�u�}�X�R�~�ƍ����̊W�ɂ��܂��܂̖��C�������n�߂Ă��鎖���͏d������˂Ȃ�Ȃ��v�u�w���_�̎��R�x�́A�g��������ŗ��n�̌��ƂȂ�B�������Ȃ����߂̓w�͂��������߂�ꂾ���Ă���v
�������グ��32�N�O�̖{���͂����x����炵�Ă���B�Ɛl�������錻�݂̏ɂ����Ă͂܂�B���f�B�A�͏d���ۑ��w���������Ă���ƌ����悤�B
����̍��m���ł��A7���ɋN�������s�A�j���[�V�������ΎE�l�����̋]���҂̎������e�[�}�̈�ƂȂ����B�n�����ɂ́u�⑰�̈ӌ������Ă���v�Ƃ����������̋���R�c����ꂽ�B
�v���C�o�V�[�ی��]�ވ⑰�̎v����A�����̕@�ւ��ꋓ�ɉ�����u�W�c�I�ߔM���(���f�B�A�X�N����)�v�Ȃǂ̉e�������낤�B
���ʁA�����͐l���l�Ƃ��đ��d������b�ł���B�����͓����ɔ�ׂēǎҁA�����҂ɋ��������|����͂����������̏d�݂�`����B���f�B�A�ɂƂ��Ă͂��ׂĂ̎n�܂�A���_�ł���\�B�������͂���Ȏv������������\�A�����̕K�v����i���Ă����B
���������߂鐺�����܂钆�A��Q�҂�⑰�̈ӌ��d���邱�Ƃ͂�����B�����Ɏ����̏d�v�������܂ňȏ�ɐϋɓI�ɁA���J�ɐ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B���N�w�E����Ă������f�B�A�X�N�����̉��P�Ɍ����Ă��A��̓I�ȍs��������Ă���B
�ς��ʉۑ肪�������ŁA���f�B�A����芪�����͗l�ς�肵�Ă����B�C���^�[�l�b�g��r�m�r(������𗬃T�C�g)�Ȃǂ̑䓪�ɂ���āA�l�X��������肷���i�͑��l�������B�����̃��f�B�A�ɐڂ��邱�Ƃ����Ȃ��l�X�ɁA�ǂ�����͂��M���Ă������B����ۑ���V���ɐ����Ă���B
�ߔN�A�ꕔ�̌��͎҂�����ɂƂ��ĕs�s���ȕ��u�t�F�C�N�j���[�X�v�ƌ��߂��镗�������܂��Ă���B�������̉������B��(�����)�A�X�������̏ꂩ��̒��O�̔r���c�B�\���⌾�_�̎��R�A�m�錠�����Ȃ�������ɂ���鎖�Ԃ��N���Ă���B
���͂��Ď����郁�f�B�A�̎g�����܂��d�v���𑝂��Ă��悤�B
�q���f�B�A���ʂ����ׂ������ƎЉ�I�ӔC�͉����A��l��l���^���ɍl���A��荂���ϗ��Ɋ�Â��������H���Ă����r�B���m���ł̐\�����킹����X�z�N���Ȃ����ށA�ɓ����肽���B
���_�̎��R�́A�����̐M���Ǝx���ď��߂đ傫�ȗ͂ƂȂ�B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���}�X���f�B�A�̖���
|
����̑����ŁB������_��������̍l�@���������킯�����A�������ĂȂ��A���_�`���ɂ̓}�X���f�B�A�̑��݂��傫���e�����Ă���B�e���r�A�V���A���W�I�A�T���������肪�}�X���f�B�A�ł������͈͂��낤���B
���K�V�[���f�B�A�Ƃ��I�[���h���f�B�A�ƌ����Ă͂��邪�A���̉e���͈͂ˑR�Ƃ��Đ��Ȃ��̂�����B�Ȃɂ��둊��ɂ��Ă���͕̂S���l�P�ʂ��B
YouTube �ʼn����̓��悪�����������̂Ƃ͂킯���Ⴄ�B����͐����Ԃ��邢�͐��������Ă̘b�����A�e���r�V���̂���͖����Ԗ�������Ă���B����ȗʂ̏����A���ɑ傫�Ȕ͈͂ɒ��Ă���B���̉e���͂̍��͂ƂĂ��Ȃ��傫���B
�l�b�g���f�B�A�����B�����Ƃ͌����Ă��A�܂Ƃ߃T�C�g�͂������A�L�����[�V�����T�C�g�ɂ���Ȃ�ɂ���A�Ǝ��Ɏ�ނ��Ă���Ƃ���͑����Ȃ��B�����̓}�X���f�B�A�̕��ꎟ�\�[�X�Ƃ��A����ɓƎ��ɘ_����t��������A�����̃\�[�X����V�������_������@������Ă���B
��X�̐��_�`���ɂ���A���s�̍����ɂ���A�����͂͂Ȃ��Ȃ����悤�����A�l�b�g���f�B�A���֏悷�邱�ƂŁA�ǒn�I�ŏu�ԓI�ȕ����͋��܂�����������Ȃ��B
�����A�������̃}�X���f�B�A�݂̍��������n�߂Ă���B�ߔN�ōŏ��ɕ\�ʂɌ��ꂽ�̂́A�t�����X�Ńe���̕W�I�ɂȂ����u�V�������[�E�G�u�h�v���ł͂Ȃ��������B
���̎G���́u���h�v�̖��̂��ƂɃC�X�����̐��l�J���閟����f�ڂ����B�l�I�ɂ͂���Ȓ��x�̒Ⴂ����Ȃ��̂h�Ƃ͌Ăт����Ȃ����A���Ȃ�Ƃ͂����u���f�B�A�v���z���Ă͂����Ȃ������e�Ղɉz������Ƃ������Ƃ𐢂ɒm�炵�߂��B
���̑傫�Ȍ��ۂ̓g�����v�哝�̂̒a�����낤�B�قƂ�ǂ̃}�X���f�B�A�̓g�����v���̓��I��\�z�ł����A�}�X���f�B�A���č����̐���ł��Ă��Ȃ����Ƃ�I�悵���B
�g�����v�哝�̂̓c�C�b�^�[�ő����̂��ƂM���Ă��܂��̂ŁA�A�C�����͋L�҉����낭�ɊJ���ꂸ�A�}�X���f�B�A�͔ނ̃c�C�[�g��ǂ������邱�Ƃ�����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̃C�j�V�A�`�u������Ƃ������Ƃ������ɑ�����悭�킩��b���B
���f�B�A�Ǝ��Ƃ̑Λ��I�Ȏp���͍��Ȃ������Ă�����A���僁�f�B�A���t�F�C�N�j���[�X�ƌĂсA�K�`���R�ő�Q���J�̐^���Œ����B
�|���ē��{�ł́A�����V����������u�]�R�Ԉ��w���v���u�^���ł͂Ȃ������v�ƌ����ċL���̒����A��艺���������B����͖k���N���f�v��F�߂����Ƃɑ����Ռ��I�Șb���B
�����V���ƌ����u�N�I���e�B�y�[�p�[�v�ƌ����A�����o�ς͌����ɋy���A���_�E�A�ʂĂ͍��Z�싅���w����(��)�ɂ܂ő傫�ȉe�������A���s���� 600 �������ւ鋐�僁�f�B�A���B�V���̐V���Ј��́u�Ƃ肠�����������ǔ��A����Ɠ��o�ǂ�ł����ΊԈႢ�Ȃ��v�ƌ���ꂽ���コ���������̂��B���ꂪ�^���ł͂Ȃ������Ă��āA�����̒����� 30 �N�ȏ�����������Ƃ������Ƃ͑傫���B
�����������{�ł́A�}�X���f�B�A�͐��������������́A�Ǝv���Ă����B���ꂪ���͂����ł��Ȃ������Ƃ������Ƃ��ߔN���炩�ɂȂ��ė����B
���ɋN����l�X�Ȏ������X�̏����W�čL��Ƃ����Ӗ��ł́A�}�X���f�B�A�̖����͔��ɑ傫���B�����Ĕނ�́u���͂̊Ď��@�\�v�����C���Ă������A��ʎs���������F�����Ă����B
�Ƃ��낪�A�i�@�E�s���E���@�ɑ����A��l�̌��͂Ȃ̂��Ƃ��������オ���ė����B��̎O�̓}�X���f�B�A�ɂ���ĊĎ�����邪�A���̃}�X���f�B�A�����������ł��邩�A���邢�͍������K�v�ȏ�����Ă��邩��S�ۂ��邢�͌�������@���Ȃ����炾�B
�v�́A�}�X���f�B�A�̌������Ƃ����̂́A�}�X���f�B�A�̗ǐS�Ɋ��҂��邵���Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�������}�X���f�B�A�́u���͂̊Ď��@�\�v�����C���Ă��邽�߁A���h�A���邢�͔����͂̕����ɌX���₷���B�E�h�I�Ȑ������ɂƂ��ėǍ�ł������Ƃ��A�}�X���f�B�A�͍�����l���ɐ��{�ƑΛ��I�ɂȂ�₷���̂��B
�e���r�A�V���Ȃǂ̃}�X���f�B�A����ْ���������ꂽ���A�S�̎�`�I�ȕ����Ɋׂ�₷���B���Ɍ��݂̃e���r�͊e�Nj��ɘ_�����ꏏ�ŁA�������ԑтɓ����悤�Ȕԑg��������A�������ԑт� CM �𗬂��A�����悤�Ȏ��ԑтɕ������͂��߁A�����悤�Ȏ��ԑтɕ������I����B
�����������Ɋ��ꂳ�����Ă��鎋���҂͋C�Â��Ȃ����A��U�e���r���痣��Đ������Ă݂�ƁA���̓����Ԃ�͂�����قɂ���v����B
����ɁA�ǂ�ȏ����ǂ��������ɗ������Ƃ����哱���͕����Ǒ��������Ă���̂��B�X�̎����҂����ꂼ��Ǝ��Ɂu����������~�����v�Ɨv�������ꍇ�A�e���r�ɂ͉�����@�\���Ȃ��B�e���r�Ƃ����̂̓V�����[�̂悤�ɏ����~�点��@�\�ȊO�̌ʑΉ��͂ł��Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���B
�Ȃɂ��A�e���r�����C����u���͂̊Ď��@�\�v�����������肢�������Ƃ͂Ȃ��B�I���ɂ�铊�[���Ȃ��A�Y�ƂƂ��Ă̋K�͂̑傫�����瑼�҂���̝y�I���Â炭�A���ԉc����ƂƂ��Ă̌o�ύ������ȊO�ɂ́A���̐�������S�ۂ�����̂��Ȃ��B����Ɍ����A�o�ϊ����ɉe���̏o�Ȃ��͈͂ł͉��ł��ł���Ƃ������ƂɂȂ�B
�l�I�ɂ́A�}�X���f�B�A�͏��̃n�u�@�\������Ă��������̂ł����āA���̎�̑I���⌟�͍������ꂼ�ꂪ�s���ׂ����Ǝv���B���͂̕s���╅�s��\���o���@�\�������Ă��ǂ���������Ȃ��Ƃ͎v�����A���ꂪ�X�F�E���v�u���v�̂悤�ɁA���{�Ɍ�������������ăC���[�W����������������̂悤�Ɏg��ꂽ�ꍇ�A�}�X���f�B�A�͍����ɂƂ��Ă��͂�L�Q�ȑ��݂ɂȂ��Ă��܂��B
���̐������̏d�v���͕ς�邱�Ƃ��Ȃ����A�}�X���f�B�A�͗]�v�ȝΎނ͓��ꂸ�ɃN���[���ȏ��������ɒ���@�\���܂��͗D�悷��悤�ɂ��Ă��炢�����B�����_���͂��̌�ɕK�v�Œ���ō\��Ȃ��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����a���̃��f�B�A�ƎЉ��
|
��1�D���a��O�E�풆���ɂ����郁�f�B�A�ƎЉ��
�y�������f�B�A�̓����z
���a���͕������f�B�A�̏o���ƂƂ��Ɏn�܂����B���a�����A�Љ��̕��y�ɑ傫�ȉe����^�������f�B�A�Ƃ��āA���W�I�����̊J�n�Ƃ��̓��������ڂ���悤�B�吳14(1925)�N�̃��W�I�̉������J�n���ɂ͓��������ǂ̌㓡�V�����ق������̒��Łu����̎Љ�v�Ƃ��Ẵ��W�I�̈Ӌ`�ɐG��Ă���A�Љ��̃��f�B�A�Ƃ��Ă̖���������������҂���Ă������Ƃ��M����B���ہA�����J�n�Ƃقړ����ɁA�u��������e�Ƃ���Љ��I���e�̔ԑg���n�܂��Ă���B���W�I�ɂ�����Љ��ԑg�͂��̌�}���ɑ̌n������A����҈�ʂ�ΏۂƂ����u���ԑg�̑��ɂ��A���e(���Y�Z�p�A�|�p�A�̈�A�Ȋw�A��A�C�{�A��w�Ȃ�)�E�Ώێ�(�����ΏہA�N�ΏہA�ƒ�w�l�ΏۂȂ�)����艻�����u���ԑg�����������悤�ɂȂ�B1930�N��ɓ���ƁA�V���ԑw�Ȃǂ̒m���K��������҂ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��������̖����݂̂Ȃ炸�A���������i�w�҂�ΏۂƂ�����K����Ƃ��Ă̖����������W�I����������ɒS���悤�ɂȂ��Ă����B
�y�����o���f�B�A�̓����z
�����o���f�B�A�Ƃ��Ă̌�����f��͊��ɖ��������E�吳������A�e�������ɂ�鍑���ւ̌[���A��`��i�Ƃ��Ċ��p����Ă����B���a���ɓ����Ă�����A���ɉf��͌�y���E��O������������f�B�A�Ƃ��āA�Љ��ɂ����Ċ��p�����悤�ɂȂ�B�����Ȃł́A�Љ���)���吳��������f����(��ɍc���s������)�ɒ��肵�A�����������^���ɂ����Ă��f�悪���p���ꂽ�B1930�N��ɂ͕����Ȃ̊�悷��f��́A���ʋ�̓I�ȓ��e(�q���A�h�ЁA�n���Ȃ�)�̎Љ��p���ނƂ��Ă̖������g�傳���Ă������B�܂�1930�N��ɂ͉f��́A���͐�̐��ւ̍����̌��W�A��ӍV�g�̂��߂̎�i�Ƃ��Ă����p�����B���B���ψȍ~�A���ljf��A�R���f�悪����f���ЂȂǂɂ���đ������삳��A���W�I�����ƂƂ��ɁA�����̐�ӍV�g�̖����̈�[��S���悤�ɂȂ��Ă������B
�y�������f�B�A�̓����z
��������l�X�̊w�K�E�]�Ɋ����̉��x���Ƃ��đ��݂��Ă����������f�B�A�ɂ��ẮA���̎����ɗʓI�݂̂Ȃ炸���I�ȑ�O���������������B�s�s�V���ԑw�́A�~�{�╶�ɖ{�̂悤�ȗ����ł̏��ЁA�����G���A�w�l�G���̎�v�ȓǎґw���\������悤�ɂȂ����B�܂��J���ҁE�_���w�ɂ����Ă��A�]�����畁�y���Ă����V����u�k�G�������łȂ��A�����G���Ȃǂ̍w�ǂ�����ɐZ�������������A�J���ҁE�_���w�̓Ǐ��s���́A�������u�w���v���邱�Ƃւ̏�ǂ��������A�E���n��(�Ⴆ�ΐN�c�Ȃ�)�ł̏����́u�ݎv�E�u���L�v����ՂƂ��邱�ƂŐ������Ă������ʂ��傫���B���Ȃ킿�A�Ǐ��Ƃ����s���͂��̎����A�u�Ǐ��K���v����V���ԑw�ƁA�����ւ̃A�N�Z�X�ɖ��������L���Ă����J���ґw�A�_���w�Ƃ̊ԂɁA�Ȃ��傫�ȕ��L���Ă����̂ł���B
��2�D��㏉���E���x�������ɂ����郁�f�B�A�ƎЉ��
�y�������f�B�A�̓����z
����E����A�Љ��̏�Ɋ��p������������f�B�A�Ƃ��āA�V���Ƀe���r���o�ꂷ��B���a28(1953)�N�̃e���r�����J�n�ƂƂ��ɁA���̑��݂͌l�w�K�̎�i�Ƃ��Ă����łȂ��A�W�c�w�K�̎�i�Ƃ��Ă����ڂ��ꂽ�B�Ⴆ��1950�N��ɂ́A�N�w����w�l�w���ɂ����āA�W�c���������Ƃɂ��ē��_�Ȃǂ̋����w�K��i�߂Ă����`�Ԃ����݂��Ă���B���ɔ_�����ɂ����ăe���r�@�����y���Ă��Ȃ������ɂ����ẮA�W�c������O��Ƃ����Љ��̎�@�͈��̍L������������B���������̌㍂�x�������ɓ���ƁA�}���ȃe���r���y�A�y�ђn��W�c�Ɉˋ������w�K�`�ԑS�ʂ̒ᒲ���ɂ��A�ނ���e���r�E���W�I�Ȃǂ̕������f�B�A�́A�l�w�K�`�Ԃ̑��l�ȓW�J�𑣂����̂ɂȂ��Ă����Ƃ�����B
���a34(1959)�N�ɂ�NHK����e���r���������J�n���A���̌��������ǂƂ��Ẵe���r�ǂ̊J�ǂ��������B�����̃e���r�ǂ����鋳����e�͓����A��w�u�����̂����Ίw�Z�����̂ł��������A���̌�̍��x�����̐i�W�ƂƂ��ɁA�Z�\��Y�ƌo�ς���e�Ƃ���u���ԑg���o�ꂷ��悤�ɂȂ�B
�y�����o���f�B�A�̓����z
�����o���f�B�A���p�Ɋւ��ẮA��㏉���Љ��ɂ�����傫�ȉ���Ƃ��āA�A���R���i�ߕ��ɂ�閯�剻���琭��̈�Ƃ��Ă�CIE�f���16�~���g�[�L�[�f�ʋ@(�i�g�R�f�ʋ@)�̑S���ւ̑ݗ^����������B���a23(1948)�N�ȍ~�ACIE�f��̏�f�͓s�s�E�_�����킸�S���e�n�ōs��ꂽ�B���̊����͖��剻����Ƃ��Ă̖����ȏ�ɁA�����o���f�B�A�̎Љ�痘�p�̋@�^�������������Ƃ����_�ŏd�v�ȗ��j�I������S���Ă����BCIE�f��̏�f�������^�c���邽�߂ɁA���̎����A�e�s���{���Ɏ����o���C�u�����[���ݒu����A�܂��e�s���{���̎Љ��S���ۂɎ����o����W���u����邱�ƂƂȂ����B����ɂ���āA�����o���f�B�A�ɂ��Љ�玖�Ɛ��i�ɂނ��Ă̋���s�����I�ȗ��t����������x�Ȃ��ꂽ�Ƃ�����B
�S�s���x���ł̎����o���C�u�����[�ݒu������1960�N��ɐϋɓI�ɐi�߂�ꂽ�B�������A�����o���C�u�����[�̐ݒu�������傷�����ŁA���̐ݒu�ꏊ��\�Z�����Ƃ��������x�I���ʂɂ����Ă͓��ꐫ�������Ă���A���̂��Ƃ��Љ��{�݂Ƃ��Ă̋@�\�̐�����i�߂Ă��������ł̖��Ƃ��ċc�_�����悤�ɂȂ����B
�y�������f�B�A�̓����z
���̎����̊������f�B�A�ɂ��Ă̕��y���݂�ƁA�Ǐ��s���̊K�w�i���A���ɔ_�����ɂ�����Ǐ����̈������A�����̒�����Љ��W�҂̘_���Ȃǂ���Ȃ������M����B�Ǐ��s���̊K�w�i���\���͐�O����傫���ς�邱�ƂȂ��������Ă����̂ł���A�܂����̂悤�ȗȓǏ��s���̊K�w�i����傫�ȋ�����E�Љ���Ƃ��đ�����X�����A����w�҂̊Ԃɋ������݂����B
��3�D70�N��A80�N��̃��f�B�A�ƎЉ��
�y�������f�B�A�̓����z
70�N��A80�N��ɂ����Ắu���U����v�u���U�w�K�v�ւ̎Љ�̊S�����܂�A���{�̊e�퓚�\�ɂ����U����E���U�w�K�̊T�O�����荞�܂��Ƃ����w�i����A�������f�B�A�ɂ���Ē����w�K�@����A���̏d�S���w�Z���炩��Љ��E���U�w�K�ւƃV�t�g�����Ă����B�Ⴆ��NHK����e���r�ł͂��̎����A���U�w�K���ӎ������ԑg�̔�d���]���������܂��Ă���B�܂����̓��e���E�Ɣ\�͗{��������퐶���ɂ������E���p�ւƏd�S���ڂ��悤�ɂȂ�B���̂悤�ȕ����ɂ��Љ��@��̊g�傪�i�ވ���ŁA�W�c�w�K�`�Ԃ̎��H�ւ̒��ڂ����S�ƂȂ��Ă������̎Љ�猤���ɂ����ẮA�����Ȃǃ}�X���f�B�A�͂��̏��Ǝ�`�������炷���e���̊ϓ_����ے�I�ɑ�������X�����]�����������B
�������A70�N��ȍ~�������p�ɂ��l�w�K�̊g�傪����ɐi�ނɂ�A�������f�B�A��l�w�K�̑��l�ȓW�J��O��Ƃ�����ŁA�����̊w�K�������Ɍ��ʓI�ɓW�J���Ă������A�܂��A�ΐl�I�E�W�c�I�Ȋw�K�����Ƃ����Ɍ��т��Ă������Ƃ����ۑ肪�A�Љ�猤���ɂ����Č��������悤�ɂȂ����B70�N�ォ��80�N��ɂ����ẮA���i�̃e���r�����ɂ��l�w�K�ƁA����I�ɍs����u�`�̒��u�E����̎��ԂƂ�g�ݍ��킹���u�A�J�f�~�[�����v���e�n�œW�J���ꂽ���A���̊w�K�`�Ԃ́A�l�w�K�ƏW�c�w�K�̐V���Ȍ��������߂铖���̉ۑ�ӎ��ɓ������̎��݂Ƃ��Ĉʒu�Â����悤�B
�y�j���[���f�B�A�̏o���z
70�N��ȍ~������u�j���[�E���f�B�A�v(�r�f�I�e�[�v���R�[�_�A���[�h�v���Z�b�T�A�R���s���[�^�Ȃǂ̏��@���A������d�b�E�ʐM����𗘗p�����l�X�ȐV�������f�B�A�`��)�̕��y�ƂƂ��ɁA�����̎Љ��ւ̊��p�����݂���悤�ɂȂ�B�Ⴆ�A80�N��܂łɑ�O�I�ɕ��y�����r�f�I�e�[�v���R�[�_�́A�������f�B�A�A�����o���f�B�A�̊��p�ɔ���I�ȕω��������炵���B�������A���[�h�v���Z�b�T��R���s���[�^�ɂ��ẮA80�N��܂ł̒i�K�ł͂��̕��y�x�◘�p�̊ȕւ��A�ً@��Ԃ̌݊������ɂ����đ����̖����c���Ă����B�]���Ă����̋@�킪�A�����W�E�����E���M�̑��ʂɂ����Đ��l�̊w�K�`�ԂɍL�ĂŔ���I�ȕω��������炷�̂́A90�N��ȍ~�̂��ƂɂȂ�B
�y�������f�B�A�̓����z
�������f�B�A�̎Љ��A���U�w�K�ɐ�߂�ʒu�ɂ��Č���ƁA�}���فE���X���̑�����A�S�Ă̎Љ�K�w�ɂ����鏑�ЁE�G���w���͂̏㏸�Ȃǂɂ݂���悤�ɁA�l�X�̏����ɑ���A�N�Z�V�r���e�B�͑傫�����サ���B�܂��Ǐ��s���̒n��(�s�s�|�_��)�i�����k�������B����ƂƂ��ɁA�����ւ̃A�N�Z�X�̊K�w�i�����莋����F���́A���猤���̒��ł͊����Ă������B�������A�E�Ƃ�w���ɂ��Ǐ��s���̊i���͍��x�������ȍ~���傫���ς�邱�ƂȂ����݂��Ă���B
���x�������ȍ~�A�Ǐ��s�����߂�����Ƃ��āA�e���r�̕��y�ɂƂ��Ȃ��u��������v�E�u��������v�����グ���邱�Ƃ������Ȃ������A�Ǐ��Ƃ��������I�w�K�����̊�ՂƂȂ�s���ɂ����āA�Љ�K�w���Ȃ����Ȃ���ʉe���͂�L���Ă������Ƃ��w�E�����ׂ��ł���B �@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����f�B�A�͂Ȃ�����̂�
|
��1�D���f�B�A�ƃW���[�i���Y��
���Љ�ɂ�������܂����A���J���l�Ɛ\���܂��B������������ɁA�}�X�R�~�w��̃V���|�W�E���ł͖��N�̂悤�ɃW���[�i���Y���̘b����ŁA���f�B�A�����ɂ��Ę_�����邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��̂ŁA���������b�����ė~�����Ƃ�����|�ŁA���̃V���|�ւ̎Q�����˗�����܂����B
�����ō����͍ŏ��ɁA���̃W���[�i���Y���ƃ��f�B�A�̈Ⴂ�ɂ��čl���Ă݂悤�Ǝv���܂��B���傤�Ǘǂ��f�ނƂ��āA����W���[�i���Y�����߂����čs��ꂽ�V���|�W�E��1(���f�B�A�����ƃW���[�i���Y���@�@�������O�E��)��������Ȃ̂ŁA����ɂ��Ă��b�����悤�Ǝv���܂��B�����ł͑�ΗT����̌����Ȏi��̉��Ɉ���ނ���ƈɓ��炳�A��N�ɍs��ꂽ�O�c�@�I���̃e���r�Ɋւ��āA���ۂ̉f�����g���Ȃ���ڍׂȕ��͂��{���Ă����܂����B���ɗ��\�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��ƁA�e���r���f�B�A�̐������A�u�������v���d�v�ł���Ƃ����Љ�I�ȕ��͋C(�c��ݒ�)�ɏ�������ĂȂ��ꂽ���߂ɁA�Ⴆ�ΗL���҂̐��̏E�����ɂ��o�C�A�X���������Ă��܂��āA�����̕s���Ƃ���������ւ̓{��Ƃ������A����I�Ȋi���Љ�_�����S�ɂȂ��Ă����Ƃ����ᔻ������Ă����킯�ł��B�v����ɁA��N�̑I���O��̐������A�����I�ȓ��c�̘b����Âɒ���Ƃ����W���[�i���Y���̖������ʂ������A����̎Љ�I�NJ�������I�ɑ���������悤�ɋ@�\���Ă����B����ȕ��͂��Ɨ������܂���(���̂܂Ƃ߂Ƀo�C�A�X���������炷�݂܂���B��Ƃ��Ĉɓ�����̎咣���Ǝv���܂�)�B
���͂��̂���l�̕����Ŕq�����Ă���܂��āA���������͂��̘_�|�ɔ[������킯�ł�����ǂ��A�Ɠ����ɁA��͂�ǂ����Ɉ�a�����c��킯�ł��B���̈�a�����W���[�i���Y���_�ɑ���A���f�B�A�����A���f�B�A�����_�̎��_�̒u�����̈Ⴂ�Ƃ������ƂɂȂ낤���Ǝv���܂��B
�����\���ے��I�ȗ�Ƃ��āA�ɓ��炳�������Ă����A�I���̂Ƃ��ɕЎR�������y���������V�[���̖������グ�����Ǝv���܂��B�ɓ�����́A���ۂɂ��̃e���r�j���[�X�̉f�������āA�u���̂悤�ȃV�[�������K�v���ʂ����Ă������̂��낤���B�W�F���_�[�I�ȃo�C�A�X���������Ă��ėǂ��Ȃ���ʂł͂Ȃ����v�Ƃ����^��𓊂��������܂����B�܂�A�������y�������邱�Ƃ����炩���Ă��銴��������Ƃ������ƂȂ�ł��B���������͂��������^�ʖڂȕ��͂ɋ^����������ł��B�m���ɁA���҂����[���Ă��炢�����Ƃ�����S�œy���������ʂƂ����̂͌��Ă��ċC�������ǂ����̂ł͂Ȃ��B����ȉ��i�ȏ�ʂ͌������Ȃ��Ƃ����C���������ɂ�����܂��B�ł������ɁA����������������e���r�ŕ��Ȃ����Ă��Ƃ����肤�邾�낤���Ƃ��v����ł��B�����e���r�ł��̏�ʂ���Ȃ���A���Ȃ����Ă������Ǝ��̂̃e���r�ǂ̈Ӑ}���������āA�l�b�g��T�����ő呛���ɂȂ��Ă��܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ނ���ŏ�����ЎR�����́A������f���ɎB���Ă��炨���Ǝv���ēy���������Ƃ������_���K�v���Ǝv���܂��B�ЎR�����̐����s���ɑ��āA�W�F���_�[�I�ȃo�C�A�X�����������J�������������čs������Ȃ��āA���ɔޏ��́A���������y���������p���������ƂŁA�e���r�J�������Ăэ������Ƃ����͖̂��炩�ł��B��p���Ƃ��Ă̓y�������p�t�H�[�}���X�Ƃ��Č����Ă����A�|�����Ƃ����Ό��@�ł���Ƃ����킯�ł��B�ł�����y���������i���Ƃ�����A����͕ʂɃW���[�i���Y���̖��ł͂Ȃ��āA����������p���Ŋ撣���Ă���l�Ԃ������Ǝv���ē��[�������Ȃ�Ƃ������{�̐������y��ЎR�����̐����I�p�t�H�[�}���X�̖��ȂƎv���܂�(�������A���ܖ{���ɓ��{�͓y�������ʗp���鐭�����y�̂܂܂��Ƃ����Ɣ������Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŕЎR�����̐헪�́A��₸��Ă����Ǝv���܂�)�B���Ȃ��Ƃ����̏�ʂŁA���f�B�A�Ɣޏ��͋��ƊW�ɂ������Ƃ�����ł��傤�B
����͓����ɁA���������I�����Ă����������Ȃ̂��Ƃ������{�I�Ȗ��Ɋւ���Ă��܂��B�^�e�}�G�Ƃ��Ă̑I���́A���҂̐���Ɋւ���咣���āA�L���҂��ǂ̌��҂̐��悢�̂��𗝐��I�ɔ��f���ē��[����Ƃ����Љ�I�d�g�݂Ȃ̂ł��傤�B�ł������I�ɂ́A�I�����āu���Ղ�v�ł���ˁB�������̓��f�B�A��ʂ��đI�����Ă������Ղ�ɎQ�����Ċy���ނƎv���܂��B�����̖��O�̓������F�������炩�������҂��A�������Ƃ�����܂Ƃ���Ƃ��K���_���}�Ƃ������I���O�b�Y�����낦�āA�X��Ԃɏ���Ď����̖��O��A�Ă��Ȃ���u��낵�����肢���܂����v���Ă����璆�𑖂���B�����W���[�i���Y���̎��_����l����Ί��m�Ƃ����ȊO�̉����ł��Ȃ������w�I�Ȍ��i�ł���ˁB�X��ԂɌ������Ď��U��ƃE�O�C�X�삪�u�������肪�Ƃ��������܂��v���ĉ�����̂��ʔ����āA���s���q�����������炩���Ă₽��Ǝ��U���Ă݂����肷��B������ĊX�S�̂������I�ȏj�Ջ�ԂƉ����Đ���オ���Ă���̂ŁA�q���������v�킸�Q���������Ȃ���Ă������Ƃł��傤�B
�ł�����e���r���f�B�A�́A�܂��ɂ��̂��Ղ�Ƃ��Ă̑I����グ��Љ�I�����������Ɖʂ����Ă����Ƃ�����B�����g�A�q���̂Ƃ����瓊�[���ɕ��������e���r�̊J�[���������̂���D���ł����B�u��t���A�J�[�����\���p�[�Z���g�A�N�̒N�ׂ��A�����V�A�\��������[�A���I�m���B�ł͑I������������̒��p�ł��B�^�o���U�[�C�A�o���U�[�C�v�B�����������܂蕶�傪���̊l�����[���Ə��ʂ������P���ȉ�ʂƂƂ��ɁA�I����Ǝ��Ԍo�߂ɂ���ď������l����ς��Ȃ���Ђ����甽�������̂�钆�܂Ō���̂ɖ���I�ȉ��y���o���܂����B�ނ�̃v���Z�X�œ����̃h���}���ߊ삱�������Ɋe�n�œW�J����Ă����̂������Ėʔ����ł����A�I���S�̂ŕ������}�{���̐ӔC�҂����̉�������Ȃ������ł���ˁB1989 �N�̎Q�@�I�ɕ����������}�E���{�����Y�������̂��̋�ݑ������\����o���Ă��Ȃ��l������ł��傤���B
��������ĊJ�[�������y�I�Ɍ���̂́A���������I�ȓ��c�Ƃ��Ă̖����`�𗝉����Ă��Ȃ�����ł��傤���B�I�����Ԃ�g��ŊJ�[�̓r���o�߂��T�X�y���X�h���}�̂悤�ɕ��Ă��܂��e���r�ǂ́A�����҂ɂ����˂��Đ����̖{�݊O���Ă���̂ł��傤���B�W���[�i���Y���_�I�Ȏ��_����͂����Ȃ̂�������܂���B�������A�ǂ����Ă����ɂ͂����͎v���܂���B�������āu�܂育�Ɓv���Ă������炢�ł�����A�������������I�ɂ��������j�ՓI�ȑ��ʂ�����Ǝv���܂��B�܂�A�l�Ԃ��Ă����̂́A�����I�ɓ��c���邱�Ƃɂ���Ă�������Ȃ��āA�l�ԏL���삯�����⊴��I�Ȃ�����ʂ��Đ��������킯�ł�����(�u�����I�v���Ă����`�e���́A�����ł͊����Ȃ��l�ԓ��m�̋삯�������w���Ďg���邱�Ƃ������Ǝv���܂�)�A����������I���ʂ����f�B�A������������ł��邾���̂��Ƃ��Ǝv���܂��B������ЎR�����̓y�������Ă����̂��A�ޏ������f�B�A��Ԃ̒��ł̎����̈ʒu�Â�(�L����)��L���҂Ƃ̋삯�����̂Ȃ��Ŏ���I�u�����I�s���v�̈�ƍl���������悢�ł��傤�B�܂�A�L���҂��ޏ��ɐ����I�ȗ͂����邩�ǂ����f����ޗ��Ƃ��Ă��A��͂胁�f�B�A�͕��ׂ��������Ǝv���̂ł��B
�ނ�́A�W���[�i���Y���_�I�Ȏ��_���S���ԈႢ���ƍl���Ă���킯�ł͂���܂���B������߂��闝���I�ȓ��c�����邱�Ƃ͊m���ɏd�v���Ǝv���܂��B�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����́A�I���ɂ�����j�ՓI�ȕ��͋C��������������A�����S�̗̂����I�ȓ��c�������N����悤�ɕ���Ƃ������z��`�I�Ȏ咣���A���͌����đS�ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A�V����e���r�Ȃǂɂ��}�X�E�R�~���j�P�[�V�����ɂ́A���������W���[�i���Y���I�ȑ��ʂ����łȂ��A���f�B�A(����)�I�ȑ��ʂ��K���܂Ƃ����Ă��āA�����Ė������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������������������������Ȃ̂ł��B
���ۂ����������ł���Ă���w��\���A���������Ă������W�����̓��e�������@�B�I�Ȑ��m���œǂݏグ�邾���ł͂܂�Ȃ��ł��傤�B�������̒d��ɏオ���Ď����̊���݂Ȃ���ɎN���āA�Ɠ��̘b��������Đ������Ă���Ƃ������Ƃ��d�v�ȃ��b�Z�[�W�ł���͂��ł��B���ہA���̗]��̃��b�Z�[�W��ʂ��Ă����A���������������e�����[���`���Ǝv���܂��B�v����Ɋw��\�Ƃ������^�ʖڂȏ��`�B�I�ȃR�~���j�P�[�V�����ɂ����A���f�B�A�I���ʂ̖G�肪����킯�ł��B�ǂ�Ȃɏ����ɏ��𐳊m�ɓ`���悤�Ƃ��Ă��A�l�ԓ��m���R�~���j�P�[�V������������ĂƂ��ɂ́A�K�����f�B�A�I�ŗV�Y�I�ȑ��ʂ�������B
�������A���͂����������f�B�A�I���ʂ������Ȃ��Ďv���Ƃ������X����܂��B���Ƃ��A����̗\�Z�ψ���p�Ŏ���҂�������b�Ɍ������Ď��₷��Ƃ��ɁA�\��O���t�̏����Ă���傫�ȃt���b�v���e���r�J�����̕����Ɍ����Čf���Ă����ʁB������ĕς��Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�t���b�v�ɏ����ꂽ���e�͗\�߈������đ����ɓn����Ă���̂ł��傤�B����ł��A�ނ͑�����b��{�C�Ő�������C������̂��Ƌ^�������Ȃ��ł��B������c�_�Ő��ʂ���������悤�Ƃ��ׂ��l�Ԃ��A�e���r�̎����҂����炿��C�ɂ��Ȃ��玿�₵�Ă���B�{���ɓ��c�Ƃ��Ă̖����`��M���Ă���̂ł���A�ނ͂��̋c�_�ɂ���đ�����������āA�����]�������邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��ƐM���Ă��Ȃ�������Ȃ��B�Ƃ��낪�����ɂ́A�ǂ��������̍l���͕ς������Ȃ��Ƃ����V�j�V�Y���ƁA�J�����Ɍ������āu���͈ꐶ��������Ă����ł��v�Ɛ�`���Ă��邩�̂悤�țZ�т�������(�y�����Ɠ����悤��)�T�݂��Ȃ��I�悵�Ă���B���������Ƃ��A�m���Ɏ��́A�����̃��f�B�A�I���ʂ����ɂȂ��āA�W���[�i���Y�����厖���ȂƎv���킯�ł��B���ꂪ�W���[�i���Y���_���x���Ă���ǎ��Ƃ������̂ł��傤�B�ł����́A�����͂��̗ǎ��ɒ��킵�悤�Ǝv���Ă���Ă��܂����B������ȉ��ŕʂ̂������Ř_���Ă݂����Ǝv���܂��B
|
��2�D�R�~���j�P�[�V�����Ƃ����a�O
���āA�悤�₭�{���p�ӂ��Ă������W�����ɉ������b���������Ǝv���܂��B
�����́̕A�u���f�B�A�͂Ȃ�����̂��v�Ƃ�����ɂ��܂����B���̂悤�Ȗ₢�����ł͖{�V���|�W�E���́u���f�B�A�����̉ۑ�ƓW�]�v�Ƃ�����ڂɂ͐��ʂ��瓚�����Ȃ���������܂��A�����Ď��́u�ۑ�ƓW�]�v�Ȃ�ĕ�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ǝv���Ă����ł��B���܂�l���n�̊w��S�̂����̂��߂ɂ�����ǂ�������Ȃ��悤�ȎЉ������܂���ˁB��w�Ń��f�B�A�����Ƃ��W���[�i���Y���_��������Ƃ����A�ł���Ό���̃W���[�i���X�g�o�����o��������l��������ق����������Ă������w�d���̎Љ�I���͂������āA���̂悤�ȋ��w�u���̋����͑��݉��l������Ă��܂��킯�ł��B�����炱����x�A���f�B�A�Ƃ͉����Ƃ����������I�Ȗ₢�𗧂Ăčl���Ă݂�K�v������Ǝv���܂��B���w�u���ɑR���邽�߂ɂ́A�܂��������̋��w�Ƃ��Ă̑����������Ƃ��ĂȂ��Ƃ����Ȃ��B������A�܂����f�B�A�Ƃ��W���[�i���Y���̌����_������O�ɁA�����𐬂藧�����Ă����{�I�ȎЉ�ߒ��Ƃ��Ắu�R�~���j�P�[�V�����v���ĉ����Ƃ������ɂ܂ŗ����Ԃ��čl���Ă݂�����ł��B
�R�~���j�P�[�V�����Ƃ������t���������͂��ܓ���p��Ƃ��Ďg���Ă��܂����A���͂��ꂪ����p��ɂȂ����̂͂��ŋ߂̂��Ƃ��Ǝv����ł��B�Ⴆ�Ύ������́A�u�e�q�W�́A�����ƃR�~���j�P�[�V������������ق������܂������v�Ƃ��u��w�̒��̃R�~���j�P�[�V���������������悤�v�Ƃ������悤�ɁA�l�ԓ��m�̓���I�ȑ��ݍ�p��F�B���m�̉�b�̂��Ƃ��w���āA�R�~���j�P�[�V�����ƌĂ�ł��܂��B�ł��l���Ă݂�A���������u�R�~���j�P�[�V�����v�̎g�����́A�������� 1990 �N�ォ��n�܂������Ƃ��Ǝv����ł��ˁB���Ƃ��ƃR�~���j�P�[�V�����Ƃ����A�V����e���r�Ȃǂ̃}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̂��Ƃ��ĂԂ̂����ʂł����B�܂肱�̃}�X�E�R�~���j�P�[�V�����w��Ō������Ă����悤�ȃ}�X�R�~�ɂ��u���`�B�v�̂��Ƃ��A�R�~���j�P�[�V�����̂��Ƃ�������ł��B���ہA���݂̕W���I�ȎЉ�w�̋��ȏ������Ă��A�u���퐶���̑��ݍ�p�v�Ɓu���`�B�Ƃ��ẴR�~���j�P�[�V�����v�Ƃ͂܂��������������Ƃ��ďЉ��Ă��܂��B
���Ⴀ�u�R�~���j�P�[�V�����v�́A�u���퐶���̑��ݍ�p�v�Ƃ͉����Ⴄ�����Ă����ƁA���̓`����Ǝ肪�N�Ƃł�����ւ��\�����Ă������Ƃ��Ǝv���܂��B�N���`���Ă��N�������Ă������ł���悤�ȁA��ʉ����ꂽ����L�����������邱�Ƃ��R�~���j�P�[�V�����ł��B���܂�ɂ�������O�̂��Ƃ������Ă���悤�ɕ������邩������܂��A�Ⴆ�Ε�����E��̉B���[���̊G�����̂��ƂȂǂ��v���o���Ă���������A����͂����Ƃ�������O�̂��Ƃł͂Ȃ����Ƃ��������肢��������ł��傤�B�l�Ԃ͓���̕t�������̂Ȃ��ł́A���������̊Ԃł����ʗp���Ȃ��Ɠ��̕\�����ꍇ���I�ɍ��o���܂��B����ɑ��ĐV���L���ɂ́A�N�����Ă��N���ǂ�ł��K���킩��悤�Ȉ�ʓI�ȕ\���̃t�H�[�}�b�g(������v�̂Ƃ��Ă̍���)���g���܂��B����������ʉ����ꂽ�����݂�Ȃ����L����Ƃ������Ƃ��A�������Ƃɂ����閯���`�̊�{�I�ȏ����ł��傤�B���̑���A����������ʓI�ȏ��R�~���j�P�[�V�����ɂ́A������B���G�����̂悤�ɁA�g�߂Ȑ����̃��A���e�B�⊴������߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ǂ����]���s���Ń^�e�}�G�I�Ȍ��t�̂����ɂ����Ȃ��킯�ł��B
�܂�A�R�~���j�P�[�V�����Ƃ������t�́A�����������u�R�~���j�P�[�V�����������Ɗ����ɂ��ĐS��ʂ킹�邱�Ƃɂ��܂��傤�v�ȂǂƎg���Ă���Ƃ��̏�I�ȃj���A���X�Ƃ͐����̈Ӗ����������A�}�X���f�B�A��}��ɂ������m�ȏ��`�B���Ӗ����錾�t�������̂ł��B�������́A���퐶���̂Ȃ��ł͓���̒N���Ƃ���(�e�Ƃ��āA�F�l�Ƃ��āA��y�Ƃ���)���͂̐l�тƂƕt�������A��肠���܂��B�����炻���ł́A���͎��ւ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ŗL�̐l�Ԃł��B����ɑ��āA�}�X���f�B�A��ʂ��ăR�~���j�P�[�V��������Ƃ��ɂ́A�e�Ƃ��F�l�Ƃ���y�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���̂悤�Ȏ��I�ȗ�����āA��ʓI�Ȍl�Ƃ��ď���`�B������A��e�����肵�Ă��܂��B
�܂�R�~���j�P�[�V�����Ƃ́A�l�Ԃ�����ȑO�̕��������̓I���E����͗��E�����A���ۓI�ȁu�s���v�ɂ���Ƃ����Љ�I�@�\���ʂ������킯�ł��B���S���̔������Ƒ�H�̌F����́A�n�拤���̂̂Ȃ��ł͓Ɠ��̍����t���g���ċC�y�Ɍ݂��̈ӎv�a�ʂ���邱�Ƃ��ł����킯�ł����A������l���Ƃ��ɐ����Ƃ�V���L�҂ƂȂ��Ę_������킷���ƂɂȂ�A��l�͂������������t���g�����ƂȂ��A�N�ɂł�������悤�ȋ��ʌ���g���ċc�_���Ȃ���Ȃ�܂���B�N�Ƃł�����ւ��\�ȒN�����u�s���v�Ƃ��ď����������A�c�_���邱�ƁB���ꂪ�Љ�̂Ȃ��̃R�~���j�P�[�V�����ߒ��Ȃ̂ł��B
������Ƒ��̃R�~���j�P�[�V�����������Ɗ����ɂ��ėǂ��e�q�W�����܂��傤�Ƃ����������͂ǂ����|���I�Ȃ̂��Ǝv���܂��B�ނ���R�~���j�P�[�V�����́A�l�Ԃ��ӂ��ɉƑ���n��Љ�̂悤�ȕ��I�ȊW�̂Ȃ��Ő����Ă����Ƃ��̊��т����킹�A�o���o���̌l���݂��ɋc�_�������A���������������̂Ȃ��ɕ��肾���Љ�I�@�\���ʂ����Ă����̂ł�����B�e�q�̓R�~���j�P�[�V�����Ȃǂ��Ȃ��Ă��A�ǂ�ȂɌ��������Ă��Ă��e�q�Ƃ����u���v�ɔ����ĕt�������Ă���͂��ł��B���̂悤�ȐM�O���e�q�Ƃ����O�ߑ�I�ȊW�̈��萫�����o���Ă����B�Ƃ��낪�A�R�~���j�P�[�V�����������Ə��Ɏ���ăX���[�Y�Ȑe�q�W�����܂��傤�Ȃǂƌ��������A�������͐e�q�W���C�����ɂ���Ă������藧���Ȃ��悤�ȕs����ȊW���Ǝv������ł��܂��܂��B��������F�B�e�q�ƌĂ��悤�ȁA�݂��ɏ�������Ȃ��悤�ɂ���e�q�W�������Ă��܂��͖̂��炩�ł��傤�B�܂�R�~���j�P�[�V�����Ƃ́A�܂��Ɏ��������ӂ��ɐ����邱�Ƃ��玄�������g��a�O������̂Ȃ̂ł��B
|
��3�D���f�B�A�Ƃ�������
�܂�A�R�~���j�P�[�V�����͊�{�I�Ɏ₵�����̂����Ă������Ƃł��ˁB�l�Ԃ��������ꂼ��ɌŗL�̊W�̂Ȃ��Ő����Ă������ł悩�����̂ɁA���̕��Ă͂��邪�[��������炵��a�O������̂Ƃ��āA�������Ƃ�W���[�i���Y�������j�I�Ɍ��ꂽ�킯�ł��B�Ƒ��̐����̂Ȃ��ɍ��Ƃɂ���ċ��炳�ꂽ�s��(����)�Ƃ��Ă̎q�����o�ꂵ�āA�S���̕��e���e�ɂ͗����ł��Ȃ��V���̌��t�̐��E����悤�ɂȂ�B�����̂̂Ȃ��ɐ����Ă����l�Ԃ������ƂȂ邱�Ƃ͂��������₵�������͂̐��E�Ɉ����N�������Ƃ������Ǝv���܂��B
�ł��A�Ȃ�����Ȏ₵�����Ƃ�������ł��傤�B�����Ίw�҂�f�B�A�͂�������ƌ��͂̂��������āA�܂�ő��l���̂悤�ɐ��������ł����A����͂��������Ǝv���܂��B��͂肻�������������Ƃ̂���悤��l�тƂ͗~�]�����Ǝv���̂ł��B�܂�A�����Ƃ��Đ����邱�ƂɁA�����̂̂Ȃ��ł����̕S���Ƃ��Đ�����ȏ�̔Z���Ȋ��т����������炱���A�l�тƂ͂����I�̂��Ǝv���܂��B
�Ⴆ�Ζ������ɓ��I�푈�ŏ����ē��{�����E�̈ꓙ���Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�Ɗ��������Ƃ́A�����̂̂Ȃ��Œn�ׂ��������Đ����Ă�������ł͓����Ȃ��傫�Ȋ��т������ł��傤�B��������I�푈�ȗ��A���̍��̊e�n�̐l�тƂ͐V���ɂ��폟�Ɋ��Œs����J��Ԃ��Ă��܂������A���N�����͌R�����N�Ƃ��ČR�l�ɂȂ邱�Ƃɓ���܂����B�܂�R�~���j�P�[�V�����ɂ����퐶���̑a�O�Ƃ́A���̌��Ԃ�Ƃ��Đ푈�Ƃ��I�����s�b�N�̂悤�ȁA���f�B�A�ɂ�鍑���K�͂̂��Ղ葛���������炷�Ƃ����̂������̎��̎咣�Ȃ�ł��B
�����ł�����Ɗp�x��ς��čl���Ă݂邽�߂ɁA����G�s�\�[�h���Љ�����Ǝv���܂��B�{�V�Ўi������{�̂Ȃ��ɏ�����Ă���G�s�\�[�h�Ȃ̂ł����A�ނ����Z�O�N���̂Ƃ�(1950 �N�㔼��)�ɁA�n���̊��q������Ă���Ɗ猩�m��̂��k����ɐ����������āA�u���Z�o����ǂ�����́v�ƕ����ꂽ�̂ŁA�u��w�֍s���܂��v���ē�����(�����w���������킯�ł���)�B����������A���̂��k�����݂��݂Ɨ{�V����̊�����āu�A���^�ˁA��w�ɍs���̂͂������ǁA��w�ɍs���ƃo�J�ɂȂ��v���Č��������Ă�����ł��B�o�J���Ă���������������������Ƃ�����u���ł������v�Ƃ������Ƃł��傤���B
�܂�A��w�ɍs���Ċw������āA���{�Ƃ������Ƃ̍s������l�ނ̕��a�ɂ��čl������A�������̂Ȃ��̍ۂɊւ��Ĉُ�ɏڂ����Ȃ����肵�Ă��܂����Ƃ́A�ӂ��Ɏ����̐g�̉��̐����������Ő����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ���Ă������Ƃł��ˁB��w�ɍs���Ė{����ǂ�Ŋw��̒m����g�ɂ���ƁA����܂ł̐����̂Ȃ��Œm�b�����Đ����Ă����l�тƂƂ͈���āA�n�ɑ������Ă��Ȃ��������l�Ԃɕς���Ă��܂��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B���ꂪ�A���������猾���Ă���u�R�~���j�P�[�V�����ɂ��a�O�v���Ă��Ƃł��B
���f�B�A�́A���̂悤�ɒn�ɑ������Ȃ���������܂��܂Ȑl�тƂɕ��y�����Ă��܂����B�������́A�����̗ߏ��̐l�тƂ��ǂ�Ȑ��������āA�����l���Đ����Ă��邩���قƂ�ǒm��Ȃ��̂ɁA�e���r��ʂ��āA�����̂���ꏊ����͉������ꂽ�ꏊ�̉w�O���X�X�����т�Ă���l�q��A�ߑa���ɋꂵ��ł���l�тƂ̎p�����Č���̊i���Љ�Ƃ������ɂ��Ē��ۓI�ɋc�_���܂��B���邢�͎������̓e���r�ʼn������ŋQ���Ă���q���̎p�����ĐS��ɂ߂ĕ�������肷��B�����琢�E�F���̉��ߊ������S�ɋt�]���Ă���킯�ł��B���f�B�A�E�R�~���j�P�[�V���������y����Ƃ������Ƃ́A�g�߂Ȗ�肪��������Ă����āA�����̖��Ɋւ��Ă̑z���͂��ǂ�ǂ܂��Ă����Ƃ������Ƃł��傤�B������A������Ċ��q�̂��k����̊��o�Ō����A�܂��Ɏ��������o�J�ɂȂ����Ƃ������ƂȂ�Ȃ��ł��傤���B
�ł��R�~���j�P�[�V�����ɂ���ăo�J�ɂȂ�Ȃ邾���A�������瓾���銽�т��Z���ɂȂ����Ǝv����ł��B�ߗׂ̐N���m�̌��ܑ����⑺�̂��Ղ�Ƃ������u���퐶���̑��ݍ�p�v�̂Ȃ��œ�����j�ՓI�Ȋ��т����A�������������悤�ȓ��I�푈�̕ɐڂ��������A���̋����̃X�P�[�����傫�����܂�ł��傤(�u�a�����߂����ē���J�����ő������N���܂�����)�B
�������������������̍��܂���āA���̕��~�߂鑤�����ł͂Ȃ��A���̏j�Ղ𐋍s���鑤�ɂ��N���邱�Ƃ��Ǝv���܂��B�ȒP�Ɍ����Ă��܂��A���f�B�A��ʂ��Ă݂�Ȃɕ���Ǝv���ƁA��肢�������撣�����Ă������Ƃł��B�ЎR�������A�����ɃJ���������ĕ��Ă����Ǝv������y�����������ł��傤�B
���������Ӗ��ł��ܒ��ڂ��ׂ��̓X�|�[�c�̃A�X���[�g���Ǝv���܂��B�����Ƃ��L���҂ɂ��肢���܂����ē��������Ă���̂ɔ�ׂāA�A�X���[�g�͘e�ڂ��U�炸�ɂЂ��ނ��ɏ������Ă���Ƃ������R�ŋP���Ă���悤�Ɍ����܂��B�ł��A�����ł��傤���B���͈Ⴄ�Ǝv���܂��B�ނ��딽�ɃX�|�[�c���̂��A���f�B�A�Ȃ����Ă͐��܂�Ȃ������ƌ����ׂ��ł��傤�B�������f�B�A�����݂��Ă��Ȃ���A100 ���[�g����9�b��ő��낤�ȂǂƂ����o�J�Ȑl�Ԃ������ł��傤���B���f�B�A��ʂ��Đ��E���̐l�тƂ����Ă���邩�炱���A���ꂾ���ނ��ɂȂ��Ċ撣�����Ă����O����͂��ł��B�����炱���c��Ȏ���������̑I��ɓ�������āA�����ł��������邽�߂̉Ȋw�I�������Ȃ���A���̑I��͂Ђ�����9�b��ő��邽�߂̗��K����I�ɌJ��Ԃ����Ƃ��ł���B�����āA9�b��ő���X�[�p�[�E�v���[����яo���āA�������͂���ɔM������킯�ł��B
�����������X�|�[�c�������Ɋy���ނƂ����̂ł���A�^����̃����[�Ƃ��t�b�g�T���Ƃ����싅�̂悤�ɁA��������邱�Ƃ��y���ق��������Ɍ��܂��Ă���킯�ł��B�������g�͂���Ȃɏ�肭�͂Ȃ�����ǁA�g�̊��o�I�Ɋy���߂�����B���Ȃ��Ƃ��A�����̃X�|�[�c�E�G���[�g���v���[�����ĉ����l�Ƃ����l�Ԃ������e���r�ł�������Ă��邾���Ƃ����̂́A�g�̂��������Ƃ��ẴX�|�[�c�Ƃ����Ӗ��ł͖��炩�ɕs���N�����A���o�����X�ł��B�ł����炢�܂����̎����Ă���(�u����v���Ƃ𒆐S�ɂ���)�X�|�[�c�����́A���f�B�A�Ƌ��ɐ������Ă����Ƃ����ׂ��ł��傤�B
���������Ӗ��ŁA�ꌩ�����Ƃ���X�|�[�c�͘e�ڂ��U��Ȃ��{�C�̑��������Ă���悤�Ɍ�����킯�ł����A�{���̓��f�B�A�ɒ��p����Ă��邩�炱���撣���Ƃ������f�B�A�I�\��������B�܂�X�|�[�c�ł����A���f�B�A�I���ʂ��ŏ�����g�ݍ��܂�Ă���B���̈Ӗ��ł́A�����̏ꍇ�Ɠ����ȂƎv���܂��B�������X�|�[�c�������I�ɂ́A���f�B�A��ʂ��đ吨�̐l�тƂɌ����Ă���Ǝv������A�^���ɓ��_������v���[������ł���B�ނ�̌����Ă���Ƃ������Ƃ��p�t�H�[�}�[���ӎ����������Ƃ�(�t���b�v���o�����Ƃ���y���������Ƃ�)�A�������ϋq�͂��炯�Ă��܂��B�܂�A���̂悤�ȃ��f�B�A�_�I�ȍ\�������ɂ��āA�W���[�i���Y���_�I�ȗ��z�_�����Ń}�X�E�R�~���j�P�[�V�����̖��͌�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ǝv���܂��B�R�~���j�P�[�V�����Ƃ̓X�|�[�c�ɂ���I���ɂ���A�N�����P������A���̋P�����N���ɔ���𑗂����肷�銽�тɖ����Ă��邩�炱�����݂��Ă���̂��Ǝv���܂��B
�ނ���������f�B�A�����ꂽ���j�ՓI�ȎЉ�ɂ̓}�C�i�X�̑��ʂ���������܂��B���̍ő�̂��̂��푈�ł��傤�B����ȊO�ɂ��Ⴆ�A�g�̉��̒N���������Ƃ�����̓I�ȗ��R����ł͂Ȃ��A���f�B�A�Ɍ����čs��ꂽ�Ƃ����v���Ȃ��ƍ߂������N���܂���ˁB���������܂��ƁA1997 �N�ɐ_�˂̒��w�����N�������A�������E�������̔Ɛl�E���̎��S�K�N���l�́A��Q�҂̏��N�̎����čŏ��Z��̏�ɒu�����Ƃ����炵����ł��ˁB�Z��̑O�͉����ɂȂ��Ă��āA�����猩��Ƃ��傤�ǂ����J�����A���O���ɂȂ�悤�ȏ��ɒu�����Ƃ�����ł��B�܂�E���������Ă�����̓I�ȗ~�]�����łȂ��A���f�B�A��ʂ��Ă�����݂�ȂɌ����т炩���������Ă����~�]���ނɂ͂�������Ȃ����Ǝv���܂��B�ŏ����玩���̔ƍ߂����f�B�A�ŕ����Ƒz�����邩�炱���A������R���������Ďq���̎���Ȃ�Ĕ��ł��Ȃ����Ƃ���ꂽ�悤�Ɏv����B������A�X�|�[�c�̃X�[�p�[�E�v���[�Ɠ����ł���ˁB
2008 �N�ɏH�t���ŋN�����ʂ薂�E�l�����ł������ł��傤�B�ނ̓��f�B�A��Ԃ̂Ȃ��Ƀg���b�N�Ŕ�э��Ƃ����v���Ȃ��B�������f�B�A�͂����������������Ղ�̂悤�ɔM���I�ɕ��܂����A�������������b��ɂ��ē��퐶���̂Ȃ��ő傢�ɐ���オ��B��������ă��f�B�A�I�Ȋ������z�����Ɛl�������E�l��Ƃ����ƍl����ƁA�ɓ��炳��̌����悤�Ɋm���Ɏ��������҂Ƃ��ĕs���ł͂����ł��B�����������f�B�A�I�ȋ�Ԃ��s���ɒf����W���[�i���Y���̔�]���Ȃ������Ǝ����v���B�������ł̓��f�B�A�I�ȗ~�]��l�Ԃ͗}���ł��邩���Ă����Ƃ���͖��������A�����W���[�i���Y���̐��`�����Ől�Ԃ������Đ�����͂����Ȃ����Ă�͂�v���܂��B
|
��4�D���f�B�A�̎�p��
���f�B�A�͂Ȃ�����̂��B��������܂ł̘b�ŕ������Ă����������悤�ɁA�u�y��������v�Ƃ����̂����̃��f�B�A�����_�I�Ȏ��_����̉ł��B�W���[�i���Y���_�I�Ȏ��_����̓����́A�����炭����l�тƂɍL���`�B���邱�Ƃ��A�Љ�I�ȈӋ`�����邩�炾�Ƃ������Ƃł��傤���A����͂��܂�ɕ\�ʓI�ȓ����ɂ����Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B���S�K�N���l�̔ƍs�̌o�܂��A���ɓ���ׂɂ킽���Ēm��������Ƃ����Ď������̐����ɂ����������̖��ɗ��Ƃ����̂ł��傤���B����Ȋ댯�Ȑl�Ԃ��o�Ă��Ȃ��悤�ɁA�݂�ȂŋC��t���邽�߂Ȃ̂ł��傤���B�ނ̂悤�ɐS�̈ł���������N���Ăяo�Ă��Ȃ��悤�ɋ�������P���邽�߂ł��傤���B����Ȃ̖����Ɍ��܂��Ă���ł��傤�B�ʂ̋���̎d���ɂ́A����ɉ����ĕʂ̐S�̈ł��������l�Ԃ�����Ă���Ɍ��܂��Ă��܂��B����ŗL�̔ƍ߂̍ו���m���Ă��������̐����ɂ͉��̖��ɂ������Ȃ��B�ł��m���Ɏ������͔ƍs�̍ו���m�肽���ł����A���̔ƍs�̗��R�͂����S���w�I�E�Љ�w�I�����(�n���n�������Ǝv���Ă�)�ǂ蕷�����肵�Ċy���݂����B
���������Ӗ��Ń}�X���f�B�A�͕̕K�v�ł��B��������͎Љ�I����u���邽�߂ł͂Ȃ��āA�P�Ƀh���}�����Ă���悤�ɂ݂�Ȃŋ������āA���������̐����[��������������ł��傤�B���w�������w���̒j�̎q���E���Ď����čZ��ɒu�����B���̎����ɋ����A�s���ɂȂ�A���������ɂ͂����Ȃ��B�����玄�����̓}�X���f�B�A��ʂ��ďڂ����������āA�݂�Ȃʼn\�b�����Ă��Ղ�̂悤�ɐ���オ�炸�ɂ͂����Ȃ��̂ł��B���̃��f�B�A�I�ȋ����Ɗ��т̎Љ�I�ȋ��U��p�͂��͂⓹���I�ȑP���Ȃǂ��āA�ނ����p�I�ȃ����^���e�B�ɋ߂��Ǝ��ɂ͎v���܂��B
�܂胁�f�B�A�̂����炷���т́A�ߑ�I�Ȗ����`�⍇����`�����Ƃ���ɂ���̂��Ǝv���܂��B����́A�|�s�����[�����̂��܂��܂Ȏ��������Ζ����ł��傤�B20 ���I�ɂ�����}�X���f�B�A�̔��B�Ƃ́A�j���[�X�̔��B�ł���Ɠ����ɁA�n���E�b�h�f���|�s�����[���y�Ȃǂ̌�y�����̕��y�̘b�ł��������͂��ł��B�`���[���Y�E�`���b�v������r�[�g���Y��}�C�P���E�W���N�\���ւ̐��E�I�ȔM���̘b���ɂ��āA20 ���I�̃��f�B�A��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B���f�B�A��ʂ��Đ��E���̐l�тƂ́A�`���b�v�����̃M�N�V���N����������r�[�g���Y�̏��p�Ȉ��̋��ѐ���}�C�P���E�W���N�\���̃r�[�g�ւ̋��U�����L���Ă��܂����B���̈Ӗ��ł́A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����Ƃ́A�u���v�̓`�B�Ƃ������́A�u��v�̓`�B�Ƃ����Љ�I�������ʂ��Ă����Ƃ������܂��B
�ł͂��̂悤�ȑO�u�������������ŁA�����Łw�J�ɉS���x�Ƃ����f��̗L���ȏ�ʂ����Ă��炢�܂��B
�`�w�J�ɉS���x��f�`
���l���Ƃ܂ő����čs���āA���̌��ւ̑O�ŃL�X�����Ă������蕑���オ���Ă��܂�������̃W�[���E�P���[�́A�y���~��̉J�̂Ȃ��Łu�W���X�g�A�V���M���A�C���A�U�A���C���v�Ɖ̂������A�P����Ă�����X�e�b�L����ɂ��āA���ԔG��ɂȂ��ėx�肾���܂��B����͐����邱�Ƃ̊��т�S�g�ŕ\�����Ă��邩�̂悤�ȑf���炵����ʂł��B�m���Ɏ����������퐶���̒��ŁA���l�ƃL�X��������A������Ƃ������Ƃ��������肷��ƁA�X�L�b�v���Ă݂���A�@�̂��̂������Ȃ����肷��ł��傤�B�������Ĕ߂����Ȃ�ƁA�����̂��Ƃ�������Ƃ������������ߌ��̕����F�l�ɕ��������肵�܂��B�ł����ꂾ���ł��B�ł����玄�����́A��������ē��퐶���̂Ȃ��ɐ��܂�Ă͏����Ă����A�����銽�т�߂��݂��A�������̓v���̍�Ƃɕ���Ƃ��ď����Ă��炢�A�f��≉���Ƃ��Ė��҂ɉ����Ă�����āA�{��f��� DVD �Ƃ��ăp�b�P�[�W�����A���x�͂����ǂ茩���肵�Ċ��т�������悤�ɂȂ�܂��B����Ǝ������͗������ĂȂ��Ă��A�C���������Ƃ��� DVD ���Đ����ăW�[���E�P���[�����Ċ��т̋C���𖡂킢�A�@�̂Łu�W���X�g�A�V���M���A�C���A�U�A���C���v�Ɖ̂����肵�Ċy���ނ̂ł��B
�܂�A�������̓p�b�P�[�W�����ꂽ���f�B�A��i����ɓ���邱�Ƃɂ���āA���퐶���̂Ȃ��̐����銽�т���͑a�O����Ă��܂��̂ł����A�t�Ƀ��f�B�A��ʂ��Ă����ƔZ���Ȑ����銽�т邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B���̈Ӗ��ŁA�������͏������邢�B�J���~���Đ����܂肪�ł���Ǝq���͊��ŁA���̒��ɑ������ăo�V���o�V���Ƃ��n�߂܂����A��l�Ƃ��Ă̎������͂���ɑ��āA�u��߂Ȃ����B�C�������ł���v�ȂǂƎ�����Ă��܂��̂ł�����B�������������́w�J�ɉS���x�� DVD �Ŏq���Ɍ����āA����������Ȃǂƌ����̂ł����疵���ȊO�̉����ł�����܂���B�ł���������Ă��܂ł��o�V���o�V������Ă��Ă͑�l�ɂȂ�Ȃ��̂������ł��B���̉f��ł��A�Ō�Ɍx���Ɍ����Ă��邱�ƂɋC�t�����W�[���E�P���[���A��ɕԂ��Ēp���������Ȃ��ėx�����߂��ʂ����邱�Ƃ��ƂĂ��厖�ȂƎv���܂��B����͋t���I�ɁA���h�ȑ�l�����Ȃ��悤�Ȕn���ȐU�镑�������炱���A�W�[���E�P���[������Č������Ƃ��ɋ�������Ƃ������Ƃ��������ɋ����Ă���Ă��܂��B
����A�n���ȐU�镑�����Ǝq��������ǂ���ł͂Ȃ��B��������l�́A�����܂莩�̂��Ȃ������ƎЉ�������Ď��g��ł��܂����B�����܂�ɂ�������͂܂��ēD���炯�ɂȂ����肷��ƂƂĂ��s�����ɂȂ�̂ŁA�y�̓��H���A�X�t�@���g�ŕ~���l�߁A���a���@���Đ����X���[�Y�ɗ����悤�ɍH�v���āA���C�����v��Ȃ��悤�ȓs�s������肠���܂����B���a 30 �N��̋L�^�f��������ƁA�����̓����Ƃ����s�s�̐��J���̈����ɂт����肷�邱�Ƃ�����܂��B�����̂ǂ�����������������ƉJ���~���������Ő삪�×����Ă����璆�̓��H���������Ă��܂��Ă�����ł��ˁB������Z�������͍s���ɒ�āA�_�����z��͐�H�������Ă�����Đ�̗����ς��Ă��������A���a��A�X�t�@���g������Ă�������肵�āA�Z�݂₷���Z��������Ă����̂ł��B����Ƃ����Ɍ������Ƃ̗������������āA�����̓y����������ɂ���Č���āA�y�������Ɠ��{�ȂǂƌĂ��悤�ȎЉ�V�X�e�����o���オ���Ă������B���̂悤�Ȍ������Ƃ̂���悤�����v���Ȃ���Ȃ�Ȃ�(�s�����v)�Ƃ����̂��A���� 20 �N�قǂ̑傫�Ȑ����I���_�ł�����ˁB�����琅���܂���o�V���o�V����銽�т��̂Ă�����ɁA��l�����͎������߂��鐭���ƌo�ςɗ��ł����̂ł��B
������Ă���Ӗ��ł͔n���n���������Ƃɕ����邩������܂���B�ł��K���������͔ᔻ�������킯�ł͂Ȃ���ł��B����Ȃ��Ƃ���������A���́w�J�ɉS���x�̂��̏�ʂ����グ�邱�Ǝ��̂��A�傫�ȗ����̂��������A�����Ėc��ȘJ�͂��������r�W�l�X�ɂ����Ȃ�����ł��B�B�e���̒��ɖ{���̊X��������̃Z�b�g�����A�X�փ|�X�g�𗧂Ă��莩���Ԃ𑖂点���肵�āA��������̉J���~�点�ĉJ�ǂ����琅�o�����A���H�ɐ����܂�����A���y�ƃW�[���E�P���[�̗x�肪���܂������悤�ɁA���邢�͌x�����o�Ă���^�C�~���O�������悤�ɉ��x���J��Ԃ����n�[�T���������͂��ł��B�����������A�������C�̍����Ƃ����v���Ȃ��悤�Ȗʓ|�Ȏd�����J�肩�����Ȃ������ȑf���炵����ʂ͍��Ȃ��ł��傤�B����ǁA���������݂�Ȃ�����̊X�̐����܂���o�V���o�V�����Ώ\���Ɋy���߂�͂�����Ȃ��ł����B�ł��l�Ԃ͂�������Ď����Ŏ��R�Ɋy���ނ̂ł͂Ȃ��A�����ł��邱�Ƃ������ĉ䖝���āA�X�[�p�[�E�v���[�Ƃ��Ă̐����܂�o�V���o�V������i�Ƃ��č���āA��������i�Ƃ��Ĕ��蔃������悤�Ȏ��{��`�Љ������Ă����B�܂�A���̎Љ�͌����č����I�ɂ͓����Ă��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�������Ԃ��Ȃ��Ȃ��Ă����悤�ł��B�܂Ƃ߂܂��ƁA���������\���グ���������̂́A�}�X�E�R�~���j�P�[�V�����́A�����������̊���h���Ԃ�悤�ȏ�I�ȉ�����`���Ă���̂��Ƃ������ł��B�ЎR�����̓y�����ł��A���S�K�N���l�̔ƍ߂ł��A�W�[���E�P���[���x�苶���p�ł������ł����ˁB���������}�X�E���f�B�A�̔����͕K�������ᔻ�����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B�l�Ԃ͂��Ƃ��Ɣ��I�Ȃ�ł�����B�����Ď��������푈��ƍ߂�X�|�[�c��|�\�Ɏ�p�I�ɐ���オ�肽���Ƃ����~�]�͌����Ď~�߂��Ȃ��ł��傤����B�ނ��W���[�i���Y����A�J�f�~�Y�����A�l�ԎЉ�̗��z�����߂Ă��������Љ�̔�����ᔻ���邱�Ƃ͗����ł��܂��B�������z��ǂ����߂邽�߂ɁA���Ȍ�������ڂ����炵�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝ��͌��������̂ł��B�l�Ԃ���p�I�ȗ~�]�ɂ���Đ�����o�ς╶����f�B�A�����Ă���Ƃ���������F�߂��Ƃ��납��A�ᔻ�̍�Ƃ͎n�܂�̂��Ǝv���܂��B
�Ō�ɂ������������}�b���Љ���Ă��������B�l�Ԃ̗c���ƃ`���p���W�[�̊w�K�s���𑊌ݔ�r���邽�߂̎����ŁA�����҂��{�^���������ēd��������Ƃ����s���𗼎҂��ǂ̂悤�ɖ͕킷�邩���ώ@�������̂ł��B���̎����̈�ŁA�����҂����ł��ŃX�C�b�`�������Ƃ�����ȍs��������Ă݂����Ƃ���A�`���p���W�[�͈��ʊW�������Ɗw�K���Ď���͎�Ń{�^���������ēd���������̂ɑ��āA�l�Ԃ̗c���͂��ł��Ń{�^���������Ǝv������ŁA�������Ă��܂����炵���̂ł��B
���Ƃ��f�G�Șb���Ǝv���܂��B���̘b�́A�����̂ق������R�̈��ʊW��c�����ĉȊw�҂Ƃ��Đ����Ă���̂ɑ��āA�l�Ԃ͐l�Ԃ������Ă��邩��A���̐l�Ԃ̍s����͕킷�邱�Ƃɂ���Ĕ�����I�ɐ����Ă���Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�q�������͑�l�����ɓ���A���̍s����͕킷�邱�Ƃ�ʂ��ď��߂đ�l�ɂȂ�B���ł��Ń{�^���������Ƃ����̂́A���̗c���ɂƂ��Ă̓X�[�p�[�E�v���[�Ɍ������킯�ł��ˁB���̈Ӗ��ł̓W���[�i���Y���_��R�~���j�P�[�V�����_�́A�l�ԂɃ`���p���W�[�ł����Ăق����Ɗ���Ă���̂��Ƃ������Ƃł��B����ɑ��Ď��̓��f�B�A�_�I�Ȏ��_����A�l�Ԃ̔��Ŕn���ȐU�镑���������邱�Ƃ���{�ɂ��Ȃ���A�����̌������������Ǝv������ł��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
������H�������Ă����f�B�A�̖������т��@2015/5
|
�W���[�i���X�g���߂����w���Ɍ����ĂȂɂ��Ƃ��Q�l�ɂȂ邱�Ƃ������A�Ƃ����{���ҏW������̈˗����A���Ȃ��炸�T�������B�������f�B�A�ƊE�ɔ�э��̂͂�����̂悤�ȋC�ł������A�܂���y���狳�����邱�Ƃ���̐g���Ǝv���Ă�������Ȃ̂����A�悭�悭�l���Ă݂�A���̎d�����n�߂Ă����l�����I�̎����߂��Ă��܂��Ă���B���̂܂ɂ���y��W���[�i���X�g�u�]�҂Ɍ����ĂȂɂ��Ƃ�������Ă����������Ȃ���Ƃ��ɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�Ƃ͂����A�R��������������Ђ˂��Ă��A�����ň̂����Ɍ��ׂ����̂��������킹�Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B���̒��ɐh�����Ďc����Ă���̂́A����������h�����y�̋L�҂�W���[�i���X�g�A�ҏW�҂������炽�������܂ꂽ��������B�܂�A�I���W�i���ł͂Ȃ��B�g���ӂ����Ȃ�������������A�P�Ȃ�u����v�B
�������A�������L������ŁA��y��������̋����̂����d�v���Ǝv�����̂��ЂƂA�����ŋL���Ă������Ƃ����C�����ɂȂ����B�ǂ̎d���ɂ������x�͋��ʂ���b���낤���A�ꌩ�h��ɂ��������郁�f�B�A��W���[�i���Y���ɂ������d���Ƃ́A���ǂ̂Ƃ���n���ȐE�l�d���̑��ʂ������A��y����w�Z�p�⋳����������ɐ\�����肷��̂���Ȃ��Ƃ��Ǝv������ł���B
���s���v���ÎĂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����
�����w�Z�𑲋Ƃ��A���ʐM�ЂɋL�҂Ƃ��Ă̐E������̂��ƁA���X�̏C������������Ă������ƂŒm����ҏW�����ɗU���Ĉ�����ɍs���A�����Ԃ�ƔM���ۂ��@���ꂽ�B�����悻���̂悤�ȓ��e�������ƋL�����Ă���B
�q�L�҂Ƃ��W���[�i���X�g�Ƃ������Ă��A�����܂�������E�Ƃ̂ЂƂɂ����Ȃ��B��Ђ����āA��{�I�ɂ͉c����Ƃ��B���h�������Ă����ΒN�ɂł���邪�A�I�������͒P�Ȃ��Ј������A�̂Ԃ�Ȃ�Ă����Ă̂ق��A��Ɍ�������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��B
�����A���̎d���ɂ͂ق��̎d���ƈႤ�Ƃ��낪����B��Ђ́A�P�Ȃ�c����Ƃ���Ȃ��B���Ƃ��������Ă��A���Ƃ��s���v���ÎĂ��A�Ӓn���Ď��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����������B�ň��̏ꍇ�A���̂��߂ɉ�Ђ��c�u��邩������Ȃ��B���̊o�����ɂ��Ă����Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ƃ����_�ŁA���̎d���͂ق��̎d���ƌ���I�ɈႤ�B���O���A������������ɂ���������ł����r—�B
���܂���l����ΎႩ�����̂��낤�A������̃J�E���^�[�Ŕ�����������X���Ȃ���ҏW�����̘b���A�킸���ɕ��Ґk�������B�����ɂ���Șb�̓L���C�S�g�ł���A�����̃��f�B�A��Ƃ����ȕېg�Ɨ��v�m�ۂɖ�N�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��Ԃ��Ȃ��m��̂����A���̕��Ґk���́A�g�D�𗣂�ăt���[�����X�ƂȂ������܂ł������ĖY��Ă͂����Ȃ����S���Ƃ��т��т��݂��߂�B
�����A�͂����肢���A�^�ʖڂɂ����قǑ��������˂Ȃ��d���Ȃ̂ł���B�����A���̎d���Ɍg���ȏ�A�Ӓn���Ăł������Î˂Ȃ�Ȃ������m���ɂ���B�ǂ��������Ƃ��B
�����҂ɂ����O�ꂵ���Ď��̖ڂ�
���ʂ̊�Ƃ�d���Ȃ�A������X�|���T�[�Ƃ̊W�͂ǂ��܂ł��~���ɕۂ��A��ɗ��v���ɑ剻���悤�ƍl���A�s������B�V���Ђ��ɂƂ�A��ސ��L����Ȃǂ�����ɂ����邾�낤�B
�������A�V���L�҂͎�ސ��L����Ƃ̊W���~���ɂ��Ă��������ł͂����Ȃ��B��ސ悾�낤�ƍL���傾�낤�ƁA�����ɉ��炩�̖��_��s�ˎ�������ΐ^���ʂ���ᔻ����B�Ǝ��̎�ނ���������Ȃǂɂ���Ď�ސ��L����̕s��������A���R�Ƃ�����L�������Ė���N���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���R�Ȃ���A��ސ��L����͓{��B�܂����������̑��l�ł���܂������A�ӂ���͐e���ɂ���肵�Ă���W�Ȃ̂�����A�{��͂���ɑ��������˂Ȃ��B
�������A��������ȂƂ���Ȃ̂����A���f�B�A�ƃW���[�i���Y���̑傫�Ȗ����́u���͂⌠�Ђ̊Ď��v�ɂ���B����Ȃ��̂͗��z�_�ɂ����Ȃ��Ɨ����y�₩�炪����U���Ă���̂������Ƃ͂����A���z�͗��z�Ƃ��ď�Ɍf�������˂Ȃ炸�A������т��Ȃ���f�B�A�ƃW���[�i���Y���ɂ������҂͏�Ɏ�҂̑��Ɋ��Y���A���ҁ��͂̋����҂ɂ����O�ꂵ���Ď��̖ڂ𒍂����܂˂Ȃ�Ȃ��B
�����������O�̘b�����A�͂̋����҂͕����ǂ���͂������A�����͂������B�s����\���A���邢�͔ᔻ��������A��������Ō����邨���ꂪ�����B
�����Łu�͂̋����ҁv�ƊȒP�ɋL�������A����ɂ͂��܂��܂Ȃ��̂�����B�����⊯���@�\�A������\�����鐭���Ƃ⊯���͕M���i���낤���A���厑�{��i������ƂȂǂ�����ɂ�����B�������N��ނ����Ώۑg�D�ł����A�x�@��@���E���@�Ȃǂ͐��Ȍ����ƌ��͂�ێ����Ă���B
����ȊO�ɂ����̍L����Ђ�@���c�́A���邢�͑��̌|�\�������Ȃǂ��W�ƊE��f�B�A�ɋ����e���͂�L���Ă���B���f�B�A���ꎩ�g�����͑��u�Ɖ����Ă��邱�Ƃ����Ă���B
���������g�D��c�́A�l�ɂ����˂炸�A�ᔻ���ׂ��͔ᔻ���A�s��������Ί��R�ƍ������������邩�B
�����͈Ղ����A�s���͓���B
���Ƃ��Όx�@��@���E���@�g�D�́A����Ȍ��͋@�ւł���Ɠ����ɁA�V���Ђ̎Љ�L�҂ɂƂ��Ă͏d�v�Ȏ�ސ�ł����ł�����B�ᔻ����������s����\�����肷��Δ��������˂Ȃ����A��ނȂǂ̖ʂŕs���v����͕̂K���̏Ɋׂ�B
�ЂƂ�����̗��������B
���܂����10�N�قǑO�̂��ƁA�k�C���̖��历�E�k�C���V��(���V)���L�����y�[�����J��L���A�傫�ȊS���W�߂��B�k�C���x�@�{��(���x)���g�D�I�Ɏ����߂Ă����u�����Â���v�Ƃ����s����n���Ȓ����Ŏ��X�Ɩ���݂ɏo�����̂ł���B
�{�肩��͂����̂ł����Ŏ���Ȃǂ͏ڏq���Ȃ����A�x�@�g�D�ɂ͑{�����͎҂ȂǂɎx�����u��v�Ƃ����V�X�e��������B�Ƃ��낪���x�́A�̎������U������Ȃǂ��Ď��ۂɂ͑��݂��Ȃ����͎҂Ɂu��v���x���������Ƃɂ��ė��������A�����̗V�������۔�ɂ܂킵�Ă����B
���R�͂ǂ�����A����͑{���@�ւł���x�@�̖����Ȕƍߍs��—���Ƃ��Ε����U���A���̂Ȃ�—�ł���A���V��1�N���ɂ�����Ԓn���Ȏ�ނƃL�����y�[���I�Ȓ����ł�������ɂ����B�ŏI�I�ɓ��x�͂��Ԃ��ԂȂ���7���~�ȏ�̕s���x�o��F�߂ĎӍ߂���Ƃ���ɒǂ����܂�A���V��ޔǂ͐V������܂Ȃǂ̉h�_�ɂ��P�����B���f�B�A�ƃW���[�i���Y���̖����ł���u���͂̊Ď��v���������ɖ��߂��Ƃ����Ă����B
�����V�̗����L�����y�[���ɖk�C���x�����X�Ȕ���
�������A���Ƃ͂���ŏI���Ȃ������B�����炭���x�͓{�苶�����̂��낤�A����Ȍ��͂�w�i�Ƃ��A�Ԃ��Ȃ����V�ɑ��ĉA�������X�Ȕ����ɏo���B
�����̓��V��ޔǃ����o�[��ɂ��A�����⎖�̎�ނ̏��œ��x�͓��V����ߏグ�A����L�҂���͔ߖ����������B
�܂��A���������߂���L�����y�[���Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ��L���������ƈقȂ�ƍR�c���J��Ԃ��A��ޔǃ����o�[�ɂ�鏑�Ђ̈ꕔ�L�q�����_�ʑ��ɂ�����Ƃ��ē��xOB�͑i�ׂ܂ŋN�������B����ɂ͓��V�����̕s�ˎ��Ă������Ƃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͋����{�������肤��Ɠ��V���������������Ƃ��������炵���B
���������������A�Ԃ��Ȃ����V�͕G�������Ă��܂��B�R�c�����L���ɂ��Ắu����юЍ��v��1�ʂɂł��ł��ƌf�ڂ��A���x���Ɨ��œ��X�Ɏ�ł������Ƃ����̂�����ɂȂ��Ă���B�����A�������̎�ޔǃ����o�[�͕ҏW�̒������玟�X�ɊO����A���l���̋L�҂��Ђ��������B�h��������J�ւ̓]���A�܂��Ɏ��r�݁X�������B
���������A�x�@�̗������͂Ȃɂ����x�Ɍ������b�ł͂Ȃ��A�e�n�̌x�@�{���ʼnc�X�Ƒ������Ă����S���I�Ȉ����ł������B�������A�S�������͂��߂Ƃ��鑼�̃��f�B�A�͂�������������m��Ȃ���Njy�����A�����͒��N�ɂ킽���ĕ��u���ꂽ�܂܂ƂȂ��Ă����B
�����̃��f�B�A�͂قƂ�ǒǐ�����
����ɓ��V�̎�ޔǂ͉ʊ��Ɏa�荞�̂����A���V�̃L�����y�[���𑼂̃��f�B�A�͖T�ς��A�قƂ�ǒǐ����Ȃ������B�ʂĂ͓��x�ɂ�����A���V�����Ȃ������E���̂Ɋւ���{������̂ɖ�N�ƂȂ�҂܂Ō����n���������炵���B
�������肾�낤�Ǝv���B���f�B�A�ƃW���[�i���Y���{���̔C���ł���u���͂̊Ď��v����S�����Ɛ^���Ɋт��A���ɂƂĂ��Ȃ��Ɏ����B�����ƒ����傭�B���ɂ����A��������B�^�ʖڂɂ����قǂ���ǂ��ڂɑ����B�t�Ɂu�͂̋����ҁv�ƓK�x�ɐ܂荇���A�˂�ɂ������A���܂����n�肵�Ă������������|�I�ɓ�������B
�����f�B�A�ƃW���[�i���Y���������`�Љ���x����
�����A���̂悤�Ȏ҂̓��f�B�A�ƃW���[�i���Y���̎d���ɂ������ׂ��ł͂Ȃ��B���Ȃ��Ƃ����́A��ɂ�������Ăق����Ȃ��ƒɐɎv���B���ꂪ�O�q������y�̋���—���Ƃ��������Ă��A���Ƃ��s���v���ÎĂ��A�@�E�E�E
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����f�B�A�̖����́u���������̂܂ܓ`����v���Ɓ@2018/6
|
���f�B�A�̖����́u���͂��Ď����邱�Ɓv���Ɗ��Ⴂ���Ă���A�V����e���r�̊W�҂�A�W���[�i���X�g�����{�ɂ͑����悤���B
�����I���ŒN�ɓ��[���邩�Ȃǂ̏d�v�Ȕ��f�������Ƃ��A���f�B�A�����Q�l�ɂ��Ȃ��l�͂��Ȃ��B������A�u���f�B�A���Ď����ׂ����͂�1�v�Ƃ����̂�����l�̏펯�ł���B
����ȏ펯����Ȃ��l�X���W���[�i���X�g�����̂��āA���f�B�A�̋���Ȍ��͂��g���錻��́A���{�Љ�̕s���v�f��1�Ƃ�����B
���{��č��̂悤�Ȗ����`���̃��f�B�A�ɉۂ���ꂽ�����́A�u��ނ������������̂܂܍����ɓ`���邱�Ɓv�����ł���B�����ɑ���P�����A�����鋖���Ȃ��Ȃǂ̔��f�������̂́A�匠�҂��鍑���̖��������炾�B
�]���āA���f�B�A�͍����ɓ`���鎖���𐭎��I�ړI�őI�ʂ�����A�o�C�A�X����̋r�F��t���ē`����ׂ��ł͂Ȃ��B���̂悤�ȁu��ۑ���v��u���_�U���v�́A���f�B�A���u�����Ɓv�Ƃ��čs�����v���p�K���_�ƌ��Ȃ����B
�e���r�ǂ̗��j�ԑg����X�^�b�t�Ɂu�����g�D�̊����Ɓv������Ƃ�����l�b�g��ł͘b�肾�B�����Ɗ�ʐ^���o�Ă���B����̓W�J�ɒ��ڂ������B
���f�B�A�W�҂́A���̎����������̎��_���猩�ďd�v���ۂ����A�ҏW���s�g���̍ő�̊�ɂ��ׂ����B���͂ɍD�s�����s�s��������ɓ����ƁA�K�������I�ȃo�C�A�X���o��B�V���͗ϗ���̖�肾�������A�e���r�Ȃǂ̕����ǂ����Ε����@�ᔽ�ł���B
�k���N�⒆�ؐl�����a��(�o�q�b)�̂悤�ȓƍٍ��̏ꍇ�A���͂ɕs�s���Ȏ������A���f�B�A�������ɓ`����͍̂���B�k���N�̏����A�i�E���T�[����������A�ň��̏ꍇ�͎��Y�ɂȂ�B���ꂪ�{���́u�̎��R�̐N�Q�v�ł���A�u�����̒m�錠���v���s�����ȏ�Ԃł���B
���{�̃��f�B�A�́A�ƍٍ��Ƃ̐^�t�Ƃ�������B
���{�W�O�����ɂƂ��ĕs�s���ȏ��͐j���_��ɕ邪�A�D�s���Ȏ����͉\�Ȍ��荑���ɓ`���Ȃ��B�����āA�O�����{��X�|���T�[�A�g�D�I�N���[�}�[�ɑ��ẮA�ُ�ɋC���g���āu���Ȍ��{�v���s���B���̌��ʁA�u�����̒m�錠���v���s�����Ƃ����_�ł����ƁA���{�̃��f�B�A�͖k���N��o�q�b�Ƒ卷�Ȃ��B
�Ⴆ�A����́u�ČR��n�^���v��u�����Ɨ��^���v�̔w��ɁA�嗤�┼���̉e�������Ă��鎖���́A�Y�o�V���ȂLjꕔ�̃��f�B�A�����Ȃ��B�����}�̐��c�����O�@�c������N�����u�Ȋw������v(�Ȍ���)�̖�������B�R�����K�����������^�₪�w�E����Ă���̂��B
���͓��{�����ł͂Ȃ����[�Ŏ҂��B���f�B�A�ɂ��u��ނƕv�����{���Ăق����B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���}�X���f�B�A�����_�`���ɉʂ��������Ƃ��̗h�炬�@2015/12
|
|
�����܂ł��Ȃ��A���{�̃��f�B�A���͑傫���ς�����B�{�e�ł͂܂��A�Љ�I���A���e�B�̋��L�Ƃ������_���炱��܂Ń}�X���f�B�A�����_�`���ߒ��ɂ����ĉʂ����Ă������������r���[����B���ɁA���f�B�A���̕ω���I�𐫂̑���Ƃ������_���瑨���A�Љ�I���A���e�B�̋��L���x����}�X���f�B�A�̗͂��h�炬���錻���`���B����ɁA���������h�炬�ɂ�������炸���{�̐��}����Ƃ��L���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̂��߂Ƀ}�X���f�B�A�Ɉˑ�������Ȃ�������ӂ܂��A�����Ƃɂ��}�X���f�B�A�ɑ���ᔻ���}�X���f�B�A�ɑ���M����ቺ������\���ɂ��Ę_����B�Ō�ɁA����̐��_�`���ߒ��ƎЉ�I���A���e�B�̋��L�ɂ����ă}�X���f�B�A���ʂ��������ɂ��čl�@����B
|
��1 �Љ�I���A���e�B�̋��L���x����}�X���f�B�A
�}�X���f�B�A�����_�`���ɂ����ĉʂ����Ă����ł��d�v�Ȗ�����1�́A�Љ�I���A���e�B�̋��L�ł���B�r�c(2000)�́A�Љ�I���A���e�B���u���������ӂ���̐��������̍s���̒��ŁA���ꂪ�{�����A��������̂��ӂ��킵���A���ꂪ�����Ƃ��炵���A�Ǝ~�߂��錻�����v(p.18)�Ƃ��Ē�`���������ŁA�}�X���f�B�A�Ƃ����Љ�I�����̎��R�~���j�P�[�V�����_�I�ȈӖ������������B���̒��ŁA�r�c�̓R�~���j�P�[�V�����������B���̑��A���A���e�B�`���̑��A�����`���̑���3������\�������Ƃ��A�����3�����܂����}�C�N���|�}�N���E�_�C�i�~�N�X�̉�������ɐ��_�`�����ʒu�t���Ă���B���ɁA�}�X���f�B�A�͐M�ߐ��̂���C���p�[�\�i���ȏ�ł���A�Љ�I���A���e�B�̋��L�𐧓x�I�Ɏx����d�g�݂Ƃ��đ������Ă���B���ہA�V����e���r���l�X�́u�[�����v�����͂Ɍ`����Ă�������ɂ́A�}�X���f�B�A�͐��_�̎嗬���`����(Gerbner et al. 1980)�A�َ��ő��l�ȏ��ւ̐ڐG��ʂ��Đl�X�ɏn�l�̋@���^���Ă���(Mutz & Martin 2001)�B���������Љ�I���A���e�B���x���鐫����O��Ƃ��āA�}�X���f�B�A�̎�X�́u�V���͌��ʘ_�v�͎�����Ă����B������������Ă������B
�ł����{�I�ȃ��x���ŎЉ�I���A���e�B�̋��L���x����̂́A�m���̋��L�ł���B���ɁA�����I�m���͖����`�Љ�ɂ����Đ����Ƃ̃A�J�E���^�r���e�B��ۂ��߂Ɍ���I�ɏd�v�ł���B�������̔C�����Ɏ��Ɨ��͌������̂��A���ƍ��͑������̂��B����������{�I�Ȏ��������L����邱�ƂŁA�Ɛѕ]���Ɋ�Â����[�s����ʂ��ėL���҂������Ƃ��R���g���[���ł���\�������܂�B�e���r�����A���Ɍ��������͂������������I�m���̋��L�ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă����B���������̎����͐����I�m���ʂƐ����ւ��Ă���(Bennett et al. 1996�GHoltz-Bacha & Norris 2001)�ANHK�����̗�O�ł͂Ȃ�(Collet & Kato 2014)�B�܂��A�k���Ȃnj��������ɂ��n�[�h�j���[�X�̋����ʂ��������ł͐����I�m���ʂ̃x�[�X���C�������������łȂ��A�����I�S�̍����l�ƒႢ�l�̊Ԃł̒m���M���b�v��������(Iyengar et al. 2010)�B�܂�A���������𒆐S�Ƃ���e���r���A�����I�m���̋��L�ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���B
�܂��A�m�������łȂ��A�������ݏd�v�Ȗ��ł��邩�Ƃ����A����ϓI�ȃ��A���e�B��A���ɂ���Đ��������f�����ׂ����Ƃ�����̋��L�ɂ����Ă��}�X���f�B�A�͑傫�ȗ͂����Ă����B�c��ݒ���ʌ����́A�ʂ̑������_�قǐl�X�̑��_�d�v�x�F�m�������Ȃ邱�Ƃ������A���̌��ʂ͑��_���̂ɓ��݂���d�v�������ʂ��̂��̂ɋN�����Ă��邱�Ƃ���������Ă���(Pingree & Stoycheff 2013)�B����ɁA�c��ݒ���ʌ������甭�W�I�Ɍ��o���ꂽ���f�B�A�v���C�~���O���ʂ́A�ʂ̑������_�قǐl�X�̔F�m�I�A�N�Z�V�r���e�B�����܂邽�߁A�哝�̂����]������ۂ̊�Ƃ��ėp�����₷���Ȃ邱�Ƃ������Ă���(Iyengar�A Peters�A & Kinder 1982�GIyengar�A Kinder�A Peters�A & Krosnick 1984)1)�B ��������Љ�ɍL���s���킽��}�X���f�B�A�̕ʂ��l�X�̔F�m�ߒ��ɉe�����邱�ƂŁA���_�d�v�x�F�m��Ɛѕ]��������L����邱�Ƃ������Ă���B
����ɁA�}�X���f�B�A�͒��ق̗������_�����肵���u�����v�튯�v��1�Ƃ��ċ@�\���A���_������X�p�C���^�r���[�Ȃǂ̃G�O�[���v���[�̒�ʂ��Ĉӌ����z�̔F�m�̋��L���x���Ă���(Noelle-Neumann 1984�GBrosius & Bathelt 1994)�B���鑈�_�Ɋւ��Č��ݑ����h���߂Ă���͎̂^���ӌ��Ȃ̂��A����Ƃ����Έӌ��Ȃ̂��B���������ӌ����z�̔F�m�̋��L�����_�̕ω��̂��������ƂȂ�̂ł���B�����ɁA�����Ƃ͈قȂ�ӌ������l���ǂ̂悤�Ș_���Ɋ�Â��Ă��������ӌ���\�����Ă���̂��Ƃ����n�l�^�����`�̓y��ƂȂ�F�m�ɂ����Ă��A�}�X���f�B�A���ʂ����Ă��������͑傫���BMutz & Martin(2001)�ɂ��A�}�X���f�B�A(���ɐV��)�̓p�[�\�i���R�~���j�P�[�V���������͂邩�Ɉَ��ȏ��ւ̐ڐG�𑣐i���Ă���B���̌��ʂ́A���������}�X���f�B�A�̕ɂَ͈��ő��l�ȏ�����܂܂�Ă���A����ɓ��퐶���ɂ����鐭���I��b�Ɣ�r���đI��I�ڐG��������]�n�����Ȃ����ƂɋN�����Ă���B
������������}�X���f�B�A�̉������Ɍ��o����Ă������ʂ̑����́A�����̐l�X���}�X���f�B�A�̒����r�I�����ȎЉ�I�����ɖ��ߍ��܂�Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă����B���Ƃ��c��ݒ���ʂ́A���_���Ƃ̕ʂ̏��ʂ��e�V���A�e���r�ǂ̊Ԃň�т��Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���B�}�X���f�B�A�̐������ʂ͂���قǑ傫���Ȃ��Ƃ���Ă�����(Klapper 1960)�A�}�X���f�B�A�ɂ���Ē������́u��b�̒ʉ݁v�ƂȂ�A�ΐl�R�~���j�P�[�V���������2�i�K�̗���ɂ���ĎЉ�I�e���͂����Ă���(Katz & Lazarsfeld 1955)�B�d�v�Ȃ̂́A�I�s�j�I�����[�_�[�ɂ���ę���]���I�ȉ��߂����������b�́u���l�^�v���̂̓}�X���f�B�A���甭�M������r�I�����ȏ��ł���A���I�s�j�I�����[�_�[�ƃt�H�����[�����̃g�s�b�N�ɂ��ĉ�b���\�ł�����x�ɂ͏�L����Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ��Ă���_�ł���B���̂悤�ɁA�}�X���f�B�A���߂��鏔���ʂ́A���ꂪ������ʂł���V���͌��ʂł���A�N���������ȎЉ�I�����Ɉ͂܂�Ă��邩�炱���Љ�I�ɗL�ӂȂ��̂Ƃ��Ď��ؓI�Ɍ��o����Ă����̂ł���B
�������A���̃}�X���f�B�A�����铯���ȎЉ�I�����Ƃ����O��́A���f�B�A���̑��l���ɂ���ėh�炬����B1980�N��ȍ~�P�[�u���e���r�����y���A1990�N��㔼�ɂȂ�ƃC���^�[�l�b�g�̕��y���n�܂�B�������A�P�[�u���e���r��ʂ��ď]���̃L�[�ǂ̕������������邱�Ƃ��ł��邵�A�l�b�g��ʂ��ĐV���L����ǂނ��Ƃ��ł���B���̈Ӗ��ł͑S���V�������f�B�A�ɂ���ĕs�A���ȕω����������킯�ł͂Ȃ�(���� 2011)�B�������A�ǂ̂悤�ȃ��f�B�A��I�Ԃ��A�����Ăǂ̂悤�ȃR���e���c��I�����邩�Ƃ����_�ɂ����āA�l�X����ɂ���I�����͉ߋ�20�N�Ԃɔ����I�ɑ��債�Ă����B
���̂��Ƃ�NHK���������������ɂ��u���{�l�ƃe���r�v�����̃f�[�^���猩�Ă݂悤�B�u���{�l�ƃe���r�v�����ł́A2000�N����2010�N�ɂ�����3��ɂ킽���Ď����\�Ȗ����e���r�ǐ���UHF��q���������܂߂Ė₤�Ă���2)�B���̕ω��͐}1�̂Ƃ���ł���B
�@�@�@�} 1�@�����\�Ȗ����e���r�`�����l�����̐���
2000�N�����10�N�Ԃɂ����āA5�`�����l���ȉ��̑I���������Ȃ��l��35������22���Ɍ��������B����A10�`�����l���ȏ�̑I����������l��21������47���ɑ����Ă���B�����L�[�ǂ̐����قڕs�ςł��邱�Ƃ��l����ƁABS������CS�����̎����ɂ���ă`�����l���̑I�����������Ă���ƍl������B����ɁA�����̕��������l�����A�^�悵���e���r�ԑg���u�����̂悤�Ɂv����l��2010�N��8���ł�������2015�N�ɂ�16���ɔ{�����Ă���B�n�[�h�f�B�X�N���R�[�_�[�̕��y�ɂ��A�������ԑg�����������Ɏ�������X�^�C�����L�����Ă���B�����܂ł��Ȃ��A�I�����̑���̓l�b�g�̕��y�ɂ���Ă���ɉ������Ă���B�l�b�g�ŐڐG�\�ȃR���e���c�͎����㖳����ł���A�l�X�͉��炩�̑I�D���x�[�X�ɉ{��������̂�I�тƂ炴��Ȃ��B���l�ȑI�D�����l�X�����ꂼ��D�݂̔ԑg��R���e���c��I�ю�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������߁A�}�X���f�B�A����������̓������ɉA�肪������悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B
�I�����̐��������������łȂ��A�l�X�͂��������}�X���f�B�A�ɐڐG���Ȃ��Ȃ����B2015�N�́u���{�l�ƃe���r�v�����́A���{�l�̃e���r�������Ԃ͒����J�n��1985�N�ȍ~���߂Č����ɓ]�������Ƃ���Ă���B����҂𒆐S�Ƃ��������Ԏ����ɑ傫�ȕω��͂Ȃ����A��N�w�𒆐S�Ɂu�قƂ�ǁA�S�����Ȃ��v�l��2010�N�ȗ��قڔ{�����Ă���B�V����ǂސl���������Ă���B2010�NNHK�����������Ԓ����ł́A���l�S�̂ɂ�����V���ڐG�̍s�җ�(1���̒��ŊY���̍s���������ł�(15���ȏ�)�����l���S�̂ɐ�߂銄��)�͕�����46���ł���A�ߔ��������荞��ł���B�������A�ˑR�Ƃ��ă}�X���f�B�A�͍ł��L�͂ȃI�[�f�B�G���X�Ƀ��[�`�ł��郁�f�B�A�ł���A�Љ�I���A���e�B�̋��L���x�������Ă���B�������A�Љ�I���A���e�B�����L�����u�}�X�v�̋K�͂͊m���ɏ������Ȃ��Ă���B���̂��Ƃ́A�}�X���f�B�A�̃��[�`�̏k�������łȂ��A�}�X���f�B�A��������́u��b�̒ʉ݁v�Ƃ��Ẳ��l�̌��������ݏo���Ă���B�Ă�2015�N�u���{�l�ƃe���r�v�����̌��ʂɂ��A�u�b��ɂȂ��Ă���ԑg�͌������Ǝv���v�Ɂu���Ă͂܂�v�Ƃ����l��e���r����u�l�Ƃ��������̘b�̃^�l��������v�Ɂu�����v���v�Ɠ������l�A�e���r���u�l�Ƃ̂�������[�߂���A�L�����肷�邤���ōł����ɗ��v�ƍl����l�͂������2010�N�ȗ��L�ӂɌ������Ă���BGamson(1992)�́A�t�H�[�J�X�O���[�v�����ŁA�}�X���f�B�A���瓾��ꂽ�����x�[�X�Ƃ�����b�ɂ���Đ����I�Ӗ����E���L���͈͂ŋ��L�����悤�ȃv���Z�X�̑��݂����o�������A���������v���Z�X�����X�ɂł͂��邪���藧���Ȃ��Ȃ����B
�l�X���e���̑I�D�Ɋ�Â��Č��������́A�ǂ݂������̂�����I�ю��ƁA�ڐG�p�^�[�������l�����A�I�[�f�B�G���X�َ̈��������傷��B���������V���������̒��ł́A�����̓�������O��Ƃ��Ă����}�X���f�B�A�̌��ʂ͎�܂�\��������B���߂ł́A�������������̕ω������_�`���ߒ��ɂǂ̂悤�ȉe����^���Ă���̂����ڂ������Ă݂悤�B
|
��2 �I�����̑��������������炷��
�l�X�����l�ȊS��I�D�Ɋ�Â��Č��������̂��������邱�Ƃ��\�ɂȂ�ƁA�}�X���f�B�A�̋c��ݒ���ʂ₻��ɔ����v���C�~���O���ʂ��キ�Ȃ�\��������B�}�X���f�B�A�͋���ȑ��u�Y�Ƃł�����A��ޖԂ����E�`���ݔ��ȂǑ�K�͂Ȑݔ����ێ����Ȃ��痘�v���グ�邽�߂ɕK�R�I�Ƀ}�X���^�[�Q�b�g�Ƃ���K�v������B����A�l�b�g���f�B�A�̗����グ�ɕK�v�ȏ��������̓}�X���f�B�A�Ɣ�r����ƒ��������Ȃ��A���̌��ʃj�b�`�ȃI�[�f�B�G���X��ΏۂƂ��邱�Ƃŗ��v���グ�邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���������āA�}�X���f�B�A�Ƃ͈قȂ�c���ݒ肵�Ă�����ɊS�����l�X�������x���݂���A�r�W�l�X�Ƃ��Đ�������B�ނ���A�I���^�i�e�B�u���f�B�A�Ƃ��ă}�X���f�B�A�Ƃ͈قȂ�c���ݒ肷�邱�ƂŁA�s��̃����O�e�[����_���헪���L���ƂȂ�ꍇ�����邾�낤�B���������}�X���f�B�A�̐ݒ肷��u�嗬�c��v�Ƃ͈قȂ�g�s�b�N�ɊS�����l�X�̊ԂőI��I�ڐG����ʓI�ɂȂ�ƁA�}�X���f�B�A���L���͈͂ŋc��̗D�揇�ʂ�ݒ肷�邱�Ƃ�����Ȃ邾�낤�B
Nie et al.(2010)�́A�T��3��ȏ�l�b�g�j���[�X���{������l�́A����ȉ��̐l�X�Ɣ�r����ƁA�d�v�ł���ƍl���鑈�_��q�˂钲�����ڂŁu���̑��v�̑I������A�d�v�x�F�m�̑S�̏��ʂ��Ⴂ���_��I�ԌX�����������Ƃ���Ă���B���̂��Ƃ́A�l�b�g�j���[�X���p�҂̓j�b�`�ȑ��_���d�v�ł���ƔF�m����X�����������Ƃ��������Ă���A�}�X���f�B�A�̋c��ݒ���ʂ��y�тɂ����Ȃ����Ƃ����\���Ɛ����I�ł���BTewksbury(2005)�́ANetRatings�Ђ̃l�b�g�{�����O�f�[�^�͂��A���Z�n�Ȃǂ̃f���O���t�B�b�N�ȗv����g�s�b�N�ɂ���ăj���[�X�I�[�f�B�G���X�����f������n�߂Ă��邱�Ƃ������Ă���3)�B�܂�A�X�l���S�����g�s�b�N��c��ɑI��I�ɐڐG���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������ƂŁA���f�������I�[�f�B�G���X�����ꂼ��قȂ�Љ�I���A���e�B�̒��ɐ�����悤�ɂȂ����B�ڂ������Ă������B
�P�[�u���e���r��l�b�g�̕��y�ɂ���ĉ\�ɂȂ�I��I�ڐG�ɂ͂������̃��x�����l������B�܂��A�R���e���c�̑I�D���x���ł̑I��I�ڐG������B���Ƃ��A�G���^�[�e�C�������g���D�ސl�̓G���^�[�e�C�������g�ɑI��I�ɐڐG���A�j���[�X���D�ސl�̓j���[�X�ɑI��I�ɐڐG����B���������R���e���c�x�[�X�̑I��I�ڐG���i�ނƁA�j���[�X�ɑ���S�̒Ⴂ�l���Ӑ}�����Ƀj���[�X�ɐڐG���邱�Ƃŕ��Y���I�ɐ����I�m�����l������@��ቺ���A���[�Q�����ቺ����B����A�����I�S��}�h���������l�̓j���[�X���`�����l����I�����C���j���[�X�ɑI��I�ɐڐG����Ȃǂ��Ă���ɐ����I�m���������A���[�Q�������i�����B���̌��ʁA�č��ł͂��������S��}�h���̋������[�҂ɃA�s�[�����邱�Ƃ̂ł���}�h���̋����c���قǓ��I����m�������܂�A�A�M�c��̋ɐ����̈���ƂȂ��Ă���(Prior 2007)�B
���ɁA�S�̂��鑈�_�Ɋւ�����ɑI��I�ɐڐG����A���_�x�[�X�̑I��I�ڐG���l������B�l�I�d�v�x�̍�������̑��_�ɋ����S�����l�X�̓C�V���[�p�u���b�N�ƌĂ�(Converse 1964)�A�Љ�ۏ�ɊS��������҂Ȃǂ��T�^�I�ł���B�l�b�g�̕��y�ɂ���ă}�X���f�B�A�ł͕���Ȃ��悤�ȏڍׂȏ���j���[�X�o�����[�̒Ⴂ�����Ȃǂɂ��A�N�Z�X�ł���悤�ɂȂ������߁A����C�V���[�p�u���b�N�̓l�b�g���g���Ă��[���m���邱�Ƃ��ł���B���̂��Ƃ́A�X�L�����_���Ȃǔ���ɕ肪���ȃe���r�j���[�X����͓����Ȃ��[��������Ƃ����_�ŁA�L���҂̐����Q���Ɛ����I�w�K�𑣐i���邩������Ȃ�(Iyengar et al. 2008)�B����ŁA�C�V���[�p�u���b�N�ɂ͋c��ݒ���ʂ��y�тɂ����A���}����ƂƂ����������I�G���[�g�����M��������I�ȃ��b�Z�[�W�ɂ��������ɂ����̂�(Zaller 2012)�A���_�̃_�C�i�~�N�X��}������\�����l������B
����ɁA���m�ȓ}�h����C�f�I���M�[�I�X���������f�B�A�����݂���ꍇ�A�L���҂����g�̓}�h���ƈ�v���郁�f�B�A�ɑI��I�ɐڐG����X��������(Stroud 2011)�B���Ƃ��A�č��ł͕ێ�I�ȃC�f�I���M�[�����l�ق�FOX News����������4)�B���������}�h�I�ȑI��I�ڐG�����܂�ƁA�}�h�Ԃł̊���I�ɐ��������܂�����A�����̋��L���j�Q�����\��������B���Ƃ��A2010�N�̕č����ԑI���O�ɂ́A��25���̐l���I�o�}�哝�̂̓C�X�������k�ł���ƐM���A���̗L���҂��L���X�g���k�ł��邱�Ƃɋ^���������Ă����Ƃ���(Hartman & Newmark 2012)�B�܂��A2003�N�ɃC���N�푈�Ɋւ��钲�����s����Kull et al.(2003)�ɂ��ƁA���Ȃ葽���̐l���u�C���N�푈�ő�ʔj�킪�������ꂽ�v�ȂǂƂ�����������F���������Ă���AFOX�j���[�X�̎����҂͍ł���F���̊��������������Ƃ����B���������}�h�I�I��I�ڐG�̓P�[�u���j���[�X�����ł͂Ȃ��A�u���O(Adamic & Glance 2005)�A�t�F�C�X�u�b�N(Bakshy�A Messing & Adamic 2015)�A�c�C�b�^�[(Conover et al. 2011)�Ȃǂł�������B�������A�}�h�I�ȑI��I�ڐG�͐����Q���𑣐i����Ƃ����|�W�e�B�u�Ȍ��ʂ������邱�Ƃ͒��ڂɒl����(Stroud 2011)�B
�܂��A���m�Ȉӌ����z�F�m�̋��L�̓}�X���f�B�A�ɂ���Ďx�����Ă������A���̓_�ɂ��Ă��ω���������\��������B���ق̗����̎��،����́A�����h�͕K��������ɑ����h�ɋ쒀�����킯�ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B�����h�͎��ɋǏ��I�ȑ����h���`�����邱�ƂŃn�[�h�R�A�����A�����h����̎Љ�I�e���ɒ�R������(���� 2006)�B�����ł͈ӌ����z�̔F�m�ƃn�[�h�R�A���Ƃ����ϓ_����A�\�[�V�������f�B�A�̉e���ɂ��ĐG��Ă������B
�ߔN�܂��܂������̐l�X���\�[�V�������f�B�A��ʂ��ăj���[�X�ɐڐG����悤�ɂȂ���邪�A�����ŏd�v�ƂȂ�̂́u�F�B�v�ɂ���ċ��L�������ł���B�t�F�C�X�u�b�N�ł͔�r�I���A���Ȑl�ԊW�Ɋ�Â����l�b�g���[�N���`������邪�A���A���Ȑl�ԊW�͓��ތ������琭���I�ӌ��̓�����������(Huckfeldt & Sprague 1995)�B�������������I�ɓ����ȑ��҂��u�V�F�A�v������͎����̐�L�ԓx�ƈ�v���Ă���m������������(Bakshy et al. 2015)�A�Љ�S�̂̒��ł͏����h�ł����Ă��A�\�[�V�������f�B�A��ł͂������������Ɠ����ӌ������l�������h���߂Ă���悤�Ɍ�����\��������B����A�c�C�b�^�[�ł͌��m��ʑ����j���[�X�A�J�E���g�ł����Ă��C�y�Ƀt�H���[�ł��邪�A�����ƈӌ���������l��I��I�Ƀt�H���[���邱�Ƃ��ł���B���������āA�����Ȑl�X�̃c�C�[�g��c�C�[�g�ɌJ��Ԃ��ڐG���邱�ƂŁA�I�t���C�����܂߂���W�c�ɂ����鎩���Ɠ����ӌ��̊������ߑ各�肳���\��������B���̂悤�ɑI��I�ڐG�ɂ���Ĉӌ����z�F�m���䂪�ނ��Ƃ́A�Љ�I���A���e�B�̋��L��j�Q���邩������Ȃ��B����A�����h�ł����Ă��\�[�V�������f�B�A��p���ăN���X�^���`�����邱�Ƃ��e�ՂɂȂ������ƂŁA�����h���n�[�h�R�A�����₷���Ȃ��Ă���\��������(�u���E���сE���� 2005)�B�O���[�o���Ȉӌ����z�������}�X���f�B�A�̐��_�����́A�u���_�ׂ邽�߂̕��@�ł���Ɠ����ɁA���ӂ����o�����߂̐����I���u(���� 2008�G96)�v�ł������B�ӌ����z�F�m�����L����ɂ����Ȃ�ƁA���l�Ȉӌ����c���������Ő��_�̃_�C�i�~�Y���������A���ӌ`��������ɂȂ�\��������B
�ȏ�ɘ_���Ă����悤�ɁA���f�B�A�ڐG�ɂ�����I�����̑����͏]���̃}�X���f�B�A���ʘ_�ɑ��ččl�𔗂��Ă���B�]���̃}�X���f�B�A���ʘ_�̓}�X���f�B�A�ւ̐ڐG��Ɨ��ϐ��Ƃ��A�l�X�̑ԓx��F�m���]���ϐ��Ƃ���t���[�����[�N��p���Ă����B�������A��L�ԓx��I�D�Ɋ�Â����I��I�ڐG�������Ȃ�ƁA���͂�f�B�A�ڐG�͓Ɨ��ϐ��ł͂Ȃ��A�ӌ���ԓx�ɂ���đI�ю����]���ϐ��Ƃ��đ���������K�ɂȂ邩������Ȃ��B���ɁA�ێ�I�ȃC�f�I���M�[�����l���ێ�I�ȃ��f�B�A�ɑI��I�ɐڐG����悤�ɂȂ�A���̐l�͐�L�ԓx�ƈ�v���������ɐڐG���邱�ƂƂȂ�A�ԓx�ω��̂��������͎����邾�낤�BBennett & Iyengar(2008)�͂��������V�������f�B�A���ʘ_�̃��f�������f�B�A�̍ŏ����ʘ_�Ɩ��t���Ă���(�}2)�B���̂悤�ȏł́A���}����Ƃ��}�X���f�B�A��ʂ����R�~���j�P�[�V�����ɂ���ėL���҂�������邱�Ƃ͒���������Ȃ�A���_���ߓx�ɍd��������댯�����B����ɁA�o�ώw�W�ȂNjq�ϓI�Ȏ����������L����ɂ����Ȃ�A�Ɛѕ]���Ɋ�Â������}�E�����Ƃ̃A�J�E���^�r���e�B�m�ۂ͂܂��܂�����Ȃ邩������Ȃ��B
�@�@�@�} 2�@�`���I�ȃ��f�B�A���ʘ_�ƃ��f�B�A�̍ŏ����ʘ_
�������A���ɎЉ�I���A���e�B���x����}�X���f�B�A�̗͂���܂����Ƃ��Ă��A���߂Ř_����悤�ɐ��}����ƂƂ����������I�G���[�g�͈ˑR�Ƃ��ă}�X���f�B�A��ʂ��ėL���҂ƃR�~���j�P�[�V��������炴��Ȃ��B�����I�G���[�g����L�����M���������I���b�Z�[�W���������_�̃_�C�i�~�Y���ݏo���Ƃ���Zaller(1992)�̋c�_�Ɉˋ�����A�\�[�V�������f�B�A��ʂ����L���҂Ƃ̐V���ȃR�~���j�P�[�V�����`�����l�������܂ꂽ�Ƃ��Ă��A�����I�G���[�g�����_�`���ߒ��ւ̃C���v�b�g��i�Ƃ��ă}�X���f�B�A�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B���ɁA�ߋ����\�N�̊Ԃɓ��{�ł͐��}�ƗL���҂̃����P�[�W����܂�A�����I�G���[�g���L���҂ƃR�~���j�P�[�V�������Ƃ��i�Ƃ��Ẵ}�X���f�B�A�̖����͂ނ���傫���Ȃ��Ă���5)�B���߂ł́A���_�`���ɉʂ����}�X���f�B�A�̗̗͂h�炬�ƁA�ɂ�������炸�}�X���f�B�A�ɂ���Ɉˑ�������Ȃ������I�G���[�g�Ƃ̂��߂����������������炷�̂��ɂ��Č��Ă������B
|
��3 ���f�B�A�|���e�B�N�X�̑䓪�ƃ}�X���f�B�A�ɑ���M���̒ቺ
�Љ�������`���}�X���f�B�A�̓Ɛ�I�Ȓn�ʂɕω�������������1990�N��ȍ~�A���{�ł͑I�����x���v�Ɛ����������x���v�𗼗ւƂ��鐭�����v�ɂ���Đ��}���L���҂Ƃ̒��ړI�Ȑړ_�����X�Ɏ����ɂ�A�}�X���f�B�A��}��ɂ��ėL���҂ƊW�����X�������܂���(���� 2012�G���k 2012)�B���I���搧�̉��ł͓}�����C�o���Ƌ������邽�߂ɋ��łȌ㉇���x���c�̂��K�v�Ƃ��ꂽ���A�V���ȏ��I���搧�̉��ł͂����������}�ƗL���҂ڌ��т����g�D����̉����A���}�͑I���ɂ�鐭���l�������㖽��Ƃ���c�����}�ւƕϗe������(���k 2012)�B�܂��A�����̑升���ɂ��n���c�����̌����ɂ���āA���}���n���ŗL���҂�����͎͂�܂��Ă���B�����ɖ��}�h�w�̊g�傪�i�݁A�u���̂ǎx���v(���{ 2006)�Ƃ��Ă�闬���I�Ȑ��}�x���ԓx�����L���҂��I���̐��������肷��X�������܂����B�����������}�h�w�͑I���̂��тɃ}�X���f�B�A��ʂ��ē`������}��̃C���[�W��X�L�����_���ɋ����������邽�߁A���}���́u�I���̊�v�Ƃ��Ă̓}��̃C���[�W���d������X�������߂��B����ɁA�}�X���f�B�A�̑����\�t�g�j���[�X��C���t�H�e�C�������g�Ȃnj�y�I�v�f�̋��������j���[�X�ɂ���Ď��������҂��X�������߁A����Y���t�Ō���ꂽ�悤�ɐ��}�E�����Ƒ��̍L��헪�ƃ}�X���f�B�A�̕X�^�C�������݈ˑ��I�ȕω�����������B��������1990�N��ȍ~�̕ω��́A�������v����吭�}�𒆐S�Ƃ���p�[�e�B�[�|���e�B�N�X (���}����)��ڎw�����̂Ƃ͗����ɁA�ނ�����{�����̓��f�B�A�|���e�B�N�X(���f�B�A����)�Ȃ����e���|���e�B�N�X(�e���r����)�̐��i�����߂Ă���悤�ɂ�������(��� 2003)�B���Ƃ��AJou & Endo(2015)�́A���}���[�_�[�ɑ���]���Ɠ��[�̑��ւ��ߔN���܂��Ă���A���̑��ւ͎����j���[�X�ԑg���̑����l�قNj������Ƃ����o���Ă���B�p�[�\�i���C�Y���ꂽ���������[�s���ɗ^����C���p�N�g�������Ă��邱�Ƃ���������m���Ƃ����悤�B
����A�O�߂܂ŊT�ς��Ă����悤�ɁA���_�`���ߒ��ɂ�����}�X���f�B�A�̉ʂ��������͏��X�ɂł͂��邪�h�炬����B�����O���[��s�ݎғ��[�̐��x�I�ω��ɂ���đI���ɂ������d�𑝂����s�s���L���҂́A��Ƃ��ăl�b�g���d������X���������A�}�X���f�B�A��ʂ����������ʂ���r�I�����ɂ����L���҃Z�O�����g�ł�����B�܂��A�O�q�̃��f�B�A�̍ŏ����ʘ_���_����悤�ɁA�l�b�g�ɂ�����I��I�ڐG�̓}�X���f�B�A�̐������ʂ�������\���������Ă���B�������A���}����Ƃ����f�B�A�|���e�B�N�X�̒��ŗL���҂Ƀ��[�`���邽�߂ɂ́A�ˑR�Ƃ��ă}�X���f�B�A�Ɉˑ�������Ȃ��B�����ŁA�I���ɂ����铖�I��L���҂̐�����ڎw�������I�G���[�g�́A�ł��邾�������̗��v�ɂ��Ȃ��悤�Ƀ}�X���f�B�A���R���g���[���������Ƃ����U�������B�������A�}�X���f�B�A�͕K�����������I�G���[�g�̈ӂ̂܂܂ɂӂ�܂��킯�ł͂Ȃ�(Zaller1999)�B�����I�G���[�g���L���҂ɓ͂��悤�Ƃ��郁�b�Z�[�W�̓}�X���f�B�A�ɂ���ĕҏW����A�Z���T�E���h�o�C�g�݂̂��L���҂ɓ͂�����B�����ɐ����Ƃ��}�X���f�B�A�ɑ��ĕs��������f�n�����܂�A�����Ƃɂ��}�X���f�B�A�ᔻ��������B�������ꂽ�����Ƃ��u���f�B�A�ɔ����̈ꕔ�����ꂽ�v�ƕs����\������̂͒��������Ƃł͂Ȃ��B�܂Ƃ߂�ƁA���_�`���ߒ��ɂ�����}�X���f�B�A�̖����͗h�炬�������ŁA���}����Ƃ͗L���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂ����ă}�X���f�B�A�Ɉˑ�����X�����ނ��닭�߂Ă���B�������A�}�X���f�B�A���ӂ̂܂܂ɃR���g���[�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����߁A�����Ƃ��}�X���f�B�A�ɑ��Ĕᔻ�I�Ȍ������J��Ԃ��f�n�����܂��B���̂��Ƃ͂ǂ̂悤�ȋA���������炷���낤���B�����ł͕č��ł̌�������Љ�悤�B
Ladd(2012)�́A1970�N��ȍ~�ɕč��Ō���ꂽ�}�X���f�B�A�ɑ���M���̑啝�Ȓቺ�ɒ��ڂ��A���̌����Ƃ��Đ����Ƃɂ�郁�f�B�A�ᔻ�ƃ��f�B�A�Y�Ƃɂ����鋣���̌������w�E���Ă���B�����̂����ꂽ�W���[�i���X�g��y�o����1950 �` 60�N��̃}�X���f�B�A�̓v���t�F�b�V���i���ȃW���[�i���Y���ɂ���Đl�X���獂���M�����l�����Ă������ALadd�ɂ�����͗��j�I�ɂ͗�O�I�Ȏ����ł������Ƃ����B�܂��A���̎����̓��f�B�A�Y�Ƃɑ���K�������������̃��x�����Ⴍ�ۂ���Ă������߁A�I�[�f�B�G���X�l���̂��߂ɃZ���Z�[�V���i���Y���ɑ���K�v�����Ⴉ�����B����ɁA�����̕č��̐��}�V�X�e���͌��݂Ɣ�ׂċɐ������Ă��炸�A�����Ƃ����g�ɑ��Ĕᔻ�I�ȃ��f�B�A���U�����邱�Ƃ���r�I�܂�ł������B�������A�����������������藧���Ȃ��Ȃ�ƁA�}�X���f�B�A�ɑ���M����1990�N��ɂ����đ傫���ቺ���Ă������B�܂��AParty Sorting �ƌĂ��}�h���ƃC�f�I���M�[�̑��ւ̏㏸�ɂ���ċ��a�}�Ɩ���}�̃C�f�I���M�[�I�ɐ�����1970�N��ȍ~�i��ł�����(Fiorina & Abrams 2008�GHetherington 2009)�B����ɁA1980�N��ȍ~�̐V���R��`�I���v�ɂ���ă��f�B�A�̋K���ɘa���i�݁A���f�B�A�Y�Ƃɂ����鋣�����������Ă������B���̌��ʁA���݂ł͂����Ζ���}�̐����Ƃ�FOX�j���[�X�ȂǕێ�h���f�B�A��ᔻ���A���a�}�̐����Ƃ����C���X�g���[�����f�B�A�̕��e�����x�����ɕΌ����Ă���Ɣᔻ���Ă���B�܂��A�����̌����̓j���[�X�̎��̒ቺ�������A���Ƀ��[�J���j���[�X�͔ƍ߂�X�L�����_���Ȃǒ�R�X�g�Ŏ������̉҂����Ƃ̂ł���R���e���c�ɏW�����A������u��ӂւ̋����v�������Ă���(Hamilton 2004)�B
�������������Ƃɂ��}�X���f�B�A�ᔻ�Ƌ����̌����A����ɔ����j���[�X�̎��̒ቺ�ɂ���Đl�X�̃}�X���f�B�A�ɑ���M��(�ȉ��A���f�B�A�M��)���ቺ����Ƃ����č��ɂ�����m���́A���݂̓��{�ɂǂ̒��x���Ă͂܂邾�낤���BNHK�ɂ��u���{�l�ƃe���r�v�����Łu������ �M���ł���v���f�B�A�Ƃ��ăe���r���������l�́A2010�N��37������2015�N��39���ւƂقƂ�Ǖω����Ȃ�6)�B�܂��A���E���l�ϒ����Ō��Ă��A���{�l�̃e���r��V���ɑ���M���͐��E�e���Ɣ�r���Ă��Ȃ荂��7)�A�܂��V����M������l�̊�����75����A�e���r��M������l�̊�����70�����1995�N�ȗ����肵�Ă���B���������āA�������\�N�̊ԂɃ}�X���f�B�A�ɑ���M�����}���ɒቺ�����Ƃ��钼�ړI�ȏ؋��͂Ȃ�8)�B�������A�S�̓I�ȐM�����̕]���ł͂Ȃ��A���ʓI�ȕ]�������Ă����Ɩ����ł��Ȃ��ω���������B�u���{�l�ƃe���r�v������2010�N�܂ő��肳��Ă����u�}�X�R�~���`���Ă��邱�Ƃ́A�قڎ����ǂ��肾�Ǝv���v�Ƃ��������ɑ���^�ۂł́A�u�����v���v�Ƃ���l�̊�����1985�N��37������2010�N��26���܂ł��₩�ł͂��邪��т��Ēቺ���Ă���(�����E���c�E�r�q 2010)�B�܂��A��������2010�N��2015�N�ɂ����đ��肳�ꂽNHK�ɑ���]���̂����A�u�ԑg�������E�����ł���v�ƍl����l��24������20���ɒቺ���Ă���9)�B�����Ƃɂ��}�X���f�B�A�ᔻ�������X���ɂ��邩�ǂ����ɂ��Ă̓f�[�^�������Ă��Ȃ����ߖ��炩�ł͂Ȃ����A���Ƃ��ߔN�ł͒����V���̉ߋ��̈Ԉ��w�֘A�ɑ��Ĉ��{���ᔻ���s�������Ƃ͋L���ɐV�����B���ہA�����V���͌���̌�Ɂu�M���ƍĐ��̂��߂̈ψ���v�𗧂��グ�Ă���A�ǎ҂̐M��������ꂽ���Ƃ�F�߂Ă���B���̂悤�ɁA�}�X���f�B�A�S�̂ł͑啝�ȐM���ቺ�͌����Ȃ����A���e�̐��m���⒆�����ɑ��Ă͏��X�Ƀl�K�e�B�u�ȕ]���������Ă���A�w�i�ɂ͌X�̃��f�B�A�̌����₻��Ɋ֘A���������Ƃ̔ᔻ�ȂǗl�X�Ȍ������z�肳���10)�B���{�ɂ����郁�f�B�A�|���e�B�N�X�̌���Ƒ��l�����郁�f�B�A�s��ł̋����̌������l�����11)�A�����I�ɂ͓��{�ɂ����Ă��}�X���f�B�A�ɑ���M���͏��X�ɒቺ���Ă����\���������Ǝv����B�ł́A���f�B�A�M�����ቺ����Ƃǂ̂悤�Ȃ��Ƃ�������̂��낤���B
|
��4 �}�X���f�B�A�ɑ���s�M�������炷����
�O�q��Ladd(2012)�́A�����Ƃɂ�郁�f�B�A�ᔻ�Ƌ����̌����ɂ���ă��f�B�A�M�����ቺ�������Ƃɂ���āA�c��ݒ���ʂ�v���C�~���O���ʁA�t���[�~���O���ʂ������ɂ����Ȃ�\�����w�E���Ă���B�����̃��f�B�A���ʘ_�̓}�X���f�B�A���M�ߐ��̍��������L���Љ�ɒ��邱�ƂŎЉ�I���A���e�B�̋��L���x���Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă����B���Ƃ��c��ݒ���ʂ������悤�ɁA�l�X�̓}�X���f�B�A��������Ɉ��̐M����u���Ă��邩�炱���A���̕ʂɏ]���đ��_�d�v�x�F�m�����Ă����킯�ł���B�������A���f�B�A�ɑ���M�����ቺ����ƁA���͂�}�X���f�B�A�͎Љ�I���A���e�B�𐧓x�I�ɒS�ۂ�����̂Ƃ��Ă݂Ȃ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���f�B�A�ɑ���M�����Ⴂ�l�قǁA�}�h�I�ȃP�[�u���j���[�X��u���O�Ȃǂ̃I���^�i�e�B�u���f�B�A�ւ̐ڐG�������A���������}�h�I�ȃI���^�i�e�B�u���f�B�A�̓}�X���f�B�A���������ᔻ���邪�䂦�ɂ���Ƀ��f�B�A�M�����ቺ����Ƃ������z�����݂���B�܂��A���f�B�A�M���̒Ⴂ�l�̓}�X���f�B�A������o�ϏȂǂ̋q�ϓI�Ȏw�W�Ɋ�Â��ē��[����X�����キ�A���g�̓}�h�����L�ԓx�Ɋ�Â��ē��[����X�������܂�B�܂�A�}�X���f�B�A�������M���ł��Ȃ����䂦�ɁA�����̌��X�����Ă���ӌ���ԓx�����ɂ���ăA�b�v�f�[�g���ꂸ�A��L�X�������̂܂ܓ��[�ɒ������Ă��܂��̂ł���B
���̂悤�ɁA�}�X���f�B�A�ɑ���M�����ቺ���A�u�ǂ����ǂ�ȃ��f�B�A���R���肾�v�Ǝv���l��������̂͊댯�ł���BZaller(1992)�́A�����I�������̍����l�قǎ���̃C�f�I���M�[�I�X���ƈ�v���Ȃ������I���b�Z�[�W�ɒ�R���������Ƃ������Ƃ��ė��_��g�ݗ��ĂĂ���B�������A�C�f�I���M�[�I�ɑΗ����郁�b�Z�[�W�����łȂ��A���������}�X���f�B�A�̒����̂�M���ł��Ȃ��Ƃ���A�����I����������r�I�Ⴂ�l�X�ł��ԓx�ϗe�ɒ�R�������悤�ɂȂ邾�낤�BZaller(1992)�̃��f���ł͐����I�������������x�ł���l���ł������I���b�Z�[�W�ɔ������₷���A���_�̃_�C�i�~�Y���ݏo���j�ƂȂ�ƍl����ꂽ���A���������l�X���ԓx�ϗe�ɒ�R�������悤�ɂȂ�ƁA���_�`���ߒ����d�������邱�ƂɂȂ��肩�˂Ȃ��B
���{�ł̓��f�B�A�M���̓��e���ڍׂɕ��͉\�ȑ�\���̍����f�[�^�͂قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ����A�M�҂炪2014�N�Ɏ��{�����I�����C�������ł͋����[�����ʂ������Ă���12)�B���̒����͑S����20�Έȏ�59�Έȉ���Ώۂɐ���(�j��)�ƔN��(20��E30��E40��E50��)��g�ݍ��킹��8�Z���̐l�����ϓ��ɂȂ�悤�ɉ�����ꂽ(N��1�A032)�B���̒��ŁA�}�X���f�B�A�ɑ����ȋ^�S�Ǝ�ϓI���f�B�A���e���V�[�𑪒肷�鍀�ڂ�V���ɍ쐬���A�f�[�^�����W�����B�}3�̏ォ��3���ڂ��}�X���f�B�A�ɑ����ȋ^�S���A����5���ڂ���ϓI���f�B�A���e���V�[�𑪒肷�邱�Ƃ��Ӑ}���Ă���B�}���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�}�X���f�B�A�ɑ����ȋ^�S�A���Ȃ킿�s�M�͂��Ȃ荂���A������̍��ڂł��m��I��(�u�����v���v�Ɓu��₻���v���v�̍��v)�͉ߔ������Ă���B����A��ϓI���f�B�A���e���V�[�̓}�X���f�B�A�ɑ����ȋ^�S�Ɣ�r����ƍm��I�����Ȃ��B�܂�A���̃T���v���Ɍ��肵�Č����A���f�B�A�ɑ���s�M�̃��x���͍������Ӑ}�I�ȑ����M�ߐ��̒Ⴓ����������قǂ̃��e���V�[������Ă���Ƃ͍l�����Ă��Ȃ��B����ɁA�}3�̏ォ��3���ڂ�p���ă}�X���f�B�A�ɑ����ȋ^�S(����0.83)�̎ړx��P�����Z�ɂ���č쐬���đ��̕ϐ��Ƃ̊֘A�ׂ�ƁA�����S�̍����l�قǃ}�X���f�B�A�ɑ����ȋ^�S������(r��0.18�A p��0.01)�A����ɐV����ǂ�ł��邩�ǂ����Ƃ͑��ւ��Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ���(r��0.03�A n.s.)�B�����S�̍����l�قǃ��f�B�A�ɑ��鐭���Ƃɂ��ᔻ�I���b�Z�[�W�ɂ��ڐG���₷���A����Ƀ\�[�V�������f�B�A��܂Ƃ߃T�C�g�Ȃǂ̃I���^�i�e�B�u���f�B�A�̗��p�����������߁A�}�X���f�B�A�ɑ���s�M���������Ă�悤�ȏ��ւ̐ڐG�����i�����̂�������Ȃ�13)�B�������A���������ȋ^�S�͐V����ǂނ��Ƃɂ���ĉ�������Ă��Ȃ��B�ȋ^�S���Ⴂ�l�قǐV����ǂނƂ����W������ꂸ�A�}�X���f�B�A�ɐڐG���Ă���l�ł����Ă��s�M��������̏����ᖡ���Ă���p������������B
�@�@�@�} 3�@�}�X���f�B�A�ɑ����ȋ^�S�Ǝ�ϓI���f�B�A���e���V�[
|
��5 ���ꂩ��̃}�X���f�B�A�Ɛ��_�`��
���f�B�A���ɂ�����I�����̑����́A�R���e���c�I�D�⑈�_�d�v�x�F�m�A�}�h���Ƃ������l�X�ȗv���ɂ��I��I�ڐG�𑣐i���A�}�X���f�B�A���̏����x�[�X�Ƃ����Љ�I���A���e�B�̋��L������ɂ���\��������B�l�X���u���܉����d�v�ȑ��_�ł���̂��v�Ƃ����F�m��u�ǂ̂悤�ȑ��_����Ɍ�������]�����ׂ����v�Ƃ�����A�u���܂��̑��_�ő����h�Ȃ͎̂^���ӌ��Ȃ̂����Έӌ��Ȃ̂��v�Ƃ������ՓI�������L�ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ���A�}�X���f�B�A���Љ�̍��ӌ`�����T�|�[�g���Ă����͎͂�܂��Ă������Ƃ��\�z�����B����ŁA�t���I�ł͂��邪���{�����̓��f�B�A�|���e�B�N�X�̐��i�����߂���A���}����Ƃ͗L���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂ����ă}�X���f�B�A�ւ̈ˑ������߂邪�䂦�ɁA�}�X���f�B�A�ɑ���ᔻ��R���g���[�������߂�U�������܂��Ă���B�����������Ń}�X���f�B�A�ɑ���M�����ቺ����ƁA�O�I���̕ω��ɓK���������_�̕ω��⍇�ӌ`��������ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�������A�������������������ɖK���킯�ł͂Ȃ��B2015�N�́u���{�l�ƃe���r�v�����Łu���̒��̏o�����⓮����m�邤���ł�������ɗ����f�B�A�v�Ƃ��ăe���r��I�������l��65���ł��邪�A�l�b�g��17���ɉ߂��Ȃ�(�V����14��)�B�܂��A�u������Љ�̖��ɂ��čl���邤���ł�������ɗ����f�B�A�v�Ƃ��ăe���r��I�������l��55���ł��邪�A�l�b�g�͖���9�����x�ł���(�V����28��)�B�ˑR�Ƃ��ĎЉ�I���A���e�B�𐧓x�I�Ɏx���Ă���̂̓e���r�𒆐S�Ƃ���}�X���f�B�A�ł���A���_�`���ɂ�����}�X���f�B�A�̖������ڂɌ����ďk�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������A���f�B�A���̕ω����ӂ܂��Ċ����̗��_�̏C�����K�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͊m�����낤�BBennett & Manheim(2006)�́A�I��I�ڐG�ɂ���ăI�[�f�B�G���X�����f������A�p�[�\�i���C�Y���ꂽ�����}�[�P�e�B���O�̃^�[�Q�b�g�ƂȂ郁�f�B�A���ł́A�I�s�j�I�����[�_�[���e���͂��ł���]�n�͏��Ȃ��A�u�R�~���j�P�[�V������1�i�K�̗���v��������\�����w�E���Ă���B�]�O�ǂ���́u�R�~���j�P�[�V������2�i�K�̗���v���ێ������Ƃ��Ă��A�O�q�̂悤�ɐ����I�S�̍����I�s�j�I�����[�_�[�͂ނ���}�X���f�B�A�ɑ���M�����Ⴂ���߁A�\�[�V�������f�B�A��܂Ƃ߃T�C�g�Ȃǂ̃I���^�i�e�B�u���f�B�A�ɂ��ڐG���邾�낤�B�I���^�i�e�B�u���f�B�A�̏��͕K�������M�ߐ��������͂Ȃ����߁A�I�s�j�I�����[�_�[�̎Љ�I�e������t�H�����[�̎Љ�I���A���e�B�ɂ����̃o�C�A�X��������\��������B
����AHolbert�A Garrett�A & Gleason(2010)�́A�����I�Ƀ}�X���f�B�A���̏��́A�\�[�V�������f�B�A������V�����`�́u2�i�K�̗���v����ĎЉ�ɍs���킽��Ǝ咣���Ă���B�\�[�V�������f�B�A�Ō����g�s�b�N�̑����̓}�X���f�B�A���̏��ł��邪(Kwak et al. 2010�GLeccese 2009)�A�����ł̓t�H�����[�Ƃ̒��ڂ̖ʎ��������Ȃ��\�[�V�������f�B�A���̃I�s�j�I�����[�_�[�������c�_�����[�h���Ă���(Himelboim�A Gleave & Smith 2009)�B���Ȃ킿�A�����̐l�ԊW���x�[�X�Ƃ����]���^�̃I�s�j�I�����[�_�[�ɂ��ΐl�I�e���ł͂Ȃ��A�\�[�V�������f�B�A����ĂȂ��������傫�ȏW�c�������I���b�Z�[�W�̃t�B���^�����O�@�\���ʂ�������B���̂悤�ȃl�b�g�������K�͂ŏW���I�ȃR�~���j�P�[�V�������A�}�X���f�B�A���̏����x�[�X�ɎЉ�I���A���e�B�̋��L�ɂǂ̂悤�Ȗ�����S���̂����A����̐��_�`���ߒ��ɂ����ďd�v�Ș_�_�ƂȂ邾�낤�B |
����
1)�������ALenz(2009)��Miller & Krosnick(2000)���A�N�Z�V�r���e�B�q���[���X�e�B�N�X�Ɋ�Â����f�B�A�v���C�~���O���ʂ̐����ɋ^��𓊂������Ă��邱�Ƃɒ��ӂ���K�v������B
2)���̃f�[�^�́A2010�N�܂ł̌l�ʐږ@�����̃f�[�^�ł���B2015�N�����ɂ͖{���ڂ͊܂܂�Ă��Ȃ��B
3)���̎咣�ɑ��锽�_�Ƃ��āAWebster & Ksiazek(2012)���Q�ƁB�j���[�X�I�[�f�B�G���X�̕��f���Ɋւ��郌�r���[�Ƃ��āAOwen(2012)���Q�ƁB
4) FOX News�͕ێ�I�ȃo�C�A�X�����ƌ����Ă���B�܂��A�I��I�ڐG�Ƃ͋t�ɁAFOX News�ɐڐG���邱�Ƃŕێ�I�ȃC�f�I���M�[�����܂�Ƃ����������ʂɂ��Ă�DellaVigna & Kaplan(2007)���Q�ƁB
5)�������A����̓l�b�g����������R�~���j�P�[�V���������������邾�낤���A���݂̂Ƃ��됭���I�G���[�g�ƗL���҂̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V������i�Ƃ��ăl�b�g���傫�Ȗ������ʂ����Ă���؋��͂Ȃ��B
6)�e���r�ǂ���ѐV���Ђɑ���M���ɂ��ẮA�{���̈(2016)���Q�ƁB
7)����́A�u���ɐM������v�u���M������v�u���܂�M�����Ȃ��v�u�S���M�����Ȃ��v�u�킩��Ȃ��v�̑I�������p����ꂽ�B
8)�Ȃ��A���̂��Ƃ͕č���؍��ł����Ă͂܂�B�č��ł�1970�N����90�N��ɂ����ă��f�B�A�M���͒ቺ�������A���̌�͒Ⴂ���x���ň��肵�Ă���B�؍����A���{���͐M���̃��x���͒Ⴂ���̂́A60�����x�̐l���}�X���f�B�A��M�����Ă���B
9)�����NHK�ɑ���]���Łu��y�ԑg�ɖʔ������̂�����v��11������14���ɏ㏸���Ă���B�t�ɁA�����ɑ���]���ł́u�ԑg�������E�����ł���v�Ƃ����]����4������5���ɏ㏸�A�u��y�ԑg�ɖʔ������̂�����v��60������56���ɒቺ���Ă���B
10)�������(2016)�́A���}�x�������f�B�A�M���Ƃقږ��W�ł��邱�Ƃ���A�u�����Ƃ����f�B�A��ᔻ���邱�Ƃ͂����Ă��A���̂��Ƃ��x���҂����ɂ����L����Ă͂��Ȃ��v�Ƃ��Ă���B
11)���Ƃ��A���{�̃I�����C���j���[�X���p�ň��|�I�������V�F�A���ւ�Yahoo!�j���[�X�́A�����̃j���[�X���f�B�A�Ƌ����W�ɂ��邾���łȂ��A�ߔN�ł̓X�}�[�g�t�H���o�R�ł̉{�����}�����Ă��邱�Ƃ���\�[�V�������f�B�A�ȂǑ��̃X�}�[�g�t�H���A�v���Ƃ������W�ɂ���B���̂悤�Ƀ��f�B�A�s��ɂ����鋣���́A�j���[�X���f�B�A�Ԃł̋�������A���Ǝ�̃A�v�����܂߂����L���v���b�g�t�H�[���ŏ���҂̒��ӂ�D�������u�َ�i���Z��v�Ɉڍs���Ă���Ƃ����悤�B
12)���̒����͊m�����o�ł͂Ȃ��I�����C�������ł��邽�߁A�����Ȃ閾�m�ɒ�`�\�ȕ�W�c����\���Ă��Ȃ��_�ɒ��ӂ���K�v������B�����I�Ƀ����_���T���v�����O�����ɂ����̍��ڂ��܂܂�邱�Ƃ��]�܂����B�{�����́A���ѓN�Y(�������w������)�A���j��(�_�ސ��w)�A��؋M�v(����������w�@��w)�ɂ���Ď��{���ꂽ�B
13)�����S�̍����l�قǃ��f�B�A�M�����Ⴂ���Ƃ́A�����_���T���v�����O�����f�[�^��p�����{���̈(2016)�ł���т��Ď�����Ă���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���}�X�R�~�̏��ƍ����匠�@2010/3
|
��1�D�͂��߂�
�M�҂́A����܂Ŏ�Ƃ��Č��@�w�I�Ȋϓ_����A������}�X�R�~(�e���r�A�V���A���W�I�Ȃ�)�������炷��X�̎Љ�I���Q���������邽�߂ɂ́A�ǂ̂悤�Ƀ}�X�R�~���K�������炢���̂����l�@���Ă����B�{�e�ł́A����ۗ̕L����c��ȏ��ӓI�ɑ��삵����A���U�̏�����o�����肷�邱�Ƃɂ��A���炪�]�ސ��_������`��������A�������\���x�����肷�铙�Ƃ������}�X�R�~�̕��Q�ɏœ_�����āA���̖��_�������Ă����B���Ȃ킿�A��q����悤�ɁA�}�X�R�~�͌���Љ�ɂ����ėl���܂ȋ@�\���ʂ����Ă��邪�A���̋@�\�̒��ōł���{�I���d�v�Ȃ̂́A�����܂ł��Ȃ��̋@�\�ł���B�������}�X�R�~�̕@�ւƂ��Ă̖����ɑ傫�Ȋ��҂��Ă��邱�Ƃ́A�ے肷�ׂ����Ȃ������Ȃ̂ł���B�������A�}�X�R�~�̕A�Ƃ�킯�����Ɋւ���ɂ����āA���̂悤�ȏ�삪�s����Ȃ�A���@�̊�{�������鍑���匠(���@�O���A1��)�������N�Q���ꂩ�˂Ȃ����ʂƂȂ�B���Ȃ킿�A�����̈ӎv�Ɋ�Â������Ƃ������O�͌`�[�����A������́g�}�X�R�~�̈ӎv�Ɋ�Â������h�ƂȂ��Ă��܂��̂ł���B�M�҂́A�ߎ��̃}�X�R�~�ɂ���삪���ƂȂ�������(�ڍׂ͌�q)������ɂ��A���̊댯����Ɋ����Ă���B���̂悤�Ȋϓ_���炵�āA�ł��T�d�Ȕz�����v�������̂��I���ł��邪�A���݂̓��{�ɂ����Ă͑I���ɂ����m�ȉ��I���[�����ݒ肳��Ă���Ƃ͌�����ɂ���B���̊댯������\���ɔF������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�m���ɁA�}�X�R�~�ɂ͍����̒m�錠��(���@21��1��)���[������Ƃ����g��������A�ő���Ɏ�ނ̎��R��̎��R(���@21��1��)�����ۏႳ���K�v������B�������A�����ɁA�}�X�R�~�ɂ͍����匠����������Ƃ����g��������̂ł���A�����I�ȕA���ɑI���ɂ��ẮA����}�ɔF�߂�킯�ɂ͂������A�^�̖��ӂ��\�o�����ׂ����̃��[�����K�v�ł��낤�B��������ӎ��ɗ����Ė{�e�ł́A��̓I�ɂ́A�܂������匠�̈Ӌ`���m�F������ŁA�����匠��N�Q�����˂Ȃ��}�X�R�~�̏��̎�������Ă����B�����āA���̖��_�m�ɂ�����ŁA�����匠�����̂��߂ɂ���ׂ����[�����l���Ă݂����B�g�}�X�R�~�̏�삪���@�̓����ɂ�����匴�����鍑���匠��N�Q���Ă���̂ł͂Ȃ����H�h�Ƃ������́A���@�w�̕���ɂ����Ă�����܂ł��܂薾�m�ɘ_�����Ă��Ȃ������_�_�ł���ƌ����A�{�e���[���w��I�c�_�̒[���ƂȂ邱�Ƃ��o�����Ȃ�]�O�̍K���ł���B�Ȃ��A�M�҂̑O��̘_���u�}�X�R�~�Ɛl���v���l���ɑ���}�X�R�~�̕��Q���e�[�}�Ƃ������̂ł������̂ɑ��āA�{�e�͓����ɑ���}�X�R�~�̕��Q���e�[�}�Ƃ��Ă���A���҂́A���@�ɑ���}�X�R�~�̕��Q�Ƃ����_�ŁA��̂̂��̂ƍl���Ă���B
|
��2�D�����匠�̈Ӌ`
�����匠(���@�O���A1��)�Ƃ́A�����̂�����͍ŏI�I�ɂ͈�l�ЂƂ�̍������匠�҂Ƃ��Č��肷��Ƃ��������̂��Ƃł���A��������A���������������ɂ��������ł���Ƃ��������̂��Ƃł���B���̓_�A����{�鍑���@(1889�m����22�n�N���z)�ɂ����ẮA�_��(�_�̈ӎv)�������ɓV�c�匠(���@1��)���Ƃ��A�V�c���������̑�����(�S�Ă̍��ƌ��͂̋A����)(���@4��)�Ƃ��Đ_���s�N(���@3��)�Ƃ���A����́u�b���v(�N��̔�x�z��)(���@18���ȉ�)�Ƃ���Ă����̂ƑΏƓI�ł���B�����匠�̋�̓I�Ӌ`���l����ɂ������ẮA�t�����X�v����(1789�N�`)�̃t�����X�Œ��ꂽ��̍����匠�T�O�����ڂɒl����B���Ȃ킿�A�i�V�I��(nation)�匠�ƃv�[�v��(peuple)�匠�Ƃ�����ł���B�O�҂̃i�V�I���匠�Ƃ́A�����匠�́u�����v�𒊏ۓI�E�ϔO�I����̂Ƃ��Ă̑S�����ƍl���A���ꎩ�̂Ƃ��ċ�̓I�Ȉӎv�E�����\�͂���������݂Ƃ͌��Ȃ��B����āA�������x�Ƃ��Ă͊Ԑ�(��\)���吧���A������A�����匠�͒P�ɍ��Ɠ����̐������̍����ɉ߂��Ȃ����ƂɂȂ�B��Ƃ��ẮA�t�����X��1791�N���@����������B����ɑ��āA��҂̃v�[�v���匠�Ƃ́A�����匠�́u�����v��l��(��̓I�ɂ́A�L���Ғc)�ƍl���A���ꎩ�̂Ƃ��Ċ����\�͂��������ۓI�ɔc���ł��鑶�݂ƌ���B����āA�������x�Ƃ��Ă͒��ږ��吧���A������A�����匠�͍����ɂ�钼�ړ����������F���邱�ƂɂȂ�B��Ƃ��ẮA�t�����X�l���錾(1789�N)��t�����X��1793�N���@����������B���̓_�A���{�����@�ɂ�����u�����匠�v�ɂ��ẮA�w���ɂ�葽���̕\����̍��ق͂�����̂́A1���Ƃ̌��͍s�g�𐳓��Â��鋆�ɓI�Ȍ��Ђ͍����ɑ�����Ƃ����Ӗ�(�����鐳�����̌_�@�B����̓i�V�I���匠�I���z)��2���̐����̂�������ŏI�I�Ɍ��肷�錠�͂��������g���s�g����Ƃ����Ӗ�(�����錠�͓I�_�@�B����̓v�[�v���匠�I���z)�Ƃ̗��v�f���܂܂�Ă���Ɨ�������̂��A���@�w�ɂ�����ʐ��Ƃ�����B���̏�ŁA�ʐ��I�����́A���{�����@�ɂ����Ă̓v�[�v���匠�I�Ȓ��ږ��吧�̋K��Ƃ���79��(�ō��ٔ����ٔ����̍����R��)�E95��(�n���������ʖ@�̏Z�����[)�E96��(���@�����̍������[)�̎O�����߂�݂̂ł���A�����̒��ړI�匠�s�g�����̎O�̏�ʂɌ����Ă������ŁA�i�V�I���匠�I�ȊԐږ��吧(�c������`)�������I�������x�Ƃ��č̗p���Ă��邱�Ƃ���(�O���E43��)�A���@�͐������̌_�@�A���Ȃ킿�i�V�I���匠�I���z�������匠�̊�{�ɒu���Ă�����̂ƍl���Ă���B�������A���̂��Ƃɂ�荑���匠�̊T�O���`�[������̂��뜜���A���͍s�g�҂������̐M���ɔ������ꍇ�ɂ́A�����́A���̌��͍s�g�҂�ᔻ�ł��邾���łȂ��A����ɂ���ɒ�R���|�����Ƃ��ł��錠���A���Ȃ킿��R�����A�����ꂴ�錛�@��̌����Ƃ��ĕۏႳ��Ă���ƍl���Ă���B
�����鍑���匠�T�O��O��ɂ���Ȃ�A�Ԑږ��吧(�c������`)�ɂ����đ�\�҂���c����I�o����I�����ɂ߂ďd�v�ȈӋ`��L���邱�ƂɂȂ�B�����āA���̑I�����}�X�R�~�̏��ɂ���Ďx�z����A�c�߂���Ȃ�A�����匠�̎����͒���������ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B�܂��A�I���́A���@�w��A��������I�o��������ł���Ɠ����Ɏ���̈ӎv�𐭎��ɔ��f������l��(�I�����A���@15��1��)�Ƃ��l�����Ă���m���� 1995: 108�n�A�I���ɂ�����}�X�R�~�̏��͑I�����N�Q�Ƃ��Đl�����ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��̂ł���B����ɁA�����̐����I�ӎv�����ړI�ɐ����ɔ��f����鐔���Ȃ��@��ł���ō��ٔ����ٔ����̍����R��(79��)��n���������ʖ@�̏Z�����[(95��)�A���@�����̍������[(96��)�ɂ�����}�X�R�~�̏��ɂ��A�����匠��N�Q����댯��������A���ӂ��K�v�ƂȂ�B�Ⴆ�A����̍ō��ٔ����ٔ������ƂɎ������ނ��Ƃ���}���A�O�c�@�c���I���̒��O�ɋ��U�̏��𗬂��Ƃ��A���邢�́A���_�����@9�������^���̕����֗U�����邽�߂ɁA�̈ӂɖk���N�̋��Ђ��֒�����Ȃǂ��l������B�������A�����匠�ɂƂ��čł��댯�������̂͌����܂ł��Ȃ��I���̉ߒ��ɂ�����}�X�R�~�̏��ł��邩��A�{�e�ł͂��̖��𒆐S�Ɍ������Ă����B
���̓_�A�}�X�R�~�̏��ɂ��A��ʂ��Ă��̎O�ތ^�����邱�Ƃɂ͒��ӂ��K�v�ł���B���Ȃ킿�A1�}�X�R�~������Ӑ}���Ď�̓I�ɏ�������ꍇ�B�܂��A2�}�X�R�~���C�t���Ȃ������Ɍ��͂ɂ���ď��̈ꗃ��S�킳��Ă���ꍇ�B����ɁA3�}�X�R�~�����͂ɂ���ď������v����Ă���ꍇ�ł���B�����āA���̊e�ꍇ�Ō������ׂ��_�͑S���قȂ�B�܂��A�ތ^1�̏ꍇ�ɂ́A�܂��Ƀ}�X�R�~���s���ȏ������Ȃ��悤�Ƀ}�X�R�~�̕ɉ��炩�̃��[����ݒ肷�ׂ��ł͂Ȃ��̂��B�ݒ肷��Ƃ�����A���̃��[���͂����ɂ���ׂ��������ƂȂ�B���ɁA�ތ^2�̏ꍇ�ɂ́A�ނ��덑�Ƌ@�ւ̃}�X�R�~�ɑ����삪���ƂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A���Ƌ@�ւ̏\�S�ȏ����J���������邱�Ƃ�A���Ɣ閧�̎�舵���̓K���������ۑ�ƂȂ낤�B�����āA�ތ^3�̏ꍇ�ɂ́A�}�X�R�~�����R���\���ɍs����悤�ɁA���Ƌ@�ւ̃}�X�R�~�ɑ���s���Ȋ���r�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̂悤�ɁA�ތ^1�̏ꍇ�ɂ̓}�X�R�~�̕\���̎��R�A��̓I�ɂ͕̎��R(���@21��1��)�̐������v�������̂ɑ��āA�ތ^2�E3�̏ꍇ�ɂ͋t�ɂ��̕ۏ�̋������v������邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ȓw���ȗv���ɑ��āA�ǂ̂悤�Ƀo�����X������đÓ��Ȍ��_�������A�}�X�R�~�̏����l����ꍇ�̍���Ȗ��ƂȂ�B�{�e�ł́A�ތ^1�̖��𒆐S�ɘ_���Ă������A���̍ۂɂ͗ތ^2�E3�̖��̑��݂���ɔO���ɒu���A�}�X�R�~�̎̕��R�ɏ\���ɔz�����Ă��������ƍl����B
|
��3�D�}�X�R�~�̏��̎���Ɩ��_
���������}�X�R�~���ʂ����Ă����̓I�@�\�Ƃ��ẮA1���j�╶�w���A�G���Ȓm�����������ɋ����Ă���鋳��̋@�\�A2�ǂꂪ�ǂ����i����`���Ă�����`�̋@�\�A3�|�\�A�X�|�[�c���A���������y���܂��Ă�����y�̋@�\�A4�l���܂ȃj���[�X���������ɓ͂��Ă����̋@�\�ȂǁA�F�X�ȋ@�\����������m�t���E���s 2006: 119�n�B�����̊e��ʂŁA�L���Ӗ��ł̏��(������A�g��点�h)���B�����ɕ��R�ƍs���Ă���B�Ⴆ�A1�J���������߂ē���Ƃ����鋫�̒n�̃h�L�������^���[����ԑg�ŁA���C�ȃX�^�b�t�ɍ��R�a�̉��Z����������A�R����₪�]��������u�����v���ۂ��킴�ƋN��������m�t���E���s 2006: 156�n�B�܂��A2���[�����̃e���r�E�R�}�[�V�����̂��߂ɎB�e�A���������g�����������ȃ��[�����h�ɂ́A���ۂɂ͗l���܂Ȗ�i��������A�u�F�Ƃ�v�����������B�g����ȂɊȒP�ɂ���Ȃɂ����������ȃ��[���������܂��h�ƃR�����g����邪�A����͎��ۂɂ͂��肦�Ȃ����[�����ł���A�����H�ׂ�Ίm���Ɏ��ʂ̂ł���m�n�� 2001: 114-115�n�B����ɁA3�j�]���O�̕v�w�����I�Ȏi��҂�R�����e�[�^�[����������Ԃ߂��肷���y�ԑg�ł́A���X�������������⊶�Ȃ����������v�w���A���̓Z�~�v���̔o�D�ł������Ƃ����m�t���E���s 2006: 156�n�B�������A�}�X�R�~�̋@�\�̒��ōł���{�I���d�v�Ȃ̂́A�O�q�������Ƃ�4�̋@�\�ł���A�����ŏ�삪�s����Ȃ�A���@�̊�{�������鍑���匠(���@�O���A1��)�������N�Q���ꂩ�˂Ȃ��B���̓_�A�ȉ��A�}�X�R�~�̏��̋�̗��O�q�̎O�ތ^�ɂ��Č��Ă����B
�܂��A�}�X�R�~�����͂ɂ���ď������v����Ă�������Ƃ��ẮA�펞�̐����̓��{�ɂ����ă}�X�R�~���푈���s�̓���Ƃ��Đ��{�̌��_�@�ւɑg�ݓ�����Ă������Ƃ���������B���Ȃ킿�A�o�Ŗ@�A�V�����@�A�����ێ��@�A���Ƒ������@���̌R����`�I�펞�@����A���_�������ꌳ�I�ɍs�����t���ǂȂǂɂ���āA�}�X�R�~�͌�������������A���{�̐푈���s�Ƃ����ړI�̂��߁A�����I�ɏ��̈ꗃ��S�킳�ꂽ�m���� 2003: 5-8�n�B�}�X�R�~�́A���{�ƌR���̎x�z���ɂ�����A���e�ɂ͎��O���{�ɂ��`�F�b�N���s���A�틵���̂��u��{�c���\�v�ȊO�͕��邱�Ƃ�������Ȃ������m�t���E���s 2006: 27�n�B
�܂��A�}�X�R�~���C�t���Ȃ������Ɍ��͂ɂ���ď��̈ꗃ��S�킳�ꂽ����Ƃ��ẮA1990(����2)�N�A�C���N�R�̃N�E�F�[�g�N�U�Ŗu������������p�ݐ푈�̍ہA�C���N�̊��e���s�ׂ̏ے��Ƃ��ꂽ�g���܂݂�̐����h�̉f������������B���܂݂�Ő^�����ɂȂ��������̉f���͑S���E���삯����A���̌����̓C���N�����o���������̂Ƃ���A���Y�푈���N�����C���N�̍s�ׂ������Ɋ���j�Ă��邩��i�����ʂœx�X�g��ꂽ�B����������l�X�́A�C���N�̔�l���I�s�ׂɕ��S���A�A�����J�𒆐S�Ƃ��鑽���ЌR�������ɐ푈�I�����Ƃ�������B�������A���A���̌����̗��o�̓A�����J�R�̔����ɂ����̂ł���A�A�����J���h���Ȃ͂����m����Y�f�����Ӎ��g�ɗ��p���Ă������Ƃ����炩�ƂȂ����B���Ȃ킿�A���̉f���́A�A�����J���{�̃��f�B�A�E�C�x���g�A��������A��点�ł������̂ł���B���{�ł�������A�����J���{�̜��ӓI�ȏ��͑傫�Ȗ��ƂȂ����m�ۉ� 2002:149-151�n�B���ǁA�A�����J����{���n�ߊe���̃}�X�R�~�́A�m���Ă��m�炸���A�A�����J���{�̏��̈ꗃ��S�����̂ł���B���A�A�����J�ɂ����ẮA��v�ȃ}�X�R�~�����{�ɍR�c������A�푈�����P���邽�߂̌����Ă𐭕{�ɒ�Ă����肷�邱�Ƃ��Ȃ���A�܂��A���{�ɂ����Ă��A�}�X�R�~���A�����J���̏����ׂ��ȏ����W���͂ɂ�錟�Ȃ����ᔻ�ɂ��̂܂ܗ��������Ƃ����_�Ƃ��Ďw�E���ꂽ�m�ؑ� 1992: 27-62�n�B
����ɁA�}�X�R�~������Ӑ}���Ď�̓I�ɏ�����������Ƃ��ẮA������֔�����肪��������B���̖��́A�I���ɂ�����}�X�R�~�̏��̊댯�����L�������ɒm�炵�߂邱�ƂƂȂ����B���̖��Ƃ͋�̓I�ɂ́A1993(����5)�N9��21���ɊJ�Â��ꂽ�����A�̕����ԑg������ɃQ�X�g�E�X�s�[�J�[�Ƃ��ď��҂��ꂽ�e���r�����̒֒�Ǖǒ�(����)���A���̉Ă̏O�c�@�c���I���̕��ӂ肩����A�I���������Ԓ��ɕǒ��Ƃ��ăj���[�X��ʂ��āA�u�A�������̔�����ڎw���Ĕ��������o�b�N�E�A�b�v����悤�Ɏw�������v�Ƃ�����|�̔������������̂ł���B���̏O�c�@�c���I���́A��̓I�ɂ́A1993(����5)�N7��4���Ɍ�������A���N����18���ɓ��J�[���ꂽ��40��O�c�@�c�����I���̂��Ƃł���A���̑I���Ŏ��R����}�͑��}�Ȃ���A���}�ȗ����߂Ė�}�ɓ]�����A���A�������ł���א�������t(�������{�V�}�}��)���a�������B���̖��͍���ł����グ���A���ɂ͎����}����̒�Ăɂ��A�ǒ��̍���ɂ�����ؐl����(10��25��)�ɂ܂Ŕ��W���邱�ƂɂȂ����m�t���E���s 2006: 157�n�B���ꂪ�����E������搂���}�X�R�~�̕ǒ��̔����Ƃ͂ɂ킩�ɐM����A�}�X�R�~�ɂ�霓�ӓI�ȏ��̊댯����Ɋ���������o�����ł���B������}�X�R�~�̏���h�~���鐧�x�I�Ȏ藧�Ă����s�ł͂قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ��_�͑傫�Ȗ��ł��낤�B
|
��4�D�}�X�R�~�̏��̎�@
����ł̓}�X�R�~�́A�����I�ɂ͂ǂ̂悤�Ȏ�@�ŏ����s���̂ł��낤���B���̓_�A���_����ɂȂ�����̎�@�́A��v�A���̂悤�ɕ��ނ��邱�Ƃ��\�ł���B�܂��A1���U�E�c��(������s��)������B����͌̈ӂɎ�����c�Ȃ��ď��𗬂�����A���邢�͋��U�̐�`�����邱�Ƃɂ���ď�삪�s����ꍇ�ł���B�܂��A2�B���E����������B����͓���̎������B�����Ƃɂ���ď�삪�s����ꍇ�ł���B���ɁA3�֒��E���o(�����郁�f�B�A�E�C�x���g)������B����̓C�x���g�o���邱�Ƃɂ���ď�삪�s����ꍇ�ł���B��̓I�ɂ́A�}�X�R�~�̏W�c�I�ߔM�ɂ��A�Љ�I�ɑ�K�͂ȃZ�����j�[���C�x���g�Ƃ��ĉ��o����A����ɂ��Ă̏�Љ�ɏ[�����Ă����B����Ɍĉ����āA���̏��͑��ΓI�ɎЉ�猸�����Ă����A���ɂ͔r�����ꂽ�肷��B���̂悤�ɂ��āA�����̊S�o���ꂽ�C�x���g�Ɍ��������邱�Ƃɂ��A����̑��_���獑���̖ڂ����炳���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ⴆ�A�������i��̖ړI�Ō��̎��d�������獑���̖ڂ����炳���邽�߂ɁA�������ȗL���|�\�l�̗����b���X�I�ɃX�N�[�v����ꍇ����������B�܂��A����Ƃ͋t�ɁA���o���ꂽ�C�x���g�ɂ��l�S��������A�����̊S�����̕����֗U�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ⴆ�A���Ƃ���ɖk���N�̋��Ђ�������A�k���N�ւ̐��ٗe�F�ւƍ����̈ӎv��U������ꍇ����������B����ɁA4�I���E�Ǘ�������B����̓}�X�R�~�ɂ���o���̂Ƃ���őI������Ǘ�����Ă���ꍇ�ł���B�Ⴆ�A���̔��\�������̈ӂɂ��炵����A�����̈ӂɕ��������o���ɔ��\���邱�Ɠ�����������B�����āA5����i���E��ی`��������B�Ⴆ�A�u �`���Ȃ��Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�܂���v�Ƌ��|�S������������A�܂��A�u����Ȃ��Ƃł悢�̂��낤���v�ƕs������������t���[�Y��A������B�����錾��݂̂Ȃ炸�A�ʐ^��f���A���y�Ȃǂ���g���A����ɂ����ɍ�ׂ������A�|�p�I�ł������錩���ȕ`�ʂ��s���B�m���ɁA�����͌����ĉR�ł͂Ȃ���������Ȃ��B�������A�����͉ߏ�Ȃ܂łɌ���҂̊���ɓ��������A���Ԃf���Ă��Ȃ���ۂ������҂Ɍ`�����A�����̒��ɓ���̐S�ۂ���o����m���� 1993:222-232�n�B���̓_�A�I���ɂ����鋕�U��s���͘_�O�ł���A�����ɂ��Ă̓}�X�R�~���̂ɓ��ʂ̃y�i���e�B���Ȃ��邱�Ƃ���������Ă悢�B�������A����ȊO�ɂ͌��ʓI�ȕ��s�����߂̃}�X�R�~�̕e�N�j�b�N�͈͓̔��Ƃ��Ĉ�ʓI�ɂ͋��e��������̂������B����āA�����̎�@�̈���ꗥ�ɋ֎~���邱�Ƃ͑Ó������������A�܂��A����͎��ۏ�s�\�ł��낤�B�������A�����匠�ɒ�������I���ɂ��ẮA�g�ǂ̂悤�ɕ��邩�h�����A�g������邩�h�Ɉӂ��ׂ��ł���A�]�v�ȑn�ӍH�v�͕s�v�ł���B�����ɂƂ��ĕK�v�Ȏ�����������ÂɒW�X�ƕ���Ƃ����p�����̗v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���̈Ӗ��ŁA�I���ԑg�ɂ����Ċe�e���r�ǂ����������������邱�Ƃ́A�ǂ����Ă����o�ߑ��ɑ����Ă��܂����Ƃ���A�Ó��ł͂Ȃ��낤�B���Ȃ��Ƃ����[���O��̑I���ԑg�̎������͏o������������\�Ƃ��A�������������������悤�Ȏ�舵�����������ׂ��ƍl����B�܂��́A�e�}�X�R�~�Ԃ̐a�m����Ƃ��đI���ɂ��ẮA�g�����������h�̂ł͂Ȃ��A�����̂��߂Ɂg���͂������h���Ƃ���茈�߂�ׂ��ł��낤�B
�}�X�R�~���g�p������̎�@�Ƃ��āA�I���̂��тɖ�莋����Ă���̂��A������A�i�E���X�����g���ʂł���B�A�i�E���X�����g���ʂƂ́A�}�X�R�~�ɂ��I�����ʂ̗\�����A���ۂ̓��[���ʂɉe����^���錻�ۂ������B��̓I�ɂ́A1�L���ƕ��ꂽ���҂�����Ɏx�����W�߂錻�ۂ���o���h���S�����ʂ�2�s���ƕ��ꂽ���҂��������ē���[���W�߂錻�ۂ���A���_�[�h�b�O���ʂƂ�����B����ɁA3�y���ƕ��ꂽ���Ґw�c��x���҂̋C���ɂ݁A�[�����炷���ۂ���y�����[�h���ʂ����낤�B�ʏ�A�I�����̒��Ō��҂ɍł��[���ȉe����^���Ă���ƍl�����Ă���̂��I���\���ł��邪�A�A�i�E���X�����g���ʂ̎��ݐ���e���͂ɂ��ẮA���݂̂Ƃ���A�w��I�Ɋ��S�Ɏ�����Ă����ł͂Ȃ��B���̓_�A�t�����X�ł̓A�i�E���X�����g���ʂ�������Ƃ��āA���[���Ƃ��̑O1�T�Ԃ͑I���\�����֎~���Ă���m���� 2005:96�n�B���{�ł́A�ȑO�A������w�V�����������u�w�I���Ɠ��[�s���x�v���W�F�N�g�����v���s���A���̗L�����m�F���Ă���B���̌����ɂ��A�u�}�X�R�~�́A�L���҂ɂ����҂̓�����c�Ȑ��̗\���ɂ͉e����^���邪�A���̗\���͓��[�Ӑ}�̕ύX�Ⓤ�[�s�����̂��̂̕ύX�ɂ͌��т��Ȃ��v�ƌ��_���Ă���B����āA�I���\�����ꎩ�̂́A���ɂ͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B�������A�I���\���́A���Ƃ��L���Ҏ��g�ɂ͉e����^���Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��A���ۏ�A���҂̐w�c�ɂ͑傫�ȉe����^���Ă���Ƃ����B�Ⴆ�A������e���ɂ��Đ��a�v�́A����̎�ނ����ƂɁu����w�c�̊����́A���Ղ́w��������x�Ə����ꂽ�����A�������Ă��肪�����A���Ղ���I�Ղɂ����āA�w�Z���i�ށx�A�w���I�����x�Ə����Ă��炦��x�X�g���Əq�ׂĂ����B�E�E�E�I�́A�y�����[�h����ԋ����B�w�c�̉^������V���p���A�y�����[�h�ŁA�ܐl�ɐ���������Ƃ�����l�ɂ������������Ȃ���A���ꂾ���ő傫�ȒɎ肾�B�y�����[�h������ƁA�����ł������ĉ��̂ɕK���ɂȂ�B�ꂵ���킢�ƕ���A������l�^�ɉ^�����Ƀn�b�p��������B�܂�A�}�X�E���f�B�A�ɂ���ĕ�ꂽ���e�͕�ꂽ���e�Ƃ��Ď���A��������Ƃɂ����Ɍ��ʓI�ȏ����A���Ɏ��w�c�ɑ��Ăł��邩���A�I�̘r�̌������Ƃ����킯���v�Əq�ׂĂ���m��� 1994: 134-135�n
�܂��A�}�X�R�~���g�p������̎�@�Ƃ��āA������T�u���~�i�����ʂ���莋����Ă���B�T�u���~�i�����ʂƂ́A�ӎ�����Ȃ����x���Œ掦���ꂽ�h��(�T�u���~�i���h��)�̒m�o(�T�u���~�i���m�o)�ɂ���Đ��̂ɉ��炩�̉e���������邱�Ƃ������B����Ƃ͋t�ɁA�ӎ�����郌�x���Œ掦���ꂽ�h���̒m�o�́A�X�v�����~�i���m�o�ƌĂ��B �Ⴆ�A1995(����7)�N�ATBS�̃I�E���^�����֘A�ԑg�̒��ŁA�T�u���~�i�����ʂ�_������@���g��ꂽ���Ƃ͋L���ɐV�����Ƃ���ł���B���̔ԑg�ɂ����ẮA�}�����Ԃ͂ق�̈�u�ł���A�ӎ����Ă��Ȃ�����͂قƂ�NjC���t���Ȃ����x�̃J�b�g�ł͂��������A�I�E���^������\�̖��������퍐�̊瓙�̃J�b�g���A�ԑg���e�Ƃ͑S�����W�ȏ�ʂʼn��x���}������Ă����B���̍s�ׂ́A�Љ�I�Ɍ������ᔻ�𗁂т邱�ƂƂȂ����B���̍ہATBS�́A�������@���u�ԑg�̃e�[�}���ۗ������邽�߂�1�̉f���\���Ƃ��ėp�����v�Ǝߖ��������A�����̗X����(���݂̑�����)�͑Ó����������Ƃ���TBS�ɑ��Č��d���ӏ����Ƃ����s���w�����s�����B����ɑ��āATBS�̑����u�����҂����m�ł��Ȃ��f���̎g�p�̓A���t�F�A�ł������v�ƎӍ߂����B���̎����́A�T�u���~�i�����ʂ̑��݂��L�����Ԃɒm�炵�߂錋�ʂƂȂ����B���̎����̌�A1995(����7)�N�ɓ��{��������(NHK)���A1999(����11)�N�ɂ͓��{���ԕ����A�����A���ꂼ��̔ԑg������ŃT�u���~�i���I�\�����@���֎~���邱�Ƃ𖾕������Ă���B�T�u���~�i�����ʂ̎��ݐ���e���͂ɂ��Ă��A���݂̂Ƃ���A�w��I�Ɋ��S�Ɏ�����Ă͂��Ȃ��B���̓_�A������T�u���~�i�����ʂɂ��āA�⌳�͂́A����܂ł̎��،����̒m���ɂ���Ă��̌��ʂ͊m���ɂ���ƌ�������̂ł͂��邪�A�ǂ̂悤�ȏ����̉��ł��̌��ʂ������Ȃ邩�Ƃ������ɂ��Ă͌��݂̂Ƃ���\���ɖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ��Ƃ���B�����āA�T�u���~�i�����ʂ́A�l�E���̌������₻��ɑ���D���E�]���Ȃǂ̊���E�F�m�ʂɑ��Ĉ��̌��ʂ����邱�Ƃ͑����̌����ɂ���Ď�����Ă�����̂́A���ۂ̔����E�s���ʂɑ��Ă̌��ʂ������������͏��Ȃ��Ƃ���B����āA�Ⴆ�A����V���i�ɂ��T�u���~�i�����ʂ�_������@�Ő�`�����Ƃ��Ă��A�����҂ɑ��ē��Y���i�ɂ��Ă̍D��ۂ�A���t���邱�Ƃ͂ł��Ă��A���ۂɓ��Y���i�킹�邱�Ƃ܂ł͂ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ���Ȃ�A�}�X�R�~���T�u���~�i�����ʂ�_������@�őI���������Ƃ��Ă��A�L���҂����ӎ��̂����ɓ���̌��҂ɓ��[���Ă��܂��Ƃ����댯���͂Ȃ����ƂɂȂ�B�������A�T�u���~�i�����ʂ́A�L���҂̊���E�F�m�ʂɑ����Ȃ�Ƃ��e����^���邱�Ƃ��ł���������Ώ\���ƍl����̂ł���A�}�X�R�~�̏��̎�i�Ƃ��āA����Ȃ�Ɋ��p�ł����@�Ƃ������ƂɂȂ낤�m�⌳ 1999: 171-181�n�B
����ɁA�ߎ��A�}�X�R�~���g�p������̎�@�Ƃ��āA������v���C�~���O���ʂ����Ƃ���Ă���B�v���C�~���O�Ƃ́A��������E���n�����Ƃ����Ӗ��ł���B�v���C�~���O���ʂƂ́A�{���A�S���w�̐��p��ŁA��ɗ^����ꂽ���(��s�h��)���A��ɑ������(�㑱�h��)�̏����ɖ��ӎ��ɉe�����y�ڂ����Ƃ������B�Ⴆ�A�������������E�l�Ƃ̊�ʐ^�̌�ɁA���̔Ɛl�Ǝ��Ă���ʐl�̊�ʐ^��������ƁA�����l�͂��̕ʐl�Ɉ���ۂ����ƌ����Ă���B���̓_�A2006(����18)�N�A��731��������舵����TBS�̃j���[�X�ԑg�̂Ȃ��ŁA���{�W�O���[����(����)�̗e�p����3�b�ɂ킽���Ė��ĂɃe���r��ʂɉf���Ă������Ƃ��A���炩�̃v���C�~���O���ʂ�_�������̂ł͂Ȃ��������ƂȂ�ATBS���s�K�ł������ƎӍ߂������Ƃ��L���ɐV�����Ƃ���ł���B�����āA���̂悤�ȃv���C�~���O���ʂ́A�I�����̏��ɂ����p������Ƃ���Ă���B���Ȃ킿�A�}�X�R�~�́̕A�u���܉����d�v�ȎЉ��肩�v�u�ǂ̎Љ��肪���ɋc�_�����ׂ����v�Ƃ������l�X�̔F���ɋ����e�����y�ڂ��Ă���(������A�W�F���_�E�Z�b�e�B���O�m�c��ݒ���ʁn)�B����āA�}�X�R�~���I���O�̑I���ŋ��������I���̑��_�ƗL���҂��d�v�ƍl����I���̑��_�Ƃ́A��v����X��������B�����āA����̑��_���}�X�R�~�ŋ��������ɂ�āA�v���C�~���O���ʂɂ��A���̑��_�́A�L���҂����Ȃ̓��[������҂�}��]���E�I������ۂ̊�Ƃ��Ĕ�d�𑝂��Ă���B���҂�}�����ӂƂ��鐭��͂��ꂼ��قȂ��Ă��邪(�Ⴆ�A�N�����ɔ��ɏڂ�������)�A�}�X�R�~�����������I���̑��_�ӂƂ��A����ɂ��ėD�ꂽ�����L������҂�}�͑I������ɂ߂ėL���ɐ키���Ƃ��ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���炪���ӂȑ��_���ǂ̂悤�ɓ��������ă}�X�R�~�Ɏ��グ�����邩���A���҂�}�̑I���헪�E���f�B�A��ɂ����Ă��d�v�ɂȂ��Ă���Ƃ����B���̂��Ƃ́A2005(����17)�N�̂�����u�X�����v�I���v�ɂ����āA����Y��(����)������̍ł����ӂȗX�����c����I���̈�呈�_�Ƃ��ă}�X�R�~�Ɏ��グ�����邱�Ƃɐ����������ʁA�O�c�@�I���Ŏ����}�������������Ⴉ������炩�ł��낤�m���2004: 194-209�n�B
�A�i�E���X�����g���ʂ�T�u���~�i�����ʁA�v���C�~���O���ʓ��́A�O�q�����悤�ɁA���܂��w���A�Ȋw�I�Ȏ������S�ɂȂ���Ă����ł͂Ȃ��A���̌��ʂ������̈���o�Ȃ��B�������A�����̎�@���P�Ƃł͌��ʂ��R�����Ƃ��Ă��A�����̎�@����̓I�ɋ�g���}�X�R�~���������悤�Ƃ����ꍇ�ɂ́A���̌��ʂ���������\���͏\���ɂ��肤��̂ł���A���̊댯���͌����Čy�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��ł��낤�B�܂��A���Ƃ����̌��ʂ��F���ł������Ƃ��Ă��A�������@���B�����Ɏg�p���邱�Ǝ��̂������ɑ���M�`�����ɔ�����Ƃ����悤�B��͂�g�^�킵���͎g�p�����h�̌����ōs���ׂ��ł���B���Ȃ��Ƃ��A�����匠�ɒ�������I���ɂ��ẮA�@���Ƃ����`�����̂邩�ۂ��͊i�ʁA�����̎�@�m�ɋ֎~���铝��I���[�������肷�ׂ��ł��낤�B�O�q�������Ƃ��t�����X�ł́A�A�i�E���X�����g���ʂ�����邽�߁A���[���Ƃ��̑O1�T�Ԃ͐��_�����̌��\��]�_���֎~����Ă���A�傢�ɎQ�l�ƂȂ낤�B����ɁA�������@�̑��݂Ɗ댯�����\���ɔF�����ĕɐڂ��Ă��鍑���͌����đ����͂Ȃ��ł��낤����A�����ɑ��Ă������@�̑��݂Ɗ댯���Ƃ����m�O�ꂷ��A�����郁�f�B�A�E���e���V�[������K�v�ƂȂ낤�B���̓_�A�ނ���}�X�R�~���g���I���̓ǂ݉��������܂߂������ɑ��郁�f�B�A�E���e���V�[��������H���邱�Ƃ����z�ł��낤�B����܂��܂����i��������Ȋw�Z�p�ɂ��A�}�X�R�~�̏��̎�@�́A���I�����A���x������ɈႢ�Ȃ��B����āA������_�̊w��I�����͍���Ƃ��s�ӁA���������ׂ��ł��邵�A�܂��A�������g�̖ڂɂ��Ď����ӂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl����B
�ʏ킠�܂�w�E����Ă͂��Ȃ����A�M�҂̓}�X�R�~������I�ɔ��\���Ă��鐢�_�������ʂ𗘗p���āA��������\�������肤��̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���Ȃ킿�A�}�X�R�~�����_�������ʂ\����ꍇ�A���ʂƂƂ��Ɍ��\�����̂́A1��������(��E2009�N7��3������5��)�A2�������@(��E�d�b�@)�A3��������(��E�����s�̗L����)�A4���������邢�͗�(��E1�A042�l)���x�ł���m�c���E�͖쑼 2009: 94-206�n�B���Y�����̑��݂���e�̐^�����m�F��������͂��̒��x�����^�����Ă��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�唼�̍����͒����̎�@�ɂ͂قƂ�Ljӂ킸�A�������ʂɂ���ڂ������A���O�̒m��ꂽ���}�X�R�~�̒����ł���Ƃ��������ʼn��̋^�����Ȃ��M������ł��܂��B����͔��Ɋ댯�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ł��낤���B�����������炻�̐��_�������̂��S���̂ł����グ�Ȃ̂�������Ȃ����A�����܂ł͂����Ȃ��Ƃ��ߌ�⑀�삪��݂��Ă��邱�Ƃ͐△�ł͂Ȃ��낤�B���}�X�R�~�����̋C�ɂȂ�A���`��̖��͕ʂɂ��āA���Ђ̑I�����_�����̃f�[�^���B�����ɉ�������x�̂��Ƃ͋Z�p�I�ɂ͗e�Ղł��낤�B�T�^�I�Ȑ��_�������@�ɂ́A1�l�ʐږ@�A2�z�t����@�A3�X���@�A4�d�b�@��������Ƃ���A�I�����_�����ł͒ʏ�A�d�b�@�̎�@�A��̓I�ɂ́A�d�b�ԍ���ׂɔ��������Ă��̔ԍ��ɓd�b�������A���������т̑Ώێ҂��璲������m���őI��RDD(Random Digit Dialing)�����Ƃ�����@���̂��邱�Ƃ������B�������A���̕��@�́A�����ɂ͓��m�����o(��������ɑI���m�����S�Ă̒����Ώێ҂œ��������o)�ł͂Ȃ��A�T���v�����O�덷�𐳊m�Ɍ��ς��邱�Ƃ͓���Ƃ̎w�E������m���� 2009: 19�n�B�}�X�R�~�̐��_������K�������鉽�炩�̎藧�Ă��K�v�ł��낤�B�Ƃ�킯���ꂪ�I�����_�����̏ꍇ�ɂ́A�����匠�ɂ��ւ�邱�Ƃł��邩��A���Ȃ��Ƃ����̒����̓K����������I�Ɍ��ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�����Ƃ��K�v�ł���B���̓_�A�I�����_�����̕��@�ɂ��Ă̓}�X�R�~�̓���I����߁A�����Ƃ��Ă���ɏ]���đI�����_�������s�����̂Ƃ��邱�Ƃ������ɒl���悤�B�܂��A�K���Ȑ��_�������Ȃ��ꂽ�Ƃ��Ă��A���̒������ʂӓI�ɗ��p���邱�Ƃɂ��}�X�R�~�̏��ɂ����ӂ��K�v�ł���B�Ⴆ�A�K���Ȑ��_�����Łu�����@���������ׂ��ł���v�Ƃ������ʂ��o���Ƃ��Ă��A���̏ꍇ�ɁA�u�����猻���@�͎���̗v���ɂ�����Ȃ��Ȃ����v�Ƃ��A�u�����͌����@�ɖ������Ă��Ȃ��v�ȂǁA�����@�ɔے�I�Ȍ��_���ɓ������Ƃ͖��m�Ɍ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A�����@�̗��O������ɐ��i���A���������錛�@�������\���ɂ��肤�邩��ł���B���_�������ʂ̜��ӓI���p�ɂ����̊댯����������邽�߂ɂ́A�q�ϓI�Ȓ������ʃf�[�^�ƃ}�X�R�~���g�̎�ϓI�Ȉӌ��E�咣�Ƃ��A�`���㖾�m�ɕ��������舵����O�ꂳ����K�v�����낤�B |
��5�D���s�@����є���̗���
(1)���s�@�̗���
�I�����̃}�X�R�~�ɂ��ẮA�I���́g���R�h����������̂��A���邢�͑I���́g�����h����������̂��ɂ��A���̎�舵���̊�{�I�ȃX�^���X���قȂ��Ă���B���Ȃ킿�A���R�ȑI�����d������Ȃ�A�I�����ɂ����Ă��}�X�R�~����ʂɋK�����ׂ��ł͂Ȃ��A�ނ��덑���̐����I�ӎv���\�������ő�̋@��Ƃ��āA�����ɑ��鎩�R�ȏ������ϋɓI�ɍs���ׂ��Ƃ������ƂɂȂ낤�B����ɑ��āA�����ȑI�����d������Ȃ�A�I���͍����̐����I�ӎv���\�������ő�̋@��Ȃ̂�����}�X�R�~�̜��ӓI�A���p�I�ȕ͌����ċ������ׂ��ł͂Ȃ��A�����Ƃ͈قȂ�����m�ۂ̂��߂Ƀ}�X�R�~�ɑ�����ʂȐϋɓI�K�����v������邱�ƂɂȂ낤�B���̓_�A���s�@�ɂ����āA�I�����̃}�X�R�~�ɑ��ċK���I�ɓ�������Ƃ��āA�ȉ��̂��̂���������B�܂��A�d�g�@�ɂ��ƈȉ��̂悤�ɖ���������Ă���B���Ȃ킿�A�ړI�Ƃ��Ă��̑�1���ɂ����Ắu���̖@���́A�d�g�̌������\���I�ȗ��p���m�ۂ��邱�Ƃɂ���āA�����̕����i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���v�A�����āA�����Ƃ��Ă��̑�106���ɂ́u���ȎႵ���͑��l�ɗ��v��^���A���͑��l�ɑ��Q��������ړI�ŁA�����ݔ����͑�100���1����1���̒ʐM�ݔ��ɂ���ċ��U�̒ʐM�����҂́A3�N�ȉ��̒���150���~�ȉ��̔����ɏ�����v�Ƃ���B�܂��A���E�I���@�ɂ��ȉ��̂悤�Ȕ����K�肪����B���Ȃ킿�A���U�����̌��\��(��235��)�Ƃ��āA���̑�1���ɂ́u���I���͓�������ړI�������Č��E�̌��ҎႵ���͌��E�̌��҂ƂȂ낤�Ƃ���҂̐g���A�E�ƎႵ���͌o���A�E�E�E�Ɋւ����U�̎��������ɂ����҂́A2�N�ȉ��̋�������30���~�ȉ��̔����ɏ�����v�A�����āA���̑�2���ɂ́u���I�����Ȃ��ړI�������Č��E�̌��Җ��͌��E�̌��҂ƂȂ낤�Ƃ���҂Ɋւ����U�̎��������ɂ��A���͎������䂪�߂Č��ɂ����҂́A4�N�ȉ��̒����Ⴕ���͋�������100���~�ȉ��̔����ɏ�����v�Ƃ���B�������A�d�g�@�̔����ɂ���A���E�I���@�̔����ɂ���A�ړI�Ƃł���(�u���Q��������ړI�v�A�u���I���͓�������m�������Ȃ��n�ړI�v)�A���A�̈ӔƂł���(�u���U�̒ʐM�����v�A�u���U�̎��������ɂ����v�A�u�������䂪�߂Č��ɂ����v)�B����āA�ƍߗ��؏�̍��������݂̂Ȃ炸�A�����I�ɂ͓��Y�L�������������R�l����L�Ҍl�ɑ��ēK�p���A�ӔC��₤�����Ȃ��B�}�X�R�~�Ƃ����g�D�̂ɂ����鋕�U�ʐM�߂⋕�U���\�߂ڂɓK�p����ɂ́A�Y�@��A�@�l�����̉ۂƂ��������N���A�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɁA�I�����݂̂Ȃ炸��ʓI�ɓK�p�����ł͂��邪�A�����@3����2��1������߂�ԑg���������ڂɒl����B�������́A�ԑg�ҏW�ɂ������ď��炷�ׂ������Ƃ��āA��������ёP�ǂȕ������Q���Ȃ�����(1��)�A�����I�Ɍ����ł��邱��(2��)�A�͎������܂��Ȃ��ł��邱��(3��)�A�ӌ����Η����Ă�����ɂ��Ă͂ł��邾�������̊p�x����_�_�𖾂炩�ɂ��邱��(4��)���f���Ă���B����2����4����2�̗v���́A������u��������(��������)�v�ƌĂ�Ă�����̂ł���m���� 2007: 465�n�B�������A���̏����́A�@�K�͂ł͂�����̂̒ʏ킠���܂ŗϗ��I�E�����I�K��Ɖ�����Ă���A�܂��A�s����̏ꍇ�̃y�i���e�B�����ʂɒ�߂��Ă����ł��Ȃ��A����ċ����K���I���͂͂قƂ�NJ��҂����Ȃ��B����ɁA�I�����̃}�X�R�~�ɑ��ē��ɋK���I�ɓ�������Ƃ��Ē��ڂɒl����̂��A���E�I���@148���̋K��ł���B����1���́A�u���̖@���E�E�E�́A�V�������͎G�����A�I���Ɋւ��A�y�ѕ]�_���f�ڂ���̎��R��W������̂ł͂Ȃ��B�A���A���U�̎������L�ڂ����͎�����c�Ȃ��ċL�ڂ��铙�\���̎��R�𗔗p���đI���̌������Q���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肵�A�����āA����2���y��3���́A�������ւ��āA�I���^�����Ԓ��y�ёI���̓����ɂ����Ă͈��̗v��(1�V�����͖���3��ȏ�A�G���͖���1��ȏ�A���𒀂��Ē���ɗL���Еz������́A2��O��X�֕��̏��F�̂�����́A3�I�������̌������͍����̓��O1�N�m�����Ɋւ��鎖�����f�ڂ�������V���ɂ����Ă�6�J���n�ȗ��A1�y��2�ɊY�����A�����������s������̂ł��邱��)�������V���E�G���Ɍ���A���Y�I���Ɋւ���E�]�_�̎��R���F�߂��A���������v����������Ȃ��V���E�G���ŁA�Еz�E�f��������̂́A���̊��Ԓ��A�I���Ɋւ��ĕE�]�_�ł��Ȃ��Ƃ��Ă���B���I�@�́A����Љ�ɂ����ă}�X�R�~�������̐�������m�錠��(���@21��1��)�̎����ɉʂ����Ă���Ӌ`�̏d�含�Ɋӂ݂āA�}�X�R�~���I���Ɋւ���y�ѕ]�_���f�ڂ��鎩�R��L���邱�Ƃ������I�ɔF�߂����(����1��)�A�I���ړ��Ă̐V���E�G������������āA������ҁE���萭�}�ƌ��т��đI����`�ɗp������댯�����������A�I���̌������m�ۂ��邽�߂ɁA���̗v���������}�X�R�~�݂̂ɑI�����Ԓ��̑I���Ɋւ���y�ѕ]�_�̌f�ڂ�F�߂��̂ł���(����2�E3��)�m�f�� 2008: 621�n�B�������A�����匠��N�Q����悤�ȏ��������ɑ��čs������悤�ȋ���}�X�R�~�́A�قƂ�ǂ��̗v�������Ă���ł��낤����A������}�X�R�~�ɂ͉���̋K���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�ȏ�A�T�ς��Ă����悤�ɁA���s�@�͑I������ʎ����闧��ɂ͂Ȃ��A�I�����̋���}�X�R�~�̏��ɂ�荑���匠���N�Q�����댯���ɑ��ẮA�قƂ�ǔz�����Ă��Ȃ��B���s�@�́A�I�����̃}�X�R�~�ɂ��Ă͑I���̌��������I���̎��R���������Ă�����̂ƕ]�����悤�B
(2)����̗���
����ł́A����͑I�����̃}�X�R�~�ɂ��āA�I���̎��R�ƌ����̂�������d�����Ă���̂��낤���B���̓_�A�I�����̃}�X�R�~�ɂ��Ăł͂Ȃ����A�ō��ق͑I���^����ʂɂ��āA1���O�^���̋֎~(���E�I���@129��)�A2�˕ʖK��̋֎~(���E�I���@138��)�A3�@��O�����}��̔Еz�E�f���̋֎~(���E�I���@142��)����������������Ƃ��Ă���A���̍ہA�I���̌������������Ă���B���Ȃ킿�A���݂ł��Ȃ����[�f�B���O�E�P�[�X�Ƃ��Ė�����ۂ��Ă���1969(���a44)�N4��23���̍ō��ّ�@�씻���́A���O�^���̋֎~�K��̍������ɂ��A�u���E�̑I���ɂ��A�펞�I���^�����s�Ȃ����Ƃ����e����Ƃ��́A���̊ԁA�s���A���p�ȋ����������A���ꂪ�K������ɂ��s���s�ׂ̔������ɂ��I���̌������Q����ɂ����邨���ꂪ����݂̂Ȃ炸�A�k��Ɍo���J�͂������݁A�o�ϗ͂̍��ɂ��s�����������錋�ʂƂȂ�A�Ђ��Ă͑I���̕��s�����������邨���ꂪ����B���̂悤�ȕ��Q��h�~���āA�I���̌������m�ۂ��邽�߂ɂ́A�E�E�E�e���҂��\�������蓯��̏����̉��ɑI���^���ɏ]�������邱�ƂƂ���K�v������B���E�I���@129���E�E�E�́A�܂��ɁA�E�̗v���ɉ����悤�Ƃ����|�ɏo�����̂ł����āA�I���������ɍs�Ȃ��邱�Ƃ�ۏႷ�邱�Ƃ́A�����̕������ێ����鏊�Ȃł��邩��A�E�E�E���O�^�����֎~���邱�Ƃ́A���@�̕ۏႷ��\���̎��R�ɑ������ꂽ�K�v�������I�Ȑ����ł���Ƃ������Ƃ��ł���v�Ɣ������A�I���̌������m�ۂ��邽�߂ɑI���^���Ƃ����\���̎��R(���@21��1��)�𐧌����邱�Ƃ�F�߂Ă���B
�܂��A�I���̌����ƂƂ��ɑI���̎��R����ʂɍl���������������݂���B���Ȃ킿�A�O�q�����}�X�R�~�̑I�����Ԓ��ɂ�����I���Ɋւ���y�ѕ]�_�̌f�ڂ𐧌�������E�I���@148��3���̋K��̍�����������ꂽ1979(���a54)�N12��20���̍ō��ٔ����́A�u148��3���́A������I���ړ��Ă̐V�����E�G�����I���̌������Q������̌��҂ƌ��т����Q���������邽�߂�ނ������݂���ꂽ�K��ł����āA�����ȑI�����m�ۂ��邽�߂ɒE�@�s�ׂ�h�~�����|�̂��̂ł���B�E�̂悤�ȗ��@�̎�|�E�ړI���炷��ƁA�����Ɋւ��锱���K��ł��铯�@235����2��2���̂����I���Ɋւ���w���͕]�_�x�Ƃ́A���Y�I���Ɋւ����̕E�]�_���w���̂ł͂Ȃ��A����̌��҂̓��[�ɂ��ėL�����͕s���ɓ��������ꂪ����E�]�_���������̂Ɖ�����̂������ł���B����ɁA�E�K��̍\���v���Ɍ`���I�ɊY������ꍇ�ł����Ă��A�������̐V�����E�G�����^�Ɍ����ȕE�]�_���f�ڂ������̂ł���A���̍s�ׂ̈�@�����j�p�������̂Ɖ����ׂ��ł���(�Y�@35��)�v�Ɣ������A���E�I���@148��3�����I���̌������m�ۂ��邽�߂̋K��ł���Ƃ��A�I���̎��R�̊ϓ_���炢���鍇��������߂��̗p���A�Y�@��̈�@���j�p�̉\�����m�肷��B
����ɑ��āA�I���̎��R�������咣���锻��������B���Ȃ킿�A���E�I���̌��҂ɑ��鈫�]����ᔻ�����f�ڂ����G���ɑ���o�ł̎��O���~�߂̋��ۂ�����ꂽ�A������k���W���[�i�������ɂ�����1986(���a61)�N6��11���̍ō��ّ�@�씻���́A�u�匠�������ɑ����閯�吧���Ƃ́A���̍\�����ł��鍑�������悻��̎�`�咣����\������ƂƂ��ɂ����̏��𑊌݂Ɏ�̂��邱�Ƃ��ł��A���̒����玩�R�Ȉӎv�������Ď��Ȃ������ƐM������̂��̗p���邱�Ƃɂ�葽���ӌ����`������A������ߒ���ʂ��č��������肳��邱�Ƃ����̑����̊�b�Ƃ��Ă���̂ł��邩��A�\���̎��R�A�Ƃ�킯�A�����I�����Ɋւ���\���̎��R�́A���ɏd�v�Ȍ��@��̌����Ƃ��đ��d����Ȃ���Ȃ�Ȃ����́v�Ƃ��A����Ɂu���̑Ώۂ����������͌��E�I���̌��҂ɑ���]���A�ᔻ���̕\���s�ׂɊւ�����̂ł���ꍇ�ɂ́A���̂��Ǝ��̂���A��ʂɂ��ꂪ�����̗��Q�Ɋւ��鎖���ł���Ƃ������Ƃ��ł��A�E�E�E���@21��1���̎�|�ɏƂ炵�A���̕\�������l�̖��_���ɗD�悷��Љ�I���l���܂��@����ɕی삳���ׂ��ł��邱�Ƃɂ��݂�ƁA���Y�\���s�ׂɑ��鎖�O���~�߂́A�����Ƃ��ċ�����Ȃ����̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɣ������A�I���̌��҂Ɋւ���\���s�ׂ́A�����匠�̎����ɕ�d������̂ł�������I�Ȃ��̂Ƃ��A�I�����ɂ�����\���̎��R(���@21��1��)���ő���ɔF�߁A�I���̎��R���m�ۂ���Ƃ��Ă���B���̂悤�ɔ��Ⴊ�I�����̃}�X�R�~�ɂ��āA�I���̎��R�ƌ����̂�������d�����Ă���̂��́A�e�ՂɌ�����A�P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�̌ʓI���f�ɂ���Ă���ƌ��_�t����ȊO�ɂ͂Ȃ��낤�B
|
��6�D������
���{�̃}�X�R�~�́A�@�I�ɂ͉c���Вc�@�l(��Ж@3��)�ł���A���l�̗���ɂ���B����āA�\���̎��R��������̎��R(���@21��)���̌��@��̌�������{�I�ɂ͋��L����Ƃ���Ă���B������}�X�R�~�̎��l�Ƃ��Ă̗������������Ȃ�A�}�X�R�~�����R�l���l�Ɏ���̈ӌ���咣�����̂͂ނ��듖�R�ł���A�܂��A���R�l���l�Ɏ���̈ӌ���咣���������邽�߂Ɋ������邱�Ƃ�(�Ⴆ�A�I���œ�������������邱��)�A���e����邱�ƂɂȂ�B�Ƃ���Ȃ�A��������@����s�����̌��E�͂��邪�A�}�X�R�~�̏��������Ĕے肳���ׂ����̂ł͂Ȃ����ƂɂȂ낤�B�Ⴆ�A�A�����J�̃j���[���[�N�E�^�C���Y��V���g���E�|�X�g�Ȃǂ̑�V���́A�����܂Łgindependent(�Ɨ�)�h�̗���ɂ��B���̂��߁A�A�����J�ł́A�����̑�V�����哝�̑I���ɂȂ�Ɩ���}���������A�x������̂͏펯������Ă���B���Ȃ킿�A�A�����J�s���́A�}�X�R�~�Ɂg�����E������s�Εs�}�̗���h�����҂���̂ł͂Ȃ��A�g����E�Ɨ��̗���h�ɂ������}�X�R�~������̈ӌ���咣�m�ɕ\�����邱�Ƃ����҂���̂ł���B���̂悤�ɁA���Ăł́A�Ɨ��̊Ŕ��f����V�����I���œ�������x�����邱�Ƃ́A�ނ��듖�R�Ȏ��Ƃ��ĎЉ�I�ɔF�m����Ă���m�� 1999: 100�n�B���{�ɂ����ẮA�}�X�R�~�͒����E������s�Εs�}�łȂ���Ȃ�Ȃ����A���ۂ����ł���ɈႢ�Ȃ��Ƃ����l�����������B���̂��Ƃ��A���{�ɂ����ă}�X�R�~���ߐM����Ă��܂������Ƃ��Ȃ��Ă���B������U�͌����ċ�����Ȃ����A�����܂Ń}�X�R�~�͎��l�ł���A�{���A����E�Ɨ��̗���ɂ��邱�Ƃ��Ċm�F���ׂ��ł���B�������A������K�͈ȏ�̋���}�X�R�~�ɂ��ẮA�ʌ̍l�@���K�v�ƂȂ�B���Ȃ킿�A�ꕔ�̌��͉���������}�X�R�~�́A���R�l�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂ́A���ƌ��͂ɂ����䌨�����鋭��ȎЉ�I�e���͂�����(������}�X�R�~�̑�l���͉�)�A�D�ނƍD�܂���Ƃɂ�����炸��������тт邩��ł���(������}�X�R�~�̌��I���i)�B�܂��A�O�q�̃}�X�R�~���ߐM���Ă��܂��Ƃ������{�̕����I���y�Ɋӂ݂Ă��A������}�X�R�~�ɂ͒����E��������s�Εs�}���������x�ŗv��������������A����Ă�����x�̋K������ނȂ����ƂƂȂ낤�B������ϓ_�ɗ����ă}�X�R�~�̏��̖����l����Ȃ�A�ꕔ�̌��͉���������}�X�R�~�́̕A���Ȃ��Ƃ������匠�ɂƂ��čł��d�v�ȑI���ɂ��Ă͕s���ȏ���h�~���āA�����E������s�Εs�}���������邽�߁A���̋K�����s���ׂ��ł���B
���̂悤�Ƀ}�X�R�~�̕\���̎��R�𐧌����悤�Ƃ���咣�ɂ��ẮA�}�X�R�~�̎��Љ�I�L�p�����y��������̂ł���Ƃ��āA�������ᔻ���\�z����悤�B�m���ɁA���̏ꍇ�A���l����}�X�R�~�̗L���錛�@��̌�����s���ɐN�Q���Ȃ��悤�ɍő���̔z�������ׂ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�������A�}�X�R�~�����B���ď���ʂ���A���a�O����Ă������ɂ��Ă��l�тƂ��������ł���悤�ɂȂ�A�����Q���𑣐i���Ė����`�I�Ȍ���ɂ��Љ�z����Ă����Ƃ����A������}�X�R�~�̔��B�������`�Љ�̐��n�𑣂��Ƃ������z�́A18���I�̊v���̐��I�����łȂ��A20���I�ɂ����Ă��J��Ԃ�����Ă����B�������A���̌����́A���ƌ��͂⋐��}�X�R�~�ɂ���삪���s���A�܂��A����i�W�������قǂނ��됭���Q�������ނ��Ă��邩�Ɍ����錻��̌�����l�����킹�Ă��A�����y�ϓI�ɉ߂��錩���ƌ��킴��Ȃ��ł��낤�m��� 1997: 173�n�B�m���ɁA�I���̎��R�͏\�Ɋm�ۂ����K�v������B�������A����͈��̃��[���ɏ]���Ă��邱�Ƃ���O��ł���A�I���̌������m�ۂ��邽�߂̃��[�������O�ɖ��m�ɍ��肵�Ă������Ƃ͂ނ��듖�R�ł���B���̓_�ŁA�O�q�������_�A���Ȃ킿1�I���ɂ����鋕�U��s���ɂ��}�X�R�~���̂ɓ��ʂ̃y�i���e�B���Ȃ��B2�I���ԑg�̎�������������������A�I���ɂ��Ắg�����������h�̂ł͂Ȃ������̂��߂Ɂg���͂������h���Ƃ������Ƃ���B3�I���ɂ����āA�A�i�E���X�����g���ʂ�T�u���~�i�����ʁA�v���C�~���O���ʓ��̎�@�͋֎~����B4�}�X�R�~���g���I���̓ǂ݉��������܂߂������ɑ��郁�f�B�A�E���e���V�[��������H����B5�I�����_�����̎��ݐ�����e�̐^�������m�F���������ۑ������A�����̓K����������I�Ɍ��ł���悤�ɂ���B�܂��A���_�������ʂ̜��ӓI���p��h�~���ׂ��A�q�ϓI�Ȓ������ʃf�[�^�ƃ}�X�R�~���g�̎�ϓI�Ȉӌ��E�咣�Ƃ��A�`���㖾�m�ɕ��������舵����O�ꂳ����B����ɁA�I�����_�����̕��@�ɂ��Ă̓}�X�R�~�̓���I����߁A����ɏ]���đI�����_�������s�킹�铙���܂߁A�}�X�R�~�̑I���������Ȃ��̂Ƃ��邽�߂̓���I�ȃ��[�����肪�K�v�ł���ƍl����B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���V�^�R���i�Ŏ����҂̕s������郏�C�h�V���[�@2020/3
|
���m����؋���������
�ԑg�����C�h�V���[���V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊւ���j���[�X��F���B�u�Ή�����肾�����v�u�Ȃ��������Ȃ��v�ȂǂƁA���{��O��ᔻ�������Ă���ԑg������������B�Ƃ͂����A�����őf�p�ȋ^�₪�N���B���`�̖����̂��Ƃ��U�镑���ԑg�ƃ��C�h�V���[�́A�����������̂��낤���H
�ԑg�̃R�����e�[�^�[�̒��ɂ́A��@�������܂���肾����3��8��(��)�̎��_�ŁA�u�v�����̓C���t���G���U��菭���キ�炢�ł��傤�v�ƁA���l�������B����܂łɂ��u�C���t���G���U����(�̕|��)�v�Ƃ̔��������Ă����l�����Ȃ��Ȃ��B
����8���A�ʂ̕ԑg�ł́A�u���C�u�n�E�X(�ł̊���)������Ă��邪�A����͌o�H���H��₷�����������v�ƁA�f����R�����e�[�^�[�������B���{�̐��Ɖ�c�A�ݖ�̐��Ƃ����Ƃ͖��炩�ɈقȂ�ӌ��������B
�����҂�|���点�Ȃ����߂̔����Ƃ͎v���Ȃ������B����⌤���҂ł͂Ȃ��R�����e�[�^�[�������A�m���鍪�����������A������Ȃ����Ƃ��炯�̐V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ��Ę_����̂͊낤���s�ׂ��낤�B
�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��y�ώ�����悤�ȃR�����e�[�^�[�̐������钆�A3��9��(��)���瓌�������s��̑�\�����n�܂����B3��13��(��)�܂ł̋͂�5���Ԃœ��o���ϊ�����3300�~�������B�R�����e�[�^�[�����̌��t�ɖ��f���A���葹�˂��l���������낤�B
�u���͊������Ȃ�����W�Ȃ��v�ƌ����l���������낤���A�����͘V�㎑���̊m�苒�o�N���ɂ��e��������ڂ��B�R�����e�[�^�[�̌��t�ɂ���Čx���S���ɂ݁A�m�苒�o�N���̃X�C�b�`���O(��������Ȃǂ։^�p���i���ւ�����A������ύX�����肷�邱��)���x�ꂽ�l�������̂ł͂Ȃ����B
���z���͂̌��@
���Ƃ̈ӌ��͑����������������̂��BWHO�d�ǃC���t���G���U�K�C�h���C���ψ��Ōc��`�m��w��w���q�������A�_�ސ쌧�x�F����䂤�a�@��������Z���^�[�Z���^�[���̐��J���v���́A2��18���X�V�́wWeb�㎖�V��x(���{�㎖�V���)�ɂ��������Ă���B���J���͊����w�̌��Ђł���A���E�G�u�͈�w�W�҂̐M���������B
�u�y���҂̊�z�u�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ�SARS�ɗގ�(2)�C���t���G���U�ɔ�ׂ͂邩�ɏd�������v���J���v�@/�@�V�^�R���i�E�C���X������(�ȉ��ACOVID-19)�͍����ł̗��s���뜜�����ɂȂ����B�����ł̐l����l�ւ̊������i�s���Ă���ɂ�������炸�A���{���{����������̓������֎~���Ȃ��������Ƃ́ACOVID-19�̊������A�d�Ǔx���ߏ��]�������d��Ȏ���ƍl������B���łɐ��ۑ�̒i�K�͉z���āA���{�e�n�ɃE�C���X���������Ă���\��������B���{�̃}�X�R�~����т��āA�d�Ǔx�͒Ⴂ�ƕ��Ă������Ƃ��A�킪���̑�̒x��ɉe�������ƍl������B��������COVID-19���S�Ⴊ���ꂽ2��13���Ȍ���A�ˑR�Ƃ��ă}�X�R�~�ŗ���Ă���̂́ACOVID-19�͋G�ߐ��C���t���G���U���x�̊����ǂł���A����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����_���ł���B����͖��炩�Ȍ��ł���B�펯�ōl���Ă��A�G�ߐ��C���t���G���U���x�̎��S���A�d�Ǔx�̎����ł���A���E�ی��@��(WHO)����펖�Ԑ錾�����邱�Ƃ͂Ȃ����A����������Ȍo�ϓI�����ɂ�������炸�A��K�͂ȓs�s���������{����킯���Ȃ����ȉ������@(2��18���X�V�wWeb�㎖�V��x���)�@�v
�u�C���t���G���U���݁v�Ƙ_���Ă����R�����e�[�^�[�͑z���͂��猇���Ă������ƂɂȂ��Ă��܂��B���܂��C���t���G���U���݂Ƃ������Ԃ�̐l�����邪�A����Ȃ�A�ǂ����Đ��E�����������N����A�����ܗւ̒��~�≄������肴������Ă���̂��H�@�����҂Ɍ������ĕ�����₷���ؓ��𗧂Ăĉ�����ׂ����낤�B���ꂱ���R�����e�[�^�[�̖����ɈႢ�Ȃ��B
�������������͋�����Ȃ�
���������R�����e�[�^�[�̔����̍ŏI�ӔC�͋Ǒ��ɂ���B�R�����e�[�^�[�����̈�A�̔����Ɍ�肪����������A�Ǒ��͕����@�Ɋ�Â��A�����������s���ׂ����B�����������͋�����Ȃ��B
��o���W�����P���ŃR�����e�[�^�[���x�ւ̋^��������Ă������͂Ȃ��B�M�҂�2014�N11��19���X�V�́w����r�W�l�X�x�Ɂu�������d���ŋN�p�����e���r�R�����e�[�^�[�����̊낤���v�������A������]���k��s�̌������wGALAC�x��2015�N3�����ɂ́u�R�����g�ɐ�含�͕K�v�Ȃ��̂��v�Ƒ肵�����͂���e�����B�e�[�}�͂ǂ�����ꏏ�B�u��O����������邱�Ƃ̊댯���v�������B
�R�����e�[�^�[�������̐�啪������͕̂�����B�R�����e�[�^�[�������ґ�\�Ƃ��Ĕԑg���Ő��ƂɎ��������Ƃ����`���������ł���B�Ռ��f��������ȉf���ɂ��āA���܂��܂ȗ���̃R�����e�[�^�[���������₩�Ɍ�荇���̂����Ȃ�����B
���ʁA1�l�̃R�����e�[�^�[�������牽�܂Ō��A�����Ė��m�̐V�E�C���X�܂Ř_����ƂȂ�ƁA�N���ǂ��l���Ă�����������B��_�ɂ���������B�Í������A�m�̋��l�ƌĂꂽ��l�����ł���A����Ȗ����Ȃ��Ƃ͂��Ȃ����B
�܂��ĐV�E�C���X�ɂ��Ă̏��͌��N����A��炵�ɒ�������B�s�m���ȏ����y�X�Ɍ��ɂ���R�����e�[�^�[�́u�댯�v�ǂ���̑����ł͂Ȃ��B����������Ă���Ǒ������ӔC�̔��͖Ƃ�Ȃ��B
���܂����������ҕs�݂�����
���̂悤�ȃ^�C�g���̓��W�L�����w���Y�t�H�x2014�N11�����ɍڂ����B�u���C�h�V���[�w�������킵���̐��́x�^�Љ�����A����������---�B�e���r�R�����e�[�^�[�̉����̔���v
�������̂͋��喼�_�����̒|���m���B���v�z�j���܂Ƃ߂��w�v�V���z�̐��j�x�ɂ����2012�N�ɓǔ��E�g��쑢�܂���܂����A���{���\����m���l�̈�l���B�|�����̓��C�h�V���[����ԑg���悭����ق����Ə������B�Љ�l�^����|�\�l�^�܂ő����Ă���A����m��̂Ɋi�D�����炾�B
�����Ƃ��A�|�����̓R�����e�[�^�[�̌��t�Ɏ���݂��Ȃ��B���̗��R���A�u�����������ԑg�̃R�����g�͈�˒[��c�Ƃ��č���Ă�����̂����炾�v(���Y�t�H2014�N11�������)�ƁA�]�����B
�m���Ɉ�˒[��c�I�ł���B���̎����͕ԑg�A���C�h�V���[�̐^��������Ă���ɂ�������炸�A�R�����e�[�^�[���m�̃P���J�܂ł���̂�����B
3��12�������̂��郏�C�h�V���[���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�����ǖ��������Ă���ہA2�l�̃R�����e�[�^�[�����݂��ɑ���̌��t���^���A�������Փ˂����B����ւ̐l�i�ᔻ�Ƃ������ʂ�����A���Ȃ��Ƃ��c�_�ƌ�������̂ł͌������ĂȂ������B
�ԑg�I����̔��ȉ�łԂ���̂Ȃ炢�����낤���A�����҂Ɍ����ĕ������Ă���ԑg���ŏՓ˂���͔̂�펯�ɂ܂�Ȃ��B�R�����e�[�^�[�̈ꕔ�͐�含���R������A�v���ӎ�����Ȃ��̂��낤���B2�l����荇������A������Ă������Ƃł��銴���w�҂͎����Ă����B�܂����������ҕs�݂������B
���R�����e�[�^�[���x�������i���́c
�����܂ł��Ȃ����Ƃ����A�R�����e�[�^�[���x�Ȃ���̂����݂����i���͓��{�����B�����̎����҂��^�����������Ă���B�V�^�R���i�E�C���X�����ǖ����_�@�ɁA�݂�����l�������Ă������̂ł͂Ȃ����\�\�B
���āA�w�^���� �o���L�V���I�x�̏���R�����e�[�^�[�͌������n�����{�����̌́E�͏�a�Y�������B�@���͂������A�s���ɂ����ʂ��Ă����B���Z�͏����h��Ƃ̎O�D�O����B�͏コ����܂��������l�������B
�w�o���L�V���I�x�ł̉͏コ��͓���Ȗ@����s���̎d�g�݂���₷������������A�s�����������Ƃ猠�͎҂ɂ͌����������B��ۓI�������̂́A�����t���قǂ̔����Ƃ������ɂ�������炸�A�u����͕�����܂���v�ƌJ��Ԃ������Ă������ƁB
�R�����e�[�^�[�͐��O�̂��Ƃɂ��ẮA�u������Ȃ��v���S�O�Ȃ������ׂ��ł͂Ȃ����B����ɂ���Ď����҂͕s���v��Ƃ��B���Ȃ��Ƃ��V�^�R���i�E�C���X�����ǂ͖�O���̃R�����e�[�^�[�ɂ͎苭������̂�����B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���u�}�X�S�~�v�Ƃ����̏̂܂ŐZ���@�l�̓��f�B�A�̕ɕ��������@2020/10
|
���u�}�X�S�~�v�Ȃ�Č��t���g���ċv�����Ȃ���
�u�}�X�S�~�v�Ƃ́A�e���r��V���E�G���Ȃǂ𒆐S�Ƃ���}�X�R�~��ᔻ�I�ɕ\������ۂɗp����̏̂ŁA�l�b�g�X�����O�̈��ł��B�}�X�R�~�ƃS�~�̍�����ŁA�܂�A�S�~���R�ƕ��̂��Ă���̂ł��B
���ɁA����̐V���Ђ�e���r��(�ԑg)������I�ɑ��ʂɏグ���Ă��܂��BSNS��ł́A2�T�Ԃ�1��́u�}�X�S�~�v�l�^�ʼn��サ�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����āA�ŋ߂ł́u�}�X�S�~�v�Ȃ�Č���Ȃ��l������A�u�������Ȃ��̂��v�Ɣᔻ����Ă���̂��A���f�B�A�̍��܂łɂȂ��X���ł���ƕM�҂͍l���Ă��܂��B�}�C���h�ȃ��f�B�A�ᔻ���s�������ƌ����Ă����ł��傤���B���f�B�A�́A�ǂ�Ȕᔻ�����Ă��ǂ��ΏۂƂ��ĔF�m���ꂽ�Ƃ������܂��B
���̍ł����Ƃ��ċ�������̂́A�u���f�B�A�͕��Ă���v�u�}�X�R�~�ɂ͕��Ȃ����R������v�Ƃ������Ό��ᔻ�ł��B�č��ł͑哝�̂�SNS����g���ė��悵�āA�}�X���f�B�A�̕��t�F�C�N�j���[�X�ƘA�Ă��Ă��܂��B���{�ł��ʋ�̓I�Ȏ���ւ̌��y�͔����܂����A������Љ�j���[�X�ŕΌ��Ƃ����ᔻ�������N����܂����B
�����x���`���[�ł�����JX�ʐM�Ђɓ��Ђ��Ĉ�ԋ������̂́A�u�Ό�����߂�v�Ƃ��������[����d�b������I�ɗ��邱�Ƃł��B�A���S���Y���ŋL����z�M����j���[�X�L�����[�V�����A�v���ł����Ă��u�L���̃`���C�X�ɜ��Ӑ���������v�Ƃ������R�Ŕᔻ����܂��B���̔��z�͂Ȃ������ȁA�Ƌ����܂����B
���������A�Ȃ��l�́u���f�B�A�͕��Ă���v�Ɗ�����̂ł��傤���B�����āA���̐S���ǂ�ǂ�i������ƁA�����N���邩�ɂ��čl���Ă݂܂����B
�����������u���Ă���v�Ƃ͉����H
���ۂɁu���f�B�A�Ɛ��������т��Ă���v�Ƃ����j���[�X���������܂����A�����ł́A���̏ڍׂɂ��Ď�|�ƈႤ���ߐG��܂���B�܂��́A�����������Ă���Ƃ͉�������l���Ă����܂��傤�B
������O�ł����A�u�t�@�N�g(����)�v�Ɓu�I�s�j�I��(�ӌ�)�v�͈Ⴂ�܂��B�t�@�N�g�͖{���ɂ������o�����ł����A�I�s�j�I���͌l�̈ӌ��ł��B�t�@�N�g�͐^�U���ؖ��ł��܂����A�I�s�j�I���͓��Ă��Đ^�U���ؖ��ł��܂���B�˂��l�߂�t�@�N�g�͎��Ԃ�����A�I�s�j�I���͎��Ԃ��Ȃ����Ƃ������ł��B
�ł́A�}�X�R�~(���f�B�A)���u���Ă���v�Ƃ����w�E�́A�t�@�N�g�ł��傤���A�I�s�j�I���ł��傤���B
�Ⴆ�AAgenda note�̏�A�Ƃ��āuPG�}�t�B�A�v�ƕ]�������X���悭�����������܂����ANewsPicks�Ȃ痎���z�ꂳ�悭�o�ꂵ�܂����A����������Ċe���f�B�A���u�Ό����f�B�A�v�u�������Ɍ�����v�ƌ�����ł��傤���B���������u�悭����v�u�悭�o�ꂷ��v�̓t�@�N�g�ł͂Ȃ��A�l�̎�ςł��B���Ă���ƌ����Ȃ�A�N�ɓo�ꂵ�Ă��炤�ׂ��ł��傤���B
Agenda note���ɂ�����A��B�̒P�i�ʔ̗̂Y�ƌ�������X�A�t�@���x�[�X�}�[�P�e�B���O�̃O��(�t)�Ƃ���������X���o�ꂳ��Ă��܂��B�u�������o�Ă��Ȃ����炨�������v�Ɣᔻ����ƁA��������̎��}�h��������镪�����A���ǂ́u���Ă���v�ƕ]�����̂ł��B����͂܂�A�u���Ă���v�Ƃ����̂��l�̃I�s�j�I���̈���o�Ȃ����Ƃ̏ؖ��ł�����܂��B
�����Ɠ����ŁA���U�����Ă���킯�ł������̂Ɂu���Ă���v�Ɣᔻ�����ꍇ�̑����́A�t�@�N�g�ƃI�s�j�I������������Ă���̂ł��B���̗��R�Ƃ��āA�G�ΓI���f�B�A�F�m�ƌĂ��u���f�B�A�������Ƃ͔��Α��̐w�c�ɂƂ��āA�L���ȕ����ɘc��ł���v�Ƃ����F�m�̘c�݂Ɋׂ��Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B
�����ŁA���鎖������Љ�����Ǝv���܂��BVallone��(1985)�́A1982 �N�Ƀ��o�m���̃p���X�`�i�l��L�����v�ŋN�����C�X���G���n�����g�D�ɂ��p���X�`�i�l�s�E�������ނɁA����������s���܂����B
�S���������e���C�X���G�����̐l�ƁA�p���X�`�i���̐l�Ɍ����āA���̔����ׂ��̂ł��B���̌��ʁA�C�X���G�����̐l�����́u���C�X���G���ɑ��Ĕᔻ�I�ł���v�ƔF�m���A�p���X�`�i���̐l�����́u���p���X�`�i�ɑ��Ĕᔻ�I�ł���v�ƔF�m���Ă��܂����B
��̓I�Ȑ����Ō����A�̓��e�ɂ��āA�C�X���G�����̐l�̓C�X���G���Ɋւ��錾�y��16�����C�X���G���ɗF�D�I��57���͔�F�D�I�ł������Ɖ��A�A���u���̎Q���҂͕��ς��ăC�X���G���Ɋւ��錾�y�� 42�����C�X���G���ɗF�D�I��26������F�D�I�ł������Ɖ��܂����B�ǂޑ��������x�����邩�ŁA�������e���܂�ŕʕ��̂悤�Ɏ~�߂�ꂽ�̂ł��B
���̂悤�ɔF�m���c�ތ����Ƃ��āA�u1 �q�ϓI�Ō��������S�ۂ��ꂽ�̋�̓I�ȓ��e���A���w�c�ɗL���Ȍ`��z�肵�Ă���v�A�u2 ���ꂽ���e�ɂ��āA���w�c�ɑ��ăl�K�e�B�u�ȏ���D��I�ɒm�o���Ă��܂��v�Ƃ�����̃��J�j�Y������p���Ă���ƌ����Ă��܂��B
Vallone��̎����ȍ~��Perloff(1989)�AGiner-Sorolla & Chaiken(1994)�AArpan & Raney(2003)�ȂǁA���܂��܂Ȍ㑱�����ł��́u�G�ΓI���f�B�A�F�m�v���m�F�ł��܂��B
���Ȃ킿�A���f�B�A�Ɍ����āu���Ă���v�ƌ����Ă��鎄���������l�Ɂu���Ă���v�̂ł��B
���u�F�m�̘c�݁v�ɋC�t���邩�H
�G�ΓI���f�B�A�F�m�̘b������ƁA���܂��āu���͘c��ł��Ȃ��I�^���������I�v�Ɣ������������吨���܂��B�u��v�Ƃ������t���l�K�e�B�u�ɕ������Ă���悤�ł����A�����ɕ����f�ł���q���[���X�e�B�N�X�Ȏv�l����̂ЂƂł�����A�S�Ă����Ƃ͌�����܂���B�ނ���u��v�Ƃ͐l�Ԃ炵���A����l�Ԃ��̂��̂Ƃ��猾���܂��B
���͕Ό������Ȃ��Ǝ咣����v�l���u�o�C�A�X�̖ӓ_�v�ƕ\�����܂��B�u�吺���o���ȁI�Ƒ吺�Œ��ӂ���l�v��A�u�l��ᔻ����z�͋����Ȃ��I�Ɣᔻ����l�v���v�������ׂ�Ɨǂ���������܂���B�����ƍs������������l�����́u�o�C�A�X�̖ӓ_�v�Ɏ����Ă���̂ł��B
�t�@�N�g�͂ЂƂł����A�I�s�j�I���͂��������Ă��ǂ��ł��傤�B�u�o�C�A�X�̖ӓ_�v�Ɏ����Ă��܂��ƁA�I�s�j�I�����Ⴄ�����Łu���̐l�̓E�\�������Ă���v�Ɣᔻ�������ł��B�܂��A�I�s�j�I�������������A���ꂪ���������t�@�N�g�̂悤�ɐU�镑���̂ŁA��������������ł��B
�]�k�ł����A�t�@�N�g�ƃI�s�j�I���̋敪�͕Ɍ��炸�A�����镪��ŕK�v�ȁg�X�L���h�ł��B�����̂悤�ɌJ��Ԃ��āu�t�@�N�g���A�I�s�j�I�����v���čl����ƁA�������g�������ɕΌ��Ǝv�����݂Ɏ����Ă��������v���m�炳���̂ŁA�ǂ��P���ɂ��Ȃ�܂��B
���������}�[�P�^�[�́u�}�X�R�~�s�M����v�ɉ����ł��邩
���f�B�A�̍����́A�u�M���v���ƕM�҂͍l���܂��B�V���ɂ���A�e���r�ɂ���Web�}�̂ɂ���A���̔}�̂ɑ���M�����Ȃ���A������^���ɔ���ł������Ƃ��Ă��P�Ȃ��k��^���b�ōς܂���Ă��܂��܂��B
�Ƃ��낪�}�C���h�ȃ��f�B�A�ᔻ�����炭�������������ŁA���̐M�����������ʑ�����n�߂Ă��܂��BSNS�̋����g�U�͂����܂��āA�G�ΓI���f�B�A�F�m�ɂ�胁�f�B�A�ɑ���s�M�������Ȃ��Ă��܂��܂����B
�ŋ߂ł́A����̐V���Ђ�e���r�ǂ̔ԑg�ɍL�����o�e���Ă���Ɓu�����v�z�̎����傾�v�ƃ��b�e�����������āA�ꍇ�ɂ���Ă͂��q���ܑ��k�Z���^�[�Ɂu�d��(�d�b�������čR�c�E�ᔻ���邱��)�v�����n���ł��B���̏́A�ʂ����Č��S�ł��傤���B
���f�B�A�_������قǁA�m���ƌo�����L�x�ɂ���킯�ł͂���܂��A�����������}�[�P�e�B���O�Ɍg���l�ԂƂ��ĖT�ς��Ă��ǂ��̂��A�������ɋ^��Ɋ����n�߂Ă��܂��B
�M���ł��郁�f�B�A�ɍL�����o�e���邩�炱���u�M���ł���T�[�r�X���v�ƔF�m�����̂ł���A�M���������Ȃ�A�l���ǂꂾ���W�܂낤�Ɠ����悤�ɐM���͓����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ɂ₩�ɐI�܂�Ă������f�B�A�Ƃ����u�����h���A��ƂƂ��āA�ƊE�Ƃ��āA�ǂ̂悤�ɐM���ɓw�߂Ă����̂��͑傫�ȉۑ�ł���A���̈Ӗ��ɂ����ėႦ�A������J���ꂽ�É��V���̃C�m�x�[�V�������|�[�g�͔��ɓǂ݉���������܂��B
�u������(���f�B�A)���Ȃ�Ƃ�����ׂ����v�Ƃ����̂͂��̒ʂ�Ȃ̂ł����A���N���Ă���n�k�ϓ��́A�����҂����ʼn��Ƃ��Ȃ�b�ł��傤���B
�����������̂́A�ǂ��炩�ƌ����L�҂̕��������̂ł����A�u���߁v�u���u�v�u�����v�Ƃ����ӌ������ɑ�����ۂł��B���Ƀ��f�B�A�ᔻ�͓}�h�����Ă���̂ɁA���܂łƈꏏ�ŗǂ����P���Ȃ��Ǝv���̂ł����c�B
������4�N��A5�N��ɁA���̋L�����������āu����Ȃ��Ƃ��������ˁv�Ə��b�ɂł���悤�Ȏ��ԂɂȂ�Ηǂ��̂ł����A�M���̒[���͍��̂Ƃ���悭������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ���ł��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����[���[�E���o�[�g�\������́u�e���r�ƊE�ւ̈ӌ��\���v�ōl�������Ɓ@2020/9
|
�@��X�e�}�ɕΌ�����ނ��~�܂�Ȃ��e���r�ǂɑ��H��3�̖��
�t�W�e���r�n���̏��ԑg�w�Ƃ��_�l�I�x�ɑ�����5�N�A�R�����e�[�^�[�Ƃ��ďo�������Ă��������Ă��������A�����̑̒��s�ǂŎ���Ƒ��̉�삪�K�v�ɂȂ�܂��āA�ǂ����Ă����̎��Ԃ��т���������ԑg�̏o�����ނ������Ƃ������ƂŁAMC�̏��q�q�������W�҂̊F����Ɂu���݂܂���A���������Ĕԑg�͂����o���Ȃ��Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�~�낳���Ă��������v�Ƒ��k�ɍs���܂����B���傤�Ǐ��q��������̒����F�����Ȃ��Ƃ��������ł�����A���k�ɂ������������k����قǒ��J�Ɂu�����ԁA���肪�Ƃ��������܂����B�܂��o��ꂻ���ɂȂ����琥��Ăт܂��̂ŁA�����Ȃ��A�����������v�Ƃ��Ή����������āA���ɂ��肪���������ł��B
���ԑg���ƂɁA����̍l�������傫���e�����Ă���
�w�Ƃ��_�l�I�x�Ƃ����͕̂s�v�c�Ȕԑg�ŁA�u���E���ǂ�t���z���ɂ́u���q��Ɓv�̂悤�Ɍ����铝���̎�ꂽ���͋C�Ƃ͕ʂɁA���̔ԑg�ł����킹�Łu������Ă��������v�Ƃ��u��{�ʂ�ɂ���Ăق����v�ƌ����邱�Ƃ͈�������܂���ł����B�����A�ł��B
�����炭�̓e���r�ǁE�ԑg�̕��j��A���S���̃v���f���[�T�[��f�B���N�^�[�ȉ�����w�̂��l���A���邢�͏��q����ȂǏo�����Ă�����X�̏��ɑ���p���Ȃǂ��傫����^����Ƃ���͂���̂ł͂Ȃ����Ǝv����ł���ˁB
����ŁA�e���r�����n��ŕ������Ă����w�����~�H���̔ԑg�x�Ƃ����ԑg�ɌĂ�Ă������Ƃ���A���O�̑ł����킹�ł͂����܂Ńe�[�}�Ƃ��č������Ă��Ȃ������u�l�b�g�ł̋����ᔻ�̑�\�ҁE�R�{��Y�v�݂����Ȏ��グ�����œˑR���^���n�܂�A�܂����i�����Ȃ����Ƃ������Ă悢�̂Ȃ�撣���Ē��邩�ƑΉ����Ă������̂́A���ۂ̕����ł͎������������e�͂قƂ�ǃJ�b�g����A�܂�ŋ����O������I�Ɏ���_�j���Ă��邩�̂悤�ȓ��e�ɂȂ��Ă��ăr�b�N�������킯�ł���B
�������ɂ���͂Ȃ����낤�ƁA�e���r�����ɂ����ǂ̗F�l�ɂ����k�b�����Ă��邤���ɁA�̐S�́w�����~�H���̔ԑg�x���������̒���ƂƂ��ɏ��������ł���ɂȂ��Ă��܂��A�L�떳��ɂȂ��Ă��܂����͎̂c�O�ł��B����ŁA�e���r�����̐���w�̕��X����͎Љ���ɂ��Ă̂��₢���킹��T�[�`�ł̂��d�b��Ղ����Ƃ������A�e���r�ǒP�ʂƂ������́A�{���ɂ��̔ԑg���Ƃ̍���̍l�������A�N�p����L���҂�W���[�i���X�g�A�����ƁA�^�����g�Ȃǂ̋N�p�@�ɑ傫���e��������̂Ȃ̂��Ǝv����ł���ˁB
�����[���[�E���o�[�g�\�������c�C�[�g�ŋ����[���ӌ��\��
�ŁA9��1���Ƀ~���[�W�V�����Ƃ��Ă������ȃ��[���[�E���o�[�g�\������SNS��Ńe���r�ǂł̎g�����ɑ��Đ錾�����Ă����ċ����[�������킯�ł��B
�����ł����A���[���[����̘_�l��ǂ�ł݂Ă���������Ǝv���܂��B����A���炭�����̓d�g���g���ēƐ�I�ɔԑg���Œ��A���|�I�ȃ��f�B�A�p���[���ւ��Ă����e���r�ǂ��A�l�b�g����̋����ƂƂ��ɋP���������Ă����ߒ��Ŕԑg�̕i���ł����͂ł����̔}�̂ɕ����n�߁A���x�̗ǂ��Ȃ������N�̈����Ȍ�y���x���ɂȂ��Ă��܂������Ƃm�Ɏ������Ă��܂��B
���s���Y�����e���r�ǂ����˂Ă���o�c
���̌��ʂƂ��āA�X�|���T�[������i��ł����A�e���r�ǂ̎��v�͑傫������B������肩�A�e���r���ςĈ�����Ⴂ����̌����ƂƂ��ɁA�A���Ől�C�̊�ƃ����L���O�ł͏��50�Ђ���e���r�ǂ̖��O���������Ƃ܂ŕ���悤�ɂȂ�܂����B�������A�����̎��v���̖���A�l�C��ƃ����L���O�̂悤�Ȑ��������Ńe���r�ǂ�_����ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��v���܂��B���������A�e���r�ǂ͔ԑg�����X�|���T�[�����ĕ�������Ƃ������Ƃ��́A���x�����ƂƂ��ɒ��N�������Ă����s���Y�̎��v�̂ق������肵�Ă���A�e���r�ǂ��������Ƃʼn]�X�Ƃ��������s���Y�����e���r�ǂ����˂Ă���Ƃ����悤�Ȓ����V���Ѓ��\�b�h�̂ق����o�c������ꍇ���m�Ȃ�Ȃ����Ƃ���v���܂��B
���[���[�E���o�[�g�\������̘b�ɕ~������`�Ř_����Ȃ�A���͎��3�̘_�_�Ńe���r�Y�ƍl���i�قɂ��Ȃ���Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B
���_�_1. ���C�h�V���[�̂悤�ȏ��Ő��̒����ɓ��������Ƃ����
��A�̃R���i�E�C���X��ł��e���r�͂��܂��܂Ȍ`�ō����ɏ������Ă��āA������ꂪ���ɗ������ʂ͂���̂ł����A����ŁA���炩�ɃR���i�E�C���X�̂悤�Ȋ����ǂ̐��Ƃł͂Ȃ��A�܂��A���O�q���̒m�����Ȃ��l���P�Ɂu��t�v��u�����ҁv�Ƃ��������꒚�ŏo�����āA���ɕ����R�����g�����Ă���Ⴊ�U������܂��B
��\�I�Ȃ͔̂�鷗��w�����Ō��O�q���̐��ƂƂ��đ����̔ԑg�ɏo�����Ă������c���b����ŁA���ł��u�R���i�E�C���X�A���������Ǝ��O�����匙���ł�����A���ɂ͂Ȃ��ė���Ǝv����ł��ˁv�Ɨ^�������A��ÊE�G�ő�ςȑ����ɂȂ����̂͋L���ɐV�����Ƃ���ł��B�����ɂ̓t�@�N�g�`�F�b�N���厖�Ƃ������Ă���ꍇ�ł���Ȃ��B���������K�Z�l�^�ł�����B
����ɁA�e���r�ʼn҂���Ǝv�����̂��͕�����܂��A���x�͑��|�\�������̃��^�i�x�G���^�[�e�C�������g�����c���b����̃}�l�W�����g�܂Ői�o���Ă��܂��B�^�����g�Ƃ��Ă̖ʔ���������Ǝv���Ă̂��Ƃ����m��܂��A�����ɐ��炸��������K�v�Ƃ����R���i�֘A�̘b��ɂ����āA�e���r�ǂ����m�������b�萫���d�����ċN�p��������̂ł���Ƃ������̓��o���킯�ł��B
���m���̂Ȃ��^�����g�E�|�l�̕s�m���Ȋ��z�Ŕԑg���
�����āA���C�h�V���[�ȂǏ��̔ԑg�ł��肪���Ȃ̂́A����������舵���Ă���ɂ��ւ�炸�o���G�e�B�I�ɕ������邱�ƂŎ����҂ɏ���͂��邱�Ƃ��u������܂��v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���X���ł��B��ʐl�̋C�������ق���Ƃ̌��O�̌��A�m���̂Ȃ��^�����g��|�l���s�m���Ȋ��z����𗬂��Ęb����������Ă��邾���ł���Ƃ����B
�R���i�E�C���X�֘A�̕��悤�₭�����̊ԂŖO����ꂽ�ƒm���A�����}���ّI���s���邱�Ƃ����܂��Ă���͂��̃j���[�X��F�ɂȂ��Ă����܂��B �ݓc���Y����A���`�̂���A�Δj�����A����₷��3�l�̃v���t�B�[����G�s�\�[�h�Ȃǂ����J��ɗ����A����ɂ��ďo���҂����z���q�ׂ邾���Ŕԑg���������Ă��܂��Ƃ������x�̒Ⴓ�ŁA�������Ɂu���̕i���̏������Ă��Ȃ��Ă��ǂ��Ƃ��鎋���҂����e���r���ςȂ��Ȃ邾�낤�v�Ƃ������[���[����̊뜜�͓������Ă��܂����˂܂���B
�ꎖ���������̂悤�Ȕԑg�̍����Ŋe�lj����тŁA�ǂ���萔����������A���ꂽ�A�Ƌ����Ă��邽�߁A�e���r�ȊO�̌�y�Ɏ����҂�����A�����K����������������I���ł��B���̊�@���̓e���r�ǂɂ�����̂ł��傤���A�l�b�g�������܂߂ĕʂ̃Q�[���`�F���W���[���Ⴂ�����҂��e���r�̑O���獪�������D���Ă��܂�����łǂ��ɂ����悤�ƌ����Ă��Ȃ��Ȃ������ł��B
���_�_2. �u�ԑg�Ŏ��グ���܂����v��U������X�e���X�}�[�P�e�B���O����߂�
����ɂ́A�I���ɏ��i��T�[�r�X��ԑg�Ŏ��グ�邱�ƂŁA���ՂɎڂ߂郍�P�����@������Ă���悤�Ɏv���܂��B�Ƃ����̂��A�ŋ߂͐헪PR��Ђ����Ȃ�ϋɓI�Ɂu���̔ԑg�Ō�Ђ̏��i���Љ�܂��v�Ƃ��������A�����������Ă���ɂ�������炸�ԑg���ł͍L���Ɩ��ł��Ȃ��Ƃ������m�ȃX�e���X�}�[�P�e�B���O�����s���Ă��܂��B
���ہA���T�[�`�̎d��������Ă���Ƃ��ɐ헪PR��Ђ�L���㗝�X�ȂǕ����̉�Ђ���u�ԑg�Ō�Ђ̏��i�����グ�Ă��炤���߂̍L���\�Z���o���܂��v�Ƃ�����Ă͕p�ɂɂ���Ă��܂��B����A���炩�ɍL���c�Ƃł���ˁB�������A�L���Ƃ͖��ł��Ȃ��^�C�v�́B
�ԑg�����������Ȃ�A�o�����Ă���l�����̃M�����������Ƃ����b�肪�悭�o�����ŁA���������Ƃ���Ŕԑg�����J�l�����A������P�o���Ă���̂��Ƃ���Η܂��܂����w�͂��Ƃ������܂��B���A�������A�����͒P���Ɍi�i�\���@�ᔽ�A�����@�ᔽ�ł����āA���蓖�Ă�ꂽ�c�Ƙg���Ēʔ̂�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������肷��������A�v���[�`�ɂȂ��Ă��Ė��ł͂Ȃ����Ǝv����ł���ˁB�u���̔ԑg�̃R�[�i�[��800���~�̃X�|���T�[���Řg��������v�Ƃ����b�����܂��ɏo��͓̂s�s�`������Ƃ͊�����ꂸ�A�������ɋ݂𐳂��ׂ��ɂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���������������l
�|���āA�����̒������Ƃ����ϓ_������e���r�ǂ��ϋɓI�ɓ���̐��}������������A�����I�ɗU������̂͋�����邱�Ƃł͂���܂���B�������Ȃ���A�����Δj����Ƃ͐��������������Βk�Ȃǂ���点�Ă��������Ă��Đe�����Ǝv���Ă���̂��A�ԑg�ŐΔj������ǂ�ǂ���グ�����̂ŐΔj����̃G�s�\�[�h�������Ă��������Ǝ�ނ���܂��B
�����āA���ۂɕ������ꂽ�ԑg���ςĂ���ƐΔj�������}�̉��v�҂ł����}�����Ƃ⍶���n�����ƂƂ��n�荇����l�����Ƃ����`�ŕ��Ă���A�q�ϓI�Ɍ��Ă��u�}�����[�Ȃǂ��s���Ȃ������ł͂Ȃ������}���ّI�ŗ��I��������Δj�͉��z�����A���`�̂����ɑ��ّI�ɏ����Ă��������͂Ȃ��v�Ƃł������������ȓ��e�Ɏd�オ���Ă��܂��B���܂�ɂ��_�C���N�g�����Ăт����肷��킯�ł����A�X�e���X�}�[�P�e�B���O�ł�����������ł�����͓����ŁA����̈ӎu���s�����Ȍ`�Ŕ��f����߂��Ă�����A�s�K�Ȏ��v�ɒ�������悤�Ȕԑg���͂�낵���Ȃ��낤�Ǝv���킯�ł��B
�ʂɂ��ׂĂ̏��o���G�e�B��NHK�X�y�V������C�O�j���[�X���f�B�A�̂悤�Ɏd�グ��ƌ��������킯�ł͂Ȃ��̂ł����A����̃������Ɣԑg�̕i���̖��͂����Ƃ�������l���Ȃ���Ȃ�܂���B
���_�_3. �ƊE�̍\�����ς���Ă���̂ɓ����d�g�݂ō�葱����̂���߂�
����\���ł́A2020�N��ʂ���Netflix�̓R���e���c����̂��߂̗\�Z������173���h��(��1��8,400���~)�𓊎�����ƌ����܂�Ă��āA���炭���n�̃R���Z���T�X�ł�150���h��(��1��5,800���~)���炢���낤�Ƃ���Ă��܂��B
�������傫�����ăC�}�C�`�����ɂ̓s���Ƃ��܂��A�䂪���̃e���r�ǂƂ����Ӗ��ł͎������̑吳�`�ENHK�l�̕����o��S�̂�3,460���~(2018�N)�قǁA�����A�^���̃R���e���c�����͔N��2,770���~(��)�قǂł��B�����͂ƌ����A���{�e���r�����Ԃ�977���~�A�e���r������874���~�ł����āA����ł��������g�̐���o��팸�������Ă��Ƃŏo�����Ă���^�����g�M���������炻���Ƃ������Ă���킯�ł�����A�܂������ł��ł��Ȃ���˂Ƃ����b�ł�����܂��B�����1���~�ł���A1���B
�܂�́A�n��g�Ƃ��������̓d�g�œ��{�����ÁX�Y�X�Ƀe���r�ԑg���œ͂��Ď��v��Ƃ����r�W�l�X���f���͐����D��Ă����̂ł����ƐL�тĂ�������ǁA���ɐl���������n�܂����A�C���^�[�l�b�g�ŋC�y�ɓ�����ς���悤�ɂȂ����Ƃ����\���̕ω��Ŏ����҂��ǂ�ǂ��Ă����܂����B�����̎����҂Ɍ��Ă��炦��O��Ŋ����Ȓl�i�ōL����ł��Ă���Ă����L������A�������ɃJ�l�̂Ȃ������N�j���̌�y�ɂ����Ȃ��Ȃ����e���r�ԑg�Ƀ_���_���Ə��i��u�����h�̍L�����o��������قǂ̂��l�悵�ł͂Ȃ��Ȃ����A�Ƃ����̂����ۂł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���C�O�ɐi�o���Ȃ����
�������A����ȏ�ɖ��ƂȂ�̂͂��������u���{�̐��x���ŁA�d�g���ɂ���ċK�����ꂽ�ƊE���A���{�l�Ɍ����ăX�|���T�[�h�x�[�X�̃R���e���c�̐��𑱂��Ă����v���Ƃ̐���́A�_�C���N�g�Ɂu���E�ɂ������{��b�҂ɑ���}�[�P�b�g���܂��������ɂ����Ă��Ȃ��A��i�I�ŕ��I�ȃe���r�ǂ̑ʖڂ�����o�c�v������ɂ����Ƃ������܂��B���܂܂Ŗׂ����Ă������疳���ɊC�O�ɖڂ�������K�v���Ȃ������̂��A�l�b�g����S���̓����ƂƂ��Ɏ��g�̎��v�����������ׂ�n�߂Ă���Q�Ăāu�C�O�ɂ������R���e���c���v�ƌ����Ă��A���쎑���̒��B����i���S�ہA���E�I�ȃR���e���c�u�����h�m���̎�i�ɂ�����܂ʼn�����t�����ŋC�Â��ʊԂɕ����g�ɂȂ��Ă����̂��Ǝv���̂ł��B
���낤���āA���{�e���r�������i�K����C�Â��ăf�B�Y�j�[�Ƃ̎��g�݂�Hulu���T�[�r�X�J�n�������̂́A���ǂ͂�����������Ȃ��Ȃ���ςȂ��ƂɂȂ��Ă��܂��B�t�W�e���r���Ǝ���FOD�����A�e�Њ撣���Ă�����̂̌��ǂ͎��O�ł���Ă���e���r�ԑg�̌������������l�b�g�ōĔz�M�ł��郌�x���̃r�W�l�X�ɂƂǂ܂�A�W���p���u�����h�̃R���e���c���C�O�z�M�ł���悤�ɂ��悤�Ƃ��A�C�O�̃v���b�g�t�H�[���Ƃ̘A�������߂Đ��E�I�Ɋy���߂�R���e���c�u�����h�𗧂��グ�悤�Ƃ����b�ɂ͂܂������ƌ����Ă����قǂȂ�܂���B���{���b�����{�l�ɂ����{�s��ŏ\���Ȏ��v�Ă������Ƃ��A�w�ɂȂ�Ƃ����̂͂����������ƂȂ낤�Ǝv���܂��B
���ʂƂ��āA�C�O�s��ł̃R���e���c�z�M�ɂ����ẮA�ނ��낢�܂܂ł���n���ɂ��Ă����؍��̃G���^���ƊE�ɕ����Č�o��q���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B������O�̂��Ƃł����A�؍��̐l���͂���������{�̔����B�C�O�ɏo�Ă����Ȃ������Ă����Ȃ��K�͂̌o�ςł���A��������{�̃e���r�ǂ͂��܂܂ł����Ɠ��{�s�ꂾ���ł��\���ɉ҂���D�NJ�Ƃł���Ɠ����ɕs���Y�������e�Б傫���̂Ŋ�@��������ʂ����ɊC�O�Ƀ{���������Ă����o�܂�����܂��B
���[���[�E���o�[�g�\�����e���r�ǂ̑̂��炭��������Ă�����e�ŁA�ǂ�ł��鎄���u�����c�c�v�ƕG�ł������̂͂��������c�_���o���҂ɉ߂��Ȃ����[���[�������āA���������ꂪSNS�ł͂��������]���ɂȂ��đ����̐l�ɓǂ܂�Ă��Ă��Ȃ��e���r�ǂ͕ς��Ȃ��̂��낤�Ȃ��Ɗ�����킯�ł��āA�Ȃ��Ȃ��V�r��܂��B
���O���C���ł��Ȃ����{�̌쑗�D�c����
�{�e�ɂ��Ă͎֑��Ȃ���A���������䂪���̃��f�B�A�̍\���ɂ����ẮA���˂Ďw�E�����V���Ќn��Ƃ��ăe���r�ǁE���W�I�ǂ��o�c������Ă��āA���o�ϑ̐��̕a���ł�����쑗�D�c���������܂Ȃ��F�Z�������c���Ă��܂��B
�e���r�̔ԑg����ɑ��w�̂Ȃ��V���Ђ̂��̂����e���r�ǂ̌o�c�����ɓV�����Ă��Đꉡ������A�ԑg�̒��g�ɒ��ډ������Ȃǂ̖��������N�����Ċe���f�B�A�̓Ɨ�����Ǝ������ʑ����Ă��܂��B�N���X�I�[�i�[�V�b�v���F�߂��Ă��āA���f�B�A�Y�Ƃ��R���O���}���b�g�����Ă���͓̂��{�̃��f�B�A�E�G�̓����Ƃ������܂����A��������o�c�����肵�Ă��܂��Ă���̂ŕϊv�����߂��Ă���Ƃ���ł����Ƃ��O���C���������Ȃ��̂ł���B
�������A�e���r�ǂ����{�ł��l���ł��Ɨ��������݂ł������Ȃ�A����ň����グ�̍ۂɐV���w�ǂɁu�m�錠����S�ۂ���v�ȂǂƂ��Čy���ŗ���K�p���悤�Ƃ�������c�_���o����b�E�ł݂�ȂŔᔻ���Ă������Ǝv���܂��B�ł��A�u�V���Ɍy���ŗ��Ȃ�Ă��������v���Ę_�w�����e���r�ǂ̓[���ł���[���B����Ȃ���ł��B
����ᐊ�ނ��܂����āB
���Y�Ƃ̖��ƍ˔\�̖��͕����čl����K�v������
�Ȃ���ŁA�e���r���܂��N���ƂƂ��ɐ��ނ��郁�f�B�A�Ȃ̂ł��傤���A�������e���r�ǂ��o�c�I�ɍs���l�܂邱�ƂƁA�e���r�I�Ȃ���̂̎��������邱�ƂƂ͈Ⴂ�܂��B
�e���r�ǂƂ͒P�Ȃ鑕�u�Y�Ƃł���A�d�g�Ƃ����C���t���ɂ���Ďx����ꂽ���Ǝ҂ɉ߂��Ȃ��̂ʼnh�͐����͂���ł��傤���A�e���r�I�Ȃ���̂Ƃ����͓̂��{�Љ���x���铮��Â���݂̍���ł����Đl�������̂ł��B�e���r�ƊE�͂Ȃ��Ȃ��Ă��A�ԑg�����l��YouTube���낤��Netflix���낤��Amazon Prime Video���낤���ǂ��łł��˔\�����A���v���グ�邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B�Y�Ƃ̖��ƍ˔\�̖��͕����čl����K�v������Ǝv����ł���ˁB�e���r�ǂɂ��A�f���Â���̏�肢�l����������c���Ă���͂��ł��B
�V���ƊE���V�����e�ƒ�ɔz��Ƃ����d�g�݂������Ė������Ă��邯�ǁA������Ǝ�ނ̂ł���V���L�҂͋L���������Đ����c��B���t�����Ēʋq���w����̎G����Ȃ��Ȃ钆�Ŕ��s�����͋�킷�邱�Ƃ����邯�ǁA�D�ꂽ�L���̓l�b�g�ł��������ǂ܂�Ďx�����đ�������B���l�ɁA�e���r��������������ŗL���҂ł��Ȃ��^�����g�Ɏ���������点�鎿�̒Ⴂ�ԑg�𐂂ꗬ�����́A�����ƍL�������҂������C�O�ɋ��߂đł��ďo����R���e���c���Ǝ������B���ł���悤�ɂȂ�Ƃ����ȂƋ����v���܂��B
�����āA�����̋c�_�̓e���r�ǂɋ߁A���������̎d���̖������l���Ă��鏔�����炷��A�݂�ȓ�����O�̂悤�ɍl���A�ǂ��ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���ē��X�Ɩ������A�ԑg�𐧍삵�Ă����邾�낤�Ǝv���ƁA���������ƊE�̉��v�Ɉ���ݏo�����Ƃ̂ނ����������������܂��B�{���Ȃ�A��Ԋ��C�̂���Y�Ƃ̈�ł���ׂ��Ȃ̂ł����B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
����点�A�����A���f�B�A�X�N�����@�}�X�R�~�́u�}�X�S�~�v�ƌĂ��H |
���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��u���܂��݂�v
���{�e���r�̎Ј�2���Ɠ��Ђɏ풓���鐧���ЎЈ����V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ����炩�ɂȂ������A�l�b�g�ł͂��̌��ɂ��āu���܂��݂�v�I�ȏ������݂��݂���B5�����˂�ɂ͂���ȏ������݂��������B
�u����@�����������߂̌��{�������Ă��炨���v
�u����͘N�� �}�X�S�~�W�҂�S���u���{�݂ɕ��荞�߂����v
�u����ҋ@�̉Ƃɉ��������āw���ǂ�ȋC�����ł������H�x�w�ꌾ���肢���܂��I�x����v
�u�����Ŗ�E�����Ă�����ł��� �������Ƃ�a�@��E��ɁA��ނ��Ă������ ���փs���|���炵�Ď�ނ��Ă�����ˁv
��ʓI�Ƀl�b�g�����y���Ă����25�N���o�߂������A�u�}�X�S�~�v�@����25�N�Ƃ�������B�}�X�R�~�͕Ό������A�����҂�����҂������߂�ڗ�ȑ��݂ŁA�l�̓���ɕs�^�ɓ����Ă��邱�Ƃ��}��Ȃ��B�������e���r�̏ꍇ�͖��c�ƂŎd�������܂��Ă����A�l�g�������܂���ʂ��Ă���\�\�B����ȃC���[�W������A����ɂ͋����^�̃}�X�R�~���l�b�g�y�уl�b�g���[�U�[�������������Ă����A�Ƃ��������o�������Ă���B
�����炱���A�l�b�g���D���Ȑl�X�̓}�X�R�~��G�����Ă������A�ނ�Ƀl�b�g�ɃY�J�Y�J�Ɠy���œ����Ăق����Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B���������l�b�g��̘b����e���r�ŏЉ�ė~�������Ȃ����A�l�b�g���L�̗p����}�X�R�~���g�����肷��Ɣ������o������́B�ŋ߂ł����l�b�g�̓��f�B�A�̉��҂ɂȂ���邪�A�I�[���h���f�B�A����͌������ꑱ�������j������B
�����g��2006�N�Ƀl�b�g�j���[�X�̕ҏW�҂̎d�����J�n�������A�����̎����f�B�A�Ɠd�g���f�B�A�̐l����́u�����H �l�b�g�ȂŃj���[�X�̕ҏW���Ă�́H �V�������Ƃ���Ă�������Ⴂ�܂�(��)�v�݂����Ȉ�����������Ă����B�Ƃ��낪2010�N�Ȍ�A�u���H�̓l�b�g�ɂ���I�v�Ƃ���ɃI�[���h���f�B�A�͂������ăl�b�g�ɎQ�����Ă������߁A����͕ς�������̂��Ƃ��Â�������B
�����������j�I�o�܂����܂��āA�}�X�R�~���Ȃ��u�}�X�S�~�v�ƌĂ�Ă���̂����l���Ă݂����̂����A�l�X�̎��̌����܂߁A���܂��܂Ȍ����v�f�����݂���B�܂��A�������D���Ȃ��̂����Ȃ����肷�邱�Ƃ������Ƃ����̂����邾�낤�B�Â��b�ɂȂ邪�A�^�[�����͋t��������邱�ƂŒm���Ă���B�Ⴆ�Ζ�Ήp�Y��MLB�ɒ��킷�鎞�́u��������킯���Ȃ��v�I�Ș_���Œ@�����B�Ƃ��낪����劈��Ƃ��̔ᔻ�́u�Ȃ��������ƂɁv���ꂽ�B�C�`���[�����킷�鎞���u����͒ʗp���邯�ǖ��͒ʗp���Ȃ��v�Ƃ������������B��t�@���A�C�`���[�t�@�����炷����܂������̂ł͂Ȃ��B�{��͗N�����낤�B
�����2016�N��SMAP���U�̎��ɂ�����ꂽ�B�X�|�[�c�����͂��߂Ƃ��������̃��f�B�A�́A�W���j�[�Y�������̑��ɂ��u�L���^�N�ȊO�S���ޏ��I�v�ȂǂƁA�ؑ���ƈȊO��4�l�����`���鎖�����ɑ��ă��K�}�}�����Ă���A�Ƃ������_���ŏ������B����A�W���j�[�Y����������o����֎~��H����Ă���^���́u���܂�SMAP�����߂͑������v�Ƃ������_���ŏ������B
�ؑ��ȊO��4�l�����҂ɂ���悤�Ș_�����������Ƃ�SMAP�t�@���͏������B�����āA���U��j�~���ׂ��t�@�����ꂼ��̎v����V���̌l�L�����ɏo���Ȃǂ����B���̎��g��ꂽ�̂������V�����͂��߂Ƃ����n�������B����ɂ��A�����V���́u�������Ɋ��Y���Ă����V���v�Ƃ������]���邱�ƂɂȂ�B����̓t�@�����炷��u�}�X�S�~�v�ł͂Ȃ��u�܂��Ƃ��ȕ@�ցv�Ƃ����������ɂȂ�B�����V�����ǎ҂����SMAP��i�삷��悤�ȓ��e���f�ڂ��A���l�̕]�����B
�����Ȃ����Ȃ���25�N�B�l�b�g��ɍL����u�}�X�S�~�v�@����U��Ԃ�
�e���͂̂��郁�f�B�A���u�����ɂƂ��ĕs���ȕ�����v�Ƃ����̂��u�}�X�S�~�v�����̗��R�̈�����A���ɂ���������B���悤�B��������l�b�g��ł̔ᔻ�ł���A�ꕔ�v�����݂�}�X�R�~�̐^�ӂ��`����Ă��Ȃ����������邪�A�Ƃɂ���焈Ղ���Ă��鎖���ł���B
����Q�҂₻�̉Ƒ��ɗe�͂Ȃ��ˌ����A��ނ�����
��������u���f�B�A�X�N�����v�����A�u��Q�҂̋C�������l����v�Ɣᔻ�����
���ЊQ���ȂǂɃw���R�v�^�[�Ŕ�����炵�A�~���̎ז�������
�����f�B�A�͕K�v���Ǝv������Ă�����̂́A���q�����͂��߂Ƃ����~�������K�v���͒Ⴂ�Ɖ��߂���Ă���(���R��������)
���u�m�錠���v�u�̎��R�v�����ɔ�Q�҂̎���������
����Q�Җ{�l��⑰������l�����Ă��Ȃ��Ɖ��߂����
���s���̗ǂ��������́u���Ȃ����R�v���s�g����
�������n�̘b��ő����̂����A�u�����Ƒ������ׂ����낤�v�Ƃ������̂̕ʂ����Ȃ��Ƃ��̌��t���o�ꂵ�A���炩�̜u�x�������Ă���Ɛ��������
���|�\�l�̔M���₷�łɈ��ނ����|�\�l�́u���܁v�̎ʐ^���
���u�����Ƃ��Ă����Ă��v�ƕK���������
���g���ɊÂ�
�����f�B�A�ƊE�l�̕s�ˎ��Ŏ���������Ȃ������ꍇ�������������ɂȂ�
�������������ă`�����`�������Ă���Ƃ����C���[�W������
���`�����`�����͂ǂ������͕�����Ȃ����A�����̍����ɂ��Ă͑��̐��Ј��Ɍ��邱�Ƃł͂��邪�c�c�B���Ƃ͑��e���r�ǂ̃v���f���[�T�[���u���c�Ɓv���Ă���Ƃ������C���[�W������
���ʂɂȂ��Ă�����Ȃ��d���Ȃ̂ɃG���\�[�ɂ��Ă���
���d�C�A�����A�K�X�A������ʋ@�ցA�_�ƁA�X�[�p�[�Ȃǐl�X�̐����Ɂu�{���ɕK�v�Ȏd���v�ł͂Ȃ��̂ɁA�ǂ��������K���ɑ����Ă���悤�Ɍ����Ă���
���e���r�̃��P�̎��A�}���ł���̂ɒʍs��W�����A�˔j���悤�Ƃ���Ɠ{����
���u�e���͂���e���r�l�ɂ͋��͂�����́v�Ƃ����ԓx�����Ă���Ƒ�������
����点�����X����
�������V���́u�T���S�����v��w���邠��厖�T�x�́u�[���ł₹��v������\�I
���v�z�I�ɕ��Ă���Ɣ��Δh����͑�������
���O�o�́u�t�@����������v�Ɏ��Ă��邪�A�V���ł����Β����E����vs�Y�o�Ƃ������Ƃ��납�B�����炱���v�z�I�Ɂg�ǂ��炩�ɗD�����ǂ��炩�ɔᔻ�I�h�ȃ��f�B�A���\�[�X�Ƃ���5�����˂�̃X���b�h�ɂ́y�����z�y�Y�o�z�y�Q���_�C�z�y���e���z�Ȃǂƒ��߂����A�u����̃\�[�X�͂��̃��f�B�A�����炻�̂���ŊJ����v�Ƃ������o�C�A�X�����O�ɂ����Ă���
���c��������̂悤�ɁA���ōS�������l���o�ꂷ��Ɓu���ȐӔC���v�u�ŋ����ď����Ă��K�v�͂Ȃ��v�Ɣᔻ�����̂��A��L�̗���̈���B���ɂ��F�X���邪�A�����́u���������ꂽ��C���Ȃ��ƂC�ł��錌���܂��Ȃ��A���v��u�����B������K�����Ǝv���Ă���v�Ƃ������Ƃ���ɂ��邾�낤�B
���ٗႸ���߁u�����ۏ�6�����������E�Q�����v�̋L�҉
�����������Ӗ��ł́A2004�N�ɔ��������u�����ۏ�6�����������E�Q�����v�ł̔�Q�����̕��e�͏̎^���ꂽ�B���e�͖����V���̍����ێx�ǒ����������A���������̓����ɑO�㖢���̔�Q�҈⑰�ɂ�����J�����B���R�́u�V���L�҂ł���ȏ�A�����Ȃ�������Ȃ��v�Ƃ�����y�̌��t������܂Ŏ���Ă�������B���ꂾ���ɁA��������Q�҈⑰�̗���ɗ������Ƃ��Ă��A���̋L�҂͎����̘b���������낤�Ǝv�������Ƃ��B�܂��A�������g���h���ɂ���l�X�̎�ނ������o��������A�u�_�u���X�^���_�[�h�͂����Ȃ��v�ƍl�����̂��낤�B�����̕��������e�ւ̎�ނ��܂߂Ď��M�����w�ӂ�Ȃ�A���ł������Łx(�얼�s�u/�W�p��)�ɂ͂���畏����`����Ă���B
���ƁA���C�^�[���@���ꂪ�����B�Ӑg�̐�ꃊ�|�[�g��ʔ��������n�̋L���A�ق�����G�s�\�[�h���������Ƒ��͂����������B
�u����ȕ��͂ł悭���C�^�[����Ă���ȁB�I���̕������͂͂��܂��v
�u�n�����q�v��u�؋��܂݂�j�v�Ȃǂ̎�ނ����Ă������������B
�u�͂��A�R���B�P�Ȃ�n��v
����ɂ��ẮA�C�����͕�����B���m�J�L�Ƃ����d���͂Ȃ�ƂȂ����N�Ȏd���Ɋ����Ă��܂��̂��B���������ď��w�Z���ォ��앶���������肵�Ă������A���|�[�g�⑲�_�ɉ����A���X�̎d���ł����͂͏����Ă���B�d���ŕ��͂��������狋���͎x�����邩������Ȃ����A����͕��͂��̂��̂ɑ��Ďx������킯�ł͂Ȃ��A�d���S�̂ɃJ�l���x�����Ă���B�������A�ʂɎ������i��ŏ����������͂ł͂Ȃ��A��i���珑���悤�����t����ꂽ���͂ł���B
����Ȓ��A�u�`���V�̗��ɏ����Ă����v�u�u���O�ł���Ă����v�I�ȕ��͂��E�F�u���f�B�A�Ō����ꍇ�́u�����͂��̒��x�ŃJ�l���҂��₪���āv�Ƃ���������ɂȂ��Ă��܂��̂��낤�B���͂��u�\���v�̈��ł͂��邪�A�C���X�g�A����A���y�̂悤�ɓV���̍˂��K�v�Ȃ��̂Ƃ͕ʂŁu�ǂ�ȃo�J�ɂł���������́v�Ƃ��������������������B�����炱���A�u�I���̕����D��Ă���v�Ɗ����Ă��܂��̂��B
�����炱���A��X�̂悤�ȃE�F�u���f�B�A�ɏ]������҂͂�����������������^���Ɏ~�߁A�����ɗ������o�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����{�̃}�X�R�~�͂Ȃ��u�����v�Ȃ̂��H�@2013/12
|
( �C���^�r���[�w�������f�B�A�̐��́x���ҁE �ÒJ�o�t )
���p�D�{���w�������f�B�A�̐��́x�����M���悤�Ǝv�������@�������������������B
�ÒJ�@����܂łɂ��A�u�������f�B�A�v���e�[�}�ɂ������Ђ⃀�b�N���o�ł���Ă��܂����A�����ɏ�����Ă��邱�ƈȊO�ɁA�����Ⴄ�������B����Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA�l�͊����Ă��܂����\�B
�{���̒��ł́A�}�X���f�B�A�́u�����v���A�u�m�M�I�����v�Ɓu�����o�Ȕ����v�ɕ����Ę_���Ă��܂��B�u�m�M�I�����v�́A�̈ӂ̔����̂��Ƃł��B�����Ԃ̉^�]�ɂ��Ƃ���Ȃ�A�����^�]�̂悤�ȁA���ӂ�����s�ׂł��ˁB
����܂ŏo�ł��ꂽ�ޏ��́A��ɂ��̌̈ӂ̔����͂��Ă��܂����B��قǂ̈����^�]�̗�Ō����A�u�Ȃ��A���̐l�͂���������ł���̂ɁA�^�]���邩�v��Njy���Ă����̂ł��B�@
�������A����͂���ő�ψӋ`�̂��邱�Ƃł����A�l�́u�m�M�I�����v�ł͂Ȃ��A�u�ǂ���Ǝv���Ă���Ă���v�u����Ă���{�l�ɂ����o���Ȃ��v�Ƃ����u�����o�Ȕ����v�ق����A�e���r��V�������邩����A�����Ƃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�u����ȓ��H�W���͒m��Ȃ������B�����A�ꎞ��~��������ł����H�v�Ƃ����悤�ȁB
���p�D�m���ɁA���܂܂ł́u�m�M�I�����v����莋����Ă��܂����B
�ÒJ�@���R�A�u�m�M�I�����v�́A�d�߂ł���B�Ⴆ�A���{�����[��������������ɋN�����u���{�W�O��ۑ��쎖���v�B�����731�����̋ɔ�v������TBS�̔ԑg���ɁA�W�̂Ȃ����{����̊�ʐ^���f���������Ƃ����O�㖢���̒����ł������A�T�u�~���i���̋^���ŁATBS�͑��������璍�ӂ��܂����B����͂����m�M�ƁB
�u�����V���ϑԋL�������v�́A���{�l(�Ƃ��ɓ��{����)�̂ł���߂ȏ��𐢊E�ɔ��M���Ă����Ƃ�ł��Ȃ����̂ł����B���̎����́A���C�A���E�R�l���Ƃ����I�[�X�g�����A�o�g�̋L�҂��A���Ԃ��ƌ������A���{�l�������������Ă������ƂŋN�������B
���邢�́A1989�N�́u�����V���T���S�ʝs�������v�B���̎����͗L���ł��̂ŁA�݂Ȃ���������m���Ǝv���܂����A����͖{�c�Ƃ����J�����}���������炩�Ɏ��쎩�������A���{���Ȃ߂�s�������ł����B
���̂悤�ȂЂǂ������I�Ȏ����������āA���݂ł����т��эs���Ă���̂ł����A���ꂾ���ł͐����ł��Ȃ��u�ُ퐫�v���}�X���f�B�A�̒��ɂ���B���ꂪ�u�����o�Ȕ����v���ƁA���͎v���̂ł��B
���p�D���́u�����o�Ȕ����v�ɂ��āA�����������b�����������܂����H
�ÒJ�@�u�����o�Ȕ����v�Ƃ́A�ꌾ�ł����ƁA���o�̃Y���Ȃ�ł��B��ʂ̓��{��������͌����ďo�Ă��Ȃ��悤�Ȋ��o���A�}�X�R�~�l�ɂ͂���B�܂��́A���������ʂɎ����Ă��銴�o���A�}�X�R�~�l�ɂ͂Ȃ��B���̎s��̓��{�l�ƗV�������u�Y�������o�v���A�}�X���f�B�A�̊�ȕɂȂ����Ă���Ǝv���܂��B
���p�D�ŋ߁A�ێ�n�G����C���^�[�l�b�g��ŁA�u�������f�B�A�v�ɂ��āA����ɘ_������Ă��܂����A���̌�����ǂ����l���ł����H
�ÒJ�@�u�������f�B�A�v�́A���͒P�Ƃő��݂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̖{�ɂ������܂������A�u�������f�B�A�v�́u���̐��v���̂��́B����́A��㖯��I�ȉ��l�ςł���u�����́v�u���̐��v�ł��B�Ƃ��낪�A�䂪���̃}�X���f�B�A�́A�u�����͂Ƃ������́v�u���̐��Ƃ����̐��v�ɂȂ��Ă���B���ꂪ�A���Ȃ̂ł��B�@
��قǁu�������f�B�A�v�͒P�Ƃő��݂��Ă���킯�ł͂Ȃ��ƌ����܂������A����͐�㖯���`�ȍl�������A����܂ʼn�X�������x���Ƃ܂ł����Ȃ��Ƃ��A���Ȃ��Ƃ����܂�^��Ɏv���Ă��Ȃ������B���ꂪ����10�N���炢�ŁA��㖯���`���̂��̂ɑ��āA�������������Ƃ�悤�ɂȂ��Ă����B�����猋�ʓI�ɁA���̖T��ɂ������e���r��V�����A�u�������f�B�A�v�Ɂu�v���Ă����v�Ƃ����������Ǝv���̂ł��B
���̂悤�ȏ��ŁA�u�������f�B�A�v���������G�����l�C���Ă��邱�Ƃ͗��ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�܂�A�̐��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��������̎M�Ƃ��āA���̎�̎G����WEB�T�C�g���o�Ă����̂ł��B
�ł�����A���܂܂ł̃}�X���f�B�A���ˑR�u�������f�B�A�v�ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��A�����̊��o���ς������Ƃɂ���āA�u�������f�B�A�v�ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B
���p�D����ł́A���{�������u��㖯���`�I�Ȋ��o�v����ω��������R�͉��ł��傤�H
�ÒJ�@���m�ɂ͕ω�������ł����B����͐��E��̕ω��A�u��킪�I������v�Ƃ������Ƃł��傤�ˁB
��㖯���`�Ƃ����̂́A�����Ȃ�ł��ˁB�u���a���厖�v�ƌ����Ă��܂������A���̕��a�́A�ČR�⎩�q���̖h�q�́A����ɂ͊j�̎P�ɂ���Ď���Ă������̂ł��B�u���@�����܂��傤�v���A�ČR�̌R���͂Ɏx����ꂽ���́B
���̖������A�����ƒm��Ȃ��爤���Ă����̂��A�܂��ɐ��̐����Ǝv���̂ł����A���ꂪ���E�̃p���[�o�����X�̕ω��ƂƂ��ɁA�ς��Ă��܂����B�[�I�Ɍ����A���ꂢ���Ƃ����ł́A�����Ă����Ȃ��Ȃ��Ă����B���ꂢ���Ƃ������āA�i�A�i�A�ɍς܂��Ă������Ƃ��A�����ł��Ȃ��Ȃ����B������ƃV�r�A�ȏɂȂ��Ă����̂ł��B
�����ЂƂ́A���x��J�Ƃ������A�ϗp�N�����߂��Ă��܂����̂�������܂���B
���̐��́A����70�N���܂葱���Ă��܂���ˁB�悭�����邱�Ƃł����A���j��60�N����80�N�����ŕω����܂��B����ɂ́A���m�ȗ��R�͂Ȃ��A�ЂƂ̎��オ�I����āA�V��������ɂȂ��Ă����Ƃ������j�̕K�R���Ǝv���܂��B
���p�D�����ЂƂA�ŋ߁u���v�̊���A�����ɍL�����Ă���悤�Ɋ�����̂ł����H
�ÒJ�@����܂ł̐�㖯��`�̃}�X���f�B�A�̒��ŁA�����Ƃ��َE����Ă����̂��؍��̃j���[�X�ł��B
��㒷�炭�A�؍��Ǝ����}�͂����Ɛe���ł����B�����āA�ߔN�܂ŁA�؍��͎����}�\�p�����̎��オ�����ł������A���{�̎q���݂����Ȃ��̂ł����B
���{�̕ێ�w���A�u�펞���A�؍������{�̈ꕔ�Ƃ��Đ푈���������Ɓv�u�k���N�̖h�g��Ƃ��Ċ؍��ɂ͊撣���Ă��炢�����Ƃ����C�����v������A�؍��ւ̃o�b�V���O���^�u�[�Ƃ��Ă����B���̎v���������������̂��A�t�W�T���P�C�O���[�v�ł��B
�������A�\�A���������Ƃɂ���āA�؍����k���N�ɑ��āu���z����v���͂��߂�悤�ɂȂ����B�k���N�͓����������Ƃ������ƂŁA�؍��͂ǂ�ǂ�G�a�I�ɂȂ��Ă����B�����Ċ؍��́A�Ƃ��Ƃ��u�������Ɓv����u�������Ɓv�ɕς��Ă��܂����̂ł��B
���̊؍����́u�����v��肪�ǂ�ǂo���Ă���̂ł����A���{�̃}�X���f�B�A�̐��͂܂������ς��Ă��Ȃ��̂ŁA�؍��o�b�V���O���^�u�[�̂܂܂Ȃ̂ł��B���̓��{�����ƃ}�X���f�B�A�̈ӎ��̃Y�����A�t�W�e���r�f���������N�������̂��Ǝv���܂��B
���p�D�e���r��V���Ȃǂł́A�u�ŋ߁A��҂��E�X�����Ă���v�ƌ����Ă��܂����H
�ÒJ�@���������āu�E�X���v�Ƃ���̂��͂킩��܂��A�l�́u��҂͉E�X�����Ă��Ȃ��v�Ǝv���܂��B
�����̐l�������u��҂��E�X�����Ă���v�́A������F�ł��B�{���Ɏ�҂��E�X�����Ă���̂ł���A���Ă̎Q�@�I�ŁA�R�{���Y�c�����Ȃ�66���[��������̂��B�����ނ��S�����ŏo�n���Ă�����A�������������[�l�������̂��B�R�{�c���ɓ��[�����l�����ׂĎ�҂��Ƃ͌����܂��A���Ȃ�̊����Ŏ�҂����[�������Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂��B
����A�ێ�w�̂ق��́A��]�ł��B�m���ɋߔN�A�ێ�w�c�̃V���|�W�E���ɁA20��̎�҂�������悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂����A����͂����܂ł��}�C�m���e�B�ł����āA���ꂪ�������Ėڗ�����A���������Ă���悤�Ɋ����邾���ł��B
���p�D�����Řb����ς��܂��傤�B�ÒJ���A���܂�����C�ɂȂ�j���[�X�́H
�ÒJ�@����́A����閧�ی�@(12��6���ɐ���)�ł��B
�������̂́A�}�X���f�B�A�͋��s�̌��Ȃǂƌ����Ă��܂����A�悭�ʂ����ȁA�ƁB�l�́A�ĊO����Ȃ�ʂ�����ۂ��܂����B
�O�c�@�͗^�}�����|�I�����Ȃ̂Œʂ�܂��ˁB����Œ����V���́A�u�Q�c�@�Ɋ��҂���v�Ə����킯�ł����A�X�b�ƒʂ��Ă��܂����B���Ԃ�A20�`30�N�O�ł���A�����������@�Ă͏����������Ȃ��Ǝv���܂��B�����}���ŏ����c�_���āA���������ɂȂ邾���������ł��傤�B
���ꂪ���܂ł͗��h�Ȗ@�ĂƂȂ�A�O�c�@�ŃX�b�ƒʂ��āA�Q�c�@�ł͏������߂�����ǂ������ʂ����B�ЂƐ̑O��������A�ЂƂ̓��t���ӂ��ƂԈČ��������͂��ł��B
����A�����V���͂��̖@�ĉ����A�u���{�����̎x���������������I�v�Ə����܂������A�悭�悭�{����ǂ�ł݂�ƁA�����O�̎x����(�����V������)��49���ŁA������̎x������46���Ȃ�ł��B������3�����āA�덷�͈̔͂���Ȃ��ł����B���ǁA���܂艺�����Ă��Ȃ���ł��ˁB
�قƂ�ǂ̍������A����̑O�Łu�@�Ĕ��I�v������ł����l���������Ă��A�ނ�͓ڋ��Ȑl�����ŁA�����̈ꕔ���Ƃ킩���Ă����ł��B
�����ė��R�͂Ƃ������A�畆���o�Łu���̖@�Ă��āA�K�v�Ȃ�Ȃ��́v�ƁA�����̍������v���Ă������炱���A���t�x�������قƂ�Ǖς�Ȃ������̂ł��B���̖@�Ă��A�X�b�ƒʂ�Ƃ������Ƃ́A���{�l�̈ӎ������Ȃ�ς��Ă����؍����Ǝv���܂��B
���p�D��͂���{�l�̊�@��������ɂ���̂ł��傤���H
�ÒJ�@�����ł��ˁB���������ꂾ���R���卑�����܂������c�c�B�ŋ߂��u�h�ʌ��v��V���ɐݒ肵�����Ƃ����ɂȂ�܂����ˁB
��펞��́A�Ȃ������Ă��A�e���u�A�����J�v�������B���{�̓G�R�m�~�b�N�E�A�j�}���ɂȂ��čD���������Ă��A�Ō�͐e���ɃP�c��@���Ă�����Ă����̂ł��B
�����āA��{�I�ɂ��̎���̓��{�́A�A�W�A�̒��ň��|�I�ɋ��������B�����́u������v���v�Ȃǂł߂��Ⴍ����B�؍������n�R���ł����B�A�W�A�œ��{�ɑR�ł��鍑�͂Ȃ��A�����قƂ�ǃU�R�ł����B��������{�͍D���Ȃ��Ƃ��������B���z�_�����ł�����Ă��������������̂ł��B
���ꂪ���܂ł́A����ł͒������͂����A�؍����͂͂Ȃ���������Ȃ������邳���Ȃ��Ă����B���̂悤�ȍ��ۏ̕ω����A���{�l���q���Ɋ����Ƃ��Ă���̂ł��傤�B
���p�D����̍�i�w�������f�B�A�̐��́x�ŁA��J�������ꂽ�_�́H
�ÒJ�@����́A���e�������ꏊ�ł��ˁI�@���i�A�G���ȂǂɊ�e����Ƃ��͎���Ŏ��M���܂����A�{���̂悤��250�y�[�W���̏������낵�̏ꍇ�́A�ʂ̏ꏊ�Ŏ��M���邱�Ƃ�������ł��B�l�͎���ŔL�������Ă���̂ł����A�ǂ����Ă��L���C�ɂȂ��āA�C�ɂȂ��āA�W���ł��Ȃ���ł�(��)�B
����́A�N���}�Ŗ钆1���Ԉȓ��ɍs���āA���Ԃ͏a�ŋA��Â炢�ꏊ��T���܂����B����́A��錧�����Ȃ����낤�A�ƁB�l�̎�����錧�̖^�s�܂ł��A���傤�ǂ��������Ԃ������̂ŁB
��10���Ɏ�����o���11���Ɉ��ɒ����̂ŁA�}���K�i���ɓ����ė�����8���܂ŏ����B���ɂȂ�ƃN�^�N�^�ŁA����ɋA��Ȃ��̂ŁA��������߂����u�z�e���Ƀt���[�^�C���œ����āA�[��4�����炢�܂ŐQ���ł��B
���p�D���u�z�z�e���͂���l�ŁH
�ÒJ�@�������A��l�ł��I�@�ŋ߂̃��u�z�́A����l�l�劽�}�Ȃ�ł�(��)�B����������Ȓl�i(4000�~�O��)�ŁA����܂�(��)�B
�����Ă܂��A��ɂȂ�ƃ}���i�ɍs���Ē��܂ŏ����B�����Ă܂��A���u�z�ŐQ��B������������t�]�̐��������ď����グ�����Ƃ��A������̋�J�Ƃ������A�v���o�ł��B
���p�D�ÒJ����́A�}���K��A�j���ȂǃT�u�J���n�ɂ����ڂ����ł����A���{�̃}�X���f�B�A���ނɂ����A�������߂̍�i�͂���܂����H
�ÒJ�@�{���̒��ł������܂������A�w�����N�C�Y�x�����L�g(��)�Ɛ�������(����)(��c�o��)�ł��ˁB����́A�o�u������ɏ����ꂽ��i�ł����A�ƂĂ��ʔ����B
�ǂ������b���ƌ����܂��ƁA���̍�i���E�ł́A���{��`�̎��ɂ���̂́A�u�����N�C�Y�̐��v�Ƃ����C�f�I���M�[���Ƃ��Ă��܂��B�w�����N�C�Y�x�̓e���r�ԑg�Ȃ�ł����A����(������)�̓~���I�l�A�݂����ɂ��̔ԑg�ɏo�ꂷ��킯�ł��B�����Ŋm���S�������ƁA���̐l�̊肢���Ƃ����ł������B�w�����N�C�Y�x�ɂ���āA��O�̃G�S����������B
���̐��E�̓��{�́A�w�����N�C�Y�x�������Ă���e���r�ǂ��x�z����u���]��ԁv�Ȃ�ł��B����c���������������e���r�ǂ�艺�̑��݂ł����Ȃ��B
�����āA�u�����N�C�Y�̐��v���听�����Ă�����{���A���E�̖���ɂȂ��Ă���B���A�̏�C�������ɂȂ�A���A�c�������{�l�B�A�����J���A�S�Ŏg���A�掵�͑��������^�����Ă���B�����̐����f�����b�������Ă��܂��B
�Ō�́A��l�����܂߂��u�����N�C�Y�̐��v��œ|���悤�Ƃ��鐨�͂��A�v�����N�������Ƃ��܂��B
20�N�ȏ�܂��̍�i�Ȃ̂ŁA�l�^�o�����Ă������ł���ˁB�@(�ȉ��A�l�^�o��)
�ÒJ�@���ǁA�v���͋N�����Ȃ���ł��B�Ȃ����ƌ����ƁA����(������)���A�u�����N�C�Y�̐��v��|�����Ƃ������Ȃ������B��l���������A�����ɖ₢������V�[��������̂ł����A�u�����N�C�Y����߂�ȁ[�v�Ƒ�O�̔�������B�M��Ƃ������A���ӎ��I�Ȏx�����āA�w�����N�C�Y�x�͏I���Ȃ������c�c�B
���̍�i�́A�}�X���f�B�A��M���Ă���A�����̓��{�l�������Ă���Ǝv����ł��B�o�u���̎���ł������A�}�X���f�B�A���̐��ɂȂ��Ă����B�܂��A���܂������ł����B�����S�͂Ŏx�����Ă���̂́A�e���r�ǂ̒��̐l��������Ȃ��āA���̓��x���̒Ⴂ������O�������Ƃ����I�`�ł�����̂ł��B
�u�������f�B�A�v�́A��������A�m���Ɉ����ł����A����ʼn�X��������x�����Ă����킯����Ȃ��ł����B���܂͋C�Â��܂������ǁc�c�B
���̌����̓��{�Љ�Ɓu�����N�C�Y�̐��v�͔��Ɏ��Ă����ł��ˁB����������I�ɂ���킵�Ă���̂����́w�����N�C�Y�x�ł��B������A�ƂĂ��ʔ����B���Ȃ�J���g�I�Ȑl�C�̂���}���K�ł����A�l����D���ȍ�i�ł��B
���p�D�Ō�ɁA�ꌾ���肢���܂��B
�ÒJ�@�{���w�������f�B�A�̐��́x�̂悤�ɁA�u�������f�B�A�v�̖����o���͂����{�́A���܂܂łȂ������Ǝv���܂��B�ǂ���Ǝv���āA�ԑg�⎆�ʂ������Ă���}�X�R�~�l�������A�������f�B�A�̐��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����āA�l��̒��ɂ�����A�Ȃ�ƂȂ����a��`�A�Ȃ�ƂȂ������A�Ȃ�ƂȂ����x�����Ȋ��o���A���l�ɖ��Ȃ̂��Ǝv���܂��B
|
 |


 �@
�@ |
|
���ɂ�����^�u�[
|
�}�X�R�~���s�ˎ��Ȃǂ̔ے�I�ȕ��s�����Ƃ��T���Ă��邱�Ƃ��w���B
���{�ł́A�L�[�ǂ�S�����ȂǍL�͈͂ɉe����^���郁�f�B�A�قǕ�����I�ɍT����X�����������A���������p���ɑ���ᔻ���������݂���B���̂��߁A���{�ɂ����Ђ����Ȃ����Ƃ�Ă��邱�Ƃ蕨�ɂ���}�X�R�~������B�Ⴆ�A���{���Y�}�̋@�֎��w����Ԃ�Ԋ��x�̓^�u�[��ł��j��Ő��_�����Ă����ƃA�s�[�����Ă���B
�����f�B�A�^�u�[
���f�B�A�̌��v�Ɋւ����A�@�ւ�]�ƈ��̔ƍ߂�s���E�s�ˎ�(���Ɏ��Ђ�n��P���̂���)���A���f�B�A�ɔᔻ�I�ȕ͂���ɂ����X���ɂ���(�������G����e���r�ȂNjƊE�Ⴂ�⓯�Ƃł����Ђ��������Ƃ͂���)�B TBS�r�f�I���͂��̍ł�����̂ł������B�V������w��p�~��V���̌y���ŗ��ȂǐV���ƊE�̌��v�Ɋւ�邱�Ƃ͐V����n�ɂ���e���r�ǂł͐[�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͂���ɑ��Ĕᔻ���������Ƃ̔������X���[�������������B�܂��A�@�ւ����͂̊Ď����f���Ȃ��猠�͂Ɉ������p���ɂȂ��Ă���Ƃ̐�������B
���L�҃N���u�^�u�[
�L�҃N���u�́A���{�̕ɂ�����ő�̃^�u�[�Ƃ�����B���������łɂȂ����̂�1969�N�̔����w�e���r�t�B������o���ߎ����ō��ٔ����ȍ~�ł���B�C�O�̕@�ւ����{�̓��ꐫ��Kisha Kurabu�Ə̂��Ĕᔻ���Ă���B
���X�|���T�[�E�L���㗝�X�^�u�[
�X�|���T�[����ԑg�̐�����L�����������邱�ƂŎ��Ƃ��������Ă��閯��(���ɓ����L�[�ǂɂ�����)�ł́A�L���}�̂Ƃ��Ď����҂̃��X�|���X�A����ӗ~�˂���ԑg���e�͎������ɂ����̂��ʗ�ł���B
2008�N6��1���A�e���r�����ŕ������ꂽ�w�V�j�b�|���l�x�ɂ����Ďi��҂̋v�čG�́u�����Ƃ����̂́A��������Ȃ��A�l�X������Ȃ��A�Ƃ����ԑg�͔��ɓ���B�悭���̔ԑg���ł����Ǝv���v�Ɣ���������ďq�ׂ��B�܂��ACM���y�����锭�����������ꐢ���ꎞ�I�ɔԑg����O���ꂽ�Ⴊ����B
���̂��߁A����(���Ɍ�������A�q��������)�Œ�����킸�A���ʔ̔ԑg��������������Ă���B�Ƃ�킯����̑������e���r�V���b�s���O�Ő�߂��Ă���ǂ���莋����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ�(���̔ᔻ�͏]�����炠��A2011�N�ɂ͊e�ǂ��ʂm�ɍ팸����悤���߂�ꂽ)�B
�ߔN�̓l�b�g�̎g�p���̑����ƂƂ��ɁA�e���r��W�I�̎������⒮�旦���������Ă���A���̎�̃^�u�[�ɂ͍L���㗝�X�͈ȑO�����q���ɂȂ��Ă��Ă���B
�Ⴆ�A2013�N�Ƀz�e����S�ݓX�̐H�i�U�����������Ŕ��o���A������ŏ��Ɍ��\�����V��}�z�e���̓}�X�R�~�����o�b�V���O�����̂ɑ��A��������O�ɐH�i�U�������o���������f�B�Y�j�[���]�[�g�n�̃z�e���ɑ��Ă̓}�X�R�~�͂قƂ�ǕȂ������B
�܂��A���O�b�h�E�B���Ȃǂ̓��ق��h����Ђő���������@�s�ׂ��A���O�b�h�E�B�����p�Ƃ���O�N��2007�N�܂Ń}�X�R�~�Ɍ��߂�����Ă������������B
������������Ƃ�A���Ƃł����Ă����ԕ����ւ̉e���̏�������Ƃ͂��̌���ł͂Ȃ��B
���L���㗝�X�̃^�u�[�ɂ��Ă�2016�N�̓d�ʏ��q�Ј��̉ߘJ���E���߂���W�������������ɔj�����邪�A�L���㗝�X�̎����̂��̂̃^�u�[�͖������������݂���B
���|�\�v���_�N�V�����^�u�[
�|�\�W�҂��ƍ߉��Q�҂Ƃ��ĕ����ꍇ�ɂ����āA�{���u�e�^�ҁv��u�퍐(�l)�v�A�u���ޑ����v�ƕ\�L����镔�����A�u(��)�����o�[�v�A�u(����)�^�����g�v�A�u�i��ҁv�A�u(�����E�̕���)�o�D�v�A�u�{�[�J���v�A�u�M�^���X�g�v�A�u����Ɓv�A�u���ޑ��t�v�ȂǂƖ{�l�̌|�\�E�ł̌������ɂ��s���R�Ȍď̕\���ōς܂���邱�Ƃ�����B
�����͂����ɁA�ߕߌ㏈���ۗ��Ŏߕ����ꂽ�����A�����N�i�E�ݑ�N�i�ōς܂��ꂽ����ő����A��q�̂悤�ɑߕ߁��N�i���L�߂̏ꍇ�͂��̌���ł͂Ȃ��B
�������A�ǔ��e���r�A�i�E���T�[�̓��Y�r�F�́A�u�w�����o�[�x�Ȃǂ̕s���R�Ȍď̂�t����̂́A�����Ɍ�������t���ĕ���̂������̍ݑ�{���ɐ�ւ��ɂ�����A�K���Ȍď̂����݂��Ȃ�����ł���A�|�\�v���̈��͂ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ă���B
�ߋ��ɋg�{���ƂƏ��|�|�\�������Ԃŏ����|�l�̈����������킪���������Ƃɒ[�������Ƃ���A���������̃^�����g�������ꏊ�ɏo������ꍇ�����ɑ��������̃^�����g���N�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������Ⴊ�����Ă���B����A����������Ɨ������l�������^�����g�ł���ꍇ�͐�����ɂ��Ȃ�A�_��ȃo�[�^�[�c�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B2014�N�ɂ̓v���싅�p�u���b�N�r���[�C���O���ŏ��|�|�\�����̐X�e�������g�{�̌���ł���Ȃ�O�����h�Ԍ��̕���ɗ��Ƃ����ٗ���N����(�X�e�ȊO�S�ċg�{����)�B
����Ƃ͋t�ɑގЂ����A�C�h���O���[�v�̃����o�[���A�������̈ӌ��ŕ��Ȃ��P�[�X������B
�܂��A���c�l�G�ɂ����āA�����o�D���p���[�n���X�����g�����E�����������N�������ۂ��A���̂͏T�����t�Ɩ����V���݂̂ł������B
�������^�u�[
���Ƃ̍����ɂ��Ă͗l�X�ȋc�_���s���Ă��邪�A�}�X���f�B�A�͂��̂�������݂̂̎��_�Ɋ�Â����s���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����w�E������B
�Ⴆ�Ώ���ő��łɂ��āB���{�̍��z���f�c�o���200���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�V�ÓT�h�o�ϊw�ُ͋k�������s���ׂ��ł���Ƃ̎咣���s�������A����ɑ��Č���ݕ����_�ُ͋k�������J��i�C�̈���������������o�ς�N��������Ƃ��A����ő��łɔ��̗����������B
���������}�X���f�B�A�͂��̂����V�ÓT�h�o�ϊw�݂̂̎��_����j���[�X����E�g�[�N�ԑg�̓��e��Ґ����邱�Ƃ������łȂ��ꍇ�Ɣ�r���Ĉ��|�I�ɑ����A���Δh����͒������Ɍ�����Ƌ����ᔻ����Ă���B���ۂɁA�ǔ��V���A�����V���A���o�V�����̑��V���Ђ͑��_�ŏ���łɎ^�����Ă���A���ł����{���ꂽ�ۂ������]������А����f���Ă���B
�܂��A�����Ȃ�1990�N�ォ��V�ÓT�h�o�ϊw����ɋُk������ϋɓI�Ɏ�����Ă������A����ɂ��č��Œ���z���ɒu�������Ȃ��Ő��𗘗p���ă}�X���f�B�A�Ɉ��͂������Ă���\�����w�E����Ă���B
�����^�u�[
���͓��{�̌x�@��͂܂舮���͂ɗR������B
���^�u�[��j��������Ƃ��āA�ŋ߂ł́w�k�C���V���x(�ȉ��u���V�v�B�n���ł͂��̈��̂Œm����)��2004�N1�����s�����k�C���x���������Njy����������B2�N�Ԃ�1,400���̋L�����f�ڂ��ꂽ��A�̃L�����y�[���Ŗk�C���x�@(���x)�͑g�D�I�ȗ�������F�߁A�g�r�s������9��6�疜�~�̕Ԋ҂ɒǂ����܂ꂽ�B�܂����V�͓��{�W���[�i���X�g��c��܁E���{�V������܁E�e�r���܁E�V���J�A�W���[�i���X�g��܂ȂǁA�e�܂���܂����B
�܂��A�e���r�����́w�U�E�X�N�[�v�x�͉���X�g�[�J�[�E�l�����̌��ؕɂ����č�ʌ��x�@�̑Ӗ��{�����E�l�Ɏ������ő�̌����ł���Ɩ\���A�O��Njy�������ʁA���Ɍx�@�ɔ��F�߂����邱�Ƃɐ��������B
����ɁA���C���L���X�^�[�̒��z�r���Y���w�T���f�[�����x�̋L�Ҏ���ɃC�G�X�̕��M�����Ŏ�ɂ̐�������Ă����Ƃ����ߋ����炩�A�x�@���������Ȃ���Ĕԑg�ł���̈��͂�������悤�ɂȂ�A���ɂ͐��쌳������ɍR���邱�Ƃ��ł����A���[�J���g�i�������o�ĕ����ł���ɒǂ����ꂽ�Ƃ���Ă���B���������݂͕s����X�y�V�����Ƃ��Čp�����Ă���B
�܂��A�l������ł���s���l�߂�A�����̃h���C�o�[���s���Ɋ����Ă���u�l�Y�~�߂�v�ɑ�\�����x�@�̕ʌ��ߕ߂̂����̖��ɂ��Ă̓��f�B�A�ł͂قƂ�Ǖ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�l�߂Ɋւ��Ă͒��L�҉�ł̎������؎t���Ȃ��Ƃ������������B
����Ɋw�Z����Ő��k�̂����ߎ��E�������N����Ƒ�Îs��2�����ߎ��E�����ȂǕ@�ւ͋����Ă��̎�������邪�A�x�@���ŋN�����������ߎ��E�����͒n�����ȊO�ő傫�����邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B
�Ȃ��A�}�X�R�~�͌x�@24���Ȃǂ̌x�@�����ɖ��������h�L�������^���[�ԑg��p�ɂɐ��삵�Ă��邪�A�}�X�R�~�E�x�@�o�������v�����Ă���Ƃ̎w�E������(���L���ɂďڏq)�B
���e�^�u�[
�V�c�A�c���ɑ���ᔻ��ł̂��镗�h�ɑ���Љ�I���͂Ȃǂɂ��^�u�[�B
2019�N�ɊJ�Â��ꂽ�u�������g���G���i�[��2019�v�ł́u�\���̕s���R�W�E���̌�v�Ƃ������W�ɂ����āA���a�V�c�̎ʐ^���K�X�o�[�i�[�ŔR�₷���悪�W������A�l�b�g�𒆐S�ɕ��c�����������B���̌��Ɋւ��āA���e�^�u�[���d������ǂ��납�A���Ԑl������ȏ�ɋe�^�u�[���d�������d�����߂�Ⴊ�o�����Ă���Ƃ����ӌ������邪�A����ŁA����n�������̂��������g���Ď�Â���|�p�ՂɁA���@�ō��̏ے��ƒ�߂��Ă���V�c�̎ʐ^��R�₷��i��W���������Ƃ����ł���A�e�^�u�[�̖��Ƃ͖{���I�ɈقȂ�Ƃ����ӌ�������B
���t�^�u�[
�t(����)�͕�����������̒c�̊��ł���t�����ɗR������B��������������͂��߂Ƃ���ꕔ�̓��a�c�̂����{�̓��a����ɖ������A���a�������\�����Ă��邱�Ƃɂ��ă}�X�R�~���ᔻ�ł��Ȃ��B�܂��A��ʓI�Ȏ����̔Ɛl��W�҂����a�W�҂ł���A�����̖{���I�Ȍ����Ƃ��ē��a��肪�ւ���Ă���ꍇ�ł����Ă����a���ɂ͈�ؐG�ꂸ�A��ʓI�Ȏ����ł��������̂悤�ȕ�����X��������B
������A��������������͂��߂Ƃ��铯�a�c�̂�ᔻ����ƕ��������������m�F�E���e�Ȃǂ����v��\�͍s�ׂ̔�Q�ɔ��W����\�������邽�߁A�e�ЂƂ������������ɂ͋y�э��ƂȂ��Ă���B
������21���I�ɓ����Ă���A���a�Ƃ��I���A��������������͂��߂Ƃ��铯�a�c�̂Ɋւ�����_�����X�Ɏw�E�����悤�ɂȂ��Ă��Ă���B���ł����������̊����[�J���̃j���[�X�ԑg�wVOICE�x�ɂ��Njy�V���[�Y�͌Q���A�X�N�[�v��A�����A���s�ȂǍs�����ǂɂ��s���ȕ⏕���x�o�����т��і\�I�����B
���A�[���t�^�u�[
Aleph�ɉ��̂����I�E���^�����Ɋւ��邱�̃^�u�[�́A�ď̂ƕ��e�ɑ�����̂ɕ�������B
�ď̂ɑ���^�u�[�Ƃ��ẮA�A�[���t�����ہA�u�I�E���^����(�A�[���t�ɉ���)�v�ȂǂƕK�������́u�I�E���^�����v�𒆐S�ɂ��ĕ���(�P�Ɂu�I�E���v�Ƃ����ȗ�����邱�Ƃ��悭����)�A�u�A�[���t�v�݂̂܂��́u�A�[���t(���I�E���^����)�v�̂悤�Ɂu�A�[���t�v�𒆐S�ɂ��ĕ��邱�Ƃ��܂��Ȃ����ۂ��݂���B�A�[���t���番�h�����Ђ���̗ւɑ��Ă��u�I�E���^������S�h�v�̂悤�ɕ���邱�Ƃ�����B
���e�ɑ���^�u�[�Ƃ��ẮA�}�X�R�~�������ҁE�ǎ҂���A�[���t��i�삵�Ă���Ɣ���邱�Ƃ�����邠�܂�A���c��r�˂���^����A�M�҂ւ̔��ߑߕ߂�ʌ��ߕ߂��莋��������������X��������ƐX�͎w�E���Ă���B�܂��A�����̏o�������ԑg��TBS�r�f�I�������グ���2018�N���݂܂ōs���Ă��炸�A�u������������Ƃ��N�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̐�������B
���߃^�u�[
���{�ɂ����鑽���̃}�X���f�B�A����o�łɂ����āA�@���@�l�ł���n���w��ɑ���ᔻ���T���邱�Ƃ��w���B�߃^�u�[�Ƃ������̂͑n���w����ču�Ƃ��đ����Ă������@���@�̖䂪�߂ł��邱�ƂɗR�����Ă���B���@���@�ƊW��f�����n���w���1977�N(���a52�N)�ȍ~�A�V���{���}�[�N�Ƃ��Ĕ��t�@��p���Ă��邽�߁u�߁v�Ƃ����P��ő��̂����A���݂͒P�Ɂu�n���^�u�[�v�ƌď̂��邱�Ƃ������B
�߃^�u�[�Ƃ������t��1970�N��ɂ͂��łɃ}�X�R�~�E�A���_�E�ōL������Ă����Ƃ����B�n���w��A�����}����т���Ɋւ���c�́E�M�҂���̍R�c��i�ׂȂǂ����O����B1970�N��ɑn���w��ᔻ�{���o�ł������ҁA�o�ŎЁA�掟�X�A���X�Ȃǂɂ��܂��܂Ȉ��͂�������ꂽ�B����́u���_�o�ŖW�Q�����v�Ƃ��ĎЉ�̋����ᔻ�𗁂сA�r�c���(����)�������ɎӍ߂��Ă���B
�܂��A2000�N��ɂ����Ă��A�n���w���ᔻ�����w�T���V���x�Ȃǂ́A�@�֎��w�����V���x��֘A��Ƃł����O�����Ђ��o�ł���G���ȂǂŌ������ᔻ���ꂽ��A�ٔ��ői����ꂽ�肵�Ă���B
1999�N10���Ɍ����}���^�}���肵�Ă���A�o�ŎГ��͓��}�̐����I�e���͂�����A�e���ɂ�����n���w��ᔻ�͖�}�����茸�����ƌ����Ă���B
�f��ƊE�ɐ��ȉe���͂����X�^�W�I�W�u���̌�p�ґ����ɂ����Ă��A�n���w����̂ǂ̔h���ł��邩���d�����ꂽ�I�l�ł��������߁A�e�@�ւɂ����Ă��[���͕���Ȃ������B
�߃^�u�[�̂����킸���ȗ�O�Ƃ��āA1970�N��́u���_�o�ŖW�Q�����v���w����Ԃ�Ԋ��x�����������ăX�N�[�v���A���̑��}�X���f�B�A������ɒǐ��������Ƃ���������B�܂�21���I�ɓ����āw�T���V���x���R�c�����ɂ��u�V�w�n���w��x���a��v�Ƃ����A�ڂ��s���͂��߂��B
���ݓ��؍��E���N�l�^�u�[
�����m�푈��A�ݓ��{���N�l��������(���N���A)�A�ݓ��{��ؖ������c�A����эݓ��؍��E���N�l�̔ƍߎ����Ɋւ��ĐϋɓI�ɕ��邱�Ƃ́A���N���A���g�D�I�Ȏ��Ѝs�ׂȂǂ��N���������Ƃ���^�u�[�Ƃ���Ă����B���������N���A�Ɋւ��Ă͖k���N�ɂ����{�l�f�v��肪�I�悵�Ĉȍ~�A��r�I�^�u�[������邱�ƂȂ������悤�ɂȂ����B
�Ȃ��A���݂ł��ݓ��؍��E���N�l�̔ƍߍs�ׂɊւ��āA�{���ł͂Ȃ��ʖ����s���@�ւ�����B�����ɒ����V���E�����V���E�e���r�����ATBS�e���r�ANHK�A�܂�ɓǔ��V���Ȃǂ���������(�ڍׂ͐��_������������Q��)�B�܂�����Ɠ��l�ɁA���Ă͍ݓ����N�l�A�ݓ��؍��l�̒����l�̏o����邱�Ƃ�1980�N�゠����܂ł͂Ȃ��^�u�[�ł�����(�ڍׂ͍��V�[���������Q��)�B �͓��R�͓��{�����̉p�Y�Ƃ���Ă������A�ނ����N�����`�l�����a���o�g�ł���Ɠ`���邱�Ƃ͐��U�^�u�[�Ƃ���Ă����B
�������ߔN�ł́A�ݓ��̐�����⎞���Ȃǂő����`�◛�����Ȃǂ͓��{�ւ̋A������ʖ����g�킸�A�܂��}�X�R�~���ݓ��ł��������Ƃ��X�I�ɕ�ȂǏo����`���邱�Ǝ��̂̃^�u�[�͈ȑO�Ɣ�r������Ă��Ă͂���B
�����ؐl�����a���^�u�[
���݂ɂ����Ă��A���{���O�Ɋւ�炸�u�V���Ђ�e���r�ǂ͓����o���̐V���L�Ҍ����Ɋւ��郁���̂����Œ����ɕs���ȕ��o���Ȃ��v�u���{�̃}�X���f�B�A�͒����Ƀ}�C�i�X�ɂȂ���A�^����`���Ȃ��v�Ƃ�������������B
���ۂɁA1972�N�̓������𐳏퉻�܂ł́A���{�̑��}�X���f�B�A(�V���E�e���r����)��1964�N��LT�f�ՂŌ��ꂽ�u�����o���̐V���L�Ҍ����Ɋւ��郁���v�̌��͂ɂ��A�������Y�}���{�̈ӌ��ɂ�����Ȃ����e�͕ł��Ȃ������B�������A�u�����o���̐V���L�Ҍ����Ɋւ��郁���v�͓������𐳏퉻���1973�N�ɔp�~����Ă���A���̌�Ɍ��ꂽ�u�����������{�Ԃ̋L�Ҍ����Ɋւ�����������v�͕��K������悤�ȏ����͊܂܂�Ă��炸�A���̌����������ĕ@�ւ̍��O�ދ������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���������u�����o���̐V���L�Ҍ����Ɋւ��郁���v����т��̌�́u�����������{�Ԃ̋L�Ҍ����Ɋւ�����������v�͍��ƊԂł̎�肫�߂ł������Ђ���������茋�Ȃ�������ł�����̂ł͂Ȃ��A���ۂɐ�q�̎Y�o�V���Ђ��u�����������{�Ԃ̋L�Ҍ����Ɋւ�����������v�Ɋ�Â���1998�N�ɖk���ɒ������ǂ��J�݂��Ă���B���Ȃ݂�(�������̖��m�ȓG�s�ׂ̔��o�ȊO�ł͂قƂ�ǎ��s���ꂽ���Ƃ͂Ȃ���)�A����̗L���Ɍ��炸�A���ׂĂ̎匠���Ƃ͋L�҂̑؍������������O�ɒǕ����邱�Ƃ��\�ł���B
���̂��߁A���ؐl�����a���ƑΗ����钆�ؖ����������x�z���Ă����p�⍁�`���܂ގ�����̎��Ԃ����m�ɕ���Ȃ����Ԃ������Ă���B
�����_���^�u�[
�C�X���G���A�����ă��_���l�ɑ���^�u�[���A�C�X���G���Ƃ͔�r�I���̔������ł�����{�ɂ����Ă�����݂���(�ڍׂ�1995�N�ɔ��������}���R�|�[���������Q��)�B�������A�c���f���ٔ��̏��i���A�z���R�[�X�g�̗��j�C����`�I��������ёi�ׂ����{�ł��[���m����悤�ɂȂ�A�ȑO�قǂł͂Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B
���j�^�u�[
���A���{�����@�{�s��̍���Ŗ���I�Ɍ��肳�ꂽ(�Ƃ����)�u����v��ᔻ���邱�Ƃ́A���ԕ����ǁANHK�Ƃ��ɂ��̕�����ŋK���ΏۂƂ��邱�Ƃ����J���Ă���B���q�͂̕��a���p�A���Ɍ��q�͔��d��1950�N���荑��Ƃ���A��(�����}�����ɂ��55�N�̐����A����ѓ����{��k�Д����܂ł̖���}����)�̌��q�͔��d�����A����ь��q�͔��d�����^�c����e�d�͉�Ђ̉^�c���j�A���邢�͂��Ƃ����̂��N�����Ă����{�ɂ����錴�q�͗��p��ϋɓI�ɔᔻ���邱�Ƃ͔�������X���ɂ���B
�s���^��������ł�����1970�N��ɂ����Ăł����A�����V���Ȃǂ̍��h�n�}�X�R�~�����q�͔��d�̑��ݎ��͍̂m��I�ɕ��Ă���B�d�͉�Ђ��X�|���T�[�ɂ��Ă��閯�ԕ����ǂȂǂɂƂ��Ă̓X�|���T�[�^�u�[�̈��ƌ����Ȃ����Ȃ����A�e�����ǂƂ��ɍ����ᔻ���K���Ώۂɂ��邱�Ƃ𑊓���̓I�Ɍ��J���Ă��邱�Ƃ���A�K����������́u�^�u�[�v�ɕ��ނ������̂��Ƃ͌����Ȃ��B�܂����ԕ����ǂł��A�X�|���T�[�ɂ��Ă���d�͉�Ђ̌��q�͔��d���Ő[���Ȏ��Ԃ����������ꍇ�ȂǂŁA���Y�d�͉�Ђ��X�|���T�[�ł��邩��Ƃ������R�ł��̕��T���邱�Ƃ͎����҂���̐M���������A���̃X�|���T�[�Ƃ̌_��ɉe�����Čo�c�����ɒ������邱�ƂɂȂ�B���̂��߁A�ʏ���{�����A�����N�������X�|���T�[�ɑ��鏈�u�Ɠ��������₩�Ɍ_��������s���Ƃ����O����B
�j�^�u�[�̈��Ƃ��ẮABARAKAN MORNING��2014�N1��20�������ŁA�o���҂̃s�[�^�[�E�o���J�����A�����̕����ǂ���u�s�m���I�I���܂Ō����̘b��ɐG���ȁv�ƌ���ꂽ���Ƃ�\�I���Ă���B
���H�^�u�[
�H�͎R���g�̑��ł���R�H�ɗR������B�R���g���܂ޖ\�͒c�ɑ��A������ă}�X�R�~�͑�X�I�ɏo�ł���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��w���B�������A�R���g�̕���ɂƂ��Ȃ������͐�������A�R���͏�ɕ����ȂǁA���a���قǂ̐���ł͂Ȃ��B
����ƃ^�u�[
�w�T���V���x��w�T�����t�x�Ȃǂ̏o�ŎЌn�T�����������ƂȂǂ̍�Ƃ̃X�L�����_������邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��w���B���؏��F�ɂ��A�\�̐^�����x���������炾�Ƃ��Ă���B�������A�Q���V�l���w��܍�u��������v�ɂ����铐�p���^�Ȃǂ͐[�����Ă���A��Ƃ̎��͂Ɋւ���X�L�����_���͕����悤�ɂȂ��Ă��Ă���B
���싅�^�u�[
�t�@����������T�烁�f�B�A�ɂ����ăX�|�[�c�E���x�z�������Ă���싅�ɑ���A�ᔻ��s�ˎ��Ȃǂ̕��邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��w���B
2015�N���납�甭�o�����ǔ��W���C�A���c�����I��ɂ��싅�q�����̍ۂɂ́A�ǔ����l�R�̐e��Ђł���ǔ��V���O���[�v(�ǔ��V���ЁE��m�V���ЁE���{�e���r)�ł��̖������グ�邱�Ƃ����Ȃ������Ƃ������������B
���̂悤�ȃ^�u�[�͋��l�Ɍ��炸�����c�ł����݂���Ƃ���Ă���A�L�����̃}�X�R�~(��ɒ����V���⒆�������Ȃ�)���}�c�_�X�^�W�A���̃r�W�^�[�p�t�H�[�}���X�Ȃ̃J�[�v�t�@���ɂ�锃����ߖ��╪���k���A�����F�s�̊ē���̖�ԏs�˂ւ̖\�͍s�ׂȂǁA�L�����m�J�[�v�Ɋւ���ᔻ����_���A����ɂ���Ă͎������Ȍ��ɓ`������x�ɂ���ȂǁA���O���f�B�A�Ɣ�r���ďڍׂɕ��邱�Ƃ�����Ă���ʂ�����B���ɋ��c�̐��тƋƐт���������2010�N�㔼�Έȍ~���������X��������B
����Œ����h���S���Y�̏ꍇ�́A�e��Ђł��钆���V���Ђ̊W�҂ɂ�闎�������̍єz�ɑ���ᔻ���ēޔC��Ɍ����t�@���N���u���Ɍ��R�ƌf�ڂ����ȂǁA�O���[�v���ł̃^�u�[�������ʂ�����B
�ߔN�ł̓v���싅�I��̃h�[�s���O�ᔽ�⌣���������ɕ���ȂǁA���Ăقǂ̃^�u�[�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B
���n���Ɠs�s�̊i���Ɋւ���^�u�[
�n���Ɠs�s�̊w�͊i���E�o�ϊi���E�����i���ɂ��ẮA�����̃L�[�ǂ͕������X���ɂ���B
2010�N��ɓ���ƁA�n������s�s�֓���邱�Ƃ̂ł����c��W���j�A�ȍ~����̐l�Ԃ̎�ɂ���āA�n���Ɠs�s�̊i���^�u�[���w�E�����悤�ɂȂ��Ă����B
�����O���̕ɂ�����^�u�[
���Ă𒆐S�Ƃ������O���A���ɕč��ł͗��_�����ꂽ�u���������݂̊댯�v�(�\���s�ׂ��d��ȊQ���������A���������݂̊댯�������炳�Ȃ�����\���̋K����F�߂Ȃ��Ƃ������)���悭�p������B�\���̐ӔC�̏��݂͌����A�l�ł��邽�߁A�^�u�[�͕\���Ҍl(���ގ҂݂̂Ȃ炸�A�e�}�X�R�~��ʈČ����Ƃ̒S����)�̒��ɂ��ꂼ�ꂠ��B�܂��A�ߋ��̗��j�I�o�܂Ȃǂ������̓��e�̕ɂ��āA�@���ɂ����̋K�����ۂ��Ă���Ƃ��������B����Łu���������K��������̂Ƃ����T�O�v���̂��̂��Ȃ����Ƃ������A���ʁA���{�ȏ�ɖ����ɑ��݂��Ă���B
���i�`�X�E�q�g���[��^�^�u�[
�i�`�X�E�h�C�c�����̃��_���l�ւ̃w�C�g�N���C���ɂ��A���E�A���ɉ��Ăł̓i�`�X��q�g���[���^���邱�Ƃ��O��I�Ƀ^�u�[������A���Ƀh�C�c�ł͖��O���(�Y�@��130��)�ɂ��֎~�A�ᔽ�҂͏����ΏۂƂ���Ă���B�t�����X��h�C�c�Ȃǂł̓��_���l��l�|�E���ʂ��邱�Ƃ͖@���ŋւ����Ă���B
���펞�哝�̃^�u�[
�����w�҂̍��c��Y�́A�w�A�����J�哝�̂̌��́c�ώ����郊�[�_�[�V�b�v�x�ɂāA�g�A�����J���O���ł́u�펞�哝�̐��v�Ƃ����펞�ɑ��鐧�x�����݂���h�Ǝ咣���Ă���B�܂��A�g�펞�哝��(�푈�𐋍s����哝��)��ɂĔᔻ���Ă͂Ȃ�Ȃ��h�Ƃ����^�u�[�����݂���B����𗘗p�����̂��A�����J���������e����������уC���N�푈�����̃W���[�W�EW�E�u�b�V���ł���Ƃ����B �@ |
 |


 �@
�@ |
|
���V���e���r����ɕ��Ȃ��u���������̃X�[�p�[�������v 2016/10 |
���u�����V�����@�v�����������H
�u�������v�̐l�X�́A�ǂ����ăE�\�̃j���[�X�������A�Ԉ�����m���ŋc�_�����Ă��܂��̂��낤���B
���f�B�A�W�҂�A�������A�����A��w�����Ȃǂ͂��ꂼ��}�X�R�~�A�����A�w�Z�A��w�Ƃ����������ɂ܂݂ꂽ���Ɉ��Z���Ă���B���X�������r�W�l�X�̐��E�ŋْ������铭���������Ă���A�ǂ�����Ėׂ��āA�����ɐ����Ă��������K���ɂȂ�͂������A�����������ؔ�������@�����Ȃ�������A�������̍l���������Ă��Ă����C�ł�����̂��B
�}�X�R�~�̒��ł��A�V���͂Ƃ��ɍ��������̂����Ă��郁�f�B�A���B�������ēI�͂���ȋL���R�ƕ��Ă���B
�V���̕��R���S�ɂȂ錴����4����B�܂��́A�����V�����@�Ƃ����@�����B����1�͍Ĕ̋K���B������3�Ԗڂ͍ŋߐV���ɐ��܂ꂽ�y���ŗ����B����3�ŐV���͂��ׂĎ���Ă���B
����Ƀv���X���āA����͎��̘̂b�����A�V���Љ��̂��߂̍��L�n�̔��p�Ƃ�����肪����ł���B���{�̐V���Ђ̑������A�����Ȃ��獑�L�n���������������Ă�����āA�Љ��������Ɍ��݂��Ă���B�����̗D���[�u���Ă����ƌ����Ă����B��蒬��z�n�A�|���Ȃǂ̈ꓙ�n�ɐV���Ђ���������ł���̂ɂ́A���̂悤�ȗ��R������̂��B
��������A�V�����������܂݂�Ƃ��Ă���@���ɂ��Č��Ă������B
�܂������V�����@�Ƃ����̂͂ǂ������@�����B�������ς���Ă���@���ŁA���͐��E�ɂ���Ȗ@���͓��{�ɂ����Ȃ��B�|�C���g�́A�V���Ђ͑S�����̂��ׂĂ�������ЂŁA�n������������Ђ������̂����A���́u���傪�N���v�Ƃ������Ƃ��B
���@�̑匴�������A�����Ƃ����̂͏��n�������Ȃ��B����͊�����Ђ̊�����Ђ���䂦��ƌ�����B���n�������Ȃ�����ǂ�Ȏ��ɂ��I�[�i�[�����蓾��B���́u�I�[�i�[�����蓾��v�Ƃ������Ƃ��d�v���B
�v����ɃI�[�i�[�͂̂��̂��ƈ��Z�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�������邱�Ƃʼn�Ђْ̋������ۂ���A������Ƃ����o�c������Ƃ������ƂɂȂ�B
�������V���Ђ̊����́A�����V�����@�ɂ���ĂȂ�Ə��n�������݂����Ă���̂��B
����������Ƃǂ��Ȃ邩�B
���Ƃ��Β����V�����ɂƂ��Ă݂悤�B�����V���́A���R�ƂƏ��Ƃ���X�����ƃI�[�i�[�Ƃ��đ��݂����Ƃ��B�����̏��n����������Ă���̂�����I�[�i�[�����邱�Ƃ��Ȃ��B���̂悤�Ɋ��S�Ɍo�c�҂�����Ȃ��ƁA�I�[�i�[���ǂ�Ȉӌ�������������Ȃ����ŁA�o�c���j���͂��߂Ƃ����Ђ̂��ׂĂ̂��Ƃ����܂��Ă��܂��B
�������A�V���Ђ̃I�[�i�[�͌���Ɉӌ�������Ȃ��P�[�X���قƂ�ǂ��B����Ƃǂ��Ȃ邩�Ƃ����ƁA����̎В����o�c�̂��ׂĂ������Ă��܂��B�������āA��ɃN�r�ɂȂ�Ȃ��В��ɂȂ�Ƃ����킯���B
����1�̗�Ƃ��āA�ǔ��V�������Ă݂悤�B�n糍P�Y��\���������M���Ȃ��A���ꂾ���̌��͂������������邩�l���Ă݂ė~�����B�ǔ��͏]�ƈ��������������̂����A���lj�Ђ̓I�[�i�[�̂��̂��B
�������ĐV���Ђ��u�������v�W�c�v�ɂȂ�
���������n����Ȃ����ׂȌo�c�̂Ȃ��ŁA�I�[�i�[�����o�������邱�Ƃ��Ȃ��̂Ōo�c�w�ɂ͂Ȃ�̃v���b�V���[��������Ȃ��B�������Čo�c�g�b�v���傫�Ȋ炵�����邱�ƂɂȂ�B
���o�V���Ȃǂ͊�Ƃ̕s�ˎ���Nj�����L���Łu�R�[�|���[�g�K�o�i���X���d�v�v�Ƃ悭�����Ă��邪�A�����̉�Ђ���ԃR�[�|���[�g�K�o�i���X�������Ȃ��̂��B�Ȃ��Ȃ�A�����̏��n���������邩�炾�B����ł̓K�o�i���X�Ȃnj����悤���Ȃ��B
�V���Ђ̊��������n����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�܂��ɔ�������Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��B����ɁA���̐V���Ђ��e���r�ǂ̊������B�����V���Ȃ�e���r�����A�ǔ��V���͓��{�e���r�Ƃ���������B��������ƁA�e���r���V���ЂƓ����悤�ɂ܂������K�o�i���X�������Ȃ��Ȃ�B
�������ĐV���Ђ_�Ƃ��č\�����ꂽ���f�B�A�́A�������̉�ɂȂ��Ă��܂��B
�ȏ�̂悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��邽�߁A��x�V���Ђ̌o�c�w�ɉ�����Ă��܂��ΐ�Έ��ׂ��B�N�r�ɂȂ邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B����́A���̋ƊE�ł͐�ɂ��蓾�Ȃ������������K���Ȃ̂��B
����ԃK�o�i���X���Ȃ��̂́A�V���Ђ�����
���E��Ō��Ă����̓��{�̃��f�B�A�\���ُ͈�ł���B���ʂ̍��ł̓��f�B�A�����ʂɔ��������B�o�c�҂����邱�Ƃ�����̂ŁA���ꂪ��ЂƂ��ă��f�B�A�Ƃ��Ăْ̋����ɂȂ���̂��B
���Ƃ���2015�N��11���ɁA���o�V�����ăt�B�i���V�����E�^�C���Y���������Ƃ͋L���ɐV�����B���o�V�����A�ăt�B�i���V�����E�^�C���Y�̐e��Ђ������p�s�A�\�����犔�������Ď���̃O���[�v�ɑg�ݍ��̂����A����͂������ʂ̊�Ɣ����ƌ�����B�������A���o�V���̂ق��͊��������n�ł��Ȃ�����A�����Ĕ�������Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���B
����Ȃ��̂͏��@�ᔽ�łȂ����A�ƕ���l�����邩������Ȃ��B���̏�Ԃ����@�̓K�p���O�ɂ��Ă���̂��u�����V�����@�v�Ȃ̂��B
�����V�����@�͂������Z���@���ŁA�����ɂ́u�����V�����̔��s��ړI�Ƃ��銔����Ђ̊����̏��n�̐������Ɋւ���@���v�Ƃ����B���O�ɏ����Ă��邱�Ƃ����̖@���̂��ׂĂŁA�u�����͏��n����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��������Ă��Ȃ��B�V���̊������̍ő�̂��̂ƌ����Ă����B
���ʂɓ����Ă���l�����ɂ͓���݂��Ȃ����A�V���Ђɖ��߂�l�ԂȂ�݂�Ȓm���Ă���@�����B
�������A�V���Ђ̐l�Ԃł��̂��ƂX�ƋL���ŏ����l�Ԃ͂��Ȃ��B�V���͊�Ƃ̕s�ˎ������������Ɂu�R�[�|���[�g�K�o�i���X���ł��Ă��Ȃ��v�u�Г����x�������v�ȂǂƏ����A�˂邪�A��ԃK�o�i���X���ł��Ă��Ȃ��͂��̐V���ЂȂ̂��B�L�҂��A���ꂪ�������Ă��邩������V�����@�ɂ��Ēp���������ď����Ȃ��̂��낤�B
���̖@�����A�V���Ђ�������Ă��邱�ƂɁA�L�҂������C�����ׂ����B�����������ׂȐg���ł́A���҂Ɍ��������Ƃ�������͂��Ȃ��B�����ɂ͊Â����҂Ɍ������̂͂��肦�Ȃ��B���_�ŏ�������l�́A�₹�䖝���K�v�Ȃ̂��B
���e���r�ǂ��������̉�
�����Ńe���r�ǂɘb����ڂ������B�V���Ђ��q��Ђ̃e���r�ǂ��x�z���Ă���Ƃ����\���I�Ȗ��́A�O�i�ŐG�ꂽ�Ƃ���B����ɁA���̃e���r�ǂ������������Ă��闝�R�́A�n��g�������Ƃւ̐V�K�Q���������I�ɕs�\�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɂ���B
�����Ȃ̔F�����ꍇ�ɂ����e���r�������Ƃ͂ł��Ȃ��B�u�����@�v�ɂ���ĖƋ����x�ɂȂ��Ă���킯�����A���̂��Ƃ��e���r�ǂ��������܂݂�ɂ��Ă���ő�̌������B
�͂����茾�����B�u�d�g�I�[�N�V�����v�����Ȃ����Ƃ��A�e���r�̖��Ȃ̂��B�d�g�I�[�N�V�����Ƃ́A�d�g�̎��g���т̗��p�����������D�ɂ����邱�Ƃ��B
���{�ł͓d�g�I�[�N�V�������s���Ȃ����߂ɁA�d�g�̌����̂قƂ�ǂ��A�����̃��f�B�A������Ă��܂��Ă���B���Ƃ��A�n��g�̃e���r�ǂ��ACS�����ł�BS�����ł�3��4�`�����l���������Ă��܂��Ă���̂����̂��߂��B
�d�g�I�[�N�V���������Ȃ����߂ɗ��������̂܂܂ɂȂ�A�e���r�ǂ͂��̉��T�ɗ^���Ă���B�e���r�ǂ́u�d�g���p��������Ă���v�Ǝ咣����̂����A���̊z�͐��\���~���x�Ƃ������Ƃ��낾�B�����I�[�N�V�����ɂ�����A���݂̃e���r�ǂ��x�����ׂ��d�g���p����2000���~����3000���~�͉���Ȃ����낤�B���݂̃e���r�ǂ́A100����1�A���\����1�̔�p�œ�������ɂ��Ă���̂��B
�܂�A�e���r�ǂ��炷��ƁA��ɓd�g�I�[�N�V�����͔��������킯���B���̂��߂ɁA�����@�E����������NJ����鑍���Ȃɓ��������邱�ƂɂȂ�B
���̑����Ȃ��A���ۂ͓d�g�I�[�N�V���������{������A���̕�����������͕̂������Ă���͂����B��������Ȃ��̂́A�e���r�ǂ͐V�K�Q����h���Ŋ���������邽�߁A�����Ȃ́u����ړI�v�̂��߂ɁA�݂��ɋ��͊W������ł��邩�炾�B
�������@�̑���
�����ŏo�Ă���̂��u�����@�v���B�����A�����ɂ�郁�f�B�A�ւ̉�����莋����j���[�X���悭����Ă���̂ŁA�������̕����������낤�B�b��̒��S�ɂȂ�̂��A�����@��4���B�����@4���Ƃ͈ȉ��̗l�ȏ��B
�������Ǝ҂́A���������y�ѓ��O����(�ȉ��u�����������v�Ƃ����B)�̕����ԑg�̕ҏW�ɓ����ẮA���̊e���̒�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�� �@�����y�ёP�ǂȕ������Q���Ȃ����ƁB
�@�� �@�����I�Ɍ����ł��邱�ƁB
�@�O �@�͎������܂��Ȃ��ł��邱�ƁB
�@�l �@�ӌ����Η����Ă�����ɂ��ẮA�ł��邾�������̊p�x����_�_�𖾂炩�ɂ��邱�ƁB
����������ɁA���{���́u�����@�����A�����I�Ɍ����ȕ�S������v�ƌ����A����ɓd�g�@76���Ɋ�Â��u��g�v�����蓾��Ƃ����킯���B
����ō������̐l�X�́A�����@4���́u�ϗ��K�͂��v�Ƃ���B�܂�A�P�Ȃ铹����̓w�͋`�������Ȃ��A�Ɣ��_�����Ă���B
�������A�M�҂��猩��Ȃ�Ƃ��܂�Ȃ��c�_���B
���������A���E�ł͂���ȋc�_�����Ă��鍑�͂Ȃ��B�u�����@�����v�u����͗ϗ��K�͂��v�Ȃ�Ă܂�Ȃ��c�_������̂ł͂Ȃ��A�u�s�ꌴ���ɔC���A���R��������������v�����̘b�Ȃ̂��B
�d�g�I�[�N�V�����ɂ���ĕ����ǂ����R�ɎQ�����ċ������N����A���̍�����ԑg�����܂��͂��Ȃ̂��B�������Ȃ��Ƃ������Ă�����l�C���Ȃ��Ȃ邵�A�l�C������Ύ����҂��l�����X�|���T�[���t���B��������ĕ����ǂ����������A�����@�ȂǕK�v�Ȃ��͂����B
�J��Ԃ����A�d�g�I�[�N�V���������ƈ�ԍ���̂͊����̕����ǂ��B������A�K���ɂȂ��ēd�g�I�[�N�V�������s���Ȃ��悤�ɐ��_��U�����Ă���B
�����Ȃ͂��̎����m���Ă��邩��A�u�����@�v���`��������B�u�e���r�̗���������Ă���Ă���̂�����A�����@������v�Ƃ����킯���B����̓e���r�ǂ��d�X���m�B�����Ă��܂��A�}�X�R�~�͖����Ǝ���������̊W�ɂȂ��Ă���B
���}�X�R�~���_���ɂ���u�����̈��v
�ŋ߂ł͉E�h�̐l�������A�������̃��f�B�A�ɑ��āu�����@�����v�Ƒ������Ă���B�M�҂��炷��Ƃ���͂܂�Ȃ��������B���t�͈������A�����}�X�R�~���u�ׂ������v�̂Ȃ�A�d�g�I�[�N�V�����ŐV�K�Q��������悤���������B
�u�����@�͎��Ȃ��Ă���������A�d�g�I�[�N�V�����ɂ��ĒN�ł��ӌ��M�ł���悤�ɂ���v�ƌ��������̂��B�����Ȃ�̂��A�e���r�ǂɂƂ��Ă͈�Ԓɂ��B
���̓d�g�I�[�N�V�����̖��́A���R�Ȃ���e���r�E�ł̓^�u�[�Ƃ���Ă���B�d�g�I�[�N�V�����ɂ��ĕK�v�������_�҂́A�e���r�ǂɂƂ��Ă͗v���Ӑl���B�M�҂����̂ЂƂ肾�B
�����n��g�Łu���͓d�g���p���͐��\�����������ĂȂ����ǁA�{����3000���~����Ȃ�������Ȃ��ł���ˁv�Ȃǂƌ��������̂Ȃ�A�e���r�ǂ̐l�Ԃ݂͂�Ȑ^���ɂȂ��āA�ԑg�͂��̏�ŏI����Ă��܂����낤�B�e���r�ŃR�����e�[�^�[�����Ă���W���[�i���X�g���A���̗����̉��b�ɗ^���Ă���̂ő傫�Ȑ��Ŏw�E���Ȃ��B
�d�g�I�[�N�V����������A�������Ȏ��{���Q�����Ă��邾�낤�B�\�t�g�o���N�Ȃǂ̍�����Ƃ��͂��߁A�O�����{�ɂ��V�K�Q���������Ƃ�����Ƃ͂�������B
�����̃e���r�ǂ͋���ȎЉ���X�^�W�I�����L���Ă��邪�A���ꂾ���f���Z�p���i�����Ă��錻�݂ł́A�����̂��߂̔�p�͂����܂ł�����Ȃ��B���ł́A�C���^�[�l�b�g��Ŏ��R�ɕ������Ă��郁�f�B�A����������̂����炻��͖��炩���B
�����̕����ǂ̌�����d�g�I�[�N�V�����ŋ��藎�Ƃ��ƍl����Δ�p�͖c��Ɏv���邪�A�d�g�����ł͂Ȃ��C���^�[�l�b�g���܂߂čl����A�����ǂ��̂��͉̂��S�ǂ����Ă����܂�Ȃ��̂�����A�V�K�Q������̂ɔ�p�͐��S���~����������̂ł͂Ȃ��B
���{�͂������Ƃ��L���ł͂��邩������Ȃ����A�Z�p���i�����Ă��邽�߂ɕ����������p���̂��̂͂����������̂łȂȂ��̂�����A�N�ɂł���͊J����Ă���B
���l�ȕ������\�ɂȂ�A�ǂ�ȋǂ������Ă��Ă��W���Ȃ��B���͒n��g�L�[�ǂ̐��ǂ������x�z���Ă��邩��A���ꂼ��̃e���r�ǂ��ُ�Ȃ܂łɉe���͂����߂Ă���B�e���͂�������������@�����Ƃ����c�_�ɂ��Ȃ�B�����������ǂ����S���̐��ɂȂ�Ήe���͂����U����A�S�̂Ō����ɂȂ�B���̂ق����A���S�ȕ����҂ł��邾�낤�B
�������A�M�҂Ȃǂ��u���������Ԃ����v�ƒ���ƁA����������������H�炤�B�}�X�R�~��A�����A�������̊�������ᔻ����ƁA�����ɍ��h�̊w�҂��o�Ă��ċ������n�߂�B
�o�ϖ��ւ̖��m�������͂�������A����ɂ������āA�����������������ɂ܂݂�Ȃ������ł���Ƃ�����A�M�҂��u�������̓o�J����v�ƌ��������Ȃ闝�R���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���u�����ܗ֒��~�v�̌��������X���[������{�}�X�R�~�̕a���@2021/1
|
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�傪�~�܂�Ȃ��B�A���A�V�����e���r���R���i�Е�F�ł���B���Ă̓����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�J�Â�������������B���_�����ł�8���قǂ̍��������Ă̊J�Âɔے�I�ȑԓx��^��������Ă���B
�����������A�����ɗ��Ă悤�₭�A��v�S�����ɂ��J�Âɉ��^�I�Ȏ��_����̎�ދL�����o�n�߂��B�u�����A�����v��n�ł䂭���ɐT�d�ȓ��������A�ǎ҂̋^���S�ɉ�����̂��̖����ł���Ǝ��C����̂Ȃ�A�@�ւ͂��̖������������̂ł͂Ȃ��A���}�ɓO���ނ��A���˂Ȃ�Ȃ��͂����B
�܂����Ď��j���[���[�N�E�^�C���Y��1��15���̓d�q�łŁA���Ă̊J�Â͒��~�ɂȂ�\��������Ɠ`�����B���{�̍��ƓI�Â��̍s���ɂ��Ă��A�́u�O���v���݂Ȃ̂��B
�������ܗւ̊J�Ë@�^��グ�����郁�f�B�A
���Ă̓����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�J�Âɂ��āA�����͂ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��B
�����ʐM�Ђ����N1��9�A10�̗����Ɏ��{�������_�����ɂ��ƁA�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̍��Ă̊J�Â��u���~����ׂ����v��35.3���ɂȂ����B�u�ĉ�������ׂ����v��44.8�����܂߂�ƁA80.1���������������߂����ƂɂȂ�B�����̓R���i�Ɋւ���ً}���Ԑ錾��1�s3���ɏo������Ɏ��{����Ă���A�R���i�Ɋւ��鍑���̊�@�ӎ���I�m�ɉf���o�������̂Ǝv����B
2�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o��O�̐��_�����ł��A�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̊J�Âɂ́A�����̍������^�╄��t���Ă����B
�����V������N12��19�A20�����{���������ł́A�u�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���ǂ̂悤�ɂ���̂��悢�Ǝv���܂����v�Ƃ����₢�ɑ��A�\��ʂ�2021�N�ĂɊJ�Â���Ƃ̉�30���������B����ɑ��A�u�Ăщ�������v��33���A�u���~����v��32���B����65���������������߂Ă���B
�ǔ��V���͍�N10��〜11���A����c��w�Ƌ������A����[��X����������Ő��_���������{�����B���̒��ɂ͔�������̐��`�̓��t�ɑ��āu�D��I�Ɏ��g��łق��������ۑ���A�����ł��I��ł��������v�Ƃ̎��₪����B�u���̑��v�������đI������17���ځB�ő��̉́u��Â�N���A���ȂǎЉ�ۏ�v��69���ŁA�u�i�C��ٗp�v65���A�u�V�^�R���i�E�C���X��v59���Ȃǂ������B�����������ɂ�������炸�A�u�����ܗցE�p�������s�b�N�̊J�Ï����v��8%�����Ȃ������B���������́u���@�����v�ƕ����17���ڒ��̍ʼn��ʂł���B
�e���r�Ȃǂ��܂߂����̐��_�������قړ����X���ɂ���B
�������Ȃ���e���́A�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̊J�Â�O��Ƃ����A�ڊ�����W�𑱂��Ă���B�����ȑO���珀�����Ă����̂��Ƃ��Ă��A���̃R���i�Ђŋ@�^��グ�悤�Ƃ���ɂ́A���ٗl�Ȋ���������B�����̐l�����̓_�ɂ͓��ӂ���̂ł͂Ȃ����B
��������8�����J�Âɔے�I�Ȃ̂Ɂc�c
�����A�����킸���ł͂��邪�A�u���̂܂܂ł͊J�Âł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������_�ɗ�������ދL�����N��������悤�₭�����Ă����B���̂��������E���Ă݂悤�B
��r�I�X�g���[�g�Ȍ��o���Ŗڗ������̂́A�����V����1��8��������2�Љ�ʂ́u�����ܗց@�J�Ê�Ԃސ����w3���܂łɉ�������Ȃ���c�x�v�ł���B�R���i�Ɋւ���ً}���Ԃ��Đ錾���ꂽ����̒����B�L���͎Љ�ʂ����J���ď�`���Ă����B���̋L���͂���1�ŁA���o����3�i�B�����đ傫�Ȉ����ł͂Ȃ����̂́A���̏�ł͖ڂɂ��₷�������ł��������B�u������W�҂́w���X�̕�炵�ɋꂵ�ސl���Ï]���҂̂��Ƃ�z������ƁA���ǂ���ł͂Ȃ��x�Ɠf�I����B�g�D�ς͓����A�N��������E���S���������o����v�悾�����v�ȂǂƋL����Ă���B
�����V����1��13���́u��������v�Ō��J�����ʂ��g���đ�W�J�����B�匩�o���́u�����ܗցw����x�����͂���̂��v�B���̂ق��ɂ��u���_�́w���~�E�ĉ����x8���v�u����ł��c�g�D�ρE�E�^�}�w�K�����x�v�u��A�C�f�A�����ʂ́H�v�Ƃ��������o�������B�M�҂̌���Ƃ���A�Ǝ���ނɊ�Â��ĊJ�Âɋ^��𓊂�������L���Ƃ��ẮA���܂ł̂Ƃ���A���̋L������ԑ傫���B
�ǔ��V����1��9���̃X�|�[�c�ʂɁu�ܗւ����s���`�v�u���h�k���⒆�~�@NTC���p�����v�Ƃ����L�����ڂ����B�ً}���Ԃ̍Đ錾�ɔ����e���Z�c�̂̓����Ȃǂ�`������e�ŁA���{�\�t�g�{�[��������́u�ܗփ����o�[15�l�����߂�ŏI�I�l�̏ꂾ���A�ǂ����邩�ߓ����Ɍ��߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�Ή��Ɏl�ꔪ�ꂵ�Ă���v�Ƃ����R�����g���Љ��Ă���B4�i���o���̑傫�Ȉ����B�A�X���[�g�����̋�Y���`���L���ł���A���ʂɓǂ߂A�����J�Â͖������낤�Ǝv������e���B
�������A�ڗ������L���͂��̒��x�����Ȃ��B���̑��ɂ́A�ߋ��̑���4�̋����_�����i�������p���̌��{�[�g�I�肪���������ق��������Ɣ����������Ƃ�`����L���A���ۃI�����s�b�N�ψ���̍ŌÎQ�ψ��̃f�B�b�N�E�p�E���h��(�J�i�_)���u����(�����ł̊J�Â�)�m�M�����ĂȂ��B�N����肽����Ȃ����E�C���X�̋}���͐i�s�����v�Ƃ̌�����\�������Ƃ����L���Ȃǂ��ʐM�Ђ̊O�d�Ƃ��ė��ꂽ���x�ł���B
�������A�А��ł��̖���^���ʂ�����グ�����̂͂Ȃ��B�{���Ȃ琢�_�����ɂ����8�����̍������J�Âɔے�I�Ȍ����������Ă��邱�Ƃ����������i�K�ŁA�����ɂ��������������W�߁A���͂��A����Ɋւ��鐭�{��g�D�ρA�����s�Ȃǂ̎p���ɋ^����Ԃ��Ă����L���������Ă�����ׂ����낤�B
���ܗփX�|���T�[�ɖ���A�˂���}�X�R�~
��q�����悤�ɁA�j���[���[�N�E�^�C���Y��1��15���̓d�q�łœ����J�Âɑ�����^�I�Ȓ����L�����f�ڂ����B��f�̃o�E���h�����Ȃǂ����p�����L���ł���A�R���i�Ђ̎����������ĂȂ��ȏ�A�u��2�����E����A���̌ܗ֊J�Ò��~�ɒǂ����܂��\��������v�Ƃ��Ă���B����܂ł̗���⌻�炷��A���ɓ��R�̋L���ł���B�������A�L���ꂽ�������̂ɂ͐V�K�����R�����B
�����A�j���[���[�N�E�^�C���Y�̂��̕��Љ��`�ŁA�����ʐM�͑����ɑ���𗬂����B���̓��{���f�B�A���u�j���[���[�N�E�^�C���Y�����v�ƃl�b�g�ŕĂ���B���́u�J�Â͍���v�Ƃ̎w�E���A�O�d���Љ��`�ł�������Ȃ����Ƃɂ���B�J�Òn�͓��{�Ȃ̂��B����Ȃ̂ɁA��q�����悤�Ɂu�{���ɊJ�Âł���̂��v��������Ɩ₤����ދL���͓��{�̎�v���ɂ͌�������Ȃ��B������܂��A���{�̃}�X�R�~�̕a���������Ă���B
�S�����œ����s��g�D�ς���ނ��Ă���L�҂́u���Ă̊J�Â�������Ƃ͋L�҂̒N�����������Ă���ł��傤�B�ł��A�����ϋɓI�ɋL���ɂ��悤�A�Љ�ɓ��������悤�Ƃ����@�^�͂���܂���B�ǂ̃��f�B�A����������w���̂��|���̂��Ǝv���܂��v�ƌ����B
�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̃I�t�B�V�����p�[�g�i�[�ɂ͓ǔ��V���Ђƒ����V���ЁA���{�o�ϐV���ЁA�����V���Ђ�����A�˂Ă���B�I�t�B�V�����T�|�[�^�[�ɂ͎Y�ƌo�ϐV���ЂƖk�C���V���Ђ�������Ă���B���f�B�A�ψ���ɂ̓e���r�ǂ�ʐM�ЁA�V���ЂȂǂ��������݂��B
�V���Ђ�e���r�ǂ��c����Ƃł���A�I�����s�b�N��傫�ȃr�W�l�X�E�`�����X�Ƃ��đ����邱�Ǝ��͔̂ے肵�Ȃ��B�������A�c���ړI���u�̘_���v��H���s�����A�������^��Ɏv���傫�ȃe�[�}����ށE���Ȃ��̂ł���A�@�ւƂ��Ă͖��������ƌ����悤�B�����Ȃ����Ԃɂ��J�ÂɌ����ē����̂��Ƃ��ŋ��͎g���Ă���B
�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�����āA�{���ɊJ�Âł���̂��A�J�Â��ׂ��Ȃ̂��B������8���������^�������ȏ���u���ׂ��ł͂Ȃ��B �@ |
 |


 �@
�@ |
|
���e���r��������̃��f�B�A�ڐG�Ɛ����ρE�}�X���f�B�A�� 2008 |
|
���͂��߂�
|
�ߔN�A���{�ł��A���C�h�V���[�ԑg��C���t�H�e�C�������g�ԑg�ȂǂŐ����̘b�肪�����Ƃ肠������悤�ɂȂ�A�e���r�ł̐����̓`�������傫���ς���Ă��Ă���B�e���r�����̐�i���A�����J�ł�
�A�u������ʔ����`���邱�Ƃ́A�����҂̐����ɑ���M�����Ȃ��A�V�j�V�Y������������v�Ƃ����ᔻ�_���������A�u�����m�������߁A�Q���𑣂��v�Ƃ����^���_������
�A�����҂̊ԂŊ����ȋc�_���s���Ă���B
���C�h�V���[�ԑg�Ȃǂł̐����֘A������Ă�����{�ł́A�ǂ��Ȃ̂ł��낤���B����ɋc�_�͍s���Ă���B�������A���{�ł͎c�O�Ȃ���A������������邽�߂̎��ؓI�f�[�^���A�����J�ɔ�ׂĂ����ւȂ�
�A�܂��q�ϓI�Ȍ������\���Ƃ͌�����B
�����Ŗ{�����ł́A�܂��́u�I���E�����Ɋւ���ӎ��ɂ��Ă̐��_�����v�����{���Ċ�b�I�f�[�^�����W���A���{�ł́u�e���r�Ɛ����v�Ɋւ��錤�����\�ł���̂��ǂ��������������B
���̌����́ANHK���������������́u����18�E19�N�x�V�����̈�n���̂��߂̋��������v�Ƃ��āA�����̈�Ƃ��Ẳ\�����������邽�߂ɍs�����B�܂�g���C�A�������ł���B
�����`�[���ɂ́A�M�҂�̂ق��ɁA���������҂Ƃ��āA������w�Љ�w���̐��i�_�����A�ꋴ��w��w�@�̈�t�N�Y�y�����ANHK�����������������_������(�Љ��)���牖�c�K�i
�A�����a�q�A���v���q���Q�������B
���āA���������������\�ł��邩�ǂ����������邽�߂ɂ́A2�̂��Ƃ𖾂炩�ɂ���K�v������B��1�_�́A���{�ɂ����Ă͂��ăA�����J�ŋN�����悤�ȁu�e���r�����v���ǂ̂��炢�N���Ă���̂��B��2�_��
�A�����������q�ϓI�ɕߑ����鉼����ݖ��ݒ�ł���̂��B�����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����̌����̖ړI�ł���B�{�e�ł͎��̂Ƃ���Љ�����B
1�D���Ăɂ������s�����̓���
/ �܂��A�����ƃe���r�̊W�Ɋւ���A���Ă̐�s���������r���[����B����ɂ��1980�N��ȍ~�̃A�����J�ł́u�e���r�����v������Â���ƂƂ��ɁA��s�����̒m�����m�F����B
2�D���������̐v
/ �����āA��s�����̒m�������Ƃɍ\�������������A�}���ŊȒP�ɏЉ��B
3�D�������ʂ̂����ȃ|�C���g
/ �����̎��{���ʂɂ��Ă����ȃ|�C���g�𒆐S�ɏЉ��B����ɂ��A���{�ɂ�����u�e���r�����v���A�A�����J�ɔ�ׂĂǂ̂��炢������ł��Ă���̂��A���{�̌���𖾂炩�ɂ���B���킹��
�A����̗p�����ݖ�A�T�O���ǂ��܂Ō����Ƃ��ėL���Ȃ̂��A���̗L��������������B
4�D�����̉\���ƍ���̉ۑ�
/ �Ō�ɓ����̖ړI�ł���A���{�ł̂��̕���ɂ����钲�������̉\���ɂ��čl����B
|
|
��1. ���Ăɂ������s�����̓��� |
��1-1 �I���̃v���X�E�}�C�i�X
1980�N�㏉���A�A�����J�ł́A���f�B�A�Ɛ����A���Ƀe���r�̌��������o�������A���{�ł͊F���ł������B1984�N����O�ˁA�����A�|���A�|����ƃX�[�U���E�t�@�[
�A�G���X�E �N���E�X��ɂ����ċ����������͂��܂���1)(Akuto, 1996)�B�܂��A�O�˂͂���܂ł̃A�����J�̌��������r���[�����̂�2)(Akuto, 1988)�A�R�����r�A��w�ɂ�����1988�N�̃u�b�V���f���J�L�X�̑哝�̑I���Ɋւ���
�A�C�x���g�̊ώ@�����A�e�퐢�_�����̌��ʂ̕��͂��s����3)4)(�O�ˁA1989�A2001)�B
����ɂ��A�A�����J�ɂ����āA1960�N��ȍ~�A�����̖��剻�A�\���I���̕��y�A�e���r���_�̎��{�ɂ��A�e���r�ɂ�鐭��������I�ɑ��������B���̌���
�A�����̑�O���A��y���������݁A�v���X�A�}�C�i�X�̉e�������ꂽ�B
�v���X�ʂƂ��ẮA�e���r�ɂ���Đ�������@�\�����܂�ƂƂ��ɁA���҂̏�E��ۂ�`�����[�̔��f����L�����B�l�K�e�B�u�L���L�����y�[�������f�ޗ���L���ɂ��邱�Ƃɍv�������B
�����A�}�C�i�X�ʂƂ��ẮA�S�V�b�v�ɂ�鐭���s�M�A�e���r�����j���[�X�ւ̕Ώd�A��y�u���ւ̑Ώ��Ƃ��ĉߏ艉�o�E�Z���Z�[�V���i���Y�����L�������B�܂��߂Ŗ{���I�ȕ�(substance reporting)����
�A���������𒆐S�Ƃ��鋣�n�^��(horse�|race reporting)�����S�ɂȂ����B
|
��1-2 �e�[�}�̓`�����A��y�u���ɂ��e��
1990�N��ɓ����āA�A�����J�ł̓e���r�̓`�����̓����ɒ��ڂ������ؓI�Ȍ����������o�ꂵ���B��\�I�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ���������ƁAJ.N.�J�y���AK.H.�W�F�C�~�\�����
�A1993�N����94�N�ɂ����āA�e���r�́u�e�[�}�̓`����(�t���[��)�v�ɂ���ẮA�����s�M�E���f�B�A�s�M���������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邽�߂̒��������{����5)(J. Cappella and K. H. Jamieson, 1997)�B2000�N�ɓ����
�A�e���r�W���������y�I���o�ɒ��ڂ������������W�����BM. A.�o�E���́A���҂���y�I�ȃg�[�N�V���[�ɏo�����邱�Ƃɂ��e���͂���6)Matthew. A. Baum, 2005)�B�܂�
�AM. �v���C�A�[�́A�����f�B�A���ł̌�y�u���̉e���͂���7)(Markus Prior, 2005)�B�����̌����ɂ��A������������ł��Ȃ��e�������邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B
|
|
��2. ���������̐v |
��2-1 �����̉���
��s�������āA����������ݒ肵���̂��A�} 1�̐}���ł���B���̐}���͏����s����ł��낤�A������z�肵�č쐬����Ă���A���̂�������A��b�I�ɒ��������̂͐}�̐^�̎l�p�ň͂����ł���B
���̍���̊�b�����̍\���v�f�́A�傫���́u���f�B�A�ڐG�v�u�F�m�Ƒԓx�v�u���R�~���j�P�[�V�����l�b�g���[�N�v�u���f�B�A���e���V�[�v��4�̑傫�ȗv�f���Ȃ��Ă���B
������4�̗v�f�̊Ԃ̊W�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����̊�b�����̃S�[���ł���B�}����ɕ`���ꂽ���̌����́A�z�肳�����ʊW��\���Ă���A�����������ŁA��悪���ʂ��Ӗ����Ă���B���ň͂����̂��Ă������
�A���f�B�A�ڐG����̉e���������Ă���B
|
��2-2 �����̊T�v
��b�����͎��̒ʂ���{�����B
�@�@�@���������F2007�N5��10��(��)�` 20��(��)
�@�@�@��������F�S��20�Έȏ�̒j���@1,800�l
�@�@�@�������@�F�K�◯�u����@
�@�@�@��(��)�F1,225�l(68.1��)
��b�����̐ݖ��37��ŁA��s��������сANHK���������������ɂ��u���{�l�̈ӎ������v�A�u���炵�Ɛ����v�����A�u�]�����̐����ӎ��v�����A�u���{�l�̃}�X���f�B�A�Ɋւ���ӎ��v����
�A�u���{�l�ƃe���r�E2005�v���Q�l�ɂ��č쐬�����B
�@�@�@�} 1�@���E�ԑg�Ɛ��_�`���E���f�B�A���e���V�[��������(��������)
|
��2-3 ��b�����̍\���v�f
����ł́A4�̑傫�ȗv�f���ƂɎ�������������B
�@�@�@��2-3-1�u���f�B�A�ڐG�v
����ʂ��琭���Ɋւ�����܂ŁA�l�X�͂ǂ̃��f�B�A����ǂ̂悤�ɓ��Ă���̂��A���炩�ɂ��邽�߂�12�̐ݖ��ݒ肵���B���f�B�A�̉e�����l�����ŁA�ǂ̕ϐ��������Ă���̂����͂���K�v������B�����Ȃ��͈̂ȉ��̒ʂ�ł���B
�������胁�f�B�A�A�e���r�������ԁA�E���ԑg�����p�x�A�j���[�X�E�ԑg�̌���
�������֘A�ԑg�����闝�R
���D���ȃe���r�W������(��y�u��)�A�D���ȃj���[�X�E�ԑg�̃^�C�v�A�����̂���j���[�X�E�ԑg�̓��e
�@�@�@��2-3-2�u�F�m�Ƒԓx�v
�����Ɋւ���F�m�Ƒԓx�Ƃ���14�̐ݖ��p�ӂ����B���f�B�A�ڐG�Ƃ̊W�ł����ƁA���f�B�A�ڐG�̌��ʂł�����A���f�B�A�ڐG�̌����ɂ��Ȃ肤�镔���ł���B���[�s���Ƃ̊W�ł�����
�A�����ƂȂ�d�v�ȕ����ł���B�����̎ړx�����܂��\���ł��邩���A����̌����̉\����傫�����E���邱�ƂƂȂ�B
�������m���A�S�A�����I�u����(�ێ�E�v�V�X��)
�������V�X�e���ւ̕]���A�����I�L�������o�A�����I�V�j�V�Y��
�����{�̐����ۑ�A���{�l���l����ׂ��ۑ�
�����퐶���ł̃��X�N���o
���e���r�E�V���ɑ���]��
�@�@�@��2-3-3�u���R�~���j�P�[�V�����l�b�g���[�N�v
�ÓT�I�����w�s�[�v���Y�E�`���C�X�x(���U�[�X�t�F���h�ق��A1944)�ɂ��w�E�ȗ��A�����s���Ⓤ�[�s���ɉe����^������̂Ƃ��āA�����c�̂�p�[�\�i���R�~���j�P�[�V�������[���ւ��Ă��邱�Ƃ��Ђ낭�m���Ă���B�܂�
�A���҂�Љ�ɑ���M�����A�ݕɑ�\�����\�[�V�����L���s�^��(�Љ�W���{)�����݂ł͏d�v�ȗv�f�Ƃ��čl�����Ă���B�����7�̐ݖ���l�����B
���R�~���j�P�[�V��������A�����c�́A�F�l��
�������g�D�A���҂ւ̐M�����A�Љ�ւ̐M����
�@�@�@��2-3-4 �u���f�B�A���e���V�[�v
�e���r�ڐG�̉e�������������ŁA�����҂��e���r�ɑ��Ăǂ̂悤�ȃ��e���V�[�������Ă���̂��l�����邱�Ƃ́A�����ւ�d�v�ł���B������4�̐ݖ���쐬�����B
���e���r�ɑ���e�ߊ�
���e���r���e���V�[(�e���r�̌����E�ԓx)
������\�́E��M�~��
�O�ˁE����E����(2006)�ɂ��A�����҂̃e���r�ɑ���ԓx�́u�ߓx�ɔᔻ�E�U���v����ԓx�A�u�ߓx�ɐM���E�v���v����ԓx�A�ȂǑ傫��������邱�Ƃ��������Ă���8)�B�ԓx�̈Ⴂ�ɂ����
�A���f�B�A�ڐG�ɂ�鐭���ԓx�ւ̉e���ɈႢ���o�Ă���ƍl������B
�����ŁA�u�e���r�ɂ��Ă��̌��߁E�����Ȃǂ��悭�������Ă���A�ߓx�ɐM���E�v������ł��Ȃ��ߓx�Ȕᔻ�E�U��������ł��Ȃ��A�K�x�Ƀe���r�̓����𗝉����A�e���r��L���ɓK�ɗ��p�E���p����l�����v��
�A�g�e���r���e���V�[�̍����l�����h�ƒ�`���āA���͂����݂����B�������邱�ƂŁA�e���r��������ɖ]�܂����e���r�ւ̑ԓx�����㌟�����邱�Ƃ��\�ƂȂ낤�B
|
|
��3. �������ʂ̂����ȃ|�C���g |
|
�����ł͒������ʂ���A���{�́u�e���r�����v�𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA�����̈�̉\���ɂ��Ă���������B�{�e�ł́A���ʂ̓s������u���f�B�A�ڐG�v�u�F�m�Ƒԓx�v�u���f�B�A���e���V�[�v�̗̈�̃|�C���g�ɂ��Ă̂ݕ���B�u���R�~���j�P�[�V�����l�b�g���[�N�v�̕����ɂ��Ă�
�A�P���W�v�����ł͂Ȃ��āA�ړx�\���Ȃǂ̕��͂��s���Ă͂��߂āA���Ԃ��݂Ă����Ƃ����悤�Ȑݖ₪�����̂ŁA�����ł͎��ʂ̓s�����犄������B
|
��3-1�@�u���f�B�A�ڐG�v�̌���
�܂��A���f�B�A�ڐG�̑��ʂŁA���{�́u�e���r�����v�͂ǂ̂��炢������ł���̂ł��낤���B���_���炳���Ɍ����A���{�ɂ����Ă��A�����J���l�A�����̑�O��
�A��y����������ł����B����ł̓|�C���g�ɂ��ċ�̓I�ɂ݂Ă݂悤�B
�@�@�@��3-1-1�@�������̏����胋�[�g
���� 1�@�����ȏ��(channel)
�����Ɋւ��邨���ȏ��Ƃ��āANHK�j���[�X�E�ԑg��������l�������������A�ω����钛��������ꂽ�B�q�����ɂ��Ă̂����ȏ�� (n��1,225)�r
�� 1 �� NHK�j���[�X�E�ԑg 38��
�� 2 �� �����̃j���[�X�E�ԑg 26%
�� 3 �� �V�� 25%
�e���r����̉e�����l���邽�߂ɁA�ǂ̃��f�B�A���琭���Ɋւ�����Ă���̂��A���̃��[�g���܂��m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���p����}�X���f�B�A�ɂ���ĉe���̗^�����͑傫���قȂ邩��ł���B
�����ł́A�����A�o�ρA�����A�n��A�����̂��ꂼ��ɂ��āA�ǂ̃��f�B�A���������肵�Ă��邱�Ƃ������Ƃ������̂��A�I��������1�I��ł�������B�I�����́u�V���v
�A�uNHK�j���[�X�E���ԑg�v�A�u�����̃j���[�X�E�ԑg�v�A�u�����̃��C�h�V���[�E���ԑg�v�A�u�G���v�A�u�C���^�[�l�b�g�v�A�u���̑��v��7�ł������B
�Ȃ��A�N��A���ʂɂ���đ傫���قȂ��Ă��邱�Ƃ����������B�S�̂Ƃ��ẮA�����̂����ȏ�Ƃ��āuNHK�j���[�X�E�ԑg�v��������l�� 38���ƈ�ԑ���������
�A20�`39�̒j��(n��115)�ɂȂ�ƁA18���Ə��Ȃ��Ȃ�A�u�����̃j���[�X�E�ԑg�v(38��)�A�u�V���v(20��)�ɂ��ŁA3�ʂƂȂ��Ă���B�����Ɋւ�����̓��胋�[�g���傫���ς���Ă������Ƃ��M�킹�錋�ʂƂȂ����B���̂��Ƃ���
�A�e���r�̉e�����傫���ς���Ă���Ǝv����B
�@�@�@��3-1-2�@�����֘A�ԑg�����闝�R
���� 2�@�����֘A�ԑg�����闝�R (�~���[��)
�����֘A�ԑg�����闝�R�́A�u����̗ǂ��������f�ɖ𗧂v��45���A�u��炵����ɖ𗧂v��41���A�u���ԂŎĂ���b�肪�킩��v��35���Ƒ��������B�傫���݂��
�A��y�u�������܂��Ă��邱�Ƃ����������B (n=1,225)
�u��������E�̓������Ƃ肠����ԑg�v�����闝�R���Ă݂��B�����֘A�ԑg�����邱�Ƃɂ���āA�����҂͂ǂ̂悤�ȗ~�����[�����Ă���̂��A�m�邽�߂ł���B��̓I�ɂ�
�A�} 2�ɂ��闝�R�ɂ��āA���Ă͂܂���̂����ׂĂ����Ă�������B
�@�@�@�} 2�@�����֘A�ԑg�����闝�R
�u���闝�R�v�ɂ��Ă��A�N��ɂ�鍷���傫���B�u����̗ǂ��������f�ɖ𗧂v�A�u��炵����ɖ𗧂v�͍���w�ɑ����A�u���ԂŎĂ���b�肪�킩��v�͎�N�w�ɑ��������B�܂�
�A�u�f��◠�b��m�肽���v�Ƃ������R�͐��㍷�����܂�Ȃ��B
�����������Ƃ���A����́u���ԂŎĂ���b�肪�킩��v�u�f��◠�b��m�肽���v�Ƃ������A�����ɋ����S���[�������߂ɁA�����֘A�ԑg������l�������邱�Ƃ��l������B���������X����
�A���̐ݖ�̕��͌��ʂ�����݂��Ă���B
�{�e�`���̌��������̂Ƃ���ŏЉ�����A�����f�B�A���ł̌�y�u���̉e���͂���M. �v���C�A�[�ɂ��A��y�u���̋��������҂قǁA�e���r�ɂ��e�����₷���Ǝw�E���Ă���(Markus Prior, 2005)�B�������������҂̃j�[�Y�ɂǂ̂悤�ɑΉ����Ă����̂�
�A�e���r�ɖ���Ă���Ǝv����B
�����Ƃ��Ă��A����������y�u���܂�o���G�e�B�[�ԑg�₨���ԑg�u���ƁA�ւ̔ᔻ�I�ԓx����ѐ����ςƂ́A�֘A�ɂ��Č������邱�Ƃ��d�v�ł��낤�B
�@�@�@��3-1-3�@�D���ȃj���[�X�E�ԑg�^�C�v
���� 3�@�D���ȃj���[�X�E�ԑg�^�C�v
1�@���e�̓`�����ɂ��ẮA����^�C�v���D���Ɠ�����l�� 50���Ƒ��������B
2�@���o�ɂ��ẮA�q�σ^�C�v�A�����^�C�v�A�ӊO���^�C�v�ŁA�قڎO������Ă���B�S�̂Ƃ��Č�y�u�������l�������ł������B
3�@�I���̓`�����ɂ��ẮA����^�C�v���D���Ɠ�����l���A71���Ƒ��������B
(n=1,225)
�j���[�X�E�ԑg�ɂ�������e�̓`���������≉�o�A�܂�u�ԑg�̃t���[���v�̂��肩�����̂��̂��A�����ς�f�B�A�ςɂǂ̂悤�ȉe����^���Ă����̂��������邽�߂̐ݖ�ł���B�����ł�
�A���e�̓`�����A���o�A�I���̓`�����ɂ��āA���ꂼ�� 3�̃^�C�v��I�����Ƃ��ėp�ӂ��āA�����Ƃ��D���ȃ^�C�v��1�I��ł������(�} 3)�B
�@�@�@��3-1-3-1�@�D���ȓ��e�̓`����
�܂��A���e�ɂ��ẮA�����⎖���̓`�����Ƃ��Ď���3�̃^�C�v����I��ł�������B
����^�C�v �F����w�i���������
�����^�C�v �F�����⓮���𒆐S�ɓ`����
�ӌ��^�C�v �F�o���҂̈ӌ�(�ᔻ�E�x��)��`����
���̌��ʁA����^�C�v��������l�������Ǝ����^�C�v(substance reporting)��������l��葽�������B1980 �N��㔼�̃A�����J�̃e���r�����Ɏ����ɂȂ����B
�@�@�@�} 3�@�D���ȃj���[�X�E�ԑg�^�C�v
�Z���e�̓`����
����^�C�v 50�� / �����^�C�v�@41�� / �ӌ��^�C�v 8�� / ���̑� 1��
�������E�����ɂ��ā�
����^�C�v�F����w�i�Ȃlj������
�����^�C�v�F�����⓮���𒆐S�ɓ`����
�ӌ��^�C�v�F�o���҂̈ӌ�(�ᔻ�E�x��)��`����
�Z���o
�q�σ^�C�v 38�� / �����^�C�v 31�� / �ӊO���^�C�v 30�� / ���̑� 1��
���L���X�^�[��Q�X�g����
�q�σ^�C�v�F�W�X�Ɠ`����
�����^�C�v�F�ʔ����`������A����ɑi�����肷��
�ӊO���^�C�v�F���_�E�����p�Ȃǃn�v�j���O������
�Z�I���̓`����
����^�C�v 71�� / ���s�^�C�v 9�� / �헪�^�C�v 18�� / ���̑� 2��
���I���I�̕ł́�
����^�C�v�F���҂̐���E�l���A���}�̗���Ƃ����ϓ_
�헪�^�C�v�F���҂̎v�f�E�����Ђ��A�헪�Ƃ����ϓ_
���s�^�C�v�F�ǂ��炪�����������A�ǂ��ǂ��Ƃ����ϓ_
�@�@�@��3-1-3-2�@�D���ȉ��o
���ɁA���o�ɂ��ẮA�L���X�^�[��Q�X�g�̓`�����Ƃ��āA3�̃^�C�v��ݒ肵���B
�q�σ^�C�v �F�W�X�Ɠ`����
�����^�C�v �F�ʔ����`������A����ɑi�����肷��
�ӊO���^�C�v �F���_����p�Ȃǃn�v�j���O������
3�̃^�C�v���������炢�I��A�q�ϕ��D�ސl�������h�ɂȂ���邱�Ƃ��킩��B�ʔ����`������A�n�v�j���O�����߂��肷��l�����A�j���[�X�E�ԑg�ւ̌�y�u�������l�����{�ł��������Ԃ������Ă����B
�@�@�@��3-1-3-3�@�D���ȑI����̎̕d��
����̒����ł́A����ɑI����̎̕d���ɂ��Ă��A�����悤�Ȍ`���Őq�˂Ă���B
����^�C�v �F���҂̐���E�l���A���}�̗���Ƃ����ϓ_����`����
�헪�^�C�v �F���҂̎v�f�E�����Ђ��A�헪�Ƃ����ϓ_����`����
���s�^�C�v �F�ǂ��炪�����������A�ǂ��ǂ��Ƃ����ϓ_����`����
����͌��������̂Ƃ���Ō��y�����悤�ɁA�A�����J��J.N.�J�y���AK.H.�W�F�C�~�\����́A�e���r�́u�e�[�}�̓`����(�t���[��)�v�ɂ���ẮA�����s�M�E���f�B�A�s�M���������邱�Ƃ��咣���Ă����B�ނ�͂����ł����Ƃ����
�A�I����ł́u�헪�^�C�v�v�̑������A�����҂̐����s�M�����߂�Ƃ����������N���Ă���B���{�ł͂��̐헪�^�C�v���D�����Ƃ����l�́A�܂�18���Ə��Ȃ��A�i�ق̌����ۑ�Ƃ͂܂��Ȃ��Ă��Ȃ��B������
�A��N�w�قǂ��̊����͍����A20�` 39�̑w�ł�31���Ƒ����Ȃ��Ă���B�܂��A���������X���������A�����͑傫�Ȍ����ۑ�ƂȂ邱�Ƃ��\�z�����B����A��q����u�ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�ȂǂƂ̊֘A�̌������K�v�ɂȂ�ł��낤�B
����܂ł݂Ă����悤�ɁA���f�B�A�ڐG�̖ʂł́u�e���r�����v���A���{�ł�������x������ł��邱�Ƃ����������B�܂��A���f�B�A�ڐG�̐ݖ�(�ϐ�)�ɂ��Ă�
�A���{�̃e���r�������\���ɕߑ����Ă���ƌ��_�Â��邱�Ƃ��ł���B
|
��3-2�@�u�F�m�Ƒԓx�v�ɂ���
�@�@�@��3-2-1 �����ɑ���]��
�@�@�@��3-2-1-1 �����ɑ���]���̌���
�����ɑ���]���Ƃ��Ă܂��A�����ւ̐M�������݂Ă݂悤�B
���� 4�@�����ւ̔ᔻ�I�ԓx
�������̂��̑S�ʂɑ��Ĕᔻ�I�ԓx�̋����l�̊����́A57���ł������B
(n=1,225)
�@�@�@�} 4�@�����ւ̔ᔻ�I�ԓx
���Ȃ��͍���̃z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�������x�����ɂ��āA�ǂ̂悤�Ɋ����Ă��܂����B���ɂ�����A��B�̂����A���Ȃ��̋C�����ɋ߂����̂�1���I��Ł������Ă��������B
���{��^�}���`�������Ɓ@�u�L���҂��m�肽����悤�Ȃ��Ɓv34�� / �u����̗��v�̂��߁v49�� / �u�L���҂��m��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓv42��
�^�}�̖ړI�@�u����̗��v�̂��߁v49�� / �u���̖����������邽�߁v27�� / ���� 25��
�P��̗��R�@�u�@�Ă̓P�L���҂ɃA�s�[������Ɛ��{�͍l�����̂Łv42�� / �u���̐���͍���̓��{�ɂƂ��ėL���łȂ�����v34�� / ���@25��
�} 4�̂悤�Ȍ`���ʼn҂ɐq�˂Ă���B������A�ړx���\�����邽�߂ɍl�Ă��ꂽ���̂ł���B����́A���������ɘb��ɂȂ��Ă����z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�������x��������ɂ���
�A�҂̈ӎ���q�˂����̂ł���B�̔w�i�ɂ���A�����S�̂ւ̐M������T�邽�߂̂��̂ł���A���̂��߂��ꂼ��̍��ڂɂ��ĒP���W�v�͂����܂ŎQ�l�ł���A���ꎩ�̂͂��܂�Ӗ��������Ȃ��B
(A)�Ɠ������ꍇ1�_�A(B)�Ɠ������ꍇ0�_�A���͕��͂��珜�O���āA�X�R�A���v�Z���āA�u�����ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�𑪒肷��ړx���\������B���z(n��923)���݂�ƃX�R�A3�A20��
�A�X�R�A2�A37���A�X�R�A1�A32���A�X�R�A0�A12���ƂȂ��Ă���B���̌��ʁA�������̂��̑S�ʂɑ��Ĕᔻ�I�ԓx�������Ă���l�A�܂�A�X�R�A2�ȏ�̐l�̊����͑S�̂�57���ł������B40����59�̔N��w�����̔N��w�ɔ�ׂĔᔻ�I�ԓx�����������B
3-2-1-2�u�����ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�ړx�̉\���u�����ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�ړx�̃X�R�A�ɂ��āA�O�q�̕��z�̗l�q���݂Ă݂悤�B�ǂ����̃X�R�A�ɉ҂��W�����邱�Ƃ��Ȃ�
�A�����l��������⍂���Ȃ�A���ꂢ�ɕ��z���Ă���B�N���j�������݂��A���͂̂��߂̎ړx�Ƃ��ď\���Ɏg���邱�Ƃ����������B���̐ݖ₩��\�������u�����ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�ړx��
�A�����ɏ\���L���ł���Ƃ�����B
�@�@�@��3-2-2 �e���r�E�V���ɑ���]��
�@�@�@��3-2-2-1 �e���r�E�V���ɑ���]���̌���
�A�����J�̌����ɂ����āA�e���r��������ɂȂ�ƃe���r�E�V���ɑ���ᔻ��V�j�V�Y�������܂�ƕ���Ă���B���{�̌���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���B�܂��e���r��
�A�V���Ђւ̐M�������猻����݂Ă݂悤�B
����5�@�e���r�ǁE�V���Ђɑ���]��
(n=1,225)
���e���r�ǁ��@�M�����Ă��� 5��
/ �܂��M�����Ă��� 41��
/ ���܂�M�����Ă��Ȃ� 41��
/ �M�����Ă��Ȃ� 12��
���V���Ё��@�M�����Ă��� 9��
/ �܂��M�����Ă��� 57��
/ ���܂�M�����Ă��Ȃ� 27��
/ �M�����Ă��Ȃ� 7��
�e���r�ǂɂ��Ă����A�M�����Ă��Ȃ��l�̕����A�M�����Ă���l�ɔ�ׂđ����Ȃ��Ă����B����̊�b�����ł́A���̂��̂̕]���ɂ��Đq�˂Ă���B
����6�@�e���r�E�V���ɑ���]��
�ǂ��炩�Ƃ����u�����_��������悤�Ƃ��Ă���v�Ǝv���Ă���l�͑S�̂�45���ɁA�u�e���r�j���[�X�͎��������Ƃ��悤�ɍ���Ă���v�Ǝv���Ă���l�͑S�̂�44���ɒB���Ă���B
(n=1,225)
�]����4�̑��ʂ��畷���Ă݂��B
�� 1�@�́A(A)�Љ���̉����������Ă��邩�A����Ƃ��A(B)��舫�������Ă��邩�B
��2�@�́A(A)�����ŋq�ϓI���A����Ƃ��A(B)���_�𑀍삵�悤�Ƃ��Ă��邩�B
��3�@�V���́A(A)�ǎ҂��m��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�`���Ă��邩�A����Ƃ��A(B)�ǎ҂̍D��S�ɂ����悤�Ȃ��Ƃ�`���Ă��邩�B
��4�@�e���r�j���[�X�́A(A)�����҂̑��l�ȃj�[�Y�ɂ��킹�č���Ă��邩�A����Ƃ��A(B)���������Ƃ��悤�ɍ���Ă��邩�B
���ꂼ��̐ݖ�ɂ��āA(A)�A(B)�̂����ǂ��炪�A�u���Ȃ��̋C�����ɋ߂��v�̂��A�҂ɑI��ł�������B�e�ݖ�Ƃ�(A)�͕ɑ��čm��I�]���ŁA(B)�͔ے�I�]���ƂȂ��Ă���B�ړx���\�����邽�߂̐ݖ�Ƃ��čl�Ă��ꂽ�B
���ꂼ��̐ݖ�̌��ʂ́A�} 5�̂Ƃ���ł������B�̖����ɂ��ẮA��1�̂悤�ɁA�u�Љ���̉����������Ă���v�Ɠ������l�̊�����60���ƁA�u�Љ������舫�������Ă���v�Ɠ������l�̊���24���ɔ�ׂĂ����Ƒ���
�A�]���͍��������B
�����������ŁA�C�ɂȂ錋�ʂ��݂�ꂽ�B�̂�����ɂ��ẮA��2�Łu���_�𑀍삵�悤�Ƃ��Ă���v�Ɠ����Ă���l�̊�����45���ɒB���āA�������]���ƂȂ��Ă���B�܂�
�A�e���r�j���[�X�̂�����ɂ��Ă��A��4�̂悤�ɁA�e���r�j���[�X���u���������Ƃ��悤�ɍ���Ă���v�Ɠ����Ă���l�̊�����44���ɂ��Ȃ��Ă���B
�e���r�E�V���S�̂ւ̌X����m�邽�߂�4�̐ݖ₩��ړx����茟�������B�{�����̋��������҂ł����t�N�Y�ɂ�镪�͌��ʂ���A�ȉ��Љ��B
�܂��A�ړx�\�����邽�߂ɁA�e��ɂ���(A)�Ɠ�������0�_�A(B)�Ɠ�������1�_�Ƃ��āu�ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�ړx�̃X�R�A���쐬�����B�X�R�A4�_����0�_�ɂȂ�
�A�X�R�A�̍����l�قǕւ̔ᔻ�I�ԓx�������Ƃ����킯�ł���B���ʂ͎��̒ʂ�ł���B
�ւ̔ᔻ�I�ԓx�X�R�A���z (n=1,028)
�X�R�A 4�_ 3�_ 2�_ 1�_ 0�_
���� 11�� 16�� 24�� 25�� 24��
4�₷�ׂĂɂ����ĕɍm��I�Ȍ��������Ă���l�X(0�_�̐l)��24���Ƃق�4����1���߂����ŁA1���قǂ̐l�X�����ׂĂ̖�Ŕᔻ�I�ȑԓx�������Ă����B
�@�@�@��3-2-2-2�u�ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�ړx�̉\��
�u�ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�ړx�̃X�R�A�ɂ��āA���z�̗l�q���݂Ă݂悤�B�ǂ����̃X�R�A�ɉ҂��W�����邱�Ƃ��Ȃ��A���z���Ă���B���͂̂��߂̎ړx�Ƃ��ď\���Ɏg���邱�Ƃ����������B�}5�̐ݖ₩��\�������u�ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�ړx��
�A�����ɏ\���L���ł���Ƃ�����B
�@�@�@�} 5�@�e���r�E�V���ɑ���]��
�Љ���̉����������Ă�@60���@1�́@�Љ������舫�������� 24��
�����ŋq�ϓI 39���@2�́@���_�𑀍삵�悤�Ƃ��Ă��� 45��
�ǎ҂��m��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�`���Ă��� 57���@3�V���́@�ǎ҂̍D��S�ɂ����悤�Ȃ��Ƃ�`���Ă��� 28��
�������̑��l�ȃj�[�Y�ɂ��킹�č���Ă��� 41���@4�e���r�j���[�X�́@���������Ƃ��悤�ɍ���Ă��� 44��
�@�@�@��3-2-3�g�Љ�E�����S�ʂɑ���M�������^�ړx�h�̉\��
����ɁA�u�ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�u�����ւ̔ᔻ�I�ԓx�v���܂߂������̎ړx���`������Ȃ����A���̉\���ɂ��Ă��������Ă݂��B��̓I�ɂ́u�ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�u�����ւ̔ᔻ�I�ԓx�v��
�A�u�����@�ււ̐M���v�u�}�X���f�B�A�ւ̐M�����v�u�����I�L�������o�v�u�����A�����ʂł̕ێ灁�v�V�X���v�u�����S�v�̕ϐ��A�Ȃ�тɁu�e���r�ڐG�p�x�v�u�e���r�j���[�X�u���v�u���C�h�V���[�u���v�̕ϐ���lj�����
�A���q���͂��s����(���q���o�@�F����q�@�A��]�@�FKaiser�̐��K�����Ƃ��Ȃ��o���}�b�N�X�@)�B
���̌��ʁA�u�Љ�f�B�A�M���v���q�A�u���x�����v���q�A�u�����S�v���q�A�u���C�h�V���[�v���q�A�u�����L���ETV�I���v���q��5�̈��q�𒊏o���邱�Ƃ��ł����B���ꂼ����q���_���Z�o���邱�Ƃɂ����
�A�҂��A�ʂɂ܂��͏W�c�Ƃ��āA�ʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B����������A5�̈��q����ɂ��āA�҂܂��͉҃O���[�v(�Ⴆ�A����j���[�X�ԑg�̎����҂Ȃ�)�̐����ρE���f�B�A�ς�]�����邱�Ƃ��ł���킯�ł���B
�������̋����[���m��������ꂽ�B�ȉ��A���ꂼ��̈��q�ɂ��Ă݂Ă������B
�@�@�@��3-2-3-1�@�����ρE���f�B�A�ς� 5 ���q�\��
�u�Љ�f�B�A�M���v���q�F
�܂��A��1���q�́A�u�M���������@�ցv�u�M�����}�X���f�B�A�v�u�����ւ̔ᔻ�I�ԓx(�}�C�i�X)�v�u�ւ̔ᔻ�I�ԓx(�}�C�i�X)�v����ɂ܂Ƃ܂�A�����@�ւ�}�X���f�B�A�ւ̐M�������������̂�
�A������֔ᔻ�I�ԓx�͎ア���Ƃ�������B�u�����I�L�����v�Ƃ̊֘A�������A�����ւ̊��҂������悤�ŁA�����[���B�w�Љ��f�B�A�ւ̐M���x��\�����Ă�����q�ŁA����u�Љ�f�B�A�M���v���q�Ɖ��߂ł���B
���̈��q�̓��_�̍����l�قǁA�Љ�A���f�B�A�ւ̐M���������A�܂��������L���ł���ƍl���Ă���B����A���q���_���Ⴂ�l(�}�C�i�X)�́A�����鐭����f�B�A�ւ̕s�M������
�A�����ɑ��Ă�����߂Ă���Ƃ����A�����ɑ��Ă̓V�j�J���ł���l�Ƃ����悤�B
�u���x�����v���q�F
�����ŁA��2���q�́A�ێ�\���x�����̎��Łu���x�����v���q�B�����Ƀ��x�����Ȑl�͐����S�ʂł����x�����A�Ƃ������ƂŁA����͗\�z�ʂ�ł���B���̕ϐ��Ƃ̊֘A�݂͂�ꂸ
�A�����ρE�����ӎ��̗̈���L�̈��q�ł���Ƃ�����B
�u�����S�v���q�F
��3���q�́A�u�����S�v���q�B�u�����S�v�������l�́u�j���[�X�u���v�������B�����Ă��������l�́A�����L�������o�������B�����Ɋ��S�̂���l�����̂悤���B
�u���C�h�V���[�v���q�F
��4���q�́A�u���C�h�V���[�u���v�̋����l�����ŁA�u�e���r�ڐG�v�������B������u���C�h�V���[�v���q�B�����ςƂ̕ϐ��Ƃ̊֘A�݂͂�ꂸ�A���f�B�A�ς̗̈���L�̈��q�ł���Ƃ�����B
�u�����L���ETV �I���v���q�F
��5���q�͂����ւ�����I�Ȉ��q�ł���B�u�����L���ETV�I���v���q�B���̈��q�̋����l�́A�u�����͗L���ł���v�Ƌ����l����Ɠ����ɁA�}�X���f�B�A�ւ̕s�M�ς������l�����ł���B���̂��߂�
�A�e���r�ɑ��Ă��ˑ����邱�ƂȂ����o�I�ɁA�I��I�ɍs��������B��1���q�̋����l�Ɠ����悤�ɐ����Ɋ��҂͂悹�Ă��邪�A��1���q�������l�Ƃ͈Ⴂ���f�B�A�ɂ͌������̂ł���B
���̂��Ƃ́A���́u�����L���ETV�I���v���q�̋����l�́A�u�Љ�f�B�A�M���v���q�̋����l�Ƃ͈���āA���f�B�A�ւ̔ᔻ�I�ԓx�������Ȃ��Ă��A���̂܂ܐ����I�V�j�V�Y���ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B���������l�X��
�A������{�ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ́A�����[���B
�@�@�@��3-2-3-2�@�����ρE���f�B�A�ςƃ��f�B�A�ڐG
�����5���q�ƒ��E��̃e���r�j���[�X�ԑg�ւ̐ڐG�Ƃ̊֘A��A�x���̃e���r�E���ԑg�ւ̐ڐG�Ƃ̊֘A���A�\���ɂ݂�ꂽ�B����̕��͂ł́A�L�͂Ȏړx�Ƃ��Ċ��҂ł���B
|
��3-3 ���f�B�A���e���V�[�ɂ��ā@
�Ō�ɁA���f�B�A���e���V�[�̂������ɁA�{�����ɂƂ��ďd�v�ȊT�O�Ƃ��Ē�Ă����A�g�e���r���e���V�[�h�T�O�ɂ��Č����������B�O�q�����悤�ɕM�҂�́A�g�e���r���e���V�[�̍����l�����h��
�A�u�e���r�ɂ��Ă��̌��߁E�����Ȃǂ��悭�������Ă���A�ߓx�ɐM���E�v������ł��Ȃ��ߓx�Ȕᔻ�E�U��������ł��Ȃ��A�K�x�Ƀe���r�̓����𗝉����A�e���r��L���ɓK�ɗ��p�E���p����l�����v�ƒ�`�����B�����ł�
�A���̃e���r���e���V�[���v������ړx���\�Ȃ̂��������Ă݂悤�B
�@�@�@��3-3-1�g�e���r�̌����h�̌���
�܂��A�l�X�̃e���r�ւ̊ւ���ׂ邽�߂ɁA���i�̃e���r�̌����ɂ��ĕ����Ă݂��B�u�e���r�ւ̗����v�u�e���r�̊��p�v�u�e���r�ւ̊��ҁv�ɂ��āA18�̐ݖ���쐬���Ă݂��B�ȉ��̘g���ň͂���18�̍��ڂɂ���
�A���ꂼ��u���Ȃ��͓�����e���r�����Ă��Ď��̂悤�Ȃ��Ƃ������邩�v�Ɛq�˂Ă���(4���@)�B���ꂼ��ɂ��āu�����邱�Ƃ��悭����v�u�����邱�Ƃ����܂ɂ���v�Ɠ������l�̊����͈ȉ��̒ʂ�ł�����(n��1,129�A�����̑�����)�B
a. ���o���点������ 89��
b. �^�����g�ɂ��h�L�������g�ɉ��o���� 89��
c. ���̒��ʼn��o����Ă��� 86��
d. �������d�� 87��
e. ����҂̗���f���Ă��� 81��
f. �m�肽�����Ƃ�`���� 76��
g. �G�����ŗD�悳��� 68��
h. �������� 61��
i. �W�J��\�z���Ă݂� 60��
j. ���邱�ƂŌ��C�����炤 55��
k. �����Ƃ��P�������� 52��
l. �s���ɂ����ނ��� 52��
m.�ʔ�����悢 51��
n. �������◠�b�ɋ��������� 50��
o. �C�y�Ȕԑg���悢 49��
p. ���Ă��ăc�b�R�~������ 42��
q. ���邱�ƂŃX�g���X�U�ł��� 34��
r. �e���r�̂��Ƃ�m���Ă��� �@12��
�@�@�@��3-3-2�g�e���r���e���V�[�h�T�O�̉\��
���̉���(n��1,129)�����q���͂����Ƃ���A�\�z�ǂ����1���q�Ƃ��āu�ᔻ�I���e���V�[�v���q���A��2���q�Ƃ��āu�ԑg�ϋɊ֗^�v���q�����o���ꂽ(���q���o�@�F����q�@
�A��]�@�FKaiser�̐��K�����Ƃ��Ȃ��o���}�b�N�X�@)�B
�@�@�@��3-3-2-1�u �ᔻ�I���e���V�[�v���q
��1���q�ŁA�����Ă���ݖ�(���q���ח�0.5�ȏ�)���݂Ă݂�Ɓue.�e���r�̏��͂��Ȃ炸���������łȂ��A����҂̗��ꂪ���f����Ă���(���q���ח� 0.61)�v�ua.�e���r�ɂ͉��o���点������(0.61)�v�ub.���|�[�^�[��^�����g���o������h�L�������g��
�A���͗p�ӎ����ɉ��o����Ă���(0.60)�v�ud.�ԑg���������d���ʼn��o����Ă���(0.51)�v�Ȃǂł���B�����́A�e���r��ᔻ�I�ɗ�������ԓx�̂��̂ŁA�����҂�]������ړx�Ƃ�����B����u�ᔻ�I���e���V�[�v�Ƃ�����B���̎ړx��
�A�O�q�����g�e���r���e���V�[�h�T�O�̂����A�O�������ł���u�e���r�ɂ��Ă��̌��߁E�����Ȃǂ��悭�������Ă���A�ߓx�ɐM���E�v������ł��Ȃ��ߓx�Ȕᔻ�E�U��������ł��Ȃ�
�A�K�x�Ƀe���r�̓����𗝉����v�ɑΉ��������̂ƂȂ��Ă���B���̕����̑���ɓK���Ă���ƍl������B
�@�@�@��3-3-2-2�u�ԑg�ϋɊ֗^�v���q
��2���q�ŕ��חʂ��������̂́A�uq.�e���r�����Ă��āA���܂��Ă���X�g���X�U������(0.52)�v�uo.�F�B�ƎG�k���Ă���悤�ȋC�y�Ȕԑg���悢(0.51)�v�Ȃ�
�A�C���炵�Ƃ��Ċ��p���Ă���v�f�ƁA�uj.�e���r�����Ă��āA���C����������悤�ȋC�ɂȂ�(0.50)�v�ȂǁA���Ȋ������ɗ��p���Ă���v�f�Ƃ���Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������B���퐶���́u���K�����u�v�Ƃ��ė��p�E���p����킯��
�A�����ł́u�ԑg�ϋɊ֗^�v���q�Ɩ��Â��Ă������B���̎ړx�́A�O�q�����g�e���r���e���V�[�h�T�O�̂����A�㔼�����ł���u�e���r��L���ɓK�ɗ��p�E���p����v�ɑΉ���
�A���̕����̌v���ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B
�ȏ�̂��Ƃ���A������2�̈��q�ɂ���āA�g�e���r���e���V�[�h�T�O���\�����邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ����������B
�@�@�@��3-3-2-3�g�e���r���e���V�[�h�ƃ��f�B�A�ڐG
���̈��q�ƁA�e���r�j���[�X�A���ԑg�̎����Ƃ̊֘A���������Ƃ���A�������̔ԑg�ɂ����Ď����Ƃ̊֘A���݂�ꂽ�B�Ⴆ�A�u���j���_�v�u�U�E�T���f�[�v�u�T���f�[�E�W���|���v�u�� 2001�v�u�T���f�[�v���W�F�N�g�v�ȂǓ��j���ɕ�������Ă���E���ԑg���悭����l�́u�ԑg�ϋɊ֗^�v���q
�A�u�ᔻ�I���e���V�[�v���q�̓��_���v�Z���Ă݂��B���̌��ʔԑg������l�ɂ���āA���̈��q���_�ɑ傫�ȍ����݂��A�ԑg�ɂ���Č���l�̃e���r���e���V�[���قȂ邱�Ƃ����������B���̂悤�Ɂg�e���r���e���V�[�h�ړx��
�A�ԑg�ڐG���������v���ƂȂ�\�������炩�ɂȂ����B
|
|
��4. �����̉\���ƍ���̉ۑ� |
�����܂ŁA��b�����̌��ʂ�����{�ɂ�����u�e���r�����v���҂̃��f�B�A�ڐG���ԁA�ӎ��̑��ʂ��猩�Ă݂��B���̌���ł͂��邪�A���{�ł��A�����J�ɂ݂�ꂽ�悤�ȁu�e���r�����v��������ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂�
�A�u�����֘A�ԑg�����闝�R�v�u�D���ȃj���[�X�E�ԑg�^�C�v�v�u�ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�u�����ւ̔ᔻ�I�ԓx�v�u�Љ�E�����S�ʂɑ���M�������^�ړx�v�u�e���r���e���V�[�v�Ȃǂ̐ݖ�E�ړx�E�T�O�̗L������
�A�m�F���ꂽ�B
�����̌��ʂ���A���̌����̈�ɂ�������ؓI�����̉\���͂������ɍ����Ƃ����悤�B�@
����A���e���́E���[�s�����͂Ȃǂ̌��������킹�čs�����ƂŁA���L���Ȓm����������Ǝv����B�{�e���A���̌����̈�̔��W�̌_�@�ƂȂ邱�Ƃ��ł���A���ɍK���ł���B
|
���Q�l����
1)Akuto. H., Media in Electoral Campaigning in Japan and the United States, Media and Politics in Japan, Univ. of Hawaii Press, (Pharr, S. & Krauss, E. Eds.), 1996, pp.313-338.
2)Akuto, H., Media and Politics in the United States, Studies of Broadcasting, 24, NHKBCRI, 1988, pp.25-28.
3)�O�ˁ@�O�A�w���f�B�A��������̑I���x�A�}�����[�A1989�D
4)�O�ˁ@�O�A�u�A�����J�哝�̑I���ƍ����̐����Q���|���f�B�A�̌��߁v�A�w�}�X�E�R�~���j�P�[�V���������x�A2001�App107-123�D
5)J. Cappella and K. H. Jamieson, Spiral of Cynicism, Oxford Univ. Press, 1997.
6)Matthew. A. Baum, Talking the Vote: Presidential Candidates Hit the Talk Show Circuit, 2005.
7)Markus Prior, News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political nowledge and Turnout, 2005.
8)�O�ˁ@�O�A����@���A�����@�܂��݁A�u�e�́w�e���r���e���V�[�x�Ɠ����̃��f�B�A���C�t�v�A�w�g�q�ǂ��ɗǂ��h�����v���W�F�N�g�@�� 3 �����x�A2006�App89-96
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����v�����߂���W���[�i���Y�� 2006/1 |
���͂��߂�
�ŋ߁A�M�҂�����ɂȂ��Ă��邠�鎄�I�ȕ���ŁA�N�����ƂȂ����f�B�A�A�Ƃ��������W���[�i���Y�������ʂ��Ă�����_���W���I�Ɏ��グ�悤�Ƃ������ƂɂȂ����B����ꂪ������ς�����Ƃ�����قǃ��f�B�A�̉e�����傫���Ȃ��Ă���Ƃ��A�Ƃ�킯���v�����{�̍����I�ۑ�Ƃ����Ƃ����f�B�A�͌���̂܂܂ł悢�̂��A�Ƃ������ӎ�����ł���B����ɂ́A���f�B�A�W�҂��������Ƃ�����l�X�Ȗ���N�����������A�����������Ƃɂ̂ݒǂ��Ă����M�҂ɂƂ��Ă��A�킪���Ƃ�U��Ԃ�ǂ��@��ƂȂ����B�傰�������m��Ȃ����A���_�͉��v�Ȃ����ăW���[�i���Y���ɖ����Ȃ��A�ł���B
���T�D���Ղł͂Ȃ��̂����_�l
���܃��f�B�A�̌o�c�҂́A���Ȃ�[���Ȗ��ӎ��ɂƂ���Ă���͂��ł���B���Ԃ���A�����������ɂ݂���D�Ɛт̑��e���r�E�̌o�c�҂ƂāA��O�ł͂���܂��B�Ⴆ�A������z���G������������N�����A�ʐM�ƕ����̗Z���̖��͋K���ɘa�A�������i�Ȃǂ̎��_�ŐV�����s���̉ۑ�ɂȂ낤�Ƃ��Ă���B�V���ɑ��胁�f�B�A�̉��҂ɂȂ����ς̂���e���r�E�����A�����I����ɗ��Ƒ��S�Ɋւ����ɒ��ʂ��Ă���B
�����ƒʐM�̗Z���̖��ɂ��Ă͖�O���ł���A�M�҂ɂ͌�鎑�i��\�͂��Ȃ��B�������A���̖�肪�����ꊈ�����f�B�A�̕���ɂ��傫�ȉe���������炷���낤���Ƃ́A�^���Ȃ��m���ł���B��������Ƃ������Ƃ������ċv�������A���������q�E����ɔ���������̌����̉e�����傫�����ł̓�肾���ɁA�V���o�c���e�Ղł͂���܂��B
�����ŁA�ꌾ�_�l�ł����Ȃ��M�҂��l����̂͊����W���[�i���Y���Ƃ������A�V���̂���悤�ɂ��Ăł���B�����A�ܐ疜��������r�����Ȃ��傫�������s���S���ÁX�Y�X�ɔz�t���Ă���V��������قNj���ȓ��{�̐V���V�X�e�������ɂ��ĕ���鎖�Ԃ́A���Ԃ�N���Ȃ����낤�B�������A�������Q���������A���f�B�A�Ƃ��Ẳe���͂��ቺ�������邱�Ƃ͏\���ɍl������B�������f�B�A�̒S����Ƃ��ẮA���̎��Ԃ̐i�s���~������ӔC������A���̊֘A�ł��A�V���̂���悤���l����������Ȃ��̂ł���B
���̓_�ŐV������̌���𗣂ꂽ���܁A�M�҂��v���̂́A���ƂƂ��ɃW���[�i���X�g�͂����������ՂɋL��������������悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B�܂�A��ނ����A�����W�߂Ċm���Ȏ����ł���Ɣ��f�������������ł͂Ȃ��A�s�m���Ȃ��Ƃ܂ł������Ă��܂����Ⴊ�ȑO�Ɣ�i�i�ɑ����Ă���A�Ƃ̎v���ł���B
���f�B�A�ɂ́A�Љ�I�ȉe���x���傫�Ȏ����قǐv���ɓǎ҂⎋���҂ɓ`����A�Ƃ�������������B���̂��߂̌����������������́A���f�B�A�W�҂̐����b��ł�����B���̈ӎv�Ɠw�͂Ƃ��������W���[�i���X�g�́A���͂⌾�_�l�Ƃ͂����܂��B�������A�����ł���ǂ��납����܂ōs���l�������ɂ������ẮA����̓��f�B�A�̎��E�s�ׂł���B�������ƂȂ�Ƌɂ߂Ĉٗ�ł͂��邪�A���܂��Ă����Ȃ�������B���ȕ\���A�Ⴆ�Ώ����ʂ̘b�Ȃǂƕ\������`�ŕ��A�ǎ҂Ɍ����^���Ă����͑����B
���f�B�A�A�������ʓI�ɂ͎Љ�I�ȐM�p�������Ƃ���Ă���V�����ɂ��A�����������Ⴊ�����݂���̂́A���f�B�A�ւ̐M����ቺ�����Ă���Ӗ��Ŏc�O�ł���B���̏��R�͂��܂��܂ł���A�����ł���ƒZ���I�ɂ͂����Ȃ��B�M�҂Ȃǂ́A�L�҂炪������������Ȃ��X�y�[�X���L���肷�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����肵�Ă���B
���ɂ������Ƃ���A�ЂƂ̉����@�Ƃ��āA���ׂ��Ώۂ��_�ɍL���Ă͂ǂ����A�ƍl����B���łɑ�Ȃ菬�Ȃ���g��ł��邱�Ƃ��낤���A�Ⴆ�A�o�ϊW�ł����Ί�Ɛ��i�Ɋւ�����v�����đ��₵�Ă͂ǂ����B�܂��A�n��Ɋւ���j���[�X���g�[���邱�Ƃ́A�V���Ɠǎ҂̊W��e���Ȃ��̂Ƃ���ɈႢ�Ȃ��B
���̂悤�ȃj���[�X�𑝂₷�ꍇ�A�I�g�ٗp�ł̐g���ۏ�����Ă���Ј��𗊂��Ă����̂ł͌o��|��ƂȂ邾�낤�B�����ŁA����܂����v���K�v�ɂȂ�B���Ȃ킿�A�Ⴆ�A����_�ɓǎ҂̎Q������ǎ҂̏������Ƃɂ����ҏW��i�߂�ׂ����낤�B�V���Â�����̂Ɣ�r����Ɗi�i�ɍH�v����P���s���Ă��邪�A�ǎ҂ɘA���A���v�̈Ӌ`��i���Ă��銄�ɂ́A����̉��v�͗]��ɂ��x�X�Ƃ��Ă���ƕM�҂͎v���B���̓_�ł́A�ʐM����ł̖�S�I�Ȓ����f���ɎQ�l�ɂ��ׂ��ł���B
���U�D�B��������Ɖ���E�咣
�V���ɂ��Ă��e���r�����ɂ��Ă��A���̃j���[�X�ŋC�ɂȂ�̂́A�����̕ƁA���̎����̉���Ƃ��ɂ߂ĞB���Ȍ`�œǎ҂⎋���҂ɓ`�����Ă��邱�Ƃł���B����������A�ǂ��܂ł�������`���Ă���q�ϓI�ȓ��e�Ȃ̂��A�����āA�ǂ����炪�`���鑤�̎�ϓI�Ȉӌ��Ȃ̂��A���ɂ߂ĕs�����ł���A�Ƃ������Ƃł���B�����ĉ��X�A�����̌̕`���Ƃ��ċL�҂�̍l����ǎ҂⎋���҂ɉ����t���Ă��܂��Ⴊ����Ƃ������Ƃł���B�����������Ⴊ�ȑO�Ɣ���݂͔��ɑ����Ă���A�Ə��Ȃ��Ƃ��M�҂͍l���Ă���B
��ʓI�ɓǎ҂⎋���҂́A�V����e���r���`����j���[�X�̓��e�͎����ł���A�`���鑤�̎v�z�≿�l���f������͎А��⏐������̉���ŕ���Ă���A�Ɨ������Ă���B���ۂɐ�ɍs��ꂽ���I���ł̊e�}�̊l���c�Ȑ���`����ƁA���̑I�����ʂɊւ���L�҂�̘_�]���v���o���A���̂悤�ȃ��f�B�A�̕Ɋւ���M�҂̎v���́A�ЂƂ̎����Ƃ��ėe�Ղɗ������Ă��������邾�낤�B
�v����ɁA�������N���A���f�B�A�ł́A���̕ƕ]���E�_�]�Ƃ̋��E���ɂ߂ĞB���ɂȂ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B�������A�]���E�_�]�A�܂�A�ӌ����q�ׂ镔���������Ă���悤�Ɏv���B���͋����͂��������������Ŕԑg���삻�̑��̌o�c�����Ă���m�g�j�͕ʂƂ��Ă��A�V���Ȃǂ̃��f�B�A���v�z���������āA������s���⋳���C�O����̑��ɂ��Ę_�]���邱�Ƃ́A�����Ĉ������Ƃł͂Ȃ��B�ނ���A���}�h����N���ɂ��邱�Ƃ́A�ǎ҂�Ɍ�������b�Z�[�W��h����Ŗ𗧂Ƃ�������������B
�M�҂����������̂́A�����̕Ɖ���E�]���E�咣�Ƃ��\�Ȍ��蓧���ɂ���A�Ƃ������Ƃł���B�����ēǎ҂⎋���҂�Ɍ����^�����˂Ȃ����̔��M���ɗ́A�}������Ƃ������Ƃł���B����́A������s���Ɋւ�鎖�������ł͂Ȃ��B����Ƃ����Y���̔����Ă�����p�i�AIT �@�킻�̑��̏��i���Ɋւ���Ɋւ��Ă����l�ł���B�����A�V���i�ɂ��Ă̏���m�点��̂͊�Ƃ� PR �ł���A�̑Ώۂɂ��ׂ��ł͂Ȃ��A�ȂǂƂ������ӌ������A�ǎ҂⎋���҂ɂƂ��ĉ��l�������`���邱�Ƃ́A�@�ւ̑厖�Ȏd���Ȃ̂ł���B
���̖��ŁA�ЂƂ�Ă�����B������А��E�咣�͂Ƃ���������E�]���͌��i�Ɏ����̕Ƌ�ʂ��āA������R�����ɂ��K�������L���Ƃ��ׂ��ł���B�܂��A�M�҂̗����L���ׂ����낤�B�Ⴆ�A���{�̍�����������̋��Z����Ɋւ���_�]�ɂ��āA���̕]�҂̗����������ł��킩��A�ǎ҂̑����炷��Ƙ_�]�ւ̐M���x���ς���Ă���̂ł͂Ȃ����B�v�͋L�҂��]�Ƃ�̓����x�����߂��Ɠw�͂ł���B
���V�D���S�̊j�S�͐M���̉�
�ŋ߂͗]�蕷����Ȃ��Ȃ������A�����납�炩�A�V���𒆐S�Ƃ��郁�f�B�A�����l�̌��ͣ�ƌĂ��悤�ɂȂ����B���@�E�s���E�i�@�ɕ��Ԍ��͋@�ւƂ��Č��_�@�ւ��ʒu�Â�����A�Ƃ������Ƃ��낤�B���ꂾ���ɁA�ЂƂ���̓��f�B�A�ւ̒����������o����A���_�l�̑�����̎��Ȃ��o�Ă����B�������A���܂͂�������Ȃ��Ȃ��Ă���悤�Ɏv���B���̌����̓��f�B�A�����l�����A�����ƒʐM�̗Z�����������قǕω������������߂��낤�B�������A���f�B�A����������̃��f�B�A�ւ̐M�����ቺ���Ă��邱�Ƃ��A�ЂƂ̌����ł͂Ȃ����A�Ƃ̎v�����M�҂ɂ͂���B
�Љ�I�ȐM�����ቺ�����鎖�Ƃ������ɂ킽�葶�݂������邱�Ƃ͂��肦���A���f�B�A�Ƃė�O�ł͂Ȃ��B���łɏq�ׂ��悤�ɁA���f�B�A�Ƃ����Ă����l�ł���A�M�҂̊S�͂�����W���[�i���Y���̐��E�ł���B����̓I�ɂ����Ί����W���[�i���Y���̐��E�Ƃ������ƂɂȂ邪�A���̃W���[�i���Y���̐��E�������̐M���Č��S�����ێ��ł���Ȃ�ΐl�ԎЉ�̖�����ߊς��邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ��v���Ă���B�������A����́A�X�̊�Ƒ̂̐����̘b�ł͂Ȃ��B
�]���āA���̏œ_�́A�����ɂ��ăW���[�i���Y�����M���������߂邩�ł���B���̂��߂ɂ́A�W���[�i���Y�����`������̉��l�����߂邱�Ƃ��挈�ł���B�W���[�i���X�g�́A���������Ƃ����{�\�I�ȗ~�]��}���Ăł����Ղɏ����ׂ��ł͂Ȃ����낤�B�����̕Ɖ���E�_�]�E�咣�Ƃ�ǎ҂⎋���҂ɓ����Ȍ`�œ`���悤�A�Ə������̂́A���̂��߂̕M�҂̒�Ăł��邪�A���̓_�ő����̒��Ԃ�F�l�炩��̍l���������B
������ɂ��Ă��A���v�̎��Ȃ����̂́A�^���Ȃ����ׂĂ�����BIT ���j�Ƃ����Z�p�v�V�ƃO���[�o�������A���̂��Ƃ��������Ă���B�܂��A��������ꂸ�ɏq�ׂ邪�A�����w���̍�����������������l�A��V�̑����ɉ��l�����߂�l�A�����͈̂��̂ŗǂ��ҋ����錠��������Ǝv������ł���l�A�Ȃǂ������ɂȂ��Ă����Ƃ͑��ӁA�Ƃ�킯�W���[�i���Y���̐��E�ł̒E���𑬂߂邾�낤�B
���Ō��
�������f�B�A�̒��j���߂Ă���V���W���[�i���Y���́A���܂Ȃ������҂��l���Ă���ȏ�ɍL���傫�ȐM���Ă���B�������A�̂��߂̎�ނ��A���̑ΏۂƂȂ����l�����̂������ł́A���Ȃ葽���̐l�������V���ւ̕s���������Ă���B���̗��R�́A�ЂƂ��Ƃł����Ǝ����𐳂����`���Ă��Ȃ��A�Ƃ����s���ł���B�Ȃ��ł��A�s�K�ȍs�ׂ��s�����Ƃ��āA�ᔻ�I�ȕ̑Ώۂɂ��ꂽ�l��������̔ᔻ���������B
�W���[�i���Y���̖����Ƃ́A������Ă����Ă��܂��A�����銩�P�����ł͂Ȃ����A�ƕM�҂͎v���Ă���B���������Ē����̑ΏۂƂ��ꂽ�l�������烁�f�B�A�̔ᔻ���ł�̂́A����������Ȃ����Ƃł���B�������A���f�B�A�̉e���͂����܂邱�Ƃɔ�Ⴗ��`�ŁA���₻��ȏ�̐����ōL�����f�B�A�S�̂ւ̎����҂�̔ᔻ�����܂��Ă��鎖���������Ӗ����A���̃��f�B�A�W�҂͂悭�悭�l���Ă݂�K�v������B�����ď��Ȃ��Ƃ��A���炪�l���N�Q�̉��Q�҂ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��悤�A�ߓx����s�������ׂ��ł���ƍl����B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����f�B�A���Ď�����Љ�I�ȕK�v���č� NGO�̗��O�ƕ��@�_����w�Ԅ� 2008/3 |
|
�j���[�X���Љ��M������Ȃ��Ȃ��Ă���B��ނ̎�@�̋������A���o��\���̐��m����ߓx�Ȃǂ������Ζ��ƂȂ���肩�A�����Ƃ̏�O���킵���ڋ߂Ԃ���I�����Ă���B�������@�ւ͌o�c�̈ێ��ɋ��X�Ƃ��Ă���A�����`�Љ�ł́u�g���v�����o���A�ӔC�������ĉʂ����Ƃ����u�����w�́v�ɑ����͊��҂ł��Ȃ��ɂȂ��Ă���̂�����ł���B�܂����f�B�A�̉������Ȃ̂�����葽���̈�ʂ̎s������̓I�ɁA��������K�v������̂����A���̖�����N���S�������̂��낤���B���_�ł͕č��́u��z�����W���[�i���Y���̂��߂̃v���W�F�N�g�v�Ƃ������f�B�A�Ď�NGO�ɏœ_�āA�ނ�̗��O�Ɗ������T�ς��Ďs�������f�B�A��ϊv���邽�߂ɓ��������邽�߂̃q���g��T��B���Ƀ��f�B�A��Ƃ̌o�c���̎���j���[�X�̌���ɂǂ̂悤�ȍ\���I�e�����y�ڂ��̂��Ƃ������͂̏d�v���ƁA�]���͂ނ�����ƂɈς˂��Ă����j���[�X�̓��e���͂ƌ�����ʑ�O�ɂ��������₷���`�ōs�����Ƃ̕K�v���ƕ��@�_�ɂ��ċc�_����B
|
|
���͂��߂�(���̏���)
|
���f�B�A�́u��4�̌��́v�ƌ����Ă���B�M�҂��j���[�X��W���[�i���Y���̊�{��������ɂ�����u�@�ւ̎g���́w���͂̊Ď��x�ł��v�ȂǂƔ������Ă���B�������A���̃��f�B�A�ɑ���u�Ď��v�ɂ��Ă͉���Љ�I�Ȏd�g�݂��Ȃ��A���f�B�A���u�\���̎��R�v��l�X�́u�m�錠���v�ɕ�d����p���𐽎��Ɏ���Ă���͂����Ƃ����u�M�����v�Ɏx�����Ă����B���͂��́u�M�����v�ɂ͍������Ȃ��ɂ�������炸�A�u�V���L�҂͏펯�Ƌ��{�����˔����Ă��āA�w�Љ�̖ؑ��x�Ƃ��Ă̖�����S���ӔC���ʂ������h�Ȑl�����ɈႢ�Ȃ��v�Ƃ��u�������̂悭�m��Ȃ������ȃe���r�����̋@�ނ��g�����Ȃ��ԑg�𑗂�͂���l�����́A���̎Љ�I�ȉe���͂̑傫���ƐӔC�����o�����ߓx�����ނ����s���Ă���͂����v�Ƃ����u�C���v�ɒ��炭�x�����Ă����Ƃ����̂�����ł͂Ȃ��̂��낤���B
�������A���̂悤�Ȕ��R�Ƃ����u�M�����v�͂��͂�n�ɒĂ��Ă��܂����B�l�X�́u�\���̎��R�Ȃǂ̑�`�����ɂ�����������āA���f�B�A�͑����Ă��܂����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����s�M�����点�Ă���B�䂪���ł� TBS(��������)���I�E���^�����̊����ɍ�{��ٌ�m���ᔻ���Ă���C���^�r���[�̃r�f�I�������Č��ʓI�Ɉ�Ƃ̎E�Q���������Ƃ����A�u�̏펯�v��傫����E��������(1989�N)�A���{�T��������(1994�N)�╺�Ɍ����s�ŋN����JR���m�R���̒E������(2005�N)�ȂǂɌ����郁�f�B�A�E�X�N�����̔�Q�△烂̐l��e�^�҈������Ă��܂������Ƃ��̍^���̖��ANHK����e���r�̔ԑg�������}�̈ꕔ�L�͋c���̈ӌ����u�Ύށv���ĉ��ς��ꂽ��(2001�N)�A���c�N�v�Ə����Y��\�̊ԂŘb������ꂽ�u��A���v�́u�A�̎d�|���l�v���ǔ��V���̓n�ӍP�Y��M�ł�������(2007�N)�Ƃ����o�����Ɍ�����悤�ȁA�����ƃ��f�B�A�����́u�s���������ڋ߂Ԃ�v�Ȃǖ����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B
��@�I�ɒ��ʂ��Ă���ɂ�������炸�A���f�B�A�̑�������ꂽ�M����S�͂ʼn���w�͂��s���Ă���Ƃ͌�����B����͒��N�E���オ��Ő��ڂ��Ă����o�c�����łɋȂ���p���}���A�o�c�̈ێ��̕��� NHK���܂ރ��f�B�A��Ƃɂ��Ă͂ނ���i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��A���v��x�O�����Ĉ��̊��Ԃ��Љ�I�M�p�����߂����Ƃɏ[�Ă�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͍l�����Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂����B�V���́u�Ĕ̉��i�ێ����x�v�Ɏ��ꂽ��z���x�ɂ��o�c�X�^�C�������łɔj�]�������Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�܂������L�[�ǂ͑S�ǂ�����1���Ɋ�������ꂵ�Ă���A�����̂��߂Ɏ���Ƃ���Łu���l�ڕW�v��v������A���ǂ͕�����]������ɂ����茻�݂ł͗B��́u�q�ϓI�v��ł��鎋�������グ�邱�Ƃ����㖽��ɂȂ�A����̓j���[�X�̕������O�ł͂Ȃ��B
���̂悤�ȏ��ʼn�X�̓��f�B�A�œ`�����Ă���j���[�X�̓��e���^���Ȃ̂��ǂ����m���߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�j���[�X�����Ă���Ȃ�A�ǂ������Ă���̂�������肪���肷�疞���ɓ����Ȃ��B���f�B�A�̕s�����⎸�s�����炩�ɂȂ�̂́A�T�����Ȃǂ������f�B�A���m�́u���̈������荇���v�ɂ��\�I�����A�l�b�g�̌f���ŗ��z�����悤�ȁA�ǂ��܂ł��{�����킩��Ȃ��u�����v���h�����Ėڂɓ��邩��ł���Ƃ������ɐS���Ȃ����ƌ��킴��Ȃ��B�������A���߂ĉ�X�����f�B�A�̌���𐳊m�ɗ������A���S�ȎЉ�I����������ɂ͂ǂ������炢���̂��Ƃ����u���������v���s����@����m�ۂ��Ȃ���A����ꂽ���f�B�A�̎Љ�I�@�\�͉��Ȃ����A�Ђ��Ă͂��̍����ƂȂ��Ă��閯���`����@�I�Ɋׂ��Ă��܂��B����ł́A�����������f�B�A�Ɋւ�������W�₻�̕��́A�͒N���s�������̂��낤���B
���ƁA���Ƀ��f�B�A�ŃR���e���c�̐���Ɩ��������Ԍo�������l�ނ��s���ł���B�����u���f�B�A�E���e���V�[�v�Ƃ����p�ꂪ���s���Ă���A�u�s�������f�B�A��ǂ݉����v�Ƃ������Ƃ̏d�v�������`����Ă��邪�A�M�҂͂��ꂾ���ł͕s�\���ł���ƍl���Ă���B���f�B�A�̒u����Ă���Љ�I�ʒu�Â���o�c��Ղ܂��A�j���[�X���܂ރR���e���c����ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ��Ă���̂��Ƃ����\���I�ȕ��͂͂��Ƃ��A���ۂ̐��쌻��Ŕ���������؎��Ԃ̃v���b�V���[���ʂ̃X�^�b�t��������Ƃ��s�����ŋN���門�C���ǂ̂悤�ȃC���p�N�g�������炷�̂��Ƃ��������I�ȗ�����i�߂Ȃ���A���f�B�A�ɑ����ʓI�ȉ��P��v������͕̂s�\������ł���B�������A�䂪���ł̓��f�B�A��ƂƂ����ǂ��I�g�ٗp���̓`���͍������c���Ă��Đl�ނ̗������͒Ⴍ�A���f�B�A���q�ϓI�ɕ��͂�������́A��ɐV���ЂŎ��т�ςx�e�����L�҂���w�����Ȃǂɓ]�g���ĒS���̂��啔���ł���A���̐�ΐ��͏[���Ƃ͂����Ȃ��̂�����ł���B
�Ⴆ�Γ��{�Ɛ������x��f�B�A��Ƃ̂����ꂽ�����Ă���A�����J���O���ł́u��]�h�A(���{���r���O�E�h�A)�v�Ƃ����V�X�e��������A�D�G�Ȑ������̐l�ނ����f�B�A��Ƃ���w�E�����łȂ��A���E��V���N�^���N�Ȃǂƍs��������悤�ɂȂ��Ă���B���̒��̈ꕔ�̐l�Ԃ� NGO��g�D���A�L�҂�e���r�E�f�B���N�^�[�o�g�҂�f�B�A�����҂Ȃǂ��ϋɓI�ȃ��f�B�A�̓��e���͂���s������������B�u���f�B�A�E�E�H�b�`(�Ď�)�v�� NGO�͑哝�̑I���ȂǑ傫�Ȑ����I�C�x���g�̍ۂɃ��C�o�������U�����邽�߂ɁA������舳�͂��������肷��Ƃ��������I�L�����y�[���̈�Ƃ��Đ����������̂��������������A���ɂ́u�����I������(nonpartisan)NGO�v�Ƃ��Ď��т��d�ˁA�Љ�I�ȐM�p���l�����Ă�����̂����������݂���B���_�ɂ����ẮA���̒��ł��u��z�����W���[�i���Y���̂��߂̃v���W�F�N�g(ProjectforExcellenceinJournalism�F�ȉ��uPEJ�v�ƕ\�L)�v�Ƃ��̎����I�ȑO�g�ƂȂ����u�뜜����W���[�i���X�g����The CommitteeofConcernedJournalists�F�ȉ��uCCJ�v�ƕ\�L)�v�ɏœ_�����āA���̗��O�ƂƂ��Ɏ��ۂɍs���Ă��郁�f�B�A���͊����̓��e�ƈӋ`�ɂ��ċc�_�������B���̂悤�Ȓ����̕��͂����f�B�A�ɓ��������A�ς��Ă����Ƃ����Љ�I�ȋ@�\���ʂ����l�ނ�c�̂���{�ł���Ă�q���g�ɂȂ�Ɗ��҂��邩��ł���B |
|
��1�D���f�B�A���u���ꂽ����̔F���@���� CCJ�� PEJ�����̌o�� |
2008�N�őn��11�N�ڂ��}���� PEJ�͂��̖ړI�Ƃ��āu�j���[�X�Y����W���[�i���X�g�₻�̃j���[�X���w�����x(�������ʂ͕M��)�s���̗����ɑ��āA�@�ւ�����͂��Ă���̂��𗝉����Ă��炤�v���Ƃ��f���Ă���B�܂��A�u2�̎g���v�Ƃ��āA1�j���[�X(�̎d��)��]������A2�W���[�i���X�g �́u�v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă̌���(principles)�v���`���邱�Ƃ������Ă���B1��B�����邽�߂ɂ́A�P�ɓ`����ꂽ�ЂƂ̃j���[�X�ɂ��Ĕᔻ�╪�͂�������ɂƂǂ܂炸�A�@�֑S��(���邢�̓j���[�X�u�ƊE�v�S��)�ʼn����N�����Ă���̂��Ƃ������Ԃ��u�킩��₷�����l�����āv������Ƃ����u(���ʂȕ��@�ɂ��)���e���́v�̏d�v�����������Ă���B������2�̖��A���Ȃ킿�W���[�i���X�g���u�W���[�i���Y������������ׂ��ŁA�������ׂ��łȂ����v�Ƃ����u���������v�����H�ł���悤�ɋ�̓I�ȃA�C�f�B�A�Ƃ��Ē���K�v������Ƃ������ӎ����������̊����̒[���Ƃ�����BPEJ�̑O�g CCJ�̊�����1997�N6���̉J���悤�̓y�j���Ƀn�[�o�[�h��w�̋��E���N���u�ɏW�܂���25�l�̃W���[�i���X�g��������n�܂����ƌ����Ă���B�W�܂����͍̂����̗L�͎��̕ҏW�ҁA�L���ȃe���r��W�I�̔ԑg�̃v���f���[�T�[��A�W���[�i���Y������̑��l�҂�R�����j�X�g�ȂǂŁA�ނ�́u�W���[�i���Y�������傫�ȑ�O(�p�u���b�N)�̗��v�ɖ𗧂��Ă��炸�A����Ȃ��Ă���Ɗ뜜���Ă����v�B���Ȃ킿�@�ւ��Љ��̐M�p�������Ƃ��Ă��邱�Ƃ����ł������B���̎���(1999�N3��)��CCJ�́u�l�X�ƕ@�ւ̂��߂̃s���[������(The Pew Research Center for the People and the Press)�v�Ƌ����Ń��f�B�A�̐M���x�Ȃǂ̒����\���Ă��邪�A�Ⴆ�W���[�i���Y������ʑ�O����M�p�������Ă���Ɠ������l�̊�����1989�N�ɂ�17�����������̂��A1999�N�ɂ͕č��S�y�Ƀj���[�X�𑗂郁�f�B�A��30���A�n���̃��f�B�A�ł�34���Ɣ{�����Ă��܂��Ă���B�����`�̍�����h�邪�����˂Ȃ����̎��ԂɁu���������ׂ����v�ɂ��Ĕނ炪�܂Ƃ߂��̂��u�뜜�̐���(AStatementofConcern)�v�ł���B1999�N�Ăɂ��̐������܂Ƃ߂��Ă����10�N���o�߂������A���Ԃ͂������������P�����Ƃ͌�����A����̂ɂ��̐����͌��݂ɂ����āA�����ĉ������ꂽ���{�̃W���[�i���Y���ɂ��Ă����͂Ȑ����͂������̂ł���Ƃ����邾�낤�B�������������Ȃ邪���̖`���������Љ��B����̃j���[�X�̐��E���c��ł��܂��u�\���v���Ɍ������ĂĂ���B
�A�����J�̃W���[�i���Y���͊�@�̎���ł���B���܂��܂ȓ_�ŋZ�I��s�������Ƃ�����̂́A�ǂ̂悤�ȕ��@�ŏ���(��O��)���ʓI�ɒ��邩�Ƃ��A�L�҂̏K�n�x���グ�悤���Ȃǂ̖��͑S���l������Ȃ��Ƃ����̂͂���قǃR�~���j�P�[�V���������B��������̃p���h�b�N�X�ł���B���f�B�A�Y�Ƃ̌o�ύ\���ƃ��f�B�A�Ƒ�O�̊W���l����ƁA�e�N�m���W�[�̊v���I�Ȕ��B���`���I�ȃW���[�i���Y���̈ʒu�Â������{�I�ɕς��Ă��܂����B�j���[�X�̎�̚n�D�͍ו������A����ɍ��킹�ă��f�B�A��Ƃ̑�������ɍ��킹�đ��p�o�c�ɏ��o�����Ƃ��钆�ŁA�@�ւ̒��Ńr�W�l�X(��Ƃ��邢�͉�Ј�)�Ƃ��Ă̐Ӗ��ƃW���[�i���X�g�Ƃ��Ă̐Ӗ��Ƃ̊ԂŘ_�����g�債�Ă���B�����̃W���[�i���X�g���ړI�ӎ��̑r���ɔY��ł���B���̌��ʁA�]���M������Ă����^�ʖڂȕ@�ւ��A�j���[�X�ɑ���o�����X�������A�ӌ���G���^�[�e�C�������g�I����Z���Z�[�V���i���ȏo�����̕ɉ���������Ă��܂��A�j���[�X�̎Љ�I���l�ɑ�����^�I�Ȍ����܂ōL�����Ă���B
�j���[�X���o�ϓI�ȉ��l�������A���i�Ƃ��āu���ʁv����ɂ�āA���f�B�A��Ƃ́u����鏤�i(���j���[�X)�v��O��Ƀr�W�l�X���f�������A���̌��ʃj���[�X���̂��̂��Љ�I�Ȏ�҂ɃX�|�b�g�Ė���N����Ƃ��A���͂��Ď�����Ȃǂ́u�]�����҂���Ă����Љ�I�Ȗ����v����E���A�P�ɐl�ڂ��������̂�ǂ����߂Ă��܂��Ƃ����\���I�ȕω���I�m�ɔᔻ���Ă���B���̕��͂͂���ɁA�W���[�i���X�g���{�����ׂ����l��v���t�F�b�V���i���Ƃ��Ă̍s����ȂǂƂ������̂�����܂ł����܂��ɂ����K�肳��Ă��炸�A�܂���т��đ��d����Ă��Ȃ������Ƃ��āA���́u�����v�m�����ăj���[�X���Љ�ɓK�ȋ@�\���ʂ����悤���߂��u���v�v���K�v���Ǝ咣���Ă���B
���f�B�A�͉��v����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�W���[�i���Y���̍������Ȃ������͕��ՓI�ł���B�W���[�i���Y���͐l�X���������s���ɂ������Ď�v�Ȗ������ʂ����u�����I�ȔC���v�����邩��ł���B�����̌����ɂ��A�W���[�i���X�g�̎d���͒P�Ȃ�R�~���j�P�[�V�����ł͂Ȃ��A��A�̎Љ�I�Ӗ��Ƃ��ċK�肳���B�W���[�i���Y���͎��ɐl���y���܂��A�l������A�܂����_�����g������������邪�A�@�ւ͂܂��܂����l�����鎄�����̐����Ă���Љ�ɂƂ��ďd�傾�Ǝv������͕K���`���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����`��̌�������̂Ƃ��Ă��̖��ɂ��Ă̓��_�𑣐i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Č��@�C�������͕\���̎��R�Ƌ��ɂ������邽�߂̐Ӗ������Ӗ����Ă���B
���́u�뜜�̐����v�̎��M�ɎQ�������APEJ�̃f�B���N�^�[�ł���g���E���[�[���X�e�B�[��(Tom Rosenstiel)���́A���̍s���͉������ʂ̏o�����ɐG�����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A���N�~�ς����s����ᔻ�����������炾�Əq�����Ă���B���̐������o���ꂽ1990�N��̌㔼�܂łɂ́A�O��l�b�g���[�N(NBC�ACBS�AABC)�̃j���[�X�ԑg���r�W�l�X�Ƃ��čs���l�܂��ė��v�܂Ȃ��Ȃ�A�܂��V���ƊE�ł͖�10�N�ɂ킽��s���������Ă����B���̌��ʑ����̃��f�B�A��Ƃł̓j���[�X����ɓ����L�҂�f�B���N�^�[�A�J�����}���Ȃǂ̐l���팸���s���A�܂��j���[�X����ɑ��Ă�茵�����u�r�W�l�X�E�X�^���_�[�h�v���K�p����邱�Ƃ��o�c���������I�ɐ錾����A���v�ސӔC�����������鎖�Ԃ��������A�č��̃j���[�X�ƊE�́u�s�k���Ə����̑����ɑ����@�����������Ă����v�ƃ��[�[���X�e�B�[�����͔w�i��������Ă���B
�܂����[�[���X�e�B�[�����͐V���ƊE���]���Ƃ��Ă����헪��������������Ă���A���̌��ʏ���������I�Ȍo�c��@�̂��߁A���̌�V���̕ҏW����Ƀr�W�l�X�̉e�����}���ɐN�����Ă��܂����ƕ��͂���B���Ȃ킿1980�N��܂ŕč��̐V���͔�r�I�������ґw���^�[�Q�b�g�ɂ���̔����j���Ƃ�A�ҏW�������̕��j�ɉ����đ�w�𑲋Ƃ����l�ȏオ�S�����悤�Șb����L���Ƃ��Čf�ڂ��Ă������߁A���̌�i�s�����w�Ǖ����̒ቺ��H���~�߂邽�߂ɍw�ǎ҂̐�����L���A���Ꮚ���҂�w���̒Ⴂ�l�ɂ��ǂ�ł��炨���Ƃ͌o�c�����ҏW�����ǂ�����l���Ȃ������B������1990�N��ɓ����ĐV���Ђ̌o�c�T�C�h���̔��헪�̑�]����}��w�Ǒw�̊g��̂��߁A�l�X�̖ڂ������A���邢�͔����u�����ۂ��v�L����v�����Ă������Ƃ����̖��̔��[�ł���ƃ��[�[���X�e�B�[�����͕��͂��Ă���B
�킸��30�l���炸�̏����ŃX�^�[�g�����u�����v�ł��������A���̌�킸��2�T�Ԃ��܂�̂����Ɏ^�����ď����ɉ�������l��400�l�ȏ�ɂӂ��ꂠ�������Ƃ����B�܂����p���_�C�A�i���c���q�܂��p���Ńp�p���b�`�ɒǂ������ꂽ���Ɍ�ʎ��̎�����Ƃ����o�������N�������߂ł���BCCJ�͋��j���ɂ��̐����Ɏ^�����Ăт�����X�ւ��������A���̗����Ƀ_�C�A�i���܂̔ߌ����N�����B�T������č����ł���v���f�B�A�̓̕_�C�A�i��F�ɂȂ��Ă��܂��A���̂��܂�ɋɒ[�ȕ�Ԃ肪������A���́u�뜜�̐����v�̓��e�������i�D�̎�����������ƂɂȂ��Ă��܂����B���́u���R�̈�v�v�ɂ���Đ��������Ԃɋ������ꂽ�W���[�i���X�g���T�������瑱�X�Ǝx����\�����Ă������̂ł���B
CCJ�͂��̌�A�����Ő錾�����u�W���[�i���Y���̍������Ȃ������v���I�Ȍ`�ɂ��邽�߂̍�Ƃ��n�߂��B�����Ƃ���300�l�ȏ�̃W���[�i���X�g�ɃC���^�r���[����ƂƂ��ɁA�u�W���[�i���X�g�̉��l�ρv�ɂ���3���Ԉȏ�ɂ킽��C���^�r���[��100��ȏ�s������w�̌����҃`�[���Ƃ����͂��A�ނ炪�ǂ�Ȍ������ӎ����ē����̎�ފ������s���Ă���̂��A��̓I�ȃq�A�����O���s�����̂ł���B�����2�N�Ԃ�21��ɂ��y�ԃt�H�[����(���J���_��)���s���A�n���Ŋ�������W���[�i���X�g��L���s��������ӌ��������B�Q���҂͍��킹��3000�l�ɂ�������B���̌��ʂ�2001�N�A�w�W���[�i���Y���̌���(The Elements of Journalism)�x�Ƃ��������ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B����ɂ́u�j���[�X�œ����l���������R�m��ׂ��A�����đ�O(�p�u���b�N)���@�ւɓ��R���҂��ׂ��v�ƋL����Ă���B�䂪���ɂ�����j���[�X�E�W���[�i���Y���̋c�_�ł́A�����u�@�ւ͂�������ׂ��v���̋c�_�Ɍ��肳��Ă��܂����Ƃ��������A���̕���͖����`�̑̐��ɂ������O(���邢�͈�ʂ̎s��)�����f�B�A�̏���P�ɋ��邾���łȂ��A�₦���Ď����A�K�v�ȏ�����Ă��Ȃ��̂ł���ΐ�����v������Ƃ����u�����͂�O��Ƃ����ْ��W�v�������Ă������S�ȃW���[�i���Y������������Ƃ����\���m�Ɏw�E���Ă���A���̖{�̈Ӌ`���ے����Ă�����̂��ƌ����悤�B���̖{�̈ʒu�Â��Ƃ��Ē����E�����ɎQ�����������o�[��́A�������Ď����ꂽ�������u�j���[�X���߂�����̕ω��ɂ��ς�����W���[�i���Y���̋��ɂ̖ړI��A����ɔ��������E�Ӗ��E�M�ӂ�ڕW�Ƃ���v���Ƃ��m�F���A���̈ʒu�Â��ɂ��Ĉȉ��̂悤�ɐ������Ă���B
��X�͂��̖{��P�Ȃ�n�܂肾�Ǝv���B��������������ɐV���ȃA�C�f�B�A�����܂�A����ɃW���[�i���Y���̐M�O���V���ɂ���邱�Ƃ�ڎw���B(����)��X�͒P�Ɍ��݂̖��ɑ���u������v����悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�W���[�i���Y���ɑ��ĕK�v�ȋ��ʔF���m�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���̂ł���B�܂��A�ڍׂȍs���K��(�u����͂���ȁA����͂���ȁv)����낤�Ƃ��Ă���̂ł��Ȃ��B�����W���[�i���Y�����ړI�������������ł���Ȃ�A���ω����鎞��̒��ŕϊv�����s���邻�ꂼ��̕@�ւ̎���I�Ȕ��f�ɂ䂾�˂���ׂ����ł��邩�炾�B�����������ɂ����W���[�i���Y���������ɂ킽���Č��S�ɐ����Ȃ��炦��Ƃ���A����͐�����ČX�̃W���[�i���X�g�����̈Ӗ��𗝉����Ď��H���Ă������Ƃɂ����������Ă���B
�w�W���[�i���Y���̌����x�ł�9�̌������L���Ă���B�����̕\���͕��ՂŁA�ނ���g���Â��ꂽ���t�����g���Ă��Ȃ����A�܂��Ɂu�W���[�i���Y���̗��O�̃G�b�Z���X�v�ł���B���̖{�ł͎��ۂɋN������������o���������ɂ������āA���̌����͂ǂ̂悤�ɉ��p�����̂����ڍׂɉ������ƂƂ��ɁA���ۂɍs��ꂽ�C���^�r���[�̔������Љ�āA�W���[�i���Y�������H���邽�߂̎v�l�@�̓���������Ă���B9�̌����Ƃ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
1�D�W���[�i���Y���̑��̐Ӗ��͐^���ł���B
2�D�܂��s���ɒ����ł���ׂ��ł���B
3�D���̖{���Ƃ͌������s�ł���\�͂ł���B
4�D����Ɍg���҂͎�ޑΏۂ���̓Ɨ����ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
5�D�Ɨ����Č��͂��Ď�����@�\���ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
6�D�����̖��Ɋւ���ᔻ����݊����s�����_�̏����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
7�D�d��ȏo�����������[���A�Љ�I�ɈӖ���������̂ɂ���悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
8�D�j���[�X���킩��₷���A��Ȃ����̂ɕۂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
9�D����Ɍg���҂͎���̗ǐS���s�����Ƃ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�����̌����Ɂu�����v�Ƃ��u�o�����X�v�Ƃ��u�q�ϓI�v�ȂǁA�W���[�i���Y�����c�_���鎞�ɂ͔��u�퓅��v�Ƃ��Ďg�����傪�܂܂�Ă��Ȃ����Ƃɂ͒��ڂ��ׂ��ł���B�M�҂̃��[�[���X�e�B�[�����͂����̃R���Z�v�g�́u�����܂��Ő��m�ɕ]�����邱�Ƃ�����ł���v�Ɛ������Ă���B�w�W���[�i���Y���̌����x�ł́A�u�W���[�i���Y���̌����Ɋւ���l���͑������_�b�I�ȒʔO�������F���Ɏ�芪����Ă���v�Ƃ��āA�Ⴆ�u�W���[�i���X�g���Ɨ���ۂɂ͒����ł��邱�Ƃ��K�v�v�Ƃ����F���Ȃǂ����̗Ⴞ�Ƃ��āA�����̌����Ɋ܂܂�Ȃ������R���Z�v�g���̂��u�������ׂ���肻�̂��̂��������t�Ƃ��Ďg���Ă���v�ƒ��ӂ𑣂��Ă���B
�܂��A�u�����v�̒��ɁA�W���[�i���X�g�l�́u�ǐS�v�Ƃ����R���Z�v�g�����ꂽ���Ƃ��A�]���̓��{�I�ȃW���[�i���Y���̉��߂ł͍l�����Ȃ��������Ƃł͂Ȃ����낤���B����͈ꌩ��L�́u�q�ϐ��v�Ȃǂ̂悤�Ɂu�����܂��v�ȊT�O�̂悤�Ɍ����邪�A�L���X�g���I���l�ςɊ�Â����l�Ԃ̗ǐS�ɑ���M���ɍ�����u�����̂ł����āA�����ėǐS�Ƃ�����`�����̉��ŃW���[�i���X�g��l��l�̏���ȍs����e�F������̂ł͂Ȃ��B
�������āA����܂Łu�����܂��ɂ����\������Ă��Ȃ������v���̂ŁA���u���ɂ͑��d����Ȃ����̂ł��������v�W���[�i���X�g�̑��d���ׂ����l�ς���̓I�Ȍ`�ŁA�������W���[�i���X�g�łȂ��l�����������ł���悤�ȕ��Ղȕ\���ň�ʉ����ꂽ�B����������͂����܂ł��u�n�܂�ɂ����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ���X�͐S�ɗ��߂Ă����K�v������B���̌����ɏq�ׂ�ꂽ�\���͌���ł͍őP�̂��̂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤���A����������̕ω��ɔ����āA�N�ł��������₷���\���ɉ��߁A�ł��邾����I�ō���N����ł��낤���G�Ȏ��ԂɑΉ��ł���悤�ɁA�����Ă��̌�������邱�Ƃ�����������ł͂Ȃ�(�Ⴆ�Β���ɒǂ��Ă���u�Ԃɓ���葱�����K�v�ɂȂ邱�Ƃ���������u�����v�͌����I�ł͂Ȃ�)�悤�Ȍ`�Ŕ��W�����Ă����K�v������BCCJ�̃����o�[�́A���̂悤�ȕK�v�����[���ɔF�����āA���̊����������I�ɓW�J�ł���悤�� PEJ�����������̂ł���B
CCJ�́u3�̃S�[���v�ɂ͈ȉ��̂悤�ɏ����Ă���B
1�D�W���[�i���Y�����Љ�Ŏ��ۂɋ@�\�����鍪�{�����Ƃ��ẴW���[�i���X�g�̐M��(���ǂ���)�𖾂炩�ɂ��A�X�V���Ă������ƁB
2�D��O(�p�u���b�N)�������̌����𗝉��ł���悤�ɂ��邱�ƁB
3�D���f�B�A��Ƃ̃I�[�i�[��o�c�w�ɑ��Ă��A�����̌������o�ϓI���Љ�I�ȉ��l������̂��Ƃ������Ƃ𗝉������A�Q���𑣂����ƁB
����ɑ��� PEJ�́u�S�[���v���u�j���[�X�Y����W���[�i���X�g�����łȂ�����������s���̂ǂ�������@�ւ��牽�������炳��Ă���̂��A���悭�������Ă��炤�v���ƂƋK�肵�Ă���B���̂��߂ɂ͌��������̋c�_�����u���e�̕���(contentanalysis)�v�ɏd�_��u���A����ɒP�Ɉ�{�̋L����ЂƂ̔ԑg�ŕ������ꂽ�j���[�X�ɑ���ᔻ�╪�͂�����������A���f�B�A�S�̂ŋN���Ă��邱�Ƃɂ��Ē�ʉ�(quantify)���ĕ��͂���v���Ƃ���萳�m�ȗ�����ł���Ƃ��Ă���B�܂�A�u�W���[�i���X�g�͉������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�Ƃ������� CCJ���S���A�u���ۂ̃j���[�X�͂��̌����ɂǂ̂��炢�]���Ă���Ƃ�����̂��A���邢�͂�������Ă���̂��v�u����͂ǂ����ĂȂ̂��v�u���̘�������������ɂ͂ǂ������炢���̂��v�Ƃ��������ɑ��������d�˂Ă����̂�PEJ�Ƃ����A����u���ݕ⊮�v�̊W�ɂ���Ƃ�����̂ł���B |
|
��2�D�V�����j���[�X�̕��͂Ƃ͉����@���� PEJ�̗��O�Ɗ��� |
�{�͂ł͑n��9�N�ڂ�2006�N�ĂɁu�V�����t�F�[�Y�v���}�����Ƃ��� PEJ�����ۂɂǂ̂悤�ȗ��O�Ɋ�Â��āA�ǂ̂悤�ȕ��@�Ńj���[�X���͂��s���Ă���̂����̓��e�ɂ��ċc�_���Ă��������BPEJ�ɂ��j���[�X�̕��͂͑傫��3�ɕ��ނł���B���ꂼ��̖ړI(���ɃW���[�i���X�g�łȂ��l�X�ɉ���m�点�悤�Ƃ��Ă���̂�)�A�Ǝ�@�ɂ��ďЉ�Ă����B
��1�j���[�X�́u���e����(contentanalysis)�v
�]��������V���L����j���[�X�̃e�L�X�g��f���𒀎��L�^���A���ꂪ�����炷�u��ہv�ɂ��Ď�ɔᔻ��W�J����悤�ȓ`���I�Ȍ`���ł́u���e���́v�͑��݂����B�������A�����̑����́u�P���I�Ŋ��o�I�v�ł��邽�ߎ��ɐ����͂Ɍ�������̂ł��������Ƃ͔ۂ߂Ȃ��BPEJ�͏]���̃j���[�X���e���͂́u��_�v���������邽�߂ɏ]���̎�@��2�_�̉��ǂ������Ă�萳�m�ȕ��͂�ڎw�����݂Ɏ��g��ł���B����2�_�́u�H�v�v��1�_�ڂ́A�܂����͂̓��e��P�������A���ɑ�O�ɗ������₷���Ȃ�悤�ɋɗ́u���l���v���邱�Ƃł���B�f�B���N�^�[�̃��[�[���X�e�B�[�����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u��X���ڎw���Ă���̂́A���f�B�A�w�҂ƌ����Ă���l�����ɗ������Ă��炤�悤�Ȑ��I�Ȍ����ł͂���܂���B��X�����悤�Ɠw�͂��Ă���̂́A���̂悤�ȁu�w�̂���l�����v�ł͂Ȃ��A�����҂ł��Ȃ��l�����ł��w�����I�ɗ����ł���x���̂ł��B���̂悤�Ȑl�����͑����w�j���[�X�̓��e���́x�Ȃ�Ă��̂ɂ��Ă͉����m��Ȃ��ł��傤�B�Љ�w�Ȋw�I�ȕ��͎�@�̒m��������Ȃ������m��Ȃ��B���������ނ�͑�����X�Ɂw������(�悭�l���Ȃ��Ă�)�[���ł�����́x��v�����Ă���ł��傤�B����Ȑl�����Ɂu����͂���������Ȃ����v�ƌ����āu�����j���[�X���e���͂ɂ��ė������Ă������Ȃ��Ƃ͂Ȃ���ł����ǂ˂��v�Ɛ������Ă��S���Ӗ��̂Ȃ����Ƃł��B�ނ���Љ�Ȋw�I�Ȓm�����S���Ȃ��l�ł��w�Ȃ�قǁA�����������Ƃ��x�Ǝw���p�`���Ɩ炵�Ĕ[������悤�ȕ��͌��ʂ��K�v�Ȃ̂ł��B���ϓI�Ȉ�ʑ�O�������I�ɗ����ł�����̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��v
PEJ�͊w�p�I�ȋc�_�ɑς�����f�[�^���W�߂ĕ��͂����邪�A�����ɂ��ꂪ��ʂ̃j���[�X�̎�ɂ������ł���`���Œ���邱�Ƃ����ڎw���Ă���̂ł���B
����ł͂��̂悤�ȁu��ʓI�ȃj���[�X�̎�v�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȑl�������C���[�W��������̂��낤���B���[�[���X�e�B�[�����́u���݂ɘA��������O(interlockingpublic)�v�Ƃ������������Ă���B�j���[�X�̎�́u�m�I�G���[�g�Ƃ����łȂ��l�X�v�Ƃ����悤�ȒP���ȍ\�}�ł͂��łɂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ă��邩��ł���B�����ł͑��l�ȃ��f�B�A�����B�������ʁA�l�X�͂��ꂼ��̃��C�t�X�^�C���̒��ł��낢��Ȏ�i�ŏ�����肷��B�e���r����̏��͂��Ȃ�̔䗦���߂Ă���Ƃ͂����A�P���Ɂu�V�����牽�p�[�Z���g�A�e���r����͂����A�C���^�[�l�b�g����́E�E�v�ȂǂƂ͊���ꂸ�A����̖���g�s�b�N�ɂ���ăo���o���ŕ��G�ɗ��܂荇���Ă���C���[�W���Ƃ����悤�B����Ɋw���̍����Ȃ��l�ł������̏o�g�n�̔ƍߗ��̑����̖��Ƃ��A�ۛ��̃v���싅�I��̃h�[�s���O�X�L�����_���ɂ��ĂȂǁA����̖��ɂ��Ă͐��ƕ��݂ɒm�����������肷��B���f�B�A����O�ɒ��悤�Ƃ��Ă�����̗ʂ����̂܂܁u���ϓI�ȑ�O�v�̒m���ɒ�������킯�ł͂Ȃ��Ƃ����̂������Ƃ����F���ł���B���������̂悤�ȕ��G�Ȏ��Ԃ͔c�����悤���Ȃ����߁A��������ɐڋ߂���\����T����݂́u���f�B�A���牽���ǂꂾ������o����Ă���̂��v�Ƃ������ʂ���̕��͂�i�߂�Ƃ����A�v���[�`�ł���B
����1�_�̐V�������͂̊ϓ_�́u�ӎv����v���Z�X�v�̏d���ł���B���f�B�A��ƂŎ��ۂɎd���������l���͂ɓ������A�j���[�X���[���̒��ŁA�j���[�X�o�����[�̌y�d�A�j���[�X�\�[�X�̑I���ƕ]���A�L���̃g�[���≉�o�Ȃǂ��A�ǂ̂悤�ȕ��j��w���A��������ȂǂŌ��肳�ꂽ�̂��A�u���̑I����������̂ɁA�ǂ����Ă��̑I�����Ȃ��ꂽ�̂��v�����I�ȕ��͂����݂悤�Ƃ�����̂ł���B����ɓ���̎�ނ���`�B�̃X�^�C����I���������ɁA�j���[�X�̎�̏��͂ǂ̂悤�ɕ�̂��|���ɉ����`���ɂ����Ȃ�̂��|�Ƃ������ɂ��Ă��l�@��i�߂Ă���B
��L�̕��͂ɂ��ďے��I�ȍD����Љ��B2003�N�̃C���N�푈�Ŏn�߂č̗p���ꂽ�u���ߍ��^�W���[�i���X�g(embedded journalist)�v�̎�ގ�@�͂���܂ő����ʂ̌����Ȃ���Ă������A���̑����͎��ۂɎ�ނ��o�������L�҂�ɂ��̌��k�Ɋ�Â��čl�@�␄����W�J�����u�f�ГI�v�Ȃ��̂ł������BPEJ�ł͐푈���N���������2003�N4��3���ɑ������u���ߍ��^�W���[�i���X�g�v�̃e���r�E���|�[�g�̓��e���͂ɂ��Ă̕����\���Ă���BPEJ�͐푈�J�n����3����(2003�N3��21�A22�A23��)�ɂ킽��A3��l�b�g���[�N(ABC�ACBS�ANBC)�ƃP�[�u���e���r(CNN�AFoxNews)���킹��5�ǂ��ߑO7������ߌ�9���܂Ń��j�^�[���A�j���[�X�ԑg����ʔԑg�̍��v40���Ԕ��̒��ŕ������ꂽ�u���ߍ��^�W���[�i���X�g�v�ɂ�郌�|�[�g108�{�͂��Ă���B����͒P�Ȃ�e�L�X�g��f���̓��e���͂̑��ɁA�u�W���[�i���Y���W�҂łȂ��Ă��킩��悤�Ɂv����̎w�W�𐔒l�����čl�@�������Ă���B���Ȃ킿�u�g�s�b�N(���|�[�g�̑��)�v�u�ҏW���{����Ă��邩�ǂ���(���p���|�[�g����x�^�悳��� VTR�ɕҏW����ĕ������ꂽ���̂�)�v�u�e���r�p�̃r�f�I�f�ނ����W�I�p�̃��|�[�g���e���r�p�ɑ̍ق𐮂���悤�ɕҏW�������̂��v�v�Ȃǂ̃f�[�^���L�^�����B�Ⴆ�u���p�� VTR���v�Ƃ������́A�e���r�ǂ͒ʏ�A�d��ȃj���[�X�ɂ��Ă̓j���[�X���[���̃f�X�N��ҏW���ȂǕ����̃X�^�b�t�̃`�F�b�N���āu���S�������āv�������邪�A���p���邢�͓`������Ă������|�[�g���u�^���ďo��(�^�悵�Ă��̒���ɕҏW���������ɕ���)�v����Ƃ����̂́A�����̃`�F�b�N�����ׂāu�ȗ�����v���Ƃɑ��Ȃ�Ȃ����Ƃ��w�E���A�e���r�ǂ����̊��Ԃ����ɖ��ӔC�Ɍ��n����̃��|�[�g�������u�]�R���Đ퓬�̍őO���ɂ���(�͂�)�v�Ƃ������Ƃ݂̂��u���l�v�Ƃ��ĕ����������Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ����̂ł���B���͂̌��� PEJ�����������u���ߍ��^�W���[�i���X�g�v�̃��|�[�g�̖��_�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�E104�{�̃��|�[�g�̂����A93.5�p�[�Z���g�́u����(fact)�v�Ɋւ���ł������B�u����(analysis)�v�͂킸��1.9�p�[�Z���g�A�u�_�](commentary)�v��3.7�p�[�Z���g�����Ȃ������B
�E��6���̃��|�[�g�͒��p���ҏW����Ă��Ȃ����f�B�A���Ď�����Љ�I�ȕK�v(�����M�K) 77VTR�ł������B
�E�����Ă������|�[�g�̖�8���͌��n�̋L�҂̕ŁA���m�₻�̑��̎�ސ�(�C���N�̏Z���Ȃ�)�̐��͂قƂ�Ǔ͂����Ȃ������B
�E47�p�[�Z���g�̃��|�[�g�͌R�����₻�̌��ʂɂ��Ă̏��ł������B����͂܂��Ɂu�퓬�̃��|�[�g�v�ł������B
�E�f���̓h���}�e�B�b�N�ł͂��������A�푈�̂ǂ����͑S���������Ȃ������B���͂��ꂽ108�{��104�̃��|�[�g�ɂ�1����U���ŕ��������l���o�ꂵ�Ȃ������B
�ȏ�̂悤�ȃf�[�^�܂������͂ł��́̕u���ߍ��^�W���[�i���X�g�̃��|�[�g�͑����āw��b�I(anecdotal)�x�ł������v�ƌ��_�Â��Ă���B�܂��u�퓬�����ɏœ_�Ă�(���ӂ̏Z���Ȃǂɂ͑S�����ӂ�Ȃ�)�A�啔�������p�ƕҏW���������Ă��Ȃ��e�[�v�ɂ������ł������B���e(content)�ɂ͖R�����������A�ו�(detail)�̕`�ʂ����ɑ��������v���߁u�ʔ���������(exciting)�A�ދ��ł�������(dull)�v���A�e���r�̃��|�[�g�́u�قƂ�ǂ̒����ƒZ�����܂܂�Ă����v�Ǝw�E���Ă���B
����ɂ��̕ł̓e���r�̕����̊��ԁA��L�̂悤�ȕΌ���Ƃ��Ă��܂��������Ƃ��āu�Ƃɂ���������������������v�Ƃ����ӌ����ߓx�ɓ��������Ƃ������Ă���B���̔w�i�Ƃ��āu�e�N�m���W�[�̔��B�v�������Ă���B����ɂ�茻�n�̃��|�[�g�������ɑ��M�ł��A�ҏW�̋Z�p�����B�������߃��W�I�̃��|�[�g���e���r�p�ɑ̍ٗǂ��������邱�Ƃ��\�ɂȂ�B�������A���̂悤�ɂƂɂ����X�s�[�h�����߂��ށE�����̐��̓j���[�X���[���Ɂu������ԈႢ�𑽔������A�W���[�i���X�g���P�Ȃ�w�`���Q�[���x�����鎖�Ԃ�U�����Ă��܂��Ă���A���ɕ����I�ȏ����Ă����ߒ��Řc�Ȃ��ꂽ��A�ߓx�ɋ������ꂽ�肵�Ă��܂����v�Ɣᔻ���Ă���B
��2�j���[�X��Ƃ̌o�c�I���ʂ��j���[�X�ɋy�ڂ��e��
�j���[�X�̓��e�ɉe�����y�ڂ��v���̕��͂͒��炭�L���ȃL���X�^�[��Ԍ`�L�ҁA�f�X�N��ҏW�ӔC�҂Ȃǂ̌l�I�Ȏw����M���̂悤�ȁu���l�I�ȓ����v�ɒ��ڂ���Ɛтɕ��Ă����Ƃ�������ł��낤�BPEJ�͂��̂悤�ȓ_�Ƃ͕ʂɃ��f�B�A��Ƃ̌o�c���j���[�X�̓��e�ɋy�ڂ��e���ɂ��Ă̑�K�͂Ȓ������J�n�����B2004�N���疈�N�A�u�j���[�X���f�B�A�̏�(TheStateoftheNewsMedia)�v�Ƃ���16����ɂ��y�Ԓ����̕��s���Ă���B���ɑ�K�͂ȕ��ł���A���̏ڍׂ͏����ʂ̘_���ŋc�_�������Ǝv���Ă��邪�A�T�ς��Ă݂邾���ŁA�V���Ђ�e���r�ǁA�����Ă��̐e��Ђł��鋐��R���O���}���b�g�̌o�c���j���j���[�X�̌���ɐ[���ȉe�𗎂Ƃ��Ă��邱�Ƃ��킩��B
2007�N�̕��̖`���ɂ́u��X�̓j���[�X�E�r�W�l�X��2007�N����V�����ǖʂɓ������A����́w����S�x�����ނ������Ƃł���v�Əq�ׂĂ���B���L�������W�߂悤�Ǝ�ޖԂ��g����ɂ͔��ɃR�X�g��������B���܂Ń��f�B�A��Ƃ͉E���オ��̐������Ȃ�Ƃ��ێ����Ă����̂ŁA���̂悤�Ȏ�ޖԂ̏k�����l�������ɍς�ł������A���݂͑��l�ȃ��f�B�A�̕��G�ȋ����Ɛ₦�ԂȂ��Z�p�v�V�ɂ�铊���̕K�v�ɒ��ʂ��A���f�B�A��Ƃ́u�k������\�͂̒��łǂ�����đ�O�ɃA�s�[���ł���̂�������Ē�`����w���ނ��ǂ̂悤�ɐH���~�߂邩�x�ɔ\�͂��X�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���ԁv�ł���Ǝw�E���Ă���B���������������ƁA�u�ߓx�Ȓn���D���`(hyperlocalism)�v�ɂ��A�C�O�x�ǂ������(�A�����J)�����̃j���[�X��D�悵����A�A�����J�����ł�����̒n��(���Ɏ��B���痣�ꂽ�n��)�̃j���[�X���_���������悤�Ȍ��ۂ��N���Ă���B
���ł̓��f�B�A��Ƃ�V���A�G���A�n��g�e���r�A�P�[�u���e���r�A�n���̃e���r�A�G���A���W�I�A�G�X�j�b�N���f�B�A(�q�X�p�j�b�N�⍕�l�������f�B�A)�A�ȏ�̃��f�B�A�̃I�����C�����̏ƐV���ȃf�W�^�����f�B�A�Ȃǂ̃J�e�S���[�ɕ����āA���̔N���Ƃ̌o�c�⓮���Ȃǂ��f�[�^��q�A�����O�����ƂɏڍׂɋL�^���Ă���B2007�N�̕œ��ɐ[�����Ǝw�E����Ă���̂́u����ɑ��铊���ɉA�肪�����v�Ă���A�L�҂�J�����}���Ȃǂ��l���팸�̊�@�ɕm���Ă���Ƃ��������ł���B�ł�2000�N����2005�N�̊ԂɁA��������e���r�E���W�I�ł͑S�̂�5�p�[�Z���g�A�S�Ăł��悻3000�l�̐l���팸���s��ꂽ���A2006�N��1�N�Ԃł����1000�l�K�͂̋}���ȍ팸���s��ꂽ���Ƃ����炩�ɂȂ����B�T�u�v���C�����[���̖�肪�I������2007�N�͂���Ɏ��Ԃ͐[���ɂȂ錩�ʂ��ł���B
���̂悤�Ȏ��Ԃ̒��ł́A�厑�{�������̃��f�B�A���P���ɒu���悤�ȁu�ƍەۗL(�N���X�I�[�i�V�b�v crossownership)�v�����n�������f�B�A���ɂ����Ắu���̂悤�ȑ厑�{���j���[�X�E�r�W�l�X�𐊑ނ��Ă����ƌ��邩�A����Ƃ��V���������̂��߂̉ߓn���ƌ��邩�Ƃ��������������J�M������v�Ǝw�E���A���͂�j���[�X�̓��e�̋c�_�ȑO�ɁA���̕@�ւ��������邩�ǂ����Ƃ������ɂ̔��f���o�c�w�������Ă���N���������������Ă���B���̂悤�Ȓ��Ńj���[�X��Ƃ͂��Z���I�ȃT�C�N���Łu�Ȃ�ӂ�\�킸�V�����r�W�l�X���f�����m������K�v�v�ɒ��ʂ��Ă���B���Ȃ킿�u�����ɂȂ遁����郂�f���v���K�v�Ȃ̂ł���A�Ⴆ���̂��߂ɁA�N�X�[���ɂȂ��Ă���u�_������(TheArgumentCulture)�F���ʓI�ȏ���]�_�����A���߂���l�|���܂߂������������d������悤�ȕҏW��ԑg����̎p���v������ɐi�s���āu����(TheAnswerCulture)�F��X�̏����ᖡ����������A�c�_���o�邱�ƂȂ��P���Ȍ��_���}�����������肷��v�ɂ܂ŕώ����Ă��܂����ƕ��͂��Ă���B�u���f�B�A�̐ӔC�҂͂Ȃ��A���̂悤�ȑI���������̂��v�Ƃ���������Njy���Ă����ƁA���݂̕č��ł̓X�^�b�t���̐��̐�ɁA�u���{�̘_���v�ɍ������A�\���I�Ȗ��ł��邱�Ƃ��F������Ă����̂ł���B
��3�Љ�S�̂ł̃j���[�X�̑��̂�c�����悤�Ƃ��鎎��
��q�̂悤�Ɍ��݂̃A�����J�Љ�ł�(���{�Љ����������)���f�B�A��Ƃ��������|���āu�j���[�X��v���ƂɑS�͂��X���邱�Ƃ����R�ƂȂ��Ă���B���̋A���Ƃ��ăj���[�X�́u���l��(diversity)�v�������Ă��܂��B�j���[�X�̎Љ�I�ȈӋ`�Ƃ��āu���͂���Ȗ�������܂���v�Ə����̐l�����F�����Ă��Ȃ��_�_���Љ��Ƃ������̂����邪�A��葽���̐l�̊S���Ăԃj���[�X����邱�Ƃōw�ǎҐ��𑝂₵���莋�������グ���肷��Ƃ������Ƃ����㖽��ɂȂ�ƁA�j���[�X�̉�ꉻ���[�������Ă��܂��̂ł���B�g�b�v�j���[�X�͂ǂ̕@�ւ������ŁA��������ʂ������̂ɂȂ��Ă��܂��B��������PEJ�̑O�gCCJ�̊������傫�Ȏ^�����Ă̂��A���E�I�Ƀ_�C�A�i���c���q�܂̎��̎��̏W�����J�I�ȕł��������A���̌�����ɃZ���u(�L���l)�Ȃǂł��̍D�܂����Ȃ��X���������ɂȂ錻�ۂ��������N���Ă���B2004�N����2005�N�ɂ����Ẵ}�C�P���E�W���N�\���ٔ���2007�N�̃p���X�E�q���g���̎��đ����₻�̌�̓^���ȂǕ��q�X�e���b�N�ɓ���̃j���[�X��F�ɂȂ��Ă��܂�����͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B���̉A�ő��̑厖�ȃj���[�X���`�����Ȃ�������A���������ɖڗ����Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂����肵������͂Ȃ��Ȃ��`�����Ȃ��̂�����ł��邪�A�C���N�푈�Ɏ���t�Z�C�������̑�ʔj����߂���ɂ��Ă͔�r�I�ڍׂɌ��Ɣ��Ȃ��Ȃ���Ă���B�Ⴆ�u�R�����r�A�E�W���[�i���Y���E���r���[�v���̌��ҏW���}�C�P���E�}�b�V�O(MichaelMassig)����2004�N2���A��A�̑�ʔj���ᔻ����_�����uNewYorkReviewofBooks�v�Ɍf�ڂ����B���̒��Łu���V���g���E�|�X�g�v���̌R���E�h�q�S���̃x�e�����L�ҁA�E�H���^�[�E�s���J�X(WalterPincus)�L�҂͓����u�b�V������������Ɍ��`���Ă����C���N�̑�ʔj��ɋ^���悷��L�����Ƌ��ɐ��k�Ȏ�ނł܂Ƃߏグ�����A���̋L���͗��R���Ȃ������ԍ����~�߂��A�{�u�E�E�b�h���[�h�ҏW�ǎ����̐i���ł���ƌf�ڂɂ������������A���̈����́uA13�v�Ƃ������ʂł͂��Ȃ���̕��������Ƃ����G�s�\�[�h���Љ�A�E�b�h���[�h���́u�����͎d�����������A�����ď\���ł͂Ȃ������B���͂����Ƌ��������ׂ��������B�����͂��̍�������Ȃ����̂ł��邱�Ƃ������Ɠǎ҂ɓ`����ׂ��������v�Ƃ����R�����g���Љ�Ă���B
�M�҂� PEJ�̃��[�[���X�e�B�[�����ƃf�B�X�J�b�V�����������ɖ��ӎ������L�����̂́A���݂����f�B�A��Ƃœ������o�������҂Ƃ��ăj���[�X�Y����L�҂�ҏW�ҁA�e���r�̃f�B���N�^�[�Ȃǂ͎����̐V���Ђ�e���r�E�l�b�g���[�N�Ȃǂ��`�������̃j���[�X�̐�߂�{�����[���⑼�̃j���[�X�Ƃ̃o�����X�ɂ͈ꉞ�C��z�邪�A���Ƒ��Ђ⑼�̃��f�B�A�����킹�����f�B�A�̑��̂��Љ�ɒ��Ă���j���[�X�̑��ʂ�C���p�N�g�Ɋւ��Ă͐ӔC�����ĂȂ����A�R���g���[�����s�\�ł���A���͌��݂��ꂪ�傫�ȎЉ���ł���Ƃ�������F���ł���B���[�[���X�e�B�[�����͂��̖��𖾂炩�ɂ���f�[�^���Ȃ��ƁA�@�ւ̊W�҂ɃC���^�r���[����ہu���Ȃ��̂Ƃ���́����̃j���[�X�ɂ��Ă��܂�ɑ����̎��Ԃ⎆�ʂ������Ă��܂��v�Ǝw�E���悤�Ƃ���ƁA�u����Ȃ��Ƃ���܂���v�Ɣ��_����Ă��܂��A�u���̖��ɂ��Ă���ɋc�_�����Ղ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ɖ��炩�̌`�Ńf�[�^�����K�v����Ɋ������Ƙb���Ă���B
PEJ�͂��̖��ɂ��Ă��ʊ��ɒ�����J�n���Ă���B�u�j���[�X�w�W(NewsCoverageIndex)�v�Ə̂��āA�T���v���ɑI���f�B�A�̕��L���E���l�����ďT��1�����I�Ƀf�[�^�ƕ��͂\���鑼�A�哝�̑I����k���N�̊j���ȂǓ���̃C�V���[�ɂ��Ă̕��͂��s���Ă���B�f�[�^���ɂ͈ȉ���2�_�ނ��₷���`�Ńf�[�^�����邱�Ƃ����߂���B����2�_�Ƃ�1)�L���̃X�y�[�X��e���r�̕�������(newshole)�ɂ���j���[�X���ǂ̂��炢�̊������߂Ă���̂��A��2)���̃j���[�X�͂ǂ̂悤�Ɏ�ނ���A���o����A��������ċL����j���[�X�ɂȂ����̂�(���̌��ʁu�肪�ǂ̂悤�Ȉ�ۂ������v�Ƃ������͂����o�I�łȂ��A������x�q�ϓI�ɂ��邱�Ƃ��\�ɂȂ�)�ł���BPEJ�͂��̕��̓v���W�F�N�g���J�n����܂ł�2�N�ȏ�̏������Ԃ�v�����Ƃ����B�j���[�X�̓��e���f�[�^�����邽�߂Ɂu�R�[�h(code)�v�Ƃ����w�W��p���邪(�ڍׂ͌�q)�A���ɂ������m�肷�邽�߂̍�ƂɎ��Ԃ�v�����Ƃ����B�R�[�h����@�_���܂Ƃ߂�̂�1�N�]�A���ꂩ�炻�̃R�[�h�������I�ɓK�p�ł���悤�ɒ������}�j���A���������Ƃɖ�1�N���������Ƃ����B���݂ł����@�_�����S�Ɋm�����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�u����Ȃ���l���A�C������v�i�K���ƃ��[�[���X�e�B�[�����͌���Ă��邪���̘g�g�݂͉�X�����{�̃��f�B�A�͂��邤���ł��M�d�Ȏ�������Ă����Ǝv���邽�߁A���̈�[���Љ�����B
���̂悤�ȕ��̓v���W�F�N�g���p���I�ɍs�����ʂƈӋ`�ɂ��ă��[�[���X�e�B�[�����́A�u��{�I�ȕϐ�(primaryvariable)�v�̓j���[�X�́u�b�肠�邢�͑��(topic)�v�ł���Ƃ��A�����ɂ킽�蕪�͂��邱�Ƃɂ��A����̘b�肪�����I�Ɏ��グ���A���ʂ���j���[�X�̑啔�����߂Ă��܂����Ԃ���������A���ꂪ�}���ɑޒ�������Ƃ������ۂ��u��Ɏ��悤�ɂ킩��v�Ƃ��Ă���B���݁u�g�s�b�N�v��4�̃��x���ɕ������Ă���A�Ⴆ�C��ϓ�(�n�����g��)�� HIV�E�B���X�̗��s�Ȃǂ̂悤�ȁu�傫�ȃe�[�}�v����ו����A��̉�����Ă����B�Ⴆ�u�đ哝�̑I���̃L�����y�[���̃j���[�X�v�́A�u���҂̐���v�u�o���v�u�w�i(�x���c�̂Ȃ�)�v�u�I���^���̎�@�v�ȂǂɎ}�����ꂵ�Ă����̂ł���B�����́u�g�s�b�N�v�ɂ��āA�ǂ̃e�[�}���ǂ̂悤�Ȍ`�Ŏ��グ���Ă���̂�(�Ⴆ�ǂ��̒n���l����c�̂ɏœ_�����Ă��Ă���̂�)�Ȃǂ̃j���[�X�́u���s�v�̐��ڂȂǂ��T�ς��邱�Ƃ��ł���Ǝw�E���Ă���B�܂����e�͏ڍׂɁu�R�[�h�v�ŕ��ނ���A�u�_��(narrative)�v�������ɕω����Ă������Ƃ����ώ@���\�ɂȂ�B
PEJ�ł͈ȉ��̃��f�B�A���T���v���Ƃ��Čp���I�Ɋώ@����B
1 �V��(���v13��)�F�y�j���ȊO�͖����`�F�b�N����B
�E�u�j���[���[�N�^�C���Y(TheNew York Times)�v�����͖����`�F�b�N����B
�E����12���͍w�Ǖ����ƍ����ł̒�](prominence)�ɂ����3�̃����N�ɕ������A���̏�ʃO���[�v�ɂ́u���V���g���E�|�X�g(TheWashingtonPost)�v�u���T���[���X�E�^�C���X(TheLosAngelsTimes)�v�u�E�H�[���X�g���[�g�E�W���[�i��(The Wall Street Journal)�v�uUSA�g�D�f�[(USA Today)�v���܂܂�Ă���B����4���̒����疈��2����I�уT���v���Ƃ���B
�E���ʁA���ʂ̃O���[�v���n���I�ȕ������đI�ꂽ�n����4�����̃O���[�v�ł���A��L�Ɠ��l�ɖ���2�����L���́u�R�[�h�v���̍�Ƃ��s���B
�E�V����1�ʂɌf�ڂ���Ă���L���͑ΏۂƂ���B�č��̐V���L���͒ʏ�A�L���̖`������1�ʂɌf�ڂ��A���������̕łɍڂ��Ă���A��ł̋L�����܂߂��ׂĂ͑ΏۂƂ���B
�E1���Ɉ�����L���͕���25�{�ł���B
2 �E�F�u�T�C�g(5�T�C�g)�F���j���`���j���̕����`�F�b�N����B
�E�����̂� CNN�AYahoo!�AMSNBC�AGoogle�AAOL(AmericaOnline)�̃j���[�X�T�C�g�ł���B�����̓j�[���Z���Ђ����肵�Ă���1���̃��j�[�N���[�U�[���ŏ�ʂɃ����N���ꂽ���̂�10�T�C�g���o���A���̒�����f�ڂ���Ă���j���[�X�̌`��(�P�[�u���e���r�̃j���[�X�T�C�g�� CNN�AMSNBC�A�V������̓]�ځ� Yahoo!�AGoogle�A��ɒʐM�Ђ̋L�����f�ځ� AOL)�ƃo�����X���l�����Ē��o���ꂽ���̂ł���B
�E�č���1���ɕ��ϖ�3000���l�����炩�̌`�ŃI�����C���E�j���[�X�ɐڐG���Ă���B
�E�ē������ԂŌߑO9������10���܂ł�1���Ԃ̊Ԃɂ��ꂼ��̃E�F�u�T�C�g�Ɍf�ڂ��ꂽ5�{�̃j���[�X�A���v25�{�͑ΏۂƂ���B
3 �l�b�g���[�N�E�e���r(3��l�b�g���[�N��PBS��������)�F���j���`���j���̕����`�F�b�N����B
�E�ߑO8������n�܂�3��l�b�g���[�N�̃��[�j���O�V���[�̖`��30���Ɉ���ꂽ�j���[�X�v90���𒊏o����B���[�j���O�V���[��2���Ԉȏ�̔ԑg�����A�㔼�͌J��Ԃ��Ȃǂ��������߂ɏȗ�����B
�E�ߌ�6��30������n�܂�3��l�b�g���[�N�̃j���[�X(30��)�����ׂĈ����B
�E�ߌ�7������n�܂� PBS�́gNewshour with Jim Lehrer�h(1���Ԕԑg)�̖`��30���������B
�E��L�̍��v3����30���͑ΏۂƂ���B
�E3��l�b�g���[�N�̎����҂�1�����ϖ�2700���l�APBS�͖�240���l�ƌ����Ă���B
�EABC�Ō��j��������j���̌ߌ�11������1���ԕ������Ă���gNightline�h�̑��A�u�j���[�X�}�K�W���v�ƌĂ��ԑg�́A���̂قƂ�ǂ�������������Ȃ����߁A�T���v���ɓ���Ă��Ȃ��B
4 �P�[�u���e���r�F���j���`���j���̔ԑg��I�����ĕ��͂���B
�E3�̃P�[�u���j���[�X�ǁACNN�AMSNBC�AFoxNews���ׂĂ�ΏۂƂ���B
�E���[�j���O�V���[�͓����Ɛ����̎�����4���Ԃ�����̂ŏ��O����B
�E�����͌��p�����̐����C�x���g(�哝�̂̋c��ł̉����Ȃ�)���p����悤�Ȍ`���̔ԑg���啔�����߂�̂ŁA3�ǂ̂���2�ǂ̕�����30����(�ߌ�2���`�ߌ�2��30��)���o����B
�E��̓��C���̃L���X�^�[��z�������͂�]�_�A�������_�ԑg�Ȃǂ��Ґ�����Ă��邽�߁A�e3�ǂ̌ߌ�6������ߌ�10��(������v���C���^�C��)�ɊJ�n����4�ԑg(�啔����1����)�̂��� CNN�� Fox��3�ԑg�AMSNBC��2�ԑg�𒊏o���ċL�^����B
�E��L�̍��v1��5���Ԃ̕�����ΏۂƂ���B�S�Ă̎����҂͓����Ŗ�160���l�A�v���C���^�C���Ŗ�270���l�ł���B
5 ���W�I�F���j���`���j���̔ԑg��I�����ĕ��͂���B
�E���W�I�����̃j���[�X�̓w�b�h���C��(���o���ƒZ���v��)������`������̂��������߁AABC�� CBS���W�I�̌ߑO9���ƌߌ�5���̃j���[�X(�e��10��)�A��������(National PublicRadio)�̒��̃j���[�X(�gMorning Edition�h30��)���T���v���Ƃ���B
�E���W�I�����͂��Ȃ�ɒ[�Ȑ����I�咣��W�J����u�g�[�N�V���[(talkradio)�v�ɓ���������A�����̒���҂����邽�߁A�ێ�h(conservative)�̃z�X�g���o��������̂���2�ԑg�A���x�����̃z�X�g�̔ԑg����1��I�ԁB
�������� PEJ�̓E�B�[�N�f�[�ō��v35�̃��f�B�A���J�o�[���A���̑��̂̒��ő啔�����߂�j���[�X���ǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă����Ă���̂��A�p���I�Ȋώ@�ƕ��͂𑱂��Ă���B
���ꂼ��̃j���[�X�Łu�R�[�h�v�������ϐ��͌���18����B�����͈ȉ��̒ʂ�ł���B
1 �R�[�h������l�̔F���ԍ�(ID)
2 �R�[�h���������t
3 �L���̔F���ԍ� ��1�`3�̓R���s���[�^�[�������I�ɋL�^����悤�ɐv����Ă���B
4 �L���̃g�s�b�N�������������t
5 �e���r�E���W�I�̔ԑg��
6 �e���r�E���W�I�̔ԑg�̊J�n����
7 ����̃j���[�X�̊J�n���ꂽ����(�^�C���R�[�h�F�b�P�ʂŋL�^)
8 ���o���̕\��
9 �L���̌ꐔ
10 �L�������ʂ̂ǂ��ɔz�u����Ă��邩
11 �e���r�E���W�I�̓���̃j���[�X�̌`��(�L���X�^�[���ǂނ������A�L�҂ɂ�� VTR�̃��|�[�g���A���p�ŃL���X�^�[�ƌ��n�̋L�҂̃N���X�g�[�N�����邩�A�Ȃ�)
12 �L����j���[�X�̓��e
13 ���C���Ŏ��グ���Ă���g�s�b�N
14 �����Ď��グ���Ă���g�s�b�N
15 �ǂ��̒n�_(���A�n���Ȃ�)�����グ���Ă��邩
16 ���̋L���̔w�i�ƂȂ�u�傫�ȃe�[�}�v
17 ���̃j���[�X�̕������I����������(�^�C���R�[�h)
18 �����I�ȉe��(�哝�̑I���Ƃ̊W)
���݁APEJ�ɂ�11�l�́u�R�[�h�v�L�^����ɍs���E��������A����3�l����5�l���x����L�̃T���v�������ׂċL�^���Ă���B���V���g�� D.C.���S���̋ߑ�I�ȃI�t�B�X�ɂ��鎖�����ɂ́u�R�[�f�B���O�E���[���v������A�R�[�h���S���̃X�^�b�t�͂��̕����ɋl�߂āA���ꂼ��E�H�b�`���Ă��郁�f�B�A�Ō��ꂽ�j���[�X���z���C�g�{�[�h�ɏ����o���Ă����A�u�����̃j���[�X�����ڂ��W�߂Ă���̂��v�Ƃ����������L�ł���悤�ɂ��Ă���B���̎��̏u�Ԃɂ��̃j���[�X�����̃��f�B�A�̕ő傫�ȃE�F�C�g���߂�\������������ł���B�ő��8�l�̃X�^�b�t���`�[���Ŏd��������Ƃ����B���������ǂ̂��炢�̕��ʂ̃j���[�X�͂��邱�ƂɂȂ�̂��A�C���[�W�����ނ��߂Ɉȉ��̐������Љ�Ă����BPEJ�ɂ��ƁA2007�N4������6����2�����Ԃɍs�������͂ł́A���v180�A10�{�̃j���[�X�����グ���B�e���r�ƃ��W�I�����킹���ԑg�̕������Ԃ̍��v��459���Ԃɂ��̂ڂ�A�L���Ɏg��ꂽ�ꐔ�͐V���Ŗ�216����A�E�F�u�T�C�g�ł͖�110����ɂ��Ȃ�B
|
|
��3�D�ނ��тɂ����āF���{�ւ̓����������
|
���[�[���X�e�B�[�����ɂ��ƁA���̃v���W�F�N�g�̖ډ��̉ۑ�͑傫��������2�_����Ƃ̂��Ƃł���B�����́A(a)�ϐ�(�R�[�h)�̓��e�̌��Ɠ��e�̏[���ƁA(b)�R�[�h�����s���X�^�b�t�̕]���̎d���ω�����(�\�͂�������)���Ƃł���B
�ϐ��̓��e�̏[���̖��ł��邪�A�܂����݂̕��̘͂g�g�݂Ɋ܂܂�Ȃ����f�B�A������BPEJ�������I�ɉ��炩�̌`�Ń��X�g�ɉ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���̂́A�j���[�X�T�����ƃu���O�A���ꂩ��e���r�̃g�[�N�V���[�Ȃǃj���[�X�ȊO�̔ԑg�ł���B�č��ɂ́uTime�v��uNewsweek�v�uUS News and World Report�v�Ƃ����j���[�X�������T����������A��K�͂ȍw�ǎ҂�����Ă���B�܂����ݓ��Ɏ�N�w�𒆐S�Ƀj���[�X��V���L����ԑg���瓾���ɁA��ɃE�F�u�T�C�g�A���Ƀu���O��ʂ��Ēm��Ƃ������f�B�A�E���C�t�X�^�C�����g�債�Ă���B�u���K�[�̒��ɂ̓W���[�i���X�g�łȂ��l�̂ق������|�I�ɑ����A���ɏ���I�A�O���I�ƃj���[�X�ƊE�Ō����Ƃ���́u�E�����v���o���Ă��Ȃ��s�m���ȏ��Ɋ�Â����]�_��ӌ��������B�������ꕔ�̃u���K�[�͐V���̍w�ǎ҂��������̃��j�[�N���[�U�[���l�����Ă���Ƃ�����ꉽ�炩�̌`�ŕ��̘͂g�g�݂ɉ����Ă������Ƃ��K�v�ɂȂ�ł��낤�B�����_�� PEJ�́u�\�����قȂ邽�߁v���͂ɉ����Ă��Ȃ����A���悻1000�l�̃u���K�[����������u���f�B�A�E�u���K�[����(Media Bloggers Association)�v�Ƌ��c���ŏ������炩�̌`�ŃR�[�h�ɉ����Ă����\��𖾂炩�ɂ��Ă���B
�l�X�̃j���[�X�郋�[�g�̓e���r��W�I�������Ƃ��Ă����l�����Ă���A����3��l�b�g���[�N�����j��������j���ɐ^�钆��0�������������g�[�N�V���[�ł͐����Ƃ̃Q�X�g���p�ɂɓo�ꂷ��ȂǁA���Ȃ�L�͂ȏ�ƂȂ��Ă���Ƃ�������������B�T���v���Ƃ��Ăǂ̂悤�ɉ����Ă������Ƃ����ۑ������B����Ƀj���[�X�̃R�[�h�����̂ɂ��A���Ƀj���[�X�̉��o�ɂ��C���[�W�̍��ق��̐�����Ȗ��ɍs���Ă���(�`�Ղ��m�F����邩)�Ȃǂ̗v�f������ł͕��͂ɉ�������Ă��Ȃ��Ƃ����u���ׁv�����݂���B�g�[�N�V���[�Ȃǂ̔ԑg���T���v���ɉ�����ꂽ�ꍇ�ɂ͂��̂悤�Ȗ����l������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
���� PEJ����ԗ͂𒍂��ł���̂���L2�Ԗڂ̉ۑ�ł���A�R�[�h�����s���X�^�b�t�̊��o�Ɣ\�͂̕������ł���B�u�ǂ̃X�^�b�t���R�[�h���̍�Ƃ��s���Ă��ϐ��̐��l�ɍ��������Ȃ��悤�ɂ���v�Ƃ����̂����ɂ̖ڕW�ł���B���ݕ����̃X�^�b�t�������j���[�X���R�[�h�����Ă��̍����k�߂���@��͍����Ă���Œ��ł��邪�A��ȃR�[�h�ɂ��Ė�85�p�[�Z���g����v���鐅���܂Ŋm�������������Ƃ������Ƃł���B�������W�r��̃v���W�F�N�g�ł͂��邪���҂������Ē��ڂ��čs�������ƍl���Ă���B
���_�̖`���ł��G�ꂽ���A�M�҂����̕��͎�@�ɒ��ڂ���̂́A���{�̃��f�B�A�̃j���[�X�Y����`�Ԃ�A��O�̐M�p���h�炢�ł���Ƃ����A�w�i���č��ƍ������Ă��邽�߁A�������ĕ��͂��ꒊ�o���ꂽ���������������ɓ��������ɂȂ�ƍl���邩��ł���B���Ȃ��Ƃ��j���[�X�̗��p�҂̑命���ł����O(�p�u���b�N)���P�Ȃ��ۘ_�����łȂ��u�������Ȃ̂��v��̓I�ɔF�����邱�Ƃ��d�v�ł���B
��̘b�ɂȂ邪���{�ł̓������\�z����ɂ������ẮA���͂�S������X�^�b�t�̈琬���傫�ȉۑ�ƂȂ�ł��낤�BPEJ�ł̓��f�B�A�E�W���[�i���Y���Ȃǂ̕���ŏC�m����L���邩�A���f�B�A��ƂŋL�҂��j���[�X�̐���Ɋւ�����E���o�������ƂɃX�^�b�t���̗p���A�K���f����2�T�Ԃ���3�T�Ԃ̊�b�I�g���[�j���O���o�ăR�[�h���̍�Ƃɐ����ɏ]������Ƃ����琬�v���O�������Ƃ��Ă��邪�A���{�ł͂��������W���[�i���Y����U�̑�w�@�C���҂̐�ΐ������������Ȃ��A�I�g�ٗp�̓`�����܂��܂������Ȃ��ٗp�����ł̓��f�B�A��Ƃ�ސE����҂Ăɂ��邱�Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ����ꂪ���邽�߁A���{����\�z�̗��蒼����]�V�Ȃ�����鋰�������B
���_�ł͕��@�_�̎��ۂɂ܂ł͓��ݍ��߂Ȃ��������A����p���I�� PEJ���ƈӌ��������d�ˁA�P�[�X�X�^�f�B��W���[�i���Y���ɑ��闝�O���ǂ̂悤�ɕ��̓v���W�F�N�g�ɔ��f������̂��Ƃ������ɂ��ė�����[�߂Ă��������ƍl���Ă���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���W���[�i���Y���̉ʂ����ׂ����� 2013/12 |
���{��������x�P�����߂ɓ��{�̃W���[�i���Y�����ʂ����ׂ������ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B
�܂��A�W���[�i���Y���Ƃ������t�����T�ň����Ă݂܂����B�H���A�u���X�ɐ��N����Љ�I�Ȏ�������ɂ��Ă��̗l���Ɩ{���𑬂��܂��[�����O�ɓ`�����ƁB�܂��A���̍�Ƃ������Ȃ��\���}�̂������Ă����v�B
���̒�`�ɏƂ炵�Č��݂̃}�X�R�~���ǂ��]������Ηǂ��̂ł��傤�H�@�����̃��f�B�A������܂����A�����ł͎�Ƃ��ĐV���ƃe���r�̃j���[�X�E�ԑg��ΏۂƂ��܂��B
��L�̒�`�ɏƂ炵�ċC�ɂȂ�̂́A�u�{����[���v���O�ɓ`���Ă��邩�Ƃ����_�ł͂Ȃ��ł��傤���B���������W���[�i���X�g���u���l�����͉���B���������Ă��̐E�Ƃ�I��ł���̂ł��傤�H�@���͂ւ̂��ڕt�����A�����̒m�錠���̗i��A�B���ꂽ�^���̔��@�Ȃǂ��̓��@�͗l�X�ł��傤�B
�ł����_�̈Ⴂ�͂����Ă��A���ɂ̓t�F�A�ŏZ�݂悢�Љ�Â���ւ̍v����ڎw���Ă���͂��ł��B�z������ɁA�W���[�i���X�g�͓����͗��z�ɔR���āA���������̖��ӎ��Ɋ�Â��ĐE���Ɏ��g��ł����͂��ł��B�������Ȃ���A�����o�����ɑg�D�̗v���␢�̒��̃j�[�Y�Ǝv���������ɔ������Ă����Ȃ��ŁA���S���牓�����ꂽ�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤���B
�m���ɂ��炵�����������Ă���W���[�i���X�g�����܂����A���̂Ƃ��Ă݂����f�B�A���A�{�����f�B�A�Ɋ��҂���Ă���������ʂ����Ă��邩�Ɩ����A��������������Ȃ�l�������悤�ȋC�����܂��B�`�[�v�Ȑ��`���A���ۂ̕\�ʂ������Ȃ������A��т��Ȃ��咣�A�������͕Ό����������B�����̏ꍇ�A�u�{����[���v����͉����悤�Ɋ����܂��B
�Ƃ�킯�e���r�̃j���[�X�E�ԑg�̃��x���̒Ⴓ�ɂ́A����������������܂��B���́A���f�B�A�͈�x���_�ɕԂ��Ď��������̊����̖ړI���m�F���ׂ����Ǝv���Ă��܂��B��m���Ŗ��ӔC�ȕ]�_�����ł��Ȃ��l���������̏����̏���Ȕ������J��Ԃ��Ă���̂�����ɂ��A�������肵�܂��B
�ŏ��ɏq�ׂ��悤�ɁA���f�B�A�̋��ɂ̖ړI�̓t�F�A�ŏZ�݂悢�Љ�Â���ɍv�����邱�Ƃɂ���͂��ł��B�����u�ɍ������Ȃ������͐����͂��������܂���B�e���r�́A���̋��߂���V���ƈ���āA�e�[�}��I�肵������@�艺���ē`���邱�ƂɌ��������f�B�A�ł��B���̍��ɂƂ��đ�ȃe�[�}����������Ƒ��ʓI�ɕ��͂��A�����Ɍ��_�ł͂Ȃ��l����ޗ���^���邱�Ƃ��ł���͂��ł��B
�e���r�̃j���[�X��ԑg�����Ă��ċC�ɂȂ�̂́A��O�Ɍ}�����A�����h�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��邩�̂悤�ȐȐ���̕��������Ƃł��B�������A���������C�ɂ��đ�O�̋��߂Ă�����̂���悤�Ƃ������ʂł���Ȃ�A���O���̂��̂ɖ�肪����̂����m��܂���B�������Ȃ��璮�O�̖��ӎ����Ⴂ�̂ł���A���̎��ׂ����ӎ������N���邱�Ƃ����f�B�A�̐Ӗ��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���ړI�ӎ����������ᔻ�A�l���Ɩ{���𑬂��[��
�ŋ߂̃��f�B�A�����Ă���ƁA���X�ɂ��Ď��̌��͎҂���҂�ᔻ���邱�Ƃ����ȖړI�����Ă��܂��A������z���グ�悤�Ƃ̎��_���ɂȂ��Ă���悤�Ɋ������܂��B
�ᔻ���_��ے肷��C�͖ѓ�����܂��A���͂͂��̗��p���Ď������ׂ����Ǝv���Ă��܂��B��Ȃ��Ƃ́A���̂��߂̔ᔻ�Ȃ̂����\���l����������ŖړI�ӎ�����������Ǝ����Ƃ��Ǝv���܂��B�Ԉ���Ă��A������������������A�i(�˂�)�݂⎹(����)�݂Ƃ��������Ȋ���ɂ����˂����肷��悤�ȕł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
���������鑤����̊�]�������A���f�B�A�̍L���l�b�g���[�N��ʂ��Ē��O��ǎ҂̒m��Ȃ����Ƃ��L���m�炵�߁A�[�ւ��Ă���邱�ƁB���������ď������l����ɂ������Ēm���Ă����ׂ����E�̓����ɂ��čL���[�����Ă���邱�ƁB���{���P�������邽�߂Ɏ��g�ނׂ��ۑ�̎w�E�ƁA�����̉ۑ�ɂ��čl���邽�߂̍ޗ�����Ă���邱�ƁB���X�̐����̒��ŖY�ꂪ���ȃ}�N���I�Ȏ��_�����Ă���邱�ƂȂǂł��B���ꂱ���A���X�ɐ��N����Љ�I�Ȏ�������ɂ��āA���̗l���Ɩ{���𑬂��܂��[���`���Ăق����̂ł��B
���{�̐V����ǂ�ł��Ďv���̂́A�������E(����)�̋����ƕω��̏��Ȃ��ł��B���E�͑傫���ϗe���悤�Ƃ��Ă��܂��B�f7(8) ����f20�A�����č���f�[���̐��E�ƕ]����Ă��܂��B2050�N�ɂ͐l���卑�g�b�v10�ɂ͐�i���ł͕č��������c��A���̑��̓A�W�A��4�J���A�A�t���J��5�J�����߂錩���݂ł��B
���R�����͌��܂�Ȃ��Ȃ�܂��B���E�����g�g�݂��傫���ϗe���Ă��Ă���̂ɁA�������̏펯�͂��܂��f7�̐��E�ɂƂǂ܂��Ă��邩�̂悤�ł��B
�V���́A���̎���ɂӂ��킵���A�V���ȃO���[�o�����_�Ő��E�ƑΛ�(������)���A�V��������ŕ��邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B�܂��A�͋q�ϓI���t�F�A�ł���ׂ����Ǝv���܂��B
�����Ȃǂ͊i�D�̎���ł��B���̑卑�Ɋւ���ɂ͑傫�Ȃ��������܂��B�����ׂ�����̕����邩�Ǝv���A���炩�ɖь������Ă��邱�Ƃ���ӂɌ����������܂��B
�����v���ӎ����A�����𑽖ʓI�ɓ`����
��Ȃ��Ƃ͎����𑽖ʓI�ɓ`���邱�Ƃł��B���̍��͊m���ɐ��E���̌o�ϑ卑�ɂȂ�܂����B���̈���ň�l������̍��������͖�6000�h��(���E88��)�ŁA�g���N���j�X�^���ƃi�~�r�A�ɋ��܂�Ă��܂��B
�Ƃ��낪1���~�ȏ�̎��Y�����l����������5000���l���܂��B�l����ɂ���Ƃ����������Ƃ͂���܂��A��ΐ��ł͓��{�̐l���̖��̐l���������ɂ��̂悤�Ȏ��Y���x���ɂ���Ƃ������Ƃł��B
�܂��A20�N���O����č��̑�w�@�ɖ��N500�l�ȏ㗯�w���Ă���悤�ł��B���̒~�ς͏��X�ɒ�����Ƃ̌o�c�͋����Ɍ��т��Ă������Ƃł��傤�B���̂悤�ɎЉ�̂���悤�́A���܂��܂Ȏ��_��������Ƃ炳�Ȃ����Ƃɂ͑S�̑����c���ł��܂���B
���Ẵ��f�B�A�����Ă���ƁA���̌��͂⌠�͎҂ɂ͐₦���Ď��̖ڂ������Ȃ�����A�_���̃x�[�X�ɂ͍��v���������Ă���悤�Ɏv���܂��B���₵�������{�̃W���[�i���Y���ł������A���{�̍��v���ӎ����Ȃ����Ƃ͂��肦�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
���́A�u���S�Ȋ�@�ӎ��v�Ƃ������t���D���ł��B�����́A�l�ԎЉ�̏����ɂ��Ċ�@�ӎ������ׂ��ł��B�������A���̊�@�ӎ��͍L���W�߂�ꂽ�����Ɋ�Â����S�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�܂���B
�ꍑ�̎��X�̃��[�h(�C��)�ɗ^���郁�f�B�A�̉e���͂͐r��ł��B�Љ���S�ł��邽�߂ɂ͂��������A�Љ�̋C�����|�W�e�B�u�ł��邱�Ƃ��d�v�ł��B�ǂ�Ȏ����ے肩�����̂ł͂Ȃ��A�z���グ�鐸�_���K�v�ł��B
���{�̓O���[�o���Ȍq����Ȃ����Ă͐��������Ȃ��h����w�����Ă��܂��B���{���ĂыP�����߂Ƀ��f�B�A�̉ʂ����ׂ������͌��t�ɕ\���Ȃ��قǑ傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����ꂩ�狁�߂���W���[�i���Y���̂�����ƐV�����\���@2015/1
|
�����A�h�Ђɂ��čl����ɂ������āA���������Ƃ̂ł��Ȃ����̂��u���v�ł��B�ҏW�ҁA�W���[�i���X�g��NPO�@�l�X�^���o�C�����ł�����]���W���N����ɁA�h�ЂƃW���[�i���Y���ɂ��ĉ��߂Ă��b���������������A�Ƃ����̂�����̌��e�ł��B��_�W�H��k�Ђ���20�N�A�����{��k�Ђ���5�N���o�Ƃ��Ƃ��Ă��鍡�A�W���[�i���Y���̐�[�́A�����ɉ����������Ă���̂��B�l����܂��A���������u�s���v�Ƃ��āA������ƍl���Ă����������b�ł��B
����̕ω��ƂƂ��ɁA�W���[�i���Y���ɋ��߂��Ă���������ω����Ă��Ă��܂��B�����{��k�Ђ�ʂ��āA���̗���͂����������悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���܉��߂āA�W���[�i���Y�������̒��ɂł��邱�Ƃ͂Ȃɂ��B�k�ЂȂǁA���\�L�̏o���������������ɁA���ꂩ��̖����ƃW���[�i���Y���̂�����ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B
���W���[�i���Y���ɋ��߂���v������m��
�n�k�A�Ôg�A�䕗�ȂǁA����܂œ��{���P���Ă������܂��܂ȍЊQ������܂��B���̒��ł��A�k�Ђ͓˔��I�ɋN���錻�ۂ̂��߁A�䕗�̂悤�ɗ\�������đΉ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��o�������Ƃ������Ƃ́A�݂Ȃ�����������Ă��邱�Ƃ��Ǝv���܂��B�W���[�i���Y��������܂ōs���Ă������g�݁A�����đ����̐l���������҂��邱�ƂƂ��āA��_�W�H��k�ЂⓌ���{��k�Ђɑ�\�����悤�ȑ�K�͂Ȑk�Ђ���A�e�n���P���^����y���ЊQ�Ȃǂ̂悤�ɁA���܂��܂Ȕ�Ђ̌���ɂ����āA���n�̗l�q��v���Ő��m�ȏ��M���邱�Ƃ����߂��Ă������Ǝv���܂��B���n�̗l�q���Ԃ��ɔc�����邱�ƂŁA�����̏������Ƃɂ����Ή�����u���邱�Ƃ��ł��A���̂��߁A�W���[�i���X�g�͌��n�ɐ^����ɓ���A���Ɋ댯�Ȍ��n�̋M�d�ȏ���͂��������S���Ă��܂����B
�܂��e���r��V������ȏ����������ɂ����ẮA����ɓ����ď������W���A���M���������S���l�����͏��Ȃ��A�W���[�i���X�g�����̊���̏�͍L�����݂��Ă��܂����B�������A�ߔN�ł�SNS�̐Z���Ȃǂɂ���āA������l�����M���邱�Ƃ��ł�(�������A���ʃf�}�Ȃǂ��L����\��������)�A���ԂƐv�����Ƃ������_�ɂ����ẮA����̓����҂ɂ�锭�M���d�v�ɂȂ��Ă��܂��B���̂��߁A�l�̏�e���V�[��\�[�V�������f�B�A���p�Ƃ��������Ƃɒ��ڂ𗁂сA�l�̏�M��ʂ����V�������̂�������N���n�߂Ă��܂��B
�܂��A���m���Ƃ����_�ɂ����ẮA�I�[�v���f�[�^�ƌĂ����̓������Ǝ��R�ȃf�[�^���p�𐄐i���铮�������E�ŋN���Ă���A���{�ł������̂▯�Ԋ�Ƃ��������Ȃ���A�f�[�^�̌��J��f�[�^���p��͍����铮�����N���Ă��܂��B���̍���ɂ́A�I�[�v���K�o�����g�̍l�����ɂ���悤�ɁA�I�[�v�����̐��i�Ǝs���ƍs�����Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������s���A���m�ȏ������甭�M���A�s���ɂ��\���I�Ȑ����Q����܂��Â���ւ̈ӎ��̌�����s�����Ƃ��ړI�Ƃ���Ă��܂��B
������������̕ω��ɂ����āA������Ƃ����ăW���[�i���X�g�����̋��ꏊ���Ȃ��Ȃ����Ƃ����킯�ł��Ȃ��A��͂肻��ł��v���ȏ��̔��M�Ƃ����Ă��A�����ǂ̂悤�ɓ`���悤�ɔ��M���邩�A�܂����n�̋��͎҂��ނ��s����ł̃l�b�g���[�N�Ƃ����ڂɌ����Ȃ����l������Ă��郁�f�B�A��W���[�i���X�g�����̊���Ƃ��̉e���͂͑傫���Ƃ����܂��B
�����̃A�[�J�C�u�̏d�v���Ə��v
�������A�v������m���Ƃ��������̍���������W���[�i���Y���ł͂���܂���B�ЊQ�́A�N����������d�v�ł����A�N�����o�����ɑ��Ăǂ̂悤�ɑΏ����A���̌�ǂ̂悤�ɗ��������Ă������𖾂炩�ɂ��Ă����p������A���ɂ��̑Ή���ɂ��Ĕᔻ������Ď��I�@�\���u���邱�Ƃ��d�v�ł��B�܂��A���̑��������N�≽�\�N��������悤�Ȃ��̂������A�n���ȍ�Ƃ̐ςݏd�˂��s��Ȃ�������܂���B
���ɁA�p�����͂��ꂩ��̃W���[�i���Y���ɂƂ��Ă��K�v�s���Ȃ��̂ƌ�����ł��傤�B�Ⴆ�A�����{��k�ЂŔ�Ђ����l�����̏،��𒆐S�ɁANHK�����k�ЂɊւ��f�������Ƃɂ��̎������N���A�l�X���ǂ��s���������A�����̂��߂ɂǂ����g��ł������A�Ƃ������������܂Ƃ߂��uNHK�����{��k�ЃA�[�J�C�u�X�،�Web�h�L�������g�v������܂��B���̃T�C�g�́A���܂ł��،��f���╜���f�����A�b�v�f�[�g�������Ă���A�Ƃ��ɐk�Ђ��玞�Ԃ����قǂɁA�������͂��̋L������Y��Ă��܂������ɂȂ��Ă��܂����̂��A���X���J�Ɏ�ނ��A�`�ɂ��Ă����Ă����̎��g�݂ƌ����܂��B
���ʂ̐l�ɂƂ��āA��͂�k�Ђ��N��������́A���̌��ꂪ�ǂ��Ȃ��Ă���̂��A�ǂ��������Ă����̂��A�Ƃ������Ƃ��ӎ����܂��B�������A�A���߂���ΔM����Y���ł͂Ȃ��ł����A�N�������i�̓���Ɏ���ɖ߂��Ă����ɂ�āA���܂��ɂ�����������̗l�q�͖Y�ꋎ���Ă����̂������B�������A�W���[�i���X�g�ɂƂ��Ă��������ߋ��̏o��������u�����܂܂ɂ��Ă������Ƃ͂ł��܂���B�ߋ��ɋN�����o������������ƌp�����Ď�ނ��邱�Ƃ́A�q�ϓI�Ȏ�����ςݏd�ˁA�����̎��_�ʼnߋ���U��Ԃ������ɂ��̏�łǂ����������Ƃ��s���Ă������̂�����������Ƃ��ɕK�v�ȍޗ��𑵂��Ă������Ƃł�����A���̋q�ϓI�ȏo�������Âɕ��͂�����p�ӂ��邱�Ƃł�����̂ł��B�܂�A�W���[�i���Y�����������̖{���͐v������m�������ł͂Ȃ��A���̌p�����ɂ���ċN����A�[�J�C�u�ɂ����Ӗ�������̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͍l���܂��B
�Ⴆ�A��s��w�����y�����ŏ��A�[�L�e�N�g�̓n糉p�����́A�����{��k�ЂŋN�����k�Ђ̔�Q�����Вn�̎ʐ^��p�m���}�摜�A��Ў҂̏،��Ȃǂ����Ƃɉ������A�ЊQ�̗l�q�𐢊E�ɓ`����f�W�^���A�[�J�C�u�u�����{��k�ЃA�[�J�C�u�v���J������Ă��܂��B���ɂ��A�u�L���A�[�J�C�u�v��u����A�[�J�C�u�v�ȂǁA�����̔�Q�ɂ������l�����̏،��Ȃǂ����ƂɁA���̎������������̂��J�ɕR�����A�`�ɂ����Ƃ��s���Ă��܂��B���������Z�p�����Ƃɂ������g�݂��A��̃W���[�i���Y���Ƃ��Ă݂邱�Ƃ��ł��܂��B
����܂ŃA�[�J�C�u�����ʂ̏��ł����ł��Ȃ��������̂��A�f�W�^���Z�p�ɂ���Ă�������̂��f�[�^�����邱�Ƃ��ł��A����ɂ���Č�������Q�Ɖ\���������A���l�b�g��ʂ��Đ��E�̂�����������W���A���������₷���Ȃ����ƌ����܂��B�܂��A�W�܂����f�[�^���������̂܂܌�����̂ł͂Ȃ��A�ǂ̂悤�ɓ`���悤�Ȍ`�ɂ��邩�Ƃ������ꂩ��A�f�[�^�r�W���A���C�[�[�V������A�f�[�^��ʂ��Ă���܂ŋC�t���Ȃ������������@��N�����f�[�^�W���[�i���Y���Ƃ������������o�Ă��Ă���̂��A�f�[�^��A�[�J�C�u�ɂ���ĐV�������̉��l�����o�����Ƃ��铮���̈�ƌ����܂��B
���̂Ƃ������N�����̂��A���̂Ƃ��N���ǂ�ȍs�����s�������B�s�����s�ׂ��ǂ��������e�����y�ڂ����̂��Ƃ��������ƂJ�ɕR�����Ă������ƁB���Ƃ��N����Ƃ������ł͂Ȃ��A���Ƃ��N����O�̗l�q�A�����Ă��Ƃ��N������̗l�q���A�������Ԏ������ƂɈ�A�̃R���e�L�X�g�܂������̏W�ς��s���Ă������ƁB�����āA�����̏��������ł������̐l�����ɓ`�����߂̏�M�̃f�U�C�����s�����Ƃ��A����܂��܂����߂��Ă���ł��傤�B�V����G���Ȃǂ̎��̃��f�B�A�A�u���O�Ȃǂ̃E�G�u�}�́A����ɂ́A�u����[�N�V���b�v�A�g�[�N�Ƃ��������A���ȏ��ʂ������M�ȂǁA���܂��܂Ȍ���ɂ͂��܂��܂ȃ��f�B�A�����݂��܂��B���푽�l�ȃ��f�B�A��ʂ��āA����̏��A����ő̌��������܂��܂ȏ�����₷���`���邽�߂ɁA�C���^�[�t�F�C�X�Ȃǂ̏�M�̃f�U�C����A���v���̂��̂��l���邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B�����ɁA�W���[�i���Y�����ł��邱�ƁA�W���[�i���Y���ɂ����ł��Ȃ����Ȃ����������Ƃ����܂��B
���W���[�i���Y�����S�����Ȃ�\��
����܂ł́A����͂����̂Ƃ��ẴW���[�i���Y���ł��������̂��A����̈ڂ�ς��ƂƂ��ɐv������m�������ł͂Ȃ��A�p�����Ƃ���ɂ�����A�[�J�C�u�A����ɒ~�ς��ꂽ����`���邽�߂̏��v���d�v���Ƃ܂Ƃ߂Ă��܂����B
����܂ŁA���f�B�A��ʂ��Ď�����`����Ƃ������Ƃ����߂��Ă������̂���A������m���i��SNS�ȂǑ���ɂ킽����̂��łĂ��Ă��邩�炱���A�W���[�i���Y���͏���`���`�ɂ��邱�Ƃ����܋��߂��Ă��܂��B�������A���ꂾ���ł͂Ȃ����̎��̂�������A�����Ɍ������Ă����Ȃ�������܂���B�܂�A���ꂩ�猩���Ă����ۑ�ɑ��āA�ۑ���ۑ肾�Ɠ`���邾���ł͂Ȃ��A�����Ɍ���������Ă������Ƃ����߂��Ă��Ă��܂��B��������`���邾���ł͂Ȃ��A���̏����l�������g���ۑ�ɋC�Â��A�s�����A�����ĉۑ�����ւƌ��������߂̃A�N�V�����𑣂����݂Ƃ��Ẳ\���������ɂ͂���܂��B
�ǂ�ȏ����A�N�ɂ��m���Ȃ���ΈӖ����Ȃ��悤�ɁA���̏������ƂɐS�����ꂽ��A�����̃A�N�V�����̃q���g�ɂ��Ă�������肵�Ȃ���ΈӖ��͂���܂���B�ЊQ�������ۂɁA�������̂ɑΏ����邾���ł͂Ȃ��A���ɗ������ɑ��v�Ȃ悤�ߋ�����w�сA���ւ̋��P�Ƃ��邽�߂̒�Ă����߂��܂��B���̂��߂ɂ��A�W���[�i���X�g�͏��̔c���⎖���̒~�ς݂̂Ȃ炸�A�ł����ɐG��Ă��闧�ꂩ��A���ɂǂ��������ł��邩�A���܂ł��邱�ƁA���ꂩ�炷�ׂ����ƂƂ��������̂M���Ă������Ƃ����߂��Ă��܂��B
�����̖��ւ̔ᔻ���Ă����ł͂Ȃ��A�ۑ���������Ă���l�������x�����A���Ƃ����c�[�����g���đ����̐l����������A�l���Ȃ����肷������������ɂ͂���ł��傤�B�������A�ᔻ���Ă̍ۂɕK�v�Ȃ��Ƃ��āA�l��ᔻ����̂ł͂Ȃ��V�X�e����d�g�݂ɑ��Ĕᔻ�����邱�Ƃ����͏d�v���ƍl���Ă��܂��B�W���[�i���Y�����l��ӂ߂�̂͊ȒP�ł����A�l�͊���d�g�݂ɂ���Đ��������邵�A�悭���������e���������ω����Ă������́B�{���I�ȉ�������������߂ɂ́A�V�X�e����d�g�݂ɑ��Ĕᔻ���A���P�����ׂ����ƍl���܂��B
���������A����N��ۑ�Ɍ�����������̒�ĂȂǁA������ݍ��W���[�i���Y���̌`�́A�C�O�ł̓\�����[�V�����W���[�i���Y���ƌĂ�Ă��܂��B�\�����[�V�����W���[�i���Y���Ƃ������쎩�̂͋c�_���n�܂�������ł����A����`���A�`�ɂ��A�~�ς��Ă��������ł͂Ȃ��A�����̐l�����̉ۑ�����Ɍ������A�N�V�����𑣂��Ƃ������A���̐�ɂ���ۑ�����ɑ��ăW���[�i���X�g�̗��ꂩ��ł��邱�Ƃ͂܂��܂���������ƌ����܂��B
�������ւ̃A�N�V�����Ƃ����Ӗ��ł́A�n��̉ۑ�����������ʼn�������c�̂ł���A�����g�������Ɍg����Ă���Code for Japan�Ȃǂ�����܂��BIT��e�N�m���W�[��ʂ��āA�s���̗͂Œn��̉ۑ�����𑣐i����V�r�b�N�e�b�N�Ƃ����l��������A����Ɏs���ƍs���̋��n�����s�����Ƃ������̂ŁA���コ�܂��܂Ȏ����̂�n��R�~���j�e�B�̃��[�_�[�����ƃR�~���j�P�[�V�������s���Ȃ��犈�����s���Ă��܂��B�ނ�̂悤�ȃ��[�J���Ȋ������W���[�i���X�g�������������A�Ƃ��ɂ��܂��܂ȏ���ނ�ɒ��A�������Ȃ���ۑ�����Ɏ��g�ރA�N�V�������s�����Ƃ����߂��Ă���ł��傤�B
�V�r�b�N�e�b�N�̂悤�ɁA�s�����Œn��̉ۑ����������̂Ɠ��l�ɁA�s���̗͂ŃW���[�i���Y������āA�����������g�ŏ��M���Ă����V�r�b�N�W���[�i���Y������Ă邱�Ƃ����߂��Ă��邩������܂���BSNS�̐Z���ɂ���ĒN������M�Ɍg���鎞�ゾ���炱���A��M�̂��߂̂���͂�A��e���V�[�̏����A�W���[�i���X�g�����ł��m�邱�Ƃ��ł��Ȃ����[�J���ȏ����s�����g�œ͂���n�C�p�[���[�J�����f�B�A�̊����ȂǁA���܂��܂Ȏ��g�݂��������l�l���s�����Ƃ����ꂩ��͋��߂��Ă��܂��B
����Ɍ����A���܉��߂čl����ׂ��́A�W���[�i���Y������Ă�͎̂������s���̈ӎ����ƌ������Ƃł��B�ǂ�ȂɃW���[�i���X�g�������u���������������Ă��Ă��A�ނ�̎��Ԃ�̗͂������ɂ���킯�ł͂���܂���B�ŋ߂ł̓��f�B�A�r�W�l�X���̂��̂̓]���ɂ��Ă��ƊE�ɂ����ĔM���c�_�����킳��Ă���A�W���[�i���X�g�������g���ǂ̂悤�ɎЉ�ƌ��������A�ǂ����������A�����ĎЉ�̂��߂Ɋ������Ă����̂��A�����ăr�W�l�X�Ƃ��ē��X�̐����̗Ƃ��x���邽�߂̓y��Â��肻�̂��̂��l���Ȃ�������Ȃ�����ł�����܂��B���������A�Ȃ��肪�ł��₷�����ゾ���炱���A����܂Ŏ������ɂƂ��ē�����O���Ǝv���Ă������Ƃ������̂��ꎩ�̂J�ɖa���A�͂��Ă����W���[�i���X�g�������������s�����]�����A�������A�T�|�[�g���Ă��������W��z�����Ƃ��K�v�ł��B�����������́A�Ⴆ�N���E�h�t�@���f�B���O�̂悤�Ȏ��������̃v���b�g�t�H�[����ʂ��������x���ȂǁA���܂��܂ȕ��@���l�����܂��B
�W���[�i���X�g�̐l�����ɂƂ��Ă��A�N�����������������M�������ɂ���ėL�Ӌ`���Ɗ����Ă��炦�邱�Ƃ�������炱���A�����̐l�����̕]���≞�����ނ�̊����̑傫�ȗƂɂ��Ȃ�̂ł��B�����ɁA�W���[�i���Y���Ƃ������݂́A����܂Œm�邱�Ƃ��Ȃ����������A�Ƃ��ɉB�����ꂪ���Ȗ����肾�Ɖ������A�Љ�ɑi���銈���ł���A�������s�����Љ�̂Ȃ��ł����Ă����̎�i�ł�����܂��B���̎�i���u���Ȃ���A�Љ�̂��܂��܂Ȗ����������A�ۑ���Ă��A�����Ɍ������A�N�V�����𑣂��d�v�ȑ��݂Ƃ��ăW���[�i���X�g����������Ƃ������Ƃ�F������K�v������̂ł��B
�k�Ђ����������ɁA�����Ď���̕ω��ƂƂ��ɃW���[�i���Y���Ƃ������݂��̂��̎��̂��₢������Ă��錻��ɂ����āA�������l�ЂƂ�ЂƂ肪�W���[�i���Y���𗝉����A�W���[�i���Y�����Љ�ɂƂ��Ăǂ̂悤�ɋ@�\���A�ǂ̂悤�Ȗ�����S���Ă���̂��B���܉��߂čl���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă��Ă���̂ł��B
���Ō�ɁB
�ȑO�A�Ƃ���d���œ����̖n�c�����ނ���@�����܂����B�n�c��͕��i�Ȃ��Ȃ������^�Ȃ��l�ɂƂ��Ă͉����Ȃ��ꏊ��������܂��A�n�c��Ƃ����ꏊ�́A�����ł������Ȃ��A���܂����Ă̏��a�̌`���c���Ă���ؑ����W�s�X�n�������G���A�ł��B�����������́A����ɂ����Ă͉��Ă�k�Ђɂ�����|��̊댯���Ȃǂ���A�댯�ȊX�����L���O�Ƀ����N�C������X�Ȃ̂ł��B���̔��ʁA�X���댯�Ƃ������Ƃ��斯���炪���o���Ă��邱�Ƃ���A����Ȃ��Ƃɓs���ōł��h�Јӎ��������n��Ƃ��āA�Ǝ��̖h�ЌP����X�̂�����ꏊ�Ŗh�Б���s���Ă���X�ł�����܂��B
�ł͂Ȃ�����Ȗؑ����W�s�X�n���c���Ă���̂��B����́A���Ă̊֓���k�Ђ̖��c������ł��B�֓���k�Ђ̔�Ќ�A�����𗧂Ē������Ɠ����̓�����b�ł���㓡�V�����͒�s�����@��ݒu���A�k�Ђɋ����ߑ�̂܂��Â���̓s�s�v��𗧂��グ�܂����B�������A���Δh�ɉ������A����ɓ��t���U�ƂƂ��ɂ��̌v��͓ڍ��B��s�����@�͉�̂���Ă��܂����̂ł��B
���̌�A��s�����@�̌���p���������ǂɂ���Č㓡���̌v��̈ꕔ�͐��i����A�\�Q���q���Y(���Ă̓�����A�p�[�g�́A�����̕s�R�S�؋؏W���Z��v��̈��)��l��������������Ƃ������ߑ�I�Ȍ����Βn�ɂ����ꏊ�A���a�ʂ������ʂ�A�����ʂ�Ƃ��������Ėh�~�̂��߂̍L�����H���݂ȂǁA���Ă̕������Ƃ̎Y���̈ꕔ�����܂��c���Ă��܂��B�������A�v��͈ꕔ�������s���ꂸ�R�̎艈���̓���������搮��������Ȃ��������Ƃ���A�R�̎艈���O�ɂ͖��v��Ƀo���b�N�����Ă�ꂽ�܂ܓs�s�J�����s���A���̌��ʖؑ����W�s�X�n�Ƃ��č������̗l�q���`����Ă���̂ł��B
�ł́A���߂Č㓡�V�����f���������v��A�s�s�v��Ƃ͂Ȃ����̂��B����������x�R�������ƂŁA�����̐k�Ђɑ���V���Ȃ܂��Â���̃q���g�ɂȂ邩������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��ŋߍl�����肵�Ă��܂��B���ɂ��A���j��R�������ƂŁA���܂��܂Ȗh�ЁA�k�Б�̉ߋ��̎��g�݂����邩������܂���B�܂��A���삪�ς��Ζh�Ђɑ��鎋�_���ς���Ă��܂��B���܂��܂ȕ���̐l�������m�b���i��A�A�C�f�A�������A�����čs������B���f�B�A�́A���̗l�q���Ԃ��ɔ��M���A���ɃT�|�[�g���Ă����B���ꂼ��̖��������ƂɁA�Ƃ��ɍl���A�Ƃ��ɂ���܂��Â����ڎw���A���g��ł������Ƃ��A���ꂩ��̎Љ�ɂƂ��đ傫�ȈӖ��������Ă��܂��B
����͂܂�A���ꂩ��̂܂��Â����s�s�Â���̈�̂��������ł���A�Ђ��Ă͂��ꂪ�h�Ђ⌸�ЂɂȂ�����g�݂ł�����܂��B���Ƃ�������ɐ����鎄���������炱���A�܂���s�s�ɑ��Ăł��邱�Ƃ��l���A�s�����A���������ō��グ�Ă����V����������z���グ�Ă������Ƃ���Ȃ̂ł��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���l�b�g����ɂ�����u�W���[�i���Y���v�̖����Ƃ� 2015/10 |
�p���̍��c����BBC�̎P���ŁA�j���[�X�T�C�g�uBBC.com�v�̉^�c�ƁA���E�e���ւ̃j���[�X�f���uBBC���[���h�j���[�X�v�̔z�M�����Ă���BBC�O���[�o���j���[�X���~�e�b�h�́A10��������{��Ńj���[�X�T�C�g�uBBC.jp�v���J�n�����B10��15���ɃT�[�r�X�J�n�ɂ��킹�����\��J�Â���A���Ђ�CEO�ł���W���E�C�[�K���������������B
�����{��ŃE�F�u�T�C�g�J�݂̔w�i�ɁA���ۏ�ւ̊S�̍��܂�
BBC.jp�́A���ۖ��A�r�W�l�X�A�G���^���A�e�N�m���W�Ȃǂ̘b��ɉ����A���E100�J���ɓW�J���Ă���L�ҁE���h�������M����j���[�X��|�[�g�A�b�萫�̍����g�s�b�N�X�ȂǁABBC.com�Ɍf�ڂ����L���̒�����A���{�����ɂ����ĊS�̍����b��𓌋��̃G�f�B�^�[���I�肵�A�|��E�ҏW�����L����r�f�I�R���e���c���f�ڂ���B�ҏW���ɂ́A�����V���L�ҁA���A�{���E���ACNN���{��ŃE�F�u�T�C�g�ҏW�ҁAgoo�j���[�X�ҏW���Ȃǂ��C���������S�q�����A�C����B
����܂�BBC�́A���{�ɓ��h����W�J���ē��{�̐����o�ς��͂��߂Ƃ���j���[�X�𐢊E�ɔ��M���Ă����ق��A20�N�ȏ�ɂ킽��BBC���[���h�j���[�X����{�̎����Ҍ����ɕ������Ă����B���̃^�C�~���O�œ��{��ŃE�F�u�T�C�g���J�n����̂͂Ȃ����B�C�[�K�����́A���\��̈��A�ŁA���{�ɂ����鍑�ۏ�ɑ���S�̍��܂���������B���Ђ����{�l��ΏۂɎ��{�������E��ւ̊S�ɂ��Ă̒����ɂ��ƁA�u�������Ȃ��v�Ɠ��������{�l�͂킸��3���ŁA4����3���u�S�͋����Ȃ��Ă���v�Ɠ������Ƃ����B
�u���ۖ��͍������Ƃ��Ă����ĂȂ��d�v���𑝂��Ă���B���{�̐�����Y�ƁA�����Đ��E�Ƃ̊W���A���E�̎����ҁE���[�U�[�ɂƂ��ĈӖ��̂�����̂ɂȂ�Ɠ����悤�ɁA���{�ł͌��N��o�ρA�e�����Y���A�ږ��Ȃǂ̐��E�I�Ȗ��ւ̊S�����܂��Ă���B���̌��ʁA�����̍����j���[�X��n��j���[�X�Ƃ��킹�āA���ۃj���[�X��������悤�ɂȂ��Ă����v�ƃC�[�K�����͌��B
���łɉp��T�C�g�ł���BBC.com�ւ̓��{����̃A�N�Z�X�͌���800��PV���L�^���Ă���B�܂����{�l�ɂƂ��Ẵj���[�X�\�[�X���e���r�E���W�I����E�F�u�ւƑ傫���V�t�g���Ă��邱�ƁA���Ƀ��o�C�������p�����j���[�X�������g�債�Ă��邱�ƂȂǂ�w�i�ɁA�N���̓��{��YouTube�`�����l���A���{��Ō���Twitter�̊J�݂ɑ����A���{��ŃE�F�u�T�C�g�̊J�݂ւƎ������Ƃ����B
����́ABBC�̊����`�����l����ʂ����v�����[�V�����A�\�[�V�������f�B�A�̊��p�A�����đ��j���[�X�v���b�g�t�H�[���Ƃ̋��ƂȂǂ�����ɓ���ēǎ҂̊l����i�߂�Ƃ��Ă���B�E�F�u����Ȃǂ����p���ăj���[�X�̔w�i���@�艺����ȂǁA�l�b�g�Ȃ�ł͂̕t�����l����j���[�X����Ă��������l�����B
���g�N�ł��L�҂ɂȂ�鎞��h�Ƀv���̃W���[�i���Y�����S������
�ߔN�A�j���[�X����芪�����͂߂܂��邵���ω����Ă���B�C���^�[�l�b�g���l�X�ɂƂ��ďd�v�ȏ��擾�̎�i�ɂȂ�ASNS��X�}�[�g�f�o�C�X�̔��W�ɂ���ĒN�ł��������̍������M�ł���悤�ɂȂ����B�C�[�K�����́u�f�W�^���Z�p���g���ΒN�ł��g�L�ҁh�ɂȂ邱�Ƃ��ł��A�N�ł��j���[�X�������������M���邱�Ƃ��ł���B�ڂ̑O�̏o�����������Ƃ����Ԃɐ��E���ɓ`������悤�ɂȂ����v�ƕ\������B
�����������ɂ����āA93�N�Ƃ������j����@�ւł���BBC�́A�@�ւ̑��݈Ӌ`�ɂ��Ăǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��낤���B�C�[�K�����́A���������j���[�X����芪�����܂��܂Ȋ��̕ω��̒��ŁA�u����ł��v���̃j���[�X��Ƃ̑��݉��l�͂���ƁA���������Ă���BBBC�̓j���[�X����ɂ����ĐM���ɑ���郊�[�_�[�I�Ȓn�ʂ��ێ��ł���v�Ǝ��M�������Č�����B
�uBBC ��1922�N����A�D�ꂽ�ɐs�����Ă����B�����Ȃ鍑�Ƃ�{������Ɨ����āA���̒��ŋN�������Ƃ����������m�ɓ`���邱�Ƃɐs�͂��Ă����B�V�����Z�p�ɂ���ĒN���������̈ӌ���\���ł���悤�ɂȂ�A�w�v���p�K���_�x�Ɓw�����x�̋��E�������܂��ɂȂ��Ă���B���̒��ŁA�����҂ɂƂ��Ė{���ɒ����E�����ł���A���ꂼ�ꂪ���f�ł���悤�Ɏ菕������j���[�X����@��Ƃ����̂́A���܂ňȏ�ɏd�v���𑝂��Ă���BBBC��ݗ��ȗ��x���Ă������l�ς́A�f�W�^���̐��E�ɂ����Ă���܂łƓ��l�A���邢�͂���܂ňȏ�ɑ厖�Ȃ̂��v(�C�[�K����)�B
���j���[�X�Ƃ́u�����v�ł���A���f�B�A�̖����͂���𗝉����ē`���邱��
�C���^�[�l�b�g�ƃX�}�[�g�f�o�C�X�̕��y�́A�u�j���[�X�v�u���f�B�A�v�Ƃ����T�O�𑽗l���������B�C�[�K�����̂��̔����́A���オ�ς���Ă��j���[�X���S���ׂ������͕ς��Ȃ��Ƃ��������ł���Ǝ��邪�A���߂Ă��̓_���܂߂āA�g�l�b�g����̃��f�B�A�̖����h�Ƃ����e�[�}�ŃC�[�K�����̈ӌ������B
--�l�b�g����ɂ�����j���[�X�̑��݈Ӌ`������ɂ��āA�ӌ������ĉ������B���{�ł͑����j���[�X����I�ȃj���[�X�ƂƂ��ɁA�l�b�g�̏����������ׂ������̂��̂�ASNS�Ōl�����J�������e��\��t���������̂��́A�S�V�b�v�≺���b�Șb����u�j���[�X�v�Ƃ��č��݂��Ă��܂��B�Љ�I�ȉ��l�̂���j���[�X�A�l�X���m���Ă����ׂ��j���[�X�ƁA�����́u���E�b��v�̊_�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�C�[�K�����F�܂���O��Ƃ��āA�u�j���[�X���W���[�i���Y���v�Ƃ����͔̂��ɏd�v�ȎЉ�I������S���Ă��܂��B�W���[�i���Y����������Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ́A�����Ŗ����`���@�\���Ă���Ƃ������ƁB�m���ɁA���̎���̓l�b�g�Ɉ��邳�܂��܂ȃe�[�}�̃j���[�X�̒�����ǎ҂��ǂ݂������̂�ǂނƂ������p�V�[���ł����A���̒��ł��̃j���[�X���M������鉿�l��������̂��ǂ����́A�Љ�̔��f�Ɉς˂��Ă���̂ł��B
BBC�̋L�҂��͂��ߓ`���I�ȃ��f�B�A�ɂ���W���[�i���X�g�́A(�������������R��)�Љ�ɑ���ӔC�������������Ă��܂��B�����āA�Љ�̐M�����l�����邽�߁ABBC�O���[�o���j���[�X���~�e�b�h�̓I���W�i���̃j���[�X��z�M���邽�߂ɑ傫�ȓ��������Ă��܂��B�����P��BBC��������j���[�X��z�M���邾���łȂ��ABBC���[���h�j���[�X�Ƃ��ăI���W�i���Ő��삵���j���[�X��z�M���Ă���̂ł��B�����āA�u���f�B�A�͎Љ�ɑ��ēƗ��A�����A���m�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����`���I�ȕҏW���j���A�j���[�X���Љ��M������邽�߂ɔ��ɏd�v�Ȃ��Ƃł��B
�����������l�ς́g�Â��h�Ǝv���邩������܂��A����͖����Ƀ��f�B�A�ɂƂ��ďd�v�Ȃ��Ƃ��ƍl���Ă��܂��B�l�b�g�ɂ́A���܂��܂ȗ���̃I�s�j�I���A�m�C�Y�A�S�V�b�v�A�v���p�K���_�Ȃǂ̏����܂����A���͂����������ɂ͂��܂�͂�����Ƃ����g�����h�������Ă��܂���B�ł����A�������̎d���Ƃ́g�����𗝉����āA�����`���邱�Ɓh�ł���A�����ňӌ����q�ׂ���Ό����������肷�邱�Ƃ��d���ł͂���܂���B
���l�b�g�������`�ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂��A���̓����͏o�Ă��Ȃ�
���{�ł́A�l�b�g�Ɍ��J�����j���[�X�ɑ��āA������g���𖾂������ɓ������̍�����Ԃł��܂��܂Ȉӌ�����ь����A�ꕔ�̃C�f�I���M�[���Ă�Łu�l�b�g�E���v�Ƃ������t�����ݏo���ꂽ�B�l�b�g�j���[�X�̈ȑO�A�Ȍ�Ő��_�̌`���v���Z�X�ɂǂ̂悤�ȕω������܂ꂽ�Ɗ����Ă���̂��낤���B
--�l�b�g����̖��ӌ`���␢�_�`���̕ω��ɂ��āB�e���r��V���E�G���̎���́A�j���[�X��ǂ�Ŋ��������Ƃ͎����̒��ɗ��߂Ă������m�l�Ƃ̉�b�ŋ��L������x�ł������A�C���^�[�l�b�g�̓o��ɂ���ĕs���葽���̐l���j���[�X�ɏW�܂�A�ӌ������킹��悤�ɂȂ�܂����B���������ω������_�`���ɂǂ̂悤�ȉe����^���Ă���ƍl���܂����B
�C�[�K�����F�m���ɁA�C���^�[�l�b�g�̑䓪�ɂ���ď��ւ̃A�N�Z�X���e�ՂɂȂ�A(�l�b�g�ŋN����)���낢��ȋ@��ɎQ���ł���悤�ɂȂ�܂����B�������A����Ɠ����ɐl�X�̓C���^�[�l�b�g�̓o��ɂ����(�ȑO�������ɑ���)���^�I�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������́A�l�X�Ƀj���[�X��͂��邱�Ƃɂ���āA���̃j���[�X������I�ȍ��ӌ`���̖��ɗ����Ƃ��肢�A�������Ă��܂����B����������ŁA�܂��������o�Ă��Ȃ��̂��A�u�C���^�[�l�b�g�́A����܂Ŗ����`�̂��߂ɉ������Ă����̂��v�Ƃ�������ł��B
���Ƃ��A�C���^�[�l�b�g�̓o��ɂ���āA�l�X�͖����`�ɂ����^�I�ɂȂ��Ă��܂����̂��A�����`�ɎQ�����邱�Ƃ���߂Ă��܂����̂��A�M�ӂ������Ă��܂����̂��B���邢�́A�Љ�̗��v�̂��߂ɖ����`�ɐ[���ւ��m����~���A���܂��܂ȃC�x���g�ɎQ������悤�ɂȂ����̂��B�����A�������̎d�������^�C�A������A���̃e�[�}�ɂ��Č������Ă݂����Ǝv���܂��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���f�W�^������A�̖����� 2018/2 |
���{�o�ϐV���ЂƕăR�����r�A��w�W���[�i���Y����w�@�A������w��w�@���w��1��29���A�w�������v���W�F�N�g�Ƃ��āA�f�W�^������̕��e�[�}�ɂ����V���|�W�E���u���ꂩ��̃W���[�i���Y�����l���悤�v�𓌑�E���c�u���ŋ����J�Â����B�𗬃T�C�g(SNS)���䓪���钆�ł̊������f�B�A�̖����A�l�H�m�\(AI)�̉e���Ȃǂɂ��ē��ĉp�̌����҂�W���[�i���X�g���c�_�B��w�����580�l���Q�������B
�p�l�����_��2���\���B��1���́u�f�W�^������ɂ�����W���[�i���Y���̖����v���e�[�}�ɁA�R�����r�A��W���[�i���Y����w�@�̃X�e�B�[�u�E�R���@���A�t�B�i���V�����E�^�C���Y(FT)�̃��C�I�l���E�o�[�o�[�ҏW���A���{�o�ϐV���Ђ̒��J�����E�ꖱ�����ҏW�ǒ����b���������B�i��͓�����w�̗э��������B
���u�������`����v�����ς�炸
�с@�f�W�^�����ȂǃW���[�i���Y���͗l�X�ȉۑ�ɒ��ʂ��Ă���B
���J���@���{�ł͂܂�7���̉ƒ낪���̐V����ǂ�ł��邪�A�f�W�^���̐��E�ɑł��ďo��K�v������B���o�d�q�ł�2010�N3���ɑn�����A��҂⏗���̓ǎґw���J�Ă����B���̓ǎ҂������Ă��邾���łȂ��A�^�U�s���̏�����l�b�g��ԂŃ��f�B�A�Ƃ��Ă̖������ʂ����ӔC������B����͎����Ɋ�Â����m�œ��@�ɕx�����A������₷���ǎҖڐ��ł�����Ɨ������Ƃ��B
�R���@�f�W�^�����ŏ��̍\�������E���ő傫���ς���Ă����B�r�b�O�f�[�^���䓪���AAI����g�����B���̂悤�ȏŁA�W���[�i���Y�����R���s���[�^�[�������Ƃ����������o�Ă��Ă���B
�с@�f�W�^���W���[�i���Y�����i�ނƉf�������Ȃǎd����������B�W���[�i���Y���̐��E���ς��̂��낤���B
�o�[�o�[�@�����ƃ}���`���f�B�A�ɑΉ��ł���悤�ɂƃW���[�i���X�g�����ɓ`���Ă���B�f�[�^��r�W���A���ȉ摜��O���ɒu���悤�ɂƁB�d������悹����킯�ł͂Ȃ��B��Ȃ̂́A�ǂ�ȑ�ނʼn������A����ɍ��������̂Ƃ��ĉ��l��������o�������B
���J���@�}���`�ȋL�҂ɂȂ�A�f�����B��悤����ɂ͐������Ă���B�d����������Ǝv���邩������Ȃ����A�u���ł��ǂ�������K�v������̂��v�Ƃ��`���Ă���A�ߏd�J���ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���B
�с@���f�B�A�ւ̐M�����ቺ���Ă�����ǂ������Ă��邩�B�Љ�痣��Ă��܂����Ɗ����Ȃ����B
�o�[�o�[�@�������͐l�C���[�ŏ��Ƃ��Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����A�ǎ҂̋C������������Ɠǂ�ł����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�F�X�ȕω����N���Ă��鐢�E�ŁA������x�͌����܂����Ȃ��Ƃ����Ȃ����A����ŕq���Ȏ������K�v������B
���J���@���Ă����l��������Ȃ����A�ォ��ڐ����Ǝ~�߂��Ă���C������B�l�X�̋C�����Ɋ��Y���A�ڐ��������Ă����K�v������B
�с@�t�F�C�N(�U)�j���[�X�ւ̑�́B
�o�[�o�[�@FT�ł�2�̓Ɨ���������Ȃ���L���ɂ��Ȃ��B����͏d�v�Ȋ���B�l�X�ɑ��Ă�萳��������ł��Ȃ���A�����`���@�\���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炾�B
�с@SNS�ŏ�����悤�ɂȂ�A�j���[�X���蔄�肳���悤�Ɋ�����B�\�[�V�������f�B�A�ƃW���[�i���Y���̑����͂ǂ����B
���J���@���o��SNS�ł����M���Ă���B�O��̏O�@�I�ł͒N���u�C���t���G���T�[�v���������ׂ��B���{�W�O�������c�C�[�g��������ʂ̐l���������āA�ނ炪���[�ɍs�����ƌĂт����Ă����B�\�[�V�������f�B�A�͏��Ɋ��p���邱�ƂŁA�ꏏ�ɂ���Ă�����\��������B
�o�[�o�[�@��������A���m�ȏ������Ƃ����W���[�i���Y���̍����͕ς��Ȃ��BFT�ł͋L�҂��u�l�̈ӌ��v�Ƃ���SNS�ŏ��M���邪�A�l������Ƃ����Ė��ӔC�ȃc�C�[�g�͋�����Ȃ��B���[����O�ꂷ��K�v������B
�с@�ǂ�ȃW���[�i���Y�����f�W�^������ɔɉh���ׂ����낤���B
���J���@�܂��̓v���Ƃ��Ď�ނ��A�����𐳊m�Ɍ@�艺���ĕ��Ă������Ƃ��d�v�B�L�҂Ƃ��Ė��ӎ�����Ɏ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B����̓f�W�^���̎�������̎�����ς��Ȃ��B
�o�[�o�[�@FT�͍��ł���{�I�ȃW���[�i���Y���̎p���ɏ]���Ă���B�w�ǎ҂̃j�[�Y�ɉ����āA�O���[�o���o�ς��ǂ������ċ@�\���Ă���̂�����������`����B
�R���@�������̓W���[�i���Y���̑�w�@�Ƃ��Ă͕č��ł����E�ł��ł��Â��A�ӔC�̂���W���[�i���Y����S���Ă����B������؋��𒆐S�Ƃ����W���[�i���Y���͂��ꂩ����d�v�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�����A����ŋ�����r�b�O�f�[�^��AI�̎���ɍ��킹�����̂ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�R���s���[�^�[�̓W���[�i���Y���̈ꕔ�ɂȂ邩�炾�B
��AI���p�A�ϗ������v
��2���ł́uAI/�f�W�^���Z�p�ƃW���[�i���Y���̖����v�����ɃR���A�ї����ƕc�����E���w�����A�n�ӗm�V�E���{�o�ϐV���Џ햱���s���������q���E���w���̎i��Řb���������B
���q�@�f�W�^���Z�p�͎Љ���ǂ��ς��A�W���[�i���Y���͂����ɖ������ʂ����Ă����̂��B���o�̎��g�݂́B
�n�Ӂ@��ƌ��Z�̗v�_�������ō쐬�E�z�M����u���Z�T�}���[�v�A���Z�Ɋւ��鎿��Ɏ�����������u���o�f�B�[�v�I�[�V�����v�Ȃ�AI�����p�����T�[�r�X�����ɒ��Ă���B����͎�ރe�[�}�̔����≼���̒ɉ��p�������BAI�ɂ̓f�[�^�ُ̈�l��l�������ɂ����֘A��������͂�����B
�R���@�č��ł������ւ̊��p����������Ă���B�Ⴆ��AI�������Ƃ��ߋ��̔�����W�����c�̂Ȃǂ̏�����Ƀp�^�[���������L�҂����̐����Ƃ�_����B����������Ƃ�5�`10�N��̋L�҂̎d���̈ꕔ�ɂȂ邾�낤�B
�n�Ӂ@���Ђ�����B��Ƃ̈ӎv���肪AI�Ŏ����������ƁA�o�Ϗ���K�v�Ƃ���̂�AI�ɂȂ�BAI��AI�����ڑΘb���A�V���L�����ǂ܂�Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B
�c���@�l�X����ʂ̏����~�߂邾���Ő������ς��ɂȂ�A�\���I�ɍl���邱�Ƃ̕������N���Ă���B�Ζʂŋc�_����@��������Ă���B���ꂩ��̃f�W�^���Z�p�ɂ͐l�ԂɎ���l���A�Θb����悤�����悤�Ȃ��̂��K�v���B
�R���@AI�̏������l����ۂɈ�ԑ�Ȃ̂͗ϗ��ł́B�Ⴆ�Ί�F���Z�p�B�R�c�^���̎ʐ^����Q���҂�x���̏������f�B�A���c�����Ă��܂��������ɂȂ�BAI���ǂ��Ŏg���A�ǂ��Ŏg��Ȃ��̂�����ʂ��Ȃ���BAI�̎g�������̂�₤�������Ă����̂ł͂Ȃ����B
���q�@�u��F�����g���Γ��_�l����ɓ���v�ƍl����L�҂��o�Ă��邩������Ȃ��B
�n�Ӂ@AI�͖������̏����܂Ƃ߂Ă���邪�A���ӎ��Ɋ�Â��Ċ��p���ׂ����Ƃ����ӎ��������ċL�҂������ނ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�с@���o�̕ҏW����̒��ŁAAI��r�b�O�f�[�^�Ȃǂ̋Z�p�Ɗ����̎�ފ������Z�����铮���́B
�n�Ӂ@�Z�p����̌�����T���v�����g���A�ҏW����Ƌ��Ƃ��邽�߂̃G���W�j�A�ƋL�҂̍����`�[�������t����B�������ǂ̂悤�ɐ������邩�A�ҏW�����ǂ�ȃf�[�^���~�����̂��Ƃ����������Ȃ�������肽���B
�R���@�l�ԓI�Ȍo���l��ǎ҂��������߂Ă��邩�𗝉�����́A�����ăG���W�j�A�����O�̓���Ȓm�����W���[�i���Y���ɕK�v���B��w�ł��f�W�^���W���[�i���Y���̑��݂��傫���Ȃ��Ă���B
�с@�č��ł͑�w�ł̃W���[�i���Y�����炪�d�������B���{�ł��̗p�̍ۂɁuAI��r�b�O�f�[�^���w�l���~�����v�Ƃ������b�Z�[�W�m�ɑł��o���Ăق����B
�c���@�Z�p���g�����Ȃ���l�ނ͕K�v�����AAI���Ȃ��Ɖ����ł��Ȃ��悤�ȉߕی�͂����Ȃ��B�ŐV�Z�p�ɐG��Ȃ���l�Ԃ̗͂���Ă�K�v������A�o�����X������B
���q�@�S�̂����n���͂��v��BAI�ƃW���[�i���Y���̊W�A�����̎�ގ�@�ƃf�W�^���Z�p�̊W�ȂǑ傫�ȕ�����ǂݎ������ŁA�L�҂��w�͋�̓I�ɉ������ׂ����l���Ȃ�������Ȃ��B
�R���@�O�[�O����t�F�C�X�u�b�N�̕������f�B�A��葽���̏��������Ă�������w�E�������BAI����ɂ̓f�[�^�𑽂����҂��L���ɂȂ�B�Ђ�����Ԃ��ɂ͖����Œ��Ă�����ɉۋ�����ȂǁA�f�[�^���g�����Ƃ̊W��ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�c���@���́A��҂̃c�C�b�^�[��t�F�C�X�u�b�N���ꂪ�ڗ����n�߂Ă���B��͂苭���̂̓R���e���c�ݏo�����B���������肷�邾���̃v���b�g�t�H�[�����͕ω��𔗂���̂ł͂Ȃ����B
�с@���{�̃l�b�g��Ԃ͐^���Ȑ����̏�ł͂Ȃ��ƌ�������Ă����B�Z�p�����܂����p���A�l�b�g��Ԃ��`����̋c�_����芈���ɂȂ�悤�ɕς��A�W���[�i���Y���ɋ����̂����҂��W���\���ɂ��Ă��������B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
��[���]] �����{�W���[�i���Y���̎v�z�@2019 |
���������{�l�͍��Ȃ��u���v���Ă���B1956 �N�ɓ����́w�o�ϔ����x���u���͂���ł͂Ȃ��v�Ɛ錾���Ĉȗ��A���x�ƂȂ��u���̏I���v�������Ă������Ƃ͎��m�̂Ƃ���ł���B�����ď��O���Ɣ�r���ē��{�́u���v�͗�O�I�ɒ����Ǝw�E����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�(�Ⴆ�A�O���b�N�A2001�G���{�A2017)�B����ł����{�����Ȃ��u���v�̂܂܂ł��邱�Ƃɋ^��̗]�n�͂Ȃ��B�{����ʓǂ���ƁA�W���[�i���Y���̌���ɂ����Đςݏd�˂��Ă����c�ׂ��܂��u���v�Ƃ����g�g�݂̂Ȃ��œW�J����Ă����Ƃ������ƁA�]���Ă��̈Ӌ`����_���u���v�Ƃ����p�[�X�y�N�e�B�u�ɂ����Ă����K���ɗ����ł���̂��Ƃ������Ƃ�[����������B�������A���̍ۂ́u���v�Ƃ́A�I�큁�s��ƂƂ��Ɏn�܂����V���Ȏ���Ƃ��Ắu���v�ł���Ɠ����ɁA����Ӗ��ɂ����Đ�O�`�풆����A���I�ɑ�������ׂ��u���v�ł�����B
�{���́A���{�́u���v�Ɋւ���d�w�I�ȗ����Ɋ�Â��Ȃ���A���̒��ɓ��{�̃W���[�i���Y���j���ʒu�Â��đ��l�Ȋp�x���番�͂��A�_�����J��ł���B�{���̑��͂́A�������Ƀ��[�c�����u�s�Εs�}�v�̌`���j�̌����ɓ��Ă��Ă��邪�A���̂��Ƃ͒��҂̊�{�I�Ȗ��ӎ����悭�\�킵�Ă���悤�Ɏv����B���҂͂܂��A���{�̃W���[�i���Y���ɂ�����u�s�Εs�}�v�Ƃ������O���u��Ȃ��Ɨ������p�����������̂ł͂Ȃ��A���{�ɔᔻ�������Ȃ��Ƃ������Ə�̃C�f�I���M�[�v�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B����́u�Ɨ��������_�v�ł͂Ȃ��A�W���[�i���Y���̎���K���𐳓������A�Œ艻���������S���Ă����̂ł���A���{�ɂ����錾�_�̎��R�Ǝ���K���̑������ے�����B�����ăW���[�i���Y�����u�Ɨ��������_�v���낤�Ƃ���ƁA�K�����͂̑����쓮�����Ă����̂��u�Ό��v�U���ɂق��Ȃ�Ȃ��B���́u�Ό��v�U�������ۂɂǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������A�����ăW���[�i���Y�������̑O�ɂ����ɔs�k�𑱂��Ă������ɂ��āA���́u���Z�Z�N��Ƃ�����ԁv�ł͏ڍׂɌ�������Ă���B�������Ă݂�ƁA��O�ɂ������㒩���V����������(1918�N)�ƁA���̕�����李���(1961 �N)�Ƃ� 40 �N�ȏ�̎��Ԃ��u�ĂȂ���m���ɘA���I�ł���B�����Ă���������O����̘A�����̂����ɂ����āA�����{�̃W���[�i���Y���͓P�ސ�Ɣs�k��𑱂��Ă����̂��Ƃ������Ƃ����������B
���݁A���{�ɂ����錾�_�E�̎��R���߂���͌������B���� NGO�u�����Ȃ��L�Ғc�v�����N���\���Ă���u�̎��R�x�v�����L���O�ł́A���{�͐�i�����̒��ōŒ�x���� 67 ��(2019�N)�ł���B�̌��ꂩ��́A�NJ��⑧�ꂵ����i���鐺�������Ε����Ă���B�����������Ԃ��A�K�������������̂��ƂŐ�������ߐ��̂��̂Ȃ̂ł͂Ȃ��A���̃W���[�i���Y���j�̂����̋A���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����\���ɂ��āA����̃W���[�i���X�g�������҂��A�{���Ƌ��ɉ��߂čl���Ă݂�K�v�����邾�낤�B
��O�͈ȉ��ł́A���l�ȃW���[�i���X�g��v�z�Ƃ����グ���Ă������A�����ɂ����Ă��u�푈�v�u���v���L�[���[�h�ƂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�r���L��ΏۂƂ������߂Ă̂܂Ƃ܂��������ł����l�́u�r���L���ʂ��������̃W���[�i���Y���_�v�ł́A�W���[�i���Y�����u�ɔᔻ�I�Ɍ����������ƂŎ��R�Ǝ�̐��̊l����ڎw�������ł���A������ς��悤�Ƃ��錾�_�����v(131 ��)�Ƒ����Ă����r�����A�W���[�i���Y���̓}�X���f�B�A�^�}�X�R�~���j�P�[�V�����̕����T�O�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�ނ���}�X���f�B�A�^�}�X�R�~���j�P�[�V�����Ƃ̂������ɋْ��W��s�ފT�O�ƍl���Ă������Ƃɒ��ڂ���B�����āA���������r���̃W���[�i���Y���v�z�̏o���_�ɁA��O���ɏ��Ɖ������V�����u�s�Εs�}�v���f���Ȃ���펞�̐��ɍR�����ꂸ�u��ѐ��̂��錾�_������v���Ă������Ƃ����u�V���̐푈�ӔC�v�ɑ���s�����ӎ������������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B
�܂��A�{�����\������\��̏͂̂Ȃ��ł��������Ȃ���Z�́u�w�풆�h�x�ȍ~�̃W���[�i���X�g�Q���v�ɂ����ẮA�����{���\����W���[�i���X�g�B(��X���A�c�p�v�A�����Y�A�V�䒼�V�A�ē��Βj�A�g�i�t�q�A�{������Ȃ�)�̊�������єނ�̃W���[�i���Y���v�z����������Ă���B�����ł͔ނ�̑����� 1920 �` 30 �N�㐶�܂�ł���A1945 �N�̔s�풼��ɋL�Ґ������X�^�[�g�����Ă��邱�Ƃ��œ_������Ă���B�����Ĕނ炪�A���N�푈�A���b�h�p�[�W(1950 �N)�A���ۓ���(1959�` 60 �N)�A�����n���A�x�g�i���푈�A����ɏ]�R�Ԉ��w���͂��߂Ƃ���A�W�A�ɂ�������{�̐푈�ӔC���ȂǂƂ̔Z���Ȋւ���ʂ��ăL�����A�`�����Ă��������������͂����B�����܂ł��Ȃ������̏o�����́A��������u�푈�v�ɋN����L���A�u�����{�v�ɂ����đ傫�ȈӖ������������̂���ł���B������ς���A�ނ玩�g�����܂��܂Ȑ��������Ȃ�����A�u�푈�v��u���v�Ƃ̊W���ɂ����āA�r���L�������Ƃ���́u�}�X���f�B�A�^�}�X�R�~���j�P�[�V�����Ƃ̂������ْ̋��W�v��s�ރW���[�i���Y���̂������̌��������݂������ƌ����邩������Ȃ��B�ނ�͂܂��A������̓ǎҁE�����҂ɌŗL���ŔF������Ă����W���[�i���X�g�B�ł��������B���₲���ꕔ�̗�O�������āA���������W���[�i���X�g�͑��݂��Ȃ��Ȃ��Ă���B���̔ނ炪�A��q�̂悤�Ɂu�푈�v����сu���v�Ɛ[���茋��ł������Ƃ̈Ӗ��ɂ��ẮA���҂̎��̂悤�Ȏw�E�͐����I�ł���B
�푈�Ƃ������Ƃ̖\�͐����ɑ剻�����̑̌��́A���ɂ�����Ƃ炦�Ԃ����ŁA���͊Ď��ƌ��I�Ȗ��ӎ������ł����B�����Ĕs���Ɍ��o�������_�̎��R���Ȃ�Ȃ�ɂ��@�ւ��������ƂƑ��悵�āA�����ɉs���Λ�����L���\�ł������ʁA�����̎d�������ڂ���Ă����B(351 ��)
����ɂ��Ă��A�u�����{�v�Ƃ����p�[�X�y�N�e�B�u�ɗ������{���̂悤�ȃW���[�i���Y���j�������A����܂Ŗw��ǒ~�ς���Ă��Ȃ��������Ƃ����X�Ȃ���s�v�c�Ɏv����B�����A���f�B�A�j���啪��Ƃ��錤���҂͏��Ȃ��Ȃ����A�f��A�L���A���W�I�A�G���A�e���r�A�T�u�J���`���[�Ȃǂ��������f�B�A�j�����͋ߔN����ɂȂ��Ă�����̂́A���҂��w�E����ʂ�A�u�d�h�ȓ��e��ǂ��W���[�i���Y���j�͌����҂����|�I�Ɂv���Ȃ��A�����{�́u���_�E�₻�̎v�z������ΏۂƂ���W���[�i���Y���j�v�̂܂Ƃ܂����������ʂƂ��Ă͖{�����قڗB��ł���B
���j�w�҂̐��c����́A���̓��{�l��푈�Ƃ̊֘A�ɂ����ĎO�̐���ɕ��ނ��Ă���B�푈�o����(A)�ƁA�e�̐푈�̌����ꎟ���Ƃ��ĕ������ꂽ�u����ꐢ��v(B)�A�w�Z�����f�B�A��ʂ��čĕ҂��ꂽ�푈�����m��Ȃ��u�����v(C)�ł���(���c�A2015)�B���c�̂��̐����ɏ]���A�����{�̃W���[�i���Y���ɂ�����L�[�}���Ƃ��Ēm����W���[�i���X�g�̑����́A(A)��(B)�ɊY������B�����Č��݁A�W���[�i���Y���̑����Ŋ������Ă���W���[�i���X�g�B�́A�����(C)�A���邢�͍X�ɂ��̎q�̐���ɓ�����l�B�ł���B��� 70 �N�̐ߖڂ̔N�ɂ������� 2015 �N�ɁA��㐶�܂ꐢ��̊������l���� 8 �����A�t�ɔs�펞�� 10 �Έȏゾ�����l�̊����� 8% �ȉ��ɂȂ������Ƃ��b��ƂȂ������A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɍ���܂��܂��u�푈�v�͉����Ȃ��Ă����B�����āu���v�����ɘg�g�݂Ƃ��Ă͈ێ����ꂽ�Ƃ��Ă��A�u�푈�v��u���v�ɐl�X�͂܂��܂����A���e�B�������ɂ����Ȃ��Ă������낤�B�K�R�I�ɁA����̃W���[�i���X�g�B�Ɓu�푈�v�u���v�̊W�����A�ϗe������Ȃ����A���̌��ʁA�W���[�i���Y���̂�������̂�����ɕς���Ă������낤�B�����l����ƁA�u���v�ɂ��Ă̕��w�I�ȗ����̂����ɗ����Đ����{�W���[�i���Y���̊�������юv�z�̗��j�I�W�J��ՂÂ����{���̈Ӌ`�͋ɂ߂đ傫���B
�{���̂悤�ȃW���[�i���Y���j�����́A(���҂��Ӑ}���Ă���ʂ�)����ƌ����̐��E���ˋ�����������ʂ�������B����̃W���[�i���X�g�́A�{���ɋL�q���ꂽ�u�����{�v�Ƃ����g�g�݂Ƃ��̒��ł̃W���[�i���Y���j�̉�����Ɏ�����ʒu�Â��邱�Ƃɂ���āA���g�̎d���̈Ӗ���\���A�ۑ蓙���Ċm�F���邱�Ƃ��ł���͂����B�܂������ɁA���҂��W���[�i���Y�������̔��W�ɂƂ��đ�w���ʂ��������Ɍ��y���Ă��邱�Ƃɂ����ڂ������B��w�́A�W���[�i���Y�������ʂ��Č���œ����l�ނ𑗂�o���Ƃ����d�v�ȋ@�\�����B���ہA�{���u���Ƃ����v�ɂ��A���҂̃[�~�i�[���̓}�X���f�B�A(�V���ЁA�e���r�ǁA�e���r�ԑg�����ЁA���W�I��)�̌���œ����l�ނ����łɑ����y�o���Ă���Ƃ����B�����ŁA��������w�̖����͂��������l�ވ琬�ɂƂǂ܂�Ȃ��B���҂������Ƃ���A�u�W���[�i���Y�����x����͍̂ŏI�I�ɓǎ�(������)�v�ł���B��w�͓ǎ�(������)�̈琬�₷����̊g��ɂ��[���R�~�b�g���Ă���B
�{�����A�����҂͂��Ƃ��A�W���[�i���Y���A���f�B�A�̌���œ����l�X�A�̎d���ɊS�����w���A�����ăW���[�i���Y���ɒ��ڊւ��킯�ł͂Ȃ����ǎ�(������)�Ƃ��ăW���[�i���Y���������x���镝�L���l�X�ɓǂ܂�邱�Ƃ�ʂ��āA���{�̃W���[�i���Y���������Ċ���������邱�Ƃ����҂������B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���R���i�ЂŖ��]�L�ً̋}���ԁI�W���[�i���Y���̖����@2020/4
|
�u�ً}���ԁv������I�Ɍč������Ƃ������]�L�̊�@�I�������Ă���B���X�X���V���b�^�[�����낳��Ă��邵�A�ٔ����������������A�S�u������ʖʉ�֎~�ƁA���܂őz�肵���Ȃ������ٗl�Ȏ��Ԃ��B���ꂪ�ւ��������1�J�������Ƃ����āA�����������̎Љ�͂���Ɏ�������������̂��낤���ƕs���ɂȂ��Ă��܂��B�܂��Ɂu��펞�v���B
���ً}���Ԃ𗝗R�ɔᔻ�����E���ꂽ�ߋ��̗��j��
�����g��Ƃ�����@�I���ԂɎs���������������A�g��h�~�ɗ͂����킹��͓̂��R���B�����C�ɂȂ�̂́A���̂��Ƃ������ē������͂��������A����Ȏ��ɍ��Ƃ̂�邱�Ƃ�ᔻ����͔̂����A�Ƃ��������������܂邱�Ƃ��B�l���Ă݂�t�@�V�Y����푈�ւƍ��Ƃ����������̂͏�ɎЉ�傫�Ȋ�@�ɂ��炳�ꂽ�����B����Ȏ������A���Ƃ����������Ȃ��悤�Ď�����@�\���}�X���f�B�A�ɋ��߂���̂����A�ߋ��̗��j������ƁA�}�X���f�B�A�����͊Ď��ǂ��납�吭���^�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ������B
����͑����m�푈�ɂ܂ł����̂ڂ�Ȃ��Ă��A3�E11�����{��k�Ђƌ������̂̎��������������B�p�j�b�N�ɂȂ�̂�����Đ��{�̓����g�_�E���̎����������B���A������Ď����ׂ��}�X���f�B�A�����\����邱�Ƃ𗬂������ɂȂ����B��ɂ���ɑ���s������̃}�X�R�~�s�M���傫�������o�����B
���̂��Ƃւ̔��Ȃ���A�E�������j�֑ǂ��A���͊Ď���N���Ɍf����悤�ɂȂ����̂������V���ŁA����������͑����ƈꖡ�Ⴄ���ʂÂ�����s���Ă���B�����������ɂ����A���f�B�A���ǂ�ȕ��s���̂��A������ƃ`�F�b�N����K�v������B
�Ƃ������Ƃŋً}���Ԑ錾���߂���}�X�R�~�������Ă݂����B
���ƌ����Ă��������̂������V�����B�����ɂ͓��Ƃ����Q���������������āA����ʂƂ�����݂̃y�[�W������B����ʂɓˏo�����L�����ڂ��A�S�̂Ƃ��Ă̓o�����X���Ƃ�Ƃ��������Ȃ�ł͂̎��ʓW�J���A����������펞�ɂ͑傫�ȋ@�\�����Ă���B
4��7������8���ɂ����āA���{�ً̋}���Ԑ錾���A���̂܂܌��o���œ`�����A����I�Ȋ�@������ł悢�̂��ƁA�e�����낢��Ȏv�������������Ȃ��玆�ʂ�������Ǝv���̂����A�����V���̏ꍇ�́A4��7���̓���ʂŁu�w�ً}���ԁx������x�l���悤�@���ӓI�^�p�Ɍ��O�v�ƌ��o����ł����B
���u�ᔻ�͎��l�����Ⴞ�߁v�ƍ֓����ގq����
�ً}���Ԑ錾���4��8���̎��ʂ��A3�ʂɁu�����w����p�x�F���������v�Ƃ����R�c�����E��C�勳���̃R�����g��傫���f���A����ʂł́u�V�^�R���i�w�ً}���Ԑ錾�x�m�肷��S���Ȃ��@�s������ΓI�͑Җ]���@��@�ɂ��v�l�������v�Ƒ匩�o���B�����o���Ɂu�@���̋�C�����ɗ��p���@�s�̌��ʂȂ̂Ɂw����Ă銴�x���o�v�u��펞�̍��@�l�����Ď��K�v�v�ȂǂƂ������������B
�傫�Șb��ɂȂ����̂́A���̓�������ʂŕ��|�]�_�Ƃ̍֓����ގq�������Ă����u�}�W���I�̌��p�v�Ƃ����R�������B��������������Ă���B
�u�s���͎��l���Ă��ᔻ�͎��l�����Ⴞ�߂��B�ً}���Ԑ錾�̔��߂����}���Ă���ꍇ����Ȃ��B�Ђ�܂��w�}�W���I�x�𑱂��悤�v
���₠�A�������B���_�����A���̃^�C�~���O�ł���������̂��������B
�����͂ǂ��Ȃ̂����Ă݂�ƁA�ڂɂ����̂�8���t�����X�|�[�c�B�u���{�w�F�ŗ͍��킹�x�w�����ł����x�v�Ƃ������o���ɂ��Ԃ���悤�ɑ傫���u���_�_�����v�Ƃ����匩�o�������A�u���ǁw�����̊F���܁x���݁v�Ə�����Ă���B
�����V����4��8���t�[���́u���W���C�h�v�Ő��ҏW�ψ��̗^�ǐ��j���A�R�����ŋً}���Ԑ錾�ƌo�ϑ�ɂ��Ę_�]���A�Ō���������߂Ă���B�u����Ȋ�@�����炱���]�������łȂ��A�����ƒ��������Ă����v�B���̋L���̌��o�����������B
�u�Ȃ�����ȋ�����v
�V���ɂ����Ă͌��o���̈�ۂ͂ƂĂ��傫���B���̌��o���͗^�ǂ���łȂ��ʂ̐l�������̂��낤���A���o���̕t�����Ɂu�ӎu�v����������B
���e���r�������������V���̋L���́c
�e���͂̑傫�������V���͂ǂ����Ƃ����A�S�̂Ƃ��ċq�ϕ�S�����Ă���悤�Ȏ��ʂ��B��⒩���炵���Ǝv�����̂�4��10���t�́u��A�s�u�͂ǂ��`�����@7����A�ً̋}���Ԑ錾�v�B�e���r�������܂߂ăe���r���e�lj����тŎ̉������Ƃ��Љ�A�Ō�ɍ�ƁE�ē̐X�B�炳��́u�������͂�Љ�̕��͋C�ɂ̂܂�Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����R�����g���ڂ��Ă��邩��A����Ɍx����炻���Ƃ������Ӑ}�͊�������B
�ł��L���S�̂̃g�[����}���Ă��邩��A���ƂȂ��ʂ邢�����ň�ۂɎc��Ȃ��B���o�������������ĞB�����B�����V���́A��̈Ԉ��w���̌������o�b�V���O�̌�A���ꂪ�g���E�}�ɂȂ��Ă��銴������B
�������A�X���v�ł̃X�N�[�v�Ɍ����邲�Ƃ��A�������t�łȂ���ޗ͂���g�����t�@�N�g�ŏ������悤�Ƃ����p���͊Ԉ���Ă��Ȃ��̂����A����̂悤�ȑ厖�ȋǖʂɂ����̃��b�Z�[�W�M�ł��Ȃ��Ƃ�����ۂ́A���܂�ǂ����Ƃł͂Ȃ��悤�ȋC������B
����A���{�����x���̎Y�o�V�����ǂ����Ƃ����ƁA4��8���̎��ʂ͔�r�I��Âȃg�[�����B�ً}���Ԃɕ֏悵�Ď����}�̒��ɁA���@�����肵�ċً}���ԏ����荞�ނׂ����Ƃ�����Ȃ��咣���o�Ă���̂����A8���t�Y�o�͂����Ȃ��猩�o���́u���@�������@��}�͔��v�Ƃ��������X�^���X���B�ł����ꂪ4��11���t�ł͌��o�����u�ً}���ԑΉ��̉����@�^�}�ӗ~�v�Ə������ݍ����̂ɂȂ��Ă���B
����A�ً}���Ԃ�����������ɂ�Đ��_���ǂ��ς���Ă����̂�����肾���A�V����e���r�̃g�[���͂��̐��_�`���ɑ傫�ȈӖ��������璍�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����{�y���N���u�u�ً}���Ԃ����炱���A���R���v�@
�}�X���f�B�A�̘_���ƂƂ��Ɍ��_�E�\���c�̂Ȃǂ̌����������ƕ\������ċc�_���Ȃ����ׂ����Ǝv�����A4��7���ɓ��{�y���N���u���ȉ��̂悤�Ȑ������o���Ă���B�����������S�����p���悤�B
�s���{�y���N���u�����u�ً}���Ԃ����炱���A���R���v
�����g�傷��V�^�R���i�E�C���X�Ɛ��{�ɂ��ً}���Ԑ錾�B���{�Љ�͂��܁A�����������ɒ��ʂ��Ă���B
�������́A���̂��������̂Ȃ������߂Ċ��݂��߂����B�e����̈�ÊW�҂��~�ς��Ă����Z�p�ƒm����M�����A����炪�\�ɔ��������悤���҂���B�܂��A���������g���������Ȃ���Â��ƁA���҂Ɋ��������Ȃ��z���Ƃ����l�Ԃł��肽���Ǝv���B
�����āA�������́A���������M���E���ҁE��ÁE�z�����A�l�Ɛl�����R�ɔ������A�c�_���A���ӂ�z���Ă��������`�Љ�̉c�ׂ��̂��̂ł���A���ʂł����邱�Ƃ����x�ł��m�F���Ă��������B
�ً}���Ԑ錾�̉��ł́A�ړ��̎��R��E�Ƃ̎��R�͂��Ƃ��A����@�ցE�}���فE���X���̕��ɂ���Ċw��̎��R��m�錠�����A�����I�{�݂̎g�p��������������̓������ɂ���ďW��⌾�_�E�\���̎��R�����̐�����邱�Ƃ����O�����B
�����̎��R�⌠���͂ǂ���A��펞�ɒu���ꂽ�����O�̐�l�����̋]���̏�ɁA���̓��{�Љ�l�����Ă��������`�̊�Ղł���B�����A�������͂����������j����A�ǂ�Ȋ�@�ɂ����Ă��A���ǂ́A���R�Ȍ��_��\���������Љ�����S�ɂ��Ă������Ƃ�m���Ă���B
�������̖ڂ̑O�ɂ���̂́A�������R���̑I���ł͂Ȃ��B������邽�߂ɑ��҂��玩�R�Ɋw�сA�݂����玩�R�ɕ\�����A�݂��ɋ��͂��������������Ă������ƁB���ꂱ�����A���ً̋}���Ԃ����z���Ă������߂ɕK�v�Ȃ̂��A�Ǝ������͍l����B
���̓����A�E�C���X�Ђ͍����������A�����`�����Ă����Ƃ����̂ł́A��@�����z�������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B��������Ă���̂́A�������̎Љ�Ɩ����`�̋��Ղ��ł���B�t
���͓��{�y���N���u���_�\���ψ���̕��ψ���������A���܂�ق߂�Ǝ��掩�^�ɂȂ��Ă��܂����A�����_�ŋM�d�Ȑ������B�O���Ŋ�@�ɑΛ����邱�Ƃ̕K�v����i���A�㔼�Ō��_�\���Ȃǂ̎s���I���R�𐧌����邱�ƂɊ뜜��\�����Ă���B
�����A���̐�������V���̈����͂��܂������B�Z�����p����Ȃ�㔼���Љ�Ăق����̂ɁA�O���̕��������p���Ă���L�����������B�}�X���f�B�A�̎p�����̂��܂���܂��Ă��Ȃ��䂦�ɂ��������������B���ɕ��Ă��܂��B
�V���J�A��4��7����2�̐������o�����B������Ȃ��Ȃ������B
�u�V�^�R���i�v�𗝗R�ɂ�����]�̕��E�ɍR�c����
�ً}���Ԑ錾���ł̎s���́u�m�錠���v����邽�߂�
���W���[�i���Y���̐Ӗ��͖{���ɏd��
�ً}���Ԃ𗝗R�ɁA���{��n�������̂̌������������悤�Ƃ����̂����̗��ꂾ���A�����������ʂ�A�����E�s���̈ӎu���ق��Ă���鑶�݂�������S�z�͂���Ȃ��B�ł������̎s�����S�z���Ă���̂́A�u���{�ꋭ�v�̂��ƂŐ������u�匠�ݖ��v�Ɣ��̍s���ɓ˂������Ă����ڂ̂�����ɂ��Ă������炾�B�X���v��肵����A�u���������v��肵����B�c��ł̈��|�I�����Ƃ������̗͂�w�i�ɁA���������Ŗ�����ʂ��ē������������߂Ă����̂����{�������B���̂悤�Ȋ�@�I���Ԃɒ��ʂ��āA�������������Ɍ������W�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂́A���̍��̎s���̑傫�ȕs�K�ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B
�����������@�R�Ɣے肷��悤�Ȑ����Ƃ𑍗���b�ɁA�����������ɂ킽���Đ����Ă���Ƃ������Ǝ��́A�{���Ȃ炠�肦�Ȃ����ƂȂ̂ɁA���͂��̐����ɂ���Ȃ錠�͂��Ƃ����A�ɂ߂Ċ�Ȃ����B������Ď�����̂��W���[�i���Y���̖���������A���̐Ӗ��͖{���ɏd���ƌ��킴������Ȃ��B
���̂Ƃ���A�z��O�ً̋}���Ԃ����X�ƌ��o���āA����ɖڂ�D���Ă���ŁA�ً}���Ԃ̂�������߂���c�_���قƂ�ǂȂ���Ă��Ȃ��B
�u�s���͎��l���Ă��ᔻ�͎��l�����Ⴞ�߂��v�Ƃ����֓����ގq����̌��t���̂ɖ��������Ǝv���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
������_�s�ꉻ��ɔs�ꂽ�č��`�����f�B�A�̊�@�@2019/5
|
���u���f�B�A�̊�@�v�̈�ʓI�ȃp�^�[��
�w����A�����J�����ƃ��f�B�A�x�̕Ғ��҂Ƃ��Ă̎��̖����́A�S�̂̌����}���������Ƃ��������A���̑�1�͂��u�A�����J�̃��f�B�A�́A���܁A���ĂȂ���@�ɕm���Ă���v�Ƃ��������o���Ŏn�߂��B
�Ȃ��A�g���ĂȂ���@�h�Ȃ̂��B���R�Ȃ���A�����J�̂��Ƃɏd�_��u���ď��������A�����ł͏ȗ��������̑O��ƂȂ镔�����܂߂ď����_���Ă݂����B
��ʓI�Ɂu���f�B�A�̊�@�v�Ƃ����A�����܂�̃p�^�[��������B����͌R��������o�σG���[�g�Ȃǂ̎x�z�K��������Ɛ肵�A���f�B�A�͌��͂̈ꕔ�ƂȂ��Ă��܂��Ă�����B
�߂��̗�̍���z�����Ă݂�����B���Ў�`�I����(�ƍٍ���)�̃��f�B�A���́A�ォ��O��I�ɓ��������B���I�ŋK�i�����ꂽ���e�ɂȂ�̂͌����܂ł��Ȃ��B����ȍ��̃j���[�X�͎Љ�̂ق�̈ꕔ�����f���o���Ȃ��͓̂��R���B�܂��A�����̎Љ����ǔF������e�ƂȂ�B��͏���I�Ԃ��Ƃ͂ł����A���Ȃ������g����߂��邵�����@�͂Ȃ��B�ǂ����Ă��I�ɂȂ�B
�����āA�x�z�K�������f�B�A�̏����R���g���[������ȊO�ɂ��A�u���f�B�A�̊�@�v�͂���B�Ⴆ�A����n��ɂ���Ă̓M�����O�Ȃǂ̏W�c���x�@���͂������A���������ɓs����������\�͓I�ɑj�Q���邱�Ƃ�����B
���N�A���܂��܂ȍ�����̗��w����������Ƃ�S�����Ă���B����A���L�V�R����̏����̗��w�����u�����W���[�i���X�g�ɂȂ肽�����A�g�̊댯��������̂Ō˘f���Ă��܂��v�Ɛ؎��ȗl�q�ŃR�����g�����B���̔����ɂق��̓��{�l��A�����J�l�̊w���̊炪��C�ɂ�������̂͌����܂ł��Ȃ��B
���ꂼ��̍��E�n��̓̕x�����́A�ق�2�N���ƂɃA�����J�̃V���N�^���N�̃t���[�_���E�n�E�X�����\���Ă���u�̎��R�x�v�̃����L���O�Œm�邱�Ƃ��ł���B�ŐV�ł�2017�N�̂��̂ŁA199�̍��ƒn��̂����A31����61���u���R�v�ł���A���R��������Ȃ������{��A�����J�A���������A��p�͂قږ���A�����ɕ��ނ���Ă���B
72(36��)���u�����I�Ɏ��R�v�Ƃ���A�����ɂ͓�ĂȂǂ̍�������(���Ắu���R�v�ƈʒu�t����ꂽ���Ƃ�����؍���2017�N�����ł́u�����I�Ɏ��R�v�ɕ��ނ���Ă���)�B�����āu�s���R�v�Ƃ��ꂽ66(33��)�̍��ƒn��ɂ̓��V�A�A�����̂ق��A������A�t���J����������(������̃��L�V�R�������Ɉʒu����)�B
�u�ł����R�v�Ƃ��ꂽ�̂��m���E�F�[�A�u�ł��s���R�v�Ƃ��ꂽ�̂͗\�z�ǂ���k���N�������B���̐��ł͂Ȃ��āA���̐l������l���Ă݂�u���R�v�ȍ��ɏZ��ł���̂́A�킸��13���ɂ����Ȃ��B�u�����I�Ɏ��R�v��42���A�u�s���R�v��45���ƈ��|�I�Ȋ����ƂȂ�B
���E�̑命���̍��̃��f�B�A�͎Љ�𐳊m�ɉf���o���Ȃ��u�䂪���v�ł����Ȃ��B
���A�����J�^�u���f�B�A�̊�@�v
�A�����J�ɘb��߂����B���̃J�e�S���[�Ō����A���������u�̎��R�v�����鏭���h�̍��E�n���1���A�����J�ł���B���f�B�A�͐����I����Ɨ����Ă���A�{���́u���f�B�A�̊�@�v�Ƃ͉������݂ł���͂��ł���B
�w����A�����J�����ƃ��f�B�A�x�œ`�����������A�A�����J�̏ꍇ�́u���f�B�A�̊�@�v�́A���̈�ʓI�ȃp�^�[���Ƃ͏����قȂ�B����́A�ނ��됭�{����u���R�v�ł��邪���߂ɁA�N�����Ă��܂����ߌ��Ƃ��猾���邩������Ȃ��B
���������������B�A�����J�̏ꍇ�A�ߋ�30�N�̊ԂŐ��_���傫���ێ�ƃ��x�����̍��E�ɕ�����镪�ɉ����ۂ��ɂ߂Đ[���ɂȂ��Ă���B�������_�����E�ɕ�����Ă��邱�̌��ۂ͋ߔN�A���̃y�[�X���ɂ߂đ����Ȃ��Ă����B���݂̓A�����J���������Čo���������Ƃ��Ȃ����x���̐��}�Ԃ̑Η��������[�������Ă���B
���E�Ő����I�ȉ��l�ς��قȂ鍑���̕��f���ǂ�قǐ[���Ȃ̂��́A���{�ł����Ȃ��݂̃g�����v�哝�̂̎x���E�s�x���̌X�����݂�Ζ��炩�ł���B���_������Ђ̃M�����b�v��2019�N4��17������30���ɂ����čs���������̏ꍇ�A�g�����v�哝�̂̎x������46���ŁA�s�x�����͔�����50���ƂȂ��Ă���A�s�x���̂ق��������B
�������A�}�h�ʂɂ݂�ƁA�͂܂������قȂ��Ă݂���B���������Łu���a�}�x���҂ł���v�Ƃ���l�̏ꍇ�A�u�g�����v�����x������v�Ƃ����̂�91���ƁA����ȏ�ɂȂ����x���̍����ł���B����ɑ��u����}�x���҂ł���v�Ƃ���w�̒��Łu�g�����v�����x������v�Ɠ������l��12�������Ȃ��A���҂̍��͂Ȃ��79�|�C���g����������B���}�h��37���ŁA���傤�Ǘ��҂̒��ԂɈʒu���Ă���`���B
�����������a�}�Ɩ���}�̎x���҂̐��͂�▯��}�̂ق����������A�����̂ق�3����1���ł���A�ύt��ۂ��Ă���B�c���3����1�́u���}�h�v�����A���̒��͂قڋϓ��Ɂu���a�}���v�u����}���v�u(�{����)���}�h�v�ƕ�����Ă���B���a�E���傢���ꂩ�̐��}�̎x���ł͂Ȃ������͂ق�̏����������Ȃ��B
�A�����J�̃��f�B�A�͂��̐��_�̕��f�Ƃ����ω��ɍ��킹�Ȃ���A���E�̐����I�C�f�I���M�[�ɂ��̕��ĉ�������悤�ɂ��Ă������B�^����1�ł���͂��Ȃ̂ɁA���f�B�A���g�����ɉ����A�ێ�����̐������A���x�����h�����̐���������悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă����q�̂悤�Ɍ��Ў�`�I���ƂȂ�A���{���̓��e�ɉ������B
�������A�A�����J�̃��f�B�A�̏ꍇ�A���_�Ƃ����u�s��v�ɍ��킹�āA���������}�[�P�e�B���O���Ă������B���ꂪ�A�����J�^�́u���f�B�A�̊�@�v�ł���B
�u���f�B�A�̕��ɉ��v�̔w�i�ɂ́A�����́u�����I�������v���߂���K���ɘa��1980�N��ɐi�e��������B�K���ɘa�́A�܂�u���{����̎��R�v�ł���B
���̌��ʁA���_�Ƃ����u�s��v�̕ω��̕�������ǂ݂Ȃ���A1990�N��ȍ~�A���W�I��ACATV��q����24���ԃj���[�X�`�����l��(�P�[�u���j���[�X)���Ƃ��Ɂu���f�B�A�̕��ɉ��v���ڗ����Ă����A���݂Ɏ���B
���́u���f�B�A�̕��ɉ��v�ŁA�x�z�K�������f�B�A�̓��e���R���g���[������Ɠ����悤�ɁA�A�����J�ł����f�B�A���u�䂪���v�ƂȂ����B�u�M�����Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł܂����������ł��낤�B���R�ȕ��A���̈Ӗ��ł�����������������Ȃ��B
���u���f�B�A�̕��ɉ��v�̍\��
���ẮA�A�����J�̐��_�͌��݂�����⍶��肾�����B�������^�����܂߁A���l����F�߂Ă��������̓A�����J�Ƃ������̐i�����̂��̂������B�V�������łȂ��A�e���r�ł̕��ǂ��炩�Ƃ������x�������̏���������B
����ŁA�암�⒆�����𒆐S�ɕێ�w�����݂��Ă����B���̑w���߂����āA���Ȃ�ێ�ɕ������b�V���E�����{�[�̃g�[�N���W�I(����ҎQ���^�̃��W�I�ł̐������ԑg)���K���ɘa�����������ɁA���W�I���ێ�h�̏���ՂƂ��Ĉ�C�ɒ��ڂ����悤�ɂȂ����B
�g�[�N���W�I�͒ʏ�̃X�g���[�g�j���[�X�ł͂Ȃ��A�����A�Љ�̑��_�ɑ��ăz�X�g(�i���)���ӌ����q�ׂ�B�G���^�[�e�C�������g���������A���Ȃ芴��I�Ȃ��̂�����A�����V���[�I�ȗv�f�������B
�����{�[�����łȂ��A�ێ�w�����̃g�[�N���W�I�ԑg�������̒���҂��l�����Ă������B����ɑR����悤�ɁA���x�����h�̃g�[�N�V���[�����X�ɓo�ꂵ�A2000�N��ɂ�AM���������łȂ��AFM������q�����W�I�ł������g�[�N���W�I�ԑg���S�Ẵ��W�I�ԑg�Ґ��̒��j�ɂȂ��Ă������B
�e���r���A���Ă͂Ȃ������悤�Ȑ����I�ȕ�̂���ԑg��1990�N��ȍ~�A���܂�Ă����B��\�I�Ȃ��̂��ێ�F�̋����ԑg�\�����u�s��v������ł��������ƂŒm����A1996�N�ɔ��������P�[�u���j���[�X��FOX NEWS�ł���B���݂̊Ŕz�X�g�̃V���[���E�n�j�e�B���܂��ɂ��������A�e�ԑg�̃z�X�g�͂��������g�[�N���W�I�o�g�҂��������B
����Ń��x�����w�����̕����e���r�������o�ꂵ�Ă����B��\�I�Ȃ��̂�MSNBC�ł���BMSNBC��FOX NEWS�Ɠ���1996�N�ɔ����������A�ێ�F��������������������A2004�N�̑哝�̑I��������Ƀ��x�����s��ɒ��ڂ��邱�ƂŁA���̓��e����C�ɍ������Ă���BCNN���������N�A���x�����F�����ɖڗ����Ă���B
��������鐭��ł���D�P�����e�K���Ȃǂɂ��ẮAFOX NEWS ��MSNBC�͐^�t�ɗ�����Ƃ�B���a�}�x���҂͕ێ烁�f�B�A��M���A���x�������f�B�A���u�t�F�C�N�v�Ƃ̂̂���B����}�x���҂͂��̋t���B�Q�[�g�L�[�p�[�ƂȂ�ׂ����f�B�A�����E�ǂ��炩�̉����c�ƂȂ��Ă��܂��Ă���B
�u���f�B�A�̕��ɉ��v�̓��R�̋A����������Ȃ����A�����u�����V���[�v�����łɃA�����J�����ɂ��Ȃ�Z�����A�����̏�ɂȂ��Ă���_�͒��ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
2016�N�͂��߂̃s���[���T�[�`�̒����ɂ��ƁA�u�I���ɂ��Ă̍ł��L�p�ȏ�v(������)�́u�P�[�u���j���[�X�v��24����1�ʂ��߁A2�ʈȉ��ɂ́u�\�[�V�������f�B�A�v(14��)�A�u�n���ǁv(14��)�A�u�j���[�X�E�G�u�T�C�g�E�A�v���v(13��)�A�u���W�I�v(11��)�Ƒ����A���̎��Ɂu�n��g�l�b�g���[�N�̃C�u�j���O�j���[�X�v(10��)�ƂȂ�B���̎����u�[��R���f�B�ԑg�v(3��)�A�u�n�����v(3��)�A�u�S�����v(2��)�ƂȂ�B
���W�I�������Ă���̂́A������b��ɂ��钮��ҎQ���^�́u�g�[�N���W�I�v���Ƃ��ɕێ�𒆐S�ɍL��������Ă��邽�߂��B
�����A���ΓI�Ɍ����A�܂��ێ烁�f�B�A�̏�͑����͂Ȃ��B�ێ�̕���FOX NEWS�A�g�[�N���W�I�A����ɂ͕ێ�n�l�b�g�T�C�g�Ɍ�����B�V���̑����A�����āA�A�����J�̕����̊�ƂȂ�n��g��3��l�b�g���[�N�̃C�u�j���O�j���[�X���ǂ��炩�Ƃ����A���x�����F��������������Ȃ��B
���������̂��A��ʓI�ȁu���f�B�A�v�Ƃ������t�ɂ͕ێ�w�ɂ͋��۔���������B�Ⴆ�A2018�N�̃M�����b�v�́u���f�B�A��M�����邩�v�Ƃ��������ł͋��a�}�x���҂�21���������u�M������v�Ƃ��A����}�x���҂�76���Ƃ͑傫�ȍ��ƂȂ��Ă���B
���u���f�B�A�̕��ɉ��v�̕a��
�u���f�B�A�̕��ɉ��v�ɂ��āu���l�ȃ��f�B�A�����邱�Ƃ͂������Ɓv�Ƃ�������������B�����g����w�̋����Ƃ��āu�������͕����̃��f�B�A���ׂȂ���A���f�B�A�E���e���V�[��{���K�v������v�Ƃ��������Ă���B
���f�B�A��ǂ݉����\�͂͊m���ɏd�v���B�����A�����命���̐l�ɉۂ��̂́A��������ꂸ�Ɍ����A���̃G���[�g��`�ł���C���炷��B
�Ȃ��Ȃ�A�����I�ȃ\�[�V�������f�B�A�̕��y�̒��A�����̐l�X�ɂƂ��ẮA�t�ɏ���ǂ݉����ɂ������ɂȂ���邽�߂ł���B�A�����J�ł͂��łɁA�u�e���r�ΐV���l�b�g�v�Ƃ��������ł͂Ȃ��A�\�[�V�������f�B�A��ʂ��ăe���r��V���̏����L���`�d����悤�ȕ������f�B�A�̎���ƂȂ����B
�\�[�V�������f�B�A�̗��p�ŁA�����͏u���ɍL���`�d����悤�ɂȂ������A�\�[�V�������f�B�A�ł͎����̎x����������D��œ`����u�I��I�ڐG�v�u�t�B���^�[�o�u���v�̌X��������B
�ێ�Ȃ�ێ�̏��A���x�����Ȃ烊�x�����h�����̏����肪�����Ă���B���ߑ��̒��A���ꂼ��̏��͎����Ɠ��������I�ȉ��l�ς����w�����ŋ��L����Ă����B���͉�ꉻ����^�R�c�{�Ɖ�������B
�A�����J�̃��x�����h�̗F�l�������A�t�F�C�X�u�b�N��ŘA��MSNBC�Ȃǂ̃��x�������f�B�A�̂���̏����|�X�g���A�ɂ߂ė��\�Ȍ��t�Ńg�����v�哝�̔ᔻ�𑱂��Ă���B�ێ�h�̗F�l�͕ێ�T�C�g����̏��Ŗ���}�@���𑱂���B���N�̗F�l���������ASNS��Ŕ�ь����c�_�ɂ́A�͂����肢���Ă���ł͂���B
�����{�̃��f�B�A�ŋN���邱��
�Ō�ɓ��{�̏ɂ��Ă������Ă��������B�u�A�����J�Ɠ��{�̏͂܂����������v�Ƃ����w�E���p�ɂɎ邪�A����a��������B�A�����J�̐����I���ɉ���f�B�A�̕��ɉ��ɔ�ׂ�ƁA���{�̂ق��͂܂�����قǂł͂Ȃ��B
�A�����J�قǓ��{�̐��_�͂܂�����Ă��Ȃ��B�e�풲���ł͊����̃��f�B�A�ւ̐M�����ɂ߂č����ق��A����K�����܂߂ĕ�����̋K�����c���Ă���B
�����A����ł����{�ł͏������u���f�B�A�̕��ɉ��v�̒�������������B�����܂ł��Ȃ����A�ێ�n�̃l�b�g��ߔN���Ȃ��s�����Ă���B�ێ�n�̏��Д̔����D���Ȃ̂́A���{�̊����̃��f�B�A�ɑ��锽��������Ƃ�����B���̕ێ�̓��������āA���x�����h�̃l�b�g���������Ȃ茵�������̂ɂȂ����B
�A�����J���u�����������v��������͓��{���ʂ�̂�������Ȃ��B |
 |


 �@
�@ |
|
���u�p�����v�V���v�@���`��O�ɗh�ꂽ�����W���[�i���X�g�������@2019/8
�@ |
�����ʐM�ɂ��A4���A�����{�̏d�v�Ȗ����ٔ��̋L�^�̑������A�S���̍ٔ������p���������Ă������Ƃ����������B
�������͊T�ˎc����Ă������̂́A�R���ߒ��̕����������Ă���A�d�v�ٔ��L�^�̕ۑ��`���ᔽ�̋^��������Ƃ����B������ɂ��Ă�����ŁA�������ጛ���������đ���ꂽ���j�I�Ȍ��@�ٔ��̌����s�\�ɂȂ��Ă��܂����B
�挎22���ɂ́A���{�N���@�\�̓����L�掖���Z���^�[���A�l�����܂ޔN���֘A�f�[�^�����ڂ���DVD�����Ă����Ƃ��āA�ᔻ���W�߂�����ł���B�����Ȃ͂��̎��Ԃ�c�����Ă������A�I����܂Ō��\���Ȃ������B
���u���͂̊Ď��v�Ƃ������f�B�A�̖���
�ߔN�������A�d�v�Ȍ������̕����������B2007�N�ɂ͎Љ�ی����̃I�����C���������f�[�^�Ɍ���s�����������Ƃ��������A�N���L�^�̂�����ȊǗ����ᔻ����Ă��邵�A2017�N�ɂ͍����Ȃ��X�F�w�����L�^���A���㎩�q������X�[�_��PKO�h�������p�������Ƃ��āA����ɂȂ��Ă���B
���������Ɏa�荞��ł����ׂ��́A����ƕ@�ւ��B�א��҂Ɗ����̕s�ˎ����������A���Ɍ�҂Ɋ��҂������Ƃ��낾���c�c�ǂ����낤���B
������グ��̂́A�X�e�B�[�u���E�X�s���o�[�O�ē�2017�N�̘b���w�y���^�S���E�y�[�p�[�Y/�ō��@�������x�B�x�g�i���푈���D�������钆�ŁA�Đ��{�������ɉB���ʂ��Ă����푈�̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��悤�Ɩz������A�V���Ђ̐l�X�̓�����`���Ă���B��90��A�J�f�~�[�܂ō�i�܂Ǝ剉���D�܂Ƀm�~�l�[�g���ꂽ���A���X�̉f��܂���܂����B
�u���̌��͂ɑ���Ď��v�Ƃ������f�B�A�̖����ƕ̎��R��搂��グ��A���ɃX�g���[�g�ȃ��b�Z�[�W�������ꂽ�{��ł́A���_�l�������ĎЉ^��q�����V���Г��m�̂��荇���A�L�҂����̗��̋삯�����Ȃǂ��X�������O�ɕ`�����B
���ł��A���V���g���E�|�X�g�̎Ў�L���T�����E�O���n�����A�l�ԊW�Ɨ��Q�W�̞~���ɔY�݂A�i�ނׂ��������o���Ă����ߒ��������[���B
���u��X�����Ȃ��ĒN�����v
�j�N�\���哝�̐�������71�N�A��т��Đ틵�͕č����ɗL���Ɠ`�����Ă����x�g�i���푈�����A���̓����͈���Ă����B�}�N�i�}�����h�����̌��ŁA�x�g�i���푈�̕��́E�L�^�̍쐬�Ɋւ�����R���A�i���X�g�A�G���Y�o�[�O�́A���̍��h�Ȃ̍ō��@�������A�ʏ́u�y���^�S���E�y�[�p�[�Y�v���Ζ���̌��������玝���o�����ʁA�ꕔ���j���[���[�N�E�^�C���Y�̋L�҂ɗ����B
�^�C���Y���̃X�N�[�v���Љ��k�������钆�A���V���g���E�|�X�g�̕ҏW�劲�x���E�u���b�h���[(�g���E�n���N�X)�́A���Ƃ��c��̕�������肵�悤�Ǝ���A�}�N�i�}�������ƗF�l�W�ɂ���Ў�̃L���T�����E�O���n��(�������E�X�g���[�v)�ɁA�������當������肷��悤�i��������A�L���T�����͔ƍߍs�ׂ��Ƃ��ċ��ہB
����Ȓ��A�����҂���f�X�N�ɕ����̈ꕔ���͂����ċL���쐬�̃`�����X�ƂȂ����̂����̊ԁA�܂����j���[���[�N�E�^�C���Y�ɐ���z����Ă��܂��̂����A������30�N�ɂ��킽��B���H����x���X�N�[�v�������ƂŁA�j���[���[�N�E�^�C���Y�͐��{����L���̍����~�߂�v�������B
�x���͕����Ƀ��[�N�����l���Ƃ̐ڐG�𖽂������A�����`�����X���ƍĂуL���T����������B�u��X�����Ȃ��ĒN�����v�Ƃ������t���A�T�d�������ޏ��̐S�ɏ����ȉ�t����B
�₪�āA�����ʂ��đ�ʂ̕������^�э��܂�A�|�X�g�̎Г��́A�@���ی�@�ᔽ��`���Ăł��f�ڂ��A�Ђ���邽�߂ɒ��~���ő�h��ɗh���B
�L���T�����̓��V���g���|�X�g�̎Ў傾�������������A���S����͕v�t�B���b�v���Ղ��p�������߁A�����ƕ⍲�ɓO���ė��������ł���B�����t�B���b�v���}�����Ă��Ȃ�������A���E�ɒm�Â̑����Z���u���e�B�Ƃ��āA�₩�ȎЌ��Ɖƒ�𒆐S�ɐ����Ă����ł��낤�B���͎Ў�Ƃ��Čo�c�������p���^���Ɏ��g��ł��邪�A������ł͂܂��S�ʓI�ȐM�p�Ă��Ȃ��B
���M���ł���u���v�Ǝ�̂�����u���q�v��
�������В��ɂȂ邱�Ƃ��A����������ł���B�v�l�v�Ȃ��W���z�[���p�[�e�B�ł��A�H���̌�A�ȒB�͕ʎ��Ɉړ����ăv���C�x�[�g�Șb�A�e�[�u���Ɏc�����v�B�͐����̘b�B�W�F���_�[�K�͂͂������肵�Ă���B�L���T�����̂悤�ɁA�����Ȃ�g�b�v�̒j���̌㊘�ɍ����������́A�O���炻�̎��͂ɂ����j���B�Ɍ������ڂŌ�����̂��B
���̂��Ƃ��L���T�������\���ӎ����ĐT�d�ɐU�镑���Ă��邪�A�����ْ��ɎN����Ă��邱�Ƃ��`����Ă���B�x���Ƃ̒��H��ł̓A�^�t�^���Ĉ֎q��|������A��s�ƂƂ̉�ł͕������������o������������߂���Ɨ��������Ȃ��B
�������ǂ�ȏ�ʂł��傫����藐�����ƂȂ��A�ǂ�Ȑl�ɂ��Ί�ʼn��₩�ɑΉ����悤�Ƃ���ԓx�ɂ́A�N��ƌo���Ȃ�̂��̂���������B�������E�X�g���[�v�̗}���C���̉��Z�ɂ���āA�u�����В��v�Ƃ������߂̃C���[�W�����A�L���T�����̐^�ʖڂŗD�����l���������яオ���Ă���B
����Ȕޏ����A�Ɏx���Ă����̂́A�������̃t���b�c���B�d���炵�������������Ȃ܂��Ɛe�g�ȃT�|�[�g�Ԃ�́A�����ɂ��M���̂�����w����Ƃ����������B�L���T�����ɂƂ��Ă͉��ł����k�ł���u���v�̂悤�ȑ��݂Ɍ�����B
����A�x���́A��͂����邪���������u���q�v�Ƃ������Ƃ���B�L���T�������j���[�Y�E�B�[�N������������������̔ނ́A��ނɌo���ɂ��܂Ȃ����ߖ������͕]���������B�������A�����Ȗʂ͂��邪�������������菶�������͂ɋ����Ȃ��p�����A�L���T�����̐^�ʖڂ��Ƌ��������B�y����@�������Ƃ���͓��u�Ƃ��������͋C���B
�u�y���^�S���E�y�[�p�[�Y�v�̌f�ڂ�����A�ЂƃL���T�����������܂Ŏ�肽���t���b�c������A�ږ�ٌ�m�ƁA�u�̎��R�v���咣����x�����������Η����钆�ŁA�L���T�����͋ꂵ�ށB
���V���g���E�|�X�g�̓z���C�g�n�E�X�̂��G���ł���A�L���T�����̈ꑰ�͗��̑哝�̂Ƃ̐e��������A�Q���̐l�ł���}�N�i�}�������͔ޏ��̒��N�̗F�l�Ȃ̂��B
�����Ńt���b�c�̏����ɏ]�����Ƃ́A����v�������Ă������Ƃ̌p�����Ӗ�����B����͌Â������S�Ȑ��E���B�x���̎咣�ւ̓��ӂ́A�댯���ڂ݂�����̎p�����������ƁB���s����u���ꂾ���珗�́v�Ƃ����ڂŌÎQ�B���猩���邾�낤�B�u�ېg�����`���v�̗��ɂ́u�p�����v�V���v�Ƃ����A�ޏ��ɂƂ��ďd���I�����������̂��B
���f�������L���T�������A�����ʼn��x���J�Ԃ��uLet�fs go!�v�̐����ƔM�ɂ́A���ɔ�߂��W���[�i���X�g�Ƃ��Ă̋����������h���Ă���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�����X�̌����NA�̎�L�w��́x�@2015/6
|
�y�������u���_�̎��R�v�Əo�ł̈Ӌ`
�_�˂̎����A���E�������̉��Q�҂ł���u�����NA�v(32)����������14�����o������L�w��́x(���c�o��)�ɁA���X������N���Ă���B�{�ɑ���]���͐l���ꂼ�ꂾ���A�u����Ȃ��͓̂ǂ݂����Ȃ��v�Ƃ����l�����Ă�������O�B�����C�ɂȂ�̂́A�u�⑰�̋��Ȃ��o�ł��ׂ��łȂ��v�u��Ŏ����͂��ׂĔ�Q�҂ɓn�����߂̖@�������v�ȂǂƏo�łɑ���K�������߂铮����A�s�����{�̔̔���w���̎��l�����߂���A�݂��o������������}���ق��o��ȂǁA�\���̎��R�ɂ�������铮�����o�Ă��邱�Ƃ��B
���u������ɂ��ꂽ�u�\���̎��R�v
��Q�҂�1�l�ł���y�t�~�N(����11)�̕��e�A�炳��́A��L�̏o�łɋ����������A��ʂ��ĕ���̃R�����g�\�B�o�ŎЂɂ���������߂鏑�ʂ𑗂����B�y�t����́A�o�łɂ���āu�d�Ăȓ�Q�v���Ă���Ƃ��A���Q�҂ɂ���L�Ȃǂ̏o�ł́u��Q�҂̏�����ׂ��ł���v�Ǝ咣���Ă���B
�ȑO�AA�̗��e����L�w�u���NA�v���̎q��Łx(���Y�t�H��)���o�ł��������A�y�t����͎��O�ɗ����Ȃ��������ƂȂǂ������ᔻ���Ă���B���N4���A�������u���Y�t�H�v5�����ɁA��Ï��N�@���v�ɂ����_�ˉƍق̌���S�����f�ڂ��ꂽ���ɂ��A�y�t����͍R�c�̐����グ���B�ނ����������������Ƃ�����A���g���R���g���[���ł��Ȃ��`�ň����̎E�Q�ɂ�������������邱�ƂɁA�����x���S������Ă���̂��낤�B
����������Q�҂̐S����l����A�⑰���@�ւ���o�ł�m�炳��ċ������Ƃ��Ȃ��悤�A�����O�ɂ͖{�̊T�v�Ȃǂ�`���Ă������ق����悩�����BA�����Ȃ��Ȃ�A�o�ŎЂ����ׂ��������낤�B����́A�⑰�ւ̔z���ł���Ɠ����ɁA�o�ŎЂ����҂̗������邽�߂ɂ��K�v�������Ǝv���B
�����A���O�ɓ`�����Ƃ��Ă��A�y�t����͏o�łɔ[�����Ȃ��������낤�B���̐S��⎩�g�̌������A�y�t���q�ׂ�͎̂��R���B�����A�u���Q�҂̏o�łɂ͔�Q�҂̏�����ׂ��v�Ƃ̌������A�u�\���̎��R�v�ɕq���ł���ׂ����f�B�A�̑������A������Ƃ��������_�]���Ȃ��܂ܕ����Ƃɂ͋^���������B
�������A�u�\���̎��R�v�ƂāA��ł͂Ȃ��B���_�ʑ���v���C�o�V�[�̐N�Q�ɓ�����Ƃ��ďo�ł������~�߂�ꂽ��A�@���ŋւ���ꂽ�킢���}��ɓ�����ȂǂƂ��ꂽ�ꍇ�ɂ͌Y���܂ʼnȂ�����B���̔��f�������͍̂ٔ����A�ŏI�I�ɂ͍ō��ق��B
�߂�Ƃ����҂Ƃ����ǂ��l�Ԃł���A���̐l����u�\���̎��R�v�Ƃ�����{�I�l�������グ�邩�ۂ��Ƃ����ō��ٍٔ����̂悤�ȏd���������A�⑰�ɒS�킹�邱�Ƃ��ʂ����ēK�Ȃ̂��낤���B�������������I�Ȗ₢���A���f�B�A�͂����Ɣ�����ׂ����낤�B
����Ɂu��Q�ҁv�u�⑰�v�Ƃ����Ă��A�l�����⊴�����͈�l�ł͂Ȃ��B���f�B�A�ł́A�y�t����̔���������ɓ`�����Ă��邪�A��͂�A�ɂ���ĎE�Q���ꂽ�R���ʉԂ����(����10)�̕�e�A���q������R�����g���o���Ă���B���q����́A�ˑR�̏o�łɌ˘f���Ȃ���A�u�Ȃ�̂��߂Ɏ�L���o�ł����̂��Ƃ����ނ̖{���̓��@���m�肽���ł��v�Əq�ׂĂ��āA�y�t����Ƃ͈�����v��������悤�Ɏ���B
��������Q�҂ł��قȂ�~�ߕ�
����܂ł��A���Q�҂���L�������������͂���������B�A���s�X�g���ˎE�����̉i�R���v�́A��L�w���m�̗܁x(�����o�ŁA�̂��͏o����)�\���Ē��ڂ���A�Ȍ�A���Y�����s�����܂ō�����ƂƂ��Ď��M�𑱂����B���w�܂��Ă���B�⑰���o�ł�ᔻ�����Ƃ����ɐڂ������Ƃ͂Ȃ����A�i�R�͓��{���Y�Ƌ���ւ̓�������ۂ��ꂽ�B���̂��ƂɍR�c���āA���J�s�l�A���㌒���A����N���A������j�炪�����E��Ă���B
�I�E���^�����̒n���S�T���������ł́A�ŏ��Ɏ����ւ̊֗^���������A�ٔ��ł͎��F�߂��Ė��������ƂȂ����ш�v���A��L�w�I�E���Ǝ��x(���Y�t�H��)�����M���Ă���B
�т��܂����T�����ɂ���ĕv���E�Q���ꂽ�����V�Y������́A���̏o�ł�Œm�����B�і{�l����͂������A�ٌ�l��o�ŎЂȂǂ���A���O�ɘA���͂Ȃ��A����Ɏ莆�⌣�{���Ȃ������B
�u�ٔ���T�������l�͂킸�������A��ɂȂ��Ă��玖����m�肽���l�����邾�낤����A���������L�^���c�����Ƃ͕K�v���Ǝv�����̂ŁA�ʂɕ��������Ȃ������v�ƍ�������B
��������͍ٔ���T�����A�т̋��q��،����Ă���A����������Ă��邩�͎@���������̂ŁA�����ɓǂ݂����Ƃ͎v��Ȃ������B
�u�ł��A�ォ��ǂ݂����Ȃ邩������Ȃ��Ǝv���āA�{������ň�������܂����v
��������́A�㐢�Ɏ����̋L�^���c�����߂ɂ́A��Q�҃T�C�h�̋L�^���K�v���ƍl���A���̌�A���g�̎�L���o�ł��Ă���B
�H�t�������ʎE���������N�����������q�厀�Y�����A��L�w���x(��]��)���o�����B��Q�҂�⑰����́A���̓��e�Ɂu�q�ǂ��̌�����v�ȂǂƔᔻ�̐����オ���Ă��邪�A�o�ł��̂��̂��Ƃ��߂�Ƃ��������ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤���B
���̂悤�ɁA�ƍ߂̔�Q�҂ł��~�ߕ��͂��낢�낾�B�y�t����̌����́A�y�t����l�̌����ł����āA��Q�҂��\���錩���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����낤�B����ɁA����13�l�A�d�y���҂�6300�l������n���S�T���������̂悤�ȃP�[�X�ł́A��Q�҈�l�ЂƂ�̏����邱�ƂȂǕs�\�Șb���B�u���Q�҂͔�Q�҂̗������Ȃ���Ώo�ł��Ă͂����Ȃ��v�ȂǂƁA��ʉ����ċc�_�ł���b�ł͂Ȃ��B�����Ɨ�ÂȎ~�߂��K�v���B
���w��́x�o�ł͖��Ӗ��ł͂Ȃ�
�w��́x�ɂ��ẮA���Ύs�����X��s���Ɂu�z���v�����߁A��[��s�����u�⑰�̓��ӂȂ��o�ł���邱�Ǝ��̋�����Ȃ��s�ׂŁA���S���Ăق����Ȃ��B���l�̎v���Ƃ��Ă͔���Ȃ��łق������A����Ȃ��łق����v�Ɣ����B�������Q�Ҋ���ɑ���z���Ƃ����Ă��A�����̂̒����o�ŕ��̔̔���w���̎��l��v�������|�̔���������̂͐q��ł͂Ȃ��B
�}���قɂ��{�������̓������o�Ă���B���Ύs�}���قł͖{���w�������A���Ɍ����}���قł݂͑��o�������Ƃ��āA�u�����ړI�v�Ɍ���ٓ�����ʼn{����F�߁A���ʂ͈�ؔF�߂Ȃ��A�Ƃ����B
���������Q�Ҋ���ɔz�����邠�܂�A�l�X�̒m�錠�����ߏ��Ɉ����Ă͂��Ȃ����낤���B�}���يW�҂́A���{�}���ً���̑������u�}���ق̎��R�Ɋւ���錾�v��ǂݒ����Ă��炢�����B
�܂��A��Ŏ����̈������߂����āA�����̃��f�B�A�Ɂu�T���̑��q�@�v�Ȃ�č��̖@�����Љ��Ă���B�ƍ߂̉��Q�҂��ƍߍs�ׂɊւ���L�̏o�łȂǂœ����������A��Q�҂̐\���ɂ���Ď��グ�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���@���Ɛ�������Ă���B���������@���̐�������߂鐺�����܂��Ă���Ƃ���������A�l�b�g�ł̃A���P�[�g�ł����l�̌��ʂ��o�Ă���悤���B
�������A���Ȃ��Ƃ�����̃P�[�X�ł́A���s���x�őΉ����ł���͂����B�y�t����1���~�̑��Q���������߂������ٔ��́AA��������Ȃ��������ߐ����ʂ�̋��z�Ŕ������m�肵�Ă���B�u�T�����t�v(���Y�t�H�Ё^6��25����)�ɂ��ƁAA�Ɨ��e�́A���̔�Q��2�l�̕����܂߂đ��z��2���~�̔����ӔC�����B���e�̎�L�̈�ł�A�̕��e�̑ސE���ɉ����A����A���g��1���~�A���e��6���~�قǂ̎x�����𑱂��Ă��邪�A���݂ł�1�����疜�~�̕����c���Ă���Ƃ����B
���̏ꍇ�A�y�t����́AA�̈�Ŏx������������������������Ȃǂ̖@�I�[�u���Ƃ邱�Ƃ��ł���B�O�q�����I�E�������̗ш�v�̖{�ɂ��ẮA�⑰�ł͂Ȃ���Q�҂���ł�������������葱���������ƕ����B�\���̎��R����Y���̂����Ŗ��ɂȂ肻���ȐV���Ȗ@������ċK�����Ȃ��Ă��A���łɖ@�I��i�͗p�ӂ���Ă���B���f�B�A�́A������������Ɠ`����K�v������̂ł͂Ȃ����B
�܂��w��́x�̕ҏW�҂́A�l�b�g���f�B�A�̎�ނɑ��āA�u���Җ{�l�́A��Q�҂ւ̔������̎x�����ɂ��[�Ă�Ƙb���Ă��܂��B����܂Œ��Ҏ��g�Ƃ��Ă͔��X����z�����A�x�����Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł��̂Łv(�ٌ�m�h�b�g�R�����)�Əq�ׂĂ���A�킴�킴�y�t���@�I�[�u���Ƃ�K�v���Ȃ���������Ȃ��B
��́u�T�����t�v�ɂ��AA�͎��M���Ă���Ԃ̐�������o�ŎЂ����Ă���炵���B�܂��A���ꂾ���̑����ɂȂ�A���炭�A���o�C�g�����邱�Ƃ�������낤�B������l����ƁA�S�z�����グ��Ƃ����͍̂��ɉ߂���悤�ȋC������B��������܂܂�Ȃ��ɒǂ����߂A�Љ�ɑ��鍦�݂�a�O�����点�邾���͂Ȃ����B�߂�Ƃ��A�ٔ�������߂������[�u���I�����҂��Љ����Ȃ���A����Ă���鏊�͌Y���������Ȃ��Ȃ�B
�`���ɏ������悤�ɁA�ЂƂ��яo�ł��ꂽ�{�ɑ���]���͎��R�ł���B���̖{�ɑ���ǂ�ȍ��]�������Ă悢�B�����A�{�̏o�ł̈Ӗ����܂������Ȃ����̂悤�Ș_�]�́A�����߂��̂悤�ȋC�����Ă���B
�ނ̍X���̂��߂ɁA���N�@�����މ@���Ă�����A�����̐l���ނɊւ�������Ƃ��A���͂��̖{�ŏ��߂Ēm�����B���e�ƂȂ��Ĕނ����ꂽ�v�w������B���������l�����Ƃ̊ւ��̒��ŁA�ނ��������u���v���������Ă������o�܂����Ď��āA�ƍߎ҂̍X���Ƃ����_�ł��낢��l����������Ƃ��낪�������B
A���N�������������^�����e���͑傫���B�u�Ȃ��l���E���Ă͂����Ȃ��̂��v�Ƃ����₢���Ⴂ�l���甭����ꂽ��A�E�l��Ƃ����҂��u�N�ł���������l���E���Ă݂��������v�Ƌ��q���鎖�����������N���Ă���BA�͈ꕔ�̐l�����Ɂu�_�v��������A���É��ŏ������S�E�������q�吶�Ȃǂ��A�uA�h���Ă���v�Ɠ`�����Ă���B
����A���A���̖{��ǂތ���A�߂̑傫���ɂ��̂̂��u�����̐l�ԁv���B�u�Ȃ��l���E���Ă͂����Ȃ��̂��v�̖₢�ɁA�ނȂ�̓������o���Ă���B���̖{���A�ނւ̘c�u���h�v��u����v���F�����邫�������ɂȂ�Ɗ肤�B�@(�����]��Ўq)
|
|
���W���[�i���X�g������ �@2015/6 |
�u��́v�̏o�ł̐���͌����A�W���[�i���X�g�����̌y���ȋc�_�ɂ��Ă����Ɏv�����B�����āA���̌y�������A�����̗̕Ɍq�����Ă���C�����ĂȂ�Ȃ��B
�W���[�i���X�g�]��Ўq���̋L�������p���Ȃ���A�R�����Ă��������B�ȉ��A���p���́u�v���Ɏ����܂��B
�u�����C�ɂȂ�̂́A�u�⑰�̋��Ȃ��o�ł��ׂ��łȂ��v�u��Ŏ����͂��ׂĔ�Q�҂ɓn�����߂̖@�������v�ȂǂƏo�łɑ���K�������߂铮����A�s�����{�̔̔���w���̎��l�����߂���A�݂��o������������}���ق��o��ȂǁA�\���̎��R�ɂ�������铮�����o�Ă��邱�Ƃ��B�v
�]�쎁�̎咣�Ƃ��ẮA��L�̂悤�ȁu�\���̎��R�v���K�����铮���͂��������Ƃ������Ƃł��B�����܂��B
�u�y�t����͍R�c�̐����グ���B�ނ����������������Ƃ�����A���g���R���g���[���ł��Ȃ��`�ň����̎E�Q�ɂ�������������邱�ƂɁA�����x���S������Ă���̂��낤�B����������Q�҂̐S����l����A�⑰���@�ւ���o�ł�m�炳��ċ������Ƃ��Ȃ��悤�����O�ɂ͖{�̊T�v�Ȃǂ�`���Ă������ق����悩�����B�v
�l�͂��̈ꕶ��ǂ�ł��ߑ������łȂ������B���ꂪ���̈�A�̎����Ɋւ���u�o�ł��鑤�̏����v�Ȃ̂��B
�y�t���̍R�c���͓ǂ܂��Ă������������A�⑰�̎咣�́u�����R���g���[���ł��Ȃ����Ƃւ̌x���S�v���痈�����̂ł͂Ȃ��B ����ȏ㏝���L���Ȃ��ł���A�Ƃ����ߒɂȋ��т��B
�q�ϓI�Ɍ���u�����R���g���[���ł��Ȃ����Ƃւ̌x���S�v�������Ă���̂́A�ǂ��l���Ă��]�쎁���͂��߂Ƃ���u�\���̎��R�v�𐺍��ɋ��ԃW���[�i���X�g�̂ق��ł͂Ȃ����낤���B�l�����������Ɠ����悤�ɍl����Ǝv���ȁA�ƌ��������B
�y�t�����g���������ꂽ�u���O�ɗ������K�v���v�Ƃ����咣��_�_�ɘb�͐i�ނ��A�u�⑰�����S�̏��ւ̔z���v�́A���̍]�쎁�̕��͂���X�|�b�Ɣ��������Ă���B
���̕��͑S�̂�ʂ��āA�_�_�ɂ�����Ă��Ȃ��̂ł���B
�����č]�쎁�����O�ʒm�͂��ׂ����Ƃ͌������A����͈⑰���u�������Ȃ��v�ׂł��B�J���������ӂ�����Ȃ��B
�]�쎁�̕��͑S�̂ɒꗬ���Ă���̂́w�\���̎��R�x�Ƃ������̂��߂Ɍl�͋]���ɂȂ�ׂ����Ƃ����v�z�ł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
��Q�҉Ƒ��́A���Ԃ��̂��Ȃ��悤�ȁA�傫�ȐS�̏����Ă���B�l����l�������邪�A�z�����邾���ł��ς���B
�l�l�̎咣�́A�u�\���̎��R�v�͌l�̑���ȋ]���ɗD�悳��Ă܂Ŏ����ׂ��ł͂Ȃ��A�Ƃ����b���B
�c�O�Ȃ���A���̖₢�ɐ��ʂ�����g��ł���W���[�i���X�g�̌����ɂ͂܂����ڂɂ������Ă͂��Ȃ��B
�����āA�⑰��艽���A��ԑ厖�Ȏq�������ւ̒����̔O������Ȃ��B����D��ꂽ�q�������ցA�Ȃ�ƌ����̂ł��傤���H�u�\���̎��R�v�����狖���ĂˁH�Ƃł������̂ł��傤���B
�w���x������ɂ���l�́A�M�p�ł��Ȃ��B
�]�쎁���g���A���̎����ɂ����āA�Ȃ��u�\���̎��R�v���A��Q�҂̐S���I���S�ɗD�悳���ׂ��Ȃ̂��Ƃ����ʓI�Ȍ����͏q�ׂ��Ă��Ȃ��B
�u�\���̎��R�v�����邩��u�\���̎��R�v��ۏ��ׂ��ł���Ƃ������ӕ��������Ȃ��̂�����A���ł��Ă��܂����B
�u���̔��f�������͍̂ٔ����A�ŏI�I�ɂ͍ō��ق��B�߂�Ƃ����҂Ƃ����ǂ��l�Ԃł���A���̐l����u�\���̎��R�v�Ƃ�����{�I�l�������グ�邩�ۂ��Ƃ����ō��ٍٔ����̂悤�ȏd���������A�⑰�ɒS�킹�邱�Ƃ��ʂ����ēK�Ȃ̂��낤���B�������������I�Ȗ₢���A���f�B�A�͂����Ɣ�����ׂ����낤�B�v
�_���̔����r�������B�����I�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��ƍl���Ă���̂ł��傤�B (�������A���f�B�A���ł���Ƃ������o�͂Ȃ��炵���B)
����ɂ��Ă��A���̘_���͂��������B�⑰�̕��́A�����NA�́u�\���̎��R�����グ��v�ȂǂƂ͈ꌾ�������Ă��Ȃ��B����ȏ�A�������L����Ȃƌ����Ă��邾�����B
�⑰�͈⑰�Ƃ��āA�����u��{�I�l���v���咣����Ă���B������P���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�����āA�]�쎁�́w�ō��فx�Ƃ������Ђ�_���Ɏ����o���B(�ǂ����̍��̐��{�Ǝ��������ł��邱�Ƃ͌��킸�����ȁA�ł��ˁB)
���̘_����W�J����ƁA���_�ʑ����́A�ō��ق��o���ׂ��ł���̂ŁA�o�ŋƊE�͔��f����K�v���Ȃ��A�Ƃ������ɖ��ӔC�ȍl���ɍs�������B
��������āu�\���̎��R�v�Ƃ�����`�����Ɓu�o�ŋƊE�̐E���̘b�v������ւ��Ă͂����Ȃ��B
�u�\���̎��R�v���ۏ���Ă���̂ł���A�u�\���̎��R�̊�@�v�Ƃ���������{���ł͂Ȃ��A�W���[�i���X�g�Ƃ��ĂȂ��u��́v�̏o�łɐ�����������̂��A���̌��Ɋւ��Ắu�\���̎��R�v���A�Ȃ��⑰�ւ̔z�������D��I�ɕۏ����ׂ������A���X���X�Əq�ׂ�ׂ��ł͂Ȃ��̂��H
�u�\���̎��R�v�Ƃ��������������g���āA�ς܂����C�ɂȂ��Ă���̂́A�W���[�i���X�g�̑Ӗ����B
(MR.�T���f�[�ɏo�������u�W���[�i���X�g�v�|�c�\�ᎁ���u�\���̎��R�v���J��Ԃ������ł����B)
�u�u���Q�҂͔�Q�҂̗������Ȃ���Ώo�ł��Ă͂����Ȃ��v�ȂǂƁA��ʉ����ċc�_�ł���b�ł͂Ȃ��B�����Ɨ�ÂȎ~�߂��K�v���B�v
�����Č㔼�́u�⑰���ɂ��F�X�Ȉӌ�������v�Ƃ��������������B���������Ȃ������⑰������A�Ƃ������Ƃ����A��������ɂ��Ă���̂́u�����������⑰������v�Ƃ������Ƃ��B
�����ł͉������������̂��A�܂������킩��Ȃ��B
�u�������Č����Ă�l�����邶���v�Ƃ������w�����x���̌����Ȃ̂��H
�u��ʉ��͔�����v�Ƃ������̌��t�ɏ]���A��Q�҂ɂ���ČʓI�ɔ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ł���u�o�łɂ���Ĕ�Q����v�Ǝv���Ă����Q�҂ɔz�����ׂ��Ȃ͓̂��R�ł���B
���炩�ɘ_���I�ɓ|�����Ă���A�������������̂��܂������s���ł���B
�ʂɐF�X�Ȕ�Q�҂����邱�Ƃ��Љ��͈̂����Ƃ͌���Ȃ��B�����A����������u�\���̎��R�v����Q�҂̐l���ɗD�悳���A�Ƃ������_�͓����o����Ȃ��B
�����Ď��́A�o�ł�s���Ǝv��Ȃ���Q�҂�����ƁA������ʉ����悤�Ɠǎ҂Ɏd�����Ă���͍̂]�쎁�̕��ł���B
(���̈�ʉ��Ɋւ��锭���̒��ŁA�Ȃ�炩�̌��_���_���I�ɓ����ꂽ�킯�ł͂Ȃ����A���ǁu���������Ȃ���Q�҂�����v�Ƃ������Ƃ𝈝����Ă��邾���Ȃ̂́A������ǂ�ł���������Ε����邩�Ǝv���܂����A���ɔڋ��Ȃ����ł��B)
����ɁA�d��Ȃ̂́u�\���̎��R�v���B�ꖪ�Ɏg���āA�u�\���̎��R���ۏ���Ă��邩��Ƃ����āA�o�ŎЂ���Q�҂̐S���I���S���l�����ɉ��ł��o�ł��Ă����Ƃ͌���Ȃ��v�Ƃ����������A���͋K�����Ă���Ƃ������Ƃ��B
�����̔������u�\���̎��R�v��D���Ă���Ƃ����|���ɂ͋C�t���Ă��Ȃ��B
�l�̂悤�ȁu�\���̎��R���ۏ���Ă��邩��Ƃ����āA�o�ŎЂ���Q�҂̐S���I���S���l�����ɉ��ł��o�ł��Ă����Ƃ͌���Ȃ��v�Ƃ����������̂����R��ۏ���Ă�����ׂ����B�]�쎁�����������I�ɂ����ł��邩�炵�����Ȃ��B
�u�{�̏o�ł̈Ӗ����܂������Ȃ����̂悤�Ș_�]�́A�����߂��̂悤�ȋC�����Ă���B�v
�����������t�̒[�X�ɂ́A�]�쎁�̎�̐����������Ȃ��B�u�����߂��̂悤�ȋC�����Ă���v�̂ł����āA�����߂��ł���Ƃ����f��͔����Ă���B
�u�\���̎��R�v��^�����ɁA�����̌��t��s�����Č���Ăق������̂ł���B
���ɐ}���ق̉{�������ɘb�͈ڂ�B
�u�}���قɂ��{�������̓������o�Ă���B���Ύs�}���قł͖{���w�������A���Ɍ����}���قł݂͑��o�������Ƃ��āA�u�����ړI�v�Ɍ���ٓ�����ʼn{����F�߁A���ʂ͈�ؔF�߂Ȃ��A�Ƃ����B�v
�u���������Q�Ҋ���ɔz�����邠�܂�A�l�X�̒m�錠�����ߏ��Ɉ����Ă͂��Ȃ����낤���B�}���يW�҂́A���{�}���ً���̑������u�}���ق̎��R�Ɋւ���錾�v��ǂݒ����Ă��炢�����B�v
����́u�\���̎��R�v�����ł͂Ȃ��A�u���@�v�����炷�ׂ����I�@�ւƂ��āA���Ђւ̃A�N�Z�X���u��������(�֎~����킯�ł͂Ȃ�)�v�Ƃ�����Q�ґ��́u��{�I�l���v�ɂ������ӎv�\���ł���B
����̍�Ƃ����Ă��������낤�B
���ۖ��A�ǂ݂����̂ł���A�����Ă�X��T���Ĕ����ēǂނȂ�A���̐}���قœǂނȂ�A�������邩��ƌ����Ă��̐}���قŎ������B
�u�m�錠���v���y�Ă���ƌ������A��������L�̒ʂ��ʎs���́u�m�錠���v�͎����Ă͂��Ȃ��̂����A�ނ��낱�̒��x�̐����œǂ܂Ȃ��Ƃ����̂́A�ǂޓ��@���Ȃ������ł���B���ɔ�_���I���B
�u�}���يW�҂́A���{�}���ً���̑������u�}���ق̎��R�Ɋւ���錾�v��ǂݒ����Ă��炢�����B�v
�ĎO�g���邱���������\���ɖl�͌�������������B�u���[�������v�Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ����A�u���R�Ɋւ���錾�v�ɂ��Ă̒��g���A��̓I�ɏq�ׂȂ��̂��̂ł��B���������ɂ�菑���Ȃ��̂ł�����̎|�L����Ȃ�A�����N��\��Ȃ肷������B
�����ɂ������́u���Ёv��_���ɐ����Ă���B���Ђ�_���Ɂu�\���̎��R�v��u�m�錠���v���Q�҂ɉ����t����W���[�i���X�g�����ɁA���̐}���ق̌��f����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���B
�܂��Ō�ɁA�]�쎁�͐G��Ă��Ȃ����A�⑰�̍R�c���ɂ�����悤�ɁA���ꂪ�M�d�ȃT���v�����Ƃ����ӌ��ɂ��āB
�l�͑S���^���Ȃ��B
���ꂾ���u���قȎ����v���A���̎����ւ̃T���v���Ƃ��ċ@�\����̂ł��낤���H�s��ɗ��ʂ����{��ǂ�ʐl�������A�������ɂǂ��������Ƃ����̂��H
�����炭�l�X�̂��̏����ȍD��S�����������낤�B��̓I�ɂǂ��M�d�Ȃ̂��A�ǂ����p�����ׂ��Ȃ̂��ɂ��Ă��A ���̎咣������l�ɂ͌��t��s�����Ăق����B
�܂�������u�q���[�Q���̃W���E�v���Ƃ������̂ł��傤���B
�]�쎁�́u�\���̎��R�v�u���@�v��_���Ɏ����o�����A�]�쎁���g���ǂ��v���̂��A�Ƃ����ӌ��͌���Ă��Ȃ��B
���̎�̕s�݂̌����ɂ����A���f�B�A�̌���������Ǝv���Ă���B
�����āA�����܂Ō��Ă����悤�ɂ��̂����W���[�i���X�g�̕��͂̒��Łu���Ёv�������ő�̘_���ł���̂�����A���́u���Ёv���������悤�Ƃ���͕̂K�R�̋A���ł���B
���̂��Ƃ��u������b�v�ł��邱�Ƃ�_���ɋc�_��i�߂鑍����b��A�u�s�����s���v��ɂ��āA���g�̑����鎩���̎��̂��Ԃ��ׂ����Ƃ����s���ݏo�����J���N���ł���A�Ƃ����̂��l�̍l���ł��B
���͌����̖\����т̃^�l�ɂ��Ă����W���[�i���X�g�������ʂ����ăW���[�i���X�g�Ƃ��ĔF�߂Ă����̂��A�A
�W���[�i���X�g�����������Ƃ́H
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���V���L�҂����� ���i�搶�������肷��ɂ������� |
���܁A�u�}�X�R�~�v�Ƃ����B�W�݂̂Ȃ炸�A���悻�d�g�⊈����}�̂ɂ���g�D�I�ȏW�c�͏\�c�ꗍ���Łu�}�X�R�~�v�̏̍����^�����Ă��܂��B�����āA���̏̍��͂��������ᔻ�I�ȗv�f���܂ݍ���ł���Ƃ�������B
�l���Ă݂�A���́u�}�X�R�~�v�ɂ́A���ꂼ�ꎞ�������ŗL�̐��藧��������B�V���̑��芢�ł͍]�ˎ��ゾ���A�����I�Ș_���킵��������S�����͖����B���̌�A���W�I�A�e���r�Ƒ����Ă����̂ł���B���ł����Ɂu�}�X�R�~�v�Ƃ�����Ƃ����Ƃ����ڂȊW������̂̓e���r�ł���ƌ����č����x������܂��B���邢�́A���̗��z�͈͂�x�O������A�����̊��ł��u�}�X�R�~�v�Ȃ̂����m��Ȃ��B���̃����N�}�[���͂ǂ��ɂ���̂��B���Ƃ��A���ł���e���r�Ɏ���܂ł���炪�w�ǎ҂⎋���҂́u���v��(�Ȃ�킢)�̊�{�ɒu���Ă��邱�ƂɈႢ�͂Ȃ��B�������A�V���͑��̎O�҂Ƃ͑傫�ȈႢ������悤�Ɏv���B����́A�V�����w�ǎ҂�����u�I�ԁv�Ƃ����_�ɂ���B���ł͔��グ�����ׂĂł���B�e���r�͎��������������ł���B���̂��߂Ȃ�A�l�̃S�V�b�v���������A���鑤�̋�������������̂��d�_�ɐ����邱�Ƃ�����B�܂������u�s���葽���v�̌��鑤�ւ̓��������ƌ�����B���̓_�A�V���͓`����ׂ����e�Ɍ�����������B���邢�́A�����������邩��V�����ƌ�����B��葽���̐l�ɓ`���˂Ȃ�Ȃ����ƂɈႢ�͂Ȃ��B�������A�ꕔ�̎��҂ɂ����`������ł悢�A�Ƃ����������������킹�˂Ȃ�Ȃ��B�u�킩���Ă����ǎҁv���l�����邱�ƁA��ɔނ�̐M���ɓ�����L�����f�ڂ��邱�Ƃ́A5�V���̑傫�Ȏg���ł���B�u�s���葽���v������ł͂Ȃ��A�����ɂ͖��炩�ȃ^�[�Q�b�g������B�ǎ҂�I�Ԃ̂ł���B
���i�搶�͒����V���Ђ̊w�|���⍑�ە��Ō��M��U����A���̏W�听�ł��鏑�̂ЂƂɁw���ނ���W���[�i���Y���x(2010)������B�����ɂ��̈�߂������Ă݂悤�B
�����`�̍������x���A�Љ�̒n�����Ă���(����)���f�B�A�̃W���[�i���Y���@�\���A�m�ł�����W����r�����ċ}���ɐ��ނ̒����������Ă���悤�Ɏv����
�u�m�ł�����W���̑r���v�A���̌����Ƃ��Đ搶�́A���f�B�A���u�Ȃ�ӂ�\�킸�g�֒f�h�̃R�}�[�V�����Y��(���Ǝ�`)�ɌX�|���n�߂��v���Ƃ��w�E���ꂽ�����ŁA���̎��Ԃ��A�{���A
�u�W���[�i���Y�������炷�ׂ����_���@�v���������u�������@�ɐZ�H����v���Ƃ܂ł̐[�����@��������ꂽ�B
����́A���݂̐V���L�҂݂̂Ȃ炸�A��X��ʂ̌����҂ɂ��d���������t�ł���B�_���ł��꒘��ł���A��X�͖{���ɏ����ȁu���_���@�v���Ȃĕ����������߂Ă��邾�낤���B��������A�Ɛт̐��҂��⏸�C�̂��߂����ɁA���Ȃ킿�u�������@�v�ɂ���ēk�Ɏ��������Ă͂��܂����B�����āA����́A�ЂƂ茤���҂̖��ł͂Ȃ��A�䂪���ɉ������w�s���S�̂ɒʒꂷ�邱�Ƃł͂Ȃ��̂��낤���B
�搶�͓������u�W���[�i���Y���ƃA�J�f�~�Y���͒�g�ł��邩�v�Ƃ����͂ŏI�����Ă���B�����ł́A�W���[�i���Y���̐��ނƕ������ɂ���A�J�f�~�Y���̌��ɗ�ɔᔻ����Ă���B������2010�N�����ł���A2004�N�x�̍�����w�Ɨ��s���@�l������n�܂�A2015�N�x�̊w�Z����@�����Ɏ���䂪���̋���s���̈ڂ�ς����A����I�ɂ� side by side �ŁA�������A���e�ł͏�Ɉ������`�Ŏ����𑨂��A�x����炵�Ă���B���ꂪ�A�u���_���@�v�ɑ��Ȃ�܂��B
���́A��������Ό������R�}�[�V�����Y���̗���ɗ�����Ă��܂����˂Ȃ�����ɂ����āA����ɍR���x�ʂ��������w���҂��������Ƃ́A�{�w�ɂƂ��Ĝ͜��Ɋ����Ȃ��B��N�Ȃ��茈�߂����ނ����Ȃ��B�����A��N�����ׂĂ���������킯�ł��Ȃ��B���N�ɓn���Ď����ꂽ�u�V���L�҂������v�͐Â��ɁA����ǖ��X�Ǝp����Ă���ɈႢ�Ȃ��B
��Ȃ��������g�̏��p���Ȃ�����A�ٕ����ȂāA����܂��܂����{�̃W���[�i���Y���̔��W�ɍv�������A�܂��A���Ē����˂Ȃ�ʐ搶�ւ̂͂Ȃނ��̌��t�Ƃ������B�@
��
���i����
(1947-�@)�@���{�̃W���[�i���X�g�B���Ɍ��o�g�B�c��`�m��w�o�ϊw�����ƌ�ɖ����V���Ђ֓��ЁB�w�|����o�ϕ��̕ҏW�ψ����o�đ��{�ЕҏW�����A���݂͔p���ƂȂ��Ă��閈���f�C���[�j���[�Y�ҏW���߁A2002�N3���ɑގЁB���N4����苞�s�w����w�l�ԕ����w�������R�~���j�P�[�V�����w��(2004�N4�����w�Ȗ��ύX�ɔ������f�B�A�����w�ȂƂȂ��Ă���)�̋����ɏA�C�B2008�N4�����l�ԕ����w���̍ĕ҂ɔ������f�B�A�Љ�w�ȋ����ƂȂ�B�����Ƃ��Ă̓W���[�i���Y���A�}�X�R�~�A���f�B�A�A�A�����J�Љ���啪��Ƃ��Ă���B2018�N��N�ސE�B
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���u�����v�̎Љ�j 2009/6 |
�`��5��u�����v���W���[�i���Y����������������`
�O��́A�u�����v�����A����܂ł̍�����ǂɂ���10���ڂɂ킽���čl�@���A���킹�āu�����v���i�ׂɂȂ������ᓙ���������B�{�A�ڂ̍ŏI��ƂȂ鍡���ł́A�ߔN�̐V��������̕���ŁA�u�����v���߂����Đ��܂�Ă���V���ȓ����ɂ��Ď��グ��B�����ŏЉ��4�̎���͂�������A�Ђ̌o�c��l��s���ȂǗl�X�Ȑ���̒��ŁA�u�����v�����菊�ɂ��Ȃ���W���[�i���Y���������������悤�Ƃ��錻��̋L�҂����ɂ��n���Ȏ��g�݂ł���B
�M�҂́A�������������ɂ�������̃W���[�i���Y���̉\����W�]���邤���ł̏d�v�Ȏ�|���肪����ƍl���Ă���B
|
|
����6�͢��������߂���V���Ȏ��g��
|
�{�e��4��ŏЉ�������V���В��̏H�R�ԑ��Y�̔����́A�o�c��@�ɂȂ�ƈޏk���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƁA�Ƃ������O���ꂪ���ȁu�����v�ɂ��ĐϋɓI�ȓ��e�������B
�u�V���̐������́A��ԉɂ����������ł͂Ȃ����B�����́A�����A�J�́E�l���������킯�ł����A�ǂ݉����̂���L���́A��͂�V���łȂ���Ύ�ނł��Ȃ��B�����ŏ������Ă������Ǝv���Ă��܂��v
�����V����2008�N1�����獂�����H���߂��鋐�z�{�ݎ��Y�̌p�����ɒ[���A�V������Ȃ�1�N�]��ɂ킽���āu�����v�𑱂��Ă���B
�����V���́A�Љ���ɐV�����A�C��������h�����A�C�̈��A�ŁA�u�����V���Љ�́A�����ōs���v�Əq�ׁA�������ە������Ƃ����B
NHK���u�����v����g����NHK�X�y�V�����u���N�U�}�l�[�v����������ق��A2009�N����́u�����̓��{�v�v���W�F�N�g��Ґ����A�u�����v��D�荞�݂Ȃ���V���ȕ̋��n��͍�����B
���̂悤�ɁA�e�Ђ��u�����v�ɒ��ڂ���w�i�́A�����Ɂu���������v�����o������ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�����Łu�����v�ɗ͂𒍂��e�Ђ̑̐���V�X�e�����l�@���Ă����B
��a. �����V���́u�����v�`�[��
�����V���́u�����v�́A����܂Ŗ����̂悤�Ɏ��グ�Ă������A�}�X�E���f�B�A�̒��ŁA�Ƃ�킯�����V�����������ɔM�S�ŁA���C�ɂ��͂����Ă������Ƃ́A1997�N12����98�N1���ɓ����{�ЂƑ��{�Ђňꔑ����́u�����̊�b���C�v���s���Ă��邱�ƂȂǂ�����M����2)�B
2008�N11�����݂ł́u�����v�`�[���ɂ��āA2006�N�́u�U�������v�ő���c�W���[�i���Y����܂���܂������ʕ`�[���̎s�쐽��̍u������Љ��B
�����V���́A2006�N4���Ɂu�����v����I�ɍs����ރ`�[�����������B�ҏW�ǒ������̃`�[����10�l�O��̋L�҂�i���Ă���B
�u�ǂ�ȕ���ł�����Ȃ��A����߂Ď��R�Ɏ�ނ��邱�Ƃ�������Ă��܂����A�ЂƂ����������ۂ���Ă��܂��B����́A�����Ƃ�����@�ŋL���������A�Ƃ������Ƃł��v3)
�O�o�̏H�R�� NHK�u�ԑg���ρv�ŁA�m�F��ނ��s�\��������4)�Ƒ�O�ҋ@�ւ���w�E���ꂽ���Ƃ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�W���[�i���Y���̊�{�ł���w�����x���A����w�A�[�������āA�ǎ҂̊F���܂ɐM�����Ă���������悤�w�͂��Ă������ӂł��v5)
�������`�ōĂсu�����v�ɗ͂𒍂��V�̐��������Ƃ�����B�Ƃ͂����A�s��͍u���̒��ŁA�u�����v�����������Ă���B
�u�W���[�i���X�g�Ƃ����d�����������A�K�R�I�ɐ��܂�Ă��镪��Ƃ����Ă��悢�v
���̂����ŁA�]���u�����v�́A�Љ�̒��Ɂu�����ǁv�����������A�����V���̍���̎��g�݂́A�����Ƃ͈Ⴄ�ƈʒu�Â��Ă���B
�u�Љ�Ɠ������̂������Ă��Ӗ��͂Ȃ��B�V�����g�D������������ɂ́A�����ł����ł��Ȃ����Ƃ���肽���B�L�҂����͐V�����W���[�i���Y����ڎw���ĕ��������܂����v6)
���̌��ʁA�`�[���ō��h�Ȃǂ��s���A1�����������Ɋ��҂��Ă���̂͂ǂ�Ȗ������낤���B2�W���[�i���Y���������グ��ׂ��e�[�}�͉��Ȃ̂��A�𒆐S�ɘ_�c���J��Ԃ����B
�����Œ��ڂ��ׂ��́A�e�[�}�ݒ�ɓ������āA�O�ꂵ���c�_������_�ɂ���B
�u�����̃����o�[���[������܂ŋc�_��s�����A�ŗD��e�[�}��������B����Ӗ��ł͂ƂĂ�����I�Ȏ葱�����Ǝv���Ă��܂��v7)
�܂�s�삪�ڎw���u�����v�́A�]���̎Љ�^�̂悤�ɁA�N��������摑��ł�����A������f�X�N��L���b�v�𒆐S�ɂ����i�ߓ��̉��ŁA�u�����v��W�J����`�ƈႤ���Ƃ��������Ă���B���N���[�g�����̂Ƃ��A���l�x�ǂ̋L�҂��[����摑�݁A���x��������f�O���ċL�҂��������߂����Ă����Ƃ��ɁA�f�X�N�̎R�{���̒߂̈ꐺ�Łu�����v�ɏ��o���Ă����P�[�X�Ƃ͖��炩�ɈႤ���Ƃ��Ӗ����Ă���B
�s��́u�����v�����܂��[�����A1���ǔ��A2����������2�������������ŁA���̂�����Ƃ��Ⴄ��@�Łu�����v��͍������Əq�ׂĂ���B
�u�������̏Ȓ��ɋ^�f�����肻�����Ƃ��A���̋ƊE�ɋ������B����Ă���ȂǂƁA����̖��ӎ����ތo���𗊂�ɁA�����̑Ώۂ��Ђ˂�o���c�_�������̂ł��v8)
������s��́A�u�A�W�F���_�E�Z�b�e�B���O�^�����v�ƌĂ�ł���B�܂��Ɉˋ����Ȃ��ŁA�u�L�҂�������̓I�\���I�Ɂw���ܒ������ׂ����Ɓx�����߂���v����������Ƃ��Ă���B
���̕��@�Ő��������u�����v��2006�N7������́u�U�������v�ł���B
�s��͍u���̒��߂�����Ɂu�����v�̍ŏI�I�ȖڕW�́A�Љ�̗��v�ɍv�����邱�Ƃ��Ƃ��������ŁA�����q�ׂĂ���B
�u�A�W�F���_�����߂鎞�A�܂����⎩�����܂��B�����Ō@�艺���Ă������Ƃ����ʓI�ɑ傫�ȎЉ�I�ȗ��v�ɂȂ��邩�ǂ����Ɓv9)
�s��̎w�E�́A�M�҂̎����Ɠ��l�ł���B�u�����v�̒��ŏd�v�ȗv�f�́A�u���Ȗ����v�u���Ж����v�I�ȕł͂Ȃ��āA�Љ�ɔg�y�͂̂���A�e���������炷�ł���B����́A��ޑΏۂ����͂⌠�Ђł���A���̕ɂ���Ċe�Ђ��ǐ����A���̌��ʎЉ�I�ω��������炷�A�܂�u���ʒ����v���Ӗ����Ă���B
�����s��̂悤�ɖL�x�Ȍo�������L�҂ɂƂ��ẮA����A�W�F���_��ݒ肷�邱�Ƃ͂���������Ƃł͂Ȃ���������Ȃ����A�Ȃ��Ȃ��ȒP�ɂł��邱�Ƃł͂Ȃ����A�����ɖ��ӎ��̍��������߂���B
��b. �����V���́u�����v�`�[��
�����V���̂悤�ɎВ��̊̂���ŁA10�l�O��́A�������Љ�Ƃ͕ʘg�Łu�����v�`�[����Ґ����Ď��g���M�҂́A1977�N�̖����V�����{�ЕǗV�R��10)�ȊO�ɂ́A�Ǖ��ɂ��Ēm��Ȃ��B�����̎Ђ́A�s��̍u���ɂ���悤�ȁu�Љ�Ƃ�������������A�����ɂ͒����ǂ�����܂��v11)�Ƃ����̂��嗬�ł͂Ȃ��낤���B
�����ŏ��l������g���Ȃ���u�����v�ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��������V���̗�����Ă����B
�����V���ɂ́u��������v�Ƃ����Ǝ��̎��_���玞�̃j���[�X��ǂ����ʂ�����B�{�e��3��Ŏ��グ���u���H���[���s���v�Njy�́u�����v�Ȃǂ��f�ڂ��Ă���B��������ʎ��ʂł��u�����v�����т��ьf�ڂ���Ă���B���ڂ����u�����v�́A1999�N12���ɘA�ڂ��X�^�[�g�����u�j���Ƃ̓����v�ł������B���̘A�ڂ̃e�[�}�́A�����o�ω��v��j��ł���u���E���E�Ɓv�̗����\����P��o���A���炩�ɂ��邱�Ƃ������B
���́u�����v�`�[���̃L���b�v���������J���́A���̎�|�����̂悤�ɋL���Ă���B
�u�����\���Ƃ͐����Ƃ⊯�������ɂ��I���ȁg�ŋ����̃V�X�e���h�ł���A�����Ƃ́w�[�ƃJ�l�x�A�����́w�V����x�A�ƊE�́w���v�x����ɂ��Ă���B���ꂼ��A�����ƂƂ��Ă̒n�ʂ⊯�������ɗ^�����Ă��錠�������p���A�[�Ŏ҂��[�߂��ŋ��������B�̗��v�ɂ���ւ��Ă���̂ł���v12)
���̘A�ڂ́A����5�l�ŃX�^�[�g���A�̂��ɎЉ�ƍ�ʎx�ǂ̋L��9�l���S�������B�������ŏ�����2002�N5���܂ł�2�N���߂��Ό��������ďI�n���̎�ނɌg����Ă����̂́A���J�Ɖ|�{�N���2�l�����ł���B
���̎�ނ̐ӔC�҂������Љ���̎R�c�N�v�͎��̂悤�Ɍ��y���āu�����v�̕�������_�����Ă���B
�u���f�B�A���l���̂Ȃ��ŁA���̒����͐V�������̑��ݗ��R���������Ƃ̂ł��鐔���Ȃ����삾���A��p�Ό��ʁA���X�N�Ƃ����_����́A����قNJ��ɍ���Ȃ���ށE�͂Ȃ��Ƃ����̂��������v�u��ޔǂ����X�̎��ʂɍv�����邱�Ƃ͂Ȃ��v�u���������I����܂ł̐M���W��z���グ��ɂ͎��Ԃ�������B��ޔ�p�͖c�����肾���A���ꂽ��ǎ҂�[�������A�ɒl������̂��Ƃ����ۏ͂Ȃ��v13)
�܂��A����������ǂ����������Ƃ���Ɂu�����v�̈Ӌ`������B
����ɂ��ĎR�c�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�V���������ɂ������̂́A��͂�A�����̓��X�̋Ɩ��������ɕ������ꂽ���̂ł���A���v�̂��߂����炾�B���C�p�������������邪�A�����ɂ́A���̂��ߐl�̂��߁A�����̒m�錠���ɂ�������`��������v14)
�����̂���Г������Ɏx�����ē����V���̒����͂��̌�������B���̓T�^�I�ȗႪ2008�N1������2009�N2���܂ő������������H�Ɋւ��钲���ł���15)�B��ރ`�[���͗V�R�L���b�v�̐��J�𒆐S�ɁA�����Ƃ���5�l���S�����Ă���B
���J�ɂ��ƁA�펞3�l�����ʂ��Ă���e�[�}����ށA���M���Ď��ʂɔ��f�����A�c���2�l�����̓W�J��������Ŏ�ނɐ�O����2 �i�K����������Ă���Ƃ����B
�u�����V���̏ꍇ�͒����Ɋ�����l���������Ă���̂ŁA�����悭�g���Ă������߂ɂ́A���̕��������Ȃ��v16)
�Ƃ͂����A�����ʂ̎�����ً}�̃e�[�}�����������ɃV�t�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂�����ŁA����͊e�Г��l�Ɛ��@�����B
�ł͂ǂ��������_�Ńe�[�}��ݒ肵�Ă���̂��낤���B
�ŋ߂̏Ȓ��Ȃǂ̔��\���̂́A�����̃z�[���y�[�W�Ɍ��J����Ă��āA��b���L�҉�̓��e���f�ڂ���Ă���B�����V���œǂ܂Ȃ��Ă��C���^�[�l�b�g�𗘗p����Ώڍׂ܂Œm�邱�Ƃ��ł��鎞��ł���B�V����e���r�Ȃǂ̃��f�B�A�̑��݈Ӌ`�́A�C���^�[�l�b�g�œǂނ��Ƃ��ł��Ȃ����e�Ƃ������ƂɂȂ�B����𐙒J�́A�u�������o�ɍ��������w�����x��W�J���邱�ƂŁA�Ⴂ�m�ɂ��Ă������Ƃ��K�v���v�Ǝw�E����B
���̂����Łu������ނ̃}�C���h����ŁA���̎��_���Ȃ��Ƃ��[����ނɍs�������Ȃ��v�Ƃ��q�ׂĂ���B
���������u�����v�𑱂��邱�ƂŁA�e�ЂƂ̎��ʂ̈Ⴂ���ǎ҂��䂫���A�M���邱�ƂɂȂ���ƌ��Ă���B���̓_�ɂ��Đ��J�́A�u�V���ւ̐M�������Ȃ��Ȃ�Ǝ��R�Ə�W�܂�Ȃ��Ȃ�v�ƌ���L�҂̎�����f�I���Ă���B�܂�L����ǂǎ҂���A�u���������������Ȃ��Ƃ�����v�u�����̎��͂ł͂��������^�f������v�Ƃ����������̂��A�u���ʉ����Ă������肤��v�Ǝw�E���Ă���B
��c. �����V���́u�����v�`�[��
����܂łɂ����X�́u�����v�̎��т����閈���V���ŁA�����ď���h���V�Љ�����u�����v�錾�������w�i�ɂ͉�������̂��B
�u�C���^�[�l�b�g������}���A���悢��V���������c��p�����o�����Ƃ���Ƃ��A�����ɂ́w�����x�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��邩��ł��v17)
����͎Љ�������A�_���ψ����ォ����u�����v�̏d�v���������ƍl���Ă����B
���ۂ�2007�N��2008�N�̐V���T�Ԃɂ́A�����̈Ӌ`���А��Ɍf�ڂ��Ă���18)�B�����ɂ́A�Ⴂ�L�Ҏ���A�ڂ̓�����ɂ������Ђ́u��Q�G�C�Y�v������Ƃ����B
�u��Q�G�C�Y���y�L�҂����ł���Ă���̂����āA�����������Љ�ɉe����^����悤�ȕ��������ƍl�����v
�Љ���A�C�ɓ������ď���͉��߂āA�u�����v�̏d�v�����������Ă���B
�u�����o�ĂΖ��炩�ɂȂ�悤�Ȏ���������ɂȂ��Ď�ނ�����_�l�̕K�v���͔ے肵�Ȃ����A����Ƃ͈���������V���Ǝ��̒��������A�V���̑��݈Ӌ`�����o����v19)
2000�N��ȍ~�ł��u�ЎR���N���́v�u���Ί�˂��^�f�v�u�h�q�������J�����҃��X�g���v�u���q����W�ɔ����Z����{�䒠�����W���v�u�ː�300�����v���͂��߁u�A�X�x�X�g�Ж��v�ȂǁA���ꂼ��̋L�҂��u�����v���肪�����ʉ����Ă���B���̂��тɎГ��ł́A�u�������������Ȃ�������v�Ƃ����S�ГI�Ȑ���オ���������B
�u���ꂪ�����V���̎Е��ł��傤�v20)�ƌ��B
�����V�������{�Ђ̏ꍇ�́A���Ƃ��ƎЉ�V�R�̒��ɁA�u�����v�ǂ���݂���Ă���B���b�L�[�h�����̎�ޔǂ̖��c��ŁA���̌���u���b�L�[�h�����v�ƌĂ������m�ۂ��Ă������A1992�N�ɓ����̎Љ���̈ӌ��ŁA�u�����v�ǂ��g�[�������B�u�`�ǁv�u�a�ǁv��2�Ǒ̐��ŁA���ꂼ��3 �` 4�l�̋L�҂�����U���Ă����B�O�҂͐����Ƃ̋^�f��Njy�A��҂͓��{�������J�o�[���Ȃ���Ǝ��́u�����v��ڎw�����̂ŁA�`�ǂ��肪�������ʂ��A�u�s�M�̖����v21)��悾�����Ƃ����B
�u�`�ǂ̒S���f�X�N���A���܂̎В�(����ޖL)�ŁA���������ۂɂ���Ă��Ă���̂Œ����ɂ͗���������v22)
���̌�A�uB�ǁv�������c��A�u�h�q�����i���B�s�����v�Ȃǂ��肪���Ă����B���̖��́A���̌㓌���n�����{�������h�q�{�ݒ������⌳���B���{���{������w�C����d�őߕ߂��鎖���ɔ��W�����B��A�́̕A1999�N�x�̓��{�W���[�i���X�g��c�܂̏���܂���܂����B
���`���V�����u�����v�`�[���́A
�u�V�R�̒��ŁA3 �`�[�����炢�ɕ����āA���ꂼ��̃`�[����������A���̒�����A���̂ɂȂ�Ǝv������̂��@�蓖�ĂĂ����Ƃ���ɁA���̃`�[���̃����o�[���V�t�g���Ă����`�ɂȂ邾�낤�v
����́A�Љ�S�̂���Ղ��Ȃ���A�u�����v�ւ̂�������������B
�u����(�S��)�N���u��Ȓ��Ȃǂł��[���͂���B���ꂼ��̋L�҂��g�����}�C���h�h�������Ď�ނɓ����邱�Ƃ��d�v�ł��B����ɒ����Ƃ��킹�āA�L�����y�[���Ƃ��ēW�J���Ă������Ƃ�����Ǝv���Ă��܂��v
�܂��u�����v�ɑ��郊�X�N�ɂ��ẮA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�ٔ��ɑi�����邱�Ƃ�|��Ă��Ắw�����x�͂ł��܂���B�v�͍ٔ��ɕ����Ȃ�������̂ł�����v
����ɔ�p�Ό��ʂ̖ʂŌ����������ɂ��ẮA���ʂ͂����ɏo��킯�łȂ����Ƃ͏\�����m���Ă���Ƃ��āA�������y���Ă���B
�u�o�L�Ȃǂ̎����̍w����o���Ɍo��������đ䏊���ꂵ���Ă��A�オ�ǂ��܂ʼn䖝���邩�ŁA����Ȃ��Ƃ͐܍��ݍς݂ł��v
����̍Ō�̌��t����ۓI���B
�u���̂��߂Ɏ��������͋L�҂ɂȂ����̂��A���̗��R���l����w�����x�����Ȃ��̂ł��v23)
��d. NHK �́u�����v�`�[��
NHK�́u�����v�̗��j�͌Â��B���������ƈӊO�Ȋ�������ǎ҂͏��Ȃ��Ȃ���������Ȃ��B����ɘI���ȉ�����������u���b�L�[�h����5���N�v24)�ȑO�ɂ́ANHK���������́u�����v���肪���Ă���B�u�����v���F�������悤�ɂȂ��Ă���́A�w�����ꂽ�x25)�������Ě���Ƃ���B���̍�i�͐����a���������h�L�������^���[�ŎЉ�L�ґ厡�_�V�オ���S�ƂȂ��Ď�ށA���삵���B�L�ҁA�f�B���N�^�[�A�J�����}���A�����}����4�l�`�[���ł���B1977�N�x�̌|�p�ՂŁA�e���r�E�h�L�������^���[����̑�܂���܂��Ă���B
�����a���m�F���ꂽ�̂��A1956�N5��1���ŁA20�N���12���ɕ������ꂽ�B
�厡�͎�ވӐ}�������q�ׂĂ���B
�u�����a�̒�m��ʔ�Q�g���h����藧�ẮA���̎��ɖ{���ɂȂ������̂��A���̈�_�ɍi���Ď�ނ��悤�Ƃ����̂��A���̃h�L�������^���[�ł��B���������͌F�{�����ɖ����Ă����������g�����t�@�C���h�̓���B���Ҋm�F����1959 �N 12 ���Ɍ������_��Ŕ�Q��ɂ����鐔�N�ԁA�����E���E�������������s�������ł��v
���̂����ő厡�́A�u�����̃X�^�C�����Ƃ�܂������A����̓e�[�}����ގ�@��K�R�I�Ɍ��肷��̂ł��v26)�ƒf������B
��Q�̎S���ڑO�ɂ��Ȃ��狙�l�֎~�������H��p�����~�߂������g�����u�����̂͂Ȃ����A���ꂾ�B�厡�́A20�N�Ƃ����Ό����o�āA�����̊W�҂̗�Âȏ،��������o�����Ƃ��邪�A�����̕ی����������m���A�`�b�\�����H�꒷�A�ʎY�Ȍy�H�Ƌǒ��c���J�����̑O������ăC���^�r���[�ɉ����Ȃ��B�����铢�����삯�Œǂ������Ď�ނ��邪�A�Ȃ��Ȃ��^������낤�Ƃ��Ȃ��B����ł��˂��Ă˂��Ď�ނ���f�B�e�[�����f���Ɍ���Ă���B
���̈���ŗL�@����ɖ`���ꂽ���҂��A�u�������ǂ�ȂɂȂ��Ă����̂��Ǝv���ƁA�{���ɋ��낵���v�Ƃ����������Â炢���t�Ō��̂��A�厡�͎����X�[�p�[���g�킸�A�����ĉ������Ă������ƂŁA�����҂ɑi����B
���̍�i�́A���̐ӔC��₤�͂��߂Ẵh�L�������^���[�ŁA�e���r���f���ꂽ��A���낢��Ȕ�����ŁA�����a�̍s���ӔC��₤�ٔ������X�ɋN�����B
�������厡�́A��������Ƃ����Ă���ŎЉ����������ɕς�邩�Ƃ����A����قǒP���ł͂Ȃ��A�W���[�i���Y���̎d���́A�̉͌��ɐ�ςނƂ����悤�ȂƂ��낪��R����ƌ����A�u����ł������A��葱���邼�Ƃ����o�傪�Ȃ��Əo���Ȃ��v�Ƃ��������ŁA�W���[�i���X�g�̎d�������������Ă���B
�u�������͊w�҂��Ⴀ��܂���A�u�������Ď���₢�A����_���邽�߂ɂ́A�ǂ��������Ēn�ׂ����������āA���̂悤��(������������)��ЂƂW�߂Ă�����������Ȃ��v�u�،�����肽���A�؋��Ř_������肽���A�����v���čs�������(����)�S�e�����Ȃ��Ă��w���ꂶ�Ⴀ�A�������������Ă݂邩�x�Ǝv�������̂ł��B��������藧�ċ�藧�Ă���Ă����A������x����̂̓W���[�i���X�g�Ƃ��Ă̎u�A�������̎�ނ̈�ԉ��ɂ��錴�_���Ǝv���܂��v27)
���������厡�X�s���b�g�������������A2005�N�ȍ~���݉����Ă����B�{�e��3��Ōf�ڂ����wNHK�X�y�V�����G���[�L���O�E�v�A�x�����̈��ł���B�����āA�����Љ��������������̉��Ő��삳�ꂽ�u�����v���A�wNHK�X�y�V�����G���N�U�}�l�[�x28)�ł������B
��ނ̂��������́A�x�@�����̒Q�����炾�����Ƃ����B
�u�s��̔w��ŋ��z�̎����Ă���ƌ�����\�͒c��E�����������A�ǂ̂悤�Ɋւ���Ă���̂��A���̎��Ԃ����������ɂ��߂Ȃ��v29)
���̌��t���璆���́A�x�@�̑{�����͂��Ă��Ȃ��N���m��Ȃ��\�͒c�̎����l������𖾂炩�ɂł��Ȃ����A�Ɓu�����v�����ӂ���B2007�N1���̂��Ƃ��B
�����́A�L�җ�22�N�̂���15�N���Љ�ʼn߂����A�x�����L���b�v�����߂������L�҂����A���͒������u�����v���u�������_���A20�N�O�Ɍ����厡�_�V��́w�����ꂽ�x�������Ƃ����B
�����́A�u�\�͒c�v�u�}�l�[�v�u���v�u�x���`���[�����v�Ƃ������L�[���[�h����5�l�̋L�҂𓊓�����B������������x�����A�x�@���A���Œ��̒S���L�҂������B10�����������u�����v�̌��ʁA�{�����ǂ���������߂��ˋ������ŁA���X�̓����o���������Ɗi�̒j�̓Ɣ��e�[�v����肷��B�܂��W����\�͒c����̏،���ςݏd�˂āA���N�U�}�l�[����Ƃ�H���Ԃ��Ă������o�܂�摑�ށB����ɖ\�͒c���}���V�����̈ꎺ�ɑ傪����ȃf�B�[�����O���[����ݒu������A�x���`���[������80 ���~���^�p�����肷�錻���\�͒c���ւ̖�����ނ���A���̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��Ă������B
�����͂��܁u�����̓��{�v�v���W�F�N�g�̃f�X�N�����Ă���B���N1���ɔ������A�ǒ��␅�m�F�����̃`�[���ŁA�o�ϕ����������X�i���I���]�̋L�ҁA�f�X�N��11�l�ł���B���̃v���W�F�N�g�̓����́A�������A�o�ϕ��A�Љ�A�Ȋw�������A�e���r�j���[�X���Ƃ����������z���č\������Ă���_���B
�����ɂ��ƁA�u������ʂ̒�����ړI�Ƀj���[�X���^�ԑg�M����ƂƂ��ɁA10�N��A20�N��̓��{�Љ�̂����������v�Ƃ����B
����A�Љ�f�X�N�̌F�c���L���u�����v�ɔM�S�ȃf�X�N�̈�l�ł���B�F�c���u�����v���ӎ������̂́ANHK�X�y�V�����w�����@���{���H���c�x30)����ނ����̂����������������B�����H���c���ق犲�������̃C���^�r���[����A�����ɓ��H�s�����P���Ȃ����Ă������������Ă����Ƃ����B�F�c�͂���܂ł̎�ތo���̒�����A�،��W�߂⎑�����͂���g����u�����v�̒��ŁA���Ɏ������͂ɒ��ڂ����B
�u�����̂����������������́A�Ƃ�킯���ŋǎ��������ۂ̒�����@��Ɏ�荞�߂Ȃ����ƍl���܂����v31)
���ŋǎ��������ۂ̒����́A�\�����Ȃǂ̐Ŗ��W�E�s���W�̌����������łȂ��A�V���₠�����ނ̎G���A���ЁA�L���A����Ƀe���r�̃��C�h�V���[��C���^�[�l�b�g�̂g�o�Ɏ���܂ŁA���ׂĂ̕����E�f��������ǂݍ���ŁA�]���E���ނ��Ă���B
�����ŌF�c�́A����̌o���𑽂��̌�y�L�҂����ɒm���Ă��炤���߁A2007�N�H����X�^�[�g�����u�������C�v�̍u�t�߂��B�����ł́A����A����̓ǂݕ�������J���̎g�����ɂ͂��܂��āA���������A�Ȓ��A�����́A��ƁA�o�c�ҁA���v�@�l�A�����A���́A�ЊQ����ɂ͗��j�I�A���ۓI�Ȗ����������g���ēǂ݉����Ă����B���C�̑ΏۂƂȂ�̂́A�n���Ŏ�����ނ��I�����A���邢�͂܂��Ȃ��I������2�N�ڂ̋L�҂ł���B
�u���̎����́A���X�̎�ނɒǂ��ĖڕW��������������������A�x�@�A���@��ނ�����ċL�҂Ƃ��Č����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƒ��߂���A�Y�ݎn�߂鎞���ɂ����������Ă��邩��ł��B����Ȏ��A�V������ނ̂��������ɂȂ�Ǝv���Ă͂��߂܂����v32)
�F�c�͂��܁A�V���ȁu�����v�Ɏ��g�ݎn�߂Ă���B�u����v�u���Łv�u�،����Ď��ψ���v�u��v�����@�v�S����4�l�̋L�҂ɂ��`�[����Ґ����āA���́u���������v����g�����u�����v��ڎw���Ƃ����B
�ȏ㌩�Ă�����́A���ݐi�s���̂��̂⍡��̓W�J�����������u�����v�ł���B����̘A�ڂł͎��グ��Ȃ������e�Ђ́u�����v�����X���邪�A�T�ːV���A�����A�o�Ŋe�Ђ́A�g���������h���m������Ӗ��ł��u�����v�����g�ނׂ��ڕW�Ƃ��ďd�����Ă���Ɛ��@�ł���B
|
|
����7�́u�����v���W���[�i���Y����������������
|
�M�҂��{�e5��̘A�ڂŒ����������|�C���g��3����B1�́A�u���\�v����̒E�p�̂��߂́u�����v�̊��p�B�u�����v�Ɓu���ʒ����v����邱�ƂŁA�u�����v�̃n�[�h����Ⴍ���A�u���\�v�ɗ���Ȃ���ނɐϋɓI�Ɏ��g�ނƂ����Ӗ��ŁA�]���̓Ǝ���ނ����̒��ɕ����B2�߂́A�W���[�i���Y���{���������͊Ď��@�\(�E�I�b�`�E�h�b�O)�Ƃ��Ắu���ʒ����v�̈Ӌ`�ł���B�����đO�͂�3�߂̃|�C���g�Ƃ��āA�u�����v���W���[�i���Y����������������Ƃ����M�҂̉������A����̎��g�݂̒�����l�@���Ă����B�����̓_�܂��āA�ŏI�͂ł̓W���[�i���Y���̍���Ɍ������\����W�]���邽�߂ɕK�v�Ǝv����ۑ��_�_�̐��������če��������B
�����A�����̕NJ��Ɍo�ς̍s���l�܂肪�����p�ƂȂ��č����̐����ւ̐M���͎��Ă��A�u�����s�M�v��ʂ�z���āA�����́u��ΓI�����v(�V�j�V�Y��)�݁A�����ւ̖��S���g�債�Ă���B���������̒��Ń}�X�E���f�B�A�ɑ���ǎҁA�����҂̕s�M�A�s�����傫���A�}�X�R�~���u�s���v��掂�͖Ƃ�Ȃ��B
���ă}�X�R�~�́A�u�l���̍ԁv�ƌ����A1950�N��̒����i��33)��60�N�ォ��70�N��̃|���I�A�����L�����y�[���A���Q�ȂǍ�����s���̖��_��Njy���Ă���34)�B�������A80�N��ȍ~�}�X�E���f�B�A�s�M���������ɍ��܂�悤�ɂȂ����B���̋�̓I�Ȍ���́A�����V���́u�T���S�����v35)�A���o�В��A��̕��В��A�����ҏW�ǒ��Ƃ��������f�B�A�W�҂ւ̖����J�����n�����o�������N���[�g�����Ɍ���ꂽ�B�Ȍ�}�X�E���f�B�A���Љ�`���т��g�D�łȂ��A���_�l�̂��߂ɂ˂���������A�������͂�g�D���͂Ɩ��������肷��g�D�ł�����ƍ��������m�ɔF������悤�ɂȂ����B�����ă��f�B�A�X�N������ƍߕɂ��l���N�Q�A�̎���K�����A�ǎҁA�����҂̔ᔻ�́A���̂��̂ɂ���������悤�ɂȂ����B
2009�N�̌��݂ł��A���{�e���r�̕ԑg�w�^���o���L�V���I�x�������������̗������̏،��҂��U�҂ł�������A�w�T���V���x�́u�����V����_�x�ǏP�������v�̋L�����A�����ȁg�x��h�ł��������ƂȂǁA���X�ɖ�肪�������Ă���B����������Â���ނ����u����A�،��҂̌������܂܂ɕ����A�f�ڂ������߂ł���B
�Ȃ����̂悤�Ȏ��Ԃ������N�������̂��B���̖��_����ЂƂ@�艺���Ă݂�ƁA���{�̃}�X�E���f�B�A�A�Ƃ�킯�W���[�i���Y����������u���\�v�ɒʂ���B�u����̌������Ƃ��L�ۂ݂ɂ���v�댯�����͂�ޖ��ᔻ�ȕɊ��炳��Ă��܂��ƁA�Ǝ��̗��Â���ނ�ӂ�A��Ԍ��������Ȃ����Ղȕɗ�����Ă��܂������ɂȂ�B���������{�e���r�̃P�[�X�́A�C���^�[�l�b�g�ɂ���ď����Ăт����Ă���_�����ڂ����B
����w�T���V���x���A����u���s�s�ҁv�Ɩ����o���j�̗��Â�����炸�A���̌����ɐU��ꂽ���ʂł���B���Ɂw�T���V���x�́A����܂ł����Â�����炸�ɁA���ʂɓs���̂��������������f�ڂ����@���J��Ԃ��Ă����o�܂�����A�N����ׂ����ċN�������g�����h�Ƃ�������B
�w�T������x�ҏW���̊��q�V�́A�ҏW��L�̒��Łw�T���V���x��ᔻ���āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�l���⎖�ۂɂ������w�^�f�x���̂́A�T�����̖����̂ЂƂ��ƍl���܂��B�����A������Ƃ����āA�L�������邤���ŊԈႢ��Ƃ����ӔC���܂ʂ����킯�ł͂Ȃ����Ƃ́A�����܂ł�����܂���v36)
�������A2009�N�ɓ����Ă��疾�炩�ɂȂ�����A�̌��́A�ꕔ�e���r�A�ꕔ�T�����̖��ł͂Ȃ��A���ׂẴ}�X�E���f�B�A���F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ĂƂ�����B
�Ƃ����̂��A�����̃P�[�X��2�̖�����Ă���B����1�́A�u���������ҁv�̈������ǂ����邩�ł���B�H�i�U�������œ��������҂��ʂ����������͑傫���������A�u�P�ӂ̓��������v�ƈ���āA�u���U�̍����ҁv�̑��݂���������ɂȂ������炾�B�܂���ՂɁu�����ҁv��u�،��ҁv�ɏ���Ă��܂��Ǝς��������܂������邱�Ƃ́A���R�̐Ƃ���K�v������B
������_�́A����̎��Ԃ��A�����ҁA�ǎ҂́A�u�}�X�E���f�B�A�S�̂̍s�ׁv�ƌ��Ȃ��Ĕᔻ���A�}�X�R�~�s�M���������ꂪ���ł��邱�Ƃ��B
�u���\�v���邢�́u���\�W���[�i���Y���v�́A�����A�s���A��Ɠ����A�u�c��ݒ�(�A�W�F���_�E�Z�b�e�B���O)�v�̃C�j�V�A�`�u�������Ă���ȏ�A�s�s���Ȃ��Ƃ��ϋɓI�ɖ��炩�ɂ���邱�Ƃ͏��Ȃ��B�܂��Ӑ}�������Ĕ��\����Ă��A���ᔻ�Ɏ���Ă��܂��\�����ے�ł��Ȃ��B���������g���\�Ђ��h����ԉ����Ă��邱�Ƃɂ���āA�A�W�F���_���R���g���[�����ꂽ�W���[�i���X�g�����́A�ᔻ���_�̉��E�܂�Ă��܂��B
�}�X�E���f�B�A�̑��݈Ӌ`�́A���͂��Ď�����u�Ԍ�(�E�I�b�`�E�h�b�O)�v�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͉ߋ��̎��Ⴉ�猩�Ă����炩�ł���B�Ƃ��낪���܂⌠�͂���邽�߂́u�Ԍ��v�Ɖ����Ă���W���[�i���X�g�����Ȃ��Ȃ��B�����̒m�錠��������Ă���}�X�E���f�B�A���A�{���́u�����v�����߂��Ȃ��ẮA�u�s�M�v�u�s���v�́A�u���f�B�A����v�ƂȂ��āA���̑��ݎ��̂��낤������B
�����ʼn��߂āu�����v�̏d�v������������Ă���B
�u�����v�́A��ނ��s�����Ƃ����Ӗ��ŁA�u�v�̌��_�Ƃ������邱�Ƃ��ł���B��������������F�����A���s������܋N���Ă���W���[�i���Y���ᔻ�̑����͔�������\���������̂ł͂Ȃ����B
�J��Ԃ����s�ˎ��̂��тɌ����̂́A�u�W���[�i���X�g����v�̕K�v���ł���B
�Ƃ�킯�A�����̃W���[�i���X�g�������A�Ђ��z���ċc�_�A��������V�X�e���̍\�z�����߂���B���̒��S�e�[�}���Ȃ����̂́A�u�����v�ł͂Ȃ����낤���B�����ɂ́A��ގ҂Ƃ��ĒP�Ȃ�u��@�v�����ł͂Ȃ��A�L�҂̎u���������܂߂āA���܃W���[�i���Y������������̍��������݂��Ă���B
�W���[�i���Y�����A�ǎ҂⎋���҂̎x���Ă������オ���������Ƃ��l����Ȃ�A�M���̎����邽�߂ɂ��u�����v�̏d�v��������̋L�҂������F������K�v������B�Ђ��z���ĂƂ����̂��A�Ј����C�ł͂Ȃ��A�w�ҁA�����҂ɂ��u�W���[�i���Y�����_�v�ƌ����W���[�i���X�g��o���҂ɂ��u�W���[�i���Y����(��)�_�v�̑o�����w�Ԃ��ƁA���킹�āu��Ǝ�`�v�łȂ��A�́u�������v�Ƃ������_��g�ɂ��邱�Ƃ��]�܂��B
�Ƃ���ŁA���f�B�A�̊�@������钆�A�u�V���Đ��̎����v�Ƃ��āA1996�N�ɂ��łɒ}�g��w�����̓V�쏟����1�u�E���\�W���[�i���Y���v��2�u�����̋����v�������Ă���_�ɒ��ڂ������B
�u����A�V�������̃j���[�X���f�B�A�Ɣ�ׁA���́g���ӋZ�h������œK�̏�Ƃ��Ē������ʒu�Â��A������������邽�߂̃V�t�g��~�����Ƃ��A�����͂悭�Ȃ�����ǒ����ڂł݂�ŗǂ̕���ł��낤�v37)
13�N�O�ƍ����Ƃł́A�V���A�e���r����芪�����͗l�ς�肵�Ă���B�����V���o�g�̓V��́u�V���v�ɂ������������A�V�����W���[�i���Y���Ƒ����Ȃ����Ă݂�A�V��̎w�E�̖{���͉���ς���Ă͂��Ȃ��B
�����2009�N�̌�������āA�������ʐM�ҏW�劲�̌����Y�́A�W���[�i���Y���̊�@�Ɓu�����v�̊W�Ɍ��y���Ă���B
�u���͊Ď��A�Љ�`�̒Nj������Ƃ��������̎�ޗ͂����W���[�i���X�g�W�c�́A���x���Љ�̊j�Ƃ��Ă̊��҂�S���B�w�W���[�i���Y���̊�@�x�Ƃ́A�������h�������\�W���[�i���Y���ɐN�H����Ă���w����̃W���[�i���Y���̊�@�x���w�����̂ł���v38)
�V��⌴�Ɠ��l�̎w�E�́A�O�o�̒����V���̏H�R������{�e�O�͂̒��ɂ������Ɍ�����B
���̂��Ƃ�����A�u�������W���[�i���Y����������������v�Ƃ����W�]���������Ă��������B
5��ɂ킽��A�ڂł́A������Ƃ͉����v��1970�N��ȍ~�̌����j��ʂ��Č��Ă����B����ɢ������Ƃ����J�e�S���[�������āA�Ǝ���ނɂ�颒�����ƌ��͒Njy��ړI�Ƃ����u���ʒ����v�ɍ��ʉ����A���̎�������Ƌ��ɎЉ�ɗ^�����e���ɂ��čl�@���Ă����B�܂��A�����������s���邤���ł̏�ǂ���_�ɂ��Ă��_�l�����B���̌��ʁA�������̐��A�́A�Љ�ɉe����^���邱�ƂƂ��킹�āA��БS�̂����C�Â��邱�ƁA����̃}�X�E���f�B�A�̑��݂�q���Ă��d�v�ȕX�^�C���ł��邱�Ƃ��W�҂ɂ���Ē��ꂽ�B
����܂Łu���\�v�ɗ���}�X�E���f�B�A�ᔻ���ǎҁA�����҂���J��Ԃ���Ă������A���܂܂��ɃW���[�i���Y���̊������̂��߂Ɂu�����v�̌��_�ɗ����Ԃ�A���̏d�v���A�\�����ĔF���A�ĕ]�����Ă������Ƃ����߂��Ă���B
|
����
1)�� 61 ��V�����E�������k��p�l���f�B�X�J�b�V�������u�V�w�n�Ɓx������}�����V���E�v�w�V�������x2008 �N 12 ����
2)�����V���Аl�ރZ���^�[�ҁw�ʍ����C�G��@�����̊�b�x�����V���Аl�ތ��C�Z���^�[�A1998 �N 5 ��
3)�s�쐽��u�A�W�F���_�E�Z�b�e�B���O�^�̒����v�ԓc�B�N�R�[�f�B�l�[�g�w�u�v�Ƃ��ẴW���[�i���X�g�x2008 �N 11 ��
4)�M�҂́A���ʓI�Ɍ��̕��������������A���e�S�ʂƂ��Ắu���ʒ����v�Ƒ����Ă���B
5)�����V�� 2005 �N 10 �� 1 ������
6)�O�f�A�s��
7)����A�s��
8)����A�s��
9)����A�s��
10)�{�e�� 1 ��(2 ����)�� P8 �Q��
11)�O�f�A�s��
12)�����V����ޔǁw�j�]���Ƃ̓����x�p�쏑�X�A2002 �N
13)����A�w�j�]���Ƃ̓����x
14)����A�w�j�]���Ƃ̓����x
15)���݂͋x�~��
16)���J���A�q�������O 2009 �N 4 �� 10 ��
17)����h���A�q�������O 2009 �N 4 �� 14 ��
18)�����V���u�������J���g���ʂ��������v2007 �N 10��14 ���А��A���A�u���������������J�������v2008 �N 10 ��15 ���А�
19)�O�f�A����h��
20)����A����h��
21)�����V�� 1993 �N 1 ��1������6 ��22�������Ƀp�[�g3�܂Ōf�ځA���{�W���[�i���X�g��c���
22)�O�f�A����h��
23)����A����h��
24)1981 �N 2 �� 4 ���́u�j���[�X�Z���^�[ 9 ���v�ŕ����\�肾�������A�����̍�{�����̎w���Œ��~�ƂȂ����Ƃ����B���j���w�V�}�Q�W���_�^�@�����ƌ��́E40 �N�x���Y�t�H�A1995 �N
25)NHK�w�����ꂽ�x1976 �N 12 �� 18 ������
26)�厡�_�V��A�q�������O 2008 �N 10 �� 6 ��
27)�厡�_�V��u���w�����ꂳ���Ă͂Ȃ�Ȃ������ꂽ�xNHK ���������� 1992 �N 5 �� 29 ��
28)NHK�wNHK �X�y�V�����E���N�U�}�l�[�`�Љ��I�ވł̎����x2007 �N 11 �� 11 ������
29)NHK�u���N�U�}�l�[�v��ޔǁw���N�U�}�l�[�x�u�k�ЁA2008 �N
30)NHK�wNHK �X�y�V�����@�����@���{���H���c�@�؋� 30 ���~�E�c���̋O�Ձx2004 �N 8��1������
31)�F�c���L�A�q�A�����O 2009 �N 4 �� 8 ��
32)����A�F�c���L
33)1957 �N�����×{���ɓ��@���̒������A�����ی�҂ɗ^��������p�i��z 600 �~�͒Ⴗ����Ƃ��āA���@ 25 ���́u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v(������)�̎��������߂ċN�������i�ׁB1 �R���i�A2 �R�A�ō��ٔs�i�B�V���Ȃǂō����I�ȎЉ�ۏ�^���ɔ��W�B
34)����c��w�q�������E�X���Y�A�q�������O2009 �N 3 �� 17 ��
35)�{�e�� 2 ��
36)���q�V�w�T������x�u�k�ЁA2009 �N 5 �� 2 ����
37)�V�쏟���u�V���Đ��̎����v�V��A����F�~�ҁw���ꂩ��݂��V���w�x�w���ЁA1996 �N
38)�����Y�w�W���[�i���Y���̉\���x��g�V���A2009 �@ |
 |


 �@
�@ |
���u�����v�̐����ƎЉ�I�W�J
�@�`�W���[�i���Y���ɂ�����Ό��́E���Ќ^�u�����v�̈Ӌ`�𒆐S�Ɂ`
|
|
���v�|
|
|
���{�ɂ����āu�����v�����������̂�1970�N��ł���B���̚���ƌ����闧�ԗ��́u�c���p�h�����|���̋����Ɛl���v(�w���Y�t�H�x)���[�I�Ɏ����悤�ɁA�u�����v�́A���炪�����Ȃ���Ό��ɂȂ�Ȃ��������A�Ǝ��̎�ނƎ���̐ӔC�ɂ����ĕ��邱�Ƃ��w���B�����A�u�����v�������Ă͑��l�ȋc�_���W�J����A�l�X�Ȓ�`�����݂�ꂽ�B���������u�����v�Ɋւ��錩����H���Ă����ƁA�L���Ӗ��ł́u�����v�̒��ɁA���ɐ����E�Љ�I�Ȍ��͂⌠�Ђ�̑ΏۂƂ����A���`�́u�����v(���u���ʒ����v)�����݂��邱�Ƃ�������B�u���ʒ����v���ΏۂƂ��錠�́E���Ђɂ́A1�u�������́v(�������G���[�g�A������x�@�Ȃǂ̍s�����́A�i�@���͂�)�A2�u�g�D���́v(�����`�̐������͂ɂ͊܂܂�Ȃ��A��ƂȂǂ̌o�ό��́A�w�p�E�����A����@�ւȂǂɂ�錠��)�A3�u�������́v(1��2�̗��҂ɂ܂�����A���҂������I�ɍ�p���錠��)�̎O��ނ�����B�������ߋ��̋�̓I����ɑ����ĕ��͂������ʁA�u���ʒ����v�̌��ʁE���ʂ��Љ�ւƔg�y���Ă����ߒ���A����ɗv���鎞�ԂȂǂ͎���ɂ���đ��푽�l�ł������ŁA���������@�����Ƃ����������I�E�Љ�I�ӎv����ߒ��ւ̉e����s���̐��_�`���ߒ��ɋɂ߂đ傫�ȉe���͂������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B����Ɂu���ʒ����v�ɂ́A���f�B�A���݂̋��������N���A����̊������Ɍq����D�z�ݏo���Ă���\�������������B���̂悤�ɂ��āu���ʒ����v���A����̃W���[�i���Y���݂̍�����l���邤���Ō���������̂ł��邱�Ƃ����B
|
|
��1. ���ӎ��ƌ����ړI |
�{�e�́A�W���[�i���Y�������ɂ����āA�������̕��Q���w�E����Ă����A�L�҃N���u���x�Ɉˋ������u���\�v�̑ɂɁA���������ʒu�Â��A�u�����v�����{�ɂ����Ăǂ̂悤�ɒ蒅���Ă������A�܂����̎Љ�I�e���͂͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��ɂ��ĕ��͂��邱�Ƃ�ʂ��āA�u�����v�̈Ӌ`��\���ɂ��čl�@������̂ł���B
���{�Ţ������ƔF�������ŏ��́̕A1974�N10���ɎG���w���Y�t�H�x�Ɍf�ڂ��ꂽ���ԗ��́u�c���p�h�����\�\���̋����Ɛl���v�ł���B�Ȍ���{�̃W���[�i���Y���́A�]���̑{���@�ւ⊯���A��ƁA�w��́u���\�v�Ƃ͈�����悵�A�u���O�̃l�^�v�Łu�Ǝ��Ɏ�ށv���A�u���Ђ̐ӔC�v�ŕ��颒�����ɖڊo�߂�B�u���������v�������������ł���A�����Ɏ����Ă����̈Ӌ`�͎����Ă��Ȃ��B���{�̃}�X�E���f�B�A�����ܒ��ʂ��Ă���傫�ȉۑ�̈�Ɂu���f�B�A�s�M�v�u�W���[�i���Y���s�M�v������B�����̃}�X�R�~�s�M�̋�̓I�Ȍ���́A���{�o�ϐV���В��A�ǔ��V�����В��A�����V���ҏW�ǒ��Ƃ��������f�B�A�W�҂ւ̒l�オ��m���Ȗ����J���̏��n�����o�������N���[�g�����̉e�����傫���B�Ȍ�}�X�E���f�B�A���u�Љ�`�v���т������̑g�D�łȂ��A�������͂�g�D���͂Ɩ�������g�D�̂ł��邱�Ƃ����������m�ɔF������悤�ɂȂ����B�����ă��f�B�A�X�N������ƍߕɂ��l���N�Q�A�̎���K�����A���̂��̂ɂ���������悤�ɂȂ����B���̖��_����ЂƂ@�艺���Ă݂�ƁA���{�̃}�X�E���f�B�A�A�Ƃ�킯�W���[�i���Y����������u���\�v�ɓ��B����B�u���\�v���邢�́u���\�W���[�i���Y���v�́A�����A�s���A��Ɠ����}�X�E���f�B�A�ɑ��čs�������A�u�c��ݒ�(�A�W�F���_�E�Z�b�e�B���O)�v�̃C�j�V�A�`�u�����\���鑤�ɂ���ȏ�A�s�s���Ȃ��Ƃ��ϋɓI�ɖ��炩�ɂ���邱�Ƃ͏��Ȃ��B�����������\�Ђ�����ԉ����Ă������Ƃɂ���āA�A�W�F���_���R���g���[�����ꂽ�W���[�i���X�g�����́A�ᔻ���_�̉��E�܂�Ă��܂��B�}�X�E���f�B�A�̑��݈Ӌ`�́A�u���́v�ɑ���u�Ԍ�(�E�I�b�`�E�h�b�O)�v�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͉ߋ��̎��Ⴉ�猩�Ă����炩�ł���B�Ƃ��낪���܂⌠�͂���邽�߂́u�Ԍ��v�Ɖ����Ă���W���[�i���X�g�����Ȃ��Ȃ��B�����̒m�錠����t������Ă���}�X�E���f�B�A���A�{���́u�����v�����߂��Ȃ��ẮA�u�s�M�v�́A�u���f�B�A����v�����������A���̑��݂��̂��̂��낤������̂ł͂Ȃ����B�|�����́A�u�L�҃N���u�����яo���ēƎ��̎�ނ����鎩���^�L�ҁv�����A�łэs���^�������ǂ�}�X�R�~�E�W���[�i���Y�����~������̂͂Ȃ��A�Ђ̂�����݂��ӂ�قǂ��L�Ҍl�̎��o�����߂Ă���B�{�e�����\�̑ɂɂ�����̂Ƃ��āu�����v���ʒu�Â��A���̖�����g���ɂ��čl���悤�Ƃ���ړI�́A�܂��ɂ��̓_�ɂ���B
|
|
��2. �������̒�`�ƕ��� �`��s�I�c�_�E��������` |
��2�|1 �������ς̑��l��
�����������ڂ����悤�ɂȂ����̂�1970�N��ɓ����Ă���ŁA�p��Ƃ��Ă��A�A�����J�́u�j���[���[�N�E�^�C���Y�v���A�ڂ����w���h���Ȕ閧�����x(�x�g�i���閧��)���Љ���V���L�����Ɍ�����̂��ŏ��ł���B�������́A�C���x�X�e�B�Q�[�e�B�u�E���|�[�e�C���O(Investigative Reporting)�����̂ŁA�����́u�����I�v�Ƃ��u���ʎ�ފ����v�u�{���I��ފ����v�Ƃ����������p�����Ă����B
���{�Ţ��������悭�m����悤�ɂȂ�̂�1972�N����u���V���g���E�|�X�g�v��2�l�̋L�҂��Njy�����u�E�H�[�^�[�Q�[�g�����v�ł���A�j�N�\���哝�̎��C�ɂ���ċr���𗁂т��B���̎��_�Ţ������́A���̂悤�ɒ�`�Â����Ă���B
�u�����Ԃɂ킽���ނ�v�������B���̑���A�����L���̂قƂ�ǂ����_�l�ɂȂ�B�������̔��\�L���ł͂Ȃ��B����ł͂��邪�A�����Ƃ���肪���̂���d���v�B
�����œ��{�� ������� ��Ɋւ��āA����}���ُ����̎G�����C���^�[�l�b�g�������Ă݂��1967�N�ȍ~85���q�b�g�����B���̒��ɂ́A�L�����̂��̂��������ł�������A�u���_�����v�Ƃ������肵�����̂������A���������̂��̂�_�����G���L���ɍi���55���𐔂����B���̂������{�V��������s���Ă���w�V�������x�f�ڂ̂��̂�30�����߂Ă���B�����������͂�������\��ɢ������������Ă�����̂���ŁA�W���[�i���Y���W�̎G����w�p�_������ЂƂǂ�ł����Ɓu�W���[�i���Y���̂�����v��u�p���v����������ɁA�����o����L�[���[�h�Ƃ��Ģ��������o�Ă���B�܂��}�X�E���f�B�A��W���[�i���Y����_�������ЂŁA�͂𗧂Ģ�������_���Ă�����͈̂ӊO�ɏ��Ȃ��A�����o����L�[���[�h�Ŏ��グ�Ă�����̂������ł���B
�����Œ��ڂ��ׂ��Ȃ̂́A�����������グ���_����G���L���A���Ђ��݂�Ƃ��̔��\�N��ɓ����������邱�Ƃł���B�G��55�����̕��ޒ��A1970�N���0�ŁA1980�N��15�{�A90�N��15�{�A2000�N��25�{�ƂȂ��Ă����āA�N��ǂ��đ����Ă���B���{�̒����j��U��Ԃ�Ɓu���ꂪ�����v�Ƃ�����̗Ⴊ�����ꂽ�̂́A1974�N10���ɔ������ꂽ���ԗ��́u�c���p�h�����\�\���̋����Ɛl���v���ŏ��ŁA�A�c�N�v���A�u�����̐��v�ƈʒu�Â��Ă���悤�ɁA���������̂��̂̔F�����A���̕ȍ~�ł���B����ɗ��ԂɐG������ĐV����e���r���u�����v���ӎ�����������1976�N�̃��b�L�[�h�������_�@�ƂȂ��Ă���B����𗠕t����悤�ɈȌ�́u�_�O���X�E�O���}�������v�u�j�c�c�����v�ȂǂŎ��Ђ̓Ǝ������ŕ���X�^�C�����o���オ���Ă������Ƃ��e�����Ă���Ɛ��@�ł���B
1980�N�A�ŏ��ɢ�������_�������k��ł́A���̑����������^�I�ł���̂������I�ł���B�؏��͂����w�E����B
�u�C���x�X�e�B�Q�C�e�B�u�E���|�[�e�B���O�\�����Β����ƂȂ�A���ɂ������A���ʕA�{���ȂǁA���܂��܂Ȍď̂����{�ł͗p�����Ă���B�������A�X�^�C���Ƃ��Č����ꍇ�A�Ƃ��ɖڐV�������̂Ƃ͂����Ȃ��悤�Ɏv���܂��v
�����w�V�������x�Ɍ������V���_���劲�̐X���O���A�u����Ƃ��Ă͔��ɂ܂����v�Ə�������ŁA�L�҂ɂƂ��ẮA�L���������̂͒������������łȂ��ׂ����Ƃ��Ǝw�E���A�u�����Ƃ������Ƃ��킴�킴搂��̂��w���Ȃ��̂��v�ƓB���h���Ă���B�����X�́A�u�����v���V�N�Ȉ�ۂ�^���Ă���̂́A�ǂ̎Ђ̋L���������悤���Ƃ����ǎ҂̕s���́u�A���`�e�[�[�Ƃ��Ẳ��l�ł͂Ȃ����v�Ǝw�E���A���\�ɗ���}�X�E���f�B�A�̑̎���ᔻ���Ă���B�܂����̎��_�ł́A ������� ��̎��Ⴊ���Ȃ��A��ۂł������ĂȂ��B�����T���P�C�V���̔�����I���A�_�O���X�E�O���}�������̔��J����ٔ����̔����������p���āu�����v�̖ړI��_�ɂ��ďq�ׂĂ���̂����ڂ����B
�u�ٔ��ŐR�������̂͌��@�����I����������B���̐[�������ł̓E�~�������Ă����������łȂ��w��ɂ��镅�s�̎��Ԃ�������o�����Ƃ��K�v���v
�܂����́A�{���̑ΏۈȊO�̂��́A�w�i�ɂ�����̂����V���Ђł���Ă����̂��u�����v���ƕ��͂��Ă���B
���{�ł̓T�^�I�ȁu�����v�́A80�N��O���ɑ������ŏo�������B�ŏ��́A1982�N�̒����V���́u�O�z�y���V���E�j�Z���W�v�^�f�A�����Ė����V���́u�~�h���\���v�^�f�A������1983�N�����V���́u������Ȏ��ȑ�w��w�������I�l�v�^�f�ł���B���������j�ɍ��܂�颒�����́A1988�N�ɒ����V�����l�x�ǂ��X�N�[�v�����u���N���[�g�^�f�v�ł��邱�Ƃ͌���ւ��Ȃ��B�������̎����́A�_�ސ쌧�x������{�����A�f�O�����o�܂�����A�����V���������Ȃ���A�����Đ��̒��̐l���m�邱�Ƃ̂Ȃ����ꂽ�A���邢�͉B�����ꂽ�܂I���P�[�X�������B1989�N�x�̃��[�N�V���b�v�ŁA����Ղ́A�����V�����l�x�ǂ́u���N���[�g�v�����グ�A�u�s������ނɋ��͓I�ŁA��ނɑ���������Ȃ��B���������s���̔����̖ʂ�����A���N���[�g�����͉���I�Ȓ������낤�v�ƍ����]�����Ă���B
90�N��ɓ����āA���{�o�ϐV���ҏW�ψ��̓c���N�O�́A�u���{��������y�[�p�[��������O�ɕ��邱�Ƃɖ�N�ɂȂ��Ă���v�W���[�i���X�g�������̂́A�u�݂������̃X�N�[�v�������͂т���A�\���Ȏ��ԂƘJ�͂𒍂����w�����x�����Ȃ����Ƃ̗��R�̂ЂƂɋL�҃N���u�̑��݂�����v�Ƃ��āA�u�����v�̏d�v������A�L�҃N���u�Ɣ��\�Ɉˑ�������{�̊�ƃW���[�i���Y����ᔻ�����B
�V�쏟���́A�w�V�� �}�X���f�B�A�ւ̎��_�x�̒��ŁA�������̃|�C���g��3�f���Ă���B
�u1�i�v�ɗz�̖ڂ����Ȃ��o���낤����(�s��)�@���� 2�Y���ӔC�����łȂ��A�����I�A�Љ�I�A���`�I�ӔC��Njy���� 3�{�����ǂɑ��đ{�����̔��������Ȃ����v���̂���3�ɂ��ẮA�M�҂͎�m�ł��Ȃ��B�Ƃ����̂��u�����v�̎�ޑΏۂɂ���ẮA�{�����ǂ������Ȃ����̂����X���邽�߂��B1990�N1���A�����V���́u���]�������߂�1��2000���~�v�̋L���́A�킸��1�����œ��������A�����l���Ƃ̊ԂŃL���b�`�{�[�����ꂽ�����ŁA�����߂̏����鏑��1��2000���~�̗��v���������Ƃ����u�����v�����A�{�����ǂ͓����Ă��Ȃ��B�V�삪��`�����̂́A(�o�ŔN����)1993�N�ł��邱�Ƃ��l����A��L�̃P�[�X�͌�������Ă�����ׂ����B���̌�����l�̃P�[�X�͑����A��ɏq�ׂ閈���V���́u���Ί�s���v�̃X�N�[�v���A�T�^�I�ȁu�����v�����A�{�����ǂ͓����Ă��Ȃ��B
�����������̒�`�ɂ��ẮA1995�N�̎��_�ł��܂��A�u����Ƃ��������m�Ȓ�`������킯�ł͂Ȃ��v�ƐV��������҂́w���ܐV�����l����x�͏q�ׂĂ���B
�u��܂��ɂ́A�g�D��c�́A���l�Ɂw�\�ɏo�������Ȃ������x������A�������B���ꂽ �������������Љ�̐��`������̌����A�����̕����ɔ�����ꍇ�Ƀ}�X�R�~�����Ȃ̐ӔC�ɂ����āA�������A���\���邱�ƁA�Ƃł������邾�낤���v�B
��s�����̒��ŁA�o�c�I���R�ƑΌ��͂Ƃ̊W����A�u�����v�̏��ɘ_�Ɍ��y�����̂��A��\��ł���B���̗��R�Ƃ��āu�I�����댯�Ȋ����Ɍo�c�������������Ƃ��S�O������Ȃ��v�ƌo�c�I�������������A�Ό��͂ɂ��ẮA�{������ƌ����Y�̑Βk������p���Ȃ���A����L�҂̕����Ƃ��Ắu���͂Ƃ̏Փˉ���v���グ�Ă���B���̌��ʂƂ��āA�u�����v�͋ꋫ�ɗ�������Ă���ƌ��Ă���B
�u�ᔻ���_�E�^�������ȂǃW���[�i���Y���̃G�g�X�ɒ�������c�݂����ɁA�ȏ�̂悤 �ȋꋫ���璲�����~�o���邱�Ƃ́A�W���[�i���Y�����̂��̂̍Č��Ɋւ��v
�O�L�̓V����w�V ����}�X�R�~�_�̃|�C���g�x�̒��œ��l�̌����������Ă���B
�u�o�u���o�ς��͂����A�V���ƊE�������s�����ɓ����Ă���́A���Ԃ�o��̂����钲���͂��������A�ނ��딭�\�W���[�i���Y���������������Ă���̂����v�B
�ʂ����Ă����ł��낤���B1990�N��́A�ُ�Ȏ�����������10�N�������B���Ƀo�u��������1992�N�ȍ~�́A���Z�@�ւ̕s�ˎ��ƓE���A���a���E�A����}�ցA�[�l�R�����E�A4��،����ʔw�C�A�呠���E�E�E�E�ƁA�����n�����{�����Ō�̋P�����������Əd�Ȃ�A���N�̂悤�ɑ�^��������Ƃ̓E�����s�Ȃ�ꂽ�B�܂��I�E���^�����̎����A�{���A�����A�_�啁���x�A���K�A��_��k�ЂȂǂ̓V�Ђɂ��}�X�E���f�B�A�e�Ђ́A��������œ��������B�ƂĂ��l�Ǝ��Ԃ��|����u�����v�ɎQ������]�T�͂Ȃ������B����ł�1998�N����99�N�ɂ����Ė����V���������u�ЎR���N���́v�ł́A�u�������̔�Q�҂̌����Ǝx����̊m����Nj����������v�Ƃ���2000�N�ɐV������܂���܂��Ă���B���̃P�[�X�́A�_���v�J�[�ɂ���ʎ��̎��Ƃ��Č��@���^�]���s�N�i�ɂ������̂��A��e����̓����ɒ��ڂ����L�҂��A���̔w�i���@�艺���ăL�����y�[����W�J���邤���ɐV���Ȏ��̖ڌ��҂�������A�^�]��̉ߎ������t�����A���@���đ{����]�V�Ȃ�����L�߂ƂȂ����B���̃L�����y�[���Ȃǂ����������ɁA�ƍߔ�Q�Ҏx���֘A�@�����������B�u�����v�Ɓu�L�����y�[���v����̉������P�[�X�ł���B
�����2000�N��ɂ͂���Ƌ��V��́u�ߊϓI�\�z�v�ɔ����āA�u�����v�́A�m���ɍL����������Ă����B�܂������V�����X�N�[�v�����u���Ί픭�@�s���v(2000�N11��)���B�o�c��Ԃ��ꂵ���Ƃ���閈���V���ɂƂ��Ė{���Ȃ�o������Ԃ��A�J�͂�������u�����v���T����͂��̂Ƃ��낪�A�t�Ɂu�����v�ɗ͂𒍂��ł���B���̂��Ƃ͋ɂ߂ďd�v�ȈӖ������B�܂袒�����������A�V���̉��l�����߂�d�v�ȕł���Ƃ̔F��������͌����ɋy���A�o�c�w�ɂ����m�ɔF������Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̑��ɂ������ʐM�Ђ́u�_�ސ쌧�x�@�̖\�s�����v�A���m�V���́u�����ŗZ���v�A�����V���́u�h�q�������J�����҈ꗗ�̉v�A�u���q����W�̂��߂̏Z����{�䒠�����W�v�A�u�A�X�x�X�g�Ёv�A�k�C���V���́u���x�����^�f�v���X�A�S���I�ɓW�J����Ă���B�����2005�N��06�N�Ɂw�V�������x���A�u�����̗́v��2��ɕ����ē��W���A�V���L�҂ɐϋɓI�ɔ��M���Ă���̂́A�������̏d�v�����ĔF������Ă��邩��Ɛ����ł���B
|
��2�|2 �������̒�`
���̂悤�ɁA�u�����v�́A1970�N��ɒ��ڂ����悤�ɂȂ�����A�W���[�i���Y���̌���Œ����ɍ������낵����B�����ē������`�I�������u�����v�̈Ӗ����e�m�ɒ�`���悤�Ƃ��鎎�݂��W�J�����悤�ɂȂ��Ă����B
���o�[�g�E�O���[���́A�w�L�҃n���h�u�b�N�x�Łu�����Ƃ͉����H�v�Ƃ��āu����͋L�҂̊Ԃł����A�Ȃ��c�_���Ă�ł���₢�ł���v�Əq�ׂĂ���B�O���[���́A�����́A��łɋ����̂��������A�Â��ǂ�����̕ɂ��Ă̍����̌Ăѕ��ɉ߂��Ȃ��Ƃ�����������Ȃ����A���ނ����`���ꂤ��Ƃ��āA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�����Ƃ́A����̌l��g�D���閧�ɂ��Ă��������ƍl���Ă��鐬�ʂ⌈��A�d�v�Ȏ�������邱�Ƃł���B�����ɂ͎O�̊�{�I�v�f������B���Ȃ킿�A���̎҂ł͂Ȃ��L�Ҏ��g�ɂ���Ē��������Ƃ������ƁA�����Ē����Ώۂɓǎ҂⎋���҂ɂƂ��Ė��炩�ɏd�v�ȈӖ������������܂܂�Ă��邱�ƁA�܂��N�������̒����Ώۂɂ��Č��ɂ����Ȃ��悤�Ӑ}���Ă��邱�ƁA�Ƃ����v���ł���v
���{�ɂ����ẮA1980�N�㏉�߂́u�y���V�����W�^�f�v�A�u�~�h���\���^�f�v�u������Ȏ��ȑ�w�^�f�v��3�̕ɂ���āu�����v���A��̓I�ɂǂ��������̂��w����������ɖ��m�ɂȂ��Ă������B
������Ȏ��ȑ�w�̎�ނ�S�����������V���̋k�O���ɂ��ƁA��ރv���W�F�N�g�`�[���̊Ԃł́A�u�����v�͈ȉ���3�̏����������̂ƒ�`����Ă����Ƃ����B
1�O���̋@�ցA�{�����ǂȂǂ̎x�����Ȃ�����I�ȓƗ���ނł���B
2���̕p�����A�Ȃ�炩�̈Ӗ��ŎЉ�I�ɍ����I�ȁA���邢�͖���N�I�ȗv�f���܂�ł�����̂ł���B
3����v�f�Ƃ��ẮA��ޑΏۂƂ��Ă͌��͈��A�\�����s�ł���B
�����ĐV�����A�u�Љ�\���A�����\���A�o�ύ\���̒��ɉB���ꂽ�����ɂ��āA���̓����ɕs�����������𖾂�݂ɏo���v���߂ɂ́A�u�̐��m���v�u���闝�R�v���s���ł���A�v���W�F�N�g�́A�u���ʉ����đ��v�Ƃ��������̐T�d�ȗ��t���v��ނ����A�u���邱�Ǝ��̂��Љ�̌��v�ɍ��v���A���e���̂������̗��v�ɍ��v����v���Ƃ��A���ʂ�ʂ��ēǎ҂ɐ������Ă������Əq�ׂĂ���B
���������F���́A�����P�Ɂu�������ĕv����Ƃ����Ӗ��ł́��s�ׂƂ��Ắu�����v������A�Љ�̌��v������ށE�̎x���ɂ���Ƃ����_�ŁA���ړI�ӎ��̂���u�����v���Ƃ��āA��蓥�ݍ���z�肵�Ă���B���̌��ʁA���Ђ͖����ł����ǐ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�{���@�ւ�s���@�ւ��Ȃ�炩�̑Ή��𔗂��邱�ƂɂȂ�B
���N���[�g�^�f�̎�ގw�������������V���̎R�{�����������w�Njy�\�̌��I�����_�x�́A�\��ǂ���A���炪���H���Ă�����̓I����������Ȃ���Г��ł̂������܂߂ďڍׂɋL�q���Ă���B�R�{�́A���̌���u�V���L�҂��l����v�u�����Ƃ͉����\�\���N���[�g�������瓾�����P�v�u�����V���́w�����x�v�u�W���[�i���Y���Ƃ͉����v�Ƃ������_�l�Łu�����v�̏d�v��������Ă���B�R�{�͂����̒�����_���̂Ȃ��ŁA�����ɂ킽���Ă����炩�ɂ���Ȃ����낤���Ǒ��ɂƂ��ēs���̈����������A�@�ւ��Ǝ��̒�����ނŕ�������ł���A���̕K�{�����Ƃ��Ċm�F�A���t���A�W�҂̏،��A���������A����ɂ͓����̋��͎҂���̌���I���̓��肪���ߎ�ƂȂ�P�[�X�������Ƃ��Ă���B�R�{�̋c�_�̃|�C���g�������4����B
1����(���邢�̓`�[��)�������Ȃ���A���̖ڂ����Ȃ������B
2���\�ɗ��炸����̒����\�͂Ŕ��@���鎖���B
3�V���f�ڂɂ���Ė\�I���A�Љ�ɒm�炵�߂�B
4���̌f�ړ��e���A���́A���Ђ��镔���A��ƂȂǂ��B�������鎖���B
���̂悤�ɕ���ɂ�������H�̒��ł̂��܂��܂Ȏ��s����̉ߒ��ŁA�u�����v�̒�`�͎���Ɋm�肳��Ă������ƌ�����B
|
��2�|3 �u�Ǝ��v�Ƣ�����
�ɂ́A�傫�������āu���\�v�Ɓu�Ǝ��v�ɓł���B�u���\�v�ɂ��ẮA���łɏq�ׂ��B�u�Ǝ��v�ɂ́A�u���ؕv�u�v�u�_���E����v�u�I���v�u���_�����v�u�L�����y�[���v�Ȃǂ�����A�u�����v������Ɋ܂܂��B�܂��u���ؕv��u�L�����y�[���v�ɂ́A�u�����v�ƘA���������̂�����B
�ł͌���̋L�҂����́A�u�����v���ǂ��F�����Ă���̂ł��낤���B2007�N�ɂm�g�j�����������������A�m�g�j�L�ҁE�J�����}��1123�l��Ώۂɍs�Ȃ����u�����v�̃A���P�[�g�ŁA���ꂼ�ꎩ�炪�s�Ȃ����u�����v�̎���������Ă���B
�u�F�ɏP��ꂽ���S���̂ŁA�����i�̕��͂��牽���F�ɏP���邩���ׂĕ��������v�u�a�@�ĕ҂̉e���ō����Ă���l���}�����Ă�����ԁv�u��t�s�����v�u�k�C����K�͓|�ؔ�Q���Ԓ����v�u�a�@���ŊŌ�w�����҂ɖ\�͂��ӂ���Ă������Ԃ̃C���^�r���[�v�u��`���݂ɔ����C�m�����̊��ւ̉e�������v�u�ŃT�C�g�Ɋ������܂ꂽ��҂̎��ԁv�u�ϐk�U�������ŋ����{���ɓ���܂ł�2�����Ԃ̒����v�u���{�݂œ����҂�����߂�����ԁv�u�ЊQ��ɂ��Ď����̂ɃA���P�[�g�������s�Ȃ��ĕs����ۑ��v�u�����ی��Õ}�����x���p�̎��ԁv�u�V��������̍��\�ɂ��Ĕ�Q�҂̎��Ԓ����v�u�������Ƃ̒k���Ɠ��D���v�ɂ��Ē����v�u�ė������a -29�̓�������W�c�ŏP�������Z���،��v
�ȏ�̂悤�Ƀe�[�}�����e���l�X�ł���B�����͂���������I�@�ւ��ƂȂǂ̔��\���ď��������̂ł͂Ȃ��B�Ǝ��̏������Ɏ�ނ��A���Ђ̐ӔC�A�܂�u�m�g�j�̒��ׂɂ��܂��ƁE�E�E�v�̃N���W�b�g�ŕ������̂���ł���B
�����A�͂����Ă����́̕A�u�����v�ƌ�����̂ł��낤���B�Ȃ��Ȃ�A�F�ɂ�鎀�S���̎��̂́A���ɂȂ������̂ł���A�ŃT�C�g�������łɂ���܂ł����X�̓E�����Ⴊ����B��L�̂ЂƂЂƂ����Ă݂�Ε�����悤�ɁA���łɂ��̂��Ǝ��̂́A�u���m�̎����v�������ƌ����Ă����B���������ɂȂ��Ă���������ɁA������@��N�����ĐV���ȃj���[�X�Ƃ��ĕ���P�[�X������B�Ⴆ�A1976�N�̃��b�L�[�h�����Ȃǂ́A�����n�����{���̔��\�ɂ�炸�ɓƎ��̃��[�g�Œ������A�čs�������Ƃ���A������u�����v�Ƒ�������������邱�Ƃ͂��łɁu�����v�ς̒��ŏq�ׂ��B
�܂�1960�N��ɂm�g�j�́u�|���I�o�Łv�L�����y�[����ǔ��V�����s�Ȃ����u���F�����v(�����p�~)�L�����y�[���Ȃǂ��A�Љ�̌��ۂ�����ɓ��ݍ���Ŏ�ނ��A��W�J���čs�����Ǝ���ނɂ��ł������B��ɎR�{���q�ׂĂ���悤�ɁA�u����(�܂��̓`�[��)�������Ȃ���Γ��̖ڂ����Ȃ������v������ƁA���b�L�[�h�����͂��łɓ���{���ɒ��肵�Ă��邵�A�u�|���I�v��u���F�����v���A���̂��̎��̂͌��m�̎����ł������B�������Ǝ��̎�ށA�����ɂ���āA���b�L�[�h�����ł́A���ʗ_�m�v�̐l��������A�q��ƊE�Ƃ̊ւ�肪��������ɂȂ�����A�u�|���I�o�Łv�L�����y�[���ł́A�S���I�ɋ}���Ȋg�����X�e���r�Ŗ��炩�ɂ��邱�Ƃɂ���Ĕ�Q���Ԃ�m�炵�߂���A�u���F�����v���߂����ẮA�{�c���t���A�R�J�̃h���X�ɐ������Ď��Ԃ����|�����肵���u�����v�ł���B�����ɂ́A�u�����v4�����̂ЂƂA�u���̖ڂ����Ȃ������v���V���ɖ��炩�ɂȂ��Ă���B��L�̂m�g�j�́u�����v�ɂ��Ă��A�M�҂́A���ɂȂ��Ă��鎖�Ă��@�艺���邱�Ƃɂ���āA�܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��V���Ȏ�����Ǝ��Ɏ�ށE�������A�Ђ̐ӔC�ɂ����ĕ������̂ł���A�����S�Ă��u�����v�Ƒ�����B
����܂ŁA�}�X�E���f�B�A�̌���ł́A�u���͂⌠�ЂȂǂ̕s����Ǝ��̎�ނŖ\���v���Ƃ��A�u�����v�̏����̈�Ƒ������Ă����B�������A���͂⌠�Ђ���ޑΏۂłȂ��Ă��l�X�ȁu�Ǝ���ށv�ɂ���āA�V���Ȏ������������Ă���P�[�X�́A��L�́u�F�ɂ�鎀�S���́v��u�V�������\��Q�̎��Ԓ����v�Ȃǂ��疾�炩�ł���B�������u�����v�Ƒ�����A��ɐ؏���X���O���q�ׂ��u��ފ����Œ������ċL���ɂ��Ă����͓̂��R�v�Ƃ����F���ɍ��v����B�u�Ǝ���ށv�ɂ���ĐV�����������������̂��A�u�����v�Ƒ����Ȃ����Ζ����ɂȂ�B���������u�����v���V���̕���펡�́A�u�L�`�̒����v�Ɩ��t���A�������͂��Ă���B
�u�w�x�@�̒��ׂɂ��Ɓx�Ƃ��������\���ňꊇ����Ă���L���̒��ɂ��A���Ȃ��Ƃ� �[���͋L�҂̒���(���)�ɂ�鎖�������Ȃ��Ȃ��B�]���́w��ޕx�ɂ��w�����x�I�ȗv�f�͑����܂܂�ė����̂ł���B�܂��A�x�@�Ȃǂɑ����ފ������w�����x�̈��ƌ����Ȃ��͂Ȃ��B�Ƃ���A�����Ŏ�ޕƖ��t�����]���̋L�������ǂ͒����̈��ł���A�Ђ��Ă͐V���L���͂��ׂĒ������A�Ƃ̎咣����������B(����)���̂悤�ȔF���͍L�`�̒����Ƃ��āA���`�̂���Ƃ͋�ʂ��������킩��₷���v
����͖����V�����{�ЕҏW�ǗV�R���A�L�҃N���u�Ɉˋ������A���\�Ɋ��Ȃ��Ǝ��̏���ގ�@�ɂ���ĕ������̂��u���`�̒����v�ƒ��Ă���B
���́u���`�̒����v�̑Ó����ɂ��čl����ہA�����V���E�R�{�����f����u������4�����v�͎����I�ł���B
�R�{�́A�u�����v�̏����Ƃ��āA
1����(���邢�̓`�[��)�������Ȃ���A���̖ڂ����Ȃ������B
2���\�ɗ��炸����̒����\�͂Ŕ��@���鎖���B
3�V��(�e���r�A���W�I�A�G��)�ɂ���Ė\�I���A�Љ�ɒm�炵�߂�B
4���̕��e���A���́A���Ђ��镔���A��ƂȂǂ��B�������鎖���B
�������Ă���B�����ŁA���\�ɂ��Ȃ��Ǝ��̎�ށA�����ɂ���Ĕ��@�������u�L�`�̒����v�ƍl����ƁA����`�̒����� ��Ƃ̈Ⴂ�́A�R�{������u4���́A���Ђ��镔���A���(���邢�́A���̌l)�Ȃǂ��B�������鎖���v���܂܂�邩�ۂ��ł��邱�Ƃ�������B
�R�{�̎���4�����̂����A1�A2�A3��������̂��u�L�`�̒����v�Ƃ��A�����4�̌��́A���Ђ�̑ΏۂƂ���A�Ƃ��������������u�����v���A�u���`�̒����v�ƒ�`�Â���A�u�L�`�v�Ɓu���`�v�̈Ⴂ�����m�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�������A�}�X�E���f�B�A���`�Ԃ��������ꍇ�ɁA�u�L�`�����v�u���`�����v�ƌĂԂ̂́A���t������Ԃ��C���[�W���Â炭�A����̓����Ƃ��Ă�����܂Ȃ��B�����ŁA�����ł͎�ޑΏۂ��A�u���͂⌠�Ђ���g�D��l���v�ł��钲�����u���ʒ����v�Ɩ��Â��āA�]���́u�����v(�܂�u�L�`�̒����v)�Ƃ̍��ʉ������݂Ă݂�B
|
|
��3.�u���ʒ����v�Ƃ��̎Љ�I�e��
|
|
�u�����v�Ƣ���ʒ�����̈Ⴂ�ŏd�v�ȓ_�́A��ޑΏۂ��u���́v��u���Ёv�ł��邩�ǂ����ł���B�W���[�i���Y�����A���X�N����Љ�ۂɂ��āA��3�҂ɓ`����ړI�ɐV���A�e���r�A���W�I�A�G���Ȃǂ̃}�X�E���f�B�A����Ĕ��\���邱�ƂƑ�����Ȃ�A����ʒ����� ��́A���Ɂu���́v��u���Ёv��ΏۂƂ��A�W���[�i���Y���{���̌��͊Ď��̖������ʂ����ƈʒu�Â�����B�����ŁA�u���ʒ����v�̈Ӗ����e�����A���m�ɂ��邽�߁A���������u���́v�u���Ёv�Ƃ͉����ɂ��āA���̊T�����m�F���������ŁA�u���ʒ����v���ΏۂƂ���u���́v�u���Ёv�̈Ⴂ�ɑ����āu���ʒ����v���������̃J�e�S���[�ɗތ^�����Ă݂����B
|
��3�|1 ���́A���Ђ̑�����
�u���́v�ɂ��ẮA���{�ł����܂��܂Ȋw�ҁA�����҂������ΏۂƂ��Ă���A�c�_�̐�����A�v���[�`�͋ɂ߂đ���ɘj���Ă���B
�u���ʒ����v�Ŏ��グ��ΏۂƂ��Ắu���́v�u���Ёv�́A�ǂ̂悤�Ɉʒu�Â����邾�낤���B�ł��L���m��ꂽ�}�b�N�X�E���F�[�o�[�̒�`�ł́A�u����Љ�W�̓����Œ�R��r���Ă܂Ŏ��Ȃ̈ӎv���ѓO���邷�ׂẲ\�����Ӗ����A���̉\�������Ɋ�Â����͖₤�Ƃ���ł͂Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B���̒�`�ɂ��Ďs���e�F�́A�u�ǂ�Ȍ`�ł���A�w�݂�����̈ӎu���ѓO�����邱�Ɓx�ł���A���҂̖����Ȓ�R�⑼�҂ւ̋������s�݂̂Ƃ����A�݂�����̈ӎu�͊ѓO������A�܂�w���́x�͔���������̂ł���v�Ɖ�����Ă���B
�܂���J�����́A�u����҂����҂����̈ӎu�ɔ����Ă܂ł�����s�ׂɌ����킹�邱�Ƃ��ł���͂��A��ʓI�Ɍ��͂Ƃ����v�ƒ�`������ŁA�u�Љ�̏��̈�ł��ꂼ��̌��͂����݂��Ă��邪�A����̒n����ɂ����ċ��ɓI�D�ʐ���L���A�s���]�ɑ��Ă͍��@�I�ɕ����I�����͂��s�g��������̂𐭎����͂Ƃ����v�ƒ��Ă���B
����A��ԏG�v�́A�������͂Ƃ͋�ʂ����ׂ��`�Ԃ̌��͂Ƃ��āu�g�D���́v�������A1970�N��̌������Ԗ���f�ނɁA���Ƃ̌��͂Ƃ��̐����I�n�ʂƂɂ��Ę_���Ă��邪�A���̒��ŁA�@�ւɑ���e���͂Ɍ��y���Ă���B�����Ē����V���L�҂��A���ԃL�����y�[�����n�߂�O�̋�Y�Ƃ��āA�O��X�|���T�[�̈�����ԉ�Ђ̔��������킢�Ɠf�I���Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��āA���̂悤�Ɏw�E���Ă���B
�u�����Ŗ��炩�ɂ���Ă���͎̂����ԉ�Ђ��A�R��i�ۗ̕L�ɂ���āA�V���Ђ�T �d�ɂȂ炵�߂Ă���Ƃ�������ł���B���̒i�K�ł̓��[�J�[�͖����I�ɂ͉e���͂��s�g���Ă��炸�A�V���Г��̑Ή��́A�e���َ̖͂��I�ȍs�g�������Ă��錋�ʂł���v�B
����Ɠ��l�̏́A2000�N��̍����ł�������B�g���^�����ԑ��k���̉��c�ׂ��A�e���r�ԑg�̌��J�Ȓ@���ɕs���������u�ł����Ă�낤���v�Ɣ����������Ƃ́A���c����X�|���T�[�Ƃ��Ď��ЂƊւ�肪�Ȃ����J�Ȃ̖��ɂ����Ă���A�u�g�D���́v��U�肩�����Ă��邱�ƂƑ��ʂ��Ă���B���̔����ɑ��āA�قƂ�ǂ̃��f�B�A�����c�����ɐG�ꂸ�A��X�|���T�[(���匠��)�̑O�ɁA��Ƃ��Đ��Ȃ��ł���B�����������������Ă��A�u�g�D���́v�ƃ}�X�E���f�B�A�̗͊W���M���m�邱�Ƃ��o����B
����A��ΗT�͌��͂��\������v�f�A���ʂɂ��āA�u���͍s�g��́v�u���͎����v�u�e���͂Ƃ��Ă̌��́v�Ƃ����T�O��p���Đ������Ă���B
�u���͍s�g��́v�́A�Љ�ɑ��ĉe���͂��s�g�ł���l��g�D�ŁA��ʂ̐l�X�ɑ��ĉe���͂��s�g����\�������������G���[�g(�����Ƃ⊯��)��g�D�B�u���͎����v�́A���͎�̂����L����u�����v�A���Ȃ킿�����G���[�g����ʂ̐l�X�ɉe�����s�g�ł����A�̐���ߒ���x�I�Ȍ����A�Љ�I�n�ʁA�܂�����Ɋւ�����I�Ȕ\�͂���B�u�e���͂Ƃ��Ă̌��́v�́A���̎Љ�W�̒��ő��҂ɑ��čs�g����A�����G���[�g����ʂ̐l�X�ɑ��čs�g����e���͂��̂��̂������Ƃ��Ă���B����ɑ�́A�u���͎����v�ɂ��āA�u�o�ό��́v�u�������́v�u�������́v�u�ے����́v��4�̌`�Ԃɕ��ނ��ꂤ��Ǝw�E����B�����āA�u���ƌ��́v�́A�u�o�ό��́v(�\�Z�z���Ȃ�)�A�u�������́v(�������x�E�g�D�Ȃ�)�A�u�������́v(�x�@�A�R���Ȃ�)�A�u�ے����́v(���f�B�A�A���Ȃ�)�Ƃ��������͎����̖ʂő��̑g�D�����D�ʂȗ���ɂ���A���̂��Ƃ����x������A����������Ă���Ɛ������Ă���B
���������c�_�܂���Ȃ�A���͂Ƃ͋����Ӗ��ł̐������͂Ɍ��肳���ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B�����͂�L����g�D��l���ł���A�召�ɂ�����炸�A���ꂼ��̏ꏊ�╔���A�y�n�X�X�̃{�X�I���݂��܂߁A���͍͂L���Љ�̏��̈�ō�p���Ă���B�]���āA�W���[�i���X�g���u���ʒ����v���s���ΏۂƂ��đ�����̂́A�����A�o�ρA�Љ�̍L�͈͂ɑ��݂���l�X�Ȍ`�Ԃ̌��͂ł���B
�܂��A�u���Ёv�ɂ��āA�J���x�j�́A���̂悤�ɒ�`���Ă���B
�u����̕���ɂ�����D�ꂽ�l���⎖������������A�Љ�I�M�p�⎑�i���Ӗ������肷 �邪�A���ʂ��Ă��邱�Ƃ́A�w�Љ�I�ɏ��F�����x�Ƃ������Ƃł���B�Љ�W�ɂ����ẮA���x�A�n�ʁA�l���Ȃǂ��D�z�I�ȉ��l��L������̂ƔF�߂��A�����̐��s����Љ�I�@�\���Љ�ɂ���ď��F�����ꍇ�A�����̐��x�A�n�ʁA�l���͌��Ђ�L���Ă���A�Ƃ����v�B
�������Č��Ă݂�Ƣ���ʒ�����̎�ޑΏۂ́A���͂���������u���E���E���v�ɂƂǂ܂炸�A�w�E�⋳��E�A�����c�̂�}�X�E���f�B�A�ȂǁA�Љ�I�e���͂�ێ�����S�Ắu���Ёv����g�D��l�����R�܂܂��B���N���[�g�^�f�̎��A�����Ƃ⊯�E�A�o�ϊE�̎�v�l���ɍ������āA�����J���Ă������o�A�ǔ��A�����̊������������f�B�A�ɂ���Ďw�e���ꂽ�����́A��ޑΏۂƂ��ē��{���\�����V���̊����Ƃ����u���Ёv��L���邪�̂ł��邱�Ƃ���Ă���B��̑�́u���͊T�O�v���炷��ƃW���[�i���Y���́A1���`�B��i�A2���L�̎Љ�I�n�ʁA3��������Љ�Ɍ����Ĕ��M����Ă߂̐��I�ȋZ�\��Z�p��L���A���������u���͎�����p���ĎЉ�I�ȉe���́A���Ȃ킿�Љ�ɑ��Č��͂��s�g���Ă���v�̂�����A���̃��f�B�A�̍ō������������g���A�u���͎ҁv�̔��e�Ɋ܂܂�邱�ƂɂȂ�B
|
��3�|2 �u���ʒ����v�̓W�J�ƎЉ�I�e��
�ȏ�̂悤�ȓ_�܂��Ȃ���u���ʒ����v�̎Љ�I�e�����l����ہA���Y�́u�v���A�ǂ̂悤�Ȏ�ނ́u���́v�u���Ёv��ΏۂƂ���̂��ɂ���āA�Љ�I�e���͂̊g��̗l���₻�͈͎̔͂����ƈقȂ��Ă���B�]���āA�u���ʒ����v�̑ΏۂƂȂ�u���́v����ʂ��������ŁA���ꂼ��ɉ������u���ʒ����v�̎������������K�v������B
�{�e�ł́u���́v���A1�u�������́v(�������G���[�g�A������x�@�Ȃǂ̍s�����́A�i�@���͂Ȃ�)�A2�u�g�D���́v(����ƂȂǂ̌o�ό��́A��ÁA�w�p�E�����A����@�ւȂǂɂ�錠��)�A3�u�������́v(1��2���҂ɂ܂�����A���҂������I�ɍ�p���錠��)�̎O��ނɕ��ނ��A������ΏۂƂ���u���ʒ����v�ɉߋ��ǂ̂悤�Ȏ��Ⴊ���������A�����Ă��ꂪ�ǂ̂悤�ɎЉ�I�e���͂��y�ڂ��Ă������������Ă������ƂƂ���B
���̈���ŁA�u�v���Љ�ɉe����^����Ƃ����ꍇ�A������ǂ̂悤�Ȏړx�łǂ̂悤�ɑ��肵���邩�Ƃ�����������B���̖��́A�Љ�I�e���͂̊g��ߒ����ǂ̂悤�ȃ^�C���X�p��(���ԓI�͈�)�ɂ����Ċϑ����邩�Ƃ������ɂ��ւ���Ă���A����܂łɂ����l���̘_�҂ɂ���Ďw�E����Ă����B
�Ⴆ�A�ɓ����j�́A�ăm�[�X�E�F�X�^����w��D.�v���e�X��̒������ʂȂǂ��Q�Ƃ��A�u�����v�̎Љ�I�e���͂̊g��ߒ��́A�u�����_�������ω��v�Ƃ������P���I�ȃ��f��(���u�����^���f���v)�Ŕc�����邱�Ƃ͍���ł���A�܂������ɂ�������������͏��Ȃ��Ǝw�E����B�ɓ��́A�L���ȁu�E�H�[�^�[�Q�[�g�v�����ɂ����Ă��A�����̃��V���g���E�|�X�g�́̕A����5������ɍs��ꂽ�哝�̑I���ł͑傫�ȑ��_�ɂȂ炸�A�ނ��덑���̊S�����܂��Ă������͍̂ٔ���c��̌�����Ȃǐ������͓����ł̋^�f�Njy���������������ʂł������Ǝw�E����B�܂�A�����ړI�ɎЉ�I�e���͂��g�債�Ă����Ƃ��������A���̉ߒ��ɕ��G�Ȑ����ߒ�����݂��Ă���Ƃ����̂ł��B���������_�ɂ��Ă��A�X�̎���ɑ����čl�@���Ă����B
��(�@)�������͒Njy�^
�����G���[�g��ΏۂƂ����u���ʒ����v�ł́A���ԗ��́u�c���p�h�����\���̋����Ɛl���v������ł���B ��c���p�h������́A�ǎ҂��猩���1�u�m�炳��Ă��Ȃ������v�̖\�I�������B�����V���̎А��́A�u���Ď��グ��ꂽ��A�����Ƃ��Ă͈ꉞ�������݂ł��邩������Ȃ��v�Ƃ��Ă��邪�A���Ԃ́A�u�����̕����́A�V������ނ���͂��߂Đ��Ɍ��\���ꂽ���Ƃł��������v�Ɣ��_���Ă���B
�܂��u�c���p�h�����v�́A2�Ǝ��Ɍ@��N�����A���t����ނŐV���Ȏ��������ނƂ����v�����������Ă���B�u���̋L���̈�s��s�A�}�ł̈ꖇ�ꖇ���A�N�������Ă��r�b�N������قǂ̎����ɗ��ł�����A�����Ȋm�F��Ƃ��Ȃ���Ă���B���̎����̌��݂́A�䂤�ɐ����̏����������ɑ�����̂��v�Ɨ��Ԃ͋L���Ă���B�����3���Y�t�H�Ђ̐ӔC�Łw���Y�t�H�x����ɔ��\����Ă��邪�A�^�[�Q�b�g�́A4���͎҂̋��������̖\�I�ł������B���ꂽ�L���̓��e���A�}�X�R�~�e�Ђ��ǂ������钆�ŁA�����̒N�����m��Ƃ���ƂȂ����B�e�Ђ̒ǐ��A�̘A���̌��ʁA�c���͎����E���A�O�ؓ��t�����������B
�����œ��ɒ��ڂ������̂́A�}�X�R�~�e�Ђ̒ǐ��ł���B�������ꂪ�Ȃ������ꍇ�ǂ��Ȃ��Ă������낤���B�O�o�̐A�c�́A�w�m���������������x1974�N10��21�����Ɍf�ڂ��ꂽ�����V���_���ψ��̐[��Y�̋����[���ӌ����Љ�Ă���B
�u����قǂ̖\�I�����[���b�p��A�����J�ōs��ꂽ�Ȃ�A���{��]��������悤�ȏՌ���^���邾�낤���A�����̍��͓��ʂȍ��ŁA���̋L���͊Ԃ��Ȃ��Y����邾�낤�v
�M�҂��[�㓯�l�A�e�Ђ��ǐ����Ȃ���A�c���p�h��66�����́w���Y�t�H�x�����A�c���ɂ��Ǐ]���鐭���L�҂ɂ���ăK�[�h����A���ʂ͓��������Ƃɂ͋��͂������Ĕᔻ���˂������Ă����̂ł͂Ȃ����Ɛ�������B�������e�Ђ����ꂼ�ꗧ���オ��ΐ���������Ȃ��������ƌ�����B�������Ă݂�ƁA�����ړI�ɎЉ�I�e���͂��g�債�Ă����Ƃ��������A���̉ߒ��ɕ��G�Ȑ����ߒ�����݂��Ă���Ƃ�����̈ɓ��̎w�E�́A���̃P�[�X�ł͓��Ă͂܂�Ȃ��B
�u�������͒Njy�^�v�̕ɂ́A���̑��ɂ������G���[�g�ł��錳�J���ŎQ�c�@�c����̑��㐳�M�̑ߕ߂܂Ŕ��W�����u�j�r�c�^�f�v��(�T������)������B�܂��s�����͂�ΏۂƂ����u���ʒ����v�ɂ́A�x�@�ɂ��ł����グ�A�l�߂𐰂炷�؊|���ƂȂ����u���������v��(�啪�V��)�A�u�u�z�u���c�I�l�ߎ����v��(�e���r�����w�U�E�X�N�[�v�x)������B
��(�A)�g�D���͒Njy�^
�u�g�D���͒Njy�^�v�̑�\�I����Ƃ��ẮA�A�}�`���A�Ƃ͂����u�_�̎�v�u�S�b�h�E�n���h�v�ƌĂꂽ�l���A���킹�āu�w��v�̌��А��A���邢�͌��͐��������Ȃ��܂łɎ��Ă���������ʒ����� ��ł��閈���V���k�C���x�Ђ́u���Ί픭�@�˂��^�f�v�������邱�Ƃ��ł���B�g�����h�ƌĂׂ�قǂ̏Ռ����Љ�ɗ^�����̂́A2000�N11��5�����j�������̋L���������B���j�Ɏc��X�N�[�v�̂ЂƂł���A���̃��[�h�̈ꕔ�����Č�����B
�u���{��70���N�ȏ�O�̑O�����Ί핶�������݂������Ƃ��ؖ������Ƃ��āA���E�I�ɒ��ڂ��W�߂Ă���{�錧�z�ْ��̏㍂�X��ՂŁA��6�����@��������10��22�������A�����c���ł��铌�k���Ί핶���������̓����V�ꕛ������(50)����l�ŒN�����Ȃ�����Ō����@��A�Ί�߂Ă���Ƃ�����V���̓r�f�I�B�e���A�m�F�����v
���̎��_�ŁA�������F�߂��u���Ί픭�@�˂��v�́A��L�㍂�X��ՂƖk�C���V�\�Ð쒬�̑��i�s�����Ղ�2�����������B�Ƃ��낪�A�����V���́A1�N�߂����2001�N9��29�������ł��ēx�X�N�[�v���f�ڂ���B�u�˂���\����Ղ� ���k���Ί팤 �O���������������v�����ꂾ�B����2003�N5��24���̓��{�l�Êw�����ł̕ɂ��ƁA�O�����������֗^�������Ί��Ղ͓��E�k���{�𒆐S��9�s����186�����ŁA����162�����ł˂����m�F���ꂽ�B3���N�ȑO�Ƃ��ꂽ�O�E�������Ί펞��̈�Ղ��ے肳�ꂽ�B���̕ŁA�����V���k�C���x�Ђ̎�ރ`�[���͐V�������(�ҏW����)��e�r���܁A���X�R����c�W���[�i���Y����܂���܂���̂����A�����̕����^�c�a�`�̑���c��w�ł̍u������ ����ʒ�����Ƃ��āA���̕����Ă݂�B
1�����V�����X�N�[�v���Ȃ���A�N���m��Ȃ����������ł���B2�����ʐM���̋L�҂������̗F�l���畷�����u���@��Ձv�̊�Ȃ��킳�b�B�u��l�̌����҂��A���X�ƋL�^��h��ւ��锭��������͕̂��ʂ���Ȃ��v(�Ǝ��̏��)3�����ʏ؋����������邽�߂ɐԊO�����r�f�I�E�J�������w�����A�����[�g�R���g���[�����K�n����(�Ǝ��̎��)�B
4�A�}�`���A�Ƃ͂����A�����V��͓��k���Ί핶�����������������Ƃ��āA1981�N�ɋ{�錧�n��d�`�����A�u�O�����Ί펞��_���v�ɏI�~����łؖ��������B
�u���k��w���_�����A�����������Ђ��������l�������A�ꖯ�Ԃ̌����҂ł���O���������̐��X�̔����A�ނ́w�Ɛсx�ɕ]����^���Ă����v(��ޑΏۂ͊w��̌��Ў�)���̃X�N�[�v�͓��R�̂��ƂȂ���A�S�Вǐ��������ƂŁA���������܂˂��m��Ƃ���ƂȂ�A���������B���̌��ʁA���ȏ��̏�������(�Љ�I�e��)���s��ꂽ�B
���l�ɑg�D���͒Njy�^�ł́A�����̂Ȃ����������@�ƔN��40�D004�����Ȃ�����Y�����Ȃ���Ȃ��o���@�Ƃ̊Ԃ̃O���[�]�[�������p���č������Œ������Ƃɋ���݂��Ă�������Ǝ҂̎��Ԃ�\�����u���H���[���s�������v��(�����V��)������B���̕ɂ���āA1999�N12���̗Վ�����Ŗ@�����������ꂽ�B
��(�B)�������͒Njy�^
�����G���[�g��s���@�ցA���邢�͊�Ƃ�w��Ƃ������g�D���͂̂悤�ɁA���ꂼ�ꂪ�ʂɌ��͂⌠�Ђ�U��̂ƈ���āA�u�o�ό��́v��u�s�����́v�Ȃǂ̕��s��Ӗ��A�c�݂����ݍ����������I�Ȍ��͂ɂ���Ė�肪�����Ă�����Ԃ𐢂ɒm�炵�߂邱�Ƃ�����̏d�v�Ȗ����̂ЂƂł���B�}�X�E���f�B�A�̎Љ�I�@�\�ɂ��āA���X�E�F�����w�E����3�̗v�f�̓���1�ɁA�u���Ď��v������B
�u�Љ�ɂ����āA�R�~���j�P�[�V�����̉ߒ��͎O�̋@�\�𐋍s����B(�`)���̊Ď��A����ɂ���Ēn��Љ�̉��l�̏��݂Ȃ�тɂ��̍\���v�f�̉��l�̏��݂ɉe����^���鋺�Ђ���у`�����X�𖾂炩�ɂ���v
���̃��X�E�F���̊��Ď��ɂ��āA���s�p�Y�͎��̂悤�ɐ������Ă���B
�u���ւ̊Ď�(���@)�Ƃ́A�Љ�ω��ɑΉ����ēK���ł���悤�Ƀ��f�B�A����� ���ɑ����Ɍx������Ƃ����Ӗ��ł���B�Ď��A���@�ɂ���āA�����͂ǂ�������悢���Ƃ����ӎu����ɕK�v�Ȓm����^������v�B
�������͒Njy�^�ɂ́A�����������Ď��Ƃ����v�f���܂܂��B���⎩���́A��Ƃ̉ߎ���Ӗ��ɂ���Ĉ����N���������Q���Q�A�ЊQ�A���́A���j��Ȃǂ����f�B�A������ʒ�����ɂ���Ė��炩�ɂ��Ă����B���̓T�^�I�Ȏ��Ⴊ�A�����V���́u��Q�G�C�Y�v�ł���B
��Q�G�C�Y�����́A1978�N������80�N��ɂ����āA���F�a���҂ւ̎��ÂɎg��ꂽ�č����̔���M���܂ɃG�C�Y�E�C���X���������Ă������Ƃ������ŁA�����̊��҂����������B1983�N�ɂ̓A�����J�ʼn��M���܂����F����A�����Ђł͑S�Ă̔���M���܂��������Ă����B���{�ł́A�ƊE���̃~�h���\���̉��M���܂̎����ɒx��Ă������߁A����ɕ��������킹�邩�̂悤�ɏ��F���x��A����M���܂��g��ꑱ�����B���̌��ʁA�G�C�Y�E�C���X�����҂��g�債���B89�N�Ɋ��҂Ƃ��̉Ƒ��������Ђƌ����Ȃ����đ��Q���������̖����i�ׂ��N�����A1996�N3�����Ƃ̘a�������������B
�����V������ʃg�b�v�Ɂu���F�a���Ẩ��M���܁v�u�w��Ёw�����x�x�炷�v�u�G�C�Y�����ґ��₵�� ���҂�Njy�v�u�g�㔭��Ёh�ɔz���v�u��s�g��҂����A�ꊇ�F�v�̌��o���Ŏ��Ԃ̏d�傳��i�����̂́A1988�N2��5���̂��Ƃ��B�Ȍ�5��25���܂œO�ꂵ���������������B����5��25���́u�L�҂̖ځv�ŁA��ނɓ�������2�l�̋L�҂��A�����Ȃ�ᔻ���Ă���B
�u���F�a���҂́g�G�C�Y�Ёh�v�u�����Ȃ́w��Q�x�ӔC�F�߂�v�u�B����Ă����]���� 3�N�ԉ������Ă����v�̌��o���Ɓu�����Ȃ������ɐӔC��F�߂Ȃ�����A���A��O�̃G�C�Y�Ђ͕K���N����v�̋L���B
�O�o�́u�E�H�[�^�[�Q�[�g�����čl�v���������ɓ����j�́A�����V���́u��Q�G�C�Y�����v�ɂ��Ă��A���̐V����e�G���A�e���r�h�L�������^���[���ڍׂɕ��͂��������ŁA�����w�E���Ă���B
�u�������w���Y�t�H�x�ł̗��ԗ��̓c���p�h�����̕�w�����V���x�̃��N���[�g�ƈقȂ�A���́w�����V���x�̕��A���{�W���[�i���Y���̗��j�I�������Ƃ��Č��y����邱�Ƃ͋H�ł���悤�Ɏv����v�B�u���̑傫�ȗv���́A�w�����V���x�́̕A�����̎Љ�������悤�ɂ͌����Ȃ��_�ł��낤�v�B
�܂��ɓ��͘_���̍ŏI�i�ŁA���̂悤�ɂ����y���Ă���B
�u��Q�G�C�Y�����́A�₪�ď������W���[�i���Y���̊S���W�߂͂��߁A����ܔN�̌㔼�������Z�N�̘a��O��ɂ����āA�e�@�ւ���Ăɂ��̖����悤�ɂȂ����v�B
�ɓ��̎w�E�́A���ۖʂ��猩��Ɛ����͂�����B�m���ɘa�����O��ɂȂ��đ傫�����グ��ꂽ���Ƃ͎����ł���B�����������V���́u���ʒ����v�́A�X�N�[�v�̒��ォ��e�Ђɑ傫�ȉe����^���Ă���B�M�҂͎i�@�L�҃N���u��17�N�ԍݐЂ��Ă����ہA�����V���̃X�N�[�v���A���̌�̕������X�N���b�v���Ă����B���̊֘A�̃X�N���b�v�����s�v�ɂȂ����̂́A�Ɩ���ߎ��v���őߕ߁A�N�i���ꂽ�����ȋǒ���2001�N�ɗL�ߔ����������n����ĈȌ�ł���A�e�Ђ̋L�҂������ނ˓��l�Ɛ��@�����B
�w�m�g�j�X�y�V�����E�����ꂽ�G�C�Y�x�𐧍삵������ς́A�u���R�����V���̋L�����ӎ������B�ǂ�������Ƃ������A�����V���ƈႤ���_�Ŗ�Q�G�C�Y�𑨂��悤�Ƃ����v�ƌ��A�����V���̋L���̑��݂��傫���������Ƃ�F�߂Ă���B�V���Ȣ������ ���ڎw���ɂ���A��͂��ڂ����������V���̋L���͌������Ȃ��̂ł���B�W���[�i���X�g�ɂƂ��āA�g�ǂ̎��_�܂Łh���ǐ�(���)�̊��������ꉞ�Ȃ�Ƃ��݂���Ȃ�A�{���{�������U���Ď������I�����}����܂łƂ��A��Q�G�C�Y�����̏ꍇ�͓r���Řa���������������_�ƌY���i�ǂ��ꂽ�����̍ō��ٔ����܂łł��낤�B�����V���́u���ʒ����v�́A�e�Ђɏ\���e����^���A���Ԃ������Č������Ă������P�[�X�ł���B
����܂Ō��Ă����悤�ɁA�u���ʒ����v���A�u�����v�Ƒ傫���قȂ�_�́A���́u���_�l�v���ɂ���B�u���_�l�v�́A���Ђ��m��Ȃ��A���邢�͒m���Ă��Ă������Ă��Ȃ��j���[�X�𑼎҂ɐ�삯�ĕ��邱�Ƃł���B���̃j���[�X���l�́A���Ђ̌�ǂ��ɂ���Č��܂�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�u�����v�̒��ɂ́A���Ђ��ǐ����Ȃ����Ȗ����A���Ж����̃j���[�X���܂܂��B
����A�u���ʒ����v�́A���̌��ʁA�e���A���ʂɂ����ē��M�������̂������B�܂�u���ʒ����v�̏ꍇ�A���Ђ����̏d�v����F�����A�x���ꑁ����ǐ�����������Ȃ��������N�����B�܂��e�Ђ̒ǐ��ɂ���ċN����g��I�ȕ��A�ǎҁA�����҂⍑���S�ʂɊS���ĂыN������p������B���̌��ʁA���͂⌠�Ђ���҂�g�D�����炩�̑Ή��𔗂��A���̂��Ƃ��Љ�ɉe����^����B
|
|
��4. ���_�ƍ���̉ۑ� |
�������A�Ƃ�킯�u���ʒ����v�́A�������͂ɗ��܂炸�A�g�D���́A�����^�̌��͂ȂǁA�Љ�ɑ��݂���l�X�Ȍ��͂⌠�Ђ�ΏۂƂ��A�����̌��́E���Ђ�����萫��s�������������邱�Ƃ�ʂ��āA�����̕���@�Ẳ����A�l�ߎ������Q���̒Njy�ȂǁA�l�X�Ȍ`�ŎЉ�I�e���͂��y�ڂ��Ă����B�u���ʒ����v�́A���@�_�ɂ����Ă��A�܂�����œ����W���[�i���X�g�̈ӎ��ɂ����Ă��A1970�N��ȍ~�A���X�ɂ��̗֊s�����m�����Ă������̂ł���B�����č���A����Љ�ɂ����鐭���I�E�Љ�I�ӎv����ߒ���A�l�X�̐��_�`���ߒ��ɂ��ɂ߂đ傫�ȈӖ�����������Ɏ����Ă���ƌ�����B
�܂��A��ނ̒��肩��ւ̈�A�̃v���Z�X���A�X�̎���ɑ����ďڍׂɌ������Ă݂�ƁA�u���ʒ����v�����Ђɂ��u�v�̘A���������N�����A�Љ�I�ȃA�W�F���_��ݒ肵�Ă������ŁA���f�B�A���݂̋���������������A����̊������������炷�Ƃ����D�z����肾����Ă���\�����������ꂽ�B�����ɂ�����u�����v�́A�u���\�v��O��Ƃ��A���\�̃^�C�~���O�݂̂����������悤�ȁu���������̃X�N�[�v����(�c���N�O)�v�ł͂Ȃ��A�Љ�̖ؑ��Ƃ��ẴW���[�i���Y�����ꎩ�̂̊������Ɍq���蓾��悤�ȁA���ݓI�Ő��Y�I�ȁu�����v�ł���悤�Ɏv����B
���_�A�����_�ł́u���ʒ����v���W���[�i���Y������������������A�Ƃ��������͉����̈���o�Ȃ��B�u���ʒ����v�Ɓu�W���[�i���Y���̊������v�Ƃ̑��֊W���ǂ̂悤�ɐ����I�ɘ_�����邩�A�܂����������u�W���[�i���Y���̊������v���A�ǂ̂悤�Ȋ�A�ϓ_�A���@�_�ɂ���Č����邩�A�Ƃ�������肪�c����Ă���B�u���ʒ����v�̎Љ�I������g���m�����A���̗L������\��������߂Ă������߂ɂ��A�����̏��_�̕��́E����������̌����ۑ�Ƃ������B�@ |
 |
�@ |
|
������ւ̋��D�A���Ȃ��@���ԗ��u�c���p�h�����v 2015/2 |
1970�N��̐����ƃJ�l���߂���b�����Ă��A���̎Ⴂ�l�ɂ͐M���Ă��炦�Ȃ���������܂���B�T���g���[�E�C�X�L�[�u�I�[���h�v�̋���1�疜�~�����ē͂����Ƃ��A�����}���ّI�Łu���\���~�������v�Ƃ��A�܂��Ƃ��₩�Ɍ��ꂽ���̂ł��B
�����������s�������Ƃ���܂ōs��������A���̒��S�ɂ����̂��c���p�h�ł����B
�����}���ق������c�����w������74�N�̎Q�@�I�́u��Ƃ���ݑI���v�ƌĂ�܂����B���ƂɎ����}���ւ̎x����v���A���z�̃J�l���I���^���ɒ������܂�܂����B�����ł��u�����牽�ł��A�����܂ł�邩�v�Ǝv�����l�͑��������B�u�c���p�h�����v�̎�ނ��n�߂��w�i�ɂ́A���������ւ̋^�₪���ԂɍL�����Ă������Ƃ��������Ǝv���܂��B
�u�c���̐��X�̋���������\������i�v�ƌ����邱�Ƃ�����܂����A���m�ł͂���܂���B�X�̋��������̂قƂ�ǂ͊��ɒm���Ă�����̂ł����B���̋����́A�����̋^�f�̈�ЂƂ�K�ɕ��ׂāA�����̑S�̍\�}�����Ԃ�o���A���̔w��ɂ���d�|����`���o�����Ƃɂ������̂ł��B
74�N10���ɔ��\���܂������A�V���͓����A�ǐ����܂���ł����B�����́A�V���������Ȃ��ƃj���[�X�Ƃ��ĔF�߂��Ȃ��悤�Ȏ���B�V���L�҂͎G���W���[�i���Y������i���Ɍ��Ă����Ǝv���܂��B�Ď��������ƂŁA���{�̐V�����悤�₭�ǂ������܂����B
��ސw�ɒǂ����ƌ����Ă��A���̘_�������̗͂Ƃ͎v���܂���ł����B���������͂������������悤���Ȃ���Ԃ������̂ł��B�u�ו���ڂ����ς��w���������o���A������������{�̂���ꂽ�����œ|�ꂽ�v�Ƃł������܂��傤���B��㐭���̈�̋Ȃ���p�ɁA����������̂��Ǝv���܂��B
�[�Ɨ��߂����v���z�̃V�X�e�����m�������̂��A�c�������ł��B����͓s��Ɣ�ׂăC���t���̐���Ȃ��A�܂��n���������n���ɁA���x�����̉��b���^���悤�Ƃ����Ƃ������͂�����܂��B�������A���̐����p���̊�{�́A�����Ȃ��������͂̊g��ɂ���܂����B
�h���̃h���Ƃ��Ă̓c���̓����́u���`�̔z���v�ɂ���܂��B�ڐ�̑����ɂƂ��ꂸ�A���h���̋c���ɂ܂ŋC�O�悭�J�l��z���ăV���p���L����B�������w�N��_�x�̃}�L���x���̓J�l�Ől�S���������Ƃ�������������������߂Ă��܂��B����̉e���͂�ۂ������邽�߂ɁA�\�ɏo���Ȃ��J�l�ɗ���悤�ɂȂ��Ă��܂�����ł��B
�c���Ƃ����l���͖{����w�����ł͂Ȃ��A�o������w�l���̒m�b���~�ς��ꂽ�l���������Ǝv���܂��B����Ęb���A�����[���Ď��ɖ��͓I�������ł��傤�B���̑�\�I���{�l�Ƃ����A����Ђ�Ɠc�����^����ɕ����т܂��B����u�����{�l�v�ƌĂт����Ȃ�悤�ȑ��݂ł��B
�c�����t�̑ސw��A���������K���@�̊��x���̉������o�āA�����ƃJ�l���߂��镗�i�͂����ԕς��܂����B�c�����S���Ȃ���20�N�ȏソ���܂����A�ނɂ��Č��{���V���Ɋ��s���ꑱ���Ă��܂��B��X�͍��Ȃ��A�c���p�h�Ƃ��������ƂƁA�ނ�����������̎���ւ̋��D��f���ꂸ�ɂ���̂�������܂���B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���V���L�҂����� 2013/9 |
10��1���Ƃ����������ŗ������グ�̔��f���߂���A���Ԃ̊S�����܂��Ă��܂��B���f�B�A�ł������ȕ������Ă��܂����B���V���L�҂Ƃ��ĐV���̌y���ŗ��ɂ��Ďv���Ƃ��낪����y�������܂����B
�܂�����łɊւ��Ď��̗���𖾂炩�ɂ������Ǝv���܂��B���͎Q�@�I�O�����т��Ď咣���Ă��܂����A2014�N4����8���ւ̑��ł����ׂ����ƍl���Ă��܂��B�����̍��z���炨�����z������鑝�ł�]�ސl�͂��Ȃ��ł��傤�B�N�������ł͌����Ǝv���܂��B�������A���݂̓��{�͎����Ɍ�����Ȃ��x�o�𑱂��Ă��܂��B�؋��Ƃ����`�Ŏq�⑷�̐���ɕ��S�����Ė��N�A���N�����ł��܂��B�܂����܂�Ă����Ȃ�����Ⓤ�[�����Ȃ��Ⴂ����ɂ���ȏ�A�؋��킹�Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl���܂��B
���̂��߂ɂ́A�Љ�ۏ���܂ލΏo�𑊓��팸���邩(�������v�Ƃ������x�ł͂Ȃ��啝��)�A���łőS�����Ɋ��芨����Ă��炤���A�n�C�p�[�C���t�����N�����Ď؋��̉��l��ڌ��肳���邵������܂���B(���I�Ȍo�ϐ����ɂ�鑝���Ŏ��x���ύt������Ƃ����u�����v��ǂ����߂�̂́A���ǁA�Ԏ������̌p���ɑ��Ȃ�܂���)
���l�Ɏ��̍l�����x�����Ă��炦��Ƃ͎v���Ă��܂��A���͋ꂵ���Ƃ����łŏ�������ւ̕��S�����炷�����ݏo���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƐM���Ă��܂��B���ō��ڂƂ��Ă͔����L���S�����ɕ��S���Ă��炤����ł��ł��Ó����ƍl���Ă��܂��B�������A�勰�Q�̎��ɑ��ł��ē��{�̌o�ς�����Ă͂Ȃ�܂���B�����A�����̌o�Ϗ��l����A���̃^�C�~���O�Ő����E���{�͉��Ƃ����ł����肢���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƐM���Ă��܂��B���킹�Đ��{�͌i�C�����܂ꂳ���Ȃ��悤�o�ϑ���������Ă��܂��B
�����̐V�����f�B�A������ł��咣���Ă��܂��B�����āA�قƂ�ǂ̐V�����i���Ă���̂��V���ւ̌y���ŗ��̓K�p�ł��B�u���B�ł͐H�i��V���̐ŗ����[���␔���ɗ}���Ă��鍑���唼���v�u�V���̓R���Ȃǂ̐H���i�Ɠ����悤�ȕK���i�v�ȂǂƂ��āA�V���w�Ǘ��̕��S�y�����K�v���Ə����Ă��܂��B
����ł̋t�i�����l����A�Ꮚ���҂ւ̑�͍l���Ȃ���Ȃ�܂���B�u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v��ۏႷ�邽�߂ɂǂ��Ώ����邩�A�y���ŗ�������Ƃ���ǂ̕����Ώۂɂ��邩�͑傫�ȉۑ�ł��B�V���ւ̑Ή����Ȃ��ɔے肷�����͂���܂��A�V���ƊE�ɒ��炭�g��u�����҂Ƃ��āA���ʂŎ��g�̋ƊE�̘b�𐺍��Ɏ咣����p���ɂ͔����Ђ��߂���܂���B
����ɂ͂����Ȍ���������A�^�ۂ͏�ɂ���܂��B���Ƀ��f�B�A�͋ƊE�c�̂̎咣���u���v�U���v�Ǝw�e���܂��B�������Ƃł��A�f�Õ�V�ł��A�_�Ƃ̕⏕���ł��B�ǂ�����������ɂ��Љ�I�Ȍ��p�͂���܂����A�x���߂���Ή�c�����Ƃ̔ᔻ����ł��傤�B
���Ɍy���ŗ�������ꍇ�A�ǂ̕���ɓK�����邩�͈ӌ��̕������e�[�}�ŁA�Ƃ���������ɗ��������܂ꂩ�˂܂���B���������ɂ߂ăi�C�[�u�Ȗ��Ɋւ��āA�u�����̋ƊE��z������v�Ǝ��ʏ�ői����̂͐V�����̂̐M�����ɋ^�`�������炷���ʂɂȂ�͂��Ȃ��ł��傤���B�e���̘_�����u�V�������F�A�����̗��v�ɂȂ�咣�������Ȃ��ȁv�Ƃ�����ۂ�ǎ҂ɗ^���Ă���Ǝv���܂��B�����A�����̋ƊE�́u�����ȁv�咣������̂ł���A�А���L���ł͂Ȃ��L���ōs���ׂ����ƍl���܂��B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���V���А����猩����u���f�v���i�ߘa���N 2019/12 |
2019�N�����悤�Ƃ��Ă���B���N�̓���j���[�X�̈�́u�����v����u�ߘa�v�ւƎ��オ�ڂ�A�V���ȓV�c�É���5��1���ɑ��ʂ��ꂽ���Ƃ��낤�B�V�c�̐��O�ވʂ͍]�ˎ���̌��i�V�c�ȗ�202�N�Ԃ�Ƃ������j�I�Ȃ��Ƃ������B
�����̐��E�ɖڂ�]����ƁA���{�W�O�̒ʎZ�ݐE������11��20���Ōv2887���ƂȂ�A�����E�吳����3�x�߂��j���Y�����čŒ��ƂȂ����B�L�^�X�V��106�N�Ԃ肾�B
����A���͌����ĉғ��𒅎��ɐi�߁A���q�͋K���ψ����11���̒���ŁA�{�錧�ɂ��铌�k�d�͏��쌴��2���@�̍ĉғ��Ɍ����A���S����܂Ƃ߂��R�����Ă𗹏������B11�N�̓����{��k�Ђő傫�Ȕ�Q�������A�{��A��������3���ł͏��߂ĂƂȂ�B
���̎p���`�Â���V�c������{�����ɂ����S�ۏ�A�G�l���M�[�E��������Ȃǂ��߂���A�u�����̕��f�v�����������i��1�N�ł��������B���̕��f�̔w�i�ɂ́A��v�e���̓�ɉ�������A���f�E�Ό��^�̈��{�����̎�@�ɔ��Ԃ��������B��v�ȐV���А�����|����ɁA����1�N��U��Ԃ�ƂƂ��ɁA����N��W�]�������B
�ŏ��ɍ����̓��{�̌��_�ɂ��ďq�ׂ�B���������_�Ƃ��Ĕ��s���������6������B�ێ�n���ǔ��A�Y�o�A���o�V���ŁA���x�����n�������A�����A�����V�����B���̗��҂̑Η������ĂȂ��������B���l�Ȉӌ�������̂͂������Ƃ����A���݂��������������ŕ������������Ȃ��s�тȏ�����B
�����炱�̂悤�ȏɂȂ����̂��B�Z���^�[���ōl����ƁA2011�N�̓����{��k�Ђ���̌_�@���낤�B
1��N�Ɉ�x�Ƃ������Ôg�������A������1�������������̂��N�����A����Ⓦ���{��łƂ������[���Ȏ��Ԃɔ��W�����̂͋L���ɐV�����B���̂Ƃ��A���_�͌����ێ��ƒE�����ɓ��ꂽ�B
�ێ�n�͌��������������A���郊�x�����n���f�B�A�͌����p�~��i���A���������V���������B����}��������Ɏ��̂������������A���̌�̈��{�����ɂȂ��Ă���͌����ێ������m�ɑł��o����A�ێ�n���f�B�A�͐����Ɋ��Y�����B
12�N12���ɔ���������2�����{�����́A���@9���̉��߉������s���A���S�ۏᐭ���180�x�]���A���h�q�����ĂďW�c�I���q����F�߂��B�����ł��ێ�n�ƃ��x�����n����������炸�ɑΗ������B14�N�ɂ͒����V�����Ԉ��w�֘A�̋L�����ꕔ�����������Ƃ��A���j�����߂����ĕێ�n���������������o�b�V���O�����B
���̂悤�ɁA�G�l���M�[�E���q�͐���A���S�ۏᐭ��A���j�F���Ƃ��������̍������`�Â��镔���ł̌������Η����A�ɒ[�ȓ�ɉ��𑣐i���Ă������ƍl������B
�u���{�ꋭ�v�̂��ƁA���{�����͍���ɂ����Ĉӌ����قȂ��}�Ƃ܂Ƃ��ȋc�_�������ɓ˂������A�ŏI�I�ɂ́u���̘_���v�ɗ����ċ��s�̌��ŏd�v�@�Ă𐬗������Ă������B�����ɕ��f�E�Ό��^�Ƃ�������{�����̖{�����݂���B�Θb�����₷�鍡���̌��_�Ɛ����͂܂�őo�q�̂悤�ɑ����`���Ȃ��A���f�B�A�s�M�Ɛ����s�M���������邱�ƂɂȂ����B
�V�c�É������ʂ������O�ɐ錾����u���ʗ琳�a(�����ł�)�̋V�v��10��22���A�c���E�{�a�u���̊ԁv�ł����Ȃ�ꂽ�B���̖͗l��������10��23�������ŕB6���Ƃ���1�ʃg�b�v�̓���L���œ`���A�e���̎А���21������23���ɂ����Čf�ڂ��ꂽ�B
�ǔ��А�(10��23��)�́u��A�̍c�ʌp���̒��S���Ȃ��`���V�������s���ꂽ���Ƃ�S��肨�j���������v�A�Y�o�А�(10��22��)�́u�S����̂��j���Ɗ��ӂ��A���߂Đ\���グ�����v�A���o�А�(��)�́u���ʂ�S���炨�j������ƂƂ��ɁA�C�O�����ꂽ�j�ӂɐ[�����ӂ������v�ƁA��������j�ӂ����������B
����A�����А�(10��23��)�́u���a�̋V���߂����Ă��A�V���~�Ր_�b�ɗR�����鍂����ɕÉ��������A�����̑�\�ł���O���̒��������낷�`���Ƃ邱�Ƃ�A������O��̐_��̂������Ǝ�(����)���e�ɒu����邱�ƂɁA�ȑO����w�����匠������������ɂ�����Ȃ��x�Ƃ̎w�E���������v�Ɩ�莋�����B
�����А�(��)�����l�Ɂu���ʂ̋V�����߂����ẮA�@���F���Ƃ��Č��@�̐������������Ƃ̐�������₤��������B���{���\���ȋc�_������A���v�킸��1���Ԃ��܂�̉�őO�ᓥ�P�����߂����Ƃɂ͖�肪�c��v�Ƃ��A�����А�(10��21��)�́u�c�ʌp���ɔ����d�v�V���ƈʒu�t�����邪�A�w���@�ɂ�����Ȃ��x�Ƃ̐����B�`���V���ł���A���@�Ƃ̐������ɔz�������߂���v�Ƒi�����B
���̂悤�ɕێ�n���f�B�A�ƃ��x�����n���f�B�A�Ƃł́A�����Ԃ�Ɖ��x���̂���А����\���邱�ƂɂȂ����B����ȊO�ɂ��A�����͎��{���ꂽ���͂ɂ��āu�i�@�̔��f���s��������I�ɕ����[�u�ɔ��Θ_�������������v�Ƃ��A����ɏH�{���܂����H�̉�Łu�@���F�̋����V��������Řd�����Ƃ��K�����v�Ƒi�����_���Љ�A��������Ă邱�Ƃɋ^���悵���B
���{����51������2006�N9���A���̐�㐶�܂�̎Ƃ��đg�t�B�������A��1�������͑̒��s�ǂȂǂŁA�킸��1�N�̒Z���ɏI������B���̌�A12�N12���̏O�@�I�ɏ������Ė���}���琭����D��B��2���ȍ~�̐�����7�N�ɂ���Ԃ��ƂƂȂ����B�����}���قƂ��ĔC����21�N9���܂ł���A���̂܂܂����Η��Œ����X�V�������邱�ƂɂȂ�B �E�E�E
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���Ď��f�W�^���s��̓j���[���[�N�E�^�C���Y�̓Ƒ��� �@2020/2 |
�����Ȃ��^�C���Y�̐L��
2007�N12���A�E�H�[���X�g���[�g�E�W���[�i��(�v�r�i)�̕ҏW�ǂ�K�ꂽ�j���[�Y�E�R�[�|���[�V������̃��p�[�g�E�}�[�h�b�N�����`�o�B�v�r�i�͂��̔N�A���s���̃_�E�E�W���[���Y���������ꂽ���Ƃɔ����ăj���[�Y�Ђ̎P���ɓ�����2007�N12���A�E�H�[���X�g���[�g�E�W���[�i��(�v�r�i)�̕ҏW�ǂ�K�ꂽ�j���[�Y�E�R�[�|���[�V������̃��p�[�g�E�}�[�h�b�N�����`�o�B�v�r�i�͂��̔N�A���s���̃_�E�E�W���[���Y���������ꂽ���Ƃɔ����ăj���[�Y�Ђ̎P���ɓ�����
2��6���A�j���[���[�N�E�^�C���Y(�ȉ��^�C���Y)�͎��̂悤�Ȍi�C�̂��������\�����B���ƃf�W�^���ł̍��v�_��525��1000���A���̂����f�W�^���ł̌_��(�����ƃN���X���[�h�p�Y�����܂�)��439��5000���A�����ăf�W�^���Ńj���[�X�̌_���342��9000���\�\�B
�ł���ۓI�Ȃ̂́A�f�W�^���Ńj���[�X�_��̐��ݓI�ڋq�x�[�X�����ł��ɂȂ������Ƃ������؋����قƂ�nj����Ȃ��������Ƃ��B2019�N����342��9000���Ƃ��������́A�O�N��������271��3000���������26���̐L�т��B
��7���̓j���[�Y�E�R�[�|���[�V�����̔Ԃ������B�P���̃E�H�[���X�g���[�g�E�W���[�i��(�ȉ��W���[�i��)�̃f�W�^���_�����߂�200������˔j�������Ƃ\�����B���o�[�g�E�g���\���ō��o�c�ӔC��(�b�d�n)�̓^�C���Y�Ƃ̋����ɂ��C���X�ƌ����A���Z�̍ŏ���6�i����5������C�o���ЂɌ��y���Ă����B
�����Ŏw�E�������̂́A�^�C���Y�̕����ˑR�A�f�W�^���_��̐L�ї��ŃW���[�i���������Ă��邱�Ƃ��B�j���[�Y�E�R�[�|���[�V�����ɂ���19�N��1�N�ԂŃW���[�i���̃f�W�^���_��22���������ĐL�ї���12�D8���������B�^�C���Y��71��6000�����ŐL�ї���26�D4���������B
�|�X�g�͐����𖾂����Ȃ�
�W���[�i�����^�C���Y�ɐ킢�ނƂ����\�}�̒��A�^�C���Y�Ƃ̂��̎�̋����ŁA����2�Ԏ�ɖ��O�̋�����S��������������Ă���Ƃ����_�ɒ��ڂ�����Ȃ��B���V���g���E�|�X�g(�ȉ��|�X�g)�̂��Ƃ��B�W���[�i���ƃ^�C���Y�̓j���[���[�N�Ƃ��������s�s�ő������A�|�X�g�ƃ^�C���Y�ɂ́A�o�ϐ��łȂ���ʎ����m�Ƃ������ʓ_������B�����͎�s���V���g���̐����ɓ��X���̂������B����A�W���[�i���͂��̐�含����Ǝ��F�������邱�Ƃ��������B
�ł́A�|�X�g�̃f�W�^���_��l���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B
���Ƃ������Ȃ��B���f����̂�������R�͂�������B���ЂƕăC���^�[�l�b�g�ʔ̑��A�}�]���E�h�b�g�E�R���̊Ԃ̓Ɠ��ȊW�ł���B
�|�X�g�͌_�����o���a��B�A�}�]���b�d�n�̃W�F�t�E�x�]�X�����|�X�g�̃I�[�i�[�ł��邽�߁A���������J����Ă��炸�A�l�������Ƃɂ��炵�����������\���A�E�H�[���X�̊W�҂��������Ȃ点�Ă��`��������Ȃ��B���s�����č��@�ւ`�`�l(���`�a�b)�ɂ��f�W�^���_��Ґ�����Ă��Ȃ��B�A�}�]���̓d�q���ЃL���h���Ɠ����ŁA���ЂɂƂ��ēs���̗ǂ����ɂ������\���Ȃ��̂��B
17�N9���ɂ͎Г��A������(�ЊO�Ƀ��[�N����邱�Ƃ����҂���Ă����̂͋^���Ȃ����̂���)�ŁA�|�X�g�̃f�W�^���_���͓��N��100�����A�O�N����u3�{�ȏ�v�̐L�т������ƋL����Ă����B
���̎��_�ł́A�W���[�i���̒��߂̌_��127���A�^�C���Y��230���������B
18�N12���ɂ͕ʂ̎Г����������Ń|�X�g�̃f�W�^���_��150���������Ƃ��ꂽ�B���̎��̓W���[�i������170�����A�^�C���Y�͖�270�����������B
�ł͍��͂ǂ��Ȃ̂��낤�B�|�X�g�̍L��ɍŐV�̐������Ȃ����Ɖ�����Ă�����̂́A�����������o���������ɂ��������͏o���Ȃ��悤�ł���B
��O�����̃f�W�^���헪
�A�}�]���E�h�b�g�E�R���b�d�n�̃W�F�t�E�x�]�X��(2018�N9���A�`�o)�B2013�N�Ƀ��V���g���E�|�X�g�̌o�c����������A�}�]���E�h�b�g�E�R���b�d�n�̃W�F�t�E�x�]�X��(2018�N9���A�`�o)�B2013�N�Ƀ��V���g���E�|�X�g�̌o�c���������
�|�X�g�̃f�W�^���헪�͌����A�ǂ��炩�Ƃ����ƃG���[�g�w�����̃^�C���Y��A��Ƃ�Ώۂɍ��߂̍w�Ǘ���ݒ肷��W���[�i���Ɣ�ׂ�ƁA��ʑ�O�w���ł������B�W���[�i���̃f�W�^���w�Ǘ��͌����z39�h���ŁA�^�C���Y�͌�18�h�����B�|�X�g�͌��z11�h���ŁA�N�Ԍ_��Ȃ炢�ł�100�h���Ɋ�����������B
���V���g���E�|�X�g���т���`�q�́u�n�����ł���v�Ƃ������ƂŁA���̌X���͖ڕW�����L�߂ɍ\���Ă������̑S������肸���Ƌ������̂�����B���̐V�����S���̎���A�|�X�g�͑S�Ă̑�s�s�̂ǂ̐V�������n���̃��V���g���ɐZ�����Ă����B1980�`90�N��ɂ̓^�C���Y�ɒǐ����邱�ƂȂ��A�S���K�͂ł̈����z�B���s��Ȃ������B
�|�X�g�̓I�����C���ł̕ҏW���j�ł��A��蒆���x�̋��{�̐l�X���ӎ����Ă���B���x�̒�����C�O�j���[�X�ƕ��сA�u���O���L����y�߂̘b���i��ň����Ă���B
���������Ă���A�f�W�^���_��̊l�������܂������Ă��邾�낤�Ǝv���邪�A�|�X�g���������o���Ȃ����߂ɁA���_���o���Ȃ��B100������150�����Ƃ����������\�ɏo���̂�����A����200�����������낤�Ǝv�����A�܂������͂Ȃ��B
17�N9�����_�Ń|�X�g�̃f�W�^���_���̓^�C���Y���130���A�W���[�i�����27����������Ă����B18�N12���ł̓^�C���Y�Ƃ̍���120���A�W���[�i���Ƃ�20�����̊J�����������B
���̌�A�|�X�g���甭�\���Ȃ��ԁA�O�q�̂悤�Ƀ^�C���Y��70�����ȏ�ςݏグ�A�W���[�i����30�����𑝂₵�Ă���B
�^�C���Y�̕�
���N�O�ɁA2020�N�����̗\������Ă�����A�|�X�g���f�W�^���_�ő����Ƀ^�C���Y��ǂ��グ�A�ł��y�ϓI�ȃV�i���I�ʂ�ɐi�߂Βǂ��z���Ă��邱�Ƃ�����A�Ɠ����Ă������낤�B��߂̉��i�ݒ�Ɛe���݂₷���R���e���c�A����ɂ͐l�ގj��L���̐����������i���ƂƂ̓Ǝ��̊W������A�ʂɁu�x�]�X���}�W�b�N�v�����Ăɂ��Ȃ��Ă��A�|�X�g���^�C���Y�̋��͂ȋ�������ɂȂ蓾��Ǝv�����B
�|�X�g���L���ȏ��������A�ǂ��������o�����Ƃ������������҂��邪�A���Ȃ��Ƃ����Ђ��ł��y�ϓI�ȃV�i���I�����ǂ��Ă���Ƃ͌����Ȃ��悤�ł���B
15�N�ɂ́A�|�X�g���I�����C���̃��[�U�[���Ń^�C���Y���������Ɛ��������B�����A�^�C���Y�͂��������Ԃ��A�Ȍ���قƂ�ǗD�ʂ�ۂ��Ă���B
�p�K�[�f�B�A�������ŋߘ_�����悤�ɁA�^�C���Y�̐����͖��_�A���}����̎^�����ׂ������A���s��̌��S�����������̂Ƃ͕K�����������Ȃ��B
���f�B�A�ƊE�ł܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂́A2�Ԏ�ł��邱�Ƃ��o�c�I�ɖ��͂�����̂��ǂ����A�Ƃ������Ƃ�����B�č��Œn���������B���Ă������ŁA2�Ԏ�ł��邱�Ƃ͂قƂ�ǂ̓s�s�ŔߎS�Ȃ��Ƃ������B1�Ԏ�̐V���͋K�͂̌o�ςɂ���čL�����ǎ҂��Ⴞ����ɑ傫���Ȃ�A�����炱����r�I���������ɑ����̓s�s�Œn�����͈ꎆ�ɍi�荞�܂ꂽ�B
�����ɏՌ��I�Ȑ���������B�����̕č��ŁA�V���L�҂̎���10�l�̂���1�l�̓j���[���[�N�E�^�C���Y�̋L�҂��B���̐���1700�l�ȏ�ŁA10�N�O��1200�l�قǂɒ�����Ă����̂Ɣ�ׂ�Ƃ͂邩�ɑ����Ă���B�S�Ă̐V���ҏW����œ����L�҂̍��v��2���l�������ƌ����Ă���B
�f�W�^���Ńj���[�X�_���2�Ԏ�ɂ��邱�Ƃ͌������B�����A(�o�σj���[�X�Ƃ���)����������������W���[�i���ɂ́A���ʉ����ꂽ���i�Ƃ����J�M������A���̋������炤�܂������o����������Ȃ��B
�u���ґ����v�̈Ӗ�����Ƃ���́A������قǂ̑S�����������ɉh���A1000�ȏ゠��n�������Ђǂ��ꂵ�ނƂ�����ԂȂ̂��B���邢�͕����ʂ��ʎ��̕���ł͂����A��̏��҂Ƃ��ăj���[���[�N�E�^�C���Y�������c��Ƃ����Ӗ��Ȃ̂��B
���ɂ͂킩��Ȃ��B�����]�ނ̂́A�|�X�g�������ɂł����炵���f�W�^���_�\���Ď��̋C���y�ɂ��Ă���邱�Ƃ��B�����A�^�C���Y�͒n���̋������肾���łȂ��A(�j���[���[�N��V���g�����܂ޕē��C�ݎ�v�s�s�����ԓ��}��Ԃ�)�A�Z���E�G�N�X�v���X������̑����˂������A�Ƒ���Ԃɓ������悤�Ɍ�����B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���ߘa�̃W���[�i���Y��������j 2020/3 |
��(1)�͂��߂Ɂ@��H�ɗ������ꂽ�ߘa�̃W���[�i���Y��
��N1������4���܂ŁA�����̍Ō��15��ɂ킽���āu�����̎����W���[�i���Y���j�v��A�ڂ��܂����B�����̓W���[�i���Y���̎p�����I�ɕς��������ł����B�L�҂����M����p���݂Ă��A�菑���̌��e�����[�v���ʐM�A�p�\�R���ʐM�ւƕς��A�ʐ^���t�B������������f�W�^���ցA�����āA�X�}�[�g�t�H�����o�ꂵ�A���攭�M��������O�ɂȂ�܂����B����ȕ����̃W���[�i���Y���̕ϑJ��������ʂ��Ă��ǂ낤�Ƃ����̂��A���̘A�ڂł����B���������܂Ŗ�50���l�̃��[�U�[�ɓǂ�ł��炤���Ƃ��ł��܂����B�ߘa�ɓ����Ă��A�W���[�i���Y���̕ω��͎~�܂�܂���B����ɑ傫�������������Ă��܂��B����́A�ߘa�ɋN�����W���[�i���Y�����߂��邳�܂��܂Ȏ��ۂɂ��āA�����⏺�a�̋��P��U��Ԃ�Ȃ���A����̉ۑ�ƁA����ׂ��W���[�i���Y���̎p��W�]�������Ǝv���܂��B�������T���j���ɔ��M���Ă����܂��B
�ߘa�ɋN���������ŁA�����ł��Ռ������͍̂�N7��18���Ɂu���s�A�j���[�V�����v��1�X�^�W�I�ŋN�������ΎE�l�����ł����B�A�j���[�^�[��36�l�����S�A33�l���d�y�����Ƃ����ƍߎj��ň��ƌ����鎖���ł��B�������Ռ��́A���̔�Q�̑傫���ƔߎS�������ł͂���܂���A��Q�҂̎������\���߂����āA����܂łɂ͂Ȃ������x�@�̑Ή�������܂����B�⑰�̗������Ƃ�Ȃ����Ƃ𗝗R�Ɍx�@�̌��\���摗�肳��܂����B��Q�҂̂��ׂĂ̎������x�@���疾�炩�ɂ��ꂽ�̂́A��������1�J���ȏオ������8��27���ł����B�����āA���̎�������邱�Ƃ��߂����āA���������f�B�A�ᔻ���N�����̂ł��B
�����ɂ����āA��Q�҂̎�����邱�Ƃ́A����܂ł͋c�_�̗]�n�̂Ȃ������̂��Ƃł����B�u�N���]���ɂȂ����̂��v�͌����̍ő�̊S���ł���A�㐢�ɓ`����ׂ����j�̋L�^���Ƃ���F�����A�L���Љ�ɋ��L����Ă����Ǝv���܂��B�u���������\���ꂽ���Ȃ��̂Ɂv�Ƃ����₢�����ɂ́A�u���Ƃ��Δ�s�@���̂��N�������A�Ƒ���m�l������Ă������ǂ����������ɕ�����Ȃ��Љ�ł����̂ł����v�u�����ŕ邱�ƂŎ������̂̔߂��݂����[���l�X�̐S�ɍ��܂�A�Ĕ��̗}�~�͂⋳�P�ɂ��Ȃ�͂��ł��v�ƕԂ��A�قƂ�ǂ̐l���[�����Ă���܂����B���Ȃ��Ƃ��A��Q�҂̎���������f�B�A�ɔᔻ���������Ƃ��������Ԃ͑z��ł��܂���ł����B���a�̏I�ՂɐV���L�҂ɂȂ�A������̌���ʼn߂����Ă������̂悤�c
|
��(2)�������\���߂铊�e�Ƀl�b�g�̔ᔻ���E��
���̃c�C�[�g�𓊍e�����̂́A�u2013�N1��21��23��44��33�b�v�ƋL�^����Ă��܂��B�u�S���Ȃ������̂����O�͔��\���ׂ����B���ꂪ�����̒����ɂȂ�B�l���l�Ƃ��Đ��������́A���̖��O�ɂ���B�l���̏d���ƃv���C�o�V�[�����Ⴂ���Ă͂����Ȃ��v�B���`�̊��[�����̐[��̋L�҉���e���r�Ō��āA���̊��z���q�ׂ����̂ł����B�����[�����́u�E�Q���ꂽ���{�l�̎����͌��\���Ȃ��v�Ƃ̕��j�𖾂炩�ɂ����̂ł����B
�C�X�����ߌ��h�̕������͂��A�A���W�F���A�����̓V�R�K�X�����v�����g���P�������̂́A�����[�����̉��5���قǑO�A1��16���̖����ł����B�v�����g�œ����Ă������{�l10�l���͂��ߊO���l���800�l���l���ɂȂ����̂ł��B�����āA���{�l10�l�̂���7�l���E�Q���ꂽ���Ƃ���{���{���m�F��(��ɐl����17�l�ł���10�l���E�Q���ꂽ�Ɣ���)�A�[��̊��[��������J���ꂽ�̂ł����B�������A�����ɂ��ẮA�⑰�̗������Ƃꂸ�A�v���C�o�V�[���z�����Č��\���Ȃ��Ƃ����̂ł��B����܂Ŏ����̔�Q�ҁA�Ƃ�킯���S�����l�̎��������\�����̂́A�����̂��Ƃł���A�ɂ߂ē��R�̑Ή��ł����B���͐��{�̔��f�ɋ����A�u�S���Ȃ������̂����O�͔��\���ׂ����B���ꂪ�����̒����ɂȂ�c�c�v�Ƃ������e�������̂ł��B���Ƃ��Ă͂ǂ��܂ł��^�����ŏ펯�I�Ȓ�N���ƐM���Ă��܂����B
�����A�X�}�[�g�t�H���Ńc�C�b�^�[�A�J�E���g���J�������́A�ʂ̈Ӗ��ő傢�ɋ������ƂɂȂ�܂��B��ӂŃt�H�����[�����S�l�������Ă��āA�ǂ������̂��낤�ƃ��v���C������ƁA���̓��e�ւ̔l�i(��)�G���ł��ӂ�Ă��܂����B�u�Q�X�̋ɂ݁v�u���O�����߂邱�Ƃ���˂���v�u���\�����炨�O��}�X�R�~�������邩��Ȃ낤���v�c�c�B�����Ɏ��̓��e�ւ̔������W�߂��܂Ƃ߃T�C�g������A������u����v�ɂȂ�܂����B
���̓��e�́u����v�ƕ��s���āA�����V���ɂ���Q�҂̎����ɂ��Ĕ����̖��悪�����Ă��܂����B���{�͎��������\���܂���ł������A�e�Ђ͓Ǝ��̎�ނňꕔ�̔�Q�҂̎���������o���Ă��܂����B�����V�������������Q�҂̐e���ɂ�����l�����u���������Ȃ��Ƃ��������Ă����̂ɂ����j�����v�u�����V���̕ɂ���ĕe�Ђ��⑰��ɉ�����ςȖ��f�v�ƍR�c���A��ނɏW�܂����L�҂������B�e��������ƂƂ��ɃC���^�[�l�b�g�ɓ��e�����̂ł����B�����V���͕ʂ̈⑰���痹��������ĕ����悤�ł����A�u���������v�u�}�X�R�~�����v�Ƃ����\�}�̒��Ŕ����͎~�܂�܂���ł����B
���́A�������d�˂�Ύ����̈Ӌ`�𗝉����Ă��炦��ƐM���Ă��܂����B�c�C�b�^�[�ɘA�����e���āA���̍l����`���悤�Ƃ��܂����B���̎��̓��e�͎��̂悤�Ȃ��̂ł����B�u���̂Ԃ₫�ɑ����̈ӌ������������܂����B���������̖��͎��ɉ��[�����ׂĂ������\���͓̂���̂ł����A�܂ɐG��A���̍l�������b���������Ǝv���܂��B���傤�͐V�������܂̊�����̕��Љ�Ȃ���A����������x�l���Ă݂܂��v�u�����{��k�Ђ̎��A������͔��ɒ���o���ꂽ��Ў҂̖�������̂܂܋L���ɂ��܁c
|
��(3)���f�B�A�X�N�����́A�Ȃ��N�����̂�
�u���f�B�A�X�N�����v�Ƃ������t���L���g����悤�ɂȂ����̂́A1990�N��ɓ��������ł����B���Ƃ��Ƃ́A�C�M���X��J�i�_�ȂǂŐ����ƂȂǂ��͂�ōs���鑦�Ȃ̋L�҉���w�����t���Ƃ���Ă��܂��B���̂��߁A�C�O�ł̓��f�B�A���c�����Č��͂ƑΛ�(������)����Ӗ������߂��A�W���[�i���Y���ɂƂ��Ă͍m��I�ȈӖ��Ŏg���邱�Ƃ����������悤�ł��B
�������A���{�ł͂���Ƃ͋t�ɁA���f�B�A�e�Ђ̏W����ނɂ���Q���w�����ƂɂȂ�܂����B���{�V������u���f�B�A�X�N�����v���u�W�c�I�ߔM��ށv�ƒ�`���A�h�~�Ɍ��������ӂƌ�����\�������̂�2001�N12���̂��Ƃł����B���̒���1���₪�铖���҂�W�҂��W�c�ŋ����ɕ�͂�����Ԃł̎�ނ͍s���ׂ��ł͂Ȃ�2�ʖ鑒�V�A��̔����Ȃǂ���ނ���ꍇ�A�⑰��W�҂̐S��݂ɂ���Ȃ��悤�\���z������ƂƂ��ɁA������ԓx�ɂ����ӂ���3��ގԂ̒��ԕ��@���܂߁A�ߗׂ̌�ʂ�É���j�Q���Ȃ��悤�ɗ��ӂ���|�|�ƕ\�����܂����B
���f�B�A�X�N�����̌��`�́A���a�̏I�Ղ�1980�N�ォ��U������Ă��܂����B���̔w�i�ɂ́A�e���r�̃��C�h�V���[��������ϋɓI�Ɏ��グ��悤�ɂȂ������Ƃ�����܂��B�����e���r�ǂ���A�L�҂����łȂ����ԑg�̃X�^�b�t����ނɉ����A������̃J����������ɏo����邱�ƂɂȂ�܂����B�܂��A80�N��͎ʐ^�T�����̑n�����������܂����B���́u�t���C�f�[�v�u�t���b�V���v��2�������c���Ă��܂��A�Ő����́A���̕�����J�����u�t�H�[�J�X�v���͂���5���𐔂��Ă��܂����B���h���I�Ȏʐ^�������������A�����o�ŎЂ�����G�����ƂɋL�҂�J�����}������������܂����B���̂��߁A��ނ���l�������Ẳ��{�ɂ��c��オ�����̂ł����B
���{�̃��f�B�A�X�N�����̌��`���ł����������̂́A1984�N�́u���X�^�f�v�������Ǝ��͔F�����Ă��܂��B�u���X�^�f�v�́A�T�����t�̓��W�u�^�f�̏e�e�v����n�܂�܂����B�f�Չ�ЎВ��̎O�Y�a�`�����Ȃɕی����������ĎE�Q�����ƁA�T�����t�������������č��������̂ł��B�O�Y����85�N�A�m�l�̏����Ɏw�����čȂ����ł������Ƃ���E�l�����e�^�őߕ߂���ėL�ߔ������܂��B88�N�ɂ͒m�l�̒j���Ɏw�����čȂ��E�Q�����e�^�ōđߕ߂���܂����A�ō��ق܂ő����A���߂ƂȂ�܂����B�������A2008�N�ɃT�C�p���Ɋό��ɏo�������Ƃ���A���T���[���X�s�x�@�ɎE�l�e�^�őߕ߂���܂��B���X�s�x�́A�Ȃ��E�Q���ꂽ������NJ����A���{�̌x�@�Ƃ͕ʂɂ����Ƒ{�����p�����Ă����̂ł����B�O�Y���̓T�C�p���Ō������ꂽ��A���T���[���X�Ɉڑ�����܂����A���u��̒��Ŏ��E���܂��B
���̂悤�Ɂu���X�^�f�v�́A���o�������琄�������̂悤�ȓW�J���݂��Ă��܂����B�^�f��������ꂽ�O�Y�����͂��ߓo�ꂷ��l���̃S�V�b�v��X�L�����_���Ȃǎ����Ƃ͕ʂ̘b����L����A�e���r�Ƃ��Ă͍������������҂���i�D�̑f�ނ������킯�ł��B�e���r�ǂ͂������ĘA���̂悤�ɓ��W�ԑg��g�݂܂����B�e���r�̎�ނ́A�L�҂�J�����}�������łȂ������Ȃǂ�S������X�^�b�t�炪�K�v�ŁA�J����1�䂠���萔�l�̃`�[���œ����܂��B���̂��߁A�j���̉Ƃ̎����吨�̃��f�B�A�����͂ނƂ����ٗl�Ȏ��ԂɂȂ�܂����B
��85�N8���̓��q�W�����{�@�ė����̂ł����f�B�A�X�N�����͋N���܂����B�������q�@���s���s���Ƃ̈����Ɠ����ɁA����Ɍ������܂������A�L�[�ǂ����łȂ��S���̒n���e���r�ǂ����X�ƌ���ɏW�܂��Ă���̂����ċ����܂����B�����̌���ł��Z�p�v�V���i�݁A�e���r�ǂ̋L�҂�X�^�b�t�����R�Ɏ�ނ��������A���ꒆ�p�c
|
��(4)����X�g�[�J�[�E�l�����̏d�����P
����X�g�[�J�[�E�l�����́A���f�B�A�A�x�@�A�i�@�s���ɐ[�����ȂƑ傫�ȓ]���𔗂����Ռ��̎����ł����B���f�B�A�͌x�@��ނ��Q�ҕ̂�����ɖҏȂ𔗂���ƂƂ��ɁA��Q�ҕ̈Ӌ`�����߂Ċw�Ԃ��ƂɂȂ�܂����B�x�@�͂��̖��C�͑{���ƉB��(�����)�̎�������������A3�l�̌x���������ƐE�A���ޑ�������L�ߔ������܂����B���ɍ�ʌ��x�{�����ȉ�12�l����ʏ�������܂����B�����āA���̎������@�Ɂu�X�g�[�J�[�K���@�v�Ƃ����V�����@�������܂�A�X�g�[�J�[���ĂɎi�@�E�s�������������̐�������Ɠ����n�߂��̂ł��B
1999�N10��26���A��ʌ�����s��JR����w�O�ŁA���q�吶�̒��쎍�D����(����21��)���E�Q����܂����B���D����͎��ƉƂ𖼏��j�Ɏ��X(���悤)�ɂ��܂Ƃ��A���������̔��(�Ђڂ�)�����̃r����莆��������ӂ����łȂ����e�̌��ꂳ��̋Ζ���ɂ܂ł܂���܂����B�u��l�̒j����W���v�Ǝ��D����̎����A��ʐ^�A�d�b�ԍ��������ꂽ�J�[�h���X�֎ɑ�ʂɓ���(�Ƃ�����)����܂����B����̑O�Ɏ�2����~�߂��A�剹�ʂ̉��y�A�G���W���̋�Ԃ������J��Ԃ���܂����B���D����͗F�l�����Ɂu�������߁A�E�����v�ƍ����A���e�ɂ��Ăāu�E���ꂽ��Ɛl�͂��̒j�v�Ǝ����������Ĉ⏑���������߂Ă��܂����B�����āA�j�̎艺�����ɐn���ŏP��ꂽ�̂ł��B���̎����̐[�����́A���̗����x���Ȃ��������E�Q���ꂽ�Ƃ��������ł͂���܂���B���D����ƉƑ��͍ĎO�ɂ킽���Ēn���̏�����ɐg�̊댯��i���A���i���悤�Ƃ��܂����B�������A�x�@�́u�����������v�u���i����Ɩʓ|����v�u���������v����������Ȃ��́v�ȂǂƎ���Ȍ��t�𓊂��Ď��a��A�����艺����悤�v�����A�g����ɂ͒������u��Q�́v�ɉ����܂����B���i������ƁA���@���ɕ��Ȃ���Ȃ炸�A��������������Ƃ����R�ƌ�ɔ������܂��B����ŁA���f�B�A�ɑ��Ă����D����̎����Ƃ͈Ⴄ�l�����������̌`�ŗ����܂����B�ꕔ�̐V����e���r�̃��C�h�V���[�A�T�����Ȃǂ́A���������x�@�������ƂɌ�������D����̎p����܂����B���D����́A����D��ꂽ����A�܂����������̂Ȃ����_�ʑ�(������)���邱�ƂɂȂ����̂ł��B
���̗R�X�������Ԃ𐳂����ƂɊ��R�ƒ��W���[�i���X�g�����܂����B�ʐ^�T�����uFOCUS�v�̋L�҂���������������ł�(��������͂��̌�A���{�e���r�̋L�҂ɓ]�g���Ă��܂�)�B��������̒����u����X�g�[�J�[�E�l�����|�⌾�v(�V����)�́A�s�Ԃ��猌���ɂ��݊�����������悤�Ȕ��^�̃h�L�������g�ł��B���{�W���[�i���X�g��c��܂���܂��܂����B��������́A���܂Ƃ��Ă����j�����Ő������X���o�c���Ă������Ƃ����݁A���̎��ӂ̐l����o���܂��B�����āA���s�⒣�荞�݂𑱂��A���ɎE�Q�̎��s����˂��~�߂܂��B��������������ނ����Ă��܂����A��l�̋L�҂��Ɨ͂Ōx�@���������e�^�҂�����o���A�ߕ߂ւƂȂ�����͌������Ƃ�����܂���B���̎�ޗ͂ɂ͂����E�X���܂��B
��������̎d���̂���ɂ������Ƃ���́A�x�@�̑Ӗ��ƉB�������Ԃ肾���ƂƂ��ɁA�S���Ȃ������D����̖��_�ɓw�߂����Ƃł��B�x�@�́A����̑Ӗ���B���H��ɊS���W�܂�Ȃ��悤�ɂ��܂��܂ȉ��������Ƃ݂��܂��B��������̒����́A���̌`�Ղ�O�O�ɒǂ��Ă��܂��B�E�Q���ꂽ���̋L�҉�ł́A�u�����~�j�X�J�[�g�v�u����u�[�c�v�u�v���_�̃����b�N�v�u�O�b�`�̎��v�v�Ƃ����������i�������Č��A�u�h��ȏ��q�吶�v�Ƃ����C���[�W���ӂ�܂����Ƃ����悤�ł��B�����̏����i�́A�X�g�[�c
|
��(5)�������\�ʼnB��������
�������\�̔g�́A�x�@�����łȂ����̊�����n�������̂ւƍL���葱���Ă��܂��B�����́A��ނ̋N�_�ł���A�^�����𖾂��邽�߂̍ŏ��̓�����ł��B��@������������{�V������́A2003�N�x������Љ�����̂ɂȂ��āA�������\�̌���c���Ƃ��̔w�i�ɂ��Ē������n�߂܂����B08�N�x����͊e�Ђ̕ҏW�ǒ��ō\������ҏW�ψ���̉��ɏ��ψ����݂��Ē����𑱂��Ă��܂��B���̎��g�݂͑O��̘A�ڂł��Љ��06�N12���́u�����ƕv(�O��)�A�����16�N3���Ɂu�����\�\������`���邽�߂Ɂv(����)�����q�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B���̓�̍��q�Ƃ���ȍ~�ɐV���ɒ������ꂽ������݂Ȃ���A���Ղȓ������̕��Q�ɂ��čl���Ă݂܂��B
05�N5���A�����\���Ȃ������I�ȗ��R�̂Ȃ��܂ܓ����Ŕ��\���ꂽ���S���������܂����B����ɂ��ƁA�ߋ�1�N�Ԃ�1���ȏ�A��Q�҂��Ŕ��\�����x�@��28�s���{���A���l�ɗe�^�҂��Ŕ��\�����̂�20�s���{���A�Љ�I�ɏd�v�ȈӖ����������E���̂ɂ�������炸�A�������̂��̂\���Ȃ������̂�27�s���{���ɂ̂ڂ��Ă��܂����B�u�O�ҁv�ł́A����������̐����ƂƂ炦�Ă��܂����A���ǂݕԂ��ƁA���̂��Ǝ��̂ɋ������o�����ɂ͂����܂���B�����������ς�������߂ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��܂��A�����Ɠ����`�ł��ܒ���������A���ׂĂ̌x�@�����炩�̌`�œ������\���Ă���̂͊m���ł��B�������ւ̊�@���ɑ呛���������オ�͂邩�ɖq�̓I�ɉf��قǂɁA�������͉����x�I�ɐi��ł��܂����B
�������\�̕|���́A�������������邾���łȂ��A���������H���Ĕ��\����鎖���������ł��܂����Ƃł��B�F�{���ł́A04�N�ɑ��q�����e���ċւ��\�͂��ӂ���������ŁA�x�@�͔�Q�҂��Ŕ��\���A���q�e�̒m�l���Ɛ������܂����B�e�q�Ƃ��������������ċȂ��Ĕ��\���Ă����̂ł��B�R�����ł�05�N�A�������������Ŕ�Q�������ɂ��������A���ۂ�30�Α�ł������ɂ�������炸46�ł���Ƌ��U�̔��\�����܂����B�v���C�o�V�[�̕ی삪���R�Ǝߖ����܂������A����͋�����Ȃ����Ƃł��B
�܂��A�u���͕͂��s����v�̌��t�ʂ�A�g���ɊÂ��Ή������o���܂��B19�N1���A��ʌ��x��z���̏����x�������Ƌ��^�]���Ă����^���������ꂽ���Ăł́A�x�@�͔��\�����A���f�B�A�̓Ǝ���ނŖ���݂ɏo�܂����B�������A����A���x�͌x���̐��ʂ��K�������炩�ɂ��܂���ł����B�e�Ђ����X(���悤)�Ɏ��₵�����߂ɁA����Ɓu�����v�ł��邱�Ƃ�F�߂܂����B18�N6���A�������s�ŋ��t���Ђ������������N�����A��E3�J���̒����������܂����B�������A���t�̂Ђ����������ł̓E���́A�{���͔��\�����ׂ����Ăł������ƍl������̂ɁA���\����܂���ł����B���̌�A�Ђ��������������t�̌Z�͌���ʌ��x�����ŁA���t���瑊�k���Ă������Ƃ��킩��܂����B�Z�����x�c
|
��(6)�������l�����̓I�ȋc�_��
���s�A�j���[�V����(���A�j)���ΎE�l�����̂̕�������߂����ẮA��N9���ɍ��m�s�ōs��ꂽ�}�X�R�~�ϗ����k��S�����c��̑S�����ŁA���s�V���Ɩ��������̋L�҂���ڂ������s���܂����B�����̌̕o�܂ɂ��āA���̕𒆐S�ɂ��ǂ��Ă݂܂��B
���A�j���В����Ŕ�Q�҂̎������\���T����悤���s�{�x�ɗv�������̂́A������������4����̍�N7��22���ł����B���̗��R�Ƃ��āu�Ƃ�킯�A�C���^�[�l�b�g�ɂ��A�N�����e�ՂɌl���⎞�ɂ͌�������e�Ղɖ��͜���(����)�I�ɔ��M�ł��錻��Љ�ɂ����āA�ЂƂ��є�Q�҂̎��������\����A�@�ւɂ����ꂽ�ꍇ�A��Q�҂₲�⑰�̃v���C�o�V�[���N�Q����A���⑰���r��Ȕ�Q����\���v���w�E���܂����B���s�{�x�͗v����3�����25���A�]���ґS���̐g������肵�܂����A���̗v�����āA�⑰�̈ӌ����������܂��B���̌��ʁA����܂łȂ�g������ƂƂ��ɍs���Ă��������̌��\���摗�肳�ꂽ�̂ł����B8��2���ɂȂ��āA�����A�⑰�ɗ�����10�l�ɂ��Ă̂ݎ��������\����܂����B20���ɂ͕�12�Ђł���u�ݗ��V�������ҏW�ӔC�҉�c�v���{�x�ɑ��đS���̎������\��v�����A27���ɂȂ��Ďc��25�l�̎��������\����܂����B�x�@�����ɂ��ӌ��̈Ⴂ������A����������\�����߂��{�x�ɁA�x�@�����T�d�ɑΉ�����悤���߂铮�����������Ƃ���Ă��܂��B
���\�ɂ������ĕe�Ђ́A���f�B�A�X�N�������N���Ȃ��悤�Ɏ���I�Ȏ�ނ̎�茈�߂����܂����B�����ׂ����Ȃ�܂����A���̓��e���݂Ă݂܂��B1�V���Ɏ��������\���ꂽ25�l�ɂ��āA��ނ���Ȃ��̈ӌ��m�F���s���S���Ђ����߂�B����班�����ꂽ�ꏊ�ɏW���ꏊ�Ǝ��Ԃ�ݒ肵�A����̉����͍T����2��ގ҂̓y��1�l�A����1�l�̌v2�l���\�ɂ���32�l���⑰�̎���̌Ăї�������Ĉӌ����m�F����B2�l�͊e�Ђ̑�\�ł��邱�Ƃm�ɓ`����4��ނɉ����Ă��炦��ꍇ�́A��ޏꏊ���ގ��Ԃ������A�ꏊ�Ǝ��Ԃ����߂�5��\��ނ̏ꍇ�͑�\��2�l����ނ��A������ʐ^�f�[�^���e�ЂƋ��L����\�\�ȂǂƂ��܂����B
�������ċ]���҂̎����́A��ނɉ������⑰�̐��ƂƂ��ɕ���܂����B���f�B�A�Ƃ��Ă͂ł������̔z�����d�˂���ނł���A�ł����B�������A���f�B�A�ƎЉ�̈ӎ��̘���(������)������ɐi��ł��邱�ƂɎ�����������Ƃ����̂́A�A��1��ڂɏ������ʂ�ł��B
���́A�̈Ӌ`��[���������Ă���w�ҁA���Ƃ�����A���f�B�A�̏]���̎咣�͑����̐l�Ɏ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����뜜�̐����o�Ă��܂����B�]�䕔�^�T�E���s��w��w�@�@�w�����ȋ����́A�������������Ă��鑊�͌���Q�ҎE�������̔�Q�ғ������\�ɂ��āA�G���uJournalism�v2016�N10�����ɒ��ڂ��ׂ��_�����܂����B�]�䕔�����́A���f�B�A�������ɂ������Ӌ`���\���ɗ������������ŁA�d�v�Ȏw�E�����܂����B���Ȃ�̌��t�ő�������Ɓu���݂́A���f�B�A�̎�ނɂ���Ď��Q�����łȂ��A���͂̐l�̕Ό���l�b�g��ł̔��(�Ђڂ�)�������w�c
|
��(7)����v���b�g�z�[���E���t�[�ƃ��f�B�A
���t�[�W���p��(���t�[)�́A���{�̒��ł͌Q������ȃv���b�g�t�H�[���ł��B�����āA���̒��ł��郄�t�[�j���[�X�͌��ԃy�[�W�r���[(PV)��150��(2016�N8���ɉߋ��ő����L�^)�Ƃ������{�ő�̃j���[�X�T�C�g�ł��B1996�N7���ɃT�[�r�X���n�܂�܂����B���݂̔z�M�p�[�g�i�[�͖�350�ЁA500�}�̂ɏ��A1���ɋL����5000�{�̔z�M���A������f�ڂ��Ă��܂��B��܂��ȔF���Ƃ��ẮA���{�o�ϐV���������قڂ��ׂĂ̑��̐V���A�ʐM�A�����A�G���A�l�b�g���f�B�A�̃j���[�X���f�ڂ��Ă��܂��B�����āA�V����1�ʃg�b�v�����e���͂�����Ǝw�E����Ă���̂��A�g�b�v�y�[�W�̍ł��ڗ��Ƃ���Ɍf�ڂ����u���t�[�g�s�b�N�X�v(���t�g�s)�ł��B���t�[�j���[�X�ł�8�{���I��܂��B
�]�k�ł����A�V���ƊE�̒��ł悭���ɂ���̂́A�u�V����1�ʂɏ����L�����o�Ă��m�l��F�l�̔����͂Ȃ������̂ɁA���t�g�s�ɍڂ�ƈ�Ă�LINE��[���Ŕ������͂����v�Ƃ����Ⴂ�L�҂����̑̌��ł��B�m���ɁA���t�g�s�ɓ���ƁA���̋L����PV�͔���I�ɐL�т܂����B���̐L�ѕ��͍��A�ȑO�قǂł͂Ȃ��Ȃ��Ă͂��܂��B���͔��u�t�߂鐬���w���͂��߁A�������̑�w�̋��d�ɗ��@�����܂����A���̑�w���̑����́u���t�g�s�v�Ƃ������t���m��܂���B���̊��̕ϗe�ɂ��Ă͕ʂ̋@��ɉ��߂ĐG��邱�Ƃɂ��܂��B�����A�l�b�g�z�M����ہA�����e���f�B�A�́A���t�g�s�ɓ��邱�Ƃ�_���A�̗p����₷���Ȃ�悤����Ԑ����������A�L���̓��e���H�v���Ă��邱�Ƃɕς��͂���܂���B
���̃��t�g�s�̑I��ɂ������Ă���̂��A��25�l����Ȃ�g�s�b�N�X�ҏW���ł��B��胁�f�B�A�̋L�҂��͂��߃G���W�j�A�A�f�U�C�i�[�A���E�A�c�ƐE�A�A�i���X�g�ȂǑ��E��̌o�������l�ނō\������Ă��܂��B30�Αオ���S�ŁA���r�̗p�҂����łȂ��V���҂��z������Ă���Ƃ����܂��B���������łȂ������A���ɂ����_�������A24����365���Ԑ��ʼnғ����Ă��܂��B
2019�N9���ɍ��m�s�ŊJ���ꂽ�}�X�R�~�ϗ����k��S�����c��ɂ́A���t�[�̕ҏW�{���̊��c�L�G�E�ҏW1����(�����͓���)��������A�ҏW���j��������܂����B���c���͖����V���L�҂��烄�t�[�ɓ]�E���܂����B01�N�ɖ����V���Ђɓ���A�����x�ǁA�����Ƒ��̎Љ�Ō�������ψ����ٔ�����S�������q�r�̎����L�҂ł����B13�N10���ɖ����V���Ђ����߁A���t�[�Ɉڂ�܂����B�����Љ������̒����̕����ł���A�����ҏW�Ґ��ǒ��̎��ɑގЂ��܂����B�����V���Ƃ��Ă���Ɏ��������Ȃ��l�ނŁA�|�ӂ���悤��������ɂ�����܂����B
���c���̐����ɂ��ƁA���t�g�s�Ɍf�ڂ���L���̔��f��́u�������v�Ɓu�Љ�I�S�v���Ƃ����܂��B�u�������v�́A�ЊQ�A�����A�o�ςȂǂ̃W�������ɊY��������̂ŁA�u���Ƃ��ǂ܂�ɂ������e�ł����Ă��Љ�I�ɏd�v�ȁc
|
��(8)���t�[�ƐV��
���t�[�ƐV���ƊE�̔���グ�̐��ڂ��ׂ�ƁA�V���ƊE�����e���̑傫�����킩��܂��B�������20�N�O��1998�N�A�V���ƊE�̔���グ��2��4900���~����܂����B���ꂪ2018�N��1��6619���~�ƂȂ�A8000���~�ȏ�����炵�Ă��܂��B����ɑ��A���t�[(���݂̎Ж���Z�z�[���f�B���O�X)��1998�N��12���~����8971���~�ւƑ傫������グ��L���܂����B�����܂Ő��������ŒP���ɔ�r����ƁA���t�[���L���������́A20�N�ԂŐV���ƊE���������������������ς݂������̂Ɠ����ɂȂ�܂��B
�����������Ƃ������āA�V���̒���(���傤�炭)�́A���t�[�Ƀj���[�X��������߂��Ƃ���w�E������������܂��B����ɂ��Ď��̍l���́A�������Ă��镔����������̂́A������Ȃ������������ɂ���Ƃ������̂ł��B����ɂ��ẮA�܂��@������߂ďq�ׂ����Ǝv���܂��B����ł͂Ȃ��A�V���̓��t�[�Ƀj���[�X�����悤�ɂȂ����̂���U��Ԃ��Ă݂܂��B
���t�[�֍ŏ��Ƀj���[�X������V���́A�����V���ł��B����́A1996�N7������ł����B�����V���́A�C���^�[�l�b�g�̓o��ɂ���ă��f�B�A�͌��ϊ����}����Ƃ݂āA�}���`���f�B�A�헪��ϋɓI�ɐi�߂Ă��܂����B���̍��A�r���𗁂тĂ����L���v�e���V�X�e���ɂ����������j���[�X��z�M���܂����B
�����̖����V���́A�p�\�R���ʐM�́u�j�t�e�B�T�[�u�v��uPC-VAN�v�ւ̃j���[�X�z�M����v���ƂƂ��Ĉʒu�Â��Ă��܂����B�j�t�e�B�T�[�u��PC-VAN�́A�d�b������g�����C���^�[�l�b�g�ڑ������ƂɃT�[�r�X��W�J���Ă��܂����B�E�B���h�E�Y95���g���Ă����o���̂���l�́u�s�[�q�������v�Ƃ����d�b����Ɠ��̐ڑ������o���Ă���Ǝv���܂��B�d�b����̗��_�́A���̎g�p���疈���V���̃j���[�X���������Ԃ����m�ɋL�^����A�d�b�����ƈꏏ�ɋL���{�������𐿋��ł��邱�Ƃł����B����Ί����ȉۋ����f���ł��B�����̃p�\�R�����[�U�[�́u�j���[�X�͗L���v�̈ӎ������m�������Ǝv���܂��B
�����ɁA�A�����J�ŋr���𗁂тĂ����{�ƃ��t�[�̓��{�łƂ��ă��t�[�E�W���p�����ݗ�����A�V���ȃj���[�X�z�M�����߂Ă��܂����B�����̃��t�[�́A�݂�Ȃ��u���b�z�[�v�ƌ�ǂ����Ƃ����{���ɏ����ȑ��݂ł����B�����V���́A�}���`���f�B�A�헪�̈�Ƃ��ăj���[�X�̔z�M��𑝂₷�I�������܂����B�������A����Ƃ͂����܂Ńj�t�e�B�T�[�u��PC-VAN�ł��B�L�����Ƃɗ������x�����Ă���Ă��郆�[�U�[���s���v����Ȃ��悤�ɔz�����܂����B���t�[�̃T�C�g�Ō�����̂́A�e�W�������ŐV�̃j���[�X�̂���7�{�Ɍ��肷�遤�A�[�J�C�u�ɂ͂��Ȃ��|�|�Ȃǂ̐�����݂����̂ł��B�����V���̓V���[�v�́u�U�E���X�v�Ȃǂɂ��j���[�X��z�M���Ă��܂������A�����ł��{���Ȃǂ̐��������Ă��܂����B
���̍�����A���X�ƃj���[�X�T�C�g���a�����܂��B�傫�ȉe���͂̂�����NTT�n�́u�O�[�v���͂��߁A�Z�F�����n�́u���C�R�X�v�A�ɓ��������n�́u�G�L�T�C�g�v�A�f�W�^���K���[�W�́u�C���t�H�V�[�N�v�A���Ōn�́u�w�O�T����y���v�Ȃǂł��B����ɖ����V�����͂��ߊe�V���Ђ��j�c
|
��(9)�u�|�X�g�E���t�[�̎���v�ƃ��f�B�A
2019�N11��18���A���t�[��LINE�̌o�c�����������ɔ��\����܂����B���t�[��W�J����Z�z�[���f�B���O�X�̐�ӌ����Y�В���LINE�̃V���{���J���[�̗ΐF�̃l�N�^�C�ALINE�̏o�В��̓��t�[�̃V���{���J���[�̐ԐF�̃l�N�^�C�����ꂼ����߂āA��������ƈ�������܂����B���̌o�c���������͓��{�o�ϐV���̃X�N�[�v�Œm��܂����B�v���b�g�t�H�[���̗��Y���ˑR�A��������Ƃɋ����A�����č��f�����܂����B���́A�u�|�X�g�E���t�[�̎���v�͊��Ɏn�܂����A�V���������S���L�͌��̈��LINE��������Ȃ��Ƃ݂Ă��܂����B���̓����������Ƃ����̂ł��B�u�|�X�g�E���t�[�̎���v�͂���Ɍ����ɂ����Ȃ�܂����B
����܂Ō��Ă����悤�ɁA���{�̂قƂ�ǂ̃��f�B�A�́A���t�[�Ƀj���[�X��z�M���A�������玩�ЃT�C�g�Ƀ��[�U�[�𗬓������ăy�[�W�r���[(PV)���グ�Ă��܂����B�����V���̏ꍇ�A���݂̌v�����@�ɂȂ���13�N�ȍ~�ŁA���̗���PV���ł����������̂�15�N����ł����B50���ȏオ���t�[�o�R����������������܂��B
�������A���̐��N�́A���炩�Ƀ��t�[����̗����������Ă��܂����B�ŋ߂�1�������̌�������܂��B���̗v���̈�ɁA�X�}�[�g�t�H��(�X�}�z)�V�t�g���i�݁A���[�U�[�����܂��܂ȃj���[�X�A�v�����g���悤�ɂȂ������Ƃ�����܂��B�����V���j���[�X�T�C�g�ւ̃A�N�Z�X���݂�ƁA1���̃A�N�Z�X���ŏ��߂ăX�}�z���p�\�R�������̂́A15�N5���ɉ̎��ASKA���ߕ߂��ꂽ���ł����B�����Ƃ̃A�N�Z�X���ŃX�}�z���p�\�R�����t�]�����̂�15�N11���ł��B�ȗ��A�X�}�z���ǂ�ǂ�L�тāA���݂̓X�}�z7:�p�\�R��3�̊����ŁA����ɃX�}�z�̊�����8�ɋ߂Â�����܂��B���t�[�j���[�X���X�}�z�c
|
��(10)�L�҂�SNS
�v���b�g�t�H�[���̓o��́A�W���[�i���Y���ɂ��傫�ȕω��������炵�܂����B�����ЂƂA�ʂ̊p�x����W���[�i���Y�������ς��������̂�����܂��B���ꂪ�A�\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X(SNS)�̍L����ł����B
�����c�C�b�^�[�ɃA�J�E���g(@pinpinkiri)���������̂�2010�N2���̂��Ƃł��B�����͓����Łu�L�҂Ƃ����Ă��܂��v�Ɩ����܂����B�����Ԃ₢�Ă����̂��킩�炸�A���܂ɂԂ₢�Ă��܂����������͂���܂���ł����B�����V���̋L����ᔻ�I�ɂԂ₢����A�����V���̌����A�J�E���g����t�H���[����������͂��܂������A�t�H�����[�͂Ȃ��Ȃ��������A1�N�ȏソ���Ă�20�l�𐔂��邾���ł����B
�Ƃ��낪�A11�N4�����{�ɓ��e�����ЂƂ̃c�B�[�g�ŗl�����ς��܂����B���[�U�[�̊Ԃōs���Ă����u���[�N�v���߂���c�_�ɔ�ѓ���ʼn�������̂ł����B����������ꂸ�Ɍ����u���[�N�v������̂��L�҂̎d���B�u���[�N�v�ɍ߂�����Ƃ���A�L�҂��u���[�N���鑤�v�ɂ����˂肻�̈ӌ��ɉ����������ŕ��Ă��܂����Ƃ��B�L�҂́u���[�N�v�œ�������^���ƐM���镶���ɒu��������悢�B���ꂪ�B���B���e���Ă�����20�l�������t�H�����[��39�l�ɔ{�����A�����ɂ�204�l�ɂȂ�܂����B�u�}�X�S�~�v�Ǝa���Ď̂Ă��邱�Ƃ̑����l�b�g�̐��E�ł����A�����̃��[�U�[���̖���^��(����)�Ɏ~�߂Ă��ꂽ���ƂɎ��͍��g���܂����B
���̌�A��^�A�x�ɓ���A���͓����{��k�Ђ̔�Вn�E�O���ŕ����{�����e�B�A�����܂����B�k�ЂŁA�c�C�b�^�[�͔�Ў҂̐؎��Ȑ������܂��܂ȂƂ���֏u���ɓ`���A���E�����܂��̐����Вn�ɑ��X�Ɠ͂��܂����B����́A���f�B�A�̗��j�����ޑ傫�ȏo�����ł����B�����{�����e�B�A��ʂ��Ēm������Вn�̗l�q�𓊍e�����Ƃ���A�t�H�����[��300�l�ɂȂ�܂����B����ɕɂ��Ă̈ӌ����Ԃ₫������ƁA���̔N��8�����ɂ�1000�l���܂����B���́A���[�U�[�ƒ��ڂȂ���Θb�ł���SNS�̉\���Ŋ����܂����B
�S���̑����̋L�҂����̎v���������������Ǝv���܂��B�͖k�V��́A��Вn����̔��M�Ƀc�C�b�^�[�̎O�̃A�J�E���g���g���A�u�Z�Z���̃X�[�p�[���ߑO���ɊJ�X���܂����v�Ȃǂ��ߍׂ��Ȑ������̓��e�𑱂��܂����B�t�H�����[�͐k�БO��4000�l����11�N5���ɂ͖�7�{��2��7000�l�ɂȂ�܂����B�͖k�V���12�N2���̖����V���̎�ނɁu���{�Ńc�C�b�^�[�����y���ď��߂Ă̑�K�͍ЊQ�ł���A����Ӗ��A���j������Ƃ����ӎ����������v�ƐU��Ԃ��Ă��܂��B
���ꂪ�_�@�ɂ��Ȃ��āA�c�C�b�^�[�����p����@�ւ̎��g�݂��L�����Ă����܂����B�����V���́A12�N�̐������u���A��30�fs�v��30�Α�̓����`���܂������A���̍ہA�c�C�b�^�[�œǎ҂ƑΘb���Ȃ���L���ɂ���Ƃ����V������@��������܂����B�܂��Г��Ɂu�\�[�V�������f�B�A������v��݂��A12�N�㔼�������ŏ\����̕����A���J�Â��܂����B
�����V����12�N1���A�u�Ԃ₭�v�L�Ґ��x������A�L�Ҍl�̃c�C�b�^�[��̈�ƈʒu�Â��܂����B35�l�̋L�҂��I��A�ϋɓI�Ȕ��M���n�߂܂����B��ޕ������ޔǁA�n���@�ւ��A�J�E���g������A���̐��͒Z���Ԃ�100���܂����B4���ɂ͋L�҂�SNS������E���u�\�[�V�����G�f�B�^�[�v������A�Г������ɂ������c�C�b�^�[���p�̃K�C�h���C�������J���܂����B���̒��ŁA�A�J�E���g�̃v���t�B�[����1���e���e�������V�����\������̂ł͂Ȃ����Ƃ��L��2�����N��c�C�[�g�͕K���������e�Ɏ^�Ӂc
|
��(11)�u����v���v�������炵������
�X�}�[�g�t�H���Ɓu4G�v�Ƃ����V�����ʐM���������炵���傫�ȉʎ����u����v�ł��B���A�ʋΓd�Ԃ̒��ŃX�}�z�ʼnf�������p��������O�ɂȂ�A�X�}�z�ŎB�e��������͏u���Ƀ\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X(SNS)�ɓ��e�ł��܂��B�������A����������y���́A�ق�̐��N�O�ɂ͍l�����Ȃ����Ƃł����B����̍Đ��ɕK�v�ȃX�g���[�~���O�T�[�o�[�͂܂����ʂȑ��݂ł���A����̃A�b�v���[�h�ɂ͒������Ԃ�������܂����B�}���Ɏ��������u����v���v�̓W���[�i���Y���ɂ��傫�ȉe����^���܂����B
2019�N6���A���Q���u�����́u�����Ƃד������v�ōs��ꂽ�ꌩ�Ƃ�Ƃ߂��Ȃ��P���̓��悪���E�����삯����܂����B�P���́A���C�I�������肩�瓦���o�������Ԃ�z�肵�A���C�I���̒�����݂ɐg���E������艟������Ƃ������̂ł����B���̗l�q�����̖{���̃��C�I�������Δ������悤�ȕ\��Ō��Ă��܂����B�N�X�b�Ə��邨�������Ƃ�����҂舣���Y�����̓���́A�����V�����R�x�ǂ̓���4�N�ڂ̖ؓ��Ȏq�L�҂��B�e���܂����B����̓c�C�b�^�[��500����A���[�`���[�u��670����A�����V���̃T�C�g�̒��ł�5����Đ�����܂����B�����āA�p���K�[�f�B�A�������ڂ̘b��Ƃ��ē]�d���܂����B�ȑO�Ȃ�V���̒n��ʂ̕Ћ��ɍڂ邾���������͂��̋L�����A���E�̃j���[�X�ƂȂ����̂ł��B
�u���{��v�Ƃ����A���E�ł��������Ƃ���錾�ꂪ�Q����ǂƂȂ��āA���{�̃}�X���f�B�A�͂���Ӗ��Ő��E�̋����������Ă��܂����B�������A�C���^�[�l�b�g����ɂȂ��āA���̎Q����ǂ͂ނ��딭�W�̑������ɂȂ邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B���E��15���l���g���p��Ŕ��M����j���[���[�N�E�^�C���Y���Ɠ��{�̐V���ł́A���������ǂ܂��K�͂��͈͂��Ⴂ�܂��B�������A���Q���̓������̃j���[�X�����E�œǂ܂ꂽ�悤�ɁA�u����v�̗͍͂������y�X�ƒ����Ă������Ƃ������܂����B
����́A�̉\�����L������܂��B15�N�ɕ����̖��ɐ����������ۖ@�����߂����ẮA����O�Ŕ��Ή^�����J��L����w�������̒c�́uSEALDs(�V�[���Y)�v�̊��������ڂ��W�߂܂����B�X���[�K�������b�v�ɏ悹�đi�����@�͐V�N�ŁA�Ⴂ����̃��b�Z�[�W�͑����̐l�X�̂��Ƃɓ͂��܂����B
�����A�]���̕X�^�C���ł́A�ނ�̎a�V����`����͓̂�������Ǝv���܂��B�V�����ʂ̓X�y�[�X�������A�����͎��Ԃ�����������Ă��܂��B���̌��ʁA���������R�c�W���f���s�i�Ȃǂ́A��^�I�Ȏ��ۂƂ��Ă����`���Ȃ�����������܂����B�������A����͂���������^��ł��j��͂�����܂��B�B�e���ăl�b�g�Ŕ��M���邱�Ƃɂ��A���ڂ���ɂ����������ۂ�`������悤�ɂȂ����̂ł��B
�X�}�z��4G�́A�����ЂƂ傫�Ȋv�����N�����܂��B���C�u����̔��M���\�ɂ����̂ł��B����܂Ń��C�u�����́A�e���r�ǂɂƂ��Ă��ȒP�Ȏd���ł͂���܂���ł����B���p���̎ԗ�����̃X�^�b�t�����s���ď��߂čs������̂ł����B�Ƃ��낪�A15�N���납��t�F�C�X�u�b�N��c�C�b�^�[�Ȃǂ����C�u����̋@�\���������A�X�}�z�ЂƂŃ��C�u�z�M���ł���悤�ɂȂ����̂ł��B�����āA���E���Ń��C�u�����Ɏ�����鎎�݂��n�܂�܂����B����14�N�H����16�N�t�ɂ����āA�����V���ƒ�g���Ă���č��̃E�H�[���E�X�g���[�g�E�W���[�i�����A�C���h�l�V�A�̃R���p�X���A�x�g�i���̃g�C�`�F���̖{�Ђ�K��܂����B�����ŋ������̂́A�ǂ̎Ђ�����ҏW�̐��X�^�W�I�������A�ҏW�ǂ̐^�ɂ����ł����M�ł���X�^�W�I��u���Ă��邱�Ƃł����B���Ă̋L�҂͎�ނ������e���L���Ɂu�����c
|
��(12)�L�҂��u������v�����
2020�N3��14���ߌ�6���A���͎���̃e���r�̑O�ŋْ����Ă��܂����B���{�W�O�̋L�҉�����p����Ă��܂����|�|�B
2020�N3��14���ߌ�6���A���͎���̃e���r�̑O�ŋْ����Ă��܂����B���{�W�O�̋L�҉�����p����Ă��܂����|�|�B
2020�N3��14���ߌ�6���A���͎���̃e���r�̑O�ŋْ����Ă��܂����B�������ꂽ�V�^�C���t���G���U�������ʑ[�u�@�ɂ��āA���{�W�O�̋L�҉�����p����Ă��܂����B�V�^�R���i�E�C���X����߂�����{�̉��2��29���ɑ������̂ł������A���̎��̉�ɑ��A�u�L�҉�ł͂Ȃ����{���\���v�Ƃ�
���̓��̉�́A�ł��낤�Ƃ������@���ɑ��A�����̋L�҂����̐����グ�܂����B���̌��ʁA����Ԃ�2��29����36������52���ɉ��сA����̐���5����12�ւƑ����܂����B�u����O�i�v�������Ǝ��͎v���A���������ْ��������܂����B�L�҉�ł̋L�҂̌���������������鎞��ł��B�����ŏ��ɂ��̎v�������������̂�05�N5���AJR���m�R���̎��̂���JR�����{�̋L�҉�ł����B107�l�̎��҂��o�������̎��̂́AJR�����S����������v��D�悵�����Ƃ��w�i�ɂ���Ǝw�E����܂����B����ŁA�L�҉�ł́AJR����Njy����ǔ��V���̒j���L�҂��ᔻ����鎖�ԂɂȂ�܂����B���̋L�҂̌����́A�m���ɍs�V�̂������̂ł͂���܂���ł����B�u����A����������A�В����Ă�Łv�ȂǂƐ����r�炰����A����I����������܂����B�����̓\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X(SNS)��l�b�g����͕��y���Ă��܂���ł������A�e���r�̒��p���Ĕᔻ�����܂�A�ǔ��V���́u�g������M�S���̂��܂�Ƃ͂����A��ɐS������ׂ���Â����������ƌ��킴��܂���B������̎w������������Ȃ��������Ƃɒp���������ł��v�Ƃ����ٗ�̂���т��f�ڂ��܂����B
���̋L�҂̍s�����������͑S������܂��A�厖�̂̐ӔC��Njy����L�҂̑��ɔᔻ���W�܂������ƂɎ��͏Ռ����܂����B�L�҂�����(���傤��)�́A�u�m�錠���v�̑�s�҂Ƃ��č������畉�����Ă���Ƃ����g�����ɗR�����܂��B�������A���̊W�̓y�䂪�낤���Ȃ��Ă���Ɗ���������ł��B�ŋ߂ł́A19�N5���ɑ�Îs�ŕۈ牀���̗�Ɍy��p�Ԃ��˂������̂ŁA�ۈ牀�����J�����L�҉�̂��Ƃ肪�ᔻ����܂����B���̂Ɏ���ߒ����m�F���悤�Ƃ���L�҂����Ɂu���̈Ӗ�������v�u�ۈ牀���ɂ͉��������x�͂Ȃ��v�Ȃǂ̔ᔻ���W�܂�܂����B�L�҂����͕����ׂ����Ƃ����������ɕ����Ă����Ǝ��͎v���܂����B�������A�������ܜ�(���傤����)�������Ă������Ƃ�����A�L�҂����₷��Ӗ��ւ̗����͍L����܂���ł����B
���݂̋L�҂́A�����������u�����鑶�݁v�ł��邱�Ƃ������ӎ����Ȃ���Ȃ�܂���B���̈ӎ����̐M�������ɂ��K�v�Ȏ���ɂȂ�܂����B���{�̃W���[�i���Y���̓������邢�͌��_�Ƃ��Ďw�E����邱�ƂɁA�L�҉���`���I�ɂȂ肪�����Ƃ������̂�����܂����B���{�̋L�҂����́A���_�l��ǂ����߂邠�܂�A�L�҉�Ŏ������o�����Ƃ��A���̔������ނ�P�Ǝ�ނ��d������X��������܂����B�����삯�o���̍��A�L�҉�ő����̎��������L�҂͖��\���Ƌ������A�������̊��o����������Ȃ��Ɓc
|
���W���[�i���Y����T�����H
���̘A�ڂ́A������ЊQ���̎����̂�����������ɁA�ߘa�Ƃ���������肪����ɂ��āA�C���^�[�l�b�g����̃W���[�i���Y���̌���Ɖۑ�ɂ��čl���Ă��܂����B�ŏI��ƂȂ鍡��́A�����̃W���[�i���Y���̎p��W�]���܂��B
�p�u�G�R�m�~�X�g�v��2011�N7��9�����́A�u�����̃j���[�X�v���e�[�}�ɓ��W���܂����B���̒��ŁA�W���[�i���Y���ɋ��߂���V�����ϗ���́A�u�q�ϐ��v�ł͂Ȃ��u�������v���ƌ��_�Â��܂����B���̓��W�́A���m�o�σI�����C���̕ҏW����j���[�Y�s�b�N�X�̏���ҏW���߂����X�؋I�F����̒����u5�N��A���f�B�A�͉҂��邩�\�\Monetize�@or�@Die?�v(���m�o�ϐV��ЁA13�N8��)�ɋ����Ă��炢�܂����B�����ō��X����͂����w�E���Ă��܂��B�u�M�҂̃o�b�N�O���E���h�A�o���A�����āA�����I�ȃX�^���X�܂Ŕ�I������ŁA���̐l�Ԃ��w���͂����v���x�Əq�ׂ�͈̂���ɍ\���܂��A�c�_��������������͂��ł��B�q�ς������̎v�z�ꍞ�܂����L�����A�����̗���m�ɂ��Ĉӌ��X�Əq�ׂ��L���̕����A�ǂޕ����������肵�܂��v�B�����������ӂ��܂��B
���̐���̋L�҂́A�u�q�ϐ��v��S�ۂ���L���̏��������P������Ă��܂����B�u�c�c�Ƃ݂���v�u�ᔻ�𗁂т������v�Ƃ������\����A���]�������č��͂قƂ�ǎg���Ȃ��u����s�������ڂ����v�Ȃǂ́A�u�q�ϐ��v�������悤�Ƃ�������̒m�b�������Ƃ������܂��B�������A���͂ł��f���ł����ׂĂ̒��앨�́A��ς�r�����Ă͐������܂���B20���I�̃W���[�i���Y���́A���̎��Ȗ���������Ȃ��玎�s����𑱂��Ă����Ƃ������܂��B�����}�X���f�B�A�����M��i��Ɛ肵�Ă������Ƃ��e�����Ă����Ǝv���܂��B
�������A�C���^�[�l�b�g��\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X(SNS)�̓o��ŁA�N�������M�ł��鎞��ɂȂ������A�͈�ς��܂����B�ɘ_�ɂȂ�܂����A�L�҂������̔��M�҂̈�l�Ƃ��āA�M�����l�����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�C���^�[�l�b�g�̎���́A�u�N�������Ă���̂��v����������܂��B�ǂ�Ȍo���̋L�҂��A�ǂ�Ȏ�ރv���Z�X���o�āA���̋L���������Ɏ������̂��B�u�������v���W���[�i���Y���̐M���̑b�ɂȂ�Ǝv���܂��B
����Ȏ���̋��E�����l���鎞�A�Ď��j���[���[�N�E�^�C���Y�̓�̕��Q�l�ɂȂ�܂��B03�N�̃C���N�푈�́A���ۂɂ͑��݂��Ă��Ȃ������C���N�̑�ʔj�킪�J��̗��R�ɂȂ�܂����B���̎��A�u�b�V����������̏������X�Ɠ��A�J����㉟�������Ɣᔻ���ꂽ�̂��j���[���[�N�E�^�C���Y�ł����B05�N�ɕҏW�ǒ����������Ă��܂����A�C���N�Ɋ֘A����12�{�̋L���ɖ�肪����A����10�{�̓W���f�B�X�E�~���[�L�҂��Ă��܂����B�~���[�L�҂̓s�����c�@�[��܂̉Ԍ`�����L�҂ŁA���������ɐ[�����肱��ŏ��Ă��܂����B�������A�����Ƃ̋������߂��������ƂŁA���̃`�F�b�N�����낻���ɂȂ�A���䂪�߂錋�ʂɂȂ�܂����B
���͂ւ̖�����ނ́u�A�N�Z�X�E�W���[�i���Y���v�ƌĂ�܂��B���{�́u�ԋL�ҁv��u�L�҃N���u�v�̎�ނɋ߂��Ӗ�������܂��B�~���[�L�҂́̕u�A�N�Z�X�E�W���[�i���Y���v�̂�������̂��̂�₤���ƂɂȂ�܂����B�~���[�L�҂͂��̌�A�C���N�푈���߂����ċN�����Ē�������(CIA)�H����g���R���������ɊW���Ď��Ă���邱�ƂɂȂ�܂��B
���̃C���N�Ƒɂɂ���̂��A�n���E�b�h�̑啨�v���f���[�T�[�A�n�[�x�C�E���C���X�^�C�����̃Z�N�n������������17�N10���̕ł����B�~�[�K���E�g�D�[�q�[�A�W���f�B�E�J���^�[��2�l�̏����L�҂��S�����A�s�����c�@�[�܂���܂��܂����B�ޏ������́u�A�N�Z�X�E�W���[�i���Y���v�̎�@�ł͂Ȃ��A�ނ���ƊE���狗�������������߂ɁA�ƊE���̂䂪�݂ɋC�Â��A�ƊE�̃h���̍s���\�����Ƃ��ł��܂����B
�C���N�̃~���[�L�҂́A�j���ƌ݊p�ɓn�荇���Ď�ދ����𑱂��A���������ɐH������ł����܂����B����A�Z�N�n���́A�����L�҂Ȃ�ł͂̎��_�ɂ����̂ł����B��A���E�̏��������ɋ����ƘA�т̗ւ��L����ASNS����Ȃ�ł͂́�MeToo(�~�[�g�D�[)�^���ւƔ��W���A�W���[�i���Y���̐V���ȉ\���������܂����B
�u�A�N�Z�X�E�W���[�i���Y���v�͂��������ł���A�W���[�i���Y���̓y��ł�����܂��B�������A�u�A�N�Z�X�E�W���[�i���Y���v�������ւ�ɂ��鎞��ł͂��͂₠��܂���B����́A�Đ��{���閧���ɖc��Ȍl������@���W���Ă�����Ԃ�\�����G�h���[�h�E�X�m�[�f�����̍����ɂ����Ď��܂��B
�č��ƈ��S�ۏ��(NSA)�Ȃǂɏ������Ă����X�m�[�f������������Ƃ��đI�̂́A�u���W���ݏZ�̃W���[�i���X�g�A�O�����E�O���[���E�H���h���ł����B���̌o�܂́u�\�I�@�X�m�[�f�������ɑ������t�@�C���v(�V���ЁA�c
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���u��������L�ҁv�͒��ق̋��Ǝ҂��I 2020/7 |
��y���ǔ��V���L�҂����߂āA�V�������h��������B�����Ɂu�Ɨ��L�ҁv�ƈ���Ă���B���ꂩ��͂ǂ��ɂ��g�炸�ɁA���R�ɕ��������Ă����Ƃ����̂��낤�B����ȂɌ��Ђ�����Ȃ��Ă��A�Ǝv�������A�����t���[�L�҂ƋL���Ȃ��Ƃ���ɁA�ނ�����������悤�ȋC�������B
���܂ł����̋C�����ŏ��������Ăق����A�Ǝ��͊�����B
���N�O�̖��h�̂��Ƃ��v���o�����̂́A���������̍���O���������̓q���}�[�W�������ŁA �u��������L�ҁv�̑��݂�˂��t����ꂽ����ł���B���쌟�����Ɛ�����͂�ł����Y�o�V���̓�l�̎i�@�N���u�L�҂ƁA�����V���̌��i�@�L�҂̂��Ƃ����������Ă���̂ł͂Ȃ��B��g�D�̒��ɋ��āA�ǎ҂����߂Ă��鎞�ɁA���߂��Ă��邱�Ƃ������Ȃ��A�L�҂̌Q��̂��Ƃ��L���Ă���B
�T�����t�̕ŋ��������Ƃ͂������邪�A���̈�͏o�ŎЂ��܂ށA�ӊO�ɑ����̋L�҂��������쌟�����ƌ�V���Ă��āA�u�閧��`�̌����݂����Ȍ��@���v(���@�L�҂��������Z����)�̐��E��`���Ȃ��������Ƃł���B
�@���E���@�Ƃ����ŋ��̌��͑g�D�͐₦���`�F�b�N���ꑱ���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B���̇�2���������쌟�����́A�ȑO������{�����ɋ߂��ƌ����Ă����B����͋�̓I�ɂǂ��������ƂȂ̂��B���錟�������⌟�������͉����l���Ă���̂��B�����������@�͂Ȃ��ߔN�A�^��������E���ł��Ȃ��Ȃ����̂��\�\�B
���@���Ƃ����g�D�̑S�̑��ƌ��@�l����`���钷���A�ڂ�|���^�[�W�����A����قNj��߂�ꂽ�����͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����A���N1���ɍ��쌟�����̒�N�������t�c���肳��Ă��A���@���̒�N����������u���@���@�����āv�������ᔻ�𗁂тĂ��ASNS��Ɂu�����@���@�����ĂɍR�c���܂��v�Ƃ������e�����ӂ�Ă��A�Ȃ��f�Џ��ȊO�͏�����Ȃ������B
�������Ƃ́A���@�����⌟�������Ɠ���I�ɐڂ��Ă���N���u�L�҂ɂ́A(�C�T���������)�\�Ȃ��Ƃł���B���t�̌�A�u���͉��������m���Ă����v�Ƃ����}�X�R�~�l�����X�Ɍ���āA(�Ȃ���)�Ǝ��͕���Ă��܂����B����̎��Ԃ�`����̂��d���Ȃ̂ɁA�������āu���ق̋��ƊW�v�Ɋׂ����l�����ɑ����B�����L�҂����̔���Ƃ�Ȃ��B
�x�����L�҃N���u�ɁA�u����A�������Ⴂ�Ȃ�v�ƌ��Ȃ̂悤�Ɍ����L���b�v�������B�{���r��ŏ�����������ɐG�ꂽ�肷��ƁA���͂��������邾���łȂ��A��ތ����Ԃ��ꂩ�˂Ȃ��B���͂��̐�y����肾�������A�M�ӂɈ��������ċL���̗ʂ͊i�i�ɑ������B�ΏƓI�Ɏi�@�L�҃N���u�ɂ́u�����t���ď����v�ƈ�u�̓��_�l�ɓq����L���b�v�������B������͓��R�̂悤�ɋL���̑��ʂ͌���B��ތ��ɂ���i�ɂ��z������l���������A�ǎ҂́u�m�肽���v�Ƃ����~���ɉ������̂́A�����ɂ������Ƃł����˂���ď������O�҂������B
�L�҂͌f�ڂ��ꂽ�L�����S�Ă��B�����āA���̋L�҂����Ȃ���Ζ��炩�ɂȂ�Ȃ��������낤�L���̂��߂ɑ��݂��Ă���B�����ɂȂ�Γ��ǂ��Ƃ����\����悤�ȋL���͖{���̓��_�l�ł͂Ȃ��B���ǂƂ̐M���W�⊲���Ɣ閧�����L�������Ƃ����A���ꂽ�L���ɂ���ċL�҂͕]������Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂����B����A�ܒ@���ɂ����Ă���3�l������@�����肹���ɁA���ЍĂуy���������Ăق����B�ɂ݂┽�ȂƂƂ��ɁA������ƌ��@�̗��ʂ�������͔̂ނ炾���A�Y�o�V���Ђɂ��ƁA�L�҂����̍s�ׂ͎d���炵������A���������ɂȂ�̂��낤�B
���͂��āA���|���^�[�W���w�x�g�i����L�x(��������)��ǂ�ŁA���@���L�҂����ɂ͂Ȃ�܂��Ɛ������B�x�g�i���ɂ́A�����m�푈�I���̌���l�X�Ȏ���猻�n�Ɏc�����Đ���������{�l���m�����������B��Ƃ̊J�����͔ނ���{�l�c�����m�̔߉^�Ɠ{����A����Ȍ��t�ő�ق��Ă���B
���g���ė̞~�����A�W�A���E���������h�Ƃ������{�̃X���[�K���͓���(���r)���疳���̓��{���m�ɂ���Ă̂ݐ^�ɐM�����A���s���ꂽ�B(����)�X���[�K����������s��Ȍ��t�ŏ����܂���A����ׂ�܂��������R������A�������Z��A�V���L�ҁA�]�R���m�ǂ��͂����͂₭���{�֓����A���āA������ƌ��ʂ����A�m���炵�ĐV�������t�A��������Ƃ��������Ƃ����������Ƃ����Ăӂ����я����܂���A����ׂ�܂����ĕ邵�͂��߂��̂ł��遄
����ɂ��Ă��A���t�̋L�҂����ɂ́A�V���L�҂��������钲���ւ̏�M��������B����1�N�̐��E���݂̃X�N�[�v�������Ƃ��Ă����̂悤�ɂȂ�B
�������J������(���G�j�O�@�c��)���������\�����������J���遄��N8��29�����̔��������ɐ��������C����������G�o�Y���u�鏑���^�s���n�l�v�u�L���Ҕ����v���������遄��10��17��������O�A���Ōo�Y�����C�����@����b�v�w�̃E�O�C�X��u��@�����v����11��7�����̔��������ɉ͈�@�������C�����X�F���E�����ȐE���⏑�S�����J�u���ׂč���ǒ��̎w���ł��v�����N3��26�����������쌟�����͐ڑғq���}�[�W������K�Ɓ�5��28�����\�\�B
�V���Ђł��ꂾ���������ΕҏW�ǒ��̓N�r���B����ȊO�ɂ����X�c����@�䕗��Q�̍Œ��Ɂu���p�Ԃŕʑ��v�^�f����A�����{�⍲���Ɣ��l�������R���������u�����v�������s�s�Ϗo�������������B
�×����o�ύĐ��������K����^�f�Ŏ��C�ɒǂ����̂����t�ł���B���̎��͕��t������ɐV���Ђɏ����s���Ă����Ƃ����̂�����A�����ԁA�V���ЂŒ����Ɍg������g�Ƃ��Ă͎������肷��v�����B
���t�͉͈䎖���⍕������Ƃ��A�����12�l�̋L�ҁA�J�����}���������Ƃ����B�u���t�ɂ̓^���R�~������������ł���v�Ƃ����l���������邪�A�����܂ŗ��đ����ɃX�N�[�v�����ƁA�����ł͂Ȃ����Ƃ��킩���Ă���B�܂�A�^���R�~��f�Џ����܂̃`�[��(�v�O�\���l)����Ԃ������ė��t���A�ʐ^���B��A����������邱�Ƃɂ���āA�u�������Ȃ�~�߂Ă����v�Ƃ����M�����ɂȂ��Ă���悤�Ɍ�����B���ꂪ�V���ȏ����ĂъĂ���B���ꂾ���̎�ԂƔM�ӂ�V���Ђ������Ăق����B
�����܂ŏ����ƁA�u���Ⴀ�A���O����Ă݂��v�Ƃ����V���Њ����⌟�@�L�҂����邩������Ȃ����A���͂��������܂��B�u�����ł���B�d����I�グ���Ăł��A����`�����܂��傤�v�\�\�B�@ |
 |


 �@
�@ |
|
���]���ߑY�q�A�{��c���@�ɂ����ۂ�U��u�����Ȃ��L�҂����v 2020/7 |
�u���{�ꋭ�v������ċv�����B�����V���L�҂̖]���ߑY�q���ƕ]�_�Ƃ̍����M���ɂ��V���w�Ȃ����{�̃W���[�i���Y���͕����̂��x�́A���̐����̋���ׂ����͊�Ղ��u���f�B�A�Ƃ̊W�v����`���o���B�����͂����Ƀ��f�B�A���R���g���[�����A���f�B�A�͂����Ɍ��͂ɒǏ]���Ă���̂��B���̍��̒����̐^���B
���L�҂̒����������_���
���܂̋L�҂́A�݂ȑ����Ă��ƂȂ����A�T�����[�}�������i��ł���B�^�ɂ͂܂������ƈȏ�̍s��������̂��ɒ[�ɋ���邠�܂�A��ޑ����Njy���A�{����f���o�����悤�Ƃ���C�����������Ȃ��B
�Z���ꔪ���̌ߌ�Z������J���ꂽ��ł́A�킸����̎O���ԑO�ɉ͈䍎�s�O�@���ƍȂ̈ė��c�������I�@�ᔽ�e�^�őߕ߂��ꂽ�̂ɂ�������炸�A�����ɂ��Ă̎���́A���O�Ɏ���𓊂��Ă��������ЁE�t�W�e���r�����B
�������A�u�����}����U�荞�܂ꂽ�ꉭ�܁Z�Z�Z���~�̈ꕔ�����������Ɏg��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł����̂��v�ƁA�u�Ȃ��v��O��ɂ����U���I�Ȏ���ŁA�́u�C�������҂Ƃ��ĐӔC��Ɋ����Ă���v�Ɠ����������������B
���R�A�L�҂́u�ǂ��ӔC���ʂ�������Ȃ̂��v�u���������Ɍ�t�����g��ꂽ���A��������̂��v�ȂǒNjy���d�˂Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����������Ȃ��B�Y�o�V���͌��@�����ɂ��Ă̎̈ӋC���݂��ANHK�͖k���N�Ή����A���{�e���r�̓|�X�g���{�ɂ��āB���̎���ɓ����邩�����ŁA�͎����̎x���Ҍ����̃��b�Z�[�W�Ƃ���������b�𑱂����B
���^�����Ă��Ă߂܂��������B����c����l�ɂ���K�͂Ȕ����^�f�́A�����j��܂�ɂ݂�厖���B��������l�͑O�@�����B���̎��₪�킸��������o�Ȃ��Ƃ́c�c�B��ɂ��鐭�����L�҂͋^�f�̏d�傳�𗝉����Ă��Ȃ��̂��낤���B�u�ق��ċ��肵�āv�ȂǁA���@������Ɍ��߂����[���ɂ��ƂȂ����]���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B���~��U����Ăł��Njy���ׂ���ʂ������B�L�҂̒����Ԃ�������_����ŁA����͌㐢�Ɍ��p����邾�낤�B
�������ۂ�U��L�҂���
�Ȃ��A���t�L�҉�͍����Ƙ����������^�����ł��Ȃ��Ȃ����̂��낤�B���Ď�̎i��i�s���́A�����Ђ̋L�҂��w�߂Ă����Ƃ����B���݂́A�����I�Ȏi��i�s����t�{�L�̒��J��h��⍲���Ɉς˂Ă���A�u���t�L�҉��Áv�͂��������肾�B���ʁA������@�́g��`(�v���p�K���_)�h�ɗ��p����Ă���B
����ɒ��J�쎁�̎w�������Ă���ƁANHK��e���r�����A���o�V���Ȃǂ����x�̂悤�Ɏw��������ŁA�����V���Ⓦ���V���A�����V���Ȃǂ��w����邱�Ƃ͂܂ꂾ(�����̎Ђ������Ђ̏ꍇ�͏���)�B
���J�쎁���������̋L�҂��w������ƁA�͖��x�A�������p�ӂ����茳�̎�����ǂ݂Ȃ��瓚���Ă���B�������̂Ȃ���������O�Ɋ��@�ɒʍ������Ђ���w�������̂ł���A����͌��͂ɂ��I�ʂƎ��O�Z�{�ł���A���f�B�A�����@�Ɏx�z����Ă���Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B
SNS�����B���A�̃v�����v�^�[�⎑���̓ǂݏグ���o���A�����O�̎s����l�b�g���f�B�A�A�t���[�����X�A���҂���^�����P�𑣂���Ă���B�ɂ�������炸���t�L�҉�́A���O�ʍ��𑱂��A�́u���ŋ��v�̕Ж_��S���A�ӎ����ς��C�z�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��B
���N�ꌎ�A���[������ŁA�������肵�Ă����Ă��Ȃ����Ƃ��������B�������Łu�܂�(���₪)����܂��v�Ɛ����o�����Ƃ��A����Ђ̋L�҂́u�w����Ȃ��Ă��A���͏o�������ƂȂ������āv�ƌ����Ă����B�ʂ̎Ђ̊��@�L���b�v�́u���܂������Ȃ��ƈ����o���Ȃ��B(���Ȃ��̂�)�g�������̉��i���h���v�Ƃ킴�킴�����ɂ����B
������ނɒ������݂Ȃ���́A���̎�ł��������A�������܂������o�����̂��낤���B�����ۂ��ӂ��Ă���̂ɉa�����炦�Ȃ��������Ɍ����邪�A���ƂŁu�H�n���v�Ŏc�тł����炦��u�������v�Ȃ̂��낤�B
�������̃��f�B�A�R���g���[��
�t�L���Ă����ƁA�u���̌�A�O�����������܂��̂Łv�ƈꎞ�ԂŏI���悤�Ƃ��钷�J�쎁�ɑ��A�t���[�����X�≽�l���̐������L�҂����͍R�c�̐����グ�Ă���B���J�쎁�́u���ł��������܂��̂ŁA��Ŏ����Ɏ�����o���ė~�����v�Ƃ��đł������B
���̌�A�����V���ƒ����V���A�����Q���_�C�́A�͈�v�Ȃ̑ߕ߂Ǝ̔C���ӔC�ɂ��Ċ��@���Ɏ�����o���Ă������A���@���̉́u�����̊F�l�ɂ��l�сv�u�ӔC��Ɋ��v�u�^���Ɏ~�ߐ����^�c�ɓ����肽���v�ȂǁA���g�̂Ȃ������앶�������B��̏�ň��{�������悤�ɓ����Ă����Ȃ�A����[������Ȃ����e���B�u�r�߂�̂����������ɂ���v�Ɠ{��ɐk�����L�҂����邾�낤�B
�����A��������N�A���{�����̃��f�B�A�R���g���[���������Ă����������B������[��������A���Ԑ�����w���̕�ɍR�c�̐����グ���A�i��i�s�̎哱����D���Ă���R�����A��̂���������v���悤�Ƃ��Ă��Ȃ������B
���t�L�҉�͐��Ԃ���������������B�I�t���R��ނ��d�����A����`�[������A����L�҃N���u�����݂̈Ӌ`���Ȃ��Ȃ���肩�A����̎�̂悤�Ɍ��͂ɗ��p����Ă��܂��B
���̂܂܂ł͓��{�̃W���[�i���Y���͊��S�ɕ��邱�ƂɂȂ�B�������L�҂͂����Ɗ�@�������ׂ����낤�B
����ȂȂ��A������TV���f�B�A�̕Ɍ��E���������f�B���N�^�[���������S�ƂȂ��ė����グ���l�b�gTV�uChoose Life Project�v�����@���@�����Ă̋c�_����������Œ��A��}�e�}�̊������Ă�ŘA���A�����ȋc�_���s���A�l�b�g��Ő���オ�����̂͌����������B�ǂ������v���ŋc�_��j���[�X�M���Ă����̂��B����ȕl�Ƃ��Ă̍��{�I�Ȏp�����W���[�i���Y���Ƃ��đ厖�ł��邱�Ƃ��Ċm�F�ł����o�����������B�@
��
�������L�ҁ@/�@�V���ЁA�e���r�ǂȂǂŐ�������ɒS������L�҂̂��Ƃł���B�����L�ҁA�����W���[�i���X�g�Ƃ��Ă��B�������͍���(����A���@�A���}�A�����Ȓ�)��S�����A�n�������͎Љ��e�x�ǂ��S������B�������͋L�҂̒��ł��o���R�[�X�Ƃ݂Ȃ���A���E�Ƃ̃R�l�N�V�������g�ɂ����邱�Ƃ�����A��ɐ����Ƃɓ]�g������A�����]�_�ƂɂȂ����肷��P�[�X�������ł���B�������̐V�l�L�҂͂قƂ�ǂ����@�̋L�҃N���u�ɔz������A�̔ԋL��(��)�Ƃ��Đ������L�҂̃X�^�[�g���B�ԂɂȂ邱�ƂŐ����̓�����E�̐l�����w��ł����B�Ԃ�1-2�N�o������Ǝ��͏Ȓ���1-2�N�S�����A���̌�͐��}�S���ɂȂ�L�����A��ς�ł����B |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
 |


 �@
�@ |
|
�@ |
|
 |


 �@
�@ |
 �@
�@ �@
�@

 �@
�@ �@
�@

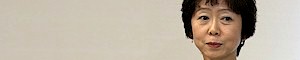
 �@-2/28
�@-2/28 �@3/1
�@3/1 �@3/2
�@3/2 �@3/3
�@3/3 �@3/4
�@3/4 �@3/5
�@3/5 �@3/6
�@3/6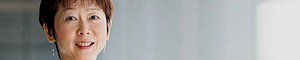 �@3/7
�@3/7 �@3/8
�@3/8 �@3/9
�@3/9 �@3/10
�@3/10 �@3/11
�@3/11 �@3/12
�@3/12 �@3/13
�@3/13 �@3/14
�@3/14 �@3/15
�@3/15 �@3/16
�@3/16 �@3/17
�@3/17





 �@�@
�@�@ �@
�@




 �@
�@ �@
�@



 �}�X�R�~����`
�}�X�R�~����`