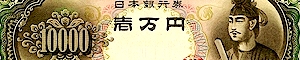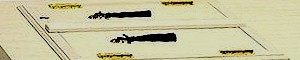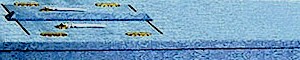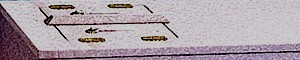|



|
|
●忘れ去られた「財政健全化」 |
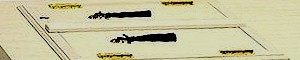

 |



|
|
●財政健全化
|
国や地方公共団体などの公的部門が、歳入と歳出の差である財政収支を改善し、借金(国債などの公債残高)を削減すること。ほぼ「財政再建」と同義語。大きく歳出削減と歳入増加の2手法がある。歳出削減では、公務員数削減などの公的部門のスリム化や、軍事(防衛)費、公共事業費、社会保障費などの削減策がとられることが多い。歳入増加では、消費税をはじめ所得税、法人税などの税収を増やす手法がとられる。単なる増税策だけでなく、アメリカのレーガン政権が採用した減税などによる景気てこ入れで、中長期的に法人税や所得税を増やす手法もある。毎会計年度の財政収支の改善だけでなく、中長期的な歳出の上限設定、計画的な増税策などで財政健全化に取り組むことが多い。国の財政健全化の指標として、歳出を借金でどれくらい穴埋めしているかを示す「公債依存度」、借金にまったく頼らずに税金と税外収入で社会保障や公共事業などの政策経費をどれだけまかなっているかを示す「プライマリーバランス(基礎的財政収支、PB)」などがある。地方公共団体では、借金負担の重さを示す「実質公債費比率」や、一般会計に占める赤字割合である「実質赤字比率」などが目安となる。
日本の財政は、1990年代のバブル経済崩壊後の相次ぐ経済対策と高齢化に伴う社会保障費の増大で、国と地方をあわせた長期債務残高(見込み額)が2018年度(平成30)末で1108兆円に達し、国内総生産(GDP)に対する比率は196%と先進国中で最悪である。政府は2010年の菅直人(かんなおと)政権時代に、財政健全化の目標指標としてPBを採用し、2020年度までに黒字化する目標を掲げた。経済成長による財政健全化を掲げる安倍晋三(あべしんぞう)政権も同目標を踏襲したが、消費税率引上げ時期の先送りなどで達成できず、2018年に、目標時期を2025年度へ先送りする新財政健全化計画を決定した。新計画では、(1)GDP比のPB赤字は1.5%程度に抑える、(2)GDPに対する国債利払い費を加えた財政赤字を3%以下に抑える、(3)GDP比の債務残高は180%台前半に抑える、という3指標を設定し、2021年度に財政健全化の進捗(しんちょく)状況を検証する。ただ内閣府は実質2%程度の成長が続いても2025年度に2.4兆円程度のPB赤字が残ると試算している。
|
|
●プライマリーバランス
|
●財政収支において、借入金を除く税収などの歳入と過去の借入に対する元利払いを除いた歳出の差のこと。そのバランスが均衡していれば、借金に頼らない行政サービスをしているということを表すが、赤字なら後々に借金が増えていることを示す。プライマリーバランスの赤字が続いている限り、それを埋めるために国債発行残高は増加せざるをえない状況が継続する。
●国の財政収支で、国債などの借入金を除いた税収などによる歳入から、国債の元利払い費など、過去の借入金返済に要する経費を除いた歳出を引いたもののこと。この収支が均衡するとは、現世代の国の財源に対する負担と、国の支出による受益とが等しくなることを意味する。財政安定化の指標となる。基礎的財政収支。PB。
●国債費関連を除いた基礎的財政収支のこと。国債の利払いと償還費を除いた歳出(一般歳出)と、国債発行収入を除いた歳入(税収など)についての財政収支。税収で一般歳出が賄われていると、国の懐具合は正常な状態で、これを「プライマリーバランスが均衡」と言う。一般歳出が税収より大きくなると、税収に加えて国債からの収入を充てることとなり、これを「プライマリーバランスが赤字」といいます
●基礎的財政収支。国の財政収支の状況を表わす1つの指標。1)国の収入のうち、国債発行による収入(つまり国の借金)を除いたものから、2)国の支出のうち、過去に発行した国債の償還と利払いを除いたものを比較した場合の収支バランスをいう。 つまり、国債発行に伴う収支は別として、税収入などの本来の収入で、国民のために使われるべき支出(地方交付税交付金、社会保障費、公共事業費、防衛費など)が、まかなわれているかどうかを示す。 プライマリーバランスが赤字の場合、新たに国債を発行することで借金を重ね、将来の世代に負担を転嫁することになる。
●文教、医療・福祉、公共事業、外交・防衛などにかかる行政費用を、借金せずに、税収などの歳入だけでどの程度まかなえているかを示す指標。国の場合、国債などで調達した資金を除いた歳入(税収・税外収入)から、国債の元利払い費を除いた歳出を差し引いて計算する。つまり借金の影響を考慮せずに、単年度の収支均衡がとれているかどうかを示す。基礎的財政収支ともよばれるほか、英語の頭文字からPBと略されることもある。
バブル経済崩壊後のたび重なる経済対策や高齢化に伴う社会保障費の増大で、日本の国と地方をあわせた借金(長期債務残高)は2018年度(平成30)末時点で約1100兆円に上り、国内総生産(GDP)に占める比率は先進国中最悪の約200%に達する見通しである。プライマリーバランスを均衡(歳出と歳入の差をゼロにする)しても長期債務残高が減るわけではないが、均衡した場合、債務は利子率に応じて増える一方、税収も経済成長率に応じて増えるため、かりに利子率と成長率がほぼ同一であれば、債務残高のGDP比率は一定に保たれ、債務残高が雪だるま式に膨らむのを抑えられる。このためプライマリーバランスは財政健全化の目安の一つとされる。
日本はバブル経済が崩壊した1992年(平成4)以降、ずっとプライマリーバランスが赤字である。歴代政権はプライマリーバランスの黒字化を目標に掲げてきたが、ことごとく失敗し、目標年次の延期を繰り返している。1999年に小渕恵三(おぶちけいぞう)政権は経済戦略会議で2008年度までにプライマリーバランスを均衡させる目標を掲げ、2006年に小泉純一郎政権は骨太の方針で2011年度に黒字化する目標を掲げた。しかし日本経済のデフレ進行や世界同時不況の影響で、政府は財政出動を柱とする経済対策を講じたため、2009年に麻生太郎政権は黒字化目標を先送りする方針に転じた。2013年、安倍晋三(あべしんぞう)政権は骨太の方針でプライマリーバランス黒字化目標を2020年度としたが、消費増税時期の先送りなどで、2018年には目標時期を2025年度に5年先送りした。
|


 |



|
|
●財政再建
|
悪化している財政状況を改善させること。主に、政府や地方公共団体の租税など、公的機関の外部性回避について用いられる。
政府や地方公共団体は、その任務を遂行するにあたり支出と徴税等を通じた経済活動を行っており、それが財政である。政府や地方公共団体には、債務不履行や極端なインフレーションの亢進が原因で、国民経済が停滞したり公共サービスを維持できなくならないようにすることが求められる。
|
|
●財政再建に関する指標・理論 |
●プライマリー・バランス
プライマリー・バランス(基礎的財政収支)とは、(税収+税外収入)から政府支出(政策的経費)を指し引いた政府の本業に伴う単年度の収支のことである。プライマリー・バランスが収支ゼロであれば、公共サービス提供のための支出が(税収+税外収入)だけでまかなえることを意味する。プライマリー・バランスの観点から財政破綻リスクを評価する際には通貨の種類を考慮する事が必須である。プライマリー・バランスの赤字を自国通貨建ての負債で賄っているうちは、赤字分の通貨発行をしている事と同じなため、それが財政破綻リスクの増大にはならない。しかし、外貨建てだったりユーロ圏のように自国で発行権を持たない通貨で赤字を賄っている場合は、政府債務が増大すると、それに伴って財政破綻リスクも増大することになる。
●ブランシャールの財政破綻の定義
ブランシャールの定義 - 政府債務/名目GDPを安定的に推移させながら、現在の財政政策態度を維持できるとき、財政は維持可能であるという。政府債務の対名目GDP比の推移を考えればよいとされる。
●ドーマー条件
1940年代に経済学者のE・D・ドーマーによって提唱された、と日本でいわれている条件。名目経済成長率が名目公債利子率を上回れば基礎的財政赤字は維持可能であるといわれる。
●ボーン条件
財政破綻が起こらないための十分条件の一つ。前期に財政が悪化していた場合には、今期はプライマリーバランス規模が改善するように財政が運営されていればよいとするもの。
|
|
●マクロバランスとの関係 |
財政の信認が失われると、国債金利の暴騰・国債暴落が起こり、同時に通貨の信認も失われる。ここで重要な事は通貨の種類である。通貨発行権を持つ政府の場合、自国通貨建ての債務が増加してもそれが返済不能に陥ることはない。しかし、ユーロ圏の国家や、外貨建てで債務を抱えている場合は、徴税や通商取引で債務返済の財源となる通貨を確保するしかないため、債務が巨大になりすぎると国債金利の暴騰・国債暴落が発生する事となる。
エコノミストの村上尚己は「政府部門は、本質的に企業・家計などと全く異なる性質を持っている。一国の経済全体は、政府部門だけで成り立っているわけではない。家計・企業など民間部門の経済行動を合わせて、『国の借金』を考えなければ問題の本質は見えてこない。財政の専門家は、政府部門だけに着目して財政赤字を論じるので、処方箋は税制変更(増税)や歳出抑制だけになる。政府部門の財政赤字の問題は、一国経済全体の広い視点で捉えて、処方箋を考えることができる」と指摘している。村上は「一国経済全体のパフォーマンスは突き詰めれば、民間の経済活動によって決まる。民間主導で経済活動が活発化することによって、政府の財政赤字を減らすことにつながる」と指摘している。
また、社会保障が充実している成熟型社会では、高齢化の進展による社会保障給付の拡大が財政支出を拡大させるため財政赤字が膨らむ。UFJ総合研究所調査部は「成熟型社会では高い成長が見込めないため、制度を工夫しコストを抑制するとともに社会を効率的に運営していく必要がある」と指摘している。
●金利
ある国の財政赤字が金利を上昇させる原因は、長期的に財政状況が悪化すれば国債の償還能力に疑念を持たれ、そのリスクを考慮した金利でなければ、資金を集めることができなくなるからである。経済学者の原田泰は「短期的な財政赤字よりも、長期的な財政状況が金利に影響を与えるはずである」と指摘している。
●経済成長率
経済成長率が低いと税収の伸びは鈍くなる。景気判断は物価変動を除外した実質GDPで見極められるが通常であるが、政府の財政については企業収益・給与ともに名目の指標であるため、実質経済成長率よりも名目経済成長率が重要とされている。税収は名目経済成長率と同じ方向に変化する。GDPが低下すると税収は減少するが、どれだけ減少するかについては、大きく減少するという説とGDPの低下率と同じだけ減少するという説がある。
森永卓郎は「名目GDPがプラスであれば税収は増え、重点配分が可能であり、財政も運営しやくなる」と指摘している。
経済学者の飯田泰之は「名目経済成長率より国債の名目利子率が高い状況である限り、財政は破綻する。つまり、名目経済成長率を増加させなければならない」と指摘している。
エコノミストの米山秀隆は「名目経済成長率と長期金利の関係は、財政再建シナリオを描く場合、極めて重要な要素となる。先進国の歴史をみると、経済が急成長する時期には、名目経済成長率が長期金利を上回っているが、成熟期に入ると名目成長率が長期金利を下回るようになっている」と指摘している。
経済学者の高橋洋一は「2000年代以降の経済協力開発機構(OECD)諸国で年次の長期金利と成長率を419のケースについて、国の数でみると、長期金利が成長率を上回ったのは192(46%)、一方で長期金利が成長率を下回ったのは227(54%)となっている。時期でみると、リーマン・ショック前では長期金利が経済成長率を下回り、リーマン・ショック後では長期金利が経済成長率を上回る国が多かった。結果として、長期金利と経済成長率のどちらが上回るかは、ほぼ五分五分という状況である」と指摘している。
税収弾性値 / 税収弾性値とは、経済成長によって税収がどの程度増えるかを示す値であり、税収弾性値が高ければ、経済成長による税収増と財政再建の効果は大きくなる。GDP1%の変化に対して、税収が1%変化すれば税収弾性値は1となる。
●対GDP比
一般的に主要国の政府債務の状況を見る場合、政府の債務額をその国のGDPで割った数字で評価する。GDPはその国の経済を表したものであり、GDPに対してどの程度の割合の政府債務であるかを確認することで、その国の債務の程度が解る。今年のGDPに対する国債残高の割合を式で表すと、分母が「今年のGDP」、分子が「今年の国債残高」となる。長期的な財政状況は、政府債務を名目GDPで割ったものが適当な指標になる。
経済学者のロバート・シラーは「ある国の債務が、GDP比で100%を超えたら財政は破綻すると考えるのは誤りである。債務とGDPから計算される比率は、純粋な時間を単位とするが、その単位として1年を用いることに必然性はない」と指摘している。
経済学者の田中秀臣はドーマーの公債命題を引用し「公債負担の問題は、国民所得拡大の問題である」「国民所得の増加を維持できれば、公債負担が増加しても財政を懸念する必要はなくなる」と指摘している。
●非ケインズ効果
経済学者のジュヴァッツィ、パガーノの研究によると、財政赤字の急拡大、政府債務残高の対GDP比率が高い水準にある、といったように財政が不健全な状態では、大胆な財政の引き締め策が人々の将来への不安を打ち消すことになり、それに関連した効果で現在の民間の消費などが拡大・刺激されGDPの落ち込みを防ぐ可能性もあるとしている。これは「非ケインズ効果」と呼ばれ、1980年代以降、デンマーク・アイルランドなどでこのようなことが観察されたとされている。
大和総研は「『非ケインズ効果』は、政府支出を抑えて金利上昇を抑制し、景気にプラスの効果を与えるとされている」と指摘している。
経済学者の若田部昌澄は「スウェーデンは非ケインズ効果の代表例としてよくとりあげられるが、スウェーデンの景気回復を支えたのは、通貨危機による為替の大幅な切り下げである。クローネ安で輸出が伸び、企業の景況感がよくなったため、それが投資が増加させ消費に向かったのである」と指摘している。
増税によって可処分所得が減少し、消費が減少することを「ケインズ効果」という。
●インフレ課税
インフレーションになると、現金価値の低下によって政府債務が減少し、課税と同じような効果がある。通貨を発行すれば、シニョリッジが国庫に収入として帰属し、直接徴税をしているかのような効果が生じる。これらを「インフレ課税」という。
エコノミストの山崎元は「財政支出もインフレに連動するため、財政支出を同じように拡大させてしまえば財政収支は赤字のままとなってしまうが、過去のストックベースの財政赤字は実質価値が減価していく」と指摘している。山崎は「インフレは実質的に、現金及び現金の同等物の保有者に対する課税である」と指摘している。
経済学者のトマ・ピケティは「財政についての歴史的な教訓としては、1945年のフランス・ドイツは対GDP比で200%の公的債務を抱えていたが、1950年には大幅に減少した。それは債務を返済したわけではなく、物価上昇が要因である。物価上昇なしに公的債務を減らすのは困難である」と指摘している。
田中秀臣は「『インフレ課税』は財政危機を回避する有効な手段となる。結果としてインフレ課税が生み出されるような穏やかなインフレ政策が、財政問題の解消に必要となる」と指摘している。
経済学者のケネス・ロゴフは「世界の主要中央銀行は、穏やかにインフレを高進させることが巨額の債務から逃れる上で有益であることを認識すべきである」「原則的に言えば、インフレは債務問題を解決する公正な方法とは言えない。短期的で穏やかなインフレ高進(例:2年間で6%程度)では、債務問題を解決することにはならないかもしれない。しかし、債務負担を軽減させ、他の手段を取るコストを減らすことができる」と指摘している。
7-8%の高いインフレ率を起こすことによって、国・企業が抱えている借金を目減りさせることを「調整インフレ」という。
|
|
●方法 |
財政を好転させるには、収入(歳入)増・支出(歳出)減かの二通りの方法があり、また負債の価値そのものを目減りさせる方法がある。
●収入(歳入)を増やす
景気回復による税収増
増税
通貨発行によるシニョリッジ
(地方の場合)国からの給付金や補助金の金額を増やす
税金以外の収入源(施設使用料や手数料収入など)を確保する
資産の売却
●支出(歳出)を減らす
事業の削減(例:特殊法人の廃止、民営化、公共事業の削減など)
事業単価の削減(例:民間委託を進める、入札・契約方法の改善など)
人件費の削減(例:公務員の数の削減、公務員の待遇を民間並みにするなど)
借入金(国債など)の利率を低く保つ
●負債の価値を目減りさせる
国債の金利が上昇した(時価が下がった)時の買い戻しもしくはスワップ
インフレーション(インフレ税)による実質的な負債の目減り
エコノミストの片岡剛士は「財政再建には、経済成長、歳出カット、増税のいずれかの選択肢しかない」と指摘している。経済学者の岩田規久男は「財政破綻を回避するためには、歳出の大幅削減、増税、中央銀行の国債引き受けのいずれかしかない」と指摘している。田中秀臣は「中央政府が深刻な財政赤字に直面した場合、これらをファイナンスする方法は、1)公債発行による借り入れ、2)貨幣発行による貨幣発行益(シニョリッジ)を得る、の2つしかない」と指摘している。
政治経済学者のアルベルト・ アレシナ、経済学者のロベルト・ペロッティらの研究によれば、OECD諸国で財政再建に成功したケースでは、プライマリーバランスの改善に対し、歳出削減の寄与が72%・増税の寄与が28%(歳出削減7:増税3)が黄金律になるとしている。アレシナは、財政再建に成功した国は、歳入拡大より歳出削減に力を入れていたのに対し、財政再建に失敗した国は、歳出削減より歳入拡大に力を入れていたとしている。
高橋洋一は「1960年以降のOECD加盟国の事例では、名目経済成長率を高くしたほうが財政再建に成功している」と指摘している。
原田泰は「増税してもそれを使ってしまっては財政再建はできない。財政再建のためには、税収を増やすと同時に歳出を抑制しなければならない。財政再建のために必要なのは、歳出と歳入の差、財政赤字を小さくすることである」と指摘している。
トマ・ピケティは「19世紀にイギリスの公的債務は対GDP比で200%の水準になったことがある。19世紀のイギリスは、歳出削減によって公的債務を減らすというオーソドックスなやり方で危機を乗り越えた。ただし、解決に1世紀を要した上、教育への投資を減少させてしまった。これは、今(2015年)の日本・欧州が『同じ轍を踏まないように』と考えさせる重要な教訓である」と指摘している。経済学者の竹中平蔵は「借金を増やさず地道に経済を成長させていけば、借金の額は減らないが所得に対する相対的な負担は軽減されていく。ナポレオン戦争後のフランスや第二次世界大戦時のイギリスもそうやった」と指摘している。
経済学者の岩田規久男は「歳出については、費用便益分析を取り入れ、費用が便益を上回るものは採用せず、便益が費用を上回るものから優先して実行すべきである」と指摘している。
森永卓郎は「収入を増やさず財政を切り詰めれば、経済規模は縮小し、借金だけが残る」と指摘している。
UFJ総合研究所調査部は「財政支出の削減・増税は、景気を悪くする要因となりうるため今の世代には不人気の政策となる。そのため、現在世代の利益を代表する政治家は、歳出拡大・減税に傾きがちとなる」と指摘している。
ケネス・ロゴフは「政府は過度に増税に依存することは避けなければならない。過重な増税は経済成長に悪影響を及ぼす。増税と歳出削減のバランスを取ることが好ましい」と指摘している。
|
|
●原因と責任の所在 |
行政機構は放っておくと、より一層膨張していくといわれており、歴史学者・政治学者のシリル・ノースコート・パーキンソンは「役人の数は仕事の量と無関係に一定の割合で増えていく」と説いている(パーキンソンの法則)。組織が大きくなれば、財政支出も拡大するため財政構造が悪化する。
経済学者のジェームズ・M・ブキャナンは著書『公共選択』で「民主主義はおカネを増やす方向には容易に働くが、政府のおカネを減らす方向には容易に働かない。従って、民主主義には、財政赤字を増大させる構造的な欠陥が内包している」と指摘している。
伊藤元重は「理論的には、発行された国公債は景気が好転したときに償還することで、解消することが可能であるはずであるが、現実的には、多くの国において政府に対する過度な支出の期待が大きく、政府は慢性的な財政赤字に陥ることが多い」と指摘している。
スティーヴン・ランズバーグは「債務自体は課税と比較して良くも悪くもなく、歳出をどう賄うかよりもまず歳出の水準・中身に関心を向けるべきである」と指摘している。ランズバーグは「巨額の財政赤字が有害であるという主張と同じ理由で、高水準の支出が有害であることは疑う余地はない。財政赤字の最も有害な点は、政府支出を管理するメカニズムを見つけ出すという問題から、人々の関心をそらすことなのかもしれない。この問題が解決できなければ、均衡予算に対するこだわりは何事もを解決してはくれない」と指摘している。
|
|
●財政再建に関する議論 |
●日本政府
●財政再建に対する批判
●政府の財政赤字と民間の財政黒字
現代貨幣理論によれば、定義上、政府の財政赤字は民間部門の富を創り出す源であるから、政府が財政を黒字化させると民間部門の富が吸い取られてしまう。例えば政府部門と民間部門だけの世界を考え、 初期状態で両部門ともに1000ドル所持していたとする。現実には中華人民共和国など海外部門の収支も考える必要があるが、ここでは無視する。すると、政府は財政黒字となり、民間は赤字となる。一方、政府の財政赤字は民間部門の黒字となる。従って、政府が債務を拡大させれば民間の富も拡大していくことになる。そして政府は永続的に財政赤字を拡大させることができる。なぜならば家計と違って政府はお金を創り出すことができるからである。すなわち、米国財務省は米国債を発行し、FRBが速やかにそれを買い取るのである。米国市民や企業に税を課したり、米国市民や中華人民共和国からお金を借りる必要は無いことを意味する。
●政府の財政赤字とインフレ
現代貨幣理論では、そもそも失業率が高いときには貨幣の創造はインフレには結びつかないと考えられている。金本位制の時代には、高い失業率の状態では金の発掘は生産性の向上と雇用の創出につながった。 そして現代的な貨幣システムは、金の発掘がマネーサプライに直接影響を及ぼしていたような金本位制とは大きく異なる。 中央銀行が実体経済にお金を注入する基本的手法は公衆から国債を買い取ることだが、国債買い取り自体は「自発的な取引」である。というのも国債を保持する公衆が国債を売るよう強制されるわけではないからである。
オリヴィエ・ブランシャールとスタンリー・フィッシャーは、財政赤字の大きさとインフレ率との間に強い正の相関がみられることはあまりないと指摘している。また、1970年代から80年代初期にかけて米国が経験したインフレは、OPECが原油価格の引き上げを狙って産油量を減らしたことにある。マネーサプライは上昇したが、あくまで原油供給減少に引き続いて起こったのであって、マネーサプライ上昇自体が直接物価上昇につながったわけではなかったという反論が存在する。
ノーベル賞経済学者ジョセフ・スティグリッツは、インフレはその抑制に多大なコストがかかるという説自体に懐疑的であり、また中央銀行の独立性が必要だとする説も神話であると述べている。
●自国通貨建て国債
中野剛志は、政府は通貨発行権を持っているので、国債は自国通貨建てである限り、そして政府に返済の意思がある限り、いくら発行しても、債務不履行になることはあり得ないと主張している。その理由は以下の通りである。国債の償還の財源は税金である必要はなく、国債の償還期限が来たら、新規に国債を発行して、それで同額の国債の償還を行う借り換えを永久に続ければよい。財政赤字はそれと同額の民間貯蓄を創出するので、民間部門の貯蓄は財政赤字の制約にはならない。財政赤字の制約を決めるのはインフレ率であり、インフレになりすぎたら、財政赤字を拡大してはならない。デフレだということは、財政赤字が少なすぎる。デフレである限り、財政赤字に制約はない。
|
|
●日本の事例 |
●中央政府
日本国政府は、多額の国債を償還するべく財政再建に努めている。
1981年 - 鈴木善幸内閣による「増税なき財政再建」
2001年-2006年 - 小泉内閣による「聖域なき構造改革」
2009年- - 行政刷新会議による「事業仕分け」
●地方自治体
国内の自治体のほとんどは財政再建に向けた努力をしている。巨額の法人税などで潤っているはずの都市部の自治体でさえも、歳出削減などの努力は進めている。
財政再建団体 / 福岡県赤池町 / 北海道夕張市
神奈川県
大阪府
北海道
岡山県 神奈川県と大阪府はともに、財政再建団体指定を取り沙汰されたことがある。その後の景気回復による増収などで危機的状況は免れたものの、2012年現在も財政状態を好転させるための努力を推進している。
北海道は道経済の低迷とともに財政の悪化が進んでおり、数年後には毎年の財政赤字が数百億円に達するとの観測もある。 |


 |



|
|
●財政健全化法の制定を 2000/2 |
わが国の財政状態は、まさに危機的状況にある。99年度末の国および地方の長期債務残高は608兆円、対GDP比で122.7%に達する見込みである他、フローの財政赤字も99年度の二次補正後では、同▲10.7%(実績見込み)と主要先進国中最悪である。このような数字は、将来の財政破綻が単なる懸念ではなく現実味を帯び始めていることを示唆しており、早晩日本国債の格下げとこれに伴う長期金利の急騰という形でマーケットが警告を発し、景気腰折れにつながりかねないとの懸念が指摘されている。
こうしたなかで、今や財政赤字問題は、衆議院選挙を控えて最大の政治の争点となりつつある。小渕首相は、「景気と財政再建の二兎は追わない、当面は景気回復に全力を尽くす」と発言しているが、野党のみならず自民党内部からも反発が高まっている。財政再建を急ぐあまり景気を失速させた橋本前政権の二の舞は避けたいという気持ちは理解できる。しかし、現時点で将来の財政赤字の膨張懸念を払拭するために何の対応も採らないで良い筈はない。過去2年間の財政大盤振る舞いの最大の問題点は、単に財政赤字が危機的水準にまで膨張したことだけではなく、国民全般にモラルハザードの蔓延と構造改革先送りの機運を植え付け始めていることにある。最近の政治主導による児童手当など福祉ばらまきやペイオフ解禁1年延期は、弱者の一律保護からチャレンジへの支援という政策理念の転換とは到底相容れない護送船団方式への逆戻りと言わざるを得ない。日本経済の自律的かつ持続的成長を図るためには、今こそ構造改革の推進と財政健全化に向けて日本丸の舵を切り替えるべき時である。
それでは、財政健全化に向けていかなる取り組みが必要であろうか。この問いに答えるためには、財政の膨張をもたらしてきた主要因が何かを改めて分析する必要がある。
第一は、公共投資の拡大である。バブル崩壊以降の景気対策の総額は120兆円を超える規模に上ったが、この結果として、年々の公共投資の規模は40兆円を超え、その名目GDP比率はバブル崩壊前の6%台半ばから2%ポイント上昇し、8%台半ばに膨張している。この水準は、米英独仏主要先進国平均(2%強)の4倍以上のレベルであり、このような高水準の公共投資が将来的に持続不能であることは、誰の目にも明らかである。
第二は、社会保障給付費の膨張である。国民皆年金・皆保険制度の下で、年金・医療などの社会保障給付は、過去一貫して経済成長の伸びを上回って推移してきた。97年度の社会保障給付費は、69.4兆円と名目GDP比で13.7%と「福祉元年」が叫ばれた73年(6.3兆円、同5.4%)の11倍以上、90年(47.2兆円、同10.8%)対比でみても1.5倍に膨らんでいる。こうした手厚い社会保障制度は少子・高齢化が急速に進展するなかで、もはやサステイナブル(持続可能)ではないことも自明である。
第三は、大幅な税収不足である。これは、景気低迷に伴う循環的な要因と経済再生を目指した大型制度減税(法人・所得税)の双方の要因が重なっている。一般政府の財政バランスがほぼ均衡していた90年度と99年度を比較すると、国税収入が▲14.4兆円(うち制度減税要因▲6.8兆円)と名目GDP比▲2.9%に達している。いずれにしても歳入と歳出のバランスが著しく失衡していることは、一国の円滑な財政運営という観点からは問題が大きい。
以上のようにみると、市場の財政破綻懸念を払拭し、国債の格下げや長期金利の急上昇を回避するためには、公共投資システム・社会保障制度・歳入構造の3分野にわたる抜本的な改革を核とした財政健全化への取り組みが不可欠である。
第一に、公共投資については、中期的な観点から他の先進諸国並の水準(名目GDP比3%以下)にまで削減することを目標に掲げるべきである。そのためには、年平均7.2%、向こう10年間で約5割強の削減が必要と試算される。これを実現する具体的な方策として、(1)公共投資は原則的に国家的なプロジェクトに限定し、地方への補助事業はPFIに切り替える形で段階的に削減する、(2)地方単独事業は地方の再生にとって真に必要なプロジェクトに限定し、地方の自主的な判断と財源調達に基づき実行する、(3)過度の分離・分割発注から公共事業の非効率化を招く温床となってきた官公需法を廃止する、などの措置が不可欠である。このような改革は痛みを伴うものの、政治と密接に結びつく形で実施されてきた公共事業のバラマキを是正する意味で極めて重要な改革である。
第二の社会保障制度改革については、これまでの延長線上の発想を超えた大胆な改革をしなければ、少子・高齢化が急速なスピードで進むなかで、給付費の抑制はおぼつかない。社会保障給付(年金・医療・福祉その他)の伸びは、1950年度以降97年度までの47年間の年平均で14.4%増、バブルが崩壊した90年代以降に限っても同5.6%と同期間の名目経済成長率の伸びを上回って推移してきた。それでも97年度時点で、国民所得に対する比率は17.8%とアメリカ(18.7%)、イギリス(27.2%)、ドイツ(33.3%)、フランス(37.7%)、スウェーデン(53.4%)などと比べて最も低いレベルにとどまっている。しかし、わが国の高齢化率(65歳以上人口比率)が現行(97年)の15.7%から2025年には27.4%と現在のスウェーデン(17.4%)を10%ポイントも上回ることを考えると、現行制度の大枠を維持したままでは、現在36.9%に止まっている国民負担率の50%以上への急激な上昇と国庫負担の増大による財政赤字の歯止めなき膨張は必至である。このような想像を絶する厳しい状況を回避するためには、原則として、社会保障給付費の伸びにキャップをはめ、国民所得比率の上昇を極力抑制する制度改革が必要である。そのためには、年金・医療・介護の各分野ごとにキャップを設定し、それを超える可能性が高まる場合には、翌年度以降、給付の抑制・削減または新たな財源確保を義務づけるよう法定(または、国会決議)するなどの措置が不可欠である。キャップのレベルは、65歳以上の老齢人口の伸び率に合わせ、伸びの上限を当初4%程度に設定し、段階的に2%以下に抑制することが望まれる。このような改革は、公的な社会保障の対象範囲をナショナル・ミニマムに限定し、個人の自己責任・自助努力をベースとした制度を構築するという社会保障にかかわる基本理念の抜本的転換なしには実現し得ないものである。
第三の歳入構造面での対応をどう考えるべきか。ここでは、2つのケースを想定した。まず、上述したような公共投資の削減や社会保障給付の抑制をしない場合(10年間の一般歳出の伸びを年平均2.5%と想定)、10年後の財政赤字の対名目GDP比率を一定の前提(名目成長率3.5%、税収弾性値1.1、長期金利3%)を置いて試算してみると、同比率は10年後も▲8.2%と高水準を維持すると試算される。仮に、同比率を▲3%以下に引き下げるとすれば、年平均36兆円(消費税率換算10.3%)もの追加財源が必要となる。これは経済活力維持の観点からは、非常な困難が伴う。そこで、先に述べた通り、(1)公共投資を向こう10年間で5割強削減する、(2)社会保障給付の伸びを段階的に2%以下に抑制することによって、一般歳出の伸びをトータルでゼロ以下に抑制するケースはどうか。その場合には、財政赤字比率は▲5.0%まで低下するが、それでも赤字を▲3%以下に低下させることを目標とすれば、年平均13.8兆円(消費税率換算4.0%)と財政健全化のためには相当規模の税収確保が必要との結論が導かれる。いずれにしても、中期的には少子・高齢化のコストを国民全体で広く薄く負担を分かち合うことが不可欠であり、今のうちから国民的な議論を深めていく努力が必要である。
以上のような方策の実効性を高めるためには、財政健全化に向けた取り組みに対して法的強制力を持たせる必要がある。その場合、橋本前政権下で立法化され現在凍結中の「財政構造改革法」をそのまま復活させるのではなく、同法の構造的欠陥を是正した新たな「財政健全化法」を制定することが望まれる。
第一に、財政健全化法の基本的精神として、経済の再生を通じて財政の健全化を実現する旨を定める必要がある。橋本前政権の失敗は、財政再建が自己目的化してしまった結果、硬直的な財政再建目標の設定とその運営に関しても景気の動向にかかわりなく一律かつ硬直的な歳出削減を目指したことから、非効率な資源配分が是正されなかったばかりか、景気悪化を招来し、かえって財政状況を悪化させてしまったことにある。このような失敗を教訓とすれば、まず財政健全化は経済の再生を通じて中期的に実現させるという基本スタンスに基づき、景気が自律回復軌道に乗った後、健全化を10年間で達成することを目標とすべきであろう。そうした観点からは、5 5年程度の中期経済・財政見通しを作成し、これをベースに中期的な視野から財政運営を行う、すなわち財政の単年度主義を改めることが肝要である。さらに付言すれば、景気が循環的な回復局面に入りつつある現時点では、必要最小限の景気への配慮を行いつつも、財政運営は景気の本格回復が始まるまでは基本的に中立型を維持すべきである。将来的に景気後退に陥るような局面では、一時的な法の効力停止条項を盛り込み目標年次の再設定が可能となるような弾力的対応も当然必要となろう。
第二に、何を健全化のメルクマールとするかであるが、フローの赤字が対GDP比で上昇しないためには、第一段階として国と地方のプライマリー・バランス(歳入から公債の発行額、歳出から利払い・償還額を除いたベースの財政赤字)の均衡化を目指す必要がある。99年度(2次補正後)のプライマリーバランスを試算すると、国が11.2兆円、地方が10.4兆円、トータルで21.6兆円(名目GDP比▲4.3%)にも達する。プライマリーバランス均衡化の実効性を高めるには、法の拘束力が国の一般会計予算のみならず決算や地方財政計画・決算にも及ぶようにすることが重要である。橋本政権下の「財政構造改革法」がザル法と言われたゆえんは、法の拘束力が一般会計当初予算のみにしか及ばなかった点にある。プライマリーバランスの均衡化を達成した後は、第二段階としてストックの赤字削減目標(例えば、長期債務残高の対GDP比100%以下)を設定することが有効と判断されるが、ストックベースで赤字を減らしていくには、現在、国と地方合わせて総額31.2兆円(名目GDP比6.2%)にも上る公債費(償還・利払い費)の圧縮が不可欠である。とくに、国債の利払い費は過去14〜15年間にわたって10兆円以上の規模に膨張しているが、長期金利が名目成長率を上回って上昇すると、国債費が発散してしまいプライマリーバランスを均衡化させても全体の赤字は改善しないという深刻な事態も予想される。これを回避するには、国債の発行年限の多様化・短期化をさらに進め、(1)借換債も含めた新規発行については原則5年以下の中短期債で行う、(2)60年償還ルールの短期化により、現金償還を進める等の措置を通じて利払い費を抑制する必要がある。国債と地方債の発行残高は総額462兆円に達しており、この利払い負担が1%低下するだけで、4.6兆円(名目GDP比0.9%)もの赤字削減が可能となる。こうした措置は、財政赤字が深刻化したアメリカでも採用され、成功を収めている。
第三は、景気が本格回復軌道に乗るまでのここ1〜2年間で、前述した公共投資、社会保障、歳入構造の抜本改革への道筋を付けておくことである。これができなければ、財政健全化は絵に描いた餅に終わりかねない。これらの改革を三位一体で行うことを大前提としたうえで、公共投資のような裁量的支出は、毎年何%削減といった硬直的な運営ではなく、その時々の景気の動向に応じた弾力的な対応ができる余地を残しておくと同時に、一定規模以上には増大しないようキャップをはめる工夫が必要である。他方で、社会保障給付を含めた義務的支出に関しては、アメリカの93年包括財政調整法で採用されたいわゆる「Pay-as-you-go条項」の導入により、目標を上回る歳出増加に対しては、増加分と同額の増税または他の歳出削減を義務づけるなど財政赤字抑制の制度的メカニズムをビルトインしておくことが必要不可欠である。連邦財政の黒字化が実現しているアメリカの経験に照らせば、経済再生・歳入構造の改革による税収増加と財政規律を強力に担保する法的枠組みの双方が相まって初めて財政健全化の達成が可能となる。
以上のような「財政健全化法」は、遅くとも本年中を目処に法制化する必要がある。実際の健全化法に基づく財政運営は、信用保証協会による保証期間の終了やペイオフ解禁など経済の異常事態が終結する2002年4月をもって発効することとし、それまでの間は、上記3つの制度改革を徹底的に推し進めることが重要である。2000年度予算成立後の最優先の政策課題は、与野党が一致協力して中期的な財政健全化の道筋をしっかりとつけ、「市場の反乱」を未然に防ぐことにあるといえよう。 |


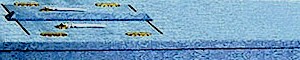 |



|
|
●財政再建最優先でよいのか 2001/4
|
●はじめに
わが国の経済政策をめぐる議論は混迷している。政策目標として、景気回復、財政再建、構造改革の三つをあげることに異論はないであろう。問題はその優先順位であり、とくに議論が分かれるのは、財政再建を優先すべきか景気回復が先かである。
こうした議論で常に問題になるのが、わが国の巨額の国債発行額や発行残高である。また、額そのものの大きさだけでなく、アメリカやEUとの比較からわが国財政の危機的状況を糾弾する声は内外に多い。こうした声を背景に強く求められているのが、財政再建の最優先である。しかし、景気の低迷やデフレが再び危惧される昨今、財政再建に一意専心、着手するのは賢明な選択であろうか。
わが国の財政赤字を放置することはできないが、その危機に対する警鐘にはいささか誇張があるように思われる。そこで以下ではまず、昨今の財政再建最優先論を三つに分類して整理し、次いでわが国の財政赤字や国債残高の現状を考えるうえで念頭におかれるべきいくつかの事実を指摘する。さらに、財政再建と景気対策をどのように順序付けるべきか、あるいは財政再建と構造改革との関連についても考えてみたい。
●財政再建最優先論の拠りどころ
わが国の財政赤字や国債発行残高の現状をまず整理しておこう。平成12年度の一般会計国債発行額は32.6兆円、国債依存度38.4%にのぼる。年々増加傾向をたどってきた結果、平成12年度末の国債発行残高は364兆円、その対GDP比は73%にも達すると見られている。国債以外の借入金等も加えた長期政府債務残高では数値はもっと大きくなり、平成12年度末対GDP比は97.1%に達するという。このほか地方自治体の債務を加えると深刻さはさらに増す。このようなわが国政府の債務状況を他の先進諸国との比較で見れば次のとおりである。平成10年度のわが国の長期政府債務残高の対GDP比 は82%(平 成12年 度97.1%)である。これに対し同年度アメリカ56.5%、イギリス44.8%、ドイツ24.7%、フランス28.3%と、わが国の数値はたしかに際立っている。こうした数値やこれらにもとづくシュミレーションによって、わが国の財政再建の必要性が叫ばれているが、問題は財政赤字や国債残高累積のどのような弊害に注目するかである。ここでは財政再建を現在の最優先課題とする議論を、その論拠によって三つに分類してみよう。
まず第一は財政破綻論であり、国債依存による赤字財政の持続可能性や国債残高の返済可能性を問題にする立場である。今日のわが国のような赤字国債による財政運営は、早晩、財政破綻さらには経済破綻を招くと見る。当否は別として、こうした立場でよく用いられるのが、年収600万円のところを毎年400万円の借金によって、1000万円の支出を続ける放漫家計のたとえである。予期せぬ巨額の収入でもない限り、このような家計はかならず破綻する。歳出削減の困難さや金利支払いを含む国債費の増額によって年々の財政赤字とともに国債残高が拡大していくと、年々の財政支出に占める国債費の割合が上昇し、いわゆる財政硬直化が進む。遅かれ早かれ国債に対する信頼は失われ、金利の暴騰を招き、国債の市中消化に困難をきたす形で財政運営がゆきづまると見る。
第二は対外弊害論である。わが国の財政赤字、国債残高の大きさは、他の先進諸国からの厳しい視線にさらされ、わが国経済の評価を低下させている。それは国際資本市場における日本企業の格下げにつながり、さらには資本調達コストを高めるなど企業の国際的な競争条件の悪化を、この立場は危惧する。
海外からこうした厳しい視線が送られるのはなぜであろうか。一つは、わが国の財政危機が顕在化すれば、わが国経済のみならず、世界経済全体に甚大な影響を及ぼすからである。しかしより重要なことは、近年先進諸国で財政赤字に対する考え方が変化してきたことである。アメリカ財政の黒字転換はよく知られているが、欧州諸国もEU発足を機に財政収支改善に努めてきた。公的部門といえども市場の評価が無視できなくなり、財政赤字は国際的に従来よりも厳しい目で見られる傾向にある。わが国の財政運営は、そうした国際経済の世論動向に逆行していると見る。
第三は構造改革阻害論である。これは、現在の赤字財政運営あるいは巨大公共投資の継続が、将来の生産力向上、活力維持のための民間の努力を阻害すること、つまり焦眉の課題である構造改革の遅延や先送りにつながるとする立場である。不況対策として採られる公共支出の拡大が、企業の改革へのインセンティブを弱め、縮小すべき産業や退出すべき企業を延命させることで「日本的経済システム」の改革が阻害されるからである。
この議論の背後には、クラウディング・アウトがもたらす金利の上昇、それにともなう民間投資の抑制を強調する議論がある。財政赤字が資金市場において民間の資金需要と競合し、その結果、金利が上昇し民間投資が「押し出」される。この面でも新産業の誕生や新企業の設立が阻害され、「大きな政府」の弊害が顕在化する。そして将来の生産力向上につながる民間投資の抑制、資本蓄積の阻害は将来世代への負担要因となるとみなすのである。
●財政赤字の別な見方
わが国の財政赤字、国債残高が現在なぜ憂慮され、早急な対策の必要性が叫ばれているかを見てきた。たしかに財政赤字を放置できないが、財政再建を唯一最重要の政策課題であるというわけにはいかない。あくまでも重要課題の一つと理解すべきである。わが国の財政危機に対してなされる最近の警告は特定の面が強調されすぎているように感じる。同じ危機ではあっても、少し視点を変えることで深刻さの度合は変わる。ここではわが国の財政赤字や国債残高に対するそうした視点をいくつかあげてみたい。
現在、国民の抱く不安の一つとして、巨額の国債返済負担の将来世代への転嫁がある。これは国債発行世代の死後、次の世代に対する増税によって国債の償還がなされる場合に生じるもので、負担の孫子への「つけ回し」としてしばしば話題になる。しかしこうした負担は世代の残す遺産や年金、社会保障その他を通じての負担や恩恵との兼ね合いで考えなければならない問題である。たしかなことは、日本のような内国債の場合、発行時においても、償還時においても国内で利用可能な資源の量に変化があるわけではないということである。マクロ・レベルでは、この意味での「負担の先送り」は生じえないのである。したがって先にあげた借金を続ける放漫家計のたとえは当たらない。この放漫家計は借金の返済には将来、家計の消費支出を削減せざるを得ないのに対し、内国債の返済の場合、国民全体の消費支出を減らす必要はないからである。たとえとしては内国債の場合、家族内での貸借に近い。
わが国の国債は内国債であり、政府の自国民に対する債務であるが、同じ国債でも外債つまり対外債務となると話は違ってくる。対外債務は外国民に対する債務である。この間にどのような差があるかといえば、内国債の償還は資源の自国内での移動であるのに対し、対外債務の返済は資源の海外への流出であり、その分自国民の可処分資源の減少を意味する。対外純債務を負うことそのことはかならずしも不健全とはいえないが、それが将来の生産力として結実しない場合は、確実に国民の負担としてのしかかる。
対外経済の観点からつけ加えるとすれば対外決済能力の問題である。国債残高の累増にともなう対外威信の低下を指摘する向きがあるものの、経常収支の大幅黒字に加えて、わが国は世界第一位の対外純資産と外貨準備を擁している。平成9年の東アジア通貨経済危機のようにわが国の対外決済能力に支障が生じるとの危惧はほとんど杞憂に近い。
前述の三つの財政再建最優先論の根拠として共通するのは、金利水準や動向がきわめて重要な鍵を握るということである。破綻の到来時期、財政硬直化の度合、あるいは民間投資抑制やそれにともなう将来への負担、いずれについてもそれが妥当する。しかしこの点について、金融安定化に対する政策措置もあって、国債を含むわが国の金利水準はきわめて低い。この低い金利水準で現に国債が市中消化されているため、政府の金利負担は国債残高と比較して意外に低い水準にとどまっていることは注目に値する。国債利払費は平成6年度から12年度までほぼ10.7兆円で一定の水準を維持している。また一般会計に占める国債利払費の割合で見ると、平成6年度の14.5%から12年度の12.6%までわずかながら低下傾向を示している。因みにこの間の利払費の対GDP比は、2.2%程度でほとんど一定している。
こうした数値の国際比較を試みよう。平成10年度の利払費の一般会計に占める割合あるいは利払費の対GDP比はそれぞれ日本の12.8%、2.2%(平成12年度12.6%、2.2%)に対し、アメリカ14.6%、2.8%、イギリス8.6%、2.5%、ドイツ12.3%、1.5%、フランス5.3%、3.0%で、日本の数値はかならずしも悪くない。
また、政府の債務状況の国際比較は、債務のみの比較でなく、金融資産・負債の純額で行うべきかもしれない。平成11年、日本の一般政府の金融資産411兆円に対し、負債625兆円、純額214兆円の負債であり、その対GDP比は43.2%である。これは、アメリカ48.8%よりは良く、ドイツ42.3%とほとんど同レベル、イギリス37.1%、フランス35.3%に比べて若干劣るといった程度である。
●マクロ・バランスから見た政策課題
それでは、財政再建や景気対策、構造改革を現在の政策課題としてどのように位置づければよいのだろうか。それには意外にもマクロ経済学の原点に立ち帰るのが有効である。国民経済計算の初歩的な議論から導出されるマクロ・バランスの考え方に沿って考えてみよう。それによれば、一国の財政赤字、貯蓄超過、経常収支の間には常に次の恒等関係が成立する。
貯蓄超過≡財政赤字+経常収支
ただし上式はこれら三者の間の因果関係を示唆するものではない。これを現在のわが国のケースにあてはめると、大きな財政赤字と大きな経常収支黒字があり、両者の合計に相当するさらに大きな貯蓄超過が存在するということである。平成11年の数値で495兆円のGDPの下で、41兆円の財政赤字と11兆円の経常収支黒字は必然的に52兆円の貯蓄超過の存在を意味する。
こうしたマクロ・バランス恒等式から、われわれは日本経済の現状と政策課題について次のようなメッセージが読みとれる。まず第一に、財政再建つまり財政赤字の縮小は、経常収支黒字の拡大か貯蓄超過の縮小、あるいはその両方があってはじめて可能になるのである。かりに経常収支は不変であるとしよう。この場合、財政赤字の縮小には貯蓄超過の縮小が不可欠である。その場合、貯蓄超過の縮小が投資の拡大で実現すれば問題はないが、日本経済の現状では、産出水準や所得水準の低下にともなう貯蓄の減少によって実現するであろう。それは不況やデフレの深刻化以外の何ものでもない。
日本経済の場合、事情は逆で、「はじめに貯蓄超過ありき」である。この大きな貯蓄超過の下で、産出水準や雇用水準を維持するには、財政出動が必要であり、財政赤字が不可欠であったのである。この意味で、これまでの財政出動がクラウディング・アウトによって民間投資を縮小したとは考えられず、とくに貯蓄拡大の原因になったとは考えにくい。それどころか、それがなければ確実に景気の落ち込みははるかに大きかったはずである。低い金利水準が何よりもそのことを如実に示している。
いま一つのメッセージは不況やデフレを回避しながらの財政再建は、それと歩調を揃えた民間投資の拡大、あるいは貯蓄を縮小する消費の拡大があってはじめて可能となるということである。過小な投資と消費の下、これだけの財政支出によりかろうじて現在の産出水準が維持できるというのは、経済の姿としてはいびつである。そのいびつさは原因から改善されなければならない。これはまさにいま一つの政策課題である構造改革のめざすところである。民間投資が活発化して新産業や新企業を立ち上げ、わが国の生産活動の成果をわが国自身が有効に使える状況を整備することが構造改革に求められている。つまり財政再建は構造改革が進む限りにおいて可能なのである。
現在、景気は低迷から後退へ、さらにデフレへと進行する可能性がある。財政危機だけが破滅的なのではない。巨額の不良債権を未処理のまま迎えるデフレ危機も破滅的である。デフレ危機の進行するなかで、歳出削減努力による財政再建が果たしてありえようか。これを考えると財政支出について求められることは、その大枠は維持しながら、内容や内訳は構造改革を促進するものでなければならないということである。 |
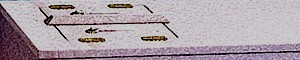

 |



|
|
●財政再建は急ぐ必要はない 2007/10
|
敢えてこのような非常識なタイトルをつけたのには理由がある。長いこと日本の財政赤字は世界で最もひどく、放置すれば急速に悪化し、後世の世代はその負担に苦労することになる、と繰り返し聴かされてきた。これは本当だろうか?
●財政再建論者にとっての不都合な真実
日本の一般政府(中央と地方政府の合計)の公的債務残高は約900兆円で経済規模(GDP )に対して180%になる。これは日本に次いで財政状態が悪いといわれたイタリアの120%よりはるかに高い。この数字はOECDのエコノミックアウトルックにある数字で、日本の財政がいかにひどいかを示す数字としてよく引用される。だが同じOECDのエコノミックアウトルックの次のページに公債の利子負担額のGDP に対する比率の国際比較が載っているのはほとんど知られていない。驚くべき数字が載っているのだ。日本の公債利子負担はGDP 比で 0.7%(2006年)と主要先進国で最低だ。しかもこの数字はこの数年下がっているのである。
なぜこんなことになるのかといえば、日本の金利が圧倒的に低いからだ。金利が低いということは、日本の国債は世界一信用度が高いということにほかならない。事実日本では国債の消化が困難という話は聞いたことがない。銀行は融資先がなく、国債を大量に所有している。一般国民も定期預金の金利がゼロという状態で国債を喜んで買っている。もし本当に日本の財政が危機的でデフォールトの懸念があるなら、こんなことにはならないはずだ。
それでは元本はどうするのか。私は元本の心配もない、と考えている。満期が来れば必ず借り換えが起こるからだ。返済を受けた人はまた次の国債を買うであろう。目下ほかによりよい運用先はない。
●国債は資産
次に国の借金は将来世代の負担だという考えだが、これも疑問だ。確かに期限が来れば増税をしなくてはならないかもしれない。だがその税収は国債を保有している日本国民に還元されるのであり、なくなってしまうわけではない。要するに金が右のポケットから出て、左のポケットに入るだけのことだ。全体としてみれば負担が増えているわけではない。これが、かつての中南米や東欧諸国のように外国人が保有しているとなると、まさしく将来世代への負担になる。しかし、日本の国債の96%は日本人が保有しており、かかる状態からはほど遠い。逆に米国財務省債券を始め膨大な外国の債券を保有している。国債は保有している人にとっては資産であり、これを老後の確実な収入として年金の足しにしようと考えている人が多い。このように国債の金利支払いや元本の返済は実は社会保障を補完するものだ。これがなぜ負担なのか?
●リカードの均等定理
次に政府が必要な資金を税金で徴収するのと借金でまかなうのとでは後の経済にとって違いがあるのかどうか。この問題は経済学の世界でも長いこと議論されてきた。200年近く前にこの問題を考えた経済学者のD.リカードは「どちらでも同じ(equivalent)。」という結論に達した。リカードの均等定理(Ricardian equivalence)と呼ばれるこの主張には反対する学者も少なくはない。国債を発行するとき、あるいはそれを返還するために増税が行われるときの経済状態や、国債を誰が保有するかなどによって効果は異なるからだが、国債は将来世代の負担になる、という主張は一般論としては成立しない。
●混乱する財政議論
財政をめぐる議論は混乱している。とくに歳入側の問題と歳出側の問題を混同している場合が多い。国債発行が続けば規律が緩み無駄な歳出の削減が進まない、というような意見だ。無駄な支出がよくないことは国債でも税収でも変わらないはずだが、増税して得られた歳入なら無駄なく使われるという根拠がどこにあるのだろうか。
こんな話もよく聞く。赤字を垂れ流し続けた夕張市はついに破産し、職員は首切られ、小学校は16から2校に、病院はたった一つになった。老人をケアすることもできなくなり、年寄りは長年住み慣れた町を棄てて近隣の町に出て行った。日本もこのまま赤字を続けるといずれこのようになる、云々。これも問題を理解していない。夕張市の苦境はそもそも炭鉱という地域を支える産業が消滅したことと、高齢化が進んで、生産的な活動が維持できなくなったことにある。財政赤字はこのように経済基盤が崩壊した結果であり、その原因ではない。仮に10年前夕張市が大増税していたら今日の事態は避けられたのであろうか。きっと住民は脱出してもっと早く夕張市は消滅していたであろう。これは民間企業でも同じだ。企業が倒産するのは最後は借金が返せなくなるからだが、原因は商品が売れなかったり、生産効率が悪かったり、余計な投資をしたからだ。これを借金が原因で倒産した、と考える人はいない。
●急ぐ理由はどこにも無い
最近財政再建の必要性を唱えるあるエコノミストに以上のような話をしたところ、「そのとおりです、根津さん。」という。彼は「今後少なくとも10年くらいは金利も低いままで、財政の問題は出てこないでしょう。問題はその先で、いずれ高齢化に伴って貯蓄率が下がり、インフレになる、そのときが大変です。いったんそうなるともう制御不可能です。だから今から準備しなくては駄目なんです。」 私もいずれは日本の貯蓄率が下がり、金利が上がり、国債の消化に苦労するような事態が来るであろうと想像する。だが、そのような事態は地震のようにある日突然襲って来るわけではない。金利上昇もインフレもある程度の期間を経てゆっくりと進行するはずだから、それに合わせて手を打っていくことが可能で、なぜ制御不可能なのかよくわからない。早すぎる財政再建は経済を縮小させるだけである。足元では企業部門が貯蓄性向を高めており、日本の資金循環上で貯蓄が急速に減少していくような状態ではない。日本の経常収支は相変わらず中国と並び世界一、二の水準で、金利は低く、インフレどころかデフレで困っているような状況だ。他方定率税減税の廃止の効果もあって政府部門の収入不足は急速に縮まっている。
2011年までにプライマリーバランスを回復する、という政府の方針は新内閣のもとで揺らぎ始めている。財政再建論者からすれば噴飯ものかも知れない。だが筆者からみれば、さまざまのオプションを議論しておくことは必要だが、人為的な期限を設けて急ぐような理由は見当たらない。経済を構成する家計や企業といった部門のバランスを度外視して、財政の均衡だけを達成すれば何かよいことがあるという議論はまやかしにしか思えない。 |


 |



|
|
●財政再建と経済成長、金融システム 2010/11
|
2008 年秋に発生した世界金融危機とそれに伴う世界的な景気後退を背景に、現在、先進国を中心に世界的に財政赤字が拡大しており、国債発行も急増している。
こうした中で、10 年5月にピークに達したギリシャ財政危機は、経済の安定的な発展のためには、財政の持続可能性を確保することが重要であることを各国に改めて認識させた。翌6月に開催されたG20 トロント・サミットにおいては、財政再建の重要性が強調され、13 年までに日本を除く先進国は財政赤字を半減させることが合意された。しかし、その後、10 年の夏にかけて、今回の欧米諸国における景気回復のペースが金融危機の後遺症もあって過去に比べて非常に緩やかであることが様々な経済指標から確認されることとなった。先進各国は、景気回復ペースが緩やかで高失業が続く中、財政再建と成長の両立という難しい課題に直面することとなった。
また、ギリシャ財政危機により、財政と金融システムの密接な関係が改めて認識されることとなった。ギリシャのみならずドイツやフランスの金融機関がギリシャ国債を大量に保有していたことから、ギリシャ財政危機はヨーロッパの金融システム全体への懸念につながり、EU各国の金融監督当局は、7月には、市場の不安を払拭するため、EU全体で協調して金融機関のストレステストを実施するに至った。
さらに、ギリシャ財政危機は、こうした危機が先進国においても起こり得ること、グローバル化により資金の流れが急速かつ大規模になっている中で、危機が時として突如かつ制御不能な形で起こり得ることも示した。財政の持続可能性を確保することは、市場の信認、金融システムの安定性を維持する上でも極めて重要であることが明らかになった。
翻って、我が国は、一般政府債務残高GDP比がほぼ200%まで上昇し、財政状況は深刻であるが、豊富な家計貯蓄を背景に、国債残高の95%が国内、特に金融機関を中心に保有されており、現時点では国債利回りも1%台前半と諸外国に比べて大幅に低い。しかしながら、高齢化の更なる進行により、こうした状況を将来にわたって維持することは難しいのではないかとの懸念から、我が国の財政の持続可能性や金融システムとの関係について不安視する意見もある。
こうした状況と問題意識を踏まえ、本章では、先進国の財政赤字拡大の現状、財政と経済成長、財政と金融システムの関係について整理した後、過去の各国の経験から、財政再建の成功例、そして失敗して危機に至った例について検討し、教訓を探る。
|
 |



|
|
●第1節 先進国を中心とした世界的な財政赤字拡大 |
|
●1.財政赤字拡大の現状と背景
|
●世界金融危機発生後、先進国を中心に財政赤字が大きく拡大
多くの先進諸国では、1970 年代の石油ショックと景気後退を経て、80 年代の長期停滞を背景に財政赤字が拡大したが、90 年代には財政ルールの導入等により財政再建が図られ、財政収支に改善がみられた。2000 年代に入ると、01 年のITバブル崩壊による世界的な景気後退に加え、アメリカ等主要国において経済活性化を目的とする減税や重点分野への歳出増等により、財政収支はいったん悪化したものの、その後世界的な景気回復もあって改善傾向がみられた(第 2-1-1 図)。
第 2-1-1 図 主要先進国の一般政府財政収支(GDP比)
しかし、08 年の世界金融危機の発生後、景気後退による税収減少、大規模な財政刺激策の実施により、多くの先進国において財政赤字は急速に大きく拡大、公的債務残高も一段と増加し、景気動向をにらみつつ、財政再建に向けた取組が求められる状況となっている(第 2-1-2 図)。
なお、財政悪化の状況は国により差があるが、各国の財政問題が世界経済にも影響を与え得る可能性があることにも留意が必要である。例えば、10 年5月にピークに達したギリシャ財政危機では、財政状況の著しい悪化に起因してソブリン・リスクが高まり、ユーロの信認に懸念を生じさせたことともあいまって、金融資本市場の動揺をもたらし、それを通じて、欧米の企業や家計のコンフィデンスも急激に悪化した。また、多くの国で国債発行が増加しており、主要先進国全体の一般政府の債務残高(グロスベース)をみると、07 年の 25 兆ドルから 09 年には 32 兆ドルへと7兆ドルも増加している(第 2-1-3 図)。これらを金融市場が消化しきれるのかどうかという点も懸念される。
第 2-1-2 図 主要先進国の一般政府財政赤字額(ドルベース)
第 2-1-3 図 主要先進国の一般政府債務残高(グロスベース)
●先進国の財政構造の概観
このように、主要先進国で財政赤字の拡大がみられるものの、歳出及び歳入の規模や構造については、各国で違いがみられる。
まず、歳入については、租税及び社会保険料収入を合わせた規模をGDP比でみると、国により4割超から3割以下と差がみられる。また、社会保険料収入は国により大きく異なっており、フランス、ドイツではGDP比 15%超の一方、カナダでは同4.5%と3分の1以下の規模となっている(第 2-1-4 図)。
さらに、租税及び社会保険料収入の内訳をみると、消費税収については、アメリカ、日本を除き、おおむね 25〜30%程度の割合となっているが、所得税収や法人税収については国により大きく異なっている。所得税収については、アメリカ等4割近くを占める国がある一方、フランス等では2割以下となっている。一方、法人税収については、日本、韓国、オーストラリアでは 15%を超えているが、欧米諸国ではおおむね 10%未満となっており、主たる税収源とはなっていない。
第 2-1-4 図 主要先進国の歳入構造(08 年)
次に、歳出規模をみると、フランス、イタリアのようにGDP比 50%前後の国がある一方、韓国では同 30%強と、国により大きく異なる(第 2-1-5 図)。しかし、歳出の内訳をみると、アメリカ、韓国以外の国では、失業保険、老齢年金等の社会保障費(医療を除く)が最大の支出となっていることは共通しており、さらに、イタリア以外では、医療費が次いで大きな支出となっている。また、アメリカでも、医療費に次いで社会保障費(医療除く)が大きい。この背景としては、高齢化の進展がある。社会保障支出(GDP比)の推移をみると、高齢化の進展に伴い、老齢年金及び医療支出が増加傾向にあることがみてとれる(第 2-1-6 図)。
第 2-1-5 図 主要先進国の歳出構造(GDP比)(08 年)
第 2-1-6 図 主要先進国の社会保障関連支出と高齢化率
このように、現在、既に社会保障支出(年金・公的医療)は、各国の歳出の中で大きな割合を占めているが、今後、高齢化が更に進展していくにつれて、一層の拡大が見込まれ、歳出拡大圧力となっていくことが予想される。特に、年金については、多くの国で財源の確保、支給開始年齢の引上げ、給付水準の引下げ等大規模な改革への取組に着手しており、今後更なる進展が見込まれるため、支出拡大は比較的緩やかなものになる一方、医療支出については、高齢化による影響に加え、新たな医療技術による一人当たりの医療支出の増加の影響を大きく受け、大きく増加していくことが見込まれている(第 2-1-7 図)。
第 2-1-7 図 主要先進国の社会保障関連支出(年金・公的医療)の見通し (IMF) |
|
●2.財政再建と経済成長、金融システム
|
●財政の持続可能性の確保の重要性と財政再建に伴うリスク
前述のとおり、世界経済・金融危機の結果、先進国を中心に財政赤字が大きく拡大している状況にある。民間資金需要が大きく落ち込んでいた危機の状況では、財政は民間需要の肩代わりの役割を果たしていたが、経済が回復するにつれ、拡大した財政赤字をファイナンスするための多額の国債発行は、次第に民間投資のための資金需要と競合関係となり、いずれは民間投資をクラウディング・アウトするというマイナスの効果もある。さらに、財政赤字の拡大・債務残高の累積の結果、財政の持続可能性について懸念が生じるような場合には、先行きの不確実性の高まりを通じて、家計消費や企業投資の抑制要因ともなる。
また、こうした実体経済への影響のみならず、財政の持続可能性についての懸念が生じた場合の影響は、国債金利の上昇(国債価格の下落)という形で金融面にも及ぶ。国債金利が急上昇してデフォルト懸念を引き起こすならば、深刻な場合には、当該国債を保有している金融機関に経営上の不安が生じ資金調達が困難となるといった事態や、更に金融システムが混乱に陥るという事態に至るおそれもある。10年5月にピークに達したギリシャ財政危機は、このような形の影響を想起させるものであった。こうしたことから、財政の持続可能性を確保することは極めて重要な政策課題である。
財政再建を進めていく際には、財政緊縮によって短期的にも経済成長に様々な影響が生じる可能性があるため、足元の景気動向も注意深く見ていく必要がある。例えば、財政再建の短期的な影響としては、先行き不確実性の低下を通じて消費・投資を喚起する可能性がある一方で、乗数効果を通じて総需要を下押しする可能性がある。
こうした観点を踏まえ、以下では、財政再建が実体経済面に及ぼす影響についての考え方を整理し、今後、先進国を中心に財政再建を進めていく上で経済成長とどのように両立を図るべきか、その方向性について検討する。さらに、財政の持続可能性に懸念が生じた場合、金融面で想定される問題について、考え方を整理する。
●(1)財政再建と経済成長の関係
●財政再建が経済成長に及ぼす影響についての考え方
財政再建が経済成長に及ぼす影響として、短期的な視点からは、伝統的なケインズ理論に基づくマイナスの影響が指摘されてきた。政府支出の減少や増税は、乗数効果を通じて民間の消費や投資等の需要を減少させ、総需要に対して下押し要因となるというものである。
これに対して中長期的な視点からは、家計の消費や企業の投資の意思決定は、現在の経済・財政状況だけでなく、将来にわたる状況をも考慮に入れた各経済主体の予算制約等を踏まえて行われると考えることができる。この場合、仮に国債発行により減税を行ったとしても、将来の増税によって穴埋めされると家計が認識するなら、将来にわたる家計の予算制約に変更は生じず、消費行動も変化しない可能性があるということになる。また、もしも家計にとって将来にわたる期待所得が増加し、予算制約が緩和すると認識すれば、現在の消費水準は増加する可能性がある。
財政運営との関係では、家計の将来にわたる期待所得が増加すると認識される可能性があるケースとして考えられるのは、例えば、現在の政府債務残高が極めて高水準となっており、やがて急激で大規模な増税の実施が不可避になる事態が予想される状況下で、そういった事態を回避すべく、十分な規模で継続的な財政再建に政府が着手した場合である。この場合には、家計の将来にわたる期待所得への影響を考えると、将来の急激で大規模な増税等に比べ、着実な財政再建の推進による増税等は、経済活動をゆがめる効果が小さく、経済厚生の損失も小さくて済む可能性が高いことから、増税にもかかわらず家計が消費を増加させる可能性がある。
また、こうした可能性は、流動性制約の下にある家計が全家計に占める割合が低い場合に高くなる。流動性制約の下では、家計は現在の可処分所得額に基づいて消費を決定しており、増税は現在の可処分所得を減少させ、消費を減少させる要因となるので、増税の影響は、伝統的なケインズ理論と同じく需要を下押しする。流動性制約下にある家計の割合が低い場合の方が、将来にわたる予算制約への影響を通じた効果は生じやすいことになる。
以上のような、伝統的なケインズ理論とは異なる経路で財政政策が需要に及ぼす効果は、非ケインズ効果と呼ばれる。中長期の観点から、財政再建が経済成長に及ぼす影響を考える上で、財政再建の継続性や政府の取組への信認といった要素の重要性を示すものといえよう。
さらに、政府が財政再建に対して着実に継続的に取り組むことへの信認が高まると、将来の予期せぬ増税といった、経済・財政状況のリスクに備えて消費を抑制する予備的貯蓄動機を低下させる効果がある。
また、財政再建を進める際に、金融緩和による内需の下支えや、輸出の増加による外需の伸びが期待できる場合には、緊縮財政による総需要への下押し効果が緩和されることになる。現在のように、欧米の主要先進国において政策金利は既に極めて低い水準となっており、先進国の景気が緩やかな回復ペースにとどまっている状況の下で、各国が同時に財政再建を進めた場合には、こうした金融面や外需による総需要下支え効果も見込めないため、財政再建が経済成長を下押しする効果が大きくなるおそれがある。
●世界的な財政再建への取組のためのG20合意
ギリシャ財政危機を背景として、先進国の財政持続可能性についてのリスクが市場で意識される中、10年6月に「G20トロント・サミット」が開催された。同サミットでは、財政再建につき、その重要性を強調しつつ、経済成長と両立させることが必要との認識が多くの首脳により共有されるとともに、先進国において既存の財政刺激策を遂行し、「成長にやさしい」(growth-friendly)財政再建計画を実施していくことが合意された。
同合意では、健全な財政は、回復を維持し、新しいショックに対応する柔軟性を提供し、人口の高齢化という課題に対応する能力を確保するとともに、将来世代に財政赤字・債務を残すことを回避するために必要不可欠とされた。また、調整の経路は、民間需要の回復を持続させるため、注意深く調整されなければならないとされた。主要国が同時に財政調整を行うことによる世界経済への下押しリスクと、必要な国が財政再建を行わずに信認を損うリスクのバランスを考慮することが必要だとの認識の下、各国の状況に即して差別化するとの基本を踏まえつつも、先進国は、13年までに少なくとも赤字を半減させ、16年までに政府債務のGDP比を安定化または低下させる財政計画にコミットした。
この合意により、先進国における財政再建への取組の前進が確認された。今後、同合意に基づき先進国が同時に財政再建を実施した場合、各国の財政再建による景気への下押し効果が、世界経済の緩やかな回復の持続性を損なうことがないよう、注視していく必要がある。なお、10年11月の「G20ソウル・サミット」においては、トロント・サミットで約束したように財政再建計画を策定・実行することを改めて確認するとともに、同時に調整がなされることによる世界経済の回復へのリスクや、即時に必要とされる財政再建を実施できないことが、信認や成長を低下させるリスクに留意することとされた。
●「成長にやさしい」財政再建とは
財政再建と経済成長の関係をみると、既に述べたように、短期的な視点からすれば、財政再建は経済成長に対して下押し効果がある。そこで、財政再建と経済成長を両立するためには、財政政策以外の政策も含めて、どのような経済財政政策運営をすれば良いのかという観点が求められる。
まず、財政再建のタイミングやペースに配慮することが必要である。景気回復局面では、税収の自然増などによる歳入増や、ビルトインスタビライザー(景気の自動安定化装置)による財政支出の減少等による歳出減が見込まれ、財政再建への追い風となる。また、経済成長率など経済状況を考慮しつつ、財政再建のペースを調節することで経済への負荷を軽くすることができれば、財政再建の取組を進めやすくなる。
また、金融政策等の他の経済政策を組み合わせることにより、財政再建による経済下押し効果を緩和することが考えられる。
まず、金融政策について、金融引締めに慎重なスタンスをとることにより、財政緊縮が景気の腰折れといった事態を招かないためのマクロ経済環境を維持する効果が期待できる。さらに、構造改革を推進し、潜在成長率を高めることにより、財政再建を進めやすくする効果がある。
加えて、財政運営に対する中長期的視点からみれば、財政再建が着実で継続的に行われることに対する信認を得られるかどうかも重要である。信認を得た状況では、緊縮財政が民需を増加させる非ケインズ効果が働く可能性もある。このため、中長期的な財政再建計画の策定や、財政再建の取組を法的拘束力のあるものにするといった財政制度上の工夫も有効である。
●(2)財政と金融システム
10年5月にピークに達したギリシャ財政危機は、財政と金融システムが密接な関係を有することを世界の人々に改めて認識させた。ドイツやフランス等の金融機関は、ギリシャを始めとする、財政の持続可能性への懸念が高まった一部のヨーロッパの国々の国債を保有していたことから、財政の悪化がヨーロッパ全体の金融システムの安定性への懸念に拡大した。
日本においても、金融機関の資産のうち20%弱を日本国債が占めていることから、金融システムの安定性を確保するためにも、財政の持続可能性の確保は重要な課題である。
●財政赤字の拡大に伴う影響
一般に、財政赤字の拡大は、政府部門がより多くの資金を市場から調達するため資金不足傾向となることから金利が上昇し、それにより民間投資を減少(クラウディング・アウト)させるという効果がある。このため、資本蓄積が低下することにより、長期的な潜在成長率が低下する可能性がある。また、政府の利払い費用負担が増加することで、更なる財政悪化や、財政の硬直化を招くおそれがある。さらに、財政赤字の拡大に伴う財政の持続可能性への懸念は、金融システムの急速な不安定化につながるおそれがある。
●金融システムへの波及経路
ある国の財政赤字が拡大し金利が上昇傾向を強めると、利払い負担増等により当該国の財政の持続可能性に対する懸念につながる。この懸念が引き金となり、各国の財政状況への注目が集まった場合には、同様に財政赤字が拡大している国の国債金利が上昇する可能性が高まり、このような国の財政の持続可能性への懸念に伝染(コンテイジョン)する。他方、金融機関は自国国債を中心に国債を保有していることが多いが、財政状況が悪化している国の国債金利が上昇(国債価格の下落)し、デフォルトへの懸念が強まる場合には、保有している国債から損失が発生する懸念につながる。この動きが金融機関の経営に深刻な影響を及ぼす規模に発展すると懸念された場合には、08年秋に発生した世界金融危機と同様に、カウンター・パーティ・リスクが意識され、金融機関は銀行間市場やCP等の短期資本市場での資金調達が困難になるため、金融システムが混乱に陥る可能性がある。
10年5月にピークに達したギリシャ財政危機を例にみると、ギリシャと同様に財政状況が悪化していたポルトガル、アイルランド、イタリア、スペインへの懸念が強まった結果、当該各国国債のドイツ国債に対する利回りのスプレッドは急拡大した(第2-1-8図)。他方、フランスやドイツ等を含むヨーロッパの金融機関は、これらの国債を多く保有していたことから、利回りの急上昇(国債価格の下落)による損失発生が市場で懸念されるようになった。このため、ヨーロッパの金融機関のCDSが急上昇したり、株価も大きく下落した(第2-1-9図)。さらに、銀行間でも、カウンター・パーティ・リスクが高まり、ロンドン銀行間翌日物金利(LIBOR)におけるドル調達金利が若干上昇するなどの現象がみられた。
第2-1-8図 ヨーロッパ各国の国債利回りスプレッド(対ドイツ国債)とCDS
第2-1-9図 ギリシャ財政危機による金融システムへの影響
●財政危機として市場が認識するタイミング
財政状態の悪化を財政危機と市場が認識するタイミングは必ずしも早くない。市場が財政危機と認識するタイミングとして、何らかのショックを契機とする場合が挙げられる。財政状態の悪化の背景として、構造改革の遅れや経済の脆弱性が存在していたとしても、この動きは緩やかであることもあり、平時においては市場で危機と認識されない場合もある。しかし、何らかのショックが発生し景気が急速に悪化すると、構造改革の遅れや経済の脆弱性が表面化する可能性があり、この状況になって初めて市場が財政危機としてとらえることになる。
また、格付け機関による格付けが良好な場合には、財政状態に対する市場の注目が低くなり、結果として市場の財政状態の悪化に関する認識を遅らせる可能性がある。さらに、格下げが一度発生した場合には、金利が上昇することで更に財政状態の悪化懸念が強まり、更なる格下げにつながる増幅的な効果を持つ可能性もある。この点についてIMFでは、1975年以降債務不履行に陥った国は、債務不履行の1年前には投資適格未満の水準に格付けされていた点を指摘するとともに、格付け機関は継続的に格付け方法の調整を行っており、国債の格付けに関しても正確性は向上してきているとし、格付け機関による格付けはおおむねうまく機能してきたとしている10。しかし、90年代の新興国の財政危機の際は、格付け機関は、格付け変更があまりにも遅すぎたこともあり、増幅的であったことが非難されていた11。10年5月にピークに達したギリシャ財政危機においても、09年10月の政権交代と、新政権による財政統計データの大幅下方修正により、徐々にソブリンCDSは上昇した。しかし、急激な上昇は、格付け機関が格下げを相次いで行った09年12月以降に発生していることから、格付け機関による格下げが、市場の認識を遅らせるとともに、格下げが更なる格下げを呼んだ可能性がある(第2-1-10図)。
第2-1-10図 ギリシャ危機におけるギリシャ国債の格付け推移
●財政危機を認識後の市場の調整速度
財政状態の悪化を財政危機と市場が認識した場合、株価の急落等金融市場の調整は急速に行われることがある。市場の価格変動の大きさを表す恐怖指数をみると、98年8月に発生したロシア財政危機や10年5月にピークに達したギリシャ財政危機では、危機の認識後に恐怖指数は急上昇していることから、市場の価格変動が大きくなっていることがうかがえる(第2-1-11図)。このことから、財政危機が市場に認識された場合には、金融市場の調整が急速に進行するため、金融システムも急速に悪化する可能性がある。
第2-1-11図 恐怖指数の推移:財政危機時は、市場は不安定化 |
 |



|
|
●第2節 財政政策運営の失敗事例
|
歴史をひもとくと、財政政策運営の失敗事例は枚挙にいとまがない。19世紀以降のソブリン・デフォルトだけでも310件以上存在するとされており、その中にはデフォルトを繰り返している国もある。例えば、ギリシャは、19世紀以来5回のソブリン・デフォルトを経験しており、独立以来、約半分の期間はデフォルトしていた。ポルトガルも19世紀以降6回デフォルトを経験している。また、世界のデフォルトをみると、10〜20年周期で多く発生しており、19世紀初頭のナポレオン戦争期、1820年代から1840年代、1870年代から1890年代、20世紀に入ってからは、大恐慌後の1930年代から50年代初め、そして80年代から90年代には新興国を中心にデフォルトが多く発生した。こうしたソブリン・デフォルトの大量発生の波は、世界的な金融危機の後に起こることが多いとされている。これは、金融危機に伴う世界的な景気後退により貿易が収縮し、新興国経済が落ち込むことに加え、金融危機により新興国への資金の流れが突然止まったり(sudden stop)、投資家のリスク回避姿勢が強まったりすることにより新興国政府の資金調達が難しくなることなど、一般に世界的な金融危機が新興国経済に与える影響が大きいことが理由として考えられている。
近年のソブリン・デフォルト事例としては、01年のアルゼンチン国債のデフォルトが記憶に新しい。本件の債務再編は現在も続いており、我が国の投資家も含め多大な損失を被っている。また、通貨の減価による輸出増加にけん引されてアルゼンチン経済は回復したものの、アルゼンチンのソブリンCDSは700bps前後と現在のギリシャと同水準で推移しており、デフォルトの将来にわたる影響の大きさを物語っている。
戦後のソブリン・デフォルトは、発展途上国や新興国で発生しており、先進国では見当たらない。しかし、デフォルトには至らなかったものの、財政政策運営の失敗が危機を招いた事例はある。そこで、以下では、こうした事例として英国のIMF危機(76年)を取り上げる。また、新興国ではあるが比較的成熟した経済であるロシアのデフォルト(98年)は、当時の国際金融市場に大きな影響を与えたことから、これについても検証する。これらの事例では、長年の構造改革の遅れに何らかのショックが加わったことにより、財政状況が急激に悪化した結果、危機に陥っており、こうした危機は先進国においても起こる可能性があることを示している。
|
|
●1.英国IMF危機(76年)
|
●(1)危機発生の背景と経緯
●「英国病」による行き詰まり
第二次世界大戦後、英国政府は、「大きな政府」を標榜し、ケインジアン経済学に基づく総需要管理政策、「ゆりかごから墓場まで」といわれた手厚い福祉政策、主要産業の国営化等の政策を行ってきた。これらの政策は、戦後から60年代まで、2大政党両党による歴代政権を通じて、政策合意となっていた。
しかしながら、70年代、こうした経済政策運営に行き詰まりがみられるようになり、構造問題が顕在化、経済状況は悪化した(第2-2-1表)。
英国産業の国際競争力は低下傾向にあったが、その背景には、手厚い福祉によって労働者の労働意欲が減退し、生産性が低下したことが挙げられる。また、労働組合の反発等により、政府は高福祉政策の改革を進められず、生産性上昇率に見合わない高い賃金の伸びが継続した。
●石油ショック発生
73年、石油ショックが発生し、原油価格上昇を要因としたコストの上昇により、60年代後半から現れていたインフレ傾向に拍車がかかった。74年、75年には、消費者物価上昇率が10%を超えて加速する中、実質経済成長率が2年連続のマイナスとなるなど、スタグフレーションに陥った(第2-2-2図)。原油価格の上昇によるコスト負担から生産が落ち込む一方、輸入額が拡大し、経常収支は赤字となった。
また、石油ショック発生以前から、失業給付等を中心に歳出は増加傾向にあったため、72年度には財政収支は赤字となり(第2-2-3図)、73年の石油ショックの影響により失業給付等は更に増加した。国債発行が増え、金利も上昇したことにより国債費が増加し、74年度の歳出は70年度に比べ28%増加した。
●市場の政策不信によるポンド暴落
財政収支赤字が続いていたことに加え、石油ショック発生後の経済混乱に対しても、政府は有効な対策を打ち出すことができなかったため、ポンドは減価し、76年3月、対米ドルで初めて2ドルを割り込んだ。その後もポンドの減価は止まらず、同年11月には1.6ドルを下回り、75年3月の2.53ドル台から、35%以上の減価となった(第2-2-4図)。
76年を通じたポンドの減価に対する通貨防衛(ポンド買い介入)のため、外貨準備が枯渇した政府は、同年12月、IMFに39億ドルの緊急支援を申請した。IMFは、英国政府からの緊急支援要請に応じる条件として、財政赤字の縮小等、財政規律の目標と計画案の策定を要請し、政府は受け入れた。
●(2)危機発生後の影響
●政策への影響〜キャラハン政権による大幅な政策転換
IMFからの要求を受けて、政府は、政策の大幅な転換を余儀なくされ、政府支出と財政赤字の削減を伴う緊縮型の予算を発表した。また、構造改革とインフレ抑制のため、国営企業の賃上げ制限にも着手した。
これらの改革に対し、労働党内の対立、労働組合からの反発もあり、キャラハン労働党政権は、79年の総選挙に敗北した。しかし、IMFの要請を受けて行ったキャラハン政権の政策転換は、次の政権を担ったサッチャー保守党政権による戦後体制の抜本的な改革への布石となった。
●経済への影響
IMFからの融資により、外貨準備の減少傾向に歯止めがかかったことを市場は評価し、ポンドの減価基調が反転し、その後数年間、増価基調が続いた(前掲第2-2-4図)。
実体経済をみると、76年末までのポンドの減価により、輸出は回復し、73年以降大幅な赤字を続けていた経常収支は、80年から83年まで黒字が継続した(前掲第2-2-2図)。
政府は、財政赤字削減のため、社会保障費、公務員給与の削減を発表し、また、前述のように、国営企業の賃上げ制限にも着手したため、国中でストライキが多発し、交通、通信を始めとする社会インフラが十分に供給されず、国民の経済活動が停滞する「不満の冬(Winter of Discontent)」となった。
●(3)危機の教訓
●構造問題の先送り
英国の、戦後から続けられてきた「ゆりかごから墓場まで」といわれた手厚い福祉政策等の構造転換に対しては、国民の反対が根強く、70年代の歴代政権が構造改革に取り組んだものの、抜本的な改革を行うことができず、結局、危機に至った。石油ショックによる経済困難は先進国共通の事象であったが、英国の場合はこうした構造問題から危機が深刻化、IMFの支援に至った。英国の経験は、問題の先送りを続けていれば、先進国であっても危機は起こり得ることを示している。
英国において石油ショックの発生がその後の財政状況の深刻化につながったように、マクロ・ショックの発生により状況が急激に悪化する可能性がある。また、根深い構造問題を抱えていては、ショックに対して適切・迅速な対応が取れず、事態の更なる悪化を招くおそれもあるといえよう。
|
|
●2.ロシア財政危機(98年)
|
●(1)危機の背景
●市場主義経済への転換に伴う構造改革の遅れ
ロシアは、80年代後半以降、原油価格の下落による歳入の減少や、社会主義経済の下で生産性の低い企業への補助金支出が増加したことにより、財政が悪化した。このため、財政改革は90年代初めからの市場主義経済への移行過程の主要課題となり、92年には、税制改革と緊縮財政策が実施された。しかし、生産の減少を背景に歳入が伸び悩む一方で、不採算企業の財務悪化に対して抜本的な構造改革を断行することができず、再度補助金を支出せざるを得なかったことなどから、歳出が増加した。このため、90年代後半になっても財政赤字の改善は進まなかった(第2-2-5表)。
●開放経済のトリレンマ(三律背反)と低水準の外貨準備
ロシアの金融政策をみると、90年代半ばにかけて市場主義経済への移行に伴う混乱と財政赤字の拡大を背景に急激なインフレが発生したことから、政策金利を高めに設定する緊縮的な金融政策が実施された(前掲第2-2-5表、第2-2-6図)。一方、為替制度では、95年にルーブルの減価を抑制するために、目標相場制(コリドール(コリドー))が実施された。他方、96年の大統領選挙後、資本取引が自由化されたことなどを背景に資金流入が加速し、97年にかけて株式市場は高騰した。しかし、ロシアの経常収支黒字や外貨準備高をみると、90年代半ばを境に減少傾向にあった(前掲第2-2-5表)。このため、急激な資金の流出が発生した場合には、開放経済のトリレンマの関係から為替レートの安定(ないしは固定)を図ることができず、経済の脆弱性が増加するおそれがあった。
●財政と商業銀行の脆弱性(海外短期資金によるファイナンス構造)
ロシアの財政赤字は、その大部分が海外短期資金によって調達されていた。96年の国債取引の自由化以降、為替市場がコリドールによって安定化していたことを背景に、高金利であるロシアの国債には大量の海外資金が流入した。96年以降、歳入に対する短期国債の発行残高は急速に増加したが、短期国債の30%は海外資金に依存していた(第2-2-7図)。また、残りの70%を保有する国内金融機関は、97年末には資金調達に占める外貨建て債務の割合が20%弱まで増加するなど、海外資金に拠っていた。このため、実質的には短期国債の大部分が海外資金に依存しており、金利の上昇や海外資金の流出及び為替の減価に対して、財政は脆弱な構造となっていた。
一方、90年代初頭の市場主義経済への移行以降、ロシア国内では商業銀行の設立が相次いだ。しかし、高金利によるクラウディング・アウト等により借入れ需要が低迷していたこともあり、商業銀行は国債への投資で収益の獲得を図った。このため、商業銀行の資産に占める国債等は、96年末には30%超に増加した。また、資金調達面では、為替レートがコリドールにより安定化されており、為替リスクが小さかったことから、低金利の外貨建てでの調達が増加し、97年末には資金調達に占める外貨建て債務の割合は20%弱なった。このため、海外資金の流出及び為替の減価に対して、金融システムも脆弱な構造となっていた。
●(2)危機発生の経緯
●財政収支の悪化と信頼に欠ける財政再建策
96年7月以降、ロシアはIMFの勧告もあり、全ての輸出関税を廃止したため、エネルギー輸出から得られる税収等が大幅に減少し、財政赤字は拡大した。さらに、97年に入り原油価格が下落に転じたことで、エネルギー産業の収益悪化に伴う税収の減少等による財政赤字の更なる拡大が懸念された。
これに対し、97年初頭に財務省は、2000年までの基礎的財政収支の黒字化を目標とした中期財政再建計画を発表した。しかし、この中期財政再建計画は、マクロ経済見通しでは低金利の継続を想定し、国際収支においては資金流入の継続を想定するなど、前提条件が楽観的な見通しに基づいていたこともあり、その後の急速な経済環境の変化によって頓挫した。
●マクロ・ショックの発生(アジア通貨危機)とデフォルト
97年7月にアジア通貨危機が発生し、世界的な投資家心理の冷え込みとともにリスク回避姿勢が鮮明となった。また、ロシア経済は、通貨危機が発生したアジア諸国と同様11)に、海外短期資金への依存度が高いにもかかわらず、外貨準備が低水準であったことから、経済の脆弱性が懸念されることとなった。加えて、98年前半には、チェルノムイルジン首相の解任とキリエンコ首相の就任に関して、政府と議会の混乱が発生した。さらに、原油価格が下落を続けたことを背景に、エネルギー産業の収益悪化等により税収が減少したことから、資金流出の進行とルーブルの減価圧力が強まった。
これに対し、政府当局は、為替市場においてルーブル買い介入を続行する一方で、政策金利を大幅に引き上げ、資金流出とルーブル減価圧力の低下を図った(前掲第2-2-6図)。しかし、政策金利の引上げは、かえって短期国債金利の大幅上昇につながり、利払い費が連邦支出の30%弱から40%前後に上昇するなど、財政の持続可能性への懸念が高まる結果となった(第2-2-8図)。また、外貨準備高は減少傾向となり、ルーブル買い介入の継続も厳しい状況となった。
一方、金融面では、ルーブルの一層の減価懸念が、短期の外貨建て債務の増加を通じた商業銀行の資金繰りの悪化に対する懸念につながった。さらに、97年以降の株式市場の下落に伴う損失に加え、財政の持続可能性に対する懸念が強まったことにより、保有している国債からの損失発生も懸念され、商業銀行に対する信頼は著しく低下した。
財政と金融の両面で持続可能性に対する懸念が強まった状況のもと、98年8月17日、政府当局は、新たな為替レートの変動範囲を発表し、事実上ルーブルを切り下げた。さらに、債務の再編まで、99年以前に満期を迎える短期国債(額面で3,870億ルーブル)等の支払停止等の措置を発表し、デフォルト状態に陥った。支払いが停止されたこれらの短期国債の債務再編にかかる政府と債権者との交渉は、99年3月までにほぼまとまり、現金による償還と新たな短期国債への転換が図られることとなった。
●(3)危機発生後の影響
●財政再建への取組
危機後の財政政策をみると、財政再建への取組として、98年以降税制改革が順次実施された。
歳入面をみると、輸出業者に対しては、99年に輸出関税を再度導入した。エネルギー産業の生産拡大と輸出の増加もあり、輸出関税収入は大幅に増加し、財政再建を強く後押しした。他方、税収の約40%を占める付加価値税に関しては、99年に税率を20%から15%に引き下げる一方で、徴税率の改善を図った。
歳出面をみると、短期国債の債務再編により、対内債務残高のGDP比は、98年末の28%から99年半ばには同18.4%に縮小し、対内債務負担は減少した。一方、対外債務残高のGDP比は、ルーブルが減価した影響から、97年末の30%から98年末には同113%に大幅に拡大した。このため、ロシア政府は、ロシア発足以前の対外債務と以後の対外債務を分離し、ロシア発足以前の債務返済を停止するなどの対外債務の再編を行った。この結果、危機後の物価の高騰の影響を除いた実質値でみると、99年の歳入が前年比9%減であるのに対し、歳出は同36%減となった。また、不採算企業に対する補助金の削減や、年金制度の確立等社会保障制度改革も実施された。
●金融システムへの影響
国内の金融システムへの影響をみると、商業銀行は、財政危機による短期国債市場の混乱により、国債への投資を積極的に展開していた銀行を中心に、多額の損失を計上することとなった。ロシア中央銀行によると、危機前の98年8月初頭に1,020億ルーブルあった銀行の自己資本は、99年5月には464億ルーブルに減少し、物価の高騰も勘案すると、実質的には資本の80%が失われた。また、ルーブルの更なる減価に伴い、外貨建て負債の負担が増加するとともに、資金繰りが悪化したこともあり、商業銀行は破たんが相次いだ。これを受けて、商業銀行に対する国民の信頼は大きく低下し、98年後半には個人預金は実質的に国有の貯蓄銀行(ズベルバンク)に移動した。商業銀行を中心に金融システムは混乱したものの、企業の商業銀行からの借入れ額が大規模でなかったことや、消費者の借入れが少なかったこともあり、金融システムの混乱が企業の資金調達や消費に与えた影響は限定的であった。
●実体経済への影響
実体経済への影響をみると、短期的には、(1)ルーブルの減価による輸入品の投入コストの増加、(2)期待インフレ率の上昇による企業の生産計画策定の難航、(3)銀行決済システムの機能不全等により、生産活動は落ち込み、失業率も98年末にかけて上昇するなど雇用環境も悪化した(第2-2-9図)。しかし、ルーブルの減価は、自動車産業や軽工業等の国内の輸入代替産業の活性化につながったことに加え、原油を中心としたロシアの輸出産業の競争力を向上させた。さらに、99年以降、下落傾向にあった原油価格が上昇に転じたこともあり、エネルギー産業を中心に生産活動は更に増加した結果、ロシア経済は急速に持ち直したため、財政危機の実体経済への影響は一時的なものにとどまった。
●(4)危機の教訓
以上でみたように、90年代に社会主義経済から市場主義経済に転換したロシアは、社会主義経済の下での生産性の低い企業に対する抜本的な改革を、財政による補助金の投入で先送りし、慢性的な財政赤字と硬直的な財政運営に依存していたこと、及びこのような経済の脆弱性が、アジア通貨危機により顕在化したことにより、財政危機に陥った。慢性的な財政赤字や硬直的な財政運営を解消するための構造改革の遅れは、財政の持続可能性を低下させ経済の脆弱性につながるため、危機への抵抗力が弱まることとなる。
また、財政再建計画の策定については、前提条件が楽観的な見通しに基づいている場合には、アジア通貨危機等のマクロ・ショックによって発生する急速な経済環境の変化によって瞬時に有効性を失うこととなる。このため、財政再建計画の前提条件は、慎重な見通しに基づいて設定するとともに、リスクシナリオを考慮に入れ、仮に経済環境に大きな変化があった場合にも適応できる対処方針をあらかじめ定めておくことで、計画に対する信頼性を常に高めておくことも重要となる。 |
 |



|
|
●第3節 財政再建の成功事例
|
本節では、各国の財政再建の成功事例について、実体経済と財政政策運営の関係、財政再建を支える制度・仕組み、財政再建を支えるその他の政策等に焦点を当て、その取組を検証する。
なお、財政再建の成功国として、持続的に財政の健全性を維持しているカナダ、オーストラリア、スウェーデン、ニュージーランド等を中心に事例を取り上げるが、一時的に財政再建を達成した国で参考となる事例についても取り上げる。
|
|
●1.実体経済の動向と財政政策運営との関係
|
財政再建は、中長期的には、財政赤字あるいは債務残高の縮小を通じて実質金利の低下をもたらし、消費や投資の拡大を通じて経済活動にプラスの効果をもたらすと考えられる。一方、短期的には、財政の持続可能性に関する先行きの不確実性を低下させ、需要を喚起させる場合もあるものの、国内需要の減退やそれを通じて雇用の悪化を招き、景気の下押し圧力となる可能性がある。このため、財政再建の実施に当たっては、景気動向に配慮し、景気の変動リスクを十分に踏まえた財政再建策の実施が不可欠である。以下では、「財政再建開始のタイミング」、「財政再建の速度」、「景気変動リスクへの対応」の3点に着目し、各国の事例を分析する。
●(1)景気循環と財政再建開始のタイミング
先進各国では、80年代後半から90年代にかけて財政再建の動きが加速した。マクロ経済的な背景をみると、70年代のオイルショックを経て低成長期に移行するに伴って、財政赤字が拡大する国が増加し、一部の国では経常赤字や為替減価、実質金利の高止まり等に直面した。さらに、90年代初めの世界的な景気後退の中で、92〜93年の欧州通貨危機や94年のメキシコ危機等が発生し、経済的な危機に直面した国では、マクロ面におけるファンダメンタルズを改善するため、財政赤字の削減に取り組む必要性が高まった。また、政治的にも、小さな政府を志向する新自由主義的な潮流の下、行政改革や規制緩和の動きが広がったことに加え、99年の欧州通貨統合を控えて厳しい財政規律が求められていたことも、各国の財政再建を後押しした。
こうした経済環境の中、各国の経験を振り返ると、財政再建開始のタイミングについては、景気回復期に財政再建を開始したケースと、景気後退期に開始したケースに分類される。財政再建は景気に対してマイナス効果が働く可能性が高いため、前者のタイミングで実施することが望ましいが、経済的な危機に直面した場合や政治的な要因から後者のタイミングで実施するケースもみられる。
●景気回復期に財政再建を開始したケース
財政再建の成功例とされる取組においては、景気の底打ち後に財政赤字削減が急速に進められたケースが観察される。例えば、カナダでは、92年に一般政府財政赤字がGDP比9%に達するなど厳しい財政状況にあったが、同年4月の景気後退終了後、93年10月の政権交代を機に歳出削減を中心とする抜本的改革を推進した。この結果、目標を上回る速度で財政赤字の削減に成功し、97年には財政黒字を達成した。また、スウェーデンでは、90年代初期の危機的な経済・金融状況の中、93年には一般政府財政赤字はGDP比11%に達したが、通貨危機に伴う為替の減価により輸出主導の回復が可能となり、景気回復の中で急速に財政再建を進めた結果、98年には財政黒字に転換した。一方、オーストラリアでは、80年代前半と90年代前半の景気後退期に財政赤字の急速な拡大を経験したが、ヨーロッパ等でみられたような差し迫った状況には追い込まれなかったことから漸進的な改革が進められ、景気回復に合わせて顕著な財政収支の改善に成功した。
上記のケースについて、経済全体の潜在的供給力と現実の需要のかい離を示すGDPギャップと財政赤字の関係をみると、財政赤字はGDPギャップのマイナス幅が縮小に転じた後にいずれもピークアウトし、その後の財政再建が軌道に乗ったことが事後的に確認できる(第2-3-1図)。財政再建を達成するための基本的な要件として、財政再建に伴う景気の下押しリスクを抑制することが重要であり、経済が回復軌道に乗るタイミングを見極めて改革に着手することが求められる。
●景気低迷期に財政再建を開始したケース
景気が減速又は悪化する中での財政再建については、経済・金融が危機的状況に直面したケースや、マーストリヒト条約における収れん基準の達成等、政治的な要請を満たすために着手せざるを得なかったケースが観察される。
前者に該当するニュージーランドは、70年代以降徐々に顕在化した失業やインフレ等の諸問題を、賃金や物価の凍結等、強力な政府介入によって抑え込んでいたが、84年の総選挙を巡る政治的混乱が為替の急激な減価を引き起こし、経済的な危機に陥った。総選挙で誕生したロンギ政権は、政府統制を廃止し、大規模な自由化を始めとする経済改革、行財政改革に着手したが、景気後退期における構造調整が景気を更に下押ししたことから、経済低迷は90年代初めまで続き、財政赤字も80年代後半から90年にかけてGDP比4〜5%台と高止まりした。その後、90年の政権交代で誕生したボルジャー政権下では、財政責任法の制定を始め、将来にわたる財政の信頼性と透明性を確保するシステムが構築され、90年代半ば以降の高成長の中で財政黒字を達成、08年までほぼ毎年維持してきた。また、アイルランドでも、80年代半ばまでスタグフレーションにより経済が著しく低迷し、財政赤字が拡大したが、景気回復が遅れる中で増税や歳出削減による財政再建が進められた。
他方、後者には、マーストリヒト条約における収れん基準の達成という条件を課せられたヨーロッパ諸国が該当する。99年の通貨統合(欧州経済通貨同盟)への参加を希望する国は、参加条件として、97年までに財政赤字をGDP比3%以内及び債務残高を同60%以内に抑制することなど、財政やインフレ等に関する基準を達成することが求められた。世界的に景気が後退する中で、ヨーロッパ各国のGDPギャップはマイナス幅が拡大する局面にあったが、こうした基準達成のため、厳しい経済状況にもかかわらず、各国では臨時措置を含む大規模な財政再建が断行された。スペインでは、93年の財政赤字がGDP比7.5%まで拡大したが、歳出削減を中心とする財政再建に取り組むとともに、インフレの抑制や規制緩和及び労働市場改革を推進して潜在成長率の向上を図り、基準を達成した。また、イタリアでは、93年の財政赤字が同10.1%、債務残高が同116%に上り、収れん基準の達成が特に疑問視されたが、通貨統合への参加が経済発展に不可欠との認識から、GDP比約1%に及ぶ一時的増税を始めとして、増税及び歳出削減、構造改革に取り組み、財政赤字削減を進めた。
●(2)財政再建のペース
財政再建に当たっては、急激な再建策の実施が景気の下押し圧力となり、税収の低下等を通じて財政収支を悪化させる可能性もある。ここでは、1980〜90年代を中心に財政再建を達成した成功事例を取り上げ、そのペースをみることとする(第2-3-2表)。
なお、以下では、各国で特に財政再建に注力したとされる政権をベースに、再建策の開始と終了のタイミング(あるいは政権の任期)を特定して財政再建期間としている。また、財政再建のペースについては、財政収支と、その要因である構造的収支、循環的収支の3点から分析している。なお、構造的収支については、財政再建策の成果を把握するため、利払い費を除いた構造的プライマリー収支をみることとする。
●財政収支の改善ペース
財政収支の改善ペースをみると、年平均2%台から1%未満まで状況は様々である。改善ペースが速い事例としては、カナダのクレティエン政権、スウェーデンのカールソン政権、英国のメージャー政権等が挙げられる。こうした事例の内訳をみると、構造的プライマリー収支の改善ペースも速い。同収支は財政再建策の成果を反映するものであり、各国における積極的な再建策の推進が寄与したものと考えられる。
一方、緩やかなペースで構造的プライマリー収支が改善し、財政再建を達成した事例もある。オーストラリアでは、ホーク、キーティング、ハワードの3政権の下で継続的に財政再建が進められ、構造的プライマリー収支の改善ペースは1年当たり平均0.4%(潜在GDP比)と比較的緩やかであるものの、財政収支の黒字転換を達成している。なお、循環的収支については、ホーク政権では91年の景気後退を反映し若干のマイナスとなったが、他の2政権ではプラスを維持している。
●速いペースの財政再建がもたらすリスク
一般的に、財政再建が急速なペースで実施される場合、政府支出及び公共投資の減少や増税による国民の可処分所得の減少等を通じて、短期的には経済に与えるマイナスの影響が大きくなる。構造的プライマリー収支が急速に改善する一方、循環的収支がマイナスとなった例としては、ニュージーランドのロンギ政権、フランスのジュぺ内閣等が挙げられる。
ニュージーランドのロンギ政権期では、84年に通貨危機が発生したことから、その打開策として緊急に構造改革、財政再建を進めなければならない状況に陥った。経済成長は鈍化傾向にあったものの景気を考慮する余裕はなく、改革が推し進められた結果、構造的収支については一定の改善がみられた半面、循環的収支の赤字は大きく拡大し、財政収支の改善幅を押し下げることとなった。フランスのジュペ内閣下では、ユーロ加盟の条件となるマーストヒリト条約の収れん基準を満たすために、短期間で財政再建が進められた。循環的収支はマイナスで推移し、急速な財政再建策の実施も影響したものと考えられる。
一方、スウェーデンのカールソン政権やカナダのクレティエン政権のように、速いペースで構造的プライマリー収支が改善し、かつ循環的収支がプラスとなった例もある。循環的収支がプラスになった要因として、スウェーデンのカールソン政権では、通貨クローナの3割を超える大幅な減価による輸出拡大が景気回復を下支えしたこと、カナダのクレティエン政権では、財政再建開始後にアメリカの景気後退が終了し、経済環境が好転するなど、いずれも外部環境の変化がプラスに作用したことなどが背景にある。
●望ましい財政再建ペース
以上を整理すると、外部環境の改善や為替レートの大幅な減価による輸出拡大等により、財政再建が経済に与える負の影響が相殺されたため、経済成長を維持しながら速いペースで財政再建を達成した例もある。一方、緩やかなペースで継続的に財政再建に取り組み、安定的な経済成長と両立した例もある。財政再建のペースについては、経済危機等の特別な事情がない限り、複合的な要素を勘案して経済に及ぼす影響を抑制しながら調節されることが望ましい。
●(3)景気の変動リスクへの対応
●景気循環への配慮を規定したルールの設定
財政再建に当たっては、厳しい財政規律を維持しながらも、景気の変動リスクに対する柔軟性を確保するための例外的な状況に対処するための規定(いわゆるエスケープ・クローズ)を設けることも重要となる。例えば、景気後退時あるいは通常の景気循環を超える重大な経済危機等が生じた場合に、財政の再建目標やその達成時期の変更等、適切な措置を講じられるような仕組みを設けておくことで、マクロ経済の安定化とともに、財政再建の継続性を確保することが可能となる。
エスケープ・クローズの重要性を示唆する例として、90年代後半の日本の経験が挙げられる。日本では、93年10月から97年にかけて景気が拡大したことを背景に財政構造改革に向けた検討が開始され、「03年度までのできるだけ早期に、国及び地方の財政赤字GDP比を3%以下とする」ことを目標とした財政構造改革法が97年11月に成立した。しかしながら、97年4月の消費税率引上げ(3%から5%)に伴う駆込み需要の反動や同年夏に発生したアジア通貨危機の影響、金融機関破たんによる金融システム不安等が重なったこともあり、景気後退が深刻化した。こうした状況の中、エスケープ・クローズがなかったため、同法に沿って98年度予算は緊縮的な財政政策スタンスがとられた結果、景気の落込みは更に深刻なものとなった。財政再建のタイミングの問題とともに、景気変動によるリスクを考慮した柔軟な仕組みが欠如していたと考えられる。
●各国の状況
各国の状況をみると、アメリカ、英国、ユーロ圏諸国、スウェーデン等では景気変動リスクに対応する制度的仕組みが設けられている(第2-3-3表)。なお、英国では、今般の世界的な経済・金融危機を受けて、現在、財政規律(ゴールデン・ルール、サスティナビリティ・ルール)の適用を一時的に止める措置を採っているほか、EUにおいても現在の厳しい経済情勢は「例外的な状況(exceptional circumstance)」とされ、安定成長協定が定めるGDP比を超える財政赤字が許容されている。
●景気変動リスクに対する対応の評価
景気後退局面における財政再建は、「景気循環増幅的」(pro-cyclical)な効果をもたらす可能性が高く、マクロ経済の安定並びに財政再建の持続性の観点からエスケープ・クローズのような弾力条項を設けることは必要であると考えられる。ただし、規定の設計が十分でない場合、あるいは運用が恣意的に行われる場合には、財政再建に対するクレディビリティを失い実現性も低下するといった弊害をもたらすことに留意が必要である。
例えば、英国においては、98年に制定したゴールデン・ルールやサスティナビリティ・ルールによって景気変動の影響を踏まえた柔軟な予算編成が可能となった一方、財政規律を遵守しているかどうかの評価に重大な影響を与える景気循環の開始時期の認定において、事後的に変更(99年から97年前半に変更)が行われた(05年7月)。こうしたことから、ルールを遵守しているかどうかの評価基準があいまいではないかという指摘がなされた。
|
|
●2.成功事例における財政再建策
|
ここでは、財政赤字削減策とそれを支える制度・仕組みについて、財政再建の成功事例を検証する。
財政再建に成功した国々の財政収支の変化の構造をみると、80年代後半から90年代にかけて構造的基礎的財政収支が大きく改善した結果、財政収支の黒字転換を達成しており、財政再建策が大きく寄与していることが示唆される(前掲第2-3-1図)。特に、カナダ、オーストラリア、スウェーデン、ニュージーランドでは、以下にみるように、(i)財政赤字削減手段、(ii)実効性を高める制度・仕組み、(iii)国内のコンセンサスの確保等に工夫がみられ、早い段階から財政再建メカニズムを確立して取り組んできたことが、成功の背景にあると考えられる。
成功事例における財政再建策の特徴を概括したものが、以下の図である(第2-3-4図)。個別の取組については、第4節において詳述するが、以下ではこれらのポイントに沿って横断的に検証する。
●(1)財政赤字削減の手段(歳出削減と増税)
財政赤字縮小のための直接的な手段として、歳出削減、増税等の措置が挙げられるが、その有効性については様々な見解がみられる。先行研究の多くは、オーストラリアやスウェーデン等、財政の健全性を維持している国では、歳入増加策よりも歳出削減策に重きを置き、歳出の中では社会保障を抑制する傾向があると指摘している。IMF(2010)は、歳出削減を中心とする財政再建の方が、増税を中心とする財政再建よりも経済への負の影響が小さく、GDP、失業率、国内需要の低下率が小さいと指摘している。Alesina and Perotti(1996)は、増税による財政再建よりも、歳出削減、とりわけ移転支出と公務員給与の削減の方が持続的で成功しやすいことを指摘している。これに対し、歳出規模抑制と共に、歳入増加も重要とする分析もある
。
●歳出削減
多くの先行研究で、歳出削減策の有効性を挙げており、その中で特に指摘されているのが社会保障費の削減である。高齢化の進展は各国共通の現象であり、今後、多くの国で社会保障費の大幅な拡大が予想されているが、制度改革等を通じて歳出の削減あるいは抑制が図られる場合には、その効果は将来にわたるものであることから、財政の持続的な改善が期待される。また、補助金等の削減も有効性が指摘されている。補助金を導入する背景は様々であり、削減を進めることが経済にとって必ずしも望ましいわけではないが、非効率な事業を誘発するような補助金を削減する場合には、財政負担の軽減とともに資源配分のゆがみの是正を通じて経済成長を高めることから、財政再建を後押しする可能性がある。実際に、各国でも社会保障費削減や補助金削減に取り組む事例が多くみられる(第2-3-5表)。その他、公務員数の削減等を通じて経常的支出の抑制を図る例もみられる。
●増税
歳入増加策として課税ベースの拡大を図る取組がみられるものの、同時に、中長期的な活力を高めるために税率の引下げを行うケースも多く、財政改善効果としては中立的となる傾向がみられる(第2-3-6表)。増税は、ヨーロッパやオセアニア各国の成功事例において、財政再建の手段として積極的に導入されたケースはこれまで多くなかった。
これに対し、90年代のアメリカでは積極的に増税政策が進められ、個人所得税、法人税等の税率引上げ、メディケア保険料の引上げのほか、個別品目(自動車燃料、たばこ、アルコール等)に対する消費税増税等が実施された(第2-3-6表)。景気回復局面に入り循環的な要因から税収が拡大したことも大きく寄与したが、株式市場の活況を背景にキャピタルゲインが増加する中で高所得層に対する税率引上げが行われたことは、増税による財政赤字削減効果を一層高めたと考えられる
。
●(2)財政再建策の実効性を高める制度・仕組み
財政赤字削減策の実効性を高めるとともに、財政再建の持続性を確保、あるいは再建後の財政の健全性を維持していくためには、制度的担保の有無及び有効性も非常に重要である。これらの実現に貢献してきた各国の制度・仕組みの事例について、「法的枠組み」、「目標設定の在り方」、「中期財政フレーム」、「予算編成プロセス」等のポイントに着目し、以下、考察する。
●法的枠組み
法的拘束力をもつ財政ルールは、説明責任・透明性の向上を図り、責任ある財政運営の遂行や財政運営の安定化に資することから、拘束力の弱いガイドラインや努力目標等に比べて、必然的に実効性が高いといえる(第2-3-7表)。過去のOECD諸国の財政再建事例の分析によれば、財政ルールが存在する場合には財政再建の規模は有意に大きく、より持続したという結果が得られている
。
また、財政ルールは財政再建に取り組む上で必要であるが、財政再建を達成した後、財政の健全性を維持していく上でも非常に重要である。財政収支が黒字化すると、減税や歳出増加を要請する動きが高まるためである。実際、アメリカでは、1998年度から2001年度にかけて財政黒字を達成したが、黒字転換と長期にわたる黒字の見通しの発表が財政ルールの運用を弛緩させ、2002年度以降、再び財政赤字に陥っている。この点に関し、オーストラリアでは、将来の経済成長見通しが健全な間は、財政黒字を維持することが規定されていた
。
●目標設定
目標設定については、財政再建に向けた工程やペースを示すものであり、財政再建に対するコンセンサスを形成する上でも重要である(第2-3-8表)。ただし、厳格な数値目標が設定される場合に、景気の変動リスクに対する柔軟性を欠くと、マクロ経済政策運営との整合性を欠き、財政再建の持続性やクレディビリティを失うおそれがある。この点に関しては、既に述べたとおり、多くの国で景気循環に配慮した規定等を採用して対応している。
このほか、債務残高の水準について目標を設定する例もある。債務残高の拡大は、利払い費の増加により財政の硬直化を招くとともに、金利の上昇を通じて民間投資を減退させるおそれがある(クラウディング・アウト効果)。EU、英国、ニュージーランド等では、債務残高を適切に管理することを求めている。
●中期財政フレーム
財政民主主義の観点から、予算は多くの国で単年度ベースで編成されているが、予算単年度主義に対しては、年度内に予算を使い切ろうとする傾向を生んだり、予算が短期的視点で立案され、経済政策運営の中長期的な安定を損ねるなどの批判がある。単年度の予算編成を維持しつつ、その欠点を補うのが中期財政フレームである(第2-3-9表)。中期的な経済・財政見通しに基づく財政運営・予算編成を行うことで、支出の効率性を高め、財政再建をより着実に進めることが可能となる。中期財政フレームにはさらに歳出総額やその内訳に上限額を設定する取組等、財政規律を担保する仕組みが規定されているものもある。
スウェーデン、英国、オーストラリア、ニュージーランドでは、予算編成に当たり経済見通しとの整合を図ることが要請されており、見通しの拘束力が強い。アメリカについては、予算編成に対する見通しの拘束力はこれらの国ほど強くないが、議会における予算審議の前提となることから、重要な役割を果たしている。
●予算編成プロセスの改革
財政政策は、財政民主主義の観点から、当然のことながら政治プロセスを経る必要があるが、政治情勢によっては、短期的な政策の振れが、財政再建に影響を与えることがある。前述の財政ルールや目標に従って、着実に財政再建を進めるためには、内閣のリーダーシップが重要となる。内閣への権限集中を意図した閣内委員会設置や、内閣の役割を明確化して権限を強化する一方で、各省庁を所管する大臣の役割・裁量を拡大、明確化させ、トップダウンとボトムアップのバランスを図る施策も導入されている(第2-3-10表)。
その他、予算編成プロセス改革では様々な政策が導入されているが、前述の財政ルールとの相互効果が期待されるのが、支出総額へのシーリング設定である。多くの国でシーリングが採用されているが、それらは原則改定されないケースと毎年改定されるケースとに二分される。
●(3)財政再建に対する国民の理解の確保(透明性の確保、説明責任の強化)
財政再建においては、歳出削減や増税措置のいずれを用いても国民に負担を求めることになる。財政再建に対する国民の理解を得るためには、財政状況等の情報の透明性を高め、説明責任(アカウンタビリティ)を強化することが前提条件となる。前述した財政ルールも、法律等において明文化され広く国民に提示している点で透明性の確保、説明責任の強化に資するものである。加えて、以下は、国民に対して直接的かつ理解しやすいように、財政状況や経済財政政策を提示する施策である(第2-3-11表)。いずれも、透明性を向上させ、国民への説明責任を果たすことを主眼としている。
●(4)最近の流れ:予算作成機関から独立した専門性の高い財政政策機関の設置
近年、欧州を中心に、予算作成機関とは別に、専門性の高い財政政策機関の設置が財政再建に効果的との議論が盛んになっている。民主主義の下では、予算編成は政治過程そのものであり、選挙の政治サイクルの中で短期的には財政赤字拡大バイアスが働きやすいことが知られている。このため、90年代からの欧米の財政再建の中では、適切な財政政策ルールの設定により財政政策スタンスに対する政治の影響を小さくし、「脱政治化」(de-politicizing)することが財政再建に有効という議論が有力になった。実際、こうした考え方は、ユーロ圏の成長安定協定を始め各国の財政政策ルールに取り入れられ、大きな成果を挙げてきた。
しかしながら、財政政策運営は、景気の見通しとも複雑に絡み、単純なルールで縛ることは難しく、景気との関係で例外規定を置く場合には、それが緩すぎる場合には財政政策ルールの実効性を減ずることにもなりかねず、ルールの設計は容易ではない。このため、2000年代半ば頃から、財政再建及び財政の健全性維持のための仕組みとして、専門性の高い分析により経済や財政の見通しを作成する財政政策機関の設置の有用性が欧州の経済学者や政府関係者の間で議論されてきた。具体的には、こうした機関が予算の前提となる経済見通しを作成し、また、短期及び中長期の財政見通しや財政政策に関わる政策の評価を行うというものである。
こうした財政政策機関をめぐる議論は、金融政策で専門性の高い分析に基づく政策運営が先進国で一般的になったことも無縁ではない。金融政策については、政治的な圧力により金融緩和が必要以上に行われ、インフレになるリスクがあるとの認識から、90年代に、我が国も含め多くの国で中央銀行の独立性が確保され専門的な分析に基づいて金融政策が行われるようになり、多くの国で物価の安定が達成されるようになった。このような経験から、財政政策についても、同様に専門性の高い分析を行う機関が財政政策スタンスの決定に関わることにより、政治的バイアスを回避し、財政の持続可能性を確保すべきという考え方が広がっている。
実際に設立されている機関をみると、具体的な業務は様々であるが、エコノミスト等専門性の高い職員が一定の独立性をもって財政政策の根本に係る業務や評価に関わる業務を行う機関であるという点では共通している。
例えば、オランダの「経済政策分析局」(Bureau of Economic Policy Analysis)は、四半期ごとに短期経済見通しを公表するほか、中長期の経済財政見通しの作成、労働や貿易等、様々な経済政策分野に関わる政策評価等を行っている。特徴的なのは、選挙の際に、各政党のマニフェストを実現した場合の経済財政への効果を分析し、公表していることである。これは、86年から行われ、各政党からの依頼を受けてマニフェストに掲げられた政策の経済効果を詳細に分析し、それぞれの政党の政策を実施した場合に財政赤字がどの程度拡大あるいは縮小するか、雇用への影響はどうか、家計の所得にはどのような影響があるかなどについて一覧性のある形で定量的に示している(第2-3-12表)。オランダでは、このような分析が有権者の政権選択に際して非常に有用と考えられており、このため、経済政策分析局の高い専門性とそれに基づく客観的な分析が非常に重要とされている
。
また、英国では、10年5月の総選挙による政権交代を機に、新たに「財政責任局」(Office for Budget Responsibility)が設置され、予算の前提となる経済見通しの作成のほか、予算案が実現した場合の経済への影響、予算案と財政目標の整合性等を財務省から独立した立場で評価している。その成果は、既に6月のバジェット・レポートに現れており、経済見通しのほか、予算案と今後の経済財政見通し、財政目標の関係をファン・チャートで分かりやすく示し(第2-3-13図)、今回の予算案により50%以上の確率で財政目標を実現できるといった評価を行っている。
このような専門性の高い財政政策機関の設置が欧州を中心に広がっており、OECDの政策勧告でも取り入れられるようになっている。
また、アメリカの議会予算局(CBO)やカナダの議会予算局(PBO: Parliamentary Budget Office)は、エコノミストを中心とする専門的知見をもつ職員が独立して経済財政見通しを行い、議会における審議に重要な参考資料を提供しており、実質的には前述のような財政政策機関と同じ役割を果たしている。
さらに、EU加盟国については、欧州委員会が経済見通しの作成や、成長安定協定に照らした加盟各国の財政政策スタンスの評価を行っているが、ギリシャ財政危機を契機に各国財政の評価・監視機能を高めるべきとの声が内外で高まっている。例えば、ECBは、欧州委員会の中に卓越した専門人材を集めて、各国の財政状況を評価し、欧州理事会等に報告する組織を立ち上げるべきとの提言を行った。こうしたことから、現在、欧州委員会では経済・財務総局(DG ECFIN)の組織再編により体制強化を図っている。
財政政策運営に関わる組織の在り方については、国の成り立ちや置かれた環境にも関わるため、ベスト・プラクティスを一概に論じることは難しい。しかしながら、政治的な財政赤字拡大バイアスの存在や、予算の前提となる見通しが楽観的になりがちであることは多くの国でみられる事象であり、予算作成機関とは別に、こうした専門性の高い財政政策機
関の役割は着実な財政再建を進める上で重要と考えられる。 |
|
●3.財政再建とその他の政策との関係
|
●(1)財政再建と金融政策
財政再建が経済に及ぼす短期的な悪影響を和らげるために、緩和的な金融政策を実施することも、財政再建の実効性・持続性を高める上で有効である。その事例の一つとして、アメリカのクリントン政権期の取組が挙げられる。クリントン政権期では、第4節で詳述するように精力的に財政再建策が進められる一方、景気が回復局面に入った後もしばらくは利上げに慎重な姿勢が採られ、金融面においても緩和的な金融政策が実施されたことが財政再建を後押しした。これにより、財政再建は軌道に乗り、98年度から01年度にかけて財政収支は黒字となった(第2-3-14図)。
90年代のFFレートの水準について、テイラー・ルールによって導かれる理論値と照らしてみると、景気回復局面に入った92〜93年においても大きく理論値を下回っており、S&L危機後のバランスシート調整への考慮もあって緩和的な水準が維持されたことがうかがえる。アメリカでは80年代から90年代にかけて比較的テイラー・ルールに沿った形で金融政策が実施されてきたが、90年代前半におけるこうした緩和的な措置は、早期引締めによる実体経済の腰折れを回避し、結果としてその後の持続的な景気回復を導く役割を果たしたと考えられる。
なお、クリントン政権期の財政再建は、政府の財政再建に対するコミットメント、国民に対する十分な説明と信認の確保により、市場から高く評価され、長期金利も低下し、実体経済を下支えした。大統領就任後初のとりまとめとなった94年度予算案は、財政再建策を盛り込んだ緊縮的な内容となったが、議会はこれに強く反発し審議は難航した。しかし、最終的には当初案に沿った形で予算が成立し、クリントン政権の財政赤字削減に取り組む力強い姿勢が市場で高く評価されることとなった。当時の大統領経済諮問委員長らによる評価にもあるとおり、こうしたプロセスを経て財政再建の実現性に対する市場の信頼を得た結果、リスクプレミアムの上昇による金利上昇が回避されたと考えられる
。
こうしたことから、この事例は財政再建と緩和的な金融政策が相乗効果を発揮した好例といえる。
●(2)規制改革、労働市場改革による潜在成長率の上昇を通じた財政再建
構造改革は、歳出削減のための個別の財政再建策と関連しているだけではなく、潜在成長率の上昇に寄与することにより、財政収支GDP比改善の上で分母対策に資するものである。ここでは、民営化、規制改革の取組事例について考察する。
(i)政府部門の民営化
政府部門の民営化は、業務運営を効率化する効果が期待されるとともに、公務員数の削減により、実質的には政府支出削減の効果も持ち合わせている。例えば、オーストラリアでは80年代より電気・通信、航空・鉄道を中心とした国営企業の民営化や資産売却が行われた。ニュージーランドにおいても、88年以降、鉄鋼、郵便、航空、通信等の国営企業の民営化が実施されている
。
(ii)規制緩和
オーストラリアでは、95年から国家競争政策が実施されている。これは、従来政府部門が独占していた分野に官民競争入札(市場化テスト)を導入したものであり、公共サービスのコスト削減が図られるとともに経済活動における競争制限的行為の禁止範囲を拡大し、徹底した規制緩和を実施することとなった。
また、オーストラリアでは、労働市場の規制緩和も実施されている。96年に労働市場の規制緩和が実施された。ここでは、硬直的な労使慣行制度の改善や、前述の官民競争入札を利用して、就職あっせん・再就職サービス提供分野への競争導入が実施され、労働市場の柔軟化が図られた。
こうした構造改革を背景にオーストラリアの全要素生産性(TFP)の伸びは上昇し、OECD及びオーストラリア準備銀行の推計によれば、70年代及び80年代には0.75%程度であったTFP上昇率は、90年代には2%まで上昇したと推計されている。TFP上昇率が高まったことにより、オーストラリアの潜在成長率は上昇し、一連の構造改革は結果的に財政再建にも寄与したと評価できる。
|
|
●4.財政再建策の評価
|
以上、各国の成功事例を概観したが、財政再建を達成するためのポイントを整理すると、以下の4点に要約される。
●(1)緩やかなペースでの着実な財政再建による成長との両立
歳出削減、歳入増加等の財政赤字削減策(財政収支GDP比の分子対策)をしっかりと進め、構造的財政赤字を着実に削減していくことが重要である。ただし、削減策の実施にあたっては、景気循環に配慮する必要がある。財政再建には少なからず景気を下押しする効果を伴うため、景気回復局面に財政再建を開始することが望ましい。循環的要因による財政の下押し圧力を緩和するためにも、景気動向に十分留意し、適切なタイミング及びペースを選択することが求められる。
●(2)財政再建の実効性・持続性を高めるための制度・仕組みづくり
財政再建の実効性・持続性を高めるための制度・仕組みをつくることが求められる。例えば、財政赤字削減策を着実に遂行するための法的枠組みを設けることも有用である。その際、エスケープ・クローズのような非常時への対処措置を設けることも重要であるが、同時に緩い運用や恣意的な運用によって実効性が失われないようにすることも必要である。また、予算編成プロセスを改革し、内閣のリーダーシップを強化する一方、所管分野内の再配分については大臣の裁量を拡大することも重要である。さらに、最近の動きとしては、予算作成機関から独立した専門性の高い財政政策機関による見通しの作成や財政政策の評価等がみられる。
●(3)財政再建に対する国民の理解の確保
財政再建に対する政治の強いコミットメントと、国民からの理解の確保も不可欠である。これらと財政再建は相互補完的な関係にあり、財政再建の実現性・継続性を高めるための重要な要素である。また、財政再建の目標・工程・ルールを明確にするとともに、政府の強いコミットメントを通じて財政再建に対する市場の信認を確保する必要がある。さらに、これにより、家計や企業にとっての先行きの不確実性の低下やリスクプレミアムの低下等を通じて、財政再建に伴う景気の下押し圧力を抑制する効果も期待できる。
●(4)規制改革・金融緩和等による補完
経済成長を支えるための各種の施策に取り組み、財政再建を支えることも有効である。規制改革あるいは労働市場改革等を通じて潜在GDPの底上げを図ること(分母対策)が重要である。また、緩和的な金融政策が維持され財政再建を補完することが期待される。 |
 |



|
|
●第4節 先進各国の財政状況と財政再建の取組
|
ここでは、先進主要国を中心に、比較的財政状況が良好であると考えられる国や財政状況に特に注目が集まっている国等、10か国・地域について、財政の現状や財政再建の取組等について各国・地域ごとに概観する。
対象期間は、原則として、おおむね1990年前後から最新時点までとしている。財政収支の範囲は、一般政府ベース(中央政府、地方政府及び社会保障基金を含むベース)を基本としているが、国によっては政策目標のベースが一般政府ではない場合もあり、その際は、各国が目標としているベースでみることとしている。
以下、アメリカ、カナダ、EU、ドイツ、フランス、スウェーデン、スペイン、英国、オーストラリア及び韓国の順にみていく。
|
|
●1.アメリカ
|



|
●(1)財政の現状(一般政府ベース)
アメリカでは、多くの州・地方政府で均衡財政ルールを採用しているため、一般政府ベースでみた財政収支は、おおむね連邦政府における財政収支の動きを反映したものである。過去30年における財政収支の推移をみると、80年代は財政赤字の拡大期、90年代は財政再建期、2000年代は財政赤字の再拡大期と位置付けることができる(第2-4-1図)。
●(2)連邦政府財政の現状
●財政収支・政府債務残高
10年度の連邦政府財政赤字は、1兆2,941億ドル(GDP比8.9%)と、過去最大となった09年度の赤字額(1兆4,157億ドル、GDP比10.0%)を下回ったものの、引き続き1兆ドルを超える大幅な赤字となっている(第2-4-2図)。内訳をみると、歳入は、景気の緩やかな回復に伴い、法人税を中心に前年度からやや増加した。一方、歳出は、不良資産救済プログラム(TARP:Troubled Asset Relief Program)(1)による企業向け支援が大幅に縮小したことから全体では減少したものの、社会保障関連支出を始め多くの項目では全般的に拡大した。
10年7月に公表されたOMBによる年央改定見通しによれば、11年度及び12年度の財政赤字は、1兆4,160億ドル(GDP比9.2%)、9,110億ドル(同5.6%)と高水準が続くものの、徐々に減少すると見込まれている。ただし、ベビーブーム世代の退職等を背景に医療・社会保障関連費が徐々に拡大する見通し等から、15年度以降は再び増加に転じ、GDP比4%程度の水準で推移することが見込まれる。
一方、連邦政府債務残高(民間保有分)をみると、危機対応による財政支出の拡大等により債務残高は急増しており、10年度はGDP比62.2%となるなど、危機以前の水準(同約40%)から大幅に拡大している。アメリカ行政管理予算局(OMB)によれば、12年度以降は、GDP比70%を超える規模で推移する見通しであるが、これは1950年度(同80.2%)以来の水準である。
●海外部門の国債保有比率
連邦政府財政の特徴として、海外資金への依存度が高い点が挙げられる。国債保有比率をみると、海外の居住者による国債保有は、09年度は46.4%となっている(第2-4-3図)。09年度は、安全資産への逃避を反映して国内の家計や金融機関による国債保有が進んだことにより、08年度に比べて海外保有比率は若干低下したものの、海外のシェアは依然として高い。政府の財政再建に対するコミットメントを明確に示し、国内・国外を通じた安定的な資金調達を維持することが不可欠である。
●(3)連邦政府における財政再建の取組
以下では、80年代以降の各政権における財政再建の取組について概観する。
(i)80年代後半の財政再建(レーガン政権)
81年に発足したレーガン政権は、70年代のスタグフレーションと国際競争力の低下により衰えた国力を取り戻すため、サプライサイドの経済政策(レーガノミックス)を推進した。具体的には、国防支出を除く歳出の伸びの抑制、大幅減税・税制簡素化、規制緩和、緊縮的金融政策等を実施した。これにより、インフレの抑制や景気の回復等、一定の成果をもたらした反面、財政収支と経常収支の巨額の赤字(双子の赤字)をもたらすこととなった。大幅な減税と軍事支出の拡大により、財政赤字は、86年度には2,212億ドル(GDP比5.0%)にまで達した。
こうした状況を打開するため、80年代後半に財政赤字削減に向けた議論が本格化した。議会が財政再建に向けて立案し、85年に均衡予算・緊急財政赤字削減法(いわゆるグラム・ラドマン・ホリングス法。以下、GRH法という。)が成立した。
<GRH法による財政再建の枠組み>
85年12月に成立したGRH法では、86年度から90年度までの各年度の財政赤字目標額を設定し、91年度には均衡財政を達成することが目標とされた。また、予算編成における財政赤字額が当該年度の目標額を100億ドル以上超過する場合には、社会保障関係費や利払い費などの例外項目を除き、大統領による一律歳出削減命令により歳出が削減されることとなった。なお、GRH法による枠組みは、歳出削減による財政再建を目指すもので、増税による再建は考えられていない(第2-4-4表)。
<80年代後半の財政再建の評価>
大規模減税の実施や国防費、利払い費の拡大に伴う歳出増等により、初年度から財政赤字目標額と実績が大きくかい離する事態となるなど、財政再建は計画通りに進展しなかった。87年にはGRH法を修正し、均衡財政の達成目標を93年度に先延ばししたものの、その後も毎年度の目標額から実績が大幅にかい離するなどほとんど機能せず、財政再建は頓挫した(第2-4-5表)。
また、制度上及び運用上の問題として、以下の点が指摘されている。第一に、一律歳出削減命令については、年度当初の予算策定段階で赤字額が目標額を上回った場合に実施が限定された。このため、年度途中に成立した補正予算等により歳出額が増えたり、あるいは当初期待したほど歳入が得られなかったりして、目標額を上回る赤字が発生した場合には拘束力がなかった。第二に、GRH法で目標としている財政赤字額は、社会保障基金の収支を含めて計算されており(統合予算ベース)、社会保障基金の黒字によって、財政赤字が本来財政再建の尺度とすべき額よりも過小に計上されるという問題が生じた。第三に、OMBによる財政赤字見通しは、議会や民間機関等の見通しに比べて楽観的なものとなる傾向がみられた。
(ii)90年代の財政再建(先代ブッシュ政権、クリントン政権)
レーガン政権期における国防費増加や大幅な減税措置等により、GRH法成立後も財政収支は改善せず、財政赤字は92年度には統合予算ベースで2,903億ドル(GDP比4.7%)、オン・バジェットでは3,404億ドル(GDP比5.5%)に達した。こうした状況の中、先代ブッシュ政権は、GRH法の反省を踏まえ、90年代の財政再建の基本的枠組みとなる90年包括財政調整法(OBRA90:Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990)を成立させた。93年1月に発足したクリントン政権でも、ブッシュ政権による財政再建の枠組みが踏襲され、財政赤字削減策の更なる強化を行った結果、景気回復に伴う税収増の効果とあいまって、98年度には1969年度以来となる財政収支(統合予算ベース)の黒字転換を達成した(オン・バジェットでは99年度に黒字化)。
<財政再建の枠組み>
先代ブッシュ政権期ではOBRA90を制定し、95年度までの5年間で約5,000億ドルの財政赤字削減目標とそれを実現するための歳出削減策・増税策を定めた。さらに、GRH法に代わる新たな財政ルールとして予算執行法(BEA90:Budget Enforcement Act of 1990)を設け、裁量的経費に上限を設ける「キャップ制」や義務的経費の拡大を抑制する「ペイ・アズ・ユー・ゴー原則」、総財政赤字額(MDA:Maximum Deficit Amount)の設定等の仕組みが導入された(第2-4-6表、第2-4-7表)。
また、GRH法の経験を踏まえて、補正予算も一律削減命令の対象に含めたり、財政収支を統合予算からオン・バジェット予算に対象を変更するなど、制度面・運用面の強化を図った。さらに、景気変動に対しては、大統領が経済情勢に応じて財政赤字上限額を調整できる仕組みや、キャップ制やペイ・アズ・ユー・ゴー原則における一律削減措置を一時的に停止する条項等を規定しており、非常時に対処するための措置が組み込まれた。
こうした財政再建手法は、クリントン政権期において成立した93年包括予算調整法(OBRA93)、97年財政収支均衡法(BBA97)に引き継がれ、更なる歳出削減策(メディケア及びメディケイド、国防費等の削減)や歳入増加策(所得税及び法人税の税率引上げ、燃料課税の増税等)を加えて、財政赤字削減を推進した。
<財政再建の評価>
先代ブッシュ政権下で新しい財政再建策が進められたが、湾岸戦争やS&L危機を受けて、裁量的経費が大幅に拡大したことに加え、メディケアやメディケイドを含む社会福祉関連支出、利払費等の義務的経費も膨張し、OBRA90による財政赤字削減効果が相殺される形となった。また、90年から91年にかけて景気が停滞したことにより、歳入が大幅に減少したことも大きく影響した。
クリントン政権期における財政収支黒字化の実現にあたっては、冷戦終結による国防費の減少(「平和の配当」)のほか、当時の大統領経済諮問委員長らによる評価にもあるとおり、ITの活用による生産性上昇期(「ニュー・エコノミー」)と重なったことが大きく影響したと考えられる。景気回復に伴う税の自然増収、特に株価高騰によるキャピタルゲインの増大を反映した個人所得税収の増加が、財政の改善に大きく寄与した(第2-4-8図)。また、第2章第3節で述べたとおり、緩和的な金融政策を継続できたことも、緊縮財政と経済成長の両立を果たす上で重要な役割を果たし、規制緩和及び投資促進策等の成長促進策の実施と相まって、好景気を支える要因となったと考えられる。
クリントン政権では、こうした環境の中、OBRA90の枠組みを踏襲して精力的に財政再建に取り組んだ結果、財政赤字は92年度の2,900億ドルをピークに毎年度400〜600億ドルのペースで減少を続け、98年度には統合予算ベースで財政収支の黒字転換を果たした。その後も、2001年度までの間、財政収支黒字を維持した。クリントン政権期では、各支出項目の伸びが他の年代に比べて大幅に縮小しており(第2-4-8図)、新たに確立された財政ルール、財政規律、財政赤字削減策等が、歳出の拡大を抑制する上で有効に機能したものと考えられる。
(iii)オバマ政権の財政再建
08年秋の世界経済・金融危機の発生以降、税収の落ち込みや積極的な財政出動による歳出拡大等を背景に、連邦政府の財政赤字は急速に拡大したが、経済の回復の見通しが次第に強まってきたことを受け、財政再建に向けた取組が本格化している。
オバマ政権における財政再建の目標については、大統領就任後の09年2月に行った議会演説で、ブッシュ政権から引き継いだ約1兆3,000億ドルの財政赤字を任期(13年1月まで)中に半減することを公約しているほか、10年2月公表の予算教書の中で、中期的な財政目標として「15年までに基礎的財政収支の均衡」(財政収支GDP比では約3%に相当)を掲げており(第2-4-9図)、具体的措置を検討するための超党派委員会(財政責任と財政改革に関する国家委員会)を設置している。同委員会は、10年12月1日までに基礎的財政収支の均衡を達成するための政策提言をとりまとめることとしており、月に一度のペースで検討を行っている。
財政赤字削減の具体的な措置としては、(i)財政規律の強化、(ii)政策課題ごとのコスト削減・歳入強化、という二つの取組に分けられる。財政規律強化の取組としては、安全保障を除く裁量的経費の伸びを3年間凍結する措置や、ペイ・アズ・ユー・ゴー原則の復活が提案されている。また、コスト削減・歳入強化の取組としては、高所得層への増税、金融機関や保険業界への課税、医療保険制度の改革等が提案されている。これらのうち、ペイ・アズ・ユー・ゴー原則及び医療保険制度改革については、関連法が既に成立しており、こうした取組を通じて20年度までに2.1兆ドルの財政赤字を削減することが想定されている(第2-4-10表)。
連邦政府財政に対する今後のリスク要因としては、州・地方政府財政の動向、GSEの経営問題等が挙げられる(詳細は、第1章第3節を参照)。
|
|
●2.カナダ
|



|
●(1)財政の現状
カナダは90年代に実施された一連の財政再建策の成功により、97年度以降世界金融危機発生までほぼ毎年財政黒字を達成し、現在もG7の中で最も良好な財政状態を維持している。連邦政府の財政収支をみると、08年度は景気後退と減税により法人税収や商品・サービス税収を中心に歳入が減少したことに加え、雇用保険給付を始めとする個人や州・地方政府への財政移転、直接支出等の政策支出増によって歳出が増加したことから、12年ぶりに財政赤字を記録した(第2-4-11図)。09年度も更なる歳入減と米自動車会社(GM、クライスラー)支援を含む景気刺激策等の歳出増により、財政赤字はGDP比3.6%まで拡大したものの、政府見通しによると10年度は同2.8%に低下し、15年度には同0.1%の黒字に転換すると見込まれている。また、債務残高については11年度に同35.3%でピークとなり、15年度には同30.8%まで低下するとされている(第2-4-12図)。
●(2)財政再建の取組
●財政再建取組の背景
カナダでは、70年代の石油ショックにより経済成長が鈍化し、景気後退や法人税率引下げ等の税制改正により歳入が減少する一方で、歳出が増加したことから、慢性的な財政赤字状態となっていた。さらに、70年代後半以降は、インフレ抑制のための高金利政策によって利払い費が膨張し、借入れへの依存をさらに高める悪循環に陥った。一般政府財政赤字をみると、85年度にGDP比8.6%と1つのピークを迎えたが、80年代末には景気回復等もあり、一時的に改善がみられた。しかしながら、90年代に入ると景気悪化から財政収支も再び悪化し、一般政府債務残高がGDP比90%を超える水準まで上昇するなど、G7ではイタリアに次いで悪い状況にあった。
以下では、80〜90年代にかけて実施された財政再建への取組とその時代背景を、政権別に整理する。
●マルルーニ政権(保守党)期(84〜93年)
現在の良好な財政状態は90年代にクレティエン政権が実施した財政再建の成功によるところが大きいとされるが、これを検証するに当たっては、成功の素地を作ったとされるマルルーニ政権による改革も併せて考える必要がある。マルルーニ政権は、税制改革等に取り組む一方で、同時期に英米で進められていた新自由主義的な行政改革を強く意識した歳出削減を試みた。
(i)財政再建策
まず、連邦政府の政策コスト見直しによる歳出削減を図るため、84年に副首相のニールセンをトップとするニールセン委員会を設置した。委員会に置かれた作業部会には民間人も多数登用され、86年には不要プログラムを廃止し、有用プログラムに予算を回すための、膨大な検討結果をまとめた報告書が下院に提出されたが、議会では十分な検討は行われず、成果は限定的なものとなった。
また、マルルーニ政権は、歳出削減を含む抜本的な行政改革を図るものとして、各省庁に柔軟な支出管理権限を認める「大臣の権限及び説明責任拡大イニシアティブ(IMAA:Increased Ministerial Authority and Accountability Initiative)構想」や連邦政府から地方への権限委譲等を盛り込んだ「公共サービス2000」を発表したが、政治的意志や実践手段等の欠如により実効性を上げることはできなかった。
他方、税制改革としては、85年以降法人税及び所得税の改革、90年には連邦税として付加価値税の導入を実施した。これらは、中長期的には政府の歳入増に寄与したが、短期的には国民負担を目に見える形で増大させることになった。
(ii)マルルーニ政権による財政再建の評価
マルルーニ政権は様々な分野にわたる財政再建を試みたが、総じて成果をあげることはできなかった。改革が失敗した要因としては、政権全体としては憲法改正と米加自由貿易協定の締結等に注力し、行財政改革に対する関心が希薄であったため、歳出コントロールに失敗したことに加え、歳出削減による公共サービス低下を懸念した国民の支持が消極的なものに止まったことなど、政府・国民双方に財政赤字への認識の甘さと現状変革に対する躊躇があったことが指摘されている。
さらに、予算編成システムの根本的欠陥により、常に歳出増加圧力が存在していたとの指摘もある。80〜94年まで採用された政策歳出管理システム(Policy and Expenditure Management System)は、予算の分野別支出限度額を設定し、複数省庁関連する分野については関係閣僚委員会で再配分する仕組みであったが、財政責任を負うインセンティブが働かず、各大臣は歳出削減ではなく、新政策に充てられる予備費(Policy Reserve)の獲得に尽力したことから、結果的に大幅な支出増につながったとされる
。
こうした中、インフレに伴う金融引締めで利払い費が増大したことに加え、景気後退に伴う歳入伸び悩みや失業給付の増大等によって財政状況は再度悪化に転じた。国民の間では財政再建の要請が高まり、93年の総選挙において保守党は大敗し、9年ぶりに自由党政権が誕生することとなった。
●クレティエン政権(自由党)期(93〜03年)
財政改革を最優先課題とするクレティエン政権は、92年度にGDP比5.6%に達した連邦財政赤字を96年度までに3%以下まで削減することを選挙公約として掲げており、これを達成するために各年度の赤字削減目標値を設定し、以下にみるとおり歳出削減を主とした急速な財政再建に取り組んだ。
(i)プログラム・レビューの導入(94年)
歳出削減の中心となったプログラム・レビューは、一律的な予算削減ではなく、政府の役割を根本的に再定義し、行政の質を変えることを目的として、6つの基準に基づいて既存政策の徹底的な見直しを行うものであった(第2-4-13表)。各省庁には閣議で承認された支出削減目標が与えられ、具体的な政策見直し作業が各省庁自身によって実施された。見直しの対象となったのは連邦政府の直轄政策支出であり、具体的な削減方法は、連邦公務員の削減(32万人(94年)→26.5万人(98年))や政府系企業の民営化、政府サービスのエージェンシー化、企業向け補助金の削減等であった。こうした結果、連邦政策分野においては、94〜98年度にかけて総額111億カナダドル(21.5%減)の削減計画が予算案に盛り込まれた。
プログラム・レビューによる歳出削減が成功した理由としては、財政危機の認識が当時一般的に広がっていたこと、財務大臣が削減について首相から強力な支持を受けていたこと、新政権であったため、閣僚がまだ自らの所管分野に固執するようになっていなかったことなどが指摘されている。また、マルルーニ政権期のニールセン委員会の経験を踏まえ、閣僚からの指示の下で各省庁自らに見直しを実行させたことが、実効性の確保につながったとされる。
95年には、時限措置であったプログラム・レビューを恒久化し、予算及び歳出を包括的に管理する仕組みとして、歳出管理システムが導入された。これにより、新規プログラムは予備費を使用せずに通常の予算編成の中で賄い、全ての新規プログラムと既存プログラムの予算増額は優先度の低い既存プログラム資金の再配分により対応することとなった。このため、各省庁には既存プログラムを見直すためのビジネスプラン(中期的業務計画)の作成が義務付けられるとともに、96年からは説明責任の向上を目的として、議会に提出する報告書の改善も実施された。
(ii)中期財政フレームの導入
財政赤字の解消を主目的とする予算編成を行うため、95年度予算編成からは、5年先までの経済見通しを踏まえて2年分の財政計画が作成されることとなった。この見通しには、旧予算編成制度における政府見通しが楽観的過ぎたとの反省から、民間による見通しを「慎重要因」を考慮して更に下方へ調整したものが用いられる。また、財政計画には不測の事態に備えて予備費(Contingency Reserve)が導入され、不使用の場合は債務削減に充当される。こうした慎重な(prudent)見通しに基づく比較的短期の中期財政フレームには、政府の財政政策に対する信頼を回復させるとともに、財政赤字削減の目標達成を確実にするねらいがあった。
(iii)その他の改革
予算編成プロセスの透明化を図り、広く国民に予算への提案機会を提供するものとして、事前予算相談プロセスが94年より導入された。これは下院の財政担当常任委員会が全国各地でフォーラムを開催するもので、利害関係者・機関の他、一般の国民も意見を述べることが可能である。収集された意見は報告書として議会に提出されることとなっている。
また、連邦政府による政府間移転の歳出削減として、州政府に対する交付金及び権限関係の見直しが図られた。これは、従来の定着プログラム財政保障(医療、保健、高等教育助成 EPF:Established Programs Financing)及びカナダ社会扶助制度(社会扶助、福祉プログラム CAP:Canada Assistance Plan)を統合してカナダ保健・社会移転(CHST:Canada Health and Social Transfer)に一本化して簡素化を図り、州の裁量範囲を拡大する一方で、従来CAPに導入されていた半額補助を廃止し、一定額補助への切替えを実施することなどによって、移転総額を減額するものであった(96年度導入)。なお、州レベルにおいても、連邦政府からの財政移転減少に加え、90年代初めの景気後退によって財政が急速に悪化したため、均衡財政を始めとする財政ルールの策定が進められ、歳出削減と増税による財政再建が図られた。
連邦政府ではその他、失業保険給付の引下げや公的年金制度改革といった社会保障制度改革、たばこ税率の引上げ等、広範囲にわたる改革が実施された。
(iv)財政改革の結果
こうした一連の改革の結果、連邦政府の財政赤字は目標を上回る速度で減少し、96年度にはGDP比1%まで低下、97年度には単年度ベースで財政黒字を達成した。93〜98年度にかけての財政収支改善幅はGDP比5.8%となり、うち歳入増による改善が同1.6%、政策支出の削減による改善が同3.9%と、と、歳出削減中心の財政再建となった。カナダの構造的プライマリー収支(一般政府ベース)をみると、95年にプラスに転じた後、2000年頃にかけて大幅なプラスを記録しており、財政構造改革が進展したことを示唆している(前掲第2-3-1図)。
(v)実体経済及び金融政策との関係
カナダ経済は地理的な特性もあってアメリカ経済との結びつきが強く、アメリカの景気変動の影響を受けやすい(第2-4-14図)。クレティエン政権が誕生し、財政再建を開始したタイミングをみると、アメリカに次いでカナダでも92年に景気後退が終了し、既に景気回復期に入っており、アメリカ経済の回復が輸出増をもたらし、カナダ経済の改善に寄与したことが考えられる。また、GDPギャップが92年を底にマイナス幅が縮小に転じたのとほぼ同時に循環的赤字も縮小に向かい、また、構造的赤字も縮小に向かったことから、経済回復が財政再建のスピードを押し上げたことが示唆される。他方で、公務員数や公共投資の削減といった歳出削減策は、失業率の高止まりを招くなど、経済回復への下押し圧力をもたらすこととなった(第2-4-15図)。さらに、金融との関係をみると、この間の緩和的な金融政策と実質短期金利の低下及びカナダドルの減価が、経済活動を下支えしたことが指摘されている
。
(vi)クレティエン政権による財政再建の評価
クレティエン政権による急速な財政再建の成功要因としては、まず、財政赤字に対する国民の強い危機感を背景として誕生した安定的な長期政権が、強いリーダーシップを発揮して改革を推進したことが挙げられる。具体的には、予算編成プロセスの大幅改革やプログラム・レビューの実施にみられるように改革の実効性を確保するとともに、事前予算相談プロセスやその他の広報活動を通して国民の理解を得る努力が結実したと考えられる。
また、財政再建の大半を、増税ではなく歳出削減という手段により実施したが、背景にはマルルーニ政権期に実施された税制改正や構造改革の効果が、クレティエン政権期になって本格的に効果を発揮したことも挙げられる。例えば、米加自由貿易協定による貿易自由化とそれに伴う規制緩和は、一時的にカナダ経済に打撃を与えたが、長期的には国際競争力強化と経済活性化に寄与することとなった。こうした経済・税制面での改革の先行が、クレティエン政権期における成功の素地を形成したとも言える。さらに、経済が回復へ向かうタイミングで財政再建に取り組むことで、税収増加に追い風を受けるとともに、歳出削減による経済への下押し圧力を相殺することができたことも大きな成功要因であろう。
こうした政治的・経済的条件とタイミングの一致が、クレティエン政権による急速な財政再建の成功に寄与したと考えられる。
|
|
●3.EU
|



|
●(1)財政の現状
EUにおいては、例外的な場合を除き、一般政府財政赤字GDP比を3%以内に、一般政府債務残高GDP比を60%以内に維持することが求められている。財政政策が各国の主権にゆだねられているEUでは、財政規律は単一通貨ユーロの信認を維持する上で核となるものであるにもかかわらず、ユーロ圏全体でみると、現在では、ほとんどの国において財政規律を遵守できていない。
ユーロ導入に向けた各国の財政再建により財政状況は改善していったものの、経済成長が鈍化すると悪化し、世界金融危機が発生した後の09年には、各国の景気刺激策や税収減等により更に悪化した(第2-4-16図)。
●(2)財政再建の取組
●背景
93年にマーストリヒト条約が発効し、経済通貨統合(EMU)を三段階で実施することとされ、99年1月からの第三段階で経済通貨統合が完成し、単一通貨ユーロが導入されることとなった(紙幣、貨幣の流通は02年1月から)。単一通貨ユーロ導入のために、同条約では、第二段階の94年1月から98年12月までのマクロ経済政策の協調強化において、ユーロに参加する条件として、経済収れん条件を達成することが義務づけられた。経済収れん条件のうち財政条件については、一般政府財政赤字GDP比を3%以内に、一般政府債務残高GDP比を60%以内にするよう決定された。このため、EU加盟国でユーロへの参加を希望する国は財政条件の達成に向け財政再建を進め、98年春にユーロに参加する11か国が決定し、99年1月からユーロが発足した。
しかし、ユーロ発足後は、景気後退や、一部の国での財政規律の緩みにより、財政規律違反が広がることとなった。
08年9月に世界金融危機が発生すると、景気後退に歯止めをかけるために各国政府が打ち出した景気刺激策は、景気を下支えする役割を果たしたものの景気後退による税収減もあいまって、財政状況を大幅に悪化させた。この結果、特に一部の国について、市場では財政の悪化に起因するソブリン・リスクに対する懸念が高まった。10年5月にはギリシャ財政危機がピークに達し、財政状況に対する懸念はヨーロッパ全体に広がっていった。
●財政政策の枠組み
財政政策が各国の主権にゆだねられているEUでは、財政規律の遵守が単一通貨ユーロの信認にとって重要であるため、以下のような財政ルールが設けられている。
(i)安定成長協定(97年決定)
「安定成長協定(Stability and Growth Pact)」では、財政規律の遵守にかかる具体的な手続きを定めるともに、「年間の一般政府財政赤字をGDP比3%以内」、「一般政府債務残高をGDP比60%以内」の財政規律の維持を義務づけている。同協定は、ユーロ参加国だけでなく、英国などのユーロ非参加国にも適用されるが、罰則の適用はユーロ参加国に限定されており、当該国のGDP比0.5%を上限に、EUが制裁金を課すこととなっている。ただし、深刻な景気後退期等の場合には例外規定があり、例えば、実質経済成長率が▲2%以下の場合には、制裁金は課されない
。
なお、05年には、安定成長協定の見直しが行われた。現行の一般政府財政赤字GDP比3%以内と一般政府債務残高GDP比60%以内の財政基準の維持を改めて堅持しつつも、過剰財政赤字是正手続の基準を緩和した。主な緩和事項は、一般政府財政赤字が3%を超えても許容される「深刻な不況期」は、原則として成長率が▲2%を超えた場合に限定されていたが、成長率がマイナスか、潜在成長率を下回る状況が長引く場合にも広げられた。また、過剰財政赤字の是正期限について、従来は赤字発生の年から数えて実質3年目までとなるような規定とされていたが、中期的な経済動向といった関連する要素を考慮して、実質4年目までとすることができる規定とし、過剰財政赤字是正手続中に予期せぬ経済事象が発生した場合には、更に1年延長できることとした。
一方、具体的な規定がこれまでなかった中期目標について明記された。それまで、中期目標は、「収支均衡又は黒字」との画一的な規定だったが、国ごとに公的債務残高や成長率などを考慮して定め、その目標に向かって各国は年にGDP比0.5%ポイントをベンチマークに構造的財政収支を改善していくべきとされた。
(ii)過剰財政赤字是正手続
安定成長協定に基づいてユーロ参加国は、財政運営の指針となる中長期の「安定プログラム」を、毎年12月1日までに提出する。なお、ユーロ非参加国の場合は「収れんプログラム」と呼ばれている。このプログラムで報告された財政状況を踏まえて、欧州委員会は、EU加盟国が過剰財政赤字となっていないかどうか等を評価する。欧州委員会は、加盟国による義務違反の事実ないしその危険性があると判断されるときは、ECOFINに報告することになっている。ECOFINは、当該国の財政赤字が過剰であるかどうかについて判定し、必要に応じて財政赤字の改善を勧告する。なお、この段階において、勧告は公表されないが、所定の期間内に必要な措置が採られないときは、ECOFINはこれを公表することができる。しかし、それでもなお効果的な措置が採られない場合には、ECOFINは必要な措置を採るよう警告したり、罰金を含めた制裁措置を当該国に課すことができる(第2-4-17表)。
なお、世界金融危機後、多くの国で財政赤字が拡大し、現在、安定成長協定に基づく財政規律は、ほとんどの国において遵守できていない。このため、2011年から14年までに、27加盟国のほとんどが、過剰財政赤字を是正することを求められている。現在、過剰財政赤字是正手続の対象となっていないのは、ルクセンブルク、エストニア、スウェーデンの3か国のみである。
●構造改革
EUでは、規制緩和、構造改革、生産性の向上、労働市場の柔軟化等による持続的な経済成長を達成することを目指し、10年間の経済成長戦略を策定している。
(i)リスボン戦略
EUでは、2000年3月のリスボンEU首脳会議において、「リスボン戦略」として、10年間の期間を念頭においた経済・社会政策についての包括的な方向性が決定された。「より多い雇用とより強い社会的連帯を確保しつつ、持続的な経済発展を達成し得る、世界で最も競争力があり、かつ力強い知識経済となること」を目標とし、年平均3%の経済成長、就業率70%、すべての学校でのインターネット接続環境整備等、様々な分野で目標が設定された。しかし、目標達成に向けた実績が十分でなかったことから、05年に改定された「改定リスボン戦略」では、戦略の範囲を絞り込み、成長と雇用を重視し、就業率を70%に引き上げることとR&D投資GDP比を3%に引き上げることが重点目標とされた。
(ii)EU2020戦略
10年6月に、リスボン戦略の後継となる今後10年間の成長戦略として「欧州2020戦略」を発表した。同戦略では、就業率の引上げやR&D投資の促進等の構造面での政策を通じて、成長力の強化を図ることとしており、「スマートな成長(Smart Growth)」、「持続可能な成長(Sustainable Growth)」、「あまねく広がる成長(Inclusive Growth)」の実現を目指すこととしている。
また、こうした3つの成長を実現するため、就業率、R&D、環境、教育、貧困といった5つの分野の成長目標を掲げている。主な数値目標は、20〜64歳の就業率を75%に引上げ、R&D投資GDP比を3%に引上げ、温室効果ガス排出量を1990年比で20%削減、高等教育の普及水準を少なくとも40%以上、削減貧困・疎外リスクを抱える者を少なくとも2,000万人削減となっている(第2-4-18図)。
●(3)財政再建にかかる課題
ユーロ圏では、ECBによって金融政策は一律に決定されるに対し、財政政策は各国の主権にゆだねられている。各国の財政規律が遵守されない場合には、ユーロの安定を阻害するおそれがあるため、安定成長協定のような財政規律があり、違反国には制裁措置も用意されている。しかしながら、同協定には例外規定がある上、制裁発動までのプロセスが長いことから、ユーロ発足以来これまで制裁措置が発動されたことがなく実効性がなかった。
また、ギリシャは01年1月にユーロに参加したが、04年11月のユーロスタットの報告書によると、ユーロ導入の審査がなされた99年の財政赤字GDP比は、申告されたデータを上回る3.4%であり、経済収れん条件を満たしていなかったことが後になって判明した。しかし、マーストリヒト条約では、統計値の過少申告による基準のクリアといった事態を想定していないために、実際には経済収れん条件に違反していたにもかかわらず、ユーロ圏からの脱退は求められなかった。
このような制度的な問題点もあり、財政規律違反が広がったことを原因として、ギリシャ財政危機が発生したことを踏まえると、今後、どのように各国の財政規律を維持するのか、安定成長協定の制裁措置も含めた厳格な適用を始めとする経済ガバナンスは、今後のユーロの信認を維持する上で極めて重要である(第1章第4節参照)。
|
|
●4.ドイツ
|



|
●(1)財政の状況
●財政収支と債務残高の状況
90年代以降のドイツの財政収支をみると、90年の東西ドイツ統一に伴い95〜96年に多額の財政支出が生じ、大幅に悪化した。その後、97年にはマーストリヒト条約に定める財政赤字GDP比3%以内の基準を達成(2.6%)し、2000年には黒字に転じた。しかし、その後は再び赤字となり、02〜05年には、景気後退や大規模な減税を背景として、安定成長協定の基準を上回る財政赤字を計上した。
2000年代後半には、メルケル政権が積極的な財政再建を推進し、好景気の影響もあって、07年には黒字に転じた。しかし、08年の世界金融危機後の大規模な財政支出や税収減により、09年の財政赤字は3.0%となっている(第2-4-19図)。
債務残高については、97年以前はマーストリヒト条約で定めるGDP比60%基準を下回っていたが、98年と99年、そして02年以降は上回っている。メルケル政権は、付加価値税率や所得税の最高税率引上げ等を実施し、07年には64.9%まで低下したが、08年の世界金融危機の後に再び増加に転じ、09年には73.4%となっている(第2-4-20図)。
●財政の構造
09年の歳出・歳入構造をみると、歳出は、約5割が社会保障費、約2割が一般財政費となっており、歳入は約7割が租税収入となっている(第2-4-21図)。
●(2)財政再建の取組
(i)財政、予算に関する基本的なルール
ドイツにおける予算制度の主な枠組みには、以下のものがある。
●ゴールデン・ルール(連邦基本法第115条)
ドイツ財政運営における最も基本的なルールであり、国債発行は、発行額を規定した連邦基本法による裏付けを必要とし、その額は予算において見積もられている投資支出総額を超えてはならないというものである。ただし、経済状況によっては例外が認められる。
●中期財政計画
1967年に成立した経済安定成長協定促進法に基づいて導入された5か年の中期財政計画である。連邦・州政府ともに、毎年作成することが義務付けられており、ローリング方式により1年ごとに改定され、予算案提出時に議会に提出される。この中期財政計画において財政収支見通しを示し、財政再建への取組を明確にした上で、それを実施するための具体的な各種施策を政策パッケージとして策定し、実施するというのがドイツにおける財政再建手法の具体的なスタイルとなっている。
●財政計画委員会(FPR)
連邦基本法第109条において、州と連邦は財政予算運営においては独立し、相互依存関係にはならないことが原則として定められている。州、連邦間における財政問題の調整を行うために、財務大臣を始め、連邦政府、州政府、市町村の代表者で構成される財政計画委員会が設置されている。
●その他
その他の制度として、概算要求に先立ち、連邦財務省から各省庁に対して、政府全体の予算額上限等を提示する「予算編成通達」や、中期財政計画の実効性を確保するために、新規施策には同額の歳出削減を条件とする「モラトリアム原則」(94年予算編成より導入)等がある。
(ii)政権別にみた財政再建の取組
以下では、1990年代以降の財政再建の取組を、政権別にみていく。
●コール政権(82年発足、キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU))
東西ドイツ統一後、旧東ドイツ地域支援のため、インフラ環境の整備や失業手当等のための財政負担が生じ、財政赤字は95年にはGDP比9.7%まで拡大した。
こうした状況の中、ドイツが財政再建を達成するための原動力となったのは、93年に発効されたマーストリヒト条約において経済収れん条件が示されたことである。同基準を達成するために、中期財政計画においては財政赤字削減が目標として掲げられ、毎年の予算削減により、財政赤字削減を実施するための施策が政策パッケージとして策定された。そのうち、通貨統合のための参加基準を達成するための取組として特に効果を発揮したのは、「投資と雇用のためのアクション・プログラム」(96年1月策定)と「成長と雇用促進のためのプログラム」(同年4月策定)である。これらの政策パッケージには、中小企業のための連帯付加税の削減、事業税の改革等の税制改革、社会保障支出の削減、労働市場における柔軟性の改善等が含まれていることに加え、97年中に中央と地方全体で500億マルクの歳出削減等が盛り込まれた。
こうした財政再建の取組の結果、財政赤字は97年にはGDP比2.6%となり、マーストリヒト条約の経済収れん条件を達成した。
●シュレーダー政権(98年発足、社会民主党(SPD))
シュレーダー政権は、発足当時は前政権で行われた財政再建路線を引き継ぐ旨を表明しており、政権初期の99年には、2006年までの財政収支均衡を目標とし、これを実施するための「将来プログラム2000」が策定された。この政策パッケージには、社会保障費の削減や補助金の廃止等の歳出削減策が盛り込まれており、財政再建が行われた。
しかし、2000年に策定された「税制改革2000」では、法人税率や所得税率の大幅な引下げが行われるなど、政権全体を通じて、むしろ税制改革を通じた雇用の促進や企業競争力を高めるような減税政策を実施した。
こうした減税政策に加え、同時多発テロやITバブル崩壊による世界経済の減速による税収減、02年8月にエルベ川流域で発生した大洪水に対処するための支出増等を背景に財政収支は悪化し、03年にはECOFINから過剰財政赤字是正勧告が行われた。
●メルケル政権(05年発足、CDU/CSUとSPDの連立政権)
(ア)歳入強化を中心とする財政再建
05年11月、二大政党であるCDU/CSUとSPDが連立協定を発表し、メルケルCDU党首を首班とする大連立政権が発足した。05年に財政赤字がGDP比3%を上回り、06年にECOFINがドイツに対し警告を発するという状況下で、メルケル政権は財政再建策の強化を打ち出した。歳入強化策として、07年の1月から付加価値税率を16%から19%に引き上げるとともに、所得税の最高税率を42%から45%に引き上げた。なお、付加価値税率の引上げによる税収増のうち、約3分の2は財政赤字削減に、約3分の1は社会保険料の引下げに充てるとされた。また、年金支給開始年齢を2012年から29年の間に65歳から67歳に引き上げることを打ち出している。
同時に、潜在成長率を引き上げるための取組として「ハイテク戦略」(06〜09年)を策定し、民間R&D投資を促進するための包括的なイニシアチブとして、(1)医療、環境、交通、安全の4つの優先的分野に重点を置いた市場の創出・拡大、(2)中小企業に重点を置いた産業と研究の連携強化、(3)イノベーション促進に向けた規制改革という3つの目標を設定した。財政赤字は、財政再建の強化や好景気の影響もあり、06年にはGDP比3%を下回るまで改善した。しかし、08年の世界金融危機による景気後退のため税収は減少し、加えて、08年11月と09年1月に打ち出された総額1,000億ユーロの景気刺激策等の影響により財政収支は悪化し、09年12月にECOFINは、13年までを期限とする過剰財政赤字是正勧告を行った。
(イ)歳出削減を中心とする財政再建
これを受けて、10年2月に発表された安定プログラムでは、「2013年まで、少なくとも毎年GDP比0.5%の構造的財政赤字を削減し、財政赤字をGDP比で3%以下とする。」との財政再建への方向性が打ち出されている。
また、10年7月には「2014年までに、財政赤字GDP比を1.5%程度に引き下げる。」との目標が打ち出され、具体的な方策としては、11年から14年までの4年間で816億ユーロ(GDP比で3.4%程度)の財政赤字削減という財政再建策が示された。この再建策には、歳出削減策として、長期失業者への手当等の社会保障費の削減や公務員の1万人以上の削減等が盛り込まれ、歳入強化策として、原子力産業に対する課税や金融危機対応のコストに関する銀行からの負担金徴収等が盛り込まれている。この再建策は、歳入強化よりも、社会保障費や補助金等の削減による歳出削減に重点を置くものである点が特徴的である。
また、09年8月に連邦政府及び州政府の財政ルールを定めた連邦基本法(109条、115条等)が改正された。従来と異なり、連邦政府だけでなく州政府についての財政ルールも規定され、連邦政府については、構造的財政収支を平時にはGDP比で▲0.35%以内に抑制し、州政府については、20年以降構造的財政赤字を許容しないことが定められた。
10年7月には、前述のハイテク戦略(06〜09年)に続き、20年までを対象とする「ハイテク戦略」が策定された。同戦略は5つの分野に重点を置き、各分野において優先テーマを設定している(第2-4-22表)。
●(3)評価
90年代以降のドイツにおいては、主としてコール政権とメルケル政権において財政再建が積極的に行われた。
コール政権における財政再建では、マーストリヒト条約で定められた経済収れん条件を満たし、通貨統合へ参加することを目標とし、これを達成するために中期財政計画と政策パッケージを有効に機能させ、結果として、99年の通貨統合に参加することができたという点では、財政再建は一定の成功を収めたということがいえる。
メルケル政権によって05年に打ち出された財政再建策は、増税を中心に歳入増を図り、財政黒字を達成したが、景気回復による税収増といった追い風があったという点には留意が必要である。歳出削減を中心とする今後の財政再建策の行方が注目される。
|
|
●5.フランス |



|
●(1)財政の現状
フランスでは、91〜93年にかけて景気が後退したことに伴い、財政赤字が急速に拡大し、90年には▲2.4%だった財政収支GDP比は、93年には▲6.4%にまで悪化した。その後、ユーロに参加するための歳出削減や付加価値税の増税の実施等により、97年には財政収支はGDP比▲3.0%となってユーロへの参加が決定し、さらに、景気回復も加わり、2000年まで財政収支の改善が続いた。
しかし、01年以降、財政収支は再び悪化し、一時改善がみられる時期があったものの、世界金融危機による影響等により、09年には財政収支はGDP比▲7.6%に達し、債務残高のGDP比は78.1%となった。この間、フランスは、03年6月と09年4月の2回にわたり、過剰財政赤字是正勧告を受けた(第2-4-23図)。 (第2-4-24図)
●(2)財政再建の取組
●政権・時代背景
80年代後半は、景気回復、歳出抑制を基調とした財政運営、国営企業の民営化等による歳入増により、財政赤字は縮小傾向にあった。しかし、91〜93年には景気の後退により歳入の減少と政府支出の増加から財政収支は急速に悪化し、90年には▲2.4%だった財政収支GDP比は、93年には▲6.4%となった。
ユーロに参加する条件である経済収れん条件達成のために、93年に成立したバラデュール内閣は、「経済・社会再建プログラム」を策定した。雇用対策を重視しつつ、歳出削減や石油製品税の増税を実施した。94年1月には、「財政5か年計画法」を成立させ、財政再建目標を示すとともに毎年の歳出の伸び率を物価上昇率以下に抑えることとした。
95年のシラク大統領就任を受けて発足したジュペ内閣も、経済収れん条件達成のために、歳出抑制や付加価値税率の引上げ等の財政再建を進め、国営企業の民営化も実施した。90年代後半には、景気回復による税収増もあり、97年には財政収支がGDP比▲3.0%となり、98年に通貨統合への参加が決定した。
さらに、97年に発足したジョスパン内閣は、2000年までに財政収支をGDP比▲2%以下にすることを目指し、中央政府及び社会保障会計の赤字削減を進め、2000年の財政収支はGDP比▲1.5%となった。
その後、所得税率の段階的引下げや連帯付加税の段階的廃止等による税収の減少と社会保障費の増大により、財政赤字が再び拡大し、02年には財政収支のGDP比が▲3.2%となり、ECOFINは、03年6月に、過剰財政赤字是正を勧告した。しかし、04年の予算において構造的財政赤字削減への取組がみられたことや景気後退を受けて、同年11月に、過剰財政赤字是正の達成期限が05年まで延長され、制裁手続が一時停止されることが合意された。
引き続き財政再建が進められ、03年には、年金満額受給に必要な保険料の拠出期間の延長等を盛り込んだ年金改革等もあり、06年まで財政赤字が縮小した。
しかし、世界金融危機による景気悪化の影響を受け、財政赤字が拡大した。09年3月に、09〜11年まで財政収支のGDP比▲3%を上回る状況が継続するとの財政収支見通しが欧州委員会により示されたことを受け、09年4月にECOFINは過剰財政赤字是正勧告を行った。
こうした事態を受け、フランスは10年以降、財政再建を進めることとなった。国内労働組合の反対やデモ活動もあったが、年金受給開始年齢の60歳から62歳への引上げや、年金の満額受給開始年齢の65歳から67歳への引上げ等を盛り込んだ年金制度改革案が提案され、10年10月27日に議会で可決された。また、11〜14年複数年財政計画案において、財政収支については13年までに安定成長協定において定められたGDP比▲3%を達成する計画を公表した。この計画と整合的な11年予算案も公表され、公務員削減及び医療保険支出の伸びの抑制等の歳出削減や、税額控除等の削減による歳入増加が盛り込まれた。
●予算の決定システムの改革
01年に制定された予算組織法により、予算関連文書の充実、歳出科目区分の再編が行われ、議会が予算をより実質的に監督できる体制が整えられた。また、予算科目ごとに目標及び業績評価指標の設定が行われるようになった。06年予算から同法に基づいた予算編成が行われている。
予算関連文書の充実が図られた結果、予算関連文書は、政府のバランスシート、損益計算書、キャッシュフロー計算書、付属文書が作成されている。
また、歳出科目区分が再編され、以前は省(ministere)、章(titres)、部(parties)、項(chapitres)に分かれ、省及び章が議決対象となっていたが、実質的には項で管理されていた。項は約850あったため、国会で実質的な審議を行うのは難しい状況にあった。01年の予算組織法の改正により、予算単位がミッシオン、プログラム、アクシオンに再編され、予算は、32あるミッシオンごとに国会で議決されることとなった(第2-4-25表)。
05年予算までは、国会で審議されるのは、予算全体の6%のみであり、実態としては、残りの94%は自動的に承認されていた。歳出科目区分の再編により、すべてのミッシオンについて国会で審議が行われるようになった。
また、ミッシオンの下には、合計123のプログラムが設けられているが、これについても国会の承認が必要とされている。なお、このプログラムの下に複数のアクシオンが設けられている。
国会で審議対象となる項目数が約850から123に減少したことで、以前に比べ、予算の柔軟性と国会による予算のチェック機能が同時に高められることとなった。
また、省等の組織単位ではなく、ミッシオンといった行政目標ごとに予算項目が再編されたことで、より予算と実際の施策の関連付けが強化された。
プログラム及びアクシオンは、人件費や経常的経費といった7つの章(titre)に分割される。各プログラムには複数の目標及び業績指標が設定されている。プログラム責任者は、プログラムの成果に責任を持つと同時に、歳出に関してプログラム内での裁量が認められている。具体的には、プログラム内であれば、章の歳出額を変更することが可能である。ただし、人件費の歳出総額は増額できないこととなっている。
08年の憲法改正により、09年の予算編成から、単年の予算編成と併せ、2年に1度、複数年の財政計画を法定化することとなった。翌年の予算については、従来どおり、プログラム単位まで支出が確定されるが、翌々年の予算については、一段上の予算項目であるミッシオンまでが確定されることとなった。これにより、複数年予算をあらかじめ策定すると同時に、毎年の歳出に弾力性を確保することが可能となった。
●成長戦略
10年補正予算で、350億ユーロの「未来への投資基金」が設立されることとなった。知識経済、競争力の強化、イノベーションの3つを目標に掲げ、5つの重点分野、すなわち(1)高等教育及び職業訓練、(2)研究、(3)産業、(4)持続可能な開発、(5)デジタル振興に対し、民間資金と組み合わせた形で投資を行い、フランス経済の成長力を高めるとしている。
●(3)財政再建の評価
●財政再建が成功した要因
94〜2000年にかけて、財政赤字が縮小した。これは、景気回復や、ユーロ参加のため、経済収れん条件達成に強くコミットする必要があったことが要因であるといえる(第2-4-26図)。ただし、財政収支はこの間も赤字であり、経済収れん条件は満たしたものの、黒字に転換することはなかった。
●財政再建にかかる課題
フランス政府は、10年以降の経済見通しについて、高めに設定されていると欧州委員会から指摘されている。実際に、欧州委員会やIMFによる経済見通しと11年以降について比べると、フランス政府の見通しは高めであることがわかる。これが、財政再建計画の信認を損なわないかどうか、今後、状況の推移を注視する必要がある(第2-4-27表)。
|
 |



|
|
●6.スウェーデン
|
●(1)財政の現状
スウェーデンでは、90年代に一連の財政再建策が奏功し、財政収支は98年に黒字に転じて以降、08年までほぼ黒字基調を維持してきた(第2-4-28図)。09年は景気後退に伴う税収減と、主に雇用面における自動安定化装置の効果や景気刺激策による歳出増により、03年度以来6年ぶりの財政赤字に陥ったものの、赤字幅はGDP比1.0%、債務残高は同51.8%と、他の先進国と比べると依然として良好な状態にあるといえる(第2-4-29図)。政府見通しによると、不確実性は残るものの景気回復が続く中で、失業保険給付等の減少によって歳出減が見込まれることから、一般政府財政収支は2012年に黒字に転じるとされている。
●(2)財政再建への取組
●財政赤字の拡大の背景
スウェーデンでは、経済・産業基盤が第二次大戦の被害を受けず、50〜60年代の高度成長期には、豊かな経済を背景に社会福祉制度の整備が進展した。しかし、70年代に入ると石油ショックを契機に経済成長が減速し、公共部門の膨張や賃金コスト上昇による産業競争力の低下等が表面化することとなった。政府は、積極財政による総需要拡大や通貨切下げによって景気を下支えするとともに、インフレの抑制を図ったが、80年代前半には財政赤字拡大に直面した。80年代後半になると、社会民主党政権の「第三の道(失業率引下げとインフレ抑制を同時追求)」政策の下、国際競争力や海外景気が回復する中で、金融規制緩和をきっかけにバブルが発生した。好景気を受けて財政収支は一時的に黒字に転じ、債務残高GDP比も大きく低下したが、80年代末から90年代初めにかけてバブルが崩壊すると、税収減や銀行救済のための公的資金投入、失業対策等の歳出増によって財政は急速に悪化し、93年の一般政府財政赤字はGDP比11.2%に達した。
以下では、こうした危機的状況下で開始された90年代の財政再建への取組とその時代背景を政権別に整理する。
●ビルト政権(中道右派4党連立)期(91年10月〜94年10月)
80年代末のバブル崩壊及び90年代初期の世界的な景気後退の中で誕生したビルト政権は、危機的状況に陥った経済・金融への早急な対処と、増大する財政赤字への対応の双方に直面することとなった。
(i)財政再建取組の背景
国内状況をみると、まず、バブル崩壊に伴って巨額の不良債権問題が表面化し、主要銀行救済のため、92〜93年にかけて653億クローナ(GDP比4.3%)に上る公的資金が投入された。90年代初期は世界的な景気後退下にあったが、特にスウェーデンではバブル崩壊に加えて好況期の賃金コスト上昇が国際競争力を低下させたこともあり、内外需が低迷するとともに失業率が顕著に悪化し、経済成長率低下に拍車をかけた(第2-4-30図)。さらに、92年末には一連の欧州通貨危機が、経済に対する信認の低下したスウェーデンにも波及したことから、変動相場制への移行を余儀なくされるとともに、92〜93年にかけて30%を超える大幅な為替減価を経験した。
(ii)財政再建策
ビルト政権は、景気後退が深刻化する中でも財政再建への取組を継続し、91〜94年にかけて中央省庁再編や国営企業民営化、地方分権化推進、各種規制緩和等を実施した。92年には、高齢者医療費の急増を防ぐとともに高齢者ケアの質向上と効率化、歳出削減を目的として、一連の社会保障制度改革(エーデル改革)が実行された。さらに、通貨危機後には、政府と野党社民党が、社会保障レベルの引下げも含む一連の緊縮策に合意するなど、国を挙げての財政赤字削減が進められた。
加えて、90年代初めには、抜本的な税制改革が実施された。この改革は、支払利子の所得控除を含む数々の税制優遇措置を制限・廃止して課税ベースを拡大する一方で、所得税率及び法人税率の大幅引下げを図ることなどによって、旧税制の抱えていたゆがみを是正し、公正性及び効率性の高い税制を構築することを目的としていた。ただし、この税制改革は税収中立を目指していたものの、景気悪化によって短期的に税収は予想を下回ることとなり、ビルト政権期における財政赤字拡大要因の一つとなった。
(iii)ビルト政権による財政再建取組の評価
ビルト政権による大規模な税制改革や社会保障制度改革等は、長期的には現在につながるシステムの基盤を整備するものであった。しかしながら、90年代初頭の危機的状況に対して迅速に対応した一方で、厳しい経済状況の中で税収減と支出増を迫られたことから、財政赤字は拡大した。こうした中、国債がデフォルト危機に直面し、財政再建の必要性が喫緊の課題として国民に浸透することとなった
。
●カールソン政権(第2次)、パーション政権(社民党)期(カールソン政権:94年10月〜96年3月、パーション政権:96年3月〜06年10月)
財政再建を掲げるカールソン政権は、就任直後から次々と財政構造改革を打ち出した。さらに、96年にはカールソン政権下で財務大臣を務めたパーションが政権を引き継ぎ、引き続き財政再建が進められた。
(i)歳出削減策
カールソン政権は、94年11月に財政再建計画を発表し、年金の物価スライド幅抑制や医療保険の保険料率引上げ等、社会保障関係費削減を中心とする564億クローナの歳出削減を盛り込んだ財政赤字削減法を成立させた。また、95年1月には、医療保険の自己負担額引上げや児童手当減額等の歳出削減の上積み等を盛り込んだ95年度当初予算案を発表し、同年4月には同修正予算案で失業手当の給付率引下げ、傷病手当の給付見直し等、更なる歳出削減の上積みを図った。両予算案における削減額は、それぞれ193億クローナ、36億クローナとなった。
さらに、95年1月のEU加盟に伴い、マーストリヒト条約の経済収れん条件を達成するため、97年までに一般政府財政赤字をGDP比3%以内とし、98年までに財政赤字を解消することなどを目標とした収れん計画を策定したことも、急速な財政再建を推進する原動力となった。
(ii)予算編成プロセスの改革
歳出削減に加え、歳出項目毎の所要額を積み上げる従来の予算編成プロセス自体が財政悪化に拍車をかけたとの指摘を受けて、財政規律を立て直すための抜本的な予算編成プロセス改革が図られ、97〜99年度の3か年分の予算編成から新たなプロセスが導入された。
改革の中心となったのは、3か年にわたるフレーム予算及び支出シーリングの導入である。複数年度予算によって、マクロ経済政策運営の方向性を踏まえた予算編成を実現させるとともに、内閣主導のトップダウンにより支出シーリングを設定し、歳出総額のコントロールが図られることとなった。まず、景気循環を通じてGDP比2%の一般政府財政黒字を維持するというマクロの財政ルールを踏まえ、経済見通しに基づいて3か年の歳出総額のシーリングが議決される。予算は更に、省庁の枠を越えて分類される27の歳出分野とその内訳である約500の議決予算に分かれており、議会によって各歳出分野についても上限(ターゲット)が設定され、その限度内で議決予算が決定される。シーリングは議会で議決が見直されない限り、翌年度以降の改定も不可能となっており、強い拘束力を有する。歳出分野または議決予算間については、シーリングの限度内で、ペイ・アズ・ユー・ゴー原則に基づく再配分の議決も行われる。これらの具体的な予算案は、各省庁からのボトムアップ案に基づいて政府が閣議決定し、議会に提出されることとなっている。
(iii)公的年金制度改革(パーション社民党政権期)
パーション政権期には、90年代初期から検討が開始された抜本的な公的年金制度改革が実施に移され、99年から段階的に新制度が導入された。90年代の危機と将来見込まれる高齢化の進展を踏まえ、公平性の確保、受給者と現役世代の受益のゆがみ修正、財政立て直しを目的とする、持続可能で安定的なシステムの構築が図られた。
(iv)実体経済との関係
カールソン政権が誕生し、財政再建に着手したのは、91〜93年までマイナス成長を記録したスウェーデン経済が底を打ち、94年に実質経済成長率が4%と急速に回復軌道に乗りつつあるタイミングであった(第2-4-31図)。実体経済回復の背景としては、為替減価や法人税の引下げ、工業から知識集約産業への産業構造の転換等によって国際競争力が改善したことから、当時GDPの約3割を占めていた輸出がまず回復し、景気回復をけん引したことが挙げられる。GDPギャップをみると、93年を底に急速にマイナス幅が縮小に向かったが、ほぼ同時に循環的財政赤字も縮小に転じ、また、構造的財政赤字も縮小に向かっており、経済回復が財政再建のスピードを押し上げたことが示唆される(前掲第2-3-1図)。他方、歳出削減に伴う公務員数削減もあり、失業率は97年にかけて高止まりした。
(v)カールソン政権・パーション政権による財政改革の評価
一連の財政再建策による中央政府の財政収支改善額は、94〜98年にかけてGDP比約8%に上り、そのうち増税によるものが同約47%、歳出削減によるものが同約53%であったとされる。この結果、一般政府の財政赤字GDP比は93年の11.2%から97年には1.6%へと縮小した後、98年には0.9%へと黒字に転換し、目標を上回る改善を果たした。
カールソン政権・パーション政権による急速な財政再建の成功要因としては、悪化した財政状況に対する国民の強い危機感を背景に、政権が強いリーダーシップを発揮して徹底的な改革を推進したことが挙げられる。90年代に国を揺るがす危機に直面したことで、既存システムの抱えていた諸問題の解決を図るなど抜本的な見直しを行い、2000年代の成長の基盤を構築することができたといえる。バブル崩壊に伴う金融危機の克服や、92年に開始されたエーデル改革、99年に開始された公的年金改革の成果については国際的にも高い評価を受けており、特に、金融危機への対応は今般の世界金融危機においても、成功事例として再度注目を浴びている。
また、議会における議決プロセスも含む、予算編成プロセス自体の抜本的な改革に取り組んだ意義も大きい。新プロセスでは、歳出総額や歳出分野への配分を内閣主導で決定する一方、下位の議決予算の配分については各省庁の裁量範囲が広く、優先順位の高い政策を賄うため資源配分の効率化が図られるなど、トップダウンとボトムアップが合理的に組み合わされた仕組みとなった。こうした実効性のある改革が、一時的な財政赤字の克服にとどまらず、持続的な財政の健全性を維持するために果たした役割も大きい。
さらに、国民の痛みを伴う徹底した歳出削減を実施する反面、法人税の引下げや産業構造の転換を促進する政府投資を行い、経済を活性化させたことは、急速な財政再建の成功に大きく寄与しただけでなく、2000年代の経済成長の基礎となった。このように、強固な財政規律を確立し、中長期的視点に基づく財政運営の基盤を構築するとともに、労働市場の改革や産業構造の転換を推進し、財政の健全性維持に不可欠な経済的基盤を整備したことも評価される。
|
|
●7.スペイン
|



|
現在、スペインの財政と財政再建への取組が注目されている。その背景には、同国は、ギリシャ財政危機以降財政状況が特に懸念されている南欧諸国等の中でも経済規模が比較的大きく、また、ヨーロッパ全体でみても5番目のGDPの規模であることがある。また、これに加え、住宅バブルが崩壊し、ストレステスト後も金融システム面で不安が払拭されていないことがある。
●(1)財政の現状
86年のEU加盟後、政府はユーロ参加を目指して財政再建を進め、その後も、ユーロ発足後の経済成長期を通じて財政は改善を続けてきた(第2-4-32図)。99年のユーロ発足時、既に財政収支赤字はGDP比▲1%台となっていたが、05年に財政収支黒字化を達成し、その後数年間、財政黒字は拡大し、国債の格付けも「AAA」を獲得した。しかし、09年、世界金融危機発生後の大型の景気刺激策と景気後退による税収減のため、財政は急激に悪化した。10年の財政赤字は、GDP比▲10%近くに上り、公的債務残高は対GDP比50%を超える見通しである。
●(2)財政状況の背景
●90年代〜ユーロ参加まで
75年のフランコ将軍による独裁の崩壊・民主化以降も、他の西欧諸国に経済発展で遅れをとっていたスペインにとって、EU加盟とユーロ参加は国民の念願でもあった。マーストリヒト条約締結当時(92年)、欧州通貨危機の影響によるヨーロッパ全体の経済停滞もあり、経済成長率はマイナス、財政赤字GDP比は92年の▲3.9%から93年は▲6.6%へ拡大していた(第2-4-33図、前掲第2-4-32図)。
このような状況から、ユーロ参加条件を達成するため、財政再建計画に幾度か修正を行いながらも取り組み、その結果、ユーロ参加への条件を達成した。99年には、財政赤字のGDP比は▲1%台まで縮小し、財政収支はほぼ均衡となった(前掲第2-4-32図)。
●ユーロ発足後の景気拡大期
ユーロ参加に向けた過程で、長期金利は徐々に低下し、参加後はさらに、これまでにない水準まで低下した。このため、低金利による信用の拡大と国外投資資金の流入により住宅建設ブームが起きた。また、経済通貨統合は、国外からの人材流入も促し、建設労働者に加え、家事代行サービスも増加し、女性の労働力率の上昇等労働市場の構造変化ももたらした。投資と個人消費の増加にけん引された10年間に及ぶ景気拡大期の中で、財政収支はほぼ均衡を維持し、さらに05年、財政収支はGDP比1%の黒字となった(前掲第2-4-32図)。また、この間、政府債務残高も減少傾向が続き、財政状況は順調に改善していた。
●住宅バブル崩壊と金融危機発生
過熱状態となった住宅市場は07年以降急激に縮小し、08年後半、折からの世界金融危機の発生もあって金融市場が混乱、投資・消費が急激に冷え込み、09年、経済成長率はマイナスに落ち込んだ(前掲第2-4-33図)。失業率も急速に上昇し、08年1月の9.0%から同年12月には14.9%にまで上昇、10年半ばには20%を超えた。経済・金融の混乱に対応するため、政府は緊急の大型財政刺激策を打ち出したことと景気後退による税収減から、財政収支は急激に悪化した(前掲第2-4-32図)。
●(3)財政再建への取組
●ユーロ参加条件達成に向けての財政再建計画
92年当時、ユーロ参加への経済収れん条件を満たすためには、財政収支の改善、消費者物価上昇率の抑制等が主な課題であった。しかし、前述の通り、当時は欧州経済が停滞していた時期であり、当初の計画の実施は難航していた。
94年、政府は新たな財政再建計画を発表し、財政再建への取組を再開したが、新計画は、教育、医療等の社会的歳出は維持しつつも、公務員給与・補助金等の歳出を削減、歳入面では、酒・たばこ税以外の増税は行わず、主に歳出削減による財政再建を目指すというものであった。また、同時に、国営企業の民営化、規制緩和、労働市場改革等の構造改革にも取り組んだことも、財政均衡とユーロ加盟条件の達成につながった。
●2000年代、財政安定化へ
90年代後半から、2000年代後半にかけての、財政収支の均衡と、債務残高の減少傾向を支えたものは、ユーロ加盟後の経済成長による安定した税収であった。経済成長、財政安定化の一方で、住宅バブルが発生し、また、賃金の硬直性から輸出競争力が低下し、構造問題の深刻化が進展していた。
●世界金融危機後の財政再建
世界金融危機後の混乱は、09年以降、収束に向かっていたが、スペインの金融危機対応のため大幅に悪化した財政収支への懸念は、ギリシャの財政懸念の影響もあり、根強いものとなっていた。10年4月、S&Pが、スペイン国債の格付けを「AA+」から「AA」に引き下げたことなどから、ソブリンCDSは上昇し、市場は依然同国財政を不安視していることを示唆した。
ヨーロッパでも比較的経済規模の大きい同国の財政不安がヨーロッパ経済全体に与える影響への懸念も背景に、10年5月、ECOFINは、追加財政再建計画の提出を求めるなど、政府に取組強化を要請した。現在、政府は、要請に従い、2013年に一般政府財政収支赤字をGDP比▲3%にまで抑えることを目標に、歳出削減については公務員給与やインフラ投資の削減、歳入増加については増税を行うなどの財政再建に取り組んでいる(第2-4-34表)。
●(4)構造改革への取組
政府は、これまでの住宅バブルを背景とした建設業の成長や観光に過度に依存した経済構造からの脱却を目指し、新たな成長モデルに向けての構造改革と、長年課題とされてきた労働市場改革にも着手している。また、住宅バブル発生の原因でもあり、対応が急務とされていた金融セクター再編にも取り組んでいる(第2-4-35表)。
●(5)財政再建の課題
●政府による経済見通し
10年5月、政府は、財政再建計画の前提とされる中期経済成長見通しの改定を発表したが、欧州委員会やOECDの見通しよりもやや楽観的なものとなっている。住宅バブルの崩壊により、家計や企業のバランスシート調整が下押し圧力となって、消費や投資が伸び悩み、内需主導の成長が期待できない中で、こうした経済見通しを前提とした財政再建計画が十分実現可能かどうか今後も注意深く見守る必要がある。
●財政再建計画の実現可能性
前述の財政緊縮法は、わずか1票差で辛うじて議会を通過した。また、10年9月、11年度予算の議会提出後、公務員給与引下げ等の歳出削減案に反対して、国内全土で大規模なデモと公務員によるストライキが発生した。現在政府が取り組んでいる財政再建策には、国民の反対が根強く、90年代のユーロ参加に向けて国民全体が前向きに支持した状況とは対照的であり、財政再建目標の達成については予断を許さない。
|
|
●8.英国
|



|
●(1)財政の現状
90年代初めの景気後退に伴い、財政収支のGDP比は急速に悪化し、93年度には▲7.7%となった。その後、財政再建や、景気回復の継続により、98〜2000年度の間、財政収支は黒字に転じた。しかし、01年以降、景気減速の影響や、ブレア政権の公的サービス充実の方針による歳出の増加もあり、財政収支は再び悪化に向かい、世界金融危機による税収減や、大規模景気対策等により、09年度には財政収支のGDP比は▲11.0%となった。債務残高のGDP比は増大し、07年度の36.5%から、09年度には53.5%に達している(第2-4-36図)。(第2-4-37図)
08年7月には、財政収支のGDP比が、安定成長協定で定める▲3%を継続的に超える見通しとなったため、ECOFINは過剰財政赤字是正勧告を行った。しかし、財政収支改善がみられなかったことから、09年4月に再度英国に対し、過剰財政赤字是正勧告を行った。
10年5月6日の下院選挙では、与党の労働党と、更なる財政再建策を主張する保守党が争い、保守党が勝利したものの、単独過半数には達しなかったため、自由民主党との連立政権を樹立した。政権樹立後の5月24日には、緊急歳出削減策を提示し、6月には新たなバジェット・レポートを発表、10月には複数年度にわたる歳出計画を公表するなど、具体的な歳出削減策を提示した。
●(2)財政再建の取組
90年代以降の財政再建の取組を、各政権ごとに分けてみていく。
●97年まで:保守党政権
90年代初めの景気後退に伴い、財政赤字が拡大した。90年度には▲1.0%だった財政収支GDP比が、欧州通貨危機(ポンド危機)の起こった92年度には▲7.4%となり、翌年度の93年度には▲7.7%となった。
メージャー政権は、景気循環に左右されやすい失業手当等の社会保障費や利払い費等を除いた歳出の実質伸び率を、実質経済成長率を下回る水準に抑制することを目標とする「コントロール・トータル制度」を93年度予算編成時から導入し、公共事業費等を削減し、付加価値税率の引上げも実施した。
こうした財政再建ルールに基づいた歳出削減に加え、景気回復もあって、94年度以降は財政赤字が縮小した。94〜96年度の間、GDP比でみて、構造的財政収支は2.6%ポイント、循環的財政収支は1.7%ポイント改善し、保守党のメージャー政権下では、主に構造的財政収支の改善により、財政収支が改善したといえる。
●97〜10年:労働党政権
97年の総選挙により、保守党政権から労働党政権に政権交代が行われた。労働党政権下では、以下のような予算制度改革が進展した。
(i)財政ルール
98年財政法において、財政安定化規律(The Code for Fiscal Stability)の制定や、プレバジェット・レポート等の予算関連文書の作成が義務づけられた。この財政安定化規律を基に、2つの財政ルールが設けられた。
(ア)ゴールデン・ルール
景気の循環を通じて、政府の借入れは投資目的に限り行い、経常的歳出には充てない。
(イ)サスティナビリティ・ルール
債務残高は、景気の循環を通じてGDP比で安定的かつ節度のあるレベルに保つ。
(ii)予算の決定プロセスの改革
98年財政法により、従来から公表されていたバジェット・レポートの発表に先立ち、プレバジェット・レポートが作成されることとなった。これは、財政に関する政府の方針や、経済及び財政に関する見通しを早い段階で示し、国民の間における議論を喚起する役割を果たしている。
また、従来から歳出を見直す枠組みとして用いられてきた公的支出調査(Public Expenditure Survey)を発展させる形で、2〜3年に一度、歳出見直し(Spending Review)が実施されることとなった。歳出見直しでは、総管理歳出(TME:Total Managed Expenditure)のうち、省庁別歳出限度額(DEL:Departmental Expenditure Limits)については、今後3年間の省庁別歳出額の大枠を決定し、原則として2〜3年間は変更は行わないこととし、複数年度で弾力的に歳出額を管理することを可能とした。
他方、社会保障費や利払い費等のように外部要因に影響を受けやすい歳出については、複数年度管理が困難なため、各年度管理歳出(AME:Annually Managed Expenditure)として、別途、管理を行う。DELとAMEの予算配分の割合は6対4程度である。
また、98年の歳出見直し以降、公的サービス合意(Public Service Agreement)と呼ばれる制度が導入されている。これは、各省に効率的な予算執行や成果(アウトカム)に重点を置いた目標を設定させ、達成状況を広く国民に報告する仕組みである。この公的サービス合意は、各省庁がどの点において公的サービスを改善するのかを明確にすることが求められており、その目標にはアウトプットよりも、アウトカムをすえることが推奨されている。公的サービス合意は、予算に直接的に反映されるわけではないが、達成度合いについて毎年公表されることとなっている。
(iii)財政再建の進捗結果
景気回復の継続と、予算の決定プロセスの改革等により、財政収支は2000年度まで引き続き改善し、2000年度の財政収支GDP比は1.9%の黒字となった。97年度から2000年度の間、GDP比でみて、構造的財政収支は3.9%ポイント、循環的財政収支は1.4%ポイント改善しており、この間、主に構造的財政収支の改善により、財政収支全体が改善したといえる。
しかしながら、01〜04年度にかけて、財政収支は悪化し、04年度にはGDP比▲3.3%となった。01〜04年度の間は、主に構造的財政収支が悪化しており、GDP比でみて、4.2%ポイント悪化した。構造的財政収支が悪化した背景には、ブレア労働党政権による公的サービス充実の方針やイラク戦争等により、歳出が増加していたことがある。
05年度及び06年度については景気が回復していたこともあり、財政赤字は縮小したものの、07年度以降は再び拡大した。特に、08年度は世界金融危機による景気後退及びそれに伴う税収減と財政刺激策の拡大により、財政赤字が著しく拡大した。09年度も引き続き財政赤字が拡大し、財政赤字は08年度にはGDP比6.7%、09年度には11.0%にまで悪化し、74年度以降で最も高い水準となった。
(iv)労働党政権が行った財政再建の評価
労働党政権の下では、歳出見直しの活用によって複数年度で効率的な予算管理を図ったり、プレバジェット・レポートの作成により予算の内容の透明性を向上させるなど、財政再建を推進するための制度上の改革が進展した。
その一方で、ゴールデン・ルール及びサスティナビリティ・ルールについては、景気循環のサイクルの終盤が近づくにつれ、財政ルールを遵守しようとすれば、景気回復の動きが弱い時期であっても財政引締めを行わざるを得なくなるという制度上の問題点が指摘されている
。
また、政府による景気の転換点の認定に変更が行われたことにより、ルールを遵守しているのかどうかの評価基準があいまいになってしまったという問題点があった。
●10年以降:保守党・自由民主党連立政権
保守党及び自由民主党の連立政権下では、以下のような財政再建が実施された。
(i)財政ルール
10年5月に発足した保守党政権は、構造的財政収支(投資的経費を除く)を財政再建の目標に置くこととした。第一に、構造的財政収支を尺度とした理由は、景気動向によって変動する循環的財政収支を除いたベースで財政収支の健全化を図ることにより、仮に景気が後退したとしても、適切な財政政策を実施するための自由度を確保することを目指したからである。第二に、投資的経費を除くとしたのは、財政再建下でも、長期的な経済成長を支えるために必要な公的投資の財源を確保するねらいからである。なお、財政目標や経済財政見通し、財政再建策といった経済財政政策にかかわる情報については、従来どおりバジェット・レポートにおいて公表された
。
(ii)財政目標
保守・自由民主党連立政権は財政再建目標として、以下の2つを掲げている。
(ア)15年度までに構造的財政収支(投資的経費を除く)を均衡させる。
(イ)15年度に純債務残高GDP比を減少に転じさせる。
(iii)財政再建策の内容
10年6月にオズボーン財務大臣は予算演説を行い、予算削減策や予算責任局(OBR:Office for Budget Responsibility)の設置について発表を行った。OBRは政府から独立した立場として経済財政見通しの作成、財政再建の実現可能性の評価等を実施することを目的とする新たな組織である。
同月、緊急予算が公表され、財政再建目標や、OBRの経済財政見通しが提示された。新政権の予算は、前政権が策定した国民医療制度(NHS:National Health Service)の改革等の財政再建策に加え、社会保障制度改革や公務員の賃金引上げを2年間凍結、子育て支援策の対象絞込み等の追加財政再建策を行うものとなった。その歳出削減効果は、14年度時点で、前政権の施策の効果も合わせて、830億ポンドに上るとの見通しが示された。また、歳入増加策として、付加価値税率引上げ(11年1月から17.5%を20%に引上げ)等も行われることとなり、14年度時点で、前政権の施策も合わせ、歳入を290億ポンド増加させるとの見通しも示された。この結果、歳出・歳入の両面での財政再建効果は、14年度時点で1,130億ポンド、15年度時点で1,280億ポンドに達する。OBRは、新政権が公表した財政再建の実現可能性について、50%以上の確率で目標達成との見通しを示した。
同年10月20日には、歳出見直し(Spending Review)が公表され、具体的な歳出計画が示された。長期の経済成長と民間主導の景気回復及び公正さを実現するとし、14年度までに、810億ポンドの歳出削減効果を見込んでいる。OBRは、同年6月の緊急予算で示された財政目標の達成時期に影響はないとの見通しを示している。
今後、各省庁は、14年度までの優先順位や、今後2年間の改革の具体的内容や期限を含む各省庁の構造改革計画、公的サービスのコストや効果を測定するための各種指標を含む詳細な業務計画を公表することとなっている。
(iv)構造改革・成長戦略
10年5月に発足した保守・自由民主党連立政権は、マクロ経済の安定、税制改革、規制緩和、インフラ整備の4つの柱から成る成長戦略を公表した。1つ目の柱のマクロ経済の安定については、財政再建によって金利負担を低下させ、企業投資の促進を図るとしている。2つ目の柱である税制改革については、法人税を今後4年間毎年1%ずつ引き下げることにより、企業の投資と成長を支えるほか、職業税(jobs tax)の改革を行うとしている。3つ目の柱としては規制緩和を提案しており、不要な規制の廃止と、規制のスクラップ・アンド・ビルドを行うワンインワンアウト・ルールを制定することとしている。また、特殊法人の再編を進め、192法人を廃止し、118法人を統合することとしている。4つ目の柱として、インフラ整備を挙げており、道路、鉄道・港湾設備、通信、学生の就職支援、在外公館による輸出支援等を行うとしている。
その後、10月20日に公表した歳出見直しの中では、上記の成長戦略と整合的な内容の今後4年間の予算計画が盛り込まれており、歳出削減を行う一方、鉄道等のインフラ整備に300億ポンド以上、通信インフラ整備に5.3億ポンドを支出するとしている。
(v)今後の見通し
英国経済は、景気が持ち直しているが、先行きの持ち直しのペースは緩やかなものになると見込まれる。新政権の打ち出した大幅な財政再建策は、景気下押し効果を伴うことが予想され、財政再建と経済成長を両立させていくことができるか、今後の行方が注目される。 |
|
●9.オーストラリア
|



|
●(1)財政の現状
オーストラリアでは、80年代前半(財政赤字のピークは83年、一般政府財政赤字GDP比4.9%)、90年代前半(同92年、同5.5%)の二つの時期に財政赤字が拡大した。その後、98年に財政収支は黒字に転換し、それ以降おおむね黒字を維持している。債務残高(一般政府)については、96年をピークに、その後は徐々に低下している(第2-4-38図)。
●(2)財政再建の取組
●政権・時代背景
第二次世界大戦後、高関税を始めとする保護主義政策によって守られていたオーストラリア経済は、70年代の石油ショックや英国のEC加盟等の影響を受けて停滞した
。
83年、ホーク労働党政権の景気刺激策により、景気は回復したが、オーストラリアの産業の競争力低下は顕著になり、経常収支は悪化、対外的な不均衡への懸念が浮上した。こうした状況を背景に、対外債務負担を減らすためには公的部門の貯蓄を増やす、すなわち財政赤字削減が必要という認識が広まり、80〜90年代を通じて実施された財政再建を促すこととなった。
80年代から漸進的に実施されてきた財政再建は、大きく二つの時期に分けられる。第一は、80年代前半の赤字拡大を受けて、83年に誕生したホーク及びキーティング労働党政権による改革(80年代半ばから90年代半ばまで)である。第二は、90年代前半の赤字拡大を受けて、96年に誕生したハワード自由党・国民党連立政権による改革(90年代半ばから00年代半ばまで)である(第2-4-39表)。ここでは、これら二つの時期に焦点を当て、いかなる形で財政再建が行われたのかを分析する。
●財政再建の枠組み
オーストラリアでは、80年代以降、財政再建に当たり、いくつかの重要な枠組みが創設されている。
まず、財政ルールのこう矢として打ち出されたのが、84年にホーク労働党政権によるトリロジー(3本の柱)である。これは、翌年度予算から向こう5年間は税収・政府支出・財政赤字の3つのGDP比を増加させないという財政目標であった。
その後、96年のハワード保守連立政権においては、「景気循環を通じて、平均的に、予算収支(budget balance)を均衡させる」財政ルール・目標が確立した(対象は一般政府のうち連邦政府)。また、これに付随する副目標という形で、毎年度の予算において、財政収支や債務残高の具体的な数値目標が設定されている。
ハワード政権は、続いて98年に予算公正憲章法(Charter of Budget Honesty Act)を制定する。これは、中長期的な財政戦略、予算編成の基本方針等、財政運営全般に関する基本的な枠組みを定める法律で、健全財政運営に関する原則に基づいた財政運営を行うこと、財政政策のパフォーマンスを検証することによって財政政策のアウトカムを改善することが目的とされている。前述の財政ルールは本法に規定され、法的担保を得ることとなった。また、予算公正憲章法では、政府による当初予算公表時等に、財政政策の目標、優先事項、評価基準を定めた「財政戦略報告書」を公表することや、定期的な財政報告を年に3回、経済・財政に関する見通しを総選挙前、世代間会計に関する報告を5年に1回、公表する旨を定めるなど、透明性、アカウンタビリティの確保もねらっている。
中期財政フレームである「将来見積り」(FE:Forward Estimate)による支出コントロールも重要な枠組みのひとつである。これは、70年代は財務省の内部資料だったが、71年に予算プロセスに正式に取り入れられ、83年には公表、80〜90年代に発展を遂げた。プログラムの優先順位とマクロ財政政策や予算方針とを調和させることが目的で、内閣主導でのコントロールにより歳出の伸び率を抑えることに重点が置かれている。次年度予算とその後3年間を対象とし、省庁別支出額等をベースラインとして固定、翌年度予算は、「将来見積り」における見積りに拘束される。厳格に複数年次にわたって歳出を拘束するものではないが、政策の変更等がなければ改定されない。各省が、予算関連新規政策や制度改正を要求する場合は、既存の「将来見積り」の範囲内でスクラップ・アンド・ビルドが求められるため、実質的にシーリングの機能を果たしているともいえる。
●財政再建の内容・手法
(i)歳出削減
前述のトリロジーが打ち出された84年には、財政再建策として、社会保障給付の削減、公務員数の削減、州政府等に対する補助金の削減等が実施されている。また、ハワード政権も、前政権から引き継がれた形で財政再建を加速させた。着任後に判明した80億ドルの歳入欠陥処理として、まず96年度から、大学、国営放送の補助金削減を始めとした歳出削減措置を実施している。そして、98年には一般政府レベルで財政収支の黒字化に成功している。
(ii)増税
増税を含む税制改革は、ホーク、キーティング、ハワードいずれの政権においても実施されている。ホーク政権においては、85年度から課税ベースを広げる税制改革が実施された。具体的には所得税の課税最低限の引上げ、税率構造の簡素化、租税特別措置の見直し、キャピタルゲイン課税、フリンジ・ベネフィット税の導入等である。キーティング政権においては、94年度に卸売税、たばこ税、石油税の段階的増税、95年度にはフリンジ・ベネフィット税の増税が実施された。
一連の税制改革で最も重要な項目のひとつが、2000年度にハワード政権によって実施された付加価値税の導入である。付加価値税の導入は、労働党政権下で何度も計画されては見送られてきた。93年の総選挙で、自由・国民党連合は、付加価値税導入を公約に掲げて敗北したが、98年末の総選挙では再び公約として掲げて勝利し、ハワード政権が誕生し、導入が実現した。同時に、付加価値税導入による租税負担上昇の抑制と、直間比率の見直しを目的として、所得税減税が実施された
。
(iii)予算編成プロセスの改革
次に、予算の決定プロセスについてみてみたい。
ホーク労働党政権は、84年に財務管理改善プログラム(FMIP:Financial Management Improvement Programme)を導入した。これは、過度に中央集権化された硬直的な管理システムを改め、各省庁に人事や財務の資源活用における裁量権を与えるとともに、結果に対する説明責任を求めるシステムへの転換を図るものである。
同じく84年に導入された歳出検討委員会(ERC:Expenditure Review Committee)も、現在でもオーストラリアの予算編成プロセスの大きな柱となっている。これは、首相、財務大臣(Treasurer)、財政・行政管理大臣(Minister for Finance and Administration)等の有力閣僚5名程度から構成される閣内委員会で、各省から提案された新規施策(支出増加・削減)を検討・決定する機能を持つ。
具体的には、予算編成時に、財政・行政管理省から提出された各省の要求書を整理したもの及び全省庁の新規政策と政府の財政状況の要約書を基に、削減総額案を決定し、各省庁へ振り分ける。各省庁はそれを踏まえて再見直し案を作成して委員会に提出、委員会はそれを基に内閣としての最終的削減案を策定する。
88年には、ポートフォリオ予算(PB:Portfolio Budgeting)が導入された。ポートフォリオとは大臣が所管する政策分野のことで、各大臣は、一定のシーリングの下、ポートフォリオ内での資源再配分を行う。具体的にどう配分するかについては、各大臣に大きな裁量が与えられるが、所管する政策のアウトカムの達成、効率的な予算の使用等についての説明責任が課される。各大臣ごとにポートフォリオを設定していることにより、意思決定及び責任体制が一元化されているといえる。
ポートフォリオ予算は経常的経費と政策的経費に区別されるが、前者については、87年に経常的経費一括配賦システム(Running Cost System)が導入された。従来予算上別項目に分かれて割り当てられていた公務員給与、旅費等の経常的経費を省ごとに一括配賦する仕組みで、用途については各省の裁量が与えられている。10%の範囲内で余った予算を翌年度へ繰り越したり前借りすることも可能である。後者の政策的経費については、ポートフォリオ内での配分には各省大臣に大きな裁量が与えられている。
99年には、「発生主義に基づくアウトカム・アウトプット・フレームワーク(Accrual-based Outcome and Output Framework)」が導入された。ここでは、発生主義会計が採用されるとともに、(1)達成すべきアウトカム、(2)アウトカム達成状況評価のための業績目標、(3)アウトカム達成のために必要なアウトプット、(4)アウトプット達成状況を評価するために必要な業績目標をそれぞれ設定することが求められる。
各省庁は、裁量権を持つとともに説明責任を負っている経常的経費を柔軟に活用し、効率的にアウトプットを提供するとともに、政策的経費を着実に執行してアウトカムの達成を目指すことになっている。
●経済成長との関係
財政再建を開始するタイミングとの関係についてみると、まずホーク政権は、83年の政権発足時の景気後退の影響を緩和するために当初は拡張的な財政政策を実施したが、80年代半ばからは緊縮的な方向へ転換している(第2-4-40図、第2-4-41図)。キーティング政権も、91年の政権発足時の景気後退の影響を緩和するために当初は拡張的な財政政策を実施したが、93年の総選挙を経て発足した第二次キーティング政権は、財政再建を開始し、財政緊縮策を採った。
ホーク政権とキーティング政権に共通するのは、景気後退を契機に政権交代し、当初は拡張的財政政策を採って、その後財政再建を開始している点である。また、どちらも景気が底を打ってから回復局面で財政再建を開始している。
第二次キーティング政権による財政再建の取組により、財政赤字は徐々に減少したが、財政収支の黒字化はキーティング政権の次のハワード政権誕生二年後の98年になってからである。
●構造改革
オーストラリアでは、上記のような直接的に財政再建に資する政策以外にも、経済成長促進により財政収支GDP比改善のための分母対策の手段として、公的部門の民営化・民間開放を主とした構造改革・規制緩和を実施している。
具体的には、国有企業の民営化、国家競争政策(National Competition Policy)、関税率引下げ、労働市場の規制緩和等である。国有企業の民営化は、航空会社、鉄道、銀行等の分野で、ホーク政権、キーティング政権、ハワード政権いずれの政権においても段階的に進められた。
また、国有企業や中央官庁に競争原理を導入する国家競争政策が、94年から実施された。ここでは、いわゆる官民競争入札(市場化テスト)を導入し、経済活動における競争制限的行為の禁止範囲を拡大し、規制緩和を徹底した。
これらの政策は、従来行政が担っていた分野を効率化または民間開放したと同時に公務員数及び歳出削減の効果をもたらした。
●(3)財政再建の評価
オーストラリアの財政再建をめぐる取組について特記すべきは、とりわけ健全な財政を担保する制度の構築であり、それは以下の点から評価される。
第一に、80年代から長い時間をかけて漸次制度を構築してきた点である。結果的にではあるが、オーストラリアの財政再建は80年代から10年以上かけて断続的に行われ、その結果、実効性を伴う予算編成制度が構築されてきた。運用上多少の変化を伴いつつも、このほとんどが政権交代があっても引き継がれ、成熟したシステムとして確立している。
第二に、制度の中身である。とりわけ、法的に担保された財政ルールである「予算公正憲章法」、実質的に多年度にわたる予算見積りとシーリングの役割を果たす「将来見積り」、内閣主導の予算編成を担保する「歳出検討委員会」を始めとした優れた枠組みが有効に機能しており、それによって、二度の財政再建の成功及びその後の恒常的な健全な財政状態の維持がなされている。
第三に、こうした制度を効果的に機能させるトップダウンとボトムアップのバランスである。予算の骨格や戦略的な資源配分については、閣内委員会に権限を集中化させてトップダウンで意志決定を行う一方、各プログラムへの予算配分や運営費の配分については、各省に裁量を与えてボトムアップで対応させている。それぞれ役割分担が明確に規定されており、このバランスが予算配分と支出の効率化をもたらしているといえる。
|
|
●10.韓国
|



|
●(1)財政の現状
●財政収支は安定的
韓国の統合財政収支は、1980年代後半に入ってから改善した(第2-4-42図)。しかし、アジア通貨危機後の98年には、統合財政収支がGDP比約▲4%と大幅に悪化した。その後、2000年に統合財政収支は再び黒字に転換し、世界金融危機後の09年まで維持した。また、管理対象収支は、98年と09年を除くとおおむねGDP比▲2%から+1%で推移しており安定している。
●債務残高は低水準
国家債務残高は、増加傾向にあるものの、09年はGDP比33.8%と他の先進国と比較して低水準である(第2-4-43図)。特に、98年と09年はGDP比で約4%ポイント上昇しており、内訳では、一般会計部門が大きく増加している。また、外国為替市場の安定のために発行される外国為替平衝証券は増加傾向にある。
●歳入と歳出
韓国の一般会計の歳入は、国税が約9割を占めている。国税の構成比をみると、付加価値税の割合が約3割、所得税が約2割、法人税が約2割となっている(第2-4-44図)。
他方、歳出については、10年度予算の配分をみると、福祉・保健分野が約3割と最も高い構成比率である(第2-4-45表)。また、予算計画によれば、今後10年から13年にかけて構成比が増加することが見込まれる分野は、教育、福祉・保健、R&Dであり、構成比が減少する主な分野は、一般行政、農林水産、社会資本整備等となっている。
●(2)財政再建の取組
(i)政権・時代背景
韓国の財政再建は、1980年代にまでさかのぼる。朴正熙(パク・チョンヒ)政権(1963〜79年)は、輸出産業支援や重化学工業化戦略による政府投資規模を拡大した。その結果、インフレが高進し、79年のオイルショック後、80年にはコメ不作もあり、消費者物価上昇率は前年比30%近くとなった(第2-4-46図)。
この状況を受け、全斗煥(チョン・ドファン)政権(80〜87年)は、金融政策及び財政政策を引き締め、87年には統合財政収支の黒字を達成した(前掲第2-4-42図)。この頃に、歳入の範囲内に歳出を抑える均衡財政の原則が確立し、以後の財政運営の基礎となった。
(ii)財政政策の枠組み
●財政ルール
上述のように、財政ルールの原則は均衡することであるが、法律等で特に明文化されてはいない。97年以降の赤字国債の発行の推移をみると、アジア通貨危機や台風被害(03年)、世界金融危機といった韓国経済に大きな影響が発生した時以外は、赤字国債発行による補正予算を組むことはほぼ行われておらず、平時における均衡財政は暗黙のルールになっていると考えられる
。
●中期財政フレーム(中期財政見通し)
04年9月に、これまで単年度主義であった予算編成を多年度編成に移行させる中期国家財政運用計画(04〜08年)が発表された。これにより、硬直的であった財政運営に景気循環を考慮する要素を取り入れることができるようになった。ただし、この計画では、毎年歳入が歳出を上回る見通しとなっていた。
これに続き09年9月に財政計画(09〜13年)が発表された。この計画では世界金融危機の影響にかんがみ、09〜12年までは財政赤字を容認するものの、徐々に縮小させ13〜14年に均衡財政となる見通しとなっている。
(iii)財政再建の内容・手法
中期国家財政運用計画と合わせて、各種制度の改革も実施されている。04年から本格実施された予算総額配分自律編成制度は、予算当局が事前に予算総額および各省庁・分野別のシーリングをトップダウンで設定し、各省庁はその範囲内で予算要求をする仕組みとなっている。また、予算成果管理制度は、各省庁が予算編成時に事業目標およびその達成度を定量化した成果指標を作成し、予算執行後はその結果・評価を外部に公表するとともに、次回の予算編成への反映を義務付ける制度である。これらの要素を含めた国家財政管理法が07年1月に施行され、法制化に至った。
(iv)経済成長との関係
統合財政収支が黒字を達成した87年以降、黒字基調が継続したが、アジア通貨危機後の98年にはGDP比▲3.9%と再び悪化した。これは、危機の影響等により経済成長率がマイナスとなり税収が減少し、景気を下支えするための財政出動を行ったためである。また、ウォンはドルに対して約5割の大幅な減価をしたため、純輸出が大幅にプラスとなり、経済成長にプラスに寄与した(第2-4-47図)。一方、金融政策はIMFの支援条件(コンディショナリティ)により高金利政策が採られ、無担保コール翌日物は98年1月に月平均で25.3%と急上昇したものの、98年末には危機前の10%台を下回る7%台まで急落しており、金融緩和に向かっていった(第2-4-48図)。99年には、輸出の好調や緩和的な金融政策もあり、財政を引締め方向に転じたが、実質経済成長率は10.7%となり、税収は回復し、2000年には統合財政収支は1.1%のプラスに転じた。
この財政再建のパターンは、今次の世界金融危機にも当てはまるものと考えられる。08年秋からのウォンの大幅な減価は、輸出を後押しし、経済を早期に回復させており、政策金利の大幅な引下げは、景気を下支えした。09年に赤字となった財政収支を均衡に戻す環境は整いつつある。11年の予算案によると、統合財政収支については、11年にGDP比0.4%の黒字に転換するとしている。また、管理対象収支については、11年にGDP比2.0%のマイナスと、10年予算比で0.7%ポイント改善するとしている。
●(3)財政運営の評価
●財政運営が安定している要因
韓国財政の安定要因は、平時には一貫した均衡財政が採られていることである。これは、予算当局によるトップダウンでのシーリングや、当年予算編成時の歳出規模抑制等が徹底されているためである。ただし、世界金融危機のようなショックに対しては拡張的な財政政策が採られ、経済を下支えしている。その後、再び均衡財政に戻す見通しを立てられるのは、金融緩和政策や通貨下落による輸出の好調等により、経済が早期に回復を果たしているためと考えられる。
●財政運営にかかる課題
韓国の財政政策は、世界金融危機のような大きなショックには対応しているものの、いわゆる景気循環に対応した財政運営を行っていないため、今後は景気循環にも対応できる財政運営が求められると考えられる。また、今後少子高齢化が急速に進むと予測される。国連推計によると、韓国全体の人口に占める65歳以上の人口の割合は、2010年は11%であるが、2030年は23.2%と20年間で約2倍となっている。また、韓国統計庁によると09年の合計特殊出生率は、1.15と超少子化社会となっている。したがって社会福祉の運営をどのような形で実施していくのかという問題は、今後の韓国の財政運営をさらに難しいものにすると考えられる。 |


 |



|
|
●デフレ脱却と財政健全化 2014/9
|
|
●1.はじめに
|
2012年秋以降の円安・株高の進行を背景として消費と生産が拡大し、これを起点として日本経済は緩やかな回復を続けている。物価についても、2013年度の消費者物価指数(対前年度比)がプラスに転じるなど、デフレ脱却に向けた動きが進展しつつある。このように、安倍内閣のもとでの経済政策(アベノミクス)は、これまでのところ一定の成果をあげてきた。こうした中で2014年4月には消費税率(国・地方)が8%に引き上げられたが、消費税の増税については景気や物価に与えるマイナスの影響を懸念する向きもある。そこで、本稿ではアベノミクスのこれまでの経過を振り返るとともに、それを踏まえて今後の財政運営のあり方について、デフレ脱却と財政健全化の兼ね合いに留意しつつ検討することとしたい。
本稿の次節以降の構成は以下の通りである。まず第2節では、アベノミクスのこれまでの経過を振り返るとともに、デフレ脱却に向けて財政政策と金融政策をどのように活用していくべきなのかについて考察する。次に第3節では、デフレ脱却と財政健全化の両立について、社会保障・税一体改革の動向なども踏まえつつ論点整理を行う。続いて第4節では、財政健全化の進め方について、歳出抑制に向けたコミットメントをどのように明確化するかということに留意しつつ検討を行う。第5節は本稿の結論部分である。
|
|
●2.デフレ脱却と「機動的な財政出動」
|
●2.1 アベノミクスのこれまでの経過
アベノミクスについての厳密な定義はもちろんないが、「大胆な金融緩和」(第一の矢)、「機動的な財政出動」(第二の矢)、「民間投資を喚起する成長戦略」(第三の矢)という「三本の矢」からなる経済政策のパッケージというのが一般的な理解ということになるだろう。このうち、第一の矢については2013年1月22日に日本銀行による「物価安定の目標」の設定と「期限を定めない資産買入れ方式」の導入がなされ、同年4月4日に「量的・質的金融緩和政策」が導入された。また、第二の矢については13年の年初に緊急経済対策の策定(13年1月11日閣議決定)とそれを踏まえた12年度補正予算案の編成(13年1月15日閣議決定)が行われ、補正予算は13年2月26日に可決成立した。また、消費税率引き上げを予定通り実施することの確認(13年10月1日)に際して「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(経済政策パッケージ)が閣議決定され、13年度の補正予算(14年2月6日可決成立)において対応がなされている。
これらはともに需要サイドから景気刺激を行うことでデフレ脱却を実現することを企図した政策対応であるのに対し、「第三の矢」(成長戦略)は主として供給サイドに働きかける政策であり、第一の矢や第二の矢よりは時間的に長い視野のもとで経済成長率を引き上げることがそのねらいとされている。第三の矢については13年6月14日に「日本再興戦略」が閣議決定され、14年1月20日に産業競争力強化法が施行されている。
アベノミクスが正式にスタートしたのは安倍内閣が発足した2012年12月26日からということになるが、金融・資本市場ではそれを先取りする形で同年10月頃から円安と株高が進展した。円安と株高の動きは2013年入り後も続き、量的・質的金融緩和の導入を機にその勢いが加速したが、5月23日を境にやや変調が生じ、その後の円安と株高の動きはきわめて緩やかなものとなっている。こうした中にあって景気動向にも13年の年央までとそれ以降で変化が見られる。このことを実質経済成長率の需要項目別寄与度をもとに確認すると、13年1−3月期には消費と外需が増加する中で民需主導の成長が実現し、4−6月期には外需の減速を公的需要が補う形で4%(年率換算・季節調整済)を上回る高い成長が続いた(図表1)。これに対し、7−9月期と10−12月期には消費の伸びが減速し、外需の寄与度がマイナスとなる中で、公的需要が民需の停滞を補うことでようやく1%程度の成長が維持されている。このように、13年の年央以降は民需が総じて弱い動きとなる中で、公的需要が景気を下支えする形で緩やかな景気回復が続いている。
●2.2 「大胆な金融緩和」と「機動的な財政出動」の関係
第一の矢と第二の矢は、いずれも需要面から景気を刺激し需給ギャップの縮小を通じてデフレ脱却を実現させようという取り組みであるが、第一の矢と第二の矢のいずれをどの程度活用すべきかという点についてはさまざまな見方がある。
この点について、リフレ政策の本来の趣旨に即して考えるならば、財政政策と金融政策をともに拡張的なスタンスで運営することが望ましいということになる。いわゆる「ヘリコプター・マネー」は、国債発行による財源を利用して政府が減税を行うとともに、その国債を中央銀行が買入れることで資金供給を行う政策枠組み(money-financed tax cut)であり、この意味でヘリコプター・マネーは金融緩和を伴う財政政策であると理解される。もちろん、減税ではなく財政支出の拡大と金融緩和という組み合わせでリフレ政策を実施するという選択肢もあるだろう。
もっとも、このような対応については2つの異なる立場からの反対意見がみられる。ひとつは、財政支出の拡大を懸念する観点から、財政による対応はできるだけ避ける代わりに、金融政策をより積極的に活用するほうがよいというものである。もうひとつは、財政健全化の取り組みにおいて増税(消費税率の引き上げ)を重視する立場からのものであり、そこでは消費税率引き上げに伴うマイナスの影響を減殺するために金融政策を活用することが主張される。
このように景気調整の役割において財政政策よりも金融政策を重視するという考え方そのものは、財政政策の実施に伴うラグの問題を考慮すると一般論としては適切である。だが、現在のように短期金利がほぼ0近傍にあり、金利の低下を通じて消費や投資を促すという金融政策の伝統的なチャネルが作動しにくくなっていることを踏まえると、金融政策の効果がその分だけ限定的なものとなる可能性があることに留意が必要である。
景気対策の手段として財政政策を活用することについては、財政政策の需要創出効果(乗数効果)が低下したという指摘がなされることがあるが、「短期日本経済マクロ計量モデル」(内閣府)を見る限り2000年代入り後については乗数の低下は確認されない(図表2)。名目金利が下限に達している(ゼロ金利制約のもとにある)場合には、名目金利の非負制約とデフレ期待のもとで実質金利が高止まりして産出量の減少が続いている状況を、財政支出の継続的な拡大によって緩和することが可能であり、この場合の乗数効果は十分に大きくなり得ることが最近の研究においても示されている。
図表2 短期日本経済マクロ計量モデルにおける乗数の推移
|
|
●3.デフレ脱却と財政健全化
|
●3.1 デフレ脱却と財政健全化:理論的整理
安倍内閣の経済財政運営には「三本の矢」のほかに「社会保障と税の一体改革」というもうひとつの枠組みがある。社会保障・税一体改革は野田内閣から引き継いだ財政健全化のためのスキームであり、この枠組みに基づいて2014年4月に消費税率(国・地方)が8%に引き上げられた(15年10月に10%に引き上げられる予定)。
消費税率の引き上げに際して大きな論点となったのは、財政健全化とデフレ脱却の兼ね合いである。消費税率の3%引き上げは、すでに予定されている社会保険料の引き上げと相まって家計に8兆円を超える負担増をもたらし、景気に大きなマイナスの影響をもたらすことが懸念されたため、2013年夏にはこの点についての対応が大きな論点となった。
この点に関する望ましい政策対応についてひとまず法制上の制約を離れて考えると、デフレ脱却と財政健全化のいずれにどの程度重点をおくかということによって、以下のような異なった対応が考えられるだろう。
(デフレ脱却重視のケース)
もし、デフレ脱却が最優先の政策課題ということであれば、景気が自律的に回復し経済全体の需給ギャップが十分に縮小するまで消費税率の引き上げを見合わせることが望ましいということになる。デフレ脱却のための処方箋としてしばしば言及される「ヘリコプター・マネー」は、金融緩和を伴う減税政策(money-financed tax cut)のことであり、消費税の増税を「大胆な金融緩和」と組み合わせるのは、政策の方向性として整合性のとれたものとなっていないからだ。この点について、消費税率引き上げに伴うマイナスの影響は金融政策の追加緩和によって相殺できるという見方もあるが、この主張が一定の妥当性を持つためには政策金利がほぼ0近傍にある現在の状況の下でも金融緩和の効果が十分に大きいということを示す必要がある。
(財政健全化重視のケース)
もしデフレ脱却よりも財政健全化のほうが重要ということであれば、税制抜本改革法において予定されている通りに消費税率を引き上げることとし、それに伴う景気の落ち込みとデフレ脱却の後ずれについては財政健全化のために必要なコストとして受忍することが基本ということになる。この点について、消費税率の引き上げに伴うマイナスの影響は景気対策(財政支出の増加)によって対応すればよいという考え方もあるが、これは財政健全化が重要という主張と整合性がとれないことになる。もちろん、財政支出の増加が一時的なものであれば、消費税の増税と財政支出の増加という組み合わせが中長期的にみると財政収支の改善につながることになるが、この主張が一定の妥当性を持つためには景気対策のための支出増が一定期間後速やかに削減されるということが担保される必要がある。
(両者の中間のケース)
消費税率引き上げの延期は、デフレ脱却を促すという点では望ましい政策であるとしても、政府が財政健全化に積極的でないというシグナルと受けとめられると、長期金利が上昇して財政運営に支障が生じるおそれもある。この点を踏まえてデフレ脱却と財政健全化を両立させるための工夫としては、消費税率を毎年1%ずつ小刻みに引き上げていくという対応が考えられる。この場合には消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要と反動減を小さく抑えることが可能になり、消費税の増税が景気に与える撹乱効果がその分減殺されるとともに、財政規律の確保についても一定の配慮をすることができるというメリットがある。ただし、この場合には税制抜本改革法で予定されている通りに税率を引き上げる場合と比べて財政収支の改善がやや後ずれすることになる。
●3.2 デフレ脱却と財政健全化:実際の対応
このようにデフレ脱却と財政健全化の兼ね合いについては、両者のいずれをどの程度重視するかによって複数の選択肢が考えられるが、実際にとられたのは消費税率の引き上げとともに景気対策を実施することで景気の失速を回避するという対応であった。具体的には2013年10月1日に消費税率引き上げの閣議決定がなされるとともに、「経済政策パッケージ」(「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(13年10月1日閣議決定))が公表され、これを受けて13年度の補正予算が編成されることとなった。
消費税率を3%と2%という組み合わせで「段階的に」引き上げるという社会保障・税一体改革の枠組みは、消費税率の引き上げが経済に与える影響を十分に精査したうえで決定されたものではないため、消費税率の引き上げが法律においてすでに予定されているという制約がある中で、それをデフレ脱却という課題と調和させるためには、補正予算による対応にやむをえなかった面はある。しかしながら、増税と財政支出の拡大による対応には、財政収支の均衡化のために増税が必要という説明と整合性がとれないことになることなど問題点も少なくない。2012年度の補正予算による政策対応は、13年4−6月期のGDP成長率が消費税率引き上げの判断材料になるという点に留意して公的需要の追加による「経済状況の好転」を図ったものであり、13年度の補正予算による対応についても14年7−9月期のGDP成長率を底上げすることにより消費税率の引き上げを円滑に進めることを企図した対応と理解されるが、このような対応をとることの妥当性については引き続き慎重に判断していくことが必要であろう。
|
|
●4.財政健全化とコミットメント
|
●4.1 中期財政計画の問題点
今回の消費税率引き上げに際してもみられるように、最近の財政運営における大きな問題点は、増税や景気回復によって税収が増加したときにそれを財政赤字の削減ではなく歳出の増加に充ててしまう傾向が強いことである。このような問題を回避するための制度的な措置としては、財政収支の均衡化に向けて複数年にわたる財政計画を策定し、毎年度の歳入歳出がその計画と整合的なものとなるよう財政運営を行うという対応が考えられるが、これまでのところ、このようなコミットメントのもとでも計画にそった適切な財政運営は行われていないというのが現状である。
民主党政権下では菅内閣のもとで「財政運営戦略」(2010年6月22日閣議決定)が策定され、これに基づく中期財政フレームをもとに複数年(3年間)の歳入歳出両面の取り組みがなされてきた。「中期財政フレーム」においては、基礎的財政収支対象経費について少なくとも当初予算における前年度の規模(「歳出の大枠」)を実質的に上回らないよう抑制に努めることとされ、具体的には各年度の基礎的財政収支対象経費を71兆円以下に抑えることとされていた。当初予算においてはこれに沿って「歳出の大枠」が守られるよう予算編成が行われたが、補正予算において歳出の追加がなされたため、決算ベースではいずれの年度においても基礎的財政収支対象経費が71兆円を超える結果となった(決算ベースでみた基礎的財政収支対象経費の総額は、76兆円(2010年度)、81兆円(11年度)、76兆円(12年度))。
安倍内閣においても2013年度予算については「財政運営戦略」と「中期財政フレーム」に即して予算編成が行われたが、13年8月に「中期財政計画」(13年8月8日閣議了解)が策定され、新たな枠組みのもとで財政運営が行われることとなった。中期財政計画におけるコミットメントの問題点は、中期財政フレームにおける「歳出の大枠」のような歳出上限(シーリング)に関するルールが存在せず、各年度において達成すべき基礎的財政収支の「目安」だけが定められていることである。この「目安」のもとでは、基礎的財政収支について一定の改善がなされれば税収の増収分を新たな財政支出に充てることが可能になり、歳出抑制を通じて財政収支の改善を図ることが制度上担保されなくなってしまうことになる。
●4.2 歳出抑制とコミットメント
財政健全化を経済成長による税収の増加(自然増)と消費税などの増税による増収措置のいずれによって達成すべきかという点については小泉内閣以来繰り返し論争がなされてきたが、現実的な判断としてはこの両者による税収増と併せて歳出抑制に取り組んでいくことが不可欠ということになるだろう。歳出・歳入一体改革において利用された「与謝野の方程式」(清水(2007))においては、「要対応額」、すなわち税収と歳出が自然体で推移した場合に基礎的財政収支の均衡化を達成するために必要な財政調整の幅がどの程度になるかを見込んだうえで、そのうちのどの程度を「歳出削減」で行うかを決定し、そのうえで両者の差額から必要な「増収措置」(消費税率の引き上げなど)を求めるという形で調整がなされていたため、歳出抑制に向けた取り組みを具体的な形で議論することが可能であった。
だが、社会保障・税一体改革と中期財政計画の枠組みにおいては、消費税率の引き上げなどによる増収額がまず決まり、それを新たな歳出と財政収支の改善にどのように振り向けるかがその後で決まるため、歳出抑制に向けた努力が行われにくい。社会保障・税一体改革のもとでは消費税の税収を全額社会保障関係費(社会保障4経費)に充てることとされているが、社会保障4経費の総額が消費税収を上回っている限り、実際にどのような支出に充てられたかにかかわらず、形式的には必ず消費税収が社会保障関係費に充てられるということが維持できるため、消費税の「社会保障財源化」はコミットメントとして実質的な意味がほとんどない(図表3)。
図表3 社会保障4経費と消費税収の関係
歳出抑制に向けたコミットメントを明確化し、具体的な工程表を策定する試みは決して珍しいものではなく、橋本内閣のもとでの「財政構造改革」や小泉内閣のもとでの「歳出・歳入一体改革」においてすでに行われてきたことである。たとえば、橋本内閣のもとでの財政構造改革においては、「財政構造改革の推進に関する特別措置法」(平成9年法律第109号)で社会保障、公共投資、文教その他9つの分野について歳出改革の基本方針と量的縮減目標が定められ、これに基づいて制度改革を実施するものとされていた。また、小泉内閣のもとでの歳出・歳入一体改革においては、「骨太の方針2006」(経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(2006年7月7日閣議決定))において、4分野(社会保障、人件費、公共投資、その他分野)のそれぞれについて歳出削減の目標額とそれを実現するための具体的な工程表が示されていた。
自民党は2010年(第176回国会)に「国等の責任ある財政運営を確保するための財政の健全化の推進に関する法律案」(第176回衆第4号)を提出したことがあるが、この法律案に各分野の歳出の削減目標を書き込んで改めて法案を提出すれば、コミットメントの明確化が可能になる。このようなコミットメントは期待の安定化を通じて消費や投資を促進するとともに、信認の確保を通じて長期金利の安定化にも寄与することになる。
|
|
●5.おわりに
|
|
本稿では、アベノミクスのこれまでの経過を振り返りつつ、デフレ脱却に向けた財政政策と金融政策の活用のあり方や、デフレ脱却と財政健全化を両立させるために望ましい財政運営のあり方、財政健全化の進め方などについて検討を行ってきた。短期金利がほぼ0近傍にある中でデフレ脱却を図るためには金融政策だけでなく財政政策を併せて活用することが適切であるが、消費税率の引き上げと財政支出の増加という政策の組み合わせが望ましいものであるかについては慎重な判断が必要と考えられる。財政健全化のためには増税や経済成長の促進による増収措置と併せて歳出抑制に向けた明確なコミットメント(各分野の歳出改革の工程表)が必要であり、これらが今後の財政運営における大きな課題ということになる。 |


 |



|
|
●日本の財政健全化―なぜ必要か 2017/6
|
●1.揺らぐ司令塔
日本の財政健全化の司令塔は、総理大臣を議長として経済財政関連大臣、日銀総裁や民間議員からなる経済財政諮問会議である。この会議は毎年6月に入ると翌年度予算編成をにらんで指針を出す。それが、骨太の方針と呼ばれている「経済財政運営と改革の基本方針」である。
「骨太2015」(2015年6月閣議決定)は、2015年度の国と地方をあわせた基礎的財政赤字のGDP比率が2010年度の水準から半減される見込みの中、財政健全化に次のような不退転の意気込みで臨んでいる。「我が国の財政状況は、債務残高がGDPの2倍程度に膨らみ、なおも更なる累増が見込まれるなど、引き続き極めて厳しい状況にあり、経済再生とともに財政健全化を達成することは、我が国の重要課題である。」
この課題の達成に向けて「骨太2015」は、2016年度から2020年度の5年度を「経済・財政再生計画」期間と呼び、その当初3年間(2016~18年度)をとくに集中改革期間と設定し、計画の中間時点(2018年度)において、改革の進捗状況を評価するとしている。具体的には、集中改革期間の努力のメルクマールとして、2018年度の基礎的財政赤字のGDP比率の目安を「−1%程度」としている。
歳出についてはさらに具体的に、国の一般歳出(基礎的財政収支対象経費から地方への財源移転である地方交付税交付金等を除いたもの)の集中改革期間を通した増加額を、それ以前3年間の取り組みを継続して、1.6兆円程度に抑えることとした。社会保障関係費についても具体的な数字が掲げられ、一般歳出と同じく集中改革期間前3年間の実績を反映して、2018年度まで1.5兆円程度の増加に抑えることとしている。
「骨太2015」はこのように財政健全化について政府の意気込みを感じさせるものであった。その一年後の「骨太2016」には集中改革期間の進捗状況についての言及はなく、「600兆円経済の実現と2020年度の財政健全化目標(筆者注:国と地方の基礎的財政収支の均衡)の双方の実現を目指す」としている。集中改革期間も2年目に入り、今年6月に取りまとめられた「骨太2017」においても、財政健全化に向けた努力の具体的な内容や成果についての言及はなく、「骨太2016」と同一の文言が繰り返されている。そして、2018年度予算編成に向け、「改革に当たっては、「経済・財政再生計画」で掲げた「財政健全化目標」の重要性に変わりはなく、基礎的財政収支(PB)を2020年度までに黒字化し、同時に債務残高対GDP比の安定的な引き下げを目指す」としている。
「骨太2017」に財政健全化の指標の一つとして債務残高対GDP比が登場したことから、政府の財政健全化の意気込みが弱くなり、「PB目標延期の布石」(日経新聞、2017年6月3日)ではないかとの懸念も表面化している。骨太方針を手掛かりとした、財政健全化に向けた政府の姿勢についてのこれ以上の検討は訓詁学となるので止めるが、藤井聡内閣官房参与のインタビューでの発言は政府の一角の雰囲気を知るうえで興味深い。骨太方針におけるPB目標の扱いについての質問に答えて、藤井氏は「PB目標は、達成時期を後ろ倒しにするのではなく堂々と取り下げるべきである。・・・PB赤字は経済を進める『ジェットエンジン』だ」(産経ニュース、2017年5月26日)と答えている。政府がこれまで進めてきた財政健全化の旗がこれほどあっさり下ろされてしまうと、総理の一政策アドバイザーの発言であるとしても、今後の財政健全化の行方が不透明になったと思われてくる。
●2.国・地方の基礎的財政収支の現状と見通し
骨太方針は、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」に基づいて政策判断と評価を行っている。その最新の結果から財政健全化の歩みと今後をみることにする(2017年1月25日経済財政諮問会議提出版)。試算は二つの経済シナリオを想定している。第一は経済再生ケースであり、日本経済がデフレ前のパフォーマンスを取り戻すと仮定し、中長期的に経済成長率は実質2%、名目3%以上となると想定している。第二はベースラインケースで、経済が足元の潜在成長率並みで推移すると仮定し、中長期的に経済成長率は実質1%弱、名目1%半ば程度となるとしている。いずれの試算も消費税率は2019年10月1日に10%に引き上げられることを前提としている。試算結果は以下の通りである。
図1はGDPの実質成長率を示したものであるが、想定されたように経済再生ケースでほぼ2%、ベースラインケースでほぼ1%程度となっている。図2は財政健全化の姿を示したものである。2015年度には国・地方の基礎的財政赤字は2010年度の水準と比べるとほぼ半減していることがわかる。「骨太2015」はこの成果をそれ以降も続けることを目指したものである。しかし、上述した集中改革期間の改革努力のメルクマールとされた2018年度における「-1%」の財政赤字水準の達成は困難となることが示され、経済再生ケースにおいて「-2.4%」、金額にしてほぼ13.8兆円の赤字が生じる見込みとなっている。基礎的財政収支の黒字化目標とされている2020年度において、経済再生ケースを想定した場合でも基礎的財政赤字のGDP比は「-1.4%」、金額にして8.3兆円程度と試算されている。ベースラインケースの場合の赤字は、図2の注に示された通りであるが、2018年度および2020年度でそれぞれ14.1兆円、11.3兆円と経済再生ケースと比べてより大きな規模となると試算されている。
このように「骨太2015」で明記された財政健全化目標の達成は現状では困難と推計されている。こうした経済財政の推移を見据えて、「PB目標」に替えて債務残高対GDP比が登場したとも考えられる。図3は経済再生ケースとベースラインケースそれぞれの債務残高対GDP比を示したものである。一見したところ経済再生ケースではこの比率は低下している。しかし、それは非常に高い名目経済成長率(2019年度以降3.7%〜3.8%)を想定している結果である。内閣府は、この仮定のもとでも2023年度以降長期金利がGDP成長率を上回り、いずれは債務残高対GDP比が上向きにとなることを指摘している。経済再生ケースより低い経済成長率を想定したベースラインケースでは、債務残高対GDP比は発散していくことが示されている。
このように内閣府試算をもってしても、財政健全化指標を債務残高対GDP比に置き換え、「PB赤字は経済を進める『ジェットエンジン』だ」と主張することは困難である。また、経済成長率や長期金利は経済や政治などさまざまな要因を反映して決定されるものである。したがって、それらの変数の合成からなる債務残高対GDP比を政策当局者にとって操作可能な変数とみなすことはできない。債務残高対GDP比は「骨太2015」で示された歳入と歳出面での財政改革努力の成果であることを忘れてはならない。
図1 図2 図3
●3.なぜ財政健全化が必要なのか
日本の財政健全化が困難に直面していることを述べた。それでもなぜ、国・地方の基礎的財政収支の黒字化を目指す財政健全化が日本で必要なのか。ここでは論点を絞り、社会保障財政の規律を守るうえで財政健全化は不可欠の手段であることを主張したい。
まず社会保障関係費が国の財政に占める大きさをからみていくことにする。2017年度の国の予算において社会保障関係費は32.4兆円である。それに対して、国税の根幹となっている所得税、法人税と消費税の合計は47.5兆円である。しかし、所得税と法人税の33.1%と消費税の22.3%は地方交付税の原資とされているので、この3税から国の予算として残る額は、33.6兆円となる。その全額を社会保障関係費に投入しても残るのは1.2兆円である。所得税、法人税および消費税以外の国の税収はほぼ10兆円なので、税収だけでは国は到底その歳出を賄うことはできないことは明らかである。
もちろん消費税以外の税収はその使途を限定されているわけではなく、ここで示したのは社会保障関係費と税収規模のイメージにしかすぎない。しかし、社会保障関係費を賄うためには国の所得税、法人税と消費税のほぼ全部を投入しなくてはならいないことからだけでも、社会保障が日本の財政で支えきれないほど大きな負担となっているかは明らかである。
社会保障に係る費用の問題はたんにその額の大きさだけではない。より悩ましい問題は、国(および地方)が公費として社会保障費用の肩代わりをする額が定まっていないことである。国は社会保障にかかった費用の事後的な負担を求められているだけで、社会保障の費用自体を抑制する手段を持ち合わせていない。
このことを医療制度を通じてみていきたい。現在日本の医療制度改革は、地域医療構想、医療費適正化計画と国民健康保険の保険者である都道府県の権限の強化の3つの柱で支えられている。いずれもわかりにくい専門用語で、医療制度のプロ以外は近づきがたいが、その中身はおおむね次のようである。まず地域医療構想とは、入院時に投入される医療資源(医療費)の水準にしたがって、病状を高度急性期、急性期、回復期、慢性期などに分類し、都道府県別にそれぞれの状態毎に必要な病床数を推計することを指す。次に医療費適正化計画は、医療費の地域間格差を縮小して、医療費全体の額を抑えていくことを目指したものである。もっとわかりやすく言えば、医療費の高い地域の費用抑制を求めるものである。最後に都道府県の権限強化とは、このようにして定まる都道府県別の病床数や高い医療費の抑制を実現するために、保険者である都道府県の指導権限を強化させることを指す。
以上が現在日本で進められている医療制度改革の根幹である。それは、病床規制、医療費の地域間格差是正、およびそれらに実効力を持たせるための保険者の権限強化からなっている。しかし、ここで生じる疑問は、その結果医療費はどう抑制され、それが医療への公費負担のどれだけの削減につながるかという、制度改革の費用・公費負担への反映が明らかとされていないことである。改革の手法はともかくとして、肝心の医療費への連関が閉ざされているのである。言い換えれば、日本の医療制度改革では増大する医療費、それに伴う公費負担に歯止めがかかっていない。
こうしたなかで、日本の財政の持続可能性を高めるためには、医療を含む社会保障の財政規律を高めることが最大の課題である。そのためのより有効な制度改革を促すためにも、総額としての財政収支の目標を定め、その範囲に社会保障関係費を抑制することが不可避である。その具体的な政策への反映の一つが、「2020年度までに国と地方を合わせた基礎的財政収支の均衡」なのである。基礎的財政収支の均衡は債務残高対GDP比の低下や安定を意味するものではないが、社会保障財政の規律を高める手段としての役割を期待することはできる。
ここでわれわれが自身に投げかけた、日本はなぜ財政健全化が必要かという問いに立ち返れば、その答えは社会保障が今後機能し続けることを可能にするためということである。それによって日本経済全体の安定性を増すことが可能となる。それほど社会保障が日本経済と財政に深く関係しているという認識が重要である。
マクロ経済学的にみればデフレ脱却を完全に果たしていない経済状態で、政策の限界的な効果が明らかに下がってきた金融政策を補完する、より刺激的な財政政策を求める声もある。そうした論点について議論する紙幅は尽きたが、以上述べたように日本財政の持続可能性への疑問が高まっているなかで、安易な財政拡大が人々の将来不安を増大させ、その結果債務の単なる上乗せに帰す危険を指摘しておきたい。
|
|
●やっぱり「財政再建目標」が間違いである 2017/7
|
●いまだ抜き取られない毒矢
去る6月9日、日本経済の方向を決定づける政府予算の方針が、「骨太の方針」として閣議決定された。
この決定に向けて筆者は、経済政策担当の内閣官房参与として、
「これまでの政府方針は予算の『規律』が厳しすぎ、増税と予算カットが過剰に進められ、結果としてデフレ不況が続き、かえって財政を悪化させている。だから真の『財政再建』を目指すなら一時的に財政規律を緩め、デフレを終わらせる積極財政を短期的に徹底展開することが必要不可欠だ」
という主張を繰り返し政府内外に提案し続けてきた。
結果、今回の「骨太」にはそんな筆者の主張が一部採用された。そして、「単なる増税と予算カット、つまり、『単なる緊縮』でなく、経済を成長させて借金の重荷を減らす」という財政目標が明記された。
この目標なら、日本人が豊かになることを通して財政問題を改善でき、大きな「前進」となったのだが――その最新の「骨太」においてさえ、「プライマリーバランス黒字化目標」(あるいは、PB目標と略称)という不条理極まりない規律は解除されなかった。つまり、PB目標という、日本に打ち込まれた「毒矢」は抜き取られなかったのだ。
このため、日本は未だに、デフレから脱却できず、中長期的な財政改善が望めない状況に置かれているのである――その理由は、以下の通りだ。
●家計とはまったく違うもの
そもそも「プライマリーバランス」(略してPB)というのは、「政府の収入と支出の差」、つまり「財政の収支」である(ただし、支出については、社会保障費や公共事業費などの通常行政のための支出が対象だ。したがって、PBはしばしば「基礎的財政収支」と言われる)。
政府は今、このプライマリーバランスの「赤字」を毎年減らし、2020年度には黒字化しよう、という「財政再建目標」を掲げている。これは一般に「2020年のPB黒字化目標」とも言われている。
そして、安倍内閣はこの目標を達成するために、2014年に消費増税を行うと同時に、様々な支出を抑制し、PB赤字を着実に縮小させてきた。実際、安倍内閣は、13兆円以上ものPB赤字を縮小させる「激しい緊縮財政」を行っているのだ。
もし仮に、政府を家計に例えるなら、「収支が赤字」なら「黒字化するのが当たり前」だと誰もが素朴に感ずるだろう。だから、この「PB黒字化目標」は、世論にすんなりと受け入れられ、官僚や政治家の中でも、その目標は至って「正しい」と感じられている。
しかし、それは完全なる勘違いだ。なぜなら、政府と家計はまったく「違う」からだ。
そもそも政府は家計では無く「企業」に似た存在だ。そして企業というものは、上手に支出を増やせばビジネスチャンスが拡大し、収入が増える存在。逆に支出を切り詰め過ぎれば儲けが減る。だから企業の収支改善には、単なる「緊縮」ではダメなのだ。それでは確実に自滅する。あらゆる企業は仕入れしたり新しい店を出したり、「カネを借りて、使う」ことを通してビジネスを拡大する。当たり前のことだ。
だからこそ政府は、家計の主婦感覚で支出を切り詰めれば収入は確実に減少し、かえって借金が膨らむ。つまり、PB赤字を無理して縮小すればするほどに、財政は悪化し、将来のPB赤字を拡大させてしまうのである。
つまり、「異性にもてたい」とあがくほどに異性から嫌われたり、「信頼されたい」ともがくほどに信頼を失っていくことがあるように、「PBを黒字化したい」と無理して緊縮すればするほどに、PBは悪化していくのである。
これこそ、PB目標撤廃が必要不可欠だと、筆者が考えている理性的根拠である。
●場合によっては消費税減税すべき
筆者はこうした主張を、政府関係者のみならず、世論に対しては『プライマリーバランス亡国論』という著書を通して、そして、与党自民党に対しては「日本の未来を考える勉強会」(代表呼びかけ人・安藤裕衆院議員)での発表を通して訴え続けた。
そしてこの度、この勉強会を構成する自民党の当選2回の28人の衆院議員達によってとりまとめられた「デフレ不況から完全に脱却し、日本経済を成長路線に乗せると同時に、 財政再建を果たすために必要な財政政策に関する提言」の中に、筆者の主張が取り入れられた。
この提言書はそのタイトルが示すとおり、「デフレ不況から完全に脱却し、日本経済を成長路線に乗せると同時に、 財政再建を果たすためには、PB制約を撤廃した上で、積極的な財政政策を展開することが必要である」ということを主張するものである。
その基本的な認識は、民間投資を補う財政出動を絞れば経済が低迷し、税収減で「財政がかえって悪くなっている」という点。
だからこそ、消費増税は凍結すべきであり、場合によっては「減税」すら視野に納めるべきではないかとも主張する一方で、PB目標に代わる新しい財政規律として、毎年度の当初予算の増額幅を2兆〜3兆円に抑えることを目安にすべきだと提言している。
600兆円経済を実現するためには年率3〜4%ずつの需要拡大が必須だが、それと歩調を合わせる形で、当初予算も3〜4%ずつ、つまり2〜3兆円ずつ拡大すべきだというのが論拠である。
ただし、当面の間はこの支出拡大だけでは、デフレ脱却を望むことはできない。だから、デフレ完全脱却を果たすためには、少なくとも2〜3年間は「建設国債」、さらには、「教育国債」を積極的に発行しつつ、補正予算を出動していくことが必要不可欠である旨も明記されている。
筆者は、この提言に全面的に賛成する。この主張はまさに、これまで筆者が主張し続けた内容と軌を一にするものだからである。
●デフレからの脱却を目指して
この提言は本年7月5日、官邸においては萩生田副官房長官に、自民党においては西村総裁特別補佐に手交された。政府、そして与党の中で、この提案が真摯に受け止められ、アベノミクスが真に成功し、デフレから完全に脱却できる果敢な財政政策が展開されることを、心から祈念したい。
ただし、この動きに対しては批判が展開され始めている。例えば、経済ジャーナリストの磯山友幸氏は、この動きを危険視し、PB目標撤廃や増税凍結などもってのほかと論じている。氏は、その理由をこう説明している。
〈 国債などの国の借金が1000兆円を超える中で、単年度の赤字をこれ以上出さないことは「当たり前」のことだろう。多額の借金を抱えている家庭が、生活費が必要だからと毎月カードローンでお金を借りていれば、いつかは財政破綻する 〉
この主張がいかに誤ったものであるかは、上記の筆者の主張をご覧頂ければ一目瞭然だろう。政府は家計と違う。企業のようなものなのであり、(今の日本のように)業績がふるわない状況では、投資を中心とした支出拡大で、業績改善を図るほかに生き残る道はないのだ。
彼の議論はそれ以外にも、1)増税による景気低迷が如何に税収を減らしているかという事実も、2)自国通貨建ての国債によって完全破綻した国家は歴史上存在しないという事実も、3)財政目標の国際標準も日本政府の「公約」における目標も(PBでなく)「債務対GDP比の引き下げ」であるという事実も、4)債務対GDP比は名目成長率が拡大すれば引き下がるというという事実も、5)名目成長率が向上すれば翌年のPBが改善するという事実も、全て無視されている。
そのうえで、上記のような政府を家計になぞらえたナイーブな批判を展開しているに過ぎないのである(筆者の主張の詳細は、繰り返すが、拙著『プライマリーバランス亡国論』を参照されたい)。
ただしおそらく、こうした誤った認識に基づく批判は、これからも繰り返されることだろう。しかしそうした批判によって、これまで緊縮が続けられ、その結果、景気も財政も悪化しているのは、先に述べた通りだ。
日本がデフレを脱却し、財政を真に改善していくために一番必要なのは、こうした誤解だらけの経済論説に騙されないことなのではないかと、筆者は真剣に感じているのである。 |


 |



|
|
●財政健全化不要論を牽制 2019/4
|
財務省は17日、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の分科会を開き、新元号「令和」の時代に向けた財政再建の議論を始めた。昨年11月にまとめた建議(意見書)では、平成について「一段と財政を悪化させてしまった」と反省し、「新時代では同じ過ちを繰り返さない」としていた。17日の分科会ではこれを踏まえた論点を示し、有識者などから挙がる“財政再建不要論”を牽制した。
「平成の財政には悔いが残る。(分科会の委員は)みな危機意識を高めている」。分科会後の記者会見で増田寛也会長代理はこう述べた。
財務省は分科会に示した論点で、流動性が高い金融資産を除いた政府の「純債務残高」の対国内総生産(GDP)比が152・8%と、イタリア(119・5%)、フランス(87・5%)などほかの主要国より高く、日本の財政状況は悪いと改めて指摘。また、海外投資家の国債保有割合は12・1%にとどまるものの、国債市場での海外投資家による売買は現物で36・1%、先物で62・9%に達し、海外投資家の動向次第で金利上昇が起こりうる状況であることを警告した。
毎年度の予算で歳入を国債発行に頼る構造が続いていることについては、将来、国債費(元本の償還費と利払い費の合計)が歳出に占める比率が増し、「(財政支出の余地が狭まることで)必要性が高い政策の実現を妨げる」と分析した。
財政支出の規模に関しては、社会保障以外の支出の対GDP比は平成27年で15・4%と、20年前の7年から2・9ポイント減ったが、イタリア(7ポイント減)、ドイツ(10・6ポイント減)などに及ばず、「諸外国と比べ緊縮財政とはいえない」(財務省幹部)とした。今後、少子高齢化が進むことに絡み、「生産性向上による成長を目指すのが当然だが、財政のあり方は中長期的視点に立った堅実な経済前提に立ち、考えることが基本」との考えも示した。
また論点は、最近注目を浴びている、財政赤字容認の「現代貨幣理論(MMT)」にも言及。「極端な議論に陥ると財政規律を緩めることになり極めて危険。日本をその実験場にする考え方は持っていない」とした麻生太郎財務相の国会答弁や、同じく否定的な日銀の黒田東彦総裁、ノーベル賞経済学者らの見解を紹介し、財政再建に逆行する主張にくみしない姿勢を明確にした。
|
|
●新たな財政再建不要論:現代貨幣理論(MMT) 2019/6
|
●注目をあびる財政再建不要論
現代貨幣理論(MMT)が注目を浴びています。代表的論客の一人がステファニー・ケルトン教授(ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校)ですが、彼女は民主党の大統領候補だったバーニー・サンダースの経済アドバイザーを務め、ポール・クルーグマン教授などとはなばなしく論戦を交わしています。
MMT(Modern Money Theory またはModern Monetary Theory)の最大の特徴は、財政再建不要論を主張するところです。MMTの理論的支柱の一人であるL. Randall Wrayによると、「独自の通貨を有する主権国家は、債務を履行できないことはあり得ない。なぜなら、債務の期限が来れば、そのたびごとに通貨を発行することで支払いができるからだ。」その点で、「主権国家は家計や企業とは違う。家計や企業は通貨の利用者に過ぎないのに対して、主権国家は通貨の発行者なのだ。」というわけです(Wray, 2015)。
●MMTの貨幣論
このように考えるのは、彼らが、主流派経済学が想定してきたものとは異なる貨幣論に立脚していることが大きく影響しています。主流派経済学は、貨幣の起源を物々交換が直面する「二重の欲望」という困難性を克服するために登場した「一般的受容性」に求めます。これは金属主義(Metallism)と呼ばれている立場です。これに対して、MMTは、貨幣の起源を、政府が発行し、それによって納税することを要求することに求めています。これは表券主義(Chartalism)と呼ばれている考え方です。このため、MMTは、しばしば新表券主義(Neo-Chartalism)とも呼ばれています。
MMTは、通常は政府と中央銀行を統合した統合政府で考えていますので、「政府が通貨を供給する」という言い方をします。もちろん、近代では、中央銀行が貨幣を供給するのであって、政府ではありません。しかし、彼らは、それを考慮しても本質は変わらないとしています。その際に利用されているのが、循環理論(Circuit Theory)と呼ばれるアプローチで、政府と中央銀行の間のバランスシート上のやり取りを詳細に追っていくことで説明しようというものです。
それを通じて、貨幣は、政府が支出をすることによって供給され(Injection)、徴税によって回収される(Distruction)と理解します。これの逆ではないことが重要です。これの逆であると、政府支出は税収によって制約されることになります。しかし、そうではないというのが、財政再建不要論につながるところです。
●部門間の貯蓄投資バランスの調整
以上のような議論は、民間部門や海外部門を考慮したとしても、基本的には変わらないといいます。マクロ経済的な側面から見ると、政府部門と民間部門や海外部門との間では、貯蓄投資バランスの合計がゼロでなければならないという制約があります。仮にここで簡単化のために海外部門はバランスしているとすると、政府部門が投資超過(財政赤字)であれば、民間部門は貯蓄超過でなければならないというわけです。これは事後的には必ず成立する関係ですが、事前的には成立する保証はありません。何らかのメカニズムが作動することによって、政府部門の貯蓄投資バランスと民間部門のそれとが整合するように調整される必要があります。
この点について、MMTは、財政のビルトインスタビライザーの機能に大きく期待します。例えば、財政赤字が過大である場合には、経済活動がそれだけ活発になっているはずだが、その場合には、制度に組み込まれたビルトインスタビライザーのメカニズムによって自然に財政収支が調整され、財政赤字と民間部門の貯蓄超過とが整合するように調整されるとしています。
●政府の雇用保障プログラム
通常想定されるようなビルトインスタビライザーの場合、それほど大きな作用を及ぼすことは考えにくいのですが、実は、この前提には、MMTの独特な失業対策の考え方があります。MMTは、完全雇用の達成を重視しますが、それをケインジアンが主張する有効需要政策を通じて達成するのではなく、政府が労働市場に直接介入することで達成すべきだと主張します。
具体的には、雇用保障プログラム(Job Guarantee program)の導入を提案しています。これは一定の賃金水準を前提に、政府が、常に希望者全員に仕事を提供するというプログラムです。これが導入されれば、不況時には多くの申し込みがあり、財政支出は増えるものの、失業者はいなくなることになります。また、好況時には、失業者が減り、申し込みが減少し、財政支出は減少することになります。このように政府が最後の雇い主(Employer of Last Resort)になることによって、政府の財政赤字は民間部門の貯蓄投資バランスと整合性が採れるはずだとします。
●インフレと完全雇用
このような場合に懸念されるのは、それほどまでに財政赤字が拡大し、通貨供給も膨張すれば、インフレをもたらすことになるのではないかということです。しかし、MMTはそれを否定します。MMTによれば、インフレは完全雇用になって初めて生じるものであり、ひとたび完全雇用が達成されれば積極的な財政政策は必要なくなるので、インフレは起きないとしています。
●政府債務の上限
最後に、どうしても残る疑問は、財政赤字を続けることによって累積される政府債務には上限はないのか、という点です。その点についてもMMTは楽観的です。
MMTによれば、そもそも、政府は通貨を供給できるので、財政支出をするための原資を調達するために国債を発行する必要はありません。にもかかわらず政府が国債を発行するのは、民間部門に利子が付く金融資産を提供するためであり、中央銀行に利子率目標を達成するための政策手段を提供するためだと説明します。
では、政府債務のGDP比が際限なく上昇を続ける可能性はないのか。この疑問については、それと並行して様々な調整が行われるはずなので(例えば民間活動の活発化による税収のGDPを上回る伸び等)、そのようなことにならないと説明しています。また、仮にそのような事態になったとしても、利子率を政策的にコントロールできるはずだし、最終的には、政府はいくらでも通貨を供給することができるので、債務不履行になることはない、とします。
●MMTへの問題提起
以上のようなMMTの考え方については、主流派経済学とはあまりに考え方が違うので、戸惑うことが多いのですが、とりあえずは、以下のような問題を提起したいと思います。
第1に、MMTが前提とする貨幣論についての疑問です。歴史的に金属主義の方が正しいのか、表券主義の方が正しいのかは、貨幣史による検証を待つしかありません。しかし、表券主義の場合、仮に徴税によって貨幣の使用を強制できたとしても、それはあくまでも「支払手段」としてであって、交換手段としての機能や、価値尺度としての機能ではないはずです。そうであれば、貨幣に後者のような機能がどのように備わってきたのかについて、説明が必要であるように思います。
第2に、政府が発行する国債を民間部門が全て購入することができるのか、という疑問です。仮に貯蓄投資バランスが整合的になるべきだとしても、民間部門が保有したいと思うポートフォリオの内容と国債の発行額とが整合的か、という問題があります。仮に国債が過剰に発行されてしまった場合、当然、国債価格が下落し、国債利回りが上昇します。これに対して、MMTは、利子率は政策変数なので、コントロールすれば良いだけで、問題はないと考えるのです。しかし、中央銀行がコントロールできるのは短期金利であって、長期金利は通常はコントロールできません(イールド・カーブ・コントロールをやっている日本は異常なのです)。こうした点については、どのように考えるのかは課題だと思います。
第3に、インフレに対する楽観的な考え方に対する疑問です。インフレは、MMTが想定しているように、完全雇用になってから初めて問題になるような非連続的な現象ではなく、フィリップス曲線が示すように連続的な現象です。したがって、完全雇用に到達する以前にインフレが高じることがあるはずですが、その時にどうするかという問題が生じる可能性があります。これは貨幣供給による財政赤字のファイナンスに対する制約にはならないのでしょうか。
第4に、統合政府の考え方に対する疑問です。統合政府の考え方は、主流派経済学でも取り入れられており、政府と中央銀行を統合するものです。これについては、現代の中央銀行は政府から独立していて、国債の引き受けも禁じられているのであって、それを無視しているという批判があります。加えて、MMTの場合には、徴税が重要な意味を持っているわけですが、これは民主主義的な国家においては、政府ではなく、議会の権限に属しています。そして議会が、政府の考える税制の変更に異論を唱えることは容易に想像できます。このような権限の分離が制約にならないのかについても、検討する必要があるように思います。
●非主流派経済学としてのMMT
財政再建の必要性を否定するという考え方としては、近年注目されたHelicopter money論や物価の財政理論などがあります。MMTは、その結論においては、そうした考え方と共通するところがありますが、MMTの特徴は、それらのように主流派の経済学の中から出てきたものではなく、いわゆるPost-Keynesian の流れをくむものだということです。その起源はKeynes やMinskyの考え方に基を辿ることができます。また、基本的な主張については、Abba Lerner が主張したFunctional Financeにもその源流が見られます。
このような特徴を持つMMTに対して、主流派経済学の立場から批判することは容易です。しかし、理論的な枠組みの外から批判するだけではMMTとの議論はかみ合いません。異なる枠組みを前提にするMMTに対しては、これまでの財政再建否定論に対するのとは別の検討を必要とします。その理論的な起源にまで遡って、その議論を丁寧に吟味する必要があるように思います。
|
|
●「財政再建しなくても破綻しない」話題の経済理論MMT 2019/7
|
自国の通貨を発行して借金できる国が財政破綻することはない。だから財政再建のために政府の支出を減らしたり税や保険料の国民負担を増やしたりしなくても、借金を膨らませて費用を賄えばいい——。
アメリカで一部の経済学者らが提唱し、主流派の学者から異端視されながらも世論の一定の支持を得る「現代貨幣理論(Modern Monetary Theory、MMT)」。「巨額債務を抱えているのにインフレも金利上昇も起きない日本が実例だ」と発言した米ニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授が7月16日、東京都内で講演し、改めてMMTの正当性を訴えたニュースも注目された。
本当にそんなうまい話があるのだろうか?アベノミクスは「異端」の領域に踏み込んでいるのか?提唱者の著作を分析した専門家に聞いた。
●現状への問題提起は「共感できる部分もある」
2018年、アメリカで史上最年少(29歳)の女性下院議員となり旋風を巻き起こした民主党のアレクサンドリア・オカシオコルテス氏が支持を表明し、一気に知名度が上がったMMT。ニッセイ基礎研究所専務理事の櫨浩一さんによると、標準的な理論体系があるわけではないという。ここでの議論は、経済学者ランダル・レイ氏の著作「Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems」(2012年)に基づく。
「MMTは現実経済の描写と、それに基づく政策提言という2つの部分から成ります。前者には共感できる部分もありますが、後者については賛同できない部分が多いです」(櫨さん)
櫨さんが評価するのは、単に政府が財政赤字を減らそうとするだけでは景気が悪化し、結果として財政赤字は期待したほど減らないおそれがあることをMMTが強調している点だ。
MMTは、ある国の経済状況を考える時、政府・企業・家計・海外という「部門」ごとの金融資産と負債の差額=純金融資産の動きを重視する。前提として、ある国の純金融資産はすべての部門の収支を合計するとゼロになるとしている。単純化して言えば「誰かの赤字は、他の誰かの黒字になる」。この考え方自体は、主流派経済学と同じだ。
するとどうなるか。政府が財政赤字(負債)を減らすと、それに伴い企業や家計などの黒字(純金融資産)も減る。その時、企業や家計が収支の悪化を避けるために支出(企業による投資や人件費への支出、家計の消費支出)を減らせば、景気が落ち込む可能性がある。そうなると当初の想定よりも税収が減り、財政はそれほど改善しないというわけだ。
「この点は財政再建に関する議論で無視されがちなので、MMTがこの問題を改めて提起しているのは正しいと思います。
つまり財政再建を成功させるためには、政府は支出の削減や増税による収支改善の努力をするだけでなく、企業に設備投資や賃上げ・雇用増を促す税制改革や規制改革などもしっかり進めなければならない、という結論を導くことができます。これは重要なポイントだと私も考えます。
ところがMMTが主張する問題解決の方向性はいま話した内容とは異なり、『失業者の増加や企業の投資の減少といった経済活動の縮小均衡を避けるためには、政府は財政再建をせず、さらに借金をして財政赤字を増やし、支出すべきだ』としています。これは間違いだと思います」(櫨さん)
●まずは「財政破綻を厳密に定義すべきだ」
櫨さんは、「自国の通貨を発行して借金ができる国が財政破綻することはない」というMMTの主張を検討する際には、「財政破綻」を厳密に定義すべきだという。
「財政破綻は3つのケースに分けられます。
(1)原理的に財政赤字が借金によって賄えなくなる
(2)今の制度のもとでは財政赤字が借金によって賄えなくなる
(3)原理的には可能だが、別の問題が生じるため財政赤字を借金で賄わない方がマシ
——というものです。
MMTは(1)の財政破綻は起こらないと言っているにすぎません。自国の中央銀行(日本なら日本銀行)に、政府が(国の借金証書にあたる)国債を買わせて自国通貨(日本円)をどんどん発行させれば、際限なく政府の支出を賄うことは原理的には可能です。
理由は後で説明しますが、日本を含む主要国では、中央銀行が国債を政府から直接買い入れることを法律で禁じています。MMTは、そのような制約があるなら法律や制度を変えてしまえばいいので(2)についても問題ない、というとらえ方をしています。
この点、各国の財政当局関係者や財政学者は(2)の財政破綻が起きると主張することが多いので、MMTの論者との間で議論がかみ合わない場合が目立つのです。
しかし最も重要な問題は、たとえ法律や制度を変えたとしても、(3)は起こり得るということです」
MMTも、政府が借金を膨らませて支出を増やしていけば、やがて全体として国内の需要が供給を上回り、いずれかの時点でインフレが起きるとしている。
万一インフレが加速し、お金の価値がどんどん下がっていくとどうなるか?
インフレに伴って価値が上がりやすい不動産や株式といった資産をたくさん持つ富裕層には、それほど悪影響はないかもしれない。しかし、わずかな蓄えや年金に頼る高齢者の暮らしは一気に苦しくなり、賃金が物価ほど伸びなければ現役世代の生活も大打撃を受けるなど、大多数の人が困ることになる。これが(3)のケースだ。
●MMTもインフレのリスクは認めている
「MMTの提唱者の間では、(景気が良く、仕事を選ばなければ誰でも職に就ける)完全雇用の状態になるまでインフレは起きないと主張する人もいますが、レイ氏は完全雇用に至る前でも物価上昇が加速する可能性はあると認めています。いずれにしてもインフレが起きたら、その時点で政府が支出削減や増税などによって物価上昇を抑えるから大丈夫、というのがMMTの考え方です。例えば、年金や生活保護の増額を物価上昇率より低く抑えて実質的な政府支出を減らす、といった手段を用いるとしています」(櫨さん)
そうした引き締め策が絶妙のタイミングで、かつ「引き締めすぎず、緩すぎもせず」という完璧な内容で実施されれば、深刻な問題は生じないのかもしれない。ただ、櫨さんは次のように指摘する。
「インフレが起きたら引き締めるという手法では、タイミングが間に合わないおそれがあります。例えば増税や支出の削減は、法律を国会で成立させたうえで、さらに実施まである程度の期間を設けるといった手順を踏むことになります。
そもそも政府が常に最善の政策を実行するとは限りません。みんなにとって心地よいインフレ率のゾーンはかなり狭く、その範囲に収まるように政策をファインチューニング(微調整)するのはとても難しいことなのです。
歴史を振り返れば、政府に自由に通貨を発行できる権限を与えると、必ずと言っていいほどその権限を乱用して大惨事を引き起こしてきました。だからこそ今では主要国は、政府の言いなりになるかもしれない中央銀行が国債を直接買い入れることを禁じているのです」
●アベノミクスとMMT「ほぼ同じという言い方もできる」
日銀が国債を民間金融機関から大量に買い入れ、市場をお金でじゃぶじゃぶにして景気を刺激する。これがアベノミクスの柱である「異次元の金融緩和」の肝だ。
政府はそのおかげで、「これほどの借金は返せないのでは」と考える人が増えて国債に買い手がつかなくなる事態を心配せずに、借金を膨らませながら高水準の支出を続けられている。
「政府と日銀は別々に存在しており、日銀は国債を政府から直接買ってはいません。確かに現状はMMTそのものではありません。ただ実態として、日銀は政府が発行する国債の大半を間接的に買い入れており、日銀の金融政策を決める審議委員も政府寄りの人が多数を占めています。見方によっては、MMTとほとんど同じだ、という言い方もできるかもしれません」(櫨さん)
かつて政治家は右肩上がりの経済が生み出すパイを切り分けていれば良かったが、低成長が当たり前となり、「誰かを助けるには誰かに負担をお願いしなければならない」時代になった。「誰も痛みを感じずに問題を解決できる」と訴えるMMTや、それと似たような主張が魅力的に見えることは不思議ではない。今回の参院選でも、国民の負担増も含む現実的なビジョンを示して財政再建の必要性を強く訴える主要政党はない。
「日本は完全雇用の状態が続いています。さまざまな要因がありまだインフレは起きていませんが、今後は急に物価が上がり出す可能性も十分にあります。景気が今より少しスローダウンしても、街に失業者があふれるような状況ではありません。大きな危険を冒してまで、財政拡張や金融緩和といった景気刺激策をさらに追加する必要はないと思います。思いきりふかしているアクセルを、もう少し緩めてもいいのではないでしょうか」(櫨さん)
「炭鉱のカナリア」という言葉がある。炭鉱で有毒ガスが発生すると、人間より早く気付いて鳴くのを止める習性があるので、労働者はカゴに入れたカナリアを連れて坑道に入ったことに由来する。櫨さんはこの言葉を引いて、次のように指摘した。
「海外のMMTの提唱者や支持者にとっては、先進国でも飛び抜けて財政状況が悪い日本でインフレも財政破綻も起きていないということは安心材料でしょう。でも、炭鉱のカナリア扱いされている日本人にとっては、大した気休めにはなりません」
|
|
●私たちは財政赤字を気にしなくてもよい世界に舞い戻ったのかも 2019/9
|
10月に消費税が10%に引き上げられます。ただ、消費税引き上げといいますか、財政再建には根強い反対があるのも事実です。
財政再建は、景気が回復するのを待つべきなのでしょうか?そもそも、財政再建を実行できる景気の状態あるいはマクロ経済のファンダメンタルズはどのようなものなのでしょうか?
マクロ経済のファンダメンタルズのうち、国債金利と経済成長率の大小関係は、財政再建に大きな影響を与えます。
国債金利が経済成長率より大きい場合は、財政赤字の継続は、政府債務残高対GDP比率を発散させるという意味で財政破綻を惹起しますから、財政再建が必要になります。こうした国債金利が経済成長率より大きな世界は「新古典派的な世界」と言えます。
一方、経済成長率が国債金利より大きい場合は、一定の条件のもとでは、財政赤字が継続しても、政府債務残高対GDP比率は放っておいても一定の値に収束するので、財政再建は不要です。しかも、消費を奨励したほうが国民の厚生(ハッピーさ)も増すので、消費税引き上げは愚策となります。こうした経済成長率が国債金利よりも大きな世界は「ケインジアン的な世界」と言えるでしょう。
では、日本では、これまで、国債金利と経済成長率はどのような関係にあったのでしょうか?
下図を見てください。国債金利と経済成長率の関係は、3つの時期に区分できます。
図 国債金利(加重平均)と経済成長率の関係
まず、バブル期を含む安定成長期(1975年から1991年まで)です。この時期は、1975年以降の国債の大量発行によりようやく国債流通市場が整備され始め、国債金利が実質的に自由化されたころです(それ以前は、実質的に規制金利の時代)。また、高度成長は終焉したもののバブルを経験するなど、平均してみれば、経済成長率が国債金利を上回っています。個別の時期を見れば、財政非常事態宣言が出されるほど、財政危機が深刻と認識されたこともありましたが、総じてみれば、財政は安定していました。
次に、バブル崩壊から旧民主党政権の崩壊までの失われた20年の時代です(1992年から2012年まで)。この時期は、デフレが深刻化し、経済成長率が低迷したこともあって、国債金利が経済成長率を上回っています。この時期、プライマリーバランスの黒字化を目指す政策が指向されたのも当然です。そうしなければ、いずれ財政が破綻してしまうからです。
実際、この時期、政府債務残高対GDP比は急上昇しています。
問題は、2013年から現在に至るアベノミクスの時代です。経済成長率と国債金利の大小関係を見ますと、平均的には経済成長率が国債金利よりも大きくなっていますので、財政赤字を気にする必要はありません。
したがって、わたしたちは財政赤字を気にしなくてもよい世界に舞い戻ったのかもしれないとも言えます。もしくは、バブルへGO!!
このとき、財政再建は不要ですし、消費税の引き上げもナンセンスです。逆に、消費税の引き上げで消費を冷え込ませるのは悪手で、国民をアンハッピーにさせてしまいます。
しかし、問題は今後です。
先のグラフを見ますと、2000年代半ばまで低下を続けた国債金利は現在横ばいになっていて、これ以上低下する様子がありません。一方、経済成長率はアベノミクス開始初期の勢いはなく、低下していくようにも見えます。つまり、いつまで経済成長率が国債金利を上回り続けるのか、予断を許さない状況と言えます。
財政健全派(財政再建が必要)と財政不健全派(財政再建は不要)の路線対立は、結局、今後も日銀が国債金利を低位で封じ込められ続けられるか否か、(潜在)成長率がマイナスからゼロ近傍にあるか否か、の見立てにあるといえるでしょう。
経済学的には、新古典派対ケインズ経済学と言えるでしょうか。
さて、国債金利がマイナスのうちに国債を大量に発行して、国債金利をさらに引き下げればよいというギャンブルも魅力的ではあるのですが、個人的には、潜在成長率はゼロ近傍で推移するだろうと思っていますし、財政に関しては政治家を全く信用していないブキャナン派ですので、いつ国債金利が経済成長率を上回る新古典派的な世界に転じてもいいように、堅実な財政運営が必要ではないかとの立場です。
なお、わたしは財政健全派だとしても、「経済成長率は今後も国債金利を上回り続ける!」との財政不健全派(積極財政派)の立場を否定できるだけの材料を持ち合わせているわけではありませんから、彼ら彼女らの意見も尊重すべきと考えています。
その上で、政府の立場にも矛盾があるのではないかと思っています。
というのは、今後の財政政策を考える上では、経済成長率と国債金利が将来的にどう推移していくのかをしっかりした根拠をもって見通すことが最低限必要だと思うのですが、肝心の政府の見立ては、内閣府「中長期の経済財政に関する試算(令和元年7月31日経済財政諮問会議提出)」にあるように、経済成長率が国債金利を上回るケース(成長実現ケース)と国債金利が経済成長率を上回るケース(ベースラインケース)という相反する2つのケースが示されています。絶妙なバランス感(笑)。
ちなみに、成長実現ケースはアベノミクス成功ケース、ベースラインケースはアベノミクス失敗ケースに他なりません。
財政再建の必要性が真逆となる2つのケースを予測されても、今後の財政政策の方向性を考える上ではまったく意味がありませんね...。政府は、出たとこ勝負!で財政運営をするつもりなのか、とても心配になってしまいます。本当に経済・財政の舵取りを任せても大丈夫なんでしょうかね?
まぁ、実際には、消費税を引き上げて財政再建を目指しているわけですから、政府としては、成長率が国債金利を下回るベースラインケース(アベノミクス失敗ケース!)を念頭に置いて経済・財政運営を行っていると思われますが、じゃあ、成長実現ケースというのはなんなのか、それはそれで不信感を抱かざるを得ないのは仕方ないでしょう。
さらに、足元では、経済成長率が国債金利を上回っている訳で、その点ではアベノミクスは成功しているとも言え、このトレンドをどう評価した上で、アベノミクスが失敗するというベースラインケースを採用しているのか、つまり、アベノミクスがどういう理由でうまくいかないと考えているのか、国民にハッキリ説明しておく必要があると思います。
特に、政府が経済・財政運営の基本と考えている(らしい)マクロ経済想定と矛盾する成長実現ケースが2019年財政検証の事実上の基本ケース(ケースIII)として、わたしたちの老後の年金の(所得代替率)見通しにも多大な影響を与えている訳ですから…。
まとめると、現在われわれは財政赤字を気にしなくてもよい世界にいるのかもしれない可能性をしっかり検証した上で、現在の財政運営と2019年財政検証を評価し、その整合性をチェックしなければならないのだと思います。 |


 |



|
|
●財政健全化が話題とならなくなった理由 2020/2
|
最近、マスコミで財政健全化がすっかり話題にならなくなった。例えば1月17日に公表された中長期の経済財政に関する試算の報道ぶりである。「わが国の財政目標」の進捗度合いを年2回示す試算で、今回、「2025年度PB(基礎的収支)の黒字化」という目標達成が、昨年夏の試算より1年遅れ、2027年度になるという内容であった。しかし各紙の報道は、淡々と事実を伝えるのみで、財政目標達成がより困難になったことの意義やその重大性を伝えるところではなかった。財政目標が、ここまで国民の関心事から外れた事情や背景を考えてみたい。
第1の理由は、財政健全化が進まず財政目標が先延ばしされても、金利や為替レートに変化はみられず、国民に不都合な事態は生じていないという、多分にわが国特有な事情である。しかし市場に変化が生じないのは、日銀による超金融緩和策、財政ファイナンスの結果であり、その政策自体の持続可能性、正当性が問われるべきであろう。「市場金利が経済成長より低い」という都合のよい状況は、世界経済の状況から見ても、長続きしないということである。
第2の理由は、財政目標の前提となる政府の試算が、都合よく策定されており、試算の信ぴょう性が薄いことである。試算(成長実現ケース)はその前提として、2020年代前半に実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率が想定されている。潜在成長率はプラス0.6%程度、全要素生産性(TFP)上昇率もバブル期並みの1.3%程度まで上昇する。これまでの試算での甘い前提は実現されず、財政赤字やPBバランスの数値は、改定のたびに悪化(PB黒字が遠のく)した。このような政権におもねった内閣府の試算が、国民の健全な危機意識をゆがめ、財政再建に対する関心を失わせている。さらには、安倍総理が「今後10年間消費増税は必要がない」と語ったことも、国民が受益と負担の問題を真剣に考えるきっかけを奪ってしまった。
3番目の理由は、世界的なポピュリズムの蔓延から緊縮財政への反発という流れが生じていることである。米国では、「財政健全派・小さな政府の共和党」、「財政拡大派・大きな政府の民主党」というのがこれまでのすみわけであったが、トランプ大統領は共和党にもかかわらず、法人税減税や大型投資などでかつてない景気拡大策を取り、一兆ドルという巨額の財政赤字を作っている。英国のジョンソン首相も、BREXITへの対応もあり、財政規律を重視したこれまでの保守党とは一線を画した政策をとっている。極めつけはEUで、これまでの厳格な財政ルールの見直しに着手している。公表された改革案では、環境投資(グリーンニューディール)とデジタル分野への投資を財政規律から外し容認する内容となっている。図は先進諸国の財政赤字(GDP比)の推移で、2019年は推計値だが米国、英国、フランス、イタリアの財政赤字が拡大しはじめていることが見てとれる。
図 財政収支の国際比較(GDP比)
4番目に、財政拡張政策を支援する現代貨幣理論(MMT)という「異教」の登場である。この理論は、政府と中央銀行は統合勘定とみなすので、政府の国債発行残高のうち日銀が保有している分は相殺(プラスマイナスゼロ)される。そこで、国債が基本的に国内でファイナンスされている国では、「政府の借金の拡大は国民の資産の拡大」ということになる。この結果、政府は、民間経済に貯蓄の余剰や需要不足があるかぎり、赤字を出す財政政策が望ましいことになる。金融政策の有効性を否定し、すべては財政政策だということで、筆者は「遅れてきたケインズ主義」と呼んでいるが、財政再建不要論に使われている。
このようなことから財政健全化が国民の関心から落ちてしまった。これをどう考えるべきだろうか。筆者が思うのは、わが国のように、国内貯蓄で財政赤字をファイナンスできる国では、ギリシャのような金利高騰、インフレといった状況は突然やってくるのではないということだ。GDPの2倍規模の借金を積み上げても、毎年予算の3分の1を借金に頼っても、国の信頼を揺るがすようなハイパーインフレや円安はやってこない。デフレ脱却は成らないまでも、物価安定・低失業率の下で国民はそこそこ安定した暮らしを維持できている。これは事実である。しかし、例えば、逃げ水のようなわが国の公的年金制度は、財政破綻の兆候といえなくもない。高齢化の下、抗がん剤やアルツハイマーの薬の開発が進んでいるが、治療に必要にもかかわらず高額で保険対象とならない、「カネの切れ目が命の切れ目」という事態も想定される。これも、約束した社会保障が提供されないということで財政破綻の一歩ともいえよう。一般会計予算の3分の1を借金に依存し、歳出の2割超の予算を過去の借金の返済に回さざるをえない状況は財政破綻の始まりともいえる。わが国では、財政破綻は突然やってくるのではなく、じわじわと押し寄せてくるのであろう。オオカミの好物は、小さな財政破綻で、それを作らない地道な努力が最大のオオカミ対策ということではないか。
|
|
●なぜ国民の財政健全化への興味は薄れたのか 2020/3
|
政府は1月17日、中長期の財政試算を公表した。政府の財政目標は2025年度の基礎的財政収支(PB)の黒字化だが、試算では3.6兆円の赤字となっており、昨年夏の2.3兆円の赤字からさらに拡大、黒字化達成は2025年度ではなく2027年度になるという内容である。わが国の財政目標の達成がまた遅れるというニュースであるが、マスコミや国民の関心は低い。その理由、背景を考えてみた。
まず指摘すべきは、政府が年2回公表する財政試算の前提が政府の都合のよい数値になっており、試算そのものへの信ぴょう性が薄いことである。試算(成長実現ケース)の前提として2020年代前半に実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率が想定されており、潜在成長率も+0.6%程度、全要素生産性(TFP)上昇率もバブル期並みの1.3%程度まで上昇することとなっている。
これまでも同様の甘い前提は実現されず、財政赤字やPBバランスの数値は、改定のたびに悪化(PB黒字が遠のく)し、真剣に考えようという国民の気持ちを逆なでしている。政権におもねった内閣府の試算が、国民の健全な危機意識をゆがめているといえよう。
次に、おそらく最大の要因と思われるのが、財政健全化が進まなくても、金利や為替レート、インフレ率に大きな変化はなく、労働人口減少の下で低水準の失業率が続くなど国民生活に大きな不都合は出ていないということである。先進国最悪の財政赤字が続いていても、日銀が借金をファイナンスするので、危険を伝えるシグナルは鳴らない。安倍総理が「今後10年間消費増税は必要がない」と語ったことも、国民の財政再建に対する関心を失わさせている。
加えて最近、MMTなる「異教」が入ってきて、都合よくそれを活用する人たちが出てきた。この理論は、政府と中央銀行は統合勘定とみなすので、政府の国債発行残高のうち日銀保有分は相殺(プラスマイナスゼロ)され、わが国のように国債が基本的に国内でファイナンスされている国では、「政府の借金の拡大は国民の資産の拡大」ということになる。したがって、政府は緊縮財政を行う必要はなく、民間経済に貯蓄の余剰や需要不足があるかぎり、赤字を出す財政政策が望ましいことになる。金融政策の有効性を否定し、すべては財政政策だということで、積極的財政政策をうたうケインズ主義と酷似しているが、財政再建不要論に使われている。
3番目に、国際的に財政再建論調が後退していることである。端的な例は、財政赤字に厳しい対応を見せる米国共和党や英国保守党が、トランプ大統領、ジョンソン首相というポピュリズム政権の下で、財政規律に対して緩い政策を容認していることである。EUも財政政策による経済の安定の維持という点に重点がシフトし、厳しい財政規律の見直し議論が始まっている。
これに対して筆者が思うのは、「財政破綻」とは何かという点である。我々には、ギリシャの財政危機の例が記憶に生々しいが、わが国では、そこに至るまでに生じる「財政破綻の始まり」が国民生活に大きな影響を及ぼすのではないかということだ。例えば「政府が約束した社会保障が提供されていない」ということ、あるいは逃げ水のような公的年金制度は、財政破綻の始まりといえなくもない。
もっといえば、一般会計予算の3分の1を国債に依存し、歳出の2割超、23兆もの予算を過去の借金の返済に回さざるをえない状況は、すでに財政破綻が始まっているともいえる。
いずれにしても、財政破綻は突然やってくるわけではなく、じわじわ押し寄せてくる。その予兆をとらえて世の中に警鐘を鳴らすのが政府の役割ではないか。オオカミの急襲に備えるには、好物である財政破綻の目を一つずつ摘んでおくことが最大の良策ということなのだろう
。 |
|
●財政健全化などいらない! 懲りない財務省 2020/6
|
我が国で初めて通常予算において赤字国債が発行されたのは1975年のことです。
ときの内閣は三木内閣。
蔵相は、「あー、うー」でお馴染み、のちに総理大臣となる大平正芳さんでした。
大平蔵相は当時、通常予算で発の赤字国債を発行したことをもって「万死に値する。一生かけて償う」と発言されています。
いま我が国に巣食っている、いわゆる「クニのシャッキンがぁ〜」問題は、ここからはじまったと言っていい。
その後、総理となった大平さんが、増税を訴えて総選挙を闘っていたTV映像を今でも覚えています。
「私がぁ、国民の皆様にぃ、増税をお願いするぅ、最ぃ後の男でありまーす」と、総裁遊説で声を張り上げておられました。
大平総理はその後、失脚することになりましたが、1982年、大平さんの後継者である鈴木善幸内閣で「財政非常事態宣言」が出され、その7年後には竹下登内閣のもとで大平さん念願の「消費税」が導入されています。
消費税導入から6年後の1995年には、今度は村山富市内閣が「財政危機宣言」を出し、2年後の1997年には橋本龍太郎内閣が消費税の税率を3%から5%に引き上げ、緊縮財政路線に舵を切りました。
これが決定打でした。
そのとき未だ、民間部門(企業や家計)はバブル崩壊でつくってしまった負債を返済し終えてなかったために、我が国はデフレ経済に突入したのでございます。
平成が終わり、令和へと時代が改まったにもかかわらず、未だデフレです。
2018年時点での日本政府の長期債務残高は、1107.4兆円です。
村山内閣時の2.7倍で、鈴木内閣時の5.4倍、そして「万死に値するぅ」と大平蔵相が言った(三木内閣)時の34.5倍でございます。
それでも、我が日本政府が破綻(デフォルト)の危機に直面したことなどございません。
それは政府債務の額がまだ小さいからでもなく、国民の預貯金に助けられているわけでもありません。
自国通貨建てで国債を発行し、国内のモノやサービスをつくる力(供給能力)が充分にあり、かつ変動為替相場制を採用している国家には、どんなに借金をしても破綻のしようがないからです。
なお、日本の財政が健全化する(政府債務を減らす)ことができないのも、べつに政府の緊縮努力が足らないからでもありません。
話はむしろ逆で、政府が緊縮するからデフレを脱却できず、デフレを脱却しないからGDPが成長しない。
GDPが成長しないから税収も増えず、政府債務の対GDP比率も低下していかないだけです。
結局、健全財政など無駄であり、かつ不要な努力なのです。
MMT(現代貨幣理論)の代表的論者である、ランダル・レイが言うように「正常なケースは、政府が財政赤字を運営していること、即ち税によって徴収する以上の通貨(負債)を供給(拡大)していること」が重要です。
この半世紀、政府は2度も「財政危機」を宣言し、緊縮財政と増税を正当化し具現化してきましたが、一向に財政健全化もデフレ脱却も達成されていません。
それでもまだ懲りない財務省は、有識者とされる人たちを集め「財政健全化が必要だ」という世論形成に必死です。
『平時の「財政健全化」重要に 財務省懇談会で指摘 / 財務省は22日、有識者を交えた「国の債務管理のあり方に関する懇談会」を開いた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた大型の財政出動を念頭に、複数の委員から将来的に財政健全化への取り組みが重要になると指摘が出た。(後略)』
彼らは執拗に「このまま政府が国債発行額を増やし続けると、やがてハイパーインフレになるぅ〜」と言うけれど… ハイパーインフレとは、年率にして13,000%のインフレ率です。
因みに、6月19日に発表された5月消費者物価指数をみますと、国際的なインフレ率の定義であるコアコアCPI(食料とエネルギーを除く総合指数)は、わずか「0.1%」という異常な低さです。
これが1年後に13,000%になる、と言うのなら、どの程度の国債を発行したらそのようになるのか、明確に示してほしい。
ご承知のとおり、令和2年度予算では補正を含め約90兆円の国債が発行されています。
それでも今の日本経済の現状(デフレ状態)では、理想的なインフレ率(2〜5%)にすら到達しないでしょう。
|
|
●景気回復局面で財政健全化をしっかりと進めることの重要性 2020/8
|
●プライマリー・バランスの黒字化は見通せなくなった
7月31日に内閣府は、「中長期の経済財政に関する試算(2020年7月)」を公表した。コロナショックが日本で本格的に生じる前の今年1月時点での試算を見直したものだ。当然のことながら、コロナショックによる経済の悪化と財政支出の大幅拡大を受けて、先行きの財政見通しは急速に悪化している。
政府はプライマリー・バランス(基礎的財政収支)を2025年度までに黒字化するという目標を掲げてきたが、成長実現ケースというかなり楽観的な経済見通しを前提とした場合でも、目標年となる2025年度のプライマリー・バランスは7.3兆円の赤字、名目GDP比で−1.1%となる。黒字化が達成されるのは、2029年度だ。1月時点での成長実現ケースでは、黒字化達成の時期は2027年度であったことから、達成時期は今回2年先送りされた。
しかし、この成長実現ケースは実質2%程度、名目3%程度のGDP成長が先行き続くことを前提としており、およそ現実的ではない。年間ベースでの名目3%台の成長は、90年代のバブル崩壊以降、我々は一度も経験したことがない。
実質、名目ともに1%台半ば程度の平均成長率を前提とするベースラインケースのもとでは、2029年度のプライマリー・バランスは名目GDP比で−1.7%の赤字が続き、黒字化の達成は全く見通せなくなる。ただし、過去7年間の成長率の平均は実質1.0%程度、名目1.6%程度であったことを踏まえれば、このベースラインケースの前提も楽観的過ぎよう。内閣府及び日本銀行の潜在成長率の推計値は、いずれも1%を下回っている。コロナショックを受けて、潜在成長率やインフレ率のトレンドが一段と下振れた可能性も十分にあるだろう。
こうした点から、2025年度のプライマリー・バランス黒字化どころか、現在の経済環境や政策の延長線上では、将来にわたってプライマリー・バランス黒字化の達成は見通せないのが現状だ。
●黒字化目標は一時的に棚上げ
ところが政府は、全く形骸化してしまったこの2025年度のプライマリー・バランス黒字化目標を、なお維持する考えを明らかにしている。歳出改革を進めれば達成は可能、と説明しているのである。
当事者自身も、流石にそれが達成可能だとは思っていないはずだ。しかし、コロナショック後の経済情勢がまだ見えず、また、さらなる追加財政出動を迫られる可能性も残されている。現時点で新たな目標値を定めると、そうした政策も制約を受けてしまう。全く形骸化してしまった2025年度のプライマリー・バランス黒字化目標を現時点で修正しないのは、コロナ対応のために財政健全化方針を一時的に棚上げしていることの表れと言えるではないか。
これは、2%の物価目標の達成を一時的に棚上げしている日本銀行の政策姿勢ともちょうど重なる。コロナショックを受けて日本銀行は、当面の金融政策運営を2%の物価目標の達成と切り離す方針を示唆している。
事態が落ち着けば、政府はプライマリー・バランス黒字化目標を正式に見直すだろう。国際公約にまで位置付けられた2020年度の黒字化目標を、以前に2025年度へと先送りしたように、次は2030年度まで再び先送りを決める可能性があるだろう。
●景気回復の追い風の下で財政健全化を進める必要
このように、黒字化目標が達成できずに繰り返し先送りされつつもなお、抜本的な財政健全化策がとられてこなかった背景には、景気回復局面では、緩やかにプライマリー・バランスの改善が見られてきたことがあるだろう。目標達成はできなくても、財政環境が改善していれば許されるといった甘えが政府にあったのではないか。
2010年度にプライマリー・バランスのGDP比率は−6.3%であったが、2018年度には確かに−1.9%にまで改善していた。しかしこれは、世界経済の回復に助けられた部分が大きいのである。
そしてひとたび景気情勢が悪化すれば、今回のように、そうした緩やかな改善は一気に吹き飛んでしまう。今回の内閣府の見通しでは、2020年度の実質GDP成長率が−4.5%となることを前提に、2020年度のプライマリー・バランスのGDP比率は−12.8%まで悪化した。実際はもっと悪化するだろう。
今回、景気悪化の引き金となったのは予見できなかったコロナ問題ではあったが、仮にそうした突発的な出来事が生じなくても、近年では10年に一度程度の頻度で、世界経済は後退局面に陥ってきたのである。
こうした点を踏まえれば、経済が回復過程にある局面では、緩やかなプライマリー・バランスの改善に甘んじることなく、積極的に財政健全化を進めるべきであった。そうしなければ、景気後退の発生と共に、10年程度をかけたプライマリー・バランスの改善分は一瞬にして失われてしまうのである。
政府には、この教訓を是非とも今後に生かし、景気後退時の財政環境の急激な悪化の可能性を織り込んだ上で、財政健全化の推進に努めてほしい。
●コロナ対策でも財源の確保を
コロナショックへの対応では、企業と雇用の支援を中心に、なお追加の財政支出が必要だろう。当然のことながら、必要な対策は講じなければならないのである。しかし、それを安易に国債発行で賄うことは問題がある。中長期的な財政環境の悪化を一段と進めないために、そして将来へと負担を転嫁しないためには、近い将来の増収策と言う形で財源をしっかりと確保した上で、財政面での必要な対策を果敢に講じるべきではないか。
形骸化したプライマリー・バランス黒字化目標を維持し、その目標を棚上げすることが、野放図な国債発行の拡大を許してしまうことがないように、国民もしっかりと目を光らせておく必要があるだろう。 |


 |



|
|
●財政の悪化 健全化めざすためには 2021/1
|
政府が発行する国債の償還までの期間が急速に短くなっている。2019年度発行分の償還は平均9年後だったが、20年度は6年8カ月後、21年度も6年10カ月後となる計画だ。
短期の資金調達が増えるほど金融市場が混乱した際の影響を受けやすくなる。このため、財務省は期間が長い国債の発行比率を高めてきたが、コロナ禍で転換した。政府の借金急増で、リスクが高い長期国債への需要が限界に近づき、日本銀行が大量購入する短期国債に頼らざるを得なくなったからだ。
国債市場では超低金利が続いており、国債の発行が行き詰まるとは当面考えにくい。だが、日銀が実質的に政府の借金を引き受ける異例の政策は、いつまでも続けられないことを、政府は肝に銘じなければならない。
借金拡大を止めるには、政策経費を税収などでまかなえるかを示す基礎的財政収支を黒字にすることが欠かせない。
内閣府が先週公表した試算によると、今年度の国と地方の基礎的収支の赤字は69兆円。昨年1月の試算から54兆円も膨らんだ。25年度に黒字化する計画の達成は絶望的である。
政府が目標とする実質2%程度という高めの経済成長を続けたとしても、黒字になるのは29年度だ。第2次安倍政権下並みの実質1%程度ならば、試算の最終年度の30年度でも10兆円の赤字が残る。
政府は、歳出と歳入の両面を改革しなければ、黒字化できない現実を直視するべきだ。
菅首相は今国会の施政方針演説で「(人口減社会を迎えるなか)国民に負担をお願いする政策も必要になる。その必要性を国民に説明し、理解してもらわなければならない」と信条を述べた。財政再建ほど、この言葉の重みが問われる課題はない。
コロナ禍のいまは、国民の命や暮らしを守ることが急務で、財政出動を惜しむべき局面ではない。ただ、感染収束後には、財政の立て直しに正面から取り組む必要がある。先送りを防ぐには、感染や景気がどのような状況になれば作業を本格化するのか、一定の目安を設けるよう、あらかじめ議論しておくことが求められる。
きのう衆院で審議入りした今年度3次補正予算案は、緊急事態宣言を前提にしていない。このため観光や飲食などの需要喚起策「Go To」事業に1兆円超が計上されている。いま優先するべきは、逼迫(ひっぱく)する医療機関や収入が減った低所得者への支援であり、予算を早急に組み替えるべきだ。
現実とずれた不要不急の事業を行う余裕などないことを、まず政府は自覚する必要がある。 |
 |


 |



|


 |



|


 |



|


 |



|




 |



|