���̍ד��E�܌��J�ƌ܌������E�m���E�~�J1�E�~�J2�E�܌��J�̔o���E�^�ӕ����E�E�E
�ŏ��̔o���E�܌��J�o��W1�E�܌��J�o��W2�E�܌��J�o��W3�E�E�E
�����˓��⒮�@/�@�⒮�E�⒮������Â��E�⒮�̌��W�E�l���ƈ�������E�⒮�Ґ��@�E�����܂̎����E���������E�⒮�̔o��1�E�o��2�E���������Ɛ�����錍�E�p�\�R�����N�E���w�҂ƕ������E��Ǝ⒮�E�\���x����l�т��E�t�͗��Ɗv�����E�N����Ă��S�̉^�����~�߂Ȃ��E���܂�ɐ������E�����Ă͂����Ȃ��l�͂Ȃ��E�l���̖����E�s�ς̉��������̂��E�o�b�V���O�o�����E���̐��ʼn��{���Y�����E�鏑�ƃ}�W�����E�l���ⓚ�E�R���i�s���̓��X�E�K���̒͂ݕ��E�R���i�͂��̐푈�ɕC�G�E�s���Ȏ���̐������E�⒮����̖@�b�E�j�͂��Â�����Ǝv���E�s�ϑ���̍Ȃƍ����E�������E�s�ϑ���̖��ƑΒk�E�j�^�̂Ȃ��l�E���l�̎ʐ^�E�z���G�����ƑΒk�E�o�b�V���O���ꂽ�l�̖����E���R���E�f���̋O���E�E�E
�@
 �@
�@ �@
�@
�܌��J�́u���݂���v�Ƃ�ޓ�ǎ��ł��邪�A���́u���݂���v�́u����(�H)�̐�����v�ɗR������ƌ����Ă���B�Ȃ��܌��J�́u�������߁v�Ƃ��ǂ߂�B�u���݂���v���u�������߁v���������ǂݕ��Ƃ݂Ȃ���Ă���B
���Ȃ݂Ɂu�܌��J�v�͉Ă̋G��ł���B
�u�܌��J�v�́A��������C�ɍs���I����̂ł͂Ȃ��A�f���I��(���炾���)�J��ւ����悤�Ȃ��܂��w���\���ł�����B�J�g(�J���g��)�������Ԃɂ킽���čs�����⓬���́u�܌��J��p�v��u�܌��J�X�g�v�ȂǂƌĂ��B�r�W�l�X�V�[���ł́A�d�q���[���ȂǂŘA������ہA��x�ɗv����`�����ꂸ���x���ǐL�𑗂��Ă��܂��悤�ȏ��u�܌��J���v�Ƃ����A���M���鑤���u�܌��J���ł��݂܂���v�ƒf������邱�Ƃ����Β�Ԃ̍�@�ƂȂ��Ă���B
 �@
�@ �@
�@
���A��܌����ɍ~��Â����J�B�܂��A���̎����B��B�~�J(����)�B�������߁B�s�G�E�āt���Í�(905�]914)�āE��l�u�܌��J�ɕ��v�Ђ���Ίs����ӂ����Ȃ��Ă��Â��䂭��ށq�I�F���r�v���o�~�E���̍ד�(1693�]94��)�ŏ��u�܌��J�����߂đ����ŏ��v�B(�u���݂���v���������J��Ԃ��~�邱�Ƃ���) �p�����Ȃ��ŁA�J��Ԃ��s���Ȃǂɂ��Ă����B�u���݂��ꎮ�v[�ꎏ](1)�u���v�́u����(�܌�)�v�́u���v�Ɠ����B�u���t�W�v�ȂǏ��̕����ɂ͊m�F�ł��Ȃ��B���ł͋G�߂ɂ������Ȃ��u�O���ȏ�(��)�J�v�k�\���{�a�����E��l�������u�Ȃ�(��)�߁v�ɕ�܂���Ă����Ǝv����B(2)�̑�Ƃ��Ắu�������N�֔�����b���ʉ̍��v�������A���̌�u�x�͕S��v�A�����āu���t�W�v�Ȍ�̒���W�ő������Ă��A�ċG�̑�\�I�f�ނƂȂ����B
��〘��������〙 ���݂��ꂪ�~��B�a�̂ł́A�����u������v�̈ӂ������ėp����B�s�G�E�āt���F�Õ�(970�]999��)�����u���݂��ꂽ�邱��قЂ̂Ƃ߂āv���a�����L(11�b�O)�u���ق����ɂ��݂����Ƃ�v�ӂ�ތN���Ђ킽�鍡���̂Ȃ��߂��v
��[��������] 〘��〙 �����݂���(�܌��J)�s�G�E�āt�����ŏW(1213)�āu�܌����ߍ~���ɂ���߂��������Ă�߂�v���o�~�E����(1691)��u���̓��∨�X���������߁q�m�ԁr�v
��[���݂���] �s�u���v�͌܌������Ȃǂ́u���v�A�u�݂���v�͐����݂��ꂩ�t �A��5������ɍ~��Â����J�B�~�J�B��B�������߁B�s�G �āt�u�\���W�߂đ����ŏ��^�m�ԁv�B�f���I�ɂ��܂ł����炾��Ƒ������Ƃ̂��Ƃ��B�u�܌��J���v�u�܌��J��p�v�B
 �@
�@ �@
�@
���ǂݕ�
�u�܌��J�v�̓ǂݕ��́u���݂���v�ł��B�u���v�͋���܌��́u�H��(����)�v�ȂǂɁA�u�݂���v�́u������v�ɗR�����܂��B�u�������߁v�Ƃ����ǂݕ�������܂����A�Ӑ}�I�ɂ����ǂ܂���ꍇ�������̂ŁA�ӂ肪�Ȃ����Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A��ʓI�Ɂu���݂���v�Ɠǂ݂܂��B
���ꌹ�E�R��
���݂���́u���v�́A�u�H��(����)�v��u���c(���Ȃ�)�v�ȂǂƓ��l�ɁA�k����Ӗ�����Ì�u���v�B�u�݂���v�́A�u������(�݂���)�v�ł���B�Â��́A�����Łu�܌��J��(���݂���)�v�Ǝg���Ă���A�܌��J�͂��̖����`�ɂ�����B�u�܌��J��(���݂���)�v�́A�a�̂Łu����v�̈Ӗ��ɂ����ėp���邱�Ƃ������B
���Ӗ�1 / ����܌����ɍ~�葱�����J�A�~�J
�u�܌��J�v�Ƃ́A����̌܌����ɍ~�葱�����J�̂��ƂŁA�~�J�̂��Ƃ������Ă��܂��B����̌܌��́A���ݗp�����Ă���V��ł͘Z���O��ɂ�����̂ŁA�~�J�̋G�߂ł��B����̌܌��ɂ́A�u�H���v�݂̂Ȃ炸�u�܌��J���v�Ƃ����ُ̂�����܂��B�܌��J�͉Ă̋G��ł��B�~�J�Ƃ����A�����Ƃ������A�J�T�ȋG�߂Ƃ������C���[�W�����������ł����A�u�܌��J�v�Ƃ����A���t�̋�������`����������i�������Ԃ�������܂���B���t�ЂƂŋC�����ς�邩��s�v�c�ł��ˁB���Ȃ݂ɁA�l�C�̃u���E�U�Q�[���u�͑����ꂭ�����`�͂���v�ɓo�ꂷ��L�����u�܌��J�v�́A�쒀�́u�܌��J�v(���݂͂�����p������q�́u���݂���v��������)���炫�Ă���A�~�J�̉J�ɗR�����Ă��܂��B
���Ӗ�2 / �f���I�ɂ��܂ł����炾��Ƒ�������
�܌��J�́A��������x�ŏI��炸�A�f���I�ɂ��炾��Ƒ������Ƃ̂��Ƃ��ł�����܂��B�~�J�̉J���~������~�肷��l�q�ɂȂ��炦���\���ł��B�J���g���������Ԃɂ킽���čs�����⓬���́u�܌��J��p�v�u�܌��J�X�g�v�ȂǂƌĂ�܂��B�܂��A�Ƃ��ɂ悭�g����̂́u���v�������u�܌��J���v�Ƃ����\���ł��B�r�W�l�X�V�[���ł͓���I�Ɏg���Ă���̂ŁA�Ӗ���g�������������Ă����܂��傤�B
���u�܌��J���v�̈Ӗ��E�g�����E�ᕶ
�r�W�l�X�V�[���ł́A��x�����ŏI��炸���x���lj����čs����Ԃ̂��Ƃ�\���Ƃ��Ɏg���܂��B�Ⴆ�A�d�q���[���ŘA�������⎑������x�ɂ܂Ƃ߂đ��炸�A�ォ��lj����邩�����ŏ����݂ɘA������i�D�ɂȂ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�l�т�Ӗ��ŁA���M���鑤���u�܌��J���ł��݂܂���v�Ƃ������\����p���܂��B�������A�l�K�e�B�u�Ȃ��ƂƂ͌���܂���B�u�܌��J���v�́A��x�ɑS�Ă��s���̂ł͂Ȃ��A�����I�ɏ������s���Ă��������Ή�����������@�������̂ŁA���炩���ߍ��ӂ������Ă���A�����ł�����������i�߂Ă����܂��B
<�ᕶ>
•�܌��J���Ƀ��[���������肵�\�������܂���B
•�܌��J���ŋ��k�ł��B���ꂪ�Ō�̎���Ȃ̂ł���낵�����肢�������܂��B
•�܌��J���Ŏ��炵�܂��B��قǂ̎����������肢�����܂��B
•�����������̂���܌��J���ɔ[�i�����Ă��������܂��B
•�܌��J���ō\���܂���̂ŁA�i������Ă��������B
•�{���̎����͌܌��J���ɓ͂��̂ŁA�܂Ƃ߂Ă����Ă��������B
•��c���܌��J���ɍs���Ă���A�����o�[�ɂ���J�̐F�������܂��B
 �@
�@ �@
�@
�����J�A���݂���A�܌��J�_
�����
�A��܌��ɍ~��J�B�~�J���ɍ~�葱���J�̂��ƁB�~�J�͎����\���A�܌��J�͉J��\���B�u�������߁v�܂��́u���݂����v�Ɖr�܂��B�_�앨�̐���ɂ͑厖�ȉJ���A���J�͑����ƌ�ʂ��Ւf�������萅�Q���N�������Ƃ�����B[���ẮA�Ă̎O���������āA���āA�ӉĂƕ������Ƃ��̔��̈ꃖ���ŁA�قژZ���ɂ�����܂��B��\�l�ߋC�ł�䊎�A�Ď��̊���(�Z���Z�������玵���Z����)�ɂȂ�܂��B]�@
�����
�܌��J�����߂đ����ŏ��@�m�ԁu���̂ق����v
�܌��J�̍~�c���Ă�����@�m�ԁu���̂ق����v
���݂���̋��Ƃ�����@�m�ԁu�^�։����v
�܌��J�Ɍ䕨���⌎�̊�@�m�ԁu���R�̈�v
�܌��J�����Ԃݐq�ʌ���́@�m�ԁu��a����v
�܌��̉J��Ђ̗��܂ł��@�m�ԁu���V���v
�܌��J�◴���g��ԑ��Y�@�m�ԁu�]�ːV���v
�܌��J�ɒ߂̑��݂������Ȃ��@�m�ԁu�����L�v
���͂��ėe�瑓���܌��J�@�m�ԁu�����I�v
�܌��J�≱�̗��̐��@�m�ԁu�ꎚ�H���W�v
�܌��J�ɂ�����ʂ��̂␣�c�̋��@�m�ԁu�D��v
�܌��J�͑�~���Âނ݂����Ɓ@�m�ԁu乐��v
�܌��J��F���ւ�����ǂ̐Ձ@�m�ԁu������L�v
���̓��∨�X���������߁@�m�ԁu�����v
�܌��J����(������)�ςӌK�̔��@�m�ԁu�������v
���݂����ƂȂ����ۖ؋��@�f���u�Y�U�v
���݂�����͂�O�ɉƓ@�����u������W�v
�܌��J�⋛�Ƃ�l�̗���ׂ��@���l���q�u�ܕS��v
���݂����Đς߂錬�̉��@�H�열�V��u���]����W�v
 �@
�@ �@
�@
��������`�ĉJ��ɗ����A�J���։��闬��̌��������A��̉Ԓd�����ɐZ�Ă��܂ЁA��̉�����ଂ䂩���܂ň��ɗ���ƂȂāA�n����ĉ����ւ��^��ōs���B
��̈ł̒��ŁA�J���^�������ƂȂė����ė���₤�Ɏv�͂��B�D���͂ˏ��A�������Q�����ė���A����Â��A���������Ă��ʂĂ����Ȃ��B�Ƃ̒����Ăēd���̉��ŁA���Ƃ��̉����Ă�Ă��s�����P�ė���BଂƂ���~���Ċ��c�̒��ւ����荞��ł��������o���Ȃ��B
���Ɓ^�_�Ƃ��ď������Ă���A���͖��ɕs���ȋC�����Ė���Ȃ����B��n�̏�𗬂�Ă�鐅���A�������ꃖ���������߂Ēn���֗��ꍞ��ōs����A��������n��̗L�肽���̐�����̂₤�ɂȂĒ�������ōs����A�l�Ԃ̒m�炸�ɂ��ԂɁA�n���̒����^��ŕ���ĕs�ӂɗ������݂͂��Ȃ����Ƃ��ӂ₤�ȋC������ꂽ�B
�Ǝv�ӂƁA�܂����҂����̒n�����瓪���グ�āA�n��̓����̎��@�ɍۂ��āA�n��Ă��l�Ԃ̉Ɖ����A�В[����˂��|���ł����͂��Ȃ����B�����̂��̋����Ȏ肪�A�����̉�Ă��Ƃ�ଉ��L����āA�Ƃ�h�蓮�����Ă��̂ł͂���܂����B
���̂₤�Ɍ��̂₤�ɁA���͂͂ƊႪ���߂�ƁA�������ɉƂ̂䂳�^�_�h���Ԃ�ꂽ�̂��������B���𗧂Ă�ƁA�����^�_���Ӑ��̉����n���֗��ꍞ��ł��₤�Ɏv�͂ꂽ�B�n���̖ウ�ƁA�n��̓����Ƃ��A���������Ɉ��Ղ�^�ւȂ����B
�������ӕs�������ӂ��U�����B
�ܘZ���o�ƌ܌��J���~�B�d���_����d�ÁT�������B�_��̊Ԃ���J�ɐ�͂ꂽ�����ė����B���̌����n��ɗ������B�n�̔�����͓��C���������B�����萂��Ă���̗t�����D�������グ��B���X�̉肪�L�т������B
�ˏ�q���J�����āA�J�C���Ă�ꀏL���Ƃ̒��֓��̌��������ƁA��̖ʂɁA�l�̑����ׂ̂Ɓ^�_���Ă��̂��ڂɂ͂Ђ��B�s�}�C�����Č���ƁA��Ə�Ƃ̊Ԃ��牽���o���T�Ă��̂��ڂɂ͂Ђ��B���Ƃ����̊Ԃ͂͂��肵�Ȃ����B�T�ւ�Ă悭����ƒ|�̉�̂₤���B���͂��Ƃ��ċ}���ŏ���グ�Č����Bଔ̔j��ڂ���|�̉肪�O�l���L�тďo�Ă�B�����̂͏�Ɉ������āA��̐��ɂЂ��₰��ꂽ�₤�ɂ��āA����ł��P�ى������֏o�������߂悤�^�_�Ɩウ�Ă��₤�ȗl�����Ă�B�����̂͒��x��̕~���������߂Ă���^�_�L�я�炤�Ƃ��Ă�B
���͏���O�l���グ�āAଔ䂩���������Č����B�납�痬�ꍞ�����A�܂����������ɂ����������Ă�钆����A�Ђ��Ђ�낵���|�̉肪�A�ޕ��ɂ������ɂ���ʂɐL�яo�āAଔɓ��������āA���߂������ɋȂĂ�B�����̒����ւ̂��˂Ă��₤�ɁA�����|�̍����n����ং͂Ă�B���̌����������炩�k��āA�����܂Ŏ˂�����ŁA�s�v�c�ȐF�Ɍ��Ă�B
���͕|�낵���Ȃ��B�|�̉��E�ݎ��̂��֕s�C���Ɏv�āA���̂܁Tଔ�ł��t���ď��~�����B����Ǐ�̊Ԃɏo�Ă��肪�C�ɂȂāA�����։��C�ɂ��Ȃ�Ȃ����Bଉ��̗L�l���v�ӂƁA���̏�֕��C�ʼn�Ă��C�ɂ��Ȃ�Ȃ����B
�������ւ��̉�͌ܘZ���L�тāA���{�������o�����B���̓��͉Ƃ̒���`�����ނ₤�ɂ����B���ւ̓y�Ԃ���͂ނ��^�_�n��j�āA�����グ�ė����B�グ�Ȃǂ͉�������x�ƂȂ����^�_�˂��ꂽ�B�ƑS�̂����ɂ��^��������ꂳ���Ɏv�͂ꂽ�B
���͓~���炩���ē�O��������̉Ƃ��ڂ邱�Ƃɂ����B��������͓�O�̉Ƃ̑O��ʂ����A���l���Z��ł��l���Ȃ����B
���́A���̉Ƃ̒��ɁA�|�̉肪�v�ӂ܁T�ɐL�тāA�ˏ�q�≦�ӂ��܂̂䂪��ł��L�l���v�Е��ׂāA�����^�_���̉Ƃ̑O��ʂ�߂����B
 �@
�@ �@
�@
�u�܌��J�v�́A�u���݂���v�Ɠǂނ��Ƃ͎��m�̎����B����قǂ̓�NJ������u�������߁v�Ɠǂޕ������Ȃ��قǁA��X���{�l�ɒ蒅���Ă���s�v�c�Ȍ��t���Ǝv���܂��B�܌��J�͔~�J�̂��Ƃ��w�������̂ł����A5���ɔ~�J�H�Ƃ�����a���������u���āA�s�v�c�ȂقǂɈ�a���Ȃ�����Ă���ʔ������t�ł��B
��������ɋ���(���̎���)����V��(���z�̎���)�ֈڍs����ۂɁA1�����قǂ��Y���̐�����덷������Ȃ���A�Z���J�Ə����������ɂ��̂܂c��������́A�u�����v���̂��̂����u�ǂ݁v�ɑ�ȈӖ������邩��Ȃ̂��B�u�܌��v���u�����v�ǂ݂܂��B�Ƃ��낪�A�����̌ꌹ���T��R�����Ă݂Ă��A�u�܁v�Ɂu���v�̓ǂ݂͂���܂���B�u���v�̌����A5�Ԗڂ̌��������c�͂āA�u���v�̌��Ƃ́H
�Ðl�́A�c�̐_���w���������t���A������ɂ��鉹���u���v�Ƃ��Ă����悤�ł��B�ȑO�ɂ������܂������A�u�����ꏊ�v�̂��Ƃ��u��(����)�v�Ƃ����A�c�̐_���R��蕑�������ꂪ�A�u���E����v�ł��B�_�k�����ł�����{�l���A���̊J�Ԃ�҂��]�ޗ��R�́A�Ðl���A�ȂƎp����Ă����u�c�̐_�v�M���A�m�炸�m�炸��DNA�ɍ��ݍ��܂�Ă��邩�炾�ƍl���Ă��܂��B�c�̐_�������~�肽���Ƃւ̊��ӂ̋C�����ƁA�L�����F�O����u���Ղ�v�����A�u�Ԍ��v�̃��[�c�Ȃ̂��Ƃ����܂��B
���n�̌��ł�����A�c�A���̂��߂̈���u���c(���E�Ȃ�)�v�ƌĂсA�c�A����S���������u������(���E���Ƃ�)�v�ƌ����܂��B�߂����肵�܌��ܓ��́u�[�߂̐ߋ�v�ł����B���ł͎O���O���́u�ЂȍՂ�v�Ƒ��Ȃ��j�̎q�̂��j���Ƃ��Ē蒅���Ă��܂����A���Ă͏����̂��߂̓��ł����B
���ł́A�c�A���@�̓o��ŁA�ߋ��Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǃX�s�[�f�B�[�ɂȂ����u�c�A���v�ł����A���Ă͎�A���ł���A�r�����Ȃ�����v���܂����B�Ƒ��͂������A�e����A�����Ԃ��܂߁A��ۂƂȂ��Ď��g�܂˂Ȃ�Ȃ������͂��ł��B�����āA���̏d�J���̎傽��S���肪�A�O�q�����u�������v�ł��B
����������炷�_���Ȃ�u�c�v�ɁA�c�̐_�̑����̂�����u���c(���E�Ȃ�)�v���u������(���E���Ƃ�)�v����A�������Ă䂫�܂��B�����ŁA�c�A����O�Ɂu�q(������)�����Ƃ��v���߂ɁA�������������g�𐴂߁u�������Ȃ��v�����K�v�ɂȂ�܂��B���ꂪ�A5��5���ł����B���̓��́A�����̓c�A���̒S����ł���A���������u�������v�́A�Ǝ��ȂLj�؉������Ă͂����Ȃ��������ł���A���̑���ɁA�j�����������������Ȃ�������Ȃ����Ȃ̂ł��B�܂��ɁA�u�����V���̓��v�������̂ł��B�����āA��������u�c�A���v���n�܂�܂��B
�܌��́A�傢�Ȃ����邽�߂̑�ȁu�c�A���̌��v�ł���Ƃ������ƁB�u���c��(���E�Ȃ��Â�)�v�Ƃ������܂����A����قǏd��C�x���g�ł��邩�炱���A�]�v�Ȍ��t���Ȃ��A�u���v�̌��Ɩ��������B����̒���5�Ԗڂ��A���́u���v�̌��ɓ��������̂ł��B������܌����u���E���v�Ɠǂ݂悤�ɂȂ����̂��ƁB�������A�٘_���������邩�Ǝv���܂����A�����̂悤�ɗ]�v�Ȓm�����������A�f���Ɏ���̂����̐��ł����B
�u���c�v�Ƃ����قǂɁA���ɂ͖L�x�Ȑ�������K�v�Ƃ��܂��B�Ðl�́A���̐������m�ۂ̂��߂ɁA�ʊ��ɟ��ɒ��킵�����Ă������j������܂��B���ɁA�c�A�����ɂ͖L�x�Ȑ���K�v�Ƃ��܂��B�R�Ԃ𗬂�鐴���͂������A�~�葱����J���܂��A�M�d�Ȑ������ł��B
���p���H�������܂ł́A�c�A�������ɍ~�葱�����ʂ̉J�́A�܂��Ɍb�݂̉J�ł������͂��B�����ŁA�u���v�̌��̉J���A�u���E�݂���v�Ɩ������܂����B�u���v�͑O�q�̒ʂ�A�u�݂���v�́u������v�Ə����L���Ƃ����܂��B�u���E�݂���v�́A�܌��ɍ~��J�Ȃ̂ŁA�u�܌��J�v�ł���B
�u�܌�(���E��)�v���u�܌��J(���E�݂���)�v���A�����������������������Ă��邱�Ƃł��傤���B
 �@
�@ �@
�@
���̐́A�����m�Ԃ��u�܌��J���W�߂đ����ŏ��v�Ƃ�������r�݂܂����B�m�Ԃ��ŏ����M�ʼn����Ă����Ƃ��A�܌��J�̑�ʂȉJ����S�ĂЂƂɏW�߂����̂悤�Ɋ����č������ł��B
�J�Ƃ����������g���Ă��邭�炢�ł�����A�܌��J�Ƃ͕����ʂ�u�J�v�ł��B����ł͈�́A�ǂ�ȉJ�̂��Ƃ��w���Ă���̂ł��傤���B
���Ӗ�
��ԊԈႦ���₷���̂��A�J�̍~�鎞���ł��B�܌��̉J�Ƃ͏����܂����A���ۂɂ�5���ɍ~��J���w���Ă���̂ł͂���܂���B�����5���̉J�ł��B
�܂�A�V�������݂̗�ł́A�~�J�̎����ɓ�����܂��B �u���炾��ƍ~�葱���~�J�̒��J�v�Ƃ����Ӗ����Ƃ�����A�m�Ԃ���ʂ̐�̐����u�܌��J�v�ɗႦ���̂������܂��ˁB
�܂��A��������]���āA�~�J�̒��J�̂悤�ɂ��܂ł����炾�瑱���Ă����l�q��Ⴆ�Ďg���邱�Ƃ�����܂��B�u�܌��J���v�Ƃ������t�����ɂ��Ă��Ƃ͂���܂��H
���R��
�Ӗ����m�F�����Ƃ���ŁA���́u�܌��J�v�Ƃ������t�̗R�������Ă݂܂��傤�B���̂܂ܓǂނƁA�u�������߁v�Ƃœǂ�ł��܂������ł����A���ۂ̓ǂݕ��́u���݂���v�ł��B
�u���v�́u�H���E�܌�(����)�v��u���c(���Ȃ�)�v�Ƃ������t�ɋ��ʂ��Ă���A�Ì�ł́u�_�ɕ������v��\���܂��B�u�݂���v�Ƃ́u������(�݂���)�v�̂��Ƃł��B
�܂�A�J���~��Ƃ����Ӗ��̌��t���ƌ����Ă��܂��B �~�J�ɍ~��J�ł��邽�߁A�~�J�Ɠ����Ӗ��Ŏg����ꍇ������܂��B�������A�G�߂��Ӗ�����~�J�ɑ��āA�܌��J�͒��J���̂��̂������Ă��܂��B
 �@
�@ �@
�@
�܌��J���W�߂đ����ŏ��
����͍]�ˎ���̗L���Ȕo�l�A�����m��(�܂����傤)���r�o��ł��B�����m�Ԃ̍�i�̒��ł��L���Ȉ��Ȃ̂ł����m�̕��������ł��傤�B���Ȃ݂ɈӖ��͂���Ȋ����u�܌��J���W�߂Ă����悤�ɍŏ��͗��ꂪ�������ȁ[�v�B�ŏ��͎R�`���𗬂���ł��B
�����ł����u�܌��J�v�ł����A���݂�5���ɍ~��J�ł͂Ȃ����Ƃ͂����m�ł��傤���B�u�܌��J�v�Ƃ͔~�J�ɍ~��J�̂��Ƃ��w���܂��B�~�J�Ƃ�����6���ł���ˁB�Ȃ��g�Z���J�h�ł͂Ȃ��u�܌��J�v�Ȃ̂ł��傤�B�����͊ȒP�B�����ł����g�܌��h�͋����5��������ł��B����5���͌��݂ł���6�������w���܂��B
���u�܌��J�v�̓ǂݕ�
���X�ł����A�u�܌��J�v�͉��Ɠǂނł��傤�B�u���݂�������߂Ă͂₵�c�v�Ɣo����v���o���X�b�Əo�Ă��܂����A�u�܌��J�v�������Ĉ�u�A�u�������߁H�v�u�������߁H�v�Ɩ��������Ƃ�����l�͂��܂��B
�u�܌��J�v�́g���݂���h�Ɠǂ݂܂��B�u���v�͋���5�����w���u�܌��E�H��(����)�v����B�u����(�݂���)�v�ɂ́u�J���~��v�Ƃ����Ӗ�������܂��B
�u�������߁v�Ɠǂޏꍇ������܂����A��ʓI�Ɂu�������߁v�Ƃ͓ǂ܂Ȃ��̂Œ��ӁB
���u�܌��J���v�Ƃ�
�m�Ԃ̔o�傮�炢�ł������ɂ��Ȃ��u�܌��J�v�����A�u�܌��J��(���݂��ꂵ��)�v�̕����r�W�l�X�p�[�\���ɂƂ��Ă͓���ݐ[����������܂���B
�u�܌��J���ɂ��݂܂���v�Ƃ����t���[�Y�������Ƃ͂Ȃ��ł��傤���B
�u�܌��J���v�Ƃ͕������܂Ƃ߂Ăł͂Ȃ��A���o���ɂ��Ēf���I�ɍs���Ă������ƁB�u�܌��J�v���\���~�J�̉J�̂悤�ɁA�������f���I�ɑ����Ă����l�ɗႦ�Ă��܂��B
�r�W�l�X�V�[���ł�E���[�����Ŏ����˗��A���Ȃǂ��܂Ƃ߂Ăł͂Ȃ����o���ɑ��M�A�A�����Ă����l��\�����t�Ƃ��Ďg���Ă��܂��B�܂��A���i�⏑�ނȂǂ����o���ɔ[�i�A��o����悤�ȍۂ��g�p���܂��B
�u�܌��J���ɂ��݂܂���v�Ƃ́A�܂Ƃ߂ĘA������ł��Ȃ����Ƃ��Ӎ߂���ۂ̌��t�ł��B
���u�܌��J���v�̗�E�g����
�r�W�l�X�V�[���ł́u�܌��J���v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤���B�ȉ��̗ᕶ�Ō��Ă����܂��傤�B
�@�@�@�u�܌��J���v��E���[��
�@�@�@A�ЂƂ̑ł����킹�̌��ł��BB�Ă�C�Ă�������B�Ă̕��������Ƃ����Ă��܂����B
�@�@�@�I�b�P�[�B����̑ł����킹�܂ł�B�Ă������Ƌl�߂Ă�����
�@�@�@C�Ă������ɂ���Ă͂���Ƃ̂��Ƃł����B
�@�@�@B�Ă�O��ɐi�߂AC�Ă��������Ă�����
�@�@�@�ł��A����ς�܂������V����D�Ă������Ă��ĂƂ����Ă܂���
�@�@�@���ǂǂ��������́I�H��x�ɂ܂Ƃ߂Ă�(�{)
�u�܌��J���v�̈�����ł��ˁB���炩���߁u�܌��J���ɂ��݂܂���v�ƒf���Ă����Γ{�点�邱�Ƃ͂Ȃ����������B�Ƃ͂����A���̕\����m���Ă���l�ł���A�����Ă��炾�炵��E���[���͑���Ȃ��ł���ˁB
�u�܌��J���ɂ��݂܂���v�ƒf��̂́A��������Ēf���I�ɂȂ炴�邨���Ȃ��ꍇ�ł��B�Ⴆ�Έȉ��̂悤�ȏꍇ�B
�@�@�@�E���M������ɐV��o�āA�lj����M
�@�@�@�E�����������̂��珇���[�i���Ă���
�@�@�@�E����̗l�q�����Ȃ���������o���ɂ��ēn��
�������ꍇ�Ɂu�܌��J���ɂ��݂܂���v�A�u�܌��J���ɂȂ��Ă��܂��܂����c�v�ƒf������Ă����Α����{�点�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�@�@�@�u�܌��J���v�̗ᕶ
�@�@�@�E�܌��J���ɂ��݂܂���B
�@�@�@�E�܌��J���ɐ\����܂���B
�@�@�@�E�܌��J���ł͂������܂����c
�@�@�@�E�܌��J���Ɏ��炢�����܂��B
���u�܌��J�v�̗ތ�
�u�܌��J�v������������Ƃ�����u�~�J�v�u��J�v�u���J�v�u���Ƃ��ƉJ�v�u6���̉J�v�Ȃǂł��傤���B�u5���̉J�v�ƌ���������̂͊ԈႢ�ł��B�u����5���̉J�v�Ȃ炢����������܂���B
�u�܌��J�v�Ǝ������t�Łu�܌�����(������E������)�v�͂����m�ł��傤���B
�u�͂��͂��A������u�܌��J�v�Ɠ�����5���̐��ꂽ�V�C�̂��Ƃ���Ȃ��āA6���̐�����̂��ƂȂ�ł���v
�ƍl�������Ȃ��I���������Ŕ����O��ł��B�������Ɂu�܌�����v�͈ȑO�͔~�J�̍��Ԃ̐�����̂��Ƃ��w���܂������A���݂ł�5���̐�����̂��Ƃ��w���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
���̏؋��ɋC�ے��̃T�C�g�����Ă��u�܌�����v�̈Ӗ��́u5���̐��V�v�Ƃ���܂��B���l�ɂ́u�{���͋����5��(����)���炫�����ƂŁA�~�J�̍��Ԃ̐���̂��Ƃ��w���Ă����v�Ƃ���悤�ɁA��p����ʓI�ɂȂ�Z�����Ă������悤�ł��B
�j���[�X��V���Ō���������u�܌�����v�͊�{�I�Ɂu5���̐��V�v�ł���Ɗo���Ă����܂��傤�B
�u������v�ƓǂނƁu�~�J�̍��Ԃ̐���v�A�u������v�ƓǂނƁu5���̐��V�v�Ǝg���������������܂��B
���Ȃ݂ɁA�u�܌��J�v�͋C�ے��ł͎g�p���T����ׂ����t�Ƃ��āu�\��A����ɂ͗p���Ȃ��v�ƋL�ڂ���Ă��܂��B
���u�܌��J���v�̗ތ�
�u�܌��J���v������������Ƃ�����A�u�f���I�v�u���炾��v�u�₦�ԂȂ��v�Ȃǂ��������܂��B
�u�܌��J���ɂ��݂܂���v�Ƃ����t���[�Y���ƌ���������̂ł���A�u�܂Ƃ߂Ă��n���ł����\����܂���v�Ƃ������������\�ł��B
���u�܌��J���v�͒f������Ă���
�N�ł��A���́A�܂Ƃ߂ăX�}�[�g�ɍs�������ł���ˁB��[�i�������ł��B���o���ɂ��Ē�o��������A��x�ŏI��点�������������ł���r�W�l�X�p�[�\�����ۂ��c
�Ƃ͂����A���ł�����ȕ��ɂ��܂��ł���킯�ł͂���܂���B�����̈ӎv�ɔ����āu�܌��J���v�ɂȂ炴�邨���Ȃ����Ƃ�����ł��傤�B�܂��A�헪�I�Ɂu�܌��J���v�ɂ���ꍇ������܂��B
���炾��Ɨ��R���킩�炸�u�܌��J���v�ɘA�����ꂽ�畠�𗧂Ă�l�����܂����A���炩���߁u�܌��J���ɂȂ邩������܂���v�Ƃ����Ζ��Ȃ��ł��傤�B�u�܌��J���v�ɂȂ肻���ȂƂ��͒f������Ă����X�}�[�g�ł��B
 �@
�@ �@
�@
�����͕S��Ƃ����������Ԃ𗷂��Ă������l�̂悤�Ȃ��̂ł���A���̉߂������čs����N��N���܂����l�Ȃ̂��B�D���̂悤�ɏM�̏�ɐ��U���ׁA�n�q�̂悤�ɔn�̌D(����)�������ĘV���Ă����҂͓��X���̒��ɂ���̂ł���A�����Z�܂��Ƃ���̂��B���s�A�\���ȂǁA�̂����̓r��ŖS���Ȃ����l�͑����B���������̍����������A��������Ă���������_�ɗU���Y���̗��ւ̎v�����~�߂邱�Ƃ��ł����A�C����̒n�������炢�A���N�̏H�͐�̂قƂ�̂���Ƃɖ߂肻�̒w偂̌Ñ����͂炢��U���������Ă����̂����A�������ɔN�����t�ɂȂ�A���̂�����������Ȃ��߂Ă���ƁA�ӂƁy���͂̊ցz���z���Ă݂����Ȃ�A�킯���Ȃ��l�����킻�킳����Ƃ����y������_�z�ɜ߂��ꂽ�悤�ɐS�����킬�A�y���c�_�z�̎菵���ɂ����ĉ�����ɂ��Ȃ��L�l�ƂȂ�A�҈��̔j���U���A�}�̏����������A�O���̂ڂɋ��������邻����A�����̌����܂��S�ɂ�����A�Z�ݓ�ꂽ�[��̈��͐l�ɏ���A�������܂ł͖�l�y����(����Ղ�)�z�̕ʑ�Ɉڂ�A
���̌˂��@�Z�ݑ��鐢���@���̉�
(�ˌ������ŕ���ꂽ���݂̂��ڂ炵���[��̏h���A���ɂ�����ĐV�����Z�l���Z�݁A�Y��Ȑ��l�`��������悤�Ȃ͂Ȃ₩�ȉƂɂȂ�̂��낤)
�Ɣ�����r�݁A�ʔ�������̒��ɏ����c���̂������B
�@�@�@������(����Ԃ�)
����(����)�͕S��(�͂�����)�̉ߋq(������)�ɂ��āA�s(��)�����ӔN���܂����l(���тт�)�Ȃ�B
�M�̏�ɐ��U(���傤����)�������ׁA�n�̌��Ƃ炦�ĘV(����)���ނ��ӂ���̂́A���X(�Ђ�)��(����)�ɂ��ė�(����)��(���݂�)�Ƃ��B
�Ðl(������)��������(����)�Ɏ�(��)���邠��B
������Â�̔N��肩�A�Љ_(�ւ�)�̕��ɂ����͂�āA�Y��(�Ђ傤�͂�)�̎v�Ђ�܂��A�C�l(�����Ђ�)�ɂ�����ցA���N(����)�̏H�]��(�������傤)�̔j��(�͂���)�ɂ����̌Ñ�(�ӂ邷)���͂�ЂāA���N����(����)�A�t���Ă��(������)�̋�ɔ���(���炩��)�̊ւ�����ƁA������_(����)�̕��ɂ��ĐS������͂��A���c�_(�ǂ�������)�̂܂˂��ɂ��ЂāA��(��)����̎�ɂ����B
�����Ђ��̔j(���)����Â�A�}(����)�̏�(��)�t(��)�������āA�O��(�����)�ɋ�(���イ)�������A�����̌��܂��S�ɂ�����āA�Z(��)�߂��(����)�͐l�ɏ�(�䂸)��A����(����Ղ�)���ʚ�(�ׂ�����)�Ɉ�(����)��ɁA
�@�@�@���̌˂��@�Z��(���݂����)���(��)���@�ЂȂ̉�
�ʔ���(�����Ă͂���)����(������)�̒�(�͂���)�ɂ����u(��)���B
��\�����A�閾�����̋�͂��ڂ�ɉ��݁A�L���̌��͂������������Ȃ��Ă���A�x�m�̕����H���ɂ���������B���E�J���̂ق�������ƖX�̏����������Ă���A�����Ԃ̖������Ăь����̂͂��̂��Ƃ��ƐS�ׂ��Ȃ�̂������B�e�����l�X�͏��̂�������W�܂��āA�M�ɏ���đ����Ă����B��Z�Ƃ����Ƃ���ŏM��������ƁA���ꂩ��O�痢���̓��̂肪����̂��낤�Ƌ��������ς��ɂȂ�B���̐��͌��̂悤�ɂ͂��Ȃ����̂��A�����͂Ȃ��ƍl���Ă������A�����ʂꂪ�߂Â��Ƃ������ɟ������ӂ�Ă���B
�s�t�Ⓓ�e���̖ڂ͟�
(�Ӗ�)�t���߂�����̂�ɂ���Œ��������ڂɗ܂��ׂĂ���悤���B
��������̗��ʼnr�ޑ���Ƃ����B������̐l�X�͕ʂ��ɂ���łȂ��Ȃ������i�܂Ȃ��B�悤�₭�ʂ�Č���U��Ԃ�ƁA�݂�ȓ����ɗ�������ł���B���p��������Ԃ͌������Ă�������Ȃ낤�B
�@�@�@��������(����)
�퐶(��悢)����(����)�̎����A�����ڂ̂̋�O�X(�낤�낤)�Ƃ��āA���͂��肠���ɂČ������܂����̂���A�x�m(�ӂ�)�̗�(�݂�)�������Ɍ����āA���(������)�E�J��(��Ȃ�)�̉Ԃ̏�(������)�A�܂������͂ƐS�ڂ����B
�ނ܂���������͏�(�悢)���ǂЂāA�M�ɏ�(��)��đ���B
�炶��Ƃ��ӏ��ɂďM��������A�O�r(�����)�O�痢(�����)�̎v����(�ނ�)�ɂӂ�����āA��(�܂ڂ낵)�̂��܂��ɗ���(��ׂ�)�̟�(�Ȃ݂�)���������B
�@�@�@�s(��)���t��@���e(�Ȃ�)��(����)�́@�ڂ͟�(�Ȃ݂�)
�����(�₽��)�̏�(�͂���)�Ƃ��āA�s(��)�����Ȃ�i�܂��B
�l�X�͓r��(�݂��Ȃ�)�ɗ�(��)���Ȃ�тāA��(����)�납���̌����܂ł͂ƌ���(�݂���)��Ȃ�ׂ��B
���N�͌��\��N�ł������낤���A���H�ւ̒������ӂƋC�܂���Ɏv���������B���̔N�ʼn����ً��̋�̉��𗷂���ȂǁA����������ςȖڂɂ����Ă���ɔ�����������Ɍ��܂��Ă���̂��B�������b�ɂ��������Ď��ۖڂŌ������Ƃ͂Ȃ��n����A���Ќ��Ă݂����A�����ďo����Ȃ�Ăт��ǂ��Ă������B����Ȃ��Ă��Ȃ��肢������Ȃ���A���̓������Ƃ����h�ɂ��ǂ蒅�����B�����ꂵ�������̂͑����č����Ă������ɁA�ו���������Əd���������邱�Ƃ��B�ł��邾���ו��͎������A��Ԃ�ɋ߂��i�D�ŏo���������肾�������A��̖h����Ƃ��Ă͎��q���ꒅ�K�v�����A���߁E�J��E�n�E�M�Ȃǂ�����B���̏�ǂ����Ă��f��Ȃ��S�ʂ̕i�X���������Ɏ̂ĂĂ��܂��킯�ɂ͂����Ȃ��B���������킯�ŁA��������ו���������͎̂d���̂Ȃ����ƂȂ̂��B
�@�@�@������(������)
���Ƃ����\(����낭)��(�ӂ�)�Ƃ��ɂ�A���H(������)���r(���傤��)�̍s�r(����)�������肻�߂Ɏv�Ђ����āA���V(���Ă�)�ɔ���(�͂��͂�)�̍�(����)�݂��d(����)�ʂƂ��ւǂ��A���ɂӂ�Ă��܂��ڂɌ��ʋ�(������)�A������(����)�ċA��ƁA��(������)�Ȃ���(����)�݂̖�(����)�������A���̓��悤�悤����(������)�Ƃ��ӏh(���キ)�ɂ��ǂ蒅(��)���ɂ���B
����(��������)�̌�(����)�ɂ��������́A�܂����邵�ށB
�����g(��)������ɂƏo(��)�ŗ�(��)���ׂ͂���A��q(���݂�)���(������)�͖�̖h(�ӂ�)���A�䂩���E�J��(���܂�)�E�n�M(���݂ӂ�)�̂����ЁA����͂��肪�����S(�͂Ȃނ�)�Ȃǂ�����́A�������ɑŎ�(��������)�������āA�H��(��Ƃ�)�̔�(�킸�炢)�ƂȂ�邱�����Ȃ���B
���̔����ƌĂ��_�ЂɎQ�w����B���̓��s�ҁA�\�ǂ������ɂ́A�u�����ɍՂ��Ă���_�͖̉Ԃ�����P�̐_�Ƃ����āA�x�m�̐�Ԑ_�ЂōՂ��Ă���̂Ɠ������_�̂ł��B�̉Ԃ�����P���g�̌����������邽�߂ɓ�������ǂ����Y���ɂ�����A�����R���オ�钆�ʼnX�o�g�݂̂��Ƃ����o�Y����܂����B����ɂ�肱�̏ꏊ�����̔����Ƃ����܂��B�܂��A���̔������̂ɉr�ނƂ��͕K���u���v���r�ݍ��ނ��܂�ł����A��������̂����ɂ��̂ł��B�܂��A���̓y�n�ł́u���̂���v�Ƃ�������H�ׂ邱�Ƃ��ւ��Ă��邪�A������̉Ԃ�����P�̐_�ɊW�������Ƃ������ŁA�����������_�Ђ̗R���͂悭���̒��ɒm���Ă���B
�@�@�@�����̔���(�ނ�̂₵��)
��(�ނ�)�̔���(�₵��)�Ɍw(����)���B
���s(�ǂ����傤)�]��(����)�����킭�A�u���̐_(����)�͖�(��)�̉Ԃ�����P(�Ђ�)�̐_(����)�Ƃ������ĕx�m(�ӂ�)���[(��������)�Ȃ�B
���ˎ�(���ނ�)�ɓ�(��)��ď�(��)�����܂ӂ����Ђ̂ݒ��ɁA�ΉΏo��(�ققł�)�݂̂��Ɛ��ꂽ�܂Ђ���莺(�ނ�)�̔���(�₵��)�Ƃ������B
�܂���(���ނ�)��ǏK(��݂Ȃ��)���ׂ͂�����̈�(�����)�Ȃ�v�B
�͂��A���̂���Ƃ��Ӌ�����(����)���B
���L(����)�̂ނː�(��)�ɓ`(��)�ӂ��Ƃ��ׂ͂肵�B
�O���O�\���A�����R�̂ӂ��Ƃɏh����Ĕ��܂�B�h�̎�l���������Ƃɂ́A�u���̖��͕��܍��q��Ƃ����܂��B�Ȃ�ɂł��������M���ł�����A�܂��̐l����u���v�ȂǂƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B����Ȏ���ł����獡��͂�����肨���났���������v�ƌ����̂��B���������ǂ�Ȏ�ނ̕��������q�ꂽ���Ɏp�������āA���̂悤�ɑm��(�K��)�̊i�D�����Č�H����̗������Ă���悤�Ȃ݂��ڂ炵���҂��������ɂȂ�̂��낤���ƁA��l�̂�邱�ƂɐS���Ƃ߂Ċώ@���Ă����B����ƁA�m�b�╪�ʂ����B�����Ƃ������Ƃł͑S���Ȃ��A�����Ђ����琳����r�Ȏ҂Ȃ̂��B�_��ɂ���u���B�p�c�͐m�ɋ߂��v�Ƃ������t��̌����Ă���悤�Ȑl�����B���܂�������Ă���(�C�g)�A���炩�Ȑ���(����)�Ȃ낤�A���������҂�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�����܍��q��(�قƂ�����������)
����(�݂���)�A�����R(�ɂ���������)�̞�(�ӂ���)�ɔ�(�Ƃ�)��B
���邶�̂�������₤�A�u�킪���܍��q��(�قƂ�����������)�Ƃ��ӁB��낸����(���傤����)���ނ˂Ƃ���䂦�ɁA�l�����͂������ׂ͂�܂܁A���(������)�̑��̖�(�܂���)�����Ƃ��ċx�݂��܂ցv�Ƃ��ӁB
�����Ȃ镧(�قƂ�)�̑����o�y(���傭�������)�Ɏ���(������)���āA������K��(��������)�̌�H����(�����������ꂢ)���Ƃ��̐l�����������܂ӂɂ�ƁA���邶�̂Ȃ����ƂɐS���Ƃǂ߂Ă݂�ɁA�������q������(�ނ��ނӂ�ׂ�)�ɂ��āA�����Ό�(���傤�����ւ�)�̎�(����)�Ȃ�B
���B���c(�������ڂ��Ƃ�)�̐m(����)�ɋ߂������ЁA�C�h(���Ђ�)�̐���(��������)�����Ƃ���(�Ƃ���)�Ԃׂ��B
�l������A�����̌�R�ɎQ�w����B�̂��̌�R���u��r�R(�ӂ��炳��)�v�Ə��������A��C��t���J������A�u�����v�Ɖ��߂�ꂽ�̂��B��t�͐�N��̖����܂ł����ʂ����Ƃł����̂��낤���A�����̓������Ƌ{�ɍՂ��Ă��铿��ƍN���̈Ќ����L���V���ɋP���A���̂��݂��݂܂ł��ӂ�����̖L���ȉ��b���s���͂��A�m�_�H�����ׂĈ��S���āA���₩�ɏZ�ނ��Ƃ��ł���B�Ȃ��A�����Ƃ�������ȏ�����ɂ��ď����͈̂ꑽ���̂ł��̂ւ�ŕM��u�����Ƃɂ���B
���炽�ӂƐt��t�̓��̌�
(�Ӗ�)�����Ȃ�Ƒ������Ƃ��낤�A�u�����v�Ƃ������̒ʂ�A�t��t�ɓ��̌����Ƃ�f���Ă����B
�@�@�@������(�ɂ�����)
�K��(���Â�)���(������)�A��R(�����)�Ɍw�q(�����͂�)���B
����(���̂ނ���)���̌�R(�����)���r�R(�ӂ��炳��)�Ə��������A��C��t(��������������)�J��(������)�̎��A�����Ɖ�(���炽)�߂��܂ӁB
��Ζ���(�����݂炢)�����Ƃ肽�܂ӂɂ�B
�����̌��(�݂Ђ���)��V(�����Ă�)�ɂ����₫�āA���r(�����͂�����)�ɂ��ӂ�A�l�����g(���݂��)�̐�(���݂�)��(�����₩)�Ȃ�B
�P(�Ȃ�)��(�͂���)�����ĕM(�ӂ�)�������u(����)�ʁB
���炽���Ɓ@�t��t(�����킩��)�́@���̌�
�É̂ɑ����u�����R�v�Ƃ��ĉr�܂�Ă�������A��̂ЂƂA�j�̎R(�Ȃ�����)���̂��ށB�����������āA�Ⴊ���܂��ɔ����c���Ă���B
��̂Ăč����R�ɈߍX�@�\��
(�Ӗ�)���ɏo�����鎞�ɔ������ĖV��̎p�ƂȂ����B���܂��l������ߍX���̎����ɁA���̖��������R���z���A���̗��ɂ����錈�ӂ�V���ɂ���̂������B
�\�ǂ͉͍��Ƃ������Ŗ��͑y�ܘY�Ƃ����B�[��̔m�Ԉ��̋ߏ��ɏZ��ł��āA���̓���̂��Ƃ������Ǝ�`���Ă���Ă����B����A�L���ȏ����A�ۊ��̒��߂��ꏏ�Ɍ��邱�Ƃ���сA�܂����̋�J��J��肠�����ƁA�o���̓��̑����A�������낵�đm���̒���n���̈߂ɒ��ւ��A���O���y�܂���m�����́u�@��v�ƕς����B���������������ŁA���̍����R�̋�͉r�܂ꂽ�̂��B�u�ߍX�v�̓ɂ͑\�ǂ̂��̗��ɂ�����o�傪���߂��Ă��āA�͋����������邱�Ƃ�B��\��������ƎR��o��Ƒꂪ����B�E��̒��ォ�琅����т͂˂āA�S�ڂ��������Ƃ��������𗎂��āA��R�̊₪�d�Ȃ����^���ȑ�ڂ̒��֗�������ł����B��̂��ڂ݂ɐg���Ђ��߂�ƁA���傤�Ǒ�̗����猩�邱�ƂɂȂ�B���ꂪ�Â�����u����݂̑�v�ƌĂ��䂦��Ȃ̂��B
�b���͑���Ă��Ă̏�
(�Ӗ�)��̗��̊≮�ɓ��������̏��čs(�����傤)�̏C�s�ƌ����ĂĂ��炭�͂������Ă��悤��B
�@�@�@�������R(���납�݂��)
�����R(���납�݂��)�͉�(������)������āA�Ⴂ�܂������B
���(���肷��)�ā@�����R(���납�݂��)�Ɂ@�ߍX(���������)�@�]��
�]��(����)�͉͍���(���킢����)�ɂ��āA�y�ܘY(�������낤)�Ƃ��ւ�B
�m��(���傤)�̉��t(������)�Ɍ�(�̂�)���Ȃ�ׂāA�悪�d��(����)�̘J(�낤)���������B
���̂��я���(�܂���)�E�ۊ�(��������)�̒�(�Ȃ���)�Ƃ��ɂ��Ƃ��x(��낱)�сA����㱗�(�����)�̓�(�Ȃ�)�������͂��ƁA��(����)����(������)��(����)���(��)��Ėn��(���݂���)�ɂ��܂������A�y��(������)����(���炽��)�ď@��(������)�Ƃ��B
����č����R(���납�݂��)�̋�(��)����B
�u�ߍX(���������)�v�̓�(�ɂ�)��(������)����Ă�����B
���]��(�ɂ��イ�悿�傤)�R��o�đ�(����)����B
�⓴(����Ƃ�)�̒�(��������)����(�Ђ�イ)���ĕS��(�͂�����)�A���(����)�̕��K(�ւ�����)�ɗ�(��)������B
��A(����)�ɐg(��)���Ђ��ߓ�(��)��đ�(����)�̗�(����)��茩��A����(�����)�̑�(����)�Ƃ������`(��)���ׂ͂�Ȃ�B
���炭�́@��(����)����(����)���@��(��)�̏�(�͂���)
�ߐ{�̍��H�Ƃ������ɒm�l������̂ŁA���ꂩ��ߐ{����Ă܂������̓����s�����Ƃɂ���B�͂邩�ޕ��ɑ���������̂ł����ڎw���čs���ƁA�J���~���Ă��ē������Ă��܂��B�S�����ň�Ӕ��߂Ă��炢�A�����܂��L���ߐ{��̌���̒���i��ł����B�����ɁA��Ɏ����Ă���n���������B���ő��������Ă����j�ɓ��������˂�ƁA�Гc�ɂ̂Ȃ�ł��Ȃ��j�����A�������ɏ�̐S��m��Ȃ��킯�ł͂Ȃ������B�u�����A�ǂ���������ł��傤���B���������̓ߐ{��̌���͏c���ɑ����Ă��āA���߂ė�����l�����ɖ������Ƃ��S�z�ł�����A���̔n�����݂����܂��B�n�̒�܂����Ƃ���ő���Ԃ��Ă��������v�������Ĕn����Đi��ł����ƁA��납��q������l�n�̂��Ƃ�炤�悤�ɑ����Ă��Ă���B���̂�����l�͏��̎q�ŁA�u�����ˁv�Ƃ������O�ł������B���܂蕷���Ȃ��D�������O���Ƃ������ƂŁA�\�ǂ����r�B
�����˂Ƃ͔��d���q�̖����ׂ��@�]��
(�Ӗ�)���炵�����̎q�q�ɂ悭�Ⴆ�邪�A���̖����u�����ˁv�Ƃ͕��q�̒��ł����ɔ��d���q���w���Ă���悤���B
���ꂩ�炷���l���ɏo���̂ŁA����̂�����n�̈Ƃ�(�Ƃ̒����̐l����邭�ڂ���)�Ɍ��ѕt���āA�n��Ԃ����B
�@�@�@���ߐ{(�Ȃ�)
�ߐ{(�Ȃ�)�̍��˂Ƃ��ӏ�(�Ƃ���)�ɒm�l(����Ђ�)����A�������z(�̂���)�ɂ�����āA����(�����݂�)���䂩��Ƃ��B
�y(�͂邩)�Ɉꑺ(��������)���������čs(��)���ɁA�J�~(��)�����(��)���B
�_�v(�̂���)�̉ƂɈ��(������)������āA��(����)��܂��쒆(�̂Ȃ�)���s(��)���B
�����ɖ쎔(�̂���)�̔n����B
����(��)��j�̎q(���̂�)�ɂȂ������A��v(���)�Ƃ��ւǂ��������ɏ�(�Ȃ���)����ʂɂ͔�(����)���B
�u���������ׂ���B����ǂ����̖�͏c��(���イ����)�ɂ킩��āA�����(��������)�������l(���тт�)�̓��ӂ݂������ށA���₵���ׂ͂�A���̔n�̂Ƃǂ܂鏊�ɂĔn��Ԃ����܂ցv�ƁA�����ׂ͂�ʁB
���������҂ӂ���A�n�̐�(����)�����Ђđ���B
��(�ЂƂ�)�͏��P(���Ђ�)�ɂāA���������˂Ƃ��ӁB
�����Ȃ�ʖ��̂₳�����肯��A
�����˂Ƃ́@���d���q(�₦�Ȃł���)�́@��(��)��(��)��ׂ��@�]��
�₪�Đl��(�ЂƂ���)�ɂ�����A�����Ђ���(����)�ڂɌ��t(�ނ��т�)���āA�n���(����)���ʁB
���H�˂̗��狏���̉ƘV�ł���A��V���������Ƃ����҂̊ق�K�₷��B��l�ɂƂ��Ă͋}�ȋq�l�łƂ܂ǂ����낤���A�v���̂ق��̊��}�����Ă���āA���ƂȂ���ƂȂ���荇�����B���̒�ł��铍���Ƃ����҂����[�ɂ��܂��ĖK�˂Ă��āA�����̊قɂ��e���̏Z�܂��ɂ����҂��Ă��ꂽ�B�������ĉ������߂����Ă������A������x�O�ɎU���ɏo�������B�́A���Ǖ��Ɏg��ꂽ�ꏊ�����āA�ߐ{�̎���~��������悤�ɒʂ肷���A����̌ςƂ��Ēm����ʑ��̑O�̒˂�K�˂��B���ꂩ�甪���{�ɎQ�w�����B���̓ߐ{�^�ꂪ��̓I���˂鎞�u(���낢��Ȑ_�X�̒��ł�����)�킪���ߐ{�̎��_�ł��鐳�������܂�(���肢���܂�)�v�Ɛ������̂͂��̐_�Ђ��Ƃ����āA���������������傫���Ȃ�̂������B��������ƁA�Ăѓ�����ɖ߂�B�ߏ��ɏC���������Ƃ��������������B�����ɏ�����āA�C�����̊J�c�A�����p(����̂��Â�)���܂��Ă���s�ғ���q�B
�ĎR�ɑ��ʂ�q�ގ�r��
(�Ӗ�)�����p(����̂��Â�)�̂�����q�ށB���̉ĎR���z���������B���B���p�������ʂ��͂��ĎR�����������Ƃ������̌��r�ɂ��₩�肽���Ɗ肢�A���Ȃ��o�̋C�������ł߂�̂��B
�@�@�@�����H(�����)
���H(�����)�ّ̊�(����)��V��(���傤�ق���)��(�Ȃ�)�����̕�(����)�ɂ��Ƃ���B
�v�Ђ����ʂ��邶�̉x(��낱)�сA����(�ɂ���)��(����)��Â��āA���̒�(���Ƃ���)����(�Ƃ�����)�Ȃǂ��ӂ��A���[(���傤����)��(��)�߂ƂԂ�ЁA��(�݂�����)�̉Ƃɂ���(�Ƃ���)�ЂāA�e��(����)�̕�(����)�ɂ��܂˂���A�����ӂ�܂܂ɁA���ƂЍx�O(��������)����(���傤�悤)���āA���Ǖ�(���ʂ�������)�̐�(����)���ꌩ(��������)���A�ߐ{(�Ȃ�)�̎�(���̂͂�)���킯�ċʑ��̑O(���܂��̂܂�)�̌Õ�(���ӂ�)���ƂӁB
�����蔪���{(�͂��܂�)�Ɍw(����)���B
�^��(�悢��)��(������)�̓I(�܂�)����(��)�����A�u�ׂ����Ă͉䍑���_(�킪���ɂ̂�������)����(���傤�͂�)�܂�v�Ƃ����Ђ������̐_��(����)�ɂĂׂ͂�ƕ����A����(����̂�)��(���Ƃ�)������Ɋo(����)�����B
��(�����Γ���(�Ƃ�����)��(����)�ɋA��B
�C��������(���グ���݂傤��)�Ƃ��ӂ���B
�����ɂ܂˂���čs�ғ�(���傤����ǂ�)��q(�͂�)���B
�ĎR(�Ȃ��)�Ɂ@����(������)�������ށ@���ǂł���
���썑�̗ՍϏ@�_�ގ��̉��̎R�ɁA���̑T�̎t�ł��镧���a�����R�����肵�Ă����Ղ�����B�u�c���ڂɖ����Ȃ����̈������A�J���~��Ȃ������炱�̈������K�v�Ȃ��̂ɁB�Z�܂��Ȃǂɔ����Ȃ��Ő��������Ǝv���Ă�̂Ɏc�O�Ȃ��Ƃ��v�ƁA�����̒Y�Ŋ�ɏ����t�����ƁA�����b���Ă����������B���̐Ղ����悤�ƁA�_�ގ��ɏ�����Č������ƁA�����̐l�X�͂��݂��ɗU�������Ĉē��ɂ��Ă��Ă��ꂽ�B�Ⴂ�l�������A�����y���������ŁA�C�t������[�ɓ������Ă����B���̎R�͂����ԉ����[���悤���B�J�����̓����͂邩�ɑ����A���␙���������āA�ۂ���͐����������肨���Ă����B���āA�����a���R������̐Ղ͂ǂ�Ȃ��̂��낤�Ɨ��R�ɏ��ƁA�̏�ɏ����Ȉ����A�≮�ɂ����ꂩ����悤�Ɍ����Ă����B�b�ɂ������T�t�̎��ւ�@�_�@�t�̐Ύ�������悤�Ȏv���������B
�ؑ�����͂�Ԃ炸�Ėؗ�
(�Ӗ�)�Ėؗ��̒��ɐÂ��Ȉ��������Ă���B�������̑�ؒ����A���̐Â�����j�肽���Ȃ��ƍl���Ă��A���̈������͂��Ȃ��悤���B
�ƁA�����̈��𒌂ɏ����c���̂������B
�@�@�@���_�ގ�(����)
����(�Ƃ�����)�_�ގ�(����)�̂����ɘŒ��a��(�Ԃ����傤�����傤)�R����(����̂���)����B
�G��(���Ă悱)�́@��(�����Ⴍ)�ɂ���ʁ@��(����)�̈�(����)
�ނ��Ԃ����₵�@�J�Ȃ��肹��
�ƁA���̒Y(����)���Ċ�ɏ����t(��)���ׂ͂�ƁA�����╷�������܂ӁB
���̐�(����)�݂ނƉ_�ݎ�(����)�ɏ�(��)���Ђ��A�l�X������łƂ��ɂ����ȂЁA��(�킩)���l���ق��A���̂قǑ�(��)�����͂��āA���ڂ������̞�(�ӂ���)�ɂ�����B
�R�͂������邯�����ɂāA�J��(���ɂ݂�)�͂邩�ɁA��(�܂�)��(����)�����A��(����)��������āA�K��(���Â�)�̓V���Ȃ���(����)���B
�\�i(��������)���鏊(�Ƃ���)�A��(�͂�)���킽�ĎR��(�������)�ɓ�(��)��B
���āA���̐�(����)�͂��Â��̂قǂɂ�ƁA��(����)��̎R�ɂ���̂ڂ�A�Ώ�(�������傤)�̏���(���傤����)��A(����)�ɂނ��т�������B
���T�t(�݂傤����)�̎���(������)�A�@�_�@�t(�ق�����ق���)�̐Ύ�(��������)�����邪���Ƃ��B
�ؑ�(����)���@��(����)�͂�Ԃ炸�@�Ėؗ�(�Ȃ�����)
�ƁA�Ƃ肠�ւʈ��(��)��(�͂���)�Ɏc(�̂�)���ׂ͂肵�B
���H���o�����āA�E���Ɍ������B�`���ɂ���ʑ��O������̌ςƂ��Ă̐��̂�\����A�ˎE���ꂽ���Ɛɕω������Ƃ����A���̐��E�����B���H�Őڑ҂��Ă��ꂽ���狏���ƘV�A��@�����̂͂��炢�ŁA�n�ő����Ă��炤���ƂƂȂ����B����Ɣn�̕@���������n�q�̒j���A�u�Z��������v�Ƃ����B�n�q�ɂ��Ă͕����Ȃ��Ƌ��߂���̂��Ɗ��S���āA
������ɔn���ނ���قƁT����
(�Ӗ�)�L���ߐ{��łقƂƂ������ꐺ�e�����B���̐����悤�Ɏp������悤�ɁA�n�̓����O�[�b�Ƃ���������Ă���B�����Ĕn�q��A�Ƃ��ɕ���������Ȃ����B
�E���́A����̗N���o��R�A�ɂ������B�̎p�ɂȂ��Ă�����̌ςł���������̓ŋC���܂������ʂƌ����āA�I�⒱�Ƃ��������ނ����̐F�������Ȃ��Ȃ�قǏd�Ȃ肠���Ď���ł����B�܂��A���s�@�t���u���ׂ̂ɐ����Ȃ���T�����������ƂĂ��������ǂ܂��v�Ɖr����K�˂��B���̖����b��̗��ɂ���A�c�̂������Ɏc���Ă����B�����̗̎�A�˕��^�Ƃ����҂��A�u���̖������������Ȃ���v�Ƃ����Ό����Ă��������Ă����̂��A�ǂ�ȏ��ɂ���̂��Ƃ����ƋC�ɂȂ��Ă������A�����܂��ɂ��̖��̉A�ɗ���������̂��B
�c�ꖇ�A�ė������������
(�Ӗ�)���s�@�t�䂩��̗V�s���̉��ō��荞��Ŋ��S�ɂӂ����Ă���ƁA�c�A�������Ă���̂�������B(���́H)�c��ڈ�ʐA���Ă��܂��܂ł��݂��݂ƒ��߂ė�������̂�����
�@�@�@���E���E�V�s��(�������傤�����E�䂬�傤��Ȃ�)
������E����(�������傤����)�ɍs(��)���B
�ّ�(����)���n�ɂđ�(����)���B
���̌��t(��)���̒j�̎q(���̂�)�A�Z��(���Ⴍ)��(��)������Ƃ����B
�₳�������Ƃ�](�̂�)�ׂ݂͂���̂��ȂƁA
��(��)����(�悱)�Ɂ@�n(����)�Ђ��ނ���@�قƂƂ���
�E����(�������傤����)�͉���(���ł�)��
�o(��)�Â�R�A(��܂���)�ɂ���B
�̓ŋC(�ǂ���)���܂��ق�т��B
�I(�͂�)��(���傤)�̂����А^��(�܂���)�̐F�̌����ʂقǂ����Ȃ莀���B
�܂��A����(���݂�)�Ȃ����̖�(��Ȃ�)���b��(������)�̗��ɂ���ēc�̔�(����)�Ɏc(�̂�)��B
���̏�(�Ƃ���)�̌S��(����)�˕�(���ق�)�^(�Ȃɂ���)�̂��̖�(��Ȃ�)������ȂǁA���肨��ɂ̂��܂Е��������܂ӂ��A���Â��̂قǂɂ�Ǝv�Ђ����A�������̖�(��Ȃ�)�̂����ɂ���������(��)��ׂ͂��B
�c(��)�ꖇ(�����܂�)�@�A(��)���ė�����(��)��@��(��Ȃ�)����
�ŏ��͗��Ƃ����Ă��������킩�Ȃ����X�����������A���͂̊ւɂ����鍠�ɂȂ��Ă悤�₭���̓r��ɂ���Ƃ����������N���Ă����B�������́u�����œs�ցv�ƁA���̊ւ��z�����������Ȃ�Ƃ��s�ɓ`���������̂��A�Ƃ����Ӗ��̉̂��c���Ă��邪�A�Ȃ�قǂ����Ƃ����Ǝv���B���ɂ��̔��͂̊ւ͓����O�ւ̈�ŁA�̂��畗����������l�X�̐S���Ƃ炦�Ă����B�\���@�t�́u���ƂƂ��ɂ��������ǏH������������̊ցv�Ƃ����̂��v���ƋG�߂͏��Ă����A�H���������ŋ����悤�Ɋ�����B�܂��������́u�s�ɂ͂܂��t�ɂČ������ǂ��g�t�U�肵�����͂̊ցv���v���Ɛt�̏��̂ނ����ɍg�t�̌������܂őz������āA������������Ɏv����̂������B�^�������K�̉ԂɁA�Ƃ���ǂ����̔����Ԃ��炫�������Ă���A�������������������̂��B������|�c��v���s�����͂̊ւ��z����̂ɔ\���@�t�̉̂Ɍh�ӂ��Ċ��ƈߑ��𒅑ւ��Ē������Ƃ����b�����オ�����c���Ă���قǂ��B
�K�̉Ԃ��������Ɋւ̐������ȁ@�\��
(�Ӗ�)���Ă��̔��͂̊ւ�ʂ鎞�A������|�c��v���s(�ނ̂��݂������̂����ӂ��ɂ䂫)�͔\���@�t�̉̂Ɍh�ӂ�\���ā@�ߑ��𒅑ւ����Ƃ����B�������͂����܂ł͂ł��Ȃ������߂ĉK�̉Ԃ�ɂ������āA�h�ӂ�����킻���B
�@�@�@������(���炩��)
�S���ƂȂ��������d(����)�Ȃ�܂܂ɁA����(���炩��)�̊�(����)�ɂ�����āA���S(���т�����)��(����)�܂�ʁB
�����œs(�݂₱)�ւƕ�(�����)��(����)�߂������Ƃ��Ȃ�B
���ɂ����̊�(����)�͎O��(����)�̈�(����)�ɂ��āA����(�ӂ�����)�̐l�A�S���ƂǂށB
�H�������Ɏc(�̂�)���A�g�t(���݂�)���(��������)�ɂ��āA�t(������)�̏�(������)�Ȃ����͂�Ȃ�B
�K(��)�̉Ԃ̔���(���낽��)�ɁA��(����)�̉Ԃ̍�(��)�����ЂāA��ɂ������S�n(������)������B
�Ðl(������)��(����ނ�)��(����)���A�ߑ�(�����傤)����(���炽)�߂����ƂȂǁA����(���悷��)�̕M(�ӂ�)�ɂ��Ƃǂߒu(��)���ꂵ�Ƃ��B
�K(��)�̉Ԃ��@�������Ɋ�(����)�́@����(�͂ꂬ)���ȁ@�]��(����)
���̂悤�ɂ��Ĕ��͂̊ւ��Ă����ɁA�����G���n�����B���ɉ�Â̑�\�I�ȎR�ł���֒�R���������т��A�E�ɂ͊��E���n�E�O�t�̏��Ƃ����y�n���L�����Ă���B��������Ə헤�A����Ƃ̋��ɂ͎R�X����Ȃ��Ă����B�������Ƃ������ɍs�����A�����͋܂��Ă��Đ��ʂɂ͉����ʂ�Ȃ������B�{���̉w�œ����Ƃ������̂�K�˂āA�l�ܓ���������ɂȂ����B�����͂܂��u���͂̊ւ��ǂ��z���܂�����(�ǂ�ȋ�����܂�����)�v�Ɛq�˂Ă���B�u�����̑�ς��ɐg���S�����ʂĂĂ���܂��āA�܂������ȕ��i�ɍ���D���A�����̎v���ɂ͂�킽��₽���悤�ł��āA���܂����Ɖr�߂܂���ł����v
�����̏��₨���̓c�A����
(�Ӗ�)���͂̊ւ����B�H�ɓ���ƁA�܂��ɓc�A���̐^������Ŕ_���������c�A���̂��̂��Ă����B���̂ЂȂт������́A�����Ŗ��키�����̑����ƂȂ����B
������炸�Ɋւ������̂��������Ɏc�O�ł�����A����ȋ��������̂ł��v�ƌ������ɔo�~�̐ȂƂȂ�A�e�E��O�ƂÂ��ĉ̐傪�O�����o���オ�����B���̏h�̂������ɁA�傫�ȌI�̖؉A�Ɉ������ĂĉB�ِ��������Ă��鉽�L�Ƃ����m���������B���s�@�t���u�ɂЂ�Ӂv�Ɖr�[�R�̐����͂���Ȃł������낤�ƃV�~�W�~�v���āA���荇�킹�̂��̂Ɋ��z�������L�����B�u�I�v�Ƃ������́u���v�́u�v�Ə������炢�����琼����y�ɊW�������̂��ƁA�ޗǂ̓��厛���c�ɍv�������s���l�͈ꐶ��ɂ����ɂ��I�̖����g���ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B
���̐l�̌��t�ʉԂ⌬�̌I
(�Ӗ�)�I�̉Ԃ͒n���ł��܂萢�Ԃ̐l�ɒ��ڂ���Ȃ����̂��B����ȌI�̖؉A�ʼnB�ِ��������Ă����l�̐l����������킵�Ă���悤�ŁA�����ނ��[���B
�@�@�@���{���(��������)
�Ƃ������ĉz(��)���s(��)���܂܂ɁA���Ԃ��ܐ��n(�킽)��B
���ɉ�Í�(�����Â�)�����A�E�Ɋ��(���킫)�E���n(������)�E�O�t(�݂͂�)�̏�(���傤)�A�헤(�Ђ���)�E����(������)�̒n�������ЂāA�R��Ȃ�B
�������Ƃ��ӏ�(�Ƃ���)���s(��)���ɁA�����͋�(����)��(������)�ĕ��e(���̂���)���炸�B
�{���(��������)�̉w�ɓ���(�Ƃ����イ)�Ƃ��ӂ��̂�q(����)�˂āA�l�A�ܓ��Ƃǂ߂��B
�܂�����(���炩��)�̊�(����)�����ɂ������Ɩ�(��)���B
�u���r(���傤��)�̂��邵�݁A�g�S(����)����A���͕��i(�ӂ�����)�ɍ�(���܂���)���͂�A����(�������イ)�ɒ�(�͂�킽)��f(��)���āA�͂��������v�Ђ߂��炳���B
����(�ӂ���イ)�́@��(�͂���)�₨���́@�c�A(������)����
����(�ނ�)�ɂ�������������Ɂv�ƌ�(����)��A�e(�킫)�E��O(��������)�ƂÂ��āA�O��(�݂܂�)�ƂȂ��ʁB
���̏h(���キ)�̂������ɁA�傫�Ȃ�I(����)�̖؉A(������)�����݂̂āA��(��)�����Ƃӑm(����)����B
��(�Ƃ�)�Ђ�ӑ��R(�݂��)��������Ƃ��Â��Ɋo(����)�����Ă��̂ɏ����t(��)�ׂ͂�B
����(���̂��Ƃ�)�A
�I(����)�Ƃ��ӕ���(����)�͐��̖Ə�����
������y(�����ق����傤��)�ɕ�(�����)����ƁA�s���F(���傤���ڂ���)�̈ꐶ(�������傤)
��(��)�ɂ���(�͂���)�ɂ����̖�p(����)�����܂ӂƂ���B
��(��)�̐l�́@���t(��)���ʉԂ�@��(�̂�)�̌I(����)
�����̉Ƃ��o�Čܗ��قǐi�݁A�w���̏h�𗣂ꂽ�Ƃ���ɂ������R(���ώR)�����̂������ɂ���B���̂�����́u�����̈��ς̏��̉Ԃ��݁v�ƌÍ��W�̉̂ɂ���悤�ɏ��������B�̓��������������̒n�ɍ��J���ꂽ���A�܌��ɏ���Ҋ����Ȃ��������߁A�����ɂ��̂�̂��ӂ܂��āu���݁v�������ď������Ƃ������A���͂��傤�ǂ��̎����Ȃ̂ŁA�u�ǂ̑������ݑ��Ƃ����v�Ɛl�X�ɕ����Ă܂�������A�N���m��l�͂Ȃ��B���̂قƂ�܂ōs���āu���݁A���݁v�ƒT�������Ă��邤���ɓ����R�ۂɂ������ė[��ꎞ�ɂȂ��Ă܂����B��{�����E�ɋȂ���A�w�ȁu���B���v�Œm����S�k�������Ƃ������˂̊≮�����āA�����ňꔑ�����B
�@�@�@�����ώR(���������)
����(�Ƃ����イ)����(����)���o(��)�łČܗ�(����)����A�O��(�Ђ킾)�̏h(���キ)��(�͂�)��Ĉ��ώR(���������)����B
�H(�݂�)����(����)���B
���̂������(�ʂ�)�����B
���݊�(��)�邱�������(����)���Ȃ�A���Â�̑����Ԃ��݂Ƃ͂��ӂ��ƁA�l�X�ɐq(����)�˂ׂ͂�ǂ��A����ɒm(��)��l�Ȃ��B
��(�ʂ�)��q(����)�ˁA�l�ɖ�(��)�ЁA���݂��݂Ɛq(����)�˂��肫�āA���͎R�̒[(��)�ɂ�����ʁB
��{��(�ɂق�܂�)���E�ɂ���āA����(����Â�)�̊≮(�����)�ꌩ(��������)���A����(�ӂ�����)�ɏh(���)��B
�邪������ƁA�E�Ԃ�������̐�K�˂āA�E�Ԃ̗��֍s�����B�����R�A�̏����ɁA��������͔̐����n�ʂɖ��܂��Ă����B�����֒ʂ肩���������̓��������Ă��ꂽ�B��������͐̂͂��̎R�̏�ɂ������������B�s�������闷�l�������ݍr�炵�Ă��̐ɋ߂Â��A�̋�������̂ŁA����Ⴂ����Ƃ������ƂŒJ�ɓ˂����Ƃ����̂Ő̖ʂ����ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��B�����������Ƃ����邾�낤�ȂƎv�����B
���c�Ƃ�茳��̂��̂Ԑ�
(�Ӗ�)�u���̂Ԑ��v�Ƃ��Ēm��������̋Z�p�͍��͂�����Ă��܂������A���c��E�ݎ�鑁���������̎���ɁA�킸���ɂ��̖̐̂ʉe���Â��悤���B
�@�@�@���M�v�̗�(���̂Ԃ̂���)
������A���̂Ԃ�����(����)�̐�q(����)�˂āA�E(����)�Ԃ̂��Ƃɍs(��)���B
�y(�͂邩)�R�A(��܂���)�̏���(������)�ɐȂ��Γy�ɖ�(����)����Ă���B
���̓�(���)�ׂ̗�����ċ�(����)������B
��(�ނ���)�͂��̎R�̏�ɂׂ͂肵���A����(�䂫��)�̐l�̔���(�ނ�����)�����炵�āA���̐���(������)�ׂ݂͂���ɂ��݂āA���̒J(����)�ɂ���(��)�Ƃ��A�̖�(������)�����܂ɂӂ�����Ƃ��ӁB
��������ׂ����Ƃɂ�B
���c(���Ȃ�)�Ƃ�@����Ƃ��(�ނ���)�@���̂Ԑ�(����)
���̗ւ̓n�����M�ʼnz���āA���̏�Ƃ����h�꒬�ɏo��B��������ŋ`�o�̉��Ŋ��������p�M�E���M�Z��̕��A�����̋��Ղ́A���̎R�̂��Έꗢ���قǂ̂Ƃ���ɂ������B�ђ˂̗��A�I��Ƃ����Ƃ���ƕ����āA�l�ɐq�ːq�˂����ƁA�ێR�Ƃ����Ƃ���ł悤�₭�q�˂��Ă邱�Ƃ��ł����B�u���ꂪ�������i�ِ̊Ղł��B�R�̘[�ɐ���̐Ղ�����܂��v�ȂǁA�l�ɋ������邻����܂������B�܂��A�������̌Î��㉤���ɍ�����Ƃ̂��Ƃ��L�����Δ肪�c���Ă����B���̒��ł������Z��̉�(���Ə���)�̕�̕������ł������U���B���̐g�ł���Ȃ��炯�Ȃ��ɍ����Z��ɂ����A�]���𐢊ԂɎc�������̂�ƁA�܂��Ԃ�G�炷�̂������B�����̓`���ɂ���A�������͕̂K���܂𗬂����Ƃ����u�܂̐Δ�v��ڂ̑O�ɂ����悤�ȐS�����B���ɓ����Ē�����t���Ƃ���A�����ɂ͋`�o�̑����E�ٌc�̋�(�w���ɔw������)���ۊǂ���Ă��莛�̕ƂȂ��Ă����B
�����������܌��ɂ����ꎆ��
(�Ӗ�)�ٌc�̋��Ƌ`�o�̑������������邱�̎��ł́A�[�߂̐ߋ�ɂ͎���ƂƂ��ɂ���������̂��悢���낤�B���E�ŕ���������l�̈�i�Ȃ̂�����A�[�߂̐ߋ�ɂ͂҂����肾�B
�@�@�@���������i������(���Ƃ����傤�������イ����)
���̗�(��)�̂킽����(��)���āA��(��)�̏�Ƃ��ӏh(���キ)�ɏo(��)�ÁB
�������i(���Ƃ����傤��)������(���イ����)�́A���̎R��(��܂���)�ꗢ��(������͂�)����ɂ���B
�ђ�(�����Â�)�̗��I��(����)�ƕ����Đq(����)�ːq(����)�ˍs(��)���ɁA�ێR(�܂���)�Ƃ��ӂɐq(����)�˂�����B
����A���i(���傤��)������(���イ����)�Ȃ�B
��(�ӂ���)�ɑ��(������)�̐�(����)�ȂǁA�l�̋�(����)���ɂ܂����ğ�(�Ȃ݂�)��(��)�Ƃ��A�܂������͂�̌Î�(�ӂ�ł�)�Ɉ��(������)�̐Δ�(������)���c(�̂�)���B
���ɂ��A��l�̉�(���)�����邵�A�܂���(����)��Ȃ�B
���Ȃ�ǂ����Ђ��Ђ������̐��ɕ���������̂��ȂƁA��(������)���ʂ炵�ʁB
��(���邢)�̐Δ�(������)����(�Ƃ�)���ɂ��炸�B
���ɓ�(��)��Ē�(����)����(��)�ւA�����ɋ`�o(�悵��)�̑���(����)�A�ٌc(�ׂ�)����(����)���Ƃǂ߂ďY��(���イ����)�Ƃ��B
��(����)������(����)���@�܌�(����)�ɂ�����@���(���݂̂ڂ�)
�܌�(����)���(������)�̂��ƂȂ�B
���̖�͔ђ˂ɔ��܂����B���������̂œ��ɂ͂����ďh�ɔ��܂������A�y����䭂�~���ċq��Q������悤�ȁA�M�p�ł��Ȃ������݂̂��ڂ炵���h�������B�Ƃ����т������Ă���Ȃ��̂ŁA�͘F���̉��`���`������T�ɐQ���𐮂��ċx�B�钆�A������J��������ɍ~���āA�Q���̏ォ��R���Ă��āA���̏�a���ɑ̒����h����āA����Ȃ��B���a�܂ŋN�����āA�g���S���������肻���ɂȂ����B�Z���Ă̖���悤�₭�����Ă����̂ŁA�܂��������Ƃɂ���B�܂����̂���Ȋ������c���ĂāA���ɋC�����������Ȃ������B�n����ČK�܂̏h��ɒ������B�܂��܂����̂�͒����̂ɂ���ȕa�ȂNjN���Đ悪�v������邪�A�͂邩�ً��̗��Ɍ������ɂ�����A�킪�g�͂��łɎ̂Ă����肾�B�l���͂͂��Ȃ����̂����A���̓r��Ŏ���ł�����͓V�����B����Ȃӂ��Ɏ������܂��A�C�͂�������Ǝ�蒼���A�������y���ɒB�̑�،˂��z���̂������B
�@�@�@���ђ˂̗�(�����Â��̂���)
���̖�ђ�(�����Â�)�ɂƂ܂�B
����(���ł�)����Γ�(��)�ɓ�(��)��ďh(���)������ɁA�y��(�ǂ�)���(�ނ���)��~(����)�āA���₵���n��(�Ђ�)�Ȃ�B
��(�Ƃ�����)���Ȃ���A����̉�(��)�����ɐQ��(�˂ǂ���)���܂����ĉ�(��)���B
��(���)�ɓ�(��)��ė�(����)��(�Ȃ�)�A�J������ɍ~(�ӂ�)�āA��(�ӂ�)��������A�a(�̂�)�E��(��)�ɂ������Ė�(�˂�)�炸�B
���a(���т傤)���ւ�����āA����(��������)����ɂȂ�B
�Z��(�݂�����)�̋�(����)���₤�₤��(����)��A�܂�����(���т���)�ʁB
�Ȃ��A��(���)�̗]�g(�Ȃ���)�S�����܂��A�n(����)����ČK��(������)�̉w(����)�ɏo(��)�Â�B
�y(�͂邩)�Ȃ�s��(�䂭����)���������āA������a(��܂�)�o��(���ڂ�)�Ȃ��Ƃ��ւǁA㲗�(�����)�ӓy(�ւ��)�̍s�r(����)�A�̐g(���Ⴕ��)����(�ނ��傤)�̊ϔO(����˂�)�A���H(�ǂ���)�ɂ��Ȃ�A����V�̖�(�߂�)�Ȃ�ƁA�C��(����傭)���������Ƃ蒼(�Ȃ�)���A�H(�݂�)�c��(���イ����)�ɓ�(�ӂ�)�ňɒB(����)�̑�،�(��������)�������B
�����A���̏���߂��āA�}���̏h�ɓ���B�����������̕�͂ǂ̂����肾�낤�Ɛl�ɕ����ƁA�u��������ꡂ��E�Ɍ�����R�ۂ̗����A���ցE�}���Ƃ����A�����������̑O�ʼn��n���Ȃ��������߂ɗ��n���Ė��𗎂Ƃ����Ƃ������c�_�̎Ђ�A���s���������ɂ��āu�͖�̂������`���ɂ�����v�Ɖr���������c���Ă���̂ł��v�Ƌ����Ă��ꂽ�B���̂Ƃ���̌܌��J�œ��͑�ϒʂ�ɂ����A�̂����Ă����̂ʼn������璭�߂邾���ŗ������������A���ցA�}���Ƃ����n�����܌��J�ɊW���Ă��Ėʔ����Ǝv���A���r�B
�}���͂��Â������̂ʂ��蓹
(�Ӗ�)���������̕�̂���Ƃ����}���͂ǂ̂����肾�낤�B����Ȍ܌��J�ӂ肵����ʂ��蓹�̒��ł́A�������͂����肵�Ȃ��̂��B
���̖�͊���ɔ��܂����B
�@�@�@���}��(��������)
����(���Ԃ݂���)�E����(���낢��)�̏�(���傤)����(����)�A�}��(��������)�̌S(������)�ɓ�(��)��A����������(�Ƃ��̂��イ���傤���˂���)�̒�(��)�͂��Â��̂قǂȂ��Ɛl�ɂƂւA������y(�͂邩)�E(�݂�)�Ɍ����R��(��܂���)�̗����݂̂�E�}��(��������)�Ƃ����A���c�_(�ǂ�������)�̎�(�₵��)�E�����݂̔�(������)���ɂ���Ƌ�(����)��B
���̂���̌܌��J(���݂���)�ɓ����Ƃ������A�g(��)����ׂ͂�A�悻�Ȃ��璭(�Ȃ���)���ĉ�(����)��ɁA����(�݂̂�)�E�}��(��������)���܌��J(���݂���)�̐�(����)�ɂӂꂽ��ƁA
�}��(��������)�́@���Â������́@�ʂ��蓹
���G�̏���O�ɂ��āA�ڂ��o�߂�悤�ȐS���ɂȂ����B���͓y�ۂœ�ɂ킩��āA�̂̎p�������Ă��Ȃ����Ƃ��킩��B�܂��v���o���͔̂\���@�t�̂��Ƃ��B�́A������Ƃ��ĕ��C���Ă����l�����̖��Ė����̋��Y�ɂ����������낤���B�\���@�t�����炵�����͂������G�̏��͂Ȃ������B�����Ŕ\���@�t�́u���͍����ѐՂ��Ȃ��v�Ɖr��ŕ��G�̏���ɂ��̂������B���̎��セ�̎���A��������A�p�����肵���ƕ����Ă������A���݂͂܂��u��́v�Ƃ����ɂӂ��킵���`�������Ă��āA�f���炵�����̒��߂ł��邱�Ƃ�B��l�̋������o���O���S�ʂ̋�����ꂽ�B
���G�̏������\���x��
(�Ӗ�)�x����A�m�ԉ��������畐�G�̏��������Ă����Ă�������
������ɓ�����悤�Ȍ`�ŁA���r�B
����菼�͓���O�����V
(�Ӗ�)���̍炭�퐶�̎O���ɗ����������납�炱�̕��G�̏������悤�Ɗ���Ă����B�O���������ɂ��̊肢�������A�ڂ̑O�ɂ��Ă���B�����`���ǂ���A���������ɕ����ꂽ�����ȏ����B
�@�@�@�����G�̏�(�������܂̂܂�)
���(����ʂ�)�̏h(���キ)
���G�̏�(�܂�)�ɂ����A�ڊo(����)��S�n(������)�͂���B
��(��)�͓y��(������)�����(�ӂ���)�ɂ킩��āA��(�ނ���)�̎p(������)�����Ȃ͂��Ƃ����B
�܂��\���@�t(�̂�����ق���)�v�Џo(��)�ÁB
���̐�(����)�ނ̂��݂ɂĉ�(����)�肵�l�A���̖�(����)�āA�����(�ȂƂ肪��)�̋��Y(�͂�����)�ɂ���ꂽ�邱�ƂȂǂ���ɂ�A�u��(�܂�)�͂��̂��ѐ�(����)���Ȃ��v�Ƃ͉r(���)����B
��X(���)�A����͔�(����)�A����Ђ͐A�p(������)�Ȃǂ����ƕ����ɁA����(���܂͂�)�A���(���Ƃ�)�̂������ƂƂ̂قЂāA�߂ł�����(�܂�)�̂������ɂȂ�ׂ͂肵�B
�u���G(��������)�̏�(�܂�)�݂��\(����)���x��(����������)�v
�Ƌ���(����͂�)�Ƃ��ӂ��́T�S��(����ׂ�)�����肯��A
��(������)���@��(�܂�)�͓��(�ӂ���)���@�O��(�݂�)�z(��)��
������n���Đ��ɓ���B���傤�ǁA�ƁX�ł���߂����ɂӂ��܌��̐ߋ�ł���B�h�����߂āA�l�ܓ����������B���ɂ͉�H���q��Ƃ����҂������B���ƕ�����������҂��Ƃ����Ă�������A����Đe�����b���Ă݂��B���̉��q��Ƃ����j�́A���O�����m��Ă��ďꏊ���킩��Ȃ������ׂ���˂̎��Ƃɒ��N�g����Ă����B�ē����ɂ͍œK�Ȃ̂ŁA����ē����Ă��炤�B�{���̔����ɂ荇���āA�H�̌i�F�͂����������낤�Ƒz��������B�ʓc�E�悱��Ƃ����n���߂��āA�������ɗ���Ƃ��傤�ǂ����э炭���ł������B���̌��������Ȃ����̗тɓ����Ă����B�����́u�̉��v�ƌĂ��ꏊ���Ƃ����B�̂����̂悤�ɘI���[����������A�u�݂��Ԃ炢�݂����v�̉̂ɂ���悤�Ɂu��l�Ɋ}�����Ԃ�悤�\���グ�Ă��������v�Ɠy�n�̐l���r�낤�B��t���E�V�_�̂₵��Ȃǂ�q��ŁA���̓��͕�ꂽ�B���ꂩ����q��͏����E�ۊ��̏��X���G�ɕ`���āA�������Ă����B�܂����F�̐����̂������ܓ��S�ʂ��Ă����B�Ȃ�قǁA�Ƃ��Ƃ��Ȑl�ƕ����Ă������A���̒ʂ肾�B�����������Ƃɐl���̖{����������邱�Ƃ�B
����ߑ����Ɍ����܂̏�
(�Ӗ�)���E�q��̂��ꂽ���F�̑��܂��A�[�߂̐ߋ�ɏ���Ҋ��ɂ݂��ĂāA�C�炢�̂���ŗ����A�o������̂��B���ۂɂ���ߑ����܂ɂ���������A�Ƃ������ƂłȂ��A���F�̏�������߂Ɍ����Ă悤�Ƃ����A�C���[�W��̂��Ƃł��B
�@�@�@�����(����)
�����(�ȂƂ肪��)��n(�킽��)�Đ��(����)�ɓ�(��)��B
����߂ӂ����Ȃ�B
���h(��債�キ)�����Ƃ߂Ďl�ܓ�(�����ɂ�)����(�Ƃ���イ)���B
�����ɉ�H���E�q��(��������������)�Ƃ��ӂ��̂���B
���������S�����(����)�ƕ����Ēm(��)��l�ɂȂ�B
���̎�(����)�A�N��(�Ƃ�����)�������Ȃ�ʖ��ǂ�����l(����)�u(����)�ׂ͂�ƂāA���(�ЂƂ�)�ē�(����Ȃ�)���B
�{���(�݂€��)�̔�(�͂�)��(����)�肠�ЂāA�H(����)�̌i�F(������)�v�Ђ����B
�ʓc(���܂�)�E�悱��(��)�E�������͂����э�(����)����Ȃ�B
���e(�Ђ���)������ʏ�(�܂�)�̗�(�͂₵)�ɓ�(��)��āA�������(��)�̉�(����)�Ƃ��ӂƂ��B
��(�ނ���)�������I(��)�ӂ���������A�u�݂��Ԃ�Ђ݂����v�Ƃ͂�݂���B
��t��(�₭���ǂ�)�E�V�_(�Ă�)�̌��(�݂₵��)�Ȃǔq(������)�āA���̓��͂���ʁB
�Ȃ��A����(�܂���)�E����(��������)�̏��X(�Ƃ���ǂ���)�A��(��)�ɏ�(����)�đ�(����)��B
���A��(����)�̐���(���߂�)�����鑐��(��炶)��(�ɂ���)�S(�͂Ȃނ�)���B
�����������(�ӂ���イ)�̂�����́A�����ɂ�����Ă��̎�(����)����(�����)���B
����ߑ�(����)�@��(����)�Ɍ�(�ނ���)��@����(��炶)�̏�(��)
���̉�}(����)�ɂ܂����Ă��ǂ�s(�䂯)�A�����̍ד�(�ق��݂�)�̎R��(��܂���)�ɏ\��(�Ƃ�)�̐�(����)����B
��(����)���N�X(�Ƃ��ǂ�)�\��(�Ƃ�)�̐���(��������)��(�ƂƂ̂���)�č���(��������)�Ɍ�(����)���Ƃ�����B
���q��ɂ�������G�n�}�ɂ��������Đi��ł����ƁA���̍ד�(�����X��)�̎R�ۂɏ\���̐��Ԃ̍ޗ��ƂȂ鐛�������Ă����B�������N�\���̐��Ԃ�����Ĕˎ�Ɍ��サ�Ă���Ƃ������Ƃ������B�ق̔�͎s�쑺�����ɂ������B�ق̔�͍����Z�ځA���O�ڂ��炢���낤���B�����͑ۂ�������悤�ɗH���ɍ���Ō�����B�l���̍�������̋������L���Ă���B�u���̍ԁy�����z�́A�_�T���N(724�N)�A�@�g���畄(�{)���R��쒩�b���l���z�����B�V���Z�N(762�N)�Q�c�E�œ��C���R�ߓx�g�̌b�����b�A�T�J�����C�������v�Ə�����Ă���B�����V�c�̎���̂��Ƃ��B�̂���r�ݒu���ꂽ�̖����������`�����Ă��邪�A�R�͕����͗���A���͐V�����Ȃ�A�͒n�ʂɓy�ɖ�����ĉB��(�u���̂Ԃ̗��v)�A�͘V���Ď�ɂȂ�(�u���G�̏��v)�A���オ�ڂ�ς���Ă��̐Ղ��n�b�L�����߂Ă��Ȃ����Ƃ���ł������B���������ɓ����ċ^���Ȃ���N���̎p�𗯂߂Ă���̖��̒n���悤�₭���ꂽ�̂��B�ڂ̑O�ɌÐl�̐S�����Ă���̂��B�����������Ƃ������̗��_�ł���A�����Ă���������킦���т��B���̔����Y��āA�܂����������ł������B
�@�@�@�������(�������傤)
�ٔ�(�ڂ̂����Ԃ�)�@�s�쑺(��������ނ�)�����(�������傤)�ɂ���B
�ڂ̐Ԃ݂͍�(����)���Z��(�낭���Ⴍ)���܂�A��(�悱)�O��(���Ⴍ)�l(����)���B
��(����)���(������)�ĕ���(����)�������Ȃ�B
�l��(���䂢)���E(��������)�̐���(������)�����邷�B
���̏�(����)�A�_�T(����)���N(����˂�)�A�@�g(������)����{(�����)���R(���傤����)��쒩�b���l(�����̂������܂Ђ�)�̏��u(�����Ƃ���)�Ȃ�B
�V��(�Ă�҂傤)��(�ق���)�Z�N(�낭�˂�)�Q�c(����)���C(�Ƃ�����)���R(�Ƃ�����)�ߓx�g(���ǂ�)��(���Ȃ���)���R(���傤����)�b�����b(���݂̂���������)�C��(���ゼ��)��(�ǂ܂Ȃ�����)�A�\��(���イ�ɂ���)���(������)�Ƃ���B
�����c��(���傤�ނ����Ă�)�̌䎞(����Ƃ�)�ɓ�(����)���B
�ނ�������ݒu(����)��F��(�����܂���)�A���ق���(������)�`(��)�ӂƂ��ւǂ��A�R��(����)��여(�Ȃ���)�ē����炽�܂�A�͖�(��������)�ēy�ɂ�����A�͘V(����)�Ď��(�킩��)�ɂ��͂�A����(����)���(��)��(�ւ�)���āA���̐�(����)�������Ȃ�ʂ��Ƃ݂̂��A�����ɂ�����ċ^(������)���Ȃ����(����)�̋L�O(������)�A����O(����)�ɌÐl(������)�̐S���{(����)���B
�s�r(����)�̈꓿(�����Ƃ�)�A����(����߂�)�̉x(��낱)�сA㱗�(�����)�̘J(�낤)���킷��āA��(�Ȃ݂�)����(��)�����Ȃ�B
���ꂩ���c�̋ʐ�E���̐Ȃlj̖��̒n��K�˂��B���̏��R�ɂ͎��������Ă��āA�����R�Ƃ����̂������B���̍��ԍ��Ԃ݂͂ȕ�̂̕��ԂƂ���ŁA��ɂ���Δ䗃�̒��A�n�ɂ���ΘA���̎}�u�䗃�A���v�Ƃ������t�����邪�A����Ȗr�܂����������������ł����Ō�͂��̂悤�ɂȂ�̂��ƁA�߂��������ݏグ�Ă����B�����̉Y�ɍs���Ɨ[��ꎞ������������̏�����������̂Ŏ����X����B�܌��J�̋�������͐���Ă��āA�[�����������Ɍ����Ă���A��(�܂���)�������p���̂قNj߂��Ƃ���Ɍ�����B���t�̏��M�������炱�����Ė߂��Ă��āA�����킯�鐺������B����������Ă���ƌÐl���u�Ȃł��Ȃ����v�Ɖr���̏�����ɔ���A���݂��݊��S�[���B���̖�A�ڂ̕s���R�Ȗ@�t�����i��炵�āA����ڗ��Ƃ������̂�������B���Ɣ��i�Ƃ��K�ᕑ�Ƃ��Ⴄ�B�{�y���牓�����ꂽ�ЂȂт��������B������������q�Ō�邩��A���߂��������Ă�����Ƃ��邳���������A�������ɉ��B�̓`�������`������̂����狻���[���A���S���Ē����������B
�@�@�@�����̏��R�E����(�����̂܂�܁E��������)
�������c(�̂�)�̋ʐ�(���܂���)�E��(����)�̐�q(����)�ʁB
��(����)�̏��R(�܂��)�͎���(��)��Ė����R(�܂����傤����)�Ƃ��ӁB
��(�܂�)�̂��Ђ��ЊF(�݂�)�挴(�͂��͂�)�ɂāA�͂˂����͂��}(����)����ʂ�_(����)��̖�(����)���A�I(����)�͂����̂��Ƃ��ƁA��(����)��������(�܂�)��āA��(����)���܂̉Y(����)�ɓ���(���肠��)�̂��˂��B
�܌��J(���݂���)�̋������͂�āA�[����(�䂤�Â���)�������ɁA��(�܂���)����(����)���قNj�(����)���B
���܂̏��M(���Ԃ�)������āA��(������)�킩���X(��������)�ɁA�u�j��(�Ȃ�)���Ȃ����v�Ƃ�݂��ސS�������āA���ƂLj�(����)��Ȃ�B
���̖�A�ږ�(�߂���)�@�t(�ق���)�̔��i(�т�)���Ȃ炵�ĉ�(����)���傤���Ƃ��ӂ��̂�������B
����(�ւ���)�ɂ����炸�A��(�܂�)�ɂ����炸�B
�ЂȂт��钲�q(���傤��)������(��)���āA��(�܂���)�����������܂�����ǁA�������ɕӓy(�ւ��)�̈╗(���ӂ�)�Y(�킷)�ꂴ����̂���A�ꏟ(���サ�傤)�Ɋo(����)�����B
�����A����(����)�_�ЂɎQ�w����B�ɒB���@�����Č��������ŁA���X�Ƃ��������������сA����(�������x����؍�)������т₩�Ɍ���A�Βi���͂邩�����Ƃ���܂ő����B�����������Ď�ɂ��߂��ʊ_(������)���P�����Ă���B���̂悤�ȉ��B�́A�͂邩�Ӌ��̒n�܂Ő_�̌b�݂��s���n��A�����߂��Ă���B���ꂱ���䍑�̕��K���ƁA�����ւ��v�����B�_�a�̑O�ɌÂ����������B�������̔��̕\�ʂɁA�u�����O�N�a��O�Y��i�v�ƍ���ł���B���G�t�̈⌾�ɏ]���Ō�܂ŋ`�o������Đ�������B�̓������t(�ӂ���炽���Ђ�)�ł���B�`�o�≜�B�������̎��ォ��͂����ܕS�N���o���Ă��邪�A���̕��ʂ����Ă���Ɩڂ̑O�ɂ����������ߋ��̏o�����������Ԃ悤�ŁA�����ւ�L��v�����B���Ɂu�a��O�Y�v�Ƃ����铡�����t�́A�E�`���F���ׂĂɒ������A���m�̊ӂ̂悤�Ȓj�������B���̖����͍��Ɏ���܂ŕ������A�N��������Ă���B�u�l�͉��������Ă����������ɗ�݁A�`�����ׂ����B��������Ζ������ォ����Ă���v�Ƃ������A�{���ɂ��̒ʂ肾�B�������߂ɋ߂Â����̂ŁA�D����ď����ɓn��B�قǑD�Ői�݁A�Y���̈�ɂ����B
�@�@�@�������_��(�������܂���)
����(�������傤)����(��������)�̖��_(�݂傤����)�Ɍw(������)�B
����(��������)�ċ�(��������)�����āA�{��(�݂����)�ӂƂ����ʞ�(�����Ă�)����т₩�ɁA�̊K(�����͂�)�㘾(���イ����)�ɏd(����)�Ȃ�A����(������)�����̋�(����)�����������₩���B
�����铹�̉�(�͂�)�A�o�y(�����)�̋�(������)�܂ŁA�_��(����ꂢ)���炽�ɂ܂��܂������A�ፑ(�킪����)�̕���(�ӂ�����)�Ȃ�ƁA���ƋM(�Ƃ���)����B
�_�O(����)�Ɍ�(�ӂ�)����(�ق��Ƃ�)����B
���˂̌�(��)�т�̖�(������)�ɕ���(�Ԃ�)�O�N�a��(�����݂�)�O�Y(���Ԃ낤)��i(������)�Ƃ���B
�ܕS�N��(���ЂႭ�˂�炢)�̂��������A���ڂ̑O(�܂�)�ɂ����тāA������ɒ�(�߂���)���B
����͗E�`(�䂤��)���F(���イ����)�̎m(��)�Ȃ�B
����(���߂�)���ɂ�����Ă����͂��Ƃ��ӂ��ƂȂ��B
��(�܂��Ƃ�)�l�\(�悭)��(�݂���)����(�Ƃ�)�A�`(��)����(�܂�)��ׂ��B
�����܂�����ɂ������ӂƂ�����B
�����łɌ�(��)�ɂ������B
�M������ď���(�܂���)�ɂ킽��B
���̊�(����)��(�ɂ�)���܂�A�Y��(������)�̈�(����)�ɂ��B
�܂��Â����猾���Ă��č����猾�����Ƃł��Ȃ��̂����A�����͓��{��i�F�̂悢�����B�����Ő�i�Ƃ��Ė���������E���Ɣ�ׂĂ�����肪���Ȃ����낤�B�p���ɓ���̕��p����C�����ꍞ��ł��āA���̎��͎͂O���A�����̟��]���v�킹��i�F������A���������Ă���B�p���͑�R�̓��X������A�����藧�������͓V���w�����悤�ŁA�炷���͔̂g�ɂ͂���悤�Ɍ�����B������͓̂�d�ɏd�Ȃ�A�܂�������͎̂O�d�ɂ����݂�����A���ɂ킩��E�ɂ�Ȃ��Ă���B������w�����Ă���悤�Ɍ����铇������A�O�ɕ����Ă���悤�Ȃ̂�����A�܂�Őe���q�⑷������ĉ������Ă�悤�ɂ�������B���̗͂т�����ƔZ���A�}�t�͎����ɐ������͂߂��āA���̋��Ȃ͎��R�̂��̂ł���Ȃ���A�l�����h�������悤�ɈӐ}�I�ɋȂ����悤�Ɍ�����B�h�����̎��̒��ŁA���̌i�F��␢�̔��l�A���{�����������ς����l�q�ɗႦ�Ă��邪�A���̏������[���J�����������A�܂��ɔ��l�����ς������܂��v�킹��B�_��̐́A�R�̐_�u��R�_(������܂���)�v�����o�������̂��낤���B���R�̎�ɂ��|�p�i�ł��邱�̌i�F�́A�N���M���ӂ邢���t�������Ă��A���܂�������̂ł͂Ȃ��B�Y���̈�͗�����n�����ŁA�C�ɓ˂��o���Ă��铇�ł���B���ގ������̑c�A�_���T�t�̕ʎ��̐Ղ�A���T�Ȃǂ�����B�܂��A���̌������킸��킵���v���������ĂĉB�ِ��������Ă���l�̎p�����̖؉A�ɉ��l��������B����⏼�}���W�߂Đ����ĐH���ɂ��Ă���悤�Ȃ݂��ڂ炵�����̈��̐Â��ȕ�炵�Ԃ�ŁA�ǂ����������̐l���͂킩��Ȃ����A��͂�S�䂩�����̂����藧�����Ȃ�Ȃǂ��Ă��邤���ɁA�����C�ɉf���āA���Ƃ͂܂�����Ⴄ�i�F�ƂȂ����B�l�ӂɋA���ďh�����B�����J���Ɠ�K���ɂȂ��Ă��āA���Ɖ_�̒��ɂ����ɗ��Q���Ă���悤�ȁA�\�����������قǐ��ݐ����C�����ɂ�����ꂽ�B
������߂ɐg������قƁT�����@�\��
(�Ӗ�)���������ł͂قƂƂ����͂��̂܂܂̎p�ł͂肠��Ȃ��B�߂̈߂��܂Ƃ��āA�D��Ɍ����Ă���B
�\�ǂ͋���r�����͊����̂��܂�傪�o�Ă��Ȃ��B���낤�Ƃ��Ă����N���N���ĐQ���Ȃ��B�[��̈����o�鎞�A�f���������̎����A�����K�������Y�����r�a�̂��S�ʂ��Ă��ꂽ�B������܂�����o���A�����ӂ��y���ނ悷���Ƃ���B�܂��A�����E���q�̔�����������B�\����A���ގ��ɎQ�w����B���̎��͑n�n�҂̎��o��t���琔���ĎO�\���ڂɂ�����́A�^�Ǖ��l�Y�Ƃ����l���o�Ƃ��ē���(�������͓��v)���āA�A���̌�J�R�����B���̌�A�_���T�t�����h�ȓ��ɂ���đ����̐l�X�̓��ɓ������A����ɂ���Ď������ׂĉ��z����A���F�̕ǂ͂��������Ȍ�������A�Ɋy��y���n��ɂ����ꂽ���Ǝv���闧�h�ȉ��������������B���̖��m�������̎��͂ǂ����낤�ƕ�킵���v��ꂽ�B
�@�@�@������
�����������Ƃӂ�ɂ���ǁA����(�܂���)�͕}�K(�ӂ���)���(��������)�̍D��(�����ӂ�)�ɂ��āA���悻����(�ǂ��Ă�)�E����(������)��p(�͂�)���B
����(�Ƃ��Ȃ�)���C���(��)��āA�](��)�̒�(����)�O��(�����)�A���](��������)�̒�(������)�������ӁB
���X(���܂���)�̐�(����)��s(��)���āA�Y(������)���͓̂V���w(��т���)�A�ӂ����͔̂g(�Ȃ�)�ə���(�͂��)�B
����͓�d(�ӂ���)�ɂ����Ȃ�A�O�d(�݂�)�ɏ�(����)�݂āA���ɂ킩��E�ɂ�Ȃ�B
��(����)�邠���(������)�邠��A����(������)��(����)�������Ƃ��B
��(�܂�)�̗�(�݂ǂ�)���܂₩�ɁA�}�t(���悤)����(��������)�ɐ�(��)�����͂߂āA����(�������傭)���̂Â��炽�߂��邪���Ƃ��B
���̂������A�悤�R(����)�Ƃ��Ĕ��l(�т���)�̊�(�����)����(�悻��)�ӁB
���͂�U(�Ԃ�)�_(����)�̂ނ����A��R(�������)���݂̂Ȃ���킴�ɂ�B
����(������)�̓V�H(�Ă�)�A���Â�̐l���M(�ӂ�)���ӂ�ЁA��(���Ƃ�)��s(��)���ށB
�@�@�@���Y��
�Y��(������)����(����)�͒n(��)�Â��ĊC�ɏo(��)�ł��铇(����)�Ȃ�B
�_���T�t(������)�̕ʎ�(�ׂ�����)�̐�(����)�A���T��(������)�Ȃǂ���B
�͂��A��(�܂�)�̖؉A(������)�ɐ�(��)�����ƂӐl���H�X(�܂�܂�)�����ׂ͂�āA����(������)�E���}(�܂���)�ȂǑ�(����)���ӂ肽�鑐(����)�̈�(������)�A��(������)�ɏZ(����)�Ȃ��A�����Ȃ�l�Ƃ͂���ꂸ�Ȃ���A�܂��Ȃ���������(�������)�قǂɁA���C�ɂ���āA��(�Ђ�)�̂Ȃ��߂܂����炽�ށB
�]��(�������傤)�ɋA��ďh(���)����(����)�ނ�A��(�܂�)���Ђ炫��K(�ɂ���)����(��)��āA���_(�ӂ�����)�̒�(����)�ɗ��Q(���т�)���邱���A���₵���܂ŁA��(����)�Ȃ�S�n(������)�͂�����B
����(�܂���)��@��(��)�ɐg(��)������@�قƂƂ����@�]��(����)
��͌����Ƃ��Ė�(�˂�)���Ƃ��Ă��˂�ꂸ�B
����(���イ����)���킩��鎞�A�f��(���ǂ�)����(�܂���)�̎�(��)����B
�����K(�͂炠��Ă�)��(�܂�)�����炵�܂̘a��(�킩)��(����)���B
��(�ӂ���)����(��)���āA����Ђ̗F(�Ƃ�)�Ƃ��B
���A����(����Ղ�)�E���q(���傭��)������(�ق���)����B
�@�@�@�����ގ�(��������)
�\����A���⎛(��������)�Ɍw(������)�B
����(�Ƃ���)�O�\��(���イ�ɂ���)�̐�(�ނ���)�A�^��(�܂���)�̕��l�Y(�ւ����낤)�o��(�������)���ē���(�ɂ��Ƃ�)�A�A��(�����傤)�̌�(�̂�)�J�R(��������)���B
����(���̂̂�)�ɉ_���T�t(������)�̓���(�Ƃ���)�ɂ��āA����(�����ǂ�)�O(���炩)��(���炽)�܂�āA����(�����)����(���傤����)��(�Ђ���)���P(������)�����A���y(�Ԃ�)���A(���傤����)�̑剾��(���������)�Ƃ͂Ȃ�肯��B
���̌�����(����ԂЂ���)�̎��͂��Â��ɂ�Ƃ����͂�B
�\����A���悢�敽���ڎw���Đi��ł����B���˂͂̏��E�������̋��Ȃlj̖��̒n������ƕ����Ă����̂ŁA�l�ʂ���Ƃڂ����b�����A�s�ē��Ȓ��i��ł������A�Ƃ��Ƃ������Ԉ���ĐΊ��Ƃ����`�ɏo�Ă��܂����B�唺�Ǝ����u�����ˉԍ�v�Ɖr��Ő����V�c�Ɍ��サ�����ԎR���C��Ɍ�����B���S�̉��D(�l��ו����^�ԏ��ƑD)������]�ɏW�܂�A�l�Ƃ��Ђ��߂��悤�Ɍ����Ă���A���������}�̉���������ɗ�������Ă���B�v�������������������ɗ������̂��Ȃ��ƁA�h����悤�Ƃ������A�܂���������Ȃ��B�悤�₭�n�����ȏ��Ƃɔ��߂Ă��炢�A�����܂��n�b�L�����Ȃ���������i�B���̂킽��E���Ԃ��̖q�E�܂̂̊����Ȃlj̖��̒n���߂��ɂ���炵�������݂��킩�炸�A�悻�ڂɌ��邾���ŁA�ǂ��܂ł�������̒��i��ł����B�ǂ��܂Œ������s���ɂȂ�悤�Ȓ����Ƃ����������ɐi�݁A�ˈɖ��Ƃ����Ƃ���ňꔑ���āA����ɓ��������B���̊Ԃ̋����͓�\��������Ƃ������Ǝv���B
�@�@�@���Ί�(�����̂܂�)
�\����A���a��(�Ђ炢����)�ƐS�����A���˂͂̏�(�܂�)�E��(��)�����̋�(�͂�)�ȂǕ����`(����)�āA�l��(����)�H(�܂�)��賓e(����)����(�������傤)�̉�(����)���ӓ������Ƃ��킩���A�I(��)�ɘH(�݂�)�ӂ݂������āA�Ί�(�����̂܂�)�Ƃ��Ӗ�(�݂Ȃ�)�ɏo(��)�ÁB
�u�����ˉԍ�(����)�v�Ƃ�݂Ă��Ă܂肽����ԎR(������)�A�C��(�������傤)�Ɍ��킽���A���S(���ЂႭ)�̉��D(��������)���](���肦)�ɂǂЁA�l��(����)�n�����炻�ЂāA�}(���܂�)�̉�(���ނ�)�����Â�����B
�v�Ђ����������鏊(�Ƃ���)�ɂ�������邩�ȂƁA�h(���)�����Ƃ���ǁA����ɏh(���)�����l�Ȃ��B
�Q(�悤�悤)�܂ǂ�������(������)�Ɉ��(������)���������āA��(����)��܂�����ʓ��܂�Ѝs(��)���B
��(����)�̂킽��E��(��)�Ԃ��̖q(�܂�)�E�܂̂̊�(����)�͂�Ȃǂ悻�߂ɂ݂āA�y(�͂邩)�Ȃ��(��)���s(��)���B
�S��(������ڂ�)������(�Ȃ��ʂ�)�ɂ��ӂāA�ˈɖ�(�Ƃ���)�Ƃ��ӏ�(�Ƃ���)�Ɉ�h(�������キ)���āA����(�Ђ炢����)�ɂ�����B
���̊�(����)���]��(�ɂ��イ���)�قǂƂ��ڂ�B
�������t�E��t�E�G�t�Ƒ��������B�������O��̉h�����A����ꐆ�̖��̌̎��̂悤�ɂ͂��Ȃ������A����̐Ղ͂������炷���ꗢ�̋����ɂ���B�G�t�̊ق̐Ղ͓c��ƂȂ�A���̖��c���疳���B�����A�G�t���R���ɋ��̌{�߂ĕ���̎��Ƃ����Ƃ����y���{�R�z�������A�`���c���Ă���B�܂��`�o�̊ق̂���������A�y���ځz�ɓo��ƁA�ቺ�ɖk��삪��]�����B�암�n�����痬���A��͂ł���B�ߐ�͏G�t�̎O�j�a��O�Y�̋���Ղ��߂����āA���ڂ̉��Ŗk���ƍ������Ă���B���j�t�̋���Ղ́A�߂��ւ����Ƃ��ĕ���Ɠ암�n�������A�ڈ̍U����h���ł����̂��ƌ�����B����ɂ��Ă��܂��A�`�o�̒��b���������̍��ڂɂ��������A���̍I�����ꎞ�̂��Ƃō��͑��ނ�ƂȂ��Ă���̂��B���͖łтĐՌ`���Ȃ��Ȃ�A�R�͂������̂̂܂܂̎p�ŗ���Ă���A�ɉh���Ă����s�̖��c���Ȃ��A�t�̑����X�Ɣɂ��Ă���B�m��́w�t�]�x���v���o�����S�ɂӂ������B�}��E���n�ʂɕ~���āA���̉߂���̂�Y��ė܂𗎂Ƃ����B
�đ���@���ǂ����@���̐�
(�Ӗ�)���B��������`�o��]�̌������A���͈ꐆ�̖��Ə����A�đ���䩁X�Ɣɂ��Ă���B
�K�̉ԂɁ@���[�݂��@�������ȁ@�\��
(�Ӗ�)�����K�̉Ԃ����Ă���ƁA�E�҂ɐ�����`�o�̉Ɛb�A���[�̔������霂����)
���˂Ă��̕]���������Ă����A�����������ƌo���̔����J���B�o���ɂ͓����O�㓪��̑��A�����ɂ͂��̊��ƁA����ɎO���������u���Ă���B���B�������̏��L���Ă����̐��X�͎U�肤���A�ʂ��U��߂����͕��ɐ������炳��{���{���ɔj��A�����̒��͑����ɂ��炳�ꋀ���ʂĂĂ��܂����B���͍r��ʂĂ����ނ�ƂȂ��Ă��Ă������͖����̂����A���F���̎l�ʂɕ��������āA���������J��h���A�i���̎��̒��ł͂킸���Ȏ��Ԃ������߂Đ�N���炢�͂��̎p��ۂ��Ă���邾�낤�B
�܌��J�́@�~��̂����Ă�@����
(�Ӗ�)�S�Ă�����Ă��܂��܌��J���A���������͂��̋C�����ɉ������ĔG�炳���c���Ă���悤��)
�@�@�@������(�Ђ炢����)
�O��(����)�̉h�s(�����悤)�ꐇ(��������)�̒�(����)�ɂ��āA���(��������)�̐�(����)�͈ꗢ(������)���Ȃ��ɂ���B
�G�t(�ЂłЂ�)����(����)�͓c��(�ł��)�ɂȂ�āA���{�R(��������)�̂`(������)���c(�̂�)���B
�܂��A����(��������)�ɂ̂ڂ�A�k���(�������݂���)�암(�Ȃ��)��藬(�Ȃ�)�����(������)�Ȃ�B
�ߐ�(���������)�́A�a��(�����݂����傤)���߂���āA����(��������)�̉�(����)�ɂđ��(������)�ɗ�(��)����(��)��B
�t(�₷�Ђ�)�炪����(���イ����)�́A�߂���(�����������)���u(�ւ�)�ĂāA�암��(�Ȃ�Ԃ���)��������(����)�߁A��(����)���ӂ����Ƃ݂�����B
���Ă��`�b(������)�����Ă��̏�(���傤)�ɂ�����A����(�����݂傤)�ꎞ(������)�̑p(�����ނ�)�ƂȂ�B
���j(���)��ĎR��(����)����A��(����)�t(�͂�)�ɂ��đ�(����)��(����)�݂���ƁA�}(����)�ŕ~(��������)�āA���̂���܂ş�(�Ȃ݂�)��(��)�Ƃ��ׂ͂�ʁB
�đ���@��(�����)�ǂ����@��(���)�̐�(����)
�K�̉�(���̂͂�)�Ɂ@���[(���˂ӂ�)�݂��@����(���炪)���ȁ@�]��(����)
���˂Ď���(���ǂ납)�������(�ɂǂ�)�J��(�������傤)���B
�o��(���傤�ǂ�)�͎O��(���傤)�̑�(����)���̂����A����(�Ђ���ǂ�)�͎O��(����)�̊�(�Ђ�)��[(����)�߁A�O��(����)�̕�(�قƂ�)�����u(����)���B
����(�����ۂ�)�U(����)�����āA��(����)�̔�(�Ƃт�)��(����)�ɂ�Ԃ�A��(������)�̒�(�͂���)����(��������)�ɋ�(����)�āA���ł����p(�����͂�)��(��������)�̑p(�����ނ�)�Ɛ�(�Ȃ�)�ׂ����A�l��(���߂�)�V(���炽)�Ɉ�(������)�āA�O(���炩)��(������)�ĉJ��(�ӂ���)�����̂��B
���炭���(����)�̋L�O(������)�Ƃ͂Ȃ��B
�܌��J(���݂���)�́@�~(�ӂ�)�̂����Ă�@����(�Ђ���ǂ�)
�암�n���֑��������암�X����ڂ̑O�ɂ��āA���̏h�ɔ��܂����B������E�݂Â̏����Ƃ����̖��̒n���߂��āA�q����A�O�̊ւɂ������āA�o�H�̍��ɉz���悤�Ƃ����̂��B���̊X���͂߂����ɗ��l�Ȃǒʂ�Ȃ����Ȃ̂ŁA�֎�ɕs�R�����ĐF�X������A����Ƃ̂��ƂŊւ��z�����Ƃ��ł����B�q����H�O�ɏo�钆�R�z���̎R�����̂ڂ����Ƃ���A�����������Ă��܂����̂ŁA�������x�삷��l�̉Ƃ��݂��āA���̏h�����肢�����B�O���ԗ��ƂȂ�A���邱�Ƃ��Ȃ��R���ɑ��~�߂���Ă��܂����B
�a�l�n�̔A���閍����
(�Ӗ�)��������ĕn�������̏h�ŐQ�Ă���Ɣa���l�ɋꂵ�߂���B���̏�h�Ŕn�������Ă���̂Ŕn���A�����鉹�������B���̋����ɂ����A�ЂȂт����������̂��B
�h�̎�l�̌������Ƃɂ́A���ꂩ��o�H�̍��ɂ����Ă͌������R�����z���˂Ȃ炸�A�����͂����肵�Ȃ��̂ňē��l�𗊂�Œ��������悩�낤�Ƃ������Ƃ������B�ł͂������悤�Ɛl�𗊂Ƃ���A�����Ȏ�҂�����Ԃ����e�����������āA�~�̏�������Ď�������擱���Ă��ꂽ�B���������K����Ȃ��ڂɂ����ɈႢ�Ȃ��Ƃт��т����Ȃ�����čs�����B��l�̌������Ƃ���A�����R�͐Â܂�Ԃ��Ă���A��H�̒��̐����������Ȃ��B���������Ɣɂ�X�̉��́A�܂�Ŗ铹�̂悤�ɈÂ��B�m��̎��Ɂu�_�̒[����y�����ڂ��悤���v�Ƃ��邪�A�܂��ɂ���Ȋ����ŁA�̒��ݕ����i��ł����A�k�����z����ɂ܂Â��āA���ɂ͗₽�����𗬂��A����Ƃ̂��Ƃōŏ�̏��ɂ����B��̈ē����Ă��ꂽ�j�́u���̓���ʂ�ΕK���s���̎��Ԃ��N����̂ł��������͉������Ȃ����邱�Ƃ��ł��K�^�ł����v�ƌ����Ă���A��т����ĕʂꂽ�B����ȕ����ȓ��ƑO�����Ă�������Ă����킯�ł͂Ȃ��������A����ɂ��Ă������܂�悤�ȐS���������B
�@�@�@���A�O�̊�(���Ƃ܂��̂���)
�암��(�Ȃ�Ԃ݂�)�y(�͂邩)�Ɍ����āA���(�����)�̗��ɔ�(�Ƃ�)��B
������(�����낳��)�E�݂Â̏���(������)����(����)�āA�Ȃ邲�̓�(��)���A�O(���Ƃ܂�)�̊�(����)�ɂ�����āA�o�H(�ł�)�̍��ɒ�(��)����Ƃ��B
���̘H(�݂�)���l(���тт�)�H(�܂�)�Ȃ鏊(�Ƃ���)�Ȃ�A�֎�(��������)�ɂ��₵�߂��āA�Q(�悤�悤)�Ƃ��Ċ�(����)�������B
��R(��������)���̂ڂē����łɕ�(����)����A���l(�ق�����)�̉�(����)���������Ď�(��ǂ�)����(����)�ށB
�O��(�݂���)���J(�ӂ���)����āA�悵�Ȃ��R��(���イ)�ɐ���(�Ƃ���イ)���B
�a(�̂�)�l(�����)�@�n(����)�̔A(��)����@��(�܂���)����
���邶�̂��ӁA������o�H(�ł�)�̍��ɑ�R(��������)���u(�ւ�)�ĂāA���������Ȃ炴��A������ׂ̐l��(����)�݂ĉz(����)�ׂ��悵���������B
����Ƃ����Đl��(����)�ׂ݂͂�A����(�������傤)�̎��(�킩����)�A���e�w(����킫����)���悱�����A�~(����)�̏�(��)���g(��������)�āA��X(�����)����ɗ����čs(��)���B
���������K(���Ȃ�)�����₤���߂ɂ����ӂׂ����Ȃ�ƁA�h(����)���v�Ђ��Ȃ��Č�(������)�ɂ��čs(��)���B
���邶�̂��ӂɂ����͂��A���R(��������)�X�X(����)�Ƃ��Ĉ꒹(�������傤)���������A��(��)�̉���(�������)��(����)�肠�ЂĖ��s(��)�������Ƃ��B
�_�[(����)�ɂ��ӂ�S�n(������)���āA��(����)�̒�����(�ӂ݂킯)�����A�����킽�����K(�܂���)�āA��(�͂�)�ɂ߂�����(����)��(�Ȃ�)���āA�ŏ�(������)�̏�(���傤)�ɏo(��)�ÁB
���̈ē�(����Ȃ�)�������̂��̂��ӂ₤�A���̓����Ȃ炸�s�p(�Ԃ悤)�̂��Ƃ���B
��(��)�Ȃ�������܂��点�Ďd��(�����킹)������ƁA��낱�тĂ킩��ʁB
��(����)�ɕ����Ă���(�ނ�)�Ƃǂ낭�݂̂Ȃ�B
���ԑ�ɂĈȑO�]�˂Œm�荇���������Ƃ����l��K�˂��B���̐l�͑�x���Ȃ̂����������ɂ��肪���ȕi���̂��₵���Ȃǂ܂�łȂ��B�]�˂ɂ����X�o�Ă��Ă���̂ŁA�������ɗ��l�̋C�������킩���Ă���悤���B���������������Ă���A�����̔���J���Ă���A���낢��Ƃ��ĂȂ��Ă��ꂽ�B
����������h�ɂ��Ă˂܂��
(�Ӗ�)���̗������h�ɂ���ƁA�܂�Ŏ����̉Ƃɂ���悤�ɂ��낰��̂��B
���o�悩�Ђ₪���̂Ђ��̐�
(�Ӗ�)�����̉��łЂ�������̐������Ă���B�ǂ����Ђ��������A�o�Ă��Ď莝���������Ȏ��̑�������Ă�����B
�܂�͂���݂ɂ��čg���̉�
(�Ӗ�)���ԑ�̖��Y�ł���g�̉Ԃ����Ă���ƁA���������ςɂ������|����z�������邠�ł₩����������B
�\������l�͌Ñ�̂������� �\��
(�Ӗ�)�{�\����l�����̂���؎p�́A�_��̐̂������������낤�Ǝv�킹��f�p�Ȃ��̂��B
�@�@�@�����ԑ�(���˂���)
���ԑ�(���˂���)�ɂĐ���(�����ӂ�)�Ƃ��ӎ�(����)��q(����)�ʁB
����͕x(�Ƃ�)����̂Ȃ�ǂ��A�u(�����내��)���₵���炸�B
�s(�݂₱)�ɂ��܁X(���肨��)����ЂāA�������ɗ�(����)�̏�(�Ȃ���)�����m(����)����A������Ƃǂ߂āA���r(���傤��)�̂����͂�A���܂��܂ɂ��ĂȂ��ׂ͂�B
��(����)�������@��(�킪)�h(���)�ɂ��ā@�˂܂�Ȃ�
��(�͂�)�o(��)�ł�@���Ђ₪��(����)�́@�Ђ��̐�
�܂�͂����@��(��������)�ɂ��ā@�g��(�ׂ�)�̉�
�\��(������)����@�l�͌Ñ�(������)�́@���������ȁ@�]��(����)
�R�`�˂̗̓��ɁA���Ύ��Ƃ����R��������B���o��t�̊J��ŁA���ʌi�F���悭�Â��ȏꏊ���A��x�͌��Ă����ׂ����B�l�X�����������߂�̂ŁA���ԑ�����Ԃ����B���̊ԁA��������ł���B�܂������܂ł͎��Ԃ�����B�ӂ��Ƃ̏h�V�ɔ��܂��͂��𐮂��āA�R��̓��ɂ̂ڂ�B�����̊₪�d�Ȃ肠���ĎR�ƂȂ����悤�Ȍ`�ŁA���┐�ȂǏ�̌Ö�������A�y���͊��炩�ɑۂނ��Ă���B��̏�Ɍ��ǂ̎��@��������āA�������܂������������Ȃ��B�R����R�ցA�₩���֓n������A���t�ɎQ�q����B�i�F�͔������A�Ђ�����Â܂肩�����Ă���B�S���ǂ��܂ł����ݓn�����B
�Ղ����ɂ��ݓ����̐�
(�Ӗ�)�������Ƃ����Â������B���̒��Ŋ�ɐ��ݒʂ��Ă����悤�Ȑ�̐����A���悢��Â��������߂Ă���B
�@�@�@���R��
�R�`��(��܂�����傤)�ɗ��Ύ�(��イ���Ⴍ��)�Ƃ��ӎR��(��܂ł�)����B
���o��t(������������)�̊J��(������)�ɂ��āA��(���Ƃ�)����(��������)�̒n�Ȃ�B
�ꌩ(��������)���ׂ��悵�A�l�X(�ЂƂт�)�̂��T�ނ�Ɉ�(���)�āA���ԑ�(���Ȃ���)���Ƃĕ�(����)���A���̊�(����)����(������)����Ȃ�B
�����܂���(����)���B
��(�ӂ���)�̖V(�ڂ�)�ɏh(���)����u(����)�āA�R��(���傤)�̓�(�ǂ�)�ɂ̂ڂ�B
��Ɋ�(���킨)���d(����)�˂ĎR�Ƃ��A����(���傤�͂�)�N��(�Ƃ��ӂ�)�y��(�ǂ���)�V(����)�đ�(����)��(�Ȃ߂炩)�ɁA���(���傤)�̉@�X(����)��(�Ƃт�)���(�Ƃ�)�Ă��̂̉����������B
��(����)���߂�����(�͂�)�ĕ��t(�Ԃ�����)��q(�͂�)���A���i(������)�⛋(���Ⴍ�܂�)�Ƃ��ĐS���ݍs(��)���݂̂��ڂ�B
��(������)����@��ɂ��ݓ�(��)��@��(����)�̐�
�ŏ��̐쉺������悤�Ǝv���A��Γc�Ƃ����ꏊ�œV�C���悭�Ȃ�̂�҂����B���Ă��̒n�ɒk�єh�̔o�~���`���A�o�~�̎킪�܂���A���ꂪ�ԊJ�����̂̂��Ƃ��A�y�n�̐l�͉�������ł���B���J�𐁂��悤�ȂЂȂт��S��o�~�̐Ȃ��J���ĈԂ߂Ă����B�u���̒n�ł͔o�~�̓����䗬�ł������Ă���̂ł����A�V�������s�̔o�~�ł������A�Â��`���I�Ȃ��̂ł������A�w���҂����Ȃ��̂Ō��߂��˂Ă��܂��v�Ɠy�n�̐l�������̂ŁA��ނ��̐���ꊪ�c���Ă����B����̕����̗��́A�Ƃ��Ƃ�����Ȃ��Ƃ܂ł��錋�ʂɂȂ����B�ŏ��̌����͗����ł���A�㗬�͎R�`�ł���B��_�E�͂�Ԃ��ȂǂƂ����A���낵���������B�̖��̒n�A�~�R�̖k�𗬂�āA�Ō�͎�c�̊C�ɗ��ꍞ��ł���B���E�ɎR���������Ԃ����āA�݂̒��ɏM�������Ă����B����Ɉ��ς��̂��A�É̂ɂ���u��D�v�Ȃ̂��낤���B�L���Ȕ����̑�͐t�̊ԊԂɗ��ꗎ���Ă���A�`�o�̉Ɛb�A�헤�V�C�����܂�����l�����݂̂���Ɍ����Ă���B���ʂ��L���ŁA���x���M���Ђ�����Ԃ肻���Ȋ�Ȃ���ʂ��������B
�܌��J�����߂đ����ŏ��
(�Ӗ�)�~�蒍���܌��J�͂₪�čŏ��֗��ꂱ�݁A���̐��ʂƐ����𑝂��A�M�������������ʼn��������̂��B
�@�@�@����Γc
�ŏ��(�����݂���)�̂��ƁA��Γc(����������)�Ƃ��ӏ�(�Ƃ���)�ɓ��a(�Ђ��)���(��)�B
�u�����Ɍ�(�ӂ�)�����~(�͂�����)�̎�(����)���ڂ�āA�Y(�킷)��ʉԂ̂ނ����������ЁA���p(�납��)�ꐺ(��������)�̐S����͂炰�A���̓��ɂ����肠�����āA�V��(����)�ӂ����ɂӂ݂܂�ӂƂ��ւǂ��A������ׂ���l���Ȃ���v�ƁA���Ȃ��ꊪ(�ЂƂ܂�)�c(�̂�)���ʁB
���̂��т̕���(�ӂ���イ)�����ɂ������B
�@�@�@���ŏ��(�����݂���)
�ŏ��(�����݂���)�݂͂��̂����o(��)�łāA�R�`(��܂���)�𐅏�(�݂Ȃ���)�Ƃ��B
���Ă�E�͂�Ԃ��Ȃǂ��ӁA�����낵���(�Ȃ�)����B
�~�R(�����������)�̖k��(�Ȃ���)�āA��(�͂�)�͎�c(������)�̊C�ɓ�(��)��B
���E�R��(����)�ЁA��(����)�݂̒��ɏM����(����)���B
����Ɉ�(����)�݂������A��M(���ȂԂ�)�Ƃ��ӂȂ炵�B
����(���炢��)�̑�(����)�͐t(������)�̌���(�Ђ܂Ђ�)�ɗ�(����)�Đ�l��(����ɂ�ǂ�)��(����)�ɗ�(�̂���)�ė�(����)�B
���݂Ȃ��ďM(�ӂ�)���₤���B
�܌��J(���݂���)���@���߂Ă͂₵�@�ŏ��(�����݂���)
�Z���O���A�H���R�ɓo��B�}�i���g�Ƃ������̂�K�˂āA���̎�����ŎR������ӔC�҂̑㗝�l(�ʓ���)�ł���A��o��苗��ɔq�y�����B��苗��͓�J�̕ʉ@�ɔ��߂Ă�������A�F�X�ƐS�������Ă��ĂȂ��Ă����������B�l���A�{�V�ቤ���Ŕo�~�����您���A����Ȕ�����r�B
�L��������ق炷��J
(�Ӗ�)�c��̕�X������₩�ȕ������̂����J�܂Ő����Ă���B����͂��̐_���ȉH���R�̕��͋C�ɂ҂�����ŁA���肪�������Ƃ��B
�ܓ��A�H�������ɎQ�w����B���̎����J�����\����t�Ƃ������́A���̎���̐l���A�킩��Ȃ��B�u���쎮�v�Ɂu�H�B���R�̐_�Ёv�Ƃ����L�q������B�����ʂ��l���u���v�̎����Ԉ���āu���R�v�Ƃ����̂��낤���B�u�H�B���R�v�𒆗����āu�H���R�v�Ƃ������̂��낤���B�u�o�H�v�Ƃ����������ɂ��ẮA�u���̉H�т����̍��̓��Y���Ƃ��Ē���Ɍ��サ���v�ƕ��y�L�ɏ����Ă���Ƃ������b�ł���B���R�A���a�����킹�āA�u�o�H�O�R�v�Ƃ���B���̎��͍]�˂̓��b�R���i���ɏ������A�V��@�̎�ȋ����ł���u�~�ρv�͌��̂悤�ɖ��炩�Ɏ��s����Ă���B�u�~�ڗZ�ʁv�̋�������������悤�ɂ������A�m�V(�m���������鏬���Ȍ���)��������ׂČ����Ă���B�m�����݂͌��ɗ�܂������ďC�s���Ă���B��R��n�̂����v���A�l�X�͑��сA����Ă���B�ɉh�͉i�v�ɂÂ����낤�B������R�ƌ����ׂ����Ǝv���B
�����A���R�ɓo��B�ؖȂ��߂�̂Ɉ��������A�ɓ����݁A���͂Ƃ����҂ɓ�����āA�_�▶���������߂�R�C�̒��ɕX���݂Ȃ��甪���̓��̂��o���Ă����B���z�⌎�̋O���̓r���ɂ���A�ƂĂ��Ȃ������ʒu�ɂ���_�̊ւɓ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���������B���͐₦�A�͓̂����āA�悤�₭����ɂ��ǂ蒅���ƁA���z������Ō����������B����̏�ɐQ�]��ŁA��������Ė邪������̂�҂����B���z������_���������̂ŁA���a�R�Ɍ����ĎR�������Ă����B�J�̂������ɁA�b�菬���ƌĂ��ꏊ���������B�����o�H�̍��ł͓��b��͗쌱���炽���Ȑ���I��ŁA�g�𐴂߂Č���ł�(���)�A�d�グ�Ɂu���R�v�Ƃ�����������Ő��̒�������Ă͂₳��Ă����B�����ł��u����v�Ƃ�����Œb�����������Ă͂₳�ꂽ�Ƃ������A�����悤�Ȃ��ƂȂ̂��B���R�̓��b�肽�����Ñ㒆���̗L���ȓ��b��A�����E����v�w�̂��Ƃ����āA���̂悤�ȍH�@������̂��낤�B��̓��ɏG�ł��҂́A���̂������Ԃ�������̂��Ƃł͂Ȃ��̂��B��ɍ��|���Ă��炭�x��ł���ƁA�O��(90�Z���`)�قǂ̍��̂ڂ݂��A�����قNJJ���Ă����B�~��ς����̉��ɖ�����Ȃ���A�t�̖K���Y�ꂸ�x�܂��Ȃ���Ԃ��炩���c�Ԃ̐����͎��ɂ����炵�����̂��Ɗ��S�����B�����̎��ɂ���u���V�̔~�ԁv���A�ڂ̑O�łɍ��肽���Ă���悤�Ɏv�����B�u����Ƃ��ɂ��͂�Ǝv�֎R���v�Ƃ����s���m���̉̂̏�����v���o�����B�ނ��낱����̉Ԃ̂ق����m���̉̂���[���Ƃ���������B���������ɁA���̎R���ŋN�������ׂ������Ƃ͏C�s����҂̝|�Ƃ��Č��O���邱�Ƃ��ւ����Ă���B�����炱��ȏ�͏����Ȃ��B�h�V�ɖ߂�ƈ�苗��ɋ�����߂�ꂽ�̂ŏ��炵���O�R���ꂼ��̋��Z���ɏ������B
��������ق̎O�����̉H���R
(�Ӗ�)�����������ȁB�H���R�̎R�̒[�ɂق̂��ȎO�������������Ă���B
�_�̕����Č��̎R
(�Ӗ�)��ɕ�̂悤�ɂ��т�������_���A��������Ă��̌��R�ƂȂ����̂��낤�B�V�̂��̂�����Ēn��ɍ~�肽�Ƃ��v���Ȃ��A�Y��Ȍ��R�̂������܂����B
����ʓ��a�ɂʂ炷�Ԃ���
(�Ӗ�)�������a�R�ŏC�s����l�͎R�ł̂��Ƃ���،��O���Ă͂����Ȃ��Ƃ����Ȃ�킵�����邪�A�������������ȓ��a�R�ɓo���āA���肪�����ɗ܂𗬂������Ƃ�B
���a�R�K�ӂޓ��̟�����
(�Ӗ�)���a�R�ɂ́A�n��ɗ��������̂��E���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ȃ�킵�Ȃ̂ŁA���������Ă����ΑK�݂Ȃ���Q�w���A���̂��肪�����ɗ܂𗬂��̂������B
�@�@�@���H���R(�͂��낳��)
�Z���O���A�H���R(�͂��낳��)�ɓo��B
�}�i���g(����������)�Ƃ��ӎ҂�q(����)�˂āA�ʓ���(�ׂ��Ƃ�����)��o��苗�(�������������)�ɉy(����)���B
��J(�݂Ȃ݂���)�̕ʉ@(�ׂ���)�Ɏ�(��ǂ�)���ė���(���݂�)�̏�(���傤)���܂₩�ɂ��邶�����B
�l���A�{�V(�ق�ڂ�)�ɂ���Ĕ��~(�͂�����)���s(�������傤)�B
���肪����@������ق炷�@��J(�݂Ȃ݂���)�@
�ܓ��A����(����)�Ɍw(������)�B
���R(�Ƃ�����)�J�(�����тႭ)�\����t(�̂����傾����)�͂��Â�̑�(��)�̐l�Ƃ��ӂ��Ƃ����炸�B
���쎮(������)�Ɂu�H�B(�����イ)���R(���Ƃ��)�̐_�Ёv�Ƃ���B
����(���債��)�A�u���v�̎����u���R�v�ƂȂ���ɂ�B
�u�H�B(�����イ)���R(������)�v�𒆗�(���イ��Ⴍ)���āu�H���R(�͂��낳��)�v�Ƃ��ӂɂ�B
�u�o�H(�ł�)�v�Ƃ��ւ�́A�u���̖щH(������)�����̍��̍v(�݂�����)�Ɍ�(���Ă܂�)��v�ƕ��y�L(�ӂǂ�)�ɂׂ͂�Ƃ���B
���R(��������)�E���a(��ǂ�)�����킹�ĎO�R(����)�Ƃ��B
����(�Ƃ���)���]���b(�Ԃ����Ƃ�����)�ɑ�(���傭)���ēV��~��(�Ă�������)�̌���(����)�炩�ɁA�~�ڗZ��(����ǂ�䂸��)�̖@(�̂�)�̓�(�Ƃ�����)���������ЂāA�m�V(�����ڂ�)��(�ނ�)���Ȃ�ׁA�C���s�@(���グ�傤�ق�)���(�͂�)�܂��A��R(�ꂢ����)��n(�ꂢ��)�̌���(����)�A�l�M(�Ƃ��Ƃ�)����(����)��B
�ɉh(�͂�)��(�Ƃ����Ȃ�)�ɂ��āA�߂ł�����R(�����)�Ƃ����ׂ��B
�@�@�@�����R(��������)
�����A���R(��������)�ɂ̂ڂ�B
�ؖ�(�䂤)���ߐg(��)�Ɉ��������A��(�ق�����)�ɓ�(������)���(��)�A����(�����肫)�Ƃ��ӂ��̂ɓ��т���āA�_���R�C(����ނ���)�̒��ɕX��(�Ђ傤����)��(�ӂ�)�Ă̂ڂ邱�Ɣ���(�͂���)�A����ɓ���(������)�s��(���傤�ǂ�)�̉_��(����)�ɓ�(��)�邩�Ƃ��₵�܂�A����(��������)�g(��)�������Ē���(���傤���傤)�ɂ�����A���v(�ڂ���)�Č���(�����)��B
�����(����)�A��(����)��(�܂���)�Ƃ��āA��(�ӂ�)�Ė�(����)����(��)�B
���o(��)�łĉ_��(����)��Γ��a(��ǂ�)�ɉ�(����)��B
�J�̖T(�������)�ɒb������(��������)�Ƃ��ӂ���B
���̍��̒b��(����)�A�쐅(�ꂢ����)������тĂ����Ɍ���(��������)���ę�(�邬)���(����)�A�I(����)���R(��������)�Ɩ�(�߂�)���(����)�Đ��ɏ�(���傤)�����B
���̗���(��イ����)�Ɍ�(�邬)���(�ɂ炮)�Ƃ���B
����(���傤)�E����(����)�̂ނ����������ӁB
���Ɋ��\(����̂�)�̎�(���イ)��������ʂ��Ƃ���ꂽ��B
��ɍ�(����)�����Ă����₷��ӂقǁA�O�ڂ���Ȃ���̂ڂݔ�(�Ȃ�)�Ђ炯�邠��B
�ӂ��(��)��̉��ɖ�(��������)�āA�t��Y��ʒx(����)������̉Ԃ̐S���Ȃ��B
���V(����Ă�)�̔~��(����)�����ɂ��ق邪���Ƃ��B
�s���m��(���傤�������傤)�̚F(����)�̈�(����)��������Ɏv�Џo(��)�łāA�P(�Ȃ�)�܂���Ċo(����)��B
�������Ă��̎R��(���イ)�̔���(�݂���)�A�s��(���傤����)�̖@��(�ق�����)�Ƃ��đ���(������)���邱�Ƃ���(����)���B
���ĂĕM(�ӂ�)���Ƃǂ߂ċL(����)�����B
�V(�ڂ�)�ɋA��A��苗�(�������)�̂��Ƃ߂ɂ��āA�O�R(����)����(�����ꂢ)�̋�X(����)�Z��(���Ⴍ)�ɏ����B
��(����)������@�ق̎O����(�݂��Â�)�́@�H���R(�͂��낳��)�@
�_�̕�(�݂�)�@��(����)��(����)��ā@���̎R�@
��(����)���ʁ@���a(��ǂ�)�ɂʂ炷�@��(������)���ȁ@
���a�R(��ǂ̂���)�@�K(����)�ӂޓ��́@��(�Ȃ݂�)���ȁ@�]��(����)
�H���������āA�߂����̏鉺�Œ��R���d�s�Ƃ������m�̉ƂɌ}�����āA�o�~���J�Â��A�ꊪ�̐��������B�}�i���g�������܂ő����Ă����B��M�̏���Ď�c�̍`�։���B���̓��͕����s�ʂƂ�����҂̂��Ƃɔ��߂Ă��炤�B
���ݎR�␁�Y�����ė[���S��
(�Ӗ�)�������ݎR���琁�Y(�C)�������낷�B�u���ݎR�v�Ɩ��O���炵�ď������v�킹��R��������������v�킹�鐁�Y�������낷�̂́A����ꂽ�[���݂��B
���������C�ɂ��ꂽ��ŏ��
(�Ӗ�)�ŏ��̉�����������ƁA�܂��ɐ^���Ԃȑ��z���������Ƃ��Ă���B���̂��܂́A����̏��������ׂĊC�ɗ�������ł���悤���B
�@�@�@���߉��E��c(�邨���E������)
�H��(�͂���)�𗧂��āA��(��)�����̏鉺(���傤��)�A���R���d�s(�Ȃ���܂������イ����)�Ƃ��ӂ��̂̂ӂ̉Ƃɂނ��ւ��āA���~(�͂�����)�ꊪ(�ЂƂ܂�)����B
���g(������)���Ƃ��ɂɑ�(����)��ʁB
��M(����Ԃ�)�ɏ�(��)��Ď�c(������)�̖�(�݂Ȃ�)�ɉ�(����)��B
�����s��(����ӂ��傭)�Ƃ��ӈ�t(������)�̂��Ƃ��h(���)�Ƃ��B
���ݎR��@���Y(�ӂ�����)�����ā@�[�����݁@
��(����)�������@�C�ɂ��ꂽ��@�ŏ��(�����݂���)
�C��R�A�͐�Ȃnji�F�̂����Ƃ��������܂Ō��Ă��āA���悢�旷�̓����̖ړI�̈�ł���ۊ��Ɍ����āA�S���}�����Ă���̂������B�ۊ��͎�c�̍`���瓌�k�̕��p�ɂ���B�R���z���A���`���A���l������ď\���قǐi�ށB���z�������X�������B�������l�ӂ̍��𐁂��グ�Ă���A�J���~���Ă���̂Ōi�F���ڂ���_���āA���C�R�̎p���B��Ă��܂����B�Èł̒������Ă����ۂ��ɐi�ށB�u�J���܂���[�����̂��v�ƒ����̎��̕�����ӎ����āA�J���オ�����炳������n���ăL���C���낤�Ɗ��҂������A���t�̉����ɓ��ꂳ���Ă��炢�A�J�������̂�҂����B���̒��A����n��A�������͂Ȃ₩�ɋP���Ă����̂ŁA�ۊ��ɏM���ׂ邱�Ƃɂ���B�܂��\���@�t�䂩��̔\�����ɏM���A�@�t���O�N�ԂЂ�����Z�܂����Ƃ������̐Ղ�K�˂�B���ꂩ�甽�Α��݂̊ɏM�����ē��ɏ㗤����ƁA���s�@�t���u�Ԃ̏ケ���v�Ɖr���̘V���c���Ă���B���ӂɌ�˂�����B�_���@�{�̕�Ƃ������Ƃ��B���̖��O�������쎛�Ƃ����B�������_���@�{�����̒n�ɍs�K�����Ƃ����b�͍��܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��B�ǂ��������ƂȂ̂��낤�B���̎��ō��~�ɒʂ��Ă��炢�A������������グ�Ē��߂�ƁA���i�����̉��Ɍ��n����B��ɂ͒��C�R���V���x����悤�ɂ��т��Ă���A���̉e�����C�ɗ��Ƃ��Ă���B���Ɍ�����͂ނ�ނ�̊ւ����蓹�����������Ă���B���ɂ͒�h���z����Ă��āA�H�c�܂ł͂邩�ȓ������̏�𑱂��Ă���B�k���ɂ͊C�����܂��Ă��āA���̓��ɔg�����肱�ނ�����z�Ƃ����B�]�̓��͏c���ꗢ�قǂ��B���̌i�F�͏����Ɏ��Ă��邪�A�����ɂ܂������قȂ�B�����͊y�����ɏ��Ă���悤�����A�ۊ��͐[���J�D�ɒ���ł���悤�Ȃ̂��B�₵���ɔ߂��݂܂ʼn�����Ă��āA���̓y�n�̗L�l�͔������[���J�����������Ă��ނ��Ă���悤�Ɍ�����B
�ۊ���J�ɐ��{���˂Ԃ̉�
(�Ӗ�)�ۊ��̊C�ӂɍ����̉Ԃ��J�ɂ�������Ă��邳�܂́A�`���ɂ��钆���̔����A���{�������Ƃ肤�ނ��Ă��邳�܂�z��������B�h����(�h�@)�̎��u���Ώ㏉����J(�Ώ�Ɉ��ށA���ߐ����J�ӂ�)�v�܂���B�u���������Đ��q�ɔ䂹��Ɨ~����@�W�ϔZ�����đ��X���v
���z��߂͂��ʂ�ĊC����
(�Ӗ�)���z�̐ɒ߂������~�肽�B���������C�̐��ɔG��āA�����ɂ����������B�߂��Z�����˂����������Ă���̂��u�߂͂��v�ƌ������A�܂��ɒ߂͂����Ȃ��Ɗ��S�����B
���傤�njF�쌠���̂��Ղ�ɏo���킵���B
�ۊ��◿���ȂɐH�Ӑ_�Ղ�@�\��
(�Ӗ�)�F�쌠���̂��Ղ�ɂł��킷�B�C�ӂ̏ۊ��ł���̂ɁA�F��M�ɂ���ċ���H�ׂ�̂��ւ����A����H�ׂ�̂��낤���B
剂̉Ƃ�˔�~�ė[���@�݂̂̍��̏Z�l�Ꭸ
(�Ӗ�)���t�����̉Ƃł́A�˔�~�����ׂĉ���̂����ɂ��āA�[���݂��y����ł���B�����Ȃ��Ƃ��B
��̏�ɂ݂�������������Ă���̂����āA
�g�����ʌ_�肠��Ă�݂����̑��@�\��
(�Ӗ�)���́A�����ɂ��g����т������Ă������Ȋ낤���ʒu�ɂ݂����̑�������B�É̂Ɂu���̏��R�g�������Ƃ́v�Ƃ��邪�A�����J�Ō��ꂽ�݂����̕v�w�Ȃ낤�B
�@�@�@���ۊ�(��������)
�]�R(��������)����(�����肭)�̕���(�ӂ�����)��(����)��s(��)���āA��(����)�ۊ�(��������)�ɕ���(�ق�����)���(��)�ށB
��c(������)�̖�(�݂Ȃ�)��蓌�k�̕�(����)�A�R��(��)���E(����)��`(��)�ЁA���������ӂ݂āA���̍�(����)�\��(���イ��)�A���e(�Ђ���)��₩���Ԃ�����A����(��������)�^��(�܂���)��(�ӂ�����)�A�J�N�O(�����낤)�Ƃ��Ē��C(���傤����)�̎R������B
�Œ�(���イ)�ɔ���(������)���āA�u�J���܂���(��)�Ȃ�v�Ƃ��A�J��(����)�̐��F(�������傭)�܂����̂������ƁA�(����)�̓ω�(�Ƃ܂�)�ɕG(�Ђ�)������ĉJ�̐�(��)�����(��)�B
���̒�(������)�A�V�悭����āA����(������)�Ԃ₩�ɂ����o(��)�Â�قǂɁA�ۊ�(��������)�ɑD�������ԁB
�܂��\����(�̂�����)�ɑD���悹�āA�O�N(����˂�)�H��(�䂤����)�̐�(����)���ƂԂ�ЁA�ނ��ӂ̊�(����)�ɏM��������A�u�Ԃ̏ケ���v�Ƃ�܂ꂵ��(������)�̘V��(������)�A���s�@�t(�������傤�ق���)�̋L�O(������)���̂����B
�]��(�������傤)�Ɍ��(�݂�����)����B
�_���@�{(������������)�̌��(�݂͂�)�Ƃ��ӁB
���������쎛(����܂ザ)�Ƃ��ӁB
���̂Ƃ���ɍs�K(�݂䂫)���肵���Ƃ��܂��������B
�����Ȃ邱�Ƃɂ�B
���̎��̕���(�ق����傤)�ɍ�(��)���ė�(������)����(�܂�)�A���i(�ӂ�����)���(��������)�̒�(����)�ɐs(��)�āA��ɒ��C(���傤����)�V���������A���̉A(����)����č](��)�ɂ���B
���͗L�떳��̊�(����ނ�̂���)�A�H(�݂�)��������A���ɒ�(��)��z(����)���ďH�c(������)�ɂ���ӓ��y(�͂邩)�ɁA�C�k�ɂ��܂��ĘQ(�Ȃ�)��(��)����(��)��鏊(�Ƃ���)�����z(��������)�Ƃ��ӁB
�](��)�̏c��(���イ����)�ꗢ(������)����A��(��������)����(�܂���)�ɂ���ЂĂ܂���(����)�Ȃ�B
�����͏�(���)�ӂ����Ƃ��A�ۊ��͂���ނ����Ƃ��B
��(����)�����ɔ�(����)���݂����͂��āA�n��(������)��(���܂���)���Ȃ�܂��Ɏ�(��)����B
�ۊ�(��������)��@�J�ɐ��{(������)���@�˂Ԃ̉ԁ@
���z(��������)��@��(��)�͂��ʂ�ā@�C��(����)���@
�@�@�@��(�����ꂢ)
�ۊ�(��������)��@����(��傤��)�����Ӂ@�_��(���݂܂�)�@�]��(����)
�(����)�̉�(��)��@�˔�(�Ƃ���)��~(����)�ā@�[��(�䂤������)�@
�@�@�@�݂̂̍��̏��l(�������)�@�Ꭸ(�Ă���)�@
���(���傤)�Ɂ@豔�(�݂���)�̑�(��)���݂�@
�g(�Ȃ�)�����ʁ@�_(����)�肠��Ă�@�݂����̑�(��)�@�]��
��c�̐l�X�Ƃ̌𗬂��y����ł��邤���ɁA��������������o���Ă��܂����B�悤�₭�����グ�Ă��ꂩ��i�ޖk�����̉_�߂��B�܂��܂���͒����B����ꡂ��ȓ��̂���v���ƐS�z�ŋC���d���B���ꍑ�̓s�A����܂ł͕S�O�\���Ƃ������B���H�O�ւ̈�A�l�̊ւ��z���A�z��̒n�ɓ����Ă܂��i��ł����B�����ĉz���̍��s�U�̊ւɓ�������B���̊ԁA������������B�����̂ƉJ���~��̂Ő_�o���Q���Ă��܂��A���a�ɋꂵ�߂�ꂽ�B����œ��ʏ����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ������B
������Z������̖�ɂ͎���
(�Ӗ�)���[�Ƃ������̂́A���̑O���̘Z���̖�ł����Ȃ�ƂȂ����N���N���ē��ʂȖ�Ɋ������B
�r�C�⍲�n�ɂ悱���ӓV��
(�Ӗ�)�V���̍r���g�������C�̌������ɍ��n����������B���̏�ɓV�̐삪�������Ă���Y��Ȍi�F���B
�@�@�@���z��H(��������)
��c(������)�̗]�g(�Ȃ���)�����d(����)�˂āA�k����(�ق��낭�ǂ�)�̉_�ɖ](�̂�)�ށAꡁX(�悤�悤)�̂����Ћ�(�ނ�)�������܂��߂ĉ���(����)�̕{(��)�܂ŕS����(�ЂႭ���イ��)�ƕ����B
�l(�˂�)�̊ւ������A�z��(������)�̒n�ɕ��s(�����)����(���炽��)�āA�z��(�������イ)�̍��s�U(�����Ԃ�)�̊�(����)�ɂ�����B
���̊�(����)���(�����̂�)�A����(���債��)�̘J(�낤)�ɐ_(����)���Ȃ�܂��A�a(��܂�)������Ă��Ƃ����邳���B
����(�ӂ݂Â�)��Z��(�ނ���)����(��)�̖�ɂ͎�(��)���@
�r�C(���炤�݂�)��@���n(����)�ɂ悱���Ӂ@�V��(���܂̂���)
�����͐e�s�m�E�q�s�m�E�����ǂ�E��Ԃ��ȂǂƂ����k����̓���đ̂���ꂽ�̂ŁA���������ĐQ�Ă����Ƃ���A�ӂ��܈ꖇ�ւ��Ăē��ɖʂ������̕�������A�Ⴂ���̐����������Ă���B��l����悤���B����ɔN�V�����j�̐�������B�����Ƃ��Ȃ��ɕ����Ă���ƁA���̓�l�̏��͉z��̍��V���Ƃ������̗V���Ȃ̂��B������u�����Q��v���낤�B�ɐ��Q��̂��ߎ�l�ɖ��f�Ŕ����o���Ă��āA���̊ւ܂Œj�������Ă����̂��B�������̌̋��֕Ԃ��莆�������Ă��̒j�ɑ����A������Ƃ����`���Ȃǂ����Ă���悤�������B���g�̊鏍�ɐg�𓊂��o���A�Z�܂����͂����肵�Ȃ����t�̖��̂悤�ɔg�ɖ|�M����A�V���ɐg�߂ėV���Ƃ��������܂����g�ɗ����Ԃ�A�q�Ɛ^���̂Ȃ��閈�̌_������āA���X�߂��d�˂�c�O���łǂ�Ȉ������Ƃ��������낤�B�����ɂ��s�^���B����Ȃ��Ƃ�b���Ă���̂������Q�������B���̒��o�����悤�Ƃ���ƁA���̓�l�̗V�����������ɘb�������Ă����B�u�s���悪�킩��Ȃ����͐S�ׂ����̂ł��B���܂�ɂ��m���ȂƂ��낪�Ȃ��A�߂����̂ł��B���V�l�Ƃ��Ď������ɏ�������Ă��������B���̌b�݂𒍂��ł��������B�����ɓ���@���������Ă��������v���������ė܂𗬂��̂��B�s���ł͂��邪�A���������킯�ɂ������Ȃ��B�u�������͂ق��ڂ��ŗ���������蒷���؍݂����肷��̂ł�(�ƂĂ��ꏏ�ɗ��͂ł��܂���)�B�����l���i�ޕ����ɂ��Ă����Ȃ����B��������Ζ����A�ɐ��ɓ����ł���ł��傤�B�����Ɛ_�͂���肭�������܂��v���������̂Ăďh���o�����A��͂�s���ł��炭�C�ɂ����������Ƃ�B
��ƂɗV�����˂��蔋�ƌ�
(�Ӗ�)�݂��ڂ炵���m�`�̎����Ɠ����h�ɁA�͂Ȃ₩�ȗV�������R�����킹���B���̏h�ɂ�т����炭�����A���������ƌ����Ƃ炵�Ă���B�Ȃ����������ŗV�������Ɏv���Ă���B
���̂���܂���\�ǂɌ��ƁA�\�ǂ͏����Ƃ߂��B
�@�@�@���s�U(�����Ԃ�)
����(���傤)�͐e���炸�q���炸�E�����ǂ�E���(���܂���)���Ȃǂ��Ӗk����(�ق���������)�̓(�Ȃ�)��(��)���Ă���ׂ͂�A��(�܂���)��(��)���悹�ě�(��)����ɁA���(�ЂƂ�)�u(�ւ�)�ĂĖ�(������)�̕�(����)�Ɏ�(�킩)�����̐���l(�ӂ���)����ƕ�����B
�N�V(�Ƃ�����)����j(���̂�)�̐�����(�܂���)�ĕ���(���̂�����)������A�z��(������)�̍��V��(�ɂ�����)�Ƃ��ӏ�(�Ƃ���)�̗V��(�䂤����)�Ȃ肵�B
�ɐ�(����)�Q�{(����)����ƂāA���̊�(����)�܂Œj(���̂�)�̑�(����)��āA�����͌Ë�(�ӂ邳��)�ɂ��ւ���(�ӂ�)�������߂āA�͂��Ȃ����`(���ƂÂ�)�Ȃǂ����Ȃ�B
�u���Q(����Ȃ�)�̂悷���(�݂���)�ɐg(��)���͂ӂ炩���A���܂̂��̐�(��)�������܂�����(����)��āA��(����)�߂Ȃ��_(����)��A���X(�Ђ�)�̋ƈ�(��������)�����ɂ��Ȃ��v�ƁA���̂��ӂ������Q��(�˂���)�āA����������(���т���)�ɁA��X(�����)�ɂނ��ЂāA�u�s�q(�䂭��)����ʗ��H(���т�)�̂����A���܂�o��(���ڂ�)�Ȃ���(����)�����ׂ͂�A����������ɂ����(����)�������Ђׂ͂��B��(�����)�̏�̌��(����Ȃ���)�ɁA�厜(������)�̂߂��݂�����Č���(��������)���������܂ցv�Ɵ�(�Ȃ݂�)��(��)�Ƃ��B
�s��(�ӂт�)�̂��Ƃɂׂ͂͂�ǂ��A�u��X(�����)�͏��X(�Ƃ���ǂ���)�ɂĂƂǂ܂��(����)���ق��B�����l�̍s(��)���ɂ܂����čs(��)���ׂ��B�_��(����߂�)�̉���(����)���Ȃ炸���Ȃ���ׂ��v�Ƃ��Ў�(����)�ďo(��)�łA��(����)�ꂳ���炭��܂��肯�炵�B
���(�ЂƂ�)�Ɂ@�V��(�䂤����)���˂���@��(�͂�)�ƌ�
�]��(����)�ɂ�����A��(����)�Ƃǂ߂ׂ͂�B
�����l�\�������Ƃ����̂��낤���A������Ȃ��قǂ̐��n���āA�ߌÂƂ����Y�ɏo���B�u�S�Ă̓��Q�v�Ɖr�܂��̖��̒n���߂��̂ŁA�t�ł͂Ȃ������H�̕��͋C���܂��������낤�A�K�˂悤�Ƃ������ƂŐl�ɓ����B�u��������ܗ��A��`���ɐi�݁A�������̎R�A�ɓ������Ƃ���ł��B���t�̓ω������܂薳���Ƃ��낾����A�u���̂���˂̈��䂦�v�ƌÉ̂ɂ���悤�ȁA���̏h�������߂Ă����l�͂Ȃ��ł��傤�v�Ƌ�������āA����̍��ɓ���B
�킹�̍��╪���E�͗L��C
(�Ӗ�)�k���̖L���ȑ���̍���ɕ�܂�ĉ���̍��ɓ����Ă����ƁA�E���ɂ͉̖��Ƃ��Ēm����y�L��C�z���L�����Ă���B
�@�@�@���z���H(�������イ��)
����(�����)�l�\������(�����イ�͂�����)�Ƃ���A��(����)����ʐ���킽��āA�ߌ�(�Ȃ�)�Ƃ��ӉY(����)�ɏo(��)�ÁB
�S��(����)�̓��Q(�ӂ��Ȃ�)�͏t�Ȃ炸�Ƃ��A���H(�͂���)�̈�(����)��Ƃӂׂ����̂��Ɛl�ɐq(����)�ʂ�A�u������ܗ�(����)�����`(�Â�)�Ђ��āA�ނ��ӂ̎R�A(��܂���)�ɂ���A�(����)�̓�(�Ƃ�)�Ԃ��������Ȃ�A�b(����)�̈��(�ЂƂ�)�̏h(���)�������̂���܂��v�Ƃ��Ђ��ǂ���āA����(����)�̍��ɓ�(��)��B
�킹�̍�(��)��@����(�킯����)�E�́@�L��C(���肻����)
�K�̉ԎR�E���肩�炪�J���z���āA����ɒ������͎̂�����\�ܓ��ł������B����ɂ͑�ォ��s�������Ă��鉽���Ƃ������l�����āA���h���邱�ƂƂȂ����B��Ƃ������͔̂o�~�ɂ�������ł���]��������ق畷�����Ă��āA���Ԃł͒m��l���������̂����A���N�̓~�A���������Ƃ������ƂŁA���̌Z���ǑP�̋����J�����B
�˂������䋃���͏H�̕�
(�Ӗ�)���A�N�̒�(��)��ڂ̑O�ɂ��Ă��邪�A���O�̌N���v���đ吺�ŋ����Ă���B������𐁂�������H���̂悤�Ɍ�������т����܂Ȃ̂��B�˂�A���̌Ăт����ɓ����Ă���I
���鑐���Ɉē����ꂽ���ɁA
�H�����薈�ɂނ���Z�֎q
(�Ӗ�)�Z��֎q�Ƃ����H��ł��ĂȂ����������B�����ɂ��H�̗����������ӂ��B�݂Ȃ���A���ꂼ��Z��֎q���ނ�������Ȃ��ł����B���̎��ɂ��H�̗������������Ă��������B
��������Ⴖ������
���������Ɠ��͓�ʂ������̕�
(�Ӗ�)�����H���Ƃ����̂ɑ��z�̌��͂���Ȃ��ƊW�Ȃ��ӂ��ɂ��������ƏƂ炵�Ă���B���������͂����H�̗�������ттĂ���B
�@�@�@������(���Ȃ���)
�K(��)�̉ԎR�E���肩�炪�J�������āA����(���Ȃ���)�͎������̌ܓ�(����)�Ȃ�B
�����ɑ��(��������)��肩��ӏ��l(�������)����(������)�Ƃ��ӎ�(����)����B
���ꂪ���h(��債�キ)���Ƃ��ɂ��B
���(�������傤)�Ƃ��ӂ��̂́A���̓��ɂ����閼�̂ق̂ڂ̕����āA��(��)�ɒm�l(����Ђ�)���ׂ͂肵�ɁA���N(����)�̓~����(��������)������ƂāA���̌Z�ǑP(������)�����您���ɁA�@
��(��)����(����)���@��(�킪)��(�Ȃ�)���́@�H�̕�
���鑐��(��������)�ɂ����Ȃ͂�ā@
�H��(����)���@�育�Ƃɂނ���@�Z(����)�֎q(�Ȃ���)
�r����(�Ƃ��イ����)
���������Ɓ@���͂�Ȃ����@�H�̕�
���ق炵�����⏬���������T��
(�Ӗ�)�u�����v�Ƃ������炵�����O�̂��̒n�ɁA����X�X�L����炵�ďH�̕��������Ă���B
��������̒n�ŁA���c�̐_�ЂɎQ�w�����B�����ɂ͐ē��ʓ������̊��Ƌт̒����̐�[������̂��B���̐́A�������܂������ɑ����Ă������A�`�������玒�������̂��Ƃ��B�Ȃ�قǁA���ʂ̕����̂��̂Ƃ͈���Ă���B�ڔ݂��琁�Ԃ��܂ŋe�����̖͗l��A�����ɏ������U��߁A�����ɂ͌L�`���ł��Ă���B�������������ɂ�����A�ؑ]�`�����폟�F��̊��ɓY���Ă��̎Ђɂ��߂������A������Y���������̎g�����������ƂȂǁA�����̂��Ƃ��܂�Ŗڂ̑O�ɕ����Ԃ悤�ɁA�_�Ђ̉��N�ɏ�����Ă���B
�ނ����ȍb�̉��̂��肬�肷
(�Ӗ�)�ɂ܂������Ƃ��B�E�܂����U���������̖��c�͂��������ɂ͖����A���ԂƂ̉��ɂ͂��� �R�I���M�����Ă���B
�@�@�@������(���܂�)
����(���܂�)�Ƃ��ӏ�(�Ƃ���)�ɂā@
���ق炵���@���⏬��(���܂�)�ӂ��@��(�͂�)������
���̏�(�Ƃ���)���c(����)�̐_��(����)�Ɍw(������)�B
�^��(���˂���)���b(���Ԃ�)�E��(�ɂ���)�̐�(����)����B
����(���̂ނ���)����(����)�ɑ�(���傭)�������A�`����(�悵�Ƃ�����)��肽�܂͂点���܂ӂƂ���B
���ɂ����m(�Ђ炳�ނ炢)�̂��̂ɂ��炸�B
�ڔ�(�܂т���)��萁��(�ӂ�����)���܂ŁA�e����(�������炭��)�̂ق���̋�(������)������߁A����(��������)�ɌL�`(���킪��)��(��)������B
�^��(���˂���)����(��������)�̌�(�̂�)�A�ؑ]�`��(�����悵�Ȃ�)���(���傤)�ɂ��ւĂ��̎�(�₵��)�ɂ��߂��ׂ͂�悵�A���(�Ђ���)�̎��Y(���낤)���g(����)�������Ƃǂ��A�܂̂����艏�L(����)�ɂ݂�����B
�ނ����ȁ@�b(���Ԃ�)�̉��́@���肬�肷
�R������ɍs����������A�������x��w�ɂ��ĕ���ł����B���̎R�ۂɊω���������B�ԎR�@�c�������O�\�O�����̏�������Ƃ��ɂȂ��Č�A�l�X���~���傫�ȐS(�厜���)���������ϐ�����F�̑������u����āA�u�ߒJ�v�Ɩ��t����ꂽ�Ƃ������Ƃ��B�O�\�O�����̍ŏ��̎D���ł���ߒq�ƍŊ��̎D���ł���J������A���ꂼ��ꎞ��������Ƃ������Ƃ��B�������`�̐����܂��܂ɗ������сA�Ï����A�����ׂ��Ă���B���Ԃ��̏����Ȃ�������̏�Ɍ��ĂĂ���A�i�F�̂悢�ꏊ�ł���B
�ΎR�̐�蔒���H�̕�
(�Ӗ�)�ߒJ���̋����ɂ͂�������̔������邪�A�����蔒������Ɋ�����̂�����������H�̕����B�����ɂ͂��������ȋ�C���������߂Ă���B
�@�@�@���ߒJ(�Ȃ�)
�R��(��܂Ȃ�)�̉���(���ł�)�ɍs(��)���قǁA��������(����˂�����)��(����)�ɂ݂Ȃ��Ă���ށB
���̎R��(��܂���)�Ɋω���(����̂�ǂ�)����B
�ԎR(������)�̖@�c(�ق�����)�O�\�O��(���イ����)�̏���(�����ꂢ)�Ƃ��������܂ЂČ�(�̂�)�A�厜���(������������)�̑�(����)�����u(����)�����܂ЂāA�ߒJ(�Ȃ�)�Ɩ��t(�ȂÂ�)���܂ӂƂȂ�B
�ߒq(�Ȃ�)�E�J�g(���ɂ���)�̓�(�ɂ�)���킩���ׂ͂肵�Ƃ��B
���(������)���܂��܂ɁA�Ï�(�����傤)�A(����)�Ȃ�ׂāA��(����)�Ԃ��̏���(���傤�ǂ�)��̏�ɑ�(��)�肩���āA�ꏟ(���サ�傤)�̓y�n�Ȃ�B
�ΎR(�������)�́@��蔒���@�H�̕�
�R������ɓ���B���̌��p�́A�L�n����Ɏ����Ƃ����B
�R����e�͂�����ʓ��̓�
(�Ӗ�)�e�̘I������Ŏ��S�܂Ő������Ƃ����e�����̓`�������邪�A�����R���ł͋e�̗͂ɂ�炸�Ƃ��A���̓��̍�����z���Ă���Ə\���ɒ����̂����߂����肻�����B
��l�ɂ�������̂͋v�ĔV���Ƃ����āA���܂����N�ł���B���̕��͔o�~�������Ȃސl���B���s�̈����厺���܂��Ⴂ���A�����ɗ������o�~�̐ȂŒp�����������Ƃ�����B�厺�͂��̌o�����˂ɂ��āA���s�ɋA���ď��i�哿�ɓ��債�A���ɂ͐��ɒm���闧�h�Ȕo�~�t�ƂȂ����B�������オ��������A�厺��(�����N�����Ă��ꂽ���̒n�Ɋ��ӂ���)�o�~�̓Y�헿���Ȃ������Ƃ����B����Șb�������̂̂��ƂƂȂ��Ă��܂����B�\�ǂ͕����킸����āA�ɐ��̒����Ƃ����Ƃ���ɐe�ʂ�����̂ŁA�����𗊂��Ĉꑫ��ɏo�������B
�s�s�Ă��ӂꕚ�Ƃ����̌��@�\��
(�Ӗ�)���̂܂܍s����Ƃ���܂ōs���āA�Ŋ��͔��̌��œ|��A���̓r��Ŏ��̂��B���ꂭ�炢�́A���ɂ�����u�ł���B
�s���҂̔߂��݁A�c��҂̖��O���A��H�Ŕ��ł����������ꗣ��ɂȂ��āA�_�̊Ԃɍs����������悤�Ȃ��̂ł���B��������r�B
�������⏑�t������}�̘I
(�Ӗ�)�����Ɨ��𑱂��Ă����\�ǂƂ͂����ŕʂ�A���ꂩ��͈�l�����s�����ƂɂȂ�B�}�ɏ������u���s��l�v�̎����������Ƃɂ��悤�B�}�ɂ�����I�͏H�̘I���A����Ƃ����̗܂��B
�@�@�@���R������(��܂Ȃ�����)
����(���ł�)�ɗ�(�悭)���B
���̌�(����)�L��(���肠��)�ɂ��Ƃ��ӁB
�R��(��܂Ȃ�)��@�e(����)�͂�����ʁ@��(��)�̓�(�ɂ���)
���邶�Ƃ�����̂͋v�ĔV��(���߂̂���)�ƂĂ��܂�����(���傤�ǂ�)�Ȃ�B
���ꂪ�����~(�͂�����)���D(����)�݁A��(�炭)�̒厺(�Ă�����)��y(���Ⴍ�͂�)�̂ނ��������ɗ����肵����A����(�ӂ���)�ɐJ(�͂���)���߂��āA���ɋA(������)�Ē哿(�Ă��Ƃ�)�̖�l(����)�ƂȂĐ�(��)�ɂ����B
����(�����݂傤)�̌�(�̂�)�A���̈ꑺ(��������)����(�͂�)�̗�(��傤)��(����)���Ƃ��ӁB
���X(���܂���)�ނ�����(������)�Ƃ͂Ȃ�ʁB
����̏鉺���y�吹���z�̏�O�A�S�����Ƃ������ɔ��܂�B���܂�����̍��ł���B
�\�ǂ��O�̔ӂ��̎��ɔ��܂�A���c���Ă����B
�I���H�����₤��̎R
(�Ӗ�)���R�𐁂��҂����H���̉�����Ӓ������āA����Ȃ���ł�������B��l���̎₵�������g�ɂ��݂�B
���܂ňꏏ�ɗ����Ă����̂���ӂł������̂́A�痢���u�Ă�悤�ɗ҂����S�ׂ��B�����H�����Ȃ���m�̏h�ɂɔ��߂Ă�������B�閾���߂��Ȃ�ƁA�njo�̐������ݓn��A���}�̏������ĐH���̎��Ԃ�m�点��̂ŐH��(�����ǂ�)�ɓ������B�����͉z�O�̍��ɉz�������ł���B���킽�������C�����ŐH������o��ƁA�Ⴂ�m���������⌥���������Ď��̐Βi�̂Ƃ���܂Ō������Ă����B
���傤�ǒ�ɖ��̗t���U���Ă����̂ŁA
��|�ďo�⎛�ɎU��
(�Ӗ�)���̋����ɖ��̗t���U��~���Ă���B���ɔ��߂Ă����������ɁA�ق����ő|���Ă���o�����悤��B
���܂��̂܂܂��킽���������������B���Ȃ���]�T���Ȃ��������ςȂ����B����Ɖz�O�̋��A�g��̓��]�őD�ɏ���āA���z�̏���K�˂��B
�I�����ɔg���͂�����
�������ꂽ�鎬�z�̏� ���s
(�Ӗ�)��ʂ��ł���g�����̖ɂ��Ԃ����āA���̏��ɔg�̎������������Ă���B����Ɍ������L���L�����āA�܂�Ō��̎��̂悤���B
���̈��̒��ɁA���ׂĂ̌i�F�͉r�݂��܂�Ă���B�����ꌾ�t����������̂�����A�ܖ{����w�ɂ���Ȃ�������{��t��������悤�Ȃ��̂��B
�@�@�@���S����
�]��(����)�͕�(�͂�)��a(���)�āA�ɐ�(����)�̍�����(�Ȃ�����)�Ƃ��ӏ�(�Ƃ���)�ɂ䂩�肠��A�旧(��������)�čs(��)���ɁA
�s�s(�䂫�䂫)�ā@���ӂꕚ(�ӂ�)�Ɓ@����(�͂�)�̌��@�]��
�Ə��u(��������)����B
�s(��)�����̂̔�(����)���݁A�c(�̂�)����̂̂���݁A����(������)�̂킩��ĉ_�ɂ܂�ӂ����Ƃ��B
����܂��A
��������@���t(������)��(��)����@�}(����)�̘I(��)
�吹��(�������傤��)�̏�O(���傤����)�A�S����(���傤��)�Ƃ��ӎ��ɂƂ܂�B
�Ȃ�����(����)�̒n�Ȃ�B
�]��(����)���O�̖邱�̎��ɔ�(�Ƃ܂�)�āA
�I��(���������)�@�H��(��������)������@����̎R
�Ǝc(�̂�)���B
���(������)�̊u(�ւ�)�āA�痢�ɓ����B
�����H��(��������)���ďO��(�����傤)�ɂӂ��A��(����)�ڂ̂̋��(����)���A�njo(�ǂ��傤)�����ނ܂܂ɁA����(���傤��)��(�Ȃ�)�ĐH��(�����ǂ�)�ɓ�(��)��B
�����͉z�O(��������)�̍��ւƁA�S����(��������)�ɂ��ē���(�ǂ���)�ɉ�����A��(�킩)���m(����)�ǂ����E��(������)���������A�K(�����͂�)�̂��Ƃ܂Œ�(����)������B
�ܐ�(����ӂ�)�뒆(�Ă����イ)�̖�(��Ȃ�)�U(��)��A�@
��(�ɂ�)�|(�͂�)�ā@�o(��)�ł⎛�Ɂ@�U(����)��(��Ȃ�)
�Ƃ肠�ւʂ��܂��đ���(��炶)�Ȃ��珑(����)��(��)�B
�@�@�@�����z�̏�(���������̂܂�)
�z�O(��������)�̋�(������)�A�g��(�悵����)�̓��](���肦)���M�ɞ�(������)���Ď��z(��������)�̏���q(����)�ʁB
�I��(���������)��(���炵)�ɔg(�Ȃ�)���͂����Č������ꂽ�鎬�z�̏��@���s(�������傤)
���̈��(��������)�ɂĐ��i(������)�s(��)����B
�����ꙟ(�����ׂ�)����(���키)����̂́A���p(�ނ悤��)�̎w��(����)�邪���Ƃ��B
�ۉ��̓V�����̒��V�͌Â��m�l������K�˂��B�܂��A����̖k�}�Ƃ������̂�������Ƃ���������Ƃ����A�Ƃ��Ƃ������܂ŕ炢���Ă��Ă��ꂽ�B���̏ꂻ�̏�̔������i�F����������������A���X�͋�̈Ӑ}��������Ă��ꂽ�B���̖k�}�Ƃ������ł��ʂꂾ�B
������������]�g��
(�Ӗ�)����̖k�}�Ƃ��炭���s���Ă������A���悢�您�ʂꂾ�B���������������Ƃ߂Ă�����������悤�ɁA�܂��Ă���H�ɂȂ��Đ�����܂��悤�ɁA����͐S�ɂޕʂ�Ȃ̂��B
�\���R�ɓ����āA�i�����ɂ��Q�肷��B�����T�t���J��������B���s����痢���u�ĂĂ���ȎR���ɏC�s�̏���������̂��A�T�t�̑������l���������Ă̂��Ƃ��������B
�@�@�@���V�����E�i����(�Ă��イ���E�����ւ���)
�ۉ�(�܂邨��)�V����(�Ă��イ��)�̒��V(���傤�낤)�A�Â���(���Ȃ�)����ΐq(����)�ʁB
�܂�����̖k�}(�ق���)�Ƃ��ӂ��́A���肻�߂Ɍ���(�݂���)��āA���̂Ƃ���܂ł����З�����B
�Ƃ���ǂ���̕��i(�ӂ�����)��(����)�����v�ЂÂ��āA�ܐ�(����ӂ�)���͂�Ȃ���(������)�ȂǕ�����B
�����łɕ�(�킩��)�ɖ](�̂�)�݂āA�@
����(���̂���)�ā@��(������)��(��)�������@�Ȃ��肩��
�\��(���������傤)�R�ɓ�(��)��ĉi����(�����ւ���)���(�炢)���B
�����T�t(�ǂ�����)�̌䎛(�݂Ă�)�Ȃ�B
�M�@(�ق���)�痢(�����)���(����)�āA������R�A(��܂���)�ɐ�(����)���̂������܂ӂ��A�M(�Ƃ���)����ւ���Ƃ���B
����܂ł͎O���قǂȂ̂ŁA�[�т����܂��Ă���o���Ƃ���A�[���̓��Ȃ̂Ŏv���悤�ɐi�߂Ȃ������B���̒n�ɂ͓��قƂ������m�̔o�l������B���̔N���������A�]�˂ɗ��Ď���K�˂Ă��ꂽ�B�����\�N�قǐ̂̂��Ƃ��B�ǂꂾ���N����Ă邾�낤���A������������S���Ȃ��Ă��邩������ʂƐl�ɐq�˂�ƁA���܂������ŁA�����������C���Ƌ����Ă��ꂽ�B�����̂�����ƈ��������ɂ݂��ڂ炵�����Ƃ�����A�[��E�ւ��܂��͂��������āA�{���E�͂͂����Ŕ����B��Ă���B�u���Ă͂��̉Ƃ��ȁv�Ɩ��@���A�݂��ڂ炵���Ȃ�̏����o�Ă��āA�u�ǂ����炢���������������C�s�̂��V�l�ł����B��l�͂��̂�����^�Ƃ������̂̏��ɍs���Ă��܂��B�����p���������������K�˂��������v�ƌ����B���ق̍ȂɈႢ�Ȃ��B�̕���̒��ɂ���ȕ�����ʂ��������Ȃ��Ǝv���A�����ɂ������K�˂Ă����Ɠ��قɉ���B���ق̉Ƃɓ�Ӕ��܂��āA�����Œm����։�̍`�֗��������B���ق�������ɗ��Ă��ꂽ�B�������ǂ��������ɂ܂���グ�āA�y�������ɓ��ē��ɗ����Ă��ꂽ�B
�@�@�@������(�ӂ���)
����(�ӂ���)�͎O��(�����)�v(����)�Ȃ�A�[��(�䂤�߂�)�������߂ďo(��)�Â�ɁA��������̓����ǂ��ǂ��B
�����ɓ���(�Ƃ�����)�Ƃ��ӌÂ��B�m(����)����B
���Â�̔N�ɂ��]��(����)�ɗ�����Ă��q(����)�ʁB
�y(�͂邩)�\(��)�Ƃ����܂�Ȃ�B
�����ɘV(����)����ڂЂĂ���ɂ�A�͂���(����)����ɂ�Ɛl�ɐq(����)�˂ׂ͂�A���܂�����(����߂�)���Ă��������Ƌ�(����)��B
�s��(�����イ)�Ђ����Ɉ���(�Ђ�����)�āA���₵�̏���(������)�ɗ[��(�䂤����)�E�ւ��܂̂͂�������āA�{��(�����Ƃ�)�͖͂X(�͂͂���)�Ɍ�(��)�ڂ����������B
���Ă͂��̂����ɂ����Ɩ�(����)��J(������)�A��(���)�����Ȃ鏗�̏o(��)�łāA�u���Â����킽�肽�܂ӓ��S(�ǂ�����)�̌�V(���ڂ�)�ɂ�B
���邶�͂��̂����艽�����Ƃ��ӂ��̂̕�(����)�ɍs(�䂫)�ʁB
�����p����ΐq(����)�˂��܂ցv�Ƃ��ӁB
���ꂪ��(��)�Ȃ�ׂ��Ƃ����B
�ނ�����������ɂ��������镗��(�ӂ���)�ׂ͂͂�ƁA�₪�Đq(����)�˂��ЂāA���̉Ƃɓ��(�ӂ���)�Ƃ܂�āA����(�߂�����)�͂邪�݂̂ȂƂɂƂ��ї�(����)�B
����(�Ƃ�����)���Ƃ��ɑ�(����)���ƁA��(����)�����������炰�āA���̎}��(������)�Ƃ����ꗧ(����)�B
�Ƃ��Ƃ��������Ԃ������Ȃ��Ȃ�A������Ĕ�߂��Ԃ��p������킵���B�����ނÂ̋���n��Ƌʍ]���b�͕�����点�Ă���B��̊ւ��߂��āA���������z����ƁA�ؑ]�`���䂩��������邪����A�A��R�Ɋ�̏������A�\�l���̗[���A�։�̒Âŏh���Ƃ����B���̖�̌��͓��Ɍ����������B�u�����̖������ȑf���炵�������������ł��傤���v�Ƃ����ƁA�u�z�H�ł͖����̖邪����邩�܂邩�A�\���̂��Ȃ����̂ł��v�Ǝ�l�Ɏ������߂��A�C��_�Ђɖ�Q�����B�����V�c�����܂肵�Ă���B�����͐_�X�������͋C�ɖ����Ă��āA���̏��̊ԂɌ��̌����R��Ă���B�_�O�̔����͑���~���l�߂��悤���B�́A�V�s�̏�l���A�傫�Ȋ肢���v��������A���瑐������A�y���^��ł��āA���n�ɂ���𗬂��A�l��������悤�ɐ������ꂽ�B�����猻�݁A�Q�w�ɍs��������̂ɑS������Ȃ��B���̐�Ⴊ���ł������ꂸ�A��X�̏�l���_�O�ɍ������^�тɂȂ�A�s���R�Ȃ��Q�w�ł���悤�ɂ��Ă���̂��B�u�����V�s�̍������ƌ����Ă���܂��v�ƒ���͌�����B
�������V�s�̂��Ă鍻�̏�
(�Ӗ�)���̐́A�V�s��l���C�䖾�_�ւ̎Q�w���y�ɂ��邽�߂ɉ^�Ƃ��������B���̔����̏�ɐ��炩�Ȍ����P���Ă���B���̕\�ʂɌ������˂��Ă��ꂢ���B���炩�Ȓ��߂��B
�\�ܓ��A����̌��t�ǂ���A�J���~�����B
������k�����a��Ȃ�
(�Ӗ�)����͒��H�̖��������҂��Ă����̂ɁA�����ɂ��J�ɂȂ��Ă��܂����B�{���ɖk���̓V�C�͕ς��₷�����̂Ȃ̂��ȁB
�@�@�@���։�(�邪)
�Q(�悤�悤)����(�����)����(����)������āA���(�Ђ�)����(����)����͂�B
�����ނÂ̋����킽��āA�ʍ](���܂�)���b(����)�͕�(��)�ɏo(��)�łɂ���B
��(��������)�̊�(����)����(����)�ē�����(��̂��Ƃ���)���z(����)��A��(�Ђ���)����(���傤)�A���ւ��܂ɏ���(�͂���)���āA�\�l���̗[����邪�̒�(��)�ɏh(���)�����ƂށB
���̖�A�����Ƃɐ�(��)�ꂽ��B
�u�����̖����������ׂ��ɂ�v�Ƃ��ւA�u�z�H(������)�̂Ȃ�ЁA�Ȃ�����(�߂���)�̉A��(����)�͂��肪�����v�ƁA���邶�Ɏ������߂��āA�����̖��_(�݂傤����)�ɖ�Q(�₳��)���B
�����V�c(���イ�����Ă�̂�)�̌�_(���т傤)�Ȃ�B
�Г�(����Ƃ�)�_(����)���тāA���̖�(��)�̊�(��)�Ɍ��̂����(�͂���)����A���܂ւ̔���(�͂���)��(����)��~(����)�邪���Ƃ��B
�u����(���̂ނ���)�V�s��(�䂬�傤�ɂ�)�̏�l(���傤�ɂ�)�A��蔭�N(��������ق���)�̂��Ƃ���āA�݂Â��瑐����(����)�A�y��(�ǂ���)����(�ɂ�)�ЁA�D��(�ł��Ă�)�����͂����āA�Q�w(����)����(�����炢)�̔�(�킸�炢)�Ȃ��B
�×�(���ꂢ)���ɂ������B
�_�O(����)�ɐ^��(�܂���)����(�ɂ�)�Ђ��܂ӁB
�����V�s(�䂬�傤)�̍���(���Ȃ���)�Ƃ������ׂ͂�v�ƁA����(�Ă�����)�̂����肯��B
����(����)���@�V�s�̂��Ă�@���̏�@
�\�ܓ��A����̎�(���Ƃ�)�ɂ����͂��J�~(���߂ӂ�)�B
����(�߂�����)��@�k��(�ق�����)���a(�т��)�@�����߂Ȃ�
�\�Z���A���ꂽ�̂Ő��s�̉̂ɂ���u�܂��ق̏��L�v���E�����ƊC��������M�𑖂点�A�F�̕l��ڎw�����B�V���Ȃɂ����Ƃ����҂��ٓ�������̓������|����S�ׂ��ɗp�ӂ��Ă���A���l�𑽂��ē��̂��߂ɏM�ɏ悹�Ă��ꂽ�B�ǂ����������̂ŕ��ʂ�葁���F�̕l�ɓ��������B�l�ɂ͂킸���ɋ��t�̏��Ƃ����邾�����B�̂����Ȗ@�؎�������A�����Œ������݁A�������߂Ȃǂ����B���̕l�̗[���̎₵���͊i�ʐS�ɔ�����̂������B
�₵����{���ɂ�������l�̏H
(�Ӗ�)���������z�����ꂽ�{���͗҂����ꏊ�Ƃ��Ēm���邪�A������̕l�͐{�����͂邩�ɗ҂������Ƃ�B
�g�̊Ԃ⏬�L�ɂ܂��锋�̐o
(�Ӗ�)�g�ł��ۂ̔g�̊Ԃ��悭����ƁA���L�ɍ������ĐԂ����̉Ԃ��o�̂悤�ɎU���Ă���B
�@�@�@����̕l(����̂͂�)
�\�Z���A��(����)��(�͂�)����A�܂��ق̏��L(������)�Ђ�͂�Ǝ�̕l(����̂͂�)�ɏM��(��)���B
�C��(�������傤)����(������)����B
�V��(�Ă��)���^(�Ȃɂ���)�Ƃ��ӂ��́A�j��(��育)�E���|��(������)�Ȃǂ��܂₩�ɂ������߂����A�����ׂ��܂��M�ɂƂ�̂��āA�Ǖ�(��������)���̂܂ɐ�(��)����(��)���ʁB
�l(�͂�)�͂�Â��Ȃ�C�m(����)�̏���(������)�ɂāA��(���)�����@�Ԏ�(�ق����ł�)����B
�����ɒ�����(�̂�)�A�����������߂āA�[����̂��т�����(����)�Ɋ�(����)����B
��(����)������@�{��(����)�ɂ�������@�l(�͂�)�̏H�@
�g�̊�(��)��@���L�ɂ܂���@��(�͂�)�̐o(����)
���̓��̂���܂��A����(�Ƃ�����)�ɕM(�ӂ�)���Ƃ点�Ď��Ɏc(�̂���)�B
�H�ʂ����̍`�܂Ō}���ɏo�Ă��āA���Z�̍��֓��s���Ă��ꂽ�B�n�ɏ���đ�_�̏��ɓ���ƁA�\�ǂ��ɐ����痈�č������A�z�l���n�����Ă��āA�@�s�̉ƂɏW�������B�O��q�E�t�����q�A���̑��̐e�����l�X������K�₵�āA�܂�Ŏ���őh�����l�ɉ�悤�ɁA��肢������Ă��ꂽ�肵���B���̔����܂����Ȃ��܂܂ɁA�㌎�Z���ɂȂ����̂ŁA�ɐ��̑J�{��q�ނ��߁A�܂��M�ɏ���ė����̂������B
���̂ӂ��݂ɂ킩��s�H��
(�Ӗ�)���ꂪ�������̂ӂ��Ɛg���ʂ�Ă����悤�ɁA���ʂ�̎��������B���͓Y�֗������Ă����B�����H���߂����낤�Ƃ��Ă���B
�@�@�@����_(��������)
�I��(���)�����݂̂ȂƂ܂ŏo(��)�łނ��ЂāA�݂̂̍��ւƔ�(�Ƃ���)�ӁB
��(����)�ɂ��������đ�_(��������)�̏�(���傤)�ɓ�(��)��A�]��(����)���ɐ�(����)��藈���荇���A�z�l(������)���n���Ƃ��āA�@�s(���傱��)���Ƃɓ�(��)��W(����)�܂�B
�O��q(����)�E�t�����q(���������ӂ�)�A���̂ق����������l�X����ƂԂ�ЂāA�h��(������)�̂��̂ɉ�ӂ����Ƃ��A���x(��낱)�сA�������͂�B
��(����)�̂��̂������A���܂���܂���ɁA����(�Ȃ���)�Z��(�ނ���)�ɂȂ�A�ɐ�(����)�̑J�{(����)�����܂�ƁA�܂��M�ɂ̂�āA�@
��(�͂܂���)�́@�ӂ��݂ɂ킩��@�s(��)���H��
�͂�Ę̂�������A�͋����̂��A���ア�������A�u���̍ד��v��ǂ�ł����Ǝv�킸�����オ���Ċ����Ɏ��@������A�܂��������܂܊����ɋ����M���Ȃ����肷��B������x�͖������Ă��̂悤�ȗ������������̂��Ǝv������������A�܂����鎞�͍������܂܂��̌i�F��z�����Ė��������肷��B�����������l�X�Ȋ������A�܂�Ől���̗܂��������ċʂƂȂ����悤�ɁA���̗͂͂ɂ���Č`�ɂ����̂��B�u���̍ד��v�̗��́A�Ȃ�Ƒf���炵�����Ƃ��B�܂��m�Ԃ̍˔\�̂Ȃ�ƗD��Ă��邱�Ƃ��B�����Q���킵�����ƂɁA���̂悤�ɍ˔\����m�Ԃ����N�ɂ͂߂��܂ꂸ�A����킰�Ȃ��ƂŁA���тɂ͂������̂������Ă����Ă���B
���\���N���� �f�����邷�@
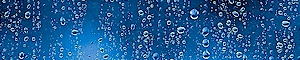 �@
�@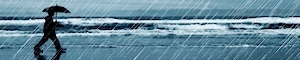 �@
�@
�Ƃ��낪�����ł��Ȃ��c����̎H��(����)�̌ꌹ�ƁA�g�����ɂ��Ă��b���܂��傤�B
�܌��ُ̈̂̂����炢�u�H���v�̂ق��ɂ�����Ăѕ��́c�H
�������͋���̌Ăі����A�܌��́u�����v�ƌĂԂƏK���܂����ˁB�����ł́u�H���v�Ə����Ƃ��K���܂����B�����Ă�����A���܂�g���Ă��܂��u���c��(���Ȃ��Â�)�v�Ƃ����ُ̂����邱�Ƃ������m�ł��傤���H
�u���c��(���Ȃ��Â�)�v�́A���̕����ǂ���Ɂw�c�A�����n�߂錎�x��R���Ƃ��Ă��܂��B�����āu�H��(����)�v�́u���Ȃ��Â��v���]���āu�����v�ƂȂ����Ƃ������ƁA�k��̂��Ƃ��Ì�Łu���v�ƌ������߁u���A���錎�v�Ƃ��āu�����v�Ƃ����������܂�A�w�_�ɂ�������x�Ƃ����Ӗ����������u�H�v�����Ă��āu�H���v�ƂȂ����Ƃ������Ă��܂��B �܂��A���ɍs���̂ɗǂ������ł��������Ƃ���u�K��(�����Â�)�v�A�k(������)�̉Ԃ��炭���Ƃ���u�k��(�����ȂÂ�)�v�Ƃ����ُ̂�����܂��B
�k�͒����̕��l�ł͋g�˖͗l(�������傤���悤)�ƌ����A���j���ɑ��������Ԃł��B������ɂ��Ă��A�c�A�����s�����ł��邱�ƁB���̈�͐_�l�ւ̂��������̂ł��邱�ƁB������j���Ӗ������߂����t���g���Ă��邱�Ƃ����������܂��ˁB
�����āA����̌܌��́w�~�̎����n������x�ł�����܂��c�B
���~�̎����n������c�Ɓu�܌�����v�u�܌��J�v�̊W
�ł́A�u�܌�����v�Ɓu�܌��J�v�͂��A�ǂ��g���܂��傤���H
�{���͋���̌܌��̌��t�ł��B���Ō����ƁA6���`7���ɂ�����܂��̂ŁA���́u�~�J(��)�v�̍��̌��t�ƂȂ�܂��B�܂�A�܌����ꁁ�~�J����A�܌��J���~�J�̉J�c�Ƃ����Ӗ�������Ƃ����N�Z���m�ł��B
�Ⴆ�A�܌�����́u(1)���݂���̐���ԁB�~�J�̐���ԁB(2)5���̋�̐���킽�邱�Ɓv(�L����)�u(1)�܌��J(���݂���)�̐���ԁB���B(2)5���̂���₩�ɐ���킽������B��������v(���{����厫�T�E���w��)
�ƁA�����ɂ���̈Ӗ��̋L�ڂ�����̂ł��B�o���Z�̂ȂǁA�G��̐��E�ł͂����Ƃ͂����肵�Ă��āA���ꂼ�ꋌ��ɏ����Ă��܂��B�ł�����A�G��ɐe����ł�����ɂ́A�܌��Ɂu�܌�����v�u�܌��J�v�Ƃ������t���Ƃ�����ƈ�a���������邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����̐��E�ł́A�u�܌�����v�͌܌��̐��V�Ɏg���A�u�܌��J�v�͋G��ɏ����āA�~�J�ɍ~��J�Ɏg���Ă���悤�ł��B
���F�N�₩�ɂȂ鍠�́u�܌�����v�Ƃ����\���Ƃ͂��낻�남�ʂ�ł����A�u�܌��J�v�͂��ꂩ�炪�܂��ɃV�[�Y���ł��B
 �@
�@ �@
�@
���ꂾ���ł͂���܂���B�o���a�́E�����͐��Ȃ���̂�������O�ł��B�{�l�����߂邾���ł͂���܂���B��l�̎�������Γ���܂��B�m�ԂȂǁA��l�����Ɏ��r�̋�̐�����c�_�����邱�Ƃ��A����̈�Ƃ��Ă��܂����B�����炱�����Ȃ̉ߒ���H��ʔ���������̂ł��B
���Čf�ڂ�����ł����A�]�ǂ̗����L�ɂ��ƁA���\2�N(1689�N)5��28���ɑ�Γc(�R�`��)�ɓ������A29�A30���Ƃ����ɑ؍݂��Ă���Ԃɋ����Â��Ă��܂��B���̋��̔���Ƃ��Ĕm�Ԃ́A
�@�@�@�܌��J���W�߂ė����ŏ��
�Ɖr���܂����B�݂Ȃ���̒m���Ă����Ə����Ⴂ�܂��ˁB
��ʂɒm���Ă����́A�u�����v���u�����v�ɂȂ��Ă��܂��B�ł�������͊ԈႢ�ł͂���܂���B�m�Ԃ͍ŏ��u�����v�Ɖr�̂ł��B���̗��R�͊ȒP�ł��B���̔N�̓��k�E�k���ُ͈�ɏ����A�m�Ԃ������ɕ����Ă�������ł��B������ŏ��̐앗���āA�f���Ɂu�������v�Ɖr�̂ł��傤�B����������āA���ł��R�`����Γc�ł́u�܌��J���W�߂ė����ŏ��v�̕����悭�m���Ă���Ƃ̂��Ƃł��B
�Ƃ��낪�w���̍ד��x������ƁA
�@�@�@�܌��J���W�߂đ����ŏ��
�ƂȂ��Ă��܂��B���̊Ԃɂ��u�����v���u�����v�ɐ��Ȃ���Ă���̂ł��B����ɂ��ẮA������r��A�m�Ԃ͘Z���O���Ɏ��ۂɍŏ��̐쉺���̌������悤�ł��B
�܌��J�͌��݂̔~�J�ɑ������܂��B��ʂɍ~�葱�����J�ɂ���āA��͑������܂��B���s�̕ےÐ쉺��ł����X�������_�ł�����A���{�O��}��(���͕x�m��E������)�ɐ������Ă���ŏ��ł���A�����Ƌ��|�̐쉺�肾�����ł��傤�B���̂��Ƃ́w���̍ד��x�ɂ��A�u���݂Ȃ����āA�M����ӂ��v�ƋL����Ă��܂��B
�����A�Ă̏����Ƌ��ւ̔z������A����Ɂu�����v�Ɖr�����m�Ԃł������A���ۂɖz���ƂȂ��ė����ŏ��̐쉺���̌��������ƂŁA��Ɂu�����v�ɐ��Ȃ����̂ł��B���������̉����ł����A���ꂾ���ŋ�̎�͑傫���ς��܂����B���₩�ȗ��ꂪ�����ɕϖe�����̂ł��B�����čŏI�I�ɔm�Ԃ́A���̌`���悵�Ƃ����悤�ł��B
�Ƃ���ŁA�̖��Ƃ������Ă���u�ŏ��v�ɂ́A�ǂ�ȃC���[�W���t�^����Ă����̂ł��傤���B��\�I�ȌÉ̂Ƃ��ẮA
�@�@�@�ŏ��̂ڂ�������M�̂��Ȃɂ͂��炸���̌�����(�Í��W����1092��)
���������܂�(���t�W�ɂ͌�������܂���)�B����ɂ��A�����艺���M�̃C���[�W����Ԉ�ۓI���������Ƃ��킩��܂�(��M�͂��ꂪ���o)�B����͍ŏ�삪�M�^(���イ����)�ɗ��p����Ă�������ł��B�܂��u�ہv�������̏����Ƃ����Z�@���F�߂��܂��B
���̂��Ƃ́w���̍ד��x�ɂ��A�u�݂̒��ɑD�������B���Ɉ�݂������A���ȂԂ˂Ƃ͉]�Ȃ炵�v�Ƃ���̂ŁA�m�Ԃ��Í��W�̂�O���ɒu���Ă������Ƃ��킩��܂��B�����������ɋ}���̃C���[�W�͂���܂���B�ǂ����ŏ����u�����v�Ɖr�̂́A�m�Ԃ���������悤�ł�(�������u�����v�����l�ł�)�B
���Ƃ��ƍŏ����r�����̂͂���Ȃɑ�������܂��A���̒��Ō��D�@�t�̉r�A
�@�@�@�ŏ��͂₭��������J�_�̂̂ڂ������܌��J�̂���(���D�@�t�ƏW)
�́u�܌��J�v���ǂݍ��܂�Ă���_�����ʂ��Ă��܂��B�܂��G�߂͈قȂ�܂����A�֓��g�́A
�@�@�@�ŏ��t���g�̗��܂łɐ��Ⴍ�[�ׂƂȂ�ɂ��邩��(�����R)
�́A�ŏ��̎��R�̖҈Ђ��r���Ă���_�������ł��B�̖��̃C���[�W�����X�ɍL�����Ă���(��������Ă���)�̂��킩��܂��ˁB�m�Ԃ̋�͌����ē`���I�ȉr�݂Ԃ�ł͂Ȃ������̂ł��B�ŏ��ɍs���Ă݂����Ȃ�܂��B �@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@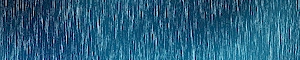
�C��w�I�ȋG�ߕω��𐢊E�Ɣ�r�����Ƃ��A���A�W�A�ł͏t�ďH�~�ɔ~�J���������܋G�A�܂����{�Ɍ���Ƃ���ɏH�J���������Z�G�̕ω����͂�����ƕ\���B
���A�W�A�ł́A�t��H�́A���ђ�C���ƈړ������C�������݂ɒʉ߂��Ď����I�ɓV�C���ω�����B����A���Ċ��ɂ͈��M�э��C��(�����m���C��)�̉e�����ɓ����č��������ȋC�c�ɕ�����B�����āA�t���琷�Ă̊ԂƁA���Ă���H�̊Ԃɂ́A�����嗤����������{�̓������ɑO��������邱�ƂʼnJ�G�ƂȂ�B���̒��ŁA�t���琷�Ă̊Ԃ̉J�G���~�J�A���Ă���H�̊Ԃ̉J�G���H�J�ł���B�Ȃ��A�~�J�͓��A�W�A�S�̂Ŗ��Ăł������A�H�J�͒����嗤���ʂł͎キ���{���ʂŖ��Ăł���B�܂��A���Ă���H�̊Ԃ̉J�G�̉J�̓���Ƃ��āA�䕗�ɂ��J�������ł��Ȃ��قlje���͂������Ă���B
�~�J�̎������n�܂邱�Ƃ�~�J�������~(�ɂイ��)�Ƃ����A�Љ�ʔO��E�C�ۊw��͏t�̏I���ł���ƂƂ��ɉĂ̎n�܂�(����)�Ƃ����B�Ȃ��A���{�̎G�߂�1�ɓ��~(6��11����)������A��̏�ł͂��̓�����~�Ƃ��邪�A����͐���K�v�Ƃ���c�A���̎����̖ڈ��Ƃ���Ă���B�܂��A�~�J���I��邱�Ƃ�~�J������o�~(�����)�Ƃ����A����������Ė{�i�I�ȉ�(����)�̓����Ƃ��邱�Ƃ������B�قƂ�ǂ̒n��ł́A�C�ۓ��ǂ��~�J�����~�J�����̔��\���s���Ă���B
�~�J�̊��Ԃ͂ӂ�1��������1���������x�ł���B�܂��A�~�J���̍~���ʂ͋�B�ł�500mm���x�ŔN�Ԃ̖�4����1�E�֓��Ⓦ�C�ł�300mm���x�ŔN�Ԃ̖�5����1����B�����{�ł͏H�J���~�J�̕����J�ʂ��������A�����{�ł͋t�ɏH�J�̕�������(�䕗�̊�^������)�B�~�J�̎�����J�ʂ́A�N�ɂ���đ傫���ϓ�����ꍇ������A�Ⴆ��150mm���x�����J���~��Ȃ�������A�~�J���������N���2�T�Ԃ��x�ꂽ�肷�邱�Ƃ�����B���̂悤�ȔN�͖ҏ��E���J�ł��������āE���J�ł�������ƁA�Ă̓V�ǂ��Ȃ��C�ۍЊQ���N���₷���B
���A�W�A�͒��ܓx�Ɉʒu���Ă���B���ܓx�̒����Ȃǂ̂悤�Ɉ��M�э��C���̉e�����ɂ����Ċ��������C��ƂȂ��Ă����������Ȃ����A�嗤���݂͉ċG�ɊC�m�����M�э��C���̕Ӊ����ɂȂ邽�߉J�������X���ɂ���B����͖k�A�����J�嗤���݂����������A��B�ł͔N�ԍ~���ʂ���2,000mm�ƂȂ�ȂǁA�M�ю����т̉J�ʂɂ����Ȃ��قǂ̉J�ʂ�����B���̖L�x�ȉJ�ʂɑ���~�J��H�J�̊�^�͑傫���B�~�J���傫�ȉJ�ʂ������炷�v���Ƃ��āA�C���h���瓌��A�W�A�ւƂȂ��鍂�������ȃA�W�A�E�����X�[���̉e�����Ă��鎖����������B
���܁A�~�J�́u�J�����Ƃ��Ƃƍ~��v�u����قljJ���̋����Ȃ��J��ܓV�������v�Ɖ������邱�Ƃ�����B����͓����{�ł͐��������A�����{�ł͂��܂萳�����Ȃ��B�~�J�̉J�̍~����ɂ��n�捷�����邽�߂ł���B���ɐ����{��ؒ�(���]�̒�������t��)�ł́A�ϗ��_���W�܂����_�N���X�^�[�ƌĂ�鐅���K��100km�O��̉_�Q�������Δ������ē��ɐi�݁A�������J�������炷�Ƃ�������������B���{�{�y�Ŕ~�J���ɂ�����6-7���̉J�ʂ�����ƁA���~����100mm�ȏ�̑�J�̓��₻�̉J�ʂ͐����ɍs���قǑ����Ȃ�ق��A��B��l�������m���ł�2�J���Ԃ̉J�ʂ̔����ȏオ������4-5���Ԃ̓��~����50mm�ȏ�̓��ɂ܂Ƃ܂��č~���Ă���B�~�J���̑��J�ʎ��̂��A���{�{�y�ł͐����ɍs���قǑ����Ȃ�B
�����\�L�u�~�J�v�̌ꌹ�Ƃ��ẮA���̎����͔~�̎����n�����ł��邱�Ƃ���Ƃ�������A���̎����͎��x�������J�r�������₷�����Ƃ���uꀉJ(����)�v�ƌĂ�A���ꂪ�������́u�~�J�v�ɓ]�����Ƃ������A���̎����́u���v���̂悤�ɉJ���~�邩��u�~�v�Ƃ����������Ă�ꂽ�Ƃ�����������B���i�̔{�A�J���~�邩��u�{�J�v�Ƃ����̂͂�����(���Ԍꌹ)�ł���B���̂ق��Ɂu�~��(�����)�v�A�����5�����ł��邱�ƂɗR������u�܌��J(���݂���)�v�A���̎��鍠�ł��邱�ƂɗR������u���J(����)�v�Ȃǂ̕ʖ�������B
�Ȃ��A�u�܌��J�v�̌ꂪ�]���āA�~�J���̉J�̂悤�ɁA�������������炾��Ƒ������Ƃ��u�܌��J���v�ƌ����悤�ɂȂ����B�܂��~�J�̐���Ԃ̂��Ƃ��u�܌�����(������)�v�Ƃ������A���̌��t�͍ŋ߂ł́u������v�Ƃ��ǂ�ŐV��5�����{�̂悭���ꂽ�V����w�����Ƃ̕��������B�C�ے��ł�5���̐���̂��Ƃ��u��������v�ƌĂсA�~�J���̐���Ԃ̂��Ƃ��u�~�J�̍��Ԃ̐���v�ƌĂԂ悤�Ɏ�茈�߂Ă���B�܌��J�̍~�鍠�̖�̈ł̂��Ƃ��u�܌���(�������)�v�Ƃ����B
�n�����ɂ́u�Ȃ����v(�������������Q��)�A�u�ȁ[�݂����v(��E���ł̕ʖ�)������B����ł́A�~�J����������䊎�ɂ����Ă̎����ɓ�����̂Łu����䊎�(�X�[�}���{�[�X�[�A���傤�܂�ڂ�����)�v��u䊎�J(�{�[�X�[�A�~�A�ڂ����゠��)�v�Ƃ����ʖ�������B
�����ł́u�~�J(���C���[)�v�A��p�ł́u�~�J(���C���[)�v��u䊎�J�v�A�؍��ł́u장마(�`�����})�v�Ƃ����B�����ł́A�Â��́u�~�J�v�Ɠ����́u霉�J�v�Ƃ����������Ă��Ă���A���݂��p�����邱�Ƃ�����B�u霉�v�̓J�r�̂��Ƃł���A���{�́uꀉJ�v�Ɠ����Ӗ��ł���B�����ł́A�~���n���ĉ��F���Ȃ鎞���̉J�Ƃ����Ӗ��́u���~�J(�t�@�����C���[)�v���悭�p������B
���C�c
�~�J�̎����ɂ́A�ȉ���4�̋C�c�����A�W�A�ɑ��݂���B
�E�g�q�]�C�c�@/�@�����k���E�����S�����疞�B�ɂ����Ă̒n��ɑ��݁B�g�������������嗤���̋C�c�B�ړ������C���ɂ���č\�������B
�E�I�z�[�c�N�C�C�c�@/�@�I�z�[�c�N�C�ɑ��݁B�₽���������C�m���̋C�c�B
�E�M�у����X�[���C�c�@/�@�C���h�V�i�����E��V�i�C����쐼�����ߊC�ɂ����Ă̒n��ɑ��݁B�g�������Ɏ������C�m���̋C�c�B�C���h�m�̊C�m���C�c�̉e���������Ă���B
�E���}���C�c�@/�@�k�����m�����ɑ��݁B�����E�����ŊC�m���̋C�c�B�@
�t����ĂɋG�߂��ڂ�ς��ہA���A�W�A�ł͐����̈Ⴄ�����̋C�c�����߂������B�����嗤���ʂƓ��{�E���N�������ʂł͂��߂������C�c���قȂ�B
�E�����嗤���ʁF�k�̗g�q�]�C�c�Ɠ�̔M�у����X�[���C�c���ڋ߂��A��ɗ��҂̎��x�̍��ɂ���Ē�ؑO�����`�������B
�E���{�E���N�������ʁF�k�̃I�z�[�c�N�C�C�c�Ɠ�̏��}���C�c���ڋ߂��A��ɗ��҂̉��x�̍��ɂ��A��ؑO�����`�������B
���������Ă��邱�Ƃ�A����������Ă��Ċ������Ȃ����ƂȂǂ���A�k���̋C�c���m�E�쑤�̋C�c���m�̊Ԃɂ́A�O���͌`������Ȃ��B
�k�Ɠ�̋C�c���Փ˂��������ɂ͓�������km�ɓn���Ĕ~�J�O��(��������)���ł��A�������ɓn���ď������k�サ�Ă����B���̑O���t�߂ł͉J���~�葱�����A���J�̊��Ԃ͊e�n���1����–2�����ɂ��Ȃ�B���ꂪ�~�J�ł���B
���~�J�O���̍ŏ�
�~�̊ԁA�V�x���A���璆���嗤�ɂ����Ă̍L�͈͂�₽�����������V�x���A�C�c�������Ă���B�V�x���A�C�c�͂����Γ쉺���Ċ��g�������炵�A���{�̓��{�C���ɑ����~�点�邪�A�`�x�b�g�����ł͍����R�����ז����ċC�c������ȏ�쉺�ł��Ȃ��B���̃`�x�b�g�����̓쑤�A�C���h-�t�B���s���ɂ����Ă̏������M�уW�F�b�g�C���������B
�~���I���t���߂Â��ɂ�A�V�x���A�C�c�͐��͂��キ�Ȃ�A����ɖk�サ�Ă����B�����Ē����嗤�ɂ͒g�������������g�q�]�C�c���ł��n�߁A���͂����߂Ă����B�t�ɂȂ�ƁA�g�q�]�C�c�͓��̓��{�⒩�N�����ȂǂɈړ������C������o���A���ꂪ�ΐ����ɏ���ē��ɐi�݁A���C���̊Ԃɂł�����C���ƂƂ��ɏt�̈ڂ�ς��₷���V������o���Ă���B
�t���I���ɍ����|����ɂ�āA��V�i�C�t�߂ɂ���M�у����X�[���C�c�����͂𑝂��k�サ�Ă���B����ƁA�g�q�]�C�c�ƔM�у����X�[���C�c���Փ˂��n�߂�B�n��V�C�}�ł݂�ƁA�g�q�]�C�c����ł������C���ƔM�у����X�[���C�c����ł������C������V�i�C��ł��߂������A���̊ԂɑO�����ł��Ă��邱�Ƃ��킩��B���ꂪ�ŏ��̔~�J�O���ł���B
��N�A�ؓ��쐼����������t�߂ł�5����{���ɁA�~�J�O���̂ł��n�߂ł���_�̑�(���I�ɂ͏����I�ȉ_�тƌĂԂ��Ƃ�����)����������B
�����ĂɂȂ�~�J�O��
5����{�ɂ͓쐼�������~�J�O���̉e�����n�߂�B5�����{����ɂȂ�ƁA�~�J�O���͂͂�����ƓV�C�}��Ɍ����悤�ɂȂ�A�ؓ��쐼�����t�߂ɒ����B
����A���Ăɓ�����5������A���M�уW�F�b�g�C�����k�サ�A�`�x�b�g�����ɍ����|����B�������A�`�x�b�g�����͏��𗬂�鈟�M�уW�F�b�g�C����������ɕW�����������߁A���M�уW�F�b�g�C���̓`�x�b�g���������ɖk�Ɠ��2�̗���ɕ�����Ă��܂��B
�����ꂽ���M�уW�F�b�g�C���̂����A�k���̕����́A�����t�߂Ŋ��уW�F�b�g�C���ƍ�������B����ɂ��̋C���́A�J���`���c�J�����t�߂œ쑤�̕����ƍ�������B���̍����̉e���ŏ��̑�C����ƁA���~�C�����������āA���̉��w�̃I�z�[�c�N�C��ɍ��C�����ł���B���̍��C�����I�z�[�c�N�C���C���Ƃ����A���̍��C���̕�̂ƂȂ�₽���������C�c���I�z�[�c�N�C�C�c�Ƃ����B
��������A�����m�����̗m��ł����C�������͂𑝂��A�͈͂𐼂ɍL���Ă���B���̍��C���͖k�����m��я�ɕ��������m���C���̐��[�ŏ��}�����C���Ƃ������A���̕�̂ƂȂ�g�����������C�c�����}���C�c�Ƃ����B
5�����{����6����{����ɂȂ�ƁA��B��l�����~�J�O���̉e�����ɓ���n�߂�B���̂��납��A�~�J�O���̓����ł̓I�z�[�c�N�C�C�c�Ə��}���C�c�̂��߂������̐F���Z���Ȃ��Ă���B����A�ؖk�⒩�N�����A�����{�ł́A���C���ƒ�C�������݂ɂ���Ă���t�̂悤�ȓV�C�������B
���k�シ��~�J�O��
�k��𑱂���~�J�O���́A6�����{�ɓ���ƁA�����ł͓��R���t�߂ɒ�A���{�ł͖{�B�t�߂ɂ܂Ő��͂��L���Ă���B
���ɔ~�J�O���͒����̍]��(���]����E�̉͗���)�ɖk�シ��B6�����{�ɂ͉ؓ��쐼�������~�J�O���̐��͌����甲����B7���ɓ���Ɠ��k�n�����~�J���肵�A�k�C�����������{�̖{�y�n�悪�{�i�I�Ȓ��J�ɓ˓�����B�܂���������A���N�����암�����J�̎����ɓ���B
7�������߂���ƁA���M�уW�F�b�g�C�����`�x�b�g���������k�𗬂��悤�ɂȂ�A�������ăI�z�[�c�N�C�C�c����܂��Ă���B����ŁA�����m���C�������{�̓�C��������Đ��V�������悤�ɂȂ�A���{�{�y�⒩�N�������삩�珇�ɔ~�J�������Ă���B
�������Ėk�サ�Ă����~�J�O���͍ŏI�I�ɁA�k���Ȃǂ̉ؖk�E�������k���ɒB����B��N�A���̍��ɂ͑O���̐��͂���܂��Ă���A�ܓV�����ɂȂ邱�Ƃ͂��邪�O���������葱����悤�Ȃ��Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B�܂��A8�����{�E���{�����ɂ��Ă���ȍ~�̒��J�͂�����H�J�ł���A�O���̖��O���H�J�O���ɕς�邪�A�O���̓�k�̋�C���\������C�c�͓����ł���B�������A�H�J�͒����嗤���ʂł͂قƂ�nj����Ȃ��B�����{�ł��H�J�͂�����̂̉J�ʂ͂���قǑ����Ȃ��B����A�����{�A����іk���{(�k�C������)�ł͔~�J���̉J�ʂ����ނ���H�J���̉J�ʂ̕��������Ƃ����X��������(�������A�H�J���̉J�ʂɂ͑䕗�ɂ��܂Ƃ܂����J���܂܂��)�B
���~�J�O���̐���
�����̈Ⴄ2�̋�C(�C�c�Ƃ���)���Ԃ��鏊�͑�C�̏�Ԃ��s����ɂȂ�A�O������������B�~�J�O�����\������C�c�͂���������͂��h�R���Ă��邽�߁A�قړ����n����k�ɂ������ƈړ������ؑO���ƂȂ�B
�~�J�O���̓쑤���\������2�̋C�c�͂Ƃ��ɊC�m��{���n�Ƃ���C�c(�C�m���C�c)�̂��߁A�C�m�����ʂ̐����C���z�����Ď����ȋ�C�������Ă���B�����A�k���̋C�c�Ɠ쑤�̋C�c�Ƃł͂��݂��̉��x�������������߁A�ʏ�͂قƂ�ǂ����w�_�̎ア�J�_�ō\�������B���̂��߁A���Ƃ��ƂƂ��܂苭���Ȃ��J���ԍ~�点��B
�������A���̊��C�⊣��������C������������A�䕗��n�\�t�߂ɒg������������C(�g����)�����������肷��ƁA�O���̊��������������āA�ϗ��_���Ƃ��Ȃ��������J�_�ƂȂ�A���ɍ��J�ƂȂ�B
2�̍��C�������߂������A���͂̃o�����X���قڂ荇���Ă���Ƃ��A�~�J�O���͂قƂ�Ǔ����Ȃ��B�������A2�̍��C���̐��͂̃o�����X�����ꂽ�Ƃ���A��C�����߂Â��Ă�����A�O���t�߂ɒ�C�������������肵���Ƃ��͈ꎞ�I�ɉ��g�O���⊦��O���ƂȂ邱�Ƃ�����B�~�J�O���̊����������m���C���̐��͊g��ɂ���Ď�܂邩�A�e�n��̖k���ɉ����グ���A����O���̉e���ɂ��J���~��Ȃ��ɂȂ����Ƃ��A�~�J���I������Ƃ݂Ȃ����B
���~�J����̓���Ȃ��̔N
�N�ɂ���Ă͔~�J����̎���������ł��Ȃ�������A���邢�͔��\������Ȃ����Ƃ�����B���E�����{(���Ɏl���n���E�ߋE�n���E�k���n��)�ł͂��̃p�^�[�������N�Ɉ��̊����ŋN����B����́A�����m���C���̐��͂��������߂ɔ~�J�O�����k���n������k�サ�Đi�݂��̂܂܉ċ�ɓ˓����A��̍��C���ƂȂ��Ď���ɓ쉺���Ă����p�^�[���ł���(���������ɂ��āA�����ȍ~�͂��̂܂ܔ~�J�����ɂȂ�)�B���̏ꍇ�ł��A�l���n���A�ߋE�n���A�k���n���ł͍�����V����⑽���Ȃ���̂́A�T�ː��V�������u�āv���K��Ă���B���̂��Ƃ���A�N�ɂ���ẮA�ߋE�n���ɂ�����(�{����)�Ă͖k���n�����������Ƃ���Ă���B
���~�J�����̓���Ȃ��̔N
�N�ɂ���Ă͔~�J�����̎���������ł��Ȃ�������A���邢�͔��\������Ȃ����Ƃ�����B���k�n��(���ɐX�E���E�H�c�̖k���k3��)�A�֓��b�M�n���ł͂��̃p�^�[�������N�Ɉ�x�̊����ŋN����B����́A�I�z�[�c�N���C���̐��͂��������߂ɔ~�J�O�������k�n������k��ł����ɂ��̂܂H�ɓ˓����A�H�J�O���ƂȂ��Ď���ɓ쉺���Ă����p�^�[���ł���(���H�����ɂ��āA���H�ȍ~�̒��J���H�J�Ƃ���)�B���̏ꍇ�ł��A�k�̖k�C���ł͒ቷ��ܓV����⑽���Ȃ���̂́A�T�ː��V�������u�āv���K��Ă���B���̂��Ƃ���A�N�ɂ���ẮA���k�n���ɂ�����(�{����)�Ă͖k�C�������Z���Ƃ���Ă���B
���A�W�A�����X�[���Ɣ~�J
�~�J�O���́A�C�ۊw�I�ɂ̓����X�[���������炷�O��(�����X�[���O��)��1�ł���B�C���h���͂��߂Ƃ�����A�W�A�Ⓦ��A�W�A�̃����X�[���́A�C���h�m������m�ɒ[���鍂�������̋C���������ł���B���E�ő��̔N�ԍ~���ʂ�L����n��(�C���h�̃`�F���v���W)���܂ނȂǁA���̒n��̃����X�[���͒n����ōł��K�͂��傫���A�L�͈͂ŘA�����Ĕ������Ă��邱�Ƃ���A���̂��ăA�W�A�E�����X�[���ƌĂ��B�܂����̉e������n��������X�[���E�A�W�A�Ƃ����B
�A�W�A�E�����X�[���̉e���͈͂͂���ɓ��ɂ܂ŋy��ł���A��V�i�C���M�у����X�[���C�c�ɂ��e����^���Ă���B��̓I�ɂ́A�쐼������ؓ�̔~�J�̍~�J�̑啔�����M�у����X�[���C�c�ɂ���Ă����炳���ق��A�����m���C���̕Ӊ������v���ɐ����C�����A���̔M�у����X�[���C�c�̉e��������C����{�E���N�����t�߂܂ʼn^��ł��ĉJ������B���̂悤�Ȋ֘A�����l���āA�C�ۊw�ł͈�ʓI�ɁA�~�J�����钆�����C���E���N�����E���{�̑啔���������X�[���E�A�W�A�Ɋ܂߂�B
�܂��A�~�J�O���t�߂̏��̑�C���݂�ƁA�~�̋�C�Ət�E�H�̋�C�̋��ڂƂȂ銦�ёO���A�t�E�H�̋�C�ƉĂ̋�C�̋��ڂƂȂ鈟�M�ёO�����ڋ߂��đ��݂��Ă��āA�~�J�́u�G�߂̕ς��ځv�̐����������B
�����{
�@�@�@������〜���k
���{�ł͊e�n�̒n���C�ۑ�E�C�ے����A���̓s�{�����܂Ƃ߂��n�悲�Ƃɖ��N�~�J����E�~�J�����̔��\������(�k�C��������)�B�܂��A�~�J����E�~�J���������Ǝv���邻�̓�(�x���̏ꍇ�́A�ȍ~�ŏ��̕���)�Ɂu����l�v�Ƃ��Ĕ��\���s���A���̔��\�ɏ]���āu�~�J���肵���Ƃ݂���v�E�u�~�J���������Ƃ݂���v�ƕ����B���̌�A5������8���̓V��o�߂𑍍��I�Ɍ������A���N9���ɍŏI�I�Ȕ~�J�̎������u�m��l�v�Ƃ��Ĕ��\����B���̍ہA����l�ł̔~�J����E�~�J�����̊����̏C�����s��ꂽ��A�ŏI�I�Ɂu���肹���v�Ƃ����\���ɂȂ邱�Ƃ�����B��ʂɁA��̒n��قǔ~�J�̓����͑����A�����5�����{����6�����{�A���k�E�k���ł�6�����{����7�����{���ƂȂ�̂����ϓI�ł���B
�~�J�����~�J�����̔��\�͒ʏ�A���̂悤�ɂ��čs����B�e�C�ۑ�͎�ɁA1�T�Ԍ�܂ł̒����\��Ƃ���܂ł̓V��̐��ڂ���A���ꂪ��r�I�������Ă���܂��J�̑����~�J�ւƕς��u���ځv�𐄒肵�āA�����~�J����̓��Ƃ��Ĕ��\���Ă���B�[�I�ɂ́A�NJ��n��œ܂��J�����㐔���ȏ㑱���Ɛ��肳���Ƃ��ɂ��̏�����~�J����Ƃ���B�~�J�����̏ꍇ�͋t�ɐ��ꂪ�����ȏ�Â��Ƃ��ł���B�����\��̍����ɂȂ�̂́A�덷����r�I���Ȃ��W�F�b�g�C���Ȃǂ̏��̑�C�̗���(���M�уW�F�b�g�C���Ɣ~�J�O���̈ʒu�W�͑Ή����悢)�̗\�z�Ȃǂł���B�����A���̒����\�̂��O���ƁA���\�ʂ�ɂ��������ꂽ�肷��B�~�J�����~�J�����̔��\�́A�m�肵�����Ƃ\����̂ł͂Ȃ��A�C�ے��ɂ��u�\��I�ȗv�f���܂�ł���v�̂ŁA�O���ꍇ������B
�������A�~�J�O����������܂ܗ��H���߂���ƁA�~�J�����̔��\�͂���Ȃ��B���H�̎����͂��傤�ǁA��N�~�J�O���������Ƃ��k�ɒB���邱��ł���A����ȍ~�͂ǂ��炩�Ƃ����ΏH�J�̎����ɓ���B�������A���̏ꍇ�ł����N�ɂ͒ʏ�ʂ�u�~�J����v���}���邪�A�u�~�J�������Ȃ��܂܈�N���z���ďd���I�ɂ܂��~�J����ƂȂ�v�킯�ł͂Ȃ��B�܂�A�~�J�������Ȃ��ꍇ�́u�͂�����ƉĂ̓V�C������Ȃ��܂ܔ~�J����H�J�ւƈڍs����v�ƍl����B
�~�J���Ԃ̏I�����\�̂��Ƃɔ~�J�����錾�Ƃ����B��{�I�ɁA�~�J�O���̖k��ɔ����ē삩��k�֏��Ԃɔ~�J�������}���邪�A�K���������̂悤�ɂȂ�Ȃ��ꍇ������B�O�����ꕔ�n��Ɏc�����Ă��܂��悤�ȏꍇ�ɂ́A���k�̒n���̕�����ɔ~�J�����ɂȂ�ꍇ������B�ߋ��ɁA��ɔ~�J���肵�������n������ɔ~�J���肵���k���n������ɔ~�J����������A�֓��n���̔~�J�����������{���啝�ɒx�ꂽ�肵���Ⴊ����B
�~�J�̖����͑����m���C���̐��͂������Ȃ��ē������̊Ԋu�����ނ��Ƃō��C���̂ւ�����u�Ӊ����v����������A�g����������₷���Ȃ邽�ߍ��J�ƂȂ�₷���B�t�ɔ~�J�����ォ��8����{���炢�܂ł́u�~�J�����\���v�Ƃ����ēV���肷�邱�Ƃ������A�ҏ��Ɍ������邱�Ƃ�����B
�~�J�̊��Ԃ͂ǂ̒n���ł�40������50���O��Ƒ卷�͂Ȃ����A���Ԓ��̍~���ʂ͑傫���قȂ�B�{�y�ł͐����ɍs���قǑ����Ȃ�A���k�����֓��E���C�E�ߋE�A�֓��E���C�E�ߋE������B�k���A��B�k��������B�암�̕��������B����쐼�����ł́A�Ί_����ߔe���������̕������ԍ~���ʂ͑����A�����I�ɓ��{�t�߂̔~�J���̉J�ʂ͋�B�암���ł������B
�@�@�@���k�C��
���ۂ̋C�ۂƂ��Ă͖k�C���ɂ�����𒆐S�ɔ~�J�O���������邱�Ƃ͂��邪�A���ϓI�ȋC�ۂƂ��āA�܂�C��w�I�ɂ͖k�C���ɔ~�J�͂Ȃ��Ƃ���Ă���B����́A�~�J�O�����k�C���ɓ��B����~�J�����͐��͂������A�k�シ�鑬�x�������Ȃ��Ă��āA�~���������������O�����������Ă��܂�ƂȂ邾���ʼnJ���~��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ��������߂ł���B�������A�L�^�I�ҏ��ƂȂ���2010�N�����ɁA�ߔN�͖k�C���쐼���𒆐S�ɃQ�������J��~�J�O������܂炸�ɐ��͂�ێ������܂ܖk�C���t�߂ɒ����Ƃ������Ⴊ�����Ɍ����悤�ɂȂ�A���ł�2018�N�ɂ́A�~�J�O���̒�ɂ���J�ʼn͐�̔×��ȂǕ���30�N7�����J�ƂȂ��Ėk�C���e�n�Ŕ�Q���y�ڂ����B
�k�C���̒��ł��쐼�������m��(�n���E�_�U�E����)�ł͖{�B�̔~�J�����ɑ�J���~�鎖������B�܂��A�k�C���̍L���͈͂ł��̎����͒ቷ����ƕs�����N����₷���ق��A���H�ȂǓ����ŊC���̓����������Ȃ�̂��A�����{�̔~�J�Ɠ������I�z�[�c�N�C���C���̉e�����Ă���B���ɁA5�����{����6����{�𒆐S�Ƃ��Č�����ꎞ�I�Ȓቷ�́A�k�C���ł̓���(���C���b�N)�̉Ԃ��炭�����ł��邱�Ƃ��瑭�Ɂu�����₦�v�Ƃ��ĂԁB�܂��A���̂悤�ɂ��������������V�C���A�N�ɂ���Ă�2�T�Ԓ��x�A�{�B�̔~�J�Ɠ��������ɑ������Ƃ�����A�u�ڈΔ~�J�v(������)�ƌĂ�邱�Ƃ�����B
�@�@�@�����}������
���}���������t����Ăւ̑J�ڊ��ɂ�����5���ɂ́A�C�c���m�̒��S������Ă��邽�ߑO�����`�����ꂸ�A�J�����������Ȃ��B�����ď��Ă��}����6������葾���m���C���̌����ɓ����Ă��̌ジ���ƕ����邽�߁A��������~�J���Ȃ��B
������
���������E�암�ł��~�J���݂���B�����ł͊e�s�s�̋C�ۑ䂪�A�~�J����Ɣ~�J�����̔��\�����Ă���B���錤���ł́A1971�N - 2000�N�̊e�s�s�̔~�J����E�~�J�����̕��ϒl�ŁA���]������̔~�J�����6��14���A�~�J������7��10���A�̉͗���̔~�J�����6��18���A�~�J������7��11���ƂȂ��Ă���B
�ڈ��Ƃ��āA�ؓ�ł�5�����{����ɔ~�J�O���ɂ�钷�J���n�܂�6�����{����ɏI���B���ԂƂƂ��ɂ���ƒ��J�̒n��͖k�Ɉڂ�A6�����{���납��7����{����ɉؓ�(���]��������)�A6�����{���납��7�����{����ɉؖk�̈ꕔ�����J�̎����ƂȂ�B���J�͂��ꂼ��1�����قǑ����B
�����N����
���N�����ł�6�����{���납��7�����{����ɒ��J�̎����ƂȂ�A1�����قǑ����B�k�ɂ����قǒ��J�͂͂����肵�Ȃ����̂ɂȂ�B
�~�J����O��5 - 6������A�~�J�Ɏ����V�݂��邱�Ƃ�����A����𑖂�~�J(�͂���Â�)�A�~�J�̑���(��̂͂���)�A���邢�͌}���~�J(�ނ����Â�)�ƌĂԁB
�~�J���蓖���͔�r�I���Ƃ��ƂƂ����J���A�����邱�Ƃ������B�~�J�̔��ɂ͈�U�V�C��������Ԃ��o�����邱�Ƃ�����B���̊��Ԃ̂��Ƃ�~�J�̒��x��(��̂Ȃ��₷��)�Ƃ����B
�~�J�̎����A���ɁA���J�̏ꍇ�́A���Ǝ��Ԃ��Z�����߁A�C���̏㉺(�ō��C���ƍŒ�C���̍��A���r��)���������A�����������邱�Ƃ�����B���̊�����V���~�J��(�䂴��)�܂��͔~�J��(��т�)�ƌĂԁB����A�~�J���Ԓ��̐���Ԃ͔~�J����(���)�܂��͔~�J�̐���ԂƌĂ�A���ɁA�C���������A���x�������B���̂��߁A�~�J����̓��͕s���w���������Ȃ�߂����ɂ����A�M���ǂ��N����₷���X���ɂ���B
�~�J�����ɂ͍~�J�ʂ������Ȃ邱�Ƃ������A�Ƃ��Ƃ��ďW�����J�ɂȂ邱�Ƃ�����B�삨��ѐ��قǂ��̌X���������A���ɁA��B�ł͏\���N��1����x�̊����ł��̎����Ɉ�N���̍~���ʂ��킸����T�Ԃō~�邱�Ƃ�����(�F�{���E�{�茧�E���������̋�B�R�n�R�������T�^��)�B�t�ɁA�֓��Ⓦ�k�ȂǓ����{�ł͔~�J�̎��������ނ���H�J�̎����̂ق����J�ʂ������B
�~�J�����̉J���r�~�J(����Â�)���邢�͖\��~�J(����Â�)�Ƃ��ĂԁB�܂��A�~�J�̖����ɂ͗����Ƃ��Ȃ����J���~�邱�Ƃ������A����𑗂�~�J(������Â�)�ƌĂԁB�܂��A�~�J������������A�J����������A�������ꂽ��܂��J���~�����肷�邱�Ƃ�����B������A��~�J(������Â�A�Ԃ�~�J�Ƃ�����)�܂��͖߂�~�J(���ǂ�Â�)�ƌĂԁB�����̕\���͋ߔN�ł͂��܂�g���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B
�~�J�������x�ꂽ�N�͗�ĂƂȂ�ꍇ�������A��Q���������₷���X���ɂ���B
�~�J�͓��{�̋G�߂̒��ł������ƍ��������Ɍ����Ȏ����ł���A�J�r��H���ł̌����ƂȂ�ہE�E�C���X�̔ɐB���i�݂₷�����Ƃ���A�����ɒ��ӂ��K�v�ȋG�߂Ƃ���Ă���B
����~�J
�~�J�̊��Ԓ��قƂ�ljJ���~��Ȃ��ꍇ������B���̂悤�Ȕ~�J�̂��Ƃ���~�J(�����)�Ƃ����B��~�J�̏ꍇ�A�ċG�Ɏg�p���鐅(���Ɉ��ɕK�v�Ȕ_�Ɨp��)���m�ۂł��Ȃ��Ȃ�A�����������N�������Ƃ������A���ɐX�A���A�H�c�̖k���k�n���ɂ����Ă͋�~�J�ɂȂ�m�������Ȃ荂���A�܂��A�H�G〜�~�G�̍~���ʂ����Ȃ��k����B�␣�˓��n���Ȃǂł́A��~�J�̌�A�䕗�Ȃǂɂ��܂Ƃ܂����J���Ȃ��ꍇ�A������1�N�ȏ㑱�����Ƃ�����B
���A���E�z��
���܂苭���Ȃ��J�����������悤�Ȕ~�J���A���̔~�J�A�J���~��Ƃ��͒Z���Ԃɑ�ʂɍ~��A�~��Ȃ��Ƃ��͂�������Ɛ����悤�Ȕ~�J��z���̔~�J�ƕ\�����邱�Ƃ�����B�A���̔~�J�����~�J(����ȂÂ�)�A�z���̔~�J��j�~�J(���Ƃ��Â�)�Ƃ��ĂԂ��Ƃ�����A�o��ł͋G��Ƃ��Ďg����ꍇ������B
�X���Ƃ��āA�A���̏ꍇ�́A�I�z�[�c�N�C���C���̐��͂��������Ƃ������A�z���̏ꍇ�́A�����m���C���̐��͂��������Ƃ��������A�ΐ����̗��H��A�k�ɐU���E����U��(ENSO�A�G���j�[�j���E���j�[�j��)�Ȃǂ��W���Ă���B
���䕗�Ƃ̊֘A
�䕗��M�ђ�C���͒n��t�߂ł͎��͂����C���z���グ�����A���m-1��m�̑Η�����w�ł͋z���グ����C�����点�Ď��͂ɑ�ʂɕ��o���Ă���B���̂��߁A�~�J�O���̋߂��ɑ䕗��M�ђ�C�����ڋ߂܂��͏㗤����ƁA�����C���ǂ�ǂ����ꂽ�~�J�O�������������č��J�ƂȂ�B�܂��A�~�J�O�����A���͂���܂����䕗�≷�ђ�C���ƂƂ��ɖk�サ�Ĉ�C�ɔ~�J�������邱�Ƃ�����B
���~�J�̍��J�p�^�[��
�~�J�̎����̑�J�⍋�J�̎�����݂Ă����ƁA�C���z�u��C�ۏɂ�����x�̃p�^�[��������Ƃ����Ă���B���{�C���ō��J�ɂȂ�₷���̂����{�C�암�ɒ����~�J�O���t�߂��C�������ɐi�ރp�^�[���ŁA��C���Ɍ������ē쐼���玼������C�����ꍞ�݁A���̋�C���R���ɂԂ����ċǒn�I�ȍ��J�ƂȂ�₷���B
�����m���ō��J�ɂȂ�₷���̂��A�~�J�O���������I�ɒ����p�^�[����A�����m���t�߂ɔ~�J�O���A�����ɒ�C�������ꂼ������p�^�[���ł���A�� - �쓌���玼������C�����ꍞ�݁A�����悤�ɂ��̋�C���R���ɂԂ����ċǒn�I�ȍ��J�ƂȂ�₷���B
���̂ق��A�~�J�O�������ɃN���E�h�N���X�^�[(�ȉ~�`�̉_�Q������~���Z���̈��)�ƌĂ��ϗ��_�̐e�_�����i����ƁA���J�ƂȂ�₷�����Ƃ��m���Ă���B���̑�C���������Ă��钆���嗤�Ⓦ�V�i�C�Ō`������A���{���ʂւ���Ă��邱�Ƃ������B
���C�m�ϓ��Ƃ̊֘A
���v�I�ɂ݂āA�ԓ��t�߂̑����m����-�����ɂ����ĊC�������㏸�E�����Œቺ����G���j�[�j�����ۂ����������Ƃ��́A���{�e�n�Ŕ~�J����E�~�J�������ɒx���Ȃ�X���ɂ���A�~���ʂ͕��N���݁A���Ǝ��Ԃ͑��߂ƂȂ�X���ɂ���B�܂��A����������-�����ŊC�������ቺ�E�����ŏ㏸���郉�j�[�j�����ۂ����������Ƃ��́A����Ŕ~�J���肪�x�߂ɂȂ�̂������A���{�̈ꕔ�Ŕ~�J����E�~�J�����Ƃ��ɑ����Ȃ�X���ɂ���A�~���ʂ͈ꕔ���������߁A���Ǝ��Ԃ͂�⏭�Ȃ߂ƂȂ�X���ɂ���B
���{�̋C�ے����~�J����E�~�J�����̏����n�߂��̂�1955�N����Ƃ���A�u���m�点�v�Ƃ��ĕ@�ւɘA�����Ă����B�C�ۏ��Ƃ��Ĕ��\���n�߂��̂�1986�N�ɂȂ��Ă���ł���B
�~�J�̎����\���邱�Ƃɂ��A���J�E���J�Ƃ������Q�E�y���ЊQ�ɂȂ���₷���C�ۂ��p�����鎞���Ƃ��Ắu�~�J�v��m�点�邱�ƂŖh�Јӎ������߂�A���J�E��������������������u�~�J�v�̎�����m�点�邱�ƂŐ����ʁE�o�ϖʂł̑��e�Ղɂ���A�u�~�J�v�Ƃ������̋G�߂̊J�n�E�I����m�点�邱�ƂŋG�ߊ��m�ɂ���(�t��ԁA�،͂炵�A����Ȃǂ̔��\�Ɠ��l�̖���)�Ƃ��������ʂ����҂���Ă���B
���؎�~�J
������3�����{����4����{�ɂ����Ă̘A���~��Â����X�Ƃ����~�J���A�̉Ԃ��炭����ɍ~�邽�߁u�؎�~�J(�Ȃ��˂Â�)�v�Ƃ����B�~�J�̂悤�ɉ������~�葱������A�W�����J���݂��肷�邱�Ƃ͏��Ȃ����A��͂�A�܂��J�̓��������A�������肵�Ȃ��V�C���������������Ƃ������B
�܂��A�u�t�̒��J�v��u�t��(�������)�v�A�u�ÉԉJ(��������)�v�Ƃ������B�u�t���v�́u���v�͒��J��\�������ł���A�t�̒��J��\���Ă���B�u�ÉԉJ�v�́A�����͂��߂��낢��ȉԂ��Â�(�炩����)�J�Ƃ����Ӗ��ł���B�u�t�J(�͂邳��)�v���A���̂���̉J���w���Č����ꍇ�������A���`�������̖�����Ӂu�t�J����A�G(��)��Ă䂱���v���A���̉�点�Ԃ��炩����_�炩���t�̉J�����炱���A��(����)�ɕ�������B�Ȃ��ANHK�Łu�؎�~�J�v�������Ƃ��ɂ́A�K��������t����悤�ɂ��Ă���B�~�̊ԁA�{�B�t�߂��x�z���Ă����嗤���C���̒���o����A�ړ������C���̒ʂ蓹���k�ɕ�A����ŁA���̖k�����C���̒���o���̓쉏�ӂɉ����āA�⎼�Ȗk���C��(��܂�)����������A�{�B��݉����ɑO��������₷���Ȃ邽�߂ɐ�����B���̂Ƃ��ɂ͓�݂ɏ���C�����p�ɂɔ������₷���Ȃ�̂��܂����F�ł���B���̂��߁A�� - �����{�����m���ݕ��ɂ����Ă����ꍇ�������A�k���{�ɂ͂��̌��ۂ݂͂��Ȃ��B�ߔN�́A�g�~�X������сA���g���̉e��������A�؎�~�J���~�ɌJ��オ�邫�炢������A�C��̕ϓ������O�����ʂ�����B�܂��A�؎�~�J�͔~�J�̂悤�ɂ����Ƒ����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A���Ԃ͈�������邢�͐������x�̂��Ƃ��قƂ�ǂł���B
��Ƃ��ẮA1990�N2���͌��̌㔼�𒆐S�ɓ܉J�V�����ŁA�����ł̓��E���ԓ��Ǝ��Ԃ͋͂�81���Ԃ����Ȃ炸�A��g�~���ے����邩�̂悤�������B�܂��A1985�N�ɂ�3���͌��S�̂�ʂ��Ċ֓��Ȑ��̑����m���n���ł͗₽���J�̘A���ŁA�����ł͓��N���ł̉���������0(�~�J���ł���6�A7���������Ă͏��̃��[�X�g�L�^)�A���{�C�ۋ���s�̓V�C�}���L�ł́u�Â�3���v�ƕ]�������ł������B���̑��A1986�N�A1988�N�A1991�N�A1992�N�A1995�N�A1999�N��3������r�I�������Ɠ܉J�V�����������e���ŁA���ԓ��Ǝ��Ԃ͖k���{�������Ă��Ȃ菭�Ȃ��������߁A20���I���ɂ����Ă�3���́A�u�̉Ԃ̏�ɂ����l�����v�A�u�s�y���E�S��̌��v�A�u�Ԍ��ɂ� �P�ȂljJ� �K���i�v�A�u���Ǝ��A�I�Ǝ��A���C���͂����J�v�Ȃǂƕs���_�ȃ��b�e�����\��ꂽ���Ƃ��������B���̑��A2002�N�A2006�N�ɂ�2������肩��3�����߂ɂ����āA��ݑO�����������A���Ӓ��S�ɉJ�̍~��₷���������肵�Ȃ������āA���V�C�L���X�^�[�̈ꕔ�ł́u�؎�~�J�̑���?�v�ƕ]���ꂽ��������B
������~�J
������5�����{����~�J�{�ԑO�Ԃ�̂悤�ɉJ���~�葱����Ԃ������B���傤�ǁA���̎������K�̉Ԃ��炭����ɂ�����A�K�̉Ԃ点��悤�ȉJ�Ƃ������Ƃ���A�u�K�̉ԕ���(���̂͂Ȃ�����)�v�Ƃ��ĂԂ��Ƃ�����B�u����v�Ƃ́u��삯�v���Ӗ����A�u����~�J�v�Ƃ͔~�J�ɐ�삯�č~�葱���J�Ɖ��߂��邱�Ƃ�����B�u�~�J�̑���v�Ƃ������B����ȂǓ쐼�����̔~�J���ɂ���A�쐼�����t�߂ɂ���~�J�O�����ꎞ�I�ɖ{�B��݉����ɖk�サ���Ƃ��ɑ����݂���B�܂��A�I�z�[�c�N�C���C����5���O���ɏo�������ꍇ�ɖk���C���̉e�����₷���Ȃ邽�߁A�֓��Ȗk�̑����m���Œቷ�Ɠ܉J�V�����������邱�Ƃ�����B���̑��A���C�X�g�[���ȂǁA���{�C��k���{���ʂ�ʉ߂��锭�B������C���̌�ʂɐL�т銦��O�����{�B��ʉ߂��āA�����m���ɒB������A��C��̗D���ȍ��C���̖k���ɉ����āA���̂܂ܒ�ؑO���Ɖ����āA�����m���A�����ɓ����{�����m���ݕ��ł��炭�������V�C�������P�[�X�����̂������ł���B
���H�J
������8���㔼������10�����ɂ�����(�n��ɂ���Ď����ɍ�������)�~�葱�����J�̎����������B�u�H��(���イ���)�v�A�u��(������)�~�J�v�ȂǂƂ��ĂԁB
���R���Ԕ~�J
������11�����{����12����{�ɂ����ẮA�A�������~�J���u�R����(������)�~�J�v�Ƃ����B�R���Ԃ��炭����ɍ~�邽�߂��̖��O������B�@
 �@
�@ �@
�@
�G���u�o�d�v(95�N5����)�B�}���ֈ�ҁu�����̐V�X���E�s�s������100�v���B���ɂ���������ł���B���ׂĂ��Ȃ����Ă���悤�ȁA���Ȃ��悤�ȁB��m�����Βk�͂��炾��ƂƂ߂ǂ��Ȃ��B�u�Βk�v�̎g�������▭�B��ؘZ�ђj�A�吳���N��㐶�܂�B�����O�S�Ɏt���B�o���������A�t�B���s����]�킵�A�R���q�h�[����ŕ����A�A�҂���B���u�V�T�v�n���ɎQ���B���G�h�̋����ł��邪�u�G��Ƃ͒��ǂ��������v�Ƃ����A�L�G������B�u��i�����g���Ɂw�����ꑰ�x�v�͖��G��̌���B
���܌��\�O���A�m�ԂƑ]�ǂ͕����ɖK��A�ʓ��̈ē��Ō���(�����ɂ͋��F��)��q�ς��Ă���B�u�����̂ق����v�̓r���̂��Ƃ��B��ӂ���g���ɂ�������Ă����B�c�c�܌��J�͂��ׂĂ̂��̂炷�̂����A���������͍~��Ȃ������̂ł��낤���B�ܕS�N�̕���ɑς��������̂Ȃ�Ɣ������P���Ă��邱�Ƃ�B�Ƃ܂��A����͍��Z������x�ł͐����ł��낤���A���߂ɕi���Ȃ��B�m�Ԃ͂��̂悤�Ɍ����̔��������̂݉r�̂ł͂Ȃ��āA�����̔������̔w�i�ɂ��铡�����O���Ђ��Ă͋`�o��]�́u�ės�ꐇ�v�̖��Ɏv����y���Ă���̂�����ł���B�L���ȁu�đ��╺�ǂ������̐Ձv�͂��̂Ƃ��̋傾�B�Ƃ���Ō����ł��邪�A���݂͓S�R���N���[�g�̕���(����ǂ�)�ŕی삳��Ă���B���Ƃ��ΉԊ��̌����Y�R���Ɠ����悤�ɁA���X�̌�������������ʂ̌����ŕ����ĕی삵�Ă���킯���B�Ƃ̒��̉ƂƂ��������B�m�Ԃ̎���ɂ������͂���(�ƁA�m�Ԏ��g�����|�[�g���Ă���)�A�w�҂ɂ��Γ�k�����̌��݂炵�����A������ɂ��Ă��܌��J����͕����I�ɓ�����Ă����B�w�����̂ق����x�̕����̂Ȃ��ł͂Ȃ��A�������Ĉ�傾�������o���ēǂނƁA�����̓n�_�J�Ɍ�����B�܂��A�n�_�J�łȂ���傪�����Ȃ��B���̈Ӗ����炷��Ə����̕ςȋ�ł�����̂����A�����̑��݂�Y��Ă��܂��قǂ̔������������Ă���̂ł��낤�B�̂̋�͓���f�X�B
�m���Ă���l������Ǝv�����A���̋�̌��`�́u���݂�����W�߂ė����ŏ��v�ł������B���߂Ă��ꂽ�D�h�̎�l�ɑ��āA�q�Ƃ��Ă̗�V����u�J�~��̂ق����A�������ė������Ă����ł���v�ƈ��A�����傾�B�����m�Ԃ́w�����̂ق����x�Ɏ��^����ɍۂ��āA�u�����v���u�����v�Ɖ��삵���B�ŏ��͓��{�O��}��(���Ƃ͕x�m��Ƌ�����)�̂ЂƂ�����A�������ɂ��̂ق�����̓������悭�Ƃ炦�Ă���A�܌��J�̍~�蒍�����X��������̕����������������ďG���ȋ�ɕς���Ă���B�Ƃ���ŁA���͔m�Ԃ͂��̂Ƃ��ɂ����ŏM�ɏ��A�����Ԃ�ƕ|���ڂɂ������炵���B�u���݂Ȃ��ďM���₤���v�ƋL���Ă���B��������A����������Ɏ��������߂Ă����悩�����̂ɂƁA���Ȃǂ͎v���Ă��܂��B�P�Ƃɋ傾����ǂނƁA�ŏ��̊ݕӂ���r��݂������B��������(?)��h��ɗh���M�ɏ�����̂ɁA�Ȃ����l���̂悤�ł���B���̂���̔m�Ԃɂ��܂ЂƂߊ��ɂ�������������̂́A���������Ƃ���ɗv��������̂ł͂Ȃ��낤���B����������Ɓu�o���v�ƌĂ�闝�R���A���̂�����ɂ���̂�������Ȃ��B���������A���ۂɂ͂������Ȃт�����̗��������͂��Ȃ̂ɁA�w�����̂ق����x�̋�ɂ͂܂���������ĂĂ���t�V���݂��Ȃ��B���ł͐̂���A���������l�̂��Ƃ��u�����J�b�R�����v�Ƃ����B
�܌��J(���݂���)�͋���܌��̉J������A�~�J�Ɠ��`�Ɠǂ�ł悢���낤�B���ڍ~�鏬�J�̂Ȃ��̖�̒҂��A������荇���Ȃ���s���l�ӂ���B���ꂼ��̊D�F�̓��P�̕\��A�ӂ���̊W�������Ă���悤���B�����A���Ƃ���҂̊S�͘b�̒��g�ɂ���̂ł͂Ȃ��A��i���̂��̂����R��Ɍ������Ă���B�����ƃX�P�b�`���Ă��邾�������A��Z�Ȃ��閡�킢������B���R���́A�q�K��m��A���q��m��A�i��ו��̗F�l�������o�Ől�B���̋�͑吳�ܔN(1916)�Ɏ����̎�ŏo�ł����w�]�ˈ���W�x�Ɏ��߂��Ă���B�Ȃ��A����ȂɌÂ���W���A�����ǂ߂��̂��B�F�l�ʼnו��ɂ��Ă̒������������{�ƌN���A��������Ï��X�œ��肵�A�R�s�[�{���đ����Ă��ꂽ���炾�B�u�{���̗p���A���Ԃ��̐j���Ƃ��ɐ^���ԂɎ_�����Ă��ĕ��O�v�̖{���A����ܕS�~�������Ƃ����B�[�ӁB���낢��ȈӖ��Ŗʔ����{�����A�܂��͉ו��̒����̏������ǂ܂���B���̋�Ȃǐ������������ɁA���������Ă���B�u�N����r�̈����͂���S���Z�I�Ɉ�����̂ɂ��炸���ČN���l�i��萶�����肵���̂Ȃ邪�̂ɗ]�̌N��o�~�t�Ƃ��Đ��q����̔O�X�Ɉ�w�̐[�������ւ�����炸�v�B
��Ƃł������������̖̂ڂ��A�悭�����Ă���B�G���̂��̂ƌ����Ă��A�����x���Ȃ����낤�B�����ɉ��������ꂻ���ȏ����ȉƂ́A�ꌬ�ł��O���ł��Ȃ��A�łȂ��Ǝ��o�I�ɍ��肪�����B�ꌬ�ł͂��܂�ɂ�����Ȃ��A�����ɂł�������Ă��܂������ŁA�������ă��A���e�B�Ɍ�����B�����̌������݂̂���������āA�傪(�G��)�n�����̂悤�Ɍ����邩�炾�B�t�ɎO��(���邢�͂���ȏ�)���ƁA�ɂ��₩�����ė����ꂻ���ȕs���芴������A����܂����A���e�B�������B���̂��Ƃ���A�����ɂ͂ǂ����Ă��u�v�łȂ���Ȃ�Ȃ������B�l���Ă݂�A�u��v�͕��̂炯��ŏ��P�ʂ��B���������āA�s����B�v�w�Ȃǂ̓�l�g�́A�u��v��Ր́u��v�ɂ���(�܂�u�s��v�ɂ�����)��]�ɔ����Ă���̂ŁA�炯��m���������킯�ł���B���łɏ����Ă����A�莆�̌���́u�s��v�B����́A�u��v�ł͂Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA�u�ȏ�A���낢�돑���܂������A�u��v�̂悤�ɔՐ̒��g�ł͂���܂����v�ƌ������Ă���̂ł���B���ꂪ����ŁA�u�O�v�ƂȂ�Ɓu�C�v�̂悤�Ɉ��肷��̂�����ʔ����B�Ƃ���Łu��́v�̓ǂ݂����A���Ƃ́u�������v�Ɠǂނ悤���B�ł��A���̋���܂����t�Ƃ��ēǂގ��́A�u��������v�ɌŎ��������B�u�������v���Ȃ�āA���{�̉͂���Ȃ��݂��������炾�B�����Ƃ��A�������g�́u�������v�h�ł��傤�ˁB���̂ق����A�n�G���Ȗ��������ƔZ���Ȃ�̂Łc�c�B
�~�J���~�葱���Ĕ×��������ȂقǑ���������͂̂قƂ�ɂۂ�ƐS�ׂ��Ƃ����Y���Ă���B
�����@/�@�����̔o��E�Z�̂̋��l�E�����q�K���A�����������S�����Ă����u�V�����{�v����̕��|���ŁA���Ƃ����낤�ɔm�Ԃ̑�\�I����̈�u�܌��J�����߂đ����ŏ��v�����������ɏo������ŁA�����畓���ɌR�z���グ�Đ�^�����ԂɏՌ���^�������Ƃ́A�i�n�ɑ��Y�u��̏�̉_�v�ɂ��`���ꂽ���������A�����̎咣���Ă��A�����炭�ۛ��ڂɌ��Ă��ۛ��̈����|�����낤�Ǝv���A���ł����u�J�ߎE���v(�H)�ɋ߂����̂�������Ǝv���B�m���ɁA�u���߂āv�̎��́u�ŏ��v�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤����[�l���ł���A���z����╽�}�ő��ɑ��A���ł���Ƃ����������������錤�����܂��ꂽ���o�����蓾��͎̂�m�ł���̂����A���̏ꍇ�A������Ɗi���Ⴄ���낤�i���`(�E�E�E�ق��Ă���A�ق��Ă��`)�Ǝv���̂������ȂƂ���ł���E�E�E�Ƃ͂������̂́A�o��E�Z�̊v�V�̎���҂ł���Ɠ����ɁA����ΐV������u�����X�ƌf�����A�W�e�[�^�[(������)�ł��������q�K�̎���w�i������A���̈��̎��ߑ㕶�w�I�Ȏʎ��E���A���Y���I�ȑ��ʂɊ������A���̕ӂ������]�������̂��낤�ƁA���̖ڂł͕]��������̂��낤�B �@
�G��́u�܌��J(���݂���)�v�ʼnāB�A��܌��ɍ~��J������A����́u�~�J�v�Ɠ��`���B���������G�߂̓������J�Ƃ����Ă��A�̂̂���ɂ��Ă͓���������ւ���K�v������B�̂́A�P�ɟT�����������ł͂��܂Ȃ��������炾�B�u�䓤(�݂�)�v�́A���쐅�n�̒Ꮌ�n�т̒n���ł���A���̒n�}�Ɂu(��)�����v�u�����v�ƌ����鋞�s�x�O�̂����肾�낤�B���ӂɂ͗���A�ؒÐ�A�F����A�j�삪����Ȕ��ւ̂悤�ɂ��˂��Ă���B���J�Ő삪�×�������A�t�߂́u����(������)�v�Ȃǂ͂ЂƂ��܂���Ȃ��B���Ƃ��Ƃ͗�����Ȃ��Ă��A�H�̎��n���ǂ��Ȃ邩�B�f��́A���܂ɍ^���ɂȂ�͂��Ȃ����ƐS�z�Łu�Q�o�����v�ł���l�����̂��Ƃ��v������Ă���B�����ɂ��Ă͒������G��I�ł͂Ȃ���ł��邪�A����قǂɌ܌��J�͂܂����낵�����R���ۂł��������Ƃ�����������B�����Ȃ�Ă��̂���Ȃ������킯���B�����悤�ȋ傪�A������傠��B�u���݂����c���Ƃ̈łƐ��ɂ���v�B�u�c���Ƃ́v�Ŏv���o���̂́u�c���̌��v���B�R���ɏ�������������c�̈��Ɏʂ钇�H�̌��B���ꂱ���G��I�ŕ����Ŕ������������A���ܕ����̊�O�ɂ���̂́A���J�̂����ʼn����ʂ��Ă��Ȃ��c�ނ̂�Ȃ�ł���A���Ȃ�ʁu�Łv�������Ă������Ȃ̂ł���B������͏������G��I�ȋ�ƌ����悤���A�[�ǂ݂���Ȃ�A����͕����̈��W���鋹�̓����r���U��ƂƂ�Ȃ����Ȃ��B������ɂ���A�̂̔~�J�͎��R�̋��Ђ������B������~�J�̐���Ԃł���u�܌����v�̋L�������Ƃ��̊�тɂ́A�i�ʂ̂��̂��������̂ł���B
���Ƀw�\�}�K���Ԃ����͂Ȃ�����ǁA�m�Ԃ╓���̌܌��J�̖���́A�����Ĕ����Ēʂ点�Ă����������B�u�L�����v�ɂ��A�u���v�͌܌�(�T�c�L)�̃T�ɓ����A�u�݂���v�͐���(�~�_��)�̈ӂ��Ƃ����B�t�̉Ԃ����ɂ�鋶�N���I����āA�~�J���ނ�����܂ł̂����z�b�Ƃ��鎞�G�̒��J�ł���B�J�ɂ������āA������菭�X�ɂ��ł����D�����A���ւ��Ԃ߂悤�Ƃ����̂��낤���A�u���āA�����͂ЂƂ¥����v�ƁA���ǂ�ł��ɐ��o���Ă���B�{���̎d�����Z�������߂ɁA�����������Ă������y���݂Ȃ̂��낤�B�J���W�߂Ċ������ꂪ�����Ȃ��Ă����́A�ݕӂ��u���Ă��鎩���̏M�������Ă���̂�������Ȃ��B���z���ɏM�Ɏ��������炿�瑗��Ȃ���A�E�f���ӂ���Ă���B�D���d���Œb����ꂽ�����܂����E�f���Ղ����ł��Ă������ǂ�́A�܂����낤�͂����Ȃ��B�D�����Ԃ����l���W�܂��Ă��āA�����Ȃ���₩���Ă���̂�������Ȃ��B�u�D����߂āA���ǂł��n�߂���H�v(��)�B���̋��ԕ��w�Ƃ́A���悻�\����قɂ��Ă���f�o��B�������A���ǂ��łD���������Ɗώ@���Ă���܂Ȃ����́A���Ԃ̈�ʂ���Ă���悤�Ɏv����B���Ԃ̋�͔��������ĊÂ����ĥ����ƕ]����l�����邵�A���������������B����ǂ��u�c�l��F�����Ђ��t�̐�(����)���v�Ȃǂ́A�����ɂ����Ԃ炵���@�ׂ����A�����ĊÂ��͂Ȃ��B�w���l�o��Ύ��L�x(1969)�����B
�����O�\�l�N�A���̑O�N�̍�B�q�K�͍��݂̈�����J�ɉ���̏��̎R���̂悤�Ɍ��Ă����B�a��̎q�K�ɂƂ��āu����������v�͎������낤���A�l�Ԃ͔ӔN�ɂȂ�ƌ����̂��܂��܂̕��i�ɑ��Ă���Ȋ��S�����悤�ɂȂ�̂ł��낤���B�u����ׂ��قǂ̂��Ƃ͌��v�͒d�m�Y�Ŏ��Q����O�̕��m���̌��t�B�u�t��a�ݏ��̍��q������������v�͐����O�S�̐��B�O�S�̒��ɂ��̎q�K�̋�ւ̎v�����������̂��ǂ����B���̐�������Ƃ��͒m���̂悤�ɒB�ςł���̂����z�����A�Ȃ��Ȃ������͂����Ȃ��B�q�K���O�S���u����������v�Ƃ����Ȃ���u����v���Ƃւ̎�������������B�v���Ύq�K�����������u�ʐ��v�͐��m�悪�q���g�ɂȂ����Ƃ����̂���������A���́u����v�Ƃ������Ƃ��u������v���ƂƓ��`�ɂȂ�q�K�̋��U���傫�ȓ��@�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�����邱�Ƃ͌��邱�ƁB���邱�Ƃ̒��Ɏ��Ȃ̏u���u���̐����������邱�Ƃ��u�ʐ��v�ł������B�w���{�̎���3�E�������Ɂx(1975)���ځB
�A��ԁA�Ƃ����������ł��邱�Ƃ������Ƃ������A���܂��o��������Ƃ��Ȃ��B���̊G��W�̋A��ɁA���������グ�ĒT�������Ƃ����邪�A�����~�܂��Ĉꐶ����������Ƃ����̂��Ȃ��Ⴄ���Ȃ��A�Ǝv���Ă�߂��B�͂�F�̒뉀������Ă��āA�^�����Ȃ��̋A��Ԃ����傱��ƍڂ��Ă���̂ɏo����Ƃ͂悭����B�����ɂ��A�Y���A�Ƃ�������ŁA�l�I�ɂ͂��܂�D���łȂ����̉Ԃɂӂƈ����̗N���u�Ԃ��B�f�o��̋A��Ԃ́A���Ȃ̂��낤�B�Ԃ��Ƃ炦�鎋�����v�������ׂ�ƁA����Ɠ_�A����Ɛ��A�O�ɂȂ�ƎO�p�`�A�܂�ʂɂȂ��āA�X�S�̂ɂӂ肻�������t�̓�������������B�m���ɂ����������ƁA������ɂ�������ɂ��炢�Ă��Ă܂��ɁA�����炫�A�̊��������Ȃ肻�����B�ȑO�A�o��̒��̐��A�ɂ��Ęb��ɂȂ������A�����́q�܌��J���͂�O�ɉƓr�́A���ׂ̖�肾���łȂ��A�ꌬ�ł͂��������ꂻ�������A�O�����ƊԂ�������A�Ƃ����ӌ��ɂȂ�قǂƎv�������Ƃ�����B���̂�����A���̂ɂ���Ă��l�ɂ���Ă������ɈႢ�������B�u���^�v(2009)�����B
�܌��J�͌Â�����o�~�ɉr�܂�Ă������A���߂Ĉ��p����̂����߂����قǂɖ��傪����B�܌��J�̈Ӗ��́A1.�u���v�͈�̐A�t���Łu�݂���v�͉J�̂��ƁA2.�u���v�͂����A�u�݂���v�͐���(�݂�)��̂��Ɓ\�\�ȂǂƐ�������Ă���B���J�Őg���S�������������Ă��锄��Ȃ��|�l���A���K��������X�������ɕs���R���Ă������A�Ȃ�Ƃ����K�������W�߂邱�Ƃ��ł����B���K�Ƃ������K�Ƃ������̂͂������m��Ă���B���āA�ɂɂ܂����ē��ւł��s���ď��X�̎��ɂ���������A�Ƃ����C�����ł���B�n��������ǁA�ނ��낻�̂��Ƃɐg���S���Z���Ă���]�T���������āA�ߜƂȋ�ł͂Ȃ��B�������͔��Ƃł���B�u�K(����)�v�͖{���A�����ő���ꂽ�u�����v�ł͂Ȃ��A���K�̂��Ƃ��Ӗ������B�u�K���A���܂����B�肥�o���Ă���ȁc�v�Œm���闎��u�����v������B�m�Ԃ́u�܌��J�̍~��c���Ă�����v�̂悤�ȁA���h�ő傫�ȋ�̑ǂɂ���̂Ă��������B�ӔN�ɔ��������Ƃ��납��u�C�Ⴂ�n�y�v�Ƃ��Ăꂽ�O��ڔn�y�́A�d�S���Ƃ����o���������Ă����B�Ȏq����q���Ȃ��������A���̍����͋g��E��u�꒼�Ƃɂ������ꂽ�B�u�Ǐ��ƂŔo����悭��(����)�c�����ɂ�����ƂȂ�ł͂̐������ɂ��ӂꂽ����r��ł���v(��쐽��)�ƏЉ��Ă���B���Ɂu���������̎������̂��������v������B��쐽��w�吳�S�b�x(1998)���ځB
���ꂩ���T�ԂقǁA�����n���ɂ͉J�͗l�̗\�o�Ă���B���悢��~�J���肾�낤���B�����͋���܌��O��������A�~��o���ΐ��^�����́u�܌��J(���݂���)�v�ł���B���̋傪�����̉w�O�̏�i���r���̂��͂킩��Ȃ����A���Ȃǂɂ͂ƂĂ������������͋C���������čD�������B�����̉w�O�͂ǂ�ǂ�J�����i�݁A�����ӂ�ł͂������̂悤�Ȓ�H�����ۂ��H�����Ȃ��Ȃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�̂̉w�O�Ƃ����A�K������ȏ����Ȓ�H���������āA�����ȃp�`���R�����Ƃ��{���Ȃǂ�����A�J�~��̓��ɂ͂���炪����������Ō����ēƓ��̏��������B�܂����̒������܂̂悤�ɃM�X�M�X���Ă��Ȃ��������ɂ́A�V�C��������A���m��ʐl���m�̐S�����݂��Ɋ��Y���悤�ȕ��͋C���o�Ă��āA���J�̋C�����Ƃ��ɂ͈����Ȃ������B���������Łu�悭�~��܂��˂��v�̈��A�����킳��A�����̉w�A�����̐H���A�������炽�ǂ邢���̉ƘH�B���̋�ɂ́A�����������Ƃ̌��������ɁA�̂̏����̕�炵�Ԃ�܂ł����z�N�����閣�͂�����B���݂���Ă��閼�����ՂȂǂ����A������̕��}�Ȍ܌��J�̂ق��������ƍD�����ȁB���̏�i�ɁA���ɂ͍��Z�ʊw���̂܂������������~�������w�̗l�q���d�Ȃ��Č����Ă���B���ꂩ����������I���o���Ă��܂����B�w�E�ځx(2010)�����B
�܂�A���ɂȂ�������N����̂ł͂Ȃ��A�ڂ��o�߂����̎������Ȃ̂���ƁA���̂悤�ȈӖ��Ȃ̂ł��傤���B�N���čs�����N�������߂̖���ł͂Ȃ��A���肻�̂��̂̂��߂̖�����A��������ƂƂ�����̖ڊo�߂ł��B���ǂ�ł��邾���ŁA�������L���o�Ă������ł��B���������A����̒��ł����ƕ������Ă������́A���̊O�ɓr��邱�ƂȂ��~��J�̉����������ƁA�ڊo�߂Č�ɕz�c�̒��ŋC�Â��̂ł��B�Ȃ����̉J���A����Ȃɂ������Đ����邱�Ƃ͂Ȃ��A�����Ƒ̂��x�߂Ă��Ă������̂���Ƃ����A�D���������̂悤�ɂ��������Ă��܂��B�������A���������ł͍���܂����A���܂ɂ́A�܌��J�̋��āA�ڂ���A���̂܂��̖��֗����čs���Ă������̂�������܂���B�w�p��o���Ύ��L�@�āx(2006�E�p�쏑�X)���ځB
���̔o��́u�������т��c�c�������߁v�Ɠǂ݂����B�u���݂���v�́u���v�́u�H���v�u���c�v�́u���v�Ƃ��A��̐A�t���̂��ƂƂ������A�u�݂���v�́u����(�݂���)�v�Łu�J�v�̂��ƁB�~�J�ǂ��A�~��Â��J�ŊO�������v���悤�ɂł��Ȃ������́A��������Ƀh�^���ƂӂĂ�����ĐQ���ׂ��Ă��邵���Ȃ��B����ȂƂ������悭���悤�ɁA���݂Ȃ����т��ѐQ����ς��Ă���̂��B����������낵�Ă��鎔����A�ǂ��ƂȂ����݂Ȃ��v�������Ă���ɂ������Ȃ��B���������~���܂Ȃ��J�A���������Q��Ƃ��Ȃ��Q�Ă��邵���Ȃ����B���������������Ă���Ȃ����Ȃ��B�~�J�ǂ��̖��ւ̎��Ԃ��A�f��ɂ͂������Ɨ���Ă���B�ۑ��Y�͎��l���������A�o��������B�������Y��ƘA��̗֍u������������Ɏ��݂������ł���B���̍앗�́A���ꂢ�Ȏ��R�̕��i��`���Ƃ������X�������������B���Ɂu���ق�舼�錩���ē��Ă�J�v�u�t��峎��̂Ă�̏H�v�Ȃǂ�����B�w���l�o��Ύ��L�x(1969)�����B
���k����1968�N�ɒk�u�̒�q�ɂȂ����A���여�̌ÎQ�B�܌��J�̎��G�AOFF�̌|�l�����ւ��Ԃ߂Ă���Ƃ����}��������Ȃ��B���摜���ۂ��A�ǂ���ł����܂�Ȃ��B�J�̓��͂����������Ȃ��ŁA�̂�т�Q���ׂ��đ��̗��ʼnJ�̒���������߂Ă���A����ȕ���͂ނ���D�������B���ꂪ�|�l�Ȃ�Ȃ��̂��ƁB���̗��ɒ�߂�����Ȃ�āA�����ɂ������Ă���B���̂Ƃ���̂ق��͂��������������Ă����̂��낤���H�@�u���̗��v���������ăz�b�Ƃ���B�B�X�����Ԃꂪ���낤�u�ʋ�ʋ��v�̐ȂŁA���k���͂������ɂ悭����ׂ�A�Ő���܂߂Ă͂��Ⴂ�ł���l�q�ł���B���Ȃ݂ɁA���̋�Ɍ�����ꂽ���ꓯ�̕]������Ă݂悤�B�u�悻�ɏo���Ă��ʗp����v�u�����ɂ��ӑĂȒj�̋�ł��v�u�w���Q(�͂���)�_�x�݂����v�u�����Q�Ă���ЂƂ���Ȃ��Ɖr�߂Ȃ��v�u���̗��������v�u���̕\��������ɐ������炷�����v�u�Â����{�l���ʂ̃m�X�^���W�[���v�c�c�݂Ȃ���Ȃ��Ƃ������Ă���悤������ǁA�i���z�h�ł���B���k���̔o���͎Ւf�S�B���ł́A���Ɂu�O���̎R�����₩�ɐl��ۂ݁v������B�w�ʋ傽������x(2013)���ځB
���O�Ɍ���Ȃ�����ǁA�������Ă��ꂵ�����Ȏq�ǂ�����������ɂ��A��Ȃ炸�Ƃ��u�����͂��邩�v�Ƃ������O���A�g�����Ń��O���O���Ă��܂����Ƃ��ߔN�����Ă����B�����炪�g�V�Ƃ��āA�����̎��Ԃ��ǂ�ǂ��Ă��Ă��邱�ƂƁA�����炭�W���Ă���̂��Ǝv���B����ɂ��Ă��A��s���z�肵�悤�̂Ȃ����@�[�Ȏ��オ�������Ă���C������B���Ȃǂ��q�ǂ��̍��A�킪�c�ɂł́u���O�v�Ƃ��������\�ȏj���̕��K�ȂǂȂ������B������u�n�b�s�[�o�[�X�f�C�v�Ȃ���̂����āB������A�킪�q�́u���O�v��u�n�b�s�[�o�[�X�f�C�v�ȂǂƂ������j�����ł́A�ނ��낱���Ƃ�e�̂ق�������疭�ɏƂꂭ�����������A�������Ȃ������B�q�ǂ��Ɍb�܂�Ȃ�������̋�Ƃ��ēǂނƁA�܂��[�����S���o���Ă��܂��B�������u���̎q��v�̖��������łȂ��A���������e�̖�����l�ނ̖����ւ̎v�����A��͏d�˂Ă����͂��ł���B�f��́A�T�C�g�u�o��q�C�����v��2010�N11��15���ɔ��\����Ă���B�S���Ȃ锼�N�O�̂��Ƃł���B�S���Ȃ��T�ԑO�̋�́u�܌��J�č���Ă䂭�̂��䂪�c���v�ł���B�u�q��̖����v��u�䂪�c���v�Ȃǂ��A�Ō�܂ŝ�̓������邱�Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ��B�w�o��q�C�����x(2013)�����B
�w�b�h�z���Ƃ����̂�����A�������Ɂu���͂�(�������E��)�v�ɂ́u���v������B�������������͕��ʁA�����ɂ́u���v�ł͂Ȃ��u��v������ƔF�����Ă���B������킴�킴�u���v������ƌ�����ƁA�����͂Ƃ������A�u��?�v�Ǝv���Ă��܂��B�����Ă��̐l�́A����������ɓ���˂������Ă���̂��낤�Ƒz������̂��B�܂�A�w�b�h�z����t���ĉ����ނ��Ă���l���v�������ׂĂ��܂��Ƃ����킯���B�w�b�h�z������͂ǂ�ȉ��y���������Ă���̂��͂킩��Ȃ��B���A���Ȃ���u���݂���v�̂悤�ɕ������Ă��鉹�y���A���̐l�̎��͂ɍ~���Ă���܌��J�̉��ɁA�n�����ނ悤�ɓ���������Ă���悤�ł���B�������ƁA�����炭�͐N���ɂ��邻�̐l�̟T�������S��v���āA�ǎ҂͂���Ɩق荞�ނ����Ȃ��̂ł��낤�B�w���}�x(2014)�����B
�[�](�~�\�T�U�C)�͐�����⏬���߂̓��{�ŏ��̏����ł���B�Ă̍�������~�̒�n�Ɉڂ�Z�ޗ����ł���B���݂̎q�K���͓����̏�Ԃɋ߂���Ԃŕۑ�����Ă���B�J������Ă���̂ŖK���l�������B�����ɐQ�]��Œ�߂Ă���Ɖ����̕���Ƃ��ǂ��q�K�̐S��Ȃ��ǂ��Ƌ��ɔ����Ă���B�����o�債�����ݎ���̐S��ł���B�a���̐�����o�܂����̂̓~�\�T�U�C�̃`���b�c�`���b�c�ƒn���B���ꂪ�y���݂ō؋����ɎT���Ă������̂��B�҂��l����悤�Ȏ����̊�т��ǂ��ƏP���B�����ł̋偃�܌��J����̎R�����������聄���������Ƃ̋A��x����ܓ��������ь炭�ӂĉ��O�̑O�Ɏ��Ȃ�Ɓ��Ȃǂ��g�ɟ��݂�B���l���q�I�w�q�K��W�x(1993)�����B
�܌��J�͉A��܌��̉J�A�~�J�̂��ƁB���x�̍�����焈Ղ��Ȃ���A�l�͔����ȏ㐅���łł��Ă���̂Ɂc�A�l�Ԃ͐��̒��Ő��܂ꂽ�͂��Ȃ̂Ɂc�A�Ƃ���߂����v���B������Ώ����ŕ��傪�o�A������Ί����ŕ��傪�o��B���Ƃ͖��Ȃ��̂ł���B���������̕���̑����̂����߂�A���̉��ŁA�זE�͐����Ȃ��Â��ɐ������J��Ԃ��Ă���B�~�葱���J�̂Ȃ��ł����Ƒ̂̉��ɖڂ��Â点�A���Ǝ��������g�߂Ɋ��Y���Ă��邱�ƂɋC�Â��B�V��ӂ̃T�C�N���ׂĂ݂�Ɓu�����܂����̊p�w���ω����Ăł������́A�܂莀�זE���W�܂������̂ł�(�ԉ��u���ƒn���̍\���ƂȂ肽���v)�v�̋L�q�������B�̂̉������ł͂Ȃ��A�\�ʂ����זE�ɕ�܂�Ă����̂��B�Ռ������ނ���A�ނ��o���̐����A���ɕ�܂�Ă���ƒm���āA�ǂ������������̂́A�N�̂����A���낤���B�q�ꐶ�̍������肼�{�[�g�����r�q�W�Ȃ��W���߂����эs���r�w���сx(2016)�����B�@
 �@
�@ �@
�@
���o��
�ےÍ������S�єn��(���܂ނ�)(���F���{���s�s����єn��)�ɐ��܂ꂽ�B���s�{�^�Ӗ쒬(���O�㍑)�̒J���Ƃɂ́A����Ƃ������������ɕ���ɏo�Ď�l�Ƃ̊Ԃɂł����q���������Ƃ���`���ƁA����̕悪�c��B�����ɂ���{�ɂ́A�c���̕������ꎞ�a����A��N�A�O��ɖ߂�����������Ƃ��ě����G�����ƌ��`����Ă���B
20�̍��A�]�˂ɉ���A����b�l(�͂�� �͂���k�锼���v��(��͂�Ă� ������)�l)�Ɏt�����Ĕo�~���w�ԁB���{���Β��u���̏��v�ӂ̎t�̋����ɏZ�܂������B���̂Ƃ��͍ɒ��ƍ����Ă����B�o�~�̑c�E���i�哿����n�܂�A�o�����邱�Ƃւ̋������������B�������]�˂̔o�d�͒ᑭ�����Ă����B
����2�N(1742�N)27�̎��A�t���v�������Ɖ���������(���F��錧����s)�̍����哆(�������� ����Ƃ�)�̂��ƂɊ�����A�h���炤�����m�Ԃ̍s�r�����ɓ���Ă��̑��Ղ�H��A�m�̎p�ɐg��ς��ē��k�n�������V�����B�G���h��̑���ɒu���ė�������B����́A40���ĉԊJ�������̏C�s���ゾ�����B���̍ۂ̎�L�Ŋ���4�N(1744�N)�Ɋ哆�̖����ʼn��썑�F�s�{(�Ȗ،��F�s�{�s)�̍����I��(���Ƃ� �낫�イ)��ɋ��������ۂɕҏW�����w�ΒU��(�F�s�{�ΒU��)�x�ŏ��߂ĕ������������B
���̌�A�O��ɑ؍݂����B�V�����ɋ߂��{�Âɂ��錩�����̏Z�E�E�G�_�F�_(�o���F�|�k)�ɏ����ꂽ���̂ŁA���n�̔o�l(�^�Ǝ��Z�E�̍�\�A�������Z�E�̗��b��)�ƌ𗬁B�w�͂����Ă�x�Ƃ������e���c�����B�{�Îs�ƁA��̋����ŗc�������߂������Ɩڂ����^�Ӗ쒬�ɂ͕������`�����G�������c��(���������Ƃ����{�����w���m���s�V���q��}�����x�A�]���������w���|�}�����x)�B����ŁA�^�Ӗ쒬�̗��l�ɂ����܂�ĕ`�����G�̏o���Ɍ�����āA�{�ɏW�߂ĔR�₵�Ă��܂����Ƃ̓`��������B
42�̍��ɋ��s�ɋ����\���A�^�ӂ𖼏��悤�ɂȂ�B��e���O��^�ӂ̏o�g�����疼������Ƃ����������邪�肩�ł͂Ȃ��B45���Ɍ������Ĉ�l�����̂�ׂ����B51�ɂ͍Ȏq�����s�Ɏc���Ď]��ɕ����A�����̍�i����|����B�Ăы��s�ɖ߂�����A����(����)�p���ŋ��������ȂǁA�Ȍ�A���s�Ő��U���߂������B���a7�N(1770�N)�ɂ͖锼���ɐ��Ղ���Ă���B
���݂̋��s�s�����敧�����ʉG�ې������̋���ŁA�V��3�N12��25��(1784�N1��17��)�����A68�̐��U������B�����͏]���A�d�lj����ǂƐf���Ă������A�ŋ߂̒����ŐS�؍[�ǂł������Ƃ���Ă���B�����̋�́u����~�ɖ�(����)������ƂȂ�ɂ���v�B�揊�͋��s�s�������掛�̋�����(����Ղ���)�B
����Ƙ_
�����m�ԁA���шꒃ�ƕ��я̂����]�˔o�~�̋����̈�l�ł���A�]�˔o�~�����̑c�Ƃ�����B�܂��A�o��̑听�҂ł�����B�ʎ��I�ŊG��I�Ȕ���ӂƂ����B�Ƒn���������������̔o�~��J���u�ԕ���A�v�������A�G��p��ł���u�����_�v����ɓK�p�����V�����̔o�~���m�����������S�I�Ȑl���ł���B
�G�͓Ɗw�ł������Ɛ�������Ă���B
���㐢����̕]��
�o�l�Ƃ��Ă̕����̕]�����m������̂́A�������̐����q�K�w�o�l�����x�A�q�K�E�����Ⴝ���́w������W�u�`�x�A���a�O���̔����Y�w���D�̎��l�E�^�ӕ����x�܂ő҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
����12��25���́u�������v�B�֘A�̔o��𑽂��r�B
�E�������Ɍ��t���悫�������� �����q�K
�E�������̐S���Ԃ⋞�O�� �،��l
2015�N10��14���A�V����w�����V���}���ق��w�锼��������W�x�̔����\�����B1903��̂������m�̔o��212������^�B
���̍앗�͕`�ʓI�ł���܂����A��̕��i�͌��������̂܂����\���Ƃ������A���z�����ꂽ��z���E�I�Ȃ��̂ł��B
�@�@�@�u�܌��J���͂�O�ɉƓv
����͕�����62�̎��ɍ�����L���ȍ�i�ł��B�܌��J���~�葱���Đ����𑝂����삪����Ă���B���̂قƂ�ɉƂ��A�ۂ�ƌ����Ă����A�Ƃ����Ӗ��ł��B
�������\����o�l�E�����q�K�́A�V���w���{�x�̕��|���ŏ����m�Ԃ̖���u�܌��J�����߂đ����ŏ��v�Ƃ��̋���ׂāA�����̕����D��Ƃ��Đl�X�ɏՌ���^���܂����B�����q�K�Ɍ��킹��ƁA�m�Ԃ̋�͋Z�I�I�ɂ��܂����āA�������낭�Ȃ��̂������ł��B
�����Ɏ���܂ł́A�����m�Ԃ̕������|�I�ɒm���x�����������ł����A�����q�K���m�Ԃ��_�i������Ă���̂Ɋ�@���������A�u���������āA���������I�v�Ƃ��̌��т��]�������Ƃ���A�悭�m����悤�ɂȂ�܂����B
�����q�K�̔o��v�V�ɑ傫�ȉe����^�����l���ł��B
�^�ӕ����́A���ی��N(1716�N)�ےÂ̖єn��(���s�s����єn��)�Ő��܂�܂����B�Ƃ́A���̗L�͎҂ł����������ł��B�����A�\��̍��ɕ��ƕ��S�����A�Ƃ������āA20�ō]�˂ɏo�܂����B���̓�N��A�]�˂ŁA�锼���b�l(��͂�Ă��͂���)�Ƃ����o�l�ɒ�q���肵�܂��B�b�l�́A�����m�Ԃ̍���A��䑴�p(�����炢������)�ƕ�������(�͂��Ƃ���)����o�~(�o��)���w�l�ŁA���̂��߂������͔m�Ԃh���Ă��܂����B
27�̎��ɁA�t���̔b�l���S���Ȃ�܂��B���̌�A�����͍]�˂��o�āA��錧����s(��������)�ɏZ�ޓ����b�l�̒�q�̌��ɐg���܂��B���ꂩ��A�\�N���̊ԁA���k�n���A�֓��n���𗷂��Ď���A�G��o�������ĉ߂����܂����B�m�Ԃ̗������u���̍ד��v�������������܂����B�@
36�ɂȂ�ƁA���ɏ��܂����B���R�̘[�ɋ����\���āA�����ɒ�Z���邩�Ǝv������A�O�N��ɁA�{�Âɕ����A���ƂȂ鎩�R�̖L���Ȓn�ŁA�G��`�������܂����B���̌�A���쌧(�]��)�Ȃǂ��V�����A45�Ō�������ƁA����Ȍ�́A���ɏZ�ݑ����邱�ƂɂȂ�܂��B�����A�Y���_(������)�A�������g(�����Ȃ����傤��)��́A�O�َЂƂ����o�匋�Ђ����A�o����ɗ�݂܂����B�@
���̌�A55�ŁA�t���̖��ł���锼�����p�����܂��B��ƂƂ��Ă��o�l�Ƃ��Ă������͗L���ɂȂ�A�ނ̎�Â��锭���ɂ͑����̐l���W�܂�悤�ɂȂ�܂����B
���̍��A�o�~(�o��)�̐��E�́A�Ƒn���������čs���l�܂��Ă���A�����͏����m�Ԃ�c�Ƃ���ԕ��̗��h�������悤�ƁA�����U��܂����B
68�̎��A���a���������A�Ȏq���q�����̕K���̊ŕa�ɂ��ւ�炸�A���̐�������܂����B�@
�@�@�@�u���݂���╧�̉Ԃ��̂ɏo��v
�~�肵����J�̒����Ԃ��̂Ă�A�Ƃ����⛌���̂悢��ł��B�u���̉ԁv�Ƃ͕��d�ɋ����Ă����Ԃł��傤�B�S���Ȃ����̂͒N�ł��傤���B�������z�����悢�قǁA�����Â��ԚL�c�c���̔ߒQ�ɂ����A�J�͍~�蒍���Â��Ă��܂��B
�Q���T��₢�Â��Ƃ��Ȃ��t�͗���
��o�����͕̂��������Y��
���߂╨�프�ɓ��̓���
�r�c����Y���ꂵ�t�̊�������
�@�@�@萂̌˂̉Δ����Ђ����]������
�@�@�@��ƁT���ɏĂ�n���̂����݂���
�@�@�@���́T�߂ɏ��J�~�o���Ė삩��
�@�@�@�ł̉J�₷����̔��͂�
�@�@�@����Ƃ̔~�ɒx������������
���ނ���ɕ~�Ĕ~������
��ɏI���������̐l
���̌˂�̂킩�߂���Ђ���
�g���ɓ��������ɐ��̏o�X����
�t�̐��R�Ȃ����𗬂ꂯ��
�@�@�@�Ȃ������Î�̗���c������
�@�@�@�ʂȂ͐��Ӓr�̐�������t�̉J
�@�@�@�킩����J�̏�������t�s
�@�@�@�b�ǂŗ��o�闷�̂���������
�@�@�@�t�J���邢���ʎ��ޗǂ̏h
�k�Ⓓ���֚e�ʎR�A��
�m�X�_�̎�����ɖ��ӓs�l
�È�˂̂��炫�ɗ���ւ���
�_�z�ɂ��̂���������ږ���
�̂��Ŗ���������J�̂Ђ�
�@�@�@����̎��Ɉ������H����
�@�@�@�܂��Ă�n���ق�ĕ�x��
�@�@�@���l�̕@�܂�������������
�@�@�@�悵��o�Ė����炵��O����
�@�@�@���̉Ԍ��ɏ���ޏ�����
�N���߂̂Ђ��������͂�̂���
�I�����m�̂���Q�⏪�̏t
�t���������̖̊Ԃ��
�Ԃ�����O�ɂU����ӂׂ���
�t�̊C�I���̂���̂��肩��
�@�@�@�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐���
�@�@�@�Ȃ̉Ԃ�⢌���鏬���C�~
�@�@�@�̉Ԃ�~����炸�C���
�@�@�@�̉Ԃ�F�o���Ђ���D
�@�@�@�t����璷�����ĉƉ���
�t���̂܂����ւ�����t����
�t���̂�����Ђ���╂�l�`
�����̂ӂ̋�̂���ǂ���
�Ԃ������������Ē��Q��
��g���⋞�����������w
�@�@�@�C���┒���ɍg����܂Ă�
�@�@�@�䂩�������Ԃ����J�̒�
�@�@�@��������特�Ȃ��J���U
�@�@�@�c��①�n�̍��U��ɂ���
�@�@�@��Ƃ��̒����E�ɂ��蕃�ƕ�
���N���\�͂��߂ʏ��S��
�t�ɍ����ĉ����^�������邩��
�@�F���Ă��ǂ�钹�H�̊^����
�T����₠��ʏ��ɔ���
�R���Ƃɕē��މ��ⓡ�̉�
�@�@�@�䂭�t��畏��Ƃ��Ēx������
�@�@�@�s�t���҂����މ̂̎�
�@�@�@�䂭�t�₨���������i�̕����T��
�@�@�@�ԚF�Ȃ����[�悭��̏t
�@�@�@���Ƃ͂�T�g�����Q�₭��̏t
�t�����ސl��|�ɂ����ꂯ��
�x�L����賎q�̉����鋴�̏�
�x�����̂���ĉ����̍�
�x������欕���鋞�̂���
�t�̗[�͂ւȂނƂ��鍁����
�@�@�@�R���⓳�����ȂЂ̏�����
�@�@�@�F������������p��퐶�s
�@�@�@�����̂��苏�̌N��x��
�@�@�@�O���l�e��Ȃ��̉�
�@�@�@���Ƃ��t���T���ق̎R������
�݂悵��T�����������R��
�܂����Ƃ����肵�Ƃ������R��
���O�U�Ă��������Ȃ�ʓ�O��
���ł̕v�w�Ȃ肵���X��
�������̌ܐl�����Ă��͂�����
�@�@�@��������b�������̉�������
�@�@�@�ɉJ�~��܌��ܓ�����
�@�@�@�˂苟�{�܂�ᤂȂ鏬�Ƃ���
�@�@�@�Ȃ������ď��̖n�̓��Ђ���
�@�@�@�O�䎛����͌߂ɂ��܂�ᕖ
�ᒠ���o�ēޗǂ𗧂��䂭��t����
��ԎR���̒��Ɏ�t����
�@�H�Ӊ䂽�����Ȃׂ̍�����
�K�̉Ԃ̂��ڂ�T���̍L�t����
��̐����E�~�̉Ԃ̎U�邽�т�
�@�@�@���������₵���̉�
�@�@�@�Ԃ���̋��̘H�Ɏ����邩��
�@�@�@�D�Ђ��ɂ̂ڂ�ΉԂ���
�@�@�@���̏H���т����e �̋�������
�@�@�@�݂�����▍�ɂ������⛠��
�a�`�̉Ԃ��闢�Ɛ��ɂ���
���Ȃ��̉Ԃ�����������ɂ��Ƃ�
���ɏ����͏Ă�ĉZ�̉�
���݂�����͂�O�ɉƓ�
���Ă݂�Η[�̍����ƂȂ��
�@�@�@�~�ɔ����߂�����l����
�@�@�@�t�𗎂��ĉ��ɕg�̏ł鉹
�@�@�@��ѐ��O�l�@�̂����t����
�@�@�@�ʂȂ͂Ƃ鏬�M�ɂ����͂Ȃ��肯��
�@�@�@�͍��̓���ƍ炭��J�̒�
���̉Ԃ⏬�M�悹�����̑O
�ĉ͂��z�����ꂵ�����ɑ���
������Ă��ʼnߍs�锼�̖�
����O��̐l�̌�����e
���[�������炷���Ԋ�
�@�@�@��a�ƂԂ�x�m�̐���T���Ƃ��
�@�@�@�ጭ���ďh�肤�ꂵ��̌�
�@�@�@�̂�ɕ������O��Ƃ�T�`
�@�@�@���낵�u���ɒn�k�ӂ�Ȃ삩��
�@�@�@��|��[���̍���ƂȂ�ɂ���
�[���␅�����������
���肻�߂ɑ��S����������J�̖[
�n���đ��̂��Ȃ��̐��
�����ɖт𐁂ꋏ��тނ�����
�ĎR��ʂЂȂꂽ��ዷ�l
�@�@�@�����ɗ[�����͂���
�@�@�@�����}���A�̂̂��ǂ肩��
�@�@�@�@�ӂɊ������܂ӑ�b��
�@�@�@�Ƃ���Ă�t���܂ɋ�͎O���
�@�@�@鶂����Ă����҂������T�납��
��������l���ɂ��ƎD�̗���
�킭��t�Ɏ���Đ�̂��ʂ�����
��������킷��e�Ȃ鑳������
�Z��̂��𒆂悫�ق�������
�����ς�Ƃ̏��[����Ƃقꂽ
�@�@�@���������m���ڂ��s���{�Ă���
�@�@�@���ӂݘH�▃������߂̐��ԍ�
�@�@�@���̕������̂ӂɖ߂��ǂ��
�@�@�@���H��]���̓�����鏪�̒�
�@�@�@���̗t��N�r�W�̞x����
���I���قǂ����Ƃ̍��~����
�啶����ߍ]�̋�����U�Ȃ��
���҂֊��ʼnߍs����������
�O�l�̏\���ɐs�������̉�
�J���T�������̌�������
�@�@�@�Z�ޕ��̏H�̖鉓���Ήe����
�@�@�@���̗t�̍��݊�Ȃ�J��
�@�@�@������}�u�̎����e�S�̒�
�@�@�@�ҏ��⏗���邶�ɏ��q
�@�@�@��x�⑺�Ȃ������ǂ̐F
�H��幮��l��ɐ���ɂ���
��߂̑����̂���
���ނ̏��M�����Ȃ鑋�̑O
���̂��t�Ɍ����ڂ�Ȃ�|�̏t
��H�̏H������l�◈��
�@�@�@�g�t��������U�s��������
�@�@�@�S�������R����闷�H����
�@�@�@�V�Ăɂ܂����̎��̓��Ђ���
�@�@�@�ь��̏O�̏M�������_���ŏ��
�@�@�@���������ɉ������ɂ���
�s�H�̂Ƃ���^"�P�_�≺����
�����Ă���^�_�������ォ��
�������鉹���ꂵ�����
�J�̂��ڂ�����ʂ���̐Ԃ�
�q�ς̂�����ᤂȂ��e����
�@�@�@���ꂵ���̖��ɂ��܂肽��ނ�������
�@�@�@�����̐���Đ��鋼���̌s
�@�@�@����������҂͕x�܂��s��
�@�@�@����E�Г�������֕��ݍs��
�@�@�@�|��ɑl�e�Ȃ��c����
�~���ǂ��܂��O��������Ȃ���
�~�߂����J�̉_�����T��肼
�g�t����p�ӂ��������P��{
����x�̒��ɓ�����Ɨt����
�ŕԂ�����g�t���ӂ̗�
�@�@�@�Ђ��c�̈ĎR�q�������炱����ނ�
�@�@�@�s�H��悫�ߒ����邩�T��l
�@�@�@�R����Ђ̘V�ɐQ�ɂ��ǂ�
�@�@�@�˂�@���K�ƏH��ɂ݂���
�@�@�@��Ǔ��݂ĐÂ��Ɏ��̉��R����
䨗�͕����B�ꏼ�I�͘I���
���������m���ݐH�֏���
���⏬�鉺�Ȃ�����Ȃ��
�鋃���鏬�Ƃ��߂ʔ��@��
�����̉e�@�t�����[������
�@�@�@���┩�����ʍ��̎�
�@�@�@��Ε�������������̒�
�@�@�@�猩����钅���͂Ȃ�T������
�@�@�@������Ă�����ЂƂ���o��
�@�@�@����r�ɂ��ƂȂ��~�̉J
�~����⏬���̂�����B��
�K��ӗ������������̗�
��݂̂̎Đ܂肭�ׂ邻�Γ�����
�Ȃ�q�̐Q�e���������
���ɓ����~�͓��Č��ЂƂ�
�@�@�@������Ղɕ����ЁU������
�@�@�@�Y�c�@�t�Ή��̑�����M����
�@�@�@�Y���܂̕ӂ��Â����ؗ�����
�@�@�@�Y�U�܂��ق̂��T�����t����
�@�@�@�Y���ɋ��������鏗����
�䍜�̂ӂƂ�ɂ��͂鑚�邩��
�ω��鐂ɉJ�̂��܂���
�N���⊣���̑����L�̖_
�ד��ɂȂ�s�����⊦�O��
������Â���慂ӒN���q��
�@�@�@�X�铕�̖��������ӂ˂��݂���
�@�@�@��B���͂���Ƃ���Αl�s
�@�@�@��܂������ĈÂ���Ȃ肯��
�@�@�@������͖̒��̒|�O��
�@�@�@�~�̔~���̂ӂ₿��ʐ̏�
�q���S���ƂɌ䓕�̌�����
�h�����Ɠ����o�����Ⴉ��
�ɂ����̗������Ȃ��G���Q����
�鋻���⌢�̂Ƃ��ނ镻�̓�
�ł̖�ɏI���̕\����
�@�@�@�O�o�̎G�ς����Ⓑ�҂Ԃ�
�@�@�@���������|�t���X�╟����
�@�@�@�M����Q�Ԃ��o�Ē�����@
 �@
�@ �@
�@
�@�@�@�܌��J�� ���߂đ��� �ŏ��@�@�@�����m��
�����̑����Ă����~�J�̍ŏ����r��ł��B�~�J�̉J�ōŏ��̐������������A���̗���̐����������|�����炢���Ɖr���Ă��܂��B�����m�Ԃ͍ŏ��̐쉺���̌����Ċ������A�ŏ��̋}���̌�������\�����Ă��܂��B
�@�@�@�������� �C�ɂ��ꂽ�� �ŏ��@�@�@�����m��
�����Ă�1���̏I���A�[��ꎞ�ɉr�܂ꂽ��ł��B�^���Ԃȗ[�����ŏ��ɂ���ĊC�ɗ������܂ꂽ�悤�Ɍ�����A�������ݑ��z�Ƌ��ɏ���1�����I�����}����ꂽ�B�u�C�ɂ��ꂽ��v�ŋ[�l�@���g���Ă��܂��B
�@�@�@����� �Ă𗬂��� �ŏ��@�@�@�����q�K
�Ă̍ŏ��́A�����悭�����l�����ĉr�܂ꂽ��ł��B�ŏ��̐��̐��ʂ͂������A�ĂƂ����G�߂��悹�ė���Ă���悤�Ɏv����Ƃ����Ӗ��B����Ƃ����[���ꂪ�A���̐�����\���Ă��܂��B
�@�@�@�ĎR�� �݂𐳂��� �ŏ��@�@�@���l���q
�ĎR�̖X�̏d�Ȃ肠���Ă������̙z�Ƃ������������A�݂𐳂��Ă���ƕ\�����Ă܂��B���čŏ������Ė�����r�A�����m�ԂƐ����q�K�Ɠ����ŏ������āA�X�̗l�ɋ݂𐳂��v�����A�Ƃ������h�̋C������\������ł��B
�@�@�@�ь��̏O�� �M�������� �ŏ��@�@�@�^�ӕ���
�u�ь��v�Ƃ����̂́A�Ă̏o�������炻�̔N�̔N�v�̗ʂ����肷���Ƃ̎��ŁA���肷���l�̎���ь��̏O�ƌĂ�ł��܂����B�ь��̍�Ƃ�����̂��H�̂��߁A�ь����H�̋G��ƂȂ��Ă��܂��B�����N�v����낤�Ƃ�����Ȗ�l���A�ŏ�삪�D���Ɨ����Ă���Ƃ�����ł��B
�ŏ����r�����֓��g�̍�i�ŗL���Ȃ̂́A�o��ł͂Ȃ��Z�̂ł��B�Z�͔̂o��Ƃ͈Ⴂ�G�ꂪ�Ȃ��A�܁E���E�܁E���E���̂̌܋�̘̂a�̂ɂȂ�܂��B�o��ł͂���܂��A�o��Ɠ����������̊���⊴���Ȃǂ�\������֓��g�́u�ŏ��v�̗L���ȒZ�̂ɂ��Č��Ă����܂��傤�B
�@�@�@�u�ŏ��� ���ɂ��� �c���� ������������ ���̒f�Ёv
�ŏ����Ɏc��������ĉ̂����Z�̂ŁA�ŏ����̓����A���S�Ȍ`���玞�Ԃ��o�߂��Ēf�Ђ݂̂ƂȂ��Ă��܂�����i���r���Ă��܂��B���͊��S�Ȍ`�ł͂Ȃ��Ă��������A�f�ЂƂȂ��Ă��������܂܂ł��悤�Ƃ�����̌����Ȕ������Ɋ������Ă���S���\���Ă��܂��B�\���Z�I�Ƃ��ẮA���͈̉̂Ӗ�����e�A���q�̐�ڂł���u���v�ł͂���܂���B�Ō�́u���̒f�Ёv���̌��~�߂ƂȂ��Ă���A�r��ɗ]�C���c��I�����ɂȂ��Ă��܂��B
���шꒃ�̔o��ŁA�u�ŏ��v�̗L���Ȕo��͂���܂���B�u�ŏ��v�̔o��ň�ԗL���ȁu�܌��J�� ���߂đ��� �ŏ��v�Ɠ����G��u�܌��J�v���g�����A�L���ȋ傪����܂��B
�u�܌��J�� ���ɂ��ւ� �����R�v
�����R������ƁA�~�J�̉J�����ɂ�����悤�ȋC����������Ƃ�����ł��B�Z�݊��ꂽ�]�˂𗣂�Č̋��̐M�B�ɖ߂鎖�ɂȂ����ꒃ���A�����R�����Č̋��ɋ߂Â��Ă����������S�[���v���Ă���l���r���܂����B
���������шꒃ�Ɠ��l�A�u�ŏ��v�̗L���Ȕo��͂���܂���B�������u�܌��J�v���������L���Ȕo�傪����܂��B
�u�܌��J�� ��͂�O�� �Ɠv
�~�J�̌������J�Ő��̐����������Ă����̂قƂ�ɁA�Ƃ�2�������Ă���l���r������ł��B��͂̐����ɂ̂܂ꂻ���ȉƂƂ����A�S�ׂ��C������\�����܂����B
 �@
�@ �@
�@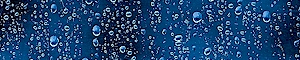
���݂���钆���d�������� ����Ǒ� �~
���݂�����m�����Βk�� ��ؘZ�ђj
���݂����A�����e�܌��� ���V�Lj�@���M
���݂����S�d�Ԃ����߂� ������
���݂���鉫�ɂ��т����~���� ��c�m�q �_�͉����Ȍ�
���݂���铔����������ɂ��� ���q��H�� �ߌ�̑�
���݂���铙�g��̌��ł��� ���c�܂���
���݂���T���U�g���菼�̉� �n�Ӑ��b ����
���݂���T��������_�����y�� �����q�K
���݂���T���Ɖ͓��̏h�ɂ��� �Έ�I��
���݂���T���̏d����قǂ����� �y��� �[��
���݂���T�L�ɔ�����ʎR�̌� �n�Ӑ��b ����
���݂���Ă�邱�ƒm�炸����Ȃ��� ���ؐ��q ����
���݂���č����ɗF�Z���K�N����Ȃ� �ь��Έ� �
���݂���ĉ����̂������� �R�{���T
���݂���đۏ����قǂ̞炩�� �ѓc��� ���
���݂�����t���Ȃ����z�̉� ����z�l �V�̐�
���݂���ɂ�����鑐�̂قƂƂ��� ��t�� �؉�
���݂���ɂӂ����ʂ��c���� �F�R �[ �� ���ʋ�W�u�C�ǁv
���݂���ɂ₪�ċg����o�ʂׂ� �|�{���p
���݂���ɏ������ɂ��鏬���� �욱
���݂���ɔG��ɂ��G�ꂵ�C���̕� �������
���݂����*���␂��ĕs���Ȃ��Ȃ� �����i�� �i����W
���݂���̂��܂�����蕂�䓰 ��
���݂���̂��ْ���V���� ���� �ĔV��
���݂���̂��U�Ȃݖ��菼�̉� �n�Ӑ��b
���݂���̎P�������ǂ�̋����� ���{�{�� �N��
���݂���̗[�g���₩���ނ� �X���Y
���݂���̖�̕�ɐj���X�� ����l ������
���݂���̖�͉������Ŗ��ɂ��� ����{��
���݂���̑��z���邩�������� ���� �ĔV��
���݂���̉��ɂ��݂ǂ���іښ� �����v���q
���݂���̘R�ďo�čs������ �Y ���_ ���_��I
���݂���̓c������Ȃ��~���� ���c�S��
���݂���̏ڂނ�n�� �X���O
���݂���̋�⌎���̂ʂ�l ����{��
���݂���̋����Ƃ����� �m�� �o�~��W�u�L��C�v
���݂���̉J���ꂽ�܂肽��ɍ~�� ���� �J
���݂���͂Ԃ₫�Â��ē��� ���a�c�֎q
���݂���₯�Ԃ���Ă�J�̉� ���ɔ��Y
���݂����O�������邷�܂Ў� ��D �Ԕ���
���݂���╧�ɉԂ����ӂꂵ�� �ь��Έ� �
���݂���╧�̉Ԃ��̂ɏo�� �o�ӕ���
���݂�������������������Ȃ��� �����L �f�t�W
���݂���▼���Ȃ���̂����낵�� ������e ��
���݂����锼�ɊL���܂��萅 �Y ���_ ���_��I���
���݂����閾���͂Â����̏h �Y ���_ ���_��I���
���݂�����͉͂������Ă��䂭 �{���퉛
���݂�����͂�O�ɉƓ� ���� �ĔV��
���݂���╽�^�̈� �R�����
���݂������̉����l�ʂ� �������� �l��
���݂�����h�Ȃ��炩����M �ƏH �Ԕ���
���݂���➨�ɂӂ��Ԃ�\�c�q ���� �o�~��W�u�L��C�v
���݂���╂���V���֕��ݔ� �g��`�q
���݂�������F�ɂ����閚�̏L(����) �Ԃ� �� �� ���ʋ�W�u�C�ǁv
���݂����Ί���ł��� ����z�l �V�̐�
���݂����D���������d�b�Ȃ� ������(1900-88)
���݂����D�H�ɂ������V���� ����{��
���݂�����K�N�Ⴆ�܂���_�̒� ��������
���݂�����@�ق����ڂ�⋛�߂� �n�Ӑ��b ����
���݂���������܂ւ������i�q �v�ۓc�����Y ������
���݂����I�m���t��ɂ��ӂ� �n粐��b �x�m
���݂����Đς߂錬�̉� �H�열�V��
���݂����l�̉��Ê��� 茍X
���݂�����W�߂đ����ŏ�� �����m��
���݂��ꔋ�ĂӖ��̂₳���g�� �����q
�܌��J�������Ɏ~�ގ������T�� �����q �Ԏ��
�܌��J����ɖ��̗L�����Ȃ� ���� �I�W�Í���W
�܌��J�Ɖ�Ԃ��炵�|�p�� ���ɞX�z ���������㊪
�܌��J�ɂ��Ȃ���n��m������ �㓇�S��
�܌��J�ɂ����`�����G�� �ꒃ �������\��N�b��(52��)
�܌��J�ɂƂ�ւ�ꂽ��킪�s�� ���삩��g
�܌��J�ɂʂ�Ă₠�����Ԓў� �욱
�܌��J�ɂ��Ă����ӂ͂͂������� ���� �o�~��W�u�L��C�v
�܌��J�Ɉ�҂��␅�n �����H�N�q
�܌��J�ɑ傫�Ȍ����J�����r �ؕ铩��Y
�܌��J�Ɏ��̔����₽�ς��D�� ���� �I�W�u�����Y�v
�܌��J�ɉƂӂ�̂ĂĂȂ߂����� �}��
�܌��J�Ɍ�K��q�ސ��ԍ� �����q�K
�܌��J�Ɍ䕨��(������̂ǂ�)�⌎�̊� �����m��
�܌��J�ɐ�Ԃ������ʕʂꂩ�� ���ؐ��q ����
�܌��J�ɔG�ꂽ�锯���قǂ��x�� ���q
�܌��J�ɉ̉J�܂���u�� �畐
�܌��J�ɕ��̌���m��X�肩�� �ܓ�����
�܌��J�ɓc�����a�̌��肯�� �֒ˍN�v
�܌��J���Ă����y���� �Έ�I��
�܌��J�Ɍӓ������܂�R�H���� �z�g����
�܌��J�Ɉ��������闬���� ��Ô���
�܌��J�Ɍy�݂̎P��������� ���X�ؘZ�� �S�C���� �킽�����J
�܌��J�ɋ��͂��߂�ʎ�킴���� �㓇�S��
�܌��J�ɍ~�肱�߂�����łȂ� ���ؐ��q ����
�܌��J�ɉB��ʂ��̂␣�c�̋� �m��
�܌��J����̕��������ɍs�� �m��
�܌��J�ɒ߂̑��Z���Ȃ�� �����m��
�܌��J�̂����������݂ėV�т��� �����W�H�� ���̗t
�܌��J�̉������u�Ă�肯�� ���ؗєV�� ���W
�܌��J�̎P�̂����Ȃ�R�� �ɓ�����
�܌��J�̎P�̒��ɂ�伋z�� �c��q �ԕ���
�܌��J�̍Ăэ�����̓� �\���d�� �d����W
�܌��J�̖��~�肩�������R �\���d�� �d����W
�܌��J�̖���������������Ƃ��� ���c���G
�܌��J�̎l���ɂ���T������ ��b �쑺����
�܌��J�̑�씒���y�̂Ђ� ��Ô���
�܌��J�̑�͂ւ�������q���� ��b �쑺����
�܌��J�̓V�ւӂ�т��|��q ����ƕq �V��啗
�܌��J�̎R����̐���̖� �͖�}��
�܌��J�̎R���Â��͂T�� �������} ���}��W
�܌��J�̓��X�����đD�͍q�� ���_���q
�܌��J�̒����ʔn������� �X���O
�܌��J�̗J�������Y�ꕑ��I�� ���]���F
�܌��J�̗J���Ɍۂ����肯�� �J����
�܌��J�̈���͏H�̂�k��� �i��ו�
�܌��J�̐���Č��Ȃ����a���� ����
�܌��J�̐��Ԃ≮������ �����q�K
�܌��J�̖ؑ\�͖ʔ��������� �����q�K
�܌��J�̐��ɎO�l��龂̋� ���F��
�܌��J�̗P���~�ׂ����J���� ����{��
�܌��J�̒��@�肩�ւ��H������ ���c�ЕF
�܌��J�̋��������� �m��
�܌��J�̑��ɂ��Ԃ����w���� ��b �쑺����
�܌��J�̒[���Â����ƃ����Ȃ肯�� ��������
�܌��J�̒|�ɉB��T�ݏ��� �ꒃ �����a�O�Nᡈ�(41��)
�܌��J�̒|�̗⒩�̃p�� �ɉ_����W ��J�ɉ_��
�܌��J�̒ӂ̉��ЂɎ�{���� �ɉ_����W ��J�ɉ_��
�܌��J���啑������łɂ��� �������� ����
�܌��J�̊I���Ђ��葐�싏 �l����W ����l��
�܌��J�̐��ɏM�͂Ȃ��肯�� ��b �쑺����
�܌��J�̗`�Ō��ɂ䂭������ ��b �쑺����
�܌��J�̗y���Ɍ���Ԃ��̂߂� �e���[��
�܌��J�̍~�̂����Ă���� �����m��
�܌��J�̍~�荞�ޒł�ꠂ̊� ���V�Lj�@�����Ȃ݂����
�܌��J�̍~����������ɉe �쌩�R�钹
�܌��J�̍~�c���Ă���� �m��
�܌��J�̋��c���ɏo��ˌ����� �q�K��W ���q�E�Ɍ�ˑI
�܌��J�̉_�ɐj�������Ȃ� ���Ԗk�}
�܌��J�̉��킭�ЂƂ�� ���ɔ��Y
�܌��J�̉������ɗ���{�����q �R������
�܌��J�̔n�̓n�M�Ƃ��ӂƂ��� �f�\
�܌��J�͂����~����̂Ɗo���� �㓇�S��
�܌��J�͑�~�薄�ނ݂����� �����m��
�܌��J���Ђƌ��̂҂�[�� �G�h-�e �[ �� ���ʋ�W�u�C�ǁv
�܌��J���y�������̂ƒm��ė� �ߍ]���}�q
�܌��J�������ݐq�˂ʌ���� �����m��
�܌��J���p�ɐ����ɂ��� �����_�Z�l ��������
�܌��J�₠���Ђ����ɏ��̌� ����
�܌��J�₨�̂ÂƎv�ӂ��̌Í] ������� �Ǘ�
�܌��J�₩���Č͂�䂭���̕� �ɉ_����W ��J�ɉ_��
�܌��J�₩����Ė߂鐙�ؗ� �h�R�l�o��W ���h�R�l
�܌��J�₫�̂ӌ���͂ł��ӂ͂͂� ���Ԗk�}
�܌��J�₯�ӂ��������Ă��炷 �����q�K
�܌��J�����������������l �Ėڟ��� �����l�\��N
�܌��J��O���������邷�܂Ў� ���_
�܌��J��O�����߂������q ����
�܌��J����̎R�����O������ �����q�K
�܌��J����Č��鑐�̉� �ꒃ
�܌��J���K�Z��(���܂�)�̑��̉� ���шꒃ (1763-1827)
�܌��J��l�Ȃ��݂̈ꌬ�� �n����W �~�V�n��
�܌��J��l�f�Ă����Ԃ� �H�F �o�~��W�ʑ��W
�܌��J��l���s����̒� ���R���
�܌��J�⍡����������� ���ߋ�e�_�R ���c����
�܌��J�╧�̉Ԃ��̂ɏo�� ����
�܌��J��얱�m���܂���₩�� �r��s��q
�܌��J��P�����ċ��ޏM�̟� ��b �쑺����
�܌��J��P�ɕt���鏬�l�` �|�{���p
�܌��J��Z�̌`���̘V�̏� ���
�܌��J��ʖ{�̗~����������L ���V�ɓ� �ɓ���W
�܌��J��\���̐��̏���� ��ŏ�l�S�r ��J��ŁA���{�đ���
�܌��J��낭�Ȃ肵���X�Nj� �͖�É_
�܌��J��ÉƉ������钬�͂Â� �䌎�̋�W ���䌎
�܌��J�⍇�H�̉��̉J������ ���Ԗk�}
�܌��J�╬���̉���̉� ��Ô���
�܌��J��l��U�Ӌ��m�� �Ėڟ��� �����O�\�N
�܌��J��y���͐Ό����Ό� ���c�ЕF
�܌��J��C�d�肷�鍖�̖{ �a�c�v���Y
�܌��J�⓰����ᶂ������̑� ���c�ЕF
�܌��J��ėP���������R �h�R�l�o��W ���h�R�l
�܌��J���̎R�c�̐l�̐� �ꒃ �������N��
�܌��J����������ʎR�̌� �ꒃ �������O�N�h��(29��)
�܌��J���͂̃G�R�̂�����M �K�c�I�� �E��
�܌��J���͂�O�ɉƓ� ����
�܌��J��V���ꖇ�����܂� �@��
�܌��J��V�����̂����� �ꒃ ���������N���(56��)
�܌��J��x�m�̍����̂����ċ��� �Ŗ{�˖�
�܌��J�⛍��������k�̑� ���c�ЕF
�܌��J�⏬�����قǂ����̂��� �Ėڟ��� �����O�\�N
�܌��J������o�������Ȑǂ��� ��
�܌��J�⋏�˂ނ��̏��̍� ��������
�܌��J��R�����ÁT������ �쑺��M ���ΐ�
�܌��J����̐��̌����䂭 �s�����ݎq
�܌��J��삤���킽�����̐� �Y ���_ ���_��I���
�܌��J��N�X�~����ܕS���� �����m��
�܌��J����̉��̑唪�b�� ��ڞq ���
�܌��J��䓤�̏��Ƃ̐Q�o�߂��� ����
�܌��J��{����Z���˖� ���m����
�܌��J��v�͂ʐ쐣�˖��M ���t �I�W�u�����Y�v
�܌��J�⑧�������ɖ؋����� �A�c �j�q
�܌��J��߂ݎ��ɐX�̉Ƃ� ������� �Ǘ�
�܌��J���h�Ȃ��炩�T��M �ƏH
�܌��J��ˌ��܂łȂ�K�� �쑺��M ���ΐ�
�܌��J����̊O�̑����� ��ڞq ���
�܌��J��܁X�o�Â�|�̒� ����
�܌��J��E��������L�̚{�� �l�c��
�܌��J��Â��ɓ��Ďx�ߔ��l ��b �쑺����
�܌��J�⌎��Ɏ���������� �����K
�܌��J�⒩�s���̂��˔� ���� �o�~��W�u���̎��v
�܌��J�⍪���͂�T�����̑� ���c�ЕF
�܌��J�≱�̗���̐� �m��
�܌��J��~�̗t�������̐F �Ŗ{�˖�
�܌��J�➨�������Ƃ��� ����
�܌��J�⊾�������Ԃ�n�̂��� ��Ô���
�܌��J�Ⓘ�݂���炸�\�� ���m����
�܌��J��D���N���ē��̖� ���\���� �}���Ύ��L
�܌��J�⟣���̐��̂������� �h�R�l�o��W ���h�R�l
�܌��J��Q�ōۂ̔K�V�� ����z�l �V�̐�
�܌��J�◄�̏����͐��s�� �䌴����
�܌��J�ⓒ�ɒʂЍs�������� ��[�N��
�܌��J���C���Ղ����萅 ����
�܌��J�⋙�w�ʂ�čs�����T���� �q�K��W ���q�E�Ɍ�ˑI
�܌��J�⋙�Ƃ̌��[�̒n���� ��ڞq ���
�܌��J�⒪���̉Ƃ̂�������� �����]�q �]�q��I
�܌��J�ⓔ���ē����G���x�[�^�[ ���菬��q
�܌��J��L����ɗ���D�̎� ��r
�܌��J��ʍؔ��Ћ���l�Â� �H�열�V�� ���X���k���̈�l
�܌��J��c���ɓ����l��l ����
�܌��J���p�����Q��ʓ��͌�q�� �Β˗F�� ���o
�܌��J��^�Ԃ�����̕��؏M ����g�t
�܌��J���т������܁T���� ��ꔒ���Y �U�؏W
�܌��J�⌥���Ȃ�Ԟ�(���h�q) ��������
�܌��J���w�ɂ��ĕ��v�� ���c�ЕF
�܌��J�◧�����肵�č��~�� ��������W ������
�܌��J��|���ق܂��Ɍ������ �������} ���}��W
�܌��J�┳�g�s�����P �ۘI �I�W�u�����Y�v
�܌��J��і��u�āT�����̓� ��b �쑺����
�܌��J�����(�݂�)�̛��o�̏��Ƃ��� �o�ӕ���
�܌��J�⌨�ȂǑł��ΐ��| �ꒃ �������l�N�h��(59��)
�܌��J��w�˂�᷂̎̏��M ��L
�܌��J�⋹�ɂ��ւ钁���R �ꒃ
�܌��J��D�H�ɋ߂��V���� �{��
�܌��J��F���͂�����Û��� �z�g����
�܌��J��F���ւ�����ǂ̐� �m��
�܌��J��ۂނ����̍��̕� ���V�}��
�܌��J�╙�Z������R�̌� �n粐��b
�܌��J���m�̓O����̒� ��������
�܌��J��\��Â�ӌK���� �� �� �� ���ʋ�W�u�C�ǁv
�܌��J���t�m�̐�(����)���̒� ��������
�܌��J���ςӌK�̔� �����m��
�܌��J��N��肽�鍪���� �S��
�܌��J�⌬�����̂����Ȃ� �����]�q �]�q��I
�܌��J��X�̏������̂ɂ��� �쑺��M ���ΐ�
�܌��J���̏o�Â閪�̐l ��b �쑺����
�܌��J��S�̓��Ђ̕����� ���R�G�q
�܌��J��J�̒����C�l�� �H�열�V��
�܌��J���͂��Â��̂��Ȃ̎R �ꒃ �������O�N�h��(29��)
�܌��J��_�̒��Ȃ�R�� �̋� �g�c�~�t
�܌��J��ё䗧��ꓕ�� �����~�̖� �Îu�̉�
�܌��J��ٝꓔ�����[ �������m��
�܌��J��E�Ƃ��ӂ��̒j��� ���V����
�܌��J��鶂̏d�����Ȃ߂����� �㓇�S��
�܌��J���ӂ͌l�ւ���̂ڂ� �쑺��M ���ΐ�
�܌��J���두�ӂސ��̒� �͓��Ɍ��
�܌��J��{�̉e����y�Ԃ̋� �ؕ���W �x�c�ؕ�
�܌��J��l�̉��Ê��� 茍X
�܌��J��T�����Ƃ͂��̂����� �쑺�~�q
�܌��J�����߂đ����ŏ�� �m��
�܌��J��Ղɒu�L�n�� �㓇�S��
�܌��J���W�߂đ����ŏ�� �����m��
�܌��J���̋��͂Ȃ��肯�� �����q�K
�܌��J��Ԃ̉��₦�ɂ��� �݂���(�É����ٔo�叴���W) �É�����
�܌��J���肢�����̎����� �Q�m��-���� �o�~��W�ʑ��W
�܌��J�Ԃ̐₦�Ԃ��ӂ�ɂ��� �v�ۓc�����Y ���̏�
�܌��J���ɒ�����̎R�o������ ���a �I�W�u�����Y�v
�܌��J�S�r���߂��镗���� �ɉ_����W ��J�ɉ_��
�������ɖ��̂�����܌��J �q�K
�����ނ�������̓���܌��J �Ȗ� �����X
�����n��l�����Ƃ��܌��J �q�K��W ���q�E�Ɍ�ˑI
���̓���܌��J�Ȃ�Ǎ~��ׂ��炸 �����q�K
���ĂĂ䂭����̕��Ƃ�܌��J �g������Y��W
��`��o�P���̌܌��J �|����� �p�c�|��
�S������͂ĂȂ����܌��J ���䋎��
�ƂĂ��ǂ�ʌ܌��J�P�������ċ��� �|�����Â̏� [�͂��]
�ɂ͂Ƃ���O�a�y�Ɏ��ӂ�܌��J �����r�Y �p�咟
�ʂ����銢�̂��Ƃ�܌��J �k�c�t��
�݂̂����̒��̗₽����܌��J �����Y
�Ђ��ɂ����S�̑ǂ�܌��J �v�ۓc�����Y ������
�ق`�Ɠ�K�d����܌��J �ꒃ �����a�O�Nᡈ�(41��)
���ɕ������C�̕��W�܌��J �������� �t��
�����異�����ɂ��Ȃ�܌��J ���R
�X�g�ɓ���O�܌��J�̉͂Ȃ��� �������� ����
����͕������炵���܌��J �Y ���_ ���_��I���
�O�䎛����a�X�ƌ܌��J �����q�K
��ˏO�̕����~����܌��J �ې� �I�W�u�����Y�v
��K����ʈ����ꂵ�܌��J �ɉ_����W ��J�ɉ_��
�S�����̖��Ő�����܌��J �Γ�賎q�Y
�l���������炸�̓m�̌܌��J �����t�v �\�Ζ�l�\��������
�����͖������ɂ݂ʌ܌��J �����q�K
���̓��_�ɂ킩��܌��J �����~�̖� �Îu�̉�
�����ɂӂ�o������܌��J ���ɔ��Y
��(��)�܂��Ƃ����Ӌ�܌��J ���V�Lj�@�f��
�P�����č`��������܌��J �O�c���� �V��������W
�P�����Ό܌��J�̗₦���܂肭�� ���؊G�n
�P���ĎP�����䂭��܌��J ��Ô���
�䓁����ɋ���(����)�Č܌��J ���}��(?-1714)
�\���q�������ʓ��܌��J��� ���v���q�q
���͈�x�܌��J�������� ���c�j (�������ɂ�)
�y�Ԃɐςގ��h�̍������܌��J 賎q�Y��W �Γ�賎q�Y
����Ⴋ�ɉƂ��܌��J��T �l����W ����l��
�����̖�������܌��J �ő�
��͗P�����Ђ���Č܌��J �������f
��O���Ԃ铔��܌��J �ɉ_����W ��J�ɉ_��
��͓n�鏬�M���Ȃ���܌��J ��b �쑺����
�嗱�ɂȂĂ͂ꂯ��܌��J �����q�K
���j�Ɍq�������܌��J ��b �쑺����
�ƈ�ӂƐ��肯��܌��J �ꒃ �����a�O�Nᡈ�(41��)
���ɂ�鑺�̉�c��܌��J �͓��Ɍ��
�����ɖO���܌��J�ɖO���� �������ݎq
�A�������܌��J��T ���� �f�\
�R�r�̂����Ђ��킩���܌��J��T �ѓc��� ���
�R���̎}����Č܌��J �q�K��W ���q�E�Ɍ�ˑI
�R�ԃq�Ɍ��͂�T�R��܌��J �G�� ���J����P�q
�R���̂��남��e����܌��J ��������
��ɘȂ܌��J�P�̗��ɉ邪 �g����u�g �ݓ��̉�
��z���Č܌��J�̌������ɂ��� �������� ����
�����ɓu���Ă���܌��J ��ؐ^���� ������
���~�܂ŎR�r�̂ɂقЂ�܌��J ��b �쑺����
�{��Q�����Q��܌��J�Q ���{���� ���ނ̍�
�}������܌��J�P�̑O������ ���l���q
��Ɖ䂪���������Q��܌��J �x�c�ؕ�
�̏o�}�֗��܌��J ���� ����
�V�������ۂ����Ɍ܌��J �����ő� ���w
���тƂ�]��̗��Ƃӌ܌��J �Y ���_ ���_��I���
���l�����_�������܌��J��T ������g ���J�X
���}�ɖ��܌��J�̈Â��Y�� ��b �쑺����
���̓��∨�X���܌��J �����m��
���X�ƕa�҂̂˂ނ�܌��J �ѓc���
���Q���Q�Ă̖钷���܌��J ��ᵎq �I�W�u�����Y�v
�ł̎ɂ̎�a�݂���܌��J �q�K��W ���q�E�Ɍ�ˑI
��ꠂɋ��铰�F��܌��J �G�� ���J����P�q
���N�̒�������܌��J �O�p
�����ɂ��T����܌��J �����t�|��W
�����̐��b�ق̂ƌ܌��J ���R���_ ���_��W
�����ɍD�����܌��J�� ���c�S��
�C�R�Ɍ܌��J���ӂ�ꂭ��� ���V�}��
�C���̋����t���ӂ�ӌ܌��J �h�R�l�o��W ���h�R�l
�k���ɎP�����ĘȂ�܌��J �ѓc���
����̏h�̗w�͂��Ȃ�ʌ܌��J �Γ�賎q�Y
�����|�̓c�ɂ�������܌��J �͓��Ɍ��
�̐��܂��肯��܌��J ���䋎��(1651-1704)
���̌̓��C���ӂƂ���܌��J��T �X�c�� �����U��
����]�̂���߂ɐ��݂ʌ܌��J �Ô���e ����Ô�
�D�ӂ��≺�����ւČ܌��J �R�[ �I�W�u�����Y�v
�D�`���̐��݂Ĉ���܌��J ���R���_ ���_
���a���╨���������Č܌��J �����j�M
�������͂��F�Ȃ��܌��J �|�{���p
����̈Ɣn����܌��J �����q�K
�����Ԃ���ǂ̂ӂ����܌��J �Y ���_ ���_��I���
���_�ɂ����������܌��J �n�Ӑ��b ����
�����ďo���旷�܌��J �l�c��
�a�݂Ă��͂��ւ̂����܌��J ���R�Ë�
�a�\�ɏĎ��𐁂��܌��J �������� ����
���a��œ��Ƃ����ʖ��܌��J �Ėڟ���
��撚�t���̂₷�߂�܌��J ���� �I�W�u�����Y�v
�Z��̂���݂��ǂ���܌��J ����
��͂���I�ɏ��܌��J �X���O
�ЎQ���ʐg�ɍ~��܂���܌��J �n�Ӑ��b ����
����n���ЂƂɂȂ�ʌ܌��J ����
���������܌��J�P��Ò�_ ��b �쑺����
�|������̌a�܌��J ���J�삩�ȏ� �� �G
�|�B�̌N�q��K�ӂ�܌��J ���c�ЕF
�|�n�⌬�̉��Ō܌��J ���K�q �I�W�u�����Y�v
�}�@�����̎���܌��J ��b �쑺����
�M���Ђ̐S���ق���܌��J ���Ԗk�}
�����▍�ɂЂт��܌��J ���� �I�W�u�����Y�v
���z�Ԃ̗t�ɑ������܌��J �ȎO����W ���{�ȎO��
�����ɖ_�ӂ�l��܌��J �q�K��W ���q�E�Ɍ�ˑI
�D���⒅�����ł悲���܌��J ���V�H�g��
�M�������T�ԍ炭�܌��J ����z�l �V�̐�
�M������܌��J�P���h�̎� ���엧�q
�D�����Z�J�łȂ�܌��J ��
�m�ԓ��̔�z�c�ɍ����܌��J��� �� �R�E�q
�ς̍��̏M�ɂ�������܌��J ����
�ׂɓY�͂ʍ��H�|���T��܌��J 賎q�Y��W �Γ�賎q�Y
�t�������ĕ��L�t��܌��J �G�� ���J����P�q
�t�Ă�̐�������܌��J �\���d�� �d����W
����₠��߂��킩�ʌ܌��J �X
�@�r�̕��t�������܌��J �q�K��W ���q�E�Ɍ�ˑI
�M�łČ܌��J�͂₭�~�݂ɂ��� �������� ����
������̕ǂ�����o��܌��J �ؕ���W �x�c�ؕ�
�ւ̔��Ɍ܌��J�̉ԏ���邩�� �������� ����
峂���̕ǂ�����o��܌��J �x�c�ؕ�
�s���ŗ���鑗���܌��J ��������
�F�Ȃ��̒��O����܌��J �͖�É_ 腖�
�N�������̒ӂ̗�܌��J �ɉ_����W ��J�ɉ_��
���ɂ��܂ʼnݎԂ�܌��J �G�� ���J����P�q
����̕�܌��J������ ���V�Lj�@�����Ȃ݂����
�X�֕v�̊��X�ֈ��Č܌��J�̒����� �l�Ԃ� �勴����
�����鉎���ʂ�Ă�܌��J ��Ô���
�������������Ȃ�܌��J��� �����W
���a�̏��������ւʌ܌��J ��������W
���̑����ɂقӂȂ�܌��J �c���Y
�R�̐Ԋ����Ă��܌��J �{���M�v
�~�����ɍ~�o������܌��J �ʑ�
����Ȃ��C�̂�������܌��J �����q�K
����~������܌��J �I�� �I�W�u�����Y�v
�J��͎R���肯��܌��J ��Ô���
��ɂ��Ή���ς�܌��J �\��
���}���Ԃ̂Ȃ��܌��J��� �ΐ�j�Y �l��
�����ĂĐ�g���炵�܌��J �c[�ꂢ]���� �ɂ��ǂ낭
�n�ōs���a�c���K�̌܌��J �����q�K
�n�q�̂����܌��J�P�̔j��₤ �����W�H�� ���̗t
�n���т��̏o�ŁT���ւ炸�܌��J��T �K�c�I�� �E��
�������P��܌��J ��Ô���
���͂��ėe�瑓���܌��J �����m��
�������ɋ���(����)�Č܌��J ���V�}��
�������ėe����܌��J �m��
�S�@�̐�����m�炸�܌��J ���֟N[�J�C]�q
�V�Ƃ��Ȃ�ł���g��܌��J �ؕ���W �x�c�ؕ�
�̎q�̔G��ė�������܌��J �l����W ����l��
���낵���₯�ӂ��a�ސg�ɂ��݂���� �����q�K
�͂���炭���݂��ꔋ��J�R�� �������l
�P�H�Ӑ��̎��肳�݂���T ���эN�� ����
�X�ɐ��ӂ鑐�������h���䂳�݂���T �A�]���d�N
�������ĕ�ɎT�������݂���� ����k�m
�傫�����݂��ꂤ�������͂֔�� �c���T�� �ԊԈ��
�e���������݂���͍]�����Ⴍ���č~�� ���{���� ���X�Ȃ�ȏ�
�푈�悠��ȘH�n���݂���ĎI�H���� ���{���� ���X�Ȃ�ȏ�
�i�q��茩�邳�݂���̊i�q���� �����r�Y �r����
�]���悳�݂���d�Ԍ~�̂悤�ɂ䂭 ���{���� ���X�Ȃ�ȏ�
�ΐl�Ɍ�Ɉ�����݂���T �H�� �M�q
���X���݂���̉͋D�Ԃ͈�D�J�ɂēn�� ���֟N[�J�C]�q
�_���߂ċA��L�������݂���T �n�Ӑ��b ����
�y�����p�ɑ�コ�݂���T ��ꔒ���Y �U�؏W
��������т̌��F���݂���� ����k�m
���̑��ɑ������̎q���݂���� �ђːÎ}�@
 �@
�@ �@
�@
���݂�����킪�̏L�̂������ ��c�R���� ���摜 ����W
���݂����ꓕ���������� ���щ� ���� �C����
���݂�����̎R����X�ւЂт� ���щ� �C�� ���a�\�O�N
���݂����|�̍����Ƃ̂悲��� ���щ� �~�W �J�鏴
���݂���T���U�g���菼�̉� �n粐��b ����
���݂���T�Ƃ��^��炿�����߂� ���g���
���݂���T���̏d����قǂ����� �y��� �[��
���݂���T�����̂����͎\�_ ���R�� �ԗ���
���݂���T�L�ɔ�����ʎR�̌� �n粐��b ����
���݂���đۏ����قǂ̞炩�� �ѓc��� ���
���݂���ɗ[�̂͂Ȃ€�����肯�� ��c�ܐ�w���߁x���
���݂���̂��܂�����蕂�䓰 ���g���
���݂���̂������錎�𑩂̊Ԃ� ���щ� ���� �����W
���݂���݂̂�����ނ��ӂ��̂� ��c�ܐ�� ���i
���݂���݂̂Â��ƘH��U�铕 ���g���
���݂���̕��̒��߈₳�ꂵ ��c�ܐ�w�V�H�x���
���݂���̗[�g���₩���ނ� �X���Y
���݂���̖�̊ՎU�̓��̐[�� ���쑐��
���݂���̖锼�̖ڊo�߂̌䐺���� ������
���݂���̏��Ȃ��V�ɏ������� �R�����
���݂���̖щz���݂��c���� �R�����
���݂���̐�����Ȃ鐅�� ���쑐��
���݂���̒r��ߋ�̒����� �R�����
���݂���̒r���߂����釔��ɕ��� �R�����
���݂���̟��֍�Ɨ֒���� ���g���
���݂���̑����݂̂���Ɏ��� �R�����q
���݂���̉��̍��|����܂Ȃ� ���g���
���݂���ׂ̉�氓��̐^�Ȃ� ���쑐��
���݂���̉J���ꂽ�܂肽��ɍ~�� ���� �N�X�����̉� �J
���݂���̘I�������낫�t���� ���쑐��
���݂����̂ڂ肭����̐_�y�� �R�����
���݂����킪�ς銟�̖��@���� ���쑐��
���݂����T���������y�����C ���쑐��
���݂����꒱�Ƃ�ŗ��l�� �R�����
���݂����Ă�Č��̂��ւ�݂� ������
���݂���╽�^�̈� �R�����
���݂������̉����l�ʂ� �������� �l��
���݂���������ׂ������ʋD�� ���g���
���݂���␙���琙�֔����� �n粔���
���݂����ڐ����@�͐��̒� �R�����
���݂����Ⴢꂨ�ڂ��r�� ���쑐��
���݂����D���������d�b�Ȃ� ������
���݂�����@�ق����ڂ�⋛�߂� �n粐��b ����
���݂����I�m���t��ɂ��ӂ� �n粐��b �x�m
���݂��ꔋ�ĂӖ��̂₳���g�� �����q
���݂��ꔋ�Ƃ��ǂ����f���Ă���� ����ȓ� �O��
���݂��ꔋ�炫���������s �����q
�܌��J�������Ɏ~�ގ������T��(�x�Y�Ȃ����ɂ�) �����q
�܌��J�ɂ��悢����ؑ]�̐� �����q�K �܌��J
�܌��J�Ɉ�ؔ������ �����q�K �܌��J
�܌��J�Ɍ��ӂ̌����ʘV�n���� �����q�K �܌��J
�܌��J�Ɍ�K��q�ސ��ԍ� �����q�K �܌��J
�܌��J�ɔG��Ĕ�эs����������� ������
�܌��J�ɐ��̂��͂�Ă��̑� �����q�K �܌��J
�܌��J�ɉΎ�̏������s���� �����q�K �܌��J
�܌��J�ɐC���ĊJ���镧���� ������
�܌��J�Ɋ}�̂ӂ��c�A���� �����q�K �c�A
�܌��J�ɐ��̊}�ʂ��ʂ�� �����q�K �܌��J
�܌��J��*(��+)�������̉H �����q�K �܌��J
�܌��J�̂��т�����̔w �����q�K �܌��J
�܌��J�̂Ƃ��������������� �����q�K �܌��J
�܌��J�̂ǂ���Ԃ�ɍ��̔�����Ƃ� �����q�K �܌��J
�܌��J�̂͂����ł̂�ēn���� �����q�K �܌��J
�܌��J�̂͂����ŏ�肵�n���� �����q�K �܌��J
�܌��J�̂ӂ��Ƃ��Ȃ蒁���R �����q�K �܌��J
�܌��J�̂ӂ�ׂ�����m�Ƃ��� ����S��
�܌��J�݂̂��邵�R�Ƃʂ������� �����q�K �܌��J
�܌��J�̒��ɓV�R������ �����q�K �܌��J
�܌��J�̓��o�ŗ������l ���R�̋�
�܌��J�̎P����Ȃ蒇�̒� �����q�K �܌��J
�܌��J�̉����₵���Âɂ��� �����q�K �܌��J
�܌��J�̍��H�T�ς铁���� �����q�K �܌��J
�܌��J�̍��H���o���铁���� �����q�K �܌��J
�܌��J�̈����s������ �����q�K �܌��J
�܌��J�̓V�ւӂ�т��|��q ����ƕq �V��啗
�܌��J�̏h�肵�Ƃɖ����� �����q�K �܌��J
�܌��J�̏�����������y�U�� �����q�K �܌��J
�܌��J�̊���т��薭�`�R �����q�K �܌��J
�܌��J�̕�������ʂق���� �����q�K �܌��J
�܌��J�̝ۂ̂Ƌe�̎���ꂩ�� �����q�K �܌��J
�܌��J�̐���Ȃ�Ƃ����ɐ[�� �����q�K �܌��J
�܌��J�̐��Ԃ≮������ �����q�K �܌��J
�܌��J�̖̊ԂɈÂ��剾�� �����q�K �܌��J
�܌��J�̖ؑ]�͖ʔ��������� �����q�K �܌��J
�܌��J�̐X�̒��Ȃ蓃��d �����q�K �܌��J
�܌��J�̐��ɂƌ������� �R�����
�܌��J�̐����ɂ��c��� �E���� ��W�O ���a��N
�܌��J�̓D�𗬂��ĊC���Ȃ� �����q�K �܌��J
�܌��J�̓D�Y�r�ɒĂ���Ȃ� �����O�S
�܌��J�̌ω��鏬������ ������
�܌��J�̖��邪�@���ӂ�ɂ��� �����q�K �܌��J
�܌��J�̐ΐ�o�����[�R�� �����q�K �܌��J
�܌��J�̒|��A�ޞw�� �����q�K �܌��J
�܌��J�̒���������܂������ �����q�K �܌��J
�܌��J�̑��ɒ��݂ĕ��B �R�����
�܌��J�̉ו���������ˌ����� ������
�܌��J�̑��ʔ��ӎ��Y�ꂽ�� �����q�K �܌��J
�܌��J�̍~����������ɉe �쌩�R�钹 �D��
�܌��J�̋��c���ɏo��ˌ��� �����q�K �܌��J
�܌��J�̉_�₿����ĂقƁT���� �����q�K �܌��J
�܌��J�̉_���������ޑ����� �����q�K �܌��J
�܌��J�̉_����Ȃ蔠���R �����q�K �܌��J
�܌��J�̉_���Ђ킽��ߐ{��� �����q�K �܌��J
�܌��J�̔n�̓n�M�Ƃ��ӂƂ��� ����f�\
�܌��J�̒��e���ؗ���L�� �����q�K �܌��J
�܌��J�̔������̂މ����̉� ����ƕq �L��
�܌��J�͐l�̗܂Ǝv�ӂׂ� �����q�K �܌��J
�܌��J�͐��ɂ��������� �����q�K �܌��J
�܌��J�͕��ɂ�����⒰������ �����q�K �܌��J
�܌��J���[�̐F�ɂ����ꂯ�� �����q�K �܌��J
�܌��J���[�̐F�����J���� �����q�K �܌��J
�܌��J���p�ɐ����ɂ��� �����_�Z�l ��������
�܌��J�₭���т��̎��̍� �����q�K �܌��J
�܌��J�₯�ӂ��������Ă��炷 �����q�K �܌��J
�܌��J�₵�ƁU�G�ꂽ����� �����q�K �܌��J
�܌��J�₾�܂đ��c�Ƃ鏗 �����q�K �܌��J
�܌��J�₿�Ђ����Ƃ̓y�H �����q�K �܌��J
�܌��J��Ƃ�������T�M�̉� �����q�K �܌��J
�܌��J��Ȃ��߂Ă��炷���� �����q�K �܌��J
�܌��J�����Ɍ��̂��菈 �����q�K �܌��J
�܌��J��C���R�̗ڗ��������ʂ�� �R�����
�܌��J�����Ԃ��T���� ���R�̋�
�܌��J��O�������Ђ��� �����q�K �܌��J
�܌��J����̎R������������ �����q�K �܌��J
�܌��J�≺�ʉ��̑O�ʼn��ʂ����� �����q�K �܌��J
�܌��J��T�͂Џ�鑁�c�M �����q�K �܌��J
�܌��J��܌��J��蕶���N �����q�K �܌��J
�܌��J��ܗ��̗��H�̌K�� �����q�K �܌��J
�܌��J�≼����邮���� �����q�K �܌��J
�܌��J��X��̂������̖{ �����q�K �܌��J
�܌��J��P�����Ύ蓾���� �����q�K �܌��J
�܌��J��n�c�𗎂����M �����q�K �܌��J
�܌��J���ؕ��ԑ��̊O �����q�K �܌��J
�܌��J��V�ɂЂT���s��̎R �����q�K �܌��J
�܌��J��h���̑V�̊��n �����q�K �܌��J
�܌��J�⏬�������{�̏� �����q�K �܌��J
�܌��J�⏬���̊p��嗋� �����q�K 嗋�
�܌��J�⏬���̊p��嗋� �����q�K �܌��J
�܌��J�⏬�G�ɂ��܂镶�̏� �����q�K �܌��J
�܌��J�⏭���̉����K���� �ݓc�t�� ������
�܌��J�≪���X�Ɖ��q�� �����q�K �܌��J
�܌��J�⏯���ɂƂ܂��l�O �����q�K �܌��J
�܌��J��䎷���Ă���ɂ��� �Β˗F�� �镗
�܌��J��˂����낵�����̏��X �����q�K �܌��J
�܌��J�⌎�o�邩���̔����� �����q�K �܌��J
�܌��J�⌎�o�鍠�̔����� �����q�K �܌��J
�܌��J�⒩���[���̏����T �����q�K �܌��J
�܌��J�⏼�}�R���đ��̏h ����S��
�܌��J��I�ւƂ�����́T�� �����q�K �܌��J
�܌��J��Y�̖ؗ��Ă鐅�̒� �����q�K �܌��J
�܌��J����[��n���̉_ �����q�K �܌��J
�܌��J�␅�ɂ���鑐�̗� ���ΓC �ԉe
�܌��J�␅���݂ɍs�����ʂ̐� �����q�K �܌��J
�܌��J��D�ӂӂ����R �����q�K �܌��J
�܌��J��D�ӗN�����˂̒[ �����q�K �܌��J
�܌��J�◬���ɐޑۂ̉� �����q�K �܌��J
�܌��J�╂����肽��D�Z�� ����S��
�܌��J�⋙�w�ʂ�čs�����T���� �����q�K �܌��J
�܌��J��Y�U�ςސ[�� ���쑐��
�܌��J�⋍�ɏ悽��F�s�̎R �����q�K �܌��J
�܌��J��c���̓��̑��� �����q�K �܌��J
�܌��J�┩�ɂȂ�Ԑ��̕c �����q�K �܌��J
�܌��J���ɏ��^ �����q�K �܌��J
�܌��J���p�����Q��ʓ��͌�q�� �Β˗F�� ���o
�܌��J��_�o�a�̒��肬�� �����q�K �܌��J
�܌��J�┳�Ȃ����̊� ���ΓC �ԉe
�܌��J��z�n�����������d�� �����q�K �܌��J
�܌��J���ł̎q�̉��̑�� �����q�K �܌��J
�܌��J�����̗��ɂč����� �R�����q
�܌��J�����}�W�Ӑu�a ������
�܌��J��Ђ̂͂Ȃ�T�Ԃ��邽 �����q�K �܌��J
�܌��J��w�˂ɗ������ӎP�ƎP �����q�K �܌��J
�܌��J��F���̓��̂܂�� �����q�K �܌��J
�܌��J�◨�̒��̌Òz�n �����q�K �܌��J
�܌��J�╙�Z������R�̌� �n粐��b ����
�܌��J�┖���Ђ��ӎR�̓� �����q�K �܌��J
�܌��J�⒎������{�̏� �����q�K �܌��J
�܌��J��I�̔��Џo��萅�� �����q�K �܌��J
�܌��J��o�����w�F�ɂȂ� �����q�K �܌��J
�܌��J��N����肽�鍪���� ����S��
�܌��J�⑫�ʊ�ő������ �����q�K �܌��J
�܌��J����̏��}�̔n�� �����q�K �܌��J
�܌��J��t�̂����̑����� �����q�K �܌��J
�܌��J��S�̌����闅���� �����q�K �܌��J
�܌��J���두�ӂސ��̒� �͓��Ɍ��
�܌��J�⊛������ŊO������ �n粔���
�܌��J��{����X�� �����q�K �܌��J
�܌��J���v�ӂĂȂ����q�K �����q�K ����
�܌��J�O������������ �����q�K �܌��J
�܌��J�O�S�l�̖��C�Ȃ� �����q�K �܌��J
�܌��J�l���ďM�̉��肩�� �����q�K �܌��J
�܌��J���̋��͂Ȃ��肯�� �����q�K �܌��J
�܌��J����啧�̓�����͂�T �����q�K �~�J��
���Ђӂꂵ���݂���P�̏d���肵 ������
�������ɖ��̂����ނ�܌��J �����q�K �܌��J
�����������s���Ȃ�܌��J �����q�K �܌��J
��������܌��J�_���}�̒[ �����q�K �܌��J
�������␅������܌��J �����q�K �܌��J
���������ɔH�X����������܌��J �����q�K �܌��J
�����n��l�����Ƃ��܌��J �����q�K �܌��J
������Ȃ����݂�����̒����� ���щ� ���~�W ���a�\�N
�����Ԃ�Ă��������Ƃ��݂���� �����_�Z�l ��������
���̓���܌��J�Ȃ�Ǎ~��ׂ��炸 �����q�K �܌��J
���̍Ղ����K�̉Ԃ������ɂ� �����q�K �܌��J
���낵���₯�ӂ��a�ސg�ɂ��݂���T �����q�K �܌��J
�����A��T�܌��J�P�̂��̈�� ����q�Y
���肳����܌��J�_��փP�� ���g���
���c��H�n�̞O�◐�� �����S�[
���˂�Ƒ啧����܌��J �����q�K �܌��J
�Ȃ��ׂ肻���a�Q��̂��݂���� ���g���
�͂�����ɔ����q��܌��J �����q�K �܌��J
���ꂠ�Ӕ���������܌��J ���g���
���肻�߂����݂���P�ɐg���܂��� ���g���
��邬�Ȃ��܌��J��ɋ��M�o�� ���g���
�킬�ւɂ͌܌��J�_�旧�������� �����_�Z�l ����
���Ȃ�����ǂĂ璅�Ԃ��ꂳ�݂���T ���쑐��
���݂Ȃ����щz�������݂���� �R�����
��l����ҏS�ǂ�܌��J �����q�K �܌��J
�ꑺ�͐��̖̊ԂɌ܌��J �����q�K �܌��J
�O�䎛����a�X�ƌ܌��J �����q�K �܌��J
���̒��̂ǂ����f�w�̌܌��J�悭�ӂ� �������
�����̂����邩�Ǝv�ӌ܌��J �����q�K �܌��J
�l���ԗ��̘L����܌��J �����q�K �܌��J
�����͖������ɂ݂ʌ܌��J �����q�K �܌��J
���������N�Ԃ����Ƃ��݂���T �����q�K �܌��J
�����Ȃ����c�̏��܌��J �����q�K �܌��J
�P�����č`��������܌��J �O�c���� ������W
�P�H�Ӑ��̎��肳�݂���T ���эN�� ����
�X��̕��ƁT������܌��J �����q�K �܌��J
�X���N��肻�ނ�܌��J �����q�K �܌��J
��тۂ�ۂ낳�݂���� ��c�R���� ���摜 ����W
�o���̂Ȃ��݂��߂���܌��J �����q�K �܌��J
�o�����ċ���鐺��܌��J ������
�Â�������̑����܌��J �����q�K �܌��J
�N���g�Ɍ܌��J����ʂ��̂ӂ��� �����q�K �܌��J
�y��Y����͂��݂���T���̂��ڂ��܂� ��c�R���� ���摜 �w�_�W
�n���Ȃ����݂��ꐅ�̋���ɂ� �S���R�H�� �̉�
�n�Ԃ̓Q�̐Ղ�܌��J �����q�K �܌��J
��Ղ̐Ί_�͂���܌��J �����q�K �܌��J
�����⒩���炯�ނ�܌��J ����S��
�ǂ����鋍�̓��Ђ�܌��J �����q�K �܌��J
�Ĕ������݂��ꔋ�ƌ��В��� �㓡��ޕv
��̋q���X�ɋ���ʌ܌��J ���R�̋�
���G��郌�[���S���܌��J ������
�啧�₾��肾���ƌ܌��J �����q�K �܌��J
��a�삳�݂���̐����ꂯ�� ���쑐��
��Ƃ�~��Ƃ��m�炸�܌��J �����q�K �܌��J
��C�̂���`�ƌ܌��J ������
���̋��Ă��炫�܌��J �ѓc��� �S��
����ǂ��ɂ��T�ւČ܌��J �����q�K �܌��J
�嗱�ɂȂĂ͂ꂯ��܌��J �����q�K �܌��J
�V�łƂ��ӂ��̂Ȃ�ނ��݂���� �����_�Z�l ����
���z�Ɋ������݂���P�Ȃ炸 ���g���
���q���肳�݂���͂��̂��邱�� �R�����
�q�͊�Ă��݂���Ђт��ӂ�ɂ��� �ѓc��� ����
��߂Ȃ��g���܌��J�̏Ƃ�܂� �����q�K �܌��J
�Ƌ����邱�Ƃ��y���܌��J��� ���q
���ɂ�鑺�̉�c��܌��J �͓��Ɍ��
�A�������܌��J��� ����f�\
�R���̗]�ԂɉK�̉Ԃ������� �����q�K �܌��J
�R�r�̂����Ђ��킩���܌��J��T �ѓc��� ���
�R���̎}����Č܌��J �����q�K �܌��J
�����܌��J�P���X���� �E���� ��W�O ���a�l�\�l�N
��ɘȂ܌��J�P�̗��ɉ邪 �g����u�g �ݓ��̉�
���O�h�̕_�т���т���ɂ��݂���� ���g���
�����ɓu���Ă���܌��J ��ؐ^���� ������
�S�u������̓y�����݂���T �Β˗F�� ���o
�߂��݂̌܌��J�P�͐[������ ���q
�܂���̖ؑ]�̗��H���܌��J �����q�K �܌��J
�܂�������Z�̗��H���܌��J �����q�K �܌��J
�����͐�ƂȂ肯��܌��J �����q�K �܌��J
�����͑��I������܌��J �����q�K �܌��J
�T�Ɍ܌��J�̑����т��� �����q�K �܌��J
�̏o�}�֗��܌��J ���� ����
�~���̂Ԃ邳�݂���̖�̉珰���� ������
�V�������ۂ����Ɍ܌��J �����ő� ���w
���̒��ɒ����������܌��J �����q�K �܌��J
���X�ƕa�҂̂˂ނ�܌��J �ѓc��� ����
��ꂩ���Ė����̂�����܌��J �����q�K �܌��J
�X茂��č~��V��ʌ܌��J ���쑐��
�ؑ]�O���R�̒���܌��J �����q�K �܌��J
����������ӂ̏h��܌��J �����q�K �܌��J
�˂̗t�ɂ��݂����d���Ђ������� ���쑐��
�K�C�ɕ����M��Č܌��J��� �x������
�V�␅�ւ��������܌��J �����q�K �܌��J
��␅�ɂ��������܌��J �����q�K �܌��J
�ł̎ɂ̎�a�݂���܌��J �����q�K �܌��J
�����ɖ_�ӂ�l��܌��J �����q�K �܌��J
�Ј�{�Ƃ����䓰�ƞЂ̑�������݂��� �������
���Y�̂��ƁU�Z���܌��J �����q�K �܌��J
���Y�̂���T�Z���܌��J �����q�K �܌��J
��峏Ă�������݂���v�ƂȂ� �O���鏗
�����U���ꌩ�����Ȃ�ʌ܌��J �͓��Ɍ��
�����₳�݂���T���̔��g�t �n粐��b ����
����̉_���݂��̂��̋�̂��݂��� ��c�R���� ���ؓ�
���A�����ĉ���̌Í]�̂��݂���T ����S��
���r�Ɋ^�����Ȃ�܌��J �����q�K �܌��J
�D��̊C�ɂ��T����܌����� �����q�K �܌��J
�m�P�̕������ӂ��݂���r������ ���щ� ���� �����W
�C�ۑe�S�̕�������炸���݂���� ���g���
�����̂Ƃ��������܌��J �����q�K �܌��J
�k���ɎP���ĘȂ�܌��J �ѓc��� �։ԏW
�����|�̓c�ɂ�������܌��J �͓��Ɍ��
�̋���������݂���P�Ɍ��� ���щ� ���~�W ���a�\�N
���̑��̂��������R���݂���� ���щ� �C�� ���a�\�N
�a��Ɏ}���Ђ��T��܌��J �����q�K �܌��J
�����₳�݂��ꐰ��T�V�S�� �y��� �Ђ̛�
�a�X�ƘV�̍�H�̂��݂���� �����_�Z�l ����
�G�ꂻ�ڂ��݂���P���Ђ낰�o�� ������
�G�ꂻ�ڂ��̗H����܌��J ���쑐��
����̈Ɣn����܌��J �����q�K �܌��J
���ǂӂčs���M�A��܌��J �����q�K �܌��J
�q����Č܌��J���̖��͂� ��c�ܐ�w���߁x���
�ʗ��̑�̌܌��J���Č����� ���{������
���_�ɂ����������܌��J �n粐��b ����
�c�A�����K�̑���܌��J �����q�K �܌��J
�j�܂����݂���P������������ ������
����̐l�̊���̉Ԃ�܌��J ���R�̋�
�a�݂Ă��͂��ւ̂����܌��J ���R�̋�
�a�l�ɑ�̌�����܌��J �����q�K �܌��J
�a�l�̖��Ȃ�ׂČ܌��J �����q�K �܌��J
�ڂ��܂������������炳�݂���T �����q�K �܌��J
�ڂ��ނ�����������炳�݂���T �����q�K �܌��J
��̉��ɕǂ̗�������܌��J �����q�K �܌��J
�钚�X�r�Ǘ���܌��J �����q�K �܌��J
�ЎQ���ʐg�ɍ~��܂���܌��J �n粐��b ����
���Ƃ͂Ȃ�Ď��̎��݂���Ă���� �������
���|�̂��炷�ɐԂ��܌��J �����q�K �܌��J
�|��O����܂肳�݂���� ���щ� ��鮏W ���a�\�l�N
�M�ɂ��n�̂˂��܌��J �����q�K �܌��J
������҂���Ƃ��ɂ��݂���� ����ȓ� �~�ƍ�
�V�m�Ɍ܌��J�̋q������ ����f�\
�V��̌����������܌��J��� �����_�Z�l ����
�ݑ܂ƕ��ȂƂȂ����݂���� �����_�Z�l ����
�D�Ԃ��݂���ʂ₤�ɍs�����܂� �����q�K �܌��J
���̋����͂ꐅ�Ђ��Ă��݂���� �R�����
�ς̏�ɑۂ̐��Ђ���܌��J �����q�K �܌��J
���܂͂��ĎP���ӗ��̌܌��J �����q�K �܌��J
���⍡�\�X�̂����̌܌��J �x������
�@�r�̕��t�������܌��J �����q�K �܌��J
�@����陂��̂т���܌��J �����q�K �܌��J
嗋��̌��܌��ɏo��܌��J �����q�K �܌��J
嗋��̊p�̂ԍ���܌��J �����q�K �܌��J
�s�_��\�O�����݂���T ������
�X���ɔn�����������܌��J �����q�K �܌��J
�������ʂ����Ƃ̕悳�݂���� ����S�V��
�����ʕx�m�V����ЂĂ��݂���� ���V�ߎq ���S�W
���Ђ̂������̂͂����܌��J��T �����q�K �܌��J
�K�˂��Â��Ȃ�˂��܌��J��� ���R�̋�
�L��Ƃ��݂���P������������ ���g���
�Ԃ��K�N�����K�N�F���݂���T �����q�K �܌��J
�ދ��⎅�̏��������݂���T �����q�K �܌��J
�����������o�ł���ǂ��݂���� ���g���
���ӂ����|�̂���݂�܌��J �����q�K �܌��J
��̓��̍����ӌ܌��J �R�����q
��̓����P�������܌��J �����q�K �܌��J
�������ɂ킪���݂���̎P�� ������
�ݓ��Ȃ邳�݂���̋�̒��ɗ��� ���� �N�X�����̉� �M
����Ȃ��C�̂�������܌��J �����q�K �܌��J
��@�ɍ��������ӌ܌��J �����q�K �܌��J
�_���R���s����ʂ��܌��J �����q�K �܌��J
�_���߂ċA��L�������݂���T �n粐��b ����
���̐��܌��J����ɗ͓��� �����q�K �܌��J
���}���Ԃ̂Ȃ��܌��J��� �ΐ�j�Y �l��
�ʔ��⋍�̂����Ђ��܌��J �����q�K �܌��J
�����Đ����Ƃ���܌��J �����q�K �܌��J
�n�ōs���a�c���K�̌܌��J �����q�K �܌��J
�w���̃f�W�^���ɂ��݂��݂���� ���g���
���ŋ�������܌��J �����q�K �܌��J
�@�����������鎩���̃u�����Y���݂��� ������@
 �@
�@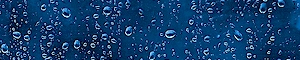 �@
�@
���݂���ĉ�h�Ȃ���Ȃ����� �Ėڐ���
���݂���Ƃ݂����葐�̗t����� ����
���݂���ɂ����A��ӂ◷�ł� �x�l
���݂���ɂ₪�ċg����o�ʂׂ� ���p
���݂���ɓ�V�̉Ԃ̂���݂��� ���m�N
���݂���ɏ������ɂ���q���� �욱
���݂���ɐ������Ԃ݂�V�̉� �I��
���݂���ɗ��ꂠ�肭�₩�U���� �I��
���݂���ɗP�ʂ�F�����ӂƂ��� ����
���݂���Ɋp���Ԃꂸ��q�� ����~��
���݂���Ɋ�ʂ炵������̎� ���S
���݂���ɉ��Ȃ��≽�̂Ђ� �Ėڐ���
���݂���̂܂����Ƃ��Ɏ����肯�� �Ėڐ���
���݂���݂̂�������͂��F�쓹 ���
���݂���̎O���O��~���肯�� �I��
���݂���̒��ɎO�x�̂��Ԃ�� �Ėڐ���
���݂���̖����S����ߋ�� ���p
���݂���̖�͉������Ŗ��ɂ��� ����{��
���݂���̐K�����T����т��� ����
���݂���̉ʂʓ��Ђ�䪉ג| ����~��
���݂���̐��{�������� ��������
���݂���̘R�ďo�čs������ �Y���_
���݂���̉��ƌ����p �I��
���݂���̐��w��������� �������g
���݂���̋�⌎���̂ʂ�l ����{��
���݂���̏I�b�C�̂��炭�Ȃ� ����
���݂���̔��Z�ւ����ނ��j���� �Q��
���݂���͂炵��O�̔n���H �U�m
���݂���͋�ӂĂ͂����邽�Ƃ֍� �Ėڐ���
���݂�������ɂȂ�قǘV�ɂ��� ����~��
���݂������̌܌��̏����� �x�l
���݂�������ɂȂ�ʂ��ڑ� ��ؓ��F
���݂���₩�����̕�̋��̈� ���[
���݂���₳�݂��Ό���炵 ����
���݂���₾�܂Ēʂ�q�K �I��
���݂������㑋�̎������� �]��
���݂����ƂȂ�ւ�����ۖ؋� �f�� �Y�U
���݂����ƂȂ����ۖ؋� �f��
���݂����ʂꉖ���Ԃ鑐�̈� ���Z
���݂����ӂ������|��R�̉� ���c��虬
���݂����܂�����̑��� ���Z
���݂����킷��ċ��肵�W�H�� ���c��虬
���݂����O�������邷�܂Ў� �I��
���݂����e�Ԋ����Ƃɖ�� ��ؓ��F
���݂������Б܂̂Ђ������� �x�l
���݂����N�����T��̂�����} ���p
���݂����Ⴉ�����͕��̈� ���� �����ƏW
���݂����[�H���ӂė��o�� �יa
���݂�����̐S�̂������낫 ����b�l
���݂����锼�ɊL���܂��萅 �Y���_
���݂����閾���͂Â����̏h �Y���_
���݂���▲���Ƃ����ӉF�Â̎R �n�ꑶ�`
���݂�����͂�O�ɉƓ� �^�ӕ���
���݂���▅�ƌ����͋v���Ԃ� ���H
���݂����݂̎R���ӂ肵�Â� ��������
���݂�������u���F�S �]���v��
���݂����z�ւ�₤�Ɏq�K ��g
���݂����허��l���v�Џo�� �]���v��
���݂������~���؋q���� ���
���݂��������̌ѐ������� �O��R
���݂������̂�����͗��Ē� ��ؓ��F
���݂���␥�ɂ��O��ʂ�l ���p
���݂����͂Ȃɕ���i ���ɔ��Y
���݂���➨�ɂӂ��Ԃ�\�c�q ����
���݂����A�c�̒��̂����Ԃ� �D��
���݂������Ȃ鎞 �x�l
���݂���⎀�Ȃʖؑ]�H�̊ۖ؋� ����b�l
���݂���ⓒ�̔�O�R�ɉ����� ���p
���݂�������F�ɂ����閚�̏L �k�u���l��
���݂����z�n�̓��ɖ��̊C �O��R
���݂��������̏��Ƃ̐Q�o���� �^�ӕ���
���݂���⎨�ɖY�ꂵ�̐� �O��R
���݂����W���ė҂��ׂД� �욱
���݂�����t�m�̓O����̂��� ��������
���݂����w�o�Č��Ă��` �O��R
���݂�����̎Ђ݂̂ق��� �O��R
���݂���⑫��A�̕������ �O��R
���݂��������O��T���̘R ��ؓ��F
���݂����_���e�قǐ��Ė� �x�l
���݂���╗��ė��Č˂�J�N �ᒇ
���݂�����̍�肩�R ����
�܌��J�ĉ����e���ʉ���₵�� ����
�܌��J�ƂȂ�ĉ��Ȃ��������� �ʉF �V�ޑ蔭��W
�܌��J��*�ق������Ⓢ�≮ �ؓ�
�܌��J�ɂ�����鐺��s�f�� �{��
�܌��J�ɂ��T���ؑ]�̔��ʒ� ���Z
�܌��J�ɂ��Ȃ���n��m������ �㓇�S��
�܌��J�ɂ��Âނ�I�ɂ̔����i ����
�܌��J�ɂ炫�r����� �D��
�܌��J�ɂȂ��ߏo����������� �b�{
�܌��J�ɂɂ���ʔ~�̑a�e�� �x�l
�܌��J�ɂʂ���U�T�L�̗� 慒|
�܌��J�ɂʂ�Ă₠�����Ԓў� �욱
�܌��J�ɂ��Ă����ӂ͂͂����� ����
�܌��J�Ɉ�g�����Ȃ��Ղ��J ���� �����p
�܌��J�ɉ��Ǝv�ӂĔ�u �\��
�܌��J�ɖ�������Ƃ���Ȃ� �x�l
�܌��J�ɉƂӂ�̂ĂȂ߂����� �}��
�܌��J�ɐS���������S���̉� �j�}
�܌��J�ɉ����������� ���쉳�R
�܌��J�ɐ��̎���������� ��ؓ��F
�܌��J�ɏĂĂւ�����̖� ����
�܌��J�Ɍ��̐������肯�� �ؓ�
�܌��J��⣂Ȃ���T���c�̉� �D��
�܌��J�Ɍӓ������܂�R�H���� ����
�܌��J�ɑD�ŗ����邷�U�߂��� ���R
�܌��J�Ɋ^�̂��悮�ˌ��� ����
�܌��J�ɑ��������낫���钅�� �x�l
�܌��J�ɑ�������ӂ̓������ �ɗ�
�܌��J�ɋ��͂��߂�ʎ�킴���� �㓇�S��
�܌��J�ɐj�̈��O�ւ̐� ���
�܌��J�Ɋւ̊�p�킽��� ���
�܌��J�ɗׂ��������ɂ��� �@�s
�܌��J�̂����͞w�����݂̂��� �Ėڐ���
�܌��J�̂����ɏ��Ȃ��[���� ���m�N
�܌��J�̂���������� ��g
�܌��J�̂��߂��Ă�u���� ���
�܌��J�̂͂Ȃ���~�≮�`�D �z�l
�܌��J�̂悻�ɕ��̂͂Ȃ���@�̒r ����
�܌��J�̎d���͒|�ɗ[���� �x�l
�܌��J�̑��s�k�����͊Ԃ̎R �S��
�܌��J�̖���������������ƍ� ���G
�܌��J�̗[���〈���ďo�_�� �x�l
�܌��J�̗������Ȃ���L ���
�܌��J�̓����ɐ�T��� �T��
�܌��J�̐��Ԃ͔��̂͂����� ����
�܌��J�̐��Ԃ�s��̐ጩ���� �n�ꑶ�`
�܌��J�̎����ɂ������ĉ��� �x�l
�܌��J��ূ����̖��s�� �I��
�܌��J�̗P���~�ׂ����J���� ����{��
�܌��J�̋�����U��Č���� ����
�܌��J�̒[���Â����ƃ����Ȃ肯�� ����
�܌��J�����ɂ͂���ʼn��� ���쉳�R
�܌��J�̐F���ǐ��a�� ����
�܌��J��䊂ނ�`��̖��� ��������
�܌��J�̊o����Ȃ��∰�Ε� ���c��虬
�܌��J�̓����������萙�̐F �f�s
�܌��J�̒�������N���� �I��
�܌��J�̍~���߂Ă₹�Ƃ̎� ���c��虬
�܌��J�̉_���Ɨ��邢���̏� �욱
�܌��J�̉_�ɐj�������Ȃ� �k�}
�܌��J�̉_���x�ނ��@�̐� ���p �܌��W
�܌��J�̉��킭�ЂƂ�� ���ɔ��Y
�܌��J�͂����~����̂Ɗo���� �㓇�S��
�܌��J�͉��ւȂ���Đ���Ȃ� �m��
�܌��J�͎P�ɉ��Ȃ����J�ԍ� �T��
�܌��J�͉G�̂Ȃ��ʖ閾�� ���
�܌��J�܂�����q�����Ȃ�� ��ؓ��F
�܌��J�����R�肩�͂�� ����
�܌��J�₤�������͂ʑ�z�q �S��
�܌��J�₫�̂ӌ���͂ł��ӂ͂͂� �k�}
�܌��J�₯�Ԃ�͏o���Ƃ̓� ����
�܌��J�₳��ł����鏉�֎q ���p
�܌��J��Ԃ�Ă̂�����̂��� ���
�܌��J��Ȃ����a�鎆�ÁT�� ����
�܌��J��ЂƂ�͂Ȃ�T�|�̌� ��������
�܌��J��ЂƖ闒�̂��ւ��_ ���ɔ��Y
�܌��J��Ђ�ӂ�����L���X�� ����
�܌��J��ӂ葐�炵��̂��� �ؓ�
�܌��J��܂������K�̉� ��������
�܌��J��܂����l�Ƃ�c�ނ�� �I��
�܌��J��݂���݂���T�M�̒� ���
�܌��J��ނ����䓛�̗L���� �n�ꑶ�`
�܌��J��ꐺ�������̖{ �Y��
�܌��J�����̔��̘Ԃŋ��� �Q��
�܌��J��O�����߂������q �Ėڐ���
�܌��J���֗l�̂̓n���� ���Z
�܌��J�◼�����̌҂ւ� �\ ����
�܌��J�⊣�����̂ɂ͉��| �f�� �������
�܌��J���K�̋Ȃ��ꂨ�Ƃ� ���쉳�R
�܌��J��g�Ҕn�̔����Ȃ����c ���_ ���Y��
�܌��J��P�ɕt���鏬�l�` ���p
�܌��J�▔�ꂵ����L�̗� ����
�܌��J�⍇�H�̉��̉J������ �k�}
�܌��J��N���S�̂�����} ���p
�܌��J��i�͂��͂�ʉY�̏M �H��
�܌��J��y�l�`�̂ނ��ГX �욱
�܌��J��[�����炭�_�̂�� �D��
�܌��J��邩�Ǝv�ւΐ����� �]���v��
�܌��J�����ɒ|�̒��� ����~��
�܌��J�≜�͎��ŋq�͗l ���R
�܌��J��x�m�̉��̑���n ���p
�܌��J��x�m�̍����̂����ċ��� �Ŗ{�˖�
�܌��J��R��������ĂȂ��̊C ���H
�܌��J��삤���킽�����̐� �Y���_
�܌��J��܁`�o��|�̒� �O�Y����
�܌��J�⒧�������̊��� �욱
�܌��J����̗L���̂��˂Ԃ̉� ���
�܌��J�⒋�̌{�������ّ� �ޚ�
�܌��J�⒋���̖��ɂ��̎R �������g
�܌��J�⒋�Q�̖��ƘV�ɂ��� �]���v��
�܌��J��ĕ��̔n�̌B ����
�܌��J��Ē��̖̓�ԓE�� ���
�܌��J�⌎�͒ʂ��ʕs�j�̊� �z�l
�܌��J��؋����o���̉� ���쉳�R
�܌��J��{�D���̂���Љ� �f�� �f�۔���W
�܌��J�▍���Ђ����E�̏h ���c��虬
�܌��J��~�̗t�������̐F �Ŗ{�˖�
�܌��J�╂�����ꂩ��ɂ�� �ؐ�
�܌��J�◄�̏����͐��s�� ����
�܌��J���C���t������ �^�ӕ���
�܌��J������̖��Ē��̂ɂق� ���
�܌��J��ϔ��ɂ��邳����� ����
�܌��J��L����ɗ����t�̎� ��r
�܌��J��c�M�̒��ɚe���^ �n�ꑶ�`
�܌��J��^�Ԍ��Ă݂̂��炷�� ��ؓ��F
�܌��J��^��̒��҂̐����� ��������
�܌��J�⌥���Ȃ�מ� ����
�܌��J�◳���g��ԑ��Y ���� �]�ːV��
�܌��J��F���͂�����Û��� ����
�܌��J��ŋ�������̟���{ ����
�܌��J��ۂނ����̂����̕� �}��
�܌��J��܂̏����Γ� ���q
�܌��J��t��̐_�����͂��� ��������
�܌��J���m�̐�����̒� ����
�܌��J����Ђ������{�莛 �Ėڐ���
�܌��J��e�̌�����Ƃ̓� �O��R
�܌��J����c�Ă�鋞���� �V�x �]�˖������q
�܌��J�����悲��ʈ�`�� ����
�܌��J���[�g�͂�Ӑ� �욱
�܌��J�⌬��藎�邠��ߑ� ���m�N
�܌��J��_���قǐ��Ė� �x�l
�܌��J��I�̗t�ɂ���*��܂��ڂ� ����
�܌��J�����������́T�{ �А�
�܌��J��n�ł��o���n�̌B �ؓ�
�܌��J��n���͂���ǒ��̓��� �H��
�܌��J��鶂̏d�����Ȃ߂����� �㓇�S��
�܌��J��@�Ђ鉹�����̒� ����
�܌��J�����Ƃ����܂̌�� ��ؓ��F
�܌��J���b�o�����ɂ킩�ꂯ�� ���D
�܌��J��Ղɒu�L�n�� �㓇�S��
�܌��J�ʃL�����V�̐� �O��R
����ߐ^�ԉĂ����܂�Č܌��J��T ����
�����Ò��̖��c�ɂ܂�܌��J �I��
���ƁU���ʂ�T��������܌��J ����~��
����`�ɂƂӂӂ��B����܌��J ����
�����̎q�̓���z�X�܌��J�� �Օ�
�����T�˂̂��ق̂䂪�݂�܌��J �ޚ�
����������ʂꂽ��K��܌��J �ؓ�
�����l���ӂЂق��ւ��܌��J �y�F
���ӂƂ��Ɋ����~����܌��J ����
���̔�͏����ɂȂ�ʌ܌��J ����
�����`���̊��������݂��ꂼ ����
�����܂��ĉ����̂ӂ�т�܌��J ���
���߂Ă��̒������邠��܌��J �]���v��
��̐g�����Ă����ӂ�܌��J �Ėڐ���
��`�ɐ����C������܌��J �Y���_
�U������͂ĂȂ����܌��J ����
�ɂ��܂�Đ�z�l��܌��J ���
�˂鎖�͂���ɂ��܂����܌��J �ɗ�
�́T�X��l�n�ւ���܌��J ���p
�Ђ��`�ƒ����g�ɂ��܌��J ���K茍X
�ЂƂ肩��̔�����܌��J ���m�N
�Ђ˔��̖��Ȃ����܌��J �ؐ�
�ӂ��Əo�Ċւ��A���܌��J �]��
�ڂ�`�Ɖׂ�������܌��J �q��
�����ꂠ�ЂĂ݂Ȃ��납�Â炳�݂���T ���ɔ��Y
������N�Ă������܌��J �I��
��Â��Ȃ�_�䂩���܌��J �{��
���`�Ɛl���h��܌��J �ؓ�
�������̂����Ȃ����ʌ܌��J ����
��邳�ɐA�c������܌��J �I��
����͕������炵���܌��J �Y���_
��������̋�Ȃ��܌��J �c��P�N
�O������Q�߂ɂ���ތ܌��J ���p
�O������F��̎R���܌��J �Ȑ�
���̖��킯�ӂ��o���Č܌��J �\��
�捇�̏M�̂������܌��J �ؓ�
�l���Â��|�̂��݂���|�̌� �x�l
�݂̂Ђ��ƁT����T�܌��J ������
�P������͌Â��܌��J ���l
����̂������Ƃ����ӌ܌��J ���ɔ��Y
���}�₻�̖�����Ɍ܌��J ���l
�ʂ��Ȃ��g�͌܌��J�̌Ԉ�b �O�Y����
�N�������݂���̒��̗[���� ���ɔ��Y
�ۂ݂��������ւ����ڂ��܌��J �c�����
���X�������݂��ꂭ�����Ȃ�ɂ��� �Ėڐ���
���ւ������߂肯��܌��J �ؓ�
����̏��͌�������܌��J ����~��
�l�����y�p�O�܂Ō܌��J ���Z
�����̂��Ԃ炽��Ȃ�܌��J ��������
�������Β��̏��܌��J �� �x�m��
��͗P�����Ђ���Č܌��J �������f
��܂ł̈Ӗ��͒N����܌��J �y�p
�喼���G�ɖ���܌��J �I��
�V�̕������ӂɐ��ׂ��܌��J �q��
���[�݂̂̂�`��܌��J �l�e
�D���ɗ��Č܌��J�ɍ~�ꂯ�� �D��
�x�y�ɖڂ͂��ł������܌��J �r������
�Q�鎖���o���Ă݂�܌��J ���(����)
�����̂ق���͂�ӂ�܌��J ���~
�R����ďM������Č܌��J �Q��
�R����l�߂��g�܌��J �m��
�R���̂���`�Ȃ���܌��J ����
�쉹�̓��g�ɂ���܌��J �K��
�ˉH���[���Ȃ�Ό܌��J �b��
�܁`�○�ɐQ�Ȃ���܌��J ���P
�����̒�ʂ�������܌��J �c��P�N
���P�̐K�̏d����܌��J ���Z
���тƂ�]��̗��Ƃӌ܌��J �Y���_
�����܂Ă�����܌��J�݂�� ���p
����������炵�܌��J �U�m
���f�̗t�͎s�ɔG�ꂯ��܌��J ���� ����
��(���)�ɂ݂���́T�Â݂�܌��J �ܖ�
�����̕Н�����܌��J ���H
�͗l���ʎ��̂������܌��J ���~
�џ���B���ɒ�����܌��J ����
�C�̂�������`�̌܌��J �P��
���ɕ�������܂�܌��J ����
�����ɎP�̂��܌��J �y�F
���C������c�A�̌܌��J �H��
���c�ւ̎������ɂ��݂���T ��ؓ��F
��Љ��̗��̑����܌��J ���Z
�C�������݂���R����̎� �ᒇ
�C�R�Ɍ܌��J���ӂ�ꂭ��� �}��
�̐��܂��肯��܌��J ���䋎��
�֕s���߂����܌��J �c��P�N
���]�̉e�ӂ薄�ߌ܌��J �I��
�D�ӂ��≺�����ւČ܌��J �R�[ �����Y
���a���╨�������ӂČ܌��J �j�M
�������̓y�����ނ�܌��J ��N
�Đn�Ă��V�C���������܌��J ���Z
�������͂��F�Ȃ��܌��J ���p
���Ȃ������̂��͂���܌��J 慒|
�����Ԃ���ǂ̂ӂ����܌��J �Y���_
�����ďo���旷�܌��J ����
ᤂɂ�*�ᒠ�̂��߂��܌��J �������g
ᤂʂ��ӓc�q�̂�������܌��J ���p
���V�̒��ɗ�����܌��J �H��
�Z��̂���݂��ǂ���܌��J ����
�����̐��̂�邳��܌��J ���Z
����n���ЂƂɂȂ�ʌ܌��J ����
���̂ڂ閶�̓�����܌��J �K��
���̗t�ɕ��������܂�܌��J �I��
�M���Ђ̐S���ق���܌��J �k�}
�D���⒅�����ł悲���܌��J �H�g��
���̌˂����͂��ė҂��܌��J ����~��
�����⛇�����������܌��J ���R
�^�q�����悮��o���Č܌��J ���쉳�R
���ɉH�̂�����s�v�`��܌��J ����~��
�s���Ȃ��a�̂����т�܌��J ��������
�s���ŗ���鑗����܌��J ����
�������狴��������܌��J ���
�ω��̖j��͂Ȃ��܌��J �I��
���ɂ�錎���֎��ʂ��݂���� ����
���[��^���̂��悮�܌��J �ԗf
���̎q�̌܌��J����c�A�} ���Z
�ނ̏��̈��育�T���܌��J ���Z
���ɑ����낱���˂�܌��J ���p
��̓��ɂ��Â�R�Ƃ̌܌��J ����~��
������ʂȂ������̌܌��J ����~��
�̂�̐F���ւ�܌��J ���Z
�C�ۂ̐F�����͂��܌��J ���Z
���������Ĕn�����ނ�܌��J �t��
�����̖ڂɂ��I��܌��J �O��R
�������ɋ����Č܌��J �}��
�S��˂�|���䂪�݂ʌ܌��J �Y��
���̎q�̗��o�����܌��J ��������
���߂��ɛ��N�������܌��J �ᒇ
���{�ł����̉��b�܌��J ��������@
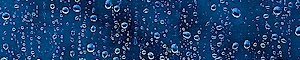 �@
�@ �@
�@





 �@
�@

 �@
�@ �@
�@ �@
�@













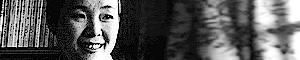









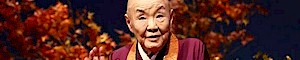













 �@
�@ �@
�@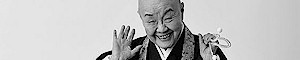 �@
�@
 �@
�@ �@
�@