 �@
�@���痘�x / ������̎���Ɨ��x�E��ђ��̗��j�E�M���Ƃ̏o��܂��E�M�������E�G�g�ƒ����E���x�Ɛ����E��䒃���̎��E���x�̐����I�S�E���x�ƑT�E�u��ђ��v�Ɓu���сv�E��ƍ���̕����E�痘�x���b
�@
�x���a�@�э��a�䗼���@��g�@�䖘�뉺�V�|�@
���{����@����뉺��@�������@�H�^�l�@�D���l�@
�䑗��ā@�M�{�ɂČ��t�\�@������@
�z�R�@������@�����ތ��@
�\�l���@�@�@�@�@�@���x�@
�����l�@
�V��19�N2��13��(1591)�L�b�G�g���̎g�ҁA�x�c(���ߏ��Ēm�M)�E�ѐA(��)(������)�ɂ��A��ւ̑ދ��𖽂���ꂽ���x�́A���̖�ɂ킩���ڊy�̉��~����ɂ����B���̑D����܂ʼn��������ɁA������ɗ��Ă���Ă���2���ɋC�Â��B�H�ė^��Y���ƍא�O��(����)�ƌÓc�D���ł������B���l�̎p�����āA�����̐^�̗����҂����S����̊����̏���A��D�����ꂽ�O�ւ̉ƘV�ł��鏼��(���n��N�V)�ցA�ԗ�����ˏ������킵������ł���B�������闘�x�Ō�̏���Ƃ���Ă���B

���ɗ��x���N�Ƃ�����l�B������B�����̉ƌ��̂ЂƂł���\��Ƃ�4��ڂɍ]��(��������)�@����1662�N�������]���ď��Ƃ����{�Ɏ��N���łĂ���B�l�ɂ���Ċ�炩���O���ς���Ă��邪�A�ȉ��̂S���͏�Ɋ܂܂�Ă���B���������A���R�E�߁A�א쒉���A�Óc�D���B�����A���x�̎q���ł��鏭�����������(������)�ɓ������l�B���R�A�L���V�^���喼�ŃL���X�g����M���ăt�B���s���ŖS���Ȃ����B



���s�s�㋞��́A�x��ɉ˂����Ă�����ʂ̋��ł���B�P�ɖߋ��Ƃ������B794�N�̕��������c�̂Ƃ��ɁA�������̋���̖k������ʂ�u����H�v�ɖx���n�鋴�Ƃ��ĉˋ�����A�����̂��͉̂��x����蒼����Ă��邪�A���݂������Ɠ����ꏊ�ɂ���B���������ȍ~�A�x��E�݂���E���ɂ����Ă͐��ޒ�������������A�x���n�邱�ƁA�����߂苴��n�邱�Ƃɂ͓��ʂ̈Ӗ��������āA���܂��܂ȓ`���╗�K�����܂��w�i�ƂȂ����B���݂̋���1995�N(����7�N)�ɉ˂������ꂽ���̂ł���B �@
�u�ߋ��v�Ƃ������O�̗R���ɂ��Ắw��W���x�����ŁA����18�N(918�N)12���Ɋ��w�ҎO�P���s�̑����̋���ʂ����ہA���̎����ċ}���A���Ă����F��ŏC�s���̎q�����ɂ������ċF��ƁA���s�����ƂƂ��Ɉꎞ�����Ԃ�A���q�������������Ƃ����B �@
�w���ƕ���x�����ɂ͎��̂悤�Șb������B�ےÌ����̌������̗����l�V���M���̓n�Ӎj���钆�ɖߋ��̂����Ƃ�ʂ肩����ƁA����������������A����X���ċ��낵���̂ʼnƂ܂ő����Ăق����Ɨ��܂ꂽ�B�j�͂���Ȗ钆�ɏ�����l�ł���Ƃ͉������Ǝv���Ȃ�����A����������n�ɏ悹���B����Ə��͂����܂��S�Ɏp��ς��A�j�̔�������ň����R�̕����֔��ōs�����B�j�͋S�̘r���Ő藎�Ƃ��ē����邱�Ƃ��ł����B�r�͐ےÍ��n��(���s������)�̓n�Ӎj�̉��~�ɒu����Ă������A�j�̋`��ɉ������S�����߂����Ƃ����B �@
�ߋ��͋���̖����ł��������B�w���������L�x���\�ɂ��A���q�V�c�̒��{�����@�̏o�Y�̂Ƃ��ɁA���̕�̓�ʓa�����ߋ��ŋ�����s�����B���̂Ƃ��A12�l�̓��q�����ł��炵�Ȃ��狴��n��A���܂ꂽ�c�q(��̈����V�c)�̏�����\������̂��̂����Ƃ����B���̓��q�́A�A�z�t�E���{���������ߋ��̉��ɉB���Ă����\��_���̉��g�ł��낤�Ə�����Ă���B���{�����͏\��_�������_�Ƃ��Ďg�����Ƃ̒��ɒu���Ă������A�ނ̍Ȃ����̊��|�������̂ŁA�����͏\��_����ߋ��̉��ɒu���A�K�v�ȂƂ��ɏ������Ă����Ƃ����B �@
�퍑����ɂ͍א쐰���ɂ��O�D���c�̉Ɛb�a�c�V�ܘY�������ŋ��҂��ɂ���A���y���R����ɂ͖L�b�G�g�ɂ�蓇�Ív�Ɛ痘�x�����ꂽ�B�܂��G�g�̃L���X�g�����߂̂��ƁA1597�N�ɂ́A���{��\�Z���l�ƌĂ��L���X�g���}���҂́A�����Ō������߂Ɏ����Ԃ�藎�Ƃ���A�}���n����ւƌ����킳�ꂽ�B�������A���x�̎�́u�ڊy�勴�v�̂����Ƃɔ����ꂽ�Ƃ̋L�^������A���̍��߂苴�̖����ڊy�勴���Ȃ킿���݂̒��������Ɉړ]����Ă����ƍl�����Ă���B����a�q�̓����s����������n��ہA���{�͖߂苴�̖��������āu���N���v�Ɖ����������A�����̊Ԃɂ͒蒅���Ȃ������B �@
�œ���O�̏����≏�k�Ɋւ��l�X�͉ł����Ƃɖ߂��ė��Ă͂����Ȃ��Ƃ����Ӗ�����A���̋��ɋ߂Â��Ȃ��Ƃ������K������B�t�ɑ����m�푈���A�������Ƃ��̉Ƒ��͖����ɖ߂��Ă���悤����Ă��̋��ɓn��ɗ��邱�Ƃ��������B�@

���x�ւ̎g�҂��O�ɁA�O�c�̕����ɂ��A�ؑ��͓�Ŕ����č~�낳�ꂽ�B�@
2�T�ԑO�ɖL�b�G�������A��a�E�S�R�S���̑喼�ŏG�g�̒�B���̌��͎҂ŗ��x�����R�Ǝx�������̂��G���Ɩk�����ł���B�����Ă����̂����a�ƐΓc�B���̒��Ԃ��吭���ŁA�k�����ƂƂ��ɖؑ�������ꂽ���A�G�g�ɂ���܂�����@���ƐS�����������B�@
���x�͐Γc�̋C�ɂ���邱�Ƃ����Ă���B�G�g���珬�c���ɗ��Ĉ��A����Ƃ̗v���ɁA�ɒB���@�͒x��s�����������B����̏G�g�ւ̂Ƃ�Ȃ��𒇉���̂����x�ł������B

�l�����\�@�͈͊��@�ᔇ�@�c�����E�@
�@�����������イ�@�肫�����Ƃ@�킪���̂ق�����@���ԂƂ��ɂ��낷�@
�烋�䓾��̈ꑾ���@���������V�ɝe�@
�@�Ђ�������@�킪���������̂ЂƂ����@���܂��̂Ƃ��� �Ă�ɂȂ�����
�u���\�N�̂킪���U���ڂ݂�ƁA�����ɂ͔ߊ�E��y�E�����E�h�J�A�܂��Ƃɂ��܂��܂Ȃ��Ƃ��������B�������A���̐l���Ƃ����������B�Ƃ����āA���̂킵�ɂ͐��ւ̎������Ȃ���Ύ��̋��|���Ȃ��A�܂��������Ȃ���Έ������Ȃ��B�͈� �I��I�G�C�b�I�N�\�b�I��؍����A����ł��j�Z����B�����Ă킵�̂��ꂩ�璴�l���鐢�E�A�����ɂ͔ߊ����y���A�������h�J���A����ɂ͖�����������Ȃ���̐��E�ł���B�����A���ꂩ�炻�̐��E�Ŏ��R���݂ɗV�Y�O�������悤���B�v�@
���K�c���e/�������_�Ё@
�u���\�N���̒����l�����߂����Ă������A�{���ɁA��������Ƒ�@�������̂́A�e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ����B���܂�A�킪�A���̖��Â̗�����ؒf���ׂ��������ӂ邢�A���ɂ��c�t�����ɖŎE���A���ʂ̐^�l�ƂȂ肨�������̂��B�v�@
�����؏��O/�}�����[�@
�u��������܂Ŏ��\�̗���d�˂��B�E���Ɨ͂݁A�j�ĂƒQ�����ߋ��ł��邪�A�\���������A��A�i�j�N�\�A�䂪�����ɂ͋������̕�����B�얭�A���@�A�����Ȃ��A�c���Ȃ��A�V�n�ꖇ�̋ɒn�Ă��B���Ԃ̔ϗ݂��ݕ�������A��g�ɂ͎w���G�ꂳ���ʂ��B�v�@
�������Δ�/�������_�Ё@
�u�l�������Ɏ��\�N�B�����A�����A����!(���R�Ƒ�債�����ɔ����鐺)�B���̕őc���������A�Ƃ��ɒf���낤��(�܂��ɁA���E���݂̐S��)�B���݂͂����瓾�(���Ɏg���镐��)�̈�{�̑��������������āA���܁A�܂��ɉ䂪�g��V�ɝe�̂�(���܂�A�����̉_�����ꂽ�A�������肵���S��)�B�v�@
���x�̍֍��͝e⣍ցB�Ӗ��́A����߂铹��ł����(����)���Ȃ����A�܂�A����͒��g��������̂ł���A���̒��g���厖�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��B�@
�� �@
�u�͈͊��v�T�ɂ�����u��(����)�v�Ɠ������A�吺���邱�Ƃł��낤���A�ՍϑT�Ō����u���v���̂��̂��Ǝv���B�ՍϑT�́u���v�ɂ͎l��������A�C�s�҂ւ̎��B/�t��(����; �o�ƁA�݉Ƃ��킸�A�t�Ƌ����ɂӂ��킵���w���l����������T��)�ւ̈Њd/�t�킪�͗ʂ����߂���������/����炷�ׂĂ��܂ވꊅ�ł��邪�A���x�͎��ɖʂ��Ď���ɂ��́u���v�����B�@
�u�c�����ɎE���v�F��K�l�Y�̈��p����u����ցv��1���u��B�����v�ɓY��������d�J�̈�߁u�V���������n�����āA�֏��R(�։H)�̑�����D�����Ď�ɓ���邪�@���A���Ɉ����Ă͕����E���A�c�Ɉ����Ă͑c���E���A�����ݓ��ɉ��đ厩�݂A�Z���l���̒��Ɍ������āA�V�Y�O���Ȃ��v���ނ���A�u�ՍϘ^�v�ɂ��� �u���Ɉ����Ă͕����E���A�c�Ɉ����Ă͑c���E���A�����Ɉ����Ă͗������E���v�ɂ��ׂ��Ǝv���B�@
�s�������A���O�ʓ`���|�Ƃ���ՍϑT�̎v�z�ɂ����ẮA�o�T��c�t�̎c���������Ɉ�Ƃ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���x�̍֍��ł���e⣍ւɂ����̈ӎv������Ă���B�E���A���ꕨ�A�c�����ɎE���A����Ƃ�������̂�E�p���A�����Ē��w�l�S�A�������������������ŗ��x�������Ƃ��Ă��邱�Ƃł��낤�B���x������q���Ċт��ʂ����\���̐��E�A��q�����̐V���ȍ�@�]�A�������̘̂Ƒn�ӁA�������@����ɂ���B �@
�����������ׂĂ̑����A⣁A�Ђ��Ă͒��̓��̓���V�ɝe���A���t�ł͌�蓾�Ȃ��T�̓�����Ƃ��A�����Ă��̑T�̓��������Ă��邱�Ƃ��������̓��A�T�̓����̂��́A�^�����s�������邱�Ƃ��Ƃ��闘�x�̂��̈��́A���{�ՍϑT�̎O�t�A������(�剞���t=��Y�Ж��A�哕���t=�@�������A�֎R�d��=���S���J�R)�̈�l�Ə̂���A�哿���̊J�R�ƂȂ����@�������̋C���݂Ȃ�����u���c��B�f���A���я�ɖ����B�@�֓]���鏈�A��������ށv�Ɠ��������Ƃ��đ����˂Ȃ�Ȃ��B �@
(��1/���тƂ͗���(=�s���Ȍ�)�̂��Ƃł���B�]�k�ł͂��邪�A�u�@�X���L�v�ɂ��ƁA���x�͐ؕ����N�قǑO�̒���ɁA�u���сv����͂��܂�t��a���̖n�ւ��f���Ă����B��2/�ߏd�������Ɍ����A����冂̑T�m�A�����x�̈���x���ɍ������Ă����Ƃ��Ă��A�ӂ͌��O�ɂ���Ƃ��ׂ��ł��낤�B) ���x�Q�T�̎t�ł������哿���Ìk�@�a���́A���x�̑哿���R��A���ъt�̏�ɗ��x�������u�����߂ɘA���������A�G�g�̐���吭������k�����̏����ɂ�菕�������A���x�͂�����Ŏ���(�u�痘�x�R�����v)�A�T�̓��ɎQ�������̂Ƃ��āA���Ȃ��Ƃ����x���������̂Ƃ��āA�܂��Ƃ̕\���҂���ׂ����̓��ɂ����đT�̓���S������Ƃ����̂��낤�B�@
�哿���J�c�@�������́A��Y�Ж��̌���o�g�̈�H�A�琹�s�`�̖����̈����p���A�哹�̐^�����������������A���_�ƌ������Ŏ������B�����A�哿���J�n�ɂ������ĕ��������u���镧�a��݂����A���@�����@����@����݂��āu���l���̎R���ɗ����āA���̂��߂ɓ����ڂށB�ߐH�̂��߂ɂ��邱�Ɣ���v�Ɛ����A���r�Ɂu�V�m�s�r�̌�A���͎���ɋ��A���t�o���ɋ�����Z�߁A���O�~�M(�ɂ傤�˂�)�A�����u�o慎�A�����s��A��H�K�ցA�Z���s���A�c�g(���Ƃ�)����(�����)�ɂ������嫂��A���c�s�`�̖������Ȃċ��ԂɊ|�݂�����A�������ʂ𝛖����^���n�ɑA������ז��̎푰�Ȃ�B�V�m�������邱�Ƌv�����Ƃ������Ə̂��邱�Ƃ��������B���͂�����l����A��O�ɖȐ₵�A��c����A�܋r�e���ɖ�؍����ςċi���ē����߂����Ƃ��A���ɌȎ�����������҂́A�V�m�Ɠ��������A��̐l�Ȃ�B�N�������Čy�������B�םсA�םсB�v(�u�����Ɍ`�̏�ŗ��h�ɂȂ�A�w�k���W��A�K�邪�s�Ȃ��Ă��A���c�s�`�̖��������ɂ����Ȃ���ΐ^���͒n�ɑB�����ȑ����ŋr�̐܂ꂽ�e(�Ȃ�)�Ŗ�؍����ςȂ���Ȃ�Ȃ��悤�Ȑ��������Ă��Ă��A�Ȏ����������Ă���҂͏@��Ɠ������������̐l�ł���v(�u���{�����T�v�z�̓W�J�v���{����)�Əq�ׂ邪�@���ɁA�܂��Ƃɕ����̐������������悤�Ƃ���������r�̑T�m�ł������B�����ė��x�����܂��A�����̑T�̓����Ȃ��炦�邪���Ƃ��A�܂��ɗ��x�����S���A�������A�����ʂ����̒��̓����̂��̂��낤�B
 �@
�@�����x�Ō�̎莆 2
�킸����J����̉[1��21���A��N���J���O�ɗ��x���哿���Ɋ�i������w�R��u���ъt�v�̏�ɒu�������x�̖ؑ����s�ސT�Ƃ��������������(���Ђ����Ԃ���˂���������͂������������A�R���������V�c�A�ۊցA���}�a���܂ł�����œ��݂��Ă���)�B�@
���x�͐e�����喼�̍א쒉���◘�x���N�̂ЂƂ�ŎR�ĕ���ɗ��ݕK���ɕٖ��ɓw�߂邪�A�ĕ��������Ƃ����݂Ƃ������������ɂ܂Łu��Έ��(�����ނ���)�v�ƒf��ꂽ�B��̉�O���ԏZ�g���@���▜�㉮�@�������x�̎莆�ɂ߂���������ނ��B�@
2��14���G�g�͗��x����ɒǕ��B���̂Ƃ������̂��T�ɂ��Ă��a�̂��u���x�߂͂Ƃ����ʕ���̂��������告�ɂȂ�Ǝv�ւv(���告�͖����̍߂ō��J���ꂽ�������^�̂���)�ł���B���x�̎���ɋa�̂悤�ɌQ�������l�e�͂Ȃ��A���̓n���Ɍ�����ɂ����̂́A�א쒉���ƌÓc�D���̓�l�����������B�@
2��16�����x�͎ŎR�ĕ��Ɏ��̕Ԏ����o�����B���x�̍Ō�̎莆�B

���Ƃ���ɓV�C���\��(�悭�Ȃ�)��@���Ȃ����Ȃ�����@������

����@�v�ƂƂ��ɐD�c�M���Ɏd���Ă�������A���x��14�ΔN���̏G�g���u���g�Y�v�ƌĂт��Ăɂ��A�G�g�́u�@�Ռ��v�ƌh���Ă���B�R�荇��Ȍ�́u�}�B(�}�O��̗�)�v�ɂ����A�₪�āu��l�v�u�֔��l�v�ƂȂ�̂����A�S�̉���̂ǂ����Ɂu���̐���オ��̉��߁v�Ƃ����ӎ����������̂�������Ȃ��B�G�g�̂ق����ƍٓI���͂ɐ������ꂽ���A���Ă̗��x�̉����Ȗʉe�������ԂƁA�ڋ��������ߋ��̎��������܂��܂����A���V��̂����ɂƑ����݂��̂����Ǝv����B�@
2��25���G�g�͋��ъt�̗��x�ؑ����Ђ����낵�A�ߋ��ɂ��炵�����ɂ����B�m�点�������x�͐Â��Ɏ������r�B�@
�u��(�Ђ�����)��䂪����̈ꑾ��(�ЂƂ���)���������V�ɝe(�Ȃ�����)�v�@
2��26�������ڊy���~�Ɉڂ��ꂽ���x�́A�����s�R���Ŏ���̒��ۂ��g���Ē��̒��̓����Â����̂���������B����͖剺�̎��c�W�H��ł���B���N69�B�@
�����͑�J��蹂��~�藋�Ƃǂ낭�t�̗��������r��Ă����B���~�̎���͑喼�㐙�i���̎w������R���O�炪�|�A���A�S�C�����āA���d�ɂƂ�͂�ł����B���x�̖剺�̑喼�������A���x�~�o�̂��ߕ��͍s�g�ɏo�邨���ꂪ����Ƃ̏���������炾�B�@
���x�̎�͌��g�̈��АےÎ�E��q�O�Y���q��ɂ���ďG�g�ɓ͂���ꂽ���A�G�g�͌������������A�ߋ��ɂ��点�Ɩ������B���x�̎�����ъt�̗��x�ؑ��œ��݂�������Ƃ����A�ނ����炵�����̂������B�A�����đ哿���̌ß�͂��ߎO���V�����Y�����Ƃ�����A�k�����˂˂Ƒ吭���̂Ƃ�Ȃ��ŋ~���Ă���B �@
 �@
�@���痘�x 1
�����̍䏤�l�B�́A�L�x�ȍ��͂�w�i�Ɏ��̌��͎҂���ڒu�����͂��ւ�A�����s�s��z���Ă����B���x����̍����B�̈�l�ł������B�@
�u��ђ��v�Ƃ����͎̂��ɂ͂��������̏����Ȓ����̒��ōs������̂ł������B��̌��ē|��Ƃ܂ł����A���̉��G���؛����Ɉ͂܂�邵�Ă�����̏��l���A�ȑf�ɂ܂�Ȃ������̒��Œ��̓��𖡂키�A�������ґ�̒�����Ɍ��܂Ŗ��ʂ��Ȃ��ْ��������o�����B����ȏ���ґ�͂Ȃ��n�ӂ��ɂ߂������ƌ�����B�@
��b�ɁA���x�͏G�g�����ĂȂ����߂ɓ�����ϒ����������������������ւ��c���A���Ƃ͂��ׂĐ�̂ĂĂ�����������ƌ����Ă���B�@
�痘�x�͍�̗T���Ȓ��O�A����(�ƂƂ�)�ɐ��܂ꂽ�B�������璃�̓��ɐe���݁A�k�������ŕ���Љ��ɂ�ђ����w�сA��@���̑�я@���ɎQ�T���ď@�Ղ̖@�����B�@
���̓��������ĐM���ɐڋ߂��A��ɏG�g�̒����Ƃ��Ďd��������听�����B�k��̑咃������d��ȂǓV����̒����Ƃ��Č�����U��������A���c���̖���G�g�̓{��ɂӂꎩ�n�����B���݂̒�����Ƃ̎n�c�ł��蒃���Ə̂����Ă���B
 �@
�@���痘�x 2
1568�N(�i�\11)�㗌�����M������ɖ�K(�R����)���ۂ��ƁA���O�͍R��h�Ƙa���h�ɕ����ꂽ�B���̂Ƃ��a���h�Ƃ��ĐM���ɋ߂Â������l�E���l�̒Óc�@�y�E����@�v�Ɛe���������W����A�M���ɒ����Ƃ��Ďd���邱�ƂɂȂ����B73�N(�V����)���s�E���o���ɂ�����M���̒���ɏ�����A�����75�N�ɂ͓������M���̒���œ_���̖��߂Ă���B�����M���̖���N�W(�������)�ɂ͔ᔻ�I�ł������B �@
1582�N(�V��10)�̐M���̎���A�G�g�Ɏd���d�p���ꂽ���A����Ȃ钃���Ƃ��Ă̗�����z�����A����Α��߂Ƃ��Ă̖���������ɋ����Ȃ��Ă������B85�N�G�g�̊֔��A�C���̋֗�����ł́A���e���V�c�Ɍ�������G�g�̌㌩���߁A87�N���s�E�k��V���{�ɂ�������j�I�Ȓ���u�k��咃���v�𐄐i���A�u�V����̒����v�̖���s���̂��̂Ƃ����B�@
���l�Ƃ��Ă̖������ق����܂܂ɂ������x�ł��������A89�N�哿���R��̘O��Ɏ��g�̖ؑ���u�������ƂȂǂ��s�h�s���̍s�ׂƂ��ĂƂ��߂��A91�N�G�g�̖��ɂ�莩�n�����B���N70�ł������B�G�g�����𗠂Ŏx���A�܂����x�̍ő�̗����҂ł������O�H�G��(�G�g�̒�)�̎��ɂ�錠�͓����Ɋ������܂ꂽ�Ƃ̐����L�͂ł��邪�A�^�̗��R�͕s���ł���B���x�̒��̓��͒��O�̊Ԃɔ��B������ђ��̓`�����p���A����Ɠ_�O�`���̊����A�Ƒn�I�Ȓ����Ɠ���̑n���A�����̐��_���̐[���Ƃ����ʂŌ���̒����̊�b�����肠�����B �@
�܂��A�]���̒���͋����I�ȗV�����������������A�����̊ȑf�����͂���A����̎���ɂ�т̔��ӎ����т����B������҈��̂悤�ȓ���~�Ƃ����ɏ��̒���������A�����ɂ��Ă��A�����Y���w�����Ă�����y�Ă�����A�u�@��(���x)�^�v���q�������������B���̑��̓���̃f�U�C���ɂ��Ƒn�I�Ȏ��݂���āA�]���̖������S�̒��ɑ��A�V��E�����́u���풃�q�v��u���˒��q�v�Ȃǂ�ϋɓI�ɂƂ肠�����B�܂��A�|���͑T�̖n�Ղ𒆐S�ɂ����A�T�́u�͒W�Վ�v�̐��_�𒃂̓��ɋ��߂��B�@
�痘�x�ɂ͒��j�����Ǝ��j����(���x��Ȃ̘A��q�ŏ@�~�Ƃ�����)�̓�l�̑��q�������B1591�N�A�痘�x��71�Ŏ��n�������͂Ƃ���46�ŁA�����͔�˂̋��X���߂̋��ɁA�����͉�Â̊��������̋��ɐg�����B�������Ԃ��Ȃ��O�c���Ƃ⓿��ƍN��̈����Ŏ͖Ƃ��ꋞ�s�̖{�@���O�ɓy�n��^������ƍċ����F�߂�ꂽ�B�����A�����́A�Ăѐ��Ԃɂ͏o�Ȃ��ƌ��S���Ă����̂ʼnƓ��p�����A�̂��ɍא쒉���̕ی���A�L�O�̒n��1607�N�A62�ŖS���Ȃ��Ă���B�@
���x�̐Ղ��p���������͑哿���O�ɂ��������x�̋������{�@���O�Ɉڂ����B���ꂪ���݂̕\��Ƃ̕s�R���ł���B�����̉B�ٌ�A��Ƃ��p�����q�̏@�U�͗��x�̘̂ђ��𐄐i���A�����钃�����m�������B��ɎO�j�@�����s�R���\��ƁA�l�j�@��������������ƁA��j�@�炪���x�����ҏ��H��Ƃ̑c�ƂȂ��Č��݂ɂ�����B
 �@
�@�������E�痘�x 3
��̂܂����A�ꎞ���́A�u���R�s�s�v�u���l�̉^�c����s�s�v�Ƃ���ꂽ�B�����̑喼���A��̏��l�����̍��͂̑O�ɋ����A���@�����f�������Ƃ͊m���ł���B����ɂ���č�̏��l���������Ȃ������Ƃ͂����Ȃ��B�@
�D�c�M���͂��̑����ɓS�Ƃ��������B����͋����ɑ��z�Ȗ�K��v�����A�u�����Ȃ������Ă������v�@�Ɠ��������B�@
�������̎��A��K��Ȃ������Ȃ�A�����炭�M���͍�̂܂����Ă��������ɈႢ�Ȃ��B�����Ȃ�A�u���R�s�s�v���邢�́A�u���l�̉^�c����s�s�v���A�킸���Ȏ��ԓ��Ɋ��S�ɔR���s���Ă��܂��B�Ռ`�������Ȃ�B�c��̂͊D�������B�����l����ƁA�䂪��K����邱�Ƃɂ���Đ������т�ꂽ�͍̂K�^�������B�������A����͂܂����̂��̂̌��͎҂ɑ�������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�@
���̎��A���x�́A(���Ƃ��܂��͋������Ă��A�l�Ԃ��������Ȃ����͂Ȃ��̂��H)�@�ƁA�K���ɂȂ��Ă��̓������߂��B�@
���x�̋��߂铹�Ƃ����̂́A�����ĉB�҂̓��ł͂Ȃ������B�@
�u�������瓦��Ă��A�^�̉����͂Ȃ��B����͂����ɁA���̋ɈӂƂ����A�̓��̋ɈӂƂ����Ă��A���ǂ͉B�ق̔��w���v�@
���������퓬�I�ȋC�T�͗��x�̋��̒�ɂӂӂƂ������Ă���B���x�͓�����̂͌������B�ǂ�ȓ�肪�ڂ̑O�Ɍ���悤�ƁA�E�C�������Ă���ɗ����������čs���̂��l�Ԃ��Ǝv���Ă���B����������͂����C�T�����ĂΎ����ł���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B��͂��i���K�v���B��i�́A����������l�Ԃ̋C�����̎������ɂ��B�@
�u�����ɂȂ�C�������ǂ��ݒ肷�邩�v�Ƃ������Ƃ��A���x�ő�̉ۑ�ł������B�B�ق�ے肵�A�ō����͂ɗ����������čs���̂ɂ͂ǂ���������̂��B��Ƃ������R�s�s�́A�O���l�鋳�t�������ɏn�߂悤�Ƃ��A���ǂ́A�u�l�H�̂܂��v�������B���x�́A�u��̂܂����A�D�c�M���Ƃ������͎҂ɋ��������̂́A�܂����g����̐��_�������Ă��Ȃ��������炾�v�ƍl����B�ł͂ǂ����邩�B�@
�u�܂��ɏZ�ވ�l��l���A�܂��тƂƂ��Ă̐��_�������Ƃ��v�܂��тƂƂ������t���l���������̗��x�̓��̒��ɂ́A�O���l�鋳�t����₢���A�u���[���b�p�ɂ�����s���v�̎p���������B

���������āA�痘�x�ƌZ�G�g�Ƃ̖�ɔg�����_�̑������A����ɍ��܂��Ă��邱�Ƃ��G���͂悭���m���Ă����B�܂�ɐG��āA�ۂǂ���ʂ��W�J�����B���̓x�ɂ����炭�G���́A(�Z���Z�����A���x�����x��)�@�ƁA���f�̏���������ɈႢ�Ȃ��B�����ƌ����A(���x�͂��Ƃ��V����̒��l�Ƃ͂����Ă��A�Z�ɕ}������Ă���g�Ȃ̂�����A�^����ꂽ���^�ɑ��钉���S�����ׂ���)�@�ƍl���Ă����B�ꌾ�Ō����A�u���x��A�����Ƃ��܂����v�Ƃ������Ƃł���B�Ƃ��낪���x�͂��܂����Ȃ������B����ɂƂ��āA�G�g�ɋ������邱�Ƃ́A�u�����̒��̐��_���������邱�Ƃ��v�Ǝv���Ă����B���̂��Ƃ͓����ɁA�u�܂��тƐ��_���������邱�ƂɂȂ�v�Ƃ������Ƃł���B�@
�L�b�G�������ʑO��ɁA�G�g�̕�吭���@(��)�@�ƏG�g�̍Ȗk����(���˂ˁE����)���疧�g�������B�@
�u��������������������܂�����A���Ȃ����֔��l�Ɏӂ��Ă��������v�Ƃ�������ł���B���������x�͒��d�ɒf�����B�u���͂�A�����Ɏ����Ă͂��͓Y�������������Ă����ʂ��Ƒ����܂��B���D�ӂ́A�����ĖY��܂���v�ƁA���g�ɓ`�����B���������x�͂��̂��Ƃ��A���ɂ����҂ɁA�u�����V���ɖ��𐬂����҂��B�����̒Q��ɂ���Ď���Ƃꂽ�Ƃ����ẮA����̒p���v�ƁA���m�̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���B���x�ɂƂ��āA�u�܂��҂Ɛ��_�v�Ƃ����̂́A���̂悤�ɓ��X�ƕ��m�̖ʖڂɒʂ�����̂������Ă����B

�M���͑傫�������B�����āA�u��@�ՁA�l�����ȁv�Ə�@���ɂȂ����B���x�͂ق��Ƃ����B���������Η��x�ɂƂ��āA����͊����ꝱ�̑叟���������B�M�����}�f�Ȍ��͎҂ł���A�ɂ��������g�����߂ē��点�����Ƃɕ��𗧂Ă�A���̏�ő̂]�����{���ďo�čs���Ă��܂����낤�B�����āA�u���̖���ȏ@�Ղ���������v�ƁA����^����ɈႢ�Ȃ��B�Ƃ��낪�M���͂���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������B�ɂ��������g�����߂ē����ė������A���x�́A�u�ɂ��������������ȏ�́A���Ȃ������Ɠ��������̐l�Ԃ��v�ƌ����Ă��A���𗧂ĂȂ��B�t�ɏ�@���ɂȂ��ăj�R�j�R���Ă���B�痘�x�͐M���̑ԓx�Ɋ��Q�����B�����āA(�����������m���A���{�ɂ������̂�)�@�ƈ�������B�@
���̓��A���x���_�Ă�����M���͂��܂����ɋi�B�������A���̍��̐M���͍�@�������m��Ȃ��B�����o���ꂽ���q�������Y�ƒ͂݁A�K�u���Ƌi�B���̍����ȋi�ݕ����Ђǂ����x�̋C�ɓ������B���������i�ݕ����܂��A�u�s���̎R���v�ɂ�����A�M���炵���i�ݕ��ł������B�A��ۂɐM���͌������B�u���Ƃ����͖̂ʔ����B�����K�����B���܂����t���ɂȂ�v�ƍ������B���x�͕������������B�����āA���̒��ɍ��܂łɂȂ������A�傫�Ȑ����b�オ�N���Ă����̂��������B

��̂܂��̏��l���璃�̓���������ꂽ�M���́A�u����͐����Ɋ��p�ł���v�ƍl�����B�M���͓V���ւ̓����܂�������ɑ������Ă������A�����ɑ��鋋�^�ʂōs���l�܂��Ă����B���̍��̋��^�͂����܂ł��Ȃ��y�n�ŗ^������B�����畐�m�����ɂ́A�u�ꏊ�����v�Ƃ����l��������Ă���B�ꏊ�����Ƃ����̂́A�u�ЂƂ��ɖ���������v�Ƃ����Ӗ����B�ЂƂ��Ƃ����͓̂y�n�̂��Ƃł���B���������Ē������瑱���Ă����������̖��c�������A���m�Ɍ��炸�퍑����̓��{�l�̉��l�ς́A�u�y�n�v������ɍl���Ă����B�ꏊ�����Ƃ����̂́A�u��ł��y�n�𑽂����������B�����̓y�n��D�����Ƃ���z�́A�������ł���Ɛ키�v�Ƃ������Ƃł���B�@
���A���{�̍��y�͂�����L���͂Ȃ��B�M���͊O���l�̐鋳�t����A���E�n�}���������A���邢�͒n���V���������āA���̂��Ƃ��悭�킫�܂��Ă����B�@
�u���{�͋����v�Ƃ����̂��M���̎����������B������A�u������A����ʂɕ����ɓy�n��^���Ă����̂ŁA�₪�ē��{�̍��y�ł͎��܂肪���Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����y�n�s���A���Ȃ킿���^�s����Ɋ����Ă����B���ܐM�����l����̂́A�u�y�n�ɑ���ׂ����l�̂��镨���v��B��������^�Ƃ��ė^�����镨���v�Ƃ������Ƃ��B�@
��̂܂��ʼn�O�ƌĂ�鏤�l��\�����ɉ�A��@�ՂƂ����������q�ɋƎ҂���A���̓_�O��U�镑��ꂽ�M���́A�V�˓I�ȑM���ɂ���āA���̉�����������B�܂�A���̓��͋��^�ɂ��Ȃ�B

�M���͂���ɍH�v�����B����́A�u����̊J�Ì��́A���������ɏ�������v�Ɛ錾�������Ƃł���B�܂蒃�̉���ȒP�ɂ͊J���Ȃ��Ȃ����B�J�����͐M���̋��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ă݂�A����̊J�Â��p�e���g���ɂ��A���̌����̈��M�������Ɉ����Ă��܂����Ƃ������Ƃł���B�@
���������Ɛ�Ɛ���́A�M�����Ӑ}�������ʂB����͔ނ̕����喼�������A���^�Ƃ��Ă̓y�n�����A�ނ��뒃����̖����~������悤�ɂȂ������Ƃł���B�@
�u�N�X��B���x�̎蕿�͌������B�ǂ��ǂ��̓y�n����낤���H�v�ƌ����Ă��A���̕����喼�͎�����ɎB��B�u��������A�M���l���������ɂȂ��Ă��邠�̂����q�����������܂��v�ƌ����B���邢�́A�u���߂Č|�̉����x�����J�����Ă͂��������܂��B����ɂ���āA���̐��Ђ����܂�܂��v�ƍ�����B�@
�M���͋��̒��Ńj���}���Ə��B(��킪��������) �Ǝv�����炾�B�������ēV���l�̐D�c�M�������ɂȂ��āA���̓��Ɋւ��̂��鉿�l��V���ɒ�o�������Ƃɂ��A�y�n��ӓ|����������̕����喼�̉��l�ς��傫���ς���Ă������B��𑈂��āA�u���̂��钃�������ɓ���悤�v���邢�́A�u���̖��ɂ���āA�������x�J�������v�Ƃ�����]�����܂��Ă���������ł���B�喼�����̒��̓��ɑ�����v�́A���̂܂ܖ��Ԃɂ��L�����Ă������B

���Ƃ����̓����ɂ߂������̈�����Ƃ����Ă��A��������̈��̏��l�ł������痘�x���A�Ȃ����{�̍ō����͎҂ł���L�b�G�g�ɂ����܂Œ�R�������̂��A�l���Č���Η��x�̐��_�͂ɂ͌v��m��Ȃ����x�Ȃ��̂�����B�@
����̂��̋��x�Ȑ��_�́A�����܂ł��A�u�����͂܂��т�(�s��)�ł���v�ƍl�������ȕێ��ɂ���B�����ė��x�̍l�����A�u�܂��т�(�s��)�v�̎v�z�́A���ꂪ�͂��߂ē��{�Ő����̂ł������B���Ă̓��{�ɂ͂��������l���͂Ȃ��B�@
����́A��q���喼���ɑ��A�ǂт����Ƃ��钬�l���B����́A�u���͎҂̓Ɛ�ł����������A��O�ɉ�������v�Ƃ������Ƃł���B�����ɂ܂��A���͎҂̑�q���ɂ́A�R��@�������悤�ɁA�u���̖��l�Ƃ́A�������������A���̓�������̖ڗ��������A���̓��Ɏu�[���҂������v�Ƃ���������ݒ肵���̂ɁA���x�̓s�^�����Ă͂܂����B���������ĎR��@�猩��Η��x�́A�u���̓��̖��l�v�ł���B������������Ƃ����ĎR��@��́A�_�O�̖��l������P�Ɂu���l�v�Ƃ��ċM�킯�ł͂Ȃ��B����͑��ɂ��A�u�@���v�ƁA�u�̐���ҁv�̓�n���ݒ肵�Ă���B�@���Ƃ����̂́A���̋Z�p�ɒ�����������u���̓��̎ҁv�ł���B�@
�̐���҂Ƃ����̂́A�u�苖�s�@��(�����Ȃ�)�ŁA���Ɏu���ҁv�������B�R��@��́A���̎�����҂ɂ��āu�ꕨ���������A���̂������ЂƂA�앪�ЂƂA�蕿�ЂƂA���̎O�ӏ��̒�����������v�ƒ�`���Ă���B�@
�ꕨ�Ƃ����͓̂����̂��Ƃ��B�܂�A�u�����Œ��̓��Ɏu���Ă���l�X��������҂Ƃ������B�܂�̂тƂ́A�u���������Ȃ��āA�ǂт������݁v�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B�@
���l�ł������痘�x�́A���̘̐���҂����ɐ[���S���������B��������S���������̂ł͂Ȃ��A������ɒu�����B���������Ă��ꂪ�A��q���̑喼���ɑ��啝�ȉ��ǂ��������̂́A�u�喼����̐���҂̒��ɋ߂Â��悤�v�Ƃ������Ƃ��B

���������ė��x�̍l����A�u�܂��т�(�s��)�v�Ƃ����̂́A�����̐g�߂ȂƂ���őc�����͂��߁A�u����v�ƌĂꂽ�Љ�I��ʎ҂����̎��Ԃ�g�ɐ��݂Ċ�����Ƌ��ɁA������̂܂��̓��䉮���c�̋���ɏW�܂�L���V�^�������̎��ԂƂ��A����������ďo���オ�������̂��Ƃ�����B�@
������A���䉮���c�⋳��Ől�X���O���l�鋳�t���������A�u���[���b�p�̂܂���s���v�Ƃ��A�ЂƖ���������̂𗘋x�͓��̒��ɂ��肾���Ă�����A�����Ă���̎����S�́A�u���������{�ł͂��߂Ă̎s���ɂȂ낤�v�Ƃ������Ƃł������B�@
���ʂȂ�A���̂܂ܐ��m���Ԃ�����Ă��܂��B�܂�A�O���l�鋳�t������������A�u������ꂽ����ӎ��������[���b�p�̎s���v�ɋߕt�����Ƃ��A���̍l������s�������̂܂����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�@
���������x�͂����͂��Ȃ������B�ő�̗��R�́A��͂舢��Ƃ����|�\�҂̑��݂ł���B���킽���́A����̌|�\�������ĎЉ�I�R�v���Ƃ��A�܂��g������̕���ɂ����B���̈ӋC���݂�M��ɂ��Ă��āA�����`�����͂��߁A�����̌��͎҂������A���̈���ɐڋ߂��A�����̓���Z�\�������B

���x�͂₪�āA�u�s���Ƃ������t�́A���̂܂܂ł͓��{�ɓ���܂Ȃ��B�����Ƙa���̌��t�����肾���ׂ����v�����l���āA���ɁA�u�܂��тƁv�Ƃ������t�����肾�����̂ł���B�@
���x�������̒������A�u�s���̎R���v�ƌ����̂ɂ��A���̕ӂ̈Ӗ������߂��Ă���B�R���Ƃ����ȏ�A��������w�t�̖k�����═��Љ��̌����A�u�B�ق̐��_�v�Ɩ����ł͂Ȃ����Ƃ͊m�����B����������́A�u�����邽�߂̊�n�v�Ƃ��Ă̎R���ł͂Ȃ��B�u�O�ɏo�邽�߂̊�n�v�Ƃ��Ă̎R���ł���B�܂�A�R���ɉB�ق��Ă��A����͈�̐�������E�����A�����������̊Վ�ɐZ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����ɋN���������ɁA�u�ǂ��Ώ����ׂ����v�Ƃ������Ƃ��A�Â��ɍl��������̂͂����B�@
�痘�x�����U��ʂ��āA�u���Ɋ���ł���A�܂��퓬�I�ł������v�Ƃ�����䂦��́A���́A�u�키���_�v�ɂ���B�@
�l���Ă݂�A�Ō�̍Ō�܂œ��{�̍ō����͎҂ł���L�b�G�g�ɑ��A�Ȃ�ۂ��������Ƃ����̂́A�G�g���猩��A�u���l����̍ő�̔����v�ł������ɈႢ�Ȃ��B����������́A�痘�x�Ƃ������݂́A�u��������l�̔����v�ł������B�������G�g�́A����"��������l�̔���"�Ɏ���Ă��ʂ����B�G�g�́A��̓��ӂȐl�S�Ǘ����@�ł���j�R�|����A���i�̂�T���Ȃǂ������āA���x�����_���悤�Ƃ����B���������x�͂��̎�ɏ��Ȃ������B�Ō�܂ŌȂ�ۂ����B����́A����̓Ƒn�ł���A�u�܂��тƂ̐��_�v���A�т��ʂ�������ł���B�@
���̈Ӗ��ł����A���ܗ��x�́A���Đe�������������̏��l����@���ɂ��A����"�܂��тƂ̐��_"���������悤�ȋC������B

���x�̓R�g�R�g�ƂЂƂ�ŏ��B�����āA(�܂��ɉ��́A�G�g��Â��Ă�肽�������B���̍����Ȑ���オ��҂̓����A��x�ł������瓥�݂Ԃ��Ă�肽���Ɗ肢�����Ă���) �����ɗ����ꂽ�Ìk�̓���m�b�����Ƃ͂����Ȃ��B���x���g�ɂ��A�G�g�ɑ��āA(���̍����`�L�ȕ@��@���܂�A���݂��̂��݂̂��Ă�肽��) �Ƃ������O���������̂ł���B�@
���������ꂪ�������ꂽ�B���x�͊ϔO���Ă����B(���̍s���́A���ɂ���Α�l�C�Ȃ��B�܂��ɏG�g�����猩��A���̍߂͖����ɒl������̂�) �ƍl���Ă���B�@
���������āA���܂悵�����̉��~�ɓ����āA�Â��ɏG�g�̍߂̐\���n����҂g�ɁA���̖������Ȃ������B�܂��ɁA����n�������ɖ��邢���𓊂��錎�̂悤�ȐS���ł���B�@
�����A�G�g����̎g���������B�u�֔��l�́A���̕��ɐؕ���\���n���ꂽ�v�ƍ������B���g�Ƃ��Ă���ė����͓̂�q�O�Y���q��A���АےÎ�A���c�W�H��̎O�l�������B�@
�痘�x���ؕ������̂́A�V���\��N��\�����̂��Ƃł���B�����̋L�^�ɂ��A���̓��͑�J���~��A�������������Ă����B���̗��̍Œ��ɁA���x�͓��X�ƕ�������B����������̂͒��̒�q���c�W�H��ł������B����͓�����M�����������ŁA�����ɗ��x�̎���a�藎�Ƃ����B��͘e�̕����ɍT���Ă�����Ȃ̏@���ɓn���ꂽ�B�@���͂����A�v�̎�𔒌��ŕ�B���̎����x�́A���̉̂ƁA�̂��c�����B�⌾�͎̉̂��̂悤�Ȃ��̂ł���B�@
���x�߂͂Ƃ����ʕ�̂��̂������@���告�ɂȂ�Ƃ����ւ@
���告�Ƃ����̂́A�����܂ł��Ȃ��������^�̂��Ƃ��B�������^�́A�w�҂̐g�ł����������̒�ɐM������āA����̍����ʂɏ������B�����i�҂��A���^�̑��@�����ς�槌����āA���^����B�̑厖�{�ɍ��J�����B���̂��߁A�厖�{�Ŏ����^�̉��삪�s�𑖂菄��A�u�a�𗬍s�点�A������ǂ����Ƃ����A����В[����E�����Ƃ����B�@
���x���������^�Ɏ������Ȃ��炦�Ă���ȉ̂��r�̂́A�V���\��N�̓ɏG�g�ɂ���āA��ɒǕ����ꂽ���̂��Ƃ��Ƃ����B �@
 �@
�@���痘�x 4
���x�̕��͍�ō����ȑ古�l�ł���A�ނ͓X�̐Վ��Ƃ��ĕi�ʂ⋳�{��g�ɂ���ׂɁA16�Œ��̓��ɓ���B18�̎��ɓ����̒��̓��̑��l�ҁE����Љ�(���傤����)�̖��@��23�ōŏ��̒�����J�����B�@
�Љ��̐S�̎t�́A�Љ������܂ꂽ�N�ɖS���Ȃ����u��(��)�ђ��v�̑c�E���c���(���ケ���A1423-1502)�B����͂��̈�x�̒�q�ŁA�l�ԂƂ��Ă̐����𒃂̓��̖ړI�Ƃ��A����̋V���I�Ȍ`�����A���ƌ��������҂̐��_���d�������B�啔���ł͐S���������Ȃ��Ƃ������R�ŁA���~���Ŏl�����Ɉ͂������Ƃ��A��̒����ւƔ��W���Ă����B�@
�Љ��͎���������u�s���̔��v(�s���S�����炱��������)�ɑT�v�z���̂荞�݁A�����Ȗ������q��ӖړI�ɗL����̂ł͂Ȃ��A���퐶���Ŏg���Ă���G��(���قȂ�)�𒃉�ɗp���Ē��̓��̊ȑf���ɓw�߁A���_�I�[����Nj����A�g�̂сh����̓I�ɕ\�������B�@
���x�͎t�̋���������ɐi�߁A�g�̂сh�̑Ώۂ𒃓���݂̂Ȃ炸�A�����̍\���₨�_�O�̍�@�ȂǁA����S�̗̂l���ɂ܂Ŋg�債���B�܂��A�����͒���̑唼�������E���N����̗A���i�ł��������A���x�͐V���ɞْ��q�Ȃǒ������n�삵�A�|���͑T�́u�͒W�Վ�v�̐��_�f���������n���I�B���x�́g����ȏ㉽�����Ȃ��h�Ƃ����Ɍ��܂Ŗ��ʂ��Ȃ��ăC�u�V��ْ̋����ݏo���A���c�������100�N���o�Ę̂ђ���听�������B�@
���͂ɗN�����R�s�s�E��ɖڂ������̂�1568�N�ɏ㗌�����M���������B�ނ͈��|�I�ȕ��͂�w�i�ɂ��āA����n�ɂ��A�R�����������o�����S�C�̋����n�Ƃ����B�����āA�V�������m�ɖڂ��Ȃ��M���́A��⋞�̒��O(���l)���狭���I�ɒ�����̖��i���グ(�M���̖������)�A���́E���������łȂ������̖ʂł��e����ڎw�����B�M���͋���^�����Ɛb�ɂ̂ݒ���̊J�Â������A�����̖J���ɍ����Ȓ��q��^����ȂǁA������ʂŒ��̓��𗘗p���܂���B�@
������ł������Ȓ��q�͏d��邯�ǁA�퍑���������ɂƂ��Ė�������͈ꍑ���ɒl������̂ŁA���̉��l�͍��Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ����̂������B�L���ȃG�s�\�[�h�ł͖��������u���w偊��v�����L���Ă�����a�̕����E���i�v�G�B�ނ͐��x�ɂ킽���ĐM���𗠐��Ă���A�⍓�ȐM���Ȃ�ⓚ���p�ŕ߂炦�Ďa��n�Y�Ȃ̂ɁA1577�N�A�M�M�R����Ă������v�G��2���̕��ŕ�͂����~�������ŁA�u�������w偊���n���Ζ��܂ł͒D��ʁv�Ɛ��������B���˂Ă���M�����A����肪�o��قǕ��w偊���~���Ă�������m���Ă����v�G�́A�u�M���ɂ̓��V�̎�����w偊�������I�v�ƁA�Ȃ�ƕ��w偊��ɉΖ���l�߂Ď����̎�ɔ���t���A������Ƃ��������ēV��t�𐁂�������B����ł͐M�����Ȃ��ǁA���킪�l�̖������E���鎞�オ���{�ɂ������B(���x��43�̎��ɋv�G��Â̒���ɒ����Ƃ��ď�����Ă���)�@
�M���͍�Ƃ̃p�C�v����茘�łɂ���ׂ��A�����E�̒��S�ɂ��Ē��l�ł�������3�l�A����@�v(�������イ)�A�Óc�@�y(�������イ)�A���x�𒃓�(���ǂ��A���̓��̎t��)�ɏd�p�����B���x��1573�N(51��)�A1575�N(53��)��2�x�A�M����Â̋��s�̒���Ŋ��Ă���B�M���̉Ɛb�͒��̓��ɗ�݁A�X�e�[�^�X�ƂȂ钃�����~���������B�ނ�ɂƂ��Ă̍ō��̉h�_�͐M�����璃��̋����邱�ƁB�K�R�I�ɁA���̓��̎w����ƂȂ闘�x�͈�ڒu�����悤�ɂȂ����B�@
���x60��1582�N6��1���A�{�\���ɂĐM���������̃R���N�V�������ꓯ�ɔ�I���鐷��Ȓ���Â��ꂽ�B�����Ă��̖�A�M���͖��q���G�̖d���ɂ��A�����̖�������Ƌ��ɉ��ɎU�����B�@
��p�҂ƂȂ����G�g�́A�M���ȏ�ɒ��̓��ɔM�S�������B�G�g�Ɋ������ꂽ���̓��D���̕����͋����ė��x�ɒ�q���肵�A��Ɂu���x�\�N�v�ƌĂ��A�א�O��(�K���V�A�̕v)�A�D�c�L�y��(�M���̒�)�A���R�E�߁A�Óc�D���ȂǗD�ꂽ���킪���܂ꂽ�B�@
1585�N(63��)�A�G�g���֔��A�C�̕ԗ�œV�c�Ɏ��璃�����Ă��֗�����𗘋x�͎��d��A�V�c����u���x�v�̍���������(����܂ŏ@�ՂƖ�����Ă���)�B���̂��ƂŁA�ނ̖��͓V����̒��l�Ƃ��đS���ɒm��n�����B�@
���N�ɑ���ŏG�g�ɉy�����A�ǂ���������s�J�́u�����̒����v�Œ������喼�E��F�@�ق́A�u�G�g�Ɉӌ���������̂͗��x�������Ȃ��v�ƋL�����B�@
���G�g�͒�����D���A������{�\���ő�ʂ̖���������Ď��������Ƃ�����A�����ł��钃�킪�s�����Ă����B�����ŗ��x�͐ϋɓI�ɊӒ���s�Ȃ��V���ȁu���i�v�ݏo���Ă����B�V����̒��l�̊Ӓ�ɂ͐��ȐM��������A�l�X�͑����悤�ɗ��x���I�������~������悤�ɂȂ����B���̉ߒ��ŗ��x�͎����D�݂̏a���X�g�C�b�N�Ȓ��q���A�낭����g�p���Ȃ��Ǝ��̓��@�Şْ����Y��y�ĐE�l�ɑ��点���B��������f�p���̒��Ɂg��т˂�h�Ȃ�ł͂̉����݂����ْ��q���A�l�X�͂���܂Ől�C�������������i�������Ԃ悤�ɂȂ�A���x�̖����͂���ɍ��܂����B�@
1587�N(65��)�A�G�g�͋�B�肵�����I�ɓV��������ʂ������j���ƁA���O�ւ̌��͌֎���ړI�Ƃ��āA�j��ő�̒���u�k��咃��(��������̂�)�v��k��V���{�ŊJ�Â���B���Ƃ═�m�����łȂ��A�S���⒬�����g���ɊW�Ȃ��Q���������ꂽ�Ƃ�������A�܂��ɍ����I�s���B�G�g�́u���q1�����Ă��邾���ł����v�ƍL���Ăт����A���x���������o��S�������B�����̒���ɂ́A���x�A�Óc�@�y�A����@�v�A�����ďG�g�{�l�Ƃ���4�l�̍��Ȋ�Ԃꂪ���B�q�a�ł͏G�g�鑠�̒�����S�ēW������A���S��ɐ݂���ꂽ���Ȃ͎���800�����ȏ�ƂȂ����I�G�g�͖����C�Ɋe���Ȃ����Ď���A���璃�����Đl�X�ɂӂ�܂����Ƃ����B

���H�ɒ�̗����t��|�����Ă������x�����ꂢ�ɑ|���I���ƁA�Ō�ɗ����t���p���p���ƎT�����B�u���������|�����̂ɂȂ��v�Ɛl���q�˂�Ɓu�H�̒�ɂ͏������炢�����t������������R�ł����v�Ɠ������B�@
����q�Ɂu���̓��̐_���Ƃ͉��ł����v�Ɩ��ꂽ���̖ⓚ(�ȉ��̓������u���x�����v�Ƃ���)�B�u���͕��̗ǂ��l�ɓ_(��)�āA�Y�͓��̕����l�ɒu���A�~�͒g���ɉĂ͗������A�Ԃ͖�̉Ԃ̗l�ɐ����A�����͑��߂ɁA�~�炸�Ƃ��J�̗p�ӁA���q�ɐS����v�u�t���l�A���ꂭ�炢�͑����Ă��܂��v�u�������ꂪ�\���ɂł��܂�����A���͂��Ȃ��̂���q�ɂȂ�܂��傤�v�B������O�̂��Ƃ������ł�����Ƃ������x�B�@
���G�g�͒��̓��̌��Ђ��~�����āu��`�̍�@�v�����A������G�g�Ɨ��x�����������鎑�i�����Ƃ����B���x�͂��̍�@��D�c�L�y�ւɋ��������ɁA�u���͂���������Əd�v�Ȉ�Ԃ̋Ɉӂ�����v�ƍ������B�u�����ĉ������v�ƗL�y�ցB���x�H���u����͎��R�ƌ��Ȃ�v�B���x�͔�`�Ȃǂƌ������������Ԃ�����@�͑S���d�v�ł͂Ȃ��Ɛ������B�@
�����x���v��������~�̏����Ȓ����u�҈�(��������)�v(����)�́A���E�܂Ŗ��ʂ��킬���Ƃ������ɂ̒����B�ނ��l�Ă�������(�ɂ����)�́A�Ԍ������������ɒ�ʒu�ɂ���A�������������Ĕ����悤�Ȍ`�ɂȂ�Ȃ��ƒ��ɓ���Ȃ��B����͓V���l�ƂȂ����G�g���������B���������m�̍��ł��铁���O���˂������Ă�����Ȃ��B�܂�A��x�����ɓ���ΐl�Ԃ̐g���ɏ㉺�͂Ȃ��A�����Ƃ������F���̒��Łu�����̑��݁v�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B���̂悤�ɁA���̓��Ɋւ��Ă͏G�g�Ƃ����ǂ����x�ɏ]�������Ȃ������B�@
���u���̒��ɒ����ސl�͑�����ǁ@���̓���m��ʂ́@���ɂ����܂��(���̓���m��˂Β��Ɉ��܂��)�v(���x)

�����ė�1591�N�I1��13���̒���ŁA�h��D�݂̏G�g�������������Ƃ�m��Ȃ���A�u���͌Â��S�Ȃ�v�Ɨ��x�͕��R�ƍ��y���q�ɒ������ďG�g�ɏo�����B���̉Ɛb��O�ɁA�G�g�̓����c���ׂ�Ă��܂��B�@
9�����22���A�����E�����Ȑl���Ől�]���W�߂Ă����G�g�̒�E�G�����a�v����B�G���͏��喼�ɑ��u���X�̂��Ƃ͗��x���A���̂��Ƃ͏G��������v�ƌ�������قǗ��x���d�p���Ă����B���x�͍ő�̌�돂���Ȃ������B�@
���ꂩ��1�������2��23���A���x�͓ˑR�G�g����u���s���o�č�Ŏ���ސT����v�Ɩ��߂���B���x���Q�T���Ă��鋞�s�哿���̎R���2�N�O�Ɏ���ŏC�������ۂɁA��̏�ɖؑ��̗��x����u�������Ƃ��߂ɖ��ꂽ(���m�ɂ͗��x�̊�t�̌��ɑ哿����������ɒu����)�B�哿���̎R��͏G�g���������Ă���A�ォ�猩���낷�Ƃ͖���ɂ܂�Ȃ��Ƃ����̂��B�G�g�͗��x�Ɏ͂��𐿂��ɗ������āA�㉺�W���n�b�L���ƕ����点�悤�Ǝv���Ă����B�@
�G�g�̈ӂ����Ɛb�c�̃g�b�v�E�O�c���Ƃ͗��x�̂��Ƃ֎g�҂𑗂�A�G�g�̍�(�˂�)����(�吭��)��ʂ��Ęl�т����̌��͋�����邾�낤�Ə�������B�����A���x�͂����f�����B�u��`�̍�@�v�Ɍ�����悤�ȁA���͂̓���Ƃ��Ă̒��̓��́A�u�̂ђ��v�̊J�c�E���c������A�t�̕���Љ����A��ɔے肵���͂����B�G�g�ɓ���������̂͐�y���l�����łȂ��A���̓����̂��̂����J���邱�ƂɂȂ�B�@
���x�ɂ͑����̖�킪�������A�G�g�̊��C�ɐG��邱�Ƃ��F������āA����Ǖ�����闘�x�𗄂̑D����Ō��������̂́A�Óc�D���ƍא�O�ւ�2�l�����������B�@
���x���Ӎ߂ɗ����A���̂܂܍�֍s���Ă��܂������ƂɏG�g�̓{�肪���_�ɒB�����������B�@
2��25���A���x���͎R�傩��������艺�낳��A���s���ߋ��̂����Ƃ����ɂ����B�@
26���A�G�g�͋C�����܂炸�A���x���䂩�狞�s�ɌĂі߂��B�@
27���A�D����O�ւ��q���������x���~���ׂɖz���B�@
������28���B���̓��͒����痋����V�r��Ă����B���x�̂��Ƃ�K�ꂽ�G�g�̎g�҂��`�����`���́u�ؕ�����v�B���̎g�҂͗��x�̎�������ċA��̂��C���������B���x�͐Â��Ɍ����J���u�����ɂĒ��̎x�x���o���Ă���܂��v�B�g�҂ɍŌ�̒������Ă���A���x�͈�ċz���Đؕ������B���N69�B���x�̎�����ɂ��ꂽ�ؑ��̉��ɎN���ꂽ�B�@
���x�̎�����7�N��A�G�g���a���ɏA�����E����B�ӔN�̏G�g�́A�Z�C���N���������x�ւ̎d�ł���������A���x�Ɠ�����@�ŐH�����Ƃ�����A���x���D�ތ͂ꂽ���������Ă������Ƃ����B�����17�N���1615�N�B���Ă̐w�̐�͍�̊X���œy�Ɖ����A�L�b�Ƃ͂����ɖŖS�����B

���x�A�D���ɐؕ����߂��o�����Ƃ͒��l�������ޏk�������B���얋�{�̎����ŎЉ�Ɉ��肪���߂���ƁA���x��D���̂悤�ɋK���̉��l�ς�j�ĐV���Ȕ��ݏo�����̓��͊댯������A�ێ�I�ʼn�ȁu��킳�сv�Ƃ���鏬�x���B��̉��₩�Ȃ��̂��嗬�ɂȂ����B�@
���x�̎q���́A�哿���ɂ������̐�@�U���Ƃ��ċ����A�@�U�̎��j�E�@�炪�u���ҏ��H��Ɗ��x���v���A�O�j�E�@�����u�\��ƕs�R���v���A�l�j�E�@�����u����ƍ������v�����ꂼ��N�������B���x�̒��̓���400�N��̌���܂Ŏc��A���␢�E�e���̐�Ƃ̒����ŁA�����̐l�����났�̂ЂƎ����y����ł���B�@
 �@
�@���痘�x 5 �ؕ��̐^��
�Ȃ����x�͎��ȂȂ���Ȃ�Ȃ������̂��E�E���̗��R�͍������{�j��ő�̃~�X�e���[�̈�ł��E�E���̎�|����ƌ�������̂����钃��̋L�^(�Óc�@�y���L)�̒��Ɏc����Ă��܂��B �@
�V��15(1587)�N�A�G�g�͋�B�肵�Ė����Ƃ��ɓV���l�ɋ߂Â��܂��E�E���̍�����G�g�͎���̌��͊�Ղ�s���̂��̂Ƃ���ׁA�������x�z�̐���~���悤�ɂȂ�܂��B �@
�V��16(1588)�N�A�w����x�����{�A�_�����畐������グ�Ĕ����̉��E�ݎ��A���m�Ƃ̊ԂɌ��i�Ȉ�����������Ƃ����̂ł����B �@
����܂ł͏G�g���g���܂ߐg�����킸���͂̂���҂��������R�Ɋ��鎖���o���܂����E�E�������A�S���肷��Ƒ̐����ێ�����ׁA���i�Ȑg�����x���K�v�ƂȂ��Ă����̂ł��B �@
�G�g�͊e�n�̑喼�����ɑ��Ă��x�z�҂Ƃ��āA����܂łɂȂ��������ԓx�������悤�ɂȂ�܂��E�E�֓��̑喼�E�k�����́A���]�̈ӂ�\�����Ȃ��������ߑ�R�ōU�ߓ���A�̒n�̂قƂ�ǂ�v�����Ă��܂��B �@
�X�ɓ��k�̑喼�E�ɒB���@�́A�d���̓���������ƌ������������A�ؕ����O�ɂ܂Œǂ����܂�܂����B

�u���x�ȊO�ɂ́A�֔��l�Ɉꌾ������\���グ����҂͂��Ȃ��v(��F�@�ق̏���) �@
�G�g�Ɉӌ��ł���喼�͏��Ȃ��Ȃ�A�߂Â������o����̂͒��l�̗��x�����ƂȂ��Ă����܂��E�E�����������x�𗊂��ē���ƍN��O�c���ƁA���������Ȃǂ��W�܂�悤�ɂȂ��Ă����܂����B �@
�������l����芪���喼�����̓����́A�g���̓��������߂Ă���G�g�ɂ͕s���ȓ����Ɖf��܂��E�E�G�g�͂₪�ė��x�̒��̓��ɑ��Ă��K����������悤�ɂȂ�܂����B �@
���̓��̔�`��������ۂɂ́A�G�g�̋��Ėڂ̑O�ōs�����E�E���x�Ƒ喼�����̒��̓���ʂ����Ȃ���Ɏ��~�߂������悤�Ƃ����Ƃ������Ă��܂��B �@
�X�ɗ��x�ɏՌ���^���鎖�����N����܂��E�E���x�̈���q�ł��钃�l���G�g�̋@���˂��Ƃ������R�ŕ@�Ǝ����������Ƃ��ꏈ�Y���ꂽ�̂ł��B �@
���l�ł���t�炦�Ηe�͂͂��Ȃ������ÂɎ������Ƃ�������o�����ł����E�E���x�ƏG�g�Ƃ̍a�͂܂��܂��L�����čs���܂����B �@
�V��18(1590)�N�@���x69�A���Ɍ���I�Ƃ�������o�������N����܂��E�E�G�g�Ɨ��x�����Ȃ�������ł̂��ƁE�E���̎��A�G�g�͗��x���Ȃ��O���������Ƀ`���b�g��������������d�|���܂��B�@

�Ƃ��낪���̎��A���x���s�����̂́A��e���Ŏ�苎�鎖�ł����c �@
�u���x�́A��e���܂������������Ă܂���ˁE�E�|�b�Ɣ����Ęe�ɒu�������ł��傤�E�E�G�g�ɂ��Ă݂�ǂ���������ł�����d�グ�Ă����̂��ȂƊ��҂����̂ɖ������ꂽ�E�E���ꂪ�G�g�ɂ��Ă݂�Η��x�Ƃ̕ʂ�ɂȂ����̂��ƍl���܂��v �@
��l�̑Η��́A���͂���Ԃ��̂��Ȃ��Ƃ���܂ŗ��Ă��܂����B �@
�V��19(1591)�N�A���x�ɂ��Ă̌��߂�����\���G�g�̎��ɓ����Ă��܂��c�u���x�������̖��������������������ƂɁA���݂̂̒��q��s���ȍ��l�Ŕ��肳���Ă���v�ƌ������ł����B �@
�X�ɋ��s�̎��A�哿���Ɏ������h�킹�邽�߂̖ؑ�����点���Ƃ����̂ł��E�E�����A�哿���ɂ͗��x�̖ؑ�������܂������A����͑��z�̊�t���������x�Ɋ��ӂ��A�������Ǝ��ɍs�������ŗ��x����点�����̂ł͂���܂���ł����B �@
�������G�g�́A�����Ƃ炦�܂����E�E�u����Ă���̂͑哿���̎R��̘O�t���E�E�G�g�������鎖������R��Ɏ����̖ؑ���u���Ƃ͎v���������Ă���I�I �@
�G�g�̎��ɓ����������̏��́A���x���댯������G�g���߂̒����ɂ����̂��ƍl�����Ă��܂��B �@
�V��19(1591)�N2��13���A�G�g�͗��x�����s����Ǖ����鎖�����߂܂��E�E���������܂�܂ō�ŋސT���鎖�����܂�܂����B �@
�����ɏG�g�́A�哿���ɂ��������x�̖ؑ������s�̈��ߋ��̂����ƂɎN���܂����E�E�����ɎӍ߂��A���]���˂Ζ{�l���������Ȃ�Ƃ��������ł����B �@
���x��炤�喼�̒��ɂ́A�G�g�̕�ƍȂ�ʂ��Ęl�т�Ƃ悤��������҂�����܂��E�E���������x�͂�����Ŏ����܂��c �@
�u���̓��œV���ɖ�������킵�����������ɂ����Ƃď��������𗊂����Ƃ����Ă͖��O�ł�����܂��v �@
���x���܂��V���ɖ����͂������l�Ƃ��Ẵv���C�h����i��ŋ����邱�Ƃ͏o���܂���ł����E�E���x�̍Ō�̎莆�Ƃ������̂��c����Ă��܂��B�@

�������Ă�����G�g���S����߂Ă����̂ł͂Ȃ����E�E���x�͂�������Ă����̂����m��܂���B �@
�u�܂��G�g�ɂ��������������̂ł��E�E�ꉞ�A�P���J���ӂ���������ł����瑊�肪�������Ďӂ��Ă���A�����炭�U��グ���������낵���ł��傤�E�E���������x�̕��ł́A�|�p�ƂƂ��Ă����ē���������Ƃ����s���ɂ͏o�Ȃ������v �@
���s�Ǖ�����10����A�G�g�͍Ō�̌��f���������链�Ȃ��Ȃ�܂��E�E����͐ؕ���\�����鎖�ł����B �@
�V��19(1591)�N2��28���A�~�肵����J�̒��A���x�̉��~��3000�l���̕������݂͂܂��E�E���x�ɐؕ���\���n���g�ҁA���x�̔����́c �@
����_�Ă��ĂȂ����������Ƃ����܂��B �@
���ꂪ���x�Ō�̒��ƂȂ�܂����E�E���̖�A���x�͐ؕ��A���̓���ɐ�����70�N�̐��U�ł����B �@
�痘�x�̎���A�G�g�͂��̈ꑰ���������A��ƈꑰ�̓o���o���ɂȂ�A���x�̒��̓��̓`���͊�@�ɎN����܂��E�E�������A������~�����̂�����ƍN�ȂǗ��x�ɏ������鎖�������������������ł����B �@
���x�̎���A���x�̎q�A�����͉�Âɑ����ސT�̐g�ƂȂ����E�E���̎��A�������x�����A�G�g�ɉ��͂��肢�o���̂����x�Ɛ[���e���̂�������Â̑喼�A���������Ɠ���ƍN�ł����B �@
���x�̎���3�N��A�����͏G�g�ɋ����ꋞ�s�ɖ߂�܂��E�E���̏��������x�̓`�����p���������Ƃō��������A�\��ƁA����ƁA���ҏ��H��ƂȂǂ̒��̓��̗��h�����܂�邱�ƂɂȂ����̂ł��B �@
��Îᏼ�ł́A������Ƃ̃��[�c��z�������������̂Ԓ���J����Ă��܂��B �@
�u�p���҂̏��������s�ɖ߂�Ȃ�������S�Ă̂����̕����Ƃ����͕̂ς���Ă������낤�Ǝv���܂��v �@
���x�̎���A�܂��Ȃ��G�g�́A��B�ɖ��쉮���z�� �@
����ł́A�Ō�ɁE�E�ߔN�A��B�ŗ��x�ƏG�g���J�����̂���������܂����E�E���x���������G�g�̑z���ɂ܂���b�ł��B �@
���ꌧ���Îs�A���쉮��ՁE�E�G�g���z�������̏�Ղ���ߔN�A���ڂ��ׂ���\��������܂����E�E�����̌�ł��B �@
����܂ŏG�g�́A���쉮��ł͉����̒��������p���Ă��������m���Ă��܂����E�E�������A�������������͑f�p�ł܂����������܂��E�E���x�����O�����Ă��������ɂ悭�������̂ł����B �@
�G�g�����̍��ɏo�����莆�ł� �@
�u���x���D�ނ悤�ȉ��~�ɂȂ�悤�˂�ɑ����Ăق����v(�G�g�������Ɉ��Ă��莆) �@
���Ă͗��x�̑��钃���ɕs�������炵�Ă����G�g�A���������x�̎���A�����o�����ɗ��x���`���悤�Ƃ��Ă����f�p�Ȕ������������ł���悤�ɂȂ����̂����m��܂���B �@
�u����A���x�̍�@�ŐH�������܂������A�������������܂����v(�G�g����e�Ɉ��Ă��莆) �@
�퍑����A���̌�̓��{�̊�b�ƂȂ�v�V���s���Ȃ����Ƃ̎��𐋂����痘�x�E�E���̗��x�̎���N���߂��̂́A���ɓV���ɋ삯�̂ڂ�Ȃ���ؕ��𖽂����链�Ȃ������L�b�G�g���g��������������܂���B�@
 �@
�@���u�痘�x�v�Ƃ������O

�y��z�� (��gDthD�̉���)����B�o�T���ŁA����̌`�����Ƃ�A�����̎^�Q�⋳�����q�ׂ����́B�l�傩�琬����̂������B���`�ɂ͌��n�o�T�ނ����㕪���A�\���Ȃǂ̈���������A�L�`�ɂ͌o�̖{�����d�˂ĉC���Ő������_��(����)�A����łȂ��U���ł�������32������߂Ƃ����ḉ�(����납)�Ȃǂ��Ӗ�����B����(����)�B��u(�ӂ�����)�B����(������)�B�NjN��(��������)�B�@
�y�J�o�z�������傤 ����B�O���o�̂����A�{�o�̗\���Ƃ��Đ��������̌o���B�@�،o��{�o�Ƃ������ʋ`�o�̗ށB�o�T���Ђ��Ƃ����ƁB���̂Ƃ��������(��)���J�o��Ƃ����B�@
�y���M�z���傤���� �������M�B���@��M����S�B�@
�y���M��z���傤���@�u���傤����˂�Ԃ�(���M�O����)�v�̗��B�@
�y���M�O����z���傤����˂�Ԃ��@�e�a�́u���s�M�v�̍s�������ɂ������(������)�B7��120�傩�琬��A��ɂ̖{��Ƌ~���A�߉ޏo���̖{���Ȃǂ�����A�^�����c�̋������q�ׂ����́B�^�@�Řa櫂ƂƂ��ɕ��O�œǂށB���M��B�@
�y����z�͂� ����B�̔����B���ʂɂ͟��όo�ɂ���u���s����A�����Ŗ@�A���Ŗś߁A��ňy�v�̌㔼�̘��������B�߉ނ���R�ŕ�F�̍s���C�߂Ă����Ƃ��A��������O�̔�����Ċ��삵�A��̔�����������Ƃ��������������Ȃ������̂ŁA�����̐g�𗅙��ɗ^���邱�Ƃ�ĕ������Ƃ��ł����Ƃ����B�@
�y����z������ (��gDthD�̉���́u��v�ƈӖ�́u��v�����킹������)����@
�y�����z�����Ԃ� ����B�߉ޔ@�������Ɍ����O�ɏo�����ɁA�߉ނ������Ď��Ɛ��������́B���k����(�т��Ԃ�)�A������(�����Ԃ�)�A���ɕ���(�т���ԂԂ�)�A�S������(���邻��Ԃ�)�A��ߊܖ���(���Ȃ���ނɂԂ�)�A�ޗt��(���傤�Ԃ�)�A�߉ޖ���(���Ⴉ�ނɂԂ�)�̑��́B�ߋ������B�u�����Ԃ₭��(������t)�v�̗��B�@
�����ʉ�(������)�̘�(��)�@����B�ߋ��������ʉ�(����)�Ƃ�����B�ȗ��ɏ����̋�������������B�u���̈��͂Ȃ��Ȃ���(��������)�A�O(�������)�̑P�͕�s����(�O�P��s)�A���瑴�̈ӂ�����(����)�A���ꏔ���̋��Ȃ�(��������)�v�B�@
�y櫕��́z����Ԃ]���@����B�����^�Q����́B���O�ʼnr�ޘa櫁A���l(���܂悤)�A��(��)�A���A�a�́A�P����(����)�ȂǁB�@
�y櫕���z����Ԃ]���@����B���̌������^�Q������B���Ɂu���ʎ��o�]�㊪�v�ɂ���@����F�������݉������^�Q�����u����فX�v�Ŏn�܂��\��B

�y�����s�v�c�z���������]�ӂ����@(�u�@�،o�]�ϐ�����F����i�v�ɂ����̋�u�O���[�@���C�A�������s��v�c��v����)�����玞���d�˂Ē����l���Ă��킩��Ȃ��s�v�c�Ȃ��ƁB�@
�y�S�z�� (��pathaka�̉���A�S��(���̂�)�̗�)����B�����V���ŏ�����̗w�B����܂��͞���Ř�(��)�E��(���傤)���r�̂��A�O��̌������^�Q������́B�Z�����͂��ꉹ�ꉹ���������L���Ď��Ԃ������Ă������B�@
�y�O�ފω��͓��q�i�i��z�˂�҂���̂�肫�]�Ƃ����@(�u���v�͘A���Łu����ˁv�Ƃ�)����B�u�@�،o�]����i�v�̒��̘�(��)�B�ω��̗͂�O����Ƃ��́A�G�����̊Q�������悤�Ƃ��Ă��A���̓��͓ˑR�����ɂ��܂ꂱ����Ƃ������ƁB�@
�y�@���S�z�ɂ�炢���@�@���̏��ꂽ�F�g������������題o�̔���̘�(��)�B���S(�ڂ��)�ɗp����B�@
�y�����z���傤���傤 ����B�@��̂Ƃ��A���t���o���Ȃǂ̏��߂̈��������āA���a�̂��߂ɒ��q���ƂƂ̂��邱�ƁB�哪�A���̂Ƃ������B�@
�y��@�z����ڂ� ����B�o����u���āA�߉߂����(����)����V����@�B�ߏ��������邽�߂ɁA���ʂɍs���@�v�ŁA�Â��͉���(����)�Ƃ������B�@��@�A�ω���@�A����ɜ�@�Ȃǂ͖ōߐ��P�̌㐶���̂��߂ɍs���A�g�˜�@�͒��썑�ƁA���Љ����̋F������߂čs����B���ÈȌ�A�@��@������ŁA��@�͖@��@�̗��̂ƂȂ����B���u����o�����(��)���B������O�u���邱�ƁB�@
�y�����Ŗ@�z�����傤�߂��ۂ� ����B�����͂��ׂĕϓ]�����ł�����̂ŁA�s�ς̂��͈̂�Ƃ��ĂȂ��B�u���όo�v�́u���s����A�����Ŗ@�A���Ŗś߁A��ňy�v�̎l���̈�B�@
�y���Ŗś߁z���傤�߂]�߂��@����B���όo�ɐ����l���̈�B���ł̐��E���璴�E���邱�ƁB����(�˂͂�)�ɂ͂��邱�ƁB�@
�y��s�y�z���傤�ӂ��傤 �u�@�،o�]��s�y��F�i�v�̂��ƁB���̒���24���̘�(��[�h���s��遖��ꏊ�Ȏ҉��F�s���F���ꓖ�������샌��)��������q���s���邱�ƁB�@
�y�_��z���� (��geya�u����(��������)�v�܂��́u�d��v�Ɩ�)����B�\�o�̈�B�o�T���A�U���̋������d�˂Ę�(��)�ŏq�ו~��(�ӂ���)�������́B�@
�y��݁z���傤���� ����B���Ԃ̗���ɂ������Ȃ��A�P��I�ɑ��݂��邱�ƁB��ɂ��邱�ƁB���������ɋ��Z���Ă��邱�ƁB�@
�y��ݗ�h�R�z���傤�����]��傤���ス��@(�u�@�،o�]���ʕi�v�ɂ��鎩���(��)�̈��)����B�߉ނ̎����͉i���ł���A���ւ̂��߂ɓ��ł����������A���͏�ɐ��@���O�����ϓx���Ă���Ƃ������ƁB�@
�y��������z���傠���܂����@����B���������Ă͂����Ȃ��Ƃ������ƁB�������r�̘�̏���B�@
�y�z������� ����B�o��_�̕��͂̏I���ɁA���̌������ق߂ďq�ׂ�C���B��B�@
�y���z���グ ����B���̓�������������̎��B��B�@
�y��ǁz���� ����

�y���m�z���Ⴍ���� ��m�̈�B�@��̍ہA��(��)�������A����(���Ⴍ���傤)��U����̑m�B�@
�y�~�~�s�{���z�����ӂ��ス�� (�u�@�،o�]���֕i�v�ŁA�ɗ���(�����ق�)���߉ނɁA�@�؈��̖@�������悤��������ɁA�߉ނ̓�������(��))�~�݂Ȃ�~�݂Ȃ�����ׂ��炸�̈ӁB�@
�y�l��z���� �l�̋�B(�l�̋傩�琬��Ƃ��납��)�u��(��)�v�ُ̈́B�@
�l��̐_��(���݂���)�@�����������犙�q����ɂ����ĉ̂�ꂽ�G�|(��������)�Ƃ��Ă̐_�̂̈��B���̐_�̂ɑ��č��l(���܂悤)�̂Ɠ����`���̎����܂̎l��̗̉w�B�u���o�鏴�v�ɏW�ڂ���Ă���B�@
�y�ȘC�g�́z����͂��� ���όo�̎l��̘�(��)�u���s����A�����Ŗ@�A���ŖŖ��A��ňy�v�̈ӂ�\�킵���Ƃ�����u�F�͂ɂقւǎU��ʂ���A�킪�����ꂼ��Ȃ�ށA�L��(����)�̉��R���Ӊz���āA��������(��)�Ђ������v�̎��ܒ��l��l����������Ȃ鍡�l�́B�����ɁA�O�@��t�̍�Ƃ������A���݂ł͔ے肳��Ă���B������������C�w�̐��E�ō���A�����𐮂���̂ɗp�����A�܂���K���̎�{�⎚��\����ѕ��̏����������̂ɂ��g��ꂽ�B�ł��Â�������̂͏���O�N�́u�������ŏ����o���`�v�ł���B�����Ɂu���v����������ꂽ�̂͊��q���ォ��A�u��v����������ꂽ�̂͂��Ȃ��Ǝv����B����͎��B�@
�y�^�Q�E櫒V�E櫒Q�z���� ���S���Ăق߂邱�ƁB���Q���ď̎^���邱�ƁB(�u����v�Ƒ���)����B��������ĕ������ق߂������邱�ƁB������������s��ꂽ����ɂ�镧��櫉́B�@��櫒V�A�S��(��������)櫒V�A�ɗ�櫒V�ȂǁB�O��҂͘a�̂̑́B�@
�y���z���� (�u���v�̓��v��)�T�@�ʼnΑ��̎��A���Ŋ��ɉ����Ȃ���������킽���V���B��ɂ͏��ɉ����Ȃ��ŁA��(��)�������āA�_�̂����������邾���ɂȂ����B�@
�y�\�o�E�\��(�P�E)�z���イ�ɂԂ�]���傤�@����B�o�T�̌`�Ԃ��`������e�ɂ���ĕ��������́B�C����(���ソ�灁�_�o)�A�_��(���⁁����܂��͏d��)�A����(��������u�A��A����܂��͌NjN��)�A��ɓ�(�ɂ��ȁ�����)�A�ɒ�H����(���Ă�����������@����A�{��)�A苑ɉ�(���Ⴞ�����{��)�A�����ɒB��(���Ԃ����܁����\�L)�A���g�ɓ�(�����ȁ�栚g)�A�D�k���(���������၁�_�`)�A�D�ɓ�(�����ȁ�����)�A������(�тԂ�Ⴍ�������A���L)�A�a������(�킩��ȁ����L)�B�O�O�҂͌o���̌`������A���҂͌o���̓��e���痧�Ă����ށB�\�o�B�@
�y�P���Ɂz���� (�u���Ɂv�͞�gDthD�̉���ŁA�L�`�ł͘�܂�����u�ƖB�̗w�̈�)���O�ʼn��ɂ̂����ɂ������M��̗̉w�̏́B���l�`���ƘN�r�`���Ƃ�����A�@������V��@�ŗp����B�@
�y����z��Ⴍ���� ����B���T�̌o�E�_�Ȃǂ��o���₷���C�����������́B��B�@
���@�̘��@����B������Ĕ����Ȗ@�����������(������)�B�@
�y���S�z�ڂ�� ����B�������^�Q���邽�߂ɁA�Ȓ��ɂ̂��Čo���Ȃǂ����r������́B����(���傤�݂傤)�B�����B�l�ӂ̖@�v�̈�B�@��̂͂��߂Ɂu�@�����F�g�A���Ԗ��^���v�Ȃǂ̘�������ĕ������^�Q������́B
 �@
�@��������̒��̓�
�@
16���I�㔼�ɂ͋E���̕x�T�ȏ��l�����̊Ԃł͒��̓����L�����Ă��܂������A�M���͏��l��������L���ȓ���������グ�Č��͂̌֎��E�Ɛb�ւ̖J�܂Ƃ��ėp�����ƌ����܂��B���т��������Ɛb�ɒ�����̉����⒃��J�Ë������܂Ƃ��ė^���鎖�ŁA�̒n���Ɛb�ɗ^�������Ȃ��悤�ɂ���Ƃ�����ł��B���ɒ���n�ސl�X�̊ԂŒ�����̏����̓X�e�[�^�X�V���{���ƂȂ��Ă��܂������A���̎�������ɔ��Ԃ��������Ǝv���܂��B �@
�M�����|�ꂽ��ɂ��̌�p�҂ƂȂ����G�g�́A�M���Ɠ��l�ɒ��̓��𗘗p����ƂƂ��ɁA�֒��Œ�����Â�����哿������ōL���l�����������̒�������֎������肵�Ē��̓��̕����I�n�ʏ㏸��}��܂����B���̓��������̎���̕����Ƃ��邱�ƂŎ����̌��Ќ���ɂ��Ȃ��悤�Ƃ����Ǝv���܂��B���̏W�听���k��咃��ł����B �@
���̎���A�G�g�̉��Œ��̓���傫�����W�������̂��痘�x�ł��B�ނɂ��ẮA���̓��ʎj�ł�����x�q�ׂ܂������A�ڂ����q�ׂ����Ƃ��ꂾ���Œ������W��������{�ł��Ă��܂��܂��̂ł����ł͐\����Ȃ��ł����������܂��B�@

���x���G�g�ƑΗ����Ď��w�ɒǂ����܂ꂽ��ɒ��̓��̎w���I�n�ʂɗ������̂͗��x�̒�q�E�Óc�D���ł����B���x�����ԂŒ���������������q�ْ̋�������W�E���Ԃł̐g�����ɑ����Ȃ����̓���ڎw�����̂Ƃ͈قȂ�A���Ԃ���L�Ԃɓr���ŐȂ��ڂ�����M�l�Ȃ�݂����ƁE���l�̋敪��݂�����Ƃ������������Ă��܂��B���x����s�˂̊y�Ă��D����ŁA�D�����Ǝ��̓�����D��ł��܂��B����܂ł̓���̕]���ɂ͑���ꂸ���g�̉��l�ςɂ�蓹��̉��l��V�������o���Ƃ����_�ŋ��ʂ���ƌ����܂��B�܂�������̐D�c�L�y�́A����Ŏ�N���Ɛb���K�₷��ۂɒ��Ȃ�����艜���~�ɒʂ�u����䐬�v�̋V����ł߂��ƌ����Ă��܂��B���ɂ͏G�g�Ƃ̏Փ˂����������̓��̎������������߂悤�Ƃ��Ă������x�ɑ��A�ނ�͎��̐����Ɍ��F����ی삳��镶���Ƃ��Ē��̓��������鎞��ɂ����Č��͂ɂ��v���ɉ��������͈͓̔��ʼn\�Ȍ��蒃�̓��̌|�p�������߂Ă����Ƃ�������I�Ԏ��ɂȂ������̂Ǝv���܂��B �@
17���I�ɓ��蓿�쎁��������������������̌X���͑����A�D���̒�q�E���x���B�͍��Y�̐V�������Ɏ��グ�Ė������ď��喼�ɕ����^���܂����B�����̓���́u���������v�ƌĂ꒿�d����鎖�ɂȂ�܂��B���B�͊��i�\�O�N(1636)�ɏ��R�E�ƌ��̑O�œ_�O������h�_�ɗa����܂��B����͔ނ̗��V�����쐭���Ɍ����ɍ̑����ꂽ�����Ӗ����Ă���A���喼�ɂ����B�����w�Ԃ��̂�����������悤�ɂȂ�܂��B��ʂɉ��B�̒��̓��͗D��Ŕ�r�I�����b�N�X�������͋C�������̂ł������ƌ����A���ꂪ�u�������ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�������̋��X�@�a�́u�P�@�a�v�ƌĂ��قǗD���E�[���ȗ��V�̒��̓����s���A�F�G�̂����m���Ă���点�D��ŗp���܂����B�ނ̗��V�͗D���Ȏ���D�ޒ���M���Ɏ�����鎖�ƂȂ�܂��B�ЋːΏB�͗��x�̒��j�E�瓹���Ɋw�сu�V��̂�сv���d��ȂǗ��x�̍D�݂ɋ߂����̓����s���܂����B�ނ̗��V�͏��R�E�ƍj�ɍ̑����ꉓ�B���ɑ����Ď嗬�ƂȂ�܂��B �@
�ނ�喼���l�����̐������F�̕����Ƃ��Ă̒��̓��̂������͍���������ŁA���x�̑��E��@�U�͎d��������������������݂̂Ȃ���Ԃŗ��x�̗�������ޒ��̓���Njy���Ă��܂����B�����A�@�U�͂����������𑧎q�B���d�������鎖�ŕ��y�����悤�Ƃ��Ă��܂������A����M���ƌ𗬂������L���悤�Ƃ��Ă����悤�ł����B�@

���쐭�����������������ɂ́A���쎁�ƌ��т�����p���l���͂���������~���܂����B�ނ�͏��喼�Ƃ��o�ϓI�Ɍq��������������鎖�ɂȂ�܂����A���̓���ʂ��đ喼�ƌ����������Ă����̂ł��B�܂����̎����͈�ʒ��l�⏗���ɂ����̓����L����n�߂Ă���A�ΏB���̑���������u�����V�ԁv���ď������l�̐S����������͉̂���I�Ȏ��ł����B��{�I�ɒj���Ɠ��l�Ɋ��K�ɏ]�����A�j���Ɠ��Ȃ��鎖�ɔ������p�Ȍ���������͔̂�����悤�z�������߂�ƌ������e�ł����B�@

�G�g���{���Œ�����s���Ĉȗ��A���X�ɒ���ɂ����̓������t���Ă����܂��B�������̗l���͐��Ԉ�ʂƍ����قȂ��Ă���A���̌�ʼn���E�̕����ȁE�V�Y(�o�Z�Ȃ�)���Â���鎖���ʗ�œ�������̒�����Ȃǂ��D�܂ꂽ�悤�ł��B17���I���ɂ͏�C�@�{�����@�e���ɂ�蒩��̒����l��������Ă����܂��B�����~�𒆐S�ɂ��Ē����s�����@���p���ĉ��Ȃ��y���ށA��r�I�V��������𒿏d�A�|�����ł͓`���I�M���������d��Ƃ��������i���m������Ă����܂��B����ł͑��Ƃ͈قȂ����Ǝ��̒��̓�����������Ă����ƌ����܂��B����͑��c����E�痘�x�ɑ�\�����̂ђ������J�둫������̓����ɋ߂��V���I�Ȑ��i�������Ă����̂ł��B �@
17���I�㔼�ɂ͌㐼�@�E�^�h�@�e���炪�����D�݁A�㐼�@���e�����l�X�𒆐S�Ɍ���ꂽ�q�����ƒ����y������Ő^�h�@�e���͕��Ƃ��܂ߍL���͈͂̐l�X���q�Ƃ��ď����Ă��܂��B�߉q��꤂͊y�Ă�p����ȂNJO���̗��V�������ꂽ�ƌ����܂��B���̈���ŁA�a�̂╨����߂Ɠ��l�Ɂu��`�`���v�������̂Ƃ��ꂽ�̂����쒃�̓��̓����ł����B�@

17���I�㔼�ɂȂ�Ə@�U�̑��q�����͒��j�E�@��(���ҏ��H���)�����������ƁA�O�j�E�@��(�\���)������ƂȂǂ��o�ċI�B����ƁA�l�j�E�@��(�����)������O�c�ƂɎd���������ꂼ�ꋒ�_�����ɒu���Ċ������Ă��܂��B���̓��̒��S�n�ł��鋞������������Ŋe�n�ɗ��V��`���鎖�ŁA���x�̌����ƌ������݂����莟��ɎO�̐�Ɨ��͗͂�L���Ă������ɂȂ�܂��B�܂������A�\��Ƃ���͐V���ȗ��h���������܂�Ă��蓡���f���␙�ؕ��ւȂǂ�y�o���Ă��܂��B���ւ͈ɐ��O�{��t�ňɐ���S�����E�Ԋ��ŋ������L���A��q�̏K���ɉ����āu�`���v��^���Ă��܂����B����œ��l�ɕ\��Ƃ��番���ꂽ�R�c�@徧�́u�����v�^�v�u�����֖���v�Ƃ��������������s���Đ��Ԃւ̌[�ւ�i�߂Ă��܂��B17���I������蒬�l���Ώۂɒ��̉���������������Ă��܂����A���̑�\�I���݂ƌ�����ł��傤�B18���I�ɂȂ�Ɨ���Ƃ̈ꓕ�@�����u������b�v�u�����l�^���v�Ȃǂ̒��������s����ƂƂ��ɁA���̓��̍L����ɑΉ������V�����m�Õ��@�Ƃ��ĕ\��Ƃ̔@�S�֏@��(�ꓕ�̎��Z)�E���s���Ƃ����k���āu�������v���J�n���Ă��܂��B��x�ɑ��l����ɂ���E�L�Ԃōs���ȂNj����̂�����Ɣ�ׂĈقȂ��Ă������ߔᔻ������܂������A�����w�Ԑl�����������������A���l����ΏۂƂ��Ă̋����@���K�v�Ƃ���Ă��莵�����͒蒅�B���l�������e����X�y�[�X���m�ۂ��邽�ߍL�Ԃ�p���A��{�w�K�Ƃ��Ă̔������K���d�鎵�����͐�Ɨ��ɂ����Ă�����ɑΉ������ω���]�V�Ȃ����ꂽ���������Ă��܂��B�܂��A���̎����ɎO��ƂƂ���q���`���x�E�y�̐��Ȃnj`�����������Ă��܂��B�������A���s���͍]�˂ɍ�����u���֓��ւ̒��̓��̍L����Ɉ�������Ă��܂��B�@

�喼�����͑������X�e�[�^�X�V���{���̂��߂�Ќ���̕K�v�����蒃����̎��W�ɗ͂𒍂��܂����B17���I�㔼�̈ɒB�j����18���I�����̓��Ëg�M�͐������̒���E�������Â������Œm���Ă��܂����A�_���Ȃǒ��̓��ɂ���������͂������̒��������S���Ă����悤�ł��B���̓�l�ɑ�\�����悤�ɁA���������������Ď������s�킹�喼�͖��ڏ�݂̂̒���ł������̂��ʗႾ�����悤�ł��B�������Ē��̓��ɂ�����������������ꂽ�喼�̒��ɂ͓���̕��ނȂǓ��������S���������������܂����B�Ⴆ��18���I�O���̏�����W�͉Ƒ�����⑼�Ƃ���̎ؗ������}�E���@�E�t���i�Ɏ���܂ŋL�^�����ނ����u�O�������W�v���܂Ƃ߂Ă��܂��B �@
�ނ��A�S�Ă̑喼�����̓��̎������ł��Ȃ������킯�ł͖ܘ_����܂���B18���I�㔼�̖���R�͐ΏB�����w�ї��x�̗�������ޘ̂ђ����D�݁A�����Ύ��璃����Â��܂����B�܂������̓�����łȂ�����̍D�݂̓�����V���ɍ�点���蒃�Ȃ�v�����肵�Ă��܂��B�܂��ΏB���`���҂Ƃ��ĖƋ����s����قǂ̘r�O�ł����B�������̏����s�����ΏB���ɍ��h���w�ѐ^��q�̓`������r�O�ŁA�喼�ɒ������������薼����������W����ق��ɂ�͂莩��̍D�݂̓������点���肵�Ă��܂��B�܂��s���͒��������ʁE��ʂɕ��ނ������N���������u�Í��������ځv��Ҏ[�������ł��m���܂��B �@
�������̑�V�Ƃ��Ēm����19���I���̈�ɒ��J���A�ΏB�����C�ߍD�݂̓������点�邾���łȂ�����q��݂��ē�����������Ɛb�ɋ��������肵�Ă��܂��B�܂��u������v�u�]��c�S�v�̌��t�Œm����u�������W�v���Ē��̓��ɂ����闝�O������Ă����܂��B��ɒ��̓��̋ߑ㉻��i�߂邱�ƂɂȂ闠��Ƃ̌��X�ւƂ��e�����������̂͒m���Ă��܂��B�@

19���I�ɂȂ�ƒ��l�̒��̊y���ݕ������l����������悤�ɂȂ�܂��B������̕��ނ̑��ɒ�����ÓT�E��L�܂ŋL�^�����u���햼���}�b�v��Ҏ[�������̑��Ԓ����̂悤�ɒ��팤��������ҁA�k���̑K���ܕ��q�̂悤�ɓ��@�̈�Ƃ��Ē�������W�ߒ��̓����s���Ă����ҁA�ɐ��̒|��|�ւ̂悤�ɒ��ԂƋ��{�����߂�ړI�Œ���n�ގ҂܂ő��푽�l�ł��������́A���̓����x�T�w�𒆐S�ɒ��l�ɂ��L�����t���Ă��������Ӗ����Ă��܂��B�@

������ɂ́A���̓��͗��x�玞��̂悤�ɕ����̎���Ƃ��Ď�����ے����鎖�͂���܂���ł����B���������l�E���Ƃ��킸�X�e�[�^�X�V���{���Ƃ��āA�K�{���{�Ƃ��ď㗬�K�w�̕����f�{���x�����������������Ɖʂ����Ă����̂ł��B�ߑ�ɓ���ƁA���|�I�ȋZ�p�E�R���͂������m�������^���镗�������܂蒃�̓������̐�����Čh������t���̎��オ���炭�����܂������A���̕��������܂�ƐV���ɑ䓪�������ƉƂ���������̃X�e�[�^�X�V���{���ɒ��̓���I�Ԃ͎̂��R�Ȑ���s���ł����B�ނ�́u�ߑ㐔��ҁv�Ƃ��Ē���������W����݂̂Ȃ炸�Ǝ��̊����Ŏ�����Â炵���̓��̗��j�ɓ��M���ׂ���ł��`�����鎖�ɂȂ�̂ł��B�@
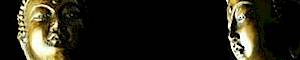 �@
�@


 �@
�@ �@
�@

 �@
�@

 �@
�@ �@
�@

 �@
�@

 �@
�@
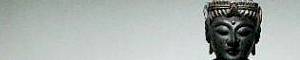









 �@
�@
 �@
�@

 �@
�@




 �@
�@ �@
�@