
藩の御用品、将軍家・公家・諸大名家(諸侯)への贈答品として焼かれた磁器だけに民間の窯(民窯)の磁器と比べ格調高い仕上がりになっている。民窯の磁器との違いを出すため、独特の形状「木盃形」をしているものが多く、伝統的な「花鳥・山水」の文様に加え、着物の文様「染織文様」を応用するなどデザインにも工夫が凝らされている。金や銀を用いない落ち着いた色調だが、えも言われず美しい。
鍋島焼は諸侯のための実用品として焼かれた磁器だけに圧倒的に食器が多い。なかでも皿は独特の形状「木盃形(高台が高く円形)」のものが大部分を占める。変形の皿もあるが、ほとんどの皿は一尺・七寸・五寸・三寸いずれかの木盃形だ。成形は轆轤(ろくろ)細工により行われるが、整形には削り出しによる「丸物造り」と型にかぶせることによる「型打ち造り」とがある。いずれの整形法によっても形状は緻密で一分の歪みもない。鍋島焼の形は端整さの一言に尽きる。
■色
鍋島焼の美しさは地の色にある。「透明感のある白(純白)」地があってこそ染付の藍、上絵付の赤・緑・黄、青磁にあってはその青が映える。民窯の代表的有田焼「古伊万里」は金や銀を多用した金襴手(銀襴手)が世に知られているが、鍋島焼は金や銀を用いない。華やかながら抑制のきいた配色だ。品格を意識した抑制のきいた配色、落ち着いた色調によって醸し出される上品さと言える。
■デザイン
実用性と品格を意識した抑制のきいたもので、伝統的(中国風)な花や鳥、山水画調の文様もさることながら着物の染織文様を応用したデザインや地の白を活かしたデザインなど「純和風」と言うべきものは実に斬新だ。和漢両様、また、和漢融合のデザインは鍋島焼の独創と言っていい、工芸美の極致たる所以である。
■美意識
鍋島様式の花や葉などの素材は、いずれも計算され洗練された文様となって表現されている。余白や青海波(せいがいは)などの連続地紋を巧みに使い分け、全体としての美しさを作り上げる構成に現代のデザインに通じるものがある。色絵磁器である色鍋島で使われる色は、染付の藍を別にすれば上絵の赤・黄・緑の三色に限定され、その中で美しい色絵をつくりあげている。鍋島様式の特徴のひとつに櫛目高台があり、高台部に寸分の狂いなく、櫛の目のように等間隔に描かれた文様は、描きはじめと描き終わりの見分けがつかない程の精密さである。
■種類
代表的なものは色彩のある色鍋島で、将軍への献上品や他藩公への贈答用に特別に焼かれたものである。染付の鍋島のことを藍鍋島といい、作品の大半がこの藍鍋島と青磁釉をかけて焼かれた鍋島青磁である。その他、銹釉を使った銹鍋島、呉須をいれた釉薬を流し掛けて焼き上げた瑠璃鍋島がある。
鍋島様式の特徴の一つに規格化された形がある。鍋島焼は城内での使用をはじめ、食生活用品の比率が高く、ほとんどが会席膳用の食器といわれている。木盃の形をした深めの皿に高めの高台をつけた、高台皿と呼ばれるものが、七寸皿、五寸皿、三寸皿などのサイズでつくられていた。
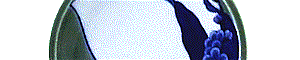 |
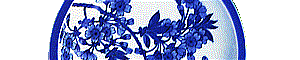 |
 |
 |
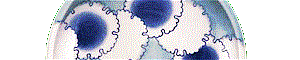 |
 |
 |
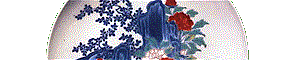 |
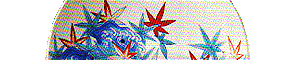 |
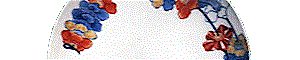 |
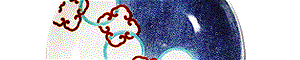 |
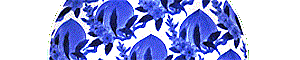 |
 |
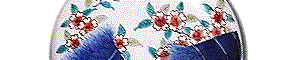
鍋島焼は城内で使用する御道具として焼かれたが、大きな目的は京都御所をはじめ、将軍家、徳川諸藩、諸大名への献上品にふさわしい最高級の作品の製作であった。磁器製作の最先端をいく鍋島藩にとって、その技術を高め秘匿することが極めて重要であり、何度かの移転ののち1670年代に秘窯と呼ばれる大川内山に藩窯を移したり、有田の中心部に赤絵町を設けて赤絵屋を登録し、一定地域に居住させ管理保護したことなどから知ることができる。赤絵町のシステムを保持するために、大川内山の藩窯で焼かれたものも、他の有田の窯のものと同様にこの赤絵町に持ち込まれて絵付けされていた。その御用赤絵屋として有名なのが現在13代になる今泉今右衛門家である。
藩窯の監督ともいえる陶器方役副田(そえだ)氏の系図によると、鍋島藩窯は寛永(1624-44)時代に岩谷川内(いわやごうち)に副田日清を派遣した頃にはじまり、寛文(1661-73)時代に南川原(なんがわら)へ、延宝(1673-81)時代に大川内山(おおかわちやま)(現在の佐賀県伊万里市)に移窯し、明治4年(1871)の廃藩置県で藩が無くなるまで鍋島焼が焼成された。大川内山以前の作品を古鍋島(初期鍋島)や松ケ谷手と称し、その製陶技術の最盛期は、元禄時代を中心とする時期と考えられている。

相場師の作った美術館、老人にはきついロケーションだが半日楽しむ。懐かしい小学校の裏山を思いださせてくれた。



