|
����y
�@ |
|
��y�͕����܂̐��E�ł��B���̕����܂̐��E�ɐ��܂�邱�Ƃ��������ɂƂ��Ă̋~���ł��B���ꂪ�^�@�̊�{�I�ȋ����ł��B��y�Ƃ́A���y���Ƃ����{���Ƃ������鈢��ɔ@���̍��y�ł��B�������l�Ԃ̐����鐢�E�ɂȂ��炦�č��y�Ƃ��Č�����Ă��܂��B
�l�Ԃ̋~�ς��Ȃ����y�Ƃ��āA�܂�A��y�Ƃ��Č�����Ă���̂ł��傤���B����͎������̋~�����A�l�I�Ȏ���l�̐S�̈��炬�ɂƂǂ܂�Ȃ�����ł��B�������A�������̐S�����������A�S�����炩�ɂȂ邱�Ƃ͑厖�Ȃ��Ƃł��傤�B
�������A�l�Ԃ̋~���Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA�����P�Ɏ���l�̐S�����炮���Ƃł͖{���̋~���ɂȂ�܂���B������l�X�Ƌ��Ɉ��炮���Ƃ����藧���Ȃ��ƁA�������͋~���Ȃ��̂ł��B
�Ȃ��Ȃ�A�l�Ԃ́A�����ǂ���A�l�Ɛl�Ƃ̊ԕ����鑶�݂�����ł��B�������͊W���Ă��܂��B���E�ƂƂ��ɂ��鑶�݂ł��B���҂ƂƂ��ɐ����鑶�݂ł��B
�ł�����A�����������X�������т��߂��݂��A����͂������̒��ŋN���銴��ł���܂��B�������Ƃ��ɂ��鑊�肪�߂���ł���Ƃ��ɁA���ЂƂ肪��ׂ܂����B�߂����͂��ł��B���ꂪ�l�Ԃ���Ƃ������Ƃ̋�̓I�Ȏp�ł��B
���̂悤�Ȏ������̐����邱�Ƃ̌������A�^�@����y�������Đl�Ԃ̋~�ς𖾂炩�ɂ��Ă������{�I�ȗ��R�ł��B��y�Ƃ͈���Ɍo�Ɂu���ꏈ(������������)�v(�Ƃ��Ɉ���E�ɐ�����)�Ƃ���܂��B���Ȃ��������Ƃ��ɐ����邱�Ƃ̂ł��鐢�E�ł��B
����́A�����Ď����������ʂɍl���Ă���悤�Ȏ���̐��E�Ƃ��Ắu���̐��v�ł͂���܂���B�܂��A���[�g�s�A�Ƃ��Ă̗��z���ł�����܂���B����́A�l�Ԃ������������̂ɐl�Ԃ������镧���܂̐��E�Ȃ̂ł��B
���������l�ԉ̑�n�Ƃ��Ă̏�y�������A�l���������݂��Ă�܂Ȃ��������̒N�����A���������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����E�Ȃ̂ł��B�@ |
 �@ �@
���\�O�����E�\�ܕ����E�\�㕧���̋N�� |


 �@
�@ |
����ɁA�C���h�̋N���Ƃ���A�������A���A�O�����A�l�����A�����A�Z�����A�������̎���(���̎������܂ł𒆉A(���イ����)�Ƃ���)������A�������N���Ƃ���A�S�����A������A�O����̎O�����A�����āA���{�N���Ƃ���A������A�\�O����A�O�\�O����̎O���������킳���āA�u�\�O�����v�ƂȂ����Ƃ�����B���́u�\�O�����v��12-13���I���A��ʂɕ��y�����B16���I���A�\������A��\�O����̓��������u�\�ܕ����v�ƂȂ�A���̌�A��\�܉���A�O�\������A�\����A�S����̎l�����������u�\�㕧���v�ƂȂ����B �@
���́A�������u�s�������v�A���u�߉ޔ@���v�A�O�����u�����F�v�A�l�����u������F�v�A�����u�n����F�v�A�Z�����u�\�ӕ�F�v�A�������u��t�@���v�A�S�����u�ϐ�����F�v�A������u������F�v�A�O����u���\�ɔ@���v�A������u���\(�����キ)�@���v�A�\�O����u�����E����@���v�A�\������u�ّ��E����@���v�A��\�O����u�ʎ��F�v�A��\�܉���u���������v�A�O�\�O����u����F�v�A�O�\������u�����F(����������)�v�A�\����u���������v�A�S����u�ܔ閧(�����F)�v�����I�ꂽ���B�@
�u�s�������v�u���������v�u����@���v�u�����F�v�̕��́A�����̓`���Ƌ��ɓ��{�ɓ����Ă������ŁA���Ɂu�����E����@���v�́A�O�@��t��C�������g�Ƃ��Ē����ɓn��^���������p�̑攪�c�Ƃ��Ď����A���������E��䶗�(�܂�)�ɕ`�����^���������L�̕��ł���B�@
�C���h�N���́u���A�̕��v�A���������A�̕��Ƃ��đI�����ꂽ�L�^�͂Ȃ��B15���I���ɏ\�O���̈Ӌ`�𐳓������邽�߁u�\�O�����v���U�삳�ꂽ�Ƃ�����B�����̐^���́A�F���̐����̒��Ɍ��������ꂽ�����̂�萶���邱�Ƃ��䶗��͕\�����Ă���A���A�����T���\�㕧�̈Ӌ`���������䶗���������ł���B��X���ڂŔF�����Ă��錻�ۊE�̕��l�́A�����╧��ɕ\������镧�����A�����Ȃ蕧�������˂�������̃C���h�̕����́A������{�Љ�̊e���@���J���Ă��镧�����̎p�Ƃ͑傫���ق�
��B����Ƌ��ə�䶗����`��ς����������ɂ����Č`���͂�����Ƃ����B�@
�@�����ŕ\������㹖�(����)��䶗��@�A����Ƃ��ĕ\�����ꂽ�p�Ԍ`���������䶗��@�B�펚(���ザ/���ꂼ��̕��̏ے��Ƃ��ĕ\����������)�ɂ��@��䶗��@�C���ꂼ��̕��̌����̌`���Ƃ��ĕ\�������̏�������|�����͈�_�����Ȃĕ\�������O����(����܂�)��䶗��̎l��ł��邪�A���̌��`�̓C���h�ɂ����ĕ������C�@����Ƃ��ɗp����y�d(���Ƃ͓y�ō�������̂��A�����A���{�ł͖ؐ��ō����悤�ɂȂ����C�@�d)�ł���A���@���J�镧�����܂߂�����(����)���̂��̂���䶗��ł��邱�Ƃ���͂��܂��B�@
�܂�A�\�O���T���\�㕧�̕��́A�������`�̍��{�^�`�ƂȂ��䶗��̒�����I�����ꂽ���Ȃ̂ł���B
�@ |
| ���������V�̋N��
|
���݁A���{�̑��V��9���ȏオ�����ł���Ƃ����邪�A�������V�̌`���̃��[�c�͂ǂ��ɂ���̂��낤���B�e�@�h�͑��V�Ɍo�T��ǂނ��A�����ɏ�����Ă�����e�͑��V���̂��̂ƊW������Ƃ͎v���Ȃ��B�����Ƃ͎ߑ��̋����ł���A�ߑ����g�͒�q�ɁA�u�����̑��V�͒��̎҂����邩��A�o�Ƃ�����q�����͂���ɂ�����炸�Ƃ��悢�v�Əq�ׂĂ��邩��ł���B����������q�����͎ߑ��̑��V�ɐϋɓI�ɎQ�����Ă��鎖�����������Ȃ��B
���{�Ō��ݍs���Ă��镧�����V�Ō����銵�K�̃��[�c�́A�ߑ��̟��ϒ��O�̗l�q��ߑ��̑��V�Ȃǂ��N���Ƃ��Ă�����̂Ƃ�����̂ŁA��������Ă������Ƃɂ���B
�ߑ��͒����`�������̂��ƁA�V�N���}���Đg�̂̐������B���Ȃ��Ȃ����B�����̎����������A����̃}�K�_�����琔�S�l�̒�q��A��Ėk���Ɍ������čŌ�̗��ɏo���B���𑱂��ĖN��ɁA�ߑ��̓N�V�i�K���Ŏ����}�����B����80�ł������B
���ߑ��̕��̑��V
�ߑ���68�̔N�A���F�[�T�[���̑�ѐ��ɂʼnJ�����߂����Ă����B�����Ɏߑ��̐��܂ꂽ�J�r���邩��g�҂������B�ߑ��̕��ł����щ�������̎�����\�m���A���q�ɉ�����Ƃ����m�点�ł������B�ߑ��͏�щ��̕a���̒m�点����ƁA��q�������J�r����ւƏo�������B
�ߑ��͉����������A�{���̐l�X�ɕ��@��������B�ߑ����J�r����ɒ����Ă���7���ڂɉ��͑�������������B�������䂳���ƁA�ߑ��͏d�b�����Ƒ��V�̏�����i�߂��B��������̍�����n�������`�ʼn��̂��炾��A���ꂢ�ɐ@���Ƃ������ƁA���̕z�őS�g�����ɔ[�߂��B7�̕�ň�̂𑑌��������ƁA�������̏�Ɉ��u���A�^��ŕ҂Ԃ𐂂�߂��炵���B���̂��Ɖ��l���ɎU�炵�A���������Ď��҂����{�����B
���𑒏�ɑ���ہA�ߑ��͐e�̉��`�ɕ邽�߂Ɏ��犻���������B�ߑ��̒�A�q���A�]��������������B�e�ɑ���Ō�̍F�s�́A���̈�̂��Ō�܂Ŏ�邱�Ƃ��낤�B���̊���������4�l�́A��щ��̎q���A���A���ɂ�����B���{�̑��V�ɂ����āA�̐l�̎��q�A�Z��A���ƌ����������̎҂����������K��������B����͎ߑ����n�߂Ƃ�������̐[���l�X���A��щ��̊���^���ő��V���c���ƂɗR�����Ă���B�Ȃ����̂��ƉΑ��ɕ����Ă��邪�A����̓C���h�̓`���I�ȑ��@�ł���B
��������̋N��
��̂����ɔ[�߂�O�ɍ����Ő�������B���ꂪ�����ɂ����铒���̋N���ł���B��̂�s���͌��n�������ォ��s��ꂽ�Ƃ�����B�o�T�̒��Ɏ��̂悤�ȋL�^������B
�������m������������A�������A�̂���Ȃ��B���l����������āA�u�ߑ��̒�q�͏Ԃƌ������A�����Đ���ł͂Ȃ��B�����ɗA��̂ɋ߂Â����ɂ��S��炸�A�̂���Ȃ��̂����̏؋��ł���v�Ɣ����B�ߑ��͂�����āA�u�̂𐴂߂Ȃ����Ƃ͂悭�Ȃ��B��̂ɋ߂Â����҂͐�������v�ƌ����āA��q�����ɑ̂��킹���B�ߑ��́A�u��̂ɐG�ꂽ�҂͐g�̂��ߕ������ɐA��̂ɐG��Ȃ������҂́A��Ƒ����낵���v�ƌ������B
�C���h�ł���̂�s��ƍl����K�����������悤�ł���B�C���h�̌Ñ�̖@���ł���w�}�k�̖@�T�x�ɁA�u���̂ɐG�ꂽ�҂�10����ɐ��߂���B���̎�����t�̂��߂ɑ��V���s���w�����܂�10����ɐ��߂���B�Α���Ɏ��̂��^�Ԏ҂����l�Ȃ�v�Ƃ���B
����O�njo�̋N��
�w���ߖ�G��18�x�ɁA�����̍ۂɑm���̒��Ōo����������u���鎖�ɒ������҂��A�w����o�x������u���A���l�̂��߂ə�肹��Ƃ����L��������B���Ƃ����̂́A���҂ւ̖������F��Ӗ��ŁA���݂̉���ɂ�����B�������ォ�畧��q�����V���s���A�njo���s�����ƍl������B
���҂ɖ@�b�������邱�Ƃ́A�ߑ����s�����Ǝv����L�^������B���҂̉ƒ��K��A�e���̐l�X�ɑ��Đ��@���ꂽ���Ƃ́A�w�@��栚g�o�x�ɂłĂ���B��щ������䂳�ꂽ���ɂ��A�ߑ��͒�q�A�{���̐b�Ȃǂ̐l�X�ɐ��@���Ă���B
���̂悤�Ȏߑ��̍s��������ƁA�h�Ƃ�M�҂��A���҂̂��߂��u�o�A���{����@���˗�����邱�Ƃ�����A���̋��߂ɉ����邱�Ƃ͏O�������߂̋@��Ƃ��Ȃ����B
���]�։��̑��V
�ߑ��͈���҂ɁA3������ɓ��ł���Ƃ̐錾�����ꂽ�B����҂͂��̐錾���đ�ςɋ��������A����͕ς����Ȃ������ł������B�����Ď����͎ߑ��̑��V�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA�ߑ��ɂǂ̂悤�ȑ��V��������悢���Ƃ̎w���������Ƃ���A�]�։��̑��V��͔͂Ƃ���悤�ɂƓ������B
�]�։��Ƃ́A�V���ꂷ��`����̒鉤�̂��ƂŁA�푈�ɑ�ύI�݂ȉ��̂��Ƃł���B���̓]�։��͑����E���x�z���鉤�ł��邪�A�����̑���͂��̓]�։���͔͂Ƃ��čs���ƌ���ꂽ�̂ł���B
�ł͓]�։��̑��V�͂ǂ̂悤�ɍs���̂��B�܂����̐g�̂����Ȃŕ�݁A���̏��V�������z�ŕ�݁A����������Ă��̒��ɖ������Ď��̂�[�߂�B����ɊO����S�̊��ň͂݁A��d���ɂ���Ƃ����Ă���B
���̂��Ƃ����鍁���Ă��ĉΑ��ɂ����B�킩��Ȃ��̂́A�S�̊��ł͏Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B��������Ƃ����̂́A��̕ۑ��̖�ڂ����邪�A��͂�Η͂����߂邽�߂ł��낤�B���݁A�K���W�X��͔Ȃł̉Α������Ă���ƁA�d�̏�ɒ��ڈ�̂��悹�ďĂ��Ă���B�����č������S�ɏĂ��Ȃ��܂ܐ�ɂق��荞��ł���B
���ߑ��̎��̍��m
���̍��m�́A�����O�����Ēm�炳��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͈�Â̔��B�������ĕa�����͂����肵�Ă���A���̌o�߂����������\���ł���B�����͐^����Njy���鋳���ł��邽�߁A���ɒ��ʂ��邱�Ƃ����Ƃ�Ȃ��B�ߑ��̏ꍇ�A�����̎��ʎ��������������ŏ��̑���͈����ł������B�����͎ߑ��Ɍ������A���Ȃ��͂��łɒn��ł̖������ʂ����A��q���������Ȃ��̋���������Ă����܂��̂ŁA���܂������ςɓ����Ă��������Ƃ��肢����B����ɑ��Ďߑ��́u�����悠����ȁB���͂���3�J�������矸�ςɓ���v�ƁB������āA����������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
���ߑ��Ō�̐H���Ƃ���(���Ƃ�)
�ߑ��̓}�c�����̏Z�ރp�[���@�[�ɍs���Ė@�b�������B�@�b�͑�ϊ����I�Ȃ��̂ŁA��������b��H�̃`�����_�͂���Ƃ��Ďߑ���H���ɏ������B�H���͑�ςɍ��Ȃ��̂ł���A���߂��炵�����̂ł������B�����ĂȂ��Ɏߑ��ɂ��������ł��Ȃ��������o�Ă����B�����Ŏߑ��͒�q�ɂ����H�ׂ�ȂƂ����A���������͂�������ɂ����B���̂��Ǝߑ��͂��̐H���ɂ�����A���ʂقǂ̋�ɂ����B���̎ߑ����H�ׂ������͓�Ƃ���Ă��邪�A���̂������̈��ł���Ƃ����Ă���B�Ȃ����̐H�������������`�����_�́A��ςɌ���������A�ߑ��̓`�����_�������Ă���B
���Ė@���̐H���ʁu����(���Ƃ�)�v�Ƃ����B�C���h�Ŏ��H�ƔH�Ƃ������t������A���H�͑m�����H�������鎞�Ԃł���A�H�͑m�����H�������Ă͂����Ȃ����Ԃ��w�����B���ꂪ���{�ɂ��`���A���H����(�Ƃ�)�Ƃ������t�ɂ�����Ă��������̂Ǝv����B
�������̐��̗R��
�Ƒ���e�ʂ̐l���A�ՏI���ނ������l�ɖ����̐�����������K�������݂ɂ��c����Ă���B�M��ɐ������ĐO�����点����A�V�����Ȃɐ������߂点�ĐO���ʂ炵���肷��B���̖����̐�����������s�ׂ́A�ߑ��̗ՏI�Ɉ���҂����������グ�����Ƃɂ��ƂÂ��Ă���B
�ߑ��͗��̓r���A�H���ɂ������ċꂵ��ł����B�ނ��؍݂��Ă����p�[���@�[�Ƃ������́A�������̂��߂Ɉ�҂����Ȃ��B�����Œ������̂�ł͂��邪�A��҂̂���N�V�i�K���܂ŋA�邱�ƂɂȂ����B���̓r���A�����Ȑ�̕ӂŋx�e�����ꂽ�B
�ߑ��͍A�������Ďd�����Ȃ��̂ŁA���s�̒�q�̈���ɐ�̐�������ň��܂��Ăق����Ɨ��B�������߂��̐�͐��������Ă����̂ŁA�����̐�ɋ��݂ɍs�����Ƃ��Ă����B�������ߑ��͋߂��̐�ŋ��ނ��Ƃ�������B�ߑ��ɂ��������Ă�����x�o�����ł݂�ƁA���łɐ�͂��ꂢ�ɂȂ��Ă����B�����ň���҂͊�ɂȂ݂Ȃ݂Ɛ�������ŁA�ߑ��ɍ����グ���B�ߑ��͂��������ƌ����Đ������B���̐����ߑ��̍Ō�̈����ł������B
���ߑ��̎�����
�����̑��V�ł͕��ʁA�[�������Ƃ��ɔ��̌o�����т�𒅂�B����͏���̍ۂɒ��鑕���ŁA����̓r���ɓ��œ|���Ƃ��̈ߑ��̂܂܉Α��ɂ��ꂽ�B���Ďߑ��̏ꍇ�A�}�c�����̃v�b�N�T�Ƃ����l����A���F�̈ߑ���ꂽ�B��q�̈���͂�����ߑ��ɒ��������B�r���}�Ȃǂɂ���Q�߉ޑ��̈ߑ������F�ɂȂ��Ă���̂��A�v�b�N�T���瑡��ꂽ���F�̈ߑ��𒅂Ă��邩��ł���B���̈ߑ��͂��̂܂ߑ��̎������ƂȂ����킯�ł���B
�������o���Ǝ��؉Ԃ̋N��
�ߑ��͑����̏C�s�m�ƈꏏ�ɁA�N�V�i�K���ɂނ����Đi�B�N�V�i�K���̓����Ƀo�c�_�C�͂�����A���̕ӂ܂ł��ǂ蒅����������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�o�c�_�C�͂̓����̒��̂́A�����o���̗тƂȂ��Ă���A�ߑ��͂��̗т̒��ŋx�݂����ƌ���ꂽ�B
����͍����o���̗т̒��ɐ̑���������̂ŁA�����Ɏߑ��ɋx��ł����������B���̂Ƃ������o������ʂɉԊJ���A��͔��h�̉Ԃ��~�蒍�����B
�ߑ��̟��ς̖͗l��`�����}�ł́A���ɂȂ��Ă���ߑ��̎l����傫�Ȏ����A4�{���邢��8�{�`����Ă���B���ꂪ�����o���ł���B������1�{�œr������2�{�ɕ�����ĕ`����Ă���B���{�̑��V�ɂ́A���̎��؉Ԃ�p����K�����S���Ō�����B����́A�ߑ��������o���̖Ɉ͂܂�ĖS���Ȃ�ꂽ���Ƃ���A��ʂ̐l�̑��V�ɂ��ے��Ƃ��Ďg���Ă���B�����ɂ���̂́A�ߑ������ɂȂ����Ƃ��A�����o���������Ԃ��炩���ċ��{�������ƂɗR�����Ă���B���������{�ł́A�y���̂Ƃ��ɖ��������y�n�̎l���ɂ����u�����Ƃ�����������A�������Ȃǂ̎�p�I�ȗp�������������Ƃ��l������B
�����k�ʐ��̗R��
�l���S���Ȃ�ƁA���߂ĕz�c�̈ʒu��ς��ĕ~�������B���ɓ���k�����ɂ��ĐQ������Ƃ������K������B����͎ߑ������ł����Ƃ��A����k�Ɍ����ċx�܂ꂽ�Ƃ������ƂɊ�Â��Ă���B
�o�c�_�C�͖͂k�ɐ���������A��Ɍ������ė���Ă���B���̉͂̓����ɂ��鍹���o���̗т̂Ȃ��ŁA�ߑ��͓���k�A�����A�E�e�����A��𐼂Ɍ����ċx�܂ꂽ�B����k�ʐ��Ƃ����A�E�e�����ɂ���Q�������q��̖@�ƌ����Ă���B
���ՏI�̒m�点�Ɵ���
����̓N�V�i�K���̒��ɍs���A�W���Ŏߑ��̎��̋߂����Ƃ��������B���̐l�X�͂�����ƁA�吨�̐l�X���Ō�̐������Ɏߑ��̂��ƂɏW�܂����B�ߑ��̎��ςɓ���Ƃ����B���ς̋��n�͊o�҂��������B�ł��鋫�n�ł���̂ŁA�}�l���S���Ȃ��Ă����ςɓ������Ƃ͂���Ȃ��B�ߑ��������������ςɓ���Ƃ����m�点���āA�y�n�ɏZ��120�̊w�҂̃X�o�h�����ߑ��̋������A��q�ɂȂ肽���Ɗ�����B
�ߑ��͍Ō�̋���������ƁA�Â��ɟ��ςɓ������B����ߑ��̟��ς�l�X�ɓ`����ƁA��n���k���A�V�̑��ۂ���A�����ĉԂ��~�蒍�����B
���ߑ��̍Ŋ��̌��t
�ߑ��͍Ŋ��܂ňӎ����͂����肵�Ă���A�����Ƃɂ���C�s�m�����ɍŌ�̌��t���c�����B����́A�u�C�s�m������B���O�����ɍ����悤�A�w�������̎��ۂ͉߂�������̂ł���B�ӂ邱�ƂȂ��C�s�����������Ȃ����x�v���ꂪ�Ō�̌��t�ł������B���ł����͖̂����̖�Ƃ����A�킪���ł�2��15���ɟ��ω���ƂȂ܂��B
���Ō�̂��ʂ�ƒʖ�
�ߑ����S���Ȃ�ƁA�l�X�͒Q���߂���ŁA��ڂł��������畧��q���邱�Ƃ�������B����҂́A���̊肢������āA�吨�̓�⏗���M�҂����ɑO�ɐi�ނ��Ƃ��������B�����ŏ��������͈�̂ɋ߂Â��A���܂��܂ȍ���Ԃ����������B���ߗ�(���Ȃ��)���͂��߁A�����̒�q�����͎ߑ��̈�̂̍��E�ɂׂ͂��āA�����ɂ��Č��Ȃ����𖾂������B
�����̋��{
����͑����Ƀ}�c�����̏W���ɍs���āA�ߑ��̎����������B��������l�����͔߂���ŋ����A�n�ʂɓ|�ꂽ�҂��������B
�����Ń}�c�����͏]�l�����Ɂu���ɂ��鍁�ƉԗւƊy������ׂďW�߂�v�Ɩ������B��������l�X�́A�o���邾�������̂����ƉԗւƊy��ƕz�n�������āA�ߑ��̂��鍹�����̗тɌ��������B�z�ł������̎P�����A������d�ɂ�����߂��炵���B�����Ďߑ������y�Ɖԗւƍ��ŋ��{�����B���̂悤�ɂ��Ă��̓��͉߂����B
���̓��̖�A���������͈���҂ɁA�ߑ��̂��߂�7���Ԃ̋��{��\���o���B����҂��痹����ƁA�}�c�����͗����������悤�ɉ��y�Ŏߑ������{�����B��������7���ڂɉΑ�����������}�����B���̓��̒��A�}�c�����͎ߑ��̈�̂����y�ŋ��{���Ȃ���A��̒��܂ʼn^�B�l�X�͒���|�����A���ɏ��������œ�����҂����B�����Ĉ�̂��悹����`������ɓ������Ƃ��A�V����͉��J�̂悤�ɍ~��A��̂̂��Ƃɑ����̐l�X���]�����B
���ߑ��̑���
8�l�̃}�c�����̎w���҂͓����琅�����Ԃ��đ̂𐴂߁A�V�����ߑ������Ďߑ��̈�̂��������B��������̂��т��Ƃ������Ȃ��B����͈�̂��ɉ^�ڂ��Ƃ�������ł���B�����Ŕނ�͖k�̖��ʂ��Ē��̖k�ɉ^�сA�k�傩�璬�̒����Ɍ������A�������獶�ɋȂ����ē��傩��O�ɏo���B�����o�āA���n���ĕ��Ɏ���A���̓��Ɍ�`���~�낵���B
����{��(������)�̗R��
�ޗt���҂�500�l�̒�q��A��ĉ����ɂ����Ƃ��A�ߑ��̕a�C�̒m�点�����B�ŕa�ɂƋ}���ŃN�V�i�K���Ɍ������r���A��ɂ܂�������l�ɏo������B���V�ɒ����}�̂�����{�Ԃ����K��������̂ŁA���V���������̂ł��낤�B�����ŔނɎߑ��̂��Ƃ�₢�������ƁA���łɈ�T�ԑO�Ɏ��S���A���̑����ɏo�Ă��̉�������Ă����ƌ�����B��������ޗt�́A�Α��ɒx��Ȃ��悤�ɂƓ����}�����̂ł������B
���{�ɂ͂܂�͂Ȃ��̂ŁA�����ɑ��V�Ɉ�{����g���B��̎��̓C���h���Y�ŁA�Ӑ^�a�������{�ɂ����炵���Ƃ����Ă���B
����(������)�F�V�L�~�Ȃ̏�Ώ����B�u�����сv�Ƃ������B�u�v�Ƃ������B)
�����ł̉Α�
�C���h�ł͉Α��ō����g�����A���{�ł́A���V�̎��ɖ������ďč�����B������p���ďč����A���؋��{�ɂ�����̂ł��낤�B
�C���h�ł͎ߑ��̎�����Α����s���Ă����B�Ւd�̉Α����鏊�ɍ���ςݏd�ˁA���̏�Ɋ������u���A���𒍂��ʼn����ĉΑ��ɂ���B���V�ɂ͉Ԃ�����鑼�A12�ڂقǂ̍��������Ď��҂����{����K��������B���̍��͉Α��̐d�Ɏg�p����̂ł���B
���ߑ��̉Α�
�}�c�����͈���Ɉ�̂̏����̎d����q�˂��B�����ň���́A�ߑ����畷�������@��ޓ��ɍ������B
�����Ń}�c�����̐l�X�́A�ߑ��̈�̂�V�����z�ŕ�B���ɂق������Ȃŕ�B���ɐV�����z�ŕ�B���̂悤��500�d�Ɏߑ��̈�̂���ŁA�S�̖����ɔ[�߂��B���̒���ɍ���ς݁A�����Ɏߑ���[�߂������悹�A�]�։��Ɠ����悤�ɓS�̊ʂłӂ��������B�����č������������A�}�c������4�l�̑������d�ɉ����悤�Ƃ������_���Ȃ������B����́A�ߑ��̒�q�̉ޗt���҂̓�����҂��Ă���ꂽ����ł���B
���̂Ƃ��ޗt���҂͉Α���ɓ��������B�ނ͍��������ɂ��������āA�������Đd�̉���3��E�ɂ܂��A�ߑ��̑����ɗ�q�����B���̂Ƃ����ɓ����Ă����ߑ��̑����p������킵���Ƃ����B���̂悤�ɉޗt�ƏC�s�m����q�����Ƃ��A�Α��̐d�͎��R�Ɖ��������ĔR���オ��A���̂Ȃ��̈�̂��Ă��グ���B
���ҍ��@�v�̃��[�c
�������Ďߑ��̊D�����������ꂢ�ɔR���A���̂Ȃ��͈⍜�����ɂȂ����B���̂��ƓV����J���~�蒍���ʼnΑ��̐d���������B䶔������ނƁA�}�c�����̐l�X�͈⍜���W�߂ċ��̂��߂ɓ���A�W���ɉ^�B���߂̉�����ň͂ނƁA7���̊ԉ��y�ƍ��ŋ��{�����B
���{�ł��Α����I������⍜������̌����d�Ɉ��u���āA�ҍ��@�v���s�����A���̃��[�c�͂����ɂ���Ƃ�����B
���ߑ��̎ɗ�
�ߑ��̓��ł��e�n�ɕ����ƁA���̍��̉����A�ߑ��̎ɗ��z���Ăق����ƃN�V�i�K���֗v�������B�������Ďɗ���8����1���e���ɕ��z���ꂽ�B���z�������ƂɁA���[���A���������悤�ɐ\���o�������B���������łɈ⍜�̕��z�͏I����Ă����̂ŁA�g�҂�䶔��̊D�������Ԃ����B�������Ďߑ��̈⍜��8�̑����k������Ă����ɔ[�߂�ꂽ�B�܂����[���A���͊D�̓���������J�����B
�������k�̋N��
�ߑ��̈⍜���J��K���͂�����n�܂����̂��낤�B�����̑����k�̏ꍇ�ɂ́A�ߑ����g������҂ɏq�ׂ����Ƃɂ��B
�ߑ��́A�����̈�̂��Α��ɂ������ƁA�l�҂ɑ����k�����ׂ��ł���ƌ����Ă���B�����āu�����Ɉ⍜��[�߁A�ԗւ܂��͍������������ė�q����B����͌����l�̑����k�ł���Ǝv���Ƒ����̐l�̐S�͐Â܂�B�����Ď���ɂ͓V�̐��E�ɐ��܂�邱�Ƃ��o����v
���̂悤�Ɏߑ��͌�����B
�����ɗ��̔���
1898�N�A�l�p�[���̍����߂��̃s�v���[���@�ŁA�t�����X�l�̍l�Êw�҃y�b�y���ɗ��ق������B���̕\�ʂɁu����͕��ɐ����̎ɗ���[�߂��ł���v�ƋL����Ă����B
�@ |
 �@ �@
�����A���͒��L(���イ��) |


 �@
�@ |
�^���@�̑��V�̋V���ɂ����čs��������@�̒��̕\�����Ɏ��̋傪����B �@
�h���āA�^���������@�������E������O�E�E�E���E�E�E���Ǝ�(������)�A�s���̐��A�łƎ�(������)�A�s�ł̖ŁA���ŋ��ɕs���Ȃ�B���ď̂��ׂ��炴��҂��B�����ɍ����̖S�ҁA�O�k�̉��A���Ƃ��Ƃ����ɑ��E�Ɏ�āA�앂�g(�ȂԂ���)�𗣂�Ă܂��ɒ��L�ɂ���A����č��A�߉��\�P�̈╗�ɔC���āA�Ȃ��Ȃ�����䶔��̋V���������A�@���L���̓�����������݂āA�V���ɐ��쓾�E�̈���(���傤)���F��B�Z�喳�V�̉�R�₵�āA�{���s���̑̂��Ă��E�E�E�Ƃ���A�O���Ɏ��������A��������(�։��]���ɂ�鎟��)������Ԃ������B �@
�������T�Ȃǂł́u���L�v�̌`�́A���̎�ׂ����̖{�L�̌`�̔@���A���̊Ԃ̐l�̐g�́A������5-6�Έʂ̌`�ʂɂ��āA���ׂ̏�F���ȂĐ���A����ɂ͌������B���̑������鎞�Ԃ͋ɏ��������͎������A�����͖����Ȃ�A�Ɛ������Ă���B�������ꂪ�u���A�v�ɂ����镧���̋N���ł���B���̊��Ԃ��u�����v�Ƃ����B �@
�`���́u����@���v��^�������̋��呦�����{���Ƃ��闼���E��́A�u�����E��䶗��v�Ɓu�ّ��E��䶗��v�̗����E�������B�����E��������E�ɑ����鏔�����O�̒��ɏ\�O���T���\�㕧������A�����̕��̌������ȂĖS�҂̖������F�鋟�{���A�N��(���)�̕����Ƃ��čs���邱�ƂƂȂ����Ɖ��߂ł���B �@
�Z�喳�V(�ނ�)�́u�Z��v�Ƃ́u�n�A���A�A���A��v�ܑ̌�u�F�������̍��{�v�f�v�������\������v�f(���̊E��\��)�u�́v�̓����������u�ّ��E�v�u���v�ƁA��Z�Ԗڂ́u���v(���_�E��\��)�u�S�v�̓����������u�����E�v�u�q�v�����킹�����̂ŁA���̗��E�́u���q�s��v�ł���Ɛ����Ă���B |
|
�����A(�l�\���)�ɂ���
�@ |
����������O����C���h�ɂ����������ςɁA�]���։����Ƃ����̂�����܂��B�����̐l�X�͐����Ƃ����̂́A1�̐����I���Ƃ܂������ɐ��܂�ς��A����͂��������ԗւ���]����悤�ɁA���܂邱�Ƃ��Ȃ��ƍl���Ă����̂ł��B���̐��ɂ�����A���̏u�Ԃ��玟�̐�����܂ł̊Ԃ̎����A����𒆉A(���イ����)�܂��͒��L(���イ��)�ƌĂт܂��B
�@
�Ƃ���ŁA���̐��܂�ς����ł����A������P�ʂƂ��Đ��܂ꂩ���Ƃ����̂ł��B����҂͏������ŁA������킵�����͓̂��ŁA���l�ɎO�����c�@�Z�����ŁA�������Ȃ���ǂ̂悤�Ȏ҂ł���A���������z���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����̂����A�v�z�ł�(�����A�l�\����������Ė����A�Ƃ����̂́A����ɂ��܂�)�B
�@
�����͒��o���I�ȓ]���։�̍l�����͍̂�܂���A���A�v�z���Ȃ����ł����A��������Ղ��������߂ɁA���A�v�z�����(�^����������߂̎肾��)�Ƃ��č̂����Ă��܂����B�������A�����܂ł����ւł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B
�@
���āA�킪��y�@���R�W�ю��h�ł́A�u�얳����ɕ��v�Ɩ�ɂ̎��߂��Ĉ��S(����)�Ă���҂͒��A�̏�Ԃ��Ȃ��A�Ɛ����܂��B�ՏI�ԍۂ̂��Ƃ��\���̂��O���ł����Ă��A�܂���������ɏ̂��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���ԂɊׂ����҂��A�l�̏̂��邨�O�������ɂ��邾���ł��A�����Ɉ���ɕ��̗��}��ւ��ĉ����ł���\�A���ꂪ�킪�@�h�̎Ƃߕ��ł��B�܂��o�T�ɂ��A�����̑��₩�Ȃ��Ƃ́A�s�҂��q�W���Ȃ�����̑����ł���Ɛ�����A���}�ɂ������������̂́A���₩�ɋɊy�̕�r�̘@�ɑ����Ɛ�����Ă��܂��B
�@
�Ƃ��낪�A���̂��Ƃ�m�炸���O���Ɏ����X���Ȃ��҂́A���A����̂ł��B���̐��������߂Ė������ƂɂȂ�܂��B����䂦�@�R��l�́A�u�Z��(�����̐��E)���w���āA���L�ɐ������ށv���Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA���܂����S�Ă��Ȃ��l�ɔO�������߁A��y���˂��킵�߂Ă�����̂ł��B
�@
����ł́A���A���̖@�v���c�ނ̂͂ǂ����ĂȂ̂ł��傤���B�܂��ǂ̂悤�ȐS�łƂ߂�悢�̂ł��傤���B
�@
�o�T�ɂ��A��y�̘@�̒��ɐ��܂ꂽ�҂��A���̑O���̑P���̉ʕ�ɂ���āA�̊J�������ɑ����x���̍�������Ɛ�����Ă��܂��B���̍����u�؍��̏��(�������̂����)�v�Ƃ����܂��B���������āA���A���̖@�v�́A�S���Ȃ����l�̉؍��̏�肪�ꍏ������������悤�ɁA�S���Ȃ����l�Ƌ��ɜ������邱�ƂȂ̂ł��B
�@
���A�̊Ԃ̎l�\����́A���̂��Ƃɐ[���v����v���A�����ɂƂ��Ă��������̂Ȃ��l�̎����_�@�Ƃ��āA�����ɖڊo�߂�悤����w�߂邽�߂́A����ΏC�{���Ԃł��B�@ |
 �@ �@
���\�O���ƕ�(�S��)�̋��{ |


 �@
�@ |
���ׂĂ̕�����䶗��̒��ɑ��݂���B��䶗��͉F�����̂��̂ŁA�u���v�u�s���v�ł���Ɠ����Ɂu�Łv�u�s�Łv�ł���B�l���l�Ԃ̑̂��h���Đ����Ă���̂́A�ꙋ�߁A�܂�F�������̒��łق�̈�u�ł���B���͖̂łт悤�ƁA�y�̒�����A��C�̒�����A���̉F���̒�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ȃ��A�i���̎��Ԃz�������ɑ��݂��Ă���ƍl����B��䶗��̒��S�ɂ������@�����̍����̂�
���A���z�n�́u���z�v���ے����Ă���B���̉F���̈����I�\���́A�u���v�Ƃ��Ă�����l�ԂɂƂ��āA���̊E(�ّ��E)�Ɛ��_�E(�����E)���s��(���)�Ȃ邱�Ƃ�����Ă���B��䶗��̐��E�͈̑�ȉF���̍\������
�A�ŏ��Ȃ�l�����\�����Ă���̂��B���̂��Ƃ������^���̊�{�ŁA�l�������Ă���Ƃ����݂���F�E(���ۊE)������̖łэs�����F�E(�l�̖ڂɂ͌����Ȃ����E)�Ɏ���u���E�v�ɂ����Ă��A���N�ė։��]�����鐢�E�������
���Ă���B�����𖧋����`�Ƃ��ĕ\���������̂���䶗��ŁA�����I�ł���Ɠ����ɔ��I�Ȑ��E�ς́A���ɂ��O�����ɂ������͎������A�O��(�ߋ��A���݁A����)�̎�������\�������Ă���B�@
�����̋N���́A�߉ނ̖Ō�A�߉ނ̋�����M����M�҂��߉ނ𐒔q���邽�߂ɍ��グ���B�������A���O���������Ƃ��Ă̐��q�����������悤���B����͖����I�ɉ��߂���A�F���̍��{�v�z�Ɋ�Â��{�\�R(����݂���)��\���哃(stu-pa�E�X�g�D�[�p/�����k�E���Ƃ�)�A��䶗�(�d)�ł������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B���m�ȋL�q�͂Ȃ����A�߉ޔ@�����͂��߂Ƃ��镧�������ꂽ�͎̂߉ޖŌ�4-5�S�N�̋I��1���I���Ƃ�����B �@
�ߑ����O������̓���(����)��\�����ꂽ���A��q�̈���(���Ȃ�E�����)�ɐ��������t�Ɏn�܂�B�u�����A����Ƃ��A������A�˂Ƃ��āA�����A�˂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@�Ƃ��A�@���A�˂Ƃ��āA�����A�˂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�����A���炪�@�u�^���̋���/�@�E(dharma�E�_���} dha-tu�E�_�[�c)�^��/�F���̐^���v�̓����ƂȂ�A�����M���Ȃ����B��������(�^���̋�����������ߑ�)�Ǝv���Đ��i�ɓw�߂Ȃ����Ƃ������Ƃ��B �@
��q�B�́A�ߑ��̖S�[��䶔�(�Α�)�ɕt���A�⍜�������ăC���h�����e�n���ɕ��ɗ��������Ē������B�������A��q�B��l�X�͎ߑ����ÂсA���O���̎ߑ��̑��Ղ�o����J
�����������̑���Ȃǂւ̐��h�̔O�������ƂɂȂ�A�����̔��W���ԗւɚg���Ė@�ւȂǂ̐��q�Ώۂ̑�֕��������悤�ɂȂ����A���̎����͎ߑ��������ȑ��݂Ƃ��Đ��q����A�l�Ԃ̌`�ɕ\�����邱�Ƃ͍l�����Ȃ������B�����o�ɂꕧ���Ƃ��Ắu�߉ޖ��v�u�߉ޔ@���v�̕����������
�悤�ɂȂ����B���������Ό����o���ŁA�ߑ��̏o���́A�ߋ��̉��N����������Ɍ��т��A�����ɍė����O������������u�\�ӕ�F�v�̌����Ƃ��ĐM�����悤�ɂȂ�A�u�ϐ�����F�v�̎��߂∢��ɏ�y�������u���\�ɔ@���v�ȂǁA�������̕�������
�ɕ\������Ă������B�����̕�������̐��q�Ώۂ��A����̊o��̓�(���A�˖@�E����)���J�����̂ł���ƁA�߉ނ̋������`�����Ă���B �@
��(���E��)�ɂ͑傫�������āu�@���v�u��F�v�u�����v�̎O��ނ�����B �@
�u�@���v(tatha-gata�E�^�^�[�K�^)�́A�@���ɗ�������ҁA�@����蓞�������ҁA�@�������肵�҂ŁA���̑��̂ŁA�F���̐^����@���ɑ̓����ė����҂ł���A���g���~����Ō��R�Ƃ��đ��݂��镧(�����g�E�����傤���)
�ł���B�u����@���v(maha-vairocana�E�}�n�[���@�C���[�`���i/��Ḏɓߔ@���E�т邵���)�̂悤�ȁu�F�����v�A�@���ƈ�̉������ƌ��Ȃ��ꂽ�ߑ����u�߉ޔ@���v�Ƃ��ĕ\�����ꂽ�u�l�ԕ��v�A�u���\�ɔ@���v�u��t�@���v�̂悤�ȁu���z���v������B �@
�u��F�v(bodhisattva�E�{�[�f�B�[�T�b�g�o/���F)�́A��S���ĕ����ɓ���A�l�O����(������������E���ς邽�߂�4�̐���)���A�Z�x(�Z�g�����E6�̒m�b)�̍s���C���A�㋁���(���傤���ڂ����E����)�����O��(�������ザ�傤�E����)�A�\���(�\�M�A�\�Z�A�\�s�A�\����A�\�n�A���o)�E�O�_�S��(��������̂ɗv���鎞��)�̏C�s���o�ĕ��ʂ����҂������B����u�o���l�v�ƂȂ�A�u�@���v���̓������^������̓I�ɕ\�����铭�������镧(���@�g�E���傤�ڂ����/�@���̕��g�Ƃ��Ď��߂̎�������̂אl�X���~�ς��镧)�ł���B����́u�ϐ�����F�v�̂悤�Ɍo�T�ł����H�I�ɐ��@���s���A�O�����������A�~�ς��镧�Ȃ̂��B �@
�u�����v(vidya ra-ja�E���B�f�B�����[�W��)�́A����o��(������@��)�̋��߂����{�g(���ߗg�E���傤��傤���/�@���̕ϐg�����p)�������A���X�̈������~�����鏔���������B�u���v�͌����̈Ӌ`�ŁA�m�b�������A�܂��^���ɗ���(��)���u���v�Ƃ����B�u���v�͉��l�̈Ӌ`�ŁA�q�͂��ȂĈ�̖���𝔔j����Г��������������B�ّ��E��䶗��ł́A���̊E�̌���G�l���M�[�������A�����E��䶗��ł́A���_�E�̗��ʂɂ���A�{�A�~�A���A���ȂǂƂ������S�̍�p�������Ă���B �@
�S�҂̋��{�����鑤�́A��䶗��̐��E(�F��)�ς̒��ɁA�l�ԊE�ɐ�����Љ����Ɍ�����ŁA���E�̗��z�I�v�z�ς��ς��Ȃ���S�҂����E�Ɏ���։��]�����钆�ŁA���̌����ɂ��m�b��l�X�ȗ͂Đ������A�^�̕��Ɛ��蓾����ɁA��X�̐�����O���E�ɂ���������Y���~�ς��Ă���邱�Ƃ��肤�̂ł���B �@
��䶗��G(���䶗�)�̕��̔z������݂�ƁA�����E�ɂ����Ă͒����ɁA�ّ��E�ɂ����Ă͏�i�����Ɂu����@���v������A�u����@���v�𒆐S���ő��̕����z��A���̖����⑊�݊Ԃ̊W��\���Ă���B�u���E������̐��E�Ƃ���ϓ_�����䶗������߂����ꍇ�v�S�҂̗։����������╧�̌�����\���������̂��A��䶗��G�̒��̕��̎p�ƂȂ�B �@
�u���A�v�̕��́A�S�҂͎��ɍs���ߒ��ł܂��ɓ��̂��łэs���A�����O���E�𗣂ꂽ����̕��ł��邽�߁A�u����@���v�́A���ߗg(���傤��傤���/��������O���������Ȃ�p�ɕω�(�ւ�)���ċ������铱����)�Ƃ��ď������u�s�������v�Ɏp��ς��A������ގ�������l���~���B�e�p�́u�s�������v�̓����Ƃ����鐸�_�E�̗��ʂɂ���{�����݂Ƃ��������{�̌`���������ɂ��A���̊E�ɂ����錌�t���(�G�l���M�[)���݂Ȃ��鉊��w�����Ă���ƍl������B �@
���u�߉ޔ@���v�ɂ����āA���j��ɑ��݂����߉ޖ����u�ߑ�/�S�[�^�}�E�V�b�^���_�v�̐��@�������B���@�ł́A�u�߉ގO���v�Ƃ����悤�Ɂu�߉ޔ@���v��{���Ƃ��č��E�̘e���Ɂu�����F�v�u������F�v���J���(�z�u)�Ă���B���̎O�����u�����F�v�l�����u������F�v�ƂȂ�B �@
�O�����u�����F�v�́A�u����̒m�b�v�Ƃ������A�߉ނ̒�q�̒m�b�̑��l�ҁE�ɗ���(�����ق�)�̕ω��g(�ւ���)���B�m�b�̍s�A�����ʎ�g�������̍s���s�����ƂŁA�O���n(=�o��̋��n/���㐳���o)�邱�Ƃ��o���A�u�ʎ�S�o�v�ł͊ώ��ݕ�F�̐��@�̏�ʂ�������Ă���B�l�����u������F�v�̌����Ƃ��āu�����̍s��v������B������҂����̍s���肤���ƂŁA�u������F�v�͋������߂̗͂������~���Ă����B �@
���A�ɂ����Ă͖����{���̕��E�ɂ͒H�蒅�����Ƃ̏o���Ȃ����Ƃ������A�����u�n����F�v���Z��(�n���A��S�A�{���A�C���A�l�A�V)�։����������A�����Z�������܂悤�S�҂�掵���E�̐^�̕��E�ɓ������Ƃ��Ă���B�߉ނ��\�Z�����疜�N���o�������Ɂu�\�ӕ�F�v�Ɏp��ς��ė����A�l�ދ~�ς̐��@���s���܂ł̊Ԃ́u�n����F�v�����ׂĂ̐l���~
���Ƃ����B �@
�Z�����u�\�ӕ�F�v�ŁA�O�����~�ς��ׂ������������邱�ƂƂȂ�A���A�𗣒E����܂ł̕��ɂƂ��Ă͐l�ԊE�̋ꂵ�݂�����������Ă��Ȃ��̂ł���B���A�Ō�̎������u��t�@���v�ɂ��āA�l���������œ���邱�Ƃ̏o���Ȃ��������{�l��̓��̐S�g�u�a�v���Ŗ����A��Y����������̂��ƍl���ėǂ��Ǝv���B�@
���A�𗣂�^�̕��E�ɓ����ꂽ���́A�e������{���̂ւ̏��Ō�����������ω����čs���B�\�O���(�����E)�y�я\�����(�ّ��E)�̍��{���ƂȂ�u����@���v�Ɏ���܂ł́A������u���@���v���u����@���v�̓����Ɉʒu����̂ɑ��A�O����u���\�ɔ@���v�����Ɉʒu����Ă���B�u���\�ɔ@���v�̗��e�����A������u������F�v�S�����u�ϐ�����F�v�ƂȂ�B�\������u�ّ��E����@���v�����̕��A��\�O����u�ʎ��F�v�A��\�܉���u���������v�A�O�\�O����u����F�v�A�O�\������u�����F�v�A�\����u���������v�A�S����u�ܔ閧(�����F)�v�̌����́A�^�̕��Ɛ��蓾����ɏO���E�ɐ�������������������Y����~���Ă������̂ƍl�����A�����Ɋ��ɉi�㋟�{�̐����g�ł���ƍl������B |
���O���̋��{�@
�����̗������u�O���v�Ƃ����A�ߗׂ̐l������ߐe�҂��r�ƂɏW�܂��ĎO���̋��{������B���̓���������͓�{������B�����Ŏ��҂��Z�E���������n���ꏉ�߂ĕ��ɂȂ�B����܂ł͖��킸�ɖ��y�ւ܂�������{�����s���悤�ɂƐ����͈�{������B���̓��A�܂����Ɏ������c�q��Z���A����������ĕ�Q�������B��Q�肪���ނƎQ��҂͖{�V�ŐU��������B�H�������ނƖS���Ȃ����l�̒����𐅂ŐA���ڂ炸�ɉƂ̓��A�ɖk�����Ɋ����B���̂Ƃ������������Ȃ��悤�ɘm�����u���v���|����B�����͈����Ԃ��߂���ƕЕt����B���̏K���͑����ł����u�����������v�Ƃ�������̂ł���B�n��ɂ���Ă͂��̓��A�����Ɏؗp���������Ԃ������ɂ��z�{��͂����肷��B�܂��������o�������Ǝ��҂����O�ɎЎ��ɗ��Ă��肢�̂����Ŋ���Ȃ��������̂�����ɂ܂Ŏ����z���Ȃ��悤�ɁA�ߐe�҂ɂ���āu����ǂ��v���s���B���s�̋|�c�ɂ��鎜�����̕s�����͕ʖ��u�ۂ�����s���v�Ƃ����A�N�z�҂ɐM������B���̎��ւ̊���ǂ��́A����҂���萬�A��������̈Ӗ������������B�܂��A����ǂ������Ȃ��ƁA���c�q����ł�Ƃ������Ă��܂��A�Ƃ����Ă���B�@ |
���������{�@
���S��������萔���Ď����߂��������Ƃ����A�Ȍ㎵���߂��Ƃ̊����A�l�\����ԋ��{����̂��������{�Ƃ����B�����̓��A��̏Z�E�����{�̓��k�Ɏ����߂��Ƃ̋��{���L���A����̂����g�ɕ��ׂ��������k(�܂��͎��{���k)�Ƃ�������̂��n�ɂ����A�������{�̕�Q��̂����ꖇ�����͂����B�n��ɂ���Ă͓��k���Ƃɒu���A�������ƂɈꖇ����n�ɂ����B�������ɂ͋ߐe�҂ɂ���āA���҂����O���Ă����ߗނ⎝��������u�`�������v������B���̍s�ׂ́A���҂̗썰���p�����邽�߁A�썰���Ă�₷���ƍl������ߗނȂǂ�����̂��ƍl������B�O�\�ܓ��߂̌������̋��{���u�n�c�[���`�v�Ƃ��u�n�c�f�C�j�`�v�Ƃ����A���O�݂������Ă���𑐗��̗��ɂʂ���A�������ɒ݂邵�ĕ�ɋ�����B���҂����̎R��o��Ƃ�����Ȃ����߂ɂƂ����Ă���B�l�\����߂̎��������ɂ͎��҂̍����Ƃ̓��𗣂��Ƃ����A���̓��������Ċ��̊��Ԃ̋��Ƃ���B�Ւd��Еt���A�ʔv�d�ɔ[�߁A�_�I���B���Ă����_�ǂ��̎������͂����B�n��ɂ���Ă͖݂𝑂��A�l��ۂ߂Ē|�Ăɓ����֔[�߂�B������u�l�\��݁v�Ƃ����B |
�����{
�@
�@���̌`�ł����A���{�قǁA�������̐g�߂Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤�B�@���E�@�v�ɂ���Q��A��c���{�ɐ��q���{�A����ɂ͐j���{�ɐl�`���{�A�S���Ђ�����߂ċ��{�Ƃ������ŁA�������̏@���I�s�ׂ�����Ă��܂��B
���ꂾ���ł͂Ȃ��A�Ⴂ�l�����܂ł����e���r�̉e���Ȃ̂ł��傤���B�S��ʐ^�ȂǂƏ̂�����̂�����ɋ��|���āA�u���{���Ă����Ȃ��Ɓv�Ǝv�킸���ɏo���������̂���̏�Ԃł��B
��̑S�́A���{�Ƃ͉��ł��傤���B���Ƃ��Ƌ��{�Ƃ́A�u�H����ߕ��@�m�̎O��ɋ�������v���Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B�����āA�S���Ȃ����l�����M��ꂽ�肷�邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɂƊ���ċ��{����ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��̂ł��B
���ꂪ���̊Ԃɂ��A���{���M��ƍЂ�����A�����̐g����邽�߂̓���ɂ���Ă����̂ł��B����́A���������g�������𗘗p���Ď����̗~�]�������悤�Ƃ��Ă������ʂł���܂��B
���{�́A�����܂̑傢�Ȃ鐢�E�������������������Ƃ̕\���ł��B���ꂪ�A���҂����{���Ȃ��Ǝ����M����A���ɍЂ����N����A�����狟�{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƁA���{�������̗~�]�������铹��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����Ȃ̂ł��B
�����ł͂Ȃ��āA���{�Ƃ́A�u���@�m�̎O��v�Ƃ��Č�����Ă���^���̐��E�ɑ��ĂȂ������̂ł��B�{���ɑ��h�����ׂ����E�A�{���ɑ�ɂ����ׂ����E�������������Ƃł��B����͎����𒆐S�ɂ��Đ����Ă�����̂��A���������̂��̂������������܂̐��E�ɁA�����ЂƂ����ɐ����邱�Ƃ̂ł��鐢�E�������������Ƃł��B���̊��������{�̌`���Ƃ�̂ł��B�@ |
��������/�s������(Acala�E�A�`����/�����A�s�����������A�������A�����g��)�@
�����Ɩ��̕t�����ɂ́A�ܑ喾���Ɣ��喾��������A�ܑ喾���́A�u�s�������v�𒆐S�ɓ�����k���͂ގl����(���u�~�O��(��������)�����v�A��u�R䶗�(����)�����v�A���u��Г�(�������Ƃ�)�����v�A�k�u�����鍳(�����₵��)�����v)�ŁA���喾���́A�ܑ喾���Ɂu�G�؍���(��������)�����v�u���\��(�ނ̂����傤)�����v�u�n��(�Ƃ�)�����v�����������̂������B���Ɂu�E��(�����Ⴍ)�����v�u����(������)�����v�Ȃǂ����邪�A��\�܉���ƌ\����́u���������v���悭�m���Ă���B�@
�s�������́A����@���̋��������{�̑�������(���ߗg�E���傤��傤���)�A�ΐ��O��(�����傤����܂�)�ɏZ���ē��O�̓��Ə��X���q�C(�����E�P�K��)���Ă��A��̖��R�≅�G��łڂ��Ƃ�����B�@
��������ɂ͗l�X�Ȍ`�����邪�A�g�̍��F(���A�ԁA�̂��̂�����)�ŁA�E��Ɍ��u�ϔY������f�����v�A�����㮍�(�����E��)�u���݂̕��ւ������v�������A�ٔ��������ɐ��炵�A���ڔ���A�E�ڌ��J���A�����͗�������J���A���̗��[�̉�����݈����͗������㖔�͉��ɓ˂��o���A���{�̊�ŁA�Ή���w�ɂ��A�E�����o���A��ՐɉE�r�݉����č��������͗����Ă���B�@
�s���������ő��ɁA��哶�q�Ɣ��哶�q������A�s���O���Ƃ����ꍇ�ɂ́A��哶�q����㹗�(����)���q�Ɛ���(��������)���q���e���Ƃ��Ĕz�u�����B���哶�q�͂��̓�哶�q�ɁA�d��(������)���q�A�d��(����)���q�A���ӒB(���̂���)���q�A�w��(���Ƃ�)���q�A�G��k��(������)���q�A���Ĕ�u(���傤���傤�т�)�̘Z�������������́B�@
�s�������́A��ʓI�ɋF���̑�\���ł���A�C����(�^���@���h�̏C������V��@�̏C����)�̎R�x�C�s(���C�s�Ȃ�)�ɂ͏�ɖ{�n���Ƃ����J���镧�ŁA���̌����́A�s���������w�����^�ԂȉΉ��ɏے�����Ă���B�Ή��́A���Ԃ̈ł��Ƃ炵�A������Г���Ă��s�������Ƃ�\�킵�A�^�������ɂ�����얀�F���ŁA���ЁA���v(���a���ЁA�a�������A�Ɠ����S�A��ʈ��S�Ȃ�)���F�肷�邽�߂ɏC�@����u�s���@�v��A���ƈ����̂��߂ɏC�@����u�����@�v�Ȃǂ�����B �@ |
����/�߉ޔ@��(S'a-kya�E�V���[�L��/�߉ލ��̏o�g�ł���߉ޖ���(���Ⴉ�ނɂ�����)�u�ߑ��E�S�[�^�}�E�V�b�^���_�v��@�����Ƃ���)�@
���j��̕����J�c�u�ߑ��v���A�^���ɖڊo�߂���ҁ��u��F�v(bodhisattva�E�{�[�f�B�[�T�b�g�o/���F)�Ƃ��Ċo����J�������Ƃ��A���Ō�ɐ����ȑ��݂Ƃ��Đ��q����A��������̌��`�����グ����i�K�ŁA�u�F/sattva(�T�b�g�o�E�l)�v�Ƃ��Ắu��F�v�̐��q�ϔO���āu���z���v�́u�@���v�������グ�u�߉ޔ@���v�ƂȂ����B
�@ |
���O����/�����F(Man~jus'ri-�E�}���W���V�����[/���ꛙ���̗��A�֎ꎺ���E���)�@
�ʏ́u���g�˕�F�v�Ƃ������A��敧���o�T�u�،��o�v�u�@�،o�v�ł��̓���������Ă���B�u�O�l���Ε���̒q�b�v�Ƃ̌��t������悤�ɁA�m�b�̑��l�҂Ƃ��Đ��߂��邪�A���������v�z�̒��ŁA�߉�(�ߑ�)�̒���q�ł���u�ɗ���(�����ق�)�v���m�b�̑��l�҂ł���Ƃ�����B����͕����`���̓`���o�H���قȂ�A���ꂼ��̓`�������ߒ��ł̋����̈Ⴂ�ɂ����̂��B�����(���傤����)�����Łu�ɗ����v��m�b�҂Ƃ����̂ɑ��A�߉ނ̓��Ō�A�C���h�ɐ��܂ꂽ�u���ꛙ���v(�֎ꎺ���A���A�Ⴕ���͑��̖�)��m�b�҂Ƃ�����敧���̋����Ƃ̈Ⴂ�ɂ���B�@
�����`���Ƃ͕ʂɁA�����`����2�̓`���o�H�ɕ������B�C���h����쉺���ăZ�C����(�X�������J)��r���}���o�R��4���I���ɕS��(������)�ɓ��B�����u����������E���敧���v�ƁA�C���h����k�サ�ăA�t�K�j�X�^����蒆��������o�R�����I�ɐV��(���炬)�ɓ��B�����u��敧���v������B���{��6���I����(����538�N)�ɓ`�����A��ʓI�ɑ�敧���̋����Ƃ���Ă���B�@
�����F�̌����́A���̐�(�����Љ�)�ɂ�����Ԉ�����l������Ȏv�z��s�ׂ�f����A�l�X�̖����△�q�𐳂��āA�^���̒q�b��^���A�K���Ȑl�ԎЉ�֓����Ƃ��Ă���B�@
�����╧��Ɍ����ʓI�ȗe�p�́A����ɖ�����f���錕�������A�E��ɒq�b��^����o���������A���q�̑���ɍ����Ă���B���^�ɂ͗l�X����A����ˁA�ܑ��ˁA�Z���ˁA�����˂Ȃǂ�����A�ܑ��˂̂��̂������B�@
�����F�̔z���ɑP�����q�A�D�U��(���Ă�)�A���ɔg���O��(�Ԃ����͂肳��)�Ȃǂ�����B�u�،��o�v�ɐ��������F�̋����ɂ��ɗ�������q��A��Č��ǂ��A���̓����]����b����A�P�����q���\�O�l�̎t����K�˂ċ����̗��ɏo���Ƃ����b������A���̘b���瓌�C���\�O���̏h�w���]�ˎ���ɂ����邱�ƂɂȂ����Ƃ����B�@
�ّ��E��䶗��ɂ����Ē��i���t�@(���イ�����͂��悤����)�̗t�㐼���@�Ɩ��Â��A�����E��䶗��̌����\�Z�����ɔz�u�����B
�@ |
���l����/������F(Samantabhadra�E�T�}���^�o�b�_��/�O�֑���ɗ��AVis'vabhadra�E���B�V�����@�o�b�_��/�A���)�@
������F�́A����̒q�b(�q�E�d�E�)�ɑ��Ď��߂̕�(���̗��E��E�s)�Ƃ���Ă���B����Ƌ��Ɏ߉ޔ@���̓�e�m�Ƃ���A�Z�̉�������ۂɏ��߉ޔ@���̉E���Ɏ�(����)���Ă���B�@
�Z�̉�������ۂɂ��ẮA�ߑ��̐��݂̕�Ƃ���門��v�l�����̔��ۂ̖����������Ƃ�����D�����ƌ�����b���c����Ă��邪�A���́u�Z�v�̈Ӗ��ɂ́A�Z�g����(����ς�݂�)�Ƃ��Ắu�z�{(�ӂ�)�E����(������)�E�E�J(�ɂ�ɂ�)�E���i(���傤����)�E�T��(���傤)�E�m�b(����)�v��\���Ă���B�^���@�͓��ɒq�b�Ǝ��߂́u���̂��v�Ƃ��ċ��������A������F�͗͋������ߐS��\�킷���ŁA���̎��ߐS�́u�����̍s��v�Ƃ����A�}�l�����ׂĕ��ɐ���s�����߁A���̊肢�������Ă���B �@
�s��ɏ\�̊肢������B�@---�@�������X�h���邱�Ɓ@�@��(�̉���)���̎]���邱�Ɓ@�L�����{���C�����Ɓ@�Ə�(����)�����(����)���邱�Ɓ@�����𐏊�(������)����(���)���Ɓ@�]�@��(�Ă�ڂ����)���̋����𐿂����Ɓ@���̉i���𐿂����Ɓ@��ɕ��𐏂Ċw�Ԃ��Ɓ@�P�ɏO���ɏ����邱�Ɓ@�����F������邱�Ɓ@---�@
�Ȃ��A������F�͑���@�����ő��Ƃ��āA�ّ��E��䶗��̒��i���t�@�╶��@�Ȃǂɔz�u�����ق��A�����̓��ő��Ƃ��ċ����F(������(��������)�@�̒���)�Ɠ����Ƃ���Ă��邱�Ƃ�����B
�@ |
������/�n����F�@(Ks.itigarbha�E�N�V�e�B�K���o/�k�t��f�k�A���P�k)�@
�n����F�͎߉ނ̓��Ō�56��7�疜�N���o������(����)�ɍēx���̐��Ɍ����Ƃ�������ӕ�F������܂ł̊ԁA�����Ȃ鈫����Г�ɑ��Ă��{�邱�ƂȂ��A�����邱�Ƃ��Ȃ��A�傫�Ȏ��߂Ǝ����̐S�ŁA�O���̂��ׂĂ̐l�X���ꂵ�݂���~�ς���Ƃ�����B�p�͓����ۂ߁A���邩��ɗD�����A�g�߂ɐڂ��邱�Ƃ̂ł���p(�����`)�A�����o�ƍ���̎p(�m�`)�����A��̂������J���Ă��鎞�ɂ͉E��Ɏ���������A����ɕ��������Ă���B�@
�X�p�⓻�ɒn��������悭����������B�Â�������̓����ɂ͘Z�̒n��(�Z�n��)�␅�q�n���A���@�̋����₨���Ɏq��n����q��n���Ȃǂ��J���Ă���B���̂����Z�̂̒n���́A�n���A��S�A�{���A�C���A�l�A�V�́u�Z���v��\���A�S�҂̖��y����ɁA���҂��u���A�v�ɍ݂�։��]���̋��n����S���Ă���ƍl������B�����ɂ��̐��̌����Љ�ɂ�����u�Z���։�v��ʂ��āA�l�X���ꂵ�݂�Г��~���Ă䂱���Ƃ��鐾������������Ă���B �@
�n����F�̐����Ǝ��̌����́A���Ǝ��̗��E�ɂ������@��������A�ǓƂȋC���������������Ă��e�̎����S�����������Y���̔O�����߂��Ă���B�q���̂悤�Ɏア�҂ɑ��Ă͎O��(�ߋ��E���݁E����)�������������̗͂��Ȃċ~���Ă������Ƃ���B���q�n���ł́A��c��X�ɂ�����ߋ��̐��q���{���s�����Ƃ����łȂ��A�����A�����i���Ɏ���܂Ő��q�Ƃ��Ă̕s�K���N���Ȃ����Ƃ��肤�ݗ싟�{���s���邱�ƂƂȂ�B�@
�^���@�ł͑�l���S���Ȃ������͖{������@���̞����ł���(��)�����ʔv�̉����̏�ɏ������A�c�Ȏq���S���Ȃ������͒n����F�̞����ł���(��)���������B�@
�ّ��E��䶗��ɂ͒n���@�̎呸�Ƃ��ĕ�F�`���Ȃ��A����ɂ͛�������@�؏�ɗ��āA�E��ɕ��������Ă���B
�@ |
���Z����/�\�ӕ�F(Maitreya�E�}�C�g���[��/�\���A�~�ᗜ�A������A�~����A����)�@
�\�ӕ�F�́A���F�[�_�E�E�p�j�V���b�h(2500�N���O)�߉�(�ߑ�)�̎���C���h�����̓�勳�n�̈����s�h�̑c�Ƃ��Ď��݂����\�ӂƂ͕ʂ̎҂ƌ����A�\�ӂ̋��`�v�z�ɂ��M����\�ӕ�F�̐M���L�܂����Ƃ�����B�@
�\�ӕ�F�͎߉ނ̓��Ō�56��7�疜�N���o������(����)�ɍēx���̐��Ɍ���A�O�x�̐��@����J��������O���̋~�ςɂ����镧���Ƃ�����B���̐��@��ɂ͗��ԂƂ����Ԃ��炫�A���؎O��Ƃ�����B
�\�ӕ�F�͕ʖ��E������F�Ƃ�����ꂱ�̐��̏O�����������߂̐S�ŋ~�ς���Ƃ��������\�킵�Ă���B�@
����ɁA�^���@�c�O�@��t��C�́A���̜\�ӕ�F�̏�y�Ƃ����s����y���ς��A���̐���āA�ߑ��Ōォ�痈���̜\�ӕ�F�o���̊Ԃɂ����錻���̋~�ςɂ��������Ƃ������Ă���B�^�������ɂ����Ă͖����i���ɂ킽���t�̋����ɓ�����A�s����y�ւ̉����g�����v�z�̂��ƂɊς����邱�Ƃ��ł��o����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@ |
��������/��t�@��(Bhais.ajya�|guru�E�o�C�V���W���E�O��/�E�ЁABhais.ajya�|vaid.u~ryaprabha�E�o�C�V���W���E���@�C�f�������v���o�n/��t�ڗ����A�Ή��ŁA�Ή��P��
)�@
��t�@���́A����ɖ�ق������A�E���^�������сA�u�a�v�ɋꂵ�ސl�X�ɖ��^���A�S�g�����{(��)�{�����������B
��ق͗ڗ�(���)�Ƃ������(����)�ō���A�ڗ��̕����𗁂т邱�Ƃň�̐S�g�a������Ƃ���Ă���B���̂��߂ɁA��t�@���͖�t�ڗ����@���Ƃ��Ă�A������ڗ����E�̋���ɂ��āA�O���̕a�����~�������̎��a�������Ƃ�����B�a�C�����̐����\�킷���Ƃ��čL���M���W�߂Ă���B�@
�^���ɗ���ł����A�R���R���Ƃ́u�����ɑ����Ɂv�Ƃ����Ӗ��ŁA�Z���_���Ƃ́u�\���̑����Ȃ���ҁv�������A�}�g�E�M�́u�ۉ��Ƃ����鋶�ۂ̔@���̍~���̑����Z����ҁv�Ƃ����Ӗ��ł���B�@
�E��Ɍ��ԗ^���́A�l�X�̊肢�𐬏A���������\���A�P�ɕa�C�̋ꂵ�݂���菜���Ƃ��������łȂ��A�\��̑��������Ă���B���̒��́u���D��v�u�����Ɣ�v�u���a���y�v�̎O���肪���O�ɐM����A�g�̂̌��N�ƕa�C�����̐���Ƃ����Ă���B�@
�����̌��w�ɂ͉���(���Ԃ�)�Ƃ����鎵�̏����ȕ�������A���e�ɂ́A��ɓ��ւ���������F�Ǝ�Ɍ��ւ�������(��������)��F�A����ɏ\��_��(���イ�ɂ��傤)���]���Ă���B�l�V���Ƃ��āA�����V(�������Ă�/��)�A�����V(�������傤�Ă�/��)�A�L�ړV(���������Ă�/��)�A����V(������Ă�/�k)���z�u����Ă���B��䶗��ɔz�u�������p�́A���\�ɔ@�������������̐�����y�Ƃ����̂ɑ��A��t�@���͓�����y�̌����ɗ��v���{�����Ƃ���Ă���B
�@ |
���S����/�ϐ�����F(Avalokites'vara�E�A���@���[�L�e�[�V�����@��/�����I�k���[���)�@
�ϐ�����F�́A������F�Ƒ��Ȃ����\�ɔ@���̘e��(�킫��)�Ƃ��Ĕz�����B���̒��̎��Ԃ�����̂܂܂Ɋς��A�l�X�̐����A�����ǂ���ɋꂵ�݂�Y�݂��~���A������芪�������Г���������Ƃ�Ƃ��Ă���B �@
�p�͎O�\�O�g�����͎l�\�g����Ƃ����ω�(�ւ�)���A����ɉ����ĎO�������݂ɁA�����Ȃ�ꏊ�ɂ����R�ɏo�����A�~�ύs���s�����Ƃ���A�ώ��ݕ�F�Ƃ������B�O�\�O�g�̕ω��g(�ւ���)�������E�����̎O�\�O�ω��⒁���O�\�l�ω��̎D������̋N��Ƃ��Ȃ��Ă���B�o�T�ɂ��L���o�ꂵ����ƂȂ�A���@�@�،o(�݂傤�ق�����傤/�@�،o)�́u�ϐ�����F����i(�ӂ���ڂ�)���\��(�ω��o)�v��A�u�ʎ�(�g������)�S�o(�͂�ɂ�͂�݂������傤)�v�Ȃǂ悭�m��ꂽ�o�T�ł���B�u�ω��o�v�́A�l���������ő������鑽���̍Г�⋰�|�ɑ��ẮA��S�Ɋϐ�����F�̖��q�͂�M���O����A�~����Ƃ������Џ�����������o�T�ŁA�u�ʎ�S�o�v�͖����ɂ�����u��(����)�v�v�z������o�T�ł���B �@
�䉻(������/�O���ϓx�̂��߂ɂ��̏ꂻ�̎��ɉ����ĕς���p)�̎O�\�O�g�́A�k��(�悤��イ)����(��イ��)���o(�����傤)�~��(����)�V�Y(�䂰)����(�тႭ��)�@��(���)�ꌩ(������)�{��(���₭)����(������)����(�Ƃ�����)����(��������)��t(�����悤)����(���傤���傤)�Г�(���Ƃ�)����(����߂�)�O��(����ق�)���(�����)�\��(�̂����傤)����(���̂�)������(���܂���)�t��(�悤��)�ڗ�(���)������(���炻��)���(������)�Z��(�낭��)����(�ӂ�)�n�Y�w(�߂낤��)����(�������傤)��@(�����ɂ�)�s��(�ӂ�)���@(�����)�r��(���Ⴗ��)�Ƃ����A�����̍s��(���傤��/�������s���p)�̑�\�I�Ȏp�́u���ω��v�Ƃ����A��(���傤)�ω��Ɓu�Z�ω��v�́A�\���(���イ�����߂�)�ω��A���(����)�ω��A�@�ӗ�(�ɂ傢���)�ω��A�n��(�Ƃ�)�ω��A�s��㮍�(�ӂ�������)�ω��A�y��(�����Ă�)�ω��ƂȂ�B�@
�l���́A���ω���@�ӗ֊ω��̂悤�ɏ����I�Ȏp�̂��̂���n���ω��̂悤�ɜ|�{���ʼnΉ���R�₵�A����������������̂܂ŗl�X�Ȏp�����Ă���B
�@ |
���S�����@
�S���Ȃ��ĕS���߂��u�S������v�Ƃ����A�ߐe�҂��ĂсA��Q�肵�A���k�𗧂Ăċ��{����B���̓��Ɍ��炸���k�𗧂Ă�Ƃ��͑O���ɕ�֍s���ē��k���}���A��ӉƂɔ��߂ċ��{���Ă��猚�Ă���̂��Ƃ���Ă���B�Ȃ��A���Ă����k�ɂ��ꂼ��̎Q��҂��������ׂ����������̂�я�ɂ��Č��ԏK��������B�����ɒ��j�A�����Ƃ��Đ��܂ꂽ���Ǝv�������̕��ցA���q�ɐ��܂ꂽ���Ǝv�����牺�̕��Ɍ��ԁB���̎��͑��̎��Ɨ����Č��Ԃ̂��悢�B���͂��̎����K�i�Ƃ��ēV�Ɍ������ď��邩�炾�Ƃ����@ |
�����ފ݂ƐV�~�E�N�����{�@
�������I����čŏ��Ɍ}����ފ݂��u���ފ݁v�Ƃ����A�ߗׁA�e���A���̂̐l�������ފݎQ��ɖK���B�S���Ȃ��Ă���ŏ���᱗��~����u�V�~�v�ƌĂсA���ފ݂Ɠ��l�ɋߏ���e���A���̂̐l�������u�~�Q��v�ɖK���B��̏Z�E���V�~�̉Ƃ����A�~�I�̋��{������B�����ĕ�ł͎{��S���{���s���A�V�~�̉Ƃł́A�W�҂ƂƂ��ɂ��̖@��ɏo�Ȃ���B����A�N���Ƃɉ���Ă��������N���Ƃ����B������A�O����A������A�\�O����A�\������A�O�\�O�������ȔN�����{�ł���B�N�����{�͖�����菭�����߂ɍs���B�u�����܂͍Ñ����Ȃ����瑁�߂ɋ��{����̂������v�Ƃ����Ă��邩��ł���B�O�\�O����͒����グ�Ƃ������B���̋��{�ɂ���Ď��҂̗썰�͐��܂��c�ɂȂ�Ƃ����A�t�t���k���グ��B�t�t���k�Ƃ́A���̐��̏�̕��̗t���c���A��������ĉ����������A���k�Ƃ������̂ł���B���̖�`����ė�͓V��E�֏����Ă����Ƃ���Ă���B�k���q�ł͂�����u�ʂ꓃�k�v�Ƃ��u�������k�v�ƌĂсA�\����ɏグ��K�킵�ƂȂ��Ă���B�l�̈ꐶ�͌����ɂ����ē��X�̌o�߂ɂ��������ĐL�W���邾���łȂ��A�����ɂ����Ă������グ���o�Đ�c�ƂȂ�̂ł���B�@ |
����T��/������F(Maha-�|stha-ma pra-pta�E�}�n�[�E�X�^�[�}�E�v���[�v�^/���d�F�ʖ����������A�吸�i�A���吨)�@
���\�ɔ@���ƎO�ʈ�̘̂e���ƂȂ�ϐ�����F���u���߂̕��v�ɑ��A������F�́u�m�b�̕��v�Ƃ�����B�����F���u�m�b�̕��v�Ƃ����邪�A�����F���߉ނ̓���q(�\���q�̓��̓���q)�ł������ɗ���(�����ق�)�̕ω���(�ւԂ�)�ł���̂ɑ��A������F�͖ژA(����������/�ژA)�̕ω����ł���Ƃ����Ă���B�@
������F�̖��̗R���́A�u�ϖ��ʚ�o(����ނ�傤���カ�傤)�v�Ƃ����o�T�ɒq�b�̌����Ȃĕ�������Ƃ炵�A�O�r�𗣂ꂵ�߂Ė���̗͂����ށB����̂ɑ吨���Ɩ��Â��Ɛ�����A�傫�Ȓq�b�́u�����v�Ől�X�̕��q�������J���A���ɂ͊o��Ɏ��炵�߂�����������Ƃ���A�u�����v�Ƃ��������t����ꂽ�B�@
�u�O�r�v�Ƃ́A���{�ŌÂ���������u�O�r�̐�v�̂��ƂŁA�u�Γr�v�u���r�v�u���r�v�̎O�r��n���u�n���v�u��S�v�u�{���v�̎O���E�ɂ��������ꂵ�݂��Ƃ�����B�n���G�Ȃǂɂ��`����u�ŔM�n���v�u���̒r�n���v�u�j�̎R�n���v�ɚg�����Ă���B�@
�l���́A����ɘ@�̉Ԃ������A�E��ɂ��̉Ԃ����������J�����Ƃ��鐨���������Ă���B�@�����A���̐��Ŏ��ۂɋ~���ɓ�����F���g�킹�Đl�X�̕��q�������J�����߂�Ƃ����p����\�킵�����̂��Ƃ�����B�ّ��E��䶗��ɂ͊ω��@�ɔz�u����Ă���B
�@ |
���O���/���\�ɔ@��(Amita-bha�E�A�~�^�[�o/���\�ɔk�����ʌ��AAmita-yus�E�A�~�^�[���X/���\�ɍM�z�����ʚ�AAmr.ta�E�A�����^/���ʐ���ŁA�ØI���@��)�@
�u����ɏ�y�v�̌��t�̂悤�ɏ�y�@���y�^�@�ň��\(��)�ɔ@������{���Ƃ����J��A�u�얳����ɕ��v�̘Z������(�O��)��������A����ɔ@���̗�(����)�ɂ��Y�݂�ꂵ�݂���~���A���S�邱�Ƃ��o����ƐM�S����Ă���B�@
��y�n�@�h�ł́u���\�Ɍo�v�Ƃ����o�T���悭�njo����A�u�ɗ�����A���̌����͖��ʂɂ��āA�\�������Ƃ炷�ɖW����Ƃ��낪�Ȃ��B���̌̂ɍ����Ė��ʌ��@���Ƃ����B�܂��A�ɗ����敧�̎����y�т��̐l�������ʖ��ӂɂ��Ĉ��m�_��(������������/����)�Ȃ邪�̂ɖ��ʚ�Ɩ��Â��v�Ɛ�����A���\�ɂ̓T���X�N���b�g��Ŗ��ʎ��Ɩ�A�u�m�b�Ǝ��߁v��\���B�m�b�̌��Ǝ��߂̌����͖��ʖ��ӂŌ���Ȃ����Ƃ��������Ƃ���u���ʚ�@���v�Ƃ������B�@
����ɔ@���͐����ɂ���Ɋy��y�̋���ŁA��ɂ̎l�\����Ƃ��������̐����{��͂Ƃ��A�{��͂ɑ����ӂ̔O���Ƃ��ĘZ���̖�����������̂��Ƃ����Ă���B�@
��y�^�@�J�c�̐e�a(������)��l����́u�V�ُ�(����ɂ��傤)�v�ɂ́u�P�l�Ȃ����ĉ������@�����∫�l����v�Ƃ����傪����A�ǂ�Ȉ��l������ɔ@���̖{��͂ɂ��Ɋy��y�ɉ����o����Ƃ������߂̋���������Ă���B����������́u���l���@�v�Ƃ������Ƃ��Ӗ�������̂ŁA�����Ȃ�l�̈��ƁA�����������������ɏ����@���Ɍb�܂��Έ���ɔ@���̗͂��Ȃď�y�։����o����Ƃ��������̍L�������������̂Ȃ̂��B�@
�l�̐������S���Ȃ鎞�ɓ�\�ܐl�̕�F������ɔ@���Ƌ��Ɍ}���ɗ��āA��y�֓����čs���A������u��ɂ̗��}(�炢����)�v�Ƃ����B�@
��������̗l���͗l�X���邪�A�悭��������p�ɁA�����卿(�������ӂ�)�ɂ��Ĉ���ɒ��(���傤����)�����Ԃ��̂ƁA����ɓ]�@�ֈ�(���͐��@��Ƃ�����)�����ԗ���������B
�@ |
�������/��(�����キ)�@��(Aks.obhya�E�A�L�V���[�r��/���A���k�A�����A�s���A���ќ�)�@
�u���v�Ƃ́u�s���v�u���ќ�(�ނ����)�v���Ӗ�����B�����Ȃ�U�f�ɂ��ł������A�i���ɉ��݂�{�������ʂ��Ƃ����ŕs���ɐ����O���ϓx�ɂ����镧�Ƃ�����B�e�p���������u���F�g(�߂���������)�@���v�Ƃ������A���̐���̂��Ƃɓ������E�ɖ���(�݂傤��)��y���i�邱�Ƃ���A��t�@���̕ʏ̂ł͂Ȃ����Ƃ�����������B�@
��������Ɍ����ʓI�ȗe�p�́A�U���̊p������Ŏ����A�E��͌w��L�����^���Ⴕ���͎{����(���ނ�)�������ł���B�@
������䶗��̒��ł́A�m�b��\���u�����E�v��䶗�(���_�E)�ƁA��̃��m����i���鎜�߂�\������u�ّ��E�v��䶗�(���̊E)�̒�����S�������u����@���v�̕��g�Ƃ��āA�u�ܒq�v�E�u�ܕ��v�̔@�����z�u����邪�A���@���͋����E�ܒq�@���̈ꑸ�Ƃ��āA����@���̓����ɔz�u���ꂢ��B�����E�̌ܒq�@���́A�����E����E���E����(�ق����傤)�E���\�ɁE�s�A(�ӂ������傤����)�ŁA�ّ��E�̌ܔ@���́A�ّ��E����E���(�ق��Ƃ�)�E�J�~�؉�(�����ӂ�����)�E���ʎ�(�ނ�傤����)�E�V�ۗ���(�Ă炢����)�ł���B�@
�����E�͐l�Ԃ̐��_�E��\���A��䶗��ł͐��_(�S)�����(����/�㎯)�ɋ�肻�ꂼ��̓�����������Ă���B���̂����ɂ͑���@���𒆐S�Ƃ��ē��E��E���E�k�ɔz�u�����ܒq�@��(�㎯����]���ē����ނ̒m�b)������A���ꂼ��̑����ɕ����Ēm�b�̓�����\�����Ă���B�@
����@���̋��ߗg(���傤��傤���)�Ƃ��Ă̕ω��g���u�s�������v�ƂȂ�@���A���ꂼ��̔@�����܂��l�V���̖����ɕω�(�ւ�)����B�@
�������E����@��(�ω��g/�s������)�@�E�̐��q(�ق������������傤��)/���@�̑̐�(���m�̎��̂���)�ƂȂ�m�b�����@��(�ω��g/�~�O��(��������)����)��~���q(�������傤��)/��~���̂悤�ɖ@�E�̖��ۂ𐳂����f���Ƃ�m�b�������@��(�ω��g/�R䶗�(����)����)�������q(�т傤�ǂ����傤��)/���ʂ�ł��ĕ�����@�ƂȂ�ς���m�b�����\�ɔ@��(�ω��g/��Г�(�������Ƃ�)����)���ώ@�q(�݂傤������)/���@�ʂ����̒����悭�ώ@���I�݂ɐ���������m�b���s�A�@��(�ω��g/�����鍳(�����₵��)����)������q(���傤��������)/�����m�㋁���(���傤���ڂ���)�n�Ɨ����m�����O��(�������ザ�傤)�n�̗D�ꂽ��(����)(�s��)�𐬏A����m�b
�@ |
���\�O����E�\�����/����@���@(Maha-vairocana�E�}�n�[���@�C���[�`���i/���d��ḎՓ߁B������ՏƁE����ՏƁE�Տ�)�@
����@���͖����̋���Ƃ��Ă̍��{���ŁA�����v�z�́u�F�������̍����́v�ł���Ɠ����Ɂu�F���̂���Ƃ���Ƃ������̃��m�̍\���v�f���Ȃ����j�v�ł���B�����ł͐M�����グ�Ă����N��������@���ł���A���ׂĂ̕�������@���̉��g�ƂȂ�B�@
��������Ɍ������@���́A���ނɕ������A�q���������ł�����̂������E����@���ŁA�@�E��������ł�����̂��ّ��E����@���ł���B�ّ��E����@���̕����́A��ʓI�ɋ����E����@�����J���Ă��邱�Ƃ������B
�@ |
����\�O���/�ʎ��F(Prajn~a-�E�v���W���j���[/�ʎ�B�m�b�E�b�E���E����E����)�@
�ʎ��F�́A�o��邽�߂́u�ʎ��(��)�m�b�v���ے��������́A�����u�ʎ�g�������v�̍s�鋳�����������������Ƃ�����B�u��F�v�́u���F�v�̗��Łu�o�蓾���ҁv�������悤�ɁA�^�������́u���g�����v�v�z�ł́A���̔ʎ�̒m�b���ȂĂ���ΒN�����^�̌��(�o��)�邱�Ƃ��o����Ƃ���B�@
�����͍���Ă��Ȃ��̂ŁA��ʂɂ悭�m���Ȃ����A������䶗��ّ̑��E�ł́A�����@�̒������Ƃ��ĎO�ژZ�](������������)�̎p�Ŕz�u����A���@�ɂ͓��](�ɂ�)�̔ʎᕧ��Ƃ��Ĕz�u����Ă���B�l���́A�b�h(�������イ)������㹖�(����)�߂ŕ����Ԃ�A���(�ڂ傤/�o��)��m�b��\�����������̂�����B�o�T�⌕�������Ȃ����ꂼ��̎�ɂ͈قȂ�������ł��邪�A�Z�]�̎�́u�Z�g�����v���ے����Ă���Ƃ�����B�@
�ّ��E��䶗��̎����@�͕s�������Ƃ����ő��̎l�V���̉@�Ŕʎ��F�����S�ɔz�u����Ă���B���̏��Ȃ́A�������鐢�̒��ŁA�~�]�̎������瓦��邱�Ƃ̏o���Ȃ��}�v�ɐ�������̔ϔY��ł��j�邽�߁A����@���̋��ߗg�ł���s����������E�ҐS���ȂĉΉ������{�̌`����\��������f�����Ă����̂��Ƃ����A���̎��H�Ƃ��Ă̌����̐^�m�邽�߂ɁA�ǂ����Ă��ʎ�̒m�b�̂�̓������ʎ��F�̗͂��K�v�ɂȂ�������ł͂Ǝv���
��B�@
���@�́A����F�̎��u����v�����u���̒m�b�v���s��������̓��ʂɁA�u�ʎ�g�������v�̍s�����H���邽�߂ɕK�v�ƂȂ����u�ʎ�̒m�b�v�Ɩ����ɂ�����u��v�z�v���{���ƂȂ��Ă���B
�@ |
����\�܉���E�\���/��������(Ra-gara~ja�E���[�K���[�W��/��苁AVajra�E���@�W���|ra~ja�E���[�W��/����������K����)�@
�T���X�N���b�g��(����)��Ra-ga(���[�K)�͈���E��~�E�ԐF���Ӗ����ARa~ja(���[�W��)�͉����Ӗ�����BVajra(���@�W��)�͋������Ӗ�����B����Ra-gara~ja(���[�K���[�W��)��Vajra(���@�W��)�|ra~ja(���[�W��)�Ɠ���̂Ƃ���ʖ����Ȃāu�������v�Ɩ��ƂƂȂ�A�u��������F�v�͈�����������F�s�Ƃ��Ďp��ς������̂Ȃ̂ł���B�@
�����������܂��A�s�������ȂǂƓ������u�@���v�̋��ߗg(���傤��傤���)�Ƃ��Ă̎p�ŁA�l�Ԃ̐S�̗��ʂɂ���{�A�~�A���A���ȂǂƂ������u�����v�̓����������ł���B���̔@�����Ɂu���~�Ð��v����S�ɏ�����������A�����^�������v�z�ɂ�����u�ϔY�����v�̐���������Ă���B
�@ |
���O�\�O���/����(��������)��F(Aka-s'a-garbha�E�A�J�[�V���[�K���o/���ގ̟P�k�A���́AGagana-an~ja�E�K�K�i�[�A�j���[�W��/�X�F��)�@
�^���@�c�O�@��t��C���Α��哿����u���������@(�����ق�)�v�̋��������������Ƃ����`�L���c���Ă���B�u�����v�Ƃ́u�����������L�v�Ƃ����A����F��(�^���ɗ���)��S���Տ����邱�ƂŁA�L���͂��ǂ��Ȃ�s�Ȃ̂��B��C�́A���g�̑嗳�P�Ԃ�y���̎��˖��ł��̖@���C�@���A�o�Ƃ����ӂ����Ƃ�����B���Ƃ́u���v�������̉F���S�̂ɐ����鐶����\���A�����̌����ς��^�����o��u��(����)�̋��n��m�b�v�������Ă���B��C�����̋���F�̋������@���C�@���A����̐g���ȂĒn���̐���������̓����Ȃ���s�r���A���̒q�b��ꂽ�̂ł���B�@
����F�̌`���́A����ɕ�����\�킷�@�ؖ��͕����̔@�ӕ��������A�E��ɒm�b�̗����������̂���ʓI�ł���B�ّ��E��䶗��ł͋��@���\�����Ă���B
�@ |
���O�\������E�S���/�����F(����������)�@(Vajrasattva�E���@�W���T�b�g���@/���F�����d�F���A�������E�������E������E�閧��E�������F���d�F�Ɩ�)
�����F�Ƃ́Avajra(���@�W��)�u�����v���u�i���v���Ӗ����Asattva(�T�b�g�o)�́u�l�v���Ӗ�����B�����p���̋���Ƃ��āu�t�@(�ӂق�)�̔��c�v�̑��c�ƂȂ��Ă���B�@
�������˂̒n�Ƃ����V��(�Ă�/�C���h)����V���N���[�h���킽�蒆���ցA�����ċ�C�������g�Ƃ��ē�(����)�ɓn����{�ɓ`�������^������(�O���`������)�̋��`�́A�u�t�@�̔��c�v�Ɓu�`��(�ł�)�̔��c�v�ɂ��`�����ꂽ�B�@
�u�t�@�̔��c�v�́u����@��>�����F>����(��イ�݂傤)>���q(��イ��)>�����q(������)>�s��(�ӂ���)>�b��(������)>�O�@�v�̔��c�̂��ƂŁA�u�`���̔��c�v�́u����>���q>�����q>�s��>�P����(����ނ�)>��s(�������傤)>�b��>�O�@�v�̔��c�ŁA��ʂɉ��̂ɓ�ʂ肠��̂�����킵���v���A�Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ��B����ɂ͖����̐_�邪����A��ʕ���(�����E���傤)�Ƃ͈قȂ�閧����(�Ђ݂�������)�̉��`����߂��Ă���̂ł���B�@
�u�t�@�v�Ƃ́u�t�@�̊�v�������A��̒��ɂ��鐅�������ƚg���A���̐�����H�����ڂ����Ɏ��̊�Ɉڂ��p�����Ƃ������B���̕t�@�̔��c�̑��J�c�Ƃ��Ắu����@���v�́A�����̍��{���Ƃ���A���z�Ƃ��ďے������F�������̍����̂ł���A�܂��A�F�����\�����邠��Ƃ������̃��m�̗v�f�ł��邱�Ƃ������A���j��̐l���Ƃ��Ă͑��݂��Ȃ����A�^������������̋������u�����F�v�֏��p���A���̋������u���ҁv�ɏ��p���ꂽ���Ƃ́A�����v�z�ɂ����Đ�ΓI�Ɋm�����ꂽ���`�Ȃ̂��B�@
�u�����F�v�͖�����`���������j��̐l���Ƃ��ĕs�ڂ����A�^���̊o����J�����u�ߑ��v���i������u�i���l�v�Ƃ��ē���̂ŁA����@���̐��@�́u�����F�v��ʂ��Ă��̋������u���ҁv�Ɏp���ꂽ�B�@
�O�@��t(��C)�́u�t�@�B(�ӂق��ł�)�v�ɂ��A�u���ҁv�͎ߑ��̖Ō㔪�S�N���A��V��(���C���h)�̓S��(���@)�ɓ���A�����ŋ����F�Əo������̋������A���̑O�Ő^��(�ɗ���)���u���Ƒ���@������X�ɐg�ɕς��ċ���̒��Ɏp�������A�@��͋�(��ḎՓߔO�u�@�v(�т邵��Ȃ˂�ق��悤)�Ƃ����o�T�ꊪ)������A���̋����𗴖҂Ɏʂ�����Ǝp�����ł������Ƃ����B���̐^���閧�̖@���͂��߂Đ��Ԃɗ��z�����̂��u���ҁv�ŁA���j��l���Ƃ��Ă̓`���҂ƂȂ����̂��u�`���̔��c�v���B�@
������䶗��ł́A�����E�O�\�����̈�Ƃ��Ĉ��@���l�e�߂̈�ɔz�u����Ă���B�����(�肵�ウ)�̖{���Ƃ��āA���S�̏����̏��@�͎��������̖{���ɑ��Ȃ�Ȃ��Ɗo��Ƌ��ɁA���(�o��)����ؗL��E�ɗ^���悤�ƁA�~�O����(��������)�ł͕��{�̌`����\���A�ϔY�Ə��m�̓���f��������������Ă���B�ّ��E�ł͋�����@(�������ア��)�̒����Ƃ��Đ�����q(���傤��������)�u�����m�㋁���(���傤���ڂ���)�n�Ɨ����m�����O��(�������ザ�傤)�n�̗D�ꂽ��(�������s��)�𐬏A����m�b�̂��Ɓv�̉�E����\���A������F�Ɠ���Ƃ�����Ă���B
�@ |
|
���R���E�n�܂� |
���ʔv
�ʔv�͂��Ƃ��Ǝ�M����Ƃŗp����ꂽ���A�����T�m���v��ɒ�����������炵�A�����ɓ]�p���ꂽ�Ƃ���Ă���B�ՍϏ@�̑m�̓��L�w��ؓ��H�W�x�A����4�N12��30���Ɂu�ʔv�A�Âɂ��閳���Ȃ�A�v�ȗ����ꂠ��v�Ƃ���B�܂�14���I�ɏ����ꂽ�w�����L�x�ɁA��̏���J���Ă����ʔv�̗��ɁA�̂���������b������B
���(���݂�)
拂͓V�c�⏫�R�Ȃǂ̋M�l�̑���������ɔ����A����ł��炽�ɂ����̍��ŁA������ȂƂ������B�_�{�c�@���S�ŕ��䂳��A10���ɗ˂ɑ���ꂽ�Ƃ��ɁA�u�C�����P��(�����Ȃ����炵�Ђ߂݂̂���)�v�Ƃ���������Ȃ����ꂽ�B
���@��
�@���͓V�c�����ʂ����̂��̌䏊�̌ď̂ɋN��������̂ł���A���@���n�܂�B�ۊ։Ƃł͋������(1207)�����������Ƃ��A�u�@���@�v�Ə̂������Ƃ��n�߂Ă���Ă���B�@���a�͑T�@�ɋA�˂�����������(1305�`58)���u�����@�a�m�R�勏�m�v�Ə̂��ꂽ�̂��n�߂ł���B�Ȃ��O�㏫�R�����`���̈ʔv�̖��́u�����@�a�y�O�{�告���V�R��T���v�ƒ����B
�Ȃ�����13�N7���ɁA����܂Ŏm�ȏ�̗L�ʂ̎҂ł����F�߂��Ȃ������@�a�܂��́A�勏�m�Ƃ��������������ɂ��F�߂���悤�ɂȂ�B
������
�T�@�Ȃǂł͑����̎��ɓ��t�����̑O�ň����������邪�A���̋N�����x��(�����܂�)���Ƃ��ĉΑ��ɂ���̂��V�����������́B��������x(����)�Ƃ������A���T�ł͉ޗt(�����傤)���߉ނ����тɂ���Ƃ����x���Ƃ����Ƃ��邷�ƁA�w��F���ٌo�x�ɋL����Ă���B
�����~
���{�ł̖З��~��́A���ÓV�c��14�N(606)�ɂ͂��܂�A���̔N��莛���Ƃ�4��8���A7��15���ɍւ�݂����B�Ė�3�N(657)7��15���ɉ��ɐ{��R�̌`�������ǂ��āA���̐��ŁA�n�߂ĖЗ��~��s�Ȃ�ꂽ�B
�����y��
���y�]�_�Ƃł���I�y�������Ƃ̈ɒ�F���A���a12�N(1937)2��25�����S�������A���̎��̑��V�ɔނ̗F�l�����ɂ���ĉ��y�����s�Ȃ�ꂽ�B���ꂪ���{�ł̉��y���̎n�܂�ł���B
������
�C���h�ł͏o�Ƃ��Ă������̂܂܂����A��������{�ł͎�����đ��������߂��B
�w���{���I�x��588�N�A�h��n�q�͕S�ς̑m�����ɁA����̖@�𐿂��A�P�M����S�ςɔ������Ă���B�����V�c(701�`756)�o�d������ď����Ə̂��ꂽ�B
���O���l��
���l�̕�́A����̏@�����A���������ɖ�������Ă���B��̔N��ɂ͊���2�N(1737)�Ȃǂƒ����̔N���ō��܂�Ă���B����13�N6���R�̋�����n���ɊO���l�̖����n����߂�ꂽ�B
���ߋ���
�h�M�k�̎��҂̎��S�N�����A�����A�������L���ߋ����͐����V�c�̍��́u�_�S��v�ƌĂ�Ă����B
���{�ł̉ߋ����̎n�܂�́A�~�m(794�`858)�ŁA���O�̖���ł������B
���Α�
���{�ōŏ��ɉΑ����s�Ȃ�ꂽ�͕̂�����ł́w�����{�I�x�̕����V�c4�N(7OO)��3��10���̏��ɁA�������̑m�����̈�̂��̈����Ƃ������ʼnΑ��ɂ��ꂽ�Ƃ���B����2�N��ɁA�����V�c���V�c�Ŏn�߂ĉΑ��ɂ���Ă���B
���Α���
�Α���͂����ĎO����ƌĂ�A�O���͋��s���O��5�P���̎O�������w���B�w���ƕ���x�ɕ揊�́A��a���A�Y��߁A�͏㑺�A�D���̌O���Ȃ�v�Ƃ���B
������
�ߐe�����������ꍇ�A���̊��ԑr�ɕ����邱�Ƃ������Ƃ������A�u���v�͑r���𒅂邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B���̊����̂͂��܂�́A�V�����N(672)3��18���A�O�N��12��3���ɕ��䂵���V�q�V�c�̎������m�����ʂŎn�߂ēo�ꂷ��B�u���{���I�v�ɂ��ƁA�u����͈��ܘA��~��}���ɂ��킵�āA�V�c�̎����s���v��ɍ������B�s���v��͂��Ƃ��Ƃ��r���𒅂āA�O�x����(���������Ĉ�����\��)�����A���Ɍ������Ĕq�v�Ƃ���B
�ߑ�ł́A����7�N�ɑ吭���z���ɂ��u�����߁v����߂�ꂽ���A����͕��Ƃ̐����̗p���A�勝���N(1684)�̕����߂������������\6�N(1693)�̐��A���тɌ������N(1736)���₵�����̂��߂��B
���o�����т�
���҂Ɍo�������Ă���߂𒅂���̂́A�^�������̌o�T�ɂ����̂ł���B�w�s����_�ϐ^���o�x(707�`709�N���̕�痬�x��)�ɁA�u�������̖S�҂̂��̐g�����[�ߕ��ɏ]���Đ^�����Ȃ��A�g�`�f�����đ�����E�A����̐g���E�ĂĂ������ɏ�y�ɐ�����v�Ƃ���B
�������q��
����23�N12��25���A����w�҂̑�Ε��F�̍Ȃ̎��S�L�����u���������v�V���Ɍf�ڂ��ꂽ�B����ɂ��ƁA�u���Ԃ��̋V�͕��ɂ��T��������ׂ���v�Ƃ���B
�����c��
���a3�N12��25���̃N���X�}�X�̖�A�S����Ⴢœ|�ꂽ�V���^���̏��R���O(1881�`1928)�ɑ��āA�z�n������ł͌��c�����s�Ȃ�ꂽ�B
������
����11�N5���A���̌|�W�����玀�̉�U��\���o���B������Y����U�B�S���̕a�@���㗝�����k�S�����Տꂵ���B
��w�̎��K�̂��߉�U�p�̈�̂�o�^���錣�̂̉�́A���a30�N(1955)9���Ɍ������ꂽ�B����𓌋���w���e��Ƃ����A�����Ȃ̊�ł͉�U�͈̂�w��2�l�ɂ��Ĉ�̕K�v�ł���Ƃ����B
���S���t�N���u
�Ō�̏��R�A����c��̎��j�ł���c�v���吳11�N38�Ŏ��S�����B���̐l�̓S���t�����ӂ������̂ŁA�[���̎��Ɍ̐l���D���������i�������悤�Ƃ����ӌ����������������B�������O�Ⴊ�Ȃ��Ƃ������ƂʼnƗ߂�������̂ŁA�Z�킽���́u�Z�킾���ōŌ�̂��ʂ�����������炻�̊ԉ������Ă���v�Ƃ����āA�����ŃN���u�����̂Ȃ��ɓ��ꂽ�̂ł���B
�����T
�����`�t�̎�(1550�N)���L�����w�����@�a�����L�x�Ɂu�����̌䏊(�r��)�ւ́A���X���A�������Q�点���v�Ƃ����L��������B�w�d��������Ɖi�㒠�x�̖��a2�N(1765)5��20���̋L�^�ɂ́A�u��i�@��ܗl��V���l�䍁���v�Ƃ���B
������R�[��
�w���͋L�x�m��3�N(1153)12��8���̋L���ɁA�u���[�䎺(�o�@�@�e��)���������B��ɓ��荵��삲��Ɉڂ����̐��̗т̒��ɑ���A�@�����[�͂�������������R�ɓo��A���̂Ȃ��ɔ[�߂��v�Ƃ���B
�����ʎ�
����34�N�A���R�����w���҂̒��]������12��13���A��A�K���̂���55�Ŏ��S�����B���V�͈⌾�ɂ���؏@����̋V����p���Ȃ��A�R���V��ɂ����č��ʎ������s�����B����̐��ʂɊ������u���A���V�W�̈��A�A�_�ޏ��̒����A��ΐ����̉������s�Ȃ�ꂽ�B
���U��
���a7�N(840)5���A�~�a�V�c�͍c���q�ɁA�l�͎��˂��͓V�ɋA��A�悾�������c��A�S������ɂ��Ă���������邩��A�����̍��͕��ɂ��ĎU�����Ƃ𖽂��Ă���B�V�c�̎���A�⌾�ʂ�R�隠�̕��W���ʼnΑ�������A�����ӂ��đ匴�쐼�R��̏�ɂ܂����B(�����{��I)
�����@
552�N�A�S�ς̐������́A�Ԗ��V�c�Ɏ߉ޑ����������B�V�c�͂��̑���h���ڂ��J�邱�Ƃ𖽂����B��ڂ͊��ő�a�̉ƂɈ��u���A���C���̉Ƃ��̂ĂĎ��Ƃ����B���{�̎��̂͂��܂�ł��邪�A���������z�ł͂Ȃ��B
�����l(��������~)
�V�c�̑�r�̎��Ɂu���l�v�Ƃ������t���͂�������A�����������l�́A�]�ˎ��ォ��n�܂����B�u����֗ߍl�v�ɂ��ƁA����8�N(1680)��108��㐅���V�c����ɂ������āA�����ł̌������A����(���z)����~���ׂ��Ƃ����֗߂��o���ꂽ�B�u���ɂĂ����̂��킪�������Ȃ��悤�ɁA�������X�܂ŁA�c�邱�ƂȂ����悤�Ɂv�Ƃ̂��Ƃł���B����������~�߂͌c��3�N(1867)�A121��l���V�c����ɂ������Ă��A�u��������~�v�̐G�ꏑ�����o�Ă���B�Ȃ���~���Ԃ́A���G�ꂪ�o���ꂽ1��4������S�P���@�v�̂���4��14���܂łł���B
������
���̐��ɕʂ�������鎞�Ɏc�����̂ŁA���ꂪ����ɂȂ����͕̂����������ł���B���i3�N(1182)7���A���Ƃ̈ꑰ�������V�c��i���ēs�������������ɁA���F�����x���r����������Ԃ��ē����r���̋���K��A�u�����Ȃ݂�u��̓s�͍r��ɂ����ނ����Ȃ���̎R�����ȁv�̎������c���Ă���B
�������̋֎~
����5�N6��28���������֎~����A����Ȍ�̑��V�͐_���܂��͑m���Ɉ˗����邱�Ƃ����߂�ꂽ�B�����Ƃ͎����̐M����Ƃ���ɂ���čs�Ȃ����V�ŁA�]�ˎ���̐_���A�͂Ƃ��Ɏ����ł����āA�r��ȉ��̐l�X���_���A�̎�����ɑ����čs�Ȃ����B
�����̉�U
�]�ˎ���̈�Ƃ̎R�e���m(1705�`61)�́A���4�N(1714)2��7���A���s���i��̋���4�l�̒j�̎��̂���U����B���ꂪ���{�ŏ��̈�w��U�ŁA����1�P����ɉ�U�ԗ�Ղ��s�Ȃ����B�����ɓ����Ė���2�N(1869)��U�Ɋւ���@�����o���A����ɂ́u�a�҂̐��肠��͎����U�������v�Ƃ���B�z���}�����ɂ���̂̒����ۑ����\�ɂȂ����̂�19OO�N���ł���B
�����S�L�g
�V���̎��S�L�g�̎n�܂�́A����6�Nl��14���w���V�^�����x����̍L���ł���B���e�͎��S���m�Ƒ��V�̈ē��ŁA�u�{��12���̒��O��������i�͂̕����i���a�������A����15���ߌ��ꎞ�z�n���ʂ蓯���@����o���A�ňɍX�q��~���֑����������蔤�ɂ������F�l���ׂ̈ɂ�������쎁�F�l�v�Ƃ���B
����
�Ƃ͎̗�ɂ���čs�Ȃ����V�ł��邪�A12���I�̎�w�ҁA��q���Ҏ[�����u��q�Ɨ�v���A���{�̎̊�ɂȂ��Ă���B����{�ōŏ��ɍs�Ȃ����͓̂y���̖쒆�njp�ŁA�c��4�N(1651)6���ɁA���̐���̑��V���ōs�Ȃ����B���ŗї��R�͖���2�N(1656)3���ɕ�r�쎁�̎��s�Ȃ��Ă���B
���}��
�N��̎��ɍۂ��āA�b������������Ė�������邱�Ƃ������B�u���{���I�v�̒��ŁA��11��̐��m�V�c��28�N10���A�V�c�̕�̒�̘`�F�����S���Ȃ�ꂽ�B�u��̂͒z��ɑ��������A���̂Ƃ��ߏK�̎҂��W�߂āA�S���������܂܂ŁA�˂̂܂��ɖ��߂��Ă��B�����o�Ă����ȂȂ����߁A���鋃�����߂����B���ɂ͎���ŕ����Ă����A���Ⓓ�������H�ׂ��v�Ƃ���B���̂Ȃ��ŏ}���͌Â��K���ł���Ƃ����Ă���̂ŁA����ȑO�ɍs�Ȃ��Ă������Ƃ�������B
���S��
�j���̐S���̍ŏ��͓V�a3�N(1683)�A�V���s�̏�ƂȂ��q�̒��E�q��Ƃ̏�ł���B�ߏ����w�S���n�͕X�̍���x�̂Ȃ��Łu�N�����߂����̌_��A���ɕ������͐��ʂ̂��ꂪ���߂̂����s�̏�v�Əq�ׂĂ���B���ŗ��s�𑱂����S�����]�˂ɔ�щ����̂ŁA���{�͋���7�N(1722)�S���֎~�߂��o���Ɏ������B
���_��
���{�ɕ������������Ă���A�V�c�̑��V�������ōs�Ȃ���悤�ɂȂ�A����͖����ɂȂ�܂ő������B���̊Ԑ_���ōs�Ȃ�ꂽ���̂ɁA����ƍN�̑��V������B����5�N6��28���A���{�͎������֎~���A�_���܂��͑m���Ɉ˗����đ��V���s�Ȃ����Ƃ��߂��B�������ʂł̐_���Ղ��s�Ȃ���悤�ɂȂ����B
�����k�ʐ�
���҂̓���k�Ɍ�����Ƃ����K���́A�߉ނ����ςɓ��������̎p��͂����Ƃ����Ă���A�w�ՏI�����x�w���όo�㕪�x�w���ꈢ�܌o�x�ɍڂ��Ă���B�w���ꈢ�܌o�x�ł́u���A����ɍ�����B�킪�œx�̂��ƁA���@�͖k�V��(�k�C���h)�ɂ���ׂ��B���̈����������Ă̌̂ɁA����~���ɖk�ɂ����ށv�Ƃ���B�Ȃ��̌o�T�́w��L�x�ł��k�����������Ă���A���{�ł́w�h�ؕ���x�̂Ȃ��œ�������(1027)����̂�k�����ɂ��ꂽ���Ƃ��L����Ă���B
�����O�̎��S�L�g
�]�ˎ���̐��m��̐�o�҂ł���i�n�]���́A76�̕���10�N(1812)8���ɁA�`���V�Ɏ��摜����̎����������ėF�l�ɔz�t�����B���̓��e�́u�]���搶�V�����ĉ�����߂���̂���Ƃ����ǂ��`�����A���w�V�����邢�͊����D�ނ��Ƃ����݁A�����V���̂��Ƃ����y���ށB
���N�͋g��̉Ԃ����A�����肵�ċ��ɂƂǂ܂邱��1�N�A���t���s�ɋA��A�悲���������ďo��ꂵ�ɁA���B���q�~�o�����ّT�t�̒�ƂȂ�A���ɑ�債�Ď��ɂ���A���������������Ė����ɂ܂��A��҂́A���炭�W�܂�̌`�Ȃ�c�v���������N�ɂ͑h���ʒm��F�l���Ăɑ����Ă���B
�V���ɍڂ������S�L���Ƃ��ẮA��Ƃ̐ē��ΉJ���A����37�N(1904)4���ɔx���̂��ߐe�F�̔n��Ɉ˗����Č��q�Ŏ����̎��S�L���������Ă�������B
�u�l�{�����ȂĖڏo�x��������Ԃ��̒i�L�����܂��Ȃ�A4��13���ē����v���̍L���͎��S����Ɠ����Ɍf�ڂɂȂ����B
���{��S 1
�{��S�@�v�͏�Q���Ȃ���S�ɑ��Ď{���@��ŁA���̓T���́w�~��������S�ɗ���x�ł���B�����Ɏ{��S�o�T���Љ�ꂽ�͓̂���(618�`907)�ŁA���{�ł͕�������ɓV��E�^���@�̑m���ɂ���ďЉ�ꂽ�B���b��l�`�L�Ɂu��l������{��S�@�������[�C����������v�Ƃ���B
���{��S 2
�����ɂ�����@��̖��̂ł���B�܂��́A�{��S��(��������)�̗��́B
��S���ŋꂵ�ޏO���ɐH�����{���ċ��{���邱�ƂŁA�܂����̂悤�Ȗ@����w���B����̐�c�ւ̋��{�ł͂Ȃ��A�L����̏�����ɑ��ďC�����B �{��S�͓���̌����ɍs���s���ł͂Ȃ��A�m�@�ł͖����C����邱�Ƃ�����B
���{�ł͐�c�ւ̒ǑP�Ƃ��āA᱗��~��ɍs���邱�Ƃ������B�~�ɂ͑c��ȊO�ɂ������閳�����⋟�{����Ȃ�������K��邽�߁A�ˊO�ɐ���I(�{��S�I)��ׂ��Ă����Ɏ{���K��������A��������M�ɒʂ�����̂�����B �܂������ȍ~�͐헐��ЊQ�A�Q�[���Ŕ�Ƃ̎��𐋂������ҋ��{�Ƃ��Đ���ɍs����悤�ɂ��Ȃ����B
�����l�̗�����߂ɐ�݂�M�̏�ōs���{��S���{�́u��{��S�v�Ƃ����A�Ă̎����ɐ�ōs�Ȃ���B
���R��
�s���w�~�������ɗ���o�x�Ɉ˂���̂ł���B�߉ޕ��̏\���q�ő������Ə̂���鈢��҂��A�Â��ȏꏊ�ō��T�ґz���Ă���ƁA����(����)�Ƃ�����S�����ꂽ�B���������čA�ׂ͍��������f���A���͗���ڂ͉��Ō���X����S�ł������B���̉�S������Ɍ������āw���O�͎O����Ɏ���ŁA���̂悤�ɏX����S�ɐ��܂�ς�邾�낤�x�ƌ������B����������A�ǂ������炻�̋�����邩�Ɖ�S�ɖ₤���B��S�́w����ɂ͂����S���ɂ����̏O���A�����鍢��̏O���ɑ��Ĉ��H���{���A���E�@�E�m�̎O������{����A���̎����͂̂сA���������E���邱�Ƃ��ł��A���O�̎��������т邾�낤�x�ƌ������B���������̂悤�ȋ��K���Ȃ�����́A�߉ޕ��ɏ��������߂��B����Ǝ߉ޕ��́w�ϐ�����F�̔����B���̐H���������A���́w�������H�ɗ���v�x(�������������)�������ĉ�������A���̐H�ו��͖��ʂ̐H���ƂȂ�A��̉�S�͏[���ɋ�����A���ʖ����̋����~���A�{��͎������������A���̌����ɂ�蕧�����ؓ����邱�Ƃ��ł���x�ƌ���ꂽ�B����������̒ʂ�ɂ���ƁA����̐����͉��тċ~��ꂽ�B���ꂪ�{��S�̋N���Ƃ����B
����ŖژA�u᱗��~�o�v�ɂ��߉ޕ��̏\���q�Ő_�ʑ��Ə̂����ژA���҂��A�_�ʗ͂ɂ��S����̍s����T���ƁA��S���ɗ����A���͑�������������Œn���̂悤�ȋꂵ�݂Ă����B�ژA�͐_�ʗ͂ŕ�����{���悤�Ƃ������H�ו��͂��납�A�����R���Ă��܂����H�ł��Ȃ��B�ژA���҂͎߉ނɉ��Ƃ�����~���肾�Ă��Ȃ��������˂��B����Ǝ߉ނ́w���O�̕�̍߂͂ƂĂ��d���B���O�͐l�Ɏ{�����������肾�����̂ʼn�S���ɗ������x�Ƃ��āA�w�����̑m����\���Ԃ̉J�G�̏C�s���I���鎵���\�ܓ��ɁA���y����p�ӂ��Čo����u���A�S���狟�{���Ȃ����B�x�ƌ������B�ژA���������̒ʂ�ɂ���ƁA�ژA�̕�e�͉�S�̋ꂵ�݂���~��ꂽ�B���ꂪ᱗��~�̋N���Ƃ����(���������̌o�T�͌㐢�A�����ɂ����đn�삳�ꂽ�U�o�ł���Ƃ��������L�͂ł���)�B
����2�̘b����������A���q���ォ�瑽���̎��@�ɂ�����᱗��~�̎����Ɏ{��S���s����悤�ɂȂ����Ƃ�����B
���{��S�@
�s���w�~�������ɗ���o�x�Ɋ�Â��C�@�ŁA�r�̔ȁA���̉��Ȃǂ̐Â��ȏꏊ�œ����Ɍ�����3�ڈȉ��̒d��ׂ��ďC����B�ɗ���ƌܔ@��(�E���F�g�E�ØI���E�L���g�E���|��)�̖����O�u�̉����͂ɂ���āA��S�̍ߏ��ł��A�Q���������A�V�l�����y�ւƉ���������B �Ȃ���S�͖�ԂɊ�������Ƃ����̂ŁA���v�ȍ~�ɍs���B�܂��g�˖ł��铍�E���E�Ξւ̑��ł͍s��Ȃ��B�{�����w�ł͍s��Ȃ��B�������Ƃ����Ȃ��B���������Ȃ��B����炳�Ȃ��B����𐠂�Ȃ��B�����ɐ^���������Ȃ��B��@�I����͒����Ɍ��������ĐU��Ԃ�Ȃ��ȂǓƓ��̋֊��̂����@��{�`�Ƃ���B�����̌��܂�͉�S���g�˖ⓔ���A���A���␔��̉��A�吺��l�̎������������ƂɗR������B ���̂悤�Ȏ{��S�@�͖����n�̏C�s����ł́A�s�҂̏C�s���~���ɐ��A����悤�ɂƖ���s����B
�����������ȍ~��᱗��~�s�����ƏK���������ƂŎ{��S�͓����ɐ���ɍs����悤�ɂȂ�A��L�̂悤�ȋ֊��̂Ȃ���@���s����悤�ɂȂ�B���̂悤�Ȗ@��ɂ͉�S�͒��ڗ邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA���{�����H���͖{�`�ɏ]���Đ�����R��ɓ����ĉ�S���Ɏ{���̂���Ƃ���B �{��S�͑���Ȍ���������Ƃ��āA���̌������c�ւƉ������ǑP�Ƃ��čs����悤�ɂȂ�A����炩��᱗��~�s���ƂȂ��Ă��邪�A���҂͍������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����B
���Ί�
�Ŋ������邱�Ƃ��Ɏu��(������)�Ƃ������A��11�㐂�m�V�c��32�N�ɁA�c�@���������B���̂Ƃ��a��̐l���Ί�������Č��サ���B�V�c�͂�����ق߂Đ��̑�A���̐���^����B�Ί��͓V�c�y�эc�e�ȊO�͗p���Ȃ������B�����đ�36��l���V�c(596�`654)�̎��ɐb���̊��͖��g�p���A����h��ׂ��ƒ�߂���B�܂�645�N�A���A���̐암���ē��邱�Ƃ���߁A�r��������Β������H�l�ɐΊ�����点��悤�ɂȂ�B
����
�Δ�͌���ɍ���Ō㐢�ɓ`������̂����A��21��Y���V�c�̎���ɁA���q�����y�Ƃ����҂������B�V�c�͐��y�̌��т��^���ĕ�����A���̏�ɔ�𗧂Č��т����B���ꂪ���{�ŕ��ɔ�𗧂Ă�n�܂�ł���B
�����V��
����6�N9���ɓ����_�c���q���ӂ�őݎԋƂ��c��ł�����і^�������p�̐l�͎�19�p��������̂��n�߂Ƃ����B
�������k
�����k�͈�̂�č������{���邽�߂̂��̂ŁA������5�̍��݂����A��������ꂽ���̂ł���B�w���{�I���x�̍N��4�N(967)�Ɂu5�E�����тɈɉ�E�ɐ�����26�P���A�����k6���𗧂Ă�ׂ��B��|�����ꍂ��7�ځA�a8���A�V�c��Y�݂ɂ��Ȃ�v�Ƃ���B
������������
���{�ň��y�������n�߂ďЉ���̂́A���@�w�҂̎s�����b���m�ŁA����39�N(1906)�w��t�̌����`���x�̂Ȃ��Łu�����p�̔@���������Ĉ�p�ɑ����邱�ƂȂ��B�����p�Ƃ͗ՏI�ɍۂ����ɋ�ɂɔY�ފ��҂����ċ�ɂȂ����đ����������ނ�p�������v�Ƃ���B���a51�N�A���{���y������ݗ�����A���a58�N�ɓ��{����������Ɖ��̂��ꂽ�B
�����A���{
�l������Ŏ��̐�����܂ł̎l�\����Ԃ𒆉A�Ƃ����A���̊Ԏ������Ƃɋ��{���s���B���̋��{�͕��T�́w���Ԍo�x�w�n����F�{��o�x�Ȃǂɂ���B�w���Ԍo�x�ɂ́u����Z��c�S�ł̓��A�y�юO�����Ȃ����������ɂ́A�܂��{��o������u�u�����ׂ��v�Ƃ���B���{�ł͏\���I������l�\����̖@�v������ƂȂ����B
���䔯
�䔯�́A�m�ɂȂ邽�߂̓��x���̈ꕔ�ł��邪�A���̖ړI�͔ϔY��f���A�R���ȐS���������߂ł���B���T�ł́w�ߋ����݈��ʌo�x�w�،��o�x�w�⋳�o�x�ȂǂɋL����Ă���B�V�c�̒䔯�͑啧�a�����Ă������V�c(701�`756)����n�܂����B
���f�X�}�X�N
��f�X�}�X�N�̋N���̓M���V���A���[�}���ォ�炠�������A���{�ł͖���14�N(1881)�̐V���W138���Ɂu�咹�\��N�̕v�l�̑��͂��܂����ʂȂ炴��O�ɐp�D�������āA���̖ʂɖ`���Ĕ͂ƂȂ����肵�䂦�A���|�����g�ɂ����킸�o����Ɛ\���\�Ȃ�v�Ƃ���B���ꂪ�n�߂��B
���V��
���҂̊z�ɎO�p�̕z�𒅂��镗�K���e�n�Ɏc����Ă��邪�A���̗R���͑T�@�̓������܂Ƃ߂��w���p�ѐ��K�x(1653)�́u�݉Ƒ��S�v�ɋL����Ă���B�u�z�X�ə��������A�S�҂̊z�Ɍ��ԁv�Ƃ���B
�������썑
�{���s�ɂ��鑽�������쉀�́A�吳12�N�A�T�@�n�̏@���@�l���b�@�̊J�R���A�����D���Ƃ������Ƃ���A��̂��������苟�{�������Ƃ���n�܂����B�Ȃ������̋��{�́w�~���{�����t�����^�x(1516)�ɏ����ɑ������������^����Ă���B
���[�����̎U���U�y
�[���̎��A�⑰�͊e���y�������Â�������A�����������肷��B���̗R���́w�ՏI���@�x(701�N���̋`���)�Ɂu�����̐���S�҂̏�ɒ����B�܂����y��S�҂̏�ɎU���邱�ƎO���Ձv�Ƃ���B
������
662�N�A���m�V�c�̍c�@�����B�o�_�̖쌩�h�H�͏o�_�̎m��(�͂���)�ɂ���(���ԐF�̔S�y)���Ƃ�A�l�n�̌`������ĕ�˂̎��͂ɕ��ח��Ă��B���ꂪ���ւ̎n�߂ł���B
������
�����V�c�̍c�@�ŁA�����̓Ă��M�҂ł�������c�@(760�v)��������ꂽ�Ƃ��A�⌾�ɂ���Ĉ�[�͖�ӂɎ̂Ă����A�J�I�ɂ��炳�����Ƃ����B
�����d
���d�Ƃ͕��������u����{��d�̂��Ƃł��邪�A�݉Ƃɕ��d�����u���邱�Ƃ́A�V���V�c��14�N(686)3��27���ْ̏��ɁA�w���{���I�x�Ɂu�����Ƃ��Ƃɕ��ɂ����A���Ȃ킿��������ьo��u���A�����ė�q���{����v�Ƃ���B�����ȍ~�͎������Ə̂��ďZ���1���ɕ��������u����Ƃ����������A��ʂ̏����͎��@�����s�������蕧��ǂɓ\����x�ł������B
���@��
�� �S�P���@�v
�u�S�P���v�@�v�͂��Ƃ��Ǝ́u���L���v���ō̗p�������́B�w��L�x(BC402�`221)�Ɂu�m��3���ɂ��đ���B���̌��⑲�L���v����܂ł͑r�Ղł��������A���L���������ċg�ՂƂ���B���{�ł�687�N9��9���ɕ��䂳�ꂽ�V���V�c�̕S�P���@�v��12��19���ɍs�Ȃ�ꂽ�B
�� ������E�O���
������͒����ōs�Ȃ�ꂽ���ˊ����A�����Ɏ������ꂽ���̂ł���B�܂���ˊ��͕����̎O����ɓ�����A���S���25�P���ڂɍs�Ȃ��ՋV�ł���B�������757�N�̐����V�c�̂��̂��n�߂Łu�m��ܕS�]�l�𓌑厛�ɋc���āA�ւ�݂���v�Ƃ���B�O����͊��q����ɓ����Ă���ŁA1186�N�̕��d�t��3������n�߂ł���B
�������@
�剻2�N(646)3��22���ɏ������b�̕���̐�����߂��A�E����菔���ɂ�����܂ő��n������A�Ƃ���ǂ���ɎU�����邱�Ƃ��ւ���ꂽ�B���1�N(701)�ɍ��ꂽ���߂����肳��A�S����ѓ��H�̕t�߂ɖ������邱�Ƃ��ւ���ꂽ�B
���r��
����2�N(1869)�ł̐��m�����^�Ɂu������p���A���F�̕z�Ђ������ĖX�q�̂܂��������A�܂����ȑ܂̎��ӂ���������Ȃǂ������đr�l����������v�Ƃ���悤�ɁA���m�̑r�͂ɂ��Ă̏Љ�Ȃ��ꂽ�B�r�͂����{�ŗp����ꂽ�͖̂���14�N3��13���A���V�A�c��A���N�T���h��2���̎��S�̂Ƃ��ŁA��畞�̍����ɍ����������ĕ��r�̈ӂ�\�����Ƃ����߂�ꂽ�B���ꂪ�₪�Ĉ�ʂɂ����y���Ă������B
������
���҂̐g�̂𐴂߂铒��̍�@�́A701�N���̋`���w��������o�x�̕t�^�ɗՏI���@�Ƃ����o������B�����Ɂu�M�j�A�M���A�������͐l����A�܂��ɖ��I����Ɨ~���c�����ɂđ���������ɂ��A�V��߂𒅂��v�Ƃ���B
����l��
���E�ŏ��̗�l�Ԃ̓A�����J�ŁA1905�N�̂��Ƃł���B���{�ł͑吳6�N(1917)���́u��F�v���u�R�r�����v�����グ���̂��ŏ��ł���B���ꂪ���y�����̂͑吳12�N�ɋN�����֓���k�Јȍ~�̂��Ƃł���B
���Z���K
���҂ɘZ���K����������K���́A�O�r�̐��n�鎞�̓n�����ł���Ƃ����Ă���A��͒�������`��������K�ł���B�ݕ����o���Ă���ݕ������ɔ[�߂����A�㊿����Ɏ��K����������Ă���͎��K��p����悤�ɂȂ����B���{�ł͎��K�ł͂Ȃ��A�����ݕ����p����ꂽ�B�������ꕶ�K���g���`���́A�]�ˎ��㏉���̊��i�ʕ�Ȍ�̂��ƂŁA�Z���g���̂͘Z�n���Ɉꖇ�Â������Ƃ�����������B�@ |
 �@ �@
���\���M�� |


 �@
�@ |
�\���M��(���イ��������)�́A�n���ׂ�10�l�̍ٔ����ɑ��Ď��߂���M�S�̈��ł���B���O�͏\�����Ղ�A�����Č�̍߂��y�����Ă��炤�Ƃ����Ӑ}���������B�\���͎��҂̍߂̑��ǂ��ӂ݁A�n���֑�������A�Z���ւ̗։���i��ȂLjؕ|�̑Ώۂł������B��ʂ�腖��ɑ���M�ƂƂ���������邪�A腖��ȊO�̍ٔ����̒m���x���Ⴂ�����ł���B�@
���\���Ƃ��̖{�n�@
�`�L��(��������)=�s������ �@
���]��(���傱������)=�߉ޔ@�� �@
�v�鉤(�����Ă�����)=�����F �@
�܊���(������)=������F �@
腖���(����܂���)=�n����F �@
�ϐ���(�ւ傤����)=���ӕ�F �@
�R��(��������)=��t�@�� �@
������(�т傤�ǂ�����)=�ω���F �@
�s�s��(�Ƃ�����)=������F �@
�ܓ��]�։�(���ǂ��Ă���)=����ɔ@�� �@
���o�� /
�����������ɓn��A�����ƏK�����Ă����ߒ��ŋU�o�́u腗������L�l�O�t�C����������y�o(���́u�a�C�\�������o�v)�v������A�ӓ��ɏ\���M�͐��������B�����o�T�̒��ɁA�u���n�V����鄷�s�ōߌo�v�u�n�{�\�����x�V�v�u����~��V���������ōߌo�v�Ƃ��������œ����̏\��������o�T�����݂���B�@
�u�a�C�\�������o�v�������̂́A�����ւƎ����ւƂ�����̕����V��̌����ł���B�����ւ́A���҂����g�̖v��̈������F�肵�čs���V��ŁA���̌̂Ɂu�a�C�v(�܂��́u�t�C�v)�Ƃ����p�ꂪ�p������B�{���́u�\���o�v�́A�����ւ���Ƃ����o�T�ł������B�����ւ̏�ɂ����āA�\���̈ʔv�����u���A�\����}��ēV���E�n�{�E�����ւ̏�\�����邽�߂̎��ƕM���A���̈ʔv�̑O�ɋ�����ꂽ�B�����𑗂邽�߂̍�蕨�̔n�����ׂ���B�����ւł́A�S�҂̂��߂̒Ǖ��E�C�����Ƃ��āA�⑰�����s����V��ł���B��̋V������������u�\���o�v�̎�̂́A����Ɏ����ւ̕��ւƗ͓_���ڂ��čs���B�������A����ɂ������̐U�蕪���́A�S�̂����������āA���҂��Z���A�S�҂ɂ͈ꕪ������U����Ɛ�����Ă���B���̔z���́A�u�a�C�\�������o�v�݂̂Ȃ炸�A�u���艝���\����y�o(���́u�o�v)�v�u�n����F�{��o�v�ł��������Ƃ���ł���B�@
���{�ł́u�n����F���S�����\���o(���́u�n���\���o�v)�v������A���������ɖ��@�v�z�Ɩ��E�v�z�Ƌ��ɍL���Z�������B�u�n���\���o�v���ɂ́A�O�r�̐��E�ߔk���o�ꂵ�A�u�ʓs�ڋX��(�قƂƂ���)�v�Ɩ������`�ʂ���A���͂��a�K�����т�ȂǁA���{�Ő��ꂽ���Ƃ��������킹��ʂ������ɂ���B���E�v�z�̐Z���ɂ��Ă͌��M���L�����Ƃ���鉝���v�W�����̒[���ł���ƍl�����Ă���B���q����ɏ\�������ꂼ��\���Ƒ�������悤�ɂȂ�A���オ����ɂ�Ă��̐��������A�]�ˎ���ɂ͏\�O���M�Ȃ���̂����܂ꂽ�B�@
�����E�� /
���{�ł͏\���M���������܂ꂽ���ő��E�ɂ��Ă̏����I�ɑ������B�����͌Î��L�Ɍ�����悤�Ȗ��m�Ȓ�`�̖�������̍��̑��E�ςŁA���R�Ǝ��ソ���s�����E�ł������̂ɑ��A��������̐��E���ڍׂɒ�`�t�����n���̑��E�ς͓����Ǝ̉e����F�Z�����A�l��l��l�ɑ����������̂ł������B���@�v�z�����s���������͑��E�ς��N���[�Y�A�b�v����A���m�ȏ��������������I���E�ł���n�����L�������ꂽ�B���{�̒n���̑��E�ς͂قƂ�ǂ������R�������A�����̍��ق�����A�O�r�̐�E�̉͌��E�D�ߔk(������)�ƌ��߉�(������)��������ł���B�@
���\���̐R�� /
���҂̐R���͒ʏ펵��s����B�v���Č�A�������Ƃɂ��ꂼ��`�L��(������)�E���]��(�\�l��)�E�v�鉤(��\���)�E�܊���(��\����)�E腖���(�O�\�ܓ�)�E�ϐ���(�l�\���)�E�R��(�l�\���)�̏��ŐR��������B�R���Ŗ�肪�����Ɣ��f�����Ύ��̐R���ɉ�鎖�͖����A�����ē]�����A���ׂĂ��킯�ł͂Ȃ��B��ʂɁA������腖������ŏI�R���ƂȂ�A�����Ŏ��҂̍s�������肳���B���������(����)�ƌĂсA�u������n���v�Ƃ������p��̌ꌹ�ƂȂ����B�@
����̐R���Ō��܂�Ȃ��ꍇ�A�lj��̐R�����O��A������(�S������)�E�s�s��(�����)�E�ܓ��]�։�(�O���)�ƂȂ�B�������A����Ō��܂�Ȃ��ꍇ�ł��Z���̂����ꂩ�ɍs�����ɂȂ��Ă���A�lj��̐R���͎����~�Ϗ��u�ł���B�������n�����E��S���E�{�����̎O�����ɗ����Ă����Ƃ��Ă������A�C�����E�l���E�V���ɋ����Ȃ�Γ����ς܂��d�g�݂ƂȂ��Ă���B�@
�Ȃ��A�����̖@�v�͑������ƂɎ���̂́A�R���̂��тɏ\���ɑ����҂ւ̌��߂̒Q����s�����߂ł���A�lj��̐R���̎O��ɂ��Ă̒ǑP�@�v�͋~�����Ȃ��������߂̎M�Ƃ��ċ@�\���Ă����悤���B�@
���݂͊ȗ�������ʖ�E���ʎ��E�������̌�͎l�\����܂Ŗ@�v�͂��Ȃ������ʗቻ���Ă���B
�@ |
 �@ �@
�����N(���傤�˂�)�ƍs�N(���傤�˂�) |


 �@
�@ |
�u���N�v�u�s�N�v����ӂƂ��Ắu���̐��ɐ������N���v�u���S���̔N��v�Ƃ��u�v�N�v�Ɩ̂ŁA�ǂ��炪�����N�ŁA�ǂ��炪���N����������̂����m�ł͂Ȃ��B���ɂ��A�u�s�N�v���u���N��v�A�u���N�v���u�����N�v�Ƃ��Ď�舵���Ă���B�@
����R�ɂ���]�ˎ���̐Γ����͂��߂Ƃ���Â��Γ������Ă݂�ƁA�w�ǂ��u���N**�v�ƍ���ł���B���a20�N�㔼�ΈȑO�́A���@�́u�N��̂ƂȂ����Ɋւ���@���v�Łu�����N�v���g���Ă����B���̖@���̎{�s��u���N��v���g���킯�����A�@���{�s�O�̕�����̎��S���̔N����̎���ł����������ɂȂ�悤�A�u���N�v���u�����N�v�Ƃ��Ďg���Ă���B���Ȃ݂ɁA�o�����Ă��琔���Ԉ����͐��������N�����̉d�����S���Ȃ����Ƃ��́A�u�s�N���v�Ƃ��Ă���B
�@ |
 �@ �@
������ |


 �@
�@ |
�������Əč��@
���ɂ́A�����E�č��E�h��(�������E��ɓh�鍁)�ȂǗl�X�Ȃ��̂����邪�A���ɂ͈Ⴂ�Ȃ��A����ɍ��ꂽ�������č��Ɏg���`�b�v��̍����������̂ƍl���Ă悢�B�m�����g�p���鍁�F�ɂ́A���炩���ߊD�̒��ɕ�����̍����ł߂Ė��ߍ���ł���B�@�h�ɂ�邪�O��ɕ����Ă��̍���������B�������O�{���Ă邪�A�O�{�łȂ�������Ȃ��Ƃ������܂�͂Ȃ��B���̈Ӌ`�́A����(�@����)�@�ؕ�(��F��)������(������)�̕��A�������ׂĂ̕��ɕ�����Ƃ������ƂŁA�{���ꕧ�ł���Έ�{�ƍl���Ă悢���ƂɂȂ�B�������A���́u�O�v�Ƃ����Ӗ��ɂ́u�O������(����݂���)�v(�g�E���E�ӂ̎O�Ƃ�����)���͂��߂Ƃ���l�X�ȈӖ�������A���̌������������Ɨ����ł���B�����ɂ���č��ɂ��땧�̋��{�ɑ���F�O������A���{�ł�����ł��ǂ��̂ł���B�č��̍����z�̋߂��܂Ŏ����グ�Ă��獁�F�̒Y�̏�ɗ��Ƃ��l���������A�������������܂���Ȃ��B���̊z�̋߂��܂Ŏ����グ��̂��́A����̕��X�̖S�҂ɑ���F��̔O�����R�Ƃ��̂悤�Ȏp�ɂȂ��������ł���B�@
�����č��̈Ӗ��@
�����́A���C�������(���サ)��ؕЂ������Ă��܂��B�M�т̒n�ł͐����L�∫�L��h���ړI�Ŏg�p����A���̌��ʂɂ��A���X�����C�����Ő����������悤�ɂ����Â�����̊��K�ɂ��A���{��C�s������ꏊ�𐴂߂邽�߂ɍ���������܂����B�@
���߉ނ��܂̒�q�ɕx�ߊ�(�t�i�L)�Ƃ������m�����܂����B�x�ߊ�́A�Z�̑A��(�Z���i)�Ƌ��Ɉ�O���N���A�͂��Č̋��ɂ��������Ă܂����B��l�͈ꍏ���������߉ނ��܂����}���������A�h�炷��C���������߂č������Ƃ���A���̉��͂��߉ނ��܂̉�(����)�֓V�W(���ʂ���)�ƂȂ��ē͂��A��l�̋��{����S�����ꂽ���߉ނ��܂́A�������܂��̂����ɂ��o�����ɂȂ�A���@�����ꂽ�Ƃ��������`��������܂��B�@
���̌����`���ɂ��A��l�̂悤�ɐS�����߂āA�O���Ȃ��獁���A���A�ǂ��ւł����߉ނ��܂͂��̂��p���������ɂȂ�A���肪�����@�������A�����҂͈��S(����)�邱�Ƃ��o����Ƃ����M�����܂ꂽ�̂ł��B�@
�������͎����ȊO�̗l�X�Ȑ����̉��b�ɂ���āA����̐���(���̂�)��ۂ��Ă��܂��B�@
�܂��A����c���܂����Ȃ���A�������͐l�ԂƂ��āA���̐��ɐ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��B�@
���ɓ�����������̐��ɎȂ���A����̐S�̉^�ѕ��ɂ���āA�ǂ��S�A�����S�ǂ���ɂ������Ă����܂��B�m���Ă��m�炸���A�߂�Ƃ��Ă��܂����Ƃ�����ł��傤�B���č��́A�����d�˂Ă���߂������Ɏ~�߁A���̍߂����č��̍���Ƌ��ɖł��Ă��������A����c���܂�A���X�̉��b����������A�l�X�ɑ��銴�ӂƋ��{�̐S�����߂Ă��Ă݂Ă͂������ł��傤���B
�����ƁA�S�̒��ɁA����₩�ȑ��蕨���͂����Ƃł��傤�B
�@ |
 �@ �@
�����߉� |


 �@
�@ |
�s�K�����̏K�킵���L�܂������̂��B�u���v�͔������Ƃ���u����Ȃ��́v�ƚg���Ďg�����ƂɂȂ����̂��B�@
�u���v�́u�����v���̂łȂ��u�������́v�Ƃ����`��������B�@
�����A�`�̎���ɐ`�̎n�c��ɂ͂�������̏��������B�n�c��́A�ŏ��͏��Ԃɏ��̉Ƃɒʂ��Ă������A����ɏ����������Ԃ�������Ȃ��Ȃ����B�����̏�蕨�ł��������C���ŒH�蒅�������̉Ƃɍs���悤�ɂȂ����B���̂��߂ɁA�S���s���Ȃ��Ƃ�����悤�ɂȂ����B�������������錫���������Ƃ������̂Ƃ���Ɏn�c�邪�������Ă������@���Ȃ��ƍl�����B���̕��@�Ƃ́A�n�c��̌�a���玩���̉Ƃ܂Łu���v�𐂂炵�ė���Ƃ������@�������B�Ȃ�Ƌ��́u���v���D��łȂ߂�Ƃ����B���ꂩ�疈���n�c��͋��̍s���܂܂ɖ������̏��̉Ƃɒʂ����ƂƂȂ����B�@
���̓`������A�q���������邨�X�ŁA���X���J����O�Ɍ��ւ̑O�����ꂢ�ɑ|�����ق��肪�����Ȃ��悤�ɐ����܂��A�u���艖�v�����ċq�������Ƃ�������|���邱�ƂɂȂ����悤�ł���B�@
���́A���ꂱ�������{����Ƃ��ɏC�@�����@���̂��̂����_�ƂȂ��Ă���B�@
�^�������̍�@�ł́A�܂��ŏ��ɖ{���ɎO��(����炢)���A����������u�ً�v�Ƃ����ĕ���Ȃǂ̓_��������B���ꂪ���q����������O�ɍs�����y���╔���̊m�F�Ɠ������ƂŁA�������{�̑ΏۂƂȂ镧�����������߂ɍs���m�F�s�ׂł���B���ɁA��Ɂu�h���v��h��S�g�𐴂߂�B���ꂪ�����ɍ����Ȃǂ��{�����q��������ĂȂ����������邱�Ƃɂ�����B���ɁA�u���������v(���Ⴗ������)�Ƃ����ĎU��(���傤)�Ƃ����_�ɐ���t���ĎO�x���߂�A���ꂪ���ւ̑O�ɐ����܂��s�ׂƓ����ł���B���ɁA�u�����v(���傤�݂傤)�Ƃ����߂̕t�����o�������A���{�̑ΏۂƂȂ镧�������̂ł���B���ɁA�njo���͂��܂�B���ꂪ���Ƃ̉�b�̓��e�ł���B�����A���q����ւ̐ڑ҂ł���A�b��������A���y�����ӂ�܂����ƂȂ̂ł���B |
 �@ �@
���z�{ |


 �@
�@ |
���z�{ 1�@
�z�{(�ӂ�)�Ƃ����Ƃ��@���̂Ƃ��ɂ�������֕��ł������z�{���v�������ׂ܂����A��ʓI�ɋ��i���{�����Ƃ����{(������)�Ƃ����A���@������ĕ�������ȂǁA�S�ւ̎{����@�{(�ق���)�Ƃ����܂��B���ɁA���؎{(�ނ���)�Ƃ����ĉ����̂ɂ��|��邱�Ƃ̂Ȃ��͂�^����z�{������܂��B���Ƃ��A�{���؎�(���ނ�����)�Ƃ����ʖ�������ω����܂��^���Ă�������z�{������ł��B�@
�z�{�́A�����̓s������ɂ��đ��������邱�ƂŁA����͕��ɋ߂Â���i�̂ЂƂł����畧���k�̑��̂Ƃ߂ł��B�����ȈӖ��ŁA����������A�L���ȐS�ɂ���s�ׂ͕z�{�ƌ����܂�����A���Ƃ��A�₳�����፷(�܂Ȃ�)����Ί�������邱�ƁA�v�����̂��鉷�������t�������邱�ƁA������Ƃ����S�Â��������邱�ƁA���Ԃ�Ȃ��䂸�����肷�邱�ƂȂǂ����h�ȕz�{�ɂȂ�܂��B�@
����A����(�݂傤��)�̕z�{�Ƃ������t������܂��B����͎����̗~������߂Ă̕z�{�ŁA�����_�߂��邱�Ƃ����҂�����A�ǂ����ɖ��O���ڂ邱�Ƃ���тƂ�����A���z����������A�D���l���Ǝv��ꂽ���Ƃ��A����Ȃ��Ƃ��`���b�Ƃł��v���������ł̕z�{�̂��Ƃł��B���������z�{�͕s����{(�ӂ��傤���傤��)�Ƃ����邭�炢�ŁA�����������Ă��܂��܂��B
�u�n��(�Ђ�)�̈ꓔ(�����Ƃ�)�v�Ƃ����b�́A�n���������������̔��̖т��Ă��߉ނ��܂ɕ����������ȏ����ȓ����啗�ɑς��čŌ�܂ŋP���Ă����Ƃ����b�ł��B��������������Ċ�i�����傫�ȓ��U(�Ƃ��낤)�̓��݂͂�ȏ����Ă��܂����̂ł��B�@
�z�{�Ɏ���(���ʂ�)��⍂��(�����܂�)���͋֕��ł��B�u����Ȃ��Ƃ����ł��Ȃ��Ă��݂܂���v�Ƃ����������Ɓu�����Ă��������v�Ƃ����ԓx�������Ă͂��߂ĕz�{�͌���(���ǂ�)�ƂȂ�̂ł��B
�@ |
���z�{ 2�@
�P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�ňقȂ�܂��B���ɁA�z�{�Ƃ������t�͘Z�g����(�Z�̌��̕��@)�̑�1�ɍ̂苓�����Ă�����̂ŁA�u�l�̐g�ɂȂ��čl����v�Ƃ������Ƃł��B�m�����F�l�̃j�[�Y���@�m���c�ޖ@�v�͖@�{�ƌ����A�F�l���m���̐g�ɂȂ��ċ��i���{���̂����{�Ƃ����s�ׂł��B���ɍ��{���������Ă�����(�Ȃɂ������Ă��Ȃ�����)�̐l������܂�����A�������݂Ȃ����Ƃ����Ă����s�s�\�Ȃ��Ƃ�����܂��B���T�ɂ͖����̐l�́A�̐g�{(�g���̂ĂĐl�̂��߂ɂ���)�S���{(�v�����̐S������)�a��{(���邢�\��Ŏ��͂�a�܂���)����{(�D�����፷��������j����{(����₩�Ȍ��t��������)�[�Ɏ{(�����Ă���l�������������)�����{(�Ȃ��䂸��)�Ȃǂ����h�ȕz�{�ł���Ƃ���Ă��܂��B�����ŁA�z�{�Ƃ͋��z�Ɉˑ������A�^�S�ËS�ɂȂ炸�A�����̏o���邱��(�z)���߂����̂ł��B�@
�Ƃ���ŁA���z�{�̌o�ϊw���ЂƂB����͔~�����v�搶�ɂ�邨�z�{���_�ŁA���z�{�̊z�͕z�{������҂ƕz�{����҂̊W�Ō��肳��邻���ł��B�z�{���鑤�ɒn�ʂ���������z�ɂȂ�܂��A�h�Ƒ���͈ʂ̒Ⴂ�m���ɂ����z�̂��z�{��K�v�Ƃ��܂��B�܂��A�z�{���鑤�̐g���Ɉ˂��Ă��z���ς��܂��A���h�ȑm���̂ɂ͍��z�Ȃ��z�{���A�삯�o���̑m���ɂ͂���Ȃ�̂��z�{���n����邱�ƂɂȂ�܂��B�@
�������A���ۂɒm�肽���̂͋�̓I�ȋ��z�ł��傤�B�n��ɂ����܂����������ӂŎ����������Ă���̂́A�Ⴆ�Α��V�̎��͔N����12����1(1���̋����{�{�[�i�X/12)�A���̑��̖@�v�̎��͂���10����1��ڈ��ɂ��Ă��܂��B�H���������グ�Ȃ��ꍇ�ɂ͂��H����A�������炨�����ɐ���ꍇ�ɂ͌�ʔ�Ƃ��Ă��ԑ���ނ̂����J�ȕ��@�ł��B�܂�A�N��600���~�̏ꍇ�ɂ́A���V�ł�50���~�A�@���ł�5���~�̂��z�{�ɂȂ�܂��B����́A�ЂƂ̖ڈ��ł��̒ʂ�ɂ���K�v�͗L��܂���B�J��Ԃ��܂����z�{�Ƃ͋��z�Ɉˑ������A�^�S�ËS�ɂȂ炸�A�����̏o���邱��(�z)���߂����̂ł��B�@ |
 �@ �@
�������� |


 �@
�@ |
��������(���ジ) 1�@
�u������v�͕����܂ɂ��܂��肷�鎞�Ɏg���@��ƌĂ����̂̈�ł����A�a���āu�������v�Ƃ��Ă�܂����A�u�쐔�v��u����v�Ə�������A�u�O��(�˂�)�v�ȂǂƂ��Ă�܂��B�@
�O��Ƃ������O�́A�u�얳����ɕ��v�Ȃǂƕ����܂�O���Ȃ���A���̂����O�����������鎞�ɁA�������������Ƃ������v�Z���邽�߂Ɏg�����Ƃ��炫�����O�ł��B���́A����Ƃ������O���̂����̂��Ƃ�����킵�Ă���̂ł��B�����(�˂Ђ���)����A������J(��)���āA����O���Ă���A�ϔY�������A���ʂ���Ƃ����킯�ł��B�@
�u��槵�q�o(���������傤)�v�Ƃ������o�̒��ɂ́A�n�����Ƃ������̉����܂��A������u�a(�����т傤)�Ȃǂ̖��ŔY�݁A�ǂ�������S�̕�����������ł��傤���ƁA���߉ނ��܂ɂ��q(����)�˂������ɁA���߉ނ��܂͖�槵�q�̎��S���ō���������^���A���̎���J��Ȃ��畧�̖��������Ȃ����Ƃ�����������Ɛ�����Ă��܂��B�@
�����܂��A���̒ʂ�Ɏ��s���A�S�̕��������Ƃ͂����܂ł�����܂���B�@
���āA����̌`���̐��͏@�h��p�r�ɂ���ĈႤ�̂ł����A��̐������͕S������Ƃ��Ă���̂����ʂł��B�������̂ł͐甪�\�̂��́A���Ȃ����̂ł͌\�l�A�O�\�Z�A��\���A�\���Ȃǂ̂��̂�����܂��B�@
�������A�܂�ɂ͂���ȊO�̂��̂�����܂����A�����ɂ������悤�Ȉ�ʓI�Ȃ��̂́A���ׂāA��槵�q�o�̒��ɂ���S������ɁA�\�{������A�����̈ꂩ�ɗ����Ă���Ǝv���Ă���������悢�̂ł��B
�@ |
��������(�O��) 2�@
����͒ʏ��108�̎삩��Ȃ�A���̐��ɂ��Ă͒ʐ��ł͐l�Ԃɂ�108���̔Ϝ�������A����𐔎�ɂȂ��炦�Ă��̔Ϝ������������Ă����̂��A�Ƃ���Ă��܂��B�������A����̋N���Ƃ����̂��悭�������Ă��Ȃ��̂ŁA����ƔϜ��̐��̊W�Ƃ����̂�����͂����肵�܂���B���Ƃ��Ɛ���͐^����O�����������������邽�߂Ɏg�킽�v�Z�@�ł��B���̓_�ł̓J�g���b�N���k�������Ă��郍�U���I�������Ӗ��������Ă��܂��B���̐�������Ƃ��͕K������Ɏ����܂��B�C���h�ł͌×��A�E��͐���Ȏ�A����͕s��Ȏ�Ƃ���Ă��܂����B���̕s��Ȏ�𐴂߂邽�߂ɂ��A����͍���Ɏ��̂ł��B��ʂ̒h�M�k�̕����A�ܘ_108��̐���������Ē����Č��\�Ȃ̂ł����A���̎�ނ���Ȏ������͏@�h�ɂ���ĈႢ�܂��̂Ŋe��ɂ��q�ˉ������B�������͈����ɂ���108��̔O����������A�u���J��v�u�l���J��v�Ƃ�����A�ʏ�̔����A��������4����1�̒����̐�����������ɂȂ�Ƃ����ł��傤�B�@ |
 �@ �@
�����k |


 �@
�@ |
�����k 1�@
�X�g�D�[�p�̂��Ƃ������ŕ\�����đ����k(���Ƃ�)�q�����k�r�Ƃ����Ă��܂����A�X�g�D�[�p�Ƃ͂��߉ޗl�̂��ɗ�(�����)�����܂肷�铃�̂��Ƃ������܂��B���߉ޗl�̓��Ō�A������炢�A������S�̋���ǂ���ɂ��Ă���l�X���ɗ��q�߉ނ̂����r������铃�����āA���߉ޗl�����܂������Ƃ����𒆐S�ɏW���A���߉ޗl�̂��̐��ւ̏o���A�����A���ςɂ��Đ[���l���܂����B����ɂ��܂��ƁA���߉ޗl�͐^�@(����ɂ�)�q�^���r�̐��E���炱�̖����̐��E�ɏO���ϓx(���ザ�傤������)�̂��߂Ɍ��ꂽ���l�ł���A���ł��čĂѐ^�@�̐��E�ɋA�҂��ꂽ�����ŁA�^�@���̂��̂ł���ƍl�����̂ł��B���������āA�^�@���痈��ꂽ�Ƃ����Ӗ��Ŕ@���Ƃ������܂��B�^�@�q�^���r�͕��ՓI�łȂ���Ȃ�܂���B���肳�ꂽ����A����ꂽ�n�悾���̐^�����Ƃ����Ȃ�A�^���Ƃ͂����Ȃ�����ł��B���̎����̏ꏊ�Ő������Ă��A���Əꏊ�ɂ���ĕς��悤�ł͐M�����������Ƃ��ł��܂���B���������āA�^�������ԂƋ�Ԃz���Ă���悤�ɕ��l���i���Ȃ̂ł��B�����āA���ՓI�ł���܂�����A�ǂ̂悤�Ȏ��ɂ��A�����Ȃ鏊�ɂ��s���n���Ă��鑶�݂łȂ���Ȃ�܂���B�F���ɕՖ�(�ւ�܂�)���Ă���̂ł��B�����ŁA�����k�ʼnF���ɕՖ����Ă���p��\�����Ƃ��āA�`���ꂽ�̂��ܗ֓��ł��B�C���h�ł͌Â�����F�����\�����Ă�����̂́A�n�E���E�E���E��̌܂̗v�f�ł���Ƃ����v�z������܂����B�F���S�̂������̂ɑ���(�ӂ���)�����̂ŁA�����k�ɂ��̌`�������ꂽ�̂ł��B�@
�����k�͉F���ɕՖ����Ă���^����\���A���̐^�������l�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��������Ɏ������Ƃ��Ă���̂ł��B�ł�����A���ł��ǂ��ɂł����l�͂������������łȂ��A�u��؏O�����L�����v(�����������ザ�傤�����Ԃ����傤)�Ƃ����āA�����Ƃ�������҂��ׂĂɕ���������̂ł��B�@
�F�l����Q�̐܂ɂ����k���n�ɗ��Ă�̂́A�F���̐^���ɐG��A�������J�������āA���ǂ��Ӌ`����l����������Ɛ����A���̉���(����)���F�邽�߂Ȃ̂ł��B�����āA���̋F�肪�����̈��y�����łȂ��A�S���l�̐����͂��Ƃ��ł����A�����Ƃ�������҂̈��J(����˂�)���肤���Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B
�@ |
�����k 2 / �u�����v�Ɓu���k�v�ɂ���(���@�吹�l�̖@�`)�@
���u�����v���O�o�Ǝ҂̖@���@
�u���������v�Ƃ����ᔻ�I�Ȍ��t���悭���ɂ��܂����A���͕������˂̒n�E�C���h�ɂ����Ă͉����E�@���̏K���͂Ȃ��A�o�Ǝ҂��A�Ƃ��ɑ����Ƃ͕ʂ́u�@���v��p���邱�Ƃ͂���܂���ł����B�������A�����ɂ����āA�{���Ɂu���v(�����ȁ����O�̒ʏ�)��u恁v(���݂ȁ����҂ւ̑��薼)������K��������A���̌×��̏K�����畧���E�ł͏o�Ǝ҂ɉ����A���Ȃ킿�@�����^������悤�ɂȂ����̂ł��B�@
�܂�A�����͒����̊��K�Ɋ�Â��Đ��܂ꂽ���̂ł���A����ɋA�˂����l��������@�ɗ^������u�o�Ɩ��v�������̂ł��B�@
�����̑T�@�ł͑m�������ꍇ�A�ʔv�ɏo�Ɩ��Ƃ��Ẳ������������Օ�����������Ă��܂����A���̑m���́u���O�v�̉������p����ꂽ�̂ł����āA����ɐV����������t����̂ł͂�܂���B�@
�����{�̏ꍇ�@
���{�ł́A�����`���̎��ォ�璆���Ɠ������o�Ɩ��E������Ƃ��Ẳ������p�����Ă��܂����B�ޗǁE��������ɂ����ẮA����(���傤��)�V�c�ɂ͏����A���������ɂ͍s�o�Ƃ����悤�ɁA�㗬�M�����������Ɖ����Ȃ����@�����^�����܂����B�����܂ł��o�Ɩ��Ƃ��Ẳ����ɏ��������̂ŁA�����̂悤�Ȏ�������Ƃ͂܂������قȂ�܂��B�������㒆���Ȍ�́A���@�����������V�c��㗬�M���̖@���ɁA���̎�����@����������Ⴊ����������悤�ɂȂ�܂��B���̊��K�͕��m�K���̑䓪�ƂƂ��ɏ㋉���m�̊Ԃɂ��s����悤�ɂȂ�܂��B���������������悤�ɂȂ����̂́A�����Ă�15���I���t�Ȍ�ƍl�����Ă��܂��B��ʖ��O��M�k�Ƃ��鎛�@�́A���m�̗�(1467�N)�Ȍ�̓�S�N�Ԃɋ}�����A���̊Ԃɏ����ɂ����鑒���E�ǑP�̋V�炪���W��������ł��B�@
�������ɐG����Ă��Ȃ����@�吹�l�@
���@�吹�l�͌���5�N(1253�N)4��28���ɗ����J�@���ꂽ��A�䗼�e�𐳖@�ɓ�����܂������A���̍ۂɁu���@�v�̈ꎚ�����Ƃ��āA���Ɂu�����v�A��Ɂu���@�v�̖@����������ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B�������A���@�吹�l�̌䏑�S�W�ɂ��u�����v�̌��͂���܂���B���@�剺�̕x�؏�E�́u��E�v�A��������́u��s�v�ȂǁA��������u���O���疼����Ă������́v�ł����āA��������ł͂���܂���B�܂�A�吹�l�̌�ݐ������ɂ����ẮA�o�Ɩ��A�������Ƃ��Ă̖@���Ȃ��������͂���܂������A��������̊��K�͂Ȃ��A�܂��@��������̈Ӌ`����������Ă���䕶������܂���B���{�R��㐢���L��l(1402�N-)�̎���ɂȂ�ƁA����ɉ�����t���镗�K���L���s����悤�ɂȂ�܂����A����́A���@�̑��V�E�ǑP�V�炪���Ԃɐi�o���Ă����Ȃ��ŁA���@�@�̐M���u�e�Ƃɓ`�������邽�߁v�̑[�u�ł������ƍl�����܂��B�@
��59��������l�́A�u�S��ւ̉��(������)�ɂ́E��(����)���t������̏��������̈ӎu����(�͂�)�ނׂ��炸�A��o�̌��p�ɔC���ׂ��A�����͊W(����)���A�����ɈӋ`����ƈӓ�(�����낤)�ׂ��ƂȂ�v�ƒ��߂���u�S���Ȃ����l�ɑ������͌�{���ւ̏���E�njo�����{�ł���A���̌����͂������Ă͂��߂ĉ����ɈӋ`��������v�Ƌ��ł��B�ȏ�̂悤�Ɍ��݂̂悤�ȉ���(����̉���)�͓��@�吹�l����c������l�̎���ɂ͂Ȃ��A�吹�l����ł����200�N����������ɐ��܂ꂽ�u���j�I�Y���v�ł���A�吹�l�̖@�`�̏ォ��̐l�̐����ɂ͈�؊W�Ȃ��̂ł��B�@
�����k / �C���h�̕����M�ɗR���@
�u���k�v�́A����̃X�g�D�[�p�𗪂������̂ł��B�ߑ������ł��A�⌾�ɂ��������č݉Ƃ̐l�B�̎�ʼnΑ��ɕt���ꂽ��A���̈⍜�͔��ɕ�������A���ꂼ��̍��Ɉ⍜�����߂��������Ă�ꂽ�Ƃ����܂��B�����āA�A�V���[�J���̎��ォ�畧��������Ɍ��݂����悤�ɂȂ�A�ߑ��̈⓿�����̂ԕ����k�̎��R�Ȋ���̔��I�Ƃ��āA�����M���S�C���h�ɍL�܂�܂����B���̕������X�g�D�[�p�Ƃ������̂ł��B�����E���N�E���{���ł��A���ꂼ��Ǝ��̗l���ŕ�������������A���܂��܂ȕϑJ���o�č����̑����k(���Ƃ�)�Ɏ������̂ł��B�@
������ɕs���̂��̂ɔ@
���{�ɂ����Ă����k�́A��������(������)������W�A���邢�͋��{���Ƃ��Ĕ��B���܂����B�����A���B���悭���k���{�Ƃ��ėp���Ă���̂͌ܗ֓��̌`���ꖇ�̖̔ɂ����ǂ������k�ł���A����͂�����u�ꎞ�̒ǑP�v�ł��B���@�吹�l�͖剺�����̏\�O����ɁA�얳���@�@�،o�̎������������߂��Z�ڂ̗����k�𗧂Ă��ƕ������Ƃɑ��āA���̌���Ƃ��āu��(��)������̌䂻�Ƃɂ��@�،o�̑�ڂ���(�����)�����ցv(�䏑1335�y�[�W)�ƁA����Ƃ����k�𗧂Ă�Ȃ�A�@�،o�̑��(�얳���@�@�،o)���������߂Ȃ����Ɗ��߂��Ă��܂����A�䋳������Ă���̂́A���k���{�Ƃ������V�������A�ǑP���{�̂����ŏd�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�u�얳���@�@�،o�Ƃ����@�̌������L��ł���v�Ƌ�����ꂽ�̂ł��B�@
�܂��A�吹�l�́u���ؐ��������v�ɂ����āA�u�L��͐��̐����E���͎��̐����E�����̐����Ɖ]�����L����̐����̎��Ȃ�A���͉̌̂䓙�O�������鎞���k�𗧂ĊJ�ዟ�{����͎��̐����ɂ��đ��ؐ����Ȃ�v�ƁA���ؐ����̌����𖾂�����Ă��܂��B����́A���ؐ����̌������Ȃ���ΐ��藧���Ȃ������̉��V�̎���Ƃ��āA�g�����Ă���̂ł��B�܂�A���k�𗧂ĂȂ���Ό̐l�������ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���ؐ����̌����͈�O�O��ł���A���̈�O�O��̓��̂ł����{���ɂ���Ď��҂̐������\�ƂȂ�Ƃ������Ƃ𖾂�����Ă���̂ł��B����͓����̌㔼�Ɂu��O�O��̖@�����(�U)�肷��(��)�����Ă���͑��䶗��Ȃ�v�Ɩ�������Ă���Ƃ���ł��B�@
���ǑP���{�̍��{�͐M�S����@
���̑��A�吹�l�́A�䏑�̐����ŖS���Ȃ������X�̈⑰�֎����̗�܂����Ȃ���Ă��܂��B������������u���k���{���Ȃ����v�Ƌ��ɂȂ��Ă��܂���B���@�吹�l�̌̎t�ł��������P�[�̂��߂ɋL���ꂽ�u���v�ɂ��A���k�Ɋւ��錾�t�͈ꌾ������܂���B�u�얳���@�@�،o�v�̂���ڂ������邱�Ƃ����̐l�ւ̍ō��̒ǑP���{�ł���Ƃ���A�܂��A�����Ă���⑰�������C�s�ɗ�݁A�������Ă����A�S���Ȃ����l�X�ւ̉���ɂȂ�Ƌ������Ă���̂ł��B�@
�u�m���ɓ��k���{�����Ă����Ȃ���Ό̐l�͐����ł��Ȃ��v�u���������Ȃ���Βn���ɑ�(��)����v�ȂǂƐ����̂́A���k�Ⓝ�k���u���ׂ��̎�i�v�Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�A���@�吹�l�̌䐸�_�Ɩ@�`�ɔw���u�ȋ`�v�Ȃ̂ł��B�u�����v���u���k�v�������ɂ܂������W���肹��B���������肷��v���́A�������ł��{�l�̐��O�́u���@�ւ̐M�s�v�ɂ���̂ł��B�@
�����k���Ȃ����������邩�@
���k�͞���̃X�g�D�[�p�̉��ʁA�����k�̑��𗪂������̂ł��B���ăC���h�ɂ����āA�ߑ��̓��Ō�A���̈⍜����������Ċe�n�Ɉ��u����A�����ɃX�g�D�[�p(��)����������M���W�߂܂����B�����ē����q���{���邱�Ƃ͂������A�������{�͑�ςɌ����̂�����̂Ƃ���Ă��܂��B���̌�A���̌`�A�ޗ��͍��ɂ��A����ɂ���Ă��܂��܂ɕς��܂����A�킪���ł͐Α���̌ܗ֓����⸈A�܂��ؑ��̌d���A���Ȃǂ��e�n�Ɍ����܂��B�@����A���V�ŋ���������k�����̈��Ƃ��āA�̐l�ւ̒ǑP���{��A�{�傪������ςނ��߂Ɍ��������̂ł��B |
�����k�ɏ�����Ă��镶���@
�^���@�ł�����������k�͌ܗ֓��k�Ƃ������A��E���E�E���E�n�ܑ̌�ɏۂ��āA���E�����E�O�p�E�~�E�l�p�̌ܗւ����݁A���ꂼ��ɞ����ŁA���̎�q�́u����E���E��E�E���v�̕�����������܂��B����͂܂���閦�i�����キ�j�E����ɁE�E�s�A�E����ّ̑��E�̌ܕ���\���A���ʂɏ�����鞐���͋����E�̑���@����\���Ă���A�����E�ّ��̗����̑���@�����\����̂ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B�܂��A�\�ʂ́u����E���E��E�E���v�̉��ɂ͊e�����̖{���̎�q��^���������A���̉��ɐ���̉������L���̂́A���ׂĂ̐��삪�Z��@�E�̐��ł���A����@���Ƃ��̕��g�ł�������̖{���Ƃɂ���ċ~���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B�@
���ʂ̞����̉��ɂ́A�u�͂�E�ǂڂ��E����ڂ������v�̕�����������Ă��܂����A�͂�͑吏����F(��������)�̎�q�ŁA�������̊肢�����Ȃ��A��Y����菜������������A�ǂڂ��͖ň����F(�߂���������)�̎�q�ŁA�n���E��S�E�{���Ȃǂ́A����ɋꂵ��ł���҂������~���ĉ�����Ƃ����Ӗ�������܂��B�܂��A�u����ڂ������v�͏�y�ς̐^���ŁA��������̂���y�ɕς������������܂��B�@
���ّ��E�ܕ��i���������������Ԃj�@
�����̑����̈��ŁA�����̐��E�ς�\�������E��䶗��̂�����1�A�ّ��E��䶗��i�ّ���䶗��j�̒��S�Ɉʒu����5�̂̕��̂��Ƃł���B��̓I�ɂ́A����@���A���i�ق��Ƃ��j�@���A�J�~�؉��i�����ӂ������j�@���A���ʎ��@���A�V�ۗ����i�Ă炢����j�@�����w���B�@
�����ł͋����E��䶗��Ƒّ��E��䶗���2���ł��d�����Ă���A���������킹�ė��E��䶗��i�܂��͗�����䶗��j�Ƃ����B�����͂������7���I���ɃC���h�Ő������������o�T�Ɋ�Â��āA�����I���E�ρA���̐��E�����o���������̂ł���B�ّ��E��䶗��́u����o�v�̏����Ɋ�Â��č��ꂽ���̂ŁA�T���X�N���b�g��̌��̈Ӗ��́u�傢�Ȃ鎜�߂��琶������䶗��v�ł���B�܂�A����ɂ́u�E�v�i���E�j���Ӗ������͊܂܂�Ă��Ȃ����A�u�����E�v�ƑɂȂ�W�ŁA���{�ł͕�������ȗ��u�ّ��E�v��䶗��Ə̂���Ă���B�@
�ّ��E��䶗��͑S����12�̋��ɕ�����Ă���A���̂����A���S�ɂȂ�u���䔪�t�@�v�ɂ͘@�̒����ɑ���@���A���͂�8�̉ԕقɂ͕��A�J�~�؉��A���ʎ��A�V�ۗ����̎l���ƁA�����A����A�ώ��݁i�ω��j�A���ӂ̎l��F���ʒu���Ă���B���̂����A����@���Ǝl�������킹�đّ��E�ܕ��ƌĂԁB����@���ȊO�̎l���̈ʒu�ƕ��p���܂Ƃ߂�Ǝ��̒ʂ�ł���B�@
�����@�� �����i�ّ��E��䶗��ł͏���A�����E�ł͐���������j�Ɉʒu���u���S�v�i�����J�����Ƃ���S���N�������Ɓj��\���B�@
���J�~�؉��@���@����i�E���j�Ɉʒu���u�C�s�v�i���������ēw�͂�ςނ��Ɓj��\���B�@
�����ʎ��@���@�����i�����j�Ɉʒu���u���v�i���̎����邱�Ɓj��\���B�@
���V�ۗ����@���@�k���i�����j�Ɉʒu���u���ρv�i��肪�������邱�Ɓj��\���B�@
���ܒq�@���@
����@�����u�@�E�̐��q�i�ق������������傤���j�v�ōō��̒q�B�@
��閦�@�����u��~���q�i�������傤���j�v�őS�Ă��f���o���q�B�@
�@�����u�������q�i�т傤�ǂ����傤���j�v�őS�Ă̑��݂��ɂ݂�q�B�@
����ɔ@�����u���ώ@�q�i�݂傤�������j�v�őS�Ă𐳂����ώ@����q�B�@
�s�A�@�����u������q�i�݂傤�������j�v�őS�Ă��~�����@��m��q�B�@
���ّ��E�ܔ@���@
����@�� �@
���@���͓����Ɉʒu���A���S�i�����J�����Ƃ���S���N�������Ɓj��\���B�@
�J�~�؉��@���͓���Ɉʒu���A�C�s�i���������ēw�͂�ςނ��Ɓj��\���B�@
���ʎ��@���͐����Ɉʒu���A���i���̎����邱�Ɓj��\���B�@
�V�ۗ����@���͖k���Ɉʒu���A���ρi��肪�������邱�Ɓj��\���B |
������@�� 1�@
�\�O����13������t�B����@���͖��d��ḎՓ߁i�}�J�r���V���i�j�̖�ŁA���̔��B�����`�ԁB�F���̑S�Ăi�����A�F���`�����z������ΓI�ȕ��A�����̍��{�̕��Ƃ��Ĉʒu�Â���Ă���B�����\������ׂɁA����������g�ɂ��Ȃ��Ƃ����@���̖�j���āA�ܕ��̕�����E�r�ցi�r���j�Ȃǂ̏����g�ɂ��āA�ꌩ��F�̎p�̂悤�ɉ₩�Ȏp�ŕ\���B�����E�̑���@���A�A�����E�֑ɗ��̎呸�B�q��������сA�q�d�@�g�B����@���̒m�b�őS�Ă�f��������̐̂悤�ȋ��������������B�@
�ّ��E�̑���@���A�ّ��E�֑ɗ��̎呸�B�����@�g�B��߂������������ԁB�����̍��͋����E�̑���@����菭�Ȃ��B �@
�T���X�N���b�g��ł̓}�n�[���@�C���[�`���i�A���Ȃ킿�u�̑�Ȍ��Ǝҁv�B��C�̊J�����^���@�ɂ����āA�ł��d�v�ȃu�b�_�B�O�@��t�i��C�j�ɂ��ƁA������@���ɂ�����_�∫���́A���ׂđ���@���̌����ł���A����@���̐g�͉̂F�����̂��̂ł���B�����ɁA�P���̔��o�̒��ɂ�����@���͑��݂���B����@���́A���@�ɍ������ґz���s���Ă���p�ŁA���E�i�ّ��E�E�����E�j�}���_���̒��S�ɕ`�����B �@
����@���́A�^�������ɂ����Ĉ�؏��������̍��{���Ƃ��ċA�˂��ϑz����Ă���{���ł��B �@
����@���̖��O�́A����̒q�b�̌����A���Ɩ�Ƃŏ�Ԃ��ω����鑾�z�̌��Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǑ傫���A���̐��̑S�Ă̂��̂ɒq�b�̌�������ڂ��āA���܂˂�����Ƃ炵�o���A�܂����߂̊����������ŕs�ʼni���ł���Ƃ��납��A���ɑ��z�ł���u���v�Ɂu��v�������āu����v�Ɩ��Â����Ă��܂��B �@
�^�������̍��{�o�T�ł���w����o�x�Ɓw�������o�x�ɂ́A�O���̋~�ώ҂Ƃ��Ă��ꂼ��ّ̓I�Ȑ��i�������A����̐������������������F���͂��ߏ��_��������Ă��܂����A�����̑S�Ă̏����́A����@�����o�����A����@���̓������ꂼ�ꂪ���S���A�܂��O���~�ςɂ��Ă��Ă��鏔���̓���������@���̓��̌����ł���Ɛ�����Ă��܂��B �@
���{�o�T�ł��闼�o�ɂ́A����@���̓��̌�������A�����̏����Ƃ̊W�ɂ����Đ�����Ă��܂����A���̊W��}���������̂��ّ���䶗��E�����E��䶗��ŁA���̗���䶗��̂��ė����i���E�j��䶗��ƌĂ�Ă��܂��B �@
���̗�����䶗��ɕ`����Ă������@���̎p�́A�߉ޔ@���∢��ɔ@���̂悤�ȏo�Ƃ̎p�ł͂Ȃ��A���������������i��j���ȂǁA��ʂɕ�F�`�ƌĂ��p������đ��̔@���Ƃ͈قȂ��Ă���_�������Ƃ����܂��B��F�`�̎p�ł������@���́A�F���̐_�i���Ƃ��l�����閧���ς���A�F���̐^�����̂��̂�������ΓI���S�̖{���Ƃ��ĉ��҂̎p������Ă���Ƃ����Ă��܂��B���̎p�͒鉤�ɂӂ��킵���ܕ��������������A��F��肳��ɂ���т₩�ȑ��g���g�ɂ܂Ƃ��Ă��܂��B�w�ɕ������w�͉~���傫�Ȃ��̂œ��ւ�\���A���������ꂷ��ō��̒n�ʂ��ے�����ɂӂ��킵���Ќ��̂���p�ł��B �@
����@���̎p�̊�{�͕ς��܂��A������䶗��ɕ`��������@���̎�̌��ѕ��i�j���قȂ�Ƃ��납��A�×����ّ�����@���E�����E����@���Ƌ�ʂ��ČĂ�Ă��܂��B �@
�ّ�����́A�G��ō��̏������Ă����A���̏�ɉE�̏��������ˍ��E�̐e�w�̐�����킹�x����u�@�E���v�����сA�����E����́A���̑O�ɂ����������̐l�����w���̂��A�E�̌��������Ĉ���u�q����v������ł��܂��B �@
�����̕��Ƃ������̍��{�͑���@���ŁA���̑��̕��l�͑���@���̓��̌���Ƃ���Ă��܂��B�ł����疧���̕��l���Љ��ɍۂ��āA�ŏ��ɑ���@���ɂ��ďq�ׂ����Ă��������܂��B����@���ɂ́u�����E����v�Ɓu�ّ�����v�Ƃ�����܂����A����͕ʁX�̕��l�ł͂Ȃ��A���̐��E��q�Ɨ��̓�ɕ����čl���A���ꂼ��̒����Ƃ��ĕ\�����ꂽ���̂ł��B�����āu�q�v�̐��E�̑���@���ɂ��Đ����ꂽ���T���u�������o�v�A�u���v�ɂ��Ă̂��ꂪ�u����o�v�ł��B����ɂ����}���������̂��A�����ّ�������䶗��ł��B �@
�����ł́A����@���͉F���̐^����\���Ƃ���A�܂��F�����̂��̂Ƃ���܂��B����@���͉F�����̂��̂�_�i���������̂ł���A��̂��̂͑���@������o������Ƃ����B�܂�A��̂��̂͑���@���ɑّ������̂ł���i�ّ��E�j�A�܂���̂��̂͑���@���̂Ȃɂ��̂ɂ���������Ȃ����łȒq�̌����ł�����i�����E�j�Ƃ��l������B�@
���đ���@���͉F����_�i���������̂Əq�ׂ܂������A��������Ǝ��������܂ߑS�Ă̂��̂͑���@���ɂ���Đ����A����@���Ɋ܂܂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ł�����S�Ă̂��̂�����@���ł���A�������}�l�ł����g�������ł���̂ł��B �@
������@�� 2�@
��敧������h�����������ɂ���Đ��ݏo���ꂽ��ΓI�ȑ��݂ł���B�����ɂ����đ���@���͕��@���̂��̂ł���A�F���̍��{������킷���݁B�F�����\������X�����ۂ̑S�Ă͑���@�����猻�o���A�߉ޔ@�����͂��߂Ƃ���S�Ă̕��l�͑���@���̉��g�ƍl�����Ă���B�����̒��ł͑���@���͕��̒��̉��ł���A���̔@�����S���ӈ߂������܂Ƃ��đ����i��Ȃǂ�g�ɕt���Ă��Ȃ��̂ɑ��A����@���͓��ɕA���ɂ�����i�悤�炭�j�A�r�ɂ͘r���i���j�����Ă���B�܂��A��䶗��̒��ő���@���͒����ɕ`����Ă���B�@
����@���ɂ�2�̎p������A1�́w���������x�i�������傤���傤�j�Ɋ�Â������E����@���ł���A����1�́w����o�x�Ɋ�Â��ّ�����@���ł���B�����E����@���͒q��������сA���ɂ͌ܒq�����Ԃ��Ă���B�ّ�����@���͖@�E�������ԁB�@
����@���̓T���X�N���b�g�Łu�}�n�[���@�C���[�`���i�v�ƂȂ�A�u�}�n�[�v�́u�傫���v�A�u���@�C���[�`���i�v�́u���z�v�̈Ӗ��ŁA����Ƒ���@���ƂȂ�B�u�}�n�[���@�C���[�`���i�v�����̂܂܉���A���d��ḎՓߔ@���i�܂��т邵��Ȃɂ�炢�j�ƂȂ�B����@���́w���������x��w������x�Ő�����Ă��邪�A��ḎՓߔ@���͂���ȑO�Ɂw�،����x��w���ԋ��x�Ő�����Ă���A�F���̍��{���ے����鑶�݂Ƃ���Ă���B�܂�A�F�����̂��̂�����킷�̂���ḎՓߔ@���ŁA���̐��E�ς������E�Ƒّ��E��2�̎��_���猩��������������@���Ƃ�����B�o�T�ɂ��A��ḎՓߔ@���͘@�ؑ����E�̒��S�ɂ��āA���̘@��ɂ�1000���̉ԕق�����A����1��1���Ɏ߉ޔ@�������鐢�E������Ƃ����B |
������ɔ@���@
����ɔ@���͐����Ɋy��y�����X�������Ƃ���A�S�Ă̎҂��Ɋy��y�ɓ������l�Ƃ����B���̎O�g�̖@�g���̍l���ł͉F���̐����͂ƂȂ�B�w���ʎ����x�ɂ��A�Ñ�C���h�̍����������݉��@���̐��@���Đl�X���~�������ƍl���A���ʂ��̂Ăďo�Ƃ��Ė@����u�i�ق������т��j�Ɩ�������Ƃ����B�@����u�͏C�s�Ǝv�҂��d�˂����Ɂu�l�\���̑��v�𗧂āA����𐬏A�������Ƃɂ���Č����J������ɔ@���Ƃ����B���̏C�s�ɂ͋C�������Ȃ�قǒ����N����v�����Ƃ���A���̊ԍl���߂��Ă������Ƃ��瓪���c��オ�����Ƃ������Ă���B�����\���̂��u�܍��v�҂̈���ɔ@���v�ŁA�ޗǂ̓��厛��܍��@�̈���ɔ@����������ɂ�����B�l�\���̑��̑�\����ɂ́A�O�������肪����B����́A"�������ɂȂ����Ƃ��Ɏ��̋�����[���M���ĔO�����\���Ă��Ɋy��y�ɉ����ł��Ȃ��l������Ȃ�A���ɂȂ�̂���߂悤"�Ƃ̂��̂ł���A�@����u������ɔ@���ɂȂ������Ƃ��炱�̊肢�͊�����ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ă���B����ɔ@���͑����̏ꍇ��i���}������ԁB�ܒq�@���̈ꕧ�B�@
�ǂ�Ȉ��s�������҂ł��u�얳����ɕ��v�Ə�����Ɋy��y�ɉ����ł���A�Ƃ̍l��������y�M�Ƃ����B���@�̎���ɓ������Ƃ��ꐢ�̒��ɕs�����L�܂�����������ɓ��{�ł���y�M�����W���A���ꂪ���t�����B���݂ł�����ɔ@���͏�y�@�A��y�^�@�̖{���ƂȂ��Ă���B�@
�߉ޔ@�����Ɗ�{�I�ɂ͓����p�ŁA�{���E�^���A�]�@�ֈ�A�������Ԃ��A�X�ɋɊy��y���琶������̂��}���ɗ���Ƃ��̗��}�����B����ɔ@�����O�����Ƃ����ꍇ�́A���Ɋϐ�����F�A�E�ɐ�����F���]���邱�ƂƂȂ�B�܂��A����ɔ@�������}����ہA�e���ł����\�ܕ�F���ɂ��₩�Ɉ����A��Ă���l�q��`������\�ܕ�F���}�}�̍��������B�@
�����̎��������Ƃ̈Ӗ�����u���ʎ��@���v�i�ނ�傤����ɂ�炢�j�A�����̌��������Ƃ̈Ӗ�����u���ʌ��@���v�i�ނ�傤�����ɂ�炢�j�ƌĂ�邱�Ƃ�����B�T���X�N���b�g�Łu���ʁv�́u�A�~�^�v�ł��邽�߈���ɔ@���̖��O���t�����Ƃ̐�������B�܂��A12�̓��̌����S�g���甭�����Ă���Ƃ���A�\������Ƃ��Ă��B |
����閦�@�� 1�@
�\�O����7������t�B����ň߂̒[���ɂ����Ă���̂������ł��B�����n���ȑ��݂ŁA�l���܂��͌ܕ��̂ЂƂƂ����J����̂���ʓI�ł��B���̂悤�ɑS�Ă��f���o���Ƃ����Ӗ��Łu��~���q�v�ƌĂ��q��\���܂��B��t�@���Ɠ����ƌ����l����������܂��B��閦�@�҂͞������A�N�L�V���r�����̓A�V���N�q�A�A�V���N�k�Ɖ]�ЁA�ĕs�������͖����ƂƂ����܂��B�������j��s�����������͕|�؋������i���A�ߋ��v���̐̈��䗅�ɏo�����A����@�҂̉������A�C�s���I����Ęʼnʂ�暂��A�P���ɟēy���������A���@�x��������łȂ�Ƃ����܂��B���͂ł́A�嚢���q�̓��ɏZ���A����̜����Ϝ��j�����C�̟ĕ��S���������鎖���i��A�F�A���A���A��̎l��F���ś��Ƃ��܂��B�����̑`�ɂ́u���V���N�q�łƂ͖��ќ��Ɩ����A�������䗅�ɍ݂�v�ƁB�����S�ɂ́u�ŏ��ɖ��㘩�ɉ����ĕ��S��ᢂ��A���V���N�ł̉����Ɉ˂邪�̂ɁA���ނ̕��S��暓����v�ƁB�������S�ɂ́u������������������A�������ʐ��E���Ƃ炷�v�Ƃ���܂��B���͂ɉ���������E��䶗��ɂ́A�������ւ̒����ɍ����A�����ّ��E��䶗��ɂ���ẮA�V�ۗ����@�҂Ɠ��{���ɂ��āA����@�҂̓����ł��B�@
����閦�@�� 2�@
�����ɂ�����M�Ώۂł���@���̈ꑸ�ŁA��閦���Ƃ������B�܂����T�ł͈�閦�k�ȂǂƂ����ʂ��s���A�����ȂǂƂ����B�O����`�͌܌؋����n�B��q�i�펚�j�͕��{�̋��т�\���E�[��(huuM)�B�@
��閦�@���͖����ɂ���������E�ܕ��̈�ŁA�����E��䶗��ł͑���@���̓����i��ʂł͑���@���̉����j�Ɉʒu����B�B���v�z�ł����u��~���q�v�i�������傤���j������������̂Ƃ����B�܂��ّ��E�̓����A���@���Ɠ��̂ƍl�����Ă���B�@
�����̃A�N�V���[�r���Ƃ́u�h�邬�Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ŁA���̔@���̌��̋��n�������i�_�C�������h�j�̂悤�Ɍ��łł��邱�Ƃ������B�́A�E�����̍b���O���Ɍ����ĉ����A�w��Œn�ɐG���u�G�n��v�i����������j�����ԁB����́A�߉ނ��������߂ďC�s���Ɉ����̗U�f�������A�����ނ����Ƃ����`���ɗR��������̂ŁA�ϔY�ɋ����Ȃ����łȌ��ӂ������B�@
�u��閦�����o�i���όo��Z�s���@����j�v�ɂ��A�́A���̛O�k���E���瓌���畧�̍����o�Ĉ��䗅��i�A�r���b�e�B�[�A����E�P���E���y�Ɩj�Ƃ�����������A�����ɑ���@�����o���������A���ќ��̊���C�s���āA����ќ��ƈ��~��f�ł����A�������ĕ��ƂȂ�A���܌��ɂ��̕����y�ɂ����Đ��@���ł���Ƃ����B������l����ƁA��̖����Ŕނ̎펚���{��̐��u�E�[���v�Ƃ��ꂽ�͖̂������Ă��邪�A�����ł����{��Ƃ͉�~�Ɋ�Â����̂ł͂Ȃ��A�����̖W���ƂȂ�ϔY�Ȃǂւ̓{��ł���B��~���炭�鏬���ȓ{����A���Ɍq����傫�ȓ{��ɏ��������̂ƍl����ׂ��ł��낤�B�@
���{�ɂ����鈢閦�@���̒����́A�ܕ��i�ܒq�@���j�̈�Ƃ��đ������ꂽ���̂��啔���ł���A��閦�@���P�Ƃ̑�����M�͂܂�ł���B�d�v�������w��i�ň�閦�@���Ə̂���Ă�����̂ɂ́A�ޗǁE�@������a��q���u�̖ؑ������A�a�̎R�E����R�e���@�̓�������������B |
�����@���@
���ꖼ�q�����������������@�ŕ��S�̘łŏW�c�̓����������G���݁A�Ԕ��F���A��������閦�@���Ɠ������ڋ����ƌ����A�q���A�����A��~���q�A���S�������Ĉ������~�������A��͉E��̂Ђ�����O�ŊO�Ɍ�����{���؈���Ƃ�A���Ƃ͍��ꎫ�T�Ɉ˂�Ζ@��̔��̂ŕ��@�̓G�����|����ҏ��̛�i���ق��j�̎��������A�o�ւ̏o�����Ȃ킿���S�B�@ |
�����k 3�@
�����k�͂����납�狟����悤�ɂȂ����H�@
���k�́A�O�m���N(810)8��8���A�O�@��t���͓��̍��ɍ��M�����������ꂽ�Ƃ��A����4��8��5���A��2��8���A����5���̔��k�����Ă�ꂽ�Ƃ����̎��Ɏn�܂�A���ꂪ��ʂɍL�܂����ƌ����Ă��܂��B�@
�������k�Ƃ͂Ȃ�ł����H�@
�����k�Ƃ́A���Ƃ��Ƃ��߉ނ��܂̈⍜��[�߂��ˁA���ɗ������Ӗ�����u�X�g�D�[�p�v�ƌ������t�̉��ʂł��B�ł�����A�u���s�k�v�u�����k�v�u�����k�v���ƕ\�L���܂����Ⴂ�͂���܂���B���Ƃ����Ӗ����猩��A�d�̓���O�d�̓��Ȃǖ{���͓������̂Ȃ̂ł��B�����k�̏㕔�ɍ��݂������Ă��܂����A����͂��̖��c�Ƃ�������ł��傤�B�܂��A�����X�g�D�[�p�͂��߉ނ��܂����߂Ƃ��鍂�m�B�̂���ɗp�����܂����B���ł́A��ʂ̕����S���Ȃ����ꍇ�������k�����������{���܂����A�S���Ȃ����l�������ɂ���ĕ��⍂�m�ɋ߂����݂ɂȂ�܂�����A�����k(�X�g�D�[�p)�����Ă�̂͑傫�Ȍ����ɂȂ�̂ł��B(�ǑP)�@
�܂��A�@�h�ɂ���Ă����ق͂���܂����A���X�A�����k�ɋL���̂悤�Ȃ��̂�������Ă���̂��������܂��B����́u�����v�ƌĂ�A�Ñ�C���h�����̍�����ł��B�ォ��@
�u�L���v(���)�u�J�v(����)�u���v(�Α�)�u�o�v(����)�u�A�v(�n��)�@
�Ə�����Ă���ꍇ������܂����A����́u�ܑ�v�ƌ����āA���̉F���╧�A�Ђ��Ă͎��������\�����Ă���5�̌��f�̂��Ƃł��B������y�����̂��珇�ɏ����Ă���A���̉F����������������������������Γ���ł���A�Ƃ������Ƃ�\���Ă���̂ł��B�@ |
�����k 4�@
���k(�Ƃ���)�A�܂��͑��s�k(���Ƃ�)�Ƃ������܂����A���V�A�N��@�v�Ȃǂł���ɗ��Ă�����Ȃǂ��������ג����̂��Ƃł��B���s�k�Ƃ́A�T���X�N���b�g��́u�X�g�D�[�p�v(�p�[���[��ł̓g�D�[�p)�������Ŏʂ������̂ŁA�X�g�D�[�p�Ƃ́A�C���h�ɂ����āA�y�܂イ�^�ɓy��グ�Ă������˂̂��Ƃł��B�́A���߉ނ��܂��N�V�i�K���ł��S���Ȃ�ɂȂ����Ƃ��A���̈⍜�ɕ����A�����C���h�ɂ��������̍��ł��ꂼ�ꕧ�ɗ��������Ăċ��{�����Ƃ������Ƃł��B���̂悤�ɁA�������ĂĈ⍜�����{���镗�K�́A���̌���C���h�ōs�Ȃ��A�����̓`�d�ɏ]���āA��������⒆���A�W�A�A�����A���N�A���{�ɂ��`����Ă��܂����B�厛�@�ɂ���d���A�O�d���Ȃǂ������������K���猚�Ă�ꂽ���̂ł���A�ܗ֓��A��⸈�(�ق����傤����Ƃ�)�A����ɂ͂���ł���Γ��ւƍL�܂��Ă������킯�ł��B���̂悤�ɁA���̌����́A���@�̌쎝�ɂȂ���傫�Ȍ���������Ƃ����̂ŒǑP���{�̖@�v�ɍۂ��ẮA�������̐l�ɂ߂��炷�Ӗ��Ŕ��k�����Ă�悤�ɂȂ�܂����B�@
�����k�@
�̐l�̂��߂Ɂu���k�v�𗧂Ăċ��{����Ƃ����̂́A�����{���̋����ł͂���܂���B���{�l���L�̎Љ�K���ł��B�@
���j�I�ɂ́A�܂��C���h�ɕ����M������܂����B�o�T�ɂ́A�ߑ������ł��Ĉ⍜���W�J���ɕ������A���ꂼ��ɓ������Ă�ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B���̐����ƕϑJ�ɂ��ẮA����������܂����A�₪�āA�ߑ��̈⍜�̓�(���ɗ���)�����łȂ��o�[����o���Ȃǂ������A��̐M�̃V���{���Ƃ��āA�e�n�Ɍ��悤�ɂȂ������Ƃ͊ԈႢ����܂���B�@
���̕����̌`�����x�́A�����֓n���āA���B�����ؑ����z�̉e���������Čd�̓��̂悤�ȘO�t(�낤����)�ɕς���Ă������̂ł��B���̏ꍇ�A�ނ���A�����M�Ƃ��������������@���ے����錚�����Ƃ��Č��������悤�ɂȂ������̂ŁA�e�n�ɁA�d�A�O�d�̓����������т܂����B�@
���̌������Ƃ��Ă̕������A����ɁA���{�ɂ����Ă͋��{���Ƃ��Ă̈Ӗ��ɕώ����Ă����A�`���ό`�����^�����Ă����܂����B�����͂����ς�A�����ł����@�������ł��Ȃ��A��c�̒ǑP�ɗp�����A�揊�ɗ��Ă���悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B�傫�����A���������~�j�`���A�ɂ����Ƃ��납��o�����A�ŏ��͐Γ��ł������A�₪�Ė�p����悤�ɂȂ��āA�p���k��A����ɂ́A����𗪂������k(�����k)���p�����Ă������̂ł��B�@
�����̔��k�́A�n���Ε���ܑ̌���Ӗ����Ă���ܗւ��`�ǂ������̂Ƃ��āA�S�̂��܂ɂ��т�Ă��܂��B����͌ܗ֓��̖��c�ł��B���������ė��j�I�ɂ݂Ă��A�M�̑ΏۂƂȂ镧���ƁA���҂̂��߂ɒǑP���{�Ƃ��ė��Ă铃�k�Ƃ́A�܂������ʂ̂��̂ł��B�@
���@�吹�l���䏑�S�W�̂Ȃ��ŁA�L���Ӗ��Łu���k�v�ɂ��Č��y����Ă�����͔̂��҂𐔂��܂��B�������A���e������A�܂��A���@��̈Ӌ`�Ƃ��������A�C���h����{�̏K���Ƃ��ē��k�Ɍ��y�������̂��唼�ł��B�Ⴆ�A�C���h�ŕ���(�X�g�D�[�p)��j���b(�u��掖@���v)�Ƃ��A������j�܂��邽�߂ɁA��n���o(�݂���)�̓��k(����)�����ĂĂ��@�،o��掂̍߂͏����Ȃ��ƌ�w�삳�ꂽ��(�u�P���؏��v)�A�����k�����Ă��ߋ��̌̎�(�u���a��Ԏ��v)�Ȃǂ�������Ă��܂��B�@
���吹�l�͑�ڂ̌����������@
�u��`���`�v�ł́A���k��̈Ӗ��Ɏg���Ă��܂��B�@�،o���i��\��́u���v�Ƃ́u�F���g�̓��k������Ȃ�v�Ƃ���܂��B���Ȃ킿�A�����ł͌�{���������҂́A�킪�g�����@�̓��̂ł���ł���ƌ�邱�Ƃ������Ă���̂ł��B���̏ꍇ�̓��k�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��A��������k�ł͂Ȃ������A�Ȃ����@�،o�̑���̓��A�܂�̈Ӗ��ł��B�@
���ǁA�吹�l�����k�ɂ�鎀�ҋ��{�ɂ��Č��y����Ă���̂́A�u�������������v�Ɓu���ؐ��������v�̓�҂����ł��B����ȊO�͎��ҋ��{�Ƃ͊W����܂���B���̂����A�u�������������v�ł́A�u��(�݂܂���)�ʂ�c�q�̂ނ���(��)��O�̏\�O�N�ɏ�Z�̂��Ƃ�(���g�g)�����Ăđ��̖�(������)�ɓ얳���@�@�،o�̎����������āE���͂��܂��c�v�Ƌ��ł��B�����ő吹�l�́A�@�E�����ɍL������(������)�̌����̑傫����������Ă��܂��B���̌䏑�ő吹�l�́u���k�̌����v�ł͂Ȃ��u��ڂ̌����v�������A�v�Ȃ̐M�S�����コ��Ă���̂ł��B�@
�吹�l��ݐ���菭���O�̎���ɂ́A�^����O���̐�(�Ђ���)�ɂ���āA���k�ɂ�鎀�ҋ��{�̕��K���}���ɕ��y�����悤�ł��B�����ɂ͓��R�A�^���̌ܗւ̎�q(�n���Ε����\������)�∢��ɂ̖���(�얳����ɕ�)��������Ă��܂����B���̂Ȃ��ŁA�����������O���̑�ڂł͂Ȃ��@�،o�̑�ڂ������ꂽ���Ƃ�吹�l�͂ق߂��A��ڂ̌���������ꂽ�̂ł��B�ł�����吹�l�́A���̌䏑�̖����Ɂu������X�̌䂻�Ƃɂ��@�،o�̑�ڂ��������ցv�Ƌ����Ă���̂ł��B���������āA���̌䏑�́A�u���k�𗧂ĂȂ����v�ƁA���@�Ɋ�Â����K���̂����コ��Ă���킯�ł͂���܂���B�������A���������̏ꍇ�A���k�𗧂Ă��̂́A�������g�A�܂�ݑ�̐M�k�̑��ł����đm���ł͂���܂���B�܂��āA���@�傪�咣���Ă��邱�Ƃɍ��킹��A����ΐM�k���m�������ɏ���ɗ��Ă����k��吹�l���ق߂�ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�@
�܂��u���ؐ��������v�ł́A�吹�l�́u�L��͐��̐����E���͎��̐����E�����̐����Ɖ]�����L����̐����̎��Ȃ�A���͉̌̂䓙�O�������鎞���k�𗧂ĊJ�ዟ�{����͎��̐����ɂ��đ��ؐ����Ȃ�v�ƈ�O�O��E���ؐ����̌�����������Ȃ��œ��k���{�ɂ��ďq�ׂ��Ă��܂��B�܂�A��O�O��̐����͗L��E���ɂ킽��̂ł���A�����ł͔��̐����Ƃ��đ��ؐ��������グ���Ă���̂ł��B�����āA���̑��ؐ����ɂ��Đ�������栂��Ƃ��Č��V��m�̍Ř@�[�ɂ킩��₷���A�������@�ɂ���ĕ��y���Ă������k���{�����グ�����̂Ƃ��������܂��B�@
�u�ϐS�{�����v�ő��@�̖{���̎���������āA��������O�O��E���ؐ����̌������Ȃ���ΐ��藧���Ȃ��Ƃ���Ă���̂Ɠ����ł��B�u�ϐS�{�����v�̑��@�̖{�����A�u���ؐ��������v�̓��k���{���j�܂̑ΏۂƂ��ċ������Ă���̂ł��B���̓�̌䏑�ł́A���̈�O�O��̓��̂ł����{���̈Ӌ`�𖾂�����邱�Ƃɑ吹�l�̌�{�ӂ�����̂ł��B���̂��Ƃ́A�u���ؐ��������v�̌��_�Ƃ��āu��O�O��̖@�����(�U)�肷��(��)�����Ă���͑��䶗�(�܂�)�Ȃ�A�����̏K�������Ȃ��̊w�҂�߂ɂ����炴��@��Ȃ�v�Ƌ����Ă��邱�Ƃ�������炩�ł��B���������āA�u���ؐ��������v�̈�߂��A�����܂�栂��ł���A���k�𗧂ĂȂ���ΐ����ł��Ȃ��Ƌ����Ă���킯�ł͂���܂���B�@
���ǁA�吹�l�͐M�k�Ɂu���k�𗧂ĂȂ����v�Ƃ͋L����Ă��܂���B�����A�䏑�ɂ͐M�k�����k���{��������͒���������������܂���B�l�������x�؏�E�A�r��Z��A��������ɂ����߂��Ă��܂���B�܂��āA�吹�l�䎩�g�A�S���t�E���P�[�̂��߂ɓ��k���{������邱�ƂȂǂ���܂���ł����B�v����ɁA�u���k�͌̐l�̒ǑP���{�̂��߂ɕs���v�Ƃ��錻�݂̏@��̘_���ł́A�吹�l�̎�v�剺�̓��e�͐������Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B�@
�ȏ�̂悤�ɁA���k���{�Ƃ́A�����܂ł��吹�l�̕��@�̖{���Ȃǂł͂Ȃ��A���݂̓��{�̎Љ�K���ɂ����Ȃ��̂ł��B�@
���u�T���@�E�������v�v�̈Ӌ`�@
���݁A���{�ŗp�����Ă����ʂ̓��k�ɂ́A�O�����ɑ�(��)���Ă��܂������҂�ǑP���{�ɂ���ċ~�ς���Ƃ������e�̌��t�������ȂǂŋL����Ă���̂����ʂł��B���@���@�̓��k�ł͕\���Ɂu�ǑP���{����v�Ɨ����Ɂu�T���@�E�������v�v�ƋL����Ă��܂��B�������A�����̌��t�͏@�傾�����g���Ă��錾�t�ł͂���܂���B�u�ǑP���{����v�Ȃǂ͓��@�@�g���h�̓��k�ɂ������Ă��邵�A�u�T���@�E�������v�v�͐^���@���y�@�̓��k�ŗp�����Ă��܂��B�@
���ʁA�����e�h�ŗp�����Ă���u�T���@�E�������v�v�̈Ӗ��́A������u�^�^�������v�ł��B�u�T���@�E�������v�v�́u�@�E�v�Ƃ͐X�����ۂƂ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�u�@�E��v�܂蕂����Ȃ��u������v�̂��Ƃ��Ӗ����錾�t�ł��B���{�l�͒����ԁA���{���Ă��炤�l�̂��Ȃ��u�@�E��v�́A�����������ɍЂ��������炷�ƍl���Ă��܂����B�����ŁA�̂���u�@�E��v���Ԃ߂邽�߂ɓ��k����������K�킵�����{�̊e�n�ɂ������̂ł��B�@
���̏ꍇ�̖�������Ӗ�����u�@�E�v�Ƃ������t�́A�×��A��������z�E�J�C�A�}�����z�E�J�C�A�������z�E�J�C�T���m���V(�u�@�E����̔сv�̈�)�ȂǂƂ����Ă������̂��A�����p��́u�@�E�v�Əd�Ȃ����Ƃ��납��g����悤�ɂȂ����Ƃ�����������܂��B������ɂ���A�@�E�O���Ƃ����ƁA�������A��������w���Ă������Ƃ͖����ł��B���̂悤�ɁA�����A�u�T���@�E�������v�v�Ƃ������t�́A�����̕����̊e�@�h�̓��k�ɂ��L����Ă���A���{�Ɠ��́u�^�^���M�v�̖��c�����錾�t�ł��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��̂ł��B�@
�v����ɁA���k�̌`�Ƃ����A���ʂƂ����A���ǂ́A�K���̎Y���Ȃ̂ł��B |
�����k 5�@
�����k�Ƃ́A�C���h�́u�X�c�[�p�v�Ƃ������t�̉��Ɋ��������Ă����̂œ��Ɩ�܂��B�@
��������ܕS�N�قǑO�A���߉ނ��܂���������ɂȂ�ꂽ�Ƃ��A�l�X�͂��̂����̕����ŕ����Ă��ꂼ��̒n��Ɏ����A��܂����B�l�X�͂��̂������ӂ����悤�Ȍ^�ɓy����������グ����(�X�c�[�p)�̒��ɂ��[�߂����{���܂����B���̓��������̑����k�̌��ł��B���̌^�́A�C���h���璆���A���{�ւƓ`���A���オ���ɂ�āA�y�܂イ�̌^����d���A������ܗ֓��ւƂ��̌^���`����ꌻ�݂̑����k�ƂȂ�킯�ł��B�@
�����������Ă鑲���k�ɂ͂���ڂ�������Ă��܂��B����́u�@�،o�v�̂Ȃ��Ɂu�@�،o��������鏊�ɂ͂˂ɂ��̋������^���ł��鎖���ؖ����邽�߂ɁA����@�����ƂƂ��ɂ�����āA�߉ޔ@���𑽕̒��ɏ�����āA����@���Ɣ��ɕ��э�����v�Ƃ��邱�Ƃɂ��ƂÂ��Ă��܂��B�ł�����A����ڂ̏����Ă��鑲���k�͑�������킵�Ă���킯�ł��B�@
���@���l�͑����k�̌��������̂悤�ɂ���������Ă����܂��B�@
�u�����k�̐��ʂɓ얳���@�@�،o�̎������������\���Ȃ����B�k���������Ɩk���͂����k�ɂ����肻�̌����������ς��܂�œ�̊C�ɍs���A��C�̋ꂵ�݂��Ă��鋛���������̌������ċ~����ł���܂��傤�B���A���̕����畗�������A���͂����k�ɂ����肨��ڂ̌����������ς��܂�Ő��̎R�ɍs���A���̎R�ɏZ��ł���l�X�ȓ����������A���̌��������ς��̕��ɂ�����{�������܂ʂ���邱�Ƃł���܂��傤�B�܂��āA�����k�ɂ������������Ă��镧�l�ւ̌����͂͂���m��Ȃ����̂�����A�X�ɉ����Ă��̂����k�ɂӂꍇ������q�����l�����ɂ��A���̌����������������Ƃ��ł���ł���܂��傤�B�v�@
�܂葲���k�͑������Ă�����ƁA�@�،o�̋��������H����������A�S���l�̒ǑP���{�ׂ̈ɂ��Ȃ��邱�ƂɂȂ�̂ł��B�@ |
��������(�ނ���ڂƂ�)
�@
�����ɂ��A�����҂̂��Ȃ����ҁB���{�̖��Ԃł͎��ҕ���K�����{���Ă����⑰������Ƃ݂Ă���B�������q�����₦��Ȃǂ��ĕ��J�҂����Ȃ��ƁA���̉��O�͒m�F�≏�҂�n����M��B������<�O�E���쓃>��z�����J��A�ԕ��ɂƂ߂���A᱗��~�̍ۂɖ����I��������肷��B
�@
�Ƃ���܂��B�����ł͗։�(�������J��Ԃ��A�����̐��E�ł���Z�������肩��������)����̒E�p�A���邽�ߏC�s���邱�Ƃ�����Ă���A�Ƃ�킯��y�@�ɂ����ẮA����ɕ��̏O���~�ς̖{���M���A��爢��ɕ��̖��������āA�����Ɋy��y�ɉ����ł���(�Ɋy�ɉ����ĉ�E����C�s��ςނ��Ƃ��o����)�ƍl�����Ă���킯�ł�����A���O���c���ꂽ�҂ɍЂ����y�ڂ��A�Ƃ����̂͋ɂ߂Ĕ��I�ȁA�ނ�����{�Ɠ��̏K���Ǝv���܂��B�������Ƃ����A���������͂��̓y�n�̐�c�ł���A�J��҂��s�K�ɂ��āA���̎q�����c�����Ƃ��o�����A�₦�Ă��܂������̂ł���܂��B�~�����ɂ��閳�����ɂ��ẮA�y�n�̐�c�ł͂���܂��A�����̎��@�ݗ��ȗ��A���炩�̌`�Ŋւ���Ă���ꂽ�Ƃ̕��X�ł���A�����Ă������Ƃ͂ł��܂���B���Ƃ����āA�����N���Ǘ����邱�Ƃ��Ȃ�������̂܂܂ɂ��Ă����A�����ꕗ���������ʂĂĂ��܂��܂��B
�@
�ȑO�͂����̕���W�߂āu�����ˁv������Ă��܂���(������u�����ς݁v�Ƃ����܂�)�B����ł��傫���A�`�̈قȂ������łƂĂ����R�Ƃ������̂ł͂���܂���ł����B��ɏq�ׂ��Ƃ���A�������܂Ƃ߂ĐV����<������>���������Ē������̂́A���̊�i�҂ɂ�����ẮA�S���̌��m��ʐl�X�ɑ��鋟�{�ł���A��敧���̐����u�����s�v�̊�{�ł���u�Z�g�����v��1�ł���A<�z�{>�ɑ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@
�������ɂ��ď��������������Ē����ƁA�܂����̌`�Ƃ��ẮA�c�`�E�����`�E�O�p�`�E�~�`�E���`��5���琬��u�ܗ֓��v�ƌĂ�܂��B�܂�����g�ɂ��Ă͂ߒ��E�ʁE���E�`�E�G�Ƃ݂Ȃ��ϑz����s�@������܂��B���ꂼ��ɏ�����Ă��鞐���ł���(��)�A�ォ��?(�L��)�E�d(�J)�E��(��)�E?(�o)�E��(�A)�Ɠǂ݂܂��B���ꂼ��̈Ӗ��́A��E���E�E���E�n�ł���A�����̍\���v�f�ł���܂��B�����5���u�ܑ�v�Ƃ����A���ɐ^�������ɂ����Ắu�ܗցv�Ƃ�Ԃ��߁A���̞������L����Ă��铃���u�ܗ֓��v�Ƃ����̂ł��B�܂��u���ꏈ�v�ł����A�g����Ɍo�͋Ɋy��y���܂��肢���N�����Ƃ������߁A����͏�y�̕��E��F�����Ƌ�Ɉ�̏��ŏo����Ƃ��ł��邩��ł���A�Ɛ����Ă���B��̏��Ƃ͏�y�̂��Ƃł���B�h�Ƃ����Ӗ��ł���܂��B
�@
�߉ނ̓��Ō�A��q�B���⍜�����A�������Ăċ��{�����̂��n�܂�Ƃ����Ă��܂��B���̓����C���h�ł̓X�g�D�[�p�Ƃ����A���ꂪ���{��́u�����k�v�ƂȂ�A�O�d�A�d�̓��ƂȂ�܂����B����ɂ��̌`���܂˂āA���k�������悤�ɂȂ�܂����B
�@
�Z�����k�ɂ��Ắu�L���[�N�v�Ƃ����������L����Ă��܂��B����͐^���ŁA�g����ɔ@���h���Ӗ����Ă��܂��B�ߋ��v���̐́A�����݉����̋��������@����F���Ɋy��y�̌������u���A�l�\���̐���𗧂āA����������s�𐬏A���Ĉ���ɕ��ƂȂ�܂����B����ɕ��̐����Ɋy��y�ł́A�@������A���̑厜�̌��ɉ�҂����āA��̋ꂩ�瓦�ꂵ�ނƓ`�����܂��B���k�̗����ɂ́A���́u�o���v�̞������݂��܂��B����͐^���Łg����@���h���Ӗ����Ă��܂��B�F���̐^���E�����i���������{���ŁA�\���̏�����S�̓I�ɕ����A�Ƃ���܂��B�@ |
 �@ �@
������ |


 �@
�@ |
�����ɂ͒ʏ���ׂ�����������܂��B���Ƃ͗ϗ��I�ȖڕW�A���Ƃ͐�����̋K���ł��B�����ɋA�˂���(�o�Ƃ�����A�m���̒�q�ɂȂ�����A���l��M�����肷�邱��)�Ƃ��ɂ͕����̑����̏@�h(���G��y�^�@)�ł͉�����邱�Ƃ���܂��B����������ƌ����܂��B�������܂��Ƃ��̏؋��ɖ��O�����炦�܂��A���ꂪ�����ł��B���������āA�����Ă���Ԃɉ�����������̂��{���̎�|�ł��B��y�^�@�̏ꍇ�ɂ͉����̑���ɖ@�����������܂��B�����̊�{�I�ȉ���5����܂��B1�D�s�E����(�E���Ȃ�)2�D�s������(���܂Ȃ�)3�D�s����(����Ȃ��Ƃ����Ȃ�)4�D�s�ό��(�R�����Ȃ�)5�D�s������(�������܂Ȃ�)��X�̓��퐶�����l���Ă݂܂��Ƃ����̉��������Ɏ�邱�Ƃ͋ɂ߂č���Ȃ��Ƃł��傤�B���Ƃ͔����̂Ȃ��ϗ��K��ł�����A���Ȃ��Ƃ���Ɉӎ�����낤�Ƃ���p�������������邱�Ƃ��d�v�ł��B���͉����ӎ�����Ɏ�낤�Ƃ���p�������������܂��ƕ��l�Ɩ����ے��Ƃ��ĉ���������̂ł��B�h�M�k�̐l�X�ɐ��O�ɉ����������Ȃ��̂͑m���̑Ӗ��ł��B���Ȃ��Ƃ����̂悤�Ȃ��Ƃ�h�M�k�ɒm�点��K�v������܂��B���������܂��āA���͒h�M�k�̕��X����������Ƃ������̂��������������Ƃ͗L��܂���B���O�̐M�S�Ɋ�Â����O�Ɏ������Ȃ������������A����͕��l�̒�q�ɂȂ�킯�ł�����i��ʼn����������邱�Ƃɂ��Ă���܂��B�Ƃ���ŁA���O�̐M�S�����f�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ͂ǂ�������ǂ��ł��傤���B�ŋ߂͐l���������������A����܂őS�����̂Ȃ������l���Ɋy��y�ɂ����肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ���������܂��B���̂悤�ȏꍇ�ɁA�ЂƂ̔��f�ޗ��ɂȂ�̂����̎��_�ŕ\�������M�̂�����(�z�{)�ł���܂��B���̂悤�Ȏ���ɂ���ĉ������Ƃ������̂��蒅���Ă��܂����悤�ł��B�o����Ȃ���̎������łȂ��A�ߏ��̂�������ɂ����b�ɂȂ��Ă����̂��ǂ��Ǝv���܂��B�@
���@�h�ɂ���ĉ����̂����͂������̂ł����H�܂��A�����ŏ@�h���킩��܂����H�@
�����̉����͊T�ˈȉ��̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B�@
�w�w�M�m�x�x�w�w�M�m�y�y�@�x�x�w�w���m�@
�w�w�������A�x�x���A�y�y���@���A���m��M�m���ʍ��ƌĂт܂��B���q����ȑO���炠���������ł͂��ꂪ��{�ł���܂����A���q����ɋN�����@���v��(�H)�ȍ~�̕����ł͂��ꂼ��������o���悤�ɂȂ��Ă��܂����B���ʂ��猩��ƈȉ��̓������L��܂��B�@
����y�@�ł͗_��������y�y�Ƃx�x�Ƃ̊ԁA���邢�͂x�x�̑���ɂv�_�Ƃ����������邱�Ƃ������B�@
����y�^�@�͉��������̂ʼn������Ȃ��B�����Ŏ߂w�w�Ƃ����@�����g���B�@
�����@�@�ł͓��@�ɂ��Ȃ�œ�����������A�ʏ�͂w�w���M�m�̂悤�ɂȂ��Ă���B�@
���V��@�A�^���@�A�T�@���͊�{�`�����̂܂g�p���Ă��܂��B�@
�Ӗ���\���グ��A�@���͌����������܂��B�y�y�@�A�y�y�@�a�A�y�y���A�y�y�����ł������݂ł͂y�y�@����ʓI�ł��B�����͌����ɂ�����n�ʁA���Z�A���i����������2�����ł��B�����͐�����̖��O�ɂȂ�A����2�����ł��B�ʍ��͕����ɑ���A�ːS�̃X�e�[�W(�i�K)�������܂��B�A�ːS�������ꍇ�ɋ��m(�j)�E��o(��)�A��ʂ̐M�҂͐M�m�E�M���A�q���̏ꍇ���q�E�����A�c���̏ꍇ�c���E�c���A���܂�ĊԂ��Ȃ��ꍇ�d�q�A���܂�Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ͐��q�ɂȂ�܂��B�@
�����҂̏@�h���킩��Ȃ��ꍇ�͉����͂ǂ�����悢�̂ł��傤���H�@
�S���Ȃ������̕���K���ǂ����ɗL��͂��ł��B�V���тŕ���S���ꍇ�ɂ́A�S���Ȃ��������M���Ă����@�h���ǂ��ł��傤�B���������Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Ȃ������g���ǂ��Ǝv���@�h(���@)�ʼn����������Ă��炤�̂��ǂ��Ǝv���܂��B�@ |
 �@ �@
���e�@�h�̑��V |


 �@
�@ |
|
�������V�̏ꍇ�A��Ԓ��S�ɂȂ�͎̂��҂Ǝ��҂����ɓ����@�h�̂��{���ł���B���������V�ł͂ǂ����Ă����҂ɏœ_�������̂ŁA�V���̍\���������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�����������Ӗ��ō���͖{���𒆐S�Ƃ������V�����Ă������Ƃɂ���B�����@�h�̖{���݂�ƁA���̕ҏW���ʂ͑���A�V��@�A�^���@�A��y�@�A��y�^�@�A�T�@(�����@)�A���@�@�̏��Ɏ��グ���Ă���B�����ł��@�h�����܂ꂽ���Ɏ��グ��B�V��@��806�N(�Ő�39��)�A�^���@��823�N(��C49��)�B���ꂼ�ꕽ�����J�s(794)�̂��Ƃɒa�������B���Ɋ��q����ɂ͂����āA1175�N�ɏ�y�@���@�R(42��)�ɂ���ĊJ���ꂽ�B���ɐe�a����y�^�@���J�������A�u���s�M�v�����̂�1225�N��(52��)�Ƃ���Ă���B�T�@�̈�̑����@�͓�����������A���ė���1227�N(27��)����n�܂�B�{�R�ł���i���������Ă�ꂽ�̂͂���16�N��ł���B���@���J�@��錾�����̂�1253�N(31��)�ŁA���̔N������54�Ŏ��S�B�e�a��80�ōX��10�N������B�@�R�A�e�a�A�����A���@�̂�������V��@�̔�b�R�ŏC�Ƃ����Ă���B���@���@�͓��@�̍������(1246-1333)��h�c�Ƃ��A1911�N(�吳���N)���@���@�ƌ��̂���B�Ȃ��ՍϏ@��1191�N�`�����Ă���B�@ |
���V��@�̑��V�@
�V��@�͓`����t�Ő�(767-822)���@�c�ŁA���̑����ɂ͎O��̋V��������B�w�@�،o�v��ǂ݁A�������A�߂�ł��P�������́B�u����Ɍo�v��ǂ݁A�Ɋy�����ɓ������́B�����Č����^���ɂ���č߂�ł�����̂ł���B����̏ꍇ�ɂ��̐l�̐��E�֓���������@���s�Ȃ���B�@
(��)�u����Ɍo�v�𒆐S�Ƃ���������@�@
����́A�@
��A��x����A�u�o���O�A�������l�A�s�܁A�O�����@�̌܂���Ȃ�B�@
�k��x�l�Ƃ͔����蓾�x���邱�ƂŁA�o�Ƃ�����ɔ�����A�m�ɕK�v�ȉ������邱�Ƃ��Ӗ�����B������̂͐����̋���������A�܂����̏@���Ƌ�ʂ��邽�߂ł���B�@
�k�u�o�l�ł́A�u����Ɍo�v�������A���̌����ɂ���Č��Ɏ��邱�Ƃ��F�肷��B�@
�k�������l�Ƃ͎��҂ɖ@���^���āA���ς̐��E�ɍs�����Ƃ������@�����Ƃł���B�@
�k�s�l�͎��҂������̋Ɋy��y�Ɍ����Đi��ōs���ے��ł���B�@
�Ō�́k�O���l�Ƃ͐S�����肵�����n�ɓ��邱�Ƃ��������A�@�،o�������ĎO���ɂȂ邱�Ƃ������B�@
�V���̍\�����A�ڍs�A���̂ɂ���Đ�������w�҂����邪�A���̐}�����g���ƒ�x���́A��������̕����ƌ������ƂɂȂ�B����u�o����l�̍s��܂ł͐������琼����y�ւ̈ڍs�ߒ��ƂȂ�A�O�����͖@�،o�O���ɂ�鐹�Ȃ鐢�E�Ƃ̍��̂ł���B�@
���Ă��̃v���Z�X���ׂ������Ă����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B�@
��A��x���ł͔�����d�������A���̎��u���e��v(�������e�����̂Ă��)��������B�u���]�O�E���A�����s�\�f�A���������ׁA�^���ҁv(�~�E�A�F�E�A���F�E�ɐ��܂ꂽ�҂́A������҂Ƃ̕ʂ�̏�͒f���������B�^���̓��ɓ���A�^�̉��ɕ�)�B���ɜ��������O�A����������B�O�A���Ƃ͕��E�@�E�m�̎O�ɋA�˂��邱�Ƃł���B�����āu�O����������A�����̈ʂɓ���B�ʂ͑�o�Ɠ����イ���A���ꏔ���̎q�Ȃ�v�Ə�����B�@
��A�u�o(�����傤)���́A�n�߂ɕ��E�@�E�m�̎O��ɗ�����A�\������������A�@
�u�cূɐV�~��(����)�������ɐs���ė��ፚ�ɕ��ꑧ�����Đ�ĘI���ڗ�B�ߍƐ��ҕK�ŔV�|�B�ɍƉ�Ғ藣�̗��B�@�����B���������V�߂Ēv�����}���ڂ̐�����߂܂�ɂ́B�c�v�@
(�����Ɂk�����l���̉����s���A�I�̖��͂ɂ킩�ɗ������B�߂������Ȑ��ҕK�ł̝|�B�ɂ܂������ȍ����҂͏�ɕʂ�闝���B�얳����ɕ��̖�����O���A���}�̐�����M���A���₩�ɂ��̓y�n�𗣂�āA���Ɏ���B)�@
�O�A���̂��Ǝ��҂̂��߂Ɂu�����v�Ɓu����Ɍo�v�������A������s�Ȃ��B����́A������A�܂�������t�ɂ���Ə����A�@�����c��������؏O���ɐU������邱�Ƃ������B�����ł́A�u��ɏC�߂�������(����)��ʂɉ�����B�v�Ƃ���悤�ɁA����͎��҂Ɍ�������B�܂��Ō�ɂ́u���̌�������؏O���̌��̂��߂ɕ����Ɍ������A���y���ɉ������܂��悤�Ɂv�ƌ��ԁB�@
�l�A���Ɏ��҂����̐��ɓ������������s�Ȃ���B�����ł͊ۂ���~���������Ď��̉��x������������B�@
�uূɐV�~��(����)����̕������ĕږّR����B��Ƃ̎������������f�₷�B�j�āB�A���ᒩ�ɕ��腉��ݍ��V�ߋƂ�₢�A�I�̗[�ɏ����A�Ǎ����Ԃ̋�Y�ɋ����B�R���嫂����{�̉���͖{��L�����Ďl�d�܋t�̗ނ��̂ċʂ킸�B�c�ω������͎�𐂂�ē����܁X�̐��O�͊y��t���Č}���ʂ��B�肤���͗H�V������i�̘@��ɓo��A���₩�ɐS���̌d�����P�����Ƃ��B�c�얳����ɕ��A�얳����ɕ��v�@
(������(����)����̕��������A�ڂ�����Ē��ق���B��߂̋Ƃ̎��ɂ���Ēg���������r�₦���B���������腖����͐��X�̍ߋƂ�₢�A�͂��Ȃ������[�ׂɏ�����A�ǓƂ̍��͐₦�Ԃ̂Ȃ���Y�ɋ����B�������Ȃ���Ɋy��y�̎�͏O�����~���肢���L���A�ǂ�ȍߐl�����̂Ă邱�Ƃ͂Ȃ��B���ߐ[���A��x�ł��O�����������҂͌��̂ĂȂ��B�c�ω��Ɛ�����F�͎�������ē����A����q�͉��y��t���Ă��}���ɗ���B���҂̊肢�͑����@�̑�ɓo��A���₩�ɐS�̒q�b�̌����P�����Ƃ��B�얳����ɕ��A�얳����ɕ�)�B�@
�������Ď��҂͔ފ݂ւƓ������B�@
(��)������������@�@
�������Ƃ͌����^����O�u(�˂�)���đ���@�������{���A����@���̎��߂̌������O���̒��ɒ������悤�Ɋ肤���̂ł���B�����^����ՏI��@�ɗp������͌Â��A�u�����v�W�v�������M(982-1017)�́A�O���ɂ���ċɊy�������ʂ����Ƃ���25�l����Ȃ錋�Ђ�g�D���āA�����ԋ߂ɂЂ��������Ј��������Ɏ��e���A�F�ŏW�܂��ĔO�����������B�܂����S�������Ƃ��A�����^���ʼn��������y����̂ɂ����n���ɍs���Ȃ��悤�ɓ����������̂ł���B�@ |
�������̎d��
��i�����ɂ��{���̈���ɔ@�����A�������ĉE�ɂ͍��c�E�V���t�A���ɂ͏@�c�E�`����t�̊G�����|�����܂��B�{���̑O�ɂ͒����킪�������܂��B���i�ɂ͒����ɍ��F�A���̗��e�ɂ낤�������ĂȂǂ������܂��B���E�Ɉʔv���܂�܂��B���i�ɂ͒����ɉߋ����A�싟�V�A���E�ɉԗ�������܂��B�o���ɂ͍��F�A��A���������A����Ȃǂ�u���܂��B
�����{�̐S��
���̋߂ɂ͕��т������A�낤�������Ƃ����A������1�{��3�{���Ă܂��B����
(1)�O�� / (2)�� / (3)�\�� / (4)���� / (5)���� / (6)�J�o�� / (7)�@�،o�u���ʕi�v�Ȃ� / (8)�h�� / (9)���� / (10)�O�� / (11)��������u�o���܂��B
���V��@���@�̑����`��
���d�̑����͎��@�̓����̑����`���ɑΉ�����Ƃ����܂����A�ʂ����Ă����Ȃ̂����m�F���Ă݂����Ǝv���܂��B�܂����d�̔z�u�̗��R�₨�����̓��e�����ꂪ��{�ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�W���I�ȓ����̔z�u�́A�������ʂɐ{��h��u���A�{�����u����Ă��܂��B�O���`���̏ꍇ�A�������ĉE������ŁA�{�����߉ޖ��̏ꍇ�A�E������A�������ӁA�{��������ɔ@���̏ꍇ�͉E���ω��A����������F�Ƃ��܂��B�{���ɂ͒���Œ����������܂��B�����ɂ͐���V�������܂��B���e���ɂ����ꂼ�ꋟ�{���������܂��B��ɂ͐��łȂ��ϐ����������g���������܂��B
�{��d�̑O�����E�ɒޓ��U�������Č������܂��B���O�ɂ͌˒��������܂��B�J���Ƃ������t�͂�����J���邱�Ƃ���o�����̂ł��B
�{��d�̑O�ɂ͑O�����u����A��ɎO�(�������F�A�E�����A���ؕr)�A�܋�̏ꍇ�ɂ͍��F�𒆐S�ɁA���E�ɓ�����A�ؕr��ƂȂ�܂��B�@��̎��ɂ́A���ɑŕ~���|���A�����̊ԂɎO��ɐ������َq�A�ʕ����������܂��B�V��@�͖��������Ă��܂��̂ŁA�O���̑O�ɖ��d���ݒu�����A�����Ă��̏��脉�(����)�A�h���A��顁A���ԁA�����A�ъ��A�`㻁A�݁A�َq�Ȃǂ����E��ŕ��ׂ��܂��B���ɗ�Ղ𒆉��ɍ��ɍ��e���ɂ͍��F�A�����A�o�{���u����A�E�e������(�y��)���u����܂��B�@ |
���^���@�̑��V�@
�^���@�͋�C(774-835)���J�����^�������̋����ŁA���̐g�̂܂ܕ��ɂȂ鑦�g������ڎw���Ă���B�F���̐����ł������@���ɕ�܂�Ă���A���ӕ�F�̏�y�ł���s��(�Ƃ���)�V�Ɏ��҂𑗂邱�Ƃł���B���̉@�œ��肵����C�́A���ӂ��n��ɍ~��Ă��鎞�ɂ͗͂����킹�Đl�X���~�ς���Ƃ����Ă���B�@
�����ł͍���R�^���@�̋V������グ��B�܂���̂�[�����Ă���A���̑O�Ŏ������s�Ȃ���B�^���@�̑��V�̓����́A��(���傤)�̋V���ɂ���Ƃ����Ă���B�͓��ɐ��������������邱�ƂŁA�����ł͕��̈ʂɂ̂ڂ邽�߂̏d�v�ȍ�@�ł���B�@����5�̒q�b���ے����鐅���A��q�̓��ɒ������Ƃɂ���ĕ��̈ʂ��p�����邱�Ƃ��Ӗ�����B���V�̏ꍇ�ɂ͂��̌����������A����ɔϔY��j��@���̌ܒq������킷�܌؋n�œ��ɐG���B�@
�k����l��A�h���@��A�O���ρ@�O�A��S�@�S�@�l�A���������@�܁A�O��@�Z�A�\���@���A�_���@���A���������@��A���������@�\�A��䓁���@�\��A���O�A�O��@�\��A���܉��@�\�O�A���@���@�\�l�A���ՏI�厖�@�\�܁A�O�����}��@�\�Z�A�Z�n������@�\���A�s����@�\���A�s���Z����@�\��A���ӎO���@��\�A������@���A����o��@���A�]�ȏ�B�@
���̍\���͂܂�����̐��߂���n�܂�B���ɕ��l�������Đڑ҂��A�����ĕ��l�̗͂��^���A���肢����Ƃ����v���Z�X�����B�܂��̂ɍ��𒅂��Đ��߁A�k�O���ρl�ŋƂ̌����ł���g�́E���E�ӎ��̎O���C���[�W�Ő��߂�B���������͍����Ŏ���𐴂ߕ���F�����}������B�@
�k�O��l�͕��@�m�ɋA�˂��A�k�\���l�ł͕����^���A���ꂩ��s�Ȃ��V���̐��A���F��B���肢������e�́A�u�����̐���앂���y�̉������ɐs���āA�s����y�̑����������B����č��^�������̋����ɔC���đ������̋V�����A�O�������̖@���🭂ŁA�V���ɐ��쓾�E�̈��ۂ��F��B�v(�����A����͓�ɂ��鍑�y�ł̈������s���āA��y�ɐ���������ƂȂ����B����č��^�������̋����ɔC���āA�����̎��̋V�����A�O�������̖@�����������ŁA���炽�ɐ��삪�ꂵ�݂̐��E����J������ēs����y�Ɏ�����邱�Ƃ��F��)�B�@
�k�_���l(����Ԃ�)�Ƃ͐_�X�̐g���A�͂Ƃ������ƂŁA���X�̕����������Ė@�y������邱�ƁB�u���������S�����̑����̒�́A�Ɋy�։��������ł��邩��A腖��@���y�ьܓ��̖��y�̊��������~�Ղ��Ă��Ă���B�]���Ă���疻�y�̊��������A�Ȃ�тɋƂ𗣂ꓹ�邽�߂ɔʎ�S�o�������A���̂��ƓV�㐢�E�ɉ������邽�߂ɂ����̎�Ɏ҂ł���@���A��F�̖��O�������č~�Ղ����ӂ��A���҂̐������肤�v�B�@
�k���������l�����Ƃ͕��������̂��ƂŁA�u�얳�A�A������A������A��������A�����Ɋy�v�Ə�����������B�@
�k�����l�Ƃ͓���ɕ���F���}���A�@�y���������́B�@
���́k��䓁���l�͎��҂�䔯���邱�ƁB���̒䔯�͕����F�̑O�ōs�Ȃ���B�@
�k���O�A�O��l�͕��@�m�ɋA�˂��A�k���܉��l�ł͎E���A���݁A�����A�ό�A�����̌܂����Ȃ����Ƃ𐾂��B���Ɏ��҂ɖ@���������A�k���ՏI�厖�l�ʼnF�����������Ƃ��瑶�݂��Ă������Ƃ�����킷�u���v������������B�@
�k�O�����}��l�ŎO���𗈌}���A�k�Z�n������A�s����A�s���Z����A���ӎO���l�Œn���̋ꂵ�݂��A�k������l�Ő^�������̖ڎw�����g�������ے������A�k����o��l�Łu����o�v����u���A�k�]�l�ŕ����^���Ċ��O��@���I������B�@
������ʂ��čs�Ȃ���50�������邽�߁A��-��A�\��-�����ȗ�����40���ɏȗ�������A����ɒZ���ȗ����邱�Ƃ�����B������ɂ��Ă����̋V���ő�Ȃ��Ƃ́A���������������F�Ɍܑ������Ē��d�ɂ��ĂȂ����Ƃł���B�@ |
�������̎d��
(����R�^���@)��i�����ɂ��{���̑���@�����A�������ĉE���ɏ@�c�̍O�@��t���A���ɂ͑���@���̉��g�ł���s�������̉摜���܂�܂��B�{���̑O�ɒ�����A���ъ�������܂��B���i�̒����ɉߋ����A���E�Ɉʔv���܂�܂����A�^���@�̂�(�C���h�̗�@�ɂȂ����)�������č��ɌÂ��c��̈ʔv���A�E�ɐV�����c��̈ʔv���܂�܂��B���i�ɂ͑O����u���ē��~��~���A���F�𒆐S�ɁA�낤�����A�ԗ��Ȃǂ�����܂��B���d��O�ɂ͌o����u���A���F�A�낤�������āA�ԗ��āA��Ȃǂ�u���܂��B�Ȃ��^���@�͕��h�������A���ꂼ��܂�������l�ł��̂ŁA�ׂ������Ƃ͕�ɂ����˂邱�Ƃ���ł��B
�����{�̐S��
���̋߂ɂ͕��т������A�낤�������Ƃ����A������3�{���Ă܂��B����ł�����
(1)������q / (2)���� / (3)�O�A / (4)�O�� / (5)�\�P�� / (6)�����S / (7)�O�Ė�� / (8)�J�o�� / (9)�ʎ�S�o / (10)�{���^�� / (11)�\�O���^�� / (12)�����^�� / (13)�� / (14)�F�蕶 / (15)����ŏI���܂��B�@ |
����y�@�̑��V�@
�@�R��l��1212�N�A���k�ʐ����āu�����ՏƏ\�����E�A�O���O���ێ�s�́v�̌o��������80�Ŏ��������B��y�@�̑��V�Ƃ́A�@�v�ōs�Ȃ��鏘���A���@���A���ʕ��Ɏ����ƈ�����������������́B�@
�u�����v�ł͕��O�ō����ĕ������{���A�����ŕ��@�m�̎O��Ɍh�炷��B�����Ď���ɕ���F�̗��Ղ��肢�A���U�炵�ĕ������{����B�����ĕ��̑O�Ɉ�̍߂�������A���̉�����F��܂ł������ɂ�����B�@
���Ɂu���@���v�͎��҂̒�q�ɂ���u������v���s�Ȃ��B�����œ��t�͍����ɓo��o�������A���̌�����q�ɂȂ������҂ɉ������̂ł���B���́u���ʕ��v�́A�@�v���I����ɂ�����A���̉���ɂ���Ė@�v���C���邱�Ƃ��ł������ƂɊ��ӂ��A�����������肷��̂ł���B�@
�u���o�v�ł͗��}�������Ղ肵�A��ɐ����A�߉ޔ@���A�\���@���̎O�������}������B���ɜ�������������B�@
��x��@�ł́A�u��v���O�x�����Ȃ���䓁�̌`���������̂����҂̓��ɂ��Ă�B���ɎO�A�O��Ɖ�����������B�@
���ɊJ�o�����u�o�֑����B�����́u���ʎ��o�v�̂Ȃ��́u�l����v���A�u�ϖ��ʎ��o�v�̂Ȃ��́u�^�g�ϕ��v���ǂ܂��B�@
�k���蕶�l�ł́u��킭�͒�q�����I�̎��ɗՂ�ŁA�S�]�|�����A�S���������A�S���O�����S�g�ɂ������̋�ɂȂ��A���y�ɂ��đT��ɓ��邪���Ƃ��A���O��O�����܂��A���̖{��ɏ悶�Ĉ���ɕ����ɏ�i���������܂��B�ނ̍��Ɏ����Ă̂��A�Z�_���͂ď\���E�ɓ����̏O�����~�ۂ���B�v�ȂǂƏq�ׂ�B�@
�k�[�����l�ł́A�u����(���傤)���{�Ɋy�E�A���ؕ�o�ʁv��3��ǂށB�@
�ʖ�̍���(����)�͓��ɒ�܂��Ă��Ȃ����A�O������Ƃ���B�@
(���V)��A��꜓�A���x�O�A�R���O�u�l�A������@
���V�͓����A�O���A������ɑ����č��(������)���s�Ȃ���B��꜂͊�������V���ŁA���̍�@�͊��ɐi�݁A�č����Ďߍ��ɎO���ނ��A���[(��q)�ň�~����`���A���̕���������B�@
�u�͊J���H�L�̐F�A�g�͌f�������̉��B��������N꜂̈��B�Ǐ������A�ʒB�P���v(�͒������F�ŊJ���A�g�͎����̉��B�Ȃ����N꜂̈��B������������A�P���ʂ�)�B�����Ċ����N�����đ���֍s�����߂̕�����������B�@
���x(����)�͈����̂��ƂŁA���t�͊��̑O�ɐi�ݏč����Ă���A2�{�̏��������A���̂���1�{���̂Ă�B����͉��ꂽ�n��𗣂��Ƃ����Ӗ��ł���B����1�{�̏����ň�~�������ĉ��x�̘���q�ׂ�B��̍Ō�ɂ��S�ʂ̎����q�ׂāA�u�얳����ɕ��v�̔O����10����B�@
�Ō�̉���̂��Ƃɂ��\�O�������A�����ė��Ղ����������Ƃ̓V��ɑ����������B���̋V���ł͎��҂𐼕���y�ɑ���͂���̂����ƂȂ��Ă���B�@ |
�������̎d��
��i�����ɂ��{���̈���ɔ@���A�e���Ɍ������ĉE���ϐ�����F�A�������č���������F�B����ɍ��c�P����t(�E)�@�c�~����t(��)�̑�(�|����)�����u���邱�Ƃ�����܂��B�ʔv�͏�i�̍��E�ł��B���i�ɂ͑O����u���A�����Ɏl�p�����~��~���A�܋(�����ɍ��F�A���E�ɂ낤�������āA�ԗ��Ă������)���͎O�����ׂ܂��B���̉������ɂ͗싟�V���u����A���E�ɂ͐��Ԃ��������܂��B�o���ɂ͍��F�A���������A��Ȃǂ��u����܂��B
�����{�̐S��
���̋߂ɂ͕��т������A�낤�������Ƃ����A�����𗧂Ă܂��B����
(1)���� / (2)�O��� / (3)�O�� / (4)������ / (5)�J�o�� / (6)���ʎ��o�̂Ȃ��̎l���� / (7)����� / (8)�ꖇ�N���� / (9)�ۉv�� / (10)�O����� / (11)������� / (12)����� / (13)�O�g�� / (14)������B
����y�@���@�̑���
�{�����ʂɐ{��d���u����A����ɂ��̒����ɋ{�a���ނ����Ă��܂��B�{���̖{���͈���ɕ����قƂ�ǂŁA����Ɉꕧ�̏ꍇ�ƁA����ɎO���`���̏ꍇ������܂��B�{��d�̏�̏���ɂ͖{���ɋ�����ꂽ������ƁA�����A��O�ɍ��F�𒆐S�Ƃ����܋���������A���̎�O�̑�O���ɂ����������F�𒆐S�Ƃ����܋���������Ă���̂��킩��܂��B���������z�u�̃~�j�`���A�ł��ƒ�̕��d�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B
�@ |
����y�^�@�̑��V�@
��y�^�@�͎�������ɘ@�@��l�ɂ���đ傫�����W�����B��l��1499�N�̓��łɐ旧���āA���V��@���ׂ����⌾����A���̓��e������Ȍ�̑��V�̍�@�̊�b�ɂȂ��Ă���B��y�^�@�͉������Ƃ������҂ɑ��A���O�̓����ÂсA�S������s�����̂ł���B�]���Ď��҂̉�E���͂��������@��ǑP����̍�@�͑��݂��Ȃ��̂����O�ł���B�@
���o�͂܂����҂ɖ@���������A���ꂩ��u�A�����ʎ��@���v�Ŏn�܂�u���M��v�Ȃǂ�������B�u���M��v�́u���s�M�v�̍s���ɂ���7��120�傩��Ȃ�ł���B�@
(���V)��A�搿����ɓ�A�O�x��O�A�H�O���l�A�\���܁A���M��Z�A����@
���V���n�܂�ƁA���炵�Ĉ���ɂ̗��Ղ��肢�A���O��A�O���A����A����Ƒ����B���ɎO�x(����)�̗���������Ƒł��o���A�H�n�O��(�얳����ɕ�)���r������B�u�\���v�̓��e���͎��̂悤�ɒ�߂��Ă���B�u�v���ɖ���̗��͎���I�������߂��A�V���̂ւ��Ă��邱�ƂȂ��B������ɉ������J�A���悢��f���������ʗ��̏�A�܂����肪�����B����ɔ@���͂�����ϔY����(�����傤)�̉䓙�����݂��܂��A�����̔ߊ�𗧂Ă������B�܂��Ƃɂ��̖{��̗͂ɂ�炴������ł��o�������̓�������c�v�������āu�\���v���I���ƁA�u���M��v�A�u�얳����ɕ��v�̔O���\�ՁA�a�]�A����Ƃ����悤�ɐi�߂���B���̂悤�ɏ�y�^�@�͑��̏@�h�ƈႤ�_�́A�������Ȃ����ƁB�������Ȃ����Ƃ��グ����B�@ |
���^�@��J�h
�������̎d��
���d�̌`��������y�^�@�ł��A��J�h�ł͋{�a�ɂ����������Ă��ē�d�����̂悤�Ɍ�����̂ɑ��A�{�莛�h�ł́A�{�a�ɂ����������܂���B
���ď�i�����ɂ��{���̈���ɔ@���̉摜���f���A�E�e�ɏ\�������A���e�ɋ㎚�������|���܂��B��i�ɑO�����E�ɉؕr(���т傤)��A�����ɉΎɍ��F�A���̑O�ɍ��(������)������܂��B���̉ؕr�ɂ͞�(������)��������̂������ł��B���i�ɂ͑O���u���A��̏�ɁA�܋�̏ꍇ(�����ɓy���F�A�����ĒߋT�̐C��A�ԕr���ꂼ��������܂��B�O��̏ꍇ�������č����ԕr�A�E�ɐC�������܂��B�܂��C��̒ߋT�̕����͏�ɕ��d�̒��S�Ɍ������Ă��܂��B�ߋ����͌������č��ł��B���~�͖@���ȊO�A����ɂ͗p���܂���B�s�p�̔��i�Ƃ��āA��(���)���ꂩ��u���M��v�u�O���a�]�v�u�䕶�ܒ��ꕔ�v���K�v�ł��B
�����{�̐S��
���d�̑O�ɍ��蓔�����Ƃ����A�낤�����A�����̏��ɉ����܂��B�����͍��F�̑傫���ɍ��킹�Đ܂�A1�E2�{���ɉ̂����������ɂ��ĊD�̏�ɒu���܂��B
(1)�u���M��v����u / (2)�u�O���a�]�v�������܂� / (3)�u������v�������܂� / (4)�u�䕶�v
�N���@�v�̑����́A���~�͑O��A���Ȃǂ݂Ȋ|���܂��B�F�͍g�A���A����������ł��悢�Ƃ���Ă��܂��B�낤�����͈���������X�ɂ��܂��B�ˌ������̂낤�����͔��ł悢�悤�ł��B�@ |
����y�^�@�{�莛�h
�������̎d��
��i�����ɂ��{���̈���ɔ@���̉摜���f���A�E�e�ɏ\�������A���e�ɋ㎚�������|���܂��B�܂��͐e�a���l(�E)�@�@���l(��)�������邱�Ƃ�����܂��B��i�ɏ���u���A�����ɂ낤�������āA�O�ɉΎɍ��F�A���̍��E�ɕ��ъ�A�ؕr�e�������܂��B���̉ؕr�ɂ͞�(������)�������܂��B���i�̑O��ɂ͍��F�ƈ�̂낤��������(�ߋT�̃f�U�C���ł͂���܂���)�A�ԕr�̌܋������܂��B���i�E�ɉߋ��������u���܂��B�o��(�a�]��)�̏�ɂ͐��M��A�a�]����a�]���ɓ���Ēu���܂��B�ߋ����͔N��@�v��S���l�̖����ɂ�������̂ݗp���A���i�͈����o���̂Ȃ��ɂ��܂��Ă����܂��B
�����{�̐S��
���߂�
(1)�u���M��v����u / (2)�u�a�]�v�Z��������܂� / (3)�u�䕶�́v / (4)�u�̉v�����a���܂��B
�@ |
|
���ՍϏ@
|
�������̎d��
��i�����ɂ��{���̎߉ރ��A�e�|�Ƃ��Č������ĉE�ɑT�@�̊J�c�̒B����t�A���Ɋϐ�����F���܂�܂��B�܂��������ĉE�ɎO�����̉摜���܂邱�Ƃ�����܂��B������Ɨ싟�V��{���ɋ����܂��B���i�ɂ͐�c�̈ʔv���܂�܂��B�����ɉߋ����A���E�Ɉʔv�ł��B���i�ɂ͑O����u���A�܋(���F�𒆉��ɂ낤�����A������e���)����܂��B���d��O�ɂ͌o����u���A���F�A��Ȃǂ�u���܂��B�ՍϏ@�ɂ͑����̕��h������܂��̂ŁA��̏Z�E�ɑ��k�����̂��m���ł��B
�����{�̐S��
���d�̑O�ɍ��蓔�����Ƃ����A�낤�����A�����̏��ɉ����܂��B������2�{�ȏ㗧�Ă܂��B���ꂩ����3�x�炵�č����A�njo�ɓ���܂��B
(1)�u�ʎ�S�o�v����u / (2)�u���Ў�v��3�� / (3)�u�{������v / (4)�u���@�@�،o����i��v / (5)�u��c����v / (6)�u�l�O���蕶�v��3��B
�č��̏ꍇ�A��1��ŁA���ɂ��������������Ƃ͂��܂���B���̐}�͗싟�V�̂Ȃ�ׂ����ŁA�����Ȃǂ̓��ʂȓ��ɋ����܂��B�@ |
�������@�̑��V�@
�T�@�̈�@�h�ł��鑂���@�́A����(1200-1253)���@�c�ł���B���{�@�T�͓����́u���@�ᑠ�v�ł��邪�A�����ɂȂ��āu���@�ᑠ�v���݉Ɨp�ɂ܂Ƃ߂��u�C�؋`�v���ҏW���ꂽ�B���s�̍݉Ƒ��@�͏@�̎���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�u�T�����K(����˂�)�v(1103)�����q����ɓ��{�ɓ`���e�������������B���{�ł͒����̂悤�ɑ��V�͔h��łȂ��������A��������łȂ���ΔF�߂��Ȃ������B�������z���A�����A�ʔv�A�r�J�A����A��V�A�Z���K�Ȃǂ͒����̕��K�������ꂽ���̂ł���B�܂��T�@�̑��V�͊y���炵�ē��₩�Ȃ̂������ł���B�@
�k����l���o�A�䔯�A�����B(���V)��A���慌o��A���O�u�O�A��꜔O�u�l�A�����@��܁A�R���O�u�Z�A�������A����慌o�B�@
���o�́u�⋳�o(�䂢���傤���傤)�v�܂��́u�ɗ��當(�����炢����)�v���O�ԓǂ�ʼn������B�u�⋳�o�v�͎ߑ������łɂ������Ē�q�����ɍŌ�̐��@���������̏�i������Ă���A�T�@�ł͏d���Ă���B�u�ɗ��當�v�͎߉ނ̈⍜���q���邨�o�ŁA�Α���ł��ǂ܂��B�����ɏ�����Ă���̂́A�@
�u��S����A�����~���A�߉ޔ@���A�^�g�ɗ��A�{�n�@�g�A�@�E���k�A�䓙��h�A�ȉ䌻�g�A�������A�������́A��暕��A�ȕ��_�́A���v�O���A�����S�A�C��F�s�c�v�@
(��S�ɒ��炵���Ă܂�B�߉ޔ@���̎ɗ��͌��X�͖@�g�A�@�E�̓��k�ł���B��g�������ē��������A���̉����̌̂ɉ�������B��킭�ΐ_���̗͂������ďO���𗘉v���A���S���A��F�s���C�߂�)�Ƃ������e�ł���B���ɉ����������B���̒��g�́u���A�ԁA���C�A���������A�ɗ��當����u���A�W�ނ�Ƃ���̌����́A�V�S����(�V�������҂̗�)�ɉ�����B��肤�Ƃ���͎l�剏�ӂ̎����ŕ�n(���҂̕����E)�𑑌����Ƃ��B�v�@
�k�䔯�l�ł͓��t�͊��̑O�ō��������A�������Ę��������B�@
�u�䏜颔��A����O���A�i���ϔY�A�����Łv(�܂��Ɋ�킭�́A�O���ƂƂ��ɔϔY�𗣂�āA�ϔY��ł��������Ƃ��v�B�@
�k�����l�͜������������A���Ɏ��O�A�����s�Ȃ��B���̂��Ɠ��t�͗p�ӂ������������ɌO���āu�O����������A�����̈ʂɓ���B�ʂ͑�o�Ɠ����イ���A���ꏔ���̎q�Ȃ�v�ƎO������B�ȏ�A�䔯�E�������Ď��҂��҂ɂ��Ă���A���`�̑��V���n�܂�B�@
��A���慌o(�ɂイ����ӂ���)�͊��ɔ[�߂�V���ŁA���ۂ͂��łɔ[������Ă���B�܂��ɗ���������A���ɉ������������A�u�㗈慌o��������́A(����)�ɉ�����B��킭�́A�����̎����ŕ�n(��y)�𑑌����Ƃ��B�v�@
��A���O�u�B�����đ��͑O���̖�ɍs�Ȃ�ꂽ���A���͓��慌o�ɑ����Ă�ށB���̈Ӗ��́A�u(����)�����āA�������łɐs���đ喽�ɂ킩�ɗ��B���s�̖���Ȃ邱�Ƃ𗹂��Ď�ł��ȂĊy�ƂȂ��B���₤�₵�����O�̐��O�𐿂��āA����ŏ����̍���(�̑�Ȗ�)���u���B�W�ނ鏊�̍������S�H�𑑌����B�v�Ƃ����ď\�̕��̖��O��ǂݏグ�A���Ɂu�ɗ��當�v��ǂݏグ��B�@
�O�A��꜔O�u(������˂�)�́A�����N�����đ���ɕ����O�̋V��ł��邪�A�Ō�̎R���O�u�܂Ŏ���Ȃǂ̑��V���Œʂ��čs�Ȃ��Ă��܂��B�@
�l�A�����@��ł́A���t���@�x(�����܂�)���E���A�����Ɖ~����`���B���Ɉ����@���������B�ꎚ�ꊅ�ňꋓ�ɕ����E�ɓ��点��Ƃ����B�@
�܁A�R���O�u�̎R���Ƃ͂��Ƃ��Ɠy����̂��Ƃł���B���t�͎��҂Ɂu���łɉ��ɏ]���Ď�ł���B���Ȃ킿�@�ɂ����䶔����B�S�N�����̐g���Ĉ�H���ς̜l�ɓ��炵�ށB���Ő��O��߂�Ŋo��(�삪�o��)���������ĔO���v�B���ɕ��̖��������ĉ������B�@
�T�@�͏�y�𗧂ĂȂ����A������������Ă����V���̉e�����A���ςƂ���y�̌��t�������̌��t�̒��Ɏg���Ă���B�@ |
�������̎d��
��i�����ɂ��{���̎߉ޖ��A�������ĉE�ɓ����T�t�A���ɂ͑��c�E壎R�T�t�̊G�����܂��܂��B���̗��T�t�̂ȂȂߑO�Ɉʔv�����u����܂��B���i�ɂ͌܋(�����ɍ��F�A���E�Ƀ��[�\�N���āA������e���)���u����܂��B���i�͒����ɉߋ����A���F�A���E�ɍ��t�A���ɐ��ԁA�E�Ƀ��[�\�N���Ă��z����܂��B
�����{�̐S��
���̂���
(1)������q / (2)�J�o�� / (3)������ / (4)�O�A��當 / (5)�O���當 / (6)�ʎ�S�o / (7)�{������� / (8)�C�؋` / (9)��S�������� / (10)�l�O���蕶 / (11)������q
�č��ꍇ�A��2��ŁA�ŏ������ɂ������������A���͂��������������ɍ��F�ɓ���܂��B�@ |
�����@�@�̑��V�@
���@�@�̑��V�́u�@�،o�v��M���A�u�얳���@�@�،o�v�̑�ڂ�����҂́A�K����R��y�ɍs�w���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ������@���l�̋��������ǂ���ɂ��ĉc�܂�Ă���B���o�͊����Ɏn�܂��āA�njo�A��������A���������B�[���ɐ旧���Ắu���e��v�������Ē䔯�A�������邪�A����͑T�@�̉e���ł���B�@
(���V)��A�����@��A�����@�O�A�J�o��@�l�A�����E��V�@�܁A�������@�Z�A����@���A����@���A�l���E�O�A�@��A�ޓ��B�@
���V�͓��t����̌�A�����ł͂��܂�B�u�䍟����@���A�\���O��e��(�悤����)���A��g�e���O��O�A���ʐڑ��A����v(���̓���͐_�X�̎�̂悤�ŁA�\�������@�m�Ɏ��ꕧ���O���~�ς̂��߂Ɏp�������n�߂��B���̌䑫�̑O�ɓ��𒅂��ė�q����)�B�O���̌�Ɂk�����l�ł���B�����ŏ�������}���_���́A�߉ށA��F�A���@���F�Ȃǂł���B�njo�́u�@�،o��\���i�v�̒�����u���֕i���v�Ȃǂ���u����B�@
���Ɉ������ł���B����������݂�ƍŏ��ɕ��A��F�̖����グ�A�ނ�Ɏ��̂悤�Ɍ�肩����B�u�܂��ɍ����̓���Ɋ��f�����u���A�����̋V���C���鏊�̈��ʂ���B����͎������l�g���A�������������@�ɂ������P�j�q�Ȃ�B�R���嫂��c��ʋߗ��a���̂������Ƃ���ƂȂ�A���Ō�A���̐���s������嫂��A�c���遛���A���������ʁB�����A�߂����ƁB���ܗ�炪���O�̍s�����l���A�@�������^���ā����ƍ����B����킭�Ώ㗈�����̕��ɏ����A�厜��߂̌��𐂂ꋋ���ė������Ċm���Ɏ���̕�y�ɐێ悵���������܂��Ƃ��������B(�����œ��t�͏��������A�O�x�~����`��)���A�����Ɍ哹�̗v���������B�ނ�Œ����A�悭������v�O����B���ꏔ�@�����̊o�̑O�ɂ��S�̂ɂ��炴����̂Ȃ��B������̂Ăĉ������������B��ݗ�R�̏��̏�͎���ɂ��炴�鏊�Ȃ��B���������Ă������ɂ��s�����B�R��Α����{�o�̐^�s�͑��������̏�Ɍ����A�Փߊo���͒����ɂ��u�o����Ɍ�����c�v���Əq�ׂ�B���̂��Ɓu�얳���@�@�،o�v�̑�ڂ��\����S�Տ�����B�@
���@�@�ł́A���̂悤�ɕ��ɂ��@�،o���Ƃ����Ƃ�����R��y�ɉ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B�@ |
�������̎d��
��i�����ɂ��{���̑��䶗��܂��͎O���A���̑O�ɓ��@���l���J��܂��B�O�́A�������ĉE������@���A�����Ɂu�얳���@�@�،o�v�̑�ځA���Ɏ߉ޔ@���̉摜���܂������̂ł��B�O���܂����ꍇ�ɂ́q�e�|�r�ɑ单�V(�E�r�S�q��_(��)���܂邱�Ƃ�����܂��B�ʔv�͂��{������i�Ⴂ���̏@�c�̍��E�Ɉ��u���܂��B
���i�ɂ͑O����u���A�ŕ~��~���āA�܋(���F�𒆉��ɂ��āA��̂낤�������āA�����)������܂��B���ɉߋ����𒆉��ɒu���A���i�����ɐ������āA���̗����ɉَq��ʕ����悹�鍂�t(������)�A�����č��[�ɐ��ԁA�E�[�ɂ낤�������Ă�����܂��B�܂������̒i�ɗ싟�P�������A���̍��E�ɍ��t��u���A�َq�E�ʕ���������Ղ��������܂��B
���d��O�ɂ͌o����u���A�o�{��u���܂��B�����ĉE���ɖ؏ނ��u����܂��B
�؏ނ͓njo�A����̂Ƃ��ɑł��̂ŁA����20�N���l�Ă��ꂽ���̂ł���B
�����{�̐S��
�����тƂ����������A�낤�����ɉ��Ƃ����A������1�{��3�{(���@�m�̎O��ɋ��{����)�𗧂Ăċ����܂��B�����𗧂Ă�ꍇ�A�}�̂悤�Ȉʒu�ɗ��Ă܂��B�܂��W�̂��鍁�F�̏ꍇ�ɂ͉̂����������ɗ���悤�ɂ��ĐQ�����܂��B
(1)�����A���� / (2)�J�o�� / (3)���@�@�،o���֕i��� / (4)�~�ߏO / (5)���@�@�،o�@�����ʕi��\�Z / (6)����� / (7)�^�z / (8)�u�얳���@�@�،o�v���J��Ԃ������� / (9)�� / (10)��ʉ���� / (11)���� / (12)�u���������_�v�q�� / (13)�u�@���C�s��v�q�� / (14)�u�ϐS�{�����v�q�� / (15)�u���v�q�� / (16)�����@ |
�����@���@�̑��V�@
���@���@�̑��V�͑�Ύ��㐢�@��̓��L��l�ɂ���Ċm�������B���@���@�̑��V�͌̐l�̑��g�������肢�A��{���̈Ќ��ɏƂ炳��ė�R��y�Ɍ�������悤�ɋF�O����B�@
(���V��)��A�m���o�d��A��ڎO���O�A�njo(���֕i�A���ʕi)�@ |
�����d�̗��j
���d�́A���q�̑Ώۂł��邨�߉ޗl�∢��ɕ��Ȃǂ̂��{�������Ղ肷�邱�Ƃ�ړI�ɏ�������A�Â��͔��P����ɂ����̂ڂ�܂��B����686�N�ɓV���V�c�́u�����Ƃ��Ƃɕ��ɂ���蕧���y�ьo��u���A��q���{����v�Əق��o����܂����B
���{�̌���́A�c��M�Ƃ������y�̂Ȃ��ŁA�c��̈ʔv�����u��������Ղ�����̕����d������Ă���悤�ł��B���݁A�m�������d�̑O�œnjo���s���Ă��܂����A���������`���蒅�����̂��A���ɂ���Ă͖����ȍ~�̂��ƂŁA����܂ł͕��d�������Ă��A�~�I�ȂǂɌ������Čo���������肵�Ă��܂����B�]�ˎ���ɕ��y���������̕��d�́A��y�^�@����@�@�̏ꍇ�͖{�����Ղ邽�߂ł���܂������A����ȊO�ł͑����͈ʔv�I�Ƃ��Ďg���Ă����悤�ł��B
�����d�̍\��
���d�̍\���͕��ʏ㒆����3�i�ɂȂ��Ă��܂��B�ŏ�i�ɂ͐{��R���`�ǂ��Ă���{��d(����݂���)������A���̐{��d�̏�ɂ��{�����Ղ��Ԃł���{�a(�����ł�)���L�����Ă��܂��B���̒��ɊG���╧���̂��{�����܂�A���E�̂��e�|�ɂ́A�@�c�Ȃǂ̊G�����|�����܂��B���̐{��d�̏�ɂ͏��(���킶�傭)���u����A���ъ�⒃����Ȃǂ��������܂��B
2�i�ڂ͒����ɑO�삪�u����A���̏�ɎO���܋������܂��B3�i�ڂ͍ʼn��i�ō��F��ԗ��ĂȂǂ�u���܂��B���̑��A���d�̑O�Ɍo����u���A�����Ɍo�{�A�����A���F�Ȃǂ����u���܂��B���d�̑����̎d����A�ʔv�̈ʒu�Ȃǂ́A�@�h��n��ɂ���ėl�X�ł���̂ŁA�����ɏグ�����̂͂����܂ł��Q�l�����Ƒ����A���ۂ͂��̒n��̏@�h�̎��@�ɂ������肤���Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B�@ |
 �@ �@
���n���̑��� 1 |


 �@
�@ |
���k�C��
�ʖ�E���V�Ƃ������ق��V��𗘗p����ꍇ�������B�ʖ�ɂ͒���q���ϋɓI�ɎQ�����A�ʖ邪�I���ƁA�ʖ�Ԃ�܂����p�ӂ����B���V�͌ߑO���ɍs�Ȃ��A�č��̂��Əo���B�Α���ŏč��̌�A�Α������B���̂��ƁA�������⎵�����̖@�v���s�Ȃ��A�u���������v�ƌĂԐ��i���Ƃ��̗������Ƃ�B�D�y�s�ɂ͎��@��270�P���ŏ�y�^�@�������B��ق͖�400�B���قł͒ʖ�̑O�ɁA�����s�ł͑��V�̑O�ɉΑ����s�Ȃ���B
�����ł́A���T�Ԃ��͑e���{�i�ŁA����ƂƂ��ɓn���̂�����B�����̈ꕔ�ł͋��Ԃ̑���Ɂu���Ԏ��v�𗘗p����n�悪����B
���X��
�����ł͉Α��������Ƃɒʖ���s�Ȃ��B�ʖ��6������n�܂�A�X�s�ł͎��@�Ȃǂōs�Ȃ��A�����1�����炢�B�����⍜�ƈʔv�A��e�̑��A�u�����ς��сv�ƒc�q�������čՒd�Ɉ��u����B���T�Ԃ��͎�t�ł��̏�Ԃ�������B���V�I����͂������ɕ�n�ɍs���A��������B��n����A���Ə������̖@�v���s�Ȃ��A���i���Ƃ����s�Ȃ��B�������͐X�s�ł͎O�����A���ˎs�ł͌����ɍs�Ȃ��̂���ʉ����Ă���B
����茧
�ʖ�͈�ʂɎ���ōs�Ȃ���B�ʖ�Ԃ�܂��̏��҂����҂́A���T�Ƃ͕ʂɁu���H���v���ށB�ʖ�̂��ƂɉΑ����s�Ȃ���B���̍ہA��e�E���ԂȂǂ���l���g���čs���B�Α���őm���̓njo�̂��ƈ⑰�A�Q��҂��č����A�⑰�͎Q��҂Ɉ��A����B�����̂��ƈ⍜���Ւd�Ɉ��u������A���V�̏���������B�Α����ɂ���̂́A��̂�{���ɓ���邱�Ƃ��ւ������߂ƍl������B�����n���̑��V�͎��@�ōs�Ȃ���B�n�߂ɉ�҂�����ɓ���A�⑰���s�ē��ꂷ��B��҂͏č������܂��⑰�Ɉ��A���ċA��B���T�Ԃ��͂��̏�Ԃ��ł���B�����͑��V�����ɍs�Ȃ��̂����ʂł���B
���{�錧
���s���ł͒ʖ�͎���ōs�Ȃ����A���V���͎����莛�@�������B���s�ł̓z�e���𗘗p���Č��Ԃő��V���s�Ȃ����Ƃ�����B�ʖ�̂��Əo���ƂȂ�A��l�ԂʼnΑ���ɍs���B�������̂��ƁA�⍜���Ւd�Ɉ��u���đ��V���s�Ȃ��B���V�̂��Ƃɖ������s�Ȃ��A���̂��Ǝ������@�v�܂ł��s�Ȃ��A�Ւd��8���ڂɓP�������B���T�Ԃ��͂��̏�Ԃ��ł���B�Ȃ��C����s�ł́A�ʖ�̑O���ɉΑ����s�Ȃ���B
���H�c��
�H�c�s�ł͉Α��̂��ƂŒʖ���s�Ȃ��̂���ʓI�ł���B��̂�[���������ƓB�������s�Ȃ��A�Α���Ɍ������B�Α��ꂩ��߂�����⍜���Ւd�Ɉ��u���A�ߐe�҂݂̂Œʖ���s�Ȃ��B�s���암�ł͍��ł��ߗבg�D�����V�S�ʂ��Ƃ肵�����Ă���B�ʖ�̗����ɑ��V���s�Ȃ���B�n��ɂ���đ��V�I���ԍۂɁA��҂̑O�ň⍜�́u�����v���s�Ȃ��鏊������B���V���Ə������@�v���c�܂�A���̂��ƈ⑰�͈⍜�Ƒ����k�������ĕ�n�ɍs���[�����s�Ȃ��B�����̌�A���i������H�ׂ�B
���R�`��
�R�`���ł͒ʖ���u������v�ƌĂсA�O���u��ω��u�̐l���W�܂��Č�r�̂����a����B�ʖ�̗����A���V�ɐ悾���ĉΑ����s�Ȃ���B�o���ɂ͌��ֈȊO�̏�����s�Ȃ���B�Α��ꂩ��A���ƁA���Ɛ��Ő��߁A�⍜���Ւd�Ɉ��u���đ��V���s�Ȃ��B���V�͕��ʎ��@�ōs�Ȃ��邪�A���V�I����A�����̖@�v���s�Ȃ���B�����͎������̊������ɍs�Ȃ���B���T�͂��̏�Ԃ��B
��������
�����s���ł͎����3���A���Ƃ��V��ōs�Ȃ���B�������ł͑��V�O�ɉΑ�����n��ƁA���V��ɉΑ�����n�悪����B�����s�ł͑��V�̑O�ɉΑ����s�Ȃ��B���V�̂Ƃ��A�e���̒j���͖��̂��݂����p������B��Îᏼ�s�ł́A���V�̌�Α����s�Ȃ��B����ɒ|�ʼn�������A�������犻�������点��B�Α��ꂩ��A��A�������@�v�̂��Ɛ��i���Ƃ����s�Ȃ��B�����s�ł͍��T�Ԃ��͍��ʎ���ɍs�Ȃ��B
|
����錧
���ł͒ʖ�Ԃ�܂��ɖ݁A������A�����p�ӂ����B�Α��͑��V�̌�ɍs�Ȃ��n��ƁA�ʖ�O�ɉΑ�����n�悪����B���ˎs�ł͉Α��̌�ɒʖ邪�s�Ȃ���B���V�̂��Ɗ���S���l���u���ځv�Ƃ����A�g���̎҂��S������B�܂������Ƃ����āA������V����������B�Α���ł͓njo�̂��ƁA�č����s�Ȃ��A�������ƂȂ�B�����ł͓����ɖ������邱�Ƃ������A�������I�����牖�������Đ��߁A���̂��Ƃɐ��i���Ƃ����s�Ȃ��B���T�Ԃ��͂��̏�Ԃ��B
���Ȗ،�
�F�s�{�s�ł͑��V�̂��ƂɉΑ������B�_�����ł͌���ɒ|�ʼn�������A���������点��B�Α���ŏč��̂��ƁA�Α��B�������̂��ƁA���ő̂�����߂Ă���⍜�����u���A�������@�v�̂��Ɛ��i���Ƃ����s�Ȃ���B�����ɂ͓y�����s�Ȃ��n����c���Ă���B���T�Ԃ��͂��̏�Ԃ��B
���Q�n��
�����ł͑����g�Ƃ��ċߗׂ̂ЂƂ̑��ݕ}���������Ă���B���암�̑O���s�⍂��s�ł́A�`���I�ȏK���������Ă���B�ʖ�̂��Ƃ̒ʖ�Ԃ�܂��́u����߁v�Ƃ��Ďh�g���o���K��������B�S����_�����ł͍��ʎ��̂��ƁA�u�ł͂̔сv�Ƃ����V����邱�Ƃ�����B���V�̌�A�Α���ł͈�̂�䶔��ɂӂ��A�������̂̂��A����̌����d�Ɉ⍜�����u����B�����ŏ������@�v���s�Ȃ��A���i���Ƃ����Ƃ�B������u���ƔO���v�ƌĂԁB���T�Ԃ��͂��̏�Ԃ��B
����ʌ�
�Y�a�s�ł͉Α��͑��V�̂��Ƃł��邪�A�����s�ł͉Α��̂��Ƃɑ��V���s�Ȃ���B���V�͉Y�a�s���{�s�Ȃǂ̓s�s���ł��V��ōs�Ȃ���悤�ɂȂ����B�S����_�����ł́u�o�����̑V�v������A����Œ��q���������肷�邵�����肪�c����Ă���B�Α��ꂩ��A��ƁA���␅�ő̂𐴂߁A�⍜���Ւd�Ɉ��u����Ă��珉�����@�v���s�Ȃ���B���T�Ԃ��͂��̏�Ԃ����������A�����s�ł͊������ɕԂ��K���ł���B
����t��
�َR�s���͂��߂Ƃ��đ��V�����̒��ɉΑ����s�Ȃ��n�悪�������A��t�s�ł͑��V��A���q�s�ł͒ʖ�̑O�ȂǂƓ������ł��قȂ��Ă���B���q�s�ł͍��T�͒ʖ�A���V�̗����ɏo���B�Α���̍��������A��t�s�ł͈ꕔ�����قɎ��߂邪�A���q�s��َR�s�ł͑S�����߂�Ƃ����B���V�����ɏ������̖@�v���s�Ȃ��A���̂��ƁA�u���������v�Ƃ������i���Ƃ�������̂͋��ʂł���B���T�Ԃ��͓����Ԃ��B
�������s
�s�S���ł͎��@���V��ł̑��V�������B�܂��ʖ�ɎQ��҂��A���V�ɎQ��҂������������B���V�͒ʖ�̗����s�Ȃ��A���V��Ɉ�͉̂Α��ƂȂ�B�Α���A�������@�v�A���i���Ƃ��̏��ɐi�߂���B�Ȃ����T�Ԃ��́u�������v�ɍs�Ȃ���B
���_�ސ쌧
�ʖ�E���V�Ƃ�����ōs�Ȃ���n�悪�������A�s�s���ł��V�ꗘ�p�������Ă����B���͌��s�͎����8���ł���B�����ł͈ꕔ�A���V�̒��ɉΑ����ɂ���n��(�쑫���s)������B���V�̂��ƁA�Α����䶔��ɂ��ꂽ�⍜�����u���Ă̏������@�v���s�Ȃ���B���T�Ԃ��͉��l�ł͊������ɍs�Ȃ��邪�A���c���s�A���ˎs�Ȃǂ��̏�Ԃ�������B
|
���V����
�V���ł͏�y�^�@�̒h�Ƃ������B���V�E�ʖ�͎���ōs�Ȃ��ꍇ�������B�V���s�ł͉�قł̑��V�������B�ʖ�͌ߌ�7�����͂��܂�A�ʖ�̌�ɂ͑m���ɂ��@�b������B�����̑��V���I���ƁA���ɓB���������ďo���ƂȂ�B�V���s���ł͋����̏K���������Ă��邪�A�_�����ł͖쓹��������āA��ӂ̑�����s�Ȃ��n�悪�c����Ă���B�Α���ł͓njo�A�č��̂��ƍ������B���ق͎g�킸������p����B�⍜�͍Ւd�Ɉ��u���A����ŏ������@�v���c�ށB���T�Ԃ��͑��V��2�T�ԑO��ɍs�Ȃ��B
���x�R��
�x�R�s�ł͒ʖ�ɂ́u���ԉ�(������)�v��p�ӂ��A�Ւd�ɏ���B�������V���s�Ȃ��邪�A�����s�ł͏o�ق̂����Ɋ��𔒂̂��炵�Ɋ����ė�l�Ԃɉ^�Ԋ��K������B�܂������Ắu�P�̍j�v�Ƃ����āA���ɂȂ������̂��炵�z���⑰�̐l�������A��ɂƂ��čs�Ă����K�������������A���݂ł͑��V�̑O�ɔ����z����Ɏ�邱�Ƃő�p���Ă���B�Α��̂��Ƃ̍������ł́A�����s�ł́u���������v���s�Ȃ���̂ŁA���ق��傫�Ȃ��̂��p�ӂ����B�A���ƈ⍜�𒆉A�d�Ɉ��u���A���������s�Ȃ��B���T�Ԃ��͕x�R�s�ł͓����Ԃ��B
���ΐ쌧
����s���ł͒ʖ�͎���ōs�Ȃ����A�߂��̎��@�ōs�Ȃ����Ƃ������B�k���ł͑r�傪���̑����𒅂�K��������B�����̑��V�̌�A�Α��B���������⍜���A��ɔ[�߂�n�������B����s�ł͍��T�Ԃ��͂��̏�Ԃ��ł���B
�����䌧
����s�ł͒ʖ�E���V���͎��@�ōs�Ȃ��邱�Ƃ������B�[���ɂ́A�j���ɂ͒䓁�A�����ɂ͂͂��݂�����Ƃ����K��������B���䌧���n���ł͑T�@�̎��@�������A���V�͎���ŌÂ�����̓`���I�ȏK��������čs�Ȃ��Ă���B�o�����ɂ͌���ő������������A���q���������肷��B�܂��r��͔��̂��݂����𒅂Ă���B�Α���ɂ͈ʔv�A��e�̑��A���Ԃ����Q����B����ɋA���Ă��牖�Ő��߁A�������܂ł̖@�v���s�Ȃ��B����s�ł͍��T�͂��̏�Ԃ��������B
���R����
�ʖ�E���V�Ƃ�����ōs�Ȃ��邱�Ƃ������A�܂��匎�s�ȂǁA�Α����s�Ȃ��Ă���A���V���s�Ȃ��n�悪�݂���B�Α�����6���ƒႢ�B�����ł͗F���ł����V���s�Ȃ����Ƃ������A���̏ꍇ�ɂ́u���l�`�v����ꂽ�肷��B�����ł͏o���ɂ������āA�O���u�̐l�X����r�̂���������A��ɉ��������Ă������犻�������点���肷��B�b�{�s�ł͑��V��ɉΑ������A�������Ă��珉�����@�v���s�Ȃ��B���T�͂��̏�Ԃ��B
�����쌧
�ʖ�E���V�͎���ōs�Ȃ��B�ߗׂ̐l�X�̑��ݕ}���ōs�Ȃ���B���{�s�ł͉Α��̌�A�⍜�ɂ�鑒�V���s�Ȃ����A����s�ł͑��V�̂��ƉΑ�����B���̂Ƃ��r��͔��̕z��g�ɂ���n�悪����B�̐l�����O�P�����w��������ꍇ�A�[���ɂ������Č���������B���䶔��ɂӂ������{�s�ł́A���V�̂��Ə������@�v���s�Ȃ��A���̂��ƕ�n�ł̖������s�Ȃ��B���T�Ԃ��͂��̏�Ԃ��ɂ���B
����
�ʖ�E���V�͎���ōs�Ȃ����Ƃ��������A���R�s�ł͎��@���������B�܂����R�s�ł͏�y�^�@�������A���̏ꍇ�ɂ͖�����ɐ����(���)�������Ȃ��ꍇ�������A�T�@�ł͖��т�p�ӂ���B�s���ł͔��������̏������⑰�ɑ����čs�Ȃ��B���ł́u�p���ʎ߁v�̉e���Ő_���̑��V������������B���V�̂��ƂɉΑ����s�Ȃ��邪�A�S���ł͓y���̒n�悪�c����Ă���A���̍ۂɂ͖�ӂ̑��肪�s�Ȃ���B���T�Ԃ��͊������ɍs�Ȃ���B
������
�ʖ�͎���A���V�͎��@�ōs�Ȃ����Ƃ������B�����e�n�Ɂu���g�v���c����Ă��邪�A�s�s���ł͑��V�Ђ��s�Ȃ��B�É��s�A���c�s�ł͑��V�̑O�ɏo�����A�o���ɂ������ẮA�m���ɓnjo���Ă��炤�B���̓A�[�`���������A���̂��ƉΑ��ɂ���A�⍜�������Ď��@�ɍs�����V���s���B�⍜�͑��V�̌�A�����̕�n�ɖ�������A���̂��Ɛ��i���Ƃ����s�Ȃ���B�É��s���ł́A���̏�ō��T�Ԃ����s�Ȃ��B
�����m��
�ʖ�A���V�͎���������A���É��s�ł��V��ōs�Ȃ��P�[�X��������B�ʖ�ɂ́A���T�̑��u�҂������v���o���K��������B���É��s���ӂ̐��ˁE��{�ł́A�r�傪�������𒅂���K�����c���Ă���B�o���ɂ������Ē��q������K��������B���V�̂��ƁA�Α����A���̓��ɏ������@�v���s�Ȃ���B���T�Ԃ��́A�������ɍs�Ȃ���B
|
���O�d��
�����7���ȏ�B���ʈɐ��A����s�ł͔N�����ߓ�����Ă��邪�A�r�Ƃł͂�����͂����B�ʖ�́u�鉾�v�Ƃ����A����ōs�Ȃ��B�܂��u�g�v�����V�̎�`��������B�Îs�⏼��s�͑��V��ɉΑ����s�Ȃ����A���h�ł͒ʖ�̑O�ɉΑ����s�Ȃ��B�܂��ɐ��s��F��s�ł͑��V�ɐ悾���āA�Α����s�Ȃ��Ă���B���V�̂��ƁA�o���ɐ悾���ďo�����̑V�����n�悪����B�Α��̌�A��n�ɖ������邪�A��n�ɂ͖�ʔv�⎀�ԉԁA�����k�Ȃǂ��p�ӂ����B���T�Ԃ��͊������ɍs�Ȃ��B
�����ꌧ
�����͋ߗׂ̐l�̎�`���ɂ���čs�Ȃ���B���V�̂��Əo���B�o���͌��ֈȊO�̏�����o���B�܂���Œ��q����������A����������A��y�^�@�̒h�Ƃł͍s�Ȃ�Ȃ��B�F���s�ł͊����A���ւ���o�������œnjo������u��߁v�̎����s�Ȃ���B�Α��̌�A���ւʼn����ӂ肩���Ă���Ƃɓ���A�ҍ��s���s�Ȃ��B���̂��Ɖ�H�ł���u���d�グ�v���Ƃ�B�F���s�ł͎�t�ō��T���o���ƈ��������炢�A��ɉ���i���B
�����s�{
���s�ł́u���V�v�Ƃ�ԑV����ɏo���̂������ł���B�܂��u�F���v�ɂ́u���l�`�v�����đ��V���s�Ȃ��B���V�̏����͒�����ōs�Ȃ��A�ʖ�͎���ōs�Ȃ���B���V�ɂ͒|�Ւd���g�p�����B�o�����ɖ���Œ��q�������邪�A��y�^�@�̉Ƃł͍s�Ȃ�Ȃ��B�Α���A�⍜�������d�Ɉ��u���Ė@�v���c�܂��B���s�{�ł͋��Ԃɞ�(������)��B���s�s���ł͉���ɏ��i�����p������B
�����{
���s���ł��V��ł̑��V�������Ă��邪�A����ȊO�ł͎���ł̒ʖ�E���V�������B���V�̂��Əo���A����Œ��q������̂���ʓI�ł��邪�A��y�^�@�ł͍s�Ȃ�Ȃ��B�܂������Ƃ����āA������V������������Ă���B�Α��̂��ƁA����ɋA�邪�A���̎��A�����|������A����ʼnƂ̒��ɂ͂���B�������̖@�v�̂��ƁA�u�d�グ�v�Ƃ������i���������B���T�Ԃ��͊������B
�����Ɍ�
���V�ɂ͋ߏ��̐l����`���K��������B���V�̂��Əo���A���̎�����Œ��q������̂���ʓI�ł��邪�A�O�g�n���ł͍s�Ȃ�Ȃ��B�Α���ł͞�(������)�̎}�𐅂ɐZ���A���ɐU��|����V��������B�Α��̂��ƁA����ɋA�邪�A���̎��A�����|������A����ʼnƂ̒��ɓ���B�������̖@�v�̂��ƁA�u���i�����v�Ƃ������������B���T�Ԃ��͊������B
���ޗnj�
������ɂ́A���ʔv�Ɩ�ʔv��2��p�ӂ���B�܂��ޗǎs�ł͋t���������s�Ȃ����Ƃ�����B���V�̂��Əo���A���̎�����Œ��q������̂���ʓI�ł���B�܂��B�Α��̂��ƁA���������ĉƂɓ���B�����ď������ƎO�����̖@�v���s�Ȃ��A���i���������B���T�Ԃ��͊������B
���a�̎R��
�����ɂ͌ݏ��g�D������A���V�͐��b�������S�ɍs�Ȃ��B���V�͗F���̑��A�O�זS�̓���������B�r�Ƃɂ́u���v�ƋL���������ɗ��Ă�B���V�̂��Əo���A���̎�����Œ��q������̂���ʓI�ł���B�܂�����������Ƃ�����B�Α��̂��Ɖ�����������A����ʼnƂɓ���B�������̖@�v�̂��ƁA�u���i�グ�v�Ƃ������������B���T�Ԃ��͊������B
|
�����挧
�S���͎���ł��邪�A�s���͎��@���ł���B���V�͋ߗבg�D���r�Ƃ���`���K��������B����s�𒆐S�ɂ����n���ł͖�����ɁA�������u���肾�v�Ƃ�сA4�̒c�q��������B�[���͏o���ԍۂŁA����܂ł͖k���̂܂܂ɂ��Ă����B�ʖ�́u���v�Ƃ�ԁB�����ł͔������Α��㑒�V���s�Ȃ��B�Ďq�s�����V�O�ɉΑ����s�Ȃ��A�ߌォ�瑒�V���s�Ȃ���B�Α��̂��ƁA������������A����ʼnƂɓ���B�������̖@�v�̂��ƕ�n�ɖ����ɍs���A���̂��Ɓu���i�グ�v�Ƃ������������B���T�Ԃ��͊������B
��������
�S�̂Ɏ���ł̒ʖ�E���V���������A���]�s�ł͎��@�ł̑��V�������B�ʖ���u�鉾�v�Ƃ����A���̎��Ԃ͌��܂��Ă��Ȃ��B���̂��߁A����q�͓K���r�ƂɖK��ďč�����B���ď��]�s�A�o�_�s�ł͑��V�̑O�Ɉ�̂��Α��ɂ���B���V�̂��ƁA���������������̖@�v���s�Ȃ����A��n�ɖ����ɍs���B���̂��Ɓu���܂��v�Ƃ������i���������B���T�Ԃ��͓����B
�����R��
���R���ł͗F���͉Α��ꂪ�x�݂̂��߁A���V���s�Ȃ��Ȃ��B�ʖ�́u���v�Ƃ����B���V���I���Əo�����̑V����A�̐l�Ƃ̐H���ʂ�̂��ƁA���ɉԂ����ďo���ƂȂ�B����Œ��q������K��������B�Α��̂��ƁA����ɗp�ӂ��ꂽ���������ĉƂɓ���B�ҍ��@�v�̂��ƁA�u�d�グ�v�Ƃ������i���������B���T�Ԃ��͓����s�Ȃ����Ƃ������Ȃ��Ă���B
���L����
�L�����͏�y�^�@�̒h�Ƃ̑����n��ł���B���V�̂��ƁA����n���ł͖���Œ��q������A�Ă��܂��K�������邪�A��y�^�@�̑������|�n���ł͍s�Ȃ�Ȃ��B�S���ł͒�Ŋ���3��܂킷�K��������B�Α��̂��ƁA����ʼn��������ĉƂɓ���B�������̖@�v�̂��ƁA�u���V�v�Ƃ������i���������B
���R����
�ʖ�E���V�Ƃ�7���ȏオ����ōs�Ȃ��A���@������2���B���V�ɂ͋ߗבg�D�����S�ƂȂ��čs���B���V�̂��ƁA����Ō̐l�̒��q���������著����������肷��B���d�݂̂ő��V���s�Ȃ��n�������B�Ƃ����l�Ԃ܂ł̂킸���ȋ����ł���ӂ̑���̗l�ɑ����g��ōs���B�Α��̂��ƁA���������ĉƂɓ���B�������̖@�v�̂��Ƃɂ́A�u�܂Ȃ����炢�v�Ƃ������i���������B���T�Ԃ��͊������ɍs�Ȃ���B
|
��������
�ʖ���u����v�Ƃ����A�ߐe�҂��u�ʖ錩�����v�����Q���Ē��₷��B���V�̂��ƁA�o���ɂ���������Ō̐l�̒��q���������著��������B���̎��A�������V�����s�Ȃ���B����n���ł́A���s������l�Ԃ̂��Ƃ𑒗��g���1�������B�Α��̂��ƁA�������̖@�v���s�Ȃ��A�u�܂Ȃ��������v�Ƃ������i���������B���T�Ԃ��͊������ɍs�Ȃ���B
�����쌧
�O�@��t�̐��a�̒n�Ŏ��@�������B�r�Ƃł͐_�I�������s�Ȃ������ɔ������̏�Ɂu���v�Ƃ������������B�ʖ�̉��͍����s���ł͎��@�ōs�Ȃ��A�n���ł͎���Œʖ�A���@�ő��V���s�Ȃ��B���V�̂��ƁA�̐l�̒��q���������著��������B�܂��ߐe�҂̏��������ɎO�p�̎�������ʼnΑ���ɂ������K���c����Ă���B�Α��̂��ƁA�������̖@�v���s�Ȃ��A�u�Ȃʂ��v�Ƃ������i���������B���T�Ԃ��͊������ɍs�Ȃ���B
�����Q��
���V�̏����͋ߗׂ̑g�D�����V����`���B���V�̂��ƁA����Ō̐l�̒��q���������著��������B�Α��̂��ƁA�⍜�����̂܂ܕ�n�ɍs���A��������B���̂����쓹����ꏏ�Ɏ����Ă����B�A���A�������̖@�v���s�Ȃ��A���̂��Ɓu���������v�Ƃ����Đ��i���������B���T�Ԃ��͊������ɍs�Ȃ���B
�����m��
���m�s�ł͎��@�ł̑��V�������A���V�Ђ𒆐S�ɏ������i�߂���B�܂��y���������A���̎��ɂ͓y���p�̊����p������B���V�̏����͋ߗׂ̑g�D�����V����`���B���V�̂��ƁA���̏�ɉH�D�����Ԃ��A���̏�ɒ��q���悹�A����Ō̐l�̒��q������A�H�D���O��U�邵�����肪�c���Ă���B�Α��̏ꍇ�A�⍜��S���E���A�쓹����ꏏ�Ɏ����ĕ�n�Ŗ�������B�A������ƁA�������@�v���s�Ȃ��A�u���i�����v�Ƃ����Đ��i���������B���T�Ԃ��͂��̏�Ԃ����s�Ȃ���B
|
��������
�S�ʂɎ���ł̑��V���������A�����s���ł��V��ōs�Ȃ����������B�ʖ�ɂ͋ߐe�҂��u�鉾�����v�ɉَq�����Q����B���V�̂��ƁA�o���ɂ���������Ō̐l�̒��q������A��������3��܂킵���肷�邵�����肪�c���Ă���B�Α��̂��ƁA�⍜���g���A�Ƃɓ���O�ɑ̂𐴂߁A���̂��Ə������̖@�v���s�Ȃ��A�u���i�グ�v�Ƃ����Đ��i���������B���T�Ԃ��͊������܂łɍs�Ȃ���B
�����ꌧ
�ʖ�E���V������ōs�Ȃ���B������ɂ͖��c�q�������邪�A�����49��������n��ɂ���ĈقȂ�B���V�̑O�ɐg�������Łu�o�����̑V�v��H�ׂ�B�o���ɂ������ẮA����Ō̐l�̒��q������A��������3��܂킵���肷�邵�����肪����B�Α��̂��ƁA�⍜���g���A�Ƃɓ���O�ɑ̂𐴂߁A���̂��Ɓu�O���Q��v�̖@�v���s�Ȃ��A�u���i�����v�Ƃ����Đ��i���������B���T�Ԃ��͊������܂łɍs�Ȃ���B
�����茧
���V�͒ʖ�A���ʎ��A�Α��A�O���Q��A�������̏��ŁA�������܂ōՒd������B�ʖ�ɂ́u�ڊo�܂��v�̂��߂ɉَq�����Q�������A�ŋ߂ł͍��T�ɑ������B���V�̂��ƁA�o���́A�������犻���o���邵�����肪����B�Α��̂��ƁA�⍜���g���A�Ƃɓ���O�ɉ��ő̂𐴂߁A���̂��Ɓu�ҍ��s�v���s�Ȃ��A�u�����P���v�Ƃ����Đ��i���������B���T�Ԃ��͊������܂łɍs�Ȃ���B
���F�{��
�l����7������y�^�@�ŁA�F���ł����V���s�Ȃ��B�]���ĉΑ���͖��x�ł���B���V�́u�����g�v�̐l���������A�ʖ�ɂ͋ߐe�҂�����َq���u�鉾�����v�Ƃ��Ď��Q���A����q�ɂ͈���тȂǂ��U�镑����B�F�{�s�ł́A�ߑO���ɉΑ��ɂ��A�ߌォ���V��Ȃǂő��V���s�Ȃ���P�[�X�������B�o���ɂ́A����Ō̐l�̒��q������A����3��܂킵���肷��n�悪����B�Α��̂��ƁA�u�ҍ��@�v�v���s�Ȃ��A���V����`�����l���˂��炤���i���������B���T�Ԃ��͊������܂łɍs�Ȃ���B
���啪��
�ʖ�́u�҂������v�A�ʖ�Ԃ�܂����u�ʂ�̑V�v�ȂǂƂ����A�ߐe�҂Ō̐l���ÂԁB�ꕔ�̒n��ł͑��V�O�ɉΑ�������Ƃ��������B�o���ɂ������ẮA��҂ɂ���z��B����Ō̐l�̒��q������A����3����肷��n�悪����B�Α��̂��ƁA�⍜���g���A�Ƃɓ���O�ɉ��ő̂𐴂߁A���̂��Ɓu�������@�v�v���s�Ȃ��A���i���������B���T�Ԃ��͊������܂łɍs�Ȃ���B
���{�茧
�{��s�ł͒ʖ�E���V�Ƃ��V��ōs�Ȃ����������Ȃ��Ă���B���V�̌�A�o���ɂ������ẮA����Ō̐l�̒��q������K��������B�Α��̂��ƁA�u�������@�v�v���s�Ȃ��A���i���������B�����s�ł͉Α��ꂩ��A������A�_�E�ɂ�����P���������邱�Ƃ�����B
����������
�V��ł̑��V��4���ŁA6��������ł���B����ōs�Ȃ��ꍇ�A���V�̌�A�o���ɂ������ẮA��������o�����Ƃ������A���̂��������~���ق����ł͂��K��������B�Α��̂��ƁA���̂܂ܕ�n�ɍs����������B���̂��Ɓu�������v�܂ł̖@�v���s�Ȃ��A���i���������B��q���ł͉Α��̂��ƁA�ʖ�A���V�ł���B
�����ꌧ
�r�Ƃł͑��V�̑O�ɕ��|�����A������ɔ[���܂Ŕ��̎���\��B�[���ɂ͕G�������Ȃ��邽�߁A���͒Z���āA�[�������g�p�����B�ʖ�ɂ͋ߗׂ̐l���W�܂�B�ߔe�s�𒆐S�Ƃ��鑽���̒n��ł́A�Α��̌�A�⍜�����u���đ��V���s�Ȃ��B�[���͑��V�̓����ɍs�Ȃ��A���̂��Ɛ��i���Ƃ�������B�Ă͒ʖ���s�Ȃ킸�A�����ɉΑ�������B�@ |
|
�� |
�����̗\�� / �a�l�̉Ƃ̕t�߂ʼnG�̖���������Ǝ����߂Â��Ƃ����B�G�͎��L�𑁂�������ƐM���Ă��邩��ł���B�@
�������� / �a�l�̗ՏI���߂��Ȃ�ƁA��ː��݂̂ɓ���ăK�[�[�ɐZ���A�g�߂Ȏ҂��珇�ɕa�l�̐O�𐅂ł��߂��A�����̐������܂����B�����������ƁA�u���Ăсv�Ƃ����Ď��҂̖����ő吺�Ŏ��҂̖����Ă�A�O�ɏo�ċ��B�@
���҂͐Â��ɔ[�˂Ɉڂ��A�k���������ɐQ������B���҂̊�𔒂��z�ŕ����A���҂̖K�⒅�����c�̏�ɋt���ɂ��Ē���������B�������̂��߂ɐn����g�߂ɒu���B�����ɏ�����u���Ĉ�{�ԁE��{�����E��{�낤������������B�������t���ɗ��Ă�B�_�I�ɂ͔�����\��B�@
������ / ���O�g���Ă��������q��t�̕Ă𐆂��A�ꗱ���c�����R����тɂ��Ĕ�����{���Ă�B���т͎��҂��P�����ɎQ��ٓ����Ƃ������A�����̋��ɂ���l�̗썰�������Ɉ������ǂ����Ƃ������̂ł��낤�B�@
���u�g / ���V�̏�������I���܂ŕ��S���Ď���s�����V�g���u�u�g�v�Ƃ����B�u�g�͏\���˂̃J�N�����O�g���J�N���E�`�Ƃ������B���҂��ł�Ƒg���ɒm�点��B�g������m�点�����S�˂�������݂ɗ��āA���ƂƑ��k���ĕ��S�����߂ď����ɂ�����B���S�͎��̂Ƃ���ł���B�@
�e���m�点�E�������E������E�C�P�~��(�挊�@��)�E���}���E��t���Ƃ��̈��A�E����ȂǁA���͑��Ƃ��͂��߃J�N���̐l�̐H���A��҂̐ڑҁA���тɂ��Ƃ��̑V�����炦�A��n���܂ōs���B���Ɛe���͈�؎���o���Ȃ��B�@
�e���m�点�ł͐H�����o����邪�A�H���͕K���H�ׂ邱�Ƃ��K�킵�ł���B�������͘d������Ɋւ�����̂ł���(���)�B������͏K���ɏ]���Ē��V�̎w�����č��B���؉ԁE���U(��)�E�������āE�낤�������āE�V�W�E�����E���E�����E�����k�Ȃǂ����B���͒|�ŗ��������r���̗t��}���Ċp�����B�|�̂ɂ��Ď���\��A���낱��`���Ď֕��Ɋ��������B�@
�@�h�ɂ��n��ɂ���ĈقȂ邪�A�^�@��k�ł͑�����͂��Ȃ��B�����Q��͎��ɂČo���ċA���n�ɎQ��K���ł���B�����k�͎g���Ă��Ȃ��B�@
���鉾 / �ߐe�҂ƍu�g�̐l���鉾������B�u�g�̐l�ɂ͍�E���E���َq���o���A��ɂȂ�A���Ă��炤�B�ߐe�҂͐����E�낤�����̓��������Ȃ��悤�ɋC���g���B�@
������ / �[��ɐe�ނ������Ă��瓒���������B�ߐe�҂͒����𗠕Ԃ��ɒ��ē�т���d�ɏc���т��A�ς��߂���ɓ����������B������Ē��ɐ��������Ď��҂��N�������B���炢�̐��ɓ��𒍂��łʂ�߁A�����ۂō��Ԃ��ɂ������B�g�̂𐁂����߁A�������t���ɂ��ăI�R�]���������B�є��͎��ɎĊ��ɔ[�߂��B�g�������͕����̏����ɗ������B�������I���ƁA�o�b�`�����}�����Ԃ�A�������̊������ɍ����ė����ł����Ă��ɍs�����B�Ă���͒n�悲�Ƃɒ�܂��Ă���B�����Ɏg��������͈�T�Ԃ͎g��Ȃ������B�@
���[�� / ���҂̓��ɎO�p�Ђ����сA�����C�̑����𒅂���B�ꔽ�̎N�ؖȂ��甒���C�E�b�|�E�r�J�E���܂����B���ɍ��z�c��~���Ď��҂����点�Ď�ɓ��ɑ܂��|�����B�܂̒��ɂ͘Z���K�̑���Ɏ��ō�����K�l�㖇�ƁA���O�Ɉ��D�����i������B������������̝d�w�ɐ�����|����B�����͗F������������A�F���̓��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����͘m�l�`�����̒��ɓ��ꂽ�B���̐��ʂɘZ���̖���(�얳����ɕ�)��\��A�W�̏�ɏ㓙�̒����Ɛn����u�����B�@
�������� / ���d�̑O�Ɏl�܂�ɂ���䭂�~���A�ςĕU�̏�Ƀ���(�S��)�_�Ɏg���|���{����ׂĊ������u���A�V�W�ŕ����B�~�Ă̐��͉Ƃ��ƂɈقȂ��ƂقǑ��������B���݂͕~�ė��ƂȂ��Ă���B���сE�c�q�E���ԁE���ԁE�����E�������������A���O�̏ё�(�ʐ^)�ɍ����{�����������̑O�ɒu���B�@
���҂̕���ɓ��鎮���s���@������������B���t���ʔv�������A���҂Ɉ�����n���njo���s����B���t�č��E�����A�ߐe�ҁE��҂̏��ɏč�����B���v�̌o��ǂ݁A���V�̏I����c��ɕ���B�@
���O���� / ���������I���A�������Ɠ����悤�ɒɎl�܂�ɂ���䭂�~���A�~�ĕU��ς�Ő������Ɋ������u���A����������O�ɒu�����B�����ɐe���A�E���ɉ�҂��ʒu�����B���t�������̓njo�����Ď����i�߂�ꂽ�B���݂͓��������O���������˂Ă���B�@
���o�� / ���͓�{�̃����_�����ɒʂ��Ďl�l�ŒS�����B�ڂŎO�������A�o�����ɖ���ʼn����B����̏����́A�����E���U�E���؉ԁE���E��ʔv�E���сE�V�W�E�������āE�낤�������ĂŁA��҂����̌�ɑ������B�@
������ / �������ĕ挊�𐴂߁A�C�P�~���̍��}�Ŋ����~�낵�Đ������Ɉ��u���A�l�܂�ɂ���䭂����Ԃ����B�����̍ۂɂ�䭂��l�܂�ɂ���̂ŁA����͎l�܂�ɂ���䭂ɂ͍���Ȃ��B�ߐe�҂ɎO�L���y�������ČL����n�����B�ߐe�҂��ς߂C�P�~���ɔC���ċA�邪�A�A�r�͌����U������Ă͂����Ȃ��B�����Ŏ�����ĉƂɋA��B�@
�C�P�~���͒��S�Ƀ����_�𗧂Ăēy��A�����ɐ���y�����ꂢ�ɂ����B�Ō�Ƀ����_���Ė���u�����B���͗\�ߐ��I�Ԃ��A��x�I���͎̂��ւ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���Ŏ育��Ȃ��̂�T���ċC�ɓ���Ύ��G�ꂽ�B�˂̑O�Ɉ�̉ԓ��E�������āE�낤�������āE���؉ԁE���т��������B�@
���@�� / �����̗����ߐe�Ґ����������ւ̗�Q�����A�~�Ă͋��ɃE�Z(�ʍڂ�)�čs�������A�~�ė��ɂȂ����B���ł͂��{���œnjo�̌�ɂ��ւɒ���B�r�Ƃ͂��z�{�E�āE�������Q����B�@
�ߖ�́A�Z���ڂŎ�����m�����Ă��o��������B��͍u�g�̐l�Ɛe�����W�܂��ĔO����������B�u�҂����������v�ɎQ��B�V���������H������B���A�̊��Ԓ��͐_�ЁA����n�ɎQ��Ȃ��B�_�Ђ̍ՓT�̂���Ƃ��͕s�������ĎQ�w����B�@
�l�\����܂ł͖�����ɎQ��A�������ƂɎ��Q������邪�A�e���Őg�߂��Ɍ��߂��Q����Ɩ��O�������ēn���B��y�@�̉Ƃł͑����k�������p�ӂ��āA�������ƂɎ��œnjo���Ă��炢�@�����L���������k���ꖇ�������ĕ�ɎQ��B�@
�l�\����̊��ݖ����ɂ͎l��̖݂����Ɏ����ĎQ��B������m�����njo�ɗ���B�����A�̋��{�̂��ߐe���E�m�Ȃ̏���������B��ȑV�͕����̂��Ƃ��A�{�V�Ɠ�̑V�ɂ���B�������̌��Ԃ�������B�@
���̓��ɃV���E�o�P�Ƃ����āA���҂̌`���������ߐe�҂ɕ��z����B���i�グ�͎l�\����ɂ���B���\�������O�����ɂ�����Ƃ��͎O�\�ܓ��Ɏ��z���Ă���B�����͑����̗����ɂ�����A�������ɂ��鏊�������Ȃ����B�@
�N���́A����������J�����Ƃ����B��A���A��O�A�ꎵ�A��܁A�O�O�A�܁Z�N��������B�N�����Ƃɑm�������Ė@�������A�ߑւ��Ƃ��ĖؖȈꔽ�����ɔ[�߂�B�܁Z�N�����I����Ɩ������ɂȂ�B�@
����n / ��n�͎R��┨�n�̋u�ɂ���A�Ƃ��Ƃɕ����������蕪�Ƃ��{�Ƃ̕����g�����肵�Ă���B�ߍ݂̐ނ��g�����p�Γ��`��W���������A���R�̂܂܂̂��̂�����B��͈�l�̎��҂Ɉ��̕搧�ł���B�v�w��͍]�ˎ���ɂ͊p�Γ���{�ɕv�w�A���ł��邪�A�������ȍ~�͐Γ��͕ʂɂȂ��āA�v�͍��A�Ȃ͉E�ɕ��ׂĂ���B��W�̕��ԏꏊ�ɂ���Đ����m�邱�Ƃ��ł���B�@
����������Ε摊���ɂ������������āA�����������̕��ʂ�~�n�Ȃǂ�肤���M�͂Ȃ��c���Ă���B���҂̋��{�͖~�E�ފ݂ɂ���B�@
���E�ҁE�펀�ҁE��ЁE�����ҁE�q���҂Ȃǂ͋����ƍl�����A���̗썰�͗V�S�ƂȂ��ĕ��Q���A��X�̂��������������A�u�a���͂�点���肷��ƐM�����Ă���B�J�N����n���L�҂ŁA�������{�̂��ߕ�W�̑O�ɉԁE�����E�낤�����E��������������A���{�x������邱�Ƃ�����B
|
�����ފ݁@
�u�ފ݁v�Ƃ́u���Ȃ��̊݁v�ƌ����Ӗ��ł��邪�A�u���Ȃ��̊݁v�Ƃ͗��z�̐��E�A���̐��E�̂��Ƃł���B��X�̏Z�ސ��E(����/���̐�)�������̐��E�ł���̂ɑ��āA�����̊C(�։�̐��E)���z�������Ƃ�̐��E�������Č����B���E�����n�ƌ��������Ă��ǂ��B���z�̋��n�B���̋��n�B�@
������u���ފ݁v�̏K���͓��{�݂̂ɍs���āA�t���H���ɑc��̗���Ղ�悤�ɂȂ����B�C���h�ł͍s���Ă��Ȃ��������A�V�i�ł��s���Ă��Ȃ������炵���B�ݑ��M�҂͎��@�ɎQ�w�E��Q���A�m���ɓnjo�E�@�b���s���Ă��炢�������s����B���̖@����u�ފ݉�v�Ƃ������A�u�ފ݂ɓ���@��v�̈Ӗ��ł���B�����t���H���̑O��O���̎����Ԃ������čs���@��������B���~(᱗��~��)�Ƌ��ɍł����O�����ꂽ�A�����̒��ɂƂ��������s���ł���B����̐����Ȃ��ĕ������i����A�ǂ��@���ł���Ƃ����B�{�M�ɉ��Č×��s��ꂽ�s���ł���A���̋N���͌Â��A�������q�̍��Ƃ������Ă���B�@
�ÓT���U������ƁA�哯(��L��802�N)�ȗ����ɍL���s���Ă����̂ł���B�@
�t���H���̓�G�ɉ����ē��ɕ������Ȃ��A������u�ފ݉�v�Ə̂��邱�Ƃ́A���炭�u�ϖ��ʎ��o(�όo)�v���z�ς̐��Ɋ�Â����̂ł���B�@
�Ⴆ�A�P��(���㒆����y���̑听��)�́u�όo�`�v�̒�P�`�ɓ��z�ς��߂��t���H���ɂ́A���z���^�����o�Đ^���ɖv���邩��A���̓��v�̏����ς��đ�������ɕ��̍�(�Ɋy�E���y��)�̏��݂�m��A�Ȃ��ċӕ�̐S���N���ׂ����Ƃ���������̂ł���B�@
���A����ɕ��̏�y���ς��邱�Ƃ�ފ݉�Ɩ��t�������Ƃ́A�������u�όo�`�v�̎U�P�`�ɓ�͔�����栚g�Ɋ�A���݂͑����ފ݂ł��邩��A�����g�������̋`�Ɋď̂��悤�ɂȂ����̂ł���B�@
���������̍�Ɠ`�����B��O��G�ފݎ��ɂ͏t���H���̑O�㎵���Ԃ͒��镽���ɂ��āA���͐�����������t�̔��Ԃ̔��|�𗣂�Đ�������ɂ̔��t�̘@��ɌX�����̂Ƃ�����ŁA������y��ފ݂Ɩ��t�������̂ł���Ƃ����B�@
�×����l�V�������ɉ��āA�ފ݉�ɗ�����q�����K���s��ꂽ���Ƃ��A���̖@��́u�όo�v���z�ς̐��ɋN����u���ׂ����̂ł��낤�B |
���ފ݉�
�@
�ފ݉�Ƃ͏t���̓��ƏH���̓��𒆐S�ɑO��O���ԁA���v�����Ԃɂ킽�镧���s���ł���B���̊ԁA�l�X�͐�c�̕�Q������A���ōs���Ă���������Ď����̋Ɋy�������肤�B�ފ݂Ƃ������t�́A�u�ފ݂ɂ�����v�Ƃ����Ӗ��̃T���X�N���b�g��p�[���~�^�[����o�Ă�����̂ŁA�Y�ݑ��������̐��E������(������)�ɁA�Y�݂̂Ȃ��Ȃ������̐��E��ފ݂ɚg���A���̊��Ԃɍ��݂���ފ݂Ɏ��邱�Ƃ�ڎw���B
�@
���̍s���͓��{�ł̂ݍs���Ă�����̂ŁA���i�Z�N(1269)�ɓ��{�ɗ��������̑�x�T�t���O�́u���{�ŏt�H��G�ɔފ݉���߂�͎̂��ɑA�܂������Ƃł���v�Ɗ��z���q�ׂĂ���B�����납����{�Ŕފ݉�s����悤�ɂȂ������͂����肵�Ȃ����A�������㏉���A�哯���N(806)�ɍs��ꂽ�@�v���N���ł���Ƃ����������B����́w���{��I�x�Ɂu�����V�c�̂��߂ɁA�S���̍������̑m�ɏt�H���A�����̊ԁA�����ʎ�o��ǂ܂����v�Ƃ���̂������Ƃ���B
�@
�ފ݉���{�ɂ����݂��邱�Ƃ���A���{�ɂ��Ƃ��Ƃ��������z���q�������s�������ꂽ�Ƃ����������B�ފ݂̎����ԁu���̔�(�Ђ̂Ƃ�)�v��u���}��������v������s�����c���Ă���B���͓��̕��̂��{�₨���A�����͓�̕��́A�[���͐��̕��̂����₨�{�ɎQ��̂ł���B����ɂ���Ĕ_�k�̈��S���F��ƂƂ��ɁA�����ߓ��Ƃ��đc��̗���܂�Ƃ��납���Q���O���Ɍ��т₷�������̂ł��낤�ƍl������B
�@
���̎l�V�����ł͔ފ݂ɐ���ɏW�܂�A��g�̊C�ɒ��ޗ[�������ċɊy��y�ɐ��܂�邱�Ƃ��肤�M������B����̊z�ɐ������q�̎��M�Ɠ`������u�߉ޔ@���@�]�@�֏��@���Ɋy���咆�S�v�̕��������邱�Ƃ���A�C���u�ĂĎl�V�����Ɛ����̋Ɋy��y�����������Ă���A�܂�l�V�����̐���͋Ɋy��y�̓���ɂ�����A�Ƃ����̂ł���B�t���ƏH���̓��ɑ��z�͐^������o�Đ^���ɒ��ނ̂ŁA���̐^���ɒ��ޗ[���͈���ɕ��̌���ł���ƌ��ė��}��q�݂����Ɩ]�ނ̂ł���B�@ |
���ߕ��@
�ߕ��ƕ����ƁA2��3��(���t�̑O��)�̓��܂��̂��Ƃ��v���܂����A�����u�ߕ��v�Ƃ́A�ǂ�Ŏ��̂��Ƃ��A�G�߂̕�����ڂ�����킷���t�ŁA���t�A���āA���H�A���~(�̑O��)�̔N4��܂����B�@
�u�S�͊O�A���͓��v�Ɛ����グ�Ȃ��瓤���܂��u���܂��v�͖�����̍s���ł��B�{���ő�A���ɍs�Ȃ��Ă����u�ǙT��(���Ȃ���)�v�Ƃ����A�Ђ����S�ɂ��Ƃ��A���S��ǂ������A�u�a����菜�������`���̋V���ɋN������Ƃ����Ă��܂��B�܂��A���ɍЂ������߁A�X�p�Ɏ̂Ă�Ƃ������K�ɋN��������Ƃ�����������܂��B�u���v�́u���Łv�̂��ƂƂ������Ă��܂��B������ɂ��悱���̕��K�����킳��A���t��V�����N(�G�߁A�t)�̎n�܂�ł���ƍl���A���̑O���Ɉ�N�̍Ђ��A�����菜���A�V�����N�̍K���������A�u���܂����v�ɂȂ����Ǝv���܂��B�@
���܂��͖{������ōs�Ȃ�����̂ŁA�ƒ��̑����J�������u�S�͊O�A���͓��v�Ɠ����܂��Ȃ���A��Ƃ̈�N�̍K�����肢�܂��B�n���ɂ���ẮA�u�S�͊O�v������A�Ă���ꍇ��u�S�͓��A���͓��v�Ƃ����ꍇ�A�u���͓��v�݂̂������ꍇ������܂��B�܂��A�܂��ꂽ����N�̐������H�ׂ�ƈ�N�Ԍ��N�ɕ�点��Ƃ�����`��������܂��B�@
�^���@�̎��@�ł́A���̎��ɂ��킹�A��ǙT�̌얀�������Ƃ����A�u�����v�Ƃ������Џ����̂��߂ɁA�e�l�̐��N�����ɂ��킹�������萯�����{����s�����s�Ȃ��܂��B�@
�u�����v�Ƃ́A�u���܂�v�Ƃ������A�l���ꂼ��̐��N�ɂ��{�����A�����ɂ��{���{�A�����ɂ��{���h�A�{���j���߁A����Ƃ��̐l�̈ꐶ�̉^�����x�z����Ƃ�����j��z�����A���N���������킹���{����A��J�^�̍s���B�C���h�N���B�@ |
|
���n���̑��� 2 / �R�`�����@ |


 �@
�@ |
���c�q
�@
A 13�A���͊�Ƃ������Ƃł��������A��肵�Ă��Ȃ��B13�̐���13�����炫�����ł��낤���H13���͑��V�̎��ɂ͊|�����A�D���{�̎��ɁA13����13�̂����т�������̂͒c�q�Ƃ͈قȂ�B
���A���V�̒c�q�̂���6���������Ԃ��ďグ��Ƃ����̂́u���l�̃Y�_�܂̒��ɂ͔�����6�A�ꕶ�K6������v�Ƃ������K���炫���̂ł��낤���B���Ȃ킿�A���҂��Z�n���ɒc�q���グ����A�Z���K�͘Z���K�A���ɎO�r�̐�̓n�����Ƃ�������B���A�e�n�̓`���ł��l�̂Ƃ��낪��������A�l�l��16��(�l�Ǝ��̑��ʂ���)�Ƃ����n�������A���łȂ��̂́u�싟�Ƌ����v���������Ă��邩��ł���B
�@
Q �������邩�A���Ȃ����̋�ʁB
�@
A ���c�q�Ƒ��V�̎��ɂ͂��Ȃ��B(�o����̋��{�ł���)�B
�@
Q ���̕~�����A�܂���A�����B
�@
A �����̑Ίp��3�Z���`�ʂ��炵�Đ܂�B�܂�ڂ̕����ɂ���B
�@
Q �c�q�������鎞�ԁB
�@
A ���c�q�͎��S�㒼���ɋ�����A���V�ɂ͓����̒��V���ɍ��B
�@
Q ����Ɏ����Ă����̂͂����H
�@
A �o����ɉΑ���Ɏ����Ă����A�Α���ɂ���Ɏ����Ă����B
�@
Q �V�����c�q�͂�������̂��H
�@
A �D���{�̏����̎��ɏグ��B
�@
�����O�o�ɂ���
�@
Q ��������̂��H
�@
A ���{���n�܂�O�ɏ�������B
�@
Q �����Ă͂����Ȃ��H���́H
�@
A ���A���A�����̂��镨(�j���A�j���j�N�A�^�}�l�M��)�B
�@
�����тɂ���
�@
Q ���т������鎞�ԁH
�@
A ���V�̓������A�O�Ő������V�O�ɏグ��B
�@
Q �`�H
�@
A ������(����)�B
�@
Q ���̒u�����H
�@
A ���O�g�p�̔��Ł{���ɑ}���B���肪�������2�{��}����������B
�@
Q ���o�������ɗ���ꂽ(�Z�E)�ɏo�����̂Ƃ́H
�@
A �����Ƃ����َq���x�B(�����A�ʖ�ɂ͐H���̏������K�v)
�@
���\�O��(�|��)�ɂ���
�@
Q �\�O���Ƃ͂Ȃɂ��Ȃ�������̂��H
�@
A ���������33������̖@���̎�蕧�l�ł��B
�@
Q ���g���̂��H
�@
A �D�A���������{�̎�����|����B
�@
�����������̖@�v���ȗ����čs���ꍇ������܂����A�S���Ȃ��������̉e���͂Ȃ��̂ł��傤���H
�@
A �ȗ����Ă͂����Ȃ��B�ʏ푒�V�Ɉ��������D�A�������A35���̋��{������̂͑ΊO�I�ȗ\�C���{�ł��B35���̎��ɂ�49���\�C�̊��グ�@�v�����l�ł��B�������A�\�C���{���s���Ă��Ă����������49����7��7���ɂ́A�e���͎��Q��Ƃ���Q��͓��R���ׂ��ł���܂��B
�@
�����ʎ������Ɏ��Q����v�����v�ɂ��Ă̐����B
�@
A �����̓��Ɉꏡ����ĂŖ݂����A�l�݂����c���49�̖݂����Ƃ����K���A������u�Ђ��ς�݁v�u���̖݁v�ق����낢��ȁu�싟�Ƌ����v������悤�ł����A�ŏ�n���ł͍��ʎ������Ɏ��Q����v�����v�̕��K�͕����Ă���܂���B
�@
�����V�̍ې_�I�ɔ�������\��̂͂Ȃ����H
�@
A �_�͕s��(����)�������邩��B(���͍��s��Ƃ�����)
�@
Q ���܂œ\���Ă����̂��H
�@
A 49�����B��ʓI�ɂ͊��グ�@�v(35��)�܂ŁB
�@
Q �Â����d�͊J���Ă����̂��A�߂�̂��B����͂Ȃ����H
�@
A ����c�l�ɂ��܂���ł���悤�J���Ă����ׂ��ł��B���̓s���ł���Ύd�����Ȃ��ł��傤�B
�@
�������ɋ��@�A��@�A���@3����ꍇ�A�u���ꏊ�ɂ���
�@
A ���������@�͊��̏�A���@�A��@�Ɍ��炸���ɂ͔w�̍������̂Ŏ�O���Ⴍ�Ȃ�悤�ɔz�u����B
�@
Q ���܂ŏ����Ă����̂��H
�@
A ���グ�@�v(35��)�܂ŁB
�@
Q 3��̂����ǂ��܂ł��ŏ����x�ɏ���Ȃ�������Ȃ��̂��B
�@
A �ŏ����x�͔��@�A��ʓI�ɂ͋��@������B��@�͍ŋ߂̕��K�ł��B
�@
���[���ɂ���
�@
Q �����̏��������ƒj���̈Ⴂ / �����̎d��
�@
A �t����(���ɓ���������)�ň�̂𐴂߁A�j���͕E����B�����ɂ͓����̑O�ɐg�̂���߁A���V�Ȉߕ��𒅂��A���ς��قǂ����ق��������B
�@
Q �����̎��p�ӂ��镨�H
�@
A ���(�o��q)�𒅂��A���ɂ͎O�p��̕z�X�����A�葫�ɂ͎�b�r���Ɣ����܁A��炼����𗚂�����B��ɂ͐�����ɂ��点�A��ɃY�_�܂�������B
�@
Q �����̍ہA���V���͗�����ׂ����H
�@
A �����͐e���ł��ׂ����́B�������˗��������̌���ł͂Ȃ��B
�@
Q �X�y�|�X��A�k�����ɓ��������Ȃ��ꍇ�͂ǂ���������K�����B
�@
A ������(�����Ɋy��y�̂����)�H
�@
Q �����̍ۂɊ��̒��ɓ����t���i�ɂ��āB
�@
A ���ɑ�(�̂̃o�b�O)�A�āA������A�����鎀�o�̗��H�̎x�x�B
�@
Q �Z���K�A�Ă����鎞�ԂƗ��R�H
�@
A �o���̎��ɓ����B�Z���K�͎O�r�̉͂̓n�����A�Z���K�Ƃ�������B
�@
Q �����ꏊ�ɍՒd�����鎞�ɕ��d�����ɉB��Ă��܂����Ƃ����邪�����̂ł��傤���H�B
�@
A �����Ƃ͂����Ȃ��B���ƂɒV�����{�����鎞�ɂ͂����̈ӌ����B
�@
Q �r��̂��䂸��̎g�����A�����鎞���H
�@
A ���V�̎n�܂鎞�ɑr��̗����Ɋ|����B
�@
Q ���䂸��Ƃ́H
�@
A �̂̑r��(��)�͔��ł��������ƂɗR�����Ă���悤�ł��B
�@
Q ���l�ɉ��ς���̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���H���ɏ����B
�@
A ���R�̐g�����Ȃ݂Ɛe���̐S�z��ł��B
�@
���Օ����ɂ���
�@
Q �ǂ̏ꏊ�ɓ\�邩�H
�@
A �o�������ꏊ�̊O���A���ȂǂɌЂœ\��(���œ\�邱�Ƃ�����)�B
�@
Q ���\��̂��H
�@
A �o��������A���~��|�����߂Ă���\��B
�@
Q ���R�H
�@
A ���߂̈Ӗ��ƖS�����̖��������̈Ӗ��B
�@
���Α���֍s�����́A�������ɂ���
�@
Q ���Q������́H
�@
A ���傤����A���ʔv�A�⍜���A�l�؉ԁA���@�A���ԁA1�{�ԁA�č������āA�����A��-�\�N�A�����A���сA�c�q�A�������A�Α�����(�Α����A�҂��Ă���Ԃ̈��ݕ��A���َq�Ȃ�)�B
�@
Q ���Q����i���̐����H
�@
A �l�؉ԁ|���߉ޗl�����ςɓ����鎞�ɍ����o�������F�ɕς����Ƃ��������o���тɂȂ��炦�A�Ђ��Ă͎��҂����ςɓ��鐴��̋��E���ے����Ă��܂��B
�@
A ���@�|�D���ɂ����č炭�@�͕��̋����̏ے��ł�����A����̋��E���ے�������̂ł�����܂��B
�@
A ��{�ԁ|���߉ޗl�����ł���鎞�ɁA���߉ޗl�̏\���q�̈�l(��ޗt)�͉������ꂽ���ɂ��āA�����ň�{�̉Ԃ��������l�ɏo��A�ނ��炨�߉ޗl�̓��ł����炳��A���̉Ԃ͔ނ̏���蓾�����������̂��ƌ��ꂽ���ɂ��܂��B���A���ł̎��A�����o���̒����}�����ꉺ�������������痈�Ă���Ƃ������܂��B
�@
A �����|�͓̂��t�������܂œ_��䶔��ɂӂ��܂������A���݂͋V���̂Ȃ��Ŏg�p���܂��B
�@
A ���с|���������������(������)���̐l�ɂ͍����グ�Ȃ��Ƃ������邵�ɔ��𗧂Ă�Ñ㉏��@�ł�����܂��B
�@
A �c�q�|���߉ނ��܂��S���Ȃ��鎞�A��q�����������̗ǂ��c�q��ɂ��Ă���������ꂽ���A�����オ��Ȃ��Ŗ����ƂɎc��܂����B������^�ǂ��Ă̂������ł��B
�@
Q �����Ƃ̈Ⴂ�͂���܂����H
�@
A ���V�̑O�̉Α��𖧑��ƂƂ炦�Ă������������܂����A�{�������Ƃ͌���A�{���V(���ʎ�)���s���ꍇ�ɁA�܂��͐e���݂̂ő��������鎖�������B�܂������ƍ��ʎ��̈Ӗ��̈Ⴂ�́A�����͌̐l�̐M����@�h�̑��V���̎��ł���A���ʎ��Ƃ͑����ł���Ƌ��ɁA�̐l�̐��O�̐E�Ƃ�l�����Â���(�|�\�l�̉��y���Ȃǂ̍��ʎ�)�̕ʂ�̎��ł��B���������ĕ��ʑ��V�̏ꍇ�u���ʎ�������s���܂��v�ł͂Ȃ��u���V�v���́u���V�A���тɍ��ʎ��v�Ƃ����̂��������B
�@
�����ʎ��̍ۂɎ��i���̎�ށA�y�т��̖����A���l�̏��Ԃ͒N�ɂ���̂��H
�@
A �r�傪�ʔv�����B�⍜�A�ʐ^���͋ߐe�҂ő��k���˗�����B
�@
Q ���؈ʔv2���̑��V��̈����H
�@
A �u�V�A���v�Ə�����Ă���ʔv�͉Α��ꂩ�炨��Ɏ����Ă����܂��B������͊D���{����49���܂ł̈ʔv�B���グ�@���̎��ɍ��h��̐V�����ʔv�ɐ�����(������)�����Ă��炢�܂��B
�@
Q �č����鎞�̎菇�A�����̗ʂƉH
�@
A �傫�ȑ��V�ł́A�r�傻���ĉƑ��̏č��A���V�ψ����A�s���A�����A�Ζ���̎В����̌�A�ߐe�҂��i��ē�����B��ʎ҂͔����̏č����B���ʂ̑����͉č��ł��邪�A��������Ɗm�F���Ă����B
�@
A �č��̎d���́A����ɂĐ��������������킹�Ă���E��ō����܂݊z�̂Ƃ���ɒ����č��F�ɂ����A�X�Ɉ��܂�ō��x�͊z�ɒ����Ȃ��ł��̂܂܍��F�ɂ����̂���������@�Ƃ���Ă��܂����A���V�̂悤�ɑ�R�̕����č������Ƃ��ɂ͈��ōς܂���̂��悢�ł��傤�B
�@
���M�m�Ƌ��m�̈Ⴂ�H
�@
A �M�m�͐M�S�̓Ă��j�̐l�Ƃ����Ӗ��B���m�͐M�S���Ă����Ɍ��J������Љ�I�ɂ��v���̂������l�B
�@
���~�j�i(�����i)�̏�����H
�@
A �i�̏㕔������13�����|���A��i�����Ɉʔv�Ɠ��k�A�ʔv���Ɏʐ^�A��i�E��13���̕��сA�ʐ^�̗������Б��ɒc�q�B�������Ȃǂ͓K���ɔz�u����B
�@
����l�ԂŊ���[�߂Ă��獇�����Č������t
�@
A ���Ɍ��܂��Ă���܂���A������O���������ĉ�����
�@
�������͂���Ă������̂��H
�@
A �{�R�ɓ��ɕ�����]����ꍇ�ȂǂłȂ���ΕK�v�Ȃ��ł��傤�B�R���Ȃǂɔ��������łɕ�������Ă���ꍇ�͎d���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@
������������ꍇ���������g���Ă����̂��H
�@
A �������ɂ͂̂ǂڂƂ��A�Ɠ������A���������܂��B�����ł�35���̊��グ�@����A������[������ꍇ�������悤�ł��B�����Ɣ[���͎��ƒn��ɂ�荷�ق�����܂��B
�@
�����Ԃɂ���(�}���L��)
�@
Q �����Ă����Ȃ��Ԃ͂���܂����B���Ƃ��o���Ƃ��E�E�E�H
�@
A ��ʓI�ɂ́A�g�Q��ł̂���Ԃ͎g���܂���B
�@
Q ���ނ��̉Ԃ̈Ӗ����炵�āA�Ԃ̐��ʂ͂ǂ���Ɍ�����̂��H
�@
A ���Ԃ̐��ʂ͔q�ޑ��Ɍ����܂����A�}���L�ԂƂ����̂́E�E�E�H
�@
Q ���Ђ̉Ԃ̕i���A�ʂɂ��Ė������Ă��������Ă���ł��傤���B
�@
A �Ƃ��Ɉ����]���͂���܂���̂Ŗ������Ă���Ǝv���܂��B
�@
�������|�\�N�Ɖԃ��|�\�N�̈Ⴂ�H
�@
A ���V�̎��ɂ͐ԃ��|�\�N�łȂ���Δ����|�\�N���ԃ��|�\�N�Ŗ�肠��܂���B�����ł̐ԃ��|�\�N�͈�ʓI�ɂ͂��j�V�p�ɂȂ�܂��B
�@
�����̖؋��Ɠh�̖؋��Ƃ̈Ⴂ�H
�@
A ���ؖ؋��͍����Ȃ��̂ɑ����悤�ł����A�h��͑ʖڂƌ������̂ł�����܂���B�w���͍D�݂̖��ł��B
�@
���r������߂�ہA��ԂɌ��߂鎞�̊
�@
A �s��ł͔������r��Ƃ����������悤�ł����A���n�ł͐Ռp�����r����Ƃ߂܂��B�������A�Ռp�����q���̏ꍇ�Ƃ��A��ނȂ��ꍇ�ɂ͐e���ŋ��c���Č��߂邱�Ƃ��̂��܂����ł��傤�B
�@
�����D�̂Ƃ��A���ԁA���Ԃǂ��炪�K�����H
�@
A ���Ԃ������̂ł́E�E
�@
���̂��܂̕\�����ɂ��Ă̋��
�@
Q ���O�E�䕧�O�E����݁E�܂��D�̏ꍇ�̕\�����́H
�@
A ���O�͏@�h���킸�g����B��ʓI�ɂ͓����A�ʖ�Ɍ�������O�A���V�ɂ͌䍁�T���A�䕧�O�B�D�ɂ͌䕧�O�Ə������������ɊD�{�Ə����Ηǂ��B
�@
������̑I�ѕ��@�h�Ƃ̈Ⴂ�Ǝ�����
�@
A ��y�@�Ɠ��@�@������ł����A���͂قƂ�LjႢ������܂���B�������͍���e�w�Ɛl�����w�̊ԂɊ|���č������܂��B
�@
�������̗��ĕ��A�{���̌��܂�́H
�@
A �����̖{���͕��ʈ�{�ł����̂ł����A2�{����3�{�グ�Ă����\�ł����{�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����L�}���͂���܂���B�����@�ł̐����ȏグ���͍��ƉE��2�{(�}������)���グ�A�����ɏグ��1�{�͗���ŔO���Ă���グ�܂��B�܂��A�n��̏K���Ƃ��đ��V�̑O�ɂ�1�{�A���V�̌��2�{�Ƃ����`���͂���܂��B���Ȃ݂Ɏ��͎��@�̊e���l�ɂ͖���1�{�Âグ�A���V�Ɩ@���ɂ�3�{�グ�Ă��܂��B
�@
���ތ�A�J�l�A�؋��̒u���ʒu�͌��܂��Ă���̂��H
�@
A ���ɃJ�l�A�����ɏތ�A�E�ɖ؋��ł��B
�@
���Ȃ��������K�v�Ȃ̂ł����H
�@
A �������A�����Ƃ����ƁA�l���S���Ȃ������Ɏ������Ă����邾���̂��̂ƍl���Ă����������悤�ł����A����͑�ςȊԈႢ�ł��B�������͖{������ł���K�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ݕ��̎q�Ƃ��Ă̐����������A�ݕ��̉�����S�Ƃ��Đ��i�v���܂��Ƃ��������̏Ƃ��Ă����������̂ł���܂��B�C�؋`�ɂ́u�O������������Ȃ킿�����̈ʂɓ���v�Ǝ�����Ă���܂����A�����Ƃ͎��ǂ������ׂ��S�̂��܂���(���@)�������đՂ��A�����k�Ƃ��Ď��o�������炵�����鎖�ł���܂��B���ꂪ�Ƃ������ɂ݂₰�Ƃ����悤�ɂƂ����ʂ̌X��������̂ł����A�F�������߂Ă��������������̂ł��B�@ |
 �@ �@
�����{�̂����� |


 �@
�@ |
���ꕶ����(�I���O10000�N�`�I���O800�N�O)�@
�ꕶ����@�ɂ́A�f�@�̌��Ɉ�̂߂�̂����ʂ������悤�ł��B�܂��A�Z���̋߂��ɂ܂Ƃ߂Č@��ꂽ���ɁA�y���Đ���ׂ���A�쌴�Ŋ����`����Ă��̒��Ɉ�̂���ꂽ��A�؊��ɓ���邱�Ƃ��������悤�ł��B�@
�ꕶ���������ɂȂ�ƁA��̂�����ł����A���g���g�ɂ����肵���������悤�ł��B�@
���퐶����(�I���O800�O�`�I����200�N)�@
�퐶�����ʂ��đf�@��̌��Ɉ�̂�����u�y������v����ʓI�ł����B�������ǂ̒��x�̍L����������Ă������͕s���ł����A�퐶����͂��߂ɒ��N��������`����ꂽ�x�Ε�(���a1�`2���[�g���̔�̐������ȐŎx���Ď����グ����)���A�퐶����O�����ɂ��P��(�₫���̂��P)���g����悤�ɂȂ�܂��B�����Ɍ@���Č����P�����ĐȂǂłӂ�������Ȃǂ̂��������������悤�ł��B�@
�܂��A���ł͔��^�̖؊��������A�֓��ł͂�������������̂�قɓ���Ȃ����đ��悪�s����ȂǁA���܂��܂ȑ��������B�����悤�ł��B�@
��������(�I����200�N�`�I����700�N)�@
�Õ�����ɂ́A�a���@���A����y�������(���`���a��)���o�ꂵ�܂��B��n�͐���琔�\��̋K�͂̕��������̂ł����A���ꌧ�̕�����Ղ̂悤�ɐ��S���̕��`���a�悪����ł���Ƃ��������܂��B�@
���̕��`���a��͂₪�đO����~���ɔ��W���A�S���I�ȍL����������܂��B�@
�Õ�����̌���ɂ́A�����W�������i�݁A�n���̌��͎҂���ቺ���A�Õ������^�������^�Õ��≡�����̕悪���������悤�ɂȂ�܂����B�@
�����j����(�����ŏ����ꂽ���j�����鎞��)�@
��a�������S�����������A���肵�Ă���ƂƂ��ɁA���͎҂̑��V�͑�|����ɂȂ��Ă��܂��B������͎҂̏ꍇ�ł����A�q�{(������݂̂�)������A�ߐe�҂������őr�ɕ����V���������̂��߂̋V�����s�����Ƃ���Ă��܂��B���̟q�{�ł̒ʖ�͍��ł�(���a�V�c�̎����̍ۂɂ�)�s���Ă���悤�ł��B�@
�����A��ʐl�ɂ��ẮA鰎u�`�l�`�Ɂu���̎�����⊻�L��ǂ���(�̈͂�)�����A�y���ăc�J�����B�n�߂Ď������A��r(�r�ɕ���)���邱�Ə\�]���Ȃ�B���ɓ�����ē���H�킸�B�r��L�����A���l�A���ĉ̕����������B�߂ɑ����A�Ƃ������Đ����ɂ�����ă\�E�����A�Ȃė����̔@�����B�v�Ə�����Ă��܂��B�@
(���ʂƊ��ɔ[�߂邪�A��(�����{��)�͍�炸�A�y��グ�ęn(���)������B���Ƃ��A�����������ď\�]���͑r�ɕ����A���̊Ԃ͓���H�ׂ��A�r��͐��������ċ����A���l�͂��̎���ʼn̕��E���H����B�@
��������ƁA��Ƃ������āA�����ł݂��������A�����ň�����ɗ���(�ط��)�𒅂ğ�������̂Ƃ��Ȃ��悤�ɂ���B)�@
���ł��c�ɂɍs���A�����ɂ͎O���Ԃ͈��ݐH�����R�Ƃ����Ƃ��낪����Ƃ������܂��B��̑O�܂ł͂��ꂪ������O�ł����B���������K���́A�p�ꂸ�������̂��Ɗ��S�������܂��B�@
���剻�̉��V�������߁@
����645�N�A���ߍ��Ƃ�ڎw���āA�剻�̉��V�̏ق��������܂��B�����N�ɔ����̏ق��o����܂����B�q���ւ��A�g���ɂ���čׂ�����̑傫�����߁A�}���╛���i���֎~���܂����B�ق́A��K�͂ȑ��V���u���납�Ȑl���s�����Ƃł���A���̕n�������Ƃ͂����ς猠�͎҂��傫�ȕ����邱�Ƃɂ���Ă���v�Ə����Ă��܂��B�@
���̔����߂������āA�Õ�����͏I���܂��B�@
���剻�̉��V�������ꏊ�̒�߁@
�����قɂ́A�u����킵�������ɖ��������A�ꏊ�ɖ�������v�Ƃ��āA��n���߂܂����B����́A��(701�N)�̑�߂̑r���߂ɂ����Ă��A�u�c�s�Ƃ��̓��H�̑��ɖ������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƒ�߂��܂����B����́A�����炭���̂̈���ɋ߂����Ƃ�����Ă������Ƃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�@
���Α��@
7���I�ɂȂ�ƕ����̉e�����āA�Α����s����悤�ɂȂ�܂��B���{�ɂ�����ŏ��̉Α��́A����700�N(8���I����)�A�@���@�̑c�E�����������Ɠ`�����Ă��܂��B(���������́A7���I�͂��߂̈�Ղ���Α��̐Ղ����@����Ă��܂��B)�@
703�N�����V�c���⌾�ɂ���ĉΑ�����܂��B���̌�A�����V�c�A�����V�c�A�����V�c�ƉΑ��������܂����A���̌�V�c�Ƃ̉Α��͓r�₦�A840�N�~�a��c����ĂщΑ����n�܂�܂��B�@
�~�a��c�́A�u���͓V�ɏ����Ă���̂ɖS�[����ɂ����āA����ɗd�����Z�ݒ����Ĉ������Ƃ����Ȃ�����A�Α��㍜���ӂ��ĎR�̒��ɎT���U�点�v�ƈ⌾���A�匴�쐼�R�ɎU������܂����B�����c���A���������s���邽�߂ɁA�ׂ��Ȉ⌾�����������ł��B�@
������ / ��C�@
811�N�^���@�̊J�c��C(���O�@��t)�́A���s�̊X�ɑł��̂Ă��살�炵�ɂȂ��Ă�����̂��A����(�������́E���s�s�����)�ɖ���(�u�����������H)�����Ɠ`�����Ă��܂��B�ȗ�����ƒ��Ӗ�(�Ƃ�ׂ�)���A���s�ɂ����鏎���̕�n�ƂȂ�܂��B�@
���u�����v�W�v�@
���̂���A���̐��̖����Ǝv�킹��Q�[��u�a�̗��s�ɂ̂��āA���@�v�z���L����܂��B�l�X�͋~�������߂ċɊy��y���܂��B�����ɁA���S�m�s���M������A�Ɋy��y�֍s�����߂̕��@������܂��B����͋�̓I�ȗ�������Ȃ���̐��@�ŁA���M�̒n����Ɋy�Ƃ����v�z�͑����̐l�X�ɍL�܂�܂����B���M�͂Ƃ��Ƃ�l�Ԃ��q�ꂽ���̂ƂƂ炦�A�u�얳����ɕ��v��O���ċ~�������߂�悤�����܂��B�@
�܂��A���M���u�����v�W�v�ɏ������ՏI�̍�@�́A��X�܂ő��V�ɉe����^���܂��B�����̑��V�̍�@�̑��������M�Ɏn�܂����Ƃ����Ă��܂��B�@
�������ɂ�鏎���̋��{ / �m�E���Ł@
1181�N�A�����{��{�a�̑�Q�[���P���܂��B�������͑�\��u����L�v�ɁA�u���̂قƂ�ɁA�Q�����ʂ��̂̂����ЁA�����m�炸(4���]-����)�B�E�E�E���������ɖ��������āA�ς��s�����肳�ܖڂ����Ă��ʁE�E�E�B�͌��Ȃǂɂ͔n�ԂȂǍs�����ӓ����ɂȂ��v�Ə����Ă��܂��B�܂��ɒn���̂悤�Ȃ��肳�܂��A���̕��͂͐��m�ɓ`���Ă��܂��B�@
���̂Ƃ��A�m�a���̑m�E���ł����s�̒����߂����Ď��҂��܂����B���̂��ƂɊ������͂�قNJ��������̂ł��傤�B����L�ɂ́u���Ŗ@��Ƃ����l�A�E�E�E�����m�炸���ʂ邱�Ƃ�߂��݂āA���̎�݂̂�邲�ƂɁA�z�ɁA���̎��������āA���������ނ�v�Ə����Ă��܂��B�@
�u���v�́A100���镧����̈Ӌ`��^�����A�����̍����ł���s�łł��邱�Ƃ��Ӗ����邻���ł��B�u���v�Ƃ͎��҂ƕ��̉����Ӗ����܂��B�m�E���ł́A�܂��Ƃɖ����������҂����{����Ƃ����A�@���҂炵���u��̌������l�ł����B�m�E���ł́A���̒���2�����Ԃ��̍s�ׂɖv���������������ł��B�@
�������̗��s�E���q����@
���q����ɂ́A�����̂��߂̕������������ւ�܂��B�@�R�̏�y�@�A�A���̏�y�@�W�������e�a�̏�y�^�@�A��Ղ̎��@�A���@�ɂ����@�@�Ȃǂ��J����܂����B������������̋~�ς��f���܂����B�@
��y�@�́u�N�ł��O����������Ɋy��y�ɂ������Ƃ��ł���v�A���@���u�N����1�x�̔O���ŕ��ɂȂ邱�Ƃ��ł���v�Ɛ����A���ʂȏC�s���i�������Ă��A�����ł���Ƃ����l�����͑����̖��O�Ɏ������Ƃ���ƂȂ�܂����B�܂��A���@���@�،o����ʂ��Ė��O�~�ς��s�����Ƃ��܂��B�@
��y�^�@�̊J�c�͐e�a�ł����A����ɂ�����p���̑�ȕz���҂����܂�܂��B1415�N�ɑ�J�{�莛��8��ڂƂ��Đ��܂ꂽ�@�@�����̐l�ł��B�@�@�́A��y�@�̊J�c�e�a�́u�P�l�Ȃ����ĉ����𐋂��B�����∫�l����v(�V�ُ�)�Ƃ������t�̎v�z�������A���ׂĂ̖��O���~�ς���ƍl�āA���̋������L�߁A���ꂪ���O�̊ԂɎ�����܂��B�@
�܂��A���q����ɂ͑v����T�@(�ՍϏ@�⑂���@)������(�v)����`�����܂��B�T�@�͈ʔv����{�Ɏ������݂܂����B���Ƃ��ƕ����ɂ͈ʔv�͂���܂���ł����B�T�@�͎̑��V�Ɏg���Ă��܂������A���{�ɂ��ꂪ�`������ƁA���m�̊ԂɍL����܂����B�@
���]�ˎ��� / �@
�]�˖��{�͂͂��ߎ�w���d�p���܂��B�`�⒉�Ƃ������v�z�ɍ]�˖��{���ڂ����A�����x�z�̒��S�v�z�Ƃ������Ƃ͗e�Ղɗ����ł��܂��B�@
�ł́A�l�͎��˂A�V�ɏ��鍰���u���v�ƒn�ɍ~����́��u鮁v�ɕ������B�ƍl�����Ă��܂�����A�y�����ւ��܂����B�@
���]�ˎ��� / �h�����x�@
�]�˖��{�́A�������@���R���͂������Ĕ������N�����̂�����邽�߁A�������@�O������������āA���O���x�z���邽�߂̓���ɂ��悤�Ƃ��܂��B���̂��߂ɍ�������x���A�u�{�R�������x�v�Ɓu���������x�v�ł��B�@
�u�{�R�������x�v�́A�e�@�h�̖{�R���߂Ă��̑����Ƃ��Ď��@�̎x�z�̌n�����A�����ʂ��Ď��@���x�S�̂{���x�z����Ƃ����ړI�ō���܂����B���̌����𐧌�������m���̋���ɂ��K���͋y�т܂����B�@
�܂��A���{�̓L���V�^����r�����邽�߂Ɂu���������x�v�����܂����B�N�����ǂ����̎�(�h�ߎ�)�ɏ��������A���́u�@�|�l�ʒ��v(�ː�)������A�����̐l�X���L���V�^���ł͂Ȃ����Ƃ��ؖ����܂���(�����ؕ�)�B�l�X�͂��̎������ؕ���������A���s�⌋���A���z���͂Ă͑��V�����o���Ȃ��Ȃ�܂����B�₪��1637�N�ɋN�������V���E�����̗������������ɁA���������x�͋�������Ă����܂��B�O�ꂵ���L���X�g���k�e������(�@�����)��B��L���V�^���̂��Ƃ͂͂悭�m���Ă���Ƃ���ł��B�@
���]�ˎ��� / ���������̊����@
���������x�����ꂽ����́A�ӂ������͑��V�炵�����V�����܂���ł����B�������A���������x�����������ɂ��������āA���@�̑��V�Ɋւ���͂���������A���ɂ͒h���̏Z�E�����V�����v���鎖�ԂƂȂ�܂����B���@���͢�@��h�ߐ����V�|�v���U�삵�A���V�ւ̎��@�̊֗^���������悤�Ƃ��܂��B�U��Ƃ͒m��Ȃ��h�Ƃ́A��@��h�ߐ����V�|�v�ɂ���āA�l�����ʂƒh�ߎ���������������A�L���V�^���łȂ����Ƃ��ؖ�������A�������������V���s�����Ƃ����`���t�����܂���(�Ǝv������ł��܂��܂���)�B�@
���̂Ƃ��ɒ�߂�ꂽ���ɂ�鑒�V�͊�{�I�ɂ͌���ɂ܂ň����p����Ă��܂��B���V�ɍۂ��ẮA������n�������ւ̎ӗ�A������������d�������ւ̎ӗ�A������A�ʖ��@�v�̎ӗ�Ȃǎ��@�ւ̎x�������K�v�ƂȂ�܂����B�@
����ɂ��h�����x���������A���V�̂����ƁA���̑��V�ɂ���Ė����͒h�Ƃ���A�{�R�͖����������I�Ȏ�����Ƃ����V�X�e�������グ���܂����B�����͂ق���т������Ȃ�������Ɏ����Ă��܂��B�@
�܂��A���̎���ɂ͑��V�ɂƂ��ďd�v�ȏ������o����܂��B��y�@�̑m���ł��銴�@�Е�棂��������u�������ߏW�v������ł��B�u�������ߏW�v�́u�����v�W�v�ƕ���œ��{�̑��V�ɑ傫�Ȏw�j��^���܂����B�u�������ߏW�v�͑��V�̍ו��ɂ킽���Ď��ׂ��ɁA�������V�̎���������Ă��܂��B�@
�������ېV / �_���Ղƕ������V�@
�ېV���{�́A�_���̍������������߁A������������̂�܂��B1868�N�_�������߂́A�_�Ђ��畧���F��r�����悤�Ƃ�����̂ł������A������u�p���ʎ߉^���v�������N�����A�S���I�Ȏ��@�j��ɂȂ����Ă����܂��B���{�ɂ���̉����͂��ނ��ڂ��Ă������ɑ���Љ�̔�����������x���܂����B1872�N�ɂ͐_�������q�̑��V���s�����Ƃ��F�߂��A�_���Օ�n���s���e�n�ɂ����܂����B�@
1873�N�ɂ͐_������������ɂ̂��Ƃ�A�Α��֎~�߂��o����܂����B�u�Α��͕����k�̂��̂ŁA�Α��͎c�s�̂���݂ł���v�Ƃ����̂����R�ł����B�������Α��֎~�߂͔��ߌ�2�N��ɂ͎�������܂��B��n�s���Ȃǂ̗��R���������̂ł��傤���A�������{�̒������U�肪���������܂��B�@
���������̂���o���ꂽ(1874�N)�u��n�y��������K���v�ɂ���āA��n�ȊO�ւ̖������֎~����A���{�̕�n�▄���Ɋւ���K���ɑ傫���e����^���Ă������ƂƂȂ�܂����B�@
�ꎞ�͈ېV���{�̕ی�̉��A�_���Ղ����������Ȃ���悤�ɂȂ�܂������A�����1882�N�_�������E�����߂��o���ꂽ�̂��_�@�ɁA���ɂȂ�܂����B
�@ |
 �@ �@
�����{�ɂ�����Α��̎n�܂� |


 �@
�@ |
���{�ɂ�����Α��́A�����V��4�N(����700�N)3���ɑm������䶔��ɕt�����̂��n�܂�ł���ƁA�����{�I�̋L�^�ɂ���B���2�N12��(703�N1��)�ɂ́A�����V�c�����̓V�c�Ƃ��Ă͂͂��߂ĉΑ��ɂ���A�V�c�̑������������V�c�A���������̌����Ƃ��̕ꌳ���̗�������܂��Α��ɕt���ꂽ�B����Ȍ�A�V�c���Α������̂́A�㒹�H��c��k���̊e�V�c�ȂǁA�ꕔ�̗���̂����A�Ȃ���Ȃ������̂ł��邩��A8���I�����̂��̎���́A�Α������̕������ۂ��������Ƃ��A�@������̂ł���B�@
�����ȑO�́A�Ñ�̓��{�l���S���Α����s��Ȃ������Ƃ����A�����ł͂Ȃ��炵���A�h�l�ȂǍs�H�̓r�ɓ|�ꂽ�҂Ȃǂ́A�Α�����Ă����炵���B�q�ǂ��̈�[���܂��A�Α�����邱�Ƃ����������悤�ł���B�@
�����͌����g�ɏ]���ē������A�����O���ɋ��������������m�ł���B�A����͓��{�̊e�n������A�y�؎��ƂȂǂ��N�����Ă���B���̒�q�̍s����܂��A�t�̋������āA���{�e�n�����������A���O�ɉΑ���i�߂��Ƃ����Ă���B�ނ炪�Α��̕��y�ɂƂ߂��̂́A�����v�z�Ɋ�Â����̂��Ǝv���邪�A���ꂪ���{�l�̊Ԃł���������R���Ȃ������ꂽ�̂́A���{�l�̕����`���I�ȗ썰�ς��A�Α��Ƃ������̂ɑ��āA�����I�ɓ��������炾�Ǝv����̂ł���B�@
�Ñ�̓��{�l�ɂƂ��āA�썰�Ƃ������̂́A�g�̂Ƃ͕ʌ̑��݂ł������B�l�����܂��Ƃ������Ƃ́A�썰������҂̐g�̂ɏh��Ƃ������Ƃł���A�l�����ʂ�Ƃ������Ƃ́A�썰���g�̂�����Ƃ������Ƃ������B�썰�͈ꎞ�I�ɐg�̂����邱�Ƃ��������B���_�����Ƃ��������ł���B������A�l�тƂ͐l�����_������A���肵���Ƃ��ɂ́A�썰���Ăі߂��Ă��邱�Ƃ��F�����B����ł��Ȃ��A�썰�������܂ł��߂�ʂƂ��́A�썰�����̐g�̂������āA���̂��̂ɏ��ڂ����̂��낤�Ƃ�����߂��̂ł������B�@
�@���ɂ���ẮA�l�͐����Ă������̎p�ł��̐��Ɍ}������Ƃ����M������B���������M�ɂ����ẮA��̂���������A�܂��ďĂ��Ă��܂��Ȃǂ́A�l�����Ȃ����Ƃ��Ƃ����悤�B�������A�Ñ�̓��{�l�����ɂƂ��ẮA�g�̂͗썰�̉��̏h�肾��������A������Α����邱�Ƃɂ����āA�ُ�Ȓ�R�������邱�Ƃ��Ȃ������̂ł���B�@
���t�̐l�`�{�l���C�́A�����̎��̑O��ɐ������l�ł���B���̍�i�̂Ȃ��ɁA�Α����r�́A���邢�͘A�z������̂�����������B������ǂ݉����Ȃ���A�l���C�̎���ɂ�����Α��̃C���[�W�ɂ��čl���Ă݂����B�@
�y�`���q�𔑐��̎R�ɉΑ����鎞�ɁA�`�{���b�l���C�̍��̈��@
�����肭�̔����̎R�̎R�̍ۂɂ�����Ӊ_�͖��ɂ�������ށ@
�����̎R�́A�l���C�̎���Α����s����Ƃ��낾�����炵���B�����ŋM�����Α����ꂽ�Ƃ���L�^������A���̔҉̂��A���������M���̉Α����r���̂Ǝv����B�R�ۂɂ����悤�_�Ƃ́A�Α��̉��������Ă����Ă���̂��낤�B���̉��ɁA���҂̗썰���d�ˍ��킹�A���҂Ƃ̕ʂ���������Ă��邱�Ƃ��f����B�l���C�́A�{��̐l�Ƃ��āA���M�Ȑl�тƂ̔҉𑽂̂���������A�Α����r�������̉̂ɂ́A�Â��C���͊������Ȃ��B�@
�M�ꎀ�ɂ��o�_���q���g��ɉΑ����鎞�ɁA�`�{���b�l���C�̍��́@
�R�̍ۂ�o�_�̎q��͖��Ȃ��g��̎R�̗�ɂ��Ȃт��@
���̉̂ɂ����Ă��A�썰�͖��ƂȂ��āA�R�̕�ɂ��Ȃт����܂��r���Ă���B�l���C�̎���A�썰�́A�g�̂𗣂�Ă��A���ꎩ�̂͑��݂������A�₪�đ��̐g�̂ɏh���āA���炽�Ȗ��Ƃ��Đ����Ԃ�ł��낤�Ƃ����A�M�̂悤�Ȃ��̂��������B���ꂪ�A���̉̂Ɍ�����悤�ɁA�Α��̃C���[�W��O�����ɂƂ炦�������̂ɈႢ�Ȃ��B�@
�ȏ�2��́A�����̎���A�Α����L�������������̉̂ł���B�Ƃ��낪�A�l���C�ɂ́A�ŏ��̍Ȃ�S�������Ƃ��ɉr�̂������āA�����ɂ��Α��̂��Ƃ��Î�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ�����������B���̉̂́A��{�ł͎��̂悤�ɂȂ��Ă���B�@
�`�{���b�l���C�̍Ȏ����Č�ɋ������Ԃ��č�肵�́@
�c�咹�̉H�Ղ̎R�ɓ������ӂ閅�͍����Ɛl�̉]�ւΊ⍪�����@
�݂ĂȂÂݗ����ǂ��������Ȃ������݂Ǝv�Ђ������ʂ�����@
�ق̂��ɂ��ɂ������Ȃ��v�ւ@
����ɂ͈ٖ{�������āA����ɂ��A�Ō�̕������قȂ��Ă���Ƃ����̂ł���B�@
�ȂÂݗ����ǂ��������Ȃ������݂Ǝv�Ђ������D�ɂč����@
�����Ă���Ǝv�����Ȃ��D�ɂȂ��Ă����Ƃ́A�Α�����Ă����Ƃ����Ӗ��ł���B���ꂪ�����A�l���C�̉r�����{���̎p�������Ƃ�����B�҉̂̑Ώۂ���Ȃ͓����̎��ȑO�Ɏ��Ƃ���Ă���̂ŁA�Α��͓����̎��ȑO�ɂ��Ȃ���Ă����؋��ɂȂ�B�@
�l���C�̐��U�ɂ͕s���Ȃ��Ƃ������A�w�҂̘_���̎�ɂ��Ȃ��Ă��邭�炢�ł��邩��A�ނ�����l�́A�M�҂̂悤�Ȏ҂̂悭�Ȃ�����Ƃ���ł͂Ȃ��B�������A���̔҉̈���Ƃ��Ă��A�ЂƂтƂ̑z���͂�~�����ĂĂ�܂Ȃ��Ƃ́A�l���C�͂������ɑ�̐l�ł���B
�@ |
 �@
�@
�����{�̖������� |


 �@
�@ |
�����̔����܂ł́A���{�l�̖����͓y�������|�I�ɑ����A�Α��͈ꊄ���x�������Ƃ����B��������s�Ȃǂ̊����̑�s�s��A�^�@�n�тɕ��Ă���A�w�ǂ̐l�͓y������Ă����̂ł���B�@
�Α����}���ɕ��y����̂͐��̂��Ƃł���B����ɂ́A�s�s���̐i�W���e�������ƍl������B�܂��A�s�s���ɔ����]���̑�Ƒ����x����̂��A�~�j�Ƒ���P�ʂɂ����Ƒ��悪���y�������Ƃ��w�i�ɂ���Ǝv����B���a40�N����ɂ́A�Α��̕��y����30���p�[�Z���g�ɂȂ�A�����ł͎���99�p�[�Z���g����قǂɐi�B�@
����ɂ��Ă��A�������j�̒��ŁA�y���Ɋ���e����ł����������A�������Z���Ԃ̂����ɉΑ������ɐ��܂�Ƃ����̂́A����Ӗ��ŋ����ׂ����Ƃł���B���ɐ������ꂽ��n�E�����@�߂��A�Α��̕��y���������Ƃ�������������ɂ���A�����̈ӎ��̂Ȃ��ɂ���������y�낪�Ȃ���A���肦�Ȃ����Ƃ������B�@
���{�l���×����X�ƕ����Ă��������ς�썰�ρA���̗����Ƃ��Ă̈�̂ɑ��銴�o���A�Α��ɑ��Ċ��e�ȕ��y�������炵�����炾�낤�B����A����̓��{�l�͕��������ɂǂ��Ղ�Ɛ��܂�A���̕������Α��Ɋ��e���Ƃ������������B���e�Ƃ������́A��̂��̂��̂ɑ��āA�����̋��`�͖��ڒ��Ȃ̂ł���B���̂��Ƃ��A���{�×��̗썰�ςƌ��т��āA��̂ɑ��閯�����L�̑ԓx�����������̂ł͂Ȃ����B�@
���悤�ɁA���{�l�́A���̖����Ɣ�r����ƁA���҂̈�̂ɑ��āA���ΓI�ɖ��ڒ��Ȗ����ł���Ƃ�����B�����������_�I�ȓy�낪�����āA�����ɑO�q�����悤�Ȍ����I�Ȏ���d�Ȃ������ʁA�Z���Ԃ̂����ɉΑ��������I�ɕ��y�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł���B�@
�����ŁA������x���j��k��A���{�l�̖��������ɂ��Ē��Ղ��Ă��������B�@
�Ñ���{�̖��������ɂ��ẮA���܂�ڂ������Ƃ͂킩���Ă��Ȃ��B�퐶����ȑO�ɁA���ł��P����؊���p���ēy�����Ă������Ƃ͂킩���Ă��邪�A���̏ڍׂ܂ł͖��炩�łȂ��B�܂��A�Õ�����ɂ́A�召���܂��܂ȌÕ����قڑS���K�͂ł���ꂽ���A�����݂͂ȁA�x�z�K���̂��̂ł����āA���O�̖����Ƃ͂������ꂽ���̂������悤���B�@
�u���a�������v�Ƃ������쎞�㏉���ɏ����ꂽ�����ɂ��ƁA���{�ɂ����ẮA�y���A�Α��A�����A�쑒�A�ё��̌킪�������B�@
�쑒�͈�̂��Ɏ̂Ēu�����̂ŁA�����Ƃ������Ƃ����A�܂����̑�ނɔC���邱�Ƃ���A�����Ƃ���ꂽ�B�ё��Ƃ͈�̂�̏�ɒu�����̂ł���B�Ƃ��ɁA��̂ڒu���ꍇ�ƁA���ɔ[�߂Ēu���ꍇ�Ƃ��������B���̂ق��A���A�Ɉ�̂������߂���@�Ȃǂ��������悤�����A�y���ƉΑ��������ẮA���쎞����͂邩�ȑO�ɂȂ���Ȃ��Ȃ����悤�ł���B�@
�Α������{�ł͂��߂ĂȂ��ꂽ�̂́A�O�e�ŏq�ׂ��悤�ɁA�����I�����ł���B�����A����͏㗬�̐l�X�̊Ԃɍs����ɂƂǂ܂�A��ʂ̖��O�ɂ͂Ȃ��Ȃ��L����Ȃ������悤���B�@
���炭���{�̖��������̒��S���Ȃ����̂́A�y���ł���B�y���Ƃ́A���Â̂��Ƃ͂����m�炸�A���҂̈�̂����Ɏ��߂āA�n���ɖ���������̂ł���B�@
���ɂ́A�傫�����ނ��ē�`�Ԃ���A�ЂƂ������A�ЂƂ�Q���Ƃ������B�Q���͍����p�����Ă���W���̊��Ƃقړ��l�ł��邪�A�����͎��҂��������p���Ŏ��߂���̂ŁA�c���̉��̂悤�Ȍ`���������̂����������B�@
�����ɔ[�߂�ɂ������ẮA���҂̐g�̂������܂�Ȃ��A�G�𗼎�ŕ����Ă��̏�Ɏ�𐂂��悤�Ȏp�����Ƃ点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����d���������҂̐g�̂́A�e�Ղɂ͋Ȃ���Ȃ�����A��Ƃ����葫�Ƃ����A���͂ڂ��ڂ��Ɛ܂�Ă��܂������낤�B����ł��ڒ����Ȃ��̂́A���{�l�̓L���X�g���k�̂悤�ɂ́A��̂Ɏ������Ȃ�����Ȃ̂ł���B�@
�n��ɂ���ẮA��̂��r��ł��肠������A�炸���܂�Ď��������肵���B�܂��A�O�r�̐�̓n�����Ə̂��āA�Z���K��������������������A����͕����̋��`���e�����Ă���̂ł��낤�B�@
�y���̊��́A���N�����ƕ��H���ĕ����̂ŁA���̏�̓y���זv���ĕ�Ɍ����J�����ƂƂ��Ȃ�B�����h�����߂ɁA���炩���ߕ挊������傫�����̏�ɒu�����Ƃ��������B���ꂪ��ɂȂ��āA��W���ɔ��W���Ă����̂ł���B�@
����ȂǁA������{�̈ꕔ�̒n��ł́A�̕��K���������Ƃ����B����́A�����㐔�N�̌�ɁA���҂̈�̂����o���Ă��ꂢ�ɐƂ������̂ł���B����ł́A�l�H�̐ΌA�̂Ȃ��Ɋ���[�߂镗�K���������̂ŁA�ΌA���̉q����ۂ��߂ɁA���̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ����悤�ɂȂ����̂ł��낤�B�@
���ɉΑ��ɂ��āB���쎞��ɂ́A���A���Ȃǂ̑�s�s�ɂ����āA��ʂ̏������Α�������悤�ɂȂ����B�]�˂ɂ����Ă��A���ˌ��⍻���Ȃǐ��ӏ��ɉΑ��ꂪ�݂���ꂽ�B�����́A���݂̂悤�ɉΑ��F�̒��ŏĂ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�n�ʂɌ����@������ɐd��ςݏd�ˁA���̏�Ɋ���u���āA����ɐd���d�ˁA�ɂ����ł₭�Ƃ������̂ł������B�Η͂͂����������̂ł͂Ȃ������낤����A�Ă�������ɂ͎��Ԃ�v�����ł��낤�B�@
���̎��[�́A����^�@�n��ɂ����ẮA���ׂĂ������A��̂ł͂Ȃ��A�̂Ǖ��Ƃ����āA�̂ǂ̂�����ɁA���̎p�̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Ďc���������ȍ��������A�邾���������悤�ł���B����ȂƂ���ɂ��A���҂̈�̂ɂ������Ȃ����{�l�̓������_�Ԍ�����B�@
�����A�����ߕӂ̉Α���̑����́A���X�g�����̉Α��F���̗p���Ă���B����́A�F�̒��Ƀp�C�v�ł����炦�����X�g���Ƃ������g�悤�̂��̂����炦�A���̏�ɁA�����悹�ďĂ����̂ł���B�Ă������́A���g�݂̌��Ԃ��������ĉ��ɂ���M�̂����ɗ�����B�@
����A���̂ق��ł́A��Ԏ��̘F���D�܂��Ƃ����B����́A�����ǂ��̘F�̒��ɁA�����悹����Ԃ��͂ߍ���ŏĂ��Ƃ������̂ł���B���X�g�������ƁA����������ۂɁA�̂Ǖ������Ă��܂��̂ɑ��āA��Ԏ��ł́A���̌`���傫�����Ȃ�ꂸ�ɁA�̂Ǖ������̂܂܂̌`�Ɏc�邩��ł��낤�B�@
���Â�̕����ɂ����Ă��A�F�̒��̉��x�́A700�x����900�x�ɕۂ����B�����̐��l�ł��ꎞ�ԗ]��ŏĂ�������A���ꂢ�����ς荜����ƂȂ�̂ł���B�@
(�NjL / �����ېV����̔p���ʎ߉^���̒��ł́A�Α��͕��������̐^���ƌ����A���̂�����ʼnΑ��֎~�߂��o���ꂽ�قǂł������B�������A�s�s�����҂𒆐S�ɁA��Ƃ��Ď��ۓI�ȗ��R����A�Α��̎��v�͋����A���������Ȃ����ēP��Ă���B)
|
 �@
�@
���q�K�̖����k�` |


 �@
�@ |
�����q�K�̐��M�ɁA�u����v�Ƒ肷���т�����B���̑O�N�A����34�N��2���ɏ����ꂽ��i�ł���B�ӔN�̎q�K�́A20�䔼�ɂ����������j�����ƂŐҒŃJ���G�X�������A��Ɏ��ƌ����������������𑗂��Ă����B�J���G�X���������āA���Ɍ����J���قNjꂵ���ڂɂ����Ȃ���A���j�ۂ����]�𖾝��ɂ������߂��A�n��ӗ~�͐����邱�ƂȂ��A�u�a���Z�ځv���n�߂Ƃ��āA���Ɏ���܂Ŗ��i�ݏo���������B����Ȏq�K���A�����̎����A�����Ɏ��Č�����̂����̍�i�ł���B�S�тɎq�K�����O�̃��[���A�����ӂ�A���ɂ������������nj㊴�������炵�Ă����B�@
��т́A���㊻�ɓ�����邱�Ƃ̋�������Q�����Ƃ���n�܂�A�y���A�Α��A�����A�����A�~�C���Ƃ�����ɁA�����̊e�`�Ԃɂ��āA���ꂼ��̒��Z���ڍׂɕ��͂��Ă���B�����ԋ߂ɍT�����҂��������������āA���̌������ɂ́A�����҂Ƃ��Ă̔��͂��������Ă���̂ł���B�@
�܂��A���͋����ł��₾�Ƃ����B�����ł���������Ԃ̒��ɐQ�����ꂽ�����A�g�̂̂܂��ɂ�������������l�߂��Đg�����ł��Ȃ��Ȃ�A���܂����B�܂őł��ꂽ�̂ł́A�����Ԃ����Ƃ��Ɏ葫�������Ƃ��ł��ʁB��킭�́A�W�̂Ȃ����ɐQ�����Ăق����Ƃ����B����ɂ��Ďv���Ȃ����̂́A�����̑��V�ɂ����Ă��A���҂͊��̒��ɐQ������A���̐��ɗ������������邱�Ƃɂ����ẮA�q�K�̎���ƕς���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�������ɂ��������l�߂��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������A������҂����Ƃ̍Ō�̕ʂ����������ɂ́A��͂芻�̊W�ɓB��ł����B�����ɉΑ���̘F�̒��ŏĂ���Ă��܂��̂ł��邩��A�Ȃɂ��B��ł��Ƃ܂ł͕K�v�Ȃ��낤�Ǝv����̂��B�@
�����̒��ŁA�q�K���ŏ��Ɏ��グ��͓̂y���ł���B�y���͍��ł��A�n���ɂ���ĂȂ���Ă���B���{�̖@���Ŗ����ɂ��Ď����܂��Ă���̂́A�������ȏ��ǂ́u��n�y�і����Ɋւ���@���v�Ƃ������̂ł��邪�A�����ł͉Α��������Ƃ���A�y���͑O����̈╨�̂悤�Ȉ������Ă���B�q����y���͍D�܂����Ȃ��Ƃ������R����ł���B�������A�q�K�̎���ɂ����ẮA�y�����L�͂ɍs���Ă����ł��낤�B�q�K�������悤�ɁA�Q���ő�������̂�����A�����Ƃ����āA����܂�Ȃ��č������p���̂܂܁A�c�ɒ����~���l�̊����Ă߂��đ�������@���������B�@
���̓y���Ƃ������̂ɂ��āA�q�K�͈�티�|���̂悤�Ȃ��̂��ȂČ���Ă���B�@
�u�����̒��Ɏ����������ɂȂ��Ă���Ƃ��čl�ւČ��ʂցA���̓S���S���S���h���Ɖ��ɗ�����B�{�傪��L���ꂽ�̂ł��炤�A�y�̉������̊�̏�̏��֗����ė����₤�ȉ�������B���̂��Ƃ̓h�^�o�^�h�^�o�^�Ɠy�͎����̏�ɗ����ė���B�܂������ԂɊ��߂Ă��܂ӁB�������Đl�v���͖��߂���ɓy���������đ����p��ɓ��ł߂Ă��B���������������Ă����߂��A�����琺���o���Ă�����������̂ł͂Ȃ��v�@
�������܂ܖ��߂�ꂽ��ǂ����悤�A���߂�ꂽ��ɐ����Ԃ�����ǂ����悤�A���̖�́A�×��l�ނɋ��ʂ����ϔY�ł������B�l�͎���ł��܂�����ł����A���̐��̖������̂Ă������������炵���A���̖������H��Ƃ��Ȃ��Č����̂ł��낤�B���������S����e�[�}�ɂ������̂ɁA�G�h�K�[�E�A�����E�|�[�̗L���ȏ����u�������������v������B���Ǝv���Ēn���ɖ������ꂽ���̂́A�����̔��q�ɐ����Ԃ��Ă��܂����҂̋��|�Ɛ�]��`������i�ł���B�q�K�����̍�i��ǂ�ł������ǂ����ɂ��Ă͊m���Ȃ����A�q�K�̕��͂ɂ́A�ϐl�|�[�ɒʂ���A�l�Ԃ̔ϔY��˂������Ă݂Ă���悤�ȂƂ��낪����B�@
���ɁA�q�K�͉Α��ɂ��Č��B���{�̉Α��͓`���I�ɖ�Ă��Ƃ��A���O�ɂ��������g�d�̏�Ɋ����ڂ��A���Ԃ������ďĂ��Ƃ������̂ł������B�܂��̖����A���V�Ă��Ƃ��������B�Ƃ��낪�A�q�K�̎���ɂ͉Α��F�Ƃ������̂���������n�߁A�����ȂǓs��ɂ����ẮA�Α���̘F�̒��ŏĂ������̂������Ă��Ă����B���ꂪ�q�K�̋C�ɂ͂���Ȃ������炵���A���̂悤�ɟT����f���Ă���B�@
�u�����̉��˂̗����Ă��鍟���̉Α���Ƃ��ӎ҂͊������鏊�Ɏd�肪�����đ��d��̒��ֈ���������Ė�ɂȂ�ƊF���ꏏ�ɏ��Ă��ɂ��Ă��܂ӂ̂��Ⴓ���ȁB����ȏ��֊���������̂��}�����A��ɏ����Ă��ɂ�����Ǝv�ӂƁA���܂�ʂ킯����Ȃ����B��ł����ł��Ђ��ς�����Ă��Ă��܂ӂƂ��ӂȂ�ɂ��Ă������А肪�����������Ă��Ɨ��Ă͑��̂܂�₤�ȁA�ꂵ���Ă����̏o���ʂ₤�ȕςȉ}�Ȋ���������B����ɏ����Ă��Ȃ�Ƃ��ӂ̂͗������̗����݂��₤�Őr�����ɂ܂��Ă���B�Α��Ȃ炢�����̂̉��V�I�Α��������ŋC�������Ă��ł��炤�v�@
�q�K�́A�Α��F�ŏĂ���邱�Ƃɂ��āA���Ȃ荬�������F���������Ă����悤���B���Ȃ��Ƃ�����ɂ����ẮA�Α��F�̒��̉��x�́A�ێ�700�x����900�x�ɕۂ���A���͖��_��̂��܂����₩�ɉq���I�ɏċp�����B���肶��Ə����Ă��ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂������Ȃ��A�q�K�̂悤�ɂ��ꂱ��Ƌ�s�����ڂ�����A�������������肷��܂��Ȃ��A�l�Ԃ͂�����������ƍ�����ɂȂ��̂ł���B�ނ���A�����ւ̖������u���̂����ɒf�����Ă���A�����Ƃ��č��ɂȂ邱�Ƃ��ł���̂ł��邩��A����Ȃɂ��Ƃ�����̂Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�@
�q�K�͂��̂ق������A�����ɂ��Č��A�����͂ł�����~�C���ɂ��Ăق����Ƃ����悤�Ȍ��������炵�Ă���B(���ہA������l�̒��ɂ́A����@�g�̂悤�ɁA�F�X�Ȏ���K�����āA�~�C���ɂȂꂽ���̂��������̂ł���B)�@
�����̖����@�́A��̂ɂ����Ă͍s���Ă�����������Ȃ����A�q�K�̎���ɂ����Ă��A���łɔF�߂�����̂ł͂Ȃ������B�@
�q�K�́A���̕������������N�̏H�ɖS���Ȃ����B���N36�ł������B���̈�[�́A�F�l�����Ɍ�����A�c�[�̑嗴���ɓy������ꂽ�B�������Ė������琔�N�o�Č�A���̕�̏�ɁA��㹓�̎�ɂȂ�Δ肪���Ă�ꂽ�B�q�K�͓y���̊��̒��ŁA�ʂ����Ăǂ̂悤�Ɋ������ł��낤���B
|
 �@
�@
��腖��剤�Ǝ��҂̑h��(�����l�̕����I������) |


 �@
�@ |
�N�����q�ǂ��̍��ɁA�u����������腖��l�ɐ�����v�Ƃ����āA�e��Z�킩�狺�����ꂽ�o�������邱�Ƃ��낤�B�l�͎��ʂ�腖��剤�̍ق����āA�Ɋy�֍s���邩�n���֗����邩�A�U��킯����B���̍ۂɁA�l�̍ߏ�̂����ɂ��A�����Ƃ����̂͂����Ƃ��߂��d�����̂ŁA����ɒn���֗�����ɂƂǂ܂炸�A��܂Ŕ�����Ă��܂��Ƃ����̂ł���B�@
���{�̖��O�ɕ������Z������̂́A���q����ȍ~�̂��Ƃł���B�e�a����@�͂��߁A�V�����^�C�v�̕����҂����O�̒��ɓ���A�O����@�،o�̋������L�߂��������ŁA���O�̊Ԃɕ����y�ւ̊����܂����B�܂��A����ɔ����āA�����I�ȍl�������L�����Ă������̂ł���B�@
�����̋����̒��ł��A�����̓��{�l�ɂƂ��āA�����Ƃ�����₷�������̂́A�։��]���A���ʉ���̊ϔO�ł͂Ȃ������낤���B�@
���{�l�ɂ͌×��A�����鐶�����ɂ͗썰������A����͌`���łтĂ�����������Ƃ����A�A�j�~�Y���I�ȐS�����������B�Ƃ��ɁA�l�Ԃ̗썰�́A���̂��łы����Ă����ł��邱�Ƃ͂Ȃ��A���҂̎��ӂ�Y���Ȃ���A���ɂ͐_�ƂȂ��ēV��ɏ��ƍl�����Ă����B�ꍇ�ɂ���ẮA�썰�͂ق��̎p����Đ����Ԃ邱�Ƃ��������B�Ƃ��Ɏq�ǂ��̏ꍇ�ɂ́A�ق��̎q�ɐ��܂�ς�邱�Ƃ��A���҂�����A�M�����Ă������̂ł���B�@
���̌Ñ�I�ȊϔO�ɁA�����̋��������т����Ƃɂ���āA���҂̍Đ���A�O���̈����Ƃ������A�V�����l�����������Ă����B�����́A�l�Ԃ̍ߋƂɐ[��������邱�Ƃł���������A���O�̕��������̒��ŁA腖��剤�̉ʂ����������́A���ɑ傫�Ȃ��̂ł������B腖��剤�����́A�l�Ԃ̍ߋƂɍŌ�̍ق����������̂���������ł���B�@
�����ɗ��s�������O�|�\�E���o�̂Ȃ��ɁA腖��剤�̍ق��ɂ���āA���҂��S��Ƃ����b���o�Ă���B�@
���o�u������v�́A�ʖ����u��S����h��杁v�Ƃ����悤�ɁA��Ƃ̎��𐋂������̂������Ԃ��āA���ɂ͐_�ƂȂ镨��ł���B�����Ԃ�́A腖��剤�̎��߂ɂ���ĉʂ������̂ł���B���̏�ʂ��A���o�͎��̂悤�Ɍ���Ă���B�@
10�l�̏]�҂ƂƂ��ɎE���ꂽ���I�������A腖��剤�̑O�Ɉ������Ă��Ă���ƁA腖��剤�́u���Ă����\���ʂ��A���l���Q�肽�́A���̏��I�Ɛ\����́A�O�k�ɂ��肵���̎��́A�P�Ɛ\���Ή����Ȃ�A���Ɛ\���߂��Ȃ�A�别�l�̎҂Ȃ�A������A���C�����֗����ׂ��A�\�l�̓a�������́A����ɌW��A��@�̎��ɂ̂��ƂȂ�A������A����x�A�O�k�֖߂��ĂƂ点���v�Ɛ錾����B�@
�Ƃ��낪�A�]�҂������A������͂Ƃ������A��l�̏��I��O�k�ɖ߂��ė~�����ƍ��肷��̂ɂق�����āA11�l�Ƃ��ǂ��߂��Ă�낤�Ƃ����A�u����ڂƂ������O�ɏ�����A���{�ɂ��炾�����邩���Ă܂���v�Ɩ�����B���{������ƁA�]�҂����͉Α��ɂ���đ̂��Ȃ����A���I�͓y���ɂ��ꂽ���߂ɑ̂����邱�Ƃ��킩��B�@
�����ŁA腖��剤�́A���̂悤�ɁA���I��l������߂����ƂɌ�����̂ł���B�u���Ă�����̍^��ɁA�\��l�Ȃ�����߂��ĂƂ点���Ƃ͎v�ւǂ��A���炾���Ȃ���ΑF���Ȃ��A�Ȃɂ��ɏ\�l�̓a�������A���C�����ւ͗����ׂ��A��炪�e���ɗ��܂�E�E�E������Ώ��I��l�߂��v�@
�܂��A�u����̎�v�Ƃ������o�̒��ł́A����e���A�����̎q�����ɂ������Ă���̂������悤�ƁA腖��剤�ɍ��肷���ʂ�����B�@
腖��剤�́A���̐^�S�ɂЂ���āA��e��O�k�ɖ߂����Ƃ��A�߂��ׂ��̂����邩�ǂ������ׂ�����B�Ƃ��낪�A���̏ꍇ�ɂ��A��e�͉Α��ɂ���đ̂��c���Ă��Ȃ��̂������B�����ŁA�ق��ɖ߂��ׂ����[���Ȃ����ǂ����A���ׂ�����ƁA�u�������܂��҂͑�����ǁA������҂ƂĂ����Ȃ���A�����ĎO���ɂȂ�����̑̂���v���邱�Ƃ��킩��B�@
�u��{�������߂��A�������ɐ���ςւ邩�A��䂫�����߂��A�䂪�q�ɉ�͂ꂵ���ɁA����ɂĂ��ꂵ���炸�A�͂�䂢�Ƃ܁A�Ɛ\�����A��{�P�ƂƑł������܂ւA�������ɐ����ς�A���߂��Ԃɓ���̌䏊�ɏo�ŁA�ԉ��R�ւ��Q�肯��v�@
�����̘b�Ɏf����̂́A�썰���ӂ����іڂɌ�����`���Ƃ��đh������Ƃ������Ƃł���B�h������̂́A�����̑̂Ƃ��Ă̏ꍇ������A�������̂悤�ȓ����̌`�����ꍇ������B�Α�����Č`���c���Ă��Ȃ��ƁA�������g�̎p�ł́A�����Ԃ邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�����Ă���B�@
�����̘b�̔w��ɂ́A���܂��܂ɋ��܂��������������������̂ł��낤�B���܂����錴���͂ƂȂ������̂��A���{�×��̗썰�ς⎀���ςł��������Ƃ́A�z���ɓ�Ȃ��B
|
 �@
�@
�����{�l�̎����ςƑ��E�� |


 �@
�@ |
���҂��ǂ̂悤�ɖ������邩�́A�����̎����ς⑼�E�ςɂ�����邱�Ƃł���A���̖����̕����̍��{���Ȃ����̂ł���B���̕����̎v�z������ɒu���L���X�g�������ɂ����ẮA��̂͒��J�ɏ����āA����ׂ������ɔ�����B��̂�����ȂNj����ꂴ��^�u�[�ł���B����A�։��]���̂Ȃ��ō��̎��̂�M����C���h�����ɂ����ẮA��̂��̂��̂͏d��ȊS���ɂȂ�Ȃ��B�@
��̂̈����Ƃ����_�ł́A�y���ƉΑ��͗��ɒ[�Ɉʒu����B���������āA���̗��҂�����̕����̒��ŋ������邱�Ƃ́A�ʏ�͍l�����������Ƃł���B�������A���{�ɂ����Ă͉��̂������A�Η��킸�ɋ������Ă����B��e�ŏq�ׂ��悤�ɁA���{�̒������j�̒��ł́A�y�����嗬�ł������Ƃ�����̂����A����ł��A�Α������ނׂ����̂Ƃ��āA�r�����ꂽ���Ƃ͂Ȃ������̂ł���B�@
����ɂ́A���{�l���×������Ă��������ς�A���̔w��ɂ���썰�Ɠ��̂Ƃ̊W�ɂ��Ă̌������A�w�i�ɂ��������̂Ǝv����B�@
���{�l�{���̏@���ӎ��̒��ł́A���Ƃ������̂́A���̂Ƃ͕ʂ́A���ꎩ�̂����̂��Ƃ��Ȃ������̂ł������B���́A���̂����̏h��Ƃ��āA���́A���邢�́A���́A��̂̐l�Ƃ��Č���邪�A���̂������ʂĂ���ł��A�Ȃ����̂Ƃ��Đ��������A���ɂ͂��̐��ɂ���l�X�ɑ��āA���_�ɂ��Ȃ�A�܂��A��a�_�ɂ��Ȃ����B�������ċ��ɂɂ����ẮA����c�l�Ƃ��āA�_�X�̍��ɗ邱�ƂƂ��Ȃ�̂ł������B�@
�×��A���{�l�ɂƂ��ẮA�l�̎��Ƃ́A�썰�����̏h�肽����̂𗣂�āA��x�Ɩ߂�Ȃ���Ԃ��Ӗ������B�썰�͂܂��A�ꎞ�I�ɓ��̂𗣂�邱�Ƃ�����B�ł��邩��A�l�����_�����Ƃ��ɂ́A�K���ɂȂ��ė썰���Ăі߂����Ƃ����B�ߔN�܂Ŋe�n�ōL�͈͂ɍs���Ă����A������Ƃ������A�̋V���́A���{�̑��������̓������Ȃ����̂ł��������A����͂��̂悤�ȗ썰�ςɗ��t�����Ă����̂ł���B�c���ɂ����āA�u������̋{�v�Ƃ����V�����`���I�ɍÂ���Ă������A������A������̐������ꂽ�`�Ԃƍl������̂ł���B�@
�썰���Ȃ��Ȃ��߂炸�A��̂��`������n�߂�ƁA�l�X�͂��悢�掀�Ƃ������̂����ꂴ������Ȃ��Ȃ����B�����Ȃ�ƁA�c���ꂽ�S�[�́A�����Ă����Ƃ��̂��̐l�́A���̎p�Ȃ̂ł���Ƃ͊�����ꂸ�A����Ȃ鍰�̔����k�ɉ߂��Ȃ��Ȃ�B�����k�ɂȂ��Ă��܂�����̂́A�ꍏ��������������K�v������B�����łȂ��ƁA���삪���ڂ��āA�Ж�������炳�Ȃ��Ƃ�����Ȃ��̂ł���B�@
���{�l�́A�ǂ������҂̈�̂ɖ��ڒ��ȂƂ��낪����Ƃ����A���ꂪ�܂��Α������y�����ЂƂ̔w�i�Ƃ��Ȃ��Ă���̂����A���̗��R�̑唼�́A�ȏ�̂悤�ȗ썰�ςɂ���B�@
�Ƃ���ŁA�썰�̂ق��́A���̂𗣂ꂽ��A�����ɉ����ւƂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��킯�ł͂Ȃ��A���҂̕��⑰�̎��ӂɕY���Ă�����̂ƍl����ꂽ�B�⑰�����{�����̂́A���҂̖S�[���̂��̂Ƃ������A���̕Y���썰��ΏۂƂ��Ă����̂ł���B�@
���̕Y���썰���A�����Ɏ��̂������̂Ƃ��čl�����Ă������́A�������^�̗�ɂ悭����Ă���B��������̐l�X�́A���^�̉��삪�w�G��ɂ������āA���̖���D�����̂��ƁA�^���Ɏ�����̂ł���B�@
�������A�썰�����Â�́A���̐��������Ă��̐��ɍs�����̂ƍl����ꂽ�B���̐��Ƃ́A�Ñ�l�̈ӎ��̒��ł́A�����炭�V��ł������ƍl������B�����āA���̐��Ƃ��̐��̐ړ_�ɂȂ�̂́A���������R�ł������B�썰�́A�ܐ߂ɂ��A���̐�����R��`����Ă��̐��ɖ߂��Č���A�l�X�̐����l�������̂ł���B�@
���{�e�n�ɌÂ�����s���Ă���A�Ղ��N���s���̖w�ǂ́A�_�ƂȂ����썰���R�����邢�͂��̑�ւƂ��Ă̈ˑ�Ɍ}������A�˂��炤�Ƃ����̍ق��Ƃ��Ă���B�_���̏��s���́A�����̌n���������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B�@
���҂̗썰�����̐��Ɉڂ�̂́A����33�N�����������A�����Ƃ�50�N��̂��ƂȂ̂��낤�ƍl����ꂽ�B�⑰�ɂ����J���A���̂����肪�ߖڂƂȂ邵�A�܂����̍��ɂ��Ȃ�A�썰�����炬�����āA���̐��ɏ��A����c�l�Ƃ��āA�_�ɂȂ邱�Ƃ��ł������낤�ƍl����ꂽ�̂ł���B
|
 �@
�@
���q(������) |


 �@
�@ |
���{�̌Ñ�ɍs���Ă������V�V��ŁA���҂�{������܂ł̂��Ȃ蒷�����ԁA���Ɉ�̂������u���A�ʂ��ɂ��݁A���҂̗썰����A���Ԃ߁A���҂̕������肢����̂̕��s�E�������Ȃǂ̕����I�ω����m�F���邱�Ƃɂ��A���҂̍ŏI�I�ȁu���v���m�F���邱�ƁB���̊������u����ꏊ�����w�����Ƃ�����B�q�̊��ԂɈ�̂����u�����������u�q�{�v(�u������݂̂�v�A�u���t�W�v�ł́u���炫�݂̂�v)�Ƃ����B�@
���Õ����ɂ݂�q�@
�u�Î��L�v�u���{���I�v�ł͟q�A�u���t�W�v�ł͑�q�Ƃ���A�M�l��q�ɂ����L�^��A�����A�z������L�^���U������邪�A��̓I�ȕ��@�Ȃǂ͋L�^����Ă��Ȃ��B�@
�u���{���I�v�ɂ����ẮA�ꏑ�̋�ŃC�U�i�M���C�U�i�~�������ہu�ɜQ�����~�������T���q�ʔV�|�v�̟q�ʂ�V�t�F(�A���m���J�q�R)�̟q�u�֑��r�����q�V�v(�ꏑ�̈�u��r���q�L�V�v)�A��8�̒����V�c�̕����ɂ��̈�̂��h�H�ɂ��C�H�Ɍ����ʂ��ĖL�Y�{�ɂ�������́u↝��V�c�V�r�t�����h�H�Ȝn�C�H�J���厧�q��沉Y�{ਝىΟq�ʝىΟq�ʍ����J�ߔV���엘�v������A���̌㐔�サ�ĂɋԖ��V�c(�Ԗ��V�c32�N4��15��(571)����)32�N5���ɉ͓��Îs�ɟq���A�H8���ɐV���̖����q�������q�Ɉ��������u�܌��q����內�Îs�H�������q��V�������g�����q���������q���������q��������㌎�����w�G�㍇�ˁv�ƋL�q�����B�Ȃ����̂Ƃ���1�N�ɖ����Ȃ��q�ł���B�@
���@���ɋL�^���ꂽ�q�@
�ɔ��\���B��l�\�Z����俀���ɂ́A���҂͊����Ȃ��ĝ�(����)�߁A�e�o�͎r�ɏA���ĉ̕����A�Ȏq�Z��͔��z���Ȃ��ĕ������B�M�l��3�N�O�ɟq���A���l�͓���m���Ă����ށB�u���ҝʈȊ��ؐe�o�A�r�̕��Ȏq�Z��Ȕ��z�����M�l�O�N�q���O���l�m�����y���u�r�D�㗤�n���V�v�Ƃ���A
�܂��ɔ��\���B��l�\�Z������(�����̂���)�ɂ́A���҂͉����ɉ��ğq���A3�N���o�āA�g�����(����)��ő���A����v�̑r��3�N�����u���ҟq�������S�O�N���g������������y�v�V�r���F�O�N�Z��O�����I�L�������ە���وȑ��V���^���掀�Ґ������ߎԔn�u���摤�𑒎�ॎ控���v�Ƃ���B�����̋L�^����A�`���E�����Ƃ��A�M�l��3�N�ԟq�ɂ������Ƃ��M����B
�Ȃ��A�q�̏I����͊���ɖ��������B�����q�̊��Ԃ͑�K�͂ȕ���̐����ɕK�v�������Ƃ��l������B�@
���q�̐��ށ@
�q�̋V���͑剻�̉��V�ȍ~�ɏo���ꂽ�����߂ɂ���āA���V�̊ȑf���╭��̏��^�����i�߂�ꂽ���ʁA�����ƂƂ��ɓ��{�ɓ`������ƌ�����Α��̕��y������A�}���ɐ��ނ���B�@
����r�ɂ�����u�q�{�v�@
�q�{�́u������݂̂�v�Ƃ������œV�c�̑�r�̗�ɁA�܂��u�Ђイ�v�Ƃ������ōc�@�E�c���@�E���c���@�̝ʑ��̋V�܂ł̊ԁA�c���{�a���ɉ��݂�����̈��u���̖��Ƃ��Ďg�p����邱�ƂɂȂ��Ă���A���ɉ����Ă͏��a�V�c��喾�c�@�A���~�c�@�̕���̍ۂɐݒu����Ă���(�������A���c���@�͌��݂̍c���T�͂ɂ���߂��Ă�����̂́A���ۂɂ͕������㖖���ȍ~�A����Ă��Ȃ�)�B�����13���ڂɈ�̂����߂����͌䏊����{�a���̟q�{�Ɉڌ䂳��A�����45���ڂ�ڏ��ɍs�����r�̗��ʑ��̋V�܂ł̊ԁA�q�{�q��̋V���n�߂Ƃ��鏔�V�����s����B�@
���q�̖��c�@
�ʖ�͟q�̕��K�̖��c�ŁA�q�̊��Ԃ�1�������A���邢�͐��������ɒZ�k���ꂽ���̂Ƃ����������B����ł��Ă͍L���s���A����ł��ꕔ�̗����Ɏc�镗���Ɛ̕��K�́A�q�̈��̌`�Ԃƍl������B�@
�����Ă�(���܂��)�@
���{����щ���̖��ԐM�ɂ����鎀�҂̍����Ăт�������p�s�ׂł���B����s�t�I�Ȃ��̂ƌ��Ȃ��������̉\�����M����ꂽ�Ƃ��납�炭��B����ł͉Α��ɕt�����̂���ʓI�ŕ����̊ϔO�͐����ɂ������A�㐢�Α������S�ɒ蒅����܂łɂ͒������Ԃ�v���A����܂ł͓y�����嗬�ł������B���ɌÑ�ł͖�������O�ɟq(������)�Ƃ��������Ԃ�݂��A�����ւ̖]�݂�������Ƃ����B��̓I�Ȃ��̂Ƃ��ẮA���҂̏o���Ƃ̉����ɓo���āA�吺�Ŏ��҂̖����Ă肷�镗�K���������B�@
���Ă����L�^�Ɏc���Ă����Ƃ��ẮA��������́u���E�L�v����2�N8���ɓ��������̖����������S������s��ꂽ�Ⴊ������B���̂��Ƃ���������̋M���̊Ԃɂ��V���̊��K���c���Ă������Ƃ�����������B�@
����ł́u������(�}�u�C�O�E�~)�v�u���Ă�(�^�}�X�A�r�[)�v�Ȃǂ̌ď̂�����A�v�����ł́u�}���u�J�l�[(�����͂������A�Ƃ����悤�ȈӖ�)�v�ƌĂ��B�}���u�J�l�[�ŋ����[���̂́A�V�����獰�̏o������������̌��ӂ�ɑz�肳��Ă���Ǝv����_�ł���B
|
 �@
�@
�����{�l�̕� |


 �@
�@ |
�����������{�l�̊Ԃɕ��ʂɍs���Ă����̌`���͉Ƒ���ƌĂ����̂ł���B���@���邢�͌����̕�n�̈�p�ɕ�𗧂āA���̕\�ʂɁ����Ƃ̕�ƕW���̂������Ƃ���ʓI���낤�B��̉��ɂ͔[���p�̃X�y�[�X���݂����Ă��āA�����ɚ�Ɏ��߂���������B�����オ����ɂ͓K������Ԃ��B�@
���������Ƒ���̌`������ʉ������̂͂����Â����Ƃł͂Ȃ��B�Ƒ��̐������ƒP�ʂő����邱�Ǝ��̓��쎞�㒆���ȍ~�̂��Ƃł��邵�A�܂��č����̂悤�ȕ悪�����͔̂�r�I�ŋ߂̂��ƂȂ̂��B�@
����ɂ́A�Α��̕��y�Ƃ���������邾�낤�B�܂��Ƒ��悪�嗬�ɂȂ邱�Ƃ̔w�i�ɂ́A�Ƒ��̒��ɂ�����ȁ���̒n�ʂ̕ω��ƁA����ɂƂ��Ȃ��Ȃ̑��V�̂�����̕ω�����p���Ă���ƌ�����B�@
�Ȃ��v�̐��𖼏��͖̂�������ȍ~�̂��Ƃł���B����ł��邩��A�Ȃ����ʂƂ��̈�[�͗����̕�n�ɑ����邱�Ƃ����������B�v���̕�n�ɑ����Ă��A���̖��͗����̂��̂��L���ꂽ�̂ł���B�����E�����̐w�˓c�w�C�̓��L�ɕ�e�̎����L�����Ƃ��낪���邪�A�����ǂނƁA�w�C�̕�e�̕�ɂ͗����̐���t���āA�u�֓��}�l��v�Ɩ�����Ă���̂��킩��B�@
���̗�ɂ݂���悤�ɁA�����ȑO�̓��{�l�́A�l��ɑ����邱�Ƃ����������̂ł���B�Â���n�ɍs���ƁA�l�̖���������悪�������ƂɋC�Â��B���ɂ���ẮA�����̕���Ĉ�ӏ��ɐςݏグ�Ă���Ƃ��낪���邪�A�����̕�͖w�ǂ��l��ł���B�s���扑�̂悤�Ȗ����ȍ~�Ɏn�߂�ꂽ�Ƃ���ł��A�l��͈��|�I�ɑ����B�@
�����A�����̌l��ɂ��Ă��A�������������ɑk�����x�ŁA����Ȃɗ��j���Â��Ƃ��v���Ȃ��B������ʊK�̍������͕̂ʂƂ��āA�������l��ɑ���ꂽ���Ƃ𗠕t������j�I�Ȏ����͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��Ƃ����Ă����قǂł���B�@
���{�����̊Ԃōs���Ă��������ƁA���̖ڂɌ�����`�Ƃ��Ă̕�ɂ��āA�ȒP�ɐU��Ԃ��Ă݂悤�B�@
�ꕶ����̈�ւ��悭���ׂĂ݂�ƁA���̒G�����Z������Ȃ�W���������̊�{�P�ʂ��������Ƃ����������B���̏W���͒��������ɕ�n��i���Ă��āA���������ʂƂ����ɖ������ꂽ�B�����̌`���͒��ږ��߂���̂���A�y���ɔ[�߂Ė��߂���̂܂ŁA�o�ϗ͂ɉ����Ă��܂��܂������悤���B�y���̒��ł������Ƃ��悭�݂�����̂́A�ۂ��\�̂悤�Ȍ`���������̂ł���B���Â�ɂ���A���҂����͏W���̒��S�ɖ��葱���A��������̂Ƃ̐��_�I�ȂȂ���������Ă͂��Ȃ������悤�Ȃ̂��B�@
�퐶����ɂȂ�ƏW���̋K�͂͑傫���Ȃ�A���ɍ����߂��炵�����W�����o�ꂷ��B������n�͏W���̊O�ɍ���邱�Ƃ������Ȃ����B�@
�Õ�����ɂ́A���q�I�ȋ����͕̂��āA��ʖ��O�̏�ɌN�Ղ���w���o�ꂷ��B����ɔ����A�̕悪�Ɨ������Õ��Ƃ��đ��c����A�����炵�̗ǂ��ꏊ����W���������낷�悤�Ȍ`�ɂȂ�B�����̖��O�͏W�c��n�ɁA���ԑw�͒ᕭ�u�̕�n�ɑ���ꂽ�B�ȊO�͌l�Ƃ��ĂłȂ��A�W���̐����Ƃ��ďW�c�I�ɑ���ꂽ�Ǝv����B�@
�����������A�Α������y����悤�ɂȂ�ƁA�s�̋M�������͈ꑰ�嗬���ƂɉΑ���������A�擰��[���������Ă�悤�ɂȂ����B���̏ꍇ�ł��A�Ȃ̑��V�͕v���ł͂Ȃ������ōs��ꂽ�悤�ł���B�v�w�ʕ�͌Õ�����ȑO����́A���{�����̌Â����K�������p���ł����̂��Ǝv����B�@
�����҂����̊Ԃł́A�����M��ʂ��Č����_��Ō���A���Ԃ��ՏI���}����ƊF�ő��V�̏����ɂ�����A����͋����̕�n�ɑ������B�@
��ʖ��O�ɂ��Ă͂��킵���L�^���Ȃ����A���ߐ��ł͏���̕�n�ɑ����y�����邱�Ƃ���߂��Ă����B�v�w��Ƃɂ͂�����邱�Ƃ��Ȃ������悤�ł���B�@
�����ȍ~�ߐ��Ɏ���܂ł́A��n�͈ʊK�̍������̂��̂����A�W�����Ƃɏ���̏ꏊ�ɗp�ӂ��ꂽ�����̂��̂������悤���B���O�͏W���̐����Ƃ��Ă݂̂����ɖ��邱�Ƃ��ł����B������̂̕�̏�ɁA��̖����L�����悤�ɂȂ�̂͋ߐ��ȍ~�̂��Ƃ��Ǝv����B�܂��č����̂悤�ɁA�Ƒ��P�ʂő���悤�ɂȂ�̂́A�����Ǝ���������āA�����ŋ߂̂��Ƃɑ�����̂ł���B
�@ |
���Ñ�̕搧
�͂��Ƃ͂͂Ԃ�(����)�́u�́v�ƁA�ꏊ��\���u���v�̍�����ő���������킷�B�˂͓y�肻���ɖ�A���������ł���A��͒n���ɖ������ĕ��u�̂Ȃ����̂��������A��ʂɂ͎��҂𑒂�ړI�ō��ꂽ�ꏊ�S�Ă��ӂ��ށB
���ČÑ�̏W���ł͒����L��̈������҂̖����n�ɂ��Ă�̂́A�ꕶ����̓����ł���B�I���O4000�N�O����I���O200�N����܂ł́A���҂͏Z���̋߂��ɖ������ꂽ�̂ł���B�����ɂ͎��҂͐g���̋�ʂȂ������ё����Ă���B���@�͑唼���y���ŁA���ɂ͉Α����ꂽ�c������[�߂��y��`�e�����������Ă���B���������炩�̗��R����A�L��ɑ���Ȃ��҂ɓK�p���ꂽ���Ƃ��l������B
���āA�ꕶ����̓y���̏ꍇ�A���҂͐L�W���������̎p�ő����Ă���B�����ė����Ƃ��Ɉ�̂������ٔ����Ă���̂ł���B�����������u�́A�����炭���҂̑̂Ɉ��삪�Ƃ���A���ꂪ�����o���ďZ���Ɉ��������邱�Ƃ�����Ă̏��u�ł��낤�B���ɐ����������A�����P�����Ԃ����肷�鏈�u�������悤�Ȕz������������B
���҂ƈꏏ�ɕ����i�����镗�K�́A�ꕶ����ɂ͖k�C���������Ƃ��̗�͏��Ȃ��B����������A�r�ւ��͂߂���̂͑������A����͐��O�g�ɂ��Ă��������i�����̂܂������܂ꂽ���̂ł���B
|
���퐶����
���҂Ɛ��҂����ڂɊւ�肠��������ł���ꕶ�Љ�ɑ����퐶����́A�u���Ҋρv���傫���ω������B�嗤���痈���������A�V�����_���Ɛ��x���g���ēn�Ă����Ƃ��A�ꕶ�����̕��K�͏I���Ɍ��������̂ł���B
�퐶�������͋ߋE�n���ɐV�����搧�������炵���B�E���ł͕��`���a��ƌĂԁA�l�����a�ŋ�悵������y�������悪�o�ꂵ���B���̕�ɂ́A�����Ɍˎ�𑒂�A�e�ɍȁA���͂ɂ��̎q�Ƃ����u�Ƒ���v�̌`���ƂĂ���B2��ڂ͐��̕��`���a��̈�ӂ���Ĉ�i�Ə������c�ނƂ������F�����B���̋K�͂�1��10���[�g������Ⴊ�����A���҂̐�����Ԃ����L����Ԃ����҂ɗ^���Ă���B
���������A�k��B�ł͎x�Ε���P������������Ă���B�P���͖퐶�����������ɂ����ċ�B�e�n�ɕ��z���Ă���B���̑��@�͌Õ����㒆���܂ōs�Ȃ��Ă��邪�A���̌�A�������Ă���B
|
��������
3���I����7���I�ɂ͌Õ����オ�o�ꂷ��B���̑O�����Ɍ���ꂽ�Y��ȋK�͂̑O����~���́A���̑唼��������l�̍����𑒂�݂̂ł���B����͑O����~���̋@�\�ł���Ƃ�����H�N�A���ʂƂ��������̎���A�p���ɂ������Ր��̕���Ƃ������@�\�����������Ă���B����[�߂��Ύ��́A��̂╛���i����邽�߂ɑ����Ă���A���ɂ͓����⑽���̕ɋʐ����Ȃǂ��u����A�g�̗��e�ɂ͑����⌕�A�g�Ȃǂ����x��ꂽ�B�������������i�́A�P�ɍ��M�Ȑg�������������łȂ��A�@���I�ȈӖ����������������̂ƍl������B
��������{�ɓ�������̂ɍv���������������q�́A�u�������q�`��v�ɂ��ƁA����26�N(618)�ɁA����̕���Ȓ�(���Ȃ�)�ɒz�����Ƃ���B���O�ɕ���c�ޏK���͂��̂悤�ɌÂ����炠��A������u���ˁv���邢�́u�����v�Ƃ��ł���B
���Ñ�Ƃ̕�����
�������傫���ω������̂́A646�N�ɏo���ꂽ�u�����߁v����ł���B���̂Ƃ��ɂ́A��̑傫����z�����ԁA�l���Ȃǂ��ׂ����K�肳�ꂽ�B�܂��}���̕����֎~�����Ă���B�����̗��R�́A��n���c�ɔ�p�������肷���錻������܂��߂���̂ƁA�����ЂƂɂ́A�����̕������������̂ł���B���ȉ����q�ȏ�̎҂͏���p���ĕ�����A�����͈��̑��������߂āA�U�����邱�Ƃ�������Ȃ������B���(701)�Ȍ�͎O�ʈȏ�̎҂���������������ꂽ�B
�������ˌÕ�
���̎����ɂ́A����p���������ȐΎ��A���邢�͐����ȐΎ����o�ꂵ���B���̓T�^��1972�N���@���ꂽ�����ˌÕ��ł���B������1�{�̏����������̂ō����˂Ƃ���B���̌Õ���7���I������8���I�����̂��̂Ƃ���A����h��̎l�ǂɂ͌����E�鐝�E���ՁE���Ƃ����l�_�A�ߎ��̒j�����`����A�V��ɂ͐��h�A�������ǂɓ������`�ʂ���Ă���B���̕掺���ɂ́A�M�l������l����������Ă���B���ɂ͕v�w����������邪�A���̏ꍇ�͍��ʂ̏����Ƃ��ĕv�̕�ɓ������ꂽ���̂ł���B����A�lj�ɏ���ꂽ�掺�Ɋ֘A���āA���J�ȍ��̊�������A�O��̂Ȃ��ʖ��A���邢�͐�����������炳�ꂽ���Ȃǂ̕����i�������B����Ɏ��҂́u�`�v�⎞�ɂ͂��̂т��Ƃ��L�����掏�����̎����ɐ��܂ꂽ�B
���{�ł̊�́A��������̉e���ŁA7���I�̌㔼����8���I�̌㔼�̍��ɍs��ꂽ�B�͂��ߓy����ɍ̗p���ꂽ���A���̌�A�Α��̗��s�ɂƂ��Ȃ��A�Α���ɂ���������A�Α�����L�̂悤�ɂȂ��B�������A�Α���̏ꍇ�́A�Α�����[�߂������o�ɒ��ڍ����ꂽ���̂����B�����B���Ƃ�����炪�A8���I�̏����ɂ̂��肳��Ă���̂ł���B�掏���ɂ́A����瓺�����قɒ��ڍ����ꂽ���̂̂ق��A�����`�܂��͒Z����̍ג������E�����E��̂��̂�����B
���Α��̉e��
�w�����{�I�x�ɁA�����m�ł��铹��������700�N�A���ɍۂ��ĉΑ����⌾���A��q����������䶔��ɕt�����ɂ��ĎU�����������q�ׁA�u�V���̉Α������Ɏn�܂�v�ƋL���Ă���B�����̉Α��Ȍ�A�����̕��y�ƕ��s���āA�Α����V�c���͂��ߋM�a�̊Ԃɋ}���ɕ��y���Ă������B����ɂƂ��Ȃ��A����܂ł̉������Ε���Ί���͎p�������A�����āA���C�A���فA���܂ɉΑ�����[�߂�V�����搧���o�ꂵ�Ă���̂ł���B
�w�Î��L�x��M�^���������b�����C(723�v)�̕�ƕ掏���b��ƂȂ����Ƃ�����B�掏�͉Α���������[�߂��؟C�̉��́A�ؒY��~������ɗ������ɒu����Ă����B�Ȃ��⍜�ƈꏏ��4���̐^�삪�������Ă���B���̐^��͖��E�ɋP����ł���A4�͖����Ƃ�����B
�������̑����̒n
���łɓޗǎ���(710�`784)����A��s�̓����ɕ�邱�Ƃ͖@���ŋ֎~����Ă���A���鋞������͓����̕�͈����������Ă��Ȃ��B�������ł����̕��j�͊т���Ă���A�V�c�E�M���̕�͂�������x�O�ɑ����Ă����B�ł͈�ʏ����̕�͂ǂ��������B�w�O����^�x861�N�̏��ɁA�S�������E���q�n��5�ӏ�����߂��Ă��邱�Ƃ��L����Ă���B�܂��w������L�x�ɋ��̎��ӂ̎R��E�͌����A�ނ珎���̑������ł����B���̐��k�̂�������A�M���A����̒����R�A�������т��A���łɕ������ォ��̑��ꂾ���̂ł���B
|
����������(794�`1185)
�M���̕���ɂ͑����k�����Ă�ꂽ�B850�N�̐m���V�c�̐[���˂ł���B921�N�A�V��@�̑m�E�nj��̈⍐�ɁA�u���O�ɕ�n�����߁A���ꂻ�̑O�Ɏ���k���̏��n�ɂ��Ăق����B�������O�ɏ�������B�Ԃɂ���Ȃ���A���̓��̒��ɓ������A3���ȓ��ɖ�������v�ȂǂƂ����c���Ă���B�Γ��Ɋւ��Ắu�Α��s�k�O�ɍ��^��łق����B�����^����O�ɖ����I���A���ς炭�����s�k�𗧂āA���̉����@��A��������ɂ����ď�ɓy�����x���B�l�\����̂����ɐΑ��s�k������āA���ĕς���ׂ��B����͈��炪�Ƃ��ǂ�����̕W���Ȃ�B���s�k�ɁA�����A�܉F�A����ɂȂǂ̐^�������u���v�Ƃ���B
�������̎����́A���鋞�ɂȂ��Ă���͋������ɕς�����B����6�N(936)�ɑ�����b�ɏA�C�������������́A���̑��V�c�ƕ���o�̕�Ɍw�Ă���B���̔ނ��A�`���̑c���⍂�c���̕悪�ǂ��ɂ���̂��m��Ȃ����B�����M���̑��V�͑����Α��ŁA�Α���܂ł͒����Ă������A�����ɂ͗�����킸�A����Ő��߂����܂��ĉƂA��A���グ�͌̐l�̓���̎q�ȂǁA�g���̉��̎҂����قɔ[�߂ĕ揊�ɔ[�߂��̂ł���B
938�N�A�s��l���́A�O���������ċ��ŏ����������A�S�[���E���u�얳����ɕ��v�Ə����ĉΑ����Ă���B
������[���̗��s
1085�N�A���M�@�e��������A�⍜������R�ɔ[�߁A��̏�Ɉ���ɓ������āA�O���m��u���B1108�N�A�x�͓V�c�̈┯������R�ɔ[�߂�B���̂悤��12���I�ɓ���ƍO�@��t����̒n�[����R�ɁA�Α�����┯��[�߂鍂��[����������ƂȂ�B�m��3�N(1153)�Ɏ��������o�@�@�e���̏ꍇ�ɂ́A�����䏊����⍜�𐼗тɈڂ��ĉΑ����A�@�����[���䍜���z�ɂ����Ă������ɍ���R�ɓo��A���̒n�şq�������ƁA�w���͋L�x�͋L���Ă���B���ӂ̏�y�Ƃ��Ă̍���R�֔[�����邱�Ƃ́A���@�̎���̓V�c��M���̊肢�������̂ł���B�܂�����R�[�����ە����A�����S���ɍL�߂����쐹�̗͂��������B
���n�[���̕����͍���R�������Ċe�n�Ɋg�U���Ă������B�w���͋L�x��1167�N�ɂ́u�n���ɔ[�������̏�ɌܗΓ��v�𗧂Ă�v�Ƃ����L��������B���������ܗ֓���p�����[���́A�����[�����s�̒[���Ƃ��āA�₪�Ċ��q�E���������ʂ��ď����ł��т�������������悤�ɂȂ�B
|
�����q����(1185�`1333)
���q����A���q�ł͕����E�m���̖������@�ɕ��n�Ƃ₮��̓���������B���@���ł̕��n�����ł́A�ܗΓ��̕�W�𗧂Ď��͂ɕ�����ʂ��邽�߂̓y�����߂��炵�Ă���B������̌`�Ԃ͑��n���ł͌����Ȃ��u�₮��v�ł���B���̎O�������͂ގR�X�̐���R���ɁA�����̊⌊���J���A���Ɍܗ֓��Ȃǂ��[�߁A��ǂɋ����ŋɊy��y���`���ꂽ�B�����ɚی�����������A�����ɉΑ������[�߂�ꂽ�B
�������̐��x���Ƃ�l��Ȃ���A�s�s����i�߂Ă������q���{�ɂƂāA���n�̏��Ȃ����q�̎��͂̎R�X�ɁA����Ȃ₮�炪����ꂽ���̂Ǝv����B�₮��ɑ���ꂽ�̂́A�����̊��q�҂Ƃ̈ꕔ�ŁA��ʏ����́A�������̏�J�Ɠ��������Ӓn�̒J�Ԃ̑��n�ɑ���ꂽ��A���邢�͂��̕t�߂ʼnΑ�����A�����̔[�����Ȃǂɖ������ꂽ�̂ł��낤�B
���e�a�̕���
1262�N�A��y�^�@�̊J�c�e�a���f�������A���̕����ɂ��āw�e�a��l�G���`�x�ɂ́A�u���̎���9���Ƒ����𓌎R�̑�J�ɔ[�ߐΔ�𗧂āA���c�ɕ��z������9����[�߂�v�Ƃ���B
���q�̓쑤�̍��l��т���́A�����̐l������������A���Ɏc���ꂽ�����Ȃǂ���A���O3�N(1333)�A���q���{�ŖS�̍ۂ̐펀�҂��܂Ƃ߂đ���ꂽ���̂Ƃ������B���������̌セ�̕t�߂�������Ȃ�̐��̐l������������A���{�ŖS�������ł͂Ȃ��A�����̕�n�n�тł������Ƃ����������B���q�̒�����芪�����E�͂���������n�E��n���L�����Ă����̂ł���B
���֓����S�̔�
���m�̕�ɂ͑����k���������A����ɂ̎펚�Ȃǂ����ޔ�͕������m��13���I�������痧�Ă����̂ŁA�֓��n��ɑ���������B��͐��O�ɂ��炩���߁A����̉���������ė��Ă���ꍇ�������Ƃ����B����͎���ɕ�𗧂ĒǑP���{��������A7�{�����ʂ������ƌ����Ă��邩��ł���B
|
����������(1336�`1573)
���m�̗�(1477)�Ȍ�́A�����̎��@�ŋ����ɕ�n��݂��Ă���Ⴊ�������o�Ă���B16���I�������ɂ́A����Ɏ���m�����ɑ��A��{������Ƃ��ċ����n�ւ̓y���������Ă��邪�A����́u�������v�ł�����A���łɊ��������ƂȂ��Ă������߂̗�O�[�u�ł���A���{�̊�{�p���Ƃ��Ă͂����܂ŋ������@�ł̑����֎~�ł����B�܂������Ȃ��傫�ȗ͂������Ă�����b�R��������l�̗��ꂩ��A�������@�̋�����n�Ɉ��͂������Ă����B�������Z�l�����́u���@�̖{���߂��ɕ�𗧂āA�����ŏ����ɂ킽���ĒǑP���{�������v�Ƃ����肢�������Ƃǂ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����B�������ēs�s���̎��@�Ƌ�����n�ւ̖����Ƃ����A�ߐ����猻��ɂ܂ŘA�����Ă����n�̂�������o�ꂵ���B
|
���]�ˎ���(1603�`1867)
�Α��擃�͊��q���ォ�����A�ߐ��ɓ����Ă����������������ꂽ��A�]�ˎ��㖖���ɂ܂ŋy��ł���B�Ƃ��낪����ƕ��s���āA�]�ˎ��㏉������A�擃�ɐV�����`�Ԃ����������悤�ɂȂ�B����͐듪�^�Ɗp��^(�l�p����)�ƂŁA�듪�^�̂��̂́A�������R�`�����Ă���B�p�Γ��ł͓����Ɉʔv�`�Ƃ����Ă悢�����̂������̂�����B���������`�͈ʔ�̉e���������̂ƍl�����A���\��������ɂ��Ă��炽�Ɍ����������̂̑����͕������ł���B���̐Γ��ɁA�����A�v�N�����A�N��A�����Ȃǂ�����A�u��c��X�V��v�Ƃ���ꍇ�Ȃǂ����Ȃ��Ȃ����A�{�����͎��҂̗삪�h����̂ƌ��킳��Ă����̂ł���B�@�h��n���ɂ���Ă��قȂ�A��y�^�@�̂�����Ȗk���n���ł́A�\�ʂɁu�얳����ɕ��v�Ƃ݂̂��邵�A���ʂɌ̐l�̐��������邷���Ƃ����ʂł������B
����A����������ߐ��ɂ����A�M����喼�A���Ȃǂ̂��߂̑傫���ܗ֓���������������Ă���B���������ܗ֓����⸈��A�킸���Ȃ���ˑR�Ƃ��đ�������Ă���B�����̌ܗ֓��ɂ́A�O��Ɠ��������̓����ɉΑ����[�������̂����邪�A�����͊�d���ɖ����{�݂��݂����Ă���B�Α������ʂł���B
�]�ˎ���͒h�ƂƎ��@�Ƃ̊W���m�����A���@�̋����ɕ悪�c�܂ꂽ�B�����̎�暉@��1640�N�ɑ��c���ꂽ���A�����̂����̒����ŁA��̂��P���ɔ[�߂�ꂽ���̂������A�P�͏튊�Ă��̑��P�ł������B�؊��̏ꍇ�ɂ͍����ƐQ���ŁA�قƂ�ǂ������ł������B
�y���̏ꍇ�ɍł����ʂɂ͖؊��Ɉ�̂�[�߂�����������̂ł���B�܂��Α����L���s�Ȃ��A�Α������l���𑠍����z�܂ɔ[�߂Ė���������A�P�ɉΑ����݂̂߂����̂�����B
�����쏫�R�̕�
1958�N�A�����̑��㎛�̓��쏫�R�̉����ɔ����A��K�͂Ȓ������s�Ȃ�ꂽ�B�����ɖ�������Ă����̂́A��㏫�R����G���E�Z��Ɛ�E����ƌp�E���Əd�Ȃǂł���B���R��̕�W�́A�Ɛ�̓����̂ق��A�ƌp�E�Əd�E�ƌc�E�ƖΓ��̐ΐ��ł���B
����ƕ���̏ꍇ�ɂ́A���W�Ƃ��A���̉��ɐΎ����݂����Ă���B�Ύ��ɂ́A���R�͓����Ɩ؊����A�v�l�E�q���̏ꍇ�ɂ͖؊����p�����Ă���B���R��́̕A�ƌp�̂��̂�3�����A�Ύ��̑傫����1��2���A�[��2���ł����B���R�����̐Ύ��́A�v�l��y�юq����̂��̂ɔ���S�ő傫���A���R��ɂ̂ݓ����̒��ɖ؊������ߊ��̂��̂ł������B
�����̕�ɂ́A���R�̏ꍇ�A���E���E���N�����E�݈ʊ��ԁE�I���N�����E�v�N��E���|���ʁE��拍������܂�Ă����B
�ɒB���@(1636�v)�̗�_�E���P�a�̒n����\�̒����ɂ��ƁA��̕��͐Ύ��ŁA�����̑傫����1.8���A1.2���A�[��1.45���ł����B���̐��@�̕���́A�ߐ������̑喼��̍\����m�邤���ŏd�v�ł���A�{�i�I�ȋߐ��Ύ���̂͂���ƍl������B
�����s�a�J��ɓ��@�@�̎��@�Ő���@������B1644�N���Ă�ꂽ���̂ł��邪�A���H�v��̂��߁A�������ꂽ�B���̑ΏۂƂȂ����ʐς�1,800�������ŁA��W400��A��̖�2,200�́A�����y����7���ł������B���̂Ȃ��ɋI�B����ƊW�̕悪9���A��W�̉��ɂ͐̊W�����Ă���A��̂�[�߂����̏�ɂ́A���̕掏���[�߂��Ă����B
�����i�ɂ́A�F���@�̕揊����A���̎苾�Aꈍb�̋��A�m��̂����A���˕��̐������Ȃǂ��������ꂽ�B���ɂ��̋��A��̑܂Ȃǂ��������B��̂̉��ɂ́A���C�悯�̂��߂̖ؒY������Ă���A���ɂ͏��O���������Ă����B(�͉z��s�w�@��o���ꂽ�]�ˎ���x�Y�R�t)
���l�Z�m�̕�
����ܑ㏫�R�j�g�̎���A1702�N12��14���A�ԕ�̋`�m�������g�ljƂɓ�������A��������̂��Ƒ�ΗǗY��́A�g�ǂ̎�������Đ�x���̎�N�̕�ɕɖK��Ă���B���N2��2���`�m�S�����ؕ����Đ�x�����̋���̕摤�ɑ���ꂽ�B�������ɂ͐�N�̌㎺�ł�������@���{��ƂȂ��Ė@�v���s�Ȃ�ꂽ�B�����ɂ͐��������̒��b�N�X�Ƃ����������������Δ�𗧂Ă�͂��ł��������A���Е�s��������ւ��āA�P�ɉƗ��Ə����ė��Ă�悤�ɂȂ����B���ꂩ��O����ɂ�46�l�����߂��Ă����̒����ɁA�̒n���l�����Ă�ꂽ�B���̑�ɂ͖������F�邱�Ƃ��L����Ă���B�Ȃ��������̂悤�ɔނ�̉����͂��ׂāA�n�ƙ��̕����������Ă���B
���V���̕�
�g���̗V�f�ł́A1750�N�Ȍ�A��������2�`3��l�̗V�����������A�N��70�l���S���Ă���B�����S����Ɩ钆�Ɋf���t���Â�ɂ��ĉ^�яo����A��Վ��A���������邢�͑剹���ɉ^���B������g���̐��Ɠ��Ɠ��3�J���̓������ݎ��Ƃ����Ă����A���̓����ݎ��ɁA���Ε��Ƃ��ē������Ă�ꂽ�B��Վ���n�����ɂ���u�V�g�����쓃�v�ɂ�2������l�̗V���������Ă���B����ɂ́u���܂�Ă͋�E�����Ă͏�Վ��v�ƍ��܂�Ă���B
�V�h�̗V�f�ł́A�k���̐��o�����������ݎ��ɓ�����A1�N����15�l���ނ��A���a9�N����吳12�N�Ɏ���152�N�Ԃ�2,200�l���������܂�Ă���B�R����������č���Ɂu�q��������v�����邪�A�u�q���v�Ƃ͗V���̂��Ƃł���B(�����q�w�h������x)
���Y���҂̕�
�]�˂̖k���ˌ��͌Y��ŁA���҂���ڂ͂����ς��y�@�̉���@�ŁA�{���͈���ɔ@���ł���B���̎��@�̋����ɂ͌Y���҂����悻20���l�]�肪�������ꂽ�Ƃ�����B���̒��ɂ́A�l���m���Y�g�┪�S�������Ȃǂ�����B�܂������Ɛl�Ƃ��āA���ˌ��ŏ��Y���������g�c���A�A���{�����Ȃǂ�����B
�����̐����n
�]�ˎ���̑��ɂ͑��7�悪����A���̒��ŋK�͂̑傫���̂������n�ł���B���݂̐���O�́A�����ɓ���܂ł͐�����A�Y��A�Α���𒆐S�Ƃ��������n���������B����3�N�ɌY�ꂪ�p�~����A�Α���ƕ�n�����{��Ɉڂ��ꂽ�̂ł���B
|
������
����5�N�ɖ@���ɂ���Ď����Ղ��֎~����A���V�͂��x�Đ_��E�m���ɂ��x�����ƂɂȂ����B����3�N�Ɏ��@��n�͂��x�č��L�n�ƂȂĂ����̂ŁA�r���i�߂ɂ��_���ՊϔO�����h�v�z�����������߁A�_���Ւn�Ƃ��Ė���5�N�ɓ����s�c��n�Ƃ��ĐR�E�J���E�G�i�P�J�E����̊e��n���J�݂��ꂽ�B�s�c��n�́A�͂��߂͐_����n�Ƃ��ďo���������A�Α���ے肷��_����n�͎���ɂ���Ȃ��Ȃ�A�₪�ċ�����n�Ƃ��Ă̐��i��тт��B����22�N�ɁA�s�X�n�ɎU�݂����n�̈ړ]���j����Ă���A����36�N�ɁA���@�̋�����n���ړ]���������ꍇ�ɂ́A���̐Ւn�����t����|����������ĉ��������サ���B
��K�͂Ȏ��@��n�̈ڑ��́A�吳12�N9���̊֓���k�Ђ̕�����Ƃɔ��čs�Ȃ�ꂽ�B���������̂Ȃ��ŁA������n�́A�吳12�N4���ɊJ�݂��ꂽ�B�����s�c�̑�����n�͓��{���̌�����n�ŁA�s�S���琼�֖�29�L���̒n�ɖʐ�133�w�N�^�[�����߁A����4�������n�ŁA�c���͒ʘH�A�뉀�Βn�ɂȂ��Ă���B�����ɂ͌R�l�̓��������Y�A��Ƃ̉i��ו��A�Ėڟ��Ȃǂ̕悪����A���̑���6��2000��Ƃ�����B���̎�̌�����n�͂��̌�e�n�ő����č����悤�ɂȂ�A���a10�N6��4���ɂ͏��ˎs�ɔ����쉀���J�݂��ꂽ�B�������N���Ƃɖc�����������s�s�ɂ����ẮA��s���̎�������������������Ƃ͍���ŁA�����܂��܂����ꂪ��艻���Ă���B�@ |
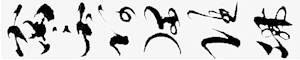 �@
�@
�������� |


 �@
�@ |
�������͎��҂����߂̋V���ł��B���̎��܂ő������Ă����l���A�ՏI���}���l�ԂƂ��Ă̎���(���A����)�͖����Ȃ��ł��B����͑�ςȕω��ł���傫�Ȋ���I�E�S���I�e���������炵�܂��B���݂��Ă������̂������Ȃ�킯�ŁA����܂Ō�肩���Ă����l�����������Ă���Ȃ��Ȃ�̂ł��B���̂悤�ȕω��ɑΏ����邽�߂ɐ����Ă���l�Ԃɑ��āu���₵�v�̋V���A���Ԃ��悷�邽�߂̃C�x���g���K�v�ł��B���ꂪ�������ł��B�������́A�@�����z���A�@�h���z�����l�ԂƂ��Ă̍s�ׂł��B������A�������͐�s���ׂ��ł��B��y�@�ł͈���ɗl�̂��͂ɂ���āA���҂͋Ɋy��y�Ƃ������E�ɐ��܂�ς��܂��B���̋V��������s���̂��m���ł��B���̋V�����s���ΕK���A��ɋɊy�֑���͂��邱�Ƃ��ł��܂��B�����l���邱�Ƃ��M�Ƃ������̂ł��B�ŋ߂͐M���Ȃ��̂ɋV���Ƃ��đ������c�ނ��Ƃ����邩�Ǝv���܂��B�������A���̂悤�ȏꍇ�ł��������͉c�ނׂ��ł��B�����Ȃ������̈⌾�ő��V�����Ȃ��ꍇ�������܂��B�������A�⌾��j���Ă����������s���ׂ��ł��B���V�͖S���Ȃ������̂��̂ł͂Ȃ��A��Ɏc���ꂽ���҂ɊW����S�Ă̐l�̂��߂̂��̂ł��B���V�̕��@�͂����R�ł����A�Ȃ�ׂ����O�W�̂������l��吨�W�߂ĕʂ�̋V�����c�ނׂ����Ǝv���܂��B�@
�����o�@
���o�́A���̂܂ܕ����Ă��Ă����������Ă���̂��킩��܂���B����͊��ꂽ�����̗�������̂܂ܓǂ�ł��邩��ł��B���������u���o�v�Ƃ̓T���X�N���b�g��́u�X�[�g���v�̊����ŁA�D���Ȃǂ́u(�c)���v���Ӗ����A�c���Ɖ����ƂŐD�����o���オ��܂����A�̒ʂ����c�����Ȃ���Ί��������܂���B��������]���āu�Ȍ��Ȍ��܂莖�A�K���v�Ƃ����Ӗ��ƂȂ�A�����ɂ���������܂����B�������Ȃ���A�����̂��o�͊Ȍ��Ȃ��̂͏��Ȃ������ɐ����������Ȃ��Ă��܂��B���o�Ƃ͊�{�I�ɂ��߉ނ��܂̐��X�̐��@�̌��t�������L�������̂��ƌ����Ă��܂����A���ۂɂ͂ǂ�ȌÂ����o�����߉ނ��܂̎��㐔�S�N�قnjo���Ă���Ҏ[���ꂽ���̂Ȃ̂ł��B����͉��̂��ƌ����܂��ƁA�����̂��V����B�́A�������g�����Ƃ������ɁA���߉ނ��܂�����������������L�����A�Ï��ɗ����Ă����̂ł��B���̈Ï������鎞�ɂ́A�F�A�u�@���䕷�v(���͂��̗l�ɕ����܂���)�Ƃ͂��߂ɏq�ׂ��̂ł��B�ł�����A��T�̂��o�́u�@���䕷�v����n�܂��Ă��܂��B���̗l�ɈÏ�����ē`����Ă������߉ނ��܂̐��@���A�����`����������q�����n���N��ɂ���ď��������e���قȂ�A���債�ē`�����Ă����܂��B�����Ă��ɂ́A���e�����ʂ����������̈Ⴄ���o���a�����邱�ƂɂȂ�̂ł��B���̑��ɂ��A���̒��ł̂��V����̐����̂�����������ꂽ����(��)�A�����������X�̂��o�̒��߂�����������(�_)������A�O�q�́u�o�v���āA�u�o�v�u���v�u�_�v�́u�O���v�ƌ����܂��B���̐��V�L�ŗL���Ȓ����̓�����̂��V����A�����͂��̎O���̕����w���C�߂��҂Ƃ��āu�O���@�t�v�Ƃ����̍��������̂ł��B�@
�������@
���Ƃ��Ƃ͕������n�߂��߉ނ̎p�̂��Ƃł��B�������2500�S�N�O�A�߉ނ͂��܂��܂ȏC�s�̂̂��A�����J���ău�b�_(Buddha)�ɂȂ�܂����B�u�b�_�Ƃ́u�����J�����l�v�Ƃ����Ӗ��ł��B�����ŁA�u�u�b�_�v���̒�����ɖ��A�u�u�b�_�v�Ƃ��������u���Ɂv�Ƃ��������Ɏʂ����̂ł��B���́u���Ɂv���ȗ�����āu��(�ԂA�قƂ�)�v�Ƃ������t�ɂȂ�܂����B�ł�����u�����v�Ƃ́A�u�قƂ��̑��v�̂��ƂŁA�����Ӗ��ł͌����J�����߉ނ̂��Ƃ��w���܂��B�@
�������@
�ЂƂ��ƂŎ��@�Ƃ����Ă��A���ꂪ�Ȃ��Ȃ����G�ŁA�ȒP�ɐ�������̂͂�����Ɠ���̂ł��B��ʓI�ɂ́u���������u������A���V����̏Z�ތ���������Ƃ���v�Ƃ����Ӗ��ł����A�܂���������܂��B�����ŁA�܂��͌��t�̉�����炷�邱�Ƃɂ��܂��傤�B���Ƃ�����́A�����ł́u�����v���Ӗ����܂����B�㊿�̖���(�߂��Ă��A�݈�57-75�N)�̎���A�ޗt����(�����傤�܂Ƃ�)�Ǝ��@��(�����ق����)�Ƃ����C���h�̑m���A�͂��߂Ē����ɕ�����`�����Ƃ�(�ِ��A�������ƌo�T�������炵���Ƃ�)�A��l�͍��e��(�����낶)�Ƃ�������u�}�o�فv�ɑ؍݂��܂����B���܂ł������ɔ��܂��Ă���킯�ɂ͂����܂���A��l�̏Z�ޏꏊ�����āA�����n�ɏ���Ă���Ă������Ƃ���A���n��(�͂���)�Ɩ��Â����܂����B����Ȍ�A���V����(�m��)�̏Z�ޏꏊ���u-���v�Ƃ����悤�ɂȂ����̂ł��B���{��Łu���v���Ă�Ɣ�������̂́A���N��ɗR������Ƃ�����(chy*ol����q���A���邢��char������)��p�[����̃e�[��(thera�����V��)�̉����Ƃ�����Ȃǂ�����܂����A�͂����肵�����Ƃ͂킩���Ă��܂���B�@�́A���͎��͂̓y��(�ǂׂ��A�_)�̂��Ƃł������A�͂��̂��錚���Ȃǂ��Ӗ�����悤�ɂȂ�A�����Ȃǂɂ��g���܂����B���݂ł́A���̂Ȃ��̕ʓ�(�ʎ�)�̂��ƂŁA���ƍ��킹�Ď��@�Ƃ����悤�ɂȂ����̂ł��B�@ |
 �@
�@
���q�ǂ��̎��Ƒ��� |


 �@
�@ |
�q�ǂ��̎��قǔ߂������̂͂Ȃ��B�܂��A�q�ǂ��̑��V�قǁA�݂ĒɁX�������̂͂Ȃ��B�Α��ɕt���Ă��A�������炢�܂ł̏����Ȏq�́A�����\���ɔ��B���Ă��Ȃ�����A�����Ƃ����ԂɏĂ��Ă��܂��A���Ƃɂ͊D�����c��Ȃ����Ƃ�����B����ł��A�q���������e�����́A��D�������Ț�Ɏ��߂ĉƑ��̕�ɑ���A�₪�Ă͎����������ꏏ�ɓ����ƁA���̖������F��ł��낤�B�@
����Ȃɉ����Ȃ�����܂ŁA�q�ǂ��̎��͒��������Ƃł͂Ȃ������B���쎞�ォ��ߑ�̖閾���ɂ����ẮA���l���l�ƎY�q���A�S�������Ɉ���Ƃ̂ق����������������炢�ŁA�q�ǂ��̎��S����m���͍��������̂ł���B�܂��A�_���ł́A�ꂵ������̌����炵�Ƃ��āA�d���E�����g�D�I�ɍs��ꂽ�Ƃ����L�^������B�@
���q���A�̂̓��{�l�́A�ǂ̂悤�ɑ������Ă����̂��낤���B�@
���{�l�́A�×��q�ǂ��Ƃ������̂ɑ��āA���ʂȊ���������Ă����ƍl������B�����̃��[���b�p�l���A�q�ǂ�����ʎ������A���n���A���邢�͏o�����Ȃ��̑�l�Ƃ������Ă��Ȃ��������Ƃ́A�A���G�X���u�q�ǂ��̒a���v�Ƃ����{�̒��ŁA�͐������Ƃ���ł���B���̂悤�ȕ����ɂ����ẮA�q�ǂ��̎����A���ʂȂ��̂ł͂Ȃ��A���̖��������ڒ��ɍs��ꂽ���낤�B�@
�������A������̓��{�l�́A�q�ǂ��̎�����ʂ̂��ƂƂ��Ď~�߂Ă����B�q�ǂ����A��l�Ɠ������썰�������݂ł��������A��l�ƈႢ�A���̗썰�́A�܂��\���ɔ��B�����A����A�Ԃ��J���Ă��Ȃ����̂ł������B�����ł��邩��A���̗썰�́A�Ԃ߂��A�������܂��ׂ����̂ł������B�@
��l�����ꍇ�A��̂͗썰�̔����k�ł���A����Ȃ�u���́v�ɋ߂����̂Ƃ��Ĉ���ꂽ����A�V�������썰�͌h���ĉ��������A�₪�Ă���c�l�Ƃ��āA�_�ɂȂ邱�Ƃ����҂��ꂽ�B�@
�Ƃ��낪�A�q�ǂ��̗썰�́A�e�����⑰�̂��Ƃɖ߂��Ă��邱�Ƃ��A�������҂��ꂽ�̂ł���B�@
�܂��A�q�ǂ��̈�̂́A��l�̏ꍇ�ɂ�����悤�Ȗ��ڒ��Ȉ����͎Ȃ������B���̕���A�q�ǂ��������Ԃ����Ƃ��ɁA�e�Ղɏo�Ă�����悤�ȍH�v�����ꂽ�B�������ꂽ��n�ł͂Ȃ��A�Ƃ̕~�n�̒��ɖ��߂�悤�Ȃ��Ƃ��������悤�ł���B�@
���q�ǂ��̗썰���A�ʂ̐����āA���܂�ς�邱�Ƃ��A�������҂���Ă����B����q�ǂ��̗썰���A�ق��̎q�ǂ��̌`���Ƃ��Đ��܂�ς��Ƃ����M�́A�����̗։��]���Ƃ��W��肪���邾�낤���A���{�×��̗썰�ςɐ[���������Ă���Ǝv����̂ł���B�@
���q�ǂ������܂�ς�����Ƃ��ɁA��������Ƃ킩��悤�ɁA�q�ǂ��̈�̂ɂ��邵��t���镗�K���L������ꂽ�̂́A���̂悤�ȗ썰�ς̌���ł���B�����悤�Ȃ��邵���F�߂���q�ǂ������܂�Ă����Ȃ�A����͎��q�̐��܂�ς��ɊԈႢ�Ȃ��̂ł������B�@
���̎q�ǂ������́A�̂̎q�ǂ��ɔ�ׁA���ʊm���͌���Ȃ��[���ɋ߂��Ȃ����B����ł��A�s�K�ɂ��Ď��ʎq�ǂ��͂���B�����A���̐e�����́A�̂̐e�̂悤�ɂ́A�q�ǂ��̗���Ԃ߂邽�߂̏\���ȗ]�T�����ĂȂ��悤���B���̎q�́A��l�Ɠ����悤�ɉΑ��ɂ���A�w�ǂ���l�Ɠ�����ɓ���B�ނ�́A�ق��̎p�ɐ��܂�ς������A�V���ɂ₷�炤���Ƃ����҂���Ă���悤���B �@ |
 �@ �@
���Α��ƈ⍜���d �@ |


 �@
�@ |
�ߐ��ȍ~�̓��{�l�́A���҂̈�̂��Α����������ŁA���̈⍜��厖�ɕۑ����Čh�ӂ��Ƃ������Ƃ���{�ɂ��Ă������A���ꂪ���[���b�p�l�̖ڂɂ͊�قɉf��̂��Ɩ����w�҂̎R�ܓN�Y�͂����B(�u���̖����w�v)
�@
�Ƃ����̂��A�Α��Ƃ͈�̑���̋��ɂ̕��@�ł���Ƃ̌������O��ɂ��邩�炾�낤�B����ƕۑ��Ƃ͑���������B�����A�Α��̖{�Ƃ���C���h�ł́A�⍜�͐�̐��ɗ�����āA�ۑ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B��̂ɂ�����邱�Ƃ͑S���Ȃ��̂ł���B����ɑ��āA��̂ɂ�����镶���ł́A�L���X�g�������܂߂āA�`���c�����܂܂Ŗ�������̂����ʂł���B
�@
���{�ʼnΑ����������ꂽ�͕̂����V�c�̎���A����700�N�̂��Ƃł���B���̌㎝���V�c���A�V�c�Ƃ��Ă͏��߂ĉΑ�����A������_�@�ɂ��čc����M�������̊ԂʼnΑ����L�܂��Ă������Ƃ����B���̍ہA�⍜���ǂ̂悤�Ɏ�舵��ꂽ�������ƂȂ邪�A�R�܂͏����̉Α��ɂ����ẮA�⍜�͕K�������厖�Ɉ����Ȃ������Ɛ��_���Ă���B
�@
�R�܂́A���c���j�����p���Ȃ���A�Ñ�̓��{�l�ɂƂ��ẮA����̗썰�̂�������S�̒��S�ł����āA��̂��̂��̂͂��܂���ƂȂ�Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B�������������ɂ����ẮA�Α���̈⍜�ɂ��Ă��A���܂���Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�Ɛ��_���闝�R�͏\���ɂ���B
�@
�⍜�����d�����悤�ɂȂ�̂́A���������̎���̑O�ォ�炾�ƎR�܂͂����B�������g�������̕�n�ł������ؔ��̒n�ɏ����������A�ꑰ�̏��S������߂ɁA���̈⍜�J�ɖ��������B�܂��A���V�c�͊��O8�N(1011)�ɉΑ����ꂽ�����ŁA���̉Α������~�鎛�Ɉ��u���ꂽ�Ƃ����A�����Ŗx�͓V�c���Α������������Ɉ��u����A���̌䍜���Ɍw�ł���̂������Ȃ����Ƃ���B
�@
���̂悤�ɁA11���I�����ɂ��āA��̂��Α����������ŁA���̍������̕�n�Ɉ��u���Čw�ł�Ƃ����A�����Ɠ����悤�Ȉ⍜���d�̑����������A�����̊Ԃł��蒅���Ă������ƎR�܂͐��_���Ă���B
�@
�ʔ����̂́A���̂悤�Ȉ⍜���d�����̒蒅�ɁA����R���[������������Ƃ������Ƃł���B�[���A�[���Ƃ����āA�g�̂̈ꕔ��⍜������R�֎��߂镗�K��12���I���납��M���Љ�𒆐S�ɍL�܂����B����́A����R���A�^�������̍��{����ł���ƂƂ��ɁA�������������R�x�M�̗��ł��������ƂƊ֘A���Ă���B����R�֔[�����邱�ƂŁA�Ɋy��y�ɐ��܂�ς��Ƃ����M���A���������s�ׂy�������킯�ł���B
�@
����R�ւ̐M���L�������ĉ�������̂ɍ��쐹�����������A�ނ�͑S���ÁX�Y�X��������Ȃ���A�����ɂ������č���R�ւ̌�����i�߂ĕ������B�[���͌����̏ے��I�Ȍ`�Ԃƍl����ꂽ�̂ł���B
�@
�ȏ�̉ߒ����A�R�܂͎��̂悤�ɑ�������B�u�܂����ɁA11���I��������ɂ��āA�Ƃ�킯�M���̊ԂɈ⍜(�Α���)�ɑ���ϔO��ԓx�ɕω����F�߂���悤�ɂȂ�A���ꂪ12���I�̍���R�[���̈�ʉ��Ƃ����܂��āA�������Ɉ⍜�̕ۑ��Ђ��Ă͈⍜�̑��d�Ƃ����ϔO�ݏo�����B�����đ��ɁA���̂悤�ȊϔO�̈�ʉ��𐄂��i�߂邤���ő傫�Ȗ������ʂ������̂��A��y���̐M�Ɨ����M�̗��z�ł������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��낤�v
�@
���̋c�_���ǓI�ɂ݂�ƁA�Α��Ƃ����A�⍜���d�Ƃ����A���{�×��̕��K�ɍ������������̂ł͂Ȃ��A�O���̕����ɐ��܂������ʂ��Ƃ�����ۂ�^����B�������A�����������{�ɂ́A�̕��K�ɏے������悤�ȁA�⍜�d���镶�������݂����Ƃ�������������B
�@
�́A����≂���ȂǂŁA�ߔN�܂ōs���Ă������K�ŁA�����邢�͕����ƌĂ��B�ꎞ�I�Ȗ����̌��ʔ�����������̂̍���A�����{�i�I�ȕ�ɖ�������Ƃ������̂ł��邪�A���ꂪ�⍜���d�̌��_���ƍl���邱�Ƃɂ́A����Ȃ�̗��R������Ƃ�����B
�@
�R�܂͂܂��A�⍜���d�́A�Ñ�ɂ����čs���Ă���������(����)�̋V��Ɍ��_������̂ł͂Ȃ����Ƃ���ܗ��d�̐����Љ�Ă���B������ɂ����ẮA���҂������ԕ������A���̈�̂�������������ŁA���������Ƃ������Ƃ��s��ꂽ�B���̋V���̐��_���������������́A���ꂪ�⍜���d���Ƃ���̂ł���B
�@
�Ƃ����A������Ƃ����A���҂������������̉ߒ��ɂ��炵�A���̌�Ɉ⍜������Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă���B
�@�@ |
 �@ �@
�����{��ًL�ɂ�����������̑h�����b�@ |
   �@
�@
|
�R�ܓN�Y���́u���{�l�̗썰�ρv�Ƃ�������̒��ŁA�u���{��ًL�v�����グ�Ȃ���A�Ñ���{�l�̗썰�ς̕ϑJ�͂��Ă���B����͊�{�I�Ɍ����A���{�×��̃V���[�}�j�Y���I�ȗ썰�ςƁA�����I�Ȑ��E�ςƂ��Z�����Ă����ߒ��Ƃ��ĂƂ炦���邱�ƂɂȂ�B
�@
���{��ًL�́A�O�m�N��(810�|823)�ɓޗǖ�t���̌i�����傪��q�������̂Ƃ���Ă���B�ޗǂ��畽�������ɂ����Ă̗�قɊւ��閯�ԗ��z�̐��b���W�߂����̂ł��邪�A�����ɂ͋L�I�Ɍ���Ă���悤�ȉ䂪���ŗL�̗썰�ςƁA�O���v�z�Ƃ��Ă̕����I����ϔO�Ƃ��A�Ǝ��̗Z�������������Ă���Ǝ��͓����Â��Ă���B
�@
�䂪���ŗL�̗썰�ςƂ́A�V���[�}�j�Y���I�ȓ�����ттĂ���A�Ǝ��͂����B�l�Ԃ̗썰�Ƃ����͓̂��̂���V��������̂ł���Ƃ����̂��A���̊�{�I�ȑO��ł���B���̟������������āA���ꂪ�����Ă���l�ԂɂƂ���ƁA�����ꂽ�l�Ԃ͂�����_������̏�ԂɂȂ�B�����ߗ�ƌ��������邱�Ƃ��ł���B����A�V�����������ʂ�V���p�j���āA�يE�����܂悤���Ƃ�����B�����E���ƌ��������邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ɁA�V����������ߗ�ƒE���̑̌n���A�V���[�}�j�Y���Ƃ��Ă̓��{�×��̗썰�ς��`�����Ă����Ƃ���̂ł���B
�@
�ߗ쌻�ۂɂ��Ă̌��y�́A�L�I�Ɏl�ӏ�������Ƃ����B1�A�}�e���X�I�I�~�J�~���V�̊≮�B��������Ƃ��̃A�}�m�E�Y���m�~�R�g�̐_������A2�_�������̍ۂɐ_���V�c���^�J�~���X�r�m�~�R�g�̗�ɂ���Đ_�����肷�邱�ƁA3���_�L�ɂ�����A���}�g�g�g�r���m�\�q���̐_������A4�����L�ɂ�����_�{�c�@�̐_������A�̎l�ł���B
�@
�L�I�ɂ����邱���̐_�����������Â���Ƃ���A���Â���߈˂���V�������́A�߈˂����ޏ��I�Ȑl�i�̕��ɊS�������Ă���Ƃ������Ƃ��낤�B�Ƃ������Ƃ́A�Ñ���{�ɂ����ẮA�V���[�}���Ƃ��Ă̛ޏ��̎Љ�I�Ȓn�ʂ����ɍ����������Ƃf���Ă��邩�炾�A�ƌ��邱�Ƃ��ł���B����ɑ��ė�ًL�ɂ�����ߗ�́A�V�����̕��ɏd�_���u����Ă���A�Ǝ��͂����B
�@
�L�I�ɂ�����E�����ۂɂ��Ă̋L�q�Ƃ��ẮA�C�U�i�M��X�T�m�I�̉���̍��K�₪��������B�C�U�i�M���X�T�m�I������ł͂��炸�A���������Ĕނ�̗V�����ł͂Ȃ��A���̂�����������g�̐l�ԂƂ��Ă̔ނ玩�g���يE�K�������킯�Ȃ̂����A���������e���炵�āA�E���I�V���[�}�j�Y���̈يE�K��杂̃o���G�[�V�����Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B
�@
�C�U�i�M�̈يE�K��杂ɂ����ẮA�C�U�i�M�̓C�U�i�~�����߂ĈيE��K���B����ɑ��ăC�U�i�~�́A�����͂��łɃ����c�w�O�q�����Ă��܂����̂ŁA���͂���Ƃɂ͖߂�Ȃ��Ȃ�������ǂ��A���Ȃ���������^�u�[�����A����A��߂����Ƃ��ł���Ƃ����B���̃^�u�[�Ƃ́A�����čȂ���C�U�i�~�̎p�����Ȃ��Ƃ������̂ł������B�������C�U�i�M�͉���Ɍ������ē�����r���A�U�f�ɕ����Č���U��Ԃ�C�U�i�~�̎p�����Ă��܂��B���̂��߂ɃC�U�i�M�̓C�U�i�~��A��߂����Ƃ��ł��Ȃ������A�Ƃ����̂����̐��b�̍��i�ł���B
�@
���̃C�U�i�M�̈يE�K��杂̍��i�́A���{��ًL�ɏo�Ă���V�����̈يE�K��杂ɂ��������������Ă���B���̏ꍇ���ڂ��ׂ��Ȃ̂́A���̈يE�K�₪�����ł����Ƃ���̘Z���։�̃A�i���W�[�ɏd�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��B�����ɁA��ًL�̎���̖��O���A���{�×��̗썰�ς̏�ɁA�����I�Ȑ��E�ς��d�ˍ��킹�n�߂Ă������Ƃ��f����Ƃ����̂ł���B
�@
���{��ًL�̐��b�͑S���ŕS�\�Z�����邪�A���̂����V�����̑h�����e�[�}�ɂ������̂��\�܉�����B�����ɋ��ʂ��Ă݂���v�f�Ƃ��ẮA�܂��A�V�����������يE��K�₵�A�����Ō�������������h��������ɕ����Ƃ������ƁA������́A�����Ԃ������ɏh��ׂ��g�̂��c���Ă���悤�ɁA�����Ԃ��̐g�̂����̂܂ܕۑ����Ă����悤�ɂƁA�V�����̎�̂���l���������c���Ă������Ƃł���B
�@
�V�����̈يE�K�₪�E���I�V���[�}�j�Y���̐M���A��̂̈����Ԃ̕ۑ����q�̕��K���A���ꂼ��\���Ă��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����낤�B
�@
�����ŋ����[���̂́A�������̈يE�K��ł���B���Ƃ��ď㊪��O�\�b�����グ��B�V�b�L�����c�_��N�����H�㌎�\�ܓ��Ɏ���ŁA����̍���腗����̂��Ƃɍs���A�O�����o�đh�����Ƃ�������ł���B
�@
�L���̗V�����͖��E����̎g�ғ�l�ɓ�����đ�͂�n��x�썑�Ɏ���B�x�썑�Ƃ͉���̍��̂��Ƃł���B���̉����̋{�a�ɂ�腗��剤������B腖��剤�̂��Ƃł���B�����ōL���́A�S�Ȃ��S�̓B��ł���S�̓�ɔ����ċꂵ��ł���l�q����������B����ɓ�̕��ɍs���ƁA�S���������悤�ɂ��ċꂵ��ł���̂���������B���̏�ŁA�ނ�S�҂����̐��O�̍߂ƁA���E�ɂ�������ʉ���̓���������āA�L���̗V�����́A�������Ɠ����������ǂ��Ă��̐��ɐ����Ԃ�B
�@
���̘b�̒��ɏo�Ă���x�썑�������Ō����n���̃C���[�W�Əd�Ȃ��Ă��邱�Ƃ͗e�Ղɂ݂ĂƂ�邪�A�����Ō����n�����V�`�n�`�n���Ƃ��������I�ȍ\���̒��Œn���Ɉʒu�t�����Ă���̂ɑ��āA�����ŕ`���ꂽ�n���́A���̐��ƘA�������n���ɂ��邱�Ƃ�����������B�C�U�i�M�͖K�₵������̍����܂��A���̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@
���{��ًL�̂��̐��b�ɂ����ẮA���{�×��̉���̍��̃C���[�W�ɕ����I�Ȓn���̃C���[�W���d�Ȃ��āA�����̖ڂ��猩��Β��r���[�Ȓn���Ƃ��ĕ`����Ă���悤�Ɋ�������B
�@
���̑��̕���ɂ����Ă��A�V�����̈يE�K��́A�قړ����悤�ȃC���[�W�Ō���Ă���B���̑�O�Z�b�ł͕\�ʂɏo�Ă��Ȃ����A�����̕���ł́A���҂������̈�̂��c���Ă����悤�ɂƈ⌾���������ŁA������ɐ����Ԃ����Ƃ������Ɍ���Ă���B
�@
�܂��A���̑����̕���ł́A���̐��ɖ߂�ɂ������āA�V������腗�������A����̍��Ō����������Ƃ������Č���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁA�^�u�[���ۂ����Ă���B����ɂ��S��炸�A�h�����V�����́A����������̍��Ō����������Ƃ�l�X�ɕ�����Ă�܂Ȃ��B������Ƃ����āA�^�u�[�j����߂��邱�Ƃ��Ȃ��B
�@
�Ƃ����킯�ŁA���{��ًL�ɋL���ꂽ���{�l�̗썰�ςɂ́A���{�×��̑��ƊO�������Ƃ��Ă̕����Ƃ��A�Ԃ��荇���A�n�������Ƃ����ӂ��ɁA�_�C�i�~�b�N�ȓW�J�������Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@
(�Q�l)
�@
���{��ًL�㊪��O�\�@�D�����ל��s�?
�@
�V�b-�A����,沑O���{�q�S���̖�.�����{��F�V�c�V��,������.�c�_��N�����H�㌎�\�ܓ��M�\,�A������.甔V�O��,�����\��,�X�S�V����V�H:�u�g�L��l,�꒸雝���,�ꏭ�q��.��������,��郓x��,�H���L���.�x�֔V�ȋ��h��.������,�s���ޕ�,�L�r����.��g�l�H:�w��������?�x��:�w�x�욠��.�x��������,�L�����l,�Ε��lj�.�O�L���{.���{��,���L��,����?���V��.���ٜA���H:�w��������,�˓��ȗJ�\�V��.�x�����ꏗ.���V,�̎���.���c�B�Œ��ʐK,�Ŋz�ʍ�.���c㊔��l�},���l����,������.����V��:�w��m������?�x�A������:�w����V�Ȗ�.�x����:�w��m摍ߖ�?�x��:�w��s�m.�x�⏗�V,��:�w�䛉�m�V.���Ꭹ�Əo��.��,?���}�Z.�x���ٜA���H:�w�𛉖���,�҉���.�R�T��?��V��,�ܖϐ�B.��~����,�������.�x�������V,���L�䕃.���r�M�V��������.�c�B���������g�ŗ�,���c��.�g�O�S�i,��O�S�i,�[�O�S�i,����S�i,?���Ŕ�.�A�����V,�ߎ���:�w��!�����V���?�x����:�w���,��q,��m�s��.��ח{�Ȏq��,���E����,���ݔ��_�ȋ��{�\�_?,���ݏ����j������Ҏ�,���l�����D��,�����ț@��,�s�F�{����,�s���h�t��,�s�z�X�Ҕl��.�@���ߌ�,��g嫏��������c�B��,?��S�i�c�ڑŔ��V.�ɍ�!���!�����ƌ��?���������g��?�����䑢�ś��S,�܍ߋ�.�T�T���Y��.��Q������������֓�����,������?�V��,�ȏ�.���܌��ܓ����ԋ瓞���ƔV��,���������V,�B�ǑŎҋQ�M��.�䐳�����,���K�������ƔV��,�O���{���함,����㋎O�N�V��.�䖳�Z��,�㉺���控����,����?���o�`.��K���ԋ�.�x�}�z�{�Ĉꏡ�V��,�������V��.�z�{�ߕ����V��,����N���ߕ�.����S��,�Z�������{��,笊萶�V.���ŕ�F��,���������ʚ�ēy.�����V��,���k�����ʟēy.����V�H��,���\�N�V��.�T�������P������o.�A���b�p�j,���q�o��.�����l,�������q�������X.���q���A��,�����Е�����,�����厧�J�V.���o,���H:�w����.�x�A���⏭�q�]:�w��N�V�q?�x��:�w�~�m���,��c�t��,���V�����S����.�x�ҔV��,�����S��.�v�A����?�P���V��,��?���z��.��ߓ���V��?��,�嘩�S�@�A?,�N�s�M��?�����S�]:�u���݊ØI,�����c�ۖ�.�v��,���z���V��.�A����ב���,���ś��S,���{�O��,�V��,�����.�����Ȍ�,珎.
�@ |
 �@ �@
���������㖖���̑������i �@ |
   �@
�@
|
���q����̏��߂ɐ��삳�ꂽ�u�Z���G�v�̈�Ɂu��S�����v������B��S�Ƃ͐l�������Ƃ́A�����ł��Ȃ��ł���썰�̂����������킷���̂����A���̉�S�̗l�X�ȗl�����G�Ɍ������̂��u��S�����v���B���̂����A�u�ˊԉ�S�v�Ə̂���Ă���ꖇ�́A�������㖖�����犙�q���㏉���ɂ����ẮA�����ꏊ�̗L�l���f�킹��M�d�Ȏ����Ƃ��Ȃ��Ă���B
�@
�G�ɂܑ͌̂̉�S���`����Ă���B�ނ炪����Ƃ���͎��̖̂����ꏊ�����ł���B���ɂ́A�O�̐��y�ˁA��̐ΐϒ˂�����ق��A�l�l�̎��̂ƁA�U�����������`����Ă���B
�@
���y�˂͋M���Ȃǂ̐g���̍����҂�y���������́A�ΐϒ˂͉Α��܂��͉�����̕悾�낤�Ǝv����B���̂̂�����͖̂؊��ɔ[�߂��A��̂���̏�ɐQ�������A��͔̂�����������ԂŒn��ɉ�������Ă���B�����̈�̂́A�����̂��܂�`�������̂ƍl������B��������̖��܂ł́A�g���̒Ⴂ�҂̊Ԃł́A��̂�살�炵�ɂ��镗������ʓI�������̂��낤�B
�@
�˂⎀�̂̍��Ԃ�D���悤�ɉ�S��������Ă���B�ނ�͂��̕��ɑ���ꂽ��̂��甲���o�Ă����S��Ȃ̂ł���B���̉�S�̂ЂƂ肪�A�G�̏���鐂�����Ă���̂�������B�����鐂́A��S�ɂƂ��ẮA���Ă̎������g�̖S�[�Ȃ̂�������Ȃ��B�ނ͎������g�̖S�[�ƑΖʂ��邱�ƂŁA���������Ă���̂��낤���B
�@
���̊G�́A��X�ɑ����̂��Ƃ������Ă����B�܂��A��������̏I��肱��܂ł́A�����̊Ԃł͕����Ƃ����āA��̂�살�炵�ɂ��邱�Ƃ����ʂ������炵�����ƁB���̂��Ƃ́A�����̏�������̂ɓ��ʂȉ��l��F�߂Ă��Ȃ��������Ƃ���Ă���̂��낤�B
�@
���ɁA����̗썰����S�ƌ����`�ŕ\�ۂ���Ƃ������Ƃ́A�����̐l���l�Ԃ̎���̂�����ɐ[���S������Ă������Ƃ��f�킹�邱�ƁB��S�Ƃ����ϔO�͕����`���̂��̂ƍl�����邪�A����ɁA���̊G�ɂ���悤�Ȏp���Ƃ点���̂́A�����̓��{�l�̊����������Ǝv����B
�@
�����̋����ł́A��S�Ƃ͘Z���̈�ł���A���l�̗썰�̈ꕔ�͂����ł��܂悤���ƂƂȂ��Ă����B�썰�����̂܂������܂悢�A�Ȃ����A�����̖S�[�ƑΖʂ���ȂǂƂ����C���[�W�́A�����̓��{�l�����o�������j�[�N�ȉc�݂������ƍl������B���炭�A���{�l�̗썰�ς��A�����ɐ[����������Ă���̂��Ǝv����B
�@
�܂��A���̊G�ł͓y���ƉΑ��Ƃ������ԃC���[�W�Ƃ��ĕ��u����Ă���B�y���������̐i�������`�Ԃ��Ƃ���A�Α��͂���Ƃ͒f�₵�������`�Ԃł���B���݂̌��ɒf�₵���������̂��A������ʂɋ������Ă���Ƃ��낪�A���̊G�̂����Ƃ��l��������Ƃ��낾�B
�@
�Ƃ�����A���̊G�ɕ`���ꂽ���i�́A����ӂ�ؔ��Ƃ��������s���ӂ̑����ꏊ�̃C���[�W���̂��̂ƍl���Ă悢���낤�B�l�X�͎��҂̖S�[�𑒑��ꏊ�ɕ��u�������Ƃ́A�w�njڂ݂邱�Ƃ��Ȃ������B�����͎��҂Ɖ�S�̐��E�ł����āA�����Ă���҂��߂Â��ׂ��ꏊ�ł͂Ȃ������̂ł���B �@ |
 �@
�@
�����Ⴂ�����u�����r���v |
   �@
�@
|
���lj悩���ށA�Ñ�j�b�|���@
�����͎��㌀����j�h���}���D���ł悭����̂ł����A�����̐l�X�̕������ǂ�����čČ�����̂��A�����s�v�c�Ɏv���Č��Ă��܂��B�ʐ^�⌻�����c���Ă��鎞��Ȃ�܂������A�����I���O�̂��ƂƂȂ�ƂقƂ�ǎ肪���肪�Ȃ������Ɏv����̂ł����c�B�搶�́A�����j�̂�����������Ă��鐔���Ȃ����Ƃ�1�l�ł�������Ⴂ�܂����A�����j�̌����Ƃ͂ǂ�������@�ł������̂Ȃ�ł����H�@
�����A��i�A�lj�E�G�����Ƃ������G��ނȂǁA�肪����͂��낢�날��܂��B���͌Ñオ���Ȃ̂ŕ������i�����S�ł����A���Ƃ����Ă���ԎQ�l�ɂȂ�͕̂lj�ł��ˁB�@
�����������A�搶�͍����ˌÕ��lj�̐���N�㌈��Ɋւ���_����������Ă�������Ⴂ�܂��ˁB�@
�͂��B�lj�ɕ`����Ă���l���̕������琻�쎞��������o���Ă݂��Ƃ���A���{�������̕����������������悤�ɂȂ�����̂��悻20�N�Ԃɍi�邱�Ƃ��ł��܂����B�@
���Ȃ��A����Ȃ��Ƃ�����̂ł����H�@
���{�́A7���I�����̌��@�g�h�������璆���ƌ𗬂��n�߂܂����A���������������n�߂�̂�7���I����̓V��������ł��B���̕lj�̕����́A����������������܂����S�ł͂Ȃ�����ł��B�@
���Ⴆ�A�ǂ�ȂƂ��낪�H�@
1�݂͋̍������ł��B���{�͂��Ƃ��ƍ���(������)�������̂��A719�N�ɒ����ɕ���ĉE��(������)�ɕς���̂ł����A���̕lj�ł͂܂�����(������)�̂܂܂ł��B�܂��A��߂̐������߂̒��ɓ����Ă��Ȃ��̂��A�����̒����ł��B�������A�㒅�̐����E(���)�����z�����t���Ă�����A���������̂́A���炩�ɓ��̉e���ł��B�@
�����{���ƒ������������荇���Ă���̂ł��ˁB�@
�����ł��B�������ƏƂ炵�����čl����ƁA���炭684�N����703�N���̊Ԃɕ`���ꂽ���̂��Ɛ����ł��܂��B�@
���Ȃ�قǁB���Ȃ݂ɁA�����������������O�́A���{�͂ǂ��̍��̉e�����Ă��Ȃ������̂ł����H�@
���͒��N�����̍����n�����̉e�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���N�����Ŕ������ꂽ����펞��̕lj�ɂ́A�����ˌÕ��lj�Ƃ�������Ȃ��̂������ł���B�@
���Ñ���{�ƒ��N�����ɂ́A���B���l���Ă���ȏ�ɐ[���ւ�肪�������̂����m��܂���ˁB�@
���u�\���v����|�p�֕\��L���Ȑl�����ց@
���搶�́u���֓W�v�Ȃǂōu���������ȂǁA�l�����ւ̂������ł�����Ă�������Ⴂ�܂����A���������l�����ւ͂ǂ������ړI�ō���A���Ɏg���Ă����̂ł����H�@
����ɂ͂��܂��܂Ȑ�������܂��B�}���̑�p�Ƃ����Ƃ������A�q(������)�̋V�灃���҂̍������炰�邽�߂̋V������\�������Ƃ������Ȃǁc�B�����A������ɂ��Ă����炩�̂��̂�\������Ӑ}�ō����悤�ɂȂ����̂͊m���ł��B�F(������)�������Ă�����A�����������Ă�����A�������Ă�����ƋV��I�Ȃ��̂������ł��B�@
���ȑO�A�ǂ����̔����قŁu�x���Ă�����ցv���������Ƃ�����܂����B�@
����͌���̍��̂��̂ł��傤�ˁB�����o�ɂ�A�V��I�Ȃ��̂���u����v��u�|�p�v�Ƃ��Ă̈Ӗ������������Ȃ��Ă������悤�ŁA���܂��܂Ȍ`�̏��ւ������悤�ɂȂ�܂����B�x���Ă�����A�q������Ă�����A���o���Ƃ��Ă�����ƁA���������\����{���ɖL���Ȃ�ł���B�@
�������j�����������ł��A�M�d�Ȏ����ł��ˁB�@
�����̐l�X�̕�����������̂܂ܕ\������Ă��܂�����A����قǗǂ������͂Ȃ��Ƃ������炢�ł��B���Ɋ֓��Ō��t�������l�����ւ͐��������A�o���G�e�B�ɕx��ł���̂ŁA���ɎQ�l�ɂȂ�܂��B�@
���n��ɂ���ē��F������̂ł����H�@
���Ƃ��Ɛl�����ւ�5���I�ɋE���ō����悤�ɂȂ�܂������A�����Ŕɉh�E���ނ��Ă�������Ŋ֓��ɂ��`�����A�֓��ł�6���I���Ő������}���܂����B�@
�ł�����E���ł͏����A�֓��ł͌���̂��̂������̂ł��B�������E���͂��̌�A�y�n�J��������ɍs�Ȃ�ꂽ�Ƃ������Ƃ�����A�y���ɖ��܂��Ă������ւ��ꂽ��A�ǂ����֍s���Ă��܂����\���������A���܂萔���c���Ă��܂���B����A�֓��͓c�ɂ��������Ƃ�����A�y�n�J���̉e�������قǎ��A������������鐔�������̂ł��傤�B�@
�����Ⴂ�����u�����r���v�@
���搶�͕����ƈ�i���Ƃ炵�����Č����������Ƃ̂��Ƃł����A�����̕��ł������ʔ��������������������ł��ˁB�@
�r���̐F�̘b�ł��ˁH�@
�������B���{�̑r���͂��Ƃ��Ɣ��ŁA���ꂪ���A���A���ƕς��Ă������Ɓc�B�@
�����Ȃ�ł��B�Ñ�̑r�������������Ƃ������Ƃ́u���{���I�v��u�@���`���`�v�ȂǂŒm���Ă����̂ł����A��������ɂȂ�ƂȂ������ɕς��Ă��܂��̂ł��B�ǂ����Ă��낤�Ǝv���Ē��n�߂���A���낢��Ɩʔ������R����������ł���B�@
���ł́A�ŏ��ɔ����獕�֕ω������̂͂ǂ�ȗ��R�������̂ł����H�@
718�N�ɗ{�V�r���߂��o����āA�u�V�c�͒��n��e���ȏ�̑r�ɂ́u���I(���Ⴍ����)�v�𒅂�v�ƒ�߂�ꂽ�̂����������ł��B�����̒��ߏ��ɂ��ƁA�u���I�v�Ƃ́u������n���߂̐F�v�̂��Ƃł��B����͒�����
�u�����v�Ɂu�c�邪�r���Ƃ��āu����(���Ⴍ����)�v�𒅂�v�Ə����Ă���A���̒����̐���^�����Ē�߂����̂ƍl��������̂ł��B�Ƃ��낪�A���͂����ő傫�Ȋ��Ⴂ��Ƃ��Ă��܂�����ł��B�@
���Ƃ����܂��ƁH�@
���ł����u���v�Ƃ́A�D�`���������ڂׂ̍������z�̂��ƂŁA����͔����z�̂��ƂȂ̂ł����A�ǂ������킯�����{�l�͂���������̃X�Y�Ɖ��߂��A�X�Y�F�A�܂蔖�n�ɐ��߂Ă��܂����Ƃ����킯�Ȃ�ł��B�@
���{���ł����H�@����܂��傫�ȃ~�X�ł��ˁB�@
�Ԕ����Șb�ł����A���̓����ɏ����ꂽ�����ɂ͂�����Ə����Ă���̂ł�����A�ԈႢ����܂����B�@
������ł͕���͂����܂����(��)�B�@
�͂�(��)�B
���́u���I�v�̐F�́A��������ɂȂ�ƋM���K���ɂ��L�܂��āA���n�������F����������ɔZ���Ȃ��Ă����܂��B����͂�荕�������[���߂��݂�\������ƍl����ꂽ����ŁA����
�u��������v�ł��A�Ȃ�S���������������u��������Ɏ���ł�����Ȃ͂����ƔZ���F�𒅂�̂ɁA�����͍Ȃ̑r�����甖���F���������Ȃ��v�ƒQ����ʂ�����܂��B�@
�����𒅂Ă͂����Ȃ������̂ł����H�@
�{�V�r���߂̎��A�r�ɏd���y������߂��A�����ɂȂ�Ƃ���ɂ���Ē���F�����߂��܂�������ˁB���̌㕽������ɂȂ�ƁA��ʓI�ɍ���������悤�ɂȂ�܂����B�@
���Ƃ��낪���̌�A�����������A�����Ă܂����ɕς�����ł���ˁH�@
�����Ȃ�ł��B�������������͎̂�������ŁA�r���]�ˎ���ɐ��F���o�ꂵ���肵�܂����A��{�I�ɂ͔��������܂��B�����āA�����ېV���@�Ƀ��[���b�p�̑r����������č��ɂȂ�A����Ɏ����Ă��܂��B�@
����������ɔ��������������R�́A����������ł����H�@
�܂��͂�����Ƃ͕����Ă��܂��A�����v���ɂ͗{�V�r���߈ȍ~�A�r�������������̂͏㗬�K�������ŁA�����͈�т��Ĕ��̂܂܂������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�@
�Ƃ����܂��̂́A�����z���������߂�ɂ͐���������܂����A��Ԃ�������܂��B�̂͐l�̎����u�q��(������)�v�ƍl���Ă��āA��x���p�����r�����������Ă����悤�ł����A����Ȏ�Ԃ����������̂��������ȒP�Ɏ̂Ă��Ƃ͍l���ɂ����B�@
����ɁA��c��X�p���ł����`����ς���ɂ́A�����E�C������͂��ł��B��������͂邩�ɐM�S�[������ł�����A�`����ς��邱�Ƃɂ���Ă������Ђ����N����̂ł͂Ȃ����Ƃ���"����"���������������Ǝv���܂��B�@
���m���ɁA�H���̍�@�Ȃ�Ƃ������A�������̌`����ς���̂͒�R������܂��ˁB�@
���́A�{�V�̑r���߂őr�������Ƃ���Ĉȗ��A�����ȍ~���{���ł͂����ƍ��̂܂܂�������ł��B�i����`�����d��{���ł́A��x���߂����܂����ȂɎ�葱���܂����B����Ɠ����悤�ɁA�����͋M���́u���v�ɂ�����Ȃ�����A�u���v�Ƃ����F����葱���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA�M���̉e���͂����ꂽ��������ɁA����"������"������Ԃ����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�@
���㗬�K���́u���܂莖������v�Ƃ������R�ō����A�����͌`����ς��邱�Ƃւ̋����o�ϓI���R�Ȃǂ���A���Ƃ����F���X�p���ł����킯�ł��ˁB�@
�����ł��B������\���܂����ʂ�A�u���v�Ɋւ���V���⎀���ςƂ������̂́A�����ȒP�ɂ͕ς�Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B�O�q�̟q(������)�̋V��̂悤�ɁA����������ŗx������A���邢�͋����������肷�邵�����肪�Ñ�ɂ�����܂������A���̓`���͌���̂��ʖ�Ɍ����܂��B�����Ă���l������A���̖T��ł���������ő����������Ă���l������c�B���̂悤�Ɏ��B�́A�Ñ�̕��K��O�̂悤�Ɏp���ł���̂ł��B�@
���u���v�}�[�N�̓�������@
���Ƃ���ŁA���̌����̃e�[�}�́H�@
�S���Ȃ����l�̊z�ɕt���遢�̔����z������܂���ˁH �u�z���v�u�����v�Ƃ����Ă��܂����A���̋N�������Љ��������������Ǝv���Ă��܂��B�@
���G�ɕ`���ꂽ�H�삪�K���t���Ă���Ƃ����قǃ|�s�����[�Ȃ��̂ł����A���������Ă݂�ƁA���̂��߂̂��̂�����܂���B�@
���́A����������O���炠�镗�K�ŁA���q����́u�k��V�_���N�G���v�ɂ��`����Ă��܂����A�r��⊻��S���l���t���Ă����悤�ł��B�Ƃ��낪�Ȃ�Ƃ��́��}�[�N�A�Õ�����̏��ւ�lj�ɂ���������`����Ă����ł���B�Ȃ����Ñォ�炸���Ɨ��j��ɓo�ꂵ�Ă���}�[�N�Ȃ�ł��B�@
���搶�́A���ꂪ�z���ƊW������Ƃ��l���Ȃ̂ł��ˁH�@
�����Ȃ�ł��I �z���̗R���͂܂��͂����肵�Ă��܂��A���}�[�N�̎��Ӗ���������̋N��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���āA���A������i�߂Ă���Ƃ���ł��B�K���ǂ����Ō��ѕt��--����ȗ\���������ł���B�@
����������ꂽ���̐搶�̊�Ԃ��炪�ڂɕ����Ԃ悤�ł�(��)�B�@
����͂��́��}�[�N�𒆐S�ɁA�r���j�̌����𑱂��Ă������Ǝv���܂��B�r���̌�����ʂ��āA���{�l�̎����ς������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����҂��Ă��܂��B
�@ |
 �@�@ �@�@
���������� |
   �@
�@
|
���{�ɂ����ċ��������_���E�����E�̎O�@���́A�������Ղ̒��ō��̂��ʂ������B�@
�������ՂƂ͉����B�@
����́A��������V�Ƃ������l���̓��ʉߋV��𒆐S�Ƃ��āA�l�X�̐S�ɋ����ݏo�����u�ł���B�������A�������Ƃ����u���v�Ƒ��V�Ƃ����u���v�̑��V�������A�u�������Ձv�̂��ׂĂł͂Ȃ��B�@
�u���v�͂��Ƃ��ƌ����̂��ƂŁA��܍ΑO��ōs����j�q�̐��l�̎��̍ہA�M���͊����A���Ƃ͉G�X�q�i���ڂ��j���i���ԁj�邱�ƂɗR������B���݂ł́A�a�����琬�l�܂ł̂��܂��܂Ȑ����s�����u���v�Ƃ���B�@
�u�Ձv�͐�c�̍��J�ł���B�O����Ȃǂ̒ǑP���{�A�t�ƏH�̔ފ݂�~�A����ɂ͐����A�ߋ�A�����A�Ε�ȂǁA���{�̋G�ߍs���̑����͐�c���ÂсA�_���J����ł������B���݂ł́A���������A���܂ł̔N���s�����u�Ձv�Ƃ���B�@
�������Ղ̈Ӌ`�ɂ��Ă��A���낢��Ȍ���������B�����w�҂̋{�c�o�́A�����w�������Ձx�Ŏ��̂悤�Ɏw�E�����B�l�X�̓n���̓��ƐS���Ă��ċV��ɎQ������킯�����A���̍ۂɂ͕K���O��Ƃ��ăP�K���̏��A���ꂼ��l�̃��x���łƂ��Ȃ��Ă���B���Ȃ킿�A�u�P�K���̔r���v�Ƃ������Ƃ��������Ղ̈�̖ړI���Ƃ����̂ł���B�@
���|�]�_�Ƃ̐ē����ގq���́A�����w�������Ղ̂Ђ݂x�Ŏ��̂悤�ɐ��������B�������ՂƂ́u�����Ƃ��Ẵq�g�v���I�ȑ��݂ɂ��邽�߂̔����i�������̂ł͂Ȃ����B�������ՂƂ����V��̈߂i�́j���ƁA���̉����猻���̂͐��X�����g�̏�̏����ۂł���B�����Ƃ͈��ނ��ΐ��Ɛ��B�̌��F�ɑ��Ȃ炸�A���V�͓��̂̎��B�������}�����܍ΑO��͑�����ł���B���Ȃ킿���́u������̎Љ�v�A���́u���Ɛ��B�̎Љ�v�A���́u���̎Љ�v�A�����čՂ́u���̂����������̎Љ�v�ł���B�V��Ƃ͐������ɏ��i�����鑕�u�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂ł���B�@
�������A�������ՂƂ͐l�Ԃ̍��̉c�݂ł���Ƃ�������������B�������Չ�Ђ̒��ɂ́A�������Ƃ͐V�Y�V�w�̍�������������u�����v���ł���A�����Ƃ͎��҂̍���ފ݂ɑ���͂���u�����v���ł���Ƃ��āA�������ՋƂ��u���̂����b�Ɓv�Ƃ��ĂƂ炦�Ă�����̂�����B�@
�������������܂��܂Ȍ������ӂ܂��Ȃ�����A��͂�A�����������邱�Ƃ����������Ղ̑傫�ȈӋ`�ł���ƌ����悤�B����ł��A������I���ʼnԉł������܂点�Ȃ��痼�e�ւ̊��ӂ̎莆��ǂޏ�ʂ�A���ʎ��Ō̐l�ւ̈��ɂ̔O���������Ē������ǂ߂Ȃ��Ȃ��ʂȂǂł́A���ɋ���ȋ����̃G�l���M�[�����܂�Ă���B�܂��A�����Ȏq�ǂ��̎��O���c�̕�Q��̂Ƃ��Ȃǂɂ��A�W�܂����Ƒ��̐S�ɂ́A�����₩�Ȃ�����m���ɋ����Ƃ������̂��萶���Ă���B����͂��ăC�M���X�̐l�ފw�҃��B�N�^�[�E�^�[�i�[���u�R�~���j�^�X�v�Ɩ��Â������̂ɒʂ��Ă���ƌ�����B�@
�R�~���j�^�X�Ƃ́A�g����n�ʂ���Y�A����ɂ͒j���̐��ʂȂǁA����Ƃ�������̂������R�ŕ����Ȏ����I�l�Ԃ̑��݊W�̂�����ł���B�Ȍ��Ɍ����A�u�S�̋����́v�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B�^�[�i�[�͎咘�w�V��̍\���x�ɂ����āA���_���l�N�w�҃}���e�B���E�u�[�o�[�́u��Ɠ��v�Ƃ����v�z�A�t�����X�̓N�w�҃A�����E�x���O�\���́u�J���ꂽ�����v�u�����ꂽ�����v�Ƃ����l���������p���ăR�~���j�^�X���������B�@
�R�~���j�^�X�́A�܂��@���V��ɂ����Ĕ�������B��ʂɋV���Ƃ́A�Q���҂̐��_���ǓƂȎ��Ȃ��������A��荂���A���傫�ȃ��A���e�B�ƗZ�������邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă���B���ɏ@���V���ɂ����ẮA��ʂ̐M�҂ɂ͓��B���邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȏ@���I�ȍ��݂�ނ�Ɋ_�Ԍ�������Ƃ����Ӗ��������傫���B�J�g���b�N�̐_��Ƃ̖ړI�́u�_��I����i�E�j�I�E�~�X�e�B�J�j�v�̏�ԂɒB���邱�ƁA���Ȃ킿�_�̑��݂��������A��ɂȂ�Ƃ����_��̌������邱�Ƃɂ��邵�A�M�S�ȕ����k���ґz������ړI�́A���䂪����o�����Ȃ̌��E��ł��j��A���������ɓI�ɂ͈�ł���ƌ�邱�Ƃɂ���B����ǂ��A�H��̍��m�Ȃ炢���m�炸�A�N�����Ɨ͂ł����������݂ɓ��B�ł���킯�ł͂Ȃ��B�����ŁA��ʂ̐M�҂ɂ��Q���ł�����ʓI�ȏ@���V���Ƃ������̂��l�Ă��āA�ނ�ɂ������₩�Ȓ��z�̌��������A���̐M��[�߂����悤�Ƃ����̂ł���B�@
����́A�L���X�g���╧���Ƃ�������@���Ɍ���Ȃ��B����܂Œn����ɓo�ꂵ���l�ޕ����̂قƂ�ǂ��ׂĂ��A���炩�̏@���V���ݏo���Ă����B�������A���ׂĂ̋V�����@���I�ł���킯�ł͂Ȃ��B�����W���A�ٔ��A�j���A�����A�X�|�[�c���Z�A�����ă��b�N�E�R���T�[�g��l�̊������ՂɎ���܂ŁA����������h�ȎЉ�I���s���I�ȁu�V���v�ł���B�������������I�ȋV���ɂ��A�l�����傫�ȏW�c���`�̈ꕔ�Ƃ��Ē�`���Ȃ����Ƃ����Ӌ`������ƌ����悤�B�l�I�ȗ��v���]���ɂ��Č��v�ɕ�d���邱�Ƃ������߁A�Љ�̒c�������߂邽�߂̃V�X�e���Ƃ��ẮA�����I�ȋV���́A�@���I�ȋV�������͂邩�Ɏ��H�I�ł���B���̋@�\���y�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������Љ�ɗ��v�������炷���炱���A�V���I�s�����i�����Ă����Ƃ��l������̂ł���B�@
�^�[�i�[���A�R�~���j�^�X�͉����܂��@���V���ɂ����Ĕ�������Ƃ��Ȃ�����A�����傫�������āA�L�����j�E�Љ�E�����̏����ۂ̗��������݂Ă���B�����ă^�[�i�[�́A���́u�S�̋����́v�Ƃ��ẴR�~���j�^�X�ɋC�Â����Ƃɂ��A�u�Љ�Ƃ́A�ЂƂ̎����ł͂Ȃ��A�ЂƂ̃v���Z�X�ł���v�Ƃ����i���_�I�ȎЉ�ςɓ��B�����̂ł���B�@
�����āA�u�S�̋����́v�́u�����m�v�ށB���Ƃ��ƋV���ɂ̓����o�[������m�������L���邽�߂́A����u�i���b�W�E�}�l�W�����g�v�Ƃ��Ă̑��ʂ�����B��Ƃɂ����āA�����̒���ɂ͂��܂�A�V�N�j�ꎮ�T�A�n���L�O���T�A�e��i�������邢�͎Б��Ȃǂ́A��������Ј��ԂɁu�����m�v�ݏo�����߂̕������u�ł���ƌ����悤�B�@
�`���I�����̂ɂ����ẮA�u�����m�v�͋V���݂̂Ȃ炸�A��������A�����`���A���邢�͘V�l�̒m�b�A���b�⓶�w�A�����čՂƂ����`�Œ~�ς���A�`������Ă����B���ăO�����Z�킪�̏W���A���c���j���������Ă����̂́A���̂悤�ȁu�����m�v�̑S�e�������̂ł���B�����ɂ́A�̘b�̂悤�ł��āA���̓R�~���j�e�B���ێ����^�c���邽�߂̖������̕��@��A���Q�Η����N�������Ƃ��̑Ώ��̃m�E�n�E�Ȃǂ�����Ă��邱�Ƃ������B�t�ɁA���̂悤�ȈӐ}�����邱�Ƃ�Y��Ă��܂����n���s�s�ɂ����āA�Ղ��`�����`�[�����Ă��܂����̂ł���B�@
�������u�����m�v�́A�`���I�����̂̐ꔄ�����ł͂Ȃ��B��L�������Ƃ���C���^�[�l�b�g�̐��E�ɂ��悭������B�������A�C���^�[�l�b�g�ɂ����ċ��L�������̂͋L�������ꂽ�m�I���ł���A�`���I�����̂̂���͎�Ƃ��ċL��������Ȃ��S�I���ł���ƌ����邾�낤�B���R�Ȃ���A�������Ղ��S�I���̔��M���u�ł���B |
�Б��⍑���̂悤�Ɏc���ꂽ�Ј��⍑���̐S������������ړI�����V�������݂��邪�A���݂̒n����ōł�����ȋ����ݏo���S�I��u�Ƃ����A��͂�I�����s�b�N�ɐs���邾�낤�B�I�����s�b�N�͂��̊J��A���X�̃X�|�[�c���Z�A�����đ��̍��̐l�X�Ƃ̌𗬂ɂ���ċ�����₦�ԂȂ����ݑ�����C�x���g���B��O�O�l�N�̃I�����s�b�N�́A�ܗ֔��˂̒n�A�e�l�ŊJ�Â����Ƃ������Ƃł��ĂȂ�����オ����������B�Ñ�M���V���ɂ�����I�����s�A�̍ՓT���Z�́A�E�m�̎��𓉂ޑ������Z�Ƃ��Ĕ��������Ƃ����B���̈Ӗ��ŁA��ꐢ�I�ōŏ��ɊJ�Â��ꂽ�A�e�l�E�I�����s�b�N�Ƃ́A�X�E�P�P���������e����A�t�K�j�X�^���A�C���N�ŖS���Ȃ����l�X�̗���Ԃ߂�s��ȁu�l�ޑ��v�ł������̂�������Ȃ��B�@
�I�����s�b�N�݂̂Ȃ炸�A���[���h�J�b�v�▜��������Ƃ��������ۓI�ȃC�x���g��A���̊J��E��ɑ�\�����悤�ɁA�V����ՓT�Ƃ́A�l�ނɂƂ��Ė������ʂ̖�������ł���A�l�Ԃ̖{�\�I�~���̏W�c�I�ȃV���{���Ƃ����Ă悢�B���������l�Ԋ���̍ł��f�p�ȗ~���Ƃ��āA�������Ȃ�тɑ��V�������邱�Ƃ��ł���B�@
���̐��U�ɂ����āA�قƂ�ǂ̐l�Ԃ��o�����錋���Ƃ����c���ɂ͌������A���ׂĂ̐l�ԂɖK��鎀�S�Ƃ��������ɂ͑��V�Ƃ����`���ɂ���āA��{���y�̊�����ߗׂ̐l�X�ƕ����������Ƃ����K���́A�l��E�����E�@�����āA���Â��猻�݂Ɏ���܂ōs���Ă���B���̓��Z�����j�[�͂���ɁA����ׂ��F������ɂ����Ă����R�p������邱�Ƃ��\�z�����u�s�ł̋V���v�ł���A�����炭�l�ނ̑����������i���ɍs����ł��낤�B�@
�������A�������Ȃ�тɑ��V�̌`���́A���ɂ��A�����ɂ���āA����߂Ē��������ق�����B����͐��E�e���̃Z�����j�[�Ƃ������̂��A���̍��̒��N�|��ꂽ�@���I�`�����邢�͖����I���K�Ƃ��������̂��A�l�X�̐S�̎x���Ƃ������ׂ��u�����I���ǂ���v�ƂȂ��Ĕ��f���Ă��邩��ł���B�@
���{�̋V������O�ł͂Ȃ��B�������Ȃ�тɑ��V�ɕ\�ꂽ�킪����@�ɑ�\����镐�Ɨ�@�Ɋ�Â����A���̕��Ɨ�@�̌��́w�Î��L�x�ɑ�\�������{�I���ǂ���Ȃ̂ł���B���Ȃ킿�A�w�Î��L�x�ɕ`���ꂽ�C�U�A�����̓��{�I�V���̊�ƂȂ��Čp������Ă����̂ł���B�@
�����m�푈�Ȍ�A�킪���̎Љ�`�Ԃ͑傫�ȕϊv�𐋂��A���ĕ����̒������e�������B����ɂ�������炸�A�܂��A�_�O�E����E�����E�l�O���Ƃ������X�^�C���̕ʂȂ��A�����̌������̒��ɁA�ԉł������C�i�Ŋ|�j����U���i�F�����j�ɂ������`�ɂ����āA���{�l�Ƃ��ẲA�z���V���̓��P�������ɕ\������Ă���B�@
������{�̌�����������ƁA�]���̃X�^�C���̃n�E�X�E�G�f�B���O��X�g�����E�G�f�B���O�Ȃǂ̐V�����͂����藐��āA���̃J�I�X�̏�ԂƂȂ��Ă���B���̂悤�ȃJ�I�X�̒��ŁA�u���{�Ő̂���s���Ă����_�Ђł̐_�O�����������v�Ƃ��������N�����Ă��邪�A�_�O���Ƃ͌����ē`���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̗��j�͈ӊO�ɂ��V�����̂ł���B����ǂ��납�A�L���X�g�����A�����A�l�O���Ȃǂ̌������̃X�^�C���̒��ň�ԐV�����̂��_�O���Ȃ̂ł���B�@
�������Â�����A���{�l�͐_���̌��������s���Ă����B�ł�����́A�Ƃ����_�̑O�ŁA�V�Y�ƐV�w���Ƃ��ɐ����邱�Ƃ𐾂��A���̌�Ő_�X���ƂɌ}���āA�Ƒ��A�e�ʂ�ߗׂ̏Z���ƈꏏ�ɂ���������H�ׂē�l���j��������̂ł������B�܂�A�̂̌������ɂ͏@���҂���݂��Ȃ������̂ł���B�_�����L���X�g�����W�Ȃ������Ȗ��ԍs���ł������킯���B�@
�������A���{�ɂ����銥�����Ղ̋K�͂ł��������}������@�͎�q�w���Ȃ킿��w����{�Ƃ��Ă����B�̂̎�������̗���͓��R�Ȃ��珬�}�������x�z���Ă�������A���̈Ӗ��ł͓��{�`���̌������̃x�[�X�͎ł������Ƃ�������B�@
���݂����q�ɓ`��鏬�}������@�̃��[�c�͓����A��́A�������̉Ɨ����������}��������c�Ƃ��銙�q����ȗ��̋|���Ɣn�p�̗�@�ł���B������́A�����`���̗�V��@�̎t���������}�����G��c�Ƃ�����̂ŁA��������ȗ��̊������Ղ����̃}�i�[�S�ʂ̋K�͂Ƃ��Ă̗�@�ł���B�@
���}������@�̉e�����̂��ƁA���{�̌������͖{���A�Ƃ̒��Ŋ�������s�ׂ��������A�����Ȍ�ɐ_�Ђōs���_�O������������ɂȂ����B�����������ꂾ�����L���X�g�����̌������ɉe�����ēo�ꂵ�A�����O�O�N�i���Z�Z�N�j�ɋ{���̌����ōs��ꂽ�c���q�i�̂��̑吳�V�c�j�Ɛߎq�P�Ƃ̍��V�����������ł���B���̂��肳�܂�����A���O�̊ԂɁA�u�c���q�a���̂悤�ɂ��������ɐ_�O�Ō������������Ă݂����v�Ƃ��������L�܂钆�ŁA���O�l�N�ɓ���J��_�{�i���݂͔ѓc���ɂ��铌����_�{�j����ʍ�����ΏۂɁA��_�{�̐_�O�Ŗ͋[���������s�����B����ɗ��O�ܔN�A�A�����J�A��̍����h�N�g���Ɛ��̍����̖��A���{����̃J�b�v���ɂ���āA���ۂɖ��Ԃł̐_�O����ꍆ���s��ꂽ�̂ł���B�㌎�����A�ߌ�l���O�O������O�Z���Ԃ̋����A���̌�͒鍑�z�e���Ɉړ����Ĕ�I���B���̖��Ԑ_�O���̓i�C�g�E�E�G�f�B���O�ł��������B�@
���̐_�O���ɂ��āA�����̐V���́u����ł���_�A�ȈՌy�ւɂ��āv�ƎO�O�������ق߂������Ă���B���̓���J��_�{�́u�d�|���v���q�b�g���āA�S���e�n�̐_�Ђ��_�O���������s���悤�ɂȂ����̂ł���B�Ȃ��A�z�e���̒��ɏ��߂Đ_�O������������̂��鍑�z�e���ŁA�吳���N�i����O�N�j�̊֓���k�Ђœ���J��_�{���������߂ł������B�@
�_�O�������̗��j�͂��������S�N�ɂ������A������L���X�g�����̓��������������Ƃ����A����ΊO���ɂ���Đ��܂ꂽ���̂ł���Ƃ����_�������[���B�L���X�g���̊O���́A�����ɂ������e����^�����B���{�ŕ��O���������͂��܂����̂���������̖����ŁA�����@����Ɋe�@�h���������ɎQ�������B���㎛��z�n�{�莛�ł����炪�s���Ă���B�@
�������ɂ͑傫�ȉe�����y�ڂ����ɂ���A���{�ɂ�����L���X�g���̕z���͕s�U�ƌ������͂Ȃ��B��������͒v�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�����Z�N�̐؎x�O�����D�P������S�O�Z�N�����āA���܂��ɐM�k���͕S���قǂŁA�l����͈ꁓ�ɂ������Ȃ�0�E�こ�ɂƂǂ܂��Ă���B����ł͏@���E�̐��E�V�F�A�O�O���̊Ŕ������Ƃ������̂��B�@
����A�ׂ̊؍�������ƁA���{�Ƃ͑�Ⴂ�ŁA��܁��ł���B���̓�Z�N�Ԃő啝�ɐM�k�����������������A���������������ɑ����Ȃ���ꁓ�Ɠ�܁��A���̈Ⴂ�͂ǂ����痈���̂��낤���B���낢��ȗ��R���l�����邪�A��ɂ́A�L���X�g�����猩�āu����₷���v�̈Ⴂ���������̂ł͂Ȃ����ƌ�����B�؍��͓`���I�ȏ@�����y�Ƃ��Ď̉e�����������Ƃ��m���Ă���B�͈�܁A��Z���I�ɒ��N�����ƌ��т��ċ����e���͂����������A�t�Ɉꎵ���I�ȍ~�͉����ƂƂ��ɐ��ނ���B�������ɁA�ߑ㉻�ƂƂ��ɃL���X�g���������Ă����B�ƃL���X�g���͂�������u�V�v�Ƃ������ʂ̃R���Z�v�g�������Ă������䂦�ɁA�X���[�X�Ɍ�オ�s��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ�������������B�@
���{�ɂ͉������������Ƃ����ƁA��{�Ƃ��ČÐ_���ɑ�\�����A�j�~�Y���ł���B���R�E�̂����鎖�����I���݂Ƃ݂Ȃ��u�₨��낸�v�I�ȏ@���ςŁA�L���X�g���Ƃ͓��ꂩ�ݍ���Ȃ��B�A�j�~�Y���Ɂu�V�v�͑��݂����A�u�V�v�̕����͌Ñォ��V�c�Ƃ����ō����͎҂̂��̂������̂ł���B���̂��ߓ��{�ł̓L���X�g���`���̓�������u�V�v���邢�́u�V�ɂ��܂��_�v�Ƃ����T�O�����̂ɋ�J�����̂��B�L���X�g�������猩��A���ɋ��`������ɂ����A�`���ɂ����y�n�ł������̂��낤�B�@
���̓��{�ŕz��������Ȃ������L���X�g�����A�Ȃ�������E�ƃu���C�_���ƊE�ł͑听�������߂��B�Ƃ��ɏ����̃j�[�Y�������Ƃ��傫���Ƃ���邪�A���S�┒�S���ɑ�\����鏗�q�̃~�b�V�����E�X�N�[����A��q�E�����E�R�w�@�Ƃ������L���X�g���n��w�̃C���[�W�͍����A�`���y���E�E�G�f�B���O�͍����Ɏ���܂ő�l�C�ł���B�_�O���̒a���ɂ���Č�ނ���������A��㔪�O�N��ɎO�Y�F�a�ƎR���S�b�A�_�c���P�Ə��c���q�A���Ђ�݂Ɠ�J�F���b�Ȃǂ̌|�\�l������Ō����������Ĉȗ��A���݂ɂ܂ő����傫�ȃu�[���ƂȂ����B�@
�c����|�\�l�Ƃ������u�Z���u�v�̋V����C�t�X�^�C������ʂ̐l�X���^����Ƃ����A�X�m�r�Y����}��Ƃ������̃V�~�����[�V�����������Ɍ��邱�Ƃ��ł���B����ȑO�ɂ��A���a���\���錋�����ł���c���q�i�����V�c�j�Ɣ��q�q�܂̍���̋V�ɂ���ăE�G�f�B���O�h���X���蒅������A�Ό��T���Y�Ɩk�����}�̌�����I���������z�e���ōs��ꂽ���Ƃɂ���ăz�e���������s������Ƃ������ۂ��������B�@
���̃V�~�����[�V�����́A�������݂̂Ȃ炸���V�����l�ŁA��㔪���N�̐Ό��T���Y�Ɣ���N�̔���Ђ�̑��V�͂��܂��܂Ȍ`�ł��̌�̓��{�l�̑��V�ɉe����^�����ƌ����Ă���B���{�ɂ����Ắu�_�v�u���v�u�l�v�̎O�ʈ�̂�����Ǝv���邪�A�����ł́u�l�v���V���̃g�����h������Ă���킯�ł���B |
���{�l�̑��V�ɂ��Č��Ă݂悤�B�������ɂ�����_�O���Ɠ��l�A�����̓��{�l�͐̂��畧�����V���s���Ă����Ǝv���Ă���B�������ɁA���V��@�v�ɕ������֗^����悤�ɂȂ����͕̂����`���ȗ������i�K���猩�邱�Ƃ��ł���B�܂��A���{�Ɏ���܂ł̃C���h�A�����A���N�Ƃ������e�n�̕����ɂ����邱�Ƃ��ł���B�������A�����̋@�\�͑��V��@�v����Ƃ���悤�ɂȂ����̂́A���{�݂̂̌��ۂł���A������]�ˎ���ɂ܂ʼn���B�@
���łɎ�������̑T�m�̌�^�ɂ͑��V��@�v�ł̖@�ꂪ�����܂܂�A�����������������Âi�ޗl�q���킩�邪�A�������V�̕��y������I�ɂ����͓̂��얋�{�ɂ�鎛���i�Ă炤���j���x�ł������B�L���V�^���̒Ǖ������߂����{�́u�L���X�g���֎~�߁v���o�������A�l�X���L���V�^���łȂ����Ƃ��ؖ����邽�߂ɂ͂����ꂩ�̎��̒h�ƂɂȂ邵�����@���Ȃ������B���ꂪ�������x�ł���B�Z�����L���V�^���łȂ����Ƃ��ؖ����邽�߂ɂ́u�@��l�ʒ��i���イ����ɂ�ׂ��傤�j�v���쐬���A���ꂪ�����ɌːЂ̖�ڂ��ʂ������B�@
���@�[�̍s���@�\�Ƃ��Ďg�����Ƃ������{�̊�݂����A���ۂ��̋@�\�͗L���ɉʂ�����A����ɂ���Ď��@�͑������Ă������Ƃ��\�ɂȂ����̂ł���B���̒��ŁA���@����n���Ǘ����A�u�ߋ����v�Ƃ������҂̌ːЂ��Ǘ����邱�ƂɂȂ����B���҂Ƃ̐ړ_�Ƃ������������@�ɗ^�����A���҂𑗂鑒�V���m���ɂ�镧�����蒅���Ă����킯�ł���B�@
����A�����ېV��A�_������������ɂ�A�_�����̑��V���������������͂��܂�A�����Ƃ͈قȂ�_���Ձi���������j���o�ꂵ���B���̐_���Ղ̎�ȍs���́A�A�H�i���̂��ق������j�A�ʖ�Ձi�₳���j�A����ՁA��O�ՂȂǂł���B�������A�_���Ղ͍L�����y����ɂ͎���Ȃ������B�_���Ƃ����́A���ՋV�炪�����ɔC����Ă������A���C�o���ł��镧���̗͎͂�܂�Ȃ��ƌ��Đ_���Չ^���𐄐i�����킯�����A���Ljꕔ�ɍ̗p���ꂽ�݂̂ɏI������̂ł���B���������͂���قNj��łɓ��{�ɒ蒅���Ă����̂��B�@
�������A���̑��������̍���ɂ͎̑��݂��������B�������V�ł́A���@�̖{���W���Ɉ��u����Ă���{���̑��A�^���@�n�Ȃ�u�얳��t�ՏƋ����v�A��y�@�E�^�@�n�Ȃ�u�얳����ɕ��v�A�T�@�n�Ȃ�u�얳�߉ޖ��v�A���@�@�n�Ȃ�u�얳���@�@�،o�v�Ƃ������A���̏@�h�̃V���{���ƂȂ��Ă���d�v�Ȍ��t���L�����|����{���Ƃ���B���̊|���̑O�ɞl��u�����A���ߔq�ޑΏۂ́A�����܂ł��{���Ƃ��Ă̊|���ł���B�|���ւ̔q�炪�I���Ă���l�ɑ��Ďv�����������Ƃ������Ƃ��A�������V�ɂ�����ŏd�v�|�C���g�ł���B�������A�������V�Q��҂̂قƂ�ǂ́A�̐l�̎ʐ^�����A�l�Ɍ����ė�q����B�����Č̐l��z���Ă͋����A����������܂�ŏč����A�⑰�ɏd�X�������A�������ŁA�{�����܂������������đޏꂷ��B�@
�܂����V���n�܂�A�{���ɑ���njo���I��ƁA���t�͂������Ƒޏꂷ��B���̌�A�⑰�����ɂ���Ğl�ɕʂ�Ԃ�������A�����Ŕނ炪�l�������ďo���ƂȂ�B���̂Ƃ��A�{���ɓnjo���Ď��҂������t����ɑޏꂵ�Ă��܂��A�o���ɂ͗������Ȃ����Ƃɋ^������l������B�������A���̗��R�͊ȒP���B���҂͐��������̂ł���A�����ł́A���҂̓��̂͂��͂�P�Ȃ镨�̂ɂ����Ȃ�����ł���B���邢�́A�������Ă��炸�A���҂́u���A�i���イ����j�v�ƌĂ�鐶�Ǝ��̒��ԗ̈�ɓ������̂�������Ȃ��B���̏ꍇ���A�c���ꂽ���̂ɂ͉��畧���I�Ӗ��͂Ȃ��B�@
�������A�͈Ⴄ�B�����N�w�҂̉��n�L�s���́A�����w�Ƃ͉����x�ɏ����Ă���B�@
�u�ł́A���̓��̂́A���ƂƂ��ɒE���ł��썰���Ăі߂��Ă��āA�߁i��j����\���������̂Ƃ����B������A����A��̂����̂܂ܒn���ɑ���A������B���ꂪ�����i���j���d�����鍪�{���o�ƂȂ�̂ł���B���������I���ꂩ�炷��A���҂̓��̂́A�߂��������ׂ��Ώۂł���A�Ƒ��i�⑰�j��������ƊǗ����ׂ��ΏۂȂ̂ł���B�o���̂Ƃ��A�����I�ɂ͑m���͊W���Ȃ��A�I�ɂ͉Ƒ����W���A���̞l���^�Ԃ̂́A���R�Ȃ̂ł���v�@
�w�̑��l�҂ł�����n���ɂ��A�@
�ł͎��҂𓉂�ł��낢��ȋV�����s���B�n�߂ɂ܂��k���̉��Ƀx�b�h��݂��āA�����Ɉ�̂����u����B����͎̋K��ł���B���̂��Ə���ǂ��Ď��ɂ��܂��܂Ƃ����K��̉��ɋV����i�s����B�����ďo���ƂȂ�A��n�ɑ���B�����瑒��܂ł̂��̊ԁA��̂��ƂɈ��u���Ă������A���̂��Ƃ�q�i�Ђ�j�i������j�Ƃ����B���シ���Ɉ�̂𑒂�킯�ł͂Ȃ��B�����̑��V�ɂ����āA���ʖ�������荐�ʎ������ނ܂Şl�����u���Ă���̂́A��w��@���̎��Ԑ����͕ʂƂ��Ă��A�܂����{�×��̏K���Ƃ��Z�����Ă���Ƃ��Ă��A����͎ɂ�����q�̎c�e�Ȃ̂ł���B�@
�ł́A������q�̋V�����o�āA��̂�n���ɑ���A����ɂ��̌�̋V�����������A����������A�̋V���S�̂��u�r�v�Ƃ����B��̂߂�u���v�́u�r��v�̈�i�K�ɂ����Ȃ��B������I�Ɍ����A�u�����v�ł͂Ȃ��āu�r���v�ł���B�܂��A����͍��i����j���Ԃɍs��ꂽ���Ƃ���A���{��́u�������Ձv�͎ł́u�����r�Ձv���������Ƃ����B�@
�������V�̒��ɂ́A���̂悤�Ɏ��V�̋V�炪��荞�܂�Ă���̂ł���B���n���ɂ��A�C���h�ɂ�����{���̕����ɁA�ʂ����č��̂悤�ȑ��V�̋V�炪�������̂��ǂ��������^��ł���Ƃ����B���Ƃ��A����̎�҂ł���u�\�i���イ�����j���u�����͒����`���̑r�����J�̎d���𓐂�ő��V��@�v�̏��V�������Ă���v�ƌ�����ƁA�w�����Ɨ�V�߁i�Ԃ����ꂢ�����j�x�̏��ɏo�Ă���̂ł���B���������n���́A�u����Ȃ��悤�ɂ����ċL�����A���{�����͂�������ꂽ�@���Ƃ��đ��݂���B���͕����M�҂ł���A�I���o�̒��Ő����Ă���v�Əq�ׂĂ���B���̌��t�́A�����̓��{�l�ɂ����Ă͂܂���̂��낤�B�@
���ĕ������V�ɂ́A�ȊO�̏@���̉e���B��Ă���B���V�̋A�H�A��҂ɑ��Ĉ⑰���͓���Ƃ��Č䈥�A������B���̂Ƃ��A�u���߉��v�̏����Ȏ��܂��悭�n�����B���V���I���ċA��ĉƂɓ���O�A���̐��߉���g�̂ɂӂ肩���邽�߂ł���B�Ȃ��A����Ȃ��Ƃ�����K�v�����邩�Ƃ����ƁA���V�Ŏ��҂Ɗւ��A�����q�i�����j�ꂪ�����ł��낤����A����������Đ��߂邽�߂̉��Ȃ̂ł���B |
�u���҂��q��v�Ƃ������z�́A�����ł��ł��Ȃ��B����͓��{�×��̎����ςł���A�_���ɂȂ����Ă���B���{�l�́A�C���h�l�⒆���l�ƈقȂ�A���҂��q�ꂽ���̂ƍl���Ă����B���{�l�͐l�����ʂƁA�u�s�K���������v�Ȃǂƌ������A���ȂȂ��l�Ԃ͂��Ȃ��킯������A�l�̐l�����̂��̂����ׂĕs�K�ŏI�邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�}�]�q�Y���I�Ƃ������A���Ɋ�ȍl�����ł���A������ł́u���v���u�s�K�v�ȂǂƂ͐�ɕ\�����Ȃ��B�u���v���u�A�V�v�ƂƂ炦��L���X�g���k�̒��ɂ́A���҂ւ̗�ɔ�����Ƃ��āu���߉��v��ے肷��M�҂�����B�@
�������A�����琢�E�I�Ɍ��Ċ�L�e���c�Ȏ����ςł����Ă��A�×��̏K���̓`���͊ȒP�ɂ͏����Ȃ��B���{�×��̎����ς́A�������V�̒��ɂ���荞�܂�A�����Ɛ����Ă���̂ł���B�@
�܂��A���V�Ɠ��{�l�̎����ςƂ��d�Ȃ荇������������B�����ł͂����ɉ��̈Ӗ����Ȃ��B�������A���������{�l�͈ˑR�Ƃ��Ă�����P�Ȃ镨�̂Ƃ��čl���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B��s�@��D�Ȃǂ̎��̂̋]���҂̈�̂́A���Ƃ������ɂȂ��Ă��Ă��T�����߂悤�Ƃ���B�����܂ł��썰�Ƃ����Ƃꎋ����Ƃ����ӎ�������B���̊��o�͓��{�l�Ǝ��̑c��ρA�c��ӎ��ł���A���܂��Í������A���E���Ɍ�������̂ł���B�������A�����ɂ����݂������A��������B�����āA���̊��o�������ɗ��_�����āA����ɑ̌n���������̂����Ȃ̂ł���B���n�����킭�A�����炭����͐��E�ŗB��̗��_�̌n�ł���Ƃ����B�@
���{�l�̑c�슴�o�͕��������ɋ߂��킯�ł���B���̂悤�ɁA�������V�̒��ɂ́A���͐_���������荞��ł���̂��B���m����S�w�Ɠ����悤�ɁA���V�ɂ����Ă��_���A�����A�������荇���Ă���̂ł���B�@
�������Č���ƁA���{�l�̐����ɖ��������������ՂƂ́A���܂��܂ȏ@���̎M�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��悭�킩��B�����炱���A�{���̖`���ɂ��o�Ă����悤�ȁA�_�ЂƋ���Ǝ����g����������{�l�̃G�s�\�[�h�����p�����̂ł���B�@
���������Չ�قƂ���������I�Ȋ������Վ{�݂ɂ����Ă��A���܂��܂ȏ@���̋����͓���I�Ɍ�����B��������ɂ́A�_�a���`���y��������̂����ʂ����A�n���w��̉���p�ɕ��d�����炦�����������������B�ŋ߂ł́A�Ñネ�[�}�鍑���l�ގj��ōł����������Ȃ��������Ƃ���A�Ñネ�[�}����������Ƃ����̂�����B����ɂ́A�M���V���_�b�̃I�������|�X���_�̐_���Ɉ͂܂ꂽ�������A����Α��_���E�G�f�B���O�Ȃ���̂��o�ꂵ�Ęb����W�߂Ă���B�@
���Չ�قɂ����Ă��A���{�ő�́u�k��B���_�t�v�̂悤�ɁA�����̑��V���͂������A�_���p�̐_�a��A�L���X�g�������V�p�̃`���y���܂Ŕ��������̂�����B���V���Ō�́u���ȕ\���v�ł���u���Ȏ����v�ƂƂ炦��l�X�̂��߂ɁA�F�����A���ʑ��A�C�m���A���ؑ��A�K�[�f�j���O���Ȃǂ������ł���ݔ��������Ă���B�܂��ɁA���ł�����B�@���I�Ɋ��e�ȓ��{�Ȃ�ł͂̎{�݂�������Ȃ��B�@
�Ō�ɁA�������Ղ���{�ő�̏@���ł���ƌ����l������B�@�������̐l�Ԃł��A�M�S�̂܂������Ȃ��l�ł��A�g����m�l�A�F�l�̌�������V�ɂ͕K���Q��B�u�������Ձv�̎l���������́A�_�������������L���X�g�������z�������{�ő�̏@���Ȃ̂��Ƃ����̂ł���B�@
�������A�������Ղ́u�@���v���̂��̂Ƃ������A�u�@�V�v�Ƃł��ĂԂׂ����̂��낤�B�@���́u�@�v�Ƃ��������́u���Ƃ̂��Ɓv�Ƃ����Ӗ��ŁA�������l�Ԃ�����ŕ\���ł��郌�x���������E�ł���B����A�F���̐^���̂悤�Ȃ��̂��B���́u���Ƃ̂��Ɓv����̓I�Ȍ���Ƃ��A���K�Ƃ��Đl�X�ɓ`���邱�Ƃ��u�����v�Ƃ����B�@
���Ƃ���A���m�Ȍ���̌n�Ƃ��Čł܂��Ă��Ȃ��u���Ƃ̂��Ɓv�̕\�������肤��͂��ł���B���y��_���X���������낤���A�V���Ƃ������̂��������낤�B�܂�A�L���Ӗ��ł́u�V�сv���ƌ����Ă悢�B�u�V�сv�ɂ��Ă̕s���̖����w�z���E���[�f���X�x���������C�^���A�̕����j�ƃ��n���E�z�C�W���K�́A�u�V�т͕��������Â��v�Əq�ׂ����A���ْ͐��w���}���e�B�b�N�E�f�X�x�̒��Łu���V�͗V�т����Â��v�Ə������B���ہA���E�j�����Ă��A���o�E���n�E�����ăI�����s�b�N�Ȃǂ̗����̌Â��u�V�сv�̋N���͂���������V�Ɛ[���W������B�@
���������A���O���N�O�Ƀl�A���f���^�[���l�����҂������u�ԁA�T�����q�g�ɂȂ����Ƃ������A���V�Ƃ͐l�Ԃ̐��_�I�c�݂ɂ�����r�b�O�o���ł���A�l�ނ̑��݊�Ղ��̂��̂ł���B�@
�Ñ�̓��{�ł́A�V�c�̑��V�ɂ��������l�X���u�V���i�����тׁj�v�ƌĂ�ł����B�������ՂƁu�V�сv�̂Ȃ��������قǖ��炩�ɂ��錾�t�͂Ȃ��B�@
��ꐢ�I�́u�@�V�v�̎���ł���B�u�@�V�v�Ƃ́A�u���v�����߁A�S����������c�݂Ƃ��Ă̓N�w�E�|�p�E�@�����������ꂽ�傢�Ȃ鐸�_�̐��E�ł���B�����āA����͊������Ղ��̂��̂ł�����B�u�@�V�v���^�Ɏ��������Ƃ��A���{�l�͂��͂�A�l������ł��u�s�K�v�Ƃ͌ĂȂ��ł��낤�B |
 �@�@ �@�@
���@�v�̂�������ƐS�� |
   �@
�@
|
���N������@�v�E�@���ɂ���
�@
������܂ł̖@�v
�@
�������@��ɑ��V�̎��ɂ����b�ɂȂ������B�������܂��B
�@
���A�O�����A�l�����A�����A�Z�����A�ՏI���玵����(�l�\���)�܂ł́A�Ւd�Ɋ����������́A�����������A���̈ʔv�����u���܂��B��ɏq�ׂ܂����A������(�l�\���)���O�����ɂ킽��ꍇ�A�������������Ƃ���n��������܂��B�����d���������܂łɂ͗p�ӂ���������낵���ł��傤�B
�@
�������@���̓����A�Ƃ����A�������@�v���c�݂܂��B
�@
�S�����@�g���̎ҁA�F�l�A�m�l�������܂��B
�@
���@�~�@�~�A�~���U���ƂƂ̂��A���i�����������܂��B�����ĕ�Q������܂��B
|
���N���@�v�̈�ʒm��
�@
�l�\����̖@�v�ň�i�������Ƃ͏��~�ƔN���ɂȂ�܂��B���S�������N�̏ˌ�������������Ɖ]���A���S���ē�N�ڂ��O����ƂȂ�܂��B(����́A�������N�̂��߂ł����l����e�̑ٓ��ɏh����������Ƃ����Ӗ��ʼn��Ď��ɐ������0�˂ƂȂ�܂����̂��玄�����̐����̂Ȃ��ł�0�˂Ƃ͐����܂���ł����B���̏K���������Ă����̂́A��ォ�炾�ƕ����Ă���܂��B)���̂���7�A13�A17�A23�A27�A33�A50����Ƒ����܂��B�F�{�ł́A23�A27����߂�25������c�ނ��Ƃ������悤�ł��B�܂��N���@�v�͖����ɂ���̂����z�ł����A�s���ɂ�薽���̑O�ł����܂��܂���B
�@
�������́A���߂ɊW�҂֘A�����܂��B
�@
1) �N���@�v�́A�ˌ������ɉc�ޏK�킵�ł����A���O�̋x���ɉc�ޏꍇ�������Ȃ��Ă��܂��B
�@
2) �m���̗\���q�ˁA�����A�ꏊ�����肵�܂��B�����A���߂ɊW�҂ɘA�����܂��B
�@
(�A���͓d�b�܂��́A�n�K�L�����ɂ�)�d�b������ł͂ǂ����Ă�����ɂ�����Ǝv������ւ͈ē�����o���܂��B�܂���H�Ȃǂ̏ꍇ�l�������肵�Ȃ��ƍ���܂��̂ŕԐM�p�t�������邩�����t�����g�p���܂��B
�@
�����̈ʔv��{�ʔv(�ߋ���)�ɑւ��܂��B
�@
�������@�v�܂łɁA���h��Ⓜ�̖{�ʔv�A���邢�́A�ߋ�����p�ӂ��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�������@�v(�O�\�ܓ��A�l�\����A�����A�Ƃ�����)�ł́A���V�ɗp�������̈ʔv�́A�{�ʔv�Ǝ��ւ��邱�ƂɂȂ��Ă���܂��̂ŁA���ē��������Ă��������܂��B�{�ʔv�́A���h��܂��͓��̂��́A���邢�͌J��o�����ɂȂ��Ă�����̂ł��B�Ȃ��A��y�^�@�ł͖@������p���܂����A��������ɂ��ʔv��p���邱�Ƃ�����܂��B���̂��ʔv�͂����܂Ŗ�ӑ���p�̉��ʔv�ł��B ���������߂������̈ʔv�́A��Ƒ��k���ď��u���܂��B
�@
���@�v�̌�A��H���s�Ȃ��܂��B
�@
1) ��Ȏ҂̕��X���A��������Ȃǂł��ĂȂ��̂��ʗ�ɂȂ��Ă���܂��B
�@
2) �{��́A�����ň��A�����A���z�{�́A���炩���ߗp�ӂ��Ă����܂��B
�@
3) �m������H�ɎQ������Ȃ��ꍇ�́u��V���v�A��ʔ�Ƃ��Ắu��ԑ�v��ʓr�ɕ�ނ��Ƃ�����܂��B
�@
���A��Ɉ����������n�����܂��B
�@
1) ��H�ɂ́A��������t����̂���ʓI�ł��B
�@
2) �����������A�F����ɕ����ꏏ�ɂ������A�肢�������ꍇ������܂��B
�@
3) ��܂╗�C�~��l�����p�ӂ��A�����A��ɕ֗��Ȃ悤�ɂ��Ă����܂��傤�B
�@
������c�̈ʔv���Q�l�ɂ��܂��B
�@
1) ���߂Ĉʔv��I�ԏꍇ�́A���d�̗l����T�C�Y�ɍ��킹�܂��B�܂��A����c�̈ʔv������ꍇ�́A�傫���A�`�Ȃǂ��Q�l�ɂ��܂��B
�@
2) �{�ʔv�́A���h��܂��͍��h���̓��̂��̂������ł��B�܂��A�������������ʔv���������������J��o�����̂��̂��肾�����͂���o�ʔv������܂��B
�@
���{�ʔv�ɁA��(���傤)�����܂��B
�@
1) �{�ʔv�ɁA����(�@��)�A���S�N�����A�����A���S�N��Ȃǂ��������݂܂��B
�@
2) �m���ɂ��肢���Đ����܂��B���̎����͂�����ق�����@�Ƃ����܂��B���ɉ���(�@��)���������ʔv�ɐ��@�����܂��B������Ă�ق��_��@�Ƃ����܂��B
�@
�����Ƃɂ��A�ʔv��u���ꍇ������܂��B
�@
1) �ʔv�́A�{�Ƃ̂ق����Ƃɂ��p�ӂ��A���ꂼ��̂��ƒ�ŋ��{�����ꍇ������܂��B
�@
�����d�ƕ���̏���
�@
1) ���d�������߂ɂȂ�ꍇ�́A�N���@�v�܂łɂ��p�ӂ����Ƃ����{�ɕ֗��ł��B���łɂ���c����̕��d������ꍇ�́A����̂��������ς܂��Ă����܂��B
�@
2) �@�v�̋@��ɁA���d�E����̎����_�����s�Ȃ��A���ւ���s���i�̍w���������ꍇ�������悤�ł��B
�@
3) ���d�̕�C�́A�u�������v�ƌĂ�Ă��܂��B�e���J�Ɏ��O���Đ��A�����d�ł͋����̒������s�Ȃ��܂��B
�@
4) �u�������v�̎��A���{����ʔv�͕�ɗa���Ă��炤�̂������ł��B���̏ꍇ���m���ɂ��肢���āu���������v�Ɓu�����v���s�Ȃ����Ƃ�����܂��B
|
���@�v�̊�b�m��
�@
�@�v�̐i�ߕ��́A�@�|�@�h�Ȃǂɂ��قȂ�܂����A����A��فA���@�Ȃǂōs�Ȃ��ꍇ�́A�����ނˎ��̂Ƃ���ł��B
�@
1�D�ꓯ����E���� 2�D�J���̈��A(�ȗ���) 3�D�낤�����A�����ɓ_��4�D�m���ɂ��킹�ė�q 5�D�njo 6�D�č��@7�D�@�b 8�D���̈��A�A��H�̈ē�9�D����(��H) 10�D���J���̈��A
�@
��L�����⑫����
�@
1�D����A���@�Ɋւ�炸�@�v�O�ɒ��قȂǂ̐ڑ҂��s���܂�
�@
2�D�@�v���n�߂�ɂ�����{�傪���A�����܂��B�u�{���͂��Z�����Ƃ���A���z���������܂��Đ��ɗL��������܂����B�������܂�聖������(�̐l��)�́{�{�N���@�v�����肨���Ȃ킹�Ă��������܂��B�v�Ƃ����悤�Ȉ��A���̂בm���̕��Ɂu��낵�����肢�������܂��v�Ƃ̂א[����炵�܂��B���@�ł̏ꍇ���炽�߂Ĉ��A�͂������قɂĂ̐ڑ҂̌�A�{���œnjo���n�܂邱�Ƃ������悤�ł��B
�@
3�D���@�ł̏ꍇ�A�m���ɂ��C�����܂��B
�@
4�D�m��������Ɏw�����Ȃ��ꍇ�A�m���ɍ��킹�ė�q���܂��B
�@
5�D�Ȃ�ׂ������ɂĔq�����܂��B��ނȂ��ꍇ�A���ꂵ���Ȃ����x�ɑ�������Č��\�ł��B�����̎ア���A�N�y�̕���������ꍇ�A�����Ȃǂ��������Ă����S�z����K�v�ł��B
�@
6�D�njo�̓r���A�m�����獇�}������܂�����{�呤�̑�\���珇�ɏč����������܂��B�����͑��V�̎��قnj����ɍl����K�v�͂���܂���B���O�ɐi�ݍ��������[�����A�����ЂƂ܂ݍ��F�ɗ��Ƃ��A������x�����̌�A��炵�ĐȂɖ߂�Ƃ��������ł��B
�@
7�D�ӂ���m��@����Ȃ������Ɋւ���b��S�ɍ��݂Ȃ���A�Â��ɔq�����܂��B
�@
8�D�{��͑m���Ɍ����q�ׂ���A��H�̗\�肪���邱�Ƃ��Q��҂ɓ`���܂��B
�@
9�D��H���n�܂�O�ɎQ��҂Ɍ���\���q�ׂ܂��B���̂Ƃ��Ɍ̐l�Ƃ̃G�s�\�[�h�Ȃǂ������Ȃ��爥�A�������Ƃ悢�ł��傤�B
�@
10�D�����o���Ȃǂ̖Y�ꂪ�Ȃ��悤�S�z������������̂ł��B
�@
���Q��҂̐Ȉ�
�@
�@�v�̐Ȉʂ́A���V�قǐ_�o���ɂȂ�K�v�͂���܂��A�ڏ�̕��A�����̕��A�̐l�Ɛe�����������́A�Ȃ�ׂ�����ɂȂ�悤�ɂ��܂��B�{��́A�@�v�̐i�s�����Ƃ߂܂��B
�@
���ˌ�����(���傤���߂��ɂ�)�����@�v(�������ق��悤)
�@
�ˌ��Ƃ͎��S�������������A�����͂Ȃ��Ȃ������̎��������܂��B�u�ˁv�Ƃ����̂́A���Ƃ��Ƃ��߂ł������邵�Ƃ����Ӗ�������A�̐l���S���Ȃ��Ă���\�O�P���ڂ��������̂߂ł������Ƃ����A�����̎�o�̋������炫�Ă��܂��B
�@
�ˌ������ȊO�̌��X�̖���(���S�������Ɠ�����)�ɂ��A�m���ɂ��o�������Ă����������肵�Ė@�v���c�ނ��Ƃ��u�����v�Ƃ����܂��B
�@
�����������l�\���(�����A)�Ƃ́H�@
���S���Ă��玵�T��(�l�\���)�́A�u���A�v�Ƃ����܂��B���̊ԁA���̎҂����{���鎖�ɂ���ď��߂āA���҂̗�͖����ɋɊy��y�ɐ�������ƍl�����Ă��܂��B���̋��{�́A�S���Ȃ�ꂽ�����琔���Ď������ƂɁA������(����Ȃʂ�)��(�ӂ��Ȃʂ�)�O����(�݂Ȃʂ�)�l����(��Ȃʂ�)����(���Ȃʂ�)�Z����(�ނȂʂ�)������(�����A�A�l�\���)�ƍs�Ȃ��܂��B
�@
����́A�l�����S���Ė��y�ւ����܂���腖��l(����܂���)�̑O�ōق�����Ƃ����Ă��܂����A���̐R�����������Ƃɂ����ƐM�����Ă��邱�Ƃ���A���̓��������Ƃ��Ė@�v���s�Ȃ��킯�ł��B�ŋ߂ł́A�������̖@�v�ƁA���������������ǂ��炩�̖@�v�ƁA�v���ɏȗ����邱�Ƃ������Ȃ�A�����āA�l�\����̖@�v�����Ă���Ŋ������Ƃ���Ƃ����̂���ʓI�ȏK���ƂȂ��Ă��܂��B���̂��Ƃ́A�S�P���̖@�v�����܂����A���̂Ƃ��n���ɂ���ẮA�����ڂƂ��̂��߂̋��{�ł���u�{��S��v(��������)�����킹�čs�Ȃ��Ƃ��������܂��B�S���������ނƁA1��������̔N���@�v�ɂȂ�܂��B�܂��A�F�{�ł͎O�����ɂ܂������Ă͂����Ȃ��Ƃ̌����`��(�u�n�I�A�ꂪ�g�ɕt���v�̌�C���킹)�ŁA�l�\����ڂ��O�����ɂ܂�����ꍇ�͎O�\�ܓ��Ŋ������̖@�v������n��A�⑰�����邪�A�����͂������܂���B���ɐ^�@�͋C�ɂ��܂���̑m���ɂ����k���ꂽ�珮�A�ǂ��ł��傤�B
|
�����~�Ƃ��ފ�
�@
�����~�̍s��
�@
���~�͐����ɂ́A�u����ڂ�᱗��~��v�Ɖ]���A��N�Ɉ�x���̓��ɂ͎��҂̗삪�Ƃɖ߂��Ă���Ɖ]���A�e�Ƃł͐���I�����A�}�����Ă��}�����܂��B���̂��~�̍s���́A�����I�ȍs���ł����@�h�ɂ�錈�܂�̂悤�Ȃ��̂͂Ȃ��A���ꂼ��̒n���ŌÂ�����`�����Ă�����������ōs�Ȃ��Ă��܂��B��ʓI�ɂ́A�����\�O�������~�̓���Ƃ��ď\�Z���܂ł̎l���ԂɁA���~�̍s�����s�Ȃ��܂��B�Ƃ���ɂ���ẮA����̎�����ꃕ���x��̔����\�O������\�Z���ɍs�Ȃ��Ƃ��������܂��B
�@
��᱗��~��(����ڂ�)
�@
���~�͐������́u᱗��~��v�Ƃ����܂��B����᱗��~��̗R���ɂ��ẮA�u᱗��~�o�v(����ڂ傤)�Ƃ������o�̒��ɏ�����Ă���u�ژA�`���v(�������ł�)����o�Ă��܂��B�u�߉ނ̏\���q�ł���ژA���A���鎞�S���ꂪ�n���̉�S���ŋꂵ�݂������Ă���̂�m�肻�̋~���铹�������Ď߉ނɐq�˂��Ƃ���A�w���O�̕�́A���O�~���[�����l�ɗ⍓�ł������ߋƂɂ���Ēn���ɂ���̂�����A�����ɂ��O���{��������x�Ƃ����܂����B�����Ŏ߉ނɋ�����ꂽ�Ƃ���ɁA�����\�ܓ��ɉĂ̏C�Ƃ��I�����m���ɁA�S���̈��H�����{�����Ƃ���A���̌����ɂ���ĕ�͒n���̉�S���̋ꂵ�݂���E���V��E�֏オ�邱�Ƃ��ł��܂����B�v���̉�S�ɋꂵ��ł��邠�肳�܂��A����(�T���X�N���b�g��)�ŃE�����o�i(�t���Â�ɂ��ꂽ�悤�ȋꂵ��)�Ƃ����A᱗��~��͂��̉����]���ė����Ė~�Ƃ����悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B�܂�A᱗��~��Ƃ͂��̐��ւ����Ă��炱�̐��ł̋Ƃɂ���ċꂵ��ł����c�ɂ����A�����Ă���҂����������ĉ�����ċ~���Ă��������Ƃ����肢�����߂��Ă���s���ł��B
�@
���u�~�x��v
�@
�߉ނ̒�q�ژA����e�̋ꂵ�݂��~�������ƂŁA��ϊ��ŎO���ԗx���Ċ�т�\�킵���̂��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B
�@
���u���~�A��v�Ƃ́H
�@
���~�͐�c�̗삪���e�Ɖ���߁A��N�Ɉ�x���̐�(�ފ�)���炱�̐�(����)�Ɍ����Ƃ����܂��B���̎��A���̐��Ɍ�����蕨���A�m�₠�邢�́A�L���E����֎q�ō�����n�ŁA�A�鎞�ɏ��̂����Ƃ����Ă��܂��B����͗��鎞�A�n�Ȃ̂͐̂��������𑁂�����������A�A��ɋ��Ȃ̂́A���̐��̖��c���������y���݂Ȃ���A�肽������Ƃ������ƌ�ŏq�ׂ܂���̐�������܂��B
�@
���ׁ̈A���~�̏��������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B��c�̗삪�A��ꏊ�Ƃ��āu�����d�v��u����I�v�������肵�A�e���Ő^�S�������Ă��}������̂������{�ł��B
�@
������I(���傤��傤����)
�@
�\�O���̒��ɂ́A�܂����d�𐴂߁A���ɂ͐�c�̗���}���邽�߂́u����I�v�����܂��B���̐���I�́A�~�I�A��c�I�A���܂��ȗ�I�A��Ղ�I�ȂǂƂ����A�K���}���������O�ɕ��d�̑O�≏��Ȃǂɏ���܂��B�̂́A���d�̑O�ȂǂɁA�V�䂩���Ŕ�݂�����A4�{�̂��̒|��ؑg�Ȃǂ𒌂Ƃ��āA���̏�ɒI�����A�^�Ԃŕ҂�����~���Ă���ςȒI����������̂ł��B�I�ɂ́A���d����ڂ����ʔv���(������)�A���C�A�C��A�ԗ��āA�����A�����Ȃǂ������܂��B����ɁA�@�̗t����ɂ��āA�����̔_�앨������A������ꂽ���A�c�q�Ȃǂ������܂����A�Ȃ�ׂ�����̋������̂�A�Ԃ̓��̎�����͔̂����܂��傤�B
�@
�܂��A���蔢�Ŏl�{�̑���t�����֎q�̋���L���E���̔n�Ȃǂ�����܂��B����́A��c�̗삪���ɉׂ��������A�n�ɏ���ċA���Ă���Ƃ������ƁA�n�ɏ��A���Ă��āA�߂�ɂ͂�����苍�ɏ���ċA��Ƃ����A��̌����`�����M�����Ă����Ƃ��납��������̂ł��B�����āA���̋��n�̂��߂ɂ����⋟���������܂��B�ŏ��͓����Ɍ����Ă��}�����A����������ɂ́A����O�ɑ��肾�����߂ɊO���Ɍ����Ă����܂��B
�@
�������A�����ł͂����������ʂȐ���I�͍���Ȃ��Ȃ��āA���d�̑O�ɏ����Ȃǂ������āA���̏�ɐ^�Ԃ��Ŏq��~�����x�̂��̂������悤�ł��B�Ƃ���ɂ���ẮA���d�̈��o����I�ɂ��炦�Ă��܂��邱�Ƃ�����܂��B���d�̔���߂āA�ʔv��I�ɒu���ꍇ�Ɣ��𖾂����܂܂ňʔv�����d�ɒu�����܂܂ɂ���ꍇ�Ƃ�����܂��B
�@
���V�~�̋��{
�@
���s�K����������A���߂Č}���邨�~�̎����u�V�~�v�Ƃ��u���~�v�Ƃ����āA���ɒ��J�ɋ��{����̂���������ɂȂ��Ă��܂��B���̂Ƃ��́A���܂������������̂ق��ɁA�̐l�̍D���Ȃǂ��o���邾�����������܂��B�����Đe����̐l�ɂ䂩��̂��邩�������������āA�m���ɂ��o���グ�Ă��������Ă���A���i�����ł��ĂȂ��܂��B
�@
�܂��A�V�~�ɂ͐e���Ȃǂ���~�������邱�Ƃ�����܂����A���ʂ̂��~�̂��߂̖~�͏H���͗l�Ȃǔ������ʐF�ŕ`�����Ȃǂ�I�т܂����A�V�~�̏ꍇ�͔̒���F�̒�p���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���~�̍Ō�̓��ɂ́A����������āA��𑗂肾���ĐV�~�̍s�����I���܂��B����̋߂��ɕ�n������ꍇ�ɂ́A�ňē�����悤�ɂ��ė���n�܂ŋA�点�A���̌エ���ɂ��̒������߂�K�킵������܂��B
�@
�܂��A���������Ȃǂ́A���̖~���M�Ȃǂɂ̂��āA���C�ɗ����܂����A�@�h�ɂ���Ă͂��̗l�ȗ�𑗌}����s���������������Ȃ��Ƃ��������܂��B
�@
�Ƃ���ŁA�u�~���{�v�Ƃ́A�������Ă������A�N��̐����炨�}�����ċ��{���邱�Ƃł�����A��������(�l�\���)���߂��Ă��珉�߂Č}���邨�~���A�{���̈Ӗ��ł́u�V�~�v�ƂȂ�܂��B�܂�A�S���Ȃ�ꂽ�����Z�����ȂǂŁA��������(�l�\���)�̏I���Ă��Ȃ��V���̗�́A�܂���������Ă��炸���}���ł��Ȃ��킯�ł�����A�~���{�͂��Ȃ��ŁA���N��҂��ĐV�~�Ƃ��܂��B�ꕔ�̒n���ł́A�����������Ƃ��C�ɂ����ɁA���߂Č}���邨�~�����ׂĐV�~�Ƃ���Ƃ����Ƃ��������܂��B
�@
�����ފ�
�@
�O���̏t���̓��ƁA�㌎�̏H���̓����u�����v�Ƃ��āA���̒����̑O��O���������킹����T�Ԃ��u�Ђ���ފ݁v�Ƃ����܂��B���̔ފ݂Ƃ������t�́A�Ɋy��y�Ƃ����^���̗��z�̋�(���̐��E)���Ӗ����Ă���A�������Y�ɖ��������̐��́u�����݁v�ɑ��āA���z�̔ޕ��̂Ƃ���(��)���������t�ł��B�����ł́A�������̔ޕ��݂̊ɂ��́u�ފ݁v������Ƃ���Ă���A������l�͂����ɂ��ǂ蒅�����Ƃ��o����Ƃ���Ă���܂��B�����āA���̌��́u�ފ݁v�������邽�߂Ɏ��H���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Z�̎��H���@�̎����u�낭�͂�݂Z�g�����v�Ƃ����܂��B
�@
����́A�����̂����Ă�����̂𑼐l�ɕ����^����u�ӂ��z�{�v�A���߂����u�����������v�A�ς���u�ɂ�ɂ��E�J�v�A�w�͂���u���傤���i�v�A���Ȕ��Ȃ�����u���傤�T��v�A�^���ɂ��ƂÂ��l���������������u�����q�d�v�̎��H�������߂Ă�����̂ł��B
�@
���ފ݂ɕ��d�₨��ɋ�����Ԃ␅�A�����A�����A���͂��Ȃǂ��A���͂��ׂĘZ�g���������H���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��B�����͖{���A�����ɐ����̒��ŏ�ɂ����낪���Ď��H���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł����A���ۂɂ͂����Ă��̐l���A��N������������Đ�������킯�ɂ͂����Ȃ����̂ł�����A���߂ċC��̂悢�t�ƏH�̔ފ݂̎����Ԃ��炢�͎��H���܂��傤�Ƃ����̂��u�ފ݁v�̎n�܂�ł��B
�@
���ފ݂̎��ɂ́A���~�̗l�ɂ��낢��Ə������肷��K�v�͂���܂��A�O���Ƌ㌎�̔ފ݂̓���ɂ́A���d�����ꂢ�ɂ��|�����āA�V��������ԁA�̐l�̍D���A�G�߂̉ʕ��₨�͂��A�ފ݂��Ȃǂ����������܂��B
�@
���āA�ފ݂ɂ����̂̂��͂��ł����A�Ăі��������܂��B�����R�P�����������̂��ۂ߂āA����ɊÂ��ς��������܂Ԃ����`���A���̉Ԃ̍炭�悤�Ɍ������̂Łu���͂��v�Ƃ�сA���O�̉Ԃ��炢���悤�ɂ͂Ȃ₩�������̂Łu�ڂ������v�Ƃ��Ăꂽ�Ɖ]���̂��Â�����̂����ł��B
|
��Q&A�@
���@�v�̕���
�@
���Ȃ��Ƃ��O����܂ł́A�⑰�͒j���Ƃ������r���𒅗p���܂��B����ȍ~�͏����Â����ɂ��Ă����܂��܂��A�ǂ�ȏꍇ�ł��Q��҂��y�������ɂ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B
�@
�������d�̈��u�ꏊ�@
���ɒ�܂�͂���܂���B���낢����M�Ⓙ��������܂����A������炸�������J��C��������ł��B�Â��Ő����ȏꏊ�ł���A���������ė�q�ł��܂����A���C�Ⓖ�˓���������āA�Ȃ�ׂ����Ƒ������ė�q���₷�����Ɉ��u����̂��ǂ��ł��傤�B�����ɂ��Ă����l�ɒ�܂�͂���܂��A�����ł́A�u�{��������(�ق�炢�Ƃ������Ȃ�)�v�u�����L��k(�������Ȃ�ڂ������)�v�Ƃ��������������āu�킾���܂�₱�������̂ĂĂ��܂��Γ��������Ȃ��A�ǂ���T���Ă�����k���Ȃ��B����Ƃ���Ύ����̐S�̂Ƃ���₱����肩�炠��Ǝv�������̂��Ƃ��v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�@
���Ɉ�ʓI�Ȃ��͎̂��̂Ƃ���ł��B
�@
��ʖk���E�E�E�����d����������悤�Ɉ��u���A�k�����͔�����悤�ɂ��܂��B(���s�̐_�Е��t�̂قƂ�ǂ���������Ă���܂�)
�@
������y�E�E�E������y���q���邽�߂ɁA�����d�𓌌����Ɉ��u����B
�@
���l�������̉ԍՂ�@
���߉ޗl�̒a�������j��������̂ł��B�Ñ�C���h�E�J�r�����̉��q�Ƃ��Ă����܂�ɂȂ������߉ޗl�́A���E�̎�œV�n���w���A�u�V��V���B��Ƒ�(���̒��ōł��������͉̂䁁���ɂł���)�v�Ɛ錾���ꂽ�Ƃ����܂��B�킪���ł͐��ÓV�c�\�l�N�ɉԍՂ�̍s�����n�܂����Ɠ`�����Ă��܂��B�ȗ��S���̂����Ŗ��N�l�������A�Ԍ䓰������A���߉ޗl�̒a���̂��p�ɊÒ��������ďj���悤�ɂȂ�܂����B�Ò���������̂́A���a���̎��A�������ÉJ���~�炵�Ă��g�̂���߂��Ƃ����̎��ɗR�����܂��B
�@
�����̉œ���ɐ���̂���c�ւ��݂₰�������Ă����ƕ����܂��������悢�ł��傤���H
�@
��ʓI�ɐi���p�̂��������A���₩�g���̐����Ō��сA�u����c�l�v���̉��V�w�̖��O��\�������Ď����čs���܂��B�n���ɂ���Ă�"�����ԂƂ�"�̏ꍇ������܂��B
�@
����ɐ���������킯�́H
�@
��ɂ����鐅��A��̑O�̐����Ȃǂɓ���鐅�̎����u脉��v(�܂��͈���)�Ƃ����܂��B脉��́A����̃A���K�A�A���J����]�������̂ŁA���{�Ƃ��������Ӗ����A�̂��ɂ́u�ϔY�̍C��v�Ƃ����悤�ȈӖ��t�����Ȃ���܂����B
�@
���Z��͎O�l�@�N�������d���܂�����̂��H
�@
�S���̖@���̑��k�ŌZ��O�l�ŕ�ɍs���ꂽ���A�Z�E�̑O�ł̌��������ł��B
�@
�Ƃ��p�������j�̌������́u�S���̎l�\����܂ł����d�����Ƃɂ��Ă���̂����A���̔�p���Z��O�l�ŎO���̈ꂸ�o���悤�ɂƌ�������A�O�j���������v
�@
�O�j�̌������͓��R�̂悤�Ɂu�Z�̒��j�͉Ƃ𑊑������̂�����A��c��e�̗�����{����̂͒��j�̂Ƃ߂ł���A�O�j�̎���������K�v�͂Ȃ��B����Ɏ��j�̌Z�́A�����͎����ŕ��d���Ă܂邩�炢���ƌ����Ă���v
�@
���j�̌������́u�ʂɒ��j�̂Ƃ���łȂ��āA���j�̎��������d���܂��ĕ��̋��{�����Ă������킯�ŁA�����͎����ł�邩����Ƃ̂����d�ɂ͋����o���Ȃ��v
�@
����ɑ��Ē��j���u���ɋ��{���������������ł���̂����������B���������A�������������ɕ��d������ΐ�c��e�̍�����������ǂ��Ȃ��ƕ����Ă���B������{�Ƃɗ��h�ȕ��d��u�������v
�@
�O�l�O�l�̈ӌ����o���Ƃ���ŏZ�E���O�j��肩���܂����B
�@
�u���Ȃ��͐�c��e�̋��{�͒��j�̂Ƃ߂ł���O�j�̎����͕K�v�Ȃ��ƌ����܂����ˁB�v�u�Ƃ���ł��Ȃ��A��Y�̑����͂����̂ł����H�v
�@
�O�j�u�����ł��B��Y�͎O�l�����ɂ��炤�̂����R�ł�����v
�@
�Z�E�u����Ȃ炲���{�����j�܂����łȂ��A�O�l�ŕ����ōs���ׂ��ł��B���{�͒��j�܂����A��Y�͂��������܂��ł̓��V���悷���܂��B����Ȃ��Y�����Ԃ��Ȃ����B�v
�@
���j�u�������A��Y��Ԃ��v�̌��t�ɑ��Z�E�́u���Ȃ�����قǂ������Ȏ��������܂����ˁB���������ɂ����d�����܂肷��Ƃ���c�₲���e�̍�����������悭�Ȃ��ƁA�Ƃ�ł��Ȃ��B�����{�Ƃ͖S���l�Ɛ[�������Ɍ��ꂽ�l�������o���邨���ĂȂ��ł��B���ł��ǂ��ł��A�����܂������Ƃ��Ɏv���āA�����₨�Ԃ₲�т������グ��Ƃ��������s���ł��B�����d���Z���l��l�����܂肵�����{�Ȃ������炢�����ł����H��葽���̕��X�������{���ĉ�����̂ł�����A�����e�����тł���v
�@
�X�ɑ����ďZ�E�́u(���j��)�������ł����d�����܂肳��邱�Ƃ͂ƂĂ��悢���Ƃł��B�Ɠ����ɁA���Ƃł��O�j����̂��ƒ�ł����܂肷��ɂ͂ǂ�����������悭�b�������ĉ������B��������Y���l����킸���ȏo��ł͂���܂��v
�@
���ЂƂ育��
�@
�����d�Ƒ����i�Ƃ����d���ƂƂ��Ă��邩��ł��傤���A�ӂƎv�����Ƃ��������܂��B��ɂ��������Ă���܂����A���N�l�������͉ԍՂ�ł��B���̉ԍՂ��������(����´)�Ƃ����̂��ŋ߂̎�N�w�̕��X�͂��܂育�����Ȃ��悤�ł��B
�@
�悭�v���̂ł����A����Ō������������A�q�����Y�܂ꂽ��{�Q��A�N���X�}�X���j�������Ǝv���ƁA�N�����܂�Ώ��w�A�ōŌ�ɂ����b�ɂȂ�̂������ł������ł��B�������̏��w���_�Ђɂ��Q�肵�Ă���Q��Ə��w�̃n�V�S�����Ă���悤�ł��B
�@
����ΐM�ɖ��ߑ��ȓ��{�l�ł����_�╧���������Ă��Ƃ����b�͕��������Ƃ�����܂���B���{�l�͑��_���A�������̐_�l�╧�l��M���邱�Ƃ��o����Ƃ������Ƃł��B����̓A�W�A�A�����X�|���n�т̔_�k�����̓����ŁA�R�̐_�A�ɏh��_�A����ڂ̐_�Ƃ����悤�ɁA�ǂ��ɂł��_�l�������łɂȂ�ƐM���Ă��J�肵�Ă��������ł��B
�@
����́A�ƂĂ����a�Ȃ��Ƃł���f���炵�����Ƃł��B�悭�����d�Ɛ_�I�������ł��܂肵����_����ƕ�����̌��܂����Ƃ��A���̓�����ƕ����܂����A��l������̂��A�_�I�Ƃ����d�������ł��܂肵�����A�������ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������ɂ����A�Ƃ�����Ƃǂ��炩�ɂ�����肪���ɂȂ�̂����߂Đ_�I�Ƃ����d�����ɂ܂��Ă͂����Ȃ��Ɛ̂̐l�͌������̂�������܂���B
�@
�܂��A�u���邤�N�ɂ����d�₨����Ă͂����Ȃ��v�Ǝ��ɂ��܂��B�Ȃ�����Ȏ���������悤�ɂȂ������E�E�E���̃��|�c�͋�B�n�����猾���n�߂����̂ł��B�́A��B�̂��a�l�����邤�N�̕��d�w���֎~�߂��o�������Ƃɂ��܂��B
�@
�Ȃ�����ȕz�߂��o�������Ƃ����Ƃ��̍��̗�͋���ŁA��N�\���̂Ƃ�������邤�N�͏\�O�����ɂȂ�킯�ł��B�܂�ꃖ���������ł����炨�a�l�ɂ͍��邱�Ƃ��N����B����́A�Ɨ������̋������ꃖ���悯���ɕ���˂Ȃ�Ȃ��B�������A�˂̍����͋ꂵ���B�Ɨ������ɂ͏\�����ŏ\�O�������炳��������ŁA���a�l�͗l�X�Ȑߖ��i�߂��킯�ł��B���̂ЂƂ����d�w���֎~�߂ʼnƗ������̉ƌv�̏o������������Ƃ������ł��B���ꂪ�����ƌ����킯�ł��B
�@
�ȑO����Ȏ�����܂����B�u�䂪�Ƃ͖����p���H�ł�������������l�ɋ����邲�т��Ȃ�����p�����炲�тɑւ���悤�ɁE�E�E�������q���B�͔��Ńp�����������炢���ƌ����܂��B�������Ƀp���ł����܂�Ȃ��ł��傤���H�v����͂��ꂵ���ނ̎���ł����B
�@
�Ȃ��Ȃ�A���̂��Ƒ��́A���тɂ���p���ɂ��남�������鎖�ɂ��Ă͂��ӌ����܂Ƃ܂��Ă��܂��B���ē����ł����A���������͂��s����������܂��A�p���ł����܂��܂���B�^�S�̂����������������Ȃ�Ε��l�A����c�l���������Ȃ͂�������܂���B���Ԃ����������������̂����肢�������܂��B
�@
�Ƒ������d�ɂ��Q�肷�邱�Ƃɂ���Ďq���B�����l�₲��c�l�֎�����킹��Ƃ����C�������炿�܂��B �@ |
 �@
�@
���� |


 �@
�@ |
(����A�Ђ�(�l))�Ƃ́A��̂�[�߂đ��邽�߂̗e��B�ؐ��̏ꍇ�͖؊�(��������)�A�Α��̏ꍇ�͐Ί�(��������)�Ə̂����B
�@
�����̓��{�ł͉Α����قƂ�ǂł��邽�߁A����ɓK���������g�p����Ă���B�傫�������ēV�R�؊��ƍ����̃t���b�V�����ɕ�������B �V�R�؊��́A��ނ��w(�q�m�L)�A��(���~)�A��(�L��)�Ȃǂ̖��C�ނ��p����ꍂ���i�ł���B����t���b�V�����́A�������������̊Ԃɐc�ނ����ē\�荇�킹�A�\�ʂɓV�R��(�˂��嗬)�𔖂��X���C�X�������̂�\�����˔\�荇���A�ؖڂ����Ɉ�������v�����g�����A�z��\�����z���芻������B �ŋ߂͔M�щJ�т̕ی��n�����g�������Ēn�������̗L�����p����A���ɔz����������i�{�[�����̃G�R�����o�n�߂Ă���B �܂��A�`��͂��ꂼ�ꔠ�^�A�J�}�{�R�^�A�R�^�A�M�^�Ȃǂ�����A�O�ςɂ͒������{�����������A�ܖʒ����A�O�ʒ����A��ʒ����Ȃǂ̒�����������B�T�C�Y�͉Α���ɂ�������鐡�@���قȂ�B��ʓI�Ɋ֓��͑傫�߂̊����g���Ă���B�W�ɂ͈�̂̊��������悤�ɐ�p�̊W�ŊJ�����������Ă��鎖�������B
�@
�����̂قƂ�ǂ͔����嗬�ŁA�f�ނƂ��Ă̓|���G�X�e�����p�����Ă��邪�A���i�ɂ�荂���ȑf�ނ��g���A���[�X���̑������{����Ă���B
�@
���̉��i�͈������̂ł������~�͒������Ȃ��A�������̂ł͐��\��〜100���~�ȏシ����̂�����B��̂Ƌ��Ɉ��p�i�₨�C�ɓ��肾�����ߕ��E���ЂȂǂ��i�Ƃ��Ĕ[�߁A���̂܂܉Α����鎖�����邪�A�ŋ߂͊���肩��Α��ꑤ�ł͂�������l����悤�ɌĂт������Ă���(���Ƀv���X�`�b�N�ނȂ�)�B����������ł͎Ќ�I�E���K�I�Ȏ��������ꂪ������ʂ�����B
�@
�����̗��j
�@
�퐶����ɂ́A�P���╮�u��Ɋ����g��ꂽ�B�퐶���u��̊��͒Z���A���@��2���[�g�����x�̑g�ݍ��킹���`�؊����嗬�ł������B���ɂ͒ꂪ�J�[�u���Ă��芄�|�`�؊��̂悤�Ȋ�������A�g�ݍ��킹�Ί����k��B�Ȃǂɂ���B
�@
�Õ�����ɂ́A�؊���Ί����g��ꂽ�B���̌`�͗l�X�ŁA�؊��ł͙��蔲�����̊��|�`(��肽������)�A�g���������`�A�����`(�Ȃ���������)�Ȃǂ�����A�Ί��ɂ͊��|�`�A�����`�Ȃǂ�����B
�@
�Õ�����ɐ��s�������|�`�؊�(��肽��������������)�́A���a1���[�g���O��̂��Ȃ葾���ۖ��c�Ɋ���A�����蔲���đ�l1�l�̈�[�����[�ł���悤�ɂ������ł���B���̖��̗R���́A�|���c�ɂ���Ă������悤�Ɍ����邱�ƂɗR��������̂ƍl������B�M�`�؊�(�ӂȂ�����������)�������悤�ȑ�����B���̒����͕��ςł�5���[�g���O��A�������̂�8���[�g���ɂ�����сA1�l�̈�[��[�߂�ɂ͒�������B�����i�����邽�߂Ƃ��v���邪�A�������ł͂Ȃ��Ƃ����ӌ�������B�������A3�������ē�����Ƒ������Ɋe��i��[�߂Ă���������B�ގ��̓R�E���}�L�����|�I�ɑ����B
�@
���q���ォ��͒M�^�̊�(����)���嗬�ƂȂ����B���݂��g�p����Ă���u����(����)�v�Ƃ����ď̂͂��̌`��ɗR������B�����͂܂��Α����嗬�ɂȂ�O�A�y��������ۂɑ����p����ꂽ�B��O�̐��˓��n����Ƃ����f��́w�J���]�[�搶�x�ł��A��̂�M��̊��ɓ���Ė_���킽���A�j2�l�Ŗ_��S���ʼn^�ԃV�[�����o�ꂷ��B�Α����\�ł����������̊��ɑΉ�����Α��ꂪ���Ȃ��A�d��R���Ƃ��Ă����ꍇ�͉Η͂��ォ�����̂ŁA���ۂɉΑ������y����̂͐���҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ł͓y���̌����������āA��ɐQ�����g���Ă���B
�@
���u�����v�Ɓu�l�v
�@
�l�ԁA�N�ł�����K��������̂��������B���Ȃ݂Ɋ����ƞl(�Ђ�)�ɂ͖��m�ȈႢ������B��̂̓����Ă��Ȃ������܂ŕ��Ƃ��Ă̒i�K���u�����v�Ƃ����A��̂������ĕ��ƌĂԂ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������̂��u�l�v�ɂȂ�B �@ |
 �@
�@
���u���v�r�� 1 |


 �@
�@ |
|
���u���v 1 |
��1�A���̒m�点
�@
�l��50�N�Ƃ̌��t������܂����A���̔N��ɂȂ�Ƒ��̐l���A�c����A��������B�̎��A�e�Z���̎��ƌ����`�ŁA���ɂ��čl���A�܂����炩�̌`�Ŏ��҂���̒m�点��������ƂƂ��ɁA���̋V����܂��̌����Ă���l�������Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B
�@
��87��ŁA����m�点��J���X�ɂ��ď����Ă��܂����A����m�点��g�҂Ƃ��ẴJ���X�̎p�́A�S���̈�ʎЉ�Œm��킽���Ă���悤�ł��B���̂ق��ɂ��A���҂Ƃ̔}�̂₭�Ƃ��āA�����A�A���A�̋�(�l��)�A�V�́A���A�Ȃǂ�ʂ��ē��퐶���̒��ŁA�l�X�Ȍ`�̂ő̌���������͐���������܂��B�����̑̌��́A���{�S�̂ɋ��ʂ���悤�ł��B���ł��_�X�A�������̏Z�ޓy�n�Ƃ���鏊�Ő�������l�B�́A�����̒��Ŏ��R�ɐg�ɒ����̂ł��傤���A���ɕq���Ɏ��̒m�点���L���b�`����\�͂�����Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@
�a�̎R�ɉł���15�N�]��ɂȂ閺�ցu�J���X�̖����Ŗ��̉ʂĂ���Ă�l������v�ƌ����b���������A�u�a�̎R�̐l�͒m���Ă����v�ƌ����āA�J���X�̖�����J���X�̍s���ɂ�鎀�Ɋւ���m�点�̓`�������̂ł����A���������m���́A�a�̎R�Ɍ��炸�_�k�����ł�����{�l�ɂƂ��Ă͏��a2�A30�N��܂ł́A(��1)�ł̏펯�Ƃ��Ĕ������Ă����̂łȂ����Ǝv���܂��B���ꂪ�V��̑r���╶���ƈ��������ɁA���������\�͂��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A���������̂̐�������l�Ɨ��̐��̕����I�����̒��ŁA�s�K�v�ƂȂ�����čs�����Ǝv���܂��B�s��̕����I�������g�ɒ������l�X�ɂƂ��Ă͑��Ɍ������̒m�点��A��Z���Ȃǂ��L���b�`����\�͂ɗ���Ȃ����퐶���ɂ���āA���������\�͂͑r�����Ă������悤�Ɏv���܂��B�����Đ�c��X���`���Ă������X�̎����A���M�Ƃ��ē`������Ȃ��Ȃ�A���ł△�S�̓������ǂ��Ă���C�����܂��B
�@
�n�k��ΎR���Ȃǂ̓V�Ђ̗\�m�͊w��̐��E�ł�����ƕ����܂����A�쐶�̓��������͗\�m���@�m���ē����鎖���o����悤�ł��B���̑̌��ł͏��a2�A30�N��ɂ́A�C�̒j���B�͒n�k�A�R�Ύ��A�����Ԃ̓V�C��(��2)�������z�̌��A�_��[�Ă��ŗ\���ł��܂����B���������ŁA��w�̐��m���������Ȃ��l�B���A����3�����x�O����A�����Ă��͗\�����Ď������߂Ē��J�ɕʂ�̓����Ǝ��Ԃ��߂����Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@
���ẮA�����͂Ȃ��A�����ƂȂ����m�鎖���o�����̂��Ƌ^�₪������Ǝv���܂����A�F�X�Ȍ`�ԂŁA����̐l�B�Ɏ����}����҂���̒m�点���L���b�`���A��������y�n�̓`����M���~�߂Ď����߂���������Ǝv���܂��B���̂悤�l�Ԃ̑����̒��Ŏ������߂鎖�̏o�����̂́A����ł������Ƃ��̐��������ĕ������̏o��������̉��b��������Ȃ��Ǝv���܂��B
�@
(��1) �ł̏펯�c���������̂̒��Ő�����ł́A�ƁA�v�A�Ƃ̉��œ����̂���ł����B�Ⴆ�A�����̎҂������}����ƁA�����ɉƑ��̑��V�O�̕����A���V�̕����A���V�̐H�����̎�`���A�q���B�ɔz��َq���A���z�c�A�z�V�̑V�A�Ɠ��s�ƌĂ��g�D�ŁA�v�A�Ƃ������ɑ�Ȃ���肩����邽�߂̗p�ӂ����܂����B�������������o���邽�߂ɁA�łɂ͉ł̏펯�A���{������܂����B���ɋV��ɂ͂��̏펯�͑�ł������悤�ł��B�����̉S�Ɂ���O���\�܂������݂��悤����^����ȉłȂ炢��ǂ���(�A���Ă���)�\�㗪���͉ł̔�펯���S�������̂ł��B�������D���鎖�́A�ł̏펯�ŁA���҂̒����s�̏������̎�ŖD���čs���܂��B���ꂪ�o���Ȃ��Ƒ����̏����ɂȂ�ƌ����S�ł��B(���s�c�����̏��O���[�v�ŁA���V�Ȃnj݂��ɏ��������Đ����Ă����V�X�e��)
�@
(��2) �������z�c���o�鑾�z�́w�������x���ޑ��z�́w���x�ł��B�����ۂ����z�̂܂��ɉ_���Ԃ�l�F�ɂȂ�܂��B�����n����ŁA�[���ɔ����������锒�����z�͋ߓS�d�Ԃɏ���đ�a���n�闤�����猩���܂��B��a��֒��ޔ������z�B�V�����]�_�Ђ̐X����z�E�_�Ђ̐X�Ƃ��̌������̌������̓�̏�z������܂��B
�@
��2�A���Ɩ��M(����������āA�����s��)
�@
(1)�Ɛl�֎��̒m�点(�Ɛl�̒N���������}���邩������Ȃ��Ƃ����m�点)
�@
���~�����ɃJ�r��������Ǝ��҂��o��B(���̂����͍L�����z�����Ă���B�~�����ɃJ�r���������N�x�ɕ��e�Ǝ��ʂ����B�ȗ��~��t���������Ȃ��Ȃǎ���͑���)
�@
�����X�̖����ς��Ɛl�����ʁB(�ǂ��̉ƒ���~�����□�X�͎�w���ƒ�ł������B)
�@
�����C�Ȗ��}�Ɍ͂��Ƃ��A�ߏ��ł͊`�Ȃǂ̎��̕����s��̎��A���������قǁA�����Ղ�Ǝ���t����ƁA���̉Ƃ̐l������(���̂悤�Ȃ������������邱�Ƃ��炩�A���̂Ȃ镨�A�`�B���������B���f�B�Ȃǂ��ɐA�����炢���Ȃ��ƌ����B������������Ȃ�߂���ƁA��Ɠ����ŁA�o���邾�������̐l�ɐH�ׂĂ��������B�ߏ���m�l�֔z��)
�@
(2)�����Ăԃ^�u�[�Ƃ��āA��(����)�����A���������s���������
�@
����ɒ܂���Ă͂����Ȃ��c�e���������ʁB�e�̎��ɍۂɁA��Ȃ�
�@
����ɔ��������A�����ɂ��ׂĂ͂����Ȃ��c�e������
�@
������œ]�ԁB����ɗ�����B�Ɛ_�l�ɌĂ��(����)�c���O��ς��Ȃ�������Ȃ��B(���O��ς��邱�Ƃɂ���āA��������]�̂͂��̎q�ł͂���܂���Ɛ_�l�ɒm���Ȃ��悤�ɂ���B�ːЂ̖��O�̕ύX�͕�����Ȃ����A����̌Ăі��A�L���S�ĕύX�B�w�Z���V�������O�Œʗp�������A���݂͂ǂ̂悤�ɂ��邩�m��Ȃ�)
�@
���k�܂���ɐQ��Ǝ��ʁc���l�͖k���ɐQ�����̂ŁA���������̂��Ƃ������B
�@
�����������Ɛl�����ʁc���͏��̍�������l�ɑ݂��Ă͂����Ȃ��B
�@
(����)�����e�̑�ȋ��������Ă��܂����B�e�͕��ʂɕ����Ă���ƁA�������˂Ă��܂����B�������ꂽ�����Ɠ]�|���������Ȃ��������B�����������̂ł悩�����Ƒ����̎ҒB�́A�e���Ȃ����߂Ă����B�����̎҂͋��̗�͂Ɉꂽ�B���Ƌ��͏��̍��������Ɉ���Ȃ�������Ȃ��B
|
|
���u���v 2 |


 �@
�@ |
���ɂ���ȕ���Ƃ������e���r�ԑg������炵���A���肦�Ȃ��Ƃ�������̌��b�Ȃǂ��h���}���Ɏd���Ă��ԑg������炵���B�����{���̘b���Ɗ��������ƕ��Ă���邪�A���͂��̕��ėޘb�̘b������ȂǁA�܂���������Ȃ肵�Ă��܂��B
�@
�����珑�����������ł����A���B�̎���͉Ȋw���𖾂ł��Ȃ�����������������ł��傤���A�s���Ȃ��b��s�v�c�ȏo�������F�X�Ȍ`�ԂŌ��������鎖������܂����B�����āA����������̂Ђ�ɏ悹�Ă�������Ǝ~�߂āA�q������l���M����p������܂����B���̐M����S�ɉ����Đl�Ԃ������������čs���p�⎀�A�����Ď���V�ƁA�l���Ō�̓Ɠ��̋�C�A���l�ȑ��V�V���̌����A�^���ɂ�������Ǝ��A�����Ă��܂����B���̔N��́A�I��������߂��������薘�ɐ��܂ꂽ�l�B�ŁA��̋��ƂȂ�̂łȂ����Ǝv���܂��B������Ă���l�ɂ́A��͂薀�d�s�v�c�Ȏ��B�M�����Ȃ�����������܂���B���̃V���[�Y�͌�������ł͂Ȃ��o�Y����n�߂Ă��܂��B�l�͊F�l�ԂƂ��đ����������Đ��܂�A�����܂������������Č��y�֍s���˂Ȃ�Ȃ��B�����������{�̕����K���A�V��S���|��ꂽ�S�̓`����^���Ɏ~�߂Ă���������K���ł��B
�@
��1�A�a�l������m�点��A�ʂ��������p��s��(���d�s�v�c�Ȍ���)
�@
�����̋��A�����O�ɂ���������
�@
���e�������Ȃ�E�E�E�F�B�Ɠ�l�ŋA��̓r���̎��A����̉e���}�ɔ����Ȃ��Ē����Ȃ��������ł��B2�l�łǂ������̂��낤�ƌ����Ă���ƁA�u����������ƁA�N���ɕs�K���N�����̂�������Ȃ��v���Č����̂ŁA����ĂċA�����Ƃ���A���C�ɐE��֏o�����������A�a�@�Ő����̎������������ł��B�K���������������ł����A���̎����ɂ������Ǝ�(����)�̐����������Ă������āB���҂�H��̉e������������A�Ȃ������肷��͕̂��������ǁA����������������̂˂ƁA�b�����B��x���ʂƒ���������ƌ�������Ǖ��͂܂������Ă��܂��B�Ƃ̂���(����2�N�{�����e�B�A�����ɂāA4�A50�Α㒆�S�G�k�B20�����x�̒��ŁA�����̐l�������o���y�ѕ������o���L��Ƃ��ŁA����������オ�������A�ꏊ���a�@�̂��߉��N�����̂ł����Œ��~)
�@
�����R���ۂ̕ω��B�K��҂��˂����������E�E�E�^�钆�̎��A���ւ̌˂���������������̂ŁA�v�w�ŊO�ɏo���B�N�����Ȃ���������ōl����ƈŖ�ł������͂��Ȃ̂ɁA����̂悤�ɖ��邩�����B�ӂƖ�������ƃr�b�N������قǔ������P���Ă����B�S�Ă��ꓙ���̋P���ł������B��ōl����Ƃ��̒��ň�����傫���Ĉ�w�̋P���̐����������C������B������̔������P���^���ȋ�Ɛ��͌��������Ȃ��B�u�Y�킾�˂��v�ƒ��߂Ă������u�����Ɏx�Ⴊ�����Ă͂����Ȃ��̂ŐQ�悤�v�ƕz�c�ɓ��������������������ĐQ��ꂸ�A���̘b�����Ă���ƁA��l�́w�������x�̓d�����B�����A�d�b�͈�ʉƒ�ɂ͂���قǂ̕��y�͂Ȃ������B�d��ʂł��������A���N��㖜���ŁA�n���o�g�҂��e��e�ʂ̂��߂ɂƍw���̔g���������B(���a44�N���B�v�w�̌o��)
�@
�����̑��E�E�E�@
���̋ʂ��݂��B���̋ʂ��o��ƕ������B���l���˂��J���ē����Ă����C�z���������B�����d�̂��������������B���ʔv���|�ꂽ�B�����q���Ђт������ĂȂ��̂ɁA�|�����Ɠ�Ɋ��ꂽ�B���{���������B�����̉��i���͐l�����ʂƂ����Č������B����Ȃ�(���̋C�����Ȃ�)�ɁA���[�Ɩ����ɉ�ɗ����p�������B���w�Z����A�ׂ̉ƂɏZ�ޓ������ŁA���̗ǂ������ِ��̗F�B����50�N�Ԃ�ɓd�b��������A�w�Z����̊y�����v���o�b���������(�ꐶ�����Nj������`)�b���A�Ȃ�ō����ɂƎv���Ă���ƁA����m�炳�ꂽ�B��l��q���������̂ŁA���Ⴏ��ɉ��������A�ꏏ�ɕ��������ȂǍ��X�t�Ԃ��Ă��Ƒ��X�ɐ����������������ł���B�ꐶ�̕ʂꂾ�����ƒm�����B
�@
��2�A�a�l�̎����̑O
�@
(���a21�N���A�̌���40�Δ��B�̏W30�N���A���菬�w�Z���F�B�̏W���B����͈��Q���̏��w�Z����̘b�ŁA�����ł͗L��܂��A�����ɂ������̎p�ŏ����Ă���悤�ɁA���ނ̘b����������܂�)
�@
�����O�̎p���Ĉ�ԑ����̂��A����ɂȂ�ł����B�����������ŁA���w�Z����A�w�Z�A��ɕ������b�ł��B���́A��قǕ|�������̂��A�u�|���˂��v�ƌ����Ɓu�߂����b�Ȃ̂�v�ƒN�����������̂��o���Ă��܂��B����ōŊ����݂Ƃ鎞��ŁA���̂悤�Ȏ����O�ɂ����錻�ۂ��������̌�������A�a�@�ֈ�t���Ăтɍs���A�N���������ɑ����čs���A�ՏI���}�����悤�Ɏv���܂��B
�@
�u��(����)�̂��ꂳ�A���������͂���������Ǝv�����̂ŁA��������̂��n������̏��֑����������ł��B���n������̑O�ɍs���ƁA�̒��̗܂��h�H�[�[���Ĉ�C�ɏo�������ł��B���ʑO�ɂ́A���n������̊�ɂȂ�ƌ����邪�A���n������̏��֍s������A���n������Ɠ�����ł��ꂳ����}���Ă���āA�u�A�g����낵�イ�ɂȁv���Č����������ł��B���͕������Ȃ��������ǁA�S�̐����Č����̂��A���⎨�ŕ�������̂ƈ���āA�̒�(���炾���イ)�ɂӂ킟�[��Ƃ��Ă��݂ǂ���̂Ȃ��A�������������ł��B����ĂāA�����ċA������A��������������Ƃ��낾�����B�ƌ����Ӗ��̂��b���܂����B���낵���āA�����͂�����ƕ������ڂ��Ă��܂��B
|
|
���u���v 3 |


 �@
�@ |
��1�A���̊ԍ�(���̂܂���)
�@
���炪���l�ɂȂ�B
�@
���炪�c���B
�@
���炪�ǂ������Ȃ�B
�@
���苾�ƌ����āA��̕������Ɍ����ĂĊ������B
�@
���ڂ������Ȃ��Ȃ�B�ڂ����Ȃ��Ȃ�B
�@
�����ڂɖ������蔒�������傫���Ȃ�B
�@
���̂ǂ������B����~������B
�@
���������Ǐo�Ă���ƁA�N�������Ƃ��Ȃ��u�ǂ��l�������v�u���b����|���ĉ������Ă����鎖���o���Ȃ������v���A�ڂ���A�ڂ���Ƙb���o�Ă���ƁA�₪�āA�ڂ̗͂��Ȃ��Ȃ�ƁA���ĂтƂ����āA�j�̐l�������̏�ɂ������āA���ɍ�(���ɂ���)�̐l�̖��O��吺�ŌĂԂ̂������ł����A�u�̂́A���̂悤�Ȃ��Ƃ������炵���v�Ƃ������ƂŁA�c�O�Ȃ��炻�������V����s�����l�A�����l�ɂ́A�o����Ă��܂���B���̎���́A�����ł͂���܂��A��������Ăт̂ЂƂłȂ����Ǝv���܂��B
�@
(1)����
�@
�̏W�n�ƍ̏W�N�B�����Q�����쒬�B���a33�N�A34�N���A��F�a���Z�����F�B�B�����ł̍��Ăт̕��K�́A��̎���͂ɂ��������p�̂ЂƂ̂悤�ł����A�a�l���������A���������ɒ|�Â֕Ă�����āA�w���ꂪ�Ẳ��₼�[�x�ƌ����āA�a�l�̂��ƂŕĂ�U�镗�K�������������ł��B
�@
(2)�ǂ�Ȏ��ɍ��Ăт����邩
�@
�������̐��̑O�Ŏ��̒��O�ɂȂ�ƍ���т������ɏオ���Ė��O���Ă肵���ƌ����B
�@
���̂͏o�Y�ŁA�Y���̐l�����������̂ŁA��Y�ŋC���������Y�w�B
�@
���q�������ɂ����ɂȂ������B
�@
���傯�������ċC�������B���������ɂȂ������B
�@
���q������˂₨����A�r�ɗ����ċC�����������́A�ߏ��̐l�����܂��āA���O���Ăё������B�����ł��B
�@
(3)���ĂтŐ����Ԃ����l�@
�̏W�n�F��s�y�����ɂ���s���̋߂��̌䕗�C������k����B�̏W���F����22�N10��31���B�N��a9�N���܂�
�@
�m����n
�O�r�̐�͕��ł����B����11���Ԃ̎�p�������̂ł��B�������Ő��āA�S�����o���āA�����Ƃ���������̂ł��B�����̃P���C�h��(���[�Ɠ��[�̊�)�������Ƃł��B���̎�p���ɁA���́u�O�r�̐�v�Ɓu���̐��v�����܂����B
�@
�O�r�̐삪����܂��ĂˁA���̌��������Ԕ��ɂȂ��Ă��܂����B���傤�ǃR�X���X���̂悤�ł����B���͎O�r�̐�̒��ɂ��܂����B�����ǂ�ǂ�A�ǂ�ǂ�ӂ��Ă��āA���̐����܂��₽���̂ł��B�����X�̂悤�ɗ₽���̂ł��B������������̐����X�̂悤�ɗ₽���̂ł��B���̂߂��������A��������ǂ�ǂ�₽���A�₽���A�����������Ă���̂ł��B���́A�����A���̐�����܂ŗ����玀�ʂ̂��Ȃ����āA�ǂ����Ŋ����Ă��܂������A���������o���܂���B����Ɓu�Ȃɂ��Ă���̂�A�������ɂ����Łv���Ă��������������畷������̂ł��B
�@
�܂��͐^���Âł��B���������������āA�������Ă����ƃ��C���C�Ɛ�����������̂ł��B�����ĊF�������̕��̏��܂ŁA�A��čs���A�삩�炠���Ă���܂����B
�@
���͎O�r�̐�Ƃ́A�삾���琅������Ă����Ǝv���Ă��܂������A���ł����B�����Ŏ��́A�ӂ����炠�����āA�����炠�����܂����B����ƁA�₽�����ŁA�����X�̂悤�ɂȂ��Ă����̂��g�����Ȃ�܂����B
�@
�ڂ��J���ƁA���͐́A���a33�N���璆�w�Z�̐��w�̐搶�����Ă��܂��āA���k�B���A�����������ƁA�Ăё����Ă���Ă����̂ł��B���̎�p�̓��̈�T�ԑO�ɁA�җ�̓����������Ƃ����āA�����Ă�ł���Ă��܂����B���̎q�B���F�ŗ��Ă���Ă����̂ł��B
�@
���ꂩ�����5�N�����܂����B���͂������ĉ���֗��Ă��܂����A�R�o�������قǂɌ��C�Ȃ�܂����B
�@
��2�A�����̐�(�܂��݂̂�)�D���ɐ�
�@
�����̐��Ƃ́A��ʂɌ����u���ɐ��v�ł��B���ɐ��́A�ߐe�҂̍Ō�̕ʂ�ł��B��ʂɂ́A���e�ƌZ��o���̂悤�ɂȂ��悭���A���O�ɂ݂͌��ɁA�u���ɐ��͎���Ă�邩��ȁv���Ƙb�������Ă������̎҂Ȃǂ��s���܂��B
�@
(1)�����邩
�@
���̒���a�l���A�������݂����ƌ����B����Łu�����A�Ǝv���ĕa�l��������g���Ă������q�ɂ݂������Ď����Ă����ƁA�����������̎����ƂȂ�B���̂����ԍہB���̑��ŁA�O�������J���āA�ڂ�������������Ǝ����K�ꂽ�Ƃ��āA���ɐ��̗p�ӂƂȂ����B
�@
(2)�N��
�@
�A�ꍇ��(���҂��v�Ȃ��)���j���ꂩ�猌�̔Z�����ɐg��������B���̂��Ɛ��O�A���ʂɏ��������Đ����Ă����l�ŁA���ɐ����Ƃ�ƁA���݂��ɘb���Ă���Ɛ��O�ɐg���̎҂ɘb���Ă����l������B�ՏI�ɗ���������l�����̔Z���l����A���̔Z���ЂƂւƂ���B
�@
(3)�ǂ̂悤��
�@
����g�p�����䒃�q�ɉƂ̂��邶���A�Վ�肪��������B���ꔢ�ɒE���Ȃ�����Ŕ��ɂ܂��A���ؖȎ��ł��邭��Ƃ����āA�O��Z���B�c�������͌��֖߂��B
�@
(4)���̑�
�@
�����������ƁA���҂��d������̂ŁA�̂��_�炩�������ɍ��ǂ֓����Ă����Ȃ��Ɠ���Ȃ��Ȃ�̂ŁA���̕ӂ肩��V�炪�Ă��ς��Ǝ蕪�����Ă����߂��B
|
|
���푈�Ǝ� |


 �@
�@ |
�u���v�������Ă��āA�ǂ����S�̒��ŁA�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��������ɂ����āA�͂Ȃ�܂���ł����B���ɂ́A���͕̂ʂƂ��āA���܂����ŏ����Ă���̂́A����ł́u���̋V��v�ł��B���ɂ́A����ł̎��A�a�@�ł̎��A���̎��̎O�ɑ�ʂ���܂����A�V��ł͂���܂��A��������B���Y��Ă͂����Ȃ��A�u�푈�Ǝ��v������܂��B
�@
����u�����̐l�X�̈ꐶ�v�������n�߂�94��ɂȂ�܂��B���{�l��9��4���D�݂܂���B
�@
9�͋�ɒʂ��A12��29���ɐ����̖݂����Ȃ��n��̓`����A4�͎��ɒʂ��A���ł������̒��ԏ��4�Ԃ����ԂɂȂ��Ă��鏊���A���鎖������܂��B94�́u�����イ���v�Ƃ��ǂގ����o��10�͏d�ɒʂ��A�]��D�̂܂�Ȃ������ł����B���������Ӗ����ӂ��߂āA����̂ݓ��ʂɋV��ł͂���܂��A���Ɏd���Ă������̂������������ɂ��܂����B
�@
�������Ȃ���A�푈�Ǝ��ɂ��ẮA�V��ł͂Ȃ����ƁA����B���펞���̎��́u��܂ł����Ă����v�u�v���o�������Ȃ��v�ƌ����l�B�̏o�����A���d�ɍŏI�̏͂Ŏ���֎p���̗\������Ă��܂��B����͖��C�̎���ł��鏬�w���A���w������̋L���̌ĂыN�����Ă��炢�A�̌��������܂����B�Ȃ��A�����̐l����̎���͍T���A�ߍx�n�ɂ��܂����B
�@
���āA���̎���͐��܂ꂽ�N�1�ˈႤ�ƁA���̎��̋L����̌��́A�M�����Ȃ����̈Ⴂ������܂����B���a17�N4�����܂�̎��̕v�́A��P�ŏ��a19�N���܂�̒��w���낤��(�w������)�������B���a18�N1�����܂�̎��́A�S���o���Ă��Ȃ����A�푈���I����Ă������A����m�点��T�C�������Ђт��ƁA������ƌ����ċ����A�o�����̓x�ɔ��n�ł������m�s��(����������)���A��čs�����ƁA�܂��̐l���b���Ă��܂����B���̂悤�ɁA���̔N��̐l�B�͐��̕����Ƌ��ɂ߂܂��邵���A�����܂����B����70���炢�B
�@
�������P�Ǝ���
�@
������1 (����80�Α�O�������B�̏W������23�N5���B�̏W�n�����̗�)
�@
������̕��ł��B���w�Z�l�N���ł����B��P�ł˂��A��ł��B�^���Âȋ�ł����B���̋܂��Y��Ɍ���P���̂ł��B���X�Ƃ܂��A�{���ɂ��ꂢ�ł����B�Ƃ��낪��Œm�����̂ł����A��P���ė����Ă�����͔��e�������̂ł��B���߂Ă̑����P�̌��ł��B�����钩�A���͍��̌��̐��̂�m�����̂ł����B���B�͐�������ĕ����čs���܂����B���̂Ƃ����̖ڂɉf�����̂́A��������Ɖ���������l�̎��̂ł����B��̋߂�������-�Ǝ��́A���́A���̂������̂ł��B���ꂩ��A��ɂ͐����Ȃ����̂���������Ă��܂����B��̐��́A�Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ��A���̂Ő��������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��B���ꂩ��A���̂́A�d�Ȃ�悤�ɉ�������Ă��܂����B��̒��Ő܂�d�Ȃ����l�����̂ł����B���͐�̐��Ɏ�����Ă��܂��A��͂����ɂȂ��Ă����Ƃ����炱����ŕ������Ƃ��������܂����B�₽�����̐삪�A�����̐�ɂȂ��Ă��āA���̐삪���̂̐�ɂȂ��Ă��܂����B�M����Ȃ����ł��B�����ł͂��肦�Ȃ����ł����A���ꂪ�푈�ƌ������̂ł����˂��B�|�����A�����A�����������A���������߂����̒��̏o�����Ƃł��B�^���Â̒��ɋP�����́A�����o���Ă��܂��B
�@
�����Ǝ��̒J�ԂŐ����c��������
�@
������1 (���a�̏I��荠�B������َ�H�|�����ɂ�)
�@
���w�Z�̎��A�H�ꓮ����(�X�m�{�ƌ���ꂽ�Ǝv��)���P�ɂ����܂����B�搶�������Ȃ����ƌ����ĊF���Ƃ֏o�܂������A���͑����s���R�Ȃ̂ŏo�܂���ł����B�Â��ɂȂ����̂ōH����o�ăr�b�N�����܂����B��R�̐l������ł��܂����B���邾���c���Ă��܂����B���͑S���Ă��쌴�ł����B���͈ꐶ�����Ă��쌴�̒�������ċA��܂����B���Ǝ��͎���d�B���Â��v���܂����B
�@
������2 �B��ꏊ���Ƃ肠�����Ă��������т�
�@
���̎���3��4���A���Ɛ�̘a�̎R�Ŏ��̖����̏W�������̂ł��B(�̏W������22�N8��)
�@
�a�̎R��Ƃ��̋߂��ł̏o�����ł��B�a�̎R�ɂ͏Z�F������܂����̂ŁA�A�����J�́A�a�̎R���ڈ�ɂ��āA����Ă��܂����B��̎���͏Ă��쌴�ŁA�g���̂Ȃ��l�͎R�֓����āA�X�Ől�Ɍ�����Ȃ��悤�ȂƂ���։B��悤�ƁA�T���܂����B���������ꏊ�������ăz�b�Ƃ��Ă���ƁA���������āu�ǂ��v�ƌ����ĕ�������֓n���˂Ȃ�Ȃ������B�悭�������т����̂��Ǝv���܂��B
�@
������3 �a�̎R��̌@��Ǝ���
�@
�ォ�玟�X�Ɣ��e���~��悤�ɗ����������ł��B����ŁA���x�ɔ�э������ł��B��э���ŁA�����ꂵ���̂Ŋ��������ƁA����͎��̂ł����ς������������ł��B����Ƃ܂��A���e�������悤�ɗ����Ă��āA�ꂵ���̂Ŋ��������ƁA�܂�����͎��̂̌J��Ԃ��Ő������т������ł��B�l�Ԃ̓M���M���ɂȂ�ƁA�|���ƌ�������͏����邵�A�����悤�ɗ����Ă��锚�e�͐Ԃ����ꂢ�ȉɌ������B���̂����̎��͕��̂ł����Ȃ������B
�@
������4 �������͂������Đ����̂т�
�@
��P�ɂȂ��āA����w���ɂ�������Ăɂ����B�R�̖̉��֓�������肾��������ǁA�R�֒����O�ɔ��e�������Ă����B�����������āA�g����荂�����������̂Őg��n�ׂ��ɂ��Ĕ����������āA���e�̉J����K���ł�����A�B�ꂵ�ē����ď��������B�����ł��B
�@
������5�@�l�Ԃ��āA���̋C�ɂȂ�ΐ������т���̂�
�@
�����s���̂����C������ɂč̏W�B80�Α�A4�l�̎G�k(�̏W������23�N6��29��)
�@
�I���A���w�Z�̎��̔����o���͂��������B���ɕĂ���������āA���������������B�d�ԂŁA�ł̎����܂肪����ƁA������@�肾���āA���̉w�ō~��ĂЂ�����B�K��������B�����Ђ炢�������B�����̋z��������E���āA������ق����A�V�������Ŋ����Ĕ������B���̍��͂Ȃ�ł����ꂽ�B������̂ɕK���������B�悭�����̂т����̂�B
|
|
�����s�ƒm�点�l |


 �@
�@ |
��1�A���s
�@
�����̐����I���ƁA���s�֒m�点�ɑ���܂��B���s�Ƃ́u�u�v�̂悤�ȑg�D�ŁA���s�ɂ���đ��V���S�Ă��Ƃ�͂��炤�g�D������܂����B���̑g�D�͂������O������m��Ȃ��l�������Ȃ�܂������A���a40�N��͎c���Ă���܂����B
�@
�����ֈڏZ���āA���s�g�D��m�炸�ߗׂ�����Ƃ���`���֍s���āA�u���s�Œv���܂��̂Łv�Ƃ��f��ɂȂ�A�˂�߂���č��̎��Ԃ������Ă��������`���Ɍ˘f���p������܂����B
�@
���a50�N��ɓ���ƁA���������̓y�n�ő�X���������l�����łȂ��A�O���̐l�B���ǂ�ǂ�ӂ���̒��ŁA���V���A���s�ƒ���̐��b�Ŏ�������قōs���A����ōs�����K�����炢�ł����܂����B
�@
���s�g�D���C���ƂȂ�ɏ]���āA������s�̂悤�Ȍ`�Ŋ֗^�����悤�ɂȂ�A�₪�āA���s�̕���ɂ�荡�܂œ��s������Ă����V����Ɠ��e�A�����ɂȂ��`�ֈڍs���A�ǂ�ǂ�V���A�V�炪�ȑf������邱�Ƃɂ���āA���V������ƌĂ��E�Ƃ̂Ƃ���֑��V�̎�`�������肢����`���ƂȂ����悤�ł��B
�@
������������̊֗^���ǂ�ǂ�C���ƂȂ��Ă����A����10�N�㍠�ɂȂ�Ƒ��V�����S�Ă����v�炤�`�����L����A���݂̌`�ԂւƐi�悤�Ɏv���܂��B
�@
������s�̐��ނ́A�O������̐l�X�̈ڏZ�����ł͂Ȃ��A����̗���A�l�����A��㐶�܂�̐l�B����w�̍��ɂ���鎞���ɂȂ������Ȃǂ�����v���͂���܂����A�V���A�V�炪�傫���ς�������ɂ��֗^���Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@
���V�̕��@��(��1)�����������A�Ă��ꂪ�����A�s��܂̂���ւ̂�����肪�����A����n��(����)�̕�ɂ�����邱�Ƃ�����A�u�̂悤�ȑg�D�̕K�v���������Ȃ������Ƃɂ��傫���e�����Ă���Ǝ��͍l���܂��B
�@
(��1) ���a30�N�O��ӂ�܂ł́A�����̕��K�������ɂ͎c���Ă��鏊������Ȃ�̌����Ŏc���Ă��܂����B�����Ƃ́A���`�̊��ł����B�����`�̊��ŐQ�������̂ł͂Ȃ��A�̂�܂�悤�ɍ��艱�̊��ɑ̂������悤�ɍ���܂��B�����͍s���łȂ��Ă��A��̒��ɏĂ��ꂪ����܂������A�y�̒��ɖ��߂���@���c���Ă����悤�ł��B
�@
��2�A���点�̐l�̌Ăі��ƍs��
�@
�w���点�x�w�Ă���������x�Ƃ́A�����̐l�B���畷�������t�ŁA�w��ł͂ǂ̂悤�ɕ\�L����Ă���̂��m��܂��A���S��e�ʉ��҂͂������ł����A�ߏ��A���A���s�Ȃǂ֎蕪�����Ēm�点�đ���l�̎����A�u���点�v�u���点����v�u���点�l�v�u�Ă���������v�Ƃ����悤�Ȍ������Ŏ��͕����Ă���܂����A���̂悤�Ȏ��̌��t�͓���̂ŏ����ł́u����v�ƌ��߂鎖�́A���ɂ͂ł��܂���B
�@
���ɂ��u�g���v�Ƃ����l�����܂����̂ŁA��������Ə����̓���P��ł͂Ȃ��A�s�������̂܂܂ɕ\���������R�����I�ɁA�g�p����Ă��錾�ꂪ�A�����̓���p��Ƃ��āA�����̐l�X���g�p���Ă��錾�t�ɂȂ����Ǝv���܂��B
�@
���点�̐l�̍s��
�@
(�̏W�n�F�����s����������قɂĎG�k��������Ƒ��菑���m�[�g�ȂǁB���a�̏I��荠���畽���̂͂��ߍ��������߂��m�[�g���)
�@
���点����͉��l���B���̉Ƃɏ��������l���ŁA�m�点�ɑ���܂��B���a2�A30�N��͂܂�����قǓd�b�����B���Ă��Ȃ������̂ŁA�����͓d��A�d�b�A���ꂩ��2�A3���Ԓ��x�Ȃ�����čs���܂����B��̂Ƃ����A��̓��s��h�����ߕK��2�l�ōs���܂����B
�@
��ʂł́A���s�̂ЂƂ������Ŏ��҂�������Ă��܂����̂ŁA���S���m�F�����Ɖ��l���̂��点��������肢���܂��B���点�̐l���͂��̉Ƃ̐e�ʉ��҂�A���点��Ƃ̋����A�l���ȂǂŌ��߂��܂��B���҂ɉ��̉����l�A���O�e���݂̏��Ȃ��l���s�����悤�ł��B�ǂ̂悤�ɒm�点�邩�Ɛ\���܂��ƁA
�@
���܂����s�ɒm�点�܂��B���s�͂����ɏW�܂莀�҂ɂ܂��W�̎�`���ɂ�����܂��B�ׂɒm�点�܂��B�ׂ̐l�͗בg��u�̑g�D�̐l�B���œ`���܂��B���ׂ̐l���܂��̂ł͂Ȃ����悤�Ɍ��œ`���čs���܂��B�`����l�́A�K�����ւ���o�܂���B��������ł���A���i�o���肵�Ȃ��،˂Ȃǂ���o�܂��B�����͎g�p���܂���B�����͕߂Ă��������ł��B�ׂ֍s�����x�ł��A�������ނƒ������ďo�܂��B��ɂƂ����Ȃ����߂������ł��B
�@
�����֒m�点�܂��B���ւ͑r�傪�s���܂����A���̎��Ɏ��l�Ɉ����삪���Ȃǂ��Ă͂����Ȃ��̂ŋ}���ł����܂��B��������t���Ȃ����߂ɓ����ʂ����K���X�̃R�b�v�������r�Ȃǂɐ������āA���҂̖����ɒu���ƌ����l�����܂����B���Ɏ��l�̗삪�r��ƈꏏ�ɂ��čs���Ă��肢����̂��ƌ����l�����܂����B����Ɏז�����Ȃ��悤�ɁA��������͂����p�ӂ��Čo�������Ɏ��҂̏��֗��ĉ��������Ƃ̎��ł����B
�@
���{�Ƃ�g���ɁA�}���Œm�点�܂��B�ʖ�͕��i���ŋ삯���܂��B�r���ōs���Ǝ����܂��Ă��܂����Ɨp�ӂ����Ă������ɂȂ邩��ł��B�ŋ߂͒ʖ���r�����ʗ�ɂȂ�܂����B
�@
�����点�̐l�́A�K��2�l�ōs�������ł��B���ʂ̐����Ɣ��̍s���ōs���܂��B�Ƃ��o�鎞�́A�g��Ȃ��o����A��������o�āA�������ނƕK���ɓ����t���A���点�̉Ƃ֒����ƁA�Ƃ̊O����`���Č��֓��ɂ͓��炸�A�O����m�点�A�A��̈��A�͌��킳�Ȃ��悤�ł��B�m�点�����Ƃ́u�Ђ���v�������Ȃ��悤�ɁA�H�����o���悤�ł��B
|
|
��������[���܂�(1)
|


 �@
�@ |
��1�A�����̕�̓��F
�@
�����̕�̓��F�́A��ɂ͕K���Z�n������ƏĂ��ꂪ����܂����B
�@
�Â�������8�A90��̏����B�̉��炷��ƁA���}���n��������̐��ʂɂ����������āA�Z�n�����������̔��^�̒��ɘZ�̕���ł���ɂ�������Ⴂ�܂����B�����āA����ɂ́A�l�Ă���ƌĂ��A�Ă��ꂪ����܂����B����(����23�N)�Ă���ŁA���҂��Ă��Ă���̂�A�n��̕�Ƃ������(�ЂƂ͂�)�̓��ƕ����Ă��܂�����(���f�������Ă͂����Ȃ��̂ŏꏊ���͏Ȃ��܂��B)���͂ǂ��Ƃ����s�̕���(�Ђ�́��n��)�ŏĂ��Ă�����Ă���ƕ����Ă��܂����A����̎��ł�����A���Ȃ�(�Nj�����)��������̂ł���܂���̂ŁA�܂������Ă�����A����ɂ�(��邵��)�ł��B�Ƃ̉ł����B
�@
�܂��A�s���Ƃ����āA�����ɂ͍s�������ɂȂ������悪���悠��܂��B���̕����̓C���^�[�l�b�g�u�����̖��b�v�ʼn͓��s���Ə����̍s���̏ꏊ��s��̂���Ɋւ��鎖�ŏ����̐l�B�ƍs���̂�������20�N�x����21�N�x�ɂ����Ė��b��92�b�����95�b4��A�����A�����ɏ����Ă���܂��̂ŁA�����ł͏ȗ��������܂��B
�@
�܂��A����̂��Ƃł��̂ŁA���w�Ŗ��f��s�ސT�͖����ƐM���܂����A���������Ă͂����Ȃ��̂ŁA�ꏊ�͐\���܂��A�����Ɩ��ӎ��ɒʉ߂��Ă���ꏊ�ɂ����������F�ƁA���������A�Ȃ����̂��݂��Ă��̂ɁA�Ȃ�ŁA���̂悤�Ȃ���ނ�����̉��˂Ȃ̂�����ƁA�s�R�Ɏv�����L���̂���l������������̂łȂ����Ǝv���܂��B
�@
���āA�b�͕ς��܂����A����80�Α�㔼����90�Α�̕��X�𒆐S�ɑ��V�̍̏W�m�F�����Ă��܂����A�����Ⴍ�đ���̐S����莟��֎p���A�c���˂ƈӋC���ݍ̏W�����Ă�������A���̕��B�̔N��́A4�A50�Α�̐l���ō��̓���������̐l�B�Łu����Ȃ��ƕ������̂łȂ��v�Ǝ����̍̏W�ł����B���������݁A�����l����̍̏W�Łu���̍��͗אl(�ƂȂ�т�)�����Ă̎����������B��������������Ă̐����������v�Ɩڂ��ׂ߂Č���ĉ������܂����B���͐푈�����{�����̓��ʂ��������莝���Ă������Ǝv���Ă��܂������A�����ł͂Ȃ����ƂɍŋߋC�����܂����B�����Ɂu�����J����(��)�₽���v�̖��b������܂����A���̔N��ɂȂ�Ɩ����������J��(IC�J���H)�ɂȂ�܂����B�����ĎႢ���̂悤�ȁu�c���˂Ȃ�Ȃ��v�ӋC���݂����AIC�J���̒��ł����{�����̐S�́A������Č���������A�`�����ς���Ă��A�Ȃ����ƐM����悤�ɂȂ�܂����B
�@
(��)�₽���E�E�E��x����̂Ƃb�Ƃ͏����Ⴂ�܂����A��B�ł́u��������ނ���v�B�l���ł́u�Ƃ��ۘb�v�ɗނ��A�������I�[�o�[�ɘb�������ċ�����b������l���u�₽���v�u�₽�����v�ƌ����܂��B���b�ɑ����܂����A������˂��Ă��܂��B�C���^�[�l�b�g�́u�����̖��b�v�ł����܂��B���R���當���J���̍��A�����J�֓n�����j�̘b���B
�@
��2�A���V�̏����\�\������[���܂�
�@
�w���x�̔��f�������ƁA���s(�ǂ����傤)�ƌĂ��g�D���A�葁�������Đi�s���čs���܂����B���̑g�D�́A�O��������Ă��܂����A�y�n�ɐ������c�B���������K�̒��ł���グ���בg�I�ȑ����̌ݏ���g���Ԃ̂悤�Ȑl�B�ł��B�e�ʂ̎ҒB�́A�r���̗p�ӂł��ѐ����⎆�\��ȂǕ����̗p�ӂɂ�����܂����A���s�����Ŏ葁���ʂ̕����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��d��������܂����B�g�̒��ׂƔ[���ł��B���ꂪ�I���ƒʖ�ƂȂ�܂��B
�@
�́A�̂̂��Ƃł����A�����ɂ͑����̝|(������)������܂����B�|�ɂ��ނ����҂͑������ƌ����Ă��̉Ƃ͑��������̂̒�����j�Q����Ă�����̌����Ȃ��|������܂������A�Ύ��Ƒ��V�͂��̝|���O����܂����B�l�̎��Ƃ́A�����v���܂��ɂ́A�u�l�Ԃ͒N�ł��ō��ɑ��Ԃׂ����݂ł��邩��A�l�̎��͑����������ĒN�������l�ɍs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������_�������ɂ������đ��Ɍf�����Ă����̂łȂ����ƍ̏W���Ďv���܂����B
�@
�����������_���A�����̐�����ʖ�܂ł̑����̐l�X�̎葁�������̒��ɂ���܂������A�ʖ�܂ł̎葁���d�����o���Ă͂��߂đ����̉łł����āA�o���Ȃ����͎̂��i���Ȃ��Ƃ��ꂽ�S�������ɂ͂���قǂł��B
�@
�����s���������̒m�蕛��ƌĂ�鏗���ɂ��Ɓ���O�S���^�܂������݂��悤����^����ȉłȂ炢��ǂ���(�������Ă���)�^���ʂ����Ȃ��(�A����A��Ȃ���)���m���^��S���B�����ĉ������������̘b�ł́A���̑��V�̎�`���ŁA�܂������݂��D�����̏o���Ȃ��łł́A���̑��V�̎��͖𗧂����ŁA���f�������A�p�������������B����ȉł���ł͂��߂��B�o�����ė��Ȃ����B�Ƃ����Ӗ��������ł��B
�@
���Ȃ݂Ɏ��҂̗������̒����́A��`���̐l���ɂ����܂����A��l�ȏ�ŖD���܂��B���̂��炵�ؖȂ��ꔽ�n����A�Ă�łɖD���n�߂܂��B�N�����w�D����D���n�߂�ƕʂ̐l�͂����݂�D���A��������A�܂�t����B�O�g�ƌ��g����Ƒ���t���A�܉��A�������A�ŏo���オ��܂��B���҂̒����͖D�����Ԃ����ɂȂ�悤�ɁA�蕪�����Ăʂ��Ă����܂��B�D���ꏊ����������Ȃ��悤�ɑ���̑��x�Ɍ����ɂ��čs���܂��B�펯�Ƃ��đ����҂����������܂���B
�@
���ꂪ�o����̂́A�����w�Z����A��ƕ��d�Ɏ���A�����ɒu���ꂽ�^�j�z�ŖD�����K�������Ă����e���^�������ł��B�D�����D���Ȃ����x�ŁH�Ǝv���܂����A���������̂̒��ŋ��ɐ����Ă����鎖�A�q���Y�݁A�q����Ă�\��(���C�ňߐH�����āA�q���̕a�C������ɑΉ��o���鎖)�͑�Ȏ��ł����B
|
|
��������[���܂�(2)
|


 �@
�@ |
���[���̂��ߎ��҂ւ��鎖
�@
������[���܂œ��s�̐l��ߏ��̐l�ɂ���Ď��̂悤�ȍs�����A�Ă��ς��Ƃ����Ȃ��܂����B���ꂪ�ǂ̂悤�ɂ���ƌ������܂�͂���܂��A���ꂼ��Ɏ����Ɍ�������������`���܂��B�܂��A���ꂩ�珇�ԂɂƂ������܂�͂���܂��AA������ɂ́AB���o���������Ă��Ȃ��ƁAA�����鎖���o���Ȃ���������܂��B���邱�Ƃ͌��܂��Ă���̂ŁA�����ɏo���鎖���u���I���ꂪ�܂����ĂȂ��v�ƋC���������A�u���I����ł͐l�肪����Ȃ��v�������������A������s���A�܂������֍s���Ď�`�����@�ł��B�Ⴆ�Ύ��ɑ����𒅂���ɂ́A������D���l�A���܂�D���l�A�ѕR��D���l�A���́���D���l�A�Ƃ��ꂼ��A�����B�����R�̗l�ɏ��������̂ł��A��l�ȏ�ŖD���܂��B���̂Ƃ��A�������Ȃ̂́A���Ɍ��іڂ�����܂���B�����ɂȂ��5�A6�l�ŖD���Ă����܂��B�ǂ����āA���̑O�ɗp�ӂ��Ă��Ȃ��̂��ƕ�����܂����A�p�ӂ���ƌ������́A����҂��Ă��鎖�ɂȂ邩��ł��B���l�ɍ��͂��ʖ�֑r���ōs����܂����A����������ŁA���i���ŋ삯�����ƌ����`�A�S���Ȃ�ł��Ȃ��A����Ȃɑ������y�֗����ȂǁA�v�������ʎ��ł����B�Ƃ�����������݂̋C�����ŁA�r���ł͍s���܂���ł����B
�@
���āA���̒������D���オ��O�Ɏ��҂́u������߁v���o���Ă���K�v������܂��B���҂̑̂s�̐l���ʍ��~�ɘA��čs���A�̂����ꂢ�ɐ��߂܂��B���̎��A�������Ȃ̂͂��炢�A�ɐ������ē��𑫂��܂��B������w�t����(�������݂�)�x�Ƃ����܂��B
�@
�̂𐴂߂���A�̂̌���S���E���Ȃōǂ��܂��B(���A���A�`�A���A����A�ڂ��J���Ă���ƕ������܂��B�d�����ĊJ�����܂܂̎��́A�E���Ȃ�u���Ă��̏��ڂ̕��ɐ����z���A�����̌��іڂȂ��Ŋ����܂��B���̎�2�A3���̐l���u���m���߁v�ŗ�����܂��B�o���m���߁p�Ƃ́A�\�͂����͂��ĂȂ����A�ł����܂��ꂽ�A�`�Ղ͂Ȃ����ׂ܂��B�������Ē������������܂��B
�@
���[��
�@
�[���́A�����͍����ł����B�c���̒j��(����23�N60��)�̘b�ɂ��ƁA���a27�N���A����܂肽����ŁA�������č����ɔ[�߂��A�����o���Ă���B�Ƃ̎��ł����B
�@
(���a���ォ��̒m�l�ɂĐ܁X�ɕ������߃m�[�g���B����19�N�L�B�̏W�n�A�b�Ҏ���B��c�ݏZ�B����23�N����80�Ό㔼�B�j���B���̖��N�N�ɂĖʉ20�N�O���炵��)
�@
�[���̎��͐g���̎҂͗��ꂽ���֍s�����āA���s�̒j�����ł����߂��B�����������̂ŁA����Ŏ��Ԃ��o�ƍd�����č����Ɏ��܂�Ȃ��̂ŁA�ǂ����Ă������|�L���A�|�L���Ƃ����܂�鉹������B���̎p��A�����̂͐g���̎҂ɂ͂炢���Ȃ̂ŁA���ꂽ���ōs���������ł��B�Q���ɂȂ����̂́A���s�̑g�D�����ꂽ������ŁA���a30�N�̏I��肩��40�N�ɂȂ�܂����Ȃ��B��ŏĂ����A���̕���ɘA��čs���āA�Ă��悤�ɂȂ��Ă���ł��B�Ǝ҂������Ď�`���悤�ɂȂ��Ă���ł��B���ɂ��������Ǝ҂�����܂����B��ɂ͉����ł��Ă��ꂪ����܂�������A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��������肩��ł���B��Ƀ{�[���A�{�[�����č����Ă��Ă͂�����ƌ������A���˂�̂ł����˂��A���̉������Ƃ������Ȃ��̂ł���B����ɏL����������������܂������炻�̕ӂ肩��Ǝv���܂��B
�@
���ꂱ��G�k(�����B���[���̏j�V�A�s�j�V�܂̎g����)�E�E�E�m���Ă���悤�Œm��Ȃ��펯�E�E�E
�@
(�̏W�n�����̗��̏����ȋi���X�Ŏl�l���G�k�B����23�N9��9���B)
�@
���ʖ�̓��ɂ͉����͂����a�����܂��璸���Ă��܂����B
�@
�����͂��Ă�����āA��ʔv�ɂ������Ă�����āA���ʖ�̂��č������Ă��炤�B
�@
���O�́A��(A����)�͕v�����S�������͂ˁA�ߋ����ɂ͏����Ă���������ǁA�ʔv�ł͏����Ă�����ĂȂ��B�v�w�ʔv�ɂ��Ă��炢�����Ǝv���āB
�@
��l�̉����͂ˁA�a���l���u�ǂ�Ȑl������v�ƕ����͂����̂ŁA�u�������낢�A�y�����l�������v�ƌ��������̂�����w�ߋg�c�x�Ɠ���ĉ��������B
�@
��(T����)�͉ߋ������ʔv�������Ă�������B���̕v�͌܌��ɖS���Ȃ����̂ŁA�w�H(����)�x�Ƃ�����������Ă����������́B������A�������炭�Ɓu�����A��l�̖������E�E�E�v���āA��������Ȃ�
�@
(A����)��ʔv��49���܂Ŕ���(���炫)�ŁA���̌�͐F�����ėǂ����Ęa���������ĉ��������B
�@
�������I��ʔv���Ĕ��Ǝv���Ă����B
�@
����A���d�̏j�V�A�s�j�V�ɂ���
�@
�����Ă��鎞�ɕ����鎞�́A�j�V�܁B
�@
���Ƃ��ɁA�[���ŕ����鎞�́A�߂��݂̕s�j�V�̑܂Ŏ����čs���̂����āB
�@
���d���n�߂Ďg�����́A�Ԃ����[�\�N���Ă�̂����āB���̎��A�g���̂��܂イ�����Ȃ���B�ւ��A����Ȃ������ł��ւA���Ȃ��A���Ă���ׂ��Ă��āA�����Ă����Ȃ��ƂȂ��B��������(���_�I��)�����Ȃ������A�n��Ƃ̈�̊�������������Ȃ��B
�@
���G�k�K���K������
�@
��ʔv�������͌䕧�d�̒��Ƃ͌���Ȃ�����A�i�D�悭�F�X�Ȏp�Œu���Ă͂�l�����邩��˂��B�e���r�̓��{�̏펯�A������Ȃ��B�k�C�������B�܂œ����Ȃ��J�����ւ��Ȃ��B��������̏펯���āA�@�h�ɂ���ĈႤ�̂₩��B�ǂȂ��A�Ȃ�̂��˂��B�悧-���l����A�ƂȂ�قǂƎv�����ǁA�w�j�V�A�s�j�V�x�������ԈႦ��ƈ̂���(��ςȎ�)�ɂȂ��B���̗l�Ȏ��`���������ǁA���́A�a�@���璼�ڏĂ���ցA�Ǝ҂��A��čs���āA�����ő�������������������@��������āB�ƂɋA��Ȃ��ŁH�����v����B
|
|
��������[���܂�(3)�E�E�E���V�̏���
|


 �@
�@ |
������(�����イ)���̈Ӗ��Ɗ����̂��m�点
�@
���݂͑��V�̓��A���͒ʖ�Ƒ��V��2���ԁA�ˌ��Ɋ����Ɣ����ɏ����ē\���Ă���Ƃ�������x�ƂȂ�܂������A���̌`���͓��s���ɂ�鑒�V�ł͂Ȃ��A�Ǝ҂ɂ�鑒�V�ɂȂ��Ă���A���V�̓����A���͒ʖ�Ƒ��V�̓���2���Ԃɗ�����āA�\���Ă���悤�ł����A�Ƃ��犻���o�����Ǝ҂ɂ��肢����A�܂�����̉�قȂǂōs����悤�ɂȂ�ƁA��w�u�����v�̎���\��Ȃ��Ƃ������Ȃ�܂����B
�@
�������A�����������a�̎��㖘�́A�Ǝ҂��܂����V�͋Ǝ҂̉�قłȂ��A����A���A��فA�ł����Ȃ��鎖����ʂł����B����䂦�Ɏ���̌ˌ����Ɂw�����x�̎��͓\���Ă��܂����B�����������Ƃ���A���݂͂܂��A�u�����̎����݂����Ƃ����邩�v�ɑ��āA����ƌ����l�́A���a�̌㔼���ɐ��܂ꂽ�l�́A�����̐l���̌��҂Ǝv���܂��B
�@
�������������ɖn�Łw�����x�Ə��������́A�ʖ�A��������m�点�鎆�����̖�ڂł͂���܂���B�w�����x�Ə����������A��ɖ��́A�ˌ��ȂljƂւ̓�����ɓ\���Ă���Ƃ́A�u�Ƒ��Ɏ��l�������Č��݁A�Ƃɂ�����ނ݂̊��Ԃ��߂����Ă���܂��v�ƌ����ӂŕ\�����Ă��鎆�ł��B�u�����v�̎����\��������́A���݂̗l�ɔ������������x�ł͂Ȃ��A�吳����̐l�B�̋L���ɂ��܂��ƁA�̂́A�������Ԃ͊����̎������Ԓ��������Ɠ\���Ă������Ǝv���Ƃ������Ă��܂����B�������Ԃ́A7��(�Ȃ̂�)�A�܂���49��(�����イ���ɂ�)�Ƃ̉��Ă��܂��B�����̎��͂��܂ł͂��Ă������s���B
�@
���������Ԑ���(��������Ζ���)
�@
(������Ƒ��菑���m�[�g���B�̏W������23�N8��1���B�䔎���وē��{�����e�B�A������ɂāA�ō���90�̉\����50�Α�ł�������ƍ̏W)
�@
(����)�̂������̐����́A�ߏ��Ƃ̕t��������A���ς�Ђ�����A�ܐ�A���̎����(�����A�����������p�[�}���֍s��)�A���Ɍ����w����x���͂������悤�ł��B
�@
���Ԃ͒j�������S�������̕����A�����̎��S��������蒷�������ł��������A�������̂̎��ŕ�����Ȃ����ǁA�����̏d�v�������炢�ł��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@
�����̉Ƃł́A�q�ǂ��͊w�Z�֓o�Z�A�߂Ă���l�͎d����֏o�Ђ��A���҂Ƃ̊W�̐[���ɂ���āA���������߂�ꂽ����������A���̊Ԃ͋x��ł����ȂɂȂ�Ȃ����オ����܂����B�{�ɂȂ���������Ă��邪�A�ŋ߂̗�ɂ͊����x�݂̓��������Ȃ�����A�������̂�������́A�Ȃ��Ȃ����̂��ȁB�Ƙb���܂����B
�@
�������ƉΖ���
�@
(�Ζ����͊�������(���݂���)�Ɠ����łȂ����Ǝv���Ă���B�̐l�ɂĊm���ߕs�\)
�@
�ǂ̉Ƃɂ��A�_�l�ƕ��l���J���Ă��܂����A�_�l���Ō����Ȃ����܂��B
�@
�����S�̂��ǂ����킩��܂��A�V����A�Ƃł́A�_�I���B�����Ƃ��w�ӂ����x�ƌ����Ă���ꂽ�Ǝv���܂��B�_�I�͓V��ɁA�����Ɂw�_�x�ƌ������������āA�\���Ă��܂����B���̉��ɕǂɂ��Đ_�I������܂����B�ʐ^���B���ĂȂ������̂ŁA�v���o���̐����ł����A�_�l�̑O�ɗ����Č��グ�����A�_�ƌ��������͂����茩���A�_�I�̐��ʂ������̗����Ə�����Ԃ��������C�����܂��B�������A�V�䂩�牽�������Ă��Ȃ��A���̔������邵�Ă����Ǝv���܂��B
�@
�������āA�_�̐��E�͂ӂ�����ĕ��̐��E�ƂȂ����ƍl�����悤�ł��B�����Ŏϐ������̂����鎞�̉̎g����������܂��B����(�d�ł��т𐆂����߂ɒz�Â��ꂽ�ݔ�)�̊D�����ł���߂�(�D�̏�ɉ����܂�)��������̐������ʼn��g�p���܂��B
�@
������7���Ȃ�A49���Ȃ�A���̉Ƃ���߂��������I���Ǝ��_�l�֍s���ċ{�i����ɁA���߂�ꂽ�����������āA���܂ǂ̊D�𐴂߂Ă��܂ǂɉ�����āA�H������鐆����ƌĂԌ��݂̃_�C�j���O�����������Ă��炢�A���߂Ă�����āA���ʂ̐����֖߂�܂��B
�@
�{�i����ɉ������ƂŁw�Ζ����x�ƂȂ�����̐������畁�ʂ̐����ɖ߂�܂��B
�@
(��) �����ł������̎��̐����̕��@�͑S�̓I�ɑ��߂ɕ��K���������̂��A�܂��̏W����������ł��邱�Ƃ�����A�\���ȍ̏W���o���Ă��܂���B�����Ă��܂����A�\�������ł��Ă��܂��A�����20�N�قǑO���E�B����҂��܂�������A�̏W�s�\�ɂāA�����̍̏W�������܂����B�̏W�ʂ����Ȃ��̂ł����A�u�v�͐_����^������̈�̕����ŁA���Ƃ��Č��Ă��镔���B�l�Ԃƕ��Ɛ_�̎��̈�̂��肩���B���{�S��������������܂��A�L�I�̎��ォ��̕��K�A�K�����A���Â��Ă��������炵�����K�Ǝv�������܂����B
�@
�w�x�͐_�̂��́B���ɂ���ĕs��ƂȂ������Ŏg�p���鎞�A���̏�(����)������߂āw�x���g�p���Ă��܂��B�������I���A�{�i����A�_����́w���x��Ⴄ���ɋ����������܂����B����ɂ���āA�_�I���ӂ����ł����������O����_�l�͍����A���̐��E�������Ő��߂��܂��B�����̖��b�̌��͂��߂̖����t�Łu�l�Ԃ��_������A�������݂��[��ȁA���ǂ��[�A��炵�Ă������̘b�ł�����ĂɁv�ƌ����ČÑ㖯�b(�����V�c�̘b�B�_�Е��t�̘b)�̌��n�߂����܂�̏������畷���Ă��܂��B���̎�������킩��悤�ɁA�l�Êw�▯���w����������ƕ����Ă��Ȃ��ƁA�����o���Ȃ����b����`���s������������̂������ł��B�����ƉΖ��������������`���̈�łȂ����Ƃ������Ă��܂��B
|
|
��������[���܂�(4) �E�E�E�n�����痈���l�̑��V�ƌǓƎ�
|


 �@
�@ |
���悢��[�����̍Ō�̎d�グ�ƂȂ�܂����B�����܂łɂȂ�ƁA���̓��e�͏W�܂��Ă��ꂼ�ꎩ���̂���ׂ����Ƃ��d�オ�鎞�ԂƂȂ�܂����B�������āA�V�炪��Ȃ��ł���悤�ɒ����͖D���I����Ă��邩�B�����̒u���i�X�͂���������B�����A�����A���т́A�Ƃ�������ƌ����܂��B���֑������l�͉����������A�Ƃ̎���̃V�L�r�̎�z�͂ƋC�������͂��܂�܂��B�����ē��e�̎�œ���ƂȂ�܂��B
�@
�������A���̋V��͏����ł́A�����ƐQ��������܂����A�Q���̏ꍇ�͓���ɂ���Đg�̂𐴂߂܂��B�����̏ꍇ�́A�̂��s�҂Ȃǂ̌�͂Ȃ����Ȃlj��҂ɒ��ׂĂ��炢�AOK���o��ƁA�g�̂��d������O�ɁA�o���邾�������葫������������ɔ[�߂܂����A�Q���̏ꍇ�́A�����Ă����Ɠ����悤�ɁA����̍��֗������߂ɁA���S�̍Ō�̎��҂֑���S�g���������āA�g�̂����ꂢ�ɂ���(����)�A�����������Ă��炢���g(�������ɂȂ�܂��B)�������āA�g�U�������Ă��炢�܂��B�l���Ō�̋V��ł��鑒�V�́A�ƒ�������Ƒ��Ɉ͂܂�Đh��A��є߂��݂����ɕ����l�������z�������m�Ƃ��Ă̏����̋V��ł��B
�@
���������V��̈���Œn�����瓭���ɗ��āA���̒n�Ŗ��y�֍s���l������܂����B���̂Ƃ����̒n�Ő��܂����Ă��Ȃ��Ă��A���̒n���̓��e���ҁA�R���A��ӂ�z���Ȃ��物��̍��̌}���ɏ]���l�����܂����B
�@
���������Ƃ��A���҂�m��܂��̐l�B�́A�ʖ�ɉ��������͂Ǝv���̂́A���{�l�̋V����ɂ��Đ��������j�ƐS������N���Ă���͓̂��R�̐S��ł����B�����������́A�����Ă��h�ƂƂȂ��Ă��鎛�ւ��̂ނ̂ł��B
�@
�����Œn�����痈��ꂽ�l�͌̋��̎��ւ��肢���邩�n��̎��ւ��肢���邱�ƂɂȂ�܂��B����ɂ���ẮA�@�h����Ȃ�����R�֑���l�����܂����B�ŋ߂͋Ǝ҂��S�đ�Ȃ����ĉ������܂����A���a4�A50�N�㖘�͒n��������֗����l�́A��Ђ⏤�X�Ȃǂ߁A�����͏Z�݂��݂��Ђ̗��ɓ�������ʂł������A�]�E��V���Ј��֕����̖����n���Ȃǂɂ��A1�l����3�A4�l�ŃA�p�[�g�A�����Z��ƌĂԏZ���Ő������Ă��܂����B�����Ă��́A���҂̌̋��֘A�����A�Ζ���A���͏Z���̎�����A�����������Ԃ��n������삯�����e�Ƌ��ɉ����V���Ƃ�s���Ă����悤�ł����A�����͏@�h������A���Ƌy�э��Ƃ̏@�h�̎��ł����������̂ŁA����Ă��悤�ł��B(�l�V������������肢����Ə@�h����Ȃ���������Ă��炦��ƕ����܂����B�����Ă��Ȃ����A��S�������������������܂���B(����͎����Ă��܂���)���������́A(���ׂĂ��܂���)����R�֑���Ώ@�h�ɊW�Ȃ�����������������ƈ�ʏ펯�I�S���Ƃ��ē`����Ă���b���Ă��܂��B
�@
���a40�N��A��㖜���̍����A�n��������ւ����l�̌ǓƎ����������悤�ŁA����Ƃ��ēK�i���ǂ����킩��܂��A�n�����瓭���ɗ��������������M�s�ʂɂȂ�A�s���m�ꂸ�ƂȂ����v��q����T���ɁA�l�V�����ɗ��Ă����悤�ł��B
�@
�l�V�����ł́A�~�ɓ���Ɛ�c��W�҂̉�����肤��D�������Ă���l�X�̒��ɁA��������A���֏o�Ă������A���̊Ԃɂ��s���m�ꂸ�ɂȂ����q��e�̎p�����߂āA����Ă���l�B�̎p���������悤�ł��B
�@
�������������������������N������l�B�́A���̎���ɂȂ��ĉ����ɂ��Ă̐S���A�����̎��ɕ��̐S����g�ɂ����l��������������Ⴂ�܂��B
�@
���ẮA�ǓƎ��̎���͏����̎���łȂ����V�����ł����A���{�l�̐S��������p�ł��̂ŁA���̎���������܂��B
�@
�m�ǓƎ��̎���1�n
�@
���a����̎l�V�����ł́A���ȏ�ɖ~�ɂȂ�ƑS�����瑽���̓��Y�i��Ò��Ó���̔��X�̃e���g���Ђ��߂��悤�ɒ����Ă��܂������A�ЂƂ���傫�ȃe���g������܂����B�e���g�̒��́A�T���l�R�[�i�[������n������̍s���s���҂ׂĂ�����Ă��܂����B�����ɂ́A������v���̐^���Ȃ܂Ȃ����ŏ��Ԃ��֎q�ɍ����đ҂��Ă���p������܂����B�u���S�ґ䒠�̎ʐ^�ɏ���ĂȂ����́A�����Ă��邩������Ȃ��v�ƌ����āA�������Ă��邩������Ȃ��ꏊ���A�m�l��ɔ��܂�A�T�������l�������悤�ł����B�������A�������ǂ̂悤�ɐ��������ԈႦ���̂��A�̋��̐l���A���ɐ����Ă����͂��̎���̐l���m�炸�A����A��邱�Ƃ��o�����ɁA��l�ł��̐��֍s���������Ȃ������A�ǓƎ��̓������邭���ƂɂȂ����l���A����Ȃ�̐l���ł����̂łȂ����Ǝv���܂��B
�@
�m����2�n
�@
(����R�ʼn������ꍇ�B���������Ă���l������U����88��)
�@
(����)�l�����܂�Ȃ獂��R�֍s���ĉ����������Ă��炦�����B���O�ł����炦��̂�B���̐��͌̋��ŕ�炵�����̂Ȃ炻�����Ƃ�(���̂悤�ɂȂ���)�B�����A���O����ĂȂ���������Ȃ��Ȃ�A���ɂ��̂�ł����̂��悤�����Ƃ���A�����Ŏ���������ɖ���Ă��Ă��Ă��̂�ł����Ƃ����B���̎��͕K��2�l�ōs���̂�ŁB�����ɂ������Ȃ��悤�ɁA�ȁB���̂Ƃ��ɁA�S���Ȃ���(��)���������������Ă�����A����R�֒����܂łɘm��������ē�V���Ă��炠����̂ŁA���ɂ���Ƙm����������R�̓��ɂ���J�̏��̖ւ�������Đ�ɂӂ�������ɋA���Ȃ��(�A��Ȃ���Ȃ�Ȃ�)��B���̂Ƃ��J���X���A�\�A�[�A�Ɩ��āA�ĂтƂ߂Ă��A�����̐l�̎��Ƃ͊W�Ȃ����Ƃ���������Ɠ`���Ƃ��Ȃ���B�o���Ƃ���B�O����Ɏ����}����l�̃J���X�̖���������悻�������Ђ�����A�邱�Ƃ����l���ċA��ƊԈႢ�͂Ȃ��B�����łȂ��ƁA���ɂ�����A�m�������ЂƂ̂��̂ɂȂ邩��ˁB�����̐l�̎�������������́A�������Ȃ��̂�����A�J���X���ǂ�Ȗ������Ă��A�U��������肹���A�Ђ�����A��Ƃ̕����ȊO�͌����ɑO�������ċA��̂��Ƌ����Ă��������܂����B
�@
�L���ɂȂ������{�Ő����Ă��鎄�ł����A���ɑ�����{�l�̐S���ł��傤���A���������������ŋߒ����܂����B
|
|
��������[���܂�(5)�E�E�E���V�̏��� |


 �@
�@ |
���[���O�A�Ō�̕ʂ�ʖ�(�鉾(��Ƃ�))�̏���
�@
�ʖ�̏���
�@
���V�̏������I��鍠�ɂȂ�ƁA�Ō�̕ʂ���Ƌߐe���҂��ʖ�ւƂ���Ă��܂��B
�@
�ʖ�̎���鉾�ƌ����悤�ɁA�ʖ�̋q�͈�l��l�����҂ƍŌ�̕ʂ��ɂ��ݔ߂���ŁA�������҂Ƌ��ɂ��܂��B���҂̓��e�́A���҂̖T�𗣂�邱�ƂȂ��A�q�B�������ނ��킵�Ȃ��玀�҂��Âт܂��B�����������ŁA���V�̏�����`���̐l�B�́A�ʖ�֗����q�B��������莀�҂ƁA���҂̊W�ғ��m���C�����悭�Ζʂł���悤�ɁA�߂��݂���₷��Ƃ�̐S�������Ƃ��ł���悤�ɂƁA�S����ɋC�����āA���낢��Ə��������Ă����܂��B
�@
���҂��ǂ��łǂ̂悤�ɐQ�����邩�B���̕��@
�@
��1�A���Ԃ։^�і��o���āA�k���ŐQ������
�@
���̒m�点������ƕ��d���J���A�����������ď����Ȃ��悤�ɓ����̎����l�u���B(���҂��A���ė���܂ŁA�����Ŗڗ����Ȃ��d��������B�V������{�Ȃǂ̎��ŁA���D�A�D�A�l�p��������A�Ȃǂ�܂�B����͋ߏ��̎q���B�ɐ܂莆�̂��������A�������Ȃǂ����̕�����ɂ���đ��V�̎��ɔz��)�ʖ�̏����~�����Ɠ������������d�̔���߂Đ������ɐQ�����A�a������ɖ��o�������Ă��炢�A���ɐg�߂Ȑl�Ǝ��҂Ɍ���������Ă�����Ă���k�����̕����Q������B����͐S�����~�܂�A��t���ՏI��`���Ă��A�a������̖��o���Ă���łȂ��ƁA���̐��E�̐l�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ŁA�����Řa��������}���āA���o���Ă���k���ɕς���B
�@
��2�A�t�������A�t�����c
�@
���҂̊��c�̏ォ��A���c�̑���ɋt���Ɋ|���鏊������悤�ł����A���̍̏W�ł́A���������Ƃ͂���B�Ă��ǂł����B(�t������(���c)�Ƃ́A�����̋܂̕����������ɁA���̕������ւ���悤�ɁA������̂łȂ��ł��|���܂�)
�@
��3�A�t������
�@
�t�������͗ǂ������܂����A���̍̏W�ł́u�t�������������v�Ƃ����̏W�͎����Ă��܂���B�����ł͂��Ă��Ȃ������̂��ȂƎv���āA�������̐l�ɕ������Ƃ���A�҂̎���ł́A���Ă��Ȃ����A���������Ƃ́u����v�̍̏W�́A������������܂����B�܂��A�u�����̎��̕��F��A���x�ō��������������Ⴂ����(��o)�̏��֒u�������ǁA���������������Ȃ��A�C�ɂ����ĂȂ���������v���̉��Ă��܂��̂ŁA���̕��K�͏����ɂ��������Ǝv���܂��B�̏W�Ώێ҂����̏ꍇ�햯��Ώۂɂ��ڂ��Ă��鏊�ɂ�����̂ŁA����������d��i�������Ƃł͂�������������܂���B
�@
��4�A������
�@
�u���悯�̐n���́v�Ƃ����āA��A�͂��݁A�����A�|(�|�̐�̈�����O�p�ɂ�������(�߂ɐ�ƎO�p�ɂȂ�)�����ɒu���B���ɒu���ƌ����l�����������A���ɂ͉��l�`(�Ƃ��ɂ傤)���������̂ŁA���悯�̐n���͖����ɒu���܂��B
�@
���l�`�͐����`�̕z1���̔��ؖȂ�p�ӂ��܂��B
�@
(1)4���ɐ�܂��B�����`��4���o���܂��B(2)4���̓�2�����ɂ���4���ɂ��܂��B���ꂪ�葫�B(3)�����`�̂����Ă��܂��B1�������ɂȂ�܂��B�����ꖇ��4�����ɂ��Ă��̈����ɂȂ�܂��B�c�肪��ɂȂ�܂��B���ꂼ����葫�A��Ƃ������Đl�`���o��������܂��B�S��4(���̐�������)�ł��B
�@
�����͐��m�̋Z�p���������ꂽ���̂łȂ��A��������吳�����̓��{�Ɠ��́A�l�`���̕��@�ł��B(���V�̓��s�g�D�����������̔�������p�[�}������(�����e�t)���邩��)
�@
��5�A�䋟���̉�
�@
�����ɂ������̉Ԃ������܂��B�K���X�̉ԕr(���̒��ɉԂ̌s�̕�����������A�����ʂ�������)�Ȃ���K���X�̃R�b�v�ɉԂ���ցA�����B
�@
�Ԃ́A�}����(��я��A�X�~)�A������(�R�X���X�A�Ȃł���)�A�����(���z�ԁA������)�ȂǂŁA���{�̈�ʉƒ�ł͉����ɂł��A���Ă�����̂ŁA����̂����������́A�s�̒������́A�ڗ����Ȃ����́A�Ŏ��z�Ԃ͑傫�����A�䎛�ɂ͉����̎��ɂ��A���Ă���o���邾�����������̂�������Ă���B�R�b�v�Ȃǂɓ����B
�@
�_���ȉԂ́E�E�������͐_�l�̖ŁA�V�L�r�͕��l�̖łǂ�����g��Ȃ��B������̂�������(��������)�A�₩�Ȃ���(�ڂ���A���Ⴍ�₭�͎��ɐA���Ă��邪�T����ׂ��Ǝv��)�B�䋟���Ԃɂ͐Ԃ��ԁA�̂��̂͂��̂܂�Ȃ��B�A���~�͑��Ԃ����Ȃ��̂ŁA�X�~�A��я���������Ă���̂��Ǝv���Ă���B
�@
��������ƈꌾ
�@
�햯�̓y���݂̂ɂ������`���b�̍̏W�̓�������Ă��܂����A�����́u�L�I���b�̗��v�Łu�S����_�Е��t�̒n�v�Łu�Ñ㖯�b�̕�Ɂv�ł��B���������`���̒n�����ł͐_�l�̗̈�A���l�̗̈�A�l�ԁA�����A���A��A�M�Ɠy���̐l�B�̐����̒��ŁA��������Ǝ���Ă��܂��B���̐��E���A�s��̐��E�ƕ����̐��E����������Ƃ킩��Ă��܂��B�����̓��ꐫ�́A�����s���B�_�Ђ̒��ɍs��̕悪����B���݂�2�����ɂȂ�܂������A��ɏĂ��ꂪ����B���݂Ɛl�ԒB�̗̈�̒n���������肵�Ă���B�����w�̍D���ȕ��͏����̒n��10�������ĉ�����A�a�݂��ɂȂ�y�n�ł��B�l�̈ꐶ�����N���ł�10�N�ɂȂ�܂����A�։�v�z�̂�������Ƃ��������ł́A�܂��܂��N�������������������ƌ��`�����Ă���܂��B�Ȃ������͓y���ƉΑ�������܂����A����͓y�����Љ�܂��B�s��Α����L�߂܂����B��̏��ʼn��̍s��悪�c���Ă��邩���Љ�܂��B�܂��A��ʓI�ɖ̕��͐_�l�̕��B���͐l�ԓ����̕��Ƃ��Č���Ă��܂��B
|
|
��������[���܂�(6)�E�E�E���V�̏��� |


 �@
�@ |
���y�������̓���Ɣ[���ƏĂ��ꖄ���̓���Ɣ[��
�@
�����̖������@�͓y���p�ƕ�n���ɂ���Ă���ċp�̓��ނ̖������@���`������Ă��܂��B�n��ɂ���ĈႢ�܂����A�����n��̓�����ł��y�������Əċp�����̓��A������鎖�������܂��B���̍̏W�ŁA��������Ƃ������̌`�Ԃł̓y���̍̏W�͏�c�n��̕���24�N��80�Α�̒j������̓y�������ł����A���̒n��̕�͕����ɓ��������O��Ǝv���܂����A���ꖘ�ċp�ꂪ�g�p�̗L���͕ʂƂ��đ��݂��Ă��܂����B�̏W�i�ׂđz�����܂��ƁA���a20�N�����薘�A�y���͂������̂łȂ����Ǝv���܂��A�����̕��@�̍̏W��[���ǂ݉����Č��܂��ƁA���̕��@�ɐ�����������̂��ƒf�Ȃ��炠��܂��B
�@
�����ŁA�����̐�����(���肪�O��ȏ�̏������Z������)�ɓy�������o����q�˂��Ƃ��돼���͑S�̓I��7�A80�Α�ȏ�̔N��̕��ɂ��ƁA�u�����������炵���B�g���ł͂Ȃ����A�o���Ă���v�Ȃǂ�����܂��B���݂́A�y���͂���܂���B�܂��A�͂�����ƌ��A�̌��〈���o���҂���̏W�o����̂̓A�g���肬��10�N���낤�Ɛ������Ă��܂��B�����͌Ñォ��S�ςȂǂ���̑嗤���������̕��������ɖL���Ȓn�ł���܂��B�ŋߊ؍��̃e���r�ŕS�ρA�����̌��t�A�V����Ă炵�āA���������������Ă��܂��B����l�������𗎂Ƃ�����A�т��r��Ŋ������肷�邱�Ƃ́A�����Ⴄ�ɂ��Ă��A�����������Ă��܂��B�������ł͂����������K���c���Ă�������̌������B���A�m���Ă���l�����邱�Ƃ́A�y�����b�A�����w�ɗ��܂炸�A�����čs���������Ƃ��đ�Ɏv���Ă��܂��B
�@
���������Ӗ��Ŏ��ɂ��ẮA���J�ɏ����镶��(�J���X�̖����Ŏ��̗\����m�铙������S�ς���̂��̂Ƃ�������������܂���)���c���悤�ɑ�ɂ��Ă��܂��B
�@
���y�������̓���Ɣ[��
�@
����͎��̐f�f������Əo���邾��������������Ċ����ɂ���܂��B���Ԃ����Ǝ��҂��d�����Ċ����̒��ɓ���Ȃ�����ł��B���̂��߂ɐQ���̗l�ɒ��J�ɂ͂��܂���B�e�ʒB���A�e�����҂����ő̂�@�����߂Ȃ���ׂ̂܂��B�s�҂Ȃǂ̏��Ղ͂Ȃ����A�Ȃnj��܂��B�����̒��ɂ͊����������M�₨���̗t���~���Ă��܂��B���̂����ɕz�A���͘m��~���Ă��܂��B���҂͍d�����Ȃ��悤�Ɏ葫��̂ɂ��Ă������ē���܂��B�����炸�ɓ����Ɩ������ē����̂ō���܂��ĉ��ɉ������ނ̂ŁA�|�L���A�|�L�����̐܂�鉹�����܂��B������������A�����֓���鎞�̍�Ƃ̐�����e�ɕ������̂�h�����߂ɓ��e�͕ʂ̕����ɂ��܂��B���V�l���A�������Ɣ[���̎��͑̂�������A�葫����������Ȃ���o�������ĉ����邻���ł��B����ƍd�����Ă��Ă��A�₳���������̂��鍜�ɂȂ�A�����������Čo�������ĉ�����ƁA�d�������炪�A�Ԏq�̗l�ɖ��S�̏_�炩����ɂȂ邻���ł��B
�@
�������Ċ����ɓ���Ă�����āA�����𒅂Ă���悤�Ɍ����牺���A�ォ��W�����܂��B�ʉ��]�ސl�͊W���J���Ă����܂�Ȃ������ł��B�o���̑O�ɂ�������ƊW��߁A���߂̍r��Ŋ�����������A�_���������݂܂��B�������Ď��҂͕��ւ̏o�����܂��܂��B
�@
���Ă��ꖄ���̓���Ɣ[��
�@
���a50�N��ɂ͂���Ə��������s�g�D(�u�Ƃ͕ʂ̌`�ԂŁA���݂��Ɏ�`���������ԑg�D)���ǂ�ǂ�����ē��s�g�D�̑��V�W���s�����V�V����Ǝ҂����������悤�ɂȂ�܂����B
�@
���ꖘ�A���s�g�D�ōs��ꑒ�V�̓���͒n��̌����ق̑q�ɂ��̘e�ɑ���ꂽ������̒��ɕۊǂ���Ă��ĕK�v�Ȏ��ɊǗ��S���҂����Ď�鎖���o���܂����B����̗p��́A�Â����瑱���ƌn�̉Ƃ͕ʂł����A�傫�Ȃ��炢���Ȃǂ͏ꏊ�����܂����A�V��������Ă��A���N�セ������̐��炢�Ƃ��Ďg�p���Ȃ�����ł��B���{�̋V��́A�w���N�x���悭�����A���݂ł�(��1)���V�̋V��͓���̐����Ƃ͔��̍s�������Ă��܂����B
�@
������̗p�ӂƓ��������l�B����̎d���B
�@
�[�˂Ȃ�(��̕����ł��鎞�́A��������Ęm�Ƃ����������Ă��邪�A��ʂł́A�������ڂ�Ă��悢���Ŕ̊Ԃ̕����Ȃ�)�K���ȏꏊ���(�ނ���)��~���āA���������ĂāA���̉��ɐn����(��ł����ł������Đ�����)�悯�ɒu���āA�����𑩂ɂ��Ă��A����������قǂ����B�����֓����u���ċt�����ƌ����Đ��̒��֓�������B�����ʂ�ނƓ����O���ۂƌ����Ď�O����O������(�������Ɍ�������)��������ł���܂����B
�@
���������l�́A�ʏ��3�l�ōs���B�����Ă��g���̐l�j����l�Ǝ��҂����S�ケ�̉Ƃ����l(�Ȃ͂��Ȃ��B���j�Ȃ�)�ł��܂����B�����́A�j�͗���(��2)6�ڂ̂Ȃ��ӂ�ǂ��ŁA���͕��@�قɍ����B�~�͒����ɑт͍r����������B�r��̂������ɁA���͎�@���Ŕ����A�o���Ԃ�̌��������炸�A�������ď�ɂ����Ă����ށB���҂͑S���Ŕ��������z�ɎO�p�ɐ��ē\��B
�@
����ɓ���Ƃ܂�3�l�͈�t�A�͎����O�[�ƈ��݂ق��Ă���n�߂܂��B���l��̕��ɍ��点�A���̒��֑������ĐƁA��A��A�̂J�ɐ܂��B���̌㓪���瓒�������Ĕ���܂��B�S�g����ďI���ƁA���J�ɂƂ����āA��@���ʼn��x���������Ƃ�܂��B���ɒ��J�ɑ̂��ӂ��܂��B���̎��Y��ɐ@���������c���Ă���ƁA���܂�ς�������A�{(����)�ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B�j�͊�����ꂢ�ɂ����Ă��炢�܂��B�����͊�����ς��Ă��炢�܂��B�������Ă��ꂢ�ɂ��Ă�����āA���ɑ����𒅂��Ă��炢�܂��B
�@
(��1) ����Ɣ��̍s���E�E�E���������O�ɒ���B���l�̈�{���B�H�ו��œn���A���Ŏ��B�ȂNJ����������K���͍����c���Ă��܂����A�̂̓���W�H�ŋ����킹���������u�C�����̈������̂����Ă��܂����v�Ƙb���Ă��鏊�ցA�o��܂����B�C�����ʎ��͉��������̂��Ɛq�˂�ƁA���炢���̓W�����@�ŁA�ꏏ�ɂ��̏�ɓW�����Ă͂����Ȃ��ƌ����āA����̂��炢���Ɠ���̂��炢���̈Ⴂ���w�т܂����B�w�^�K�x�̈Ⴂ�ł����B�C�x���g��W���Ŋw�|���̊č��Ȃ��C�y���u�������̂ł��傤���w���{�l���Ȃ��B�x�ƋV����d�鍂��҂ɓ��������܂����B
�@
(��2) �Ȃ��ӂ�ǂ��E�E�E�r���Ōp���ڂ̂Ȃ���B���1m���炢�̒����Œʏ�́A���Ȃ��B
|
|
����(�Ђ�)�̎����ꂱ�� |


 �@
�@ |
��1�A���̍ޗ��Ɛ��@
�@
�����͎R���Ȃ��̂Ŗ؍ނ͑�ϋM�d�ł����B�؍ނ͏����̐l�͑���a�֔��t�ɏo�܂����B�Ƃ������͎R������ցA���̖Ƃ��̖���Ƃ���ƁE�E�E�ƌ�������ɍw�����܂��B
�@
�����ł͂Ȃ����A���݂��ۑ�����Ă��邪�����̓c���Ƃɒ��j�����܂ꂽ������a�œV�܂œ͂��悤�Ȍ�̂ڂ�̖_���w�������ƕ������L��������܂��B���̂悤�ɉ�������̍w���ł��̂ŁA(��1)�؍ނ͑�w�ȋM�d�i�ł������Ǝv���܂��B
�@
���̂悤�ȋM�d�i�ł����玞��ɂ��܂����A�f���G�ɕ`���ꂽ�悤�Ȋ����ǂ̉Ƃł������w���Ƃ͂��Ă��Ȃ������悤�ł��B�̏W�m�[�g�ɂ��錻��80�Α�㔼�̒j���̘b�ł́B���s���ԂŊ�p�Ȑl���A����Œ|��G�ō��l�������Ƃ��B���͑�p�i���g�p����Ƃ��������Ƃ��B��M�ƌ����l�����܂����B1�l�M���̂�2�l�A3�l�ƐF�X�Ƒ傫�����������悤�ł��B�ʂɂǂ̖Ƃ̌��܂�͂Ȃ��������A���̖͎���҂�(��)�ɒʂ���ƌ����čD�܂�܂���ł����B�����̓��j�̖�������̂ŁA�Ă���ŏĂ����͗ǂ����y���ł͌h�����Ă����悤�ł��B
�@
���͕���₷������y���̎��͑����y�֖߂��v�ƌ����Đ����D�ސl�����܂����B�����Ɛ�O������̎��オ���������܂ł́A���҂̉ƒ��ǂ��m���Ă��铯�s�����ɂ���āA���̗l�ɂ���̂���ԗǂ��ƁA���y�ւ̋V������Ȃ������Ȃ��Ă����Ǝv���܂��B
�@
���̐��@�̐����́A�F�X����悤�ł����A42��(���ɂ��Ⴍ)�ƌ����āA������2��4�̐�������{�̂悤�ł����B����2��4���B��1��4������ʓI�ł������悤�ł��B
�@
���̐����́A�N���������̂��A�ǂ����čL�܂����̂�������܂��A�N�������Ƃ��Ȃ��l�͐��܂ꂽ���Ǝ��ʎ��̉����A�u������A�v�ƌ����̂��A�ƌ������͍L���m���Ă��܂��B
�@
�g�w���x�ƌ����J���Đ��܂�A�w��x�ƌ�����Ď��ʁh�����Ƃ����܂����A���l�ɐl�Ԃ́g��2���c4���̏����琶�܂�A�[��2��4����1��4���̌��A��h�ƌ�����Ƃ��납�炱�̐��@�o����Ă���̂������ł��B
�@
(��1) �Â�����̉Ƃ����������đւ����āA����������̗l�����������Ƃ��ǂ�ǂ�����Ă��܂��܂������A���̏����A��S���Ƃɂ͉���o��������܂����B�V���䓰�ɕ������w��̑�a��(���\����͐�Ȃ̉Ƃ��������]�ˎ��ォ���a��������̌`���ɉ���)�咷���`���̐���@������܂��B���̉Ƃɂ͎O��̗��h�Ȃ���������A��i�������āu���܂�v������܂��B�����ɂ���ςȁu����o���v������܂��B������̗��h�ȉ���o��������̂́A�R�����͓��͖łȂ��m�����S�ł����̂ŁA�̕�����Ԃ̂�h���h�̖�ڂ�w�����Ă��邽�߂ł����B
�@
��2�A���̒��ɓ���镨
�@
���̒��Ɏ��҂����߂���ƁA���̐��֍s���ċ�J���鎖���Ȃ��悤�ɂƊ��̒��F�X�Ȃ��̂����܂����B�܂����l�`�ł��B�Z���K�B�n�̂��́B���сB�`�̏��B���̑���̂��̂Ȃǂ����܂����B
�@
��1�A���l�`(�Ƃ��ɂ傤)
�@
�e�����ʂƒ��������܂��B�q�����ʂƐe������܂��B���̍\�}�ł͍��Ȃ��ꍇ�́A���̔Z���ҁA�F�l���ɂ���Ă����܂��B��l�ŗ҂����̂ŁA���̐��ɏZ�ގ҂����̐��Ăѓ���Ȃ��悤�ɁA�b��������(��)�Ƃ��Đl�`�����܂��B�ꖇ�̐����`�̕z�����ꂼ��4���ɐ��Ă��̔�����2�����葫4���ɐ�A�c��Ŋ�Ƒ̂����d�グ�܂��B
�@
��2�A�O�r�̐�̓n���D�̑D���ɘZ���K�Ƃ��āA���͈ꕶ�K���Ȃ��̂œ���(10�~)��6��
�@
��3�A���悯(�����݁A�n�̂��̂��݂���ȂǁB���A�����������l������)
�@
��4�A�`�̏�
�@
�e�ɏo��������Ɋm���߂邽�ߐe�Ɍ�����B
�@
��5�A�y�Y(�Z�n���֖��c�q)
�@
��6�A���̑��Ɏ��҂̌l�̂��̂Ƃ���
�@
����A��̕i(�G�̍D���Ȑl�͊G��Ȃ�)�����B�܍�(�Q���Ȃ����ߎ�q�Ƃ��ĐA����)
�@
��3�A�w�l�X�̈ꐶ�x�̏W�蒠
�@
���V�W�́A���݂͂��ׂċƎҔC���ƂȂ葺�������̂ł̍s���͕����ɓ����ĊɂȂ�A����ł�����̌����ًy�ђ�����ɂ��鎛��擙�̐��b������Ă��钬������邪�A�ʂ̉���͂ǂ�ǂ������^���������Ă���悤�Ɏv���܂��B�����������Ƃ�����̏W�ɕ����Ă��z�[���֓�����z�[���X�e�C�ւƂȂ��Ȃ�������鎖������Ȃ�܂����B
�@
��������������A�ŋ߂͏��a���ォ��̍̏W�m�[�g���J�����������Ȃ�܂����B���ẮA�o���邾���������ɁA���[���m��A��̎Q�l�y�є�r�ΏƉ\�ɂƁA���̎O�n�_�ł��̏W���ۊǂ��n�߂Ă��܂��B�ߍx�̍̏W�ɂ���Ĉ�w�A�����̑f���炵���Ɋ������Ă��܂��B
�@
1�A�����̉���ł͏����A�H�g��A�z�{�B2�A�����̉���ł͏����A�����B3�A�y�����̉���ł́A�����A�O���A�Ə����ߍx�̐l�B����̍̏W�ł��B�S�Ď���(�N��A���a18�N���܂ꌻ�ݕ���24�N)���]�Ԃɏ����30���ȓ��ōs����͈͂̉�����̍̏W�ł����A�̏W�������قǏ������Ă������Ȃ��A�������Ñォ��h�����y�n�A�����V�c����ݏ���������A�s���F���I�̏Z�݉ƂƂ��A�r�⋴�菼���̒n�ɍs����������ɂȂ��āA�I�����}����ꂽ�y�n�ł��邱�Ƃ��������Ă��܂��B
|
|
���[���ƒʖ� |


 �@
�@ |
��1�A�[���̗l�q
�@
���҂̔[���������I���ƁA�C�������l���u�Ō�̂������ւǂ����v�u���ʂ�ɍs���Ă�����Ⴂ�v�Ƃ��A�u�҂��Ă�������Ⴂ�܂���v�u�Ō�̂ЂƂ��ƌ��킵�Ă�������Ⴂ�v�ȂǐS�����߂����t�ŁA���e����ʂ̐e�����[���l�̏��ցA�[���������I��������Ƃ̒m�点������܂��B����������ꂽ�l�B�́A�[���ɂ���Ă�����̐��E�ɍs���Ă��܂����҂ɂ������āA���ʂ�̈��A�ւ����A���҂̑O�ɍ���܂��B�ŋ߂̊�(�Ђ�)�́A�W�Ɋ�̈ʒu���A�J�����ɂȂ��Ă���悤�ł��B�������Ȃ���Ǝ҂ɂ��肢�������������̂Ŋ������Ղ��Ƃ�s���Ă������́A�W�Ɏ��҂̊��`���J�����͂���܂���ł����̂ŁA�����͔[�������̐��ł̎��ۂ̎p������Ō�ł����B
�@
�u�������̐��A���ė���̂�Łv�u�A���ė��鎞�A���q�ɂȂ�Ȃ��łˁB�m��Ȃ����֍s�����Ⴀ���߂�v�ȂǂƗ։��M������������A�u���b�ɂȂ����Ȃ��A�L��v�u��J�������Ȃ�����ɂ��Łv�ƁA���̐��ł̐S�̌𗬂Ȃǂɉ����A�u�����Ăꂽ�炷���ɍs������҂��Ă��Ă�v�ȂǁA���ꂼ�ꂪ���҂Ƃ̊W�ɍ��킹�����t�Řb�������āA�������o�čs���܂��B���̂悤�ɁA�[���O�ɍŌ�̐��|�������Ă����V��̎���́A���������̂Ŋ������Ղ��s���Ă��܂����B�܂��A�����A���҂��łĂ��璇�ԓ��Ŏ��}���Q�������܂����B�����̏ꍇ�́A�ʏ�M�����ł����B�M�́A�����̂悤�ɔ_�k���ƂƂ��Ă���ƒ�ɂ́A�����Ă��͂���܂����B�ݖ����Е���1�l�M����4�l�M���͉����̉Ƃɂ�����܂����B�����ŁA���҂ɍ����傫���̒M���A�N�������Q���܂����B�������A���s�g�D���܂�����������ł��̂ŁA���ꂩ���ƒ�ɂ���M�����Q�����悤�ł��B
�@
���͏������Č}������̂ł͂Ȃ��̂ŁA�����A�����̖��ƕ������Ă��Ă��A���̊m�F�����������܂ł́A�����đ��V�̘b��p�ӂ͂����A����S���т��܂��B�₪�ď��ɂ��Ă���҂��A���֗��������ƒm�炳���Ƒ�}���Ŋ�����A�ǂ̕������ǂ̂悤�Ɏg�����A�Ȃǂ��߂Ȃ���A�����̂����Â��A�H���Ƒ���n�߂܂��B
�@
���҂̔�����������ĂĖD�������܂��B��(�Ђ�)�͒j�B�̎�ŁA�������͏������̎�ō���܂��B���܂������݂��^�悤����^����ȉłȂ�^����ǂ���(�A���Ă���)��̂悤�ȉS������܂��B���s�Ŕ��������d���Ă鎞�A���Ԃ̑���܂Ƃ��ɂȂ�Ȃ������Ƃ��ĉłɍs���˂Ȃ�Ȃ��ƌ����Ӗ��̎�܂�S�ł��B���������̂̒��ŏ����Ƃ��Ď�w�Ƃ��Ă�������Ɛ����̂�肭�肩��A�l�t�������A�펯�A�V��Ƃ����鎖���o����悤�^�����ĉłɍs���̂���ʂ̏����ł��������̎��ł��B
�@
�u�ׂ͉�������l���v�̎���ƂȂ������݂ł́A���Ȃ��炸�����ɋꂵ�ގ��Ǝv���܂����A���a30�N��ʖ��́A���s�͂��Ƃ�芥�����Ղ�u�A�Ղ�ȂǑ��������̂Ő������Ă��܂����B���������y��ő��V���s���܂����B����䂦�ɁA�����o�Y�����ɋ��͂��Ĉ����݁A��т������Ƃ��펯�ł����B
�@
������������̐l�B�̋��͂ɂ��A�Q���͒j�����̎�Ŋ��֓���Ă��炢�܂��B�����́A���S���킩��ƁA�����Ɏ�肩����܂��B�̂��d������O�ɁA�o���邾���������҂����̒��ɍ��点�܂��B��(�ӂ�ǂ�)�͂��܂���B���̑��肻�̕����ɔ��̕z�����Ԃ��܂��B�܂��A�����͒������ォ�猨�Ɋ|����悤�ł��B�䂩���A�������Ǝv���Ƃ̎��ł����B
�@
�Q���̏ꍇ�́A���̑̌��ł͊��̉��ɔ����z��~�����̏�ɑ����̂��ĐQ�����܂��B��݂͂�����������Ŏ�̕������ɂ��đg�݂܂��B���ɎO�p�z��t�����n�`�}�L�����߁A�������������O�ɒ��t���A��1��4��(3�����̕z���ɐ܂�A2���̖D������)�̔����т�O���тɒ��߂�B�����牺�̗����̌��Ԃɂ܂���(�Ƃ�)�l�`�B�Z���K(5�~�͕R�����ɒʂ��ėւɂ�����B10�~�͎��ɂ���ށB�ǂ���ł��悢)�B�`�̂�(�������ɂ�)�B�����ɂ��Ȃ��Ă����c�q���͖��т����܂��B���ɓ���Ă��悢���A�����������ꂾ���͕K������Ă����悤�Ɏv���܂��B����ȊO�ɓ��ʑ�ɂ��Ă������̂�����܂����B
�@
�Ƃ���ŁA���u(��������)���ނ��킷�Ƃ������Ƃ�����܂����A���̈Ӗ��������Ђ̍��ꎫ�T�ł���ׂ�ƁA�w�Ăщ�Ȃ���������Ȃ��ʂ�̂Ƃ��Ȃǂɐ���t�ɂ��ň��݂��킷���Ɓx�Ƃ���܂��B���܂��ẮA�[���ɂ������l�́A���҂��^�ъ��ɐQ�����A�W�����ē�ł���B�܂��͓B�ł������Ď��҂̍����o����A�������͂������肵�Ȃ��悤�ɊW����������Ƃ߂���A���Ԗ��͍��~�̒ʖ���s�������֊����^�Ԃ܂ł��s���܂��B�B�ł��́A�J�i�d�`���g�킸�ł������܂��B���̎��[������l�́A�n�߂�O�ɁA�������ނ��킷�悤�ɐ��������ɓ���āA�����ނ��킵�Ă���[�����n�߂܂����B���̎��̐����ނ��킷���Ƃ��A�w���u(�݂������Â�)�����킷�x�Ƃ����܂����B�[���Ɍg������l�́A�̂ɉ���U�肩���āA���������Đ��߁A���̌㕗�C�ɓ���A�̂����߂Ă���A�ʖ�̐Ȃ֓��肽���Ă��͖鉾�߂܂��B
�@
��2�A�ʖ�
�@
�ʖ�͎��S�������̓��������O���ʖ�����ʂ̂悤�ł����A��O�́A���V���I����ď������܂ŁA�ʖ邾�Ƃ����ĕ��ԂŐQ���܂肷��l�������悤�ł��B�ŋ߂͎��S�������̖�ɒʖ�����Ă�������ɑ��V�ƂȂ�Ƃ��낪�����悤�ł��B�܂��A�ʖ邩��r���𒅂鎖���ŋ߂̋V��̂悤�ł��B�{���̒ʖ�́A�m�点���ĂƂ���̂��Ƃ炸�A����ĂĒʖ�ւ܂���܂����B�Ƃ������ƂŁA�����ȕ��i����I�ђʖ�̐Ȃɒ������Ƃ��A�V��ł������悤�ł��B�ŋ߂͎��S�Ƌ��ɂ��ꂱ��Ƒ���A�O���ł��ׂďI���ƂȂ��Ă���悤�ł����A���a�̏I��育�납������ɉ����Ă�(���A����24�N)�̈�ʂƂ��ẮA
�@
(����)���S�����сA���c�q(���҂̓�����̏��ɖ��сA���c�q�ǂ��炩��u��)
�@
(����)�������s�̐l�ɖD���Ă�����Ă���𒅂āA�ʖ�̋q���}����B
�@
(��O��)���V�Ă���œy�ɂ�����A������t���Ă�����āA���̐����炠�̐��ցB
|
|
���ʖ�E�鉾(��Ƃ�) |


 �@
�@ |
�ʖ�(����)�Ƃ͈�ʂɂ͑����̑O��ɍs����V��ł��B��O�Ƃ��đ������̓�����Ђ�����(��1)�Z�j�����݂āw�F��(�Ƃ��т�)�x�ɓ�����ƁA���̓��͑��V���������A���V����������A�ʖ���Ӎs���܂��B�w�F���x�̓����I���Ă��瑒�V�ɂȂ�܂�
�@
�ʖ�͈�ӂł����A���V�����w�F���x�ɂ�����ƒʖ�͓�ӂȂ�܂��B�܂��A�e�����e���������̏ꍇ�A�����O��Ƒ������I������ӂƂœ�ӂ����Ȃ��Ƃ�����܂����B���̎��A�F���ɂ�����ƎO�ӂɂȂ�܂��B�ʖ�̎�����ʂɌ��t�Ō������́w���ʖ�x���́w�鉾(��Ƃ�)�x�Ƃ����܂��B
�@
���ʖ�Ɩ鉾�͓����ł����A���҂֑���C�������Ⴂ�܂��B���ʖ�֍s���͂��ʖ�̋V��ɎQ������A�̊��o������܂����A�鉾�֍s�����̐S�́A��l�Ŗ��y�֍s���ɂ͗҂����낤�B���̋C�����Ŗ�X���ɂȂ��Ă��A�炸�A�F�ƎG���Q������A�Y���Q������A�v���o�b�������肵�Ȃ���A������X�C���₳�Ȃ��悤�ɔԂ�����B���e����e�̂悤�ɐڂ��Ă����F�⏕�������Đ����Ă������ԓ����ʂ��ɂ���Ŋ��Y���A�����}���܂��B
�@
(��1) �Z�j���c�Z�P�Ƃ������B��������`������B���̓��̗�炻�̓��̋g����肤�B
�@
�揟�\�ߑO�g�A�ߌ㋥�B
�@
�F���\���[�g�A���ߋ��A���V�͊�(�F�������̌�C�Ŋ�)�B
�@
�敉�\�ߑO���A�ߌ�g�B
�@
���Ł\�ő�̋����B
�@
����\�����g�B
�@
�Ԍ�(���������)�\���ߋg�A���[���B
�@
(1)�ʖ�̗l�q�Ɩ鉾�ɓ��閘�@
�ʖ邪�n�܂�8���������O�ɂ��V�l�����o�������ɗ����܂��B�njo�̐�����������ƈ�l��l�ƏW�܂�A�������������ċA��B�c���Ă���l�B�ɂ��V�l���@�b������B�ߏ��̐l��m�荇���A�F�l�A���ԓ������X���Đ��������ċA��l�A�O����������l�A��r�̂������ċA��l�����A9������10�����ň�ʂ̐l�͂قƂ�NjA�12���ɂȂ�Ƒr�傪���A���āA�鉾������l�ȊO�͊F�A�����悤�ł��B���V�l�����A��ɂȂ�܂��B(���Ԃ́A���܂��Ă͂��܂��A�����������̒��x�̎��Ԃ������悤�ł��B)�njo�͂��V�l�����łȂ��ω��u���r�̂̉�Ȃǂ̏����B���O���\�v�ŏ����ĉ�����Ȃǂ�����܂����B���̌�͖鉾�ɂȂ�܂����A�V�炪���ֈڂ�̂łȂ��A�����������e�����ƂȂ�A���܂Ŏ��҂��ÂԂ̎p���A�鉾������B�Ƃ��������������܂��B
�@
(2)���҂̈����Ȃǂ̑��V�G�k
�@
�����Ɗ�������
�@
�����菺�a8�N(�H)���܂�B�j���BI����B����21�N9���̏W
�@
�̂̊����͊ۂ����^�������B���҂����鎞�A���Ԃ����ƁA��������Ȃ��Ȃ�B�����Ȃ��ē����̂ŁA�d������ƍ���܂�Ȃ��Ɠ���Ȃ��̂ŁA�|�L�\���|�L�\�����č����܂�鉹���������̂ŁA�e�ʂ̎҂́A���̕������Ȃ��ꏊ�֍s�������B(��c�n��̕�)
�@
�����̍d���������܂��Ȃ�
�@
�����菺�a10�N���܂�B�j���BMA����B����21�N11��9���̏W
�@
�͍̂d������ƁA�d���������܂��Ȃ����������B�N�����鎖�͏o���Ȃ��������A���ɂ́A�����`�����Ēm���Ă���l�����āA���̐l���Ă�āA�܂��Ȃ��������B
�@
�����҂̈���
�@
�����菺�a10�N���܂�B�j���BMA����B����21�N11��9���̏W
�@
�͎̂��҂��o��Ɓu�F�������v�Ƃ����āA���̐��ֈ�l�ōs���̂́A�҂������猙���Ƃ����āA��(�Ƃ�)��T���Ă��邩��������܂��Ƒ�ςȂ̂ŁA�ߊ��Ȃ��悤�ɂ����B
�@
�����菺�a10�N���܂�B�j���BMA����B����21�N11��9���̏W
�@
���҂��o��ƁA�e�ʂ̎҂��o�Ă��āA�̂����������������ׂ���B�������āA�E�����̂łȂ������ĂȂ��\�\�͕̂n������������A�������́A�ŕa�l�͂炩������Ȃ�
�@
�����菺�a18�N���܂�B�����BSA����B���a59�N2���̏W
�@
�q���̎������ǁA�F�B�̂��ꂳ���j�Ŏ����āB���͌��ĂȂ����ǖځA���A�@�A���A�`�A���ɖȉԂ��l�߂āA�̊O���j�ۂ���Ȃ��悤�ɁA���Ăӂ����ŁA���ꂩ��g�̂��瑫�̐�܂ŎN���z�ł܂������Ă�������B
�@
���s���
�@
�����菺�a10�N���܂�B�j���BMA����B����21�N11��9���̏W
�@
�͎̂��l���Ă��Ȃ������B�s��́A��ɂ₫�������āA�����ŏĂ����B
�@
����
�@
�����菺�a15�N���܂�(�H)�BS����B�����B���a56�N�̏W
�@
�͍��͍s���łȂ����ǁA�䂩�獇�����ď����ɓ����āA�͍��̕悪�o�����B�Ă��������������A��ɏĂ��Ƃ������ɂ��������āA�����ۂ��[��B�ۂ��[��B���Ē��˂鉹�����āA�����傭�͈������A�]�肢�����̂ł͂Ȃ������B
�@
�����菺�a18�N���܂�B�j���BMY����B����21�N11��9���̏W
�@
�̂͋����悾��������A���̂悤�ɁA��ƌ����āA��n������ēy�n���ĂȂ������B����ɖ��߂鎖���o�����̂ŁA�����ɖ��߂��B
|
|
���y��(�挊�@��Ɠ���) |


 �@
�@ |
���悢��o�����߂Â��Ă��܂����B�����ł͓y���ł���n��ƉΑ��̒n�悪����܂����B���Ƃ��Ə����S�͓̂y���ł������̂��A����Ƃ��y���ł��������A�s��M����Α��ɂȂ����̂��A����Ƃ����s�̐��ނȂ̂��A�o����l�ɂ͎c�O�Ȃ���o����Ă��܂���B�y���́A�Α��ɂ����Ă��ł����A�����́u���s(�ǂ����傤)�v�Ƃ����ݏ���I�Ȗ��������g�D������A���ׂē��s�ɂ���ĂƂ肨���Ȃ��Ă���܂����̂ŁA���̑g�D�̉�̂ɂ�葒�V�̋V����傫���ς�����悤�ȋC�����܂��B
�@
���ɉΑ��Ƃ͈قȂ�A�y���n��ł̍̏W�͂ނ��������A���݁A���֓y���ɂ��ċ����Ē�����l��80�Α�㔼�̒j����l�݂̂ƂȂ��Ă��܂��B�����́w�����̎��͓��s�ŁA���Ă��܂�������A�܂���������(���s���̂�)�̂��ƂŁA�킩�炵�܂������x�ƌ������`�Ԃł����ƒf���܂��B�����������Ƃ���A�\���ȍ̏W�ł͂���܂��A���̂悤�ȍ̏W�����Ă��܂��B
�@
���܂��ẮA�]�k�Ȃ���A���݁w���x�ɂ��Ă������ƁA�m�[�g���߂���A�܂��̏W�����ď�Ɂw���x�ɓ���āA�ǂ������Ă���܂��ƁA���L�̂��b�����ƕ\�����ׂ����킩��܂A���b�I�Ō������痣��āA�ق��Ƃ����̏W�ɏo��܂����B
�@
(����͕���24�N���݁A60�Α�㔼�̏����̎G�k�����ɂ܂Ƃ߂܂���)
�@
�������A���M�������Ǝv���̂����Ǔǂ�������܂��B�L���Ⴂ�������炲�߂�Ȃ����B�Ƃ��Ă����������̂������̂Ŋo���Ă���̂����ǁA�M�҂̑c�ꂪ���̉Ԃ��������̂́u�l�Ԃ̎��̂�H�ׂĈ���Ă��邩�炾�v���āA���̂ˁB
�@
���̉Ƃ̐E�Ƃ͕挊�@��̐E�Ƃ������́B���̉Ƃ̎�l�́A�挊�@��̈˗�������ƁA�K�����̉Ԃ̉����@���Ă����֎��҂߂��̂����āB
�@
��������������A�c�ꂪ�̒�������ď��ɕ����Ă������̂��ƁA�d�b�̖�������A�v����`�B���邵���Ƃ��������̂ŁA�c��̑ւ��ɕM�҂��`�B�ɑ��鎖�ɂȂ����炵���̂ˁB
�@
���̓`�B�̋A��̏o�������ƂĂ������������Ă������̂ˁB���̉��𔒂������݂������悤�ɍ��̉Ԃ��炢�Ă����́B����̍��͒��ԂƂ͑S������āA�d���ŁA���̏�Ȃ��������̂ɁA�ǂ����Ől���t���Ȃ��قǂ́A�ǂ̂悤�ȕ\�����}�b�`���邩�\�����Ȃ��̂�����ǁA�|���قǂ̔������Ȃ́B���̎��B�M�҂́w���͐l�Ԃ̎��̂�H�ׂĈ��������������x�ƌ������c��̌��t���S�g��ʂ��ē`������B
�@
�ƌ������Ӗ��̎��������Ă������B������܂��M�҂Ɠ����C�����ɂȂ鎖���o�����قǂ̂��炵�����M�������ƌ���ĉ��������B
�@
���挊�@��̌��t
�@
�y���̏ꍇ�A�挊�@��͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B�ɂ��č̏W�Ɏ�肩���������A�u����Ȃ�킩��Ȃ��v�Ɗ�������(���݂������)��������̂ŁA��L�̌����q���g�ɕs����ɂ������Ă݂܂����B
�@
�����̏ꍇ�A�������ׂ��Ƃ���ł͎�������낤���A�u�挊�@��v�̌��t�͂������B�Α���ŁA(�����ɂ͎s�c�̉Α��ꂪ�Ȃ��̂ő��s�̉Α���֍s��)�l�Ă���̌W��̐l���ǂ̂悤�Ɍ��������킩��Ȃ��B���̌��t�͑��{���ł͒����łȂ����m�l�B�����ʂɕ������Ƃ���A70�ΑO�ォ��̍���҂́u�l�Ă���̐l�v�ƌ�������ԑ�������܂������A�y���̐��ނƋ��ɁA�u�挊�@��v�̌��t�������A�l�����̂܂܂̌`�Ŗ������鎖����z���ł����A�Α��ꂵ���z���ł��Ȃ�����ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�����܂����B
�@
�����������Łu�����A�����ł�������(���x��)�A�A��Ȃ�����A�����ɋA���đ��k�֍s�����Ǝv���Ă���̂����ǁA�Ƃ̉��n���o�g�҂��炠��܂����B�挊�@��Ƃ͊W����܂��A�n���o�g�҂ɂƂ��āu��v�ƕ����V������A�u��x�A���ĉ]�X�v�Ɣ]�����悬�鎞�ォ������܂���B�����Ɠ��s�g�D���c���Ă���A����ɂȂ鑶�݂ɂȂ�����������܂��B
�@
���挊�@��
�@
�o�����߂Â��ƁA�}���ŕ���@��˂Ȃ�܂���ł����B�N���@�邩�̖��ł����A�����ł́A��͂蓯�s�g�D�ōs��ꂽ�Ǝv���܂��B���̒��Ō��߂�ꂽ�|�ɏ]���āA�s��ꂽ�ƍl�����܂��B(�Ⴆ�Ώ��Ԑ��A�g���Ȃ�)�܂��A��l�ł͂���ǂ��̂�3�A4�l���x�ł��낤�Ǝv���邪�����܂ł������ł����A�����̓y���͍����ł��̂œ��Ƃ͈̔͂ŕ挊�@��̓��ԂȂǂ��������̂łȂ����Ǝv���܂��B����A�y���̍̏W�����āA�������V��̍̏W�́A��N�̍̏W�x���10�N�̍̏W�x������傫�������v���m��܂����B�����o���̂�����������Ă����A�̏W���𗊂�ɁA�ꉞ���L�̂悤�ɂ܂Ƃ߂܂����B
�@
���y���̕挊�@��挊�@��Ɠ��Ƃ̐l�B
�@
���Ăі����P�Ɂw�挊�@��x�ƌĂꂽ�悤�ł��B
�@
���挊���@��l�͓��s�g�D�ɂ��̂łȂ����Ɛ������Ă��܂��B
�@
���挊�@��͓y���y�ѓ��s�g�D�������Ȃ������_�ŁA�Ǝ҂ōs����悤�ɂȂ����Ǝv���B
�@
���挊�@��̐l����Q���҂͓��s���ԂŁA�|�����܂��Ă����Ǝv����
�@
���_����̍s��(���_�l���甃��)
�@
�����ł͂���܂�����ɂ́A�������鎞�_�l����y�n���V�炪���锭�\���܂����B�r�̉Ƃ̐l������@��Ƃ�������߂�ƁB�l���ɃT�J�L�ƃV�L�r�����ĂāA�����A�āA���A���X�A�����A����(1���K�Ȃǐ_�l�ւ̓y�n���)�𒆉��ɂ����A�a��������J���Ă��炢�o��ǂ�ł�����Ă���挊���@��n�߂��B
�@
�܂��A�����ł́A�p���ʎ߂z�����H�Ղ�̋V�炪����܂��B�H�Ղ�ɂȂ�ƁA�n��(����)�������̎��[�ɂ���o���܂��B�H�Ղ�̓����A���̖�O�ŁA�n�ԂƎQ���҂ւ��o��ǂ�ł��炢�܂��B������_�Ђ܂ŁA�n�Ԃ̍j���悿�悿�������獂��҂܂ňꓯ�Ɋ|�����Ƌ��ɁA�����čs���܂��B���ݒ��w2�N�̑����A�c�t�������O�̔N��ł������A�����̒n��̖@��ɂ��݂��ĉ�����A�n������_����̂̍Ղ�ɎQ���̌o�������܂����B
|
|
���Α� |


 �@
�@ |
��1�A��n�̉Α���Ƃ��̎���
�@
����́A�y���̍̏W�ɑ����A�����ɂ����ĉΑ��́A���a30�N��͂܂���̏Ă�������݂ŁA��̉Α����s���Ă����悤�ł��B���a30�N��A40�N�㏉�߂̍��́A�����͂܂��قƂ�ǂ��A�����̓y���̐l�B�ŁA��߂��Ă��܂����B�܂��V���A�����̗��ȂNjߓS�����ɂ͋ߓS�Z��������Ƃ�����K���Ă̒�t���Łw�����Â����Ԃ��x�̊_���̉Ƃ�A�������݂��A�܂���𗧂āA���̖�S���łȂ������ň͂܂ꂽ�ߓS�̋n�Ȃǂ��ڂɂ��܂������A���̂��납��l�����A���a30�N4��6��l�B��40�N7��1��l�B��50�N13��1��l�ƃE�i�M�o��ɑ������A�n��r�������Ə����܂����B����ɔ����A��̎p���Ă��ꂪ�����A�}���n���̏ꏊ���ς��A�����������Ă����܂����B
�@
���܂��ẮA��ɂ���Ă���ł����A�����̐l�B���ȒP�ɖڂɂ���Ă���̂��邨��A���͖ʉe���c������́A���͂����قƂ�ǂ���܂���B�݂Ȃ��o����Ă��鏊�ł́A�w���Â݂�x�̐�������̏��̂���ł��B�Â�����Z��ł���l�́A���ꂪ�Ă��ꂾ�����̂��Ǝv���l������Ǝv���܂����A���ꂾ���ɁA�܂��ʉe�̎c���Ă��邨��ł��B��n���ɓ�����Ɩʉe�͊������܂���B�K�������猩����̂ŁA�����猩�ĉ������B��n�͂��̒n�ɖ���ꂽ�l�B�̂��Ƃł��B�����猩�邾���̂������ĉ������B�K���K����������ĉ������B��������ĉ����鎖��M���āA��������Љ�܂��B������͂܂��c���Ă��܂��B��������̓y�������Ă��܂��Əo������o���܂��B�ꏊ�̂��Љ�͂������A�ŋ����ĉ������B�������ƎU�����ĉ�����Əo������o���܂��B
�@
���Љ�ɖ����܂������A���b�������ł��������̐l�X�͋L�I�̎��ォ��̓`�����ՁA���K�ȂǑ����̕���c�߂��肷�邱�ƂȂ����̎��㖘��Ɏp���ʼn������Ă��܂��B���͂��������������ւ�Ɏv���Ă��܂��B�����ł����A�����͂����������Ă���ƁA���̓y�n�Ő��܂������l�łȂ��ƌ��߂����Ă��܂��A30cm���x�̌Â����������W�Ƃ̏o���A�����V�c�̎Y���ɂЂ�Ђ�ƕ����č~�肽�Ɠ`������O��̉ԂƂ̏o��A���b�Ƃ��ē`�����Ă���A�u���R�r�́A��ւ̖v���K�����Ɩ��b�̐��E�ɐZ�鎖�̏o�����K�ȂǁA�Ă���ɏo����Ƃ��A�����͌����Ė����A���j�𗠐�Ȃ������̒n�ł���ƐM���Ă��܂��B
�@
���āA�����͎s�c�̉Α��ꂪ����܂���B�����ŁA���̉Z���쉀�ʼnΑ������˂�������悤�ɂȂ�܂����B���a49�N�ł������Ǝv���܂��B���܂��ܑr�傪�������܂�łȂ��������Ƃ���A�e�����m�l���Ԃő��V���s���A�F�l�Ƃ��Ď�`�����o�������ƂɎs�c�̉Α���ł̌o�����Љ�܂��B
�@
��2�A����V�̌�A�s�c�̉Α���ł̌o��
�@
�܂��A���V�Ђ̎Ԃ����V��ł��鎀�҂̎���ցA������a����ɗ����܂����B�Ă���ւ����̂���������l�B10���قǂ����V�Ђ̎Ԃ̌��̏��^�o�X�ɏ��̂ł����A���V��̎����o�X�ɏ�閘�ɋߏ��̐l��q�ǂ��B�A�ʍs�҂ւ��َq��z��܂����B(�ʏ�͎q�ǂ��݂̂������ł����A������̎q�ǂ��B�����Ȃ������̂ŏo������l�F����ɔz��܂���)
�@
�Α���ɒ����ƁA�����̂����̐l�B�͉������ł���l�Ă��̂���������P�[�X���ɑ���ꂽ�ꏊ�֍s���܂����B�₪�āA�Q��Ԃ��A�������悹�Ă���ƁA�Ă���̃P�[�X�������֓�����A�������߂��܂����B����ƌW��̐l���A�Ă��I��莞�Ԃ��������A���E���̏ꏊ(�������ł���)�Ǝ��Ԃ��������A���̎��Ԃɗ��ĉ������ƌ����A�����Ԃł������̂ŁA�A��l�����܂����B
�@
�W��̐l�̎w�������ꏊ�ő҂��Ă���ƁA�D�����ꂢ�ɏ�����āA�������������ɂȂ��ĐQ��ɐQ�����ꂽ�p�ŁA�Ă��ꂩ��o�Ă��܂����B���B�͂��������V��͂͂��߂Ăł�����܂܂ɁA���ꔢ�ł����������ĂƂȂ�ւ킽���čs���܂����B�N���V��̌o���҂炵���l���u��S������́A�w�̂Ǖ��x�́A��ԏ�ɒu���Ă�v���̑O�Ŏ���ӂ�킹�Âы����āA����ɓ���鍜���E���Ȃ��l�Ɂu���̐l���҂��Ă͂�(�҂��Ă���������)��v�ƁA���ӂ���Ȃ���A�X�P�W���[���ɉ����āA�i�݂܂����B�啪�̂̎��ŁA�܂����̎��̗l�q�ȂǁA�������鎖�����Ă��܂���ł����̂ŁA����o���ł����A�������č���ɍ������߂�ƁA���҂̎���ւ̋A��͑��V�Ђ̃o�X�łȂ������Ǝv���܂����A�ǂ̂悤�ɋA������Y��܂����B���������҂̎���ł́A�H���̗p�ӂ����Ă��邩��H�ׂċA��悤����ꂽ�Ǝv���܂����A�q�ǂ���u���Ă��Ă��܂������ƁA�������Ă������Ƃ���A�N���ɑS�g�ɉ���U���Đ��߂Ē����āA���͋A��܂����B
�@
��S������́w�̂Ǖ��x�ɂ��ẮA���̐l�B�́A�l�������}����ƁA�V�����ɂ����S������ցw�̂Ǖ��x��[�߂܂��B���N�Ɉ�x�ƕ������悤�Ɏv���܂����A���́w�̂Ǖ��x�ň�̂̑傫�ȕ��l�������A�Ȃ�̂��̏����ȕ��l������A�̂Ǖ������߂��l�B�֎����n�����ƕ����܂������A��S������͎f���Ă���܂���B���܂��̘b�ł��B��S������͎l�V��������Ɠ��l�ɑ��̐l�X�ɂƂ��Ă͑�ϐe���݂̂��邨������ł��B
�@
���~�ɂ͒n�����炫�āA���l�ɂȂ������̂ɂƂ��ẮA�@�h�̖����l�V��������͗L��A���Q�肵����𗊂ނƑ̂���������Ɖו������낵���Ƃ��̂悤�Ɍy���Ȃ�A�w���݂�����x��w�T�x�ӂ�ł́A�s�v�c�ƌ̋��̐l�Ɉ����u���̐��̎҂������ĉ��������̂����v�ȂǂƘb���A����������т����肵�܂��B
�@
����͕�n�Α��ł��B���̋V��́A�ǂ����Ă�����҂֕������ƂȂ�s���ȋC�������������ɂȂ����������X�Ǝv���܂��B�����������ŐF�X�����Ē����鎖�����ӂ��Ă��܂��B�L��������܂��B����������܂œ��s�g�D������Ǝҁ��l�Ɗe�g�D�̒��ő̌������Ă��������A���̉ߒ��̒����ĎQ��܂����B��Ɏp�����Ă��������܂��B�����B
|
|
����n�Α��̑��� 1 |


 �@
�@ |
(����)�����s���BM����B���a4�N���܂�B�����B(�̏W�n�A�̏W��)��쒆���a�@�Ŏ�H�|�{�����e�B�A�ɂĕ���7�N�O��B
�E�E�E�������̂܂ܕ����ɕς��Ă��܂��B�b�����O���Ӗ��s�������������������B�E�E�E
�@
���ʂ̓��̂��Ƃł���A�V����(��1)���ʂ�C�����낵�����A�ォ�痚���č~��Ă͂����Ȃ��̂�(���~�����痚���𗚂��ēy�ԑ��֍~��Ă����Ȃ��̂́A)����������B(���̋V�炾����)�܂��A�����̓��ʂ̂���(�V��⎀�ɂȂ��銵�K)�͕��ʂ̐����ł͂��܂����B���V�ɏo�鎞�͐V�����������͂�����A�͉̂j���ɍs�������A�R�֍s�������V�����������̂����낵���肵�Ȃ��������A�����ł������o�������q������܂���Ȃ��B�����A��܂�����āA�ȁB�����܂ɂȂ邩����āA�ȁB��������X�̐����ŁA���q�����ꂽ�茇�����肷�邱�Ƃ������܂����B�����炩�����Ƃ�������ɖ߂��Ă��炢��(��2)���Õ���(���q��)�֎����Ă����ƁA�ǂ���(�C��)����̂��A���ꂢ�Ɍp���ł��炦�܂����B
�@
(��1) �������̂́A��ʂɂ͖�ɐV�������̂����낷���Ƃ͊�(����)�����B�ǂ����Ă��A���낳�˂Ȃ�Ȃ����́A�w���ǁx�̒Y�D�m���{�ɂ͐�����ɂ͂��т𐆂����̕��A���������A����́A�Ȃǂ�������ɁA���ꂼ��̂��̂������āA������d�����ׂĒ���������q���z����Ă����B������w���ǁx�Ƃ�����)�w���ǁx�̐d���Ђ���(�ނ���)��Ɏc��Y��D�̕����ʼn��ʂ�C�̒�������A���悯�A�Ƃ����B�n�ʼn��ʂ�C�̒�������ė������B
�@
(��2) ���Ƃő�Ȓ��q����������������܂��B���̎��y��ł��т𐆂��Ă�����̑�̏�Őn���������悤�ɖ̔ʼn��̑�ɕ��s�ɂ���Ԃ��悤�ɕ��s�ɏ㉺�������܂����B���݂̂悤�ɂ��ߍׂ₩�ł˂��Ƃ�ƂȂ�܂����B�����̖����q�ł��������A���ʓ��ł��l�l�̑O�Ŏg�p�ł��܂����BM����̌������Õ�������̏C�U���@�Ɠ��������Ǝv���܂��B
�@
��n�̉Α����6�n������̂���ɂ���B��}���n������̏��ł�����u���܂��B�}���n������͂���̐��ʂɂ����܂��B
�@
�N�������Ȃ��Ȃ�ɂȂ�܂��ƁA���̗בg(����)�̐l�B����`���܂��B
�@
�Ƒ��̐l�B��A�בg�̐l�B���`���ɗ��Ă��ꂽ�l�B�ɁA�傫�Ȃ����Ɂu���₭���͂�v���܂��B�������̕��@�́A�V(����)�̘m���������~���痚���āA���̂܂܂ł�����S���ŁA�Ƃ��o�܂��B��ɍs�����A���ɎO�p�̔����z�����܂��B�H�삪���Ă��锒���O�p�̕z���z�̏��ɒ��߂āA����ɍs���܂����B����ւ������ɂ́A�֎q�Ƃ��卪�A�j���W���Ȃǂ�ʂ蓹�̗����֒|�ɓ˂��h���āA���[�������̓�����܂Œ|�Ɏh������̒ʂ蓹�������܂��B�����͈�{�̒|��6�A7���ʂ�(�c��)�����āA����ɓ˂��h���̂ł��B
�@
��̓�����ɂ��n��(�}���n��)����������Ⴂ�܂��B�����܂Œ|�Ɏh�����������܂��B���n������̏��ɂ�����u���ĕ�W�����ĂĂ������肵����Z�E�����ĉ������܂��B�}���n������̑O�̂����Ɍ�o�������Ă��炢�܂��B�Z�E����͌�o���I���ƋA��܂��B�����Ď��B���A��܂��B�A��ƉΖт����������܂��B
�@
�Ƃ𒋉߂��ɏo�Ă��A�����čs���Č}���n������ɒ����Ă��o���I��鍠�͂��傤�Ǔ������ނ��낾�����Ǝv���܂��B�[����w�ɂ��ĉƂɂ��ǂ蒅���Ɠ�������ŁA�Ζт����͖邾�����Ǝv���܂��B�{�[���A�{�[�����Ă���̏Ă��ꂩ��A�����͂����鉹�����܂��B���̉��ցA��������̎�����R�ɍ��킹�܂����B
�@
��A�����B��A�����B(�ЂƂȂʂ��B�ӂ��Ȃʂ�)�Ƃ��܂��B�E�E�E���̈Ӗ��͂Ȃɂ��ǂ�����̂��A�킩��܂��A����ł��̎��̍̏W�͏I���ł��B
�@
���]�k�@
�ꏏ�ɂ����l�B�ƁA�ĂɂȂ�ƕ��l�̂��т��ǂ̂悤�ɂ��悤���Ƃ������́B���т�������̂��O�o�ȂǂŖ�ɂȂ������A�d���Ȃ����炿����Ɖ��F���Ȃ��Ă��Ă��̂Ă�킯�o���Ȃ��������ė₽���������Ă������ނ킯�Ȃ��ǁA����̂�˂��B���̉Ƃ͈�ԏ��߂Ɏ����ł��傤�A�����Ď����H�I������炷��������́B����Ȃ炲�т��_�炩�����A�ȂǏ��Ȃ�ł͂̎G�k�ɉԂ��炩���Ă���܂����Ƃ���A���̂悤�ȍ̏W���o���܂����B
�@
(1)���̂�����
�@
(����)�����s���BF����B���a23�N�O�㐶�܂�B�j���B(�̏W�n�A�̏W��)�����s�����ŎG�k�ɂĕ���22�N���B
�@
�l�̐��Ƃ͎��Ȃ�ł����ǂˁA�����̕��l�̂��т́A�����H�ׂ�̂ł����A�①�ɂɕ��ƕ�̓�l���ł����A���l�̂��т͎R���肾���炯���������܂�̂ŁA�^�b�p�[�ɐ������āA���̒��ɖ������т����āA���l�ɐV�������т�������̂ł����A���łӂ₩���̂ŁA���������������������ƃ^�b�p�[�̕ꂪ��邨�����H�ׂȂ��ŁA���͂�����ׂ�̂ł���B����Ƃ������ǂ�ǂ�ł��āA������������H�ׂ邱�ƂɂȂ邯�ǁA���������炷���ɂȂ�̂ŁA�H�Ԃɐ���H�ׂ�̂ŁA�������Ă������Ⴄ�̂ł���B
�@
�Z�̎��ł͖{���ɋ����邲�т����ł��ꏡ�ł�����A���ꂪ�����ł�����B����ŁA�����(�M)�ɎR���肵�Ă�����A����ł͍ς݂܂���B
�@
(2)��Ƙb��
�@
(����)���B�����B����9�N���܂�B�����B(�̏W��)����24�N8���B
�@
���������́A���̎����菑���Ă��邩��A�s�v�c�Ȏ���������́B�Ƒ��Ƙb���Ă���ƁA�����`�����̉Ƃ͂���������A���~�ɂȂ�Ƃ��������Ɠ����݂����B�Ƃ̒��������������Ă���̂ɏo�����̂����āB���ꂩ��Q�Ă����璋�Ԃɉ�����������b�ɗ��鎞��������ĕ������B�����������A����������M������B
|
|
����n�Α��̑��� 2 |


 �@
�@ |
��(1)�����̕�n�Ƙ@�Ԍ`����Ɩ�ӑ���
�@
(�̏W���A����B���a56�N�A57�N���y�j�w�����Ԃ�蕷�����������B�@��͕���24�N9���m�F�̂��ߍ����̕�֍s���Ċm�F�B����̒����ɂƓ얳����ɕ��ƒ����Ă�����)
�@
���̋L���ł́A�m������͑�^�̃����K��ς�ŏo���Ă���A�傫�Ȏl�p�����˂̂��闧�h�ȉΑ��������n�ł����B�������@��Ɋ���(�Ђ�����)�̏ꏊ���ς��܂������A����͂�������Ǝc���Ă���܂����B�Α��ꂪ�����Ȃ�ƁA�V����p���`���̌��̏����́A��������Ǝv���܂����A�e����q�l�Ԃ̑����Ǝ��̋V����A�����̍s���`����s��ƉΑ��`���Ȃǂ́A�Ă��ꂪ�����Ȃ��Ă��A�p�����ė~�����Ǝv���Ă��܂��B
�@
������
�@
���āA�@�Ԃ̌`����������Ƃ́A��107��(�O��)�Łw����Z�n��(�}���n��)�̏��ɒu���ċA��x�ƏЉ�܂������A�����ł͂��̘@�Ԍ`����ɏ悹�܂��B���̑�������ł͊����@��ƌ������悤�ł��B���̘@��́A�����������̏��������Ă����M�c�Ƃ��A����4�N�����A9��9���Ɏ{�債���Ƃ���܂��B��ϗ��h�ȋ��x�̍����Ȃ̂ł��傤�A�j���������鏊���Ȃ����N���J�ɂ��炳�ꂽ�������������Ȃ��Ŏc���Ă��܂����B
�@
����ӑ���(���Ƃ�����)
�@
���V�̗�̐擪����ւ��ǂ蒅���ƁA�@��̎�����O���ɂ܂��܂��B(�Ƃ��o���������ƌ������������܂�)����́A���҂̗삪���ɂ����Ȃ��A�Ȃnj����𗣂ꂠ�̐��֍s�����������Ƃ����v�����A��ƂȂ��ĉƂA�낤�Ƃ���ƍ���̂ŁA�A�铹�����҂ɂ킩��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂��ƌ����Ă��܂��B������ӑ���Ƃ����̂������ł��B�܂��A���Ƃ������悤�ł��B
�@
���M�c�̕�
�@
�����̕��M�c�̕�ƌ����l�����܂��B����͐M�c�Ƃ̕�̂�����̈Ӗ��Ǝv���܂��B�u�@�Ԍ`����v�̖��͕̂X�㎄�����t���܂����B�����ł́A����A�@��A�Α�A��A�Ɛe���݂̂��閼�̂�����܂����A���㖼�̂łȂ������̐l�ɏo����Ė��O�ׂ܂�)
�@
��(2)�����n��
�@
(�̏W�B����24�N8���B�����w�O���痧�������َԒ��B���a22�N�������܂�ݏZ�B�j��)
�@
�̏W�Ƃ��Ă͒Z������̂ł����A�����n��ł���107��Ɠ����̏W���o���܂����B���n������̏��֊�(�Ђ�)��u���ċA�邻���ł��B65�ʼn������ɏo����̂́A�����������n��ł��B����͏��Ȃ��̂ł����A��n�ɂ����銻�܂킵���̋V����s���Ă����̂łȂ����Ǝ��̋@������҂��Ă��܂��B���Ă͎��ɂƂ��ė����͐��n�ł��̂ŁA�V��̍̏W���L�Ƃ��Đl�̈ꐶ���g�[�^���Ƃ��ď��������o����Ɗ�]�������Ă���قǂ̒n�ł��B����䂦�A����������s��s�̍̏W�i���p�����킹�Ē����N���̐ςݏd�Ȃ�ŁA�o���オ��܂����A�����͂��̓y�n�ŁA���̓y�n�̕������j�����Ղɂ������남���������ς��邱�ƂȂ��A��ɓy�n�̐l�B�����`���Ă����p��������A���������p�����Α�������̑��V�����S�ɏ����Ă��Ȃ��̏W�o����n�悪���鎖��S���玩���Ɏv���Ă��܂��B
�@
�s�j3��P649�Ɏ��̂悤�ȕ��ʂ�����܂��B
�@
�w�������A�V��14�N(1843)�t�E�H�E�~�n�j���[�Ȃ׃n�A������������(��炶)�E��E�������A���n�k�쓧��(�����܁E�_�Պ��̎�)�E�[�Ȃ��A�ؖȐD��̂ݎd��x�Ƃ���܂��B�����͂�������͖Ȃ̎����͂����鍠�́A�Ⴊ�~��ς��������A�c�����ȉԂŐ^�����ɂȂ����ƌ�����قǂ̖Ȑ��Y�n�ł���A�ȍ�A�ؖȐD��͔_�ƌo�c�̊�Ղ�����グ��ꂽ�L���ȓy�n�ł��邩��V���`�������L���Ȑ����Ɛ��_�̂�Ƃ肪���R�̂̒��ň炿�A���݂��Ă��邩��ƁA�M���Ă��܂��B
�@
���]�k�@
�l������
�@
���l������A���Ȃ�(����ق�)�[���t���������Ȃ��Ă��A�ߏ��Ő����o���̎�`���Ȃ�A�Ȃ�Ȃ�(�Ȃ�ł�)�A���ꂼ��Ă�ł�(�����)�A�O�|���Ȃ莝���čs���āA�Ȃ�Ȃ�Ǝ�`������Ȃ��B
�@
���ŋ߂͂Ȃ��Ȃ������ǁA�u�����ڂ̉��X����B�����������ł��v���ď��������A�܂�����Ȃ��B����͂������疳���Ȃ����̂��Ȃ�
�@
���F�X�Ȏ��������Ȃ����Ȃ��B�S���Ȃ�����w���悯�x�⌾���āA��������ꂽ�Ȃ��B���͏���ŁA�ō�����̂�����炵����B
�@
�����̂ˁA�������b�����ǁA�������̎�6���K������̂ɁA�p�ӂ��ĂȂ������̂����āA����łˁA����ĂĂ���ƁA���V�Ђ̐l���������6���K�o���āA�����炢����(���z)���܂����ǁA���ɓ���܂������Č���ꂽ���āB���V������͂Ȃ�ł��p�ӂ��Ă���炵���B����20�N�قǑO�炵�����ǁB�֗��ƌ������A�҂����ƌ������A�킩��ǂ��[�Ȃ�
�@
���Α��̎��₯�ǁA����œ��ʂɐd�g��ŏĂ����ȁA�r�����ɍs���ƏĂ��ĂȂ�������A�d�����Ă������Č����Ă����B���a�̏��߂���͐M�c�̕�(�����̕�̎�)�A����ɐV���ɂ��͍��ɂ��l�Ă���̉��˂�������˂��B�����������̍��͑��������Ǝv����B
�@
���͈̂�҂̐f�f�Ȃ�������A��t���Ă��n�߂�Ɗ��̒�����M���M�����Đ��������b�B
|
|
����n�̉Α��̎d�� |


 �@
�@ |
(����A�̏W���B���a50�N��𒆐S�̍̏W�������E���W�߂܂����B)
�@
�[���ɂȂ�ƁA�Α����n�܂�܂��B���ԂɌ}���n���A�@��Ȃǒn��ɂ���ĈقȂ邪�A�u���ꂽ�������Α����邱�ƂɂȂ�܂��B�Α�������l�͓��s�̑g�D�����鍠�̂��Ƃł�����A���s�g�D�̂�������ōs���܂����A(���s����e�y�ю��҂ɋ߂��l��Α��̐��Ǝ҂ɂ���čs���Ă����悤�ł�)�����̌o���҂����Ȃ��Ȃ�A�̏W���Ă��Ă��قƂ�ǂ��q�ǂ��̍��ŁA���ۂɂƂ肨���Ȃ����l�����Ȃ��Ȃ�A�w�l�̎��x�̋V��͑��������̂ŁA�e�ʁE����(���s�Ȃ�)�ȂǂłƂ肨���Ȃ����o���҂Əo��Ȃ��Ȃ�܂����B
�@
���Α���̖�����ł̉Α�(�Α�������)
�@
���͂��������Ȃ�܂������A���a�̎��㍠���́A�ǂ̕�ɂ��Α��ꂪ���Ă��܂������A������������܂����B���͂ǂ����������A�ǂ����Ă����v�������Ȃ��̂ł��������̉Α���ŁA�����N�z���܂������˂��A���a40�N��㔼���댩����������܂��B����ł���ׂ��̂ł����A��͂�A���҂��o�����ɉΑ������@���������悤�ł��B
�@
����͏����ߍx�̂ł����Ƃł����A�l�����Ƃ����ސS�́A�召�������Ƃ��Ă������łȂ����Ǝv�������ł͂Ȃ��̂ł����A���̎�����o���܂��B
�@
�m����n
(����A��̏ꏊ�A�����̋ߍx�ŁA�����s���Ɠ������A�͓��s��悪����܂��B�吳�O���͒m��܂��A�吳����̎��A����ɂȂ�Ɖ͓��������x�o���̂ł͂Ȃ��A�e�ʂ̎҂ƃO���[�v�ŁA�܂������������l�ɏo����Ă��܂��B���͓̉�����̈�ƌ�����B��̘b�B����10�N��㔼�̏W�B���蓖��70�Α�B�j��)
�@
�����ł��Ȃ��B��͂肱���Ő��܂�āA�����ň�������̂́A���ʂƂ��͂�͂�s���̂���ɂ͂��肽���̂ł���Ȃ��B���̂���������ň̂����߂܂������B�s���̕悪�����ς��ɂȂ��āA�n�����̓y�n���Ȃ��̂ł���B����ŁA����n���Ă�����ƌ������ɕ悪�ł��邱�ƂɂȂ����̂ł���B����Ɩ{�Ƃ̎҂͕悪����܂���Ȃ��B�V�������ƂɂȂ�ƕ���Ȃ��B(����Ȃ���Ȃ�Ȃ�)�����ł���B�Ƃ������ł��낢��Ȗ�肪�������悤�ł��B����Ȃ���ȂŁA�Α���̖�����(�s���̕�ȊO)�ւ͍s�������Ȃ��B���Č����āA���߂��b�ƁA�Α���̍����ƁA�Α��̎d��������܂����B
�@
�������A����͏����ł͂Ȃ��ߍx�ł��B
�@
���Α���̍���
�@
����l�͓��s���͒n��̐l�ō��炵���̂ł����A���͒m�����Ȃ��̂ł悭�킩��Ȃ��B�͂��߂Ɏ��̏Ă���̓y�n�ʂ������āA9�ڂ̊ۑ��̖_�������Ɖ��˂ɂȂ�Ƃ������܂����A���Ă��A4�{�̊ۑ��𗧂ĂĘm�������ĉ�������蓛�^�̒��ɓ����̂��Ǝv���܂��B
�@
���ꂩ��A�m�Ŋ�������A�����z�ł܂�����A����������Ƃ���̂ł����A�����𗝉����邱�Ƃ��ł����A�悭�킩��Ȃ��B��R�̘m��d�A�Y�Ȃǂ���R�K�v�̂悤�ł����B���������ԑO�������Ă����������̂ł����A���s�̑g�D�̏d�v�������܂����B
�@
�e�ʈꓯ�ŏo������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���܈��Ă��˂��ɗ�������悤�ɉ��x�������������ď������Ƃ����̂ł����A���ɂ͖����ł����B�킩�������́A��l�̎��ɑ��āA�n��̐l�B�S���̋��͂��K�v�ł��낤�Ǝv�����B�������l����ł����A�m��Y�A�d�̗ʂ̑����B�܂��l�Ă��͑��z������ł���Ă��n�߂ė����̒��ɏĂ��������Ă����Ԃ̂悤�ł��B�钆�́A�g�������ɍs�������ł����A���X�̂܂������ɍs���āA�_�łЂ�����Ԃ��Ȃ���Ă��̂������ł��B��Ӓ����������݂Ȃ���Ă��̂������ł��B
�@
���]�k�@
���V�͐l�̈ꐶ�̒��ł��A��ԑ�ł����A�V��̕��������܂��傤�Ƃ����ďo������̂ł��Ȃ����A���V�̋V��ɂ����Ă��A�Ǝ҂֍s���ċ����Ă��炤���ł͂Ȃ��B����7�A80�Α�̐l���Ǝ҂Ɏ�`���Ă����������o���҂��قƂ�ǂƂȂ�A�����܂ł͂킽�������ł������ǁA��������͋Ǝ҂ɂ��̂�ŁA���Ă�������B�ȂǂƁA�Ȃ��Čo���҂��}���ɂ��Ȃ��Ȃ�܂����B���e�������I��������̓����玟�̍̏W�ɂƂ肩�����āA�����ł����삪�����Ǝv���قǁu�����Ă͂Ȃ�A���v�ƁA���͓I�ɍ̏W�����Ă��܂����A���a40�A50�N�゠����̍̏W�i�̕ł��߂��鎖�������Ȃ�܂����B����Ȃ킯�ŁA���I�[���ł͓B��ł��Ȃ��B�S���͎̂g�p���Ȃ��B�Ȃǂ��o�Ă��Ă����̏͂͏I�����Ă���ȂǁA���Ă��܂��B
�@
�����������Ƃ���A�������ƂȂ������邾�낤�Ȃ��Ǝv�����A�̏W���Ԃɍ��킸�A�������тꂽ���Ǝc�O�Ɏv���Ă���V����A�u���Ɛl�̐S�v�Ȃǁw������Ɨ]�k�A�l�������x�̍��ڂ����邱�Ƃɒv���܂����B�w�����̐l�X�̈ꐶ��107��x����A�V���[�Y�Ƃ��ē���܂��̂ŁA�����lj������B
�@
���̂��߂��̃V���[�Y�ł́A����͂������ƑO�̍��ڂ��Ƃ��A�܂���̍��ڂ��Ƃ��L��܂����A���̍��ڂł́A�������ڂꂽ�A�������ڂꂻ�����A�u�܂����v�Ǝv���ď������������́B�����������̂������Ă����܂��B�������w�t�����x�ȂǁA��������������ł��p�ӂ��Ă����˂Ǝv���Ă���A�N��̐l�B�ɂ��Q�l�ɂȂ鎖�ɏo���킷��������܂���B
�@
������҂҂���ɂ��Ă�������
�@
(�b�ҏ��a4�N���܂�A�j���̖�)
�@
�Z�͏��w�̒܂��ɂ��Ă���B�܂̍��̏�����5��(���ԁB2cm)�L���Ă���́B�푈�ɍs���Ă��鎞�A�F�A���w�̒܂�L���Ă���̂����āB���Ƃ��ɁA����̍��̑ւ��ɁA�܂����āA�R����e�ɑ����Ă��炤�̂����āB��n�ŁA�����M���đ�ɒN�����܂�b���āA�����Ă������āB�I��㍡�ł��b���Ė����Ă�����āB
|
|
���y�� |


 �@
�@ |
��(1)�ȒP�ȑ��V
�@
�o���́A�ŋ߂͒�10���Ə����Ă���̂�����悤�ɂȂ�A�����瑒�V�Ƌ����Ă��܂������A��������2������3�����A��ԑ����悤�Ɏv���܂��B�̂́A�����͕�̏Ă���ŏĂ��̂œ��v�̌オ��ʓI�ł����B�y���̏ꍇ�́A�A�肪�x���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ŁA�G�߂ɂ����܂����A��͂�2������3�����Ó��Ǝv���܂��B�������A�ŋ߂͂����������V�̒��莆���݂Ȃ��Ȃ�܂����B
�@
���V��2��킯�ł͂Ȃ����A�n��̐l�̏ꍇ�͏o������斘�t�������āA�H��������B
�@
�e�ʉ��҂�n��ł����ɐe�����l�⓯�Ƃ̐l�B�́A�H�����I���ƕ�֊���[�߂Ă��瑒�V�҂̉ƂɋA��A���̑m���Ăьo�������Ă�����āA�����Ԃ�鍠�����ݐH�����āA���̑��������B���̂܂G���Q�ƂȂ�ЂƂ����邪�A�d���ɂ��������݂̂₰��������Ă�����ЂƂ�����܂����B�̂́A�������Ƒ��V�͓������炢����ɍs���܂����B����䂦�ɊȒP�ɂƌ����A�n��S�̂��炾���ł������ė��Ȃ��Ă͂ƁA����Ȃ�ɑ�ςł��������Ƒg�D�Ƌ��ɓy�n�ɏZ�ގ҂̋`���A�l����܂߁A�ݏ��I�`�Ԃ��܂ߑ�ςł����B
�@
��(2)��������Ƃ��鑒�V
�@
��1�D�Z�����l�B�≓�����炫�āA���V���I���Ƃ����A��l�Ȃ�
�@
���a4�A50�N��ɂȂ�Ɗj�Ƒ��������n�߁A���Ɣ_�Ƃ�x�k�c�������Ă����悤�ɂȂ�܂����B�����������������Ă��A��X���܂ł̂��炾�炵�����V�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@
12������1�����y���H������ɂ��ɂ����H�ׂ܂��B
�@
���̂��ɂ���́A��Y�̐l���������ƌ����Ă���炵���B�H�ׂ�ƈ��Y���ƌ��������`��������炵���B
�@
���o��������
�@
�����̏ꍇ�́A��͒n��A�n��ɂ���̂ŁA�ǂ̉Ƃ���������Ă������Ď��Ԃ̂�����Ȃ����Ɏ������������̂�(���ƕ悪�ꏏ�̏������邪�A�������ꂽ���ɂ��鏊�����邪�]�藣��Ă��Ȃ��B)�o�����āA��֒����ƁA�}���n������̑O��A�@��̏�Ɋ���u���āA���̎���܂��ɂ���A��̋x�e���̗l�ȕ����A���͎��̂������������ɏオ���āA�r�傪�斘���ĉ��������l�ɂ���������āA���O���b�ɂȂ����G�s�\�[�h�Ȃǂ�������㗿����H�ׂāA1���Ԃ���2���Ԉ��ݐH�����Ď��R���U�ŋA���čs���B
�@
��2�D�o��
�@
���Ƃ��o�鎞
�@
���͂����������~�ɒu���Ă���܂��̂ŁA���~����o���̂���ʓI�ł����A�o���͂����������ֈȊO����o���Ă����悤�ł��B���ֈȊO�o���o���鏊���Ȃ��ꍇ�́A������ł��悢����A���ւ͍T���������悢�ƕ����܂����B
�@
�o�����o�鎞�͏o���̕~���ɃS�U��~���āA�~�����܂������B�����ē���ł͂����Ȃ��ƌ�����B
�@
���̋V��͓���Ƃ͔��̎�������̂��펯�ŁA���������O�ɒ��t���A�H������{���A�Ȃǂ��낢�날�邪�A�~���܂Ȃ��͓̂��퐶���ł��~���ނƁu�e�̓��ނ̂Ɠ����v���Ƃ�����ꂽ�o���҂������Ǝv���܂����A�~���́u���o�̎R�v�Ƃ����ĕ~���̏�Ɋ�����U�����Ă���^�яo���Ƃ��������炵�����A�����͓���ł͂��Ȃ��ƌ�������A�܂������̂��낤�Ǝv���܂��B
�@
�����o��ƁA���҂����O�g�p���Ă������q���A����o��O�̏��ł��܂��B��������悤�ɂ��Ċ���܂��B���q���A���𗧂Ăăo�V���[���Ƃ��̂́A�삪�A���ė��Ă��A���������ŐH�ׂ���̂͂Ȃ��B���̐��ŐH�ׂ�̂��Ǝ��҂�����̂��Ƃ̎��ł��B
�@
�܂��A����A��A���ƉȂǂƂ����Ăі��ʼn�R�₷��������܂����B���̋V����삪�A���Ă��Ȃ����߂ƌ����l������܂����A���҂��s�������Ƃ炷�̂��ƌ����l������܂��B
�@
����n�ւ̓�
�@
��n�ւ̓��́A�ȑO�����Ă���悤�ɁA��ւ̓��ɂ͐|�ɉ֎q�ȂǐH�ו��Ȃǂ����̗��[�ɍ������܂�Ă���B�X�C�A�����Ȃǂ������Ă��鏊���������悤�ł��B�܂��������A������������Ă����悤�ł��B��n�ւ̓��ł͘b��������U���������A���Ă͂����Ȃ��B�삪���Ƃ������܂����B�܂��A�����^�l�ɂ͐H�����O�́u�L�����v�ȂǁA���ꂼ��ɂƂ��ׂ������ς������悤�ł��B
�@
���]�k�@
(1)�ʔv�̏���͂ǂ���
�@
���ʔv�̏���͕�����������ĉE��������B�������ł��B
�@
����̘b
�@
��l�͒��j�B���������B�������ēт̈ʔv������܂����B
�@
�ł���̐�c��X�̈ʔv�B�����̐�c��X�̈ʔv�B��l�̈ʔv�B���̈ʔv
�@
(2)���O����(�t����)
�@
����̘b
�@
��l���S���Ȃ������A���̉�����������B�؏��������āA����������Ă����Ƃ��ꂪ�@�h�̏ؖ��ɂȂ�B�w�t�C�V�x����������Ă���Ǝ����S���Ȃ������A�h�ƂłȂ��Ă����v�Ȃ��āB
|
|
�����̂��낢��1 �E�E�E���̐��ł̏I�� |


 �@
�@ |
���̐��ɐ��������Ă����l�������}����ƁA���ɕ�炵���������̐��ɐ������l�Ƃ̌����ƐS�������Ă̂Ȃ���́A���V���I���Ƃ��̐��Ƃ��̐��ɕ�����āA�݂��ɕʐ��E�ɑ��݂��A�����Ȃ�w�͂������Ă��A�݂��������ƐS�������ĂȂ��鎖�͏o���Ȃ��Ȃ�܂��B���̂悤�Ɉ�l�̐l�������̐������������V�����w���V�x�ƌ����܂��B
�@
���ẮA���̌��l�Ȃ�V���ɑ��āA���͏����ł́A�Ǝ҂��s���A���V�o�Ȍo�����������Ă��܂���B�����̏Z������̍̏W���W�߂Ă����̂ł����A���̌��l�Ȃ���̂��A�����Ǝ҂���̋V�������o��Ȃ��Ƃ��Ă��A�s�ސT�ȋC�����āA�܂��̌����e���ǂ������l���ŁA�ǂ����Ă��S�������݂܂���B�����ŁA���Q���암�ł̑��V�̌���u�������ďЉ�܂��B�Ȃ��A�����ł̑̌��́A���V�Ђ̃p���t���b�g�Ɠ����`�Ԃł��̂ŏȂ��܂��B
�@
����ӑ���
�@
���̌o���ł͏����ȑ����ł��̂ŁA�����e�˂���̌ˎ傪�S���Q�����܂��B�o������ƁA����S�����l��擪�ɓ��e����e�ʑ����̐l�������܂��B����擪�ɁA���̂悤�Ȃ��̂������ďĂ���܂ōs�����܂��B
�@
�����҂̎ʐ^�E�E�E���g�̖̑�t���̎ʐ^���Ăɓ���Ă��܂����B�y�n�̎ʐ^����������������Ă��Ă��A���ꂢ�Ɏʂ��ĉ������܂����B
�@
�����ʔv(�ʔv�͂܂��ł��Ă��Ȃ��̂ŁA�����X�Ɏ���҂��Ă����悤�Ɏ��̑O����́A�p�ӂ��܂���B����́A���ɑ��������u�����A����Ăĉ��l���̐l���}���ō��̂Ɠ������_�ł��B�����ŁA�������������������ɂ͑�������Ƃ����C�����ŁA���ʔv�ɂ��܂�)
�@
���ʔv�̍����́A�u�Ђ��v�Ƃ���|���ׂ��c����ɂ����|���AU�^�ɋȂ��A�̏�ɒ|�Ђ������āA�����������Ԃ��āA�����������āA���ʔv������܂��B
�@
�����̑��ɔ_���ƁA�䎛�ɂ��ꂼ��̗p�r�ɂ���ĕۊǂ���Ă��鑺�����L�̕����g�p���Ă��܂����B�ۊǂ���Ă��Ȃ����̂́A�n��̎҂ɂ���ċ}���ō��܂��B
�@
����(�͂�)�A4�{��(���ق��)�Ƃ����āw���s����x�w���ŖŖ@�x���̎l���n��̕��@�����������̂�4�{�����܂����A����������܂��B
�@
(1) �l�ԁE�E�E(�锒������4�F���A���ꂼ��̐F���������čג����|���ɂ������ŁA�Ђ�Ђ炷��悤�Ɋ����t�������̂ŁA�����́A�ג������ɍ��E�������ڂ����āA�ג����|���Ɏ߂ɗ����`�Ɋ�������ƁA�Ɠ��̎ΐ������łЂ�Ђ�Əo���܂��B
�@
(2) �l�E�E�E(���̎��Ƌ�̎����ג����|���Ɋ�����4�{����āA�����r���ג����R�b�v���ԃr���ɂ��Ă����܂��B��������Ԃƌ����܂�)
�@
(3) ���ԁE�E�E���������l�قɐ��ĉԂ����A���V�������ɂ��āA������̑卪�Ɏh���܂��B
�@
�\��(�܂�)�┦(�͂�)�Ȃǂ̐F�́A������5�F�B�_�l��7�F�������ł��B�̂͂��̒n��A�n��ɐ_�Ђƌ䎛������A���܂�鎞�͐_�Ђŏj�������������A�ꐶ���I���鎞�͌䎛����ŕ��l�ɂȂ邽�߂ɁA���̒n��̂���ɂ���Ă��������܂��B�܂�A�����̒��ɐ_�ƕ��������ɑ��݂��Ă��܂����B�Ⴆ��12��31���̖�ɕ��d�̌˂�߂Č䐳��������}���܂��B�~�ɂȂ�ƍ��x�͐_�l�̐_�I�ɔ����Ŗ����Ђ��A�����ĕ��l���}���܂��B�܂肱�̃G���A�͐_�A���͕��̒n��ł��B�Ɩ��苤�L����̂ł��B�\
�@
��������(��イ����)�E�E�E�|�ɐԂ���ɔ��f�̗t�݂݂̂��������B���̂ق��C���Ȃǂ�����܂����B�܂��ܐF(�����̐F)�̐���������ΐF�̍��̂����|�Ȃǂ�����܂����B
�@
�o�����Ԃ͂������͂����������ŁA�ꎞ���ɂȂ�Ǝ��X�ƏW�܂��Ă��܂��B���������W�܂�Ɓu��������Ƃ��͗��Ă邩�v�u�Ăтɍs���Ă��A�q���ނ������Ă���ƁA��͂������邩��q���A��ė�����v�Ƃ����̂�A�ƋC���g�������A���������܂��B(��ӑ���֍s������ЂÂ���A��ӂ���A���Ď����o�����l�̘̐b�Ȃǂ��āA�ÂԐȂ�A��̎��̂��y�Y���Ȃǂ�����l�B��l��A��`���҂̈Ӗ��������āu��v�ƌ���)�Ƃ������肵���A�����낭��������āA�n��S�̂ŁA������܂����B
�@
���Ă���̕�֒���
�@
�Ă���֒����ƒ������A�~�`�Õ��̂悤�ɂȂ��Ă��āA�������O����ɂ܂��A��������ɒu��10�ؑ��炸�̉Ƃ������āA�����ɐH���ƁA������p�ӂ��Ă����āA�����Ŏ��҂��Ă��I���܂ŁA�҂��܂��B�����ŁA�r�傪�A���҂Ƒr�傪����������a��A���̘b���Ƃ����āA���҂����炩�ɏ��V��������A�n��̐l�B�̌���ŁA�������Ă��̐��ֈ��炩�ɍs���鎖�݂͂Ȃ���̂������ł��鎖�A���ꂩ�����낵���ƈ��A�����āA�H���Ǝ����ނ��킵�A���҂̐��O�̓����������Ȃ��玞�����ƁA���e�͐Ȃ𗧂��A�����E���ɐȂ𗧂��܂��B�����ŁA���J���ƂȂ�A��y�Y�̂����Ȃǂ̓������܂�l�������āA���R�ɋA��Ă����܂��B
�@
���A�鎞�̒���
�@
�A�蓹�͎q�ǂ��ł��悢�̂ŁA�j���ƈꏏ�ɋA��B���������ł͋A���Ă͂����Ȃ��B�������Ɠ�������ʂ��Ă͂����Ȃ��B�K���ʂ̓���ς���B��l�ł͋A���Ă͂����Ȃ��B�U������Ă͂����Ȃ��B�]��ł͂����Ȃ��B�ƌ����`�����Ă��܂��B�����j��ƁA�삪���ė���Ƌ���A�������܂��B
�@
���ƂɋA���
�@
�Ƃ��o�����̏o����������Ă͂����Ȃ��B�Ƃɓ���O�ɉ���̑S�̂Ɋ|���Đ��߂�B
�@
�����T
�@
���T�́A�u������݁v�Ƃ������܂����B�����͔_�k�����҂ɂƂ��đ�ςł����̂ŁA��Ă�A�������A���ǂ�Ȃǂ̕��i�����Q�����悤�ł����B�ǂ̉Ƃł��ꏡ�܂͑�X�g�p����̂Ōp���Ă����̂�����܂����B�ꏡ�܁A�O���܁A����ԑ����g�p���Ă����悤�ł��B
|
|
�����̂��낢��2 �E�E�E�y���E�����E�Α��E���� |


 �@
�@ |
�ŋ��ł̌䑒���ɂ͓y��(�n)�A����(��)�A�Α�(��)����(��)�A��4��ނ̕��@������̂������ł��B����́A�����̎��̍̏W�i�m�[�g����ł͂Ȃ��A����֔��s����Ă�����s���j����������ʐM(�u�b�̎�ɁA6�vH20�N4��1�����s�B��y�@���y���Z�E�E�O���p�F��)�ɍڂ��Ă��܂����B����ɂ��Ɛl�����ʂƁA4��ނ̂������ő��V���s���邻���ł��B������l��(������)�ƌ����A�ŋ��p��(�H�Ǝv���܂�)�ŁA���B�̎��͂ɂ�����̂́A�w�n�A���A�A���x�̎l�傩��o���Ă���Ƃ����Ӗ��Łu���V�l���a�C�v�ƌ�������\�����t���u�l��s��(�������ӂ��傤)�v�ƌ����̂������ł��B
�@
���B�̐g�͎̂l��Ō`������A���ʂƁA�y��(�n)�A����(��)�A�Α�(��)����(��)�A��4��ނ̕��@�ő��V���s����̂������ł��B
�@
�����n���V�ɂ��ā\�y��(�n)�A����(��)�A�Α�(��)����(��)�\
�@
��(1)�n�c�y���B
�@
�n�͓y�̎��ł͂Ȃ��u�`�����邱�Ɓv�������̂������ł��B�l�Ԃ̎����Ă���`���镨�Ƃ́u�g�̂��`�v�ƌ������ƂɁA�Ȃ�悤�ł��B
�@
�����̓y���̊��́A���̍̏W�ł́A����(�܂�����)�ƉΑ�������܂���(�����͓y���������������y�ɖ��߂���@�ł����A���e�ɂ�茾�t��I�т܂��B�\���ڍח�)�����͖����̕�Ŏg�p���Ă��܂����B�̏W��U��Ԃ��čl���܂��ƁA�y���̕����Â��A�Α��̕����V�������V�@�ł��낤�Ǝv���܂����A�Α��̏ꍇ�͍s���ƌ����A���ɏĂ��ꂪ����܂��B�ƂȂ�ƁA�s��悪��������o�������̂����ɂȂ�܂����A���ݎ��̍̏W����͉��o���Ă��܂���B���̍̏W�ɂ��ƍ������V�̌��҂͏��a10�N�ȑO���܂�̒j���ŁA�Ȍ�͐Q���ł��B�����Ƃ͒M�̒��ɑO�����݂Ɏ葫��g�̂��d������O�ɋ}���ŋ��O�ɐ܂����݁A��K�����ɂ��ĒM�̒��֎��҂𗇂œ���A����o���Ē����𒅂��悤�ɁA�ォ�甒���z���|���܂����B�������A�Q�������Ɍ������A���R�ɓy�ɂ������Ă���閄�����@�ł��B
�@
�������A�����̏W�n�߂����a40�N��O���̎g�p�͂Ȃ��A���s�Z�j�ł������A�܂��ǂ̕�ɂ��Α��p�Ă��ꂪ�c���Ă��܂����B�����̉Α��A�y���̋V��ɂ��ẮA���V��Ƃ��[���A�����ɑ�����舵���Đ������Ă��܂��̂ŁA�����ł͏ȗ����܂����A���͖��Ԍ����`���b�̍̏W�ɗ͂����Ă���̌����炵�܂��ƁA�����ɂ͉Α��Ɠy�����ނɂ������b�͐������c���Ă��܂��B�Α��͓��R�Ȃ���s��b�ł��B��������͑S���I�ɕ��z���Ă���y����������u�������H��c�َ���g���������܂��ꂪ�A�������o�Ĉ����ɍs�����b�v���A���l�Ȍ`�Ԃŏ����ł��`������Ă��܂��B���̌�b��f�i������y���̕��@�ŁA���҂͖�������܂��B���̖����͎��̂悤�ȕ��@�ł��B
�@
�挊���@��O�ɁA�܂��_��n�ʂɎh���Č@�鏊�ɑO�C�҂̊����Ȃ������ׂĂ���n�ʂɂ�����(�l���Ǝv���m�F���Ă��Ȃ�)�u���āA4�ڂ���7�ڂ��炢�y�̉��ŁA�ꂵ���Ȃ��悤�ɋ�C�������܂��B�����ׂ͍��|�̖_����߂������ė��Ă܂��B���Ă͏����ł͂���܂��A�y���ɂ����낢�날���Ď��̂悤�Ȍ`���̂��̂�����悤�ł��B������A3�N���x�ōēx���@���A���̍����ɓ���Ă���ɔ[�߂���@�����邻���ł��B���̎��A���ɂ��ƌ@��o�������𐅂ł悭����Ĕ[�߂���@�������K�����邻���ł��B
�@
���̂ق��ɁA����ȓy���ɂȂ�܂����A�G�W�v�g�̃s���~�b�g�Œm���Ă���u�~�C���v�����A���{�ł��������悤�ł��B���͎c�O�ɂ��m�炸�A�����ł��܂��A���k�n���Ɂu����3��v�̃~�C��������̂͗L���������ł��B���̎���́A�o�H�O�R�́u�ؐH��l�v�̎���ł��B��l�͐��O����̎���\�o����H�ׁA�����Ă��鎞����y���̊��ɓ���A����~�C���ɂȂ�悤�w�͂��ꂽ��������邻���ł��B(�����̎���ŁA�y�������̋V�炪�����Ȃ�ꂽ����͓��s�̑g�D���c���Ă������̎���(���̓��s�Ŏ��ۑ̌��̏W�͏��a48�N���ŏI)
�@
��(2)���c�����B
�@
���݂͂قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ������ł��B�Â��L�^�ɋI�B�̌䎛�̏Z�E(���̖��O������Č�����)���A�S���Ȃ������A��̂����M�ɏ悹�ĉ��ɕ����@���������Ə�����Ă��邪��������̐����ł��傤�Ƃ���܂����B���݂͍q�C���Ɏ��l���o�A�̍��ɁA��̂�A��A��Ȃ����̂݁A�����֒��߁A�D�J���炵��3�����ċ���V������邻���ł��B�����̐����V��̍̏W�͂Ȃ����A�`�Ɛ�̗p�r����Ȃ��ƍl���܂��B
�@
��(3)�c�Α��B
�@
���̂��Ă��āu�����v�ɂ����J����@�ŁA���{�ł͕����ƂƂ��ɉΑ��̕��@���A�����ꂽ�B�����u�����ꂽ���́v�ƍl�������{�l�ɉΑ��͑f���Ɏ�����A���݂ł͓s��͂������A�c�ɂł��Α��������Ȃ����Ƃ���܂��B
�@
���Α��Ɠy���͏����̑��V���@�Ƃ��āA�̏W������܂��̂ŁA����Ƌ��ɂ̂��Ă��܂����A���̎������Ă���܂����ʂ�A�����͍s���̕��K���ŋ߂܂Ŏc���Ă���܂��B�s���ɂ́A�Ă��ꂪ����܂����B�����̕��K�ŁA�͓�����Q��A��������Q��A�n�掵��Q��̕��K�͑�Ɏv���Ă��܂��B���̍̏W�ł́A���a15�N���܂�̏����ŁA�n�掵����A�o��ǂނ悤�Ɉ�C�ɘb���ĉ�����A��e�ƕ���������܂���A����̂������Ǝ�������Č��l�Ȃǂɏo����āA���b����ŏ����Ă���܂����A�s���M���Ă���̂ł͂Ȃ��A�s������R�̂Ŏ����p�́A�����������p��w�L�I�̏����x�ƌ��킵�߂�y��̗͂�������܂���B�܂������u�q�ꂽ���́v�ƍl�������{�l���]�X�ƍl����̂��A�Ȃ�قǂƎv���܂����A�����ɂ͏������u�q�ꂽ���́v�̎v�z�̌��_�ƍl���錌�~�o(�R�c�R�c��30�]�N�������Ă��܂����A���o�ƌ��������ܗ������ł��B�������A�����n��ɓ`�����閯�b��S�ɉB���ꂽ���t�̉�ǂ̊����Łu�������q��v�̉��̌��o�ƂȂ����ɉ�Ǝv���Ă��܂��B
�@
��(4)���c�����B
�@
�ŋ߂́u�����v�̌ꂪ�����Ă��邻���ł��B���̂��O�ɒu���A����b�̎��H�ɂ��A��������̂ɔC���邻���ł��B���{�ł��Â��͕������s���Ă����炵���A�u��S�����v�ɂ͂��̗l�q��������Ă��邻���ł��B
�@
�\�l��(������)�ɂ��Ă̊w�╔���͏�L���̊�e���Q�l�����Ƃ��Ă��܂��B�\
|
|
�����̋V��Ǝ��̋V�� |


 �@
�@ |
��1��15�N�u���D�v����n�܂����w�l�X�̈ꐶ�x������25�N��3���A����ŏI���ƂȂ�܂����B�җ�̔N����n�܂��ČÊ�̔N�ŏI���Ƃ͐��ɗL��K���҂Ƃ��Â��Ɗ�сA���܂ł����ǂ��������x���ĉ��������F�l�S�����\���グ�܂��B
�@
���āA�l�͂��̐��ɐ��������Ēa�����A���ɂ���Ă��̐����炠�̐��ցA�썰�Ƃ��ĉ���̍��֑����A���̐����A���̐�����߂�ꂽ�N��A�N���ɂ���Ė����d�˂��A�����ō��ꂽ�V����d�ˁA�����̐ߖڂ��N���A�[���Ȃ��炠�̐��Ƃ��̐��ňꐶ���I����ƍl�����Ă���̂łȂ����ƁA�l�X�̈ꐶ�����������݂Ȃ��犴�����܂����B
�@
(���L�̋V��͏����Ŗ����A�吳�A���a10�N��̐�O���܂�̐l����A�����ȑO�����c���ݏZ�҂ŁA�ߋ��͕ʂƂ��Ēʏ̈̂��l�A���������̉�(���ƁA�������Ȃ�)���������A�m�l���Ԃ̕��X����̍̏W�ł��B)
�@
�@�@�@�����̋V��������̋V��
�@
���a��(�o�Y)
�@
�Y�C�Â��Ɛ_�I�A���ԁA��K(�_�I�A���d�̏�ɂ���̂�)��������)�[�ˁA�y�ԓ��ɘm��~���n��̎Y�k����ɂ���ďo�Y�B
�@
�����S(��)
�@
�����m�F���铯�s�֒m�点���s�͎��֒m�点�A���V�W�͓��s�̌ݏ��g�D�őS�Ď���s�Ȃ��B
�@
���Y�_�ƎY��
�@
���܂��Ƃ����A���сA�����ɐ쌴�̐��Y�_�l������B(3)�A5�A(7)�A(8)�A11���ڂɐԔт������܂��B()��������͂��A���A���A��̂ǂꂩ���������33���ɂ��тƏ��������Ă�������̑V�ƌ����܂��B�Y�w�́A���ؒ��㕪�؎��ō����������ށB���ꂩ�犟��_�炩�����т�3�����炢���̌�͂��тɓ������������̂���t����B
�@
������
�@
���сA�����ς�A�����тȂnjĂі�����B���ʂƂ�����łЂƂ������A�Ă��Ƃ��Ȃ��ŕ����B�����l�͂����Ă�����������l��g���̎҂������B���т͎g���̂Ă̂�������Ɉꗱ���c�������O�g���Ă������q�ɐ���B�Ђ����Ƃ��o�鎞�A���ւł��B���q�ɂ͔�����{���Ă�B
�@
���Y��
�@
�Y���͑卪�̗t�A���A���A�����ł��n��ɁA�Ƃɂ���ĈႤ���A�Y�k�ɂ���čs����B�Y�k�͍������ɍ����đ������炢�ɓ���A���̏�ɐԎq��u���ĐB���̏����͕֏��A�엿���߂Ȃǂ֎̂Ă�B
�@
������
�@
����̓��͓���̂��܂ǂ��g�p�����O���y�Ԃŋt�����œ������V�L�r�≖������A��ꏬ���̂��炢�͎��B���ςނƎY�w�ȊO�͎��ɉ��ς�����B
�@
���O���j��
�@
�O����(�݂�����)�j���B���n��(�䂼��)�̏j���B���ƌĂԁB�V�����ɓ������킹��������B�����͍g�Ŋz�Ɂ����O�A�j���͑�Ɩn�ŏ����j���Ƃ��Y���𒅂��A�܂�тƖj�g��t����_�Ђ֍s���Č䕼��������Đ��ߕ֏��Y�����𐴂߂���A���͂��������ȂǁA������͉�Ⴄ�Ƃ�����B
�@
���O����(�����̗���)
�@
���V�͓��s�ȊO�̐l�̎�`���͂Ȃ����s�Ɛg���݂̂łƂ肨���Ȃ��܂����A�O���̒��ɂȂ�ƁA�����̐l�B�����Ă������Ă��Ďז����Ȃ��悤��`���ċA��B�����Q��ŕ�֍s���m����e�ʒm�l�Ŗ@��������B49�����̂���グ�@�������Ă悢�B
�@
��������\�\���Ђ���
�@
�E�u���C���C�E�}�N���q�L�ȂǂƂ��Ă�܂��B�o�Y�O����q�ǂ��̖��O���l���A�����Ɏq�ǂ��̖��O��t�����ɏj���V�̎��ɔ��\����܂��B�V�ɂ͒c�q3�ƐԔсE���E���E�����Y�_�l�ɋ����܂��B
�@
��������
�@
�V��͂����Ă����̔{���ōs���܂��B�ЂƎ���(������)�A�O�\�ܓ��A�l�\����Ƒ����Ă����܂��B�����̓��́A�m�����Ăі@�v�����Ă��炢�܂��B
�@
���O�\�O���̋{�Q��
�@
�������ƂɕS���O��ɉ��x���Y�y�l(���Ԃ��݂���)�{�Q������܂��B�j���Ƃ��O�\�O���ɏ��Q�肪�s���܂��B���̓��́A�n��ɂ���`�O������܂����A���̓������Q��Ő_�̎q�Ƃ��āA�������ɎQ��܂��B
�@
���O�\�ܓ��̊�����
�@
�O�\�ܓ��܂łɕ�O�ɓ��������āA�e�ʉ��҂��ĂсA��O�ŋ��{�̓njo�������Ė@�������܂��B���̓����������Ƃ����A���i���Ƃ��ŋ�����H�ׂ܂��B�O�\�ܓ����I���ƁA�Ƃ̐_�I�ɃI�q�J���������܂��B
�@
�����̑�
�S���̂��H�����߁A���ߋ�A�������A���a���Ƃ��Ĉ�N�ƂȂ�܂��B���Ő_�̎q����l�ԂƂ��ēƗ����ꎵ�O�̋V�炪����܂��B�_�̎q�Ɛl�ԂƂ̊E�̉S�Ƃ��āu�Ƃ����v�̓��w�Ɂ�s���͂悢�悢��(�_�̎q�Ȃ̂ŁA���v)��A��͂��킢��(�l�ԂɂȂ��āA�������|��)�Ƃ�����߂�����܂��B���������ɏo��q�����܂����B(��:������)
���l�\����̊�����
�}���`���E�C���Ƃ����A���҂̗썰�́A���̖@���̏ނ̉��Ƌ��ɂ��̐��ɗ����Ƃ����܂��B�����āA�S�P���A���~�A������A�N��������܂��B��ʂɂ͎O�\�O�N�̒��グ�ł����܂����A�\���������܂��B����͏j���ƂȂ�A�r���͒��Ȃ��ŏj���̒����𒅂܂��B�\����܂ł͕��Ō\������I���Ə��V���܂��B �@ |
 �@ �@
���u���v�r�� 2 �@ |


 �@
�@ |
���ՏI����ʖ�܂�
�������̐�
�����Ă͐l���ӎ��������A�ՏI�ɂȂ�ƁA���̐l�̍����Ăі߂����߂ɁA�j�q�������ɓo��吺�ŋ��ё�������A�������܂�����A��ɂ������肵���B�吺�Ŏ��҂̖��O���Ă�ō������Ƃ��߂����Ƃ��邱�Ƃ��u������v�Ƃ����B�܂���ɐ�����������A�������܂��邱�ƂŁA���Ƃ������Ԃ��Ăق����Ɗ肤�⑰�̐؎��ȋC�����̌����ł���B�u���ɐ��v���邢�́u�����̐��v�́A�M�A�ȁA��̗t�𐅂ɐZ���A����Ŏ��҂̌������邨���A���̗͂Ő����Ԃ点�悤�Ƃ����̂ł���B���̎��ɐ��́A���̒��O�ɍs�Ȃ�����̂ƁA����ł���s�Ȃ���ꍇ������B�܂������̋߂Â����a�l���A�������݂����Ƃ������Ƃ��u�肢���v�Ƃ����B
����̂̈��u�̋V��
��̂͂قƂ�ǂ̏ꍇ�ɖk���ɂ���B�Ƃ���ɂ���Ă͑���������������ɂ͐����A�m���Ă�Ŗ��o������Ƃ��ɂ͖k���ɂ���B�܂��k���Ɠ����ɁA��𐼌��ɂ�����Ƃ��������B����́u���k�ʐ��v�Ƃ����āA�����\�����y�ɋɊy������Ƃ���������y�M��A�߉ނ����ςɓ��������Ɏ�����p���ɕ키���̂ł���B��ɂ͂��炵�������A��͋��̏�ō���������B�z�c�⛠���͏㉺�������܂ɂ��鏊������B������u�T�J�T�S�g�v�Ƃ����B�܂���̂𐴂߂�(������)�Ƃ��ɗp���铒�́A��ɂ��炢�̂Ȃ��ɐ������Ă��瓒��������(�T�J�T�~�Y)���@�����B�����͋V�����p���s�Ȃ��Ƃ��̓����ŁA�����R�̗͂������₷�����������邽�߂ɁA����ōs�Ȃ���K�����ӎ��I�ɔr������킯�ł���B�����ɂ́A���҂̍��͌����Ƃ��Ƃ��Ƃ����ɂȂ��Ă��邽�߁A���҂̐��E�ɂ����������킹�����̂Ƃ����B�����Ė�Ԃɑ�����s�Ȃ����̂��A���҂����Ԃɖ��y�ɒ����悤�ɔz���������̂Ƃ����B
��������
���҂̖����ɑ��u���A�����ɐ����A��{��(���҂̏���)�A���[�\�N�Ȃǂ������邱�Ƃ��u������v�Ƃ����B������ɗp���������[�\�N�͂��ꂼ��1�{�����ĉ����Ă����B���ꂪ2�{���Ǝ��҂̗삪�ǂ���ɍs������悢�������Ƃ����Č����B�܂��ח�����߂ɗp����J�~�\����Z���̂��Ƃ��u��蓁�v�Ƃ����B�u���ʒu�͖����⋹�̏�ȂǓy�n�ɂ���ĈႢ�����邪�A����ɂ��Ƃ��́u���v�͏Z�E���̐l�̔����������c��ł���Ƃ����B���ɖ���(���҂̎g�������q�ɎR����тɂ��A���т̏�ɏ����̂��߂ɔ���1�{�𗧂Ă�B���ɂ���Ă͎��҂̎g�p��������2�{���Ă鏊������)�▍�c�q��������B���N�����Ȃ̏�Ύ��ł���V�L�~�͐_�̈ӎu�̐�G�������Ƃ����ŁA���̎��͓łł��邽�߁A�u���������v����V�L�~�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�u��{�ԁv�Ƃ������A���҂̖����Ɉ�{�Ԃ𗧂Ă�̂ɗp����B���҂̕���������ăV�L�~�𗧂Ă�̂́A�����̖叼�Ɠ����őc��̗�A�ΐ_���h�点�Ė�ɗ��Ă�̂Ɠ������z�ł���B�u���сv�ɂ��ẮA�H�������̂�{���Ȃ�A�����{���Ƃ����l������A���̌`�ł���ی`�ɂ��ċ������B�o���̍ۂɂ́A����𒃘q���Ɩ��т𓊂��Ċ�������A���V���`���擪�ɕ��������ĕ�n�ɋ�����n�������B�܂����c�q�́A����ł���P�����ɍs�����߂ٓ̕��ł���Ƃ����M������B���������u�ۂ��v�`�̂��̂ɁA�����c�q������B����͌��ɏh��c��̗���A�������̕�ŏ����A�c�q�̂Ȃ��ɏh���Ă��炢�A�����H�ׂ邱�Ƃőc��ɏj���Ă��������s���ł���B������ɂ́A���тƖ��c�q�̗�����������n�����������A���т����A���邢�͖��c�q�����Ƃ����n�������B�܂�����s�}���ł́A���тɔ�2�{�𗧂Ăċ����A�Z�E���u�J�~�X���o�v�����Ŏ��҂̔�����A���o�������Ɩ��т̔����Ƃ����B���d�͊J���đŕ~(�O�p�̕z)�𗠌����Ĕ������ɑւ��A�����E���[�\�N�ɉ����鏊�A���d��߂Ă��܂����Ƃ�����B�_�I�͎��̉�������݁A�݂��������邩����������p�ӂ����̑O���B���悤�ɂ��ē\��B�����_�I�����Ƃ����A����������܂ł��̂܂ܓ\���Ă����B���ɂ���Ĕ����Ƀ�(����)�Ə����B
���ʖ�
�ʖ�͂��Ƃ��Ǝ��҂̑h�����肤���߂̂��̂ŁA��n�̋߂��ɉ��̏����𗧂Ď��҂̖����ĂсA��̂��䂷��A���Ď��҂������Ԃ�悤���܂��܂ȓw�͂��p���p����ꂽ�B���������h���̂��߂̊��Ԃ�ʖ�Ƃ����B�h���s���𑒎��̃X�P�W���[���ɓ���Ă����킯�́A����ɂ���đh�����Ⴊ�������Ƃ������Ƃł���B����𗠕t����悤�ɁA�S���Ɏ���ł��琶���Ԃ����Ƃ����`�����������c����Ă���B���̑����͎O�r�̐��n�����b��������ԉ������Ă����Ƃ������̂ł���B����͍��ł����u����̐��E�v�����Ă����b�Ƌ��ʓ_�������đ�ςɋ����[���B���݂͎��҂̑h���V��͍s�Ȃ�Ȃ����A��ʎ��̂����債�A����Ɠ����ɋ~�}��Â��i���������߁A���ɂ������l�����𐁂��Ԃ��Ⴊ��ςɑ����Ȃ��Ă���B�u�Վ��̌��v�����ڂ��W�߂Ă����ł���B���̒ʖ�͕��ʖS���Ȃ�����̈�ӂ��������A�������F���̏ꍇ�ɂ͑������o���Ȃ��̂ŁA��ӂɂȂ邱�Ƃ�����B���̎��ɂ͍ŏ��̔ӂ͂������ւōs�Ȃ��A2���ڂ̖�͐����̒ʖ�Ƃ��čs�Ȃ��̂ł���B�ʖ�͑m�������O�Œʖ�s�����A���̂��ƉƐl�E�e������Ӓ��A���[�\�N�Ɛ������₦�Ȃ��悤�ɔԂ�����B�ʖ�͕ʖ��u���g�M�v�ƌĂ�A�ʖ�ɏo����邹��ׂ�����������ׂ��Ƃ�������A�u���݂��������v�u�����������v�Ƃ����`�ŁA�g����e�����l����َq��{�^�݂��͂�����B
������
�����ɂ͂������Ȃ��ԘU�E�ԗւ́A���҂̗삪�h������悤�ɂƂ̏���ł���A�����ɂ���͖������̎��͂����ƐM����ꂽ�B���E�k��B�ł́A�Ɛg�̎҂����ʂƁA���̐��Ō����ł���悤�ɂƁA����̐擪�̐l���u�ԓE�܁v�������A�s�������l���Ԃ����̑܂̒��ɓ���Ă��Ƃ������K���������B����͉Ԃ��Ȃ���A��c�̂��鐢�E�ɍs���Ȃ��ƍl���Ă������߂ł���B���Ƃ��ƉԂ́A�G�߂̗���}����ˑ�(�삪���ďh��)�̈�Ȃ̂ł���B�����Ă͋G�߂̕ς��ڂɁA�c��̗���}���čs�Ȃ��u�n�i�v�ƌĂ��s�����s�Ȃ��Ă����B���V�ɑ����p�����Ă���e�̉Ԃ́A��������̍�����M��Ă����B����9��9���̏d�z�̐ߋ�ɂ́A�e�������݁A�e�̉ԂɖȂ����Ԃ��āA���̖Ȃɔ����G���ƒ�����ۂĂ�ƐM�����Ă����̂ł���B
��������
�[���ɐ悾���āA���҂ɔ������炵�̌o��q�𒅂���̂���ʂ̕��K�ł���B�o��q�A�܂�o�����������߂𒅂���N���́A���Ƃ��Ɛ^�������̐��Ɋ�Â����̂ł���B�_���j(����̕���)�̈З͂ɂ���āA�����g�ɑтт�Ȃ�߂ɏ����A�����}����Ƃ��ɂ��S�����ꂸ�A��̕��������ĈԂ߂�Ƃ����u�_���j�o�v�̈�����痈�Ă���B�o��q�͎�b��r�J�A�����Ĕ��̓��ɑ܂��g�ݍ��킳��Ă���B�o��q�͏���̑����ł���A����͐�����y�Ɍ����ď���ɏo������Ƃ������z������B���܂��͂�����Ƃ��ɂ́A���͂����Ƃ�A���ɂ͔��̎O�p�z�����A��ɐ�����������A��ɘZ���K�̓��������ɑ܂�������B���̎O�p�z�͂�������A�z������̂ŁA�]��i�D�̂������̂ł͂Ȃ����A�O�p�z�͂����Ďq�����t�������̂ł��邽�߁A��������邱�ƂŎ��҂����܂�ς���Ďq���ɕԂ邱�Ƃ�����Ă����Ȃ��Ƃ������ƁA������͎O�p�͎ւ̓���A�z������̂ŁA���̎ւɕԂ�Ƃ�����������B���Ď������̐F�ł��邪�A���͊��݂̒����ɊW�̐[���F�ł���B�܂��_���̎g���������A�����A���ρA���ւł���̂��A������E�̏ے�������ł���B���č���ɂ������ɂ����𒅂�Ƃ����̂́A�܂蔒���������Ă�̂��߂̐F������ł���B�_�O�������̂��Ƃł̔�I�̐Ȃɂ́A�ԉł͑����Ԃɖ߂邱�Ƃ��������߂ɐF���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
���[��
���҂�[������Ƃ��Ɉꏏ�ɂ���������̂ɁA���ɑ܁A��A�o�T���邢�͐��O���p�����^�o�R�A���A�����Đ��ԂȂǂ�����B���҂ɂ��������́A�ӂ���Ƃ͋t�ɁA�����ق������ɍׂ��ق����茳�ɂ���(����2)�B���ɑ܂̂Ȃ��ɂ͘Z���K�A�ւ��̏��A�����B�܂������ɍf�A�D�A�R���̎��A��3��ʁX�ɕ�݃I�q�l���ɂ������̂�����Ƃ��낪����B���̊D�͖ڃc�u�V�ɁA�͈����ɓ����t���邽�߂��Ƃ�������u�b�\�E�Șb�ł���B�����̕����i�Ƃ��ċ��A�J���U�V�A�苾�Ȃǂ����邪�A�Α������y���Ă���͔R���Ȃ����̂͋ւ�����悤�ɂȂ����B
|
���o�����疄���܂�
���o��
���V�̂��ƁA�o���͗�l�Ԃ܂łƂ������ƂŁA����ł͏o���ɔ����V������ςɏ��Ȃ��Ȃ����B���V�̂��ƉƂ���o������Ƃ��ɁA���̕������ɏo���Ƃ���ƁA�������ɏo���Ƃ���Ƃ�����B�������ɏo���ꍇ�ɂ́A����k�ɂ��邱�Ƃ�D��ɂ���ꍇ�ł���B���Ă��̊���S���̂͒j���ŁA���Ƃ����������B����́u�I�C�g�}�S�C�v�Ƃ�����C���킹���痈�Ă���B�������犻���ɏo���Ƃ��ɁA�|�ō�����u����v��������Ƃ�����@������B���̖�͖��y�ւ̓����������킵�A�V���̂��Ƃɂ͔R���Ă��܂��B����͎��҂̗삪�߂��ė��悤�Ƃ��Ă��A�傪�Ȃ��Ȃ��Ă���A2�x�ƋA��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̎�p�ł���B���Ɋ����̑�̏�ɒu���A���̉����Q��҂�����3�x���Ƃ����V����s�Ȃ��n��������B����͎O�x(����)�̗�Ƃ����A�C���h�ł͍Ōh��ɂ�����B�������͓�̂䂢���Ɠ����悤�ɉE��������B�������Ƃނ炢���Ƃ����A���V�̎��ɍs�Ȃ���肩���ł���B����܂����E�������āA���ʂ̓�͉E�ɋ����ɂ͍��ɂȂ��B���͐_�i�̈ʒu����Ƃ���ŁA���ʂ̐l�ɂƂ��Ċ��ޏ��ƂȂ�B��O�łȂ��O�Ɍ����ĂЂ��Ⴍ�̐��𒍂��̂����Ђ��Ⴍ�Ƃ����A��ӂ̂�����̎��ɂ͂��̂悤�ɂ��Ď�𐴂߂�B����������铮������邱�Ƃɂ���āA���S����肻�̒��ʂ��铭��������̂ł���B����̎n�܂�ɂ�����A�Ƃ̖�Ŏ��҂̒��q����������A���ɉ����ĔR���Ƃ��낪����B������܂����҂̗삪���ǂ�Ȃ����߂̎�p�Ƃ���Ă���B
�������̋V
�ŋߏo���ɂ������āA�����n�g�����u�����̋V�v���������Ă��Ă���B���͐̂���l�Ԃ̍����^�шڂ����̂Ƃ��ꂽ�B�u�Î��L�v�ɂ��u�����ɔ��q�璹�ɂȂ��āA�V�ɂ͂����āA�l�Ɍ������Ĕ�ї������B�v�Ƃ���B�`�x�b�g�ŗL���Ȓ����ł́A�l�Ԃ̈�̂ɐH�ׂ�����B���Ɏc���ɂ݂��邱�̕������A���͒��͓V�̎g���Ƃ��āA����V�ɉ^��ł����Ƃ����Ӗ��������Ă���B�]���ē������̂܂ܒn��Ɏc����Ă��邱�Ƃ͋t�ɕs�g�Ȃ��ƂȂ̂ł���B�o�����f�_�`�Ƃ����A�o���������̎���Œx���Ɓu���l���P�����w������Ă��܂��v�Ƃ����n��������Ƃ����B
����ӂ̑���
��Ƃ����͎̂R�̊ɂ₩�ȌX�ΖʂŁA�����Ɏ��̂��^�Ԃ��Ƃ��ӂ̑���Ƃ������B���ē����́A��Ƀ��[�\�N���Ȃ���p�Ȃǂɗ��Ă�B�����͎��҂̗�����̐��ɓ]�������邽�߂̉ł���B��͎��҂̑����A�ʔv�͑����l�A�V�͂��̍Ȃ����B�V�J�o�i��4�{����2�̑�ɗ��Ă�B�V�J�o�i�����̂͐e���ŁA����̏���ƂȂ�B����͐_�Ђ̑O�͔����Ēʂ�B����͎��҂��ւɉ����邽�߂̎�p�ł���Ƃ�����������B�g��T�q�́u���{�l�̎����ρv(�u�k��)�̒��ŁA�Ñ���{�l�͐��܂�邱�Ƃ́A�ւ���l�ɂȂ邱�Ƃł���A���ʂ��Ƃ͍ĂюւɋA�邱�Ƃł���ƌ����Ă���B�����Ď��҂ւ̕ϐg�V��̂��߁A�u����̏��́A�擪�����A2�ʂ��ق����A���邢�͗��ւł��邪�A�ق����Ɨ��ւ̈�v�́A���҂̖{���̈�v���Î�����B�܂�ق����͗��ւȂ̂ł���v(99��)�B�����āu����̂Ȃ��Ő擪���������ւ́A�����n�ɓ�������ƕ挊�̎��͂��߂���A�Ƃ���ɂ���ẮA���҂ƂƂ��ɖ��������B�v(����)�Ƃ���B����͈ꌩ��Ȑ��Ɏv���邪�A���n�̖����͂قƂ�ǂ��ւ�_�Ƃ��ĐM���Ă��Ă���A�l�Ԃɔ�����ĂȂ��ւ̐_��I�ȗ͂邽�߂ɁA�����������ւ̖���ƍl�����̂ł���B�܂�����̐i�ݕ��ŁA3���i���1��������Ƃ������̉^�т��s�Ȃ�����������(�X)�B���Ė�ӑ���̖����Ə����Ɍ��̗�ł݂Ă݂�B�ŋ߂͖�ӑ���͗�l�Ԃ̔��B�Ō��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������߁A���V�̈Ӗ���T�邽�߂ɂ�����̖�����c�����Ă����̂����ʂł͂���܂��B
��͒Ìy�����̂��̂ŏ��a42�N�̑����s����̋L�^�ł���B
��A���� / ��A����2�� / ��A����2 / ��A�ԗ�4 / ��A����2 / ��A�Z��6 / ��A����4 / ��A�_���_��1 / ��A�ǑV1 / ��A��V1 / ��A��X1 / ��A�l�� / �ʔv���V�W����������
����ɂ͂��ꂼ�����������l�̖��O���L����Ă���A�J�n�O�ɂ��̖��O�Ɩ�������������̂ł���B
���m���ł݂�ƁA���̗Ⴊ����B�Ő�[�́u�ē��v�ŁA���[�\�N��|������6�{���Ă��u�Z���v�����B�����擕�U���邢�͐���B�ԘU��^�c�K�V��������ꍇ�ɂ́A���̑O��Ɉʒu����B�ȉ��A�ԁA�V�J�o�i�A�m���A���҂̒����A�싟�A���A�ʔv(�r�傪����)�A���A�����Č������̏��ł���B�{���͎l�{���ŁA�����͊e�@�h�ɂ���ĈقȂ�B���̂��Ɛ��Ԃ���������ʉ�҂������B
������
�����Ƃ͎��҂�y�̂Ȃ��ɖ��߂�悤�ɍl���邪�A�����Ă͑h���E����������āA�n�ʂɐQ�����A���̏�ɖ̗t���Ȃǂ����Ԃ��������ł���Ƃ����B����ɒ����ƁA����Ɋ���u���A���̉�������3��܂��Ƃ��A��̉���3��܂��Ȃǂ̏�����s�Ȃ��Ƃ��낪����������B�����̂Ƃ��͋ߐe�҂��Q�A�m�����njo����B�͂��߂Ɋ����Œ݂邵�Č��ɓ����B���̎��A���̔Z�����ɓy������݂Â����B��ӑ���̋A��́A�s���̓���ʂ�Ȃ��̂����ʂł���B���҂��߂��ė��Ȃ��悤�ɂƂ������@�ł���B�����̋A��ɂ͐l�̉Ƃɗ��������̂ł͂Ȃ��Ƃ���Ă����B���ɖ������I���ĉƂɓ���Ƃ��̍�@���u�삪����v�Ƃ����Ă���B�ƂɋA������܂�������ő̂ɉ����ӂ肩������A������̍b�ɎĐ��߂��B�܂��C�ɋ߂��n��ł́A�l�ɍs���C����̂ɂ�������A�C�Ŏ��A�e�����Q�������ɊC����Z���A�����̂ɂӂ肩�����肵����������B����͋q�����̓X��ɉ���u���ԁv�Ɠ����ŁA�C���ŃP�K�������Ƃ��ȗ������`�ł���Ɩ��c���j�͌����Ă���B
��������
�Α��������Ƃ̍����⑰���D�̂Ȃ�����E���������Ƃ��u�������v���邢�́u�E���v�Ƃ����B�����Ă͓��m�������܂ɉ������҂Ɉ�����n���A�ł��Â��N(����)�O���ɉ����ĉΑ������߁A�������͗����ɍs�Ȃ�ꂽ�B��̂��ߐe�҂݂̂ŁA�Վ�肪�ŏ��Ɏn�߂�B�܂��m�h�{�g�P(���V��������)���͎�����E���Ƃ��낪�����B��ʂɑ������ɏE���č��قɓ���A���ɏ�̍��ւƏ��ɏE���čŌ�ɓ��������قɓ����悤�ɂ���B�u�l�Ԃ͍̑̂��ɂ���ē��A���A���A����A�����̎��A����ɂ��ꂼ�ꂪ���̍��ɕ������A�v49�ɂȂ�B�����̎l�\����͂������炫�Ă���A��ł�������Ƌ��{�ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ�����������B
|
���������ƔN��
�u���v�Ƃ͓���ƈقȂ��Ԃɂ��邽�߁A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ԃ������B�]���āu����v�����łȂ��A�u�����v�����ł���A�����`���Ɣ����M������B�V�����s�Ȃ��O�ɂ͐g�𐴂߁A�V���������ƂɁA�u���i���Ƃ��v���s�Ȃ��B���̎��ɂ͕��i�̔��łȂ��A���i���ŊC�̂��̂�H�ׂ�ƁA����������Ƃ����B���͐���̏h����̂ł��邽�߁A�u���i���Ƃ��v�ɖ𗧂̂ł���Ƃ����B���ƑΏۓI�Ȍ��t�ɐ�(�n��)������B���͗�I�ȗ͂ɂ���Ė������ꂽ��Ԃ������A�P�Ƃ͂���������Ԃ������A����ꂽ��Ԃ������B���ʐ��́A���Ȃ�Ղ��V����s�Ȃ��A�������J�n���邱�Ƃ������B�܂��j���ɂ͋�����H�ׂ邪�A���ɗ\�j�̍Ղɋ����鋛�ނ̓q���L�ɂ��Ă���B�J�n���q���L�ł���킵�Ă���̂��B�Ȃ��j���Łu���q���L�v�Ƃ����ƁA�I���ɂ��悤�Ƃ����Ӗ��Ɏg���邪�A����͏j���ł́u�I���v�Ƃ������t�͊��ނ̂Łu�I�q���L�v�Ƃ������t��p����̂ł���B
�����A
���Ď���49���̊Ԃ́A���҂̗�͉Ƃɂ���ƐM�����Ă����B�܂������ł́A49���܂ł͒��A�̊��ԂƂ����āA�Z���։�̊Ԃ����܂���Ă���Ƃ��ꂽ�B���̂��ߖ~�߂��Ɏ��S�����ꍇ�͂������A�~�ȑO��49���ȓ��ɖS���Ȃ����ꍇ�ł��A�V�~�𗂔N�s�Ȃ��Ƃ����n�悪����B�܂���ʂɎl�\�����3�J���ɂ܂�����Ƃ悭�Ȃ��Ƃ����āA35���ڂɎl�\����̖@�v�����킹�čs�Ȃ��Ƃ��낪�����B����́u�����イ�ꂪ�g�ɂ��v�Ƃ�����C���킹���痈�Ă���B
���`������
�`���Ƃ͂��̂��̂��v���������������ɂȂ���̂ŁA���݂ł͎��҂̈ߑ��⎝�������A�e�����҂�ɔz�邱�Ƃ��u�`�������v�Ƃ����Ă���B�����Ă͌����p�����邽�߁A���邢�͌̐l�̗͂ɂ��₩�邽�߂ɁA�̐l�̗͂��������߂�ꂽ�ߑ��⎝�������`����ꂽ�B�`�������̎����͊��������������܂ł������B
���N��
���ҋ��{�̂��߂̕�����N���Ƃ����A1�E3�E7�E13�E17�E23�E27�E33�N�Ɏ��{���A�O�\�O����ŏI���Ƃ��邪�A�_���W�Ɏd�����҂́A�O�N���őc��_�ƂȂ�Ƃ����B���Ɍ\�E�S�N�����グ�Ƃ��Ă���Ƃ��������B�N�����Ƃɂ́A���̏Z�E���������{���Ă��������B�l�͎��ʂƃz�g�P�ɂȂ邪�A���̃z�g�P�͂܂�����Ă��Đ_�I�ɍՂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������O�\�O����̂Ƃނ炢�����Ńz�g�P�͌��������A�_�ƂȂ��Đ�c�̒��ԓ��肵�āA���x�͉Ƃ̎��_�ƂȂ�Ƃ����Ă���B�]���ĎO�\�O����܂ł̊Ԃ́A�q�������z�g�P�̖ʓ|�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł���B�N�����s�Ȃ��̂́A���҂��M�����߂�̂��{���̖ړI�������̂ł���B�ŏI�̔N���ł���A�u���������v�u�₢��v�ɂ́A�ʔv���n�⎛�ɔ[�߁A�u��������k�v��u�����p���k�v���A��n�ɗ��ĂĐ_���J�肩����̂ł���B��������k�Ƃ́A�}���̔������ĕ\�ɉ����������A���Ɍo�������������̂ł���B���k�͕��ʕ�ɗ��Ă���̂ŁA�V�������݂���͈̂�����A�O����Ȃǂ̔N���̎��������B �@ |
 �@ �@
���⏑
|


 �@
�@ |
���m�[�x���̈⌾
�_�C�i�}�C�g�̔����҃A���t���b�h�E�m�[�x��(1833�`96)�́A�m�[�x���܂�n�݂������ƂŐ��E�I�ɒm���Ă��邪�A���̏܂͔ނ̈⌾�ɂ��������Đ��܂ꂽ���̂ł���B���́A�ނ̈⌾���̃m�[�x���܂Ɋւ��镔���ł���B
�S���Y�͂��̒ʂ菈�����邱��
�⌾���s�҂͊�������S�ȗL���،��ɓ������A���N���̑O�N�x�ɐl�ނɍł��v���������҂ɁA���̗��q���܋��̌`�ŗ^����B
�E�̗��q��5�������A�����w�̕���ōł��d�v�Ȕ����܂��͔����������ҁA���w�̕���ōł��d�v�Ȕ����܂��͉��P�������ҁA�����w�܂��͈�w�̕���ōł��d�v�Ȕ����������ҁA���w�ōł����o���闝�z��`�I�X���̍�i���������ҁA�����Ԃ̗Z�a�E����R�̔p�~�������͍팸�E�܂��͘a����c�̊J�Â���ѐ��i�ɍł��v������҂ɁA���ꂼ��ꕔ��^���邱�ƁB
�E�̏܂́A���҂̍��Ђ��킸�A�ł��܂��ׂ��҂Ɏ��^����̂������̊�]�ł���B1895�N11��27��
���i�|���I���̈⏑
�i�|���I���̈⌾���́A1821�N8��15���A�Z���g�E�w���i���ŏ����ꂽ�B���͂��̍ŏ���3�����ł���B
1�D���̓��[�}����̐M�k�Ƃ��Ď����B50�]�N�O�A���̋��ɕ�����Đ��ꂽ����ł���B
2�D�킽���̈�̂̓Z�[�k�͔Ȃɑ����Ăق����B�킽�����[��������t�����X�����̒��ɂ��肽������ł���B
3�D�킪�ň��̍ȃ}���[�E���C�Y�͏�ɂ킽���ɖ�����^���ė����B�����Ő�������ɂ������ĐS����̈����������B�킪���q�͖����c���̂��߁A��킭�ΐ��̂��܂��܂̗U�f�Ɋׂ�Ȃ��悤��肽�܂��B
���t�����N�����̌`������
�A�����J�̎����ɂ��Ȃ��Ă��鐭���ƁA�x���W���~���E�t�����N����(1706�`1790)�́A�⌾���Ɏ��̗l�ɏ����Ă���B
����̕������A�����Ŏ��R�X�̌`�ɍH�����X�e�b�L���A�킪�F�ɂ��Đl�ނ̗F�ł���W���[�W�E���V���g���ɑ���B�������̃X�e�b�L�����ʂ��ے�����Ƃ��Ă��A�ނ͂���ɒl���A����ɂӂ��킵���l���ł�����B
���z�A���E�|�g�}�[�L�A������
�A���[���`���̎��Ɖƃz�A���E�|�g�}�[�L�́A1955�N�Ɏ��S�������A�ނ̈⌾���ɂ́A���Y�̈ꕔ���s�̌���Ɉ②����Ƃ������B����������ɂ͏������t���Ă����B
���͈ȑO���o�D����]���Ă������A�˔\���Ȃ����ߖ]�݂����Ȃ�Ȃ������B���͌�N�ɂ͎s�̎��ƊE�ɏd�v�Ȓn�ʂ��߁A����ɗ����Ƃ͕s�\�ƂȂ����B20���y�\(500���~����)���������Ċ���Ƃ��A�˔\����Ⴋ�o�D�ɖ��N���w����^���邱�ƂƂ���B�������A���̓��W����ۑ����A�V�F�C�N�X�s�A�́w�n�����b�g�x���㉉����ۂɂ́A�����b�N�̓��W���Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ������Ƃ���B
�V�F�C�N�X�s�A�́w�n�����b�g�x�ɂ́A���q�n�����b�g�����œ����t�����b�N�̓��W���������Ċ��S�ɂӂ����ʂ�����B�|�g�}�[�L�́A����ł��炻�̊[���ƂȂ��ĕ���ɗ����Ƃ�]�̂��B
���s�����c�A�[�̊�
�A�����J�̃W���[�i���X�g�ł���V�����̃W���Z�t�E�s�����c�A�[(1847�`1911)�́A1903�N�ɕ��w�ƃW���[�i���Y���Ɋ����l�ɑ���s�����c�A�[�܂𐧒�A�܂��R�����r�A��w�ɃW���[�i���Y���u����ݗ����邽�߂�100���h������t�����B�ނ͈⌾�̂Ȃ��ŁA���q�Ǝq���ɑ����̂��肢�����Ă���B
�u���[���h�v�Ƃ����V�����ێ������S�Ȃ��̂Ƃ��A�i��������`����\���t����B���̐V����ێ������s���邽�߂ɁA�킽���͎����̌��N�Ƒ̗͂��]���ɂ����B�����ŒP�Ȃ���ׂ���荂�����@����A����������@�ւƂ��Ĉ琬�����킽���Ɠ����ԓx�ł��̌o�c�ɗՂ�łق����B
�Ȃ��u���[���h�v�͔ނ̎���19�N�ɂ��Ĕp�����ꂽ�B
���q�g���[�̎��ƌ����̐錾��
�h�C�c�̐����ƃq�g���[�́A1945�N�A���炻�̖�����邱�ƂɂȂ����B�ނ̈⌾���ɂ́A�{���}���A�Q�b�x���X�A�����ăt�H���E�r�����[���ؐl�Ƃ��ď������Ă���B
�����̔N����ʂ��āA���͌����̐ӔC�����Ƃ͏o���Ȃ��ƐM���Ă������A�����킪���U�̏I����ڑO�ɂ��āA���͒��N�^�̗F��𐾂���������l�̏������킪�ȂƂ��邱�ƂɌ��ӂ����B�ޏ��́A���Ɖ^�����Ƃ��ɂ��邽�߁A����̎��R�ӎv�ŁA�G�̕�͉��ɂ��邱�̓s�s�̎��̂��Ƃɂ���Ă����̂ł���B�ޏ��͎��̍ȂƂ��āA���g�̈ӎv�Ŏ��ƂƂ��Ɏ��ʂ��Ƃ�I�B�ޏ��̍s���́A���������̂��߂ɓ����Ă����N���̊ԂɁA������l���]���ɂ������̂������Ă���邾�낤�B���̍��Y�́A�Ȃ�炩�̉��l������̂͂��ׂāA�킪�}�Ɋ��A�}�����݂��ʏꍇ�́A���ƂɊ���B���Ƃ����ł��Ă����ꍇ�́A�����Ȃ��w����^����K�v�͂Ȃ��B
(����)�ȂƎ��́A�s�k��~���̋��J��Ƃ�邽�߁A����I�������B������l�̈�̂́A��������12�N�ԁA���Ƃ̂��߂ɖ����̑啔��������ē��������̏ꏊ�ŁA�����ɉΑ��ɂ��Ă��炢�����B
���o�[�j�X�E�r�V���b�v�̖�
�n���C�̃J���n���n���Ƃ̍Ō�̉����o�[�j�X�E�r�V���b�v��40���G�[�J�[���z����y�n�𑊑��������ƁA�⌾���Ɋw�Z�̐ݗ��E�ێ��̂��߂̐M�����Y���c���悤�Ɏw�������B
���̓n���C�����ɃJ���n���n�w���Ə̂���S�����̊w�Z��ݗ����A�ێ���ړI�ɁA���̐M�����Y�ɓ��Ă邽�߁A�c�]�̎��̓��Y����ѕs���Y�̂��ׂĂ��A���L�̎���҂Ƃ��̑����l�A��������l�Ɉ②����B���͎���҂ɑ��A�M�����Y������������2����1���z���Ȃ��͈͂ŁA�p�n�̔����A�w�Z�̌��z�A�K�v�ݔ��̍w���Ɏ����Ɣ��f������z���x�o����悤�w������B�܂��A����҂���Y�̎c�]���A�����ƍl������@�œ������A���̔N�Ԏ��v�ŁA���t�̋��^�A�����̕�C��A���̑��̗Վ�����x�o���A�܂����̈ꕔ�ŁA�ǎ����̑��̕n���w���̈�p�����ɓ��Ă�悤�w������B��p�w���̑I��ɂ��ẮA�������邢�͍����̃n���C�l��D��Ƃ���B
���X�~�X�\�����������A�����J�̕�
���V���g���c�b�ɍs���ƕK���K���ꏊ�ɃX�~�\�j�A�������ق�����B���̔����ق̓A�����J�ōł��R��������̂ŁA���̊�b�̓C�M���X�l�̈�Y�ɂ��B
�W�F�[���Y�E�X�~�X�\��(1765�`1829)�́A�T���ȃC�M���X�̉Ȋw�҂ŁA���l���Ă�������[���b�p�ʼn߂����A�ꗬ�̉Ȋw�҂����ƌ�������B�ނ̓C�^���A�̃W�F�m�@�Ŏ��S�������A�A�����J�ɂ͈�x���K��Ă��Ȃ��̂ɁA�S���Y�����̃w�����[�E�W�F�[���Y�E�n���K�[�t�H�[�h�ɁA���̂悤�ȏ��������Ĉ②�����B
�n���K�[�t�H�[�h���q�����c�����Ɏ��S�����ꍇ�A���邢�́A�q�����⌾���c�����ɁA�܂���21�ɒB����O�Ɏ��S�����ꍇ�A����������Y�́A���V���g���c�b�ɁA�X�~�\�j�A���E�C���X�e�B�`���[�V������ݗ����邽�߁A�A�����J�ɂ���������邱�ƁB
�n���K�[�t�H�[�h�́A1835�N�A�q�����c�����Ɏ��S���A���̋����A�����J�ɑ���ꂽ�B������1846�N�X�~�\�j�A���E�C���X�e�B�`���[�V���������ꂽ�B
�������L�d�̈⏑
�����G�́u���C���\�O���v�ŗL���Ȉ����L�d(1797�`1858)�́A61�̂Ƃ��ɗ��s�����R�����ɂ�����A�����o�債�Ĉ⏑���������߂��B
������ċv�Z�a�̎؋���ԍς��Ăق����B
�{�⓹��ނ蕥���Č��݂̏ꏊ�̗����ނ����A�l�ɑ��k�̂������߂Ăق����B������������ł��邪�A���̋����Ȃ��̂ŁA�ǂ��Ƃ����R����̐g�ł���̂ŁA�ǂ����[�܂�悢���@���l���ĉ������B�G�̓���≺�G�̂������͒�q�����Ɍ`�������Ƃ��Ă���Ăق����B��ɂƂ����ɂ͂��荇�킹�̒������A�d��ɂ͒����Ԉꏏ�ł������̂ŁA�e������{�̂�����{�ǂ���ł�������ł���B
���ї����A�̈���͐_���ւ̋F��
�R�A�E�R�z10���������߂��ї����A(1497�`1571)�́A�җ���}����ɂ������āA3�l�̑��q�ɁA���͂��Ėї��Ƃ�ɉh�����邱�Ƃ�����Ĉ�����������߂��B
����11�̎��A���|��̂ӂ��Ƃ̉��~�ɂ������A���͓�������̏��֗��̑m���K��A�O���̍u���Â��ꂽ�B���̂Ƃ�����a�����̍��ɏo�Ȃ��ꂽ�B�������l�ɓ`�����肢�A11�̎��ȗ��A�����܂Ŗ����̂悤�ɔO��̍s�𑱂��Ă���B����́A������q�݁A�O�����\�Ղ�������̂ł��邪�A���̍s�ɂ���āA�����̂��Ƃ͐\���܂ł��Ȃ��A�����ɂ����Ă��쌱���炽���ł���ƕ����Ă���B�܂��A�����g�����̐��ɂȂ���āA�����̊肢�����F�肵�Ă���B�����A���������F�肪���A��g�̎��ƂȂ�ƍl���A���ʂȎ��Ǝv����̂ŁA��O���ɂ����Ă��A�������̔q�݂������Ȃ��̂��悢���Ǝv���B����͒��������̂�������F���Ă������Ǝv���B(�ї����A�̈��12��)
������@���⏑�ɂ�����Y�̎g����
�������l�̓���@��(1539�`1619)���A�{�q�����q��ɂ��ĂĎc�������́B�ނ͖{�\���̕ς̖�ɐM���ɒ���ɏ�����{�\���ɔ��܂��Ă����B���{���ɂ܂�����������E�o���Ă���B
��A���͂͂��ƋN���A������������ɏ��ɂ��悤�ɐS������B��������d�����Ȃ��̂ɓ������g���͖̂��ʂȂ��Ƃł���B�܂��p���Ȃ��̂ɖ����������A���l�̏��ɒ���������̂͒���Ƃ����p�ł���B����ɁA�������܂����p���͈ꍏ���������ƂȂ������ɍς܂��Ă��܂��悤�ɁB�������ł��Ƃ��A�����ɂ��傤�Ȃǂƍl���Ă͂Ȃ�ʁB�����ڂ��������ɂ��܂��邱�Ƃł���B
���̈�P��17������Ȃ�A�@���͂����{�q�����q�傩�琾�����Ƃ�A���̂��̊��̂Ȃ��ɓ��ꂽ�Ƃ����B
���q�d��̈⏑
����G�R�̏��q�d��(1617�`1673)���A���Ǝ��̏d���ɂ��Ă��⌾�B
���Ȃ��͐��܂�����肯���Ȃ��A�^�ʖڂł��肷���āA�f���łȂ��Ƃ��낪����B�����ŁA�悭�l�Ɛe���݁A�ӌ����A���X�̎҂܂ł˂�Ɍ��t�������A�����ɘb���₷���悤�ɐS�����A�g�̏�b�������A���̐l�̍˔\��m��ׂ��ł���B
�ƘV�⎩���̋C�ɓ���҂������Ђ����ɂ�����A�����̉��҂��Ƃ�����A�{�l�ɍ���ʖ��ɂ��A�~�ɂ��ڂꑡ�����D�ނ悤�ȉƘV�́A�t�S���l�ɐS���邱�ƁB���̂悤�ȏꍇ�A�����ɂ����~������A�g���ق�ڂ��G�Ǝv���m��ׂ��ł���B���Ԃ̎�l�́A���̂��Ƃ��킫�܂����A�Ƃɒ����d����ҁA���邢�͉ƕ��̂悢�҂̎q�ł��邩��ƁA���l�ɑ��������Ȃ���ڂɎ�肽�āA�����悤�ɕ���������Ȃ���Ђ����̐S�ɂ���Ďg�����߁A���̎҂ɂ����m���A�����ӂ�҂������B�����ς�A�l���悭���Ďg�����Ƃ��̗v�ł���B
���L�b�G�g�̎q�ϔY
�G���́A�G�g��57�̂Ƃ��ɂ��������q���ŁA����6�ł������B�G�g�̖��O�̌�A�ܑ�V�̉ƍN�A�}�O�A�P���A�i���A�G�Ƃ��ؐl�Ƃ��ċL����Ă���B����͌��݂ł����u�ً}�⌾�v�Ƃ�����B
�G���������ɐ�������悤�ɂ��̏����t���̏O�Ƃ��Ă����ݐ\���B����ȊO�ɂ͉������v���c�����Ƃ͂Ȃ��̂ŁB
8��5���G�g
�����q���G�̈˗���
���q���G���s���4���O�ɍא쓡�F�ɂ��Ăď����ꂽ�莆�B�⏑�Ƃ����������U�̎莆�ł��邪�A��M�ƂȂ����B
��A(�א�)�䕃�q�Ƃ��A�M���̎���������ł��Ƃǂ���ꂽ���������A�����������Ȃ����Ƃł���B��������x�͕������������悭�l���Ă݂�Ɠ��R�Ǝv�����B�����������Ȃ����ȏ�́A�킽���ɖ������Ă��炢�����B
��A�䕃�q�ɐi�シ�ׂ����Ƃ��āA���X�ے�(�Â̍�)���ƍl���Ȃ���㋞�����҂����Ă���B�������A�n�A�ዷ��]�܂��Ȃ�A������܂����]�ݒʂ�ɂ���B
��A�킽�������x���̂悤�ȑ厖�������Ċ��s�����̂́A���̒����Ȃǂ��Ђ����Ă������߂ł����āA����ɖړI������킯�ł͂Ȃ��B�����\�����S���̂����ɂ͋ߋE�肷�邩��A���ꂩ��͏\�ܘY��^��Y�ȂǂɓV��������A�B���������ł���B
���R���d���̈⏑
����G���̌�q���ł������R���d���́A���Ă̐w(1615)�ɉ����O�ɁA�ȂɈ⏑���c���Ă���B����ׂ͍��Ȏw����^���Ă���B
��A���Ȃ��̌Â������ɂ��т��͂��Ȃ��悤�ɁA���������āA���X�����Ȃǂ��āA���������f�̂Ȃ��悤�ɁB
��A�ǂ������z��50�������Ă��邩��A���Ȃ��̕��Ŏg���ĉ������B
��A�L��ڂ̑O�ɒu���āA�悭�сA����^���ė{���ĉ������B
��A�q���ɂ�2���Ɉ�x�������т������A��������\���Ɉ�x�͔���A���������䂤�悤�ɂ��Ăق����B�����Ȃ��V�т͂����Ȃ��悤�ɁB
(�܂������������Ƃɂ͍č������߂Ă���B)
��A���̕��̂��ƁA�����킵���Ƃ��낪����č����Ăق����B��l�̂��ǂ��̂��߂ɂ��A�����ɂł����ɂ��A���̏����ɂ���Ďq������ĂĂق����B�j�̐g���ɂ͂��܂�Ȃ����A�S�̗��������l��I��ŁA���ɂ��Ăق����B
���{�{�����̈⏑
���G�̌����ł���A�w�ܗ֏��x�̒��҂̋{�{����(1584�`1645)�́A����7���O�Ɂu�ƍs���v�Ƒ肵�����̈⏑���c���Ă���B
��A���X�̓������ނ����Ȃ�
��A�g�ɂ��̂��݂������܂�
��A��낸�Ɉ˜�(����)�̐S�Ȃ�
(�r����)
��A���_�͋M�����_�����̂܂�
��A�g���̂Ă������͂��Ă�
��A��ɕ��@�̓����͂Ȃꂸ
���]�ˎ���̈⏑
�]�ˎ���̏����͈⏑�ȂǏ����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����A���ɂ��炸�B���݂͂�ȏ����Ă����̂ł���B����͍����̖@���̂悤�Ɉ�Y�����̊����߂��Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�t�Ɉ⏑���c���Ď��O�ɖ��̋N����̂�h�����̂ł���B
�c��4�N(1651)�́u�����Վ��̒�߁v�Ɏ��̂悤�ȋK�肪����B
��A�����Վ��́A�������Ɉ⌾����쐬����B���e�ށA����A�ܐl�g�����������A���N��3�l������ɂ���B
��A�܂������ł��a�C�����ď��u�����o���Ȃ��ꍇ�ɂ́A���e�ނ�g�̎҂����������āA�a�l�Ɍ����ď��u��������悤�ɂ���B
���������u�����Ȃ��܂܂ɖS���Ȃ����ꍇ�ɂ́A�e�ނ⒬�̎҂����������đ����葱�����s�����B
�䌴���߂́w���̕����́x�Ƃ��������ɁA
�u�����r�Z�Y�͗ՏI�ƂȂ������A���O�Ɋm���Ɏ��M�ŏ��u�����c�������ƁA�N��ܐl�g�ɏؐl�Ƃ��ĉ��������̂B����ꎵ���߂��Ă��瑠���J���A�e�ޒ������������Ă�����m���߂�ƁA���ꂼ�ꂪ��蕪���킽���Ăق����Ƃ̈ӌ����o���B�����Ŗژ^�̒ʂ菑���L���āA���Ȃ��l�ɂ����̔�r�ɂď�����(�w�肳�ꂽ���Y)�𑗂�܂����B�ǂ��������肭�������v�Ƃ���B
���{���钷�̈⌾
�]�˒����̍��w�҂ł���{���钷(1730�`1801)�͑�ςə{���ʂȐ��i�ŁA���ꂪ�⌾�̂Ȃ��ɂ�������Ă���B���ʂ̈⌾���ł́A�Ɠ���Y�̎w�������S�����A�ނ̏ꍇ���V�ƕ�ɂ��Ăׂ̍����w�����c���Ă���B���͎����̕�ɂ��Ă̎w���ł���B
��A��n7�ڎl���A�^��������֊Ē˂�z���悤�ɁB���̂����ɍ��̖�A����悤�ɁB�˂̑O�ɂ͐Δ�����Ă邱�ƁB�˂̍����͎O�l�ڂ���B�ł�A���y���ł����ĕ���Ȃ��悤�ɂ���B�̂��̂��A��������Ă���Ƃ��낪����A�Ƃ��ǂ�������Ē����Ă����B�A������̎�ނ͎R���̉Ԃ̂悢�̂�I��ŐA���Ăق����B
���ɔ\���h�̈⌾
�ɔ\���h(1745�`1818)�́A�]�˂ɏo�ē����̓V���̑��l�҂ł��鍂�������ɑ��ʂ��w�B51�̎��ł���B���ꂩ��72�܂ł�17�N�ԂɁA���ʂ̂���3��5��L����������B�ނ͕a�̏��Ŏ��̂悤�Ȉ⌾���c�����B
�u�]�̂悭���{���ʂ̑厖�Ƃ��Ȃ�����́A�܂�������t�����搶�̂��܂��̂Ȃ�A��낵���搶�̕摤�ɑ���A�����ĎӉ��̈ӂ�\���ׂ��v
�ނ́A�⌾�ʂ艺�J���̍��������̕�ׂ̗ɔ[�߂�ꂽ�B
�����v�ԕׂ̈⌾
�C�R�R�l���v�ԕ�(1879�`1910)�́A1910�N���̍��Y�������̈�ǂ̒����Ƃ��ď�荞�݁A���Ɍ������r���Œ��v�A�S�����S�����B�c���ꂽ��i�̂Ȃ��ɒ����̎蒠������39�łɂ킽���Č��t���c����Ă����B
�u�����̕s���ӂɂ��É��̊͂ߕ������E���A���ɐ\�����A����ǒ����ꓯ���Ɏ���܂ŊF�悭���̐E����蒾���Ɏ���������c�ނ�ŕÉ��ɐ\���A�䂪�����̈⑰�����ċ�����Җ����炵�ߋ������A�䂪�O���ɂ�������̂��ꂠ��̂݁v
(�Ђ炪�Ȃ̕����A�����J�^�J�i)
���ؔɂ̈⌾
��������̉�Ɛؔ�(1882�`1911)�͌̋��̋v���ĂɋA��A���R�̂Ȃ��Ő����𑗂����B����4�����O�ɏ������莆�̂Ȃ��ɁA
�u���n�ɂďĂ��c�肽�鍜�D�͂��ł̐ߍ��ǎR�̉��̃P�V�P�V�R�̏����̍��ɖ��߂Ă������ꂽ���A�����͎R�̂��݂����������A�v���o�����}������߂Ă��̐��̉����ƕ��܂�ƎƂ��̂ĂāA�Â��ɉi���̕����Ȃ閰��ɂ��ׂ������낤�B�v�Ƃ���B
���ґ��ɏ��̈⌾
���{�l�o�R�Ƃ̃p�C�I�j�A�ґ��ɏ�(1886�`1923)�́A38�˂̎��Ɋ֓���k�ЂŎ��S�����B�Ă����Ƃ��甭�����ꂽ�ނ̈⏑�ɂ́A
�u�⍜�܂��͊D���Ȃ�ׂ��ۑ������邱�ƁB�����D��ۑ�����Ƃ��́A�������ʂɗ��߁A�K���̎����ɁA�X�C�X�������R�̒����ɖ��߂邩�A���邢�͂����ꂩ�̃N���o�X�ɓ����邱�Ɓv�Ƃ���B�Ȃ��⍜�͔�b�R����ɔ[�߂�ꂽ�B
���e�r���̈⏑
�G���w���|�t�H�x�̐��݂̐e�ŁA��Ƃ̋e�r��(1888�`1948)�́A�V�N���}���邽�тɈ⏑�����������Ă����Ƃ����B���̂Ȃ��̈��
�u���͂�����˕��������ĕ����𐬂��A�ꐶ���߂Ȃ���炵�܂����B���K�������Ǝv���܂��B�v �@ |
 �@ �@
���Ñ�M���V���E���[�}�̑��V
|


 �@
�@ |
���_�ɂ��A���{�̌Ñ�̐M�͌Ñ�M���V���̂���Ƒ�ςɎ��Ă���Ƃ����B�����ŁA�{���ɂ������ǂ����ׂĂ݂邱�Ƃɂ����B�����̓E�C���A���E�e�O�́u���X�g�E�A�N�g�v�ɂ�����B
�Ñ�M���V���E���[�}�l�̐M�ɏ]���A�썰�͌����ƈقȂ������E�֍s���Ď���̐������c�ނ̂łȂ��A�n���ɂ����Đ����𑱂���B�����Ŗ����͑�ςɏd�v�ȋV���ł������B�����̋V���͈�̂�揊�ɑ���Ɠ����ɁA���������悤�ɑ��邱�ƂƐM�����Ă����B���̂��߁A���V�̏I���ɂ́A�̐l�̑�����3�x�ĂсA�����āu�������₩�Ɂv��3�x�J��Ԃ����B��ɂ��A�u�N�X�������ɜڂ��v�Ə����ꂽ�B�܂��A�̐l�̂��߂Ɉߗނ═��Ȃǂ��ꏏ�ɖ��������B�����āA���҂̂��߂ɂ͐H����������ꂽ�B��������Ȃ��썰�ɂ͈��Z�̒n���Ȃ��A���ɂ͉���ƂȂ��Ă��܂��Ƃ����M���������B
�������P�Ɉ�̂����邾���ł͂Ȃ��A�`���I�ȋV�����s���K�v���������B�J���M�����c��̈�̂͋V���Ȃ��Ŗ������ꂽ���߁A�썰�������o���B�����ň�̂��@��Ԃ��A���߂đ��V���s���܂œ��{�̌��t�ł����u�����v���Ȃ������Ƃ����B���������M�����邽�߁A�����̐l�X�͑��V���^�ʂ�s�����Ƃ��ƂĂ���ł������B�l�X�́u���v�����A���V���s���Ȃ����Ƃ��Ă����̂ł���B
�펀�������m�����𑒂邱�Ƃ�ӂ������R�B���A�A�e�i�C�̐l�X���E���Ă��܂����Ƃ����������N�����Ă���B�܂��d�߂̔Ɛl������@�Ƃ��āA���Y�������Ƃɂ����V���s��Ȃ��Ƃ����Y���������B����͓��̂����łȂ��A������������Ƃ������@�ƌ����邾�낤�B
|
�����V�̖@��
�M���V���̗��@�Ƃł���\����(�O640�`����)�́A�����Ɏ�X���ґ�֎~�̋K���݂��A���҂̎������q�ɑ��āA�A�e�l���L�̍��Ɛ��q�������B�u�v���^�[�N�p�Y�`�v�ɂ��ƁA�\�����́A�u�������̊O�o�╞�r���ɂ��Ă��@�����߁A���K���ƕ��c�Ƃ����߂��B�O�o�ɂ�3���ȏ�̒�����t���邱�Ƃ�A����ɂ͍����ȐH����A�����U��p���邱�Ƃ��֎~���A�܂������͖�ԊO�o����Ƃ��ɂ͓����K�v�ł������B�܂��߂��݂�\�����߂Ɏ����̑̂������ނ�������A��������������A�܂����l�̑��V�ɍ������邱�Ƃ��ւ���ꂽ�B�܂����҂̂��߂ɋ����]���ɂ�����A3���ȏ�̕������邱�ƁA�����̎��ȊO�͑��Ƃ̕�ɍs�����Ƃ��ւ����v�Ƃ���B�܂����̌�A�v���^�[�N(�H�`431)�̎���ɂ́A�j�q�����������@�Ɉᔽ�����ꍇ�ɂ́A�j�q�Ƃ��ď��X��������Ɋׂ��Ă���Ƃ��āA�w�l�ē���蔱����ꂽ�Ƃ����B
���M���V���l�̑��V
�M���V�A�ƃ��[�}�l�́A���҂ɑ��h���͂炢�A���҂��A�_���ŐN���Ă͂Ȃ�Ȃ���Ԃɕۂ����B�ł���Ȑl�X�̊Ԃɑ��h���͂炢�A�ᔽ�҂��s���_�ƈ��]�������ނ邾���łȂ��A�\�����̖@���ɂ���Ĕ�����ꂽ�B���҂ɕ���ꂽ���_�́A�ނ�̑��V�̑傫���ɂ���킳�ꂽ�B�����Ŏ��҂̖����ɂ���āA����y���ɍs�����Ƃ��ł��A���ꂪ���Ȃ�ʂƂ��ɂ͉��N�����E��f�r���Ƃ����^���ς��ނ���x�z���Ă�������ł���B
����̈��u
�ނ�͎��҂̖ڂ�����A�܂�����������B���̂��Ɣނ̊�͕���ꂽ�B�قƂ�ǑS�Ă̎��㏈�u�́A�ߐe�҂ɂ���čs�Ȃ��A���̔�p���g���ɂ���ĔP�o���ꂽ�B
���ɑ̂��₽���Ȃ�O�ɁA�S�g��L���A��̂������B���̂��ƁA�̂ɓ�p��h��A���O���p�����ߕ��𒅂��đS�g���B
�L�͎҂��O���Ŏ��ꍇ�A���n�ʼnΑ�����⍜��قɂ���A���炽�߂đ������s���ĉh�_��������ꂽ�B
�����̑O�ɁA���҂̌��ɁA�n���̉͂�n���n����̂��߂̉ݕ��������ꂽ�B���̂ق��Ɏ��҂̌��ɁA�������ō�����P�[�L�������ꂽ�B����͒n���̔Ԍ��̌��{���Ȃ��߂邱�Ƃ��ړI�ł������B�܂���̂𑗂�o���܂ł̊ԁA���҂̔����h�A�Ɋ|����ꂽ�B����͉Ƒ����ߒQ�ɂ��邱�Ƃ��������B�܂��A���҂�����̑̂𐴂߂鐅�̓������e�킪�h�A�̑O�ɒu���ꂽ�B
�Ñ�l�ɂƂ��āA���҂���C�������Ǝv���Ă����B����́A�������I���₢�Ȃ�A���ׂẲƍ�����͏��ꂽ�B
�������ƒ���
�����A�����̊��Ԃ́A�����Ă��Ȃ������悤�ł���B�Ñ�̖����́A�����ɍs���ȊO�́A����3�A4���ڂɍs�Ȃ�ꂽ�B���ɕn�����l�́A�����s��ꂽ�B�Z���r�E�X�̈ӌ��ł́A�Α��͎���8���ځA������9���ڂ��]�܂����Ƃ��ꂽ�B����������͎��͎҂Ɍ���ꂽ�B������ɂ�����ʂȏ����Ȃ��ł́A���d�ɍs�����Ƃ��o���Ȃ������B�����ł́A��̂�17���Ԉ��u�����B�����Ď��T�͓����ɍs�Ȃ�ꂽ�B����͌��Ɏキ�A��͊��鎞�ԂƂ݂Ȃ��ꂽ����ł���B
�Ƃ��Ɍ��̍s�����������S������A���̍ЊQ���N�����ꍇ�ɂ��A���̉�����f����A�X�A���@�A�w�Z���A�����ꂽ�B�����āA���ׂĂ̓s�s�́A���ӂ�\�����B��X�̓\�N���e�X�̎���[���Q���߂���ł���A�e�l�l��m���Ă���B
������
�A�e�l�̌R�l�y���N���X�́A�T���X�肵�ăA�e�i�C�ɋA��ƁA���̐푈�Ŏ��l�X�̑��V��ɍs���A����ɂ���ĕ�O�ŒǓ����������Ċ�����^�����B���̑��V�̖͗l�́A�c�L�W�f�X�́w���j�x�̒��ɏq�ׂ��Ă���B
�u���V�̍s����2���O�ɁA����������d�ɐ�m�҂̈⍜���Ղ�A�⑰�̎҂����͂��ꂼ��S�䂭�������̂��������B�����̎�������ƁA����͕����ʂɎ����̞l�Ɉ⍜��[�߁A������Ԃɂ̂��Ĉ����čs���B���҂͓��������̎҂����̍��ƈꏏ�ɔ[�߂���̂ł���B����ɕ����̂�����ꂽ�l�˂��A��̂܂܂���ɑ����B����͍s���s���ƂȂ��Ĉ�̂����e����Ȃ�Ȃ������҂����̂��߂ł���B����ւ̎Q���͎s���A�����l�̕ʂȂ��������B�܂��⑰�̏��B�͕�n�ɏW�܂��ĒǓ��̒Q����������B�s��͍��Ƃ̕�n�ɂ��ƁA�l�����u���A�����������ꂽ���ƁA�펀�҂ɒǓ��̌��t���q�ׂ���B�v
���y�́A���҂�V�E�ɓ������߁A���邢�͈�����Ԃ߂邽�߁A���邢�͎��҂̈⑰�̔߂��݂�]�����邱�Ƃ��ړI�ł������ƌ����B
�������ƉΑ�
�����ƉΑ��̓M���V�A�l�ɂ���Ď��n���ꂽ�B��̃M���V�A�l���A�Α��ɂ��e���������A���n�I����̏K���́A���҂����邱�Ƃł������B�N�w�҂��A�Α��Ɋւ���ӌ��������Ă����B�l�Ԃ̑̂��n���Ε���4�v�f�ō\������Ă����ƍl�����A�ŏ��̌����ł���ɋA�����߂ɉΑ����s��ꂽ�Ƃ����ӌ��B�܂����҂̍��̏o�����邽�߁A���͉̂���Ă���Ǝv���Ă��āA����䂦�ɉɂ���ď����K�v���������Ƃ������B�܂������e���s�����ȕ�������藣����āA�V�̏Z�܂��֔��Ă��邽�߂ɁA������������藣�����߂ɍs��ꂽ�Ȃǂ̈ӌ��ł������B
�ނ炪��̂�R�₵���d�́A���̌`���͂Ȃ��A�ޗ������܂��܂ł������B��̂��A�ςݏd�˂�ꂽ�d�̏�ɒu���ꂽ���A�ő��ɒP�ƂʼnΑ�����Ȃ������B�d�̏�Ɏ�X�̓����̂ق��A�M�d�ȓ�p�ƍ��Ȃǂ����ɒ����ꂽ�B
���R�l�͔ނ�̕���ƈꏏ�ɔR�₳�ꂽ�B���l�ɁA�ނ炪���Â����ߕ����������B�ނ炪��������{���Ă��炤���߂ɁA�⌾�̒��Ɏw���������B�Α��̉́A���҂̋ߐe�҂��F�l�ɂ���ē_���ꂽ�B�ނ�͈�̂������R����悤�ɕ��ɋF�����B
���R�ƈ̑�Ȗ�l�̑����ł́A���҂ɑ��h��\�����邽�߂ɁA�R�l�Ƃ��̈���́A�d�̂܂���3�������B�d���R���Ă���ԂɁA���҂̗F�B���A���ɗ����ă��C���𒍂��Ō̐l�̖����ĂB�d���S�Ă��ĉ���������ƁA�ނ�̓��C���ʼn̎c��������A���ƊD���W�߂��B�⍜�̓��C���Ő���A���̂��ƃI�C����h��A�⍜�ƊD�͒قɔ[�߂�ꂽ�B�ق̍ގ��͗l�X�ŁA�̐l�̓����ɂ������؍ށA�A����A��A�����g�p���ꂽ�B
�������̏ꏊ
���ʂ̐l�����ꍇ�A���̍��ق́A�ԂƉԗւŏ���ꂽ�B��ʓI�K���ŁA���ق���n�ɖ��������܂ŕz�ŕ����A����������Ȃ��悤�ɕی삵���B
�����Ɋւ��Ĉ�̂�������Ɋ��ɉ�����������Ƃ��ώ@���ꂽ�B�V�Ɋ�������邱�Ƃ��A���̐l�̍K���̂��߂ɂȂ�Ǝv��ꂽ�B���n�M���V�A�l�́A��̂����������̉Ƃɗp�ӂ��ꂽ�ꏊ�ɖ��߂��B�����ăe�[�x�l�́A���҂̗e�������Ă��Ȃ��Ƃ����Ă�ׂ��łȂ��Ƃ����@���������Ă����B�����Ă���̎���ɂ����Ă��A�s�s�̗̈���́A�����̏ꏊ�ɁA�L�O���Ƌ��ɖ��߂�ꂽ�悤�ł���B
�Ñ�ɂ́A���@�����҂̂��߂̌����ł����������̗Ⴊ����B���҂ɖ��_��^���邱�Ƃ��A���@�����Ă�ŏ��̋N���ł������B�������̎���ɂȂ��āA��ʓI�K���ɂ��A���҂͓s�s�̊O�⊲�����H�̒[�ɖ��������悤�ɂȂ����B����͎�ɓs�s�ɓ`�����邩������Ȃ��L�Q�ȓ��������邽�߂ł���B�����́A�����̐d���A�ނ�̉ƂɔR���ڂ�댯��h�����߂Ƃ������Ƃ�����B
�ǂ̉Ƒ����A�K���ȕ��������Ă����B���n�I�M���V���̋��ʂ̕挊�́A�n���̓����ł������B�����Ă̂��̎���ɂ́A���������H����Ă������B��͈�ʂɐŐ�������A�A�[�`����Ɍ��Ă�ꂽ�A�����Đl�Ƃ����|�p�I�ŁA�⑰�́A���̌��ŕ�炵���B�Β��ɉƑ��A���A���҂̋Ɛт����̌`���ō��܂ꂽ�B�R�l�̕挊���A�ނ�̕���ŏ���ꂽ�B����͋L�O���Ƃ��Ĕނ�̋L����ۂ��߂ɒu���ꂽ�̂ł���B
|
�����[�}�l�̑��V
���[�}�l�́A���V�ɑ傫�Ȓ��ӂ����B�M���V�A�l�Ɠ������A��������Ȃ����҂́A�y���ɓ���Ȃ��ƐM���Ă�������ł���B��������Ȃ��ƁA���y�̉͂�n��܂ł�100�N�̍Ό����K�v�ł������B
�]���Ĉ�̂��A�����ł��Ȃ������ނ�͕�����āA�������s�Ȃ����B�܂����R���̂������Ƃ��ɂ́A��̂ɓy�������A�������Ȃ��҂͔�����ꂽ�B���̂��߁A�ǂ�Ȏ�ނ̎�������Ȃ������̂ł���B
�����̏���
�l�������ԍۂɌ}����Ƃ��A�ނ�̋ߐe�҂́A���ōŌ�̑���߂��悤�Ƃ����B���͌�����o�Ă������Ƃ�ނ�͐M��������ł���B���̂��Ǝ��҂̎w�ւ��O���A�Α��p�̂܂��ɏグ��O�ɁA�Ăт����B���̂��ƈ�̂�n�ʂɒu���A��ɕa�l��u�����Ƃ͌Ñ�̏K���ŁA�����m�����ǂ������m�F�����B��̂́A���ɓ��Ő��߁A�����̖ʓ|������z��ɂ���č����h��ꂽ�B
���Ĉ�̂ɂ́A�̐l�����O�����ł��ǂ����𒅂����A�Ō�̏o�����ɑ��������A�����O�Ɍ����ă\�t�@�[�ɏ悹�Č��ւɒu���ꂽ�B�����ň����̎����Ȃ��ꂽ�B�\�t�@�[�́A�t�ƉԂŏ���ꂽ�B�̐l���h�_�̉������Ă�����A����͓���ɒu���ꂽ�B�������d�݂́A�M���V���l�Ɠ����悤�ɁA�n���̓n�D�Ǝ҂̂��߂Ɏ��҂̌��ɓ����ꂽ�B�܂��C�g�X�M�̎}���A�Ƃ̃h�A�Œu���ꂽ�B
���Α��̗���
���[�}�l�́A���ߎ��҂������B�����͌Ñ�́A�����čł����R�̕��@�ł��邪�A�ނ炪�M���V�A�l����Α��̏K���𑁂��ɍ̗p�����B����̓��[�}��2�̉��k�}�̖@���A����у��[�}�ŌÂ̖@�T�\��\�Ō����Ă���B�������A���a���̏I���܂ʼnΑ��͈�ʓI�ɂȂ�Ȃ������B��������̂��G�ɂ���Č@��Ԃ��ꂽ�̂�m�����c��̔��f�Ő��E�I�ƂȂ����B������L���X�g���̐Z���ƂƂ��ɉΑ��������Ă������B������4���I�̏I���ɂ͌����Ȃ��Ȃ����B
7�ˈȑO�̎q���͉Α������������ꂽ�B���l�Ɉ���ɑł��ꂽ�l�́A���ꂪ�������ꏊ�ɖ��߂�ꂽ�B����ɗr�������ɂ��ɕ����Đ_���ɂ����B
�����͈�ʎs���ƕ�����2��ނ��������B����c��A�E�O�X�g�X(�O64�`14)���A���̑�����F�߂邱�Ƃɔ��Ɋ��傾�����B�l�I�����́ATaciturn�ƌĂꂽ�B�c���ŁA�܂��͎�N�Ŏ����V��Acerbic�ƌĂꂽ�B�c���Ǝ�҂͐��l��葁�����߂�ꂽ�B���̑������Ӑ}���ꂽ�Ƃ��A���̂��A�Ď��l�ɂ���Č������7�A8���̊ԕۂ��ꂽ�B�����Ēj�q���ނ炪�锈��ǂ��������B
�l�I���V�ł́A��̂͒������u����Ȃ������B�����̓��ɐl�X���W�܂�A���̂́A������^�яo���ꂽ�B�\�t�@�[�͋��Ǝ��F�̍��ȕz�ɕ����A�̐l�̋ߐe�҂̌��Ɏx����ꂽ�B
|
���V�[�U�[�̎�
�V�[�U�[(�O102�`44)���u���[�^�X�ɈÎE���ꂽ���Ƃ́A���܂�ɗL���ŁA�V�F�[�N�X�s�A�́w�W�����A�X�E�V�[�U�[�x�ɂ́A���̓^�������������ƕ`�ʂ���Ă���B�u�v���^�[�N�p�Y�`�v���݂�ƁA�V�[�U�[���ÎE���ꂽ(3��15��)��A�⌾���\����A���[�}�s���̈�l��l�ɑ����̑��蕨���^�����邱�Ƃ��킩�����B���������c�Ȉ�̂������L��ɉ^��Ă����ƁA�Q�O�͍��|����֎q����������Ă��āA��̂̂܂��ɐςݏグ�A����ɉ����Ĉ�̂��Α��ɂ���(3��20��)�B
�E�F�C�S�[���ɂ��ƁA��͍̂L���5���Ԃ��肨�������Ɉ��u����A���V��3��20���ɂ��ƂȂ܂�邱�Ƃ����܂�A���̓��̗[���A���g�j�E�X�́A�V�[�U�[��J�ߎ^����̂��̂��A���̂��Ɩ����������������s�������ƂŁA��̂��Α��ɂ����B
������
�n�����s���Ɠz��́A�ȑf�Ȋ���ʼnΑ��p�̂܂��̎R�։^�ꂽ�B�����O�Ɏ��q���́A��ɂ���ĉΑ���։^�ꂽ�B�S�Ă̑������A��ԂɎ��s����邽�߂ɏ������g��ꂽ�B���������̌�A���̑����͓����ɍs����悤�ɂȂ����B�l�̕��ʂ̑����́A��ɖ�ɍs��ꂽ�B����ɋK��������A���ꂼ��̖����������Ă�l������l�A���邢�͎��i�Ղƌ����A���߂𒅂Ă����B
����̍ŏ��ɊNJy��t�҂��s���A�j�������̂��߂Ɍق��Ă����B�\��\�ɂ��ƁA�����̃t���[�g�̐��́A10�ɐ�������Ă����B���ɂ��ǂ��҂��̂��x�����B�ނ�̈�l�́A�����Ă����̐l�̌��t�ƍs����͕킵���B�����̔o�D�́A����Ƃ���K�Ȍ��t���Љ���B�����Ď��R�z�ꂪ�������B�ނ�̎�l���z������R�ɂ����̂ł���B
��̂̑O�Ɍ̐l�A����єނ̑c��̑����^�ꂽ�B�����̑��́A�����̌�ɍĂэL��Ɉ��u����A�̐l���푈�Ŗ����������Ȃ�A�h�_�̉����⋭�D�i�Ƌ��ɓW�����ꂽ�B
�L�͎҂̑����ł́A�ނ炪���������������������^�ꂽ�B�V�C���̑����ł́A�������������̓s�s���瑗��ꂽ2,000���̉������^�ꂽ�ƌ����Ă���B���҂̌�Ɍ̂́A�l�̗F�l��r�ɕ����ē����B�������q�ƁA�����ڂ��ڂ��ɂ��������������B�ߐe�҂͈ߕ��������A�����Ĕ����D�ŕ������A���������������肵���B�����ɏo�Ȃ��������̂Ȃ��ɂ́A�ޏ���̋��𑱂����܂ɑł��A�j���������҂������B����������͖@���ɂ���ċւ����Ă����B
���Ǔ�����
�L���Ȏs���̑����ł́A���̂��L��܂ʼn^�ꂽ�B�����ĉ��d����Ǔ��������A�ނ̑��q�A�ߐe�҂�F�l�A�s�������ɂ���čs��ꂽ�B�Ǔ������̖��_�́A�����ɂ���@�ɂ���Ē�߂�ꂽ�B�V�[�U�[�͔ނ̍Ȃ̎��ɁA�Ⴂ�����w�l���^���邱�Ƃ̏K���������B��������̌�ɘV�������E�������킸�A�Ǔ������ɂ��h�_��������ꂽ�B�����̊ԁA��͉̂��d�̑O�ɒu���ꂽ�B
�V�[�U�[�̎��̂́A���������Ԃ��������Ȏ��@�̂悤�ȃp�r���I���Œu����A�E�Q���ꂽ���̈ߕ��͖_���g���t�B�[�ɂ���Čf����ꂽ�B�����Ĕނ̑��́A�ނ�������̍��ՂƋ��Ɉړ��ł��铹��ɂ���Ă��炳�ꂽ�B�A�E�O�X�g�X��̎���ɁA�����l���ق߂�������Ǔ��������A�قȂ�ꏊ�ł��s�����Ƃ����K�ƂȂ����B
�������ɂ���
�Ñ�l�́A�c�搒�q�ɂ���āA�����̉ƂɎ��҂߂��ƌ����Ă���B�A�E�O�X�g�X�́A�A�N�`�E���̐퓬�̑O�ɌR�l�ւ̉����ŁA�u�G�W�v�g�l�́A�ނ�̕s���Ɋւ���l�����m�����邽�߁A��̂ɖh���������{�����B�v�ƌ������B�h�������ɂ��Ă̓w���h�g�X���q�ׂĂ���B�y���V���l�́A��̂��ł��邾�������ۑ����邽�߂ɂ낤��ނ�̈�̂ɓh�����B���[�}�l�͐_���Ǝs���̍l������A�s�s�ł̖��Α����ւ����B�Ƃ��Α��ɂ���Ċ댯�ɂ��炳�ꂽ��A��C�����L�ɂ���ĉ�������Ȃǂ̗��R�ł���B�܂��W���s�^�[�̐_�Ɏd����Վi�́A��̂ɐG�ꂽ��A��n�֍s���̂������Ȃ������B�����Ń��_���l�̊Ԃő�Վi��i�Ղ��A�����������q�ׁA�����Ď���ɂӂ�Ȃ��悤��̂ɕ������u���ꂽ�B
�������ƉΑ�
�����̏ꏊ�ɂ͌l�ƌ��Ƃ��������B�����̕�́A�ڗ����₷���A�����ׂ��^�������o�����邽�߂ɁA�쌴����A���H�̂��ɂ������B�����Ĕ���Ȑ��̍���������n�ɑ͐ς��A�אڒn��s���ɂ����B
��������n�͔������ꂽ�B�L�͎҂̎q���́A����ێ����錠�����������B
��Ǔ��ɕ��݂��錠�����A���O�ꂽ�����Ƃ��āA�V�[�U�[�ɗ^����ꂽ�B�l���Α�����A�����ꏊ�ɂ����Ė��߂���`����Bustum(�o�X�^��)�Ƃ������B�Α��p�̂܂��̎R���A�l���������Ւd�̌`�ɑg���Ă�ꂽ�B�d�͗e�Ղɉ������~�A���A�I�[�N�ނ��g��ꂽ�B�܂����Ǝ������⏕�Ɏg��ꂽ�B
�Α��̐d�́A�̐l�̃����N�ɂ���Ă�荂�Ⴊ����A�L�Q�ȓ������~�߂�C�g�X�M�̖��u���ꂽ�B�����Ċ댯�h�~�̂��߂ɉƂ���60���̋�����u�����B�Α��p�̐d�ɑ�ɏ悹����̂��u���ꂽ�B�̐l�̖ڂ͊J���ꂽ�B�ߐe�҂���̂ɍŌ�̃L�X�����A�����܂œ_�����B�ނ�͉����������邽�߁A���ɋF��A�����Ȃ������͍K�^�ł���Ǝv��ꂽ�B�ɍ����𓊂����݁A�܂��I�C���̓������J�b�v��M�A�ނ炪��������Ƃ��L�O����M�́A�ߕ��Ƒ����A�܂��̐l�̂��̂����łȂ����������̕����R�₵���B�����́A�̐l�������Ă���Ƃ�����������̂��I�ꂽ�B
���҂��R�l�̏ꍇ�A�d�̏�ɔނ̕���(��V�Ƌ��D�i)���悹��ꂽ�B�c���L�͎҂̑����ł́A�R�l���Α���̂܂���3��E�ɉ�����B�����t���܂Ɏ����A�����ăg�����y�b�g�̉��ɍ��킹�A���݂��̕�����Ԃ����Ă��B���̏K���̓M���V�A�l����肽�悤�ł���B����͂Ƃ��ɂ͖��N��ōs�Ȃ�ꂽ�B��X�ȓ����A���Ɍ̐l���D���ł������������Α���ɓ������܂ꂽ�B
�Ñ�ł͕ߗ��͓z�ꂩ�����m�Ƃ����B�K���A�̊Ԃł́A�z�ꂪ�ނ�̎�l�̐d�ŔR�₳�ꂽ�B�����ăC���h�l�ƃg���L�A�l�̊Ԃł́A�Ȃ��v�̐d�̏�ɋ]���ƂȂ����B
���ƊD�͍ł������ȍ��肪�U��܂��ꂽ�B�N�����x�̃����N�ɏ]���āA���킩�^�J���嗝���₩���̍��قɓ����ꂽ�B�y���ł́A�S�Ă̑����Ƌ��Ɉ�̂����ɓ����ꂽ�B�����͐�����ꂽ�B���[�}�l���ǂ̕����Ɍ�����ꂽ���킩���Ă��Ȃ����A�A�e�l�l�͐����������Ė������ꂽ�B
�̐l�̈�̂���ɒu�����ƁA���E�҂ɂ���ď��邽�߂ɁA�I���[�u�����j���̎}�Ő�����3��ӂ肩�����B���ꂩ�瑑�d�Ɂu�o�����Ă��悢�B�v�Ƃ������}�ʼn��x���w�ʂ�x������Ԃ����B
�Α���3���ԁA�⍜�͓y�ɖ����������Ȃ������B��҂͐S�g����߂邽�߉Ƃɖ߂�A�����ӂ肩�������ƁA�̏�ɕ������B�Ƃ���߂邽�߁Aⴂ��|ⴂő|�����߂�ꂽ�B������s�Ȃ��l��Everriator�ƌ������B
���Ǔ��̏K��
�����̌��9���̊ԁA�Ƒ��͑r�ɂ��A��ł̋V�����s��ꂽ�B���̊ԁA�@��ɑ����l��̐l�̊W�҂��Ăяo�����Ƃ́A�s�@�ł������B9���ڂɐ��т�������ꂽ�B����ŋV���͏I�������A���҂ւ̕�[�͈Ȍ㉽�x���s��ꂽ�B���ɂ́A���Ɛ��тƉԗւ�������ꂽ�B��̑O�ɂ͏������Ւd���ݒu����A�����č��������ꂽ�B�Ԑl���������邽�߁A�����v�������ꂽ�B�����́A���҂Ɛ��҂̂��߂ɍs��ꂽ�B��ɂ͈�ʂɓ��A���^�X�A�p���A���Ȃǂ��������A���҂̗삪���ĐH������Ǝv��ꂽ�B
�L�͎҂̑����̌�ɂ́A�̐l���Ԃ߂�̂��߂̋��������łȂ��A��҂ɐ����̔z�����s��ꂽ�B�����m�̃V���[��Q�[���B���ꂪ�����Ԃ��������B�V�B���̑��q�̃t�@�E�X�g�^�X�́A���̎��㉽�N�����āA�S�����̌h�ӂ�\���������m�̃V���[��\�����B�܂����̈⌾�ɏ]���ċ������Â����B
�r�̊��Ԃ́A�k�}�ɂ���Ē�߂��Ă����B���V�������đc�����Ȃ��߂邽�߁A�����͕v��e�̎���10�J���ԁA������1�N�ԑr�ɕ������B�ЊQ�̏ꍇ�ɂ����̑r�Ƃ��āA�����I���邢�͌��̎w���ŁA�d���S�̂���~���A�@���X�͕���ꂽ�B�ߓx�̔߂��݂̂�������ƁA���@�̐_�����őł���A�Ւd�͂Ђ�����Ԃ��ꂽ�B���̂悤�ȋɒ[�Ȕ߂��݂́A�c���ɂƂ��ĕs���ł������B�r�̊ԁA���[�}�l�͉ƂŎ��������B�ǂ̌�y���������A�ނ炪���߂𒅂��̂̓G�W�v�g�l�̏K�����痈�����̂ł���B
�Ƃ̏���ƂȂ�Ǝv�����_���Ȃ��B�����͋��Ǝ��F�̑��������O���A�j���Ɠ��������߂𒅂��B���̑r�ŁA�c���͎w�ւ��O���A�s�������̓o�b�W���A�����ė̎��́A��@�ŕ��i�̈֎q�ɍ��炸�A���ʂ̃x���`�ɍ������B
����̂͂Ȃ�
���[�}�l�́A�ꐶ�̊Ԃɔނ玩�g�̂��߂ɕ�����Ă���A�⌾�ɂ���ĕ�����Ă邱�Ƃ��w�������B���̔�p�͎����ŕ��S�����B�������̕�́A��ʂɑ嗝�ő����A�M���V�����ɉ��ɖ��A����ꂽ�B
���ʂ̕�͒n���Ɍ��z���ꂽ�B���̑������A�n����n(�J�^�R�[��)�̖��O�ŃC�^���A�ɂ܂����݂��Ă���B�ǂŐ���ꂽ�E�݂ɍ��ق��u���ꂽ�B�����̔������̒��̌E�݂Ƃ̗ގ��_����A�R�����o���A�ƌĂꂽ�B��͎�X�̒����ƒ��ŏ����A����̌��t����������܂�Ă���B
��̂���P�ɖ�������ꍇ�A����̌��t���A�̊��ɍ��܂ꂽ�B��͔��Q���ꂽ�L���X�g���k�̂��߂ɉB��Ƃ̖�ڂ��ʂ������B
�@ |
 |


 �@
�@ |














 �@
�@ �@
�@ �@
�@






 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@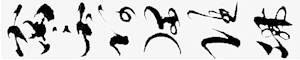 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@