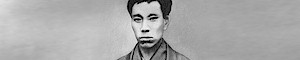|
|
|
■死生観・死に様・往生・・・ |
|
 |
|
| 電児 | 春の陽に桜日傘で目を瞑り 知らぬ阿弥陀に道を聞きたい 桜散る風に背を向け目を瞑り 縁者亡者のささやきを聞く 花吹雪右に左と肩揺すり 倶生神はと手をさしのべる 春の陽に肩のお神に子守唄 閻魔いぶかる夢見の話 善事なし暇な毎日悪事なし 倶生つきあう無事な一生 |
| お市の方 | 風さそう花よりもなほ我はまた 春の名残をいかにとやせむ さらぬだに打ぬる程も夏の夜の 別れを誘ふ郭公(ほととぎす)かな |
| ねね・醍醐の花見 | 咲けば散り散れば咲きぬる山桜 いやつぎつぎの花さかりかな |
| 阿南惟幾 | 大君の深き恵に浴みし身は 言い残すべき片言もなし |
| 安藤九郎左衛門 | 老いの身はいづくの土となるとても 君が箕輪に心留まる |
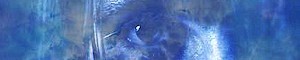
|
|
| 安藤広重 | 東路に筆を残して旅の空 西のみくにの名所を見む |
| 伊達政宗 | 馬上少年過 時平白髪多 残躯天所許 不楽是如何 曇りなき心の月を 先だてて 浮世の闇を照らしてぞ行く 咲きしより今日散る花の名残まで 千々に心のくだけぬるかな |
| 伊東義益 | 閑かなる 時世に花も おくれじと 先づ咲きそむる 山桜かな |
| 伊藤博文 | 万里平原 南満州 風光闊遠 一天の秋 当年戦跡 余憤を留む 更に行人をして暗愁牽かしむ |
| 井原西鶴 | 辞世 人間五十年の究まり それさえ我にはあまりたるに ましてや浮世の月見過しにけり 末二年 追善発句 月に尽きぬ世がたりや二万三千句 如貞 念仏きく常さえ秋はあわれ也 幸方 秋の日の道の記作れ死出の旅 万海 世の露や筆の命の置所 信徳 残いたか見はつる月を筆の隈 言水 |
| 井上井月 | 何処やらに鶴の声聞く霞かな |
 

 |
|
| 一の台 (秀次側室) |
つまゆへに くもらぬ空に 雨ふりて 白川くさの 露ときえけり ながらへて ありつるほどの 浮世とぞ 思へばなかる 言葉もなし |
| 一休和尚 | 須弥南畔(この世界)誰か我禅に会う 虚堂来る也 半銭に値せず |
| 身後精魂何処にか去る 黄陵の夜雨馬嵬の風 | |
| 一遍 | みづから一念発心せんよりほかには 三世諸仏の慈悲も済ふこと能はざるものなり 一代聖教みな尽きて 南無阿弥陀仏に成り果てぬ わが亡骸は野に捨て獣に施すべし |
| 宇喜多秀家 | 御菩薩の種を植えけんこの寺に 緑の松のあらぬ限りは |
| 羽川珍重 | たましいのちり際も今一葉かな |
| 英一蝶 | まぎらかす浮世の業の色どりも ありとや月の薄墨の空 |
| 岡倉天心 | 十二万年夕月の夜 訪ひ来ん人を松の影 |
| 岡田以蔵 | 君が為め尽くす心は水の泡 消えにし後は澄みわたる空 |
 |
|
| 沖田総司 | 動かねば闇にへだつや花と水 |
| 加賀千代女 | 月も見てわれはこの世をかしくかな |
| 快川紹喜 | 心頭滅却すれば火もまた涼し |
| 芥川龍之介 | 水涕や鼻の先だけ暮れ残る |
| 貝原益軒 | 越し方は一夜ばかりの心地して 八十路あまりの夢を見しかな |
| 柿本人麻呂 | 鴨山の岩根し枕けるわれをかも 知らにと妹が待ちつつあるらむ |
| 葛飾北斎 | 人魂で行く気散じや夏野原 |
| 蒲生氏郷 | 限りあればふかねど花は散りぬるを 心短き春の山風 |
| 甘粕正彦 | 大博打元も子もなくすってんてん (大ばくち身ぐるみ脱いですってんてん) |
 


|
|
| 紀貫之 | 手に結ぶ水にやどれる月影の あるかなきかの世にこそありけれ |
| 鬼坊主清吉 | 武蔵野にはじかる(=はだかる)程の鬼あざみ 今日の暑さに枝葉しおるる |
| 戯僧 | 世の中はしやのしやの衣つつてんてん でくる坊主に残る松風 |
| 吉川経家 | 武夫の取り伝へたる梓弓 かへるやもとの栖なるらん |
| 吉村寅太郎 | 吉野山風に乱るるもみじ葉は 我が打つ太刀の血煙と見よ 曇りなき月を見るにも思うかな 明日は屍の上に照るやと |
| 吉田松蔭 | 親を思う心に勝る親心 けふの音づれ何ときくらん(親兄弟当て) これほどに思定めし出立を けふ聞く声ぞそうれしかりける かへらじと思い定めし旅なれば ひとしほぬるる涙松かな 身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも とどめ置かれし大和魂 かくすればかくなるものと知りながら やむにやまれぬ大和魂 |
 |
|
| 宮沢賢治 | 方十里稗貫のみかも稲熟れて み祭三日そらはれわたる 病のゆえにもくちんいのちなり みのりに棄てばうれしからまし |
| 菊五郎(六代目) | まだ足らぬ踊り踊りてあの世まで |
| 芹沢鴨 | 雪霜に色よく花のさきがけて 散りても後に匂ふ梅が香 |
| 近松門左衛門 | それ辞世さる程さてもその後に 残る桜の花し匂はば |
| 空海 | 生のはじめに昏(くら)く生の終わりに冥(くら)し |
| 空也 | 無覚の聖衆来迎空に満つ |
| 契沖 | 心平等といえども事に差別あり 差別の中心はまさに平等たるべし |
| 月照 | 曇なき心の月も薩摩潟 沖の波間にやがて入りぬる |
 |
|
| 原石鼎 | 松朽葉かからぬ五百木無かりけり |
| 源実朝 | 出でて去なば主なき宿となりぬとも 軒端の梅よ春を忘るな |
| 乞食女 | ながらえばありつる程の浮世ぞと 思えば残る言の葉もなし |
| 幸徳秋水 | 爆弾のとぶよと見てし初夢は 千代田の松の雪折れの音 |
| 江藤新平 | ただ皇天后土我が心を知るのみ |
| 荒木村重・妻 | みがくべき心の月の曇らねば 光と共に西へこそ行け |
| 香川玄悦 | 仏神の恵みに叶う我が流儀 末世の人を救いたまへや |
 

 |
|
| 高橋多一郎 | 鳥か啼くあつま武男か真心は 鹿島の里のあなたと知れ |
| 高杉晋作 | おもしろきこともなき世をおもしろく すみなすものは心なりけり |
| 黒田官兵衛(如水) | 思ひおく言の葉なくてつひに行く 道は迷はじなるにまかせて |
| 今川氏真 | なかなかに世をも人をも恨むまじ 時にあはぬを身の科にして |
| 佐久間盛政 | 世の中を巡り果てなる小車は 火宅の門を出るなりけり |
| 佐々成政 | この頃の厄妄想を入れ置きし 鉄鉢袋今破るなり |
| 駒姫(伊満) | 罪なき身も世の曇りにさへられて ともに冥途に赴かば 五常のつみもほろびなんと思ひて 罪をきる弥陀の剣にかかる身の なにか五つの障りあるべき |
| (「恨の介」おこぼ) | 南無阿弥陀 蓮(はちす)の露とこぼるれば 願ひの岸に到る嬉しき |
| 斎藤道三 | 捨ててだにこの世のほかはなき物を いづくかつひのすみかなりけむ |
 |
|
| 細川ガラシャ(伽羅奢) | 露をなどあだなるものと思ひけん わが身も草に置かぬばかりを 先立つは今日を限りの命ともまさりて 惜しき別れとぞ知れ 散りぬべき時知りてこそ世の中の 花も花なれ人も人なれ |
| 在原業平 | つひに行く道とはかねて聞しかど 昨日今日とは思はざりしを |
| 坂 英力 | うきくもを払ひかねたる秋風の 今は我か身にしみぞ残れる |
| 薩摩守平忠度 | さざなみや志賀の都は荒れにしを 昔ながらの山桜かな 行きくれて木の下のかげを宿とせば 花や今宵の主ならまし |
| 三浦義同(道寸) | 討つ者も討たるる者も土器よ くだけて後はもとの塊 うつものもうたれるものもかわらけよ くだけて後はただの土くれ |
 

 |
|
| 三好長治 | 極楽も地獄もさきは有明の 月の心にかかる雲なし 三好野の梢の雪と散る花を 長き春とや人のいふらん |
| 三村元親 | 人といふ名をかる程や末の露 きえてぞかへるもとの雫に |
| 三村勝法師丸 | 夢の世に幻の身の生れ来て 露に宿かる宵の電(いかづち) |
| 三島由紀夫 | 益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに 幾とせ耐へて今日の初霜 散るをいとふ世にも人にもさきがけて 散るこそ花と吹く小夜風 |
| 三遊亭一朝 | あの世にも粋な年増がゐるかしら |
| 山岡鉄舟 | 腹いたや苦しき中に明けがらす |
| 山下奉文 | 待てしばし勲残して逝きし戦友 後な慕いて我も行きなん |
 |
|
| 山崎宗鑑 | 宗鑑はいづこへ行くと人問はば ちと用(癰)ありてあの世へといえ |
| 山上憶良 | 士やも空しくあるべき万代に 語りつぐべき名は立てずして |
| 山川唐衣 | 我ながら何に名残を惜しむらむ 思ひおくべきこともなき世に |
| 山村通庵 | 本来の宗風端無く達通す 眼光落地 自性真空 |
| 山田風太郎 | いまわの際に言うべき一大事はなし |
| 山之手殿(寒松院) | 五行をばその品々に返すなり 心問わるる山の端の月 |
| 山本五十六 | 天皇の御楯とちかふ真心は とどめおかまし命死ぬとも 弓矢とるくにに生れし益良雄の 名をあらはさむときはこのとき |
 

 |
|
| 司馬江漢 | 江漢が年が寄ったで死ぬるなり 浮世に残す浮絵一枚 |
| 柴田勝家 | 夏の夜の夢路はかなき跡の名を 雲居にあげよ山郭公(やまほととぎす) |
| 車持娘子 | 我が命は惜しくもあらずさにつらふ君によりてそ長く欲りせし |
| 十返舎一九 | この世をばどりゃお暇せん香の 煙とともに灰さようなら |
| 緒方襄 | すがすがし花の盛りにさきがけて 玉と砕けむ大丈夫は 死するともなほしするとも我が魂よ 永久にとどまり御国まもらせ |
| 商人の娘 | おのづから心の水の清ければ いづれの水に身をや清めん 生まれ来て身には一重も着ざりけり 浮世の垢をぬぎて帰れば 死ぬる身の教えなきとも迷うまじ 元来し道をすぐに帰れば |
 |
|
| 小西来山 | 来山はうまれた咎で死ぬる也 それでうらみも何もかもなし |
| 小堀遠州 | 昨日といい今日とくらしてあすかがは(飛鳥川) 流れてはやき月日なりけり 昨日といひ今日とくらしてなす事も なき身の夢のさむる曙 |
| 小林一茶 | 盥(たらい)から 盥へうつる ちんぷんかん |
| 松前公広 | 来し道も帰る道にも只独り のこる姿は草の葉の露 |
| 松尾芭蕉 | 旅に病んで夢は枯野をかけ巡(廻)る |
| 上杉謙信 | 四十九年一睡の夢 一期の栄華一杯の酒 極楽も地獄も先は有明の 月の心に懸かる雲なし |
 

 |
|
| 織田信孝 | 昔より主をうつ海の野間なれは尾張を待てや羽柴筑前(勢州軍記) むかしより主をうつみのうらなれは むくいをまてやはしはちくせん(川角太閤記) 昔より主をうつみの野間なれば おはりを待や羽柴筑前(北畠物語) むかしより主をうつみの野間なれば むくひをまてや羽柴筑前(張州府志) いにしへも主を内海の縁(浦)あれば むくいをまてや羽柴筑前(三河後風土記) 昔より主を内海の浦なれば尾張を待てや羽柴筑前(氏郷記) |
| 新門辰五郎 | おもいおくまぐろの刺身河豚の汁 ふっくらぼぼにどぶろくの味 |
| 森鴎外 | 余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス |
| 真木和泉 | 大山の峯の岩根に埋めにけり 我が年月の大和魂 |
| 神保長輝 | 帰りこん時ぞと母の待ちしころ はかなきたより聞くべかりけり |
 |
|
| 親鸞 | 我なくも法は尽きまじ和歌の浦 あをくさ人のあらん限りは 常陸の人々ばかりぞ この者どもをも御あはれみ あはれ候ふべからん いとをしう人々あはれみ思しめすべし |
| 諏訪頼重 | 自ずから枯れ果てにけり草の葉も 主あらばこそ又ぞ結ばめ |
| 世捨て人 | 呉くれぬ憂さ嬉しさも果てぬれば おなじ裸のものの身にこそ |
| 正岡子規 | 糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな 痰一斗糸瓜の水も間にあはず をとゝひのへちまの水も取らざりき |
| 清河八郎 | 魁けてまたさきがけん死出の山 迷ひはせまじすめらぎの道 |
| 清水宗治 | 世の中におしまるる時死にてこそ 花も花なれ色もありけり 浮世をば今こそ渡れ武士(もののふ)の 名を高松の苔に残して |
 

 |
|
| 西郷一族(会津) | いざたどらまし死での山道手をとりて 共に行きなば迷わじを なよたけの風にまかする身ながらも たわまぬ節はありとこそ知れ(西郷千重子) 死にかへり幾度び世に生るとも ますら武夫となりなんものを 武士の道と聞きしをたよりにて 思ひたちぬるよみの旅かな あいつねのおちこち人に知らせてよ 保科近悳けふしぬるなり 秋霜飛んで金風冷たく 白雲去って月輪高し 手をとりてともに行きなば迷はじよ いざたどらまじ死出の山みち |
 |
|
| 西行法師 | 捨て果てて身儚きものと思いしも 雪の降る日は寒くこそあれ 願はくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月のころ 世の中を思へばなべて散る花の わが身をさてもいづちかもせむ 花さへに世を浮き草になりにけり 散るをおしめばさそふ山水 そらになる心は春の霞にて 世にあらじともおもひ立つかな 花よりは命をぞなお惜しむべき待ちつくべしと思ひやはせし |
| 石川五右衛門 | 石川や浜の真砂は尽きるとも 世に盗人の種は尽きまじ |
| 石谷・斎藤道三家臣 | 名を惜しむ命やかへん世の中に ながらへはつる習ひありとも |
| 石田三成 | 筑摩江や芦間に灯すかがりびと ともに消えゆくわが身なりけり |
| 絶海中津 | 虚空地に落ち 火星乱れ飛ぶとも 筋斗を倒打して 鉄囲を抹過せん |
 

 |
|
| 千利休 | 人世七十 力圍希咄吾這宝剣 祖仏と共に殺す 堤ぐる我が得具足の1つ太刀 今この時ぞ天に抛 |
| 川端茅舎 | 朴散華即ちしれぬ行方かな |
| 川島芳子 | 家あれども帰るを得ず涙あれども泣く所を得ず |
| 泉鏡花 | 露草や赤のまんまもなつかしき |
| 浅野長矩 | 風さそふ花よりもなほ我はまた 春の名残をいかにとやせん |
| 前田慶次郎 | 生くるまで生きたら死ぬであろうと思ふ |
| 前田夕暮 | 雪の上に春の木の花散り匂ふ すがしさにあらむわが死顔は |
| 鼠小僧次郎吉 | 天が下古き例はしら浪の 身にぞ鼠と現れにけり |
| 足利義輝 | 五月雨はつゆかなみだか時鳥 わが名をあげよ雲の上まで |
 |
|
| 足利義尚 | もしを草あまの袖じの浦波に やどすも心有明の月 出る日のよの国までの鏡山を 思し事もいたづらの身や |
| 足利義政 | 何事も夢まぼろしと思い知る 身には憂いも喜びもなし |
| 太宰治 | 池水は濁りににごり藤なみの 影も映らず雨ふりしきる |
| 大田垣蓮月 | 願わくばのちの蓮(はちす)の花のうえに くもらぬ月をみるよしもがな |
| 太田道灌 | かかる時さこそ命の惜しからめ かねて亡き身と思い知らずば 身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし大和魂 |
| 大久保一翁 | なにひとつ世のためはせでまうつしに のこす姿の恥ずかしきかな |
 

 |
|
| 大高源吾 | 梅で飲む茶屋もあるべし死での山 |
| 大西滝治郎 | これでよし百万年の仮寝かな |
| 大石内藏助 | あらたのし思いは晴るる身は捨つる 浮世の月にかかる雲なし 極楽の道はひとすぢ君ともに 阿弥陀をそへて四十八人 |
| 萱野三平重実(涓泉) | 晴れゆくや日頃心の花曇り |
| 大前田英五郎 | あら嬉れし行く先知れぬ死出の旅 |
| 大谷吉継 | 契りあれば六つの衢に待てしばし 遅れ先だつことはありとも |
| 大津皇子 | ももづたふ磐余の池に鳴く鴨を 今日のみ見てや雲隠りなむ |
| 大田南畝 | ほととぎす鳴きつるかたみ初鰹 春と夏との入相の鐘 |
| 大島澄月 | 澄む月のしばし雲には隠るとも 己が光は照らさざらめや |
 |
|
| 大道寺政繁 | 後の世のかぎりぞ遠き弓取りの いまはのきはに残す言の葉 |
| 大内義長 | 誘ふとて何か恨みん時きては 嵐のほかに花もこそ散れ |
| 大内義隆 | 逆ならぬ君の浮名を留めおき 世にうらましき春の浦波 討つ人も討たるる人も諸共に 如露亦如電 応作如是観 |
| 大葉子 | 韓国の城(き)の上に立ちて大葉子は 領巾(ひれ)振らすも大和へ向きて |
| 瀧沢馬琴 | 世の中の厄をのがれて元のまま かへすは天と地の人形 |
| 沢庵和尚 | かかる時さこそ命の惜しからめ かねて亡き身と思い知らずば 全身を埋めてただ土を覆うて去れ 経を読むことなかれ 百年三万六千日 弥勒観音幾是非 是亦夢非亦夢 弥勒夢観音亦夢 仏云応作如是観 |
 

 |
|
| 叩々老人 | 五斗(醤油のかす)はおき後生(来世)も乞わぬ我が腰を 折りて今日はい左様なら |
| 但木土佐 | 雲水の行方はいづこむさし野を ただ吹く風にまかせたらなん |
| 池田和泉守 | 露の身の消えても心残り行く 何とかならんみどり子の末 |
| 竹久夢二 | 日にけ日にけ かっこうの啼く音ききにけり かっこうの啼く音はおおかた哀し |
| 中山信名 | 酒も飲み浮かれ女も見つ文もみつ 家も興して世に恨み無し |
| 中野貫一 | 無理おごり朝寝かけ事慎みて なりはひはげめ国は栄えん |
| 中野竹子 | 武士の猛き心にくらぶれば 数にも入らぬ我が身ながらも |
| 朝倉義景 | 七転八倒 四十年中 無他無自 四大本空 かねて身のかかるべしとも思はずば 今の命の惜しくもあるらむ |
 |
|
| 長野業盛 | 陽風に梅も桜も散りはてて 名にぞ残れるみわの郷かな |
| 鳥居強右衛門勝商 | 我が君の命に代わる玉の緒を 何いとひけむもののふの道 |
| 弟橘比売 | さねさし相模の野に燃ゆる火の ほむらに立ちて問いし君はも |
| 天狗小僧霧太郎 | 生涯を賭けて盗めど今までに 身に付く金は今日の錆び槍 |
| 田中河内介 | ながらへてかはらぬ月を見るよりも 死して払はん世々の浮雲 |
| 土肥原堅二 | わが事も全て了りぬいざさらば さらばさらばではい左様なら 有無の念いまは全くあと立ちて 今日このころの秋晴れの如し |
 

 |
|
| 土方歳三 | 叩かれて音の響きしなずなかな よしや身は蝦夷が島辺に朽ちぬとも魂は東(あずま)の君やまもらむ |
| 島津義久 | 世の中の米と水とを汲み尽くし 尽くして後は天津大空 |
| 島津義弘 | 春秋の紅葉はついに留まらず 人も虚しき関路なりけり |
| 島木赤彦 | 我が家の犬はいづこにゆきならむ 今宵も思ひいでて眠れる |
| 東郷茂徳 | いざ児らよ戦うなかれ戦わば 勝つべきものぞゆめな忘れそ |
| 東条英機 | たとへ身は千々に裂くともおよばじな 栄しみ世をおとせし罪は さらばなり苔の下にてわれ待たん 大和島根の花薫るとき 我ゆくもまたこの土地にかへり来ん 國に酬ゆることの足らねば 明日よりはだれにはばかるところなく 弥陀のみもとでのびのびと寝む |
 |
|
| 陶晴賢 | 何を惜しみ何を恨まん元よりも この有様の定まれる身に |
| 道元 | 渾身求むるところなく 活きながら黄泉に陥つ |
| 徳川家康 | 人生とは重き荷を背負いて遠き道を行くが如し 嬉しやと二度さめて一眠り うき世の夢は暁の空 先に行くあとに残るも同じこと 連れていけぬをわかれとぞ思う |
| 細川幽斎 | いにしへも今もかはらぬ世の中に こころの種を残す言の葉 |
| 内藤信順 | 世の中は時雨となりてきのふ今日 ふみとどむべき言の葉もなし |
| 楠木正季 | 七生まで只同じ人間に生まれて 朝敵を滅ぼさばや |
| 楠木正行 | 返らじとかねて思えば梓弓 亡き数に入る名をぞとどむる |
 

 |
|
| 日野俊基 | 古来の一句死も無く生も無し 万里雲尽き長江水清し 秋を待たで葛原岡に消える身の 露のうらみや世に残るらん |
| 乃木希典 | うつし世を神さりましし大君の あとしたがひて我はゆくなり |
| 乃木静子 | いでまして帰ります日のなしと聞く けふの御幸にあふぞ悲しき |
| 波多野秀治 | 冬のきて山はあらはに木の葉散り 残る松のみ峰にさびしき |
| 萩原朔太郎 | 行列の行きつくはては餓鬼地獄 |
| 八百屋お七 | 世の哀れ春吹く風に名を残し おくれ桜の今日散りし身は |
| 伴 信友 | いまわには何をかいわむ世の常に いいし言葉ぞ我が心なる ついに逝くときはきにけり残りいて なげかん人ぞかなしかりける |
 |
|
| 板垣征四郎 | とこしへにわがくに護る神々の 御あとしたひてわれは逝くなり |
| 飯田蛇笏 | 誰彼もあらず一天自尊の秋 |
| 飯尾宗祇 | 眺むる月にたちぞ浮かるる |
| 尾崎紅葉 | 死なば秋露のひぬ間ぞ面白き |
| 富樫源次 | マスラオのマスせんずれば 若き血潮ほとばしりじっと手をみる |
| 武川信臣 | 世にしばし赤き心はみすてども 散るにはもろき風のもみぢ葉 |
| 武田勝頼 | 朧なる月もほのかにくもかすみ 晴れて行くへの西の山の端(は) |
| 武田勝頼夫人(桂林院) | 黒髪の乱れたる世ぞはてしなき 思いに消ゆる露の玉の緒 |
| 武田信勝 | あだに見よたれも嵐のさくら花 咲き散るほどは春の夜のゆめ |
 

 |
|
| 武藤 章 | 現世 ひとや(獄舎)のなかのやみにいて かの世の光ほのに見るかな |
| 仏行坊 | ゆこうゆこうと思えば何も手につかず ゆこやれ西の花のうてなへ |
| 平行盛 | ながれての名だにもとまれゆく水の あはれはかなきみはきえぬとも |
| 平薩摩守忠度 | 行き暮れてこの下陰を宿とせば 花や今宵の主ならまし |
| 平田篤胤 | 思う事の一つも神に勤めをへず けふや罷るかあたらこの世を |
| 平野国臣 | みよや人嵐の庭のもみぢ葉は いづれ一葉も散らずやはある |
| 柄井川柳 | 木枯しや跡で芽をふけ川柳 |
 |
|
| 別所長治 | 今はただ恨みもあらず諸人の いのちにかわるわが身と思えば |
| 別所長治・妻 | もろともに消え果つるこそ嬉しけれ おくれ先立つならいなる世を |
| 別所友之 | 命をも惜しまざりけり梓弓 すゑの末まで名を思ふ身は |
| 別所友之・妻 | たのめこし後の世までに翅をもならぶる鳥のちぎりなりけり |
| 戊辰戦争・二本松藩士 | あす散るも色は変わらじ山桜 |
| 戊辰戦争・武士の妻 | なよ竹の風にまかせる身ながらも たわまぬ節はありとこそきけ |
| 豊臣秀吉 | 露と落ち露と消えにし我身かな 難波の事も夢のまた夢 |
| 豊臣秀次 | 磯かげの松のあらしや友ちどり いきてなくねのすみにしの浦 月花を心のままに見つくしぬ なにか浮き世に思ひ残さむ うたたねの夢の浮世を出でてゆく 身の入相の鐘をこそ聞け 思ひきや雲居の秋の空ならで 竹編む窗の月を見むとは |
 

 |
|
| 北条基時 | 待てしばし死出の山辺の旅の道 同じく超えて憂き世語らん |
| 北条時頼 | 業鏡高く懸げ三十七年 一槌にして打ち砕き大道坦然たり |
| 北條氏照 | 天地(あまつち)の清きなかより生まれ来て もとのすみかに帰るべらなり 吹くと吹く風な恨みそ花の春 紅葉の残る秋あればこそ |
| 北條氏政 | 雨雲のおほへる月も胸の霧も 払ひにけりな秋の夕風 我が身いま消ゆとやいかに思ふべき 空より来りくうに帰れば |
| 北條氏直 | 結びして解くる姿はかはれども 氷のほかの水はあらめや |
| 堀 光器 | 神かけて誓ひしことのかなはずば ふたたび家路思はざりけり |
| 本因坊算砂 | 碁なりせば劫(コウ)など打ちて生くべきを 死ぬるばかりは手もなかりけり |
 |
|
| 本間雅晴 | 戦友ら眠るバタンの山を眺めつつ マニラの土となるもまたよし |
| 本居宣長 | 今よりははかなき世とは嘆かじよ 千代の棲家を求めえつれば |
| 夢窓疎石 | それ 道に去来生死の相なく また 安危治乱の変なし |
| 無抑和尚 | 傀儡抽牽六三年 喝 春風天を拂う |
| 明智光秀 | 順逆二門に無し 大道心源に徹す 五十五年の夢覚め来れば 一元に帰す 心しらぬ人は何とも言はばいへ 身をも惜まじ名をも惜まじ |
| 毛利元就 | 友を得てなおぞうれしき桜花 昨日にかはる今日のいろ香は |
| 矢沢頼綱の母 | 死出の山月のいるさをしるべにて 心の闇を照らしてぞ行け |
| 柳亭種彦 | われも秋六十帖の名残かな |
 

 |
|
| 有島武郎 | 愛の前に死がかくまでも無力なものだとは この瞬間まで思はなかった |
| 与謝蕪村 | 白梅に明くる夜ばかりとなりにけり |
| 良寛 | 散る桜残る桜も散る桜 うらを見せおもてを見せて散るもみじ 草の上に蛍となりて千年を待たむ 妹が手ゆ黄金の水を給ふと言はば |
| 林忠崇 | 真心のあるかなきかは屠りだす 腹の血潮の色にこそ知れ |
| 林八右衛門 | 六十路ふるやぶれ衣をぬぎすてて 本来空へ帰る楽しさ |
| 倭建命 | 倭は国のま秀ろばたたなづく青垣山ごもれる 倭しうるはし (大和は国のまほろばたたなづく青垣山ごもれる大和しうるはし) |
 |
|
| 西郷隆盛 | 大君のためには何かおしからむ為 薩摩の迫門に身は沈むとも |
| 和泉式部 | あらざらむ此の世のほかの思ひ出に いまひとたびの逢ふこともがな 生くべくも思ほえぬかな別れにし 人の心ぞ命なりける |
| 有馬皇子 | 磐代の浜松が枝を引き結び 真幸くあらばまた還り見む 家にあれば笥に盛る飯を草枕 旅にしあれば椎の葉に盛る |
| 近藤勇 | 孤軍援け絶えて俘囚となり 君恩を顧念して 涙 更流る 一片の丹喪 よく節に殉じ 雎陽は千古 これわが儔 他に靡きて今日また何をか言はむ 義を取り生を捨つるは わが尊ぶところ 快く受く 電光三尺の剣 ただ まさに一生をもって君恩に報いむ |
| 織田信長 | 人間五十年 下天のうちに比ぶれば 夢幻のごとくなり 一たび生を得て 滅せぬもののあるべきか(「敦盛」) |
 

 |
|
| 藤原定子 | 夜もすがら契りしことを忘れずは 恋ひむ涙の色ぞゆかしき |
| 小野小町 | あはれなりわが身の果てや浅緑 つひには野辺の霞と思へば |
| 鑑真和上 | 願わくば坐して死なん |
| 最澄 | 心形久しく労して 一生ここに窮まれり |
| 花山天皇 | われ死ぬるものならば、まずこの女宮達をなん、忌のうちに皆とり持て行くべき |
| 鳥羽天皇 | 常よりも睦まじきかな郭公(ほととぎす) 死出の山路の友と思へば |
| 近衛天皇 | 虫の音のよわるのみかは過ぐる秋を 惜しむ我が身ぞまづ消えぬべき |
| 源為義 | 父を斬る子 子に斬らるる父 斬るも斬らるるも宿執の拙き事 恥ずべし恥ずべし 恨むべし恨むべし |
| 源頼政 | 埋れ木の花さく事もなかりしに 身のなるはてぞ悲しかりける |
| 源實朝 | 出でて去なば主なき宿と成りぬとも 軒端の梅よ春をわするな |
 |
|
| 足利家時 | わが命をちぢめて、三代の中に天下を取らしめ給へ |
| 平清盛 | やがて討手を遣わし 頼朝の首をば刎ねて 我が墓の前に懸くべし それぞ孝養にてあらんずる |
| 木曾義仲 | 所々で討たれんよりも 一所でこそ討死をもせめ |
| 平重衡 | 願わくば逆縁をもって順縁とし 只今最後の念仏によって 九品蓮台に生を遂ぐべし |
| 弁慶 | 六道の道の巷に待てよ君 遅れ先立ち習いありとも |
| 源義経 | 後の世もまた後の世も廻り会へ 染む紫の雲の上まで |
| 後醍醐天皇 | 身はたとえ南山の苔に埋るとも 魂魄は常に北闕の天を望まんと思う |
 

 |
|
| 真田幸村 | 関東軍 百万も候え 男は一人も無く候 |
| 武田信玄 | 大ていは地に任せて肌骨好し 紅粉を塗らず自ら風流 |
| 酒井忠勝 | 死にともなあら死にともな死にともな ご恩をうけし君を思えば |
| 早野巴人 | こしらへて有りとは知らず西の奧 |
| 曲亭馬琴 | 世の中の厄をのがれてもとのまま 帰るは雨と土の人形 |
| 東福門院和子 | 武蔵野の草葉の末に宿りしか 都の空にかえる月かげ |
| 安国寺恵瓊 | 清風払明月 明月払清風 |
 |
|
| 楠木正行 | 返らじとかねて思えば梓弓 なき数に入る名をぞ留むる |
| 宗峰妙超 | 仏祖を截断して 吹毛常に磨く 機輪転処して 虚空に牙を咬む |
| 北条氏政 | 吹きと吹く風な恨みそ花の春 紅葉も残る秋あらばこそ |
| 春日局 | 西に入る月を誘い法を得て 今日ぞ火宅をのがれけるかな |
| 絵島 | 浮き世にはまた帰らめや武蔵野の 月の光のかげもはづかし |
| 阿部重次 | 天てらす月のひかりともろもろに 行すへすゞし曙のそら |
| 平田靱負 | 住みなれし里も今更名残りにて 立ちぞわづらふ美濃の大牧 |
| 瀧善三郎 | きのふみし夢は今更引かへて 神戸が宇良に名をやあげなむ |
| 都々逸坊扇歌 | 都々逸もうたいつくして三味線枕 楽にわたしはねるわいな |
 

 |
|
| 岡田以藏 | 君が為尽くす心は水の泡 消えにし後ぞ澄み渡るべき |
| 大田實 | 大君の御はたのもとにして死してこそ 人と生まれし甲斐ぞありけり |
| 松岡洋右 | 悔いもなく怨みもなくて行く黄泉(よみじ) |
| 林子平(六無斎) | 親も無し妻無し子無し版木無し 金も無けれど死にたくも無し |
| 河上彦斎 | 君が為め 死ぬる骸に 草むさば 赤き心の 花や咲くらん 君を思い君の御法に死ぬる身を ゆめ見こりなそつくせ世の人 かねてよりなき身と知れど君が世を 思う心ぞ世に残りける |
 |
|
| 平徳子(建礼門院) | いざさらばなみだくらべむ郭公(ほととぎす) われもうき世(よ)にねをのみぞなく |
| 赤松義村 | 立ちよりて影もうつさじ流れては 浮世を出る谷川の水 |
| 尼子勝久 | 都渡劃断す千差の道 南北東西本郷に達す |
| 天野隆良 | 不来不去 無死無生 今日雲晴れて 峰頭月明らかなり |
| 伊香賀隆正 | 思いきや千年をかけし山松の 朽ちぬるときを君に見んとは |
| 伊丹道甫 | あたの世にしばしが程に旅衣 きて帰るこそ元の道なれ |
| 大内晴持 | 大内を出にし雲の身なれども 出雲の浦の藻屑とぞなる |
| 大嶋澄月 | 澄む月の暫し雲には隠るとも 己が光は照らさゞらめや |
| 大嶋照屋 | 仮初めの雲隠れとは思へ共 惜しむ習ひそ在明の月 |
| 太田隆通 | 秋風の至り至らぬ山陰に 残る紅葉も散らずやはある |
 |
|
| 岡部隆豊 | 白露の消えゆく秋の名残とや しばしは残る末の松風 |
| 岡谷隆秀 | 時有りて自から至り時有りて又還る 清風水を度り明月天に在り |
| 小幡義実 | 宝剣を呑却して名弓を放下す 只斯の景のみ有り一陣の清風 |
| 垣並房清 | 勝敗の迹を論ずること莫かれ 人我暫時の情一物不生の地 山寒うして海水清し |
| 蒲生大膳 | まてしばし我ぞ渉りて三瀬川 浅み深みも君に知らせん |
| 木付統直 | 古へを慕うも門司の夢の月 いざ入りてまし阿弥陀寺の海 |
| 熊谷直之 | あはれとも問ふひとならでとふべきか 嵯峨野ふみわけておくの古寺 |
| 黒川隆像 | 夢亦是夢 空猶是空 不来不去 端的の中に在り |
| 黒田孝高 | おもひおく言の葉なくてつひに行く 道はまよはじなるにまかせて |
| 斎藤義龍 | 三十餘歳 守護人天 刹那一句 佛祖不傳 |
 |
|
| 相良義陽 | 思いきやともに消ゆべき露の身の 世にあり顔に見えむものとは |
| 島津歳久 | 晴蓑めが玉のありかを人とは々 いざ白雲の末も知られず |
| 少弐政資 | 花ぞ散る思へば風の科ならず 時至りぬる春の夕暮 善しやただみだせる人のとがにあらじ 時至れると思ひけるかな |
| 高橋鑑種 | 末の露もとの雫や世の中の おくれさきたつならひなるらん |
| 高橋紹運 | 流れての末の世遠く埋もれぬ 名をや岩屋の苔の下水 かばねをば岩屋の苔に埋みてぞ 雲ゐの空に名をとゞむべき |
| 立花道雪 | 異方に心ひくなよ豊国の 鉄の弓末に世はなりぬとも |
| 筒井順慶 | 根は枯れし筒井の水の清ければ 心の杉の葉はうかぶとも |
| 筒井定慶 | 世の人のくちはに懸る露の身の 消えては何の咎もあらじな |
| 鳥居景近 | 先立ちし小萩が本の秋風や 残る小枝の露誘うらん |
| 鳥居勝商 | 我が君の命にかわる玉の緒を 何に厭ひけん武士の道 |
 |
|
| 中村文荷斎 | 契あれや涼しき道に伴いて 後の世までも仕へ仕へむ |
| 新納忠元 | さぞな春つれなき老とおもうらん ことしも花のあとに残れば |
| 二条良豊 | 秋風や真葛原に吹き荒れて 恨みぞ残る雲の上まで |
| 祢宜右信 | 風荒み跡なき露の草の原 散り残る花もいくほどの世ぞ |
| 野上房忠 | 生死を断じ去って 寂寞として声なし 法海風潔く 真如月明らかなり |
| 波多野秀尚 | おほけなき空の恵みも尽きしかど いかで忘れん仇し人をば |
| 平塚為広 | 名のためにすつる命は惜しからじ つひにとまらぬうき世と思へば |
| 別所治忠 | 君なくば憂き身の命何かせむ 残りて甲斐の有る世なりとも |
| 北条氏照 | 天地の清き中より生れ来て もとのすみかにかえるべらなり |
| 北条氏政 | 吹くとふく風な恨みそ花の春 もみぢの残る秋あればこそ 雨雲のおほへる月も胸の霧も はらひにけりな秋のゆふかぜ 我身いま消とやいかにおもふべき 空より来りくうに帰れば |
 |
|
| 細川高国 | 絵にうつし石を作りし海山を のちの世までも目かれずや見ん なしといひありと又いふことの葉や 法のまことの心なるらん |
| 前野長康 | 限りある身にぞあづさの弓張りて とどけまいらす前の山々 |
| 松井康之 | やすく行道こそ道よ是やこの これそまことのみちに入けり |
| 三浦義意 | 君が代は千代に八千代もよしやただ うつつのうちの夢のたはぶれ |
| 右田隆次 | 末の露本の雫に知るやいかに つひに遅れぬ世の習ひとは |
| 三原紹心 | うつ太刀のかねのひゞきは久かたの 天津空にも聞えあぐべき |
| 宮原景種 | 逃るまじ処を兼て思い切れ 時に至りて涼しかるべし |
| 三好義賢 | 草枯らす霜又今朝の日に消えて 報のほどは終にのがれず |
| 宗像氏貞 | 人として名をかるばかり四十二年 消えてぞ帰るもとの如くに |
| 薬師寺元一 | めいとには能わか衆のありけれは おもひ立ぬる旅衣かな |
 |
|
| 山崎隆方 | ありと聞きなしと思うも迷いなり 迷いなければ悟りさえなき |
| 冷泉隆豊 | みよやたつ雲も煙も中空に さそひし風のすえも残らず |
| 小野木重勝室 | 鳥啼きて今ぞおもむく死出の山 関ありとてもわれな咎めそ |
| 鶴姫(つるひめ) | わが恋は三島の浦のうつせ貝 むなしくなりて名をぞわづらふ |
| 徹岫宗九 | 殺仏殺祖 遊戯神通 末期一句 猛虎舞空 |
| 高橋お伝 (贋作) |
なき夫の為に待ちゐし時なれば 手向に咲きし花とこそ知れ
嬉しきも憂きも夢なり現なり さめては獄屋看ては故里 子を思ふ親の心を汲む水に ぬるる袂の干る隙もなし しばらくも望みなき世にあらんより 渡し急げや三途の河守 |
| 夜嵐お絹 | 夜嵐の覚めて跡なし夢の花 |
| 清水次郎長 | 六でなき四五とも今はあきはてて 先だつさいに逢うぞ嬉しき |
| 種田山頭火 | もりもり盛りあがる雲へあゆむ |
| ある死刑囚 | 何もかもわれ一人(いちにん)のためなりき 今日一日のいのち尊し |
 死生観 死生観 |
|
 死に様 死に様 |
|
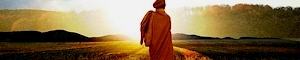 往生 往生 |
|
 

 |
|
 

 |
|
| 電児 |
不詳 いやつぎつぎの花さかり . ■倶生神 人が生まれるときに倶(とも)に生じ、常にその人の両肩にあって、その人の善悪の行動をしるして閻魔王に報告するという同名、同生の二神のこと。同生神ともいう。経によっては倶生神(ぐしょうじん)を一人といい、男女(なんにょ)の二人にするなど一様ではない。男女の二神の場合は、同名は男神で左肩にあって善業をしるし、同生は女神で右肩にあって悪業をしるすという。華厳経には「人の生まるより二種の天あり、常随(じょうずい)侍衛(じえい)す。一を同生といい、二を同名と曰う。天はつねに人を見るも、人は天を見ざるがごとし」とあり、十王経には「そのときには世尊、大衆に告げていわく、もろもろの衆生、同生神、魔奴闍耶(まぬじやや)というものあり。左の神は悪を記す。形、羅刹(らせつ)のごとし。つねに随って離れず、ことごとく小悪をも記す。右の神は善を記す。形、吉祥(きちじょう)のごとし。つねに随って離れず、皆微善をも録す。総じて双童(そうどう)と名づく。亡人の先身の、もしは福、もしは罪の諸業を皆書して尽くす閻魔法王に奉与す。其王、簿をもって亡人を推問し、、所作を算計し、悪に随いてこれを断分す」とある。薬師経には「その人の屍形(しぎょう)は臥(ふ)して本処にあり、閻魔の使人(しにん)、その神識を引いて閻魔法王の前に置く、この人の背後に同生神あり、その所作のもしは罪・もしは福に随っていっさい皆書し、ことごとく持して閻魔(えんま)法王に授与す。時に閻魔法王、その人に推問し、所作を算計し、善に随い悪に随って之を処分す」とある。薬師琉璃(るり)光如来(こうにょらい)本願功徳経には「もろもろの有情には倶生(ぐしょう)神(じん)有って、その所作に随って、もしは罪、もしは福、皆つぶさにこれを書して、ことごとく持して閻魔法王に授与す。そのとき彼の王は、その人に推問して所作を計算し、その罪福に随ってこれを処断す」とある。 |
| お市の方 | (1547-1583)織田信長の妹。初め小谷城主浅井長政に嫁いで三女(淀君、常高院、崇源院)を生み、のち柴田勝家と再婚。羽柴秀吉に居城北の庄を攻められ、夫とともに自決。 |
| ねね | 天文11年-寛永元年(1542-1624)高台院は豊臣秀吉の正室である。杉原(木下)家定は兄。秀吉の養子となり、後に小早川家を継いだ小早川秀秋は甥。北政所として知られる。幼名には諸説ある。名は一般的に「ねね」とされるが秀吉や高台院の署名などにおね、祢(ね)、寧(ねい)と言う表記があるため、「おね」と呼ばれることも多い。また甥にあたる木下利房の備中国足守藩の文書「木下家譜」やその他の文書では、「寧」「寧子」「子為(ねい)」などと記されている事から「ねい」説もある。従一位を授かった際の位記には豊臣吉子の名があるが、これは夫・秀吉の名を受けたもの。法名は高台院湖月心公。 |
| 阿南惟幾 | (1887-1945/8/15)日本の陸軍大将、終戦時の陸軍大臣。 阿南惟幾の自決 . |
| 安藤九郎左衛門 | ( -1566)上州箕輪城主長野家の武士、城外の白岩山で戦死。 直垂の裏に血書の辞世を残す。 |
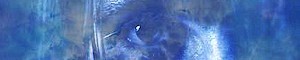 

 |
|
| 安藤広重 | 寛政9年-安政5年(1797-1858)浮世絵師、江戸の町火消しの安藤家に生まれ家督を継ぎ、その後に浮世絵師となった。現代広く呼ばれる安藤広重名は使用しておらず、浮世絵師としては歌川広重が正しい。 |
| 伊達政宗 | (1567-1636)戦国時代の武将、奥州(後の陸前国)の戦国大名、陸奥仙台藩の初代藩主。本姓は藤原氏、家系は伊達朝宗を祖とする伊達氏。第16代当主・伊達輝宗と最上義守の娘・義姫(最上義光の妹)の嫡男。幼名は梵天丸、字は藤次郎、諡号は貞山。神号は武振彦命で青葉神社に祭られる。幼少時に患った疱瘡(天然痘)により右目を失明し、また、戦国屈指の教養人として、豪華絢爛を好むことで知られていた。諱の「政宗」は伊達家中興の祖といわれる室町時代の第9代当主・大膳大夫政宗にあやかったもので、この大膳大夫政宗と区別するべく藤次郎政宗と呼ぶことも多い。 |
| 伊東義益 | 天文15年-永禄12年(1546-1569)日向伊東氏十一代当主、伊東義祐の次男。虎房丸、左京大夫。兄が早世したため後継者に定められ、都於郡城主となって義祐の後見を受けた。智勇に優れ、温厚な性格であったため父以上に家臣団、民衆から慕われたという。家督相続後も、当主として引き続き都於郡にあり、佐土原の義祐との二頭政治が行われた。1569年都於郡の岩崎稲荷に参籠中、病にかかって死去。都於郡城中のすべての者が剃髪して菩提を弔うという異例の葬儀が行われた。妻は一条房基の娘で、伊東大炊介の計らいで結婚するという。妻との間に伊東義賢・祐勝の2人と、さらに娘1人(伊東祐兵正室、阿虎の方)を儲けた。 |
| 伊藤博文 |
天保12年-明治42年(1841-1909)政治家。明治憲法の起草に関わり、初代・第5代・第7代・第10代の内閣総理大臣および初代枢密院議長・韓国統監府統監・貴族院議長・兵庫県知事(官選)を務めた。立憲政友会を結成・初代総裁。元老。位階勲等は従一位大勲位。爵位は公爵。称号は名誉博士(エール大学)。死後に大韓帝国より功績を讃えられ、「文忠公」の諡号が送られた。幼名は利助、のち俊輔(春輔、舜輔)とも称した。「春畝(しゅんぽ)」、「滄浪閣主人(そうろうかくしゅじん)」などと号し、「春畝公」と表記されることも多い。名の博文を「ハクブン」と有職読みすることもある。アジア最初の立憲体制の生みの親であり、また自ら作った制度の下で政治家として活躍した最初の議会政治家として、その功績は現在に至るまで世界各国で高く評価されている。 博文は、ハルビンにて朝鮮独立運動家の安重根によって暗殺されるという最期を迎えています。その前日に詠んだとされる漢詩と、最期の言葉があります。 「万里平原、南満州 風光闊遠、一天の秋 当年戦跡、余憤を留む、 更に行人をして暗愁牽かしむ」 ( 南満州にはどこまでも平原が広がっている。眺めは遠くまで広がり、空全体がまさに秋のようだ。この年になっても戦場の跡はまだ収まにらない怒りをとどめている。それがいっそう旅人を人知れぬ憂いにとらわれさせるのだ。 ) 博文は、満州・朝鮮問題についてロシア蔵相・ココツェフと会談するためにハルビン駅へと向かったのでした。列車のなかで2人は20分ほど会談したのち、列車を降りて博文はホームに並ぶロシアの要人と握手を交わします。その時、3発の銃弾が博文に発せられました。結果的にこの句が辞世の句となりましたが、博文自身も翌日に暗殺されることになるとは思いもしなかったことでしょう。 博文は自分が撃たれた時、「誰が撃ったのか」と叫んだそうです。息を引き取る前に側近たちと言葉を交わしたそうですが、その中で自分を撃ったのが朝鮮の人民だと知ると、「俺を撃つなんて、馬鹿なやつだ」と呟きました。実際、博文の暗殺後に韓国併合が行われたので、安重根のような独立派の思惑と反する結果を招きました。博文は、死の直前「誰か他に撃たれたか」と聞き、森秘書官が撃たれたことを知ると「森もやられたか・・・」と呟いたと言われています。これが博文の最後の言葉になりました。 |
| 井原西鶴 | 寛永19年-元禄6年(1642-1693)本名/平山藤五は、江戸時代の浮世草子・人形浄瑠璃作者、俳人。別号は鶴永、二万翁。晩年名乗った西鵬は、時の5代将軍徳川綱吉が娘鶴姫を溺愛するあまり出した「鶴字法度」(庶民の鶴の字の使用禁止)に因む。 |
| 井上井月 | 文政5年-明治20年(1822-1887)江戸時代末期から明治時代初期の俳人。本名は一説に井上克三(かつぞう)。別号に柳の家井月。信州伊那谷を中心に活動し、放浪と漂泊を主題とした俳句を詠み続けた。その作品は、後世の芥川龍之介、種田山頭火、つげ義春などに影響を与えた。 |
 

 |
|
| 一の台 | 永禄5年-文禄4年(1562-1595) 安土桃山時代の女性で、豊臣秀次の側室。父は菊亭晴季。はじめは三条顕実に嫁ぐが、お宮の方をもうけるとすぐに顕実は死去した。その後は、未亡人となった一の台は父・晴季によって娘のお宮の方と共に豊臣秀次の側室となった。後に正室となったとあるも、秀次正室・若御前が存命であるため、誤りである。『系図纂要』には教行寺佐栄の正室とある。 文禄4年(1595年)、秀次が豊臣秀吉に謀反の疑いをかけられ自害し、それに連座して8月2日に斬首された。享年34。戒名は徳法院殿誓威大姉。 当初、秀吉の側室となるはずであったが一の台が拒み、秀次の側室となったために秀次が自害させられたともいわれている。 菊亭晴季/天文8年-元和3年(1539-1617)安土桃山・江戸時代前期の公卿。菊亭家は別号を今出川家とも称する。左大臣菊亭公彦の子として誕生、初名実維。天文14年元服し晴季と改名。天文17年従三位に叙せられ、公卿に列す。天正7年内大臣、天正13年(1585)に従一位右大臣にまで昇る。 |
| 一休和尚 |
一休宗純(そうじゅん)は、室町時代の臨済宗大徳寺派の禅僧。 京都の生まれで後小松天皇の落胤という。幼名は千菊丸。長じて周建の名で呼ばれ、狂雲子、瞎驢(かつろ)、夢閨(むけい)などと号した。戒名は宗純で、宗順とも書く。一休は道号である。 6歳で京都の安国寺の像外集鑑に入門・受戒し、周建と名付けられる。早くから詩才に優れ、13歳時の漢詩「長門春草」15歳時の「春衣宿花」は洛中の評判となり賞賛された。応永17年(1410)17歳で謙翁宗為の弟子となり、戒名を宗純と改める。謙翁は応永21年(1414)に没した。この時、一休は師の遷化によるものか断定できないが自殺未遂を起こしている。応永22年(1415)に京都の大徳寺の高僧、華叟宗曇の弟子となる。「洞山三頓の棒」という公案に対し「有ろじより 無ろじへ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」と答えたことから、華叟より一休の道号を授かる。「有ろじ(有漏路)」とは迷い(煩悩)の世界、「無ろじ(無漏路)」とは悟り(仏)の世界を指す。応永27年(1420)のある夜、カラスの鳴き声を聞いて俄かに大悟する。華叟は印可状を与えようとするが、一休は辞退した。華叟はばか者と笑いながら送り出したという。以後は詩·狂歌·書画と風狂の生活を送った。正長元年(1428)称光天皇が男子を残さず崩御し伏見宮家より後花園天皇が迎えられて即位した。後花園天皇の即位には一休の推挙があったという。応仁の乱後の文明6年(1474)後土御門天皇の勅命により大徳寺の住持(第47代)に任ぜられ、寺には住まなかったが再興に尽力した。塔頭の真珠庵は一休を開祖として創建された。天皇に親しく接せられ、民衆にも慕われたという。1481年88歳で酬恩庵に没した。臨終に際し「死にとうない」と述べたと伝わる。酬恩庵は通称「一休寺」と言い、京都府京田辺市の薪地区にある。康正2年(1456)荒廃していた妙勝寺を一休が再興したものである。墓は酬恩庵にあり「慈揚塔」と呼ばれる。 そもそもいづれの時か夢のうちにあらざる、いづれの人か骸骨にあらざるべし。それを五色の皮につゝみてもてあつかふほどこそ、男女の色もあれ。いきたえ、身の皮破れぬればその色もなし。上下のすがたもわかず。…貴きも賎しきも、老いたるも若きも、更に変りなし。たゞ一大事因縁を悟るときは、不生不滅の理を知るなり 「骸骨」 禅林の異端者 . |
| 一遍 |
最期の御遺誡 (門人聖戒師の筆授なり) 五蘊の中に衆生をやまする病なし。四大の中に衆生をなやます煩悩なし。但し、本性の一念にそむきて五欲を家とし、三毒を食として、三悪道の苦患をうくる事、自業自得果の道理なり。しかあれば、みづから一念発心せんよりほかには、三世諸仏の慈悲もすくふことあたはざるものなり。南無阿弥陀仏。 |
|
鎌倉時代中期の僧。時宗の開祖。「一遍」は房号で、法諱は「智真」。「一遍上人」「遊行上人(ゆぎょうしょうにん)」「捨聖(すてひじり)」と尊称される。近代における私諡号は「円照大師」、1940年に国家より「証誠大師」号を贈られた。俗名は河野時氏とも通秀、通尚ともいうが定かでない。 六道輪廻の間には ともなふ人もなかりけり 独りうまれて独り死す 生死の道こそかなしけれ 「百利口語」 時宗・一遍 仏の世界 . |
|
| 宇喜多秀家 | 安土桃山時代の武将・大名。豊臣政権下の五大老の一人。通称は「備前宰相」。大名家としての宇喜多氏最後の当主であり、備前岡山57万4,000石の大名。 |
| 羽川珍重 | 延宝7年-宝暦4年(1679-1754)浮世絵師。江戸絵の元祖と言われた一世、鳥居清信の門に入り、役者絵、芝居絵を学んだ。風俗人物絵を得意とし、挿絵等も好んで描いた。奥村政信が挿絵を描かなくなってからは、近藤清春とともに画壇を背負って立ったと言われる。「南総里見八犬伝」で有名な滝沢馬琴は、珍重の実兄の曾孫にあたる。 |
| 英一蝶 | (はなぶさいっちょう)承応元年-享保9年(1652-1724)江戸時代の絵師。大阪の生まれ。本名は「多賀信香」(もしくは藤原信香)。幼名は猪三郎、次右衛門、助之丞。多賀朝湖、号暁雲、藤原信香、牛麻呂など別名多数(一蝶は晩年になってから)。 |
| 岡倉天心 | 文久2年-昭和2年(1863-1913)明治期に活躍した美術家、美術史家、美術評論家、美術教育者。本名は覚三、幼名は角蔵。弟の岡倉由三郎は英語学者。横浜生まれ。東京美術学校(現・東京藝術大学)の設立に大きく貢献し、日本美術院の創設者としても著名。 |
| 岡田以蔵 | 天保9年-慶応元年(1838-1865)土佐の郷士で土佐勤王党に加わった幕末四大人斬りの一人。「人斬り以蔵」と呼ばれた。諱は宜振(よしふる)。 |
 

 |
|
| 沖田総司 | (おきたそうじ)天保13年-慶応4年(1842-1868)江戸時代後期、幕末の新選組の隊士。副長助勤、一番隊組長、撃剣師範。本姓は藤原を称した。諱は春政、後に房良に。幼名は宗次郎。父は陸奥白河藩士の沖田勝次郎で長男。2人の姉がおり、沖田家は姉のみつが婿の林太郎を迎えて相続させる。 花を沖田、闇を死、水を土方とたとえ、死を恐れるのでなく、死により土方との別れを惜んだ句だと言われている。何故、水が土方歳三と推定できるかというと、土方の豊玉発句集の第一句 「さし向かう心は清き水鏡」 からで、土方への返句とも考えられる。 |
| 加賀千代女 | (かがのちよじょ)元禄16年-安永4年(1703-1775)俳人。号は草風、法名は素園。千代、千代尼などとも呼ばれる。 加賀国松任(今の白山市)で、表具師福増屋六兵衛の娘として生まれた。幼い頃から一般の庶民にもかかわらず、この頃から俳諧をたしなんでいたという。12歳の頃岸弥左衛門の弟子となる。17歳の頃、諸国行脚をしていた人に各務支考(かがみしこう)が諸国行脚してちょうどここに来ているというのを聞き、各務支考がいる宿で弟子にさせてくださいと頼むと、「さらば一句せよ」と、ホトトギスを題にした俳句を詠む様求められる。千代女は俳句を夜通し言い続け、「ほととぎす郭公(ほととぎす)とて明にけり」という句で遂に各務支考に才能を認められる。その事から名を一気に全国に広めることになった。享保5年(1720)18歳のとき、神奈川大衆免大組足軽福岡弥八に嫁ぐ。このとき、「しぶかろかしらねど姉の初ちぎり」という句を残す。20歳の時夫に死別し松任の実家に帰った。30の時京都で中川乙由にあう。画を五十嵐浚明に学んだ。52歳には剃髪し、素園と号した。72歳の時蕪村の玉藻集の序文を書く。安永4年(1775)73歳で没。「起きてみつ寝てみつ蚊帳の広さかな」が千代女の句として広く流布しているが、実は千代女の作ではなく、彼女以前に元禄時代の浮橋という遊女が詠んだ句である。 |
| 快川紹喜 | (かいせんじょうき)生年不詳-天正10年( -1582)戦国時代、安土桃山時代の臨済宗の僧。俗姓は土岐氏で、美濃国の出身。諱は紹喜。字は快川。妙心寺の仁岫宗寿の法を継いだ。美濃国の寺院を経て妙心寺の43世に就任し、美濃国の崇福寺から甲斐国に移った。武田信玄に迎えられて塩山恵林寺に入寺し、信玄に機山の号を授けている。織田信長の甲州攻めにより武田氏が滅亡して領内が混乱すると、中世において寺院は聖域であるとする社会的観念があったため信長に敵対した六角義弼らを恵林寺にかくまい、織田信忠の引渡し要求を拒否したことから焼討ちにあい、一山の僧とともに焼死を遂げた。このとき残した「安禅必ずしも山水を用いず、心頭滅却すれば火も亦た涼し」の辞世で知られるが(杜荀鶴の原典は「・・・火も自ずから涼し」)、これは「甲乱記」では快川と問答した高山和尚の言葉とされており、同時代文献には見られず近世の編纂物に登場していることから、本来は快川の逸話でなかった可能性が指摘されている。「滝のぼる 鯉の心は 張り弓の 緩めば落つる 元の川瀬に」という言葉でも知られる。 |
| 芥川龍之介 | 明治25年-昭和2年(1892-1927)日本の小説家。号は澄江堂主人、俳号は我鬼を用いた。その作品の多くは短編で、「芋粥」「藪の中」「地獄変」「歯車」など、「今昔物語集」「宇治拾遺物語」などの古典から題材をとったものが多い。「蜘蛛の糸」「杜子春」など、童話も書いた。 |
| 貝原益軒 | 寛永7年-正徳4年(1630-1714)江戸時代の本草学者、儒学者。筑前国(現在の福岡県)福岡藩士、貝原寛斎の五男として生れる。名は篤信、字は子誠、号は柔斎、損軒(晩年に益軒)、通称は久兵衛。成長し福岡藩に仕えたが、二代藩主黒田忠之の怒りに触れ7年間の浪人生活を送ることとなる。三代藩主光之に許される。藩費による京都留学で本草学や朱子学等を学ぶ。このころ木下順庵、山崎闇斎、松永尺五らと交友を深める。帰藩後、藩内での朱子学の講義や、朝鮮通信使への対応をまかされ、また佐賀藩との境界問題の解決に奔走するなど重責を担った。藩命により「黒田家譜」を編纂。また、藩内をくまなく歩き回り「筑前国続風土記」を編纂する。幼少のころから読書家で、非常に博識であった。ただし書物だけにとらわれず自分の足で歩き目で見、手で触り、あるいは口にすることで確かめるという実証主義的な面を持つ。また世に益することを旨とし、著書の多くは平易な文体で書かれより多くの人に判るように書かれている。70歳で役を退き著述業に専念。著書は生涯に六十部二百七十余巻に及ぶ。主な著書に「大和本草」「菜譜」「花譜」といった本草書。教育書の「養生訓」「和俗童子訓」「五常訓」。思想書の「大擬録」。紀行文には「和州巡覧記」がある。 |
| 柿本人麻呂 | (660-720頃)飛鳥時代の歌人。三十六歌仙の一人。後世、山部赤人とともに歌聖と呼ばれ、称えられている。また平安時代からは「人丸」と表記されることが多い。 |
| 葛飾北斎 | 宝暦10年-嘉永2年(1760-1849)江戸時代に活躍した浮世絵師であり、とりわけ後期、文化・文政の頃(化政文化)を代表する一人。代表作に「富嶽三十六景」「北斎漫画」があり、世界的にも著名な画家である。 |
| 蒲生氏郷 |
弘治2年-文禄4年(1556-1595)戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。初め近江日野城主、次に伊勢松阪城主、最後に陸奥黒川城主。近江日野城主蒲生賢秀の嫡男。初名は賦秀(ますひで)または教秀(のりひで)。キリシタン大名で洗礼名はレオン(或いはレオ)。子に蒲生秀行。このほか長男蒲生氏俊がいるが、廃嫡したとされる。 信長は氏郷の才を見抜いたとされ、娘の冬姫と結婚させた。岐阜城で元服して忠三郎賦秀と名乗り(信長の官職である「弾正忠(だんじょうちゅう)」から1字を与えられたとの説がある。武勇に優れ、永禄11年(1568)北畠具教・具房との戦いにて初陣を飾ると、永禄12年(1569)伊勢大河内城攻めや元亀元年(1570)姉川の戦い、天正元年(1573年)朝倉攻めと小谷城攻め、天正2年(1574)伊勢長島攻め、天正3年(1575)長篠の戦いなどに従軍して、武功を挙げている。天正10年(1582)信長が本能寺の変により横死すると、安土城にいた信長の妻子を保護し、父とともに居城・日野城(中野城)へ走って明智光秀に対して対抗姿勢を示した。光秀は明智光春、武田元明、京極高次らに近江の長浜、佐和山、安土の各城を攻略させ、次に日野攻囲に移る手筈だったが、直前に敗死した。 その後は羽柴秀吉(豊臣秀吉)に仕えた。秀吉は氏郷に伊勢松ヶ島12万石を与えた。清洲会議で優位に立ち、信長の統一事業を引き継いだ秀吉に従い、天正12年(1584)小牧・長久手の戦いや天正13年(1585)紀州征伐(第二次太田城の戦い)、天正15年(1587)九州征伐や1590年の小田原征伐などに従軍する。その間、天正16年(1588)飯高郡矢川庄四五百森(よいほのもり)で新城建築のための縄張りを行い、松坂城を築城。松ヶ島の武士や商人を強制的に移住させて城下町を作り上げた。一連の統一事業に関わった功により、天正18年(1590)奥州仕置において伊勢より陸奥会津に移封され42万石(のちの検地・加増により92万石)の大領を与えられた。松ヶ島時代(天正13年(1585)頃)に賦秀から氏郷と名乗りを改めているが、これは当時の実力者だった羽柴「秀」吉の名乗りの一字を下に置く「賦秀」という名が不遜であろうという気配りからであった。天正15年(1587)7月には、秀吉から「羽柴」の姓を賜っている。 会津においては、町の名を黒川から「若松」へと改め、蒲生群流の縄張りによる城作りを行った。なお「若松」の名は、出身地の日野城(中野城)に近い馬見岡綿向神社(現在の滋賀県蒲生郡日野町村井にある神社、蒲生氏の氏神)の参道周辺にあった「若松の杜」に由来し、同じく領土であった松坂の「松」という一文字もこの松に由来すると言われている。7層の天守閣(現存する5層の復元天守は寛永年間に改築されたものを元にしている)を有するこの城は、氏郷の幼名にちなみ鶴ヶ城と名付けられた。築城と同時に城下町の開発も実施した。具体的には、旧領の日野・松阪の商人の招聘、定期市の開設、楽市楽座の導入、手工業の奨励等により、江戸時代の会津藩の発展の礎を築いた。 以降、会津の旧領主である伊達政宗と度々対立しながらも、天正19年(1591)大崎・葛西一揆(なお、この際秀吉に対し「政宗が一揆を扇動している」との告発を行っている)、九戸政実の乱を制圧。翌文禄元年(1592)文禄の役では、肥前名護屋へと出陣している。この陣中にて体調を崩し、文禄4年(1595)2月7日、京都の伏見蒲生屋敷において死去。享年40。 蒲生家の家督は家康の娘との縁組を条件に嫡子の秀行が継いだが、家内不穏の動きから宇都宮に移され12万石に減封された(会津には上杉景勝が入った)。 家臣を大切にし、また茶湯にも興味を示し利休七哲の一人(筆頭)にまで数えられており(千利休の死後、その子息少庵は氏郷の許で蟄居している)、諸大名からの人望が厚く、風流の利発人と評される。また和歌にも秀でており、会津から文禄の役に参陣途上、近江国武佐にて故郷日野を偲んで詠んだ歌「思ひきや人の行方ぞ定めなき我が故郷をよそに見んとは」が有名。 |
| 甘粕正彦 | (1891-1945/8/20)日本の陸軍軍人。陸軍憲兵大尉時代に甘粕事件を起こしたことで有名(無政府主義者大杉栄らの殺害)。短期の服役後、日本を離れて満州に渡り、関東軍の特務工作を行い、満州国建設に一役買う。満州映画協会理事長を務め、終戦直後、服毒自殺した。 甘粕事件/1923年9月1日に起きた関東大震災のどさくさに乗じて、9月16日東京憲兵隊麹町分隊長の甘粕はアナキストの大杉栄・伊藤野枝とその甥・橘宗一(7歳)の3名を憲兵隊本部に強制連行の後、虐殺し、同本部裏の古井戸に遺体を投げ込むという、いわゆる甘粕事件を起こした。事件では憲兵や陸軍の責任は問われず、すべて甘粕の単独犯行として処理され、同年12月8日禁錮10年の判決を受ける。軍事法廷において甘粕は「個人の考えで3人全てを殺害した」「子どもは殺していない。菰包みになったのを見て、初めてそれを知った」とたびたび証言を変えており、共犯者とされた兵士が「殺害は憲兵司令官の指示であった」と供述しているなど、この結論に現在でも疑義を挙げる人は多い。「高貴な方」の罪を被ったものであった(実際には秩父宮雍仁親王が連隊長を務める連隊の犯行だった)、という説もある。甘粕は「(思想は理解できないが)大杉は人間的には立派だった」と述べているが、甘粕本人も後に同様に評されることとなる。 |
 

 |
|
| 紀貫之 |
(きのつらゆき)貞観8年/貞観14年-天慶8年(866/872-945)歌人・随筆家。三十六歌仙の1人。紀友則は従兄弟にあたる。幼名は阿古屎(あこくそ)。延喜5年(905)醍醐天皇の命により初の勅撰和歌集『古今和歌集』を紀友則、壬生忠岑、凡河内躬恒と共に編纂し、仮名による序文である仮名序を執筆した。「和歌は、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける」で始まるそれは、後代に大きな影響を与えた。また、「小倉百人一首」にも和歌が収録されている(人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける)。 随筆家としては「土佐日記」の著者として有名である。日本文学史上、おそらく初めての仮名による優れた散文であり、その後の日記文学や随筆、女流文学の発達に大きな影響を与えた。貫之の邸宅は、平安京左京一条四坊十二町に相当する。その前庭には多くの桜樹が植されており、「桜町」(さくらまち)と称された。 |
| 鬼坊主清吉 | 安永5年-文化2年(1776-1805)江戸時代の盗賊である。本格的な盗賊家業に入る前から悪に染まっていたらしく、一度捕縛され、入墨を入れられ重敲の刑を受けたが入墨を消した罪でまた捕縛され、再度入墨を入れられた上で江戸追放の刑を受けた。しかしそんなものは鬼坊主にとって全く意味がなかったようで、数人の仲間と徒党を組み、路上強盗、引ったくり、武装強盗を連日にわたって繰り返し、懸命の捜査を行う町奉行や火付盗賊改方をあざ笑うかのごとく江戸中を蹂躙した。あまりの神出鬼没振りにこの種の犯罪としては異例の人相書(普通人相書が出回る罪は当時一番重罪だった逆罪、すなわち主人や親を殺傷する罪である)が作成され、非常の捜査体制である捕物出役まで発動された。そのため上方へ逃亡し、文化2年(1805)4月彼の地で捕縛される(捕縛された場所については京都と伊勢・津の2説ある)。4月24日江戸に護送されるが、有名人である鬼坊主を一目見ようと群衆が押し寄せた。鬼坊主は北町奉行小田切直年の尋問に対して罪を認め、2ヵ月後の6月27日市中引き回しの上、小塚原で仲間2名と共に獄門にかけられた。享年30。「坊主」というあだ名が付けられているが僧侶ではなく、体が大きく風体が異様だったせいらしい。 |
| 戯僧 | (年代不明)「新著聞集」の話。堺の真言宗の僧で、日頃より酒をたしなんで、酔いの醒めていることがないという飲んべえがあった。しかし祈祷しているときは、迫力があり人々も一目おくのであった。この僧が死に遺品を調べると、遺言や辞世が出てきた。遺言には「寺と書籍は甥の僧に贈る。金三百両は草履取りに。出家の財宝は災いのもとである。衣服はそれぞれに与えよ。」とあった。 |
| 吉川経家 | 天文16年-天正9年(1547-1581)戦国時代の武将。毛利氏の家臣で、吉川経安の嫡男。子に吉川経実。養子に吉川経言。石見吉川氏であり、吉川本家の庶流の生まれである。1581年織田信長の命を受けた羽柴秀吉率いる中国征伐軍が因幡国まで侵攻してきた。山名豊国は織田氏に降伏しようとしたため、家臣の森下道誉・中村春続に追放された。森下・中村の両名は吉川元春に支援を求め、吉川一門の派遣を要請した。元春はこの要請を受け入れ、吉川一門で文武両道に優れた名将として、経家に鳥取城を守備するよう命令を下した。この時、経家は自らの首桶を用意しており、その決死の覚悟を窺うことができる。1581年2月吉川経家は鳥取城に入城する。鳥取城の守備兵は山名氏配下が1000名、毛利氏配下が800人、近隣の籠城志願の農民兵が2000人の、おおよそ4000人であった。経家はすぐさま防衛線の構築に取り掛かり、籠城の準備を進めた。しかし、兵糧の蓄えがおおよそ平時城兵3か月分しか無いことを知り愕然とした。羽柴秀吉の策略により、因幡国の兵糧は秀吉の密命によって潜入した若狭の商人によって全て高値で買い漁られており、鳥取城の城兵もその高値に釣られて備蓄していた兵糧米を売り払っていたのである。1581年6月経家の予測より早く羽柴秀吉率いる2万の因幡侵攻軍が鳥取城を包囲し、攻撃を開始した。秀吉は吉川経家の名将ぶりを知っており、無闇に手を出さず、黒田孝高の献策により包囲網を維持し続けた。鳥取城は包囲網により糧道を断たれ、陸路および海路を使った兵糧搬入作戦も失敗。兵糧は尽き、ついには餓死者が続出し始める。4ヶ月の籠城に耐えたが、同年10月吉川経家は森下道誉・中村春続と相談し、城兵の助命を条件とし、降伏することとなった。羽柴秀吉は吉川経家の奮戦を称え、責任を取って自害するのは森下道誉・中村春続だけで良く、吉川経家は帰還させるとの意思を伝えた。しかし経家はそれを拒否し、責任を取って自害するとの意志を変えなかった。困惑した羽柴秀吉は織田信長に「経家が自害しても良いか」との確認を取り、経家の自害を許可している。10月25日経家は自害し、その一生を終えた。その際に父や子供らに遺書を送っており、自分の心情を記している。その遺言状は現存している。 |
| 吉村寅太郎 | 天保8年-文久3年(1837-1863)幕末の土佐藩出身の志士。諱は重郷。一般には「寅太郎」と記されることが多い。土佐藩の庄屋であったが尊攘思想に傾倒して土佐勤王党に加盟。平野国臣らが画策する浪士蜂起計画(伏見義挙)に参加すべく脱藩するが、寺田屋事件で捕縛されて土佐に送還され投獄される。釈放後、再び京都へ上り孝明天皇の大和行幸の先駆けとなるべく中山忠光を擁立して天誅組を組織して大和国で挙兵するが、八月十八日の政変で情勢が一変して幕府軍の攻撃を受け敗れて戦死した(天誅組の変)。 |
| 吉田松蔭 |
吉田矩方(よしだのりかた)文政13年-安政6年(1830-1859)長州藩士、思想家、教育者、兵学者。一般的に明治維新の精神的指導者・理論者として名が挙げられることが多い。贈正四位。 文政13年長州藩士・杉百合之助の次男として生まれる。天保5年(1834)叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の養子となるが、天保6年(1835)大助が死去したため、同じく叔父の玉木文之進が開いた松下村塾で指導を受けた。 しかしアヘン戦争で清が西洋列強に大敗したことを知って山鹿流兵学が時代遅れになったことを痛感すると、西洋兵学を学ぶために嘉永3年(1850)九州に遊学する。また江戸に出て佐久間象山の師事を受けた。嘉永5年(1852年)、長州藩に無許可の形で宮部鼎蔵らと東北の会津藩などを旅行したため、罪に問われて士籍剥奪・世禄没収の処分を受けた。 嘉永6年(1853)マシュー・ペリーが浦賀に来航すると、師の佐久間象山と黒船を視察し、西洋の先進文明に目先を囚われた。安政元年(1854年)に浦賀に再来航していたペリーの艦隊に対してアメリカ密航を望んだ。これは開国に求められる豪快そのものであった。しかし密航を拒絶されて送還されたため、松陰は乗り捨てた小舟から発見されるであろう証拠が幕府にわたる前に奉行所に自首し、伝馬町の牢屋敷に送られた。この密航事件に連座して師匠の佐久間象山も入牢されている。幕府の一部ではこのときに佐久間、吉田両名を死罪にしようという動きもあった。が、老中首座の阿部正弘が反対したため、助命されて長州の野山獄に送られている。 安政2年(1855)出獄を許されたが、杉家に幽閉の身分に処された。安政4年(1857年)に叔父が主宰していた松下村塾の名を引き継ぎ、杉家の敷地に松下村塾を開塾する。この松下村塾において松陰は長州藩の下級武士である久坂玄瑞や伊藤博文などの面々を教育していった。なお、松陰の松下村塾は一方的に師匠が弟子に教えるものではなく、松陰が弟子と一緒に意見を交わしたり、文学だけでなく登山や水泳なども行なうという「生きた学問」だったといわれる。 安政5年(1858)幕府が無勅許で日米修好通商条約を締結したことを知って激怒し、討幕を表明して老中首座である間部詮勝の暗殺を計画する。だが、弟子の久坂玄瑞、高杉晋作や桂小五郎(木戸孝允)らは反対して同調しなかったため、計画は頓挫し、松陰は長州藩に自首して老中暗殺を自供し、野山獄に送られた。 やがて大老・井伊直弼による安政の大獄が始まると、江戸の伝馬町牢屋敷に送られる。幕閣の大半は暗殺計画は実行以前に頓挫したことや松陰が素直に罪を自供していたことから、「遠島」にするのが妥当だと考えていたようである。しかし井伊直弼はそれほど甘い人物ではなく、素直に罪を自供したことが仇となって井伊の命令により「死罪」となってしまい、安政6年(1859)10月27日に斬刑に処された。享年30。生涯独身であった。 |
 

 |
|
| 宮沢賢治 | (1896-1933)日本の詩人、童話作家。郷土岩手の地を深く愛し、作品中に登場する架空の地名、理想郷を「岩手(いはて)」をエスペラント風にしたイーハトヴ(Ihatov、イーハトーブあるいはイーハトーヴォ(Ihatovo)等とも)と名づけた。その空前・独特の魅力にあふれた作品群によって没後世評が急速に高まり国民的作家とされるようになった。 |
| 菊五郎(六代目) | 六代目 尾上菊五郎(ろくだいめ おのえきくごろう)明治18年-昭和24年(1885-1949)大正・昭和時代に活躍した歌舞伎役者。本名は寺島幸三(てらしまこうぞう)。俳名は三朝。屋号は音羽屋。初代中村吉右衛門とともに、いわゆる「菊吉時代」の全盛期を築いた。歌舞伎界で単に「六代目」と言うと、通常はこの六代目尾上菊五郎のことを指す。 逸話/六代目は桃屋の花らっきょうが好物だった。それを物語るのが臨終間際のエピソード。六代目は「桃屋の花らっきょうが食べたい」と消え入るような声で呟いた。これを聞いた東京劇場の支配人は東京中を探したが見つからなかった。当時は戦後の混乱で砂糖が統制下にあり、当時の桃屋の社長が「肝心の砂糖がないなら作らない方がいい」と一時生産を休止していたのである。仕方なく他社のらっきょう漬を買って届けたが、彼は口にするなり「こりゃ桃屋の花らっきょうじゃない! 普通のらっきょうだ! 下げろ!」といい後は見向きしないまま逝った。 |
| 芹沢鴨 | 文政10年-文久3年(1827-1863)幕末の水戸藩浪士、新選組(壬生浪士)の初代筆頭局長。前名は下村嗣司。諱は光幹。本姓は平氏。家系は常陸平氏の平成幹の流れを汲むという芹沢氏。父は芹沢外記貞幹。 文久3年9月芹沢が懸想していた吉田屋の芸妓小寅が肌を許さなかったため、立腹した芹沢が吉田屋に乗り込み、店を破壊すると主人を脅して、小寅と付き添いの芸妓お鹿を呼びつけ罰として2人を断髪させる乱暴を行っている(「浪士文久報国記事」)。 13日近藤らは芹沢派の新見錦(この時は副長に降格)に乱暴狼藉の罪を問い詰めて切腹させた(「浪士文久報国記事」)。 14日吉田屋での事件が問題となり、朝廷から芹沢の逮捕命令が出たことから、会津藩は近藤、土方、山南らに芹沢の処置を密命する。乱暴狼藉は表向きの理由で、水戸学を学び、天狗党の強烈な尊王攘夷思想の流れをくむ芹沢を危険視したという説もある。 16日(「川瀬家文書」による)新選組は島原の角屋で芸妓総揚げの宴会を開いた。芹沢は平山五郎、平間重助、土方歳三らと早めに角屋を出て壬生の八木家へ戻り、八木家で再度宴会を催した。その席に芹沢の愛妾のお梅、平山の馴染みの芸妓桔梗屋吉栄、平間の馴染みの輪違屋糸里が待っており、すっかり泥酔した芹沢たちは宴席が終ると女たちと同衾して寝た。大雨が降る深夜、突然、数人の男たちが芹沢の寝ている部屋に押し入り、同室で寝ていた平山を殺害し、芹沢に斬りつけた。驚いた芹沢は飛び起きて刀を取ろうとするが叶わず、真っ裸のまま八木家の親子が寝ていた隣室に飛び込むが、文机に転び、そこを刺客たちがよってたかってずたずたに斬りつけ、芹沢を殺すと刺客たちは立ち去った。平山の死体は胴体と首が離れており、芹沢と同衾していたお梅も首を切られ惨殺された。別室にいた平間は逃亡。吉栄と糸里も難を逃れ姿を消したという。 |
| 近松門左衛門 | 承応2年-享保9年(1653-1725)江戸時代前期の元禄期に活躍した人形浄瑠璃と歌舞伎の作者。本名は杉森信盛。生まれは越前国または周防国、長門国といわれる。竹本座に属する浄瑠璃作者で、中途で歌舞伎狂言作者に転向したが、再度浄瑠璃に戻った。「出世景清」は近世浄瑠璃の始まりといわれる。100作以上の浄瑠璃を書いたが、そのうち約20曲が世話物、残りが時代物であった。世話物とは、町人社会の義理や人情をテーマとした作品であるが、当時人気があったのは時代物、特に「国性爺合戦」であり、「曽根崎心中」などは昭和になるまで再演されなかった。同時期に紀海音も門左衛門と同じ題材に基づいた心中浄瑠璃を書いており、当時これに触発されて心中が流行したのは事実であるが、世話物中心に門左衛門の浄瑠璃を捉えるのは近代以後の風潮に過ぎない。また、門左衛門は「虚実皮膜論」という芸術論を持ち、芸の面白さは虚と実との皮膜にあると唱えたといわれるが、これは穂積以貫が記録した「難波土産」に門左衛門の語として書かれているだけであり、門左衛門自身が書き残した芸能論はない。忌日の11月22日(明治以降は新暦で行われる)は近松忌、巣林子忌、または巣林忌と呼ばれ、冬の季語である。 ■辞世文 近松は、享保9年11月22日(1724)72歳で亡くなる。その2週間前に、礼装で端座する最後の姿を描かせた自筆の辞世文を残した。 代々甲冑(かっちゅう)の家に生まれながら、武林を離れ、三槐九卿(さんかい きゅうけい)につかへ、咫尺(しせき)し奉りて寸爵(すんしゃく)なく、市井に漂(ただよう)て商買(しょうばい)しらず、隠に似て隠にあらず、賢に似て賢ならず、ものしりに似て何もしらず、世のまがいもの、からの大和の教(おしえ)ある道々、妓能、雑芸、滑稽の類まで、しらぬ事なげに、口にまかせ、筆にはしらせ、一生を囀(さえづ)りちらし、今はの際にいふべく、おもふべき真の一大事は、一字半言もなき倒惑、こころに心の恥をおほひて、七十あまりの光陰、おもへばおぼつかなき我世経畢(わがよへおわんぬ) もし辞世はと問人あらば、 それぞ辞世 去ほどに扨もそののちに 残る桜が花しにほはば 享保九年中冬上旬 入寂名 阿耨院穆矣日一具足居士(あのくいんぼくいにちいちぐそくこじ) 不俟終焉期 予自記(終焉の期を待たず、予め自ら記すの意)春秋七十二歳印 のこれとは おもふもおろか うづみ火の けぬまあだなる くち木がきして ■辞世文大意 私は武門の家に生まれながら、武門を離れて三槐九卿(宰相や公家ら高位の人のこと。公卿ら)に、咫尺し(ごく身近に仕え)たが、自分には寸爵(なんの爵位)もない。 庶民の中で暮らしても商売しらず、隠者のようで隠者でなく、賢者のようで賢者でなく、物知りのようで何も知らぬ、世のまやかし者である。唐や大和の教えになる道理や、芸能・雑芸・笑い話の類まで、何でも知らぬことがない風をして、口から出任せ、筆の走るままにしゃべり散らしてきた。いまわの際になって、他人に伝えたり、自分が思う真の一大事は、一言半句もなくて当惑し、心中ひそかに恥じ入っている。七十余年の歳月を顧みると、思えばとりとめない一生を過ごしたものだ。 もし辞世はと問う人があったら、 それぞ辞世 去ほどに扨もそののちに 残る桜が花しにほはば [私が書いた浄瑠璃の作品が、後々まで残るならば、そのひとつひとつが私の辞世だ]=「去ほどに、さても、そののち」は、浄瑠璃の語り出しの決まり文句。桜は、桜木に彫った板木で刷った板本で、浄瑠璃の正本をいう。 のこれとはおもふもおろか うづみ火のけぬま あだなるくち木がきして [埋み火が消えずに残るわずかな暇に書いたたわいない作品が、あとあとまで残れと思うだけでも、愚かなことだなぁ] |
| 空海 | ( 弘法大師空海は辞世の句を残していない、これは「十住心論」の引用。) 宝亀5年-承和2年(774-835)平安時代初期の僧。「弘法大師」の名(諡号〈醍醐天皇921年贈〉)で知られる、真言宗の開祖。俗名は佐伯眞魚(さえきのまお)。日本天台宗の開祖最澄(伝教大師)とともに、旧来の奈良仏教から新しい平安仏教へと日本仏教が転換していく流れの劈頭に位置し、中国から真言密教をもたらした。能書家としても知られ、嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆のひとりに数えられる。 迷いの世界の狂人は狂っていることを知らない、生死の苦しみで眼の見えないものは眼の見えないことが分からない、生れ生れ生れ生れても生の始めは暗く死に死に死に死んでも死の終りは冥い 「秘蔵宝鑰」の序 空海(弘法大使) 真言宗開祖 . |
| 空也 | 延喜3年-天禄3年(903-972)平安時代中期の僧。天台宗空也派の祖。阿弥陀聖(あみだひじり)市聖(いちのひじり)市上人と称される。民間における浄土教の先駆者と評価される。父は醍醐天皇。踊念仏、六斎念仏の開祖とも仰がれるが、空也自身がいわゆる踊念仏を修したという確証はない。門弟は、高野聖など中世以降に広まった民間浄土教行者「念仏聖」の先駆となり、鎌倉時代の一遍に、多大な影響を与えた。 |
| 契沖 | 寛永17年-元禄14年(1640-1701)江戸時代中期の真言宗の僧であり、和学者(国学者)。摂津国尼崎(現在の兵庫県尼崎市)で生まれた。釈契沖とも。俗姓は下川氏、字は空心。祖父下川元宜は加藤清正の家臣であったが、父元全は尼崎藩士から牢人となる。契沖は、幼くして大坂今里の妙法寺の丰定(かいじょう)に学んだ後、高野山で阿闍梨の位をえる。ついで大坂生玉の曼陀羅院の住持となり、その間下河辺長流と交流するが、俗務を嫌い畿内を遍歴して高野山に戻る。その後、和泉国池田郷万町村(現在の和泉市万町)の伏屋重賢のもとで、日本の古典を数多く読んだ。妙法寺住持分を経て、晩年は摂津国高津の円珠庵で過ごした。 |
| 月照 |
(げっしょう)文化10年-安政5年(1813-1858)幕末期の尊皇攘夷派の僧侶。名は宗久、忍介、忍鎧、久丸。 文化10年(1813)大坂の町医者の長男として生まれた。文政10年(1827)叔父の蔵海の伝手を頼って清水寺成就院に入る。天保6年(1835)成就院の住職になった。しかし尊皇攘夷に傾倒して京都の公家と関係を持ち、徳川家定の将軍継嗣問題では一橋派に与したため、大老の井伊直弼から危険人物と見なされた。西郷隆盛と親交があり、西郷が尊敬する島津斉彬が急死したとき、殉死しようとする西郷に殉死を止めるように諭している。 安政5年(1858)から始まった安政の大獄で追われる身となり、西郷と共に京都を脱出する。そして薩摩藩に逃れたが、藩では厄介者である月照の保護を拒否し、日向国送りを命じる。これは、薩摩国と日向国の国境で月照を斬り捨てるというものであった。このため、月照も死を覚悟し、西郷と共に錦江湾に入水自殺した。月照はこれで亡くなったが、西郷は奇跡的に一命を取り留めている。享年46であった。「眉目清秀、威容端厳にして、風采自ずから人の敬信を惹く」と伝えられる。 |
 

 |
|
| 原石鼎 |
(はらせきてい)(1889-1951)出雲市に生まれる。簸川中学で子規門の俊秀教師、竹村秋竹に俳句を学び、松江の奈倉梧月の句会に投句。文学との葛藤で京都医専中退。後に深吉野の診療所を預かり、新鮮な吉野詠を「ホトトギス」に投句、虚子から激賞された。大正4年「ホトトギス」社に入り、作句に専念、大正俳壇の雄となった。大正10年俳誌「鹿火屋」を発行、主宰した。虚子著「進むべき俳句の道」において最長文で評論されている。 大正ホトトギス作家の作品の特徴は、自然の事物の描写を通して、永遠なるもの、神秘的なものへの憧れを高らかに表現するところにあった。その文体は古風で格調高い。俳句の題材となるのは、山や谷、海、空など、スケールの大きい景色であり、またそのような大自然に囲まれた人間の生活であった。原は二十代の後半に、辺境の地東吉野に居住し、厳しい自然を俳句で描写しつつ、その中に研ぎ澄まされた美を表現してみせることに成功して、俳壇に衝撃を与えた。 |
| 源実朝 | 建久3年-建保7年(1192-1219)鎌倉幕府の第三代征夷大将軍である。鎌倉幕府を開いた源頼朝の子として生まれ、兄の源頼家が追放されると12歳で征夷大将軍に就く。政治は始め執権を務める北条氏などが主に執ったが、成長するにつれ関与を深めた。官位の昇進も早く武士として初めて右大臣に任ぜられるが、その翌年に鶴岡八幡宮で頼家の子公暁に襲われ落命した。子はおらず、源氏の将軍は実朝で絶えた。歌人としても知られ、92首が勅撰和歌集に入集し、小倉百人一首にも選ばれている。家集として金槐和歌集がある。 |
| 幸徳秋水 | 明治4年-明治44年(1871-1911)明治時代のジャーナリスト、思想家、社会主義者、アナキスト。本名は幸徳傳次郎。秋水の名は、師事していた中江兆民から与えられたもの。大逆事件で処刑された12名の1人。 「大逆事件」(幸徳事件を指す)/明治天皇を爆裂弾で暗殺しようとした計画が発覚、この事件をきっかけに多くの社会主義者、アナキストに対して取り調べや家宅捜索が行なわれ、根絶やしにする弾圧を、政府が主導、フレームアップしたとされる事件。敗戦後、関係資料が発見されて事件の全容が明らかになった。暗殺計画にいくらかでも関与・同調したとされているのは、宮下太吉、管野スガ、森近運平、新村忠雄、古河力作の5名にすぎなかった。1910年5月25日に多数の社会主義者・無政府主義者の逮捕・検挙が始まり、1911年1月18日に死刑24名、有期刑2名の判決。1月24日に11名が、1月25日に管野スガが処刑された。 |
| 江藤新平 | 天保5年-明治7年(1834-1874)佐賀藩士、政治家である。幼名は恒太郎・又蔵。諱は胤雄、号は南白。朝臣としての正式な名のりは平胤雄(たいらのたねお)。明治6年朝鮮出兵を巡る征韓論問題から発展した明治六年政変で西郷・板垣退助・後藤象二郎・副島と共に10月24日下野、明治7年1月10日に愛国公党を結成し12日民撰議院設立建白書に署名。副島、後藤らの帰郷を思いとどまるようにとの説得にもかかわらず翌13日に離京。すぐには佐賀へ入らず2月2日長崎の深堀に着き様子を見る。2月10日佐賀へ向い11日憂国党の島義勇と会談を行い12日佐賀征韓党首領として擁立された。そして、政治的主張の全く異なるこの征韓党と憂国党が共同して反乱を計画する。2月16日憂国党が武装蜂起し士族反乱である佐賀の乱が勃発する。佐賀軍は県庁として使用されていた佐賀城に駐留する岩村高俊の率いる熊本鎮台部隊半大隊を攻撃、その約半数に損害を与えて遁走させた。しかし、やがて大久保の直卒する東京、大阪の鎮台部隊が陸続と九州に到着した。佐賀軍は福岡との県境へ前進して、これら新手の政府軍部隊を迎え撃った。政府軍は、朝日山方面へ野津鎮雄少将の部隊を三瀬峠付近へは山田顕義少将の部隊を前進させた。朝日山方面は激戦の末政府軍に突破されるが、三瀬峠方面では終始佐賀軍が優勢に戦いを進めた。また朝日山を突破した政府軍も佐賀県東部の中原付近で再び佐賀軍の激しい抵抗にあい、壊滅寸前まで追い込まれている。政府軍は司令官の野津鎮雄自らが先頭に立って士卒を大いに励まし戦い辛うじて勝利する。この後も田手、境原で激戦が展開されるが政府軍の強力な火力の前に佐賀軍は敗走する。新平は戦場を密かに脱出し鹿児島・鰻温泉に湯治中の西郷に会い、薩摩の旗揚げを請うが断られ、続いて高知の林有造、片岡健吉のもとを訪ね武装蜂起を説くがいずれも容れられなかった。このため、岩倉への直接意見陳述を企図して東京への上京を試みる。しかしその途上、現在の高知県安芸郡東洋町甲浦付近で捕縛され佐賀へ送還される。手配写真が出回っていたために速やかに捕らえられたものだが、この写真手配制度は江藤自身が明治5年に確立したもので制定者本人が被適用者第1号となった。4月8日新平は急設された佐賀裁判所で司法省時代の部下であった河野敏鎌によって裁かれ、4月13日処刑・梟首された。享年41。ここで行われた判決「除族の上、梟首」は江戸時代の旧法、明治時代の新法にも先例の全く無いものであった。なお、梟首された際の写真は全国の県庁に掲示された。これは新平が禁じたはずの刑罰であった。その後、江藤系の人物はことごとく司法省を追われた。 |
| 荒木村重・妻 |
荒木村重/天文4年-天正14年(1535-1586)戦国時代から安土桃山時代の武将・大名。利休七哲のひとりである。幼名を十二郎、のち弥介(または弥助)。明智光秀より4年前に織田信長に反逆した武将として有名である。先祖は藤原秀郷である。 天正6年(1578)10月村重は有岡城(伊丹城)にて突如、信長に対して反旗を翻した(有岡城の戦い)。一度は翻意し釈明のため安土に向かったが、途次寄った高槻城で家臣の高山右近から「信長は部下に一度疑いを持てばいつか必ず滅ぼそうとする」との進言を受け伊丹に戻った。織田軍羽柴秀吉は、村重と旧知の仲でもある黒田孝高を使者として有岡城に派遣し翻意を促したが、村重は孝高を拘束し土牢に監禁した。その後、村重は有岡城に篭城し、織田軍に対して1年の間徹底抗戦したが、側近の中川清秀と高山右近が信長方に寝返ったために戦況は圧倒的に不利となった。 天正7年(1579)9月2日村重は単身で有岡城を脱出して尼崎城へ、次いで花隈城に移り(花熊城の戦い)最後は毛利氏に亡命する。同年12月13日落城した有岡城の女房衆122人が尼崎近くの七松において惨殺され、「百二十二人の女房一度に悲しみ叫ぶ声、天にも響くばかりにて、見る人目もくれ心も消えて、感涙押さえ難し。これを見る人は、二十日三十日の間はその面影身に添いて忘れやらざる由にて候なり。」と記されるほどの残虐な様子だったという(信長公記)。12月16日京都に護送された村重一族と重臣の家族の36人が、大八車に縛り付けられ京都市中を引き回された後、六条河原で斬首された。立入宗継はその様子を「かやうのおそろしきご成敗は、仏之御代より此方のはじめ也」と記している(立入左京亮宗継入道隆佐記)。その後も信長は、避難していた領民を発見次第皆殺しにしていくなど、徹底的に村重を追求していった。天正9年(1581)8月17日村重の家臣を匿いそれを追求していた信長の家臣を殺害したとして、高野山金剛峯寺の僧数百人が虐殺された。 天正10年(1582)6月信長が本能寺の変で横死すると堺に戻りそこに居住する。そして豊臣秀吉が覇権を握ると、大坂で茶人・荒木道薫として復帰を果たし、千利休らと親交をもった。はじめは妻子を見捨てて逃亡した自分を嘲って「道糞」と名乗っていたが、秀吉は村重の過去の過ちを許し、「道薫」に改めさせたと言われている。銘器「荒木高麗」を所有していた。天正14年(1586)5月4日堺で死去。享年52。 |
| 香川玄悦 | ( -1777)産科医。鍼灸が得意で、独学で産科を修得し、香川流の産科の名を高めた。自ら「医は仁術」を実践した。 |
 

 |
|
| 高橋多一郎 | 文化11年-万延元年(1814-1860)幕末の武士。水戸藩士。桜田門外の変の首謀者の一人。諱は愛諸、変名は磯辺三郎兵。 井伊大老暗殺計画では、江戸での井伊暗殺と同時に薩摩藩兵が上京し大阪から京都に入り朝廷を守護する事になっていた。高橋はこの薩摩藩士と合流するため息子・荘左衛門らと共に大坂へ向った。安政7年(1860)3月3日関鉄之介らが江戸城桜田門外で井伊大老暗殺に成功したが、薩摩藩は動かず京坂での挙兵計画は頓挫する。大坂に潜伏した高橋は井伊暗殺成功を知り、薩摩藩兵の上京を待っていたが、潜伏地を幕吏に探知され、四天王寺境内の寺役人小川欣司兵衛宅にて息子・荘左衛門と共に自刃した。享年47。 |
| 高杉晋作 |
天保10年-慶応3年(1839-1867)長州藩士。幕末の長州藩の尊王倒幕志士として活躍。奇兵隊など諸隊を創設し、幕末長州藩を倒幕に方向付けた。諱は春風。通称は晋作、東一、和助。字は暢夫。号は東行。変名を谷潜蔵、谷梅之助、備後屋助一郎、三谷和助、祝部太郎、宍戸刑馬、西浦松助など。のち、谷潜蔵と改名。贈正四位。 薩摩藩と会津藩が結託した宮廷クーデターである8月18日の政変で長州藩が追放され、文久4年(1864)1月高杉は京都進発を主張する急進派の来島又兵衛を説得するが容れられず、脱藩して京都へ潜伏する。桂小五郎の説得で2月帰郷するが、脱藩の罪で野山獄に投獄され、6月出所して謹慎処分となる。7月長州藩は禁門の変で敗北して朝敵となり、来島は戦死、久坂玄瑞は自害する。8月イギリス、フランス、アメリカ、オランダの4カ国連合艦隊が下関を砲撃、砲台が占拠されるに至ると、晋作は赦免されて和議交渉を任される。 この講和会議において、連合国は数多の条件とともに「彦島の租借」を要求してきた。高杉はほぼ全ての提示条件を受け入れたが、この「領土の租借」についてのみ頑として受け入れようとせず、結局は取り下げさせることに成功した。これは清国の見聞を経た高杉が「領土の期限付租借」の意味するところを深く見抜いていたからで、もしこの要求を受け入れていれば日本の歴史は大きく変わっていたであろうと後世に分析されている。時に高杉晋作、24歳であった。 功山寺挙兵の銅像幕府による第一次長州征伐が迫る中、長州藩では俗論派が台頭し、10月福岡へ逃れる。平尾山荘に匿われるが、俗論派による正義派家老の処刑を聞き、再び下関へ帰還。12月15日伊藤俊輔(伊藤博文)率いる力士隊、石川小五郎率いる遊撃隊ら長州藩諸隊を率いて功山寺で挙兵。後に奇兵隊ら諸隊も加わり、元治2年(1865)3月俗論派の首魁椋梨藤太らを排斥して藩の実権を握る。同月海外渡航を試みて長崎でイギリス商人グラバーと接触するが、反対される。4月下関開港を推し進めたことにより、攘夷派・俗論派に命を狙われたため、愛妾・おうの(後の梅処尼)とともに四国へ逃れ、日柳燕石を頼る。6月桂小五郎の斡旋により帰郷。 慶応元年(1865)1月11日付で晋作は高杉家を廃嫡されて「育(はぐくみ)」扱いとされ、そして同年9月29日藩命により谷潜蔵と改名する。慶応3年(1867)3月29日新知100石が与えられ、谷家を創設して初代当主となる。 慶応2年(1866)1月21日土佐藩の坂本龍馬・中岡慎太郎・土方久元を仲介として、晋作も桂小五郎・井上聞多・伊藤俊輔たちと共に進めていた薩長盟約が京都薩摩藩邸で結ばれる。 5月伊藤俊輔とともに薩摩行きを命じられ、長崎で丙寅丸(オテントサマ丸)を単独購入。 6月の第二次長州征伐(四境戦争)では海軍総督として丙寅丸に乗り込み、周防大島沖に停泊する幕府艦隊を夜襲してこれを退け、林半七率いる第二奇兵隊等と連絡して周防大島を奪還。小倉方面の戦闘指揮では、まず軍艦で門司・田ノ浦の沿岸を砲撃させた。その援護のもと奇兵隊・報国隊を上陸させ、幕軍の砲台、火薬庫を破壊し幕府軍を敗走させた。その後さらに攻勢に出るも小倉城手前で肥後藩の猛反撃に合い、一時小康状態となる。しかし、幕府軍総督小笠原壱岐守の臆病な日和見ぶりに激怒した幕府軍諸藩が随時撤兵し、7月将軍徳川家茂の死去の報を受けた小笠原がこれ幸いと戦線を離脱したため幕府敗北は決定的となり、この敗北によって幕府の権威は大きく失墜し、翌慶応3年(1867)11月大政奉還への大きな転換点となった。晋作自身は、肺結核のため桜山で療養生活を余儀なくされ、慶応3年(1867)5月17日江戸幕府の終了を確信しながらも大政奉還を見ずしてこの世を去る(享年27)。臨終には、父・母・妻と倅がかけつけ、野村望東尼と山県狂介、田中顕助が立ち会ったとされるが、田中の残した日記によれば、彼はその日京におり、詳細は定かではない。 なお、木戸孝允・大村益次郎らによって、現在の靖国神社に、東京招魂社時代の始めから吉田松陰・久坂玄瑞・坂本龍馬・中岡慎太郎たちと共に表彰・鎮魂され祀られている。 |
| 黒田官兵衛(如水) | 黒田孝高/黒田如水(くろだよしたか/くろだじょすい)天文15年-慶長9年(1546-1604)戦国時代、安土桃山時代、江戸時代前期にかけての武将・大名である。豊前国中津城主。孝高は諱で通称の「官兵衛」並びに出家後の「如水」の号で有名である。豊臣秀吉の側近として仕え、調略や他大名との交渉などに活躍した。「ドン・シメオン」という洗礼名を持つキリシタン大名でもあった。慶長3年(1598)8月豊臣秀吉が死去した。如水は同年12月上洛し伏見屋敷に居住したという。この頃、如水が吉川広家に宛てた書状が残されている。「かようの時は仕合わせになり申し候。はやく乱申すまじく候。そのお心得にて然るべき候」これは、如水が遠からず天下の覇権をめぐって大乱が起きると予想していたことを窺わせる。慶長5年(1600)徳川家康らが会津の上杉景勝討伐のため東へ向かうと、7月17日石田三成らが家康の非を鳴らして挙兵し(西軍)、関ヶ原の戦いが起こった。嫡男・長政は家康の養女を正室として迎えていたことから秀吉の死去前後から家康に与し、豊臣恩顧の大名を多く家康方に引き込み後藤基次ら黒田軍の主力を率いて家康に同行、関ヶ原本戦で武功を挙げた。中津に残っていた如水も、家康方(東軍)として行動した。石田三成の挙兵の知らせを用意させていた早舟から受け取った如水は、兵力の大半は長政が率いていたため如水は金蔵を開いて領内の百姓などに支度金を与え、9千人ほどの速成軍を作り上げた。9月9日再興を目指して西軍に与した大友義統が毛利輝元の支援を受けて豊後に攻め込み、東軍の細川忠興の飛び地である杵築城を包囲攻撃した。城将・松井康之と有吉立行は如水に援軍を要請、同日、如水はこれに応じ、1万人と公称した兵力を率いて出陣した。道中の諸城を攻略した後、9月13日石垣原(現在の別府市)で大友義統軍と衝突した(石垣原の戦い)。黒田二十四騎に数えられる母里友信らの活躍もあって、黒田軍は大友軍に勝利した。如水は西軍に属した熊谷直盛の安岐城、垣見一直の富来城、太田一吉の臼杵城、毛利高政の角牟礼城と日隈城、毛利勝信の小倉城、毛利信友の香春岳城などを次々と落としていった。国東半島沖の豊後水道付近では関ヶ原より引き上げてきた島津義弘と立花宗茂と戦い軍船を焼き沈めている。そして11月に入り加藤、立花、鍋島勢を加えた4万の軍勢で九州最後の敵勢力である島津討伐に向かったが11月12日に肥後の水俣まで進軍したとき、徳川家康と島津との和議成立による停戦命令を受け、軍を退き解散した。関ヶ原の合戦の後、長政は家康から勲功第一として筑前国名島(福岡)で52万3000石を与えられた。如水も中津城から福岡城に移り、そこでその後は政治に関与することなく隠居生活を送った。慶長9年3月20日(1604)京都伏見藩邸にて死去。59歳。 |
| 今川氏真 | (いまがわうじざね)天文7年-慶長19年(1538-1615)駿河の戦国大名。駿河今川氏10代当主で、大名としての今川家の最後の当主である。父・義元が桶狭間の戦いで織田信長によって討たれたためその領国を受け継いだが、武田信玄と徳川家康の侵攻を受けて敗れ、戦国大名としての今川家は滅亡した。その後は北条氏を頼り、最終的には徳川家康の庇護を受けた。今川家は江戸幕府のもとで高家として家名を残した。 |
| 佐久間盛政 | 天文23年-天正11年(1554-1583)織田氏の家臣。佐久間氏の一族。玄蕃允。勇猛さから鬼玄蕃と称された。佐久間盛次の子。佐久間安政、柴田勝政、佐久間勝之の兄。 |
| 佐々成政 | 天文5年-天正16年(1536-1588)戦国時代・安土桃山時代の武将。尾張国出身。父は佐々成宗(盛政とも)。通称内蔵助(くらのすけ)。家紋は棕櫚。馬印は金の三階菅笠。天正15年(1587)九州の役で功をあげたことを契機に、肥後一国を与えられた。秀吉は性急な改革を慎むように指示したとも言われる。病を得ていたとも言われる成政は、早速に太閤検地を行おうとするがそれに反発する国人が一斉蜂起し、これを自力で鎮めることができなかった(肥後国人一揆)。このため失政の責めを受け、安国寺恵瓊による助命嘆願も効果なく、摂津国尼崎法園寺にて切腹させられた。享年53。 |
| 駒姫(伊満) |
-文祿4年(1577?-1595)最上義光の娘、豊臣秀次に嫁ぐが、斬首される、15歳だった。山形城主最上義光の次女駒姫はその美しさにより、時の関白豊臣秀次の側室に召され、お伊満の方として聚楽第に迎えられた。しかし太閤豊臣秀吉の養子である秀次は、秀吉に実子秀頼が生まれると疎んじられ、ついに1595年秀次は秀吉から謀反の嫌疑をかけられ、高野山で切腹させられた。同時に秀吉は秀次の子女妻妾三十余名を京都三条河原で悉く斬首した。駒姫もその中に入っており、従容として斬られた。 「罪なき身も世のくもりにさへられて 友に冥途に趣ハ五常のつみも ほろひなんと思ひて 伊満十五歳 罪をきる弥陀の剣もかかる身の なにか五つのさわりあるべき」 最上義光も秀次の謀反に加担した嫌疑で一時幽閉され、この恨みから関ヶ原の戦いでは東軍についたともいう。義光は娘駒姫の死を悲しみ、駒姫の霊を慰めるために天童の高擶(たかだま)から専称寺を山形城下に移したという。なお専称寺のあたりはかつて寺町という名前で他にも多くの寺が建ち並ぶ。 最上義光(もがみよしあき)/天文15年-慶長19年(1546-1614)戦国時代から江戸時代前期にかけての武将・大名。出羽(後の羽前国)の戦国大名。最上氏第11代当主。出羽山形藩初代藩主。伊達政宗の伯父にあたる。本姓は源氏。家系は清和源氏の一家系・河内源氏の流れを汲む足利一門・斯波氏の血筋で、最上氏は奥州探題の大崎氏の庶流。大崎氏はもともと斯波氏を名乗っており、次男斯波兼頼が羽州探題として最上郡(今の村山郡)に入部し最上氏を名乗るようになった。関ヶ原の戦いにおいて東軍につき、最上家を57万石の大名に成長させて全盛期を築き上げた。 最上義光の娘 「駒姫物語」 . |
| 斎藤道三 | 明応3年-弘治2年(1494-1556)戦国時代の武将。美濃(岐阜県南部)の戦国大名斎藤氏の初代当主。かつて、斎藤道三は北条早雲らと並ぶ下克上大名の典型であり、僧侶から油商人を経てついに戦国大名にまで成り上がった人物だとされてきた。しかし古文書「六角承禎条書写」によって、美濃の国盗りは道三一代のものではなく、その父の長井新左衛門尉との父子二代にわたるものとする理解が有力となっている。父は長井新左衛門尉(豊後守)。道三の名として、法蓮房・松波庄五郎(庄九郎)・西村正利(勘九郎)・長井規秀(新九郎)・長井秀龍(新九郎)・斎藤利政(新九郎)・道三などが伝わるが、良質な史料に現れているのは、藤原(長井)規秀・斎藤利政・道三などのみである。子に義龍、孫四郎(龍元、龍重)、喜平次(龍之、龍定)、利尭(玄蕃助)、長龍(利興、利治)、日饒(妙覚寺19世住職)、日覚(常在寺6世住職)。また、長井道利は弟とも、道三が若い頃の子であるともされる。娘に姉小路頼綱正室、帰蝶(織田信長正室)など。道三は美濃の戦国領主として天文23年(1554)まで君臨した後、義龍へ家督を譲ったが、ほどなくして義龍と義絶し、弘治2年(1556)4月に長良川河畔で義龍軍に敗れ、討ち死にした。 |
 

 |
|
| 細川ガラシャ(伽羅奢) | 永禄6年-慶長5年(1563-1600)明智光秀の三女で細川忠興の正室。諱は「たま」(珠、玉)または玉子(たまこ)。キリスト教信徒(キリシタン)として有名。子に、於長(おちょう、1579年生前野景定室)、忠隆(1580年生)、興秋(1584年生)、忠利(1586年生)、多羅(たら、1588年生稲葉一通室)などがいる。
細川ガラシャ . |
| 在原業平 | 天長2年-元慶4年(825-880)平安時代初期の貴族。従四位上・蔵人頭・右中将。歌人であり、六歌仙、三十六歌仙のひとり。また「伊勢物語」の主人公とみなされている。別称の在五中将は在原氏の五男で右近衛権中将であったことによる。 |
| 坂 英力 | 天保4年-明治2年(1833-1869)江戸時代後期(幕末)の仙台藩の重臣。仙台藩では500石を食む重臣であった。仙台藩の使者として上洛した際、徳川慶喜と直接会談して感銘を受け、藩の宿老・但木土佐と共に仙台藩の佐幕派として藩政の中枢を掌握した。戊辰戦争においても但木と共に奥羽越列藩同盟の主導的な役割を果たした。しかしこのため、戊辰戦争終結後の明治2年(1869)但木と共に死刑に処された。享年37。 |
| 薩摩守平忠度 | (たいらのただのり)天養元年-元暦元年(1144-1184)平安時代の武将。平忠盛の六男。平清盛、教盛、経盛らは兄。子に忠行がいる。熊野の地で生まれ育ったとの伝承あり。治承2年(1178)従四位上。治承3年(1179)伯耆守。治承4年(1180)正四位下薩摩守。 |
| 三浦義同(道寸) | (みうらよしあつ)生年未詳-永正13年( -1516)戦国時代初期の東相模の武将、小大名。通称は三浦介。出家した後、道寸(どうすん)と号した。通常「三浦道寸」の名で呼ばれることが多い。父は扇谷上杉家の上杉高救(上杉定正の実兄)。母は西相模の豪族大森氏頼の娘。官途は従四位下陸奥守。初期戦国大名の典型とされる北条早雲の最大の敵であり、平安時代から続いた豪族・相模三浦氏の事実上の最後の当主である。子は荒次郎義意。娘に太田資康室がいる。 |
 

 |
|
| 三好長治 | (みよしながはる)天文22年-天正5年(1553-1577)戦国時代から安土桃山時代にかけての阿波国の大名。三好義賢の長男として生まれる。永禄5年(1562)父が久米田の戦いで戦死したため、家督を相続する。伯父三好長慶によって畿内の支配力を強めた三好氏の中でも、本国阿波を預かる重要な役割を担っていた。しかし幼少のため、重臣の篠原長房の補佐を受けていた。 有名な分国法である新加制式を定めたり、永禄9年(1566)足利義栄を将軍として擁立して上洛するなどの事跡を遺しているが、いずれも篠原長房や三好三人衆など家中の有力者による主導の結果である。 足利義昭を奉戴する織田信長の上洛により劣勢となった三好氏は、本圀寺襲撃(六条合戦)でも戦果を挙げられず、次第に畿内から追われて本国に撤退した。 元亀元年(1570)四国に退いた三好三人衆と篠原は本州への反攻を画策。摂津では、管領細川家の嫡流細川六郎(信良・昭元)を大将に担ぎ、三好一門の大半を結集して(信長派となった従兄弟である宗家の三好義継を除く)、織田信長との戦いに挑んだ(野田城・福島城の戦い)。この時は劣勢に追い込まれたものの、石山本願寺の加勢や近江での朝倉氏・浅井氏の決起などもあって信長軍を退かせ、摂津・河内・和泉の三国をほぼ三好家の勢力下に取り戻した。しかし、その後和睦して本国の阿波に撤退した。 天正元年(1573)不仲となった重臣の長房を、異父兄である細川真之と協力して同年内に攻め滅ぼした。だが、強権を振りかざす長治の治政に対し、讃岐の香川之景や香西佳清らは連名で実弟の十河存保に離反を警告する書状を送りつけたため、これを憂えた存保からも長治の暴政について諫言を受けている。だが、これを疎んじた長治は却って存保を無視して兵3000人を以って香川・香西両氏を攻め、両氏の三好氏からの離反を決定的なものとした。 天正3年(1575)三好氏にとって半世紀以上も畿内・和泉における根拠地であった顕本寺が法華宗であった為か、長治は阿波全土の国人や領民に対しても法華宗を強要した。ところが、国人や領民の支持を失った上に他宗からの反感まで招き、阿波一国の支配力さえ喪失しかねない状態まで悪化した。このような国内の混乱は、隣国・土佐の長宗我部元親による阿波侵攻を誘発、海部城や大西城などが落とされた。 天正4年(1576)細川真之とも対立し、これに真之を支持する元親をはじめ福良氏なども協力したため、長治は圧倒的に不利となる。天正5年(1577)長宗我部元親の助力を得た細川真之と阿波荒田野で戦い、敗死した。享年25。 |
| 三村元親 | 生年未詳-天正3年( -1575)備中の戦国大名にして備中松山城主。三村家親の次男。母は阿波三好氏の女。毛利軍は三村元親の手で要塞と化していた本城・備中松山城から攻めることはせず、周囲を固める端城を次々と落としていく作戦に出た。端城を落とした毛利軍は備中松山城を取り囲んで持久戦とし、多勢に無勢の状況で同城は陥落した。元親は妻子・家臣とともに落ちのびを図るが、もはやこれまでと覚悟を決め、毛利軍に使いを出して検使のもとでの切腹を願い出た。毛利氏は願い出を認め、元親は旧知の間柄であった毛利家中・粟屋元方が見守る中、辞世数首を残して松連寺で自刃し短い生涯を終えた。以下はそのうちの1首。「人といふ 名をかる程や 末の露 きえてぞかへる もとの雫に」元親は戦国武将の顔とは別に、詩歌に精通するなど典雅を好む教養人としての顔も有していた。細川藤孝とも親交があり、藤孝は備中松山城篭城中の元親に「八雲集」を届けたという。元親は自害に際し、その藤孝にも1首送っている。その後、元親の子・勝法師丸も捕らえられ、助命嘆願の声もあったが、その利発さを恐れた小早川隆景によって殺害された。これによって戦国大名としての三村氏は完全にその命脈を絶たれ、元親の叔父・親成ら傍流が他家の家臣として残るのみとなった。 |
| 三村勝法師丸 | 三村元親の子。捕らえられ、敵の本陣に送られる際、扇に辞世を書き付け、朝の露と消ゆ。年八歳。 |
| 三島由紀夫 | (1925-1970/11/25)小説家・劇作家。晩年には民兵組織「楯の会」をつくり右翼活動に傾倒、日本の新右翼・民族派に多大な影響を及ぼした。本名・平岡公威(ひらおかきみたけ)。代表作は小説に「仮面の告白」「禁色」「潮騒」「金閣寺」「豊饒の海」四部作など。戯曲に「サド侯爵夫人」「わが友ヒットラー」「近代能楽集」などがある。唯美的な作風が特徴。1970年楯の会会長として自衛隊にクーデターを促し失敗、割腹自殺を遂げ世間を騒然とさせた(三島事件)。筆名の「三島」は日本伝統の三つの島の象徴、静岡県三島の地名に由来するなどの説がある。 |
| 三遊亭一朝 | (1846-1930)武州所沢(現在の埼玉県南部)出身の落語家。本名、倉片省吾。(戸籍上は倉片圓蔵、かつて3代目橘家圓蔵を名乗っていたためか、いつの間にか戸籍の名前まで圓蔵になってしまっていた)実弟は同じく落語家で弟弟子の三遊亭圓鶴。 |
| 山岡鉄舟 | 天保7年-明治21年(1836-1888)日本の武士・幕臣、政治家、思想家。爵位は子爵。剣、禅、書の達人としても知られる。鉄舟は号、他に一楽斎。通称は鉄太郎(鐵太郎)。諱は高歩(たかゆき)。浅利義明門下の剣客で、一刀正伝無刀流(無刀流)の開祖。勝海舟、高橋泥舟とともに「幕末の三舟」と称される。 |
| 山下奉文 | (やましたともゆき)明治18年-昭和21年(1885-1946)日本の陸軍軍人。第二次世界大戦当時の陸軍大将である。官位は陸軍大将従三位勲一等功三級。シンガポール攻略という大きな戦績をあげた山下だったが、東條英機から一定の意図を持って、距離を前線から置かれる目的のために満州に配置され、その後は大きな作戦を任される事はなかった。しかし、敗色が濃厚となった昭和19年(1944)第14方面軍司令官として起用され、日本軍が占領していたフィリピンの防衛戦を指揮する事になった。ダグラス・マッカーサーらの指揮する連合軍に対して勇戦するが、台湾沖航空戦での誤った戦果報告に基づいて立案されたレイテ決戦を大本営から強いられ、本来予定していたルソン島での決戦を行うことはできなかった。飛来する敵航空機がまったく減らないことから、山下は台湾沖航空戦の戦果発表を誤報と考え、このレイテ決戦に反対していた。このとき山下の部下には、敵の意図や行動を正確に予測するために「マッカーサー参謀」という揶揄を含んだあだ名をつけられていた名参謀堀栄三中佐がおり、あらゆる困難を排して状況把握に成功していた。捕らえられた米軍パイロットの尋問からもそれは裏付けられたが、南方軍総司令官寺内寿一は命令を変えなかった。このためレイテ決戦に多くの兵力が投入されたが、制海権と制空権を敵に握られていたため輸送船の大半が撃沈され、彼らの多くは虚しく海没することになった。つづくルソン島の戦いでは、ルバング島の小野田寛郎少尉からの「敵艦見ゆ。針路北。」との報告で、迅速な部隊配置に成功するが、徐々に兵力差で圧倒され、最終的には山岳地帯へ退いての持久戦に追い込まれている。昭和20年(1945)9月3日フィリピンのバギオにて降伏した。降伏時は捕虜として扱われたが、すぐに戦犯としてフィリピンのマニラにて軍事裁判にかけられ、マニラ大虐殺等の責任を問われ、死刑判決を受けた。死刑判決後、米陸軍の法務将校からなる山下の弁護団は、判決を不服としてフィリピン最高裁、アメリカ連邦最高裁判所に死刑執行の差止めと人身保護令の発出を求める請願を出した。しかし米最高裁は6対2の投票で請願を却下し、山下はマニラで絞首刑に処せられた。処刑は軍服の着用も許されず囚人服のままで行われている。昭和34年処刑された他のBC級戦犯とともに靖国神社に合祀された。 |
 

 |
|
| 山崎宗鑑 | 寛正6年-天文22年(1465-1553)戦国時代の連歌師・俳諧作者。本名を志那範重、通称を弥三郎と称し、近江国の出身とされるが、本名・出自については諸説あり定かではない。室町幕府9代将軍足利義尚に仕えた(近習とも祐筆とも)が、義尚の陣没(延徳元年、1489年)後出家し、摂津国尼崎または山城国薪村に隠棲し、その後淀川河畔の山城国(摂津国?)山崎に庵「對月庵」を結び、山崎宗鑑と呼ばれた。現在大阪府島本町山崎に「宗鑑井戸」「宗鑑旧居跡」が残されている。大永3年(1523)ごろ山崎の地を去り、享禄元年(1528)讃岐国(香川県観音寺市)の興昌寺に庵「一夜庵」を結びそこで生涯を終えた。「一夜庵」の名は宗鑑が長居の客を厭い一夜以上の宿泊を断ったからといい、建物は修復を重ねながら現地に残されている。宗祇・宗長・荒木田守武などと交流し俳諧連歌を興隆した。宗鑑の連歌作品として伝わるものはわずかであるが、俳諧連歌のもっとも早い時期に編纂された俳諧撰集「犬筑波集」があり、その卑俗奔放な句風は、江戸時代初期の談林俳諧に影響を与えた。なお、荒木田守武とともに、俳諧の祖と称される。能筆家としても有名で生計は書を売ることによって立てていたとも伝わる。晩年「ヨウ(できもの)」を患いそのために命を失うことになる。 |
| 山上憶良 | 斉明天皇6年-天平5年(660-733)奈良時代初期の歌人。万葉歌人。従五位下。下級貴族の出身で、姓は臣(おみ)。702年の第七次遣唐使船に同行し、唐に渡り儒教や仏教など最新の学問を研鑽する。帰国後は東宮侍講を経た後、伯耆守、筑前守と国司を歴任しながら、数多くの歌を詠んだ。仏教や儒教の思想に傾倒していたため、死や貧、老、病などといったものに敏感で、かつ社会的な矛盾を鋭く観察していた。そのため、官人という立場にありながら、重税に喘ぐ農民や防人に狩られる夫を見守る妻など社会的な弱者を鋭く観察した歌を多数詠んでおり、当時としては異色の社会派歌人として知られる。抒情的な感情描写に長けており、また一首の内に自分の感情も詠み込んだ歌も多い。代表的な歌に「貧窮問答歌」「子を思ふ歌」などがある。「万葉集」には七十八首が撰ばれており、大伴家持や柿本人麻呂、山部赤人らと共に奈良時代を代表する歌人として評価が高い。 |
| 山川唐衣 | (1817-1889)会津藩士山川尚江の妻。名は艶。浩・健次郎兄弟の母。会津藩士西郷近登之の嫡女として会津若松に生まれる。20歳で山川家に嫁し、12人の子を産み、うち5人は夭折したが7人の子女を育て上げ、賢婦人の誉れ高かった。夫、尚江重固が49歳で没し、剃髪して勝昭院と称した。父近登之に似て和歌をよくし、歌集も残されている。 |
| 山村通庵 | ( -1751)松坂の人、医学を後藤左一に学び、自右一と名乗る。剃髪し通庵と号す。彼の説は「師は灸の治療に心をつくしたが、私は温泉の効用を試みるために諸国に出向き、その効き目を実地に試してみた。但馬の城崎、上野の草津の湯は天下に類を見ないほどすばらしい。しかし現地まで行くことが出来ない者のためには治療を施す」と言う。寛延4年7月80歳にして死亡。 |
| 山田風太郎 | 大正11年-平成13年(1922-2001)日本の小説家。本名は山田誠也(せいや)。伝奇小説、推理小説、時代小説の三方で名を馳せた、戦後日本を代表する娯楽小説の大家。忍法帖シリーズに代表される、奇想天外なアイデアを用いた大衆小説で知られている。『南総里見八犬伝』や『水滸伝』をはじめとした古典伝奇文学に造詣が深く、それらを咀嚼・再構成して独自の視点を加えた作品を多数執筆した。学生であった戦時中から戦後しばらくにかけて書き記していた日記は記録文学の傑作との呼び声が高く、著者の再評価にもつながった。 |
| 山之手殿(寒松院) | (かんしょういん)生没不明-慶長18年( -1613)真田昌幸の妻、気位も高いが性根もすわった賢妻。山之手殿の出生にについては諸説があり、定かではない。
一つは「宇田下総守頼忠」の娘といわれ、一つは京の公家「菊亭晴季」の娘ともいわれ、また、甲州侍「遠山右馬亮」の娘ともいわれる。仮に宇田頼忠の娘だとすると、関ヶ原の西軍大将であるあの石田三成も宇田頼忠の娘を妻に迎えている事から、2人は義兄弟だった事になる。だとすると、昌幸と三成は色々な縁で結ばれており、西軍に味方した1つの動機になったのではないか。話はそれたが、山之手殿は昌幸に嫁ぎ、永禄9年に長男「信之」を、永禄10年に次男「幸村」を生んだ。諸小説には気位の高い女として登場するが、それ以前に毅然とした態度と気丈な一面がうかがえる諸説もある。武田家滅亡時、真田の郷に潜んでいては危ないと感じた母子は、吾妻の岩櫃城に向かう。その時、野武士らしき者に襲われたので、母は息子2人を気遣って、「母はここで自害するゆえ、母の事は気にせず働かれよ。信之・幸村ともに岩櫃にて運を開かれよ」といって自害しようとした。幸いこれは味方の軍だったので事無きを得たが、この事からも御方が事に当たる時の毅然とした態度がうかがえる。やはり子息を愛していたのであろう。山之手殿は関ケ原の合戦の前に大阪城の人質となったが、これは後に「河原綱家」(河原殿の兄の息子)に救出される。関ヶ原の合戦後は昌幸と共に九度山に配流、慶長18年同地で没した。 真田幸村の娘 . |
| 山本五十六 | 明治17年-昭和18年(1884-1943)大日本帝国海軍の軍人。26、27代連合艦隊司令長官。位階勲等は元帥海軍大将・正三位・大勲位・功一級。空母機動部隊を編成し、真珠湾攻撃、マレー沖海戦、ミッドウェイ海戦などを指揮した。 |
 

 |
|
| 司馬江漢 | 延享4年-文政元年(1747-1818)江戸時代の絵師。蘭学者。鈴木春重(すずきはるしげ)は同一人物。本名は安藤峻。浮世絵師だったが、後に洋風画を描くに至った。平賀源内と接点があり、彼を通じて前野良沢や小田野直武に師事したとも言われている。 |
| 柴田勝家 | 大永2年-天正11年(1522-1583)戦国時代から安土桃山時代の武将・大名。本能寺の変後、織田氏の後継者問題では信長の三男・織田信孝の烏帽子親を務めていたこともあり、信孝を推したが、明智光秀を討伐したことで実績や発言力が大きかった羽柴秀吉(豊臣秀吉)が信長の嫡孫・三法師(織田秀信)を擁立したため、織田氏の家督は三法師が継ぐこととなり、信長の遺領配分においても河内や丹波、山城を増領した秀吉に対し、勝家は北近江3郡、長浜城(現在の長浜市)を得るにとどまり、勝家と秀吉の立場は逆転してしまった(清洲会議)。この後に羽柴秀吉の仲介を受けてお市の方と結婚している。その後勝家は滝川一益、織田信孝と手を結んで秀吉と対抗するが、天正11年(1583)賤ヶ岳の戦いで秀吉に敗れ、越前北ノ庄にてお市とともに自害した。享年62。 |
| 車持娘子 | (くるまもちのいらつめ)奈良時代の女性。夫がひさしくおとずれないのを苦に病床にふし、臨終に夫をよび、和歌をよんで死んだという。そのときの歌が「万葉集」巻16におさめられている。 |
| 秀吉 | 豐臣秀吉(とよとみひでよし)/羽柴秀吉(はしばひでよし)天文6年-慶長3年(1537-1598)戦国時代(室町時代後期)から安土桃山時代にかけての武将・戦国大名。本姓は豊臣氏。生まれは尾張国の半農半兵の家。はじめ木下氏を名字とし・羽柴氏に改める。本姓としては、はじめ平氏を自称するが、近衛家の猶子となり藤原氏に改姓した後、豊臣氏に改める。 尾張国愛知郡中村の百姓として生まれ、織田信長に仕え、次第に頭角を表す。信長が本能寺の変で明智光秀に討たれると、中国大返しにより京へと戻り、山崎の戦いで光秀を破り、信長の後継の地位を得る。その後、大坂城を築き関白・太政大臣に任ぜられた。豊臣姓を賜り、日本全国の大名を従え天下統一を成し遂げた。太閤検地や刀狩などの政策を採るが、慶長の役の最中に、嗣子の秀頼を徳川家康ら五大老に託して没した。墨俣の一夜城、金ヶ崎の退き口、高松城の水攻め、石垣山一夜城など機知に富んだ逸話が伝わり、百姓から天下人へと至った生涯は「戦国一の出世頭」と評される。 |
| 十返舎一九 | 明和2年-天保2年(1765-1831)江戸時代後期の大衆作家。日本で最初に、文筆のみで自活した。「東海道中膝栗毛」の作者として知られる。 |
|
東海道というと誰もが思い浮かべるのは、「東海道中膝栗毛」に出てくる弥次さん、喜多さん。東海道の名所紹介をヒョウキンな二人の道中に仕立てたこの滑稽本は、当時の娯楽小説として爆発的なベストセラーとなり、江戸中の風呂屋や床屋は一九の話題でもちきりだったといいます。ところが、失敗しても明るい朗らかな弥次さん喜多さんを、洒落と風刺の利いた軽妙な筆で描いた十返舎一九は、なかなかの気むずかし屋さんだったとか。 ■東海道中膝栗毛 滑稽本というのは宝暦(1751-1763)以後江戸に発生した新しい小説で、滑稽の中に風刺や教化を盛り込んだ本として書かれていましたが、一九が執筆した「東海道中膝栗毛」は、人物の会話を中心として描いていて当時としては新趣向といえる代物で、あまりに突飛なため版元は出版をためらったといいます。ところが、これを出版してみると大当たり(最初は「浮世道中膝栗毛」と題して出版)。江戸から箱根までの初編のみで完結するつもりだったのが、二編では箱根から岡部まで、三編は岡部から荒井(新居)までと書き継がれ、八編の大阪見物まで、東海道を8年がかりで完結しました。さらに「続膝栗毛」では、金毘羅、宮島の参詣を終え、木曽街道を経て弥次さん喜多さんはやっと江戸に帰ってくるという、全12編20年がかりの執筆でした。 「東海道中膝栗毛」が大当たりした原因は、まずその文学ぶらない大衆性にあるといえます。永年続いた大平の世の中で、実力も経済力もない武士階級に対する反発を、無邪気で飾り気のない弥次喜多という町人を主人公に、わかりやすく描く語り口。そしてストーリーは、道中や宿場で起こるあらゆる人々との交流から想像されるアクシデントが写実的に軽快な調子で展開していき、遊廓、宿場、名物、身分に応じた言語などを使った巧みな描写。弥次喜多の常識をはずれた洒落と与太の連発、洒落や失敗がかもしだす罪のないカラッとした笑い、各地の風俗が方言をまじえながら端はしに織り込まれた粋なユーモアが、当時の江戸っ子をはじめ庶民の心をとらえたのでしょう。 ■年俸12両のサラリーマン 十返舎一九は、駿河国寸駿府町奉行の同心の子として生まれ、本名を重田貞一といい、通称は与七。父親は奉行所の書記をしていました。大人になって父のあとを継ぎ奉行所に勤め、駿府町奉行小田切土佐守に従って大阪に転勤しました。大阪では、お上から食禄をいただいて芸道修行の生活でしたが、大阪に来た目的でもあった年来の作家志望を満たすべく、近松門左衛門の門をたたきます。役人を続けながら、近松の門下で並木千柳、若竹笛窮らとの合作で浄瑠璃本を近松与七の名で書きあげました。このころ十返舎の号を香道の「黄熟香の十返し」に因んでつけ、武士の片手間ではダメだと考えて年俸12両の役人生活に見切りをつけます。 武士をやめたあと、大阪で義太夫語りの家に寄宿したり、材木商家に婿入りして離縁になったりしていますが、後に江戸に出て、蔦屋という地本屋の食客となって多くの黄表紙や洒落本を発表し、貧乏ながらも作家を業とするようになりました。そして、たびたびの東海道の往復で資料を蓄積して書きあげた「膝栗毛」の大ヒットで、洒落本作家の地位を確立します。 ■気むづかしい一九 一九は、そのユーモラスな作品とはおおよそ対照的な案外の気むづかしく偏屈な性格で、到底作品に見るような軽快な男ではなかったようです。あるとき、膝栗毛の熱心なファンの某資産家が、この滑稽な一九と旅ができたならさぞ面白かろうと、旅費雑用いっさい負担の条件で頼みこみ、念願がかなって一九とともに旅をしたという人の話。そのときの一九は、その某氏が弥次喜多から想像した人物とは正反対で、むっつりとして口をきかず、しごくあっさりしていて宿に着けばさっそく机に向かって几帳面な日記をつけるという始末。なんにも面白くないので退屈して途中で逃げ帰ったといいます。一九はひとり旅を好んだといいますから、某氏が逃げ帰ったのは、ねらいどおりだったのかもしれません。 ■変わり者 一九は、一時期は相当な暮らしをしていたようですが、20年にわたって人気作家であったにもかかわらず、晩年は酒におぼれて借家住まいの貧乏世帯でした。その貧乏にまつわる一九の奇行の数々が伝えられています。 ある年の新春、年賀に来た客を無理矢理に入浴させ、その間にその客の着物はじめ腰のものまですべてを拝借して、近所に新年の挨拶をすませたということがありました。 また、家財道具を質にいれては飲んでしまうので、家の中には何一つなくなってしまったときのこと。殺風景な家の壁に紙を張り、タンスや床の間、違い棚、掛け軸置き物などを描いて、正月の鏡もちまで絵にかいた餅、まるで芝居のような光景の中に平然と居たという、滑稽を地でいくような愛すべき一面も見られます。 一九のこのような奇行は、師と尊敬した太田蜀山人の影響ともいわれます。 ■死んでも洒落で 江戸文学に数々の功績をのこし、十返舎一九は天保2年(1831)8月6日67歳で江戸長谷川町の裏長屋で病死しました。一九は、自分の死を予期していて、前日、頭陀袋へ線香花火をいっぱい詰めておいたので、火葬場で弔いの人々を驚かせました。 |
|
| 緒方襄 | (1922-1945)熊本県出身、日本海軍軍人、海軍少佐、関西大学出身、海軍第13期飛行科予備学生。昭和20年3月21日第一神風桜花特別攻撃隊神雷部隊桜花隊・「桜花」搭乗員、母機一式陸上攻撃機に搭乗 鹿屋基地を出撃、九州南方洋上にて戦死。戦死後、海軍少佐に昇進。 |
 

 |
|
| 小西来山 | 承応3年-享保元年(1654-1716)江戸時代の俳人。十萬堂の号がある。「近世畸人伝」にその名が見え、同書によれば、浪華(大阪)の南今宮村に住しており、酒を好み、物事にこだわらない人物だったという。 |
| 小堀遠州 | 小堀政一(こぼりまさかず)天正7年-正保4年(1579-1647)江戸時代前期の近江小室藩藩主。茶人、建築家、作庭家としても有名であり、遠江守に任じられた事から、一般には小堀遠州(こぼりえんしゅう)の名称で知られている。幼名を作助、元服後、初めは正一、後に政一と改める。道号は大有宗甫、庵号は孤篷庵。正室は藤堂高虎の娘。子に小堀正之、娘(池田重政室)らがいる。 |
| 小林一茶 | 宝暦13年-文政10年(1763-1828)江戸時代を代表する俳諧師の一人。本名を小林弥太郎。信濃北部の北国街道柏原宿(現長野県上水内郡信濃町大字柏原)の貧農の長男として生を受ける。3歳の時に生母を失い、8歳で継母を迎える。継母に馴染めず江戸へ奉公に出、25歳のとき二六庵小林竹阿に師事して俳諧を学ぶ。29歳の時、故郷に帰り、翌年より36歳の年まで俳諧の修行のため近畿・四国・九州を歴遊する。39歳のとき再び帰省。病気の父を看病したが1ヶ月ほど後に死去、以後遺産相続の件で継母と12年間争う。一茶は再び江戸に戻り俳諧の宗匠を務めつつ遺産相続権を主張し続けた。50歳で再度故郷に帰り、その2年後28歳の妻きくを娶り、3男1女をもうけるが何れも幼くして亡くなっていて、特に一番上の子供は生後数週間で亡くなった。きくも痛風がもとで37歳の生涯を閉じた。2番目の妻(田中雪)を迎えるも老齢の夫に嫌気がさしたのか半年で離婚。3番目の妻やをとの間に1女・やたをもうける(やたは一茶の死後に産まれ、父親の顔を見ることなく成長し、一茶の血脈を後世に伝え。1873年に46歳で没)。文政10年閏6月1日(1827)柏原宿を襲う大火に遭い、母屋を失い、焼け残った土蔵で生活をするようになった。その年11月19日その土蔵の中で65歳の生涯を閉じた。 |
| 松前公広 | 慶長3年-寛永18年(1598-1641)蝦夷松前藩の第2代藩主。旧字体での表記は公廣。沢庵宗彭から仏道を、小幡景憲から軍学を学んだという。 |
| 松尾芭蕉 | 寛永21年-元禄7年(1644-1694)現在の三重県伊賀市出身の江戸時代前期の俳諧師。幼名は金作。通称は藤七郎、忠右衛門、甚七郎。名は宗房。俳号としては初め実名宗房を、次いで桃青、芭蕉(はせを)と改めた。蕉風と呼ばれる芸術性の高い句風を確立し、俳聖と呼ばれる。芭蕉が弟子の河合曾良を伴い、元禄2年3月27日(1689)江戸を立ち東北、北陸を巡り岐阜の大垣まで旅した紀行文「奥の細道」がある。以下の句が著名である。 古池や蛙飛びこむ水の音 名月や池をめぐりて夜もすがら 夏草や兵どもが夢の跡 (岩手県平泉町) 閑さや岩にしみ入る蝉の声 (山形県・立石寺) 五月雨をあつめて早し最上川 (山形県大石田町) 雲の峰いくつ崩れて月の山 (山形県・月山) 荒海や佐渡によこたふ天河 (新潟県出雲崎町) 花の雲鐘は上野か浅草か (東京都) 初しぐれ猿も小蓑をほしげ也 (三重県伊賀市) |
| 上杉謙信 | 上杉輝虎(うえすぎてるとら)享禄3年-天正6年(1530-1578)戦国時代の越後の武将、大名。後世、越後の虎とも越後の龍とも呼ばれた。上杉氏の下で越後の守護代を務めた長尾氏出身で、初名は長尾景虎(ながおかげとら)。兄である晴景の養子となって長尾氏の家督を継いだ。主君・上杉定実から見て「正妻の甥」且つ「娘婿の弟」にあたる。のちに関東管領上杉憲政から上杉氏の家督を譲られ、上杉政虎と名を変えて上杉氏が世襲する室町幕府の重職関東管領に任命される。後に将軍足利義輝より偏諱(へんき)を受けて最終的には上杉輝虎と名乗った。周辺の武田信玄、北条氏康、織田信長、佐野昌綱らと合戦を繰り広げた。特に五回に及んだとされる武田信玄との川中島の合戦は、後世たびたび物語として描かれており、よく知られている。自ら毘沙門天の転生であると信じていたとされる。 |
 

 |
|
| 織田信孝 | 永禄元年-天正11年(1558-1583)安土桃山時代の武将・大名。織田氏の一族。伊勢中部を支配する豪族神戸氏を継いだため、神戸信孝(かんべのぶたか)とも。 堺にて渡海の準備中に本能寺の変が勃発、逃亡兵が相次いだため積極的な行動はできず、明智光秀の娘婿である従兄弟の津田信澄を殺害した程度であった(しかし信澄が本能寺の変に加担した証拠は存在しない)。その後、摂津国富田で「中国大返し」後の羽柴秀吉軍に合流、名目上の総大将として山崎の戦いに参戦し、仇である明智光秀を撃破した。信長の弔い合戦の総大将であったにも関わらず、清洲会議において織田氏の後継者は甥の三法師に決まる。信孝は三法師の後見役として兄信忠の領地であった美濃国を与えられ、岐阜城主となる。その後、秀吉と対立する柴田勝家に接近し、勝家と叔母のお市の方との婚儀を仲介した。こうして織田氏宿老格の柴田勝家・滝川一益らと結び、同年12月三法師を擁し秀吉に対して挙兵する。しかしこの挙兵は秀吉の迅速な行動によって降伏せざるを得なくなり、人質を出して三法師を秀吉に引き渡した。天正11年(1583)賤ヶ岳の戦いが起きると、信孝は再度挙兵する。しかし兄・信雄によって同年4月居城の岐阜城を包囲され、頼みの勝家も北ノ庄城で自害すると、岐阜城を開城して秀吉に降伏した。信孝は尾張国知多郡野間(愛知県美浜町)の大御堂寺(野間大坊、平安時代末に源義朝が暗殺された場所)に送られ、自害した。享年26。首は神戸城では受け取りを拒否され、検視大塚俄左衛門が伊勢関町の福蔵寺に持ち帰った。寺では首塚を作り手厚く弔った。 |
| 新門辰五郎 | 寛政12年-明治8年(1800-1875)江戸時代後期の町火消、鳶職、香具師、侠客、浅草浅草寺門番である。父は中村金八。町田仁右衛門の養子となる。娘は江戸幕府15代将軍徳川慶喜の妾となる。「新門」は浅草寺僧坊伝法院新門の門番である事に由来する。 武蔵国江戸下谷(東京都台東区)に生まれる。幼少の頃に実家の火事で父が焼死、或いは自宅から出火し近辺を類焼した責任を取り自ら焼死した経験から町火消になったと伝えられる。浅草十番組「を組」の頭である町田仁右衛門の元へ身を寄せ、火消や喧嘩の仲裁などで活躍する。仁右衛門の娘を貰い養子縁組し、文政7年(1824)「を組」を継承する。侠客の元締め的存在で、弘化2年(1845)他の組と乱闘になり死傷者が出た際には責を取って入牢している。幕府の高級官僚だった勝海舟とも交流があったと言われる。その一方で、博徒・小金井小次郎を子分のように可愛がった。上野大慈院別当覚王院義観の仲介で一橋慶喜(徳川慶喜)と知り合ったと伝えられ、娘の芳は慶喜の妾となっている。元治元年(1864)禁裏御守衛総督に任じられた慶喜が京都へ上洛すると慶喜に呼ばれ、子分を率いて上洛して二条城の警備などを行う。慶応3年(1867)大政奉還で江戸幕府が消滅し、鳥羽伏見の戦いの後に慶喜が大坂から江戸へ逃れ、上野寛永寺に謹慎した際には寺の警護、上野戦争での伽藍の防火、慶喜が水戸(茨城県)、静岡と移り謹慎するとそれぞれ警護を務めている。なお、慶喜が大坂城から逃げる時に忘れてきた家康以来の金扇の大馬印を回収し、東海道を下って無事送り届けた。慶喜とともに静岡に住み駿河国清水の侠客である清水次郎長とも知縁であったと伝えられる。遠江国磐田郡での製塩事業にも協力した。明治になると東京へ移る。明治8年(1875)没、享年75。 |
| 森鴎外 | 文久2年-大正11年(1862-1922)明治・大正期の小説家、評論家、翻訳家、戯曲家、陸軍軍医、官僚(高等官一等)。陸軍軍医総監(中将相当)・正四位・勲二等・功三級・医学博士・文学博士。 |
| 真木和泉 | 真木保臣(まきやすおみ)文化10年-元治元年(1813-1864)江戸時代後期の久留米水天宮祠官、久留米藩士、尊皇攘夷派の活動家である。父は真木旋臣、母は中村柳子。和泉守従五位下に任官し、真木和泉守もしくは真木和泉として有名。安政の大獄によって吉田松陰・橋本左内の指導者をうしなった後の尊攘派を形而上下にわたり先達として指導した。贈正四位。 会津藩と薩摩が結託して長州藩を追放した「八月十八日の政変」が起こると、7卿とともに長州へ逃れ、翌年に長州藩の過激派とともに禁門の変(蛤御門の変)を起こして、久坂玄瑞らとともに天王山で自害する、享年52。「八月十八日の政変」/文久3年8月18日(1863)中川宮朝彦親王や薩摩藩・会津藩などの公武合体派が長州藩を主とする尊皇攘夷派を京都における政治の中枢から追放した政変である。文久年間に起きたことから文久の政変とも呼ばれている。 |
| 神保長輝 | 神保修理(じんぼしゅり)天保5年-慶応4年(1834-1868)幕末期の会津藩の軍事奉行添役。会津藩家老・神保内蔵助の長男。初名は直登。諱は長輝。弟に北原雅長。妻は会津藩士井上丘隅(きゅうぐ)の次女、雪子。藩主・松平容保に仕え、上洛などに随行した。1868年の戊辰戦争で容保が新政府軍と戦う決意をすると、時勢の流れから敗戦を読み取って恭順するように進言したが、かえって佐幕派の藩士の怒りを買った。将軍徳川慶喜、藩主・容保ら幕府首脳が鳥羽・伏見で戦っている兵を捨てて、大阪から江戸へ脱出した責任を取らされ江戸三田の藩邸で切腹を命じられた。 |
 

 |
|
| 親鸞 | 承安3年-弘長2年(1173-1263)鎌倉時代初期の日本の僧。浄土真宗の宗祖とされる。明治9年(1876)明治天皇より「見真大師」(けんしんだいし)の諡号を追贈されている。親鸞は、法然(浄土宗開祖)を師と仰いでからの生涯に渡り、「真の宗教である浄土宗の教え」を継承し、さらに高めて行く事に力を注いだ。自らが開宗する意志は無かったと考えられる。独自の寺院を持つ事はせず、各地につつましい念仏道場を設けて教化する形であった。親鸞の念仏集団の隆盛が、既成の仏教教団や浄土宗他派からの攻撃を受けるなどする中で、宗派としての教義の相違が明確となって、親鸞の没後に宗旨として確立される事になる。 自分はわるい人間であるから、如来のお迎えをうけられるはずはないなどと、思ってはならない。凡夫はもともと煩悩をそなえているのだから、わるいにきまっていると思うがよろしい。また、自分は心がただしいから、住生できるはずだと、思ってもならない。自力のはからいでは、真実の浄土に往生できるのではない。 |
| 諏訪頼重 | 永正13年-天文11年(1516-1542)信濃国の戦国大名。諏訪氏の第19代当主。諏訪頼満の嫡孫で諏訪頼隆の子。宮増丸。刑部大輔。上原城城主。諏訪大社大祝(おおほうり)。武田勝頼の外祖父にあたる。 武田氏では信虎が駿河へ追放され嫡男武田晴信(信玄)が国主に推戴され、信濃侵攻を本格化させる。翌天文11年(1542)6月伊那郡を支配する高遠頼継と手を結んだ晴信に本拠・上原城を攻められた頼重は7月桑原城で降伏し、弟の頼高と共に甲府に連行され、東光寺に幽閉された後に自刃する。 |
| 正岡子規 | 慶応3年-明治35年(1867-1902)俳人・歌人・国語学研究家である。名は常規(つねのり)。幼名は処之助(ところのすけ)で、のちに升(のぼる)と改めた。俳句・短歌・新体詩・小説・評論・随筆など多方面に渡り創作活動を行い、日本の近代文学に多大な影響を及ぼした、明治時代を代表する文学者の一人である。死を迎えるまでの約7年間は結核を患っていた。享年34。辞世の句より、子規の忌日9月19日を「糸瓜忌」といい、雅号の一つから「獺祭(だっさい)忌」ともいう。 余は、今迄禅宗の悟りということを誤解していた。悟りということは、如何なる場合にも平気で死ねる事かと思っていたのは間違いで、悟りという事は、如何なる場合にも平気で生きて居ることであった。 「病床六尺」 |
| 清河八郎 | 天保元年-文久3年(1830-1863)幕末の志士で、浪士組の幹部であった。出羽国庄内藩領清川村(現・山形県東田川郡庄内町)の郷士の斉藤豪寿の子。幼名元司。諱は正明。本名は斉藤正明。贈正四位。 天保14年(1843)清川関所役人の畑田安右衛門に師事し勉学に勤しむ。かなり優秀であったようである。弘化3年(1846)後の天誅組総裁藤本鉄石と会い親交を深めた。弘化4年(1847)江戸に出て古学派の東条一堂に師事。才を認められ東条塾塾頭を命ぜられたが、固辞。安積艮斎に転塾。その傍ら、北辰一刀流の開祖千葉周作の玄武館で剣を磨き免許皆伝を得え、江戸幕府の学問所昌平黌に学んだ。その後、清河塾開設(江戸市内で学問と剣術を一人で教える塾は清河塾だけであった)。 安政2年(1855)3月から9月にかけて、母親を連れて、清川村を出発。善光寺、名古屋、伊勢、奈良、京都、近江、大阪、宮島、岩国、天橋立、鎌倉、江戸、日光などをめぐる大旅行をする。その記録「西遊草」は、幕末の旅行事情を知るうえでは貴重な資料である。内容は各国の名士との出会いなどを中心に書かれているが、清河の性格からか辛辣で手厳しい批評が多い。 万延元年(1860)に起こった桜田門外の変に強い衝撃を受け、倒幕、尊王攘夷の思想が強まる。この事件を契機に、清河塾に憂国の士が集まりだす。 同年、八郎を盟主として虎尾の会結成。発起人は山岡鉄太郎(鉄舟)他十五名。横浜外国人居留地を焼き討ちし、尊王攘夷の精神を鼓舞し、倒幕の計画をたてたが、この密計が幕府の知るところとなる。しかも文久元年には八郎に罵詈雑言を浴びせてきた者を斬り捨てたため、幕府に追われる立場となっていた。 八郎はこのような事情から京都に潜伏したり、東西諸国を遊説してまわり尊攘倒幕の内約をとりつけにまわった。 その後、松平春嶽(幕府政事総裁)に急務三策(攘夷の断行/大赦の発令/天下の英材の教育)を上書する。尊攘志士に手を焼いていた幕府はこれを採用。浪士組が結成される(234名)。八郎は上手く幕府を出し抜いた。 文久3年(1863)2月23日将軍徳川家茂上洛のさい、その前衛として八郎は盟主として浪士組を率いて京都へ出発。京都に到着した夜、八郎は浪士を壬生の新徳寺に集め本当の目的は将軍警護でなく、尊王攘夷の先鋒にあると述べる。これに反対したのが、近藤勇、土方歳三、芹沢鴨らであった(鵜殿鳩翁が浪士組隊士の殿内義雄・家里次郎の両名に、京に残留することを希望する者の取りまとめを依頼し、根岸友山、芹沢鴨、近藤勇らが残留し八郎と袂を分かつ、彼らは壬生浪士(壬生浪)となり、後に新選組へと発展してゆく。)。二百名の手勢を得た八郎は翌日、朝廷に建白書の受納を願い出て幸運にも受理された。 このような浪士組の動静に不安を抱いた幕府は浪士組を江戸へ呼び戻す。八郎は江戸に戻ったあと浪士組を動かそうとするが、京都で完全に幕府と対立していたため狙われていた。 文久3年4月13日幕府の刺客、佐々木只三郎、窪田泉太郎など6名によって麻布一ノ橋で討たれ首を切られた。享年34。「女士道」によると首は石坂周造がとりもどし、山岡英子(山岡鉄舟の妻)が保管し遺族に渡したという。八郎死後、幕府は浪士組を新徴組と改名し庄内藩預かりとした。 |
| 清水宗治 | 天文6年-天正10年(1537-1582)日本の戦国時代の武将で、備中国高松城主。通称長左衛門と呼ばれ、清水宗則の子にあたる。初め三村氏家臣、後に毛利氏家臣となった。三村氏の有力配下石川久智の娘婿となり、子供に景治、兄に宗知(月清入道)がいる。 1582年統一政策を進める織田信長の家臣羽柴秀吉が中国攻めを行うと、宗治は高松城に籠城して抗戦する。秀吉は降伏すれば備中国を与えるという条件を出したが、宗治は応じなかった。そのため、黒田孝高(官兵衛)が策した水攻めにあって城は落城寸前に追い込まれる。この水攻めの最中の6月に京都で本能寺の変が起こって織田信長が死去し、その報を知った秀吉は宗治の切腹を条件に城兵を助命する講和を呼びかけ、宗治は信長の死を知らぬまま、その数日後に兄の月清らとともに水上で切腹した。享年45。 秀吉は信長の敵討ちのために一刻も早く京へと戻りたいところであったが、「名将・清水宗治の最期を見届けるまでは」と陣から一歩も動かなかったといわれている。後に小早川隆景に会った秀吉は「宗治は武士の鑑であった」と絶賛したという。 |
 

 |
|
| 西郷一族(会津) | 西郷頼母(さいごうたのも)(1830-1905)会津藩家老。時勢を見抜く目をもった人物といわれ、特に、藩主松平容保の京都守護職就任に強硬に反対しました。「この時勢に京都守護職など薪を背負って火に飛びこむようなもの」と極言して諌めましたが、徳川宗家を大事と考える容保に容れられませんでした。やがて、会津藩は新政府軍の征討の標的となりますが、頼母は恭順論を唱えますが容れられませんでした。戊辰戦争では、頼母は会津藩白河口総督として出陣。白河城での攻防1ヶ月。死闘を演じましたがついに白河城は官軍の手に落ちました。会津落城後は仙台より榎本軍に投じ函館戦争に参加。のち、日光東照宮宮司となった旧主容保のもとで禰宜として仕えたのち会津に戻り、裏長屋で余生を送りました。 西郷一族の悲劇/会津城下が新政府軍の乱入を許した慶応4年8月23日、様々な悲劇が起こりました。白虎隊の悲劇もこの日のことでしたが、城下の武家の子女にも同様のことが起きました。中でも、西郷頼母一族は城からの総篭り(篭城命令)に対し、女子供が入城すれば篭城戦の足手惑いになるとして入城を拒み自刃を遂げました。頼母の母(58歳)、妻(34歳)、妹2人(26歳と23歳)、5人の娘の9人の他一族親類の家族12人の総勢21人の集団自決でした。この西郷一族の自刃は会津戦争の悲劇として現在も語り伝えられています。 |
 

 |
|
| 西行法師 | 元永元年-文治6年(1118-1190)院政期から鎌倉時代初期にかけての武士・僧侶・歌人。父左衛門尉佐藤康清、母源清経女。俗名は佐藤義清(さとうのりきよ)であり、憲清、則清、範清とも記される。出家して法号は円位、のちに西行、大本房、大宝房、大法房とも称す。勅撰集では詞花集に初出(一首)。千載集に十八首、新古今集に九十四首(入撰数第一位)をはじめとして二十一代集に計265首が入撰。家集に「山家集」(六家集の一)「山家心中集」(自撰)「聞書集」、その逸話や伝説を集めた説話集に「撰集抄」「西行物語」があり、「撰集抄」については作者に擬せられている。 |
|
■西行の生い立ち 東西を結ぶ東海道にある小夜の中山は、「古今和歌集」「千載和歌集(せんざいわかしゅう)」「後撰和歌集」など20余りの歌に出てくる歌枕であり、峠付近には数々の歌碑、句碑が残されています。 その中でも西行法師の次の歌は西行晩年の陸奥修行の途中で詠んだ代表作とされる歌で、芭蕉をはじめ多くの歌人俳人がこの歌枕を訪ねて東海道を旅しています。 年たけてまた越ゆべしと思ひきや 命なりけり小夜の中山 窪田章一郎氏は「西行の研究」の中で「この歌は西行の全作品中のピークになっているものと見るべきもので、30代の初頭と69歳の現在との旅が、久しい時間の経過の上で把握され、人生的な味わいが全体からにじみ出ている歌である。徹頭徹尾、自己を歌おうとしてきた西行が、旅中にこの歌を詠んでいることは、その点から見ても、西行の文学を象徴する意味をもつということができる」と高く評価しています。 ■俗人時代の文化的環境 西行法師は、鳥羽天皇の元永元(1118)年、藤原秀郷(俵藤太)の流れをくむ秀郷流の武門の家柄である佐藤氏の嫡子として生まれ、俗名を佐藤義清(のりきよ)と名乗りました。父親は幼少の頃世を去りましたが、母は堅物源清経の娘で、説によれば「梁塵秘抄口伝集」「蹴鞠口伝集」に出てくる清経ではないか、とされており、そうだとすれば、清経の雅な血が流れていたということになります。 佐藤家は私領であった紀伊国田仲庄を荘園として寄進し、自ら預所として財をなしていきます。佐藤家は徳大寺家と先の関係(寄進先)にあったため、義清は元服後の多感な時期を徳大寺家の家人(けにん)として過ごしています。この徳大寺家は和歌の雰囲気を濃厚に持った一族で、若き日の義清に少なからぬ影響を与えました。一方で義清は当時流行のスポーツであった蹴鞠の名手であり、また西行が陸奥へ旅する途中鎌倉を通過するとき、頼朝に示した流鏑馬(やぶさめ)の射手としての見識は「吾妻鏡」で有名です。芸術的な環境にあってその感受性から非凡な才覚をあらわし武勇にも秀でた、義清の魅力的な人物像が浮かんできます。 ■自己形成的な出家 義清は崇徳天皇の保延六(1140)年10月15日、23歳で出家しました。このことについて藤原頼長は日記「台記」(康治元・1142)に次のように記しています。 俗時自リ心ヲ仏道に入レ、家富ミ年若ク、心愁無キモ、遂ニ以テ遁世ス。人之ヲ歎美セルナリ。(原漢文) 生のスタイルを変える出家は当時めずらしくないとしても、何不自由ない権力者の嫡子が若くして出家したことは、知る人ぞ知る突然の出来事であったようです。 西行という法号は西方極楽浄土をねがう浄土信仰にもとづいて付けた号といわれます。学僧として世に立とうとしたのではなく、信仰と作歌とを身をもって体得し、紫衣をまとう形式よりも純粋な信仰心を求め、文学表現を深めようとする自己形成的な出家でした(窪田説)。 ■歌の才覚 やがて西行は鳥羽院の警護役である北面の武士となります。この身分は六位と下級であり、23歳で出家したため五位にあがることはなく宮中資格を持ちませんでした。このことは27歳の時「詞花和歌集」の選にあたり選ばれた彼の歌 身を捨つる人はまことに捨つるかは捨てぬ人こそ捨つるなりけれ が、「読み人知らず」とされたことにつながっています。出家後、法皇の崩御により西行の宮中での力はさらに衰えますが、主家に徳大寺実能がいたことや、実能の妹待賢門院璋子が鳥羽天皇の后であったなどのつながりから堀河局、兵衛局ら女房たちとの歌会に招かれるなど、歌や信仰によるつながりを続けました。もちろん西行の並外れた詩才がものを言ったことは言うまでもありません。西行没後の勅撰和歌集である「新古今和歌集」では最高の入集、94首を数えました。これは「新古今和歌集」の親裁後鳥羽院の賞揚、推挙が影響したとされ、「後鳥羽院御口伝」によれば 「おぼろげの人、まねびなどすべき歌にあらず」 と賞賛しています。 ■旅の意味 西行は「山家集」「五首述懐」の中で、 うかれ出づる心は身にもかなはねば いかなりとてもいかにかはせん という歌を詠んでいます。これは花であれ旅であれ憧れるものを目指して心が身から離れていくことを現しています。西行は旅という非日常的空間に己を置くことによって独自の美意識を展開し、また旅によって西行の美意識が磨かれていったともいえます。数奇にまかせて旅に出ることは、遁世者とは名ばかりの風来であったわけではなく、当時は現世の数奇と来世の救済の矛盾解決を求める宗教的文学理念でした。旅は芸術家であり宗教家である西行の人生の証であったのでしょう。 最初の大きな旅は、おそらく西行が30歳以前のこと、祖先の出身地である陸奥(みちのく)平泉へ歌枕を訪ねる旅を敢行しています。陸奥から帰洛後、真言霊場の高野山に入って草庵を結び、その生活は30年に及びました。 仁安三(1168)年、51歳のころ、讃岐を目指して四国への長い修行に出ました。時は鳥羽院政の末期、乱世の気配が高まる情勢にあり、この旅は崇徳院の鎮魂という政治的意味を含んだ旅であったと言われています。そのような目的にあっても、讃岐修行の旅の作には備前国児島あたりから瀬戸内海を渡る途中で眼にした漁民、商人などの生きざまがいきいきと描かれており、若年期の歌よりも多面的で深みのある西行の数奇心がうかがえます。 乱世の間は伊勢に疎開して過ごし、文治二(1186)年、69歳の西行は、ほぼ40年ぶりに陸奥へ東大寺再建の勧進修行に赴きます。老西行にとってはさいはての陸奥への旅は不退転の決意を要した旅であったはず。この旅は西行の心にひそむ菩提心の発露に他ならないでしょう。この旅の途中、東海道を下りつつ、代表作というべき二首を詠んでいます。 東の方へ相識りたりける人の許へまかりけるに、小夜の中山見しことの昔になりける思ひ出でられて 年たけてまた越ゆべしと思ひきや 命なりけり小夜の中山 東の方へ修行し侍りけるに富士の山を見て 風になびく富士のけぶりの空に消えて 行方も知らぬわが思ひかな ■数奇の達成 西行がいつ陸奥の旅を終えたのか明らかではありませんが、文治三(1187)年には嵯峨の草庵に入っていたようです。嵯峨で詠んだ「たはぶれ歌」には うなゐ子がすさみにならず麦笛の 声におどろく夏の昼臥し などとあり、杖にすがって昼寝にまどろむ西行の老いが印されています。長旅の疲れと、この時代に稀な70歳に達したという自覚が、西行に迫り来る死を予期させ、生涯の数奇を自ら締めくくる決意をさせたようです。「御裳濯河歌合」と「宮河歌合」の自撰です。それまでは流行をきわめた歌合に自作を出さない方針を貫いてきた西行が、「伊勢の太神宮に奉らむ」として独創的な自歌合制作を試みたのでした。 文治五(1189)年のころ、西行は高尾の神護寺に登山し、そこで少年の明恵にむかって「 この歌は即ちこれ如来の真の形体なり、されば一首詠み出でては一体の尊像を造る思いをなす、一句思ひつづけては秘密の真言を唱ふるに同じ。」 と和歌の本質を説いています。この言葉にはのちの明恵上人に対する潤色が混じっているかもしれませんが、西行の到達した和歌観の究極と読み取れます。しかし、西行は年来かかわってきた数奇を無条件に肯定したわけではありません。上記の言葉の前に、花や月をはじめ眼に見え耳に満ちる万物すべて「虚妄」であり、みずからも年来「この虚空如なる心の上に於いて種々の風情をいろどる」わざをしてきたが、むなしくも「さらに蹤跡無し」と、痛切な反省を告白しています。これは、数奇の魔性を知りつくした詩人の真率な述懐の言葉なのでしょう。 西行は最晩年「慈円」と名乗り、建久元(1190)年2月16日、弘川寺にてその生涯を閉じました。 |
|
| 石川五右衛門 | (いしかわごえもん) -文禄3年( -1594)安土桃山時代に出没した盗賊。出生地は伊賀国・遠江国(現・浜松市)・河内国・丹後国などの諸説があり、伊賀流忍者の抜け忍であったのではないかという説もある。一説に三好氏の臣石川明石の子で、体幹長大、三十人力を有し16歳で主家の宝蔵を破り、番人3人を斬り黄金造りの太刀を奪い、逃れて諸国を放浪し盗みをはたらいたが、文禄3年追捕せられ、京都三条河原で一子とともに釜で煎殺されたという。また遠州浜松生まれで、真田八郎と称したが、河内国石川郡山内古底という医家により石川五右衛門と改めたという説もある。 |
| 石田三成 |
永禄3年-慶長5年(1560-1600)安土桃山時代の武将・大名。豊臣政権の五奉行の一人。 関ヶ原/慶長5年(1600)7月三成は家康を排除すべく、上杉景勝・直江兼続らと密かに挙兵の計画を図る。その後、上杉勢が公然と家康に対して叛旗を翻し、家康は諸大名を従えて会津征伐に赴いた。これを東西から家康を挟撃する好機として挙兵を決意した三成は、大谷吉継を味方に引き込もうとする。吉継は、家康と対立することは無謀であるとして反対したが、三成との友誼などもあって承諾した。これには秀吉存命の折の茶会で、らい病を患っていた吉継の膿が茶に落ちたとき余人が回し飲むのをためらった際、三成が吉継のためにそれを飲み干したためその友情に報いようとしたという説もある。 7月12日兄・正澄を奉行として近江愛知川に関所を設置し、家康に従って会津征伐に向かう後発の西国大名、鍋島勝茂や前田茂勝らの東下を阻止し、強引に自陣営(西軍)に与させた。7月13日三成は諸大名の妻子を人質として大坂城内に入れるため軍勢を送り込んだ。しかし加藤清正の妻をはじめとする一部には脱出され、さらに細川忠興の正室・玉子には人質となることを拒絶され屋敷に火を放って死を選ぶという壮烈な最期を見せられて、人質作戦は中止された。 7月17日毛利輝元を西軍の総大将として大坂城に入城させ、同時に前田玄以・増田長盛・長束正家の三奉行連署からなる家康の罪状13か条を書き連ねた弾劾状を諸大名に公布した。7月18日西軍は家康の重臣・鳥居元忠が守る伏見城を攻めた。しかし伏見城は堅固で鳥居軍の抵抗は激しく、容易に陥落しない。そこで三成は、鳥居の配下に甲賀衆がいるのを見て、長束正家と共に甲賀衆の家族を人質にとって脅迫する。8月1日甲賀衆は三成の要求に従って城門を内側から開けて裏切り、伏見城は陥落した。8月2日三成は伏見城陥落を諸大名に伝えるべく、毛利輝元や宇喜多秀家、さらに自らも連署して全国に公布する。 8月からは伊勢方面の平定に務めたが、家康ら東軍の反転西上が予想以上に早かったため、三成は関ヶ原で野戦を挑むことを決める。9月15日東軍と西軍による天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いが始まった。当初は西軍優勢であり、石田隊は6900人であったが、細川忠興・黒田長政・加藤嘉明・田中吉政ら兵力では倍以上の敵に攻められたものの、島左近・蒲生頼郷・舞兵庫らの奮戦もあって持ちこたえた。しかし西軍全体では戦意の低い部隊が多く、次第に不利となり、最終的には小早川秀秋や脇坂安治らの裏切りによって西軍は総崩れとなり、三成は戦場から逃走して伊吹山に逃れた。 その後、伊吹山の東にある相川山を越えて春日村に逃れた。春日村から新穂峠を迂回して姉川に出た三成は、曲谷を出て七廻り峠から草野谷に入った。そして、小谷山の谷口から高時川の上流に出、古橋に逃れた。しかし9月21日家康の命令を受けて三成を捜索していた田中吉政の追捕隊に捕縛された。 一方、9月18日東軍の攻撃を受けて三成の居城・佐和山城は落城し、三成の父・正継をはじめとする石田一族の多くは討死した。 9月22日大津城に護送されて城の門前で生き曝しにされ、その後家康と会見した。9月27日大坂に護送され、9月28日小西行長、安国寺恵瓊らと共に大坂・堺を罪人として引き回された。9月29日京都に護送され、奥平信昌(京都所司代)の監視下に置かれた。10月1日家康の命により六条河原で斬首された。享年41。首は三条河原に晒された後、生前親交のあった春屋宗園・沢庵宗彭に引き取られ京都大徳寺の三玄院に葬られた。 |
| 絶海中津 | (ぜっかいちゅうしん)建武元年-応永12年(1334-1405)南北朝時代から室町時代前期にかけての禅僧。道号は絶海のほかに要関、堅子、蕉堅道人など多数ある。足利義満・足利義持などの二代の将軍をはじめ、多くの有力な守護大名、また朝廷においても伏見宮栄仁親王らの帰依を受けた人物で、その存在は当時の仏教界でも大きく、周信と並んで臨済宗夢窓派の発展に寄与したということで評価は高い。後小松天皇や称光天皇らも中津に帰依した人物の一人であり、その死後に前者は仏智広照国師、後者は聖国師という勅命による追贈を行なった。また、中津は著書に「絶海和尚語録」「蕉堅稿」(詩文集)などを残している。 |
 

 |
|
| 千利休 | 大永2年-天正19年(1522-1591)中世末期、戦国時代、安土桃山時代の茶人。何も削るものがないところまで無駄を省いて、緊張感を作り出すというわび茶(草庵の茶)の完成者として知られる。茶聖とも称せられる。 利休最後の手紙 . |
| 川端茅舎 | (かわばたぼうしゃ)(1897-1941)東京都日本橋蛎殻町出身の日本の俳人、画家。日本画家である川端龍子とは異母兄弟。本名は川端信一(かわばたのぶかず)。別号、遊牧の民・俵屋春光。高浜虚子に師事し、虚子に「花鳥諷詠真骨頂漢」とまで言わしめたホトトギス派・写生派の俳人。仏教用語を駆使したり、凛然とし朗々たる独特な句風は、茅舎の句を「茅舎浄土」と呼ばしめる。 |
| 川島芳子 |
(かわしまよしこ)(1907-1948)清朝粛親王の王女。本名は愛新覚羅 顕シ(あいしんかくら けんし)(シは王ヘンに子)、字は東珍、別名は金璧輝。歌集では和子という筆名を使用。他に芳麿、良輔などと名乗っていた時期もある。日本人の養女となり日本で教育を受ける。清朝復辟のために日本軍に協力し、戦後中華民国政府によって「漢奸」として訴追され刑死したとされる。 旅順では粛親王一家は関東都督府の好意により、日露戦争で接収した旧ロシア軍官舎を屋敷として提供され、幼い顕シも日本へ養女へ行く前の一時期をそこで過ごした。やがて粛親王が復辟運動のために日本政府との交渉人として川島を指定すると、顕シは川島の身分を補完し両者の密接な関係を示す目的で川島の養女となり、「川島芳子」と改名し、1915年来日した。芳子は当初東京赤羽の川島家から豊島師範付属小学校に通い、卒業後は跡見女学校に進学した。やがて川島の転居にともない長野県松本市の浅間温泉に移住し、松本高等女学校(現在の長野県松本蟻ヶ崎高等学校)に通学した。地元では芳子が松本高女まで馬で通ったエピソードが有名である。 1922年に実父粛親王が死去し、葬儀のために長期休学したが、復学が認められず松本高女を中退している。17歳で自殺未遂事件を起こし断髪、男装となる。断髪の原因は山家亨少尉との恋愛問題であるとも、養父浪速に関係を迫られたためであるともいわれているが、諸説あって明らかではない。断髪した直後に女を捨てるという決意文書をしたため、それが新聞に掲載されるなど、芳子の男装は直後から新聞に取り上げられ、真似して断髪する女性が現れたり、ファンになった女の子が押しかけてくるなど、ちょっとした社会現象を起こしたようである。 1927年、旅順で蒙古族の将軍パプチャップの息子カンジュルジャップと結婚するが、夫の親族となじめず、2年ほどで離婚。その後上海に渡り、上海駐在武官の田中隆吉少佐と交際したことから特務工作に関わるようになり、上海事変の謀略工作に関わったといわれている。上海での活躍から「東洋のマタ・ハリ」と呼ばれる。 1931年9月関東軍により満洲事変が勃発し、11月清朝最後の皇帝であった愛新覚羅溥儀が関東軍の手引きで天津から満洲に脱出した。芳子は残された溥儀の皇后婉容を天津から連れ出すことを軍から依頼され、婉容を天津から旅順へ護送する任務を行っている。 1932年溥儀を執政とする満洲国が中国大陸北部に成立すると、川島芳子は新京で満洲国女官長に任命されたが、実際には就任していない。この頃芳子をモデルにした村松梢風の小説「男装の麗人」が発表され、芳子は「日本軍に協力する清朝王女」として世間の注目を浴びるようになる。 1933年関東軍の支援のもとに安国軍(定国軍ともいう)が創設され、芳子が総司令に就任し、熱河作戦に従軍した。安国軍がどれほどの規模で、実際の活動はどのようなものであったかは明らかではないが、このニュースは日本や満州国の新聞で大きくとりあげられ、芳子は「東洋のジャンヌ・ダルク」「満洲のジャンヌ・ダルク」などと呼ばれた。 当時はラジオ番組に出演し、余った時間に即興で歌を披露し、それがきっかけでレコードの依頼がくるなど、非常に人気があった。芳子が歌う『十五夜の娘』『蒙古の唄』などのレコードが発売されている。なかには蒙古語で歌っている部分があるが、意味が通じないところもある。これは一時期蒙古人の夫と結婚して草原で暮らしていたので、その時に聞き覚えたものではないかと思われる。作詞者としては1933年に「キャラバンの鈴」(作曲:杉山長谷夫、唄:東海林太郎)というレコードを出している。 同年小説「男装の麗人」を連載していた「婦人公論」本誌に、独占手記として「僕は祖國を愛す」を掲載させ、1940年自伝「動乱の蔭に」を出版している。この頃には李香蘭などの映画スターとの親交もあった。また「昭和の天一坊」と騒がれた相場師の伊東ハンニや右翼の笹川良一と交際したり、天津で、中華料理屋「東興楼」を経営するなどしている。 世間から注目され一見華やかな存在であった芳子は、深い孤独を抱えていた。芳子は満洲国が清朝の復辟ではなく日本の傀儡国家に過ぎないことが明らかになると、日本軍(関東軍)の満洲国での振る舞いや日中戦争などを批判するようになり、軍部からは「危険人物」として監視されるようになった。軍による暗殺計画もあり、本人もそのことを察知していたという証言もある。1939年頃療養のために福岡に滞在、療養後は北平(北京)に戻り、終戦を迎える。 1945年8月第二次世界大戦(と日中戦争)の日本の敗戦とともに、同年10月北平で中国国民党軍に逮捕され、漢奸(中国語で国賊、売国奴の意)として訴追された。1947年死刑判決を受け、1948年3月25日北平第一監獄で銃殺刑に処された。 |
| 泉鏡花 | 明治6年-昭和14年(1873-1939)明治後期から昭和初期にかけて活躍した小説家。戯曲や俳句も手がけた。本名、鏡太郎。金沢市下新町生れ。尾崎紅葉に師事した。「夜行巡査」「外科室」で評価を得、「高野聖」で人気作家になる。江戸文芸の影響を深くうけた怪奇趣味と特有のロマンティシズムで知られる。また近代における幻想文学の先駆者としても評価される。代表作に「婦系図」「歌行燈」「夜叉ヶ池」など。 |
| 浅野長矩 | (あさのながのり)寛文7年-元禄14年(1667-1701)江戸時代前期から中期頃の大名。播磨赤穂藩の第3代藩主。官位は従五位下、内匠頭。官名から浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)と呼称されることが多い。元禄赤穂事件を演劇化した作品群忠臣蔵を通じて有名な大名である。 |
| 前田慶次郎 | 前田利益(まえだとします)天文2年?-慶長10年?(1533-1605)戦国時代末期から江戸時代初期にかけての武将で、瀧川一族の出身、前田利家の義理の甥。慶次郎などの通称を持つ。武勇に優れ、古今典籍にも通じた文武両道の将だったが、奇矯な振る舞いを好むかぶき者(傾奇者・カブキ者)としても知られた。妻は前田安勝の娘で、間に一男三女をもうけた。嫡男の前田正虎は従兄弟の前田利常に仕えた。娘は、戸田方勝の妻、北条庄三郎(北条氏邦末子)の妻など。孫娘(戸田方勝の娘・幾佐)は今井局と名乗り、幼少だった前田綱紀の養育にあたったと言われる。 山陰のくるる片野の鷹人は かへさもさらに袖のしら雪 ねやの戸はあとも枕も風ふれて あられよこぎり夜や更けぬらん 山柴に岩根のつつじかりこめて 花をきこりの負ひ帰る道 |
| 前田夕暮 | (まえだゆうぐれ)(1883-1951)本名・前田洋造(洋三とも)、明治から昭和期にかけての歌人。 |
| 鼠小僧次郎吉 | 寛政9年-天保3年(1797-1832)盗んだ金を貧乏人たちにバラまいて「義賊」と呼ばれたといわれる大泥棒・鼠小僧次郎吉は天保3年(1832)5月8日に捕縛されました。歌舞伎の中村座の木戸番の長男で建具職人をしていましたが、バクチで身を持ち崩し借金に追われて、無宿人となり、1823年頃から武家屋敷に泥棒に入るようになりました。武家屋敷を狙うのは別にお金のありそうな所を狙おうという意味ではありません。武家屋敷は被害にあっても届け出ればむしろ「盗賊などにやられるとは不届き至極」とおとがめを受ける可能性がありますので、まず届けることはありません。彼は身のこなしが軽く、ひとけのない所をうまく狙って盗んだので人を傷つけることなく、しかも処分に困るような物品には手を付けず現金だけを狙いました。1825年には一度捕まって入墨の上追放の刑を受けています。十両盗めば首が飛ぶ時代にこの刑はやはり被害届が出ていなかった故でしょう。しかし彼はこれで泥棒から足を洗いませんでした。更に盗みを続け、この日松平宮内少輔の屋敷に忍び込んだ所を捕まりました。二度目ですので刑も厳しく、同年8月19日市中引廻しの上鈴ヶ森刑場で打首獄門になりました。 彼のお墓が回向院にあります。伊勢屋四郎兵衛という商人が施主となって、建ててあげたものだそうですが、その墓石は「盗人の墓を削り取ったものを持っていればギャンブルに強くなる」という俗説のため大量に削り取られています。 |
| 足利義輝 | 天文5年-永禄8年(1536-1565)室町幕府の第13代征夷大将軍、在職・天文15年-永禄8年(1546-1565)。父は第12代将軍の足利義晴。なお、第10代将軍足利義稙の養子となった阿波公方足利義維は叔父で、その子である第14代将軍・足利義栄は従兄弟にあたる。 |
 

 |
|
| 足利義尚 | 寛正6年-延徳元年(1465-1489)室町幕府の第9代将軍、将軍在職・文明5年-長享3年(1473-1489)。父は第8代将軍・足利義政。母は正室の日野富子。晩年に義煕と改名しているので、こちらのほうが本名であるが一般的には義尚の名で知られている。応仁の乱で叔父の足利義視と将軍位をめぐって争う候補として押し立てられた。応仁の乱後に将軍親政を開始し、衰退した幕府権力を回復しようと六角征伐を行なうなど、積極的な幕政改革を行なったが、六角征伐の最中に病に倒れ、父母に先立つ形で死去した。 |
| 足利義政 | 永享8年-延徳2年(1436-1490)室町幕府の第8代征夷大将軍、在職・宝徳元年-文明5年(1449-1473)。本姓は源氏。家系は清和源氏の一家系 河内源氏の名門 足利氏の嫡流 足利将軍家。官位は征夷大将軍内大臣従一位を経て、左大臣。贈太政大臣。父は第6代将軍の足利義教。母は日野重光の娘で義教の側室である日野重子。乳母で側室に今参局。正室に日野富子。同母弟に足利義視、同母兄に足利義勝。異母弟に足利政知。室町幕府の全盛期を築いた第3代将軍・足利義満の孫にあたる。幕府の財政難と土一揆に苦しみ政治を疎んだ。幕政を富子や細川勝元・山名宗全らの有力守護大名に委ねて、自らはもっぱら数奇の道を探求した文化人
。 文化面では功績を残している。庭師の善阿弥や狩野派の絵師狩野正信、能楽者の音阿弥らを召抱え、東山の地に東山殿を築いた(のちに慈照寺となり、銀閣、東求堂が現在に残る)。この時代の文化は、金閣に代表される3代義満時代の華やかな北山文化に対し、銀閣に代表されるわび・さびに重きをおいた「東山文化」と呼ばれる。 |
| 太宰治 | 明治42年-昭和23年(1909-1948)昭和を代表する日本の小説家。本名は津島修治(つしましゅうじ)。昭和8年より小説の発表を始め、昭和10年「逆行」が第1回芥川賞候補となる。主な作品に「走れメロス」「津軽」「お伽草紙」「斜陽」「人間失格」など。 諧謔的、破滅的な作風で、坂口安吾、石川淳などともに新戯作派、無頼派とも称された。大学時代より自殺未遂、心中未遂を繰り返し、昭和23年玉川上水にて山崎富栄とともに入水した。 |
| 大田垣蓮月 | (おおたがきれんげつ)寛政3年-明治8年(1791-1875)江戸時代後期の尼僧・歌人・陶芸家。俗名は誠(のぶ)。菩薩尼、陰徳尼とも称した。 |
| 太田道灌 | 永享4年-文明18年(1432-1486)室町時代の武将。武蔵国守護代。本姓は源氏。家系は清和源氏の一家系である摂津源氏の流れを汲み、源頼政の末子で鎌倉幕府門葉となった源広綱の子孫にあたる太田氏。諱は資長。扇谷上杉家家宰太田資清(道真)の子で、家宰職を継いで享徳の乱、長尾景春の乱で活躍した。江戸城を築城した武将として有名である。 |
| 大久保一翁 | (おおくぼいちおう/大久保忠寛・おおくぼただひろ)文化14年-明治21年(1818-1888)江戸時代末期(幕末)の幕臣。明治時代の政治家。東京府知事・元老院議官・子爵。低身分から出世した一翁は、実力ある官僚と評価され、松平慶永や勝海舟ですら、敬服したと言われている。勝の出世の方途を開いたのが、一翁であり、元々は一翁は勝にとって上司に当たる。勝にとっては、敬服というよりも、恩義がまずあり、後は、幕末時に共に政局混乱終息に動いた数少ない同志としての思いが強いといえる。勝の方が重要な政局に当たったため、一翁の名は勝ほど知られていない。勝海舟や山岡鉄舟らと共に江戸幕府の無血開城に貢献した「江戸幕府の三本柱」といわれる。 |
 

 |
|
| 大高源吾 | 大高忠雄(おおたかただお・源五・源吾)寛文12年-元禄16年(1672-1703)赤穂浪士四十七士の一人。子葉という雅号を持ち、俳諧にも事績を残した。赤穂藩では、金奉行・膳番元方・腰物方、20石5人扶持。父は大高兵左衛門忠晴。母は小野寺十内の姉(貞立尼)。弟に小野寺幸右衛門秀富(小野寺十内養子。四十七士の一人)がいる。本姓は安倍氏。家紋は丸に三盛亀甲花菱。 |
| 大西滝治郎 | (1891-1945/8/16)旧日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。兵庫県氷上郡芦田村(青垣町を経て現在は丹波市)出身。海軍兵学校第40期生。「特攻生みの親」として有名ではあるが、これが事実であるかは議論の余地がある。 日本の敗戦を見とどけると、8月16日「特攻隊の英霊に曰す」で始まる遺書を遺して割腹自決。遺書には特攻で散華した兵士達への謝罪と共に、生き残った若者に対して軽挙妄動を慎み日本の復興、発展に尽くすよう諭している。自決に際しては敢えて介錯を付けず、また「生き残るようにしてくれるな」と医者の手当てを受ける事すら拒み、特攻隊員に詫びるために夜半から未明にかけて半日以上苦しんで死んだという。享年54。 |
| 大石内藏助 | 大石良雄(おおいしよしお/よしたか)万治2年-元禄16年(1659-1703)播磨国赤穂藩の筆頭家老。元禄赤穂事件で名を上げ、これを題材とした忠臣蔵で有名になった。内蔵助(くらのすけ・内藏助)は通称で、内蔵寮の次官のことである。諱は良雄。本姓は藤原氏。家紋は右二ツ巴。 |
| 萱野三平重実(涓泉) |
(かやのしげざね)延宝3年-元禄15年(1675-1702) 江戸時代前期の武士。赤穂藩浅野氏の家臣。通称三平(さんぺい)。討ち入り前に忠孝のはざまで自刃した赤穂藩士として有名。俳人としても知られ、俳号は涓泉(けんせん)。父は萱野重利。
旗本大島義也の家老萱野重利の三男。兄に萱野重通・萱野七之助(13歳で夭折)がいる。姉も二人、妹も一人いる。 萱野氏は源氏の子孫で、鎌倉時代から戦国時代にいたるまで摂津国萱野村(今の箕面市萱野)に領地を持つ豪族で、地名を姓として「萱野氏」を名乗っていた。江戸時代になり美濃国出身の旗本の大島氏に仕えることになり、その所領である椋橋(くらはし)荘(現豊中市大島町)の代官を勤めた。 重実が13歳の時、父の主人大島出羽守の推挙を受けて播磨国赤穂藩主浅野長矩に仕えた。大島家と浅野家は同じ山鹿素行の門下生であり、かねてより親しかったためである。元禄13年の赤穂藩の分限帳によると、重実は多儀清具(中小姓頭)支配下の中小姓(小姓とは別物。中小姓は武士の格のひとつ。赤穂藩では馬廻役のひとつ下の階級と位置づけられる)で、「金12両2分3人扶持」とある。 しかし元禄14年(1701年)3月14日、主君の浅野長矩が江戸城松之大廊下で吉良義央に刃傷に及んだ。重実は早水満尭と早駕籠で事件の第一報を赤穂へもたらした。江戸から赤穂まで普通の旅人なら17日、飛脚で8日かかるところを僅か4日で走破している。この道中、自らの母親小満の葬列に偶然にも出くわし、同行の早水満尭に「一目母御に会っていけ」と勧められるも、「御家の一大事」と涙ながらに振り切り、使いを続けた逸話がある。赤穂到着後、重実は大石良雄の義盟に加わる。 赤穂城開城後、郷里の摂津国萱野村へ戻ったが、父の重利から大島家へ仕官するよう強く勧められる。大島家は吉良家との繋がりの深い家柄であり、同志との義盟や旧主への忠義と父への孝行との間で板ばさみになった重実は、元禄15年(1702年)1月14日、主君の月命日を自分の最期の日と決め、京都の山科の大石良雄に遺書を書き、その中で同志と共に約束をはたせぬ罪を詫び、かつ同志の奮起を祈る心を述べ、自刃(切腹)した。享年28。今も重実の辞世の句碑が切腹した長屋門西部屋の横に残っている。 赤穂浪士の墓所のある泉岳寺には、重実のものとされる供養碑が立てられている。また、彼の実家である萱野三平旧邸の長屋門は国道171号(当時の西国街道)沿いに現存し、大阪府指定文化財となっている。 また、重実の墓は、箕面市民病院建設のために山中から千里川畔に移され、萱野三平旧邸の500mほど南に位置する萱野家の墓地内にある。 兄重通は重実の忠死を悼み、親族の萱野長好(重通や重実の姉の子)を重実の養子としてその名跡を継がせた。長好の死後は重通の庶子萱野重存をさらにその養子に入れて継がせている。 後年事件をもとに制作された『仮名手本忠臣蔵』では、早野勘平とされ、腰元のお軽と駆け落ちをし、最後は自害して果てる悲劇の人物として描かれている。なお、舟橋聖一作『新・忠臣蔵』やNHK大河ドラマ『元禄繚乱』では、兄の重通から、旧赤穂藩士らとの付き合いを咎められた上に折檻を受け、それを苦に自害するという筋になっている。 |
| 大前田英五郎 | 寛政5年-明治7年(1793-1874)江戸時代末期に活躍した侠客。栄五郎とも書く。本姓は田島。大場久八、丹波屋伝兵衛と並び「上州系三親分」とも、新門辰五郎、江戸屋寅五郎と共に「関東の三五郎」とも呼ばれて恐れられた。昭和期に好まれ、任侠ものの映画の題材とされた。 |
| 大谷吉継 | 永禄2年-慶長5年(1559-1600)戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名。越前敦賀城主。名前についてはては「吉隆」とも。業病(当時の認識)を患い、面体を白い頭巾で隠して戦った戦国武将として有名である。 輿に乗って指揮したと云われるが、関ヶ原に「西軍が先に着陣」した時に秀秋の裏切りを見抜いて居て史実の小早川隊の進軍経路の要所に「馬防柵」を築いたと云われる。自害した吉継の首は側近である湯浅五助の手により関ヶ原に埋められ、東軍側に発見されることはなかった。 辞世の句は「契りあらば 六の巷に まてしばし おくれ先立つ 事はありとも」で、これは戦闘中に訣別の挨拶として送られてきた平塚為広の辞世「名のために 棄つる命は 惜しからじ 終にとまらぬ浮世と思へば」への返句となっている。 |
| 大津皇子 | 天智天皇2年-朱鳥元年(663-686)天武天皇皇子。母は天智天皇皇女の大田皇女。同母姉に大来皇女。妃は天智天皇皇女の山辺皇女。 朱鳥元年(686)9月天武天皇が崩御すると、1ヶ月も経たない10月2日親友の川島皇子の密告により、謀反の意有りとされて捕えられ、翌日磐余(いわれ)にある訳語田(おさだ)の自邸で死を賜った。「日本書紀」には妃の山辺皇女が殉死したと記されている。「万葉集」の題詞には死の直前に姉である大来皇女が斎王を務めている伊勢神宮へ向かったとある。享年24。 |
| 大田南畝 |
(おおたなんぼ)寛延2年-文政6年(1749-1823)天明期を代表する文人・狂歌師。漢詩文、洒落本、狂詩、狂歌などをよくし、膨大な量の随筆を残した。名は覃(ふかし)。通称、直次郎、七左衛門。別号、蜀山人、玉川漁翁、石楠齋、杏花園。狂名、四方赤良。また狂詩には寝惚先生と称した。江戸の牛込生まれ。勘定所幕吏として支配勘定にまでのぼりつめたが、一方、余技で狂歌集や洒落本などを著した。唐衣橘洲(からころもきっしゅう)・朱楽菅江(あけらかんこう)と狂歌三大家と言われる。 天明7年(1787)に寛政の改革により、政治批判の部首「世の中に蚊ほどうるさきものはなしぶんぶといひて夜もねられず」を詠んだとされたことや、田沼意次の腹心だった土山宗次郎と親しかったことで目を付けられ、戯作者の山東京伝らが弾圧されるのを見たこともあって狂歌は止める。蜀山人はそれ以降の筆名。墓は小石川の本念寺(文京区白山)にある。 |
| 大島澄月 | 肥前平戸城主松浦隆信の家臣。永禄8年(1565)5月隆信の相の浦城攻撃に加わるが、殿軍となり敵の追撃を受けて戦死。 松浦隆信(まつらたかのぶ)享禄2年-慶長4年(1529-1599)肥前国の戦国大名。嵯峨源氏一流松浦氏25代当主。父は松浦興信。子に松浦鎮信、松浦親、後藤惟明、松浦信実。法名は印山道可。平戸松浦家出身。1541年に父の興信が死去したものの、しばらくは家中の混乱もあり家督を継承できず、1543年になってようやく家督を継いだ。1550年には南蛮貿易を開始して、鉄砲や大砲を購入。平戸城下に明の商人を住まわせるなどして、貿易による巨万の富を築き上げた。その財力を背景にして、松浦半島を制圧している。有馬氏や龍造寺氏などの近隣の強豪の脅威に備えながら、志佐氏や波多氏などを攻撃しつつ一族をまとめ、永禄年間には、長年対立してきた相神浦松浦家の松浦親をついに屈服させた。相神浦松浦家には有馬晴純の子の松浦盛が養子になっていたが、新たに平戸松浦家より隆信の子の親(養父と同名)が入り、親(養父の方)を隠居させて盛を他家(有田氏)に追いやることにより相神浦松浦家の平戸松浦家への従属は決定的となる。一方で武雄後藤氏の後藤貴明へ養子に送った惟明は龍造寺隆信の子の後藤家信により後藤家を追われた。 |
 

 |
|
| 大道寺政繁 | 天文2年-天正18年(1533-1590)小田原北條家臣。小田原征伐の後、自害させられる。孫九郎(幼名)政重(別名)。墓所は群馬県松井田町の補陀寺。 |
| 大内義長 | 天文元年-弘治3年(1532-1557)周防・長門国の戦国大名。周防大内氏の最後の当主。豊後大友氏の第20代当主・大友義鑑の次男として生まれる。天文12年(1544)実子の無い叔父の大内義隆の猶子として迎えられ、室町幕府第12代将軍・足利義晴から一字をもらって晴英と名乗る。弘治元年(1555)陶晴賢が毛利元就との厳島合戦で敗死すると、血縁があるとはいえ一度解消された経緯のある養子だった義長の求心力は低く、ただでさえ陶晴賢の謀反やその他の内訌で弱体化していた家臣団は完全に崩壊し、大内氏は急速に衰退していく。毛利元就の防長経略で弘治3年(1557)3月毛利軍は山口へ侵攻。義長は寡兵で良く防戦したが、結局は高嶺城を放棄して重臣内藤隆世の長門且山城へ敗走する。しかしすぐに毛利軍の福原貞俊により且山城を包囲され、隆世は義長の助命を条件に開城し、自刃した。しかし義長も長福院(現・功山寺)に入った後に毛利軍に囲まれて自刃を強要され、自害した。享年26。 |
| 大内義隆 |
永正4年-天文20年(1507-1551)周防の守護大名・戦国大名。周防大内氏の第31代当主。本姓は多々良氏。家系は百済聖明王の血をひく渡来氏族の系譜をひく周防国の在庁官人・大内氏。周防・長門・石見・豊前・筑前守護職。父は大内義興、母は義興の正室である内藤弘矩の女。正室は万里小路秀房の女・貞子。実子に大内義尊、問田亀鶴丸。養子に大内晴持、大内義長、尾崎局(毛利隆元正室)。幼名は亀童丸。官位は従二位兵部卿・大宰大弐・侍従。 大寧寺の変/険悪な関係にあった陶隆房(周防国守護代)は天文20年(1551)8月謀反の兵を挙げた。重臣の内藤興盛(長門国守護代)も黙認し、義隆を救援することはなかった。義隆は親族である津和野の吉見正頼を頼ろうとしたが、暴風雨のために逃れることができず、長門深川の大寧寺に逃亡し、そこに立て籠もった。このとき、義隆に従った重臣・冷泉隆豊の奮戦ぶりは目覚しかったが、多勢に無勢であり、義隆は隆豊の介錯で自害した。享年45。 義隆の実子の大内義尊も、9月2日陶軍の手によって殺害された。義隆・義尊の死により事実上、周防大内氏は滅亡した。なお、この時、周防に滞在していた太政大臣三条公頼をはじめとする多くの公家たちもこの謀反に巻き込まれ、殺害された。また、義隆の死を以って日明勘合貿易が断絶した。 |
| 大葉子 |
(おおばこ)(生没年不詳)上代日本の女性。調伊企儺(つきのいきな)の妻。 調伊企儺は、難波の人。応神天皇の代に弩理使主という者が百済から帰化し、その曾孫弥和は顕宗天皇の代に姓調首を賜わった。伊企儺は、その子孫で、号して調吉士。欽明天皇の代に新羅がまた背き、任那を亡ぼしたので、朝廷は紀男麻呂を将として問罪の師をおこし、伊企儺はこれの副将であった。妻大葉子とともに軍に従い、敗れ虜となった。 |
| 瀧沢馬琴 | 曲亭馬琴(きょくていばきん)明和4年-嘉永元年(1767-1848)江戸時代後期の読本作者。著作堂主人とも。本名は瀧澤興邦(たきざわおきくに)。筆名の曲亭馬琴は、読み方を変えると「くるわでまこと」(廓で誠)、すなわち遊廓でまじめに遊女に尽くしてしまう野暮な男という意味である。 |
| 沢庵和尚 | 澤庵宗彭(たくあんそうほう)天正元年-正保2年(1573-1646)江戸時代の臨済宗の名僧。大徳寺住持。諡は普光国師(300年忌にあたる1944年に宣下)。号に東海・暮翁など。但馬国出石(現兵庫県豊岡市出石町)の生まれ。紫衣事件で出羽国に流罪となり、その後赦されて江戸に萬松山東海寺を開いた。書画・詩文に通じ、茶の湯(茶道)にも親しみ、また多くの墨跡を残している。一般的に沢庵漬けの考案者と言われているが、これについては諸説ある。 全身を後の山にうずめて、只士をおおうて去れ。経を読むことなかれ。斎を設くることなかれ。道俗の弔賻(おくりもの)を受くることなかれ。衆僧、衣を着、飯を喫し、平日のごとくせよ。塔を建て、像を安置することなかれ。謚号を求むることなかれ。木牌を本山祖堂に納むることなかれ。年譜行状を作ることなかれ。 「遺戒」 |
|
天正元年-正保2年(1573-1646) 江戸前期の禅宗の名僧。号は沢庵、諱が宗彭(そうほう)。現・兵庫県豊岡市出身。父は出石(いずし)城主・山名祐豊(すけとよ)の重臣。1580年(7歳)、主君の山名家は織田軍・秀吉の攻撃で滅ぶ。1582年(9歳)、沢庵は出石にて出家。同年、本能寺の変が勃発。1594年(21歳)、師に従って上洛。新たに大徳寺三玄院で師事し宗彭と名乗る。さらに堺・南宗寺に学び、1604年(31歳)、印可を受け沢庵の号を授かる。1609年(36歳)、大徳寺の第154世住職に選ばれるが、沢庵は高い地位には興味を示さず、3日後に大徳寺を出て南宗寺に移った。1620年(47歳)、故郷に戻り宗鏡寺の庵に住む。 この時代、2代徳川秀忠は政権安定の為にも、僧侶が巨大な力を持つことを好まず、各地の有力寺院に弾圧政策をとっていた。1627年(54歳)、後水尾天皇が大徳寺&妙心寺の僧に紫衣(しえ=高僧に朝廷から与えられる法衣)を賜ったことを、幕府は「事前に届け出せずに行なった」と問題にする。朝廷に対する幕府の優位を明確にするため、そして紫衣勅許の乱発を防ぐため、幕府は認可した僧にしか紫衣着用を許さないという方針を決めていた。 1629年(56歳)、幕府の宗教界への圧力や紫衣の取り上げに抗議していた沢庵ら4名の高僧は流罪となり、沢庵は出羽国・上山(かみのやま)藩に預けられた。同年、後水尾天皇も譲位。「心さえ潔白なら身の苦しみなど何ともない」とする沢庵。配流先では名僧への敬意から藩主が春雨庵を寄進するなど厚いもてなしを受けた。 流刑3年目の1632年(59歳)、2代徳川秀忠が死去。大赦令が出され紫衣事件の関係者は許される。1634年(61歳)、故郷に帰るも3代徳川家光に懇願されて江戸に上る。家光は歯に衣を着せぬ沢庵の気骨に惚れ込んでいた。家光は周囲にイエスマン以外の相談役が欲しかったのだ。1638年、国師号を辞退。1639年(66歳)、家光は沢庵の為にわざわざ品川に東海寺を建て開山を依頼。沢庵は故郷に戻りたかったが、将軍自らの説得により引き受ける。2年後、かつての配流先の藩主が東海寺の中に春雨庵と同じ庵を建立して寄進。1646年、「夢」の一字を書き残し江戸にて他界。享年73歳。家光が沢庵のもとを訪れた回数は75回にも及び、そこからも沢庵の人間的魅力がよく分かる。幕府から剥奪された紫衣を最終的に奪還した。 沢庵は茶の湯や書画もよくし、剣禅一致を説いた著書「不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)」を剣豪・柳生宗矩に贈り、その思想は宮本武蔵にも影響を与えた。沢庵の「不動智神妙録」、柳生宗矩の「兵法家伝書」、宮本武蔵の「五輪書」は後の武道家の聖典となる。ちなみに沢庵死去の同年に宮本武蔵も他界しており、翌年に柳生宗矩が死去している。 漬物「沢庵」の考案者ともいわれるが、次のような話も伝わっている。沢庵漬けはそれまで“貯(たくわ)え漬”と呼ばれ、関西では保存食として親しまれていた。ある時、家光から“最近は何を食べても美味しくないので何か良いものがあれば食べさせてくれ”と言われた沢庵は、快諾して翌朝10時に訪問するよう答えた。翌日、家光を茶室に通した沢庵はそのまま姿を消し、午後3時を過ぎてやっと現れた。空腹で倒れそうな家光の前に出された食膳には、大根の漬け物2枚と、おかゆのみ。家光はガツガツとかき込み「これは旨い」と2杯目を所望した。腹が満たされた家光に向かって沢庵はこう言った「毎日高価な食材を食べて口が贅沢になっているので、これからは空腹になってから食事されますように」。家光は怒ることなく、その漬け物を“貯え漬”ではなく“沢庵漬”として江戸に普及させたという。 ■ 若き武蔵が京都大徳寺の大仙院で沢庵と戦って負けたいう話は、残念ながら吉川英治の創作とのこと。 ■ 墓巡礼記 かつては広大な面積を誇った東海寺。沢庵の墓は自らが住職を務めた東海寺の墓所にあるけれど、境内が今は小さくなっており、墓所はJRの線路を越え、本堂から200mほど離れた“飛び地”になっている。 沢庵の遺言がキョーレツで、宗教者としては空前絶後といっていい。 (1)自分の葬式をしてはならない (2)香典はいっさいもらってはならない (3)死骸は野外に埋めて二度と参ってはならない (4)墓は造るな (5)朝廷が名(禅師号)を与えようとしたら断れ (6)法事をしてはならない という実に驚くべきもの。達観しまくり!“墓を建てるな”との遺志だけど、徳の高い沢庵を偲ぶ人々は多く、残された人間の愛が墓を建立させた。東海寺の墓の上には楕円形の岩がドシンと乗せてあり、それがまるで漬物石そっくり。何ともユニークな墓だ。この他に、故郷である兵庫県豊岡市出石町の宗鏡寺にも墓がある。 |
|
 

 |
|
| 叩々老人 | (年代不明)駿河の国に叩々老人という者がいた。禅に興味を持ち、生涯を酒落に暮らしたが、あるとき子供が紙の幽霊を作って木に掛けて人を驚かしていたが、この老人、こんなものでは駄目だと白の浴衣を着て竹馬に乗って、夜中森林の前を徘徊した。時に侍がこれを見て、剣を抜いて切ろうとした。老人は竹馬から落ちてそのショックで腰の骨を挫いてしまい、それ以来病の床に伏せるようになって、遂に死亡した。 |
| 但木土佐 | (ただきとさ)文化14年-明治2年(1817-1869)幕末の仙台藩の奉行。本名は但木成行(ただきなりゆき)。但木氏は橘姓、遠祖は伊賀守重信に発し、下野足利群但木に8000石を領し郷名を氏とした。重信は初代「伊達朝宗」に仕えたなど諸説があり家歴は極めて古い。政宗時代に入り慶長から慶安年間まで58年間にわたり職を奉じた但木重久が有名であるが、その弟惣右衛門久清が別に家を建てることを許される。これが但木土佐の系である。正統の系は重久から行久へと続き、召出しとして繁栄する。土佐の系となる別系は久清を祖とし、世臣となる新しい系で、久清の子但木重信は元禄7年(1694)に若老、永代着座に列し、同8年に奉行職に栄進して1500石を領した。但木土佐は幕末における当主で、戊辰の危機に当たり奉行に挙げられて国政を執行し、軍事を総官した。土佐は前奉行の放漫財政の後始末をする為、倹約令を出し文久2年(1862)10万石の分限で藩を運営することを宣言する。土佐は、佐幕開国の保守主義を主張し、尊攘派と対立した。藩財政が破産同様となっていて、尊攘派が主張するような藩主自らが上洛して中央で活動できる状態でないことを土佐は知っていた。そして幕府の政権奉還の時には病の主君・伊達慶邦に代わり会議に与った。朝廷は仙台藩に会津討伐の挙兵を命ぜられた時、土佐は会津に謝罪させようとしたが果たせず、奥州鎮撫総督が東下して会津討伐を促したので、やむなく仙台藩は兵を動かした。やがて会津は降伏となり、藩主は総督・九条道孝の前に出て会津のために弁訴したが、参議・世良修蔵らはこれを許さぬばかりか、のちに奥羽一円を掃蕩する陰謀が世良の密書により発覚する。仙台藩強硬派はこれに激怒し、世良を捕縛して処刑し、同日、白河城を攻略。また、九条総督と醍醐参謀を捕らえて仙台城下に軟禁した。奥羽越列藩同盟を起こし、官軍に対して白河、相馬、越後諸道で徹底抗戦したが、まもなく三春、相馬、米沢諸藩は官軍に降り、仙台藩も撤兵した。藩主は遠藤允信らの議を受け入れて降伏。藩論一変することで、叛乱の責任者をなった土佐は縛につき、東京に拘禁される。明治2年叛逆首謀の罪で、土佐は坂英力と共に麻布仙台屋敷において斬刑に処された。享年53。 |
| 池田和泉守 | 有岡城落城/天正7年12初旬(1579)有岡城内で事件が起きます。城内の人質である荒木方の妻子らを警護するため残っていた池田和泉守が、子供の身を案じる句を残し、火縄銃で頭を撃ち抜き自害します。荒木村重を説得するために尼崎城に向かった荒木久左衛門らでしたが、村重は尼崎・花隈両城の明け渡しを拒否。荒木久左衛門らは、説得を断念しそのまま有岡城に戻らず出奔してしまいます(有岡城に戻り人質らと運命を共にしたともいわれています)。激怒した信長は、有岡城に残された荒木方の将兵の妻子らの処刑を命じます。 |
| 竹久夢二 | 明治17年-昭和9年(1884-1934)日本の画家・詩人。本名は竹久茂次郎(たけひさもじろう)。数多くの美人画を残しており、その作品は「夢二式美人」と呼ばれ、大正浪漫を代表する画家である。また児童雑誌や詩文の挿絵も描いた。文筆の分野でも詩、歌謡、童話など創作しており、なかでも詩「宵待草」には曲が付けられて大衆歌として受け、全国的な愛唱曲となった。また、多くの書籍の装幀、広告宣伝物、日用雑貨のほか、浴衣などのデザインも手がけており、日本の近代グラフィック・デザインの草分けのひとりとも言える。 |
| 中山信名 | (なかやまのぶな) -天保7年(1787-1836)江戸後期の国学者。常陸(ひたち)国久慈(くじ)郡石名坂(いしなざか)村(茨城県日立市)の医者坂本玄卜(げんぼく)の子。通称平四郎、のち甚四郎、号柳洲(りゅうしゅう)。享和2年(1802)16歳のとき江戸に出て、塙保己一(はなわほきいち)の門に入り「群書類従」編纂(へんさん)の校訂に力を尽くした。23歳のとき旗本中山有林(ゆうりん)の養子となり、書物御用出役(かきものごようでやく)から出役頭取(とうどり)に進む。保己一が和学講談所教授になったことにより、広く彼の名が世に出る。著書に「南巡逸史」「南山考」「氏族志料」「守護地頭(しゅごじとう)考」「常陸治乱記」「常陸編年」「新編常陸国誌」など歴史・地誌類を中心に多数あるが、「新編常陸国誌」は信名在世中完成せず、色川三中(いろかわみなか)、栗田寛(くりたかん)の修訂・増補を得て、約100年後に集大成された。 |
| 中野貫一 |
弘化3年-昭和3年(1846-1928)29年の歳月をかけて商業規模の油田を掘りあてました。米国より機械掘りを導入し、日本の石油王と呼ばれた。 中野家は、越後国蒲原郡金津村で代々庄屋を勤めていた大地主でありました。文化元年(1804)中野貫一翁の曾祖父、次郎左衛門が草生水油(石油)採掘権を買い取り「泉舎(イズミヤ)」を号し、また当時の「草生水油稼人」をも号するようになりました。中野貫一は14才にして父を亡くし、庄屋と「泉舎(イズミヤ)」を引き継ぐことになりました。明治6年「石油坑法」が公布されると直ちに新潟県庁に石油試掘を出願、許可を得て翌明治7年自分の所有地内に草生水場を開坑して若干の出油に成功することができました。その後明治19年まで停滞しましたが、塩谷地区で成功をおさめ、3600L/日の採油を得るに至りました。その成功もつかの間、明治19年共同油井が坑法違反として採掘禁止とされました。この塩谷事件は、同年6月3日新潟県知事篠崎五郎名で坑法違反を理由に塩谷区域の坑業禁止・油井および借区権没収の命令が出されたことに始まったのでした。中野貫一、九鬼義孝、眞柄富衛、鶴田熊次郎らは禁止の不当性を主張し、県・政府に請願運動を続けること5年に及んだが受け入れられなく、他の人が脱落するなか、中野貫一は一人これを不服として行政裁判所へ訴え、明治24年勝訴し賠償金35000円を得ることができました。その間、中野貫一は、明治21年の日本石油の創立にも、発起人として参画していました。 最初の試掘から29年目の明治36年(1903)初めての商業規模の油田を掘り当て金津鉱場開発の端を開いたのでした。当時の二大石油会社であった日本石油及び宝田石油に次ぐ大産油業者に成長、明治、大正時代に「石油王」と呼ばれるに至ったのでした。このあと中野貫一は、朝日、柄目木、天ケ沢と事業を拡大し、明治43年頃には日産2361KLを産出していました。さらに、秋田県や北樺太の石油開発にも手を広げることになりました。 大正7年に100万円の資金で中野財団を設立し、教育や社会福祉事業を始めました。旧金津小学校講堂は中野貫一が寄付した金津尋常小学校の施設です。このほかに近隣の小学校にも寄付を行っていました。また、金津掘出神社は中野貫一が金津村内に12社まつってあったのを現在の1社にまとめたもので、現在でも庭園が名残をとどめています。 明治39年には金津村の村長に就任することになりました。しかし、明治42年に原油のため池が決壊し、水田に油が流失した責任を取って村長を辞職し、鉱業会の会長も辞任することになりました。 明治39年に中央石油(株)を設立し、社長となり、明治42年中野合資会社を組織しました。これは、大正3年中野興業株式会社に改められ、石油、林業、土地開発等の事業を手掛けるようになりました。石油だけでなく、農地の開墾、教育への還元など常に自分の出身地のことに責任を持った人であったと言えます。そして中野貫一は終生金津を離れませんでした。これは、日本石油、宝田石油が本社を大都市に移転させたことと対照的でした。もともと地主であるということもその要因として考えられるますが、むしろそれより一郷村に過ぎなかった金津のことを常に思いを巡らせ、それとの石油事業との共存を考慮していたのではないかと考えられます。現在でも亡き中野貫一のことを「中野様」と呼ぶ人が見られるが、それほどに社会や地域に対する貢献が大きかったと思います。 中野貫一は、昭和3年(1928)に死去。中央石油は既に大正9年に日本石油に買収されており、中野興業もその後、昭和17年帝国石油に合併されました。 |
| 中野竹子 | 嘉永3年-明治元年(1850-1868)娘子軍の隊長。会津藩士・江戸詰勘定役中野平内の長女で江戸に生れ、薙刀と学問を修める。戊辰戦争がおこると郷里に帰り、母孝子、妹優子とともに坂下で児童に読み書き、薙刀などを教えていた。新政府軍が城下に迫ると、出陣の許可を得て母や妹ともに柳橋の戦場に出撃。敵弾に倒れ、妹の手により介錯され果てた。墓は坂下の法界寺にある。 |
| 朝倉義景 |
天文2年-天正元年(1533-1573)戦国時代の武将。越前の戦国大名。越前朝倉氏第11代(最後)の当主。 天正元年(1573)8月8日信長は3万を号する大軍を率いて近江に侵攻する。これに対して義景も朝倉全軍を率いて出陣しようとするが、数々の失態を犯し重ねてきた義景はすでに家臣の信頼を失いつつあり、「疲労で出陣できない」として朝倉家の重臣である朝倉景鏡、魚住景固らが義景の出陣命令を拒否する。このため、義景は山崎吉家、河井宗清らを招集し、2万の軍勢を率いて出陣した。 8月12日信長は暴風雨を利用して自ら朝倉方の砦である大嶽砦を攻める。信長の電撃的な奇襲により、朝倉軍は大敗して砦から追われてしまう。8月13日丁野山砦が陥落し、義景は長政と連携を取り合うことが不可能になってしまった。このため、義景は越前への撤兵を決断する。ところが信長は義景の撤退を予測していたため、朝倉軍は信長自らが率いる織田軍の追撃を受けることになる。この田部山の戦いで朝倉軍は大敗し、柳瀬に逃走した。 信長の追撃は厳しく、朝倉軍は撤退途中の刀根坂において織田軍に追いつかれ、壊滅的な被害を受けてしまう。義景自身は命からがら疋壇城に逃げ込んだが、この戦いで斎藤龍興、山崎吉家、山崎吉延ら有力武将の多くが戦死してしまった。 義景は疋壇城から逃走して一乗谷を目指したが、この間にも将兵の逃亡が相次ぎ、残ったのは鳥居景近や高橋景業ら10人程度の側近のみとなってしまう。8月15日義景は一乗谷に帰還した。ところが朝倉軍の壊滅を知って、一乗谷の留守を守っていた将兵の大半は逃走してしまっていた。義景が出陣命令を出しても、朝倉景鏡以外には出陣してさえ来なかった。8月16日義景は景鏡の勧めに従って一乗谷を放棄し、東雲寺に逃れた。8月17日平泉寺に援軍を要請する。しかし信長の調略を受けていた平泉寺は義景の要請に応じるどころか、東雲寺を逆に襲う始末であり、義景は8月19日賢松寺に逃れた。一方、8月18日信長率いる織田軍は柴田勝家を先鋒として一乗谷に攻め込み、手当たり次第に放火した。この猛火は、三日三晩続き、これにより朝倉家100年の栄華は灰燼と帰したのである。 従兄弟の朝倉景鏡の勧めで賢松寺に逃れていた義景であったが、8月20日早朝、その景鏡が織田信長と通じて裏切り、賢松寺を襲撃する。ここに至って義景は遂に壮烈な自害を遂げた。享年41。死後、高徳院や小少将、愛王丸ら朝倉一族も信長によって全て虐殺され、かくして朝倉家は完全に滅亡した。義景の首は信長によって、京都で獄門に曝された。 その後、浅井久政・浅井長政共々髑髏に箔濃(はくだみ)を施され、信長が家臣に披露したというのは事実であるが、杯にして酒を飲ませたというのは作り話である。 |
 

 |
|
| 長野業盛 | (ながのなりもり)天文15年-永禄9年(1546-1566)戦国時代の武将。上野長野氏。長野業正の子、母は保戸田氏。幼名は松代。通称・新五郎、左衛門大夫、左京亮、右京進、信濃守、弾正忠。子に極楽院鎮良。 |
| 鳥居強右衛門勝商 | (とりいすねえもん)天文9年-天正3年(1540-1575)戦国時代の足軽。奥平信昌(当時は奥平貞昌。後に織田信長から「信」の一字を拝領して改名)の家臣。名は勝商(かつあき)。 |
| 弟橘比売 | 弟橘媛/乙橘媛(おとたちばなひめ)日本神話に登場するヤマトタケルの后。弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)大橘比売命(おおたちばなひめのみこと)橘皇后(たちばなのおおきさき)「古事記」では弟橘姫とも言う。彼女の事跡は日本書紀の景行紀、および古事記の中巻、常陸国風土記に記されている。 |
| 天狗小僧霧太郎 | 都鳥廓白浪(みやこどりながれのしらなみ) 「都鳥廓白浪」は、所謂隅田川物と呼ばれる歌舞伎の一つで、謡曲「隅田川」の松若伝説、近松門左衛門が書いた浄瑠璃「雙生隅田川」を基にして書かれた作品である。吉田家のお家騒動、松若と梅若の兄弟、忍ぶの惣太、遊女花子らは、多くの先行作で使われてきた素材だ。 先ずは惣太が梅若丸を介抱して、その胸を擦る場面に始まる。少年梅若丸の儚げな様子に観客の感性覚醒し、惣太の男の色気に陶酔する。そして、遊女花子の登場に、観客の期待は胸を裂かんばかりに膨らむのだ。その遊女花子が、実は盗賊の首領天狗霧太郎であるという驚き、更に実は松若丸であったという混乱は、舞台を楽しむしかないという気にさせる。 さて、吉田家の嫡子松若丸は、如何なる少年だったのか。父親が政治的に陥れられて失脚した上殺害され、お預かりの重宝も奪われ、お家は断絶となった。この混乱の最中、盗賊となって重宝の行方を追い、尚且つ遊女に身をやつすことで当局からの保身を図る。 歌舞伎において、女装は通常とは異なった意味を持つ。元々歌舞伎役者は全て男性なので、舞台に登場する女性は女装した男性ということになる。男性である登場人物が女装している場合を、どのように区別するのかは難しいが、つまりは役者がどういうつもりで演じているかが最も重要なのである。 「都鳥廓白浪」では、二幕目に遊女花子として登場した松若丸は、惣太との恋の絡みに、観客をうっとりさせる。三幕目では、松若丸は天狗小僧霧太郎としての正体を現すが、姿は花子のまま、声だけが男の発声になることで霧太郎を表現する。丑市に、霧太郎が花子の姿のままなので、妙な気持ちになると指摘されると、松若丸は女の発声に戻って、丑市が混乱するのを楽しんでみせる。ここで言う女の発声、花子の声というのは、歌舞伎役者の女形の発声であって、本来の女の発声とは大きく異なっている。同時に、花子は松若丸という少年なのであるから、本来の女の発声とは違っていることは、物語の構成上正しいという認識も成り立つわけだから、丑市が妙に感じる発声は、むしろお梶やお市に対して観客が感じるはずの不自然さなのだ。 観客は、丑市の混乱を、自身の混乱として体験する。丑市は霧太郎の女装を結果的に楽しんでいるが、観客はそうではない。丑市が酔って寝入った後、姉さん被りをした手拭を取り、天狗霧太郎/松若丸の姿に戻る場面を、観客は最も興奮する瞬間として心待ちにしているのである。 大詰/原庭按摩宿の場 花子こと松若は系図を奪おうとする丑右衛門を殺し、系図を手に入れた上からは早速立ち退こうとする。ところに惣太が現れ両者立ち回りとなる。惣太はわざと松若の手にかかり、梅若殺しを懺悔して息絶える。そこへ捕り手がなだれ込むが松若は悠々と飯を食べて捕り手をあしらう。 |
| 田中河内介 | 文化12年-文久2年(1815-1862)出石藩にあって井上静軒に、ついで天保11年京都に出て山本亡羊に学び、14年中山家諸大夫田中綏長の養子となり、同家諸大夫を勤め、弘化2年従六位下に叙せられ、河内介に任ぜられた。嘉永3年以降、国事に関して忠能に種々の献策をし、一方では攘夷を策して志士との交わりを深めたが、次第に忠能と疎隔するに至り、文久元年主家に難が及ぶのを避けることを理由に職を辞し官位を返上した。この間とくに西国の志士と通じ、遊説すること三度、平野国臣・松村大成らと交誼を結ぶ。翌2年柴山愛次郎・清河八郎らと義挙を企て、島津久光の上京を迎えて決行せんとしたが、久光は志士の暴発を抑えようと計った。その結果寺田屋の変となり、河内介らの計画は頓挫し、海路鹿児島に護送される途中、5月1日播磨灘で子の瑳磨介と共に斬殺され、死体は翌日讃岐小豆島に漂着した。 |
| 土肥原堅二 | 明治16年-昭和23年(1883-1948)大日本帝国陸軍大将。謀略部門のトップとして満州国建国及び華北分離工作で暗躍。極東国際軍事裁判(東京裁判)でA級戦犯となり死刑判決を受ける。1978年に靖国神社に合祀される。 |
 

 |
|
| 土方歳三 |
天保6年-明治2年(1835-1869)新選組副長、蝦夷共和国陸軍奉行並箱館市中取締裁判局頭取。諱は義豊。雅号は豊玉。幕末期の幕臣。新選組鬼の副長として皆に恐れられた。戊辰戦争では幕府側指揮官の一人として図抜けた軍才を発揮している。家紋は左三つ巴。 函館戦争/土方歳三最期の地碑10月20日、蝦夷地鷲の木に上陸後、歳三は間道軍総督となり五稜郭へ向かった。新選組は大鳥圭介総督の下本道を進んだが、歳三には島田魁ら数名の新選組隊士が常に従っていたと言う。箱館・五稜郭を占領後、歳三は額兵隊などを率いて松前へ進軍し松前城(福山城)を陥落させ、残兵を江差まで追撃した。この時、榎本武揚は土方軍を海から援護するため、開陽丸で江差沖へ向かったが、暴風雨に遭い座礁。江差に上陸して開陽丸の沈没していく姿を見守っていた榎本と歳三は、そばにあった松を叩いて嘆き合ったと言われ、今でもその「嘆きの松」が残っている。江差を無事占領した歳三は、一度松前城へ戻り、12月15日榎本が各国領事を招待して催した蝦夷地平定祝賀会に合わせて五稜郭へ凱旋した。その後、幹部を決定する選挙が行われ、榎本を総裁とする蝦夷共和国(五稜郭が本陣)が成立、歳三は幹部として陸軍奉行並となり、箱館市中取締や陸海軍裁判局頭取も兼ねた。箱館の地でも歳三は冷静だったと言う。箱館政府が樹立され、榎本らが祝杯を交わしている時も歳三は1人沈黙を保ち、「今は騒ぎ浮かれる時ではない」と言っていたと伝わる。1月から2月にかけては箱館・五稜郭の整備にあたり、3月には新政府軍襲来の情報が入ったため、歳三は新政府軍の甲鉄艦奪取を目的とした宮古湾海戦に参加、作戦は失敗し多数の死傷者が出るも、歳三は生還する。 明治2年4月9日新政府軍が蝦夷地乙部に上陸を開始。歳三は、二股口の戦いで新政府軍の進撃に対し徹底防戦する。その戦闘中に新政府軍は鈴の音を鳴らし、包囲したと思わせる行動をとり、自軍が包囲されたと思った土方軍は動揺した。これに対し歳三は「本当に包囲しようとするなら、音を隠し気づかれないようにする。」と冷静に状況を判断し、部下を落ち着かせた。また、戦いの合間に歳三は部下達に自ら酒を振舞って廻った。そして「酔って軍律を乱してもらっては困るので皆一杯だけだ」と言ったので、部下は笑って了承したと言う。土方軍が死守していた二股口は連戦連勝。しかし、もう一方の松前口が破られて退路が絶たれる危険が起こったため、やむなく二股口を退却、五稜郭へ帰還した。 そして明治2年5月11日(旧暦)新政府軍の箱館総攻撃が開始され、新選組隊士島田魁らが守備していた弁天台場が新政府軍に包囲され孤立したため、歳三は籠城戦を嫌って僅かな兵を率いて出陣。新政府軍艦朝陽が味方の軍艦によって撃沈されたのを見て「この機会を逃すな!」と大喝、箱館一本木関門にて陸軍奉行添役大野右仲に命じて敗走してくる仲間を率いて進軍させ、「我この柵にありて、退く者を斬る!」と発した。歳三は一本木関門を守備し、七重浜より攻め来る新政府軍に応戦、馬上で指揮を執った。その乱戦の中、銃弾に腹部を貫かれて落馬、側近が急いで駆けつけた時にはもう絶命していたと言う。歳三の命によって台場方面に進軍していた大野率いる兵士らは一時勢力を盛り返していたが、突然乱れて大野の必死の指揮にも関わらず総崩れとなった。大野がやむを得ず引き返したところ、同じく陸軍奉行添役の安富才助から歳三の戦死を知らされたと言う。歳三の遺体は小芝長之助らに引き取られて、他の戦死者と共に五稜郭に埋葬されたとも、別の場所に安置されていたとも言われる。享年35。 |
| 島津義久 | 天文2年-慶長16年(1533-1611)戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。薩摩の守護大名・戦国大名。島津氏の第16代当主。戦国最強とも称される島津軍団を使いこなし、九州を制覇した名将である。家系は源頼朝の長庶子ともいわれる忠久を祖とする島津氏。島津氏の第16代当主。室町幕府の薩摩守護職・大隅守護職・日向守護職。第15代当主・島津貴久の嫡男として伊作城に生まれ、幼名は虎寿丸と名づけられた。通称は又三郎。元服して忠良。後に第13代将軍・足利義輝からの偏諱を受け、義辰、後に義久と改名した。慶長5年(1600)関ヶ原の戦いにおいては京都にいた義弘は西軍に加担することになる。この間、再三義弘は国元に援軍を要請するが、義久も忠恒も動かなかった。戦後、西軍への荷担は義弘が行ったもので、義久はあずかり知らぬ事であったとして、講和交渉を開始する。家康に謝罪するため忠恒が上洛しようとするが、義久は「上洛は忠孝に欠けた行い」と反対している。忠恒は義久や義久の家臣の反対を振り切って上洛した。義久は忠恒の上洛を追認し「病のために上洛できないため、代わりに忠恒が上洛する」と書状を送っている。結果的に島津家は改易を免れ、本領安堵の沙汰が下った。 |
| 島津義弘 | 天文4年-元和5年(1535-1619)戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。九州の南端、薩摩国の戦国大名。島津氏の第17代目当主。16代当主島津義久の弟であり、義久の補佐役を務め、戦国期における島津の版図拡大に大きく貢献した。木崎原の戦いにおいて日向国の大名伊東義祐率いる3000の兵に対し300の寡兵で奇襲しこれを打ち破り、伊東家をその後の滅亡へと導いた。朝鮮の役(文禄・慶長の役)では日本側の記録によれば「鬼石曼子(グイシーマンズ)」として朝鮮・明軍から恐れられていたことで知られている(現存する朝鮮側資料に「鬼」を冠した記載は見つかっていない)。慶長の役の泗川の戦いでは、朝鮮半島南岸の泗川城に攻め寄せた明・朝鮮軍を寡兵を持って大いに打ち破った。秀吉の死によって日本軍が朝鮮半島より総退却となった際に起こった露梁海戦では朝鮮水軍の主将李舜臣を討ち取っている。関ヶ原の戦いでは西軍に属し敗戦となったが、退却戦においてまたもや寡兵で東軍側に突撃し徳川家康の本陣近くを通過、敵中突破を果たして退却することに成功し、この退却戦は「島津の退き口」と呼ばれ、全国に名を轟かせた。 |
| 島木赤彦 | 明治9年-大正15年(1876-1926)明治・大正時代のアララギ派歌人。本名は久保田俊彦。別号、柿乃村人。長野県諏訪郡上諏訪村角間(現諏訪市元町)に生まれる。長野県尋常師範学校(現信州大学教育学部)を卒業し、教職の傍ら短歌を作る。正岡子規の歌集に魅せられ、伊藤左千夫に師事。明治36年「氷牟呂」を創刊。左千夫の死後、大正4年齋藤茂吉に代わって短歌雑誌「アララギ」編集兼発行人となる。写生短歌を追求し赤彦独特の歌風を確立。アララギ派の歌壇での主流的基盤構築に貢献した。大正15年胃癌のため死去。戒名は俊明院道誉浄行赤彦居士。 |
| 東郷茂徳 | (とうごうしげのり)明治15年-昭和25年(1882-1950)日本の外交官、政治家。太平洋戦争開戦時及び終戦時の日本の外務大臣。欧亜局長や駐ドイツ大使及び駐ソ連大使を歴任、東條内閣で外務大臣兼拓務大臣として入閣して日米交渉にあたるが、日米開戦を回避できなかった。鈴木貫太郎内閣で外務大臣兼大東亜大臣として入閣、終戦工作に尽力した。にもかかわらず戦後、開戦時の外相であったがために戦争責任を問われ、A級戦犯として極東国際軍事裁判で禁錮20年の判決を受け、巣鴨拘置所に服役中に病没した。東郷は剛直で責任感が強く、平和主義者である一方で現実的な視野を併せ持った合理主義者であったが、正念場において内外情勢の急転に巻き込まれて苦慮するケースが多かったと言える(ノモンハン事件の解決などで軍部から高く評価される一方で、開戦終戦を巡るやりとりでは吉田茂らいわゆる「和平派」から批判を浴びている)。 |
| 東条英機 | 明治17年-昭和23年(1884-1948)日本の陸軍軍人、政治家。現役軍人のまま第40代内閣総理大臣に就任した(在任期間は昭和16年-19年)。階級位階勲等功級は陸軍大将・従二位・勲一等・功二級。永田鉄山の死後、統制派の第一人者として陸軍を主導する。日本の対米英開戦時の内閣総理大臣。また権力の強化を志向し複数の大臣を兼任し、慣例を破って陸軍大臣と参謀総長を兼任した。敗戦後に連合国によって行われた東京裁判にてA級戦犯とされ、処刑された。その高い事務処理能力から「カミソリ東條」とあだ名された。 |
 

 |
|
| 陶晴賢 | (すえはるかた)大永元年-弘治元年(1521-1555)戦国時代の武将で、周防大内氏の重臣。周防守護代。周防国富田若山城主。本姓は多々良氏。家系は大内氏の庶家・右田氏の分家にあたる。初名は隆房(たかふさ)で、晴賢と名乗ったのは1551年に大内義隆を殺害した後に、大友晴英(後の大内義長)を当主に据えて後、厳島の戦い前に出家するまでの数年間だけである。 |
| 道元 | 正治2年-建長5年(1200-1253)鎌倉時代初期の禅僧。日本曹洞宗の開祖。晩年に希玄という異称も用いた。同宗旨では高祖と尊称される。諡号は、仏性伝東国師、承陽大師。一般には道元禅師と呼ばれる。徒に見性を追い求めず、座禅している姿そのものが仏であり、修行の中に悟りがあるという修証一等、只管打坐の禅を伝えた。主著正法眼蔵はハイデッガーなど西欧の現代哲学者からも注目を集めた。 この生死は即ち仏の御命なり。これをいとい捨てんとすれば、即ち仏の御命を失わんとするなり。これにとどまりて、生死に着ずれば、これも仏の御命を失うなり。仏のありさまをとどむるなり 「正法眼蔵(生死)」 道元 曹洞宗開祖 . |
| 徳川家康 | 天文11年-元和2年(1543-1616)日本の戦国武将・江戸幕府の初代征夷大将軍。徳川氏の祖。本姓は当初藤原氏、次いで源氏と名乗った。家系は三河国の国人土豪・松平氏。永禄9年勅許を得て徳川氏に改姓。通称は次郎三郎。幼名は竹千代。応仁の乱以降100年以上続いた戦乱に終止符を打ち、織田信長、豊臣秀吉により統一された天下を更に磐石のものとし、264年間続いた江戸幕府を開府し、その礎を築いた。日光東照宮・久能山東照宮などで「東照大権現」(とうしょうだいごんげん)として祀られている。戦国時代に、三河国・岡崎に岡崎城主・松平広忠の子として出生。幼名は竹千代。当時の松平氏は弱小であり、広忠は臣従していた今川氏に竹千代を人質として差し出す事となった。一時、家臣の裏切りにより織田氏の人質となるが、最終的には当初の予定通り今川氏に送られた。今川氏の元で人質として忍従の日々を過ごすが、桶狭間の戦いにおいて今川義元が討たれた後、今川氏の混乱に乗じて独立し、織田信長の盟友(事実上は客将)として版図を広げていく事となる。やがて、本能寺の変において信長が明智光秀に討たれると、その混乱に乗じさらに勢力を広げた。豊臣秀吉との小牧・長久手の戦いを経て豊臣氏に臣従。秀吉の元で、家康は最大の領地を得る事となり、豊臣政権の五大老筆頭となる。秀吉の死後、関ヶ原の戦いに勝利し、天皇から征夷大将軍に任ぜられ、江戸に幕府(江戸幕府・徳川幕府と呼ぶ)を開いた。死後、江戸時代を通じて、御家人・旗本には「神君」「東照宮」、一般には「権現(様)」(ごんげん-さま)と呼ばれた。 |
| 細川幽斎 |
[
変わらない悠久の時の流れの中に、和歌は言葉によって心の種を残していくものです。そのように私の歌と心も残るならば有難いことです。]
(天文三〜慶長一五 1534-1610) 号:玄旨 本名藤孝。三淵伊賀守晴員の次男(実父は将軍足利義晴という)。母は清原宣賢の娘。忠興の父。七歳の時、伯父細川常元の養子となり、足利将軍家に仕える。永禄八年(1565)、将軍義輝が三好党に攻められて自殺した後、奈良興福寺に幽閉されていた義輝の遺児覚慶(のちの義昭)を救出し、近江へ逃れる。その後、義昭を将軍に擁立した織田信長の勢力下に入り、明智光秀とともに丹波・丹後の攻略などに参加。これらの功により、信長から丹後を与えられた。光秀とは親しく、縁戚関係にあったが、天正十年(1582)本能寺の変に際しては剃髪して信長への追悼の意を表した。その後豊臣秀吉に迎えられ、武将として小田原征伐などに従う一方、千利休らとともに側近の文人として寵遇された。慶長五年(1600)、丹後田辺城にあった時、城を石田三成の軍に囲まれたが、古今伝授の唯一の継承者であった幽斎の死を惜しんだ後陽成天皇の勅により、難を逃れた。徳川家康のもとでも優遇され、亀山城に隠棲。晩年は京都に閑居した。熊本細川藩の祖である。剣術・茶道ほか武芸百般に精通した大教養人であった。歌は三条西実枝に学び、古今伝授を受け、二条派正統を継承した。門人には智仁親王・烏丸光広・中院通勝などがいる。また松永貞徳・木下長嘯子らも幽斎の指導を受けた。後人の編纂になる家集『衆妙集』がある。『詠歌大概抄』『古今和歌集聞書』『百人一首抄』などの歌書のほか、『九州道の記』『東国陣道の記』など多くの著書を残す。 |
| 内藤信順 | (ないとうのぶより)幕末会津の人、通称介右衛門。隠居して可隠と号した。内藤家6代目信思の長男として生まれ、信思が若くして亡くなった為、七代目を継いだ叔父の信全の養子となった。家老職につくが、38歳で辞職する。戊辰戦争の際、菩提寺にて一族13人が自刃している。 |
| 楠木正季 |
(くすのきまさすえ)
生誕不詳-延元元年/建武3年(1336) 鎌倉時代後期から南北朝時代の武将。悪党として知られる河内国の豪族・楠木正成の弟。1336年(建武7年/延元元年)に兄の正成は九州から京都目指す足利尊氏の軍に対して新田義貞の指揮下で戦う事を命じられ、湊川の戦い(兵庫県神戸市)において戦って敗北する。「太平記」などには兄・正成と刺し違えて自害したと記され、このとき有名な「七生報国」(七たび生まれ変わっても、朝敵を滅ぼし、国に報いるの意)を誓っているが、一部ではこれが正成の発した言葉と誤解されている。また、腹を切って割腹自殺したという話もある。 楠木正成(くすのきまさしげ) 永仁2年?-延元元年/建武3年(1294?-1336) 鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将。鎌倉幕府からは悪党と呼ばれた。建武の新政の立役者として足利尊氏らと共に活躍。尊氏の反抗後は新政側の軍の一翼を担い、湊川の戦いで尊氏の軍に破れて自害した。明治以降は「大楠公(だいなんこう)」と称され、1880年には正一位を追贈された。 |
| 楠木正行 |
(くすのきまさつら)不詳-正平3年/貞和4年(1348)南北朝時代の武将。楠木正成の嫡男。「大楠公」と尊称された父の正成に対して小楠公(しょうなんこう)と呼ばれる。前名は正之(まさより・まさこれ)と伝わる。 「太平記」に父との「桜井の別れ」の当時は11歳であったとあることから1326年とも推測されているが、これは多くの史家が疑問視している。楠木正成の長男として河内国に生まれた。幼名は「多聞丸」。幼少の時、河内往生院などで学び、武芸を身に付けた。延元元年/建武3年(1336)湊川の戦いで父の正成が戦死した後、覚悟していたこととはいえ、父・正成の首級が届き、衝撃のあまり仏間に入り父の形見の菊水の短刀で自刃しようとしたが、生母に諭され改心したという。正行は亡父の遺志を継いで、楠木家の棟梁となって南朝方として戦った。正成の嫡男だけあって、南朝から期待されていたという。足利幕府の山名時氏・細川顕氏連合軍を摂津国天王寺・住吉浜にて打ち破っている。 正平3年/貞和4年(1348)河内国北條(現在の大阪府四條畷市)で行われた四條畷の戦い(四條縄手)において足利方の高師直・師泰兄弟と戦って敗北し、弟の楠木正時と刺し違えて自害した。先に住吉浜にて足利方を打ち破った際に、敗走して摂津国・渡部橋に溺れる敵兵を助け、手当をし衣服を与えて敵陣へ送り帰した。この事に恩を感じ、この合戦で楠木勢として参戦した者が多かったと伝えられている。 かねてより死を覚悟しており、後村上天皇よりの弁内侍賜嫁を辞退している。そのとき詠んだ歌が「とても世に 永らうべくもあらう身の 仮のちぎりを いかで結ばん」である。 この合戦に赴く際、辞世の句(後述)を吉野の如意輪寺の門扉に矢じりで彫ったことも有名である。決戦を前に、正行は弟正時・和田賢秀ら一族を率いて吉野行宮に参内、後村上天皇より「朕汝を以て股肱とす。慎んで命を全うすべし」との仰せを頂いた。しかし決死の覚悟は強く、参内後に後醍醐天皇の御廟に参り、その時決死の覚悟の一族・郎党143名の名前を如意輪堂の壁板を過去帳に見立てその名を記して、その奥に辞世(「かへらじと かねて思へば梓弓 なき数にいる 名をぞとどむる」)を書き付け自らの遺髪を奉納したという。地の利を失っては勝ち目が薄い。家督は三男の正儀が継いだ。 |
 

 |
|
| 日野俊基 | 生年不詳-元弘2年/正慶元年( -1332)鎌倉時代末期の公家である。父は日野種範。文保2年(1318)即位した後醍醐天皇の親政に参加し、蔵人となる。後醍醐の朱子学(宋学)志向に影響を受け、鎌倉幕府討幕のための謀議に加わる。諸国を巡り反幕府勢力を募るが六波羅探題に察知され、正中元年(1324)の正中の変で日野資朝らと逮捕されるが処罰は逃れる。京都へ戻るが、元徳3年/元弘元年(1331)発覚した2度めの討幕計画である元弘の変で再び捕らえられ、鎌倉の葛原岡で処刑された。明治維新後、南朝(吉野朝廷)が正統とされると俊基は倒幕の功労者として評価されるようになり、明治20年俊基を主祭神とする葛原岡神社が神奈川県鎌倉市梶原に創建され、俊基自身にも従三位が追贈された。 |
| 乃木希典 | 嘉永2年-大正元年(1849-1912/9/13)日本の武士(長府藩士)、軍人。陸軍大将従二位勲一等功一級伯爵。第10代学習院院長。贈正二位(1916)。家紋は「市松四つ目結い」。「乃木大将」「乃木将軍」などの呼称で呼ばれることも多い。東郷平八郎とともに日露戦争の英雄とされ「聖将」と呼ばれた。若い頃は放蕩の限りを尽くしたが、ドイツ帝国留学において質実剛健な普魯西(プロイセン)軍人に感化され、帰国後は質素な古武士のような生活を旨とするようになったという。乃木は他の将官と違い省部経験・政治経験がほとんどなく、軍人としての生涯の多くを司令官として過した。また、明治天皇の後を追った乃木夫妻の殉死は、当時の日本国民に多大な衝撃を与えた。山口県、栃木県、東京都、北海道など、複数の地に乃木を祀った乃木神社がある。また、幾つかの文献で元帥となっている場合があるが、乃木が元帥だった事実は無い(元帥の称号を賜る話があったが、乃木本人が固辞したため)。 |
| 乃木静子 | 安政6年鹿児島藩医・湯地定之・貞子夫妻の4女(7人兄弟姉妹の末っ子)として出生。幼名はお七、またはお志知。明治5年当時、数え14歳の時に海外留学から帰国した長兄・定基に呼び寄せられる形で家族揃って東亰赤坂溜池2番地の湯地定基邸に転居、東亰府麹町區にある麹町女學校に入学する。麹町女學校は明治初期に創立され、明治中期に廃学になったため現存しない。陸軍軍人・伊地知幸介や野津鎮雄らの勧めにより、数え20歳で希典と結婚。 明治45年7月明治天皇が糖尿病により逝去、その後の大正元年9月13日明治天皇を追って希典と共に乃木邸(現在の東京・港区赤坂にある乃木神社)にて胸を突き殉死。享年54。 |
| 波多野秀治 | (はたのひではる)天文10年-天正7年(1541-1579)丹波の戦国大名。波多野氏最後の当主である。天文10年(1541)波多野晴通の子として生まれる。晴通は波多野氏本家の当主であり、秀治はその後を相続したはずと考えられるのだが、なぜか一族の伯父である波多野元秀の養子となった上で家督を継いでいる。波多野氏は秀治の祖父・波多野稙通の死後から三好長慶に服属していたため、秀治は最初は三好氏の家臣であった。そのためか、正親町天皇の即位式のときには列席していた。だが、長慶死後の永禄8年(1566)秀治は居城の八上城を奪還し、戦国大名として独立した。また、播磨の別所長治を娘婿として同盟を結んでいる。永禄10年(1568)織田信長が足利義昭を奉じて上洛してくると、信長の家臣となった。天正2年(1575)信長が派遣してきた明智光秀の軍勢に加わって丹波で織田氏に反抗する豪族の討伐を担当したが、天正3年(1576)1月に突如として叛旗を翻し、光秀の軍勢を攻撃して撃退した(黒井城の戦い)。これに激怒した信長は、光秀に命じて再度の丹波侵攻を命じた。これに秀治は八上城で籠城して対抗、光秀の攻撃を1年半にもわたって耐え抜いた。しかしながら光秀の調略で味方であったはずの丹後・但馬における豪族が織田氏に寝返り、さらに長期の籠城戦で兵糧も尽きてしまい、天正7年(1579)に光秀に降伏した。その後、秀治は弟の秀尚と共に安土城に送られたが、信長の命令で6月2日に安土の浄巌院慈恩寺で磔に処された。享年39。なお、この日は奇しくも本能寺の変からちょうど3年前の出来事である。 |
| 萩原朔太郎 | 明治19年-昭和17年(1886-1942)大正・昭和期の詩人、作家。群馬県東群馬郡北曲輪町(現:前橋市千代田町)に、開業医の父・密蔵と母・ケイの長子として生まれる。旧制県立前橋中学校(現・群馬県立前橋高等学校)の在学中に「野守」という回覧雑誌を編集して短歌を発表した。1907年第五高等学校に入学し、翌年第六高等学校に転校するが、チフスで中退。1910年・1911年2度慶應義塾大学予科に入学するが、どちらも短期間で退学した。1919年5月上田稲子と結婚し、葉子と明子の2女をもうけるが、1929年6月離婚。1938年4月大谷美津子と再婚するが、1年余りで離婚した。1942年「帰郷者」で透谷賞受賞。1942年急性肺炎で死去。享年56。 |
| 八百屋お七 | 寛文8年-天和3年(1668?-1683)江戸時代前期、江戸本郷の八百屋太郎兵衛の娘。 伝 八百屋お七 . |
| 伴 信友 | 安永2年-弘化3年(1773-1846)江戸時代の国学者である。幼名は惟徳。通称は州五郎。号は事負。博覧強記で、古典の考証に優れていた。平田篤胤、橘守部、小山田与清とともに、「天保の国学の四大人」と呼ばれる。若狭国小浜藩士・山岸惟智の四男として生まれたが、天明2年(1786)同藩の伴信当の養子となる。享和元年(1801)村田春門を介して本居宣長没後の門人となり、宣長の養子の本居大平に国学を学ぶ。文政4年(1821)息子の信近に家督を譲り、以後、学問に専念した。平田篤胤に君兄と慕われていたが、後に篤胤と決別した。師弟関係を好まず、弟子はとらなかった。弘化3年京都の堀川で死亡。 |
 

 |
|
| 板垣征四郎 | 明治18年-昭和23年(1885-1948)昭和期の陸軍軍人である。満州国軍政部最高顧問、関東軍参謀長、陸軍大臣などを務めた。関東軍高級参謀として石原莞爾とともに満州事変を決行。ナチス・ドイツに迫害されたユダヤ人難民の日本による保護に貢献した。敗戦後、東京裁判にて死刑判決を受ける。現在は靖国神社に合祀されている。 |
| 飯田蛇笏 | (いいだだこつ)明治18年-昭和37年(1885-1962)日本の俳人。本名、飯田武治(いいだたけじ)。別号に山廬(さんろ)。山梨県東八代郡五成村(のち境川村、現笛吹市)の大地主で旧家の長男として生まれる。五成村では、古くから俳句が盛んで蛇笏も9歳の頃より俳句に関心を持つ。旧制甲府中学(現山梨県立甲府第一高等学校)を経て、明治38年早稲田大学英文科入学。早稲田吟社の句会に参加。若山牧水らとも親交を深める。高浜虚子の主宰する「ほとゝぎす」にも投句した。この時は号を玄骨と称していた。明治42年虚子が俳句創作を辞め小説に傾倒するとともに、蛇笏も俳句から遠ざかり、早大を中退し帰郷。その後、虚子の俳壇復帰と共に俳句の創作を再開し、「ほとゝぎす」への投句を復活する。大正3年愛知県幡豆郡家武町(はずぐんえたけちょう、現西尾市)で発刊された俳誌「キラゝ」の選者を担当。大正6年同誌の主宰者となり、誌名を「キラゝ」から「雲母(うんも)」に改める。大正14年に発行所を甲府市に移す。昭和7年処女句集「山廬集」を出版。故郷・境川村での俳句創作活動を続け、昭和37年没。享年77。忌日の10月3日は「山廬忌」という。 |
| 飯尾宗祇 |
(そうぎ)応永28年-文亀2年(1421-1502)室町時代の連歌師。号は自然斎、種玉庵。姓は飯尾というが定かではない。生国は、紀伊とも近江とも言われている。若いころ京都相国寺に入り、30歳のころ連歌に志したという。宗砌、専順、心敬に連歌を学び、東常縁に古今伝授を授けられた。 文明5年(1473)以後、公家や将軍、管領の居住する上京(かみきょう)に種玉庵を結び、三条西実隆他の公家や細川政元他の室町幕府の上級武士と交わった。また、畿内の有力国人衆や周防の大内氏、若狭の武田氏、能登の畠山氏、越後の上杉氏ら各地の大名をたずねている。長享2年(1488)北野連歌所宗匠となり、名実ともに連歌界の第一人者となった。この職は、まもなく兼載に譲り、明応4年(1495)兼載らと「新撰菟玖波集」を編集した。生涯を通じ、たびたび各地を旅したが、1502年弟子の宗長、宗碩らに伴われて越後から美濃に向かう途中、箱根湯本の旅館で没し、駿河桃園(現:静岡県裾野市)定輪寺に葬られた。 応仁の乱以後、古典復興の気運が高まり、地方豪族、特に国人領主層に京都文化への関心と連歌の大流行が見られた。宗祇は、連歌本来の伝統である技巧的な句風に「新古今和歌集」以来の中世の美意識である「長(たけ)高く幽玄にして有心(うしん)なる心」を表現した。全国的な連歌の流行とともに、宗祇やその一門の活動もあり、この時代は連歌の黄金期であった。 連歌の作品として「水無瀬三吟百韻」「湯山三吟百韻」「葉守千句」があり、句集に「萱草」(わすれぐさ)「老葉」(わくらば)「下草」(したくさ)、紀行文に「白河紀行」「筑紫道記」(つくしみちのき)、連歌論に「吾妻問答」「浅茅」などがあり、古典の注釈書も多い。和歌の西行、俳句の松尾芭蕉とともに連歌を代表する漂泊の人である。 |
| 尾崎紅葉 | 慶応3年-明治36年(1868-1903)日本の小説家。本名、徳太郎。「縁山」「半可通人」「十千万堂」などの号も持つ。江戸生れ。帝国大学国文科中退。明治18年(1885)山田美妙らと硯友社を設立し「我楽多文庫」を発刊。「二人比丘尼 色懺悔」で認められ、「伽羅枕」「多情多恨」などを書き、幸田露伴と並称され明治期の文壇の重きをなした。明治30年(1897)から「金色夜叉」を書いたが、未完のまま没した。泉鏡花、小栗風葉、柳川春葉、徳田秋声など、優れた門下生がいる。俳人としても角田竹冷らとともに、秋声会を興し正岡子規と並んで新派と称された。 |
| 富樫源次 | 「魁!!男塾」(さきがけおとこじゅく)週刊少年ジャンプに掲載された宮下あきらの漫画作品キャラクターの一人。略称は「男塾」。 |
| 武川信臣 | (1845-1868/慶応4年当時24歳)会津藩家老内藤介右衛門信順の三男。三彦(かずひこ)。家老内藤介右衛門、主席家老梶原平馬の実弟である。温厚な性格で文武に長じており、特に和歌の道に通じていた。鳥羽伏見の戦いに敗れ、江戸に帰った後、藩士の帰国には従わず彰義隊に加わり、別働隊幡随院分屯信意隊長として上野で戦い、敗れた後、江戸市中に潜伏中を密告され捕らえられる。場所は以前会津藩上屋敷であった和田倉門の糺問局の獄に入れられ、隣室には公用方であった広沢安任がいた。会津藩士家老の弟という事で、拷問を受けるが節を守り、小伝馬町の獄中にて斬首。 |
| 武田勝頼 |
天文15年-天正10年(1546-1582)戦国時代から安土桃山時代にかけての甲斐の武将・戦国大名。甲斐武田家第20代当主。武田二十四将の一人と数える場合もある。当初は諏訪氏を継いだため、諏訪四郎勝頼、あるいは信濃・伊奈谷の高遠城主であったため、伊奈四郎勝頼ともいう。または、武田四郎、武田四郎勝頼とも言う。父信玄は足利義昭に官位と偏諱の授与を願ったが、織田信長の圧力によって果たせなかった。そのため正式な官位はない。 長篠の戦いで敗北を喫し多くの有力武将を失い領国の動揺をも招いた武田に対し、織田信長・徳川家康の反攻は更に積極的になる。長篠合戦後、三河から武田方が締め出されたのを皮切りに、信長の下命を受けた嫡男・信忠を総大将とした織田軍によって東美濃の岩村城を陥落させられ、城将である秋山信友を失った。遠江でも、家康によって依田信蕃が降り、二俣城を奪還された。これに対して勝頼は武田領国の再建を目指した。天正5年(1577)信玄期の宿敵であった上杉謙信と同盟を結んだ。また同年、甲相同盟を強化するため、北条氏政の妹を継室(遠山夫人は信勝出産後死去)として迎えた。翌天正6年(1578)越後で上杉謙信が病死すると、謙信の二人の養子である上杉景虎(旧名・北条三郎)と上杉景勝(謙信の甥)との間で家督を巡り御館の乱が起こる。勝頼は北条氏政の弟(遠縁との説もある)であり北条から上杉に養子として出されていた景虎の支援を要請されて越後への出兵を行い調停を試みるが、外交方針を転換して、妹の菊姫を景勝に輿入れさせ、景勝の支持にまわった(甲越同盟)。武田家が景勝と和睦し越後を去った結果、戦いは景勝が勝ち、景虎は自害した。甲越同盟の成立は東上野において沼田領が獲得できたものの、同時に甲相同盟の解消を招いたため、勝頼は西の織田と対決すると同時に北条対策が必要になり、常陸国の佐竹氏との連携をはかっている(甲佐同盟)。また、駿河では徳川と北条の挟撃を受ける事態に陥った。この話を聞いた東国諸侯は「勝頼はこのたび大欲にふけって、義理の通し方を間違えた」と勝頼をそしったという(「小田原北条記」)。また武田滅亡後に庶民の間で「無情やな 国を寂滅(じゃくめつ) することは 越後の金の 諸行なりけり」という勝頼を嘲る落首がはやったという。 天正9年(1581)徳川軍の攻撃によって高天神城は窮地に陥るが(高天神城の戦い)、もはや勝頼には後詰することが出来なかった。高天神城落城は武田家の威信を大きく下げることとなり、国人衆は大きく動揺した。これを境に織田・徳川からの調略が激しくなり、日頃から不仲な一門衆や日和見の国人の造反も始まることになる。勝頼は、近い将来攻め込んでくるであろう織田・徳川連合軍への備えのため、躑躅ヶ崎館より強固な韮崎の地に新府城を築城して防備を固めるとともに、武田軍団の再編成を目指した。しかし、そのために膨大な軍資金を支配下の国人衆に課すことになり、皮肉にも却って国人衆の造反を招く結果となった。なお国人衆の反発は勝頼の中央集権化を目指した政策に原因があるとする意見もある。天正10年(1582)2月信玄の娘婿で外戚の木曾義昌が新府城築城のための負担増大への不満から織田信長に寝返る。勝頼は外戚の木曾義昌の反逆に激怒し、即座に木曾討伐の軍勢を送り出した。しかし雪に阻まれ進軍は困難を極め、地理に詳しい木曽軍に翻弄された。その間に織田信忠が伊奈方面から、金森長近が飛騨から、徳川家康が駿河から、北条氏直が関東及び伊豆から武田領に侵攻してくる(武田征伐)。これに対して武田軍では組織的な抵抗ができなかった。勝頼の叔父・武田信廉は在城する対織田・徳川防戦の要であった大島城を捨て甲斐に敗走し、信濃伊那城においては織田軍が迫ってくると城主・下条信氏が家老によって追放され、織田軍を自ら迎え入れてしまった。信濃松尾城主の小笠原信嶺、駿河田中城主の依田信蕃らも織田・徳川連合軍の侵攻を前に戦わずして降伏する。さらに武田一族の重鎮である穴山信君までも勝頼を見限り、徳川家康を介して織田信長に服属を誓った。これにより武田氏に属する国人衆は大きく動揺する。この情報に接した武田軍の将兵は人間不信を起こし、疑心暗鬼に苛まれた将兵は勝頼を見捨て、隙を見ては次々と逃げ出したのである。唯一、抵抗らしい抵抗を見せたのは勝頼の弟である仁科盛信が籠城する高遠城だけであった。また母の実家である諏訪家の一門諏訪頼豊は「勝頼から冷遇されていた」と言われているにも関わらず、武田征伐に乗じて諏訪家再興をしようとする家臣の意見を聞かずに鳥居峠の戦いで戦死している。同年3月勝頼は未完成の新府城に放火して逃亡した。甲斐の有力国人で一門衆の小山田信茂と、信濃国人である真田昌幸が、勝頼を受け入れることを表明した。勝頼が選んだのは武田家の本領である甲斐国人・小山田信茂の居城である岩殿城であった(注:小山田氏の居城は谷村城で、岩殿城は小山田領内の武田家直轄の城であるという説もある)。しかし、信茂は織田信長に投降することに方針を変換し、勝頼は進路をふさがれた。後方からは滝川一益の追手に追われ、逃げ場所が無いことを悟った勝頼一行は武田氏ゆかりの地である天目山を目指した。しかし、その途上の田野でついに追手に捕捉され、嫡男の信勝や正室の北条夫人とともに自害した(天目山の戦い)。享年37。これによって、450年の歴史を誇る名門・甲斐武田氏は滅亡した。後に徳川家康により菩提寺として景徳院が建てられ、嫡男の信勝や正室の北条夫人と共に菩提が祭られている。江戸以降に再興する武田家は勝頼の兄で盲目のため出家していた次兄・海野信親(竜宝)の系譜である。 |
| 武田信勝 | 永禄10年-天正10年(1567-1582)戦国時代の甲斐の武将。甲斐武田家の第21代当主。祖父は武田信玄、祖母は諏訪御寮人。父は武田勝頼。母は遠山直廉の娘で織田信長の養女である遠山夫人。大名としての甲斐武田家の最後の当主である。 天正10年(1582)織田信長の甲斐侵攻(武田征伐)が始まると、武田家の諸将は次々に寝返り、一度は信濃に出陣した勝頼も甲斐へ撤退した。3月3日信勝は勝頼に対して新府城での徹底抗戦を主張したが、受け入れられなかった。勝頼一行は小山田信茂を頼るべく、郡内地方を目指して避難するが、笹子峠を目前に小山田の裏切りにあった。このため一行は日川沿いに逃亡したが、天目山の麓の田野で織田方の滝川一益に捕捉された(天目山の戦い)。進退窮まった勝頼・信勝らは覚悟を決め、最後の抵抗を行ったと伝えられている。なおこのとき、勝頼の命令で家臣の土屋昌恒を師として「環甲の礼」を執り行ない、甲斐武田氏伝来の家宝である「楯無の鎧」を着用して、武田氏の当主となったといわれている。織田軍の攻撃に抵抗した後、土屋昌恒に介錯させて自刃したといわれる。享年16。信勝の死によって、大名としての甲斐武田氏は滅亡した。武田家の名跡は従弟の穴山勝千代(武田信治)が継ぎ、勝千代早世後は徳川家康の5男武田信吉がその名跡を継ぐが、これも夭折したため断絶している。このため、武田の嫡流(男系)は信勝の祖父である武田信玄の次男竜芳の子の信道が引き継ぎ、伊豆武田氏となり、紆余曲折の末に高家武田氏として存続した。 |
 

 |
|
| 武藤 章 | (1892-1948)昭和の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。東京裁判で唯一中将として絞首刑判決を受けた。1937年盧溝橋事件に際して参謀本部作戦課長として対中国強硬政策を主張し、12月中支那方面軍参謀副長として赴いた。1939年陸軍省軍務局長、1942年近衛第2師団長(スマトラ・メダン)、1944年第14方面軍(フィリピン)の参謀長に就任した。武藤は参謀として、著名な軍人の下で軍務を尽くしたと言われている。陸軍省軍務局長の時、東條英機との考えの相違により軍中枢から近衛第2師団長に遠ざけられる。東條の失脚後は、第14方面軍司令官に任命された山下奉文の希望により第14方面軍参謀長に任命され、フィリピンの地で終戦を迎えた。 |
| 仏行坊 | ( -1756)仏行坊はもと日枝山無動寺の住職であったが、院務がいやで坂本に隠居して、ひたすら念仏三昧に明けくれていた。ある年の3月に、山僧が師の庵を訪ねると、また桜の季節に再び来たまえという。そこでその時期になって訪れると、ただお茶を出すだけで、何のもてなしもしない。「今日は花見だからもてなしがあると思った」と言うと、「花を見て、それでも心がもの足りないではいけない、足るを知りなさい」と説教を受ける。 仏行坊僧都敬己は、もと日枝ノ山無動寺善住院の一代なれども、院務をいとひ、まだ中年なりしころ、院を辞して坂本に隠居し、律儀をたもち、ひたすら念仏の一行に帰す。しかはあれどまた風月の情やまず。俳譜をたしみ、佃房と交深し。その句、聞伝しが多かる中に、俵物に松卵もあり冬籠。因果応報の心をとて、おどしたるむくひにくづるかゞし哉。蚊ひとつに施しかぬるわが身哉。是は浄土に志を決したる身にも、流石に我執の離れがたきをみづからいましめたる意とぞ。俳諧には都不覚と名をしるさる。また草花にすきて、朝がほ、あるは、なでしこ、さゆりのたぐひすら、同じ花ながら様かはりたるもの数十百種に及べれば、此境界にしては奇僻なり、と人はいひけるとかや。また奇なる話は、或としの弥生に、山僧多く伴ひて師の庵をとふに、さくら盛なるを皆めでければ、此花のうつろはぬうち再び来給へと約せらる。さりければ他日又さそひあひて行たるに、ひねもす唯茶を出さるゝ斗にて、何のもてなしもなし。長き日も暮かゝりければ、けふは花見とて招き給ふからに、たゞにはあらじとおもひしに、たがひたることなめりといひしかば、師かほをしはめて、さてもにがにがしき山法師かな。わが若かれし時までは、さはなかりしぞよ。かかる花を見ながら尚こころの飽たらで、飲食を求るやうやはある。かく足ことをしらぬこゝろにては、山王や大師の冥加もよもあらじ、、といましめられしかば、各花の興もさめて、すごすご帰りしとなん。佃房がとひし時も似たることにて、雅話数刻に及びしかば、門前にうる所の蕎麦をとり来てこゝにてたうべんや、煩らはしとおぼさばかしこへいきてんや、とたづねしに、しばらく首を傾けて思惟し、門前へ行て参れとありし。世情に疎きことすべて此類ひなり。宝暦六年丙子の歳4月17日今は限りにみえしかば、とし比つかへたる下部の僧、師の画像をもち来て、枕辺により、今まで師の御賛を乞んと思ひしかども、呵たまはんを恐れていひ出ざりき。今は御限と見ゆれば、一言つけて賜むや、とこふ。師よしなきことをするもの哉、といひながら筆をとりて「ゆかうゆかうとおもへば何も手につかずゆこやれ西の花のうてなへ」とかきて、西にむかひ合掌して逝ぜられしとぞ。 |
| 平行盛 | (たいらのゆきもり) -元暦2年( -1185)平安時代末期の武将。平清盛の次男である平基盛の長男。父が早世した後、その菩提を弔いながら過ごしていたが、これを憐れんだ伯父の重盛によって養育され、平家一門の栄達にともない左馬頭に任官する。正五位下に昇叙し播磨守、左馬頭にもなる。また歌人としても名を上げた。治承・寿永の乱においては、倶利伽羅峠の戦い、三草山の戦い、藤戸の戦い、屋島の戦いなどに参加。特に藤戸の戦いにおいては、大将軍として佐々木盛綱率いる源氏方と対戦した。元暦2年(1185)3月壇ノ浦の戦いにおいて最終的な敗北を喫し、従兄弟の資盛、有盛とともに入水自殺(平家物語)。 |
| 平薩摩守忠度 | (たいらのただのり)天養元年-元暦元年(1144-1184)平安時代の武将。平忠盛の六男。平清盛、教盛、経盛らは兄。子に忠行がいる。熊野の地で生まれ育ったとの伝承あり。治承2年(1178)従四位上。治承3年(1179)伯耆守。治承4年(1180)正四位下薩摩守。 |
| 平田篤胤 | 安永5年-天保14年(1776-1843)江戸時代後期の国学者・神道家。幼名正吉。通称半兵衛。寛政2年元服してからは胤行と名乗り、享和年間以降は篤胤と称した。号は気吹舎(いぶきのや)、家號を真菅乃屋(ますげのや)。医者としては、玄琢を使っている。死後、神霊能真柱大人(かむたまのみはしらのうし)の名を白川家より贈られている。 秋田藩士の子として生まれ、成人してから備中松山藩士の兵学者平田篤穏の養子となる。本居宣長らの後を引き継ぐ形で儒教・仏教と習合した神道を批判し、やがてその思想は水戸学同様尊皇攘夷の支柱となり、倒幕後の明治維新変革期の原動力ともなった。その思想は後の神仏分離や廃仏毀釈にも影響を与えた。 |
| 平野国臣 | (ひらのくにおみ)文政11年-元治元年(1828-1864)日本の武士・福岡藩士、志士。通称は次郎、巳之吉。諱は種言、種徳。贈正四位。攘夷派志士として奔走し、西郷隆盛ら薩摩藩士や真木和泉、清河八郎ら志士と親交をもち、討幕論を広めた。文久2年(1862)島津久光の上洛にあわせて挙兵をはかるが寺田屋事件で失敗し投獄される。出獄後の文久3年(1863)三条実美ら攘夷派公卿や真木和泉と大和行幸を画策するが8月18日の政変で挫折。大和国での天誅組の挙兵に呼応する形で但馬国生野で挙兵するがまたも失敗に終わり捕えられた。身柄は京都所司代が管理する六角獄舎に預けられていたが、禁門の変の際に生じた火災を口実に殺害された。 |
| 柄井川柳 | (からいせんりゅう)享保3年-寛政2年(1718-1790)江戸時代中期の前句付の点者。名は正道。幼名勇之助。通称は八右衛門。柄井家は代々江戸浅草新堀端の竜宝寺門前町の名主の家系で、宝暦5年に家を継いで名主となった。 |
 

 |
|
| 別所長治 | 永禄元年-天正8年(1558-1580)戦国時代から安土桃山時代の大名。別所安治の嫡男。通称は小三郎。正室の照子は波多野秀治の妹(娘とも)。 元亀元年(1570)父・安治の病死により叔父の吉親・重宗を後見役に若くして家督を継ぐ。別所氏は早くから織田信長に従っており、家督を相続した長治も天正3年(1575)信長に謁見、翌年も年頭の挨拶に訪れている。信長が中国の毛利氏を制圧しようとすると、それに呼応して先鋒の役を務めようとしたが、中国方面総司令官が成り上がりの羽柴秀吉であることに不満を感じ、妻の実家である丹波の波多野秀治と呼応して信長に反逆した。多くの周辺勢力が同調、従わなかった勢力も攻め、東播磨一帯が反織田となる。これにより長治は、信長の命を受けた秀吉の軍勢に攻められることとなる。長治は三木城に籠もって徹底抗戦して秀吉を手こずらせ、さらに荒木村重の謀反や毛利氏の援軍などの好条件も続いて、一度は織田軍を撃退したものの、やがて秀吉の有名な「三木の干し殺し」戦法に遭い、神吉城や志方城などの支城も落とされ、毛利氏からの援軍も途絶えて、遂に籠城してから二年後の天正8年(1580)城兵達の命を助ける事と引き替えに妻子兄弟と共に自害して果てたという。介錯は家臣の三宅治忠が行った。享年23。 |
| 別所友之 | 永禄3年-天正8年(1560-1580)戦国時代後期・安土桃山時代の武将。別所安治の次男。通称:彦進。兄に別所長治、弟に別所治定がいる。若年でありながら、勇猛で近隣に勇名を轟かせる。兄・長治に従い、織田信長に反抗する。しかし、長治から命を受けて宮の上の構えを守っていたが、羽柴秀吉の軍勢に攻め込まれ、善戦するも空しく、長治ら3200の兵が籠る三木城に合流した。1580年に味方は降伏。友之は17歳の妻を先に刺殺し、長治の脇差で切腹自害した。享年21。 |
| 豊臣秀吉 | (羽柴秀吉)天文6年-慶長3年(1537-1598)戦国時代(室町時代後期)から安土桃山時代にかけての武将・戦国大名。本姓は豊臣氏。生まれは尾張国の半農半兵の家。はじめ木下氏を名字とし・羽柴氏に改める。本姓としては、はじめ平氏を自称するが、近衛家の猶子となり藤原氏に改姓した後、豊臣氏に改める。尾張国愛知郡中村の百姓として生まれ、織田信長に仕え、次第に頭角を表す。信長が本能寺の変で明智光秀に討たれると、中国大返しにより京へと戻り、山崎の戦いで光秀を破り、信長の後継の地位を得る。その後、大坂城を築き関白・太政大臣に任ぜられた。豊臣姓を賜り、日本全国の大名を従え天下統一を成し遂げた。太閤検地や刀狩などの政策を採るが、慶長の役の最中に、嗣子の秀頼を徳川家康ら五大老に託して没した。墨俣の一夜城、金ヶ崎の退き口、高松城の水攻め、石垣山一夜城など機知に富んだ逸話が伝わり、百姓から天下人へと至った生涯は「戦国一の出世頭」と評される。 |
| 豊臣秀次 | (羽柴秀次)永禄11年-文禄4年(1568-1595)/戦国時代(室町時代末期)から天正時代の武将・大名・関白である。豊臣秀吉の姉・日秀の子で、秀吉の養子となる。通称は孫七郎(まごしちろう)。幼名は治兵衛(じへえ)。はじめ、戦国大名・三好氏の一族・三好康長に養子入りして三好信吉(みよしのぶよし)と名乗っていたが、後に羽柴秀次と改名する。正室は池田恒興の娘、継室は右大臣・菊亭晴季の娘。側室は、最上義光の娘・駒姫(お伊万の方)、淡輪徹斎隆重の娘・小督局、大島新左衛門の娘・お国など、ほか多数いる。文禄2年(1593)秀吉に実子・秀頼が生まれると、秀吉から次第に疎まれるようになる。秀頼と秀次の娘を婚約させるなど互いに譲歩も試みられたが、けっきょく文禄4年(1595)7月8日秀吉の命令で高野山に追放され、出家した(これ以降、出家した関白=禅閤となり、豊臣の姓から豊禅閤〈ほうぜんこう〉と呼ばれた)。同年7月15日に切腹を命じられ青巌寺・柳の間にて死亡。享年28。 |
 

 |
|
| 北条基時 | 弘安9年-元弘3年(1286-1333)鎌倉時代末期の北条氏の一門。鎌倉幕府第13代執権8在職1315-1316)である。父は普恩寺流の北条時兼。子に最後の六波羅探題となった北条仲時。六波羅探題北方などを務める。正和4年(1315)執権となり、翌年には北条高時に譲り出家する。元弘3年(1333)後醍醐天皇の倒幕計画から元弘の乱が起こり、幕府に反旗を翻した新田義貞らが鎌倉を攻撃し、奮戦したのち自害した。享年48。 |
| 北条時頼 | 嘉禄3年-弘長3年(1227-1263)鎌倉時代中期の鎌倉幕府第5代執権(在職1246-1256)である。北条時氏の次男で、4代執権北条経時の弟。8代執権北条時宗の父。 |
| 北條氏照 | 天文9年-天正18年(1540-1590)戦国時代の武将。北条氏康の3男で北条氏政の弟である。別名、大石源三、北条(平)陸奥守、宗家の虎に呼応し「如意成就」と刻まれた龍の印章を使用した。 |
| 北條氏政 | (1538-1590)相模国小田原城主、北條家第四代目当主、通称新九郎。隠居後は相模守、截流斎と号した。秀吉の小田原攻め後、その責任をとらされ自害させられる。 |
| 北條氏直 | (1562-1591)安土桃山時代の武将。相模国小田原城主。幼名は国王丸、通称は新九郎、斎号は見性斎。氏直の治世は、氏政の後見による部分が多い。また小田原征伐の際も、氏政の意見により籠城することとなった。氏直は小田原開城後、高野山へ追放されるが、のち許されて一万石の大名となるが、死去してしまう。氏直の死により、小田原北條の嫡流は断絶するが、北條氏規の子氏盛があとを継ぐこととなり、江戸時代まで命脈をたもち明治維新まで続いていくこととなる。 |
| 堀光器 | 通称粂之助。父清左衛門は普請奉行配下の下級武士で、粂之助は文武に優れ、会津藩校南学館の助教授であった。戊辰戦争の際、吉村寅之進と共に容保の命で米沢藩に援軍を請う為に米沢へ至り、援軍を乞うが、米沢藩はすでに恭順に傾いていた為、会津藩の要請に応える事はなかった。この上は仙台藩に頼ろうと同行の吉村は説くが、粂之助は、君命を果たせぬ上は、死をもって報いるしかないと、その夜遺書をした為旅籠の主人に金子を渡して死後を頼んだ。慶応4年9月4日享年31歳にて自刃。 |
| 本因坊算砂 | (ほんいんぼうさんさ)永禄2年-元和9年(1559-1623)江戸時代の囲碁の棋士。一世本因坊。本姓は加納、幼名は與三郎。法名は日海、後に本因坊算砂。生国は京都。 |
 

 |
|
| 本間雅晴 | 明治20年-昭和21年(1887-1946)日本の陸軍軍人・陸軍中将。太平洋戦争においてフィリピン攻略を指揮し、戦後「バターン死の行進」の責任を問われて処刑された。本間賢吉の長男として新潟県佐渡島畑野町に生れる。佐渡中学、陸軍士官学校(19期)を経て、大正4年(1915)陸軍大学校(27期)を優等で卒業。 |
| 本居宣長 | 享保15年-享和元年(1730-1801)江戸時代日本の国学者・文献学者・医師である。名は栄貞。通称は瞬庵、春庵(しゅんあん)、鈴屋大人(すずのやのうし)と号した。当時、既に解読不能に陥っていた「古事記」の解読に成功し、「古事記伝」を著した。紀州徳川家に「玉くしげ別本」の中で寛刑主義をすすめた。 死すれば、妻子眷族朋友家財万事をもふりすて、馴れたる此世を永く別れ去りて、再び還来ることあたはず、かならずかの汚きよみの国に行くことなれば、世の中に、死ぬる程かなしき事はなきものなる… 「玉匣」 |
| 夢窓疎石 | 建治元年-観応2年(1275-1351)鎌倉時代末から南北朝時代、室町時代初期にかけての臨済宗の禅僧。七朝帝師。父は佐々木朝綱、母は北条政村の娘。道号が夢窓、法諱が疎石。 |
| 無抑和尚 | (年代不明)備州東南の山に無抑和尚という世俗を捨てた男がおり、「亡我法数」を編集して名を残した。 |
| 明智光秀 | 享禄元年-天正10年(1528-1582)戦国時代、安土桃山時代の武将。本姓は源氏。家系は清和源氏の摂津源氏系で、美濃源氏土岐氏支流である明智氏。仮名は十兵衛。雅号は咲庵(しょうあん)。惟任光秀。妻は、妻木煕子。その間には、嫡男・光慶(十五郎)、織田信澄室、細川忠興室・明智珠(洗礼名:ガラシャ)がいる。 光秀と称念寺 縁の段 . |
| 毛利元就 | 明応6年-元亀2年(1497-1571)室町時代後期から戦国時代にかけての安芸の国人領主・戦国大名。安芸の国人領主から中国地方のほぼ全域を支配下に置くまでに勢力を拡大し、戦国時代最高の名将の一人と後世評される。用意周到な策略で自軍を勝利へ導く稀代の策略家として名高い。本姓は大江氏。家系は大江広元の四男毛利季光を祖とする毛利氏の血筋。寒河江氏などは一門にあたる。家紋は一文字三星紋。安芸国吉田郡山城(現在の広島県安芸高田市吉田町)を本拠とした毛利弘元の次男。幼名は松寿丸(しょうじゅまる)、仮名は少輔次郎(しょうのじろう)。 |
| 矢沢頼綱の母 | 矢沢頼綱(やざわよりつな)/永正15年-慶長2年(1518-1597)戦国時代の武将。真田頼昌の子。真田幸隆は兄。幼名源之助。名は頼幸とも。受領名は薩摩守。子に矢沢頼康(嫡男)、矢沢頼邦、女子(海野幸貞妻)。若い頃出家し京都鞍馬の僧となるが、程なく郷里に戻って還俗し、武田信玄に仕える兄の幸隆の下で信濃先方衆として活躍する。幸隆や後を継いだ甥の信綱に従い、更に長篠の戦いで信綱が亡くなると、真田家を継いだ甥の昌幸に従って上野国岩櫃城を攻略し城代となった。その後も独立勢力となった真田氏の重臣として、小那淵城、名胡桃城、小川城の諸城を攻略。さらに沼田城も攻略し城代となり、北条氏邦の侵攻を受けるが、上杉景勝の援軍を得てこれを撃退するなど活躍した。 |
| 柳亭種彦 | (りゅうていたねひこ)天明3年-天保13年(1783-1842)江戸時代後期の戯作者。長編合巻「偐紫田舎源氏」などで知られる。 |
 

 |
|
| 有島武郎 | 明治11年-大正12年(1878-1923)日本の小説家。学習院中等科卒業後、農学者を志して札幌農学校に進学、キリスト教の洗礼を受ける。1903年渡米。帰国後、志賀直哉や武者小路実篤らとともに同人「白樺」に参加。1923年軽井沢の別荘(浄月荘)で波多野秋子と心中した。作品に「カインの末裔」「或る女」「惜みなく愛は奪ふ」がある。 |
| 与謝蕪村 | 享保元年-天明3年(1716-1784)江戸時代中期の日本の俳人、画家。本姓は谷口、あるいは谷。「蕪村」は号で、名は信章通称寅。「蕪村」とは中国の詩人陶淵明の詩「帰去来辞」に由来する。俳号は蕪村以外では「宰鳥」「夜半亭(二世)」があり、画号は「春星」「謝寅(しゃいん)」など複数の名前を持っている。 |
| 良寛 |
宝暦8年-天保2年(1758-1831)江戸時代の曹洞宗の僧侶、歌人、漢詩人、書家。俗名、山本栄蔵または文孝。号は大愚。 形見とて何か残さん春は花 夏ほととぎす秋はもみじ葉 |
| 林忠崇 | (はやしただたか)嘉永元年-昭和16年(1848-1941)幕末の大名で、上総国請西藩の第3代藩主。幼名は昌之助。号を一夢。請西藩主忠旭の五男として生まれる。嘉永7年(1854)忠旭が隠居するが、兄忠貞はすでに早世しており、自らも幼少であったため、叔父忠交が家督を相続した。慶応3年(1867)忠交の死により、幼少であった忠交の子忠弘に代わって家督を相続する。忠崇は文武両道で幕閣の覚えめでたく、将来閣老になる器と評されていたとされる。慶応3年(1867)大政奉還の報を受けた藩は洋式軍の調練を行なうなど有事に備えたが、戊辰戦争勃発にともなって藩論は恭順派と抗戦派に分かれて伯仲した。同年閏4月に撤兵隊、伊庭八郎や人見勝太郎率いる遊撃隊など、旧幕府軍が来訪して助力を要請するや、自ら脱藩して藩士70名とともに遊撃隊に参加した。新政府は藩主自らの脱藩を反逆と見なし、林家は改易処分となる。脱藩した忠崇らは幕府海軍の協力を得て、館山や箱根、伊豆などで新政府軍と交戦する。その後は奥州へ転戦するも、旧幕府側の相次ぐ敗北により戦況は悪化し、盟主の仙台藩も新政府軍に恭順する。徳川家存続の報を受けた忠崇は、戦争の大義名分が果たされたとして仙台にて新政府に降伏。江戸の唐津藩邸に幽閉される。明治2年(1869)甥忠弘が東京府士族として家名存続が認められたものの、家禄は35石に減らされ、その後の秩禄処分によって困窮した生活を余儀なくされる。明治5年赦免。維新後は開拓農民、東京府や大阪府の下級官吏、商家の番頭など、一介の士族として困窮した生活を送った。林家は旧諸侯にもかかわらず、改易の事情から華族の礼遇が与えられる事はなかった。明治26年(1893)旧藩士による林家の家名復興の嘆願が認められ、忠弘は男爵を授けられて華族に列する。その際、分家していた忠崇も復籍して華族の一員となり、翌年には従五位に叙された。その後は宮内省や日光東照宮などに勤めた。昭和16年(1941)次女ミツの経営するアパートにて病死。享年94。 |
| 林八右衛門 | 明和4年-天保元年(1767-1830)百姓一揆の指導者とされ牢死した村役人。上野国(群馬県)那波郡川越藩前橋分領東善養寺村百姓庄七の長男。5歳のとき父が病死、母の再婚先で養われる。9歳のとき祝昌寺光円につき手習いを始め、次いで禅養寺に入り恵陳を師とする。15歳で寺を出て本家林七右衛門家に寄居、18歳で本家養女菊と結婚、分家する。25歳のとき伊勢参宮し、帰村後名主となる。40歳代のころ借金、火事などで家を潰すが、やがて立て直し、53歳で再び名主となり、藩の勧農野廻り役を命じられた。文政4年(1821)藩の増徴目的の租法変更に対し難渋願書を提出。同年11月江戸藩邸への門訴に出立した百姓の引き戻しを命じられ、中止の説得に努めた。一揆を中止させたが各村の年貢願書の案文を指導したため、翌年入牢、一揆発頭人に当たるとされ永牢の判決を受けた。牢内で「勧農教訓録」を書き上げる。 |
| 倭建命 | 日本武尊(やまとたけるのみこと/「古事記」では倭建命と表記)こと小碓命(おうすのみこと)またの名を日本童男(やまとおぐな)は、景行天皇の皇子で、仲哀天皇の父とされる人物。日本神話では英雄として登場する。記紀の記述によれば、2世紀頃に存在したとされる。実際には、4世紀から6、7世紀頃の複数の大和(ヤマト)の英雄を具現化した架空の人物という見方もある。 倭建命「古事記」景行記 > 夜麻登波 久爾能麻本呂婆 多多那豆久 阿袁加岐 夜麻碁母禮流 夜麻登志宇流波斯 |
 

 |
|
| 西郷隆盛 | (さいごうたかもり)本名/隆永(たかなが)文政10年-明治10年9月24日(1828-1877)日本の武士(薩摩藩)、軍人、政治家。薩摩藩の盟友大久保利通、長州藩の木戸孝允(桂小五郎)と並び、「維新の三傑」と称される。 |
| 和泉式部 |
(いずみしきぶ・生没年不詳)は平安時代中期の歌人。天元元年頃(978?)出生とするのが通説。中古三十六歌仙の一人。「小倉百人一首」56番「あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな」の作者。 越前守の大江雅致の娘。和泉守の橘道貞の妻となり、夫の任国と父の官名を合わせて「和泉式部」の女房名をつけられた。道貞との婚姻は後に破綻したが、彼との間に儲けた娘小式部内侍は母譲りの歌才を示した。 はじめ御許丸(おもとまる)と呼ばれ太皇太后宮昌子内親王付きの女童だったらしい(母・平保衡女が昌子内親王付きの女房であった)が、それを否定する論もある。まだ道貞の妻だった頃、冷泉天皇の第三皇子為尊親王(977-1002)との熱愛が世に喧伝され、身分違いの恋だったとて親から勘当を受けた。為尊親王の死後、今度はその同母弟敦道親王(981-1007)の求愛を受けた。親王は式部を邸に迎えようとし、正妃が家出する因を作った。 親王の召人として一子永覚を儲けるが、親王は寛弘4年(1007)に早世した。寛弘末年(1008-1011)一条天皇の中宮藤原彰子に女房として出仕。40歳を過ぎた頃、主君彰子の父藤原道長の家司で武勇をもって知られた藤原保昌と再婚し、夫の任国丹後に下った。万寿2年(1025)娘の小式部内侍が死去した折にはまだ生存していたが、晩年の詳細は分らない。京都の誠心院では3月21日に和泉式部忌の法要が営まれる。 |
| 有馬皇子 | (ありまのみこ)舒明天皇12年-斉明天皇4年(640-658)孝徳天皇の皇子。母は左大臣・阿倍内麻呂の娘・小足媛。天智天皇の娘、明日香皇女・新田部皇女姉妹とは母方の従兄妹になる。後世には「有馬」と表記される例が多い。 大化元年(645)父の孝徳天皇が即位。孝徳天皇は同年の12月9日都を難波宮に移す。しかし、白雉4年(653)中大兄皇子が、都を倭京に戻す事を求めた。しかし、孝徳天皇はこれを聞き入れなかったため、中大兄を初めとする皇族達やほとんどの臣下達が倭京に戻ってしまった。皇后の間人皇女でさえ兄に従い、戻ってしまった。失意の中、孝徳天皇は白雉5年(654)の10月10日崩御した。このため、斉明天皇元年(655)1月3日宝皇女が再び飛鳥板葺宮で斉明天皇として即位した。 有間皇子は、心の病を装って牟婁の湯に療養に行き、飛鳥に帰った後に自分の病気が完治した事を斉明天皇に伝え、その土地のすばらしさを話して聞かせたため、斉明天皇は紀の湯に行幸した。飛鳥に残っていた有間皇子に、中大兄皇子の意を受けたと思われる蘇我赤兄が近づき、斉明天皇や中大兄皇子の失政を指摘し、自分は皇子の味方である事を伝え、斉明天皇と中大兄皇子打倒の計画を練った。この時、有間皇子は母の小足媛の実家の阿部氏の水軍を頼りにし、天皇達を急襲するつもりだったという説が最近出てきている 。 しかし、赤兄の密告によりこの謀反計画は露見し、彼は守君大石・板合部連楽達と捕らえられ、斉明天皇4年(658)11月9日中大兄皇子に尋問された。その時、有間皇子は「全ては天と赤兄だけが知っている。私は何も知らぬ」(天與赤兄知。吾全不知)と答えた。有間皇子は、同年11月11日に藤白坂で絞首刑に処せられた。これに先んじて、磐代の地で彼が詠んだ2首の辞世歌が「万葉集」に収録されている。 |
| 近藤勇 |
天保5年-慶応4年4月25日(1834-1868)新選組局長。晩年は幕臣。勇は通称、諱は昌宜(まさよし)。慶応4年から大久保剛、のちに大久保大和。家紋は丸に三つ引。 戊辰戦争/三条河原鳥羽・伏見の戦いにおいて敗れた新選組は幕府軍艦で江戸に戻る。3月幕府の命を受け、大久保剛と改名した近藤は甲陽鎮撫隊として隊を再編し甲府へ出陣したが、甲州勝沼の戦いで新政府軍に敗れて敗走し、その際、意見の対立から永倉新八、原田左之助らが離別する。その後、大久保大和と再度名を改め、旧幕府歩兵らを五兵衛新田(現在の東京都足立区綾瀬四丁目)で募集し、4月下総国流山(現在の千葉県流山市)に屯集するが、香川敬三率いる新政府軍に包囲され、越谷(現在の埼玉県越谷市)の政府軍本営に出頭する。 しかし、大久保が近藤と知る者が政府軍側におり、そのため総督府が置かれた板橋宿まで連行される。近藤は大久保の名を貫き通したが、元隊士で御陵衛士の一人だった加納鷲雄に近藤と看破され、捕縛された。その後、土佐藩と薩摩藩との間で、近藤の処遇をめぐり対立が生じたが、結局、4月25日中仙道板橋宿近くの板橋刑場(現在の東京都板橋区板橋および北区滝野川付近)で斬首された。斬首される直前、近藤は「楽しかったな。」と言ったという。35歳(満33歳没)。首は板橋と大坂の千日前、京都の三条河原で梟首された。その後の首の行方は不明である。 |
| 織田信長 | 天文3年-天正10年(1534年-1582)日本の戦国時代から安土桃山時代にかけて、世に多大な影響を残した武将・戦国大名・政治家である。当時の常識や権力に囚われず、新しい考え方や文化を積極的に取り入れる見識の広さ、合理性と冷徹さを兼ね備えた知性によって、統一者のいなかった政治的混沌を収集に向かわせた人物である。その事業は大方向を示したところで重臣の一人・明智光秀の裏切りに遭い、自刃に追い込まれたことによって頓挫した。しかし、政権の実質的後継者となった羽柴秀吉が、信長の築いた足場をもとに天下統一を進め、ついには成し遂げることとなったことから、秀吉が継ぎ、徳川家康が完成させる形となった日本近世の形成事業の創始と言うべき位置づけにあった政治家である。 織田信長 幸若舞「敦盛」 . |
 

 |
|
| 藤原定子 | 貞元2年-長保2年(977-1001)平安時代、第66代一条天皇の皇后(号は中宮、のち皇后宮)。脩子内親王・敦康親王・び(女美)子内親王の生母。通称は「一条院皇后宮」。「枕草子」の作者清少納言が仕えた女性である。 |
| 小野小町 | (生没年不詳)平安前期9世紀頃の女流歌人。六歌仙・三十六歌仙の1人。小野小町の詳しい系譜は不明である。彼女は絶世の美女として七小町など数々の逸話があり、後世に能や浄瑠璃などの題材としても使われている。だが、当時の小野小町像とされる絵や彫像は現存せず、後世に描かれた絵でも後姿が大半を占め、素顔が描かれていない事が多い。故に、美女であったか否かについても、真偽の程は分かっていない。 |
| 鑑真和上 |
持統天皇2年-天平宝字7年(688-763)奈良時代の帰化僧。日本における律宗の開祖。俗姓は淳于。 ■戒律 唐の揚州江陽県の生まれ。14歳で智満について出家し、道岸、弘景について、律宗・天台宗を学ぶ。律宗とは、仏教徒、とりわけ僧尼が遵守すべき戒律を伝え研究する宗派であるが、鑑真は四分律に基づく南山律宗の継承者であり、4万人以上の人々に授戒を行ったとされている。揚州の大明寺の住職であった742年、日本から唐に渡った僧栄叡、普照らから戒律を日本へ伝えるよう懇請された。 仏教では、新たに僧尼となる者は、戒律を遵守することを誓う必要がある。戒律のうち自分で自分に誓うものを「戒」といい、僧尼の間で誓い合うものを「律」という。律を誓うには、10人以上の正式の僧尼の前で儀式(これが授戒である)を行う必要がある。これら戒律は仏教の中でも最も重要な事項の一つとされているが、日本では仏教が伝来した当初は自分で自分に授戒する自誓授戒が行われるなど、授戒の重要性が長らく認識されていなかった。しかし、奈良時代に入ると、戒律の重要性が徐々に認識され始め、授戒の制度を整備する必要性が高まっていた。栄叡と普照は、授戒できる僧10人を招請するため渡唐し、戒律の僧として高名だった鑑真のもとを訪れた。 栄叡と普照の要請を受けた鑑真は、弟子に問いかけたが、誰も渡日を希望する者がいなかった。そこで鑑真自ら渡日することを決意し、それを聞いた弟子21人も随行することとなった。その後、日本への渡海を5回にわたり試みたがことごとく失敗した。 ■日本への渡海 鑑真第六回渡海図最初の渡海企図は743年夏のことで、このときは、渡海を嫌った弟子が、港の役人へ「日本僧は実は海賊だ」と偽の密告をしたため、日本僧は追放された。鑑真は留め置かれた。 2回目の試みは744年1月、周到な準備の上で出航したが激しい暴風に遭い、一旦、明州の余姚へ戻らざるを得なくなってしまった。 再度、出航を企てたが、鑑真の渡日を惜しむ者の密告により栄叡が逮捕され、3回目も失敗に終わる。 その後、栄叡は病死を装って出獄に成功し、江蘇・浙江からの出航は困難だとして、鑑真一行は福州から出発する計画を立て、福州へ向かった。しかし、この時も鑑真弟子の霊佑が鑑真の安否を気遣って渡航阻止を役人へ訴えた。そのため、官吏に出航を差し止めされ、4回目も失敗する。 748年、栄叡が再び大明寺の鑑真を訪れた。懇願すると、鑑真は5回目の渡日を決意する。6月に出航し、舟山諸島で数ヶ月風待ちした後、11月に日本へ向かい出航したが、激しい暴風に遭い、14日間の漂流の末、遥か南方の海南島へ漂着した。鑑真は当地の大雲寺に1年滞留し、海南島に数々の医薬の知識を伝えた。そのため、現代でも鑑真を顕彰する遺跡が残されている。 751年、鑑真は揚州に戻るため海南島を離れた。その途上、端州の地で栄叡が死去する。動揺した鑑真は広州から天竺へ向かおうとしたが、周囲に慰留された。この揚州までの帰上の間、鑑真は南方の気候や激しい疲労などにより、両眼を失明してしまう(最近の研究では渡日翌年に書かれた手紙が鑑真の直筆の手紙の可能性が高いことから、完全に失明はしていなかったとする説もある)。 752年、必ず渡日を果たす決意をした鑑真のもとに訪れた遣唐使藤原清河らに渡日を約束した。しかし、当時の玄宗皇帝が鑑真の才能を惜しんで渡日を許さなかった。そのために753年に遣唐使が帰日する際、遣唐大使の藤原清河は鑑真の同乗を拒否した。それを聞いた副使の大伴古麻呂は密かに鑑真を乗船させた。11月17日に遣唐使船が出航、ほどなくして暴風が襲い、清河の大使船は南方まで漂流したが、古麻呂の副使船は持ちこたえ、12月20日に薩摩坊津に無事到着し、実に10年の歳月を経て仏舎利を携えた鑑真は宿願の渡日を果たすことができた。 なお、皇帝の反対を押し切ってまで日本に来た理由について、小野勝年は日本からの留学僧の強い招請運動、日本の仏教興隆に対する感銘、戒律流布の処女地で魅力的だったという3点を挙げている。それに対して金治勇は、聖徳太子が南嶽慧思の再誕との説に促されて渡来したと述べている。 ■日本での戒律の確立 唐招提寺753年(天平勝宝5年)12月26日、鑑真は太宰府観世音寺に隣接する戒壇院で初の授戒を行い、754年(天平勝宝6年)1月には平城京に到着し聖武上皇以下の歓待を受け、孝謙天皇の勅により戒壇の設立と授戒について全面的に一任され、東大寺に住することとなった。4月、鑑真は東大寺大仏殿に戒壇を築き、上皇から僧尼まで400名に菩薩戒を授けた。これが日本の登壇授戒の嚆矢である。併せて、常設の東大寺戒壇院が建立され、その後761年(天平宝字5年)には日本の東西で登壇授戒が可能となるよう、大宰府観世音寺および下野国薬師寺に戒壇が設置され、戒律制度が急速に整備されていった。 758年(天平宝字2年)、淳仁天皇の勅により大和上に任じられ、政治にとらわれる労苦から解放するため僧綱の任が解かれ、自由に戒律を伝えられる配慮がなされた。 759年(天平宝字3年)、新田部親王の旧邸宅跡が与えられ唐招提寺を創建し、戒壇を設置した。鑑真は戒律の他、彫刻や薬草の造詣も深く、日本にこれらの知識も伝えた。また、悲田院を作り貧民救済にも積極的に取り組んだ。 763年(天平宝字7年)唐招提寺で死去(入寂)した。76歳。死去を惜しんだ弟子の忍基は鑑真の彫像(脱活乾漆彩色麻布を漆で張り合わせて骨格を作る手法両手先は木彫)を造り、現代まで唐招提寺に伝わっている(国宝唐招提寺鑑真像)が、これが日本最古の肖像彫刻とされている。また、779年(宝亀10年)、淡海三船により鑑真の伝記「唐大和上東征伝」が記され、鑑真の事績を知る貴重な史料となっている。 |
| 最澄 |
(767-822) 平安時代の僧で、日本の天台宗を開く。近江国(滋賀県)滋賀郡古市郷(現在の大津市)に生れ、俗名は三津首広野(みつのおびとひろの)。生年に関しては天平神護2年(766年)説も存在する。先祖は後漢の孝献帝(こうけんてい)に連なる登萬貴王(とまきおう)で、応神天皇の時代に日本に渡来したといわれている。 夏4月、もろもろの弟子たちに告げて言われた、「わたしの命はもう長くはあるまい。もしもわたしが死んだあとは、みんな喪服を着てはならない。また山中の同法(同門の弟子)は、仏のさだめた戒律によって、酒を飲んではいけない。ただし、わたしもまた、いくたびもこの国に生れかわって、三学(戒・定・慧)を学習し、一乗(「法華経」の教え)を弘めよう。 「叡山大師伝」 最澄 . |
| 花山天皇 | 安和元年-寛弘5年(968-1008)在位は永観2年-寛和2年(984-986)第65代の天皇。平安時代中期にあたる。諱は師貞(もろさだ)。かつては華山天皇とも表記されていた。 |
| 鳥羽天皇 | |
| 近衛天皇 | |
| 源為義 | |
| 源頼政 | |
| 源實朝 | |
 

 |
|
| 足利家時 | |
| 平清盛 | |
| 木曾義仲 | |
| 平重衡 | |
| 源義経 | |
| 後醍醐天皇 | |
 

 |
|
| 真田幸村 | 真田幸村の娘 . |
| 武田信玄 | |
| 酒井忠勝 | |
| 早野巴人 | |
| 曲亭馬琴 | |
| 東福門院和子 | |
| 安国寺恵瓊 | |
 

 |
|
| 楠木正行 | |
| 宗峰妙超 | (1281-1337) 臨済宗の僧
「仏祖を截断し 吹毛常に磨く機輪転ずる処 虚空牙を咬む」(仏祖さえも否定超克して吹毛の剣にも比せられる性根玉をいつも磨いてきたその心の機は虚空が牙を咬むとも言える、空が空を行じる心境と言えよう) 「遺偈」 |
| 北条氏政 | |
| 春日局 | |
| 絵島 |
規律に縛られた大奥女中と、華やかな人気役者の恋物語「絵島事件」は、江戸時代の大スキャンダルだった。絵島は七代将軍徳川家継の生母である月光院に仕えた大奥年寄りである。事件は「兼山秘策」によると芝増上寺への参詣にかこつけて、芝居見物をしたうえ、生島新五郎ら数人の役者を呼び寄せ、酒宴におよんだということである。
同書では、絵島について四十歳近い派手好みの美しい女性で、生島も非常に美男子であったと述べている。当時、同様の事件は他にもあったにもかかわらず、絵島事件だけが騒がれたのは何故か。それは絵島の主人月光院を排斥するため、六代将軍正室天英院を中心とした一派や幕臣たちが、権力闘争の材料として攻撃の槍玉に上げたからだ。勢力争いに翻弄された哀れな絵島は、信濃国へ流刑となった。生島は三宅島へと流され、連座者が一千人以上におよぶという大事件となった。江戸を追われ、恋人との仲を裂かれた絵島。どれほど我が身の不運を嘆いたことだろうか。 絵島生島 . |
| 阿部重次 | |
| 平田靱負 | |
| 瀧善三郎 | |
| 都々逸坊扇歌 | |
 

 |
|
| 岡田以藏 |
天保9年-慶応元年(1838-1865)土佐の郷士で土佐勤王党に加わった幕末四大人斬りの一人。「人斬り以蔵」と呼ばれた。諱は宜振(よしふる)。 香美郡岩村(現南国市)に二十石六斗四升五合の郷士岡田義平の長男として生まれる。弟に同じく勤王党に加わった岡田啓吉がいる。嘉永元年(1848)土佐沖に現れた外国船に対する海岸防備のために父義平が藩の足軽として徴募され、そのまま城下の七軒町に住むようになり、以蔵自身はこの足軽の身分を継いでいる。 武市瑞山(半平太)に師事し小野派一刀流剣術を学ぶ。武市の門を叩く前にも、我流ながらかなりの剣術の腕前であった。安政3年(1856)武市に従い江戸に出て、鏡心明智流剣術を桃井春蔵の道場・士学館で学ぶ。翌年、土佐に帰る。 万延元年(1860)武市に従って中国、九州で武術修行する。その途中、豊後岡藩で武市と別れ、以蔵のみ岡藩にとどまり直指流剣術を学ぶ。文久元年(1861)江戸に出て、翌年土佐に帰る。その後、武市の結成した土佐勤王党に加盟。しかし、なぜか後に名簿から削られている。武市の意向なのか分からないが、暗殺の現場には、武市の指示に従って進んで出ている。武市は、粗暴で愚鈍な(余りにも教養・道徳心に欠けている)以蔵を表だって置くことを良しとせず、裏方として暗躍(邪魔な人物を天誅)させたともいわれている。 土佐藩下目付けの井上佐一郎をはじめ、同志の本間精一郎や池内大学、森孫六・大川原重蔵・渡辺金三・上田助之丞などの京都町奉行の役人や与力、長野主膳(安政の大獄を指揮した)の愛人村山加寿江の子多田帯刀などを天誅と称して暗殺(村山加寿江は橋に縛りつけられ生き晒しにされた)。世間からは「人斬り以蔵」と呼ばれ薩摩の田中新兵衛と共に恐れられた。 八月十八日の政変後、勤王党は失速。武市が土佐に戻ると以蔵は土井鉄蔵と名を変え、一人京都に潜伏した。しかし元治元年6月頃(1864)幕吏に捕えられ入墨のうえ京洛追放、同時に土佐藩吏に捕われ国元へ搬送される。土佐藩では吉田東洋暗殺・京洛における一連の暗殺について土佐勤王党の同志がことごとく捕らえられ、上士格の武市瑞山を除いて厳しい拷問を受けた。以蔵も過酷な拷問に耐えたが、遂に全てを白状し、慶応元年5月11日(1865)打ち首、晒し首となった。辞世の歌は「君が為尽くす心は水の泡消えにし後ぞ澄み渡るべき」。墓所は高知県高知市薊野駅近郊の真宗寺山(しんしゅうじやま)にある累代墓地。俗名・岡田宜振として埋葬されている。 |
| 大田實 |
明治24年-昭和20年6月13日(1891-1945)日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。千葉県長生郡長柄町出身。旧制千葉県立千葉中学校より海軍兵学校41期入校。入校時成績順位は120名中第53位、卒業時成績順位は118名中第64位。 海軍における陸戦研究の第1人者として海軍陸戦隊指揮官を精勤した。 太平洋戦争最後の激戦であった沖縄戦の際に於ける海軍側代表として沖縄根拠地隊司令官であり米軍上陸時に約1万人の部隊を率いて沖縄本島小禄半島での陸戦を指揮したが米軍の攻撃を受けて司令部が孤立し那覇小禄地区豊見城にあった海軍壕内にて拳銃で自決。死後海軍中将に特別昇進する。 穏やかで包容力に富み、小事に拘泥せず責任感の極めて強い人物で、いかなる状況に遭遇しても一言の不満も漏らさず人を誹謗するような言行動は絶えてなかったといわれる。 陸軍の首里から摩文仁への撤退に際して、海軍司令部は作戦会議に呼ばれず、直前の5月24日ごろ(異説あり)になって初めて知らされたとされる。いったんは完全撤退と受け止め、重火器を破壊して南部への撤退を始めるが、後に「第32軍司令部の撤退を支援せよ」との命令を勘違いしたことがわかり、5月28日には再び小禄へ引き返した。6月2日に改めて「摩文仁へ撤退せよ」との命令が出されるが、大田は今度は従わなかった。命令を意図的に無視したのか、米軍に退路を断たれて撤退できなかったのかは不明である。 自決する直前の6月6日に海軍次官宛てに発信した電報は余りにも有名である。当時の訣別電報の常套句だった「天皇陛下万歳」「皇国ノ弥栄ヲ祈ル」などの言葉はなく、ひたすらに沖縄県民の敢闘の様子を訴えている。 ■海軍次官宛の電報[現代語訳] 沖縄県民の実情に関して、権限上は県知事が報告すべき事項であるが、県はすでに通信手段を失っており、第32軍司令部もまたそのような余裕はないと思われる。県知事から海軍司令部宛に依頼があったわけではないが、現状をこのまま見過ごすことはとてもできないので、知事に代わって緊急にお知らせ申し上げる。 沖縄本島に敵が攻撃を開始して以降、陸海軍は防衛戦に専念し、県民のことに関してはほとんど顧みることができなかった。にも関わらず、私が知る限り、県民は青年・壮年が全員残らず防衛のための召集に進んで応募した。残された老人・子供・女性は頼る者がなくなったため自分達だけで、しかも相次ぐ敵の砲爆撃に家屋と財産を全て焼かれてしまってただ着の身着のままで、軍の作戦の邪魔にならないような場所の狭い防空壕に避難し、辛うじて砲爆撃を避けつつも風雨に曝さらされながら窮乏した生活に甘んじ続けている。 しかも若い女性は率先して軍に身を捧げ、看護婦や炊事婦はもちろん、砲弾運び、挺身斬り込み隊にすら申し出る者までいる。 どうせ敵が来たら、老人子供は殺されるだろうし、女性は敵の領土に連れ去られて毒牙にかけられるのだろうからと、生きながらに離別を決意し、娘を軍営の門のところに捨てる親もある。 看護婦に至っては、軍の移動の際に衛生兵が置き去りにした頼れる者のない重傷者の看護を続けている。その様子は非常に真面目で、とても一時の感情に駆られただけとは思えない。 さらに、軍の作戦が大きく変わると、その夜の内に遥かに遠く離れた地域へ移転することを命じられ、輸送手段を持たない人達は文句も言わず雨の中を歩いて移動している。 つまるところ、陸海軍の部隊が沖縄に進駐して以来、終始一貫して勤労奉仕や物資節約を強要されたにもかかわらず、(一部に悪評が無いわけではないが、)ただひたすら日本人としてのご奉公の念を胸に抱きつつ、遂に‥‥(判読不能)与えることがないまま、沖縄島はこの戦闘の結末と運命を共にして草木の一本も残らないほどの焦土と化そうとしている。 食糧はもう6月一杯しかもたない状況であるという。 沖縄県民はこのように戦い抜いた。県民に対し、後世、特別のご配慮をしていただくことを願う。 |
| 松岡洋右 | 明治13年-昭和21年6月27日(1880-1946) 日本の外交官、政治家。日本の国際連盟脱退、日独伊三国同盟の締結、日ソ中立条約の締結など第二次世界大戦前夜の日本外交の重要な局面に代表的な外交官ないしは外務大臣として関与した。敗戦後、極東国際軍事裁判の公判中に病死。 松岡洋右 . |
| 林子平(六無斎) |
元文3年-寛政5年(1738-1793) 江戸時代後期の経世論家。高山彦九郎・蒲生君平と共に、「寛政の三奇人」の一人。名は友直。のちに六無齋主人と号した。 姉が仙台藩主伊達宗村の側室に上がった縁で兄とともに仙台藩の禄を受ける。 仙台藩でみずからの教育政策や経済政策を進言するも聞き入れられず、禄を返上して藩医であった兄の部屋住みとなり、北は松前から南は長崎まで全国を行脚する。長崎や江戸で学び、大槻玄沢、宇田川玄随(げんすい)、桂川甫周(ほしゅう)、工藤平助らと交友する。ロシアの脅威(きょうい)を説き、「三国通覧図説」「海国兵談」などの著作を著す。「海国兵談」の序を書いたのは、仙台藩医工藤平助であった。また「富国策」では藩の家老佐藤伊賀にあて藩政について説いたが、採用はされなかった。 「海国兵談」は海防の必要性を説く軍事書であったため、出版に協力してくれる版元を見つけることができなかった。そこで子平は、16巻・3分冊もの大著を自ら版木を彫っての自費出版にて世に問う決意をする。「海国兵談」は寛政3年(1791)仙台で上梓された。しかし、老中松平定信の寛政の改革がはじまると政治への口出しを嫌い、消極的外交策に立つ幕閣に目を付けられ、「三国通覧図説」も幕府の危険視するところとなり、両著はともに発禁処分が下され、「海国兵談」は版木没収の処分を受けることとなった。しかしその後も自ら書写本を作り、それがさらに書写本を生むなどして後に伝えられた。 最終的に、仙台の兄の下へと強制的に帰郷させられた上に禁固刑(蟄居・ちっきょ)に処され、そのまま死去する。蟄居中、その心境を「親も無し妻無し子無し版木無し金も無けれど死にたくも無し」と嘆き、自ら六無斎(ろくむさい)と号した。 「三国通覧図説」はその後、長崎よりオランダ、ドイツへと渡り、ロシアでヨーロッパ各国語版に翻訳された。それは地図の正確性には乏しく、特に本州・四国・九州以外の地域はかなり杜撰に描かれているものであったが、後にペリー提督との小笠原諸島領有に関する日米交渉の際に、同諸島の日本領有権を示す証拠となった。 |
| 河上彦斎 |
(かわかみ げんさい、天保5年- 明治4年 / 1834-1872 ) 尊皇攘夷派の日本の武士(熊本藩士)。諱は玄明(はるあきら)。
文久3年(1863年)、熊本藩親兵選抜で宮部鼎蔵らと同格の幹部に推される。一般的に「人斬り彦斎」などと呼ばれているが、彦斎が斬った人物で確実なのは佐久間象山だけで、後はいつ誰を何人斬ったのかは明確に伝わっていない。 容姿は、身の丈5尺前後(150cmほど)と小柄で色白であった為、一見女性の様であったという。剣は我流で、片手抜刀の達人(片膝が地面に着くほど低い姿勢からの逆袈裟斬り)であったと伝えられている。 伯耆流居合を修行したという説もあるが、その根拠となっているのは、当時、熊本藩で最も盛んだった居合が伯耆流だったという事と、所作こそ異なれど伯耆流には逆袈裟斬りの業が多い点が、その理由として挙げられている。 八月十八日の政変後、長州へ移り、三条実美の警護を務める。その後、元治元年(1864年)6月の池田屋事件で新選組に討たれた宮部鼎蔵の仇を討つべく再び京へ向かう。7月11日、公武合体派で開国論者の重鎮、佐久間象山を斬る。この象山暗殺以降、彦斎は人斬りを行なっていないとされている。 第二次長州征伐の時、長州軍に参戦、勝利をあげる。慶応3年(1867年)に帰藩するが、熊本藩は佐幕派が実権を握っていた為投獄される。このため、大政奉還、王政復古、鳥羽・伏見の戦いの時期は獄舎で過ごす。慶応4年2月出獄。佐幕派であった熊本藩は、彦斎を利用して維新の波にうまく乗ろうとするが彦斎は協力を断る。 維新後、開国政策へと走る新政府は、あくまでも攘夷を掲げる彦斎を恐れた。二卿事件への関与の疑いをかけられ、続いて参議・広沢真臣暗殺の疑いをかけられ明治4年(1872年)12月斬首。しかし、この暗殺事件に彦斎は無関係といわれており、新政府の方針に従わなかった為の斬首とみられる。 戒名を『應観法性居士』。墓は池上本門寺。また、京都の妙法院と熊本の桜山神社に仮墓が一つずつある。 人物像 / 平生は礼儀正しい温和な人物であるが、反面平気で人を切る残忍性も併せ持っていた。勝海舟は「河上はそれはひどい奴サ。コワクテコワクテならなかったよ」「会話の中に誰それが野心があるというのが出るとハハアそうですかなどと空嘯いてとぼけているが、その日スグト切ってしまう。そしてあくる日は例のごとくチャンとすまして来て、少しも変わらない。喜怒哀楽をあらわれずにだよ」とその恐ろしさを説明している。あまりのひどさに勝が切りすぎだと抗議すると、河上は「ソレハあなたいけません。あなたの畠に作った茄子や胡瓜は、どうなさいます。善い加減のときにちぎって、沢庵にでもおつけなさるでしょう。アイツラはそれと同じことです。」「いくら殺したからと言って何でもありません。」と反論したという。だが、海舟は、竹添進一郎がそんな非情な人物ではないと弁護していたことも紹介している(勝海舟『海舟座談』)。 |
 

 |
|
| 鶴姫 1 |
伝説上だけの女性かもしれない。その伝説さえも現代になってから作られたものの可能性がある。それを承知してはいるのだが、あえて鶴姫(1526?-1543?)を採り上げることにした。
●わが恋は三島の浦のうつせ貝 むなしくなりて なをぞわづらふ 私の恋は、まるで三島の浜辺の空貝のよう。虚しくて、彼の名を思い浮かべるだけでとてもつらい。 この『戦国百人一首』をまとめるに当たってかなりの数の辞世に触れたが、「辞世」だというのに、この歌ほどストレートに「恋」について詠んだものはまだ他に出会っていない。鶴姫は、伊予国大三島(現在の愛媛県今治市大三島)にある大山祇神社(おおやまずみじんじゃ)の第31代大祝職・大祝安用(おおほうりやすもち)の娘だ。戦国時代、島を守るために三島水軍の女武将として戦った。当時、中国・九州地方では周防の大内氏が力を拡大しつつあり、瀬戸内海へも進出しようとしていた。大祝家当主の大祝安用は大山祇神社の神職だったため、戦の折は自ら戦場に赴かず、一族の者を陣代として戦場に派遣していたという。1541年、大内氏の軍が大三島に侵攻。当時大祝職は長男の安舎だった。河野氏、来島氏との連合軍で大内軍を迎え討つべく、陣代として2男の安房が三島水軍を率いて出陣。だが、安房は討死した。そこで鶴姫が立ち上がった。美しいが同時にたくましく育った少女・鶴姫は仲間を引き連れ軍に加わったのだ。大薙刀を振るって活躍し、その年2度も大内軍を撃退したのである。しかし1543年、どうしても瀬戸内海を勢力下に置きたい大内義隆は、もう一度大三島を襲撃した。またもや鶴姫は、新たな陣代となった彼女の恋人・越智安成と共に戦ったが、その安成が討死してしまった。大祝職の安舎は、ついにあきらめ、大内氏との講和を結ぶことを決断。だが、鶴姫は残った兵を集め、今一度沖で停泊している大内軍に夜襲を掛け、大三島から追い出すことに成功した。しかし恋人を亡くした鶴姫は、生きる望みを失い入水自殺して18年の生涯を閉じたのである。これらは全て伝説だが。今も、大山祇神社には、多くの武将たちが奉納した武具が多く残されている。源義経や頼朝が奉納したという国宝の鎧などが有名だ。それらと共に展示されているのが「鶴姫所用の鎧・紺糸裾素懸威胴丸」だ。胸部が膨らみ、腰の辺りが細く締まっている細身の鎧である。ぱっと見て素人でも「女性用の鎧か?」と思うほど、明らかに他の鎧とは違った形状である。だが専門家によると、実は中世の甲冑が男女それぞれに作り分けられたことはないという。女性用の甲冑に見える当該の鎧も、より実戦的な甲冑が作られていった過程におけるデザインの一つらしい。つまり男が着用する鎧だ、とのことだ。確かに、展示されている甲冑類の中には、他にも腰の部分が締まった細身のものも見られるのだが。研究結果は尊重したいが、「鶴姫の鎧」の細さ、デザインに一瞬「女性ものか?」とはっとするのも事実だ。本当の持ち主は鶴姫なのか、それとも別の人物か。展示ケースの中の青い鎧は何も言わない。 |
| 鶴姫 2 |
鶴姫は大山祇神社の大祝職(大宮司)・大祝氏の娘。兄に大祝安舎と大祝安房がいます。父・安用は顔立ちが整った体格が良い鶴姫をことのほか可愛がりました。幼い頃より神道書や連歌、琴、さらに武術や兵法を習わせたとされます。鶴姫が八歳のときに父・安用が病死し、大山祇神社のしきたりで大祝安舎は大祝職、大祝安房は大三島を警護する水軍大将・祝職を継いで三島城の陣代になります。大三島は中国地方の守護大名・大内義隆の攻略を受けていました。1541年6月に大内氏配下の水軍の将・白井房胤らが攻め寄せます。次兄の安房が陣代となって出陣河野氏や来島氏と連合して大内軍を打ち負かしました。この戦いで次兄の安房が討死。鶴姫が十六歳のときでした。同年10月に再び大内軍が攻め寄せます。このとき陣代として三島水軍を率いたのは鶴姫でした。(鶴姫の幼なじみである越智安成が率いたともいわれています)
鶴姫と越智安成は安房の遺志を継いで大内軍に戦いを挑みました。鶴姫は早船(小型船)を率い奇襲をかける作戦を決行します。鶴姫は「我は三島明神権化の者なり、我と思わん者は出だせたまえ」と大声を張り上げ長刀を振るいます。敵将を何人も討ち取るなど活躍して大内軍を撃退しました。鶴姫は思いを寄せ合う越智安成と力をあわせ三島水軍を再建します。1543年6月二度の敗北に業を煮やした大内義隆は、陶隆房の軍勢をもって、大三島に攻め寄せます。過去二回の合戦に敗れている大内軍はあらゆる兵力を結集してきました。鶴姫と越智安成は早船を率い全力で迎え撃ちますが敗色が濃くなります。鶴姫たちの退却の時間を稼ぐために越智安成は早船に乗り、敵の将船をめがけて突撃。この戦いで越智安成は討死しました。これを受けて大祝職の安舎は大内氏との講和を決断します。しかし鶴姫はもう一度、残存兵力を集結させると大内軍に夜襲を仕掛けました。大内軍は不意を突かれ壊走。鶴姫は大三島を守り抜きました。戦死した越智安成を想う鶴姫は戦いのあとに三島明神への参籠を済ませると、ただ一人小舟を沖へ漕ぎ出し、入水したと伝えられています。十八歳の生涯でした。 |
| 鶴姫 3 | 戦国時代の伊予(現・愛媛県)にいたとされる伝承上の女性。1966年(昭和41年)に小説『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』が発表されてから知名度が上がった人物で、同書が出版されるまでは小説の舞台である大三島の島民さえも彼女のことを知らなかった。鶴姫は、現在では大三島の観光業に大いに利用されるコンテンツとなっているが、その実在性をめぐり疑問や指摘、批判も挙がっている。 |
|
■概要
鶴姫は、瀬戸内海の大三島にある大山祇神社の大祝職(大宮司)・大祝安用(おおほうり やすもち)の娘で、兄に大祝安舎(やすおく)と安房(やすふさ)がいたとされる。 彼女の生涯は、たびたび大三島に侵攻した周防の大内氏の軍勢に対して兵を率いて立ち向かい、交戦してこれを撃退するも、最期は戦死した恋人・越智安成(おち やすなり)の後を追って自殺したという「鶴姫伝説」として知られている。また、大山祇神社は併せて、同社が所蔵する重要文化財の紺糸裾素懸威胴丸(こんいとすそすがけおどしどうまる)は鶴姫が使用したもので、日本に唯一現存する女性用に作られた鎧であると主張している。 しかし、「鶴姫伝説」が広まった発端は、大祝家の末裔である三島安精(みしま やすきよ)が1966年(昭和41年)に著した小説『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』にあり、同書が発表されるまで、鶴姫の存在は大三島の島民にすら知られていなかった(「鶴姫伝説」の知名度上昇の経緯にて後述)。加えて、鶴姫の実在性やその事績については、当時の中国・四国地方の歴史的状況に基づく観点から疑問が出されており、三島が『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』を執筆する際に典拠とした文献であるという『大祝家記』(おおほうりかき)も、現在は行方不明で確認できないという問題を抱えている。さらに、紺糸裾素懸威胴丸が鶴姫の用いた女性用の鎧であるとする大山祇神社による言説も、三島が同書中にて提唱したのがその最初、つまり1966年から登場したもので、一部の甲冑武具研究者は、神社側の主張に対して否定的・批判的な見解を表明している。なお、大三島の下条地域には「おつるさん」という小さな祠があるが、関係は不明である。 |
|
|
■時代背景
戦国時代、周防の大内氏が中国・九州地方で勢力を拡大し、伊予の河野氏の勢力下である瀬戸内海へもその勢いが拡大の一途を辿っていた。大山祇神社の大祝職たる大祝家当主は、神職を務める立場から戦場に赴くことはなかったが、戦が起きた場合は一族の者を代理役の陣代に立てて派遣していた。1522年(大永2年)に大内氏が大三島へ侵攻してきた際には、鶴姫の兄・安舎が父・安用の陣代として出陣し、大祝家と同じく越智氏に出自する河野氏や村上水軍の援護を受けて大内軍を撃退したという(第一次大三島合戦)。 |
|
|
■鶴姫の生涯―「鶴姫伝説」―
■鶴姫の生い立ち 『大祝家記』によれば、鶴姫は1526年(大永6年)正月、伊予・今治の別名にあったという大祝家屋敷にて、大山祇神社第31代大祝職・大祝安用とその女中・妙林との間に生まれたとされる。彼女は顔立ちが整った大きな女児で、生後百日足らずで声を上げて笑い、成長すると力量・体つきも優れて男子も及ばぬほどの勇気を備えるに至り、人々から明神の化身ではないかと噂されたという。父・安用はそんな鶴姫を寵愛し、幼時より武術や兵法を習わせたとされる。 ■大内氏との戦いと鶴姫の活躍 1541年(天文10年)6月に大内氏配下の水軍の将・白井縫殿助房胤らが侵攻すると、大祝職となった長兄・安舎に代わって次兄の安房が陣代となって三島水軍を率いて出陣し、河野氏や来島氏と連合して大内軍を迎撃するも討死した。兄の戦死を聞いた鶴姫は三島明神に祈請し、明神を守護しようとして甲冑を着て馬に乗り、大薙刀を振るって敵陣へ駆け込むと味方を奮起させ、大内軍を撃退したという。同年10月にも大内氏が侵攻すると、戦死した安房に代わって16歳の鶴姫が出陣し、大内軍を撃退したとされる。この戦で、鶴姫は甲冑の上に赤地の衣を羽織って早舟に乗り込み、これを見て遊女が近づいてきたと誤認し油断した敵方に攻撃を仕掛け、敵船に乗り移ると素早く敵将の小原中務丞隆言を捕えて「われは三島明神の鶴姫なり、立ち騒ぐ者あれば摩切りにせん」と啖呵を切って小原や敵兵を討ち取り、焙烙や火矢を放って大内軍を追い払ったという。彼女はまた、この戦いの後に安房の跡を継いで陣代となった、安舎配下で一族の越智安成とやがて恋仲になったとされる。 ■恋人・越智安成の戦死と鶴姫の最期 1543年(天文12年)6月、2度の敗北に業を煮やした大内義隆は、陶隆房の水軍を河野氏の勢力域に派遣し、瀬戸内海の覇権の確立を目論んだ。河野氏とその一門は全力で迎え撃つが、多勢の大内軍の前に多くの一族が討たれ、鶴姫の右腕で恋人でもあった安成も討死した。これを受けて大祝職の安舎は大内氏との講和を決断したが、鶴姫は残存兵力を集結させると島の沖に停泊中の大内軍に夜襲を仕掛けて壊走させ、大三島から追い出した。しかし、戦死した安成を想う鶴姫は、戦いの後に三島明神への参籠を済ませると沖合へ漕ぎ出し、そこで入水自殺して18歳の生涯を終えたと伝わる。鶴姫は辞世の句として「わが恋は 三島の浦の うつせ貝 むなしくなりて 名をぞわづらふ」と詠んだといい、『大祝家記』にある彼女の伝記は「鶴姫入水したまう所、鈴音いまに鳴り渡るという也」という一文で締め括られているとされる。ただし、『大祝家記』は戦後の彼女の動向について、自殺以外の2つの別伝も掲載しているという。1つは今治の大祝家屋敷に戻って祈祷に明け暮れる生活を送ったというもの、もう1つは今治の別宮宮司の大祝貞元の子・八郎安忠(のち安舎養子となり大祝職を継ぐ)に嫁いだとするものである。 |
|
|
■紺糸裾素懸威胴丸―「伝・鶴姫所用の鎧」―
大山祇神社が所蔵する紺糸裾素懸威胴丸は、1901年(明治34年)3月27日に「紺糸威胴丸」の名称で、他の甲冑とともに「甲(よろい)52領」として古社寺保存法に基づく国宝(いわゆる「旧国宝」、現在の重要文化財)に一括指定された。その後、1969年(昭和44年)6月20日付で従前一括指定されていた上述の「甲」は1点ずつ分割指定され、「紺糸威胴丸」は現行の「紺糸裾素懸威胴丸」に名称変更された。 紺糸裾素懸威胴丸は、黒漆塗盛上本小札(ほんこざね)を紺糸で威すが、胴部は鉄札と革札の1枚交ぜで毛引威(けびきおどし)、草摺(くさずり)は革札で素懸威(すがけおどし)にて仕立てる。胴の立挙(たてあげ)は前2段、後3段、衝胴(かぶきどう)は5段で、草摺の間数および段数は11間5段であり、兜・大袖は欠いている。寸法については、胴高は胸板より胴尻までが35cm・背中の押付より胴尻までが39.5cm、胴廻りは立挙部が108cm・胴尻部が75cm、草摺の長さは32.5cm、小札は一枚あたり長さ6.9cm・幅1cmである。胸板(むないた)など金具廻(かなぐまわり)には黒漆塗皺韋を貼って小桜鋲を打ち銅覆輪をかけ、耳糸(みみいと)・畦目(うなめ)および花緘(はながらみ)には白糸を、菱縫(ひしぬい)には紅韋を用い、後立挙二の板に紅の総角を結び下げる。重量は飾り台も含めて8.0kgである。 これらの点から、画家で甲冑研究家の山田紫光は、同鎧は当世具足が出現する以前の様式のもので、室町時代末期の天文から永禄年間に製作されたと推定している。 同鎧の外観の大きな特徴としては、胸部が大きく膨らんでいる一方で腹部が腰に向かって細くすぼまり、草摺の間数が一般的な胴丸のそれより多く、脇部分が「仕付脇引」(しつけわきびき)と呼ばれる特殊な構造をとっていることが挙げられる。三島安精は、胸部が膨らみ腰部がすぼまった胴の形状は女性の体形を反映したものと考え、それをもとに『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』を執筆・発表した。これに続いて神社も同説を掲げ、日本に現存する唯一の女性用の鎧であると唱えるようになった。 |
|
|
■「鶴姫伝説」の知名度上昇の経緯
三島安精は1963年(昭和38年)に紺糸裾素懸威胴丸を観察した際、胸部が大きく膨らんで腰部が細くすぼまった胴の形状を見て、同鎧は女性用の鎧ではないかと思い付いた。三島は次いで、大祝家の事績を綴った社伝の『大祝家記』という文献に記されているとされる「鶴姫の比類無き働き、鎧とともに今に伝はるなり」という一節と同鎧を結び付けて考え、紺糸裾素懸威胴丸は鶴姫が着用した鎧で、父の大祝安用が彼女のためにあつらえたものであるとする説を提唱したうえで、『大祝家記』に記載されているという鶴姫の伝記の内容と紺糸裾素懸威胴丸についての自身の着想とを結び合わせ、豊富なフィクションで脚色した悲劇ロマンス小説の『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』を1966年に執筆・出版した。 同書の刊行から2年後の1968年(昭和43年)、甲冑武具研究家の笹間良彦が、三島や大山祇神社側の見解を「直感」で肯定して紺糸裾素懸威胴丸を着用した姿の鶴姫の肖像画を描き、同社へ奉納したところ、これが人気を集め、同画は大三島の観光ポスターや地酒のラベル、土産物の煎餅や饅頭の箱のデザインに広く利用されるようになった。これにより、それまで島民さえもその存在を知らなかった鶴姫は「大三島の観光の宝」ないし「島のシンボル」的存在としてその知名度を高めていき、1990年(平成2年)3月には、ふるさと創生事業の下で「国宝とロマンの島」をキャッチフレーズに町のイメージ形成に注力していた当時の大三島町(現・今治市)により彼女の銅像が藤公園に設置された。さらに1993年(平成5年)、『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』を原案としたテレビドラマ『鶴姫伝奇 -興亡瀬戸内水軍-』が放映されたことで、鶴姫の名は全国的に知られるようになった。 大三島では、1995年(平成7年)より鶴姫の一生を題材にした「三島水軍鶴姫まつり」が毎年行われている。そのほか、2009年(平成21年)4月から2010年(平成22年)3月にかけて、ミュージカルの『鶴姫伝説-瀬戸内のジャンヌ・ダルク』(高橋知伽江作・作詞)が愛媛県東温市の坊っちゃん劇場にてわらび座により1年間ロングラン公演され、のべ8万7千人余を動員した(2014年(平成26年)11月より2016年(平成28年)1月まで再演)。 |
|
|
■「鶴姫伝説」の真偽をめぐる疑義・問題
上記の通り、「鶴姫伝説」は1966年の小説発表後から平成初めにかけて、観光や各種メディアによる紹介を通じて知名度を高め、関連行事も催されるようになり、大山祇神社所蔵の紺糸裾素懸威胴丸も「女性用の鎧」として知られるようになった。しかし、「鶴姫伝説」の真偽については主に歴史的・史料的観点から、紺糸裾素懸威胴丸を「女性用の鎧」とする言説は甲冑研究の分野から、いずれも否定されている。1988年(昭和63年)時点ではあるが、当の大山祇神社の宮司ですら、鶴姫の伝承にはいまだ確たるものがないと証言しており、郷土史家の喜連川豪規(きれがわ ひでき)も、鶴姫について「鎧が生んだお姫さま」とコメントしている。小説家の和田竜は、著書『村上海賊の娘』において、主人公の景(村上武吉の娘)が憧れる女性として鶴姫を登場させているが、「鶴姫伝説」については「観光資源なので、大事にしないといけない」と置きつつも「僕は正直、創作だと思ってるんですよね。なので小説の中では幻だ、という書き方をしました」と述べている。 ■歴史的・史料的観点からの指摘 三島安精が『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』の執筆にあたって下敷きにしたという『大祝家記』は、三島によれば江戸時代後期の1761年(宝暦11年)正月に大祝安躬が同家相伝の記録や口伝の書をまとめて著した「門外不出」の家記であり、文体は『予陽盛衰記』に似ているとされる。彼が小説執筆時に実際に参照したのは、さらに祖父の安継が1876年(明治10年)頃に原本を書写したものであるというが、大山祇神社は『大祝家記』の所在を確認しておらず、三島が所持・使用していたという安継による写本も、彼の没後は行方が明らかでない。大山祇神社の大祝職を務めた大祝家(現・三島家)に伝来した『三島家文書』には大三島合戦に関する文書も含まれるが、『大祝家記』と異なり、その中に鶴姫もしくは女性が合戦に加わり、水軍を率いて大内軍と交戦したとする記述はそもそも見当たらない。『三島大祝家譜資料 全 三島家蔵版』(1912年(大正元年)刊)には、1541年6月の合戦では大三島側が勝利したとあるが、鶴姫が大内氏の武将・小原隆言を討ち取ったとされる同年10月の合戦(先述)については記されていない。小原の足跡に関しては、『大内氏実録』巻29に「(天文)十年六月十八日、また伊予へ赴き、七月二六日まで滞在して三島(大三島)、甘崎、岡村、能島、印島(因島)に戦ふ」とある一方、同書には鶴姫に討たれたはずの1541年10月より後の行動についても記されており、小原は大内氏滅亡後に毛利元就に臣従している。作家の鷹橋忍はこれに加えて、鶴姫が最後に戦った1543年6月の合戦については一次史料が存在しない上、この時期の大内氏は第一次月山富田城の戦いで出雲の尼子氏に敗北し、かつ義隆の養嗣子・晴持が死亡した直後で、安芸・備後の尼子方勢力に対して備える必要があっても伊予にまで戦線を広げる理由がないと指摘している。さらに、義隆が1544年(天文13年)9月23日付で剣や神馬などを大山祇神社へ奉納した旨の文書が残る。これは大三島が彼の支配下に入ったことの宣言とも解釈され、作家の跡部蛮は、記録は残っていないが大三島側は2度目の合戦で大内氏に敗れており、義隆への配慮から抗戦した鶴姫の存在を秘匿せねばならなかったが、江戸時代になってから私的な史料の『大祝家記』上で、誇張を交えながらも彼女の活躍を伝え残そうとしたのではないか、と推測している。なお、江戸時代当時の大祝家は、1658年(万治元年)に安躬の高祖父である安長が社家との間に相論を構え、松山藩により大祝職を17年間停止されて以降、社家の一部と対立関係が続いていた。安長の後、大祝職への復帰が許された安朗(安躬の祖父)も、有力社家と摩擦を起こして藩に訴えられた末に藩領内からの追放を命じられ、一時は大祝家が一家ごと大坂に移住し浪人生活を余儀なくされる事態が発生していた。さらに代が下ってなおも、安躬自身が社家側との間に争いや訴訟を抱えていた。鷹橋は、『大祝家記』が執筆された動機として訴訟を大祝家の方へ有利に導こうとする意図があったのではないかとみて、藩や社家に対して正当性を訴えたい大祝側が、自らを仮託して鶴姫という悲劇の生涯を歩んだ人物を生み出したのではないかと推察している。その他、「鶴姫伝説」は神功皇后の三韓征伐伝説をもとにして作られたのではないかとする指摘もある。 ■紺糸裾素懸威胴丸は「女性用の鎧」ではないという指摘 上記の通り、紺糸裾素懸威胴丸については、三島安精が『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』を発表して以降、大山祇神社側により鶴姫が使用した女性用の鎧であると主張されるようになった。しかし、この説はあくまでも三島個人の思い付きによるもので、確実な記録や厳密な研究に基づいて導き出されたものではない。紺糸裾素懸威胴丸を着用した鶴姫の肖像を描き、「鶴姫伝説」の広まりを結果的に促進することとなった笹間良彦にしても、後に発刊した自著において同鎧を鶴姫が着用した女性用の鎧として紹介しているが、その説明の多くは三島の見解に依拠しており、笹間自身は同説を支持していながら、「直感」よりも具体的・論理的な論拠を特に示しているわけではない。これに対して、笹間と同じく日本甲冑の研究家ではあるが、山岸素夫や藤本正行は、そもそも中世(室町から戦国時代)の日本で作られた甲冑の中に女性用のものは見られないということを指摘している。とりわけ山岸は、室町時代末期に山城での攻防を中心とした徒立(徒歩)戦が一般化したことにより、徒立戦用の鎧である胴丸や腹巻には様々な工夫や形状の変化が施されるようになったということを、実際の甲冑遺品を多数調査した上で解き明かしている。それは、鎧を着用した将兵の活動や歩行の便の向上をはかるため、胴の胸回りを大きめに張り出して胸部に間隙を設けることで呼吸を楽にし、胴裾を腰骨に乗せるように細くすぼまった形に仕立てることで肩にかかる胴の重量を分散させ、長時間の甲冑着装に耐えうるよう疲労を減らすことを目指したものであった。つまり、室町時代末期の甲冑の胴は、敏捷に活動するために誇張した胸部と引き締まった腰部を備えた、軽快な逆三角形状の胴へ変化する傾向にあったのである。腰回りから大腿部にかけてを防御する草摺の間数も、それまでの定数は7間ないし8間だったのが、室町時代末期には9間・10間・11間とより細かく分割して足さばきを良くするようになった。これらの特徴は、紺糸裾素懸威胴丸と同じく室町時代末期に製作された他の遺品にも現れている。山岸は以上の指摘に加えて、大鎧・腹巻・当世具足など、一般に男性用とされる様々な甲冑を女性に試着させる実験を行ったが、いずれも問題なく着用できた結果をも挙げ、紺糸裾素懸威胴丸は三島安精ら大山祇神社側が主張するような「女性用の鎧」ではなく、室町時代末期の特徴が顕著に表れたものと理解すべきであると結論付けた。さらに彼は、(三島が考えたように)胸部が膨らみ腰がすぼまった胴の形をもって当該の鎧を女性用であると推定することについては、そうするならば室町時代末期の甲冑はすべて女性用になってしまうと批判し、それは「甲冑を知らぬ者の言である」と否定的な評価を下している。上記の山岸の批判を補う形で、鷹橋忍は「欧米化した女性ファッションに馴染んだ現代人の感覚をもって「婦人物」(レディース)と断じるのは、些か性急に思える」と述べている。その他、漫画家活動の傍ら歴史研究をも手がける本山一城も、大山祇神社宝物館を訪れた際のできごととして、「鶴姫の鎧」の話を信用した見学客が、展示してある別の室町時代後期の甲冑数点を指して、ここにもあそこにも女性用の鎧があると叫んでいたのを見かけたという話を『刀剣春秋』紙上に紹介して、神社の言説を問題視している。なお、江戸時代の大名家の一部においては、婚礼調度品の一つとして女性のための甲冑がまれに製作されたことがある。それらは基本的な構造が通例の男性用甲冑と変わらず、実際に着用されたかどうかも不明な、形式的なものでしかないが、彦根藩主井伊家伝来・弥千代所用の朱漆塗色々威腹巻(彦根城博物館所蔵)や松代藩主真田幸貫の正室・雅姫所用の魚鱗胴畳具足(真田宝物館所蔵)などをはじめいくつかが現存している。その点からも大山祇神社による「紺糸裾素懸威胴丸は日本に現存する唯一の女性用の鎧である」という主張は正確ではない。 |
|
| 高橋お伝 (贋作) |
後藤吉蔵の殺害現場に残されていたお伝の(書置)なるものが、折れ釘流の、しかも仮名ちがいの多い拙い文章であったのに、辞世となるとこのように流暢な歌ができるというのは、不思議というしかない。これらの辞世はすべて他人の創作である。前の三首は当時の「朝野新聞」の記者の手になるものであろうし、あとの一首は高橋でんなる女性をわが国毒婦伝中の代表的人物に祭り上げるのに多大な功績のあった元兇の一人、仮名垣魯文の作である。 悪女・毒婦 . |
| 夜嵐おきぬ 1 |
幕末から明治初期に実在した毒殺犯原田きぬ(はらだ きぬ、生年不詳、弘化元年(1844年)説 - 明治5年2月20日(1872年3月28日))をベースとして生まれた新聞錦絵等における登場人物及び後年製作された映画作品のタイトルである。原田きぬ本人については処刑の時に発行された『東京日日新聞』の資料があるが、正確な資料は少ない。夜嵐おきぬの物語は現実の原田きぬのそれというよりは、それに脚色を加えたフィクションである。木下直之は夜嵐おきぬの物語について「物語も画像も必ずしもキヌの事件に必ずしも内在する必要はなく、戯作者と絵師の判断に委ねられる」と述べている。夜嵐の異名は、お絹が処刑の際に詠んだとされる辞世「夜嵐のさめて跡なし花の夢」からきている。
1844年あるいは弘化年間前後の時代に、三浦半島城ヶ島の漁師・佐次郎の娘として生まれたらしい。彼女は16歳のときに両親と死別し、伯父に引き取られ江戸に出て芸妓になることになり「時尾張屋」において「鎌倉小春」と名乗りその美貌から江戸中の評判を取る。そのとき、大久保佐渡守(下野国那須郡烏山藩三万石城主)に見初められ、黒沢玄達(日本橋の医者)を仮親とし、大久保家の御部屋様(側室)となり、名を花代と改めた。安政4年(1857年)、世継ぎの春若を生んだが、その3年後に佐渡守が44歳で死去し、二人の新婚生活に終止符が打たれた。花代は当時の慣例に従って仏門に入りることになり、名を「真月院」と改め、亡き夫の冥福を祈る生活に入ったが、これは半ば強制されたもので、真の信仰心から仏門に入ったのではなかったので、そのような生活には馴染めず、やがて欝状態になり、勧める人があって箱根に転地療法に出かけることになった。同所で「今業平」の異名を持つ日本橋の呉服商紀伊国屋の伜、角太郎と出会うことになり、やがて二人は恋に落ちた。江戸に戻った後も二人の関係は続き、角太郎がきぬの元に通う生活が始まった。だが、そのような禁断の恋が許されるはずもなく、やがてその乱行不行跡が大久保家の知るところとなり、きぬは同家から追放された。その後、角太郎に縁談が持ち上がり、彼の足はおきぬから遠ざかっていった。 その後きぬは元の芸者の生活に戻ることになった。戊辰戦争時、旧幕府時御鷹匠であり、その後金貸し業を生業としていた東京府士族の小林金平が、明治2年おきぬを気に入り身請けした。そして彼は浅草の歌舞伎三座付近の猿若町に妾宅を設けおきぬを住まわすことにした。小林はきぬを溺愛し、彼女の求めるものなら何でも与えた。 彼女は歌舞伎役者の璃鶴(「璃鶴」は三代目嵐璃珏の俳名、後の二代目市川権十郎)との役者買いにのめり込み、恋人との結婚を願い、障害となる旦那である小林金平を殺鼠剤で毒殺した。逮捕、裁判にかけられたとき、彼女は妊娠しており、死刑判決を受けた後、出産まで刑の執行が延期され、小塚原刑場で処刑された。当時近代刑法が確立しておらず、断頭の後三日間梟首に処せられた。執行に際し残した辞世の句「夜嵐のさめて跡なし花の夢」から、きぬは「夜嵐おきぬ」と渾名で呼ばれるようになったと物語上はなっているが、実際のキヌは辞世を残してはいないという(『明治百話』上・p.32)。不義密通に対する罪で璃鶴は懲役3年だった。なお、蜂巣敦は大久保忠美がお絹を妾にしたが世継ぎが生まれたので捨てたところ、その放浪先で殺人事件を起こしたのだとこの事件の顛末を記述している。原田キヌの墓は東京都墨田区東駒形3丁目21番地、赤門福巌寺にある。 |
| 夜嵐おきぬ 2 |
(本名:原田きぬ) 明治5年2月20日(1872年3月28日)、東京浅草で女の生首が晒された。捨札にはこうある。「東京府貫属、小林金平ノ妾ニテ、浅草駒形町四番地借店、原田キヌ。歳二十九。此ノ者ノ儀、妾ノ身分ニテ嵐璃鶴ト密通ノ上、金平ヲ毒殺二及ビ候段、不届至極二付、浅草二於テ梟首二行フ者ナリ」
要するに、29歳の元芸者、原田きぬは妾の身分でありながら嵐璃鶴という歌舞伎役者と不義密通を重ねた上、主人を毒殺したために梟首(きょうしゅ=晒し首)を云い渡されたというわけだ。なお、現代人の我々には「妾の身分でありながら云々」は些か奇異に感じられるが、当時は妾を持つことは公然と認められており、妾といえども貞操を要求されたのである。事件を報じた2月23日付の『東京日日新聞』によれば、きぬは2月20日に小塚原刑場で処刑され、その日から3日間晒されたという。美人だったそうだ。そして、これまでに何人もの役者を手玉に取って来た毒婦であると断じている。しかし、この記事には金平がどのような方法で毒殺されたのかについては記されていない。おそらく殺鼠剤(=砒素)の類いを食事に混入されたのではあるまいか。また、『新聞雑誌』明治5年2月号によれば、きぬは逮捕された時に身籠っており、獄中で男子を出産し、身寄りに預けられたという。出産を待って処刑されたのだろう。この事件は巷では「夜嵐おきぬ」を呼ばれて大評判となった。元芸者の美人妾と美少年の歌舞伎役者という取り合わせが、市井の人々の心を掴んだのだろう。新聞雑誌は彼女のことを大袈裟に書き立て、3巻セットの読み物まで出版された。即日完売するほどの人気だったという。やがて芝居が上演され、繰り返し映画化もされた。新東宝の『毒婦夜嵐お絹と天人お玉』(57)が今のところの最後の映画化である。ちなみに「夜嵐」とは、浮気相手の芸名「嵐璃鶴」と、きぬの嵐の如き乱行ぶりを掛けたものとするのが定説である。きぬの辞世の句「夜嵐のさめて跡無し花の夢」から取ったとの説もあるが、彼女は辞世の句を残していない。この句は後の創作である。なお、浮気相手の嵐璃鶴もまた不義密通の罪で3年の徒刑を云い渡されている。釈放されたのは明治7年9月のことだ。その後は市川権十郎と名を改めて歌舞伎役者を続けたという。 |
| (未調査) | |
 ■死生観 |
|
|
■最澄 (767-822) 天台宗開祖
夏4月、もろもろの弟子たちに告げて言われた、「わたしの命はもう長くはあるまい。もしもわたしが死んだあとは、みんな喪服を着てはならない。また山中の同法(同門の弟子)は、仏のさだめた戒律によって、酒を飲んではいけない。 ただし、わたしもまた、いくたびもこの国に生れかわって、三学(戒・定・慧)を学習し、一乗(「法華経」の教え)を弘めよう |
|
|
■空海 (774-835) 真言宗開祖
迷いの世界の狂人は狂っていることを知らない 生死の苦しみで眼の見えないものは眼の見えないことが分からない 生れ生れ生れ生れても生の始めは暗く死に死に死に死んでも死の終りは冥い |
|
|
■源信 (924-1017) 天台宗学僧 仏弟子である君よ、この年ごろ、世俗の望みをやめ、西方浄土に往生するための行を修してきた。今、病床にあり、死を恐れないわけにはいかないであろう。どうか目を閉して合掌して、一心に誓いをたててください。「往生要集」 |
|
|
■法然 (1133-1212) 浄土宗開祖 ある弟子が尋ねた、「このたびは本当に往生なされてしまうのでしょうか」と。法然は答えた、「自分はもと極楽にいたものであるから、こんどはきっとそこへ帰る」 と。法然にとって極楽とは、帰るべき故郷であったのである。 |
|
|
■明恵 (1173-1232) 華厳宗の僧 われ如来の本意を得て、解説の門に入ることができた、汝等も如来の禁戒を保ち、その本意を得て、来世共に仏前で再会せん (弟子への訓戒) |
|
|
■親鸞 (1173-1262) 浄土真宗の開祖 自分はわるい人間であるから、如来のお迎えをうけられるはずはないなどと、思ってはならない。凡夫はもともと煩悩をそなえているのだから、わるいにきまっていると思うがよろしい。また、自分は心がただしいから、住生できるはずだと、思ってもならない。自力のはからいでは、真実の浄土に往生できるのではない。 |
|
|
■道元 (1200-1253) 曹洞宗開祖 「この生死は即ち仏の御命なり。これをいとい捨てんとすれば、即ち仏の御命を失わんとするなり。これにとどまりて、生死に着ずれば、これも仏の御命を失うなり。仏のありさまをとどむるなり」 |
|
|
■一遍 (1239-1289) 時宗の開祖 六道輪廻の間には ともなふ人もなかりけり 独りうまれて独り死す 生死の道こそかなしけれ |
|
|
■宗峰妙超 (1281-1337) 臨済宗の僧 「仏祖を截断し吹毛常に磨く機輪転ずる処虚空牙を咬む」 (仏祖さえも否定超克して吹毛の剣にも比せられる性根玉をいつも磨いてきたその心の機は虚空が牙を咬むとも言える、空が空を行じる心境と言えよう) |
|
|
■一休 (1394-1481) 臨済宗の僧 「そもそもいづれの時か夢のうちにあらざる、いづれの人か骸骨にあらざるべし。それを五色の皮につゝみてもてあつかふほどこそ、男女の色もあれ。いきたえ、身の皮破れぬればその色もなし。上下のすがたもわかず。……貴きも賎しきも、老いたるも若きも、更に変りなし。たゞ一大事因縁を悟るときは、不生不滅の理を知るなり」 |
|
|
■蓮如 (1415-1499) 浄土真宗中興の祖 それ、人間の浮生なる相をつらつら観ずるに、おおよそはかなきものは、この世の始中終まぼろしのごとくなる一期なり。…我やさき、人やさき、今日とも知らず、明日とも知らず、遅れ先立つ人は、もとのしずく、すえの露よりもしげしといえり。されば朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり。…されば、人間のはかなき事は、老少不定のさかいなれば、誰の人も、はやく後生の大事を心にかけて、阿弥陀仏を深くたのみまいらせて、念仏もうすベきものなり。あなかしこ、あなかしこ 「白骨の文」 |
|
|
■沢庵 (1573-1645) 臨済宗の僧 全身を後の山にうずめて、只士をおおうて去れ。経を読むことなかれ。斎を設くることなかれ。道俗の弔賻 (おくりもの)を受くることなかれ。衆僧、衣を着、飯を喫し、平日のごとくせよ。塔を建て、像を安置することなかれ。謚号を求むることなかれ。木牌を本山祖堂に納むることなかれ。年譜行状を作ることなかれ。 |
|
|
■鈴木正三 (1579-1655) 江戸時代の禅僧 万事をうち置て、ただ死に習うべし。常に死を習って、死に余裕を持ち、誠に死する時に、驚かぬようにすべし。人を教化し仏法を知る時にこそ、知恵は必要だが、我が成仏の為には、何も知識はあだなり。 ただ土と成りて、念仏をもって、死に習うべし 「驢鞍橋」 |
|
|
■盤珪 (1622-1693) 臨済宗の僧 身共は、生死に頼らずして死まするを生死自在の人とはいいまする。又、生死は四六時中に有て、人寿一度、臨終の時、はかりの義では御座らぬ。人の生死に預からずして、生るる程に、何れも生き、又死るゝ程に、死が来らば、今にても死る様に、いつ死んでも大事ない様にして、平生居まする人が、生死自在の人とは云、又は、霊明な不生の仏心を決定の人とは云まする 「説法」 |
|
|
■白隠慧鶴 (1685-1768) 臨済宗の僧 涅槃の大彼岸に到達しようと思えば、つつしんで精神を集中して、それぞれの臍下、気海丹田を黙検せよ。そうすれば、まったく男女の相もなく、僧俗の区別もない。老幼、貧富、美醜、地位の高下なぞの差別の一点の痕跡もなくなる。このように精神を集中して、細かく工夫精進して昼夜おこたることがなければ、いつしかあれこれ考える想いもつき、妄情煩悩も消えて、盆をバラバラに投げこわし、氷の塔をぶちこわすように、たちまち身心ともに打失しよう 「仮名葎」 |
|
|
■良寛 (1758-1831) 曹洞宗の僧 形見とて何か残さん春は花 夏ほととぎす秋はもみじ葉 |
|
|
■西行 (1118-1190) 歌人 願はくは花のしたにて春死なん そのきさらぎの望月のころ |
|
|
■吉田兼好 (1283-1352) 歌人 誰でもみんな、本当にこの生を楽しまないのは、死を恐れないからだ。いや、死を恐れないのではなくて、死の近いことを忘れているのだ。しかし、もしまた、生死というような差別の相に捉われないと言う人があるなら、その人は真の道理を悟り得た人と言っていい 「徒然草」 |
|
|
■熊沢蕃山 (1619-1691)陽明学者 生死は終身の昼夜であり、生死は終身の昼夜であり、昼夜は今日の生死にあたる。生死の理も、昼夜を思う ごとく、常に明かにすれば、臨終とても別儀は無い。薪つきて入滅するごとく、寝所に入で心よく寝るが如く、何の思念もなく、只明白なる心ばかりである。 「集義和書」 |
|
|
■伊藤仁斎 (1627-1705) 儒者 天地の道は、生有って死無く、実有って散無し。死は即ち生の終り、散は即ち実の尽くるなり。天地の道、生に一なるが故なり。父祖身投すといへども、しかれどもその精神は、すなはちこれを子孫に伝へ、子孫又これをその子孫に伝へ、生生断えず、無窮に至るときは、すなはちこれを死せずといいて可なり 「語孟字義」 |
|
|
■新井白石 (1657-1725) 政治家・学者 礼は生を養い死を送り鬼神につかうるところとなりとぞ「礼」に記せり。又明にしては礼楽あり、幽にしては鬼神ありとも侍り。幽と明とは二つなるに似たれと、誠は其理一つにこそはかよふらめ。是により通せば彼にも又通じぬべき 「鬼神論」 |
|
|
■山本常朝 (1659-1721) 佐賀藩士 二つ二つの場にて、早く死ぬかたに片付くばかりなり。別に仔細なし。胸すわって進むなり。図に当らぬは犬死などといふ事は上方風の打ち上りたる武道なるべし。二つ二つの場にて、図に当るやうにわかることは、及ばざることなり 「葉隠」 |
|
|
■本居宣長 (1730-1801) 国文学者 「死すれば、妻子眷族朋友家財万事をもふりすて、馴れたる此世を永く別れ去りて、再び還来ることあたはず、かならずかの汚きよみの国に行くことなれば、世の中に、死ぬる程かなしき事はなきものなる…」 |
|
|
■山片蟠桃 (1748-1821) 町人学者 生れば智あり、神あり、血気あり、四支・心志・臓腑みな働き、死すれば智なし、神なし、血気なく、四支・心志・臓腑みな働くことなし。然らば何くんぞ鬼あらん。又神あらん。生て働く処、これを神とすべき也 「夢之代」 |
|
|
■広瀬淡窓 (1782-1856) 漢学者 生死は人の能く知る所に非ず。いわんやすでに死の後をや。死後の知るべからざる、なほ生るる前の如きのみ。 「約言」 |
|
|
■横井小楠 (1809-1869) 政治思想家 人と生れては人々天に事ふる職分なり。身形は我一生の仮託、身形は変々生々して此道は往古来今一致なり。故に天に事ふるよりの外何ぞ利害禍福栄辱死生の欲に迷ふことあらん乎 「沼山閑話」 |
|
|
■正岡子規 (1867-1902) 俳人 「余は、今迄禅宗の悟りということを誤解していた。悟りということは、如何なる場合にも平気で死ねる事かと思っていたのは間違いで、悟りという事は、如何なる場合にも平気で生きて居ることであった。」 |
|
|
■暁鳥敏 (1877-1954) 真宗大谷派の僧 生と死のうねりをなして常住の いのちの水の流れゆくなり 無二寿をおもう心に死を超えて 生もおもはずたゞほがらかに |
|
|
■種田山頭火 (1882-1940) 俳人 何処でも死ねる体で春風 何時でも死ねる草が咲いたりみのったり |
|
|
■室生犀星 (1889-1962) 詩人・小説家 人間の永い生涯には妻が先に死んでくれた方がいいと、ちょっとでも考えない人があっただろうか、その夫が若し先に亡くなったら、ああしよう、こうしようと死後の策を考えない婦人があっただろうか、折々職しっかりした眼附と身構えを持って見合せた眼こそは、たしかに今まで生きて来た善後策を講じかかる、のっぴきならない眼附だったのである。どちらかが生きのこった時には、先ず後始末をしなければならないのである。「生きたものを」 |
|
|
■堀秀彦 (1902-1987) 評論家 老年も死も、よく分からないから不気味であり、よく分からないから、何かが在るようにも思われる。そしてそれだからこそ、生命は尊厳なのだ。 「死」 |
|
|
■吉野秀雄 (1902-1967) 歌人 死はほんとうにおそろしい。わたしは年60余になったし、これまでになんども死にそこねたような病人だから、もはやいつ死んでもかまわぬといえる覚悟がありそうなものだが、それがなかなかそうはいかず、死はいまもっておそろしい。 「生のこと死のこと」 |
|
|
■高見順 (1907-1965) 作家 電車の窓の外は 光りにみち 喜びにみち いきいきといきづいている この世ともうお別れかと思うと 見なれた景色が 急に新鮮に見えてきた 「死の淵より」 |
|
|
■松田道雄 (1908-) 評論家 生きるということは、世の中のつまらなさとは無関係なのだ。死にたくないから生きているというだけのことだ。そのかわり生きていきたくなくなったら、いつだっておさらばするというのが、市民の自由というものだ。 「老人と自殺」 |
|
|
■花田清輝 (1909-1974) 評論家 しかし、そうはいうものの、やはりわたしは、人眼をかすめて、とろとろと燃えつきてしまうような死にかたよりも、猛烈ないきおいで燃えあがり、派手にあたりに火の粉をバラまいたあとパッと消えてしまうような死にかたのほうに心をひかれる。 「犬死礼讃」 |
|
|
■村尾勉 (1914-)医学博士 一生を頑健に生きたような人は、木が次第に枯れてゆくように、あるいは朽木がいっきに倒れるように、きわめてあっけなく安楽な死を遂げるものである。 「死を受け容れる考え方」 |
|
|
■瀬戸内晴美 (1922-) 小説家、仏子号「寂聴」 いずれは逃げられない私の死に様は、果してどの様なものか、どんな変死にせよ、やはりあんまり人の目に不様でない死に様を願うのは、まだ私がしやれ気のある若さの証拠であるかもしれない。 「死に様」 |
|
|
■野坂昭如 (1920-) 小説家 人間は年中死を意識している、そして、意識しながら、上手に死ぬことはいっさい考えず、ただもう不老長寿をのみねがい、健康こそが人間の幸せと信じこんだふりをする、あまりに意識し過ぎる怯えが強すぎて、具体的に考えない。 「死について」 |
|
|
■横尾忠則 (1926-) 画家 肉体で現世にいるということは確かに苦痛である。因果のサイクルから解脱しない限りわれわれはいつまでたってもこうしてこの世に生まれてこなければならない。この世は神の国に入るための修行の場でもある。しかし、この修行の場での修行を怠れば、永遠に神の国に入ることが許されず、ついにその魂までもこの宇宙から消滅しかねない。これ以上の悲劇がどこにあろう。肉体であろうと霊魂であろうと、自分がこの宇宙のどこかにいるということは素晴らしいことである。 「生れ変り死に変る」 |
|
|
■死を考えるのは死ぬためじゃない、生きるためなのだ。 アンドレ・マルロー
■死は人生の終末ではない。生涯の完成である。 マルチン・ルター ■人は死ぬ。だが死は敗北ではない。 ヘミングウェイ ■人間は死を怖れる。それは生を愛するからである。 ドストエフスキー ■人間は、無意味に耐えられない。 ドストエフスキー ■生きているということは一つの病気である。誰もがその病気によって死ぬ。 ポール・モーラン ■死の恐怖は死より怖ろしい。 ロバート・バートン ■なぜ死を恐れるのですか。まだ死を経験した人はいないではありませんか。 ロシアの諺 ■明日できることは今日やるな。他人ができることは自分がやるな。 ローマのジョーク ■死への絶望なしに生への愛はありえない。 アルベール・カミュ |
|
|
■生きたいと思わねばならない。そして死ぬことを知らねばならない。 ナポレオン
■未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん。 孔子 (生もわからないのにどうして死がわかろう) ■人は、いつか必ず死ぬということを思い知らなければ、生きているということを実感することもできない。 ハイデガー ■充実した一生は、幸福な死をもたらす。 レオナルド・ダ・ビンチ ■このところずっと、私は生き方を学んでいるつもりだったが、最初からずっと、死に方を学んでいたのだ。 レオナルド・ダ・ビンチ ■自分の死を他人にとられてなるものか! フィリップ・アリエス ■他人のために暮らすのはもうたくさんだ。せめて、このわずかな余生を、みずからのために生きようではないか。 モンテーニュ ■人生行路の目的(終点)は死である。これは我々が必ず目指さざるをえない目標である。どこで死が我々を待っているかわからない。だから、いたることころでこれを待とうではないか。 モンテーニュ ■われわれは死の恐怖によって生を乱し、生の苦悩によって死を乱している。 モンテーニュ ■いかに死ぬかを教えられる人は、いかに生きるかも教えられる。 モンテーニュ |
|
|
■人間は死と不幸と無知とを癒やすことができなかったので、幸福になるためにそれらのことについて考えないことにした。 パスカル
■われわれは絶壁が見えないようにするために、何か目を遮るものを前方においた後、安心して絶壁の方へ走っているのである。 パスカル ■最初の呼吸が死の始めである。 フラー ■私達は生まれたとたん死にはじめている。 マリニウス ■人生は一歩一歩、死に向かっている。 コユネイル ■人生は旅行であって、死はその終焉である。 ドライデン ■死ぬよりも、生きているほうがよっぽど辛いときが何度もある。それでもなお生きていかねばならないし、ま■生きる以上は努力しなくてはならない。 榎本健一 ■愛する者、親しい者の死ぬることが多くなるに従って、死の恐怖は反対に薄らいでゆくように思われる。 三木清 ■人間というやつは、いま死ぬという土壇場にならないと、気のつかないことがいろいろある。 山本周五郎 ■すべての人々は、自分以外の人間は、みな死ぬものだと思っている。 エドワード・ヤング |
|
|
■我々が誕生を喜び、葬式を悲しむのは何故か?我々がその当人でないからだ。 マーク・トウェイン
■死の事は考えるに及ばない。我々が手伝わなくても死は我々のことを考えてくれるから。 シェンキヴィチ ■われわれはすべて、無意識下に、われわれ自身には決して死は起こり得ないとする、基本的な知識をもっている。 キューブラー・ロス ■生まれてきた以上は死んでいかねばならず、生きている限りは不幸から逃れることを得ない、ということ意外に何も確実なことはない。 クリスチアス ■生涯をかけて学ぶべきことは、死ぬことである。 セネカ ■太陽も死もじっと見つめることは出来ない。 ロシュフコー ■人間的に言えば死にもよいところがある。老いに決着をつけねばならないからだ。 ラ・ブリュイエール ■墓場は、一番安上がりの宿屋である。 ラングストン・ヒューズ ■生きることは病であり、眠りはその緩和剤、死は根本治療。 ウェーバー ■死が老人にだけ訪れるというのは間違いだ。死は最初からそこにいる。 ヘルマン・ファイフェル |
|
|
■人生は夢である。死がそれを覚まさせてくれる。 ホジヴィリ
■我々は、大人も子供も、利口も馬鹿も、貧者も富者も、死においては平等である。 ロレン・ハーゲン ■人は死ぬ瞬間までも、もしかしたら助かるかもしれないという空想し得る力を与えられている。 武者小路実篤 ■「死というのはたぶん海みたいなものだろうな。入っていくときは冷たいがいったん中に入ってしまうと…」 セスブロン ■死ぬことはなんでもないが、この世とお別れすることが僕には辛い。 マルセル・パニョール ■生は死の始まりであり、生きることは死ぬためなのである。死は終結であると同時に開始であり、別離であると同時に近しい結びつきである。 ノヴァーリス ■もし一人の人間によって、少しでも多くの愛と平和、光と真実が世にもたらされたなら、その人の一生には意味があったのである。 ドイツ哲学者アルフレッド・デルプ神父 ■人生はほんのに一瞬のことに過ぎない。死もまたほんの一瞬である。 シラー ■死に至る病とは、絶望のことである。 キエルケゴール ■哲学とは死のリハーサルである。 ソクラテス |
|
|
■過去と将来に支えられて現在が成立する。 ハイデガー
■命長ければ、恥多し。 荘子 ■バカに不安なし。 ゲーテ ■自己の存在と意味は他者によって与えられる。 R.D.レイン ■人間は意味を求める動物である。この解答を得た人は、どんな辛苦にも耐えられるが、解答を得られない人はその未来を失い内的に崩壊してしまう。 フランクル ■「悟り」といふ事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思つて居たのは間違ひで、悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であつた。 正岡子規 ■すべての人間は生まれつき、知ることを欲する。 アリストテレス ■死と同じように避けられないものがある。それは生きることだ。 映画「ライムライト」 ■今年死ぬ者は、来年は死なずに済む。 シェイクスピア ■人は誰しも、一人で生き、一人で死ぬものである。 ヤコブセン |
|
|
■天国はすごくいいところらしい。だって、行った人が誰一人帰ってこないのだから・・・
■自分の終末のあるがままの姿を受け入れると思っていても、あるべき姿を追ってしまう。 ■パスカルの賭け…フランスの科学者で宗教思想家であったパスカルは、死後の生命を信じるか信じないかを賭けとみなすことできると言っている。もし、人が死後の生命の存在を信じていたのに、実はそれが存在しなかったとしても、別に損したことにはならない。しかし、死後の生命が存在するにもかかわらず、それを無視して信じなかったために、手に入れ損なったとしたらもう取り返しがつかない。つまり「信じれば全てを手に入れることができ、そのことで失うものは何も無いんだから、死後の永遠の生命を信じる決断の方に賭けるべきだ」というのがパスカルの結論である。 ■来世信仰はあらゆる民族、文化、時代を超えて信じられてきた。これらの共通点をみず、蓋然性を一切無視して、死後の生命の存在を否定するのは非理性的な態度である。 ■死を看取った経験がある人は、あまり死を怖がらない。 ■自分の死は次に死ぬものに対してよい教育になる。 ■「よりよく生きる」ことが死の恐怖を免れる最良の方法である。 ■日本社会はイエスかノーか、白黒をハッキリせずナァナァの灰色社会だったけど、死に至る数ヶ月は本人が決めることを決め、自分の運命を人任せにしてはいけない。 ■「病気になってから不安でしょうがないの」と口に出せた方が元気になる。 ■死んだらどうなるかを考えるより、死ぬまでに何をするのかが大事。 |
|
|
■身を縮めて悩んでいても、楽しく笑っていても同じように時間はすぎていく。だったらやれるだけのことをやったらいい。そのためには、やりたいと思ったことはとにかく口に出すことだ。
■死は終わりではなく、別れのとき。 ■死は自然なものだ。毎日一生懸命生きなきゃと思うもよし、世の中そんなものよと達観するもよし。 ■死は魂の変容である。 ■死は人格が完成したときに訪れる。 ■人は死ぬことは避けられないが、死に方はある程度選べる。 ■私たちはガンになるかならないかを自分自身でコントロールすることはできないが、もしガンとわかったら、これにどう対応するかは、自分自身で決めることができる。 ■死後の生命の存在を厳密に証明することは不可能。死で全てが終わってしまうことも証明不可能。 ■死は境でも点でもなく「分布」である。 ■死は生と対極にあるのではなく表裏一体である。 |
|
|
■死は生の対極としてではなく、その一部として存在する。 村上春樹
■「今をよく生きる」ことが哲学の賢人に共通する言葉。ソクラテスも孔子にもあてはまる。 ■死を自覚することによって生の味わいは深くなる。 ■人生の目的とするもの(死生観や成功イメージ)は、生きるための支えになる。 ■死は永遠の解放、安らぎの訪れ。 ■生とは自分が選んできた人生であり、試験問題のごとく思い通りにならない。人生最後の試験問題とは死に方であり、周りの人々に大いに感謝することである。 ■死は終局ではなく、新たな人生の始まりであると考えること。 ■極楽までの旅にしても出発までの準備を含めて楽しまなきゃ損である。 ■死を視る事、帰するが如し 死ぬことを家に帰ることのように考えること。死に臨んで泰然として恐れない様子。 ■自己表現の手段を奪われると、人間はがっくりと気力を失ってしまうものなのだ。 |
|
|
■愛の対象を持つと死への免疫力が高まる。
■仏様の国へ行って先に逝った身内や友人と会う。その時恥ずかしくないように毎日を一生懸命に生きる。美しい思い出というお土産をもって仏様の国に行きたいからそのお土産を作るために生きるのである。 ひろさちや ■自分の役割を意識し、それらを多くの人のために使う。すべては神やほとけから預かったものですから。 ■感謝上手は喜び上手、喜び上手は受け入れ上手。 ■人生とは自分にとって都合のよい選択肢をいくつ作れるかにかかっている。 ■自分の希望と不安をどこにどのくらい持っているかで死生観が変わる。 ■あなたが不安や希望を持つのは今のこと?死ぬ前?それとも死後のこと? ■人はあらゆる「欲望がなくなった時」死といえるのではないか? ■雨が痛みだとしたら、海は死である。 ■終末期における『妥協』という言葉は「身の丈の受け入れ」「自己責任のある選択」のことである。 |
|
|
■人生最大のやり残し感とは、「自己表現」ができていないことである。
■死とは人生最期の自己表現の場である。 ■世の中が平和でも、戦争がなくても人は死にます。必ず死にます。その時に生まれてきてよかった、生きてきてよかったと思いながら、死ぬことができるでしょうか?そう思って死ぬことを大往生といいます。 永六輔 ■電車の窓の外は 光にみち 喜びにみち いきいきといきづいている この世ともうお別れかとおもうと 見なれた景色が 急に新鮮に見えてきた この世が 人間も自然も 幸福にみちみちている だのに私は死なねばならぬ だのにこの世は実にしあわせそうだ それが私の悲しみを慰めてくれる 私の胸に感動があふれ 棟がつまって涙がでそうになる ・・・ 高見順 ■誰でもみんな、本当にこの生を楽しまないのは、死を恐れないからだ。いや、死を恐れないのではなくて、死の近いことを忘れているのだ。しかし、もしまた、生死というような差別の相に捉われないと言う人があるなら、その人は真の道理を悟り得た人と言っていい。 吉田兼好 ■それ、人間の浮生なる相をつらつら観ずるに、おおよそはかなきものは、この世の始中終まぼろしのごとくなる一期なり。さればいまだ万歳の人身をうけたりという事をきかず、一生すぎやすし。いまにいたってたれか百年の形体をたもつべきや。我やさき人やさき、きょうともしらず、あすともしらず、おくれさきだつ人はもとのしずく、すえの露よりもしげしといえり。されば朝には紅顔あって夕には白骨となれる身なり。すでに無常の風きたりぬれば、すなわちふたつのまなこたちまちにとじ、ひとつのいきながくたえぬれば、紅顔むなしく変じて桃李のよそおいを喪いぬるときは、六親眷属あつまってなげきななしめども、更にその甲斐あるべからず。さてしもあるべき事なれねばとて、野外におくって夜半のけむりとなしはてぬれば、ただ白骨のみぞのこれり。あわれというもなかなかおろかなり。されば人間のはかなきことは老少不定のさかいなれば、たれの人もはやく後生の一大事を心にかけて、阿弥陀仏をふかくたのみまいらせて、念仏もうすべきものなり。あなかしこ。あなかしこ。 蓮如上人 ■居心地とは認められていることである 居心地とは許されていることである 居心地とは攻撃されないことである 居心地とは役割があることである 居心地とは瞬間的なことである 居心地とは自分中心なことである 居心地とは、居場所、つながり、支えがあって成り立っている 青木和広 |
|
|
|
|
 ■死に様 |
|
|
■死に方の理想を持たないのが理想
「理想の死に方」、あるいは「理想のお葬式」ということについても、やはり、「考えないこと」がいちばんたいせつだと思います。 つまり、「わたしはこういう死に方が理想です」とか、「このように葬られるのが理想です」とかという理想に縛られないことです。多くの人がいかなる死に方がすばらしい死に方かと考え、そんなものがあると思っているようですが、それは錯覚です。死などというものは、わたしたちが選べるものではありません。 自殺という手がありますが、しかし、自殺だって自分の思いどおりの死に方ができるかどうかはわかりません。 ビルから飛び降りて一気に死ぬのがいいと思っても、ビルの下をだれかが歩いていて、その人を巻き添えにして殺してしまうかもしれない。そうすると、その人の理想とは違ってくるでしょう。 ガス自殺が苦痛が少ないと聞いたからそれでいこうと思っても、ガスが隣の家まで漏れてその家の人をガス中毒にさせてしまうかもしれないし、ガスに引火して爆発し、おおぜいの人が死んでしまうかもしれない。 このように、自殺ですら自分の思いどおりには死ねないのです。死ぬということは、わたしたちの思いどおりにはならないものです。それを思いどおりにしようと思うその心を捨てることがたいせつなのです。 よく「畳の上で大往生できればいい」などと言いますが、ばかげたことばです。畳の上で死のうと事故で死のうと、死んだ瞬間に当事者はその場にはいなくなるのですから、関係ないことです。いい死に方だ、悪い死に方だなどというのは、たいてい周りの人が言うことです。 事故や事件で死んだ人に「こんな無残な死に方をした」などと言いますが、でも、死は死でしょう。どんな死に方でも、死んだその人にとっては厳粛なる死なんです。それを無残だと言うその遺族の見方がおかしいのです。 なぜ無残な死に方と見るかといえば、その対極に「安らかな死」というような理想を想定しているからでしょう。 しかし、今言ったように、そんな理想を持っていてもそのとおりには死ねないのですから、まず理想を持つことが欲でありエゴイズムだということを認識してほしいと思います。 そのへんのところは、おおぜいの人が錯覚しています。 たとえばある著名な作家が、病気を苦にしてもはや自分は形骸化してしまったと言って自殺しました。すると、それを美しい死に方だなどと言ってほめる人がいますが、それはおかしい。別にけなす必要もありませんが、ほめる必要もないんです。どんな死に様でもいいのです。 これが美しい死だとかこういう死に方をすべきだとかと、死に方に差をつけると、あの人の死に様は悪かったとかもっといい死を迎えるにはこうしたほうがいいなどと、どんどん脅しの宗教になっていくわけです。 そこがほんものの宗教とニセモノの宗教の分かれ目で、仏教はそこを説いていかなければならないのに、お坊さんたちは逆にニセモノのほうに便乗している。そこがお坊さんが堕落していると非難されるゆえんであり、葬式仏教と悪口を言われる理由なのではないでしょうか。 |
|
|
■明智光秀 56歳
本能寺の変にて主君・織田信長を討った光秀。が、豊臣秀吉が中国地方から戻ってきて山崎の合戦に突入する。光秀は、味方になってくれると思っていた細川幽斎などに見放され、決戦に挑むが負けてしまう。こうして逃げた光秀だが、途中農民に見つかり、殺されてしまう。その死体はずっと放置されており、光秀かどうかわからなかったという・・・ |
|
|
■朝倉義景 41歳
織田信長に攻撃され、浅井長政とともに姉川で合戦するも敗戦。その後、一乗谷へ逃げるも、織田軍が迫ってきた。義景は家臣の進言により、平泉寺へ身を寄せたが、家臣の裏切りにより、平泉寺は包囲されてしまう。最期を悟った義景は絶望に打ちひしがれながら自害した。 |
|
|
■足利尊氏 53歳
室町幕府を樹立した足利尊氏。52歳の時に、背中に腫れ物ができました。侍医の坂十仏に治療をさせましたが、良くなりませんでした。ちなみに治療法は、おできに針を刺して膿を出し、火で炙って揉んだ薬草を貼り付けるというもの。さすがの尊氏も力任せに膿を出され、悲鳴をあげたようです。死亡する一週間前はこのおできに非常に苦しみ、寝返りも打てずにいた。膿が悪臭を放ち、とうとう1358年4月29日午前4時に息をひきとった。 |
|
|
■足利義満 51歳
栄華を極め、好き放題生きた義満。が、病気には勝てなかった。咳がすごく、風邪が悪化して急性肺炎で死亡した。義満死後、新将軍となった息子は、父が大嫌いだったので、義満に築いた基盤を全てぶち壊すこととなる。 |
|
|
■足利義教 47歳
足利義教は室町幕府六代将軍である。前代未聞の「くじ引き」で決まった将軍であったため、常に家臣らに馬鹿にされないよう強気の政治を行った。そして有力な一族をどんどんと消していき、まさに恐怖政治を行った将軍である。「次はわしの家が危ないかもしれない」と感じた赤松家は、将軍を家に招くことにした。赤松家で将軍を迎えた宴会が始まり、酔いも回った頃、なにやら音がした。「落雷であろう」とのんびりとしていたその瞬間、義教の背後の障子が開き、数十人の武士が襲い掛かった。そして首を刎ねられたのである。 |
|
|
■尼子経久 84歳
一代で山陰地方を制した梟雄・経久。この人の最大の失敗は「後継者育成」だった。民からも好かれ、名城・月山富田城を拠点に数多くの戦を勝利した。が、子供に恵まれなかった・・・最後は孫に跡を譲るも、孫は毛利元就と合戦となりボロ負け。最後まで尼子家を心配しつつ死んでいった。のち、尼子家は滅亡することとなる・・・ |
|
|
■在原業平 56歳
伊勢物語の主人公で、絶世の美男・平安時代のプレイボーイの代表でもある業平。様々な諸説があるが、個人的にこの説をとろうと思う。業平は未開の地である東国へ旅立つこととなったが、どうやらお妃候補として大事に育てられた藤原高子と不倫したのが原因らしい。34歳の時16歳の高子と出会い、2人は恋に落ちたが、親兄弟によって引き裂かれた。そして高子は清和天皇の妻となるが、2人の関係は続いていた。それがバレてしまい、業平は都を追放されてしまう。晩年は、高子がよく参拝した神社の近くに住み、56歳で死去したとされている。 |
|
|
■安藤広重 61歳
東海道五十三次などで有名な江戸の浮世絵師安藤広重。この頃、コレラが大流行し、広重もかかってしまいました。死を覚悟した広重は遺書を書きました。借金の返済や遺品の始末を家族に頼み、残してやる金もないけどあとは頼むな!と言った内容。が、翌日まだ生きてたので余裕が出たのか、今度は2通目の遺書を作成。自分の死体の処理方法や、お通夜の心得まで、ありとあらゆる細かいことを書きました。こうして二通の遺書を書き終えた三日後、この世を去りました。 |
|
|
■芥川龍之介 35歳
芥川龍之介の人生には、いつも母の「フク」が棲んでいた。フクは龍之介が11歳の時に発狂して死んでしまったのです。母の兄に引き取られた少年・龍之介の心には、いつも「私の母は発狂して死んだ」というトラウマがありました。30歳の時に毎日新聞の記者になった時に病気となり、それが引き金となり不眠症に。以後、睡眠薬を飲み続け、次第に神経を衰弱させていきます。いつも「将来に対するぼんやりとした不安」が心にありました。次第に不安は心を蝕み、死にたいと思うように。そして睡眠薬だけではなく、アヘンを原料とした薬も飲み始めました。とうとう昭和2年7月23日午前1時 龍之介は東京田端の自宅で致死量の睡眠薬を服用し、自殺したのです。 ■ 葬儀は、7月27日谷中斎場で行われました。700名を超える会葬者の中、文壇人が次々と弔辞をよみました。泉鏡花のあとに菊池寛が涙ながらに読んだ弔辞です。 「われらは君が死面に平和なる微光の漂へるを見て甚だ安心したり。友よ、安らかに眠れ。・・・ただ悲しきはき君去りて我等が身辺とみに蕭条(しょじょう)(もの寂しいさま)たるを如何せん。」 |
|
|
■井伊直弼 46歳
幕府の大老であった直弼は、安政の大獄で幕府に反抗する多くの人々を弾圧した。直弼を恨む水戸藩の浪士たちが直弼を殺害したのである。直弼の首を刎ねたのは有村次郎左衛門。以前から直弼のもとには「怪しい動きがあるので身辺に気をつけたほうがいい」と助言する者が多くいたが、直弼はいつもと変わらない警護の人数で屋敷から江戸城へ向かった。その行列が桜田門外に差し掛かったとき、行列の先頭に訴状を持った武士が現れいきなり抜刀。そして周囲にかくれていた刺客たちがいっせいに直弼の駕籠をめがけた。直弼は駕籠から引きずり出され、有村に首をはねられたのである。有村は剣先に直弼の首をかかげたまま歩いたが、有村自身も数箇所も斬りつけられており、もはや動けぬ・・・と、自害した。直弼の首は雪の中放置されていたところ、辻番によって発見されたのである。 ■ 1860年3月3日 雪の振る日だった。この日、幕府の大老が市中で暗殺されるという大事件「桜田門外の変」が起きたのである。井伊直弼は幕府にはむかう志士達を「安政の大獄」で処分しまくった。それに恨みを抱いた水戸藩の浪士たちが暗殺をもくろんだのである。襲撃は一瞬の出来事であった。この大老暗殺事件により、幕末の動乱はさらに激しくなっていくのである。 |
|
|
■今川義元 41歳
戦国初期、力を持っていた今川家、京都上洛を目指し、桶狭間へ向かった。そこへ織田信長の奇襲に会い、「桶狭間の合戦」となった。予期していなかった奇襲に今川軍は総崩れとなり、信長軍の服部小平太に槍で疲れ、毛利新介に首をとられてしまった。義元は切りかかる毛利新介の指を食いちぎったという。大大名の義元は、雨の中 泥だらけになり這いずり回り、討ち取られたという。 |
|
|
■石川五右衛門 ?歳
世紀の大泥棒石川五右衛門もついに御用となった。そして五右衛門は釜茹での刑に処されることに。仲間が次々と煮えたぎった釜の中に落とされ、死んでいく・・・五右衛門はその様子を目を見開き見ていた。自分の番になると、「念仏を頼む」と言い、死んでいった。 |
|
|
■石田三成 40歳
関が原の合戦。小早川秀秋の裏切りによって西軍は総崩れとなり、石田三成は敗走した。伊吹山に逃げ込むも、とうとう捕らえられた。東軍諸将の前につれてこられ、斬首が決定した三成。斬首の直前、「のどが渇いた」と言った。兵らは「白湯はない。柿でも食え」というと、三成「柿は痰の毒である」と言った、みな大笑い「どうせもう死ぬくせに」。三成「ばかものどもめ。大義を思うものは最後の瞬間まで命を大事にするのだ」と一喝したのであった。 |
|
|
■一休 87歳 室町時代の臨済宗の僧。当時の禅宗界をしんらつに風刺して、人間的な禅風を目指した。文明13年11月、寒さや高熱がおそう「ぎやく」にかかり、21日朝に没した。死ぬにあたって彼は「死にとうない」といって、座ったまま眠るように死んだという。 |
|
|
■一遍 50歳
一遍とは鎌倉時代の僧侶で、「南無阿弥陀仏」と唱えれば極楽へいけると説いた人であります。全国を歩き回り教えを唱え、16年間苦しい生活をしながら歩き続けた。そのため健康を害し、動けなくなってしまう。死を察した一遍は、弟子たちに「ワシが死んだ後は葬式をするな。わしの亡骸は野に捨て、獣に与えよ・・・」。そういって、皆が見守る中座禅を組むような姿勢のまま息を引き取った。 |
|
|
■池田輝政 50歳
姫路城を築いた池田輝政。徳川家康の娘を妻に迎え、「姫路宰相百万石」と言われるほどの大出世をした。家康も輝政をとても気に入っていた。そんな輝政が脳卒中で倒れてしまい、そのときはなんとか命はとりとめたが、多少言語障害が残るように。一ヵ月後、脳卒中の再発作に襲われそのまま命を落とした。 |
|
|
■伊能忠敬 74歳
江戸時代、日本地図を作成するために日本中を歩き回った人。56歳の時に思い立ち、72歳になるまで日本地図作成の夢にむけて全国を測量して回った。その距離、地球一周に匹敵する。旅の途中、持病の喘息でツライ思いをしたが、それでも一生懸命測量し続けた。とうとう72歳の時に病床につく、この時、まだ地図は完成していなかった。そして忠敬は74歳で死去。その後、弟子達が「この地図は忠敬先生の名で出したい」と、忠敬の死を隠す。3年後、日本発の実測地図「大日本沿海興地全図」が完成し、ようやく忠敬の死が公表された。 |
|
|
■板垣退助 83歳
幕末から明治維新を生きた政治家。西郷隆盛らとともに征韓論を主張したが破れるが、ここからが本領発揮。立志社を創立し、自由民権運動を展開。その後、自由党を結成し全国を遊説してまわった。が、岐阜県で開かれた自由党懇親会で、外に出ようとしたところ待ち構えていた27歳の男に胸を短刀で刺されてしまう。板垣は血まみれになるが、命だけは取り留める。ちなみにこの時に「板垣死すとも自由は死せず」という言葉が生まれた。本人が言った言葉ではないようですが・・・傷害事件の後も、元気に政界で活躍し、リタイアした後も元気に生きた。83歳で死去するが、十二分に天寿を全うしたであろう。 |
|
|
■石川啄木 27歳
20歳の頃、このような言葉を言っていた。「ボクには2つの敵がいる。貧乏と病気だ。貧乏には打ち勝つことはできても、病気には勝てない」。ずっと悩まされていた啄木は悪化し、高熱に苦しめられるように。そして明治45年4月13日、早朝より危篤となり妊娠八ヶ月の妻や親友の若山牧水に看取られ死去。死ぬ前日、妻の節子に「おまえには気の毒なことをした。早く子供を産んで丈夫に育ててくれ」と言った。が、妻の節子も一年後、結核で死去。 |
|
|
■池大雅 54歳
画の大家・池大雅は、妻・玉蘭といつまでも仲良く暮らしていました。40歳頃に「大雅様式」を確立させ、画家として不動の地位を手に入れた。が、若い頃に絵を書く為に散々いろんな場所へ旅行していたため、足腰を痛めてしまう。そして54歳の時に大病を患ったが、医者が勧める薬を飲まなかった。そして静かに死んでいったのでした。 |
|
|
■井原西鶴 52歳
江戸時代の俳諧師&作家。「好色一代男」「日本永代蔵」など数々の作品を残しました。49歳頃から病気がちになり、淋しい内容の作品を書くように。そして老後の住みかとしていた場所で、秋の雨が降り注ぐ中死んでしまいました。 |
|
|
■上杉謙信 49歳
越後の龍・上杉謙信は、酒が死ぬほど好きだった。そのために脳卒中で死んだといわれております。武田信玄が死に、将軍から上洛するよう命令がありました。京都では織田信長が上洛し、天下をわがものにするべく動いており、謙信も「そろそろ行くか・・・」といった感じでした。出兵の準備にとりかかるも、突然春日山城のトイレ内で倒れてしまったのです。そのまま意識が回復することなく、49歳の若さで息を引き取ってしまいました。 |
|
|
■上田秋成 76歳
江戸時代の国学者で「雨月物語」の作者でもあります。生まれつき虚弱体質で、5歳の時は天然痘にかかり死にかけました。両親が加島稲荷で必死にお願い。この時、両親いわく「真夜中に神社から加島の神様が現れ、私たちの愛情の深さに免じて、息子に68歳という寿命を授けよう」と言ったらしい。以後、秋成は「自分は68歳でお迎えが来る」と信じて、そして死を覚悟していました。ところが68歳になってもお迎えは来なかった。さらに69歳になっても死なない。それから秋成はなんだか自暴自棄になってしまいました。覚悟をしていたのに、死んだ妻のもとへもいけない、「天はなぜ我を生んだのか」と、嘆き続けました。そして念願(?)のお迎えがきました、1809年6月27日のことで、弟子の家でひっそりと死を迎えました。 |
|
|
■梅原竜三郎 98歳
洋画家。昭和60年12月25日、風邪でたんを詰まらせ呼吸困難に陥り、入院。入院前に医者に「アトリエに、描きかけの絵がある。見てきたまえ」といった。もちろんそんなものはないのである。翌年1月14日から昏睡状態に陥り、肺炎を起こし、15日、「胸が痛みますか」という医者の問に「心配ない、心配ない」と答えたのが最後の言葉となった。 |
|
|
■榎本武揚 73歳
幕末を生きた生粋の江戸っ子。箱館戦争のトップになりながらも、あまりにも優秀だったため殺すのは惜しいとなり、新政府に入ることとなった。以後は新政府で外務大臣や文部大臣などを歴任。老後、将軍だった徳川慶喜が公爵となった。旧幕臣たちはとても喜び祝宴を開き、記念写真を撮ることに。が、榎本の姿が見つからない、彼は「慶喜様と一緒に撮影などという失礼なことは出来ぬゆ・・・」という謙虚さ。そして明治41年に老衰にて死去。 |
|
|
■エノケン・榎本健一 66歳
喜劇俳優。本名榎本健一。昭和44年12月全身に黄疽症状が現われ、翌年の元旦に入院。病名は肝硬変であった。3日に「ドラが鳴るんだよ。船が来たよ、ほらほら」といい、妻のよしえが鷲き「お父さん、船なんか一人で乗っちやだめですよ」というと「うるせいや、早く乗れ」と答えたという。5日。よしえが「病院を出たら温泉にでも行きましょうか」というと「ありがとう」といった。これが最後の言葉である。 |
|
|
■太田道灌 54歳
あまりにも頭が良すぎたために主君に疑われるようになった太田道灌。主君上杉定正は、不安になり道灌を暗殺することに。暗殺者である曽我兵庫は、道灌かお風呂から出てきたところを斬りつけた。死ぬ間際に道灌は「当方滅亡!」と叫び息絶えた。「私が死んだら、当家は滅亡するであろう」という意味である。道灌の言うとおり、主家である扇谷上杉家は滅亡へと歩んでいくこととなった。 |
|
|
■お市の方 37歳
織田信長の妹であるお市。最初の夫である浅井長政が殺され、柴田勝家と再婚。が、勝家と豊臣秀吉との戦いが始まり、夫である勝家が負けた。北庄城に戻った勝家のもとに、秀吉の追撃の手が忍び寄り、お市の方は3人の娘を城外に脱出させ、みずからは勝家とともに自害、炎の中へと消えていった。 |
|
|
■大石内蔵助 44歳
播磨赤穂藩家老、のち赤穂義士の首領。討入後、翌元禄16年2月4日、切腹を命じられる。切腹の座に呼び出されたとき、背後から義士の一人が「追っつけおあとから」と声を掛けると、「お先に」と笑って静かに出ていった。 |
|
|
■大宅壮一 70歳
政治・社会時評家。昭和45年10月26日、山中湖の山荘で息苦しさを訴え、急遽帰京して入院。11月18日、昏睡状態から覚めた彼は「ああ、腹が減った。何か食うものをよこせ」とどなった。11月22日午前3時4分、一度心臓が停止したが、3時43分に永遠に止まった。死ぬ直前に妻に「おい、だっこ」といったという。 |
|
|
■織田信長 49歳
武田を滅ぼし、悠々と本能寺で茶会を開いた信長。が、家臣である明智光秀に裏切られ、本能寺を攻められる。最初はどこかで喧嘩でもしているのかと思っていた信長。が、小姓の森蘭丸が「明智光秀謀反!」と言いやってきた。信長は「是非もなし・・・」とつぶやくと、槍で応戦するが、勝ち目なしとわかると、部屋に入り自害した。信長の愛した舞「敦盛」の「人生五十年」にはあと一年足りなかった 。 |
|
|
■大久保彦左衛門 80歳
ずっと徳川家に忠義を尽くしてきた大久保彦左衛門。幕府の世となり、もはや戦で活躍するということはなくなってきた。ということで、武功派だった大久保家はもはや時代に取り残されてしまった。63歳になった彦左衛門は今まで尽くしてきた徳川家に対し、不満をぶちまけた「三河物語」を執筆。「大久保家は親族を戦死させまくってまでも徳川家に奉公してきた。妻や子供までも食べるものも無く、がんばってきた。が、家康殿はそろばん勘定がうまい者を大事にしている。大久保家を何の罪があって肩身の狭い思いをさせるのか!」。彦左衛門は死ぬまで武骨者として生きた。むしろ時流に逆らいながら生きた。最後まで無念の思いを抱きつつ死んでいったのでした。 |
|
|
■沖田総司 27歳
新撰組の中で一番剣術が優れていると言われていた男である。1864年、有名な池田屋事件の戦闘中に血を吐いた沖田総司は、そのまま労咳(肺病)となり治ることはなかった。闘病生活を続けることとなる。死ぬ3日前に、多少元気になった総司はふらりと庭へ歩いていった。そこに黒猫が一匹寝ていた。嫌な顔をしている猫だった。総司はその猫を斬ろうと刀を取るが猫に逃げられてしまった。総司は面倒をみてくれているおばあさんに向かい「ばぁさん、斬れない。おれは斬れないよ・・・」と言うとそのまま寝込んでしまった。その3日後、「ばぁさん、あの黒猫はまた来ているんだろうなぁ」と言うと、そのまま息をひきとった。 |
|
|
■尾崎紅葉 37歳
尾崎紅葉といえば「金色夜叉」を執筆した人、明治30年に発表し大人気に。31年に「続金色夜叉」32年に「続々金色夜叉」を発表したが、この頃から具合が悪くなる。明治34年には伊豆修善寺へ療養するも、大人気作家だったためゆっくりと休ませてもらえなかった。体調は次第に悪化し、病院に行くと「胃がん」と診断されてしまった。以後、自宅で静養することに。ある日友人たちがお見舞いにいった、すると尾崎紅葉はみんなの顔をじーーーっと見回し「どれもこれまずいツラだなぁ」と笑った。この時紅葉は周囲に気がつかれないようそっと袖で涙をぬぐった。最後は笑って終わりにしたいという江戸っ子らしい気遣いだったのでしょう。そして、数日後息を引き取ったのでした。 |
|
|
■太田道灌 54歳
太田道灌は室町幕府時代の武将である。この頃、関東では山内上杉氏と扇谷上杉氏が激しい勢力争いを繰り広げていた。が、幼い頃から優秀であった太田道灌の功績で扇谷上杉氏は山内上杉氏をしのぐ勢いであった。扇谷上杉氏の当主であった定正は平凡な男で、太田道灌さえいなければ倒せると踏んだ山内上杉氏は定正に「太田道灌が主家を乗っ取ろうとしている」という嘘の情報を流した。それを信じた定正は、太田道灌が風呂に入っている時に家臣の曽我兵庫を使い殺害した。太田道灌は倒れながら「当方滅亡!!」と叫んだ。これは「私を殺害したことにより、扇谷上杉家は滅びる」というものである。その言葉通り、優秀で忠実な譜代の家臣・太田道灌を失った扇谷上杉氏は滅亡していくのであった。 |
|
|
■緒方洪庵 54歳
幕末の「適塾」を主催していた洪庵。福沢諭吉や大村益次郎など多くの人材を育て、また名医としても有名だった洪庵は、高い評価を得ていた。この洪庵の名声は幕府にも届き、将軍つきの医者として迎えられた。もともと洪庵はそんなに健康な方ではなかったので、江戸へ行くのを断った。それでも幕府は来いといい、しぶしぶ江戸へ。そこで家来を10人養えと言われ、出費がかさみ気苦労だらけ。江戸に出て10ヶ月ほどでストレスのためか大量の血を吐き、その後すぐ亡くなってしまった。 |
|
|
■小津安二郎
映画監督。『晩春』『東京物語』が有名。昭和38年4月11日、ガンセンターに入院。手術中は、「ナンマイダ、ナンマイダ」と唱えていたそうである。一度退院した彼は、10月12日再入院。「何も悪いことをした覚えはないのに、どうしてこんな病気にかかったんだろう」と言った(10月19日)。「右足がどっかに行っちゃったのかね。ベッドの下に落っこちているんしやないかね」12月12日死亡。それは還暦の誕生日であった。 |
|
|
■小野妹子 不明
小野妹子は遣隋使として聖徳太子の国書を隋に届けた人物。ところが、隋の皇帝から託された返事を無くしてしまい、天皇側近らが激怒し、流刑となった。これを推古天皇が救いの手をさしのべ、許された。その後、もう一度隋へ派遣され、その功績が認められた。以後、冠位十二階の第一位という最高位まで昇りつめたが、いつ亡くなったかは不明である。 |
|
|
■春日局 65歳
三代将軍家光の乳母であり、大奥に君臨した女帝。春日局は家光が26歳で天然痘を患った時、回復を祈願し、薬絶ちを誓った。病気になった時、一切薬を口にしないという誓いであります。そして64歳で病気になったが、春日局は薬を一切飲まなかった。家光自らが見舞いにいき、薬を飲ませようとしても、春日局は涙を流しならがお礼をしたが、一滴も薬を飲まなかった。春日局の死に、家光は非常に悲しみ、七日間喪に服した。乳母の死に対して、将軍が七日間も喪に服すなど異例のことである。それほどまでに家光にとって春日局の死の悲しみは深かったのだろう。 |
|
|
■加藤清正 50歳
豊臣恩顧の家臣でありながら、関ヶ原では徳川方についた清正。心の中は複雑でありました。豊臣秀吉の息子・秀頼は大事だが、豊臣家を選べば徳川家康に嫌われ、加藤家は大変なことになる。死ぬ前に行った秀頼と家康の二条城での会見で、清正は豊臣家の為に忠誠心を発揮し、その後熊本へ帰る途中の船の中で具合が悪くなった。その後病状は悪化し、舌がもつれてうまく喋れないように。そして1611年6月24日 死去した。この後すぐに起こる豊臣家滅亡を見ずにすんだのが幸せだったのかもしれない。 |
|
|
■蒲生氏郷 40歳
死ぬ数年前から下血があったらしく、消化器系の癌・もしくは十二指腸潰瘍と思われます。朝鮮出兵の時に血を吐き、一時は治りましたが翌年また悪化。首の筋肉はやせ落ち、眼の下にはむくみがあり、そのまま治らず1595年2月7日、京都で死去しました、他にも毒殺説も。織田信長にもその才能を褒められた氏郷でしたが、あまりにも才能があったがために天下人・豊臣秀吉に嫌われ、石田三成によって毒を盛られたという説があります。 |
|
|
■葛飾北斎 90歳
富嶽三十六景などの浮世絵で有名な北斎。一度68歳の時に脳卒中で倒れたがなんとか命は助かった。その後73歳の時に名作「富嶽三十六景」を完成させる。90歳で倒れた時に言った言葉が「ああ、あと5年長生きできれば、ワシは本当の画家になれるのに」。画家としての完成意欲は尽きることのなかった北斎でした。 |
|
| 江戸時代後期の浮世絵師。生涯に93回引越しをし、酒も煙草ものまずただひたすら描き続けた。嘉永2年4月風邪をひき、枕頭には娘や弟子たちが集まった。ここで彼は「ひと魂でゆく気散しや夏の原」と辞世をよみ、「あと10年生きたいが、せめてあと5年の命があったら、本当の絵師になられるのだが」とつぶやいて息を引き取った。 | |
|
■和宮 32歳
孝明天皇の妹で、十四代将軍・家茂と結婚した皇女。幕末の動乱期だったため、様々な問題がありました。家茂と和宮は予想外に仲が良かった。そんな幼い夫婦でしたが、なんと家茂が死んでしまった。以後、剃髪して静寛院宮となるが、時代は静かな時間をくれなかった。戊辰戦争となり、とうとう江戸城は明け渡されることに。その時、徳川の為に朝廷に様々な行動を起こした。明治10年、脚気を病み箱根の塔ノ沢温泉へ療養しに行きましたが、突然の発作が起きそのまま亡くなってしまいました、まだ32歳でした。 |
|
|
■勝海舟 77歳
明治32年1月19日 「これでおしまい」と言い残し、眠るように死んでいった、とても静かな死に方であった。ちなみに勝海舟の奥さんは、自分が死ぬ時「私を勝海舟と同じ墓に入れないでください」と遺言した。死んでまで勝海舟と一緒にいたくなかったらしい。 |
|
| 幕末・維新期に幕臣として、また新政府高官として活躍。明治32年1月19日午後5時頃、風呂から上がると坐り込んで「胸が苦しいからブランデーをもって来い」と家人に命じる。それをグラスに入れ「今度はどうもいけないかもしれんぞ」といって一口飲んだとたん、倒れて意識を失った。脳溢血であった。彼が息をひきとったのは2日後の午後5時。最後の言葉は「コレデオシマイ」である。 | |
|
■川路聖謨 67歳
日本で始めてピストル自殺をした幕末を生きた人である。川路聖謨は幼い頃から優秀で、徳川のために生きた男であった。幕臣として徳川幕府のために一生懸命働き、いい家柄でもないのに必死で勉強し出世していった。そしてプチャーチンと交渉するほどまで上り詰めていった。慶応四年三月十四日 知り合いから「江戸城が明け渡される」という話を聞く。その前日、勝海舟と西郷隆盛が江戸開城の話し合いをしていたのである。それを知った川路聖謨は、もうこれまでだ・・・と思った。幕府を薩摩に潰される・・・・。そう思った川路聖謨は三月十五日、家の人に「この品を買ってきてくれ」と外に出し、一人でピストル自殺したのである。まさに徹底した「幕臣」だった。 |
|
|
■川端康成 72歳
「雪国」「千羽鶴」などを書き、日本人で初めてノーベル文学賞を受賞した川端康成。家族には恵まれていなかった。1歳の時に父を亡くし、2歳で母をなくし、7歳で祖母をなくし、10歳の時に姉、そして14歳の時に祖父もなくなり、天涯孤独の身となっていた。川端康成本人は、自殺という行為に非常に否定的であった。芥川龍之介が自殺した時も、否定し続けていた。そんな彼が、逗子になる仕事部屋でガス管をくわえて自殺した。その自殺にはスキャンダラスな噂や様々な憶測が飛び交ったが、今も謎のままである。 |
|
|
■岸田劉生 38歳
大正時代の洋画家。娘をモデルとした「麗子像」は有名。昭和4年12月14日夜、劉生は徳山の料亭で銀塀風に舞子を描いた。そのあと筆を持ったまま脇息にもたれ「気持が悪い」といった。発病後2日して、医師から慢性腎臓炎による視力障害と診断された。18日、彼は「暗い」「目が見えない」と叫び、以後頻に「バカヤロ−」を繰り返した。12月20日。吐血して死亡。 |
|
|
■吉川元春 57歳
毛利家の為に尽くしてきた元春でしたが、56歳の時に化膿性炎症(皮膚にできる膿)をわずらう。以後、具合が悪くなりはじめる。そんな中、親友である黒田如水がお見舞いにと「鮭」を調理し、元春をおもてなし。元春は「鮭は血をやぶるものだから、今これを食べたら病気はますますひどくなるであろう・・・。が、せっかく如水が自分のために用意してくれた食事を食べないなんて悪い」と、鮭を食べたのです。だがこれがまずかった、その晩、元春の病状は悪化し、死んでしまったのである。 |
|
|
■北政所(おね) 76歳
豊臣秀吉の正室だった北政所。秀吉が亡くなると、大阪城の実権は秀吉の側室・淀殿へと移った(息子・秀頼を産んでいるから)。貧乏時代から、秀吉と2人で豊臣家を築いてきた北政所にとって、そんな大阪城に未練はなく、京都へ移り住むことに。そこには、加藤清正など、北政所を母親と慕う多くの武将が訪れた。そして、関ヶ原の戦いでは徳川家康を支持、58歳の時に高台寺を築き、平和な余生を過ごした。 |
|
|
■喜多川歌麿 54歳
江戸時代の浮世絵の大家。浮世絵の魅力に取り付かれ、様々な作品にとりかかり、他の絵師たちにも大きな影響を与えました。幕府は風俗上よくない絵を描いた人を取り締まることに。そして歌麿は摘発されてしまいました。ここで入牢3日と、手鎖50日の処罰を受ける。これが精神的にかなりダメージを与えたらしく、さらにこの事件により歌麿の絵はますます話題に。量産に追われた過労も手伝い、54歳で死んでしまった。 ■ 江戸時代の美人がで有名な歌麿。女性達に大人気となり、一躍売れっ子の絵師に。が、歌麿がもてはやさてたのは5.6年だった。当時、松平定信が寛政の改革に取り組み、質素・倹約をモットーにし、派手な娯楽は一切禁止となった。そんな中、歌麿は豊臣秀吉が美女達に囲まれて酒を飲むという場面を描いた。これが大問題に、将軍をバカにしていると、幕府が怒り、捕らえられてしまったのである。歌麿は牢に入れられ、手鎖50日の刑に、これがショックで、以後病気がちとなり、死去した。 |
|
|
■北原白秋 57歳
詩人、歌人。詩集『邪宗門』がある。白秋は昭和12年、糖尿病と腎臓病による眼底出血で、原稿が読めなくなる。昭和16年の末、歩行困難、呼吸困難になり、翌年2月入院。4月より自宅療養することとなる。11月2日の午後4時頃、白秋は「なに、負けるものか、負けないぞ」とうめいた。長男が窓を開くと「ああ蘇った。隆太郎、今日は何日か。11月2日か。新生だ、新生だ。この日をお前達よく覚えておおき。私の輝かしい記念日だ。新しい出発だ。窓をもう少しお開け。ああ、素晴らしい」しかし最期の発作では「一度安心したせいか、もう打ち勝つ気力もない。駄目だ、駄目だよ」とあえぐようにつぶやいた。 |
|
|
■木戸孝允 45歳
木戸孝允(桂小五郎)は、長州藩出身の人。桂小五郎時代は色んな活躍をし、いろーーんな逸話を残している。明治となり「木戸孝允」になってからは途端に今までの輝きは失せていきます。常に病気がちで、どこかが具合が悪く、何度も辞職を願い出るが却下。征韓論の時も、大久保利通とタッグを組み西郷隆盛と対立するも途中で病気になりリタイヤ。次第に大久保利通の権力が増大し、何かと反抗するもなんせ病気だらけでイマイチ。つねに病気がまとわりついていた。西南戦争のときは、大久保から主導権奪回のチャンス!と張り切るが、またも病気。もはや電報でしか、戦況を知ることはできなかった。そして持病(いろんな)はどんどんひどくなり、明治天皇も「こりゃもうだめかな」と、お見舞いにきました。ある夜、いきなりガバっとおきて「西郷、もう大抵にせんか」と怒鳴った。そして眠りにつき、息を引き取ったのでした。 |
|
|
■空海 61歳
嵯峨天皇に気に入られ、真言宗を日本に広めた空海。50歳後半になると、皮膚が化膿し炎症を起こし始めてきました。その頃から空海は穀物を絶つように。穀物断ちとは、中国に古くから伝わる修行で、人間の体内には虫がすんでおり、その虫が寿命を縮めようとしている。その虫が穀物を餌にしているので、穀物を食べないことで虫を駆除し、身を清めるというもの。空海は穀物断ちをしながら瞑想の日々を送りますが、835年3月21日午前四時、多くの弟子に見守られながら瞑想した姿勢のまま死去しました。 |
|
|
■楠木正成 42歳
最後まで後醍醐天皇に忠誠を尽くした悪党・楠木正成。足利軍に攻められるも、最後まで果敢に戦った。最後は73名となり、全員で近くの民家に入り自害した。最後の言葉は「七回生まれ変わって、朝廷の敵を倒す」 |
|
|
■黒田如水 59歳
豊臣秀吉の軍師として活躍していた如水。その頭の良さに秀吉に疎まれることとなった。関ヶ原にて天下を取る野望も消え、以後は大人しいおじいさんとなっていった。自分の死期を悟ると、突然偏屈なおじいさんとなり、家臣らを困らせ始めた。困った息子の黒田長政が「父上、家臣らが困っておりまする」とお願いした。すると如水「ばかもの。わしが偏屈で嫌なじじぃで死んでいったら、家臣はみな「長政殿が主君になってくれて良かった」と、喜ぶであろう!」。最後まで軍師らしい死に方をした。 |
|
|
■国定忠治 41歳
「赤木の山も今宵限り・・・」のセリフで有名な国定忠治。殺人・ゆすり・博打・ケンカに明け暮れ、つねに追われていた。忠治には愛人2人と本妻がいたが、愛人とエッチの最中に脳内出血のため倒れ、半身不随になる。愛人は、本妻に忠治を引き取ってくれるよう頼むが、妻は「愛人の上で倒れた夫はいらない」と拒否。さらに、もう一人の愛人も拒否し、家来の中にも親分の面倒をみようと言う人は誰もいなかった。そんな中、忠治の仲間の一人が「あいつが捕まると、俺の悪事もバレる。それは困るから俺が引き取る」と名乗り出た。その男は、半身不随の忠治を物置に放置したままに、忠治は自分の糞尿にまみれながらすごした。かくまっている噂が流れ、とうとう捕らえられた。忠治は罪状が多すぎたため、江戸へ送られた。そして磔の刑に処されたのである。忠治は、病気の身でありながら、槍で2.3度突かれても死なず、結局14度も突かれ死んでいった。 |
|
|
■後醍醐天皇 51歳
足利尊氏によって都を追放された後、南朝を作り、尊氏のいる北朝と対立するも、ふとした病がきっかけで病床に伏してしまった。最後の言葉は「たとえ我が身が吉野の苔に埋まろうとも、魂は京都御所の天を臨んでいる」。臨終の際まで足利尊氏を恨んで死んでいった。 |
|
|
■小西行長 43歳〜45歳?
キリシタン大名として有名な武将。石田三成と仲が良く、関ヶ原の合戦では西軍に入る。が、裏切りにより西軍は惨敗、小西行長は逃走した。キリシタンゆえに自害することが出来ずにいたところ、伊吹山中にいた庄屋・林蔵主をみつけ、「そこの人、きてくれ」と声をかけた。そして、自らを小西行長だと語り「わしを家康のもとに連れていき、褒美を貰え」と言った。行長は家康のもとへ引き出され、処刑された。 |
|
|
■小林一茶 65歳
江戸時代の俳人である。一茶の生涯は波乱万丈である。50歳を過ぎて、初めて結婚。やっと家と家庭を手に入れた一茶だったが、生まれた四人の子供が次々と死んでしまう。そして妻までもが死んでしまい、一茶は61歳で全てを失ってしまったのである。62歳の時に28歳の女性と再婚するが3ヶ月で離婚。64歳の時に32歳の女性と結婚。が、家が火事で全焼してしまう。一茶はかろうじて残っていた土蔵で生活するが、持病の中風が悪化し、死んでしまった。一茶が死んだ翌年、妻が一茶の子供を出産。自分の子供を見れず、一茶は死んでしまったのである。 |
|
|
■小泉八雲 54歳
江戸時代の作家。アイルランド人の父とギリシャ人との母の間に生まれたラファディオ・カーンは、両親の愛に恵まれず叔母さんに育てられました。イギリス→アメリカ→日本へと渡り、明治二十九年に日本へ帰化。このとき、小泉八雲という名前になりました。西洋文化が大嫌いだった八雲は日本文化を愛し、多くの怪談を残しました。ある日、八雲を突然の心臓発作が襲います。そしてその日に眠りにつき、そのまま少し笑い、息をひきとりました。 |
|
|
■小早川秀秋 20歳
関ヶ原の戦いの寝返り男。西軍でありながら、間際になり徳川家康のいる東軍に寝返り、勝敗の決め手を与えた。そのため家康から多くの恩賞を貰うことに。が、敵・味方からも「裏切り者」のレッテルを貼られ、屈辱的な日々を送る。世間からも非難され、ノイローゼ状態に、弱冠20歳の若者に、この状況は耐え難いものだった。三成の亡霊が・・・など、口走っていたという。そして関ヶ原の戦いから二年後、死去。小早川家はその後、断絶となる。 |
|
|
■近藤勇 33歳
新撰組の局長であった近藤勇。鳥羽伏見の戦いで破れてからも、「甲陽鎮撫隊」を結成し、あくまでも官軍と戦い続けようとした。そして最後は下総国流山でまたも闘うべくノロシをあげるも、新政府軍に捕らえられてしまった。捕まった近藤は1868年4月25日に東京・板橋の刑場で処刑され、その首は京都・三条河原へ運ばれさらされることとなった。 |
|
|
■幸田露伴 80歳
明治・大正時代の文豪幸田露伴は、大往生の末80歳で死去しました。晩年は体力が衰え、糖尿病も患いほとんど寝たきり状態に。昭和22年7月11日の朝、孫が露伴のもとへ行ったところ、「おじいちゃまが血だらけ」と言いました。それからはもういつ死んでもおかしくない状況に、27日頃は痛みも感じず、睡眠薬も効かず、鼻血ばかり出していました。娘が「おとうさん死にますか?」と聞くと「そりゃ死ぬさ」と答え、「じゃあおれはもう死んじゃうよ」と言い、意識が途切れがちに。そして7月30日、家族が見守る中静かに息を引き取ったのです。 |
|
|
■斉藤道三 62歳
下剋上を成し遂げた戦国の梟雄は、自分の子ではない長男・義龍と険悪に、とうとう義龍は父・道三を討つべく兵をあげた。主君を殺しのしあがった道三に味方はおらず、老巧な作戦で義龍軍を翻弄するも兵力の数が違いすぎた。敗色の濃くなった道三は、戦場を離脱するも義龍軍の長井十左衛門に見つかった。十左衛門は生け捕りにしようと、道三が疲れるのを待っていたが、そこに小牧源太という男が道三を見つけ首をとった。この2人は功名争いをし、怒った十左衛門が「オレが最初に槍をつけたという証拠を残してやる!」と、道三の鼻をもぎとった。無残な姿となった父・道三の首実験をした義龍は「身からでたサビである。ワシを恨むなよ」と言った。 |
|
|
■真田幸村 46歳
関が原の合戦で西軍にいた幸村は父・昌幸とともに高野山へ追放された。武士として返り咲く日を夢見ていた幸村。そんな頃、徳川家が豊臣家を攻めるという大阪の陣の情報が耳に入る。武士として今一度・・・こう願った幸村は大阪城へ入ることに。豊臣秀頼を取り囲む人々は、幸村らの戦略をまったく聞きもしなかった。幸村らは「こうなっては仕方がない。徳川家康だけを狙おう」。こうして天王寺にて後のない幸村らは死に物狂いで戦う。そして囲みを突破し、家康本陣へ、家康はこの時、死を覚悟した。が、家康は逃げることに成功し、幸村らは戦い疲れ、近くの寺で休息をとる。この時、名もない武将に討ち取られてしまうのであった。 |
|
|
■真田信之 93歳
真田昌幸の嫡男です。父親と弟の幸村が関ヶ原にて西軍となり、信之は東軍(家康側)という、家族でバラバラとなった真田家。かろうじて信之は「真田家」の名前を守ることができたが、気苦労の多い人生となった。なんといっても弟・幸村は大阪の陣で家康の馬印を倒してしまうほどの大活躍。そのため、いつも徳川家から「危険視」されていたのでした。晩年、真田家で家督争いがおき、なんとか解決したものの、心労がたたったのか病床につくように。家臣たちは薬を飲むようすすめたが「我、すでに生きすぎたり」と、薬を拒み続けた。そして眠るように死んでいった。辞世の句は「西へちろり 東へちろり あかつきの 明星のごとき わが身なりけり」。歌のとおり、ほんとに将軍家に気を遣いまくった人生だったのでしょう。 |
|
|
■佐藤忠信 26歳
源義経の郎党。義経四天王の1人。義経が都落ちする際、逃げる義経の身代わりになるため京都に残った。隠れていたが、とうとう見つかり、敵に殺されるくらいならといきなり縁の上に走り出し、腹を十文字に斬った。腸が飛び出したが死にきれず、刀の先を口にくわえ、縁の下へ真っさかさまに落ちて自害した。見事な死に様であったという。 |
|
|
■三条実美 55歳
幕末から明治にかけて、岩倉具視と同じ公卿で活躍した政治家。幕末は苦労したが、新政府になってからは太政大臣になったりと大活躍をしている。55歳の時に世界的に「アジア風邪(インフルエンザのこと)」が大流行した。どんな薬も効き目がなく、発熱から4日後には40度以上もの高熱が出る、さらに肺炎を併発し、体力が著しく低下、もはや手のほどこしようがなくなり、危篤状態に陥る。危篤の急報を聞いて、明治天皇までもが見舞いにやってきた。そして、そのまま亡くなり、国葬が行われた。 |
|
|
■坂本龍馬 32歳
幕末をさわやかに生きた男である。土佐藩出身で、海援隊を結成し、薩長同盟を取り仕切り、日本の未来を見ていた男であった。幕府にとっては邪魔者以外の何者でもなかった。1867年11月15日、京都にある土佐藩出入りの近江屋で、龍馬は仲間の中岡慎太郎と一緒にいた。龍馬は使いの峯吉に軍鶏(しゃも)を買うよう言い、部屋にいた。すると下で「坂本先生はおいでか?わしらは十津川からきた」という声が、相撲取り出身で、龍馬の世話役をしていた藤吉が二階へ行き、龍馬へことづけした。そして藤吉が引き返してくると、突然襲い掛かってきたのである。「ほたえな!」(騒ぐなと言う意味)と叫んだ龍馬だったが、その瞬間部屋の扉が開き、刺客が「こなくそ!」と叫びながら中岡慎太郎の後頭部を切りつけた。龍馬はすぐさま抵抗しようとしたが、頭を斬られた。刺客は倒れた二人をみて「もうよい。もうよい」という言葉を残して消えていった。龍馬は中岡慎太郎に向かい「俺は脳をやられた。もういかん」とかすかに叫び、息を引き取った。数分後、軍鶏をぶらさげて帰ってきた峯吉によって二人は発見され、中岡慎太郎はわずかに息があったが、翌日絶命した。30歳であった。ちなみにこの日は、龍馬の32歳の誕生日であった。 |
|
| 土佐藩の志士。度応3年11月15日の夜、竜馬は京都の醤油屋、近江屋の3階で中岡慎太郎と話し合っていた。8時頃3人の男が訪れ、竜馬の従者に切りつけ、そのあと竜馬と中岡の両名を切った。刺客が帰った後、竜馬は息を吹き返し、残念、残念といいながら、隣室まで這出したが「おれは脳をやられたからもう駄目だ」と微かな声でいってこと切れた。 | |
|
■西郷隆盛 51歳
倒幕の中心にいたにもかかわらず、西郷は見解の違いから明治新政府に入ることはなかった。また、明治新政府に対して不満を募らせる元薩摩藩士たちが西郷のもとに集まり始め、新政府に反旗を翻し「西南戦争」が勃発した。薩摩軍は新政府軍の反撃にあい鹿児島へ逃走。城山にこもったがもはや勝負はついていた。西郷らは5日間を洞窟ですごすも、死を覚悟し山を降りた。その途中で見つかり、下腹を銃弾で撃たれてしまう。西郷は一緒にいた別府晋介に「もうこのへんでよか」と言い、別府に介錯をまかせ自害した。その後、別府は西郷の首を埋めたが、山県有朋に発見され検死が行われた。検死後、黒田清隆と大山巌が山県有朋に遺体の引渡しを求めた、理由は「西郷の功績をたたえ、手厚く葬りたい」というもの。許可を得ることができ、後輩達によって手厚く葬られた。 |
|
|
■俊寛 37歳
俊寛は平清盛を討つべく計画をたてたが失敗に終わった。鹿ケ谷の陰謀と呼ばれるクーデター計画の首謀者として、他の2人とともに鬼界ヶ島へと流される。都育ちの3人が暮らしていける環境ではなく、何とか力を合わせ生き延びていた。そんなある日、とうとう都から使いがやってきた。喜んだ3人だが、平清盛は俊寛だけは許さず、そのまま一人取り残されることに・・・遠くへ消えていく船に向かい、ずっと「船に乗せてくれ・・・」と叫び続けた俊寛。いきている望みは都へ残してきた妻子といつか会えるまで・・・・というものだった。そんな妻子が亡くなったという話を島に様子をみにやってきた人に聞いてしまった。俊寛はもはやいきていく望みをなくし、その日から一切食べ物を口にせず死んでいった・・・・ |
|
|
■清水次郎長 74歳
街道一の大親分と言われた次郎長。20歳頃からいかさま博打をやり続け、ケンカも強かったためどんどん縄張りを広めていった。ヤクザの大親分となった次郎長が、政府から街道の取調べをしてくれないかと頼まれた。これが次郎長の人生を変えることに。この取調べの統率力が大変良かったため、政府との交渉が多くなり、明治天皇の側近である山岡鉄舟に出会ったことにより、社会事業家として成長していく。そして、地元のために力を注ぎ、庶民から慕われるように。晩年は妻と静かに暮らし、妻に看取られ息をひきとった。 |
|
|
■島崎藤村 71歳
詩人、小説家。『夜明け前』が有名。昭和18年8月21日、中央公論に連載の『東方の門』の第3回分を書き上げた。その直後に脳溢血を起し、22日午前零時35分死去した。彼の最後の言葉は「涼しい風が吹いてくる」であった。 |
|
|
■菅原道真 59歳
無実の罪で大宰府に左遷された道真は、ひたすら都に戻ることを願っていた。願叶わず、環境からなる脚気に悩まされ、さらには慢性的な腹痛が出るようになった。とうとう都へ戻る望みを諦め、死んでいった。道真は怨霊となり、京都を恐怖のどん底へ突き落としていく。 |
|
|
■杉田玄白 85歳
解体新書で有名な江戸時代の医師。もともと胃に持病があったが、大きな病気もなく過ぎていった。84歳の時に前立腺肥大(もしくは前立腺ガン)になり、尿が出なくなるように、さらにしゃっくりが多くなった。そして翌年の1817年4月17日に息を引き取った。この時代にしては大往生の85歳である。 |
|
|
■杉原千畝 86歳
杉原千畝は昭和初期の外交官です。満州・フィンランド勤務をへて、リトアニア領事館代理となりました。ここへやってきたのがユダヤ人狩りを逃れてきたポーランドの難民たち。ポーランド難民たちがナチスから逃れるには、シベリアを通過し日本経由でアメリカへ行くしか道がなかった。そのため大量のピザを発給してくれるようやってきたのでした。杉原は日本の外務省へ交渉するも、日本は「日独伊防共協定」があったため、答えはNO。が、領事館の前には死から逃れる為に多くの難民が必死になって発給を待っていた。そして杉原は「この人たちを見殺しにするわけにはいかない」と無断でピザ発給をしたのです。連日、何百枚も書きつづけた杉原。その数は2039枚で、助けた人は約6000人(家族もいるからね)。これは映画の「シンドラーのリスト」で、シンドラーが助けたユダヤ人の5倍であります。が、日本に戻ってくると「独断でビザを発行した」ということでクビに、この時47歳でした。それからは色々と仕事をし、「国際交易」のモスクワ支店長に。昭和43年8月のある日、イスラエル大使館から電話が、それはイスラエルのニシュリ参事官が、ボロボロになった紙(杉原ビザ)を持って、28年間杉原を探していたというものだったのです。68歳の杉原は、翌年イスラエルに招待され訪問。そこでバルハフティック宗教大臣が杉原を出迎えた。この人は、かつて領事館でユダヤ人代表として杉原に会った人だったのです。そして杉原はイスラエル政府からヤド・バシェム賞(諸国民の中の正義の人)を日本人として初めて受賞したのです。感動の再会を終えた杉原は、その後鎌倉市内の病院で静かに息を引き取ったのでした。 |
|
|
■千利休 70歳
秀吉の時代、茶人として権力を持っていた千利休。秀吉の怒りに触れ、切腹を命じられた。秀吉の弟たちが大反対するも、千利休が切腹を受け入れた。切腹の理由はさまざまな説がある。切腹の日、千利休は辞世の句を詠んだ。「人生七十 力囲希咄 ・・・・今この時ぞ天になげうつ」。70歳の千利休は腹を切る力がなく、傷口に手を差し込み、はらわたをつかみ出して死んだ。 |
|
|
■世阿弥 81歳
農村の余興であった猿楽を、芸術にまで高めた人物。子供の頃から美男子だった世阿弥は、12歳の時に室町幕府三代目将軍・義満にヒトメボレされ、寵愛を受ける。義満は世阿弥をことの他可愛がり、猿楽を芸能分野で大きく発展させた。義満が死去すると、義満のことが大嫌いだった息子が四代将軍となる。義満に気に入られていた世阿弥を嫌い、72歳の世阿弥を佐渡島へ流刑にしてしまう。80歳近くなった頃、許されて京都に帰ることが出来たが、まもなく死去してしまう。 |
|
|
■千姫 70歳
千姫は徳川家康の孫である。父親は2代目将軍秀忠・母は織田信長の妹であるお市の方の次女・お江与という、超サラブレット。そして豊臣秀吉の息子・秀頼と結婚が決まっており、7歳の時に11歳の秀頼のいる大阪城へ嫁いだ。1614年実家の徳川家康が、豊臣家を滅ぼすため動き出す、これが世にいう大阪の陣。とうとう豊臣家は滅ぼされてしまうが、千姫は落城寸前に救出された。翌年、姫路城の本多忠刻と再婚、子も生まれ、幸せな生活を送っていたが、夫の忠刻が死んでしまう。以後、千姫は出家し、静かに余生を過ごした。 |
|
|
■平清盛 64歳
平氏にあらずんば人にあらず・・・と言われるほど栄華を極めた平氏。源氏が台頭し始めた、平氏の雲行きが怪しくなり始めた頃、平氏の棟梁・清盛発病。比叡山の水で体を拭っても熱は下がらず、妻・時子は「夢限地獄から迎えがまいった」という夢をみた。清盛は死ぬ前に「源頼朝の首を我が墓前に置け」と言い、死去。 |
|
|
■平将門 ?歳
将門は関東のヒーローである。朝廷に対抗してみずからを親皇と称し、関東を仕切ろうとした。が、藤原秀郷率いる朝廷軍がやってきて、戦いとなる。そこで眉間に矢を射られ死亡。首は京都に晒されたが、その首が「今一度戦いを!」と叫びながら飛んでいった。将門の首が落ちてきたのは今の東京大手町、ここに将門の首塚が建てられている。 |
|
|
■高見順 58歳
小説家。詩集『死の淵より』が有名。昭和38年10月3日、食道ガンの診断を受ける。第1回の手術は10月9日。2回目の手術は翌年の7月。『死の淵より』は8月に書かれた。昭和40年8月、医者から「もうエンジンのないグライダーが風に舞っているようなものです」と宣告される。8月16日、彼が設立のために奔走した「近代文学館」の起工式のメッセージを口述した。「はじめも終りもありがとうございました、としかいえません。一世一代の大風呂致を広けっ放しで病に倒れましたが、どうか末長く頼みます」翌17日午後5時32分、導師の『喝』の声とともに死亡。 |
|
|
■武田信玄 52歳
織田信長を倒すべく京都へ向かっていた信玄。途中で発病する、病は一向に治る気配はなく、とうとう一度甲府に帰ることに。甲府に帰る途中に具合が悪化し、「我が葬儀は無用である。3年間はワシの死を隠せ。ワシの遺体は甲冑を着せ、諏訪湖の底に沈めるように」と遺言して息を引き取った。なお、信玄の死を聞いた天敵・上杉謙信は食事中であったが、「惜しい人物をなくした」と涙を流したという。 |
|
|
■武市半平太 37歳
土佐勤王党のリーダーであった半平太。弾圧され捕らえられてしまう。自らの死を悟った半平太は、「切腹というのは腹を一文字に掻き斬る者が多いが、古法によると十文字と三文字が作法だそうだ。拙者はどちらかの方法で死ぬつもりだ。世の中の人々に半平太の心が乱れたからと言われるのは心外であるから、半平太の心構えを同志に伝えてくれ」。こう言って、半平太は刀を左腹に突き立てると、右に三たび斬った。手際も鮮やかな古式三文字割腹であった。 |
|
|
■伊達政宗 69歳
東北の覇者である独眼竜政宗。徳川の世になると、政宗の出番はなくなっていった。60歳を過ぎると息子に家督を譲り、花鳥風月を愛する日々を送った。そんな政宗も、しだいにやせ細り、食べ物は葦で作ったストローで流し込みながらでしか口に入らなくなってきた。死ぬ間際、江戸で将軍家光に会い、徳川家の恩愛を感謝した。家光は医者を差し向けたが、もはや医師がみてもどうにもならない状態だった。こうして臨終が迫り、辞世の句を詠むと、静かに横になりこの世を去った。「曇りなき 心の月を先だてて 浮世の闇を 照らしてぞゆく」 |
|
|
■伊達輝宗 42歳
伊達輝宗は、伊達政宗の父親である。幼い頃疱瘡にかかり、片目が見えなくなってしまった政宗を嫌った実母・義姫は、次男の小次郎を次期当主にしようとした。輝宗は政宗を可愛がり、伊達家を継ぐのは政宗と決めた。政宗はそんな父を慕っていたが、輝宗が敵である畠山氏にさらわれてしまった。政宗は激怒し、畠山軍を追いかけ、そして追いついたが攻撃することができない。相手側に父親がいるからであった。父の輝宗は大きな声で「家門の恥を残すな!!わしとともに撃て!」と叫んだ。政宗は涙を流しながら父親のいる畠山軍へ向かい一斉射撃を命じ、伊達家は勝利した。その後、政宗は父をさらった畠山家を惨殺したという。 |
|
|
■田沼意次 70歳
江戸時代の10代目将軍・家治時代に賄賂政治をしまくった老中。家治が全面的に信用しており、やりたい放題だった。家治が死去すると、今まで「田沼政治」に不満を持っていた人たちが一気に爆発し、とうとう老中の座を奪われてしまった。住んでいた城と所領を没収され、心血を注いで築いた相良城が取り壊されてしまった。それがものすごく悲しかったらしく、取り壊されてから5ヵ月後、死んでしまった。 |
|
|
■滝沢馬琴 82歳
南総里見八犬伝を書いた人。48歳の時に南総里見八犬伝を刊行し大人気に。65歳から眼が悪くなり始め、68歳になると右目が失明。そしてとうとう74歳の時に左目も失明してしまい、長生きしすぎたことを嘆くように。眼が見えなくなってからは、南総里見八犬伝の続きを亡き長男の嫁に書かせ、とうとう完成させた。その後、激しい胸痛に襲われ、1848年11月6日に死去した。 |
|
|
■高杉晋作 29歳
生きていればおもしろかったであろう幕末の男である。長州藩出身で、吉田松陰に学んでいた。奇兵隊を結成し長州征伐では幕府軍と戦った。気まぐれではちゃめちゃ。だけどとても慕われていた。そんな高杉晋作は結核にかかっていた。体力が限界となり、療養生活に入る。世話になっている野村望東尼に向かい、「おもしろきこともなき世をおもしろく」と書いた紙を渡すと、望東尼が「すみなすものは心なりけり」と続けた。すると晋作は「おもしろいのう」とつぶやき、そのまま息絶えた。 |
|
| 長州藩士。度応2年小倉城攻撃を指揮していたが、以前からの肺患が悪化する。翌慶応3年4月病床で、「面白きこともなき世を面白く」と書いた。あと望東尼が「すみなすものは心なりけり」とまとめると「面白いのう」と笑って目を閉じた。 | |
|
■谷崎潤一郎 79歳
エロティシズムの世界を確立させた谷崎潤一郎。痴人の愛など傑作を生み出した。昭和39年に体調を崩し入院。治療生活に疲れ、こんな生活を繰り返すなら死んだ方がましたと、毎日のように死にたい死にたいと言っていた。最後はシャンペンを飲み、好物のぼたん鱧を食べ危篤となる。病院で酸素吸入のマスクをつけるも、突然マスクをはずしのげぞって死亡した。 |
|
|
■高村光太郎 73歳
智恵子抄で有名な作家である高村光太郎。最愛の妻・智恵子が狂気の末死んでから7年後、結核になってしまう。高村光太郎は「人間の生涯とは苦しみの連続だ。死んでやっと解放される。これで楽になれる」と語った。また「ぼくには智恵子がやってくる。ぼくは智恵子と二人でいつも話し合っている。だから寂しいことなんてちっともなかったのさ」と話した。最後の詩は「智恵子の裸形をこの世に残してわたしはやがて天然の素中に帰ろう」というものであった・・・ |
|
|
■竹久夢二 50歳
挿絵画家として一世を風靡した夢二。自由奔放な恋愛遍歴を持ち、人気画家として名誉を得ましたが、晩年は人気が落ち目になってきました。ここで心機一転!と、欧米に行くが、途中結核を煩い帰国。そのまま信州の高原療養所に入院となりました。夢二はキレイな空気を吸い、治療に専念するも昭和9年9月1日 入院して9ヵ月後に死亡しました。入院してからの間、見舞い客はほとんどなく、臨終を迎えても肉親は誰も姿を現しませんでした。夢二は医者と看護婦に「ありがとう」と言ったきり、この世を去りました。 |
|
|
■太宰治 38歳
津軽屈指の大地主の子供として生まれ、何不自由ない生活をしていけるはずだった。芥川龍之介の影響を受けており、芥川が自殺した時に強い衝撃を受けた。その4年後、睡眠薬を飲み自殺をはかるが未遂に終わる。その後、大学に進み井伏鱒二に教えを請う。その年に銀座のカフェの従業員とまたも睡眠薬自殺するが、またも未遂に終わった。その後も何度も自殺を図るもすべて未遂。さらには麻薬中毒にもなった。そして最後の作品「人間失格」を書くと、「死」にとりつかれた太宰治は、山崎富栄という女性と玉川上水で入水自殺。入水前に富栄に自分の首を絞めさせたらしく、死体には縄が首にまきついたままだった。そして二人はお互いを紐で結び合って心中したのである。 ■ 玉川上水から引き上げられた太宰と富栄の遺体は、出版社の人たちによって、人目を避けて結んだ紐を切り離され、別々の場所で荼毘に付されました。 また、「骨の一部でもいいから一緒に埋めてほしい」という富栄の願いもかなえられませんでした。太宰の遺骨は望んだとおり、三鷹市禅林寺の森林太郎(鴎外)の墓に向かいあって葬られました。 毎年6月19日の太宰の命日「桜桃忌」には、大勢の女性太宰ファンが花束を持って、おまいりにやってきます。「死ぬ気で恋愛してみないか」とじっと目を見つめながら迫った太宰の言葉の魅力は、今でも多くの女性を捉えて離さないようです。 |
|
|
■円谷幸吉
幸吉は2通の遺書を残しました。そのうちの1通、家族にあてた遺書には、私たちが知るべき彼の人生の全てが表れているようでした。 「父上様、母上様、三日とろろ(註)美味しゅうございました。 敏雄兄、姉上様、おすし美味しゅうございました。 克美兄、姉上様、ブドウ酒とリンゴ美味しゅうございました。 巌兄、姉上様、しそめし、南ばん漬け美味しゅうございました。 喜久造兄、姉上様、ブドウ液、養命酒美味しゅうございました。 又、いつも洗濯ありがとうございました。 幸造兄、姉上様、往復車に便乗させて戴き有難うございました。 モンゴいか美味しゅうございました。 正男兄、姉上様、お気を煩わして大変申しわけありませんでした。 (中略) 父上様、母上様、幸吉はもうすっかり疲れ切ってしまって走れません、何卒お許しください。気が安まることもなく御苦労、ご心配をお掛け致し申しわけありません。 幸吉は父母上様の側で暮らしとうございました。」 (註 / 彼のふるさと福島県須加川で1月3日に食する習慣がある。) ■ 幸吉の自殺はその遺書によって、より深い印象を人々に与えました。むしろ、幸吉の遺書は自殺そのものより印象深かったと言い換えてもいいかもしれません。幸吉の遺書は、単純そうに見える文章によって、まことに驚くべきものを人に伝えています。その点で、多くの作家たちが述べた感想はまことに興味深いものでした。 川端康成は、『円谷幸吉選手の遺書』において、「繰り返される《おいしゅうございました》といふ、ありきたりの言葉が、じつに純ないのちを生きてゐる。そして、遺書全文の韻律をなしてゐる。美しくて、まことで、悲しいひびきだ」と語りました。さらに「ひとえに率直で清らかである。おのれの文章をかへりみ、恥ぢ、いたむのは勿論ながら、それから(川端)自身を問責し絶望する」、そして「売文家の私はここ(幸吉の遺書)に文章の真実と可能性を見えたことはまことであった」と文豪川端康成を感嘆させました。 文章力というものが訓練によって身につくものだとすれば、幸吉のこの文章の力を説明することは出来ません。独特の生い立ちや生活環境が、彼にしか持てない表現力を身につけさせたとしか思えません。 ■ 野坂昭如は、「何というすさまじい呪いであるかと受け取った。・・・いわれなき重圧を背負わされ、疲れはてたあげくの、悲鳴といえばいいのか。《ありがとうございました》《美味しゅうございました》のくどくどしいくりかえしが、生者調伏(生きている者を呪い殺す)の呪文のごとき印象」を与えると語りました。 沢木幸太郎は『長距離ランナーの遺言』において、「円谷の遺書には、幼いころ聞いたまじないや(不気味な)呪文のような響きがある。農村の奥深く眠っている土俗の魂が秘められているように思える」と書き、日本を代表する前衛的戯作者・唐十郎の『腰巻お仙-振袖火事の巻』をとりあげます。 ■ 芝居『腰巻お仙-振袖火事の巻』の主人公は唐十郎自身が演じましたが、その名は円谷幸吉の姓と耳なし芳一の名をつなぎ合わせた「円谷芳一」です。そして、経文を体中に書きつけて身を守った『耳なし芳一』に倣(なら)って、「円谷芳一」の体に「一族血縁の文」と唐が呼んだ幸吉の遺書を書きつけさせます。ここで唐は、円谷芳一を守る幸吉の遺書が、呪文のような「一族血縁=古い日本的な紐帯(ちゅうたい)」の底知れぬ不気味さを表現していると感じているかのようです。唐は、戦後の日本を覆いつくした西洋的合理主義の底に、したたかに生き残っている古い日本の情念を見たのでしょうか。 饒舌を避け食べ物に対する礼だけを言うことが生涯の全てに対する礼であることを雄弁に語っていること、単純な言葉の繰り返しによる表現によってそのことが際立たせられていること、そしてこれらが『日本的なもの』の規範に従っていることを、この遺書は人々につよく印象づけます。 |
|
|
■豊臣秀吉 62歳
天下統一を成し遂げた秀吉。が、跡継ぎが側室である淀君の生んだ秀頼一人しかいなかった。幼い秀頼を残して死ぬのが心配でしょうがなく、五大老(徳川家康・前田利家ら)に死ぬ間際までしつこいくらい秀頼のことをお願いして死んでいった。天下統一を成し遂げた男であったが、最後まで秀頼のことを心配しつつこの世を去っていった。 |
|
|
■豊臣秀次 28歳
豊臣秀吉の甥である秀次は、秀吉に子供が生まれないため、秀吉の後を継ぎ、関白となった。その後に淀君に秀頼が生まれてしまう。秀吉は関白を秀次に譲ったことを後悔し、秀次を切腹するよう追い詰めたのである。そして秀次の妻子や妾あど30人以上が三条河原にて処刑された。 |
|
|
■徳川家康 75歳
豊臣を滅ぼし、名実ともに天下をとった家康。江戸幕府を開き、大御所として政治の世界で君臨していた。ある時、茶屋四郎三郎が「最近京都では鯛のてんぷらなるものが流行しております」と伝えた。家康はその食べ物に興味を持ち、早速調理。かなり気に入ったらしく、なんと丸々二匹分の鯛のてんぷらを食べた。その四時間後、急に腹痛を訴えた、そしてのどに痰が絡んで苦しみだしたのである。すぐさま寝床についた家康だが、病状は悪くなるばかり、とうとう息を引き取ってしまいました。 ■ 鷹狩での発病からほぼ3ヶ月間、病状は一進一退を繰り返していましたが、ついに4月17日家康は駿府城中で死去しました。4月2日に家康は、「遺体は久能山へ埋葬、葬儀は増上寺で、位牌は三河大樹寺に立て、一周忌が過ぎたら日光に小堂を建て関東八州の鎮守とするよう」遺言します。 秀忠は、家康が生きている間はその一言一句に一切逆らうことが出来なかったのですが、死んでしまえばもう怖くはありません。自らの政権安定のため家康の神格化を図り、家康の遺言のほとんどを無視します。 遺体はその夜のうちに降り続く雨のなか久能山に送られ、葬儀はその場でしかも神道の形式にのっとって、(天皇に習って)夜儀で行われました。増上寺には葬儀ではなく中陰(49日までの間)の法要を行うよう命じました。当初予定されていた『大明神』という諡号(しごう)は秀吉と同じであるという理由で、天台宗の僧天海の進言により『大権現』に変更されました。 1年後、日光に東照宮が立てられ、金の輿(こし)に乗った遺骸と神体は1300人を超える行列を従え久能山から日光へと遷座(せんざ)しました。これもまた家康の遺言にはなかったことです。 |
|
|
■徳川家光 48歳
徳川幕府三代目将軍。幼い頃から病気がちで、マラリヤや腫れ物、痘瘡など多くの病気にかかっていた。34歳の時に、どうやらうつ病になったらしく、江戸城に引きこもり誰にも会わなくなり、酒を飲んでごまかしたりしてすごした。当時、うつ病という病気はなかったが、当時の家光の様子を書くと、御三家が見舞いに来ても顔を出さない/めまいがする/落ち込みが激しい/手足が冷える/鷹狩りに出かけたが、ずっと駕籠の中に入ったっきり/少しの物音でビクビクする/短期になり、理不尽な怒りで家臣を困らせる/夜、眠ることができない、などなど。だいぶ回復はしてきたものの、頭痛や歩行障害など様々な病気となり、48歳で死んでしまった。 |
|
|
■徳川光圀 73歳
水戸黄門で有名な徳川光圀。若い頃か遊び人だったが、39歳で水戸藩2代目藩主となり活躍する。63歳の時に家督を譲り、隠居生活に入った。隠居生活では、大日本史の編纂に没頭するが、だんだんと食欲がなくなり、酒をまずいと想うように、そして次第に呼吸が弱くなり、息をひきとった。死ぬ5日前にも大日本史を気にかけており、3箇所訂正するなど、名君らしい最期となった。 |
|
|
■徳川吉宗 68歳
徳川八代目将軍は、暴れん坊将軍として時代劇でも有名。22歳の時に紀州藩主となり、33歳で将軍となった。徳川家康を尊敬しており、健康法も全て家康を見本にした。そのため健康であった。一度脳卒中を発症したが、後遺症もなく大好きな鷹狩りも出来るように。生涯健康で過ごしたが、68歳で死去。死因は脳卒中の再発か、もしくは前立腺がんとも言われている |
|
|
■徳川綱吉 64歳
徳川時代の将軍の中で評判が悪かった綱吉。「生類憐みの令」を出し、人間より動物を大切にするようになり江戸庶民の不満を買いまくった。そんな綱吉の死は当時流行していた麻疹にかかって死んだというもの。御台所(正妻)が殺したというウワサもある。そして御台所もすぐさま後を追い、自害したとされている。また、綱吉の死を聞いた人々は声をあげて喜んだらしい。 |
|
|
■徳川慶喜 77歳
最後の将軍となった慶喜。大政奉還をし、徳川家康から260年ほど続いた江戸幕府に終止符をうった。慶喜を死刑に!という声が多くあったが、戦犯扱いされることなく駿府に移り住んだ。彰義隊や白虎隊など多くの人が幕府のために最後まで抵抗したのに、慶喜は「これからの長い年月、日々退屈しないようにせねばならぬな」と語ったという。実際、本当に趣味に生きた。特に好きだったのがカメラ。さらに2人の側室との間に21人もの子供を生んだ。食べることには困らず、明治時代を楽しみ、死んだのは大正二年である。 |
|
|
■徳川夢声 77歳
話術家。昭和46年7月22日、腎孟炎で入院。7月末、彼は妻に爪を切ってもらうと、その手を目の先にもっていってじっと眺めた。妻は病人が自分の手を見詰めるようになると、まもなく死ぬという話を思い出して「疲れますよ」といってその手を下ろした。3日後の8月1日午後零時20分、妻に「おい、いい夫婦だったなあ」といって死亡。 |
|
|
■鳥居耀蔵 78歳
鳥居耀蔵といえば、幕末「妖怪」といわれた人。幕府の手足となって、邪魔者を徹底的に追い続けた人であります。有名な蛮社の獄にも絡み、稀に見る残酷な幕吏として有名ですね。ボスの水野忠邦が失脚すると連座して捕らえられる。人々を監視する立場にあった耀蔵は、一転して監視されながらの生活に、解放されたのは江戸が東京になってから。その時もかつての部下に対してさんざん洋風嫌いを熱弁し、徳川直参であるというプライドを失っていなかった。そして明治5年に死去しました。 |
|
|
■唐人お吉 51歳
本名は斉藤きち。14歳の時に下田で芸者となり、美人だったため評判に。お吉の運命が変わってしまったのは17歳の時。当時、下田には日米通商条約の締結を迫るハリスがきており、対応に苦慮した下田奉行所は美人のお吉を妾にさせ、ハリスとの交渉を楽にしようとしたのである。幕府はお吉に莫大な大金のお給料を提示するも、お吉は将来を誓い合った恋人もいるため何度も何度も断った。お役人や地元の名士に何度も頼まれ、とうとう断れなくなってしまったお吉は泣く泣く了解する。そして4ヶ月ほどハリスに仕えるが、外国人の妾となり大金を手にしたということで、お吉は世間から白い目で見られることに。ラシャメンと罵られ、下田に住むことが出来なくなってしまったお吉は、様々な場所を点々とするが、どこに行っても「唐人お吉」のレッテルがついてまわった。次第に酒に溺れるようになり、身も心もボロボロに。最後は下田の川に身を投げ、自らの命を絶ったのであった。 |
|
|
■東郷平八郎 87歳
日露戦争で日本を勝利に導いた東郷平八郎は、偉大な提督として一躍有名に。日露戦争後は海軍軍令部長となり、伯爵に叙された。さらにアドミラル・トーゴーとして賞賛を浴び、軍事参義官・元帥と出世街道まっしぐら。さらに東郷御学問所総裁に就任し、皇太子(昭和天皇)の教育係となった。あまりにも英雄的存在となり発言力が重すぎてしまったため、晩年はやや煙たい存在に。そして昭和八年ごろから咽頭ガンにおかされ、死去した。死の直前に侯爵に叙され、日比谷公園で国葬が営まれた。 |
|
|
■長屋王 ?歳
屋敷跡が発見されたことで有名になった長屋王。聖武天皇へ謀反しようとしているという藤原氏のでっちあげによって、弁解の余地のないまま屋敷を囲まれた。そして無念の自害。自害後、無実ということがわかった。 ■ 長屋王(ながやのおおきみ、天武天皇13年-神亀6年 684?-729 ) 奈良時代の皇族。官位は左大臣正二位。皇親勢力の巨頭として政界の重鎮となったが、対立する藤原氏の陰謀といわれる長屋王の変で自害した。 |
|
|
■中浜万次郎 71歳
中浜万次郎(ジョン万次郎」といえば、14歳の時に土佐沖から漂流し、ハワイへ上陸した人。以後、アメリカで勉強し、漂流から10年後日本へ戻ってきました。英語が喋れて国際的にも通用する人だったので薩摩藩の教授をしたり、捕鯨活動をしたりと活躍する。明治維新後は現在の東大の教授となり、英語を教えました。そして明治三年にはヨーロッパへ出張をし、帰ってきてからすぐに脳溢血を起こして倒れ、命はとりとめましたが以後表舞台に出ることはなかった。 |
|
|
■中原中也 30歳
昭和10年ごろの日本は、結核で死ぬ人が一番多い頃でした。特に20〜30歳までの人が多く死んだため、亡国病とまで呼ばれるほど。そして、詩人の中原中也も結核になってしまったのです。中也がかかったのは「結核性脳膜炎」。結核患者がくしゃみや咳をしたことにより感染し、その結核菌が脳を襲うのです。中也は入院した時すでに歩行困難や頭痛、そして眼球が異常なほど膨れ上がっており、うわごとばかり言っていたそうです。そして入院してから16日後、中也は親しい友人と家族に見守られて息を引き取ったのでした。最後の言葉は「ボクは本当は親孝行者だったんですよ。今に分かる時がきますよ」。 |
|
|
■夏目漱石 50歳
「坊ちゃん」「吾輩は猫である」を執筆した文豪。明治を代表する文豪・漱石は二つの病気にいつも悩まされていた。一つは神経衰弱 そしてもう一つは胃の病気でした。42歳で本格的に胃が痛くなりはじめ、「門」を執筆中とうとう入院。その後、修善寺温泉で静養することとなり、8月6日の暑い日に一人で修善寺へ。修善寺へ着くと同時に病状が悪化し、多くの血を吐いた。なんとか命はとりとめたものの、その後は病状悪化を繰り返す。そして大正五年の11月22日に机にうつぶせになり倒れる。最後に「死ぬとこまるから・・・」とつぶやくと、そのまま意識を失い死去した。 |
|
| 明治末期から大正初めの小説家。『坊っちやん』『こころ』。漱石は晩年、糖尿病と神経痛と皮膚病とノイローゼと、持病の胃潰瘍に悩まされていた。大正5年11月21日連載小説の『明暗』188回を書き上げ、翌22日女中に書斎に倒れているところを発見される。12月9日、漱石はひどく苦しみ始め、自分の胸をあけて「早くここに水をぶっかけてくれ。死ぬと困るから」というようなことを言い、看護婦が水を含んで吹きかけると「ありがとう」といい、そのあと意識を失ってしまった。 | |
|
■永井荷風 81歳
若い頃はかなりの自由人。反感を抱いていた父が死ぬと、さらに自由人に。そして73歳で文化勲章を受章し、文壇においては不動の地位を築いた。晩年は孤独だった。一人暮らしをしている永井荷風の家には誰も遊びに来ることはなく、書斎には万年床が敷かれており、部屋はホコリだらけだった。ある朝、いつものように朝食を食べに近くの喫茶店へ、その帰りに気分が悪くなり、病床に伏すことに。そして朝、お手伝いさんがやってきたときに見た光景は、上半身を布団から乗り出してうつぶせに倒れている永井荷風の姿であった。 |
|
|
■新田義貞 37歳
鎌倉幕府を滅亡させた義貞だが、足利尊氏と対立。後醍醐天皇の味方につき、尊氏軍とバトルになった。状況は不利だった。家臣達は義貞を逃がそうとしたが、「部下を失って自分ひとりが助かるなどできぬ」と敵の中へ突入しようとした。そこで馬を蹴ったが、ちょうど敵の矢が義貞の乗った馬に当たり、義貞は田んぼに転げ落ちた。やっと立ち上がったところを眉間のど真ん中に矢を討たれる。もはやこれまでと悟った義貞は、みずからの首を切り、田んぼに突っ伏して死んだ。 |
|
|
■二宮尊徳 70歳
一昔前は、小学校とかに銅像が多く置かれていた二宮尊徳。実は身長182センチ体重94キロという、銅像からは想像がつかないデカイ男でした。農村の復興に尽くしまくった人生で、死ぬ寸前まで働き続けた。さすがの尊徳も年には勝てず、疲労の蓄積により病床についてしまい、そのまま息をひきとったのでした。 |
|
| 江戸後期の農政家。通称金次郎。安政3年10月20日、今市の居宅で多くの崇拝者に囲まれ、「葬るに分を越ゆるなかれ、墓や碑を立てるなかれ、ただ土を盛り、そのわきに松か杉一本を植えれば足る」といって息を引き取った。 | |
|
■野口英世 51歳
2歳の時に囲炉裏に転落し、左手の自由を失ってしまった野口英世。障害に負けずに勉強に励み、医学の道を目指してアメリカへ。蛇の毒の研究をし、細菌学者として「世界のノグチ」にまで上り詰めました。そして黄熱病の研究のため、西アフリカへ旅たったのです。ここで自らが黄熱病にかかり、命を落としてしまったのでした。ちなみに黄熱病のほかにも梅毒を併発していました。いつどこで梅毒に感染したのかは謎ですが、どうやら女性関係はルーズで、若い頃は頻繁に遊郭へ通っていたとの事です。 |
|
| 梅毒の病原体であるスピロヘータの純粋培養に成功したほか、数々の病原体の研究に従事した。1924年アフリカ西南部で黄熱病が発生したため、1927年秋、彼は調査のため現地のアクラに向かった。翌年の元旦より黄熱病の症状を訴えるようになる。5月10日頃から再び黄熱病の症状を訴え、13日見舞いに来た医師に、一度黄熱病にかかって免疫になったのになぜ再発したのか「どうも僕には分からない」と語った。20日には意識不明となり、21日正午頃、息を引きとった。 | |
|
■乃木希典 64歳
明治時代の陸軍軍人。日露戦争で大活躍した人です。満州から凱旋してきた時、乃木は明治天皇にこういいました。「旅順攻略に半年も費やして、多くの犠牲を出してしまいました。この責任は割腹してお詫びしたいと思います」。すると天皇は「今は死んではならぬ。死を願うなら余が世を去ってからにせよ」と言ったのです。この時、天皇は55歳 乃木は58歳でした。以後、乃木は軍事参議官と学習院院長を兼任。なぜ学習院の院長??というと、乃木は二人の息子を日露戦争で戦死さえていたので、二人の代わりに沢山の子供を・・・という願いから。明治45年7月30日に明治天皇が崩御。この日から乃木は毎日続けていた日記をやめ、赤坂にある自宅の表札をはずしました。9月13日天皇の葬儀が行われました。この日、乃木(64歳)と、その妻・静子(54歳)は、部屋に明治天皇の写真を飾り、自害したのでした。 |
|
|
■服部半蔵 55歳
伊賀出身で忍者のリーダーであった服部半蔵。江戸時代になり、屋敷を与えられた(現在の半蔵門)。時代が平和になり忍者の仕事が無くなってきた。次第に配下の忍者達は不満を漏らすようになり、盗みを働くように。その取締を幕府から命じられた半蔵だったが、逆に襲われそうになる。なんとか解決したものの、半蔵は責任をとって出家した。 |
|
|
■平手政秀 62歳
信長の教育係だった政秀は、責任感が強く、マジメな男だった。当の信長はうつけ者で、毎日毎日奇矯な振る舞いばかり。何度政秀がたしなめても、信長のうつけは治ることがなかった。そんな頃、信長の父、信秀が死亡、その葬式の場でも信長は乱行に及んだため、政秀は死を持って信長を諌める覚悟を決めた。こうして政秀は自分の教育の仕方が悪かったと責任を取り、切腹。信長は政秀の死を悲しんだという。 |
|
|
■平賀源内 52歳
源内はエレキテルを発明するなど、江戸時代においての天才であった。色んな方面に手を出すマルチ人間であった。源内の中には天才であるがゆえの狂気も潜んでいた。ある日源内は殺人を犯す、こうして小伝馬の牢獄へ、そしてその罪も定まらぬうちに病死した。 |
|
|
■平塚らいてう 85歳
「原始 女性は太陽であった」という名言を残した、女性解放運動の先駆者・らいてう。女性の権利を高めるために運動し続けた、84歳の時にガンが見つかる。最後は「わたしはいつ死んでもいいのよ。もう充分に生きたわ。自分の好きなことをやって私の一生はとても幸せだった」と語った。死んだのは昭和46年。 |
|
|
■樋口一葉 24歳
「たけくらべ」「にごりえ」などの作品を出した明治時代の作家。たけくらべを発表し、森鴎外らから絶賛され、これから!という頃に喉がはれてきた。風邪をひいたと思っていた一葉だったが、いつまでも治らない。次第にやせてきて、目がどんよりしてくるように。そして高熱が続いた。心配した妹が病院に連れて行くと、もはや絶望的な状態となっていた。妹は動揺し、泣きに泣いたその数ヵ月後、一葉はもはや起きることもできなくなってしまった。馬場狐蝶がお見舞いに訪れた時、一葉にはすでに死の影が見えていた。狐蝶が「暮れにもう一度来ますね。その時にまた会いましょう」ちおうと、一葉は「その時、私は何になっているのでしょう。石にでもなっていましょうか」とつぶやいた。そして静かに息を引き取った。 |
|
| 明治中期の小説家。「たけくらべ」「にごりえ」を発表。明治29年11月3日、教師の馬場が一葉を見舞い「冬休みにまた上京しますから、そのときまた参りましょう」といった、すると一葉は苦しそうな声で「その時分には、私は何になっていましょう、石にでもなっていましょうか」と切れ切れに言った。それから20日後、彼女は死んだ。 | |
|
■藤原道長 62歳
藤原全盛期を作り、自らの人生を「望月の世」とまで詠った道長でしたが、最後の夢は極楽浄土へ行くことであった。53歳にて最高権力を握った道長でしたが、その後は体調が悪くなり、顔色が悪くなってくる、どうやら糖尿病だったらしい。やがて目が見えなくなりはじめた。最後には背中に大きな腫れ物が出来て、うみを出すために鍼治療、それはものすごく痛かったらしく、道長は悲鳴をあげた。そしてその数日後、息を引き取った。 |
|
|
■藤田東湖 50歳
幕末の水戸藩の代表的な人物である。水戸藩の中心的人物であった。1855年10月2日 江戸は大地震に襲われた。江戸にいた東湖は、地震と気づくと、別室にいる母を助けに行った。母は火鉢をつけっぱなしにしているのを思い出し「火鉢の火が!!」と叫び、また家の中に戻ってしまったのである。東湖は慌てて母を追いかけたが、その瞬間またもものすごい揺れが、そして懇親の力を込めて母を庭に放り投げ、自らは建物の下敷きにあったのである。 |
|
|
■福沢諭吉 67歳
65歳の時に脳卒中を起こし、昏睡状態に陥ったが、なんとか回復した。二年後に再発し、この時はとうとう助かることはできなかった。諭吉の命を縮めたものは「酒とタバコ」と言われている。特にタバコは死ぬまでやめることはできなかった。 |
|
|
■船橋聖一 72歳
風俗小説家。昭和50年の秋、文化功労賞を受けることになったが、弟たちがお祝いの品を届けなかったことから癇癪を起こし「弟妹たち合わせて100万円もって来い」と怒号した。そのあと彼は心臓喘息の発作を起こした。翌年1月13日、再び発作を起こし意識を失う。午後零時58分急性心筋梗塞により死亡。 |
|
|
■別所長治 23歳
豊臣秀吉に攻撃されることとなった三木城、当主が別所長治だった。秀吉は城攻略の作戦として兵糧攻めを行う。三木城には食べるものがなくなり、餓死者が続出。人肉まで食べるほど飢えはすさまじいものだった。とうとう長治は「私の一族が切腹するので、城兵の命を助けてください」と助命嘆願。こうして長治は四人の子をみずから刺し殺し、切腹となった。 |
|
|
■ペリー 63歳
幕末、黒船で日本にやってきたペリー。日米和親条約を結び、日本の鎖国を打ち破った有名な人物である。実は日本にいる頃からちょっと体調が悪かった。日本での任務が終わるとヨーロッパ経由で本国へ帰国。その後、「日本遠征記」の編纂に力を注ぎ、1858年にこの作業を終えた3ヵ月後、妻の実家で心臓発作となり死去した。 |
|
|
■北条仲時 28歳
鎌倉時代の十三代執権基時の息子であり、最後の六波羅探題のボスだった人。後醍醐天皇により鎌倉幕府を討幕する動きが強まっていた頃、足利尊氏の裏切りにより六波羅探題はもはや戦う気力がなくなってしまった。尊氏率いる天皇勢に追われることとなった六波羅探題の人々は、逃げる決心をすることに。仲時は最後の時を妻子と過ごし、翌朝出発した。様々な追っ手が逃げる仲時らに襲い掛かり、仲間たちは次々野武士に殺された。仲時は最後まで味方が助けに来てくれると信じていたが、助けに来る味方であったはずの佐々木時信はすでに天皇勢の味方についていた。もはやこれまでと察した仲時らは、逃げ延びた132人と同時に切腹するという壮絶な死を遂げた。切腹した場所は、死臭が充満し目をそむけたくなる惨状だった。その2週間後、鎌倉幕府は滅亡することとなる・・・ |
|
|
■北条早雲 88歳
戦国大名第一号と言われ、一代で北条家を築いた梟雄。関東を制覇し、早雲二十一か条という家訓を残した。そんな早雲は老後も元気で、死ぬ前には三浦半島に旅行にまで行ってました。さすがに歳には勝てず、三浦半島に船遊びに行った帰りから具合が悪くなり、そのまま息を引き取った。 |
|
|
■北条氏康 57歳
北条五代の基盤を築いた人。そして上に書いた北条早雲の孫。まわりは強敵だらけだったが、ひとつも引けを取らない男でした。病名はわからないが突然病に倒れ、自分の子供の顔もわからなくなるほど。いっときは回復したんだけれども、再びぶりかえし一年以上闘病生活となる。最後は小田原城で息を引き取った。 |
|
|
■北条泰時 60歳
鎌倉幕府の三代目執権。すぐれた政治家であったが、なんせマジメで忙しい日々を過ごしていた。57歳の時に体調を崩し、いっときは精神錯乱状態に、出家もせず、まだ仕事を続けた。無理がたたって、具合が悪くなり、赤痢になってしまう。体は火の様に熱くなり、苦しみもだえながら死んでいった。人々は、まるで平清盛が死んだ時と同じようだと囁きあい、また後鳥羽上皇の怨念だとも噂された。 |
|
|
■北条時宗 34歳
鎌倉幕府八代目執権。この時代は、蒙古が襲来してきた時期であり、ものすごく大変だった。総指揮にあたった時宗は、国を守るために働き、心労続き。蒙古は2度日本を襲ってきたが、二度目の弘安の役の二年後、相当なストレスが溜まっていて執権の座を弟に譲った。そのまま体調は悪化し、とうとう水も飲めなくなった。そしてそのまま衰弱して息を引き取った。 |
|
|
■保科正之 62歳
三代将軍徳川家光の弟。日の目が当るはずじゃなかったのに、家光に気に入られ会津藩をもらう。そして「会津藩はどんなことがあろうとも将軍家を守る」という家訓を残した。この保科正之の家訓がのちの会津藩を激動の中に巻き込むこととなる。51歳になった正之は目の病気(白内障)になり、失明寸前に、さらに老人性不眠症に悩まされた。死を覚悟した正之は、死の準備をし始めました。そして病が悪化すると、娘婿の稲葉正通を小田原から呼び寄せ、残った息子の後見人となるよう遺言を残して死んでいった。 |
|
|
■松永久秀 67歳
足利将軍殺害・大仏焼き討ち・主君殺しの三悪をやってのけた久秀も、織田信長の勢力の前には抗うことはできなかった。だが、野望は尽きることなく、信玄が上洛するというウワサを聞いた久秀は信長に反旗を翻した。信玄が上洛途中に死去。信長は久秀の持つ名器「平蜘蛛の茶釜」を渡せば許してやると言ったが、久秀は「ワシの白髪頭と平蜘蛛の茶釜をヤツに渡すくらいなら」と、みずからの体に茶釜をくくりつけ、爆死という壮絶な死を遂げた。天下を取れる器と言われつつも、信長の一武将に成り下がった自分の身が悔しかったのだろうか・・・ |
|
|
■前田利家 61歳
豊臣秀吉に秀頼のことを頼まれた利家だったが、次なる天下を狙い、徳川家康が動き出していた。家康にとって、今一番邪魔な実力者は利家であった。利家は死ぬ間際に「わしが死んだら必ずや騒ぎが起こるであろう。もし秀頼様に対して謀反を行うものがあればすぐさま兵を率いて大阪へ行け」と、遺言した。最後まで秀吉に頼まれた秀頼を思いこの世を去った。この後、利家が死んだことにより世の中は大乱へと突き進んでいくこととなる。 |
|
|
■松平清康 25歳
清康は、徳川家康のおじいちゃんであります。この頃の松平家はまだ小さく、織田と戦いをしておりました。そんな中、清康は「阿部定吉が織田と内通しているのではないか?」という疑問を持ちました。阿部定吉は全く身に覚えが無く、息子の弥七郎に「ワシは絶対に内通などしておらん。万が一ワシが殺された時は、この手紙を渡し、裏切っていないことを証明してくれ」と言いました。ある時 戦がおきました。そのとき、一頭の馬が暴走したのです。弥七郎はその暴走を見て「自分の父が殺されたのだ!」と勘違いしてしまい、すぐさま本陣へ行き、清康めがけて刀を抜き、斬り殺してしまったのであります。弥七郎はすぐさま取り押さえられ殺されましたが、清康は何がなんだかよくわからないまま殺されてしまうという非業の死を遂げたのでした。 |
|
|
■松尾芭蕉 50歳
「おくのほそ道」などを書き、旅に生きた松尾芭蕉。もともと腰や腹が痛むという持病を持っていた。旅の途中、下痢に襲われ、病床につく。下痢は一向に止まらず、しだいに衰弱していった。もう起きることもままならなくなった芭蕉は最後にこの句を詠んだ。「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」こうして芭蕉はゆっくりと息を引き取った。 |
|
| 江戸時代の俳人。『奥の細道』などの作品を残し、俳句を芸術にまで高めた。元禄7年秋、大阪に来ていた彼は1日に20回にも及ぶ下痢に悩まされた。赤痢であったといわれる。9月9日「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」という発句を弟子に書き取らせる。10日に「一生旅で過ごし、かねては草を敷き土を枕にして死ぬ自分と覚悟していたのに、こんな立派なしとねの上で、大勢の人々に付き添われて死ぬとは冥加に尽きる」と涙を浮かべて語る。11日には、下痢するものがなくなるくらいにかれる。障子に蝿がとまっているのを弟子が取ろうとしているのを見て「何事も上手下手はあるものだな」といい、それから眠りに入り、午後4時頃息を引き取った。50歳。 | |
|
■前野良沢 81歳
杉田玄白とともに「解体新書」を作った人。が、蘭語に未熟な杉田玄白が出版を急いだため、良沢な納得がいかないナと、翻訳者として名前を残すことを辞退し、解体新書に名前を残すことは無かった。玄白が富と名声をゲットしたが、良沢はゲットできず地道な人生を歩み始める。解体新書が出たときは52歳でしたが、その後もひっそりと学問に打ち込みました。ずっと良沢を支えてきた妻が死んでしまうと元気がなくなってきました。そしてひっそりと生涯を終えたのです。蘭学史上優れた功績を残したというのに、かなり淋しく静かな死に様でした。 |
|
|
■正岡子規 35歳
明治の歌人・正岡子規は21歳の時に初めて血を吐きました。肺結核と診断され、血を吐きながらでも泣き続けるといわれる子規(ほととぎすのこと)から名前をとり正岡子規と名乗りました。結核菌は次第に体をむしばみ、慢性的な痛みが続きました。死ぬ三ヶ月前の苦しみは相当ひどかったようで「誰かこの苦を助けてくれるものはあるまいか。誰かこの苦を助けてくれるものはあるまいか」という言葉を連載していた新聞に残しています。動くだけでも激痛が襲い、麻酔薬も効かなくなり、気が狂うほどの痛みに耐え続けました。そして「なろう事なら星にでもなってみたいと思うようになる」と言った。明治35年9月19日 泊まっていた高浜虚子や母や妹が気がつかない間にひっそりとこの世を去りました。 |
|
|
■南方熊楠 74歳
生物学者、民俗学者。昭和16年8月、南紀の暴風のなか、裸で菌類のかたずけをしてから発熱。12月28日、病状が重くなったので、家人が医者を呼ばうとすると「医者はいらん」と断わり、「天井に美しいおうちの花が咲いている。医者が来るとその花が消えてしまうから呼ばないでくれ。縁の下に白い小鳥が死んでるから、朝になったら葬ってやってくれ」と不可解なことをつぶやいた。夜になってから「私はこれからぐっすり眠るから、羽織を頭からかけてくれ。ではお前達も休んでくれ」といった。そして翌午前6時30分、死亡。 |
|
|
■源義経 31歳
兄・頼朝と不仲になり、奥州平泉へ逃げていた義経。源氏の権力に屈した藤原泰衡に裏切られ、攻撃される。もはやこれまでと悟った義経は、みずから妻子を殺し、屋敷に火をつけ自害した。義経の首は酒漬けにされ鎌倉へ送られるも、頼朝は首をも鎌倉に入れなかった。焼けただれ、腐敗した義経の首実験を行ったのは梶原景時である。 |
|
|
■源頼朝 52歳
源頼朝の死は謎に包まれております。なにしろ鎌倉幕府の記録である吾妻鑑に、頼朝の死についての部分がぽっかりと抜けているのです。そのため頼朝の死については色々な説があるのです。一番多い説が、落馬してしまい、そのまま息を引き取ったというもの。他にも、北条政子に殺されただの、持病の糖尿病が悪化しただの、毒殺されただの・・・いまだ頼朝の死因は謎であります |
|
|
■宮本武蔵 61歳
数々の伝説を残している剣豪。諸国を旅し、生涯剣術試合では負けたことがないといわれている。佐々木小次郎との試合後、熊本藩の細川家へ客分として招かれる。年老いた武蔵は霊厳堂という洞窟にこもり、有名な「五輪書」を書き上げた。その後、病生活に入ることに。絶命した時、武蔵は帯を締め脇差を持ち、片方のひざを立てながら死んだという。 |
|
|
■宮沢賢治 38歳
生前は、作家として名声を得ることができなかった哀しい人生の宮沢賢治。農民だったので、骨身を惜しまず働き続け、長年にわたって体が衰弱していきました。その後、教師をしながら「注文の多い料理店」を自費出版し、苦労をしながら働き続けました。結核となり、一ヶ月以上寝込んでしまう。それからはほとんど病床で過ごし、この頃「雨にも負けず 風にも負けず・・・・」を、家族宛の遺書として残しました。昭和八年九月 自宅にて血を吐きました。そして水を飲み、自分の体を拭き清めながら、息を引き取りました。 |
|
|
■三島由紀夫 46歳
昭和45年11月25日の昼。陸上自衛隊市谷駐屯地で三島由紀夫と東武方面総督との会見がありました。そして、突然総督を拘束し、バリケードを作り部屋に立てこもったのです。「要求に従わなければ総督を殺す!」と宣告し、バルコニーの上から「諸君の中に俺と一緒に立つものはいないのか!!」と激を飛ばしました。反応がないのを見ると、おもむろに上着を脱ぎ上半身裸に、用意していた短冊を取り出し、由紀夫に心酔している大学生を介錯人として背後に立たせました。そして左わき腹に小刀を深くつきたて、そのまま右へ力を込めました。最後の意志を持って首をあげ、介錯人が日本刀を持ち首を斬りつけました。が!!首がうまく切れず、半分つながったまま、慌てて二度三度斬るつけるが、刃こぼれしてしまいうまく斬ることができない。結局、他の男があわてて介錯したのです。もし腹を斬った時点で意識があったのなら、ものすごく痛かったことと思います・・・ |
|
|
■毛利元就 75歳
一代で中国10カ国の覇者となった元就。長男隆元が死に、孫である輝元に英才教育をほどこしていた。輝元は大の酒好き、とにかく酒だけは飲みすぎるな!といっつも注意していた。そんな元就は酒をあまり飲まずにいたが、中風になり寝込むことに。なんとか治るが、その後桜の見物に行った後、死亡した。 |
|
|
■護良親王 27歳
後醍醐天皇の第一皇子である。足利尊氏ら鎌倉幕府の武士によって鎌倉幕府は滅び、天皇を中心とした国を作ろうとした後醍醐天皇。その政治のやりかたは、武士にとっては最悪なものだった。足利尊氏を中心とした武士たちが天皇へ刃を向けるかもしれないと心配になった護良親王は足利尊氏を敵視した。だが武士の力を恐れた後醍醐天皇は、護良親王を幕府に引き渡したのだった。父親に裏切られた護良親王は、鎌倉へ送られ土牢生活に、護良親王の存在を危険視した足利尊氏の弟は、家臣に護良親王の殺害を命じる。護良親王はその家臣に向かい「お前はわしを殺しに来たな!!」と抵抗した。暗殺者の振り下ろした刀を口でくわえるほど抵抗したが、とうとう首を取られてしまった。暗殺者はあまりの恐ろしい形相をした首を、恐怖のあまり藪の中へ投げ捨てたという。 |
|
|
■森鴎外 60歳
医者嫌いで有名だった森鴎外。執筆に命を賭けており、医者にかかれば執筆をストップさせられる。執筆をせずに1年長生きするのがいいか、執筆をして1年早く死ぬのがいいか?書くのをやめたからと言って寿命が長くなるかどうかはわからない。という考えを持っていた。60歳になった頃、足がむくみはじめ家族が病院に行くように言うが拒否。インフルエンザになってしまい、とうとう診察を受けたが、すでに手遅れであった。鴎外を看た医者は「顕微鏡で調べたら結核菌がいっぱいで、まるで純培養を見るようであった」と語った。そして、親友に遺言を述べて死去。 |
|
|
■ヤマトタケル 30歳
日本武尊(ヤマトタケル)は悪党退治に向かうも、病気になってしまった。故郷に戻りたい気持ち一心だったが、立ち上がることが出来ずそのまま死去。死後、白鳥となり飛び去ったと言われている。 |
|
|
■山本勘助 62歳
武田信玄の軍師、山本勘助。上杉謙信との戦い、川中島の合戦において、信玄に「啄木鳥戦法」という作戦を進言する。この作戦は謙信に見破られ、武田軍は窮地に追い込まれた。作戦を見破られたことを恥じた勘助は、死を持って責任を取る覚悟を決める。「逝くことは流れのごとし」と告げ、激戦の修羅場へと飛び出していった。八十八の傷を負い、討ち取られたとも、自害したとも言われる。 |
|
|
■柳生宗矩 76歳
24歳の時徳川家康に仕え、三代将軍家光時代に「柳生新陰流」を将軍家の兵法として完成させた宗矩。宗矩の次男・友矩は美貌な上・剣も文も才能があり、柳生家は安泰かと思われたが、友矩が病死してしまった。気の毒に思った家光は、柳生家に対して目をかけるように。そして宗矩を病魔が襲う。家光は瀕死の宗矩を見舞い、願いはあるか?と尋ねた。宗矩は「柳生の地に寺を建立し、無き父の霊を弔い、四男にその寺を守らせたい」と言いました。家光はその言葉を快諾し、宗矩の死後従四位の官位を贈り、長年の忠勤に感謝したのでした。 |
|
|
■柳生十兵衛 43歳
柳生家は、徳川家の兵法指南役をつとめている家。初代指南役の長男だった十兵衛は、13歳の時に三代将軍・家光の小姓となるが、19歳の時に家光の怒りを買い、クビに。以後、行方不明になるが、12年後またも家光の側近となる。この間、諸説があり、実は隠密(スパイ)として動いていたなどがある。以後、家光の側近として働くが、43歳の時に出かけた鷹狩りで謎の死をとげる。矢で射られ、暗殺されたと噂された。 |
|
|
■柳沢吉安 57歳
五代将軍徳川綱吉に寵愛され、破格の待遇を与えられた側用人柳沢吉安。綱吉が死に六代将軍家宣になると、飛ぶ鳥を落とす勢いで権力を持ち続けた吉保にも陰りが出てきた。そして綱吉の葬儀が終わると、隠居し、別荘に引きこもりました。この別荘でかなり優雅な老後を過ごしたそうです。そして別荘に入って5年後、静かに眠るように息を引き取りました。 |
|
|
■山内千代 61歳
「山内一豊の妻」として大河ドラマの主役にもなった千代。良妻賢母の代表的な人で、夫を織田信長の家臣から土佐24万石の大名に仕立て上げた人物である。2人の間には子供がおらず、家督は一豊の弟・康豊の息子・忠義に譲ることに。一豊が61歳で死去した後、千代は土佐を去り京都へ移り住んだ。千代は京都で尼となり、ひっそり暮らす、そして夫・一豊と同じ61歳で死去した。 |
|
|
■山内容堂 46歳
幕末の土佐藩主だった容堂は、もともとかなりの遊び人だった。そんな容堂は藩主になると態度を変え、恩義のある徳川家のために働いた。幕府は滅亡し、新政府誕生となる。ここで容堂は新政府の要職となるが、薩摩出身者が優遇され土佐出身者は疎外され始める。自分を軽く見る新政府に腹を立て、病気を理由に辞任。その後、中風で倒れまだ46歳という若さで死去した。 |
|
|
■山岡鉄舟 52歳
幕末の剣客。江戸城無血開城に貢献。明治20年左脇腹にしこりができ、胃ガンと診断された。翌年7月18日、医者の診断では胃穿孔のため急性腹膜炎を起こしていることが判明。19日の払暁に「腹痛や苦しきなかに明けがらす」と辞世の句を詠む。そして手にうちわを握り、座禅を組んだまま大往生をとげた。 |
|
|
■ヤン・ヨーステン 60歳
東京駅にある「八重洲」という地名は、この人物からきている。関ヶ原の戦いがあった1600年、ロッテルダム(オランダ)から出た船が座礁し、日本に漂着した。この中に、ヤン・ヨーステンが乗っていたのである。徳川家康はヤン・ヨーステンを重宝し、八重洲に屋敷を与えた。ヨーステンは日本のために海外貿易を行うが、次第に借金がかさむようになり、幕府から信頼を失っていく。60歳になったヨーステンは、オランダへの帰国を望むようになり、日本を出てパタヴィア(今のジャカルタ)へ行き、本国への帰国を願い出るも、借金が多すぎたため却下された。泣く泣く帰国を断念し、日本に戻ることにしたヨーステンだったが、なんとその船が座礁し、沈没してしまう。ヨーステンは、オランダも日本の地も踏むことができなくなってしまったのであった。 |
|
|
■由井正雪 47歳
江戸時代の幕藩体制が完成したのは三代将軍家光の時。その家光が死に、幼い家綱が将軍になると江戸は不安に包まれた。幕府に不満をもつ人が多く集まり、謀反が企てられた。その中心人物が由井正雪。江戸城を火薬で爆発させ、それを合図に江戸を火の海にし、その混乱の中江戸城へ突入し将軍を拉致しようというもの。この計画は事前にばれてしまい、由井らは逃走、そして旅籠に入ったところで見つかってしまい、自害した。この事件を「由井正雪の乱」といい、1500人以上の人々が捕らえられ、由井の一族は全て処刑された。 |
|
|
■与謝蕪村 68歳
江戸時代の画家&詩人。芭蕉につぐ俳人と言われ、池大雅に継ぐ画家ともいわれた人。幼い頃に家が破産し、住み込みで俳句を学ぶも、その後放浪の旅に。普通の暮らしをし始めたのは45歳の時、一応奥さんができました。59歳の時に初めて女性に恋をしちゃいました。それからの蕪村は女性遊びをするようになり、老いらくの恋として祇園の遊女・小糸にベタボレ。遊女と遊ぶのにお金がかかるため、俳句を描きまくった。かなり小糸に本気だったんだけど、小糸はまだ若い、門人たちが蕪村と別れるよう仕向け、この恋は終わってしまいました。あまりのショックに蕪村は持病の胸痛に襲われ病床につくように、そしてそのまま死んでしまいました。 |
|
|
■吉田松陰 29歳
松下村塾をつくり、幕末の志士たちにさまざまな教えを行った松陰。井伊直弼の安政の大獄によって「危険人物」とされ、捕らえられる。伝馬町の牢獄に入れられ、処刑を待つことに。この時、「身はたとえ武蔵の野辺に朽ちぬとも とどめおかまし大和魂」から始まる「留魂録」の執筆を始めた。処刑の日、牢を出るとき、何人もの入牢者が「替わってあげたい」といって泣いた。松陰の処刑後、弟子である長州藩の高杉晋作らは、松陰の意思を継ぐべく幕末の嵐の中へと突入していく。 |
|
|
■与謝野晶子 66歳
明治の歌人。妻子ある歌人・与謝野鉄乾と略奪結婚し、12人の子供を産んだ。パワーに満ち溢れる女性だったが、50歳半ば頃突然狭心症の発作を起こす。以後、心臓病に悩まされるが「新新訳源氏物語」を完成させてからすぐに脳溢血で倒れた。左半身が付随となるが、それでも歌を詠みつづけた。昭和17年の正月に久しぶりに狭心症の発作を起こし、病状は悪化。なんとか4ヶ月ほど持ったが、尿毒症を併発し、意識不明、そのまま息を引き取った。 |
|
|
■良寛 73歳
江戸後期の曹洞宗の僧。諸国行脚の後、郷里越後に住んだ。文政13年7月、激しい下痢を患う。症状は夏から秋にかけ一進一退した。そのときの反古のなかに「ぬばたまの、夜はすがらにくそまり明かし、あからひく、昼はかわやに、走りあえなく」の歌がある。大晦日、介抱していた貞心尼は「生き死にの境離れて住む身にも、通らぬ別れのあるぞかなしき」と口ずさむと、良寛は「裏を見せ表を見せて散るもみじ」とつぶやいた。明けて1月6日夕、眠るが如く去った。 |
|
|
■渡辺崋山 49歳
幕末の人。蘭学を学んでおり、高野長英などと親交を深めていた。海外の事情をわかってくるにつれ「このままでは日本は危ない」と思うように。それが幕府にとって「一般庶民をいたずらに恐がらせている」と、いうことになり、捕らえられてしまう、これが有名な「蛮社の獄」。判決は主家(田原藩・三宅家)へ身柄引き渡しの上、永蟄居ということとなり貧乏生活突入。弟子が生活の足しになれば・・・と、崋山の絵を売りさばいたりしました。これが問題となり、お咎めが主家に及んでは迷惑をかけてしまう・・・と、考えた崋山、こうして崋山は物置で割腹自殺したのでした。 |
|
|
■バッハ(1685〜1750) 65歳
ドイツの作曲家。1750年の7月、その夏の熱さが彼を苦痛と衰弱におとしいれた。彼は死の床から起き上がり「クリストフ、紙を持っておいで、いま頭のなかに音楽が鳴っている。それを書き取っておくれ。それがこの世で私が作る最後の音楽だ」といって、また眠り込んだ。夜明けにバッハは妻を呼び「私に音楽を聞かせておくれ。もはやその時だから、お別れほ死の歌を歌っておくれ」と頼んだ。家族たちは讃美歌を歌うと、彼の顔は大変柔和になった。7月28日夜10時15分死亡。 ■ヴォルテール(1694〜1778) 84歳 フランスの哲学者。小説家。1777年、17年ぶりにパリに帰った彼は、15日目に血を吐き、重体におち入った。翌年5月30日、病床で司祭が「あなたはまもなくご臨終です。死の前にイエス・キリストの神性を認める気はありませんか?」という問にたいし「イエス・キリスト?」とつぶやいたあと、「静かに往生させてもらいたい」といったのが最後の言葉であった。 ■アダム・スミス(1723〜1790) 67歳 イギリスの経済学者。『国富論』の著者。61歳のときに母をなくした彼は、それ以来健康が衰えた。晩年の1790年7月中旬、見舞いに来た友人に、自分のノート16冊を焼いてもらい、安心したようになった。そして「私は皆さんと一緒にいたいのですが、お別れしてあの世に行かなければなりません」といって寝室に去り、17日に死んだ。 ■J・ワシントン(1732〜1799) 67歳 アメリカの初代大統領。晩年の12月12日、習慣にしていた乗馬の散策中にみぞれにあい、風邪をひいた。14日午後10時頃秘書に「葬式はていねいに頼む。しかし私が死んでも、3日間は墓に入れないでくれ。いいかね?」と言残し、静かに絶命した。 ■カント(1724〜1804) 80歳 ドイツの哲学者。カントは一生独身で過ごし、毎日同じ町の同じ場所を、同時刻に散歩するという生活を続けた。1803年12月、彼は自分の名前も書けないほどぼけてきていた。翌年2月11日の夜、彼は友人からスプーンで、葡萄酒と水を甘く割った飲み物を差し出され、かろうじて飲むことができた。このとき「よろしい」といい、これが最期の言葉となった。翌朝彼は息を引き取った。 ■ナポレオン(1769〜1821) 52歳 フランスの皇帝。1815年6月、ワーテルローの戦いに破れたナポレオンは、セント・へレナに流刑の身となった。ここで彼は数年の内に、食欲不振と足のむくみを訴えるようになった。1821年3月から、ろくな手当を受けることなく、病床についたままとなった。4月に「私はイギリスの暗殺者に殺されるのだ。私の骨はセーヌ河のほとりに埋めてくれ」と遺言した。5月5日午後5時「神よ、フランス国民、私の息子、軍隊の先頭」と、とぎれとぎれにつぶやきながら死んだ。そのとき左目から涙がこぼれていたという。イギリスの薬学者がナポレオンの遺髪を検査した結果、死亡前約4か月にわたって砒素系の毒物を摂取していたことが判明した。 ■べー卜ーヴェン(1770〜1827) 57歳 ドイツの音楽家。彼は1815年、45歳の時に、完全に聴覚を失った。1826年秋頃から腹水がたまり始め、12月20日に最初の腹水穿刺が行なわれた。翌3月23日、医者は彼に死が近付いていることを告げた。彼の顔は変り、やがて周囲の友人に言った。「友よ拍手を。喜劇は終った。」そのあと彼はつぶやいた。「残念だ、全く。遅すぎたよ。」 3月26日の午後、ウィーンの街に雷雨が襲った。彼は雷にむかって右手を上げたが、やがて倒れた。死因はアルコール嗜好による肝硬変であるという。 ■ゲーテ(1749〜1832) 83歳 ドイツの小説家、劇作家。1832年3月16日、ゲーテは風邪をひき、床についた。22日午後11時30分、椅子の隅に身を寄せかけたままで亡くなった。「窓を開けてくれ。明りがもっと入るように」と言ったのが最後の言葉である。「もっと明りを」という印象的な言葉はこれに基づいている。 ■ドストエフスキー(1821〜1881) 60歳 ロシアの小説家。『罪と罰』で有名。1881年1月25日夜、執筆中にペンを落とし、それを拾うために本棚を動かしたとたん喀血した。2月9日朝、彼は妻に言った。「アーニア、僕はもう3時間もずっと考えていたんだが、今日、僕は死ぬよ」11時頃目覚め彼は言った。「君を残していくのがとても心配だ。これから生きていくのが、どんなに苦しかろう」。夜8時30分、死亡。葬儀には約3万の人々が、修道院の教会堂まで棺のあとに付き従ったという。 ■ワーグナー(1813〜1883) 70歳 ドイツの作曲家。1883年彼は前年からベニスのホテルに滞在していた。2月13日午後、彼は机の前で苦しているのを召使が見付けた。「医者と妻を」と彼は言った。妻のコジマが駈けつけ、薬を飲ませたが利き目はなかった。召使が衣服を脱がせかかると、ワーグナーは「私の時計を」といって、それを最後に妻の腕のなかでこと切れた。 ■ユゴー(1802〜1885) 83歳 フランスの小説家。『レミゼラブル』が有名。晩年の5月18日、彼は倒れ、ベッドの中で言った。「君、死ぬのはつらいね」「死んだりなさるものですか」「いや死ぬね」しばらくして「ここで夜と昼が戦っている」とつぶやいた。22日の朝から臨終の苦しみが始まり、午後1時37分に息を引きとった。最後の言葉は「黒い光が見える」だった。このときすざましい嵐がパリを襲い、雷が鳴った。 ■ゴッホ(1853〜1890) 37歳 オランダ人の画家。1890年5月、パリ北方の小さな町オーヴエルに行き、絵を描き始めた。7月27日の夕刻、麦畑のなかで自分の胸をピストルで撃った。弾は心臓を外れたが、彼は重症のまま歩いて宿屋に帰った。明くる日、急報を受けて駈けつけた弟のテオに、ゴッホは「泣かないでくれ。僕はみんなが幸せになるようにと思って、こんなことをしたんだ」と言った。28日の夜「僕はこんなふうに死んでいきたいと思ってたんだ」といった。29日午前1時半、息を引きとった。生前に売れた絵は、1枚だけであった。 ■イプセン(1828〜1906) 78歳 ノルウエ−の戯曲家。『人形の家』で有名。1900年72歳のとき卒中に襲われ右半身が不随となった。1906年5月頃から、衰弱が激しくなり、月半ばからこん睡状態が続くようになった。22日の昼頃、看護婦が家人に少し良くなられましたというと、彼は「とんでもない」と言った。翌日の午前2時半、死亡。 ■マーク・トウェーン(1835〜1910) 75歳 アメリカの小説家。『トム・ソーヤの冒険』で有名。死ぬ1年前に彼は「私は1835年ハレー彗星とともにこの夜に生れた。来年はまた彗星が近づく。私は彗星とともに、この世を去りたい」と言った。翌年、ハレー彗星が現われた翌日の4月21日、彼は突如狭心症の発作を起こし、絶命した。最後の言葉は「じゃあまた。いずれあの世で会えるんだから」と言ったという。 ■ルノワール(1841〜1919) 78歳 フランスの印象派の画家。ルノワールは後半生リューマチに苦しみつつ、最後の20年は手に鉛筆を縛りつけてまでして、描き続けた。1919年12月2日、普段と同じように静物画を描き終え、午後7時頃眠りにおちた。8時頃、いきなり彼は「パレットをよこしなさい。この2羽の山しぎは」といった。彼は幻の鳥を見ているのである。「山しぎの位置を変えてくれ。早く、絵具を、パレットをよこしてくれ」彼は、午前2時静かに息を引き取った。 ■コナン・ドイル(1859〜1920) 71歳 名探偵「シャーロック・ホームズ」の作者。彼は第一次大戦に出征した息子を失ったこともあって、晩年神霊学に凝り始めた。1929年秋、彼は倒れ、療養の結果、翌年春に一時回復したが、夏から再び悪化した。30年7月7日朝7時半、妻に「この地上で最も優秀な看護婦へ、と刻んだ勲章をお前のために作るべきだと思う」と言った。8時半、死後世界を信じていた彼は安らかに死んでいった。 ■キュリー夫人(1867〜1934) 67歳 フランスの物理学者。死ぬ年のはじめからラジウムの放射能のため、白血病の症状が現われていた。7月3日午後「これはラジウムで作ったのですか。」などのうわごとを言い、注射に来た医師に「いやです、構わないでください」とさけんだあと、こん睡におちいった。それから16時間後、死亡。 ■バーナード・ショウ(1856〜1950) 94歳 イギリスの戯曲家。病床に付いたのは94歳で、看護婦に「お前さんは私の命をまるで、古い骨董品のようにもたせようとしているが、私はもうだめだ。おしまいだよ。私は死ぬんだ」といい残して死んだ。 ■チャーチル(1874〜1965) 91歳 イギリスの政治家。最後の日に近い誕生日に「私は随分沢山のことをやって来たが、結局何も達成できなかった」と娘に語った。最後の言葉は「何もかもウンザリしちゃったよ」である。 |
|
|
|
|
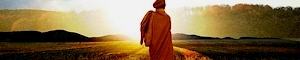 ■往生 |
|
|
■人相見の忠告
今は昔、雲林院に菩提講を始めた聖人がいた。もと九州の人で、名うての盗人だったが、捕えられて7度も牢にいれられた。7度目に捕えられたときには、とうとう「この度はこいつの足を切ってしまおう」という判決が出た。そこで男を賀茂川原に連行して、まさに足を切ろうとした。そこに一人の人相見が通りかかり、この盗人を見て処刑人に、「どうかわしに免じて、この人の足を切らないでくれ」と頼んだ。処刑人は、「こいつは名うての悪党で、今度は検非違使が集まり、足切りに決定されたのだ」と答えた。人相見は、「この男は必ず往生する相を備えている。だから、絶対に切ってはいけない」と言う。処刑人は、「これほどの悪人がなんで往生などするものか。訳のわからぬ相を見ることだ」と言って、かまわず切ろうとした。人相見はその切ろうとする足の上に座り、「この足の代わりにわしの足を切れ。必ず往生する人相のある者の足を切らせ、黙って見過ごしたら、後世の罪は免れないだろう」と言って大声で叫ぶので、処刑人たちは、検非違使の所に行き報告した。協議の結果、「あれほどの立派な人相見が言うことだから」と、足を切らずに男を追放することにした。 その後、この盗人は強く道心を起こし、すぐさまもとどりを切って法師となった。そして、日夜阿弥陀の念仏を唱え、心から極楽に往生したいと願っていたが、雲林院にすむようになって、この菩提講を営むようになった。遂に命が終わるときになって、誠に人相見の言ったとおりに非常に尊い姿で息絶えた。「長年悪を好んで行なっていても、心を入れ替えて善に向ったなら、このように往生するものだ」と言って、人々は皆尊びあったという。 |
|
|
■木の上での往生
今は昔、摂津国豊島郡の滝の下に大きな松の木があった。その木の下で一人の修業僧が野宿していると、ちょうど8月十五夜のこと、月が非常に明るくあたりは静まりかえっていたが、突然空から妙なる調べと櫓の音が聞こえてきた。その時、この木の上で声がした。「私を迎えにおいでになったのでしょうか」。すると空のなかで「今夜は他の者を迎えるために別のところに行く。お前は来年の今夜迎えるはずだ」と答え、それ以外物音一つ聞こえなかった。やがて音楽は次第に遠ざかって行ってしまった。この木の下の修業僧は、初めて木の上に誰かいるのに気がつき、木の上の人にどなたかを尋ねた。すると木の上で、「今の櫓の音は阿弥陀様が衆生を極楽に運ぶ筏の音なのだ」と答えた。 木の下の僧はこの言葉を聞いたが、他人に語らないまま、翌年の8月15日になった。その夜、そっと前の木の下に行き、昨年聞いた言葉を信じて待っていると、夜中になって、去年のように空に妙なる音楽が聞こえ、木の上の人を迎えて行ってしまった。僧はこれを見て、人々に語り伝えたという。 |
|
|
■地獄の火の車
今は昔、殺生など罪深い行ないに明け暮れている男がいた。こんなある日ある人がこの男に、「罪をつくった者は必ず地獄に墮ちるぞ」と教えてやった。これを聞いた男はまるっきり信じようともせず、「とんでもないでたらめだ、何を根拠にそんなことを言うのか」と言って、ますます殺生を繰り返した。 そのうち、この男は重い病に罹り、数日のうちに死に頻した。その時、この男に火の車が見えた。それを見て以来、病人はひどく恐怖の念にかられ、一人の偉い僧を招き、「私は長年にわたって罪を作ってまいりました。ある人が、『罪を作ったものは地獄に墮ちる』と言って注意をしてくれましたが、それはでたらめと思い、罪を重ねてまいりました。今死ぬときになって、目の前に火の車が私を迎えに来ています。とすれば、罪を作るものは地獄に墮ちるということは本当でした」と言って、長年の間、信じなかったことを後悔し、ひどく悲しんで泣いた。僧は枕元でこれを聞き、「お前は、罪を作ると地獄に墮ちるということを信じなかったが、今火の車を見て信じる気になったのか」と言う。病人はそうだと答えると、僧は、「それなら、阿弥陀の念仏を唱えれば必ず極楽に往生する、ということを信じなさい。これも仏様が、お教えになったものだ」と言う。病人はこれを聞いて、手を合わせて額にあて、「南無阿弥陀仏」と千度唱えた。すると僧は病人に、「火の車はまだ見えるか、どうだ」と言う。病人は「火の車は急に消えてしまいました。金色の大きな蓮華一葉が目の前に見えます」と言うや、そのまま息絶えた。そこで、僧は涙を流し、感激し尊んで帰って行ったという。 |
|
|
■辞世の歌二句
信士梅心は、徳島の人である。普段より連歌俳諧などの風流をたしなみ、生涯を健康に病気もせずに暮らしてきた。ある時、そばにあった懐紙に、「世は夢と見し間も夏の一夜かな。唱うれば心涼しや南無阿弥陀仏」と言う二句を書き、筆を置いて念仏し突然に亡くなった。時に亨保4年6月9日、82歳。 |
|
|
■江戸土産の阿弥陀様
信士玄光は丸屋庄兵衛の息子で、若いときから商売のために毎年江戸に出向いていた。あるとき増上寺に寄ったおり、そこで念仏を習い、それ以来念仏が日課となった。毎年京に上るときには、まず主人と父母とに対面し喜んだ。4月下旬主人に暇を願い、阿弥陀の像を買い江戸土産と称して父母に贈り、その時に念仏の尊いことを話した。5月に入って、両親に向かって、「私は今月15日には、必ず寿命が終わります。このことは、春よりわかっていたのですが、もう時期が近づいていますので話しました」と言う。両親はこれを聞いて信じることができず、単なる冗談と考えていた。信士は5月の初めに自分の法名を書き残し、命日も5月15日と書いた。病ということもなく、5月15日12時、頭北面西になって、称名を唱えながら眠るように死んでいった。39歳。 |
|
|
■浮世を離れての往生
関超上人は、伊勢の国蓮華寺の主人である。俗性は浅野内匠頭の家臣吉田忠左衛門の甥である。四十七士が追福のため出家したこともあり(1702)自分も浮世の欲を離れ諸国を遍歴し、人里離れた山で念仏を納めていた。しかし様々な奇怪なこともあって、かって伊勢の越坂で念仏三昧を行なっていたときの師が、上人とともに同居することとなった。二人は横になることなく、あるいは一週間続けて念仏を唱えることも度重なった。安永5年(1777)8月10日、上人は沐浴して、白の服をまとい、西方に向かって正座して念仏を唱えながら亡くなられた。79歳。 |
|
|
■葬具の準備
信士了雲は、近江の国の人で、俗名は治兵衛生。左官業を営み、日頃から正直者で言葉も少なく、殺生を嫌って蚤や蚊も殺すことも退けた。寛政2年3月、健康そうに見えるにもかかわらず、新町の葬具屋に出かけて、自分のために葬具一式こしらえてほしいと頼んだ。これを聞いた主人は、自分の葬儀道具を自分から求めるものは例がないと言って断った。治兵衛が無理に頼むと、店では代金を頂いておかないことには道具を作らないというので、金3分と1貫文を置き、「来月10日過ぎには取りに来るからそれまでは他言くださるな」と言って帰った。 その後程なくして治兵衛は病床についた。4月13日は祭りで、11日には神輿もできるので、彼は起きてこれを見に出かけた。かくて13日の朝、息子の善次を呼び、自分はもう命がないから、死んだ後のことはこの手紙に書いてあるから、一家、親戚が揃ったおりに開くようにと遺言した。女房驚いて近くに寄ると、しばらく念仏を唱えていたが、そのまま眠るようにして絶命した。親類どもが寄り合ったところで書き付けを開いてみると、亡き後のことが詳しく記され、葬具まであつらえてあったのにには皆不思議なことだと感じた。61歳。 |
|
|
■養子の死
浄誉信士は松坂の生まれで、加藤源兵衛の養子である。父母には孝行し、家業の暇には俳諧・茶道などをたしなんでいた。文化3年2月1日急に腹痛を起こしたが、医薬では治療ができなかった。同月末には、手足が冷え、気力を失って心ここにあらずというふうになった。そこで頭北面西し、右脇を下にして伏した。この間、念仏を唱え続けていた。同日夜2時、両親に向かい、「人の死期は定まりないといわれていますが、父母に先立って命を終わるのは不孝のいたりです。しかしこの定めは逃れませんので、永の別れとなります。」と言って、短冊を求め、筆にて あそびよきところ見ざしぬ法の桃 と書いて、それから夜の偈を唱え称名を唱え、笑顔のまま静かに死んでいった。 |
|
|
■殺生を嫌った男
居士摂心幽如、俗名奥田吉郎兵衛は一志雲郡の人である。その性質はまっすぐで慈悲心に溢れていた。42歳の夏の頃に病に伏し、医薬の効き目もなく困っていたとき、ある人が生きた鯉を食べれば、必ず病が治るといった。しかし吉郎兵衛は、「自分の命のために魚の命を取るのは不仁の甚だしいものである」と言ってこの鯉を川に放した。6月6日、予め死期の時を悟り、親類を招いて、死後のことまで詳しく遺言し、又浄土での再会を懇ろに約束した。8日の夜になって、臨終の行儀を整え、西に向かって座り、声だかに念仏を休むことなく唱えた。その夜も朝に近くなって、時が来たと言って、弟を呼び阿弥陀経を読経させ、自分もあとについて勤め終り、念仏数100回のあと「合掌にひるがおの露こぼすまじ」と口づさんで、合掌の手も乱さないまま、めでたく往生をとげた。 |
|
|
■夢での知らせ
釈光顕妙峰尼は、一志郡の円照寺俊諦の実母である。年頃になって浄土を願う志が強く、日頃から称名を唱えていた。年老いて病床に伏すようになってからは、以前にも増して称名を唱えるようになった。ある日俊諦が寺にいないときに、妙峰尼は隣家の老女を招き沐浴潔身して、衣服をあらため、臨終の用意などをしていた。しばらくして俊諦帰ってきてこれを知り、母に向かって「このようなことをしていては、ますます病気が重くなり、苦しみも増すばかり」と戒めた。母はこれに答えて、「別に煩わしいこともなし、ただ今にも往生するときの用心にと、このように準備をしていたまで」と言った。さてどんな因縁であるのか、死の2・3日前より絶えず見悶えを繰り返し、見ていても大変に辛いので、看病の人々も眉を顰めては、「果たして往生の時にはどのようになることであろう」と心を痛めていた。同日夕方にはその苦しそうな様子も和らぎ、枕を北に向け、面を西に向けて称名を唱え始めた。その夜隣家の信者を招いて、臨終及び死後のことまでを語ると、その人は死が近いと思ったのか、家にも帰らず、退いて次の間で仮眠しはじめた。そのうち前にも増して苦しそうな様子に、皆驚いていたが、やがて夜明け近くには苦しそうな様子もやんだ。そして称名を始めると、いつの間にかとなりに寝ていた信者が起きて、一緒に称名を唱え始めた。俊諦いぶかりながら、いつの間に来たのかと問うと「私の命が終わるとき、必ず起こすからと約束したが、夢の中に現われ、今こそ命終りなりと告げたので、目を覚ましたのである」と答えた。皆奇異の思いを抱いた。暫くして称名の声と共に、合掌のまま面に笑みを含み、静かに往生した。時に77歳。 |
|
|
■臨終時の発心
伊勢の国の幸助、若いときから相撲好きで、三瀬川と名乗っていたが、生まれつき邪険で、常に喧嘩口論が絶えなかった。あるとき蕎麦を食べている最中、突然に熱が出て、その苦しそうな様子はまるで、五逆の罪人の臨終に際して、地獄からの迎えの火車の出会ったようである。そこでその日の夕方、菩提寺の住職を招き、自分の罪を懺悔し、自分のごとき罪人でも助かる道はあるのかと尋ねた。僧侶は詳しく浄土経の中の教えを説き聞かせると、たちまち信心を起こし、浄衣を着て仏前に座り、合掌して声高に念仏を始めた。その力強いこと鉄でも貫くようである。翌朝8時になって、親しく仏国からの来迎を見ようと、しばしば空を見上げては、歓喜の色を表し、称名とともに、合掌の手も乱さないまま往生をとげた。時に41歳。 |
|
|
■1日10回の念仏で往生
童女香林、俗名幾代は名古屋の奈良屋の娘で、幼年より父母が教えた念仏を日課で10回唱えていた。亨保21年に重い疱瘡を患い、治らないとみるや両親は「念仏すれば極楽へ行ける」と言って念仏をさせた。ある日両親に向かって「只今地蔵が来て私の手を取り極楽へ導いてくれる」と言って喜んでいる。両親はなお念仏に励めと言えば、高い声で称名をしていたが、暫くして阿弥陀様が現われ極楽に引き合わせると語り、頻りに念仏を唱えながら息絶えた。死相うるわしく遺体は柔らかで、臭いもなかった。 |
|
|
■酒のための往生
意得功忍信士、俗名は喜兵衛、名古屋巾下の者なり。性質が正直な為、人の誘いを信じてよく念仏を唱えていた。常に酒を好み、一時病に伏して薬も思うように利かない頃、酒が飲みたいと言えば、その妻「もし酒が飲みたければ、ひたすら念仏を唱え、極楽に行ってそこの酒を飲んだらよい」と答えた。病人が笑って、浄土にどうして酒があるものか」といえば、妻は「如来の力でどうして酒がないことがあろう。それよりもまず往生が大事」と言う。そこで病人早く行きたい一心で念仏を唱え、23日過ぎて、夢の中で極楽へ行ってきたことを語り始めた。「いつの間にか八功徳池ともいうべき水際にいると、そこに菩薩がおり、ここは極楽かと聞くと、そうだという。ここには酒があるのかと問えば、「この池の水、皆酒なり、自分で汲んで飲んでみなさい」と言う。そこで一升ほど飲んでいい気持ちになったところで目が覚めた。妻これを聞いて「浄土にどうして酒があるの。先にあると言ったのは念仏を勧める方便」だと言えば、病人言う、疑うのならこの気をかげと、暫く息をつめて吹き出してみると、酒気室内に溢れた。妻も不思議に思い、如来の力に感激した。さて一両日、喜兵衛ますます休まずに念仏を唱え、何の苦もなくやすらかに往生をとげたという。 |
|
|
■死の前の極楽見物
喜曾松は、三河の勘助の息子で、6歳の頃から父と共に朝夕には本尊前に座って念仏を日課としていた。10歳の頃より病気になり、医療を尽くしたが、その効果なく段々と病が重くなった。父が枕元に行けば、「悲しい悲しい」と言う。父はそんなに悲しければ、死ぬかも知れないから念仏を唱えなさいと言うと、童子は「死ぬのは嫌い、死ぬのは嫌」と言う。父また「そんなに死ぬのが嫌なら、いよいよ念仏をしなさい。念仏をすると死ぬことのない極楽に行ける。また念仏を唱えれば極楽に行って、悲しいことはなく、楽しいことばかりだ」と勧める。そこで童子は「そんなによいところなら行きたい」という気持ちになった。1週間ほどして童子は、手習いの師匠を呼んで下さい、と言うので看病の者はすぐに、師匠を連れてきた。童子は目を開いて「御師匠様、私は死ぬことのない極楽に参ります。今日はいとまごいを述べます。」言い終わると、目を閉じ念仏を唱え始めた。翌日童子は、苦痛の様子もなく眠るようにして息絶えた。この知らせを聞いた親類、隣家の人々は集まり童子の傍で念仏をしていると、死んだはずの童子目を開いて、尊い所を拝んできたと言う。父が訳を聞くと、阿弥陀様の所に行って来たという。そこにはきれいな蓮の花が咲いており、その花の上には子供たちが大勢遊んでいた。阿弥陀様が早く来いというので、すぐに行くと答えた。父が阿弥陀様のところにいつ行くのかと問うと、明日の4時と答えた。翌日4時、童子は念仏を唱えながら眠るようにして息絶えた。 |
|
|
■百万遍
江戸北本所御組屋敷の武士須藤所右衛門は、生まれてこの方仏教書を見たこともなく、浄土往生の気持ちもなかった。ある日、日頃の冷酒の毒気が体に回ったのか、医薬の術では治すことが難しい病になった。死の兆しが現われ、ただ死を待つのみとなった。彼の兄弟は集まって念仏を百万遍唱えることを勧めるが、所右衛門、自分は百万遍をして死ぬことは無用であるとしてこれを退けた。同じ所に宗円という武士が、一緒に念仏を唱えてやろうということになり、これには所右衛門、大いに喜んで聞き入れた。さて、約束どおり宗円は4、5人誘って病床にやってきた。「人は病気になったら、死を待つ他はない。死んで身にそう宝は念仏の他はない。我等も念仏往生を願い朝夕に祈るが、寿命があれば70でも生きる。もっぱら念仏を唱えよ」と勧め、往生極楽の念仏を唱えて帰っていった。翌日明け方、右衛門は阿弥陀如来の来仰をおがもうと、病床から起き上がり、数回礼拝していると、傍にいた女房が、体に悪いという。それを聞き入れずに礼拝が終わって、南無阿弥陀仏と大声で三遍唱えてから、そのまま安眠するようにして息絶えた。 |
|
|
■悪人往生
信州更級郡の清兵衛は、若年の時江戸に出て生活していたが、性質が悪く人も3、4人殺害している。あるとあらゆる悪事を働いたが、発覚せず国元に帰った。しかし積み重なる悪事の報いと、酒の患いで苦しむ身となった。しかるに村人の中に念仏の信者に勧められ、日課に10遍程唱えるようになった。あるとき人に向かって、「吾は22日に死ぬなり」と公言した。諸人は何月かと尋ねると、月は知らないが22日なりと言う。10月頃より痛みに苦しみ、傍目にも苦しそうである。訪れる人には、自分は若いころから悪をなしてきたゆえ、これくらいの苦痛は数にも入らない。ありがたいことに極悪の行ないも懺悔しながら念仏を唱えれば、苦痛も和らぐといって喜んでいるのである。夜中でも念仏を唱え、その声は2、3丁も聞こえるほどである。20日より病苦が増し、22日に伯父が来て病を問うた。今日は22日だが、今月でなければよいがと言えば、いかにも今日である、今苦痛に耐えかねてものを言わずうつ向きに伏していたが、半時ほどして大きく嘆息して、「ようやく楽になった。かねてのとおり、今日只今往生なり」と言って、本尊の前に線香を立てさせ、西に向かって念仏すること20回、面に笑みを浮かべてそのまま息が絶えた。49歳。 |
|
|
■肉食から精進へ
伊勢の国の長兵衛は菩提を求める心はなかったが、病にかかってから52歳で出家した。しかし仏道に励む様子もなく、常に肉を食らうという悪僧であった。58歳の9月より、重病になり姉の円寿尼が懇ろに勧めてから、日課に念仏を始めるようになった。ある日姉が、そなたは肉が好きであったが、この念仏には、肉食しても差し障りがないないので、欲しければ料理してくると言えば、念仏の間は食わないほうがいい、隣家の焼きものの臭いも、うっとおしいという。大した変わりようである。さて正月になって、念仏のおかげで来る2月15日には往生遂るという。姉はそなたのような生ぐさ坊主が何を言うといえば、「私のような極悪人でも助かる念仏なれば間違いない」と答えた。さて2月14日の朝、今日は必ず往生するので、仏壇を掃除し花を供え、親の位牌を出してと願い通りにさせ、大いに喜んだあと念仏を続けた。日没の頃になって鉦を打ち鳴らし回向をした後、そのまま息絶えた。死相は笑みを含み、歓喜の様子であった。亨年59歳。 |
|
|
■自分の葬具作り
越前中川村の次郎右衛門は、農家で忙しい身であったが、若いときより仏教を信じ、念仏を怠らなかった。68歳の頃から日課三万遍を続け、命が終わる3年前より葬式の道具をこしらえ、蔵に隠しておいた。天保12年10月27日の夜、9時にこの蔵に入って、歌6首を書き残し、縄を首にかけて、西方に向かい、端座合掌して大往生を遂げた。縄を首にかけたのは身が傾かないためで、病はなかった。歌に、「この裟婆の五濁悪世にいるよりも、急ぎまいらん阿弥陀の浄土へ」があった。歌の道は知らない人であったが、このような歌を残したのを見聞きして、人々は驚きと共に賛えない人はなかったという。 |
|
|
■予告された死
相州足柄上郡に武右衛門という人がいた。その性質はまっすぐで、壮年の頃より念仏を始めた。明治15年4月隣村へ用事があって行く途中、変な僧侶に出会い、「汝近いうちに極楽に行くので、早く帰って心支度をせよ」と言った。これを聞いた武右衛門は直ちに家に帰り、自分の持ち物を整理し、翌日には葬具、経かたびら、脚当、ずた袋などを用意し、また数珠、御守りなど残らずずた袋に入れておいた。次の日は終日無言で過ごし、次の日は終日念仏をして死の来るのを待った。あくる日、座敷に入って布団を敷かせ、頭北面西に伏して、小声で念仏を唱えながら息絶えた。その姿が釈迦の涅槃像に異ならないと、人々は驚いたようすである。時は明治15年4月、亨年75歳。 |
|
|
■用意のよい死
島田駅四丁目の浅田賢治郎の母ふさは、常に仏教を信じ、行ない正しい老婆であるが、風邪と病で寝込んだ。息子の賢治郎は種々医療を尽くしたが、老体に効果もみえず、明治15年8月半ばに、病人は来る28日に往生すると言った。そのように危篤には見えなかったが、27日の夜賢治郎を呼んで言った。「かねがね言っているように明日は往生の日、ついては仏壇の下に仕舞ってある箱をとってこいと言う。いわれるままに持って来ると、その中に葬儀に着るせがれの無紋の上下、娘3人が用いる白無垢、他に金150円を取りだし、これにて葬儀の万事を整えよと、賢治郎の前に差し出した。せがれを始め、母の用意のいいのに驚いた。翌日、端座合掌し、「はてぬれば間もなく我は西へ行く阿弥陀の浄土に住ぞ嬉しき」と辞世の句を残してめでたく往生を遂げた。76歳 |
|
|
■彼岸の死
幡豆郡松木嶋村の勇助は、若いころより川船乗りを職としていた。平生は念仏をするようにもみえなかった。万延元年7月24日発病し、治療を勧めるのに、薬を飲むことを嫌い、我は彼岸中に往生を遂ることは兼ねてからの願いだったので、医薬は必要ない、しかし我のごとき悪人が彼岸中に往生することは覚束ないことであるが、出来れば中日に往生の用意をしたいと告げた。葬式用の草鞋は前もって用意して2階にあるものを使い、また見舞に訪れる人には、世間話をせずただ、往生のための念仏を唱えて欲しいと語った。不思議なことに8月9日の彼岸中日朝。称名終え苦痛なく往生した。 |
|
 |
|