
�@
�V���H(��������)����(�ނ�)���イ���邱�ƂȂ��ꎞ�����(�͂�ꂢ)�Ȃ��ɂ������炸 �V�͌��H���������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��A�K������̂悤�Ȓ��b������ď����Ă����B�����������Ђ����ɍ��̊��ɏ����L���āA����V�c�ɕ�������̋�Ƃ����B�@
�V��܂��Đl�ɏ��� ���͈ꎞ�h���邱�Ƃ������Ă����ǂ͖łт�B�@
�V�m��n�m���m��l�m�� �B�����Ƃ������̂͂����K���I��������̂��B

�V�ɋ��n�ɕ��� �ߒQ�ɂ��ꂽ�荧�肵���肵�Đg�����������邳�܁B�@
�V�ɂ���Δ䗃(�Ђ悭)�̒��n�ɂ���ΘA���̎} �v�w���[���������݂��ɗ��ꂪ�����ԕ��ɂ���B�@
�V�ɋU(����)��Ȃ� �V���͌����ł���B�@
�V�Ɍ�����n�Ɏ����� �閧�∫���̘R��₷���B

�V�ɏ]�����̂͑����V�ɋt�����͖̂S�� �V���ɏ]�����̂͑���������ɔ�����҂͖ŖS����B�@
�V����(������)�܂�n���C(�ʂ�����)�� �����V�̉��ɂ��w�������ߌ����n�̏�������Ƃʂ����ŕ����B���̒�������ď������Ȃ��Đ����Ă������܁B�@
�V�ɑ������V�����ő�����@
�V�ɓ��(�ɂ���)�Ȃ� ���z����ł���悤�Ɉꍑ�ɓ�l�̌N�傪�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
�V��(�ɂԂ�)��^���� �V�͈�l�̐l�Ԃɂ����������̒�������_��^���Ȃ��B

�V�ɂ�����S�n ���ɂ��ꂵ���āA������������C���B �@
�V�̗^�������炴��������Ă��̙�(�Ƃ�)�߂��@�V�̗^���Ă������͎̂��悤�ɒ�߂�ꂽ���̂ł���A���Ȃ��Ƃ������čЂ����������ƂɂȂ�B�@
�V�̎�(���܂���)�@�V�̗^������́B�V���B�V�^�B�V�b�B�@
�V�̖ԁ@�����������͂Ƃ��Ă�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�V�̎��B�V�ԁB�@
�V�̔Z��(���E����)�@�V����^����ꂽ�����Ȉ��݂��́B�ØI�B�㓙�̎��B

�V�̂Ȃ���͂Ȃ������ׂ�����Ȃ���͂̂���ׂ��炸�@�V�ЁE�n�ς͔�������@�����邯��ǂ������̏������Ђ��͂̂���邷�ׂ��Ȃ��B�@
�V�̔z�܁@�V�͑P�ɂ͑P�ʁA���ɂ͓V�������ꂼ��ɂ��Ȃ������̂�z����B�@
�V�̔��\�@(�V����̂悢��������̂̈�)���B�@
�V�̊�(�܂Ȃ�)�@�V���s���l�̑P���E���ׂ̊Ď��B�V�̖ځB�@
�V�̖ځ@���z�B���B

�V�͍����ɋ�(��)���Ĕڂ����ɕ����@�V��͍��������ĉ��E�̐l�X�̐����A���̑P�����Ď��������Ȕ��f������B �@
�V�͐l�̏�ɐl�炸�l�̉��ɐl�炸�@(����@�g)�l�Ԃ͖{�������ŋM�ˁE�㉺�̍��ʂ̂�����̂ł͂Ȃ��B�@
�V�͎��珕����҂������@�V�͑��l�̏�������Ȃ��Ŏ��g�œw�͂���҂������Đ���������B

�V�����ő�����@���l���Q���悤�Ƃ��Ă������Ď��g���Ђ����������Ƃ̂��Ƃ��B�@
�V�����݂��l���߂��@�s���ł���ƓV������l���߂��肵�Ȃ��ŁA�݂�����C�{�ɓw�߂�B�@
�V����(��)���@���ɍ������ƁB���炵�������ł��邱�ƁB�u�ӋC�V���Ղ��v�@
�V�Ƃ��n���(�ނ���)�Ƃ��@�����E����(�炢�炭)�œV�n���ƂƂ���ӋC�����邱�ƁB

�V�ԉ���(��������)�a�ɂ��ĘR�炳���@(�u�V�q�]���O�́v�ɂ��)�V�̖Ԃ͂Ђ낭�A���̖ڂ͂��炢�悤�����A���l��R�炷���ƂȂ��߂���B�V���͌����ŁA�������Ȃ������̂͑��ӕK���V������B
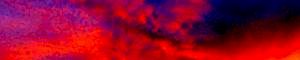
�ʖڂ����@���_���ۂ����B�炪���B�@
�ʖڊےׂ�@���ɖʖڂ�������B�Ђǂ����_�������Ȃ��Ă��܂��B�@
�ʖڂ������@���_����������B�����̕s��ۂɂ���Đ��]����������B�̖ʂ������Ȃ��B�@
�ʖڋʂݒׂ��@���ʖڂ������@
�ʖڂ��{���@�̖ʂ킸�ɂ��ށB�@
�y�ʖڎ���z�ʖڂ��Ă��˂��ɂ�������B�����u�ʖڎ�����Ȃ��v�ŗp����B�@
�y�ʖږ����z�p���������Đl�ɍ��킹��炪�Ȃ��B���ԂɊ�������ł��Ȃ��قǒp�������B�@
�y�͊C�z�͂ƊC�B�͊C�͍ח����(����)��/��l���͓x�ʂ��L���Ă悭�l��e(��)��邱�Ƃɂ����B

�R����o����(�܂���)�@�͂��߂͂����̂���ł��������Ƃ����ʂƂ��Ė{���ɂȂ��Ă��܂��B�@
�R�Ŋ�(�܂�)�߂�@�����ŕ\�ʂ����ꂢ�ɂ݂�������B���܂����B�u�R�Ŋۂ߂����̒��v�@
�R�ɂ��@���Ƃ��{�C�łȂ��ɂ��Ă��B�ق�̏����ł��B����ɂ��B�����āB�@
�R�̔�@�܂������̂����B����ׂ��Ƃ��������������ɂ��Ƃ������́B�@
�R�͂˂��@�����̈ӂ�\�킷��B�ԈႢ�Ȃ����̒ʂ肾�B�܂��������B�������˂��B�@
�R�����ց@�ꍇ�ɂ���Ă͂�������i�Ƃ��ĕK�v�ł���B�@
�R��f(��)���@�����������B
 �@
�@���V�l�ܐ�
�����ɂ͘Z�̐��E������B�Ƃɂ��镧�d������ƁA�݂�ȉ������ɂƒi�����菭�����ׂ��Ȃ�A�܂��ŏ㕔���牺�ɂƈ�i���Ƃɍׂ��Ȃ��Ă���B����͏O�����E�̘Z����\���Ă���B������A�n���E��S�E�{���E�C���E�l�E�V�A�����Ĉ�ԏ�̓V�����E�ɓ�����̂ł��낤���B�Ƃɂ������̂悤�ɏo���Ă���B�l�ԊE�̕����������镧�d�̓����ł���A�O�i�قǂɕ�����A�{�����J��A�ʔv���J��A�䋟�������镔���ƂȂ��Ă���B�@
����ŁA��R�ǂ����Ƃ����Ă��̑P�Ƃ̌����ɂ���Ď���E���V�E�ł���A�l�ԊE�����������ƂĂ����K�ŁA�ꂵ�݂��Ȃ��A��ɉ��y�������������鐢�E�ł�����Ƃ����B�����͐��ɒ����A�Z���l���V�̓V�l�ł�����͐l�ԊE��50�N�Ŏ�����500�N�A�s���V�̈���͐l�ԊE��400�N�ɑ�����������4000�N�ƁA�r�����Ȃ����Ԃ��߂����B�@
������������Ƃ����ĉi���ł͂Ȃ��āA�V�E�̏Z�l�Ƃ������Ƃ͂܂��O���̗։�̐��E���o�Ă��Ȃ��̂ŁA������͎����������莀��͉��̐��E�ɗ����Ă��������Ȃ��̂��Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�A�ꂵ�݂��Ȃ��̂ʼn�E��]�ނ��Ƃ��Ȃ��A�C�s�����邱�Ƃ��Ȃ�����������g���ʂ��������Ȃ̂�����B�@
�Ƃ���ŁA����͏�y�ɉ����������ƍl����������邩������Ȃ����A��������͂��̓V�E�̏Z�l�ɉ߂��Ȃ��B�����̐��E�ς̒��̏�y���Ȃ̂ł��邩��A�����y�ɉ�������ƌ����Ă��A����Ă��Ȃ����蕧�E�ɂ͂����Ȃ��B��y�Ƃ��������ȑ������E���A���͂����͓V�E�ɉ߂��Ȃ��B���߉ޗl�Ɠ������̐��O�܂ŏC�s�������ɋ߂Â����s�҉ʂ�������i�K�̕��̂݁A�V�E���畧�E�ɂ�����ƌ������A�����܂ŏC�s����̂́A����͂����ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B������V�E�ɂ������Ƃ��Ă��A�݂�Ȃ��������͂��x�͉��̐��E�ɂ�����A�܂��C�s�����Č��Ȃ����蕧�E�ɂ͂����Ȃ��B�@
�����āA�V�E�Œ������y�̐��E�ŗI�X�Ƃ��Ă����Ƃ��Ă��A������������]������Ƃ����Ƃ��ɂ͂ƂĂ��Ȃ��ꂵ�݂ɏP����̂��Ƃ����B���̂Ƃ����߂Â��Ă����Ƃ��Ɍ����܂̐��S�̑��̂��Ƃ��u�V�l�ܐ��v�ƌ����B�o�T�ɂ���ď������Ⴂ�����邪�A�܂��A�@���̉ԏ��肪���ڂ݁A�A�߂�����A�B�e�̉��Ɋ��������A�C�ڂ�ῂ݁A�D�V�E�̉��{�ɂ��Ă��y���߂Ȃ��B�����Ȃ��Ă���Ƃ��̎����ڂɁA���悢��n���̏\�Z�{���̋ꂵ�݂��P���V�E����ނ��Ƃ�������Ă���̂��ƌ����B�@
����ȋꂵ�݂𖡂키���炢�Ȃ�A���x�ł����̐l�ԊE�ŋ�y�𖡂킢�A�����ł��������d�ˁA�ꐶ�����ґz���Ĉ���ł���E�ɋ߂Â��悤�ɐ��i���������悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���������Đl�ԊE�ɂ���͖̂{���͂ƂĂ��Ȃ��A���̃`�����X�Ȃ̂�������Ȃ��ƍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��A���₻���l���Ȃ����Ƃɂ͐��ɂ��������Ȃ��ƌ�����̂�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�l�ԊE�ɍĐ�����̂�����ȂɊȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ƌ����邩��B�@
�Ƃ���ŁA����ɐ����鎄�����͍��A���̂��������K�Ȑ��������Ă���B�̂̐l��������A����͓V�l�̏��Ƃ̂悤�ɂ�������̂ł͂Ȃ����B�ǂ��֍s���ɂ��Ԃ�����A�V�����ɏ��ΐ͉̂������������������������̈�A�Ԃōs���Ă��܂��B��r���͂������̉����{���̏����e���r��C���^�[�l�b�g�ň�u�ɂ��Ď�ɓ������B�܂�Ŏ�����щz���Ă��邩�̂悤�ɂ��ł��N�Ƃł��ǂ��ɂ��Ă��g�тŘA�����o����B���Ȃ���ɂ��ĉ��y�����x�����ł��y���߂�B��s�@�Ő��E�����s�����ł���B�܂��ɓV�l�̂悤�Ȑ��������Ă���Ƃ͌����܂����B�@
�����l����ƁA�����������̐��E����ނ��Ƃ��ɂ́A�n���̏\�Z�{���̋ꂵ�݂��邱�ƂɂȂ�̂ł��낤���B���ɒ��菄�炵�����낢��ȓd�g���Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�����A���ɐS�n�悢���𒅂Ă��S�n�悳���������A�������Ȃ��̂Ɋ��������A���ɂȂ��Ă��Ă��ڂ�ῂ݁A�ǂ��ɂ��Ă��y�����Ȃ��Ƃ������Ƃ�����ł��낤�B�܂��ɓV�l�ܐ��̂悤�ȋꂵ�݂����ڂ�����l�͍Ŋ��̎����}����̂�������Ȃ��B�@
���܂�ɂ��֗��ʼn��K�ȉ��ł��o���Ă��܂����Ƃɉ��̊������Ȃ��Ȃ����������̖��H�͂�͂�ꂵ�݂����܂Ƃ��̂ł��낤�B����������O�̂悤�ɂ��̉��K�Ȑ��E�ŕ�炷�������ł͂��邯��ǂ��A���ɁA������������̗������ؕ����������������邱�Ƃ���Ȃ��ƂȂ̂ł͂Ȃ����낤���B�Ԃɗ��炸�����Ăǂ��ɂł��s���Ă݂�B�g�т�C���^�[�l�b�g���g��Ȃ��B�e���r�����Ȃ��B���y��f���̂Ȃ����R�Ƃ̌�炢�𖡂키�B�������邱�Ƃœ���ł͖��킦�Ȃ��A���炬��������Ƃ������Ƃ�����̂��낤�Ǝv���B�������Ă�����E�Ɏ�����Ƃ������Ƃ̈Ӗ������߂邱�Ƃ�����̂�������Ȃ��B�@
�����p��ŁA�Z���ō��ʂ̓V�E�ɂ���V�l���A�����̖��Ɍ}���鎀�̒��O�Ɍ����5�̒����̂��ƁB
��ʟ��όo�ɂ����ẮA�ȉ��̂��̂��u�V�l�ܐ��v�Ƃ����A��̌ܐ��ƌĂ����́B����͕��T�ɂ���ĈقȂ�B
1. �ߏ֍C�V�i�����傤�������j�F�ߕ����C�Ŗ����݂�
2. ����؈ށi�����傤�����j�F����̉�顂��ނ���
3. �g�̏L�q�i�������イ�킢�j�F�g�̂�����ďL���o��
4. �������o�i����������j�F���̉����犾������o��
5. �s�y�{���i�ӂ炭�قj�F�����̐Ȃɖ߂�̂�������
���̂����A�ِ��������̂�3�ڂŁA�u�g�̏L�q�v�̑����
�w�@��栚g�o�x��w���{�s�W�o�x�ł́u�g��̌��ł��v
�w���d����o�x���ł́u�����̌��ł��v
�w�Z�g�����o�x�ł́u���Ⴕ���Ώu῁i�܂������A����߂��j�v
�ƂȂ��Ă���B
�Ȃ��A�w���@�O�o�x�ɂ́A���̓V�l�̌ܐ��̎��̋�Y�ɔ�ׂ�ƁA�n���Ŏ��Y������16����1�ɖ����Ȃ��Ɛ����Ă���B�w�����v�W�x�ł́A�w�Z�g�����o�x�̐��Ɉ˂�A�l�Ԃ��y���Ɋy�~����V�l�ł��Ō�͂��̌ܐ��̋�Y��Ƃ�Ȃ��Ɛ����āA���₩�ɘZ���։��E���ׂ��Ɨ͐����Ă���B
�܂��A�����̖{�n����ł���w�F��{�n�x�ɏo��u�ܐ��a�v�Ȃǂ́A���̓V�l�ܐ��ɗR������B�@
�V�l�ܐ��Ƃ������t������B�V�l�Ƃ͓V�E�ɂ��ޏZ�l�̂��ƂŁA�V�E�Ƃ́A�����Ƃ���������̂���������˂Ȃ�Ȃ��Z���̈�ԏ㕔�Ɉʒu���鐢�E�̂��Ƃł���B�������͂��܌b�܂ꂽ�l�ԊE�ɐ����Ă͂��邯��ǂ��A����݂͂Ȃ����˂Ȃ�Ȃ�����������ƍl����̂����E�̕����k�̏펯�ł���B�����Ă����P���̋Ƃɂ���Ď��ʏu�Ԃ̐S������A���̐S�̎����ɏ]���ė��������܂�ƍl����B
�����ɂ͘Z�̐��E������B�Ƃɂ��镧�d������ƁA�݂�ȉ������ɂƒi�����菭�����ׂ��Ȃ�A�܂��ŏ㕔���牺�ɂƈ�i���Ƃɍׂ��Ȃ��Ă���B����͏O�����E�̘Z����\���Ă���B������A�n���E��S�E�{���E�C���E�l�E�V�A�����Ĉ�ԏ�̓V�����E�ɓ�����̂ł��낤���B�Ƃɂ������̂悤�ɏo���Ă���B�l�ԊE�̕����������镧�d�̓����ł���A�O�i�قǂɕ�����A�{�����J��A�ʔv���J��A�䋟�������镔���ƂȂ��Ă���B
����ŁA��R�ǂ����Ƃ����Ă��̑P�Ƃ̌����ɂ���Ď���E���V�E�ł���A�l�ԊE�����������ƂĂ����K�ŁA�ꂵ�݂��Ȃ��A��ɉ��y�������������鐢�E�ł�����Ƃ����B�����͐��ɒ����A�Z���l���V�̓V�l�ł�����͐l�ԊE�̂T�O�N�Ŏ�����500�N�A�s���V�̈���͐l�ԊE��400�N�ɑ�����������4000�N�ƁA�r�����Ȃ����Ԃ��߂����B
������������Ƃ����ĉi���ł͂Ȃ��āA�V�E�̏Z�l�Ƃ������Ƃ͂܂��O���̗։�̐��E���o�Ă��Ȃ��̂ŁA������͎����������莀��͉��̐��E�ɗ����Ă��������Ȃ��̂��Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�A�ꂵ�݂��Ȃ��̂ʼn�E��]�ނ��Ƃ��Ȃ��A�C�s�����邱�Ƃ��Ȃ�����������g���ʂ��������Ȃ̂�����B
�Ƃ���ŁA����͏�y�ɉ����������ƍl����������邩������Ȃ����A��������͂��̓V�E�̏Z�l�ɉ߂��Ȃ��B�����̐��E�ς̒��̏�y���Ȃ̂ł��邩��A�����y�ɉ�������ƌ����Ă��A����Ă��Ȃ����蕧�E�ɂ͂����Ȃ��B��y�Ƃ��������ȑ������E���A���͂����͓V�E�ɉ߂��Ȃ��B���߉ޗl�Ɠ������̐��O�܂ŏC�s�������ɋ߂Â����s�҉ʂ�������i�K�̕��̂݁A�V�E���畧�E�ɂ�����ƌ������A�����܂ŏC�s����̂́A����͂����ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B������V�E�ɂ������Ƃ��Ă��A�݂�Ȃ��������͂��x�͉��̐��E�ɂ�����A�܂��C�s�����Č��Ȃ����蕧�E�ɂ͂����Ȃ��B
�����āA�V�E�Œ������y�̐��E�ŗI�X�Ƃ��Ă����Ƃ��Ă��A������������]������Ƃ����Ƃ��ɂ͂ƂĂ��Ȃ��ꂵ�݂ɏP����̂��Ƃ����B���̂Ƃ����߂Â��Ă����Ƃ��Ɍ����܂̐��S�̑��̂��Ƃ��u�V�l�ܐ��v�ƌ����B�o�T�ɂ���ď������Ⴂ�����邪�A�܂��A�@���̉ԏ��肪���ڂ݁A�A�߂�����A�B�e�̉��Ɋ��������A�C�ڂ�ῂ݁A�D�V�E�̉��{�ɂ��Ă��y���߂Ȃ��B�����Ȃ��Ă���Ƃ��̎����ڂɁA���悢��n���̏\�Z�{���̋ꂵ�݂��P���V�E����ނ��Ƃ�������Ă���̂��ƌ����B
����ȋꂵ�݂𖡂키���炢�Ȃ�A���x�ł����̐l�ԊE�ŋ�y�𖡂킢�A�����ł��������d�ˁA�ꐶ�����ґz���Ĉ���ł���E�ɋ߂Â��悤�ɐ��i���������悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���������Đl�ԊE�ɂ���͖̂{���͂ƂĂ��Ȃ��A���̃`�����X�Ȃ̂�������Ȃ��ƍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��A���₻���l���Ȃ����Ƃɂ͐��ɂ��������Ȃ��ƌ�����̂�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�l�ԊE�ɍĐ�����̂�����ȂɊȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ƌ����邩��B
�Ƃ���ŁA����ɐ����鎄�����͍��A���̂��������K�Ȑ��������Ă���B�̂̐l��������A����͓V�l�̏��Ƃ̂悤�ɂ�������̂ł͂Ȃ����B�ǂ��֍s���ɂ��Ԃ�����A�V�����ɏ��ΐ͉̂������������������������̈�A�Ԃōs���Ă��܂��B��r���͂������̉����{���̏����e���r��C���^�[�l�b�g�ň�u�ɂ��Ď�ɓ������B�܂�Ŏ�����щz���Ă��邩�̂悤�ɂ��ł��N�Ƃł��ǂ��ɂ��Ă��g�тŘA�����o����B���Ȃ���ɂ��ĉ��y�����x�����ł��y���߂�B��s�@�Ő��E�����s�����ł���B�܂��ɓV�l�̂悤�Ȑ��������Ă���Ƃ͌����܂����B
�����l����ƁA�����������̐��E����ނ��Ƃ��ɂ́A�n���̏\�Z�{���̋ꂵ�݂��邱�ƂɂȂ�̂ł��낤���B���ɒ��菄�炵�����낢��ȓd�g���Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�����A���ɐS�n�悢���𒅂Ă��S�n�悳���������A�������Ȃ��̂Ɋ��������A���ɂȂ��Ă��Ă��ڂ�ῂ݁A�ǂ��ɂ��Ă��y�����Ȃ��Ƃ������Ƃ�����ł��낤�B�܂��ɓV�l�ܐ��̂悤�ȋꂵ�݂����ڂ�����l�͍Ŋ��̎����}����̂�������Ȃ��B
���܂�ɂ��֗��ʼn��K�ȉ��ł��o���Ă��܂����Ƃɉ��̊������Ȃ��Ȃ����������̖��H�͂�͂�ꂵ�݂����܂Ƃ��̂ł��낤�B����������O�̂悤�ɂ��̉��K�Ȑ��E�ŕ�炷�������ł͂��邯��ǂ��A���ɁA������������̗������ؕ����������������邱�Ƃ���Ȃ��ƂȂ̂ł͂Ȃ����낤���B�Ԃɗ��炸�����Ăǂ��ɂł��s���Ă݂�B�g�т�C���^�[�l�b�g���g��Ȃ��B�e���r�����Ȃ��B���y��f���̂Ȃ����R�Ƃ̌�炢�𖡂키�B�������邱�Ƃœ���ł͖��킦�Ȃ��A���炬��������Ƃ������Ƃ�����̂��낤�Ǝv���B�������Ă�����E�Ɏ�����Ƃ������Ƃ̈Ӗ������߂邱�Ƃ�����̂�������Ȃ��B�@
�́A���C���h�̖��d�ɍ�(�܂�������)�ɂU���̍��������āA���̎�̖���P�����Ɛ\�����B���̉��̑��̍����ɗD��Ă����_�́A���ɓ����̍L�傳�ł���B���̓����̓��̍L���͂P������̂ɂV���V���������A���̉�L�͂P������̂�42����������قǂł���B
���̉���1000�l�̍@�������������āA���ꂼ�ꂪ�s���\���ďZ��ł����B����1000�l�̍@�̂����A���̒[�ɏZ�ލ@�́A�������̖��ŁA�ܐ��a�̏���i�������ł�̂ɂ傤���j�Ɛ\�����B�܂��͑P�@����Ƃ��\�����B���̏����1000�l�̍@���A��Ԃ̏X���ł������B�剤�͂��̍@�������̂Ēu���āA���̓s�ɂ͒ʂ�Ȃ������B�Ȃ̂ŁA�_�������A�����Ȃ��B����͂��邪�A�����ʂĂāA�������̎c�[���������ł���B�Ղ�T��������������Ă��ċ��낵�����ƕ��X�łȂ��B�V��̌ܐ��͐l�Ԃɂ�������̂��ƍl����ƁA�Q���ɓ����Ă�����܂��肪�s���邱�ƂȂ����Ă���B
�ܐ��Ƃ́A�V�l�Ɏ�������ƌ����Ƃ����T�̐����̂��邵�̂��Ƃł��B���̂T�̂��邵�Ƃ́A�w���όo�x�ɂ��ƁA�ߕ��C�q�E����؈ށE�g�̏L�q�E���������E�s�y�{���B���̌܂B�V�l�͗։�ɂ�����̂̂Ȃ��ōł��b�܂ꂽ�����𑗂�܂����A���̓V�l�������͕K�������}���܂��B����܂ł̌������g���ʂ������V�l�́A�����}���A�܂��ʂ̐����܂��B�l�Ԃɐ��܂�邩�A�n���ɐ��܂�邩�A��S�ɐ��܂�邩�A�{���ɐ��܂�邩�A�C���ɐ��܂�邩�B�ܐ�������A�䂪�g�̎���m�����V�l�́A�_�ʗ͂Ŏ����̗����̎p�����Ă��܂��A�[�����]���܂��B�����������A�Ђǂ��b�܂�Ȃ����ɐ��܂�邱�Ƃ�m�邩��ł��B�����āA�V�l�͎��ӂ̂��Ȃ��A����ł����̂ł��B
�Ƃ��������A�ܐ��a�̏���B����ȕs�g�ʼn��炵�����ŌĂ��@�́A��قǂ̏X���ł������̂ł��傤�B
�@�i�ܐ��a�̏���j�́A�u�l���������ނ܂��B�߂�������ǁA����͉ߋ��̏h�Ƃł���v�Ƃ��v���ɂȂ��āA���O�ڂ̐��ω����}���A�F�����Ƃ���A�ω��̌䗘�v�͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��A�@�͐��܂�ς����o�����āA���̐g�̂܂܁A���Ɠ����O�\���\��̔��e����������F�̐g�̂ƂȂ����B���̐g��������o���Ď��͂��Ƃ炷�B����ƁA�{��������P������ł���B
�����������ɂȂ��邱�ƂȂ̂ŁA�剤�͈�r�ɂ��̋{�֍s�������C�����ɂȂ��āA�s�K���ꂽ�B�@�̎p�����āA�u����͖��������v�Ƌ��ԁB�剤�͂�������āA�����Ԃ�ƒ����ԁA���̋{�ɂ͗��Ȃ������̂��Ǝv��ꂽ�B���̊ԁA�����Ђ����畧��O���Ă������Ƃ��A�@���܂𗬂��A���������\���グ���̂ŁA�剤�͂�����āA�߂��Ԃ���ɉ������Ăė܂𗎂Ƃ��ꂽ�B���ꂩ���́A���̍@���������A���̍@�̂��Ƃ͌ڂ݂Ȃ��Ȃ����B
�c���999�l�̍@�B�͏W�܂��đ��k�������Ƃ́A��������ł������낤���B�P�l���v�����Ƃł��ߐ[���̂ɁA�܂���999�l���v�������Ƃ̍ߐ[���͂����܂ł��Ȃ��B�u�����ɖ����v�Ƃ͊���ʂ��Ƃ��������A999�l�����ꂼ��ɍl�������Ƃ����ƂɁA�ǂ��������̂��Ƃ݂ȂŌv���������B
�剤�́A���̍@�̕��ɉ��q�ł������ł��ł�����Ȃ��Ƃ��v���ɂȂ����B�������A���܂��P�l�̉��q�����܂�Ȃ��̂ŁA�剤�͒Q���āA���ɋF�����B����ƁA�F�������������āA�P�@����͉��D�Ȃ������B
�c��̍@�B�͂��̂��Ƃ��āA���k�������Ƃɂ́A�u���S�ł��Ȃ����Ƃł���B�債�Ă悭�Ȃ����ł��A�q��݂�����r�܂����Ȃ���́B�܂��ĉ��q�����܂������ʂƂ���ցA���������q�ł������ł��ł����Ȃ�A���B�͉i�v�Ɏ̂Ă��Ă��܂��B�ǂ����悤�v�ƁA���̂��́A�܂Ɉ��ŒQ���������B�@�B�����̏���i�ܐ��a�̏���̂��Ɓj����D�����ł���ԂŁA�剤�̌�O�ɎQ���Đ\�������邱�Ƃɂ́A�u�@�̌���D������܂����B���q�ł������ł����ł��ɂȂ�����A���B�A990�l�i�Ȃ�990�l�H�@999�l�łȂ��āB�P�Ȃ鏑���ԈႦ�ł��傤����ǁj�݂Ȃő�ɂ����b�\���グ�܂��傤�B������߂��������Ƃ͂������܂��܂��v�@�����͐\���グ�����̂́A�e�X�̐S�͎��i�̂ق̂��ŔR���o������ł���B���Ȃ�ΘR��Č����Ȃ�����ł���B������A�w�،��o�x�ɂ́A�u���l�͒n���̎g���A�悭���̎�q��f�B�O�ʂ͕�F�Ɏ��Ă��邪�A���S�͖鍳�̂��Ƃ��ł���v�Ƃ����Ă���B���̍@�B�̑Ԃ�剤�͂܂��ƂƎv���āA�u�悫���ȁA�悫���ȁv�Ƃ�����������B
999�l�̍@�B�͑�P�����7�ɓ�����{�a�ɏW�܂�A�u�ǂ����悤���v�ƒQ���������B�܂����܂�Ă��鉤�q�̉ʕ�̒���m�낤�Ƃ��āA����肢�t�������āA���̉��q�̂��Ƃ��₢�ɂȂ����B�u��F����i�ܐ��a�̏���̂��Ɓj�̛s�݂Ȃ������̂́A���q���������B�܂����̉ʕ�̒������Đ\���B�s�R�Ɏv����̂ł��v�@�肢�t�́A�������J���Đ���Đ\�����̂ɂ́A�u�s�݂Ȃ����Ă����q�͉��q�ł�������Ⴂ�܂����A�������8500�ł��B���y�����ɂ��āA���̉��̎����A�������݂Ȏ��R���݂ŁA���y�������炷���҂ł���܂��v
�@�B�͉��o��قǎ����������ŁA�肢�t�ɋ���ꂽ�̂ɂ́A�u���̉��q�̂��Ƃ�剤�̌�O�Ŏ��̌����܂܂ɐ���Đ\���グ�Ȃ����B�J���͖]�ݒʂ�Ɏ�点�悤�B���̉��q�͂����܂�ɂȂ��ĂV���ڂɋ㑫���ʂ̋S�ƂȂ��āA�g�̂�����o���A�s���͂��߁A�V�����݂ȏĂ��s�����Ă��܂��ł��傤�B���̋S�͎O�F�ŁA�g�̏�͂U�O��i�P��͂��悻�Rm�j���܂��B�剤�͐H���Ă��܂��܂��B���̂悤�ɐ\���̂ł��v�B�܂��A�u�S�g�����X�X���̋S�������đ啗���N�����A�吅���o���āA�V�����݂ȊC�ɂ��Ă��܂��ł��傤�Ɛ\���グ�Ȃ����v�ƌ����āA�@�B�͊e�X�̕��ɏ]���āA�J����肢�t�ɗ^�����B����@�͋�500���A�܂�����@�͋�1000����^���A���ꂾ���łȂ��A���тȂǂ̐D���ނ͔���Ȃقǂɗ^�����B�肢�t�͊��ŁA�u����܂����v�ƕԎ���\���グ���B�@�B�́u�������p�v�ƌ��~�߂Ȃ������B�肢�t�́u�ǂ����ċ��ɔw���܂��傤���v�Ɛ\���グ�ċ������B
���P�������āA�@�B�͑剤�̌䏊�ɎQ���āA���k�Ȃ���ɂ́A�u�@�̌���D�̂��ƁA���q���������C�|����ł��B�������肽�����̂ł��B�肢�t�������Ă������Ȃ����B���܂�ɋC�ɂ�����܂����Ɓv�B���̂Ƃ��A�剤���u�����Ƃ��Ȃ��Ƃ��v�Ǝv���āA���̐肢�t���������B�@�B�́A���O�ɐ\���t���Ă�����F����̂��Y�̂��Ƃ��A�u�q�͂ǂ��炩�\���v�ƌ����Ȃ���A���Ⴆ�Ȃ����낤���ƁA�e�X�̐S�̂����͂܂�ŋS�̂悤�ł���B
�肢�t�͎G���i�l�̉^���Ȃǂɂ��Ă̑������L���������j���J���Ėژ^�����Ă݂�ƁA���q�̉ʕ�̂��炵�����Ƃ͐\���܂ł��Ȃ��B�u�@�̌�N�͂����قǂł����v�ƁA�肢�t���₤�ƁA�@�́u360�v�Ɠ�����ꂽ�B�肢�t�͓��L�ɂ܂����Č���ƁA�܂��o�Ă��ĂƂ܂�Ȃ��B�u����قǂ��炵������������҂��A����ʂ悤�ɐ\�����Ƃ̐S�ꂵ����v�Ƃ͎v������ǂ��A�������Ȃ���A�ȑO�̖̂悤�ɂ悤�ɐ���Đ\���グ���B
�剤�͂��̂��Ƃ��������ɂȂ��āA�u�e�ƂȂ�A�q�ƂȂ邱�ƁA���܂��܂ɂ��L�����Ƃł���B���̐������̂��Ƃł͂Ȃ��B�����܂ł��܂��q�Ƃ������̂��������Ƃ��Ȃ��B�����Ȃ�S�ł����܂�Ă�����̂Ȃ�ΐ��܂�Ă����B�݂��ɐe�Ǝq�ƒm���āA�P���ł����Č�Ȃ�A�ǂ��Ȃ낤�Ƃ��ꂵ���͎v��Ȃ��v�Ƃ����āA�p�������Ȃ������B�@
 �@
�@���ւƏ\����
�Ñ�̉ԕ��E�y��̕��͂���A�����̋C��E�A���Ȃǐ��@����Ƃ����A�V�����u���l�Êw�v�Ȃ�Ǝ��̍l�Êw������J�������҂̌��т͑傫���B���͂���ɂƂǂ܂炸�A������]�E��r�����̕���ɂ����Ă��A�����ŐϋɓI�ȍs���͂Ɖs���ȓ��@�́A����ɂ����ꂽ�\���͂ŁA�����̖�S�I����𐢂ɖ₤�Ă����B���̒���1���ŁA�u�ցv�Ƃ����A�A�j�~�Y���̎���ɓ����ɘj���ĐM�̒��S�ł��������������A�ǂ����āA�ǂ̂悤�ɂ��̗͂������Ă��������Ƃ����A�@���̍����ɉ������i�]�ɒ��킵�u�@���Ƃ͉����H�v�Ƃ�������ɃO�C�O�C�Ɠ������Ă����̂��{���ł���B�ǎ҂͋����̒��ŁA�u�G�f���̉��ŃC�����ւɂ����̂�����ċ֒f�̖̎���H�ׂ�v�Ƃ��������Ƃ��L���Ȉ�b���A�Ȃɂ��Ȃ��~�߂Ă����͂����B���������ꂱ���u�ցv�����āu�M�v�����Ȃ��̂Ƃ��Ĕr�˂����ے��ł������Ƃ����������C�t������邾�낤�B�u�X�v�̎���A�L���̒n��_�Ƃ̌����ɂ���āA�X�����ۂݏo���u�ցv�́A�s���E�Đ������Đ��B�̏ے��ł����_�ł������B�X���J���ċ����������́A�X�̖ŖS�ɂ��^�������č������Ŏ��X�ɖł�ł������B�X�̐_�u�ցv�͉Ɨ��̐_�u�o�[���v�ɂ���ĎE����A�u�o�[���̐_�v���܂��A�ߍ��Ȑ��E�̏s��ȑn����(���@�E�G)�ɂ���ĎE�C�����B�������Ēn���C�̐_�X���A�ނ���Ղ�_�a���p���Ɖ����O�ɁA�����Ɩł�ł����B���āu�엀�̔����ʁv�Ƃ����Ȃ���(����������)�����̈�p�Ő��܂ꂽ��_�������A(�����Ȃ��瑼�������ĔF�߂�)���_���E�L���X�g�����ăC�X�������ł���B�\���˂̓L���X�g���̏ے��ł���B�L���X�g���̕z���̗��ɁA�����̓����̖ŖS������A�ً��k�̔��Q������A�����̑㏞�Ƃ��ẮA�X�̖ŖS�ƍ������̐i�s���������B�\���˂����ւɑ�\�����A�j�~�Y���Ǖ��̃V���{���������B������{�ł͂ǂ����H�@
�X�Ƌ������Ȃ���A���Ɏ���܂ŐF�Z���u�M�v��ێ���������u�ꕶ�v�ɔ�������{�̏@���ρE���R�ςƁA�����̂���ƑΔ䂳���Ȃ���A�s�т̎�����~�����_���̕����A���Ȃ킿�A�j�~�Y�����l�b�T���X�����B�@
 �@
�@���\���˂͂Ȃ��L���X�g���̏ے��Ȃ̂�
��1. �R���X�^���e�B�k�X�͂Ȃ����F�����̂� �@
���́A�\���˂��L���X�g���̏ے��ɂȂ����̂́A�C�G�X������ł���300�N�قǂ����Ă���ł���B�悭�m���Ă���Ƃ���A�L���X�g���́A���[�}�鍑�ł͒��炭���Q����Ă������A313�N�ɃR���X�^���e�B�k�X1��(Flavius Valerius Constantinus �| �ȉ��A�R���X�^���e�B�k�X�ƋL��)�ɂ���Č��F����A��ɍ����ɂ܂łȂ����B�\���˂��ے��Ƃ��ĔF�m����n�߂��̂��A�w�V���x�����݂̌`�Ő��������̂��A�L���X�g���̊�{�I�ȋ��`�����܂����̂����̍��ł���B�ǂ����A�R���X�^���e�B�k�X�ɓ��������|���肪���肻�����B �@
�R���X�^���e�B�k�X�́A���[�}�鍑�̐�������R���X�^���e�B�E�X�̎q���ŁA��e���L���X�g���k�Ƃ������Ƃ������āA���Ƃ��Ɨ��c��Ɣ�ׂ�ƃL���X�g���ɂ͊��傾�������A�ގ��g�́A�L���X�g���k�ł͂Ȃ������B�]�@���K�ꂽ�̂́A��������}�N�Z���e�B�E�X�Ƃ̔e�������̎��������B����ȑO�ɐM���Ă����@������g�̔j�ł�\������A���_�_�҂ɂȂ肩���Ă����R���X�^���e�B�k�X�́AP��X��g�ݍ��킹�����m�O�����̖�(����ɂ��Ɣ�����)�����āA�����V���Ȑ_�̌[���Ǝ��A���̃��m�O�����m�̏��ɕ`�������Ɠ`�����Ă���B �@
���̂��̃��m�O�����́A�L���X�g�ɑ�������M���V����N���X�g�X(�ԃσǃЃу�?)�̍ŏ��̓��ł���J�C�ƃ��[��g�ݍ��킹�����̂ŁA�L���X�g�����ے�����L���������B���[�́A���e��������R�ɑ�������̂����A�M���V�������̑啶���́A���e��������P�ƌ`�������ł���B������A�R���X�^���e�B�k�X�̂悤�ȃ��e���������̐l�ɂ́A�L���X�g���̃��m�O�����́AP��X�̑g�ݍ��킹�Ɍ������͂����B �@
�R���X�^���e�B�k�X�����Ɍ������̋L�����A�����Ȃ��]�̉B�g�ł��������́A���_���͊w�I�ɋ����̂���e�[�}�ł���B�L���X�g���̃��m�O�����́A�t�@���X(phallus)���邢�̓y�j�X(penis)�̓������ł���(�����āA�Ίۂ̕t�����y�j�X�������猩���`�Ɏ��Ă���)P�Ƀo�c��������L���Ƃ����߂ł���B�R���X�^���e�B�k�X�ɂƂ��āA����͋������Ӗ�����L���������̂ł͂Ȃ����낤���B �@
�Ȃ��A�R���X�^���e�B�k�X�������̖��������̂��́A��ōl���邱�Ƃɂ��悤�B���̌�A�R���X�^���e�B�k�X�R�́A���̏�ł͈��|�I�ɗ������ɂ�������炸�A�}�N�Z���e�B�E�X�R���~�����B�I���̐킢�Ŕj��A�ŏI�I�ɁA�R���X�^���e�B�k�X�́A���Ă������[�}�鍑���ē��ꂵ�āA���[�}�c��ƂȂ邱�Ƃ��ł����B�������āA�R���X�^���e�B�k�X�́A�L���X�g�̐_�Ɋ��ӂ��āA�L���X�g�������F���A���̌�A�L���X�g���́A�鍑���ŋ}���ɕ��y�����B �@
�����������j�I�o�܂��l����Ȃ�A�\���˂��L���X�g���̏ے��ɂȂ����w�i�ɂ́A�C�G�X���\���˂Ŏ�����Ƃ����ȏ�̗��R������悤���B�����̋L���Ƃ��Ă̂w��45�x��]������A�\���˂ɂȂ�B��������܂Ŏ咣���Ă����悤�ɁA�L���X�g�����A�l�ގj�̒j�����Ɍ��ꂽ�����R���v���b�N�X�̏@���ƈʒu�t����Ȃ�A�Ȃ��\���˂��L���X�g���̃V���{���Ƃ��đI��邱�ƂɂȂ����̂��𗝉����邱�Ƃ��ł���B �@
���[�}�鍑�ł́A�����ԁA�\���˂ɂ�����Y���A���Y�̕��@�Ƃ��č̗p����Ă������A�R���X�^���e�B�k�X�́A�����p���A�i��Y���̗p�����B����������A�R���X�^���e�B�k�X���\���˂ɐ��Ȃ�Ӗ������o���Ă������Ƃ��킩��B328�N�ɁA�R���X�^���e�B�k�X�̕�w���i�́A�G���T�����Ő��\���˂����A���̌�A�\���˂ɑ���M���n�܂����B �@
�R���X�^���e�B�k�X�́A325�N�Ƀj�P�A����c���J���A���Ȃ�_�Ǝq�Ȃ�C�G�X�Ɛ���͑S���قȂ�Ƃ���A���E�X�h���ْ[�Ƃ��ĒǕ����A�O�ʈ�̂̋��`���m�������c��Ƃ��Ă��m���Ă���B�O�ʈ�̂Ƃ́A�_�ɂ��Đl�Ƃ������`����тт��C�G�X���A�_�Ɛl�̔}��ƂȂ�A�����ăC�G�X�����Y�����A�܂�}�����(����)����邱�ƂŁA�_�Ɛl�Ƃ���̂ƂȂ�(����~��)�Ƃ������`�ł���B �@
�J�g���b�N�ł��M���V�������ł��A�L���X�g���k�́A�悭�w���g���ď\����`���B���̍ہA�w�͐e�w�E�l�����w�E���w�̎O�w��L���A���̓�{��܂�Ȃ��邱�ƂŁA�O�ʈ�̂�\���B���̂��Ƃ́A�\����`�����ƂƎO�ʈ�̂̋��`�ɂ͖��ڂȊW�����邱�Ƃ������Ă���B �@
�\����`�����A����A�܂��ォ�牺�ցA���ɁA�J�g���b�N�ł͍�����E�ցA�M���V�������ł͉E���獶�ւƓ������B�ǂ���̏ꍇ�ł��A�ォ�牺�Ɉ��������́A�V��̐_�ƒn��̐M�҂����ѕt����}��I�Ȑ��A�܂�C�G�X��\���A����ɉ������������Ƃ́A�C�G�X�̖��E��\���B�L���X�g���k�́A�\����邱�ƂŁA�C�G�X�Ƃ����t�@���X�I���݂���������L���X�g���̌��_�����A�_�Ɛl�Ƃ̈�̂��m�F���Ă���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B �@
��2. �������t�@���X���q�������炷 �@
�����Ƃ́A���J���̗p����g���Ȃ�A�z���I�t�@���X�̏ے��I���@�ł���[��]�B�q���́A��Ƀt�@���X�����@���Ă��邱�ƂɋC���t���A��̑z����̃t�@���X�ƂȂ邱�Ƃŕ�̗~�]�������Ƃ�~�]����B�����ŁA�y�j�X�A�]��������A�q�������������z���I�t�@���X�Ƃ��ď��L���邱�Ƃ�~�]����B �@
[��] ���J���̗p��@�ł́A�z���I�Ώۂ̏ے��I���@������(castration)�ł���̂ɑ��āA�����ɂ�����y�j�X�̌��@�̂悤�ȁA�ے��I�Ώۂ̌����I���@�́A���D(privation)�A�q������z������[�̑r���̂悤�ȁA�����I�Ώۂ̑z���I���@�́A����(frustration)�ƌĂ�ŋ�ʂ����B�܂�A���J���ɂƂ��ċ����Ƃ́A�����ʂ�y�j�X��藎�Ƃ������I���@�ł��Ȃ���A�y�j�X���Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��Ƃ����z���ł��Ȃ��A��̃y�j�X�ɂȂ�z�����A���ɂ���āA����I�E�ے��I�ɋ֎~����邱�ƂȂ̂��B �@
���̕�q�����W�́A�����I�i�K�̃i���V�V�Y���̉�����ɂ���B �@
�� �ߐe�����A�i���V�V�Y���A��e�̒j��(�t�@���X)�ł��邱�Ƃ́A�������ꂪ��������A�����ł������肷�ׂĂ̗~�]���I���ɒB���A�����~�]�����A�������҂ɑi�����A�����������t���g���K�v���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����B����͐l�ԂɂƂ��Ă̈��̎��ł���(�i���V�X�_�b�A�����i�K�̑��H)�B���������āA��e�Ǝq���̎��̕��i��W���A���̑z���I�Z����f�����p��������̂����̖��Ȃ̂ł���[�Γc �_�V�F���̃��J���\���_���͂Ɣ\�L�̑��ݘ_] �@
���̖�(Nom du Pêre)�Ƃ́A�����甭�������(Non du Pêre)�ł�����A�z���I�t�@���X�ɂ���q�������֎~����B�����Ƃ����Ă��A�����ʂ葧�q�̃y�j�X�����킯�ł͂Ȃ��B�z���I�t�@���X���ے��I�Ɍ��@���邾���ł���B���@(����)���Ӗ�����p��́gwant�h�������ɗ~�](����)�Ƃ����Ӗ��������Ƃ���킩��悤�ɁA�����ɂ���č���錇�@���A���@�߂悤�Ƃ���~�]���\�ɂ���B �@
�~�]�͏�Ɍ��@�Ɍ������Ă���A���@�߂鑊������߂Ă���B������A�����т́A�g�̂̉��ɂ���mJacques Lacan�FEcrits tome 2, p.298�GEcrits, pp.817-818�n�B�����ɂ����Č݂��ɐG�ꍇ���y�j�X���S�A�L�X�ɂ����Č݂��ɐG�ꍇ���O���A�����ɂ����Č݂��ɐG�ꍇ������Ɠ����̌��O�A�r���ɂ����ĐG�ꍇ�����ƕ����邢�͔A���ƔA�A�������o���肷���ق̗ځA�����o���肷�鎨���Ԃ���A����琫���тɓ�����g�̂̉��́A�����̐g�̂ɑ�����Ɠ����ɑ����Ȃ����`�I�Ȑ��i��тт�B �@
�Љ�V�X�e���̋��E�ɐN�����闼�`�I���ݎ҂��A�Z���Z�[�V�����������N�����悤�ɁA�g�̃V�X�e���̋��E�ɐN�����闼�`�I���ݎ҂́A�G���e�B�V�Y�����䂫�N�������A�Љ�V�X�e���̒����̑̌��҂��A���E��̗��`�I���ݎ҂��X�P�[�v�S�[�g�Ƃ��Ĕr������悤�ɁA���͋����ɂ�萫�I���y���֎~����B �@
�C�G�X���A���낢��ȈӖ��ŁA���E��̗��`�I���ݎ҂������B�_�ł���Ɠ����ɐl�ł�����A���_�����k�ł���Ɠ����Ƀ��_�����k�ł͂Ȃ��A���[�}�鍑�̓����ɑ��݂���Ɠ����ɊO���ɑ��݂����B���̗��`���䂦�ɁA�X�P�[�v�S�[�g�Ƃ��āA�j���邱�ƂɂȂ�B�L���X�g���k�����́A�C�G�X�������Ƃ��������̌����o�ď��߂āA�C�G�X�����������̃t�@���X�ł��邱�ƂɋC���t�����B �@
�����ɂ���Ăۂ�����������A���J���͑Ώۂ��Ɩ��t����B�Ώۂ��́A���@�߂悤�Ƃ���~�����䂫�N�����B�l�X�́A�C�G�X�̖S�[���Ȃ��Ȃ������ƂɋC�����ƁA���\���ˁA���B�A�����A���t�A����z�A���[�z�Ƃ������C�G�X�̌��@�̍��Ղ��c�����╨���A�Ώۂ��Ƃ��āA�ǂ����߂��B���Ƀq�g���[�́A��������ɓ����ΐ��E�𐪕��ł���Ƃ������ƂŁA�y�j�X�ƌ`���Ă��邻�̐��╨�����]�����B �@
���{�����̓`�����A�C�G�X�̓`���Ǝ��Ă���B �@
�� ���{�����������A�n�ˏo�V�A�w�`������V�B�Q�b���A���ȁA�J����[�ؐe]�����V�A���ߋ��A�r�����V�B �@
���{�����͔����ƂȂ��āA�˂���o�āA���}�g�̍���ڎw���Ĕ��ōs���ꂽ�B�Q�b�������A�����ł��̊����J���Ă݂Ă݂�ƁA���炩�ȕz�̈ߕ��݂̂��ނȂ����c���Ă��āA�r�͖����Ȃ��Ă����B�@[���{���I ] �@
�� �V�g�͕w�l�����Ɍ������B�u����邱�Ƃ͂Ȃ��B�\���˂ɂ���ꂽ�C�G�X��{���Ă���̂��낤���A���̕��́A�����ɂ͂����Ȃ��B���˂Č����Ă����Ƃ���A�����Ȃ������̂��B�����A��̂̒u���Ă������ꏊ�����Ȃ����B���ꂩ��A�}���ōs���Ē�q�����ɂ��������Ȃ����B�w���̕��͎��҂̒����畜�����ꂽ�B�����āA���Ȃ���������ɃK�������ɍs�����B�����ł��ڂɂ������B�x�m���ɁA���Ȃ������ɓ`���܂����B�v [����, �}�^�C�ɂ�镟����] �@
�b���R���X�^���e�B�k�X�ɖ߂��A�Ȃ��ނ��������̖��Ȃ����������������̂����l���悤�B�t���C�g�ɂ��A�l����������̂́A��]���[�����悤�Ƃ��邽�߂ł���B�������Ƃ͔������ɂ��Ă�������B �@
�� Der Inhalt dieser Phantasien wird von einer sehr durchsichtigen Motivierung beherrscht. Es sind Szenen und Begebenheiten, in denen die egoistischen Ehrgeiz- und Machtbedürfnisse, oder die erotischen Wünsche der Person Befriedigung finden. Bei jungen Männner stehen meist die ehrgeizigen Phantasien voran, bei den Frauen, die ihren Ehrgeiz auf Liebeserfolge geworfen haben, die erotischen. Aber oft genug zeigt sich auch bei den Männern die erotishe Bedürftigkeit im Hintergrunde; alle Heldentaten und Erfolge sollen doch nur um die Bewunderung und Gunst der Frauen werben. �@
�����̋�z�̓��e�́A���ɂ͂����肵�����@�t���ɂ���Ďx�z�����B�������́A���̐l�̗��ȓI�Ȗ�S�ƌ��̗͂~����G���e�B�b�N�Ȋ�]���������i��o�����Ȃ̂��B�Ⴂ�j�ł́A����������S�I�ȋ�z���A���̐��A�ɖ�S�������Ă��鏗�����ł̓G���e�B�b�N�ȋ�z��������o�Ă���B�������A�j�ɂ����Ă������G���e�B�b�N�ȗ~�]���w�i�ɂ͂����茻���B���ׂẲp�Y�I�ȍs���Ɛ������A�����ς珗�������̏^�ƍD�ӂ邱�Ƃ�ڎw���Ă���B [�t���C�g�F���_���͓���; Gesammelte Werke Bd] �@
�j�̏ꍇ�A���͗~�����~���j���z�������ł���e�X�g�X�e�����̐�����Ƃł���B�R���X�^���e�B�k�X�́A���͂ւ̋����~�]�������Ă������A����́A�����ɂ��Ă����Ƃ����~�]�Ɠ����ł���A���������āA���͂́A���������̗~�]�̑Ώۂł���y�j�X�ɂ���ďے������B�����A�ނ̌R�͗ŁA�ނ̖�]�͔ے肳��悤�Ƃ��Ă����B���ꂪ�A�y�j�X�ł���Ƃ���̂o�ɂw(�o�c)���t�����Ă������R�ł���B �@
�t�@���X�́A��������邱�ƂŁA�������ė~�]�̑ΏۂɂȂ�B���ǁA�R���X�^���e�B�k�X�́A���[�}�c��Ƃ����ے��I�t�@���X�ƂȂ邱�Ƃ��ł����킯�����A����Ɠ����ɁA�C�G�X�E�L���X�g���^�ɕ��ՓI�ȃt�@���X�ƂȂ邱�Ƃ��ł����B �@
�������ꂽ�t�@���X�́A�������ꂽ���ƂŖ��ɂȂ�킯�����A���ꂽ��Ȃ閳�ł����Ă͂Ȃ炸�A���ՓI�Ȗ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B�������ꂽ�t�@���X�́A���J���̃}�e�[���ł́A�啶���̑��҂`(�Ⴆ�A�q���ɂƂ��Ă̕�)�ɂ����錇�@�̃V�j�t�B�A���r�Ƃ��āA�r(�`)�ƋL�����B���J�������҂̃��`���[�h�\���ƃ}���[�� �@
�� �r(�`)�́A���w�̏W���_�ɂ������W���A�܂����v�f���܂܂Ȃ��W���ł��� [John P. Muller �� William J. Richardson�FLacan and Language: A Reader's Guide to Ecrits] �@
�ƌ������A����͂ǂ����߂�����悢���낤���B �@
��W���́A{0}�ł͂Ȃ��āA{��}�ƋL�����B�g0�h�́A�ۂ�����ƊJ�������̌`�����Ă��āA���\�����A�g1�h��g2�h�Ɠ��l�ɁA�v�f�̈�Ƃ��Ĉ�����̂ŁA{0}�͋�W���ł͂Ȃ��B��W���ł��邽�߂ɂ́A�g0�h����A�����Ƃ��Ă̓��ꐫ�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ΐ��́A���̖��E���Ӗ�����L���ł���Ɖ��߂ł���B���̋�W����\���L���́A�t�@���X�̃M���V����(�Ӄ��ɃɃ�?)�̓������Ɠ����ł��� [�o����F�F�D�����ސl�����o �_�V�C���J���ƗՏ����, p.212]�B�C�G�X���܂��A���Y����邱�ƂŁA���I���݂Ƃ������ꐫ�E���āA�t�@���X�Ƃ��ĕ��ՓI�ȑ��݂ƂȂ����B �@
��3. �L���X�g���ƕ����̋��ʓ_ �@
�C�G�X�E�L���X�g�ƂƂ��ɁA�K�E�^�}�E�V�b�_�[���^���܂��A�l�ގj�̒j�����Ɍ��ꂽ�����R���v���b�N�X�̏@���̊J�c�ƂȂ����B�L���X�g���̏ے����\���˂ł���̂ɑ��āA�����̏ے��́A��(�܂�)�ł���B�́A������(���������Ė���)�ے��ł���\�������ɐ���L���ł���B�����ȑO�ł́A���z���˂�\���L���Ƃ��Ďg���Ă����悤�����A�ǂ���ɂ��Ă��A����͒j�������������L���ł���B���Ȃ݂ɁA�K�E�^�}�E�V�b�_�[���^�́A�����z����Ə̂��Ă����B �@
�ɂ́A���ƁA�t�����̉E������A�E���͂◝����\���̂ɑ��āA���́A���߂∤��\���B�q���h�D�[���ł́A�������z�̓����Ƃ͋t�Ȃ̂ŁA���͎���\���Ƃ����B�����������I�����̏@���Ɠ����t����Ȃ�A�����ɂ́A�����ӂ��킵���B�E�́A�i�`�X����\���Ƃ��Ă��m���Ă���B�t�@���X��f�O�������̕����ƃt�@���X���Ȃ킿�u�������e�v��ڎw�����E�̃i�`�X�ł́A�������t�ł��邪�A�Ƃ��ɋ������o���_�ƂȂ��Ă���B�@�@
 �@
�@�������w�Ɛ_
�ʏ펄�����́A�u�����w�҂Ɛ_�v�Ƃ͂܂����������A�Ƃ������G���m�̂悤�Ɏv��������������Ƃ��Ɓu�_�͂����Ɋ����ł��邩�v���ؖ�����̂������w�̃X�^�[�g�ł������B�Ƃ��낪���̊Ԃɂ������w�́u�_�̕s�݁v���ؖ�����w��ɂȂ��Ă��܂��A���x�͂����s���Ƃ���_�������������w�҂����킷��Ƃ����J��Ԃ����͂��܂����̂��Ƃ����B�����w�҂ł��钘�҂́A�Ɠ��̐���ł������킩��₷���A�u�����Ɣj�ǁv���J��Ԃ��_�Ɗw�҂̊W���A�n�����ĂĖ\�I���Ă����B�@
�{���u�_����������w��v�ł���u�S�\�̐_�̑��ݏؖ��v�ł��������R�Ȋw�́A��̂�����_�ɔw�ނ��悤�ɂȂ����̂��낤��?�@
��1��������17���I�ɂ͂��܂����B�����颋ߑ�Ȋw�̖閾������̎��ł���B�V�����w��(���R�Ȋw)�́A�܂������Ӑ}���Ȃ������̂Ɏ���ɐ����̖�����\�����ƂɂȂ�A�������Ȋw�҂́A�_���u�͂邩���Ȃ��̖����̒n�v�ɒǕ����A�u�Ȃ��v�Ɩ₢������_�̗̈�ƁA�u�����Ȃ��Ă���v�Ɠ�����l�̗̈�Ƃ��Ă��܂����B�@
��2����18�`9���I�A�l(���R�Ȋw��)�͑������āA�_��s�v�Ƃ��邢�����̈�����n�����A�܂��܂��_�͐��サ�Ă������B�������̈����Ƃ́A�p���h�b�N�X(�k��)�ł���A�i�v�@�ւł���B���p�ȂǂȂǂł������B�@
�Ƃ��낪�A�V�ԂȐ_�͂ǂ��������ȂȂ������B20���I�ɂȂ��Đ_�̔������͂��܂����B�����w�҂̎�_�́u�Ȃ��v�ɓ������Ȃ��ƋC�t���A�_�͂��́u�Ȃ��v��A�����Ă������B�����͉i�v�@�ւł���B���p�̎��s�ł���A�l�ɂ͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��m���̖��ł���A�F���̐������ł���A�t���N�^���ł���A�J�I�X�ł���A�Ƃǂ߂͗ʎq���_�ł������B�@
�����Ƃ��M�����u���Ƃ����m�����́A�Ȋw�╨���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���ǐ_�����ő�̓q���t�ł���A�l�͐_�̋C����Ƃ��̂����ڂ�ɗ^���Ă��邾���ł���A�Ȋw�҂͖��͂ł������B�����w�҂͉F���̍\�����Ȃ��邱�Ƃ͂ł��Ă��A�u�Ȃ��o�������v�ɂ͖��͂ł������B�_�͂��������p�ӂ��A�w�҂͂���ɓ�����̂ɐ���t�ł������B�ȒP�ȂƂ���ł͉��̗����オ����Ƃ��V��ȂǁA�\�m��\�z��W����t���N�^���ł���J�I�X�ɂ������Ắu���G�n�v�őR���悤�Ƃ��Ă��邪�A�͂����Đ_�ɏ��Ă�̂��H�ʎq�_�ɂ������ẮA�����⓹���܂ŋ��o����Ă���̂��B�@
���͒��҂��A�u�F���N��Ɋւ���F���_�̊�@�v�ɁA���߉ޗl�̏��̏�ł��낤�낵�Ă��邾���̐l�́A�����V���@���łȂ��Ă����������ŏ[���ƌ����Ă��邭�炢�ł���B�Â܂�Ƃ���u�_�̒���Ƃ́A���Ǖ����w�҂̖��m�ł���A�����F���ł���A��l���o�ł���B���߉ޗl�̏��̏�ɂ���ɉ߂��Ȃ������w�҂挪���ł���I�v���Ƃ����̂����_�ł���B�@
 �@
�@���s�s�Ɠ��{�l
���z�w�҂ł��钘�҂́A�J�~�T�}�Ƃ̊֘A�Ƃ������j�[�N�Ȏ��_�Ő����̓s�s�Ɠ��{�̓s�s�̈Ⴂ���w�E����B�����̓s�s�ɂ͂��̒��S�ɐ_�a������A�������ǂ�����ł�������Ƃ����s�s���z�̍\���ɂȂ��Ă��邪�A���{�ł̓J�~�T�}�͓s�s�̊O�ɂ���̂��Ƃ����B�����(��_���Ƃ���)�����̐_�ƁA�X���甭�������S���̐_�X�Ƃ̈Ⴂ�����邪�A�傫�ȈႢ�́A�Ñ���{�ł̓J�~�T�}��(�s�s�ɂȂ�)�y�n������Ă������Ƃɂ���̂��Ƃ����B�@
���Ă̓��{�͂��킵���R�т���ŁA�×����ďo�����킸��7���̉��ϕ��삪���������n�Ƃ��āA�ƂĂ��Z�߂��Ԃɂ͂Ȃ������B���������Ꮌ�n���Z�߂��Ԃɂ��Ă������̂��J�~�T�}�������Ƃ����̂ł���B�L�I���͂��ߊe�n�̕��y�L��_�Ђ̗R���ɂ́A�_�X�̍�����̕����`��������������B��������������̂��ƁA�J�~�T�}�͂��ׂĎp���B���Ă��܂��B�����Ȃ��J�~�Ɛl�����Ԃ̂��ޏ��ł������B鰎j�`�l�`�ɂ���悤�ɁA�ޏ���ʂ��ď��߂č����`������邱�ƂɂȂ�ƌ��� �B�@
���{�̓s�s�ɂ͂Ȃ����c�_�����l���Ȃ��B���̑�����l�͓s�s�̊O�ɒ���̐X���R�Ƃ��đ�Ɏ���Ă����B���l�̂Ȃ��s�s�͊ȒP�ɖłԁB���鋞�ȑO�̓s�s�͂��ꂢ�ɏ��������āA���ł͂��̏ꏊ����킩��Ȃ��B�X����������ɕ������@���i�o���A���x�͖�O�s�Ƃ��ē��키���ƂɂȂ����B(���l�@�Ё��y�n�̐_�@�l�����n�̐_)���c�_�k���n���������ƁA�_�Ɛl�͂��̋��E����݂��A�l�͐_���h���Ղ��Ă������A���c���g�傳���ɂ��������Ď���ɐ_���Ղ邱�Ƃ����낻���ɂȂ�A�`�[������Ă����B���ɍ��̓��{�̓s�s���������Ȃ̂́A�ꏊ�Ƃ��Ă����_�I�Ȉ˂��Ƃ��Ă��J�~�������Ă��܂������߂��낤�B�@
��_�^�C�K�[�X�ƃg�������̊W�ɁA�V�����_�Ɛl�������ĐV�����s�s�̎p������B�J�~�Ɍw�ł�Q���͍�_�Ƃ������S�ł����āA�����Ă���ɂ����́u��Ӊ��B�v�̃��[�g�i�q�ł͂Ȃ��B�ł���ΌՂ̐_�̋x������n�����Z�b�R�ɂق��Ȃ�Ȃ��B��_�^�C�K�[�X������������̂́A���܂������{�͐X�����ĎR�����ēs�s�ɃJ�~���Ղ邱�Ƃł͂Ȃ����B�@
 �@
�@���_�Ȃ����j�b�|��
�ʏ��ł͒���̐X�Ɠ��{�̐_�X�ւ̋����v��̔O�������Ă��邪�A���̐��̌��z��ʂ��āA�����̏@�����z�ƊX����̎v�z�ɂ��s�����@�̃��X�����Ă���B�^�C�g���́A�L���X�g����C�X�����̓s�s���A���ׂĎ��@�𒆐S�Ɍ��Ă��Ă���̂ɔ����āA��������ɂ��Ȃ��@���s�݂̓��{�̒��̂�����ɋ^���悵�Ă���悤�ɂ�������B�@
������̕������l�͕����̐��ƂŁA�ނ����҂ɐ��E�̏@���ɂ��Đu�˂�`���Ƃ��Ă���̂����A���҂̔����ʼn��[���l�@�͂ƁA�킩��₷���\���͂ɂ́A�ʏ�����̂��������@���Ɋւ���m����F�����A�����ɐł��������Ȃ��̂����������v���m�炳��A�������ɔ��Ȃ����Q����ق��Ȃ��B�@
�薼�ɂ�������炸�A8�͂̒���5�͂́u�A�����J�̎�҂��푈�ɍs�����R�v�Ƃ��A�u�C�M���X�l�̉Ƃ͂Ȃ��邩�v�u�X�p�Q�b�e�B�̂����ɂȂ����[�O�i�[���v�u�}�z���b�g�͂Ȃ��R�[���������������v�ȂǁA���������ς��������Ő��E�̐����ρE�@���ρE�ϗ��ςȂǂ���A����������{�́A���{�l�̐����ρE�@���ρE�ϗ��ςƑΔ䂵�Ă݂���̂��B�@
���{�ɐ_�X�����Ȃ��Ȃ����̂́A(�ے��I�ȕ\������)�哌���푈�̔s��ɂ���āA����Ή��Ă̐_�ɖłڂ��ꂽ����ł���B�@
�{�����{�̐_�X�́A������}�j�C�Y��(�����R���E���l�ԋ�)��A��~�Y��(���싳)�̒i�K�ł����āA����ɏ@���Ƃ�������(��؋�Ƃ���)�����I�N�w�ł��镧�����d�Ȃ������̂����A�����͑����̏@�h�ɕ�����ċ��`�������܂��ɂȂ�A����ɐ����I�Ȍ������v�ɑ��A�m�͑����ƕs���ȔO���̒��ɓ�������ł��܂��B�@
��㖳�䖲���̕����̒��ŁAGHQ��R�~���e�����̖d���ɂ܂�܂ƛƂ��āA���{�l���_�X�������Ă����̂ɂ������鎞�Ԃ�K�v�Ƃ��Ȃ������̂ł���B�����������Ƃ�����A�Ȃ����{�l���C�O�ŗ�������Ȃ����Ƃ������R���͂�����ƕ����яオ���Ă���B���҂͍Ō�Ɂu�_�l�����Ȃ��Ȃ�n�낤�ł͂Ȃ����v�Ƃ����B�����̏@�����E���{���ł͓����ʂ��̂��A���̖{�͑����^���Ă����̂��B�@
 �@
�@���ω��̌��ɕ�܂��
����ȏ��]�̑O�ɁA���c�@�P�t�̏Љ�����ǂ݂������������B�@
���@
�V�����{���o�܂����B���x�́A�����@�̑匴�O���T��Ƃ̑Βk�ł��B���傳�܂͍��N���\���ł����A���̐��U��M��Ŋт��ꂽ���ł��B�@
�����Ă��̐l�Ԃɂ́A�M�͂ǂ����Ƃ炦�ǂ��낪�Ȃ��āA�B���Ȃ��̂ɗ��܂��Ă��܂����A���傳�܂ɂƂ��ẮA�M�͐����S�����ł��A�m���Ɏ��݂�����̂ł��B�@
��̖����@���āA�����܂ł̊m�M�ɂ�����̂́A�����̂��Ƃł͂���܂���B���傳�܂́A�����̂悤�ɉ��ŏ����Ȑl�ł����A���Ⴂ�Ƃ��́A���Ɍ������C�s���d�˂Ă����܂����B�������܂ŋ���ȋ����S�������Ƃ́A�j�m�ɂ����������Ƃł��B�@
�l�Ԃɂ́A���ꂼ��̉^���������āA�Ƃ��ɉߍ��ȏɒu����邱�Ƃ�����܂��B�����œ���邩�A�����邩�́A����d�̍��ł��B���̎���d�̍������߂�̂́A��������̐M�S�ł��B�@
�M�S�Ƃ����̂́A�Ȃɂ������ނ����ɐM���邱�Ƃł͂Ȃ��A�܂������Ƃ������݂̏�������ߐ[�������o���邱�Ƃ���n�܂�܂��B�łȂ���A�ڂɂ͌����Ȃ�����Ǒ傢�Ȃ���̂ɓ���������Ƃ������������A�g�ɂ��Ȃ��̂ł��B�@
�ߑ㕶���́A�M����̈ˑ��S�����߂���̂Ƃ��āA�a�O���Ă��܂����B�������ɂ���������ʂ�����̂ł����A�{���̐M�͐l�Ԃ̎����𑣂��܂��B�@
�P�H�̓c�ɂɏZ�ޘV��̎p�ɁA���������̊�]��������̂́A���̑ޔp�������̒��ɁA�ߑ�l�������߂�ׂ��l�Ԃ̌��_������������Ă��邩��ł��B�@
���@
�������c�t�́A���C���~�ȘV��̌��t�̈����A�܂�Ŏ蒆�̎�ʂ������ނ悤�ɁA�₳�����������Ɏw�������Ă����B�@
�����e���r�Řb����Ă�ł����\�ҁE�쎋�ɂ��ĘV��́A�����͂��̔\�͂͂Ȃ��Ɣے肵�Ă��邪�A������Ӗ��ł����������ۂ�^��������ے肷��l�����Ɏ���āA�Ȃ�̂��߂炢���Ȃ��V����I���ۂ⌋�ʂ��������R�ɔ�������ƁA�f���ɐM�����邩��s�v�c�ł���B�@
���Ȃ݂ɕ]�҂́A������S�쌻�ۂ�t�e�n���Ȃǂɑ��āA�ے���m������Ȃ�����j���[�g�����ȃX�^���X�ł���B�����Ȃ�����ے肷��Ƃ����̂́A���Č����Ȃ������ۂ�E�C���X��ے肷��̂Ɠ���������ɒʂ��邵�A�܂��܂��s���S�ȉȊw�\������������������炾�B�@
�Ƃ͌����A����m�F���Ȃ��A�o���Ȃ����Ƃᔻ�ŐM�����ނ��Ƃ��A���������v�����ے肵�Ȃ��B�@
���ɁA���{�̃e���r�ɋ��ʂ��鋻���{�ʂł̎��g�݂���́A�ǂ����Ă��ŏ�����ӎU�L����@������Ȃ����Ƃ��m���ŁA���̂��Ƃ������Ȗڂ�܂点�Ă���B�@
�Ƃ��낪�A�p�m�̐l���c�t�Ɩ��C�̐l�匴�V��̊ԂŌ��킳���A���₩�ȃI�[���ɕ�܂ꂽ��b�̒�����A���X�Ɣ�������s�v�c�Ȍ��ۂ��A�[���M�S�ɕ����ꂽ�V��̌����甭������Ƃ��A�u���̐l�̌������ƂȂ�{���Ȃ̂��v�Ƃ������R�ɑz���Ă��܂��̂��B�@
�V��̗c���̍��p�ꂩ����M��ɐs�����������s�҂̐��X���A�����Ȃ����Ȃ��u���������ɂ���������[�����v���Ƃ������R�Ɍ������l�����邾�낤���B�@
�ܘ_���������b���I�݂Ɉ����o�������c�t�̕��X�Ȃ�ʗ͂ƁA����ȏ�匴�V��ɑ��鑸�h�̔O���a�����ė͂�����B�@
���c�t�́A�V���]����(�g���X�g�C��)���u�C�����̔n���v�̐M�S�Ɠ������̂Ƃ��Ă���̂����A���̗��ɉߓx�̉Ȋw���\��`��绂����A�E���Ƃ�������ɑ��āA���P�����A���������A�`�[�����Ģ�����@���v�ɑ����A���͋ɂ܂�Ȃ����{�����ɑ���ɗ�Ȕᔻ���ǂݎ���̂��B�@




