�̐���Տ�l�`�E�w�Ȑ��莛�E�Ǝ�q�w�z���w�E�b�M��(�e�a�̍�)�@
�،��̎v�z�E���@�ƓV�c�E�����̖����E���l�S���E�����C�E��u�̔Y���E���͂���̂����@
�B�҂̌n���E�_�Ђ��ĉ��E��Ղ��ς��E�_�ƕ��̂������E�̐��E�E�����Ǝ��E�_���@
�S�w�E�ω��l�Ɓu�ØI�v�E�@�h�ᔻ�����E�⒮�u�߉ށv�E�l�������� �ƃX�b�^�j�p�[�^�@
��(��)���������E��͔����E��͔����}�E�����̚g�������E��Î��E�z���ƌ���E�Ȃ����{�ŕ��y�����̂��E�Ȃ����������ʂ���̂��E�܊ς̘��E�K���ł����E���{�l�_�ƕ����E�іV��Ɩ��D�l�E���n�ŋ����W�@�E��������ł͂����Ȃ��E�E�E �@
���@�E��Ձ@���̐��E
�@�@�@

 �@
�@���u�@��o�i�_���}�p�_�j�v
���́A��Տ�l�̐������E���C�t�X�^�C��������Â��錾�t������������Ȃ��Ƃ������Ƃ��A��������悭�l���܂��B�����������Ă݂܂��ƁA �@
��ڂ́A�V�s�A����������ƁA�ꏊ�s�Z�Ƃ������Ƃł��B��Տ�l�͗V�s�̗��ɏo�Č�A���ʂ܂ŗ��ɕ�炵�A��̏��ɒ�Z����Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B�����������C�t�X�^�C�����̂����A�Ƃ��������т��������҂́A���{�ł͔��ɒ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@
��ڂ́A����ƊW���܂����A�̂Ă�Ƃ������ƁA���Ȃ킿�A�����L�Ƃ������Ƃł��B���ɖ���������X�ł�������̕������ĂȂ��͓̂��R�ł����A�����ł͂Ȃ��āA��Տ�l�͐������Ƃ��Ė����L�ɓO�����ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B�̂Ă邱�ƂɓO����A���R�A���ׂĂ̂��Ƃ��̂āA�䂪�g�����̂Ă邱�ƂɂȂ�܂��B�ՏI���߂Â����ۂɈ�Տ�l�́A�u�r�͖�Ɏ̂Ăďb�Ɏ{���ׂ��v�Ɩ����Ă��܂����A����͐g���̂Ă邱�ƂɓO���Đ�������Տ�l�ɂ��ď��߂Č����錾�t�ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B �@
�O�ڂ́A����Ȃ��Ƃ������ƁA�܂�͐g�ƌ��t�ƐS�̔�\�͂Ƃ������Ƃł��B��Տ�l�̍ďo�Ƃ̓��@�͂͂����肵�����Ƃ͂킩���Ă��܂��A�����炭�ꑰ���̉����ɂ�鑈��������邽�߂Ƃ������Ƃ��������Ǝv���܂��B���G��ǂ�ł��܂��ƁA�V�s�̒��ŁA����U�肩�����Ĕ����Ă��鑊��ɑ��āA�B�R�Ƃ�����\�͂̑ԓx�Őڂ����Տ�l�̎p��A���{�̐������̕��m�����ɑ��Ĉ�������������Ȃ��ۍ��̈�Տ�l�Ǝ��O�̎p�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@
���̑��A������z���̃X�^�C���Ƃ����_���狓���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�������A��y�A�O���A���Z�A�x��O�����ł��傤���A�����́A���ɁA��Տ�l�̃��C�t�X�^�C���Ƃ������ƂɌ���܂��āA���̑傫�ȓ����Ƃ������ׂ��V�s�Ɩ����L�A�����Ĕ�\�͂Ƃ������ƂɊւ��āA���̕����ɂ����郋�[�c�����߂鎎�݂��������Ǝv���܂��B �@
�ƌ����܂��Ă��A���̃��[�c�{���́A����قǓ�����Ƃł͂���܂���B�Ȃ��Ȃ�A ���̎O�A���Ȃ킿�ꏊ�s�Z�A�����L�A��\�͂́A�{���̕������߂������������̂��̂�����ł��B�{���̕����Ƃ́A��͂肨�߉ޗl�i�ߑ��j�A���Ȃ킿�S�[�^�}�E�u�b�_�̋����A�����Ă���������p�����n�����̋����ł��B �@
���ߑ������ƈ�Տ�l �@
���n���T�̗l�X�Ȋp�x����̎��ؓI�����Ƃ����A����̌��n���������̐��ʂɂł��邾����Â��āA�V�����ߑ����A���n�����������߂���̂ł����B�����ł���ꂽ�ߑ������̎p�́A�]���̗l�X�Ȍo�T�̋L�q�����̑I������č��グ���Ă������`�i�ߑ��̓`�L�j�̋�������̂Ƃ́A�S�������������̂ł����B�������d�v�Ȃ��̂��Љ �܂��B �@
������܂ŕ��`���`���Ă����悤�ȁA�ߑ��̐���������ł܂ł�40�N�̊Ԃ̐��@�ƕz���ɂ���āA���Ȃ�傫�ȕ������c���ł�������A�e�n�ɐ��ɂ���i����A�ߑ����e���ɂŐ����������c��ł����Ƃ����̂́A�ǂ����㐢�ɍ��ꂽ�����̂Ȃ����̂ŁA���ۂ́A�ߐ�͐��U�A�ꍹ��i��o�������n�o�ƏC�s�ҁj�Ƃ��āA��H���ꏊ�s�Z�̗V�s�����𑗂�A���������̒�q�����ɁA���̌`�ŋ�����������݂̂ł������B �@
�����������āA�ߑ��̓��Ō�A�ߑ���40�N�̖c��Ȑ��@���A�������̕���q�������A ��K�͂ɏW�����āA���W�����Ƃ����̂����肦���A���ۂɂ́A�����̒���q�E����q�������V�s���A�ߑ��ɂ���Č��ꂽ��r�I�����̎��̌`�̋������o�T�Ƃ��ĈÏ����Č��p���A�����������t�ɏK���āA���̌`�ŐV���ɏ@���̌�������Ă������B �@
�������Ō��p���ꂽ���̌`�̋������A�u�X�b�^�E�j�o�[�^�v��u�G���܌o�E�L���i�v�̉C���o�T�����A�����āu�@��o�v�Ɏc����Ă���A�ꎞ��������������U���o�T���Â��āA�C���o�T�͌�̕������l�ɂ���ĐV���ɕt�������ꂽ���̂��Ƃ����̂͑S���t�ŁA�C���o�T�����������o�T�̌����̌`�Ԃł����� �B�@
������ɂƂ��Ȃ��A�]���A�ߑ��ɂ���Ē��ډ����ꂽ���̂Ƃ���Ă������ɂ���Đ������ꂽ���������A���Ȃ킿�Z���E�\�N�E�l���E�������Ȃǂ́A�A�V���[�J���̍����������͂��߁A���̌㉽������������č��グ��ꂽ���̂ŁA�ߑ��╧��q�������������̂͂����̌����I�Ȍ`�Ԃɉ߂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B �@
�����������m���Ă��镧�`���A���S�N����ɂł��������Ă���A���j�I�����Ƃ̊W�͕s���ł���B �@
�Ƃ܂��A������Ƃ������������ł��܂��܂������A�Ȃ�����Ȗʓ|���������Ƃ� �]���Ă��邩�ƌ����܂��ƁA����͂������낢�Ɗ�����l�ɂ͂ƂĂ��������낢�ɂ߂ďd�v�Ȃ��Ƃ�����ł��B���͂����m�����Ƃ��A10�N�����������������n�����Ɋւ���s�����̖����A����ɂ���Ĉ�C�ɐ���������Ƃ��ł����Ɗ������قǂł����B ���̂悤�ɂ��Ă���ƁA�ŏ��̈�Տ�l�Ƃ̃��C�t�X�^�C���ł̑傫�ȋ��ʓ_�A���Ȃ킿�ߑ��̐��U�т����V�s�������A�m�邱�Ƃ��ł��܂��B����́A�ߑ��̎��ۂ̌��t�ƔF�߂��鎟�̉C���o�T�ɂ���Ă��������m�邱�Ƃ��ł��܂��B �@
�������ȏo�Ǝ҂́A�[���v�����Ȃ���A�Ӌ��̒n��V�s����Ƃ��ɁA���A��A�ցA�l�ԂƂ̐ڐG�A�l���b�A�Ƃ����܂̂��̂��A����Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@
���m�b����ɑ��d���A�P�����ŁA�����̊댯�����ł����Ȃ����B�ƒn�Ŗ���Ƃ��ɂ͕s�����ɑł������A���̎l�̎v���ς��ɑł������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@
���U��C�s�҂Ƃ��Ă̎ߑ��̗V�s�����́A�m��悵���Ȃ����Ƃł��B������A���̈�v�́A�V�˂݂̂��Ȃ�����s�v�c�Ȉ�v�Ƃ����ׂ��ł��傤�B �@
�����Ƃ��A�C���h�ɂ�����V�s�����́A�����Ďߑ��̃I���W�i���ł͂Ȃ��A�E�p�j�V�� �c�h�̓`���������p���o�������������ŔӔN�ɉƂƉƑ����̂ĂėV�s�ɏo�邱�Ƃ𗝑z�Ƃ������ƁA�����āA��o�������n�̋�s�҂����̏C�s��������H�ƗV�s�ɂ���ĉc�܂�Ă������Ƃ́A�Y��Ă͂Ȃ�܂���B�����̊J�c�ł���ߑ����A�����̓`���̒�����o�ꂵ�Ă����킯�ł��B �����āA�u�̂Ă�v�����L�Ƃ������Ƃɂ��Ă��A�ߑ��̌��ꂽ�������͂�����Ǝc����Ă��܂��B �@
���l�X�́A�u�����̂��́v�Ƃ������Ƃɂ���ĒQ���߂���ł���B�l�����L������̂́A��ɕς��Ȃ����̂ł͂Ȃ�����ł���B���ꂱ���A�����Ƃ����{���������̂��ƌ��ɂ߂āA�Ƃ̐����ɗ��܂��Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
���l���A�u���ꂱ�������̂��̂��v�ƍl������̂��A���ʂƂ��ɂ́A�̂Ăčs���̂ł���B���̂悤�ɒm���āA�m�b����l�́A�����̂��̂ɂ��Ă��������Ƃ����C�����ɑ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
�������̂��̂Ɏ��������ߑ����邩��A�i�������Ƃ��́j�h����߂��݁A���邢�́i��ɓ��ꂽ�Ƃ��́j��т��A�̂Ă��Ȃ��B����䂦�A���ق̐��҂����́A���L������̂��̂ċ����āA�����݂̂����߂�C�s�̐����ɓ����čs�����̂ł���B�@
�����āA����Ȃ����ƁA��\�͂ɂ��Ă��A�ߑ��͎��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B �@
����̏o�Ƃ̓��@�ɂ��āA �@
������Ƃ��Ė\�͂��ӂ邤�悤�Ȃ��Ƃ��痣�ꂽ���Ƃ����J���̎v�����������̂��B�����Ă���l�X�����Ȃ����B�����ǂ̂悤�ɉ}�����ꂽ���A���̐S����낤�B�@
�Ɛ錾���A�����ɂƂ��āA����Ȃ����ƁA��\�́A�s�E���̈�肢�������ɋ������������A�������o���Ă��܂��B����䂦�A�ߑ��́A��q�����ɑ��Ă��A����Ȃ����ƁA�_���ɉ����Ȃ����Ƃ�����Ă��܂��B �@
����u�i�o�Ƃ̒�q�j�́A�̂����ɂӂ�܂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B��ӂ∫�ӂ̂��錾�t������Ă͂Ȃ�Ȃ��B������������ȑԓx���K���Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�G����_���킹�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
�����t�ɂ���Ď��ӂ��ꂽ�Ƃ��́A���������ߒ����D�@�Ƃ��āA�傢�Ɋ�тȂ����B�@
�����h�̍��傽���₻�̑��̗l�X�Ȑl�X���������ĂĂ��邽������̌��t���āA���𗧂āA�r�X�����G���錾�t��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�D�ꂽ�l�́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��A�����ɑΗ�������̂Ƃ́A�Ƃ炦�Ȃ�����ł���B�@
���{�炸�A���ꂸ�A�����ɂ����A���悭�悷�邱�Ƃ��Ȃ��B���₩�ɐ��@�����āA�������������Ă���B���̂悤�Ȑl�����A�T�܂�����钾�ق̐��҂ł���B�@
�ǂ��ł��傤���B�ߑ��̋����͂��炵���ł��ˁB�����āA�������Ďߑ��̎��ۂ̌��t����ׂĂ݂܂��ƁA�|�Տ�l�̐������Ƃ̋��ʓ_���܂��܂����炩�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B �@
���u�@��o�v�ɂ��� �@
���̂悤�ɗD�ꂽ���@���c�����ߑ����₪�ĔN���o�ĖS���Ȃ�A����q���������V�ƂȂ��āA�������c�̖G��̂悤�Ȃ��̂��ł��Ă���̂͑���q�A�Б���q�̎���ł������A�Ƃ� �����Ƃ��ŋ߂̕����w�҂ɂ���Ď咣����Ă��܂��B ���̍��ɂȂ�ƁA�݉Ƃ̕����M�҂�����I�ɑ����Ȃ�A���C���h�e�n�̓s�s�̋ߍx�ɋ_�����ɂ̂悤�ȏC�s�������i����͂��߂��悤�ł��B�����k�����́A�o�ƁE�݉Ƃ̌��i�ȋ�ʂȂ��A�V���E�����̓��ɂ́A���̂悤�Ȑ��ɂɏW�܂��Ă��āA�����I�ȉ������āA���@������A�T��C�s�ɗ�肵���悤�ł��B�����āA���̍��ɍ���͂��߂��̂��u�@��o�v�ł��B �@
�u�@��o�v�i�_���}�p�_�E�^���̌��t�E�����̎��W�j�́A���̂悤�ȍŏ����̕������c�ŁA�����k���������ɘN�����邽�߂ɍ���n�߁A�N�����o��Ƌ��Ɏ���ɑ傫���Ȃ�A ���鎞�ɐ���������A�����Ɏ���܂ŏ�ɏd���Ă����ł��|�s�����[�Ȍ��n�����o�T�ł��B�u�@��o�v�̌����邱�Ƃ̂ł���p�́A�����I�ȋL�q�͑S���Ȃ��āA �����k���w�сA�Ï����A��ɍl���A�̂ɖ����Ă����ׂ��������A423�̒Z�����̌`�Ō���A�����26�̏͂ɕ����Ĕz�Ă��܂��B �@
���ŌÑw�̖@�� / �o�������̏� �@
����������Ő��炵�Ă��邩��Ƃ����āA���f��������������Ƃ����āA���܂ꂪ����������Ƃ����āA�o�������ł���킯�ł͂Ȃ��B�^���ł���A�����ɐ�����l�A���̂悤�Ȑl�����A�K����l�ł���A�o�������ł���B�@
����������̂ł���A�������̂ł���A�����Ƃ���������̂ɏ�������āA�E�����Ƃ��Ȃ��A�E�����邱�Ƃ��Ȃ��A���̂悤�Ȑl�����A���̓o�������ƌĂԁB�@
�������ݍ����l�X�̒��ɂ����āA�����ݍ������ƂȂ��A����Ƃ��Ė\�͂��ӂ邤�l�X�̒��ɂ����āA���₩�ł���A���ł��䂪���̂Ƃ��Ď�荞�����Ƃ���l�X�̒��ɂ����āA������荞�܂Ȃ��A���̂悤�Ȑl�����A���̓o�������ƌĂԁB�@
�����̐��ɂ����āA�������̂ł��낤�ƒZ�����̂ł��낤�ƁA���������̂ł��낤�Ƒ傫�����̂ł��낤�ƁA�P�����̂ł��낤�ƈ������̂ł��낤�ƁA�^�����Ȃ����̂��䂪���̂ɂ��Ȃ��A���̂悤�Ȑl�����A���̓o�������ƌĂԁB�@
���ߋ��ɂ��A�����ɂ��A���݂ɂ��A���珊�L���邱�ƂȂ��A���ꕨ�ŁA������荞�܂Ȃ��A���̂悤�Ȑl�����A���̓o�������ƌĂԁB�@
�����̐��̗~����U��̂āA�ꏊ�s�Z�ɗV�s�̐��������A�~����ł��s�����A���݂������邱�Ƃ�ł��s�����Ă���A���̂悤�Ȑl�����A���̓o�������ƌĂԁB�@
���i������o�Ȃ���j�@�̗t�ɐ����t���ĂȂ��悤�ɁA���̐�ɊH�q�����~�܂�Ȃ��悤�ɁA�~�]�ɉ���Ȃ��A���̂悤�Ȑl�����A���̓o�������ƌĂԁB�@
�����y����s�����Ɏ̂āA�ϔY�Ȃ��A�������������A���E�̒N�����D�ꂽ�E�ҁA���̂悤�Ȑl�����A���̓o�������ƌĂԁB�@
���݂́u�@��o�v�ł́u�o�������̏́v�͍Ō�ɒu����A�S����41�̎���ł����āA ����ł����A����ł����Ƃ����d���ŁA�ǂ������l���^�̃o��������������Ă��܂����A �ŏ��͂����ŏЉ�����炢�̗ʂ��������̂��A����ɕt��������Ă����A�ŏI�I�ɑ傫���Ȃ������̂Ǝv���܂��B�Ō�ɒu���ꂽ�̂͏d�v����������ł��傤���B�Ō�ɒu���ꂽ�����������Ƃ��Â����������Ƃ������Ƃ́A���̌��n�o�T�ɂ������邱�Ƃł��B �@
�����ŁA�Ȃ������k�Ȃ̂Ƀo�������̂��������ɂ���̂����A�����l���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B �@
�o�������́A�C���h�̃J�[�X�g���x�ōŏ�ʂɈʒu����g���ŁA�o���������̐_���K�����Ӗ����܂��B�g���Ȃ̂ŁA�o�������͐��P�ł��B��X�e����q�ւƁA�_���E�͈����p����Ă����܂��B�������āA�@���I���ЂƓ`������������Ă����Ƃ��l�����܂��B �@
�������Ȃ���A��o�������n�̏o�ƏW�c�ł���ŏ����������c�̐l�����ɂƂ��ẮA�� ��͕ςȂ��Ƃł��B�����k�����́A�@���҂Ƃ��Đ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ��āA���̊K���ɐ��܂�Ȃ���A����̑I���ŏ@���҂ɂȂ����l����������ł��B����Y�݁A���f���A�w�͂��A���������Ă����l�����ɂƂ��ẮA���������ƕ��ɐ��܂ꂽ�Ƃ������R�����ŁA�傫�ȔY�݂��Ȃ��A���f���Ȃ��A���ɍ˔\�����߂�ꂸ�ɁA�\�ߕ~���ꂽ���[���ɏ�邾���ŏ@���ƂɂȂ��Ă����l����������Ƃ������Ƃ́A�F�߂��������Ƃ������ł��傤�B����́A�� ���@���̑��̉����ɂ��Ȃ肦�܂��B �@
���������āA�����͂����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��咣����Ƌ��ɁA�^�̏@���҂��ǂ�����˂Ȃ�Ȃ�������������Ɗm�F���Ă����K�v�����������̂Ǝv���܂��B�u�o�������ƌĂԁv�̏����u�^�̏@���҂ƌĂԁv�|�Ɠǂ݂�����ƁA����������̓��{�l�ɂ��������藈�镶�ɂȂ�悤�Ɏv���܂��B �@
����ɂ��Ă��A���̌����u�@��o�v�́u�o�������̏́v�̓��e�����܂��ƁA�ŏ����������c�ɑ��������E��O����̕���q�����������Ɏߑ��̎����ꂽ�������Ƌ����ɒ����ł��낤�Ƃ��������f���܂��B�u�@��o�v�̍ŌÑw�o�T�́A���ڎߑ��ɂ���Đ����ꂽ���̂ł͂���܂��A�����̕���q�������ߑ��̋������ǂ������A�����k������̂�����Ă����ׂ���ȋ����Ƃ��Ăǂ̂悤�ɕێ����A���̐���ւƓ`���Ă������Ƃ������������Ă���Ƃ����Ӗ��ŁA�ɂ߂ďd�v�ł��B �@
�m���ɁA���̎����A�݉ƐM�҂�����I�ɑ��������ƂƐ��ɂ���������͂��߂����Ƃɂ���āA�ߑ��Ⓖ��q�����̍��قǁA�ꏊ�s�Z�̗V�s�����͋�������܂��A����ł������Ƃ��Ă͂����Ǝc���Ă��܂����A�����L�Ɣ�\�͂�������ł��邱�Ƃ́A�ߑ��������̂܂܂ł��B���̂悤�ɂ��āA����ȍ~�A�����k�����́A���������������A�ߑ��̐������Ƌ����������p�����Ƃ��A���オ�ς�肷���āA�\�ʏ�͂ǂꂪ�ߑ����̐l�̂��̂����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��A����͗l�X�Ɍ`��ς��Ȃ���A�Ȃƈ����p����A��Տ�l�̎���ɂ������Ă������A�����������Ă���ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@
���@
�����ɂ����Ȃ鎞���A���݂ɑ��č��݂������Ă�����݂̐Â܂邱�Ƃ͂Ȃ��B���E�݂������Ă��Ȃ��Ȃ�ΐÂ܂�B����͌Â�����̋����ł���B�@
�����ׂĂ̂��̂͏�i�\�́j�ɋ����A���ׂĂ̂��͎̂��������B�䂪�g�Ɉ�����ׂāA�E���Ă͂Ȃ�Ȃ��A�E�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@
�������Ȑl������������ł���ƒm��Ȃ�A�ނ͂���ɂ���Ă��łɌ��҂ł���B�����������Ȑl������������Ǝv���Ȃ�A�ނ͂܂����������҂��ƌ�����B�@
�����̐l�̉߂������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̐l�ׂ̈������ƁE�ׂ��Ȃ��������Ƃ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ׂ̈������ƁE�ׂ��Ȃ��������Ƃ��������Ȃ����B�@
�������������ׂ��A����������A�����������ׂ��Ȃ���A���������܂�B������ �����Ȃ������ꂼ�ꎩ���̂��Ƃł���B�l�͑��̐l�𐴂߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@
 �@
�@���Ò��ƕS�������̑��M
�������A�Ȃ����ЂɁu���܂���v�Ƃ��u����v�u���v�Ɩn�������āA������t���ɓ\��̂��낤���B���̓_�͋^��Ƃ��Ďc��B������̗R��杂ɁA���̃q���g������̂��Ǝv���ď������ׂĂ݂����A�K�����������ł͂Ȃ��悤���B������Œa�����ɊÒ���������s�ׂ̗R���́A�u�����V�玫�T�v�ɂ��ƁA����v�l�������r�j�[���Őg������������A�Y�C���Â��Ė��J���̉��ŁA���ꉺ�������Ԃ̎}���Ƃ낤�Ƃ������A�E�e������炩�ɑ��q��a�����ꂽ�B�u���j�o�v���ɂ��̎��̗l�q���L����Ă���A�u���̎���F�E�e��萶���A���R�Ƃ��Đg��@�ɏZ�݂��������B�n�ɑ��čs�����Ǝ����A���������g���Ė�����P�����A��ꓖ�ɓV��V�����~�x���ēV�l���ƈׂ�A�����̋��f���A�O�E�ɏ�Ȃ��A��̏O�����Ė�����Ȃ炵�ނׂ��ƁB�V��ߞ����R�Ƃ��ė������A�G�����������ĕ�F��������A�㗳��ɍ݂�č����������A���߂�������B�������(����)�Đg�S����Ȃ�v�Ƃ���B������͎߉ނ̒a�����j�����߂̂��̂ł��邪�A��������荁����A���̐g�̂���������Ƃ������Ƃ���A������(�ԍՂ�)�ł͒a�����̑��ɊÒ����������Ƃ����̂ł���B�������A�u���j�o�v�̋L�q�ł́A�������̂͊Ò��ł͂Ȃ��A�����ƂȂ��Ă���B���̓_�ɂ��Ă��u�����V�玫�T�v�ɂ��ƁA�Ò���p����悤�ɂȂ����͍̂]�ˎ��ォ�炾�낤�Ƃ��Ă���A����ȑO�ɂ͌ܐF�������������ėp�����炵���B������18���I�O���̋��a�N�ԍ��́u���Ώ\��v��1�Ɋ�����ɒ���p���Ă��邱�Ƃ�A����5(1822)�N�����́u���Ԏ��߁v��2�Ɂu�܍��������T���悵�݂�����ǁA�]�˂ɂĂ͒������Ă��T����v�Ƃ����L�q�����p���Ă���A�]�ˎ���Ɏ���ɍ�������Ò��ֈڍs���Ă��������Ƃ�����������B �@
�ȏ�̊�����̗R������j����́A�Ò����{���p�����Ă����킯�ł͂Ȃ��������ƁA�����ĕS����֏����̂܂��Ȃ��ɂȂ���v�f�͌��o���Ȃ����Ƃ��킩��B�u���j�o�v�̋L�ڂ���b�Ƃ��čl����̂ł���A�u�����v�Ǝ��Ђɖn�����Ē��������Ƃ��ׂ��Ƃ�����A�nj��ł���ǂ̖���������A���Ђɂ́u���v�������́u�Ò��v�������A�������͕������ŏ������ƂɂȂ��Ă���B �@
�܂�A���̑��M�͍]�ˎ���ȍ~�ɐ����������̂ƍl���邱�Ƃ��ł��A���Ƃ��Ƃ̊�����Ƃ��������V�炻�̂��̂���h�������K���ł͂Ȃ��悤�ł���B �@
�����ŁA���̋^��𐄑�����q���g�ƂȂ�̂��A����Ò��́u���ڑҁv�Ƃ̊W�ł���B���Q�ł����\�s��쒬�ȂǓ�\�R�ԕ��ł́u�����v�ƌĂ��ғ�������A�����ŕH�◷�l�ɒ���Ò��Ȃǂ̐ڑ҂�����Ƃ����K��������B����͒n��̊O���痈�K����҂����҂��邽�߂ɍs����s�ׂł��邪�A�u���܂���v�Ə��������Ђ��t���ɓ\��s�ׂ́A���҂̋t�̈Ӗ��ŁA�܂�r���������Ƃ����S�ӂ���A�O����Z�����Ăق����Ȃ�����(�Ƃł͕S����ւȂ�)�ւ̑�Ƃ��ċt���ɓ\��̂ł͂Ȃ����낤���B�u�Ò��v=���ҁA�u�Ò��v���t���ɂ���=�r���Ƃ������Ƃł���B�������Ò����Ƃ̎��͂ɎT�����Ƃ�A�ᒠ�ɂӂ肩����s�ׂ́A�����ɊÒ��̎��͂�M���Ă̂��Ƃł��낤�B �@
�Ò��̎��͂Ɋւ��鑭�M�ɂ��ẮA���ǁA�]�ˎ���ȍ~�̊�����ł̊Ò��̎g�p����b�Ƃ��āA�����ɖ��Ԃ̐S�ӂ������Ēa�����������Ƃ�����B�Ƃ͂������̂́A�n�����āu�t���v���ē\��Ƃ����s�ׂ��A����ꂽ�n��̂��̂ł͂Ȃ��A���Q���݂̂Ȃ炸�A�S���e�n�ɂ����ʂ��Č�����͉̂��̂ł��낤���B���̓_�����͕s�v�c�ł���B���̍s�ׂ��L���蒅�����߂��v���͉��Ȃ̂��B���R�����I�Ȃ̂��A����Ƃ����炩�̕����ɂł��Љ��āA��ʂ��čL���������̂Ȃ̂��A�悭�킩��Ȃ��B�����������_�͕����Ɩ���(���ԓ`��)�̌����̕��G���������Ă���B �@
 �@
�@�����N���̊���
���N���̊����`�Ԃ́A�\��x���N�ł��B�\��x���N�Ƃ́A����̗p��Ō����܂��ƁA�u�����ɂ���čs������B�s�ɂ���Ď�������B���ɂ���Ė��F������B���F�ɂ���ĘZ��������B�Z���ɂ���ĐI������B�I�ɂ���Ď���B��ɂ���Ĉ�������B���ɂ���Ď悪����B��ɂ���ėL������B�L�ɂ���Đ�������B���ɂ���ĘV���A�D�A�߁A��A�J�A�Y��������v�Ɛ����A�܂��u������ł��邱�Ƃɂ���čs�͖ł���B�s��ł��邱�Ƃɂ���Ď��͖ł���B����ł��邱�Ƃɂ���ĘV���A�D�A�߁A��A�J�A�Y�͖ł���v�Ɛ�����鋳���ł��B �@
�ŋ߂̕����w�҂̌����ɂ���āA���̏\��x���N�̋����́A�ߑ����S���Ȃ��Ă���S�N�ȏ�o���Ă��琬�������Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂��B�����������b���������̂́A���̂��悻�S�N�̊ԁA�ߑ��ɂ���Đ����ꂽ�������ǂ̂悤�ɕω����āA���N���ւƂȂ��Ă��������A�Ƃ������Ƃł��B �@
�����������������������|���Ă��A�܂����̂тĂ���悤�ɁA�����I�����~��(��)�����₳��Ȃ��Ȃ�A��Y�͂܂������Ă���B �@
��������ŌÂ̌��n�o�T���u�X�b�^�j�p�[�^�v��4�́u������́v�ł���A�����Ɏߑ��̒����̋������ۑ�����Ă��܂��B�ߑ�������̏o�Ƃƌ��ɂ��Č��̂��A��\�܌o�ł��B�ߑ��͎��̂悤�Ɍ��͂��߂܂��B �@
���_�������Ė\�͂��ӂ邤�悤�Ȃ��Ƃ��痣�ꂽ���Ƃ����J���̎v�����������̂��B�����Ă���l�X�����Ȃ����B�����ǂ̂悤�ɉ}�����ꂽ���A���̉}������S����낤�B �@
�ߑ������̒����}������o�Ƃ��u�����̂��\�͂ɑ��錙������ł��������Ƃ��A���ɑf���Ɍ���Ă��܂��B�ߑ��͏o�ƏC�s�҂ƂȂ�A�t�����߂ėl�X�ȏC�s�҂̖��@���܂������A�[���ł��鋳��������Ă����M���ł���t�ɏo����Ƃ͂ł��܂���ł����B �@
���C�s�҂�t�ƌĂ��l�������������A[�_����]�G�������Ă���̂����āA���͐�]�I�ɂȂ����B���̂Ƃ��A���́A[�l�X��]�S���̉���ɓ˂��h�����Ă�����{�̖���A���������̂ł���B �@
�����̖�ɂ���ē˂������āA�l�X�͂���������Ɍ������ė։Ă���B���̖������������������A���͂�։邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���B �@
���ꂪ�A�ߑ��̍��{�������ł����ړI�Ɍ�������t�ł��B�M���ł���t�ɏo����A�o�Ǝ҂̐��E�������_����R���̏C����ł��邱�ƂɁA�ߑ��͐[����]���܂��B�ǂ��ɍs���Ă����Z�̒n�͂Ȃ������̂ł��B�������A���̐�]���A��Ɍ��ƌĂ�邱�ƂɂȂ鍪�{���������ƁA�ߑ��͌��̂ł��B���ꂪ�A�l�X�����ꂩ��˂��������Ă���u��{�̖�v�̔����ł��B�����āA���̖�����l�X��։��Ă���(�Ǝv�킹�Ă���)�������ƌ��̂ł��B �@
�Ȃ��։��˂ɏo�Ă���̂��s�v�c�Ɏv���邩������܂��A�ߑ��̎���̃C���h�Љ�͗։�v�z��������������ł����B�։�Ƃ́A�ꌾ�Ō����A����ł�����ł��܂������ׂ����̂Ƃ��Đ��܂�Ă���Ƃ����i���̋�̘A���ł��B�m�b����l�����́A���̖�������։�Ǝv�z����E�o���āA���_�̎��R���l���������Ɗ�����̂ł��B�ߑ����A�l�X���։�̎v���ɂ������ꂵ��ł���̂����āA�J�����o�����ƌ���Ă��܂��B �@
�����Œ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A939�̌o���ł��B�u��{�̖�v���։�Ƃ����ꂵ�݂̌����ł���A���̖���Η։�͂Ȃ��ƌ���Ă��܂��B����́A�ŏ��ɂ������������N�̃p�^�[�����Ƃ��Ă��܂��B���������āA���́u��{�̖�v�̍��{���������A�ł������̉��N�����ƌ���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����������́u��{�̖�v�ɂ��Ďߑ��ɋ����Ă��炢�܂��傤�B �@
��[�։��]��^��[�̐���]��[���܂ł����̐��E�ɑ��݂������Ƃ��������I]��]�ł���A�Ǝ��͌����B�z�����ނ悤�Ȍ�����[�X�̏Փ��I]�~���ł���A[����ɕ�����ł���]���͗~������v�������ׂ�ꂽ�Ώە��ł���A�~�]�̓D�����z���Ă����͓̂���A�Ǝ��͌����B �@
�����Ō���Ă����]�Ƃ́A�l�X������ł�����ł��܂����܂ꂩ���Ǝv�킹�Ă��鍪�{�����ł�����A�l�ԑ��݂̍���ł������]��~�]�̍��{�ƂȂ��Ă����]�ł��B����́A���݂��Ă������A�����Ė����Ȃ�̂͂��₾�A�������������Ƃ�����]�ɂق��Ȃ�܂���B�ߑ��́A���́u��{�̖�v���鍪���I������]�̔����ɂ���āA���ׂĂ킩���Ă��܂����̂ł��B����ł́A���������������Ƃ��āA���̌�����ł���ɂ́A�܂�u��{�̖�v�����������ɂ́A�ǂ���������̂ł��傤���B �@
���ߋ����痭�܂��Ă���[�^����]�������オ�点�Ȃ����B�����Ɍ������ĉ������Ȃ��悤�ɂ��Ȃ����B���݂ɂ����āA�������L���Ȃ��悤�ɂ��Ȃ����B��������A���Ȃ��́A�Î��ۂ�����ł������ƂɂȂ邾�낤�B �@
�������[�ߋ����ݖ�����]���ׂĂɂ����閼�Ƒ̂���Ȃ�ʂ̎�(���F)���A�����̂��̂ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A[�݂肵���̎�����]���݂��Ȃ�����Ƃ����ĒQ���߂��ނ��Ƃ͂Ȃ����A�܂����ɂ��̐��E�ɂ���Ȃ��玸�����͉̂����Ȃ��̂ł���B �@
�l�Ԃ����ꂩ��˂��������Ă��鍪���I������]�́A�ߋ��ɑ��鎷���A�����ɑ���A���݂ɂ����鏊�L�Ƃ����O�����Ɍ����čL�����Ă����̂�����A�����A�A���L����߂Ȃ����A������������I��]����������āA���R�ɐÎ�ɐ�������A�Ƌ����Ă��܂��B�ߋ��Ɩ����Ǝ��͂Ɍ����Ĕ�юU���Ă����������A���܂����Ȃ鎩���ւƎ��߂��Ă݂�ƁA�u���Ƒ̂���Ȃ�ʂ̎��v(���F)�������������ɏ��L���Ă��邩���킩���Ă��܂��B���̖��F�����L����Ƃ́A�����Ŏ������ʂ̂��̂Ƃ��ė��ĂāA���������̂Ȃ����̂Ƃ��Ď���Ă���A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B����́A�����Ƃ������݂̍\���Ɋւ�邱�Ƃł�����A����ł����A�������̖��F�̏��L���ꂵ�݂̍������Ƃ����̂́A�킩��C�����܂��B�u�������������v�u�����͘V�����v�u�����͕a��Ŏ��ʂ��낤�v�Ɨl�X�ɋ�Y����̂́A�ߋ��̎����ƍ��̎������ׂ���A�����̎�����������������肷�邩��ł͂Ȃ��ł��傤���B����͐₦���ʂ̎�����ۂ������悤�Ƃ��邩��Ȃ̂ł��B���ꂩ���������A�m���Ɉ��y�������邩������܂���B �@
���āA�����ŁA �@
�@ �u��{�̖�v�����I������] / �� �@
�@ �u���Ƒ̂���Ȃ�ʂ̎��v / ���F �@
�@ �u�����̂��̂ɂ��邱�Ɓv���L / �� �@
���o�ꂵ�܂����B���ꂼ�ꂪ��̌����Ƃ��Đ�����܂����B���ꂪ�A���N���̍ł������̌`�ƌ����܂��B �@
����q�̋��� / ���āA�ߑ����S���Ȃ��Č�A���������������͂��̒���q���������V�ƂȂ��āA�������ߑ��̋������L�߂��Ă����܂��B�ނ�̋����́A�u�X�b�^�j�p�[�^�v��5�́u���E�́v�Ɏc����Ă��܂��B����q�����̋����̐������̓����́A�ߑ�������Ƃ��ēo�ꂳ���邱�Ƃł��B���̎�@�́A��X�܂ŕ����o�T�S�̂̓����ɂȂ�܂����B�����ŁA���ɏЉ�Ă��������̂́A�u�o��������탁�b�^�O�[�̖₢�v�Ƒ肳����܌o�ł��B �@
�@>�@������A���������ǂ������Y��������̂��A�����Ă������������Ǝv���܂��B �@
�@>�@��Y�́A���L�������ƂȂ��āA������̂ł��B �@
�����ɁA�^����m��Ȃ��܂܂ɁA�����ɂ��l�X�͂���Ԃ����L�𑱂��邽�߂ɁA��Y�������Ă��܂��B����䂦�A��Y�������Ă��鍪�����ώ@���āA�悭�m���āA���L�����Ȃ��悤�ɂ���̂��悢�̂ł��B �@
���ߋ��ɂ����Ăł���A�����ɂ����Ăł���A���݂̎��͂ɂ����Ăł���A���܂����̒����ɂ����Ăł���A���炩�N���m���Ă�����̂�����Ȃ�A��������߂邱�Ƃ��A������m���߂邱�Ƃ��A������ӎ����邱�Ƃ��������Ă����āA����Ԃ��Đ����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ��Ȃ����B �@
���炩�ɁA�����ł́A��Ō����ߑ��ɂ���Ĕ������ꂽ���{�^�������p���A�����āA��̌����Ƃ��ď��L���͂�����Ǝw�E����A���L����߂邱�Ƃɂ���ċꂪ��菜�����ƁA���`������Ă��܂��B �@
��O����̕���q�����̋��� / ���āA���̐���ɂȂ�ƁA�o�ƁE�݉Ƃ̒�q�����������A���Ȃ�傫�Ȑ��ɂ���������͂��߂āA�܂��܂������̋��`�����i��ł������ƍl�����܂��B���̎����̋������܂Ƃ߂��Ƃ����u�@��o�v�ɁA�ߑ��̒��S�̋����ł����������I������]�����A���̂悤�ȕ���������܂��B �@
�����������������������|���Ă��A�܂����̂тĂ���悤�ɁA�����I�����~��(��)�����₳��Ȃ��Ȃ�A��Y�͂܂������Ă���B �@
�����I�����~��(��)����̌����ł��邱�Ƃ��A�m�F����Ă��܂��B����͂��̌�̕���q�����̈ËL���ڂɂȂ����悤�ł��B���ɏЉ��̂́A�u�G���܌o�v�L��i����̋����ł��B�������O����̕���q�����̏W���ł���Ƃ���Ă��܂��B �@
���Ԃ�悤�ɂ��т���������I�����~��(��)���Ȃ��̂ł���A�ǂ��ɂ��A��o���悤���Ȃ��ł��낤�B�o��(�u�b�_)�͈�̏��L�����ł������Ă���̂ɁA���炩�ɖ���B����A���̎��Ɠ��́A���̊ւ�肪���낤�B�@
�����̋��߂���̂́A�F�`�A�����A���A�����A���G�A�v�l�������́A����ł��ׂĂł���B�����͋��낵�����̂ł���A���͂���Ɋ������܂�Ă���B�����̗L��l����Ɍ��߂�u�b�_�̒�q������̂́A�������o�āA�����ׂ������̗̈�z���A���z�̂悤�ɋP���Ă���B �@
����́A�Z�̔F���̑Ώۗ̈�̋��`���i�W���A�Z��(�Ꭸ�@��g��)����̌����̈�Ƃ��āA�l�����͂��߂����Ƃ������o�T�ł��B���́A��m�Ɩ��̑Ό��ł��B�@�g�̂́A�N��������̂��B�g�̂���������̂́A�ǂ��ɂ���̂��B�g�̂͂ǂ��Ő����Ă��āA�ǂ��Ŗł���̂��B �@
����̌��ł���g�̂́A����������̂ł��Ȃ��A���̂��̂�������̂ł��Ȃ��B���ɂ���Đ����A�����ł���ɂ���ď��ł���B��̎�q���c�ɔd����āA��n�̎����Ɛ����̗����ɂ���Đ�������悤�ɁA���](�F��z�s��)�A�Z�E�A�Z��(�Z�̔F���̗̈�Ɠ���)�����ɂ���Đ����A�����ł��邱�Ƃɂ���āA�ł���B �@
���̌o���ł́A�g�̂���̌����ł��邱�Ƃ����A���̐g�̂̍����Ƃ��Ă̗l�X�ȍ\���v�f���A���ɂ���Đ����A�����ł��邱�Ƃɂ���ď��ł��邱�Ƃ��A������Ă��܂��B���̌��]�̒��̎�ƍs�Ǝ����o���o���ŏ\�N�Ɏ�荞�܂�Ă��܂��B �@
�ŏI�i�K�̉C���o�T�Ɖ��N�� / ����܂Ō��Ă����悤�ɁA���オ�i�ނɂ�āA���͂��i�݁A��̌����Ƃ������̂������Ă��܂������A�܂��A���ꂼ��̂��̂��ǂ��炪���[����������ׂāA�c�ɕ��ׂ悤�Ƃ��������͏o�Ă��܂���B���ꂪ�����n�߂�̂́A�ŏI�i�K�̉C���o�T���W�߂��Ƃ����u�X�b�^�j�p�[�^�v��3�́u�傢�Ȃ�́v�̍Ō�̂Ƃ���ł��B �@
�������A�����̖�̏W�܂�ɂ����āA��q�����Ɍ��n�߂�Ƃ����ݒ�ŁA������܂��B�u���ɓ����l�X�Ȑ^�������邪�A�����̐^�����w�Ԃ͉̂��̂��߂��Ɩ₤�l������A���ɓI�ɂ͈�̐^���𐳂����w�Ԃ��߂ł���A�Ɠ����Ȃ����v�A��Ƃ́A�u���ꂪ��ł���A���ꂪ��̌����ł���v�Ɓu���ꂪ��̎~�łł���A���ꂪ��̎~�łɎ��铹�ł���v�Ƃ������Ƃł���A�ƑO�u�����āA����������������܂��B �@
���l�X�����̏�Ԃ��炠�̏�ԂւƂ���Ԃ�����Ԃ����܂�Ă͎��ʗ։��I���݂ł��葱����̂́A�ق��Ȃ�ʖ����̌̂ł���B�@
���Ȃ��Ȃ�A�����Ƃ͑傫�ȋ������ł���A���̂��߂ɖ����̉ߋ��ȗ��A�։��]�����Ă����̂ł���B�������A�m�b��������Ȃ�A�l�͓�x�Ɛ��܂ꂩ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�@
���ǂ̂悤�ȋꂪ������ꍇ�ł��A���ׂčs(�s�ׂ̎c�])�����ƂȂ��Đ����Ă���B�s���~�ł���A�ꂵ�݂͐����Ȃ��B �@
�Ɛ����A�����p�^�[���̕��ŁA���Ɏ�(�ӎ��̗���)�A�I(���̂Ƃ̊ւ��)�A��(����A�C��)�A��(�����~��)�A��(���L)�A���s�A�Ƃ̐ێ�A�E�E�E�Ō�ɁA���̊�����̂��Z�̔F���̑Ώۂɂق��Ȃ�Ȃ��ƁA������Ă��܂��B���ꂪ�C���o�T�̒��Ŋm�F�����A���N���̔��W�̍ŏI�i�K�ł��B���Ԃ͂ł�����܂����A�܂��c�ɕ��ׂ悤�Ƃ͂��Ă��܂���B �@
���́A�\��x���N�����̓��e�Ƃ��邱�ƂɁA�����ԕs���������Ă��܂����B���Ƃ��������A����͋ɂ߂Ē��ϓI�Ȃ��̂��낤�Ǝv��������ł��B�������A����܂Ō��Ă������Ƃ��炷��A���N���Ŋ̐S�Ȃ̂́A���Ԃł͂Ȃ��āA�����I�����~���ɂ����ɂ���ꂪ�˂���������A����ɂ���ċꂵ��ł��邩�ɁA����J����邱�Ƃł���A�ʂ̎��Ƃ������������ǂ�����ĉ��������A���y�Ȑ��E������Ă����邩���l���邱�Ƃ̂悤�ł��B �@
 �@
�@�������ِ�� �u�يE�v�Ƃ��Ă̎l��
���͐́A��b�R�̓����ɒ����Ƃ����m�������B(�����͓V��4�N(960)�ɗ��t�ɔC����ꂽ���厛���d�a�����S(���S)�̒�q�ł���B)���鎞�A�����͑m�[���o�ę̂ɍs��������A�����̐����U���A�o�������c�����܂܍s��������܂��Ă��܂��B���̌�A��10�N���o�߂������A���ɍs���͂킩��Ȃ������B�����̒�q���q�����60�Β��ɂȂ�������A�ɗ\��Ƃ��ĔC���ɉ����������m�͂ɔ����Ĉɗ\���ɒ������B���q�͓����m�͂̔�̂��ƏC�@���s���A�ɗ\�����̐l�X�����q���h�����B �@
������̂��ƁA���q�̑m�[�̑O�ɗ��ĂĂ���،����̊O�Ɉ�l�̘V�@�t�������B���̊i�D�͍����𒅂��āu��M�P�������s�m�Y���^������c�����^���j���L�����A�m�B���Б��j���e�|�m�z�e�v�Ƃ�����t����H�̎p�ł������B�m�[�̏h�������Ă����y�n�̐l�����̘V�@�t��吺�Ŕl���Ēǂ������B���̋��ѐ����Đ��q����q���J���Č�H�ɋߊ���āA�}��E�������̊������A�V�@�t�͔�b�R�ɂę̂ɍs�����܂܍s���s���ɂȂ��Ă��������ł������B���q���₢�q�˂�ƁA�����́u�䃌�A�R�j�e�̃j���^���V�ԃj�A�S�Ãj�v�G�V�J�o�A���m���탒�σW�e�A���N�A�������e�j�㐶���F�����g�v�q��V�j�A���A�u���@�m���J�������j�s�e�A�g�����e�����H���V�e�������o���P�e�A�j�O�������w�e�R�\�Ɋy�j�n�����Z���v�g�v�q��e�V�J�o�A���`�̃����[�j���s��Y�V�e�A�����ʃ����L��������e�A���m���j�R��j�s�e�A�ɗ\�m���j���_���֑D���q�e�����j���e��A�ɗ\�]��m�����j����V�e�N���߃V�c����B�v�Ɠ����A�m�[���o�Ă��̂܂ܐՂ�����܂����B�₪�āA�����m�͂��ɗ\��̔C�����I���㋞��3�N�������Ă��̖�t����H���ɗ\���ɂ���Ă����B���x�͓y�n�̐l�X���ނ��M�ьh�������A�Ԃ��Ȃ��ɗ\�̌Î��̌�̗тɂāA���̖�t����H�����Ɍ������Ē[���������A����悤�Ɏ��B�y�n�̐l�X�͊e�l���@�����C�����B���̂��Ƃ́A�]��A���g�A�y�����ɂ������`���āA5-6�N�ԁA���̖�t����H�̂��߂̖@�����c�B�u���m���X�j�n�A�I�����s���k���i���j�A���m���j�t�e�A���N�������C�X���o�u���m���X�m�l�������K�׃j�A���m�����j��m�g�g���W�e�������w����v�g�}�f�i���l�F�]�e�A�߃r�M�r�P���v�܂�A�u���m���X�v=�l���͂܂���������������Ȃ����ł���̂ɁA�����̎��������Ă���������s���悤�ɂȂ����̂ŁA�������Ɍ�H�̐g�ƂȂ��Ă����łɂȂ����ƌ��`�����Ă���B �@
���Ȃ݂ɁA�����̒�q�ňɗ\�瓡���m�͂ɔ����Ĉɗ\�ɒ����ďC�@���s�����u�Ðq�v�́A�u�䖧�������v�u���������v�u���@�v�����v�ɂ��Ɓu�Ð^�v�ƌ����A�Z���͗Ֆ@���C���Ă���B�u���@�v�����v�Ɂu�Z���͗Ֆ@(����)�͗Ֆ@�ҁA����ɖ[�Ð^�A�ɗ\��m�́A���\�B�C�V�v�Ƃ���B�܂��u�J��苗��`�v�ɂ��ƁA�Ð^�̒�q�c�c�������m�͂̂��ƂŒ��� �N��(995-9)�ɕ��������@���s���Ă���B�Z���͗Ֆ@�́u���������v�ɂ́A�����A���t�A�a���A�Y�w�̂��߂ɏC���Ƃ���A���I�Ƃ������ނ���M���̎��I�C�@�̐��i���F�Z�����̂ł���B�܂��A���������@��9���I�܂ł͋ʑ̂��F�O���鍑�ƓI�C�@�Ƃ��Ĕ��B������A10���I�ɂ͗L�͋M���̎��I�C�@�ւƓ]������Ƃ����B�܂�A�����͈ɗ\�瓡���m�͂ɂ�鎄�I�C�@�ł��邱�Ƃ��킩��B �@
���āA��ɏЉ���u���̕���W�v�����ِ�杂ł́A�l���́u���@�m���J�������v�A�u�I�����s���k���v�ƕ\������Ă���B�u���̕���W�v�̑��̐��b�Łu�l���m�Ӓn�v�ƕ\������Ă���悤�ɁA�l���͕��@�̕��y���Ă��Ȃ��u�ӓy�v�ł������ƔF������Ă����̂ł���B�Ȃ��A�Ӓn�Ƃ́A���{����厫�T�ł́u��ɂ̕��q�ɋ^�f������Ȃ��牝�������҂̐��܂��Ƃ���v�ƏЉ��Ă���B �@
�����Œ����̘b���ɖ߂낤�B�����́A�̂��炻�̂܂܍s��������܂��Ă��邪�A����Ɠ��l�̍s�ׁA�܂�̂���̒E�o杂͓��{�̘̐b�ɑ�����������̂ł���B���̑�\�I�Șb�Ƃ��āu�O���̌아�v������B �@
����R���ɘa���Ə��m�������B���m�͎R�ɉԂ����ɍs���������ɖ����Ė�ɂȂ��Ă��܂��B���m�͎R���̈ꌬ�̂��k����̉Ƃɔ��߂Ă��炤���A���͂��̔k�͋S�k�ł������B���Ƃ����ē����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���A�֏��ɍs���A�֏��̐_�̓����ő����瓦�����B�_����͎O���̌아��Ⴂ�A�ǂ������Ă���S�k�ɓ������Ȃ���悤�₭���ɖ߂�A�Ƃ������b�ł���B���m�͈يE(�R)�ł̎������o�����A���ɋA���Ă���̂ł��邪�A�̂͂��傤�LjيE�Ƃ̋�(�S�k�̂��鐢�E�Ɠ������R�E��)�Ɉʒu���Ă���ƔF�����邱�Ƃ��ł���B�̂Ɋւ��ẮA�ѓ��g�������̈Ӗ��A�̘b��V��ɂ����邻�̈ʒu�Â��A�֊��⑭�M�A�̐_�̓`���Ȃǂ��l�@���Ă��邪�A�����͂���ƁA�͈̂يE�֎Q�����������A�ϐg�̏�A���̐��ƈيE�Ƃ̋��Ƃ����C���[�W�������Ă���Ƃ���Ă���(�u�}�_�ƙ̐_�|�يE�ƍ��̐��̋��|�v�u�k�Њw�p����)�B ���̙̂Ɋւ��閯�����炷��ƁA�u���̕���W�v�̒������̂�ʂ��Ďl���ɓn��Ƃ����s���́A�l�����يE�ł��邱�Ƃ��ے����Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B�l�������@�̕��y���Ă��Ȃ��u���@�m���J�������v�A�u�ӓy�v�ł���Ƃ����u���̕���W�v�̋L�q�����łȂ������̍s�ׂ�����A�����̋E��(����)�̐l�X�̎l���ɑ���F���̗l�����_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B �@
 �@
�@�����̉̔�E���
�������q�K / �F����\���͂Ȃ�ďH�̕� �@
������ّT / �q�K���߂���Պ��߂����͏H �@
���֓��g / �����R�R�ƈ�{�̓��ʂ肽��왎��킪���Ȃ肯�� �@
����c�� / �[�z�����D�@
�@�@�@�@�@�@���|�߂����̒Z���@����ӂ����a������͂� �@
�@�@�@�@�@�@���������ʑf���́@���X�̓��̒���� �@
�@�@�@�@�@�@�y���ӂݐ��ӂݗ��ā@�ɂ��݂��錌�������䂩�� �@
�@�@�@�@�@�@�����܂����j���������ā@���Ƃ��Ђ����Ⴍ����� �@
�@�@�@�@�@�@���͒����ڌ��̐Â����@�����ЂȂ��h�i������ �@
�@�@�@�@�@�@�������鏶�̂������́@�����֕��ƌ���� �@
�@�@�@�@�@�@�ɗ\�̍��ɍ���̎R�́@�ݓ��ɗ��Ĉׂ����Ƃ��Ȃ� �@
�@�@�@�@�@�@���������ˌ�͗V�Ԃ��@���̋��ɐ���Ȃ���� �@
�@�@�@�@�@�@���̂ݓ��ɐZ��Ђ܂Ȃ��@���֍s�����ɍs���� �@
�@�@�@�@�@�@�O�ł��Ċ��������܂Ӂ@�݂������������Ɏc����@
���͖쐴�_ / ���Ƃ₳���S����I�̂��̂��� �@
���⑺�^�� / �O����ΉԊJ���@ �@
���l�́u���v����X�͌o���ł���B�������A����́u���v���o�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�n�C�f�K�[�u���݂Ǝ��ԁv(��g����)���w�E����悤�ɁA�u���v�Ƃ͂����Ă��l�X�Ȉʑ��������āA����ƒn��ł��قȂ�A�����̂��̂ł͂Ȃ��B�u�����ρv�Ƃ�������Ő��E�����n���Ă݂�ƁA�u���v�͑傫���l�ɕ��ނł���̂ł͂Ȃ����B��́A�����̓��̓I�����������ɑ��݂���ƐM����Ƃ����l�����B����͒����̐_��v�z��s�V�����A�G�W�v�g�̃~�C���M�ɑ�\�����B���{�ł��Ñ�̏퐢�̍��̐_�b������ɂ��Ă͂邾�낤�B�썰�͕ʂƂ��āA���̂̑��݂��d�����A���ꂪ�����i���������邱�Ƃ��\�ł���Ƃ��������ςł���B��ڂ́A���̂͏��ł����Ƃ��Ă��썰�͕s�ł��Ƃ����l�����B����̓L���X�g���̓V���ƒn���Ƃ����������ς�A�����̒n���Ɋy�v�z�A�։�v�z����\�I�Ȃ��̂ł���B�����ɂ͓��̏d���̎v�l�Ƃ͈قȂ��āA�l�̗썰��������يE�ɂđ��݂�������Ƃ����l��������B�����Ď���̗썰�ɑ��Ă������d�v�������̂������ł���B�O�ڂ́A���̂��썰���ł�ł��܂����A����ɑ�ւ���s�őΏ�(��p��)�ƂȂ��Ď���̐��E�ő��݂���Ƃ����l�����B����͓��{�́u��c�v�ɑ�\�����c��M�����Ă͂܂�B��q��������L����썰�Ƃ͈قȂ�A33�����49����Ƃ����������グ���o��ƁA���҂̌��͎���ɏ��ł��A�u����c�l�v�Ƃ�����X�̉Ƃ̎��҂̏W���̂Ƃ��āA�Ƃ��i���������ɂ����đ��݂�������B�Ⴆ�A���~(᱗��~)�ɂ͉Ƒ�X�̊e�l�̎��җ�ł͂Ȃ��A��c�Ƃ������̏W���̂��}���āA�������āA�����čĂё���B���ꂪ���{�̂��~�̌`�ł���B�����̘Z���։�v�z�ł́A���҂̉��҂�����E���{���邱�Ƃɂ���āA���҂́u���܂����v�͒n���E���S�E����E�o���Đl�ԊE�֓]��(���܂�ς��)���邱�Ƃ��ł��邪�A���̎v�z�̊�w�ɂ́A�����܂Ŏ��җ썰�̌��͕ێ�����Ă���B�c��M�Ō�����Ƃ̂���c�l�Ƃ��Ă̖v�����Ƃ͑ΏƓI�ł���B�����āA�l�ڂƂ��ẮA���̂�썰�A�����đ�p�������ł��邪�A���݂̍s���Ɏ��Ȃ��]�W�������邱�ƂŁA�����z�������n��̓�������̂ł���B����͈�ʓI�ȁu���v�̊T�O�Ƃ͈قȂ�悤�����A�����Ђ炭���Ƃ�A�_�Ƃ̈�̉��Ȃǂ̐_��I�̌��邱�Ƃɂ���āA�u���v�z���邱�Ƃ��ł���Ƃ����l�����ł���B�O�q�̎O�̐��͓��̂�썰���̉i���E���ł�O��Ƃ��āA�l�Ԃ́u���v�̌�ɖK���u���v�̐��E�ł̂������₤�Ă��邪�A���̑�4�̐��́u���v�̎��Ԃ̉�������Ɂu���v���l����̂ł͂Ȃ��A���Ԃ����A���Ǝ��������z���悤�Ƃ��Ă���B�l���H�ɂ�����O�@��t���A�u���v�ł͂Ȃ��u����v���Ă���Ƃ���A���ł��u���v�̑��݂Ȃ̂ł���B �@
���̂悤�ȁu���v�̂�����͒n��Ǝ���ɂ���ĈقȂ��Ă���A�����I�T�O�Ƃ�������B���������A�l�Ԃ͎���m���Ă��邪�A�T���͎���m��Ȃ��Ƃ����B���҂̓��̓I�I�����u���v�ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���̂͐l�Ԃ݂̂��Ƃ����̂ł���B�u���v���o�����A�w�K���A�������A�����ĊT�O���E���L�����ꂽ���ƂŁA�T������i�������l�ԂɂȂ����킯�ł���(�Q�l�F�V�J���I�u���Ɛl���̖����w�v�j�j�Џo��)�B�����āA�l�Ԃ��Ȃ��������s���̂��Ƃ����A���̓I�ȓ��̂̏I�����A�Љ�̒��Łu���v�Ƃ��ĔF�m�������ƂƂ��Ă̈Ӗ�������B�l�Ԃ̓��̓I�Ȏ��ɔ����s���E����Ԃ��A�Љ�I�Ȏ��Ƃ��Ď�e�����邽�߂̕���Ƃ�����̂ł���B �@
���āA�u���v��m�邱�Ƃ́A�����Ɏ����������Ă��邱�Ƃ����o���邱�ƂɂȂ���A���Ǝ��̋��ڂ�F���ł��邱�Ƃɂ��Ȃ�B�����A���̋��E�F�����Ȃ��ꍇ�A�����������Ă��邱�Ƃ̏ؖ��悤�Ƃ���Ȃ�A���ɓI�ɂ͎��������ʂ��Ƃ���Ď����́u���v���m�F���悤�Ƃ���ꍇ���o�Ă���B�ߔN�A��҂̏W�c���E���Љ���ƂȂ������A����������ƁA���E������ҒB�͕��i�u�����Ă���v�Ƃ������ȑ��݊��o���ŁA�����s���Ɏv���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B���Ƃ����ȑ��݂��m�F�������Ɩ��ӎ��̂����ɍl�������A����I�������A����A�����m�F���悤�Ƃ����̂�������Ȃ��B �@
����͐g�́E�ƁE�n��E���ƂƂ������l�X�Ȋ��́u���v�Ɓu�O�v���{�[�_���X�����A�u���ȁv�Ɓu���ҁv�A�u���v�Ɓu���v�ȂǎЉ�ɂ����鎩�ȑ��݂m�ɗ��������(����Ύ��ȓ��ꉻ�����)��{�����Ƃ�����Ȏ���ɂȂ��Ă���B���Ɋւ��Ă��A�u���v�̌��������ɂ���u���v��F���ł���͂�{�����𐮂��邱�Ƃ��ł��Ȃ���A���ꂩ��̐��̒��́A�u�����Ă���v�Ǝ��o���邱�Ƃ�����A�������͂̌��ނ����Љ�ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B�@
���Ắu���v��m���i�́u�����v�̒��ɓ��݂��Ă����B�u�����v�Ƃ͉Ƃ�n���`����̂Ƃ��āA������đ�X�p����Ă������������̂��Ƃł���B���̒��ł��l���V��̂������E�����E�搧�̖�����ʂ��āA���̒n��ɐ��܂ꂽ�l�Ԃ́A���̒n��Ő�������ߒ��ŁA���҂́u���v�������邩�������E�̓����邱�Ƃ��ł��Ă����B���҂̑̂�u������v�A�`(����)��n����ʼn^��ŕ�܂ő���u��ӑ���v�A�����ēy���ł̕挊�@��ȂǂȂǁB�ߐe�҂�ߗ҂��S���Ȃ����ہA�Z���Ǝ��҂Ƃ̋������͋߂����̂������͂����A���ł̓Z�����j�[�z�[���ł̑��V�A���Ȋ��Ɨ�l�ԁA�ݔ��̏[�������Α���Ȃǂ̓o��ŁA���҂Ƃ̋������͑����A���̃��A���e�B���ȑO�ɔ�ׂĊɂȂ��Ă��Ă���B �@
�u���v��m�邱�ƂŐl�Ԃ̓T������i�����邱�Ƃ��ł����B�����́u���v�͌o���ł��Ȃ����A���l�́u���v�͌o���ł���B���̂悤�ɏq�ׂ����A���݂ł͑��҂́u���v�Ɋւ��Ă����A���e�B�������Čo�����Â炭�Ȃ��Ă���B�l�Ԃ��u���v�Ƃ͉�����Ƃ����₢���l����̂�����ȎЉ�I�ł́A�u���v�𗝉��ł��Ȃ���u���v�������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����͐l�Ԍl�݂̖̂��ł͂Ȃ��A�l�Ԃ��Љ���\�����邽�߂ɕK�v�Ȏ��ȑ��݂̔F����(�u���ȁv�Ɓu���ҁv��F�������)�ɂ��e�����Ă�����ł���B�u���ҁv��F������͂��F�����ƁA�u�Љ�̒��ɑ��݂��Ă��鎩���v�Ƃ�����������A�u���������ׂĂ̒��S�ł���A�����̈ӎ��̒��ɐ��̒������݂���v�Ƃ��������ݗ����̋t�]���ۂ��N���肩�˂Ȃ��B�����āA��������{�̎�҂̊ԂɁA��5�̎����ς��蒅���邩������Ȃ��B�l�Ԃ͎��牽���Ȃ��Ȃ�B���̂��썰���B�����āA����������ł��܂��Ɛ��̒��̑��݂����������Ă��܂��B���̂悤�Ȏ����ς̂��Ƃł́A���{�̓`���I�ȑc��M�����������Ă��܂��A������x���Ă����Ɛ��x�⎛�h���x���傫���ϗe���Ă������낤�B �@
�����������ȑ��݂̊m�F�́A�u���ԁv�Ɓu��ԁv�ɂčs������̂ł���B�����̑��݂��ߋ��E���݁E�����Ƃ������Ԏ��Ɉʒu�Â��邱�Ƃł���A�g�́E�ƁE�n��E���E�Ƃ�����Ԏ��Ɉʒu�Â��邱�Ƃł���B���̍�Ƃ��A�u�����v�Ƃ���������ē`������Ă��������A�܂��l���`���Ă���������́E�m�b�E�m����f�ނƂ��čl���Ă������Ƃ͏d�v�ł���B���ꂩ��̐��̒��ł́A���̎��_���s���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B���Ƃ��Ă̂ݐ����Ă������Ƃ��ł���̂́A�P�Ȃ錶�z�ł���A�͕K���R�~���j�P�[�V�������Ƃ�A���҂Ƃ̊W��z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u�l�̊ԁv�ƕ\�L����u�l�ԁv�̑��݂͎����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�q�g�ƃq�g�̊ԕ����z����Ă͂��߂āu�l�ԁv�ƂȂ�̂ł���B �@
���̊ԕ��ɂ͌����E�n���E�Љ��Ȃǂ́u���v�����邪�A���́u���v�̒��Ŏ��Ȃ��m������͂�{���Ă�����v�f���u�����v�ł���B�u�����v���Â����́A�m�X�^���W�[��������������̂ƈ����̂ł͂Ȃ��A����=�������i�Ƃ��Ă����Ɉ����Ă������𗝉����邱�ƂŁA���݁E�������������A���̂����猩���Ă���B����͐����Ă��邱�Ƃ𑊑Ή������Ƃł���A���ꂪ�B���ł���ΐ����Ă��邱�Ƃ��Ύ����ł���̂ł͂Ȃ����B�u���Ƃ͉����v���l����s�f�̓w�͂͐l�Ԃ��u���v���p�����Ă������߂ɕs���ƌ�����B �@
 �@
�@������1
������2�N�i1276�j38�@�ʕ{�S�։���J���i�`���j�B ��Տ�l���L��̍�����L�O�̍��֕��Z�̓r���A�ʕ{����̗��ŔZ���ɂ�����a����B�����֔����̉�������u�ߌ��x�̎R���ƁA�����l�ʂ̓S�֒n���̓����Ŗ��O����V�����Ă���B������~�����Ƃ́A�l�Ԃɂ͖����ł���B�ߌ��R�[�̉̐_�A�ߌ������ɋF��B�v�ƍ�����B��Ղ�21���̒f�H�F�������ƁA�������̉�������u�呠�o�̌o�����ꎚ��ɋL���A�̖��������������߂A�n���߂邱�Ƃ��o���悤�B�v�Ƌ����Ă��ꂽ�B��Ղ����O�̑m�⎛�X�̑m�̋��͂āA�����������s���Ă���ƁA���O�������H�ו�����i���ċ��͂����B�قƂ�ǂ̒n���͐Â߂邱�Ƃ��ł������A�Ō�ɎO�Ԏl���̕��C���ǂ����Ă��Ƃ܂�Ȃ��B��Ղ��ēx�Q�Ă��ċF��Ɓu���̕��C���~�߂�ɋy���B����͌o���̌��͂Ɖ���̗͂����킳����ƂȂ����̂ł���B�����ɏ������C��z���A�����Ȃ��a���K������ł��낤�v�Ƃ������������B���̂悤�ɂ��ēS�ւ̊J���ɐ��������B�����F���ׂ͈�Ղ̘J����ӂ��A����������i�����B�������̐Ղ́A�i�����ƂȂ�A��Ղ̑������u���A�u���{�������J��v�u��Տ�l���u����v�ƌf�z �B�@
���������N�i1288�j50�@�Ō�̋A���̍ہA�͖�ʗL�̍��]�ɂ��A�����ɘZ���̖����������B �@
�u�s�����v�u���i���d���v�ƕ���Łu�̐���Ձv�͏@���ɊS�̂���҂ɂƂ��Ă͎��m�̌ď̂Ƃ�����B��ՂɊւ��钘��ł́u�̐���Ձv�ƕ���Łu�㐹��Ձv�u������Ձv�Ȃ�ď̂����䐴���u��ՂƎ��O�@���c�v�勴�r�Y�u��Ր��v�I�c�E�u��Տ�l�E���̎v���ҁv���씎�u��Ր��̑����I�����v�����Вj�u�Ⴋ���̈�Ձv�ɎU������B�X�Ɂu��@�ցv���ɂ͋{���G���u��Տ�l�̖���v���䐴���u��Տ�l�̔A�Ö@�v�ł͔A�Ö@�̒m�����ڏq����Ă���B�@
�{���i�j���I���ɂ��Ă̒m���͑O���ȑO�́u�_�_�{���o�v�O���́u������o�v�u�����G�a�_�v�u�b���o�v�Ȃǂق�2000�N�O�Ɋ������Ă���A�����`���ȗ��c��Ȓ��삪�����┼������킪���ɗ��������B��C�̓������̂Ȃ��ɂ��������c��A�킪�����̈�w���ł���O�g�N���́u��S���v�͉i��2�N�i982�j�Ɋ������Ă���B�@
���ɕ{���ɔ[�߂�ꂽ����璘��ɕ{�ŏC�s������Ղ͉{���ł����Ǝ�������_�҂����邪�����܂ʼn\���̌��ɉ߂��Ȃ��B�u�_�_�{���o�v�ł������E����E����345��̖{���̑����͓��{�̕��y�̒��ł����炵�Ă���A�����҂͂��Ƃ��m���K���͂�����d�Ċ��p�����B���̂Ɉ�Ղ݂̂��u�㐹�v�u�����v�Ƃ��Đ��q�����̂��B�@
���u��Ր��G�v�Ɍ��ꂽ�a�C�E�a��@
�u��Ր��G�v�ɋL�ڂ���Ă���a�C�E�a���9���ł���B�@
�i1�j���O�������͐M�҂Ɋւ���a�C��6���Ň@�헤���̈��}�̒��������A�������Ŏ��O5-6�l���a�B�㑍���u������ɕ��v�̕a�C�C�����̓�{�������a�D�ߍ]���Ŏ��O13�l��Ĕ��a�E�������u�Ԃ̂��Ƃ̋���v���a���L�ڂ���Ă���B�@
�i2�j��Վ��g�̕a�C��3���ŇF���s�V�s���ɔ��a���u�����{���v�̎������s�����Ƃ����b�G���ŕ������킵2�T�Ԑ������邪����̒��������Ƃ����b�B���g���Ŏ���\�����Ĕ��a�����b���L�q����Ă���B�@
9���̕a�C�͊�ՂɊւ��鏃���ȏ@���I�Șb�͂Ȃ��A�܂��Ĉ�Ղ���̓I�Ɏ��Â����L�q�͂Ȃ��B��Ղ��u�܂�тƁv�ł����a�́u��v�����L���Ă���ɉ߂��Ȃ��B���O�������͐M�҂́u�M�v�����S�e�[�}�ł���B�܂���Վ��g�̕a�C�ŕa�������m�Ȃ͈̂ݒ���Q�ł���u����̒��������v���Ƃ͊�ՂƂ͉������B�Ƃ���u��Ր��G�v�ȊO����u�㐹�v�u�����v�Ɋւ���`�ʂɔ����čs����������܂��B�@
����Ղ̎{�Á@
�u���E�V�E�a�E���v�̒��Ől�Ԃ͈ꐶ���I��邪�A�L���X�g���ł́u���E���E�Đ��v�̘_���Ŏ���̐��E�̐R����\�肵�A��敧���ł́u�����v���ď�y���ŏ����鈢��ɕ��̘@�̐��E������B�����͏����`����u������P�v�̕s�V�s����̕�����c���������ŏI������B�����ȑO�́u�։�̐��E�v�Ƃł��]���ׂ��ł��낤���B�@
��Ղ̎{�Âł͖{���i�j�A���A�A����i�O�j�A����Ö@���l������B�@�@
�@�{���i�j�Ö@�͐�q�����悤�ɔ����E�嗤����ړ������Ö@�ł��邪�A����E�F�쐹�i�C���ҁj�̖��ԗÖ@�A�Ⴆ�g���J�u�g�ƃT�\���͋��ɖғłł��邪�Ő��������������łƂȂ鎖���i��ˋ��j�u���m��w�v�j�����m���A�V�s���Ɏ{�Â�����������ʁB�@
�A���s�������ł̔A�Ö@���i�m4�N�i1296�j�́u�V�瑐���v�Ɉ�Ղ��|�̓��ɔA����������A���̔A�����a�Ɍ����ƐM���Ė��O�����������Ă���l���䎌�t���ŕ`����Ă���B�u��ՂƐ_�X�̏o��@-�����Ƃ�������-�v�Ŏw�E���������E�����E�����E���W�@�c�i�J���g�j�ւ̔��W����u��ՂƂ̈�̉��v�Ɠ��l�́u��ՂƂ̍��́v�ł���B�L���X�g���̌��i�ȋ��`�Ƃ͈قȂ邪�A�p���ƕ�������ʂ��ăC�G�X�ɋ߂������Ƃ����M�҂������s�s�ɂ͏[�����Ă����B�A���̖̂���͌���́u����厫�T�v�́u�l�A�v���u����Ǝ厡�v�ɂ́u�t��̒��É��A�~���A���t�z���i�v�Ȃǂ̖�����L�ڂ��Ă���B�@
�B����Ö@�C����Ö@�͓ޗǎ���̌����c�@�̎{��@��d���̏������C�ȂǖڐV�����͂Ȃ����A��ՂɌQ�������h�}�̔畆�a�i�O�a�j���҂��H�͈�Ղ̊�Ղ�M�����Ƃ��]���悤�B��ጁi�����j�Î������������B�i�u�ٖ{���c���L�v�j�@
�ɗ\�E���㉷��A�F��E���m��A�L��E�͒��i�S�ցj����͈�Ղ̌��т����������A���Â�����������܂���ł���B�i���j����͌��݃A���J����ł��邪�����㉷��͗�����ł���A�����̕H�L�^�ɂ͓���̓��͗����ŏL���Ƃ̋L�q���c���Ă���B�@
�����O�����߂����́@
���q����̐l��6�S���l�i�����Z�u���j�l���w�Ō������{�v�j��1���ɑ�������u���艝���Z�\���l�v�̕��Z�����s������Ղł��邪�A���O�́u�얳����ɕ��v�ƂƂ��Ɍ����́@�K�������҂����͓̂��R�ł��낤�B�Z�\���l���Z���\�ɂ�����Ղ̋��`�ƗV�s�����邱�ƂȂ���u�㐹�v�u�����v�Ƃ��Ă̎��ÂƁu�x��O���v�̖��͂��傢�Ȃ�z���͂ł������Ǝw�E���Ă��������B��Ր��a�n�����K�˂����Ƃ�����ꒃ�Ɂu�Ƃ����������Ȃ��܂����̔N�̕�v�Ƃ����傪����B�u���Ȃ��v�Ƃ́u�얳����ɕ��v�ł���u��Ր��v�ł���̂�������Ȃ��B �@
���C�����Ȃт��A�ʕ{�s�̓S�։����܁A���C�������B�̂Ȃ���̂ЂȂт����͋C��Y�킹�铒���ꃊ�]�[�g�Ƃ��āA�ʕ{�����̒��ł��_���g�c�̐l�C�Ԃ肾�B�n���ɂ́u���@�J�c�̈�Տ�l���J��������n�v�Ƃ����`�������p����Ă���B�u��Տ�l�`���v�̒n�A�S�ւ�T�K�����B�@
��Տ�l��1239�N�A�l���͈ɗ\���E����̐��܂�B���q���{����A�ɗ\��~���x�z������E�ł������͖쎁�̉ƌn�ŁA10�ŏo�Ƃ������A���̎��ア������A�����ĕ��m�ɖ߂�B �ȑт��q���������������A�Ăяo�ƁB1274�N�ɔO���̋�����������u�V�s�v�ɏo���Ƃ����B���̗���̈���S�ցB�S�ւ̓����̊C�ݕ��ɂ́A��Ղ��㗤�����Ƃ����u��l���l�v������B �S�։���X�̒��S���ɂ����Ղ䂩��́u����R�E�i�����v�B�i������т́u���C�{�v�ƌĂ�A�S�։��˂̒n�ɂӂ��킵���n�����낤�B�@
�i�����ɂ͈�Ղ̖ؑ����͂��߂Ƃ����`������������Ƃ��ē`���B���N9���ɍs����u�����ݍՂ�v�ł́A�ؑ����݂����ɏ悹�A�t���s���擪�ɗ�������A��������Ő��߂�u�����ݖ@�v�v������B�����l�����B�e�n����삯�t�����A�̓����q�����Ȃ��Ȃ��Ƃ����B�@
��ՂƓ����͖쐩�̌��݂̏Z�E�A�͖쌛������́u��Տ�l�`�����S�ւ̂܂��Â���ɖ𗧂̂Ȃ�A���ꂵ������v�Ƙb���B �n���ʼn���h���o�c����㓡���邳���́A�u��Տ�l�T����v��2003�N�Ɍ����B�u�n���ł���Ղ���Ƃ̉�(���ɂ�)���Y����悤�Ƃ��Ă���v�Ƃ����v������A�u��Ղ���Ĕ����v��ړI�ɕ�����d�˂Ă����B�@
���̐��ʂ����N3���A�u��Տ�l�ƓS�։���v�ɂ܂Ƃ߂��B���N2���ɂ́A�ʕ{��w�̕�����������(�����E�я����i����)�Ƌ��͂��čs�����������ʂ��u�����������Ȃ�Ȃ�\�������̊w�p�������\�v�Ƃ��Ĕ��\�B�я������́u(�S�ւɓ`����Տ�l�`����)�P�Ȃ�`���ł͂Ȃ��A(�S�ւȂǂ��܂�)�ʕ{�ߌ����ӂ�K��Ă���v�ƌ��_�t���Ă���B
 �@
�@���ʓ���t����
�V��@�́A����25�N(806)�����V�c���J�@�̒������������B���厛(�ޗ�)�̑啧(Ḏɓߕ�)�J��(752)����54�N�B�l�S�r�p�����a�̍�����V���ȕ������ɑJ�s(794)���ꂽ12�N��B���₩�ȗ��j�̃h���}���_�Ԍ��邱�Ƃ��o����B�哯3�N(808)�J�@2�N�ڂ̔�b�R�ɁA���R�ƂЂƂ�̋�s�m�������B���̖��́u����v(�������傤)�N��30�B�ɗ\�̍������S(���݂̈��Q���k���s�Ėڂ��邢�͂��̎��Ӑ�����)�̏o�g�B�̂��́u�ʓ���t����v�ł���B����̂���܂ł̐��������́A���܂�m���Ă��Ȃ����A�l���ł̎R�x�C���ɗ�炵���A�l����ꉡ�ł͊J�R��̈������Ȃ���Ă���B�䂩��̎��͏��R�ɘŐ����E���R�����������B�c�t�Ő�(43��)�́A�����g�Ҋw���Ƃ��ċA��3�N�ځB����̕��O�ꂽ�ˊo���������Ē�q�����������B���̗��N�^���@�̊J�c�ƂȂ��C��l(38��)����b�R�ɍŐ����l��K��B�Ⴂ����ɂƂ��ĕ����̗��Y�Ƃ��琂́A�@�x�ɐZ��Ȃ��������̉ʂ����ׂ��g�����������ɔR���オ��B ����͎R��ɂ����Ď�Ɍ������w�B�Ő���蓌��(��C�̐M���閧��)���w�Ԃ悤�w�����A�C�̘a��(�����̂킶�傤)(�����̋�C�̌Ăі�)�̂��ƂցA���Ԃ̒�q�ł��隢���E�ה͂����ƂƂ��ɖ������r�ɂ���B���̂��Ƃ͂��܂�m���Ă��Ȃ��B�̂��ɚ����͉�����ڂ̍���(����)�ƂȂ�A�ה͎͂R�������ċ�C�̂��Ƃō���R�J�n�̒��S���Ȃ����ƂƂȂ�B����͂���ɏC�s�ɐ�O����B�c�t�Ő��ɑ���ɉe�̂��Ƃ��]���A�w���ɂ͐g����q���ė����������B����͂��������߉ނƒ�q�����̊W��f�i�����A���̌�̓V��@�����ɑ���̍v�����ʂ������ƂɂȂ�B ����V�c�̌��B�c�t�Ő�����(822)56�B���܂�ɑ������鈣�����ʗ��B�������A����͔߂���ł���͂���Ȃ��B�c�t�Ő��̈⌾�ɏ]�������d�@�����̒����˂Ȃ�Ȃ��B���̓����A�^���@�̋�C��l�́A����V�c�̉A�ɂ����āA��ɐ^����ɖk���������V��@���y��i�����s���Ă����B����͂���������������̂Ȃ��A����܂łɔ|�������Ƃ����̐l���ƒ�Ƃ̍��X�ɂ���āA���ł����������d�@�����̒����ɑ������A�}�炸����C�̐^���@��������H���~�߂邱�ƂɂȂ�B���̑剶�͌����ēV��̖���݂̂Ȃ炸�a���ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������Ɏ����������M�̂�����(����)�́A����܂ł̘J���J���������B���݁A��������̑�܂�S���������t����(�d�v������)���A���育�����ɕ����Č�H(������)�܂��������Ƃ̋L�^����A���肪�܂�S����b�R�Ƌ��̓s��ޗlj��҂̋�J���ǂݎ���B����ɁA�u�`�q��S�����v(�d�v������)�̎��M��t�́A�c�t�Ő��̐��_���q�אh�������܂Ȃ��q���ł��Ȃ��M�d�ȉ����ł��B���M���I����56�͊�����c�t����̎��B�m���Ƃ��čō��ʂ̓`����@�t�ʂ����������̂��A��C�ɒx��邱��28�N�B���Ȃ݂ɁA��t��拍��́A���8�N(866)�Ő��ɓ`����t�A�~�m�Ɏ��o��t���������̂��{�M�ŏ��A�x��邱��55�N��C�ɍO�@��t��拍��ƂȂ�B�ӔN�ɂ������Č���́A���蒷�N�̌��J�ɑ���d�����܂�܂̂Ȃ��Ɏ������B�u���M�G��W�v�u�o���W�v�ȂǂɌ��肪�����������c����Ă���B����̐l�ƂȂ���u�����ɂ��ĕ��R�����Ƃ����A�鑴�̎��f���x�тĎ�ɗ����������v�ƋL����A���̍��X�����ׂ̂܂��B�l�G�Ս��Ȋ��̔�b�R�ł̐���50�N�B�c�t�Ő��Ƃ̋��̐���14�N�ԁB���ڂ̍��嚢���̎���A�{���ł���Α�O��ڂ̍���ɔC�����闧��ɂ���Ȃ�����A�����ČȂ�\�ɏo�����ƂȂ��A�ʓ��E�⍲(76��)�Ȍ�e���݂����߁u�ʓ���t�v�Ə̂���ꂽ�B����s��18�N�̒������o�āA���܂��܂ȓ����������Ȃ���A�V��@��b�R������Ђ�������A���U���d�̉����s�ɏI�n�����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�c�t�Ő��Ǖ�̏�[���A���E���ɂ߂��~�ς̐��m�B�����M�S���f���m�邱�Ƃ��ł���B�����t����̌�A�����y�@�c�t�Ő��̂��_���e�ɁA����������荇�������Ƃ����h�ȕ_������������Ă���B���F�ɖ��������u�ʓ���t���v���R�[�Ɍ�������B�������A�ߔN�ɂ�����A�����t�̌��т�Y��A�l�X����Y�ꋎ���悤�Ƃ��Ă���B�����������Ԃ��������̂͗l�X�v������������B�ɗ\�������S�o�g�A�ʓ���t����̐��i�ɂ��A�킪���́u�V��@�������v�����̂͗��j���ؖ�����^���B�S�ȗ���(�������肽�@���̂���킷�ꂽ���肷��)�V��̐��_������ɓ����˂A�傫�����q�̑c�t���a����ے肷�邱�ƂɂȂ�B�����̌̎��ɁA����Ղ��Έ�˂��@�����l�̉����v���Ƃ���B���݂������Y�ꋎ���悤�Ƃ��Ă���B�@�肨�����̂́u�ʓ���t����v���̐l�ł������B�������ǁA��t�̂��⓿�Ɏv�������炳�˂Ȃ�Ȃ��B �@
�́@�������Ɂu�z�O�����L�v�Ȃ镐�������葍�́i����Y�j�Ɠ�l�̖��i�L�P�A����P�j��ׂ����B��䂪�S���Ȃ��ȁi���w�@�j���}�������A���L���S���Ȃ����B���̎��㏬��Y�͏o�Ƃ����B �@
�������Ďo�P�i�L�P�j�͑��͍��̉E��V��ƍ������A�E��V���ڔ��u���v����B���P�i����P�j�͑㊯��F���ɂ̍Ȃ����̎���Ԗ[�����ƌ�����B �@
�㊯���ɓ@�ʼnƒ��ꓯ�������Ă̏j���̐ȂŌ�䖽�w�@�Ǝ����䑾�Y���q�傪�g��Ō�Ə������}��B�㊯���ɂ̈�q�|���̖��ƈ��������ɏ�����ɉ��S���邱�Ƃ�A�Ȃ����͋��N�ւ̒��`���Ă�\�����ė����ƂȂ�B���Y���q�傩�珬��P�̎E�Q�𖽂���ꂽ���ɂ́A����P��A��ĒE�o��}��B���S�͂����܂ŋU��ł������B �@
��� �@
���ɂƏ���P�͎R���ɗ������сA�����ŏ��[�����ƒ|���ƍĉ��B�����͕������������邪���₵����P���ɗ������т�����B���Y���q�傩�珬��P�E�Q�̉��������Ԗ[�����A�E���Z����ǂ����B �@
�v�w�A�Z��o���A�e�q�̂�����݂Ɗ����̒��Ő�N�E��Ƃւ̒��`���Ăŏ���P�̐g����ɂ����̎���؋��Ƃ��Ė��w�@�Ƒ��Y���q��̌��ɓ͂���B �@
��O�� �@
�o�Ƃ�������Y�͓���̈�Տ�l�ƌĂ�Ă���B�E��V��͓���ŏC�s���ł��邪���M�s�ʂ̖L�P���Y����Ȃ��B�L�P�͗V�s�ɏo�|�����l�ɏo����{���˗����A��ɔ�э������ƁA����O�ɂ��Ďڔ���t�ʼnE��V��ƍĉ���ʂ����B�u���𑁂݊�ɂ�����T���̊���Ă����ɉ���Ƃ��v���v�����A����B �@
�㊯���ɂ⏬��P�ƍ���������ɒH�蒅�����Ƃ���ɒǂ��肪�����h�킷��B��l�͋�X�E���ɏo��A�}������ɖ߂�ꑰ���ĉ��B��䑾�Y���q��͑����Ɏ�����ɗ�������ꑰ�̉�ł�}�邪�A�E���A�����A���ɂ̎�ɂ��E�����B�i�߂ł����߂ł����j �@
 �@
�@���u�̐���Տ�l�`�v ���a54�N(1979)�ē�/�����H
 �@
�@���w�� / ���莛(��������)
��Տ�l���u�얳����ɕ��v�����������Ė{���Ɍf�����Ƃ���A�ǂ�����Ƃ��Ȃ��ǂ����肪���A�Ԃ��~��A�������y���������A���_�ɗ����ꂽ����ɔ@����25��F�Ƌ��ɁA�̕��̕�F�ƂȂ����a���������B���莛���V�q�V�c�̒���ɂ���đn�����ꂽ���N������A����ɔ@����������y��萾�莛�ɗ��}�����͗l�Ȃǂ�`�������D���ȕ��������A�Ō�͕�F���O�݂Ȉꓯ�ɖ{���̘Z���̊z�ɍ�����q����̂ł������B�@
�����莛(���s�s��������V��)�@
���莛�͔���A�V�q�V�c6�N(667)�V�c�̒���ɂ��n������܂����B���Ƃ��Ƃ͓ޗǂɂ������̂ł����A���q�����ɋ��s�̈������(���݂̏㋞�挳���莛�ʏ��쐼����)�Ɉړ]���A���̌�A�V��19�N(1591)�ɖL�b�G�g�̎��������ɍۂ��Č��݂̎O�������̒n�Ɉڂ���܂����B�@
�����[���A�a���A�G�g�̑����E���̊ۓa���A�˂������Ƃɂ��A���l�����̎��Ƃ��Ė������A�܂����M�m�s�͓����ɂđP���u���C���A��Տ�l���O�����Z���s�Ȃ��܂����B�@
�����������A�@�R��l���������̑��r�m�s��蓖���������Ĉȍ~�A��y�@�ɂȂ�A���݂͖@�R��l�̍���E���R��l�P�b�[暋�̗�������ޏ�y�@���R�[���h�̑��{�R�ł��B�@
�u�s�����}��(���i9�N�k1780�l���s)�v�ɂ��܂��ƁA�\��͎����Z�p�A�k��͎O��ʂ�ɖʂ��A6500���̋����ɓ������@��18����������A�܂��O�d�����݂��܂��B�A ���̓����A�O���`�l���Ԃ́u�����ʂ�v�ɂ͑召11�����̎��@������A���������ɂ́A�����������̖傩��o�Ă͎��̖��������Ƃ������������ŁA�܂蕻�Ŏd��ꂽ�����ƂɓƗ����Đ���ꂪ�����Ă��܂����B�u���莛����֍s�����v�A�u����֍s�����v�Ƃ����A�V�т��Ӗ�����قǂɎ����E�킢�͗����������Ă����ꏊ�������ł��B�@
�Ƃ��낪�A�����ېV�Ő�N�]�������s�������ֈڂ�A�����̐헐�u�֖�̕ρv(�����̕�)�ŕӂ�͏Ă��쌴�ƂȂ��Ă��܂��܂����B���������₵���w�i�̂��ƁA�����ւ̎肪�����^���悤�Ɩ���5�N(1872)�A���̋��s�{�Q���Eꠑ������́A���łɎŋ������A�����������̏W���Ă������莛�����Ǝl���������オ�����ʒu�ɂ��������@������(���@�E�l��)�ɖڂ�����n(�v��)���A�O���`�l���ԂɐV�����H��ʂ��A��劽�y�X����낤�Ƃ����B���ꂪ���݂́u�V���ɒʂ�v�ł��B���̂��ߐ��莛�́A6500��L���Ă��������̓��A4800�]�̓y�n��v������邱�ƂɂȂ�܂��B�@
�����Z�p�ɐ��莛�̕\��(�l�r��)������A�ʏ́u���炽���v(�V���ɎO������)�ƌĂ���ɂ́A����30�N���܂Ő��莛�̍���(�k��)���������Ƃ������Ƃ́A�����n�����������ł͒m��R������܂���B�@
�܂����莛�͋��s�̒��S�n�Ɉʒu���邽�߂ɐ헐���̉e�����₷���A����܂�10����̉Ђɑ����Ă��܂��B�������A���̂��тɑ����̐M�҂����ɂ���čČ�����Ă܂���܂����B���݂̓S�R���N���[�g�̖{���͏��a39�N(1964)�Ɍ��Ă��܂����B�@
�x�d�Ȃ�Ύ��̔ߌ��́A�������đ����̐l�X�莛�Ɍ��������A�O���̐M�����ł����̂ł���܂��B �@
����ˁ@
������̍�Ɠ`������w�ȁu���莛�v�́A�a���ƈ�Տ�l����Ȗ��ƂȂ��Đ��莛�̉��N�Ɨ쌱���܂��B�@
���̗w�Ȃ̒��ŁA�a�����̕��̕�F�ƂȂ��Č���邱�Ƃ��A�\�y���͂��ߕ��x�Ȃnj|�\�̐��E�ő�������A�]�ˎ��ォ�琾�莛�֎Q�w���邻�̋̐l������������܂����B���ɕ��x�Ƃ������A�����E�����E�V��(1804-44)�̂���ɋ��s�Ŋ����˗��̑c�E�˕��O�Y(�~��)�́A�K��̌n�������\�y�I�ȐF�ʂƉ̕��I�ȐF�ʂa�������D�ꂽ�|�����������Ƃ����A�V�۔N�Ԃɂ͎R�����ƂƂ��ɋ���ő傢�ɗ��s���܂������A�ނ畑�x�Ƃ̒��ɐ��莛�̘a���M������܂����B�@
���̐M���A���a�E�����̎���܂œ`���������x�Ƃ�����܂����B���莛�́u��ˁv�Ɍ|����B���F�肵�āu��q�v���[���邱�Ƃɂ́A���̂悤�Ȑ[�����j�I�ȈӖ�����߂��Ă���̂ł���܂��B�@
�܂����莛��55���A���`������l(1554-1642)���u�����i8�j�v�삵�ė���̑c�Ƌ���Ă����邱�Ƃ��A�u��q�v�Ƃ̋����J��ێ�����䂦��ł���܂��B�@
���������O�}����(�㐙�{)�đ�s��/����@
�����Ɏ�������̐��莛���`����Ă��܂��B�{���E���Ɂu��������v�Ə����Ă���܂��B�������ɂ��鍠�̐��莛�ŁA�V��5�N(1536)�̖@�̗��ɂ�艊��(�S��ڂ̉�)���A�V��8�N(1539)�ɏ㓏���ꂽ���̐��莛�ł���Ǝv���܂��B��ʓ��̐l�X�ɒ��ڂ���ƁA��O�ɂ͓��Ђ��������������Q�w���Ă��āA���̑��ɂ͕������l�����荞��ł��܂��B�܂��{���E���̒��Ɏ��t����ꂽ�u�@�ցv��]����Q�w�l�̎p��A�{�������Łu����v�̌o�ؑ����k�ɕ����������Ă�����Ă���Q�w�l�̎p�������܂��B��O�����ɒ��ڂ���ƁA����������Ԃ����u�Ԏt�̓X�v���A�܂��A��ʉE�[�ɂ͊i�q���ɉ��{���|�𗧂Ċ|�����u�|���v���`����Ă��܂��B���莛�͂܂������u�����v�ɂ����ėl�X�Ȑl�X���o���肷��M�̏�ł����B�@
�����S�@(���s�s�����撆�ؒ�)�@
���莛�̓�A���X�X�̒��S�ɂ���B��������ɓ����������a���̂��߂Ɍ����������������̋N����Ɠ`�����A�ʏ̘a�����̖��Œm���Ă���B�{���ɂ͘a���̖@�̑��Ɠ����̑������u����Ă���Ƃ����B�����ɂ͎����̕�Ɠ`����傫�ȕ�⸈�����B�����ɂ͎��������O�������u���[�̔~�v�ɂ��Ȃ�Ō�ɐA����ꂽ�Ƃ����~������A���̖T��Ɂu�����@�t�������Ɓ@���Ԃ��@����ɂ����́@�����҂����v�Ǝ����̉̔肪���Ă��Ă���B �@
 �@
�@���̂��̌�Ǝ�q�w�E�z���w
����q�w�Ƃ��̔w�i�@
���ꂩ���q�w�̂��b�ł��B��q�w�͍]�ˎ���Ɋ��w�Ƃ��đ��d����܂����B���̂��ߎ�q�w�́A���{�l�̃����^���e�B�[�ɐ[���e�����������Ǝv���܂��B������A��q�w��������x�m�邱�Ƃ́A������m��Ƃ����Ӗ��ł��K�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ɩl�͎v���Ă��܂��B�@
��q�w�͑v�̎���Ɏ���(��q)�ɂ���Ċ������ꂽ��w�ŁA�v�w�Ƃ������܂��B�܂���q�w�͓V�̗��ƌ������Ƃ��������邽�ߗ��w�Ƃ��Ă�܂��B�܂��p��̕����Ȃǂł́Aneoconfucianism�@�܂�V�Ƃ悭�\������܂��B����ł͐V�����Ƃ͂ǂ������Ӗ��ł��傤���B����ɂ́A��q�w��������������w�i��m��K�v������܂��B�@
�Z���E�@�E���̖�700�N��(���ŖS220�N����v����960�N)�͒��������̉�������ƌ����܂��B�@��ɂ͓V��@�A����ɂ͉،��@�Ɠ��{�ɑ傫�ȉe�����������������v�z�����܂ꂽ�̂����̎����ł����B�����l����ƁA���{�̌Ñ㍑�Ƃ̌`�����Əd�Ȃ邱�̎����ɁA���{�����������̊�Ƃ��悤�Ƃ������Ƃ͂������R�̂��Ƃł����B���̊Ԃɂ͐����ƕ����̒S���҂̎m��v�w���唴�M���ł����B�ނ�͊����ł���Ȃ��琭���Ɋւ���S���Ⴍ�A���w�A�|�p�A�N�w�A�@���ɋ����S�����߂��܂����B�@
�������A�����ܑ̌�̍������ɑ����̖唴�M�����v�������܂����B�����č����̒����璆�����ē��ꂵ���̂��v�ł����B�v�̐����̓��F�͕��������ɂ���܂��B�ߓx�g�Ȃǂ̌R�l���͂������Ƃŋ��S�͂������������̎�����ӂ݂āA�v�ł͌R�l�������l���d�����܂����B���̑�\�I�Ȍ��ꂪ�ȋ��̐��x�ł��B��l�̗p�����ł���ȋ��ł́A���E��Ƃ����Ă悢�قǂ̓�ւ�˔j�����҂݂̂����i��������邱�Ƃ��ł��܂����B�ȋ��͍̉ŏI�I�ɐ��я��ɏd�˂��܂��B���̌��ʁA��ԏ�ɂ͎�Ȃō��i�����҂̓��Ă����̓��Ă�������悤�ɒu����܂����B���̐l�̓��Ă̏�ɂ����ꂽ���߁A���̓��Ă̂��Ƃ��u�����v�ƌĂ����ł��B(�u�̎O��N�v�w�b)�����炭�u�����v�Ƃ���������������R�������悤�ɏo�F�̏o���������̂ł��傤�B�ȋ��̓�ւ�˔j���Ė�l�ƂȂ����U���̎m��v�w�͈�����̊����Ƃ��āA�k����������̈����̒��ŁA���Ƃ̂��߂ɐ^���ɐ����ɂ����g�݂܂����B���̂悤�ȐV���̒m���l�̉ۑ�́A�����v�z�Ƃ��Ă̎v�z�̍ċ��ł����B�������̎v�z�Ƃ��Ă͂�͂�ȊO�ɂ͂Ȃ��B���̂��߂ɐV���Ɏ���������邱�ƂɂȂ�܂����B�@
�E�q�Ɏn�܂�v�z�͂��Ƃ��Ɛ��E��F���ɂ��Ă̓N�w�I�Ȏv���������Ă��܂����B�������A�V���v�z������@������̕����ɂ͑s��Ȑ��E�ς�����܂��B���̂��߂ɁA�V���v�z�╧���ɑR���邽�߂ɁA���E�ς��̊m�����K�v�ł����B�v�w�A���w�ȂǂƂ��Ăꂽ��q�w���V��w�ƌĂ��̂́A���E�ς�F���_���Ƃ��Č��܂�ς�������߂ł����B�@
������(��q) (1130-1200)�@
��q��19�ʼnȋ��ɍ��i���A�����̖���ɂ�50�N�ԓo�^����܂����A���ۂɊ����Ƃ��Ċ��������̂�9�N�Ԃł���A�Ǘ��Ƃ��ĉh�B�����Ƃ͂����܂���B�������A�����Ƃ��Ă͔M�S�ȍs���������Ȃ��܂����B��Q�[�̋~�ρA�s�����Ȑŋ��̔p�~�A��l�̑��q�̕s�n�������ݏ������Ƃ��铮������������ȂǁA�M�S�Ɏd���𐋍s���܂����B�ނ������Ƃ��Đ��n�Ȑ����𑗂��Ă������납��A�ނ̎���ɂ͖������������đ����̋����𐿂����̂��W�܂�܂����B�ނ̎���͎�q�w�͔��Q���܂��B��q�w�Ƃ����ƁA���w�ł���ێ�I�Ƃ̌Œ�ϔO������ꍇ������܂����A���Ȃ��Ƃ��ނ̎���ɂ͕ێ�I�v�z�ł͂܂���������܂���ł����B�@
�����C�_�@
��q�w�ɂ��ƁA�l�Ԃ��܂ނ��̐��E�E�F���͋C���琬�藧���Ă��܂��B(�`�����̐��E)�@���̐��E�͋C�Ƃ�������Ε������琬�藧���Ă��܂��B�n���ɂ����ċC������A���̋C�ɂ͓��Â�����܂����B���̋C�͗z�C�ł���A�Â̋C�͉A�C�ƂȂ�܂��B�z�C����͖Ɖ��A�A�C����͋��Ɛ������܂�܂��B�܂��y�͂����̗v�f���܂Ƃ߂錾��u�j�K���v�̂悤�Ȗ������͂����܂��B���̂悤�ɂ��āA�����̓`���I�ȉA�z�܍s�����琢�E�̐�������������܂��B�@
���̐��E�́A�������Ȃ���A�������ł͂Ȃ��������Ă��Ă��܂��B�G�߂͏t�ďH�~�ƋK���I�ɂ߂���A�`�̎킩��͊`�̎����Ȃ蓍�͂Ȃ�܂���B���̂悤�ɁA���E�𒁏��Â��A���E�������Â��Ă�����́E�����̖{���𗝂ƌĂт܂��B���Ƃ͐��E�𐬂藧����������^���Ă��܂��B��������̂ɁA�X�����ہA���R�ɁA�����ĎЉ�ɒ�����^������̂����u�V����Ȃ����́u���v�ƌĂ��`����̌����ł��B�����ŗ����x�z������̂�X�����ۂ��ׂĂƂ��������łȂ��A�Љ����ܗό�ƌĂ��̓��ڂ��u����Ƃ����Ƃ���ɁA��q�w���ł��鏊�Ȃ�����ł��傤�B�@
���l�Ԙ_�@
�����͗��ƋC���琬�藧�ƌ����܂������A����͓��R�l�Ԃɂ��Ă������܂��B�l�Ԃɂ����闝�Ƃ͖{�R�̐��ł���A�C�͋C���̐��ł��B�{�R�̐��͂��ׂĂ̐l�ɋ��ʂł����A�C���̐��͐l�ɂ���ĈقȂ�܂��B��q�w���X�̐l�Ԃ̋��(�g��)�F����̂��A�l�Ԃ��\�����Ă���C�͐l�ɂ���ĈقȂ�Ƃ������Ƃ������ɂ��Ă���ł��傤�B�������A��Ȃ��Ƃ͋C���̐��ɂ���ē܂炳��Ă���{�R�̐�(��)�ɖ߂藝�����߂邱�Ƃł��B���̂��߂Ɏ�q�͓�̂��Ƃ��d�����܂����B�@
��́u�h�v�Ƃ������ƂŁA����̐U�镑���̈ꋓ�����ɂ�����܂ŗ��ɂ��Ȃ�������悤�ɓw�߂邱�ƁB���h�܂��͎��h�ƌĂ�A�p�����������ċ݂𐳂��ė�V�ɂ��Ȃ����p������ʂ����Ƃł��B��q�w�͓V���Ɛl�~��Δ䂵�āA�~�](�l�~)�������ēV���ɏ]�������d�����܂��B���̂Ă�ł͎�q�w�̓��S���X�e�B�b�N(���i��`�I)�Ƃ��������܂��B��q�w�̌`���ɑ傫�Ȋ�^�������l���ŁA��q���h�����Ă�܂Ȃ��������ɐ�́A�u�쎀�ɔ���ꂽ�Ǖw�̍č��͋�����邩�v�Ƃ̖�ɑ��Ď��̂悤�ɓ����������ł��B�u����͒�߂������s�ׂł���A�������ׂ��ł͂Ȃ��B�쎀�̂��Ƃ͋ɂ߂ď��̂��Ƃł��邪�A�߂��������Ƃ͋ɂ߂đ�ł��飁@
���ƈ�͊i���v�m�܂��͋����ł��B�����̓����ł���V����Nj����邱�Ƃ���q�w�͏d�����܂����B�����Ɏ�����(�i��)�@�m�ɓ��邱�Ƃł��B��̓I�ɂ͎������ώ@������A�u�l���v�u�܌o�v�ǂ��邱�Ƃł����ɓW�J����Ă��闝��m�낤�Ƃ��邱�Ƃł��B��q�w�͋ߑ�I�Ȏ��R�Ȋw�Ƃ͈قȂ�܂����A�����ւ̒T�����_�������Ă��܂����B���h�Ƌ����͊��S�Ȑl�i(���l)�ɓ��邽�߂̎�q�w�̏d�v�ȕ��@�_�ł����B�@
����̒����͎ɂƂ��Ă͎��̎���ł����B���̎���قǎ�҂��������܂ꂽ���Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B�@
���̌�A�������̍��Ƃł��閾�������ꂷ��ƁA�ȋ��͕������܂��B�܂���q�w�͊��w������܂����B���̂悤�Ȓ��ŁA���z���ɂ���ĊՐÂ��ꂽ�z���w�́A��q�w�ɑR����L�͂Ȏ�w�ƂȂ�܂����B�@
�����z�� (1472-1528)�@
28�ʼnȋ��ɍ��i�B35�Ŏ��̌��͎҂ɋt����č��J���ꂽ�ނ́A�n���Ƌ�Y�̒��ŁA�v��̗��ێR�̎v�z���p���A�z���w�Ƃ��Ċ������܂����B�@
�z���w�̊�{�ɂ́u�S�����v������܂��B�S�����Ƃ͎�q�w���咣�����������x�z���闝��S�̒��ɂ̂ݔF�߂闧��������܂��B��������̋c�_�ł����A�z���w�����q�w�ɑ��ĂȂ��ꂽ�ᔻ������A���ꂪ�킩��₷���Ǝv���̂ŏЉ�܂��B�@
�ŏd������Ă��铿�ڂɁu�F�v������܂��B�Ƒ���������{�Ƃ���ɂ����ẮA�e�ɑ���v���Ƃ�������F�͂����Ƃ��d�v���������̂ł��B��q�w�ɂ����ẮA�F�Ƃ͐e�Ǝq������Ƃ����̊Ԃɂ͍F�Ƃ��������x�z���Ă���ƍl���܂��B�������A�����Ȃ�A�����e���S���Ȃ����ꍇ�͂ǂ����B��q�w�̗��ꂩ��͍F�Ƃ������͂����łȂ��Ȃ��Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�������A�����ɂ͐e���v���F�͎q�̐S�̒��ɂ��葱����B���Ƃ͎������x�z�������̒��ɂ�����̂ł͂Ȃ��A�S�̒��ɔ���������̂��A�Ƃ����̂��S�����Ƃ������Ƃł��B�@
���̂悤�ɐS���d������z���w�ł́A���ʂ̐��������f�͂Ƃ������A�ϗ��I�����u�ǒm�v�Ƃ��đ�ɍl���܂��B�l�Ԃ̓��ɖ{���I�ɒN�ɂł���������ǒm���\���ɔ������邱�Ƃ��u�v�ǒm�v�Ƃ����܂��B�z���w�́u�v�ǒm�̗ϗ��v�Ƃ����܂��B�@
�z���w�̓��F�̂ЂƂɒm�s���ꂪ����܂��B���̒m�s����́u�m���Ă���Ȃ��������H���Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�m�ƍs�Ƃ͌����s���ŁA�s�Ƃ킯��ꂽ�m�͖{���̒m�ł͂Ȃ��Ƃ����܂��B�l���Ă݂�u�m��v�Ƃ����s�ׂ��̂��̂��A�����ɒm�I�ȍs�ׂƂ��������A����Ӗ��ł͂��̒m�낤�Ƃ��铖�̃��m�Ɍ�����(�D��A�������肷�邱�Ƃ��܂�)�Ƃ����s�ׂ�O��Ƃ��Ă��܂��B�܂��́A�����������炱�̂悤�Ɍ����邩���m��܂���B�u�F��v�Ƃ��u���v�Ƃ������ɂ��Ę_����l���A�����A�{���ɗF��∤��������������Ă��Ȃ��Ƃ���Ȃ�A�{���͂��̐l�́u�F��v��u���v��m��Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����낤���B�u�m��čs�Ȃ킴��́A�m�炴��Ȃ�v�Ƃ������z���̌��t������܂��B���Ȃ��Ƃ��A���̒m�����̐l�ɐl�����������ނƂ������A���̐l�̐������ɔ��f�������̂łȂ��Ƃ���Ȃ�A�{���̒m�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B�@
������ɂ��悻�̈Ӗ��ł́A�z���w�͎��H�I�Ȋw��ł��B�����ɖ��{�ɔ�����|�����剖�����Y���z���w�҂ł����B����㒬�^�͂ł���Ȃ���A�V�ۂ̑�Q�[�̎��̖��O�̋���������ł����ɋ����̌v��𗧂Ă�ɂ��������ނ̕��X�Ƃ����C���̂Ȃ��ɁA�z���w�҂Ƃ��Ă̑剖���V���݂邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�@
�]�ˎ���͓��{�l�̃����^���e�B�[�ɑ傫�ȉe�������������ƌ����܂��B���̒��ł���q�w��z���w�Ȃǂ̎�w�͏d�v�ł��B�@
��q�w�͓��{�l�̒��ɂ����̉��l�ς�A���t�����悤�Ɏv���܂��B�w�Z�ł��A���ɐ搶�����k�ɑ��āA�u�p���������B�����ƋC���������߂ăV���L�b�Ƃ���v�Ǝ��ӂ���Ƃ��A���̂悤�ȋC�����̔w��ɂ͎�q�w�I�ȁu�h�v�̗ϗ�������Ǝv���܂��B�������A��q�w�͈���ԈႦ��ƒ��g�̂Ȃ����i��`�Ƃ̔ᔻ���邱�ƂɂȂ�܂��B����̗����U�镑���ɂ��āA�ꋓ��������Ƃ����ɂ��Ȃ��悤�ɂƂӂ�܂��Ƃ��A�O����͌��R�����҂Ɍ����悤�Ƃ��A���g������Ȃ��A�Ɣᔻ�����͈̂ɓ��m�ւł����B�ɓ��m�ւ́A��q�w�̂悤�ȓ��ʂƊO�ʂ̕s��v��ᔻ���āA���ʂƊO�ʂ̈�v���u���v�Ƃ������t�ŕ\�킵�����Ƃ͂悭�m���Ă��܂��ˁB�z���w�̊�{�ɂ���q�w�ɑ��铯�l�̔ᔻ������܂��B�z���w���u�S�v���d�����A�S�̓��ɓ��݂���u�ǒm�v��s�������Ƃ���������̂����̌���ł��傤�B�@
�������A����ŗz���w�ɑ���ᔻ������܂��B�ї��R�͗z���w��ڌ�̊w�Ɣᔻ���܂����B�u�ڌ�v�Ƃ͑T�@�̂悤�ɏC�s�̓r��œˑR�Ɍ����J�����ƂȂǂ��Ӗ����Ă����Ǝv���܂��B���̌���ł͕K�����������Ӗ��ł͂Ȃ��ł��傤���A���R�������ڌ�Ƃ́u��ϓI�v�Ƃ̔ᔻ���ӂ���ł��܂��B�������^�ɐS�Ŏv�����ƁA�������Ɗm�M�������Ƃ��A�{���ɐ��������͂ǂ��ŕۏ����̂��A���ꂪ��ϓI�Ō��łȂ��Ƃǂ̂悤�ɂ��ďؖ������̂��A����͌Â��ĐV�����N�w�̍��{���̈�ł��B��q�w�̑�����̔ᔻ�́A�z���w�̎�ϐ��ŁA��ϓI����邽�߂ɂ��i���v�m���K�v���Ǝ咣���܂��B��q�w�͕ێ�I�Ŗ����ȍ~�̋ߑ㉻�ɗ����͂�����O���I�̈╨�ƌ����邱�Ƃ��������ł��傤���A��q�w���S�͋ߑ�I�Ƃ͌����Ȃ��܂ł��u�i���v�m(����)�v�Ƃ����Ȋw�I���_�����Ă������Ƃ͌������ĂȂ�Ȃ��ł��傤�B�@
������ɂ���A��ɂ������u�F�v���߂���z���w�̎�q�w�ᔻ�Ɍ�����悤�ɁA�]�ˎ���͎I���ڂ͈̔͂ł̎v����_�����W�J����܂����B���̈Ӗ��ł́A��q�w�A�z���w�A�Êw�Ȃǂ̃O���[�v���z���āA���]�ˎ���̓��{�l�̃����^���e�B�[���x�z���Ă������ƁA�����āA���̖��c�Ƃ��āA���݂̓��{�l�̂��̂̍l�������ɂ����Ȃ���ʉe����^���Ă��邱�Ƃ͊m���ł͂Ȃ��ł��傤���B �@
 �@
�@���b�M��̏��� / �����ɐ����������̏���(�e�a�̍�)
�u�b�M���v�͎j���Ƃ��Ă͌Â��̂ł����A���ꂪ�c�����邱�Ƃ́A20���I�܂ł��܂�m���Ă��܂���ł����B1921�N�ɁA�h������(1875-1928)�Ƃ����^�@�j�̊w�҂��A���s�̐��{�莛�̕ɂ̒������s�Ȃ��Ȃ���A���̎莆�����R�ɔ������܂����B������2�N�̌�A�܂�1923�N�ɁA�u�b�M���̌����v�Ƃ����{�ł��̎j���𐢂ɏЉ�܂����B���̌����ɂ́A�莆�̎ʐ^�ł������ł��ڂ��Ă���܂��B�h���搶�̑����̓w�͂ŁA�u�b�M���v������ƍL���m����悤�ɂȂ�܂����B�������A���̓��e�ɑ����̖�肪�܂܂�Ă��邱�Ƃ���A�h���搶�̍Z���́A����Ӗ��Ō����̏o���_�ɂ����Ȃ������ƌ�����ł��傤�B��̓I�ɂ����ƁA���������A�ϑ̉����A���Ď��A�����ً`�̌��t�A���͂⌾�t�̐���A�̂̕����A�������Ō����Ȃ��Ȃ������Ȃǂ̖��ŁA�u�b�M���v�͂��Ȃ��ǂ��ɂ����j���ƂȂ��Ă���̂ł������܂��B�ł�����A�h���搶�̂��������o�Ă������65�N�ɂȂ�܂����A�w�҂̉�ǁE�����͌��݂ł������Ă����Ԃł������܂��B�@
�h���搶�̂����������\���ꂽ����ɂ́A�e�a�̓`�L�ɂ��Ę_��������܂����B����́A������u�e�a ���E�_�v�Ƃ����_���ł����B���̘_�́A�ȒP�Ɍ����ƁA�e�a�͗��j��̑��݂��A���邢�͉ˋ�̐l�����A�Ƃ����_�c�Ȃ̂ł��B���̖��E�_�͓�̏؋��Ɋ�Â��Ă��܂��B���̈�́A�e�a�ɐG��銙�q����̌Õ����Ȃǂ̎j���́A�^�@�̒��̂��̂������A����c���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̓�́A�^�@�̒��̐e�a���A���ɉh���ɋP�����l�`�̃C���[�W�́A���S�N���̒����Ԃɍ��グ�����̂ŁA���܂���j�I�ȐM�����������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�]���āA�e�a���{���ɐ����Ă����̂����m�߂邱�Ƃ͏o���܂��A�������Ɖ��肵�Ă��A���̐��U�̊�������̓I�ɒm�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ł����B���������̒��ɁA�u�b�M���v�����߂ďo�ė����̂ł����B���̎莆�̓��e�ɂ́A�e�a�̐������o���������肠��Əq�ׂĂ��邱�Ƃ���A�e�a�̐����Ă������Ƃ��A�������Ƃ��m�F�ł��A���E�_�͏��ł��邱�ƂɂȂ�܂����B�����āu�b�M���v�́A���j��̐e�a�̌����̂��߂ɁA���̎j���̈�Ɉʒu�Â����܂����B���݁A�e�a�̓`�L�̌����ŁA�u�b�M�����Ɉˋ����Ȃ����̂͂߂����ɂ���܂���B�@
���́A�h�N�^�[�_���̌������s�Ȃ������ɁA�u�b�M���v�����߂ēǂ݂܂� ���B���̎��́A�e�a�̂��Ƃɋ���������܂����̂ŁA���̎莆���j���Ƃ��ĕ]���������Ƃ������Ƃ��ēǂ̂ł����A�莆��ǂ�ň�ԋ������̂́A�e�a�Ɏ����I�ɐG���莆���A���Ə��Ȃ��Ƃ������Ƃł����B���̓��e�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�b�M��̂��ƁA�܂�ޏ��̓��퐶���A�ϔO�A��]�Ȃǂ����|�I�ɑ����̂ł��B���̂��Ƃ�������₢�Ȃ�A���͂��̎莆�̂��L�����j�I�ȉ��l�����o���܂����B���Ȃ킿�A���̕����͐e�a�̓`�L�����ɂƂ��Ă����łȂ��A��y���̈�ʓI�ȐM�҂̐M�A�����ď����̎���A����ɂ͓��{�̊��q����ɂ��������̐�������l�X�ɕ\�킷�j���ƌ��Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���ݍs�Ȃ��Ă��鏬�����́A�o���邾���e�a�̖�肩�痣��āA�莆�̕ʂ̖ʂׂ悤�Ƃ�����̂ł��B�@
���u�b�M���v�̌��������ɂ��ā@
���āA�u�b�M���v�̓��e�ƈӋ`�ɐG���O�ɁA���̌��������̖����O�q�ׂ����Ǝv���܂��B�莆���̂��̖̂��͘h�������搶�̎��ォ�瑽���̗D�ꂽ�w�҂���苓���āA�K���ɑ啔�����������Ă��������܂����B���̑��̖��͎莆�̐��Ƃ������Ƃł��B�h���搶���������������ɁA18���̌���������܂����B(���̂ق��A�u���ʎ��o�v�Ƃ������T�̈��p�ʖ{���t���Ă��܂������A�莆�Ƃ��Đ����邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ŁA�����ł͏����Ēu���܂��B)����18���������̎莆�ɂȂ邩�Ƃ����_�ɂ��ẮA���낢��Ȑ�������܂��B�h���搶�́A�������Z���������ɁA10�ʂ̎莆�ɐ������܂����B�������A�����A�����Ȃǂ̗��R�ŁA9�ʁA�܂���11�ʂ���Ȃ��Ă���Ƃ�����������܂��B���ł�10�ʂƂ������ƂɁA��́A����ł͂Ȃ��Ă��܂����A�ł̏����A�����Ď莆�̕������́A�h���搶�̍Z�����班�X�ς���Ă��Ă��܂��B�@
���̑��̖��͎莆�̔N������ �m���邱�Ƃł��B10�ʂ̓��A3��(��1.2.5)�ɂ́A�N�������t���Ă���A�ق���4��(��4.8.9.10)�ɂ́A���Ɠ��������L����Ă��܂��B���Ƃ�3��(��3.6.7)�ɂ́A���̓��t��������܂���B�������K���ʂ̃q���g���A�莆�̒��Ɍ��t���邱�Ƃ��o���܂��B���̈�͌b�M��̍ł��B4��(��7-10)�ɂ͔ޏ��̍��L����Ă���A���̓�2��(��9.10)�ɂ́A���ꂽ�N�����x�̓Ђ̔N�Ƃ����`�ŏ����Ă���܂��B������́A2��(��4.8)�̎莆�ɁA�����ꂽ�N���ʂ̎�ŏ������܂�Ă��܂��B����́A���炭�莆�̎�M�҂ł���o�M��A���邢�͊o�M��̑��ł���o�@(1270-1351)�����������̂ŁA���Ȃ�M�����������ƕ]������Ă��܂��B���������l�X�ȏ؋��Ɋ�Â��āA�S10�ʂ̏����ꂽ�N�A������̂͏����ꂽ���܂ł��A�m�邱�Ƃ��o���܂��B����ɂ���ď����ꂽ�������������Ă��܂��B��ԑ����̂�1256�N�A���Ȃ킿�b�M�����N��75�̎��̂��̂ŁA��Ԓx���̂�1268�N�A�b�M��87�̎��ɏ������莆�ł��B�����̎莆�͌b�M��̔ӔN�̏�Ԃ��悭�\���Ă��܂��B�@
���̎��̖��́A�莆�̕����̉�ǂł��B�ޏ��̎莆 �̕����́A�啔���A�������ŁA���X�ɕЉ����⊿���������U�炵�Ă���܂����A�V�N�̂��������⒎�����łȂ��Ȃ������Ȃǂ̖��ŁA�䂪���Ȃ�o�Ă��āA��ǂ̘_�������Ȃ�����܂���ł����B���̂����A���_���t���Ă��܂���̂ŁA�Ⴆ�Α�8�ʂɂ����s�A�u���Ƃɂ́A���Ƃ��ɂĂ��͂��܂���ւ́v�Ƃ����ӏ��́A�莆�̎�M�҂ɑ��Č����Ă��镶��Ȃ̂ŁA���̎莆�͖��ł͂Ȃ��A�ʂ̐l�ɑ��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����_�����A��������܂����B���ǁA���̉����́u���Ƃ��v�Ƃ������t�ɑ��_��t���āu���Ƃ��v�Ɠǂ݁A�Ì�̖��q�Ƃ����Ӗ��ɉ�ǂ��邱�ƂŁA�������t�����܂����B���̂悤�Ȗ��͐���������܂������A���ł͊w�҂̑����̓w�͂̂������ŁA��ǂ̖��ɂȂ�ӏ��́A10���P�������c���Ă��܂���B�����āA�����������̉ӏ��ɂ��A�����͂̂��鉼�������Ȃ�o�ė��Ă��܂��B�@
���u�b�M���v�̊T���@
���āA���ɂ͎莆�̓��e�ɐi��ōs�������Ƒ����܂��B�܂��A�u�b�M���v�̓��e����ɊȒP�ɏq�ׂ����Ǝv���܂��B�莆�́A���e�̏ォ�猩��ƁA�O�̃O���[�v�ɕ��ނ��邱�Ƃ��o���܂��B���̕��ނ́A�K���Ɏ莆�̔N�����̏����ɂ҂����蓖�Ă͂܂��Ă��܂��B�ŏ��̃O���[�v�͑�1�ʂƑ�2�ʂ���Ȃ��Ă��܂��B���̓�̎莆�͋���1256�N�ɏ����ꂽ���̂ŁA�����Ƃ�����Ƃ����@����̏��ނł��B���̓��e�́A�b�M���̊o�M���7-8�l�̉��l�����낤�Ƃ������S��`�������̂ł��B���l�Ƃ����̂́A���̎���̍ʼn��w�̘J���҂ŁA���j�Ƃɂ��ƁA�z�ꂩ�_�z�ɋ߂��g���̐l�̂��Ƃł��B���l�͓y�n�Ƌ��Ɍb�M��̍��Y���\��������̂������̂ł��B���̍��Y�̈ꕔ�𖺂ɏ��邱�Ƃ��A���̏���Ő����ɕ\��������ł��B�������A���̉��l�͂����Ɋo�M��̏��֍s�����̂ł͂Ȃ��A�b�M����ɁA�o�M��̂��Ƃ֍s�����悤�ł��B�]���āA���̎莆�͈⌾���̂悤�Ȃ��̂Ɖ��߂��Ă��悢�Ǝv���܂��B���̉��l�͌�̎莆�ɂ��G��Ă���܂����A���������莆����A�����̉��l�̎���ق�̂�����ƉM���܂��B�@
���̎��̃O���[�v�͑�3�ʂ����6�ʂ܂ł̎莆����Ȃ��Ă��܂��B����4�ʂ͑S��1263�N�ɏ����ꂽ���̂ŁA�b�M��̕v�A���Ȃ킿�e�a�ɂ������莆�ł��B����4�ʂ́A�ԈႢ�Ȃ��A�e�a�̖S���Ȃ������Ƃ�`�����o�M��ɑ��āA�b�M�Ԏ��Ƃ��đ������莆�ł��B���̓���3�ʂƑ�5�ʂ́A�e�a�̐��U�̏o�������q�ׂ����̂ŁA���Ȃ蒷�����̂ł��B���Ȃ킿���̑�1�́A�e�a����b�R�̓V��@�̏C�s���ꂩ�痣��āA���s�̘Z�p�����Ă�A�������q���Ӗ��[�������������閲�����āA��������������Ƃ��ď�y�@�̊J�c�A�@�R(1133-1212)�̒�q�ɂȂ����Ƃ����o�����ł��B�����Ă�����́A�e�a��1231�N�ɕa�C�ɂȂ�A�a���ɕ����Ȃ���@���I�Ȏ��o��̌��������ƁA�܂�~���ׂ̈̐l�Ԃ̗l�X�ȓw�͂͌��ǂނȂ������̂ŁA����̌v�炢�����߂āA������S�Ɉ���ɕ��̂͂��炫�ɔC������ق��ɁA���͂Ȃ��Ƃ������o�̏o�����ł��B���̓�̎莆�́A�����܂ł��Ȃ��A�^�@�̊w�҂̊S�������āA�W���I�Ɍ��������悤�ɂȂ�܂����B���̔����œO��I�Ȍ����̈��Ƃ��āA��3�ʂ̒ǐL�̒��ɂ���u���m�v�Ƃ������t���߂��錤�����グ�邱�Ƃ��o���܂��B�b�M��ɂ��A�e�a�͔�b�R�ɂ������A�u���m�v�A�܂肨���̓��̑m���Ƃ������ɂ��Ă����Ə�����Ă��܂����A�w�҂͂���Ȃɋ͂��ȕ���ɂ���Ă��A�e�a�̏@���I�Ȕw�i�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ��āA���̎���̕������L�����ׂāA�u���m�v�Ƃ͋�̓I�ɂǂ�Ȃ��̂������̂���m�낤�Ɠw�͂��܂����B�܂���3�ʂ̂�����̖ڗ������v�f��Y��Ă͂����܂���B����͌b�M�g�̖��̘b�̂��Ƃł��B�ޏ��͖��̒��ŁA��l�̐e�a�͊ω���F�̉��g�ł���Ƃ����ڊo�������܂����B���̖��͐�10�N�O�̂��̂ł����A���̎�����A�b�M��͐e�a����ʂ̑��݂Ƃ��đ��h�����̂ł��B���̂��Ƃɂ���āA�b�M�����̐^�@�̊J�c�M�̐��҂Ƃ��ĔF�߂Ă������Ǝv���܂��B�@
���̑�3�Ԗڂ̃O���[�v�́A��7�ʂ����10�ʂ܂ł� �莆����Ȃ��Ă��܂��B����4�ʂ�1264�N����1268�N�̊Ԃɏ����ꂽ���̂ŁA�b�M��̎����̋߂Â��������̎莆�ł��B���̃O���[�v�̎莆�ɂ́A�O�̓���b�M��̓���o����o�������悭�`����Ă��܂��B�Ⴆ�A�N���̔Y�݁A�a�C�A�V�l�ڂ��Ƃ����b�����X�ɏo�Ă��܂��B�܂��A�Ƒ��̘b�A���Ɋo�M��̑����ւ̊��ӁA�������̐����⊈���q�˂���̂Ȃǂ��܂܂�Ă��܂��B�܂��A�Q�[�Ɨ��s�a�ɂ��G��Ă���܂��B���̋��̌��ʁA�b�M��̉Ƃɂ������l�̉��l�́A��l���q��������ł��܂��܂����B�܂��Ƃɖ���ς̋����̌��������낤�Ƒz���o���܂��B���̃O���[�v��2�ʂɂ́A�d�̑��s�k�A���炭�ܗ֓����낤�Ǝv���܂����A�Δ������Ă��炢�����Ƃ�����]�������\���Ă��܂��B�b�M��́A�����߂Â��ɂ�āA���̑��s�k���͂₭�d�オ��悤�ɉv�X��]���܂����B����͉��炩�̗��R�ŁA�ޏ��ɂƂ��čł���Ȋ�]�̂悤�ł����B�܂��A�Ō�̎莆�̒��ɁA�b�M��̏@�����������������܂��B����͔O���𒆐S�ɂ��鐶���ŁA����ɕ��̖��O���̂��Ȃ���Ɋy��y�ɐ��܂�ς����҂���������̂ł��B���̐��E�́A���̐��̔߂��݂�炢���Ƃ��S�R�Ȃ��Ɋy �ŁA�v�����ʂꂽ�e�q��F�l�ɍĂщ��ɈႢ�Ȃ��ƍl�����Ă��܂��B����4�ʂ̎莆�́A���q����̓���I�Ȍ���������A�����Čb�M�g�̊�]�Ǝ��]�A�@���I�Ȋ��҂���l�ԓI�ȍD�������܂ł���镶�͂ŁA�{���ɑ�Ȏj�����Ǝv���܂��B�@
�����̌������@�ɂ��ā@
���Ɂu�b�M���v�̈Ӌ`�ɐG���O�ɁA���̌�����̗���Ɩ��ӎ��𖾂炩�ɂ��Ă��������Ǝv���܂��B�����܂ł��Ȃ��A���̂悤�Ȏj���͗l�X�̗��ꂩ�猤�����邱�Ƃ��o���܂��B���̌�������́A�͂�����ƌ����A�^�@�w�ł��Ȃ��A�����w�ł�����܂���B�܂��A�N�w�ł��Ȃ��A�@���w�ł�����܂���B���ꂼ��̕���͎��̌����̎��ӂɐG��܂�����A������x����ɂ�����������܂����A�킽�����̕���́A�ǂ��炩�ƌ����ƁA�u�@���j�v�Ƃ������̂ł��B���j�w�̑ԓx�����̎j���ɑ��Ď�낤�Ǝv���܂��B�@���j�Ƃ��������́A�@�����ۂ�ΏۂƂ��܂��B���̗���͂ł��邾���@�����ۂ�����̍l�����łƂ炦��̂ł͂Ȃ��A�ނ��딭����������̒��łƂ炦�Ă������Ƃ�����̂ł��B�ł�����A�����̌����͏@���̐^���̒T���ł͂Ȃ����Ƃ��A���f�肵�����Ǝv���܂��B�������A�@���̑̌�����j�̌��ۂ̓��Ɍ����������A�^�@�w�╧���w�Ƌ��ʂ̖��_�����邩���m��܂���B�܂��A�@���N�w��@���w�Ɠ����悤�ɁA��r�@���̖��ɂ��A������x�܂ŋ���������܂��B���ɁA���鎞��₠�镶���̏@���̌��́A�ʂ̎���ƕ����̂���Ǝ��Ă��邩�A�܂��͎��Ă��Ȃ����Ƃ����l�@���A���̊S�������Ă��܂��B����ɂ�������炸�A�@���̌����u�@���j�v�Ƃ�������Ō������悤�Ƃ�����ӎ����A���̌��������ł��B����ɏ@���̌��Ɏ~�ǂ܂�܂���B���̑̌����o���_�ɂ��āA�ʂ̌��ۂɌ������������Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A���n���c�₻�̋����A�C�s��V���A��q�̑ΏہA�s�҂̑g�D�A�����ċ��c�̔ے肷�邢������M�A�_�b�A�ْ[�Ȃǂ��A�����[�����j�I�Ȍ��ۂƂ��Ď�舵���܂��B�ȏ�̂悤�ɁA�������{�̏@���L���������邽�߂ɁA�@���̌�����n�߂āA�e���ʂ𑍍��I�ɂ���߂悤�Ƃ����̂��A���̕��@�_�ł��B�@
���u�b�M���v�̖��_�@
���̂悤�ȕ��@�_���Ȃāu�b�M���v�ׂ�ƁA�ǂ�Ȗ�肪�o�ė���ł��傤���B����͌����܂ł��Ȃ��A�������Ȃ����炢�������̂ł����A�����ł͂��̒��̎O���炢����苓�������Ǝv���܂��B���̎O�́A(��)��y���̐��E�ρA(��)�����̐M�Ɛ������A(�O)�^�@�̐M�I�ȓ��e�Ƃ������ł��B�����A�����ł͍l�@�͈̔͂𒆐��@���Ƃ������ۂɌ��肵�Ă��������Ǝv���܂��B�Ƃ����̂́A���̎O�̖����A�����̂��̂̍l�����Ƃ��̎���̈�ʂ̌o���̗p�Ɉʒu�Â������Ǝv������ł��B���{�̒����@�������ɂ���ꍇ�A�O�����Ă��̍��{�I�ȑO��Ɠ������A�傴���ςɏグ�Ă��������������悤�Ɏv���܂��B���̈�͖���ςƂ������ƁA�܂肱�̐��̈�̂��͉̂i������\�͂������Ă��Ȃ�����A�M���o���Ȃ��Ƃ����l�����ł��B������́A��������ȍ~�̐_�������Ƃ����_���ƕ������͂������ʂ��銴�o�́A�����ɂ́A�قƂ�ǂȂ������Ƃ������Ƃł��B�ނ���A�_�X�����E��F���A�����悤�ȏ@���I�Ȕ͈͂Ɉʒu�Â�����Ƃ��������̕����A���|�I�ɑ��������悤�ł��B���̂ق��̓���������܂����A�ꉞ�A���̓��O���ɂ����āA���{�̒����@���̖����l�@���čs���܂��傤�B�@
�������̏�y���̐��E�ρ@
���̑��̖��́A�����ɂ������m���̐��E�ςƂ������Ƃł��B��y���́A�����m�̂悤�ɁA���q�����̈�̌n���ŁA���̎���̍ő�̌n���ł����B(���̂ق��ɂ́A�T�Ɠ��@�Ƃ����n��������܂����B)��y���́A���ɒ����̖���ςɊ�Â��Ă���M�ƌ����܂��B�܂�A���̐��̖��퐫��s�M������Ɋ����Ȃ��l�ɂ́A�Ɋy��y�ɐ��܂ꂽ���Ƃ�����]�́A����܂苭���o�ė��Ȃ�����ł��B��y���́A�ȒP�ɐ�������A����ɂƂ��������A�`���I�ȏC�s�ł͌�肪�J���ɂ����l�X�ׂ̈ɁA�ʂ̐��E�A��y��n��グ�܂����B���̈ꐶ���I���ď�y�ɐ��܂�ς��A��y�͍ō��̊��Ȃ̂Ō�肪�J���₷���A�N�ł����ɒB���邱�Ƃ��o���܂��B�ł�����A���̐M�������Ȃ�����̐��ŏC�s����K�v�͑S���Ȃ��A��������ɕ���[���M����S�Ŗ����𑗂�A��y�ɐ��܂�邱�Ƃ��肦�����̂ł��B���ׂ̗̈B��̍s�͔O���A�܂舢��ɂ̖��O���u�얳����ɕ��v�Ƃ����`�ŏ̂���Ƃ������̂ł��B�^�@�̉��߂ɂ��A�O���͈���ɂɑ��ċ~�������߂�F��ł͂Ȃ��A�~���������ۏ���Ă��邱�Ƃւ̊��ӕ̕\���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��y���́A�C�s�̔\�͂��キ�A���܂莩�M�̂Ȃ��l�ɂƂ��ẮA���ʂ̖��͂������Ă��鋳���ł����B���ɁA����ς����鏊�ɍL�܂��������ɂ́A��y�����L���M�҂̋A�˂��W�߂܂����B�@
�u�b�M���v�ɂ́A����ςƂ������o����y���Ƃ����M���A�p��\���Ă� �܂��B����ς́A��́A�b�M��̌o����������ߌ��I�����̗��ɁA�O��Ƃ��Ă���܂��B���̋��̗���グ��A��3�ʂ�4�ʂɁA�앨���o���Ȃ��ċQ�[���L����A��l�̒j�̉��l�����ɁA�b�M������ʂ����m��Ȃ��Ƌ��ꂽ���Ƃ�������Ă��܂��B�܂���8�ʂɂ́A���l���F�����Ă��܂������Ƃ��L����Ă��܂����A���炭������Q�[�̂����ł��傤�B�܂��A��9�ʂ�10�ʂɂ��ƁA���s�̔M�a�ׂ̈ɁA���l�̉��l�������A���̗p�ɂ͊o�M��ɏ���ɂȂ��Ă����q���Ƒ�l�̉��l���܂܂�Ă��܂����B�ʂ̉��l�́A��ꕨ�����ɏo�Ă��ĕs���R�ɂȂ�A�R�X������ԂɂȂ�܂����B�����̏؋�����A�b�M��̖ڂɂ������E�́A�m���ɋ��̐��E�ł������ƌ��_�o���܂��B�@
���̂悤�ȋQ�[��a�C�ׂ̈ɁA�����̐l�X�̎����́A���݂̂��y���ɒZ�����̂ł����B�l���j�w�҂ɂ��ƁA�����ɂ����镽�ώ����́A�j�������Ȃ��ׂɔ��ɓ��v���Ƃ�ɂ����̂ł����A���炭40�ɉ߂��Ȃ��������낤�ƌ����Ă��܂��B���ώ�����40�ƌ����Ă��A�S������҂����Ȃ������Ƃ�����ł͂Ȃ��A�����m�̂悤�ɁA�b�M���e�a�̂悤��80�Α�܂Ő������l�����܂����B�]���āA�����̐l�B�͒������ł���\���͂����Ă��A���̎������͂��Ȃ�Ⴂ�Ƃ������Ƃ��A�F���o���Ă��܂����B���̎��o�������̖���ςɌĉ����āA�����̎���Ƃ���Ɍ���܂����B���̈Ӗ��ŁA����ς͒����̑�\�I�Ȏv�z�ƌ�����Ǝv���܂��B�@
�b�M��̏�y�M�́A���R���̖���ςɍ��Â��Ă���Ǝv���܂��B����͊��q�����̊�����(1153-1216)�́u����L�v�Ƃقړ����p�^�[���ł��B�u����L�v�̏ꍇ�ɂ́A���̐��̍ЊQ�̌����@�v�z�Ő����Ă��鏊����ӏ�����܂��B���@�Ƃ����̂́A���̐��̈������S�A�����ĕ����̋����̗�����C�s�������Ɋׂ鎞���̂��Ƃł��B�b�M��͎莆�̒��Ŗ��@�̂��Ƃɂ͐G��Ă��܂��A���@�Ƃ������t���A�ޏ��͂������������ł��傤�B�莆�ɂ͖��@�Ƃ����悤�ȋ��`�I�ȊT�O�ł͂Ȃ��A�����ƈ�ʓI�ȕ\�����o�ė��܂��B�Ⴆ�A��10�ʂɏ�y�̂��ƂɐG��āA�u�ȂɎ������炩�炸�v�Ƃ������t���o�ė��܂��B���Ȃ킿�A��y�͌����̈Â��l�q�ɔ�ׂ�ƁA�Â��Ȃ����E�A�܂���̐��E�ɈႢ�Ȃ��ƍl���Ă���̂ł��B�u�Â��Ȃ��v�Ƃ����\���ɂ́A�ʂɐ[���Ӗ��ȂǂȂ��Ǝv���l�����������m��܂��A����ɂ����ʌ����A���Ȃ킿���̌���̂Ȃ����ƌ����Ă���ȏ�A����͏�y���̌����Ɋ�Â��Ă���\���Ȃ̂ł��B�b�M��͂��̊ȒP�Ȍ������ŁA��y���̍��{�I�ȓ���\���Ă���̂ł��B���̓\���Ƃ́A���̈Â����E�Ƃ��̖��邢��y�Ƃ����\���ł��B���`�I�Ȍ��t�ŕ\������A�u�}���q�m�A�Ӌ���y�v�A�܂肱�̉��ꂽ���E���}���ė���āA���̋Ɋy��y�����ŋ��߂悤�A�Ƃ����M�I�ȓ��@����o���\���ł��B���̓\���̐��E�ς��A�b�M��́u�Â��炸�v�Ƃ������t�̗��ɂ���Ǝv���܂��B�@
��y���̓��́A���̒����̕����v�z�ɔ�ׂ�ƁA���ƂȂ����n�I�ŁA�f�p�Ȏv�z�Ɍ����邩���m��܂���B��敧���́A��ʂɂ��̂悤�ȓ\���̐��E�ς�ے肵�āA���̑���ɁA�ꌳ���A�܂�^���͗B��̂��̂ŁA��ɕ�����̂́A�l�Ԃ̋U��ɉ߂��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����܂����B���̂悤�ȍl�����́A�V��̖{�o�v�z�A�^���̑��g�����A�T�̌��������Ȃǂ̕������`�̘_��Ɏp��\�킵�Ă��܂��B���̈ꌳ���͏�y���̎v�z�Ƃɂ��e�����y�ڂ��܂����B�Ⴆ�A���k����y�Ƃ��������A�܂茻�݂̋ꂵ�����E���A���̂܂܋Ɋy��y�ɑ��Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������_������܂��B�e�a����敧���̈ꌳ���𗝑z�̌����Ƃ��āA�F�߂܂������A�����A���݂̏�Ԃł��̗��z����邱�Ƃ͔��ɓ���̂ŁA���̌�����y�ɏ��炴��Ȃ��ƍl���܂����B�ł�����\���̏�y�v�z���A�l�Ԃ̌��݂̗L�l�Ɉ�Ԃӂ��킵�������ł���Ǝ咣���܂����B�V��A�^���A�T�Ȃǂ̋����́A�@���̎v�z�Ƃ��ẮA�y���ɔ����ŗD�ꂽ�l�����ł���Ƃ��Ă��A�����̈�ʂ̐l�X�̎����ɂ͂҂����荇��Ȃ������悤�ł��B���ʂ̐l�͓V���T�Ȃǂ̏C�s�͏o���Ȃ��������A��������������J�����ꂽ���Ƃ�����]����������܂���ł����B��y���́A����Ӗ��ň�ʂ̐l�����̂܂܂Ō}���悤�Ƃ��������ł��B�����I�Ȑ��E�ς�p���Ȃ���A�^���ɓ������Ƃ���@���v�z�ł��B�b�M��́u�Â��炴����y�̃C���[�W�́A��ʂ̐l�̒��Ɍ��ꂽ���z�̈��ł��B�@
�����ŁA���Ȃ蕪����ɂ������ƂɁA�����G��čs������ �Ǝv���܂��B����͉��l�ɂ��Ă̂��Ƃł��B���ɉ��l�̏@���I�ȌX�|�͂ǂ��ł��������Ƃ������ɂ��āA�l���Ă��������Ǝv���܂��B�����܂ł��Ȃ��A���̖��ɂ������j���͂قƂ�ǎc���Ă��܂���B�ł�����A���̘b�͑z����̋ɉ߂��Ȃ������m��܂���B����ɂ��Ă��A���l�ɂ��@���I�Ȗʂ����������Ƃ��炢�ł��F�߂Ă��炦��A���̘b�����ʂł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���l�Ƃ������̂́A���ɔ��R�Ƃ������ۂł�����ǂ��A�g������ԒႢ�����̘J���҂ƌ����܂��B���l�̎�l�́A���l������������肷�錠���������܂������A�b�M��̏���͒��x���̌����������j���ł��B���͌b�M��̎��ゲ�납��A�l�Ԃ����邱�Ƃɔ�����l�X�Ȗ@���I�A�@���I�ȏ��u���o�Ă��Ă��܂����B�ł�����A�b�M��̏���́A�����Ɍ����A�����̏��ނł͂Ȃ��A���������̉Ƒ��ɏ��镶���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���l�̎�l�́A���̉��l�̊�]���A������x�܂ŔF�߂܂����B�Ⴆ�u�b�M���v�̑�9�ʂɂ��ƁA�u�Ƃ��l�Y�v�Ƃ������l�́A�o�M��̂Ƃ���֏���ꂽ���Ȃ������̂ŁA�b�M��͂��̑����{�����Ƃ����悤�ł��B���l�͂����̕����I�ȍ��Y�ł͂Ȃ��A�������x�ɂ�����ʼn��w�̏]�҂Ƃ��āA��舵��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ɂ͎�l�̈�ԑ厖�ȏ]�҂ɂȂ鉺�l�����܂����B�Ⴆ�A�e�a�̐e���Ȓ�q�ɂȂ����@�ʂƂ����l�́A���炭���l�̌`�Őe�a�Ɍ��ѕt�����ƍl�����Ă��܂��B���̏ꍇ�́A���l����l�̏@���I�ȉe�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�@
���l�̏@���ɂ��ẮA�F�X�l���邱�Ƃ��o���܂��B���̒m���Ƌ��炪���Ȃ�Ⴂ�ꍇ�A�_�_�A���Ȃǂ̐��q�A�܂����M�I�ȐM�����|�I�ɑ����� �ł͂Ȃ����Ƒz������܂��B���������ꂾ���ł͂Ȃ��A�����ƃ��x���̍����ʂ��������悤�ł��B�Ⴆ�A�b�M��̑�9�ʂɂ��ƁA�ׂ�̉��l�͕����́u�����v�A�܂葭�l�I�Ȃ��V����ɂȂ��������ł��B�����A�����ɂȂ��Ă����l�̐g�����������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�O�Ɠ��������l�̋`���͒S�����悤�ł��B���l�̎d�������Ȃ���ł́A�@���I���������Ȃ�����āA�����Đ�C�̂��V����ɂ͐��蓾�Ȃ��ł��傤�B�������O���̂悤�ȍs�́A���ƊȒP�ɂ��̐����ɑg�ݓ���邱�Ƃ��o���܂��B���T���q�̓�����K�v�ł͂Ȃ����A�d���Ȃǂ����Ȃ���ł��A����ɂ̖��O���̂��邱�Ƃ͏o���邩��ł��B���̓_�ł��A��y���͉��l�ɂӂ��킵�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B������̃|�C���g�́A��y���A���ɐ^�@�͓`���I�ȕ����̕��@�ł͋~���Ȃ��l�B�Ɍ�����ꂽ�����ł���Ƃ������Ƃł��B�ʼn��w�̉��l�����́A���̐l�X�����������������ɖ����ꂪ���ł��傤�B����ɁA������l�����邱�Ƃ́A���l�́u�b�M���v�������悤�ɁA�Q�[�A���s�a�Ȃǂɂ���āA���Ȃ�Ⴍ���Ď��ɂ܂����B���������l�����ɂƂ��ẮA�Ɋy��y�Ƃ������z�́A���̂��������͓I�Ɏv�����ł��傤�B�������ꂪ�������͂��ł��B�ȏ�̗��R�ŁA���l����y���ɋA�˂���\���͏\���������Ǝv���܂��B���ۂɂ����������Ƃ����������ǂ����A���ɕ�����ɂ������ł����A���炭���l�̊���͈̔͂͂����ւ��A��l�̏@�����炢�͂悭�m���Ă��āA���̉e������ԋ��������ł��傤�B���������ł���Ȃ�A�b�M��̉��l�͔O���̍s���y�̐M������Ă����Ƒz������܂��B�@
�������̏����̐M�@
���ɂ́A�����ɂ����鏗���Ƃ��̐M�Ƃ������ɐi�݂����Ǝv���܂��B�u�b�M���v���番����悤�ɁA�����̏����͋ߐ��̏�����萶���̓Ɨ��ƌo�ϓI�Ȏ��R�𑽏������Ă��܂����B�����������悤�ɁA�b�M��͎O�l���炢�̎q���ƈꏏ�ɁA�e�a���痣��ĉz��̍��ŕ�炵�܂����B����͗����ł͂Ȃ��A�����ʋ��̂��Ƃł����B�b�M��͎����̉Ƒ�����y�n�Ɖ��l�Ȃǂ̍��Y�𑊑����܂����B���̍��Y���Ǘ�����ׂɉz��̌̋��ɋA��A�����ŔӔN���߂����܂����B���q�̖��A�o�M��́A���s�Ɏc���Đe�a�Ǝ����̎q���Ƌ��ɕ邵�A�莆�ŕ�̌b�M��Ƃ��т��јA�����܂����B���̕�Ɩ��̊Ԃɂ́A�g�����e���݂�10���N�ɂ킽���Ă����Ƒ����܂����B���̓�l�͋��ɓ����悭�āA�\�͂�����A�Ɨ��I�Ȑl���ł����B�o�M��̕��́A�e�a���S���Ȃ�����A���̂���Ɍ�e���A�܂�e�a�̏ё������u���铰�F�����ĂĂ��炢�A���̊Ǘ��̐E�ɂ��܂����B���̌�e���́A���ǁA�{�莛�ɓW�J���܂�������A�o�M��͂���Ӗ��Ŗ{�莛�̑n���҂ƌ�����Ǝv���܂��B�b�M��̕��́A�莆�������悤�ɁA�����̍��Y��ϋɓI�ɊǗ����܂����B80�ɂȂ��Ă��͂��������A����ɉv�X�w�͂��܂����B�b�M��̍��Y�́A�v�̐e�a�̍��Y�Ɣ�ׂ�ƁA���|�I�ɑ����̂ł��B�e�a�̕��́A��́A��q�B�̊�t�ɗ����Ă��܂����B����Ȃ̂ɁA�b�M��͎����Ă�����Y���A�e�a�ł͂Ȃ��A�����̎q���ɏ��낤�Ƃ��܂����B�莆�̑�1�ʂƑ�2�ʂ́A����̊o�M��ւ̈⌾���ɈႢ�Ȃ��̂ł��B���̈�Ⴊ���炩�ɂ���悤�ɁA�����̏����́A�ꍇ�ɂ���ēƗ�����o�ϗ͂��������悤�ł��B�@
�b�M��̏@�������́A�莆�̏��X�ɕ����I�Ɍ����Ă��܂��B��ɐ\���グ �܂����悤�ɁA��y�́u�Â��炸�v�Ƃ����z��������Ă��܂����B���̋��̑����ꐶ���ς�ŁA���̌���Ɋy�ɐ��܂ꂽ���Ƃ������҂��A�M�̒��S�ɂ��Ă��܂����B���̊m�M����A�O���̍s���o�ė��܂����B���̔O�����̂���K���͖����̐����ɗZ������ł��āA�b�M��̐M�͒N�ł�����������قǐ��Ɍ��ꂽ�Ǝv���܂��B��y���������Ɍ������v�z�ł��������Ƃ́A�C���h�ƒ����̋N���ɂ܂ők�邱�Ƃ��o���܂��B���{�̕����̒��ł́A��y���Ɠ��@�@�����ɏ����̋A�˂������t���܂����B��y���̏����~�Ϙ_���A�����̏����y�̎v�z���t��ɂƂ��Ă��邱�Ƃ́A�ے�o���܂���B����͊ȒP�Ɍ����A�����͒j����蕧���̌����J���ɂ����̂ŁA��x�A�j���ɐ��܂�ς��A���̌`�Ō��ɐi�ޕ����ԈႢ�Ȃ��Ƃ����l�����ł��B��y���͈�ʂɕ����̓���C�s���o���Ȃ��l��Ώۂɂ��鋳���ł��B�����ɑ��ẮA�����̍��ʓI�ȓ`�����p���ŁA�����̗����������F�߂Ă��܂����A�����ɋ~���̊�]��^���܂����B��������ɕ��ɖ���C���邾���ŁA�K���Ɋy�ɐ��܂�邱�Ƃ�����܂����B����Ӗ��ŁA�����͉��l�Ǝi���悤�ɂ��̐��̔ڂ����g���Ɉʒu�Â����Ă��܂�������A��y�̋~�����悭���������͂��ł��B�c�O�Ȃ���A�u�b�M���v�ɂ́A��y���̏��������̘_�����͂�����Ƃ͏o�Ă��܂���ǂ��A�b�M���̘_���������Ƃ��Ȃ��Ƃ͑z�����ɂ������Ƃł��B������ɂ��Ă��A�b�M��̐M�͏����̗��ꂾ���ł͂Ȃ��A�l�ԑS�̗̂��ꂩ��̐M�ł��B���ׂĂ̐l�X�́A����������ɕ��̑ΏۂɂȂ��āA��y�ɐ��܂�邱�Ƃ��o����Ƃ����m�M�ł��B�b�M��̏@�������͂����̍݉ƁA�܂葭�l�I�Ȑ����ł͂Ȃ��A��Ƃ��ĕ邵�܂����B�b�M��Ɗo�M��́u��v�Ƃ������́A�����m�̂悤�ɁA�u���܁v�Ƃ����Ӗ�������܂��B���̖��O�́A��������l�̖@���A���Ȃ킿��ɂȂ������Ɏ����������O�ł��B�b�M��́A�������g����ł��邱�Ƃ�ڊo���Ă��āA�����ɂ́A�����ɑ��āu���܁v�Ƃ����S�t��2�P��(��3.10��)�Ŏg���Ă��܂��B��������ɕ`���ꂽ�b�M��̏ё����M���ł���Ƃ���A�T�^�I�ȓ�̎p�A�܂蔯����A�@�߂𒅂āA�O��������Ă���Ƃ����p�����Ă��܂����B���̏ё�������ƁA�b�M��͏@�������Ɉ�g�����������悤�ł��B��̐������l���鎞�A�u���ƕ���v�ɕ\���ꂽ�����@(1155-1213)�Ƃ����������v���o���܂��B�ޏ��́A��ʂɓ�̗��z�I�Ȏp�ł��傤�B�����@�͕������̖��ŁA�����Ĉ����V�c(1178-85)�̕�ł����B�����m�̂悤�ɁA�d�m�Y�̍���ŕ��Ƃ�7�̈����V�c���łтĂ��܂��܂����B���̔ߌ��I���������������Ƃ��āA�����@�͐��Ԃ��̂āA�����̓��x���ē�ɂȂ邱�Ƃ�f�s���܂����B���̎���̋M���̏����ɂƂ��ẮA����͔��ɈӖ��[�����S�ł����B�Ȃ��Ȃ�A�M���̏����̔��͂��̂����������āA�������̏��ł����B����Ă��܂��A���炭���̎p�ɂ͖߂�Ȃ������ł��傤�B�����@�́A��ɂȂ��ċ��s�̑匴�ɂ������@���Ă�A���p�Ȑ����𑗂�Ȃ���A���Ƃ̕����A�Љ�Ƃ̌������قƂ�ǐ₿�܂����B�b�M��������@�Ɣ�ׂ�ƁA����_�͂��Ȃ�ڗ����Ă��܂��B�b�M��͓�̎p�����Ă��Ă��A�Ƒ��ƍ��Y�ɊS�����������܂����B�����@�̗��z����l����ƁA�b�M��͏����̓�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ������f��������邩���m��܂���B�������A���̔��f�͕����̓`���I�ȑm�������A�܂�m���͑��l�̊��������߂āA�ʂ̐��E�ς�{���� �߂ɎЉ�����������ׂ����Ƃ����ϔO�Ɋ�Â��Ă��܂��B�b�M��́A�v�̐e�a�Ɠ����悤�ɁA�m��������F�߂Ȃ��ŁA�e�a�̌��t�����Ȃ�A�u�m�ɂ��炸���ɂ��炸�v�Ƃ����V�������z�ɐ����܂����B��̓I�Ɍ����A�O�ʓI�ɂ͉Ƒ��ƒ��ԂƎЉ�痣��Ȃ��Ă��A���ʓI�ɂ͏@���I�Ȑ�����M�S�ɉc�ނƂ������Ƃł��B���́u��m�v�Ƃ��������́A��y���̋A�ˎ҂ɂƂ��čł��ӂ��킵���������Ȃ̂ŁA���݂̐^�@�ɂ́A���ꂪ�@�������̗��z�Ƃ��ċ������Ă��܂��B�b�M��́A���炭���̗��z�Ɋ�Â��Đ������Ǝv���܂��B�@
�������̐^�@�̍\���@
���ɂ́A�����ɂ�����^�@�̍\���Ƃ������ɂ��āA�l�@���čs�������Ǝv���܂��B�u�b�M���v�������ꂽ����́A���n�^�@�̋��c���`������n�߂������ł����B���̂���A�e�a�̋����𒆐��̗��j�I�A�@���I�Ȏ���ɓK�������铮�����N����܂����B�u�b�M���v�͏����^�@�̎p�ɂ��āA����q���g���܂�ł��܂��B�����ŁA�u���M�����M�v�Ɓu���s�k�v�Ƃ����b���o���_�ɂ������Ǝv���܂��B�u���M�����M�v�Ƃ́A20���I�̐^�@�ɂ����Ď�v�Șb��ɂȂ��Ă��Ă��܂����A���̈Ӗ��́A�������g������ɂɔC���ĐM�S���N����܂��ƁA�����̐M�S�����̐l�̖͔͂ɂȂ�A���̐l�ɐM�S�̌o����������悤�ɂȂ�A�Ƃ������̂ł��B�����Ȃ�A������D�ꂽ�@���s�ׂ͂Ȃ��ł��傤�B�܂�A�M�S�̐��������Ȃ̂ł��B�����̑�5�ʂɂ��ƁA�e�a�͂��̂��Ƃ�ڊo�������A�J��Ԃ����o��������悤�ȏC�s����߂āA�M�ɐg��C�����Əq�ׂ��Ă��܂��B���̎莆�́A�^�@�̈�ԑ�ȏ@�������ł���M�S�̏�Ԃ��A�悭�`������̂ł��B�^�@�̋��`�ɂƂ��āA�M�S���厖�Ș_��͂���܂���B�M�S�́A�Ɋy��y�ɐ��܂�錴���ł���A�O�����̂��邱�Ƃ́A�����M�S�̕\���ł���A�ʂ̖ړI�◘�v�ׂ̈̍s�ׂł͂���܂���B�܂��M�S���̂��̂��A�����ō��グ����̂ł͂Ȃ��A�ނ���l�Ԃ̑ԓx��Ӑ}����ؒ��~���āA����ɕ��̓����ɔC���邱�ƂȂ̂ł��B�M�S�͐S�̗L�l�ł���A����ɂɐe���Ȍl�I�ȏ�ԂȂ̂ł��B���̓_�ŁA�^�@�͏C�s�̏@���ł͂Ȃ��A�M�S�̏@���ƌ����܂��B���̐M�S�p�S�̎v�z�́A�e�a���猻�݂Ɏ���܂ŁA�^�@�S�̗̂��j�ɂ킽�錴���ł��B���ɐ^�@�̐^�����Ǝv���܂��B�b�M��͂��̌����𗝉����Ă��āA�莆�Ɂu���M�����M�v�Ƃ����b���������̂��Ǝv���܂��B�@
�@���ɂ́A�����̑�7�Ƒ�8�ʂɏo�ė���u���s�k�v�̖�����苓�������Ǝv���܂��B���s�k�́A�b�M��ɂƂ��Ĕ��ɑ厖�Ȃ��Ƃł������A ���݂̐^�@�w�҂͂��܂�S�������Ă��Ȃ��悤�ł��B���ہA���`�I�ȗ��ꂩ��͑��s�k�����߂��ɂ����ƌ����܂��B���s�k�Ƃ������̂́A�ܗ֓��̂悤�ȐΔ�ŁA���ʁA�l�̕�A���邢�͖S���Ȃ����l�̋L�O�Ƃ��āA�܂��͕����ׂɍ��ꂽ���̂ł��B���������K���͏C�s�I�ȍs�ׂł�����A�C�s��ے肷��^�@�̎v�z�ƍ����Ă��Ȃ��悤�ł��B�]���āA�b�M��̑��s�k�͋��`��A��ƌ����܂��B�܂��͂��̑��s�k�́A�����Ă���ԂɎ����̕�Ɍ��Ă�����Ƃ������̂������̂ł��傤���B����ɂ��Ă��A�^�@�̗��z����͊O�ꂽ�s�ׂł��B����Ƃ����̑��s�k�́A�e�a�̋L�O�Ƃ��Č��Ă�ꂽ�����������̂ł��傤���B����Ȃ�A�����̋L�O�ł͂Ȃ��A�J�c�M�I�ȈӖ��������Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA���͎v���܂��B������ɂ��Ă��A�b�M��̑��s�k�́A���ƂȂ��A�����I�ȏ@���̌��ۂ̂悤�Ɏv���܂��B�����āA�^�@�̒����I�Ȗʂ��悭�\���Ă���Ǝv���܂��B�@
�����I�ȏ@�� �Ƃ́A��̂ǂ�Ȃ��̂ł��傤���B�����̏@���ɂ́A�����܂ł��Ȃ��A��ނ̈قȂ����������̂��̂�����܂����B�V�����Ƌ����������ł͂Ȃ��A�_���Ɩ����M�Ȃǂ��܂܂�Ă��܂����B���̎�X�l�X�Ȋ��̒��ŁA�ǂ�ȏ@���ԓx���L�͂ł��������ƌ����܂��ƁA����͑��_�_�I�Ȉӎ����낤�ƁA���͎v���Ă��܂��B(�ܘ_�A���_�_�ƈ�_�_�͐��m�̊T�O�ŁA���ɖ��ɂȂ�_������܂����A��芸�����g�킹�Ē����܂��B)�����̏@���� ���_�_�I�������Ƃ����Ă��A��_�_�I�ȌX�����Ȃ������Ƃ͌����Č����܂���B���q�����̏�y���ƑT�Ɠ��@�́A�F�A��_�_�I�Ȗʂ�����܂����B�������A����̈�_�_�I�Ȉӎ��Ɣ�ׂ�ƁA���q�̂͋����Ȃ������Ǝv���܂��B����̈�_�_�ӎ��́A�����̐_�X��썰�∫���Ȃǂ�l�Ԃ̌o���͈̔͂���A�o���邾���ނ��悤�Ƃ��܂��B�B��F�߂���_�́A���̐��E�z���āA���邢�͕݂��āA����̂��̂Ɍ����Ă��Ȃ����݂ł��B�]���āA����̈�_�_�I�ӎ��͕��ՓI�ȍl�����ł��B����ɑ��āA�����̏@���̐_�͓���I�ȍl�����ł����B�ƌ����̂́A���Ȃǂ͐�ΓI�ȑ��݂ŁA���z�������̂ł������Ƃ��Ă��A����̌`������Đl�Ԃƌ����܂����B�����̐l�B�́A���́A���A�ꏊ�Ȃǂ���ɑ�ɂ��܂����̂ŁA�_�╧���A�ǂ�Ȍ`�ŁA���A�ǂ��Ɍ���邩�Ƃ������Ƃɂ��āA���ɕq���ł���܂����B���̈Ӗ��ŁA�����̏@���͑��_�_�I�ƌ����܂����A�����̑��_�_�́A�K��������_�_�ƑΗ����Ă��܂���B���̓_�ŁA��_�_�Ƃ������m�̊T�O���g���Ă��A����͐��m�I�ȗ����ł͎g���Ă���܂���B�@
�e�a�́A���̑��_�_�I�Ȓ����ɕ��G�ȋ����������܂����B����ɕ��ɑ��Ĉ�_�_�I�ȐM�S���������܂������A�����̓���I�ȐM���A������x�܂ŔF�߂܂����B�_���̐_�X�ɑ��ẮA���Ȃ�ᔻ�I�ȗ����������Ƃ悭�����Ă��܂����A�ϋɓI�ȕ]��������܂����B�Ⴆ�A�_�͔O���M�҂ɉe�̂悤�ɔ����āA����Ă�������Ƃ������܂����B�����̐������̐M�̒��ł��A���ɐ������q�M�������Ă��܂����B�܂��A��y���̂����鎵�c���m�ɑ��Ă��A�M�I�ȑԓx��\���܂����B�����Ă����������߂�a�]�킵�A���̒��ō��m�A�@�R�͐�����F�A���邢�͈���ɕ��̉��g�ł���Ƃ����قǂ܂łɁA���h�̔O�������܂����B���̑� �h�̔O�́A�T�^�I�Ȓ����M���Ǝ��͎v���Ă��܂��B�ȏ�̂悤�ɁA�e�a�͈�S��C�̏�y�M��i�߂Ȃ���A�����I�ȐM�������Ȃ�����Ă��܂����B�@
19���I���납��A�u�V�ُ��v�Ƃ����^�@���T�����̂������l�C �ɂȂ�܂����B����́A��_�_�I�Ȑ^�@�v�z��O�ʂɏo���āA�����͂̂���\���ŏ�����Ă��܂��B�u�V�ُ��v�͎�����Ɋ������������̂ł���A�e�a�̋����𒉎��ɓ`���Ă��鐹�T���Ǝv���܂��B�������A�ǂ߂ΓǂނقǁA����I�ȏ@���ς̂悤�Ɋ����܂��B�����ɏ����ꂽ�̂ɁA�����炵���Ȃ��l�����������Ă��܂��B�ł�����A��������ɂȂ��ď��߂Đ��ɏo���A�Ƃ������Ƃ����ȂÂ��܂��B�u�V�ُ��v�̓��ɒ����^�@�̎p��{�����Ƃ���A�m���ɋ͂��Ɍ��o�����Ƃ��ł��܂����A��������A�{�莛�̌��z�̕��ׂ�A�����ɒ����I�ȍ\�����͂�����Ɠǂݎ��܂��B�{�莛�̐�������ƁA�̑�ȓ��F�Ƃ�����̓��F���ڂɓ���܂��B�傫�������e�a�̌�e���ŁA��������������ɓ��ł��B���̍\���́A�e�a�̕����d�Ă���悤�Ɍ����܂��B�ܘ_�A����ɂ͗��j�I�ȗ��R������A�{�莛���e���̕悩�甭�W�����������Ƃ������ƂƑ傢�ɊW���Ă���ł��傤�B�����A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�@���I�ȗ��R���������悤�Ɏ��͎v���܂��B�܂�A�J�c�M�Ƃ������̂��A�����^�@�̏d�v�ȗv�f�ƂȂ��Ă���A���̎���̕��ʂ̐M�҂̈ӎ��̒��ł́A�e�a�ƈ���ɂ�����Ȃɋ�ʂ���Ă��Ȃ������ƍl������̂ł��B����ɁA�b�M��̑\���̊o�@�̉e���ɂ��A�e�a������ɂ̉��g�ł���ƌ����Ă��܂����B�ł�����A�J�c�M�����W���āA�e�a�ɑ���u�Ȃǂ̋V�����{�莛�̍��{�I�ȍs���ɂȂ����̂ł��B���̊J�c�M�́A���炭�^�@�̏@�h�̌`���ɑ�Ȗ������ʂ����ł��傤�B���̐M���Ȃ���A�^�@�͏@�h�Ƃ��ďo���ł��Ȃ������ƁA���͎v���Ă��܂��B�����Č����܂ł��Ȃ��A���̊J�c�M�͒����I�ȏ@�����ۂł����B�u�V�ُ��v�̎v�z�������ɂ���܂������A���̊J�c�M�̔w�i�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă��܂����B�����̋A�ˎ҂́A�����A�J�c�M��ʂ��ď��߂Ă��̐M�S�p�S�Ƃ����v�z����悤�ɂȂ����Ǝv���܂��B�J�c�M���Ȃ���A�e�a�̗D�ꂽ�v�z�͍����܂Ő����c��Ȃ����������m��܂���B�ł�����A�����^�@�̍\���͓�̗v�f����Ȃ��Ă��܂����B��͐M�S�Ƃ����@���I�ȗ��z�A������͊J�c�M�ł��B���̓�́A�u�b�M���v�́u���M���l�M�v�Ɓu���s�k�v�Ƃ����b�ɁA���łɌ���Ă���Ǝv���܂��B�@
���u�b�M���v�̎j���I���l�@
�Ō�ɁA�u�b�M���v���j���Ƃ��ĕ]�����悤�Ǝv���܂��B���͒����̕���������Ȃɕ��L���ǂ��Ƃ͂���܂��A�m���Ă������ł́A���̂悤�Ȏj���͎v���o���܂���B�����̕����̒��ɂ́A�F�X�Ȃ��̂�����܂��B�Ⴆ�A�Õ����͎R�قǎc���Ă��܂��B�܂��u�ʗt�v�̂悤�Ȑ����Ƃ̓��L�A�����āu��ȋ��v�̂悤�Ȗ��{�̗��j���グ���܂��B�����́A�����A�Љ�A�o�ρA�@���j��A���ɑ�Ȃ��̂ł��B�������A�b�M��̎莆�Ɣ�ׂ�ƁA�̌��I�Ȗʂ������Ă��܂��B�ق��ɂ́A�����̓��L���w�A�Ⴆ�u�X�����L�v�Ɓu�\�Z����L�v�𒍖ڂ��Ȃ���Ȃ�܂���B����͋��s�̋M���̉��l�ςƔ��ӎ���O�ʂɏo���āA���w�Ƃ��Ċ����I�Ȃ��̂ł��B����ɂ�����炸�A�u�b�M���v�Ɣ�r����A�����Ɉ�������͋C��\���Ă��܂��B������̕����́A�@�R�E�e�a�E���@�Ȃǂ̕��Ƃ̎莆�ł��B�����́u�b�M���v�Ɠ����悤�ɁA��g��̋l���L����Ă��܂����A���e�͏@���W�̘b�����|�I�ɑ����̂ł��B�����ɔ�ׁA�b�M��̎莆�͔��ɑf�p�ł��B���e�͓���̑̌�����ŁA��ǂ��������ł́A���܂�債�����̂ł͂Ȃ��Ƃ�����ۂ��邩���m��܂��A���̎莆�̏����ȑf�p���́A���ɑ傫�ȓ����ƌ����܂��B����C���Ȃ��̂ŁA�����̑̌��������Ɠ`���Ă���镶���ł��B���̂悤�Ȏ莆���ق��Ɏc���Ă���ł��傤���B�u�b�M����́A���ɒ����̏��^�Ȑ��ƁA���͎v���Ă���܂��B
 �@
�@���b�M����� / �{�莛�W
���̖��͌b�M��M�́u�b�M������v�ɏ�����A1921�N�ɖ{�莛�Ŕ������ꂽ�B���̏���ƌb�M���o�W�����B�e�a�͍ȑт������������߂Ă̑m�����A���̕v�w�̎p�����̎莆�ɖ��������B�e�a�v��ɏ����ꂽ���̎莆�͖S���v�ւ��Ă������Ɍ�����B�@
���̎���ł������̐S�����@���͔��W����B�^�@�̏o���_�ɂ��ꂪ�������B�O����J��b�M�̎�ɐ��܂�����ɏ��̂́A�S���v�ւ̐s�����ʎv���Ə̖��O�����B�@
�b�M�������ƌĉ�����悤�Ȗ����e�a�ɂ�����B��b�R�ōs���l�܂����e�a��1201�N�ɋ��s�̘Z�p���ɂ�����A�����Ő������q������A�u�ω������Ȃ��̍ȂɂȂ�v�Ƃ��������ł���B���̌o�܂��u�b�M������v�ɏ�����Ă���B����ɂ��e�a�͖@�R�ɋA���A�ȑт����B���̖������E��ɋL�����e�a��������o�W�����u�F���e�v�ł���B�@
���̐e�a�����O����J��B���̑O�ɂ͔O�������p�����r������҂ɂȂ������u����Ă���B�{��O����`����l���̏o���_�ɂ������̂����̖����ł���B����͂܂��b�M��ƂƂ��ɕ����H�������B��҂���{�ƂȂ鎭��͓�l�̗����ے����邩�̂悤���B�@
�b�M�����ɁA�e�a�����E�ɁA�����Ɂu�����{���v��u���Ǝ��̎O��������������B�������ׂ�A��l�����������ĂƂ��ɔO�����Ă���悤�Ɍ�����B�@
�e�a�������������́u�얳����ɕ��v�̘Z�������̑��Ɂu�얳�s�v�c�����v�̔��������A�u�A���s�\�����V���@���v�̏\������������B������{���Ƃ���̂͐e�a����n�܂�ƌ�����B�@
�e�a��������{���Ƃ����͔̂ނɂƂ��Ă̔O�����������q�ł͂Ȃ��������Ƃ��悭�����Ă���B�����Ώ@���͋������q�ɉ߂��Ȃ��Ɣᔻ�����B�������e�a�ɂƂ��Ă̔O���́u�{��v�Ƃ������E�̍��{���_�ɂ��u�^���v�̋~���̕\�ꂾ�����B�u�{��Ɩ����v�Ƃ�����S�ƌ䖼�́A���E�ɒʂ��镁�ՓI�@���������ɂ���B�u�l�C�̂����݂ȌZ��v�u�l�C���E�v�̏@���ł���B�@
���̐e�a�̌��t�͔Y�߂�N�B�~�̐S��߂����B�B�~�����̊������L�����u�V�ُ��v�̘@�@�{���o�W�����B�@
���̎���ł���҂̐S�����@���͔��W����B�u�V�ُ��v����҂𒆐S�Ɉ�ʂɓǂ܂�n�߂��̂�20���I�ɂȂ��Ă��炾�B�V���Ȏ�͂܂��ꂽ����ł���B�@
���e�a��e�ƌb�M�@
���ɓ����Ă����̂Ƃ���ɐe�a�̌�e�����ނƌb�M�����ׂĂ����Ă������B��l��������������荇���Ă���悤�ȕ��͋C���������B���̌b�M�̑O�ɁA�b�M�e�a���畷�������t���L�����u�b�M��v�����ׂ��Ă����B�ÕM�̉��������̕��͊���Ă��Ȃ��Ɠǂ݂ɂ������A�K���ɑΏƂ��ēǂ߂�悤�Ɋ����ɂ������̂��u���Ă���A���������Ɠ��e���킩��B���ۂɐe�a�ƌb�M��̏ё��̑O�ł����ǂނƁA���ڂ̑O�Őe�a���ޏ��Ɍ�肩���Ă��邩�̂悤�������B�u�V�ُ��v�Ɠ��l�ɐe�a�̓������������Ă���u�e�a���C�u�v�̎����A�M�d�ȑ̌��������B�@
1921�N�ɐ��{�莛�ł��̏�������Ȃ���A����l�̒m��e�a���͂Ȃ������ƌ����Ă����B�e�a����b�R���o�ĘZ�p���ɂ�����A�u�㐢�����̂点���܂Ђ���Ɂv�A��\�ܓ��ڂ̋łɐ������q�̎����Ė@�R��l�ɋA�������Ƃ������ɏ�����Ă���B�u�b�M��v�͐N�e�a�̋����̂��܂��`���ꂽ���ɋM�d�Ȏ����ł���A�傫�Ȕ����������B�u�b�M��v�ɂ��e�a�̔�b�R���R�̗��R�́u�����o�Âׂ����v�����߁A�u�㐢�v���F��Ƃ���������̖��ł��������Ƃ��悭�킩��B�e�a���@�R�ɋA�����̂́u���s�M�v�ɏ�����Ă���悤��1201�N�̂��Ƃł���B����܂ʼn��x�������Ă������A�u�b�M��v���������ꂽ1921�N��1201�N�Ɠ�����60�N�Ɉ�x���銱�x���u�h�сv�̔N�ł���B�����Ŋv���̔N�ƌ���ꂽ�h�т̔N�ɓ��{�ŏ��߂ɒ��ڂ����̂́A���̍ݐ�����601�N�̐h�т̔N���o�������������q(574-622)���낤�B1921�N��1201�N�Ɠ����h�т̔N�ł���ƂƂ��ɁA�܂��������q��O�S����̋L�O���ׂ��N�ł��������B���͐������q�̓��������������Ă���̂��Ǝv���Ă���B�@
�܂����́u�b�M��v�ɂ́A�e�a���������q�̎����āu�㐢�̂�������鉏�ɂ��Ђ܂�点��Ƃ��Â˂܂�点�āv�A�@�R��l�̂��Ƃ�K��Ă��A���̏�ł����ɒ�q�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��A�܂���������S���ԁA�J�̓�������̓����A���������������@�R��l�̌��t���āA����Ɣ[�����Ė@�R��l�ɋA�˂������Ƃ��L����Ă���B�u�܂��S�����A�~��ɂ��Ƃ�ɂ��A�����Ȃ�厖�ɂ��܂��Ă��肵�ɁA�����㐢�̂��Ƃ́A�悫�l�ɂ��������ɂ��A���Ȃ��₤�ɐ����o�Âׂ������A�����ꂷ���ɋ�����Ђ����A�������܂͂肳���߂Č�Ђ����A��l�̂킽�点���܂͂�Ƃ���ɂ́A�l�͂����ɂ��\���A���ƂЈ����ɂ��点���܂ӂׂ��Ɛ\���Ƃ��A���X���X�ɂ���������������肯�߂Ƃ܂Ŏv�Ђ܂�炷��g�Ȃ�v(�u�b�M�������v)�@
��������195�������āA���N�ȏォ�����Ă���Ɩ@�R��l�ɂǂ��܂ł����Ă����Ƃ������ӂ��ł߂��̂ł���B�����炭�͂���܂Ŋw��b�R�ł̐�����̕����ɏƂ炵�Ė@�R�̋������l����ƂƂ��ɁA�Ō�͕��ʂ��̂ĂĖ@�R��M���邵���Ȃ��Ƃ����C�����������̂��낤�B�e�a�̐T�d�Ȑ��i�Ǝv���A�����čŌ�͂����M����Ƃ���������͂����ɂ��悭�\��Ă���B�e�a�̒��������Ǝv���Ƃ�������̔�����ɑg�ݍ��킳��Ă��邪�A�{���̎v���Ƃ������̂͂����������̂��낤�Ǝv���B���ʒm���疳���ʒq�ւƔ��̂ł���B�@
���b�M��Ɍ���u���������y�ցv�@
���́u�b�M��v�ɋL���ꂽ�e�a�̌��t����A�e�a�̐����傩���y��ւ̓]���̉ߒ��������Ă���B����͐�����̋������Ԉ���Ă����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B���̋����������ɂ����炷���̂�m�������ʁA���̓������߂�������Ȃ������̂ł���B����������~���ɂ��Ȃ��玟�̒i�K�ɐi��ł���̂ł���B�₪�āu���s�M�v�Ƃ��Č������铹�̂肪��������n�܂��Ă���B������̍������Ȃ��u���ʂ̖@�v�𒆐S�Ɍ��Ă݂悤�B�@
�ߑ��̐��������n�����͌������m�I�ȏ@���Łu����(���N)�̖@�v(���ʗ�)�𒆐S�Ƃ��Ă���B�������P���Ȉ��ʗ������Ȃ�A���������ʗ�����b�Ƃ���Ȋw�Ɠ��l�ɁA���m�I�Ɏ�e���邾���ōςނ��낤���A���ꂪ�ߋ����A�����A�����ɓn��u�O���̈��ʁv�ƂȂ�ƐM���K�v�ƂȂ�B�����M���Ȃ����̂ɂƂ��Ă͉��̉��l���Ȃ����̂��낤�B����ǂ��납�~�]�̕����܂܂ɐ��������l�ԂɂƂ��Ă͂������Ďז��Ɍ�������̂��낤�B�c�O�Ȃ��ƂɌ���ɂ����Ă͂��̈��ʂ̖@�����邱�Ƃ��܂���ʂ��Ă���B�܂����̈��ʂ̖@��m�邱�Ƃ���n�߂Ȃ���Ȃ炢����ł���B�u�M��E�v�͌��n�����̒��ɂ�����A�e�a��y���قǂł͂Ȃ����A�ߑ��̌��t��M���邱�Ƃ��畧���͎n�܂�B���ʂ̖@�ɂ��Č����A�u�P���P�ʁA�������ʁv�����S�ł���B�@
���������Ȃ�����A���ۂɂ͂��̐��E�ł͈������h����悤�Ɍ����邱�Ƃ�����B����ɂ��Ă͂��łɎߑ��ݐ�������^������҂������悤�ł���A�܂�����ł����ʂ̖@�����Ƃ��ɂ͔��_����邱�Ƃ��낤�B�ߑ������ʂ̕\��鎞�ԓI�Ȃ���͔F�߂���ŁA���ԓI�ɂ���邱�Ƃ͂����Ă��K�����̈��ʂ͕\��A���ɂ��̐����������Ƃ��ɂ͂�����Ƃ��ꂪ�킩��Ƃ��Ă���B�u�������Ƃ����Ă��A���̋Ƃ́A�����̂悤�ɒ����Ɏa�邱�Ƃ͖����B�������A�����ɂ����ނ��Ă���A�����s���������l�X�̍s�������m��̂ł���B�̂��ɁA���̕���Ƃ��ɁA�������ꂵ�݂��N����B�v(�u�����̌��t(�E�_�[�i�E���@���K)�v)�V�ォ��n���܂ł̈�����܂߂����E�����邱�Ƃ͎ߑ��̌��t�ɂ͂�����Ɛ�����Ă���B�@
�������Ă��̐��̂��Ƃ����ł͂Ȃ��u�O���̈��ʁv���������B���̏�ł���ɂ�����z���āu���̐��Ƃ��̐����Ƃ��Ɏ̂Ă��v�ފ݂̟��ς̐��E��������Ă���B�u�z�藬���ώ��̐����炵�s�����ė]�����Ƃ̂Ȃ��C�s�҂́A���̐��Ƃ��̐��Ƃ��Ƃ��Ɏ̂Ă�B���������ւ��������E�炵�Ď̂Ă�悤�Ȃ��̂ł���v(�u�X�b�^�j�E�p�[�^(�u�b�_�̌��t)�v)�B�e�a���u�����o�Âׂ����v�����߁A�u�㐢�v���F��Ƃ����̂́A�u�O���̈��ʁv��M������ŁA�Z���։�̒��̍ō����ł���V�㐢�E�ɐ��܂ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�������ڎw�����Z���։���z�������E�Ɏ��낤�Ƃ�������ł���B�@
�����Ɏ���̂��܂����ʂ̗��@�ɂ��B�u��(��)�A�W(��)�A��(��)�A��(��)�v�́u�l���v���ς����H���邱�Ƃʼn\�ɂȂ�B�u�����v�����̎��H�ŁA���n�����ł́u������(�����A���v�A����A���ƁA�����A�����i�A���O�A����)�v�A��敧���ł́u�Z�g����(�z�{�A�����A�E�J�A���i�A�T��A�q�d)�v���������B���̎��H�����Ƃ��ĔϔY��f���s�������̐��Ŕފ݂Ɏ���B�@
�ł͌����ŔϔY���ł��s�����Ȃ�����������̐����։�̒��ɂƂǂ܂邩�Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��B�����ʼn�E�ł��Ȃ������Ƃ��Ă�������߂�K�v�͂Ȃ��A�ߑ��͉��ɔϔY���c�����Ƃ��Ă��l�����ς��čs�����҂͖����̐����ɂ͖߂�Ȃ��Ɛ����Ă���B�����̈��͂��̐������ŖŒ��̉ʂ������炷�킯�łȂ��A����ɂ������̐����𗣂��Ƃ����Œ��̉ʂ���B����͐�ɏq�ׂ��A���ԓI�ɂ���邱�Ƃ͂����Ă��K�����ʂ͕\��A���ɂ��̐����������Ƃ��ɂ͂�����Ƃ��ꂪ�킩��Ƃ������Ƃ̉�����ɂ���A�u��(��)�A�W(��)�A��(��)�A��(��)�v�́u�l���v�̈��ʂƁu�O���̈��ʁv��g�ݍ��킹�����̂ł���B�@
�u�ǂ�ȋꂵ�݂�������̂ł��A���ׂđf���ɉ����ċN����̂ł���Ƃ����̂��A��̊ώ@�ł���B�������Ȃ���f�����c��Ȃ��~�ł���Ȃ�A�ꂵ�݂̐����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂����̊ώ@�ł���B�C�s�m���A���̂悤�ɓ��𐳂����ς��āA�ӂ炸�A�Ƃߗ��ŁA��S���Ă���C�s�m�ɂƂ��ẮA��̉ʕ�̂����̂����ꂩ��̉ʕ��҂��꓾��B���Ȃ킿�����ɂ�����ؒq���A�����͔ϔY�̎c�肪����Ȃ�A���̖����̐����ɖ߂�Ȃ����ł���v(�u�X�b�^�j�E�p�[�^(�u�b�_�̌��t)�v)���l�̌��t���\�Z��J��Ԃ���Ă���B�@
�����e�a�́u���������ځv�u���������v�Ɠ��l�̂��Ƃ�������Ă���B�ߑ��ɂ����Ă͎����������ł���悤�Ɂu���y�����v�����S���������낤���A���ꂾ���ł͂Ȃ���y���́u�ޓy�����v�ɓ�������̂����łɐ�����Ă���B��y���̌��_�͊m���Ɍ��n�����ɂ���B��y���͂����ΐ����傩�畧���ł͂Ȃ��Ɣᔻ�����B����͂��ꂩ��q�ׂ�悤�ɐ�����̈��ʂ̖@�̏�ɂ���ɏ�y�̈��ʂ̖@����������炾���A�����̊�{����͂���Ă͂��Ȃ��B���n�����̉�����ɂ���A�ނ����y�傪�J���ꂽ���Ƃŕ����͊��������ʂ�����B�@
���͂��̈��ʂ̗��@���A���n�����ɂ����Ă͍��݂̏O�����o���_�Ƃ��A���������E���邩�A��E���������̖������J��Ԃ����́A���݂��獟�݂ւ��A���݂���ފ݂ւ̈���ʍs�̈��ʂł��邱�Ƃ��B���̈��ʂɊ�Â��ƌ��݂̋�̉ʂ͉ߋ��̖����̈��̌��ʂł���A�܂����݂̋�Ɩ��������ƂȂ��ė����̋�������炷�B���̘A���̒��ɂ��邱�Ƃ�m�炳���B�����ߋ����ɂ����ĉ�E���Ă�����͂₱�̐��Ɋ҂��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA���̐������邱�Ƃ͉ߋ����ʼn�E���Ă��Ȃ��������Ƃ������Ă���B��������������Ɗ��������͉ߋ����ʼn�E���������Ƃ͎v���Ȃ��B�ߋ����̖����������̋�ƂȂ��Ă���Ǝ����̂ł���B�@
���̂��ߎߑ��ł����Ă��A�����͂���܂Ŋ����ƂȂ����v�ɐ����̋ꂵ�݂��o�����Ă����Əq������̂ł���B�u�킽�����͊����̐��U�ɂ킽���Đ����̗���v�Ɍo�߂����ė����A-���̐��U�A���̐��U�Ƃ��肩�����̂͋ꂵ�����Ƃł���B�v(�u�^���̌��t(�_���}�E�p�_=�@��o�̌��T)�v)�e�a���܂��u���X���X�ɂ���������������肯�߂Ƃ܂Ŏv�Ђ܂�炷��g�Ȃ�v�ƌ������A����͐����̈��ʂ�M�������ʂł���B���ꂪ���͍��݂̏O�����N�_�Ƃ���u�����̈��ʁv�̓����̈�ł���B�ߑ��͎��ۂɂ͊ґ��̔@���E��F�������͂������A������������݂��N�_�Ƃ��邱�̈��ʂɊ�Â��Ƃ��̂悤�Ɍ��킴������Ȃ��̂ł���B�@
���ꂪ���̌�ɏq�ׂ��y���N�_�Ƃ���u��y�̈��ʁv�ɂȂ�ƈ���Ă���B�@�R�͂��̓x�̉����͎O�x�ڂ����A����͂��Ƃɉ����𐋂��₷���Əq�ׂ邵�A�܂�����ґ��̕�F�ł��邱�Ƃ��q�ׂ�̂ł���B�u���I���̊������Â��Ė{�t����̂��܂͂������݂��тɂȂ�ʂ�ɂ��̂��т��ƂɂƂ��₷���v(�e�a�u���m�a�]�v)�A�u���A���ƋɊy�ɂ��肵�g�Ȃ�A�����߂Ă��ւ�䂭�ׂ��v(�u�@�R��l�s��G�}�O�\���v)�B�@
����͈��ʂ̋N�_�����y�����y�ɓ]���������Ƃɂ��B�u���݂̈��ʁv�ł͍��݂��o���_�Ƃ���̂ŁA���̈��ʂɂ���Đ������J��Ԃ����݂ɗ��܂葱���邩�ފ݂Ɏ��邩�̂ǂ��炩�ŁA�����։������ł���B�u��y�̈��ʁv�ƂȂ�Ə�y�̔@�����o���_�Ƃ��Ă��̉���ł��鉝���Ɗґ��̗��������o�Ă���B�^�����z������ʂ̖@�ł���B�����͂ǂ���ɂ�����̂ŁA�ґ�������̂��u��y�̈��ʁv�̓����ł���B�����ߑ����ґ��̔@���E��F�Ƃ��Ď��Ȃ猋�ʓI�ɏ�y�̈��ʂ�F�߂邱�ƂɂȂ�B������ł���敧���ł́u�v�������̎߉ޕ��v������A�ߑ��͂��̉����Ƃ���B����͏�y���̊ґ��Ɠ��l�̕����ł���A��y�̈��ʂ�F�߂��̂����R���낤�B���Ǖ����A���ɑ�敧���Ƃ��Ă͉����A�ґ��̗���������̂��]�܂����̂ł���B���̂悤�ɐe�a��y���͕����̈��ʂ̊����Ƃ����Ӗ��������Ă���B�@
�b�����ɖ߂��A���͂̏C�s�ŔϔY��₿�����Ƌ�̈��ʂ̘A�������z���邱�Ƃ��ł���Ȃ�A�������z���ğ��ςɎ���Ăѐ����ɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ��B���������ꂪ�ł��Ȃ��ƂȂ�ƁA�������J��Ԃ������Ȃ��B���̍��y�̏O�����N�_�Ƃ���u�����̈��ʁv��M���邱�Ƃ͕����̊�{�����A���̈��ʂ�M�������ʂ����炳��邪�A���҂̏ꍇ�͏o�������A��X�}�v�ɂƂ��Ă͏o���s�\�ł���B���ꂪ�u�@�̐[�M�v�ł���B�~�]�l�ԂɂƂ��Ă̈��ʂ̐M�ł���B���̈��ʂ͓��ꂪ�����Ƃ̘A���Ƃ��āA�ߋ������݂��������O���ɓn���X�ɂ̂��������Ă���B�����̋�E�ɂ��邱�Ƃ����̈��ʂ������Ă��鉽���̏��ł���B�@
�u�����̈��ʁv�͌������ʗ��Ƃ������̗̂��m�I�ȗ����𒆐S�Ƃ��āA�u�����։�v�̐����̘A�����Ƃ����O���̐���M���邱�Ƃ�g�ݍ��킹�����̂Ȃ̂ŁA�u�@�̐[�M�v�͎�����[�����߂����ʂ����炳��闝�m�I�Ȏ��o�ł�����B����������͕��ʒm�ł���B�@
�����ɂ����Ă�����̈��ʂ��v�������B����͂��łɏ�y�ɂ���@�����N�_�Ƃ�����ʂł���u��y�̈��ʁv�ł���B��y�̔@���̖{������Ƃ��č��y�̏O���������ŐM�S�ċ~����ʂ������炳��A����ɂ�����܂����Ƃ��ď�y�ւ̉��������Ƃ����ʂ������炳���B�@�����N�_�A�o���_�Ƃ���@������̈��ʂł���B�����M����̂��u�@�̐[�M�v�ł���B�����ł̖@�́u��y�̈��ʂ̖@�v�u�@������̈��ʂ̖@�v�ł���B���ꂪ���͂̐��E�ł���B���̐M�͒m�ɑΉ�������Ζ����ʒq�ł�����B���ꂪ�u�M�S�̒q�d�v�ł���B�u���[�M�v�͐����̈��ʂ̐M�Ə�y�̈��ʂ̐M��g�ݍ��킹�����̂ł���B�u�����̐M�v�ƌ����邪�A�����ɂ͕����̈��ʂł���u�����̈��ʁv������A�����M������̂��B������̈��ʂ����Ă͂��̐M�͂Ȃ肽�����A�u�������V�v�Ɋׂ�̂͂��̂��Ƃ��킩���Ă��Ȃ�����ł���B�@
���́u��y�̈��ʂ̖@�v�́A��y�̑c�t����n�܂邪�A���̎���ł͖@�R�����̒[�����J���A�e�a�́u���s�M�v�ɂ���Ċ������ꂽ�ƌ����Ă������낤�B����ɂ�蕧���̈��ʂ̖@�����������ƌ�����B�����A�ґ��̗����������������ƂȂ�B����X�͂��肪�������ƂɁA���łɖ@�R�A�e�a�ɂ���Ċ������ꂽ���̂���邱�Ƃ���n�܂��Ă��邪�A����܂łɂȂ����̂�������Ƃ̓���͑z����₷����̂����邾�낤�B�e�a�͂����Όo�T�̓ǂݑւ����s�����A�u��y�̈��ʂ̖@�v������������c�݂������ɂ���B�@
���̂悤�Ɍ�Ɋ����������ꂩ�猩��Ζ@�R�̋�������邱�Ƃ͗e�Ղ��낤���A�e�a�͒��N��b�R�Ő�����̏C�s�������l�Ԃł���A������̈��ʂ��g�ɂ��ݍ���ł���B���ꂩ�猩��Ώ�y�̈��ʂ̐��E�i�ނ̂́A���̒i�K�Ƃ����Ȃ������]���ł���B�e�a���Z�p���ɂ������Ă���@�R�̒�q�ɂȂ�܂ł̕S��\�ܓ��Ԃ����̓�����悭�\���Ă���B�u�b�M��v��ǂ݂Ȃ��犴�S�[�����̂��������B�@
�܂��Z�p���Ŏ������͊ω������Ȃ��̍ȂɂȂ�Ƃ������̂������ƍl�����Ă���B���̖������L�����̂��u�F���e�v�ł���B������o�W(���)����Ă���B�e�a�̔Y�݂Ƃ��̉����A���̌�̐e�a�ƌb�M��̏o��������ɂ���B�N�̔Y�݂ƒj���̏o��B���̔w��Ɍ�����̂��@�R�ƈ���ɕ��̑��݂ł���B�@
���͌��̊G�Ɛ^�������߂�t�Q���@
���̑��ɂ�����ׂ����̂͑��X���邪�A�{�莛�W��������A���͏�ݓW�������̂Ő�ɂ��̂��ƂɐG��Ă����B�����Ō����G�ɁA�e�a�ƌb�M�Əd�Ȃ���̂��������B������͌��̓V�����悤�Ȏ��摜�ƁA�u�R�~�T�v�Ƃ����낢�ċF��悤�ȏ������ł���B���ꂪ�o��O�̐e�a�ƌb�M��̎p�ɏd�Ȃ��Č����Ă���B�͌�(1907-1946)�͍L����(�k�L�����p��)�o�g�̉�ƂŁA��N2007�N�����a�S�N�ɓ�����A������L�O����W������������ߑ���p�ّ��A�L���ł��J���ꂽ�B���̍ۂɂ����̊G���������A������Ɉ�ۂɎc�����B��N�͂܂�1207�N�́u����(���i)�̖@��v���甪�S�N�̔N����������ł���B�@
�͌��̎��摜�͎O��ނ��邪�A�L���������p�ُ����̂��̂́u�X�q�����ނ鎩�摜�v�ł���B���̎��摜�͐푈���ɕ`���ꂽ���̂ŁA���̂ǂ����V�̈�p�����悤�Ȏp�͋��̎���̒��Ő^���̔������߂Ă������Ă���p�̂悤�ɂ��A�܂��~�������߂Ă���p�̂悤�ɂ�������B�N��I�ɂ͎O�\�㔼�̂��̂����A�^�������ߋꂵ�ސN�̎��摜�ƌ����Ă������낤�B���̎���̑����̎�҂������悤�ȋC������������������Ȃ��B�������߂��Ƃ͒N�����q���ɍ���Ȏ���̒��Ő^�������߂悤�Ƃ��Ă����悤�Ɍ�����B���̎p�ɔ�b�R����̐e�a�Əd�Ȃ���̂�������B�e�a����b�R�Ő^�������߂Ȃ��炵���ΓV�������Ƃ��������̂ł͂Ȃ��낤���B�L���X�g���Ɂu�_�̒��فv�Ƃ�������̂�����B���߂Ă��F���Ă��_�͒��ق����܂܂ł��邱�Ƃ�\�����̂��B�����ł���������u�@���̒��فv�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B���߂Ă������Ȃ����̂��Ȃ����߂�������Ȃ��l�Ԃ̎p�������ɂ���B���ꂪ�@�R�Əo��O�A�{��Əo��O�́A�㐢���F���Ă����e�a�̎p���낤�Ǝv���B�l��������x�͒ʂ铹�ł���B�@
������́u�R�~�T�v���͌���\��̍�i�ł���B�P�Ɋ�肩�����Ėڂ���������͘낢�ċF���Ă���悤�Ɍ�����B�薼�͍�҂̖��̖�����������̂����A���̕��͋C���L���X�g���́u�~�T�v��A�z������B�����̋F��ɋ~�������߂���̂�������B���̍�i�͍�҂��X�|�������I�[�̉e���������o�Ă���ƌ�����B���I�[�̓L���X�g���̏@����ƂƂ��Ă悭�m���A���̍�i�����I�[�̂��@�����������p���ł���悤�Ɍ�����B�@
���ɂ͂��ꂪ�e�a�Əo��O�̌b�M��̎p�Əd�Ȃ�悤�Ɍ�����B�ޏ��͔Ӎ��Őe�a�Ƃ̏o��̌o�܂͂͂����肵�Ȃ����A�ޏ������������̍K�����F��Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��A�e�a���l�Ɍ㐢���F��C���������������̂ł͂���܂����B�����łȂ������K���Ȍ�����]�ނ����Ȃ�A�����͂��肦�Ȃ������m���Ƃ̌����ɓ��ݐ�͂����Ȃ��B��l���ǂ��Ō��ꂽ���͂͂����肵�Ȃ����A�������@�R�̋������������������ƍl����������R�Ɏv����B������܂��e�a���@�R�ɏo��܂ł̎����̂��Ƃ�ޏ��Ɍ�����̂��Ǝv���B�͌��̍�i�́A���̌������@�ɂ��̌����O�ɂ��̍�i��`�����ƌ�����B���͎����̂��ꂩ��̍K���F���Ă����̂��낤���B���邢���͌��͎����̋C�����ɓ��e�����̂�������Ȃ����A�܂����������̗����҂Ƃ��Ď����̋C�������ق������̂�������Ȃ��B���̋����Ƙ낭�����A�₪�Đ^���ɂ����ďo��Ƃ��A�e�a�ƌb�M��̑��̂悤�Ɍ������������ɂȂ�悤�Ɍ�����̂ł���B�@
�e�a�ƌb�M��̏o��ȗ��A�t�Ə�y���̉��͐[���B�����20���I�ɂ����Ă������ł���B�u�V�ُ��v���N�𒆐S�Ɉ�ʂɓǂ܂�n�߂��̂͐��V(1863-1903)�Ƃ��̖剺�̉e�����傫���B���V���u���_�E�v�s�����̂�1901�N��20���I�̏��߂̔N�ł���B�L���������s�o�g�̑q�c�S�O(1891-1943)���u�V�ُ��v�����~���ɂ��ď������u�o�ƂƂ��̒�q�v��1916�N�ɔ��\����A�x�X�g�Z���[�ƂȂ����B�u�o�ƂƂ��̒�q�v�͐t�̏@�����w�ł���B�܂����łɏq�ׂ��悤�ɁA�u�V�ُ��v�Ɠ��l�ɁA�e�a�̌��t�����ۂɂ��̏�ŕ������u�e�a���C�u�v�Ƃ��Ă�����L�����b�M��́u�b�M��v�����{�莛�Ŕ������ꂽ�̂�1921�N�̂��Ƃ��B�����ɂ͐N�e�a�̎p�ƌb�M��̎p���L����Ă���B���ꂪ���������܂Ōb�M��̑��݂͍��̂悤�ɑ傫���͂Ȃ������͂����B�����́u�V�ُ��v��u�b�M��v�͌ÓT�Ƃ��������A�V�����������ꂽ�����Ƃ��ĐN�̐S��߂炦���̂��Ǝv���B�@
�܂���ɏq�ׂ��͌���20���I�O��������Ƃł���A�����ɂ�������20���I�O���̐t������B�͌��̎��摜�Ɓu�R�~�T�v��20���I�̐t�Q�����\���邩�̂悤���B�u�V�ُ��v��u�b�M��v�����ꂽ�̂��A�͌��̊G�����ꂽ�̂��A�ނ�20���I�O���̐t�Q���������̂��낤�B�e�a�ƌb�M��̕����20���I�O��������҂̐t�ƌĉ�������̂��h�����i���̐t�ƌ����ׂ����̂��������̂��Ǝv���B����͒P�Ȃ郍�}���e�B�V�Y���ł͂Ȃ��B�t�̐^���Ȑ^���ƈ������߂�p�������ɂ���B�e�a�ƌb�M��̑��݂́u���ʎ��v�ɏƂ炵�o���ꂽ�t�ł���A��l�Ȃ̂ł���B�����Ɏ䂩�ꂽ��҂͂������̗��z���Ƃ����̂��낤�B
 �@
�@���،��̎v�z
��ḎՓߕ��́A�����ƃC���[�W���₷���悤�ɂ����Γ��厛�̑啧�������B���̓ޗǂ̎��������Z�܂��ޗnj����ɂ��铌�厛�̑啧�B�@
���厛�͌��݂��،��@�̑��{�R�ł��B�@
���啧�����Ƃ����i�V���i���E�v���W�F�N�g�@
�����V�c�̔���ɂ�葢��ꂽ���厛Ḏɓߕ����́A������������́u�A�m�E���@���{1�_�������̔閧�\���{�̖ʉe�̌����������v�ɂ��ƁA�S���e�n60�ӏ��Ɍ��Ă�ꂽ�������E�����ƃl�b�g���[�N���ꂽ�z�X�g�}�V���Ƃ��č��ꂽ�����ł��B���厛�𑍍������Ƃ��āA���ʃ\�t�g�Ƃ��Ắu�@�،o�v�Ȃǂ�ʂ��đS���̍������E�����Ə��l�b�g���[�N���\�z�����̂�8���I�̑啧�����Ƃ����i�V���i���E�v���W�F�N�g�B604�N�ɐ������q���u�\�������@�v�Łu�O��(���E�@�E�m)���h���v�ƕ����V�X�e���̃K�o�i���X��\���������Ƃɑ����A����̓I�ȍ��ƋK�͂̒���V�X�e����v�E�J�������̂��A���厛���z�X�g�}�V���Ƃ����������l�b�g���[�N�̍\�z�ł����B�@
���ƓI�ȏ��l�b�g���[�N�Ɋւ���v���W�F�N�g�Ƃ��Ă͌���ȂǂƂ͔�ׂ��Ȃ��قǁA�������ꂽ���̂�������ł��ˁB�������A�n�[�h�ƃ\�t�g��������ƘA�g����悤�v����Ă܂��B�n�[�h�A�C���t�������������āA�\�t�g�A�R���e���c���Ȃ��Ȃ�Ĕn���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B���������Ӗ��ł��A�̂̓��{�̂ق������V�X�e���̐v�ɒ����Ă�����Ȃ����ȁA�Ȃ�Ďv���܂��B�@
���������K�͂̃v���W�F�N�g���Ђ��ς�郊�[�_�[�V�b�v���A���̍����ƂȂ�v�z�����܂̓��{�ɂ͂Ȃ��ł���ˁB���₢��A�����ƋK�͂������ȃv���W�F�N�g�ł����A���[�_�[�V�b�v��v�z�̌��@���ڗ����炢�ł����B�@
�V�X�e���S�̂��I�ɐv�ł��Ȃ��āA�ڐ�̏����ȃp�[�c�ɂ����ڂ������Ȃ����A���̃p�[�c�ɖڂ��ڂ����Ƃ��ɂ͂����O�̃p�[�c�̂��Ƃ͖Y��Ă��܂��Ă��肵�܂��B������������Ȃ��B�ɓx�ɃV�X�e���v�l�����@������Ԃł��B����Ɋ����I���z�������āA��������ɃV�X�e���I�v�l���쓮������Ƃ����|������肷����B�Ȃ̂ŁA������Ƃ����C���^���N�V�����̃f�U�C��������ɂ��V�X�e���I���z���ł��Ȃ��B���̂�����͂���������ƃV�X�e���I�Z���X��{���K�v������܂���ˁB�@
���������A���V�X�e���Ƃ�����IT�̂��Ƃ��Ǝv���Ă�ӂ�������܂���ˁB�啧���������l�b�g���[�N�����V�X�e�����������Ƃ��킩���Ă��Ȃ���ł���(�u���{����^���������v�Q��)�B�������A���ꂪ�����╧���A���z�����f�B�A�ɐV���������Ƃ����v�z���\�t�g�ɂ����}���`���f�B�A�ɂ����V�X�e���ł��������Ƃ������ł��Ă��Ȃ������肷��̂́A��قǃZ���X�������Ă��邩�A��������̂��ʓ|���̂ǂ��炩�ł͂Ȃ��ł��傤���B�@
������Ƙb���E�����܂����B�߂��܂��B�@
���،��Ƃ������V�X�e���@
�،��o�ɂ͂ǂ�����������������ȏ��V�X�e���̃C���[�W�����܂Ƃ��܂��B�@
�u�،��o�v�ł������������̂́A���o�̂Ȃ��ɑ傫�Ȑ��E���S�����荞��ł��܂��̂��Ƃ����l�����ŁA���ꂪ����ɂ���B�ȒP�ɂ����Ɓu�ꑦ���E������v�A���ꂪ�u�،��o�v�Ő�����邢���{�I�ȍl�����ł���B�@
���́u���o�̂Ȃ��ɑ傫�Ȑ��E���S�����荞��ł��܂��v�u�ꑦ���E������v�̎v�z���A�ޗǂ̑啧�������Ă������̘@�قɂ��\������Ă��āA�@�ق̈ꖇ�ꖇ�ɕ����I���E���ЂƂ��`����Ă��āA���̑S�̂ʼn،��I�ȎO���琢�E���\������Ă��邻���ł��B���̎O���琢�E���܂�����ȃl�b�g���[�N��z�N�����܂��B�@
���ۂɂ���̓l�b�g���[�N=�Ԃ̃C���[�W�ŕ\������Ă��āA��ḎՓ߂���ߓV�ɂ��点����Ԃł�����ɗ��Ԃ́A�u���іڂɂ����ʂ��݂��ɑ��f���A�f�����삪�܂��f�������Ė����ɉf����W�ł����āA�،��̏d�X���s���������v�̂��Ƃ����܂��B�p��ł́A������p�[���E�l�b�g���[�N�Ƃ����B�@
���ɗ��Ԃ̓��C�v�j�b�c�̃��i�h���W�[(�P�q�_)�Ƃ����Ă��܂����A���i�h���W�[���ЂƂ̃��i�h�̂Ȃ��ɑS���E�������Ă���ƍl����̂ɑ��A�،��̎v�z�ł͂�������̂ɐ��E�̂�������̂������Ă���ƍl���܂��B���ꂪ�u�����̈�厖�n�A�a���V���������܂��炩�����v�ł��������،��̎������G�@�E(�����ނ��ق�����)�̃C���[�W�ł��B�̂Ȃ��ɕ��Ղ�����A���Ղ̂Ȃ��ɂ�������B�@
���u���q�v�́u�ĕ��_�v�Ɖ،��@
������������߂Ď���̑傫�Ȏv�z�́A���Ƃ��ƒ����ɂ������A�F���I���삩��l�Ԃ��l����u���q�v�́u�ĕ��_�v�͖�����̂�����v�z�ƃC���h�I�v�҂̓T�^�ł���u�،��o�v�̎v�z�Ƃ��A�����̉،��@���������������̂��Ƃ����܂��B�@
���q�́u�ĕ��_�v������ƁA����̑Η����A���t��_���ɂ����Ă����Ȃ��Ȃ�A�Η��͂���ɑΗ��݁A�����ɓ����������A���_�͏��Ղ���݂̂ł���Ƃ����B�l�Ԃ�����������炤���Ƃ���߁A���̈��炬�����߂悤�Ƃ���Ȃ�A�c�_�⑈���ɂ��������̂ĂāA��̈�Ƃ��Ắu�V��v�ɂ܂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B�@
�V��(�Ă�)�Ƃ́A��̈�ł���A�����̂��̂ł��邻���ł��B�@
�u���Ǝ��A�ƕs�A���Ɣ�̑Η����A����͂������ɑ�����A���҂��Đ������鑊�ΓI�ȊT�O�ɂق��Ȃ炸�A��̖����̑Η������A���̂܂ܐ��E�̎����v�Ȃ̂��Ƃ����B�܂��ɖ������܂߂āA���ׂĂ������ɓ����Ă���B�@
����Љ���u�����E���E�E�y���{�����̎��R�ƕ��a�v�ł��Ԗ�P�F���A���|�����Ƃ�������Ñ�̖����L��Ԃ���A���L�������L�������Ă����Ə����Ă������Ƃɂ��ʂ���ȂƎv���܂��B���L�������L�����z�ŁA���ǁA����͌��|�������݂��̈قȂ鑊�ł����Ȃ��A����͖{���͕s��ł���ƁB�@
�u�u�������v�Ƃ�������Ɂu�����v��������I�v�Ŗl�͘_�̏Փ˂�����������@�Ƃ��Đ��m�I�ȕُؖ@�Ɠ��m�I�ȕs��̕��@������Ə����܂������A���q�́u�V��v�͂܂��ɐ�̈�Ƃ��Ă̕s��ł��B�@
���ꂪ�،��o�́u�ꑦ���E������v�̎v�z�ɘA������B�������������đ傫�Ȉ�ւ̓����ڎw�����m�I��_���I�ȍl�����ɑ��āA���m�ł͑��_���I�ɖ�����������܂܂̑Η������������̂܂ܕs��̈�Ƃ݂�B�������q�ł���Ɠ����ɔg�ł���Ƃ����C���[�W�ɋ߂��B�Y�݂�����������Ă�������������悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�Y�݂���������邱�Ƃ����̂܂ܔF�߂�p�����Ƃ�܂��B���ƏO���͓����ŁA���������ƏO���ƂȂ�A�O�������ƕ��ɂȂ邻���ł��B�@
���،��̎v�z�@
�����ɂ��ẮA�l���g�A�O�ɁA������������́u��C�̖��v��u�O�́A�NJ��B�v�A���Џ@�v����́u������ʎ�S�o�v�Ƃ������{��ǂ��Ƃ����邭�炢�ŁA�����킩��Ȃ��h�f�l�ł��B�@
���̖{��ǂ̂́A�������͕����ɂ��Ă��m���Ă��������ȂƂ����v���������āA��������́u�A�m�E���@���{1�_�������̔閧�\���{�̖ʉe�̌����������v�ɁA�T�̗�ؑ�ق��ӔN�قƂ�lj،��̂��Ƃ���������ĖS���Ȃ������ƂɋC�Â��������w�҂ł���A�،��̐��E�ςɊS�������Ă����f�C���B�b�h�E�{�[����t���b�`���t�E�J�v���̂悤�Ȑ��m�̉Ȋw�҂ɊS�������Ă��������w�҂Ƃ��āA���̖{�̒��҂ł��銙�c�ΗY���Љ��Ă��ċ���������������ł����B�@
����ɂ��Ă��u�،��̎v�z�v�Ƃ͂悭���������̂��ȂƁA���̖{��ǂ�Ŋ����܂����B�،��o�Ƃ����̂́A�@���Ƃ������v�z�ł��B�Ȃ̂ŃL���X�g���Ȃ��́A�M���V�A�N�w�Ȃɋ߂��B�@
�v�z�Ƃ��Ċm�����ꂽ�����̉،��́A���{�ɂ����Ďv�z�Ƃ������������̍s�@�̂Ȃ��ɐ������ꂽ�Ƃ����܂��B�@
��C�͓��{�l���ꂵ���g�D�͂ƒ��ϗ͂ɒ����A�\�Z�S�̓N�w�̌n�ɂ����ĉ،�����ɒu���A�������\�Z�S�ɐ������̂ł������B�N�w�Ƃ��Ẳ،��͖����I�s�@�̗��_�Â��ɗ��p���ꂽ�̂ł���B�@
���{�ɂ����Ďv�z�Ƃ��Ẳ،��͂����H�I�Ȗ����̍s�@�ɕϊ����ꂽ�B����ɐV���̉،����z���������R���h�̖��b��l�͉،��Ɩ�����Z�������Ȃ������ō��T��g�݂܂����B���b�̏ꍇ���v�z�������H���d�������̂ł��B�@
���v�z���琸�_�ց@
����ɒ����ɂ����Ă͋���Ȏ�������������V�X�e���_�I�Ȏv�z�ł������،��́A���{�Ɏ�e�����Ȃ��ŁA�u���������݂̂͂Ȃ������v�Ƃ������u�����q�v�ɑ�\�������{�l�̎��R�ςɒ蒅���A�v�z���疯���I���_�ɕϊ�����Ă����܂����B�@
�����Ȃ����́A�����Ȃ���̂̂Ȃ��ɖ����Ȃ���́A�̑�Ȃ���̂��h���Ă���Ƃ����u�ꑦ���v�̎v�z�́A���{�l�̐�������ɂ��҂����肷����̂��������B��ɍ炭��ւ̃X�~���̉Ԃ̂Ȃ��ɑ傢�Ȃ鎩�R�̐������������邱�Ƃ��ł���̂́A���{�l�̒��ϗ͂ɂ��B�ؓ��⒃���̗��O�ɂ����̐��_�͐����Ă���̂ł���B�@
���̖{��ǂ�ł��،��o�̂��Ƃ͖l�ɂ͂悭�킩��܂���B�����̂��Ƃ��킩�����Ƃ͂����܂���B�@
�ł��A���g�͂킩��Ȃ��܂ł��A�،��o���邢�͉،��@�Ƃ������̂��ǂ̂悤�ɂ��Ē����Ō`�𐬂��A���ꂪ�؍�����{�łǂ��W�J���ꂽ�̂��Ƃ��������A�u�،��o�v�Ƃ��̂ق��́u�@�،o�v�u�ʎ�o�v�Ƃ̊W�͂Ȃ�ƂȂ����߂������ł��B����Ɠ����ɁA���Ă̓i�V���i���E�v���W�F�N�g�Ƃ��Đ��i����A������T��ʂ��A�܂����{�l�̎��R�ςƂ���̂ƂȂ����،��̎v�z���͂��߂Ƃ��镧�����A���܌����Ȃ܂łɌ���̐�������̏ۂ���Ă��邱�Ƃɂ��炽�߂ċ����������܂����B�@
���@
�@��������悭�킩��Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ��悭�킩��������ɂ����O�ɁA�،����@���Ƃ������v�z�ł������Ƃ����F�����܂߂āA����͂��������������ƕ����ɂ��Ă��l���Ȃ��Ƃ��߂��ȂƎv���܂��B���̂��ƂɌ��炸�A���{�l�͉ߋ��̓��{�̂��Ƃ�Y�ꂷ���Ă܂��ˁB�s���A�ӑĂɂ��قǂ�����܂��B����ȏ�Ԃ�����C�O�ɑ��ē��{���������A�J�E���^�r���e�B���ɉʂ������Ƃ��ł��Ȃ���ł��傤�ˁB�����Ƃ����Ȃ��ƁB �@
 �@
�@�����@�ƓV�c
���@(���@�Љ�)�ƓV�c(�u���Ɓv*)�Ƃ̊ւ��̕��������߂�Ȃ�A���ƕ����A����ɂ͕��@���`�܂ŗe�Ղɂ����̂ڂ邱�Ƃ��ł���B���ƕ����Ƃ����g�g�̂��Ƃŋ}���Ȕ��W���Ƃ������@�Љ�́A�������㒆�������Ƃ��āA�u���Ɓv�ɂ��ی�E�����͂̒ቺ��w�i�Ɏ������͂���A��̐������͂Ƃ��ēƕ����n�߂邱�ƂɂȂ�B�Ƃ͂������@�Љ�����Љ�ɂ����Đ��͂�ۂ��߂ɂ́A�u���Ɓv�Ƃ̖��ڂȊւ��͈ˑR�Ƃ��ĕs���ł������B�����ŕ�������ȍ~�̎��@�Љ�́A�u���Ɓv�̓����Ƃ͈��̋�����ۂ��Ȃ�����A���̐��h��}��Ƃ��āu���Ɓv�Ƃ̐ڐG�������������Ƃ�����B�@
*�{�e�ł́A�V�c����т���ɏy������c�̑��݁A����̌��ЂƐ����I�g�D���\����@�I�l�i�Ƃ��Ă̓V�c�E��c���u���Ɓv�ƌĂԂ��Ƃɂ��A�u�V�c�v�̌ď̂͗p���Ȃ��B�܂������Љ�ɂ���Ȃ���@���I���ꂩ��Ǝ��̈ӎu�\���ƎЉ�I�s���������Ȃ����@�E�m�c����т����̏W���̂��A���@�Љ�ƌĂԂ��Ƃɂ���B�@
���@�Љ�Ɓu���Ɓv�Ƃ́A�쎝�ƋA�˂Ƃ����o���W�ɂ���Č����ɋ�������Ƃ��������I�ȔF��������Ǝv���A���̑f�p�Ȍ����ɋ��莛�@�Љ�͎�����đ��������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ�*�B���������̌��������҂Ɏe���ꂽ���̂ł͂����Ă��A�����Ɍ������咣����̂́A�˂Ɏ��@�Љ�̑��ł��������Ƃ͌��߂����Ȃ������ł���B���@�Љ�́u���Ɓv�Ƃ̊W�̈ێ����͂��邽�߂ɓƓ��̘_���ݏo���A����ɐ��𗠑ł������邱�Ƃɂ��A���Ƃ��ƂɁu���Ɓv�Ɍ������Ď��@�Љ�Ƃ̑o���W�̍Ċm�F�����Ƃ߂��̂ł������B�@
*�u���Ɓv�́A�������J�҂Ƃ��Ă̑����ƁA����M�̑ΏۂƂ��Ă̑����������A���@�⎛�@�Љ�ƐڐG���邩����ŁA���̂悤�ȑ������u���Ɓv�̑O�ʂɌ����邱�Ƃ͂Ȃ��B�����Ŗ{�e�ł́A�_�_�Ƃ̊ւ��Łu���Ɓv���{���I�ɂ��@���I�Ȍ��Ђ�x�O�����Ę_��i�߂邱�Ƃɂ���B�@
���Ƃ��A���@�Љ�u���Ɓv�֕��t��E�\��ɂ́A�u������S�̒O���𒊂A���悢�斜�̕��N���F�����A�v(�u���ƎG�M���v���v)�ɗނ����\���������Ό��o�����B���������߂ċF���ɂƂ߁u���Ɓv���쎝���A�u���N�v�܂�݈ʁE�����̒�����}�肽���Ƃ��邱�̕\���́A������u���썑�Ɓv�̘_�����ے��I�Ɏ����ƂƂ��ɁA�쎝�E�A�˂̌����ɂ���Č����ɂ����ċ�̓I�ȈӖ��������ƂɂȂ�B���Ȃ킿�u���Ɓv���ێ�����F���́A�����܂ł��Ȃ����@�Љ�ɓ��L�̋@�\�ł���A���̌��Ԃ�Ƃ��āu���Ɓv�̋A�˂����҂���A����������͎��@�Љ�ɗL���ȍٌ������߂�ꂽ�̂ł���B�@
�܂������ɕ�������u���Ɓv�Ǝ��@�Љ���A���E�����E�ɑ�����u���@�v�Ɓu���@�v�ɒu�������A�u���@�͕��@�̎�Ȃ�A���@�͉��@�̕�Ȃ�A�v�Ɨ��҂̊W���K�肵�A�u���@�̍ċ��v���u���@�̉i�Łv�̕K�v�����Ƃ���Ƃ����ؓ������A�u���Ɓv�̎��@�Љ�ւ̗D���𐳓������邽�߂́A�u���썑�Ɓv�̘_��������i�߂��A������u���@�v�E�u���@�v���݈ˑ��̘_���ɂق��Ȃ�Ȃ�(���q�╶�k�ȉ��A���Ɨ����l��|��l�l��)�B�����Ă��̑��݈ˑ��̘_���ƁA�u��X�������Ȃĉ䎛�̒h�z�ƂȂ��A�Ⴕ�䎛�������ΓV���������A�Ⴕ�䎛�������ΓV����������A�v(�u���厛�v�^�v���Z)�Ƃ����A�h�z����u�����v(�u���Ɓv)��}��ɓV���̐����ƈꎛ�@�̐�������̉�����_���Ƃ́A���炩�ɑ����̊W�Ƃ��ė�������悤�B�@
�ی�Ɠ����𒌂Ƃ��鍑�ƕ������`�[������ߒ��ŁA��s�k��̎��@�Љ�͎���̑������x���邽�߂̘_����͍������B���̌��ʂƂ��Đ��ݏo���ꂽ���@�Љ���L�̘_���́A����������̐����I�Ȑ��͂��}���ɋ��܂镽������̌���܂łɁA�L�����E�����E�ɕ\���Ƃ��Ă܂��F���Ƃ��Ē蒅���邱�ƂɂȂ����B�����Ă����̘_���́A���ゲ�Ƃɓ��L�́u���Ƃ��ւ̈ӎ��̂Ȃ��ŁA�����Љ�ɂ����Ď����I�Ȗ������͂��������̂ł���B�@
���Ď��@�Љ�́u���Ɓv�w�̈ӎ��Ɗւ��́A���R�Ȃ��玞��Ə�ɂ���đ��l�ł���B�����Ŗ{�e�ł́A���@�Љ���ݏo�����_���̊����Ȃ��u���Ɓv�w�̔F���ɂ��Č��������̓I�ȑf�ނƂ��āA���q�������ɂ������F���@�c�̟E�t�@���߂��鎛�@�Љ�Ɓu���Ɓv�Ƃ̂��Ƃ�ƁA����ɕt�����Ă�����拍����_���Ƃ肠���邱�Ƃɂ���B�����ē����̓�s�k��Ɠ����̎��@�Љ�A�@���Ɂu���Ɓv�̑��݂�F�����A�܂��ǂ̂悤�Ȏv�f�ɂ�肱��ɑΉ��������ɂ��āA���@�Љ�̑��Ɏ����������čl���Ă݂邱�Ƃɂ������B�@
�����O(��O����)�N�A��F���@�c�͓����@�ɂ����āA���ґT����刢苗��Ƃ��ē`�@�������A����ɑ����(�R��)�O�k�͋������������B�����ĎR��O�k��������q�ׂ��A�u�䎡�V�Ɛ\�A���Z�Ɛ\�A�ɉ�R�̌쎝�ɂ���āA�V���̂��邶�ɂĂ܂��܂�����ɁA�v(�u���g�Л�b�R�s�K�L�v)�Ƃ̈ꕶ�́A�R��݂̂Ȃ炸���@�Љ�u���Ɓv�ɂ������S��̈�[��@���Ɍ���Ă��悤�B�@
�u���Ɓv�ɂ́A�V�c�E��c�l�Ƃ����l�i�I�ȑ��݂ƁA�u�V���v��̌�����@�l�I�ȑ��݂Ƃ�����ʂ�����B���@�Љ�ʂ����쎝�̋F���́A�l�i�Ɩ@�l�Ƃ����v�f���������u���Ɓv��ΏۂƂ�����̂ł���B�����Ď��@�Љ�̌쎝�ɂ��A�u���Ɓv�͂��̐����Ǝ������Ȃ��炦�邱�Ƃ��ł���Ƃ����F���́A�u���Ɓv�쎝���u�V���v�ɉh�̏����Ƃ���u���썑�Ɓv�̎v�z�ƑS�������ł���B�����Ă��̔F���́A�u���@�v�̓`���ȗ��A���N�ɂ킽����ƂƎ��@�Љ�Ƃ̐ڐG�̂Ȃ��Ŋm�łƂȂ��Ă������̂ł���B�@
�܂��l�i�Ƃ��Ắu���Ɓv�쎝�̓T�^�Ƃ��āA���a�������邱�Ƃ��ł���B���Ƃ��A�����\�O(�����l)�N�����V�c�́u�s���v�ɂ�葾�����������厛�ɉ�����A�u���S����njo�s���v���������Ă��邪(�����╶�k�ȉ��A���Ɨ����l��|�l�O����)�A�ʑ̂́u�s���v�ɂ������ċΏC���ꂽ�njo���͂��߉��߂��瓾�x�E����ɂ���Ԃ��܂��܂Ȗ@�v�́A�u���@�v�`����萳�j�ɋL����邩����ł������ɂ��Ƃ܂Ȃ��B�܂���������̏����ɏ������ꂽ�^���E�V�䖧���ɂ���Ă��A���a�̋@�\�͒S���邱�ƂɂȂ�B�i�v��(����O)�N�A���H�V�c�́u��s���v�ɂ�����A������m���ɂ��u���v�Ƃ��ċ{���Łu�E���o�@�v���ΏC����A�C���Ɂu�����v���������Ƃ�����(�u����L�v���l)�B�܂��u�s���v�ɍۂ��Ē��ڂɁu���Ɓv�̕a�����߂�Վ��̏C�@����ł͂Ȃ��A���炩���ߕa���E�����˂��邽�߂ɁA�N���s���Ƃ��Ă̌㎵����C�@��匳���@�ɂ������߉����A�֒��́u��Ԗ鋏�v�Ɍ�쎝�m�ɂ���āA�ʑ̈����̋F�����ΏC����Ă����̂ł���B�Ȃ����a�̋@�\�́A�u���Ɓv�l�݂̂Ȃ炸�M���w���͂��ߎЉ�I�ɍL�����߂�ꂽ���̂ł��邪�A�u��Z�v�Ɓu���V�v�̉�����}�邽�߂́u���Ɓv�̎��a�ƁA�����̎��a�Ƃ͂��̂����琫�i���قɂ��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�@
����A�@�l�Ƃ��Ắu���Ɓv�̌쎝�́A�u���ƕ����v�̂��߂̋������ŏ����o�Ȃnj썑�o�̓njo���͂��߁A�u���y���Ђ��A�J�͂��v����u���J�����āA���ɍ��y����߂�Ƃ��v���Ԃɓ]���A�u��������~���v���邽�߂̑匳���@���̏C�@�Ƃ����������ŋΏC����Ă����B���̑匳���@�̏ꍇ�A�u�V���v��l�i�I�ɑ�\����u���Ɓv�̋A�˂ɂ��A�{������匳���������u�ނ̉����̋��������v����Ƃ������̂ł���B�܂�u�����̕�A���G�̗v�v�Ƃ���鑾�����@�́A�u���Ɓv�l�̐��h��O��ɁA�u���Ɓv���̌�����u�V���v�̈����������������̂ł�����(�����|�l�l�l�Z�E�l�せ��)�B�����l(���l�Z)�N�A�㍵���c�͎���m�a�����[�@�e���ɁA�@
(�[����)�@
�u�哴�䏑�A�E���o�@�̎��A�b���L��A�����l�N�v�@
���N�̎O���̖�^�A���x�̕ψً���̏��A��捂̏��A���ɐ���@�̗쌱�Ȃ�A�����݂̂Ȃ炸���N���[���炭�A���J�������킸�A���ꖔ�얀�̗��v�Ȃ�b�A�@�͂̎���ӂ���Ƃ����m�炸�A���܂̎��ɂ����ẮA���������ׂ���A�����ʔq���k���J�l�����(�}�T)�A�ތ��A�l���\�ܓ��@
���u���v�̉��Ɂu�S�v�@
�Ƃ̏����𑗂�A���炪�V�c�Ƃ��č݈ʂ��������O�N�́A��E�q�C�E���A�̎O�_�������V�ЁE�����̂������N�ɂ�����A�܂��N�����q���E�a���������A�傢�ɐS�z���Ă����Ƃ���A���[�@�e���̏C�����E���o�@�̖@�͂ɂ�肱�ƂȂ������A�܂������l�N�̋C�����ł��邱�Ƃ��얀�̗��v�ɑ���Ȃ��A�傢�Ɋ��ӂ��A�@�e���ւ̊��܂��������Ɏ��v�炤����ł���Ə��������Ă���B�����āu�V���v���������������C�@�ւ́u�b���v�́A�u���Ɓv�쎝�̎��тƂ��Ď��@�Љ�ɂ��m�F����A��X�܂Ō�����邱�ƂɂȂ�B�@
���̂悤�ɐl�i�I���@�l�I�ȑ��݂ł���u���Ɓv���쎝���鎛�@�Љ�̏@���I�����Ƃ��̐��ʂ��߂���F���������A�u���썑�Ɓv�v�z�����ꂩ��x���Ă����Ƃ����悤�B�@
���Đ^���E�V�䖧����`���鎛�@�ł́A�ݑ��̐M�҂ɕ����������邽�߂̌�����A�����s�҂Ɉ�苗��ʂ������邽�߂̓`�@���ΏC����Ă����B�Ƃ���Ŗ{���Ƃ̌��т��ɂ���āA�M�҂ɂ͐M�S�̋@�����A�s�҂ɂ͎t�m�̎��i��^����V���ł���͂��̟��A�u��@�̓��́A�썑���l�̓��Ȃ�A�v(�u��F���@�c�����⍐�v)�Ɨ�������Ă������Ƃ͒��ڂ���悤�B�����ɂ����ďt�H��G�ɍÂ��ꂽ�́A�u���a�̐���ɒ��썑�Ƃ̂��ߎn�ߏC������Ƃ���Ȃ�A�v(�u����L�v���l)�Ƃ���悤�ɁA�������u���썑�Ɓv�̖������ɂȂ��@��Ƃ��ċΏC����Ă����B�����̒[����^����V���ł����錋���ƁA�u�V���v�ɂ������u���썑�Ɓv�Ƃ͒��ڂɂ͌��т����������̂ł��邪�A�u�ܒq�̐��A�O���𗘂��ĕ���迂��A�O���̕��A�@�E��Ղ����ĝӐ�A�v(���O)�Ƃ����\���A�܂�ɂ����Ď�҂ɂ��������u�ܒq�̐��v���ے�����@���̒m�b�ƁA�V���̂Ȃ��ł́u�O���v�s�ɂ����͂��A�̏ꂩ�炠����O���Ɛ��E�ɋy�Ԃ���������}��Ƃ���Ȃ�A�Ɂu���썑�Ɓv�̋@�\�킹�邱�Ƃ͉\�ƂȂ낤�B�����͑m���ɂ�镧���C�s�̊K��ɂ��鎩���s�Ƃ��Ă̌����E�`�@���A�u���Ɓv���Ƃ��čÂ���邱�Ƃɂ��A�O���ɗ��v��^���闘���s�A�܂�u���썑�Ɓv����������p�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ�킯�ł���B�@
�Ƃ��낪���̂悤�ȋ@�\���������E�`�@�ɁA�u���Ɓv����Î҂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A��҂Ƃ��Ċ֗^���邱�Ƃɂ��A�u���썑�Ɓv�Ƃ͕ʂ̌��ʂ����@�Љ�ɔh�����邱�ƂɂȂ�B�@
�O�m�\�O(�����)�N�A�����c�͍O�@��t�ɂ�����������������(���������ϒq�@��)�A����Ɂu���M�@���L�v�ɂ́A�u�����c�E����E�~�a�E�m���A�V�Z�E�V��E��V�E��V�̍����Ďl��A�܂�����E�~�a�@�{�F���A�v�ƋL�����悤�ɁA�����c�ȉ��́u���Ɓv��c�@�ȂƂ��������Ō������A�u�������v���u���ʂɓ��v�����Ƃ����(�u����L�v���l)�B�~�a�E�m���ȉ��̎�@�ɂ��Ċm�͓����ʂ��̂́A����E���㗼��c���O�@��t�ɂ��������ğ��������́A���Ȃ��Ƃ��������̐^�������̋��c�ɂƂ��ďd�v�ȈӖ����������͂��ŁA�u�~�a�v�ȉ��̏��F���A�u���Ɓv�̐^�������ւ̊ւ������߂�Ӑ}�̂��Ƃɂ������Â���ꂽ�ƍl������B�@
�܂����ד�(�����)�N�A�F����c�͓����ɂ����Č������A���Őm�a���ɂ����ďo�Ƃ𐋂�����A���쌳(�せ��)�N�ɂ͓����@�ɂ����ĉv�M��刢苗��Ƃ��ē`�@���u�����o�v���̂���(�u���{�I���v�A�u����L�v���l)�B�F���@�c�������ɂ����ē`�@�������Ƃ́A�Ȍ�u����̉��P�v�Ƃ��āA�u���Ɓv��@�̐��ƔF�������悤�ɂȂ�B�����芙�q����ɂ�����܂łɁA�����@���œ`�@�𐋂��@���𖼂̂����A�܂��^���s�҂Ƃ��ďC�s�̓��ɓ������u�����v�E�u�V�q�v�́A�u�����@�v���̂����~�Z�@�c�A�u�������v���̂����T�R��c�A�u�������v���̂�����F���@�c�ł������Ƃ�����(�u�����q�L�v*)�B�@
*�u�����q�L�v�́A�����R��Εُ��Ƃ��Ă�A��f�́u�䖝���v���������ϒq�@�ܕ�̒�q�`��(�ϕ�)���A�����̂ڂ镽���@�����̎R�匵�����u�Δj��l��掑c�t�L�v�ɉ��߂Ĕ��_�����݁A�����̎R��ɗD�z���邱�Ƃ��咣�������̂ŁA��k������ɐ��������B�u�䖝���v�ƂȂ�сA���q����ȍ~�̓������m�̎R��ւ̈ӎ���m�邱�Ƃ̂ł���j���ł���B�@
���̂悤�ɓ���̎��E�@�Ɩ@�����u���Ɓv�Ɍ����E�`�@���������Ƃ��������́A���̐��h�̐��Ƃ��Č㐢�܂œ`������A�܂����@�Љ�̓��ŗD�z�������i�E�������ւ邽�߂̋��菊�ƂȂ�Ƃ����A�������Đ����I�ȈӖ������������Ƃ͗e�Ղɑz���ł��悤�B�@
�O�q�̂Ƃ��蓿���O(��O����)�N�A��F���@�c�́u������̉b��v�Ɋ�Â��u�Ð�鉤�̉��F�v�܂�F���@�c�̐��ɂ��������āA�����@�ɂ����ē`�@����(�u��F���@��L�v)�B��F���@�c�͂��̏o���ɂ����藼����䶗�������Ɍ�����Ƃ����������A����ɊO�c�����@���Y�́u�c�����p���ׂ��̑��v�������́u���Ƃɓ���ׂ��̒��v��\�������Ƃ����B�o�����̊�ɏے������悤�ɁA��F���@�c�͐��U�ɂ킽�蕧�@�ւ����A�˂��悹�A�c���̍��ɂ́u�y���ܕ~���Ă��Č얀�@��̂��A�����ɏ���ču�_���[�v���A���l����ɋy��ł́u�o�_���w���āA�����@�����v�߂�Ƃ����قǂł���A�֒����L��쎝�m�̐w����V��E�^�������̎���(�����F���̏���)��M�S�Ɋw�B�����Ē�ʂ�ނ��Č�́A��펛���~��茋�����A����ɐm�a�����m�@�e�����F���u�@�c�̐����v�̌p�������Ƃ߂������̑����ɂ��ʂ����ꂸ�A���������ďo�Ƃ̌�ɑT�����u�����v�̓`�����͂���A�����O�N�̓`�@�ɂ��������킯�ł���(�u��F���@�c�����⍐�v)�B�@
�c����薧���ֈ���Ȃ�ʊS���Ă�����F���@�c�́A����̓`�@�ɐ旧���Ė{�i�I�Ȗ����C�w��ς�ł����B���łɊ�����(��O���O)�N�ɂ́A�T����肻�̐�ɂ�����`�������ؗp�����ʂ��Ă���A�܂��`�@��������A�����ɐm�a���ɓ`���L�̐^��������T������`������Ă���(���|���O����A��o������F���V�c����)�B�܂��L����łȂ��A���여�̐^�������Ɋւ���^����펛���~�ɐq�˂Ă���A���[����̉��L������撍�����`������(���O���|����l��)�B���̂悤�Ɍ�F���@�c�́A�����C�w���d�˓��d��@�𐋂��邱�Ƃɂ�莩��刢苗���ڂ����Ă����킯�ŁA���̎p���͂��͂�u���Ɓv�ʗ�Ƃ��Ă̖����ւ̊ւ��A�܂�쎝�����g�̗����傫���z���A��l�̐^���s�҂Ƃ��Ă̂���ł������B�@
�m���Ɍ�F���@�c�̐^�������ւ̌X�|�́A���u���Ɓv�̂Ȃ��ł͂Ƃ��ɂ��킾���Ă���悤�Ɍ�����B���������x�̍�����������u���Ɓv�́A�˂ɖ����Ƃ̊ւ��������Ă���A��F���@�c�݂̂�����ł���ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��F���@�c�̓`�@�ƁA���̑O��ƂȂ镽��E�����c�̌��������Ƃ��Ē蒅���A�u���Ɓv�ɂ��^�������Ƃ��̋��c�ւ̊ւ�肩���������Â����܂��p������A����Ɍ�F���@�c�̌�������������ʂƂ��āA�@�c�̌X�|�𗝉����ׂ��ł͂Ȃ��낤���B�����Ŗ@�c�̓`�@�����@�Љ�̓����Ő��g��ɂ��āA�������l���Ă݂邱�Ƃɂ������B�@
��F���@�c�̒��N�̔O��ł����������@�ɂ�����`�@�̓����A�u�쐐�Ǝ����A�����f������A�������d�̎����A�n�͐k�����A�V�͌��s�����v�킵���Ƃ���(�u��F���@�c����⍐�v)�B���̊�́u�@���A�̉����v�ɂق��Ȃ炸�A�s��O������q�ɟ��������ۂɓ���̒n���������쐐�ɂȂ炤���̂Ɨ������ꂽ(�u�䖝���v*)�B�����Č�F���@�c�̓`�@�������������Ƃ��۔������ɂ��ẮA�@�c���炪�L���̂����A�܂������ɂ����Ă��`������邱�ƂɂȂ邪�A����ɂ͓V�n���R���x�z�����ΓI�ȁu�@�v(����@��)�̈ӎv�Ƃ����@���I�Ȍ��Ђɂ���āA�����@�ɂ�����@�c�̎�@�𐳓�������Ƃ����Ӗ����������̂ł͂Ȃ��낤���B�@
*�u�䖝���v�́A��߂ŐG��邱�ƂɂȂ邪�A��F���@�c�̓`�@�ƁA���̊��܂ɂ��v�M�ւ̑�t���������߂���R��̑i�ׂɑ��āA�����ϒq�@�ܕ��̍����Ɣ�_��ᔻ���邽�߂ɁA�����O(��O�ܔ�)�N�ɐ�q�������̂ł���B���Ȃ��Ƃ����q�����������k������ɂ����Ă̓������m�̈ӎ����M�����Ƃ̂ł���D�j���ł���B�Ȃ��ܕ�͓����̎����u����L�v�̕Ҏ҂ł�����B�@
��F���@�c�̓`�@���߂���A�R��O�k�̋������������������Ƃ͂��łɐG�ꂽ�Ƃ���ł���B�R�呤�̍R�c����������F���@�c�͉@��������A�u�V��R�́A�c��{���̏��v�ł���u�A�˂͗]���ɒ��߁v����Ƃ��āA�u��������̗ՍK�v����A�u������c�̉���v�ɂ�铌���ł̓`�@�ɗȏ������߂��Ƃ����(�u���g�Л�b�R�s�K�L�v)�B���̎R��̔����̔w�i�ɂ́A�u�ȏ㌳�c�ȗ��A����`�@�Z�ӓx�ɋy�ԁA�A�����̗��V�������A�R��ɉ����ēV�q�̟��ꖳ�����A�v(�u�����q�L�v)�̒ʂ�A�����ɂ͘Z�x�́u�V�q�v������ɂ�������炸�R��ɂ͂��ꂪ�Ȃ��Ƃ��āA����̗D�ʂ��ւ铌�����̎咣�ɉM����悤�ɁA�u�V�q�v�̏�̑I���ɂ��u���Ɓv����̏����̌��������܂�Ƃ����ӎ����A�����E�R��̂�����ɂ��������ƍl������B�܂��u����Ɖ]������Ɖ]���A�V�Z�E�V���@��`���邱�ƁA�j�T�ɍڂ���Ƃ��둴�ᑽ���Ƃ����Ƃ��A�����Ƃ��ē`���̑c�ɗA�◬�₦����́A�ɉ~��V�剺�ɂ���A�v(�u�䖝���v)�Ƃ���悤�ɁA�u���Ɓv���ӂŕ���ɓ����͑����Ƃ��A�u���Ɓv���炪�`�@������̖@���ɘA�Ȃ邱�Ƃ͋H�ł���A���̖@��������́u�����v���֎�����悤�ɂȂ�̂����R�̐���s���ł��낤�B�@
���Ȃ킿�@�c���`�@�𐋂��ē���̖����@���ɗ邱�Ƃ́A�@���Ƃ������ގ��E�@�̂�����ɂƂ��Ă��A�u���Ɓv�̌��Ђ��}�������Ƃ����Ӗ����������B�ł́u���Ɓv�Ƃ��������I�Ȍ��Ђ́A���@�Љ�ɂ����Ĕ@���Ȃ�F�����Ă����̂ł��낤���B�@
����������A���@�Љ�ւ̍c���E�M���̎q��̐i�o���}���ɐi�ނȂ��ŁA�������琢���̏o���̍���������M��(�c���E�M���o�g��)�d����ӎ������܂�邱�ƂɂȂ����B�u�|���̋M��A�Ŗ�̗]���v���Z�����鎛�E�@�A����炪�A�Ȃ�@����o�d����@��������]������邱�Ƃɂ��āA�������w��ɖ����ȋ��菊�����o�����Ƃ͍���ł���B�������M��ӎ������@�Љ�̉��l�ς�傫����������̂ł��������Ƃ͊m���ł���B�����܂ł��Ȃ��M��̒��_�ɗ��̂́u���Ɓv�ł���A���E�@�E�@���ɂƂ��āA�u���Ɓv���}������邱�Ƃ͋M��ӎ�����������̂ł���A�������}�����u�M��v�̑��݂ɂ���Ď��E�@�E�@���̉��l�͂����������܂邱�ƂɂȂ�B�ł͎��@�Љ�ɍ����ڂ����u���Ɓv�ɂ́A���̂悤�Ȑ����I�ȈӖ������Ȃ������̂ł��낤���B�@
��q�̂Ƃ���A�Ñ���u���Ɓv�́A���J�҂ł���ƂƂ��ɐM�̑ΏۂƂȂ鑶�݂ł��������A���ƕ����Ɋւ�邩����́A�����Љ�ɂ����錠���͕ʂƂ��Ė{���I�ɌŗL�̏@���I�Ȍ��Ђ������̂ł͂��肦�Ȃ��B�{�������̉��́A�����܂ŕ��@�𐒌h���܂��삷�闧��ɂ���A���ꎩ�̂ɏ@���I�Ȍ��Ђ��t������͂����Ȃ��B�Ƃ��낪��펛���~����F���@�c�ɕ�悵���t�@��ɂ́A�u��N���b�r�����A���q�s�ӂɂ��āA�{���։��̐E�ʂ�����A�X�����@���̐����ɋ����ׂ����̂Ȃ�A�v(���O���|��O��l��)�Ƃ̕\����������B�u��N�v�܂��F���@�c���`�@�����̂́A���ӂ̕��q��g�ɂ��Ă��邩��ł���A���łɁu�։��v(�]�։�)�Ƃ��Ă̎��i������Ă���킯�ł��邩��A�@���̐����Ƃ��Ďe��邱�Ƃ��ł���Ƃ����\���ł���B�u�։��v�Ƃ́A���@�ɂ�萢�E�����鉤�A�Ƃ���Ȃ������u���v���Ӗ�����͂��ł��邪�A�j���サ���Ε��@�A�˂̌����u�����v���������Ƃ��ėp�����Ă���B���Ƃ��A�u���Ԍo�ɉ]���A�Ⴕ�����́k�ʒE�J�l����Ɨ~����̎��A�։��̈ʂ���̎��A�S�����k��J�l�ʂ̎��A�܂����̉����ׂ��A�v(�O�c�Ɩ{�u�O��G�v����)�Ƃ̈ꕶ�Ɍ�����u�։��v�͖��炩�ɐ����̑��݂ł���A�������ē�������u�����v�Ɨ�������Ă���B���Ȃ킿���@�ɋA�˂��鐢���́u�����v�ƁA�V���瓝���̂��߂̗֕��������ꂽ�u�։��v(�u�����v)�Ƃ��d�ˍ��킹��Ȃ��ɁA�u�����v�ɏ@���I�Ȍ��Ђ�^���悤�Ƃ���_�������o�����B�A�˂ƕ��q�Ƃ��������������邩����ŁA�u�����v�́u�։��v�Ƃ̕]����^�����A�����Љ�̓����ɏ@���I�ȗ͂�ۏ����ƂƂ��ɁA���@�Љ�ɂ����Ă��u�@���v���p�����邱�Ƃ����F�����̂ł���B���Ȃ�畧�q������`�@�����u���Ɓv�́A���@�ɂ�萢���Љ�����߂�u�։��v�ł���A�u�@���̐����v���p���ɑ����������݂Ƃ��ĕ]�����ꂽ�ƍl������B�@
�`�@���������u���Ɓv���}������鎛�E�@�E�@���́A�������x�z���邽���́u�����v�ł͂Ȃ��A���E�����E������u�։��v�_�ɋ��킯�ŁA�����Љ�ɂ����錠�����ւ�݂̂Ȃ炸�A���̒��z�I�ȏ@���I���Ђɋ����āA�������玛�@�Љ�̂Ȃ��ŗD�z�����ʒu���咣���邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ낤�B�@
���Č�F���@�c�́A���˂Ă���^�������̍ċ��ƁA���̍��{����ł��铌���̕����������Ӑ}���Ă����B�`�@�ɐ旧���ē������@�ɂ����ĉ��s���ʂ�������F���@�c�́A�O�@��t�̌�e�Ɍ������A�u�C�w�m�\�l���ȂāA�����ɏZ���A�^���̋��`���З������ނׂ��̎��v�E�u�~�Z�̑m�V���������ׂ��̎��v���̘Z�����ɂ킽��u���������̏��X�v���h�����u���ɋL����(���O���|��O�ꎵ��)�B�����ē`�@�𐋂�����ɁA���̏��R�v���e���ɏ�������킵�A�u���ׂɉʂ�������̏��A���O�̖{���߂ɖ������L�ʁA���̏�͖������C�s���A���悢����썑�Ƃ̍��F����ɂ��ׂ��A�v�Ǝ���̊��S�ƌ��ӂ��q�ׂ�ƂƂ��ɁA�u�������������̗`���A���@�̉e�O�ɉ����Čh���̏��X�A�ĕ������̂��Ƃ��A�v�Ƃ��ē��������̏��X���L�����u���̈ĕ��������A�@�c�̈ӌ��ɓ������A�����ɂ킽��؋��ƂȂ鏫�R�̕ԏ�����߂��̂ł�����(���O���|��O�ꎵ�l)�B�@
��F���@�c�����̍Č��Ɏ������������́A�u�����v�̈��ɏے������悤�ɁA�@�c�O�@��t���u���@�̖{���v�Ƃ��đ������Ă����킯�ŁA���̍ċ��͐^�������̋����ɂ��Ȃ���B�^�������̔��W�ɂƂ��Ȃ��A�ו������������@���̋��菊�Ƃ��Ă̎��E�@���n�������Ȃ��ŁA���Ȃ��Ƃ���������ȍ~�A�u�]���ɏy�����A�䒩�ގ����ȂčŒ��ƈׂ��A�v�Ƃ��ꂽ�����̗D�ʂ̎��Ԃ͎���Ɏ����Ă�����(�u����L�v����)�B���������̈���ŁA�������҂͈ˑR�Ƃ��Đ^���@�m�̋ɈʂƂ��ċ@�\���Â��Ă���A�u�A���������҂́A��Ƃ̊ю�ɔA���@�̒����ׂ�A���@���͏����ɏ�Ƃ����ǂ��A���@���͓Ƃ��ɍ݂�A�v(�u�䖝���v)�Ƃ���悤�ɁA�������҂́u���@�̒����v����u���@���v�����˂Ă����B����ɂ́u�����j��ɋy�Ԃ̎��A���{�����̑召�������A�C���������ׂ��A�v(�u����L�v����)�A�u�ፑ�̍�����́A�(����)�̎�����̌̂Ȃ�A�v(�u�䖝���v)�Ƃ��āA���@�Љ�Ɛ����Љ�̈ꕔ�ɂ��������Œ��Ƃ���F�������݂��Ă������Ƃ͎����ł���B�������n������ʂƂ���Ȃ�A�����̈ӎ����m�F�����̂́A�����܂œ����ċ�����̂��Ƃł���A��F���@�c�̍ċ��̌��Ɓu����̉��P�v�ɂ��`�@�ɁA���@�Љ�ɂ����铌���̗D�z�����ʒu�ƈӎ����Ċm�F�������Ƃ����Ӗ������������Ƃ͊m���ł��낤�B�@
���Đ^�������͕��������ȍ~�ɁA���̎����ɂ���čL�Ə��여�ɑ傫�����h���邱�ƂɂȂ�B�����ĉF���@�c�ɂ�葢�c����A�v�M�𗬑c�Ƃ���L�̐^�������̋��_�ƂȂ����m�a���ƁA���여�̐^�������̗��c���n�������V�c�̒��莛�ƂȂ�����펛�Ƃ́A��������^�������̖@����`���钆�j�I�Ȏ��@�ƂȂ����B�m�a���́u�䎺�v�Ə̂���Ė@�e�����Z�����A��펛�ɂ͏��여�̕��h���O����`����O��@�E�����@�E�������@���͂��߂Ƃ���@�Ƃ��n������A��������ȍ~�̐^�������̖@���Ƌ����́A���̗�������v�Ȓ��Ƃ��Ĉێ����ꂽ�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂��B�������Ɂu�m�a�E�����̊��A�|���̋M��A�Ŗ�̗]���ɂ��āA�e�ꗬ�̖@���ƈׂāA�l�C�̐�捂���ߋF��A�v(�u�䖝���v)�Ƃ���Ƃ���A�M����@��Ƃ��Č}���Ă��������̗����͑z���ɓ�Ȃ��B����ɑ��č��{����ł��铌���ɂ́A�����ɔ䌨�ł���u�|���̋M��A�Ŗ�̗]���v�̎��m�₻��炪�Z������@�Ƃ́A�㐢�ɂ�����܂Ō��o���������B���炩�ɓ����͋M�킪�~�Z���鎛�@�ł͂Ȃ��A�M����n�߂Ƃ���^���@�m���o�d����R������@��̉�����A�^���@�m�̋ɈʂƂ��Ă̓������҂�u������ł������B�Ƃ��낪�ċ���̓����͐m�a�E��헼���ɑ��āA�u�v��m�a�E��헼���́A�����̍��E�ɍ݂�āA��t�̈�@���Z�����A���ɒ���̌쎝��@(�}�})���A�����������̗������F��A�g����ΎԂ̗��ւ̔@���A�����̓Ɏ�����A�v(���O)�Ƃ��āA�����̋@�\���������̑������x����u���ցv�E�u�v�Ƃ����ʒu��^���Ă����B������@���݂̗D����A����w�i�����Ĉ�T�ɂ��߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�^���������f���鏔���@�̂Ȃ��ŁA�M�킪�Z�����邱�Ƃ̂܂�ȓ������咣����D�z��������Ƃ��̈ӎ��́A�����ς��F���@�c�̓����ċ��ɋ����Ă���Ɛ������邱�Ƃ��ł��悤�B�@
��F���@�c�́A���߂ł��G��邱�ƂɂȂ邪�A�����ɕ��h���Ă����^�������́u�@���̈Ꝅ�v�����Ӑ}���Ă����B�����Ŏ���̖����C�s�̓���Ƃ��čċ�������o���Ƃ͕ʂɁA���h�����X�̖@���̋��_�ł���m�a�����펛�ł͂Ȃ��A�u���@�̖{���v���铌���̍ċ�����Ă��̂����ɓ��R�̂��ƂƂ����悤�B�����Č�F���@�c���������ċ������Ӑ}���A���̂܂ܓ����Z�m�̈ӎ��ɉe����^���A���̌��ʂƂ��āA��q�����Ƃ���ċ����_�@�ɁA�m�a�E��헼�����u���ցv�E�u�v�Ƃ��A����ɂ͎��@�Љ�ɂ����ē������D�ʂ��߂�Ƃ̈ӎ����A�����Ƃ��̎��ӂɒ蒅���邱�ƂɂȂ����̂ł͂���܂����B���ꂪ���������ɂ����Č�F���@�c���ʂ������A�����I���@���I�Ȗ����Ƃ������ƂɂȂ낤���B�@
�Ȃ���F���@�c�̓`�@�ɂ�����A�刢苗����Ƃ߂��T���ɑ��銩�܂Ƃ��āA���̖@���̑c�ł���v�M�֑�t������U�͒�������A����拍����߂���R��Ɛ^�����c�Ƃ̑��_��������A���ƁE���ƂƎ��@�Љ�ɑ傫�Ȕg��𓊂����������A���̖��ɂ��ẮA��߂ʼn��߂čl���邱�Ƃɂ������B�@
���������̒��j�ł���O��@���̐������f�����펛�@�ɏZ���������~�́A��F���@�c�̗c����莘���Ƃ��Ďd�����Ƃ�����(�u���`���L�^��������v)�B�c�N����̌𗬂ɂ��Ă͊m�͓����������A�����@�œ`�@��������O�N�̓�����(��O����)�N�A���̏o�Ƃɐ旧���āA���łɌ�F���@�c�͌��~��刢苗��Ƃ��Č������Ă���(�u��F���@��L�v)�B�܂����������ɊS�̐[����F���@�c�́A��q�̂Ƃ���A���̈ȑO���珬�여�̎������߂���A���~�Ƃ̐ڐG�������Ă����B�@
���đ�펛��n����������𗬑c�ɓ���������`���鏬�여�́A�����������@�����ɂ����āA�傫������O��(���ˎ��E���C���E���S�@�e��)�Ƒ��O��(�O��@�E�����@�E�������@�e��)�̂����鏬�썪�{�Z���ɕ��h�����B��펛�̉@�Ƃ����_�ɑ��������O���́A��������@�����ɎO��@�J�c���o�̂��Ƃ��番�h�������̂ŁA���o�̒�q��C�E���o�E�����𗬑c�Ƃ��āA�O��@�E�����@�E�������@�̊e�������܂ꂽ(�u�����v)�B���̂����O��@���͑�펛�O��@��{���ɁA�����Ƃ�킯���여�̒��j�Ƃ��Ĕ�@�Ɛ�����`�������A��i��(���O��)�N�ɉ@�Ɠ��F���Ď����A���̉@����������@�@��̌��тƂȂ�Ȃ���(�u��펛�V�v�^�v���\)�A�@���͈ꎞ�f�₷��ɂ��������B�����Č����O(���܈�)�N���[���O��@���Č�����ɂ���юO��@�����ċ����ꂽ���̂�(�u��펛������⎟��v)�A���@�ɓ`�������O��@���̖{���E�����́A���[�������I�ɑn�������@�Ɉڂ��ꂽ�B�܂����[�͎��炪�ċ������O��@���̖@���ƕ@�Ƃ��q���[�ɕt�����邱�Ƃɂ��(�u�����v)�A�O��@���̐����͎O��@�𗣂�A�@�ɓ`�����邱�ƂɂȂ����B�Ȃ����[�͎O��@���̐������f����@���̗��c�Ƃ���Ă���B���̂悤�Ȍo�܂���A��펛�@�ɏZ�����錛�~�́A���[�E���[�̖@���ɘA�Ȃ邱�Ƃɂ��A�O�@�@���̐�����`������Ɏ������B�@
�����O(��O����)�N��\����A���łɓ`�@�𐋂��Ă�����F���@�c�́A���~�̕a�����̒�q�������玨�ɂ��A�a���ɂ��������~�̂��Ƃɏ���𑗂���(��펛�����u��F���@�c���˓����З����r�v�A���O���|��O�ꔪ��)�B�@
���J�X�ɔ���̗R�A�������\���A�ނ������v��������A�����З��̎����A�b����S��������̏��A��ɔO��v���Ƃ���Ȃ�A�Ⴕ�P�����ł�����A�@���t���̏����̎�m�����߁A�n�I�ׁX�ɐq�˖K���ׂ���A����Č̂ɒZ�D��i���Ƃ���Ȃ�A�O��@�̐����ɐ[�������̎u�𑶂���́A�h���̑R�炵�ނ�Ȃ�A���łɔ閨�̉��|���ɂߗ��ʁA���@�̐����ɗ�A�ނ��@���̈Ꝅ����ׂ����A���Ⴀ��ׂ��炴��A�ߖ@�v�Z�̊��ׂ��A�ς����|�͓����ɋ��������L�ʁA�ԕ�̎�A�����������đ��`����̏��A�����m����̌́A�Z�D��i�ޏ��k�J�l���Ȃ�A���������������҂ɂ���荂���A�a�̂ɂďo�d������Ƃ����ǂ��A�������p�k���l����̏��A�З�����ׂ��A�@���Ƃ��āA�܂��ނ���C����ׂ��b�̗R�A�v�������Ƃ���Ȃ�A�\�����̎|�ɐ����A�鉺�����ނׂ��A�h���Ĕ����A�@
(�����O�N)(��F���@�c)�@
������������@
�E�̏���̓��e�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B���~�̕a�C���Ĕ��������Ƃ����畷���傢�ɋ����Ă���A�����ċ��̎��ɂ����肻�̉������˂����Ă���B�����ˑR�Ƃ��ĕa�͂��������Ȃ��Ȃ�A�u�@���v�`����]��ł���̂ŁA���̈ӌ���e��Ă��炦��A�K��ċ����𐿂������v����������킵���B�u�O��@�����v���������悤�Ƃ̋����ӎv�́A�܂��ɑO���̈����ɂ����̂ł���B���łɓ`�@���Ė����̉��|���ɂ߁A�����Ȗ����@���ɗĂ���A�u�@���̈Ꝅ�v�̎��i�͏\���ɔ����Ă���͂��ł��낤�B�܂������Ȃ����Ƃ��i�Ȃ�A�����ƕ��@���L�܂�b�ƂȂ낤���B���킵�����Ƃ͓����ɓ`���Ă���B�Ԏ��ɂ��āA����ł͌��~�̈ӌ��𐳊m�ɒm���̂ŁA�Z���ԏ��ł��悱���Ă��炢�����B���ē������҂Ɍ���������B���~�͕a�g�ŏo�d�͂��Ȃ��܂����A���҂ɂ��̖���A�˂邱�Ƃ͖��������߂邱�ƂɂȂ낤�B�@���̂��߂ɂ��A����Ƃ���C�����ׂ��ł���ƍl���Ă���B���~���\�������Ȃ�A���ҕ�C�̐鉺���Ȃ����ł��낤�B�@
��F���@�c�����~�Ɍ������āA�u�O��@�����v�����̈ӎv�������̂́A��q�̂Ƃ��茛�~���O��@���̐������p�����Ă�������ł���B�����Ė@�c�����~�ɋ��߂��̂́A�u�@���̈Ꝅ�v�̂��߂́u�O��@�����v�̓`���ł������B�u�h���v�ɂ��u�O��@�����v�̋����Ƃ́A���炩�ɉF���@�c�̖����������p�����悤�Ƃ̈Ӑ}�ƁA����̏o���E��@�̊���ӎ������\���ł��낤�B���Ȃ킿��F���@�c�͂��́u�h���v���f���邱�Ƃɂ��A���炪����E�L�����ו������������u�@���̈Ꝅ�v���͂���ɍł����������Ƌ������Ă���B���Ȃ킿�P�ɏ���E�L���̎�����`�����ꂽ�^���s�҂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�O�߂ŐG�ꂽ�u�։��v�Ƃ��Ă̗�����������邱�Ƃɂ��A��F���@�c�͌��~�ɕt�@���������Ƃ߂��킯�ł���B��F���@�c�̏���̕��ʂ́A���~�̊����u�x����悤�Ɍh��������A�u���Ɓv�����̕����Ƃ��Ă͒��d����ۂ��Ȃ���A����������Ŏ���̈ӌ��̎�������v������̂ł������B�����Č�F���@�c�͂��̋��v�̑㏞�Ƃ��āA���~���g�Ɩ@���̖����̂��߂Ƃ��āA���ۂɂ͕a�g�̂ɏo�d�̂��Ȃ�ʓ������҂ւ̏A�C�������߂��̂ł������B�@
���ǂ̂Ƃ���A���~�͌�F���@�c�̈ӌ���e��A������ꂽ���X���ɓ����O���҂ɉ��C���ꂽ(�u�������ҕ�C�v)�B���Ȃ݂Ɍ�F���@�c�ɓ`�@���������T�����A����ɐ旧������N�ɓ������҂̖��ɗA��@�̑O���ɂ͈꒷�҂ɏ��C���Ă���(���O)�B���̗��l�̒��ҏA�C����A�^���@�m�ɂƂ��ē������҂������Ɋ��]���ׂ�����ł��������Ƃ������Ƃ��A�܂����ҕ�C��㏞�ɓ`�������Ƃ߂���F���@�c�̏p��̍I�݂����M�����Ƃ��ł��悤�B�@
���Č�F���@�c�̈ӌ������������~�́A�@�c�̏���������������̎O����\�ܓ��ɐ����𑐂����������(���O���|��O����)�B���̐����ɂ́A���~����F���@�c�ւ̕t�@��e�F����ɂ������Ă̎��ӏ��ɂ킽��������L����Ă����B�����̏����Ƃ́A�u��t�����̖@�C�k���l�E�鉜�͓����ɍ݂�A�R��Ώ�����ȂČ�{���Ɉ��Ă��ׂ���A�c�t�̒u���ɈႤ�ׂ��炴��b�̎��v�Ƃ��āA�u�c�t�̒u���v���f���Ȃ���u����v���u�{���v�Ƃ��邱�ƂɊm�F�����Ƃ߂��ꍀ�A�u�����Ɖ]���A�����Ɖ]���A�ꎖ�Ƃ����ǂ��A�L�̑��Ƃɓn����ׂ��炴��̎��v�Ƃ��āA�u����v�̔�@���u���Ɓv�ɗ��o�����ʂ��Ƃ����Ƃ߂��ꍀ�A�u�{���E����߉��A���Ƃ��o���ׂ��炴��̗R�A�c�t��X�̋N�����L��A�v�Ƃ��āA�{���E������펛�O�ɗ��o�����ʂ��Ƃ����߂��ꍀ�A�u�ꑸ��_�Ƃ����Ƃ��A(����)��`���̖@�Ȃ��A�l���b���L��ׂ��炸�A�v�Ƃ��āA�`���ʂ��̔�@�̔〈�����ވꍀ�A�u���l�̌�G�Z�͌������ׂ��b�A�}���n�I���s�̎��v�Ƃ��āA�@�c�́u��s�v�����Ƃ߂��ꍀ���X�ł���B���Ȃ킿�����Ƃ́A�u����v�@���𐳓��Ƃ��鏳�F�Ƃ��̑����̕ۏA�����Ė@�c�Ɉ�^���s�҂Ƃ��Ă̗��s��v��������̂ł������B�����āu���̏��X�Ⴕ����Ȃ���͂A�䐳���̏��A�ܘ_�̌䎖����ׂ���A�v�Ƃ��āA�����̏������e����邩����́A�u�����v�̖@�������͍����x���Ȃ��Ƃ������~�̈ӌ����`����ꂽ�B�Ȃ������̏����ɉ����āA�u�����E�{���E����v�̔〈�ɂ͖@�c�̑�펛�ւ́u�ՍK�v�����Ƃ߂��Ă���B�܂��������ҕ�C�ɂ��āA���~�́u���쑊�����Ɍ�A�v�Ƃ��Ă������ɐ\���悵�Ă���A������������C���ꂽ�̂͐�q�̂Ƃ���ł���B�@
�ł͌��~�͌�F���@�c�́u�@���̈Ꝅ�v�����}���A���̕t�@��F�߂��̂ł��낤���B���Ȃ��Ƃ��u����v�����u��{���v�Ƃ��邱�Ƃ́A����Ă��Ȃ���Ăł������͂��ł���B�����������̖����ɋL�����u�O��@�Ꝅ�̎��A���ɐ����̉@�Ƃ𗣂�ׂ��炸���́A�Ꝅ�ނ��R��ׂ���Ƃ����ǂ��A���F���X�����̔�v�̐S�Ɍ�A�v�Ƃ̕\���́A���~�̋����ӎv���������̂ł͂Ȃ��낤���B�^�������̖@�������여�Ƃ�킯�O��@���Ɉꓝ����邱�Ƃ́A�u�����̉@�Ɓv�ɖ@�����`������邩����傢�Ɍ��\�Ȃ��Ƃł��邪�A�@���ŗL�̔�@���t�m���璄��֓`������邱�Ƃ́A���ɂ������������d���ł���ƌ��~�͌��B�@�c�ƌ��~�̈ӎv�́A�����Ŗ��炩�ɖ������邱�ƂɂȂ�B�@�c�́u�h���v�ɂ�����������́u���Ɓv�Ƃ��Ă̗�������菊�Ƃ��āA�ו������������u�@���̈Ꝅ�v���A�L�Ə��여�̐�����`������邱�Ƃɂ��������悤�Ƃ����B����E�L��ɂ킩�ꂽ�@���́A�u�։��v�ł���@�c�̑��݂̂Ȃ��ňꓝ����A�����ɂ͂��͂╪�h�͂��肦�ʂ��ƂɂȂ�B�Ƃ��낪���~�́A�ˑR�Ƃ��ĕ��h�����@���ɋ����������Ă���@���̉����ȂǑS���l���Ă��炸�A�@�c�́u�@���̈Ꝅ�v�̈ӌ����A���여�Ƃ�킯�O��@���𓌖��̒��_�Ƃ���@���̊K�w���Ƃ����`�Ŏe��Ă���̂ł���B�܂�@�c�͖@�����h�̔ے�Ƃ��āA������~�͖@�����h���O��Ƃ��āA�o���S�����������������ŁA�u�@���̈Ꝅ�v�𗝉������̂ł���B�@�����h���������邱�ƂȂǂ��肦�Ȃ��A����̂ɖ@�����`�������@�ƂƓƎ��̔�@�́A���X�����Ƃ��Ď��˂Ȃ�ʂƂ����̂��A���~�̖{���ł͂Ȃ��낤���B�@
�܂���F���@�c���u���Ɓv�Ƃ�������ɋ���Ȃ���u�@���̈Ꝅ�v���������悤�Ƃ��邱�Ƃւ̊�䂪�A���~�̐����ɋL�����t�@�̏����Ɍ����Ă���B���Ƃ��A�`�����ꂽ��@���u���Ɓv�֓`���A�@�Ƃ���{���E���L���̎����o�������ւ�������́A��펛�O�ɋ��Z����@�c���A�O��@����`�����ꂽ��ɁA�u���Ɓv�̋����ɂ���@��{���������O�Ɏ����o���ł��낤���Ƃ�\�����A�@���̗��o���x���������̂ł��낤�B�܂��`��ʂ��Ő����ނ̔〈���ւ��A�@���ԗL�̕t�@�̎菇�݁A���������炵��s���͂������Ƃ����Ƃ߂�Ƃ��������́A���������u���Ɓv�̗�����̂āA��^���s�҂Ƃ��Ă̏C�Ƃ�v���������̂ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�@
���̌��~�̐����ɑ��Č�F���@�c�͎l���O���ɕԎ��𑗂�A�u�P����ɑm�Ƃ̖@����ɂ��ׂ��̗R�A�Ă��Ƃ���Ȃ�A�v�Ƃ��đQ���m�k�Ƃ��ďC�s�������Ȃ��ӎv�������ƂƂ��ɁA�u�������G���ׂ��炴��̎��A��ɍ��̎��m�����ނׂ��A�v�Ƃ��āA����E�L����ӑR�Ƃ���ӎv�̂Ȃ����Ƃ�`���Ă���B�Ƃ��낪���̏���ɁA�u�����ꎆ�ɏ����u����ׂ���̎��A�ꌩ�̌�A�����ɗa���u�����ނׂ��A���@�̏��n���ȂāA�Z���З��̎����ɁA���摊���̖@����v���ׂ����̂Ȃ�A�v�Ƃ��āA���~���`�������@���L�����u�ꎆ�v�܂�ꗬ�`���̖ژ^�͂��������ɗa���A�@���n���āu�Z���v�ł���悤�ɂȂ����Ȃ�A���߂Ď���ɔ�@�̓`���������邱�Ƃɂ������Ƃ����ꕶ���L����Ă���(���O���|��O��ꔪ)�B�����͌��~�̒�q�ł��邪�A�����͌�F���@�c�ɋߎ������̒����������Ă���A�@�c�́u�Z���v�̐܂ɓ������璀���`�������������Əq�ׂĂ���̂ł���B���Ȃ킿��̏���ɂ͖��L����Ă��Ȃ������@�c�̑�펛�u�Z���v�̈ӎv�ƁA�����Ɍ��~�̐Ղ��p���������Ƃ����ӌ������̈ꕶ�ɂ͎�����Ă���̂ł���B�@
���̌�F���@�c�̏���ɋL���ꂽ�u�Z���v�̈��́A���~�ɁA���������̏Ռ���^�����̂ł͂Ȃ��낤���B�l����\�Z���Ɍ��~�͕t�@��𑐂��@�c�ɕ����(���O���|��O��l��)�B���̕t�@��ɂ́A�l���\�l���ɑ�펛�ɂ����āu���X�����̔鉜�v���`������A�u�։��v����@�c���u�@���̐����v�Ƃ��邱�Ƃ����L�����ƂƂ��ɁA�@�c�ɏ��炪���Ƃ߂�ꂽ�u�镧�E���䶗��E�d���E�����ɉ@�Ɠ��̎��v�Ɓu��퓙�ɉۂ��Č�З��L��ׂ��̎��v�ɂ��Ăׁ̍X���L����Ă���B���̂Ȃ��Ō��~�́A�u�A�������@�c�m�a�����Ȃčc���ƈׂ��A�鋳��`���̔@���A���܂܂������ȂĐ哴�ɖ̂���A�������ȂČ�{���ɒ�߂���A�v�A�u�A�������͍c���Ɛ���A�����͕����ɋP���A�v�ƋL���Ă���B���Ȃ킿�F���@�c���m�a�����u�c���v�Ƃ����悤�ɁA��F���@�c����펛���u�哴�v�E�u�c���v�Ƃ��ĎO��@�����u��{���v�Ƃ��邱�Ƃɂ��A�@���́u�����v�ɋP���Ƒ傫�Ȋ��҂��悹�Ă���̂ł���B�P�ɖ@���̓`���ɂ�����u�ՍK�v����݂̂Ȃ炸�A�@�c����펛�Ɂu�Z���v���u�����̌���v�ƂȂ邱�Ƃɂ��A�O��@���͓����@���̒��_�ɗ����A�����������́u�哴�v�E�u�c���v�ƂȂ�킯�ŁA���@�Љ�̂Ȃ��Őm�a���u�䎺�v�ɏy�����ʒu���߂邱�Ƃ��ł���B���~�͂��̕t�@��𑐂����l������ɖv���邪�A����܂ł̊ԁA�u�����ɍڂ���Ƃ����ǂ��A��X����̒n�A��߂Đ哴�ɋV�k�[�J�l������b�A�v(���O���|��O��)�Ƃ��āA�u���Ɓv���ӂ̕��擰�Ƃ��Ă̈�ʂ�����펛���A�u�哴�v�Ƃ��Ă͑��������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ̊����������Ȃ�����A�u�@�c�̌�Z���v(���O���|��O��)�ɋ���������葱�����̂����ɓ��R�Ƃ����悤�B�@
���~�ɂƂ��Ė@�c�ւ̖@���`���́A���炪���������O��@�������여�̂Ȃ��Ő����ł��邱�Ƃ̏ے��ɂق��Ȃ�Ȃ��B��������F���@�c�ɂ��u�@���̈Ꝅ�v���Ȃ����A�O��@���͏��여�ɂƂǂ܂炸�����́u�{���v�ƂȂ�A�܂��@�c���u�Z���v����Α�펛�͐m�a���ƂȂ�ԁu�哴�v�ƂȂ�킯�ŁA��펛�ƎO��@�̗��҂͎��@�Љ�ɂ����ėD�ʂ��ւ邱�ƂɂȂ낤�B�܂�@�c�ւ̖@���`���́A���@�Љ���ł������Đ����I�Ȗ������ʂ������̂ƔF������Ă����킯�ł���B�@
������ɂ��Ă���F���@�c�́A���~�̐��O�ɎO��@���̐������p�����A���瓌���u�@���̈Ꝅ�v���Ȃ��������ƔF���������Ƃł��낤�B�����ďC�s�̏�Ƃ��đ�o�����Č����Z���������A���Ɍ��~������������@�c�̑�펛�u�Z���v���������邱�Ƃ͂Ȃ������B�@
���~�͍Ŋ��܂Łu�@�c�̌�Z���v�Ɋ�]���Ȃ��ł����悤�ł��邪�A�u�Z���v���Ȃ���Ȃ������ꍇ�ɂ́A�O��@���̖@���ƕ@���A���~������ƒ�߂Ă��������ɑ������������ŕt�@�������Ȃ�������쐬���Ă���(���O���|��O��Z���E��O�l)�B��������ɂ��G�ꂽ�悤�ɁA��F���@�c�͈Âɋߎ����铹���ւ̑��������~�ɋ��v���Ă����B����Ƃ��闲���̗���ɋꗶ�������~�́A�����̍��ɂ��������@�k��厞�������A�@�ő�X�Ύd���Ă����u�֓��쎝�v�̋F���𗲏��ɏ���A���{�̌㉇�ɂ�藲���̗������낤�Ƃ��A�܂��厞������𗹏�����(���O���|��O��O�l�E��O��Z�l)�B�����Č��~�̖v��A��F���@�c���㏂�ɂ������ƁA���{�̌㉇�������闲���Ƃ́A�e�X�@���Ɖ@�Ƃ̐����ł��邱�Ƃ��咣���đ��_���N�����A�����Ɍ��~�̖@���͌�F���@�c��������ւ̗���ƁA���~������Ƃ��������̗���ɕ����̂ł���B�܂����̑��_�́A�����̖@������o���ɓ`��邱�Ƃɂ��A���҂̖v����@�Ƒ�o���Ƃ̑��_�Ƃ��ĈȌ���p������邱�ƂɂȂ����B�܂�u�@���̈Ꝅ�v���Ӑ}�����F���@�c�̖@�������́A���@�Љ�ɂ�����@���ւ̋��������̂Ȃ��ŁA���ʂƂ��Ă��̖v��ɁA��펛�Ƒ�o�����������@���̕���Ƒ��_�Ƃ��������������炷���ʂƂȂ����̂ł���B �@
��F���@�c�̓`�@���߂���A���(�R��)�O�k�������������A���ǖ@�c�̈ԕ��ɂ���āA�����O(��O����)�N�����ɓ`�@�������������Ƃ͂��łɐG�ꂽ�Ƃ���ł���B�Ƃ��낪�R��̕���͂���ł����܂邱�ƂȂ��A�V���ȓW�J�������邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿���N�Ɂu��F���@��̏܁v�Ƃ��āu�{�o��t拍����v�M�m���Ɏ�����v���ُ��������ꂽ���Ƃ[�Ƃ��āA���N�����Ɂu�R��i�ׁv���N����A�Ȍ�u�{�o��t拍��v���߂��铌���ƎR��̑��_�����肩������邱�ƂɂȂ�(�u����L�v���l)�B�@
�m����拍��Ƃ́A�V�c�E�����ɂȂ���Ă��̖v��ɋƐт⓿���ÂсA�u���Ɓv���璺�������Ö��ł���A���̖@���̂ق��ɑ�t���E��F���E���t���E�T�t���E�a�����ȂƂ�����A�Ƃ��ɑ�t���ɂ��ẮA��ϔ�(���Z�Z)�N�ɍŐ��E�~�m�ɑ���ꂽ�`����t�E���o��t������Ƃ���(�u���Ᏼ�v)�B�Ƃ���ŎR��Ɠ��������͉v�M�ւ̖{�o��t���̒������߂���r�i�����肩�������ƂɂȂ邪�A���̑��_�̌o�܂��ȒP�ɂ��ǂ�Ȃ��ŁA拍������@�Љ�ɂ����Ă��Ӗ��ɂ��Ĉ�l�����݂����B�@
�����O�N�����A�u�R����拍�����߂��ׂ��ނˑi�\�āA����������A���{�����ɕ��Ă��Đ\�]�A�v�Ƃ��āA�R��O�k�͉�����{�����ɕ��Ă��A�v�M����t���ɑ��������Ȃ����ƁA�T���͐����ɂƂ��ĊQ���邱�ƁA�n���̗R���ɂ���Đm�a�����R�喖���Ƃ��ׂ����Ɠ����u���Ɓv�ɑi�����B����ɕ��ďO�͂������č�{�ɂ�����A���g�Ђ̎��d���Ȃǂɉ��������̂ł���(�u���g�Л�b�R�s�K�L�v)�B�܂��u�R��i�ׁv�̉Q���ɕa���ɂ���������V�c�́A�����F���̍b����Ȃ����䂵�A�����Ɍ�F���@�c�̉@���͏I���A�������ɉԉ��V�c���H�N���ĕ�����c�̉@�����n�܂�B�@
��������ĉ��c���N�ƂȂ����\���A�u�R��i�ׁv���������ԉ��V�c�ƕ����@�c�́A�u拍��̎��A�R�告�����Đ\�A����肫�����߂��ӂ�ʂ��i�̑�ڂȂ肯��A�����v�M�m��拍����~������ׂ��̗R�A��|��������Ȃ�A�v(���O)�̂Ƃ���A����V�c���������������{�o��t�����߂��̂ł���B�R��̕���͂����܂������A�����t�����~���ꂽ�������͑傢�Ɍ��V�����B�u�m�a�E���E���厛���A�������O�̏��������ɏ]���ׂ��炴��̗R�A�݂ɒ���𑗂藹�ʁA���Ĕނ̟������A�v(�u����L�v���l)�Ƃ���悤�ɁA�����@�����Ђ������͑��݂ɒ�������킵�āA�u���Ɓv�̊ւ��@��ւ̏��������₷�邱�Ƃ�\�����킹�A�������������Ɍ��������������B�����E�m�a���E��펛�E���厛�E�����E���C�����́A�{�o��t�����u��@�̋K�́v�܂蓌���S�̖̂��_�ƔF�����A�R��̑i�ׂɂ���t���̒�~�ɂ��āA�u�`�ɖ����̏D�i�݂̂ɔA�߂Ɉ�@�̖ŖS�����k��́l�����̟b�A�v�Ƃ̊�@��������A��̂ƂȂ��Ă��́u�����Ԃ��v��}�낤�Ƃ���(���O���|��O�l�܋�E��O�l����)�B����瓌�������̘A���̌`���ɐϋɓI�Ȗ������ʂ������̂͐m�a���E���厛�̏O�k�ł���A�����֒���𑗂�u���S�v�����߁u��v�Ɓu���v�@��̒�~���Ăт������̂ł���B�Ƃ�킯���厛�O�k�͕q���ɔ������A�������ɓ��厛�����̐_�`��啧�a�ɓ��������A�u���Ɓv�ւ̍R�c�̈ӎv��\������(�u���厛���N�v)�B�Ȃ����厛�̒�����������̓��A��펛�͕K��������������������������(�u���g�Л�b�R�s�K�L�v)�A���̂��Ƃ���ɓ��厛�Ƒ�펛�Ƃ̊Ԃł̖{�����_�ɔ��W���邫�������ƂȂ�B�@
�N���������c��N�ɂȂ��Ă��u���Ɓv�͓��������̑i���Ɋm����ٌ����������A������u���Ђ̖ʖڂ����v�����̂Ǝ�������厛�O�k�́A�����{�̐_�`�O����㗌�����A�܂��u���̏㐹�f�P�����𑗂�A�Вd��ɑ啧�a�㉺�̏������D���ɐ������߁A�m�����Ăߒu���Ƃ���Ȃ�A�v�Ƃ��āA�u���f�v�������ʏꍇ�ɂ͎������F�������ӌ��ł��邱�Ƃ�m�a���E���C�����Ђɓ`���A���������s�����Ƃ�悤���Ƃ߂�(���O���|��O�Z�����E��O������)�B����ɓ��������͑�t���̒�~�ɂ��Ė��{�ɑi���A��������������{���i����e��A�u�����\��拍��̎��A���̈������ɔA�������t�����ׂ��̗R�v��Z�g���T��ɓ`�B���A��t�������ׂ��ł���Ɓu���Ɓv�ɑt�������̂ł���(�u���g�Л�b�R�s�K�L�v)�B���̂悤�Ȍ����̋��ہA�_�`�㗌�E������ɉ����Ė��{�̉���̌��ʁA���c��N�������ɉv�M�̖{�o��t�����镚����c�@�邪������A�_�`���A�������̂ł�����(���O�A�u����L�v���l)�B�@
�������{�o��t���̕����ɖʖڂ��������R��O�k�́A�������ɑt�����A���g�Ђ̐_�`�̓�����]�c����ƂƂ��ɁA���R���n�ߖ����̏O�k�ɑ��Ē���𑗂�㗌�𑣂����B�܂��R��̑t����������u���Ɓv�́A�R�傩�璼�ږ��{�ւ̑i�ׂ����߂�ƂƂ��ɁA�u�߂ɎR��t���֓��ɉ�����v�邱�Ƃ𗝗R�ɁA�_�`�����̉����𖽂���@��������Ă���(���O��|��O���O�l�E��O���l��)�B���͂�u���Ɓv�͎��Ԃ̑ŊJ��S�ʓI�ɖ��{�ɈςˁA����͉i����@�̖��z�ɂ��������A�u������@�̑i�ׁv���������u�V����捁v�E�u�l�@�v�ɏ��̂��ߕ�����c���M�̍��������m���o������R���@�ɕ�[����Ƃ�������Ƃ�݂̂ł�����(���O��|��O���l�l)�B����A���{�̊m����Ή����Ȃ��܂܂Ɏ��𑗂�R��O�k�́A���c��N�\���ɖ��{���̌R������I�őނ��Ȃ���_�`�㗌�����s���A���Ђ̐_�`�Ƃ��ǂ������ɕ��u���A�u拍�����߂�ꂷ�́A�i�ׂ̓���ɂ��炷�v�Ƃ̑ԓx���ł߂�(�u���g�Л�b�R�s�K�L�v)�B���̂悤�ȏ�w�i�Ƃ��āA�u���Ɓv�͎���ɎR��̈ӂ�e�������ɌX���A�����c�O�N�����ɂ͓��厛�ʓ��ɑ��A�����O�k�́u��������Ύ��@����Ă��A�����q�𗔑i�ɊA�p�ɏ�s�����\����v�Ƃ����O�k�̍s�����A�u���ӂ̐r�����A���t�̎���A�r�߂ė]��L��A�v�Ɣ��A�����F����̑ދ��𖽂����̂ł���(���O��|��l���O��)�B�@
���N�\���A���{�͂��Ɏg�҂��㗌�����A�u��t�����������ւ��悵���X�䎺�\����v�Ƃ��āA�ēx�v�M�̑�t����ԏシ������Ŏ��Ԃ̉�����}�邱�Ƃɂ��A���Łu拍���ɐ_�`�̑��ցA�R��̐\�������ɔC�čً�������ւ��悵�v��t�������B���̖��{�̈ӌ��������āA�u����\���v�M�m��拍��̎��A���������\���Ƃ���Ȃ�A�v�Ƃ̕�����c�@�邪������A�v�M�̑�t���͍ēx��~����A����ɏ����ɂ킽��v�M�m���̑�t���t�����ւ���@���������A�i�ׂ͎R��O�k�̏��i�Ƃ��ďI������(���O)�B�@
�ȏオ�A�����ƎR��Ƃ̑��_�ɓ����E�R��̏������e�X�̎v�f������ʼn�����A����Ɂu���Ɓv�Ɩ��{����݂���拍����_�̌o�܂ł���B�����Ă��̑��_����A�u���Ɓv����������拍����A���@�Љ�ɂ����Ĕ@���ɔF������Ă�������m�邱�Ƃ��ł���B�����ϒq�@�ܕ�́A拍����_�̌��ʂ��������̔s�i�ƂȂ������Ƃ�s���Ƃ��A�R�呤�̎咣�ɑ��锽���̂��߂Ɂu拍��G�L�v(���Q���ޏ]�߉ƕ�����)�𑐂����B�{���ɂ͈ȉ��Ɍf����Ƃ���A�R��i�ׂ̑��_�Ƃ����e�X�ɑ���ܕ�̌������A��܉ӏ��ɂ킽���Čf�����Ă���B�@
�@�u�q�ґ�t�����ƈׂ���ۂ�̎��v(������t���̋N����V���t�q���Ƃ���R��̎咣�ւ̔��_)�@
�A�u�`���E���o����t拍��̎��v(����t�������̌o�܂ƒ��������p)�@
�B�u�O�@��t拍��̎��v(�O�@��t�����������Ƃ߂�ό��t��ƒ��������p)�@
�C�u�q�ؑ�t拍��̎��v(�q�ؑ�t�������̌o�܂ƒ�������і�l��\)�@
�D�u拍��m�O�̎��v(拍������ꂽ�m����O�����L)�@
�E�u拍���������b�̎��v(拍������ꂽ��b�ꁛ�����L)�@
�F�u�����@�c��̐Êς̎��v(�F���@�c�ւ̓`�@������������Êϑm�����v�M�Ɣ䌨������R��̎咣�ւ̔��_)�@
�G�u�Α����Ȃē`���̒�q�ƍ����鎖�v(�`����t�̋Α��ւ̟ɂ��A�Α��̒�q�O�@��t��`����t�̒�q�Ƃ���R��̎咣�ւ̔��_)�@
�H�u�����N���ɋy�Ԃƍ����鎖�v(�^���@�ɂ͍O�@��t�̑���拍�������ʋN��������Ƃ̎R��̎咣�ւ̔��_)�@
�I�u�m�a���ɉ�����銯���̎��v(���o��t�̒�q�H�傪�m�a���ʓ��ł��������Ƃɂ��A�m�a������������Ƃ��邱�Ƃ��咣����R��ւ̔��_)�@
�J�u�v�M�m���̎��v(�v�M�̗���)�@
�K�u���ł̔N��拍�������������v(���ł̔N��拍������ꂽ���ρE�Êϑm���̎���)�@
�L�u�t�����o��Ƃ����ǂ����������̗�v(�t���ɂ�������炸拍�������Ȃ����������E�����̎���)�@
�M�u���b拍��̎��v(��t�����ʗnj������b��t�ƌĂԎR��ւ̔ᔻ)�@
�N�u��t���Ȃē`���̒�q�ƍ����鎖�v(�O�@��t��`����t�̒�q�Ǝ咣����R��̘_���ւ̔ᔻ)�@
���G���u毁v�A�ӂ��u�Łv�@
�����R�傪��N����拍����_�̋�̓I�ȑ��_�Ƃ́A�`�����镧�@�̎��ɂ��Ă��A�u���Ɓv�̐��h�ɂ��Ă��A�R�傪�����������D�ʂɂ��邱�Ƃ��咣���邽�߂̘_���ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̗D�ʂ��֎����邽�߂ɁA�`���E���o��t���u�{����t�̍��̎n�v�Ƃ��A�O�@��t��`����t�̉��ʂɈʒu�Â��A�F���@�c�ɕt�@�����Êϑm�����v�M�ɕ��ׁA拍��̒������u���Ɓv���h�̏ے��Ƃ��ċ������A�����@���̋��_�ł���m�a�����R�喖���ɒu�����Ƃ����̂ł���B�����Ă����̑��_�̂Ȃ��ɁA拍������������ɂ͔@���Ȃ����������A拍��ɂ͔@���Ȃ�Ӌ`�����ƍl�����Ă��������M����B�@
�܂���t�������̏����Ƃ��ĎR��O�k���f�����̂́A�u�����̈�ɕ��v���āu�����̖@��`�v�����Ƃ����u�O�@�̌��v�ł���A�܂��u��t���͌ܓ��̍łȂ�A�v(�u���g�Л�b�R�s�K�L�v)�̂悤�ɁA�u�ܓ��v(�����E�\�c�E�����E�T�v�E�a��)�������Ƃ������Ƃł���A���̂�����̏������v�M�͖������Ă��Ȃ��Ǝ咣����B�Ȃ�قǓ`���E���o�E�O�@�E�q�ؑ�t�ɂ́A�u�n���̐l�v�Ƃ����o�������ʂ��Ă���A����������ɝܕ�̔��_�͂Ȃ��A�����ɂ����đo�����[�����������Ƃ��邱�ƂɂȂ낤���B�������u�ܓ��v�ɂ��ẮA�嗬�ɂ���ĕ]���͑傫���ς��͂��ŁA�����@���̗��ꂩ��u�g���̑c�v�Ƃ����v�M���A�R��O�k����́u�ꉺ�̉v�M�v���Ȃ߂��邱�ƂɂȂ�(���O��|��O���l��)�B������ɂ��Ă���t���̒����́A�u���Ɓv�ɂ���t�́u�O�@�̌��v�Ɓu���s�v�w�̕]���������Ƃ�����̂ƁA���@�Љ�ł͈�ʓI�ɔF������Ă������Ƃ͊m���ł��낤�B�@
���q�������ɂ�����{�o��t�����_�̎��_�ł́A�R��O�l�Ɠ�����l�ɑ�t������������Ă����킯�ł��邪�A���̑�t�����e�X�̎��v����ǂ�قnj�ɒ������ꂽ���ɂ���āu���Ɓv�̐��h�̗D����ƎR��O�k�͎咣����B���Ȃ킿�u�`����t�͓��ł̌�l�\�ܔN�A���o��t�͖Ō�O�N�A�O�@��t�͓���̌㔪�\�Z�N�A�q�ؑ�t�͖Ō�O�\���N�v�Ƃ��āA�u�鉺�̉��߂��ȂāA���s�̗D��ƈׁv���Ƃ����̂��R�呤�̎咣�ł���B����ɑ��ĝܕ�́A�u�Ⴕ�߂����Ȃď���Ə̂��A�`���E���o��k�ށl�̗��m���k���ρE�Êρl�j�����ƈ����ׂ��A�܂��V���t�@���拍��́A���ł̌�Z�S��Ɖ]�X�A�Ⴕ�������Ȃė��ƈׂ��A�`���E���o�͌��c�@��ɏ���ƈ����ׂ����A�v�Ƃ̘_��W�J���A�u�����̒x��A拍��̑O��A���Ɏ��̉��ɍ݂�A�v�Ɣ��_�����B��t�������ꂽ�u���s�v�̗D����A���ł���̎��ԓI�ȉ��߂ɂ�茈�肵�悤�Ƃ����R��̎咣�́A�����̖@�����Ȃ߂悤�Ƃ̈Ӑ}�̂��ƂłȂ��ꂽ�����ɁA���܂�Ɍ����t��ɂ�����B���������̂悤�ȗ��s�s�Ƃ��v����_���ɂ���āA�`���E���o�E�q�ؑ�t�ƍO�@��t�Ƃ̍��ق��������A�����Ƃ̌��u���������Ƃ����R�呤�̈Ӑ}�́A�P�ɐ�t�̌����Ƃ������Ƃ݂̂ł͐������������Ƃ���ł���B�@
�����܂ł��Ȃ���t�����n�߂Ƃ���拍��̑t���͖�l�ɂ�肨���Ȃ�����̂ŁA��������拍������������ƁA��l�́u��\�v������āu���R���V���v������̊���̐S����\����B��������拍��́A�������ׂ��m���̍������㐢�ɓ`���邽�ߒǑ��������̂ł���B�������u�v�ꂨ����݂��拍��́A�����Փ��̏́A�����r��̖@�Ȃ�v�A�u拍��E�����́A���ɑق��A���O�l�Ɋ��ނ�̈��Ȃ�A�v�Ƃ̕\���ɉM����悤�ɁA拍��ɂ͉ߋ��́u���v�E�u���v�����炩�ɂ��邱�ƂƂȂ�сA�㐢�ւ́u�r�v�E�u���v�Ƃ����ړI���������B�����Ă�茻���I�ɂ́A�u�v��̑����́A����炭�͈��̍����ƈ����ׂ��A�v(�u�䖝���v)�Ƃ��āA拍��͈₳�ꂽ��q�����́u�����v�Ɨ�������Ă����̂ł���B�܂�拍����_�̌_�@�ƂȂ����v�M�̑�t�������́A�P�ɉv�M���g�́u�����v�����A�ނ��낻�̖@���ɘA�Ȃ芩�܂����T���A�����Ĕނ����҂��Ƃ߂铌���Ɠ������c�́u�����v�ɂق��Ȃ�Ȃ������B�����œ��������Ƌ����������R��ɂƂ��Ă��A�܂��������ɂƂ��Ă��A���̂悤�Ȗ������͂�����t���ɋ����������Ȃ��ŁA拍����_���W�J�����ƍl������B�@
�v�M�̖{�o�l�t���́A�O�߂ŐG�ꂽ��F���@�c�ւ̓`�@���u���̑s�ρA�@�̋K�́v�ƔF�����ꂽ�Ɠ��l�ɁA�v�M�̖@���ɘA�Ȃ鎛�E�@�E�@���́u�����v�Ƃ��Ď��@�Љ�ɔF������A���̎����E���������߂�Ƃ��������I�Ȍ��ʂ��������킯�ł���B�����Đ�t�́u�����v�����ЂÂ�����̂��A�u�O�@�̌��v�E�u���s�v�ւ̕]���Ɋ�Â��u���Ɓv��拍������ł��������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B��������F���@�c�̌㉇�����������������s�i���R�呤�����i����拍����_�̌��ʂ���m����悤�ɁA拍��̒������c�t�̕����ւ̕]���ɂ���Ăł͂Ȃ��A�ŏI�I�ɂ͏O�k�E��k�̐����I�Ȑ��͂Ɛ��������Ƃٖ̋��ȊW�ɂ���Č��肳�ꂽ�������ʼn߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�@
�{�e�ł́A���@�Љ�Ɓu���Ɓv�Ƃ����т���쎝�ƋA�˂̑o���W�Ƃ��������̂��ƂŁA�����Ɋ��q�������ɂ������F���@�c�̐^�������ւ̊ւ��Ƃ��������ʂ��āA���@�Љ�u���Ɓv��@���ɔF�����@���Ȃ�v�f�̂��ƂɁu���Ɓv�ƑΉ��������ɂ��čl���Ă݂��B�@
���@�Љ�͐����Љ�̂Ȃ��Ŕ��W���Ƃ��邽�߂ɁA�u���Ɓv�Ƃ̑o���W�̌����ɌŎ����A���̈ێ���}�邽�߂ɂ��܂��܂Ș_���ݏo���Ă������A�����̘_���͎��@�Љ��������L�́u���Ɓv�w�̔F���Ǝp�����ӂɂ����āA�͂��߂ċ�̓I�ȈӖ��������̂ł��낤�B���Ƃ��A�u���썑�Ɓv�̘_���ł���A�u���@�v�E�u���@�v���݈ˑ��̘_���ł���A�u�։��v�̘_���ł���A�����͌����Ď�����z�����Œ�ϔO�ł͂Ȃ��A����w�i���ƂɌŗL�̈Ӗ��Ɩ����������Ď��@�Љ�ɂ���g���ꂽ�ƍl����ׂ��ł���B�����ē���̎���w�i�̂��ƂŁA���@�Љ�Ɓu���Ɓv�Ƃ̌��̂������́A������铖���҂̌��ɂ��A�������Đl�ԓI�ȐF�ʂ������ƂɂȂ�̂����ɓ��R�̂��ƂƂ����悤�B�{�e�ł́A���̌��ɒ��ڂ��Ȃ���A���@�Љ�ɂƂ��Ắu���Ɓv�̑��݈Ӌ`�ɂ��āA��̓I�Ȏ���E��̂Ȃ��Ō��������݂��킯�ł���B�����ōŌ�ɁA�e�߂̏������f���邱�Ƃɂ������B�@
���@
���߂ł́A�Ñ�ȗ��́u���Ɓv�Ǝ��@�Љ�Ƃ̊ւ��܂��A�ꌩ���قƂ��������F���@�c�̓`�@�Ɛ^�������ċ��̈Ӑ}���A���@�Љ�ɋy�ڂ��������I�E�@���I�ȈӖ����A�������̑��ʂɊm�F�����B�l�i�I���@�l�I�ȑ��݂ł���u���Ɓv�����̗��ʂ���쎝���邱�Ƃ́A�u���썑�Ɓv���f���鎛�@�Љ�̊�{�I�ȔC���ł���B���@�Љ�ɂ����Ė{���͎����s�ł���͂��̎����Ȃǂ̖@��E�@�V���A�u���Ɓv�̌��ɂ���āu���썑�Ɓv�̋@�\�������s�ɓ]�����鎖��͐������B�Ƃ��낪�@��E�@�V�Ɂu���Ɓv����Î҂Ƃ��Ă݂̂Ȃ炸��҂Ƃ��Ċւ��������Ƃ́A���@�Љ�ɂ���ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ����B���Ƃ��A�F���@�c�̐��ɂȂ炢�A��F���@�c�������ɂ����ē`�@�������@���ɘA�Ȃ������ʂƂ��āA�����Ɠ����@���́u�։��v��i���邱�Ƃɂ��A���@�E�@���̍ċ��ƂƂ��Ɏ��@�Љ�̓��Ŏ����E�������ւ�L�͂ȋ��菊���킯�ł���B�`�@���@���ɘA�Ȃ�F���E��F���@�c�̂悤�ȁu���Ɓv�́A�P�ɋM��̒��_�Ƃ��Ă݂̂Ȃ炸�A�������E�ɌN�Ղ���u�։��v�ƔF�����ꂽ�킯�ł���B�����ČÑォ�璆���̎��@�Љ�́A�쎝�����u�����v������̋ɂɁA����Ɣq���ׂ��u�։��v�𑼕��̋ɂɂ��āA���̗��ɊԂ�͈͂Ƃ��āu���Ɓv���e�ꂱ��ɑΉ������Ƃ����悤�B�@
���@
���߂ł́A�u���Ɓv�̗����O��Ɂu�@���̈Ꝅ�v�̂��ߎO��@�����������Ƃ߂��F���@�c�̈ӌ��������A�@���̌p���ɋ����������Ȃ���A�O��@���́u�����v�Ƒ�펛���u�哴�v�ƂȂ邱�Ƃ����҂���@���~�̎v�f�̂Ȃ��ɁA���@�Љ�u���Ɓv�̌��Ђ�@���ɔF�����Ă������������B����́u���Ɓv�Ƃ�������ɋ���Ȃ��番�h���������@���̈ꓝ���͂��낤�Ƃ���@�c�ƁA�O��@���𓌖��@���́u�����v�Ƃ��ĔF�߂邱�Ƃ��u���Ɓv�ɂ��Ƃ߂錛�~�Ƃł́A���炩�Ɂu�@���̈Ꝅ�v�̗����ɑ傫�Ȋu���肪�������B���������҂��ꗂ͑[���ꂽ�܂܁A���~�̓������ҕ�C�����Ԃ�Ƃ��āA�@�c�ւ́u�O��@�����v�̓`�����Ȃ���A���҂͊e�X�̎v�f�ɂ��������āu�@���̈Ꝅ�v�̒B�������������̂ł͂Ȃ��낤���B���~�ɂƂ��Ė@�c�ւ̖@���`���ɂ́A���炪��������O��@���������@���̂Ȃ��Ő����ł���Ɓu���Ɓv�ɏ��F����A�܂��`���̏����Ƃ����@�c�̏Z���ɂ���펛���m�a���Ɠ��l�Ɂu�哴�v�E�u�c���v�ƂȂ�A���E�@�E�@�����u�����v�ɋP���Ƃ����ɂ߂ďd��ȈӖ����������B�܂�u�A���v�Ƃ��Ắu���Ɓv�̌��Ђ́A�@���⎛�E�@�ɑ��āA���@�Љ�ɂ�����D�ʂ�ۏ���u�����v�Ƃ����@���I�Ȍ��Ђ�t�^������̂ƔF������Ă����킯�ł���B�@
���@
��O�߂ł́A��F���@�c�̓`�@�̊��܂Ƃ��Ē������ꂽ�v�M�m��拍����߂��鑊�_�̌o�߂����ǂ�A�s�i�����������̎R�呤�ւ̔��_��ʂ��āA���@�Љ�ɂ����ĔF������Ă���拍��ɑ������������Ƃ��̋�̓I�Ȗ����ɂ��čl���Ă݂��B�c�t�̉ʂ������u�O�@�̌��v�E�u���s�v�������Ƃ��āA���̐\���ɂ���Ē��������拍��́A�n�c�ɑ���u���Ɓv�̐��h�𐄂��ʂ�d�v�Ȏw�W�ł������B���������ւ̊��܂Ƃ��đc�t�ɒ������ꂽ�{�o��t���̂悤�ɁA拍��͑c�t�̌����𖼖ڂƂ��Ȃ���A���͖��́u�����v�A�܂肻�̖@���E���E�@�ɑ�������ւ́u���Ɓv�̐��h���ے�������̂ł���B������拍������ꂽ�c�t������k�́A����̑�����@���E���E�@���u���Ɓv�̊i�ʂȐ��h�ɗa�邱�Ƃɂ���āA���@�Љ�ɂ����ėD�z����������֎����邱�ƂɂȂ�B���ꂪ���������ƎR��̑o�����A�v�M��拍��ɋ����������������A���ƁE���Ƃւ̑i�ׂ����肩���������R�ł����낤�B�Ȃ��{�o��t��拍����_���R�呤�̏��i�ɏI������ő�̗v���́A��F���@�����畚���@���ւ̈ڍs�̂��ƂŁA�D���Ȑ������͂����R��̋��d�Ȍ��ƁE���Ƃւ̑i�ׂɂ����̂ƍl�����A�c�t�̕������ے�����͂���拍��̒����́A���ǂ̂Ƃ��됢���Љ�̗��Q�Ɩ��_�ɂ�荶�E�������̂ɉ߂��Ȃ������̂ł���B�@
���@
�ȏオ�A��̎����ʂ��Ď��@�Љ�́u���Ɓv�ւ̊ւ����l�����{�e�̏����ł��邪�A�܂�Ƃ���A�����Љ�Ɠ��ꕽ�ʂɕ������鎛�@�Љ�́u���Ɓv�ɑ���F���ƑΉ��́A����Ə�ɂ�葽�l�Ȍ`�Ԃ��Ƃ�Ƃ��Ă��A�܂��Ɠ��̘_���Ƃ������w�I���������݂�ꂽ�Ƃ��Ă��A���̋��ɂɂ́u���Ɓv�̌��Ђɋ���܂�����𗘗p���A����̎��@�Љ�Ɛ����Љ�ɂ����鎛���E���������߂�Ƃ����������Đ����I�Ȏp���ɋA������̂ł͂���܂����B�@
 �@
�@�������̖���
���{�̕����́A�l�X�ȗ��j�I����̂����ŗ��𐳂���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�u�m�c�̂Ȃ������v�Ƃ����A����߂ē���Ȍ`�ԂɂȂ��Ă��܂��܂����B�F���u�m�c���v�Ǝv���Ă�����͎̂��́u���c�v�A�܂�M�҂̏W�c�ł����āA���ɂ��������Đ������鏃���ȏo�Ǝ҂̏W�c�Ƃ������͓̂��{�ɂ͂Ȃ��̂ł�(�����T�@�̑m���������A����Ɉ�ԋ߂��`���c���Ă��܂�)�B�ł����玄�������{�̕����҂����ɐG���@��͂قƂ�ǂȂ��̂ł����A����A�X�������J�Ⓦ��A�W�A�A���邢�͊؍����p�̂��V�����͊F�A���ɂ����������{���̑m�c�����𑗂��Ă��܂��B�����ɁA���{�̕����ƁA����ȊO�̍��X�̕����Ƃ̊Ԃ̌���I�ȕǂ��ł��Ă��܂��܂��B���̕ǂ����z���āA���ׂĂ̕����҂��ЂƂ̏@���̃����o�[�ł���Ƃ������o�������߂ɂ́A��X���g���悭�����w�сA���������Ɍ����Ă���_��A���邢�͋t�Ɏ��������̕���������Ă���_����������F�����������ŁA�Θb���Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�@
�ȑO�A�����g�����ڕ������b�ł����A���镧���̐e�r�c�̂�����ł������W�߂āA����ŃX�������J�ɕۈ牀���������ł��B�n�����X�������J�̑��ɗ��h�ȕۈ牀�̌����������A�n���̐l�����͂���������Ƃ������Ƃł��B�����b�ł���ˁB�Ƃ��낪���̒c�̂̐l�����́A���{���爢��ɗl�̕����������Ă����āA���̕ۈ牀�̐^�Ɉ��u���A�ʂ��Ă���X�������J�̗c�q�����ɋ����āA�������̈���ɗl�Ɏ�����킹�u�얳����ɕ��v�Ə��������Ă���̂ł��B����͂����b�ł����H ���͋��낵���b���Ǝv���܂����B���̒c�̂̐l�����́A���̘b�����������Ɍ���Ă����܂������A�����u�X�������J�̏�������ƁA���{�̏�y�n�����͖{���I�ɈقȂ�@��������A���ɂ��̂����킹�āA���������̋��`���A�����������̕�����Ȃ��c���q���B�ɉ�������̂͂悭�Ȃ��v�ƌ����ƁA��ϋ������l�q�ŁA�u�ł�����������A���̎��߂̊Ⴉ�猩��Ό��ǂ͓������E���ƕ����܂����B�ł����珬��̐l���������āA���O����������Ɋy�ɍs����Ⴀ��܂��v�Ƃ���������Ă����܂����B�u������������͓������v�Ƃ����咣���A���敧������荞��ł������Ƃ�����摤�̏���Ȑ헪���Ƃ����A��ԑ厖�ȓ_���w��ł��Ȃ����炱���Ȃ�̂ł��B�u����Ȉً��k��A�{���Ȃ�Βn���s�������܂��Ă��邨�O�B���A�_�̈��ɂ���ċ~���Ă�낤�Ƃ����̂��B���ӂ���v�ƌ����Ȃ���A�A�W�A��A�t���J�ɕz�����A�A���n����̓y��������Ă������L���X�g���鋳�t�����̎p�ƃ_�u��܂��B�@
�e�r�c�̂̐l�������A�Ȃɂ������S�������Ă���Ƃ��A���S������Ȃ�Ďv���܂���B�F����A�D�����āA�l�̂��߂ɂȂɂ����Ă������Ƃ����C�����ň�t�́A���h���ׂ��l��������ł��B�ł͈�̂ǂ��ɊԈႢ������̂ł��傤�B�����͂ЂƂB��������{�Ƃ����������E�̒������ŗ������āA����Ő��E���̂��ׂĂ̕��������������Ƒ����_���Ă���Ƃ���ɖ�肪����̂ł��B�ӔC�̈�[�́A�����������l����M�҂����ɍL�߂Ă���A���{�̕����e�h�ɂ�����܂��B�������{�ł����ʗp���Ȃ�����ȍl�����A�܂�ł��ꂪ���E���ǂ��ւ����Ă��������Ă��炦��ō��̋����ł��邩�̂悤�Ɏv���オ���Ė����������A���ǂ��ꂪ�܂��̍��̐l�����ɑ傫�ȊQ��^���邱�ƂɂȂ�A�Ƃ������̍\�}�́A��O�̑哌�����h���\�z�Ɠ������̂ł��B���́A�̂̂悤�ɁA���̏@���������̂��āA�Ђ�����M�Ґ����g�傷�����ł悢�A�Ƃ�������ł͂���܂���B�ЂƂ�ЂƂ�̐l�Ԃɐl��������悤�ɁA�ЂƂЂƂ̕����ɂ͕����̌����Ƃ������̂�����܂��B������F�����o���鎞��ɂȂ��Ă���̂ł��B����̕����Ɍh�ӂ��A����d���A�u���{�ɂ͂��������l��������̂ł����ǂ��v���܂����v�Ɖ��₩�Ɏ��������̍l������A����ł��ꂪ������Ă����̂ł���Ȃ猋�\�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B�Ƃ�������Ȃ̂͊w�Ԃ��Ƃł��B�������C�s���āA�����������Ђ炭�̂Ȃ�w��͂��قǕK�v�ł͂���܂��A�����l�ɋ����Ă������Ƃ����̂Ȃ�A���Ȃ��Ƃ��A���E�ɂ͂��낢��ȍl���̕��������݂��邱�Ƃ�A�����̋��`�����{�I�ɂ͂ǂ��������̂ł��邩�Ƃ����������𐳂����������邭�炢�̕��͕K�v�ł��傤�B�����̂��Ƃ�m��Ȃ����V����Ƃ����̂́A���̕߂����m��Ȃ����t����Ƃ����̂Ɠ����ŁA���b�ɂ��Ȃ�܂���B�����ǂ�ł�����F����ɂ��肢���܂��B�ǂ����A�����̂��Ƃ���t�����āA���̃N�[���ŃX�}�[�g�Ȗ{���̎p���A���̑吨�̐l�����ɏЉ�Ă����Ă��������B�����̖������J����Ƃ���A����͋V���̎����Ő������т鑒����������łȂ�(�������͂���ňӖ�������̂ł���)�A���߉ޗl�̎���̂悤�ɁA�Ⴂ�l���������ɎQ�����Ă���A�i�D�����W�c�Ƃ��Ă̕����������������ł��傤�B�����āA���̊i�D�ǂ����l���邽�߂́A��Ό������Ȃ��Ղ̊����A���Ȃ̂ł��B�ł�����A���{�����Ƃ͒��ڂ̉����Ȃ��Ă��A������w�Ԃ��Ƃ͂ƂĂ���Ȃ��ƂȂ̂ł��B�@
��N�ԁA���̂��Ƃ��菑���Ă��āu�ԑ�̍��X�Ƃ����̂͊��S�ȗ��I�^�N���v�Ǝv���Ă��邱�Ƃł��傤�B�܂��A�����͓�����ł��B�ł����͗��̑��ɂ��A�A�r�_���}�ƌĂ�镧���̈��N�w�̌n���������Ă��܂����A�����Ǝ��R�Ȋw�̊W�ɂ��Ă����낢��l���Ă��܂�(�������A���̕���ɂ͉������C���`�L�w�҂���R����̂ō����Ă���̂ł���)�B���������ʂ̕���ɂ��Ă��@��������炲�Љ�Ă����܂��傤�B�����A���ƃA�r�_���}�Ǝ��R�Ȋw�ƁA�O�̂����̂ǂ��D�悷�邩�A�Ɩ��ꂽ�Ȃ�A���̓��{���������ʂ��Ă��邢���Ȗ����l�������A�ǂ����Ă���������˂Ȃ�Ȃ��Ǝv�����̂ł��B���ӂ��������̃R�����ł������A���͎��͂ƂĂ��^�ʖڂȂ�ł�(�����������ƌ����̂��s�^�ʖڂ�������[��)�B�A�ڒ��A�����Ȑl���猃��₨�_�߂̌��t�����������܂����B������̌��t����������������܂��A���Y�ǂȂ��̂ŁA���������̂͂��ׂĖY��܂����B�Ƃ����������̐l�����̋�����ǂ�ł��������Ă���Ƃ������Ƃ�m��A�{���ɂ��ꂵ���v���܂����B�܂��A�@��������炲�������т܂��傤�B���肪�Ƃ��������܂����B�@
 �@
�@�����l�S��
���͕������E�̖@���ł�����A�ƂĂ��ێq��K�Ō����Ȃ��̂ł��B�{���ɁA�ꌩ�����Ƃ���ł̓o�J�o�J�����v����قǎێq��K�Ȃ̂ł��B�������A�@���Ƃ������͖̂{�������������̂ł��傤�B�����܂��Ȓ�`��A����������Ȋ�������琢�̒������ꒃ�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ł�����A�����̗����o�J�o�J�������炢�Ɏێq��K�ł���Ƃ������Ƃ́A�����Ƃ����@�����ƂĂ������Ȗ@���̌n�������Ă����Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂����A����́A����قnj����Ȗ@����K�v�Ƃ���قǁA�����͏o�Ɛ��E�̉~���ȉ^�c���d�v�����Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��B���ۓI�Șb����ł͉����`���܂���A��̓I�ȗ�������āA���̌����Ȏێq��K��������I���܂��傤�B����͓D�_�̘b�ł��B�@
���ł́A�d��ƍ߂̂ЂƂɐޓ��������Ă��܂��B��u���u�l�̕��𓐂�A�g���ƌĂ��A�ƂĂ��d���߂ƂȂ�A�m�c����i�v�Ǖ��ɂȂ�̂ł��B�����ł����u���ނȁB����g���ł���v�ƁA�܂��ƂɒP���Ȃ������ɂȂ�̂ł����A���ꂾ���ł͖@���Ƃ͂����܂���B�u���ނƂ́A�ǂ������s�ׂ��w���̂��v���͂����茈�܂��Ă��Ȃ���A�K����K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��B�ł́A���ɂłĂ���A���ނƂ����s�ׂ̐��X�����Љ�܂��B�@
�u�n�����v�F���ڂ̕�����������Ȃǂ��n���ɖ��߂��Ă���̂�m���āA����𓐂ޏꍇ�B���ȂǁA�@�邽�߂̓����p�ӂ������_�ł͌y�ƍ߂ł��B�y�ƍ߂Ƃ͔��Ȃ��������ŋ������ł��y���߂̂��ƁB�n�ʂ��@���Ă��y�ƍ߁B�ł�����A����p�ӂ��Ēn�ʂ��@������A�y�ƍ߂���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�n�ʂ̒��̚�ɐG������h�炵���肵���疢���߁B�����߂��ƁA�m�c�Ǖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ�����ǁA������ꃉ���N�y�������^�����܂��B�����āA���̚�����Ƃ̏ꏊ����ړ����������_�ŁA�{���̐ޓ��߂ɂȂ�܂��B�ł́A�₻�̂��͓̂��������A�ǂ�Ԃ���̒��ɂ���āA����Œ��̂������������Ƃ�̂͂ǂ��ł��傤���B�ǂ�Ԃ肪�����ɐG������y�ƍ߁A���̂��Ƃǂ�Ԃ�������疢���߁A���S�ɂ�������������_�Őޓ��߂ł��B���ɂ���̂������ł͂Ȃ��A�l�b�N���X�̂悤�ȕR��̂��̂ŁA�������Ś₩���������グ�Ď�낤�Ƃ����ꍇ�͂ǂ��Ȃ�܂����B��Ńl�b�N���X�ɐG��Όy�ƍ߁A���������疢���߁A�����Ă��̃l�b�N���X�̉��̒[���A��̌�����ق�̏����ł��O�ɏo����A���̎��_�Őޓ��ł��B�ł͚�̒��ɁA�J���s�X�݂����Ȕ����������ݕ��������Ă��āA������X�g���[�ŋz�������Ĉ��ޏꍇ�͂ǂ��ł���(�J���s�X�Ƃ����̂́A�C���h�̍��������i�T���s�X�ɂ��Ȃ�ł���ꂽ���O�ł��B�������ł����H)�B�X�g���[�ň��ޏꍇ�A�J���s�X���A�X�g���[�̒�����ɏ�ɏ����Ă���Ԃ͂܂��I�[�P�[�B�����߂ł��݂܂��B�Ȃ��Ȃ�A�z���̂���߂�J���s�X�͍Ăњ�ɖ߂��Ă�������ł��B�X�g���[��ʂ����J���s�X�����̒��܂œ����Ă����i�K�ł��܂����v�B�t�ɃX�g���[�𐁂��A���̒��̃J���s�X���ɖ߂����Ƃ��ł��邩��ł�(�����ȁ[)�B�ł��A���̒��̃J���s�X���S�b�N���ƈ��݉�������A�����߂����Ƃ͂ł��܂���A���̎��_�Őޓ��ƂȂ�̂ł��B�ǂ��ł��A���܂������B�n���̚�̒��̕��𓐂ނ����ł��A���ꂾ���̏ꍇ�������K�v�Ȃ̂ł��B�����āA���̂悤�ȕ��ނ��u�n�����v�ȊO�ɂ܂��O�\�ȏ゠��܂��B���Ȃǂ́A���������ׂ�������D���ŁA�ǂ݂Ȃ���v�킸���Ă��܂��̂ł��B�S���Љ�ł��Ȃ��̂��c�O�Ȃ̂ł����A�ʔ�����������������Љ�܂��傤�B�@
�u�ŕ��v�F�E�ł����h�ȓD�_�ł��B���V���E�ł���ȂǂƂ����Ă��҂�Ƃ��܂��A����͊֏���ʂ鎞�̒ʍs�ł̘b�ł��B���E���A�ǂ��ł������ł����A��ʂ̗v���ɂ͊֏�(���Ȃ�Ŋ�)�Ƃ������̂������āA������ʂ邽�߂ɂ͒ʍs�ł�˂Ȃ�܂���B�C���h�ɂ�������������֏����e�n�ɂ����āA�ʍs�l�͒P�Ȃ�ʍs�������łȂ��A�������ޕ��i��������x�ȏ�̉��l�̏ꍇ�A�����̕��i�ł�˂Ȃ�Ȃ������̂ł��B��`�ŁA���̂悤�ȕn�R�l�Ȃ�ΐŊւ��t���[�p�X�ł����A�������݂₰�⑽�ʂ̏��i���������ސl�͂���ɉ������ŋ���˂Ȃ�Ȃ��A����Ɠ����ł��B���V����͌����Ƃ��Čl���Y�������Ă��܂���A�܂��ԈႢ�Ȃ��t���[�p�X�ł��B�������ꍇ�ɂ���ẮA���l�̂��镨��l����z�{���Ă�����āA������������܂܊֏���ʂ�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����蓾�܂��B���̏ꍇ�́A�o�Ƃ�����Ƃ����ĖƏ�����邱�Ƃ͂Ȃ��A���i�ɂ͐ł��������܂��B���V����͂����������ł��܂���A�����炭���̏ꍇ�͕��[�ɂȂ��ł��傤�B�Ƃ��낪�A������������āA�߂̉��┫�̒��Ȃǂɕi�����B���Ċ֏���ʂ낤�Ƃ��邨�V�������炵���̂ł��B�����ׂ��ł�Ȃ��̂ł�����A����͍��Ƃ��炨���𓐂��ƂɂȂ�܂��B�����ŗ��ł́A���̂悤�ȒE�ōs�ׂ��ޓ��ł���Ƃ����܂��B�������g���ł��B���������ڂ��������ƁA�ېŕi���B�����Ǝv���āA����ɐG������y�ƍ߁A���������疢���߁A�B�����܂ܐŊւ̖��ʂ肷���Ĉ�����ݏo�����疢���߁A�����ē���i��ޓ��߂��������܂��B�܂��A�֏��̒�����i���������ɖ�̌������֕��蓊���Ă����āA�֏���ʉ߂��Ă��炻����E���Ƃ����������̒E�ł��l�����܂����A���̏ꍇ�́A�i�����֏��̌������֕��蓊�����i�K�Őޓ��ƂȂ�܂��B�������l�����āA�ꏏ�ɗ������Ă��邨�V����Ɂu���́[�A���͎��A���Ȃ���ڂ̕��������Ă���܂��āA�������܂܊֏���ʂ�Ɛ����Ɛŋ����Ƃ��Ă��܂��܂��B�����ł����k�ł����A�֏���ʂ�Ԃ����A���̕i���������Ă��Ă��炦�Ȃ��ł��傤���B���V���܂Ȃ�A�֏��̖�l���t���[�p�X�Œʂ��Ă���܂��ł��傤�B�����֏���ʂ邱�Ƃ��ł��܂�����A�����̂��z�{�͂����Ă������������ł������܂��B�������ł������܂��傤���v�ȂǂƂ��������܂��B������������āA���l�̒E�łɋ��͂����ꍇ���A���̖V����͐ޓ��߂ɂȂ�܂��B�E�łŗ��v���̂ł����瓖�R�ł��ˁB�@
�O�\��ޑS�����Љ�ł����炢���̂ł����A����ȃy�[�W�������C������܂���B���̂�����ɂ��Ă����܂��傤�B�����Љ���̂͗��̒��́A�ޓ��Ɋւ��邫�܂�ł����A���������̗��j�̒��ŁA���̗��ɑ��Č�̎���̐l�����X�ɒ��߂����Ă����܂��B���̒��߂ɂ́A���̒��ł͌����s�����Ȃ������A�����Ƃ����ƍׂ������Ⴊ��t�łĂ��܂��B��������ĕ����̖@���̌n�́A�܂��܂��݂���������A�ו�������Ă������̂ł��B�_�͍ו��ɏh��Ƃ����܂��B�N�ł�����u�ŕ������G�c��搂����傾���������̐^���ł͂���܂���B�܂��ɏd���̋������Ȃ���A�������������O�i�𑱂������̐��E���܂��A���^�����̕������E�Ȃ̂ł��B�@
 �@
�@�������C�̂͂Ȃ�
�Â�����̎���������ƁA���V�����́A�傫�������ē��ނ̏C�s�����Ă������Ƃ�������܂��B�ЂƂ��ґz�B�����ЂƂ͂��o�̕��ł��B�܂荿�T�����Đ��_���W�������A���o���w�Ԃ��ƂŒq�d�����킯�ł��B���ł��X�������J�Ȃǂ̏�������ł́A���̂�����������Ă��܂��B���F���߂𒅂��X�������J�̂��V���A��R�𑖂�������얀���������肷�邱�Ƃ͂���܂���B�����Ă��̌`�́A���{�̏@�h�ł����Ȃ�A�܂��ɑT�@�̏C�s���̂��̂ł��ˁB���������ƁA�T�@�̊F������͊��������Ȋ���Ȃ���̂ł����A�ł����߉ޗl����̂��V����́A���ɂ��ƂÂ����m�c������������Ȃ���A�����������C�s�����Ă����̂ł�����A���̑T�@�ƑS�������Ƃ����킯�ł�����܂���B�Ƃɂ����A���߉ޗl����̂��V�����̏C�s�X�^�C���͔��ɃV���v���ŁA�������I�������̂ł��B�@
�悭�A�N���⌳�U�ɁA�₽���₽����̐��ɂ�����ďC�s���Ă��镧���҂̗l�q���e���r�ɉf��܂����A�����������C�s���A�{���̕����ɂ͂���܂���ł����B�����̐S�𐴂炩�ɂ���̂ɁA���𗁂т����ĉ��̌��ʂ�����͂��܂���ˁB�S�𐴏�ɂ��邽�߂ɂ́A�����̗͂ŐS�̒��̈����v�f�A�܂�ϔY���ЂƂ������Ă����������͂Ȃ��̂ł��B�ł����畧���ł́A�������邱�ƂɂȂ�̐_��I�ȗ͂��F�߂Ă͂��܂���B���𗁂т�̂́A�����g�̂̉���𗎂Ƃ����Ƃ������ړI�ł��B�����疈�����𗁂т���͂��܂���B�������Ɉ�x�A�g�̂����ꂽ���ɂ��������т���̂ł��B�@
�Ƃ���ŁA���߉ޗl�̎���A���V����͐����т̑��ɁA�T�E�i�ɂ������Ă��܂����B����͂�����ƈӊO�ł���B�����т͐g�̂𐴌��ɕۂ̂��ړI�ł����A�T�E�i�̖ړI�́A�C�s�Ŕ�J�����g�̂������b�N�X�����āA���N�ȑm�c�����𑱂��Ă������Ƃɂ���܂��B���̏ڂ��������A�g�����́A�݂ȗ��̒��ɏ�����Ă��܂��B�T�E�i�Ƃ����Ă��A���݂����ɁA�ؑ���̂���ꂽ��������z�����Ă͂����܂���B���ܕ��C�ƌ��������������ł��傤�ˁB�y�����˂āA����A���̒��ɃJ�}�h��݂��܂��B�����ʼn������ƁA���̔M�C�����̒����Ă���܂��B�������J�}�h����͂��������Ɖ����łĂ��܂�����A�������߂̉��˂��邢�͉������̑��������Ă��܂����B�[���Ɏ����M���Ȃ�����A�����ȓ��������g�������߂Ē��ɓ���܂��B���̔M�C�͂��Ȃ苭���Ĕ畆���Ă��t���̂ŁA��ɂ͔M��h�����߂̓D��h��A�g�̂ɂ͐����|���Ă����܂��B�����ł����Ƃ��Ă���ƁA�����܂��̒������̂悤�Ɋ�������n�߂܂��B��t���������āA�g�̂��y���Ȃ����玺����o�āA�O�ŗ₽�����𗁂сA�D�Ɗ��𗬂��܂��B�C���͂܂��ɃT�E�i�ł��ˁB���̂��Ǝ��Ȃ�₽���r�[���ł�����ŁA�u�����ĂĂ悩�����[�v�ȂǂƋ��ԂƂ���ł����A������邨�V����̂��Ƃł�����A�����Ɛ����W���[�X������Łu�o�Ƃ��Ă悩�����[�v�Ƌ��Ԃ�ł��傤�ˁB�@
���͐�N�A���I�X�֍s�����̂ł����A��s�r�G���`�����̂����ŁA�T�E�i�ɓ���@�����܂����B���ɏ����Ă�����̂�萏��������ł��āA�����Ɨ��h�Ȗؑ��̕���(�Ƃ����Ă���A�O�l����Έ�t�ɂȂ鏬���Ȃ��̂ł���)�������āA���̖����痧�����F�����n�[�u�̏��C���A���������Ɛg�̂��݁A�����ɓ����ď\�b������ƁA�����܂��h�b�Ɗ��������o���Ă��܂��B��A�O�������ĊO�ɏo�āA�O�C�Őg�̂��₵�Ă܂�����A�Ƃ������Ƃ����x���J��Ԃ������ɁA�Ȃ��g�̂̓ŋC���ǂ�ǂ��Ă����悤�ȑu�₩�ȋC���ɂȂ�A��������ʐl�ɂȂ����悤�ł����B�X�^�C���ɈႢ�͂����Ă��A�����̂��V�������A�T�E�i�ɓ���A���Ɠ����悤�ɁA�u�₩�ȋC�����ɂȂ��āA�u�����A�܂��C�s�ɗ�ނ��v�Ƃ����āA���C���������̂ł��傤�B�@
���̂悤�ɁA�T�E�i�ƕ����m�c�́A�Ñ�C���h�̎��ォ��[�����т��Ă��܂����B�����ĕ��������ӂ̍��X�֍L�܂�ɂ�āA�T�E�i�̐ݔ����A�����̍��ւƓ`����Ă������̂ł��B�������A�C���h�ő���ꂽ���o�����悤�Ȍ`�̕������A���{�֗���ƌd�̓��ɕω�����悤�ɁA�{�����ܕ��C�ł������m�c�̂����C���A���{�ɂ܂œ`����Ă���ƁA���Ȃ��������̂ɂȂ�܂����B�ǂ��������̂ɂȂ����̂��A�ڂ����m�肽�����́A���S�������̖��q���C�������ɂȂ�悭������܂��B�O�ŕ��������M���������A���ʂ��āA���a�ɗ������ނƂ����X�^�C���ł��ˁB�T�E�i�������ݏ�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B���{�ł����̒��ɂ����C������ꂽ��ԌÂ���͓��厛�ł��B���̂����C�͍��ł͎g���Ă��܂��A����ȓS�̓��D�ł������ϗ��āA���̂����ŕ�����g�߂�Ɠ����ɐg�̂�Ƃ����A�C���h�̃T�E�i�Ƃ͂��Ȃ������������ɂȂ��Ă��܂��B�����āA���̗����̓�����́A���ꂢ�ȓ��j���ɂȂ��Ă��܂��B���ꂱ�����A���{���̂����C������A�܂�K���̓���������j������ɂȂ������R�ł��B�������ܕS�N�O�̃C���h�Ő��܂ꂽ�T�E�i�̏K�����A���{���̂����C������̌��z�l���ɉe����^���Ă���Ƃ������b�ł����B�@
 �@
�@����u�����̂Ђ����ȔY��
����ɑ��ė��́A���V�����ۂ̓��퐶���Ŏg���@���Ȃ̂ł�����A���ꂢ���Ƃł͍ς݂܂���B�o�ƏC�s�҂Ƃ͂������g�̐l�ԁB����ȖV�������A���\�l�A���S�l�ƏW�܂��ďW�c����������̂ł�����A�����Ƃ����L���Ƃ��낪�A������Ƃ���Ɋ���o���Ă��܂��B���������������̂ǂ�ǂ낵�������������A�m�c�������ł��邾���X���[�Y�ɉ^�c���Ă������Ƃ����̂����̖ړI�ł��B�ł����痥�́A���߂���A�V����B�̉B�ꂽ�A�̖ʂɏœ_�����킹�ď�����Ă��܂��B�V�����̈ߐH�Z�A��������Ƃ͂����茾���Ȃ�A���~�A�H�~�A���_�~�A���K�~�Ɍ��͗~�ƁA���悻�V����ɂ͎����킵���Ȃ��l�X�ȗ~�]���ԗ��X�ɕ`����Ă���̂ł��B�@
�������A���̖ړI�́A�����������~�]��}���Đ���ȏC�s�҂Ƃ��Đ�����ɂ͂ǂ�������悢���A�Ƃ����₢�ɓ����邱�Ƃł�����A�{�����ɐ^�ʖڂȂ��̂Ȃ̂ł����A�m�炸�ɓǂނƁA�܂�ŕ����ɂ͗~�]�ɖڂ̂���l���肢�邩�̂悤�Ɏv���āA�������Ă��܂��܂��B�×��A�����閧�̏��Ƃ���āA��ʐl�̖ڂɐG��ʂ悤�铽����Ă������R���A�����ɂ���܂��B�@
���ł����A��������āu�T�����v�̃R�����œۋC�ɏЉ�ł���قNjC����������悤�ɂȂ�܂������A�������Ȃ玄�ȂǁA�u�����閧�R�k�߁v�őm�c���珈�������قǁA���̎�舵���͌�������������Ă����̂ł��B�����������p���ŏ�����Ă�����̂ł�����A�����ɂ́A��ʐl���v�������Ȃ��悤�ȁA�V�����̔Y�݂��J���`����Ă��܂��B����͂������������̒��A�����̖V�������ꂵ�߂Ă����A����a�C�ɂ��Ă��Љ�܂��傤�B����͎��ł��B�@
���߉ޗl����A���łɃC���h�ł͈�p�Ƃ������̂����܂�Ă��܂����B����̓C���h��ŃA�[�������F�[�_�ƌĂ�Ă��܂��B�ŋ߂ł͊����ƕ��ԓ��m��w�̑�\�Ƃ��ėL���ɂȂ��Ă��܂����ˁB���̋N���͂��߉ޗl������ꂽ�A�I���O�̎���ɂ܂ők��̂ł��B�Â�����������ƁA�����̃C���h��p�̃��x���͂��Ȃ�̂��̂������悤�ł��B���Ẫ��C���͊����Ɠ������Ö@�ł����A���̑��ɊO�Ȏ�p��������ɍs���Ă����悤�ŁA�]�̐؊J��p�̋L�^�����c���Ă��܂��B�@
���āA����Ȏ���A�l�X��Y�܂������낢��ȕa�C�̒��ł��A���ɂ����̈������̂̂ЂƂ����ł����B�����̂��A���Ƃ����a�C�́A�{�l�̂炳������ɓ`���Ȃ��Ƃ����_�ŁA���Ɠ��̔ߎS�����܂�ł��܂��B���鎑���ɂ��ƁA�L���ȃ}�K�_���̃r���r�T�[���������ɂȂ��ĔY��ł����Ƃ���A�o���������@�������u�܂��A���l�A���̂��̂ł������܂����B���l�����ɂ��Ȃ肠�����āB�������������D�������̂ł͂������܂��v�Ƃ͂₵���Ă��Ƃ������Ƃł��B�@
�o�Ɛ����𑗂�V�����ɂƂ��Ă����͑�G�ł����B�Ƃɂ�������@��̑����C�s�҂����ɂȂ�Ƃ����̂́A�ق�Ƃ��ɂ炢���ƂȂ̂ł��傤�A���̒��ł�������Ƃ���ɁA���̂炳���L����Ă��܂��B�����̎��̎��ÂƂ��ẮA�i�C�t�Ŋ���������p���������悤�ł����A���߉ޗl�͂�����ւ��Ă��܂��B���R�͂͂����肵�Ȃ��̂ł����A�A���ɐn�����Ă�Ƃ����A�ߌ��ȕ��@���������ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ł͂ǂ�����Ď��������̂ł��傤���B����ɂ��Ă͎��̂悤�ȋL�^������܂��B�@
�����u������a��ł��܂������A�O�ɏo�Ă���������܂ł˂������Ƃ���A���܂�̒ɂ݂ɂ��܂�ł����A��ꂵ��ł��܂����B���̎����߉ޗl���A��߂̗͂Ɉ�����Ă��̔�u�̂Ƃ���ւ����łɂȂ��Đq�˂��܂����B�u��u��A���O�͉����ꂵ��ł���̂��v�B�����Ŕ�u�͍������Ă��߉ޗl�������āA�ꂵ���ɗ܂𗬂��A�����Ȃ���a����ڂ����\���グ�܂����B���߉ޗl�͂������Ⴂ�܂����B�u���͐�ɁA���O���������������҂�����������Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ���Ȃ��������v�B�u�͂��A�������Ⴂ�܂����v�B�u�Ȃ�Ȃ����O�͂��̂悤�Ȃ��Ƃ������̂��v�B�u������A����܂�ꂵ����������ł��v�B�u�ꂵ���̗]���������Ƃł��邩�炨�O�ɍ߂͂Ȃ��B���A���O�����ɖ�����B�a�C���ꂵ������Ƃ����āA�܂Ȃǂł��̎�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����������@�͓����B����g�����A�����ɂ����̂ł���B����A���������Ő�����A���l�ɐ点���肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B����Ɉᔽ����҂͍߂ƂȂ�v�B�@
�܂莤�͖����Ŏ����A�Ƃ���������Ă���̂ł��B�����Ă��߉ޗl�͒�q�����ɁA���̎����������߂Ɏ����������Ă��������܂����B���������̎�����������ƁA�������邾���łȂ��A�h���q�Ƃ����_�ʗ͂������邻���ł��B���̎����̍Ō�́A���̂悤�Ȍ��t�ŏI���܂��B�@
�u�k�����R���̏ꏊ���O�n�����Ƃ������������B����ɂ͎O�̉Ԃ��炢�Ă���B��͑����A��͏_��A�O�ɂ͊��͂Ƃ����B���͉̌Ԃ���������ƒĂ���悤�ɁA���̎��a���܂��A���ꂪ�����A�M���A���A�����A�����A���邢�͂��̑��̏����̂ǂ�ł����Ă��A�F�Ă��Ċ�����т�B�o�����^����ɂ�����������B�����Ɋ�����т�v�B�@
������ĕ���q�����͊��삵�ď������Ƃ������Ƃł��B�@
��U�����Ǝv���܂����B�������A���̓����Ċ��삷��̂�����q�Ȃ�A���̎��Ö@���ď���肷��̂��܂��A����q�ł��B���̋ꂵ�݂͂�قǂ̂��Ƃ�������ł��ˁB�����ɂ́A���X�A����g�̐l�ԂƂ��Đ����Ȃ���A���Ƃ�����ΓI�Ȕ�����ڎw���A�����C�s�҂����̂���̂܂܂̗l�q���f���o����Ă���悤�Ɏv���܂��B�����ʂ�A�ォ�牺�܂ŁA�l�Ԉ�l�A�܂邲�ƕ�ݍ��ޕ����̏C�s�����Ƃ������̂��ēx�m�F���Ă݂�̂��d�v��������܂���B�@
 �@
�@�����͂���̂��̂�
�����āA���߉ޗl�����̗�ɂ��ꂸ�A�����̉��ŁA�����Ƃ����A���E�ɗ���݂Ȃ������I�Ŏ��H�I�ȏ@���ݏo����܂����B�����炱���A�����͍��ł��A�����̃V���{���Ƃ��āA�����镧�����Ő��q����Ă���̂ł��B�@
���߉ޗl�́A�����������J������A���̑̌��𑼂̐l�����ɂ������āA���Ɍ��̊�т������������ƍl���āA�z���̗��ɏo�����܂����B�ŏ��̕z���̑���́A�x�i���X�̋߂����쉑�ɂ����ܐl�̏C�s�҂����ł����B�����鏉�]�@�ւł��B���̌�������̐l���������X�ƒ�q�ɂȂ�A�����m�c�͋}���Ɋg�債�Ă����܂��B�@
�������A���̂悤�Ȕ��W���ɂ����Ă��A�����C�s�҂̏Z�݂��́A���ς�炸�̉��ł����B�����̑m�c�̗l�q��`���Ă݂��Ȃ�A�X�̒��ɓ_�݂���傫�Ȗ̉��ŁA�O�X�܁X�A�ґz�ɐ�O�����u�����̎p�����������Ƃł��傤�B�����Ă����ɂ́A���@�Ƃ������݂̂͂�����܂���B���߉ޗl���z�����n�߂�����̂��̍��A�C�s�҂��Z�܂����߂̏Z���A�܂莛�@�Ƃ������̂͂܂����݂��Ȃ������̂ł��B�@
�����̌����́A��̐��Y�������~���āA���ׂẴG�l���M�[���C�s�ɒ����Ƃ����_�ɂ���܂�����A���X�̐��������͂��ׂĈ�ʎЉ��̕z�{�ɂ���Ă܂��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���̐��������̒��ł��A�ł������ł��������Ȃ̂́A�s���Y�܂�A�y�n�ƁA���̏�Ɍ����̌����ł��B���Y���������Ȃ��C�s�҂������A�����̗͂Ŏ��̕~�n����ɓ���A�����Ɏ��@���������邱�ƂȂǂł���͂�������܂���B����͂��ׂāA��ʎЉ�̐M�҂���̊�i�ɗ����Ă����̂ł��B�@
���̋L�^�ɂ��܂��ƁA���߉ޗl�����߂ĐM�҂����������@�́A�|�ѐ��ɂƂ������̑m�@�ł����B�L���ȏꏊ�ł��ˁB��i�����̂̓}�K�_���r���r�T�[�����ł��B���l�����炱���A�L��ȓy�n�ƁA���h�Ȍ������ՁX�Ɗ�i���邱�Ƃ��ł����̂ł��B�@
���̒|�ѐ��ɂ�Ƃ��āA���ꂩ��̕����m�c�͐������̑m�@�����L���邱�ƂɂȂ�܂��B��ԗL���Ȃ̂͋_�����ǓƉ��A�����ċ_���ł��ˁB�����̑m�@�͂��ׂāA�M�҂���̊�i�ł��B�܂�A�M�҂������Ō��ĂāA��������̂܂܁A�����m�c�Ɋ�t����Ƃ����`�ŁA���L����m�c�Ɉڏ�����킯�ł��B���Ă���ł͖��ł��B�@
�u���V�������A������������ŕ�炵�Ă��邤���ɁA������������ł��āA�C�����K�v�ɂȂ�܂����B���̏C���̔�p�͈�̂ǂ�����čH�ʂ�����悢�ł��傤���v�B�@
���ʂɍl����Ȃ�A���̑m�@�͂��łɐM�҂���m�c�ɏ���n���ꂽ���̂ł�����A���L���͑m�c���ɂ���܂��B���������āA���̏C���͑m�c�̐ӔC�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�u��������i�����M�҂���ɁA���̌�̏C���̐ӔC�܂ŕ��킷�͉̂��z�A�C���͂܂��ʂ̐l�����ɂ��肢���悤�v�Ƃ����킯�ł��B�Ƃ��낪�A���@�̏��L���Ɋւ��闥�̋K��������ƁA�Ⴄ���Ƃ������Ă���܂��B����͎��̂悤�Șb�ł��B�@
���鑺�̒��҂��A���[�t�����҂̂��߂ɂ��������ĂĊ�i�����B���[�t������͂����ɂ��炭�Z��ł������A�܂��Ȃ��V�s�̗��ɂłĂ��܂��A���̎��͖��Z�ɂȂ��Ă��܂����B���҂́u���[�t�����҂��܂��A���Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ����A����Ȃ炱�̎���m�c(�T���K)�Ɋ�t���悤�v�ƍl���A����m�c�Ɋ�i���Ȃ������B�Ƃ��낪���ꂩ��Ԃ��Ȃ��A���[�t�����߂��Ă����B�����̎����A���ł͑m�c�̏��L�ƂȂ��Ă��邱�Ƃɋ����āA���߉ޗl(�܂胉�[�t������̂�������)�ɑ��k�����Ƃ���A���߉ޗl�̔����́u�{�傪�A����̐l���w�肵�ĕz�{�������̂��A���Ƃŕʂ̐l�Ƃ��m�c�ɕz�{���Ȃ������ꍇ�A���߂̕z�{�������L���ł����āA��Ԗڂ̕z�{�͖����ƂȂ�v�Ƃ������̂ł������B�܂肱�̎��̓��[�t������̂��̂Ȃ̂ł��B�@
�����Ă���ɑ����Ă��߉ޗl�͎��̂悤�ȏd��Ȃ��Ƃ�錾���܂��B�u�y�n�͉��ɑ�����B��������ь������̔��i�͎{��ɑ�����B�����Ă��ꂪ����{�傪�����ŕ�C���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�@
�ȏオ���̒��̘b�ł��B����͂ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA�{�傪�����Ŏ������ĂāA����̂��V����Ȃ�A�m�c�Ȃ�֊�i�����ꍇ�ł��A���̖{���̏��L���͂����Ǝ{��̑��ɂ����āA�V�����́A�����������ďZ��ł��邾���Ȃ̂ł��B�܂�؉Ƃł��ˁB�ł����炻�ꂪ����A�{���̏��L�҂ł���{�傪�A����ŏC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B�V�����͂�����ďZ��ł��邾���ł�����A�����Œ����K�v�͂���܂��A���̂����A���@�̐^�̏��L�҂ɂȂ邱�Ƃ͂ł��܂���B�����āA�ƒ���˂Ȃ�܂���B���̉ƒ��Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ����ƁA����������̂ł͂Ȃ��āA�V����Ƃ��Ă̐��炩�ō����Ȑ�������X���邱�ƂȂ̂ł��B�z�{�̉ʕ�Ƃ����̂́A�܂�Ȃ��l�ɕz�{����������h�Ȑl�ɂ����������傫���Ȃ�ƍl�����Ă���̂ŁA�����̕z�{���������ɗ��h�Ȃ��V���Z��ł����A���ꂾ���傫�ȉʕ����邱�ƂɂȂ�܂��B�@
�ł�����A�����ɏZ�ޖV�����炩�Ȑ����𑗂��Ă���Ɓu�����A�悩�����v�Ǝ{��͈��S���܂��B���ꂪ�ƒ��ł��B�܂肨�V�����@�ɏZ�ނ��߂ɂ́A����ɂ݂��������h�Ȑl�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B�@
���̂悤�ɁA���̉�����o�������������A�M�҂���Ƃ̋����̒��ŁA���@�������n�߂�悤�ɂȂ�A���ꂪ���݂̕������E�ɂ܂ő����Ă��Ă��܂��B�����Ɖƒ����Ă��邨�V���������A�����łȂ��l������ł��傤�B�����Ă��Ȃ����V����ɂ͓��K�v��������܂���ˁB�@
 �@
�@���B�҂̌n��
�܂��A��Ƌ��̍���͔��Ί������A���̓y��̒��ɁA�Ȃ܂Ȃ܂������Ђ��U�����ꂽ�B���́u�V�Í��W�v�A�u�S�l���v�̑I�҂ł���V�ˉ̐l�́A���̍����h���������ł���B���ɋ`�����́A����ɂ����ۂ����قǂ̌Ú�ɂ������߂��A�y�Ƃ��Ă݂̂̎p�ł������B���̓y���ق����ƁA�킸���ɍ��Ђ炵�����̂����������A�肩�ł͂Ȃ��B��t�ɂ����Ă͓y�݂̂ł���B����͂܂����Ƃ�����Ȃ��Ƃł���B�ł��Â���Ƌ����y���ł��邽�߂Ɉ⍜�̌`�[���c���A�Α��̋`�����̈⍜�͓y�Ɖ����A�ł��V������t���m�͐��O�̎����ł��邩��A�⍜�͂Ȃ��y����݂̂Ȃ̂ł������B�@
���̖�A�킽���͎��V�ɂ����ĉ����ߑR�Ƃ��Ȃ��v���ɂ������B�݂��ɖ����̎O��ʂ��A�P�ɑ������̕����݂̂ɂ���āA�g�������Ė���̂��B���j�̎����́A���̎O�҂����̊W���Ȃ����Ƃ����Ă���B�������A�������ʂ̎����͂Ȃ��̂��낤���B�Ⴆ���ꂪ�P�Ȃ���R�ł������ɂ���A�O�҂ɋ��ʂ����^��������͂��Ȃ����B���͂Ƃ�����A�O�҂̎��Ղ������ȒP�ɋL���Ă݂悤�B�@
��Ƌ��́A�����M�������̗����������q�����̑�̐l�ł���B�����S������z���������̘Z�j���甭�������Ƃ̖����ɑ��������A�ނ̕��r���̍��ɂ͌����̒n�ʂ���E���������Ȃ܂łɗ����Ԃꂽ�B�������A�r���A��ƕ��q�͉̐l�Ƃ��ďd�p����A�̓��̏@�ƂƂ��Č�̓���A���ɁA���Ƃ̑b�ƂȂ����B�������A����͐V�����m�̑䓪�ɂ��M���̒������ł������B���V�̌N�A�㒹�H�@�͂��̗����̋M�����������ׂ��A�̓����n�߂�����|���Ɍ������グ��B�����āA��Ƌ��́u�V�Í��W�v�Ҏ[�ɂ������āA�܂��ɂ��̌㒹�H�@�̎��X�ȉ���ɋꂵ�߂���B���̂��߁A�u���v�̗��v�̎��s�ɂ���Č㒹�H�@���B��ɗ������ƁA��Ƌ��͂����܂��㒹�H�@�̋w�G�k���ƂƉ��ʂ����сA���{���̐������Ƃ���Ȃ��}���A�k�R��������(��̋��t��)�ɂ����Ώo���肷��܂łɂȂ�B�����Ă��ɐ���ʌ���[���̈ʂɓo��߂�B���̌����ȗ���s�ׂ̐^�ӂ́A���炭��q���Ƃ̖��啜�A�Ɖ̓��@�Ƃ̖n��ɂ������낤�B�@
�������㏫�R�`�����́A���`�����Ëg�̗��ňÎE����A�Z�`�����a�v�������߁A�킸�����ŏ��R�ƂȂ����߉^�̐l�ł���B�������{�͎O��`���_�Ƃ��Ď���ɐ��ނ��Ă䂫�A�������y�Ꝅ���p�����闐�����}���悤�Ƃ��Ă����B���̂��߂₪�ċ`�����͐����Ɍ��C�������A���R�̖��߂𓊂������Ă��܂��B���ꂱ�����A���R��p���ɒ[�����u���m�̗��v�u���̈������ł������B�����ɔw���������`�����́A�嗐�̂Ȃ����R�ɎR���c���A�Ђ������̐��E�ɖ��v���Ă䂭�B�����ċ`�����̊�ɂ݂�R����Ƒ��܂��āA��Ɂu���R�����v�Ƃ����啶���T�������`�����ꂽ�̂ł���B�@
��t���m�Ƃ́A���A���q�я��H�̐��≮��l�E�e�������q��̉捆�ł���B�O��҂��A����̒��S�ɂ����ė��j�̉Q�ɖ|�M���ꂽ�̂Ƃ͈قȂ�A�ނ͂��������̒��G�t�A�����Ă͐��G�t�ł���Ȃ������B�������A�L���Ȓ��O�ł������ނ́A�Ɠ�����ɏ����ĉB����������A�O���̉Ƃ������I�X�Ɖ��ɗ�ނ��Ƃ��ł����B�����Ă��̍�i�́u�����l�����v�ɍڂ�قǐ��ɔF�߂�ꂽ���̂ł������B���Ȃ݂ɁA�����ł́u�����A��t�A�����v�ƕ��я̂���Ă���B�܂����������u�O���薭�ʐ_�v�Ə^�����قǂ̒���Z�I�̎�����ł��������B�ނ͑������̑�T�T�t�Ɛe�������сA��t�����O�Ɍ��Ă������ɂ́A�T�t�̐�����܂�Ă���B�@
�ȏ�O�҂̎��Ղ��ȒP�ɋL���Ă܂��C�Â����Ƃ́A���Ɍ|�p�����̐l�ł������Ƃ������Ƃł���B��Ƌ��͉̐l�A�`�����͑�p�g�����A��t���m�͉�Ƃł���B�������A�킽���͂����������Տ�̋��ʍ��ɂ��܂�Ӗ������������Ȃ������B�ނ���A�ނ�̓��ʂɉ������ʂ������̂͂Ȃ����A�v�Ă����̂ł���B�@
�R�{���g�́u�ÓT�ƌ��㕶�w�v�ŁA�܌��M�v�̐��Ƃ��āu�B�҂ɂ͎O��ނ�����B��ɂ́A�����̐g���̎҂ʼnB������������ҁA��́A�����̑m���A�����čŌ�ɁA���ɊK���̒Ⴂ�B�҂ł���v�Əq�ׂĂ���B�����ɂ킽���͈�̃q���g���B�܂�A�u�����̐g���̎҂ʼnB������������ҁv�Ƃ������ʍ��̔����ł���B��Ƌ��͖���M���Ƃ��āA�`�����͏��R�Ƃ��āA�����Ď�t���m�͗T���Ȓ��O�Ƃ��ẲB�Ҏ�ł���B�@
�u�����̐g���ʼnB�ҁv�ƂȂ�̂́A�����Ɍl�I�B�Ҏ�ɂ��̂ł͂Ȃ��B�����ɂ͋���ȁu���v�̎��㐸�_�������Ă���B����́A���j�I�K�R�����ł͕ЂÂ��ʁu���̐S�v�ł�����B�@
�㒹�H�@�����߂ɂȂ��āA��Ƌ��͓Ɨ͂Łu�V����W�v��Ҏ[����h�_�ɗ����邪�A�ߐl�㒹�H�@��̉̕S�]������Ƃ�悤��������B�̓��̏@�ƂƂ��āA���S�ɑI�G�̂ɍĂѐ����I�������������̂ł���B�u�V�Í��v�Ɏ������S�Ȕs�k�������B�@
�ӔN�A��Ƌ��͍��㏬�q�R�R���Ŏ���u���q�S�l���v��҂ށB����́A�㒹�H�@�ւ̂܂�����Ȃ������ł������B�Ȃ��Ȃ炻���S��̉̂ɂ͓V�c(�z���A�O���A����)�M��(����⹁A���Z�A���ƕ��A�������^)���A�߉^�̍Ŋ��𑗂����l�X�̍삪�Z�߂��A�������Ō�̓��͌㒹�H�@�Ƃ��̎q�����@(���n����)�̉��O�̉̂ł������B�@
���q�R�̉B�Ғ�Ƌ��́A�u�S�l���v�̕Ҏ[�ɂ���Đ��s�A���D�A�m�ԂƑ����B�҂̕��w�̑b�Ƃ��Ȃ����̂ł���B�@
�`�����́u���R�����v���܂��A�B�҂̕����ł������B�ނ͐��U�A���R�a�̑��z�ɂ�����葱���A����ƂĂ��ɖ����ɏI������̂������B���l�Ƃ��Ă̍��܂ƌǓƂ��A���z�E�����Ƃ����u�l�H�̊y���v�ɕϊ������B���̊y���̊O�A�����̐��͋Q��Ɛ헐�ɋꂵ�ޖ������̒n���ł��������B�l�H�̊y���ɂ͌������~���G�l���M�[�͖]�ނׂ����Ȃ��������A���捜�������ӂ�A�l�ނ����ӂ�A����ɂ����{�����̍ō���Ƃ����u���R�����v���`�����ꂽ�B����͂₪�āu��сA���сv�Ƃ����B�ҕ����̒ꗬ�ɂȂ�B�@
��t���m�͐����̉B�҂������B�ނ͑O��҂̂悤�Ɍ��l�Ƃ��Ă̍��܂���B�ق����̂ł͂Ȃ��B�V�ˉ�Ƃ��A���܂����ƂƂ�����Ⴂ�Ȑ��E�ɐ��܂ꂽ�ɂ����Ȃ��B������A�ނ̊G��͕K�������B�҂̕��ł͂Ȃ��B�ނ���A�ؗ�ȁu���A�\�G�v�́u��сA���сv�Ƃ������g�[���Ƃ͖����ł���B�������A�킽���͎�t��ُ̈�Ȃ܂ł̍ז��`�ʂɁA�������āu�B�ҁv�̓�����������̂ł���B�ނ��ƋƂ�����A��Ƃɐ�O�������Ƃُ͈�ł����ł��Ȃ��B�ނ���ނ͂��܂�ɕ��}�Ȑ����҂������B�������A���̕��}�Ȑ����҂�����قǂ܂łɁu�ז��v�ɖ��v����Ƃ��A�킽���͉B�҂Ƃ��Ă̋��C��������B�����Ɍ������牓������Â��ȋ��C�ł���B�@
��������n�̈��ɁA�����̎O�҂�����Ƃ����ꎖ����A���X�Ǝv����y�����B�����ĎO�҂Ɂu�B�҂̌n���v�������B�ǂ���炱���̋��R�́A�킽���ɓ��{�����̈�̌^�������Ă��ꂽ�悤���B�܂�A���j�̕��̕����ɂ����[�����_�������Ƃ������{�����Ɠ��̌^�ł���B�@
 �@
�@���_�Ђ��ĉ����낤�H
�����ނ������b�͕ʂƂ��āA�킽���̐��܂������Ƃ͓��������̏H�t�_�Ђ̋����ɂ������B��Ƃ������̐_��ŁA����o�̑�w�����������B���h�ȂЂƂŁA�q���Ȃ���_�E�Ƃ������̂̕s�v�c�ȕ��͋C�Ɋ���e����ł����B�������A������Ƃ����Đ_����_�Ђɂ킽���͂��܂��ɋ������Ȃ��B���̍ő�̗��R�͐_�����ǂ��܂ŏ@�����A�悭������Ȃ����炾�B���o�I�ɂ����Ȃ�A�ɐ���o�_�̂��̎Гa���z�������Ƃ��ʔ����Ȃ��̂ł���B�A�b�P���J���Ƃ��Ă��Č��ǂ��낪�悭������Ȃ��B����ɓ��{�����A�_�Ђ͌����ɋy���������K�܂Ŋ܂߂�Ɩ����̐_�l�̔×��A�������ŗL��݂��Ȃ��B�J�h�̃^�o�R���Ȃ݂ɓ���ɖ��v���Ă��āA�킴�킴�u�_�̓��v�Ȃ���̂̐��_����������C���N���Ȃ��B�����Ƃ����Ȃ�_�Ђ̏������A���O�⍥��Ȃǂ̖ڏo�x���Â����ŁA�������ɊJ�^�E�Ɠ����S�E��ʈ��S�E�w�Ɛ��A�E�������A�E�a�C�����ƌ������v���j���[�̃I���p���[�h���B�����܂ŗz�̃v���X�u���ŁA���o�̈Â����Ȃ��B�a��⎀�͉A���q�ꂾ����Ђ������P�����߂�̂ł���B�^�����ȃ��C�V���c�ɂ�����Ƃł��V�~�����Ƃ���ĂăN���[�j���O�ɏo�����z���B���{�l�̐����D���A����D���͂���ȂƂ��납�炭��̂��낤���B�u���߁v���傽��v�z�Ƃ����@���͂���������قł���B�@
�����A�ŋ߂�����ƍl����ς��镶�͂ɏo������B�@
�i�n�ɑ��Y�u���̍��̂������v�́u�_��(1)�v�ɁA�_���ɁA���c�����`���Ȃ��B���Ƃ����̓��X�ɂ����Ñ�l�����́A�n�ʂɊ���o������̘I���ЂƂɂ���(����)�֍�(�����)�̑傫�����������A��ق��������B����o��������A���̂܂��𐴂߁A�݂���ɑ��ݓ���Ă������ʂ悤�ɂ����B���ꂪ�A�_���������B�ނ��A�Гa�͕K�v�Ƃ��Ȃ��B�Гa�́A�͂邩�Ȍ㐢�A�������`����Ă���ƁA��������K���Ăł������ł���(�i���ȗ�)�B�@
�Ƃ���B�@
�����łӂ��̂��Ƃ��A�킽���ɂ͔[���ł����̂ł���B���߂�Ƃ́A�������̈Â����́A�A�Ȃ���̂̔r���ł͂Ȃ��u�،h�v�̂����Ƃ��f�p�Ŏ��R�ȍs�ׂ��Ƃ������ƁB���܂ЂƂ͎Гa���z�̃A�b�P���J���́A���Ƃ��Ɨv��Ȃ����̂�v��悤�ɂ������߂̃A�b�P���J���Ȃ̂��Ƃ������Ƃł���B�������@�̃}�j�A�b�N�ȑs�킳�Ƃ�������ƑΛ�����ȑf�n�u�����ƒm�ꂽ�B�@
�@����ɓ����͂����B�u�����Ō����Ă����˂Ȃ�Ȃ����A�Ð_���ɂ́A�_���猻���̗����˂���Ƃ����������v�̔ڂ����͂Ȃ������v�ƁB�����ɂ����āA�킽���̓n�^�ƕG��ł����B�_���Ƃ́A�ߑ㎩��̕���Ƌ�Y��O��Ƃ����~�ώv�z�Ƃ��Ă̏@���Ƃ͂܂������W���Ȃ��B����Ȃ��̂͐_�����猩��ǂ�ȑ�v�z�ł��낤�Ɩ����̏�h��ɂ����Ȃ��B����ɂ͐l�Ԃ��K���ɐ����邽�߂̎�O����Ȏ����ǂȂǂ��܂�������������m��ʐ��E���Ƃ������Ƃ��B�@
�{���́u�_�Ȃ���̓��v�Ƃ́A�厩�R�̕s�v�c���ւ̑f�p�ȋ����ł���A�����ɐ����̖{�������āA�l�Ԃ̋������A���������炻�����邽�߂ɓ꒣�肵���A���̋���_���Ƃ����̂ł���B����͎v�z�Ƃ������Ƃ��ł͂Ȃ������̋n�ւ̋��D�ł���B��������͉����Ȃ��Ƃ��������ւ̓���Ȃ̂��B�@
��������o������悤�ɁA��|���Ȃǂő����K���J����Ƃ��ْ̋��ɔ����A�J�������̒��ɂ͐_�l�̖������������D�ꖇ�������������ŁA�������肷��̂ł���B�������A�������_��̋Ȃ̂��B�@
�ɐ��_�{�̐_�̂͌䍰��(�݂��܂���)�̔��@��(�₽�̂�����)�����A���ꂪ�ǂ����������܂������`����Ă��Ȃ��B���Ƃ������͎̂p���������f��������A���Ƃ������S�����ɉf���Ă��Ă����̂Ȃ��Ƀ����S�Ƃ������̂�����킯�ł͂Ȃ��B�Ȃ̂ł���B�ނ�̏@���I�Ӗ������ƂȂ�Ζ���⑾�z�M�ƌ��т��čl���˂Ȃ�Ȃ��B������ɂ���Ŏ��̂̂Ȃ��u���v�Ƃ������̂�����̏ے��ɂȂ��Ă���̂��B�Ƃ���Ȃ�A�_���K���ɂ����đ�敧���́u��v�̎v�z�Ɛ_���́u��Ȃ�_��v�̍l�������Ƃ͈ĊO�������肢�����̂�������Ȃ��A�Ə���Ɏv�����̂ł���B�������{�l�͑嗤�`���̕������ނ�������v�z�Ƃ��Ď��ꂽ�̂ł͂Ȃ��A���썑�Ƃ◈���v�z�Ƃ��Ď��ꂽ�̂�����A�n�߂���_�������ǂ��K�������̂ł͂Ȃ����Ƃ͊m���ł���B�ɂ�������炸�A�����̋�v�z�����Ԃ�ɏ�I�Ȗ���ςƂ��Ăł͂��邪�A���{�����ɒ蒅�������̂́A�ɐ��_�{�͂��Ƃ�葺�̐_�Ђ����ł�����T������X�̂Ȃ��̖���݂Ƃ��āA����ꂪ�Ȃ���ł�������ł͂Ȃ��낤���B����_�������邱�Ƃ̓M���V���̃A���[�e�B�A(�^���̂����炳��)�Ȃǂɂ������邪�A���Ƃ���]���ԋ�Ԃ̔��w�Ƃ��Ă̓��{�l�̔��ӎ��́A�_�Ђ̐_��Ȃǂɂ��̎n�������邱�Ƃ��ł���̂�������Ȃ��B�@
�����Ȃ�ƎГa���z������_�������Б��̃A�b�P���J���Ƃ����܂�Ȃ��Ƃ́A���͂���߂ĖL���Ő[���Ӗ��������������l���ł���悤�Ɏv���Ă���B���Ƃ��Έɐ��_�{�̎��N�J�{�ɂ܂�鏔�s���̌o�ϓI�A�����I�c�傳�͈��|�I�Ȃ��̂��B�S���\�l�̋{��H�A����O�S�N�̖ؑ]�q�m�L�ꖜ�{�ȏ�A�V�����鑕���E�_���ܕS�_�A���H��O�S���~�Ƃ����K�͂ł���B����Ȃ��Ƃ�_���Ȃ���̂��߂ɓ�\�N���Ƃɐ�N�ȏ���s�Ȃ��Ă��Ă���̂����A�J�{�̒��S������{���a�͂킸���\���̌��z�����B���Ƃ������̂̏d�݂Ɛ[����Ɋ�����̂ł���B�@
�i�n�ɑ��Y�͈ɐ��_�{��K�ꂽ�����ɕʋ{�ł���ꌴ�{�ɂ�������肱���L���Ă���B�@
���������ꌴ�ɂ����锒���͌�����ʂɕ~���ꂽ�ꏊ�́A���͑J�{�̂���������Ƃ̕~�n�Ȃ̂ł���B�������A�Ȃ܂����Гa����������A�ȑO�����ɎГa������A��������͎Гa�����Ă��閳�̂悤�Ȃ��̋�Ւn�ɂ����A�Ð_���̐_��������������B�@
�ɐ��_�{�͔N�Ԑ�Z�S���̍�s��������Ƃ����B�Ȃ����W���[����������́u���ɐ��Q��v�ɂƂ��Ă܂����������̂��ƂȂ���A�_�Ƃ����ڂɌ����Ȃ����̂Ɏd����_�E�����̑�^�ʖڂȎp���v���ƁA����ƐS�����܂�̂͂킽�������ł͂���܂��B����ɖ��v�����_�Ђ̂������܂�����A��u�ł��u��Ȃ���́v�̓�������������Ǝv���̂ł���B�@
 �@
�@����Ղ��ς�
���ẮA�ޗǂւł�����ɂ͂Ȃɂ������̐S�̏�����K�v�Ƃ����B���s���Ȃǂł͗��\�ɂ��ޗǁE���s�͂ЂƂ�����ɂ���邪�A����s�s�Ƃ��Ă̕��e�����j�I�������܂������Ⴄ���̂ł��邩��A�ӎ��̂����ł͓ޗǍs���͂�����Ƃ��������s�������B�@
���������ʐ����J�ʂ������܁A�킽���͗ג��ւł�����قǂ̋C�₷���ŁA���ꂱ����肩���̎d�������̂܂܂ɂ��Ăł��ޗǂ֍s�����Ƃ��ł���B���s����ޗǂւ͒P�Ɂu���o��w�v����u�ߓS�ޗljw�v�ւƂ����A�_����_�ւ̈ړ��ɉ߂��Ȃ��Ȃ����B�@
����Ȃ킯�ŁA��N�̕��A�ޗǍ��������قŁu��Ր��G�v�W���J�Â����ƒm���A���̐g���̂܂ܒn���S�ɔ�я�����B�u��Ր��G�v�͂킽���ɂƂ��āA���U���邱�Ƃ��Ȃ�ʂƂ�����߂Ă����K�����̕K�������ł���B�@
���̂킯�́A�u��Ր��G�v���P�Ȃ鎞�@�J�c��Տ�l�̍s��G���ł͂Ȃ�����ł���B�u���G�v�����́A���̋ɖk��Y������j�́A��Ȃ܂ł̃h�L�������^���[�ł���A�r���Ƃ����R�͂ɋ����킽��ǓƎ҂̋��т�����ł���B���̓����́A��O�̔M�����������˂��j��A�l�Ԃ̍����I�₢�����ւƏ��������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B�@
�����A�킽���̎v������ɔ����āA�u���G�v�͂��܂�ɐÎ�ɕ�܂ꂽ�G��ł������B���̈ٗl�Ȃ܂ł̐Â����͂ǂ����痈��̂ł��낤���B�@
�����ɂ���킸�A����̗����ČǓƓƈ�Ȃ���A������Ƃ͂����Ȃ�B���������ЂƂ�Ȃ�A��������ƂȂ�B�@
���̌��肠�鐶���̂��▽���邱�Ƃ����Ƃ����̂ł͂Ȃ��B��ՂɂƂ��Ď��Ƃ́u�ǓƓƈ�v�Ȃ邱�Ƃ������B�ώG�Ȑ��̎������̂ĂāA�ƈ�ł��邱�Ƃ����ł���B���̊o��Ɛ[�����@���u�ǓƁv�Ȃ̂ł���B�@
�ߑ㎩��ɂƂ��ČǓƂƂ́A�s���Ɛ�]�̎�v���ł������B��������ՂɂƂ��ČǓƂƂ͐��̖{���ł���A�ƈ�Ƃ�����Ύ�̐��ł���B�����ցA�����������ϔY����荞�܂�邩��A�l�Ԃ̋~�����������̉c�݂͑��u���̗̈�v�Ȃ̂ł���B�@
�������閽������ɕ��̌䖽�A���ʂ邢�̂�������ɕ��̌䖽�Ȃ�B�@
�����Łu���ʂ邢�̂��v�Ƃ������Ƃ��A�u���G�v�����������ڂł���ƒm���B���̍���G�������|�I�Ɏx�z����ٗl�ȐÎ₱���́A�u���ʂ邢�̂��v�ł������B�@
����ł͈�Ղɂ����āu���ʂ邢�̂��v�Ƃ��Ă̈���ɕ��Ƃ͉��ł������̂��B�߉ނł��ω��ł�����@���ł��Ȃ������͉̂��̂Ȃ̂��B�@
�T�ɂ�����߉ޔ@���A�����ɂ��������@������Ղ́u���̗̈�v�Ƃ����Ȃ�A�u���G�v�͑��݂����Ȃ������Ƃ킽���݂͂�B��Ղɂ����Ă͂ǂ����Ă�����ɕ��łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B���Ȃ킿�A�����ɂ́u�Y���v�Ƃ������Ƃ��ւ���Ă���̂ł���B�u�V�s�v�Ƃ������Ƃ��ǂ����Ă��ւ���Ă���B���؏��O�͈�Ղ��u�G�X���Ƃ��ėV�s����O���v�ƂƂ炦�m�Ԃ́u�y�݁v�ɔ䂵�Ă��邪�A�V�s�͕K������������̗V�Y�O���ł͂Ȃ��B���̔w��ɖ쐂�ꎀ�ɂƂ����s��Ȃ܂ł̊o�傪���邩��ł���B����͂����܂ŕ����̍s�ł����āA���Ƃ��x�O���Ƃ����ǂ��y�����̋����~�x��Ƃ͈�����悷���̂ł���B���Ȃ킿�y���Ƃ����y�n�ւ̎������犮�S�ɓƗ����Ă���̂ł����āA���̓_�͈�Ղɂ���Ė��m�ɏs�ʂ���Ă����B����͌�ɕY���V�s����l�X���O�A�y�n�Ɛ��ƂƉƒ�����M�҂������O�ƕ��������Ƃ�����m���B�@
�ł́A��Ղ̕Y���V�s�Ƃ͔O���̋������L�߂邽�߂̋����̗��ł������̂��B���������Ȃ�A�e�a����@�̉����̗��ƕς��ʂ��ƂɂȂ낤�B�ނ����Ղ͂����܂Łu�̂Đ��v�ł����āA�����Ƃ������@�c�߂��������͊ł������B�u�̂ĂĂ����v�Ƃ������̈�O���A��ӏ��ɒ�Z���邱�Ƃ������Ȃ������B��Z�͎����ł���Ƃ����l�Ԃ̎~�݂������h�����A��Ղ݂͂Ă����B�l���̍����͖쎁�̏o�g�ł����Ղ́A�킢�s��ė��U���y�n���������ꑰ�̔߈������g�ɂ��݂đ̌����Ă����B���Ȃ킿���ꂱ���͒����I�Ȓn�������̋���Ȏ���̂ЂƂł���A���̂��Ƃɍł��ꂵ�ЂƂ������B����l�́u�g����v�Ƃ���������Ȏ���ł͂Ȃ��A�������Ŏ̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��y���̎���ł������B�@
�u�̂ĂĂ����v�Ƃ́A�u�̂ĂĂ����~��������v�Ƃ��u�̂ĂĂ��������Ԑ�������v�Ƃ������������̏������̌��t�ł͒f���ĂȂ��B�u�̂ĂĂ����v���̂��̂ł���B�S���݂��u�̂ĂĂ����v�Ȃ̂ł���B�����Y���V�s�Ƃ����̂��B�����ĕY���V�s�ɂ͎����������C�s������s�v�ł������B�����ɂ͐ԗ��X�Ȑ��̖{�������������āA�ߐH�Z�͂��肬��܂Ő�l�߂���B�����Đ��̏́A�O���Ƃ����������ЂƂ̍��̐������ɂȂ��Ă��܂��B�@
�O�����A�x��A�Y���������邱�Ƃ������u���ʂ邢�̂��v�̏Ȃ̂ł���B����͐l�Ԃ̓y���������䂪���҂�H���j���ċ���u���̂��v�ł͂Ȃ��B�Î�ƈ����Ƃ��Ắu���̂��̂��v�ł���B�@
�u���G�v�̈ٗl�Ȃ܂ł̐Â����́A���̗̈�̐Â����ł������B����͂܂��G���̔w�i���Ȃ��R�͂̐Â����ł��������B���āA����قǂ܂łɃV���ƐÂ܂肩���������i���A�킽���͌������Ƃ��Ȃ��B�������A�_�i�Ƃ��ėV�s�����Ղ�̎p�������������B�ꂷ��B�܂肱�̊G���̎�l���͈�Ղł���Ղ̍s��ł��Ȃ��A�����킸����ۂނ���ɔ������Î�ȎR�͂̂������܂��ł������B�Ƃ���Ȃ�A����ɗ��}�}�̂悤�ɁA�[�l�����ꂽ����ɕ������_�ɂ̂��ĎR�̂��Ȃ��������A�Ƃ�����������̂������̊G��Ƃ́A�u���G�v�͂܂��������������̂Ȃ̂ł���B�u���G�v�̔w�i����R�͂��̂��̂��O���ł���A���̗̈�ł���A�����ɂ����Ɋւ�邢�̂��̏h���Ȃ̂ł���B�܂�́A���̊G���̋��ٓI�������A���̎����I�d�݂́A�@����Ƃ��Ă̋����Ƃ͉����䂩����Ȃ��Ƃ��납�炭��̂ł����āA���l�̍������������獪���̐����������u�Â��Ȃ鋩�сv�Ƃł������������t���Ȃ��̂ł���B�l�q��s�����A��z���߂��炵�ĕ��E��`�����G��͎R�قǂ���B�������A�����̎R�͂����̂܂ܕ��E�ł���G��́u���G�v�������Ăق��ɂȂ��B�u����͖����Ȃ�v�ƈ�Ղ͂����B�̂Ă������g�ɂق��ɂȂɂ����邩�B�����R����삠��A�����Ă����������ʐl�Ԃ̉c�݂�����A������M��������������ՂƂ����������ʂ�߂��Ă䂭�B�@
�u��Տ�l��^�v�ɂ��A��Ղ͗R�ǂ̖@�����t�ɎQ�T��������A�u�ƂȂӂ�Ε��������Ȃ��肯��얳����ɕ��̐����肵�āv�Ǝ��Ȃ̋��U��悵�����u�܂��܂��v�Ɣے肳��A���������A�u�ƂȂӂ�Ε��������Ȃ��肯��얳����ɕ��Ȃނ��݂����v�ƕԂ����Ƃ����B���ł��������b�ł͂���A��Ղ̋��U�Ƃ��Ă͂���ł��܂��s�\�����Ƃ킽���͎v�����A���t�͈�̏Ƃ��ĂƖ��Ă�^�����Ƃ����B��Ղ̔O���Ɂu���t�̏ؖ��v�Ƃ����u�����h���A�͂����ĕK�v�ł��������ǂ����B������ɂ���A�Y���V�s�̐g�ɂ͎�ЁE���ĂƂė]�v�ȉו���������������Ȃ��B�@
 �@
�@���_�ƕ��̂�����
�Ƃ��낪�킽���̕�͔M�S�ȓ��@�@�̒h�k�ł���A�킽�������Z��͖��������������d�̂܂��Ŗ@�،o�������A�������͂����Q����������Ă���(���܂ł��@�،o�̈ꕔ������Ă���)�B�������������킪�Ƃ̏@���I��d����͂������ē��قȂ̂ł͂Ȃ��B�_���K���Ƃ������t�����炼�炵�����炢������܂��̂��Ƃ������B�����炭���{�����̒������������������낤�B�@
�����\�O�N�x�@���N�ӂɂ��Ɛ_���n�M�k������ꉭ���S���l�A�����n�����ܕS���l�ō��v����ƗD�ɓl���Ă��܂��B�܂���{�̑��l������킯�ŁA�_��������̐M�k��d�o�^����ʂł���؋��ƂȂ�B�ނ��_���ƕ����͂܂������َ�̏@��������A���̂��Ƃ́u�C�X�������ƃL���X�g�����d�ɐM���Ă���ЂƁv�Ƃ������炢��قȂ��Ƃ̂͂��ł���B�ǂ����Ă����Ȃ�̂��H�@�Â��ĐV�����^��ɂ�������B�@
�܂��A�_���ƕ����Ƃ��u�@���v�Ƃ������t�ň��ՂɂЂƊ��肷�邱�Ƃ����������̂��A�Ǝv���B�@���Ƃ������̂������ȒP�Ɂu���̋~�ρv�ƂƂ炦�Ă݂�B����ƁA�S�̔Y�݂�l���̋^��Ƃ������d���ۑ����������̂Ɏ��⋳��ɑ��������邱�Ƃ͂����Ă��A�_�Ђւ����Đ_�傳��ɂ�����A�Ƃ����͕̂��������Ƃ��Ȃ��B�܂�_���Ƃ́A�ǂ������̋~�ςƂ͖����̂Ƃ���Ő��藧�����ł���炵���B�@
����A�F�������@���Q�q���铹������F����_�Ђɂ������A�����̐_�傳��̂��b���@��������B���̐_�Ђ͐��E������Y�ɓo�^���ꂽ�M�d�ȍ���Гa��i���Ă���B�Ȃ��M�d���Ƃ����ƁA���̎Гa�͍����̂悤�ɓƗ������q�a�`���ɂȂ�ȑO�́A�q�a�E�Q�a��̌^�̎Гa�Ȃ̂ł���B�܂�M���������̏�ƐM�̏�Ƃꎟ���ő����Ă�������̂Ȃ���ł���炵���B�{���钷�̂����u�_�Ȃ���̓��v�A���{�����ŗL�̎��R�@���Ƃ��Ă̐S�̉��l�ρE���ӎ��̂���悤���܂������Ă�������̂Ȃ���ł���炵���B�@
�Ñ���{�l�́A�V���v�z�̂悤�ȁu���v�̌`����w��̐m�`�����̎v�z�╧���̎��o���������₤�����v�z�Ƃ͖����ł������B����ɂ́u�_���v�Ƃ��đ̌n�����ꂽ�v�z�Ƃ������������B�Ñ���{�l�̏@���Ƃ́A�����̏ꂪ���R�ւ̈،h���q�Ƃ��ď���A�܂��������邱�Ƃ������B�����ɂ͕����ߑ㎩��ɂ��G�S�C�Y���͑��݂����A����ɂ̓L���X�g���̂悤�Ȑ_�ւ̐�Ε��]�ƐR���Ƃ���������ȃh�O�}�����肦�Ȃ������B�������������Ɂu�_�Ȃ���v�Ȃ̂ł���B����́u���v�ł���Ȃ��B���������̈ꌩ�Ƃ炦�悤�̂Ȃ����}�g�S�R���́A�E�����E�����E�L���X�g���̊O����̏P���ɂ���ăR�e�R�e�Ɂu�v�z�Ƃ��Ă̐_���v�ɉ�����������Ȃ������炵���B�@
�������ɂ������Đ_�̈˂肵��Ƃ��Ă��K(�ق���)��(�₵��)�܂ł������Ɛ_���̑g�D�I�����ɑg�݂��܂�A�u�_�C�R�[���V�c�v���ɍĕ҂����ɋy��ŁA�_���͋ߑ�ȍ~���S�ɏ@���Ƃ��Ă̗v�f������Ă��܂����B���Ƃ����ɍ��Ɛ_���Ƃ����S��͏��ł��Ă��A�_�Ђ̂������܂��͐����K���Ƃ��Ă̔N���s���A�F�菊�A������Y�Ƃ��Ă̂ݐ����c���Ă���ɂ����Ȃ��B�����A�ł���B���{�l�ɂƂ��Đ_�ƕ��̂������́A����قlj������̂Ȃ̂��B�@
�ɐ��_�{��o�_��Ђ��Q�q���Ă��A�Ȃ��@���I�������������Ȃ������̓��{�l�Ƃ������̂��A�t���I�ɂ����ЂƂ́u�_�Ȃ���̓��v�̊��������p�ł���̂�������Ȃ��B�@
���Ƃ��ΐ_�O�����E�{�Q��E���O�E�\�O�Q��Ƃ�������A�̗���͐l�Ԃ̐����ɂ������u�S�̂������v�Ƃ��ē��{�l���|���Ă������̂ł���A���̂������̐[���ɐ��ނ������������̂����͐_�Ȃ���Ƃ������ӎ��̈����ł��낤�B�����P�ɖ������K�Ƃ��Ă����Â���킯�ɂ͂����܂��B����ƁA���̖��ӎ����䂦�ɍĔF����ӂ��Ă���������{�̐��_���i�̂䂪�݂ƕn�����A�������āu�_���v�ւ̕s�G�����ۗ�������̂ł���B�G��ʐ_���M��Ȃ��ł͂Ȃ��āA����炢�G��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����������ւ̖��ӎ����A�ۗ��̂ł���B����Ɓu�_���K���v�Ƃ������{�l�Ǝ��̏@�����o�́A�_�ƕ��̗ǂ��Ƃ����ł͂Ȃ��A�_�������挱�I�Ȉ����̏�Ƃ��ĂƂ炦�A�����ĕ���������K�v���Ȃ���������ł͂Ȃ��낤���B�@�������Ƃ��Ă͐��Ɩ��قǂ��Ⴄ�_���́A���{�l�̓���̉c�݂̂Ȃ��ł͖��ӎ����ɒ������āA���������ꐫ�̂����炷��̈����̂悤�ɂ͂��炫�A���Ƃ���ɂ����炤���̂ł͂Ȃ������B����͌�����{�l�̖��@���△�ߑ��ƈꖬ�ʂ�����̂ł͂���ɂ���A�S�₨�P���͐���@�g�̊T�O�Ɠ��ꎋ����A��_�̂ƌ�{���͌`�̈Ⴂ�����ł���A�������傭�u�Ў��v�Ƃ����ЂƊ���̐���Ƃ��Ď��܂��Ă��܂��̂ł���B�_�ƕ��̂������͈ӊO�Ɓu�����ċ߂��v�����Ȃ̂ł���B�@
�Ȃ�Ȃ�����_�Ȃ���̓��Ƃ����A�v�z���肦�ʐS�̂��������������ɏ[���Ȏ���������̍r�p�������_���y�ɖK��Ă���Ƃ����悤�B�@
�u�v�z���肦�ʐS�̂������v���Ƃ��������Ă��悢��������Ȃ��B�C���̏o��������O�̒��߂ɂ���Ĕ��ꂷ��Ƃ����A�������ꂾ���̂��Ƃɂ�������ʐ����͂���������B���t���Ӗ������ȑO�̉��݂̂̐��E�ł���B�����͉��ɂł��������Ӗ���t�����邪�A���t����Ƃ͂���𑼂̌Q�ꂩ��d������Đl�Ԃ̑��֓��肷�邱�Ƃ��B���̏u�ԁA�_���͐l�Ԃ̓s���ɂ���������ɑ���B���c���^���_�i�҂ƂȂ��̓��ł���B�@
����́A�_���ɂ����ẮA�����ɂ����Ă͎��^���ɂ�����Ƃ����悤�B����ɂ����������Ӗ��Ȃ�����́A�_���s���̃o�b�N�~���[�W�b�N�ɉ߂��Ȃ��Ȃ�A��������̂���ŕ��������̂��̂ƂȂ����B����ł悢�ƁA�킽���͎v���B�Ӗ��Ȃ����E�Ƃ́A����l�̈Ӗ��t���A���l�t���̕a����̉���ł��낤�B�͂邩�Ñォ�瑱���_�Ȃ���̓��Ƃ́A�����炩�ŁA���邪�܂܂ŁA�����Ď��Ȏ咣���Ȃ��S�̓������ł���B���{�����̂����̖��邳�������ɒʂ���̂ł���B�_�ƕ��́u�����ċ߂��v�������ł���B�@
�����̉F����_�ЎQ�q�̂���A�_�傳�����ɂ��P�������Ă���邱�ƂɂȂ����B�@
�A��̗F�l���킭�u�V���_����̂��P�����āA�ǂ낵���납�H�v�B�킽���͖ق��Ĕ����邾���������B�@
 �@
�@���̐��E
�@���̑傫�ȖړI�̈�����̋~�ςł���Ƃ���Ȃ�A�͂���ɑ傫���ւ���Ă���B�����̐��E�ςł́A�l�̍��i���܂����j�ɂ́u���i����j�v�Ɓu鮁i�͂��j�v������Ƃ����B�l�����ʂƁA���i����j�͓V�ɏ���A鮁i�͂��j�͒n�ɐ��i�����j��B�����āA�q������c���J��V�����s���A�V�ƒn���炻�ꂼ��߂��Ă��čĐ�����ƍl�����Ă���B�@
�����l�ɂƂ��čő�̕s���́A�q�����r�₦�Ă��܂����Ƃł���B�Ȃ��Ȃ�A�����q�����r�₦�A��c�ł��鎩�����J��V����s���Ă���Ȃ��Ƃ�����A�킪���i����j��鮁i�͂��j�͕����܂܂��܂悢�A�i���ɍĐ��ł��Ȃ�����ł���B�{���̈Ӗ��Ŏ����͎���ł��܂��̂ł���B�@
�Ȃ�A�ǂ����ׂ����B�V���̗�����Ȃ����Ă��܂��A���̂悤�Ȏ��Ԃ𖢑R�ɖh����ƍl�����̂��B�l�X���݂ȍK���ɕ�炵�Ă���A�Ƃ��₦��Ƃ����s�K�Ȏ��Ԃ��N���Ȃ��ƍl�����̂ł���B�����Ŏł́A�������d���B�������������s���邱�Ƃɂ���āA���҂݂̂Ȃ炸���҂����~����Ƃ����̂��̎v�z�ł������B�@
�u��v�Ƃ��������ɂ��̎v�z�����߂��Ă���B�㊿�̋��T�����������w���������x�͍ł����Ђ��镶���̉�����Ƃ����B����ɂ��ƁA��Ƃ́u�_�Ȃ�B�p�m�̏̂Ȃ�v�Ƃ���A�_�a�Ȃ��Ƃ����̈Ӗ��ł���Ƃ����B�u���v�ɑ���u���v�̂悤�Ȃ��̂��낤�B�@
�܂��A�A���J�������������Ă���A�J�ɔG���́u�G�v�Ƃ������Ɏ��Ă���B���̕����w�ҁE�i�ʍفi���傭�����j�́A�A���J�������̉��́u���v�͉��ɐ��ꂽ�q�Q�ł���Ƃ����B�������q�Q�͂��킲�킵�āA���������ɂԂ���B����A�J�ɔG�ꂽ�q�Q�͏_�炩���X���[�Y�ł���A����āu��v�Ƃ͐l�Ԃ��Љ�ŃX���[�Y�ɐ������鋳���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B�@
���@���ł��邱�Ƃ̗��R�͂܂�����B�����N�w�҂ŁA�����̑��l�҂Ƃ��Ēm������n�M�s���ɂ��A�@���Ƃ́u���Ȃ�тɎ���̐����ҁv�ł���Ƃ����B�l�ԂɂƂ��ċ��ɂ̓�ł��鎀��̐������ł�����̂͏@���������B�����āA�l�݂̂Ȃ炸���̖����̍l����������ɍł��}�b�`�����������ł����Ƃ��A���̖����ɂ����ĐS����x������A���̖����̏@���ɂȂ�̂ł���B�@
�����̏ꍇ�A�������ɍł��������肭��u���Ȃ�тɎ���̐����v�ɐ��������̂��ł���A�̂��Ƃɓo�ꂷ�铹���������B���̂��߁A�⓹���͊������Ɏx������A�����@���Ƃ��Ă̒n�ʂ��̂ł���B�����͊������̎x�����Ȃ��������߁A�����ł͊m����n�ʂ邱�Ƃ��ł����A���ɂ͍����@���ƂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�@
���̎O�̏@���̎����ς����Ă݂�ƁA�����ɂ́u�։��]���v�A�����ɂ́u�s�V�����v�A�ɂ́u�����Đ��v�Ƃ����R���Z�v�g������B�����͐������āu���v�ɂȂ낤�Ƃ���B�����͐�������̉����āu��l�v�ɂȂ낤�Ƃ���B�����āA�͐����Ă���Ƃ��ɂ́A�u���l�v�ɂȂ낤�Ƃ��A����͑c����J�ɂ���Đ��̐��E�ɉ�A����킯�ł���B�@
�c��̍��J�Ǝq���̔ɉh���������d��̐��E�ς́A�u�F�v�Ƃ����ꕶ���ɏW���B�ł́A�u�F�v�Ƃ͉����B�c��͉ߋ��ł���A�q���͖����ł���B���̉ߋ��Ɩ������Ȃ����ԂɌ��݂�����A���̌��݂Ƃ͌����̐e�q�ɂ���ĕ\�����B�e�͏����̑c��ł���A�q�͏����̎q���̏o���_���B������q�̐e�ɑ���W�́A�q���̑c��ɑ���W�ł�����B�@
�����Ŏ͎��̎O�̂��Ƃ�l�Ԃ̖��߂Ƃ��đł��o�����B���́A�c����J�����邱�ƁB���́A�ƒ�ɂ����Ďq���e�������A���h�����ƁB��O�ɁA�q���ꑰ���������ƁB�����āA���̎O�����킹�����̂����A�u�F�v�Ȃ̂ł���B�u�F�v�Ƃ����ƁA�قƂ�ǂ̐l�́A�q�̐e�ɑ����ΓI���]�̓����Ƃ�������������Ă��邪�A�����ł͂Ȃ��A����ł��Ȃ��������̐��ɍĂыA���Ă��邱�Ƃ��ł���Ƃ����u�����Đ��v�̎����ςƌ��т��Đ��܂�Ă����ϔO���u�F�s�v���B���͑S�l�ނɋ��ʂ����s���ł���A���|�ł���B�������A����ɂ���āA�����l�͎��ւ̋��|�����炰���̂��B�@
���n���ɂ��A�����Đ��̑��ړI�́u�ԗ�v�ł���B����O�ɂ��ċ��|�ɋ�����l�ɑ��āA�u�S�z���Ȃ��Ă��A���Ȃ����݂Ȃ��Y�ꂸ�ɕK���Ăэ~�낵�܂��v�Ƃ��������Đ��̖�����Ƃ��A���͕|������ǂ��A����ւ̈��S���͐��܂��B���́u�����Đ��̐����v������̌��t�ɖ|��Ƃ���A�u�S���l�̑z���o�����v�Ƃ������Ƃ��Ɖ��n���͂����B�@
����Ӗ��ł́A�u�F�v������ΐl�͎��ȂȂ��̂ł���B����́A�����������Ƃ��B���̊ϔO�ƌ��т����u�F�v�́A���Ɏ����t�]�����u�����̘A���v�Ƃ����ϔO�ݏo�����B�c����J�Ƃ́A�c��̑��݂��m�F���邱�Ƃł���A�c�悪����Ƃ������Ƃ́A�c�悩�玩���Ɏ���܂Ŋm���ɐ����������Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B�܂��A�����Ƃ����͎̂��ɂ���Ă�ނ��������ł��邯��ǂ��A�����q��������A�����̐����͑������Ă������ƂɂȂ�B�Ƃ���A���ݐ����Ă��鎄�����́A�����̐����̎����������Ă����ƁA�͂邩�ȉߋ��ɂ��A�͂邩�Ȗ����ɂ��A�݂Ȃƈꏏ�ɋ��ɐ����Ă��邱�ƂɂȂ�B�������͌̂ł͂Ȃ���̏W�������Ƃ��āA�ߋ����������A�ꏏ�ɐ�����킯�ł���B���ꂪ�̂����u�F�v�ł���A���݂̌��t�ɂ���A�u�����A���̎��o�v�Ƃ������Ƃ��B�����ɂ����āA�u���v�ւ̂܂Ȃ����́u���v�ւ̂܂Ȃ����ƈ�C�ɋt�]����B���ꂪ�̎����ςȂ̂ł���B�@
���̎����ς́A�u���ȓI��`�q�v�Ƃ������㐶���w�̏d�v�ȍl�����Ƃ���߂Ă悭���Ă���B���ȓI��`�q�Ƃ́A�C�M���X�̐����w�҂ł��郊�`���[�h�E�h�[�L���X���������w�����B�h�[�L���X�ɂ��ƁA�����̓��͈̂�̏�蕨�i�r�[�N���j�ɂ����Ȃ��̂ł����āA�����c�葱���邽�߂ɁA�����̈�`�q�͂��̏�蕨�����X�ɏ�芷���ĂƂ����̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A�̂ɂ͎�������̂ŁA���B�ɂ���ăR�s�[�����A���ɓ��̂��c���A�����ɏ��ڂ�킯���B�@
���@���ł��邱�Ƃ̏ؖ��ɘb��߂��ƁA����͂��葒�V���s�����Ƃ��B���V���@���ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�K���Ƃ��Č���l�����邪�A���V�Ƃ͕�����Ȃ��@���V��̍����ł���B�u������ю���̐����v���`�ɂ������̂������V�ł���A���Ɏ͑�����������d�������B�@
���Ƃ��Ɓu����v�ƌĂꂽ�Ñ�̎O���[�v�͑����̃v���t�F�b�V���i���W�c�ł���A�����Ȏ̑n�n�҂Ƃ����E�q�̕�e�����V��肢�A���邢�͉J��Ɍg���ޏ��i�݂��j�������Ƃ����B�J��́A�����̐��������E����d�v�Ȕ_�k�V��Ƃ��āA�Ñ�ɂ����Ă͐���ɍs��ꂽ�B�����w�̌ÓT���̌ÓT�ł���t���C�U�[�́w���}�сx�ɂ́A���J�Љ�ɂ�����J��̋V�炪�����Љ��Ă���B����䂦�ɁA�u��v�͎��v�́u���v�A���Ȃ킿�u���Ƃ߂�v�̈Ӗ��ł��������B�Ȃ��Ȃ�A�Ñ�l�̐����ōł��؎��ɂ��Ƃ߂�ꂽ�̂́A��鯂̎��̉J�ł��邩�炾�B�@
�����āA�̔������̂��̂������V��ƕ��������������т��Ă����B�������w�҂̔���Î��ƓN�w�҂̔~���Ҏ��Ƃ̑Βk�w��̎v�z�x�̒��ɁA��l����ƂƖn�Ƃ̑Η��ɂ��Č�荇������A���̂悤�ȉ�b�����킳��Ă���B�@
����E�q�͑������ł�������ł���B�@
�~���ق��B�@
���쑒�����ƌ������炨����������ǂ��A�̕����ŁA�w��L�x�l�\��т̂����̑啔���͂ˁA�����̋V��Ȃ�ł���B���ՂȂ�ł��B�@
�~�������ł��ˁB�@
���삻������S�����Ă������B����ŁA�n�q�W�c�́A���̍H�l�W�c�ł������B���́A�u���̂Â���v�ł��B�@
�~���n�q�́u���̂Â���v�ł����B�����čE�q�͑������ł���ƁB�@
����Î��ɂ��A�E�q�̕��e�ƕ�e�͐����̌��������Ă��炸�A�E�q�͎������ł������Ƃ����B�E�q�����O�O�N�قnj�ɓo�ꂷ��Ўq�̕�e�́A�Ўq���q�ǂ��̍��ɑ����V�т�����̂������ĉƂ��O��ւ����A������u�Е�O�J�v�ł悭�m���Ă���B�Ўq�̎t�ł���E�q���q�ǂ�����ɂ͂悭�����V�т������悤���B�@
�������ł���A�����e�𑁂��S���������߁A�n���Ƌ��̂����ɕ�Ɠ�l��炵�������E�q�̏��N����B���ł�����q�ƒ�ł���B�����̎d�������Ȃ���A�E�q����Ă���B����ȕ�e�Ƃ��̎d�����E�q�͂ǂ̂悤�Ɍ������낤���B�����炭�A�[�����ӂ̔O�Ƒ��h�̔O��������̂ł͂Ȃ����낤���B�E�q�͕�e�̉e���̂��ƁA�u����قǐl�Ԃ̑������d�����l����s�ׂ͂Ȃ��v�ƍl���Ă����Ƃ������ɂ͎v���Ȃ��B�����łȂ��ƁA�E�q����������قǂ܂łɑ���ɉ��l��u�����R���܂������킩��Ȃ��Ȃ�B�@
���݂ł͍E�q�̕��e�͎R���Ȃ̉����R�l�M���ł������Ƃ���Ă��邪�A�����̍E�q�͕��̖����m�炸�A���̕揊�Ȃǒm��R���Ȃ������B�������A�E�q���̊ԂɋL�^���ꂽ����̖��𑽂��W�߂������ł���w��L�x�́u�h�|�i�����j�сv�ɂ́A����������Ă���B����ɂ��ƁA�E�q�����̕��D�̏���ɉ����������Ƃ��A���̘V�k�ɋ������ĕ��̕揊��m��A���������Ƃ����B�揊�͉������Ȃ��̂����ʂ����A�E�q�͂����Ă��̕�������������Ƃ����̂ł���B�@
����̍����Ƃ����s�ׂɂ́A�E�q�̑z�������ݏo�Ă���悤�Ɏv���B���e�ɑ���e���̏�͂������A�u�[�����������Ȃ�������O�͕v�w�ɂȂ�Ȃ�������l���A���߂Ď���ɂ����Ĉꏏ�ɂ��Ă�肽���v�Ƃ����Ȃ��肢�����߂��Ă���悤�Ɍ�����B�E�q����ɂ�������Ƃ́u���Ǝ����݂߂āv�A�l�Ԃ̐^�̍K����₤�s�ׂ������̂ł���B���̂悤�ȍE�q�͛ޏ��̎������ł��������䂦�ɁA�_�̎q�ł������̂��Ǝ��͎v���Ă���B�@
���̐_�̎q�ł���E�q�̐��U�́A�����Čb�܂ꂽ���̂ł͂Ȃ������B�E�q�́u�q�v�͑��̂ŁA�u�E�v�����ł���B���́u�u�i���イ�j�v�A���l����̌ď̂ł��鎚�i�����ȁj�́u����i���イ���j�v�B�I���O�܌ܓ�N�ɘD��裗W�i�����䂤�j�A���݂̎R���Ȃɐ��܂ꂽ�Ƃ���Ă���B�O�O�ΑO��܂ł̍E�q�́A�D�̍��Ɏd���āA�q�ɔԂ�q��̎���W�����Ȃ���w��ɗ�B�����ĎO�Z�̂Ƃ��Ă̍��ɍs���A�l�O�̂���ĂѐĂ���D�ɖ߂����B���̎����ɂȂ��āA�q�H�i����j���{�q�y�i�т���j�Ƃ�������q�������W�܂��Ă��āA�E�q�̖����͍��܂��Ă������B�@
�E�q���D�̍��ł���Ȃ�̃|�X�g���̂͌܂O���߂��Ă��炾�����B�ܓ�Œ��s�̑㊯�ƂȂ�A�l�Ŏi�@�����ƂȂ����B�s�����Ƃ��ĐⒸ�����}�����킯�����A���̂Ƃ��E�q�͈��̍s�����v�����݂��B���ꂪ���s�ɏI��������߂Ɏ��E���A�ܘZ�̂Ƃ��ɘD�̍����o��B�@
�Ȍ��l�N�ԂƂ������́A�E�q�͑��A�q�A�v�A�A�A�A��A�^�ƁA�����𗬘Q���āA�����̐����I���z���������Ă����N���T�����߂��̂ł���B�ł́A�ނ̐����I���z�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��������B����͓����ɂ�鐭���A���Ȃ킿�u������`�v�ł������B������`�Ƃ́A�@���Ől�����R���g���[�����邱�Ƃɂ���Đ������s���u�@����`�v�ɑ�����̂��B�D�ɓ`�����̕������x���w�сA�����U�𗝑z�̐l���ƌh�炵���E�q�́A�����ɂ����鐭�������̐��x�ɖ߂��ׂ��ł���Ǝ咣�����B���Ƃ����A�E�q�̎�����܂O�O�N���̂̋I���O��ꐢ�I�̍��ł���B���̌Ái���ɂ����j�̗��z�̐������������邽�߂ɁA�ނ͓�����`�����̂ł���B�@



 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@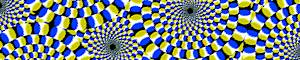 �@
�@ �@
�@


 �@
�@



 �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@


