������ł����Ȃʈ�㕷��
�@
���̂Ƃ��A���̒�����̒����������x�Ŗ�l����l�A�����ɂ����B�����͋C�̑����j������A�u�����B�|�v�ƁA�����ł��A�����܂Ɏa���ς�����B���ؐ悪�y���A����ɓ��݂��ނƁA��l�͂�قLjӋC�n�̂Ȃ��j�炵���A����Ɠ����o����(�p�����g�ق̒ʖA�[�l�X�g�E�T�g�E�̎�L�ɂ��ƁA�u�����̌x�앺�͊��{�̎��j�A�O�j���炠�߂����̊łł������B�݂ȗ�����тсA���͓��̑��ŕ҂~���������X�q�A�m�����\���^�̎���h�����̖X�q�����Ԃ�A�n�I���Ƃ����O���𒅁A�n�J�}�Ƃ����y�e�B�R�[�h�݂����ȃY�{�����͂��Ă����v)
�@
�Ɠ����ɁA���B���������o�����B���͂���͐��������A�Ƃ݂��̂��B�ɓ��r����S�����݂��Z���r�����ꂳ���Ȃ���A�����ɓ������B�ɂ���ƂȂ�A�r�オ��ԑ��������B
�@
���A�����Â�̕����͂��ԂƂ��B��_�Ȓj�ł͂Ȃ����V���A���|�S���ɂԂ��o���Ă����B�����͂ӂƋC�ɂȂ��Č܁A�Z���œ��݂Ƃǂ܂����B
�@
������x�A���Ό���ɂЂ��Ԃ��A����˂�ɒ��ׂĂ݂��B�Ă����Ƃ���A�����������Ă���B
�@
(�������)���̒j�ɂ́A���̓��u�Ƃ������A�v�z�Ƃ����قǂ̂��̂͂Ȃ����A�Ȃɂ����d���Ƃ������̂���D���������B�̂����A�Ɩ{�ق̒��ɔE�т��B��������n���̐���ς���O�w���������Ă��Ă��̏�ւ̂����B���̉��ɐV�����Ζ�����������A���ΐ��Ȃ��ʼn������B���ƁA�����悭�R���͂��߂��B
�@
�����͓������B�Ƃ��낪�A�Â����߂ɕ��p�������A��̔j�ꌊ�������炸�A��ނȂ���݂����ɍ���悶�̂ڂ��āA�ނ������֔�B
�@
���A�Ȃ��Ȃ��n��ɒ������A�̂�@�������Ă���C�Â��ƁA�[���̒�ɗ�������ł����B���ʂȂ�Βė�������Ƃ��낾���A�����́A�̒����������Ă݂����A������܂�Ă��Ȃ������B�Ȃɂ��A���������������ɑ̂��o���Ă���j�炵���B
�@
�D�܂݂�̂܂ܕ����͑傢�����ō�����~�������������A�Ȃ������Ȃ������B�����ō������ɉ̔R���𒍈ӂԂ����ώ@���A�₪�ĉΒ����ǂƉ��������ʂ���̂��݂āA���Ⴊ�B
�@
���̂��ƕ����́A�E�����āA�������Ă���B�@ |
���j�̓|���̏�M�͏��A�̌Y���̂��݂��Ƃ�����͂��܂�A���{�̊������n�܂���
�@
�����́A���Ƃł���B�˓@�Ő����A����났���Ɗ�����点�����ŁA���ꂪ���Ă����܂��Ă���Ƃ����A���̒j�̂����Ƃ��s�C���ȂƂ��������B
�@
���Ƃ��A�䍒�R�đł�肿����Ƃ��Ƃ̂��Ƃ����A�J�̖�A�u�r��A����������B�x�x�����v�ƁA�������B�r��́A�ւ��Ƃ������܂�A�\�l���̑����ߏւƊ����A�ԁA�Ȃǂ��A�˓@�̂Ȃ����킯�܂���Ă��₭�������B
�@
�u�����܂��Ă������܂��v�u�悵�B�����͏��A�搶�̖�l�ꓯ�ł�����������B���O���o��v�ƍ����͂������B���ُ̈펙�́A�����ʂ��ɂ�������e���Ȃ悤�ɂ݂��邪�A���͂����ł͂Ȃ��B�����Ɣ˂̏d���ɁA�������Ă���B���������̋��Ղ͗e�ՂȂ��̂ł͂Ȃ������B�����Z�N�A�]�˓`�n���̍��Ŗ��X�̂��߂Ɏa��ꂽ�g�c���A�́A����Ζ��{�ɂƂ��ė��b���q�ł���B���B�ˏd���̈ꕔ�ł͖��{�ɉ������āA���Θ_�����������A�����́A��㕷�������čI���Ɍ����������B
�@
�|�����́A��������肶��B
�@
�����͂���ȏ����Ă����B���Ƃ����āA�����͏��A�̖�l�ł͂Ȃ������B���̂����F�l�̕��̎t���Ƃ������ƂŁA���������Ă�����ɂ����Ȃ��B
�@
�r��́A�ڑG�̂�����Ȃ���B���A��l�̂͂�����ł���B
�@
�����A�݂Ȃŏo�������B
�@
�����A�Ƃ����Ă��A�����ł���B���A�̎��[�́A�Y��̏��ˌ��̓y���ɂ���B�Y������r��́A�j���ܘY�̏]�҂Ƃ��ČY��ɂ䂫�A���X�ɍ������Ė_�l�߂̎��̂����炢������Y��t�߂ɖ��������B
�@
���̎��̂̎S������ڂ��Ă���B���藣����Ă���͓̂��R�Ƃ��Ă��A���炾�͉��ш�Ȃ��ԗ��ł������B�ߗނ́A�����������Ƃ��Ă��܂������̂��낤�B
�@
�r��́A�t���̎�̔��������Ă܂��������Ă��A�j�́A�����̕��J���ʂ��Ŏt���̓��ɒ����A����ɓ��s�������A�̗F�l�Ŕ˂̓T�ゾ�����ѓc�����́A�����̑т������A���H��d�̒������ʂ��ŁA���A�ɒ������B
�@
(���̂ꖋ�{��)�ƁA�����́A�ɂ���v���ŁA�\�s�E����Ȑ��{��������B�j���ܘY�ɂƂ��ē|���̏�M�́A���̈����Z�N�\����\�����̑��ł̏��ˌ��ŁA�ԗ��̌Y���̂��݂��Ƃ�����͂��܂����Ƃ����Ă����B����ɂ����A���{�̊����͂��̒�����͂��܂����Ƃ����邾�낤�B�@ |
���������O�ł͗�m�ł������Ō�̝��Ύu�m�͎a��ߐl�ƂȂ���
�@
�����A�����ɂ����Q�m������̌����͑傢�ɋ����A����A���M�V���A���ё@�V���A�呺�叕���ċւ����B
�@
�u�ߓ�͂��ʁB���m�Ƃ��ċ�����䂦�A�����ɘA�q�����������ǂ����A����Ă��ɐ\���Ă��炢�����v�u�������v�ƁA�O�m�Ƃ��V�R�Ƃ��ē������B�Ȃ����Ύu�m�Ƃ��ł̌ւ�������Ă����̂ł��낤�B
�@
�V���{�̌Y�@�����ǂł́A�p�����������̈ꖡ�̑��݂ɋC�Â��Ă��Ȃ����Ƃ���݂Ƃ��ĂЂ����ɉB�֑������B
�@
�����A�O��ƁA���鐝�ɑ��Ă͋ɌY�������ėՂB
�@
�����̎m�Ђ����A�����ɗ����A�鐝�̎��r�������͂Ȃ��āA�I�c���Y��ɞ������B
�@
���������ɁA�O�}�̐�����Ȃ�B
�@
���Y�̏ꏊ�͌I�c���ł���A���@�́A���m�ɑ����ł͂Ȃ��A�a��ł���B
�@
����́A�O���B
�@
�ق�̐��J���O�Ȃ�A�����͗�m�ł���A���̍s�ׂ͓V�n�Ƃ��Ă��������A����́A���M�̉h���������ł��낤�B
�@
�����́A���́u��v�̂��ǂŏ�Γ}�̋����u�ɂ���ď��Y����A���ɉi���̍ߖ��𒅂��B
�@
�����A�u�m�Ƃ��ĔɏW�ꂽ�҂́A���a���N�u�}��^�e�v�Ƃ��ċ{���Ȃ��Ҏ[���^�������̂����ŁA���l�S���\�]�l�ɂ̂ڂ��Ă���B���̂����A�����Ȏ҂͑吳���ɑ��ʂ���A���ׂĂ͖����_�Ђɍ��J���ꂽ�B������l�A�O�}�Ǝ鐝�����͂��̂Ȃ��ɂӂ��܂�Ă��Ȃ��B�@ |
���g�c���A
�@
���v�z�Ə��A�͏����ŏ��^
�@
�i�n�@�v�z�I�l�Ԃɂ�����C���Ƃ��Ă̊�Ƃ������Ƃŏ��A���l���Ă݂�ƁA���̐l�͎v�z�Ƃ̒��ł͂����Ƃ������I�ȑ��݂���Ȃ����A�v�z�ƈȊO�ɂȂ�悤���Ȃ��l���Ƃ������������܂��B���́A���A���q�ǂ��̎����炠�܂�D���łȂ��A��l�ɂȂ��ĂӂƋ��������������ɁA����ȏ����ŏ��^�Ȑl���������Ƌ������킯�ł��B���傤�Lj����̔��e���т��ނ���āA�ԗ��ɂȂ��āA���敗�ɓ����Ă����⍜���ɂނƂ�����ł���l�����A�Ȃ�Ȃ����B�v�z�ƂƂ��Ă̏��A�̊���A�K���X�̌��ɂ��Ƃ���ƁA�K���X�̊�͔��ɔ����āA���ɂ��������Ȃ����Ƃ����悤�Ȋ����������ł����A�v�z�グ���A�������͎v�z��N���o�������Ƃ����̂��l�Ԃɂ����āA���͂��������C�����قƂ�ǎ����Ă��Ȃ���ł�����ǁA���������C���������Ă����l�Ƃ������ƂŁA���{�̎v�z�j���l���邱�Ƃ��ł���B
�@
�����A�͗D�������番����Ղ���������
�@
�����̕��͖͂����ŁA�l�ɂ킩��₷�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA����͂ЂƂ̐S���Ƃ��Ď����Ă���ɂ����Ȃ��B���A�̏ꍇ�A�ނ�ɂ킩��悤�ɏ����̂́A�K�v�������Ă������Ă����킯�ł��B����͌����I�ɐ������Ă����̂ł͂Ȃ��A�D�������琬�����Ă���킯�ł��B���̏��N�ɂ͂��������������ői�������B������D���������̐S�ɂ������B���Ƃ��낪�Ȃ��āA�S�����炯�o���āA�Ȃ������N�̐S�ɂ܂œ��ݍ���ŁA���͂����䂢�Ƃ���܂ōs�͂�����Ƃ������ƂɂȂ��āA���A�ɂ͍I�܂����Ă����������͓��{�ꂪ�������Ă��܂����̂��Ǝv���܂��B
�@
����@����������̓I�ȗv�����Ȃ��ƁA������V�˂ł����䂤�ł͂����������͍͂��Ȃ��킯�ł��傤�B
�@
�i�n�@�Ȃɂ��돼�����m�Ƃ����Ƃ��������悭�����܂�����ǂ��A�{���I�ɂ͂����̎������ł��傤�B���߂Đ玚���̏C�Ƃ�������A�ȒP�Ȋ����̓ǂݕ�����������肵�ɗ��鏭�N�B�������鏉������̏�ł�����A���A�Ƃ��Ă͎����������Ă��鋳�{��{�L���u�����g�ł͘b���ł��Ȃ��Ƃ����Ƃ��낪����܂����ł��傤�B
�@
���]�˖����ɐl���̂��Ƃ��l����v�z���łĂ���
�@
�i�n�@������ɂ��Ă��A���A�����������j�I�i�K�ł́A�l���Ƃ����t�B�N�V�����𐘂��āA�v�z�`��������Ƃ������Ƃ́A������s�\�������Ǝv���܂��B�]�˖��ˑ̐��ɂ�����l���Ƃ����̂́A�������g�������t��������x�g���A���ł����āA��̓I�ɐl���Ƃ����̂͂ǂ����Ƃ����`�ł͏o�Ă��ɂ������A�㐢�̗��j���l���Ă���قǂɍ]�ˏ����Ƃ����̂͋ꂵ���Ȃ������Ǝv����ł��B�����Ďm��v���l���̂��Ƃ��l���A���Ƃ�S���ׂ��ł���Ƃ����l�����A�]�˖����ɂ͂͂�����Ƃ���킯�ł��B���j���l�����ŁA�V�c�Ƃ����t�B�N�V�����������ɍ��グ��A�l���̂��Ƃ��͂����肷��B�V�c�𐘂��Ȃ���ΐl���̂��Ƃ͂͂����肵�Ȃ��B�ȒP�Ȑ}���ł����܂��ƁA�V�c�𑨂��邱�Ƃɂ���āA�l���������ɂȂ��ł����āA���R���F���������ȂƂ������Ƃ�����ƌ����邵�A�l�������ł����āA���̏ꍇ�A�V�c�Ƃ����t�B�N�V�����������͍����]�����Ȃ�������Ȃ��Ǝv����ł��B�㐢�̑ΓV�c���o�ŁA�܂�㐢�̐��L���Ŋ������Ⴂ���Ȃ��Ǝv���B���͗��j�I�@���ŕ�������Ƃ����̂͋��ȕ��ł����A���A�ɂ�����V�c�̖��ɂ��Ă͔��ɖ������ɂ�����~�߂���Ȃ�ł�����ǂ��B����1�A���Ƃ��܂ł�����܂��A���͖����Ȍ�̓V�c�����D�݂܂���B
�@
�����A�������Ƒ̐��ɋz�����ꂽ
�@
����@��܂��Ɍ����āA���������̏��A���͑h����܂߂Ă܂��Ɋv���Ə��A�ł��ˁB�Ƃ��낪�������Ƃ�������ɓ���ƁA�v���̗v�f�͌�ނ��A������c�j�ςɊ�Â��ېV���_�̉��g�Ƃ������ƂɂȂ�A���邢�͏����Ȑ��ӂɂ���Đl�������}���̋���҂Ƃ����`�ɂȂ��āA����������Ƒ̐��̒��Ɉ��S�ɋz������Ă��܂��B���čŌ�ɂ͒P�Ȃ鐽�S���ӂ̐l���Ƃ��������e�Ȗ͔͂Ƃ��ċ��ȏ��ɕ������߂���B
�@
�܂菼�A���Ƃ������̂́A�v���Ƃ����{�����ɂȂ�ɂ��������āA���͂╜�����s�\�ȂقǂɞB�������Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B���Ƃ͂��Ȃ�n�b�L�����Ă����̂��A���ɂȂ��Č����A���Ƃ������̂��@��o�����Ƃɂ́A���Ȃ荢��Ƃ��Ȃ��قǂɂȂ��Ă����Ȃ����B���������ꂪ��̓I�ɏ��A��������グ�悤�Ƃ��鎞�ɂ��A�����ȓ_�ōs�l������A���������肷�邱�ƂɂȂ�Ǝv����ł��B
�@
���{�@�l�Ԃ��̂��̂Ƃ��ẮA���A�͂������v���N�������悤�Ȍ_�@�������Ă��܂�����ǁA���A�Ƃ����l�Ԃɕt�������v�z�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�ꌾ�ł͐���������Ȃ����G�Ȃ��̂�����B�܂�A���A�̎v�z�Ƃ����̂́A���̐��U���Ƃ��Ă݂Ă������I�ɐ��ڂȂ����͓]�����o�Ă���悤�Ɏv���܂����A�v�z���e���猾���Ă��A�����̖������܂v�z�Ƃ��Ǝv���܂��B
�@
�w�ЖЗ]�b�x�̕]���ɂ��Ă��A���_�I�ɂ����A�����ȍ~�̓V�c�����Ƃ̏d�v�ȃC�f�I���M�[�I�x���ɂȂ�悤�ȑ��ʂƁA�Б��Ў��̐��_�Ȃǂɕ\���Ă���悤�Ȏ�̓I���H�҂̎������_�A�܂�`���I�Ȏv�z�̒�����A�ߑ�I�l�̎�̓I���_�ɑ�肤����̂Ƃ��Ē��ڂ���鑤�ʂƁA�����̖ʂ��w�E�ł���Ǝv���܂��B�@�@
�@ |
| ���u�����v�Ƃ������� |
   �@
�@
|
�����C�M�͓��{���Ƃ����v�z����������ՓI����
�@
�V���̈�l���A���ɑ��Ď��₵�܂����Y�͎���ƂɌ��T�������Ă��܂���A�L�������Ő\�������܂��B
�@
�u���B�킪���̖{�Ɣލ��Ƃ́A�����Ȃ邠���肪�������v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ǝv���܂��B���C�M�́A�����̓x���Ɠ��]�ɂ�����������Ă���悤�Ȓj�ł�����A�u���l�A�킪���Ƃ������A���̍��́A�d���E�ɂ���l�́A���̂Ԃ������������܂��v�ƁA��ʓ��������āA������@���܂����Ƃ����܂��B���̈ꌾ�͕������̒v���I���ׂ����A�����������g�̋���Ȏ������ׂ̂Ă��܂��B���́A�A�����J�w�䂭�ЗՊۂɂ����Ă��A�͒����ɂ��Ȃ���(�R�͑���������������)�A���K�̎w�����͂܂��Ƃ������ׂ��R�͕�s�́A�唴�o�g�̖ؑ��ےÎ��B(�ꔪ�O�Z�`���Z��)�ŁA�����������̔\�͂��Ђ�����ɁA�����������N���Ȃ̂ł��B���̖ؑ��Ƃ����l�͖�����A�u�H�M�v�Ƃ���������
�@
�ĉB�ق��Đ��ɏo�Ȃ������Ƃ����A���ɂ��ꂢ�Ȑl�Ȃ̂ł����A������̑��L�^�ɁA���ɂ��Ă�������Ă��܂��B�u(�g����Ⴍ�Ƃǂ߂��Ă������߂�)�n�I�s���ŁA��ςȃJ���V���N�ł�����A�N�������Ă��܂����v�ЗՊۂ̍q�C�����D�������Ƃ����Ċ͒�������o�ė����A�ؑ���̂ق����瑊�k�̎g�������Ə��́u�ǂ��ł�����v�Ƃ������q�ŁA�u�͂Ȃ͂������̂́A�����m�̐^���ŁA�Ȃ͂��ꂩ��A�邩��A�o�b�e�[��(�{�[�g)�������Ă���v�Ƃ����n���������Ƃ����܂��B�D���������łȂ��u�܂�s����������ł��v�ƁA�����₩�Ől�𒆏����邱�Ƃ��Ȃ������ؑ��H�M������Ă��܂��B���͏��C�M���A����Ȏ������畕�����ւ̔ᔻ�҂ɂȂ�A���̂܂܂ł͓��{�͂Ԃ��Ƃ�����@���A�����������I����(�������͗��_)�֎��������������l���Ǝv���Ă��܂��B�C�M�͈̑�ł��B�Ȃɂ���A�]�˖����ɁA
�@
�u���{���v�Ƃ����A��������������Ƃ̂Ȃ��A���˂�������x���̍������Ǝv�z�|�����Ƃ��Ă͖��̂悤�ɒ��ۓI�ȁ|�T�O�������������ł��A���͊�֓I�ȑ��݂ł����B���������̎v�z�ƁA�E�̊���ƁA�s���o�̐헪�I�˔\�������āA�����ېV�̍ŏ��̒i�K�ɂ����āA���{��\(���͋}���ɗ��g���Ă��łɂ����܂łɂȂ��Ă��܂���)�Ƃ��āA���{�݂���������Ȕے肳���A�����炵�������{�����ɁA�ꔭ�̏e�����Ƃǂ납���邱�ƂȂ��A�����䂸���Ă��܂����l�Ȃ̂ł��B����Ȃ����₩�Ȑ����I�|��������Ă̂����l�����A���{�j�ア���ł��傤���B���̃o�l���A�E�̂��Ƃł��B���A�����J�ł́A���{�̂��炢�l�͂��ꑊ���ɂ��������B���{�͂��������B�@ |
�����I�͓�Ƃ��݂��ƂɎ��{
�@
�|�V���Ƃ͂ǂ�����ׂ����B�Âڂ��Đ��E�̑吨�ɓK��Ȃ��Ȃ��������̓��압�������Ƃ̉��̉��ɂ��Ȃ���A����Ȃ��Ƃ��l���Â��Ă��܂����B�ނ��A���I�\�z�̐V���Ƃ́A�����܂ł�����ƂƂ������̂��R���p�X�̃V���ɂ��āA�~�����������Ƃ�����̂ł����B���I�͟Ӑg�̗J���Ƃł������A�������l�ƌ�肠���ėJ���̏��ق������Ƃ����Ƃ���͂���܂���B�^�̗J���Ƃ����̂́A�匾�s�ꂵ����A�����ς���ė܂����ڂ��Ƃ������̂ł͂���܂���B���̎���A���������J���Ƃ͌��̐��قǂ������āA�R�ł���ł����ł��A�ۖ�����Ԃ��قǂɖi���Â��Ă��܂����B���I�̗J���͂����������̂ł͂Ȃ��A����̋Ɩ��̂Ȃ��ɂ����炵���d����ʂ��Ƃ������̂ł����B
�@
����ɁA����͂��������ʒu�ɂ����̂ł��B
�@
�A�����J����A�������ƁA���N���ď��I�́A���{�̍��������ł��銨���s�̐E�ɏA���ċ��ɂ̒��g��m��A���ŁA����ǂ͂������g���ق��̗��R��s��R�͕�s�ɂȂ�A����ɂ́A����疋�{�̌R�����t�����X���ɕς���ׂ��v���A�݂��ƂɎ��{�Ɉڂ��܂����B��ƂŁA�����ɂ݂��Ă��܂����B���m���x�Ƃ������{�̓`���I�Ȃ��̂��ꋓ�ɉ�̂��邱�Ƃ͖��˔ے�|�܂莩�Ȕے�ɂȂ�܂����炻���ɂ͎���ӂꂸ�A������c�����܂܁A���Q�̎q���m�����R�̎m���ɂ��A�������畺�����u��ł����ĕ�W����Ƃ����A����ΐV����d�\���̌R���ł����B�Ƃ��ɊC�R��傢�ɏ[�������悤�Ƃ��܂����B���[���b�p�̒鍑��`�ɑ��ẮA���[���b�p�^�̍�������ȊO�ɁA�Ɨ������̕��@���Ȃ������̂ł��B���܍l���Ă��A����ȊO�ɕ��@�݂͂���܂���B�@ |
���������Ƃ͊O������肽���͂��ׂĕԂ��M�p����������
�@
�u���̘b���o�����łɐ\���܂��ƁA�������Ƃ́A�n�̋ɂ���o�����܂����B�����{���w�������O���ނ��Ђ����܂����B���炽�ɖ������Ƃ͎؋������܂����B�������A�n�R�����ɒu���Ă��A����ɖ����E�吳�E���a�̍����́A���E���イ�̕n�R�_�����̓��{�ɂ�т��߂ċ��ɂ��炵�Ă���قǂɕn�R�����܂������A�O������肽���͂��ׂĕԂ��܂����B
�@
�u���Ƃ̐M�p�v�Ƃ����̂��A�厖�������̂ł��B
�@
���͈�㔪���N�̏t�̓����h���ɂ����āA�����ŁA���e���E�A�����J�̂��鍑���A��i������肽���A����͕Ԃ��܂���A�Ƃ������Ƃ��킴�킴�L�҉���Č��������A�Ƃ������Ƃ������A�������Ƃ��v���āA�܂����ڂ��v���ł����B���`�Ȃ��̂ł����B
�@
����́A���掩�^���Ă���킯�ł͂���܂���B
�@
�����A��������̐V�����Ƃ��ł��A�؋�����ō�������Ă��鏈�������A���������X�ƕԂ��Ȃ��Ƃ������悤�ȍ�������������܂��B
�@
�����Ƃ́A���オ�������̂��A�Ƃ������Ƃ��������������̂ł��B
�@
�\�㐢�I�̔������Ƃ�������ɂ����āA�Âڂ��������̒�����o�ċߑ㍑�Ƃ낤�Ƃ����̂́A���{�����������̂ł��B���̂��Ƃ��ق������ׂ̂��������̂ł��B��������Ԃ��ׂ����̂�Ԃ��Ȃ���ΐA���n�ɂ���Ă��܂��̂ł��B�łȂ��Ă��A���Ƃ̐M�p�Ƃ������̂��Ȃ��Ȃ�܂��B���ƂƂ����̂������ł�����A�M�p���Ȃ����Ă��܂��A������ł��Ȃ��Ȃ�̂ł��B�M�p�������ɑ厖���Ƃ������Ƃ́A�]�ˊ��̐l�B���A���̏[�����������̏��i�o�ώЉ�ł̌o���ŁA�S���m���Ă����̂ł��B�@ |
�����I�ƌI�{�͖��{���ł�ł����{��h�b�N���𗧂��ƒm�茚�݂���
�@
����́A�O�ɂׂ̂����{��̋���ȃh�b�N�̎{�H�ēɁA���b�̌I�{�����q������т܂����B
�@
���j�̂Ȃ��ŁA�F���������l�������܂����A�I�{�����q�Ȃǂ͂����ł��ˁB�����j�ł��B
�@
���{�̌��t�̎q�ŁA���b�����Ẵt�����X�ʂł����B���l�J�`��͎�Ƃ��ĊO���������������A�O����s�ɂȂ����肵�܂����B���{������́A���Ɏd�����A�V���L�҂Ƃ��ďI�n���܂������A�a���̊w��E���{�͖������N��ꓙ�̐l���ł��B���e�͏G�˔��łȂ��A���������A���悻���ɉ������S�����Ƃ��������Ȃ��A���Q�������m�I���i�̑�\�҂Ƃ������ׂ��l���ł��傤�B����́A���U�A�����炢�Œʂ��܂����B������A�I�{���_�̖��Œm���Ă��܂��B
�@
���{��h�b�N�H���̖ڕ@������������|�I�{�̏���������(�u������e�v)�ɂ��A�������N�\���{�̂悭����ĕ��̌��������������悤�ł��|��j�̌I�{�����l�Ŋւ��o�āA���ɂɋA�낤�Ƃ��Ă���ƁA�w��ɔn�̒��̂Ƃǂ낭�������āA��R�킯�Ă��܂��B���{����������Ă̋A��̏��I����ŁA�u�₠�A�����q�a�A�悭�Ȃ��ꂽ�ȁA�����A�����v�ƁA�����͂肠�����B�I�{�̂����Ƃ��ق߂��̂ł��B
�@
���́A���I�̂��̂��Ƃ����������āA����Ƃ����܂Œ����Ă����킯�Ȃ̂ł��B
�@
���̃h�b�N���o������������́A���Ƃ����{���S��ł����y���t�����Ɓ��Ƃ������_���̂����ł��傤�B
�@
���I�͂��͂▋�{���S�тĂ䂭�̂��A�S�g�Ō���Ă��܂��B�n�̋ɂŖ��{���S��ł��A����₪�|���̂ł͂Ȃ��A���Ȃ����Ƃł��A���̃h�b�N�̂������ŁA���y�������Ƃ������Ȉꍀ������������A���{�ɂƂ��Ă��߂Ă��̖��_����Ȃ����A�Ƃ������ƂȂ�ł��B
�@
���I�́A���̎���̓��{�ɂ��̓y�����|���{��h�b�N���|�傫���𗧂��Ƃ�m���Ă������A����Ă������̂ł��B�@ |
���F���y��̔˕��̑��l�������Y
�@
����ˎm��G�d�M�́A�ނ��ƒ������Ă̏G�˂ł����B���A�����Ȑl�Ԃ�A�l�߂��ݕ����A�e�̋w�̂悤�ɂɂ���ł��܂����B����A����͎����̔˂̋l�߂��ݕ����̂̂����āA�u�Ǝ��̍l�������l������ĂȂ��v�Ƃ����܂������A���邢�͂�����������܂���B�������A�����ŗL�\�Ȏ������^�C�v�̐l�ނ𑽂������Ƃ��ł��܂��B����ɍ���˂́A���s���瓌���Ɉڂ����V���{�ɁA�L�\�ȍs�����Ǝ���������邱�ƂɂȂ����̂ł��B
�@
�F���̔˕�(�˕����Ƃ����Ă���낵��)�́A�����̖{�����������Ă����Â��݂Ɏ��������Ȃ������Ƃ�i�ߊ��^�C�v�𑽂��o���܂����B
�@
���B�́A���͂̑��삪���Ȃ̂ł��B�ł����犯���@�\������A�������܂����B
�@
�y���́A���ɂȂ����͂��炸�A��ɂ������Ď��R�����^�����Ђ낰�܂����B
�@
����́A���̂Ȃ��ɂ����āA�����ɕ���������Ă����l�ނ�V���{�ɒ��܂��B
�@
���̑��l���́A�����������Ƃ��A�]�˓��{����Ђ������ő�̍��Y�������Ƃ�����ł��傤�B�@ |
���V���Ƃ̃v�������Ȃ��̂ő勓���Č��w�ɔ��q�����ۂ�
�@
�����̓v�������Ȃ����߂Ɏ�肫���Ă����Ƃ���ł�������A�Óc�̂��Ƃ���A���Ă���ƁA�߂��炵���V�����Ă��܂����B���F�̑�v�ۂɂ����̂��Ƃ����܂��B���ɁA�����́A�u����ꂪ�Óc�搶�Ƃ��ċ��A���̉��ɂ����v�ƁA�����܂��B
�@
�����̂��炵����ʂ��Ǝv���܂��B
�@
�����ɁA�����ېV���͂��A�ǂ�ȐV���Ƃ����邩�A�Ƃ����ʐ^�������Ă��Ȃ��������Ƃ�������킵�Ă��܂��B�����Ă��Ȃ��̂�������O�ł��ˁB�܂����������̎��̂��������{���A�ɂ킩�ɉ��ĂƏo���킵�āA���ꂩ��N����邱�ƂȂ��A�����Ƃ��Ȃ����i�Ƌؓ��̌n���������������낤�Ƃ����̂ł�����A����́A�ʐ^������ق������������̂ł��B���{�̂悤�ȍ������ɂ����āA���ꂪ���ɂȂ��Ă����Ƃ�����A�ׂł����ˁB
�@
�����ς�킩��Ȃ����߁A�������O�������ɂ䂱������Ȃ����A�Ƃ������ƂŁA�p�˒u����������đ��X�̖����l�N�H�A��q���c��(�������͑S����g)�Ƃ���\�l�قǂ̊v�������̌������A�勓���Č��w�ɔ����܂��B
�@
�u���ƌ��w�v�Ƃ����ׂ����̂ł����B���E�j�̂ǂ��ɁA�V���Ƃ��ł��đ��X�A�v���̉p�Y�����������n���̂������������Ă܂���āA�ǂ̂悤�ɍ�������ׂ�����������Ă܂���������������ł��傤���B
�@
����́A�����������Ƃ́A�D�������q�����ۂ��ł����B���̒��ɒ��B�̑����،ˍF������܂��B�F���̑�v�ۗ��ʁA�܂��ɓ����������܂��B�����́A����Ԃł����B�@ |
���p�˒u���͈ېV�ȏ�̊v��
�@
���́A�������ƂƂ������̂���̗��̕��̂悤�ȁA���̊��̏�ɒu���Ă���ł��킩��悤�ɘb�������̂ł��B�͂��߂ďo������O���̐l�ɐ������Ă���悤�ȋC���Řb�����Ǝv���Ă��܂��B
�@
�����l�N(�ꔪ����)�̔p�˒u���B���̓��{�j��A�ő�̕ϓ��̈�ɂ��Ă��b���܂��B����́A���̎l�N�O�̖����ېV�ȏ�ɐ[���ȎЉ�ϓ��ł����B
�@
�����ɁA�����ېV�ȏ�ɁA�v���I�ł�����܂����B
�@
��ςȂ��̂ł����B���{�ɌN�Ղ��Ă�����S���\�̑喼�������A���ɂ��ď��ł����̂ł��B�m���|��������ł��ˁ|���̉Ƒ��̐l���͕S��\���l�ŁA�����̐l�����O�疜�Ƃ��܂��ƁA�Z�E�O���ɂ�����܂��B�����̂ЂƂтƂ��A���������Ɏ��Ƃ��܂����B
�@
�v���Ƃ��������悤�̂Ȃ������I��p�A�O�Ȏ�p�ł����B���ꂪ�����A�e�n�Ɏm���̔�������сA�܂�����푈(�����\�N)�Ƃ�����唽��p�ޝ��݂ɂȂ�܂����B�Ƃ��낪�����͂��ɐÏl�ɂ����Ȃ��܂����B
�@
�Ïl�Ƃ����Ă��A�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�Ζ�ɂ��炨�������ʼnΖ���^�т����悤�Ȋ댯���w��ł������Ƃ͂����܂ł�����܂���B�[��A��ƈ��������A�C�����ւ��A�l�X�ƁA�Ζ���^�т������i���v�킹�܂��B��܂������Α唚�����������̂ł��B�Ԃ��A�^�т�����܂����B
�@
�����Ƃ��������́A���������܂��B����������͂��̔����ɂ��Ă͏q�ׂ܂���B
�@
�喼��m���ɂƂ��āA�p�˒u���قǂ����ɂ��ꂽ���Ƃ͂���܂���B
�@
�����ېV�́A�m���ɂ��v���ł����B�����̕��m�����ɂ܂����B���̗��j����i�s���邽�߂Ɏx����ꂽ����Ȍo��|�R�����A�����̂��߂̔�p�|�͂��ׂď��喼����������Ă̂��Ƃł����B
�@
���̂��Ԃ����A�̒n�Ƃ肠���A���m�͂��ׂĎ��ƁA�Ƃ����p�˒u���ɂȂ����̂ł��B�Ȃ�̂��߂̖����ېV�������̂��A�����͎v�����ł��傤�B
�@
�喼�E�m���Ƃ����Ă��A�|����������F�����͂��߂������̔ˁA��������炾���������҂Ƃ��Ă̍��Ɏc��A���͕����ɂ��Ƃ��Ƃ����̂Ȃ�A�܂��킩��₷���̂ł��B�����������́A�����҂��s�҂��A�Ƃ��ɍr�C�ɂƂт��ނ悤�ɕ����Ɏ��Ƃ���A�Ƃ����̂��A���̖����l�N�̔p�˒u���Ƃ����v���ł����B���炢���Ƃł����B�v����ɁA���m�͂��������Ƀn���L�������܂��傤�A�Ƃ������Ƃł����B�@ |
���������ƂƃL���X�g��
�@
�������ƂƃL���X�g���Ƃ����b�����܂��B
�@
�Ƃ����āA�@���������b���������͂���܂���B���A���̓L���X�g���ɂ͊S������܂����A�N���X�`�������Ⴀ��܂���B
�@
�����̂悤�ɃL���X�g���ɂ́A��ʂ��ċ���(�J�g���b�N)�ƐV��(�v���e�X�^���g)�̓������܂��B
�@
��������͂ӂ����ȂقǐV���̎���ł��ˁB�]�ˊ����p�����Ă��������̋C���ƃv���e�X�^���g�̐��_�Ƃ��悭�K�����Ƃ������Ƃł��ˁB�ΕׂƎ����A���邢�͌���A���ꂪ�v���e�X�^���g�̓����ł���Ƃ��܂��ƁA�����������ł����B����͂����炭���R�̑������Ǝv���܂��B����̎��́A���̋��R�̑����ɂ��Ă̂��Ƃł��B
�@
�����Ƃ������Ă��遍�Ƃ����̂́A���肩�����܂����A�ΕׂƎ����A���邢�͎����A����Ɍ���Ƃ������d�v���ڂ����ŁA���͎��Ă��܂���B�����D���Ȑl��������Ă��āA�������������Ƃ����܂���̂ŁA�w�`�}�ƃq���E�^�����A���̂�������t�����Ă���Ƃ������x�̎������Ɛ\�������Ă����܂��B�܂��L���X�g���̈�����́A���`�̏�őË��Ƃ������Ƃ�����܂���B���̓_�A���{�̕����ɂ���A�_���ɂ���A�܂����y�S�̂��A��ϑË��D
�@
���ł�△�����ł�����܂��B�����̐��_�ƃv���e�X�^���e�B�Y�������Ă���A�Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ��A�ƃN���X�`�����̕��ł��{��ɂȂ�������������邩������܂���A���炩���ߗ\�h�����Ă����܂��B�@ |
�����n�͍�����ꍆ
�@
���āA���̐_�ˊC�R�m����A���͏m���ɓy���Q�m��{���n������т܂����B
�@
��{�͂��Ƃ��Ƒf�p�ȑ����ƂŁA�]�˂ŏ���K�ˁA�ԓ��ɂ���Ă͏����J���h�̍D���Ƃ��Ďa�낤�Ǝv���Ă��܂������A���̘b�������ēڌ債�A���̖�l�ɂȂ�܂��B�u���{��̏��搶�̖�l�ɂȂ����v�Ƒ��낱�тŌ̋��̎o�Ɏ莆�������Ă��܂����A���Ƃ��ƍ�{�͓y���̍��m�ɂ���Ƃ��ɁA�I�����_�����@�ɊS������������������A���łɁ�����������ׂ��f�n�������Ă����Ǝv���܂��B���́A���̍�{��_�ˊC�R�m�̏m���ɂ��܂����B�����Ē���ɂ�����J�b�e���f�B�[�P�̈ʒu���_�˂ł͏��A���̈ʒu����{�ł����B���l���b���������e�́A�����ΐ[��������߂��ł��낤���Ƃ͑z���ɓ����܂���B
�@
�����A���ܘb���Ă���������Ƃ���ɕ��@�����܂��ƁA�����Ƃ��ẮA�����_�ˊC�R�m���Ђ炢�ĂЂ낭���˂̎m��Q�l�����߂��̂́A�Ђ���Ƃ���Ɓ����������������瓾���������̂�������܂���B�������A�ȂɂԂ�댯�ŁA���댯�v�z�ł�����܂�����A����ɑ��Ă�����Ȃ��Ƃ��������Ƃ͏��͎v���Ă��Ȃ��B���́A��{�āA����������������邢�͑�ꍆ(���́A�Ȃ����b�ł�����)�ɂ����������̂�������܂���B�����炭���Ƃ����r�q�ɖ��������������A��{�Ƃ����r�q�Ɉڂ��ꂽ�̂�������܂���B���́A������̍��k���݂Ă��A�������ӂꂠ�����ЂƂтƂ̂Ȃ��ōő�̐l�����A���������ƍ�{���n�Ƃ��Ă���悤�ł���܂��B���Ƃ��ẮA�g�����̂Ƃ�ʖ��b�Ƃ��������A��{�����Ƃ́A�ǂ�Ȃɂ��ꂵ���������Ƃł��傤�B��{�Ƃ����H��̕r�q�ɓ��{�ŏ��̎����ڂ����Ƃɂ���āA���̟��͂��炵�����R�ƁA���Ր��������܂����B
�@
�_�ˊC�R�m��������܂��ƁA����ǂ͍�{������ɂ䂫�A�m����̓y���n�̘Q�y�����ƂƂ��ɋT�R�В�(�̂��C����)���������܂��B�C�R���K�Ɩf�Ղ��߂������Ђł����A��{�͂��̌��Ђ́����@���Ƃ��āA���u�͘Q�m�ł��邱�ƁA�˂ɍS������Ȃ����Ƃ��������܂��B���������̈琬�ƂƂ�Ȃ��ł��傤���B
�@
���܂ł��Ȃ��A�l�ނƂ����E�Ƃ��Ƃ����̂͑����ɊϔO�̂��̂ł���悤�ɁA�����g�����Љ�Ł����������邢�́����{�l���ȂǂƂ������̂́��ΐ��l���Ƃ����ɋ߂����ۓI���݂ł����B���̂悤�ɁA����ɂ�����ϔO�̈�_�Ɏ�����u�����Ƃ��A�n��̏�����E���͂������Ă悭�����Ă�����̂ł��B���A�����܂Ō����܂��B����ɂ́A�łׂ���܂ł����Ɣ��z�ł��܂��B
�@
��{�́A����Ł������W�c��������܂����B���̎����́A���̊�����Е�W�̂����ł��߂܂����B���̏Љ�ŁA�z�O�A���B�A�y���A�F�����炠�߂��̂ł��B
�@
����́A���Ƃ��V�������ł��Ă�����ɎQ���������͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ́A�吭��Ҍ�ɎF���̐����ɂ��������āA�������̐�������u�A�������������悤�Ȍ��i�������Ă��܂�����A�\�����̎v�z���z���ł���̂ł��B
�@
����̎u�́A�f�Ղɂ���܂����B���̂��߂ɂ́A���͓��ꂳ��˂Ȃ�Ȃ��B���̒i�K�Ƃ��āu�F���閧�����v���v�������A���ɂ����^�C�~���O�ɁA���B�̌j���ܘY(�،ˍF��)�����s�ɂ�сA�F���̐����Ǝ���ɂ��点�܂��B
�@
���A���̌�A�|���̏��P���̏�Ԃɂ���A�@���݂āu�吭��ҁv�Ƃ����A�C�f�A�𓊂��ď���ς����܂��B�قǂȂ��h�q�̂��߂ɏW���̂ł����A���̊Ԃɂ����ĐV���Ƃ̍\�z���܂Ƃ߂����܂����B�u�D������v�Ƃ���̂�����ł����A���ɐ�i�I�Ȃ��̂ł����B�@ |
���]�˂̈�Y�ł��镐�m�̐S�Ɛ��������Ƃ͖łڂ���
�@
�����������ɋ������܂�Ȃ��Ȃ����̂́A���͐��_�E�����̑���Ƃ��������̂����A�n�Ԃɏ��A���������ȗm���������Ƃ����Ė��̂��邵��(�S���Ꝅ���������Ă��܂���)����R�ƌ����낵�Ă��邩�̂悤�Ȋ��������̉h������ȏ㌩�邱�Ƃɑς����Ȃ��Ȃ�������ł����B�����́A�^���̕��m�ł����B
�@
�������A���́��������{���́A�������������̂ł��B�����͂����̌�������ā������̂������͂Â܂�Ƃ��떳�v���������Ƃ��ڂ�����A�u�������ē���Ƃɑ��Đ\���킯�Ȃ������v�Ƃ����āA�˂ɒp������S������킵�Ă����A�Ƃ����b��͂����Ă��܂��B����͂����Ă̒��l�ɂ��̌o�ς����K���A�ȂǂƂ����āA�������̒��l�p�ł��邱�Ƃ������������܂����B����ɂ́A��K������ׂ����Ƃ��ƂȂ��A�������˂����A�u�����v��ݒ肵�A��������l�ł���A���{�͍����̖���l�ɂ����Ȃ��A�Ƃ������肵�܂����B����ɂ́A�u�唴���x�͐e�̂������ł�����v�Ƃ������܂����B������A���x�Ƃ��Ă̎m���ۑ��������Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł��B�O����̔������Ђ����A�Ƃ����Ă���̂ł��B�v���Ƃ����̂͂��ɎS�邽����̂ŁA�ߋ������ׂĎ̂ċ�����̂ł����A�ߋ��̂悩�������̂��p�����Ȃ���ΎЉ��l�S�̃V�����ł�������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��������������̂ł��傤�B
�@
�������A�p�˒u���ɓ��ӂ������Ƃł́A�����̐ݒ�ɂ��Ă͑傫���^�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���A����ɂ́A���ꎩ�g����g�ʼn����ł��Ȃ��قǂ̖���������܂����B����́A���m�������������̂ł��B�Ƃ��ɎF�����m���D���������̂ł��B�l�ԂƂ��ĐM���ł���̂͂��̑w���Ǝv���Ă��܂����B���̑w�𐧓x�Ƃ��Đ��������������͂ł�������Ȃ��B���Ƃ����āA����ɂƂ��ĕ�Έȏ�̂��̂ł��镐�m��p�ł����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@
����푈�̐^�̌����͂����ɂ���܂��B
�@
�����ɁA������ق�ڂ������{�́��c�_���������Ėłڂ����A���͂ƕ��͂������Ėłڂ����̂ł��B���܂����A���́����m���ł���G���������Ƃ��܂����B����̂Ȃ����́A���́������Ƃ������Ƃɂ���܂��B�����������ĂƂ��ɐV�����ƁA���_�̖ʂŒ��荇���ď\�����F�̂Ȃ������m�̐S�Ɛ������Ƃ������̂��A���{�́������Ƃ����Ƃ������Ƃ��A����́A���ƕS�N�̂��߂ɐɂ��݂��A�S���Â������̂ł��B�w���N���_�x�̕��͂̌��z���́A���̕���ɂ���܂��B
�@
����푈�ɂ����铖���̎F���m���R(���w�Z�R)�́A��ꖜ���ł����B�����́A�����ɂ��ďI�n�ϋɓI�ł͂���܂���ł����B����狽�}�l�����N����Ƃ����̂ŁA����͂�ނȂ��A���C�M�ɂ��킹��ƁA�g���킽���Ă��܂����̂ł��B�Ȍ�A�����́A���ɂ��ĂȂ�̈ӌ����ׂ̂Ă��܂���B���E����悤�ɂ��Đg���䂾�ˁA���J���̐킢�̂��ƁA���{�R�̏d�͂̂Ȃ��ŁA�ʕ{�W��������茩�A�u�W�ǂ�A���̂ւ�ł悩�낤�v��˂�A�Ƃ����Ď��Q���܂����B
�@
���̐킢�̋K�͂́A��ςȂ��̂ł����B��B�e�n�̋��˂̎m�����ĉ����A�����O���ɂ������܂����B�F���𒆐S�Ƃ�����{�ŋ��̎m�����������ʂ��Ƃɂ���āA�\�I�ȗ��A���S�N�̃T�����C�Ƃ������͖̂ł̂ł��B
�@
�ł��ƂŁA�����ӎO��V�n�ˈ�������̂Ȃ��ōČ����܂����A����͂��͂⏑�ւ́����m���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ɂ́A���{�́A�R������⍑�������ʂ��ĕ��m�I�Ȃ��̂����悤�Ƃ��܂����A�����́A������V�n�˂̕��m���ł͂Ȃ��A�Ђǂ������čd���������A����߂Đl�H�I�ȕ��m���ł����B����푈�ׂĂ䂭�ƁA���Ɋ����̂����A�������Ẳʕ��̂悤�ɐV�N�Ȑl�Ԃ����ɁA��������o���킵�܂��B��������A���܂͂��܂茩������Ȃ����{�l�����ł��B����炱���A�]�ˎ��オ�̂������ő�̈�Y�������̂ł��B�����āA���̐��_�̖��c���A�����Ƃ������Ƃ����������̂ł��B�@ |
���������@�̕s���ō����łт�
�@
�܂��Ƃɂ��̓_�A�������@�́A���ԂȂ������������@�ł����B����ł��A�������ア���ς��́A����������Ȃ��Ȃ������̂́A�܂��������Ƃ��������ЂƂтƂ������Ă��āA�T�����Ȃ��̉ӏ�����̂Ɛ��_�łӂ����ł�������ł��B���̌��@���������ɓ������������A�܂����O��ڂ̏��a�O��(����Z�N�Ȍ�l�ܔN�܂�)�ɂȂ��Ă���A���̉ӏ��ɑ匊�������A���ɂ͌��@�́��s�����ɂ���č����ق�т�Ƃ͎v�������Ă��Ȃ������ł��傤(���łȂ�����N�̒������̔��E�������҂̕�J���㗃���ɂ���Ă����Ȃ��܂������A�V�c�͑��k�������܂���ł����B���O��N�A���R�͖��F���ς��������܂������A����܂��V�c�̒m�炴��Ƃ���ł����B���a�ɂȂ��āA�����̕{�́A�S���ւ̕����a�̂悤�ɂȂ����̂ł�)�@�@
�@ |
|
���O�l���猩�����{�l |
   �@
�@
|
���w���������^�x�@�}���R�E�|�[��
�}���R�E�|�[�� (Marco Polo, 1254~1324) �̓x�l�`�A�̏��l�ŁA1275�N�Ɍ��̑�s�Ɏ���A�t�r���C��Ɍ�������17�N�Ԓ����ɂƂǂ܂����B
1292�N�ɐ�B���A1295�N�Ƀx�l�`�A�ɋA�����B
�w���������^�x�́A�W�F�m�o�̕ߗ�(���N���]���̐킢)�ƂȂ��Ă���1298�N�ɓ����̃��X�`�P�����Ɍ����������́B�����̋{�a�̕`�ʂ́A����̒��������F���̘b���`�������̂ƌ�����B�H�l�̏K���ɂ��ẮA�N���ɂ����ꂽ���̂��A�{�l�̃z���Ȃ̂��킩��Ȃ��B
���`�p���O(���{��)�́A���̂����A�嗤�����ܕS�}�C���̑�m���ɂ���A�ƂĂ��傫�ȓ��ł���B�Z���͔畆�̐F��������߂̐������D��ȋ������k�ł����āA�Ɨ������Ȃ��A���Ȃ̍��������������Ă���B���̍��ł͂����鏊�ɉ�������������̂�����A���l�͒N�ł�����ȉ��������L���Ă���B
�����̍����̈��{�a�́A���ꂱ�����������߂ŏo���Ă���̂ł����B��X���[���b�p�l���Ɖ��⋳��̉��������łӂ��悤�ɁA���̋{�a�̉����͂��ׂď����łӂ���Ă���B���������āA���̒l�ł��͂ƂĂ��]���ł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�����������̈ꎖ�����͐���Ƃ��m���Ă����Ă��炢�������炨�b�����邪�A�`�p���O�����̋������k�́A���������̒��ԂłȂ��l�Ԃ�ߗ��ɂ����ꍇ�A�������̕ߗ����g������x�������Ȃ���A�ނ�͂��̗F�l�E�e�ʂ̂��ׂĂɁu�ǂ��������ʼn������B�킪�Ƃł�������ɉ�H���܂��傤�v�Ə��ҏ���A���̕ߗ����E���ā\�\�ނ��𗿗����Ăł��邪�\�\�F�ł��̓�����H����B�ޓ��͐l�����ǂ̓��ɂ��܂��Ă��܂��ƍl���Ă���̂ł���B�@ |
���w���ȁx�@�t�����V�X�R�E�U�r�G��
�t�����V�X�R�E�U�r�G�� (Francisco de Jassu y Xavier, 1506~1552) �̓X�y�C�����܂�̐鋳�t�ŁA�C�G�Y�X��n�݂ɎQ���A1542�N����C���h�̃S�A�𒆐S�ɕz���ɓ��������B
1547�N�A���W���E�ɏo����{�z�������ӂ��A1549�N8���������ɏ㗤�����n�ŕz�������B
1550�N8�����˂Ɉڂ�A10�����s�����o���A11���ɎR���ŕz���A12���ɍ�ɓ��������B
1551�N1�����s�ɓ��邪�V�c�q�y�E����K��Ƃ��ʂ������A3���ɕ��˂ɖ߂����B4������R���ŕz�����A9���Ƀ|���g�K���D�����̕���ĖL��{���ɕ������B11���ɓ��n���o�q���A��1552�N2���S�A�ɋA�������B
�����ɁA�����������ۂ��邱�Ƃɂ���Ēm�肦������ł́A���̍��̐l�тƂ͍��܂łɔ������ꂽ�����̂Ȃ��ōō��ł���A���{�l���D��Ă���l�тƂ́A�ً��k�̂������ł͌������Ȃ��ł��傤�B�ނ�͐e���݂₷���A��ʂɑP�ǂŁA���ӂ�����܂���B�����قǖ��_�S�̋����l�тƂŁA���̉����̂������_���d�܂��B�啔���̐l�тƂ͕n�����̂ł����A���m���A�����łȂ��l�тƂ��A�n�������Ƃ�s���_�Ƃ͎v���Ă��܂���B
���啔���̐l�͓ǂݏ������ł��܂��̂ŁA�F��⋳����Z���ԂɊw�Ԃ̂ɂ��������𗧂��܂��B�ނ�͈�l�̍Ȃ��������܂���B���̒n���ł͓��l�͏��Ȃ��A�܂����l��������Ɣ��Ɍ����������A�N�ł����Y�ɂ��܂��B���݂̈��K�������ւ�ł��܂��B�ނ�͂����ւ�P�ǂȐl�тƂŁA�Ќ𐫂�����A�܂��m���~�͂���߂ĉ����ł��B
���ނ�͓����ɂ��Ȃ������Ƃ��̂���т܂��B�ނ�̂����ōs�Ȃ��Ă��鈫�K��߂ɂ��āA���R�������Ă��ꂪ���ł��邱�Ƃ������܂��ƁA�����ɂ��Ȃ������Ƃ����ׂ��ł���ƍl���܂��B
�����͂���قǂ܂łɕ�����ɂ���l���������܂����Č������Ƃ�����܂���B�|�p�͔��ɗD��Ă��܂��B���̍��ɂ͔n�͂��܂���(�ނ��)�k�Ő���Ă��܂��B�ނ�͂��݂��ɗ�V���������Ă��܂����A�O���l���y�̂��Ă��܂��̂ŁA(�������O���l�ɑ��Ă�)�ނ�ǂ����̂悤�ɂ͗�V���������܂���B���Y�̂��ׂĂ͈ߕ��ƕ���ƉƐb��}�����邽�߂ɗp���A�����~���悤�Ƃ��܂���B���ɍD��I�ȍ����ŁA����������āA�����Ƃ����͂̋����҂��x�z��������̂ł��B
��(���{�l������)�D��S�������A���邳�����₵�A�m���~�������ŁA����͌��肪����܂���B�܂��ނ�̎���Ɏ����������������Ƃ�ނ�݂͌��Ɏ��₵��������A�b�����肵�����Đs���邱�Ƃ�����܂���B
�����{�l�͔��l�ł��B���{�̍��̋߂��ɂ͒����̍�������A�O�ɏ����܂����悤�ɁA(���{��)���@�h�͒�������`����ꂽ���̂ł��B�����͂����ւ�傫�ȍ��ŁA���a�ŁA�푈�͂܂���������܂���B�����ɂ���|���g�K���l����̎莆�ɂ��܂��ƁA���`�������ւ�(����Ă���)���ŁA�L���X�g�����̂ǂ��ɂ��Ȃ��قǐ��`�̍��������ł��B���{�⑼�̒n���ō��܂Ŏ������������ł́A�����l�͂���߂ĉs�q�ŁA�˔\���L���ł���A���{�l���������ƗD��A�w��̂���l�����ł��B
��(���{�֍s���_����)�l�����y�Ȃ��قǑ傫�Ȕ��Q���Ȃ���Ȃ�܂���B���Ԃ͂����ƁA�����Ė�ɂȂ��Ă��吨�̖K��q�ɉ����������A����U�߂ɂ����Ă����ւ�Ă�����A�����Ēf��肫��Ȃ��悤�Ȏw����(�K����)�l�����̉Ƃɏ�����܂��B�_���͋F��A�ّz���A�ϑz���鎞�Ԃ�����܂��A��I�ɓ��Ȃ���(�]�T)������܂���B���Ȃ��Ƃ����߂̂����̓~�T���Ղ������邱�Ƃ��ł��܂���B(�_����)����ɓ�����̂ɐ₦���ǂ��āA�������ۂ������鎞�Ԃ��Ȃ��A�H���␇���̎��Ԃ���������܂���B���{�l�͂قƂ�ǖ�肪�Ȃ��悤��(�����Ȃ��Ƃł�)�Ƃ��ɊO���l�ɂ��邳�����܂Ƃ���(���₵)�A�O���l������n���ɂ��āA�����������Ă��܂��B�@ |
���w���m���L�x�@�����f�X�E�s���g
�t�F���i���h�E�����f�X�E�s���g (Fernado Mendes Pinto, 1509?~1583) �̓|���g�K���̏��l�ŁA1537�N������C���h����n�߂ɃA�W�A�E�A�t���J���L�������A���{���l�x�K�ꂽ�B
1551�N�̎O�x�ڂ̖K�����Ƀt�����V�X�R�E�U�r�G���Ɛe���������A���̎��ɂ͑����ȍ��Y��~���Ă����B
1554�N4���Ɏl�x�ڂ̖K���̂��߃S�A�������A�r���}���b�J�ŃC�G�Y�X��̏C���m�ɂȂ����B
1556�N7���ɋ�B�ɒ����A11���ɗ����������A���̊ԂɃs���g�̓C�G�Y�X���E����B
1558�N�Ƀ|���g�K���ɖ߂�A1578�N���w���L�x���������B
�����̎��@�Ƃ����̂͂����Ԃ�s��E���ŁA�ނ�̎i�Ղɓ�����V�傽���͎�������������}���Ă��ꂽ�B���̓��{�̐l�X�݂͂Ȑ�����ςɐe�ň��z����������ł���B
�����������āA�[�C���g(���f�B�I�S�E�[�C���g)���P�ӂƗF���A�܂��A��ɏq�ׂ��悤�ɁA�i�E�^�L��(����q������)���������E���ڂ̊������ɉ����邽�߂ɑ������킸������̓S�C�����ŁA���̍��͓S�C�ɖ������ӂ�A�ǂ�Ȋ����ł����Ȃ��Ƃ��S���̓S�C�̏o�Ȃ��悤�ȑ��╔���͂Ȃ��A���h�Ȓ��⑺�ł͉�����Ƃ����P�ʂŌ���Ă���̂ł���B���̂��Ƃ���A���̍������ǂ�Ȑl�������A�����ǂ�Ȃɕ������D��ł��邩���킩��ł��낤�B
�������Ă������{�l�Ƃ����̂͐��E�̂ǂ̍����������_�S�������̂ŁA�ނ́A�����̑O�ɐ����邢���Ȃ�s�s�����ӂɉ���A�����̈Ӑ}���ɂ����Đ��s���悤�ƌ��S�����B
�����̓��{�l�Ƃ����̂́A���̂�����̑��̂ǂً̈��k���������ɏ]�����̂��A�Ǝ������x�������̂�ǎҏ����͕����Ă����̂ł͂��邪�A�V�傽���͑��̐l�X���������̂��Ƃ�m���Ă���Ƃ��������̎����S�Ǝ�����̂��߂ɁA��U�����̌��������Ƃ�ے肵����A�����̐M�p�Ɋւ���c�_�ő��l�ɏ��邱�Ƃ́A���Ƃ����̂��߂ɐ�̐������댯�ɔ������Ƃ��A���_�Ȃ����̂ƌ��Ȃ��̂ł���B
������́A�ނ炪���̂�����̑��ً̈��k�������X�D�ꂽ����͂������Ă��邱�Ƃ͔ے肵��l�X������ŁA���������āA�ނ��M�։��@�����邽�߂ɂɒ������w�͂́A�R��������Z�C�����̃V���K���l���́A���̐l�X�ɂ���������A���傫�Ȏ�������сA���������āA�����ʓI�ł��낤�Ǝv����B�@ |
���w���{���@�L�x�@���@���j���[�m
�A���V�����h�D���E���@���j���[�m (Alejandro Valignano, 1539~1606) �̓C�^���A�̐鋳�t�ŁA�C�G�Y�X��̏��@�t�Ƃ��ē��{���O�x�K�ꂽ�B
��������1579(�V��7)�N7���ŁA���������̌��V�Âɏ㗤���A����ƖL��{��(�啪)��K�ꂽ�B
���N3���ɂ͐��˓��C�q�H�ō�Ɏ���A�D�c�M���Ɋ��}����A�E���e�n�������B9���ɖL��A11���ɒ���ɖ߂�A�����ň�A�̉�c���J�Â����B
1582(�V��10)�N2��20���A�V�����N�g�ߒc�������@���j���[�m�́A������o�q���S�A�Ɍ��������B
1590(�V��18)�N7���A���@���j���[�m�͏��N�g�ߒc������ɏ㗤�����B
���N3���ɖL�b�G�g�ɉy�����A�Ԃ��Ȃ�����ɖ߂����B
1592(�V��20)�N10���A���@���j���[�m�͒�����o�q���A�}�J�I�Ɍ��������B
�O�x�ڂ̗�����1598(�c��3)�N8���ŁA���̂Ƃ��͂قƂ�ǒ���ɂƂǂ܂�A1603(�c��8)�N1���ɗ��������B
�ȉ��́A��1����{���@�ɂ��ƂÂ��Ď��M���ꂽ�w���{�����v�^�x(1583)����̔����ł���B�{���͒��炭�C�G�Y�X��@�������Ƃ��Ė����Ă������A1954�N�ɏ��߂ďo�ł��ꂽ�B
���l�X�͂�������F�����A����߂ė�V�������B��ʏ�����J���҂ł����̎Љ�ł͋��Q���ׂ���߂������ď�i�Ɉ�Ă��A���������{��̎g�p�l�̂悤�Ɍ�����B���̓_�ɂ����ẮA���m�̑��̏������݂̂Ȃ炸�A�䓙���[���b�p�l�����D��Ă���B
�������͗L�\�ŁA�G�ł�����͂�L���A�q���B�͉䓙�̊w���K�������ׂĂ悭�w�тƂ�A���[���b�p�̎q���B�����A�͂邩�ɗe�ՂɁA���Z���Ԃɉ䓙�̌��t�œǂݏ������邱�Ƃ��o����B�܂����w�̐l�X�̊Ԃɂ��A�䓙���[���b�p�l�̊ԂɌ�����e�\�△�\�͂Ƃ������Ƃ��Ȃ��A��ʂɂ݂ȗD�ꂽ����͂�L���A��i�Ɉ�Ă��A�d���ɏn�B���Ă���B
���q�{���s�Ȃ�ꂸ�A�y�n�𗘗p����Ȃ��̎Y�Ƃ��Ȃ��A�ޓ��̐�����ۂ͂��̕Ă�����݂̂ł���B���������Ĉ�ʂɂ͏������M��������߂ĕn���ł���B�������ޓ��̊Ԃł́A�n���͒p�J�Ƃ͍l�����Ă��Ȃ����A����ꍇ�ɂ́A�ޓ��͕n�����Ƃ������ɂ��ēA�d�ɑҋ������̂ŁA�n��͑��l�̖ڂɂ��Ȃ��̂ł���B
�����{�l�̉Ɖ��́A��m�ŕ���ꂽ�ؑ��ŁA�͂Ȃ͂������ł�Ƃ肪����A�Z�p�͐��I�ł���B�����ɂ͂ǂ����R���N�̂悤�ȏ~����Ă���̂ŁA����߂Đ����ł���A���a���ۂ���Ă���B
�����{�l�́A�S���E�ł����Ƃ��ʖڂƖ��_���d�鍑���ł���Ǝv����B���Ȃ킿�A�ޓ��͕��̓I�Ȍ����͌����܂ł��Ȃ��A�{����܂��t�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������āA�����Ƃ������̐E�l��_�v�ƌ�鎞�ł��䓙�͗�߂�s�����˂Ȃ�Ȃ��B
���������č����y�ї̎�́A�e���̍���\�������g�債�A�܂��h�����悤�Ɠw�߂�̂ŁA�ޓ��̊Ԃɂ͒ʏ�푈���s�Ȃ��邪�A�ꓝ�����̂��Ƃɂ���l�X�́A���݂̊Ԃł͕����ɕ�炵�Ă���A�䓙���[���b�p�ɂ���������͂邩�ɐ����͈��J�ł���B����͔ޓ��̊Ԃɂ́A���[���b�p�ɂ����ďK���ƂȂ��Ă���悤�ȑ����̓�����E�����Ȃ��A�����̉��l���Ɛb�łȂ��҂��E������Ύ��Y�ɏ�����邩��ł���B
�����{�l�͂���߂ĔE�ϋ����A�Q��⊦�C�A�܂��l�ԂƂ��Ă̂�����ꂵ�݂�s���R�������E�ԁB����́A�����Ƃ��g���̍����M�l�̏ꍇ�����l�ł��邪�A�c���̎�����A����炠����ꂵ�݂��Î�悤�K���Â��Ĉ�Ă��邩��ł���B
���܂��ޓ��́A�����\�����Ƃɂ͂͂Ȃ͂��T�ݐ[���A�����ɕ���������O���Ɏ������A���{�̏��}�����Ă���̂ŁA�{����邱�Ƃ͋H�ł���B
�����ɏq�ׂ�悤�ɁA���{�l�͑��̂��Ƃł͉䓙�ɗ�邪�A���_�I�Ɍ����ē��{�l���A�D��ŗ�V�������G�ł��V���Ɨ���͂�L���A�ȏ�̓_�ʼn䓙�𗽂��قǗD�G�ł��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��Ƃ���ł���B
���ޓ��̊Ԃɂ́A�l�|�A���f�A�����A���A���J�̌��t���Ȃ��A�܂��푈�A�ؗp�ҁA�C���̖��ڂ������ĂȂ����ꍇ�������A���݂͍s�Ȃ�ꂸ�A(�ޓ�)�s�ׂ͂Ђǂ���������A�����ɏ�������B
�������ނ�Ɍ�������̈��͐F�~��̍߂ɒ^�邱�Ƃł���A����ً͈��k�ɂ͏�Ɍ��o�������̂ł���B�c�ň��̍߈��́A���̐F�~�̒��ł����Ƃ����������̂ł����āA��������ɂ���ɂ͊����Ȃ��B�ޓ��͂�����d��Ȃ��Ƃƍl���Ă��Ȃ�����A��O�B���A�W�̂��鑊���������ւ�Ƃ��A���R�ƌ��ɂ��A�B�����悤�Ƃ͂��Ȃ��B
�����̍����̑��̈����_�́A���̎�N�ɑ��āA�قƂ�ǒ����S�������Ă��邱�Ƃł���B��N�̓G���ƌ������āA�s���̗ǂ��@��Ɏ�N�ɑ����t���A���炪��N�ƂȂ�B���]���čĂт��̖����ƂȂ邩�Ǝv���ƁA����ɂ܂��V���ȏɉ����Ėd������Ƃ����n���ł��邪�A����ɂ���Ĕޓ��͖��_�������͂��Ȃ��B
�����{�l�̑�O�̈��́A�ً��k�̊Ԃɂ͏�Ɉ�ʓI�Ȃ��̂ł��邪�A�ޓ��͋U��̋��`�̒��Ő������A�\�ԂƋ��\�ɖ����Ă���A�R����������A���ɋU�葕�����Ƃ������܂Ȃ����Ƃł���B�c���q�̂悤�ɁA�������̎v���[���������̌��x���Ȃ��Ȃ�A���{�l�̂��̐��i����A�����̓������܂��ł��낤�B�������{�l�͂���𐧌䂷�邱�Ƃ�m��ʂ���A�v���͈��ӂƂȂ�A���̐S�̒���m��̂ɁA�͂Ȃ͂������������قljA���ƂȂ�B�����ĊO���ɕ\��ꂽ���t�ł́A�����ōl����ĂĂ��邱�Ƃ��ɒm�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
����l�̐��i�́A�͂Ȃ͂��c�E�ɁA�y�X�����l�Ԃ��E�����Ƃł���B���ׂȂ��ƂʼnƐb���E�Q���A�l�Ԃ̎���a��A���̂��ɒf���邱�Ƃ́A�܂�œ��E�������Ƃ��ł���A������d��Ȃ��ƂƂ͍l���Ă��Ȃ��B�����玩���̓����������ɉs���ł��邩�������ړI�����ŁA�����Ɋ댯���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�s�^�ɂ��o���킵���l�Ԃ�^����Ɏa��҂������B�c�����Ƃ��c�E�Ŏ��R�̒����ɔ�����̂́A�����Ε�e���q�����E�����Ƃł���A���Y������ׂɁA����ɓۂ݂���A���邢�͐����(�Ԏq��)��ɑ����̂��Ē����������肷��B
�����{�l�̑�܂̈��́A�����ƁA�j�ՁA�����ɒ^�M���邱�Ƃł���B���ׂ̈ɂ͑����̎��Ԃ�����A���ӂ����O����B���̋����ɂ́A�e��̉��y�≉�����������A�����͂��ׂē��{�̏@������{�l�ɋ������l�X���l�Ă������̂̂悤�Ɏv����B���̈�����ގ��̋����A�ߐH�́A��ɑ��̑����̑����̂ŁA����ɂ���ē��{�l�̗D�G�ȓV�����͂Ȃ͂��������Ȃ��Ă���B
���ޓ��̂��Ƃ��Ƃ��́A�����̌����b�����A����͒m���Ă��鏔����̒��ł����Ƃ��D�G�ŁA�����Ƃ��D��A���L�x�Ȃ��̂ł���B���̗��R�́A�䓙�̃��e�������(��b��)�L�x�ŁA�v�z���悭�\������(���ꂾ)����ł���B
����q�̂��ׂĂ̓_�ɂ����āA�^���̐��_���ޓ��̐S�̒��ɏh��Ȃ�A�ޓ��͉䓙�����D�ꂽ�f����L����ƌ�������B�Ȃ��Ȃ�A�ޓ����V���Ƃ��ėL������̂ɉ䓙�����B����ׂɂ́A�䓙�͑傢�Ȃ�w�͂�K�v�Ƃ��邩��ł���B
���ޓ��͐������̐��i�͈ޏk�I�ʼnB���I�ł��邩��A�S��G�ꍇ�����Ƃ����C�����N�������A�[�������߂邱�Ƃ��K�v�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�M��^���Ō��łȓ����ɓ��B����ׁA�y�ѐS�̓܂�������ĕs����U�f��ނ���ׂɂ́A���{�l�̓V���ł���A�K���ƂȂ��Ă��邱�̈ޏk�I���ȂقǑ傫����Q�͂Ȃ�����ł���B
�����������Ă��̕��̒��ł��т��ь��y�����悤�ɁA�䓙���K����i�̂܂��������ł���O���l�ł���A�܂�������̓����Ƃ������ɂ͐G�ꂸ�A����ɂ���Ĕޓ�����������悤�Ȃ��Ƃ͂܂����������A�������Ċ��q�̂悤�ɑ傫���s�K����N���Ă���ɂ�������炸�A�䓙�����{�ɋ��Z���邱�Ƃ���{�l���F�߂Ă���̂͋��Q�ɒl����B����ɂ��A���{�l�������ɓ����ɏ]���l�X�ł��邩����������B�@ |
���w���{�����^�x�@�h���E���h���S
�h���E���h���S�A�{�����h���S�E�f�E�r�x���E�C�E�x���X�R (Rodrigo de Vivero y Velasco, 1564~1636) �̓��L�V�R�̐����ƂŁA�]�ˏ����ɓ��{�ɕY���������L���c�����B
1608�N6������t�B���s���Վ����Ƃ��ă}�j���ɑ؍݂������h���S�́A�������ƌ��̂���1609(�c��14)�N7�����L�V�R�ւ̋A�H�ɒ������B
�������䕗�̂��߃��h���S���悹���T���E�t�����V�X�R���͏㑍����a�c��(��t����h��)�̊C�݂œ�j���A�n�����ɋ~�����ꂽ�B
�命��ˎ�{�������Ɍ������ꂽ���h���S��s�́A�]�˂֑���꓿��G���Ɖ���A����ɏx�{��œ���ƍN�Ƃ�������B
�L��ŃT���^�E�A�i�������m�q�C�ɑς��Ȃ����Ƃ��m�F�������h���S�́A�]�˂Ɉ����Ԃ����B�����č]�˘p�ɒ┑���������j�ۂ����A�T���E�u�G�i�x���c�[�����Ɖ������A1610�N8��1��(�c��15�N6��13��)�o�q�����B
������10��27���A�����Ƀ}�^���`�F���ɓ��������B���h���S�͓��{�ŋ~������������ꂽ���߂��A�J�g���b�N�炵���Ό��͂�����̂́A���{�l�ɑ����Ȃ�D�ӓI�ł���B
�����{�ɉ��Ă͒n�k������A��g���̒ʏ퐇���������Z���鎺�͐��Ȃđ��炸�A�������I���ɍH�삵�A����̊e��̌^�y�ѐF��p�ЁA�`�ɓV��݂̂Ȃ炸�A��������Ɏ���܂ŏ�Ɍ���ׂ����̂���B�\�̓g�m�̋��肵���Ɏ��荿�ɒ����Ďb����肽���A�ނ͕���ɂ��������邪�A��ӂ̋R�m�̏��L�ɂ��炸�A�����̏��L������̂Ȃ�Ǝv�͂ꂽ��B
�����s(�]��)�y�ъX�H�ɂ��V��ׂ����r�������A�s��������Ɍ���ׂ�������B���[�}�l�̐����Ƌ��ӂ��Ƃׂ��B�s�X�݂͌ɗD��Ȃ��A�F��l�ɕ��A�����������Ē��Ȃ邱�Ɛ��lj�̎s�O�ɏ����B�Ƃ͖ؑ��ɂ��ē�K���Ȃ���̂���A�����ĊO�V�ɉ��Ă͉䂪�Ɖ��D�ǂȂ�ǂ��A�����̔��͔�ꡂɏ����B���X�H���C���ɂ��ĉ��l���V���D�܂��Ǝv�͂�T���Ȃ�B
�����ɋ{��(�]�ˏ�)�̑�ꎺ����A�����ǂ��V�������ׂ��炸�B���ƂȂ�Ώ��ɂ��g(tatames)���i���䂪�Ȃ���ꡂɔ��������̂���B�g�͒[�ɋ��̐D���A���ɂĉԂ�(�J 繡)�o����V�A�O���̏����{���A���`�ɂ��Ċ��̔@���݂ɕ����͂��ׂ��r�����I�Ȃ���̂Ȃ�B�ǂ͊F�ƔƂ��Ȃđ���A����⍂�㉋���ȂĎ���㉂��`����B�V������V�ɓ������A�ؒn�͌��邱�Ƃ��B�䓙�O���l�͍��̑�ꎺ�ɂ��V���鏊�ɏ��肽����͖̂]�ނׂ��炸�ƍl�ւ��ɁA��͔V���D���A��O���͍X�ɔV�ɏ���A���ɐi�ނɜn�Љv�X�I���ɂ��Ĕ���Ȃ�B
���\�͌ܓ��ԗ��s���ďI�ɏx��(Surrunga)�ɒ��������A���q�̘����Ɉ˂�e���ɉ��đ�Ɋ��҂���ꂽ��B�Ⴕ�����Ől�̊ԂɃf�E�X㞂����A�䚠���̐b������A�\�͌Ë����̂āT���n��I��Ƃ��B
���x�͂��s�܂Ŕ��\���O���ɂ��āA���͕��R�ɂ��Ė����Ȃ�B�r���Ɍ̐������͂���ǂ��A�����葼���ɉg�D�ɂēn��A�D�͐r����ɂ��ė��q�̔n���R�ɔV�ɓ��邱�Ƃׂ��B���q�ґ��ɂȂ�ǂ��r�����l�̒n�ɏh�����邱�ƂȂ��B���ƂȂ�ΑO�ɏq�ׂ���@���A���{�����ꃌ�O���̎l���̈�̕s�т̒n�Ȃ��A�Ⴕ�����ɂ��ĉƉ��|�X�ɎU�݂��������Ə��Ȃ����A���̔@���A��ɂ��Č�ʐ��ɁA���X�H�y�щƉ����C���Ȃ钬�X�͐��E�̉���̚��ɉ��Ă����邱�ƂȂ����Ɗm���Ȃ�B
���\�͎v�ӂɁA�c�n(���)�͓��{�����ł����h�Ȃ鏊�ɂ��āA�l���͓�\�݂���A�C�����Ɖ��ɔg�ł��̂ɁA���ɏ��V�ɊC���̑�������L����B�Ɖ��͓�K����ʏ�Ƃ��A�\���I�Ȃ�B
�����{�l�͝D���D�݁A�x�ߐl�A����l�A�e���i�e�l(Therenates)�����}�j���t�߂̉���̚��������E���Ȃ�B�ޓ��͒��e��p�ЁA��ᢎ˂͊m���Ȃ�ǂ��A���x�x���B����C��L����ǂ��A���ɂɂ��đ����قȂ�B�Dूɉ��Ă͍D�����߂ɕ��n���B�A�����͉����Ƃ��D�͂��A���V�ƝDू��J���҂���ׂ��Ƃ��v�͂ꂸ�B��x�ߎႵ�����͂�p�ӂ邱�Ƃ�����A���{�ɂ͒n����U�וs�\�Ȃ�鑽�ɂ���B
�������͓V�̎���������ʗD�ǂȂ镨��L���A����̓C�X�p�j���̟���Ɏ�����A�A���~��ꡂɊ��w�Ȃ�B�_��y�щu�a��m�炸�A�����b�����邱�ƂȂ��B�����̍ő�Ȃ�s�K�́A�n���ɛ�����x�҂ؔ̚����g�Ȃ�B�R��ǂ����m�A���m�y�ѕĂɕs��̔N�Ȃ��A���n���ʂȂ邪�̂ɁA�\�����l��{�ЁA�J��O���̐l�y�ёD�̘҂�ėƐH��A�o���Ƃ���]����B
�����{�l�͈����̈��Ȃ���A�V��葼�̍X�ɑ�Ȃ霦�����A�����Ȃ̗L����Ȃ��Ȃğޑ������A�͂̌���������Ƃ��A���ɂ͕S�l��邱�Ƃ���B�ޓ��͍Ȃɛ����Ē����Ȃ炴��ǂ��A�ޏ����͔V�ɔ����A�ł�����w�l�̕v�ɔw���ĕs�`���s�Ђ�������Ƃ͐r���H�ɂ��āA���������Ȃ�B���{�l�͐r���s�q�Ȃ�ǂ������Ȃ炸�A���̂ɍI���ɂ��āA���Ƃɉ��đ��l���\�����ƍł��I���Ȃ�҂d���B
�����{�͏��đ��̚������s��ꖔ�͐�������ꂽ�邱�ƂȂ��B�x�ߐl�y�э���l�͘҂�D�ӂ��ƝɎ��Ȃ肵���A��Ɏ���c�āT���҂����邱�Ƃ͑��̐l�B�̋L���邪�@���B�ޓ��͉n�m�ɂ��Č݂��X�V���d�B
���ޓ��̎s���͗D�ǂɂ��āA�V�����ނ�҂͔��Ȃ钍�ӂ��ȂČ������c���B�Ɖ��͐r���C���ɂ��āA�s�O�Ɏ��閘����C���ɂ��B���y�n�͋���ɕx�݁A�Ⴕ�i�v�y�ѐ��₠��X�ɑ��ʂ����ނׂ��B���m�̓C�X�p�j�������ǂ��A�Y�z�����ʂɂ��Ēʏ�1�A�l�K(�t�A�l�K(Fanega)�ɂ���64�A6�A���A(1�A���A��10m�������c��)���50�A�l�K(Fanega���ʂɂ���1�t�A�l�K55.5���b�g�����c��)�����[����ǂ��A����̐H���͕ĂȂ�B�p��(pan)�͉ʕ��̔@�����ʂɐH���A���͎��Ɉ˂�ĎE��������́T���̊O�͐H�����B���؋y�ы��Ƃ̊l���͎��E�e�E�G�E��������y�ьΏ�̒��ޓ��䓙���������L����B
�����{�l�̐����͐��E�̏����ɏA���ė\���m����̂ɏ����B�f�I�X(Dios(�_))�����炴�隠���ɂ��āA���̔@�����S�ɂ��Ď��߂ɓK�ւ�@����L����͊��X�������Ǝv�͂�B�����ɉ��Ă͑O�ɏq�ׂ��邪�@���A�����͊F�����邪�̂ɁA���������ޓ���ਂ߂ɓ��H�̕s���Ȃ鎖�S�R�Ȃ��B
���w�l�͎��ҋ��Ȃ����ĉł��A�M�l�y�ё�g�B�͑��g���ɑ��c�Ȃ�ƍl�ӂ�ɂ̕v�l��L���A����50�l60�l��邱�Ƃ���ǂ��A�����Ȃčł���Ȃ�v�l�Ƃ��A���l�̎q�����ł����h���B�R��ǂ����̉���̕v�l���K�����T���V�J�ƂȂ����Ƃ��B�r���n���Ȃ�҂͗B��l��{�ЁA���͑����͂ɜ䂶�ē�l���͎l�l��{�ւ�B
�����{�����͗E�������ɂ��āA�V���ւ邱�Ǝv�����闝�q�̐l�̔@���Ȃ炸�J����Ől�Ɏ�����B���ƂȂ�Κ`�ɝD��ɉ��ėE���Ȃ�݂̂Ȃ炸�A�Ⴕ�ƍ߂�ਂߎ��Y�̐鍐�����鎞�́A�Y���̔V�����s�����~�����A���E���邪�̂Ȃ�B
�������l�͕����o�ӂ�ə�Ȃ�B�����}�ɂ��ĔE�n�Ȃ炴�����Ƃ��B
�����Z�\�Z�Ӛ��ɂ͑��ɂ̓s�s����A�A��ɂ��Đl�������A�C���ɂ��Ē����������A���F�ɉ��ĔV�Ɣ�r���ׂ����̂�ᢌ����邱�ƍ���Ȃ�ׂ��B�����ė��H���s�����Ɠ�S���O�������l�̋��Z������n�ꃌ�O�������邱�ƋH�Ȃ�B�Ɖ��s�X�y�я�s�͑P���ɂ��āA������ߏ܂��邱�Ɠ�B�l���̝ɔ��ɑ����A���������ɗe��T���Ɣ\�͂��邪�@���B�l����\�݂̎s�����A�s�̎s�͔��\�݂�����B�����̏Z���Ⴕ�C�X�p�j���y�l�̔@�����łȂ����T�ɑ��炴��ǂ��A�ޓ��͒��e��L���ł��n�����镺�m�̔@���I���ɔV��p�ӁB���|�A��A���A�y�уJ�^�i(cathanas)���i���陘�y�ђZ����L���B�����ăC�X�p�j���l�Ɠ������E���Ȃ�݂̂Ȃ炸�c�_�y�ї����̔\�͂ɉ��Ă��V�ɗ�邱�ƂȂ��B
�����̂ɚ����ɂ͏�ɐr�����ɂ̕������镺�m����ƌ��ӂ��Ƃׂ��B���͂��薼棂��d�隠���Ȃ邪�̂ɁA���E���ɕt�\���ɐM�����邱�Ƃׂ��B�����ČR����̌P���ɉ��Ă͉䓙�ɗ�鏊����ǂ��A�������j���Ƃ��邱�Ƃɉ��ẮA��鏊�Ȃ��݂̂Ȃ炸�A���O����ਂߔV�����ӎ҂����ɂ���B�@ |
���w���Ⓡ�T���x�@�Z�o�X�e�B�A���E�r�X�J�C�m
�Z�o�X�e�B�A���E�r�X�J�C�m (Sebastian Vizcaino, 1548~1615) �̓X�y�C���̒T���ƂŁA���{�̓����ɂ���Ƃ��ꂽ�`����̋��Ⓡ�T���̖ړI�������ĖK�������B
�h���E���h���S���A������ƁA�r�X�J�C�m�͓����g�ɔC������A�T���E�t�����V�X�R����1611�N6��10��(�c��16�N4��30��)�Y��ɏ㗤�����B
�]�˂œ���G���A�x�{�œ���ƍN�ɉy����A�Y��ɖ߂��ċ��Ⓡ�T���̏�����i�߂��B10�`12���ɂ͓��k�n����T�����A�����o�č��P�܂Ŗk�サ�A��������]�˂Ɉ����Ԃ����B
1612(�c��17)�N5�`7���ɂ́A���s�E���E���K��č]�˂ɖ߂����B9��16��(�A��8��21��)�悤�₭�Y����o�q���A���{�̓�����T���������A�䕗�ɑ����ĒT����f�O���Y��ɖ߂����B
�T���E�t�����V�X�R���͔j�������������߁A�ɒB�Ƃƌc�������g�ߒc�̃T���E�t�A���E�o�E�e�B�X�^���ɓ��悷��_������B������1613�N10��27��(�c��18�N9��14��)�o�q���A12���T�J�g���ɓ��������B
�r�X�J�C�m�͍]�˂ł̌��Ղ��s����������ɋ��Ⓡ�������ł��Ȃ��������߂��A��������C���ɓ��{�l�̈�������ׂĂ���B
�������ɉ��Ă͍c����̎哙���������m����S�Ȃ鎖�Ȃ��B�W�����̐l�X�̊��E��L����͖\�͂ɝ��鏊�ɂ��āA�͑����ґ����B�����邪�̂Ȃ�B
���M�����X�V���������A�����ĐS�A�v�펯�y�і��S��ɂ��āA�����y�ѕ�����d�B���O���邪�̂Ɏ������z�Ȃ�ǂ���ɕ���L���B���̔@���Ȃ�͖��c��̎�(����̈ӂȂ�)�Ɉ��鏊�Ȃ�B
����ʐl���͐r���������A�\�͔V���֒����邱�Ƃ��D�܂���ǂ��A���E�ɉ��čł��Ȃ�҂Ȃ�B�ޓ��͋��A��ਂߎq���y�эȏ����̋p���B
�����Q�l���͖��E�̐l�Ȃ��B�ޓ��̐����͉��Ɉ˂邩���ɖ����ƂȂ�O���ȏ�ꏊ�ɋ��邱�Ƃ��邪�̂ɂ��āA�E������l�����҂�ᢌ�����ΔV���a��B
�������͒����y�ѕ��ܕS���O�����ɌW�炸�A����͈�ɂ��ĕ����̏�������l�Ȃ�B�j�����ɊF椂ݏ������v�Z���Ȃ��A���̂̎��ɐr���@�q�ɂ��ėP���l���ޓ��ɂ͋y���B���_�͍��̜����������ɑ���]���鏊�������o���ւ邪�@���A�r���D��ɂ��ĉu�a�̉����邩��m�炸�A�a�̗��s���邱�ƂȂ��A�����Ζ��͊O���̕K�v�Ȃ��B
���ޓ��͑�Ȃ�҂����Ȃ�҂��F��������������Ȃ��A��N�̑啔���͔V���s�ւ�B�̎�y�юi�Ղ͈�w�r�������F��ق̐������Ȃ���B�@ |
���w���{�剤���u�x�@�t�����\�A�E�J����
�t�����\�A�E�J���� (Francits Caron, 1600~1673) �̓t�����X�n�I�����_�l�ŁA�I�����_���C���h��Ђ̓��{���ƂƂ��Ċ��A���˂̃I�����_���ْ����Ƃ߂��B
�J������1619(���a5)�N�A�f�ՑD�̗�������`���Ƃ��ď��������A1626(���i2)�N2���ɂ̓I�����_���ُ���ɂȂ����B���̍��ɂ͓��{��ɔ\�ʂ��Ă���A���N�ɂ͑�p�����s�[�^�[�E�k�C�c�̍]�ˎQ�{�̍ۂɒʖ���Ƃ߂��B
�k�C�c�ɏ]�����������p�ɓn�������A�����D�S�������ŕߗ��ƂȂ�A�呺�ɗ}�����ꂽ�B
1630(���i7)�N5���Ƀo�^�r��(�W���J���^)�ɕ����ď���A10���ɂ͌��̂��ߓ��{�ɖ߂����B
�悤�₭1632(���i9)�N�ɃI�����_�D�o�q�֎~�̉������������A���̂̕��߃o�^�r���ɕ������B
1633(���i10)�N�ɂ͏��ْ����ȂƂ��ĕ��˂ɕ��C���A1634(���i11)�N3����1636(���i13)�N5���ɓ���ƌ��ɉy�������B
1636�N6���ɂ͕��˂ɖ߂�A�o�^�r���������ăt�B���b�v�X�E���J�X�]�[���̎���ɓ����āw���{�剤���u�x�����M�����B
�����̗��̍Œ���1638(���i15)�N���A�J�����̓o�^�r���ɕ����A�����ŕ��˂̃I�����_���ْ��̎��߂����B9���ɕ��˂ɖ߂�A1639(���i16)�N2���̑O���ْ��j�N���X�E�N�[�P�o�b�P���̗����ƂƂ��Ɋْ��E���p�����B
6���ɃJ�����͖��{�Ɍ��サ�������C�̎��˂��ōs���A���{�����������B
1640(���i17)�N4���A�J�����͍]�˂ɎQ�{�����ق�Ɉڂ��v���j�~���悤�Ɖ^���������͂��������Ȃ��A�ƌ��ւ̉y�������Ȃ�Ȃ������B
11���A���˂Łu���㏤�ْ��͈�N�ȏ���{�ɑ؍݂��ׂ��炸�v�Ƃ̖��߂����J�����́A������������ė��N2��������o�^�r���Ɍ��������B
�w���{�剤���u (Besechrijvinghe van het machtigh Coninckrijck Iapan) �x��1645�N�ɃI�����_�ŏo�ł���A�P���y���́w���{���x���o��܂ŗB��̓��{�Љ�Ƃ��ďd�����ꂽ�B
���ʒu�̍������킸�A�v�l�͂��ׂĐ�����܂��͎Љ�I�̎��ƂɊW�����A��ӎ�l�Ɏd���邱�Ƃɗ͂߁A���ꂪ���̎��ׂ����ł���Ƃ��ċ������Ă���B���ɐq�˂����ʼn���̕Ԏ����A��l�͓{���Ē��ق���̂��ʗ�ł���B�̂Ɍ����v�l�͎�l���|���s�������N�����ʂ悤�ɒ��ӌx������B
�����߂�嫂����ɓ�����B���ɓ��݂͂��Ƃ���X�^�C�t�F���ł����ɒl���B�q���͎��߁A�E�l�͉ߎ��ł����Ă��A�d�E�ł����Ă����߁A���̑���X�̖{���Ŏ��Y�ɓ�������̂͊F�����ł����l�ł���B�Y�@��̎����͌l�̔ƍ߂ɂ��l�����ɏ�������݂̂Ȃ炸�A���E�Z�E��y�ђj�q�͘A�����ĎE����A�����Y�͖v�������A��E�o���y�я��q�͓z��ɉ����ꔄ�p�����B
�����{������ɖ��C�̂悤�Ɍ�����w�l�́A�ߒɂ̐F���������A�]�e�בR�Ƃ��Ď��ɏA���B
�����̍����͓��ɖ��M�I�ł�������Ώ@���I�ł������B�ޓ��͒��[�A�H�V�E�H��E���邢�͎��X�F�邱�Ƃ������B�ꃕ���Ɉ�x���@�ɎQ�w����҂͐M�S�[���ƌ��킴��ʁB
���m�����ɋM����g���ɂ͒j�F�ɉ���Ă�����̂����邪�A�ނ�͂�����߂Ƃ��p�Ƃ����Ȃ��B
���v�w�̊ԂɎ��R�I���͖����B�}�������͑o���̗��e�A���e��������ł��߂��e�ʂ̑��k���肷�鏊�ł���B��v��w��{���Ƃ��邪�A�Ȃ��v�̋C�ɓ���ʏꍇ�A�v�͓K�������_������@���ȂčȂ𗣕ʂ�����B
���ނ�͎q���𒍈Ӑ[���܂��_�a�ɗ{�炷��B���Ƃ��I�錖�����������苩�肵�Ă��A�ŝ����邱�Ƃ͂قƂ�ǁA���邢�͌����Ė����B
�����̍����͐M�p���ׂ��ƔF�߂���B�ނ�͑��̖ړI�ł��閼�_��簐i����B�܂��p��m����ȂĖ��ɑ����Q�����Ƃ͖����B�ނ�͖��_���ێ����邽�߂ɂ͊��Ő������̂Ă�B�@ |
���w�]�ˎQ�{���s���L�x�@�P���y��
�G���Q���x���g�E�P���y�� (Engelbert Kaempfer, 1651~1716) �̓h�C�c�̈�w�ҁE�����w�҂ŁA1690�`92(���\3�`5)�N�ɃI�����_���ق̈�t���߂��B
�ݔC����1691�N2���`5����1692�N3���`5���̓�x�ɂ킽���āA����E�]�ˊԂ����������B
�����w���{�� (Geschichte und Beschreibung von Japan) �x�͎����1717�N�ɂ܂��p��{���o�ł���A�h�C�c��ł�1777�`79�N�ɂ悤�₭�o�ł��ꂽ�B���m���ɔł́A���̑��͂ɓ�����B
�����ꂩ��n�ɏ���Ă�����{�l�́A�������猩��Ɣ��Ɋ��m�Ȏp�������Ă���B�Ȃ����Ƃ����ƁA���{�l�͌����w���Ⴍ�������L���̊i�����Ă��邵�A���̂����n��ő傫�ȖX�q�����Ԃ�A�����L���ӂ���O���𒅁A�_�u�_�u�̃Y�{�����͂��Ă���̂ŁA�w��Ɖ������قƂ�Ǔ������炢�ɂȂ��Ă��܂�����ł���B
���c���⑺�̕֏��̂��́A�n�ʂƓ��������ɖ��ߍ��W���Ȃ��J�������̉��̒��ɁA���̈��L������̂���������Ă���B�S�������������H�ׂ�卪�̕������ɂ���������ɉ����̂ŁA�V�������������̊���y���܂���̂ɁA����Ƃ͔��ɕ@�̕��͕s�����������ɂ͂����Ȃ����Ƃ��A���z���������������B
�������Ăǂ�ȏ������ł����ꂢ�ɏ����Ă����āA�����łȂ��̂����邱�Ƃ��Ȃ��̂́A�����̍ޗ��ł��Ƒ���邩��ł���B�]���Ă��ꂢ�ɂ��Ă������Ƃ���w�e�ՂȂ̂ł���B�Ƃ͐��⏼�̍ޖŌ��Ă��A�O������֕��ʂ����ǂ��悤�ɊJ���������Ƃ��ł���̂ŁA��ւN�I�ȏZ���ƍl���Ă悢�B
���������Ȃ���A�����̖@���������ɍl�@����ƁA�����L���X�g���k�̍��X�����A���̑傫�Ȉً��̍��ł́A�Y�ꂪ�l�Ԃ̓��̂Ŗ������A�ƍߐl�̌��ʼn��邱�Ƃ͏��Ȃ��B�����͎����̐���������قǂƂ��v���Ă��Ȃ����̃^�^�[���l�I�ȋ���ȍ������A�S����������Y�ɑ��鋰�|�̔O�Őr�������}������A�ƍ߂̌������\�ɂ��Ă���B
�������璆���l�����{�̍����A�����̔��t�h�ƌĂ͕̂s���ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ璆���ł͏��ƂƔ��t�Ƃ͌������ۂ��Ă�����֎~���Ă��邩��ł���B������Ⴂ�����l�͏�~�����܂��K���̂ĂɁA�悭���{�ɂ���Ă���̂ł���B
�����āA���肩��̓����҂̂悤�ȁA�l�Ԃ̂����݂����ȘA���͏��O���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���ق̎�l��̗�V������������A���{�l�̗�V�����������肳���B���s���A�ˑR�̖K��̐܂�ɂ���ꂪ�C�t�����̂ł��邪�A���E���̂����Ȃ鍑���ł��A��V�Ƃ����_�œ��{�l�ɂ܂�����̂͂Ȃ��B�݂̂Ȃ炸�ނ�̍s��́A�g���̒Ⴂ�S������ł��g���̍����喼�Ɏ���܂ő�ւ��V�������̂ŁA�����͍��S�̂��V��@�������鍂���w�Z�ƌĂ�ł��悩�낤�B�����Ĕނ�͍ˋC������A�D��S�������l�����ŁA���ׂĈٍ��̕i�����ւ�厖�ɂ��邩��A����������邱�ƂȂ�A�������O���҂Ƃ��đ�ɂ��邾�낤�Ǝv���B
���Z���͋ϐ����Ƃ�Ă��ď����ł���B���Ƃɕw�l�Ɋւ��ẮA�A�W�A�̂ǂ�Ȓn���ł��A���̓y�n�̏����قǂ悭���炵�������l�ɏo����Ƃ͂Ȃ��B�����A���������Ă�Ɣ�����h���Ă���̂ŁA���������̊y�����ŘN�炩�Ȋ�������C���������Ƃ��Ȃ�������A�����͔ޏ������𑀂�l�`���Ǝv�����ł��낤�B
�������̏h��͂���̏����������̎�O�ɂ́A�ӂ�����ȏ������吨�����B�ˊO�ɂ͉�J�ł��Ԃʂ�ɂȂ����m���̑m�������Ԃ��ɂȂ��Ă����B����ł��܂������Ă���؋��ɂ��߂������o���Ă����̂ŁA�݂�Ȃ͔ނ̂��Ƃ�����ł���Ƃ͍l�����A��r������Ȃ��悤�ɂ��Ă����B�������A���܂𗬂���������Ȃ�����������ʂɂ��A���{�l�͑S����W�ł������B�@ |
���w�x�[�����O�̑�T���x�@S�E���N�Z��
S�E���N�Z�� (Sven Waxell, 1701~1762) �̓X�E�F�[�f���l�ŁA���V�A�C�R�ɓ���1733�`49�N�̃x�[�����O�̒T���q�C�ŕ����߂��B
�T���̈�Ƃ��āA1739(����4)�N�ɂ͓��{�������s�Ȃ��A�X�p���x���i�߂̑��D�u�V�g���~�J�G���v���ƃ����g�����w�߂���������D�u��]�v�����͂���A�ʁX�ɓ��{�l�ƐڐG�����B
������Ɠ�ǂ̋��D�������Ă����B�������D�ɏオ���Ă��āA�V�N�ȋ��A�āA�傫���^�o�R�̗t�A���Ђ��ɂ����L���E���Ȃǂ��͂��߂��낢��ȏ��������蕨���Ђ낰���B��������낤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A���v�����ɁA�����������������ƌ������Ăق����Ƃ����ԓx�����Č�����̂ł������B�ނ�̌��Ցԓx�͂����Ԃ鍇���I�ŁA�Ꭿ�������ɍ������̂ł������B
���X�p���x���́A���{�l�̊ώ@�Ƃ��̌`�Ԃ����̂悤�ɕ`���Ă���B���{�l�́A�Ȃ�Ȃ悵�Ă��Ĕ���s�\���Ȋ����ŁA�g�������͒��w�Ɍ����邪�A����Ȃ�ΐ����������܂����s�҂Ƃ����悤�Ȓj�ɑ������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B
�����̂͂��߂ė����M���́A�ӂ����юp���������B����ǂ͂��̑D�ɂ��낢��ȍׂ��ȕi����ς�ł��āA����킹�邩�A�܂��̓��V�A�̕i���ƌ����������l�q�����Č������B�Ȃ��ł��ٍʂ���������̂́A�����̐��ߖ����o���Ă��郊���l���ł������B�i�߂����E������قǂ��炵�����ߐF�̏o�Ă�����̂��������Ƃ��Ȃ��Ƃ����Ă����B
���X�p���x���i�߂́A���̌コ��ɐ����ɂ킽���ē��{�̉��݂��܂���āA�Ԃ��ɂ��̎��Ԃ��ώ@�������ʁA���̍��͗e�ՂȂ�Ȃ����ł��邱�Ƃ�m�����B�ނ́A�悭�����̍���ڂ����ė������̂Ɗ�тɂ����Ȃ������B���̈�[�������Ă݂�Ƃ��Ă��A�܂����̖����̑D�������������ł��킩�邱�ƂŁA���[���b�p�Ō�������̂Ɣ�r���Ă��A�������Č����Ƃ�̂��Ȃ��D�G�Ȃ��̂����Ȃ��Ȃ��B�������ݕ������W���Ă݂Ă��A�\���ɂ��̗D�G�ȕ����f���Ă���B���̑��͂����ɂ�����A���̔\�͂͂��Ȃǂ�Ȃ��������������Ă���B�ނ͌�������߂āA�悭�����̍��ɗ��邱�Ƃ��ł����A���{�����A�₪�Đe�������Ԃׂ����ł���Ƌ��B�@ |
���w�]�ˎQ�{���s�L�x�@C�EP�E�c�����x���[
C�EP�E�c�����x���[ (Carl Peter Thunberg, 1743~1828) �̓X�E�F�[�f���̈�w�ҁE�A���w�҂ŁA1775(���i4)�N8���ɒ���ɒ����A���N�t�ɃI�����_���ْ��t�F�C�g (Arend Willem Feith) �̍]�ˎQ�{�ɐ��s�A���N12�����������B
�w1770�N����1779�N�ɂ킽�郈�[���b�p�A�A�t���J�A�A�W�A���s�L (Resa uti Europa, Afrika, Asia, förrättad ären 1770-1779) �x��1788�`93�N�ɂ����ăX�E�F�[�f���ŏo�ł���A���m���ɔł͂��̓��{�Ɋւ��镔��(��3���̑S���Ƒ�4���̈ꕔ)�ł���B
�����{�鍑�́A�����̓_�œƓ��̍��ł���A���K����ѐ��x�ɂ����ẮA���[���b�p�␢�E�̂قƂ�ǂ̍��Ƃ܂������قȂ��Ă���B���̂��ߏ�ɋ��ق̖ڂł݂��A���ɏ]����A�܂����ɂ͔���Ă����B�n��̎O�啔���ɋ��Z���閯���̂Ȃ��ŁA���{�l�͑�ꋉ�̖����ɒl���A���[���b�p�l�ɔ䌨������̂ł���B�������A�����̓_�Ń��[���b�p�l�ɒx����Ƃ��Ă���ƌ��킴��Ȃ��B���������ł́A���Ɍ����ɂ݂ă��[���b�p�l�̂����������Ă���Ƃ������Ƃ��ł��悤�B���̍��Ɠ��l���̍��ɂ����Ă��A���ɗ����x�ƊQ������ڂ����x�A�܂��͗��ɂ��Ȃ����@�߂ƕs�K�Ȗ@�߂̗������������Ă���ƌ�����B�������Ȃ��A���̍������̐����ɂ݂��錘�����A�@�̎��s��E���̐��s�ɂ݂���s�ϐ��A�L�v����Njy�������i���悤�Ƃ��������̂���܂���M�ӁA������100�����̑��̎����Ɋւ��A��X�͋��Q������Ȃ��B���̂悤�ɁA���܂˂����[���c�����A������A�����Č݂��������Ă��邱��Ȃɂ������̍���������Ƃ������ƁA�������͒N��l���O�֏o�邱�Ƃ��ł����A�O���l�͒N��l���Ȃ��ɂ͓����ł����A�������������ꂽ�悤�ȍ��ł��邱�ƁA�@���͉���N���������ꂽ���Ƃ��Ȃ��A�܂��@�̎��s�͗͂ɑi���邱�ƂȂ��A�����̐l���̐g��ɊW�Ȃ��s�Ȃ���Ƃ������ƁA���{�͓ƍٓI�ł��Ȃ��A�܂�����ɌX���Ȃ����ƁA�N����b�����������Ɠ��̖����ߑ����܂Ƃ��Ă��邱�ƁA�����̗l�����Ƃ肢����邱�Ƃ͂Ȃ��A�����ɐV�������̂��n��o����邱�Ƃ��Ȃ����ƁA�����I���̂������O������푈����������ꂽ���Ƃ͂Ȃ��A�������̕s���͉i�v�ɖh����Ă��邱�ƁA��X�̏@���@�h�����a�I�ɋ������Ă��邱�ƁA�Q��ƋQ�[�͂قƂ�ǒm���Ă��炸�A�����Ă������H�ł��邱�ƁA���X�A����炷�ׂĂ͐M���������قǂł���A�����ɐl�X�ɂƂ��Ă͗����ɂ����ꂵ�ނقǂł��邪�A����͂܂����������ł���A�ő�̒��ڂ��Ђ��ɒl����B
���ʎ��͗m���̑判�D�Ƃł���A���{�ւ���Ă��鏤�l���疈�N����Ȃ��������̗m�����w������B�ނ�͖{�����L���Ă��邾���łȂ��A�����M�S�ɓǂ݁A���w���Ƃ��L������B���̏�A���[���b�p�l���牽�����w�ڂ��Ƃ����ӗ~�ɔR���Ă���A�����鎖���A�Ƃ��Ɉ�w�A�����w�A���R���Ɋւ��Ă����������̎�������т���̂ŁA�������肳������B
�����{�̓�����͘m���g���Ă������J�ɂ�����Ɖב��肳��Ă���̂ŁA�A�����Ɋ���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B����瓩����ނ́A�����ڂɂ͂������ɔ����������ł��Ȃ��A�ǂ��炩�Ƃ����Αe��ŁA���ڂ���������ȓh��ł���B���������Ă��̓_�ł́A�L������A�o����钆�����i�ɂ͗y���ɗ�邪�A�M�ɋ����Ƃ�������������A�̏�ɂ����Ă��ȒP�ɂЂъ��ꂷ��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B
�����{�l�ɂ͕��C�ŕ�������Ƃ������Ȃ�����B���[���b�p�Ȃ�Α�ςȕs��@�ƂȂ邪�A���{�l�͒p���ׂ����ƂƂ͎v���Ă��Ȃ��B���̓_�ł́A��V���킫�܂����������Ɠ�����������Ƃ��Ă�B
���܂�������قɎv����̂́A�c�����ɂ��̂悤�ȉƂɔ����A�����ň��̔N�����߂����Ɗ��S�Ȏ��R�����߂����w�l���A�͂������߂���悤�ȖڂŌ����邱�ƂȂ��A��ɂ������ʂ̌��������邱�Ƃ��悭���邱�Ƃł���B
�����{�l�ɂƂ��āA��ʂ�㵒p�͂��܂�����ł͂Ȃ��A�܂��s��͂Ђ낭�s�Ȃ��Ă���悤�ł���B�����͎��ǂ��d��̂Ȃ��ꏊ�œ������Ă���A�I�����_�l����x�Ȃ炸�ڂ̑O�₻��ʂ��Ă��A�g���B���悤�ȋC�z�͂قƂ�ǂȂ��B
�����{�͈�v��w���ł���B�܂������̂悤�ɕv�l���Ƃɕ����߂Ă����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�j���Ɠ��Ȃ����莩�R�ɊO�o���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�H���Ƃ̂Ȃ��ł��̍��̏������ώ@���邱�Ƃ́A���ɂƂ��ē�����Ƃł͂Ȃ������B
�����������������҂Ƃ͂������ʂł���̂́A�����������Ă��邩��ł���B���{�l�̍D�݂ł͍������͂܂��������������̂Ƃ���Ă���B�����A�唼�̍��Ȃ�Ƃ���v�����������Ă��܂�������̂��B�傫�Ȍ��ɂ��炬�炵����������������̂́A���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͏X���s���Ȃ��̂ł������B
�����̂悤�ȏɁA���͋��Q�̊���ӂ����B��Ƃ͌���ʂ܂ł��A���Ȃ��Ƃ���������Ă͂��Ȃ��Ɖ�X���l���Ă��鍑�����A���Ƃ��Ƃ����ɂ��Ȃ����l����A�����ꂽ�K���ɏ]���Ă���l�q�������Ă����̂ł���B����A�J������Ă��郈�[���b�p�ł́A���l�̈ړ���X���͂���قƂ�ǂ̐ݔ����A�܂������̏ꏊ�ɂ����Ă܂������s�\���Ȃ̂ł���B
�����ڂ��ׂ����ƂɁA���̍��ł͂ǂ��ł��q�����ނ��ł��Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B�q���ɑ���֎~��s���̌��t�͖ő��ɕ�����Ȃ����A�ƒ�ł��D�ł��q����łA�@���A����Ƃ��������Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B�܂������Q���킵�����ƂɁA�����Ƌ��{�������Đ�������Ă���͂��̖����ɁA���������s�ׂ��悭������B�w�Z�ł͎q�������S�����A���ɍ������ňꏏ�ɖ{��ǂށB���̂悤�ȑ��X�����ꏊ�ł́A�قƂ�ǒ��͂��������悤�ɂȂ�B
�����̍��̂��ꂢ���Ɖ��K���ɂ����āA���Ă���Ȃɂ��C�����ǂ������ł����̂̓I�����_�ȊO�ɂ͂Ȃ������B�܂��l���̖L�����A�悭�J�����ꂽ�y�n�̗l�q�́A���t�ł͌����s�����Ȃ��قǂł���B�������n������A���̗����ɂ͔엀�ȓc���ȊO�̉������Ȃ��B
�����̓��[���b�p�l���ő��ɓ����ł��Ȃ����̍��ŁA�������̊ԂɁA���������̐A������������̏W���邱�Ƃ��ł���ł��낤�Ƒz�����Ă����B���������������]�݂��A���̍��قǓ��Ă͂���ɂȂ������͂Ȃ��B���͂����ŁA�قƂ�ǎ펪�����I���Ă����k�n�Ɉ�{�̎G�����猩���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����͂ǂ̒n���ł����l�ł������B���̂��肳�܂ł́A���l�͓��{�ɂ͎G���͐����Ȃ��̂��Ɨe�Ղɑz�����Ă��܂����낤�B���������ۂ́A�ł��v��ȐA���w�҂ł���A�悭�k�삳�ꂽ���ɖ��m�̑��ނ����������Ȃ��قǂɁA�_�v�����ׂĂ̎G������O�ɓE�݂Ƃ��Ă���̂ł���B
���e�Ƃɕs���Ȏ��I�ȏ���(��)�́A���{�̑��ł͏Z���ɗאڂ��ē��H�Ɍ����Č��Ă��Ă���B���̉����͊J���Ă���̂ŁA�ʂ肷����̗��l�͕\����A�傫�Ȓق̂Ȃ��ɏ���������B�ق̉����͓y���ɖ��߂��Ă���B�A�╳�A�܂��䏊����̋��ނ́A�����ł͍k�n��엀�ɂ��邽�߂ɋɂ߂ĒO�O�ɏW�߂��Ă��邪�A���M���ɂ�������������ɋ���������قǂ̈��L����������B
���]�˂Ɠs�����ԊX���̂��������ɁA�����Ă��͑��ɏ�Q�̂����H�������B���̍��̑��̏ꏊ�ł͏�Q�҂͂����H�������̂ŁA����͎��ɂ͋ɂ߂Ĉُ�Ȃ��ƂɎv��ꂽ�B
�����{�l�͑̊i���悭�_��ŁA���x�Ȏl����L���Ă���B�������ނ�̗̑͂́A�k���[���b�p�l�̂���ɂ͋y�Ȃ��B�j���͒��w�ŁA��ʂɂ��܂葾���Ă��Ȃ����A���͂悭�������l�������B
����ʓI�Ɍ����A�������͌����ɂ��Ďv���[���A���R�ł���A�]���ɂ��ė�V�������A�D��S�ɕx�݁A�ΕׂŊ�p�A�ߖ�Ƃɂ��Ď��͈��܂��A�����D���A�P�ǂŗF��Ɍ����A�����ɂ��Č����A�����ɂ��Đ����A�^���[���A���M�[���A�����ł��邪���e�ł���A���ɗe�͂Ȃ��A�E���ɂ��ĕs���ł���B
�����R�͓��{�l�̐����ł���B����́A��Ԃ���c�ւƗ���邱�ƂȂ��A�@���ɏ����������R�ł���B�@���͂���߂Č������A��ʂ̓��{�l�͐ꐧ�������ɂ�����z�ꂻ�̂��̂ł���ƐM�����Ă����悤�ł���B�������A��j�͎����̎�l�Ɉ�N�Ԍق��Ă��邾���œz��ł͂Ȃ��B�܂������ƌ������ɂ��镐�m�́A�����̏�i�̖��߂ɕ��]���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����ԁA�����Ă��͉��N�Ԃ����߂�̂ł���A�]���ēz��ł͂Ȃ��B���{�l�́A�I�����_�l�̔�l�ԓI�ȓz�ꔄ����s���ȓz��̈��������炢�A����������Ă���B�g���̍�����킸�A�@���ɂ���Ď��R�ƌ����͎���Ă���A���������̖@���ُ̈�Ȃ܂ł̌������Ƃ��̐��������s�́A�e�l�������ɂӂ��킵���̈�ɂƂǂ߂Ă���B
����V���������Ƃƕ��]���邱�Ƃɂ����āA���{�l�ɔ䌨������̂͂قƂ�ǂ��Ȃ��B����ɑ��镞�]�Ɨ��e�ւ̏]���́A�c�����炷�łɂ���������B�����Ăǂ̊K�w�̎q�����A�����ɂ��Ă̎�{��N�z�҂��狳�������B���̌��ʁA�q��������ꂽ��A���������ꂽ��ł��ꂽ�肷�邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��B
�����̍����͕K�v�ɂ��ėL�v�ȏꍇ�A���̊�p���Ɣ����S������B�����ċΕׂ��ɂ����āA���{�l�͑唼�̖����̌Q���Ă���B�ނ�̍|��������i�͌����ŁA�ؐ��i�͂��ꂢ�Œ���������B���̏\���ɒb����ꂽ�����ƗD���Ȏ���́A����܂łɐ��ݏo���������̂����鐻�i�𗽉킷����̂ł���B�_�v�������̓y�n�ɂ�����M�S���ƁA���̂����ꂽ�k��ɔ�₷�J��́A�M���������قǑ傫���B
���ߖ�͓��{�ł͍ł����d����邱�Ƃł���B����͏��R�̋{�a���낤�Ƒe���ȏ����̂Ȃ����낤�ƁA�ς�炸�����ׂ������Ȃ̂ł���B�ߖ�Ƃ������̂́A�n�����҂ɂ͎����̏��L����킸���ȕ��Ŗ�����^���A�x�߂�҂ɂ͂��̕x��x�O��ɔh��ɘQ����Ȃ��B�ߖ�̂������ŁA���̍��X�Ɍ�����Q��╨���\���Ə̂��錻�ۂ͌���ꂸ�A�܂�����Ȃɂ��l���̑������ł���Ȃ���A�ǂ��ɂ����������҂��H�͂قƂ�ǂ��Ȃ��B��ʑ�O�͕x�ɑ����×~�ł����~�ł��Ȃ��A�܂���ɑ�H�������݂̂ɑ��Č���������B�����ɁA�y�n���^�o�R�⑼�̖��p�ȍ͔|�ɂ͔�₳�Ȃ����A�����͑����Ə̂���悤�ȗL�Q�Ȃ��̂̐����ɂ͗��p����Ȃ��B
���������́A�ނ�̐g�̂�ߕ��A�ƁA���H���A�e�퓙�����ڗđR�ł���B�ނ炪���C�ɓ����Đg�̂�̂́A�T���ȂǂƂ������̂ł͂Ȃ��A�����M�����ɓ���̂ł���B���̓��͂��ꂼ��̉Ƃɗp�ӂ���Ă���A�܂����l�̂��߂ɂǂ̏h���ɂ����������ŗp�ӂ���Ă���B
�����`�͍L�������ŏ��炳��Ă���B�N�傪���ɕs���������Ƃ͂Ȃ����A�Í��̗��j�ɂ����āA�N�傪�����ɑ��Ė�]��~�����������͌��������Ȃ��B���̍��̗��j�́A�O������̖\�͂⍑���̔������玩����������E�m�̈̋Ƃɖ����Ă���B�����������₻�̏��L����N�Q�������Ƃɂ��ẮA��x��������Ă��Ȃ��B���{�l�͑����𐪕�����Ƃ����s���������������Ƃ͂Ȃ����A����Ŏ������D�������̂����������Ƃ��Ȃ��B
�����`�ƒ����́A�����Ɍ�����B�����Ă��̍��قǓ��݂̏��Ȃ����͂قƂ�ǂȂ��ł��낤�B���D�͂܂������Ȃ��B�ޓ��͂����H�Ɏ��ɂ��邾���ł���B����Ń��[���b�p�l�͖��{�ւ̗��̊Ԃ��A�܂��������S���Ď������g�т��Ă���ו��ɂقƂ�ǒ��ӂ�Ȃ��B����������������ŁA���Ȃ��Ƃ��I�����_���قɓ�����ӂ̖��O�́A�V������܂��͎V���ւ̏��i�̉חg���܂��͉אς݂̂����ɁA���ɍ����⓺���I�����_�l���炭���˂邱�Ƃ��߂Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂ł���B
�����M�͑��̍����ɔ䂵�āA���̍����̊Ԃɂ��L�����[���s���n���Ă���B����͔ނ炪�قƂ�NJw���m��Ȃ����ƂƁA�ً��̐_�w�△�m�ȑm���炪���̍����ɋ����������ɂ����̂ł���B���̂悤�Ȗ��M�͍Ղ�A�_���A�_���Ȃ���A�����̎��Ö@�A�g���ɂ������̌��ߕ����X�Ɍ�����B
�������͍����̑傫�Ȍ��̈�Ƃ����悤�B�������̃A�W�A�����������ɂ��n�������v�����݂����Ă���悤�ɁA���������̐_���Ȃ�N���͐_�A�V�A���z�A���ɑ��Ȃ�Ȃ��Ǝv�����݁A������͑��̐l���肷����Ă�ƐM������ł���B�Ƃ��Ƀ��[���b�p�l�͗��Ǝv���Ă���B
���O�q�������{�l�̍����A���`�A�����ėE�C�ɂ��Ēm���Ă���A���̍������{�������A�����̓G�ɑ��Ă܂������e�͂��Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��ċ������Ƃ͂Ȃ��낤�B�ނ�͑���ő�_�ł���Ɠ��l�ɂ܂��A�ɂ߂Ď��O�[�������߂ł�����B�����ČȂ�̌������������ނ��o���ɂ��邱�ƂȂ��A����������ُ�Ȃ܂ł̗�W���̓��ɉB���A���Q�̍D�@���˂炤�B���̍����قǁA����ɗ�����邱�Ƃ̂Ȃ��҂��A���͒m��Ȃ��B
����߂͊����������킸�A�܂��܂�����Ă͂��邪�A����ɂ�������炸���̍��ł͕s��͂���ӂ�Ă���B����ɕs����͂��炩��ċ��J���������҂����E���邱�Ƃ�����B�܂����n�ł́A����j�������������Ƃ����s���_�Ȉ��K������B
����ʓI�Ɍ����āA���{�̊w��̓��[���b�p�̐������y���ɗ���Ă���B�������Ȃ��獑�j�́A���̂قƂ�ǂ̍����m���Ȃ��̂ł��낤�Ƃ���A�Ɛ��w�ƂƂ��ɒN�ނ̋�ʂȂ�������l�X�ɂ���Ċw���B���{�l�́A�����̔ɉh�Ƒ����̂��߂ɍł��K�v�ɂ��ėL�v�Ȃ��͔̂_�Ƃł���ƍl���Ă���A���E�œ��{�قǂ��Ƃ���_�Ƃɏd���������Ă��鍑�͂Ȃ��B
���H�|�͍��������Ĕ��ɐ���ł���B�H�|�i�̂������͊����Ȃ܂łɎd�オ���Ă���A���[���b�p�̌|�p�i�𗽉킷�邱�Ƃ�����B�����A����ł̓��[���b�p�̐����ɒB���Ȃ����̂�����B���{�l�͓S�⓺���g���Ĕ��ɗǂ��d��������B���n��ؖȒn�́A���̃C���h�n�悩��̐��Y�i��菟�邱�Ƃ����邪�قړ����x�ł���B���퐻�i�A��������ɌÂ����́A����܂łɂ���Y�������̂ǂ̖����̕i�ɂ������Ă���B
�����{�̖@���͌��������̂ł���B�����Čx�@������Ɍ����������d�Ȍx�������Ă���A������K�����\���Ɏ���Ă���B���̌��ʂ͑傢�ɒ��ڂ��ׂ��ł���A�d�v�Ȃ��Ƃł���B�Ȃ��Ȃ���{�قǕ����Ȃ��Ƃ����Ȃ����́A���ɂ͂قƂ�ǂȂ�����ł���B����ɐl���̔@������Ȃ��B�܂��@���͌Â�����ς���Ă��Ȃ��B��������߂ȂǂȂ��Ă��A�����͗c�����牽���Ȃ������Ȃ�����ׂ����ɂ��āA�m���Ȓm����g�ɂ���B�������łȂ��A����҂̌��{������s�������Ȃ��琬������B���̐_���Ȃ�@����Ƃ����`�����҂ɑ��ẮA�߂̑召�ɂ�����炸�A�啔���Ɏ��Y���Ȃ��B
�����̂悤�ȍ��ł͔_��Ƃɂ��Ă̕�V�⏧��͕K�v�Ȃ��B�����ē��{�̔_���́A���̍��X�Ŕ_�Ƃ̔��B�������̂��W���Ă��邳�܂��܂ȋ����ɋꂵ�߂���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�_�����앨�Ŕ[�߂�N�v�́A�������ɔ��ɑ傫���B�������Ƃɂ����ނ�̓X�E�F�[�f���̑�����ɔ�ׂ�A���R�Ɏ����̓y�n���g����B
�����Ƃ́A�����̂��܂��܂Ȓ���`�ʼnc�܂�Ă���A�܂��O���l�Ƃ̊Ԃɂ��c�܂��B�����̏�����͔ɉh������߂Ă���B�����Ċłɂ�萧�����ꂽ��A�����̓���Ȓn��Ԃł̗A�����f�₳���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���ׂĂ̓_�Ŏ��R�ɍs�Ȃ��Ă���B�ǂ̍`���召�̑D���Ŗ��܂�A�X���͗��l�⏤�i�̉^���łЂ��߂��A�ǂ̏��X�����̋��X����W�܂鏤�i�ł����ς��ł���B�Ƃ��ɑ古�Ɠs�s�͂����ł���B�܂������̏��Ɠs�s�A�Ƃ�킯���̒��S�n�Ɉʒu����s�ł́A�������̑傫�Ȏs���Â���A�i���̔����̂��߂ɍ�������l�X���ǂ��ƏW�܂�B�@ |
���w���{�H���L�x�@�S�����j��
���V���[�E�~�n�C�����B�b�`�E�S�����j�� (Vasilii Mikhailovich Golovnin, 1776~1831) �̓��V�A�̊C�R�R�l�ŁA1811(������)�N�ɍ��㓇�ŕߗ��ƂȂ�A��N���ɂ킽���Ĕ��ق���я��O�ɗH���ꂽ�B
1804�N�Ƀ��V�A�̌����g�߃��U�[�m�t���������ʏ������߂����A���{�ɋ��ۂ����ƕ��͋�������c��ɐi�������B���U�[�m�t�����m�Ȗ��߂��o�����Ƀy�e���u���O�ɖ߂�����A�t�H���H�X�g�t��т����Ȃ̔��f��1806�N9���Ɋ������P�������B
���̕������{�͓��k���˂̕��͂����A�k���x���ɓ��Ă��B�t�H���H�X�g�t�͂��̌���瓇�ɕ��͐N�U�𑱂����߁A���{��1807�N12���Ƀ��V�A�D�ł������߂��o�����B
�S�����j�����͒��Ƃ���f�B�A�i���́A1809�N9���ɃJ���`���c�J�ɓ��������B1811�N�ɂ͐瓇�����̑��ʂɏ]�����Ă������A7��11���ɍ��㓇�ɏ㗤�����Ƃ�����A�S�����j���ȉ����V�A�l���������{���̕ߗ��ƂȂ����B
��s�͍ŏ��͔��فA��ɂ͏��O�ɗH����A��s���̐q������B
1812�N4���ɂ́A���[�����т��������V�A�l�Z�����E���������A�����ɂ͑S�����ߕ߂���A�Ăя��O�̍��ɂɗH���ꂽ�B�ĂɃ��R���h��������f�B�A�i�������㓇�ɗ��q���A���c���Õ��q����{�l�������J���`���c�J�ɝf�v�����B
1813�N6���A�f�B�A�i���͍Ăэ��㓇�ɗ��q���A���̂��ߐ����̃V�[���m�t�ƃA�C�k�l�ʖ�A���N�Z�C���o�S���č��㓇�Ɍ������B���͑Ì����A�f�B�A�i����9��28���ɔ��قɓ��`���A���V�A�l�ߗ��S�������e���ăJ���`���c�J�ɋA�҂����B
�w���{�H���L (1811-13) �x��1816�N�Ƀ��V�A�C�R����ǂ���o�ł���A�����Ƀ��[���b�p�e����ɖ|�ꂽ�B���̂����h�C�c�ꂩ��I�����_��ւ̏d��1817�N�ɏo�Ă���A�����n�ꍲ�\�Y�炪���{����w������{�I���x��1825(����8)�N�ɏo���B
���u���{�l�������Ɠ��l�ɁA���p�O�p�`��(�Ǝ��͂��������)�_粂̕����̘a�͎�粂̕����ɓ������Ǝv���Ă�܂����v�@�u�ނ��A���̒ʂ�ł��v�Ɣނ͓��ւ��B�u���̂ł��v�Ƃ���ꂪ���Â˂�ƁA�ނ͍ł����Г���@�ł����暖������B�Ƃ��ӂ͙̂_�r��Ŏ���ɚ��`��`���A�O�̐����`���ʂ��A���̂����_粂̒�������������̐����`��܂�����肵�A�������粂����������`�̏�ɂ̂��āA�҂���Ƃ��̑S�ʐς���Ă��܂��̂ł���B
�����Ď��́A�u���{����������D�����A�ו��ɓ��ӂ����̂́A�ޓ������a�Ȃ��߂ł���A���V���̕����ꂽ���߂ł���v�Ƃ��ӈꕔ�̔�]�ɂ��Ă��������̈ӌ����q�ׂĂ��悢�ł��炤�B�����g�Ƃ��ẮA�����ɛ�������{���̑ԓx�́A�S���ޓ��̐l�Ԉ��ɍ��������̂ƍl�ւĂ��B���̗��R�͎��̒ʂ�ł���B�������ݓ��{�������|�S�ɉ����ꂽ�̂��Ƃ�����A���̓������|�S�̂��ߔނ炪�ŏ����烍�V���Ƃ̘a�������߂Ȃ����͂Ȃ��ł͂Ȃ����B�Ƃ��낪���ۂ́A���{���ł͕��͂ɑi�ւĂ�������Řł͂��Ƃ����B�݂̂Ȃ炸����ꂪ�������Ă�����łȂ��A���{���ő傢�Ɉꓯ�̌��N�ێ��ɋꙧ���Ă�鎞�ɁA�����ꓯ�͎E�Q���ꂽ�Ƃ܂ŁA���R���h�N�əB�ւ������ł͂Ȃ����B������椎҂͂��̕���ɂ�āA���V���������{�̂��߂ɉ������A���{�����킪���̂��߂ɉ�����������m��ꂽ��A�����y�ɂ��Ď��画�Ђ����ł��炤�B
������ꂪ�����̈�ɝɂ��Ă�鎑���̂����A���ݓ��{�l��㞂��Ă����̂����������B����͂���ꂪ���B�A�E���A�ʝЂ��i������̂ł���A�܂����ɂ͒j�炵���Ƃ��ӂ��̂ł���B�������ނ炪���a�ł���Ƃ��Ă��A����͓��{�̓����̕��a�I�Ȑ����ɂ����̂ł���A���̚������Dू����Ȃ��ŋ��Ę҂��i���Ԃ̑����̂��߂ł���B����ނ��뗬���̜̎��Ɋ���Ă�Ȃ����߂��Ɖ]�����悩�炤�B
���ߜ��̂����ōł����{�l���x�z���Ă��͓̂��|�炵���B���{�l�͖@����̍Ȃ͈�l���������Ƃ͏o�҂Ȃ����A�{���̞ܗ������Ă��̂ŁA�T���ȘA���͉����Ȃ����̞ܗ���p�ЁA�j�ڂ��͂Â����Ƃ�屢�X�ł���B
�����Q�S���܂��̂́A��Ƃ��ē��{�l���L�̍ߜ��̈�ɝɂւ邱�Ƃ��o�҂��B�̂͐g�ɖւ��p�J�ɛ����镜�Q�̋`���́A�p�J�����������̎q�����p�J�����ւ����̎q���ɛ����ĕ��Q�̋`�����ʂ��܂ŁA�c�����瑷�܂ł��A�r�������͑\���܂ł��B���������̂ł���B���������{�l�����̝Ќ�����Ƃ���ɂ��ƁA���̋��\�ȏ�M�͍��ł͐l�̓��ɂ���قNj�����p���y�ڂ����A�p�J�͂����ɖY�����₤�ɂȂ��������ł���B
�����{�l�͐ߙL�ł͂��邪�A�嚥�ł͂Ȃ��B����暝��Ƃ��āA�ނ炪��Ɏ��A�z��傢�ɔڂ��݁A�嚥���̂ɂ��Ĕޓ��̒��Ԃ����ɐh煂ȃA�l�N�h�[�g���V�R�ł��Ă�邱�Ƃ𝧂��邱�Ƃ��o�҂�B
�����{�̚�������ɂ��ẮA�S铂Ƃ��Ĉꚠ���𑼚����Ɣ�r����A���{�l�͓V����ʂ��čł�����̐i�����ł���B���{�ɂ�椂ݏ����̏o�҂Ȃ��l�Ԃ�A�c���̖@����m��Ȃ��l�Ԃ͈�l����Ȃ��B���{�̖@���͂߂��ɝ̂�Ȃ����A���̗v�y�͑傫�Ȕɏ����āA���X���X�̜A���l�ڂɂ��ꏊ�Ɍf�������̂ł���B
�����{�l�͔_�ƁA���Y�A���ƁA���A������іȕz�̐����A�����킨��ю���̐���A�����̌����ɂ��ẮA�w��ǃ��[���b�p�l�ɗ��Ȃ��B�ނ���敨�̐������悭���m���ċ���A���낢��ȋ������i����ɍI���ɍ�Ă��B�w��������{炋Ƃ͓��{�ł͊����̈�ɒB���Ă��B���̏�A���{�l�͂�����ƒ�p�i�̐������I���ł���B�����珎���ɂƂĂ͂���ȏ�A�J���̕K�v�͏������Ȃ��̂ł���B
����`�A���z�A�����A���ŁA���ق����ċ��炭���ɂ��Ă��A���{�l�͂����郈�[���b�p�l���y���Ɍ��Ă��B�ނ�͊e�핺�{��ʂ��Ă܂��ԃ��V�ŁA�q�C�p�͉��ݍq�C�ȊO�ɂ͑S���m�Ă�Ȃ��̂ł���B
�����{�l�͂�����K����ʂ��āA�䛔���ɂ߂ēA�d�ł���B���{�l���u���X�V�������́A���̚����̖{�c�ȋ��{���������̂ł���B
���������������`�ɂɔ䂷��ƁA�@���I�Ό���E�p�������{�l�̝ɂ͐r�����ɂŁA�S铂Ƃ��Č���Γ��{�l�͋ɂ߂ĐM�S�[���ǂ��납�A���M�I�ł��ւ���B���{�l�͗d�p��M���A���̗d�p�ɂ��Ă��낢��̘̐b������̂��D�ł���B
�����{�ł͕z�������e��̏@���⋳�h�����낢��ƈ���Ă��ɂ��S�͂炸�A����͐��{�ɂ��И��ɂ��������s�����o�ւȂ��B�s���͒N�ł��D���ȏ@����M���A�܂��D���Ȃ������ł��@�|���ւ�ܗ������Ă��B�܂��ǐS���S��Ƃ��낪����Ƃ��A�܂������̓s��������Ƃ����z�@���Ă��A�N�����Ƃ��]�͂Ȃ��̂ł���B
�����{���{�͂��̗��@��ɋɂ߂ďd���㞊ׂ��V�R���邱�Ƃ��S�Ă��B����㞊ׂ̂����ł��ł��d����y�͌Y���̉Ս����ł��邪�A���{�͂�����Ᶎ�ɝ̍X���邱�Ƃ�����āA���𒀂��āA�ɂ߂Ċɖ��ɉ������Ă��B
���Ƃ͂��֓��{�l�̎��i�Ԃ�͑��̃A�W�������̂���Ƃ͑S�R��r�ɂȂ�Ȃ��B�����猩��ƁA���{�l�͎��i�Ԃ����Ƃ͉]�ւȂ��B�ނ�͗p�S�Ԃ����������B������Ƃ�����]�ւA���{�l�͐��m�l�������i�Ԃ����Ȃ��Ƃ��֍l�ւĂ��B
�����{�l�͎����̎q��𗧔h�ɌO�炷��\�͂����Ă��B�����c��������椂ݏ����A�@���A���j�A�n���Ȃǂ����ցA�傫���Ȃ�ƕ��p�����ւ�B�������ꓙ����y�́A���{�l���c�N���ォ��q��ɔE�ρA���f�A�X�V���ɂ߂čI�݂ɋ��ւ��ނ��Ƃł���B�����͛��n�ɂ��̏]���ׂ����{�l�̎��������x�����߂��@�����B
�����{�ł͔M��ɘ_ू��邱�Ƃ́A��̂ɔ��X�őe�\�Ȃ��ƂƔF�߂��Ă��B�ނ�͏�ɂ��낢��\桂����āA�����̈ӌ����X�V�������q�ׁA�������������g�̔��Ђ�M���Ă�Ȃ��₤�ȑf�U��܂Ō�����B�܂��������鎞�ɂ͌����������ʂ����Ԃ��Ę҂Ȃ��ŁA�K�����ɁA�����������͗�𝧂�����A��r���Ƃ��肵�Ă�Ę҂�B
�����{�ɂ͓y�i�̂ق��ɂ͐Α��̌��z���͂Ȃ��B���̌����͌���Ȓn�k�ł���B�ؑ��Ɖ��͑����͈�K���ł��邪�A��K�������邱�Ƃ͂���B�������g���ȟ���̂��߁A�ǂ̌������T���Ď��j�ɏo�҂Ă��B���������鉮���̎d��́A�K���ړ����ɂȂĂ��̂ŁA��������c�ӂƁA�ꌬ�̉Ɖ�����̕����ɝ̂ւ邱�Ƃ��o�҂�B
�����̂��֖��m��x���݂͂ȉƂ̑��ɒ뉀�����Ă��B���{�l�͂��̕��ɂ����ẮA�Ȃ��Ȃ��̝Ɋ�҂ł���B�����͉��Y���Ȃ��Ȃ��I�҂ŁA�둢��̂��߂Ȃ牽���ɂ܂Ȃ��Ƃ��ӘA�����V�R���B���������{�Ɖ��̍ŏ�̑����ł���A�ł��^���ׂ������ƔF�ނׂ����̂́A�㉺��ʂ��Ď���Ă�鏬���ς�Ɛ����ȂƂ���ł��炤�B
�����{�l�̓��[���b�p�l�ɔ�ׂ�ƁA�H����̂ɍׂ��B�����͊ċ֒��A�^�����Ȃ��Ă��A�ЂƂ�œ��{�l�̓�l�O�͐H�ׂĂ�B�܂����s���͂�����̐�����l�O�ł����炭���{�l�̎O�l���ޕ�����ʂł����炤�B
�����{�l�͎��ĉ����ȟ��������Ă��B���͐e�������{�l�������Â�������Ă��̂��������Ƃ͈�x���Ȃ��B�ނ�͖ʔ����b�������ŁA�悭��k�����ӁB�����҂͉������鎞�ɂ͕K���̂��̂��B
������ɂ��ē��L���ׂ��y�́A���{�̓��킪�ɂ߂Đ��I�ɂł��Ă�邱�Ƃł���B�����͓��{�Ŏg�Ă��㣂̏�v���ɉ��x���������ꂽ���̂ł���B��㣂͉��P��������Ɋ|���ςȂ��ɂȂĂ�Ă��A�������ɂ܂Ȃ��̂ł����B
�����{�ŏo�҂�قǂ̎���ނ͂ǂ��ɍs�Ă��o�҂͂��Ȃ��\�\�Ƃ��ӂ��Ƃ͂������[���b�p�l���m�Ă��B
���|���i�͂ǂ����Ƃ��ӂƁA���{�̑召���́A�����炭�_�}�X�N���������āA���E���̂����铯��̐��i�𗽉킵�Ă��B����͋ɒ[�Ȏ����Ɋ��ւ���̂ł���B�|���̑�����������̌����ɂ����ẮA���{�l�͈ꓪ�n���Ă��B�ނ�͋����̋��܂ō�邪�A����̓K���X�̋��Ɠ��l�ɗ��h�ɔ��˂���̂ł���B�����͓��{�̎w�����H��������т��ь������A����͏�v������]�Ă��A�d�グ�̔���������]�Ă��A�C�M���X���ɂقƂ�Ǘ��Ȃ��B
�����{�̓���͎x�߂̓�����y���ɂ�����Ă��B������̂ɍ��J�ŁA�S���̎��v���݂����Ȃ��ʂɋ͂��������Y���Ȃ��̂ŁA���{�l�͎x�߂����V�R�̓����A�����Ă��B
�����������{�l�͏㓙�̖ȕz�͍��Ȃ����A�łȂ����炤�Ƃ͎v�͂Ȃ��炵���B�����͐l���݂̖ȕz�͈�x���������Ƃ��Ȃ����B�����̎��Ă���C���h�Y�̃n���J�`�₤�����̂̋݊�������ƁA���{�l�����͂��ꂪ�ȐD�����Ƃ͐M���Ȃ��̂ł����B
�����{�l�͋����̑����h�����A�Α���ؑ������ނ��Ƃ��o�҂邪�A����ꂪ���O�̎��@�Ō����������画�Ђ���ƁA�����Y�p�͓��{�ł͂܂����ɖ������̏�Ԃɂ���B�܂���`��A���ł�A����ɂ����Ă����{�l�́A�������Y�p���܂����͂Ώ��Z����ɂ��郈�[���b�p�������ɔ�ׂĂ��A�Ȃق͂邩�ɗ���������Ă��B�����������ȊO�̒����ɂ����Ă͓��{�l�͂��Ȃ��p�ł���B�܂��ݕ����A���A��A���݂�ʂ��đ��c�ɂ悭�h�����Ă���B
�����{�l�͎�H�ɂ����Ďd�������ł���Ɠ��l�ɁA�Y�Ƃɂ����Ă����ނ��Ƃ�m��Ȃ������ł���B���Ƃɋ��Ƃ͍I���ŁA���ɔM�S�ɂ���ɜn�����Ă��B
�����{�l�̏��̍D���́A�ǂ̒��ǂ̑��ɍs�Ă��悭���͂�Ă��B�قƂ�ǂǂ̉Ƃɂ��A���낢��ȕK�v�i���̂�X�����Ă��B�C�M���X�ɍs���ƁA�ɏ\�݂����雏�ΓX�ׂ̗�ɉ��y��������Ɖ]�����i���悭�������邪�A����Ɠ��l�ɓ��{�ł����J�Ȍ��D�������ӏ��l�ƁA�����l�Ƃ��ׂ蓯�u�ɕ�炵����A�X���J�����肵�Ă��̂ł���B���{�l�͂����钁����ʂ��ě��ɃC�M���X�l�Ǝ��Ă��B�ނ�̓C�M���X�l�Ɠ��l�ɐ����Ƌɒ[�Ȑ��m����v������B�C�M���X�ł͂ǂ�ȉ���ʕi�ɂ��i���A�J�i�A�g�p�@�A�����҂܂��͍H��̖��A���Ă͖J�܂����������ƂȂǂ�������������������Ă�邪�A���{�l������Ɠ��l�ɂقƂ�ǂ����鏤�i�ɏ����Ȉ�������Ă��B
�����{�l�͍H���̕��̛{��ɂ��Ă��A���{�̑��̗̈�Ɠ��l�ɁA�債�Ĕ��Ă�Ȃ��B�����̌��邱�Ƃ����{�̗v�ǂ�C�i�́A�S���ł���߂ȍ\���ŁA(���̍\�z�҂������S鄂Ƃ��z��{�̖@���͂��납�A�펯���֎�ĂȂ���)�ƍl�ւ�قNJ��m�ɂł��Ă�B
�������͓��{���v�̕q���������т��іڌ������B����炪�C�݂��Ђ̖Ґ����`���A�܂����̊��ނ��k��Ȃ��҈Ђ�U�Ӊ͂���C�ւ̗������̐��ɂ�������������`���āA���̑傫�ȑD���j���I���ɑ��Ă��̂͋����ׂ����̂�����B�������ӊC���ɂ͂ǂ�Ȋ��҂ł��|���邱�Ƃ��o�҂�B���{�̐��v�͎d��������Ŋ댯�Ȃ�����V���V�R�ƂĂ�邯��ǂ��A���g�Ђ̍r�炳�̓C�M���X�̑D���Ɏ��Ă��B���P�������������ʼn҂��������A��X���̏Εw�ɝɓ��̒��Ɏg�Ă��܂ӂ̂ł���B�@ |
���w�]�ˎQ�{�I�s�x�@�V�[�{���g
�t�����c�E�t�H���E�V�[�{���g (Philipp Franz Jonkheer Balthasar von Siebold, 1796~1866) �̓h�C�c�̈�w�ҁE�����w�ҁE���{�w�҂ŁA1823(����6)�N�ɗ������A1829(����11)�N�ɃV�[�{���g�����ŒǕ������܂ŁA���{�̗��w�E�ɂƂĂ��Ȃ��傫�ȉe����^�����B�Ǖ���̓I�����_�œ��{�֘A�����̐����ɓ�����A�w���{�x�w���{�A�����x�w���{�������x���o�ł����B
���̌���{�̊J���ɔ����A�V�[�{���g�̓����֎~�߂��������ꂽ���߁A1859(����6)�N�ɍė�������1862(���v2)�N�܂ő؍݂����B
���m���ɔł́w�]�ˎQ�{�I�s�x�́A�咘�w���{ (Nippon) �x�̑�2�͂ł���B
1826(����9)�N�Q�{���̏��ْ��̓��n���E�E�B�����E�h�D�E�X�`���������ŁA�V�[�{���g�Ƃ��̏���̃n�C�����q�E�r�����K�[�����s�����B���{�l�͒ʎ��̑��A�V�[�{���g�̖�l�̍��ǍցE��{�h��E�Έ�@���E���c���Y�A��Ƃ̓o�^���A�V�[�{���g�̏��g�̈ɔV���ƌF�g�炪���s�����B
��s��2��15���ɒ�����o���A4��10���ɍ]�˂ɒ����A5��1����4���ɏ��R�ƐĂɔq�y�����B�A���5��18���ɍ]�˂��A7��7���ɒ���ɒ������B
���@����ɐ̂̓��{�̑D�͒��N�̂��̖͕̂�ł����āA�N��L�̋L�q�ɂ��A���{�l�͋I���O4 – 3�N�ɒ��N�̑D��m���Ă����B����ꂪ�_�Ђ̕�[��Ō���悤�ȌÑ�̓��{�D�̊G�͂������������̐��������Ƃ������Ă���B�Ƃ���������͓Ɠ��ȍ\���������Ă��āA�����ɂ�����܂Ŏx�߂̑��D�p����قƂ�ǎ��ł�����̂��Ȃ����A���[���b�p�̑��D�p����̉e���͊F���ł���B
���ΕׂȔ_�v�͎��R�̔אB�͂Ƌ����B���Q���ׂ��Εדw�͂ɂ���ĉΎR�̔j��͂��������āA�R�̎ΖʂɊK�i��̔������肠���Ă��邪�A����͒��Ӑ[������ꂳ�ꂽ�뉀�Ɠ����Ł\�\���s�҂���������N�̕����̐��ʂł���B
��������(���q)�˂̉������m�̉Ƒ��⏢�g���Z��ł��钬�͂���ł́A�T���ȕ�炵�Ƃ����͓̂��Ă͂܂�Ȃ��悤�Ɍ�����B����䂦���̏��͂����Ƃ߂Ă���ė�����������̊��҂́A�\�\�����Ă��͖����̔畆�a�E��a�ł��邪�\�\ဎ��̔~�ł⋹�E�����̌Â������ɋN������ނ�̏Ǐ�ɂ���āA����ꂪ���̒��ɂ͂����ė������ɋ����������ꂢ�ȏZ���́A�����n�����������Ă���ɉ߂��Ȃ����Ƃ�ł������Ă����B
�����{�l�͎����̑c���ɑ��Ă͊����ƂŁA��c�̈̋Ƃ��ւ�Ƃ��Ă���B���{����l�����ʂ̐l���V�c�̌Â��c���ɑ�����Ȃ����������A�Â��M�╗���K�����d��B����䂦�O���l���A���{�l�̖������ɒǏ]���A�ނ�̏@���╗���K���d���A�����Č��n����̓`����_�Ƃ��Đ��߂�ꂽ�p�Y�̎^���ɍD�ӂ������Ď��������ނ���̂́A���Ɍ��\�Ȃ��Ƃł���B
�������̏o���O�܂��o���ɂ�������A�����w�̒m���������͎����Ă������l�ɁA���[���b�p�l�����{�ŏW�߂邱�Ƃ�������Ă���V�Y���̃R���N�V�����₻�̑��̒��������������āA���̊S���ɔނ��������Ă������B���{�l���L�̒m���~�Ǝ��R�̒��������ɑ��鈤���Ƃ́A����閧�̖ړI�������Ƃ��悤�Ɠw�߂Ă������ɂ́A�������ɗ������B
�����{�ɂ����č����I�Y�Ƃ̉��炩�̕��傪�A��K�͂܂��͑�ʐ��Y�I�ɍs�Ȃ��Ă���n���ł͈�ʓI�Ȕɉh���݂��A���[���b�p�̍H�Ɠs�s�̐l�ԓI�ȔߎS�ƕs�i�s���͂����莦���Ă���g�S�Ƃ��ɔ��ʂĂ��A���̂悤�ȕn���ȍ����K�w�͑��݂��Ȃ��Ƃ����������J��Ԃ��q�ׂĂ������A�����ł����̐��������Ƃ��킩�����B���������{�ɂ́A����m��Ȃ��x�������A���Ή삦�������K���̐l�X�̏�ɋ������ӂ邤�H�Ƃ̎x�z�҂͑��݂��Ȃ��B�J���҂��H�������{�ł̓��[���b�p�����Ȃ���w���т����i���������Ċu�Ă��Ă͂��邪�A�ނ�͓��E�Ƃ��đ��݂̑��h�ƍD�ӂƂɂ���Ă���Ɍ�������Ă���B
�����{�̍����͏��������̒��ł��A�����̗ǂ��]���ȑ����̉Ƒ��ɔ�r�ł���B���V�\�\������喼�͎��������̉Ƒ��̂��ƂŁA������S�ɂ��o���邱�Ƃ����[���b�p�ł͂悭����͈̂⊶�ɂ����Ȃ����A���{�ł͂����������O�͖ő��ɂȂ��\�\�ނ�͎q�����ƒ�ŋ��炵�A���邢�͊w�Z�ŕ�������B
�����n���Ă܂��Ȃ������͕{���ɒ����A���̓y�n�̎Y���ł���L���Ȗ؍H�i��ҍH�i�����邽�߂ɁA�����X��������Ēʂ�߂����B���̒n���͒|�ŕ҂����ւ�悭�ł��Ă����Ă�Ƃ��ɂ͍����Ȗō������X�̉Ƌ�A���̑��̎���E�l�`�E�̒������X�ŁA�S���I�ɗL���ł���B�ߌ�ɂ����̐��i��������������̂Ƃ���ɉ^��ė������A���ۂɋZ�I�̓��O�Ȃ��Ƃ͂ǂ�Ȃɂق߂Ă��悢�قǂł���B���������̏��l�����́A����ꂪ���M�������Č����l��4����1�ɒl���Ă����������Ȃ��قǖ@�O�̒l�i���ӂ������Ă���B
���S�Z���̂����̑喼�Ƃ����K���������ɂ悭�����Ă���̂́A���̐l�����̈����ׂ��Ƒ������ł������B�[���E��V��@�Ə�i�A�S����̐e�E�����E�ւ�̉e�����݂��ʂ܂��₩�ȋ��{�Ȃǂ͂���v�ȘV��(�F���ˎ�E���Ïd��)�ɂ��A�q��������v�l�����ɂ������Ă����\�\�v����ɂ���炷�ׂẮA���{���郈�[���b�p�l�̑��h�ɒl��������ł���B
�����́A���Ƃ��Ώh�̎�l�̂悤�ȒႢ�K�w�̓��{�l�Ƃ̌��ۂɂ��Ă����ւт��������̈ӌ����q�ׂ����Ƃɑ��A���ɐ\�Ȃ��Ǝv���B���̑P�ǂȒj�Ƃ��̉Ƒ��́A�ǎ҂͐��F�����ɑ���Ȃ����A�Â��Ȗ��҂����߂����������ł��邾�������ɂ��悤�Ƃ��āA�{���ɍőP���������̂ł���B
������Ȃɑ����̐l�Ԃ��Z��ł���s��ł͍��x���ґ�ƂЂǂ��n�R�̗��ɒ[���݂���B�喼�����̐H�V�ɏo�����߂ɂ́A�ꏡ�̕Ă��琔�����A������������傫���ď㎿�̂��̂�����яo���A���x������Ă���ɒ��ׁA���������̒����炽���^�̂Ƃ��낾�����g���̂ŁA20����1�ȏ�͂ނ��ɂȂ��Ă��܂��B���l�ɋ��ށE��ؗށE���̂ق��̐H�i�Ȃ�тɎ�ނ͑喼���~�ł͂ނ��Ɏg����B����ɔ����Č�H�Ȃǂ̍Œ�̊K���̎҂́A�l�̏Z�މƂɂ������Z�߂��~�̊���ɂ����ȘI�����Ȃ��ł���B�܂������]�˂ɂ݂���Ђǂ��n���Ɛr�����ґ�Ƃ͂��̍��̂ǂ��ɂ������Ȃ��B�H���i�̒l�i�͔��ɍ����A�����炭���{�̑��̒n���̏鉺�����ܔ{�͍����B
���S���̍��݂��W�܂���ɏd�v�ȏ��Ɠs�s�ł́A�߂�Ƃ������̋@�������B����ł����ۂ̔ƍߎ҂͂܂�ł���Ƃ������Ƃ��A�����͓��{�l�S�̖̂��_�̂��߂Ɍ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������ƁA��N���A���̒��Ŗ�S�l�̔ƍߎ҂����Y�ɏ������邾���ł���B
�����傤�ǖ��w�R(Imose Jama)�Ƃ����O��ŗL���Ȏŋ����㉉���ꂽ�B���҂̒��ɂ͂�������̈ꗬ�̌|�p�Ƃ�����A�ނ�̓��[���b�p�ɂ����Ă�����ʂ̔�������ł��낤�B�������Ə�M�̂����܂Ȃ��\���Ƃ��ЂƂɂȂ����ނ�̐g�U���䎌�͑S���^�ɒl������̂ł��������A�ނ�̍����Ȉߑ��͂��̈�ۂ����߁A���ꂻ�̂��̂̕n��Ȑݔ���Y�ꂳ�����B
�����̒�����́A���ʂȐݔ������ĕ��A��ς��q�M���悭����Ă��邪�A����͓��{���イ�Ŏg���Ă���엿�ŁA�Ċ��ɂ͂��낢��Ȗ�⍒���Ɏ{���̂����ʂł���B���̂��ߘZ�A������є����ɂ͂��ׂĂ̒n���A���ɑ�s����ӂ̒n���͈��L�ɖ����Ă��āA���炵�����R���y���ނ̂ɂ����ւ�W���ƂȂ邱�Ƃ��悭����B�@ |
���w�t���Q�[�g�̓p�����_���x�@�S���`�����t
�h�E�`�E�S���`�����t(Ivan Alexandrovich Goncharov, 1812~1891)�̓��V�A�̍�ƂŁA1852�`55�N�Ƀv�`���[�`�����������t���Q�[�g�̓p�����_���ɓ��悵�A�A�t���J�E�W�����E�V���K�|�[���E���`�E���}���E���{�E�t�B���s���E���N���o�ăV�x���A�ɓ������B
�����ŃR�����F�b�g�̓I�����[�c�@���E�^���D���V�j�R�t�E�X�N�[�i�[�D���H�X�g�[�N���Ɨ����������p�����_���́A�O�ǂ��]���ă��V�A��1853�N8��10��(�Éi6�N7��16��)����ɓ��`�����B
�������ܒ����s���Ƃ̌��ɓ������������������A11��11��(�a��10��23��)�p�����_���͏�C�Ɍ��������B
12��22���ɍĂђ���ɓ��`�����v�`���[�`���́A���{�S����H���q��т�ƌ����d�˂��B
1854�N1��21��(�Éi7�N1��4��)�A�p�����_���͒�����o�q���A�y���[�͑��Ɠ���ւ��ɓߔe�ɓ��`�����B
2��9���ɓߔe���o�q�����p�����_���́A�t�B���s���؍݂��o��3��9���ɍϏB�C���̋������ɏ㗤���A4��9���ɎO�x����ɓ��`�����B
4��15���ɏo�q���Ē��N�̓��C�݂�T�����Ȃ���k�サ�A�n�a�p�Ńf�B�A�i����҂����B
�{����1858�N�ɏo�ł��ꂽ�B��g���ɔŁw���{�n�q�L�x�ɖ�o����Ă���̂́A1853�N6���̍��`�؍݂���1854�N2���̗����o���܂łł���B
����X���t�����X����A�X�E�F�[�f���l���h�C�c����A�{�҂����e�����m�Ă��₤�ɁA���{�l�݂͂Ȏx�ߌ��m�Ă��B�ޓ��͓��{��ł��A�x�ߌ�ł��������A�x�ߕ��������ȗ���ᢉ����邾���ł���B�`���Č�����A�i�s���A�K�����A�������A�������A���{���A�����ނ��x�߂���B�҂������̂ł���B
�����{�l�ł��ʂɝ̂��Ƃ���͂Ȃ��B���������ƁA��̋��ɂ܂锯�^���ڏ��ɂȂ邾���̂��Ƃł���B���̑����y�ł͂��̚����́A���[���b�p�l�Ɣ�ׂȂ���A���c�ɊJ���ċ���A��҂����قş������悭�A�������Փ��̋��{�͋ɂ߂Ē��ڂ��ׂ����̂�����B
���ޓ��͑�C�⏬�e�����ĉ��A�C�M���X�ōw�������V���\�ڂ̂������e�̐������X�������B���ׂĂ��ޓ��ɕ����������B���{�l�B���P��I���Ɍ����܂��Ǝ������Ă͂���A���̍D��S�ɂ͗c�t�ȁA�q�����݂��Ƃ��낪�V�R�����B
����������͖w��nj������Ȃ������A���F�̂����͔��ɑ����A�啔�����A����w��ǑS���������ł���B
���܂Ê�ɂ��̂́A�����A����~�����ؑ��̊K�i��A���ꂩ���c�̓��{�l�̂Ȃ݂͂Âꂽ�C�����ł���B�����y�͑S������������ʁB�ނ�͐g铂��A�ߕ����A�C���ł����ς�Ƃ��Ă��B
�����{�l�͉��̏L�����o���Ȃ��B��������ƁA鞂̉��͂��ꂢ�ɒ��グ��Ḓ��ł���B�ނ��o���̘r�́A�A�������牜�̕��܂Ō����A���ɏł��Ă�����邪�A�C�����B���̓�����X�V�������A���̜�҂͓A�d�ł���B����ɉ]�ւΒN�Ɍ����Ă����h�Ȑl�ԂȂ̂��B�����ޓ���ɂ��Ă͎d���͏o�҂Ȃ��B�����̂��āA�����܂����āA�R�����āA���̗g�傪���₷��̂��B�w��ɂ͉��������B�ޓ��́A���ƂЋ��₷�܂��Ǝv����A�O��̂Ȃ���������炤�Ǝv���肵�Ă��A���ꂪ�悢���ł��A���Ȃ��Ƃ��i��ł͂��Ȃ��₤�Ȑ��x����Ă��̂��B
���ޓ��̂��̖������̈��ɁA�ǂꂾ���̐������A�ǂꂾ���̗z�������A���j������������Ă�邱�Ƃ��炤�I�L���ȍ˔\�A�V�������邱�Ƃ́A���ׂȎ����ɂ��A�܂�ʘ�b�ɂ����͂�Ă��B�������A���e�Ƃ��ӂ��̂��Ȃ��B�{���̐����͂��S������ᶂ��A�R��ᶂ��āA�C�N�ȐV���������߂Ă��A�Ƃ��ӂ��Ƃ�����B���{�l�͔��Ɋ�潑�ŁA�V��ࣖ��ł���B�x�ߐl�̂₤�ȁA���ȂƂ��낪�����B
�����͐��ɓ��{�̕w�l�������B�j�q�Ɠ����тŁA��A���ޏ㒅�𒅂āA����������ĂȂ��B���h�Ȑg����̕w�l�́A�s���Ōォ�甯���Ƃ߂Ă��B�݂�ȐF���ŁA��̌��ꂵ���I
���Dूɑi�ւē��{�ɋ������邱�ƂƂȂ邩���m��Ȃ��B���������y�ɂ����Ă����{�͎x�߂����y���ɗD�z���Ă��B�������{�����[���b�p����R���Z�p��������č`�s�����߂��Ȃ�A�@���Ȃ�U�����Ă��A���S�ƂȂ�ł��炤�B���{��łڂ�������͔̂��������ł���B
�����B�͂ǂ����ӌ��ʂɂȂ邩�����݂ɐF�X�Ƙ_�c�������B�c�t�ŁA���J�ȕȂ����ςȓ��{�l��̂��ƂŁA�m���Ȍ��_�������Ȃ�������ł���B
���������݂ł����{�����Ĉꝧ�ɊJ�������邱�Ƃ��o�҂�B�Ɖ]�ӂ͓̂��{���P��ɂ��㏬�ł��āA�@���Ȃ�Dूɂ����֓��Ȃ�����ł���B
���ޓ��́A������A�W�A�l�Ɠ��l�ɁA���\�̝��ƂȂĂ�āA���̎��y����������Ƃ��A�ӂߗ��Ă悤�Ƃ����Ȃ��̂ł���B�����y�ɂ��ĉ����ڂ����m�肽�����Ƃ�������A�P���y�����g�D���x���O�̖{��椂�őՂ������B
�����{�l�͈���ɎO�x�H�������邪�A����͔��ɝ���������H�ו��ł���B���̋N����(�ޓ��͑�̂ȑ��N�ŁA�閾���O�̂��Ƃ�����)�ƁA���ߍ��ƁA�Ō�͔ӂ̘Z���ł���B�H���̗ʂ͔��ɏ����̂ŁA�H�|�̉����Ȏ҂ɂ͓��{�̐��`�ł͑O�ɂ�����Ȃ����ł���B�@ |
���w���{�����L�x�@M�EC�E�y���[
M�EC�E�y���[ (Matthew Calbraith Perry, 1794~1858) �͕č��̊C�R�R�l�ŁA�͑��𗦂���1853(�Éi6)�N7���Y��ɗ��q���A��1854(�Éi7)�N�_�ސ�œ��Ęa�e������������B
�y���[�����C�D�~�V�V�b�s���𗦂��ăm�t�H�[�N���o�q�����̂�1852�N11��24���ŁA��1853�N5���ɏ�C�ŃT�X�P�n�i���ɏ�芷�����͂Ƃ����B
�y���[�͑���5��26���ɓߔe�ɓ��`���A��������n�ɉ���{���Ə��}��������T�������B
7��2���A���C�D�T�X�P�n�i���E�~�V�V�b�s������є��D�v���}�X���E�T���g�K�̎l�ǂ͉Y�ꉫ�ɒ┑���A�Y���s���Ƃ̌��ɓ������B
7��14���A�y���[�͏����300�l���]���ĉY��ɏ㗤���A�t�B�����A�哝�̂̐e�����˓c�ɓ���E��ːΌ���Ɏ�n�����B
7��17���A�͑��͍]�˘p������ߔe�Ɍ������B�y���[�͗����Ɍ��Տ��ƐΒY���������J�݂�������A���`�ɖ߂����B
1854�N1���A���C�D�T�X�P�n�i���E�~�V�V�b�s���E�{�[�n�^�����ɔ��D�l�ǂ��������y���[�͑��͍��`���o�q���A�������o�R����2��13���ɍ]�˘p�ɓ������B
3��8���A�y���[�͖�500���𗦂��ĉ��l�ɏ㗤���A�ё�w����M���Ƃ�����{����\�Ə������̌��ɓ������B
3��31���A���l�œ��Ęa�e���ւ̏������s�Ȃ�ꂽ�B�y���[�͊J�`��Ɏw�肳�ꂽ���c�Ɣ��ق�������A���`�ɖ߂����B
�w���{�����L�x�́A�y���[����юm�������̒ʐM����L�Ɋ�Â��A�y���[�̊ďC�̉��Ƀt�����V�X�E�k�E�z�[�N�X���Ҏ[�������̂ŁA1856�N�ɋc��̓��ꊧ�s���Ƃ��Đ��\�������s���ꂽ�B
�����{�l�͋ɂ߂ċΕׂŊ�p�Ȑl���ł���A���鐻���Ƃɂ��Č���ƁA�@���Ȃ隠��������𗽉킵���Ȃ��̂ł���B
���ޓ��͊O���l�ɂ�����ꂽ���ǂ��V�@����̂��ɂ߂đ����A�������炻�����A���ȍI�݂��Ɛ��m���Ƃ��ȂĂ����͂���̂ł���B�����ɒ�������̂͐r���I�݂ł���A�����̏ё����h�邱�Ƃ��ł���B
���؍ދy�ђ|�މ��H�ɉ��āA�ޓ��ɗD�隠���͂Ȃ��B�ޓ��͖����E�ɗD����̂Ȃ���̋Z�p��L���Ă��B����͖؍ސ��i�̎��h��̋Z�p�ł���B���̏������͑��N�ɘi�āA���̋Z�p�ɉ��Ĕނ�ƌ`���ׂ悤�Ǝ��݂����������Ȃ����B
���ޓ��͎���삵�Ă��̂����A�܂�����l�̌��Ƃ���ɂ��Ύx�ߐl�������Ɨ��h�ɐ��삷�邱�Ƃ��ł���Ɖ]�ӁB�e�Ɋp�A��X���������{����̌��{�͐r���D�I����ł���B�A������M�҂̌��Ƃ���ɂ��ƁA�ŗǎ��̔S�y��ᶂ������߂ɁA���݂ł͏��Ă̂₤�ɗ��h�ɐ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ɖ]�ӁB
���ޓ��͌�������B���̂����̍ŗǕi�͎x�߂̌������㓙�ł���B�c�ؖȐD���������Ă�邪�A���̐����ɂ͂��܂ŏn�����Ă�Ȃ��B
���K�v�ɂ��āA����ʂ̑����|�ɂ́A�ƁX�ŗ��h�ȋ������Ă�邪�A�g���l��������Z�p��m��Ȃ��₤�ł���B�y�؍H�{��̈��錴����m�Ă�Ă����K�p���Ă͂�邪�A�H���{�̌������������m��Ȃ��B�c�ޓ��͝ɛ{�A�@�B�{�y�юO�p�@����炩�m�Ă��B���̂₤�ɂ��Ĕޓ��͓����̐r�����h�Ȓn���������̂ł����B
�����{�l�́A��潑�ȟ�����L���鑽���̑��̐l���Ɠ��l�ɁA����Ȃ��̂ɛ����鋭���D��S��L���ċ���A�ƁX�͂ނ����Ԓ������̂�熂��Ȃ��̂ł���B
���������M����Q�ƂȂĂ��B���l���\��邱�Ƃ͉���Ƃ���Ă��̂ł���B���̂₤�Ȍ��������Ȃ��̂�����A�����y�ъO���̒m�����܂�s���S�ł��邱�Ƃ����炩�ł���B
���Z�i�͑��A���ł���A���{�̒m���͔��ɖR�������i���Z�i��p�Ђ悤�Ƃ��Ȃ��B����ǂ��Ηp�A���{�ɂ��Ă͔��Ɉӂ�p�ЂČ������ċ���A�ނ�̗Ö@�͈�ʂɗL���ł���Ɖ]�͂�Ă��B
�����ʋ��琧�x�Ɏ������̂�����₤�ł���B���̂Ȃ���C�������A������K���̒j���Z���͍��ʂȂ������{�Z�ɒʛ{�����߂���Əq�ׂĂ�邩��ł���B���ꂪ���Ƃɂ�Ĉێ�����Ă����̂��ǂ����ɂ��Ă͌�Ă�Ȃ��B���̛{�Z�Ő��k���͑S��椂ݏ��������͂�A�����̗��j�ɂ��Ă̒m������������قǂ������̂ł���B���₤�ɂ��āA�ł��n�����_�v�̎q���ɂ����͛{�₪�o�҂�d�g�Ȃ̂ł���B
�����{���ق̒��ɂ́A���[���b�p�l�ƃA�����J�l�Ƃ̎��ɓK�ӂ₤�Ȃ��̂��Ȃ��B�A�����Ɉꌾ����A���{�l�͉��ق�M��Ɉ����Ă��B
�����łɏq�ׂ��₤�ɔޓ��͉�U�{��S���m��Ȃ��B�]�Ĕޓ��͒����Ƃł��Ȃ������ё��`�Ƃł��Ȃ��B�ޓ��͉��ߖ@��m��Ȃ��̂ŕ��i��`�����Ƃ��ł��Ȃ��B�R����̕�铂�\������ۂ̍ו��̐��m���A���̖{���������ɔc�������y�ł́A�ޓ��ɋy�Ԃ��̂��Ȃ��B�ނ�̕s���S�Ȃ͍̂\���ł���B
���ނ炪�Y�p�Ƃ��Ă̌��z��m�Ă��Ɖ]�ӂ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�A���r���I�݂ɐĂ����z�u����̂ł���B���Α�������ł͂Ȃ��B
�����ꓙ�̓��{��l�́A�������̒ʂ�A���̍D��S�𑽏��T�֖ڂɕ\�͂��Ă���A�������A�D�D�̍\���y�т��̑�����萂�����̑S���ɛ����āA����[��萐S���������B���C�@萂������Ă��ԁA�ޓ��͂����镔�����ڍׂɞ����������A���|�̕\��������A�����̋@�B�ɂ��đS�����q�Ȑl�X������҂����₤�ȋ������������\�͂��Ȃ����B
�����{�l�͉����ł��A�ُ�ȍD��S���������B�����ޑ������邽�߂ɂ́A���B�����玝�Ę҂��������d�|�̐F�X�ȕi���A��X�̋@�B���u�A�I������ȐF�X��ᢖ��i���A�[���ȋ@�����o�ւĂ��ꂽ�B�ޓ��́A�ޓ��ɂƂċ����ׂ����s�v�c�Ɍ����邠���镨���A�ɂ߂ďڍׂɞ������鎖�����ɟޑ����Ȃ��ŁA�m���␅���ɂ��܂ƂЁA������@����߂ւĂ͈ߕ��̊e��������������̂ł���B
���^���Ȃ����{�l�́A�x�ߐl�Ɠ������A���ɖ͕�I�ȁA�K�����̂���A�f���Ȑl���ł��āA���ꓙ�̓����̂����ɁA��ߍ����ȕ����̔�r�I�����Ȍ�����A��r�I�ǍD�Ȑ����ł͂Ȃ��Ƃ��A�O���̕����K������r�I�e�ՂɗA������邱�Ƃ����Ă��̂����o����邾�炤�B
���ꌾ���ĉ]�ւA���{�l�̋���́A���ɓA�d�Ȃ��̂ł͂������A�����̋Z��ɂ��čD�܂����炴���ۂ��o�ւ��ɉ߂��Ȃ����B�����l�͖����ɁA���{�l�����悢���������Ă�B
����l�̕v�l�͉����܂ł�����ŁA�ߋ����U��l�`�̂₤�ɐ₦�������������B�ޏ����͐₦���o�q�ɔ������Ĉ��A���Ă���A�������Ȃ������悩���炤�Ǝv�ӁB�O�������Ɍ��ȍ�ꏂƐF����ꕂ��I�ꂽ����ł���B�����w�l�͂Ђǂ��A�d�ŁA�����̐Ԃ�V����Ă����قǑP�ǂȐ����ł����B�o�q�B�͂��̐Ԃ�V���ł��邾��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗ������B�A�����̊�͍C���炯�ł���A��铂ɂ����Ȃ炵���l�q�����̂ŁA�~�ނ���������j���肵���肵�ĉ��������A����͑S����ɂȓw�͂ł����B
�������̐l���͗�O�Ȃ��ɁA�L�ɟޑ����ċ���A�ߙ������Ă�Ȃ��₤�����B�n�R�l�̂��l�q�����������A��H�̂��暝��͂Ȃ����B�l���ߏ�ȃ��[���b�p���n���̑����̙|�Ɠ������A���B���k�왧���ɜn�����Ă��̂��ƁX�����A�l���f���Ȃ��̒鍑�ł͒N�ł��Εׂł���A�N���ł��Z������������K�v�����邱�Ƃ������Ă�B�ʼn����̊K�����ւ��A�������̂悢�������܂ƂЁA�ȑf�ȖؖȂ̈ߕ������Ă�B
�����{�̎И��ɂ́A���̓��m�������ɏ�����{�l���̔��y�𖾂��Ɏ����Ă������������B����͏��������ƔF�߂��Ă�āA�d�Ȃ�z��Ƃ��đҋ�����Ă͂�Ȃ����Ƃł���B���̒n�ʂ��A�L���X�g���@�K�̉e�����ɂ��鏔���ɉ�����Ɠ��l�ȍ����ł͂Ȃ����Ƃ͊m�����A���{�̕�A�ȋy�і��́A�x�߂̏��̂₤�ɉƒ{�ł��Ɠ��z��ł��Ȃ��A�g���R�̏��[(�n�[����)�ɉ����鏗�̂₤�ɕ����Ȉ��ق̂��߂ɔ��Г��������̂ł��Ȃ��B��v���Ȑ��̑��݂��Ȃ��Ɖ]�ӎ����́A���{�l�������铌�m�������̂����ł͍ł������I�ł���A��������Ă�隠���ł���Ƃ��ӏ��ꂽ���������͂������������ł���B
�������w�l����ɉ}�킵����ꏂ����Ă�邱�Ƃ������A���{�w�l�̗e�p�͜����Ȃ��B�Ⴂ���͂悢�p�����āA�ǂ��炩�Ɖ]�ւΔ������A�����U���͑傢�Ɋ�潑�ł���A����I�ł���B����͔ޏ�������r�I�������h�������Ă�邽�߂ɐ�����i�ʂ̎��S����҂���̂ł���B
�����c�͐i�������J���̗l����悵�ċ��āA�����̌��ݎ҂����n���C���ƌ��N�Ƃɗ��ӂ����y�́A��X���ւ�Ƃ��鍇�B���̐i�������C���ƌ��N�����ꡂɐi��ł��B�����������łȂ����������āA�����≘���͒��ڂɊC�ɗ������A���͒��̊Ԃ�ʂĂ�鏬��ɗ������ށB
�����O�͊F���{�l�Փ��̓A�d���ƁA�T�֖ڂł͂��邪�����ȑԓx�Ƃ����Ă��B��铂����ڒ������ɒj�����������Ă�鈽����O����̌��i�́A�Z���̓�����萂��āA��ɍD�ӂ��錩�����������₤�Ȉ�ۂ��A�����J�l���o�ւ��Ƃ͎v�͂�Ȃ����B����͓��{�����鏊�Ɍ���K���ł͂Ȃ������m��Ȃ��B�����ě��ی�X�̐e�����������{�l�������ł͂Ȃ��ƌ���B�R�����{�̉��w���́A���̓��m�������������`���D��Ă��ɂ��S�炸�A�^���Ȃ������Ȑl���Ȃ̂ł���B�����̌��i��ʂƂ�����A�ʑ����{�̒��ɂ͈��ȑ}㉂Ƌ��ɁA����K���̖��O�̎���K�������Ȃ��Ƃ𖾂��ɂ���ɑ�����̂������B���̈������͚`�Ɍ��ɂȂ���I���ł������łȂ��A�s���_�ɂ����ꂽ����\�͂����̂ł����B
�����ق͂�������{���Ɠ����₤�ɒ������C���ŁA�X�H�͔r���ɓK����₤�ɂ����A�₦�������T������|�����肵�ĉ����ł����ς�ƌ��N�ɂ悢��Ԃɕۂ���Ă���B
����X�́A���{���D�҂̕��@���͋Z��ɉ������قȂ��̂����Ȃ����B��㉂��`�����^�����邽�߂̉ț{�I�@����L���邩�ۂ��A�D�̔r���ʂ��m���߂邽�߂̉ț{�I�@����L���邩�ۂ��͋^�͂����A���@�����S���̑D������̌^�y�ё傫���ɐ������ċ��邩��A���炭������K�v�Ƃ��Ȃ��ł��炤�B
�����ۓI�y�ы@�B�I�Z�p�ɉ����ē��{�l�͔��ȍI�k�������Ă��B�����Ĕޓ��̓���̑e�����A�@�B�ɛ�����m���̕s���S���l������Ƃ��A�ޓ��̎�H��̋Z�p�̊��S�Ȃ��Ƃ͂��炵�����̂̂₤�ł���B���{�̎�H�Ǝ҂͐��E�ɉ�����@���Ȃ��H�Ǝ҂ɂ���炸���B�ł��āA�l����ᢖ��͂����Ǝ��R��ᢒB������Ȃ�Γ��{�l�͍ł��������Ă��H�ƚ���(�}�j���t�@�N�`���|�����O�E�l�[�V�����Y)�ɉ����܂ł���Ă͂�Ȃ����Ƃ��炤�B���̚����̕����I�i���̐��ʂ�{�Ԕޓ��̍D��S�A���������̎g�p�ɂ��Ă�q�����ɂ�āA���ꓙ�l���𑼚����Ƃ̌�ʂ���Ǘ������߂Ă�鐭�{�̔r�O����̒��x�����Ȃ��Ȃ�A�ޓ��͊Ԃ��Ȃ��ł����܂ꂽ�隠�X�̐����ɂ܂ŒB���邾�炤�B���{�l����x�������E�̉ߋ��y�ь��݂̋Z�\�����L�����Ȃ�A���͂ȋ����҂Ƃ��āA���҂̋@�B�H�Ƃ̐�����ڎw�������ɉ��͂邾�炤�B
���������̎m���B�������d��㉓���̏�������`�̂�����������X�̑O�ɂ��邪�A���{�l�̂���Ɏ����Ă����p�̐������悭���ׂ�ƁA���̒��ڂ��ׂ��l���͑��̔��ɑ������y�ɉ�����Ɠ��������p�ɂ������ׂ�ᢒB�������Ă�邱�Ƃ���������ɂ��B
�����łɏq�ׂ��₤�ɋD�D�̋@萂����{�l�̊Ԃɗ���������ыN�����B�ޓ��̍D��S�͖O�����Ƃ�m��Ȃ��₤�ł���A�����{���`�ƒB�͋@�����閈�ɐ₦���@�B�̏�������`���A���̍\���Ɖ^���̌����Ƃ�m�炤�Ƃ��Ă�B�͑��̓�d�ږK��̍ۃW���[���Y���́A�@萑S铂𐳂����ލ����`�������S����`����{�l�����Ă��̂������B�@�B�̐��̕������K�c�ɕ`����Ă�đ����ŕ`����Ă�����ȏ�͂ł��Ȃ��قǐ��m�ŗ��h��㉚��ł����Ɣނ͌�Ă��B
�����{�̏@���͋������`�ł��邩��A���ɂ̒��������Ă��B�n�ĐΑ����������ؑ������@���K��H�T���V�R����B���ꓙ�̒����̐�шꗥ�̎�@�ɂ͈�ʂɑ傢�Ɏ�H�Ə�̏n���������͂�Ă�邪�A���Â���Y�p�I��i�Ɖ]�ӂ��Ƃ͂ł��Ȃ��B
���Ⴂ�����̉Ɖ��ɔ�r���Ă�T���h�ȏ����̎��@���ȊO�ɂ́A�A�����J�l�ɛ����ē��{���z�̍������z����ۂÂ������z�����Ȃ����B�����Y�p���咆�̍ł����h�Ȍ��{�́A����̐̒瓹�Ɛ��ł����B�����̂��͎̂ƁX�ȒP�ɂ��ėY�ӂȃ��[�}���A�[�`��y�i�ɂ��Đ݂����Ă��̂ł��āA���̐v���g�Ζ@�́A���̚��̍ł��ț{�I�ɂ����Y�p�I�ȍ\���̂��̂ɂ��C�G����B
������͓��隠���鏊�ɕ��y���ċ���A�����{�̕w�l�͎x�߂̕w�l�Ƃ͈قĒj�Ɠ������m�����i�����Ă�邵�A�����Փ����Y���ɂ��n�B���Ă�����łȂ��A���{�ŗL�̕��{�ɂ��悭�ʂ��Ă�邱�Ƃ��ƁX�ł���B
���n�k�ɂ�Đ������ЉЂɂ��S�͂炸�A���{�l�̓������锽���͂��\�͂�Ă�B���̓����͂悭�ޓ��̐��͂�暂�����̂ł����B�ޓ��͗��[�����A�s�K�ɋ������A�j�炵���d���ɂƂ肩�T��A�ӟ��j�r���邱�Ƃ��w�ǂȂ��₤�ł����B�@ |
���w���{�؍݊��x�@�n���X
�^�E���[���h�E�n���X (Townsend Harris, 1804-1878) �͕č��̊O�����ŁA1856(����3)�N�ɏ��㒓�����̎��Ƃ��ĉ��c�ɕ��C���A1858(����5)�N���{�Ɠ��ďC�D�ʏ�������������B
1853�N�A��C�ɂ����n���X�̓y���[�͑��ւ̓��s����]���������₳�ꂽ�B�n���X�͒������̎�����]���ċA�����ĉ^�����A�s�A�X�哝�̂̓y���[�ɂ����k���A�n���X��h�����邱�ƂƂ����B
1855�N10��17���A�n���X�͒P�g�j���[���[�N���o�q���A�C���h�ŃI�����_��ʖ�̃q���[�X�P���ƍ��������B
1856�N5���Ƀ^�C�Ƃ̏������������A8��21���ɉ��c�ɓ��������B
�a�e���̉p���ł́A���̎��̒��݂͈���̍����K�v�ƔF�߂�Δh���ł���ƂȂ��Ă������A���{���ł͗������K�v�ƔF�߂��ꍇ�ɂ̂݉\�ƂȂ��Ă����B�����œ��{���͒��݂����ۂ��悤�Ƃ������A�n���X�͂������������9��3���Ɋ`��̋ʐɓ������B
1857�N6��17���A�n���X�̓A�����J�l�̋��Z���A����ł̐d���H�Ɠ��̋����A�̎����s��������e�Ƃ��鉺�c�������c��s�Ƃ̊ԂŒ��������B
11���A�n���X�͉��c���]�˂̔������ɓ������B
12��7���A�n���X�ƃq���[�X�P���͍]�ˏ�ŏ��R�ƒ�ɉy�������B
1857�N2���A�n���X�͕a�ĉ��c�Ő×{�����B
7��23���A�~�V�V�b�s�������c�ɓ��`���A�p�����C���h�ƒ������������������Ƃ�`�����B�n���X�͂�����^�l�ɏ������𔗂����B
���ďC�D�ʏ�����1858�N7��29���A�{�[�n�^������Œ��ꂽ�B
���`��͏������āA�n���ȋ����ł��邪�A�Z���̐g�Ȃ�͂����ς肵�Ă��āA�ԓx�����J�ł���B���E�̂����隠�ŕn�R�ɉ������������ɂȂ��Ă���s�����Ƃ������̂��A�����������Ȃ��B�ނ�̉Ɖ��́A�K�v�Ȃ������C������ۂ��Ă���B�y�n�͈�D�����܂����J������Ă���B
�������͗��h�Ȃ��̂ŁA����ڂ��������Y�ꂢ�ŁA�C���Ȃ��̂ł������B���́A�ނ�̗����ɐr���D����ۂ��������B
�������āA��X�ꓯ�݂͂ȓ��{�l�̗e�p�Ƒԓx�Ƃɐr���ޑ������B���́A���{�l�͊�]��ȓ��̂����Ȃ閯�������D�G�ł��邱�Ƃ��A�J�肩�����Č����B
�����{�̖@�T�͏����k���ł���B�E�l�A���A�����A��↓��A����ɕ��e�ɛ�����\�s�ɂ͎��߂��Ȃ�����B
�����{�l���C���Ț����ł���B�N�ł�������������B�E�l�A���ق̙����ҁA������j���A�V��́A�����̙������I���Ă���A������������B���c�ɂ��V�R�̌��O���ꂪ����B�������A�Z���A���Ȃ킿��Z���g�̔����̈�ł���I�x�T�Ȑl�X�́A����ɓ��a�������Ă��邪�A�����K���͑S���A�j���A�V��Ƃ����������ɂ͂���A�S���ɂȂ��Đg铂�B���́A�����ɂ��ԈႢ�̂Ȃ��������A�ǂ����Ă��̂悤�ɕi�̜������Ƃ�����̂��A���Ђɋꂵ��ł���B
�������鎞�q���[�X�P���N������ւ䂫�A�����̒j�O�l�������ɓ����Ă���̂������B�ނ����Ă���ƁA��l�̏\�l���炢�̎Ⴂ���������Ă��āA�����Œ�����E���A�u�܂闇�v�ƂȂ��āA��\���炢�̎Ⴂ�j�̒������̓��̒��ɐg�����������B���̂悤�Ȓj���̍����͏����̒呀�ɂƂ��Ċ���ł͂Ȃ����ƁA���͕���s�ɕ����Ă݂��B�ނ́A���X���̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ɠ������B�����Ŏ��́A�|���ł���Ǝv���Ă��鏗�ƌ������āA������̎������łȂ����Ƃ�m�����Ƃ��ɂ́A�j�̕��͂ǂ����邩�Ɩ₤���B����s�́A�u�ǂ��ɂ��v�Ɠ������B
�����Ęb��́A�����̓��{���̂��̂ֈڂ����B���̐l�����̈��z���́A�M�����Ȃ��قǂł���B�v�������ނ�ۂ�A�ނ炪���Ēk�����́A�����ėB��̘b�肪����Ă���B
�����́A���{�l�̂悤�Ɉ��H��ߕ��ɂ��āA�ق�Ƃ��əL��Ŋȑf�Ȑl�Ԃ��A���E�̂ǂ��ɂ����邱�Ƃ�m��Ȃ��B���͉��l�ɂ����������Ȃ��B�����͎�Ƃ��āA�ނ�̓����̏���ɗp�����Ă���B�������̏ꍇ�́A���N�̓������ѐD����≩�F�̂��̂ƂƂ��ɗp�����邪�A����Ȃ��Ƃ͖ő��ɂȂ��B�����͗�O�ł����āA�@���ł͂Ȃ��B�����̐F�͍����D�F�ł���B�M�l�̂��̂��������z�ŁA���̑����ׂĂ̎҂̕z�͖ؖȂł���B���{�l�͎����ė~�]�̏��Ȃ������ł���B
���Ȃ�Ƃ������������d�����꓾�邩����A�����ē��{�l�����������͂��Ȃ��Ǝ��͍l����B�����������șd��������悢�Ƃ��ł��A���{�l�͋��U���������Ƃ��D�ށB
�����́A�ǂ�Ȏ�ނ̔��p�i�������I�ɍ��Ƃ����y�ɂ��āA���{�l�̏K�������Ԃ��Ă����Ǝv���B�ނ�̐��{�̓����́A�x�ƚ��ʂ̂��߂ɕi�������r�O���ӂ邤���Ƃ��A�ւ��Ă���悤�Ɍ�����B���ʋ֎~�@�́A�`�A�F�ʁA�ޗ��ƁA���ׂĂ̈ߗނ̒���������������Ă���B���ꂾ����A�Ƌ�����V�Ȃ��́A���{�ł͒m���Ă��Ȃ��B���̚��ł́A�喼�̓@��̉Ƌ�ł���A�A�����J�̋ޒ��Ō����ȐE�H�̉ƂɌ�������̂̔����̒l�ł����Ȃ��Ƃ����Ĝ݂�Ȃ��B���p�Ǝ��f�́A���̚��̏d�v�Ȋi���ƂȂ��Ă���B����͍ł����ǂ낭�ׂ����@�ɂ���ě��{����Ă���B�����̎���ɂ���āA���{�l�̂�����s�ׂ�}���悤�Ƃ��邱�Ƃ��A�₦����d���ƂȂ��Ă���B
�������l�̝ɂ������Ă����B�ނ�͊F�悭�삦�A�g�Ȃ���悭�A�K�������ł���B�ꌩ�����Ƃ���A�x�҂��n�҂��Ȃ��\�\���ꂪ���炭�l���̖{�c�̍K���̎p�Ƃ������̂��낤�B���͎��Ƃ��āA���{���J�����ĊO���̉e�������������邱�Ƃ��A�ʂ��Ă��̐l�X�̕��ՓI�ȍK���i���鏊�Ȃł��邩�A�ǂ����A�^�킵���Ȃ�B���́A���f�Ɛ����̉���������A������̑��̚��ɂ���������A��葽�����{�ɂ����Č��o���B�����ƍ��Y�̈��S�A�S�ʂ̐l�X�̎��f�Ɵޑ��Ƃ́A���݂̓��{�̌����Ȏp�ł���悤�Ɏv����B
�����́A�X�`�[��(����)�̗��p�ɂ���Đ��E�̏����̂������Ƃ�������B���{�͍��������e�����˂Ȃ�Ȃ��Ȃ邾�낤�B���{�̚����ɁA���̊�p���ƋΕׂ����s�g���邱�Ƃ�������������Ȃ�A���{�͉����炸���Ĉ̑�ȁA���͂Ț��ƂƂȂ�ł��낤�B�@ |
���w����C�R�`�K���̓��X�x�@�J�b�e���f�B�[�P
�J�b�e���f�B�[�P (Willem Johan Cornelis Huyssen van Kattendijke, 1816~1866) �̓I�����_�̊C�R�R�l�ŁA1857�`59(����4�`6)�N�ɒ���̊C�R�`�K���̋����c�����Ƃ߂��B���`�K����1855�N7���ݗ�����A�x���X�E���C�P����c���Ƃ����ꎟ�����c��11���ɓ��������B
�J�b�e���f�B�[�P�����͖��{���璍���������C�D���Պۂ�ɉ�q����ƂƂ��ɁA������c�𗦂��ă��C�P���ƌ�シ��悤���߂����B
���Պۂ�1857�N3��26���Ƀ��t�[�g�X���C�X����o�q���A9��21������`�ɓ��������B�����c�͓`�K���ŋ�����ƂƂ��ɁA�V���E�ܓ��E�Δn�E�����E���������ɗ��K�q�C�ɏo���B
1859(����6)�N1���A���{�͗��K�͂̒��z�ۂƙ��Պۂ��]�˂ɌĂъA�`�K���͗��K�q�C���ł��Ȃ��Ȃ����B
3��10���A�J�b�e���f�B�[�P�͒����s����`�K������������ꂽ�B�����ł̍u�`��4��18���������Ē�~���ꂽ�B
11��4���A�J�b�e���f�B�[�P�狳���c�����͏��D�Œ�����A27���Ƀo�^���B�A�ɓ��������B�������|���y�R���n���f�X�@�֎m�琔���́A���{�Ɏc�����B
�����̓I�ɂ��킽�钷���Ԃ̕��a�́A�����̐��i�ɉe�����y�ڂ����ɂ͍ς܂Ȃ������B���j�ɓ`������L���X�g���|�ł̖\�s�́A�S������ɐ₵�A���Ȃ��l�S���ɂ����߂���̂�����B���̖\�s�ɔ�ׂ�ƍ��̍����̉��ǂ��͂܂��i�i�ŁA���{�l�͂��Ƃ����͍��т̂��Ƃ��y�����Ă���Ƃ͂����A���肻�߂ɂ��\�s�Ǝv���邱�Ƃ́A����������������B
�����E�c�����͒m���~�ɔR���Ă���̂����{�l�̓����ł���ƌ����Ă��邪�A�܂��ƂɎ����ł���B�Ⴆ�|���g�K���l�̓n���ȗ��A���{�l�͔@���ɂ悭���[���b�p�l�̒m������Ď��Ȃ̂��̂ɂ������������A����͐��l�̏n�m����Ƃ���ł���B
�����{�l�͕�����͑������A���Ȃ莩���S�������B��X�̂��Ă��邱�Ƃ����āA�������ܑ��l�̏������S�炸�Ƃ��ł���Ǝv���A���̍l���̌��ł��邱�Ƃ�@����Ă��A�Ȃ��Ȃ����߂悤�Ƃ͂��Ȃ��B���̏�A���Ɋ�łŁA���ȊϔO�ɃR�r�����Ă���B
�����͈�ʂɓ��{�����́A�h�����������ł���ƐM���Ă���B�ޓ��͂����w�������̂��A�w�߂ł���ƍl���Ă���A��X�������Ɍw�ł邱�Ƃ������Ɋ�ԁB�ޓ��̔N���҂ɑ��鑸�h�S����я��ʂ̝|�𐽎��ɏ��炷��S�|���ȂǁA���ׂď@�������{�l�ɋ����������ł���A�܂����ߐS�������S�s���������̂́A���{�l�̌����Ƃ����v����B
�����͂������l����A���Ȃ킿���{�ɂ͂��܂�n�R�l�����Ȃ��̂ƁA�܂����{�l�̐����Ƃ��āA���P�����̕�W�Ɋ|��܂łɁA���ɏ����̎肪�L�����̂ŁA����œ��ǂ͕n���K���̋~���ɂ́A���܂�S��z���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���ƁB
�����{�ł͕w�l�́A���̓��m�����ƈ���āA��ʂɔ��ɒ��J�Ɉ����A�����̓��R�ׂ����_��^�����Ă���B�����Ƃ��w�l�́A���[���b�p�̕v�l�̂悤�ɁA�]��ł����Ȃ��B�������Ēj������i�ւ艺��������ɊÂA�v�w�A��̎��ł����A��X�����[���b�p�Ō����Ă���悤�ȁA���̒��q�ŐU�镑���悤�Ȃ��Ƃ͌����ĂȂ��B�������Ƃ����āA�����ĕw�l�͌y�̂���Ă���̂ł͂Ȃ��B���͓��{���l�̗�^�҂Ƃ�����ł͂Ȃ����A�ޏ���̗������ځA���������A�e�����[�X�Ƃ����������Y��Ɍ������p�̂��ł₩�����A�N���ے�ł��悤���B������������������ƁA���̔����������A�������͂���Ő��߂Đ^���ɂ���B
�����ɍł��͔������o�����������Ƃ́A���{�l�����ɑ�Ȗ��������ꍇ�ɁA���Ƃ����Ȃ��Ɉ������Ǝv���A���ɉ��ł��Ȃ����ƂɃ_���_���Ɛ��������R�c�Ɏ����₷�Ƃ���������Ȃ��ԓx�ł������B
�����{�l�̗I�����Ƃ����������邭�炢���B��X�͂܂��]����{�l�̖ɐM�p��u���Ȃ����Ƃ�������ꂽ�B
�������͓��{�l�̂��邱�ƁA�ׂ����Ƃ�����ɂ��A�������肳������B���{�l�͖����ɒ��J�ŁA�����ł͂��邪�A�F�X�̓_�Ŏ��]�������A���̕��ł͎����̖]�݂̔��������������Ȃ��ŁA�����������Ă��܂��̂���Ȃ����Ƃ����v���B
����X�͎Ⴂ�������Ɏw�ւ�^�����B���̖������͂ǂ������̂����������ɏo�����܂܁A��X�ɐ����ė���B�����Ƃ���A�ޏ������́A����ꂪ����ɂ�قNjC������Ă��邱�Ƃ��C�t���Ȃ��炵���B��X���ޏ������̒��ň����e�̖��ɁA�ł��Y��Ȏw�ւ�^�������Ƃ�����ƁA�����̖������͉�X�̖T�ɒp�����������Ȃ��ߊ���ė��āA���̘I�o�������������A�X�Ɏ������点�āA�����������������w�ւ����炤����������̂��Ƃ������Ƃ�m�炻���Ƃ���B����Ȗ��C�ȗl�q�͑��̂ǂ��ł���������̂ł͂Ȃ��B���������̎�������A�����̖������͎����̖��_�����Ƃ��v���Ă��Ȃ��Ȃǂƌ��_�Â��悤���̂Ȃ�A���ꂱ���傫�ȊԈႢ�ł���B
�����̍����K���ł��邱�Ƃ́A��ʂɌ�����ɉh���A�����̏؋��ł���B�S�������ق��J���҂��A�F�\���Ȉߕ���Z���A���w���̐H���ƂĂ��A���Ȃ��Ƃ�����ł́A�\���̂Ȃ����̂�ۂ��Ă���B�������[�N�[���[]�Ȃǂ����̂̂܂܁A�X���ɗ����Ă����Ƃ���A����͕n�R����ł͂Ȃ��āA�s��@�̂����ł���ƌ����B������ނ��Ȃ��ƂŁA�㗬�҂͉��ĂłȂ���A���Ɍ����ďo�Ȃ��̂ł���B
�����w�̓��{�l�́A�݂��ɗ�V�Ƃ������̂�S�R�m��Ȃ��B�j�������A�܂��j�̎q�Ɩ����A��̓����傫�ȕ��C�ɓ����Ă��邱�Ƃ����X����B��X�����̕��C�̖T��ʂ邱�Ƃ�����A�ޓ��͂��̕��C�����яo���A�ˌ��ɗ����Ē��߂Ă���B
������ɔ����āA���l�͌l�I���R�����L���Ă���B���������̎��R�����A���[���b�p�̍��X�ł��]�肻�̔�����Ȃ��قǂ̎��R�ł���B��������ъ��K�Ɉᔽ����s�ׂ́A�Ԓ��̐��x�ɂ���āA�����܂��I�����A�Ɛl�͑ߕ߂�����B�s���͂�������}���Ă���悤���B�������Ė@�K��A�K���������d����A�����Ċ댯�͂Ȃ��B
�����O�͂��̐��x�̉��ɑ傢�ɉh���A�����Ԃ�K���ɕ邵�Ă���悤�ł���B���{�l�̗~�]�͒P���ŁA�ґ�Ƃ������������ɋ��������邭�炢���ւ̎R�ł���B���ƂȂ���ґ�̋֗߂́A�×������Ԃ錵���ł���A�������̕K���i�͗����B������N���F�A���̐g���ɉ��������Y�������Ƃ��ł���̂ł���B�㗬�ƒ�̐H���ƂĂ��A�����Ċȑf�ł��邩��A�n�R�l���Ƃĕx�M�̐l�X�Ƃ��قLj�����H�������Ă����ł͂Ȃ��B���{�l�͊挒�ȍ����ł���B��͂⋙�t�����́A���Ȃ��Ƃ�����ɂ����ẮA�~�ł��قƂ�Ǘ��Ŏd�������Ă���B�������ޓ��́A�̂���������k��Ȃ���A�����Ԃ�����Ɏd�������Ă���̂ł���B
�����{�l�����̓��m�������ƈقȂ�����̈�́A�����ґ�Ɏ����S�������Ȃ����Ƃł����āA���ɍ��M�Ȑl�X�̊قł���A�ȑf�A�P������܂���̂ł���B���Ȃ킿��L�Ԃɂ������t���̈֎q�A���A���I�Ȃǂ̔��i������Ȃ��B�]�ˏ���ɂ͑����̐l�Ԃ����邪�A�ޓ��͊F�Ïl���|�Ƃ��A����͐X�ՂƂ��Ă���B����̓��[���b�p�̋{��ɂČ�������G���̑����Ƃ́A�܂��ɑ��G�I�Ȉ�ۂ���B
�����͓��{�l�قǁA���ڒ��Ȑl�킪���ɂ�����Ƃ͐M���Ȃ��B���A�㌎�̍��A����s����т��̕t�߂ŃR�����a���������A����ȋ]���҂������ł��A�Z���͏����������Ȃ������B����ǂ��납�A�ޓ��͒����s������A���ۂ�@���ė�������A�S�C��ł��Ďs���̋C���������A�������Ė�������悤�Ƃ��Ă����悤�ł������B
�����{�l�̎�������Ȃ����Ƃ͊i�ʂł���B�ނ����{�l�ƂĂ��A���̋ߐe�̎��ɑ��Ĕ߂��܂Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����A��������ނ��̐��Ɉڂ邱�Ƃ́A�������C�ɍl���Ă���悤���B�ޓ��͂��̓��e�̎��ɂ��āA�܂�Œ��ю��̂悤�ɘb���A�n�k�Ύ����̑��̓V�Ђ��Β������Ă��܂��B�����玄�͉���ɊO���l���A���{�̑�s��ɖC���������A�����Ă��̍��������ă��[���b�p�l�̎v�z�ɓ�v�����߂�悤�ȋ��d��i���Ƃ��Ă��A�Ƃ��Ă��b��͂Ȃ��낤�ƐM����B����Ȃ��Ƃ����A��������ւ̂��őP�̕��@�ł��낤�B
����ʂɂ����ď�C�ƒ���̊Ԃɂ͑傫�ȑ��Ⴊ����B���Ƃ����Ă��A����̂ق��������Ă���B���s�Ƃ���Z���̐l����L���鏤�Ɠs�s�ł��邩���r�ɕ֗��ł���B����̒��͍L���Đ^�����ŕܑ�����Ă���ɔ����A��C�̂ق��͋�襂ŋȂ��āA���݂��݂��Ă���B
�����͂��̎x�߂̑؍ݒ��ł��A�������{�͐��Ȃ鍑���Ɗюv�������Ƃ��B���{�͍����Z�����A�x�߂ɔ�ׂ�A�ǂ�Ȃɂ悢���m��Ȃ��B������l���̋��j���ɁA��������ԏ��t�߂ɏ㗤���āA�؎�炭�Ȃ�����A�R���z���J��n���āA����������݁A�Ăяo���ɋA�蒅�������̐߂́A�ق�ƂɎd�������Ɗ������B
���z���͂ɔ��ɕx��ł���Ƃ���́A���{�l�ƃC�^���[�l���悭���Ă���B�������đc��̉p�Y�I�s�ׂ����ꍇ�ȂǁA���ɍV������Ƃ���Ȃǂ��A���҂̎����_�ł���B
���l�͉��ƌ��������A�Ƃɂ������{�l�قNJ��e�S�̑傫�ȍ����͉����ɂ����Ȃ��B�������Ă����ޓ��̊��e�S���A�����ǂ��ł��낤���\��Ȃ��Ƃ������ڒ��̌��ʂłȂ������Ȃ�A���̓_�ɂ����ĉ�X�L���X�g���k�͂������ɋ���������ׂ��ł��낤�B
�����͓��{�̊C�R�m�����A�S�R�����̏�g���̂��ƂɊW���Ȃ��̂́A���{�l�̎����Đ��܂ꂽ����S����ł���Ǝv���B�ޓ��͏�g�����ǂ�Ȃӂ�����Ȃ��Ƃ����Ă��A�������Ď��ӂ������Ƃ��Ȃ��B����ɐG��Ă͎�������Ƃ����C���������������Ȃ��̂ł���B�����������ʁA���w���͑O�ɂ��������Ƃ���A�S�R��w���ƊW���Ȃ�����A�N�ɂ��}������邱�Ƃ��Ȃ��́A���O�̑O�ł����C�łǂ�ȗ��\�ł������Ƃ������ƂɂȂ�B
�����{�l�͉����ȓƗ��S�������Ă��邪�A���������������͂��̏㊯�����A���̈炿�ƌo���ɂ���Đ��������̐M�����l�����邾���̐l���ł���Ȃ�A�ޓ��͂悭���̑D���ɂ����鎩�Ȃ̒n�ʂ�ق��Ă���B���{�l�͂��̂��炢�̂��Ƃ͏\���S���Ă���B�������ĉ�X�����ɑ吺�Ŏ��B���˂Ȃ�ʂ悤�ȏꍇ�ɂ́A��X�̐��ɂ��ƂȂ����]���A�^����ꂽ���߂�v���ɐ��s����̂ł���B
���v���ɓ��{�C�R�m���ɁA���i�Ȃ�D���K���̔@���ɕK�v�ł��邩��F�������߁A�܂��ޓ��̐���ς�����������菜�����߂�B��̕��@�́A�ޓ��������c���̍��ɁA���[���b�p���R�͂ɏ悹�ċΘJ�����K�킵�߂邱�Ƃł���B���{�l�͈�ʂɂ����Ԃ�y���ł���B
���܂��ޓ��̕����ɖO�����ۂ������́A��Ɏm���̏��Ȋw�I�{���Ɉ���V�ł���B���{�l�͕q���ł��邩��A�K�v���Ƃ�����������Ȃ�A�@���Ȃ�w��ł������͂��Ȏ��Ԃ̂����ɁA���������̒m�������ł͂��邪�A��J�Ȃ��Ŋo���邱�Ƃ��ł���B�������������Ƃɂ́A������Ǝn�߂�ƒ������ܔޓ��̍D��S�͖������āA�������̕ς�������̂ɖڂ�����B�����ł��O��I�Ɋw�Ԑh���Ƃ������̂��A�ނ�ɂ͌����Ă���B
�����{�l�����̎q��ɗ^����ŏ��̋���́A���b�\�[�����̒��w�G�~�[���x�ɏ����Ă���Ƃ���̂��̂Ɣ��ɂ悭���Ă���B�����̓_�ɂ����āA���̋���͐�������ׂ��ł���B�������N���Ⓑ����Ɛe�����͂��̎q�������̂��Ƃ�]��\��Ȃ��B�ǂ��ł��悢�Ƃ��������Ɍ�����B�����炻�̌��ʂ͈⊶�ȓ_�������B
�����͈���K���̓��{�l�S���̓����ł��鎩����Ǝ����́A���ׂċ���̍߂��Ǝv���B��S�\�N�̊ԁA�S���������ƌ����������A�������ĊO���l�Ƃ����A��ɗ��Y�҂Ƃ��茩��悤�ɋ������Ă������{�������A�䒆�̊^�̂��Ƃ�����Ȃ鍑���I���������̂��A���Ȃ��������ɂ͓�����Ȃ��B���{�l�͔��ɕ��킩�肪�����B�������܂����̈�ʁA���������l�X�ɂ悭����ʂ�A�ǂ�����J�����Ȃ��ŁA���������������O���Ă��܂��B�ޓ��͐l�ς��ɂ���Ċw�сA�������Ƃɖ����̈��������A���e�A�N���҂���ы��t�ɑ��A�ŏ�̌h�ӂ��A���{�̗͂�@�K�d���邱�ƁA���������V���̂��Ƃ��ł���B���̔��ɁA�ł��T�d�Ɉ���˂Ȃ�ʎ����ł��������Ă��܂��悤�ȁA�y���ȍ����ł�����B
�����{�l�̈�����ʂ͕s�����ȓ_�ł���B���͂�����n�I�o�������B����͊F���̗אl���A������������̂��Ƃ��Ɏv�킵�߂�悤�Ȑ��{�̐����g�D���������ʂł���Ǝv���B�O���l�̊W������Ȃǂ��N�������ꍇ�A���Ăɂ��̓��{�l�̕s�������������Ă���B
�����͔ޓ��������ȁA����ׂ�����A���ꂩ�炵�́A���ł��ނ����������Ƃ͉R�����ĕЂÂ��Ă��܂��Ƃ����荇���Ǝv���Ă���B���̑��ł́A���{�͂������Ă܂��ƂɋC�����̗ǂ������ł���B�����������ĕ��������ɂ��ׂ�����ł͂Ȃ��B�P�ǂȂƂ�������X���邪�A���t�̐^�̈Ӗ��ɂ�����F��ȂǂƂ������Ƃ͑S���m��Ȃ��B
�������ł͉����ł����_�I���������B����ɂ�āA�w�l�͒j�q�Ƒ�����ŎЉ�㗧�h�Ȓn�ʂ��߂Ă���B�R��ɓ��{�̕w�l�͊���ɂ����A�����̎��R�������Ă�Ƃ͂����A�j�q�ɑ��Ă͐�ɂ����ߕ�邱�Ƃ��������Ă���B
�������ē��{�����s�s�V�ȍ��ł���Ƃ͌���Ȃ����A�������܂����������̂Ȃ��ŁA���{�l�قǒj������㵒p�S�̏��Ȃ��������Ȃ��悤�Ɏv����B���C�͑�l�̒j�������A�܂��Ⴂ�j�����F�ꏏ�ɓ���̂ł��邪�A�j�������^�����ŕ��C���璬�ɏo�Ă���̂����X��������B
�����̐ؕ�����l���Ă��A�^�̓��{�l�͒p��������A����I�Ԃ��Ƃ�����B��������{�l�͗E���ȍ����ł��邱�Ƃ��^��Ȃ��B
�����͂��������A�܂�s�ǂł��Ȃ����{�l�ς������ē��{���������B�������{�A���̍������́A�������̍����ƌ����ە��тɓ��钭�߂������Ȏ��R�̌��i�ƂƂ��ɁA�i�������ȋL���Ɏc��ł��낤�B�@ |
���w��N�̓s�x�@�I�[���R�b�N
���U�t�H�[�h�E�I�[���R�b�N (Rutherford Alcock, 1809~1897) �͉p���̊O�����ŁA1859(����6)�N�ɏ��㒓�����g�Ƃ��ĕ��C�����B�O�N�A�G���M�����ɂ���ē��p�C��ʏ���������ꂽ�B�L���ɂ����I�[���R�b�N�͎��߂��A1859�N6��4������ɓ��������B6��26���A�I�[���R�b�N�͌R�̓T���v�\�����ō]�˂ɓ������A�Z�������ւ̓��T���ɒ�߂��B9�����A�I�[���R�b�N�͔��ق����@���A�z�W�\����̎��ɔC������10�����]�˂ɖ߂����B
1860(��������������)�N3��24���A��V��ɒ��J���ÎE���ꂽ�B8��25���A�I�[���R�b�N�͏��R�Ɩɉy�������B9��4���A�I�[���R�b�N��s�͕x�m�o�R�ɏo���A�ɓ��𗷍s��3�T�ԂقǂŋA�������B11��27���A�p�l�}�C�P���E���[�X������e�̖\���œ��{�l��l�������A�I�[���R�b�N��1000�h���̉ߗ���3�����̋ł������n�����`�ɒǕ������B
1861(������)�N1��15���A�č����g�ْʖ�q���[�X�P�����ÎE���ꂽ�B�I�[���R�b�N�͊e���̌��g�Ǝ��艡�l�Ɉڂ������A3��2���]�˂ɖ߂����B���̒���I�[���R�b�N�̓��[�X�ٔ��̌��ō��`�ɏo�����A5��������ɖ߂����B�I�[���R�b�N�̓I�����_���̎��f�E�E�B�b�g��ƂƂ��ɑ�₩�瓌�C���������7��2���_�ސ�ɋA�蒅�����B7��4���A�]�˂̉p�����g��(���T��)���P������A�I���t�@���g���L�����d���������A���g�و��Ɏ��҂͂Ȃ������B
1862(���v��)�N1��23���A�|�������ۓ���S���Ƃ���g�ߒc���p���̓I�[�f�B�����ŁA���[���b�p�Ɍ����č]�˂��o�q�����B3��23���A�I�[���R�b�N�͐X�R�ĔV���ƕ��ӓ������A�����ǂ����B5���Ƀ����h���ɓ��������I�[���R�b�N�́A�{�� (The Capital of the Tycoon) ���o�ł����͂��𐮂��A���N�ɏo�ł��ꂽ�B
������̒��̎R�̎�̕����̊T�ς́A���r�p�����s�s�̂悤�ł���B���̗��R�̈ꔼ�͓��H�̓����ɂ���A���̈ꔼ�͂��т��������l�����������̏��s�s�Ɣ�r���Ă݂����Ƃɂ���Ǝv���B���X�ɂ́A�i�����R�����悤�Ȋ����������B������E����E�����i�Ȃǂ����邾�����\�\�]�˂�ɏ��������Ă�̂ł͂Ȃ��ł��낤����A�܂����������т�̂͂ǂ����Ǝv�����A����ɂ��Ă����܂�S���Ђ�������̂͂Ȃ��B
���������A���̗ގ��_�⑊��_�������킹�āA�S�̓I�ɍl���Ă݂�ƁA���{�̃��r���O(�����h���̃e�[���Y�삼���̃h�b�N�̂���n��ŁA�����h���̊C����̓�������Ȃ��Ă���)�Ƃ������ׂ����̍`�����画�f���������ŁA�����ɐ����I�ɂ킽���Ă����̂Ȃ��ɏZ�݂��������l���������爫�K���������܂�A�܂��I�����_�l���̑��̊O���l������ߋ��E���݂������Ĉ��K���������܂�Ȃ�����A���z���悭�ė��m�I�ŁA��V�����������ł���A���̂����ɏ�i�ŁA�C�^���A��Ƃ܂�������悤�Ȉ��̏_�炩�Ȃ��Ƃ�b���Ƃ������_�����邱�Ƃ��ł���B�s���J�����L��ł̂����̂������́A���炾��Ⴍ�܂�܂��Ă���i�ʂ������ē��O�Ȃ������ł���B
��������Ƃ���ŁA���g�܂��͑S�g�͂����̎q���̌Q�ꂪ�A�܂�ʂ��Ƃł킢�킢�����ł���̂ɏo���킷�B����ɁA�قƂ�ǂ̏��́A�����Ȃ��Ƃ��ЂƂ�̎q�������ɁA�����ĉ��X�ɂ��Ă����ЂƂ�̎q����w���ɂ�Ă���B���̐l�킪���Y�n�ł��邱�Ƃ͊m���ł����āA�܂����������͎q���̊y�����B
�����͓ǎ҂ɁA���̋��̓���ڂɂ��Ă����āA�V��������⑼�̖����ɂ��Ă̐��������͂̑Ώۂ����Ƃ��Ƃ����߂����悤�ɂ��˂�������B���̂��Ƃ́A�܂��܂�����l���Ă������ƂŁA��������Γǎ҂́A�����̑c�悪�v�����^�W�l�b�g����(�C�M���X�̉��ƁF1154�|1399)����ɒm���Ă����悤�ȕ������x�̓��m�ł��A�悭�������邱�Ƃ��ł���ł��낤�B�����́A12���I�̐̂ɂ܂����ǂ�킯���B�Ȃ��Ȃ�A�u���݂̓��{�v�̑����̖{���I�ȓ����ɗގ��������̂́A12���I�ɂ������Ƃ߂��Ȃ�����ł���B
���悭����ꂳ�ꂽ�X�H�́A���������Ɍ�H������Ƃ������Ƃ��̂����A����߂Đ����ł����āA�������ςݏd�˂��Ēʍs�����܂�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��\�\����͂킽�������ĖK�ꂽ�A�W�A�e�n��[���b�p�̑����̓s�s�ƁA�s�v�c�ł͂��邪�C�����̂悢�ΏƂ��Ȃ��Ă���B
�����{�l�́A���낢��Ȍ��_�������Ă���Ƃ͂����A�K���ŋC�����ȁA�s���̂Ȃ������ł���悤�Ɏv����B�Ƃ���ŁA���̌��_�̂����ł����Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃ́A�����ɂ́A�R���I�E�����I�E�����I�ȃJ�[�X�g�\�\����́A�J�[�X�g�Ƃ��������A�K���Ƃ����������悢�����m��ʂ��A�ǂ���������������肾�\�\������Ƃ������Ƃ��B
���������ɓ��{�l�́A�Ȃ�ł�����Ƃ����̂��D�ނ悤���B�I�������l�Ԃ̑g�D�̂Ȃ��ɂ͂���A�S���R�ɐZ�����Ă���̂������͒m���Ă��邪�A���{�̓����̂Ȃ��ɂ́A���̓I�Ȃ��̂��A�ǂ������ЂƂ���O����ɐi�����Ă���悤���B���锎�w�Ȉ�҂��咣����悤�ɁA����ꂪ�O�����̖ڂƎ��������Ă���Ɠ������A���̂Ȃ��ɂ͓�̊��S�ȓ��]���͂����Ă��āA���̂��̂��̂����҂����킹���@�\�̂��ׂĂ��ʂ����A�܂��Ɨ������������̎v�l���������ɉc�ނ��Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��������Ƃ���A���{�l�̓��]�̓�d���͂������ނ̕����̂݁A�����I�E�Љ�I�E�m�I�ȑS�����̂Ȃ��ɂ䂫�킽��A����������Γ�d��������@�ݏo���Ă����ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���ł��낤�B���{�ł́A�����ЂƂ�̑�\�����ƌ�����Ƃ������Ƃ͕s�\���B����X�ւ̏W�z�l�ɂ�����܂ŁA���{�l�͂��ׂđɂȂ��čs������B
�������ɐ����Ȃ��Ƃ������ƁA�܂��O�l�̂́u����v�u�ޏ��v�u����v�Ȃǂ̂������̍��ق������l�̑㖼�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���{��̕��@��̌����Ȏ����Ȃ̂����A���̂��Ƃ́A��ɂ��A���O����̍������̑��̓��퐶���̏K���̖ʂł����H����Ă���悤���B�����Ȃ݂Ƃ������Ƃɂ��Ă̂����̂��������̊ϔO�Ƃ͂܂��������̂��Ƃ����{�ōs�Ȃ��Ă��Ȃ���A���������[���b�p�ł͂���Ȃ��Ƃ�����ΕK�R�I�ɐ�����Ǝv���錋�ʂ����{�ł������Ă��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ����M�������Ă�����قǁA�����͂܂����̍�����Љ���ɒʂ��Ă���Ƃ͂����Ȃ��悤���B
�����ׂĂ������������Ƃ̂Ȃ��ŁA����ꂪ���ɒm�邱�Ƃ́A���Ɏ��Ȃ�ډ�����X���ł���A�l��`�E���Ȏ咣��������x�����Ă���Ƃ������Ƃ����A����́A���ʁA�����̍������̂Ȃ��̂�����̂ɂЂ��傤�ɔ����Ă���B���{�l�́A�����̎푰�⍑�Ƃ��ւ�A�����̈Ќ����d�A���ׂďK����G�`�P�b�g���K�肷����̂�ӂ����苑�₵���肷�邱�Ƃɂ���Ď��������ɓ�����������y�̂Ƃ����J�ɂ������āA����߂ĕq���ł���B����䂦�A���R�̂��ƂȂ���A�����͋V�������Č��ꂵ�������ł���B����炪�y�̂Ƃ����J�ɕq���ł���̂ɂ܂���������Ⴕ�āA���l����������A���l�̋C�ɂ���邱�Ƃ�����邽�߂ɁA�Ђ��傤�ɋC���g���B
���������܂ł́A�����o�����炵�āA�킽���͂����āA��ʂɓ��{�l�͐����ȍ����ŁA�l�ڂ����ꂸ���т��т��炾���(�͂����ł��Ă��ʂɔ���邱�Ƃ͂Ȃ�)�A�g�ɂ��Ă�����̂͂킸���ŁA���ʂ��̂悢�ƂɏZ�݁A���̉Ƃ͍L���ĕ��ʂ��̂悢�X�H�ɖʂ��A�����Ă܂����̊X�H�ɂ́A�s���Ȃ��͉̂������������Ƃ�������Ȃ��A�Ƃ����ӂ��ɂ������Ƃ��͂���Ȃ��B���ׂĐ����Ƃ������Ƃɂ����ẮA���{�l�͑��̓��m�������傢�ɂ܂����Ă���A�Ƃ��ɒ����l�ɂ͂܂����Ă���B�����l�̊X�H�Ƃ����A����ڂƚk���@�������Ă���l�Ȃ炾��ł��A�����������Ȃ��킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B
������́A������߂ł��邽�߂ɂ́A����قNj��낵���݂ɂ������ς����邱�Ƃ��K�v���Ƃ����Ƃ�����݂�ƁA�����ɂ���ׂāA�j����������Ɗ댯�ȑ��݂ł��邩�A����Ƃ�������������Ǝア���A�̂����ꂩ���Ƃ������Ƃł���B
�����{�l�̊O�ʐ����E�@���E�K���E���x�Ȃǂ͂��ׂāA���Ɠ��̂��̂ł����āA�����͂�����ƔF�߂�����F�������Ă���B�������ł��Ȃ�����[���b�p�I�ł��Ȃ����A�܂����̗l���͏����ɃA�W�A�I�Ƃ������Ȃ��B���{�l�͂ނ���A���[���b�p�ƃA�W�A���Ȃ����̖������Ă����Ñ㐢�E�̃M���V�A�l�̂悤�Ɍ�����B�����̂����Ƃ������ꂽ�����̂���_�ł́A���[���b�p�����ƃA�W�A�����̂�����ɂ����Ƃ�ʈʒu�ɂ�����邱�Ƃ�v�����邾���̂��̂������Ă���̂����A�������̂����Ƃ��������������s�v�c�ɂ��킹�����Ă���B
���ǂ̖�E����d�ɂȂ��Ă���B�e�l�����݂��Ɍ�������ł���A�����荇���Ă���B�S�s���@�\���������ł������łȂ��A���S�ɐ��F���ꂽ�}�L�����F���Y���̌����ɂ��ƂÂ��āA�l���������A�܂����Ɍ��������Ƃ������x�̂����Ƃ����O�ȑ̐����A���n�ł͂��܂��ȓ_�ɂ��Ă����������S�ɔ��B���Ă���B
�����{�l�́A�����炭���E���ł����Ƃ���p�ȑ�H�ł���A�w���t�ł���A�����ł���B�����̉��E���C�E�Ă͂��ׂĊ��S�ȍH�̌��{�ł���B
���������Ȃ���A�����ɂ��錚�ĕ��͂������ēƑn�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�����A�����͖ؑ��̌��z���ŁA�������̌��ĕ����������C���������̂ɂ����Ȃ��B���@����傫�ȉƂ́A�������邵���������ŁA���������������ǂ���A�Ђ��傤�ɂ悭�ۂ���Ă���B
�������͂����Ƃ��ꂢ�D���ȍ����ł���ɂ������Ȃ��B���̂��Ƃ́A����ꂪ�ǂ�Ȃ��Ƃ������A���邢�͂ǂ�Ȃ��Ƃ��l���Ă��A�����̈̑�Ȓ������Ǝv���B�Z���̂������ɂ́A���������ɂӂ���Ƃ��x���֎�����悤�ȗ]�T�͂قƂ�ǂȂ��Ƃ��Ă��A�Q���n�R�̒���͌��������Ȃ��B
�������̑S�����ɂ����ł���悤�Ɏv���邱�̃X�p���^�I�ȏK���̊ȑf���̂Ȃ��ɂ́A�̎^���ׂ��Ȃɂ��̂���������B�����āA�����͂�����݂�����ւ��Ă���B
�������̔_�n�𐮑R�ƕۂ��Ă��邱�Ƃɂ����ẮA���E���œ��{�̔_���ɂ��Ȃ����̂͂Ȃ��ł��낤�B�c���́A�O����ɏ�������Ă�����肩�A���̓_�ł��ڂɌ����Đ��R�Ǝ���ꂳ��Ă��āA�܂��ƂɋC�������悢�B
�����̓y�n�́A�y��ƋC��̖ʂŒ������قnjb�܂�Ă���A���̍����̖��������Ȑ��i�Ɗȑf�ȏK���̖ʂłЂ��傤�ɍK���ł���A����������Ȃ��@���Ɩ��ӔC�Ȏx�z�҂ɂ���Ċ�ɓ�������Ă���B�킽���́u����������Ȃ��v�Ƃ��������A���̗��R�́A�t�V�����͂킽���ɐ����̖@�T������Ƃ͂������̂́A�킽���͂��܂܂ł����ǂ����̎ʂ�����ɂ������Ƃ��Ȃ����A����ɂ���炪�킽������������Ă��Ȃ�������́A����͂��܂����Ĉ�����ꂽ���Ƃ��Ȃ����炾�B
�������̂���̎��I�ȓ����́A���铹���I�ȓ����ƂƂ��ɁA���ォ�琢��ւƓ`������B���{�l�̂����ɂ����̗�O�ł͂Ȃ��āA�����������̐��Ȃ͂Ȃɂ��ŏ��̑̎������S�ɐg�ɂ��Ă��܂����ɑ���Ȃ��B����ł��Ȃ����̏�ɁA���{�l�͂��̐����̂Ȃ��ɂȂɂ���i�őP�ǂȂ��̂̍��Ղ𑽂��Ƃǂ߂Ă���B
�����{���ǂ��ł��A�j�͂Ƃ��Ɍv�Z���ւ��炵���āA���̓_�ł̓��[���b�p�l�́u���낤�Ɓv�̍D�G�肽�钆���l�����͂邩�ɗ���Ă���B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���́A���̎�l�����͂邩�Ɍv�Z�����ł���B����ŁA�����Z��|���Z������Ƃ��ɂ́A���Ȃ炸��w�̒��@�ȍ˔\�ɂ���������̂��B
���������ɁA��H�͂���B��s�̂Ȃ��₻�̎��ӂɂ͂��Ȃ葽������B�Ƃ͂����A�����́A���̒����ɂ�����悤�ɖ����ɂ���Ƃ��Q�����ɂ���̂��悭��������Ƃ����悤�ȏ�Ԃɂ͂܂��܂��قlj����B
�������Ƃ���ɂ��A�n��͒n���ɂ���āA�����Ă܂��y�n�̐��Y���ɂ��������ĈقȂ�悤�ł���B�������Ȃ���A���{�l�͂���߂Ď��f�ŋ��R���Ă���A��ʂɕn����������Ƃ��납�画�f����ƁA�k��҂ɂ̂������̂́A���낤���Đ����Ă䂭�ɑ��邾���̕ĂƖ�A����ɂ���炪�������Ă��邽���ւ�e���ł킸������̒������̂ɂ���Ƃ̂��̂����炵���B
����ʂɁA�w�l�����̓����ɂȂ��Ă���̂́A�����₩�ȏ��炵�����ݐ[���\��Ƌ����ł���A�j�����̂Ȃ��ł��g���̂��₵���Ȃ��҂́A���̑ԓx�ɂ����̐������ƗD�낳������������B����A���w�K���̐l�тƂł����A�˂ɂ����ւ��V�������A���l�̊���Ɗ��ɂ�������v�����������A���l�̊�����Q���邱�Ƃ��D�܂Ȃ��B���̂悤�ȋC�����́A���Ԉ�ʂ���ڂőe��ȑ����̂Ȃ����c���L���s�Ȃ��Ă���Ȃ�A�ƂĂ��������Â��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤�B
�����i��q���̂�������Ƃ����M���L�����ʂ��������Ă���A�ǂ̋��ɂ��O���l�����悤�Ƃ���l�тƂ������قǂ�������߂����Ă����B�܂��������{�l�́A��ʂɐ����Ƃ��J���������ւ�̂ɍl���Ă���炵���A�Ȃɂ����������̂����邽�߂ɂ́A�����ǂ���ɑ�Q�O���W�܂��Ă���B
�����{�l�́A���ɂ͉ƒ�̌y�J���������A�j���ˊO�̏d�J��������Ƃ����_�ŁA�����̂������̂Ȃ��łЂƂ���ڗ����Ă���悤�Ɏv����̂ł���B
���S�̂̂��̖q�̓I�Ȍ��ʂ������Ȃ��Ă����B��̂��̂́A��Ȃ��Ƃ����A�w�l�����������B�����������ĐԂ��g�����Ă���Ƃ͂����A�ޏ������̂����Ƃ��݂ɂ�������ȓ_�́A�������Ă��̊�ł͂Ȃ��̂ł���B���ہA��N��喼�������ɐ�ΓI����f�I�Ȍ������s�g���Ă��邩���l����ƁA�\�Z�Έȏ�Ƃ��Ȃ�Ώ����������܂Ƃ�Ȃ��ŊO�֏o��̂͏d���ƍ߂ł���A�s�s�Ղ��Ƃ���@�߂��Ȃ������Ƃ́A�s�v�c�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��c�O�Ȃ��Ƃ��Ǝv����B
�����ݓ��{�������Ɏx�z���Ă���̂́A���̕����I�M�����ł���Ǝv���邪�A����͂���_�ł̓����o���f�B�A����(�Z���I�ɃC�^���A�k�������o���f�B�A�Ɏ��Ă��A774�N�V�������}�[�j���Q���}���l�̈�h�E�����S�o���h���ɂ���ē|���ꂽ����)������B���K����(481 – 751�N)�̃t�����X��̂̃h�C�c�ŁA����̉Ƃ��牤��I����̏�Ԃ��v�킹����̂�����B�M����̎�̘A�M���y�n�����L���A�T�N�\�������v�����^�W�l�b�g��(1154 – 1399�N)�����̃C�M���X�̍����Ƒ�̓����悤�Ɏx�z�������Ă���悤�Ɏv����B
���킽���́A���̒��҂̐��ɂ܂������^���ł����āA���{�l�̈����̑��ɂ��̂����Ƃ��������������������B�����Ă���ɂ́A�K�R�I�ɕs�����ȍs���Ƃ������̂��Ƃ��Ȃ��B���������āA���{�̏��l���ǂ��������̂ł��邩�Ƃ������Ƃ́A���̂��Ƃ���e�Ղɑz���ł��悤�B
�����鍑�ɂ����ẮA�^���ɂ������鈤�͂قƂ�ǔF�߂������B���{�͂���ȍ��ł���B���U�E�q���E�����͂�����ɍs�Ȃ��Ă��邵�A���݂⍼�\�����Ȃ�s�Ȃ��Ă���A�n�����������������B�������A�킽���̈ӌ����ׂ̂Ă����ƁA�������������Ƃ̓L���X�g���̗��@�̂��Ƃɂ�����A�L���X�g���̔������s�Ȃ��̂ɂ����ƍD�s���ȏ����̂��Ƃɂ�����Ă���ƐM�����鑽���̃��[���b�p�̍��X�ɂ���������A�͂邩�ɑ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�����{�́A�����I�Ȍ`�Ԃ�ێ����Ă���A�s���̂��ƂɂȂ��Ă���̂́A����܂łɊ�Ă�ꂽ�Ȃ��ł������ƍI���ȊԒ��g�D�ł���B���̑g�D�́A�K�R�I�ɕ����������܂��������ƂȂ�A�m�I�E�����I�i���ɂ�������ЂƂ̏�Q�Ƃ��č�p����B
���킽���̂����Ă���̂́A�j���̊W�A�@���ɂ���ĔF�߂�ꂽ�����A�����ĕw�l�̒n�ʂł���B���̓_�ɂ��ẮA�s���ɂ������̎]�������{�l�ɗ^�����Ă����Ƃ킽���͐M���Ă���B�����ł͓��{�l�������S�̂Ƃ��đ��������s�����ł��邩�Ȃ����Ƃ��������ɂ͗������肽���Ȃ��B�������Ȃ���A���e�����t�����邽�߂ɔ�������A���݂������肵�āA�������@���ɂ���č߂��ۂ���Ȃ����肩�A�@���̔F�ƒ�������Ă��邵�A�����ĂȂ��אl�̔��������ނ�Ȃ��B
�����{���{���Ƃ��Ă��鐧�x�قǁA�v�z�E���_�E�s���̎��R������I�ɗ}�����鐧�x�́A�ق��ɍl���邱�Ƃ�����B����ɂ킽���́A���{�̐������x�́A�l�Ԃ̍ŏ�̔\�͂̎��R�Ȕ��B�Ƒ����ꂸ�A�����I�E�m�I�Ȑ��������R�M�]������̂�}������X���ɂ���A����ɂ��č��₵���������ׂĂ̂��̂��������A���������i��^���Ȃ��ƐM����B
�����������ɂ��ẮA���{�l�����ׂĂ̓��m�̍����̍őO��Ɉʂ��邱�Ƃ͔ے肵���Ȃ��B�@�B�ݔ�������Ă���A�@�B�Y�Ƃ�Z�p�ɂ��鉞�p�Ȋw�̒m�����n��ł��邱�Ƃ��̂����ƁA���[���b�p�̍��X�Ƃ�������ׂ邱�Ƃ��ł���Ƃ����Ă��悩�낤�B
�����{�l�͒����l�̂悤�ȋ����Ȃ��ʂڂ�͂��܂�����Ă��Ȃ�����A�������O�����i�̖͕��������A���ꂩ��q���g�������肷�邱�Ƃ��낤�B�����l�͂��̂��ʂڂ�̂䂦�ɁA�O�����i�̗D�G����������A�ے肵���肵�悤�Ƃ���B�t�ɓ��{�l�́A�ǂ������_�ŊO�����i��������Ă��邩�A�ǂ�����Ύ�������������ςȕi������o�����Ƃ��ł��邩�A�Ƃ������Ƃ����������̂ɔM�S�ł��邵�A�܂��f�����B
�����̂悤�ɁA���E�ł��ŗǂ̓��H�������Ă���Ȃ���A�ʐM�̑��x�Ǝ�i�ɂ���_�ł́A�����͑��̕������E�ɎO���I��������Ă���B���������̂Ђ��傤�Ɍ��n�I�ȗX�ւ��A�l�тƂ̕K�v�ɂ͂Ȃ�̊W���Ȃ��A���{�Ƃ��̖�l�̂������̘A����ۂ��Ă����̂ɖ𗧂��Ă��邾���ł���B
���l������̌��ĕ��̑傫���Ȃ艿�l�ɂ��ẮA�������{�̐��_�����Ȃ蓹������������Ȃ��̂ŕ]�������Ƃ���Ȃ�A���{�l�ɂƂ��Ă͍��Ȃ��Ƃł��낤�B�����ɂ͌��z�ƌĂт���悤�Ȃ��̂͂Ȃ��B�c���������āA���E�ő�̓s�s�̂ЂƂł���]�˂̊X�H�قǁA�ނ����邵���݂��ڂ炵�����̂͂Ȃ��B�喼�̉��~�ł����A�����悤�Ȍ��ĕ��̒Ⴂ���̃o���b�N�ɂ������A���������������������B
�����ׂĂ̐E�l�I�Z�p�ɂ����ẮA���{�l�͖��Ȃ��ɂЂ��傤�ȗD�G���ɒB���Ă���B����E�����i�E���D�蕨�E����E�����ʂ�ӏ��Ǝd�グ�̓_�Ő��I�ȋZ�p���݂��Ă��鐻�i�ɂ����ẮA���[���b�p�̍ō��̐��i�ɕC�G����݂̂Ȃ炸�A���ꂼ��̕���ɂ����Ă���ꂪ�͕킵����A������ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȕi�������邱�Ƃ��ł���A�ƂȂ�̂��߂炢���Ȃ��ɂ�����B
�������A�l����⓮����ł́A�킽���͖n�ł��������K��𑽏����L���Ă��邪�A�܂��������������Ƃ��Ă���A�ʎ��I�ł����āA�����������₩�Ɏ�����Ă��邽�����ȃ^�b�`��y���ȕM�̓����́A�����̍ő�̉�Ƃł��������ނقǂ��B
������ɂ��ẮA�Ȃɂ������K�v�͂Ȃ��B���̐��i�̑n�n�҂͂����炭���{�l�ł���A�A�W�A�ł����[���b�p�ł�����ɔ�����̂͂��܂����ĂȂ������B�c���{�l�͂���߂Ă���ȕ��@�ŁA�����Ăł��邾�����Ԃ����ޗ����g��Ȃ��ŁA�ł��邾���傫�Ȍ��ʂ����Ă��邪�A�����炭���������������̋����ׂ��V�˂́A���{�l�̂����Ƃ��̎^���ׂ��_�ł��낤�B
�����Ȃ킿�A�����̕����͍��x�̕��������ł���A���ׂĂ̎Y�ƋZ�p�͏��C�̗͂�@�B�̏����ɂ�炸�ɓ��B���邱�Ƃ��ł��邩����̊����x�������Ă���B�قƂ�ǖ����ɂ���������ȘJ���͂ƌ������A���C�̗͂�@�B�������Ȃ������̗��_��^���Ă���悤�Ɏv����B�����A�����̒m�I�������I�ȋƐт́A�ߋ��O���I�ɂ킽���Đ��m�̕������ɂ����ĒB�����ꂽ���̂Ƃ���ׂĂ݂�Ȃ�A�Ђ��傤�ɒႢ�ʒu�ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɔ����Ă���炪����܂łɓ��B�������̂�����荂�x�ȁA�����Ă�肷���ꂽ�����������\�͂́A�����l���܂ޑ��̂����Ȃ铌�m�̍����̔\�͂����A�͂邩�ɑ傫�����̂Ƃ킽���͍l����B�@ |
���w��O�����̌��������ېV�x�@�A�[�l�X�g�E�T�g�E
�A�[�l�X�g�E�T�g�E (Ernest Mason Satow,1843~1929) �͉p���̊O�����E���{�w�҂ŁA���g�ٕt�ʖƂ��ė������A�O��25�N�ɂ킽���ē��{�ɑ؍݂��ē��{��Ɠ��{�����ɐ��ʂ����B���{��ʖɍ̗p���ꂽ�T�g�E�́A�k���ɐ������؍݂�����A1862(���v2)�N9�����l�ɓ��������B�����I�[���R�b�N�͕s�݂ŁA�j�[�����R�卲���Վ��㗝���g���Ƃ߂Ă����B
1863(���v3)�N8���A�T�g�E�̓A�[�K�X���ɓ��悵�ĎF���˂Ƃ̐퓬�ɎQ�������B
1864(���v4������1)�N3���A�I�[���R�b�N���A�C�����B9���A�T�g�E�̓L���[�p�[��t���ʖƂ��Ē��B�˂Ƃ̐퓬�ɎQ�������B12��28���A�T�g�E�͉p���C�R�m�����ÎE�������������̏��Y�ɗ���������B���̂Ƃ��I�[���R�b�N�̓��b�Z���O���ɏ��҂���A�A���̓r�ɒ������ゾ�����B
1865(����2���c��1)�N7�����{�A�n���[�E�p�[�N�X���g�����C�����B�T�g�E�͍]�˂̌��g�قֈڂ�A�p�[�N�X�̕㍲�̂ЂƂ�ɋN�p���ꂽ�B10��30���A�T�g�E�͐����̋��ƎҊԋ{��̏��Y�ɗ���������B11��1���A�p�ĕ����̘A���͑��͖��t�Ƃ̒k���̂��ߑ��Ɍ����A�T�g�E�̓p�[�N�X�ɐ��s�����B
1866(�c��2)�N3��6���A�T�g�E�͓��{�`�K���̊ϕ������ϗ������B11��26���A���l�ɑ������A�T�g�E�͏����ƃm�[�g�̑������������B12���A�T�g�E�͐������̎��W�Ƀv�����Z�X�E���C�������Œ���ɕ����A�F�a���E�y���E���ˎm��Ɖ�k�����B
1867(�c��3)�N1���A�T�g�E�̓A�[�K�X���Ŏ������ɕ����A�p���l��s�͎F���˂̊��҂����B�A�[�K�X���͉F�a�����o��1��11���ɕ��ɂɓ��`���A�T�g�E�͐��������Ɖ�k�����B4���A�T�g�E�̓p�[�N�X�Ɠ���c��Ƃ̉�k��ʖ���A��Ƃ̃��[�O�}���ƂƂ��ɗ��H�ō]�˂ɖ߂����B7���A�T�g�E�͓����̃~�b�g�t�H�[�h�ƐV���������E����E�F�����o�đ��܂ŗ��H�𗷍s�����B9���A�T�g�E�͉p�������E�l�����̒����̂��ߒ���ɕ������B12���A�T�g�E�͏��L���ɏ��i�����B
1868(�c��4������1)�N1��8���A�T�g�E�͑���Ńp�[�N�X�ƃt�����X���g���b�V��������c��ɉy������̂ɓ��Ȃ����B2��4���A���O�����_�˂̊O���l�����n���U���������A�p�Ă̎���R�Ɍ��ނ��ꂽ�B�T�g�E�͋��s�ł��̎����̉����ɓ�����A3���ɔ��O�ˎm��P�O�Y�̐ؕ��ɗ���������B3��23���A���O���̌��g�͋��s�Ŗ����V�c�ɉy������\�肾�������A�s�̋����ɏP���A�p�[�N�X�͏h�ɂ̒q���@�Ɉ����Ԃ����B3��26���A�p�[�N�X���V�c�ɉy�����A�ʖ�ɂ̓~�b�g�t�H�[�h���t�����B5��22���A�p�[�N�X�͑��ōĂѓV�c�ɉy�����A�T�g�E�̓~�b�g�t�H�[�h�ƂƂ��ɔ��Ȃ����B9��18������10��17���܂ŁA�T�g�E�͏��L���̃A�_���Y�ƂƂ��ɉڈɏo�������B
1869(����2)�N1��5���A�T�g�E�̓p�[�N�X�ɐ��s���ē����œV�c�ɉy�������B2��24���A�T�g�E�͎��ɂĉ��l���o�q���A�A���̓r�ɏA�����B
�{���́A1921�N�Ƀ����h���̃V�[���[�E�T�[�r�X��Ђ���o�ł��ꂽ�B�����ɂ��Ɩ{���̑O���̓V�����؍ݒ�������1880�N��O���ɏ����ꂽ���A���̌㖢�����̂܂ܕ���o����Ă����B�T�g�E��1907�N�Ȍ�͉p���̃f�{���V���C�A�ɉB���������A�e�ʂ��犩�߂���1919�N�Ȍ�ĂѕM��i�߁A�悤�₭���������B�{���́A���{�ł͏I��܂�25�N�ԋ֏��Ƃ���Ă����B
�����{�̏��l���A���X���l�Ȏ�i�ő���ɕԕꂽ���A�s���s�ׂ�����������Γ��{�̕����͂邩�ɑ傫�������B����Ȃ킯�ŁA�O���l�����̊ԂɁA�u���{�l�ƕs�����Ȏ���҂Ƃ͓��`��ł���v�Ƃ̊m�M������߂ċ����Ȃ����B���҂̐e�P����Ȃǂ́A���蓾�ׂ����Ȃ������̂ł���B
�����x�J�肩�����Č����Ă��A�Ƃɂ����喼�Ȃ�҂͎��ɑ���Ȃ����݂ł������B�ނ�ɂ́A�ߑ�^�̗����N��قǂ̌��͂������Ȃ��A����̎d��������Ă������߂ɁA�m�\�̒��x�͏�ɐ������͂邩�ɉ�����Ă����B���̂悤�Ȋ�Ȑ����̐����Ƃɂ����������̂́A�ЂƂ��ɓ��{�����O������Ǘ����Ă������߂ł������B���[���b�p�̐V�v�z�̕������̍��i�ɐ������������Ƃ��A����͐Ί�������o���ꂽ�G�W�v�g�̖ؔT��(�~�C��)�̂悤�ɕ��X�ɂ����Ă��܂����̂ł���B
�����́A���{��𐳊m�ɘb����O���l�Ƃ��āA���{�l�̊Ԃɒm���͂��߂Ă����B�m�F�͈̔͂��}�ɍL���Ȃ����B�����̍��ɑ���O���̐����m�邽�߁A�܂��͒P�ɍD��S�̂��߂ɁA�l�X���悭�]�˂���b�����ɂ���Ă����B���̖��O�́A���{�l�̂���ӂꂽ����(�F����)�Ɠ������̂ŁA�����瑼�ւƗe�Ղɂ����A��ʎ����Ȃ��l�X�̌��ɂ܂ł̂ڂ����B
�����R�̂悤�ȌQ�W���A�ǂ��֍s���Ă��������̂��Ƃ�����Ă��āA�ߕ��ɂ��������A���낢��Ȏ�������肵�����A�����̑ԓx�͎����Ē��J�������B���́A���{�l�ɑ��鎩���̋C�����A���悢�悠�������Ȃ��̂ɂȂ��Ă䂭�̂��������B
���܂��A�ނ�́A�V�c�~�J�h(�F�F���V�c)�̕����m�点�Ă���A����́A�����������\���ꂽ���肾�ƌ������B�\�ɂ��A�V�c�~�J�h�͓V�R���ɂ������Ď��Ƃ������Ƃ����A���N��ɁA���̊Ԃ̏����ɒʂ��Ă������{�l�����Ɋm�������Ƃ���ɂ��ƁA�ŎE���ꂽ�̂��Ƃ����B���̓V�c�~�J�h�́A�O���l�ɑ��Ă����Ȃ�������Ȃ����Ƃɂ��A�f�łƂ��Ĕ����Ă����B���̂��߂ɁA������ׂ����{�̕���ɂ���āA�ۂ����ł����삪���m�����Ƃ̊W�ɓ��ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂�\�������ꕔ�̐l�X�ɎE���ꂽ�Ƃ����̂��B
�����͂����A���{�̕����A�Ƃ����������̐g�U��ɁA�͂Ȃ͂������Ċ��S���Ȃ��̂��B���{�̗x��́A�����Ƃ��D����(���邢�͕s���R�ɋC�����)���̂̓���ɂ���āA�O���̃����[�g�̔��t�ʼnS����S�̕����\������̂ł���B
�������A�z�O�̎�s�ŁA�l���l���̕���ɒ������B���̒����X�H�����|����Ă����B���ꒅ�𒅂������l����������ēX��ɕ���ł������A���̂��肳�܂͂��������ȗ����o���ăC�M���X�c��J�@���ɗՐȂ��鏗����q�ς��鎞�̌��i�Ɏ��Ă����B���͂܂����̂ǂ��ɂ����Ă��A����Ȃɑ吨�̔������������̂��鏊���������Ƃ͂Ȃ������B
���������ɂ́A�����č����ł��Ȃ��ɓ�(����)�̂悤�Ȑl����������������̌��C�ɓK���Ă���ƍl����ꂽ��A�܂���ʂ̐l�����e�Ղɂ����̐l�Ԃɕ��]����Ƃ������Ƃ���Ɋ�����ꂽ�̂����A���̓��L�ɂ������Ă���悤�ɁA���{�̉��w�K���͎x�z����邱�Ƃ�傢�ɍD�݁A���\�������ėՂގ҂ɂ͑��肪����ł��낤�Ɨe�Ղɕ��]����B���Ƃɂ��̔w��ɕ��͂����肻���Ɏv����ꍇ�́A���ꂪ�������̂ł���B�ɓ��ɂ́A�p�ꂪ�b����Ƃ����傫�ȗ��_���������B����́A�����̓��{�l�A���Ƃɐ����^���ɊW���Ă���l�Ԃ̏ꍇ�ɂ͂���߂Ă܂�ɂ��������Ȃ��������{�ł������B�����������K���̎҂����̓��{����ǂ��������Ƃ��ł�����A���̍��̐l���ɂ͕��]�̏K��������̂ł��邩��A�O���l�ł����{�̓����͂����č���ł͂Ȃ������낤�B
���V�c�~�J�h���N�������ƁA���̖ڂ̂����肩�炨��̏���܂ʼnB��Č����Ȃ��Ȃ������A������������邽�тɎ��ɂ͂��炪�悭�������B�������ς��Ă���ꂽ�̂��낤���A�F�����������B���̊i�D�͂悭�Ȃ��A��҂̂����ˊ{�v���O�i�T�X�ł��������A��̂��猩�Ċ�̗֊s�͂ƂƂ̂��Ă����B���т͂����āA���̈�C���`��̕��ɕ`���������Ă������B�@ |
���w�V�����[�}�����s�L �����E���{�x�@�n�C�����b�q�E�V�����[�}��
�n�C�����b�q�E�V�����[�}�� (Heinrich Schlieman, 1822~1890) �̓h�C�c�̍l�Êw�҂ŁA1871�N�Ƀg���C�A�̈�Ղ@�����B
����ɐ旧��1864�N���E���V�ɗ������A1865�N4���ɐ����A6���ɓ��{��K�ꂽ�B
����������Ȃ�����{�l�̉ƒ됶���̂����݂��ώ@���邱�Ƃ��ł���B�ƁX�̉��̕��ɂ͂��Ȃ炸�A�Ԃ��炢�Ă��āA�Ⴍ���荞�܂ꂽ�łӂ��ǂ�ꂽ�����Ȓ낪������B���{�l�݂͂�ȉ��|���D�Ƃł���B���{�̏Z��͂����ȂׂĐ������̂���{�ɂȂ邾�낤�B
�����{�l�����E�ł������ȍ����ł��邱�Ƃ͈٘_�̗]�n���Ȃ��B�ǂ�Ȃɕn�����l�ł��A���Ȃ��Ƃ����Ɉ�x�́A���̂�����Ƃ���ɂ�����O����ɒʂ��Ă���B
���u�Ȃ�Ɛ��炩�ȑf�p�����낤�I�v�n�߂Č��O����̑O��ʂ�A�O�A�l�\�l�̑S���̒j����ڂɂ����Ƃ��A���͂��������̂ł���B���̎��v�̍��ɂ��Ă���傫�ȁA��Ȍ`�̍g�X��̏�����ԋ߂Ɍ��悤�ƁA�ނ炪������яo���Ă����B�N���ɂƂ₩��������S�z�������A�������ǂ�ȗ�V��@�ɂ��ӂ�邱�ƂȂ��A�ނ�͈ߕ���g�ɂ��Ă��Ȃ����Ƃɉ��̒p���炢�������Ă��Ȃ��B���̐��炩�ȑf�p����I
��(�L������)���ɑ��ݓ�����A���͂����ɟ��邱�̂����Ȃ������Ɛ������ɐS��ł��ꂽ�B�嗝���ӂ�Ɏg���A���Ă��ĂƏ��肽�Ă������̎��́A����߂ĕs���ŁA�������ޔp�I����������A���������������Ȃ��������̂����A���{�̎��X�́A翂т��Ƃ����Ă������قNJȑf�ȕ���ł͂��邪�A���������Â��A�˂�Ȏ����̐Ղ��M���A�����K��邽�тɎ��͑傫�Ȋ��т����ڂ����B
���m�������͂Ƃ����A�V�m�����V����e���Ƃ��̂����Ȃ������������킾���Ă��āA����A����A����ʼn��炵���V�i�̖V�傽���Ƃ͍D�ΏƂ��Ȃ��Ă���B
������A���Ŗ͗l���{�����f���炵���A�܂�ŃK���X�̂悤�Ɍ���P������⎪�G�̖~��ٓ��������Ă���X�͂����Ԃ�����ڂɂ����B�͗l�̔������Ƃ����A���k�ȍ앗�Ƃ����A�Z�[�u���Ă�(�t�����X�̑�\�I�ȓ���)�ɏ���Ƃ����ʓ����X���������B
���ؒ��Ɋւ��Ă͐��^�����̌������ׂĂ���X�����ɑ����B���{�l�͂Ƃ�킯���̖ؒ��ɏG�łĂ���B�������̒����͕s����ł���A���܂Ɍ����������g�����Β����܂�Ȃ����̂ł���B�嗝�͓��{�ł͂܂������m���Ă��Ȃ��悤���B
������ɁA�傫�Ȋߋ�����������B�ߋ�̒l�������ւ�����������A�d�グ�͊����A�������d�|��������߂čI���Ȃ̂ŁA�j�������x���N��p���̊ߋ���Ǝ҂͂ƂĂ����������ł��Ȃ��B���Ƃ��Ίߋ�̏����������Ă��钹�Ă͌܁`�Z�X�[�Ŕ����Ă��邪�A�����͋@�B���N�����ق�̂킸���ȕ��ł��邭����悤�ɂȂ��Ă��邵�A�d�|���œ����T�Ȃǂ͎O�X�[�Ŕ�����B���{�̊ߋ�̂����Ƃ�킯�f���炵���͓̂Ɗy�ŁA�S��ވȏ������A�ǂ���Ƃ��Ă��ʔ����B
�����{�l�͊G����D���Ȃ悤�ł���B�����������ɕ`���ꂽ�l�����͂��܂�Ƀ��A���ŁA�D������@�ׂ��Ɍ�����B
�������ł́A�l�X�͏��w�����ݗe�F���Ă͂��邪�A���̐g���͔ڂ����p�����������̂Ƃ���Ă���B�����玄���A���̍��܂ŁA���{�l���u�������v���E�Ƃƍl���Ă��悤�Ƃ́A���ɂ��v��Ȃ������B�Ƃ��낪�A���{�l�́A���̍��X�ł͔ڂ����p�����������̂ƍl���Ă���ޏ�����A���߂������Ă���̂��B���̂��肳�܂�ڂ̂�����ɂ��ā\�\����͎��ɂ͑O�㖢���̓r�����Ȃ��t���̂悤�Ɏv��ꂽ�\�\�����ԁA���w��_�i�������G�̑O�ɕ�R�Ɨ��������B
�����{�̏@���ɂ��āA����܂Ŋώ@���Ă������Ƃ���A���́A���O�̐����̒��ɐ^�̏@���S�͐Z�����Ă��炸�A�܂��㗬�K���͂ނ�����^�I�ł���Ƃ����m�M���B�����ł͏@���V���Ǝ��Ɩ��O�̌�y�Ƃ���ȋ�ɍ����荇���Ă���̂ł���B�@ |
���w�������{�̌��L�x�@�O���t�B�X
�E�B���A���E�O���t�B�X (William Elliot Griffis, 1843~1928) �͕č��̖q�t�E���m�w�҂ŁA1870�`74(����3�`7)�N�ɓ��{�ɑ؍݂��A����Ɠ����Ő��m�����琧�x�̓����ɐs�͂����B
�A�����1876�N�ɏo�ł����w�c�� (The Mikado�fs Empire) �x���x�X�g�Z���[�ɂȂ�A���m�w�҂Ƃ��Ă̖������m�������B���m���ɂ́w�������{�̌��L�x�́A���̑�ł���B
�O���t�B�X�̓��g�K�[�X��w�ÓT�w���Ŗq�t�ɂȂ�����������A�����Ő��l�̓��{�l���w���ƌ𗬂��A���{�ւ̊S������悤�ɂȂ����B
����̖��V�ق��č��l�̗����w���t�����߂Ă����Ƃ���A�I�����_���v�h����O���`���ǂ̖��_�厖�t�F���X(John H. Ferris)�̐��E�����O���t�B�X���A�C���邱�ƂɂȂ����B
�O���t�B�X��1870(����3)�N12��29���ɉ��l�ɏ㗤���A���N2��16���܂œ����ɂƂǂ܂�A���o�R��3��4���ɕ���ɓ��������B����ł̑ҋ��͂悭�A�O���t�B�X�͏����ɐe���������Ăčs�����B
7��18���ɔp�˒u���̌��肪�`�����A10��1���z�O�ˎ叼���d���������ɑވʂ����B
1972(����4)�N1��22���ɃO���t�B�X�͕�����A���C���o�R��2��3���ɓ����ɒ������B
1874�N7���ɋA�������O���t�B�X�́A�j���[���[�N�̃��j�I���_�w�Z�Ŗq�t�ɂȂ鏀��������ƂƂ��ɁA��q�̍����f��������Ɂw�c���x�̎��M��i�߂��B
1876�N�A�����̓j���[���[�N�̃n�[�p�[�E�A���h�E�u���U�[�Y�Ђ���o�ł���A30�N�ȏ�̒����ɂ킽���ĕč��ōł��l�C�̂�����{���j���Ƃ��ēǂp���ꂽ�B
�O���t�B�X�͖q�t�ɂȂ邭�炢������A���R�L���X�g�������`�҂ŁA���{�����m�̐땺�ƂȂ��ăA�W�A�ɃL���X�g�����L�߂邱�Ƃ����҂��Ă����炵���B
������ǂ����{�l�͐Ό���\�����t��m��Ȃ����A�����ɂȂ��Ă�������g�������Ƃ��Ȃ��B�ɂ�������炸�A�ǂ̃A�W�A�l�����g�Ȃ���Z���������ł���B
�����{�̖@���͌�H��l�ԂƂ݂Ƃ߂Ă��Ȃ��B��H�͒{���ł���B��H���E���Ă��i�����������������Ȃ��B���H�Ɏ���Ō�H����������Ă���B���₻��Ȃ��Ƃ����낤���Ǝv�����낤���A���������Ȃ̂ł���B
�����͏\�����炢�Ŏp���������A���ɑ傫�Ȓ����т̂���L���тł�����ƒ������ނ��сA��ɂ͔������h���Ă���B���Ɣ����������������ԁB�܂����̔������炵�������Ă���B���{�ōł������������͔��������{���ł���B
�����{�o�̎��R���A��V�����������A�P�ǂŗE���Ȓj�A���������A�₳�����w�l�̍��Ƃ��ĕ`������ǂ����B����Ȃ̂Ɍ�H�A�����炯�̎�A���̂�邭�Ȃ�悤�ȏ��ՁA�E�l�̌���A�ÎE�҂̔ؗE�A�����I�̌N��ꐧ�ɂ���č����Ȑl�Ԑ������ݏ������̂��A�Ȃ��������ނ̂��B�����Ȃ��͂����Ȃ��B���h��Ȃ��^��������ׂ������h�ȋ��U���悢���炾�B�܂��^�����������͍̂߂ł���B�A�����J�l�͂��܂���ɉ��ł��M���Ă��܂��قNjC���傫���A�C���I�ȍ��\�t��^��������Ԃ��l�ɖ��킳��āA���{�ɂ��čł�������l����������A����𐳂��̂͒T��j�̂悤�ȕM�̗݂͂̂ł���B���̕M�͒N�����������̌�����l���𐳂��Ă͋L�^���邾�낤�B���͈ꔪ����N�̓��{�̐^�̎p��`���B
�����̕��m�����{�́u�����v�K�����`�����Ă���B�u�w�ҁE�a�m�v���A�����J�l�u���͂��v�̎^���ł��邪�A���{�ł́u�w�ҁE���m�E�a�m�v�ɂȂ�̂����m�̖]�݂ł���B
������͈ꌩ���\�ȑg�����̂悤�����A���̐��_�����̃A�W�A�̒鍑�̎Ⴂ����R���������āA�L���X�g�����̉Ȋw�ƌ��t�̗�������w�ڂ��Ǝv�킹��̂ł���B
���������ɒ[�Ɉ���ނ͓̂��{�l�̓����ł���B����͕��̎��߂̋����̌��ʂł���B
�����{�̏Z���⍑�y�̂Ђǂ��n�R�Ƃ݂��߂Ȑ����Ɏ��͋C�����n�߂��B���{�͂��̍��ɂ��ď����ꂽ�{�̓ǎ҂��z�����Ă����悤�ȓ��m�̊y���ł͂Ȃ������B
�����ۂ̓��{�l�̐������ǂ�Ȃ��̂��m��n�߂�ƁA�悭�m�邱�Ƃ��p����̂悤�Ɍy�̂��Ă����B���͐l��⍑�Ђ��Ⴄ���Ƃ�_�Ɋ��ӂ����B���ꂪ�U�P�I�ł���Ƃ͎v��Ȃ��B
�����{�l�̂悤�ɗV�эD���ł������Ƃ����Ă������悤�ȍ����̊Ԃł́A�q�����L�̌�y�Ƒ�l�ɂȂ��Ă���̌�y�̊Ԃɋ��E���������͕̂K�������e�Ղł͂Ȃ��B���ہA�����I���̊ԂɊO���l������Ă���ȑO����A���̍��̎�Ȏd���͗V�тł������Ƃ����Ă��������낤�B�I�[���R�b�N���̖{�̒��ōł��y�����\���̈�́u���{�͎q���̓V���ł���v�ł������B����Ɏ��͓��{�͂܂��V�т�������l�ɂƂ��Ĕ��Ɋy�����Z���ł���ƕt�������������m��Ȃ��B���̓_�ł͒����l�Ɠ��{�l�̐��i�̑ΏƂ͋ɒ[�ł���B�����̊w�Z�ł͏����ǖ{�A�O���i�ÓT�̂܂��ɍŌ�̕��͂̈�Ɂu�V�т͉v�Ȃ��v�Ə�����Ă���B
�����̖�����������l�́A���{�l�����Ɉ���[�����ł����ł���A�܂����ɂ��ƂȂ����Ė��C�Ȏq���������Ă��邱�ƂɁA���̉������傢�ɑ��h�������Ȃ��Ă���B�q���̗V�т̓����Ɛe�ɂ��V�т̏��オ�A�q���̕��̑f���A����A�]���ƁA�e�̕��̐e�A����Ƃɑ傢�ɊW������A�����Ă���炪���{�ł͔��ɂ��킾���Ă��āA���{�l�̐����Ɛ��i�̂����_�̈���`�����Ă���Ǝ��͎v���B
���������̓��{�̒��ł́A�����Ă��钤���̌����ɂ��炵���@����Ă�B�����l�͂悭�ӂ�ǂ��ꖇ�ɂȂ��Ă���B�����͏㔼�g���ɂȂ�B�g�̂ɂ�������ۂ݂���������̎Ⴂ���ł����A�㔼�g���ł悭�����Ă���B����@�Ƃ����Ƃ��v���ĂȂ��悤���B�������ɖ����猩��Ɖ��̍߂��Ȃ����Ƃ��B���{�̖��́u������O�̃C�u�v�Ȃ̂��B
���ꔪ����N�̓��{�̐i���̋L�^�͂��炵���B�V�c�̐��{�͂����s����ł͂Ȃ��B���Ƃ̌R�����g�D���ꂽ�B�A�d�┽�����������ꂽ�B�o�ŕ��������̌����͂̈�ɂȂ����B���łɐ���̐V���������őn�����ꂽ�B�n���̌Â��x�z�̌`�Ԃ����Ƃ̂���ɋz�����ꂽ�B�d�łƍs���������イ�ɕ��������ꂽ�B�������x�����̂��B�g�ߒc�����[���b�p�֔h�����ꂽ�B�g�ߒc�̍\���́u��N�v���\����g���̒Ⴂ����l�łȂ��A���{�Ɛ^�̓����҂̂��߂ɕق���c���̋M����t���ł������B �V�c�͌Â��`�����̂ĂāA���A�����̂Ȃ��Ɍ����A���J�I�Ȓ��������߂Ȃ��B���ׂĂ̊K���Ԃ̌�����������A�K�����x����������B�퍷�ʊK�����@�ɂ���Ď����s���ɂȂ����B���m�̓����p�~���ꂽ�B�����̕��a�ƒ����͋����قǂ��B�i���͂ǂ��֍s���Ă������t���B���ꂪ�_�݂̂킴�łȂ��ĂȂ낤�B
���������A�A�W�A�I�����̌����҂́A���{�ɗ���ƁA���̍��Ɣ�ׂē��{�̏����̒n�ʂɑ傢�ɖ�������B�����ł͏��������m�̑��̍��Ŋώ@�����n�ʂ��������Ƒ��h�Ǝv�����ŋ������Ă���̂��킩��B���{�̏����͂��傫�Ȏ��R��������Ă��āA���̂��߂�葽���̑����Ǝ��M�������Ă���B
�����������{�l�̐��i�̈�Ԃ̓��F�ł���Ƃ����O���l�̊ԂɍL�܂��Ă���M�O�ɂ��A���{�ł͓��̂̏��������m�̂��̂ɋ߂��Ƃ����l���ɂ����͂��݂��Ȃ��B�Ƃ����͎̂����͂����łȂ��ƐM���Ă��邩��ł���B
�����ď����̏����Ɣ�ׁA�W���I�Ɍ��āA���{�̏����͔��������̂ւ̂��̗D��Ȏ�ł͑S�������̎��i������A������l�̑��g��ɂ����Ă��悭�������Č�����B�܂���V��@�������炵����i�ł��邱�Ƃł��Ђ����Ƃ�Ȃ��B���A�����A���ځA�Ƃ̏����Ǘ��A�������V�̊y���݂܂�Ȃ���ɂ��Ĉ����邱�Ƃł͈�ʂɓ��{�����ɂ܂��鏗���͂Ȃ��B
�����̖{�ɏ��������ƂŌ��₷���Ƃ��낪����̂͏[���ɏ��m���Ă��邪�A�m���Ɍ����邱�Ƃ́A�C�G�X�E�L���X�g�̏@���݂̂����{�l�̐S�ɐV���������炵�A���{�̎Љ�𐴂߁A���ƂɐV�������������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł���B�C�G�X�E�L���X�g�̋����鐸�_�����݂̂��A�Ƃ�킯�������A���{�l�ɃA�����J�l�Ɠ����ƒ됶����^���邱�Ƃ��ł���B�A�����J�l�̉߂���߁A�A�����J�Љ�̕��s�⎸�s�ɂ�������炸�A���̉ƒ됶���A�Љ���́A���{�l�����v��m��Ȃ��قǂɍ��������ł���ƐM����B
�����{�l��ʂ̓����I���i�́A�����A�����A�����A�e�A�_�a�A�A�d�A�F�s�A����A�����Ȃǂł���B�^���̂��߂̐^�����A�����A�ߐ��͎����O�̔����ł͂Ȃ��B���x�́A�ꂵ���܂ł̖��_�̊��o�����m�ɂ���ė{�����ꂽ�B���ʂ̐E�l��_���͐��_�I�ɂ��ƂȂ����r�ł���B���ۂɏ��l�͒m�\�����}�ŁA�����I���i���Ⴍ�A���̓_�Œ����l�ȉ��ł���B���{�̒j���͑��̃A�W�A�����قǏ����ɉ����łȂ��A�ނ���A�d�ł���B�����ӎ���Ќ�\�͂ł͓c�ɂ̐l�͐Ԃ�V�ŁA�s�s�̐E�l�͏��N�ł���B�_�v�͂��̐����̂ǂ�Ȃɍׂ��@�ۂɂ܂ł����M���[�����ݍ��ݐ��܂��Ă���A������Ȃ��ً��k�ł���B
���^�̃L���X�g���𒆐S�ɏW�܂邱���̗͂ƁA��̍����N���A��̍���|���S�\�̐_�̉��ɁA���{�͂₪�Đ��E�̎�v�ȍ��X�ƕ����Ȉʒu���߁A���z�ƂƂ��ɑO�i���镶�����Ƃ��āA���{�����E�̗��j�̕���ɍ������o�ꂵ����A�W�A�����̎w���I��������ł��낤�B���͂��̂悤�Ȋ�]���������ɕ����Ă���B�@ |
���w���{���̓����̓��x�@�d�E�r�E���[�X
�d�E�r�E���[�X (Edward Sylvester Morse, 1838~1925) �͕č��̓����w�҂ŁA�r���ނ̌����̂���1877(����10)�N6��18�����������B
���������̌�A�]�m���Řr���ނ̌������n�߂����A�����Ŕ����Ԃ��Ȃ�������w�����w�u���̓����w�����ɏ������ꂽ�B
9���Ƀ��[�X�͓���̊w�������đ�X�L�˂@�������A���̌㐔��ɂ킽���Ė{�i�I�Ȕ��@���s�Ȃ����B
���[�X�͑�w�Ői���_���u�`�������A�����̂��ق��O���l�ɂ͐鋳�t�������A���[�X���U������҂����������B
���[�X�͕č��ł̌����̂��߁A11���ɋA�������B
1878(����11)�N5���A���[�X�͓�x�ڂ̗����������B����ōu�`�������A7�`8���ɂ͖k�C���𗷍s���A�W�{�̏W���s�����B
��1879(����12)�N5���ɂ́A����E�F�{�E�������ł��W�{�̏W��L�˂̒����������B
1882(����15)�N6���A���[�X�͓���N�W�̂��ߎO�x�ڂ̗������ʂ������B
7��26���A���[�X�̓r�Q���E (William Sturgis Bigelow, 1850~1926) ����уt�F�m���T (Ernest Francisco Fenollosa, 1853~1908) �ƂƂ��ɁA���s�E�L���E�⍑�E�a�̎R�E�ޗǓ�������Ĕ��p�i���N�W�����B���̎O�l�̍v���ɂ���āA�{�X�g�����p�ق̓��{���p�R���N�V�����́A���{���O�ł͍ł��[���������̂ɂȂ����B
�{���́A1917�N�Ƀ{�X�g���ŏo�ł��ꂽ�B���[�X�͑�̐e���ƂŁA���{�l�̓A�d���������傢�ɏ^���A�u����ɔ�ׂĕč��l�Ɨ�����c�v�Ɣᔻ����B���M���̃��[�X��80�߂��V�l�ŁA�u�č��̍ő�̋��Ђ͎Ⴂ�j���̖������I�̍s�ׂł���v�Ƃ����{�X�g���̌x�@�����̌��t�ɐ[�������A��҂ւ̌����������߂Ă����炵���B
�����{�̒��̊X�X�����܂悢����������ۂ́A���܂ł����������ʂł��낤�B�\�\�s�v�c�Ȍ��z�A�ł������ȒɎ����̂����������ʊJ���������X�A�X�������̗���A���낢��Ȃ��܂������i�̐V��A�l�X�̗��Ă��ȕ����A��C���[�������ƒ��̍��B��X�ɂƂ��Ē�������ʕ��ƂẮA���̉��̑�n�ƁA�g�����P�������z���ƈʂł������B
�����������Ȃ��̂ɂ��W�炸�A�����l�͊��S�ɐÂ��Œ����I�ł���B��@���Œ��J�ł���B���L��A���b�Ƃ���悤�ȍ����S�R���Ȃ��c���ꓙ�̂��Ƃ����Ɉ�ۂ��c�����B�����ĉ��Z���I���Č����l�����X�Əo�Ă����̂�����ƁA���������ւ��������邷����̂��Ȃ���A�����Œ����҂��Ȃ��A�܂��E�C�X�L�[��X�ɉ����悹��҂��Ȃ�(����ȓX����������ł���)�B�������̐l�X�����̏ꏊ�����܂������ȏ����ɕ��݊���āA�Â��ɂ��������ނ��A���̏��u�������邩�Ɏ~�����B�Ăю��͂��̍s�ׂƁA�䍑�ɉ��铯���悤�ȉ��Z�ɔ����s�ׂƂ��r�����ɂ͂����Ȃ������B
�����{�l�����낢��ȐV�����l�Ă�f�����̗p�������������ƁA���̌Â������́A�x�߂Ō����閜�������ł�����悤�ȕێ��`�ɁA��������Ă��Ȃ����Ƃ����Ƀn�b�L������B
���D�ԂɊԂɍ��킹�邽�߂ɂ́A�傫�ɋ}���˂Ȃ�Ȃ������̂ŁA�r���A���̐l�͎Ԃ̎ԗւ��O�ɍs���l�͎Ԃ̍��ɂԂ������B�ԕv�����͂��݂Ɏז��������Ƃ���Řl�э����������ő��葱�����B���͑������̍s�ׂƁA�䍑�ł��̂悤�ȏꍇ�ɕK���N��l�i�G���Ƃ��r�����B
���l�X�������ł��鍑�ɂ��邱�Ƃ͎��ɋC�����悢�B���͌����ĎD�����������v�̌���������悤�Ƃ��Ȃ��B���������ʕ����̊��̏�ɁA���͏��K��u�����܂܂ɂ���̂����A���{�l�̎q���⏢�g���͈���ɐ��\��o���肵�Ă��A�G���ĂȂ�ʕ��ɂ͌����Ď��G��ʁB
�����낢��Ȏ����̒��ŊO���l�̕M�ҒB����l�c�炸��v���鎖������B����͓��{���q�������̓V�����Ƃ������Ƃł���B���̍��̎q���B�͐e�Ɏ戵�������łȂ��A���̂�����̍��̎q���B���������̎��R�������A���̎��R�𗔗p���邱�Ƃ͂�菭�Ȃ��A�C���̂悢�o���́A��葽���̕ω��������Ă���B
���D�Ԃɏ���ē����߂Â��ƁA�����h�C�ǂ̂�����]������B���̖h�C�ǂɐڂ��āA�ȒP�ȏZ��Ȃ��ł��邪�A�����ŕi���悢�B�c�ɂ̑��Ɠs��Ƃ��킸�A�x�Ƃ��n�����Ƃ��A�����đ䏊�̋�����D��K���N�^���Ō����Ƃ��Ȃ�����Ă��Ȃ����Ƃ��v���ƁA�����݂����ł���B
�����l�Ɍ��������łȂ��A�ޓ��͊F�w���Ⴍ�r���Z���A�����Z�������A�ǂ��炩�Ƃ����Ɠ˂��o���O���J���Ĕ����������킵�A�j���͍����A�F�͂����݁A�肪�������đ@�ׂœT��ł���A�����ɂ��ɂ��Ƌ����͐Â��Œ��J�ŁA���X�����B���w�������ɉߓx�ɋ@���������̂͋������ł���B
���O���l�͓��{�ɐ�����������ŁA���X�Ɏ��̂悤�Ȃ��ƂɋC�����n�߂�B�����ނ͓��{�l�ɂ��ׂĂ�������C�ł����̂ł��邪�A�������Ƃɂ́A�܂��c�O�Ȃ���A�����̍��Ől���̖��ɉ��ē����I���P�̏d�ׂɂȂ��Ă���P����i�����A���{�l�͐���Ȃ���Ɏ����Ă���炵�����Ƃł���B�ߕ��̊ȑf�A�ƒ�̐����A���͂̐����A���R�y�т��ׂĂ̎��R���ɑ��鈤�A�������肵�Ė��͂ɕx�ތ|�p�A�����̗�V�������A���l�̊���ɏA���Ă̎v�����c���ꓙ�͌b�܂ꂽ�K���̐l�X����łȂ��A�ł��n�����l�X�������Ă�������ł���B
�����{�l�̐������͋������ł���B�Ƃ͐����Ŗ̏��͖������܂�A���͂��Y��ɑ|�����߂��Ă��邪�A����ɂ��W�炸�A�c�ɂ̉��w���̎q���B�͂����Ȃ�������Ă���B
����X�ɔ䂵�ėD��ȓA�d���͏\�{�������A�ԓx�͐Â��ŋC���͈��炵�����̓��{�l�ł���Ȃ���A���̂�����@�ł���Ƃ͑S�R�l���Ȃ��B�S���l���Ȃ��̂�����A��X�O���l�ł������A���{�l�����̂�p���ʂƓ������A�p�����v�킸�A�����ĉ�X�Ɏ���Ă͗��\���Ǝv���邱�Ƃł��A���{�l�ɂ͂����łȂ��A�Ƃ̌��_�ɒB����B�����������@�Ȃ̂́A�O���l���ޓ��̗��̂����悤�Ƃ���s�ׂŁA�ޓ��͂����A�����Ėʂ����ނ���B
�����{�ɐ��N�Z�ނƁA���{�̍ł��r��ʂĂ��ꏊ�ɂ�������A�l�Z�����A���Ԃ̂����킸�A�Z�[�������̑��䍑�̔@���Ȃ�s�s�̐Â��Ȓ��ʂ�ɂ���������S���Ƃ������Ƃ�m��B
���c�ɂ̐l�X�\�\�_���\�\�́A�T���ĕs��ʂł���B�j�̕�������������������Ă��āA���X�m�I�Ȋ������B�����Y��Ƃ������ׂ������܁A�Z�l�����B
���O���l�̗��ꂩ�炢���ƁA���̍����͏����u���y�ɑ��鎨�v�������Ă��Ȃ��炵���B�ޓ��̉��y�͍ł��e�G�Ȃ��̂̂悤�Ɏv����B�a���̖������Ƃ͊m���ł���B�ޓ��͂��ׂē����ʼn̂��B
���d�������Ă���ƒj�A���A���A�����Ȃ���������q���B������������ŁA�����Î����Ă͊��Q������v���イ����B�ޓ��͂��ׂċ��낵���D��S�������āA�V�������͉��ł��ׂ��Ɍ�������B
���R�����͒N������A���J�ɁA���e�Ɏ戵���A���Ɍ������ċ��Ԏ҂��Ȃ���A�������Ɍ��߂�҂��Ȃ��B���̍s�ׂƓ��{�l�Ȃ�x�ߐl�Ȃ肪�A���̍��̕��������ĉ䍑�̑��̘H�\�\�s��̓��H�ł������\�\���s�����Ɏ�ł��낤���̌o���Ƃ��r����ƁA���Ɍ��ɂł����肽���C��������B
�����{�l�����J�ł��邱�Ƃ��ł��͋��������́A�ō��K������Œ�K���ɂ����閘�A���ׂĂ̐l�X����������s�V�������Ƃ������Ƃł���B���b�������l�X�́A�e�ɂ���Ă������ྂ�ʂ炵���A�F���̈ʒu���悭���m���Ă��āA���h���ȂĂ��������Ă���B
�����{�̏M�v�����͗D�G���Ƃ̕]��������ɂ�����炸�A���ɉ��a�ł���炵���A�e�ՂȂ��Ƃł͗��n���牓���֏o�Ȃ��B�������͉����֍s���̂ŁA�ނ��ڋ��҂Ƃ���˂Ȃ�Ȃ������B
�����{�l�̂��ꓙ�y�ё��̑@���ȍ�i�́A�ޓ������R�ɑ傢�Ȃ鈤��������ƂƁA�ޓ��������|�p�ɉ��āA������ȒP�Ȏ��(Motif)����̉�����͂Ƃ������Ă���̂ŁA���ꓙ��������ł́A���{�l�����E���ōł��[�����R�������A�����čő�Ȍ|�p�Ƃł��邩�̂悤�Ɏv����B
���䍑�ł͔��Ɉ�ʓI�ł���(���F�ł͂�����ł��Ȃ�)�w�l�ɑ��錪���Ɨ���Ƃ��A�����ł͖ڂɗ����Č����Ă���B�n�ԂȂ�l�͎ԂȂ�ɏ�鎞�ɂ́A�v���Ȃɐ旧�B����������ɂ́A�Ȃ͕v�́A�����Ȃ��Ƃ��l�A�܃t�B�[�g���Ƃɂ��������B���̑��A���낢��Ȃ��ƂŁA�w�l���Ȉʒu���߂Ă��邱�ƂɋC�����B�c�ޗʂƂ��Ă����ׂ��B��̂��Ƃ́A���{�̕w�l���A���̓��m�l������A�y���ɑ�Ȃ鎩�R�������Ă���Ƃ������Ƃ����ł���B
�����{�̏��g�̕ϒʂ̍˂͌����ł���B���͎l�l�ق��Ă��邪�A���̊e�̈�l�́A���̎O�l�̖�ڂ���蓾��B
�������߂Â��ɂ�A���ɂ��̓s��̊s�O�ŁA���͎q���B���A�c�ɂ̎q���B�����A�@�����Y��ł��邩�ɒ��ӂ����B���̎��́A���߂Â������ɂ��C�������B�q���B�̊ԂɁA���̂悤�Ȓ������O�ς̑��Ⴊ����̂́A���ׂĂ̗��ق⒃�X�����̎q���g�p�l�Ƃ��Čق��A���ꓙ�̎��傪�������̂������̎q���A�c�ɒ���������邩�炾�낤�Ǝv���B�ޓ��͓s��֏o�ė��āA�₪�Ă͌������A�����Ĕޓ��̔��e���q���Ɏc���`����B����͂����Ȃ��Ƃ��A�����I�Ȑ����ł���Ǝv����B
�����{�l�̓����́A�č��Ɖ��F�Ƃ�������ꂽ���ɑ����̑��u�Ɍ���ꂽ�B���鍑�����A���鑕�u�֗̕����ƗL�����Ƃ��Ɏ��ʂ���݂̂Ȃ炸�A���̗̍p�Ɛ����ƂɎ�肩����\�͂́A�ޓ��������ɂ킽�镶���������Ă����ؗ�ł���B������s������̂́A�������̒��x�̍����l�X�����ŁA���J�l���ؐl�ɂ͕s�\�ł���B
���a���𒅂��l�X�̌Q������ƁA���̂��炩�����a�I�ȐF��T��Ȑ܂�ڂ��A�O���̋M�w�l�B�̈ߕ��ƒ������ΏƂ������B�����ȑ̋�ɂ������蒲�a����ߕ��̏�i���Ɣ��킳�A���ꂩ����Q���ׂ����������A�����đ������ꂽ�����̓����\�\����ʂ��̍����̌|�p�I���i��@���ɕ\��������̂͂Ȃ��B
�����������N�̍�����i�ɕ��S���A���{�̌R��������Y�܂őދp���邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�Œ��ɁA���͋��s�֍s���r���A��l�̒��N�l�Ɠ����D�Ԃɏ�荇�킵���B�����A���N�l�͂߂����Ɍ������Ƃ��������A�Ԏ����̓��{�l�B�́A�ޓ������̓�l���Î������L�l����@����ƁA��x�����N�l���������Ƃ������炵���B��l�͑��ʼn��Ԃ����B�����A�ؕ����]���ɂ��ē�l�̌��ǂ����B�ޓ��͌�q��A��Ă����A�����������ꏏ�ɂ��Ȃ��������A������q�̕K�v�͖��������B�ޓ��̖ڗ����₷������������A��Ȕn�̖т̖X�q��A�C�₻�̑����ׂĂ��A���ɂƂ��Ē������Ɠ��l�A���{�l�ɂ��������̂ŁA�Q�O���ނ�����܂����B���́A���邢�͓G�ӂ��܂ސg�U���A�}����悤�Ȍ��t�������邱�Ƃ��o���邩�Ǝv���āA�����ė����܂Ŕޓ��̌�������B�������{�l�́A���̓�l���A�ޓ��̌̍��ɉ��čs������\�s(�p�ߌR��)�ɁA�܂�Ŗ��W�ł��邱�Ƃ𗝉����ʒ����ނł͂Ȃ��A�ޓ��͕��f�̒ʂ�̗�V���������ȂĈ���ꂽ�B���R���́A�䍑�ɉ����̍Œ��ɁA�k���l������łǂ�ȕ��Ɏ戵��ꂽ�����v�������ׁA�����Ă������g�ɁA�ǂ����̍����̕�����荂�������I�ł��邩��u�˂�̂ł������B
���Α���ւ̉����ɉ�X�́A�����̍ł��n���������A�䍑�̓��l�ȋ�悪�J��������ō��G���A�����ė��\�Ȍ��t�ň�t�ɂȂ��Ă���悤�Ȏ����ɁA�ԂŒʂ����B�ł��s�V�̂����j���[�C���O�����h�̑��ł��A�����̂����鏊�Ō�����Â����ƒ����Ƃɂ͂��Ȃ�ʂł��낤�B���ꓙ�̐l�X���A���ׂď��Ȃ��Ƃ��@�������炷�邱�Ƃ́A�m���ɋ����������ł���B�{�X�g���̌x�����ẮA�䍑���ł����������̂́A�Ⴂ�j���̖������ł���Ƃ������B���{�ɂ́A����ȋ��Ђ͊m���ɖ����B�����N�ł��s�V���悢�B
�����{�l�͑����|�p�ɂ����Ă͐��E��Ƃ������ׂ��A�ޓ��͂����鎖�ۂ̔����������̂��ނ炵���������B
�����{�̔_�v�́A����Ɍ܁A�Z��A��Ƃ��ĕāA�卪�A�����̐H����H���B���ۑ������Ƃ���ɂ���(��w���ł���|���͎��ɂ��������)�A���{�l�݂̈͊O���l�̂�������傫���B����́A�ޓ����Ă𑽗ʂɐێ悷�邩�炩���m��Ȃ��B�c�ɂ̎q���B���A�����ʂ�ߍ��Ă̂��߂ɁA�܂邭���o�����������Ă���̂����ẮA��������ʁB
���e��ŐN���I�ȃA���O���E�T�N�\���l��͂����\�N���O�܂ł́A���{�l�ɑ��ł��Ԉ�����l���������Ă����B�j�������������A�Ԃ�����@���w�сA�뉀����낱�сA��q�������ĕ����A���̑������I�ȏK����s�ׂ����������́A�K�R�I�Ɏキ�ĐԖV���݂����̂ł���ƍl�����Ă����B�@ |
���w���{�I�s�x�@�C�U�x���E�o�[�h
�C�U�x���E�o�[�h (Isabella L. Bird, aka Mrs. J. F. Bishop, 1831~1904) �̓C�M���X�̗��s�ƁE�T���ƂŁA���E�e�n�𗷂��Đ������̗��s�L���c�����B
���{�ւ�1878(����11)�N6���ɏ㗤���A�����E�V���E�R�`�E�H�c���o�Ėk�C���ɓn��A�A�C�k�l�̑����������B
���㗤���Ă��ɂ킽�������S�����̂́A���Q�҂��ЂƂ�����Ȃ����ƁA�����Ēʂ�Ō������鏬���ŁA�X���āA�e�����ŁA���ȂтĂ��āA���Ɍ҂ŁA�L�w�ŁA���̂ւ��n���Ȑl�X�ɂ́A�S�����ꂼ��C�ɂ�����ׂ��Ȃ�炩�̎����̎d���Ƃ������̂����������Ƃł��B
�����{�l�͗m���𒅂�Ƃ��炭�����Ɍ����܂��B�ǂ̗m�����s�������ŁA�n��ȑ̌^�ƍ����S�̂̌��ׂł���ւ����Ƃn�r���֒�����܂��B
�����̌�킽���͖{�B���n�Ɖڈ̐��S�}�C��(����S��\�L��)���댯�ȖڂɈ������Ƃ��Ȃ��܂��������S�ɗ������B���{�قǏ������ЂƂ�ŗ����Ă��댯�△��ȍs�ׂƂ܂����������ł����鍑�͂Ȃ��Ǝv���B
������قǎ����̎q�����������킢����l�X���������Ƃ͂���܂���B�������₨��Ԃ�������A����Ȃ��ŕ�������A�Q�[��������Ă���̂߂���A��������ɂ������A��������イ���������^������A�����₨�Ղ�ɘA��Ă�������A�q�������Ȃ��Ă͋C�����܂��A�܂����l�̎q���ɑ��Ă����ꑊ���ɂ��킢����A���b���Ă��܂��B
���Ȃ����q���͒j�̎q���D�܂��Ƃ͂����A���̎q�������悤�ɂ��킢�����܂��B�q�������͂킽�������̕����Ă���T�O���猾���A���ƂȂ������邵���Ⴟ�ق����Ă����܂����A�O����ԓx�͔��ɍD�������Ă܂��B
���mᝁA���炭���A��ᝁA�ቊ�A�s���N�����Ȕ��]�����s���Ă���̂�����̂͂炢���Ƃł��B����ɑ����̎O���ȏ���vጂ̂Ђǂ���������܂��B
���V�����n�͂炭���̂悤�ɑ̂�h�炵�ĕ����A�����z�ŕ��Ƃ����Ƃ��͂ق��Ƃ��܂����B�����z�͍����ɂ��鏬���ȑ��ŁA�ƂĂ��n�����A�ƁX�͕n���ɍr��Ă��܂��B�q�������͂ƂĂ������āA�Ђǂ��畆�a�ɂ�����A���������͏d�J���̂����Ō��F�������Ċ�����������A�𐆂������ʂɗ��тĂ���̂łƂĂ��X���āA���̑̂��͋ϐ����Ƃ�Ă���Ƃ͂ƂĂ������܂���B
�������ɂ͏Z�܂�������A���̑O�ɂ͂��Ȃ蕅�s�����엿�̎R�������āA�����������͂����ł��̎R������A�ǂ�ǂ�ɂȂ�܂ł������Ɠ��݂��Ă��܂��B�݂�ȍ�ƒ��̓`���b�L�ƃY�{���Ƃ����p�ł����A�Ƃ̂Ȃ��ł͒Z���y�e�B�R�[�g�������Ă��܂���B���l���̗��h�ȕ�e�������A�Ȃ�疳��@�Ǝv�킸�ɂ��̊i�D�łق��̉Ƃ�K�₷��̂��킽���͖ڂɂ��Ă��܂��B�c���q�������͂Ђ��ɉ����������ȊO�Ȃɂ��g�ɂ��Ă��܂���B�l���ߕ����Ƃ��Q���ł����ς��ŁA�s���Ƃ������Ƃ��������ċΕׂȐl�X�ɑ��Ă�������Ȃ�A�����̐l�X�͕s���ł��B
�����[���b�p�̍��̑����ł́A�܂����Ԃ�C�M���X�ł��ǂ����̒n���ł́A�������������ЂƂ�ł悻�̍��̕��������ė�����A�댯�Ȗڂɑ����Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ƃ��A����Ɉ���ꂽ��A���J���ꂽ��A�l�i���ӂ�������ꂽ�肷��ł��傤�B�ł������ł͂����̈�x�Ƃ��Ė���@�Ȉ����������Ƃ��A�@�O�Ȓl�i���ӂ�������ꂽ���Ƃ��Ȃ��̂ł��B����ɖ쎟�n���W�܂����Ƃ��Ă��A����@�ł͂���܂���B
�������̂����v�Ђ�����{�Ȃ��Ȃ�A�������͕��Ă����ɂ�������炸�A�n�q�͈ꗢ�����Ԃ��Ċv�Ђ���T���Ă��ꂽ�����A�킽�����n�������������K�����A���̏I���ɂ͂Ȃɂ����������ȏ�Ԃň����n���̂������̐ӔC������ƁA��낤�Ƃ͂��܂���ł����B
���ނ�͒��d�ŁA�e�ŁA�ΕׂŁA�别���Ƃ͖����ł��B�Ƃ͂����킽�������{�l�ƌ��킵����b�〈�����Ƃ��画�f����ƁA��{�I�ȓ����ϔO�͂ƂĂ��Ⴍ�A��炵�Ԃ�͐����ł������ł��Ȃ��̂ł��B
���킽���͖쎟�n�Ɉ͂܂�A�����ނ˗�V�����������̂������ЂƂ̗�O�Ƃ��āA�ЂƂ�̎q�����킽���𒆍���Ō����t�F���E�N܃C�\�\��ȋS�\�\�ƌĂт܂������A���������A�܂��x�������������l�тɂ��܂����B
�����{�l�͎q�����Ƃɂ����D���ł����A�����ς������Ă���̂ƁA�R�������Ƃ������邽�߁A���m�̎q�������{�l�Ƃ��܂肢������ɂ���̂͂悭����܂���B
���ނ�͉����A��������W�܂��Ă��܂��B���̉Ƃ̏��������͂킽�����������Ă���̂�m��ƁA�C���������Ă���������o���A�ۈꎞ�Ԃ킽�����������ł���܂����B������ƁA����͂���Ȃ��Ɠ����A�܂�������낤�Ƃ��܂���B����܂ŊO���l����x���������Ƃ��Ȃ��A�{�ɂ킽���́u�������O�v�������Ă����������ɂ́A����������Ď����������Ȃ߂�킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ����̂ł��B
���g�c�͖L���Ŕɉh���Ă���悤�Ɍ����A���͕n�����Ă݂��ڂ炵�����̂́A�R������~�o���ꂽ���̂킸���Ȕ_�n�͋g�c�̂���Ɠ����悤�ɂ��炵�����R�Ƃ��Ď���ꂪ�s���͂��A�����ɍk����Ă��܂��B�܂���������̂����đ�̕���̍L���_�n�Ɠ����悤�ɁA�C��ɍ������앨���ӂ�ɎY���܂��B�����Ă���͂ǂ��ł������Ȃ̂ł��B�u�����҂̔��v�͓��{�ɂ͑��݂��Ȃ��̂ł��B
�������������Ƃ������Ƃ��������߂ɁA�������A���������Ɖ������ĂĐH�ׂ������h��ɑ����z�����肷��̂͐��������Ƃł��B��@�ł͌��R�Ƃ�����߂��Ă���A����͐��m�l�ɂƂ��Ă͂ƂĂ����������ƂŁA�킽���͂��̂��q���܂̐H�ו��ɂ��������ŏ��o���Ă��܂��Ƃ���ł����B
���ǂ��ł��x�@�͐l�X�ɑ��ĂƂĂ��₳�����A���R���Ȃ�����ɂ́A�O���Â��ɔ����邩�A����ЂƐU�肷�邩����Ύ�����܂��B
���`�ɂ͓��l�̌����l�����O����W�܂����ƌx���������Ă���܂����B����ł��O�����l�̍s�y�q�ɑ��āA�x���͓�ܐl����Ύ������̂ł��B���̏�������グ���ߌ�O���܂ŁA�킽���͂ЂƂ�̐����������������܂���ł������A�e��ȐU�镑���△��@�ȑԓx�������̈�x���ڂɂ��܂���ł����B������������l�ō��Ƃ���ł���A�݂�ȈÖقɗ������Ă��邩�̂悤�ɗւ�����A���̂ł����Ԃ��킽���Ɏc���Ă��ꂽ�̂ł��B
���ߑO���ɂ͖L���̑S�Z�����W�܂�A���H���Ƃ邠�����A�킽���͊O�ɂ��鑺�l�S�����肩�A�y�Ԃɗ����Ă͂��������グ�Ă���l�\�l�ȏ�̐l�X�̒��ڂ́u�I�v�ƂȂ�܂����B�l�X�͏h�̂��邶���炢���Ȃ��Ȃ��Ă����̂��Ɛu�����ƁA�u����Ȃɂ߂��炵�����̂���l��߂���Ƃ͂��邢���A�אl�̎v�����Ɍ�����B�O���l�̏����Ȃ�āA���܌��Ă����Ȃ���A�ꐶ������@��͂Ȃ���������Ȃ��v�Ɠ����܂����B����Ŕނ�͂��Ă������Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��I
�������������ŏo��e�Ȑl�X�ɂ��Ęb�������̂ł����A�n�q�ӂ���͓��ɐe�ŁA�킽������翂ȓ����ő��~�߂����킳���̂�|��ĉڈs�����}���ł���ƒm��ƁA�����Ƃ킽��������グ�Ĕn�ɏ悹�Ă��ꂽ��A���Ƃ��ɔw���ݑ����ɂ��Ă��ꂽ��A�쑐�̐Ԃ������W�߂Ă��ꂽ��A���s�����Ă킽���ɋ��͂��Ă���܂����B�Ԃ����͗�V��H�ׂ����̂́A�Ȃɂ��q�f�܂̂悤�Ȗ������܂����B
���킽���̏h�����(�ɓ��̕����܂߂�)����O�V�����O�����ŁA����܂łقڂǂ��ɍs���Ă��A���K�ɂ������Ă��炢�����Ƃ����S���܂�v����肪����܂������A���{�l�ł��瑫�ݓ���Ȃ���ʃR�[�X���͂��ꂽ�������đf�p�ȑ����ɔ��܂邱�Ƃ��������Ƃ��l����ƁA�h���ݔ��́A�a�ƏL�C���̂����A�����قǂ��炵���A���E�̂ǂ̍��֍s���Ă��A�����悤�ɕ�翂ȂƂ���œ����̏h���ݔ��͓����Ȃ��ƍl����ׂ��ł��傤�B
�����{�̏����͓Ǝ��̏W���������Ă���A�����ł͎��ɓ��m�I�ȁA�i�̂Ȃ�������ׂ肪�����̂��킳�b��G�k����Ȃ��̂ł��B�����̂��Ƃ��ƁA�Ȃ����\�ʓI�Ȃ��Ƃɂ����āA���{�l�͂킽��������肷����Ă���Ǝv���܂����A���̑��̂��Ƃɂ����Ă͊i�i�ɂ킽���������x��Ă��܂��B���̒��d�ŋΕׂŕ��������ꂽ�l�X�ɍ������ĕ�炵�Ă���ƁA�ނ�̗��V�������I�ɂ��킽���ăL���X�g���̋����e�����Ă����l�X�̂���Ɣ�ׂ�̂́A�ނ�ɑ��Ă���߂ĕs���ȍs�ׂł���̂�Y���悤�ɂȂ�܂��B�킽���������\�ɃL���X�g��������Ă��āA��r�������ʂ�����������̂ق��ɗL���ɂȂ�����̂ł����A�����͂����Ȃ��̂ł��I
�����炭���̂܂ܔn�������Ă����Ƃ���A�����ςהn�̍s���A�ꂽ�ӂ���̓��{�l�ɉ�܂����B�ӂ���͈Ƃ����ɖ߂��Ă��ꂽ����łȂ��A�킽������邠���������x���Ă���A�ʂ�ۂɂ͒��d�ɂ����V�����܂����B����قǗ�V�[���Đe�Ȑl�X���ǂ����čD���ɂȂ炸�ɂ�����ł��傤�B
�����F�����A�n�т̂悤�ɍd���є��A��X�����܂Ԃ��A�ג����ځA�������@�A�ւ����A�����S���C�h���L�̊痧���A�Ǝ�ȓ��́A�j�̂���낵�������A���̂悿�悿�Ƃ����������ȂǁA�����ē��{�l�̊O������͑މ����Ă���Ƃ�����ۂ��܂����A����ɑ��A�C�k����͂����ւ���قȈ�ۂ��܂��B
���ɓ����[�H�p�Ɍ{���܂������A�ꎞ�Ԍ�ɍi�߂悤�Ƃ�����A�Q���߂�����傪�����܂ň�ĂĂ����{���E�����̂�����̂͂��̂тȂ��Ƃ�����Ԃ��Ă��܂����B�����͖��J�̕�翂ȏꏊ�ł����A���͔������Ƃ��낾�ƍ����Ă��܂��B�@ |
���w���m�I�s�x�@�O�X�^�t�E�N���C�g�i�[
�O�X�^�t�E�N���C�g�i�[ (Gustav Kreitner, 1847~93) �̓I�[�X�g���[�̌R�l�E�O�����ŁA1877�`80�N�Ƀn���K���[�M���Z�[�`�F�[�j�E�x�[�����݂̓��m���s�ɓ��s�����B
��s��1878(����11)�N6���ɏ�C����D�D�Œ���ɒ����A���˓��C�q�H�Ő_�˂ɏ㗤�����B
���E���s��������A�x�m�R�ɓo�����Ă��瓌���ɓ������B
8���ɃN���C�g�i�[�͒P�g�œ�k�C�������A9���ɏ�C�ň�s�ƍ��������B
���̓��{���s���@���ƂȂ�A�N���C�g�i�[��1884�N�ɉ��l�̎��A��ɑ��̎��ƂȂ������A45�Ŏ��S�����l�O�l��n�ɑ���ꂽ�B
���E���͂��̒��x�ɂ��čĂђ���ɘb��߂��Ă݂�ƁA���̒җ��̎G�R�Ƃ����c�݂́A�i�ʁA�����A�����Ɋւ���킽�������̊ϔO�Ɛ����ł���B�������j�����킸�A���{�l�͂����ȂׂĐe�ň��z���悢�B�ꔲ���ɗz�C�ȏZ���́A�q�����݂���O����ș����悭���邪�A����͓d���̔@���A�����ʂ�`�d����B
���v���e�X�^���g�̐鋳�t�̘b�ł́A�����ł͂��悻�O���l�̏Z�����L���X�g���ɉ��@���Ă���B�����l�̏ꍇ�A��x���@������̐l�͂��܂ł��L���X�g���k�̂܂܂ł���B�Ⴆ�A����鋳�t���\�Z�N�O�ɂ��鑺��300�l�̐l�ɐ�����{���Ă����B�鋳�t�����̑����ĂіK�ꂽ���ɂ́A�M�҂͏\�Z�N�O��葝���Ă����B����ɔ�ׂāA���{�ł͉��@������̂͂͂邩�ɗe�Ղ����A���̍��̖��O�͏@���̖ʂł��u����҂͓��X�ɑa���v�Ƃ������ɒ����ł���B
�����{�l�̏��g���͂ǂ�ȏꍇ�ł��M���ł���B�ނ�͐S�ꐳ���҂ŁA�����Ƃ𗯎�ɂ��Ă����݂��S�z�͂Ȃ��B
���R��̑O�����肩��A�͂⓹�[�ɘI�X�����сA�َq�A���ԕ��A���{�����蕨�A���A�K���X��A�i������Ă���B����q�̏������͐^�ꈤ�z���悢�̂ŁA�O���l�Ȃǂ͂������C�ɂ������Ă��܂��B���{�l�����낢��̓_�Ől�C������̂��A���̐e����f�p���̂������ł��邱�Ƃ͊m���ł���B
�����{�����̒n�ʂ́A���������q�ׂ����Ƃ�������炩�Ȃ悤�ɏ]���I�ł���B�����̖����͎I�Ȃ��̂ŁA�v�́A�ȂƂ����̐S�̓����Ȃǂ͂܂������������A�����̍D���Ȃ悤�ɁA�����Ď����̗~����ʂ�ɉƒ�����Ƃ肵����B
�����{�̓c�ɂ̐l�͕x�̉��b���Ă��Ȃ��B�����͎S�߂Ȃ��̂ł���B�Ă�H�ׂ邱�Ƃ̂ł���T���ȉƒ�͐�������قǂ����Ȃ��B
�����s�҂Ȃ�N�ł��A���{�̍��y�ƍ����̗��ƂȂ��ē��{���狎���Ă����B���̂��Ƃ͓��{�l�̂ق����S���Ă��āA�O���l�ɍD����悤�Ɠw�͂���B
�����ۂɒ��߂Ă݂�ƁA���҂������̂��̂ł͂Ȃ������B�����͑傫�ȑ��Ƃ��������������B�����āA���̖����̕n��Ȗؑ��Ɖ��̒��ɍ��X���ނ������Ă����̋��邳�����A�{�a�Ƃ��������ނ���o���b�N�Ƃ�������ł������B
���������A�S�̔���j�ޖ����I���K�����₷�邱�Ƃ𐭕{�͑ӂ��Ă���B�����̔��W�̊�b�́A���O�����ɂ���B�������A���{�l�ɂ͌��O�������܂��������@���Ă���B���̖ʂł̓��{�l�̍l�����́A���[���b�p�l�̂���Ƃ͂܂�������������Ă���B���[���b�p�l����킽���́A�ꋓ�������ƂɁA���[���b�p�l�̕�����K���̊T�O�Ƃ͂܂��������e��Ȃ���ʂɏo���킷�̂ł���B�c��̉��ɂ͂��ꂼ��܁`�\�l�̖������āA�������������ŏ��藧�āA��Ђ�㵒p�S����������Ƃ͎v���Ȃ����ɕ��R�Ɨ��������͂���āA�ʍs�l�����̖ڂɐg�����炵�Ă���B�ǂ�Ȓ��̘H�n�A�ǂ�ȏ����ȑ��ɂ��������ꂪ����A�����ł́A���{�l�͒j���̋�ʂȂ��A�ЂƂ̗����ɏW�܂�B
�����{�̔��W�ƁA�����e�����y�ڂ����̕����Ƃɂ͑����̏]�����Ă���B���A�킽���́A���{�]���ɂƂ�����̂́A�����Ă��̏ꍇ�A�[����Ղ��������A�ꎞ�̐ȔM���ɂ����Ȃ��A�ƌ��Ă���B�@ |
���w���{�̖ʉe�x�@���t�J�f�B�I�E�n�[��
���X�J�f�B�I�E�n�[�� (Lafcadio Hearn, 1850~1904) �̓M���V�A���܂�̃W���[�i���X�g�E��ƂŁA1890(����23)�N�ɒʐM�L�҂Ƃ��ė����A1896(����29)�N�ɋA�������_�Ɩ�������B
���̊ԁA���]���w�Z��F�{��܍����w�Z�ʼnp��������A�u�_�˃N���j�N���v���̋L�҂��o�ē����鍑��w�p���Ȃ̍u�t�ƂȂ����B
�{�� (�wGlimpses of Unfamiliar Japan�x) �͗����㏉�̍�i�W�ŁA1894�N�{�X�g���ƃj���[���[�N�ŏo�ł��ꂽ�B�n�[���̓��{�^���Ɛ��m�ᔻ�̓��[�X��肳��ɋɒ[�ŁA�ߑ㉻�E�Y�Ɖ��ւ̋������������{�ɂ̂߂荞�ޑf�n�ɂȂ����炵���B
�����{�̐����ɂ��A�Z��������A�������B��������A�c����������B�����A�悭���Ă��������قǁA���̕��O�ꂽ�P�ǂ��A��ՓI�Ǝv����قǂ̐h�������A�����ς�邱�Ƃ̂Ȃ����炳�A�f�p�ȐS�A����������Ɏv�����@���̂悳�ɁA�ڂ���������肾�B
�����{���L���X�g���ɉ��@����Ȃ�A�����₻�̂ق��̖ʂœ�����͉̂����Ȃ����A�������̂͑����Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B����́A�����ɓ��{���ώ@���Ă��������̌����҂̐��ł��邪�A���������M���ċ^��Ȃ��B
���܂�łȂɂ������A�����ȗd���̍��̂悤���B�l�������݂�ȏ������A���ς��Ő_��I�ł���B
�����l���A�Љ�ϊv�𐋂��Ă��鍑���\�\�Ƃ��ɕ����Љ�̎��ォ�疯��I�ȎЉ�̌��݂ւƕς�����Ƃ��ɓˑR�K���A���������̂̐��ނƐV�������̂̏X���̑䓪�ɁA��������߂邱�Ƃł��낤�B���̂ǂ���ɂ��A���ꂩ����{�ł��ڂɂ����邩������Ȃ����A���̓��́A���ٍ̈������ʂ�ɂ́A�V�����ƂĂ����܂������荇���āA���݂����������ĂĂ���悤�Ɍ������B
�����̂Ƃ����́A�����̐l�X�̑����A�Ȃ�Ə������Ċi�D���������ɋC�Â����B�_���̓��Ă������f�����A��������Ȃ�������ȉ��ʂ𗚂����q���̂��ꂢ�ȑ����A�^���������܂𗚂����������̑����A�݂�ȓ����悤�ɏ������Ċi�D�������B���܂́A�e�w�̂킩�ꂽ�����C���̂悤�Ȃ��̂ł��邪�A�q�_�t�@�E�k�X�̐ꂱ�݂̂��锒�����̏�i���ɒʂ���Ƃł����������A�^�����ȑ����ɐ_�b�I�ȍ����Y���Ă���B�����𗚂��Ă��悤���A�����ł��낤���A���{�l�̑��ɂ́A�Õ��ȋϐ����Ƃ�������̂��Y���Ă���B����͂܂��A���m�l�̑����X���������������C�ɘc�߂��Ă͂��Ȃ��B
���X�������ł́A�����ȑ���ʂ蔲�����܂ɁA���N�I�ŁA���ꂢ�ȗ��̂�����������������B���킢���q�������́A�^�������B�����ɁA�_�炩�����̋������z�������������́A���X�Ɠ��Ă������j�⏭�N�����́A�ƒ��̏�q�����O���āA���敗�𗁂тȂ����̏�Œ��Q�����Ă���B�j�����́A�g�y�����Ȃ��Ȃ₩�ȑ̂��ŁA�ؓ������X�Ɛ���オ�����҂͌������Ȃ��B�j�����̑̂̐��́A�����Ă��Ȃ߂炩�ł���B
���c�ɂ̐l�����́A�O���l�̎���s�v�c�����ȖڂŌ��߂�B�����ȏꏊ�Ŏ��������ЂƋx�݂����邽�сA���̘V�l���A���̗m����G��ɗ����肷��̂ł���B�V�l�́A�ނݐ[�������������g�̂���ׂ݂ė}������Ȃ��D��S��l�тȂ���A���̒ʖ�ɕς������������ꂱ��Ԃ��Ă���B����Ȃɉ��₩�ŗD��������A���͂���܂Ō������Ƃ��Ȃ��B���̊�́A�ނ�̍��̔��f�ł���̂��B���͂���܂ŁA�{�萺���ЂƂ����ɂ������Ƃ��Ȃ����A�s�e�ȍs�ׂ�ڂɂ������Ƃ��Ȃ�����ł���B
�����̑����́A���p�̒��S�n���牓������Ă���Ƃ����̂ɁA���̏h�̒��ɂ́A���{�l�̑��^�ɑ��邷���ꂽ���I���o��\���ĂȂ����̂́A���ЂƂƂ��ĂȂ��B�Ԃ̋����G���{���ꂽ������̖̂ڂ�������悤�ȉَq��B��ђ��˂�G�r���A��C���������ł������ꂽ�������̓���̔u�B�����オ�����@�̗t�̌`�������A�����̒���B����ɁA���Ɖ_�̖͗l���{���ꂽ�S�r��A�����ɕ��ɂ̎��q�̓��������^�J�̉Δ��܂ł����A���̖ڂ��y���܂��Ă���A��z�����h�����Ă����̂ł���B���ۂɁA�����̓��{�̂ǂ����ŁA�܂������ʔ����̂Ȃ������������i�ȂǁA�ǂ��ɂł�����悤�ȏX�����̂�ڂɂ����Ȃ�A���̌��������Â�������̂́A�܂��O���̉e�����č��ꂽ�Ǝv���ĊԈႢ�Ȃ��B
������܂ŗ�������������ȓc�ɂ̑��X�ƕς�炸�A�����̑��̐l�������A���ɂ��ɐe�ɂ��Ă��ꂽ�B����قǂ̐e��D�ӂ͑z�����ł��Ȃ����A���t�ɂ��ł��Ȃ��قǂł���B����́A�ق��̍��ł͂܂����킦�Ȃ����낤���A���{�����ł��A���n�ł������킦�Ȃ����̂ł���B�ނ�̑f�p�ȗ�V�������́A�������Ă킴�Ƃ炵�����̂ł͂Ȃ��B�ނ�̑P�ӂ́A�܂������ӎ��������̂ł͂Ȃ��B���̂ǂ�����A�S����f���ɂ��ӂ�o�Ă������̂Ȃ̂ł���B
�����̍��̐l�͂��̎�����A�ʔ������̂��������A�T�����肵�ĉ߂����Ă����B���̂����ĐS���y���܂��邱�Ƃ́A�Ԃ�V���D��S�ɖ������ڂ����J���Đ��܂ꂽ�Ƃ�����A���{�l�̐l���̖ړI�ł���悤���B���̊�ɂ��A�h�������Ȃɂ������҂��Ă���悤�ȁA�Ȃ�Ƃ������Ȃ��\�������ł���B�Ȃɂ��ʔ������̂�҂��Ă镵�͋C���A�炩��ɂ��ݏo���Ă���B�����ʔ������̂�����Ă��Ȃ��Ȃ�A����������闷�ɁA�����̕�����o�����Ă䂭�̂ł���B
�����{�l�́A��Ȑ��m�l������悤�ɁA�Ԑ悾���𗐖\�ɐ����āA�Ӗ��̂Ȃ��F�̉�����グ����͂��Ȃ��B���{�l�͂���Ȗ����Ȃ��Ƃ�����ɂ́A���R�����������Ă���ƌ�����B
���_���͐��m�Ȋw����������邪�A���̈���ŁA���m�̏@���ɂƂ��ẮA�ǂ����Ă��������Ȃ����ł�����B�ٖM�l���ǂ�Ȃɂ�������Ƃ���ŁA���傹��͎��͂̂悤�ɕs�v�c�ŁA��C�̂悤�ɕ߂��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A�_���Ƃ������݂ɐ�����������Ȃ��̂��B
���Ɠ����ɁA�����悤�ȗ��R�ŁA���{�̌Â��뉀���ǂ̂悤�Ȃ��̂���m������ł́A�C�M���X�̍��Ȓ���v���o�����тɁA���������ǂꂾ���̕x���₵�Ă킴�킴���R���A�s���a�Ȃ��̂��ĉ����c�����Ƃ��Ă���̂��A����Ȃ��Ƃ��킩�炸�ɁA�����x���֎����Ă��邾���ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�̂ł���B
�������v���ɁA���{�̐��k�̕��ϓI�Ȑ}��̍˔\�́A���m�̐��k��菭�Ȃ��Ƃ��\�p�[�Z���g�͏����Ă���B���̖����̐��_�́A�{�����|�p�I�Ȃ̂��B
���������A�S����ׂ����Ƃ́A�ǂ�Ȃɕn�����āA�g�����Ⴂ���̂ł��낤�ƁA���{�l�́A�s���Ȏd�ł��ɂ͂܂��]��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B���{�l���ꌩ���ƂȂ������Ȃ̂́A��ɓ����̊ϔO�ɏƂ炵�āA�������Ă���̂ł���B�V�є����ɓ��{�l��@�����肷��O���l�́A�������[���Ȍ���Ƃ����Ǝv���m�邾�낤�B���{�l�́A���������Ɉ�����ׂ������ł͂Ȃ��̂ł���B�����Ă���ȋ����ɏo�ẮA�����疽�𗎂��Ă��܂����O���l�����l������̂ł���B
�����{�l�̂悤�ɁA�K���ɐ����Ă������߂̔錍���\���ɐS���Ă���l�X�́A���̕������ɂ͂��Ȃ��B�l���̊�т́A���͂̐l�����̍K���ɂ������Ă���A�����ł��邩�炱���A�����ƔE�ς��A�����̂����ɔ|���K�v������Ƃ������Ƃ��A���{�l�قǍL����ʂɗ������Ă��鍑���́A���ɂ���܂��B�@ |
�������𗬎j
��1. ���J�� �| �I�����_�D�Y��
1598 �N6���̂��鐰�ꂽ���̌ߌ�B���b�e���_���̍`�ł́A5�ǂ̑D�������q�C�̓r�ɏA�����Ƃ��Ă���B�ړI�n�̓����b�J�����A�� ���X�p�C�X�E�A�C���� �h�B�����ŌӞ��ȂǗl�X�ȃX�p�C�X�B���A�X�ɂ��̐�ɂ����̉����g���{�h��ڎw���B��C��S�C�ŕ�������5�ǂ̑D�́A�k�C�̍r�g�ɏ��o�����B���̒���A��g�������͂�����̏d�v�ȔC����m�邱�ƂɂȂ�B����́A��Ă�A�W�A�̊e�n�ɎU���|���g�K���ƃX�y�C���̋��_���P�����A�G�R�ɉ\�Ȍ���̑Ō���^���邱�Ƃ������B��q�C����A�ǂ̐��͂������c�������������Ȑ킢������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
���̍q�C�͗��j��1 �y�[�W�ɍ��܂��o�����ƂȂ����B�����琔���邱��400�N�O�A1�ǂ̃I�����_�D�����߂ē��{�ɕY�������B 1598�N6��27���Ƀ��b�e���_���`���o�`����5�ǂ̑D�c�̂����A�����c����������1�ǁA���ꂪ���[�t�f(����)���ł���B���[�t�f����1600�N4��19���A���Ɉٍ��̒n�������̂������B�D�c�̂�����1�ǁA�w���[�t(�M��)���́A�}�[�����C���ɂ���������O�Ƀ��b�e���_���`�Ɉ����Ԃ��Ă����B����3�ǂ͂ƌ����ƁA�u���C�f�E �{�[�g�X�n�b�v(����)���̓X�y�C���ɁA�����ăg���E(�M�`)���̓|���g�K���ɏP������A�z�[�v(��])���͗��ɏP���C�ɒ���ōs�����B
1600 �N4��19���A�L��̍������Ӎ��u��(�啪���P�n�s)�̉��͂����Ɨl�q������Ă����B�������p�̋���Ȕ��D���A������낵��������Ă���B ���u���̐l�X�́A�S�߂Ȏp�̃I�����_�l �| �����ɂ͏��Ȃ��Ƃ�1�l�̃C�M���X�l���܂܂�Ă��� �| ���j�D���珕���o���A���̈���ŁA�������̂��܂�A�D������^�яo������̂�S�Ď����������B���[�t�f����19��̑�C�ƁA��ʂ̓S�C�A�Ζ�A�C�e��ς�ł����B�ŏ���110�l������g�����A�q�C���I�������ɂ͂�����24�l�������c��݂̂ƂȂ��Ă����B���̒��ɂ́A��ɔ��d�F����Ƃ��Ēm���郈�[�X�e���E�t�@���E���[�f���X�^�C���A�����ĎO�Y�j���ƃC�M���X�l�̃E�C���A���E�A�_���X�������B���[�t�f���̑D���ؑ��́A�I�����_�̗L���ȓN�w�҃G���X���X�������ǂ������̂ŁA����͌��݁A�������������قɓW�����ꂽ����B
���̌��͎ғ���ƍN�́A�Y�������I�����_�D�ɑ���ȋ������� �����B�D�ɍڂ܂�Ă������킪�A��Ԃ̖ړ��Ă������B���[�t�f�����^��ł�������͑S�Ėv���� ��A�����E���[�X�e���ƃE�C���A���E�A�_���X�͑��A�����ō]�˂ɏ��悤������ꂽ�B������2�l�́A�|���g�K����̒ʖ����Ď�蒲�ׂ��邱�ƂɂȂ�B�^�ǂ��ނ�̕ԓ��͉ƍN�̋C��ǂ����A�P�n�Ŕ�������Q���⏞���ꂽ�B���{�Ɏc������g���̂قƂ�ǂ́A���̌�f�ՂɌg�������A���{�l�����ƌ��� ���Ă���B���̕Y���҂����́A�n�}��q�C�p�A���D�p�̒m���A����ɂ͐��m�����̐틵�Ɋւ�����ȂǁA���ɖ𗧂��̂������Ă����B���̂��ߖ��{�̓E�B ���A���E�A�_���X�ƃ����E���[�X�e�����d�p����B�����āA�̒n�≮�~�A���{�̑��k���Ƃ��Ă̒n�ʂ�ނ�ɗ^�����B�����ɍ��ł��c��j�ʂ�Ⓦ���w�̔��d�F�o���Ƃ����n������A2�l�̕Y���҂̉ߋ������ł����������m�邱�Ƃ��ł���B�ނ�̒����������炵���ő�̐��ʂ́A���{����I�����_�ɔ��s���ꂽ����A�܂�ʏ����ł���B���������̓������s�g����̂�1609�N�܂ő҂��ƂɂȂ�B�Y������9�N�A�悤�₭�I�����_�D�����˂ɓ��`���A�����f�Ղ��{�i�I�Ɏn�܂�B
����ƍN���I�����_�l���d�p�����̂ɂ́A������̗��R���������B���̍��A�ƍN�̓L���X�g���e���ɖ{����� ��n�߂Ă����B�J�g���b�N�n�̃L���X�g���ɉ��@�����M���I�ȐM�҂������A���{�̌��Ђ��������Ă����B�����Łg�g�ѐl�h�܂�I�����_�l�̒m���ɖ��{���ڂ�t�����̂ł���B�v���e�X�^���g�n�̃I�����_�l�́A�ړI�͖f�Ղ����ł���A�L���X�g���z���ɂ͈�؊ւ��Ȃ����j�������B���̎����̃I�����_�l�̓��{�Y���ƁA����ɑ������{�Ƃ̐M���W�̍\�z�́A�܂��Ɏ��߂Ă����B
�������āA���{�ƃI�����_�̊W�����J�����}���邱�ƂƂȂ����B
��2. �����W�̖G��
�| ���g�K���l�����{�ɓ��������̂�1543�N�B���{�ɂƂ��ăI�����_�́A�ł��t�������̒������m���ł͂Ȃ��B�����⒩�N�A��p�ȂǃA�W�A�̍��X�Ƃ̊W�Ɏ����ẮA���R�̂��ƂȂ���X�Ɏ����k��B���얋�{�̍�������ɂ����āA���{�Ƃ̖f�Ղ�������Ă����̂́A�I�����_�ƒ����݂̂������B��������� 1641�N����1853�N�܂ő����B����200�N�ԁA�I�����_�͗B��̐��m���Ƃ��Ė���̒n�ʂ��m�������B�I�����_�́A�����͂��Ƃ�胈�[���b�p�e���̉� �w�A��w�A�m���A�Y���A����Ȃǂ��A����p�ɕ����Ԑ�^�̐l�H���g�o���h��ʂ��ē��{�ɏЉ��B����ƈ������ɁA�I�����_�͓��{�̕i����m���𐼗m�̐��E�ɗA�o���A�x��z�����B�����ɂƂ��ďo���́A�g�V�������E�ւ̑��h�ȏ�̑�ȈӖ��������Ă����B
����ȍ~�̓����W�͑傫�� �܂̎���ɕ����邱�Ƃ��ł���B���C���h��Ђ����˂̏��قŊ���1609�N����1641�N�B�o�������1641�N���� 1853�N�B�����ېV�O�������E���O��1853�N����1940�N�B����E��풆��1940�N����1945�N�B�����Đ�ォ�猻�݂Ɏ���܂̎���ł���B
��3. ���˃I�����_���َ��� (1609-1641)
����ƍN�����㏫�R�Ƃ��A���얋�{�����������̂�1603�N�B���ɉƍN�́A�f�Ղ������������I�����_�ɗ^���Ă����B����� ���[�t�f���Y�����琶�� �c������g���ɑ�����A�ނ炪���{�̃W�����N�D�Ńp�^�j(���^�C)�ɓ�������1605�N�A�悤�₭�I�����_���̎�ɓn�����B�����������̂́A���[�t�f���̐����҃N�A�[�P���i�[�N�f���ł���A�I�����_���C���h��Ђ̊͒��}�e���[�t�������B�I�����_���C���h���(VOC)�́A���̐��N�O��1602�N�� �ݗ�����Ă���B����܂ŃA�W�A�e�n�ɎU����Ă������K�͂ȃI�����_�̖f�Չ�Ђ��A��̋���ȑg�D�ɂ܂Ƃ߂��̂����C���h��Ђ��B�����̑D����ĂɏW�ߏ��D�c��g�݁A���E�̖f�Ղ����ɏ������邱�Ƃ�ڎw���Ă����B�܂��A���E�ōŏ��̊�����ЂƂ��Ă��m���Ă���B�������A���C���h��Ђ͒P�Ȃ�f�Չ�Ђł͂Ȃ��A�I�����_���{�͊O�����{�ƒʏ��W�����Ԍ������^���Ă����B���ڂɔ��s���ꂽ����ł́A���{�̓I�����_�����{�̂��ׂĂ̍`�ɓ��`�ł��鋖��^���Ă���A�f�Ղ��������シ��ӂ��ǂݎ���B���̎���͌��݁A�I�����_�̃n�[�O�������������قɕۊǂ���Ă���B
���ۂɃI�����_�D�����{�̍`�ɓ��`���A���R�̈ӂɓY�����Ƃ��ł����̂�1609�N�B���̔N�A�ŏ��̓��C���h��Ђ̌����D�c2�ǂ����˂ɓ��������B�����ăI�����W���}�E���b�c���q����̍������n����A���{�ƃI�����_�Ƃ̖f�Ղ����߂Đ����ɔF�߂�ꂽ�B�W���b�N�E�X�y�b�N�X�́A���˃I�����_���ق̏���ْ��ɔC������Ă���B��B�̖k���̒[�Ɉʒu���镽�˂́A�������p�Ƃ̖f�ՂɗL���ȗ��n�ł���B���A�c�O�Ȃ��瓖�̃I�����_�l�́A���˂ɏ��ق��u���ꂽ���Ƃ�����قNJ��}���Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A�T���ȏ��l�̂قƂ�ǂ́A���˂ł͂Ȃ�������ӂɏZ��ł�������ł���B
�I�����_�l�͕Y�����Ĉȗ�1641�N�܂ł́A���R�ɊO���o�������Ƃ��ł��A���{�l�Ƃ̐ڐG�ɂ��Ă����琧�����Ă��Ȃ������B�I�����_�l�͕��˂ɒ����������݂��A��˂̌@����s���Ă����B���{�l�̐E�l���ق����ꂽ���ɂ́A�ނ�̋Z�p�̍����Ɋ��Q�����Ƃ����B�������A���{�ɂ�����ő�̖ړI�ł���͂��̖f�Ղ͂Ƃ����ƁA���܂菇���ł͂Ȃ������B�A�W�A�ɂ��鑼�̓��C���h��Ђ���̑D���A�v��ʂ���{�ɓ������Ă��Ȃ��������ƁA�����ē��C���h��Ђ͒����ɏ��ق������Ă��Ȃ��������߁A���{�ōł����v�����������������\���ɋ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃ����̗��R�ł���B���̖����������邽�߁A�I�����_�l�͐ωׂڂ����|���g�K���D���P���Ƃ�����i�ɏo���B���R�|���g�K���l����ɔ������A�I�����_�l�̊C���s�ׂɑ���R�c�{�ɐ\�����ꂽ�B���̌��ʁA���{�͓��{�̊C���ł̐ωח��D���֎~�����B
���D�f�Ղ�������ɂȂ����ŁA���{�́g��ؐl�h����сg�g�ѐl�h��O���l�Ƃ̐ڐG�ɑ��A�ɂ킩�ɋK�������������B1614�N�A ���{�̓L���V�^���֗� �z���A���{�ŕz������������鋳�t��ꕔ�̗L�͂ȃL���V�^�����}�J�I�ɒǕ������B�֗߂͌��������s����A�����̃L���V�^�����}���̎��𐋂����B�܂��A �n�������ɓ������҂������B����1621�N�ɂ́A���{�l�����Ȃ��O���D�ɏ�荞�ނ��Ƃ��֎~����A�₪�ĊC�O�ɓn�q���邱�Ƃ��S�ʓI�ɋ֎~���ꂽ�B 1639�N�ɂ́A�O���l�ɓ��{�l���Ɏ��������������A���{����Ǖ����ꂽ�B���̒��ɂ͕��˂̃I�����_���ْ��t�@���E�i�C�G�����[�f�̖��������B�ޏ��̓o�^�r�A(���݂̃W���J���^)�ɗ�����Ă���B��x���{����������������́A���{�̉Ƒ��ƘA������邱�Ƃ�����������Ȃ������B�e�q���J�������A ���ȍق��ł���B���̂悤�ɒǕ����ꂽ�������������A�̋��������̂��܂茦�̒����n�ɂ������߂��g�W���K�^�����h�ƌĂ��莆���A���ˋ��y�ό��قɓW������Ă���B�������Ƃ����������������莆���A�W���K�^�����̈��ł���B1657�N�ɂȂ�Ɩ��{�͋K�����ɂ߁A�Ƒ��̋ߋ��������L�����g���M�h�𑗂邱�Ƃ��������B�R���l���A�E�t�@���E�i�C�G�����[�f���A���˂ɏZ�މƑ��Ɍ����ĉ��M�𑗂��Ă���B����������ˋ��y�ό��قŏ�������Ă���B
�|���g�K���l����{�l����u�����邽�߂ɖ��{���o�������_�́A�l�H���̌��݂������B���ꂪ�o���̎n�܂�ł���B1636�N�A�|���g�K���l�͏o���ɏZ�����߂�ꂽ�B�ނ�̏o����炵�́A�����̗��ɂ����āA�L���V�^�������R�̗e�^�ō��O�Ǖ��𖽂�����1639�N�܂ő������ƂɂȂ�B���̐킢�ŃI�����_�l�͖��{���ɂ��Đ�������A���ʂ͎U�X�ł������B���A�I�����_�l�͂��̒Ɏ�ʂɂ͂��Ȃ������B�|���g�K���l��Ǖ����Ă����܂Œʂ���{�ɗA���i���� ���ł��邩��A�����͈�I�����_�l�ɔC���Ă���ƁA���{��S�苭�����������B
�|���g�K���ɉJ���~��A�I�����_�ɂ����J���~��B����́A����I�����_�l�͒��̖����ł���B�|���g�K���l���Ǖ�����A�o���͎�l���������B�I�����_�l���l�̖ڂ̓͂��Ƃ���ɒu���Ă����������{�́A����Ŋi�D�̈͂��ꏊ���B1640�N�A���{�̓I�����_�l���o���Ɋu�����邽�߂̂����Ƃ��炵�����R���������B�����A���˂̃I�����_���قɂ́A�Ђ��珤�i����邽�ߐΑ���̑q�ɂ�2���������B���ْ��̃t�����V�X�E�J�����̓��[���b�p�̏K���ɕ킢�A�q�ɂ̔j���ɁgAnno Christi 1640�h�A�܂�L���X�g���a����1640�N�ƋL�����B���̈ꌏ���Ђ��ƂȂ�A�I�����_�l�͂��悢��o���Ɉړ]�������邱�ƂɂȂ����B���{�̓I�����_���ق̎��𖽂��A�I�����_�l��1641�N�A���˂���ɂ�����`�ɕ����ԏo���ɋ����ڂ����B�ȗ��A���{�Ƃ̐ڐG�������ꂽ���m���͗B��A�I�����_�̂� �ƂȂ����B
��4. �o������(1641-1853)
�o���ւ̃I�����_���وړ]�́A�����̓I�����_���Ɍ�������������Ǝv���Ă������A�K���ɂ����ʂ͂��̋t�Əo���B�o���̖ʐς͖� 1��5�畽�����[�g ���B�A���X�e���_���ɂ���_���L��Ƃقړ����L���ł���B�I�����_�l�͓��{�ɂƂ��Đ��E�ւ̑��Ƃ��Ă̖�ڂ�S���悤�ɂȂ����B���m�̉Ȋw�⏔�����I���� �_�l�̎��ʂ��ē��{�ɏЉ��A�g���w�h�Ƃ��ĉԊJ�����B�t�B���b�v�E�t�����c�E�t�H���E�V�[�{���g�͊ԈႢ�Ȃ��A���w�̔��W�Ɋ�^�����ł��L���Ȑl �� ���낤�B�V�[�{���g�͓��{�l�̊w�҂ɁA���m�̈�w���w�A���̑������I�ɉ��l�̍����m�������������B�܂��A��������̃I�����_�ꂪ���{��Ɏؗp�����悤�ɂȂ����B���̒��ł��g�r�[���h�́A���{�l�̐����ɍł��n������ł���I�����_��ƌ����邾�낤�B
���{�͓��{�l�ƊO���l�Ƃ̐ڐG�ɑ��A����������ɋ��������B�I�����_�l���܂��������K���ɔ���ꐶ�����Ă����B�o�����疳���ŊO�o���邱�Ƃ͋����ꂸ�A�������o���ɗ������邱�Ƃ��ւ���ꂽ�B�������~�R�̗V�������́A�o���ň����߂������Ƃ�������Ă���B��O�́A�g�]�ˎQ�{�h�����ŁA���̎����� �̓I�����_�l���o���̊O�ɏo�邱�Ƃ������ɔF�߂�ꂽ�B�ނ�͈�N���ɂ����ė]���Ă����悤���B�������I�����_�D�����`����8������10���̊Ԃ́A�o���� �Z�l���Z�������X�𑗂����B�f�ՑD����ωׂ����낵�A�ׂ�U�蕪���āA���l�ɔ���n���B�����đD�͍Ăѓ��{�̕i���ڂ��A���C���h��Ђ̍����̂��Ƃ� �����čs���B�̋�����̕ւ肪�͂��̂����̎����������B
�I�����_���ق��o���Ɉړ]���Ĉȗ��A���{���ۂ����K�����Ɏ�ƂȂ�A���� ����قǂ̗��v���グ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B�o���ł́A���i�̒l�i�͎��O�Ɍ��߂��A����c�������i�͂��ׂĎ����A��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�K���͊m���Ɍ������������A����Ȓ��ł����C���h��Ђ͂�����x�̎��v���グ�Ă���A �����ƈ������ɋ��A��A���A���]�Ȃǂ���{����A�o���Ă����B�X�ɁA����ⓩ����A�����A���{����o�^�r�A��[���b�p�ɑ���o���Ă����B
�����Ȑ������������Ă����o���ł��A���C����]���铌�C���h��Ђ̏��و����₦�Ȃ������炵���B���̍ő�̗��R�́A���{�������Ȗf�Ղ̊O�ɁA�l�I�Ȗf�Ղ����z�܂ŔF�߂Ă������Ƃɂ���B���̃T�C�h�r�W�l�X�̂������ŁA���و��͂��Ȃ�̕���������ɂ��邱�Ƃ��ł��A���̊z�͒ʏ�̔N���20�{�ɂ��B���邱�Ƃ��������悤���B�����̏��ْ��̔N���1200�M���_�[���������A3���M���_�[���̕����������ɂ��Ă����Ƃ����L�^���c���Ă���B
18���I�ɓ���ƁA���{�ƃI�����_�̂��ꂼ��̐����I�ȗ��R����A�o���ł̖f�Ղ��s�U�Ɋׂ����B���{�́A�f�ՑD�̐ǐ������������[ �g�Ȃǂɂ��āA�V���ȋK�������Ő݂��A�����̓I�����_���̗��v�����������B�܂��������A���[���b�p�ł̓t�����X�v�����u�����A�ꎞ�͕����m�炸�������I�����_�����C�� �������قǂɂȂ��Ă����B1795�N����1813�N�̊ԁA�o���ɓ��`�ł����I�����_�D�͋͂����ǁB���̌��ʁA�o���ɋ��Z���Ă������C���h��Ђ̏��و������́A��������f����Ă��܂����B���ْ��w���h���b�N�E�h�D�[�t�͂�ނ������A�H����ߕ��Ȃǂ���{�l�̍D�ӂɗ����Ă����B�������A�h�D�[�t�͂����Ŏ��Ԃʂɉ߂����Ă��Ȃ��B�ނ͗��a�����̕ҏW���肪���A���{�̖�l�Ƃ��ǍD�ȊW��ۂ��Ă����B�Ȃɂ����h�D�[�t�͏o���ɃI�����_�̊����f���������B�o���̎O�F���͂��̍��A�n����ł͂��߂��B��̃I�����_�����������B |
��5. ���w �| �I�����_�Ɋw�Ԃ���
16���I�̖������ʌ�̓|���g�K����ł���B�I�����_�l�Ɠ��{�l���ŏ��ɉ�b�������Ƃ����A�|���g�K����̒ʖ�݂��Ă����B�|�� �g�K���l�����{����Ǖ������ƁA����ɃI�����_�ꂪ���{�ɂ�������O����̒n�ʂ��l�����A�I�����_����g���邱�Ƃ��ʖ��|��҂ɂƂ��ĕs���̏����ƂȂ����B�g�����ɒʎ��h�ƌĂꂽ�ʖ�́A���P���Ɋ�Â��Ă���A�������ɂ͂��̐�150�l�ɂ̂ڂ����B�ނ�͒ʏ��A�O���A�����ĕ����𗬂̎��������Ƃ߂��B�܂��A�����ɒʎ��͐��m�Ȋw���L�߂��ł��d�v�Ȗ������ʂ����Ă����B�ʎ��̔\�͂����シ��ɂ�āA���m�̍��X�����ɍ��������̉Ȋw�I�m����L���Ă��邱�Ƃ��A���{�̈א��҂������F�����n�߂��B
1720�N�A���㏫�R�g�@�̓L���X�g���W�ȊO�̗m���̗A�������ɘa����B���ꂩ��Ԃ��Ȃ��w �p�m�������{�ɗA�������悤�ɂȂ� ���B�I�����_���ʂ� �Ċw�Ԋw��́g���w�h�Ƒ��̂���A���c�����ȂǍ����Ȋw�҂���z�������ʂ������߂��B������1771�N����1774�N�ɂ����āA�h�C�c�l�N�����X�́w��U �}��(Ontleedkundige Tafelen)�x��|�A�w��̐V���x�Ƃ��Đ��ɏo�邱�ƂƂȂ����B�w��̐V���x�̖|��Œ��ʂ����l�X�ȋ�J���A���c�����́w���w���n�x�ɂ܂Ƃ߂Ă� ��B����2�҂̏����́A���{�̗��w�m�ɂ�����K�{�̏��ƂȂ����B�V�[�{���g���n�߂�����̖�m�A�]�˂̎ŗ����A�����ď����^�����n���������̓K�m�Ȃ� ���A���w�m�Ƃ��Ė���y����悤�ɂȂ�B�����ł͈�w�͂��Ƃ��A�V���w�␔�w�A�A���w�A�����w�A���w�A�n���A�p���p�ȂǗl�X�Ȋw�₪���L���w�ꂽ�B
���{�ɐ��m�Ȋw�̒m����`���邱�Ƃ��A�}�炸�����C���h��Џ��و��̏d�v�Ȗ�ڂƂȂ����B�����ŃI�����_���́A�w�p���̏��و���� �{�ɑ��荞�B�J�X �p���E�X�n���x���Q���̈�w�́A�J�X�p�����Ƃ��ē��{�l�ɓ��P���ꂽ�B�w���h���b�N�E�h�D�[�t�́A�t�����\���E�n���}�̗������T�Ɋ�Â��āA���a���T�w�n���}�a���x���ďC�����B����ɂ͎��������Ȃޒ��A���{�����B�����B�R�b�N�E�u�����z�t�́A���{�̍H�|�i�����i�Ȃǂ����W�����B�������A�ł��L���ȁg�I�����_�h�̊w�҂ƌ����A�t�B���b�v�E�t�����c�E�t�H���E�V�[�{���g�������đ��ɂȂ��B
1823�N�ɗ��������t�H���E�V�[�{���g�́A���{�̍��Ƃ▯���A�����ɂ��Ăł�����葽���̏������W����Ƃ����g����ттĂ����B�A���w�A��w�A��w �ɔ����������V�[�{���g�́A���{�ɂ����čł����h���W�߂����C���h��Ђ̏��و��ƂȂ����B�ނ͒���ߍx�̓y�n��������A��m��n�������B�����Ŋ��҂����Â��A��w����w�������A�A�������\�����B�����̊w�҂⊳�ҁA���m�ƐڐG�ł��闧��ɂ��������߁A���{�̐����ɂ܂��l�X�ȕi�������W���邱�Ƃ��\�ł������B�V�[�{���g�͖Ɋւ���m������������ɁA���{�l���w�҂��炠�镨������Ă���B����͈��̖䂪���ߕt����ꂽ�����������B�܂��閧���ɁA���O�����o���֎~�̓��{�n�}�����肵�Ă����B�����͓����A�O���l�����L���邱�Ƃ��ւ����Ă������̂���ł���B���ꂪ���o���A�V�[�{���g�� 1829�N�ɃX�p�C�e�^�ō��O�Ǖ��y�эē����֎~�̏������邱�ƂɂȂ�B�g�V�[�{���g�����h�Ƃ��Ēm���邱�̎����ɂ���āA�ނ͍ȂƖ������˂��c���ē��{���������B��ɂ����˂͓��{�ŏ��̏���Ƃ��āA�f���炵�����т��c�����B�V�[�{���g�����{�Ŏ��W�����c��ȃR���N�V�����́A���݃I�����_�̃��C�f�����������w�����قɎ�������Ă���B
��6. �]�ˎQ�{ �|�I�����_�l�A���{�𗷂���
���N�s��ꂽ�]�ˎQ�{�́A�I�����_�l�Ɠ��{�l�̖�l�������ɖʉ��@���^�����B���{�e�n�̑喼�Ɠ��l�A�o���̃I�����_���ْ����]�˂ɏ��A���R�ɉy������悤�������Ă����B�����āA�������ƌĂ�鏔�O���̐���������̒�o���`���Â����Ă����B
�]�ˎQ�{�́A���ْ���擪�ɁA���و�Ə��و������A����ɉ����Ĉ����ɒʎ��ƒ���̖�l�����s���A��c�͂��悻150�l����200�l�ō\�����ꂽ�B�S�s�����I����ɂ͖�3������v�����B�g�g�ѐl�h�̍s��ɂ͍s����X�ōD��̊፷�������т����A�]�ˎQ�{�͒ʎZ���悻170����s��ꂽ�B���肩�牺�ւ܂ł𗤘H�ŁA�����ĕ��ɂ������͑��̍`�܂őD�œn��A���C���𓌂ɐi�ݍ]�˂Ɏ������B�É����|��s�ɂ́A�]�ˎQ�{�̋A�r�ɋq�������I�����_���ْ��w���~�B�̕悪���ł��c���Ă���B
�]�˂ŏ��R�ɉy������ɂ́A���X�̍����ȑ������K�v�Ƃ��ꂽ�B���ዾ�A���m��w�̓�����A��C�A�n���V�A����ɂ̓V�}�E�}��N�_�A�T���ȂǓ썑�̒����������Ȃǂ������Ă���B���m�Ȋw�̏������A���Ɋ�ꂽ�B1638�N�ɏ��R�ɑ���ꂽ�����̃V�����f���A�́A�O����̉����Ɉ�����B���̑哕�U�͌��݂��A����ƍN����������Ƌ{�Ɉ��u����Ă���B���̑哕�U�̌��ɁA���R�̓I�����_�l�ɍ����Ȍ��̒��������������B
��7. �g�����Ɂh���p
�I�����_�l�̏o���ł̐�����]�ˎQ�{�̗l�q�́A���{�l�G�t��傢�Ɏh�������B�o���̕�炵�Ԃ��`��������G�́A�����K��闷�s�҂̍œK�ȓy�Y���ƂȂ� ���B�܂��I�����_�l�̎p������̊G���ɂ��Ȃ����B�I�����_����^��Ă����G���G�{�Ȃǂ��A�G�t�ɑn��̃A�C�f�A��^���Ă����B�i�n�]���͈�x���������Ƃ̂Ȃ��I�����_�̕��i��`���Ă��邪�A���̊G�ɂ̓I�����_�ɖ����͂��̎R���`����Ă���B
�쌴�c��́A�t�H���E�V�[�{���g�̌l�I�ȃA�V�X�^���g�Ƃ� �āA19���I�����̏o���̗l�q���G�M�ō����ɋL�^���Ă���B����璷��G��I�����_�l�̊G�����������������A���̑��I�����_�ɂ܂��H�|�i�́A���茧�����p�����فA����s�������فA�_�ˎs�������قŌ��邱�Ƃ��ł���B
��8. �Ԃ̎���̏I��� �| �]�ˎ��㖖��
19���I�͐��E�̐�������傫���ω���������ł���B�I�����_�͊C�̔e���������A����ɃA�����J�ƃC�M���X�����͂��g�債�Ă����B�A�w���푈 (1839-1842)�ŃC�M���X�͒����ɑ��A���ۖf�Ս`�Ƃ���5�̍`���J�`���A���`����������悤�v�������B���{��Ǖ�����I�����_�Ō��������𑗂��Ă����t�H���E�V�[�{���g�́A�I�����_�����E�B����2���ɂ����i�������B���R�ɒ����ɃA�w���푈�̌��ʂ�m�点�A������P�p����悤�����ׂ��ł���A�ƁB�E�B����2�����V�[�{���g�̏����ɏ]��������������1844�N�A�����ȋV�����o�Ē����s��ʂ����{�Ɏ�ɓn���ꂽ�B���{�̓I�����_�����̔z���ɂ͊��ӂ������̂́A�����ɏ]�����Ƃ͋��ۂ����B�������I�����_�̓h���P���E�N���`�E�X���o���̏��ْ��Ƃ��đ��荞�݁A�ēx���R�ɊJ�������������B1852�N�A�N���`�E�X�́A�A�����J�����͂œ��{�ɊJ���𔗂낤�Ƃ��Ă���A�Ə��R�ɒ����������B���������{�͍Ō�܂Œ����Ɏ���݂����ƂȂ��A1853�N�̃y���[�̍��D���q���}���Ă��܂����B
��9. ���{�̋ߑ㉻
1853 �N�̃y���[�̍��D���q�����ɁA���{�͍������̂āA�}���ȋߑ㉻�Ɍ��������ƂƂȂ����B���ꂩ��50�N�̊ԂɁA���{�͕����Љ��ߑ�I�Ȑ��m�f���N���V�[�̎Љ�ւƋ}�ς����B�I�����_�l�͂���܂ł̓����I�Ȗ����͎��������A�����̐e���ȊW�ɕς��͂Ȃ������B�J�������A���{�Ə��O���Ƃ̌����ȐՂ͂��ׂăI�����_��ōs���Ă����B�܂���{�l�ƃA�����J�l�Ƃ̍ŏ��̉�b�ɂ��A�I�����_�ꂪ��������ʂ����Ă����킯�ł���B�������A���{�l�͐��E�̗̗͊W���ω����Ă��邱�Ƃ��@�m�����B�����Đ��m�����ɒǂ������ƁA���{�̓A�����J�ƃ��[���b�p�Ɏg�ߒc��h�������B����Ɠ����ɁA���{�͋ߑ㉻�̑b��z�����߁A���m�̐��Ƃ�w�҂���{�ɏ������B���D�A�C�R�A��w�A��w�A�y�̕���ŁA�I�����_�l�͓��{�̋ߑ㉻���x�����邱�ƂɂȂ����B
�y���[���q�̒���A���R�̓h���P���E�N���`�E�X�ɃI�����_������C�͂�h������悤�v�������B������ăI�����_���{�́A���{�ɌR�̓X���r���������サ���B���̑D�͌�Ɂg�ό��ہh�Ɖ��������B�q�C�p��C�p�A�X�ɂ͑��D�p�̋����ڎw���āA����ɊC�R�`�K�����ݗ����ꂽ�B�X���r�����̊͒��������t�@�r�E�X�Ə�g�����A�ŏ��̋��t�Ƃ��ċ��d�ɗ������B���̏��C�M�����k�Ƃ��Ė���A�˂Ă����B�ό��ۂ̐��ʂ����͂��Ă���A���{��2�ǖڂ̏��C�͂̔��������肷��B���̑D�̓��p�����Ƃ������œ��{�ɓ����������A�g���Պہh�Ɖ������ꂽ�B���̑D���A���C�M���A�����J�ɉ^�D�ł���.
���p�����ɏ���āA�G���W�j�A�̃n���f�X�ƁA�C�R��̃|���y�E�t�@���E���[���f���t�H�[���g�����������B�n���f�X�͓��{�ōŏ��̑D���C���H��Ƒ��D����ݗ������B���ꂪ��ɎO�H�d�H���葢�D���ւƔ��W����B
�|���y�E�t�@���E���[���f���t�H�[���g�́A�t�H���E�V�[�{���g�̑��Ղɑ����A����ɍŏ��̐��m���a�@�����݂����B����Ƀ|���y�̋Ɛт�A.F.�{�[�h�����AC.G.�}���X�t�F���g�AK.W.�n���^�}�AA.C.J.�w�[���c�Ɏp����A �ߑ�I�Ȉ�w����̌n�̔��B�ɑ傫����^�����B����w��w���̊�b�͔ނ�I�����_�l���z�������̂ł���B�n���^�}�͑��ɉ��w���w�Z�̎ɖ���(�����݂��傭)��n�����A�����Ŗ�w�Ɖ��w���������B�܂��n���^�}�Ɣނ̐��k�́A���{�ōŏ��̋ߑ�d�݂Ɏg�p���ꂽ�������J�����Ă���B
��10. �^��������{�����
���{���{�����ق����I�����_�̐��H�Z�p�҂̎c�����Ɛт́A���ł��͂�����Ƃ����p���c���Ă���B�R�����ȓ��{�̍��y�ŌJ��Ԃ����^����H���~�߂邽�߁A �ނ�I�����_�l�͂��̒���ɗ������������B�܂��A�ߑ�I�ȍ`�p�̌��݂ɂ��͂����邽�߁AC.J. �t�@���E�h�[�������ŏ��̃I�����_�l�Z�p�҂Ƃ��ē��{�ɏ����ꂽ�B�ނ͕������Ɉ��ϑ`�����J�킵���B���c��ΔȂɂ́A�t�@���E�h�[�����̓��������Ă��� ���邪�A���̓����͑���E���̂��߂ɋ��o���ꂻ���ɂȂ����Ƃ����n���Z���������A���݂Ɏ����Ă���B
���{���{�̗v�����āA�t�@���E�h�[�����͂���ɐ����̋Z�t����{�ɌĂъ��B�������ė��������̂��A���n�l�X�E�f�E���C�P�ł���B�f�E���C�P�͊w�ʂ����Ȃ��������A���n�Ő\�����̂Ȃ��Z�p���Ă����B�܂�A.G.�G�b�V���[�����Ԃ̈�l�������B�ނ͐��E�I�ɗL���ȉ�� M.C.�G�b�V���[�̕��ł���A��Ƃ̃G�b�V���[�͕������{���玝���A���������G�ɑ���ȉe�������ƌ����Ă���B
���n�l�X�E�f�E���C�P�̏��ق́A���{�ɂƂ��čō��̑I���ƂȂ����B�ނ͓��{��30�N�ȏ�؍݂��A�y�؋ǒ��A�܂�����Ȏ����������̖�l�ɂ܂ŏ��i�����B �����炭�ނ͓��{�ɂ����āA���������Ƃ��ĔF�߂�ꂽ�B��̊O���l�ł��낤�B�f�E���C�P�̑�z�����Z�p�́A���̗���A�����Ėؑ]�O��̎����H���ő����ɔ������ꂽ�B�ؑ]�O��̉͌��t�߂ł́A����̈قȂ�3�{�̐삪�������Ă���A�^�����p�ɂɋN�����Ă����B���n�l�X�E�f�E���C�P�́A�h�g��␅���A����ɓy��̐Z�H��h�����ߖ�A����Ƃ������H�@��p�����B�I�����_�͎R���Ȃ����߁A�f�E���C�P�͍��h�_�������݂����o���ȂǑS���Ȃ������ɂ��S�炸�A���̂悤�� �Z�p���g�����Ȃ����Ƃ��ł����B�X�ɔނ͑��`�A����`�A���l�`�ȂǓ��{�̋ߑ�`�p�̐v�ɂ��g������B���̎����A���킹��12�l�̃I�����_�l���H�Z�t���������A���{�l�̐������^�������邽�߂ɗ͂�s�������B
�I�����_����̋Z�p�ҏ��ق̂ق��ɂ��A�������{�͓��{�̊w�҂��I�����_�֔h�����Ă����B������Óc�^���̓��C�f����w�Ɋw�сA����@�g���I�����_�ɗV�w�� ���B
���{�̊J�����_�@�ɁA���{�ƃI�����_�͐����ȊO���W�����B1859�N�A���l�ɍŏ��̃I�����_�̎��ق��u����A��ɓ����ɑ�g�ق��J���ꂽ�B�܂�1868�N�ɂ͐_�˂ɃI�����_�̎��ق��ݒu���ꂽ�B�������Ȃ���A�C���h�l�V�A�ɂ���������̕��͏Փ˂́A���N�ɂ킽�闼���̗F�D�̗��j���Ȃ��Ă��Ă��A �c�O�Ȃ������ł��Ȃ������B
��11. ���j�̈�(1942-1945)
����E���́A�����ɂ킽������W�ɂ����āA��u�̒f��������炵���ŏ��ŗB��̏o�����ł���B�V�R�����̊m�ۂƑ哌�����h�� �̍\�z���������邽�߁A1942�N1��10���A���{�R�̓C���h�l�V�A�ɐN�������B�����I�����_�̐A���n�������C���h�l�V�A�́A�Ζ���V�R�S���A�Ӟ��A�X�p�C�X�ȂǓV�R������ �����ւ�L�x�������B2�����Ԃɂ킽��퓬�̖��A�I�����_���R�͍~�������B������4���l���̃I�����_�����ߗ��Ƃ��Ď��e���ɘA�s���ꂽ�B����Ɉ��������A �C���h�l�V�A�ɏZ��ł����I�����_�l�̈�ʎs���������J���L�����v�Ɉڑ�����A�����͒����k��B�̒Y�B�ɘA����čs�����B
���{�R�̃C���h�l�V�A��̂��I��Ƌ��ɏI���A�ŏI�I�ɃC���h�l�V�A�͓Ɨ����ʂ������B����A�I�����_�͐A���n��`�̗��痣�E ���A���{��1951�N �܂ŕČR�ɐ�̂��ꂽ�B���̊ԁA�ߋ��ɔ|�����͂��̓����W�͕�����A���ɂ�鏝�Ղ͍��ł��ԊW�ɉe�𗎂Ƃ��Ă���B
��12. ���{�ƃI�����_�̌���(1945-)
1952�N�A�I�����_�͓��{�Ƃ̍����𐳎��ɐ��퉻�����B�]�ˎ��ォ�疾���ɂ����ăI�����_���ʂ��������ʂȖ����͂��͂�ߋ��̂��� �ƂȂ�A�����̓��{�l�ɂƂ��ăI�����_�̓��[���b�p�����̂����̈�ɂȂ��Ă��܂����B
1950 �N��㔼�A���{�ƃI�����_�̊W�́A�o�ρA�����A�Ȋw�Z�p�̕���ŁA�V�����X�^�[�g���}�����BKLM�I�����_�q���{�ɏA�q���A�t�B���b�v�X�� �����d��Y�Ƃ̐����̊�b�����x�������B�I�����_�̐�Ԃ��A�������悤�ɂȂ�A���{�l�̕�炵�ɉԂ�Y�����B1960�N��ɓ���ƁA�A���X�e���_�� �̃R���Z���g�w�{�E�E�I�[�P�X�g�������{�l�̉��y����т�^���A�t�@���E�S�b�z����u�����g�̖��悪��������̊ϏO�̐S��D�����B���w�̑����́A���ꂼ��̑�w�Ŗ��X�ƈ��p����Ă���B
�������A�I�����_���Ăѓ��{�l�̈ӎ��ɓo��悤�ɂȂ������������́A�����I�����s�b�N���낤�B�_���́A 1964�N�ɊJ�Â��ꂽ�����I�����s�b�N�ŁA���߂� ������ڂƂ��ĔF�߂�ꂽ�B�����_���͓��{�l�I�肪�Ɛ肷��ɈႢ�Ȃ��A�Ɠ��{���̒N�������҂��Ă����B�������A�I�����_�l�I��A���g���E�w�[�V���O�� ����Ă��̊��҂͑ł��ӂ��ꂽ�B�_�������ʋ��Ńw�[�V���O���_�i�I�肩������_����������������A�ǂ�قǑ����̓��{�l���܂𗬂������낤���B�A���g���E �w�[�V���O�͍��ł��̑�ȃX�|�[�c�}���A�����Ĉꕔ�̐���ɂ͍ł��L���ȃI�����_�l�Ƃ��Ēm���Ă���B
1983�N�A���{�ƃI�� ���_�̊W�́A���茧���ޒ��̃I�����_���J�����@�ɁA�傫�Ȕ��̎����}�����B�I�����_���Ԃ��ŏ��Ɍ��Ă�� ���B����ɑ����ē��C���h��Ђ̔��D��I�����_���̌������p������킵�A�I�����_���i�Ƌ��ɂ�������̓��{�l�ό��q���Ăъ��B�S�[�_�`�[�Y��،C�Ȃǂ��l�C���W�߂��B�I�� ���_�̊G�{��ƃf�B�b�N�E�u���[�i���n�삵���gNijntje�h(�i�C���`�F)�́A���{�ł͂�����������~�b�t�B�[�����Ƃ��Đe���܂�A������킸�����̓��{�l�̐S��͂�ł���B�I�����_���������������߂����߁A�g���v�悪�ł��o���ꂽ�B���ꂪ1993�N�A�����ێs�ɃI�[�v�������n�E�X�e���{�X�ł���B
�g�n�E�X�e���{�X�h�́A�I�����_�����̋{�a�ɂ��Ȃ�ŕt����ꂽ���O�ł���B����n�E�X�e���{�X�́A�K�͂����ē��e�Ƃ��ŏ��ɑ���� ���I�����_�����͂邩�ɗ����X�P�[�����ւ�B�n�E�X�e���{�X�̗��O�́A�P�Ȃ�e�[�}�p�[�N�ɗ��܂炸�A�l�X����炵�A�����A�]�ɂ��y���ނ��Ƃ̂ł���{���́g�R�~���j�e�B�[�h ��n�邱�Ƃɂ���B�I�����_�̗L���Ȍ��z����������ŗ������сA�n�E�X�e���{�X�{�a�܂ł����Č�����Ă���B�{�a�̂Ȃ��ɂ͔��p�ق�����B�n�E�X�e���{�X���̃��X�g�����ł́A�I�����_���͂��߃��[���b�p�e�n�̗����𖡂키���Ƃ��ł���B�I�����_�����́A����n�E�X�e���{�X�ɖ{���̋{�a �� �����G��������Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����B�����ŃI�����_�̗L���Ȏ���ƃ��u�E�X�z���e�������A�lj�̊Ԃ��Ă��܂����̂��B�ނ̕lj�gApres nous le Deluge�h(�t�����X��Łg���Ƃ͖�ƂȂ�R�ƂȂ�h�Ƃ����Ӗ�)�͓��O�Ɍւ�ׂ��f���炵����i�Ƃ��āA���K�҂𖣗����Ă���B
�������j�ɂ�������Ȃ������I�����_�̑��Ղ́A�ڂ����łȂ����ł������邱�Ƃ��ł���B
���ݓ��{��Ɏc���Ă���I�����_�ꂩ��̎ؗp ��́A��ɍ�������� ���̋N����k�邱�Ƃ��ł���B�����̓��{�l�͂����Ƃ͋C�t�����ɁA�I�����_��̌��t����X�g���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���̗ǂ��Ⴊ�A�r�[���A�R�[ �q�[�A�K���X�A�s�X�g���A�I���S�[���A���Ă�ȂǁA�I�����_��̉������̂܂ܐ^�������̂ł���B�܂��A�a�@��Ӓ��A�Y�_�ȂǃI�����_��̈Ӗ��������ɓ] ���������̂Ȃǂ�����B�����̌��t�́A�I�����_�̉e�������{�l�̓��퐶���ɂ����ɐF�Z���c���Ă��邩�������A�ق�̈��ɉ߂��Ȃ��B �@ |
[�ڍ��]
�@ �O�l���������{�l �O�l���������{�l |
|
�@ |
|
�����l���g (�֓�����) |
   �@
�@
|
(1841-1890)�@�������疾�����ɂ����Ă̈ɓ������c�̌|�ҁB���l���g�i�Ƃ��������j�̖��Œm����B
�����c��̐l�C�|��
1841�N�i�V��12�N�j�A�������m���S���[���i���݂̈��m����m�������C�j�ɑD��H�E�֓��s���q�ƍȂ���̓Ƃ��Đ��܂�A4�܂œ��C�ʼn߂����A���̌�A��Ƃ͉��c�ֈڂ�B7�̎��͒Ï����䏫�Ă̈������R����̗{�q�ƂȂ�Ղ�O�������K�����B14�ő��R�Ƃ��痣������|�҂ƂȂ肨�g�Ɩ�����������́A�u���Ԃɉ��c��̐l�C�|�҂ƂȂ�B
�����l���g
1857�N�i����4�N�j5���A���{�̏���A�����J���̎��^�E���[���g�E�n���X���ʐ̗̎��قŐ��͓I�ɓ��ĊO�����s���Ă���Œ��A����Ȃ��ٍ���炵���炩�̒���������ɉ点���Ă��܂��B�������n���X�̒ʖ�w�����[�E�q���[�X�P���̓n���X�̐��b��������{�l�Ō�w�̈�����n���̖�l�Ɉ˗�����B�������A�����̓��{�l�ɂ͊Ō�w�̊T�O���悭���炸�A���̈����˗����ƌ�����Ă��܂��B�����Ō��ɋ��������̂����g�������B
�����̑命���̓��{�l�͊O���l�ɕΌ��������A�O���l�ɐg��C���邱�Ƃ�p�Ƃ��镗�������������߁A�c����̍���҂��������g�͌Ŏ��������A���{��l�̎��X�Ȑ����ɐ܂�n���X�̂��Ƃ֕������ƂɂȂ����B�����A�l�X�͂��g�ɑ��ē���I���������A���g�̉H�U�肪�ǂ��Ȃ��Ă����ɂ�āA����Ɏ��i�ƕ��̖̂ڂ�������悤�ɂȂ�B�n���X�̗e�Ԃ�����3�������8���A���g�͉��ق���Ăь|�҂ƂȂ邪�A�l�X�̗₽�������͕ς��ʂ܂܂ł������B���̍�����ޏ��͎�F�ɒ^��悤�ɂȂ�B
���Ŋ�
1867�N�i�c��3�N�j�A�|�҂����߁A�c����̑�H�E�ߏ��Ɖ��l�œ�������B����3�N��ɉ��c�ɖ߂蔯���Ƃ��c�ݎn�߂邪�A���͂̕Ό�������X�̌o�c�͎v�킵���Ȃ������B�܂��܂����ɓM���悤�ɂȂ�A���̂��ߌ�����҂Ɠ������������A�|�ҋƂɖ߂�O�����o�čĂщ��c�ɖ߂����B���g������D��̌㉇�ŏ��������u�����O�i���傭�낤�j�v���J�����A���ɃA���R�[���g�p��Q�ƂȂ��Ă������g�͔N�����̓�����Y�킹�A�x�X�����Ė\���Ȃǂ�������2�N�Ŕp�Ƃ��邱�ƂɂȂ�B
���̌㐔�N�ԁA����𑱂�����A1890�N�i����23�N�j3��27���A�����I�����ɐg���������Ď��E�����B��48�Ζv�i���N50�j�B
���̌�A���삩������グ��ꂽ���g�̈�̂�l�X�́u����킵���v�ƕ̂݁A�֓��Ƃ̕�����������ۂ����ׁA�͐�~��3�����̂Ēu�����Ȃlj��c�̐l�Ԃ͎�������g�ɗ₽���A����Ɏv�������c���̏Z�E�������̈�p�ɑ��邪�A��ɂ��̏Z�E�����g������ɒ������Ƃ��Ď��͂��甗�Q���A���c�����鎖�ƂȂ�B
�����E�ג�c��i���Ⴍ�Ă�����Ɂj�B �@
���g�̑��݂́A1928�N�i���a3�N�j�ɏ\��J�`�O�Y�����\���������w���l���g�x�ōL���m���邱�ƂƂȂ�B
�������I�ȃt�B�N�V�����̉\��
�֓������̌o���ɂ��Ă͏�������A�|�҂ł͂Ȃ������ޕw�Ő��v�𗧂ĂĂ����Ƃ����������B�������������Ȃ���Ɍ�N�̏����A�Y�ȓ��ŕ`���ꂽ�t�B�N�V�����̕������j���̗l�Ɍ���Ă���\���������A��T�ɓ`���o���̐����f�肷�鎖�͍���ł���B�@ |
�����l���g 1
�u�{���ɃR�����܂�����������������̂ł����B���̂����ɂ����ʐɂ͗���ȂƁB�v�u�{���ł��B�ł��A���L�`����B�R���X���i�̎��j�͂��Ȃ����L���C�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��A���Ȃ��̃^�����v���Č��������Ƃł��B���{��ŁA�ǂ��\�����邩�A�����A���������Ƃ����R�g�o������܂��ˁB���L�`����ƃc���}�c�������ł���ƁA�~�X�^�[�E�n���X�͒m���Ă��܂����̂ł��B�Ƃɂ�������͂��̂܂܋A���Ă��������A���L�`����v
�u���Ƃ��ǂ̂悤�Ȃ��C���ł�����������ɂ���A�����͂��̂܂܋A��킯�ɂ͂܂���܂���B�ʐ֒ʂ��A�R�����܂ɂ��ڂɂ����邱�Ƃ����̂Ƃ߂Ȃ̂ł����́v
�u���܂����l�B�ł��R���X���̋C���͕ς�܂����v
�w����[�E�q���[�X�P���Ƃ��g�Ƃ̉����ⓚ�����c�s�x�O�`�葺�E�ʐO�̐Βi���ő�����ꂽ�̂́A�����l�N�i�P�W�T�V�j�T���Q�T�����̂��Ƃł���B�q���[�X�P���͕č��̏�����{���ݑ��̎��ɔC����ꂽ�^�E���Z���h�E�n���X�Ɏd���鏑�L���ʖ������B���g�����߂ċʐ̖��������A�n���X�ɂ��ڌ��������̂���\����A�킸���O�������o���Ă��Ȃ��̂Ɏ�����̉��ق������n���ꂽ�̂ł���B
����ɁA�O���̓�\�l���ɂ͋����̂ق��Ɏx�x���Ƃ��ē�\�ܗ��̑喇���s������x������Ă���B
�������n���X�̋��ɍ����o���ɂ��ĕ�s����l�̐X�R���g�Y�́A���y�̂ɉ����̂Ɏ��������o���A�m���ɂȂ��č����~���Ăق����Ɠ����������B�u����ɂȁv�ƁA�X�R�͂��g�̋����ǂ�����t���Ă����B
�u���O�����m���Ă��ꂽ�Ȃ�A�ߏ��ɂ͕c���ѓ��������A��쎖��H���̑g���ɂ����悤�Ƃ���s�������Ă�����v
�����ł���D��H�̒ߏ��́A���˂��ˑѓ����������g���ւ̓��ꂪ�����A���Ȃ̂悤�Ɂu���������Ă��v�ƌ����Ă͂��g�����点�Ă����B���̏�A�����ɂ͎x�x����\�ܗ��̂ق��Ɉ�N�̋����S��\���������Ƃ����B
������D�������̉��ꕨ�̐����U���������ĕ�e�̂��͂Ɛ��v�����ĂĂ��邨�g�ɂƂ��āA�ꐶ�U���邱�Ƃ̂Ȃ�����ł���B���g�̋C�����h�ꂽ�B���̖��ɓ��̒ߏ����K�˂ė����B
�u�g�����A���̒ʂ肨���炩������ށB�ȂɁA��N�ԂƂ����Ήi���悤�ł��l���悤�ŒZ�����Ȃ炠�B�ڂ��ނ��Ă��܂Ă�Ⴗ���ɏI�邳�B�����������Ă��O�ƈꏏ�ɂȂ�����҂��Ă��邺�v
�u�{���ɑ҂��Ă��Ă����ˁB���̂��炾������Ă��Ă������ˁv
�������ċʐ̖��������悤�ɂȂ�A�l���ڂ̏��Ȃ̂ł���B�n���X�Ɩ���߂��Ȃ��Ă��悢�ƕ����Ċ������͂��������A�������r���ɂ���邨�g�ł��������B
���̌�̂��g�ɑ��鐢�Ԃ̖ڂ́A�\�z�ȏ�ɗ₽���������B�D����������̎d�������g��Ƃɂ͉���Ă��Ȃ��Ȃ�A�Ԍ��̉Ƃł̉��ȂɎ���d�����߂�����ƌ������B
�����͂��قǐ����ɍ��邱�Ƃ��Ȃ��������A�₪�č��������B�Z���Ǝ����ɂ������͖�������A���\���̔����Z���ɂ͎����A�����͌ܗ��B�ꉞ����ł͂��邪�A���Ԃ��K�̐��i�̋��ŁA�����������h��Ɏg�������낤���A���͂��炽�����������ɈႢ�Ȃ��B�����ɂ͕�̂��͂Ǝo���@�ܘY�̘A���ŕ�s�����ɒQ�菑�������o�����B����������Ă���Ȃ��̂Ő����ɂ�����Ƃ����킯�ł���B�����A�O�\�����������ꂽ���A����͎�؋��ŁA��s���Ƃ������ꂽ�B���Ԃ̖ڂ͑��ς炸�₽���A�u�m���i�炵��߂�j�v�ƍ��ꂽ�\���̂��g�ɂ͐h�����Ƃł������B���̌�A���g�̐����͓]�X�Ƃ���B
�]���̔O�ɂ���ꂽ���g�͏��S����₻���Ɛ���̋��̒m���S���C�ɂ����ݓ��ꂽ���A
�w�炵��߂�x�w���l���g�x�ƁA�q�������ɂ܂ł͂₳�ꂽ�B���l�̒ߏ��Ɖ��l�œ������������A����̋��ł̎̕��ɂ͑ς����Ȃ����̂��������ł��낤�B�c�Ȃ������߂������C�̔����������A�S���Ԃ߂��i�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ������B
���g�͎O���Ō|�҂ɏo�A����ɂ͉҂������K������ɉ��c�Łw�����O�x�Ƃ������̏����������J�������i���͑����Ȃ������B�������炨�g�̂ӂĂ����ꂽ�C�����@������B�A���R�[���ɓM�ꂽ�ޏ��ɂ́u��������v�̂����Ȃ�����ꂽ�B�₪�Ă��������̉Ƃ�ƍ����؋��̂����Ɏ���A���g�͕a�ɓ|���B
������\�O�N�i1890)�O����\�����A�g���S���ڂ�ڂ�ɂȂ��Ă��g�́A����̕��ɐg�𓊂��Ď��B���̕��ɂ́w���g�P���x�̖����c���Ă���B�\�������B �@ |
���^���̂��g 2
�����A�J���̈ꕑ��ƂȂ������c�B���̕Ћ��̔ߘb�u���l���g����v�͏����ɂȂ蕑��ŏ㉉�Ȃǂ�����A�S���I�ɗL���ɂȂ��Ă��܂��B�����������Ō��ꉉ�����Ă��鎖�͍����̗��j������`�����ɂ�蔻�������j���Ƃ́A���Ȃ肩�����ꂽ���ƒf���ł��܂��B
����͖����̉��c�̊J�ƈ�ł���J���j�����ҁu�����t���v�́A���g���ނɂ����������̌��e���A���a���N�A��Ə\��J�`�O�Y���j�����b�Ɩ��ł��āu���l���g�v�\�������Ƃɂ����̂���������ł���A���O�t���́u���̌��e�͏\��J�ׂ̖��d���ɐF�X�Ɨ��p���ꂽ���A����ɂ��Ď����牽��̈��A���Ȃ������B�v�Ɩ������Ă��邩��ł��B
�����ł́u���c����v��n���j�����������p�����u�^���̂��g�v�����Љ�Ă݂܂��B
��
���g�͓V�ۂP�Q�N�P�P���P�O���A�D��H�s���q�̎����Ƃ��Ĉ��m�����c�i�m�������j�Ő��܂�S�ʼn��c�Ɉڂ�Z�݂V�ŗ{���A�P�S�ŗ{�ꂨ�����m�l�̏��߂ɂ��|�҂ƂȂ�܂����B ����ł́u���v�Ƃ������A�`�ɓ������D���Ȃǂ̐g�̉��̐��b������h�ꑮ�́A���̑����܂��̂����Ă����Ƃ������Ă��܂��B
���܂���̉Z����ŋ����̏��ɂ��Ă͍C�����Ă��āA���̔��e�͕]���ɂȂ�܂����B�܂������ł�����V���̖��������ӂ��������Ƃ���u�V���̂��g�v�u�����̂��g�v�ƌĂ�A���Ă͂₳�ꂽ�ƌ������ł��B
�����S�N�i1857)���g�P�V�̎��A���{�����A�����J���ǂ��炩��̗v�]�ł��邩�A���ꂪ���̖��_�ł�����܂����A���g�̓A�����J�̎��ق̃n���X�̌��֕���ɏオ�邱�ƂɂȂ�܂����B���{�l�̉��ăR���v���b�N�X�̂��߂��A�܂����ꒆ�ɂĈ��I�݂Ȗ�l���ア���l���s�߂�\�}�̕����ϋq�Ɏ邽�߂��A���{���̃n���X���_��ł��g�����̋]���Ƃ��ĘA��ā@ �s���ꂽ�Ƃ�������ɂȂ��Ă��܂����悤�ł��B���������a����A�����J�i���R�����{���{�ɗv�������Ԉ��w�̎���ƏƂ炵���킹�A�܂��n���X�͍]�˂���A���������T�N�`���Q���܂ł�����ƌ����D�����C���̖����x�x���Q�O�������V���Q���ň͂��Ă��������A�܂��]�ˑ؍ݒ��������ƌ����P�W�ɂȂ鎛�d���݂̎g�p�l���O�����قǎd�������Ă�������������A�n���X������A���g�����邢�͊Ō�w�̖��ڂ̉��A���{�̎Ⴂ����v�������Ă����̂��ƌ������̕��������͂�����l�����܂��B�܂����c��s���x�z����E�ɍ��V���Y���炪�A���g���n���X�̌��֕���ɍs���ƌ��������ƌ��������A���{�̖�l���o��܂ł��Ȃ�����g���Ȃǂ̐��b���⓪�����̖��ɓ��������ƌ��������A����ł�����N���肦����{�炵�����i�Ɋ����܂��B
���Ă��̈����S�N�T���Q�Q���̖�A���g�͌ܐl�̖�l�ɂ����������ˉ��Ăɏ悹���̎��قւƏo�����čs���܂����B�����ė����A���čs���܂����B�������O��ł��g�Ɏ������ƌ������ƂŁA�n���X����s��ʂ��Ď���×{��\�������Ă��܂��܂����B����Ă��g���n���X�̌��ɒʂ����̂͂��̎O�邾���������̂ł��B����ʼn������Ă���悤�Ȍ��g�I�ŕa��ِl�Ƃ̗�������Ȃǂ́A�����ɂ͑S�����݂��Ă��܂���B
���̂킸���O�邩����ł��g���n���X�̕t���Y�������낳�ꂽ�̂��A�������������܂����{���̂��Ƃ͂͂�����͂��Ă��܂���B �n���X�̐l������a�C���A�v���̏��ł��邨�g�̐��i�Ɍ������������E���ɂ��g�͘V�����ِl���D�܂Ȃ������ƌ��������F�X����܂����A���������̎���30����������������P�Q���͑O����̕ԍςƂ��ĕ�s���Ɉ����� ������A���p��l�����B�̑ҋ@���Ă���ԑ������������ƂȂǂ̋L�^����i�܂��㔼��������j�������̍r���h��D���ȏ��������ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��O�q�̂������鏑���̃q���[�X�P���������ӂ��₨����A�����Ă��܂ȂǂƂ͒����Ԃɐ[���ƊW���������ƌ������Ƃ���A���g�݂̂����ق̃P�[�X�ł������ƌ�����ł��傤�B
���g�̂��̌�́A�O���≡�l�ł̌|�W�����A�ߏ��Ƃ̔����Ƃ̊J�ƁA�܂����Ǘ��̑D��T�g�̌㉇�ň����O���J������N�Ŕp�ƂƂȂ�ȂǁA�g���̐��U���߂����܂����B�����Ė����Q�S�N�A�T�P�i�����j�̎��A���̂Ȃ̂�����g�𓊂����̂����������͐�ɓ��������𗎂Ƃ����ł��B�ӔN�͌�H�̏W�c�ɐg�������A�q���B����͓��l�Ɛ𓊂���ꂳ�����܂�Ȃ�����A�l����̎{���͈�؎t�����A���m�̖��Ƃ�����H���܂����B
���̎����̎����傫�����グ���A���c�̐l�X�����g���Ȃ���̂��ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł��B�ꕔ�ɂ͔l����}�𗁂т����l�X�����܂������A����͂��g�̃v���C�h�̍����Ǝ�Ȃ̈����������ł���A���̈��������i���Ђ����Ă����ƌ�����̂ł��傤�B�������A�����n���X�̌��֕���ɏo�Ȃ��čς̂Ȃ�A�B�̎����݂ŋC�ʂ̍����|�҂ňꐶ���I����Ă��������m��܂���B�ꎞ��̓����Ɋ������܂ꂽ�A�s�K�ȏ����������Ƃɂ͈Ⴂ����܂���B �@ |
�����l���g 3
�����ŕ�炵�����X
���l���g�i�ꔪ�l��`�ꔪ���j�������ʼn߂��������N�Ԃ́A�����炭���U��ʂ��čł��K�����������X�̘b�ł���B����ɂ́A�����Ă��̑O��̂��g�����l���ɂ��Ă��L�q����K�v������Ǝv���B
�č����㑍�̎��n���X�����c�ɗ��q���A�ʐ�̎��قƂ����͈̂����O�N�i�ꔪ�ܘZ�j�����̂��Ƃł���B���Ƃ��ƕa�ゾ�����n���X�́A�������ւ̐S�J�������Ă��A�N�̕�ꂩ�猒�N���Q���A�N��������Ɠf���A���c��s�ɐg�̉��̐��b�����鏗���̔h����v�������B�����A���{�l�͊O���l���ΐl�i�ѓ��j�Ă�肵�A�Ō�̂��߂Ƃ͂����A�ΐl�̂��Ƃ֕������ȂNj��Ȃ������B����ʂĂ���s���ڂ������̂́A�`�ɏo���肷��D�������̈ߗނ̐���Ő��v�𗧂Ă��e�������āA����͌|�҂Ƃ��ē����Ă��������\�Z�A�]���̔��l�֓������i�ʏ̖��G�̂��g�j�ł������B
���g�ɂ͒ߏ��Ƃ����l�ΔN��̑�H�̗��l�������B��s����̍ĎO�̗v�������݂Â��邨�g�ɁA��s�́u�����̂��߂��B�g�𓊂������Ă���v�ƁA�Ή��Ƃ��Ĉꃖ���\���A�x�x����\�ܗ��̏������������B���j�̋������ꃖ���ꗼ����������̂��ƁA����͓r�����Ȃ�����������B����A��s�͒ߏ��ɑ��Ă͂����ꕐ�m�Ɏ�藧�Ă邩��Ƃ����Ă��g�ƕʂ��悤�ɔ������B��������̕��m�ƕ����Ēߏ��̐S�͓������B�ߏ��̐S�ς���m��A������l�i�Ȃ��j�������g���������A���̂����ɒ��߂ĕ�s�̗v���������A���{���p�ӂ������ˉ�U�ɏ悹���ċʐ̖�����������B�����l�N�܌���\����̂��Ƃł���B
�������A���̂Ƃ��͂Ȃ����O��ŋA�����i���g�̑̂Ɏ��̂����ł��Ă����Ƃ̐�������j�B���ɖ߂������g�l�͈ΐl�ɔ������������A�u���l���g�v�ƌĂ�ŕ̂݁A�p������Ɛ܂œ��������B
�����ܔN�Z�������A���c���Ђ������č]�˂Ɍ����n���X�ɓ��s�������g�́A�]�˓�����A���{�����؋���n���ꂽ�B�n���X���������̎g���𗹂������Ƃ́A�n���X�ɏ]���ăA�����J�܂ōs���o������߂Ă������g�́A���̋��̎�������ۂ������A���{�̖�l����n�q��Ⴊ�����ďo���͂ł��Ȃ��Ɛ�������A���Ԃ��Ԃ�������A���̂��ƍ��R�Ǝp���������B���炭�]�˂ɂ������ƁA�㗌���_���Ō|�҂ƂȂ��āA�|�����͂���Ή��u�m�����ɉA�ŗ͂�݂��Ă����Ƃ�������B
����A�ߏ��͍]�˂Ŗ��{�Ɉ�U�͕��m�Ɏ�藧�Ă�ꂽ���̂́A�����ېV�Ŗ��{���̂��̂�����A�E�������ƁA�V���ȐE�����߂ĐV�J�n���l�ɂ���ė����B���̂Ƃ��A�ߏ����Z�̂����c�o�g�҂������Z�ތ����ܒ��ړy����́u���c�����v�ł������B�����āA�߂��̑��D���i�g�l���j�őD��H�̎d���ɂ����B
�����A�d�����I�����ߏ��͂ЂƂ�g���i�����Ƃ��j�̍J������Ă����B�ƁA�����֕Ҋ}�������V�������̐��ȏ����ʂ肩�������B�c�c���̕ӂɂȂ�ƁA�����ŋ��i�Y�ȁj�⏬���̐��E�ł��邪�c�c����A����͂��g�ł������B���g�����Q�̖��A�V�J�n���l�i���c���j�ɂ���ė��Ă����̂ł���B��l�́A�����܂����̗����ɂ��ǂ�A���̖邩��ߏ��̒����ňꏏ�ɏZ�ނ悤�ɂȂ�B�������N�i�ꔪ�Z���j�A���g��\���A�ߏ��O�\��ł������B
�قڏ\�N�U��ɉ��l�ōĉ�����g�ƒߏ��́A���̖邩�猳���ܒ��ڂɂ������u���c�����v�ŐV���������c�ނ悤�ɂȂ�B
���́u���c�����v�ɂ��āA��Ə\��J�`�O�Y�́A���M�u���l���g�����v�i���a�l�N���j�̒��ŁA�u�z�R�����Ɏ����o���b�N���̌����������Ɖ��l�ØV�k�v�ƋL���Ă��邪�A�����炭�A����͈������N�i�ꔪ�Z���j�A���{���O���l�����n���������Ƃ��A�����Ƃ̊Ԃ��u�����邽�߂̉^�́i�x��j�̑����ɓ������J���ҁi�y���j�Z���p�Ɍ��Ă������Ǝv����B���̂Ƃ��͊e�n����吨�̏o�҂��J���҂��W�܂������A���̒��ł����c����̏o�҂��������A�����̐l�������Z���Ƃ���u���c�����v��u�y����v�̖����������̂Ǝv����B
�u�����v�ɂ��g���}�����ߏ��́A��������d���Ɉ�w���o���悤�ɂȂ�A���g�͂��g�ŁA���[�炵��������鞂Ɍ����A�D�������������f���āA�ߏ��̋A���҂��Ȃ���Ǝ��ɂ������B
���̂���A���܂��ܒ��ڂɂ��鏬�������ΐ쉮�͕ĉ����c��ł��āA���g���������̓X��K��Ă���B�X�ɂ͏���l��q�m���i�ꔪ�l�O�`�ꔪ����j�̂ق��ɏ��삩�߁i�ꔪ�l��`����O�j�������B��l�Ƃ����g�i�ꔪ�l��`�ꔪ���j�ƔN��߂������������āA�����ɂ��Ă��g�̐g�̉��̑��k�ɏ���Ă����炵���B���ɁA�̂��Ɂu�ΐ쉮�v���ĉ���������ɓ]�����Ƃ��̏���u�ΐ쉮�v�̏���l�ƂȂ������߂́A�o�䔧�Ŗʓ|�����悭�A���g���N����ΔN���ł������ɂ�������炸�A���Ȃ��y�n�ł̂��g���v���āA�ׂ����C��z��A���낢��Ɛ��b���Ă��Ă����炵���B���g�������≺�ɂ������������̓X����`���悤�ɂȂ����̂����߂̏Љ�����Ă̂��ƂƎv����B�ߏ��̋A���҂������A���g�͂��̓X�Ŕ������̘r�����B���g���̂��ɉ��c�Ŕ������̓X���n�߂��̂����̂Ƃ��̑f�n������������ł���B
���Ắu���l���g�v�̖��ł���قǎ��͂���̂܂�Ă������g���A�����ł͂������ʂ̏��i�ЂƁj�Ƃ��Č}�����A�����ŁA������x�܂���X�𑗂邱�Ƃ��ł����B
�������đ��|���l�N�̍Ό������ꂽ�B�₪�Ă��g���ߏ����]���̔O�ɂ�����悤�ɂȂ�B�����l�N�i�ꔪ����j�A��l�͈ӂ������ĉ��c�ɖ߂����B���Ƃ��Ƒ�H�������ߏ��͎����ʼnƂ����āA�����ł��g�͌����ŏK�����ڂ����������̓X���J�����B�u���g�̓X�ɍs���A���l�Ⓑ��ŗ��s�̔��^�q���l鞁i�܂��j�r�������Ă��炦��v�Ƃ����̂ŏ������͉��������A�X�͔ɐ������B���A��������̊ԁB���g�����ɖ߂������Ƃ�m�����̂̓���q�����g�́u�V�����G�v�������Ǝ�Ȃ֏����A�ŏ����S�O���Ă������g���₪�Ă��̐Ȃ֊���o���悤�ɂȂ�A���߂���܂܂Ɏ����ꍇ�A�c�c�܍��A�ꏡ�ƈ��ݐi�݁A���̂����Ɏ𗐂̋C����悷��悤�ɂȂ�B�����āA���ꂪ���ƂŒߏ��Ƃ̊Ԃł����������₦�Ȃ��Ȃ�A���ɓ�l�͌��ܕʂꂷ�邱�ƂɂȂ�B
���g�́A�O���ōĂь|�҂ƂȂ�A�ߏ��͍č���A�}���B��N���܂�ʼn��c�ɖ߂������g�́A�Ăє����X���J�����A�l��ɂȂ����Ƃ��A�n���̑D�傩�珬���������V�����u�����O�v�̌o�c��C����邱�ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�A�����i�����݁j�̐g�ł���Ȃ���A�q�O�ő�����i�����j��A�𗐂Ɖ������g�̎p�����āA�q���͎���ɉ��̂��A�X�͓�N�Ŕp�Ƃɒǂ����܂��B
���ꂩ��̂��g�́A���\�����ƂȂ����B��l�����������A�₪�āA���_�����̂��ڂ�ڂ�ɂȂ�A���g�s���ƂȂ��āA���̓��̕�炵�ɂ��������悤�ɂȂ����B���������̌���ĕ������g�́A���̂����ɔ��ʂāA���ɖ�����l�N�i�ꔪ���j�O�����A���J�̒��A���㗬�̖�I�����ɐg�𓊂��āA�܈�̐��U����邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�������āA���߂Ă��g���H�����l�������Ă݂�ƁA����̔g�ɂ��܂�Ȃ���K���ɐ��������g�ɂƂ��āA���U�B��S�x�܂���X�����ꂽ�̂́A�����ʼn߂��������̐��N�Ԃ����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł���B�@ |
�����g�����@�É������c�s�͓�
����24�N�i1891�N�j�R��27���̍��J�̖�A��l�̏��������c�X�������̈���̕��ɐg�����������B���̏����̖��͍֓������B�g���l���g�h�ƌĂꂽ�����ł���B
�����̐��U�́A�����̓������ɖ|�M���ꗬ�]�����B�c�����ɉ��c�Ɉڂ�Z��ŁA14�ʼn��c��̐l�C�|�W�ƂȂ��������ł��邪�A�����S�N�i1857�N�j�ɐl��������t����]�@���K���B�������c�ɑ؍݂��Ă����A�����J���̎��̃n���X�́g�g�̉��̐��b�h������悤���������̂ł���B
�ݒ�ᇂœ|�ꂽ�n���X�Ƃ��Ă͊Ō�����Ă���鏗������]�����ƌ����邪�A���{�͂���������̗v���Ɖ��߂��Ă����ɔ��H�̖�𗧂Ă��̂ł���B���ԂƂ��Ė�Q�����̋߂ł��������i�ŏ��̂R���Ԃň�U�ɂ��o����邪�A�x�x��25���̂��Ƃ������Ă����̑�����Ăѐ��b���肢�o�Ă���j�A�ٍ��l�̎��I�Ȑg�̉��̐��b�������Ƃ����Ό���A���̕�V�̍����i����10���j���炭��i�݂̂������A���̌カ���͉��c�̒��Łu���l���g�v�ƌĂ�A���Q����悤�ɂȂ�̂ł���B
�n���X�Ƌ��ɍ]�˂֕����������́A�����ŐE�������ꂽ����ɍs��������܂����B�����Ė����ېV���ɉ��l�Ɍ���A���ď����𐾂��������j�Ƌ��R�ĉ�ď��т����B��l���ĉ��c�ɖ߂������A���ǂ����������₦�Ȃ��Ȃ��ė����B�����͍Ăщ��c�𗣂�ĎO���̗V�s�Ō|�҂Ƃ��ē����ɏo��B���N��A�~���������ĉ��c�ɖ߂�A�x�����ď��������u�����O�v���n�߂邪�Q�N�Ŕj�]����B���̍��ɂ͊��ɃA���R�[���ɂ���Q���o�n�߂Ă���A������������ł����A���ɂ͕�����R�̐g�ɂ܂ő��Ă��܂��B�����Ĕߌ��I�Ȏ��𐋂��Ă��܂��̂ł���B
����������g����ꂽ��͈̂���������Ȃ��A������������ۂ������߁A�R���Ԃ����̓y��ɕ��u���ꂽ�܂܂������Ƃ����B���ǁA���̏Z�E����̂�������苫���ɖ��������̂ł���i���ꂪ���݂̕揊�j�B����ł���܂ʼn��c�̐l�X���猙��ꑱ���������ł��邪�A�ޏ����g�͂��̓y�n�𗣂�Ă͖߂邱�Ƃ��J��Ԃ��Ă���B������l����ƁA�u�����͂��Ȃ�Łv���g���E�����Ƃ����Ŋ����A����������Ɣޏ��̖{�ӂł͂Ȃ������悤�Ȉ�ۂ��o�Ă���B
���j�̕\����ɏo�邱�Ƃ��Ȃ��A�|�M����邾���ŏ����Ă��܂����悤�Ȃ����ł��������A�˔@�Ƃ��Ă��̑��݂��l�X�̖ڂɐG���悤�ɂȂ�B���a�Q�N�i1927�N�j�ɑ����t���������������w���b���l���g�x�A���N���̔Ō������\��J�`�O�Y���������w���l���g�x�����~���ɂ����T�C�����g�f�悪���đ����Ɍ��J����A�ޏ��̖��O�͑S���ɒm����悤�ɂȂ����B�����ď��a�W�N�i1933�N�j�A���̒n��K�₵���V�n�ˈ���A���̂��g�������w�łċ��{�̂��߂̒n�������������B���ꂪ���݂́g���g�n���h�ł���A�܂����g�����͏�����������A�����ɂ́u���g�Ղ�v�Ə̂��ĉ��c�̌|�҂��͂��߂Ƃ��鑽���̏��������̒n��K��Ė������F��悤�ɂȂ��Ă���B
���n���X
1804-1878�B�A�����J�̊O�����B40��ɂȂ��Ėf�ՋƂ��c�݁A���m�ɍݒ�����B���Č����ɏA���Ă����W����A���{���̎�����]���ďA�C���������B���c�̋ʐ�̎��قƂ��ĕ��C���A���R�Ƃ̉y���𐬌������A1958�N�ɓ��ďC�D�ʏ��������܂ł���������B����͉��c����]�˂Ɉڂ�A�T�N�X�����ԓ��{�ɑ؍݂���B�A���O���J���E�`���[�`�̔M�S�ȐM�҂ł���A���U�Ɛg���т��i���U����ł������Ƃ�������j�B�܂����{�̕��K�Ȃǂ������E�^���Ă��邪�A�B�ꍬ���̏K�������͗����ł��Ȃ��Ƃ��Ă���ȂǁA���I�Ɍ��ȂȐ��i�������Ă����Ƃ̐�������B
���u���l���g�v�̉f��
���a�T�N�i1930�N�j�ɂQ�{�����Č��J�����B���̌�W�N�ԂɂU����f�扻����Ă���A�������ɐl�C�̂������R���e���c�ł������ƍl������B�ŏ��ɂ����̐��U�������������t���́A���c�Ɉڂ�Z��ł�����Ȉ�t�B�����Ɋւ��長����蒲���������Ȃ��A���y���́w���D�x�ɔ��\���A�����ŒP�������s����B�i�����������ɋ����������������ƂȂ����̂͂���l���Ƃ̏o��ł���ƌ����邪�A���̐l���͂����Ƀn���X�̌��Ɏd����悤���������A���c��s�̈ɍ��V���Y�ł������Ƃ��`���j�B�Ō�������Ė{�i�I�ȏ����ɂ܂Ƃ߂��\��J�`�O�Y�́A��[�N���≡������Ƌ��Ɂw���Y����x�ɎQ�����������ƁB�w���l���g�x���q�b�g���āA���s��ƂƂȂ�B
���V�n�ˈ
1862-1933�B����ҁB�w���m���x�̍�҂Ƃ��Đ��E�I�ɒ����B�V�n�˂����g�n�������������͍̂ŔӔN�ł���A�˗�����ɃJ�i�_�֓n�肻�̒n�ŋq���������߁A�������ꂽ���̂͌��Ă��Ȃ��B�@ |
������u���l���g�v
�����l���g�̕���
�u���l���g�v�ƕ����Ă�����u���������Ƃ͂���v���x�̐l�������قƂ�ǂł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��ɃC���^�[�l�b�g�𑀂鐢��ȍ~�̐l�����́c�B
�a���p�̏�������l�����Ƃ����C���[�W����u�Ԓ��M���~�v��u�l�J���k�v�Ƃ��������k���̂ƃS�b�`���ɂȂ��Ă���l�����Ȃ��Ȃ����炢���B
�u���l���g�v�����u�[���ɂȂ����̂́A����80�N�ȏ���́c���a�����̂��Ƃ����疳�����Ȃ��B
�����ŁA���̃��|�[�g�ł́A���������u���l���g�v�Ƃ́A�ǂ�ȕ���Ȃ̂��H�@�܂��A���̕���͂����ɂ��āA���Ĉ��u�[�����܂����������̂��H�c�ɂ��ĉ�������݂�B
���l�c�Ƃ́A�u���v�̍��̐l�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ŁA���Ƃ��Ƃ͒����⒩�N�̐l���w���Ă������t�����A�₪�čL���u�O���l�v���Ӗ�����悤�ɂȂ����B
���g�c�́A�{�����u�֓������v�Ƃ����ɓ����c�Ɏ��݂��������B����̂����ŐE�Ƃ͌|�ҁB�u�����v�������Łu�g�v�Ə����̂͌|�Җ��炵���B
���l���g�c����̕���͈ɓ����c�B���́A�A�����J���獕�D������Ă��āA���悢����{���J�����邱�ƂƂȂ�A�y���[������鍕�D�͑����������Q�N��̈����R(1856)�N�B���l�����ۍ`�Ƃ��Č��݂����܂ł̊ԁA�Վ��ɊJ�`���ꂽ���c�ɏ���A�����J���̎��^�E���[���g�E�n���X�����C�����Ƃ��납��n�܂�B
�y���[�������Ęa�e���ɑ����āA���Ēʏ��C�D�������Ԃ��Ƃ��g���Ƃ����n���X�́A�]�˂ɂ̂ڂ��ď��R�Ƃ̒��k����]�ނ��A���c��s�͂̂�肭���Ƃ�������킷�B
�X�g���X�ɂ���ĕa�̏��ɕ������n���X�̌��֊Ō�w�̖��ڂʼn��c��̌|�҂��������g��ʂ킹��v�����n���X�����炠��A�]�˂ւ̑��~�߂ɗ��p�ł���ƍl�������c��s�͂������邨�g���g�����̂��߁h�ɂƐ�������B
���g�Ə����𐾂����͂��̑D��H�A�ߏ��ɂ́A�����͂ɂ���Ď��Ɏ�藧�Ă�Ɩ��A�����ɂ��g�ƕʂꂳ�����B
�S�̎x���������ߏ��ɂ�����ꂽ���g�́A�d���Ȃ����X�n���X�̌��ɒʂ��A�n���X�ɐs�����B
�n���X�����c���狎��������A���g�͐��Ԃ���ِl�ɔ����������u���l�v�Ɣl���A����Ɏ��ɓM��Ă����悤�ɂȂ��Ă䂭�B
�ߏ��ƍĉ�A���l�ňꏏ�ɕ�炷�����܂͐₦���A�킸�����N�ŗ��ʁB�������A���̒���A�ߏ��͂ۂ�����a�ł��̐��������Ă��܂��B
���c�ɖ߂��ď����������J�����g�����A���Ԃ̕�������͂܂��܂������A�X�������͑����Ȃ��B
���ӂ̂��g�́A��H�ɂ܂Őg�𗎂Ƃ���������A�������E�ɂ���āA�炭�߂������U���I�����B�c�Ƃ����B
���l����������Ɏ���ɖ|�M����A���̋]���ɂȂ��������̔ߌ��̃q���C���c���ꂪ�A�����ԁA�l�X�̓�����W�߁A�l�C���ւ����u���l���g�v����ł���B
|
�����g����j���甭�@������t�ƁA�L�߂�������
�u���l���g�v�̕��ꂪ�a�����邫��������������̂́A�É����ĒÏo�g�̈�t�A�����t��(�ނ�܂� �����)�B
�����ېV��A�É��ł̊J����ƂɏA���Ă����V�l�ɁA���g�̘b���������o�����t���́A����29(1896)�N�A33�ʼn��c�ɋ����ڂ��A��Ȉ�@���J���������A���c�𒆐S�Ƃ���J���j����������悤�ɂȂ�B
���̂��������ƂȂ����V�l�����A���g��������ăn���X�̌��֍s�����������c��s�A�ɍ��V���Y�������Ƃ����B
�t����30�N�ɂ킽�錤���̖��A�吳14(1925)�N�ɋ��y���u���D�v�ɘ_���\�B���a�Q(1927)�N�ɂ́u���b���l���g�v�Ƃ��ď��Љ����ꂽ�B
���̔Ō����[�N���Ɠ����̏\��J�`�O�Y(���イ�����€���Ԃ낤)���������A���a�R(1928)�N�ɏ����u���l���g�v�𒆉����_�ɔ��\�B�����ŏ��a�S(1929)�N�����N�ԁA���������V���Ɂu���̔s�� ���l���g�v�A�ڂ��A�l�C���B
���a�S(1929)�N�ɖ����t���[���珑�Љ����ꂽ�u���l���g�v�́A���݂̓��C�D�D�̑O�g�ł��铌���p�D�D���A����〜�哇〜���c�����Ԋό��q�H���`���邽�߁A�P����������ď�D�q�ɔz�z���A�u�[�������������B�ɓ��}�s�����c�܂Œʂ�32�N�O�̘b�ł���B
�O�q�̒ʂ�A�����ƁA�\��J �`�O�Y�͓����鍑��w���w���p���w�ȂŁA��Ƀm�[�x�����w�܂���܂�����[ �N���Ɠ����B�N���1897(����30)���܂�̏\��J�̕����Q�Ώゾ�B������o�g�����������ŁA�����ɕ��e�����j�ŖS�������̂������������B����ȓ�l���ǂ����C�o���������̂́A�z���ɓ�Ȃ��B
1924(�吳13)�N�A��[�����𑲋Ƃ����N���̔N�A���w���Ԃ��W�܂��ē��l�G���w���Y����x��n������B�������A�����ɂ͏\��J�������B
�Q�N���1926(�吳15)�N�A���̓��l���ɐ�[���㐢�ɖ����c������\�����B�u�ɓ��̗x�q�v�ł���B���̎��A��[�N��27�B���N�A��[�͌��������Ă��邩��A�܂��ɍK���̐Ⓒ���������Ƃ��낤�B
���ꂩ�炳��ɂQ�N���1928(���a3)�N�A��[�ɑR����悤�ɁA�\��J�����\�����̂��u�ɓ��̗x�q�v�Ɠ������A�ɓ��̏�������l���ɏ������u���l���g�v�ł���B
�\��J���A�����̋��y�j�Ƃ���Ō�������Ă܂ŁA�܂��A�����̐�����ǂ݁A�K���q�b�g��ݏo�����������̂ɂ́A��[�ɑ���R�ӎ����������ɈႢ�Ȃ��B
����ɐ��@�����̂́A�\��J��������h�����B�\��J�͕������łȂ��A������j�ŖS�����Ă����B�����}���C�����́A����ȂƂ���ɂ���������������Ȃ��B
�\��J�́u���l���g�v�ɑ����Ĕ��\�����u���̔s�ғ��l���g�v�̑�q�b�g�ɂ��A31�ō������|�܂���܂����B
�����āA�u���l���g�v�Œ��ڂ��ꂽ�A�킸���V�N��c1937(���a12)�N4��2���A39�̎Ⴓ�Ō��j�ɂ��S���Ȃ��Ă���B
|
���u���l���g�v�ɐS���������a�����̐���
���a�T(1930)�N�ȍ~�u���l���g�v�́A�f�扻�A���䉻�A�̗w�ȉ����i�݁A�u�[���͑S���I�ɍL�����Ă������B
���̍��̓��{�͕s���̂ǂ��B
���a�U(1931)�N�ɂ͖��B���ς��u�����A�����i�o������{�ƃA�����J�ْ̋��W�������Ă���������B
�����̊ԂŔ��Ċ�����܂��Ă������Ƃ���A�u���l���g�v�̕��ꒆ�A�J�������v�����Ƃ݂���n���X�ƁA���̋]���ƂȂ������g�ւ̓���S���u���l���g�v�̃u�[�����x���Ă����Ƃ�������B
�������R�����q�Ȃǐ��X�̍�Ƃ��u���l���g�v�������C�N���Ă���A���݂��ɓ����c�ό��̖ڋʂƂ��āA���g�̖����ɂ�����R��27���ɂ́u���g�܂�v���J�Â���Ă��邪�A���Ă̂悤�ȃu�[���ɂ͌��т��Ă��Ȃ��B
�܂��A���g�̊�ʐ^�́A�����̍����I�q�[���[��{���n�̎ʐ^�ƕ���ŏЉ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����A���ݍł������ڂɂ���u19�̂��g�v���͂��߁A�قƂ�ǂ̎ʐ^���ό��q�����̃����Z�ł��邱�Ƃ͎c�O���B
���Ȃ݂�1963�N4��7������12��29���܂�NHK�ŕ��f���ꂽ�P��ڂ̑�̓h���}�u�Ԃ̐��U(����E�M������)�v�́A���c��O�̕ςňÎE���ꂽ�����̑�V�A��ɒ��J�̐��U��`������i�����A��18�b(1963�N8��4�����f)�u���g�E�����v�ł́A����28�̒��u��H�����g�������Ă����B
�n���X�������Ă����̂́A�Ȃ�Ɠ��{�l�̋v�Ė��B�n���X�Ƌ��ɉ��c�ɒ��C�����ʖ�̃q���[�X�P�����͉��c�����������Ƃ�����������B���Ă݂����c�I
���A�c�O�Ȃ��瓖���̓r�f�I�e�[�v���������������߁ANHK�ɂ��^��͎c����Ă��炸�A���݂͌��邱�Ƃ��o���Ȃ��B
���V���ƕ��сA�C�O�ł��]���̍����a�������a�T(1930)�N�Ɋē����T�C�����g�f��u���l���g�v�̃t�B���������݂͂S���Ԃ̗\���҃t�B���������c���Ă��Ȃ��B
���g����̖v��120�N�ȏ�c�A��O�̂��g�u�[������80�N�ȏオ�o���A���Ԃł́A���Đl�C���Ău���l���g�v�̕����m��l�����Ȃ��Ȃ����B�@ |
|
�@ |
| ���]�˂̊X�� |
   �@
�@
|
|
�@ |
�@ |
|
�����C�� |
�@ |

 |
|
���܂Ō\�O��(���܂Ō\����) / �]�ˎ���ɐ������ꂽ���{�����N�_�Ƃ���܊X���̈�B�]�˂Ƌ������Ԋ������H�Ƃ��āA���R���ƂƂ��ɍ]�˖��{�ɂ�萮�����ꂽ�B
|
�@ |

 |
���i��h(���Ȃ��킵�キ) ���{������
�@
���C����ꎟ�B�{�w��A�e�{�w��A���ċ�\�O���A�ː���ܕS�Z�\�]�A�l���Z�甪�S��\�]�l�B���B�E���������̐�Z�A���R���̔��A�b�B�����̓����V�h�ƕ��ԍ]�ˎl�h�̈�B�h��͖ڍ��������œ�k��h�ɕʂ�A�����݂͋㒬�l�\�Ԃ��܂肾�������A��ɂ͐V�����o���Ă���B�]�˂ɏo���肷��l�X�̑��}�̏�A�g���ƕ��ԗV���̏�Ƃ��āA�܂��h����ӂɂ͍���g�t�̌��������茩���q�Ȃǂœ��킢�A�l�h�̒��ł͈�Ԃ̔ɉh���ɂ߂��B
�@
�h��̐����́A�c���Z�N(1601)�A�ƍN���w�n�O�\�Z�D��u�����ďh�w�Ɏw�肵���̂��n�܂肾���A���c���k�����̎x�z�����V���\��N(1583)�́u�k�����Ǝ���v�Ɂu�i��h�v�Ə�����Ă��邱�Ƃ���A�V���N�Ԃɂ͏h��Ƃ��Ă̋@�\�����������̂Ǝv���Ă���B
�@
���ێO�N(1718)�A�ѐ����͗��Ĉꌬ�ɓ�l�ƒ�߂�ꂽ���A�i��h�ł͖��a���N(1764)�ɌܕS�l�܂ŕ����邱�Ƃ�������A�g���ɂ��F���ƂȂ����B�V�ۏ\�l�N�̋L�^�ł́A�ѐ�����u���ѐ����Ă���\�A���������Z�\�l���𐔂��A�u���Ȃ������Ă��\�㌬�����ŁA��ɂ͎O��Z�S�l�����ƂȂ�A���ɂ͌����҂��o�����������B�����̋L�^�ł́A���̏h�ɗV�тɗ���q�́A�F���ˎm�Ǝő��㎛�̑m���ő唼���߂��Ƃ����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���������āA�قǂȂ��i��ւ��B�펟�Y���ց@�C�ӂ��Ȃǂ��Ȑ�Ƃ��ӂ���@�Ɠ�����̋�ɁA�������Ƃ肠�ւ��@������݂��̂���ɂ܂����ā@���Ƃ������낭���ނƂ��Ȃ��ɁA�邪�X�ɂ�����v
�@
���Z���̓n��
�@
�n�D�n���B�Z����(������)�ɂ͌c���ܔN(1600)�ɉƍN�ɂ��˂���ꂽ�Z���勴���˂����Ă����B�������A���\���N(1688)�A��^���ɂ�肻�̋�����������ƁA�ȍ~�A�ˋ����ꂸ�n�D�n���ƂȂ����B
�@
�u�ʐ�Z����̖{����B�������Ƃ������B�����͕����̌S����B�Z�ʐ�̑���ɂ��āA�Ér�����B�����ԗ��ɂĂ͓��Ԑ�Ƃ��ЁA�C���ɂĂ͘Z�����Ȃ�ΘZ����Ƃ��ӁB�ނ����͑勴����B�������O�勴�̑��ЂƂ�B���T�S��Ԃ���Ƃ��ӁB�^���ɓx�X�������ցA���\�N�����D�n���ƂȂ�B�����͏��萅�������Ĕ���ӂ��A�]�ˋ�������̐l�Ƃ̗p���Ƃ��v
�@
�w���C�����G�I�сx�u��X�Ƃ��ւ���m�k�������̖����ɂāA�Ƃ��Ƃɂ����ȂӁ@�тɂ����ނ��͂炴���������܂ւ���͎q�ǂ������������̂��߁@������Z���̏����ւāA���N���ɂĎx�x����ƁA����������v
|
�@ |

 |
�����h(���킳�����キ)
�@
���C����B�{�w��A���Ď��\�A�ː��ܕS�l�\�]�A�l�����l�S�O�\�]�l�B
|
�@ |

 |
���_�ސ�h(���Ȃ��킵�キ)
�@
���C����O���B�{�w��A���Č\�����A�ː���O�S�l�\�]�A�l���ܐ玵�S��\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�͂₩�Ȑ�̂ڂ��Ȃւ��v���ӂ���Ƃ��A�n������Ă��ǂ�s�قǂɋ�����i�ɗ���Bূ͕Б��ɒ��X�����Ȃ�ׁA���Â�����~��K���A�������̘L���A�V�Ȃǂ킽���āA�Q�������͂̌i�F�������Ă悵�v���F�ڂ���(�_�[)�_�̐�[�Ƃ����Ӗ������A�h�w�̂͂���ɂ́A�_�̐�[�Ɂu�����艽�h�v�Ə����Ă���������h��̂͂�����u�_�[�v�u�_�@�v�Ƃ������B
|
�@ |

 |
���ۓy���J�h(�قǂ��₵�キ)
�@
���C����l���B�{�w��A�e�{�w�O�A���ĘZ�\�����A�ː��ܕS�\�]�A�l������S��\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�͂�����J�̉w�ɂ��B������藷���̉a���ɏo���Ă���������Ȃ̊�́A���Ȃ���ʂ����Ԃ肽�邪���Ƃ��A�^���ɂʂ肽�āA���Â����̎�������̍��̑O�����Y����́A�M�������ɂ��ցAূ͛�q�̏h�Ƃ��Ђ��鏊�ƂȂւ�(����)�@���Ƃ܂�͂悢���J�ƂƂߏ��˒ˑO�Ă͂͂Ȃ����肯��@�Ƒł��Љߍs�قǂɁA�i���Ƃ��ӂƂ���ɂ�����B���ȂB���B�̋��Ȃ�Ƃ����@�ʂ������ӂ��ɂ킩�鍑�������͂���Ȃ̍���@���łɂ͂�A�������̂͂ɂ����Â�����A�˒˂̉w�ɂȂ�Ƃ܂�ׂ��ƁA�������s��������v
|
�@ |

 |
���˒ˏh(�Ƃ����キ)
�@
���C������B�{�w��A�e�{�w�O�A���Ď��\�܌��A�ː��Z�S�\�]�A�l������S�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���u���R���A������B�������ӌ˒˂��B�����ɂ���ӂ��k�u�Ƃ������u�Ȃk�u���T�����A�˂��炨���Ȃ��ւƂ��āA�Ђς�˂ւ̖��u�ق�ɂ��̂͂Â��Bূ͂ǂȂ������Ƃ܂�ƌ��ւāA�݂ȏh���ɎD���͂Ă��邫���u�R�E�ނ��ӂ̓��������������u�R���A���˂���B�Ƃ߂Ă����C�͂Ȃ����͂����⏗�u�C�G���ӂ͂��Ƃ܂�ŁA������ǂ͂Ȃ�܂��ʖ��u�Ȃނ��ӂ���Ӄg����^�_��ǂ��������ǂ��A�݂Ȃӂ�����Ƃ߂ʂ�֑傫�ɂ��܂�A�܂������邫�Ƃ߂���͏h���l�C�Ƃ���ꂽ��傫�܂̖�����˒˂Ɂ@������h�͂Â�ɂ�����ɁA�Q���͂�����̍��h�Ȃ��Ă��ɂ݂�邠��A�₪�Ă��T�ɂ����Ė��u�Ȃ�Ƃ킵����Ƃ߂Ă���Ȃ��ւĂ���u���ӂ��肩�ցB���Ƃ܂�Ȃ���܂��B���h�͂�ǂ�݂͂Ȃӂ�����܂������A���������肠����܂��ʁv
|
�@ |

 |
������h(�ӂ����킵�キ)
�@
���C����Z���B�{�w��A�e�{�w��A���Ďl�\�܌��A�ː���S�\�]�A�l���l�甪�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�@�u��u�R�E�M�l������A���B�A�m�h���啪���ꂢ�ɂȂ��́B�≮�̑��Y���q��ǂ̂͒B�҂��́v
�@
���n��(����)��̓n��
�@
�n�D�n���B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�g�����͂₭���n���̂킽���ɂ��B�k�����T�͉��Ƃ��Ӑ�Ɛl�ɂƂЂ��ɑ��킽���Ɠl�����ւ������Y���T�ā@��̖����ւ킽���Ƃ���ɂē����n���̐l�̂������@����́A�b��̉��͂���藬�ꂨ��悵�B�₪�Ăނ��ӂɂ킽�肽�ǂ�s���ɁA���ɔ��ב��Ƃ��ւ�́A���̂ނ����A�`�o�̎T�ɔ肽������͂Ђ��߂āA���͂��̋{�Ƃ��ւ�v���F�����̋{�͔n����̂͂邩��O�ɂ���A���̋L�q�͌��B |
�@ |

 |
�����ˏh(�Ђ�����キ)
�@
���C���掵���B�{�w��A�e�{�w��A���Č\�l���A�ː��l�S�l�\�]�A�l�����S�\�]�l�B |
�@ |

 |
�����h(�����������キ)
�@
���C���攪���B�{�w�O�A���ĘZ�\�Z���A�ː��Z�S���\�]�A�l���O��\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u��������ɂ�����A�Ղ������Ėk����ށ@�����Ƃ̌Ղ͖��ɂ����̂��̂������̐ƂȂ肵��߁@�펟�Y���ւƂ肠�ւ��@���Ȃ���ɂȂ�Ƃ͖����ʂЂƂ@�̂��ւɂ����ʁ@�z�ŋ����đ��̂܂���ʼn߁A������ɂ�����v���F�u�Ղ��v���̉��䎛�ɂ���u�Վq�v�̂��ƂŁA���̒��҂̗V���Ռ�O�ɂ��ȂƂ���Ă���B
�@
�������̓n��
�@
�Ċ�(�O��〜�㌎)�͕��s(����)�n���ŁA�~��(�\��〜��)�ɂ͉������˂������n���B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�]��̒��ނ珬���킽���܂�̋{��ł����A�������ɂ������T�肯��@���^�_�͂ӂ����z�ӂ���ɂĎ���̂��͂ɁY�Ă�ӂ���@��������ւ䂯�Ώ��c���̂�Lj��͂₭�����ɑ҂����Ă�Lj��u���Ȃ������́A�����ł�����܂�����u�����܂�����炩�B������A�����������q���ɁA�Ƃ܂���肾�q���u���ӂ͗��ƂƂ��A���Ƃ܂肪�������܂�����A�ǂӂ������ւ���������܂����u�����܂̏��͂��ꂢ���h�u���₤�ł�����܂��B���Ԍ������܂����V��ł�����܂����u�������͊�Ԃ���h�u�n�C�\��Ɣ���ƁA�݂����Z�ł��ł�����܂����u�����ӂ�͂�������h�u����Ɖ��Ɠ�c�ÁT�A�l�c������܂����u���͂������肠��h�u�O�l������܂����u����₤�͏h�u�����Ԃ�����������܂��v
|
�@ |

 |
�����c���h(������炵�キ)
�@
���C����㎟�B�{�w�l�A�e�{�w�l�A���ċ�\�܌��A�ː���ܕS�l�\�]�A�l���ܐ�l�S�]�l�B�鉺���Ƃ̕��h�B�h���l�n��100�l100�D�Ƃ���A�`�n100�D��������Ă����B�]�˂��o���������l�̑����́A�����z�����T���A���̏��c���h�œڂ̏h����������Ƃ���A�K���h�ɂ��ŗ��Ă̐��������Ȃ��Ă���B�܂��A�������c���h�́A���������Ə̂���铒�{�E���m��E�������E�{�̉��E��q�E�؉�E���V���̉������T���A�����؍݂̓����q�ł�������Ă��āA�]�ˎ���̌㔼�ɂȂ�ƁA���l�͏h��ȊO�̏h�̏h���͋ւ����Ă����ɂ�������炸�A��铒���Ə̂��ĉ���h�ɔ��܂闷�l�̐��������Ȃ����B���̂��ߏh��̗��đg���́A���c���˂⓹����s�ɍĎO�i�������A���{�͂��������Z���h�������F�������߁A�ȗ��A���C�������̍ۂɔ����ň�〜���闷�l�̐��͑����������B����Ȏ���������āA�鉺���̏h��ł͂߂��炵���ѐ������u���ꂽ���A�h��̍����͍D�]�����A�����Z�N(1859)�̋L�^�ł́A���Ă̐��͔��\�����ƌ������A���p�ʌ��̗��q���x�ᖳ�����܂点�邱�Ƃ��ł���Ƃ��\��〜�\�㌬�ŁA���Ƌ�E���Ƃ��ɏ�����Ă���h�͎O〜�l���������Ƃ����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�قǂȂ����c���̂��䂭�ւ͂���ƁA�����͂̂Ƃ߂���ȏ��u���Ƃ܂�Ȃ����܂��^�_�g��т��邱�ւ����܂����펟�Y���炭���ց@�~�Ђ̖����ƂĂ�Ƃ߂���Ȃ������������ė��l����ԁ@�����䂭�̂߂��Ԃ����낤�݂��������Ȃ�Ėk�u�������T�̓��́A�����ɂłւԂł��܂Ђ��܂̂���������u���ꂪ�����̂����낢���k�u�ЂƂ��Č���ӁB���ւ��̖��u���߂ւ��B�����炠�k�u�����݂��Ƃ�������A������݂����Ȗ��u�n�T�T�T�T�A���������낤���@�����낤��݂��Ƃ��܂����܂���Ă��͖�Ƌꂢ���ق���@�₪�Ă�ǂ�ւ�����A�Ă����䂳���ւ��������Ă͂���Ȃ���u�T�A���Ƃ܂肾��B������^�_�B�������ƂĂ�����B�h�̏��ڂ��u���͂₤�������܂��g�����ӂ�����ł��Ă���B�������������ɁA�������Ă��Ă���ƁA���Y���̂��ق��悱�߂ɁA����ƌ��āA�����ւɖk����т������u�������B�܂�ł��˂ւ̖k�u���������ԂĂ��߂�Ӗ��u�ӂĂւ��Ƃ��ʂ����B���ꂪ���߂�n�v
|
�@ |

 |
�������h(�͂��˂��キ)
�@
���C����\���B�����֏��A�{�w�Z�A�e�{�w��A���ĎO�\�Z���A�ː��S��\�]�A�l�����S�l�\�]�l�B���h�Ƃ��āA��p���������p�����āA���̑��͏��c������O���܂Ōp���ʂ����B�����h�͌��a�l�N(1618)�A���c���h〜�O���h�̔��������̒��ԂɁA���c���h����\�ˁA�O���h����\�˂��ړ]�����A�V�����ݒu���ꂽ�h��ŁA���c���˂ƎO���㊯�o���̎x�z�����B�h�̒����́A���̏��c���h������V�J(��)���A�֏���ʂ��ĐV���A���c���������c���ˎx�z�A���̎O�����A�����Đ��[�̈��쒬���O���㊯�x�z�ƂȂ��Ă����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���ӂ͖��ɂ���⦍������A�͂₻��^�_�ƁA���̐��������ǂ�s�قǂɁA���܂肿�����Ȃ�Ė펟�Y���ց@�l�̂����ɂӂ߂ǂ��T���ǔ�����ܖ{���n�Ȃ�����݂̂��@�k�u�R���^�_�����͂˂ւ��B���T�̖�������u�ׂ�ڂ��߁B���ӓ��̏o�鎞���A�������i�j������̂��k�u�邪�����Ă����T�͂ȁB���߂ւ��ĂƂڂ����T�A��ӂׂ̂����ɖ�u������A����k�u�n�T�T�T�T�n�T�T�T�T�����T�ɓ��{�̏h�Ƃ��ӂ́A�����̉ƍ삫��т₩�ɂ��āA���Â�̓��ɂ����ڂ悫����O�l�d�T�A�X�����ɏo�Ė����̔҂��̍H�������ȂӁB(����)�@�������֏���ʼn߂ā@�t���̎�`�������ČN����̌˂��T�ʊւ������߂ł����@�z�j���ē��̏h�ɉx�т̎����݂��͂��ʁv
�@
�������֏�
�@
�͂��ߌc�����ɔ��������̋߂��ɐ݂���ꂽ�Ƃ���A�����h�w���J�݂��ꂽ�N�̗����a�ܔN(1619)�A�h�̒��ɐV���ɐݒu���ꂽ�B�֏��̊Ǘ��͖��{����ϔC���ꂽ���c���˂��s���A�Ԏm�ƌĂ��˂̖�l�����ŋ߂��B�J�݂̓����́A�u����S�C�A�o����ȁv�ɂ��Č���������肪�s���Ă������A���i�\�N(1633)�ȍ~�ɂ͓S�C���߂��ȗ��������߂���̂ƂȂ�A�l�����Ƃ���������u���A�]�˕��ʂ���o�鏗�������d�ɉ��߂��B
�@
��������
�@
���C���O���̈�B���������Ƃ����A�������������ɉz���Ɓu�R�j���v���s�����l���������B
|
�@ |

 |
���O���h(�݂��܂��キ)�����h���O����\����
�@
���C����\�ꎟ�B�{�w��A�e�{�w�O�A���Ď��\�l���A�ː����\�]�A�l���l��l�\�]�l�B���Ƃ��Ƃ��̒n�́A�ɓ����{�Łu���{(����)�v���邢�́u�{���v�ƌĂ�Ă����n�ŁA�����z��(��a�ꓹ)�̋����C��(����)���ォ��h�̋@�\������Ă����炵���B���̌�A�ɓ��̔��l�ɂ������O���Ђ��ڂ���A�O���ƌĂ��悤�ɂȂ�A�퍑���ɂ͂��łɎO���h�ƌĂ�Ă����B�܂��A��a�ꓹ�̕���̑��ɁA�������牺�c�����ʂ��Ă������Ƃ����ʂ̗v�ՂƂ��ďd������A���{�����n�ƂȂ�㊯��(��ɔB�R�㊯���ɕ���)���u���ꂽ�B�h���͍ŏ��ɓ`�n���S�����`�n���E�v�ے��E�咆�����E���������̎l���𒆐S�ɓ�\�꒬����Ȃ铌�C���ł����w�̏h�꒬�ƂȂ�A���̑啔���̗��Ăł͔ѐ���������A�O�����Y�O�Ƒ��w�ɂ��̂��S���ɂ��̖���m��ꂽ�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���ɑ�������ɂ����Â��A�����̂��˗H�ɂЁU���A�����˂���ɋA�肪���̑ʒ��n�Ǘ��āA�Ƃ܂���}���n�m�S�̂Ȃ܂�����́A�قĂς�̗҂����Ȃ肽��̂ɂ₠��Ƃ��A�₤�₭�O���܂̂��䂭�ւ��ƁA�����͂��A��т��鏗�̂��ց^�_�V�u�����Ȃ����܂��^�_���u���T�Ђς�ȁB���T���͂Ȃ����甑��ׂ����u����Ȃ�T�A���Ƃ܂���u���������׃C(������ׂ�)�v
|
�@ |

 |
�����Ïh(�ʂ܂Â��キ)�O���h���ꗢ��
�@
���C����\�B�{�w�O�A�e�{�w��A���Č\�܌��A�ː����S�O�\�]�A�l���ܐ�O�S�l�\�]�l�B�鉺���Ƃ̕��h�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����ɂĖ݂ȂǂƁT�̂ցA�����͕��̒����₵�ȂЁA�����Ђɂ�����������A�͂Ȃ����̂��āA�Q���Ẩw�ɂ��B���T�ɂĐ摫���₷�߂�ƁA�h�͂Â�̒����ւ͂���v
|
�@ |

 |
�����h(�͂炵�キ)
�@
���C����\�O���B�{�w��A�e�{�w��A���ē�\�܌��A�ː��O�S��\�]�A�l�����S�O�\�]�l�B���h��т̊C�݂��u�c�q�̉Y�v�Ə̂��A�x�m��]�ތi���n�Ƃ��Ēm��ꂽ�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���̂͂Ȃ��ɂ܂���āA����ނƂ��Ȃ��ɁA������傷���ʼn߁A�قǂȂ����̂��䂭�ւ��B���T�ɂĂ�̂��Ԃ�Ђɂ킩��ā@�܂��߂������͂����Â����������ĂЂ��������̂��䂭�ɂ�����@�k���u���T���߂ւ܂��A����Ȃ��݂�������Ӄn�v
�@
���c�q�̉Y(�����̂���)
�@
�x�m�쓌�݂̍��u�̕ӂ������A�������������Z�̏��n�ŁA��������̕x�m�̒��]�͓��C���Ƃ���ꂽ�B
|
�@ |

 |
���g���h(�悵��炵�キ)
�@
���C����\�l���B�{�w��A�e�{�w�O�A���ĘZ�\���A�ː��Z�S�\�]�A�l����甪�S�O�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�ڂČ��g����ł����A�����͋��Ƃ��ӏ��ɂ�����B�������x�m�̎R���ʂɌ��ւāA��������̐�i�Ȃ�B�펟�Y�悠�ւ��@�݂̖��̂����͋��Ƃė��l�̂�����������ċx�₷���@�z�ċg���̉w�ɂ��B�_�Ȃ̒��������A���Â�����F�Ȃ鐺�^�_�ɁA�u���x�Ȃ�����A���B�����E�������A���B�Ă̔т��������A���B����ɂ₭�ƔK�̂��z�����������A���B���₷�݂Ȃ�����A���v
�@
���x�m��̓n��
�@
�n�D�n���B
�@
�w���C�����G�I�сx�u������v��̑P�����Ƃ��ւ�ɁA�]��Z��̐Δ肠��������݂Ėk���@���]��ɋ@�������Ԃ��^�_�͊O�Ɉ�Ƃ��������Ȃ��@�x�m��̂킽����ɂ�����Ė펟�Y���ց@�䂭���͖�����邲�Ƃ���p�ɂ���������Ƃӂӂ���̏M�@����ʼnz����ɁA�͂�������̎R�̒[�ɂ�����A���̂Â��瓹�}���v���F�u�P�����v�́u���v�̌�B���C�������}��Ɂu�����v��Ƃ��ӂɕ��Ƃ��ӎ�����B�����ɑ]��Z��̐Γ�����v�Ƃ���B
|
�@ |

 |
�������h(����炵�キ)
�@
���C����\���B�{�w��A�e�{�w�O�A���Ďl�\�A�ː��ܕS�]�A�l�����l�S���\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�n�m�S�̒|�ɂƂ܂鐝�F���A�₤�^�_�����̏h�ɂ�����(��ҏ㗹)�@�����G�I�ь�҉��@���h�̌�{�w�ɁA���喼�̂����ƌ��ցA����͍��V�̏o��Œ��v
|
�@ |

 |
���R��h(�䂢���キ)
�@
���C����\�Z���B�{�w��A�e�{�w��A���ĎO�\�A�ː��S�Z�\�]�A�l�����S�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���͂Ȃ��̂����R��̂��䂭�ɂ��ƁA�����͂���т��邱�ւ���⏗�u���͂���Ȃ�����A���B�������Ƃ������惒�������A���B����ς��̂���������A���B���x�Ȃ�����A���^�_���u���T�₩�܂������ǂ����@�Ă��鏗�̐��͂��݂���₳�Ă���ূ͔��R��̏h�@������R����ʼnz�A�q��Ƃ��ւ闧��ւ��Bূ��z�h���̖����ɂāA剐l�����ɊC���A�旈��ď��ӁBূɂĂ��炭�����x�߂ā@ূ��Ƃɔ���͂��U��ُ̒Ă〈�ǂ��남�ق��q��̏h�@������F�x(�������͓y��)����ʼnz�A���ǂ�s�قǂɁA��ɑ�J�ӂ肢��������v���F�q��(���炳��)�w���C�������}��x�Ɂu�F�x�R���̘[���q�X�ɉh��鸂𗿗��ĉ��ӂȂ�v�Ƃ���A���̍��A�q��͓��C�����̒��]�Ƃ���ꂽ�B
|
�@ |

 |
�����Ïh(�������キ)
�@
���C����\�����B�{�w��A�e�{�w��A���ĎO�\�l���A�ː��O�S�\�]�A�l����Z�S�Z�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����H�Ŕ킫�A�}�ӂ��������Ԃ��āA���ɂ��ӓc�q�̉Y�A�������ւ̕��i���A�ӂ肤�Â݂Č�������Ȃ��A�����ɓ����������������ɁA�₤�₭���Ẩw�ɂ�����Aূɂ��₵���Ȃ钃�X�ɗ���v
|
�@ |

 |
���]�K�h(�����肵�キ)
�@
���C����\�����B�{�w��A�e�{�w�O�A���Č\���A�ː���O�S�l�\�]�A�l���Z��l�S��\�]�l�B���̍]�K�h�͐������̍`���ł�����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�P���߂͂�����ɂӂ�U���āA�������������ނ������ł����A���U�Ƃځ^�_�Ƃ���݂Ȃ�݂āA�قǂȂ��A�]�K�̂��䂭�������߂���ɁA���T�ɂĉJ���͂ꂯ��@�~���炵�x�m�̍��ԂƂ����������č]�K�ɉJ���ǂ����肽��@�J��݂�����̂Â���A�s���Ӑl�̑������낰�ɁA���炵��n�́A��̉��������܂����A�V�����^�_�^�_�v ���F���炵��n�{�n�̉ו��O�\�Z�т̔��ʂ���ʂƂ���n�B
|
�@ |

 |
���{���h(�ӂ��イ���キ)
�@
���C����\�㎟�B�{�w��A�e�{�w��A���Ďl�\�O���A�ː��O��Z�S���\�]�A�l���ꖜ�l�玵�\�]�l�B�x�{�鉺���Ƃ̕��h�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���͂Ȃ��ɖ펟�Y�k�����傫�ɂ����ɓ��A����ނƂ��Ȃ��ɁA�{���̂��䂭�ɂ��B��`�n���ɏh������āA��������Y������ׂ̂����ւ��Âˍs�B���T�ɋ��q�̂��������ƁT�̂ЁA�傫�ɂ����ݏo���Ă�ǂւ��ւ�A�Ȃ�ł�����Ђ́A���˂Ă��T����т��A���א쒚�ւ������܂�ƁA����������Ƃ��A���́������������āA��ǂ̂Ă�������܂˂����u���V��Ă���������A������A���Ƃ������ɂ����Ăւ����A�ǂ��̂ق����˂Ă���u���{��̕��ł�����܂��k���u�������˂Ă���uূ�����l�ܒ�����������܂��B�Ȃ�Ȃ�n�ł��A�قĂ����܂��₤���k���u�����͂��T�A���u����K�ɂ̂āA���Y�����������낢�^�_�B�ڂ�ূ�肩��K�n�ɑŏ�A�䂭�قǂɁA���̈��{��܂��Ƃ��ւ�́A���א���ӂ̎�O�ɂāA�ʋ�肷���������݂đ�傠��BূɂĔn������f�ɓ��Č���ɁA�����Ɍ����Ȃ�ׂāA�Ђ����邷���U���̉��������A�������̂����ނ��́A���s�̋g�����ɂ��ق悻������B�q�Ƃ��ڂ����������ؖȂɖ�̂�����H�܂Ȃǂ��āA��@�̂������������Ă��Ԃ�A������s�����̏��́A�Đ��̋�ʂ��Ђ�����A�q�l�̐_�ƌ��ւ��́A���ق��͌҈����܂ɂāA���Â���c�������Ȃ�B���T��Ă₢�ɑO�������̋�����A�_�̂����ɂ������Ȃǂ��T����āA�������邭�Ђ₩������B�s���Ӓj���́A�J���Q�̐l�̂��Ƃ��A�X�ɕ�����܂炸�A���ɏ��͌��l�Ȃ��v
�@
�����{��̓n��
�@
���s(����)�n���B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�₪�č��w��ŗ����邪�A�����ǂ肵�����܂����ɁA�قǂȂ����ӂƂ��ւ�ɂ�����Bূ͖��ɂ��ӂ��א�����̖����ɂāA�����̒����A���Â�����ɉԂ₩�Ȃ肿��⏗�u�߂��Ԃ݂������胄�A���B�ܕ��ǂ���������A���^�_���u������A��ӂׁA��邪���������ė�������A���E���T�ł͂��ӂ߂֖k���u���ӂ��^�_�g�������א�̐삲�����ɏo�ނ��Ђāu����ȏO���̂ڂ肩�Ȗ��u���C�B�����܂Ȃ삲���u���͂����ł�����܂��B�₷����炸�ɁA�����̂�\�܂��k���u�����炾�삲���u����ɂ悤�̉J�Ő�����������A�ЂƂ�܂֘Z�\�l���k���u�����͍����삲���u�n������}�A�����Ȃ����g�ł�Đ���ɏo���u�Ȃ�قǁA���������Ȑ��������B�R�����Ƃ��߂ւ�삲���u�i�j���܂��A�T�A�����惒��ނ��Ȃ���g��l����������܂ɂ̂��Đ�ւ��ԁ^�_�Ƃ͂���v
|
�@ |

 |
���ێq�h(�܂邱���キ)
�@
���C�����\���B�{�w��A�e�{�w��A���ē�\�l���A�ː���S�\�]�A�l�����S��\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�g�삲���͂����ɐ삩�݂̂������ق����킽���Ă��ւ�k�u�A���펟���˂ցB��������ӂ��������킽���āA�Z�\�l���d�T�ӂ����A�����@�삲���̌��ԂɂĂ��^�_���ӂ����Ƃ���ւЂ��܂͂�����@�v����z�̂��Ƃɂ�����ɁA�������J�ӂ�o���āA�����܂��Ԏ����Ȃ�������A�����H�Ƃ�o���ł��Â��A�����͂�߂ĂقǂȂ��ێq�̏h�ɂ�����B���T�ɂĎx�x����ƒ���ւ͂���k���u�R�E�т����������Bূ͂Ƃ�T�`�̂߂��Ԃ��́v
|
�@ |

 |
�������h(�����ׂ��キ)
�@
���C�����\�ꎟ�B�{�w��A�e�{�w��A���ē�\�����A�ː��l�S���\�]�A�l�����O�S��\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�g�ł�Ă������䂭�قǂɁA�͂₭���厛�����̂��������������ւāA�����ׂ̂��䂭�ɂ����肯��@�����Ȃ邨���ׂ̏h�ɂ��Ă��肠���ɏo�����铤���Ԃ��ā@�悱�̉w�ɂ�ǂ��Ƃ�āA��̂����܂ł��炭���т̂�������₷�߂���(��җ�)�@���C�����G�I�юO�ҁ@(�O��)ূɂ��̖펟�Y���q�쑽���́A����̐�x�ɂāA�����̏h�ɑؗ��������A������킽��A��Ԃ��������݂�����A���ƂЂƂ��������^�_�Ɏx�x���āA�͂�����𗧏o����ɁA�͂⏔�Ƃ̓��������̋M�ˋ��̂͂��Ђ������Ƃ��A�≮�품��������A���בʔn��ő���A�X���̂ɂ��͂Ђ��܂����A�ӂ�����Ƃ��ɂ����ꂽ�ǂ�s�قǂɁA����ސ���������ցA�����S���������A���q���ɂ�����v
|
�@ |

 |
�����}�h(�ӂ��������キ)
�@
���C�����\�B�{�w��A���ĎO�\�����A�ː���Z�\�]�A�l���l��l�S��\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����蕽�����c����ʼn߁A���}�̏h�߂��Ȃ�ā@�X���̏��̖̊ԂɌ��ւ���͂���ނ炳���̓������̏h�@�����䂭�̓����ɂāA�ӂ낵����悢�Ƃ����ɂ�������A�c�ɂ̂�����A�n�̂͂˂���ɂ��ǂ낫�A�ɂ���Ђ悤���ɂ������ւ�������ƁA�����������܂�̒��ւ��낰�āA�傫�ɂ����Ȃ�A����������āA�c�ɂ���w3���ЂƂ�ւĖk���u�R�m�e�m�߁A�܂Ȃ������G�̍��Ăł������A���ꂨ����u�R�����n�C�A��߂�Ȃ����v
|
�@ |

 |
�����c�h(���܂����キ)
�@
���C�����\�O���B�{�w�O�A���Ďl�\�����A�ː���l�S�Z�\�]�A�l���Z�玵�S��\�]�l�B�����㒬�l�\�ԁA����̐엯�E�얾����s�ɒm�点���r�\�l�����ŋl�߂Ă����B���c�h�t�߂͖��{�̂ŁA���߂͓��c�㊯���u����A�ꎞ�c���˗̂ƂȂ邪�A�����Z�N(1794)����͏x�{�㊯���̎x�z�ɓ���o���w�����u���ꂽ�B
�@
�w���C�����G�I�сx�uূ��o�čs�قǂɁA����̎�O�Ȃ�A���c�̉w�ɂ����肯��ɁA��z�ǂ��o�ނ��ЂāA�u����Ȃ����A���̂�܂����u�����ܐ삲�����B�ӂ��肢����ʼnz���삲���u�n�C���������ɁA�������삾��ŁA��������܂���A���Ԃ�Ȃ��B�@��ł�炸�ɁA���ӂ���Ŕ��S�������܂����u�Ƃق����˂ցB�z��V������A����߂ւ��A���S�悱���������܂����v
�@
������̓n��
�@
��z�l���ɂ����s(����)�n���B���c���Ƌ��J���ɂ��ꂼ����h�̉͌���������A�쏯���̉��A��z��l�̋l�߂�����݂�����z�l�����Ǘ������B���̓n���͏\�����I���܂ł͐�z�l���ɗ���Ȃ������n�����嗬�ł��������A���l�̑����ƂƂ��ɐ�z��������l��������A������������B�����N�ԍ������z�l�����ƂƂ���҂�����A���l�ɖ@�O�Ȑ�z���𐿋�����Ȃǂ̕s�@�ȍs�ׂ��ڗ��悤�ɂȂ������߁A���\��N(1696)�ɐ쏯�����C������A��z�̓����ƊǗ����s����悤�ɂȂ��z���x���������B�������Đ�z���K�͐��Œ�߂���藿��(��D)�ƂȂ����B���K�͍ł��ȒP�Ȍ��Ԃ���D�ꖇ�ŁA�������ĕ⏕�l�����t���ƓK�v�ƂȂ�B�ō������r��ɂȂ�Ƒ�D�O�\�Ɛ�z�l���\�Z�l�A����蒣�l���l�l���́A���v�\�̐�D���K�v�ɂȂ����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�펟�Y���q�k��ূ��̂���A����������ɂ����茩��ɁA�����̋M�˂����Ԃ��Ȃ��A����̂����𑈂Љz�s���ɁA�ӂ�������i�Ƃ肫�͂߂āA�@��ɑŏ挩��A����̐������܂��A�ڂ�����ނ���A���₢�̂������̂Ȃ�Ƃ����ӂقǂ̋������A���Ƃ��ɂ��̂Ȃ��A�܂��ƂⓌ�C���̑�́A�����͂₭�Η���āA�킽��ɂȂ�ޓ�Ȃ���A�قǂȂ������z���Ę@������肽���������͂��Ȃ��v
|
�@ |

 |
�����J�h(���Ȃ₵�キ)
�@
���C�����\�l���B�{�w�O�A�e�{�w��A���Č\�ꌬ�A�ː���]�A�l���l���S���\�]�l�B�h��̒����́A����̓n����ƂȂ���h(�͌���)�ɑ����Ă������B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�z���������ċ��J�̏h�ɂ�����B�����̒��₨��ȁu���₷�݂Ȃ����܃A���^�_���������u���ǂ肩���̂Ă����₲�����k���u�R�E�펟�����͂ǂӂ����u�C���A�C���Ȃ��B��߂ւ̂�Ȃ�̂Ă������k���u����Ȃ����܂ŏ�ӂ��v
|
�@ |

 |
������h(�ɂ��������キ)
�@
���C�����\���B�{�w��A�e�{�w��A���ĎO�\�O���A�ː��S�Z�\�]�A�l�����S�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����荟�������A����̉w�ɂ����鍠�A�J�͎���ɂ悭�Ȃ�āA���͂ЂƑ����䂩�ꂸ�B����������ւ킩�ʂقǁA������ɍ~���炵����A�����ĉ��̌��ɂ��T���ݖ��u���܁^�_�����B�����Ă��ɂӂ�n�^�_�k���u�͂Ȃ�̖�����A����߂ւ��B���܂Ől�̂��ǂɂ��Ă�����߂ցB�i���g�펟����A����͉z�����A���ӂ��̏h�ɂƂ܂낤����A�˂ւ����u�i�j�Ƃ��Ƃ����ӁB�܂����c(�ߌ��)�ɂ�A�Ȃ�߂ցB�����甑�Ă܂���̂��v
|
�@ |

 |
���|��h(�������킵�キ)
�@
���C�����\�Z���B�{�w��A���ĎO�\���A�ː���S�Z�\�]�A�l���O��l�S�l�\�]�l�B�鉺���Ƃ̕��h�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�قǂȂ�������̏h�ɂ�����B�_�@�̒�������ȁu���߂��惒������܃A���B���Ƃ���₭�ƁA���卪�̂��������̂�������܃A���B���̂���Ύς�������܃A���B���₷�݂Ȃ����܃A���^�_�v
|
�@ |

 |
���܈�h(�ӂ��낢���キ)
�@
���C�����\�����B�{�w�O�A���Č\���A�ː��S��\�]�A�l�����S�l�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����ł����A�͂₭���Ȃ���̂��Ăɂ��B���T�͉Ԃ���������Ă����ȂӁ@�����ɂЂ炭������̎}�Ȃ�ł݂Ȃ߂��^�_�ɂ����Ԃ����@���Ȃ��܈�̏h�ɓ���ɁA�����̒����������A�����̗��l���́^�_���̂݁A�H���Ȃǂ��Ă�肯���펟�Y���q���ā@���T�ɗ��Ă䂫�T�̕���ӂ��ꂯ��Εz�܂̂ӂ����̒����@�����䂭�͂Â���A������̂ƌ��ւāA�V���̕z�q�ɋ₲����ւ̘e���������A�ԐF���т̂��₤�������������H��������j�A���ЂƂ��āA���ƂɂȂ肳���ɂȂ�v
|
�@ |

 |
�������h(�݂����キ)
�@
���C�����\�����B�{�w��A�e�{�w��A���Č\�Z���A�ː����\�]�A�l���O���S�O�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�݂��̂͂��������킽��A�傭�ڂ̍�����ւāA�͂₭�����t�̏h�ɂ�����k���u�A�T�����тꂽ�B�n�ɂł��̂�ӂ��n�����u���܂����A���܃A���炵�₢�܂��ʂ��B�킵�ǂ��͖��ɏo�����܂���ŁA�͂₭���ւ肽���B�₷�����������B�T�A�̂炵���܂����u�������̂�˂ւ��������u�����Ώ�ׂ��g�n�̂������ł��āA�k�����T���n�ɂ̂�B���̔n�����́A���������ɏo����Ђ₭������ցA����Ȃ���u�R���n�m�ǂ�AূɓV���ւ̋ߓ������邶��A�˂ւ��n�m�u�A�C�������ւ����炵���ƁA�뗢������������������n�k���u�n�͂Ƃ���ʂ��n�m�u�C���l�B�������ł������gূ����Y�͂ЂƂ肿�����̂ق��ւ܂���B�k���n�ɂĖ{�����䂭�ɁA�͂₭�����������ł킽��A���₳�������̂��Ăɂ��v���F�݂��̂͂�(�O���싴)�֓c�S�c����(���֓c�s)�̑��c��ɉ˂������B
�@
���V����̓n��
�@
�n�D�n���B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�͂Ȃ��̂����A���Ȃ��V���ɂ�����B����͐M�B����̌ΐ����o�A���̐����V���A�������V���Ƃ��ӁB�M�킽���̑�͂Ȃ�B�펟�Y�����ɑ҂����āA��ɂ��̏������������Ƃā@����͉_���o�ėقǂȂ݂̂����܂��V���̐�@�M��肠����Č���̒��ɂ�����B�����͍]�˂ւ��Z�\���A���s�ւ��Z�\���ɂāA�ӂ�킯�̏��Ȃ�A���̒��Ƃ��ւ�悵�v
|
�@ |

 |
���l���h(�͂܂܂��キ)
�@
���C�����\�㎟�B�{�w�Z�A���ċ�\�l���A�ː���Z�S��\�]�A�l���ܐ��S�Z�\�]�l�B�鉺���Ƃ̕��h�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����肩����(����)�A��t�V�c�����������A�������߂��Ȃ肽�鍠�A�l���̂�Lj��o���ЂĂ�Lj��u���V���Ȃ������A���Ƃ܂�Ȃ�A����ǂ�����А\�܂��k���u���̂��T�̂�����Ȃ�Ƃ܂�₹����Lj��u�����Ԃ���܂����u�Ƃ܂邩��т����͂��邩��Lj��u�����܂����Ŗk���u�R���͉������͂����Lj��u�n�C�����̖������P�ł������܂����k���u���ꂪ�����B������肶��A����߂ւ�Lj��u�n�C����ɂ�����A�����̂�ӂȂ��̂�������Ђ܂��Ėk���u���邪�Ƃ��ӂɁA����ɂ₭�̂��炠�ւ����u�}�A���邭���Ă��������T�B���̂����S�P���ɂ́A���Ƃ͂肱�܂��ւ�Lj��u�R���n���Ȃ��Ƃ��������A�n�T�T�T�T�B���ɂ��ӂ܂���܂������u�������ӂ͂����B�v�Ђ̊O�͂₭������ց@���^�_�Ƃ���ނɂ�ė��߂ӂ�����ꂵ�͂܂܂̕��@��Lj������ւ����ʂ��āu�T�A�^�_�������A���ǂ̂Ă�����u���͂₭������܂����B�\��������A������Ɠ����A����u�C������Ȃɑ��͂悲������ʂĂ�����u����Ȃ炷���ɂ��ӂ�ɂ��߂��Ȃ����܂��v
|
�@ |

 |
������h(�܂��������キ)
�@
���C����O�\���B�{�w��A�e�{�w��A���ē�\�����A�ː��ܕS�l�\�]�A�l�����l�S���\�]�l�B�O�������B��ƕl���Ɉ͂܂ꂽ�n�ŁA���т��ѕ����Q�̔�Q�ɂ��������߁A����O�N(1657)�A���{�͐V���֏���s�Ɖ��B�㊯�ɖ����ĐΊ_�ŏh�͂����邪�A���̌�������Q�̔�Q�͐₦���A�V�a��N(1682)�ƌ��\�\�Z�N(1703)�Ɂu�h�͂݁v�̉����H�����s���A����h�͂قڑS����������ڂ̐Ί_�Ɉ͂܂ꂽ�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�قǂȂ��@���A�ڈ�ނ��ʼn߁A����̉w�ɂ�����v
�@
�����̓n��
�@
�l���͂��Ƃ��ƒW���ŁA����l���삪���B��ɂ������ł��āA���q����ɂ͕l����ɕl�������˂���A���̂����Ƃɂ͋��{�h�������ē�����Ă����B�������A�������N(1499)�̒n�k�ƒÔg�Ő�͖��܂�A�y�n���זv���ČƊC���Ȃ����Ă��܂��B���ꂪ���ŁA���̌��ʁA���{�h�͔p�ꕑ�l�̑Ί݂̐V���ɐV���ɏh������A����E�V���Ԃ�D�Ō��B���̓n�D�̓n�����u���̓n���v�Ƃ����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u����肠���܂ň뗢�̊C��A�捇�Ԃ˂ɂ����̂�킽��B���ɂ������̋C���́A�D�������Ё^�_�̎G�k�A�����ɂ����荇�A�Ђ́T����ŋ����䂭�قǂɁA�ڂĂȂ��킽��āA�捇�̐l�^�_�V���͂Ȃ������т�A�߂��^�_������ɕI���������āA���˂Ԃ�����������A�����̕��i�Ɍ��Ƃ�āA���ّR�Ƃ��Ă����L�v
|
�@ |
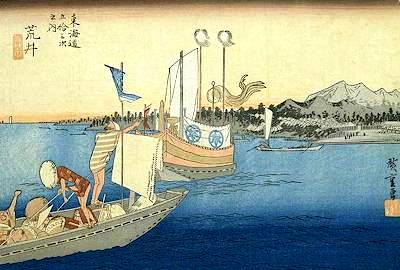
 |
���V���h(���炢���キ)
�@
���C����O�\�ꎟ�B�{�w�O�A���ē�\�Z���A�ː����S��\�]�A�l���O��l�S���\�]�l�B�V���֏��݁B���̒n��̂��Ă������쎁�́A���̐V���h�̓n�D��𗘗p���Ċ֏����\�����B���얋�{���h�w�����������A���{�͂��̐V���h�̊֏����c���A���ɐ�������̓S�C�̓���������܂邱�ƂƂȂ����B�V���h�Ɋ֏���݂������Ƃ���u���ؓn�D�v�͐V���h���P�Ƃʼn^�c���A�V���h�͂��̓n�D���ŏ��������A����̕���h�͕l���h�܂ł̕Ќp�ƂȂ�����I�ɋꂵ�������Ƃ����B�܂��A���̐V���h������h�Ɨ��n�����͂��܂�ς�炸�A���т��ѕ����Q�ɔY�܂���A���\�\��N(1699)�̖\���J�ł͊֏�����j���A�S��\�˂������A�S��\��˂������Q���A�֏��Əh�̈ꕔ���ړ]�����B���̌��ʁA����E�V���ԓ�\�����������n�D���ꗢ�ɉ������Ă���B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�قǂȂ��ӂ˂͂����̂͂܂ɂ�����A�̂荇�݂ȁ^�_�ӂ˂�������A���֏���ʼn߂���B���Y�k�����ӂ˂�������@������̂�o�����鍡�Ƃ܂��T���Ђ܂������ɂ����@����ɂĂ��A���̂��́T�Ȃ��ꂽ��́A�O�㖢���̂͂Ȃ��̂��˂ƁA�݂Â���ŏЂT�k���@�|�����āT���܂Ђ��j�Ԃ育���Ԃ��Ƃ͂��ӂ��͂�܂��@������ӂ���́A�������̂��䂭�Ɏ����݂��͂��Ă������₷�߂ʁB(�O�җ�)�@�����G�I�юl�ҁ@(�O��)���C���ɖ����T�鍡�̏ɂȂ�B���̂��ݖ����̔�R�̉����A���L���܂��ʂ��o�A������C�゠�����Ȃ肽�肵���A���\�N���A���̖��ɂ��āA�C��ɐ����̍Y�������A���Ă��ӂ��A�����n�D�̓�a�������Ћ��͂肵�A��b�̗L�������ɁA���a�炬�Q��Ȃ�Ă킽��ɓ�Ȃ��A���̖펟�Y���q�������Aূ�ł킽��āA�����̉w�Ɏx�x�ƁT�̂ցA�����̂��₫�ɕ����ӂ��炵�A�x�݂��ɁA���ɂ������̋M�ː�ԂȂ��A�M��}�����l�́A��������ɏo�ӂ˂���Ӑ��ɂ�Ă͂���A�≮�ւ��T��ɗ̂͂����₩�܂����A�ʖ����ӂ�T�n�����ɂ��ẮT����v
|
�@ |

 |
�����{��h(���炷�����キ)
�@
���C����O�\�B�{�w��A�e�{�w��A���ē�\�����A�ː��Z�S�\�]�A�l����玵�S�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���̂����͂₭�����炷���̉w�ɂ�����B�͂��肭���̂��≮���A�����Ăɏo��т�������āA�펟�Y���ց@�o���̊�̂��낫�����ɂ߂ŁT���Ȃ����������̏h�@���h�����������A���Ȃ�������ɂ������T��ɁA���Ȃ�k�͎R�U���ɂ��āA��ɑ��C���X�ƌ��ցA��i�܂��Ƃɂ��ӂ���Ȃ��v
|
�@ |

 |
�����h(�ӂ����킵�キ)
�@
���C����O�\�O���B�{�w��A�e�{�w��A���ĎO�\�����A�ː��O�S��\�]�A�l����l�S�Z�\�]�l�B�����\���̏��K�͂ȏh��B���ׂɏ鉺���ł�����傫�ȏh�ꂪ�L��A���̏h�ɔ��܂闷�l�����Ȃ��A�h��̌o�c���ꂵ���{�w���o�c�I�ɋꂵ������������A�Ђɂ��Ď��ȂǂŖ{�w�����̍Č����ł����A���P�E�̖{�w�E���㓡�ƁA�g�щƁA�n��Ƃƕς�����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����ł�炢�Ă䂭�قǂɁA����Ƃ��ӂɂ�����Bূ͉��]�O�͂̂������ɂċ�����B�펟�Y�n���ɂĂ�߂�@���B�ւ��������鋴�Ȃ�ɂ��͂̍��Ƃ��ӂׂ��肯��@���Ȃ��ӂ���̉w�ɒ����B���Ƃ���Ɩ��ɁA���߂��������Ȃӌ����@�����͂��͂˂ǂ��邫���͂߂��₱��d⦂̂ӂ���̏h�@�����̒������ƂɁA���l���������ČĂ��鏗�u���x�Ȃ���܃A���B�������Ȃ��z����������܃A���B�����̍�ŁA���ł����тł�������܃A���v
|
�@ |

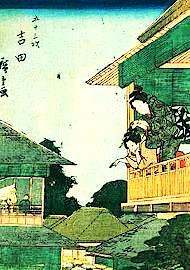 |
���g�c�h(�悵�����キ)
�@
���C����O�\�l���B�{�w��A�e�{�w��A���ĘZ�\�܌��A�ː����S��\�]�A�l���ܐ��S���\�]�l�B�鉺���Ƃ̕��h�B����͐ԍ�h�܂Ōp�����āB
�@
�w���C�����G�I�сx�u�ӂ����^�_�V�ɉׂ��Ђ������䂭�܁T�ɁA�₪�ċg�c�̂��䂭�ɂ�����@���l���܂˂����̂ق�������ূ��悵�c�̏h�̂�˂����@�����䂭�͂Â���A�������҂Ƃ͌���ꋤ�A�����������ӂ�����ׂ�荇�ܘZ�l�A�����ɂ͂Ȃ��čs�v
|
�@ |

 |
������h(���䂵�キ)
�@
���C����O�\���B�{�w��A���ĘZ�\�A�ː��O�S�\�]�A���S��\�]�l�B����͋g�c�h���p���ʂ��A��肾�����p�����Ă��B���̌���h�Ɨׂ̐ԍ�h�̊Ԃ́A�\�Z���ƒZ���A�`�n����ʂ̌\�D�ł͂Ȃ���\�ܕD�Âԍ�h�ƕ��S����Ќp���̏h�w�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�펟�Y���Ƃ�肽�ǂ�䂭�ɁA�قǂȂ�����̂��䂭�ɂ��肽�邱��͂͂��ɂ���āA�����͂��o����Ƃߏ��A���Â���߂�����Ԃ肽�邲�Ƃ��A�ʂ肽�Ă��邪�A���ł��Ђ��Ă��邳����A�펟�Y���ւ₤�^�_�Ƃӂ肫��s������Ƃā@���̊�łƂ߂��ĂȂ��Ώh�̖��̌���邳�ꂢ�Ɠ��čs��@�펟�Y���q���܂�ɑ��炯��A�损���͂Â�̒��X�ɍ�����������ɁA���邶�̔k�X�u�A�C���A�܂���܂��펟�u���V�ԍ�܂ł͂��ӏ������̂U�u�A�C���\�Z�������邪�A���܂ւЂƂ�Ȃ�A���h�ɂƂ܂炵���܂��B�������̏����ւ́A��邢�ς��o���āA���l�O���悭������\���n�v |
�@ |

 |
���ԍ�h(�����������キ)
�@
���C����O�\�Z���B�{�w�O�A�e�{�w��A���ĘZ�\�A�ː��O�S�l�\�]�A�l����O�S�]�l�B���肾�����p�����āA���͓���h���p���ʂ����B����h�ƍ��킹�Ĉ�h�̏����ȏh�w�����A���l�̈����~�߂Ŕѐ����𑽐������Ă������ƂŖ������h�ƂȂ����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u��O�ڎ�ʂ��Ђ��Ƃ��A�����������������ւ܂͂��Ă���B���������������A�킴�Ƃ����Ă���Ɩ펟�u�T�A�^�_�����ւ��Ă��邯�^�_�g�k�������T��A�����납��Ƃ�ւāA�����ā^�_������̂��䂭�ɂ�����B�͂₢�Â�̂͂�����ɂ����₭���Ƃ߂āA���ǂɂ������鏗�����ւ��B���Y�́A��ǂ���ނ��Ђ̐l���A���͂�o���ӂȂ��̂ƁA��������k���u�R�E�펟����A���T������ɉ��Ă���ȁB�O���̂�肢�B�l�������^�_���Ă�肢�͂Ȗ펟�u���T����������ցB�n�e�h�͂ǂ��������k���u�i�j����͂��T�ɂ����̂��A���ꂪ�����ցA��ǂ��ƂĂ������̂��v
|
�@ |

 |
������h(�ӂ����킵�キ)
�@
���C����O�\�����B�{�w��A�e�{�w��A���ĎO�\�Z���A�ː��O�S�]�A�l�����S�\�]�l�B��������h�܂Ōp�����āB
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����ē���ɂ�����B�_�@�̒����A�����Ƃɐ�����邵�A�啽�M���݂������ɂȂ�ׂ��āT�A���l�̂������ƁU�ށB�펟�Y���q�@��ő��̂ނ炳������͌����ɂԂ��Ƃ����铡��̏h�@�����荟�h�����������A�o�͂Ȃ�̂��₵���Ȃ钃�݂��ɋx�݂Ėk���u�Ȃ��A�����Ă��ɂނ������Ԃ�B������f���͂���߂ւ����ቮ�̂U�u�n�A����͂�����ʁB�������܂������v
|
�@ |

 |
������h(�����������キ)
�@
���C����O�\�����B�{�w�O�A�e�{�w�O�A���ĕS�\�A�ː���ܕS�Z�\�]�A�l���Z��l�S��\�]�l�B�鉺���Ƃ̕��h�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�ł��ЂT�s�قǂɁA���Â�����߁A���̍]��ӂ���ł��ւāA�啽��ɂ�����@�݂ɐ��Ӌڂ̂����݂ɏ����܂Ő��ɂЂ����啽�̐�@������啽�����ߍs�قǂɁA����̉w�ɂ�����B���T�͓��C�ɖ����T��ꏟ�n�ɂāA��ɓ������A�����̒����A���Â�����Ɍ��ւ���(����)�@���Y������o�āA���܁^�_�V�̂���������ǂ���₭���B�펟�Y�k���A���������̂Ă������āA���Y�����̂��炵��n�ł��ւ�����������ƁA�ł��ЂȂ���@�O������̋�ɂ�����A��Ȃ艪����낵�䔃�ɗ��ʂ�@�����Ăӂ���������𗧏o�A�h�͂���̏��t���ł��ցA��̂͂��ɂ�����v
|
�@ |

 |
���r��h(���肤���キ)
�@
���C����O�\�㎟�B�{�w��A�e�{�w��A���ĎO�\�܌��A�ː���S��\�]�A�l����Z�S��\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u���c�C����蔼������k�̕��ɁA���ɂ����ӁA���c���̋��Ղ��v�Ђā@���c�͂��̌ÐՂ���ނ����^�_������ʒp���������Ȃ�@�قǂȂ��r��̉w�ɂ�����v
|
�@ |

 |
���C�h(�Ȃ�݂��キ)
�@
���C����l�\���B�{�w��A�e�{�w��A���ĘZ�\�����A�ː����S�l�\�]�A�l���O��Z�S�l�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����肷�����݂����͂�ߍs�قǂɂ͂₭���Ȃ�݂̂��䂭�ɂ�����@���l�̂������Ί��ɖC�������T�����ڂ�̖����Ȃ�@����������ēc�����������킽��A�����ł�ω����ɂ�����v
|
�@ |

 |
���M�c(�{)�h(����(�݂�)���キ)
�@
���C����l�\�ꎟ�B�{�w��A�e�{�w��A���ē�S�l�\�����A�ː�����S��\�]�A�l���ꖜ�O�S�l�\�]�l�B���C���͂�������C��n���ČK���Ɍ������B���̂��ߑD�҂��ŗ��܂�l�������A�܂��M�c�_�{�̖�O���ł����鎖����A���C������̗��Ă̐����ւ�h��ƂȂ����B
�@
�w���C�����G�I�сx�u������Ƃב��A�R�������A��l�˂����������A�₤�₭�{�̏h�ɂ����肵���́A�͂������O�ɂāA�_�@���Ɩ��ɁA�q���ƁU�ނ�o���̐������B�u���Ȃ������A���Ƃ܂肶�₨�܂��B����������Ƃ킢�Ă��܂��B���������₭�͂��܂���B���Ƃ܂�Ȃ���܂��^�_�v
�@
�������̓n��
�@
�{����K���̖��܂őD�ňɐ��p�����f���镶���ʂ�̊C���B���݂͖��ߗ��Ă��Ĉ�т͗������ƂȂ��Ă��邪�A�����͂܂��C���[�������Ă��āA���̎����̍q�C���������l�́A���H�������܂ōs���A��������ؑ]����M�ʼn����ČK���ɓ������B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�o�ӂ˂���Ԃ��ցu�ӂ˂��o�郄�A�C�^�_���Ƃ���ǂ�̏��������ɂ�����u���V����܈�Ԃӂ˂ł��܂��B�䂺��������܂���펟�u���C�^�_�k���T�A������g�ӂ���͂����o�āA�萅���ӓ�������o���Ђ��܂ЁA���ꂱ�ꂷ�邤���A��ǂ̂Ă�����u���������͂�ӂ�����܂����B�M���ē��������܂���k���u����͌��J�A�T�A�펟����o�����₹���g�����^�_�ɂ��������āA�����Ă̕��֏o������B��ǂ̏��ڂ��A����ȁu�䂫�����ӁB����������ɖ펟�u�A�C�����͂ɂȂ�₵���g���Ƃ܂��Ђ��ĂӂȂ֍s�A�Ă����䂱�T�܂ł����藈��u����ǂ�����A���ӂ��肳�܂���A���݂̂܂����펟�u�Ƃ��ɂ킷�ꂽ�B��Ă����䂳��B�[�ׂ��₭�����̂��̏��ւ̒|�̂T�͂Ă�����u�z���j����Ƃ��炵�Ă����܂����ɁA�h������Ă܂��肵�悩���g�Ă����䂩�̒|�̂T���Ƃ�ɂ��ւ�B���킽���D�A�����̂������₤�A��l�܂֎l�\�ܕ��d�T�A���O�ʉׂ̂���݂̂Ȃ���^�_�V�ɂ�����͂�ЁA�ӂ˂ɂ̂�B���Ƃ��Ă�����|�̂T���Ƃė�����u�T�A�^�_���q���܂����ւȂ��܂����k���u�Ȃΐ��|���펟�u��������Ă��ăi�A�Ƃ�炩���̂��B�悵�^�_�B�C����Ă����䂳��A�傫�ɂ����́B�T�A���ő��v���B�n�T�T�T�T�@���̂Â���F�炸�ƂĂ��_��܂��{�̂킽���͘Q�����Ȃ��@�����j������A�捇�݂ȁ^�_�����݂����A�₪�đD����o���āA�����ɔ��������A�C����͂��邱�Ɩ�̂��Ƃ��A����ǘQ���Ђ炩�Ȃ�A�D���v�Ё^�_�̎G�k�ɁA�����̂������˂��͂Â�T����A�����ɏЂ́T����s�قǂɁA�����ȂЏM�A���������ƂȂ��������Ђāu���̂܂����ȁB�߂��Ԃ��₫���āA���悢���ȁB�Ȃ�Â��ł߂����͂����ȁ^�_�v
|
�@ |

 |
���K���h(����Ȃ��キ)
�@
���C����l�\�B�{�w��A�e�{�w�l�A���ĕS��\���A�ː����ܕS�l�\�]�A�l�����甪�S�l�\�]�l�B�h��̒����͓�\�Z���ŏ鉺���Ƃ̕��h�B�K���˂̏鉺���Ƃ��Ĕ��W���A�ɐ��_�{�̈�̒���������悤�ɂ�������ɐ��H����ɉ��сA�`���������ʂ̗v�n�ł��邽�߁A�{�Ɏ������Ă̐��������B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����͂₭���M�͂���Ȃ̂����ɂ�����̂荇�u�������^�_�B���ւɂ����ʂꂽ��A�M�͂T���Ȃ��K���ւ����B�߂ł����^�_�g�݂ȁ^�_�����肠����āA�����䂭�ɂ�낱�т̎����݂��͂��ʁB(�l�҉���)�@���C�����G�I�ьܕҏ�@�{�d�卪�̂ӂƂ������Ă��{���́A�ӂ�ӂ��̔M�c�̐_�̎��Ⴗ�A�����̂킽���Q�䂽���ɂ��āA�����̓n�D��Ȃ��A�K���ɂ�����x�т̂��܂�A�߂��Ԃ̏Ĕ��Ɏ����݂��͂��āA���̖펟�Y���q�쑽���Ȃ���́A�₪��ূ𗧏o���ǂ�s�v
|
�@ |

 |
���l���s�h(������������キ)
�@
���C����l�\�O���B�{�w��A�e�{�w��A���ċ�\�����A�ː��甪�S�\�]�A�l������S�\�]�l�B
�@
�w���C�����G�I�сx�u�����荟���𗧏o�A�͂�������ʼn߁A���c�Ƃ������ɂ����肵���A�l���s�̏h���o���Ђāu����͂��͂₤�������܂��B�킽��������ǂ������̂ݐ\��܂��펟�u�����A�щ��֍s�₷�h���u�C�����[�́A���喼���܁A���ӂ������炨�Ƃ܂�ŁA�щ��͗��ƂƂ��A���������ł�����܂�����A�킽���������ɂ��Ƃ܂艺����܂��g���ӂ͂����Ȃ�B�䏬�g���܂̂��Ƃ܂�ŁA���h�͂�Â��Ȃ�ǂ��A��������T���ĂɁA��Lj��킪�����ւƂ߂�Ƃ��邯����₭�Ȃ�B�ӂ���Ƃ��ڂ�Ȃ�܂��ƁT�����ЂĖ펟�u����Ȃ�A�����܂̏��͂�����łƂ߂��Lj��u�n�C����͂����₤�Ƃ��펟�u�䂤�ׂ͋{�̕����ɂƂ܂����A�Ƃؚ��ɂ����B�S�\�ŐC������Ă߂������͂��邩�B�����Ď����َq���o��������A�R�����A���܂Ă�����߂ւƁA�ʂɒ�����S������̏��A��ς���Ȃ���A�傫�Ɉ��������B�����܂̏������̂���Œy�����邪���T��Lj��u�������܂�܂����g����^�_�͂Ȃ��Ȃ���ł�āA�䂭�Ƃ��Ȃ��Ɏl���s�̂ڂ��Ȃɂ�����A��Lj����������āu�T�A���ł�����܂��B�R�����Ƃ܂肳�Ȃ����ǂ̏��[�u���͂₤�����Ȃ����܂����g�������̂����A�ӂ���͂�炶���Ƃ��Ȃ��猩�܂͂��A�����Ăނ����낵���h�ɂāA�������ɁA���T�����ւĂ悱�ɂ����݂��邺�ȂƁA���͂ꂩ�T�肵�ւ��̂��邤���Ȃ�(����)�͂���{�̍��킽�鐺�^�_�V�A�n�̂��ȁT�������Ăɂ����ցA�펟�Y���ւ������A�����������o�Ďx�x�ƁT�̂ցA�₪�č����䂭���������Â�Ƃā@�₤�^�_�Ɠ��C�������ꂩ��͂͂Ȃ݂̂₱�֎l���s�Ȃ�@�������_�c����ł����A�Ԗx�ɂ������T�肽��(����)�ŋ����s�قǂɁA�͂₭���Ǖ��ɂ�����v�]�˂𗧂����펟�Y���q�A�쑽���̒������́A���̒Ǖ�����ɐ��H(�Q�{��)�ɓ��蓌�C���ƕʂ��B���̐�A��l�͈ɐ��Q������܂���Ƌ��E���ɗV�Ԃ��A���̓��͏������đ�a�H��ʂ�A�F�����畚�������ĕ����X����ʂ��ċ��ɓ������B���̌�A��g�ł���ɗV��ŕG�I�т��I���Ă���B
|
�@ |

 |
���Ζ�t�h(�����₭�����キ)
�@
���C����l�\�l���B�{�w�O�A���ď\�܌��A�ː���S�l�\�]�A�l����S��\�]�l�B
|
�@ |

 |
������h(���傤�̂��キ)
�@
���C����l�\���B�{�w��A�e�{�w��A���ď\�܌��A�ː���S�\�]�A�l�����S�\�]�l�B |
�@ |

 |
���T�R�h(���߂�܂��キ)
�@
���C����l�\�Z���B�{�w��A�e�{�w��A���ē�\�ꌬ�A�ː��ܕS�Z�\�]�A�l����ܕS�l�\�]�l�B�鉺���Ƃ̕��h�B
|
�@ |

 |
���֏h(�������キ)
�@
���C����l�\�����B�{�w��A�e�{�w��A���Ďl�\�A�ː��Z�S�O�\�]�A�l�����S�l�\�]�l�B
|
�@ |

 |
���≺�h(�����̂������キ)
�@
���C����l�\�����B�{�w�O�A�e�{�w��A���Ďl�\�����A�ː��S�\�]�A�l���ܕS�Z�\�]�l�B
�@
���鎭��
�@
�������A����ƂƂ��ɓ��C���̎O���̈�ɐ�����ꂽ�B
|
�@ |

 |
���y�R�h(����܂��キ)
�@
���C����l�\�㎟�B�{�w��A���Ďl�\�l���A�ː��O�S�\�]�A�l�����Z�S��\�]�l�B |
�@ |
 
|
�������h(�݂��������キ)
�@
���C����\���B�{�w��A�e�{�w��A���Ďl�\�ꌬ�A�ː��Z�S��\�]�A�l�����Z�S��\�]�l�B�鉺���Ƃ̕��h�B
|
�@ |

 |
���Ε��h(�����ׂ��キ)
�@
���C����\�ꎟ�B�{�w��A���ĎO�\�A�ː��l�S�\�]�A�l����Z�S�]�l�B
|
�@ |

 |
�����Ïh(�������キ)
�@
���C����\�B�{�w��A�e�{�w��A���Ď��\�A�ː��ܕS���\�]�A�l�����O�S�\�]�l�B
|
�@ |

 |
����Ïh(�������キ)
�@
���C����\�O���B�{�w��A�e�{�w��A���Ď��\�ꌬ�A�ː��O��Z�S�\�]�A�l���ꖜ�l�甪�S��\�]�l�B�k���X�������A���i�̐��^�̗v�`�Ƃ��ĕ������W�ς�����ʂ̗v�ՂŁA��Â̒��ɂ͉���˂�F���ˁE���{�̑����~���������B�h��͖k���X���̕���_����������ɂ����Ă̒ʏ́u�����v�ɖ{�w�◷�Ă��W�����Ă����B�܂��A���ւ̕����̗A�����_�ł�����A�Ԃ̋��Ԃ��ʂ����߁A��ÁE���Ԃ̊X���ɂ͎ԗւ̕��ɍ��킹�ĎԐƌĂ�镽�������~���l�߂��Ă����B
|
�@ |

 |






 �O�l���������{�l
�O�l���������{�l





























































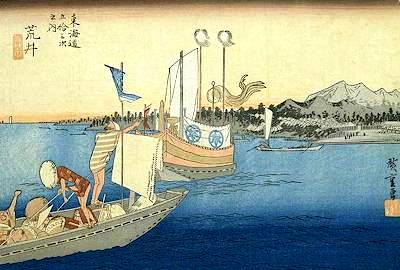






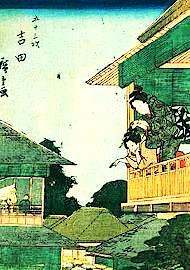















































































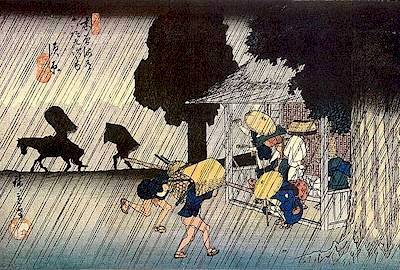





 �@
�@














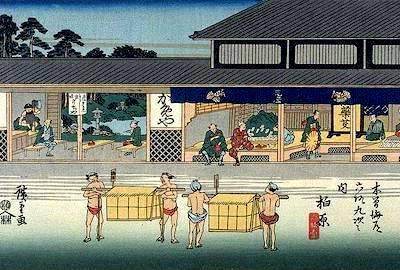









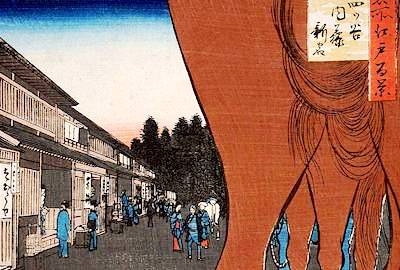

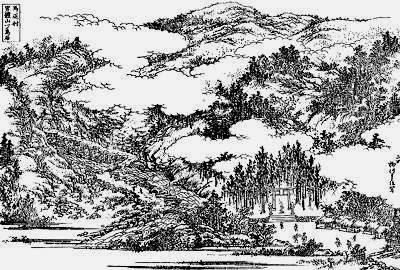 �j�̎R�@
�j�̎R�@ �����̑�@
�����̑�@