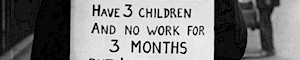 �@ �@
 �@ �@
 |
  
|
| �����E���Q 1 |
�@ |
|
���E�I�K�͂ŋN����o�ϋ��Q(world economic crisis/panic)�ł���B���鍑�̋��Q�����X�Ƒ����ւƔg�y���A���E�I�K�͂ōL���鎖�ۂ𐢊E���Q�Ƃ����B���E���̗�́A�N���~�A�푈���I���������ɍ������i���}���������Ƃɂ��1857�N�ɋN������1857�N���Q�ł���B��Ԋ��ɏd�v�Ȉʒu���߂���̂Ƃ��āA�ʎj�I�ɂ�1929�N�Ɏn�܂������E�勰�Q�������B�勰�Q�Ƃ��B
|
���w�i
��ꎟ���E����A1920�N��̃A�����J�͑��ւ̗A�o�ɂ���Ĕ��W�����d�H�Ƃ̓����A�A�ҕ��ɂ�����̊g���A���[�^���[�[�V�����̃X�^�[�g�ɂ�鎩���ԍH�Ƃ̖��i�A���[���b�p�̔敾�ɔ����ΊO�����͂̑��ΓI�㏸�A���n��ւ̗A�o�̑����Ȃǂɂ���āu�i���̔ɉh�v�ƌĂ��o�ϓI�D������ɓ��ꂽ�B
1920�N��O���Ɋ��ɔ_�앨�𒆐S�ɗ]�肪���܂�Ă������A���[���b�p�ɗA�o�Ƃ��ĐU����������ߖ��͔������Ȃ������B�������_�Ƃ̋@�B���ɂ��ߏ萶�Y�ƃ��[���b�p�̕����A�������ُ�C�ۂ���_�Ƌ��Q�������B�܂��A��ꎟ���E���̍r�p������Ă��Ȃ��e���̍w���͂��ǂ������A�Љ��`���ɂ��\�A�̐��E�s�ꂩ��̗��E�Ȃǂɂ��A�����J�����̑��̐��Y���ߏ�ɂȂ��Ă������B�܂��A�_�ƕs���ɉ����ēS����ΒY�Y�ƕ�����s�U�ɂȂ��Ă����B
1927�N�ɃW���l�[�u�ōs��ꂽ���E�o�ω�c�ł́A���Q�ɔ����ď��ƁE�H�ƁE�_�ƂɊւ��鑽���̌��c���R�c�E�̑����ꂽ�B���Ƃł͊ň��������A�H�Ƃł̓R�X�g�_�E���ړI�̎Y�ƍ��L���A�Ɛ�֎~�Ɛ��Y�����̍��ۋ���A�_�Ƃł͕��@�̉��ǂƎ����̑ݕt�ɂ��ċc�_���ꂽ�B�������A���c���̂��̂͊e���c��疳������Ă��܂��Ă����B3���ɂ͏��a���Z���Q���N�����B
������1929�N7��30���A�j���[���[�N�E�^�C���Y���M�p���k�ɒ�������悤�ȏd�厖���������B�j�R���C2���̐e���炪�A�ۗL������Y600���h����Ԋ҂����邽�߂ɃA�����J���̋�s��i����\�����Ƃ����B���ɂ����V�A�M���ɂ��ĉ��l���̈⑰�������A���z��1���h���قǂ�ۗL���A�Ԋ҂𐿋����Ă���Ƃ������o���ł������B�L���ɂ��Ɛ�������Ă��鎑�Y�̂����A���悻500���h�����M�������e�B�E�g���X�g�E�J���p�j�[�ɁA�܂�100���h�����i�V���i���E�V�e�B�[��s�ɁA���V�A�v���̂Ƃ�����s�@�ɗa�����Ă�����̂ł���B
|
���������Ȃ����@�M
�A�����J�̊����s���1924�N�������瓊�@�𒆐S�Ƃ��������̗����ɂ���Ē����㏸�g�����h�ɓ������B�����Ŗׂ����b���čD�i�C�ɂ���Ă��Ԃ����������s��ɗ����A�l�����Ƃ��A�M�p����ɂ��e�ՂɎ؋����o���A����ɓ��@�M�͍��܂�A�_�E���ϊ�����5�N�Ԃ�5�{�ɍ����B1929�N8��9���A�A�M�������x�͌��������6���Ɉ����グ���B���N9��3���ɂ̓_�E���ϊ���381�h��17�Z���g�Ƃ����ō����i���L�^�����B�s��͂��̎����璲���ǖʂ��}���A����1�����Ԃ�17%���������̂��A����1�T�Ԃʼn������̔������قǎ��������A���̒���ɂ܂��㏸������������Ƃ����_�o���ȓ������������B����ł����@�M�͎��܂炸�A�̂��ɃW���Z�t�EP�E�P�l�f�B�̓E�H�[���X�̗L���ȌC�����̏��N��������E�߂�������s���ɓ�����͋߂��Ɨ\�����A�\���O�Ɋ��������������������Əq�ׂ��B
1929�N9��26���A�C���O�����h��s�������������グ�A�A�����J�̎������C�M���X�֗��ꂽ�B���̂Ƃ����łɊ����͉��~�ǖʂɓ����Ă��邽�߁A��q�́u�Í��̖ؗj���v�ɂ��Ă͒��ڂ̌��������܂��܂ɑz�������B
|
���W�J
���̂悤�ȏ̉�1929�N10��24��10��25���A�[�l�������[�^�[�Y�̊�����80�Z���g���������B��������̊��t���͕������������A�Ԃ��Ȃ����肪�c��݊����s���11�����܂łɔ����F�ƂȂ�A�����͑�\�������B���̓�������1289��4650��������ɏo���B�E�H�[���X���͕͂s���ȋ�C�ɂ܂�A400���̌x�������o�����Čx���ɂ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�V�J�S�ƃo�b�t�@���[�̎s��͕�����A���@�Ǝ҂Ŏ��E�����҂͂��̓�������11�l�ɋy�B���̓��͖ؗj�����������߁A��ɂ��̓��́u�Í��̖ؗj��(Black Thursday)�v�ƌĂꂽ�B��25�����j��13���A�E�H�[���X�̑�芔�����l�Ƌ�s�Ƃ��������c���A�����x�����s�����Ƃō��ӂ����B���̃j���[�X�ł��̓��̑���͕��Â����߂������A���ʂ͈ꎞ�I�Ȃ��̂������B
�T���ɑS�Ă̐V�����\�����X�I�ɕ����Ƃ�����A28���ɂ�921��2800���̏o�����Ń_�E���ς������13%������Ƃ����\�����N����A�X��10��29���A24���ȏ�̑�\�������������B���̓��͎���J�n���ォ��}�����N�������B�ŏ���30���Ԃ�325��9800���������A�ߌ�̎���J�n���X�ɂ͎s�������鎖�ԂƂȂ����B�����̏o������1638��3700���ɒB���A�����͕���43�|�C���g������A9���̖��ɂȂ����B����Ŏ������z140���h����������сA�T�Ԃł�300���h��������ꂽ�v�Z�ɂȂ����B
10��29���͌�Ɂu�ߌ��̉Ηj��(Tragedy Tuesday)�v�ƌĂꂽ�B�����Ƃ̓p�j�b�N�Ɋׂ�A���̑����߂邽�ߗl�X�Ȓn��E���삩�玑���������グ�n�߂��B�����ăA�����J�o�ςւ̈ˑ���[�߂Ă����Ǝ�Ȋe���o�ς��A���I�ɔj�]���邱�ƂɂȂ�B
�ߏ萶�Y�ɂ��A�����J�H�ƃZ�N�^�[�̐ݔ������k���Ɏn�܂����s���ɋ��Z���Q�����Ԃ������A����Ȍi�C��ނ������N�����ꂽ�B�Y�Ɗv���Ȍ�A�H�ƍ��ł�10�N��1�x�̃y�[�X�ŋ��Q���������Ă����B������1930�N��ɂ����鐢�E���Q�͋K�͂Ɖe���͈͂����ŁA�����I�ȉ̖ڏ��������Ȃ��قǍ���ł������B
|
���،��p�j�b�N���琢�E���Q��
1930�N12���A�t�����X�A���n���Z��Société financière française et coloniale (SFFC) ���|�Y�̊�@�ɕm�����B���{�A�C���h�V�i��s�A���U�[���E�t���[���A����Ƀx���M�[������Ђ���Ă����j�I���E�p���W�F���k(�t�����X��ŁA�p���)�A�����ăI���G���^���E�o���N���Z�C�����ŋꂵ�߂�200�Ƒ��̃E�H�����Y��s(�t�����X��ŁA�h�C�c���)���~�ϗZ���ɓ������B �t�����X�A���n���Z�Ђ�1920�N�ɃI�N�^���E�I���x���O(1876-1941)�ƃ��U�[���E�t���[�����������B ����̎q��Ђɂ͑����m�푈�u��2�T�ԂقǑO�A�f���|���ABPERE ��2016�N�𑛂����Ă���G�h�����E���`���h�A�����ă��@�����[�E�W�X�J�[���E�f�X�^���̕��e�G�h�������Q�������B1949�N���Ƀt�����X�A���n���Z�Ђ�Société financière pour la France et les pays d'Outre-Mer (SOFFO) �Ɩ���ς��āA�A�t���J�̃t������ʉ��ɂ�����C���h�V�i��s�n��̊���Ƃ��Ċ��������B
1931�N1���A�{���r�A���f�t�H���g�����B�����đ��̓�ď��������X�ƍ��s���s�Ɋׂ����B
���N5��11���A�I�[�X�g���A�̑��s�N���W�b�g�A���V���^���g���j�]�����B���̋�s��1855�N�Ƀ��X�`���C���h�j�݂ɂ��ݗ����ꂽ�B�N���W�b�g�A���V���^���g�͊����\���ɔ����M�p���k�̒��œˑR�������Ƃ����B���������̗A�o���������o����x���Ԏ��ƂȂ�A���I�[�X�g���A�鍑�̂ւ̗Z�����ł��t�������ƁA�����Đ��{�ɂ��~�ϑ[�u���K�ɍs���Ȃ��������Ƃ��j�]�̌����ƂȂ����B3���̓ƚҊœ����̖\�I�ɑ���t�����X�̌o�ϐ��قɂ��A�I�[�X�g���A�o�ς͎�̉����Ă����B
�N���W�b�g�A���V���^���g�̔j�]���_�@�Ƃ��āA5���Ƀh�C�c��2�ʂ̑��s�E�_�i�[�g��s(�u�_�����V���e�b�^�[�E�E���g�E�i�e�B�I�i�[���v)���|�Y���A7��13���Ƀ_�i�[�g��s��������ƁA�哝�̗߂Ńh�C�c�̑S��s��8��5���܂ŕ����ꂽ�B�h�C�c�ł͋��Z��@���N����A���ʑ����̊�Ƃ��|�Y���A�e���̓h�C�c�����ɂƂǂ܂炸���������A���E�ɋy�B
��ʓI�ɂ͕č��̊����\�������̂܂ܐ��E���Q�ɂȂ������Ƃ���Ă��邪�A�x���E�o�[�i���L���͂��߂Ƃ���o�ϊw�҂͈قȂ錩���������Ă���B����͎��̂悤�ȗ����ł���B
�� 1929�N�̃E�H�[���X�̖\���͕č��o�ςɑ傫�ȑŌ���^�����B�����������͊����s��̖������������������߂ɔ�Q�̑����̓A�����J�����ɂƂǂ܂��Ă���A�����̕č��o�ς͏z�I�s���ɑς��Ă������т��������B�s�������E���Q�Ɍq�������̂́A���̌��s�|�Y�̘A���ɂ����Z�V�X�e���̒�~�ɁAFRB(�A�����J�A�M�������x������)�̋��Z����̌�肪�d�Ȃ������߂ł������B
�� �\���̌�A�č��ɂ͋����������Ă������AFRB�͂����s�ى������A�����̃}�l�[�T�v���C�̑���Ƃ͌��ѕt���悤�Ƃ��Ȃ������B����ɂ��č��ł͋����������Ă���ɂ��ւ�炸�}�l�[�T�v���C���������������B���̈��{�ʐ����Ƃ�e���͋��̗��o��}���邽�߂ɋ����������グ����Ȃ������B�����������X�̓}�l�[�T�v���C�𑝂₷���Ƃ��ł����Ɏ��X�ƕs���Ɋׂ����B���ɋ��{�ʐ�������Ă����h�C�c��I�[�X�g���A�Ⓦ�������͏\���ȋ��������������A�܂���ꎟ���E���Ƃ��̌�̃C���t���ɂ����Z�V�X�e�����ɂ߂ĐƎ�ȏ�Ԃł������B���ׁ̈A�č���t�����X�ւ̋����o�ɂ���������������Ă��܂��A���Z��@�����������B
�����̕č��哝�́A�n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�́u�����\���͌o�ς̂����ۂł���A�t�@���_�����^���Y�����S�Ő��Y��������������s���Ă���(�̂ő��v)�v�Ƃ��������́A�����x�^���ł����������x���~���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
���{�ʐ��̌��ŁA�o�ϊ�@�͂��̂܂܌o�ς̍�����������(��)�̗��o�ɂȂ���B7���̃h�C�c����̗��o��10���}���N�A�C�M���X����̗��o��3000���|���h�������B����ɐ��疜�|���h���������C���O�����h��s��1931�N9��11�����{�ʐ����~���A��ꎟ���E����̕����ł���Ƌ��{�ʐ��ɕ��A��������̊e���ɏՌ���^�����B�C�M���X�͎����Y�ƕی�̂��ߗA���ł������グ�A�`�[�v�}�l�[������̗p�����B�|���h�����$4.86����$3.49�Ɉ���������ꂽ�B�u���b�N�o�ϐ���͐��E���ɔg�y���A����E���̑f�n��������B
����1929�N2���ɋ��{�ʐ��ɕ��A��������̓��{�͐F�X�Ȏv�f����A���E�o�ύ����̒��Ő��݂𗬏o�������B �@ |
| ���e���̏�
|
   �@
�@
|
|
���\�L�̋��Q�Ɏ��{��`��i���͗�O�Ȃ��_���[�W���邱�ƂɂȂ������A���̍����̏�̉ߒ��E���x�ɂ��Ă͊e���Ȃ�̎���e�������B�A���n�������Ă��鍑(�C�M���X�E�t�����X)��A�����J�͋��{�ʐ�����̗��E�⍂�łɂ��o�σu���b�N�ɂ�鎩���ʉ݂ƎY�Ƃ̕ی�ɓw�߂����A�K�������������Ȃ������B�\�r�G�g�A�M����{�A�h�C�c�Ƃ������S�̎�`���Ƃ̏ꍇ�A�Y�Ɠ����ɂ�莑���z�������Ƃ��Ǘ����邱�Ƃŋ��Q����E�������A�S�̎�`���}��R���̑䓪���@�卑�����Ƃ��a瀂B���Q�̔����ȍ~���e���ł̒ʉݖ����������邽�߂̑����̎��݂��Ȃ��ꂽ���P��I�ȋ����̐����\�z���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A���NJO�ב���̍��ۓI�����͑���E�����IMF�ݗ�������c�_�̒��ɑ��荞�܂�邱�ƂƂȂ����B��ꎟ���E����A���E���Q�܂ő����Ă����R�k�ƍ��ە��a�����̘H���͈�C�ɕ���A����E���ւ̑傫�Ȉ���ݏo�����ƂƂȂ����B���̒��Ōo�ϐ���őΉ����A�����B���o�ό��Ƃ��Ď��������{��GDP��1934�N�ɋ��Q�O�̐����ɖ߂�A�j���[�f�B�[��������̂����A�����J��1936�N�ɂ͋��Q�O�̐����ɉ������̂�37�N�s���ɂ��Ă�34�N�̐����܂ŋt�߂肵�A1941�N�܂ŋ��Q�O�̐����ɉ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
|
���A�����J
���a�}�̃t�[���@�[�哝�̂͌ÓT�h�o�ϊw�̐M��҂ł���A�����o�ςɂ����Ď��R���C���������ύt������̂����B���̈����1930�N�ɂ̓X���[�g�E�z�[���[�@���߂ĕی�f�Ր�����̂�A���E�e���̋��Q�������������B1931�N�A�I�[�X�g���A�ő�̋�s���|�Y���ă��[���b�p�o�ς̍X�Ȃ鈫�����\�z���ꂽ���Ƃɑ�6������t�[���@�[�����g���A���Ə̂����x�����P�\���s�����B���O�����̋�s��9����305�s���A10����522�s���������B9�����{����10�����ɂ����ă��[���b�p�������o�������A�A�M�������x����o�Ă��������͑��z7��5500���h�������ł������B���̔N�̏��A�o5���h���������������Ă̌��ʂł������B���o��h�����߂ɘA�M�������x�͌��������10��9����1.5������2.5���ɁA16���ɂ�3.5���Ɉ����グ���B1932�N�㔼����1933�N�t�ɂ����Ă����Q�̒�ӂł���1933�N�̖���GDP��1919�N����45���������A������80%�ȏ㉺�����A�H�Ɛ��Y�͕��ς�1/3�ȏ�ᗎ�A1200���l�ɒB���鎸�Ǝ҂ݏo���A���Ɨ���25%�ɒB�����B�����ꂽ��s��1���s�ɋy�сA1933�N2���ɂ͂Ƃ��Ƃ��S��s���Ɩ����~�����B�Ƃ������ؐ�ō�����@�����ďW���͍��݂����߂āu�t�[�o�[���v�ƌĂ�A�H�㐶���҂̂��Ԃ�V���́u�t�[�o�[�ѕz�v�ƌ���ꂽ�B
�����������A�C�����{��`�Ɋ�Â����j���[�f�B�[��������f���ē��I��������}�̃t�����N�����E���[�Y���F���g�哝�̂͌���ʂ�e�l�V�[�여��J�����Ђ�ݗ��A�X�ɔ_�ƒ����@��S���Y�ƕ����@�𐧒肵���B
�t�[�o�[������1930��v�N�x�̍Ώo�\�Z�͑�GDP��3.4%���x���������A1934�N�Ƀ��[�Y�x���g������10.7%�܂ň����グ���B
�����A�j���[�f�B�[������͂��̌�J�g�o���̔���������A�K�͂��k�������Ȃǂ�������1930�N��㔼�ɂ͍Ăъ�@�I�ȏƂȂ����B���̂��߁A������ɂǂ�قǂ̌��ʂ����������ɂ��Ă͌o�ϊw�҂̊ԂŎ^�ۗ��_��������Ă���B�����̘J���g���������̐�グ��v���A���������̐�グ(���O�i�[�@)�͑��̑吨�̘J���҂̉��قɂȂ������B
1936�N�A���łɃC���t���X���ɂ��������Ƃ��x������FRB�͋��Z�������߂ɓ]���a����������2�{�Ɉ����グ���B�č��̍��c����GDP��40���Ƃ����O�㖢���̐����ɒB�������߁A���[�Y�x���g�哝�̂ƃw�����[�E���[�Q���\�[���������͍����ύt�ɑǂ�����A�������S����i�߂悤�Ƃ����B1936-38�N�ɂ�GDP��5.5%�̍����Ԏ������������B����������1937�N�̍����x�o�啝�팸�\�Z�ɂ��1938�N�͕s���ɂȂ�A����GDP��11%�����莸�Ɨ���4%�㏸���A�u���[�Y�x���g�s���v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�B�j���[�f�B�[�����Ԓ������x�o�Ԏ��̑�GNP�䂪10%�����N��2�x�ł���B�A�����J�o�ς̖{�i�I�ȉ͂��̌�̑���E���Q��ɂ�锜��ȌR���i�C��҂��ƂƂȂ�B�����m�푈���N����A�A�M���{�͂悤�₭�����̂Ȃ������x�o���J�n���A�܂����������̍w���Őϋɍ��������͂Ɏx�������B1943�N�ɂ͐Ԏ���30%���������Ɨ���41�N��9.1%����44�N�ɂ�1.2%�ɉ��������B�������_�E���ϊ�����1954�N11���܂�1929�N�̐����ɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ������B
|
���C�M���X
�J���}�̃}�N�h�i���h���t�͎��ƕی��̍팸�ȂNjُk������~�������̐���J���}����������A����ɕێ�}�Ǝ��R�}�̉������ă}�N�h�i���h������v���t��g�t����B����Ƃقړ�������1931�N9��21���A�|���h�Ƌ��̙[�����~�A��������{�ʐ��̕������s�����B�Ȃ��C�M���X�����{�ʐ��̕������s�����̂����������ɋ��{�ʐ���������鍑�����o�A1937�N6���Ƀt�����X�����������̂��Ō�ɍ��ۓI�ȐM�p�����Ƃ��Ă̋��{�ʐ��͒�~�����B���͂ɂ��Ȃ�̈��肪�o�Ă����C�M���X�ł͍L��ȐA���n���ێ����Ă������Ƃ��ł����E�F�X�g�~���X�^�[���͂ɂ�莩���̂ƑΓ��ȊW�������A�V���ɃC�M���X�A�M���`���A������̂Ƀu���b�N�o��(�X�^�[�����O�E�u���b�N)�𐄂��i�߂Ă������ƂɂȂ�(�������C���h�鍑�̓u���b�N�o�ω��ł����A�W�A�Ɩ��ڂȌo�ϊW�ɂ��������Ƃ��m����)�B
|
�����{
��ꎟ���E���̐폟����1���ƂȂ������̂́A���̌�̋��Q�A�֓���k�ЁA���a���Z���Q(���a���Q)�ɂ���Ď�̉����Ă������{�o�ς́A���E���Q�̔����Ƃقړ������ɍs���������ւ̉e���ɒ�������A����܂Ŏ�ɃA�����J�����ɗ����Ă��������̗A�o���}���ɗ������݁A��@�I�Ɋׂ�B���̖\���ɂ��A�s�s���ł͑����̉�Ђ��|�Y���A�E�ł��Ȃ��҂⎸�Ǝ҂����ӂꂽ(�w��w�͏o������ǁx)�B���Q�����̓����͋����ւ̉e������[���ȃf�t�����������A�_�앨�͔���s�����������i���ቺ�A1935�N�܂ő�������Q�E����A���a�O���Ôg�̂��߂ɔ敾�����_���ł͖���g����⌇�H�������}�����ĎЉ��艻�B�����ł��Ȃ��Ȃ�嗤�֓n��l�X���������B
�������������ɂ��ϋɓI�ȍΏo�g��(�ꎞ�I�R�g���܂�)��1932�N���n�܂�_�R�����o�ύX���^��(���͍X���^��)�A1931�N12��17���̋��[���̒�~�ɂ��~����̉���������A�C���h�ȂǃA�W�A�n��𒆐S�Ƃ����A�o�ɂ��1932�N�ɂ͉��ď����ɐ�삯�Či�C�𐋂������A���ď����Ƃ̖f�Ֆ��C���N�������B1932�N8���ɂ̓C�M���X�A�M�̃u���b�N����(�C�M���X�A�M�o�ω�c�ɂ��I�^������)�ɂ�鍂�Ő��J�n����C���h�E�C�M���X�u���b�N���玖������ߏo���ꂽ���Ƃ���A���{�̓������ƂȂ��Ă�����p��A���{�̎x�����������ꂽ����̖��B���ȂǃA�W�A(�~�u���b�N)���f�Ղ̑ΏۂƂȂ�A�d�H�Ɖ�������������̂̌o�ϑ̐��]����ł��o���B�����푈���͂��܂���1937�N�ɂ͏d�H�Ƃ̔䗦���y�H�Ƃ��������B����ɂ�1940�N�ɂ͍z�H�Ɛ��Y�E�������������Q�O��2�{�ȏ�ƂȂ�A�����m�푈�ɂ�����C�M���X��A�����J�A�I�[�X�g�����A�Ȃǂɑ���D���������Ă���1942�N�Ă܂Ōi�C�g�傪�������B�������펞���̓����o�ω��ł���A���������s���ƂȂ��Ă����B
1931�N12���̍��������A�C�ȗ��A�ϋɓI�ȍ����x�o����(�P�C���Y����)�ɂ����{�̌o�ϊ����͏����ɉ���������1935�N���ɂ͐Ԏ��������ɂƂ��Ȃ��C���t���X�������m�ɂȂ�͂��߁A���a11�N(1936�N)�N�x�\�Z�Ґ��͍����j��ł����M�����ٗl�Ȃ��̂ƂȂ����B����(���c���t)�͌��Q���������{���j�Ƃ����\�Z�Ґ����j��1935�N6��25���Ɋt�c���������t�������̂́A�R��������Ȕ����ɂ����A�呠�Ȃ̌��lj����s�͂��Ȃ��Ƃ̕��j�͈ێ����ꂽ���̂̓��ʉ�v���̑��̑g�݊����ő啝�ȌR�������\�Z�ƂȂ����B���ǂ��̗\�Z�͋c��ɒ�o���ꂽ���̂́A��1936�N1��21���ɓ��t�s�M�C�Ă���o����c����U���s�����ƂȂ����B���s�\�Z��������2��26���ɓ�E��Z�����������������̌��Q����`�͕�������邱�ƂɂȂ����B
�o�ϐ���ł�1931�N(���a6�N7�����z)�̏d�v�Y�Ɠ����@�ɂ��s���J���e���ɂ��A�����Y�Ƃɂ��ƊE�c�̂̐ݗ����������A�w���͂�t�^���邱�ƂŊ�Ƃ̑�����ٗp�̈�����͂������B�܂����Ƃ𒆐S�ɍ������ⓝ�p�����i�B�d�v�Y�Ɠ����@�̓h�C�c�́u�o�ϓ����@�v(1919�N)�����Ƃɕ�I���@�Ƃ��Đ��肳��A���l�̐���̓C�^���A�́u�����J���e���ݗ��@�v(1932�N)�A�h�C�c�́u�J���e���@�v(1933�N)�A�č��́u�S���Y�ƕ����@�v(1933�N)�Ȃǂ�����B1930�N��ɂ͐������̑�K�̓v���W�F�N�g�����{���ꂽ�B
|
���t�����X
�t�����X�ł͐��E���Q�̉e����1931�N�܂œ���鎖�ɐ��������B1931�N9��21���ɃC�M���X�����{�ʂ��炢���͂₭���E���|���h�̕����؉���(�`�[�v�}�l�[����)�����{���Ĉȍ~�A�t�����X�o�ς͖��m�ɉ��~���A���ׂĂ̎w�W�����Q�̐i�s���������B�O���f�Ղ͎����������t�����X��s�̋������͂Ȃ��������������A���Ƃ͑��債�����͉��������������������������ቺ�����B�J�����ԋ��͂��₩�ɉ��~���n�߁A��������̕���͌����ł������B1931�N7���Ɏn�߂�ꂽ�����ƐH���i�ɑ���A�����ʊ������x���A�C�M���X�̋��{�ʗ��E�ɑ���6�����Ԃɂ���Ɋg�傳��A1932�N2���ɂ̓t�����X�ŏ������Ɏg�p����鏬����90%�������Y�ł��邱�Ƃ��`���t����@�Ă����������B
�t�����X�͑�ꎟ���̔������Ƃ���1320�����}���N���h�C�c�ɐ������A��200�����}���N�ɑ������錻�����t���Ă������A�����ł̎x���������Ƃ�1923�N1��11���Ƀ��[���n�����̂��Ă����B�t�����X���{�̓h�C�c����̔����x������O��ɑ啝�ȐԎ��������Ƃ��Ă���A�������̎x���������҂ł��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�n�߂�1923�N�ȍ~�A�t�����͈ב֑���ʼn������C���t�����V�i�����B
1928�N�ɂ͋��ב֖{�ʐ��ɕ��A�������C�M���X���������ŕ��A�����̂ɑ��A�t�����X�̓t�������̐V�����ŕ��A�������ߌo����x�͍��������A�܂����ב֖{�ʐ��ɔے�I�ȗ��ꂩ����̗���������Ƃ�A�ΊO�����������グ�A�o����x�̍��������Ŏ�邱�Ƃ����߂��B���̃t�����X�̋��̋z���͂Ƃ�킯�����h���̋������ւ̈��͂ƂȂ�A�C�M���X���ēx�̋��{�ʗ��E�ɒǂ����ނ��ƂɂȂ����B
�C�M���X�Ɠ��l�A�t�@�V�Y���ɑR���邽�ߕ��\���݉�����������B�����ăR�~���e�����̎w���������I���E�u�����l��������t��g�t����B
|
���C�^���A
�C�^���A�͌��X��ꎟ���E��풼�ォ��o�ύ����Ɋׂ�~���m������������s�U�������Ă������߁A�t�ɐ��E���Q�̉e���͂قƂ�ǎ��A�����̃C�^���A�l�͊�����\���̒m�点���Ă��A�u�����������v�Ƃ��������ō��܂łǂ����炵�Ă����ƌ����B
1861�N�ɓ��ꂳ�ꂽ����̃C�^���A�͑�ꎟ���E���ŗ̓y���l���ł���Ɗ��҂��Ă������k�J�ɏI������B�C�^���A�ł͋��Y��`�ƍ�����`�̑Η����������Ă������A���b�\���[�j�̑g�t�ɂ��t�@�V�X�g�}�̈�}�ƍق��n�܂��Ĉȍ~�A�C�^���A�ł͋��Y��`�҂̑唼�͍��O�ɓ��S���A�X�g���C�L�ɂ��S���̒x���͉������ꂽ�B�t�@�V�X�g�͌Ñネ�[�}�̉h�������߂����Ƃ�ڎw���Ă������A�����̃C�^���A�͍r�p���Ă���A�������L���ɂȂ邽�߂̃`�����X�͑����ֈږ����邱�Ƃł������B�t�@�V�X�g�����͌����y�؍H���ƎY�Ɠ����ɂ�钆����Ƃ̐������p���ɒ��͂��A�����͓Ɛg�҂ւ̉ېłƕ�e�ւ̖J�܂ɂ��o�����͌��サ���B
|
���h�C�c
�h�C�c�͑�ꎟ���E���̔s��ŘA�������狐�z�̔������𐿋�����A�t�����X�̃��[����̂ɂƂ��Ȃ��n�C�p�[�C���t���[�V�����ɂ��A�]���̔����������̐����������Ƃ͖��炩�ƂȂ����B���̂��߃A�����J�����x�����v���Z�X�ɎQ�������邱�Ƃʼn~���Ȏx�������\�ɂȂ�A�܂��A�����J���͂��߂Ƃ���O�����{���h�C�c�ɓ�������A�h�C�c�o�ς͉X���������Ă����B
�������勰�Q�ɂ���ăh�C�c�o�ς͐[���ȏ�Ԃ֊ׂ����B�A�����J���{�͎��X�ƓP�ނ��A�����������Ă����o�ς͈�C�ɂǂ��ɓ˂����Ƃ��ꂽ�B���Ɨ���40�p�[�Z���g�ȏ�ɒB����s��L�͊�Ƃ����X�|�Y�A��ʂ̎��Ǝ҂��X�Ɉ�ꍑ���o�ς͔j�]��ԂƂȂ�B�����1931�N3��23���ɁA�h�C�c���I�[�X�g���A�ƒ��������œ��������F���T�C�����ᔽ���Ɣ����t�����X���A���قƂ��ăI�[�X�g���A���玑�{�������g�������Ƃ����������ƂȂ�I�[�X�g���A�ő�̋�s�N���W�b�g�E�A���V���^�b�g���j�]�������Ƃ͉��B�S�̂ɐ[���ȋ��Z��@�������炵���B����ɔ��������������邽�߁A�V���Ɍ������ꂽ�����O�Ăɑ��锽���́A���ƎЉ��`�h�C�c�J���ғ}(�i�`�X)�̖��i�������炵���B�n�C�����q�E�u�����[�j���O�͂��̊�@�Ƀf�t���[�V��������őΉ����悤�Ƃ������߁A�������Čo�ϊ�@�͐[���ƂȂ����B�u�����[�j���O����C���ꂽ��̃t�����c�E�t�H���E�p�[�y�����t�ƃN���g�E�t�H���E�V�����C�q���[���t�ł́A�ٗp�g�吭��ɂ��o�ψ��艻��}�낤�Ƃ������A������Ղ��s����ł��������߂ɏ\���Ȑ��ʂ��グ���Ȃ��܂ܑސw�����B
1933�N�A1��30���q���f���u���N�哝�̂̓q�g���[���ɔC�������B�q�g���[��ƃi�`�}�́A�h�C�c����c�������Ύ����������Ƀh�C�c���Y�}��h�C�c�Љ��}��e�����A�h�C�c�����̌��͂���������(�i�`�}�̌��͏���)�B���̊ԁA�O���t�ō̗p���ꂽ�ٗp�g�吭��ƁA6������̑�ꎟ���C���n���g�v��A9������̃A�E�g�o�[���̌��݁A�閧�ČR���ȂǂŎ��Ǝ҂͋}���Ɍ��������B�h�C�c�̋��Q����̉̓C�M���X��A�����J�ɔ�ׂĂ��ɂ߂đ����A������l�̒��ڂ��W�߂��B�����̎����̓��t�H��`�Ȃǂ̎�`�𗘗p�������Ȃ��̂ł������B�������q�g���[�ɂƂ��Čo�ϐ���́u���ׂĂ��R�Ɂv�����킹�邽�߂̂��̂ł���A1936�N����J�n���ꂽ��l�J�N�v��ł͎��������o�ϑ̐��ƁA����Ȃ�R���g�傪�p�����ꂽ�B�`�F�R�X���o�L�A���Ȃǂ̌R���s���Ő��{�̍��͂ӂ���݁A1938�N�ɂ�2�x�x�����s�\�ɂȂ鎖�ԂƂȂ����B�C���t�����͂����܂钆�A�g�����p������邱�ƂɂȂ�B
|
���\�A
�\�A�͋��Y��`���Ƃ��������߁A��v���̒��ł����ꍑ�A���E���Q�̉e����S�������ɍ����o�ϐ����𑱂��A1930�N�ɂ�GDP2523.3���h���ŃC�M���X���Đ��E��2�̌o�ϑ卑�ɂȂ����B�Ȍ�A�X�^�[�����̐��i����܃J�N�v��Œ��X�ƍH�Ɖ���i�߂Ă������B�\�r�G�g�̃v���p�K���_������A���R��`�����̌����҂̒��ɂ͎Љ��`�^�̌v��o�ςɊ�]�����o���҂������o�����A���ۂɂ̓z���h���[����H�Ƃ̒����Ń|�[�����h�ɒE�o���郍�V�A�l�̑Q���������N���Ă����B�ɓ��E�V�x���A�J���ɂ͐����ɂ��Ӑ}�I�ɍ��グ��ꂽ�u�ɂ킩���l�v����ʂɓ������ꂽ�B
���E�e�����勰�Q�ɋꂵ�ޒ��A�v��o�ςŌo�ϔ��W�𑱂���\�A(�\�r�G�g�Љ��`���a���A�M)�ƃ��V�t�E�X�^�[�������L���̐_�i���X�����i�B�勰�Q���ŋ~�������߂�l�X�̈ꕔ�͋��Y��`�Ɋ�]�I�Ȍo�ϑ̐������B���ɉp���̎x�z�K���ŗ��肪���o�������͗�펞��ɑ傫�ȈӖ����������B�������X�^�[�����̖ڎw�����̂̓��t�E�g���c�L�[�̍��ێ�`�ł͂Ȃ��\�A�̍��v�ł������B
|
�����ؖ���
�����͓����싞�������{�̐���(1928�N)�����ł���A�����ȗ��̕������������Ɉڍs��������i�K�ł������B�����̎�v�ȍ`�p�͂��ׂăC�M���X�ɂ��x�z����Ă���A�ł̎��匠�������Ȃ��ɂ������B���̏Œ����͐��E���Q�Ɍ�����ꂽ�B�����̕����͋��{�ʐ��ł͂Ȃ���{�ʐ�������Ă���(�⌳)���߁A�����͍����̕��������肵�Ă���A���ی��Ղɂ����͔������Ȃ������B1931�N9���ɗ��đ����ɔ����������B���ςƃC�M���X�̋��{�ʐ��x���E�͒����̌o�ςɂƂ��ĕ��̉���ł���A���ی��Ղł͂���܂ł̋◬���X�������o�ɓ]���A�����̉����⏤�H�ƁE�C�O�f�Ղ̏k���Ɍ�����ꂽ�B1934�N�ɂ̓A�����J�̋┃��@���������A�����J����̖@����~���J�n����ƍ��ێs��ł̋≿�i�͋}�����A���������ʂ̋₪���o���A�����̍����╨���̉����A��s�̓|�Y�Ȃǂ����������B
|
|
���Љ�Ȋw�ɂ�������߂Ƃ��̉e��
|
�������o�ϊw
���E���Q�́u��ʉ�ցv�u�e������ցv�ɔ������R�́A���邢�͕K�R�I�Ȏ��Ԃƍl������B�p���𒆐S�Ƃ��鐢�E�̐�����ꎟ���E���ŕ���A�č����e�����ɂȂ�r���̏o�����ł������B���E�̕x���W�߂����ʂƂ��Đ��E�I�ɒʉ݂��K�v�ł��������A���{�ʐ��̂��ƂŒʉݑn�����o���Ȃ��e���͕č�����̎����җ���҂����Ȃ������B�������č��ɂ͔e�����̐ӔC���鏀�����o���Ă��炸�A���ۘA���ɂ͎Q�������A�h�C�c�Ȃǂ̌o�ϓI�ꋫ����u�����B����Ɂu�^����`���ɂ��f�t������v�����A�č��̔ɉh�𐢊E�e���ɕ������������Ƃ��Ȃ��������߁A���E�e���̌o�ϓI�ꋫ�����Ǖč����g�ɒ��˕Ԃ����B�ݕ����k�ɂ���ĕč��̐��Y�ʂɌ����������̎x�����ׂ�����(�L�����v)���ǂ��ɂ��Ȃ�����ł���B�č��̓C���t������e���āA���̖{�ʋ��ۗL���ȏ�̎����n�����C�O�ɓ������邱�Ƃō��ە��Ƃ𑣐i���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ɂ���Ȃ���A�ނ��듊�������������グ�鎖�Ő��E�e���̗��������͊��������B�������[��`(�Ǘ���`)���D���ŁA�E�b�h���E�E�E�B���\���̍��ێ�`�ł͂Ȃ������B��ꎟ���E���̎Q����A���V�^�j�A�������ƃc�B�������}���d�����K�v�ł������B��ꎟ���E����ł����A�E�B���\�����ݗ��ɐs�͂������a�̂��߂̍��ۑg�D�u���ۘA���v�ɂ͏�@�̔��ŎQ���ł��Ȃ������B
�����e���}���N�s���h�C�c�̓V���w�I�C���t��(�����e���}���N���s���O��1$=4��2000���}���N)���������������C�}�[�����a���̃O�X�^�t�E�V���g���[�[�}���̌��т͌��ǔނ̎��ƂƂ��ɐ��A�ɋA���A���ƎЉ��`�h�C�c�J���ғ}(�i�`�X)�̖u���𑣂����B
�R���P�C���Y��`��������h�C�c�E�C�^���A�E���{�Ȃǂ��}���ɕ������A�č��̃j���[�f�B�[������͌i�C�̉Ɍ��ѕt���ɂ͏������������߁A���D�]�����������S�ɖ����ɂ͎���Ȃ������B�j���[�f�B�[���̓P�C���Y��`�̎��v���N��̐����ƍl�����A�����A���D�]���������A�u�^����`���v��FRB���ݕ����s���������ɂ��킹�āA�������}�l�[�T�v���C����������e�������S�ɏ�������ɏ[���ȁA�����E���Z�g������͑g�܂�Ȃ������B�P�C���Y���g�����o���Ă����悤�ɁA�푈�Ɛ펞�����s�ɂ��}�l�[�T�v���C�����͂ɗ]�萶�Y�͂����������̂ł���B���������Ӗ��ł��u�f�t���I�v�ȁu�^����`���_�ҁv�ɂ����1929�N�Ɏn�܂������E���Q�͑���E���̑f�n��������ƌ�����B�����A�j���[�f�B�[���͐��E�o�ς̎����M���b�v�߂�ɂ͂��܂�ɂ��������A�����o���ɐT�d�ł��肷���A���Ԃ��\���ł͂Ȃ������B�A�����J�͑���E���ɂ���Ă悤�₭�����l���Ȃ����{�x�o���n�߁A�������܂����͂ɐ�����x���������Ƃɂ��悤�₭�s������E�p���A���̂ł���(�Q��:�R���P�C���Y��`)�B
|
���o�ϊw
�}���N�X�o�ϊw�ł́A���{��`�����̌o�ς̗L�@�I�A�ւɂ���āA���{��`�o�ς̖��������E�I�ɔ����I�ɍL����댯�������Ƃ����B�����́u�s��͎��g�Œ������s���@�\�������Ă���A���{�̉���͋ɗ͂��ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ������R���C��`�̍l�������嗬�ł������B�܂��A�I�[�X�g���A�w�h�Ȃǂɂ���đ勰�Q�͒~�ς����s��̘c�݂����邽�߂̕s���̌��ۂł���Ƃ����������Ȃ��ꂽ�B�������A���̂悤�ȍl�����ł�1930�N��ɐ��E�����ʂ����勰�Q����������E�o�ς��~���グ��藧�Ă���邱�Ƃ��ł����A�V�����o�ϗ��_�����߂�ꂽ�B
�s���{�ɂ������o���ɂ��o�ώh����̓t�����X�v���O��̌[�֎v�z�̍����琷��ɋc�_����Ă����_��ł��������A�ÓT�h�o�ϊw�̉ߏ�������ւ̏����ȍ~�A���{�̉���͖��Ԃ̌o�ϊ������������邾���ł���Ƃ̍l�����ʐ��ƂȂ���(�N���E�f�B���O�A�E�g)�B�勰�Q�̔����ȍ~�A�Ăт��̘_�肪�A�����J����уC�M���X�Ő���ɘ_�c����A�A�����J�ł͋��a�}�̃t�[�o�[�������Ԏ������ƍ����s�ɔ����A�ύt�\�Z��`�̂��߂ɃN���E�f�B���O�A�E�g�̋c�_�����p�����B�܂��A�C�M���X�ł͕ێ�}�������̍����Ȃ����l�̗��_�ŃW�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y�̗��ĂɂȂ鎩�R�}�̒�ĂƑΗ������B
�P�C���Y�́w�ٗp�E���q����щݕ��̈�ʗ��_�x(1936�N)�̒��ŁA���{�ɂ������o���ɂ���āA����ꂽ�ٗp�̑n�o�ƗL�����v�̑n�o���\�ł���A�����̑����������̑����ʂ����肷��Ƃ����搔���_�Ɋ�Â��A���ŁE���������Ȃǂ̐���ɂ�蓊���傳����悤�Ɏd�����邱�ƂŁA�\�ł��邱�Ƃ��������B�܂��o�ϊw�I�ɂ��d�v�ȍv���́A�ʉ݂̉��l������藣���A�����Ƌ��Z�s��̎���(���ڋ���)�ɒʉ݂̉��l�ڂނ��т���Ǘ��ʉݐ��x�̗L������_���Ă݂����_�ɂ���B��҂̗��_�I���l�ɂ��Ă̓A�����J�c��⍑�ۉ�c�ł͏\���ɗ������ꂸ�A�P�C���Y�̒���o���R�[���͍̗p���ꂸ�A���̍��ےʉݑ̐��͋���Ƃ̙[����ۏ��ꂽ�h�����@���Ƃ��e���ʉ݂�����Ƀ����N����u���g���E�b�Y�̐����̗p�����B
���P�C���W�A���̕M���Ƃ����}�l�^���X�g�̃~���g���E�t���[�h�}���́A�j���[�f�B�[�������ڌٗp�n�o���s�������Ƃً͋}���̑Ή��Ƃ��ĕ]��������̂́A�����ƒ������Œ肵�����Ƃ͓K�ł͂Ȃ������Ƃ��A�勰�Q�̗v���𒆉���s�ɂ����Z�����ɋ��߂Ă���B
|
���Љ�S���w
�A�����J�ł́A�勰�Q���ɐ��܂ꂽ����E����̃x�r�[�u�[�}�[����̐e����̐l�X�́A���Ƀ��X�N���������Ƃ����������ʂ��o�Ă���A���̌X���͌i�C���ǂ��Ȃ��Ă��ς�炸�ꐶ�������Ƃ���Ă���B
�@ |
| �����E���Q 2 |
   �@
�@
|
1929�N�Ɏn��勰�Q�B���{��`���E�ŋ�s�|�Y�A���Ƃ̘A����������A�}���ȕs�����g�y���A���̑ŊJ��ڎw���R����`�E�t�@�V�Y����䓪�����A����E��킪�����炳�ꂽ�B
1929�N�ɃA�����J���O���̐�Ԋ��Ŏn�܂�A1933�N�ɂ����Đ��E�ɍL�������o�ϕs��(���Q)�̂��ƁB���[�̓A�����J���O���̃E�H�[���X�ɂ���j���[���[�N�����������1929�N10��24��(��Ɂu�Í��̖ؗj���v�Ƃ���ꂽ)�Ɋ�������\���������ƁB1930�N��ɓ����Ă��i�C�͉����A��Ɠ|�Y�A��s�̕��A�o�ϕs�����ꋓ�ɐ[���ɂȂ��āA1300���l(4�l��1�l)�̎��Ǝ҂��ł��B���Q�͂��悻1936�N���܂ő������B�܂����̋��Q�����E�ɔg�y���A���[���b�p�e��������{�ȂǃA�W�A�����ɂ��e�����A���{��`�e���͋��Q����̒E�o���͍����钆�őΗ���[�߁A����E��킪�����炳��邱�ƂƂȂ����B
|
|
���A�����J���̐��E���Q
|
�A�����J�̓�����(����)�����́A�����̂悤�ɂ�����ł�������������ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƕs���ɂȂ�A�����̒l������O�ɔ����Ă��܂����Ƃ����S������Ăɓ����āA1929�N10��24��(�ؗj��)�ɁA�j���[���[�N�̃E�H�[���X�ɂ��銔��������ň�ĂɊ������\�������B��Ƃɓ������Ă�����s�ɑ��A�a���҂͈�Ăɗa���������o���ɎE�����A�x������Ȃ��Ȃ�����s���|�Y�B�Z���̃X�g�b�v������Ƃ͓|�Y���A�H��͕�����A�J���҂͉��ق���Ď��Ǝ҂����ӂꂽ�B�L�����v�͂܂��܂��ቺ���A����ɕs���������Ƃ������z�Ɋׂ����B�����̃A�����J���a�}�t�[���@�[�哝�͕̂s���͎����I�Ȃ��̂ŁA�i�C�͂܂��Ȃ�����ƍl���A�܂��u���R���C��`�v�A�܂�s�ꌴ���ɔC���Ă��������Ƃ����]���̋��a�}�̊�{���j����������ߑΉ����x��邱�ƂƂȂ����B
���A�����J�̌o�ϕs���̗v���Ɣw�i
�A�����J�̋��Q�����̗v���Ɣw�i�Ƃ��Ă͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��l������B •1920�N��̐��D���̒��Ŏ��{�E�ݔ��ւ̉ߏ�ȓ��@���s���u���Y�ߏ�v�Ɋׂ����B
•�_�Y�����ߏ萶�Y�̂��߂ɉ��i�̉�������_�ƕs�����N����A�_�Ǝ����������A�����̗L�����v���ቺ�����B
•�e���Ƃ������Y�Ƃ̕ی�̂��߁A���Ő���(�ی�f�Վ�`)�ɓ]�������̂ŁA���E�s��̊g����j�~����Ă����B
•�����ɃA�W�A�̖������{�̐����A�\�A�Љ��`���̐����ȂǂŁA�A�����J�̎s�ꂪ�k�����Ă����B
•��Ƃ͐��Y���������������ߎ��Ǝ҂�����A����ɂ��̂��ߍw���͂͌��ނ��A����Ȃ鐶�Y�����ւƂ��������z�Ɋׂ����B
�����E���Q�̔g�y
�A�����J���̊����\�������E���Q�Ɋg�債�����R�́A�A�����J���O������ꎟ���E����A���E�ő�̍����ƂȂ��Ă���A���E�o�ς��A�����J�o�ςɈˑ�����̎��ɂȂ��Ă��܂��Ă������߂ł���A�A�����J�̌o�ς��j�]�������Ƃ��K�R�I�ɐ��E�o�ς̔j�]�ւƂȂ����Ă��܂����B
���Q�́A�܂��������̃A�����J���͌�����A�W�A�̐A���n�E�]�����ɍL����A����Ƀ��[���b�p�̍H�ƍ��ւƔg�y�����B�S���{��`���̑S�o�ϕ���ɋy�сA1929�N����32�N�܂łɐ��E�̍H�Ɛ��Y�͔������A32�N���ɂ͑S���E�̎��Ǝ҂�5000���l���z�����Ɛ��肳��Ă���B�Ƃ��ɋ��Q���[���ɂȂ����̂̓h�C�c�ł������B1931�N5���A�I�[�X�g���A�̋�s�N���f�B�b�g���A���V���^���g���j�Y���A������@�ɒ��������̋��Z���Q���������A�h�C�c�ɂ��������͍��O���o�𑱂��A�����͋��z�̐Ԏ��ƂȂ����B���ɑ��z�̔������ƕ�������Ă����h�C�c�̓A�����J�̎x���Ōo�ς����藧���Ă���(�h�[�Y��)�̂ŁA�h�C�c�o�ς��j�]�A���̃h�C�c���甅��������藧�ĂĂ����C�M���X�E�t�����X�̌o�ς��j�]�����B�h�C�c�ł�3�l��1�l�����ƁA���N6���ɂ̓u�����[�j���O�͔����x����������ł��邱�Ƃ𐺖������B
�����E���Q�ɑ��铖���̑�
�A�����J���O����1930�N6���A�X���[�g���z�[���[�@�𐬗������A�_�Y�������ł͂Ȃ��H�Ɛ��i�ł��ň����グ�����{�����B�e���������Y�Ƃ���邽�߂ɁA�ی�f�Վ�`�ɓ]���������߁A���E�I�Ȗf�Օs�U���N���A�������ċ��Q���������邱�ƂƂȂ����B�܂��h�C�c�̋�����~�����߁A�t�[���@�[�哝�̂�1931�N6���Ƀt�[���@�[�������g���A��(�x���P�\��)�A�\���A��E�������x������1�N��~���邱�Ƃɂ������A�^�C�~���O���x�����Č��ʂ͂Ȃ������B�h�C�c�̓����g���A���̖����̑O�ɔ����x�����s�\��錾�A�}篃��[�U���k�ō��۔�������c���J�Â���A�h�C�c�̔����x�����������O�Ă̖�12����1�ɓ�����30���}���N�܂Ō��z���A�������͎�����A�I�グ�Ƃ��ꂽ�B�C�M���X�E�t�����X�͓����ɃA�����J�ɑ������������ɂ��邱�Ƃ�O��Ƃ��悤�Ƃ������A�A�����J�͉�c�ɏo�Ȃ����A�����F�߂Ȃ������B���ǃh�C�c�Ƀq�g���[�������������āB�ΕĐ�͞B���Ȃ܂I������B
���E���Q�̋y�Ȃ������Ƃ���
���̂悤�ɁA���{��`�͎s�ꌴ���ɔC�����܂܂��Ə�ɂ��̂悤�Ȗ������N����B�����ŁA���{��`�o�ς�ے肵�č��Ƃɂ��v��o�ςɂ���ċ��Q���N���Ȃ��悤�ɂ��悤�Ƃ����̂��Љ��`�̍l���ł���B�����A���E���Q���N���������ɂ��łɎЉ��`�̐����Ƃ��Ă����\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�͂��̉e�������A�܃J�N�v��𐄐i�����B�������A�����ɃX�^�[�����ƍّ̐����`������Љ��`�����ꂩ��ώ������B
|
|
�����E���Q�̏���
|
�����Y�ߏ�
1920�N��̃A�����J���O���̐�Ԋ��Ŏ��{��`�̖��������܂��ċN�������o�ό��ۂŁA1929�N�Ɏn�܂鐢�E���Q�̎�v�Ȍ����ƍl������B�A�����J�͑�ꎟ���E���ō��܂������v�ɑ��A�ݔ������𑱂����B�����ԁA�Z��Ȃǂ��烉�W�I�A����@�A�①�ɂƂ������d�@���i�A����ɉ��ϕi�Ȃǂ̐V���ȏ��������ʂɐ��Y����A�Z�[���X�}���Ƒ�ʍL���Ƃ����V���Ȕ̔����i�@�ƌ����̔��Ƃ����M�p�̔����g����悤�ɂȂ������Ƃő�ʏ���(�K�v�ȏ�ɏ����X��)�ɔ��Ԃ����������B1920�N��㔼�ɂ͑��������i�͖O�a��ԂƂȂ�A�_�ƕs����������čw���͂��ቺ���n�߂��B�������A��Ƃ͊����u�[���Ƃ����ߏ�ȓ��@�ɂ���Ďx�����A����ɑ��Y�𑱂����B���̂悤��1920�N��̃A�����J�o�ς̔ɉh���x���Ă����̂́A�M�p�̔��Ɗ����ɂ�鎑�����B�Ƃ����A������������W�̎��Ԃ��痣�ꂽ��@�ɂ����̂ł������B���̓_�ł́A2007�N�Ɏn�܂錻��̋��Q���A���Z�H�w���琶�܂ꂽ�T�u�v���C�����[���Ȃǂ̋��Z���i�̔j�]����n�܂������Ƃɋ��ʂ��Ă���B
���ߏ�ȓ��@
1920�N��̃A�����J�o�ς̍D���̒��Ői���������u�[���̉��M�Ȃǂ̏B1929�N�A���̔����Ƃ��ċN�����������\�����A���E���Q�̈������ƂȂ����B��ꎟ���E����A���E�̋��̓A�����J���O���ƃt�����X�ɗ��ꂱ��ł����B���ɃA�����J�ł͗���������ƁA�C�M���X�E�t�����X����̐�̕ԍςɂ���ď���Ȏ���������邱�ƂƂȂ����B��s�͂��܂������������������l�ɑ݂��t���A�����l�͂�����l�тƂɊ������Ƃ����߁A���������u�[�����N����A1929�N�t����Ăɂ����Ắu�勭�C�v���ꂪ�s�[�N�ɒB�����B�������A�w���͂̒ቺ�Ɖߏ萶�Y�̃M���b�v����ʐl�ɒm���邱�ƂȂ��������Ȃ��Ă����B���@�I�Ȕ����ł�オ���������ƁA��Ƃ̌o�c���Ԃ́A�l�m�ꂸ��������Ă��܂��Ă����B�悤�₭���̂��ƂɋC�����n�߂��ꕔ�����Ƃ����̓���������n�߂Ă����B�����͂₪�āu��V��v�������A1929�N10��24���́u�Í��̖ؗj���v�ɁA��C�ɖҗ�Ȕ��肪�E�����A���E���Q���n�܂����B�����u�[���̎��Ԃ͂��̂悤�Ȃ��Ƃł������B
(���p)�u�R�����u�X�����V���g�����t�����N�������G�W�\�����݂ȓ��@�Ƃ������B�v�Ƃ������ƂŐl�тƂ͓��@�̊댯����Y��A�u�N�����������ɂȂ�ׂ����v�Ƃ����薼�̕��͂ŃW���������X�R�u�́A�l���ꃖ���ɂق��15�h����ߖĂ����D�NJ��ɓ���������A�z�����Ȃǂ�ʂƂ��Ă��A20�N��ɂ͏��Ȃ��Ƃ�8���h���̋�����ɂ��邱�Ƃ��ł��A���̓������������͏��Ȃ��Ƃ����z�l�S�h���ɂȂ�A�Ɛ������B�܂���Ђǂ������������������A���ۂ̊��̉��l�ɂ��Ă͒N���킩��Ȃ��Ȃ����B�����M�����}����(�Ȃ��ɂ͍��\�܂����̂��̂�����)�A�Z�[���X�}��������܂������B���̓�����Ђ̊������l�Ŕ����A���{�̋���ȃs���~�b�h���o���オ�����B�l�тƂ͒����l�̌������Ƃ�M����ق��Ȃ������B�u�G�݉��A�d�Ԃ̉^�]��A�z�ǍH�A���j�q�A���������̋��d�܂ł������������B���t���Ă���͂��̒m���l�������A�s��ɂ����B�v
���_�ƕs��
���ɃA�����J�����̍w���͂�ቺ�����A1929�N�̐��E���Q�̔w�i�ƂȂ����B��ꎟ���E��펞�ɐH�Ǝ��v�����܂�A���i���㏸�������߁A���E�I�ȍ������Y���s��ꂽ�B�����̓A�����J���O�����͂��߁A�A�����J�̎��{����������ăA���[���`���A�J�i�_�A�I�[�X�g�����A�Ȃǂō�t���ʐς������E�@�B�����i���߁A���Y�����債�A�������̌X�����������B���̓t�����X�E�h�C�c�Ȃǃ��[���b�p�������_�Y���̎������ɂ͂����Ĕ_�Y���ɍ��ł�������悤�ɂȂ����B�����ȊO�̍����A�ȉԁA�S���A�R�[�q�[�Ȃǂ����Y�ʂ������������A1924�N�����狟���ߑ��ɂ��_�Y�����i�̉������n�܂����B�Ƃ�킯�_�Y���A�o���̍��ێ��x�����������邱�ƂƂȂ����B
�A�����J�̔_���́A��풆�Ɏ؋������čk�n���g�債�A�@�B���w�����Ă������߁A�_�Y�����i�̉e��������Ɏk�n��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��_���������Ȃ����B�_�ƕs���͒��������A�����1929�N�H�͖L��ł��������߁A������u�L��n�R�v���d�Ȃ�A�_���̍w���͂��������ቺ���A���E���Q�̈���ƂȂ����B
�����Ǝ҂̑���
1929�N�̐��E���Q����1933�N�̃j���[�f�B�[���܂ł��O���ɕ����āA���̎����̓������܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
����1��(1929�N10���`30�N9��)�@1929�N�̎��ƎҐ���155��(�J���l���S�̂�3�D2��)�������̂��A30�N�ɂ�434���l(8�D7��)�ɑ����B�������܂����Ƃ̐[�����͔F�����ꂸ�A�l�тƂ́u���D���ɖ߂邩�v�����҂����B�X���[�g���z�[���[�@�̍��łɂ���č����s��͉���Ɗ��҂���A�B���{�ɂ��������Ƃ�n�C�E�F�C���݂��s��ꂽ�B�j���[���[�N�̃G���p�C�A�E�X�e�[�g�E�r��(���V�O)��30�N�Ɍ��݂��n�܂�A31�N�Ɋ��������B
����2��(1930�N10���`31�N12��)�@30�N�̓~���玸�Ǝ҂���C�ɑ��������B31�N�ɂ�802���l(15�D9��)�ƂȂ�B�e�����̂�s�s�͎��q�I�Ȏ��ƎҌ����̋��H��h���{�ݒ����B�܂����Q�̉e�����Ȃ������\�A�̌v��o�ςւ̊S�����܂����B31�N6���̃t�[���@�[�������g���A���̓��[���b�p�o�ς̋~�ςƂȂ�Ɗ��҂��ꂽ���A�����̓h�C�c�̋��Z���Q�Ɏn�܂�A�C�M���X�����{�ʐ��𗣒E���ĕs�������܂����B
����3��(1932�N1���`33�N3��)�@���Ǝ҂�1200��(24��)�ɒB���A���̂��납�玸�Ǝ҂̂��Ƃ����Q�����̂悤�Ɂu�d���̂Ȃ��l�v(the idle)�ł͂Ȃ��A�u���Ǝҁv(unemployed)�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�t�[���@�[�哝�̂����Ƒ�ɏ��o�������A�d���̊m�ۂ͖��Ԋ�Ƃ̐Ӗ����ƍl����ꂽ�̂Ŗ{�i�I�ɂ͂Ȃ炸�A���ƎҐ���33�N��1283���l(24�D9��)�̍ō������ɒB�����B(�j���[�f�B�[���J�n��A1937�N�܂ł�770��(14�D3��)�܂ʼn���B)
���u�t�[���@�[���v�Ǝ��Ǝ҂̔���
(���p)���ׂĂ��������l�тƂ��s�s�̌�����n�ɖؐ��i�{�[���ł������o���b�N�����̏W���́u�t�[���@�[���v�A�V�����́u�t�[���@�[�ѕz�v�A�����ς�o���ꂽ����ۂ̃Y�{���̃|�P�b�g�́u�t�[���@�[�̊��v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�v1932�N3��7���ɂ̓f�g���C�g�ŋ��Y�}�ɐ擱���ꂽ3000�l���t�H�[�h�ЍH��ɍR�c�ɋl�߂������B�s�̌x�@���̓f�����ɂނ����č×܃K�X�e�ˁA�f�����͐Ⓚ�y�Ђ𓊂��Ē�R�����B�x�����͎��e�ˌ��������A�f������4�l���E����A50�l���d�����Ƃ����������N�������B1932�N7���ɂ́A�{�[�i�X�v���̂��߃��V���g���ɏW�܂����ޖ��R�l�̃L�����v���R�������ďĂ�������(�}�b�J�[�T�[���R���w����������)�B
|
|
�����E���Q�ւ̑Ή�
|
���u���b�N�o�ςւ̓]��
�e���͂��ꂼ��A�����̐����c��̂��߂̌o�ς𗧂Ē����ɑ��邱�ƂƂȂ����B�C�M���X�ł̓}�N�h�i���h������v���t���A1931�N�̋��{�ʐ���~�ɓ��ݐ�ƁA33�N�ɂ̓A�����J���O�������{�ʐ���~�ɓ������A���E���{�ʐ��͕����B�܂��C�M���X���I�^���A�M�o�ω�c�ŃC�M���X�A�M���̎����̂Ƃ̓��b�ł�݂��đ��n��ɑ���ی�Ő���ɓ��ݐ�ƂƂ��ɁA�X�^�[�����O���u���b�N���\�z����ƁA�t�����X�̃t�����o�ό��A�A�����J�̃h���o�ό��Ȃǎ��{��`�͒ʉ݂��Ƃ̃u���b�N�o�ϐ�����̗p���邱�ƂƂȂ����B�������A�e�����u���b�N�o�ςɂ���ĕی�f�Վ�`�ɓ]�������߁A���E�S�̂̎��R�f�Ղ����ނ��Ėf�Պz���������A���E�S�̂̕s���ɂ���ɉ��������邱�ƂƂȂ����B
���{��`�����͊�@��������A1933�N6���A���ۘA������Â��ă����h�����E�o�ω�c���J�Â��A67�J�����W�܂�A���E���Q����̍��ۓI�ȑΉ������c����w�͂��s�����B�������A���̉�c�ł́A�A�����J�̃��[�Y���F���g�哝�̂͐��E�o�ϑS�̂ɐӔC�������Ƃ�ӂ�A�������ɂ��Ă̋c�_���������A�܂��ʉ݂̈���Ȃǂɂ��e���̗��Q���Η��������߁A���ǂ܂Ƃ܂炸�A�푈�ɂ������ւƌ��������ƂɂȂ��Ă��܂����B
���A�����J�̃j���[���f�B�[������
1933�N�ɓo�ꂵ���A�����J���O���̂e�����[�Y���F���g�哝�̂̃j���[�f�B�[������͔_�Y���̉ߏ苟����}���A�H�Ɛ��Y�̍��ƊǗ������߁A�啝�ȍ����o���Ō������Ƃ������Čٗp��n�o���A�����w���͂̉�}�����B�܂��A���̂��߂ɂ͘J���҂̕ی��Љ�ۏ�̏[���Ȃǂɂ����g�݁A��s���������Ď�����Ȃǎ��{��`�̘g���ł̑�_�ȉ��v�����{�����B���̂悤�Ȏ��{��`�̌��������Ȃ���A���R���C�ł͂Ȃ����{���o�ς����͂ɃR���g���[������K�v������Ƃ����l���𗝘_�������̂��C�M���X�̌o�ϊw�҃P�C���Y�ł������B�ނ͗L�����v�������邱�Ƃɂ���ĉߏ萶�Y����������Ȃǂ��߂������Ƃ̍�������ɂ���Č������Ƃ������Čٗp��n�o������A������ɂ���Ē��~������ɉ��Ƃɂ���čw���͂����邱�ƂȂǂ��������B�A�����J�͍����������L�����������Ƃ������āA����Ɍo�ϊ�@���������A����E�����}���邱�ƂƂȂ�B
���t�@�V�Y���̑䓪
���E���Q�̉e�����ł��������̂��h�C�c���a���ł������B�܂��A���n�����Ȃ��A�������������Ȃ��C�^���A���o�ς��j�]�����B�A�W�A�ł͓��{�͂��łɑ嗤�i�o���ʂ����Ă������A�����ɂ͒n�吧�x�ȂnjÂ��Љ�\�����c��A�_���s�������������A�Ⴂ�w���͂ɂƂǂ܂��Ă������߁A�����Ǝs����C�O�ɋ��߂�o�ϊE�ƌR�̎v�f�����܂��Ă����B���̂悤�ȁu�������鍑�v�ł���h�C�c�E�C�^���A�E���{�Ƀt�@�V�Y�����䓪���钼�ړI�Ȍ_�@�����E���Q�ɂ������B���ɁA�h�C�c�͑�ꎟ���E���̔���Ȕ��������t�����X�ȂǂɎx����Ȃ���Ȃ炸�A1924�N�̃h�[�Y�ĂŌy�����ꂽ���̂́A�A�����J���O���̎��������Ōo�ϕ�����}��Ƃ����}���ɂȂ��Ă������߁A�A�����J���̐��E���Q�̉e�����ŏ��Ɏ���Ȃ������B1931�N6���̃t�[���@�[�������g���A���̓h�C�c�o�ς̈����𗧂����炷���Ƃ��o�����A1933�N�ɂ͎��Ǝ҂�600���ɑ��債���B���̂悤�Ȋ�@�����܂钆�ŁA���N1���q�g���[���ɔC������A�ƍِ������J�n����B�����N3���ɂ́A����̃A�����J�łe�����[�Y���F���g���哝�̂ƂȂ�A�j���[�f�B�[������J�n�����B
������E���ւ̓�
�L��ȍ��y�E�A�������L���A�������s����m�ۂ��邱�Ƃ̂ł���u���Ă鍑�v�ł������C�M���X�E�t�����X�E�A�����J���u���b�N�o�ς��\�z���āA�r���I�ɂȂ�ƁA�㔭�̒鍑��`���Ƃł������h�C�c�E�C�^���A�E���{�́u�������鍑�v�Ƃ��ĐU�镑�����ƂɌ�����^���A���̎O���͂��ꂼ��A�u�������v�̊g�����f���āA�h�C�c�͓����[���b�p�ɗ̓y���g�����悤�Ƃ��A�C�^���A�͖k�t���J�̃G�`�I�s�A��o���J���̃A���o�j�A�ւ̐i�o�A���{�͖��B���璆���{�y�ւ̐i�o��1930�N�ォ��W�J���Ă������B���̂悤�ȐV���Ȓ鍑��`�ɂ�鐢�E���������͐��E���Q���@�Ɉ�C�ɋ��܂�A���F���T�C���̐��ƃ��V���g���̐��A���邢�̓��J���m�̐��ƌ������n����S�ۏ�̘g������A���ۘA���̏W�c���S�ۏ���@�\���Ȃ��Ȃ�A����E���ւƂȂ����Ă������B
������E����̋��Q��
����E������D�i�C�ƕs�i�C�̔g��A���x���̌o�ϊ�@�͂��������A��{�I�ɂ́u���E���Q�v������邱�Ƃ��ł��Ă���B����́A��O�̊e���o���o���̌o�ϐ������������ݏo�������ƂȂ��A���ۘA���̂��ƂŁA���یo�ϑ̐��̈����}�邽�߂̍��ےʉݐ��x�Ƃ��āA�u���g�����E�b�Y�̐��Ƃ������ےʉ݊��(�h�l�e)��A�łƖf�ՂɊւ����ʋ��聁�f�`�s�s�ɂ�鎩�R�f�Ղ̐��i�Ȃǂ��@�\�������Ƃɂ��B���̒��j�ƂȂ����̂��A�����J�o�ςł���A�h������Ƃ���Œ�ב֑��ꐧ�̂��Ƃň��肵�����o�ς̕������i�B�܂��A���{��`�����ł��s�ꌴ�������ɂ܂������A���{���o�ς��R���g���[������Љ��`�I�Ȍ����������ꂽ�����o�ϑ̐����Ƃ������Ƃ�����̗v���ł������B
��2008�N�̐V���Ȍo�ϊ�@
�Ƃ��낪���̂悤�Ȑ��E�o�ϑ̐���1970�N�ォ��傫���ω����A�A�����J�o�ς̗������݁A���{�o�ς̑䓪�A�V���o�ϒn��̑䓪�A�d�t�Ȃǒn��o�ϓ����̐i�W�ƂȂ��ŁA�s��o�ϖ��\��`(�V���R��`�o��)�̕����Ƃ������X�����łĂ���B���ɃA�����J���O���̃u�b�V��(�q)�����̉��ŋK���ɘa�����i����A���Z�H�w�Ə̂��邳�܂��܂ȓ��@�}�l�[�ɂ�闘�v�Nj����������ăT�u�v���C����肪�N����A2008�N9���ɂ͋��Z���̃��[�}���u���U�[�X�̔j�]�����������ɁA�ӂ����ѐ��E���Q�̊�@�ɗ��������Ă���B
�@
�@ |
| �����E���Q 3 / �A�����J���O���̌o�ώj |
   �@
�@
|
��������20�N�� / 1920�N-1929�N
��Ԃɕ����邱�Ƃƍ����펞�Ő��̏I����v���������a�}�̃E�H�����E�n�[�f�B���O�哝�̂̉��ŁA���������A���h�����[�E�������͊ł��グ�A���̐ŋ��������A�傫�ȍΓ����߂��g����1920�N����1930�N�܂łɍ��̕���3����1�܂ʼn������B1924�N����1928�N�܂ł�5���N�͐��E�̃h�����ĊO���s�z�͖��N10���h�������B���̂���1926�N����1928�N�܂ł�3���N�̓��e���A�����J�̔��s�z�͖��N3���h�������B���������n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�͏��K�����K�����邱�ƂŌ���������悤�w�߂��B
���̔ɉh�̊��Ԃ͓����̕����Ƌ��ɋ�����20�N��ƌĂ��B�����ԎY�Ƃ̋}���Ȑ����ɂ���ĐΖ��A�K���X����ѓ��H���݂Ȃǂ̎Y�Ƃ��h�����ꂽ�B�ό��Y�Ƃ��}�g�債�Ԃ�����������҂͔������̍s�����a���g�������B���s�s���ɉh���A��s�s�̓I�t�B�X�A�H�ꂨ��яZ��̌��݂Ŋ�����悵�A���ĂȂ�10�N�Ԃ��߂������ƂɂȂ����B�V�����d�͎��Ƃ���Ƃ█���̐�����ς����B�d�b��d�C���s�s���𒆐S�ɕ��y�������A�_�����ł͂���قǂł��Ȃ������B�_�v�͐펞�̓y�n���i�o�u���̉e������o���Ȃ��������A�܂��A��ꎟ���E��풆�ɏ����̐��Y�E�A�o���g�債�����Ƃ����������āA�_�Y���ߑ��ɂ��_�Ɖ��i�����E�_�Ə��������ɋꂵ�߂�ꂽ�B�o�ύ\���̕ω�����g���X�g(��ƍ���)�⎝����Ђɂ�鎖�Ɖ�Д������i�߂��A�����������B�̂��߂Ɋ�����Ѝ��������Ŕ��s���ꂽ�B�܂���Ќ^�����M������Ă���A�����㏸�ɂȂ������B
�����㏸���������A1929�N6���ɂ͌i�C�̓s�[�N�A�E�g���Ă����A����10��24���A�،��s�ꂪ���A1929�N�̃E�H�[���X�g���[�g����̒��ŋ�s���|�Y���n�߂��B
|
�����E���Q / 1929�N-1941�N
�A�M�������x������͋��Q���N�������킯�ł͂Ȃ��������A��s�������邱�Ƃŋ��Q��h���w�͂����Ȃ������B�Ǝ�ȋ�s�V�X�e���̑��݂ɂ��A�a���҂͎����̗a������낤�ƕs���ɋ���A���t���������N�������B��U�A���t���������N����Ƌ�s�̘A���j�]�̉\��������A��s�͗a���ɑ��鏀�����������グ���B1930�N����1933�N3���܂ł̊Ԃ�4��̋�s���Q���������A���̊ԂɌ����E�a���䗦�Ə����E�a���䗦���㏸�������߁A�ݕ��搔�͒ቺ�A�n�C�p���[�h�}�l�[�̏㏸�ɂ�������炸�A�ݕ��搔�ƃn�C�p���[�h�}�l�[�̐ςł���ʉ����ʂ�1933�N�ɂ�1929�N��3����2�̐����ɂ܂ŗ������݁A�������}���ɉ����������B
�n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�哝�̂́A�f�Օs�U�𐢊E���Q�̌����Ƃ݂Ȃ��A�f�ՐU���̊ϓ_����t�[���@�[�����g���A������A��ꎟ���E���̔������̎x�����P�\�����������ŁA�呝�Ŗ@�Ă�ʂ��ė������ލΓ��𑝂₻���Ƃ��A�ی��`�̃X���[�g�E�z�[���[�Ŗ@�ɏ����������A����̓J�i�_�A�C�M���X�A�h�C�c�Ȃǖf�Ց��荑�̕��ĂB�A�����J�o�ς͕s���Ɋׂ����B1932�N�܂łɎ��Ɨ���23.6%�ɂ��Ȃ����B�͏d�H�ƁA���ދƁA�A�o�p�_�Y��(�ȉԁA�����A�^�o�R)����эH�Ƃň��������B�z���C�g�J���[��y�H�Ƃł͂���قLj����Ȃ������B
�t�����N�����E���[�Y�x���g��1932�N�̑哝�̑I�̃L�����y�[���Ɂu3��R - �~�ρA����щ��v�v(Three R's - relief, recovery and reform.)���句���A�ނ͂��̃X�s�[�`�̒��Łg�j���[�E�f�B�[���h�̗p������B���̑哝�̑I�͐����_���ɏI���Ȃ������B1932�N3��4������y�R���ψ���������ĈÍ��̖ؗj���������N�����������n�߂��B��Â̓j���[���[�N�̌�����t�F���f�B�i���h�E�y�R�������߁A�ψ���̕͘A���V���̈�ʂ��������B�X�L�����_���̗��������r��A��̂��܂��������S�Ă̊��E�܂��������B��̋�s�V���W�P�[�g�ɂ����āA�W�����E�����K���̑��q�W���b�N��1930�N����3�N�ԁA�܂�19�l�̒��Ԃ�1931�N�Ɨ��N�A�A�M�����ł��x�����Ă��Ȃ������B�W���b�N�̓C�M���X�ŏ����ł��x�����Ă���A���19�l�͕ۗL���̑����Őŋ��̍T�����Ă����B����玩�͉̂�����@�����Ȃ��������A�W���b�N�E�����K�����C���T�C�_�[����Ɏ����߂āA���J�E���O�Ɋ����܂Ƃ߂Ĉ����Ԃֈ������p���Ă������Ƃ����������B�����łɊւ�����́A�C���T�C�_�[�������L����V���W�P�[�g�͈̔͂��ՂɊW�����B�C���T�C�_�[�̋�̓I���e�͂����ł���BJP�����K���͎劲���Ƃ���1929�N�ɃA���Q�[�j�[�E�e�N�m���W�[�Ȃ�3�Ђ̎�����Ђ����s�����V�������ăR�l�N�^�[�ɕ��������Ă����B�A���Q�[�j�[�̏ꍇ�A�����������i��1��20�h���������B�R�l�N�^�[�͂������s�ꉿ�i35�h���Ŕ��p�����B�R�l�N�^�[�ɂ́A�J���r���E�N�[���b�W�A�E�B���A���E�E�b�f�B���A�`���[���Y�E�����h�o�[�O�Ȃǂ������B
���[�Y�x���g�͑��l�ȏ����ҏW�c(�u���[���g���X�g)�ɑ傫���ˑ����Ă���A�ޓ����j���[�f�B�[������ƌĂ�鑽���̌v��Ŗ����������Ă������ƂɂȂ����B1933�N3��4�����[�Y�x���g���哝�̂ɏA�C�������̓��A���Z���Q�͑S�ĂɍL����A3��6������9���܂ł�4���ԑS�Ă̋�s�ɋx�Ɩ��߂��o���ꂽ(�o���N�z���f�[�A�����g���A��)�B���[�Y�x���g�͏A�C����ŏ���100���Ԃŏd�v�@�Ă��c��ɏ��F�����A���Q�����ɓ����o����(������u�S���c��v)�B�_�ƌo�c�̈���̂��߂ɔ_�ƒ����@(AAA)�A���Ƒ�̂��߂̃e�l�V�[�여��J������(TVA)�ɑ�\�����������Ƃ�A�M�ً}�~�ϖ@(FERA)�A���{����ƌo�c�Ɋ֗^���A���Y�����Ɖ��i�̈��艻�ɂ���ƌo�c�̉��P��}�����A�J���҂̒c������c�̌�����ۏ����S���Y�ƕ����@(NIRA)�A�܂��A���Z���x����̂��߂ɁA�،��Ɩ��̋K������������1933�N�،��@�A���Ƌ�s�Ə،��Ɩ��̕�����a���~�ς̂��߂ɘA�M�a���ی�����(FDIC)�̑n�݂Ȃǂ��K�肵���O���X�E�X�e�B�[�K���@(1933�N�A�M��s�@)���ł���B���@�Ə،�����ψ�����@�̗��@�����Ƃ��āA�y�R���ψ���̒����͍����̋L���ɐ[�����܂�Ă���B�o�ϊw��j���[�f�B�[������͎Љ��Ƃ��Ă̑��ʂ��������������B�������������]������Ȃ�A�O�f�̃E�B���A���E�E�b�f�B�����Ƃ��邵����݂�����Ȃ���A�،��E�̕��s�Ƃ������̊j�S�ɂ͈ꉞ�̑[�u���u�������̂Ƃ������ƂɂȂ�B
���یo�ϖʂł�1933�N4��19���̋��{�ʒ�~�ƕ����̐艺���ɂ��ʉ݉��l�̍����͂悤�₭������������B1934�N1���ɂ͋�������1�I���X35�h���Ƃ���������@�𐧒肵���B��k�푈������ێ�����Ă���������1�I���X20.67�h����59���ɂ܂Ő艺����ꂽ�̂ł���B�������ċ��{�ʐ����痣�E���h���������Ɉבւ�U�������B����ł̓f�t�H���g�����̃��e���A�����J�����ƑP�O����i�߃h���u���b�N���`�����A�C�M���X�̃X�^�[�����O�u���b�N�A�t�����X�̃t�����u���b�N�A���{�̉~�u���b�N�ɑR�����B
���{�̎x�o�̓t�[���@�[������1932�N��GNP��8.0%����1936�N�ɂ�GNP��10.2%�ɑ������B���[�Y�x���g���u�ʏ�v�\�Z���ύt���������A�ً}�\�Z�͍��Řd���A����1932�NGNP��33.6%����GNP��40.9%�܂ő������B�Ԏ��\�Z�����l���̌o�ϊw�ҁA���ł������Ȏ҂̓C�M���X�̃W�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y�ɂ���Đ������ꂽ�B���[�Y�x���g�̓P�C���Y�ɉ�������A���̐����ɂ͒��ӂ�Ȃ������B���v�}�\�����������Ă����P�C���Y�Ɖ������ŁA���[�Y�x���g�́u�ނ͐����o�ϊw�҂Ƃ����������w�҂ɈႢ�Ȃ��v�ƒ��߂����B�P�C���Y�����[�Y�x���g�̒܂̌`���C�ɂȂ邠�܂莩������������������悭�o���Ă��Ȃ������Ƃ����B
���ƑƂ�������Ƃւ̎x�o���A�����J�o�ς������邾���̎h����^�������̒��x�A���邢�͂��ꂪ�o�ςɈ��e���������炵���̂������ł��c�_����Ă���B�o�ς̌��S���S�̂����������Y�Œ�`����Ȃ�A�A�����J��1934�N�܂łɉO���ɏ��A1936�N�܂łɊ��S�ɉ������A1937�N�s���Ŏ��Ɨ���1934�N�̐����܂Ŗ߂����B�s���̂��Ȃ��Ɂw�A�����J��60�Ƒ��x�Ƃ����{���o�ł���A���O���̓Ɛ�I�Ȍo�ύ\����\�I�����B
�u���[�_�X�E�~�b�`�F���́u�唼�̎w�W��1932�N�Ă܂ň������A�o�ϓI�ɂ��S���I�ɂ��s���̒�ƌĂ�ł�����������Ȃ��v�Ɨv���B�o�ώw�W�ł̓A�����J�o�ς�1932�N�Ă���1933�N2���܂Œ��˂��A���̌㒅���ɋ}���ȉ𐋂��A���ꂪ1937�N�܂ő��������Ƃ������Ă���B�H�Ɛ��Y�Ɋւ���A�M�������x�w�W��1932�N7��1���ɍŒ�_52.8�ƂȂ�A�����I��1933�N3��1����54.3�܂ŕω��͖��������B�������A1933�N7��1���܂ł�85.5�܂ŒB����(1935�N����1939�N�̎w�W��100�Ƃ���B�����2005�N�ł݂��1,342�ƂȂ�)�B�������A���������w�W�̒l�͕K�����������̎��������킯�ł͂Ȃ������B�@
�@ |
| �����E���Q 4 / ������20�N�� (������20�N��) |
   �@
�@
|
�A�����J���O����1920�N���\�������ł���B
�A�����J���O����1920�N����������t�ł���A�Љ�A�|�p����ѕ����̗͋���������������̂ł���B��ꎟ���E���̌�Łu�m�[�}���V�[(Normalcy)�v(��Ԃɕ����邱�ƁA�A�����J���O���哝�̃E�H�����E�n�[�f�B���O��1920�N�̑I���X���[�K���Ɏg����)�������ɖ߂�A�W���Y�E�~���[�W�b�N���ԊJ���A�t���b�p�[������̏������Ē�`���A�A�[���E�f�R�����_���}���A�Ō��1929�N�̃E�H�[���X�̖\�������̎���̏I���������Đ��E���Q�̎���ɓ������B����ɂ��̎���͍L�͂ȏd�v����������̔��������A�O��̖����قǂ̐����Ƃ̐����Ə���Ҏ��v�Ɗ�]�̉����A����ѐ����l���̏d��ȕω��œ����t������B
������20�N��ƌĂ��Љ�ƎЉ�I�ϓ��͖k�A�����J�Ɏn�܂�A��ꎟ���E����Ƀ��[���b�p�ɍL�������B���[���b�p�͂��̎���A��킩��̍Č��Ɣ���Ȑl�I�����ɐ܂荇�������邱�ƂŔ�₳��Ă����B�A�����J���O���̌o�ς̓��[���b�p�̌o�ςƂ̌��ѕt���������Ȃ��Ă������B�h�C�c�����͂┅�������Ȃ��Ȃ������A�E�H�[���X�̓A�����J�̑�ʐ��Y���i�̑����s��Ƃ��ă��[���b�p�o�ς��������Ă����悤�Ƀ��[���b�p�̕��ɑ傫�ȓ������s�����B����10�N�Ԃ̔��܂łɁA�o�ϔ��W�̓��[���b�p�ŋ}�㏸���A�h�C�c(���@�C�}�����a��)�A�C�M���X����уt�����X�Ō������A20�N��㔼�͉�����20�N��(Golden Twenties)�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�t�����X��J�i�_�̃t�����X�ꌗ�ł͋��C�̎���(années folles)�Ƃ��Ă�Ă���B
������20�N��̐��_�́A���㐫�Ɋւ��s�A�����A���Ȃ킿�`���̔j��Ƃ�����ʓI�Ȋ��o�������ł���B��������̂�����Z�p��ʂ��Ď����\�Ɏv��ꂽ�B���Ɏ����ԁA�f�您��у��W�I�̂悤�ȐV�Z�p���A��O�̑唼�Ɂu���㐫�v��A�������B�`���I�ő����I�ŗ]���Ȃ��͎̂��p���̂��߂ɗ��Ƃ���A���z����퐶���̖ʂɋy�B�����ɁA�܂���O�̐S�Ɏc���Ă�����ꎟ���E���̋��|�ւ̔����Ƃ��āA��y�A�ʔ��݂���ьy�������W���Y��_���X�Ɏ�荞�܂ꂽ�B���̂��߂��̎���̓W���Y�E�G�C�W�ƌĂ�邱�Ƃ�����B
|
���o��
������20�N��͑���ɂ킽��V������O������̓����ŋ�藧�Ă�ꂽ�傫�Ȍo�ϓI�ɉh�̎���Ƃ��đ�������̂�����܂ł̂����ł���B�k�A�����J�A���ɃA�����J���O���̌o�ς͐펞�o�ς��畽�a���̌o�ςɈڍs���A���̌��ʊ����ƂȂ����B�A�����J���O���͐��E�ōł��x�߂鍑�Ƃ��Ă̗�����������A�����Ƃ͑�ʐ��Y���s���A�Љ�͑�ʏ����ɓ������B����ő�ꎟ���E���̎���ƂȂ������[���b�p�ł́A1924�N�܂Ōo�ς̔ɉh�͎n�܂�Ȃ������B
���̎Љ�A�o�ς���ыZ�p�̐i���ɂ��S�炸�A�A�t���J�n�A�����J�l�A�ŋ߂���Ă����ږ�����є_�v�A����ɂ͘J���ҊK���̑唼�́A���̊��Ԃ̉e����債�ĎȂ������B�����A1�Ƒ�1�N������2,000�h���Ƃ����n�����ȉ��ŕ�炷�l�X�����S���l�������B
���E���Q��1930�N��Ƌ�����20�N��̊T�O�Ƃ̊ԂɈ���������Ă���B������20�N����n�߂�������ꎟ���E����̊�]�Ɉ�ꂽ��Ԃ́A���̌�̎���̐��ނ���o�ς̍���ɓ����������B
������
��ꎟ���E��킪�I���ƁA���m�B�͉��������������ăA�����J���O����J�i�_�ɕ������A�s��ɂ͂��������邽�߂̐V���i���҂��Ă����B�ŏ��́A�펞���Y�̌����ŒZ���Ԃ����[���s�����K�ꂽ�B����͑�ꎟ���E����s���ƌĂ�Ă���B�������A�A�����J���O���ƃJ�i�_�̌o�ς́A�����������m�B���J���͂Ƃ��ĕ��A���A�H�ꂪ��V����đ�O������Y����悤�ɂȂ�ƒ����ɗ����������B
���o�ϐ���
1920�N��͋������̌o�ϐ���ɂ���đ��������O����ƌo�ϐ�����10�N�Ԃ������B�A�����J�̐�ォ�i����`�����̐������ł͕ێ�I�ȋ��a�}������3���������B3�����ɐ��{�Ƒ��Ƃ̊Ԃ̖��ڂȊW���ł߂钆���I�p�����̂����B�E�H�����E�n�[�f�B���O�哝�̂�1921�N�ɏA�C�����Ƃ��A���̌o�ς͕s���̒�ɂ���A���Ɨ��͈����C���t���̌��20%�ɂ��B�����B�n�[�f�B���O�͍������炵�A���ł��A�_�Y���̗��v�����A�ږ��𐧌����邱�Ƃ��Ă����B�n�[�f�B���O�͂��̎����܂Ő����Ă͂��Ȃ��������A���̐���̑唼���c��ʂ����B�����̐���ɂ��N�[���b�W����́u�u�[���v���ĂԂ��ƂɂȂ����B�n�[�f�B���O����уN�[���b�W�������哱�����������v�Ȏ�����1�́A��ꎟ���E���Ɉ����グ���Ă����x�T�҂ւ̏����ł����ɖ߂����Ƃ������B�������ւ̏d�ŕ��S�͌o�ς�݉��������ۂɐŎ��������炷���̂ƍl����ꂽ�B���̌��ł̓N�[���b�W�����ōs��ꂽ�B����ɃN�[���b�W�́A���Ԋ�Ƃɐ��{��������邱�Ƃ���肵�đj�~�����B�n�[�f�B���O�ƃN�[���b�W�̊Ǘ����@�ŁA����10�N�Ԃ̑唼��ʂ��Čo�ϐ������������������A���̊��Ԃ̎��M�ߏ肪�����s��̕���Ɛ��E���Q�Ɍq���铊�@�o�u�����ĂB������̂ł����������҂Ƃ��Ă̐��{�̖����̓n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�����ł��������B1929�N�Ɋ����s�ꂪ�����Ƃ��A�t�[���@�[�̌o�ϖ��⍲���A���h�����[�E�������́A���ꂪ�s��̐��ݓI�Ɍ��S�ȑ��삾�ƌ��Ȃ����B�t�[���@�[�͎��ƉƒB�����c�̏�ɌĂяo�����������邱�ƂŊ�@�ɔ���������悤�����������B�ږ��������m�肵�A�L���s�^���E�Q�C���ېł��팸�����B�s�K�Ȃ��ƂɎ��Ƃ����̎����w�͂ʼn��������悤�Ƃ������݂͎��Ԃ����P�����Ȃ������B�t�[���@�[�͍Ō�͂���ȏ㓮�������Ƃ��n�߂����A�����̗�����~�߂邽�߂̎����w�͍�͓����Ȃ������B������20�N��̈�Y�́A�w���ҒB��10�N�Ԃ̏I���ɑҋ@���Ă����S����\���������h���s�����Ƃ邽�߂̔\�̖͂����Ő��߂�ꂽ�B
�ێ��`�҂̒��ɂ͐��{�����R���C�o�ϐ����Nj����Ȃ������Ƃ������̗�����̂�҂�����B�ނ���A�M�c���̐����I�哱�͂����炩�Ɏ��ʂł���W�c�ɂƂ��Čo�ϓI���b�ݏo�������ʂ̗��v�v��̕��Ɍ������A���̂悤�Ȏ哱�͂͐��{�̊����͈͂ƌ������g���������Ƃ������Ƃł���B�����ł�1913�N�ɐݒ肳�ꂽ�Ƃ��A���E�ŗ��͍ō�7%�������B���ꂪ1916�N�ɂ�77%�ɂ܂ň����グ���A��ꎟ���E���̐���d�����B1925�N�ɂ͍ō��ŗ���25%�܂ň���������ꂽ�B1920�N��́u�m�[�}���V�[�v�ɂ���āA��ꎟ���E�����O�A�i����`�̎���������Ȃ荂�������ōΔ�Ɛŋ��͈ێ����ꂽ�B1929�N����1933�N�Ɋ|���Ẵt�[���@�[�������ł́A��l������̎����Δ��88%���������B
1920�N����1921�N�Ɋ|���Ēɐȕs��������A���̌�1920�N���ʂ��Ē������������B�A�M�������x�ƌĂ��A�M���{��1�@�ւ��A���s�ɗL���Ȏs����Ⴂ�����ƒႢ���Ȏ��{�䗦��ݒ肷�邱�Ƃőݕt���g�債�A�s����̊��Ԃɒʉ����ʂ͎�����60%���������B�u�M�p�����v�Ƃ������t�����̎���ɃA�����J�l�̌�b�̒��ɓ���A�㏸���銔���s���g������ݕt�̗��_����邽�߂ɂ�葽���̃A�����J�l���\�͈ȏ�ɔw�L�т���悤�ɂȂ��Ă������B
�������A1929�N�A�A�M�������x������͋��Z�ɘa������ێ��ł��Ȃ��Ȃ������Ƃ�F�������B������������グ�n�߂��Ƃ��ɁA����̘O�t�������B�����s�ꂪ���A��s���Q���n�܂����B
���V���i�A�V�Z�p
��ʐ��Y�͋Z�p�𒆑w�K���̎�̓͂��Ƃ���ɂ����炵���B���̎���ɂǂ��ɂł�����悤�ɂȂ������u�̑����͐�O�ɊJ������Ă������A��O�ɂ͎肪�͂��Ȃ������B�����ԁA�f��A���W�I����щ��w�Y�Ƃ�1920�N��ɋ}���������B���̒��ł������ԎY�Ƃ͏d�v�������B��O�A�����Ԃ��ґ�i�������B1920�N��A��ʐ��Y���ꂽ�����Ԃ̓A�����J��J�i�_�ŕ��ʂ̂��̂ɂȂ����B1927�N�܂łɁA�w�����[�E�t�H�[�h��1,500����̃��f��T��̔������B�J�i�_�S�y��1918�N�ɂ�30����̎����Ԃ��o�^����Ă��邾�����������A1929�N�܂łɂ��̐���190����ɂȂ����B�����ԎY�Ƃ̉e���͍L���L����A�K�\�����X�^���h�A���[�e������ѐΖ��Y�ƂƂ������قȂ�o�ϕ���ɂ܂ŋy�B
���W�I�͍ŏ��̑�O�������f�B�A�ƂȂ����B���W�I�͒N�ł��w���ł��A���̌�y���͊v���I�������B���W�I�͑�ʏ���s��̑�\�ɂȂ����B���̌o�ϓI�d�v���͂��̎���ȍ~�̎Љ���x�z�����O�����Ɍq�������B���W�I�̉�������ɂ́A���̃v���O�����͍����̃e���r�̂悤�ȑ��l�����������B1927�N�A�A�M���W�I�ψ���̐ݗ��ŐV���ȋK���̎���ɂȂ����B
�����̉f��̑O�Ɍ��ꂽ�L���f��͊��ɑ�O�s��Ƀu�[�����Ă�ł����B1930�N�ォ��1940�N��́u�f��̉�������v�́A1900�N��̒Z�������f��̎��ォ�甭�W���Ă����B���W�I�Ɠ��l�A�f�����O�������f�B�A�������B�f������邱�Ƃ͑��̌�y�ɔ�ׂĈ����ł���A�H��J���҂Ȃǃu���[�J���[�ł��x�o�ł����B
���V�����C���t��
�V�Z�p�͈ȑO�ɂ͖��������V�����C���t���ւ̎��v��n�������A�����͑����A�M���{�����S�����B���H���݂͎����ԎY�Ƃ̔��W�ɕs���������B���K�i���H�ɓ]���������̂�����A�������H�����݂��ꂽ�B�L��]��������������]�ފK��������A�����Ԃ��܂ߏ�����̎��v�����߂��B
�d�͊J���͐풆�ɓ݉����Ă������A�A�����J�ƃJ�i�_�̑����̒n�悪�d�͊i�q(���d�A���d�A���d�̃l�b�g���[�N)�ɉ����A�傫�Ȑi�W�������B�����Ƃ̑唼�͐ΒY����d�͂ɐ�ւ����B�����ɐV�������d�������݂��ꂽ�B�A�����J�ł́A�d�͔��d�ʂ��ق�4�{�ɂ��Ȃ����B
�d�b�����嗤���ɒ��菄�炳��Ă������B�ƒ�p������ߑ�I�������V�X�e���������̒n��ŏ��߂ē������ꂽ�B
�����C���t���Ɋւ���v��̑唼�̓J�i�_�ł��A�����J�ł��n�����{�ɔC���ꂽ�B�n�����{�̑唼�͂����C���t���̂̓��������������������̂Ƃ����z��ő傫�ȕ���������B���ꂪ���E���Q�̊Ԃɖ��ƂȂ����B�J�i�_�ƃA�����J�͂ǂ�����A�A�M���{�͔��̂��Ƃ����A����10�N�Ԃ͐�����炵�A�풆�ɓ������ꂽ�ŋ�����炩���炵���B
���s�s��
�s�s����1920�N��ɒ��_�ɒB�����B�A�����J�ƃJ�i�_�Ől��2,500�l�ȏ�̓s�s�ɏZ�ސl�������߂ēc�ɂ̏����Ȓ��ɏZ�ސl�����z�����B�������A���̒��ł���s�s�Ɏ䂩���l�������A�l���̖�15%�ɒB�����B�j���[���[�N�ƃV�J�S�͂��̖��V�O���݂������A�j���[���[�N�̓N���C�X���[�r����G���p�C�A�X�e�[�g�r���Ő�s�����B���Z�ƕی��Y�Ƃ̋K�͂�2�{�A3�{�ɂȂ����B����̃z���C�g�J���[�̊�{�l����19���I�㔼�ɑn���Ă������A�咆�s�s�ł͂��̐����W���ɂȂ����B�^�C�v���C�^�[�A���ރt�@�C�����O����ѓd�b�̎d���Ŗ����̏����������E�ɏA�����B�J�i�_�ł͂���10�N�Ԃ̖��ɂ͘J���҂�5�l��1�l�������ɂȂ����B�������x�̍����s�s�͒�������ܑ�Βn���ɂ���A�V�J�S��g�����g�����̑�\�������B�����̓s�s�͔w��ɍL��Ȕ_�Ɨp�n������Ă���̂ɔɉh�����B���C�݂̓s�s��1914�N�̃p�i�}�^�͂̊J�ʂʼn��b����悤�ɂȂ����B
|
������
���Q����
1920�N8��18���A�e�l�V�[�B���A�����J���O�����@�C����19�����y����36�Ԗڂ̏B�ƂȂ�A�����̎Q�������F�߂�ꂽ�B�I�����ɂ����镽���͏����̌����^���ʼn���I�Ȏ��ƂȂ����B
������ꂽ����
����ꂽ����Ƃ͑�ꎟ���E���ɑ������āA���E�Ɍ��ł���ΓI�ɂȂ����Ⴂ�l�X�������B���̌��t�͈�ʂɓ����p���ɏZ�A�����J���w�̒����l���w���Ďg��ꂽ�B��Ȏ҂Ƃ��ăA�[�l�X�g�E�w�~���O�E�F�C�AF�E�X�R�b�g�E�t�B�b�c�W�F�����h����уK�[�g���[�h�E�X�^�C���������B
���Љ�ᔻ��
1920�N��̕��ϓI�A�����J�l���x�Ɩ������ґɂ��S��D���Ă���ɂ�āA����҂͌��Ă����U�P���×~��������悤�ɂȂ����B�����Љ�ᔻ�̒��ŁA�V���N���A�E���C�X���ł��l�C���������B����1920�N�̏����w�{���ʂ�(���C���X�g���[�g)�x�͒������̒��̏Z�l�̑ӑĂŖ��m�Ȑ����h�����B�����ďo�����w�o�r�b�g�x�ł́A���N�̎��ƉƂ����̈��S�Ȑ����ƉƑ��ɔ��R���A�Ⴂ���オ�����Ɠ����悤�ɋU�P�I�ł��邱�Ƃ�F�����錋�ʂɏI���B���C�X�́w�G���}�[�E�K���g���[�x"�ŏ@���h���A�����Ȓ��ɏ@����̔����镟���`���҂Ɠk�}��g�ލ��\�t��ǂ����B
���̑��̎Љ��]�Ƃɂ̓V���[�E�b�h�E�A���_�[�\���A�C�[�f�B�X�E�E�H�[�g�������H�EL�E�����P���������B�A���_�[�\���́w���C���Y�o�[�O�E�I�n�C�I�x�Ƒ肷��Z�ҏW���o�ł��A�����Ȓ��̗͊w�����������B�E�H�[�g����1927�N�o�ł́w�g���C���C�g�E�X���[�v�x�̂悤�ȏ�����ʂ��ĐV����̗��s��}�����B�����P���͑����̐��M��L���ŃA�����J�l�̚n�D�ƕ����̋�����ᔻ�����B
���A�[���E�f�R
�A�[���E�f�R�͂��̎�����悵���f�U�C���ƌ��z�̗l���������B�x���M�[�ɒ[���A�����[���b�p�̑��n��A�����1920�N�㔼�ɂ͖k�A�����J�ɍL�������B
�A�����J�ł͓����̍ł������r���ł���N���C�X���[�r���̂悤�ɍł����ڂ��ꂽ�r�������̗l�����̂��Č��݂��ꂽ�B�A�[���E�f�R�̓����͒P���Ŋw�I�ł��邪�A�|�p�ƒB�͎��R���甭�z�邱�Ƃ����������ƌ�����B���߂͋Ȑ����p����ꂽ���A��ɂ͒����I�Ȑv���l�C���ĂԂ悤�ɂȂ����B
���\����`�ƃV�������A���X��
1920�N��k�A�����J�̊G��̓��[���b�p�Ƃ͈قȂ�����ɔ��W�����B���[���b�p��1920�N��͕\����`�̎���ł���A��ɃV�������A���X���ƂȂ����B�}���E���C����������w�j���[���[�N�E�_�_�x���o�ł������1920�N�ɏq�ׂĂ���悤�Ɂu�_�_�̓j���[���[�N�ł͐����čs���Ȃ��v�ł������B
���f��
����10�N�Ԃ̏��߂ɂ́A�f��͖����Ŕ����������B1922�N�ŏ��̑��V�R�F�f��w���̐��@�x(The Toll of the Sea)������ꂽ�B1926�N�A���[�i�[�E�u���U�[�X�͍ŏ��̌��ʉ��Ɖ��y����ꂽ�w�h���E�t�A���x�����J�����B1927�N�A���[�i�[�͏��߂Ă�����x�̃Z���t���܂މ�������ꂽ�w�W���Y�E�V���K�[�x�����J�����B
��O�̓g�[�L�[�ɔM�����A�f��ق͂قƂ�ǏI�鋻�s�ƂȂ����B1928�N�A���[�i�[�͑���������f��w�j���[���[�N�̓��x�����J�����B�����N�A�ŏ��̉������薟��f��w�f�B�i�[�E�^�C���x�����J���ꂽ�B���[�i�[�͂���10�N��̍Ō�A1929�N�ɍŏ��̑��V�R�F�A����������f��w�I���E�E�B�Y�E�U�E�V���[�x�����B
���n�[�����E���l�T���X
�A�t���J�n�A�����J�l�̕��w�Ɣ��p�̕������A�n�[�����E���l�T���X�̊��̉���1920�N��ɋ}���ɔ��W�����B1921�N�A�u���b�N�X�����E���R�[�h��Ђ��J�݂��ꂽ�B�������͌���10�Ȃ������B�o���ґS�����A�t���J�n�A�����J�l�̃~���[�W�J����1921�N�Ɏn�܂����B1923�N�A�n�[�����E���l�b�T���X�E�o�X�P�b�g�{�[���E�N���u���{�u�E�_�O���X�ɂ���đn�݂��ꂽ�B1920�N��㔼�Ɠ���1920�N��ɂ͂��̃o�X�P�b�g�{�[���E�N���u�����E�ō��̂��̂Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ����B
�w�I�|�`���j�e�B�x�n�������o�ł��ꂽ�B�A�t���J�n�A�����J�l�Y�ȉƃE�B���X�E���`���[�h�\�����t���C�W�[����(�ʖ��E�H���b�N�X����)�Ńf�r���[��w�`�b�v�E�E�[�}���Y�E�t�H�[�`�����x�\�����B�����O�X�g���E�q���[�Y��]���E�j�[���E�n�[�X�g���̂悤�Ȓ����ȃA�t���J�n�A�����J�l��Ƃ��A1920�N��ɑS���̑�O�ɔF������郌�x���܂ŒB���n�߂��B�A�t���J�n�A�����J�l�����̓W���Y�̗����ɑ傫���v�������B
���W���Y�E�G�C�W
�A�����J���O���ōŏ��̏��ƃ��W�I������ KDKA ��1922�N�Ƀs�b�c�o�[�O�ŕ������J�n�����B���W�I�ǂ͂��̌ォ�Ȃ�̗��ŋ}�����A����Ƌ��ɃW���Y�̐l�C���g�������B�W���Y�͌���I�ŁA��������܂��f�J�_��(�ޔp)�I�Ȃ��̑S�ĂɊւ��n�߂��B�j���͂���10�N�Ԃł��ł��l�C�̂��������R�[�h�̎�A�n�����h�E�X�N���b�s�[�E�����o�[�g�̂悤�ɍ����ʼn̂��X�����������B
������O���u�W���Y�v�ƍl���鉹�y�͎Љ�I�����҂ɂ���ĉ��t����Ă����B1920�N��A��O�̑����͍����u�X�E�B�[�g�E�~���[�W�b�N�v�ƌĂԂ��̂ɒ�������A�n�[�h�R�A�E�W���Y�́u�z�b�g�E�~���[�W�b�N�v���邢�́u���C�X�E�~���[�W�b�N�v�ɕ��ނ��ꂽ�B���C�E�A�[���X�g�����O�͒P��̐������ƏI���̖����ω��`�ʼn̂��Ĉꐢ���r���A�Ӗ����Ȃ��Ȃ����߂��̂��邠�邢�͔�������鑦���I�̏��@�ł���X�L���b�g���L�߁A���ɂ̓X�e�[�W�ɂ��鑼�̉��y�ƂƂ̃R�[���A���h���X�|���X�̈ꕔ�ɗp�����B�V�h�j�[�E�x�`�F�b�g�̓N�����l�b�g�̂ق��ɃT�N�\�t�H�[�����O�������B�_���X���̓v���̉��y�Ƃ̎��v�𑝂��A�W���Y�̓t�H�[�E�o�C�E�t�H�[�E�r�[�g�̃_���X���y���̗p�����B�^�b�v�_���T�[�����H�[�h���B������A�O�̊X�����邢�͔��t�y�c�̐l�X���y���܂����B������20�N��̏I���Ƀf���[�N�E�G�����g�����r�b�O�o���h�̎�����n�߂��B
���_���X
1920�N������߂Ƃ��āA�S�Ă̕����ꂪ�_���X���Z����J�Â��A�����ł͗x��肽�����V�������������A���݁A�������B�v���̗x���͑S�Ẵ��H�[�h���B�������ʂ��ē����̃^�b�v�_���X�⑼�̃_���X�̘r���n�߂��B�d������̎Ќ���y�������K�Ȃ��̂ɂ��A�_���X�z�[����C�u�~���[�W�b�N�̎�����������B�l�C�̍����_���X�̓t�H�b�N�X�g���b�g�A�����c����у^���S�ł���A�`���[���X�g������f�B�E�z�b�v���������B
�j���[���[�N�̃n�[�����̓_���X�E�X�^�C���̔��W�ɏd�v�Ȗ������ʂ������B����̌�y���ł́A������K�w�A������l�킨��т�����K���̐l�X���W�܂����B�L���ȃR�b�g���E�N���u�͍��l�̏o���҂��ٗp�������ŁA�ڋq�̂قƂ�ǂ͔��l�ŁA���l�q�̓���͂قƂ�ǂ̏ꍇ�֎~����Ă����B�T���H�C�E�{�[�����[���͑唼�����l�̏�A���y���܂����B
1920�N�㏉������l�X�ȕ��ς��ȃ_���X���J�����ꂽ�B�����̒��ł��ŏ��̂��̂̓u���[�J�E�F�C�ƃ`���[���X�g���������B�L���e���܂ꂽ�u���[�X���܂߁A�ǂ���A�t���J�n�A�����J�l�̉��y�l���ƃr�[�g�Ɋ�Â��Ă����B�`���[���X�g���̐l�C��1922�N�Ƀu���[�h�E�F�C��2�̃V���[�ɏ悹���Ĕ��������B�A�|���E�V�A�^�[�Ŏn�܂����u���b�N�E�{�g���̒Z���Ԃ̔M����1926�N����1927�N�̃_���X�z�[����Ȍ����A�l�C�x�Ń`���[���X�g�������B1927�N�܂łɃu���[�J�E�F�C�ƃ`���[���X�g���Ɋ�Â��^�b�v�̗v�f�������ꂽ�_���X�ł��郊���f�B�E�z�b�v���l�C����Ќ��_���X�ɂȂ����B�T���H�C�E�{�[�����[���ŊJ������A�X�g���C�h�s�A�m�̃��O�^�C���E�W���Y�ɓK�p���ꂽ�B�����f�B�E�z�b�v��10�N�Ԉȏ�l�C��ۂ��A���̌�X�E�B���O�E�_���X�ɕς���čs�����B����ł������̃_���X�͎嗬�ƂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A����10�N�Ԃ̈��|�I�����̐l�X�̓t�H�b�N�X�g���b�g�A�����c����у^���S��x�葱�����B
���t�@�b�V����
�f���G���̕\���ɏ���ꂽ1920�N��̎Ⴂ�����̃t�@�b�V�����͂��ł����B�N�g���A�������l������̒f��Ƃ��Ẵg�����h�ƎЉ�I�����������B�����Ⴍ�A�h�i�Œ����K���̏����͌Â����ォ��u�t���b�p�[�v(���㖺)�ƌĂ�A�R���Z�b�g���O���A�אg�̕G��̃h���X�𒅗p���A�r�⑫��I�o�������B����10�N��̔��^�͊{�܂ł̒����̂������ςł���A���̒��ɂ�����l�C�̂���ω��`���������B���ς�1920�N��܂ŏ��w�Ɗ֘A�t�����邽�߂ɃA�����J�̎Ќ��E�ł͎t�����Ȃ��̂��ʏ킾�������A���̎���ɏ��߂ċ����l�C���W�߂��B
�������̖����̕ω�
1920�N�Ɍ��@�C��19������������ƁA�����͐��ɒ����ԋ��߂Đ���Ă��������I����������������B20�N��́u�V�����v�����Ƃ���ȑO�̐���Ƃ̊Ԃɐ���ԍ����`������n�߂��B�C��19���ȑO�A�t�F�~�j�X�g�͒ʏ�A�����͌o����ςނ��A�v�Ɖƒ�������̂ǂ��炩��I����������A�{���I�ɗ�����Nj����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl���Ă����B���̍l������20�N��ɕω����n�߁A��葽���̏��������̌o���Ő������邾���łȂ��A�ƒ�����������Ɩ]�ݎn�߂��B�u�V�����v������20���I���߂̐i����`����̏��������Љ��d��I�Ȃ��Ȃ�A����̎��{��`�I���_�ɍ��킹�āA�������邱�Ƃ�ؖ]���l�I�B���������o�����Ƃ�]�B
1920�N��ɂ͓��������ɒ������ω����N�������B��ꎟ���E��풆�A�j������ʂɏ]�R�������߁A�ꎞ�I�ɏ������A�����Ă͕s�K�ƍl�����Ă������w�A�����Ԃ���ѓS�|�����Ȃǂ̐����Ƃɓ��邱�Ƃ��F�߂�ꂽ�B���j�I�ɍH��J��������ߏo����Ă������l�������Ⴂ����������A���Ȃ��Ȃ����ږ��J���҂�d�J���̑��������҂Ƃ��āA��ꎟ���E��풆�̐����Ƃɓ����ꏊ�������n�߂��B�������A��ꎟ���E��풆�̑��̏����Ɠ��l�A���̐����͈ꎞ�I�ł���A���l�������푈���I�����̍H��J���̐E������ߏo���ꂽ�B1920�N�A���l�����J���҂�75%�͔_�ƘJ���ҁA�ƒ���J���҂���ѐ���J���҂������B20���I�̏��߂ɐ��������@���́A�����̍H��ɘJ�����Ԃ�Z�k�����Œ�������悤�ɋ��������B���̂��Ƃ�1920�N��̏œ_�͎��v�Ɍ������J�����Y���Ɉڂ����B�H��̓X�s�[�h�A�b�v�ƃ{�[�i�X�̎d�g�݂ŁA�J���҂ɂ�葬�������I�ɐ��Y���邱�Ƃ����サ���B���ꂪ�H��J���҂ɑ��鈳�͂𑝂����B�H��œ������������̘J�������͊y�ł͂Ȃ��������A1920�N��̍D���͒�w�K���ɂ���葽���̓����@����Ӗ������B�����̎Ⴂ�������E�����߁A���邢�͐E�ƌP�����邱�Ƃ����コ��A�Љ�̗������Ɍq�������B
�I�������l���������ƂŃt�F�~�j�Y���^���̏œ_���ߒ����K�v���������B�S�������}�̂悤�Ȓc�̂͐����I�������p�����A1923�N�ɒj���������@�C���Ă��Ă��A���������ʂ��鐫�����g�����@�̓P�p�̂��߂Ɋ��������B�������A�����̏����͂��̏œ_�𐭎�����`���I�ȏ������̒�`�����ƂɈڂ����B
���ɎႢ�����͂��̐g�̂ɑ��錠���咣���n�߁A���̐���̐��I����ɎQ�������B���̍l�����ɂ�����ω������������ϔO�̑����͊��ɑ�ꎟ���E���O�̃j���[���[�N�m���l�E�ŁA�W�[�N�����g�E�t���C�g�A�n�u���b�N�E�G���X����уG�����E�L�[�̒���Ƌ��ɗ��ʂ��Ă����B�����ł́A�����l�Ԍo���̒��S�ł��邾���łȂ��A�����͐l�I�Փ������������I���݂ł���A�j���Ɠ����悤�Ɋ�]�������A�����Փ���}���邱�Ƃ͎��Ȕj��I�ƍl����҂�����Ă����B1920�N��܂łɂ����̊ϔO���嗬�ƂȂ��ĐZ�����Ă����B
1920�N��ɂ͒j�����w���i�݁A���q�w������K�͂ȏB���̃J���b�W���w�֓��w���n�߂��B�����͎嗬�ł��钆���K���̌o�����n�߂�悤�ɂȂ������A�Љ�̒��Ő����̂������������Ă����B�T�^�I�ȏ����͉Ɛ��w�A�u�v�ƍȁv�A�u�ꐫ�v����сu�o�ϒP�ʂƂ��ẲƑ��v�̂悤�ȉȖڂ�I�B�ێ牻�̌X�������܂������̎���ɂ����āA�Ⴂ�������K�����v�����t���邽�߂ɑ�w�ɓ���̂����ʂɂȂ����B���I����̊ϔO�ɉ�������đ�w�̃L�����p�X�Ƀf�[�g����v�ȕω���^�����B�����Ԃ̏o���ŁA�j�����ۂ͂�莄�I�ȏŋN�������B�u�y�b�e�B���O�v�Ƃ��������̐��I�W���w���B�̋K�͂ɂȂ����B
���������y��Ɋւ����葽���̒m�����ɂ��S��炸�A20�N��Ƃ���������ꂽ���{��`��10�N�Ԃ́u���炵���̐_�b�v�����B���̂��Ƃɂ��A�����鏗����������]�݁A������P�ǂȏ����͉ƂɎq���B�Ɨ��܂�A������|�������A�ŗǂ̏����ƂȂ�Ƃ����̂��Ƃ�������ɁA���̍w���͂����R�ɍs�g���A�o������肻�̉ƒ��Ƃ�ǂ����邱�ƂɊւ�����B���̂��Ƃő����̎�w�͉����A�s�����o����悤�ɂȂ����B
�������h�ƃz���Z�N�V����
�s��ł́A�����h���ȑO�Ɉ����Ă���������蕽���Ɉ�����悤�ɂȂ����B����͂���10�N�ԂɌ��J���ꂽ�f��̊���ɉe�����ꂽ�B�Ⴆ��1929�N�́w���b�h�X�L���x��w�_�̑��q�x�͐�Z������A�W�A�n�A�����J�l�ɓ���I�ł���A���R�ƎЉ�I�Ό�������B�����f��ł͍��l�Ɣ��l�����߂ċ�������悤�ɂȂ����B�i�C�g�N���u�ɍs���A���l�ƎЉ�I�����҂��_���X�����A��H���邱�Ƃ��\�ɂȂ����B�|�s�����[�\���O�ł͎Љ�V���Ƀz���Z�N�V����������Ă��邱�Ƃ̂������݂��Ղ����B�����̋Ȃ̒��Ɂw�j���ۂ����A�����ۂ��j�x�Ƃ����̂�����B1926�N�ɔ�������A�����̑����̉̎�ɂ���ă��R�[�h�����ꂽ�B���̂悤�ȉ̎�������B
Masculine women, Feminine men
Which is the rooster, which is the hen?
It's hard to tell 'em apart today! And, say!
Sister is busy learning to shave,
Brother just loves his permanent wave,
It's hard to tell 'em apart today! Hey, hey!
Girls were girls and boys were boys when I was a tot,
Now we don't know who is who, or even what's what!
Knickers and trousers, baggy and wide,
Nobody knows who's walking inside,
Those masculine women and feminine men!
�j���ۂ����A�����ۂ��j
�ǂ��炪�I���h���łǂ��炪�����h���H
���ł͂�������������Ȃ�
�o����͂Ђ������K�����ƂŖZ����
�Z����̓p�[�}�̊����т������Ă�
���ł͂�������������Ȃ�
����������ꂽ�̂͏����͏����ŏ��N�͏��N
���ł͒N���N�Ȃ̂��������Ȃ̂�������Ȃ�
�j�b�J�[�ƃY�{���A�_�u�_�u�ōL��
����ɕ�܂�ĕ����l��N��������Ȃ�
�j���ۂ����Ə����ۂ��j�I
�z���Z�N�V������1960�N��܂�2�x�ƌ����Ȃ������悤�ȃ��x���܂Ŏ�e�����悤�ɂȂ����B1930�N�㏉���܂ŁA�Q�C�o�[�����R�Ɖ^�c����A�u�p���W�[�N���u�v�ƈ�ʂɌĂꂽ�B����10�N�Ԃ̑��ΓI���R���́A���s���т��グ��l�C�X�^�[No.1�Ə�ɐV����G���Ŗ��O��������ꂽ�o�D�E�B���A���E�w�C���Y���A���̈��l�W�~�[�E�V�[���Y�Ƃ̃Q�C�W�Ō��R�Ɛ������������ŕ\����Ă���B���̎���ɂ͂��̑��ɂ��A���E�i�W�����@������E�m���@���̂悤�ȃQ�C�̐l�C������o�D���邢�͏��D�������B1927�N�A���C�E�E�G�X�g���w�U�E�h���b�O�x�Ƃ�����̃z���Z�N�V�����Ɋւ��Y�Ȃ������A�J�[���E�n�C�����b�q�E�E�����b�q�̍�i�ւ̌��y�߂������B����͋��s�I�ɐ��������B�E�G�X�g�͐��ɂ��Č�邱�Ƃ���{�I�l���̖��ƌ��Ȃ��A�Q�C�̌����ɂ��Ă������̒҂ƂȂ����B1930�N��ɕێ�I�������߂�ƁA��O�̓z���Z�N�V�����ɕs���e�ƂȂ�A�Q�C�̔o�D�B�͈��ނ��邩���̐��I�n�D���B�����Ƃɍ��ӂ��邩��I�Ԃ����Ȃ������B
|
���Љ�
���ږ��@
�A�����J���O���A����ђ��x�͒Ⴂ���̂̃J�i�_�͂��O���l�����̌X�������߁A���Ȃ��Ƃ��ږ���r�˂����B�A�����J��1924�N�ږ��@�ł́A1890�N���������ł̃A�����J���O���S�l����2�������鍑����̈ږ��ł���ꍇ�ɁA���̍�����̐V���Ȉږ��𐧌�����(�A�t���J�n�A�����J�l�͏���)�B���̂��߂ɁA20���I���߂�20�N�ԂɃA�����J�ɂ���Ă������[���b�p�l�̑�ʗ����͑啝�Ɍ��������B�A�W�A�l��C���h���Ђ����҂͈ږ����ւ���ꂽ�B1913�N�ɃJ���t�H���j�A�B�Ő��������E�F�u�E�w�C�j�[�@�̗l�ȊO���l�y�n�@�́A�A�����J���O���̎s�����錠���̂Ȃ��O���l�ɂ̓J���t�H���j�A�B�̓y�n�����L���錠���������Ƃ���(�A�����J���O�����x�z���Ă����t�B���s���l�͏��O���ꂽ)�B����͂܂��A��L�̊O���l�ɓy�n����݂���ꍇ���Œ�3�N�Ԃɐ��������B�����̓��{�l�ږ����Ȃ킿���n1���́A�A�����J���܂�̎q���B���Ȃ킿�a���Ɠ����ɃA�����J�s���ƂȂ���2���ɓy�n�̏��L�����ڂ����Ƃł��̖@����������B���ɂ�11�B�����l�Ȗ@�𐬗��������B
�J�i�_�ł́A1923�N�����l�ږ��@�ŁA�A�W�A����̂قƂ�ǑS�Ă̈ږ��𐧌������B���̑��ɂ��쉢�Ⓦ������̈ږ��𐧌�����@��������B���Đa�m����ł͓��{�l�ږ��������ɓ��邱�Ƃ�W���錠�����A�����J�ɗ^�����B
���֎�@
1920�N�A�l�X�ȎЉ�����y�����鎎�݂Ƃ��āA�A�����J���O�����@�C����18���ɂ��A���R�[���̐����A�̔�����їA�o�����ւ���ꂽ�B����͋֎�@�ƌĂ��悤�ɂȂ����B����͋����u�A���`�T���[�������v�̂悤�ȓ����҂ɂ���đ傢�Ɏx�����ꂽ�{���X�e�b�h�@��ʂ��Ė@�������ꂽ�B�֎�@���ł��A�����J�l������������ނ�]���Ƃɂ��A�V�J�S�̃A���E�J�|�l�ɑ�\�����S�Ă̖��A�ƃM�����O�̑g�D�ɂ��g�D�ƍ߂̖u���Ɍq�������B�J�i�_�ł́A�����Z���Ԃ̂ݑS���I�ɋ֎����������ꂽ���A����ł��A�����J�̋֎�@�͏d��ȏՌ���^�����B
���X�s�[�N�C�[�W�[�̗���
�X�s�[�N�C�[�W�[(�������)�́A�֎�@���オ�i�s���A���b�L�[�E���`�A�[�m�A�A���E�J�|�l�A���[�E�_���b�c�A�W���[�t�E�A���f�B�b�c�H�[�l�A�T���E�}�`�F�I�̂悤�ȃM�����O��������ɂ�āA�l�C���Ăѐ��������Ă������B�����͑g�D�ƍ߂��ޖ��A�ƌ��т��ĉ^�c�����̂����ʂ������B�x�@��A�M���{�͂��̂悤�ȑg�D���P���A���҂▧�f�ՋƎ҂̑�����ߕ߂������A�ő��Ƀ{�X�܂ŒH�蒅�����Ƃ͖��������B�X�s�[�N�C�[�W�[���^�c���鎖�Ƃ͑�ϖ��͓I�ł���A���̂悤�ȑg�D�͍����Ŕɐ��𑱂����B��s�s�ł̓X�s�[�N�C�[�W�[���H������A�����t���s���A�V���[��������Ƃ�����̍����Ƃ��ł����B�x�@�̓X�s�[�N�C�[�W�[�^�c�҂���d�G���A�P�����v�悳��Ă���Ƃ��͋q�����Ȃ��悤�ɂ��邩�A���Ȃ��Ƃ��O�����ď��𗬂����B
�����w
������20�N��͕��w�I�ɑn����������������ł���A���l���̒�����Ƃ̍�i�����̊��ԂɌ��ꂽ�BD�EH�E���[�����X�̏����A�w�`���^���[�v�l�̗��l�x�́A���̂����炳�܂Ȑ��`�ʂ̌̂ɁA�����̃X�L�����_���ƂȂ����B
1920�N������Ƃ�������ɂ͎��̂悤�Ȃ��̂�����B
�w�O���[�g�E�M���c�r�[�x�AF�E�X�R�b�g�E�t�B�b�c�W�F�����h���A�A�����J���w�ɂ�����u�W���Y�E�G�C�W�v�̏k�}�ƌ����邱�Ƃ������B
�w��������ُ�Ȃ��x�A�G�[���q�E�}���A�E���}���N���A��ꎟ���E���̋��|�ƁA����ɂ͑O������߂��������̎҂��������h�C�c�s����������̐[���Ǘ�����`�ʁB
�w�y���̂����瑤�x�AF�E�X�R�b�g�E�t�B�b�c�W�F�����h���A��ꎟ���E����̎�҂̐����Ɠ�����`�ʁB
�w���͂܂�����x�A�A�[�l�X�g�E�w�~���O�E�F�C���A1920�N��Ƀ��[���b�p�ɍ��O���Z�����A�����J�l�W�c��`�ʁB
���吼�m�P�Ɖ��f��s
1927�N5��20������21���A�`���[���Y�E�����h�o�[�O�́A�j���[���[�N�B���[�Y�x���g��s��(�i�b�\�[�S�����O�A�C�����h)����p���܂ŁA1�l���������ő吼�m�����f��s�����ŏ��̑��c�m�Ƃ��ēˑR���ۓI�Ȗ��������������B�h�i���h�E�z�[�����v���A�J���t�H���j�A�B�T���f�B�G�S�̃��C�A���q���������P���̔�s�@�X�s���b�g�I�u�Z���g���C�X����������B���v���Ԃ�35.5���Ԃ������B�t�����X�哝�̂̃K�X�g���E�h�D�����O�̓����h�o�[�O�Ƀ��W�I���h�k�[���M�͂����^���A�A�����J���O���ɖ߂��Ă����Ƃ��ɂ́A�C�R�̊͑��Ɣ�s�@�����V���g��D.C.�܂Ō�q���A�J���r���E�N�[���b�W�哝�̂���R��M�\���͂��������B
���X�|�[�c
������20�N��̓A�����J�ɂ�����X�|�[�c�u����10�N�Ԃł��������B�����̂����鏊���狣�Z���X�^�f�B�A���ŋ��������̃g�b�v�E�A�X���[�g�����邽�߂ɏW�܂����B���Z�҂̐��ʂ͓����������������V�����u�W�[�E�E�B�Y�v(����[�I)�^�X�|�[�c�E�W���[�i���Y���Ő������傢�ɗ_�ߏ̂���ꂽ�B���̏������̍ł���҂ɂ͓`���I�L�҃O�����g�����h�E���C�X��f�C�����E���j�A���������B
20�N��ɍł��l�C�̂������A�����J�̋��Z�҂͖싅�̃x�[�u�E���[�X�������B���̓����I�ȃz�[�������̓X�|�[�c�̗��j�ɐV������悵(���C�u�{�[������)�A���̍����Ȑ����͍����𖣗����A����10�N�Ԃ̍ł��m���x�̍����l����1�l�ƂȂ����B�싅�t�@����1927�N�Ƀ��[�X���V�[�Y��60�{�ڂ̃z�[��������������Ƃ��ɖ����ƂȂ����B���̋L�^��1961�N�܂Ŕj���邱�Ƃ͂Ȃ������B����1�l�̏����L�]�ȃX�^�[�A���[�E�Q�[���b�O�Ƌ��Ƀ��[�X�̓j���[���[�N�E�����L�[�X�̂��̌�̉�������̊�b��z�����B
�W���b�N�E�f���v�V�[�Ƃ����o�[���[���E�u���[��(EN)�o�g�̃{�N�T�[���{�N�V���O�Ńw�r�[���̐��E�^�C�g�����l�����A�����ł��j�����ꂽ�{�N�T�[�ƂȂ����B�C���m�C��w�̃����j���O�o�b�N�A���b�h�E�O���[���W��A�m�[�g���_����w�̃t�b�g�{�[���E�v���O�����𐬌��ɓ��������I�]�����ĂR�[�`�A�N�k�[�g�E���b�N�j�[�̂悤�ȗL���l���o�āA�J���b�W�t�b�g�{�[�����t�@���𗸂ɂ����B�O���[���W��NFL�̃V�J�S�E�x�A�[�Y�ƌ_�邱�Ƃ�1920�N�㔼�Ƀv���E�t�b�g�{�[���̔��W�ɏd�v�Ȗ������ʂ����������B�r���E�`���f���̓e�j�X�̋��Z������S�ɐ����A���j��ő�̃e�j�X�I��Ƃ����]�����ł߂��B�{�r�[�E�W���[���Y�̓S���t��ł̑f���炵�������ŃS���t�̐l�C�����߂��B�W���b�N�E�j�N���X�������܂ŁA�W���[���Y�̂悤�ȃX�^�[������邱�Ƃ͂Ȃ������B���[�X�A�f���v�V�[�A�O���[���W�A�e�B���f������уW���[���Y�́A������20�N��̃X�|�[�c�E�̋����Ƃ��āu�r�b�O�E�t�@�C�u�v�ƌĂ�Ă���B
|
������
���E�H�����E�n�[�f�B���O
�E�H�����E�n�[�f�B���O�́A�ނ�������u��ԂɋA��v(Return to Normalcy)�Ƃ�������ŏo�n�������A����͂��̎����3�̃g�����h�f���Ă����B���Ȃ킿�A��ꎟ���E���ɑ��锽���Ƃ��ĐV���ɂ��ꂽ�Ǘ���`�A�ږ��r�ˎ�`�̕����A����щ��v�̎���ɂ����鐭�{�ɂ��ϋɍs����`����̕����]���������B�n�[�f�B���O�͂��̔C����ʂ��āu���R���C�v������̂����B1920�N�̑哝�̑I���ł̔ӉĂƏH�A�n�[�f�B���O�́u���֑O�L�����y�[���v�����̍��̑z���͂𑨂����B����͐V���ő傢�Ɏ�舵���A�L���j���[�X�f��ł����f���ꂽ���Ƃł͏��߂Ă̑I���^���ł���A�n�[�f�B���O�₻�̍ȂƂ̎ʐ^�Ɏ��܂邽�߂ɃI�n�C�I�B�}���I����K�ꂽ�n���E�b�h��u���[�h�E�F�C�̃X�^�[�̉e���͂��g��������I�I���^���Ƃ��Ă����߂Ă̂��̂������B�A���E�W�����\���A�����A���E���b�Z���A�_�O���X�E�t�F�A�o���N�X����у��A���[�E�s�b�N�t�H�[�h�̓I�n�C�I�B�����ɑ����^�����l�̈ꕔ�������B���ƊE�̏ے��A�g�[�}�X�E�G�W�\���A�w�����[�E�t�H�[�h����уn�[�x�C�E�t�@�C�A�X�g�[�������֑O�L�����y�[���ɂ��̖�����݂����B�I���^�����n�܂���������11���̓��[���܂ŁA60���l�ȏ�̐l�X������ɎQ�����邽�߂Ƀ}���I���Ɍ��������B�n�[�f�B���O�����̐��ʂōł��d��Ȃ��Ƃ̓��V���g���C�R�R�k��c�ł���A���E���̌R���͂𐧌����邱�ƂɂȂ����B���̔C���́A�n�[�f�B���O���֗^���Ă��Ȃ������ƍl������X�L�����_��(�e�B�[�|�b�g�E�h�[������)�ōʂ�ꂽ�B�X�L�����_���ɂ������āA�n�[�f�B���O�́u�_��A����͒n���̎d�����v�ƌ����A�u���͓G�Ƃ̃g���u���͖������A�������܂��܂����F�l���������Ɉ�Ӓ������������z��Ȃv�Ƙb�����B�n�[�f�B���O�̔C���͐S������ɂ��ˑR���ŒZ���ŏI������B������j�Ƃ͂��̃X�L�����_�����痈��X�g���X�Ŏ��ƐM���Ă���B
���J���r���E�N�[���b�W
�J���r���E�N�[���b�W�̓n�[�f�B���O�哝�̂̎���ɑ哝�̂Ƃ��ďA�C�����B1924�N�̑哝�̑I���ł������Ɣɉh����{�Ƃ��ďo�n���e�Ղɓ��I�����B�N�[���b�W�͐V�������f�B�A�ł��郉�W�I���g���A���̔C���̊Ԃɐ��W�I�̗��j��������B���Ȃ킿�A���̏A�C�����߂ă��W�I�ŕ�������A1924�N2��12���ɂ̓��W�I�ŏ��߂Đ����I������z�M�����哝�̂ƂȂ�A���̂킸��10�����2��22���A���̂悤�ȉ������z���C�g�n�E�X����z�M�������Ƃł����߂ĂƂȂ����B�N�[���b�W�̓n�[�f�B���O�̎��R���C������p�������B�O�𐭍�ł͌Ǘ���`���D���A�����̐푈��h�~������@�Ƃ��ẴP���b�O�E�u���A�����ɂ͏������Ȃ������B
���n�[�o�[�g�E�t�[���@�[
�n�[�o�[�g�E�t�[���@�[��1920�N��Ō�̑哝�̂ƂȂ�A1929�N�ɏA�C�����B1928�N�ɂ́u��X�̃A�����J�͍����A���j��̔@���Ȃ鍑�ɂ����������悤�ȕn���ɑ���ŏI�I�����ɋߕt���Ă���v�Əq�ׂ��B�t�[���@�[�͋c�_�̑��������X���[�g�E�z�[���[�Ŗ@�ɏ������Ė@�������A1929�N�̃E�H�[���X����̌�n�������邱�Ƃ�������ꂽ�B
���J���g���̐���
�J���g���͐풆�ɋ}���ɐ����������A���S�A�H�����H�Ȃǂ̎Y�Ƃň�A�̑傫�ȃX�g���C�L�Ɏ��s������́A�������ނ�10�N�ԂƂȂ��đ唼�̑g������߁A�g�������͉��~���A�و����͋}���ɑ��������B�}�i�I�ȑg����`�͎���������B����͑�풆�̃X�p�C�@��1918�N��@�Ƃ�����i�ŘA�M���{���}���������Ƃ��傫���������B��v�ȑg����1924�N�̑哝�̑I���ő�3�̐��}���҂ł��郍�o�[�g�E���t�H���b�g���x�������B
���J�i�_�̐���
�J�i�_�̐����̓E�B���A���E���C�A���E�}�b�P���W�[�E�L���O���̃J�i�_���R�}�ɂ���ĘA�M���x�z���ꂽ�B�A�M���{�͂���10�N�Ԃ̑唼���₵�āA�o�ς���P�ނ��풆�ƓS�����ߏ�Ɋg�����ꂽ����ɒ~�ς��ꂽ���z�ȍ������炷���ƂɏW�������B20���I�����̏����o�ς̃u�[���̌�ŁA�J�i�_�̕����n�т͏����̒ቿ�i�ɔY�܂��ꂽ�B����̓J�i�_�ł͏��߂Ă̑�3�̐��}�ł���J�i�_�i���}�̔��W�ɑ傫�Ȗ������ʂ����A1921�N�̍����I���ł͑�2�}�ɐi�o�����B1926�N�̃o���t�H�A�錾�̑n�݂ƂƂ��ɁA�J�i�_�͑��̌��C�M���X�A���n(������)�Ƌ��Ɏ��������l�����A�C�M���X�A�M��n�o�����B
|
���I��
���Í��̉Ηj��
�_�E�E�W���[���Y�H�Ɗ��w���͉��T�Ԃ������𑱂��A�ߔM�������@�s���Ƒ��ւ��āA1928�N����1929�N�̋��C����͉i���ɑ����Ƃ��̂Ƃ������z��^�����B1929�N10��29���A�Í��̉Ηj���Ƃ��Ă�邱�̓��A�E�H�[���X�̊����������B�A�����J���O���ɂ����邱�̏o�����́A����҂ɂ͕s���S�ƌ����Ă������̌o�σV�X�e���ɑ���Ō�̏Ռ��ł���A���E���Q�ƌĂ�鐢�E�I�ȕs���Ɍq����A1930�N���ʂ��Ď��{��`���E�̉��S���Ƃ����l�X����E��D�����B
���֎�@�̓P�p
1933�N2��20���ɒ�Ă��ꂽ�A�����J���O�����@�C����21���͓���18����P�p�����B�A���R�[�������@�ɂ���Ƃ����I���͊e�B�ɔC����A�����̏B�͑����ɂ��̋@��𗘗p���ăA���R�[�����������B
�@ |
| �����E���Q 5 / ���E���Q�̌��� |
   �@
�@
|
��1�D�u�i���̔ɉh�v�ɐ���
1920�N��̃A�����J�o�ς́A�u�i���̔ɉh�v�ƌĂ��قǂ̉��i���𐋂����B���̉��i�����x�����v���͓����B
��́A��ꎟ���E����̃��[���b�p�̐�㕜�����v�ł���B�푈�Ŕ敾�������[���b�p�ɑ��āA���ƂȂ�Ȃ������A�����J�͂��̂��Ɛ��E�o�ς̒��S�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�����Ă����B
������̗v���́A�����ɂ�����s�s���ł���B�����Ԃ����y����ɂ�čx�O�ɓs�s���o�����A���ꂪ�Z����v�����N�����B�܂��A���[���b�p����A�҂������m���������� �ĐV�����Ƃ����āA���ꂪ�Z��݃u�[�������������B
����A�s�s�Ɠs�s�����ԓ��H�Ԃ���������A���ꂪ�L�����v�ݏo���ƂƂ��ɁA�����ԎY�Ƃ̒ǂ����ƂȂ����B���Ƃ������ɂ͎����Ԃ����ӂ�A����Â�����قǔ�s�@����ь������B
�����������̌o�ς̔ɉh��w�i�ɁA1920�N��̌㔼����A�����J�̕s���Y�Ɗ����͂₪�ē��@�̑ΏۂƂȂ�A�������Ɏ��Ԃ��痣��A�₪�ăo�u���ւƓ]�����Ă������B���S�����^�]�������œ����l���A�݂�Ȋ������B�l�X�͒����C���ꂪ�܂��܂��������̂ƐM���ċ^��Ȃ������B�܂��Ɂu�i���̔ɉh�v��M���Ă����̂ł���B
�������A�o�u���͂����͔j��B�ύt�_���痣�ꂷ����A�����́u�_�̌��������v�������A�ύt�_�Ɉ����߂����Ƃ���B�ő�̔ߌ��́A���̋ύt�_���ǂ��ɂ��邩��l�X�͎���I�ɂ����m�邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃł���B���Ȃ킿�A�o�u�����ǂ����͔j�Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��̂��B
|
��2�D�Í��̖ؗj��
1929�N10��24��(��)�A�j���[���[�N�،�������Ŋ�������\�����A���Ƀo�u�����͂�����(�Í��̖ؗj��)�B������11���ɓ����Ĉ�[��3����1�قǖ߂������̂́A���̌�1932�N�܂ł�3�N�Ԃɓn���ė��j�I�ȑ�\���𑱂��A������80���ȏ㉺�������B
����ɂƂ��Ȃ����̌o�ς��������A�f�m�o��29�N�̃s�[�N���̔����ɗ������݁A���Ɨ���25���ɒB�����B���̊ԂɌ��������5������1.5���܂ň���������ꂽ�B�������A����ł����͉����~�܂�Ȃ������B
�A�����J�́A1930�N�ɍ����Y�Ƃ̕ی�̂��߂Ɉ��������X���[�g���z�[���C�Ŗ@�𐬗������A1000�߂��A���i�ɕ���40���Ƃ������ł������A�ی�f�Ղ�W�J�����B����ɑ��ăJ�i�_�A�t�����X�A�C�M���X�Ȃǂ��[�u�ɏo�āA�ň����グ���킪�J��L�����A���E�f�Ղ͈�C�ɏk�������B
����A�C�M���X��1932�N�A�I�^����������єr���I�ȃu���b�N�o�ς����{�����B����ɂƂ��Ȃ��A�A�����J���t�����X���u���b�N�o�ς��`���������߁A�Ȍ�A�u���Ă鍑�Ǝ������鍑�v�̑Η������܂邱�ƂƂȂ����B
1933�N�A�t�[�o�[�哝�̂ɑ����Ė���}�̃��[�Y�x���g�哝�̂��A�C�����B���[�Y�x���g�͋��Q��Ƃ��ăj���[�f�B�[����������{���A�A�����J�o�ς�����ȏ㈫������̂������~�߂邱�Ƃɐ��������B
1936�N�A�P�C���Y�́w�ٗp�E���q�E����щݕ��̈�ʗ��_�x�����s����A�u�s�����ɂ͍����Ԏ��v�Ƃ������o���ꂽ�B�������A���[�Y�x���g�͌����ăP�C���Y�o�ϊw�̗L�����v�n�o������m�M�ɖ����Ď��s�����킯�ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ́A1937�N�Ɍi�C����[�Ɍ������ƁA���x�̓C���t��������邠�܂�����x�o��啝�ɍ팸���A1938�N�ɂ͍Ăьo�ς����������Ă��܂������Ƃ����������B
���ǁA�A�����J�o�ς������I�Ȑ����ߒ������߂����̂́A1941�N�ȍ~�̌R���x�o�}���ɂ��L�����v�g�傪�Ȃ��ꂽ���Ƃł������B
|
��3�D���E���Q�̌����@
�D�i�C�̂��Ƃɕs�i�C������͎̂��{��`�̏h���ł���B�o�ϊ��������R�ł���Ƃ������Ƃ́A���ɂ͋ύt�_���痣��čs���߂��邱�Ƃ����邩�炾�B������A�s�i�C�Ƃ́u�ύt�_����͂��ꂽ�o�ς��Ăыύt�_�Ɉ����߂���p�v�ł���Ƃ�������B���́A�u�����C���v���Ȃ��s���߂��āu���Q�v�ɔ��W���Ă��܂������Ƃ����_�ł���B����Ɋւ��Ă͂�������̐�发���o�Ă��邪�A�ǂ��ǂ�ł����ЂƂ������肵�Ȃ��B�����ł́A���Ȃ�̗������u�Ȍ��v�ɂ܂Ƃ߂Ă��������B
�����̌����́A�o�u�����͂����Đl�X�����ő呹���������߂ɁA������ɒ[�ɍT����悤�ɂȂ�������ł���B���Ƃ��A1000���~�Ŕ���������200���~�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ���B����Ɛl�X�́A��������800���~�����߂����ƕK���ɒ��~������B���̂��߃��m��Ȃ��Ȃ�s�i�C�ɂȂ�B���������s���͈�ʂɁu�o�����X�V�[�g�s���v�ƌĂ��B���Z���Y�̑����ŏ������ƌv�̃o�����X�V�[�g�������悤�Ƃ���ƌv�̍s�����s���̌����ƂȂ邩��ł���B���{�̃o�u��������1990�N��ɂ������������ۂ͍L������ꂽ�B��ʂɁA���Z���Y�̑r���z���傫����Α傫���قǁA�s���͐[����������������B
�����̌����́A�A�����J�����{�ʐ��x���Ƃ��Ă������ƂƊ֘A����B���{�ʐ���19���I�ɃC�M���X�Ŏn�܂�A���̌�A�u�L�����̒��S�ł���C�M���X�Ǝ����������������߂ɁA���E���̐l�X�������̃C�M���X�ɂȂ���āA���{�ʐ��Ƃ����ʉݐ��x���̗p�����v(�w�O���[�o�����Q�x�@�l��q)���̂ł���B���{�ʐ��̂��Ƃɂ����ẮA������s�͕ۗL������Ɍ��������ʂ̎����������s�ł��Ȃ��B�܂�A�s�i�C�ɂȂ��Ă����Z�}�l�[�T�v���C�𑝂₷�Ƃ����ɘa��������{���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B����ǂ���ł͂Ȃ��B1931�N�ɂ����������{�ʐ����~�����C�M���X�́A�A�o�����͂�t���邽�߈בփ��[�g��艺���A������������s�����̂ł���B���̂��߁A�A�����J�����ʂ̋������o���A�A�����J�̓}�l�[�T�v���C�����炳����Ȃ��Ȃ����̂ł���B�ʉ����ʂ𑝂₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��ɁA���ɒʉ����ʂ����炷�̂ł���B����ł�40�x�̔M�����镗���҂��A������ɊO�ɕ���o���悤�ȍs�ׂł���B���{�ʐ��x�����Ԃ�Ԃ��Ĉ��������Ă��܂����̂��B�悤�₭�A�����J�����{�ʐ��x���~�����̂́A1933�N�A���[�Y�x���g�哝�̂ɂȂ��Ă���ł���B
����O�̌����́A���یo�ϐ��x�ɕs�������������ƂƊ֘A����B���Ȃ킿�A�s���ɒ��ʂ�����i���{��`�����͈ב艺�������ɑ���A�u���b�N�o�ς����{�����̂��B�܂�A�����̗A�o��L���A���������i�C���悭�Ȃ�悢�Ƃ����ߗ��R�������W�J�����̂ł���B���ꂪ���E�f�Ղ���C�ɏk�������A���E���Q�̈���ƂȂ�������ł͂Ȃ��A����ɂ͑�2�����E���̌����Ƃ��Ȃ����̂ł���B���Ȃ݂ɁA���̂Ƃ��̎��s�Ȃ��đ���E����A�ב艺��������������邽�߂ɂh�l�e�����A�u���b�N�o�ς���������R�f�Ղ𐄐i���邽�߂ɂf�`�s�s��������̂ł���B�l�ނ͎��s�����ď����͌����Ȃ����Ƃ�������B
�������A���̂ق��ɂ��t�[�o�[�哝�̂��ύt�\�Z��`�҂ł���A�ϋɓI�ȍ��������W�J���Ȃ��������Ƃ����E���Q�̏������L���Ă��܂����Ƃ����Ȃ����Ȃ��B
�������A����͖������˂���ƌ����ׂ��ł��낤�B�����̌o�ϊw�҂̑唼�́A�u���Q�Ƃ������́A�����Ƒς��đ�����߂Ă�����̂������܂邾�낤�v�ƍl���Ă����̂ł���A ���������`���I�Ȍo�ϊw�̋������������ƐM���Ă����̂ł���B
�܂��A��ꎟ���E����A�h�C�c�Ŕ��������n�C�p�[�C���t���[�V�����̋L�������܂�ɂ����X�����������߁A���ՂȐԎ����ɂ��i�C���g����̂邱�Ƃ��S�O���������Ƃ�����B
�s�i�C�̂Ƃ��ɂ͐Ԏ����s���Ăł��������Ƃ��s���ׂ����Ƃ����P�C���Y�̕�I�������̂���悤�ɂȂ����̂́A����E����̂��Ƃł���B
|
��4�D���E���Q����w����
����E����A���E���狰�Q���������B2008�N�̃T�u�v���C�����[�����ɒ[���鐢�E�����s���́u�S�N�Ɉ�x�̕s���v�ƌ`�e����邪�A����ł����E�͕����ł���A���Q�ɂ͎����Ă��Ȃ��B�Ȃ��A���E���狰�Q���������̂��B���R�͊ȒP�ł���B
���ɁA�P�C���Y�̗L�����v�Ǘ�����Ƃ����s���ɑ��鎡�Ö������ꂽ����ł���B����͐V�^�C���t���G���U�ɑ��������^�~�t���̑��݂̂悤�Ȃ��̂Ƃ�����B�s���ɂȂ�ƁA��������������A�s�����[��������O�ɓK�ȑ̂���悤�ɂȂ����B
���ɁA���A���{�ʐ�����Ǘ��ʉݐ��x�ɕς��A�i�C�̏ɍ��킹�Ď��R�Ƀ}�l�[�T�v���C���ł���悤�ɂȂ������Ƃ�����B
��O�ɁA���A�h�l�e��f�`�s�s(�v�s�n)������A���ۋ����̐����蒅�������Ƃ�����B�f8��T�~�b�g�Ȃǂ��ʂ����Ă���������傫���B
���j�Ɂu�����v�Ƃ������Ƃ͋�����Ȃ��B�������A�勰�Q���Ȃ���q�g���[�͌��ꂸ�A���E�����N����Ȃ�������������Ȃ��B�����l����ƁA���Q�Ƃ����a�C��������邱�Ƃ͐l�ނ̍ő�̉ۑ�̈�ł��邱�Ƃ́A�����̂��ς��Ȃ��B
|
��5�D���a���Q
�Ƃ���ŁA���E���Q�͓��{�ɂ��g�y���A���a���Q�ƂȂ����B���̂��Ƃɂ��Čo�ϓI�Ȏ��_����Ȍ��ɂ܂Ƃ߂Ă����B
���{��1917�N����1930�N�܂ŋ��{�ʐ����~���A���A�o�֎~�[�u���Ƃ��Ă����B�������A�h�C�c�A�C�M���X�A�t�����X��1920�N��ɑ������ŋ��{�ʐ��ɕ��A�������Ƃ���A���{�����{�ʐ��ɕ��A���ׂ����Ƃ̈ӌ������܂����B���{�ʐ��ɕ��A����A�����̈���ƈבւ̈��肪�����I�ɒB�������ƍl�����Ă�������ł���B
1930�N1���A���ɓ��{�͋�����(���A�o�̎��R��)�����{���A���{�ʐ��ɕ��A�����B�A�����J�Ŋ�����\������3������̂��Ƃł������B
���{�ʐ����A�ɓ������Ă̍ő�̖��́A�����בփ��[�g����10���ȏ�~���̋������ŋ��{�ʐ��ɕ��A�������Ƃł������B
�����̈�㏀�V��́A�O�ꂵ���ُk�����ɂ��f�t��������Ƃ�A�������������������A����ɂ���č��ۋ����͂����߂悤�Ƃ����B���{���i�������Ȃ�ΗA�o�����₷���Ȃ�B�������{�̕���������10�����������邱�Ƃɐ�������A���Ƃ��בփ��[�g��10�������Ȃ��Ă����͂Ȃ��B �@�@�@
���̂����~���ɂ���ΊO������������ޗ���A�����邱�Ƃ��ł���B����͓��{�o�ςɂƂ��Ă��v���X�ɂȂ�B�������̂ł���B�u�l�͐L�т�Ƃ���ΐ悸�k�ށv�B���ꂪ���̍l���ł������B
�������A���Q�̐^���Œ��ɁA�f�t������ɉ�����10���ȏ���~���グ��ǂ��Ȃ邩�B�����͖����ł���B �A�o���������s���͂���ɐ[���ɂȂ�B���ł����~���s�����ǂ��ł��������邱�ƂɂȂ����̂��B�܂��ɁA���E���Q�Ƃ����u���Ɍ������đ����J���v���ʂɂȂ��Ă��܂����̂ł���B
1931�N12���A�呠��b�ɏA�C�������������͋��A�o�ċ֎~�����肵�A���{�ʐ���2�N���炸�ŕ��邱�ƂƂȂ����B�����͓��{�̃P�C���Y�Ƃ�������悤�ɁA���ł����L�����v�n�o������̂����B����� ������Ƃ�A���s���ČR������g�債(31�N9���A���B����)�A����Ɍ������Ƃ�ϋɓI�ɉ����i�߂��B�����̐���͂��Ȃ�̐��ʂ��������B����̈���32�N�ɈÎE����Ă��܂���(�����c����)�B
�������A1935�N�A���c�����c��ݍ����������ቺ�������Ƃ���A���̂܂܂ł͓��{�̍����͔j�]����Ƃ��āA�����͈�]���č��}���A�R����팸��ł��o�����B����ɔ��������R���́A1936�N�A�������ÎE����(��E��E�Z����)�B
1937�N�A�I�a�����������������ɓ����푈���n�܂�A���̂��Ɠ��{�͐푈�ւƂ܂�������ɓ˂��i�ނ��ƂƂȂ�B
�@
�@ |
| �����E���Q 6 / �j���[�f�B�[������ |
   �@
�@
|
�A�����J���O���哝�̃t�����N�����E���[�Y�x���g�����E���Q���������邽�߂ɍs������A�̌o�ϐ���ł���B
�j���[�f�B�[������͐V�K�܂���������Ƃ��Ă��B�P�Ƀj���[�f�B�[���ƌĂ�邱�Ƃ�����B����܂ŃA�����J�̗�㐭��������Ă����A�s��ւ̐��{�̉�����o�ϐ��������I�ɂƂǂ߂�ÓT�I�Ȏ��R��`�I�o�ϐ���A���{���s��o�ςɐϋɓI�Ɋ֗^���鐭��ւƓ]���������̂ł���A����E����̎��{��`���̌o�ϐ���ɑ傫�ȉe����^�����B���E�ŏ��߂ăW�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y�̗��_�������ꂽ�ƌ�����B���ẮA�����������E�勰�Q����E�������{�̍����������l��������Ƒ����̕����œ����ł���B
|
���o��
���[�Y�x���g�͑哝�̏A�C�O�̃��W�I�ł̑I�������Łu�哝�̂ɏA�C������A1�N�ȓ��ɋ��Q�O�̕��������ɖ߂��v�Ɛ錾�����B���[�Y�x���g��1933�N3��4���ɑ哝�̂ɏA�C����ƁA�����ɂ͓��j���ɂ�������炸�u�ΓG�ʏ��@�v�Ɋ�Â������̑S��s���x�Ƃ����A���W�I������1�T�Ԉȓ��ɑS�Ă̋�s�̌o�c���Ԃ������a���̈��S��ۏႷ�邱�Ƃ���A��s�̎��t�������͎����̕����Ɍ��������B���[�Y�x���g��1933�N�ɑ哝�̂ɏA�C��A�������ɑ�_�ȋ��Z�ɘa���s�������ߐM�p���k���~�܂��Ă���B
���[�Y�x���g�́A���ɏq�ׂ�100���Ԃ̒���ɃO���X�E�X�e�B�[�K���@�𐧒肵�āA���̖��ʂ�����(�A�M�a���ی����Ђ̐ݗ��Ƌ�ؕ���)�B
�X�ɋc��ɓ��������Ė�p�����Ɍi�C��ٗp�m�ۂ̐V�����R�c�����A�ŏ���100���Ԃł����𐧒肳�����B
�ً}��s�~�ϖ@
TVA(�e�l�V�[�여��J������)�Ȃǂɂ��E�ʐ^�̂悤�Ȍ�������
CCC(���Ԏ����ۑ���)�ɂ���K�͌ٗp
NIRA(�S���Y�ƕ����@)�ɂ��J�����Ԃ̒Z�k�⒴�z�_�I�����̊m��
AAA(�_�ƒ����@)�ɂ�鐶�Y�ʂ̒���
���O�i�[�@�u�S���J���W�@�v�ɂ��J���҂̌����g��
�����1935�N�ɂ͑�j���[�f�B�[���Ƃ��āA���Ǝ҂ւ̎蓖���t�E�����ی삩�玸�Ǝ҂̌ٗp�ւƂ����]�����s���AWPA(�������Ƒ��i��)��ݗ����A���Ǝ҂̑�ʌٗp�ƌ����{���݂�������Ƃ�S�ĂɍL�����B
�ΊO�I�ɂ͕ی�f�Ղ��玩�R�f�Ղɓ]���A�哝�̌����ɂ��ŗ��̕ύX��O���ƌb�ʏ���������Ԍ������c��ŏ��F���ꂽ�B�ς�����v���W�F�N�g�Ƃ��Ă͌������Ƒ��i�ǂ̎��{����ΐ��\�v���W�F�N�g (Mathematical Tables Project) ������A���v���W�F�N�g�ɂ����đΐ��\�̐��x����̎��݂��s��ꂽ�B����͒e���v�Z��ߎ��v�Z�̐��x����Ɋ�^���A����E��펞�̕ČR�̒��e�������x�̌����}���n�b�^���v��ɂ����锚�k�����Y(ZND���_)�ɉe����^�����B |
������ɑ���^��
�����̐���ɂ���Čo�ς�1933�N���ӂƂ���1934�N�Ȍ�͉X���ɂȂ������ANIRA��AAA�Ƃ���������̂��������ō��قŁu����������j�Q����v�Ƃ���ጛ�������o���ꂽ�B����ɁA�ϋɍ����ɂ��C���t���X������ѐ��{���̑�����A��������E���Z����̈������߂��s�������ʁA1937-1938�N�ɂ͎��Ɨ����ꎞ�I�ɍď㏸���錋�ʂƂȂ����B���̌�A����E���ɎQ�킵�����Ƃɂ��A�A�����J���O���j��ő�̑��嗦�ƂȂ�R���Ώo�̑���ɂ��A�A�����J���O���̌o�ςƌٗp�͋��Q���犮�S�ɗ������蒘�����g�債���B
���ǁA����GDP��1929�N�̒l��1941�N�ɏ���A����GDP��1929�N�̒l��1936�N�ɏ���A���Ɨ���1929�N�̒l��1943�N�ɉ����A�Ƃ����o�߂����ǂ����B
�j���[�f�B�[������Ȍ�̃A�����J���O���ł́A�A�M���{�̍Ώo��GDP�ɑ���䗦�����債�A�A�M���{������Ȍ����������đS�Ă̌������Ƃ�ٗp����������ƂƂȂ�A����ɑ���E���ɂ��A�M���{�̌��͋����⋐�剻���������A�A�����J���O���̎Љ�ۏᐭ��y�������B����ł͎Љ�ۏ�ԍ��̘R�k�����ƂȂ��Ă���B
���썄�u�́u���[�Y�x���g�哝�̂́w�j���[�f�B�[������x�����s���A�f�t���E�p�Ɍ��������W�[���̑�]�����s�����B���̌��ʁA�l�X�͂��̃��W�[���]���ɔ������C���t�������҂��s������悤�ɂȂ�A�A�����J�o�ς͋��Q����E�o�����v�Ǝw�E���Ă���B
�~���g���E�t���[�h�}���́u1929-1933�N��1933-1941�N�̊��Ԃ͕ʂɍl����ׂ��ł���B�勰�Q�ł͂Ȃ�����k���I��点���̂́A��s�x���A���{�ʐ�����̗��E�A���E��̍w���v��Ȃǂ̈�A�̋��Z����ł������̂͊ԈႢ�Ȃ��B�勰�Q���I��点���̂́A����E���ƌR���x�o�ł���v�Ǝw�E���Ă���B
�F��O���́u���ǂ́A�j���[�f�B�[�����ǂ��������ʁE���ʂ������炵����������O�ɑ���E���ɓ˓����Ă��܂����v�Əq�ׂĂ���B�܂��F��́u�t���[�h�}�������S�ƂȂ��āA�j���[�f�B�[������̂��ׂĂ�ے肷��^�����W�J���ꂽ�B���i���h�E���[�K�������̍��ɂ̓j���[�f�B�[������͊��S�ɔے肳�ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B
�o�ϊw�҂̖��_��́u�j���[�f�B�[���́A�w��������ɂ����ʂ��傫�������x�ƍl�����Ă������A���̌�̌����Łw���Z����E���������g�ݍ��킹������p�b�P�[�W(�|���V�[�~�b�N�X)�Ɍ��ʂ��������x�v�Ɨ��������悤�ɂȂ����v�Ǝw�E���Ă���B���́u1937�N�ɃA�����J���{�͑��ł����{���AFRB�����Z���������߂����߂ɁA1938�N�ɂ͌i�C�����܂ꂵ�A�ēx�s���ɓ˓������B���ꂪ�w1937�N�̎��s�x�v�ƌĂ����j�I���P�ł���v�Ǝw�E���Ă���B
�o�ϊw�҂̃��o�[�g�E���[�J�X�́A1934�N�̗a���ی��̐����A�O���X�E�X�e�B�[�K���@�ɂ���s�Ə،����ɂ���āA��s���ߓx�ȃ��X�N���Ƃ�Ȃ��悤�ɂ�����Z�K���̑̌n���������Ƃ��Ă���A���̋�s�K���͐��\�N�ɂ킽���āA�勰�Q�̍Ĕ���h�~�����Ƃ��Ă���B
|
�����Z����
�o�ϊw�҂̃N���X�e�B�[�i�E���[�}�[�́A�勰�Q����GDP�́A�قƂ�Nj��Z�ɘa�ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ƃ���_���\���Ă���B �x���E�o�[�i���L�́A�勰�Q������̉E�f�t���E�p�́A���{�ʐ���~�ɂ����Z�ɘa�̎����\������^�����Ƃ��Ă���B
|
����������
�o�ϊw�҂̓c���G�b�A���B���i�́u���[�Y�x���哝�̂́w�j���[�f�B�[������x�́A�����x�o�̋K�͂͑�GDP���5%�O��ƃt�[���@�[�哝�̂̎���Ƃ���قǕω��͂Ȃ������v�Ǝw�E���Ă���B
�N���X�e�B�[�i�E���[�}�[�́A�j���[�f�B�[���̍�������͌��ʂ��Ȃ������ƁA�o�ώj�I�������猋�_�Â��Ă���B���[�}�[�́A1930�N�ォ��̏d�v�ȋ��P�́A�����������h���͏��������ʂ��������Ȃ����Ƃ�(One crucial lesson from the 1930s is that a small fiscal expansion has only small effects.)��2009�N�ɏq�ׂĂ���B2013�N�ɂ́u���̍l���ł́A�勰�Q����w�ׂ�̂́A���̗��_�y��������͎����Ă݂�@�\����z�����ؓI�ȍ����ɂ���Ċm�����Ƃ������Ƃł��B1930�N��ɗp����ꂽ�Ƃ��A��������͌��ɉɔ��Ԃ������Ă��܂��B��Ȗ��_�͍������]��p�����Ȃ��������ƂȂ̂ł��B�v�Əq�ׂĂ���B
�|�[���E�N���[�O�}���́u�ꕔ�̌o�ϊw�҂͑勰�Q�₻�̈Ӗ������������ĖY��Ȃ������B���̈�l���N���X�e�B�E���[�}�[�ł���B��@�J�n����4�N�o������(2012�N)�A��������Ɋւ���D�ꂽ����(���̂قƂ�ǂ��Ⴂ�o�ϊw�҂ɂ�����)����������B�������������͊T�ˁA�����h���͗L�����Ɨ��t������̂ł���A��K�͂ȍ����h�������ׂ����Ǝ������Ă���B�v�u���Ɏ���X�e�B�O���b�c��N���X�e�B�[�i�E���[�}�[���A�s���ɒ��ʂ��Ďx�o�팸������̂͂�������������邾���ŁA�ꎞ�I�Ȏx�o�����ɗL�v���Ǝ咣���Ă���̂�ǂƂ��ɁA�w����͔ނ�̌l�I�����ł���x�Ƃ͎v��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���邱�Ƃ��肢�����B���[�}�[����������ɂ��Ă̌����Ɋւ���ŋ߂̉����ŏq�ׂ��悤�ɁA
�������d�v���Ƃ����؋��́A���ĂȂ��قNj����Ȃ��Ă��܂��|�|�����h���͌o�ς��E�𑝂₷�̂ɖ𗧂��A�����Ԏ������炻���Ƃ���Ώ��Ȃ��Ƃ��Z���I�ɂ͐��������������Ă��܂��̂ł��B����Ȃ̂ɁA���̏؋��͗��@�v���Z�X�ɂ͓`����Ă��Ȃ��悤�ł��B
�l�����͂����ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�B
���o�[�g�E���[�J�X�̓��[�}�[�̕��͂��u���̗��R�ł��łɌ��܂��Ă�������ɑ��āA��t���Ő��������s�����}���v�Ɣᔻ�����B
���o�[�g�E���[�J�X�̌����ɂ��āA�|�[���E�N���[�O�}���́u���̍����́w���J�[�h�̒�������x�Ƃ��������������B�����Ă��̎咣�ɂ���āA���̌����̎��ۂ̎d�g�݂����������m��Ȃ����A�m���Ă����ɂ��Ă��Y��Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�\�I�����v�Ɣᔻ�����B
���������́A�u�j���[�f�B�[������̑����́A���܂�ɂ��v���I�ł��肷�������߁A�����ɘA�M�ō��قɂ���Ĉጛ�����������ꂽ�قǂł������B���[�Y�x���g�哝�̂́A�d���Ȃ��A�e���[�Y�x���g�I�@���Ƃ��A�����A�ō��ٔ����ɔC�����āA����ƍ��������������߂�Ƃ�����p���Ƃ炴������Ȃ������B���ʂ̐l�X�̉�b�ɂ����āA�u�����̓j���[�f�B�[���[�v���ƌ����A��O�̓��{�ɂ����āA�u�����̓A�J���v�Ƃ������炢�̈Ӗ��ł������B�v�u��������TVA(�e�l�V�[�k�J�J������)�Ȃǂ̐ݔ��������吭����Ƃ��Ă��A�ÓT�h(�����̃A�����J�ɂ����ẮA���|�I�����h�ł�����)�ɔ������ƁA�������߂��B����Ȃɐݔ����������Đ��{�x�o������������ƍ����͔j�]���邼���|�߂����畏�����B�v�Əq�ׂĂ���B
�F��O���́A�u�A���V�������W�[���͓���TVA�ɕK���ɒ�R���A�u���Ԃ����ׂ��d���𐭕{�����͈̂ጛ���v�Ƃ����i�ׂ����x���N�����A�A�M�ō��ٔ������ጛ�������o���B������āA1943�N�ATVA�͑g�D��啝�ɕς��āA�n�����{�̎����Œn��J����S�����鐧�x�ƂȂ��āA�h�����ĎЉ�I���ʎ��{�Ƃ��Ă̑̍ق�ۂ��Ƃ��ł����BTVA�Ƌ�s�@�̓���s�ꌴ����`�҂������J��Ԃ��ᔻ���A���̉�̂����݂��킯�ł���v�Əq�ׂĂ���B |
���P�C���Y�Ƃ̊W
���[�Y�x���g���g�͍����ύt��`�҂ł���A�Ԏ������ɔے�I�������Ƃ���Ă���B�P�C���Y����Ă���������������[�Y�x���g���̗p�����Ƃ���Ă��邪�A����ɂ��Ă̓��[�Y�x���g���g���ے肵�Ă���B���[�Y�x���g�́A1934�N�ɃP�C���Y�ƈ�x��������Ă��邪�A�u���v�̐�������ŗ����ł��Ȃ������v�Ƙb���Ă���B�P�C���Y�ƒ��ڑΘb�������[�Y�x���g�́A�P�C���Y�̐Ԏ������s�ɂ��i�C�h������̘b���u�r�����Ȃ��z���b�v�Ɛ�̂Ă��Ƃ����B�Ȃ��A�j���[�f�B�[�������1933�N������{����Ă���A�P�C���Y�́w��ʗ��_�x��1936�N�ɏo�ł���Ă���B
|
�����{
���̓��{�l�̏펯�̈�ɁA���E���Q�̓��[�Y�x���g�哝�̂ɂ��P�C���Y�^�̍�������ɂ���ĉ����A�Ƃ������̂�����B
�c���G�b�́u�����̃P�C���Y����̗����̌��^(�j���[�f�B�[���^�̐���ɂ�鐢�E���Q����̒E�o�Ƃ����V�i���I�Ƌ��Z����̎�����̖���)�͓s���d�l�ɂ���čL�߂�ꂽ�v�Ǝw�E���Ă���B
�o�ϊw�҂̓s���d�l�́u�w�����I���v�x�T�O��2�ł���w���h�x�Ɓw�S�I�A�Ɓx�������ɖ������ꂽ���Ƃ��A�����m�푈�J�n�Ɏ���܂ł̍D��I�ԓx�̏\���̍����ƂȂ����B�w�j���[�f�B�[���x����͂������Đ푈�Ɍq�����Ă������v�Ǝw�E���Ă���B�c���G�b�́u���{�̃P�C���Y�^�������푈�������A�푈�ɂ���Đ��E���Q���������ꂽ�A�Ƃ��������ł��U�������咣�̋N���́A�s���ɂ����̂ł���v�Ǝw�E���Ă���B�@
�@ |
| �����E���Q 7 / ���ی��ϋ�s |
   �@
�@
|
|
[Bank for International Settlements�A����: BIS]�@1930�N�ɐݗ����ꂽ������s���݂̌��ς�����g�D�B�ʉ݉��l�Ƌ��Z�V�X�e���̈����ړI�Ƃ��Ē�����s�̐���ƍ��ۋ��͂��x�����Ă���B |
��BIS
1924�N�̃h�[�Y�ĂŁA�������������̒�����s�ɑ��t���锅���㗝�@�ւ�ݗ����邱�Ƃ͌��܂��Ă����B
�h�C�c�̑�ꎟ���E���ɂ����锅�����x�����̍s���l�܂��ŊJ���邽�߂Ƀ����O��(1930�N)����Ă��ꂽ�B�����O�Ăł́u���ی��ϋ�s�Ɋւ�����v�Ɓu���ی��ϋ�s�芼�v���̑�����A����炢����n�[�O���ɂ�蔅�����̎x�������~���������邽�߂̋@�ւƂ���BIS ���ݗ����ꂽ�B���{�́A�E�H�[���X��\�� (1929�N)�̂��Ȃ��ŃN���W�b�g��ݒ�A1930�N��BIS�n�ݎ��ɂ͊���ƂȂ��Ă����B���E���Q�����������Ƃ���i�`�}�̌��͏������A�h�C�c�����Ĕ������x���������ۂ������BBIS �͔������̎戵�@�ւƂ��Ċ����ł��Ȃ��Ȃ�A�����ɒ�����s�Ԃ̋��͂𐄐i����悤�ɂȂ����B
BIS �͎��Y�^�p���s���Ă���B1932�N3���̕ł́A���O���s��ւ̐ϋɓI�ȓ����ɂ���s�����`�ւ̉^�p���������B
���͂̎��ԂƂ��āA�n�ݎ��_��BIS �͋��a��������Ă��Ȃ��������A1932�N11���Ɏ������j�𖾂炩�ɂ����B
��BIS �͊e������s�̊���ɂāA�n���E���݂��̑��̌`�ŋ����a���Ƃ��Ď����B
��BIS �ɂ͋��ɂ��Ȃ��̂ŁA�a�����钆����s(�`)�́A���s�ȊO�̒�����s(�a)�ɂ�����BIS �̊���ɋ��������B
�����ۂɋ����a���钆����s(�a)�́A���̋���BIS ���`�̎g�r�w�}���Ƃ��ėa����B
��BIS �́A���g�̊���ɂĒ�����s(�`)�́u�ۏ؊���v���J���B
����L�́u�ۏ؊���v�����́ABIS �芼��10���̕ی����B
��������s(�`)�́A�a�����g�r�w�}��̒�����s(�a)�ɔ��p�E����������A�O���בւɕς�����A���̋@�ւɔ��p�E�����ł���B
���O���בււ̊����̏ꍇ�A������s(�`)���v������בւ�(�a)���̈בւł���Ƃ��ABIS �͂������Ɏ��Ȗ��`�Ŋ��������s����B(�a)���ȊO�̈בւł���Ƃ��ABIS �͗a�������������������ł��̋���݂��o���āA���̈בւ�B
����E���̊g��ɂ��BIS �͋�����j���[���[�N��������Ȃǂ��Ď��Y���A�����J�֔����Ă����B���̎��Y��č����Ȃ��u�G�����Y�v�Ƃ��č����������A1940�N6��25���j���[���[�N�A�M������s���������Í��d��ɂ�蓀����BIS �̒m��Ƃ���ƂȂ����B������BIS �芼��10���͑R�ł��Ȃ������B�Đ��{�͐�̃n�[�O���ɒ��Ă��Ȃ������BBIS ���̈�����A�M�������x�ł͂Ȃ��AJP�����K���Ȃǂ̖��ԋ�s�c���s���Ă����B���������C���M�����[���N���钼�ڂ̂��������̓w�����[�E�X�e�B���\����1929�N��FRB �E����BIS �����o�[�ƂȂ邱�Ƃ𐺖��ŋւ������Ƃł������B
���A�����Ƀi�`�X�W�҂̂������Ƃ�������A�u���g���E�b�Y��c������U����������āA�P�C���Y���������咣�����ɂ�������炸�p�~�����肵���B�������t�����X�ƃX�E�F�[�f�������u�����������Ƃ�(���B���ϓ������Q��)�A���ɏq�ׂ闪�D�����̌����ɂ��A�p�~�Ă�1948�N�ɗ��������ƂȂ����B
���C�q�X�o���N���BIS �ɋ������ꂽ���D��3.74�g���́A�u�^������s�v����s����BIS �ɕԊ҂��Ă����z���T���̏�A3.366�g�����C���O�����h��s�֗a�����ꂽ�B�A�����A�Ƃ�킯�A�����J��BIS �ɔ�Q������̕Ԋ҂����߂��BBIS �͎��̂悤�ɉ��������B�u���̑啔���̓A�����J�Ɍ������Ă���̂ŁA�Ԋ҂ɉ����邽�߂ɂ́ABIS �ɑ���G�����Y�Ƃ��Ă̓������������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v1947�N10���ɕĐ��{��\�̃A���h�����[�E�I�[���@�r�[(Andrew Overby)���A�ݕăX�C�X��s���Y�̓������������ɃX�C�X�ւ���Ă����BIS �͋@��ɑ������BBIS �̓����ɔ��s�ς݊����ɂ����G�����Y�ɂ�������Ƃ̃V�F�A��22.8���ł������B�����֗a������Œ���x�a�����������33.8���ɒB�����B�܂��A�����O�Ăɂ��BIS �̑ΓƎ��Y��2��9116���X�C�X���t�����ł���A1945�N�x��BIS �����Y�z��64.5���ɂ̂ڂ����B1948�N2���A�W�����E�X�i�C�_�[����@�O���ψ����Ɍ����āA���B���̖��Ԏ��{�������������ĕ����ɐU�����������ׂ��Ə��������Ă���B
BIS ����������ƃ}�[�V�����E�v�������h�C�c�̎x�����\�͂����X�ɗ��Ē������B
1950�N10����11���C���O�����h��s�����{�ۗL��BIS �����v�����Ă����B���ʂƂ��ē��{��1951�N�̃T���t�����V�X�R�u�a���ɂ���Ċ�������������B���̌�A���ۋ��Z�E�ւ̕��A��S�苭�������������W�҂̓w�͂̌��ʁA1964�N�ȍ~�ABIS�ŊJ�Â���钆����s�̉�ւ̒���I�ȎQ�����F�߂���悤�ɂȂ�A1970�N�ɂ͑����ɂƂ��Ȃ����{��s������Ƃ��ĕ��A�����B�Ȃ��A���̔N�ɂ̓J�i�_���������Ă���B�����ړI�̓O���[�o�����Z�V�X�e���ψ���̐ݒu�Ǝx�����ώ��Ƃ̊J���ł���B
1961�N11���ɋ��v�[�����^�c���͂��߂��BBIS ��1932�N11���ȗ������h����x�����Ƃ��������[���b�p�̋��s����Ǘ����Ă����B������x�[�X�Ƃ���1961�N���R�u�\���̍\�z�ǂ���A�|���h�E�X�^�[�����O�𒆐S�Ƃ��錈�ϋ@�\���ł����̂ł���B�^�c�̎��Ԃ́A�ꎞ�ɋ��̓�d���i���������ꂽ�����Ɍ�����Ƃ���A�u���g���E�b�Y�̐��Ƃ͈��̋�����u���Ă����B�|���h��@�ł͑勰�Q�̂Ƃ��̂悤�ɁA������s��BIS �ւ̗a���������o���ċ���Ɋ����āABIS ���`�̎g�r�w�}���Ƃ��ĕʂ̋@�ւ֗a�������B
1975�N7��8����BIS �͒芼���������Ă���A���s�̂��̂ƂȂ��Ă���B |
���g�D
BIS�́A���E�e���̒�����s���o������@�l�ł���A2011�N����58�����̒�����s������ƂȂ��Ă���B�ō��ӎv����@�ւ͊��咆����s�̑�\���o�Ȃ��鑍��(General Meeting)�ŁA�g�D�K��̉����A���Z�̏��F�Ȃǂ̌�����L����B�N1��A6��������7�����ɊJ�Â���Ă��邪�A�Վ�����̊J�Â��\�ƂȂ��Ă���B
BIS�̑g�D�Ƃ��Ẳ^�c���j�̌���Ȃǂ͗�����s���Ă���B������́A2011�N���c����19���̗����ɂ���č\������Ă���A���Ȃ��Ƃ��N6��J�Â����B2011�N���_�ŗ�����̋c���̓t�����X������s���كN���X�`�����E�m���C�G�A���c���͓��{��s���ٔ�������ł������B2015�N11������A�c���̓h�C�c�A�M��s�̃C�F���X�E���@�C�g�}���A���c���̓C���h������s�̃��O�����E���W���������߂Ă���B�����O�Ă��琶�܂ꂽBIS ���������āA����Ɠ��ڂ̋c���͍��O������o�Ă���B
�ݗ������̒芼��28���ɂ��\���́A1�h�C�c�E�x���M�[�E�t�����X�E�C�M���X�E�C�^���A�E���{�E�A�����J�̊e��������s�̌��E���فA2���Y���ق����̐E������ł��Ȃ��ꍇ�ɂ��̑��ق��w�����闝���A3�e����قɂ�1�����C������闝���B�u���قƓ��ꍑ�Ђ�L������Z�ƁA�Y�Ƃ܂��͏��Ƃ��\����ҁv����I�ꂽ�B4�����x�������Ԓ��́A�t�����X��s����у��C�q�X�o���N�̑��ق��C�ӂŁu�Y�Ƃ܂��͏��Ƃ��\���邻�ꂼ��t�����X������уh�C�c���̍��Ђ�L�����2���v��C���ł����B�n�ݎ���BIS ������\���́A�����ɓ��{��BIS ��E�ނ����ۂɕύX���ꂽ�ق���2013�N���݂܂ňێ�����Ă���B���s�̒芼��27��3���ł́A���{����������L6�J��12��(12)�̂ق��A�u�E��������I�o���Ă��Ȃ������ۗL���̒�����s���ق̂Ȃ�����A�������2/3�ȏ�̎^���ɂ��A9���������Ȃ��v������I�o���Ă���B���̗����͔C��3�N�A�ĔC�\�ł���B1994�N�ɂ̓J�i�_�E���{�E�I�����_�E�X�E�F�[�f���E�X�C�X���A2006�N�ɂ͒����E���L�V�R�E���B������s���A���ꂼ�����ɉ�����Ă���B
����Ɩ��̉^�c�͑��x�z�l(General Manager�A���L���)�ȉ��̐E�����S���Ă���A�E������600����ł���(2011�N����)�B
Jaime Caruana (2009�N4��1�� -)
Malcolm D. Knight (2003�N4��1�� - 2008�N9��30��).
Andrew Crockett (1994�N1��1�� - 2003�N3��31��)
���x�z�l�̒n�ʂ�1981�N�܂Ńt�����X������߂Ă����B
|
��������s�ԋ��͂̏�Ƃ��Ă�BIS
BIS�͎��̂悤�Ȋ�����ʂ��A���̖ړI�𐋍s���Ă���B
�e���̒�����s���݂̋c�_�𑣐i���A�����W�𐄐i���邱�ƁB
���Z�V�X�e���̈���ɐӔC��L���钆����s�ȊO�̑g�D�ƒ�����s�Ƃ̑Θb���x�����邱�ƁB
������s����т��̑��̋��Z�ē��ǂ����ʂ��Ă��鐭���I�ȉۑ�ɂ��Ē���������i�߂邱�ƁB
������s�ɑ����ċ��Z�s�������s�����ƁB
���ۓI�ȋ��Z�I�y���[�V�����ɍۂ��㗝�҂܂��͎���҂ƂȂ邱�ƁB
BIS�͊e���̒�����s������Ƃ����s�Ƃ��đg�D����Ă���B������s�Ȃǂ̑�\������J�Â��镑��ƂȂ�ق��A���Z�Ɋւ��邳�܂��܂ȍ��ۓI�Ȉψ���ɑ������Nj@�\����Ă��邱�Ƃł��m���Ă���B
�e���̒�����s�����݂ɋ��͂����Ƃ��Ă�BIS�̖�����@���Ɏ����Ă���̂��A������s�̑��ق��Q������u���̏���ł���B2011�N11���ȍ~�A��v��̋c���̓C���O�����h��s���ك}�[�r���E�L���O(Mervyn King)�����߂Ă���B
�X�^�b�t�E���x���ł̉���������J�Â���Ă���A��\�I�Ȃ��̂Ƃ��ăo�[�[����s�ēψ���(�o�[�[���ψ���ABCBS)�A�O���[�o�����Z�V�X�e���ψ���(CGFS)�A�x�����ψψ���(CPSS)�A�s��ψ���A������s�K�o�i���X�E�t�H�[�����A�A�[�r���O�E�t�B�b�V���[�ψ���Ȃǂ�����B
���̂ق��ABIS�́A������s�̋Ɩ��ƊW�̐[�����ۓI�Ȉψ���ł���A���Z�V�X�e���ψ���(Financial Stability Board�AFSB)�A�ی��ēҍ��ۋ@�\(IAIS)����э��ۗa���ی�����(International Association of Deposit Insurers)�Ɏ����Nj@�\����Ă���B |
���o�[�[����s�ēψ���
�o�[�[����s�ēψ���(�o�[�[���ψ���ABasel Committee on Banking Supervision(BCBS))�́A��s�ēɂ����邳�܂��܂Ȗ��Ɋւ��鍑�ۓI�ɋ��ʂ̗����i���邱�Ƃ�ʂ��A���E�e���ɂ������s�ē̋�����ڎw���ψ���ł���B�ψ���̊�����ʂ��Č`�����ꂽ���ʂ̗�������ɁA��s�ēɊւ���T���I�ȋK���A�w�j���邢�͐����������Ƃ�܂Ƃ߂Ă���B
���O���[�o�����Z�V�X�e���ψ���
�O���[�o�����Z�V�X�e���ψ���(Committee on the Global Financial System�ACGFS)�́A������s�̗��ꂩ��A���ۋ��Z�s��ɋْ��������炵���˂Ȃ������Ƃ��̏d�v���͂��邱�ƁA���Z�s��̋@�\���x���鐧�x�I�ȗv���̗�����[�߂邱�ƁA����сA���������s��̋@�\�x�ƈ��萫�̌���𑣐i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
1962�N�ABIS �̓��[���J�����V�[�s����Ɖ�c�������ɗ����グ���B���B���ϓ����̌��ϋƖ���S���Ă���BIS �́A������1958�N�ɉ��U���ċƖ����p���ł��Ȃ��Ȃ��Ă���A�V���Ƃ̊J���͍����Ă����BCGFS ��1971�N�Ƀ��[���J�����V�[��C�ψ���(���[���ψ���AEuro-currency Standing Committee(ECSC))�Ƃ��Đݒu����A1999�N�Ɍ��݂̋@�\�Ɩ��̂�^����ꂽ�B
���x�����ψψ���
�x�����ψψ���(Committee on Payment and Settlement Systems�ACPSS)�́A�x���E���σV�X�e���ɂ����錒�S���ƌ������̌���𑣐i���邱�Ƃ�ʂ��A���Z�s��̃C���t�����������邱�Ƃ�ڎw���Ċ������Ă���B���ψ���́A���K�̎x������舵���V�X�e������я،���������ς���V�X�e���̉^�p������肵�Ă���ق��A������s��������������ɂ����铮����c�����邽�߂̏�ƂȂ��Ă���B���̊ώ@�ΏۂƂ̓N���A�X�g���[���A���[���N���A�A���ۋ�s�ԒʐM����Ȃǂł���B2014�N6���A�V���Ȍ��͂̏��F���āA���̂����ρE�s��C���t���ψ���(Committee on Payments and Market Infrastructures�FCPMI)�֕ύX�����B
���s��ψ���
�s��ψ���(Markets Committee)�́A1962�N�ɂ�������v�[���̐ݗ��ƂƂ��ɁA��Ƃ��ĊO���ב֎s��̓����ɂ��Ĕ�����Ȉӌ��������s����Ƃ��Ĕ��������B���݂́A�O���ב֎s��Ɍ��炸�A������s�̃I�y���[�V�����ƊW�̐[�����܂��܂ȋ��Z�s��̒Z���I�ȓ����̂ق��s��\���̕ω��ɂ��œ_�ĂĊ����𑱂��Ă���B
|
���o�[�[������(������BIS�K��)
�o�[�[���ψ���Ƃ�܂Ƃ߂���s�ēɊւ���w�j�̂����A��Ƃ��ċ�s���ۗL���ׂ����Ȏ��{�̗ʂɊւ���w�j�̑��́B���ۓI�Ɋ������Ă����s�ɑ��A�M�p���X�N���������ĎZ�o���ꂽ�����X�N���Y�̈��䗦(������8%)�̎��Ȏ��{�ۗ̕L�����߂����́B�o�[�[���ψ���ɎQ�����Ă���e���̊ē��ǂ̋K���̌n�ɍ̗p����邱�ƂŎ��������`���Ƃ��Ă���A�o�[�[�����ӂ��̂��̂��@�I�Ȍ��͂�L�����ł͂Ȃ��B�܂��A�����̂̃o�[�[���ψ����BIS���̂��ʂ̎�̂ł��邽�߁ABIS�K���Ƃ������̂͌�����܂˂����̂ł���B
|
���o�[�[��I
1988�N�Ɍ��\���ꂽ�ŏ��̍��ۓI�ȋ�s�̎��Ȏ��{�䗦�Ɋւ��鍇�ӁB���{�ł�1988�N�x����ڍs�[�u���K�p����A1992�N�x������{�i�K�p���J�n���ꂽ�B���ۓI�Ɋ������Ă����s�ɑ��A�M�p���X�N���������ĎZ�o���ꂽ�����X�N���Y(�����郊�X�N�E�A�Z�b�g���z)�ɐ�߂�8%�̎��Ȏ��{�ۗ̕L�����߂����́B1996�N�ɂ͎s�ꃊ�X�N�ɑ���lj��I�ȍ��ӂ����\����Ă���B
�o�[�[��I�ɂ����ẮA��s���ۗL���銔���̊܂݉v�̍ő�45%�����Ȏ��{�Ɋ܂߂邱�Ƃ�F�߂Ă����B�Ƃ��낪�A�o�[�[��I�Ɋ�Â����{�����̎��Ȏ��{�䗦�K���̐���Ǝ��{���o�u���i�C�̕����w�i�Ƃ��������̃s�[�N�E�A�E�g���܂������̂ƂȂ������Ƃ���A���{�̋�s�͊����̊܂݉v�����҂��Ă����قǎ��Ȏ��{�Ɋ܂߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B���������ɑ��A���{�̋K���Ώۍs�͕K�v�Ȏ��Ȏ��{�̊m�ۂ̂��ߓ]���Ѝs����Ȃǂ̑���ȓw�͂����B�����ċK�������S�ɓK�p�J�n�ƂȂ���1993�N(����5�N)�x3���������Z�܂łɂ��ׂĂ̋K���Ώۍs���K����B�������B
���̌�A�o�u���i�C�̕���ɂ��i�C�̒�����[�������钆�ŁA���{�̋�s�̕s�Ǎ��͑��債�A���N�̌��Z�ɂ����đ��z�̍����p�𔗂���悤�ɂȂ����B���̌��ʁA���p�ɂ�鎩�Ȏ��{�̌����ɂ���Ď��Ȏ��{�䗦���Œ��(8%)�����荞�މ\�����ӎ������悤�ɂȂ����B���ꂪ��s�̗^�M�p���̌�ނ������炵�A���{�̌i�C����������������ƂȂ����Ƃ̌���������B
|
���o�[�[��II (������VBIS�K��)
�f���o�e�B�u����̈�ʉ��ȂǁA1990�N��㔼�ȍ~�̍��ۋ��Z�s��̔��W�ɏƂ炵�K���̌n�̕s�����ڗ��悤�ɂȂ������߁A��s�̃��X�N�ʂ���萸�k�Ɍv������Ȃǂ̕����Ńo�[�[��I�̓��e�̌��������s��ꂽ�B���̌��ʁA2004�N�Ɂu���Ȏ��{�̑���Ɗ�Ɋւ��鍑�ۓI���ꉻ�F�������ꂽ�g�g�v(�o�[�[��II)�����\���ꂽ�B�o�[�[��II�ł́A�����X�N���Y�̎Z���ɂ����āA����܂ł̐M�p���X�N�Ǝs�ꃊ�X�N�ɉ����A�I�y���[�V���i�����X�N���������邱�Ƃ���߂��Ă���B
�o�[�[��II�f�������Ȏ��{�䗦�K���́A���{�ł�2006�N�x�����{�s����Ă���B��̓I�ȋK���̓��e�́A�u��s�@��14����2�̋K���Ɋ�Â��A��s�����ۗ̕L���鎑�Y���ɏƂ炵�����Ȏ��{�̏[���̏��K���ł��邩�ǂ����f���邽�߂̊�v(�����鎩�Ȏ��{�䗦�����B2006�N3��27���t���Z��������19��)�ɋL�ڂ���Ă���B�܂��A2007�N2���ɂ͋��Z�����}�j���A�����o�[�[��II�ɑΉ����S�ʉ��肳��A���\���ꂽ�B
|
���o�[�[��III
�o�[�[���ψ���́A2007�N����2008�N�ɂ����Ĕ����������ۋ��Z�o�ϊ�@�̔w�i�ƂȂ�����s�ē̖��ɑ��锽�Ȃ܂��A��s�̎��Ȏ��{�̎��̌���A���X�N�Ǘ��̈�i�̋����Ƃ������ϓ_����A2009�N�ȍ~�o�[�[��II�����������Ƃ�i�߂Ă���A���̈�A�̐��ʂ̓o�[�[��III�Ƒ��̂���Ă���B�V���ȍ��ӂ̊�{�I�ȓ��e��2011�N1���Ɍ��\����Ă���A��s�ɑ��A2019�N�x���܂łɁA�����X�N���Y��7%�ɂ����镁�ʊ����Ȃǎ��̍������Ȏ��{�ۗ̕L�����߂�ȂǁA�o�[�[��II�����K������������Ă���B���̋����Ɏw�E�������_�͎��̂悤�ɐ��������B
�e�䗦�ɂ����ĕ��q�̋c�_�ɕ��Ă���A����(���X�N�E�A�Z�b�g���z)�̋c�_���u������ɂ���Ă���B
���˂ȃ��o���b�W�䗦�̓����́A���Z�K���̉�ꉻ�E�P�����ł���B
�}�N���o�ϐ����s���ċ��Z��@���N�����ӔC���ʋ��Z�@�ւɕ��킹�Ă���B
���Z��@�̐k�����牓���A�W�A�n��̋��Z��݉�������B���Z��@�͕K�������O���[�o���ł͂Ȃ��B
�K���̋�̓I���e�́A�V�e�B�O���[�v�،��ɂ��Ǝ��̂悤�ɐ��������B
��2013�N1������̓�����2019�N1���܂ł��ڍs����
�R�ATierI��4.5���ȏ�ATierI��6.0���ȏ�A���Ȏ��{�䗦��8.0%�ȏ�
����Ɏ��{�ۑS�o�b�t�@�[�܂߁A�R�ATierI��7%�ȏ�ATierI��8.5%�ȏ�A���Ȏ��{�䗦��10.5%�ȏ�
��2013�N1�����玎�s���ԂŁA2018�N1������{�i�����̗\��
���o���b�W�䗦3%�ȏ�
���������̋K��
LCR(LiquidityCoverageRatio �Z�������J��w�W�B2013�N1����莎�s���ԁB2015�N1���{�i�����\��)�@30�����̏��L���b�V���x�����ɑ��闬�����̍������Y�̔䗦100%�ȏ�
NSFR(Net Stable Funding Ratio ���������J��w�W�B2013�N1����莎�s���ԁB2018�N1���{�i�����\��)�@�Z�����B�ƒ����^�p����s���čs����s�̕�����A���Ԃ̃~�X�}�b�`���X�N�ւ̑ϐ��B�����ԌŒ肳��鎑�Y�ɑ��Ĉ��蒲�B�z�̔䗦100%�ȏオ�ۂ����B���̂Ƃ���A�M��̗a����9�������蒲�B�̌����ɂȂ�B
�����Ȏ��{�\�����ڂ��猩���o�[�[��II�ƃo�[�[��III�̑���
�ȉ�BIS�Ɋ�Â��B�o�[�[��II�͎��̒ʂ�B
�R�ATierI�@- ���ʊ��Ɠ�������
�R�A�łȂ�TierI�@- �D�抔�ƗD��o���،�
TierI�̍T�����ځ@- ���̑��L���،��]�����A�̂��A�J���ŋ����Y���ߊz(TierI 20%��)�A���Ȋ����A������s���̘A���O�q��Џo��
TierII�@- ���E��ネ�[���A�y�n�ĕ]�����z����45���A���̑��̗L���،��]�����z(45%)�A��ʑݓ|������(�������)
TierIII�@- �Z�����E���[��
�o�[�[��III�͎��̂悤�Ɍ������������Ă��邪�A�o�ߑ[�u�̏�ł���Ɍ������𑝂����ڂ�����B
�R�ATierI�@- ���ʊ��A�������ہA���̑�����v
�R�A�łȂ�TierI�@- �D�抔�A���������z���͂������{�،��@�@���o�ߑ[�u�̏�Ŏ������߂������
TierI�̍T�����ځ@- �̂��A�J���ŋ����Y(������)�A���Ȋ����A���`�Œ莑�Y�A�����O���Z�@�֏o���A�N�����Y�A��
TierII�@- ���E��ネ�[��(���������z���͂̂�����̂Ɍ���)�A��ʑݓ|�������@�@���o�ߑ[�u�̏�Ŏ������߂������
TierIII�@- �p�~�@
�@ |
| �����E���Q 8 / ���E���Q�Ƃ��̉e���@�L�[���[�h |
   �@
�@
|
�����E���Q
1929�N�`1933�N�ɐ��E�œ����ɋN�������o�ϕs��(���Q)�̂��ƁB���[�̓A�����J���O���̃E�H�[���X�ɂ���j���[���[�N�����������1929�N10��24��(��Ɂu�Í��̖ؗj���v�Ƃ���ꂽ)�Ɋ�������\���������ƁB1930�N��ɓ����Ă��i�C�͉����A��Ɠ|�Y�A��s�̕��A�o�ϕs�����ꋓ�ɐ[���ɂȂ��āA1300���l(4�l��1�l)�̎��Ǝ҂��ł��B���Q�͂��悻1936�N���܂ő������B�܂����̋��Q�����E�ɔg�y���A���[���b�p�e��������{�ȂǃA�W�A�����ɂ��e�����A���{��`�e���͋��Q����̒E�o���͍����钆�őΗ���[�߁A��2�����E��킪�����炳��邱�ƂƂȂ����B
�A�����J���̐��E���Q�@/�@�A�����J�̓�����(����)�����́A�����̂悤�ɂ�����ł�������������ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƕs���ɂȂ�A�����̒l������O�ɔ����Ă��܂����Ƃ����S������Ăɓ����āA1929�N10��24��(�ؗj��)�ɁA�j���[���[�N�̃E�H�[���X�ɂ��銔��������ň�ĂɊ������\�������B��Ƃɓ������Ă�����s�ɑ��A�a���҂͈�Ăɗa���������o���ɎE�����A�x������Ȃ��Ȃ�����s���|�Y�B�Z���̃X�g�b�v������Ƃ͓|�Y���A�H��͕�����A�J���҂͉��ق���Ď��Ǝ҂����ӂꂽ�B�L�����v�͂܂��܂��ቺ���A����ɕs���������Ƃ������z�Ɋׂ����B�����̃A�����J���a�}�t�[���@�[�哝�͕̂s���͎����I�Ȃ��̂ŁA�i�C�͂܂��Ȃ�����ƍl���A�܂��u���R���C��`�v�A�܂�s�ꌴ���ɔC���Ă��������Ƃ����]���̋��a�}�̊�{���j����������ߑΉ����x��邱�ƂƂȂ����B
�A�����J�̌o�ϕs���̗v���Ɣw�i�@/�@�A�����J�̋��Q�����̗v���Ɣw�i�Ƃ��Ă͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��l������B
�E1920�N��̐��D���̒��Őݔ��������ߏ�ɂȂ�A�u���Y�ߏ�v�Ɋׂ����B
�E�_�Y�����ߏ萶�Y�̂��߂ɉ��i�̉���(�_�ƕs��)���A�_�Ǝ����������A�����̗L�����v���ቺ�����B
�E�e���Ƃ������Y�Ƃ̕ی�̂��߁A���Ő�����̂����̂ŁA���E�s��̊g����j�~����Ă����B
�E�����ɃA�W�A�̖������{�̐����A�\�A�Љ��`���̐����ȂǂŁA�A�����J�̎s�ꂪ�k�����Ă����B
���E���Q�ƂȂ������R�@/�@1931�N5���A�I�[�X�g���A�̋�s�N���f�B�b�g���A���V���^���g���j�Y���A���Q�̓h�C�c�ɂ��g�y���u���E���Q�v�ƂȂ������A�A�����J���̊����\�������E���Q�Ɋg�債�����R�͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��l������B��1�����E����A���E�ő�̍����ƂȂ��Ă����A�����J���O���̌o�ς��j�]�������Ƃ́A�K�R�I�ɐ��E�o�ς�j�]�����邱�ƂɂȂ������B���ɁA���z�̔������ƕ�������Ă����h�C�c�̓A�����J�̎x���Ōo�ς����藧���Ă���(�h�[�Y���v����)�̂ŁA�h�C�c�o�ς��j�]�A���̃h�C�c���甅��������藧�ĂĂ����C�M���X�E�t�����X�̌o�ς��j�]�����B�h�C�c�ł�3�l��1�l�����ƁA���E�S�̂̎��Ǝ�5000���ɒB����Ƃ����Ƃ����ƂȂ����B
���E���Q�ɑ��铖���̑�@/�@�A�����J���O����1930�N6���A�X���[�g���z�[���[�@�𐬗������A�_�Y�������ł͂Ȃ��H�Ɛ��i�ł��ň����グ�����{�����B�e���������Y�Ƃ���邽�߂ɁA�ی�f�Վ�`�ɓ]���������߁A���E�I�Ȗf�Օs�U���N���A�������ċ��Q���������邱�ƂƂȂ����B�܂��t�[���@�[�哝�̂�1931�N�Ƀt�[���@�[�������g���A��(�x���P�\��)�A�\���A��E�������x������1�N��~���邱�Ƃɂ������A�^�C�~���O���x�����Č��ʂ͂Ȃ������B�e���͌o�ς𗧂Ē������ߎ��X��1931�N�̃C�M���X�̋��{�ʐ���~�ɑ�����33�N�ɂ̓A�����J���O�������{�ʐ����痣�E�ɓ��ݐ�A���E���{�ʐ��͕����B���{��`�͒ʉ݂��Ƃ̃u���b�N�o�ϐ�����̗p���邱�ƂƂȂ����B�������A�e�����u���b�N�o�ςɂ���ĕی��`�ɓ]�������߁A���E�S�̂̎��R�f�Ղ����ނ��Ėf�Պz���������A���E�S�̂̕s���ɂ���ɉ��������邱�ƂƂȂ����B
���E���Q�̋y�Ȃ������Ƃ���@/�@���̂悤�ɁA���{��`�͎s�ꌴ���ɔC�����܂܂��Ə�ɂ��̂悤�Ȗ������N����B�����ŁA���{��`�o�ς�ے肵�č��Ƃɂ��v��o�ςɂ���ċ��Q���N���Ȃ��悤�ɂ��悤�Ƃ����̂��Љ��`�̍l���ł���B�����A���E���Q���N���������ɂ��łɎЉ��`�̐����Ƃ��Ă����\���B�G�g�Љ��`���a���A�M�͂��̉e�������A�܃J�N�v��𐄐i�����B�������A�����ɃX�^�[�����ƍّ̐����`������Љ��`�����ꂩ��ώ������B
�A�����J�̃j���[���f�B�[������@/�@1933�N�ɓo�ꂵ���A�����J���O���̂e�����[�Y���F���g�哝�̂̃j���[�f�B�[������͔_�Y���̉ߏ苟����}���A�H�Ɛ��Y�̍��ƊǗ������߁A�啝�ȍ����o���Ō������Ƃ������Čٗp��n�o���A�����w���͂̉�}�����B�܂��A���̂��߂ɂ͘J���҂̕ی��Љ�ۏ�̏[���Ȃǂɂ����g�݁A��s���������Ď�����Ȃǎ��{��`�̘g���ł̑�_�ȉ��v�����{�����B���̂悤�Ȏ��{��`�̌��������Ȃ���A���R���C�ł͂Ȃ����{���o�ς����͂ɃR���g���[������K�v������Ƃ����l���𗝘_�������̂��C�M���X�̌o�ϊw�҃P�C���Y�ł������B�ނ͗L�����v�������邱�Ƃɂ���ĉߏ萶�Y����������Ȃǂ��߂������Ƃ̍�������ɂ���Č������Ƃ������Čٗp��n�o������A������ɂ���Ē��~������ɉ��Ƃɂ���čw���͂����邱�ƂȂǂ��������B�A�����J�͍����������L�����������Ƃ������āA����Ɍo�ϊ�@���������A��2�����E�����}���邱�ƂƂȂ�B
�t�@�V�Y���̑䓪�@/�@���E���Q�̉e�����ł��������̂��h�C�c�ł������B�܂��A���n�����Ȃ��A�������������Ȃ��C�^���A���o�ς��j�]�����B�A�W�A�ł͓��{�͂��łɑ嗤�i�o���ʂ����Ă������A�����ɂ͒n�吧�x�ȂnjÂ��Љ�\�����c��A�_���s�������������A�Ⴂ�w���͂ɂƂǂ܂��Ă������߁A�����Ǝs����C�O�ɋ��߂�o�ϊE�ƌR�̎v�f�����܂��Ă����B���̂悤�ȁu�������鍑�v�ł���h�C�c�E�C�^���A�E���{�Ƀt�@�V�Y�����䓪���钼�ړI�Ȍ_�@�����E���Q�ɂ������B�A�����J�łe�����[�Y���F���g���哝�̂ƂȂ���1933�N�Ƀh�C�c�Ńq�g���[���������������B
���E����̋��Q��@/�@��2�����E������D�i�C�ƕs�i�C�̔g��A���x���̌o�ϊ�@�͂��������A��{�I�ɂ́u���E���Q�v������邱�Ƃ��ł��Ă���B����́A��O�̊e���o���o���̌o�ϐ������������ݏo�������ƂȂ��A���ۘA���̂��ƂŁA���یo�ϑ̐��̈����}�邽�߂̍��ےʉݐ��x�Ƃ��āA�u���g���E�b�Y�̐��Ƃ����h�l�e�̑n�݂�A�f�`�s�s�ɂ�鎩�R�f�Ղ̐��i�Ȃǂ��@�\�������Ƃɂ��B���̒��j�ƂȂ����̂��A�����J�o�ςł���A�h������Ƃ���Œ�ב֑��ꐧ�̂��Ƃň��肵�����o�ς̕������i�B�܂��A���{��`�����ł��s�ꌴ�������ɂ܂������A���{���o�ς��R���g���[������Љ��`�I�Ȍ����������ꂽ�����o�ϑ̐����Ƃ������Ƃ�����̗v���ł������B
2008�N�̐V���Ȍo�ϊ�@�@/�@�Ƃ��낪���̂悤�Ȑ��E�o�ϑ̐���1970�N�ォ��傫���ω����A�A�����J�o�ς̗������݁A���{�o�ς̑䓪�A�V���o�ϒn��̑䓪�A�d�t�Ȃǒn��o�ϓ����̐i�W�ƂȂ��ŁA�s��o�ϖ��\��`(�V���R��`�o��)�̕����Ƃ������X�����łĂ���B���ɃA�����J���O���̃u�b�V��(�q)�����̉��ŋK���ɘa�����i����A���Z�H�w�Ə̂��邳�܂��܂ȓ��@�}�l�[�ɂ�闘�v�Nj����������ăT�u�v���C����肪�N����A2008�N9���ɂ͋��Z���̃��[�}���u���U�[�X�̔j�]�����������ɁA�ӂ����ѐ��E���Q�̊�@�ɗ��������Ă���B�@
��1929
����̃A�����J�j�ƃr�[�A�h�́A���E���Q�̔��[�ƂȂ����A�����J�̋��Q���ȉ��̂悤�ɕ`���Ă���B
�u1929�N�̏H�A�_���͕ʂƂ��č����̐l�X���u�i���̔ɉh�Ƃ�������v�̏�Ɉ��肵�Ă���Ǝv��ꂽ���̂Ƃ��A���a�}�̐���̎��Ƃ���ꂽ���H�Ƃ̂ɂ킩�i�C���A�͂������������Ăĕ����B�ꗬ��Ђ̎�v�����\����\����̂�������ŁA�����݂�40�|�C���g�߂��\�����A1600�����ȏオ�j���[�E���[�N�،�������Ŏs��ɓ������肳�ꂽ�B���̋��Q�ɂЂ��Â��ċ�s��S����Ђ�l���Ђ̔j�Y�A���łɋꋫ�ɂ������_���Ԃ̋�Y�̑����A�H���c�Ə��̕��A�|�p�ƁA�d
�d���t�Ƃ������S������ґw(�z���C�g�J���[�N���X)�̏A�Ƌ@��̋}���Ȍ��ނ��N���������A����̓j���[�E���[�N����J���t�H���j�A�ɂ���Ԃ��̂ł������B1933�N�̂͂��߂̐��J���ɁA1200���̒j�������Ƃ����ƌv�Z���ꂽ�B�d�d�j�Y�ƋQ��Ƃ��A�_���̏���l�⊠������l�̏�������łȂ��A�܂��Y�ƘJ���҂�m�I�E�Ǝґw�̏Z�ޗ�������łȂ��A��s��̔ɉ؊X�܂ł��������������B�v
���E�H�[���X
�j���[���[�N�̃}���n�b�^���n��̍œ�[�̈�p�ŁA�j���[���[�N�،������(���������)�������đ����̏،���Ђ��s���W�܂�A���E�o�ς̒��S�n�̈�B1929�N�ɂ͂��̒n���琢�E���Q���n�܂����B
�E�H�[���X�̂����@/�@�j���[���[�N�͂͂��߁A1652�N�ɃI�����_�l�ɂ���Č��݂��ꂽ�j���[�A���X�e���_���̓��A�n����n�܂�B���̎��I�����_�l���A�C���f�B�A����C�M���X�l���炱�̒n����邽�߂ɍԂ�z���A���̕ǂ��������Ƃ��낪���݂̃E�H�[���X�ł���B�Ԃ̕ǂ͂܂��Ȃ���蕥���A1792�N�ɂ��̒n�Ƀj���[���[�N�،���������J�݂���Ă���A���Z�̒��S�n���đ����Ă���B
�Ȃ��A���E�̋��Z�̒��S�n�ɂ̓C�M���X�̃����h���̃V�e�B(���s�X�̂���)�̈�p�ł��郍���o�[�h�X(�C�^���A�̃����o���f�B�A�o�g�̏��l�������Ƃ��납��t����ꂽ�n��)�A�����̊����Ȃǂ�����B
���Í��̖ؗj��
1929�N10��24���A�j���[���[�N����������ŋ�O�̊�����\�����������A�u���E���Q�v�̎n�܂�ƂȂ����̂��ؗj���ł������B�������N��ԂɂȂ����������A�Ăё�\�����āA�ʏ�̋��Q�Ƃ͈قȂ�u�勰�Q�v�ł��邱�Ƃ��͂����肵��10��29���́u�ߌ��̉Ηj���v�Ƃ����B�@
�����Ƒ���
1929�N�̐��E���Q����1933�N�̃j���[�f�B�[���܂ł��O���ɕ����āA���̎����̓������܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
��1��(1929�N10���`30�N9��)�@1929�N�̎��ƎҐ���155��(�J���l���S�̂�3�D2��)�������̂��A30�N�ɂ�434���l(8�D7��)�ɑ����B�������܂����Ƃ̐[�����͔F�����ꂸ�A�l�тƂ́u���D���ɖ߂邩�v�����҂����B�X���[�g���z�[���[�@�̍��łɂ���č����s��͉���Ɗ��҂���A�B���{�ɂ��������Ƃ�n�C�E�F�C���݂��s��ꂽ�B�j���[���[�N�̃G���p�C�A�E�X�e�[�g�E�r��(���V�O)��30�N�Ɍ��݂��n�܂�A31�N�Ɋ��������B
��2��(1930�N10���`31�N12��)�@30�N�̓~���玸�Ǝ҂���C�ɑ��������B31�N�ɂ�802���l(15�D9��)�ƂȂ�B�e�����̂�s�s�͎��q�I�Ȏ��ƎҌ����̋��H��h���{�ݒ����B�܂����Q�̉e�����Ȃ������\�A�̌v��o�ςւ̊S�����܂����B31�N6���̃t�[���@�[�������g���A���̓��[���b�p�o�ς̋~�ςƂȂ�Ɗ��҂��ꂽ���A�����̓h�C�c�̋��Z���Q�Ɏn�܂�A�C�M���X�����{�ʐ��𗣒E���ĕs�������܂����B
��3��(1932�N1���`33�N3��)�@���Ǝ҂�1200��(24��)�ɒB���A���̂��납�玸�Ǝ҂̂��Ƃ����Q�����̂悤�Ɂu�d���̂Ȃ��l�v(the
idle)�ł͂Ȃ��A�u���Ǝҁv(unemployed)�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�t�[���@�[�哝�̂����Ƒ�ɏ��o�������A�d���̊m�ۂ͖��Ԋ�Ƃ̐Ӗ����ƍl����ꂽ�̂Ŗ{�i�I�ɂ͂Ȃ炸�A���ƎҐ���33�N��1283���l(24�D9��)�̍ō������ɒB�����B(�j���[�f�B�[���J�n��A1937�N�܂ł�770��(14�D3��)�܂ʼn���B)
�u�t�[���@�[���v�Ǝ��Ǝ҂̔����@�u���ׂĂ��������l�тƂ��s�s�̌�����n�ɖؐ��i�{�[���ł������o���b�N�����̏W���́u�t�[���@�[���v�A�V�����́u�t�[���@�[�ѕz�v�A�����ς�o���ꂽ����ۂ̃Y�{���̃|�P�b�g�́u�t�[���@�[�̊��v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�v1932�N3��7���ɂ̓f�g���C�g�ŋ��Y�}�ɐ擱���ꂽ3000�l���t�H�[�h�ЍH��ɍR�c�ɋl�߂������B�s�̌x�@���̓f�����ɂނ����č×܃K�X�e�ˁA�f�����͐Ⓚ�y�Ђ𓊂��Ē�R�����B�x�����͎��e�ˌ��������A�f������4�l���E����A50�l���d�����Ƃ����������N�������B1932�N7���ɂ́A�{�[�i�X�v���̂��߃��V���g���ɏW�܂����ޖ��R�l�̃L�����v���R�������ďĂ�������(�}�b�J�[�T�[���R���w����������)�B
���_�ƕs��
��1�����E����̐��E�I�Ȕ_�Y�����i�̉����ɂ��_���̍����̂��ƁB���ɃA�����J�����̍w���͂�ቺ�����A1929�N�̐��E���Q�̔w�i�ƂȂ����B��1�����E��펞�ɐH�Ǝ��v�����܂�A���i���㏸�������߁A���E�I�ȍ������Y���s��ꂽ�B�����̓A�����J���O�����͂��߁A�A�����J�̎��{����������ăA���[���`���A�J�i�_�A�I�[�X�g�����A�Ȃǂō�t���ʐς������E�@�B�����i���߁A���Y�����債�A�������̌X�����������B���̓t�����X�E�h�C�c�Ȃǃ��[���b�p�������_�Y���̎������ɂ͂����Ĕ_�Y���ɍ��ł�������悤�ɂȂ����B�����ȊO�̍����A�ȉԁA�S���A�R�[�q�[�Ȃǂ����Y�ʂ������������A1924�N�����狟���ߑ��ɂ��_�Y�����i�̉������n�܂����B�Ƃ�킯�_�Y���A�o���̍��ێ��x�����������邱�ƂƂȂ����B
�A�����J�̔_���́A��풆�Ɏ؋������čk�n���g�債�A�@�B���w�����Ă������߁A�_�Y�����i�̉e��������Ɏk�n��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��_���������Ȃ����B�_�ƕs���͒��������A�����1929�N�H�͖L��ł��������߁A������u�L��n�R�v���d�Ȃ�A�_���̍w���͂��������ቺ���A���E���Q�̈���ƂȂ����B
�����Y�ߏ�
1920�N��̃A�����J���O���Ŏ��{��`�̖��������܂��ċN�������o�ό��ۂŁA1929�N�Ɏn�܂鐢�E���Q�̎�v�Ȍ����ƍl������B�A�����J�͑�1�����E���ō��܂������v�ɑ��A�ݔ������𑱂����B�����ԁA�Z��Ȃǂ��烉�W�I�A����@�A�①�ɂƂ������d�@���i�A����ɉ��ϕi�Ȃǂ̐V���ȏ��������ʂɐ��Y����A�Z�[���X�}���Ƒ�ʍL���Ƃ����V���Ȕ̔����i�@�ƌ����̔��Ƃ����M�p�̔����g����悤�ɂȂ������Ƃő�ʏ���(�K�v�ȏ�ɏ����X��)�ɔ��Ԃ����������B1920�N��㔼�ɂ͑��������i�͖O�a��ԂƂȂ�A�_�ƕs����������čw���͂��ቺ���n�߂��B�������A��Ƃ͊����u�[���Ƃ����ߏ�ȓ��@�ɂ���Ďx�����A����ɑ��Y�𑱂����B���̂悤��1920�N��̃A�����J�o�ς̔ɉh���x���Ă����̂́A�M�p�̔��Ɗ����ɂ�鎑�����B�Ƃ����A������������W�̎��Ԃ��痣�ꂽ��@�ɂ����̂ł������B���̓_�ł́A2007�N�Ɏn�܂錻��̋��Q���A���Z�H�w���琶�܂ꂽ�T�u�v���C�����[���Ȃǂ̋��Z���i�̔j�]����n�܂������Ƃɋ��ʂ��Ă���B
���ߏ�ȓ��@
1920�N��̃A�����J�o�ς̍D���̒��Ői���������u�[���̉��M�Ȃǂ̏B1929�N�A���̔����Ƃ��ċN�����������\�����A���E���Q�̈������ƂȂ����B��1�����E����A���E�̋��̓A�����J���O���ƃt�����X�ɗ��ꂱ��ł����B���ɃA�����J�ł͗���������ƁA�C�M���X�E�t�����X����̐�̕ԍςɂ���ď���Ȏ���������邱�ƂƂȂ����B��s�͂��܂������������������l�ɑ݂��t���A�����l�͂�����l�тƂɊ������Ƃ����߁A���������u�[�����N����A1929�N�t����Ăɂ����Ắu�勭�C�v���ꂪ�s�[�N�ɒB�����B�������A�w���͂̒ቺ�Ɖߏ萶�Y�̃M���b�v����ʐl�ɒm���邱�ƂȂ��������Ȃ��Ă����B���@�I�Ȕ����ł�オ���������ƁA��Ƃ̌o�c���Ԃ́A�l�m�ꂸ��������Ă��܂��Ă����B�悤�₭���̂��ƂɋC�����n�߂��ꕔ�����Ƃ����̓���������n�߂Ă����B�����͂₪�āu��V��v�������A1929�N10��24���́u�Í��̖ؗj���v�ɁA��C�ɖҗ�Ȕ��肪�E�����A���E���Q���n�܂����B
�����u�[���̎��ԁ@�u�R�����u�X�����V���g�����t�����N�������G�W�\�����݂ȓ��@�Ƃ������B�v�Ƃ������ƂŐl�тƂ͓��@�̊댯����Y��A�u�N�����������ɂȂ�ׂ����v�Ƃ����薼�̕��͂ŃW���������X�R�u�́A�l���ꃖ���ɂق��15�h����ߖĂ����D�NJ��ɓ���������A�z�����Ȃǂ�ʂƂ��Ă��A20�N��ɂ͏��Ȃ��Ƃ�8���h���̋�����ɂ��邱�Ƃ��ł��A���̓������������͏��Ȃ��Ƃ����z�l�S�h���ɂȂ�A�Ɛ������B�܂���Ђǂ������������������A���ۂ̊��̉��l�ɂ��Ă͒N���킩��Ȃ��Ȃ����B�����M�����}����(�Ȃ��ɂ͍��\�܂����̂��̂�����)�A�Z�[���X�}��������܂������B���̓�����Ђ̊������l�Ŕ����A���{�̋���ȃs���~�b�h���o���オ�����B�l�тƂ͒����l�̌������Ƃ�M����ق��Ȃ������B�u�G�݉��A�d�Ԃ̉^�]��A�z�ǍH�A���j�q�A���������̋��d�܂ł������������B���t���Ă���͂��̒m���l�������A�s��ɂ����B�v
���t�[���@�[�哝��
Harbert C. Hoover (1874-1964) �A�����J���O����31��哝��(�ݔC1929�`1933)�B�n�[�f�B���O�A�N�[���b�W�Ƒ�����1920�N��̋��a�}�哝�̓��̏��������߁A�o�ϐ���̎����ɂ��������B1928�N�̑哝�̑I���ŁA�o�ϔɉh�𑱂���Ȃ��ŋ��a�}�̎��R���C�̌����̈ێ����f��(�����Ƃ��ł��Η����Ă����_�_�͋֎�@�̌p�����p�~���ł������B�t�[���@�[�͌p���������B)�Ĉ��|�I�Ȏx�����ē��I�����B1929�N��3���ɏA�C���A�ŏ��̉����Łu�i���̔ɉh�v������B�ނ̐������O�́A���{�͊�Ƃ�l�̌o�ϊ����ɉ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������R���C��`�����������̂ł������B���̂���1929�N10���ɐ��E���Q���u�����Ă��A�����A�����I�ȕs���ƍl���A1�N�ȓ��̉�\�z���A���ʂ̑�����ĂȂ������B�ނ́u�D�i�C�͂��������܂ŗ��Ă���v(Prosperity is just around the corner.)�ƌJ��Ԃ����������B�������A���Q�͉̒������������A1931�N�ɂ͋�s�̓|�Y���}�����A���Ǝ҂͂���ɑ���A�܂����Q�͐��E�ɔg�y���ĉ��炩�̑���u����K�v���o�Ă����B���������̑�͒x���Ɏ����A�������g�債���Ɣ���Ă���B�e�n�ɐ��܂ꂽ���Ǝ҂̃o���b�N�����̏W���́u�t�[���@�[���v�ƌĂ�A���Q�̐ӔC�����ɕ������ƂƂȂ�A1932�N�̑哝�̑I���Ŗ���}�̃t�����N���������[�Y���F���g�ɔs��đނ����B
�t�[���@�[�����̋��Q��@/�@1930�N�ɂ̓X���[�g���z�[���[�@�𐧒肵�Ĕ_�Y���E�H�Ɛ��i�ɕ��L�����ł������A�����Y�Ƃ�ی삵�悤�Ƃ����B�������A�������ď��O�����R���č��ō���̂������߁A���E�f�Ղ͌������A���Q������ɐ[���Ȃ��̂ɂ��Ă��܂����B����ɁA��1931�N�ɂ̓t�[���@�[�E�����g���A���Ƃ��ăh�C�c�̔������Ɛ��1�N�Ԃ̎x�����P�\��ł��o�������A���łɃh�C�c�Ȃǃ��[���b�p�o�ς͉�œI���������Ă��āA�x���������ߌ��ʂ��Ȃ������B
�t�[���@�[�哝�̂̕]���@/�@�t�[���@�[�哝�̂̑勰�Q��ɂ��āA���j�w�҃r�[�A�h�͎��̂悤�ɕ]�����Ă���B�u�n�߂́A�����̌o�ϋ��Q���炢�̂��̂��낤�ƍl���A�哝�̂́u�����͑O���I�ɏ\�܉�ɂ��y�ԑ傫�ȕs����蔲�����B�d�d���̕s����蔲���邲�ƂɁd�d�O�ɂ��܂����ɉh�̎������ނ������B���x�������Ȃ邾�낤�v�ƌ������B�������A���������A���N�������ɋy��ŁA���H��c���A�A�����J�J���������A�ȂǏ��c�̂͑����I�ȕs����𐭕{�ɗv�������B���܂ŋ��Q�ɑ��ė��̑哝�̂́A����Ƃɉ�����錠���͌��@������Ă��Ȃ��ƐM���邪���Ƃ��A����u���Ă��Ȃ��������A�t�[���@�[�哝�̂͂������ɁA�J���Ǝ��{�Ƃ��Ăъ��������߂��K�͂Ȍ������ƌv��̎{�s�@������悤�c��ɗv�����A�܂��������Z���ЂƎ��L�Z����Z���Ђ̐ݗ��������������B�ЂƂтƂ��ނɔ������т����̂́A�ނ��������Ȃ���������ł͂Ȃ��A�������S���I�j�ǂƂ����d�傳�ɑ��������K�͂Ő���������\�����Ȃ��������Ƃɑ��Ăł������B�v
�l����`�҃t�[���@�[�@/�@�t�[���@�[�̓A�C�I���B�̏����ȊJ�́A���5�l��2�����ŕ�炷�n�����_���̎q�ɐ��܂�A8�܂łɗ��e�Ɏ��ʂ����B�����N�G�[�J�[���k�̗F�l�̐��E�łŃX�^���t�H�[�h��w�Ŋw�сA�z�R�Z�t���u���A���E���̍z�R���܂���ďC�s����(�`�a�c���ς̎��͒����ɂ���)�B�₪�ă����h���̍z�R��Ђ̏d���ƂȂ�A�傫�ȕx��z���ēƗ������B40�Ń����h���ɂ������A��1�����E��킪�u���A�t�[���@�[�͎������Ȃ������Ėk�t�����X��x���M�[�Ɏ��c���ꂽ�A�����J�l�̋~�o�ɂ��������B�A�����J���Q������߂�ƃE�B���\���哝�̂̉��ŐH�Ɩ��̎w��������悤���V���g���ɌĂꂽ�B���̓p���u�a��c�̘A������]�̗v���ŁA���[���b�p�̐푈��Ў҂̐H�Ƌ����̎d���ɏ�肾���A�ނ́u�̑�Ȑl����`�ҁv�Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ�A�ނ̂��Ƃɂ͊��ӂ����߂�100���l���̎q�ǂ��̏��������}�ʂ�����ꂽ�B�܂��E�B���\���̎w���Ń|�[�����h�ɂ���сA���V�A�̍�ƃS�[���L�[�̗v�����Ċv����̃��V�A�ɂ������������������B
���X���[�g���z�[���[�@
1930�N6���A���E���Q���̃A�����J���O���Ńt�[���@�[�哝�̂ɂ���Đ��肳�ꂽ�A���Ő������@�B�����Y�Ƃ�ی삵�č��������ێ����邱�Ƃɂ���ċ��Q�̍������߂��������̂ł��������A�R��A�e������Ăɍ��łɓ]���邱�ƂɂȂ��āA���E���Q������Ɋg�傷��Ƃ����t���ʂɏI������B
�t�[���@�[�哝�̂͑���܂��Ȃ����疾�炩�ɂȂ��Ă����_�Y���̉������~�߂邽�߁A�O������̔_�앨�A���𐧌����鍂�Ő�����������Ă����B1929�N�ɐ��E���Q���n�܂�ƁA�c����ɂ��ی��`���䓪���A��@�̃X���[�g�c���Ɖ��@�̃z�[���[�c�����A���Ŕ_�Y���̂ݐ��炸�H�Ɛ��i�ɂ����ł��ۂ��@�Ă��o�����B���̖@�Ă��c���ʉ߂���Ƃ������ɑ哝�̂͏��������B���̂悤�ȕی�f�Վ�`�͐��E�o�ϑS�̂��猩��}�C�i�X�ł���A���Q��Ƃ��Ă͋t���ʂł���Ǝ咣����1000���ȏ�̌o�ϊw�҂��哝�̂ɏ������Ȃ��悤�x���������A�t�[���@�[�͂�������ď������A1960�N6���ɓ��@�͐��������B����ɂ����3300�i�ڂ̂���890�i�ڂ̊ł������グ���A�A�����J�̗A���ł͕���33������40���ƂȂ����B�I�����_�A�x���M�[�A�t�����X�A�X�y�C������уC�M���X�͒����ɕI�ő[�u�\�����B���ʂƂ��ăA�����J�ւ̗A�o�̖�˂�����ꂽ���[���b�p�o�ς̊�@����������A�h�C�c�̋�s���x�̕���ƂȂ����B��ʂ�31�N�t�ɂ̓A�����J�̐��Y�ƌٗp�͍H��̒������������̂ŁA�t�[���@�[�͕ی��`�������������Ǝ咣���A�A�����J�����Q�Ɋׂꂽ�̂͌R���x�o�傳���č����ύt�����������[���b�p�e���̐������ł���ƌ�ɏq�ׂĂ���B1932�N�̑哝�̑I���ł̓t�����N���������[�Y���F���g�̓t�[���@�[�̍��Ő�����������ᔻ���A�I����ŏ������邱�ƂƂȂ����B
�e�����[�Y���F���g�����ł̌o�σi�V���i���Y���̏C���@/�@�����哝�̂e�����[�Y���F���g�̂��ƂŃj���[�f�B�[�����n�܂�ƁA���������ƂȂ����R�[�f�����n���̓w�͂ɂ��A1934�N6���Ɍb�ʏ�����@���������āA�o�σi�V���i���Y�����C�����A���p�I�A�b�I�Ȗf�ՊW���������B1936�N�ɂ̓C�M���X�E�t�����X�Ƃ̎O���ʉ���A38�N�ɕĉp�ʏ�����𐧒肵�A������39�����Ƃ̋������������B1939�N�ɂ͂��̗���Œ����@�𐧒肵�A�C�M���X�ɑ�������I�E�R���I�x�������߂��B���a�}�͂��̎��_�ł����Ő����W�Ԃ������߁A�A�o�s�U�ɔY�ގY�ƊE�̎x���������A���[�Y���F���g�̍đI���������ƂƂȂ����B
���t�[���@�[�E�����g���A��
1931�N�A�A�����J���O���̃t�[���@�[�哝��(���a�})���A���E���Q�̂��Ȃ��A���Q��Ƃ��đł��o�����o�ϐ���B�����g���A���Ƃ͎x�����P�\�A�`���Ə��̈Ӗ��ŁA��1�����E���Ŕ��������A��������푈���̎x�����`����1�N�ԉ�������Ƃ������́B���ړI�ɂ̓h�C�c�̑C�M���X�E�t�����X�ɑ��锅�����x�����A�A�����J�ɑ��镉�̎x������P�\����Ƃ������̂ŁA���E���Q���g�y�����h�C�c�o�ς������ɘa���邱�Ƃŋ~�ς��A���Q�̐��E�g���j�~���悤�Ƃ������́B���������{�������x�����A���łɋ��Q�͐��E�ɔg�y���Ă��܂��Ă����̂ŁA���ʂ͂Ȃ������B
���W���l�[�u�R�k��c �@
���t�@�V�Y���@
�@ |
| �����E���Q 9 / �j���[�f�B�[���ƃu���b�N�o�ρ@�L�[���[�h |
   �@
�@
|
|
���j���[�f�B�[������
|
1933�N����т��̌�ɍ̗p���ꂽ�A�t�����N���������[�Y���F���g�哝�̂ɂ�鐢�E���Q����̒E�p���߂����o�ϐ���̂��ăj���[�f�B�[������Ƃ����BNew Deal �Ƃ́A�u�V�K�܂������v�̈Ӗ��ŁA�~��(Relief)�A��(Recovery)�A���v(Reform)��3�q�𐭍�̗��O�Ƃ��āA�A�����J���O���̌o�ς��Č����A�h�C�c�E���{�Ȃǂ̃t�@�V�Y�����Ƃ̑䓪�Ƃ�����@�ւ̑Ή���Љ��`���\�A�Ƃ̊W�̏C���Ȃǂ̊O���ۑ�ɂ����낤�Ƃ�����̂ł������B1939�N�̑�2�����E���u����́A�펞�̐��ւƓ]�����Ă����B�j���[���f�B�[������͑���ɂ킽�邪�A�֘A���鍑����v�@�߂͎���6���ڂɗv���B
1.��s����ђʉ݂̓����@/�@�����ꂽ��s�̍ĊJ�ƒʉ݂̊Ǘ��B���ׂĂ̋�s�͂��т����A�M���{�̊ē��A���S�ȍČ����ł���Ƃ���ɂ݂͑��t�����s���A�~�ϕs�\�ȋ�s�͐������ꂽ(�O���X���X�e�B�[�K���@)�B�܂��A���{�ʐ��͒�~����A����݂�d�݂͉�����ꐭ�{�Ɉϑ��B���O�����{���ǂ̔��s���Ǘ����鎆���ɐ�ւ��A�]���̎����Ƌ���݂��������錠���͔p�~���ꂽ�B����ŋ��z�̋��������s�������Ă������O���̒ʉݔ��s�ւ̎x�z�͂͂Ȃ��Ȃ����B
2.�����~�ύ�@/�@������ɂƂȂ������Y���L�҂���і@�l�ɑ���A�M���{�̑ݕt���B
3.�_���̋~�ρ@/�@�����A�Ƃ����낱���A�ȉԁA�H���Ȃǂ̖c��ȗ]����]���̂悤�ɊO���ɔ��肳���ƌ����̂ł͂Ȃ��A�܂������s��̊g����͂���̂ł͂Ȃ��A���Y���팸���A����ɂ���Đ����������͕⏕���ŏ����A�Ƃ����_�ƒ����@(�`�`�`)�̐���B�l�̎��R�Ȍo�c�ɔC����A���Ƃ͂�������Ă͂����Ȃ��Ƃ����]���̊����Ŕj���A���{���_���̐��Y���R���g���[�����悤�Ƃ������Ƃ�����I�ł���B
4.����Ƃ̋K���Ə���@/�@�c��ȍɂƎ��Ǝ҂ɋꂵ�ގY�ƊE�ɑ��A�S���Y�ƕ����@(�m�h�q�`)�𐧒�B���݊����Ɋ��C��^���J���҂ɍw���͂����肾���ړI�ŁA�e�l�V�[�͊J������(�s�u�`)�Ȃnj����y�؎��Ƃɑ��Đ��\���h���̎x�o��F�߁A�܂��A�ƂƐ��Y�ƍ����̘H�����i���邽�ߏ��H��Ƃ�g�D�����A���v�ɑ��鋟���̒����A���i�̋����F�߂��B����ŁA�����s��ɂ����铊�@�̍s���߂�����Ђւ̗Z���̍s���߂���}����ړI����،�����ψ����ݒu�����B
5.�J���҂̕ی�@/�@�S���Y�ƕ����@�َ͌�Ɣ�ٗp�҂̒c�̋����K�肵����1935�N�ō��ق����@�̑啔�������@�ᔽ�Ɛ鍐�A�����ŋc��͑S���J���W�@�����O�i�[�@�������A�c�̋���̑��d���K��A���̎{�s�̂��߂ɑS���J���W�ψ���ݗ����ꂽ�B
6.�Љ�ۏ�̏[���@/�@�v�}�{�⎸�Ƃ�n����V��Ƃ������荑���w�ւ̎Љ�ۏ���[�������悤�Ƃ��āA���\���h���̗\�Z�𗧂āA�A�Ƒ��i���{���̐ݗ����A1935�N�ɂ͎Љ�ۏ�@�𐧒肵���B
���j���[�f�B�[������̌o�ϊw��̗��_�I���t���ƂȂ����Ƃ����̂��C�M���X�̌o�ϊw�҃P�C���Y�̗��_�ł������B�������A1933�N�i�K�ł͂e�����[�Y���F���g�͒��ڃP�C���Y�Ƙb�������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�܂��P�C���Y���咘�ł���A�P�C���Y���_��̌n�I�ɏq�ׂ��w�ٗp�E���q����щݕ��̈�ʓI���_�x�\�����̂�1936�N�ł���B
��1933
1933�N(���a8�N)�́A���E���ēx�̑��Ɍ������]�@�ƂȂ����N�ł������B�܂��A1���Ƀh�C�c�Ńq�g���[���t�������B�����ɍ���㎖�����N�����A���Y�}�Ȃǂ�@�����i�`�X�ƍّ̐����ł߂��B����2���A���{�R�͔M�͏ȐN�U���J�n�A���B���̊g���}��A���ۘA�������B����s���F�A���{�R�̓P�ނ����c����ƁA���{�͒E�ނ����B10���ɂ̓h�C�c�����������ۘA����E�ނ����B���̂悤�ȃt�@�V�Y���̍U���ɑ��A�A�����J�ł�3���ɂe�����[�Y���F���g�哝�̂̃j���[�f�B�[�����J�n���ꂽ�B���E���Q�Ƃ�����@�ɑ��A�푈�ƐN���ɂ���Đ蔲���悤�Ƃ���h�C�c�E���{�̃t�@�V�Y�����͂ƁA���{��`�̏C���ƍ����s��̊J���i�߂�A�����J�Ƃ����S���Ⴄ���������ꂽ�킯�ł���B�@
���t�����N���������[�Y���F���g
Franklin Delano Roosevelt 1882-1945 �A�����J���O����32��哝��(����})�B�ݔC1933�`1945�N�B�t�����N�������c�����[�Y���F���g�́A1882�N�j���[���[�N�̐��܂�A���哝�̃Z�I�h�A�����[�Y���F���g(���a�})�͉����]�Z�ɂ�����B�Ⴂ���납��Z�I�h�A��ڕW�Ƃ��Đ����Ƃ��u���A�n�[���@�[�h��w�ƃR�����r�A��w�Ŗ@�����w�сA��1�����E���ł̓E�B���\���哝�̂̉��ŊC�R������߂��B1921�N��������Ⴢɂ������ė����̎��R�������A���t��̐����ɂȂ������A���E�ɕ��A���A28�N����j���[���[�N�B�m���ɑI�o���ꂽ�B1932�N�A���E���Q�̍Œ���1932�N�̑哝�̑I���ɖ���}���痧��₵�A�u�j���[�f�B�[���v(�V�K�܂�����)���f���đ�ʓ��[���A���a�}�̃t�[���@�[��j���đ哝�̂ƂȂ����B�I�����́u�j���[�f�B�[���v�̋�̓I���g�͂܂������������A���I��ɐ�����o�ς̐��Ƃ��u���[���Ƃ��č̗p���āA�����I�ȋ��Q������肵�A1933�N3���ɏA�C�Ȍ�A��p�����ɐ�������{�Ɉڂ��Ă������B�܂��A�܂���̋��Z�s�����u�o���N�E�z���f�[�v�Ə̂��ċ�s��4���ԕ����A���̊Ԃɋً}��s�~�ϖ@�𐬗������č����Ƀ��W�I��ʂ��ėa�����Ăт����A���Z�̐M���ɓw�߂��B�����āA12���ɂ͖�14�N�������֎�@��p�~���A�����ɐV��������ɓ��������Ƃ���ۂÂ����B�܂��ނ́A�����}�X�R�~�Ƃ��čL�����y���Ă������W�I�����p���A���т��сu�F�Ӓk�b�v�Ƃ��č����ɒ��ژb�������Đ���̗��������߂��A�����̋����x�����邱�ƂƂȂ����B
�j���[�f�B�[������@/�@ 1333�N�Ɏn�܂�j���[�f�B�[������̎�v�ȓ��e�́A�_�ƒ����@(�`�`�`)�E�S���Y�ƕ����@(�m�h�q�`)�E�e�l�V�[�여��J������(�s�u�`)�E���O�i�[�@�E�Љ�ۏ�@�E���{�ʐ���~�ȂǁA����ɂ킽�邪�A���̂˂炢�́A�]���̎��R���C��`�̌��������߁A���{�̐ϋɓI�Ȍo�ω���ɂ���āA�������ƂȂǂ��s���Čٗp��n�݂��A�J���ҕی��Љ�ۏ�̏[���ɂ���Ď�҂��~�ς��đS�̓I�ȍ����̍w���͂���(������)���āA���Q���������悤�Ƃ�����̂ł������B
�O�𐭍�@/�@1833�N�A�s��̊g��Ɠ��{�E�h�C�c�ւ̌����̈Ӗ�����A�\�r�G�g�A�M�����F�����B���[���b�p�ɂ�����h�C�c�A�C�^���A�̃t�@�V�Y���̑䓪�ɂ́A1935�N�ɋc����肵�������@�̋K��ɏ]���Ē��������A���ڎQ��͌Ǘ���`�̓`�����ӂ܂��T�d�ɉ�������B�q�g���[���|�[�����h�ɐN�U���đ�2�����E��킪�u�����Ă���͒����@���������ăC�M���X�ւ̕���A�o���J�n���A�Ȍ�͎Q��̋@���҂����B�܂�����܂ł̃A�����J�̃J���u�C�O���̋����I�ԓx�����߁A�P�O����W�J�A�L���[�o�̃v���b�g�����̔p�~�Ȃǂ����������B�܂��A1934�N�ɂ͋c��Ńt�B���s���Ɨ��@���������A10�N��̃t�B���s���̓Ɨ���F�߂��B
��2�����E���ւ̑Ή��@/�@����ɃC�M���X�E�t�����X�x���m�ɂ��A1940�N�A�ٗ��3�I���ʂ���(�A�����J�哝�̂ł͂e�����[�Y���F���g�̂�)�A1941�N1���̏A�C�����ŁA�u���_����ѕ\���̎��R�A�M���̎��R�A���R����̎��R�A���|����̎��R�v�����̂��t�@�V�Y���Ƃ̐킢�ł���Ƃ����L���ȁu�l�̎��R�v�������s�����B3���ɂ͕���ݗ^�@�𐧒肵�Ď�����̎Q����ʂ������B�܂��`���[�`���Ƃ̑吼�m��k���s���đ��������ɂ����鍑�ە��a���ێ��ł���@�\�̑n�݂ň�v���A���̍\�z���獑�ۘA�������܂�邱�ƂƂȂ����B�ŏI�I�ɂ�12���A���{�R�̐^��p��P���đ�2�����E���ɎQ�킷�邱�ƂƂȂ����B�Ǘ���`����������A�����J�́A����ʂ��ĐϋɓI�ɘA�������̃��[�_�[�V�b�v���Ƃ�悤�ɂȂ�A�p�\��]�Ƃ̃J�C����k�A�e�w������k�A�����^��k�Ȃǂ�i�߂�B�푈���p�����钆�A����4�I���ʂ��������A�܂��Ȃ�1945�N4���A�哝�̍ݔC���ɕa�����A���哝�̂ł������g���[�}������p�҂ƂȂ����B�@ �@���@�A�����J�̊O�𐭍�
�t�@�[�X�g���f�B�A�e�����[�Y���F���g�v�l�@�t�����N�������f���m�����[�Y���F���g(�e�c�q�ƌ���)�́A�����}�q�̂��ߎԈ֎q�̐����ő哝�̂̌����ɑς��Ă����B�ٗ��4�I���ʂ��������Ƃ��画��悤�ɁA���V���g���A�����J���ƕ���Ńx�X�g�X���[�ɓ���l�C�̂���哝�̂ł������B�����ɐe���܂ꂽ�̂́A���̐�������邱�ƂȂ���A�u�F�Ӓk�b�v�Ə̂��Ă悭���W�I�𗘗p���č����Ɍ�肩�������Ƃ�����ł���A�}�X�R�~�𗘗p���������Ƃ̑�ꍆ�Ƃ������Ƃ��ł���B�܂��v�l�G���m�A���A�s���I�Œm�I�A�i���I�Ȕ����Ől�C���������B�����m�푈�̂��Ȃ���43�N�A�����m�푈�̍őO���œ��{�R���P�ނ�������̃K�_���J�i�������Ԗ₵�A���m����u�G���m�A�����邼�I�v�Ƒ劽�}���ꂽ�Ƃ����B
�����{��`�o�ς̏C��
���_�ƒ����@(�`�`�`)
�e�����[�Y���F���g�哝�̂̃j���[�f�B�[������̈�BAgricultural Adjustment Act�@1933�N5������B���Q�ȑO����̔_�앨�̉ߏ萶�Y�A���i�ቺ�ɂ��_���̍������~�ς��邽�߁A�A�M���{���_���̐��Y�팸�ɕ⏕�����x�����A�_�Y�����i����O�ɖ߂����Ƃ�ۏ������́B���ۂɔ_�Y�����i�͏オ��͂��߁A3�N�ȓ��ɔ_�Ƒ�������50�����������B��K�͔_�Ƃ͋~�ς��ꂽ���A���ʏ���_�ɂ͉��b���Ȃ��A��t���ʐς����炳�ꂽ���ߘH���ɖ�������_���o���B
�\���B�G�g���{���V�F���B�L�I�@/�@�`�`�`�ł͘A�M���{(�_������)�ɋ���Ȍ�����^���A�u�\���B�G�g�ɑ��݂��邢���Ȃ�@����K�������{���V�F���B�L�I���v�Ƃ����������������B�E�E�E�E�����팸�̂��߂ɂ́A�A�M���{�̎w���̉��ɉߌ��Ȑ��f�����ꂽ�B1933�N6���A�_�ƒ�����(�`�`�`)�͎��n���O�̖ȉԂ�4����1�������|���L�����y�[���ɏo���B���̉Ĕ_���́A1000���G�[�J�[�̖ȉԂ������|���ĕ⏕������ɓ��ꂽ�B�������ڂꂽ�Ȃ��E���ĕz�c������Ζ@���Ɉᔽ����ƍ�����ꂽ�V���l�_�v�́A�u���߂������A���l�̒U�߃A���B�Ƌ����Ă�˃F�ł������v�ƂԂ₢���B
���킢�����Ȏq�@/�@�ؓ����i�ێ��̂��߂̃L�����y�[���͂���ɐ��S���ɂ߂��B���{��1933�`34�N�̓ؓ����Y��16�����炷���Ƃ�ڕW�ɁA�q�ƔD�P���̎����s�ꉿ�i��荂����������邱�Ƃɂ����B�������Ɂu���킢�����Ȏq�v�����S�������j�E����A��̌��Ԃ��瓦���o���ăL�[�L�[�������Ԏq�Ƃ����ǂ��l�ԂƂ́u�����v�̏�悵���B�ؓ����H�Ǝ҂́A�`���I���@�ɑウ�Č����̂悢��ʓd�C�j�E�@���l���o�����B�E�E�E�v
���S���Y�ƕ����@(�m�h�q�`)
National Industrial Recovery Act�@1933�N�A�e�����[�Y���F���g�̃j���[�f�B�[���̒��Ƃ��Đ��肳�ꂽ�Y�ƐU������сA�J���ҕی엧�@�B���i�ƒ����̉��~���~�߂邱�Ƃɂ���ĎY�Ƃ������邱�Ƃ��Ӑ}���A�e�Y�Ƃ��Ƃ̊�ƒc�̂ɋ���(�����s�׃R�[�h)�������ĉ��i�ƒ����̈����}�����B��Ƃ��w������@�ւƂ��đS��������(NRA)��ݗ����Œ������J������(�T40����)���߂��B�܂��A�ٗp��n�o���邽�ߌ������Ƌ�(PWA)��ݗ����A���H�A�w�Z�A�a�@�Ȃǂ̌������Ƃ������ɍs�����B����ɂm�h�q�`��7���ŘJ���҂̌�����ی삵�A�J���g����������ђc�̌��̌�����F�߂��B�������A���̑�]���ɑ��Ă͎��R��`�̌����ɔ�����Ƃ����ᔻ�������A1935�N�ɍō��ٔ����̈ጛ�����ɂ���đS��������(�m�q�`)���p�~���ꂽ���߁A���Q��Ƃ��Ă͐��ʂ��グ�邱�ƂȂ��I������B
�S���Y�ƕ����@�̂˂炢�@/�@�Z�p�i���ɂ���ċ��剻������Ƃ��A�ߓ������𑱂������ʁA���X�N�����܂��ʎ��ƂɂȂ������B��������̗��v��i�삷�邽�߂ɂ́A��Ƃ̋����𐧌����A�A�M���{�Ƃ̋��͊W�̉��ɒ������������Y���s�����Ƃ����̍��{�I�����̂��߂ɕK�v�ł���B�Ƃ����l���Ɋ�Â��Đ��肳�ꂽ�m�h�q�`�̖ړI�́A�Y�Ƃ��Ƃ̊�Ƃ�g�D���A�A�M���{�Ƌ����Ő��Y�Ɖ��i�����A�J����������点�ĘJ���҂�ی삷�邱�Ƃɂ���āA����I�Ȋ��S�ٗp���������A�����w���͂����邱�Ƃł������B����́A�]���̎��R�����ƓƐ�̋֎~�Ƃ������R��`�I���{��`�̌���(���a�}�������Ő����i�߂��Ă���)��������A���{�����͂Ɍo�ςɉ�����A�s���J���e����F�߂āA�L�����v�Ɗ��S�ٗp���߂����Ƃ����C�����{��`�ɑ�]��������̂ł������B
�ō��ٔ����ɂ��ጛ�����@/�@�S���Y�ƕ����@(�m�h�q�`)�ɑ��ẮA�Ɛ������������̂Ɣᔻ���������狭�������B�܂��Y�ƒc�̂̒��j�ƂȂ�悤�Ȋ�Ƃ͂�����x���������A������Ƃɂ͔��̐������������B1935�N5���A�ō��ٔ����́A�S��������(�m�q�`)�̌����s�׃R�[�h�ݒ�Ə���ւ̘A�M���̊ւ����A�哝��(�s���{)�ɂ��c��̗��@���ւ̐N�Q�ł���Ƃ��Č��@�ᔽ�ƒf���A���̖�����錾�A���̂��߂m�q�`�͔p�~���ꂽ�B�������A�e�����[�Y���F���g�哝�̂́A�m�h�q�`�̒�����A�Œ�����A�ō��J�����ԁA�c�̌��A��N�J���̋֎~�Ɋւ��鍀�ڂ��c�����Ƃɂ��A�S���J���W�@(�ʏ̃��O�i�[�@)���Ă��A���肳�����B
���e�l�V�[�여��J������(�s�u�`)
Tennessee Valley Authority�@�e�����[�Y���F���g�̃j���[�f�B�[���̏d�v�Ȏ{��̈�Ƃ��āA1933�N5���ɋc��ŏ��F���ꂽ�B���{�������������Ђɂ���āA�e�l�V�[�여��̃_�����݁A�������ƁA�A�сA�ȂǑ����I�J�����s���A�n��Y�Ƃ��������A�ٗp�傳���邱�Ƃ��Ӑ}�����B�s�u�`�ɂ����20�̃_���������A�d�͋����͈��肵�A����̔_�Ɛ��Y���͌��サ�A���������߂��B
�e�l�V�[�여��́A�e�l�V�[�A�A���o�}�A�W���[�W�A�A�~�V�V�b�s�A�m�[�X�E�J�����C�i�A�P���^�b�L�[�A���@�[�W�j�A�̏��B�ɂ܂�����A�S��1000�����B���Ђ�3�����琬�闝����^�c�A���[�Y���F���g�͗�������55�̍^������̐��Z�t�`�����[�K�����A�c���l�̓e�l�V�[��w�w���Ŕ_�ƉȊw�҂̂g�����[�K���A�@���Ƃ̎㊥34�c�������G���\�[����C�������B�O�l�̗����͈ӌ��̈Ⴂ������A������ɂ߂����A����ł����d�A�X�т̍Đ��A�y��A�_�Ƃ̉��P�A�w�Z�̌��݁A���N���G�[�V�����ȂǍL�͂Ȏ��Ƃ�W�J�����B����140���̃t�H���^�i�E�_�����͂��߂Ƃ���40��̔��d�_����10��̔d�_���͌��݂��ғ����Ă���B
���O���X���X�e�B�[�K���@(��s�@)
�j���[�f�B�[������̈�Ƃ��Ē�߂�ꂽ�A��s�K�����������闧�@�B���E���Q�̔����Ƌ��ɋ��Z�E�ɑ��錵�����K����v�����鐺�����܂�A���łɃt�[���@�[�����̉��ŏ�@�ɍ���ψ���݂����Ă���(�ψ����̖��O����y�R�[���ψ���Ƃ���)�B�ψ���ł͋��Z�E�̒鉤�Ƃ���ꂽ���ڃ����K�����͂��ߑ嗧�Ď҂���������A�u�܂�Ŕn�D�_���������U������悤�Ɂv�l�₪�s���A�ނ炪�����ł��Ă��Ȃ��������ƂȂǂ��\�I���ꂽ�B���̐R�c�̒������s��،���ЂȂǂ̋��Z�E�ւ̌������K���̕K�v���F������A��A�̋��Z�K���֘A�@�����������B�O���X���X�e�B�[�K���@(��s�@)�͂��̈��1933�N6���ɏ�@��S���v�Œʉ߂��e�����[�Y���F���g�哝�̂����������������B���̓��e�́A�E�،��Ƌ�s�̕����A�E�A�M�������x�̋����A�E�a���ҕی�̂��߂̘A�M�a���ی�����(�e�c�h�b)�̐ݗ��A�v�������a���ւ̗��q�̋֎~�Ȃǂł���B�،��Ƌ�s�̕����́A���Ƌ�s���瓊�@�I���_��o�ł��Ċ�Ƃ̈���o�c��}����̂ł������B�a���ҕی�ɂ͎���Ɨ��̐��_�ɔ�����Ƃ������Θ_�����������A���̌����s�������Ȃ�������ʂB�A�M�������x�̋����́A�]���̘A�M�����ψ���猈�茠��A�M�������x������(�e�q�a)�Ɉڂ��A���ׂĂ̋�s��A�M�������x�ɉ����������B
�O���X���X�e�B�[�K���@�̈Ӌ`�@/�@��s�@��،��@�Ȃǂ̋��Z�֘A�@�͂��т��щ��肳��A�j���[�f�B�[���̒��ł��}�C�i�[�ȗ��@�ƌ���ꂪ���ł��邪�A�u���j�㏉�߂ăE�H�[���X���K�����A��s���x�𒆉���s�ɂ�鐭��R���g���[�����m�����A�a���ҕی�𐧓x�I�ɕۏႵ�����Z���x�̉��v�́A���̌ヌ�[�K������Ɏ���܂ł̃A�����J�̋��Z���x�̊�b���ł߁A���̂����Ȃ�j���[�f�B�[�����@���������������̂ƂȂ����B�v
�O���X���X�e�B�[�K���@�̔p�~�@/�@1980�N��̃��[�K������(���a�})���ŋK���ɘa�A���R�����̕����Ƃ����o�ϘH�������܂�A�،��Ƌ�s�̕����������Ƃ���1933�N��s�@(�O���X���X�e�B�[�K���@)�̌��������n�܂����B1990�N��̂h�s�D���ɓ]�����A�����J�o�ς�w�i�ɁA1999�N11���A���a�}�����������߂��E���@�̓O���X�E�X�e�B�[�K���@��p�~���A��s�E�،��E�ی������c���鑍�����Z�T�[�r�X�����R������@��(�O�����E���[�`�E�u���C���[�@)�����A�N�����g���哝��(����})���������Đ��������B���̂悤�ɐV���R��`�Ɋ�Â��ċ��Z�������R�����ɂ��炷���ƂɂȂ����A�����J�o�ς͂��̌�A���Z�H�w�Ƃ����R���s���[�^�ˑ��̋��Z���i���\�����A�T�u�v���C�����[���Ȃǂ̖��������N�������ƂƂȂ����B�@
�����{�ʐ���~(�A�����J)
1933�N3���A�A�C�܂��Ȃ��A�����J���O���̂e�����[�Y���F���g�哝�̂��A��s�|�Y�Ȃǂ̋��Z�s�������̂��߂ɑł��o�����B�h���Ƌ��̌������~���āA�A�����J�̃h���̗��o��h�~���悤�Ƃ������́B����ɂ���ăA�����J���O���͘A�M�������x�ɂ��Ǘ��ʉݐ��x���̂邱�ƂƂȂ�A���E�I�ɂ����{�ʐ��͕��邱�ƂƂȂ����B
�v���Ƃ��Ă̋��Z��@�@/�@1929�N�Ɋ�������\���������A�����ɋ�s�̓|�Y���N�������킯�ł͂Ȃ��A��1�N���30�N���玟��ɑ����n�߁A33�N�ɂ̓s�[�N�ɒB���Ĕ����I�ɑ��������B���Q�̒��������A�����31�N�ɃC�M���X�����{�ʐ��𗣒E���A�|���h��艺�������߁A�A�����J�̋������o���邱�ƂƂȂ������Ƃ��v���Ƃ��Ă�������B���Z�s������a���҂���Ăɗa�������o��(���t��)�ɓ����A��s�j�Y���}�������B
�e�����[�Y���F���g�̋��Z�s�������@/�@�A�C�����3��9��(�ؗj)�ɋً}��s�@����ʋc��ɂ����Đ��������A��s�x�Ɠ������������Ď��t��������}�����B�����10��(���j)�ɂُ͋k�����@��ʂ��A�哝�́E�c���E���{�E���Ȃǂ̋��^��15���팸�A�R�l�����̍팸�Ȃǂ�ł��o�����B�����ē��j���ɂ̓��W�I�́u�F�Ӓk�b�v�ŋ�s�̉c�ƍĊJ��A�����ɗa����i�����B���j�ɂ͈��S����������������a���ɂ߂����A�u���{��`��8���ŋ~��ꂽ�v�ƌ���ꂽ�B
���{�ʐ��̒�~�ƃh���؉����@/�@3���̋�s�x���錾�̍ۂɋ���݁E�n���̗A�o��悸�֎~���A4��5���ɂ͋��ݓ��̑ޑ����֎~����A4��19���ɋ֗A�o�֎~�߂ɂ���ăh���Ƌ��̙[�����ŏI�I�ɋ֎~���ꂽ�B�h���͑��̂��ׂĂ̒ʉ݂ƃt���[�g(�����A�A�����Ĕ��s�����)�悤�ɂȂ�A�h���؉����͂��̎��_�ł͂��܂����Ƃ�����B�h���������������Ƃɂ���ăA�����J�̗A�o�i�A�Ⴆ�ΖȉԂȂǂ̗A�o��������Ԃ����B
�Ǘ��ʉݐ��x�ւ̈ڍs�@/�@1934�N1���A�������@�����肳��A����ɂ���ĘA�M������s����������ɋ��݂Ƌ��n�������ׂĈ����n����A���������B��̍��@�I�ȋ��ۗL�҂ƂȂ����B�e�����[�Y���F���g�̓h���̋����i���40���艺���āA�����̎����ɋ߂���1�I���X��35�h���ɌŒ肵�A�Ǘ��ʉݐ��x�ւ̈ڍs�����������B�h���؉����Ƌ��{�ʐ����E���Ǘ��ʉݐ��̗̍p�ɂ���āA�������������グ��D�悵��(���ۓI�Ȉבֈ�����]���ɂ���)�����I�v���ɉ������ƌ������Ƃ��o����B
�����{�ʐ�
���{�ʐ��̈Ӗ��@/�@���͋P��������A���H���ɂ����A�]�����傫��(�����̂����Ƃ��o����)�A�������邱�Ƃ��ł���Ƃ��납��A���Ƃł������\�ł��������ߒ��݂Ƃ��Ďg���Ă����B���̋��݂��������̏��i�̉��l��\������̂��߂̊�Ƃ��Ďg�����Ƃ����{�ʐ��Ƃ����B���{�ʐ��̉��Ŕ��s����鎆���́A��ʂɊe���̒�����s(������s�A���{�ł͓��{��s)�����s�����s���ł���A������s���ۗL������݂����ƈ����ւ��ɔ��s�����[������(���ƌ����ł���Ƃ����Ӗ�)�ł���B�������M�p����鍪���́A�{�����{�ʐ��̙[�����x�ɂ������B�]���āA���{�ʐ��x�̉��ł͊e���̎����ʂ͋��ۗ̕L�ʂɐ����B
���{�ʐ��̎������ߍ�p�@/�@���{�ʐ��ł͗A�o���̍��z�͋��ŕ����A���߂����B�Ƃ������Ƃ͖f�Ղ��Ԏ��ɂȂ�Ƌ������O�ɏo�čs���A�����ʉݗʂ͌������A�����̏����͌��蕨���͉����邱�ƂɂȂ�B����ƗA���͌���A�A�o�������Ėf�ՐԎ��͉����ɂނ����B���{�ʐ��ɂ͂��̂悤�ȃ��J�j�Y��������A��������{�ʐ��̎������ߍ�p�Ƃ����B
���{�ʐ��̐����@/�@���{�ʐ���1816�N�ɃC�M���X�Ɏn�܂�A1844�N�ɃC���O�����h��s�����ƌ����\�ȃ|���h��[������(��1�I���X��3�|���h17�V�����O10�y���X���Ƃ���)�Ƃ��Ĕ��s���A19���I���Ƀ����h���𒆐S�Ƃ������ۋ��{�ʐ��Ƃ��Ċm�������B
��1�����E���Ƌ��{�ʐ��@/�@���{�ʐ���1914�N�̑�1�����E���ňꎞ��~���ꂽ���A1925�N�ɃC�M���X���͂��ߊe�������{�ʐ��ɕ����Ă����B���{�ʐ��ɂ���Ċe���̒ʉ݂͋��Ƃ̓����W�ɂ��邱�ƂƂȂ�A���݂Ɍ��������R�ɍs���邱�Ƃ��ۏႳ��Ă����B�������A���̎��C�M���X�͍��ƓI�АM�ɂ������A�������ŋ��{�ʐ��ɕ��������߁A�f�Վ��x���������A�������A�����J�Ɉړ����A�A�����J�̋��Z�ɘa�Ƒ��ւ��ăA�����J�̊����s�ꂪ�\�����鉓���ƂȂ����B���{��1930�N�ɋ����ւɓ��ݐ���(���{�ʐ��ƂȂ邱��)���A��͂苌�����ł̉��ւł��������߁A���̗��o�������Ď��s�����B
���{�ʐ��x�Ɛ��E���Q�@/�@�������A��1�����E����̓h�C�c�̔��������S�A�C�M���X�E�t�����X�E�C�^���A�Ȃǂ̑ΕĐ�̎x�����Ƃ����A���Y���̐�����j�Q����v�f�����݂���Ȃ��ŁA�A�����J���O���o�ςւ̈�ɏW�����s���߂��A�ɂ�������炸�����̃C�M���X�𒆐S�Ƃ������{�ʐ��̃V�X�e������������A�A�����J���O�������E�o�ϑS�̂ɐӔC�����Ƃ����ӎ����Ȃ��A�܂��A�����J���O���̓��[���b�p�����ɔ�ׂĒ�����s�̐ݒu���x���A�悤�₭1913�N�ɘA�M�������x�������������ߒ�����s�̖�����S���A�M�������x��������Z�@�ւɑ��\���ȓ����͂������Ă��Ȃ��������߁A���Q���g�傳���Ă��܂����B�A�����J���O���͎����I�Ȑ��E�o�ς̃��[�_�[�ɗ�������Ă��Ȃ���A���ۘA���ւ̉��������ۂ��A���[�_�[�Ƃ��Ă̐ӔC���ʂ����Ȃ������B1933�N6���̃����h�����E�o�ϋ��Z��c�ł́A���{�ʐ����E���Ƌ��u���b�N�|�t�����X�A�C�^���A���Η����A�A�����J�̂e�����[�Y���F���g�͍����o�ϕ����̃j���[���f�B�[�������D�悵�āA�����������������߁A��c�͌���2����풆�̃u���g�����E�b�Y��c�܂őS�̋��c�̏ꂪ���ĂȂ��Ȃ����B
�e���̋��{�ʐ��̕���@/�@���E���Q�̐[�����̒��Ő��E�I�ȋ��Z�s�����L����A1931�N����33�N�̊ԂɎ��X�Ƌ��{�ʐ����痣�E����B�܂��h�C�c�̋�s�j�]����31�N9���Ƀ}�N�h�i���h������v���t�̃C�M���X�����{�ʐ���~�ɓ��ݐ�A�C�M���X�Ƃ̊W�̐[���|���g�K����k������������ɂȂ�����B���N12���A���{�̌��{�B���t���֗A�o�ċ֎~������B�����1933�N3���A�e�����[�Y���F���g�哝�̂̃A�����J���O�������{�ʐ����痣�E���A�����ɐ��E�̋��{�ʐ��͕����B����A�t�����X�E�I�����_�E�x���M�[�͋��{�ʐ����ێ����A���u���b�N�Ƃ������̃u���b�N�o�ό����`������B
�Ǘ��ʉݐ��x�@/�@���{�ʐ��ɑ���ʉݐ��x�́A������s�̊Ǘ��̉��ŁA���������s�����A�Ǘ��ʉݐ��x�Ɉڍs���邱�ƂƂȂ����B�Ǘ��ʉݐ��x�ł͎����͕s������(���ɑウ�邱�Ƃ��o���Ȃ�)�Ƃ��Ĕ��s�����B�����̔��s�ʂ͋��ۗ̕L�ʂɂ��̂ł͂Ȃ��A������s�̎����Y�������Ƃ��Ĕ��s�����B
�푈�ւ̓��A�����艺�������@/�@���E�ʉݐ��x�Ƃ��Ă̋��{�ʐ���������́A�����Ɍb�܂ꂽ�A�����J���O���̓j���[���f�B�[������ɂ���č����w���͂������邱�Ƃɐ������Ă������A�C�M���X�E�t�����X�̓u���b�N�o�ό����`�����ĕی��`���Ƃ�悤�ɂȂ�A�܂����{���܂ފe���͕����̐艺��(�����ʉ݂̉��l��������)���s�����ƂŁA�A�o�𑽂����A�����Y�Ƃ���邱�Ƃ������悤�ɂȂ����B����͂���ɍ����̘J���҂ւ̒�����Ƃ����`�ł�������߂邱�ƂƂȂ�A���E�S�̂̍w���͂�ጸ�����A�܂�����������J���͂����߂ė̓y�E���͌��̊g����͂���푈�ւ̓����J�����ƂƂȂ����B�i�`�X�h�C�c�́u�������̊g��v�A���{�R����`�́u���B���v�Ȃǂ�����ɂ�����B
��2�����E����̍��ےʉݐ��x�@/�@��2�����E����͘A��������̂ɐ��E�o�ς̍��ۋ����̐��ł���u���g���E�b�Y�̐�������A�A�����J���O���̃h����B��̊�ʉ݂Ƃ��A�����艺���������N���Ȃ��悤�ɌŒ�ב��x���Ƃ邱�ƂƂȂ����B�܂����ێ��x�̈��݂ɂ����1���̌o�ς��j�]����ƁA���E�o�ϑS�̂ɉe�����y�ڂ������ƂȂ��āA���ےʉ݊���Ɛ��E��s��ݗ������B
�����O�i�[�@
�����ɂ͑S���J���W�@(1935�N����)�B���O�i�[�@�͒ʏ́B�e�����[�Y���F���g�̃j���[�f�B�[���̈�Ƃ��Đ��肳�ꂽ�J�����@�ŁA�J���҂̒c�����E�c�̌����m�ɔF�߂��B�J���g���̌�����ی삵�A�����Ȍٗp���������悤�Ƃ���K���1933�N�̂m�h�q�`(�S���Y�ƕ����@)�Ŏn�܂������A�m�h�q�`��1935�N�ɍō��قŌ��@�ᔽ�̔��f���o���ꂽ���߁A����ɂ�����Đ��肳�ꂽ�B�Y�ƊE�͖җ�Ȕ��Ή^����W�J�������A�c��ɂ����閯��}�̑����Ƃ`�e�k�ȂǘJ���E�̎x���Ő��������B
���O�i�[�@�̓��e�Ƃ˂炢�@/�@�J���҂̒c�����E�c�̌����E�X�g���C�L����ۏႵ�A��̓I�����Ƃ��đg���̑�\���ɑ������������̗p���A�J���҂̌��������ƓI�ɕۏႷ��@�ւƂ��āu�S���J���W�ψ���v(�m�k�q�a)�ɍL�͂Ȍ�����t�^�����B�܂��A�ٗp�҂́u�s���J���s�ׁv(�g���ɑ��銱�A�}���A�����A�����A�W�Q�A�ٗp�����ɂ�鍷�ʁA�g�������𗝗R�Ƃ������فA�c�̌��̋���)���֎~�����B���O�i�[�@�̂˂炢�́A�o�ϓI�ɂ͘J���҂ɍw���͂�t�^���č��������̒��������傳���A�����ĕ��z���������悤�ƈӐ}�����B
�J���g���^���̊������@/�@1933�N�̑S���Y�ƕ����@(�m�h�q�`)�A����ɑ���35�N�̃��O�i�[�@�̐���ɂ���āA�A�����J���O���̘J���^���͖@�I�ی�̂��Ɩ��\�L�̑g�D�����i�B�����ɁA�g���^�����߂����ċ����̃A�����J�J��������(�`�e�k)�����A�Y�ƕʑg����c(�b�h�n)�����܂��Ƃ����ω��������炵���B�J���g���͎��{��`�Љ�̒��Ōo�c�҂ɑ���u�h�R�́v�����Ɏ���A1938�N�ɂ͌����J����@�����߂Đ��肳��āA�Œ����(�S�Ǝ��8�N���40�Z���g)�A�J������(3�N��ɏT40����)�����ꂳ�ꂽ�B
���O�i�[�@�̏C���@/�@��2������A��퉺�ŃA�����J�Љ�ɎЉ��`��J���^���ɑ���x�������܂钆�ŁA1947�N�ɋ��a�}���������߂�c��Ń^�t�g���n�[�g���[�@���������A���O�i�[�@�́u�J���Ҋ��v�̓��e�͂������̓_�ŏC������A���̗��O�͌�ނ��邱�ƂƂȂ����B
���Y�ƕʘJ���ґg�D�ψ���(�b�h�n)
1935�N11���ɁA�A�����J�J��������(�`�e�k)�̂Ȃ��̎Y�ƕʑg�D���咣���鏭���h���`�e�k���ɐ݂����ψ���B�]���̃A�����J�̘J���^���𐄐i���Ă����A�����J�J��������(�`�e�k)�́A�n���H����Ȃ�E�\�ʑg���ł��������A20���I�ɓ���A�A�����J�̎Y�Ƃ̂Ȃ��Ŕ�n���̘J���҂��������߂�悤�ɂȂ��Ă����B��n���J���҂́A1935�N�Ƀj���[���f�B�[������̈�Ƃ��ă��O�i�[�@�����肳��ĘJ���g���^���ɑ���@�I�ی삪�����������Ƃ��@�ɁA�`�e�k�����ɎY�ƕʘJ���ґg�D�ψ���(�b�h�n)��݂����B�������A�`�e�k�͏n���H�̐E�\�ʑg���Ƃ������i�����߂��A�����⍕�l��r�����������̂ŁA�`�e�k���Ԃ����A1938�N�ɎY�ƕʑg����c(�b�h�n)�����������B�w���҂͍z�v�J���g���̃W���������C�X�B1836�N�̑哝�̑I���ł͂e�����[�Y���F���g��2�I�������x��������������������B
���Y�ƕʑg����c(�b�h�n)
Congress of Industrial Organization �A�����J�J��������(�`�e�k)���̎Y�ƕʘJ���ґg�D�ψ�������E�Ɨ���1938�N�Ɍ������ꂽ�A�����J�̘J���g���̑g�D(���̂͂Ƃ��ɂb�h�n)�B��n���̏����⍕�l�Ȃǂ̈ȑO����̏n���H���S�̐E�\�ʑg������̂��҂ɂ���Ă����Y�ƘJ���҂Ɖ�Ў�������g�D������̂ɐ��������B�ψ����͓������W���������C�X�B1937�N�܂łɑg����158���l�܂ő��������B����̃A�����J�J��������(�`�e�k)�������Ԃ���}��A�J���^���͂��̓�̑S���g�D�̉���1941�N�ɂ�800���l���z����g�D�����ɂ�����A1955�N�ɍ��������B
���Љ�ۏ�@
�j���[�f�B�[������̌㔼�A1935�N�ɐ��肳�ꂽ�A�����J���O������������ɓ]����}�������@�B���ƕی��E�ސE�����x�E�N�����x�Ȃǂ������B�j���[���f�B�[������J�n�ɔ����A�����͏㏸�����������̏㏸�������Ă������߁A���ƎҁE����ҁE��Q�҂ȂǎЉ�I��҂̐��������͑����Ă����B���Ԃ���Љ�ۏᐧ�x�̏[����v������^�������܂�A���O�^���̈��͂���`�ŎЉ�ۏ�@�̐��肪���������B�V��N���͘A�M�̈�ʍ�������̎x�o�ł͂Ȃ��A��ƂƘJ���҂����S�����B�V��ҁE��Q�ҁE������ɑ���}���A�܂����ƕی��͏B�̐��x��A�M���⏕������̂ŁA���ׂĂ̏B�ŋ��t���n�܂����̂�39�N����ł������B�܂��S���ꗥ�̌��N�ی��𐧓x�����邱�Ƃ͏o���Ȃ������B�A�����J��t��ƕی��ƊE�̔����������߂ł������B���̌��ׂ̓A�����J�̎Љ�ۏᐧ�x�̌��ׂƂ��Č��݂������Ă���B
���P�C���Y
John Maynard Keynes 1883-1946 20���I�O���Ɋ����C�M���X�̌o�ϊw�҂ŁA�C�����{��`�̗��_����āA�A�����J�̃j���[�f�B�[���������̃C�M���X�J���}�̌o�ϐ���ɑ傫�ȉe����^�����B
�P�C���Y�̓P���u���b�W�Ōo�ϊw���w�сA�Ⴂ���̓����h���̌|�p�ȏW�c�u���[���Y�x���[�E�O���[�v(�����Ƃ̃��@�[�W�j�A���E���t�A�]�_�Ƃ̃��b�g�����X�g���C�`�[��A�����Ƃ��Ă͔����Ў�`�I�Ȏv�z�̐l�X�̏W�܂�)�ɉ�����Ă����B�P���u���b�W�̌o�ϊw�̋��t����呠�Ȃ̖�l�ƂȂ�A��1�����E����̃p���u�a��c�̃C�M���X��\�p�ɉ�������B1919�N�Ɂw���a�̌o�ϓI�A���x�\���ă��F���T�C����h�C�c�ɑ��ĉߓx�Ȕ��������߂����Ƃ���̐푈�ɂȂ��邱�Ƃ��x�������ڂ��W�߂��B1929�N�̐��E���Q��͎��{��`�͊�@���}�������A�P�C���Y�͎Љ��`��ے肵�āA���{��`�ɏC���������邱�Ƃɂ���Ċ�@���������邱�Ƃ�����A36�N�Ɂw�ٗp�E���q����щݕ��̈�ʓI���_�x�\�����B�����ł͊��S�ٗp�ݏo���L�����v�̊J�����A���Ƃ��������Ƃ��������Ƃɂ���Đ��ݏo�����Ƃ���A���肩��A�����J�̂e�����[�Y���F���g�������W�J���Ă����j���[�f�B�[������ɗ��_�I�Ӌ`�t����^�����B�P�C���Y�́A��������(�łɂ��i�C�̒���)�A���Z����Ȃǂ̍��Ƃɂ��s��̓����ɂ���Čo�ϋ��Q��������邱�Ƃ��\�ł���ƍl����u�C�����{��`�v�͑傫�ȉe����^���A�Љ��`�ɑR����v�z�Ƃ��ăA�����J�E�C�M���X�̌o�ϐ���̊�{�Ƃ��ꂽ�B�P�C���Y�͑�2�����E����̃u���g�����E�b�Y��c�ł��哱�I�Ȗ������ʂ������B
�P�C���Y�̌o�ϗ��_�ɑ��ẮA�������łɃn�C�G�N�ɑ�\����锽�_���������B�n�C�G�N�̓P�C���Y�o�ϐ���͎s��̎��R�ȋ����𑩔����邱�ƂɂȂ�Ƃ��Ĕᔻ���A���R��`�̗�����т����Ƃ����B�܂�����̃t���[�h�}����̃V�J�S�w�h�ɑ�\�����V���R��`�̌o�ϗ��_�́A�P�C���Y��`���u�傫�Ȑ��{�v���Y�݂����A�ŕ��S��K�����������R�Ȋ�Ƃ̋����˂Ă���Ƃ��āA���c��Ƃ̖��c���A�K���ɘa�A���ŁA�Љ���x�o�팸�Ȃǂ́A������u�����Ȑ��{�v�_��W�J���A�`���̃s�m�`�F�g�����A�C�M���X�̃T�b�`���[�����A�A�����J�̃��[�K�������A���{�̒��]�������A�����Ȃǂɑ傫�ȉe����^���A�u�P�C���Y�o�ϊw�͌Â��v�Ƃ����Ɏ��������A���݂͂��̐V���R��`�̍s���߂����ᔻ�̑ΏۂƂ���Ă���B
���\�A�̏��F(�A�����J)
�A�����J���O���̃\���B�G�g�A�M(1922�N����)���F�́A�C�M���X�E�t�����X(1924�N)�A���{(1925�N)�Ȃǂ��x��A�e�����[�Y���F���g�哝�̂̎���1933�N�ɂȂ��ꂽ�B����܂ŃA�����J���O�����{�͔����Y��`�̗��ꂩ��A�\�A�̏��F������ł������A�e�����[�Y���F���g�͐��E���Q���[���ɂȂ钆�ŁA�\�A�ƍ������J���Ă��̎s����J�邱�Ƃ��˂�����B�܂��A���[���b�p�ɂ�����h�C�c�ƃA�W�A�ɂ�������{�Ƃ����t�@�V�Y���̑䓪���x�����A�\�A�ƍ��������Ԃ��Ƃł��̓���������Ӑ}���������B�\�A�����h�C�c�E���{�Ƃ̑Ό��ɔ����ăA�����J���O���Ƃ̒�g��]�݁A��1934�N�ɂ͍��ۘA���ɉ��������B�@ �@���@�A�����J�̊O�𐭍�
���P�O��
�e�����[�Y���F���g�哝�̂̃��e�����A�����J�n��Ƃ̊O�𐭍� Good Neighbor Policy �̂��ƁB����܂ł̗͂ɂ�鍂���I�ȃJ���u�C��������߁A�F�D�I�Ȑ���ɓ]�������ƁB���e�����A�����J�̖�����`�^�����Љ��`�ƌ��т��Ĕ��ēI�ɂȂ邱�Ƃ��������ƂƂ��ɁA���E���Q�ɑΉ����ăA�����J�̌o�ό��ł��邱�̒n��ɑ���A�����J�̎w�������ێ�����̂��˂炢�B1934�N�ɂ̓L���[�o�ɑ��ăv���b�g������P�p���Ă��̊��S�Ɨ���F�߁A�n�C�`����͊C������P���������B���̗F�D������t���A��2�����E��펞�ɂ́A���e�����A�����J�����̂قƂ�ǂ��A�������ŎQ�킵���B�܂�����̓A�����J�͂���ɂ��̒n��ւ̎x�z�������߂邱�ƂƂȂ����B�@
���v���b�g���� �@
�������@
1935�N�A�t�����N���������[�Y���F���g�哝�̂̎��A�A�����J�c��Ő��������@���ŁA���O���͂��ׂĂ̌�퍑�ւ̕���A�o�ƁA�D���ɂ�镐��A�����֎~�������́B�c����̋��a�}�Ȃǂ̌Ǘ���`���������A���[���b�p�ł̃i�`�X�h�C�c�Ɖp���̐푈�Ɋ������܂�邱�Ƃ������ӌ��������������ߐ��������B�������A1939�N9���A�h�C�c�R���|�[�����h�N�U���J�n����2�����E��킪�n�܂�A�A�W�A�ł����{����i�̓��������߂Ă���ƁA�C�M���X�̗v���������ăA�����J�c���11���ɒ����@���������A��������Ǝ����D�ɂ��A���������ɁA��퍑�ւ̕���A�o�֎~��P�p�����B����ɂ���Ē����@�͎�����p������A�C�M���X�ɑ��镐��A�o���s��ꂽ�B���[�Y���F���g�͎O�I���ʂ��������41�N3���A����ݗ^�@�𐧒肵�A�A�����ɕ����ݗ^���邱�ƂƂȂ�B |
| ���C�M���X�̋��Q�� �@ |
   �@
�@
|
���}�N�h�i���h �@
�����ƕی��̍팸 �@
���}�N�h�i���h������v���t �@
�����{�ʐ��̒�~(�C�M���X)
�}�N�h�i���h������v���t�́A1931�N9��21���A���{�ʐ����~�����B���E���Q���g�y���āA�h�C�c����̔��������X�g�b�v���A�����}���A���ێ��x�������������Ƃɂ��B���̂悤�ȃC�M���X�̋��Z�s�������܂�ƁA�C�M���X�̒ʉ݂ł���|���h�������A���̉��l���}�������B�|���h��������ƌ������Ƃ̓C�M���X�̋������o����ƌ������ƂȂ̂ŁA���ɋ��{�ʐ����~���Ǘ��ʉݐ��x�ɐ�ւ����B�C�M���X�ƌo�ϓI�W�̋��������ł����{�ʐ��͈ێ��ł��Ȃ��Ȃ�A�|���g�K���E�f���}�[�N�E�X�E�F�[�f���Ȃǂ��������ŋ��{�ʐ��̒�~(�܂��͋��A�o�֎~)�ɓ��ݐ����B�����1933�N3���A�e�����[�Y���F���g�哝�̂��A�����J���O�������{�ʐ����痣�E���A�����ɐ��E�̋��{�ʐ��͕��A�Ǘ��ʉݐ��x�Ɉڍs���邱�ƂƂȂ����B
���I�^���A�M��c �@
���X�^�[�����O���u���b�N �@
(�X�^�[�����O�Ƃ̓C�M���X�̖@��ݕ��̂��ƁB�|���h�̓V�����O�A�y���X�Ƌ��ɂ��̒P�ʁB)
|
| ���t�����X�̋��Q�� �@ |
   �@
�@
|
���t�����ʉ� �@
���l����� �@
�����\���݉������
1935�N5���A�t�����X�ƃ\�A�Ƃ̊ԂŒ������ꂽ���B����͂��̔N3���Ƀh�C�c���ČR����錾���A�����������������Ƃɋ��Ђ��������������ڋ߂��A�������������́B�������A���ۘA���K��ƃ��J���m���̏Ɩ������邱�Ƃ�����邽�߁A�R�������ł͂Ȃ��A���݉������Ƃ����`�ƂȂ����B�t�����X�͌`�������Ȃ��炾�����̂ŁA��y�͒x��A���N2���ɔ�y���������B���̃t�����X�ƃ\�A�̐ڋ߂ɔ��������q�g���[�̃h�C�c�́A�����̃��J���m���ᔽ�Ɣ��A36�N3���A�h�C�c�̓��J���m���j����錾�����B
���l��������t �@
���u����
���I�����u�����A��O�̃t�����X�̐����ƁB�͂��ߕ��w�҂Ƃ��ďo���A�W�����X�ƒm�荇���ăt�����X�Љ�}�ɓ��}�A���t�@�V�Y���^���Ŋ��A1936�N�ɐl��������t�̎ɏA�C�����B�J�����@��i�߂�ȂǁA�v�V������Ƃ������A�s���̐i�s�ɑ���L���Ȍo�ϐ����ł��o�����Ƃ��ł����A���N���E�����B��2�����E��킪�n�܂�ƁA���B�V�[�����ɑߕ߂���A�h�C�c�ɗ}������A�A�����J�R�ɋ~�o���ꂽ�B����1947�N�Ɏb����t�̎߂��B
|
| ���u���b�N�o��
|
   �@
�@
|
1929�N�̐��E���Q�Ɍ�����ꂽ�鍑��`�e���͘A���I�ȗA�o�s�U�Ɋׂ����B�e���͂܂��e���ʉ݂̕�����艺��(�����Ƃ͊e���̉ݕ��̉��l��̂��ƂŁA�ʏ��1�P�ʂ̋��ܗL�ʂŕ\�����)���s���ėA�o�𑝂₻���Ƃ����B���̕����艺�������ɂ���Ĉב֑���͌������āA�f�Ղ͂������Ă܂��܂����������B���̒��ŁA���Ɂu���Ă鍑�v�ƌ����鍑��������A���n��L���Ă��鏔���́A���ꂼ��o�ό�(�u���b�N)������Đ����c�낤�Ƃ����B���̂悤�Ȍo�ϑ̐����u�u���b�N�o�ρv�ł���A��v���̌��ϒʉ݂����Ƃ��ăO���[�v�����A�O���[�v���̊ł��y�����Ĉ���ʏ����m�ۂ��A��O����̗A���ɂ͍��ł������Ď����Y�Ƃ�ی삷��Ƃ����ی�f�Ր�����Ƃ����B
�u���b�N�o�ς̗�
�E�X�^�[�����O���u���b�N(�|���h���u���b�N�Ƃ�����)�@�C�M���X��1931�N�A��p�鍑����p�A�M�Ƃ������̂ɐ�ւ��āA���A���n�O���[�v���ĕ҂��A�|���h����Ƃ���X�^�[�����O����������B
�E�h�����u���b�N�@�A�����J���O���𒆐S�Ƃ�����k�A�����J�嗤����̃h���o�ό��Ƃ��Č`�������B
�E���u���b�N�@�t�����X�𒆐S�Ƃ����A���ɂ��x����(���{�ʐ�)��ʂ��Č������������[���b�p�����O���[�v�B
�u�������鍑�v�̃u���b�N�o��
�����́u���Ă鍑�v�ɑR����A�u�������鍑�v�Ǝ��Ȃ��K�肵���h�C�c�A�C�^���A�A���{�́u�����������v���m�ۂ��邽�߂ɌR���I�N���̓���I�B�h�C�c�͔r�O��`����������i�`�X�����͂���������ƁA�����[���b�p���璆�ߓ��ւ̐i�o���߂������B�C�^���A�̓t�@�C�X�g�����̉��ŁA�k�A�t���J����o���J����������ɒ��ߓ��ւ̖�S���������B���{�́u�哌�����h���v���\�z�������A����̓A�W�A�s��Ɂu�~�u���b�N�v��z���˂炢�ł������B
�u���b�N�o�ς̉e��
1929�N�`1933�N�̐��E���Q���ɁA���{��`��v�����u���b�N�o�ϐ�����̂������߁A���E�f�Ղ͂���4�N�Ԃ�7���������A���̌��ʁA���ĂƓ��{�Ő��疜�l�̎��Ǝ҂��o���B���̂悤�ȎЉ�s����w�i�ɁA�C�M���X�E�t�����X�E�A�����J�́u���Ă鍑�v�O���[�v�ƁA�h�C�c�E�C�^���A�E���{�́u�������鍑�v�̐��͌����߂���Η����[�������A�\�A�Љ��`�����ɑ��Ă͑o���Ƃ��x���S���߂Ȃ���ڋ߂�͍�����Ƃ������G�ȊO���W�̐i�W���o�āA�ŏI�I�ɘA�����Ɛ������Ɠ���đ�2�����E���ɓ˓������B�]���āA�鍑��`�������u���b�N�o�ϐ�����̂������Ƃ����E���������炵�����ړI�v���ƌ������Ƃ��ł���B
��2�����E����̃u���b�N�o�ς̔ے�
���̂悤�ɒ鍑��`�������o�σu���b�N������čR���������Ƃ���2�����E���������炵�����ƂȂ��A��㍑�ێЉ�̌����Ƃ��Ĕr���I�o�σu���b�N�̌`������ѕی��`�����h�~���A���R�f�Ղ𐄐i����K�v������Ƃ����F�������܂�A1947�N�Ɂu�f�ՂƊłɊւ����ʋ���(�f�`�s�s)�v������(48�N����)����A�f�Ղ̎��R���A�ł̌y���Ɋւ��鑽�p�������s���邱�ƂɂȂ����B(���̑̐���1971�N�̃A�����J�̃h���V���b�N�Ȃǂ��@�ɓ]�����邵�A�܂��f�`�s�s��1995�N�ɐ��E�f�Ջ@��(�v�s�n)�ɉ��g�A�������ꂽ�B�@
�@ |
| �����E���Q 10 / ���E���Q�O��̐��E |
   �@
�@
|
|
��1�@���E�o�ϋ��Q�ƃA�����J�̃j���[�f�B�[�� �@ |
1929�N10��24��(�Í��̖ؗj��)�ɋN�������j���[���[�N�̊��������(�E�H�[���X)�ł̊����̑�\�������������Ƃ��ăA�����J�ő勰�Q���n�܂����B
���̋��Q�́A��ꎟ���E����A�����J�̎��{�Ɉˑ����Ă������[���b�p�����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��A�܂��Ȃ����Q�̓\�A�������S���E�ɍL�܂����B���̐��E�j�������Ȃ��قǑ�K�͂Ő[���ȋ��Q�͐��E���Q(���E�o�ϋ��Q�A�勰�Q)�ƌĂ�Ă���B
���E���Q���A�����J����N�����������Ƃ��Ă͎��̂悤�Ȃ��Ƃ���������B �����ԁE���w�E�d�C�Ȃǂ̐V�����Y�Ƃ̔��W�E�Y�Ƃ̍������ɂ��H�Ɛ��Y�͂̑���E����ɂƂ��Ȃ��ߏ�Ȑݔ������Ȃǂɂ���čH�Ɛ��i�����Y�ߏ�Ɋׂ��Ă������ƁB ���Ő���̉e���ō��ۖf�Ղ��L�єY��ł������ƁB �_�ƕ���ł��A�푈������̑��Y�ɂ���Ĕ_�Y���̋������}�����Ă����Ƃ���ցA��ト�[���b�p�̕����ɂ���ă��[���b�p�̎��v���������A�_�Y�����i���}�����Ĕ_�ƕs�����[�������Ă������ƁB�_�ƕs���ɂ���Ĕ_���̍w���͂��ቺ���A�܂����Y���̐L�тɔ�ׂĘJ���҂̒������Ⴍ�}����ꂽ�̂ō����̍w���͂��ቺ�������ƁB
�v����ɁA���Y�ߏ�ƍ����̍w���͂̒ቺ�ɂ���Ď��v�Ƌ����̃o�����X���傫�����ꂽ���Ƃ������ł������B �����āA��㐢�E�̎��{���A�����J�ɏW�����A���ꂪ�y�n�⊔���̓��@�Ɏg���A�ߏ�ȓ��@�u�[�����N�����Ă������Ƃ�������\���̒��ڂ̌����ƂȂ����B
1929�N3���ɏA�C������31��哝�̃t�[���@�[(�C1929�`33)�́u���͂킪���̏����ɉ���̕s��������Ă��Ȃ��B�����͊�]�ɋP���Ă���v�Ɖ����������A���̍����łɐΒY�E���D�E�S���E�Z��݂Ȃǂ̋Ǝ�͕s���ɋꂵ��ł������A�_�Ƃ̕s���͐[�������A�_�Y�����i�̉����͑����Ă����B
�ɂ�������炸�A�����s��ł�1929�N9���܂Ŋ����͏㏸�𑱂����B1929�N9���̕��ϊ����́A8�N�O�ɔ�ׂ�4�D5�{�A3�N�O�ɔ�ׂĂ�2�{�ɂȂ��Ă����B
���̌�A������������Ԃ��Ă����������A1929�N10��24��(�Í��̖ؗj��)�ɓˑR��\�������B28�E29���ɂ���\���͑����A������1������40�����\�����A�����̉����͈Ȍ�3�N�ԑ������B
�������Q�͍����o�ς̂��ׂĂ̕���ɑ�Ō���^���A���Y�͌��ނ��A��Ƃ��s�̓|�Y���������A���Ǝ҂͑��債���B1932�N�܂ł�3�N�Ԃɖ�5000�̋�s���|�Y���A����������51���E�H�Ɛ��Y��46���E��Ɣ��グ��50���E�S�_�Y���̉��i��45���E�A�o��36�����ꂼ�ꉺ�������B
���Q���n�܂�ƃA�����J�̓��[���b�p���玑�{�������グ���̂ŁA���A�����J�o�ςɗ����Ă������[���b�p�����͑�Ō������B���ɔ���Ȕ������̎x�����ɋꂵ�݂Ȃ�����A�����J���{�ɂ���ė������肩���Ă����h�C�c�o�ς͍Ăєj�]���A���̌��ʔ����������Ȃ��Ȃ����C�M���X�E�t�����X�Ȃǂ����Q�Ɍ��܂��A���Q�̓\�A�������S���E�ɍL�����Đ��E���Q(���E�o�ϋ��Q�A�勰�Q)�ƂȂ����B
�A�����J�哝�̂̃t�[���@�[�́A1931�N6���Ƀh�C�c�̔�������A�����̐�̎x������1�N�Ԓ�~����Ƃ����t�[���@�[�������g���A��������������͏オ��Ȃ������B
�t�[���@�[�͌l��`�E���Ԃ̃C�j�V�A�e�B�u�ɌŎ����A�������ƁE�������ƁE���ƕی��Ȃǂ�A�M���{�̍����s�ɂ���Ă܂��Ȃ����Ƃ����ۂ������߂ɁA�ނ̋��Q��͌��ʂ��グ�邱�Ƃ��o�����A���Q�����邱�Ƃ��o���Ȃ������B
���̂��߁u�t�[���@�[�łȂ���ΒN�ł��悢�v�ƌ�����悤�ɂȂ�A1932�N�̑哝�̑I���ł͖���}�̃t�����N���������[�Y���F���g(���[�Y���F���g)�ɔs�ꂽ�B
�t�����N���������[�Y���F���g(1882�`1945�A�C1933�`45)�̓j���[���[�N�ɐ��܂�A�n�[���@�[�h��w�Ŋw��ɕٌ�m�ƂȂ����B1910�N�ɐ��E�ɓ���A�j���[���[�N�B��@�c���E�C�R�����E����}�哝�̌��(1920�N�A���I)���o�āA1929�N�Ƀj���[���[�N�B�m���ƂȂ�A�v�V�I�Ȑ���Œm��ꂽ�B�����Đ��E���Q���Ȃ��̑哝�̑I���Ō��E�̃t�[���@�[��j���đ�32��哝�̂ɏA�C����(1933�D3)�B
�t�����N���������[�Y���F���g�͏A�C����ɓ��ʋc������W���A�j���[�f�B�[������ƌĂ�鋰�Q������̍����ƂȂ�@�������X�ɐ��肵�Ă������B
�j���[�f�B�[���Ƃ́u�V�K�܂��������v�̈Ӗ��ŁA�j���[�f�B�[������̊�{�����Relief(�~��)�ERecovery(��)�EReform(���v)�̓��������Ƃ���3R����ƌĂ��B
�j���[�f�B�[������͍��܂ł̎��R���C�ɑウ�āA���Ƃ��o�ςɐϋɓI�ɉ�����A�������s���Či�C�ƍ��������̗��Ē�����}�낤�Ƃ��鐭��ŁA���S�ٗp�����̂��߂ɂ͐��{�ɂ��L�����v�̑n�o���d�v�ł���Ǝ咣�����C�����{��`�̑�\�I�ȗ��_�Ƃł���C�M���X�̌o�ϊw�҃P�C���Y(1883�`1946)�̗��_�����߂Ď��{��������ł������B
�j���[�f�B�[������̍����ƂȂ����@���́A�_�ƒ����@(AAA�A1935.5)�E�S���Y�ƕ����@(NIRA�A1933.6)�E�e�l�V�[�여��J������(TVA)�̐ݗ�(1933.5)�Ȃǂł���B
�_�ƒ����@(Agricultural Adjustment Act�̓��������Ƃ���AAA�ƌĂ��)�͏����E�Ƃ����낱���E�ȉԂȂǂ̎�v�앨�̍�t�ʐς�̔��p���Y���팸�������ʼnߏ�_�Y���𐭕{�������グ��Ȃǂ��Ĕ_�Y�����i�����肳���A�_���̋~�ςƂ��̍w���͂̉�ڂ������@���ł���B
�܂��S���Y�ƕ����@(National Industrial Recovery Act�̓��������Ƃ���NIRA�A�ʏ̃j���ƌĂ��)�͊�ƂɓƐ�֎~�@�̓K�p���~���Č��������̋K��������A���Y���K������ƂƂ��Ɋ�Ƃ̓K���ȗ������m�ۂ����A�����ŘJ���҂̒c�����E�c�̌�����F�߂ēK���Ȓ����̊m�ۂ�}�点�A���Y�͂ƍw���͂������邱�Ƃ�ړI�Ƃ����@���ł���B�������ANIRA��1935�N�ɍō��ٔ����ɂ���Ĉጛ���������̂ŁA���̒��̘J���҂̌����Ɋւ��镔�������O�i�[�@�Ƃ��Đ��肵��(1935.7)�B
�����ăe�l�V�[�여��J������(Tennessee Valley Authoity�̓��������Ƃ���TVA�ƌĂ��)�͓d�͊J���E�����E�y�n�ۑS�E�A�сE�_�H�Ƃ̐U���Ȃǂ�ړI�Ƃ���n�摍���J���v��ŁA���{������ȃ_�����݂Ȃǂ̌������Ƃ��s���A���̎��Ƃɑ����̎��Ǝ҂��z�����A�������x�����čw���͂𑝂₷���Ƃ�ړI�Ƃ����B
1935�N�ɐ��肳�ꂽ���O�i�[�@�ɂ���ĘJ���҂̒c�����ƒc�̌������F�߂�ꂽ���Ƃ���J���g���^�������W���A���N�Y�ƕʑg�D��c(CIO)���������ꂽ�BCIO�͏n���J���҂𒆐S�Ƃ���AFL(�A�����J�J��������)�ɑR���āA���n���J���҂𒆐S�ɑg�D����A1938�N��AFL���番���E�Ɨ������B1935�N�ɂ͎Љ�ی��@���������A���ƕی����x��V��N�����x�Ȃǂ���߂�ꂽ�B
���E���Q�����������ŋ��Q������̈�Ƃ��ĊO�𐭍�����߁A�]���̌Ǘ���`�E�c����`����P�חF�D����ɓ]�������B
1933�N�ɂ̓\�A�����F�����B�̒��ŃA�����J�����͒����ԃ\�A�����F���Ȃ��������A�t�@�V�Y�������̑䓪�ɑR���邽�߁A�����ă\�A�s��ւ̗A�o�̊g���}�邽�߂ɂ��ɏ��F�ɂӂ݂������B
�܂����e�����A�����J�����ɑ��Ă��A�]���̃J���u�C��������߂đP�O��(�P�חF�D����)�ɓ]���A���e�����A�����J�����Ƃ̗F�D�ɓw�߂����A���̔w�i�ɂ����e�����A�����J�����ւ̗A�o���g�債�����Ƃ����Ӑ}���������B
1933�N�ɊJ���ꂽ�p�����A�����J��c�ŁA�A�����J�͑P�חF�D�̕��j��\�����A�L���[�o�ɑ��Ă̓v���b�g������p�~���Ċ��S�Ɨ������F����(1934.5)�B
�����ăt�B���s���ɑ��Ă��A1934�N�ɓƗ��@�Ă𐬗������A��1935�N�Ɏ�����F�߁A10�N��̊��S�Ɨ�������B
���������j���[�f�B�[������̎��{��O�𐭍�̓]���Ȃǂɂ���āA�A�����J�̌o�ρE�Љ��1935�N���ɂ͂悤�₭������Ƃ�߂����B
�t�����N���������[�Y���F���g��1936�N�̑哝�̑I���ł͘J���҂�̎x���Ĉ��|�I�ȏ����������߂čđI���ꂽ(1940�N3�I�A1944�N4�I)�B
���݂̃A�����J�ł͑哝�̂�3�I�͌��@�ŋ֎~����Ă���̂�(1951�A���@�C����22)�A�t�����N���������[�Y���F���g�̓A�����J�j��B��l��4�I���ꂽ�哝�̂ƂȂ����B�@ |
| ��2�@�C�M���X�ƃt�����X�̋��Q�� |
   �@
�@
|
�C�M���X�ł́A1929�N5���̑��I���ŘJ���}���ێ�}��j���ď��߂đ�1�}�ƂȂ�A��2���}�N�h�i���h�J���}���t(1929.6�`31.8)�����������B�������A�܂��Ȃ��A�����J�ő勰�Q���N����A�A�����J���{�������グ����ƃC�M���X�����E���Q�Ɋ������܂ꂽ�B
�C�M���X�͕s���Ɋׂ�A�ȍH�ƁE���D�E���S�E�ΒY�Ȃǂ̎�v�Y�Ƃ̐��Y���������A���ƁE�f�Ղ��}���ɐ������B�����������Ŏ��Ǝ҂͋}�����A1929�N6���ɂ�116���l�ł��������A���N4���ɂ�176���l�A������1931�N6���ɂ�270���l�ɂ̂ڂ����B���̂��ߎ��ƕی��̋��t���������A���������������B
�}�N�h�i���h�͎��ƕی��̑啝�팸�Ȃǂɂ��ُk�����𗧈Ă������A����ɑ��ĘJ���}�͌���Ɍf����Љ�ۏᐧ�x�̏[���ɔ�����Ƃ��ċ��������A�}�N�h�i���h�J���}���t�͑����E����(1931.8)�B
�}�N�h�i���h�͂��̒���ɍ����̑喽�����сA�ێ�}�y�ю��R�}�̋��͂ċ�����v���t(1931.8�`35.6)��g�D�����B���̂��߃}�N�h�i���h�͗��؎҂Ƃ���A�J���}���������ꂽ�B���̌�A10���ɍs��ꂽ���I���ł͐��{�^�}���������A�}������������J���}��215�c�Ȃ�������52�c�ȂƂȂ����B
�}�N�h�i���h������v���t�͎��ƕی��̍팸���܂ދُk�\�Z�𐬗������A���{�ʐ��̒�~(1931.9)��ی�Ŗ@�̐���(1932.1)���s���ƂƂ��ɁA1932�N7������8���ɂ����ăJ�i�_�̃I�^���ŃC�M���X�A�M�o�ω�c(�I�^���A�M��c�A�I�^����c)���J���A�I�^�����������Ńu���b�N�o�ϐ�����̗p�����B
�C�M���X�̓I�^����c�ɐ旧���āA1926�N�̃C�M���X�鍑��c�̌��c�𐬕��������E�G�X�g�~���X�^�[���͂𐧒肵(1931.12)�A�e�����̂ɂ̓C�M���X�A�M�̈���Ƃ��ăC�M���X�����ɒ����𐾂����Ƃ������ɁA�{���ƑΓ��̒n�ʂ�^���邱�Ƃ��߂��B
�I�^����c�ɂ́A�C�M���X�{���E�J�i�_�E�I�[�X�g�����A�E�j���[�W�����h�E��A�t���J�A�M�E�A�C�������h�E�C���h�E�샍�[�f�V�A�̑�\���W�܂�A�{���Ǝ����̋y�уC���h�͓��b�Ő��x�𒆐S�Ƃ��鑊�ݒʏ���������B
���̃I�^������̓C�M���X�鍑�S�̂���O�����i��ǂ��o�����Ƃ�ړI�Ƃ��A�O�����i�ɑ��Ă͍��ł��ۂ��A�C�M���X�鍑���̏��i�ɑ��Ă͖��ł܂��͒�ł��ۂ����ƂƂ����B
����ɂ���Ĕr���I�Ȍo�σu���b�N���`������A�C�M���X�͏]���̎��R�f�Վ�`��������ău���b�N�o�ϐ�����Ƃ邱�ƂɂȂ����B�Ȃ��C�M���X�̌o�σu���b�N�̓X�^�[�����O���u���b�N(�|���h���u���b�N)�ƌĂ�Ă���B
�C�M���X���u���b�N�o�ϐ�����Ƃ������Ƃ����یo�ς��܂��܂����߂邱�ƂƂȂ�A���E�o�ς̎����������ƍ��یo�ϋ��������������A�Ȍ�u���Ă鍑�Ǝ������鍑�v�Ƃ̑Η������܂錴���ƂȂ����B
�u���b�N�o�ϐ���ɂ���ăC�M���X�o�ς͏��X�ɉɌ������A���Ǝ҂��������A�H�Ɛ��Y�w����1929�N��100�Ƃ����ꍇ�A1932�N��85�ł��������A1934�N�ɂ�104�Ɍ��サ���B
�}�N�h�i���h�̈��ތ�A�ێ�}�𒆐S�Ƃ���{�[���h�E�B���������t(1935.6�`37.5)�A�l���B�����`�F���o�����ێ�}���t(1937.5�`40.5)�����������B
�t�����X�ł́A���E���Q�̉e������r�I�x���������A1931�N�ɂȂ�Ɖe��������͂��߁A1932�N�ɂȂ��Đ[���������B
���̂��߂��̂悤�ȏɑΉ��ł��Ȃ������E�h�A�����{�ɑ���s�������܂�A1932�N5���̑��I���ł͍��h���������A�}�i�Љ�}(���Y�K������ՂƂ���i���I���a�h���})��Љ�}(�Љ��`���h�̘A�����})�Ȃǂ��c�Ȃ𑝂₵���B
���̌��ʁA�}�i�Љ�}�̃G���I���t�������������A���h�w�c�̕����Ԏ������ɋꂵ�߂���6�����œ|��A�Ȍ�14�����̊Ԃ�5�̓��t����シ�鐭���I�������������B
���̊ԁA�h�C�c�Ńi�`�X����������(1933.1)����ƁA�t�����X�����ł�1934�N�ɋɉE�t�@�V�X�g�c�̂�E�����͂̃f���E�\�����N����A�܂�����ɔ�����J���҂̃f�����N�����č������������B
���������̒��ŎЉ�}�Ƌ��Y�}�͔��t�@�V�Y���̋������������(1934)�A��1935�N6���A����ɋ}�i�Љ�}��������Đl�����(�t�@�V�Y���Ɛ푈�ɔ�����S���͂Ƒg�D�����W�������t�@�V�Y���l��������)���������ꂽ�B
������O��1935�N5���A�t�����X�̓h�C�c�̍ČR���錾(1935.3)�ɋ��Ђ������A�\�A�Ƃ̊Ԃɕ��\���݉�����������Ńi�`�X���h�C�c�̐i�o�ɑR�����B
���E�����͂̌������Η����������ōs��ꂽ1936�N5���̑��I���ł́A�l������h�������̎x���đ叟���A�Љ�}�̃��I�����u����(1872�`1950�A�C1936�`37)���Ƃ���l��������t(�Љ�}�Ƌ}�i�Љ�}�̘A�����t�A���Y�}�͊t�O����)�����������B
�u�������t�́A�T40���ԘJ�����E�c�̌����̏��F�E�t�����X��s�̉��v�E�R���H��̈ꕔ���L���E���Ǝҋ~�ς̌����y�؎��ƂȂǃt�����X�Ńj���[�f�B�[������ƌĂ�鏔��������{�������o�ϊ�@�������ł����A�ސw����(1937.6)�B
�t�����X�o�ς��Ɍ��������̂�1938�`39�N�̂��Ƃł���A����͌R����̑���ƌR���H�Ƃ̊g���ɂ����̂ł������B �@ |
| ��3�@�t�@�V�X�g���C�^���A�̐����Ƃ��̐��� |
   �@
�@
|
��ꎟ���E����A��i���{��`���𒆐S�Ƀt�@�V�Y���ƌĂ�鐭���`�Ԃ��o�������B�t�@�V�Y���Ƃ������t�͏��߂̓C�^���A�̃t�@�V�X�g�}�̐����̐����w���Ă������A���̌�ގ����������̐��ɑ��Ă��L���g����悤�ɂȂ����B
�t�@�V�Y���Ƃ́A��ꎟ���E����̎��{��`�̐�����@�Ɋׂ����Ƃ��ɏo�������c������`��ے肷��ƍٓI�Ȑ����`�Ԃł���B
�t�@�V�Y���̐��̂��Ƃł́A���Ƃ܂��͖����̔��W���ō��̖ړI�Ƃ��A�l�͂���ɏ]�����A��d���ׂ����̂ƍl����S�̎�`�ƌĂ�鐭���v�z(�����`��)�ɂ���Čl�̊�{�I�l���⎩�R�͔ے肳��A���Ƃ�Љ�S�̗̂��v���D�悳�ꂽ�B
�t�@�V�Y���̓T�^�̓i�`�X���h�C�c�ł��邪�A�t�@�V�Y�����ŏ��ɐ��������̂̓C�^���A�ɂ����Ăł������B
�C�^���A�͑�ꎟ���E���̐폟���ł��������A�p���u�a��c�ł́u���ꂴ��C�^���A�v�̊l�����F�߂�ꂽ�����Ńt�B�E���s�̕����Ȃǂ͋��ۂ���A���F���T�C���̐��ɕs���������Ă����B
���̂��߁A1919�N9���ɂ͎��l�E�����Ƃň����҂ł������_�k���c�B�I(1863�`1938)�������R�l�Ȃǂ̋`�E���𗦂��ăt�B�E�����̂���Ƃ����o�������N������(1920�D12�P��)�B
���Ƃ��Ǝ������R�����A�o�ϊ�Ղ��ォ�����C�^���A�͐��̂قƂ�ǂ��O�ł܂��Ȃ������߁A��㔜��ȍ����č�����@�Ɋׂ����B�܂��Y�Ƃ��s�U�Ɋׂ�A���Ǝ҂����債�A�H�����̑��̐����K���i���s�����Č������C���t���[�V�����ɂ݂܂�ꂽ�B
���̂���1919�N����20�N�ɂ����ēs�s�ł͘J���҂̃X�g���C�L���p�����A�_���ł͔_�����n��̓y�n��苒���Ēn��̎x���������ۂ���ȂǎЉ�s�������債�A1919�N11���ɍs��ꂽ���I���ł͎Љ�}����1�}�ƂȂ����B
1920�N�ɂȂ�ƘJ���҂̃X�g���C�L���������A9���ɂ͖k�C�^���A�̘J���҂��Љ�}���h(1921�N�ɋ��Y�}������)�̎w���̂��ƂōH���苒���A�_�����e�n�Œn��̓y�n��苒�����̂ŁA�v���O����v�킹��ɂȂ����B
�������A�J���҂͒��グ���̑��̏����Ő��{�̑Ë��Ă�����čH��苒���������̂ňȌ�J���^���͐��ނɌ��������B���̈���ŁA���̏o���������������Ƃ��Đ��͂��g�債���̂����b�\���[�j�̗�����t�@�V�X�g�}�ł������B
���b�\���[�j(1883�`1945)�͖k�C�^���A�Œb�艮�̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�t�͊w�Z�𑲋ƌ�A�X�C�X�e�n��]�X�Ƃ���ԂɎЉ��`�҂ƐڐG���A�A����C�^���A�Љ�}�ɓ��}����(1908��)�B�ނ͍I�݂ȕِ�Œm���A�Љ�}�̋@�֎��u�A���@���e�B(�O�i)�v�̕ҏW���ƂȂ�����(1912)�A��ꎟ���E��킪�u������ƎQ����咣���ē}���珜������(1914)�A�Ȍ㔽�Љ��`�^���ɂ͂������B
���b�\���[�j�́A1919�N3���A�~���m�Łu�퓬�҃t�@�b�V���v���������A���N11���̑��I���ɗ���₵����4�琔�S�[���l�����������ŗ��I�����B�Ȃ��t�@�b�V���Ƃ͌Ñネ�[�}�̊����������������ꑩ�̖_�Œc���E�������Ӗ����A�t�@�V�Y���̌ꌹ�ƂȂ����B
�������A�퓬�҃t�@�b�V���́A1920�N�̖k�C�^���A�̃X�g���C�L�ŘJ���҂ɂ��H��苒���s����ƁA�Љ�}����J���҂�\�͂ōU�����A�J���^����\�͂Œ��������B
�퓬�҃t�@�b�V���͋��Y��`�̐i�o������鎑�{�ƁE�n��E�R���Ȃǂ̎x�����Đ��͂��g�債�A1921�N5���̑��I���ł�31���I�����A���N11���ɐ퓬�҃t�@�b�V���̓t�@�V�X�g�}(���ƃt�@�V�X�g�}�A�t�@�V�X�^�})�ɉ��g���ꂽ�B
���̍��ɂ͓}��������30���l�ɒB���Ă����t�@�V�X�g�}�͐퓬�c(���V���c���ƌĂꂽ)�̌R������i�߁A�\�͓I�Ȑ��i���܂��܂����߂Ă������B
1922�N10��24���A�i�|���ŊJ���ꂽ�t�@�V�X�g�}���Ń��b�\���[�j�͐����D���錾���A28���ɂ͍��V���c�������[�}�Ɍ������Đi�����J�n����(���[�}�i�R)�B
�t�@�N�^�͍������B�b�g�[���I���G�}�k�G�[��3��(��1900�`46)�ɉ����߂̔��z�����߂����A�����͂�������ۂ��A�t�Ƀ��b�\���[�j�ɑg�t�𖽂����B
���V���c���̓��[�}���̂��A���b�\���[�j���~���m����Q��ԂŃ��[�}�ɓ������A�������Ƀ��b�\���[�j����(�t�@�V�X�g����)�����������B
���������������b�\���[�j�́A�t�@�V�X�g��]�c���ݗ���(1923)�A��1924�N�̑��I���Ńt�@�V�X�g�}�͖\�͂��g�����I���^���ɂ���đ����[����65���E375�c�Ȃ��l�����ċc��̐�Α���������A1926�N11���ɂ̓t�@�V�X�g�}�ȊO�̑S���}�����U�����A�t�@�V�X�g�}��}�ƍِ����m�������B
�����1928�N12���ɂ̓t�@�V�X�g�}�̍ō��@�ւł������t�@�V�X�g��]�c������ɍ��Ƃ̍ō��@�ւƂȂ�A�t�@�V�Y���̐������������B
���̊ԁA���b�\���[�j�̓��[�}�鍑�̍Č��������đΊO�g�������i�߁A1924�N1���ɂ̓��[�S�Ƃ̒��ڌ��ɂ���ăt�B�E���������B�t�B�E���̓_�k���c�B�I���`�E���𗦂��Ĉꎞ��̂������A���p�����(1920�D11)�ɂ���ēƗ��s�Ƃ��ꂽ�����b�\���[�j�ɂ���čēx�������ꂽ�B������1926�N�ɂ̓A���o�j�A��������̕ی썑�Ƃ����B
�����1929�N2���ɂ́A�J�g���b�N���k���قƂ�ǂ��߂鍑���̎x���邽�߂Ƀ��[�}���c���ƃ��e�������(���e���m���A���e��������)�����B���[�}���c���ƃC�^���A�����Ƃ́A1870�N�ɃC�^���A���������[�}���c�������Ĉȗ��A���[�}���c�́u���@�`�J���̎��l�v�Ə̂��A���҂͍���f���Ԃɂ������B
���b�\���[�j�̓��e������������Ń��[�}���c�Ƙa�����A���@�`�J���s���̓Ɨ��ƃJ�g���b�N���C�^���A�B��̏@���ł��邱�Ƃ�F�߁A���[�}���c�̓��b�\���[�j���������F�����B
���@�`�J���s���̓��[�}�s�̈�p�ɂ��鋳�c���̏��ݒn��ŁA�ʐ�0�D44����km�E�l��1277�l(1994)�̐��E�ŏ��̓Ɨ����Ƃł���B
���b�\���[�j���C�^���A�����Ńt�@�V�Y���̐������������Ă܂��Ȃ��A���E���Q�̉e�����C�^���A�ɂ��y�B���b�\���[�j�͓����o�ς����߁A���Ǝ҂̋~�ς����˂���y�؎��Ƃ��N�����čH�Ƃ̔��W��}��ƂƂ��ɐH�Ƃ̑��Y�ɂ��w�߂��B
�������A���̈���Ŏ����ɖR�����C�^���A�����̌o�ϊ�@��ŊJ���邽�߁A�܂��o�ϊ�@���獑���̖ڂ����点�邽�߂�1935�N10���ɂ̓G�`�I�s�A�N�����J�n�����B
�C�^���A�R���N�����J�n���Ă���4����ɍ��ۘA��������̓C�^���A��N�����Ƃ݂Ȃ��A8����ɍ��ۘA������̓C�^���A�ւ̌o�ϐ��ق����c�����B�������A���̌o�ϐ��ق͊̐S�̐Ζ����֗A���X�g����O�����ȂǕs�O��Ō��ʂ͂Ȃ������B
�G�`�I�s�A�R�͗E���ɒ�R�������A�ߑ㕺��ŕ��������C�^���A�R�͔j�|�̐i���𑱂��A�C�^���A��1936�N5���ɃG�`�I�s�A�������B
���̃C�^���A�ɂ��G�`�I�s�A�N���͍��ۘA���̌��Ђ����Ă�����ƂƂ��ɁA�t�@�V�X�g���C�^���A�ƃi�`�X���h�C�c��ڋ߂����A1936�N10���Ƀx�����������[�}���������������B�@ |
| ��4�@�i�`�X���h�C�c�̐����ƃ��F���T�C���̐��̔j�� (1) |
   �@
�@
|
1920�N��㔼�ɂ���ƈ�������߂����h�C�c�͐��E���Q�ɂ���Đ[���ȑŌ����A���������͍������A�c����͊�@�Ɋׂ����B���������̒��ŋ}���ɐ��͂�L�����i�`�X�́A1933�N1���A���ɐ������l�����A�q�g���[���t�����������B
�q�g���[(1889�`1945)�̓I�[�X�g���A�̃u���E�i�E�ʼn����Ŋ֊����̎q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���Ȋw�Z�𒆑ނ����ނ͉�Ƃ��u���ăE�B�[���ɏo�Ĕ��p�w�Z�����������s����(1907)�B���N���Ɏ��s�����q�g���[�̓E�B�[���Ŏ����ŏ������G������A���ق��J���҂����Ȃ���H�ׂ���̂ɂ��������悤�ȍ����̐����𑗂����B���̌�A�ꎞ�~�����w���ɂ��ڂ�Z��(1913)�A1914�N8���ɑ�ꎟ���E��킪�N����ƁA�������Ƀo�C�G�����A���Ɏu�蕺�Ƃ��ē��������B
�t�����h������ɔh�����ꂽ�q�g���[�͗E���ɐ킢�A2�x�������A���R�a�@�Ŕs����}���A�܂��Ȃ��މ@���ăo�C�G�����̘A���ɖ߂����B�����ČR�̐����H����ƂȂ����q�g���[�̓h�C�c�J���ғ}�Ƃ��������ȉE�������c�̂̒����𖽂����ē��}����(1919.9)�B�����čI�݂Ȑ��������Ɛ��͓I�Ȋ����ɂ���ē��p������킵�A�܂��Ȃ��}�̎w���҂ƂȂ���(1921.7)�B
���̊ԁA1920�N2���ɂ́u25�J���̍j�́v�����\����A�}�����h�C�c�J���ғ}���獑��(����)�Љ��`�h�C�c�J���ғ}(�ʏ̂̃i�`�X�͐��G����̌ď�)�ɉ��̂��ꂽ�B
�u25�J���̍j�́v�̎�ȓ��e�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
1�@�����́A�������̖����������̌����ɂ̂��Ƃ�A��h�C�c�����������邽�ߑS�h�C�c�l���������邱�Ƃ�v������B
2�@�����́A�������ɑ���h�C�c�����̕�������v�����A���F���T�C�����уT�����W�F���}�����a���̔j����v������B
3�@�����́A�킪������{���A�ߏ�l�����ڏZ�����߂邽�߂ɁA�y�n����ї̓y(�A���n)��v������B
4�@�h�C�c�������E������݂̂̂��A�h�C�c���������肤��B�h�C�c�l�̌����������݂̂̂��@�h�̂�������킸�A�h�C�c�������E���肤��B���������Ă��ׂẴ��_���l�̓h�C�c�������E���蓾�Ȃ��B
8�@��h�C�c�l�̂���ȏ�̗����͑j�~����˂Ȃ�Ȃ��B�����́A1914�N8��2���ȍ~�h�C�c���ɗ����������ׂĂ̔�h�C�c�l���A���������I�ɍ��O�֑ދ������߂邱�Ƃ�v������B
22�@�����́A�b���R���̔p�~�ƁA�����R�̌��݂�v������B
25�@�ȏシ�ׂĂ̗v�����ѓO���邽�߁A�����́A�h�C�c���ɋ��͂Ȓ������͂�n�݂��邱�Ƃ�v������B�E�E�E
���̂悤�ɑ�h�C�c�̌��݁E���F���T�C�����̔j���E�̓y�̗v���E���_���l�̔��Q�Ȃnj�Ƀq�g���[�������ɓw�͂���������`�I�Ȑ��f�����Ă���B�܂�11�`17�ɂ͕s�J�����̔p�~�E�펞�����̖v���E�g���X�g�̍��L���E�{�V���x�̊g���E�y�n���v�Ȃǂ̎Љ��`�I�Ȑ�����f�����Ă��邪�A�����͓}���g��̂��߂̋�ɂ������A���̌�q�g���[�ɂ���Ė������ꂽ�B
�i�`�X��������ڂ��W�߂�悤�ɂȂ����̂́A1923�N11���̃~�����w���Ꝅ�ɂ���Ăł������B1923�N�A�t�����X�E�x���M�[�ɂ�郋�[����̂ɂ����1���{�ɋy�Ԕj�ǓI�ȃC���t���[�V�������N����A�����s������������ƁA���N11���A�i�`�X�̓��@�C�}�����{�̑œ|�Ɛ����l����ڂ����ăN�[�f�^�[����Ă�(�~�����w���Ꝅ)�B
�������A���̃~�����w���Ꝅ�͍��h�R�ɂ���Ē�������A�q�g���[�͑ߕ߂���A���N�̍ٔ��ŗL�߂ƂȂ�A9�����ԓ������ꂽ�B���̊ԁA�����Ō��q�M�L���ꂽ�̂��L���ȁw�킪�����x(1925�N�ɏ㊪�A27�N�ɉ������o�ł��ꂽ)�ŁA�i�`�X�̃o�C�u���ƂȂ����B
�o����A�q�g���[�͐�p��]�����A�I���ɂ�鍇�@�I�Ȑ����l����ڂ������B�������A�����̃h�C�c�͐����E�o�ρE�Љ������Ɍ������Ă����̂ŁA�i�`�X�̐��͂͂قƂ�ǐL�т��A1928�N5���̑I���ł͑����[����2�D6���E12�c�Ȃ��l�������ɂ����Ȃ������B
1929�N�Ɏn�܂������E���Q���h�C�c�ɋy�ԂƁA�A�����J���{�Ɉˑ����Ă����h�C�c�o�ς͂����܂��j�]�̊�@�ɕm�����B��Ƃ̓|�Y���������A�H�Ɛ��Y�͔�����(1929�N��100�Ƃ���H�Ɛ��Y���̎w����1932�N�ɂ�53�D3�ƂȂ���)�A���ƎҐ���600���l�����B
���������̒��ŁA�i�`�X�̏����錻��Ŕj�A���Ƀ��F���T�C���̐��j���̎咣�̓h�C�c�l�̐S���Ƃ炦���B�i�`�X�͍I�݂Ȑ�`�ɂ���ď]���̐��}�Ɏ��]�������Y�K���̎x���A1930�N9���̑I���ł͑����[����18�D3�����l�����A�c�Ȑ���12����ꋓ��107�c�ȂɐL���A�Љ��}(143�c��)�Ɏ�����2�}�ɖ��i�����B���̈���ł��̑I���ł͘J���҂Ɏx�����ꂽ���Y�}��54(1928)����77�ւƋc�Ȑ����������B
���Y�}�̐i�o�����ꂽ���{��(���ɋ��Z���{�ƂƏd�H�Ǝ��{��)�ƃ����J�[(��n��)�̓i�`�X�x���ɌX���A�i�`�X�ɍ����������s�����B����ɌR�����i�`�X���x�������̂ŁA1932�N7���̑I���ł̓i�`�X�͑����[����37�D4���E230�c�Ȃ��l�����A���ɑ�1�}�ƂȂ����B�q�g���[�͓��t�����߂�ꂽ���g�t�����߂Ă�������₵��(1932.8)�B
1932�N11���̑I���ł��i�`�X�͑�1�}�ł�������196�Ƌc�Ȃ����炵�A������Y�}��100�c��(1932�N7���I���ł�89�c��)�Ƌc�Ȃ�����ɑ��₵���B
���Y�}�̐i�o�ɋ��Ђ����������{�Ƃ���J�[�͂܂��܂��i�`�X�x�������߁A���t���E�ɒǂ����̂Ńq���f���u���N�哝�̂̓q�g���[�ɑg�t�������A1933�N1��30���A���Ƀq�g���[���t�����������B
�������A���̎��̃q�g���[���t�͘A�����t�ʼnߔ����ɒB���ĂȂ������̂ŁA�q�g���[�͂������ɋc������U���A1933�N3���̑I���ł͑����[����43�D9���E288�c�ȂƂ������|�I�������l�������B
���̑I���ł́A�i�`�X�͖L�x�Ȏ�����p���đ�X�I�Ȑ�`���s������ŁA�\�͂Ŕ��Γ}�̑I���^����W�Q����Ȃǖ��\�L�̃e���Ƌ������s�����B
����1932�N2��27����A����c�������Ύ������N����ƁA���ΔƐl�Ƃ��đO�I�����_���Y�}���̃��b�x���ߕ߂��A��������Y�}�̉A�d�Ƃ��ċ��Y�}��e�������B���̎����ɂ��Ă͕s���ȓ_���������A�Q�[�����O��i�`�X��]���v�悵�����ΐ����L�͂ł���B
�i�`�X�͍���c�������Ύ����̗����A�ً}�߂��A���@���ۏႷ�錾�_�E�o�ł̎��R�Ȃǂ̊�{�����~���A�܂����Y�}��@�����Đ���l�̋��Y�}����ߕ߂����B
��������3��5���̑I���ł�288�c�Ȃ��l�������B�������A�^�}�̍��Ɛl���}��52�c�Ȃ������Ă�3����2(���@�����ɕK�v�Ȑ�)�ɒB���Ȃ������̂ŁA���Y�}��81���̓��I���Ƃ��A1933�N3��24���ɂ͑S���ϔC�@(�����@)�𐬗��������B
�S���ϔC�@�́A�Ȍ�4�N�ԍ����哝�̂̏��F�Ȃ��ɐ��{�̗��@����F�߂�Ƃ������e�ŁA����ɂ���ăq�g���[�̓ƍّ̐����m�����ꂽ�B
�ƍٌ����������q�g���[�́A�J���g�����֎~��(1933.5)�A���N7���܂łɂ̓i�`�X�ȊO�̑S���}�����U�����A�i�`�X�̈�}�ƍّ̐����m�������B
�q�g���[�́A1934�N8���Ƀq���f���u���N�哝�̂��S���Ȃ�ƁA����(�t���[���[)�ɏA�C���A�哝�́E�E�}��̑S��������A�����Ƃ��ɓƍَ҂ƂȂ����B �@ |
| ��4�@�i�`�X���h�C�c�̐����ƃ��F���T�C���̐��̔j�� (2)
|
   �@
�@
|
�i�`�X�x�z���̃h�C�c�͑�O�鍑(1933�`45)�ƌĂ��B��O�鍑�Ƃ́A���鍑(�_�����[�}�鍑)�E���鍑(�h�C�c�鍑)�Ɏ�����O�̒鍑�̈Ӗ��ł���B
�i�`�X�͑S�̎�`�̎v�z�̂��ƂŖ����`��ے肵�A�l�̎��R�E��{�I�l���͔F�߂��A���������S�̂����������������B���ɔ��Δh��_���l�ɑ��Ă͓ˌ���(SA�A�G�X���A�[)�E�e�q��(SS�A�G�X���G�X)�E�閧�x�@(�Q�V���^�|)�𗘗p���ēO�ꂵ�Ēe�������B
�ˌ����́A1921�N�ɑn�݂��ꂽ�i�`�X�̒��ڍs�����ŁA���߂̓i�`�X�̏W��̖h�q��C���Ƃ������A�₪�Ĕ��Δh�ɑ���f���Ɩ\�͂̍s�g����C���Ƃ����B1926�N�Ȍ�͑�O�g�D�Ƃ��ċ}���ɐ��͂��g�債�A1933�N���ɂ�250���l��i���č��h�R�ƕ��ԋ���ȑg�D�ƂȂ�A���h�R�ƑΗ������B���h�R�̎x����K�v�Ƃ����q�g���[�́A1934�N6���ɓˌ����̊������l�������̂ŁA�Ȍ�͐e�q�������͂ɂȂ����B
�e�q���̓q�g���[�l�̐g�ӌx����Ƃ���1925�N�ɑn�݂��ꂽ�B1934�N�ɓˌ�������Ɨ����A�ŐV�̕���ŕ������A��̒n�x�z�⋭�����e���̉^�c���s���A��ɂ͔閧�x�@�̖������S�����B
�Q�V���^�|�́A1933�`34�N�ɐݗ����ꂽ���Ɣ閧�x�@�ŁA�������i��p���Ĕ��i�`�X���q��_���l��O��I�ɒe�����A�i�`�X�̋��|�����̃V���{���ƂȂ����B
�q�g���[��19���I�Ƀ��[���b�p�ō��܂��������_���l�I�l��_�����ƂɁA�h�C�c�����͐��E�ōł��D�G�Ȗ����ł���A���̔��Ƀ��_���l�͗����Ő�ł����ׂ����݂ł���Ƃ����ɒ[�Ȑl��_�������A���_���l�𔗊Q�����B
1933�N�ɂ̓��_���l���X�ɑ���{�C�R�b�g��_���l�̌��E����̒Ǖ����s���A1935�N�ɂ̓��_���l��4����1�ȏテ�_���l�̌����������Ă��鍬���҂���s�����D���A���_���l�Ɣ_���l�Ƃ̌������֎~�����B
�����������ŁA1938�N�ɂ̓��_���l�̏��X�̑ł����킵��s�E���s���A1942�N�ɂ̓��_���l��Ő����肳�ꂽ�B�����Đ����Ƃ�_���l�����e���ċ����J�����s�킹�A���邢�͑�ʋs�E���s�����߂ɋ������e�����e�n�Ɍ��݂���A���_���l�̋����A�s�E��ʋs�E���s��ꂽ�B
�L���ȃA�E�V���r�b�c�̋������e��(���݂̃|�[�����h�����ɂ�����)��1940�N�Ɍ��݂��ꂽ�ő�K�͂̋������e���ŁA���������ł�250���l�̃��_���l���܂�400���l�ȏオ�s�E���ꂽ�Ƃ����Ă���B����E��풆�̃i�`�X�ɂ�郆�_���l�̑�ʋs�E(�z���R�[�X�g)�ł͖�500���l(1942�N���̑S���[���b�p�̃��_���l�͖�1100���l�Ƃ����Ă���)�̃��_���l���s�E���ꂽ�Ƃ����Ă���B
1932�N���Ƃ��Ď���ɉ��������h�C�c�o�ς́A�i�`�X�̎x�z���ŕ����Ɍ��������B�i�`�X�̓A�E�g�o�[��(�h�C�c�̍��������ԓ��H��)�E�y�n���ǍH���E��s��̌��݂Ȃǂ̑�K�͂ȓy�؎��Ƃɒ��肵�Ď��Ǝ҂��z�������̂ŁA���Ǝ҂�1933�N���߂̖�600���l����1935�N���߂ɂ͖�300���l�Ɍ��������B
1936�N�ɊJ�n���ꂽ�l�J�N�v��́u�o�^�[����C���v�̌R���Y�ƗD��̌R���g���v��ł��������A����ɂ���Ď��ƎҐ���1939�N���߂ɂ͖�30���l�Ɍ��������B
�����Ńt�@�V�Y���̐����m�������i�`�X�͑ΊO�I�ɂ����d�ȑԓx���Ƃ�A���F���T�C���̐��̑Ŕj�ɏ�肾�����B
1933�N1���ɐ������l�������q�g���[�́A���F���T�C�����ł̃h�C�c�̌R�������̓P�p�ƌR����������v�����A���ꂪ���ۂ����ƁA1933�N10���ɑO�N����J����Ă����W���l�[�u�R�k��c(1932�`34)�ƍ��ۘA������̒E�ނ�錾����(1933�N3���ɂ͓��{�����łɒE�ނ��Ă���)�B
������1935�N1���ɂ͏Z�����[�ɂ���ăU�[���n���̃h�C�c���A���ʂ������B�U�[���n���͐ΒY�Ȃǂ̎����ɕx�ރ��[���b�p�L���̍H�ƒn�тł��������A���F���T�C�����ł͍��ۘA���̊Ǘ����ɂ�����(�Y�c�̍̌@���̓t�����X�ɏ��n����Ă���)�A�A����15�N��̏Z�����[�Ō��肷�邱�ƂɂȂ��Ă������A1935�N1���ɍs��ꂽ�Z�����[�ł�91���̎x�����Ńh�C�c�ɕ��A�����B
1935�N3��16���A�q�g���[�̓��F���T�C�����̒��̌R������������j�����A�����������A�R����50���l�ɑ�������Ƃ����ČR���錾��ˑR�s���A���[���b�p���̍��X�����������B�ČR���錾�ł͋�R�̐ݗ����錾���ꂽ�B
���̍ČR���錾�͑S���[���b�p�ɏՌ���^�����B�C�M���X�E�t�����X�E�C�^���A�͓��N4���ɃC�^���A�̓s�s�X�g���[�U�ʼn�k���J���A�h�C�c�̍ČR���錾�����ƂƂ��ɁA�h�C�c�̋��Ђɑ��ċ����s�����Ƃ邱�Ƃ����(�X�g���[�U���)�B
�h�C�c�̍ČR���錾�ɍł��Ռ������̂̓t�����X�ł������B�t�����X�̓i�`�X���h�C�c�̐i�o�ɑR���邽�߂Ƀ\�A�Ƃ̊Ԃɕ��\���݉�����������(1935.5)�A�\�A���`�F�R�ƃ\�A���`�F�R���݉�����������(1935.5)�B
�������A1935�N6���ɂ̓C�M���X���h�C�c�Ɖp�ƊC�R��������сA�h�C�c�ɑΉp35���̌R�͂�45���̐����͂ۗ̕L��F�߂��̂ŃX�g���[�U����͕����B�p�ƊC�R����͍��ۘA���̗������ł������C�M���X���炪���F���T�C���������A�h�C�c�̍ČR���錾�����F������̂ł������̂Ń��F���T�C�����͎���������B
����Ƀq�g���[�́A��1936�N�ɁA���[���b�p�����b�\���[�j�̃G�`�I�s�A�N��(1935.10�`36.5)�ő��R�Ƃ��Ă��钆�Ń��C�������g�i�����s�����B
1936�N3��7���A�q�g���[�͑O�N�̕��\���݉������̒����𗝗R�Ƀ��F���T�C�����E���J���m���(1925�A���C�������g�̔��Ƒ��ݕs�N����������)��j�����ă��C�������g�ɐi�������B
���̎��̃h�C�c�R�͑�R�łȂ������̂ŁA��Ƀq�g���[�́u���C�������g�i�����48���Ԃ́A���̐��U�ł����Ƃ��_�o��ɂ߂������B���������t�����X������i�߂Ă���A�����͂����ۂ��܂��đދp������Ȃ������ł��낤�B����ꂪ���p�ł���R���͂͂Ђ����߂Ȓ�R�ɂ��S���s�\�����������炾�B�v�ƌ���Ă���B
�t�����X�̓h�C�c�̃��C�������g�i���Ɉꎞ�ԓx���d�����������A�C�M���X�̓����������Ȃ��������߂ɔ��������߂炢�A�h�C�c�ɂ�郉�C�������g�i����j�~���邱�Ƃ��o���Ȃ������B
���C�������g�i���ɂ���ă��J���m�̐��ƃ��F���T�C���̐��͕��A���ۏ�͂܂��܂��ٔ��̓x�����߂Ă������B�@ |
| ��5�@���{�R���̑䓪�Ɩ��B����
|
   �@
�@
|
��ꎟ���E��킪�I��������X�N�A���{�͑��i�C�̔��������㋰�Q�ɏP���A����Ɋ֓���k��(1923.9)�ɂ���ē��{�o�ς͑�Ō������B
������1927�N3���ɂ͐k�Ў�`(�֓���k�Ђ̂��߂Ɏx�����Ȃ��Ȃ�����`)�̏������߂����ċ��Z���Q��������A��s�E��Ђ̓|�Y�����o�����B
���̒���ɐ��������c�����t(1927.4�`29.7)�͋��Z���Q�̏����ɂ�����ƂƂ��ɁA�ΊO�I�ɂ͒����ɑ��ĐϋɊO��(���d�O��)��W�J���A�R���o��(1927.5�`28.5)���s���čϓ쎖��(1928.5�A���{�R�Ɩk���R�̏Փˎ���)�����������B�������A�c�����t�͒��������E����(���B�^�d�厖���A1928.6)�̐ӔC���őސw���A�l�����t(1929.7�`31.4)�����������B
�l�����t�̐�������܂��Ȃ����E���Q���n�܂����B�l�����t�͂��̎����ɋ�����(1930.1)��f�s�������߁A��ʂ̋����o�E��Ƃ̓|�Y�E���Ǝ҂̑���������A���{�o�ς͐[���ȕs���Ɋׂ���(���a���Q)�B
�z�H�Ɛ��Y��1926�N��100�Ƃ���ƁA1931�N�ɂ�75�ɗ������݁A���Ǝ҂�50���l�߂��ɒB��(�A�_�҂��܂߂��300���l�ȏ�Ƃ������Ă���)�A�J�����c�����������B�܂������E�Ă̒l�i�̖\����k�C���E���k�̗�Q�E�勥��Ŕ_���̍������[�������A���쑈�c���������A���H�����►�̐g����Ȃǂ��Љ���ƂȂ����B
�l�����t(�O���͕���(���ł͂�)��d�Y)�͑ΊO�I�ɂ͋����O����i�߁A�����h���C�R�R�k���ɒ��A�����ɑ��Ă����̎匠�d���A�����ɕ��͊����邱�Ƃ͔����ē��{�̌��v�̗i����͂������B
�������A���R����̂Ƃ���R���́A�����O������O���Ƃ��Ĕ��A����ɋ����������B���ɐ��{���R�ߕ��̔����������ă����h���C�R�R�k�������Ƃ͓V�c�̓�����(�Ƃ���������A�R���̎w��������)��Ƃ����̂��Ƃ��Đ��{���������U�������B
�������������ƌ��т��āA�R�����ł͐��E���Q�ɂ�鍑���̊�@��ŊJ���邽�߂ɖ��B(�����̓��{�ł͒������k�n���������Ă�ł���)�E���ÑS���A���n�Ƃ���A���̂��߂ɖ��֖��͂ʼn�������Ƃ������������܂����B
1931�N(���a6�N)9��18����A�֓��R(�֓��B(�����E��A�Ƃ��̕t���n��)�Ɠ얞�B�S���̌x������C���Ƃ�����{���R����)�̈ꕔ���Z�����͕�V(���݂��c�z)�x�O�̖����œ얞�B�S���̐��H�����甚�j���A����w�njR�̂��킴�Ƃ��ČR���s�����N����(�����Ύ���)�A�����܂łɕ�V�S�s���̂����B
���̓��{�R�̍s���ɑ��ďӉ�͕s��R����𖽂��A���w�ǂ�����ɏ]�����̂ŁA�֓��͂܂������܂ɒ��t�E�c���E�g�тȂǖ��S�����̎�v�s�s���̂����B
��2����Γ��t(1931.4�`31.12)�͕s�g����j��\��(1931.9.24)�������A�֓��R�͂���ɖ��B�S��ɌR��i�߁A��1932�N2���ɂ̓n���r�����̂��A�J��ȗ��N�ŔM�͂��������B�S����قڐ��������B������1932�N3���ɂ͖��B�������������B���ꂪ���B����(1931.9�`32.3)�ł���B�����Ύ����͖��B���ψȌ�A�����푈���瑾���m�푈�܂ł̏\�ܔN�푈(1931.9�`45.8)�̔��[�ƂȂ����B
�����������{�͓��{�̌R���s���ɑ��ĕs��R������Ƃ�ƂƂ��ɁA���ۘA���ɒ�i����(1931.9.21)�B�������A�����郊�b�g�������c���Ґ����ꂽ�̂�1931�N���ŁA�����c��1932�N2������9���ɂ����Ē����E���{�����@����10���ɕ����o�������A���̎��ɂ͂��łɖ��B������������Ă����B
�����Ύ����Ɏ����ŁA1932�N1���ɂ͏�C���ς��u�������B���B���ς̖u���ȗ��A�r���^�����������Ă�����C�œ��{�l�̓��@�@�m�����E�������Ƃ�������(���̎��������{�R�̖d���Ƃ���Ă���)���N����ƁA���{�R�͌R���s�����N�����A�����R�ƌ������퓬��Ԃɓ������B���C�R�̑��������{�R��2�����{���瑍�U�����s���A���킪���������A3�����߂ɂ͒����R���P�ނ����̂Ő퓬�͂قڏI���A5���ɒ�틦�肪���ꂽ�B
���{�́A�̖ڂ���C�ɒ�����Ă���Ԃɖ��B�����݂̌v���i�߂��B���{�́A�����V�Â̓��{�d�E�̋߂���孋����Ă��������Ō�̐铝���V(1906�`67�A�����c��E��1908�`12�A���B���c��E��1934�`45)��V�Â���A��o��(1931.11)�A1932�N3��1���ɟ�V�������Ƃ��閞�B���̌�����錾�����B���̌㖞�B���͒鐭�ƂȂ����̂ş�V�͖��B���c��ƂȂ���(1934.3)�B
���{�́A1932�N9���ɖ��B�������F���A�����c�菑�����B�����c�菑�ŁA���B���͓��{������܂Ŗ��ւɂ����Ď����Ă������ׂĂ̌��v�����F���A���{�̒�������S���Ɋg�傷�邱�Ƃ�F�߂��B�܂����B�����{�̏d�v�ȃ|�X�g�͓��{�l�ږ�E��������߂Ď������������̂ŁA���B���͊��S�ɘ��S(�����炢)�����ł���A��������{�̐A���n�ł������B
���̊ԁA���{�����ł�1932�N5��15���ɁA�C�R�N���Z�ƉE�������@�Ȃǂ��P���Č��{��(�C1931.12�`32.5)���ÎE����Ƃ����܁E��������N�������B�܁E������ɂ���Đ��}�����͏I�������A�Ȍ�R���̔��������܂��܂������Ȃ����B
1932�N10���ɂ̓��b�g�������c�̕������\���ꂽ�B���́A���{�̖��B�ɂ����錠�v�͕ی삳���ׂ��ł���Ƃ��Ȃ�����A���B���ς���{�̐N���s�ׂƂ��A���B���͖��B�l�̎����I�Ɨ��^���łȂ��Ƃ��Ė��B����F�߂��A���B�𒆍��̈ꕔ�Ƃ��ċ������������������č��ۘA���̊Ǘ����ɂ������Ƃ��Ă��Ă����B
���{�͂���ɑ��č��ۘA��������ł������ɔ����������ŁA��1933�N1���ɂ͎R�C�ւ��̂��A�����ŔM�͏�(�ȓs�͏����A���݂͖̉k�Ȃ̖k��)�B���̈ꕔ���Ƃ��čU�����J�n��(1932.2)�A���ۘA�����h�������B
1933�N2��24���A���ۘA������Ń��b�g�������c�Ɋ�Â����{�R�̖��B�P�ފ����Ă�42��1(����1�͓��{)�ō̑������ƁA�����m�E(�悤����)���{��\�͐Ȃ������đޏꂵ�A���{��3��27���ɍ��ۘA����E�ނ��A���ۓI�Ǘ��̓�����ނ��ƂɂȂ����B
���{�́A���ۘA���E�ތ�A1933�N4���ɂ͒�����z���ĉؖk�ɐN�����Ėk���ɔ������B�����͒���\������A5�����ɓ���(�^���N�[)��틦�肪���ꂽ�B����ɂ���Ē����͖��B���̑��݂������㏳�F���A�܂�����ȓ�ɔ��n������邱�Ƃ�����B
���{�́A1935�N�ɓ���ƍĂіh���𖼖ڂƂ��ē��ÁE�ؖk�ɐi�o���A���n��(�͖k�ȓ���)�əb��(���Ƃ�)�h���������{�Ƃ������S�����𐬗������A�������{����̕����E�Ɨ���錾�������B�@ |
| ��6�@�R����������̐����Ɠ����푈 (1) |
   �@
�@
|
1931�N9���Ɏn�܂������B���ςɑ��āA�����ł̑��Y�}�R�������d�������Ӊ�͍��ۘA���̐��ّ[�u�Ɋ��҂���Ƃ��ĕs��R������Ƃ����B���̍������{�̕s��R����ɑ��Ă͍������猃�����R�c�̐���������A�O��R��Ɠ��{���i�{�C�R�b�g�����߂�R���~���^�������������B
�������A���{�Ƃ̑S�ʐ푈��������悤�Ƃ���Ӊ�͑Γ��Ë�����Ƃ�A�u�������O�v(�܂������̓G����|���A�������ɊO���̐N����h���̈Ӗ�)�̐���̂��ƂɁA��C���ς̒�틦������Ԃ�(1932.5)�A1932�N6������50���̕������Ē��\���B�G�g���a��(1931�D11����)�ɑ���4��ڂ̕�͍U�����J�n�����B
���̍��͍g�R(�������Y�}�̌R��)�̒�R�Ɠ��{�R�̔M�͐i�U(1932.2)�ɂ���Ē��~���ꂽ���A�Ӊ�͓�����틦��(1933.5)������ʼnؖk���Ɍ�����t���A1933�N10������100���̑�R��200�@�̔�s�@��������5��ڂ̕�͍U�����J�n���A�l�����琐��(���\���B�G�g���a���̎�s)�֔������B
���|�I�ȕ��ʂ��ւ鍑���}�R�̍U���ɂ���đS�ł̊�@�ɂ��炳�ꂽ�g�R�́A���ɍ]���Ȃ̋��_��������邱�Ƃ����肵�A1934�N10���ɕ�͖Ԃ�˔j���Đ�������E�o�����B
������E�o������8���̍g�R�̎�͍͂����}�R�̒nj����Ȃ���A�M�B�ȁE�_��ȁE�l��Ȃ̕Ӌ��n�тɓ������݁A���N�������z���E�}�����͂�n��E����n�̑呐����ʂ�A���s����12500km(�n���̎��͖͂�4��km)�̑�ړ��̖��A1935�N10���ɖё̗�����g�R��蝐��Ȗk���ɒB���A���̒n�̍g�R�ƍ��������B
���ꂪ���j��L���Ȓ���(�吼�J�A1934.10�`36.10)�ł���B��1936�N10���ɂ͕ʂ̕������������Ē����͏I������B�����}�R�ɂ��5��ڂ̕�͍U���̑O�ɂ͍g�R�͖�30���̕��͂�i���Ă������A�������I����蝐��Ȗk���ɍ����������̕��͖͂�3���Ɍ����Ă����B
�ё��1937�N��蝐��Ȗk���̉����Ɉڂ����̂ŁA�����͈Ȍ�1949�N�ɒ��ؐl�����a������������܂Œ������Y�}�����̒��S�I�ȍ����n�ƂȂ����B
���̊ԁA1935�N1���ɒ����r��̋M�B�ȏ��`(�����)�ŊJ���ꂽ���Y�}���������NJg���c(���`��c)�ŁA����܂œ}�̎w�����������Ă����\�A���w���O���[�v���ނ����A�ё̎w�������m�����ꂽ�B
�ё�(1893�`1976)�͌Γ�Ȃ̔_�Ƃɐ��܂�A�t�͊w�Z�݊w�����獶���^���ɎQ�������B���ƌ�k���ɏo��(1918)�A�k����w�������}���ْ��̗�����(�������Y�}�̑n���҂̈�l)�̂��ƂŐ}���ُ���Ƃ��ċΖ����A���̊ԂɃ}���N�X��`���w�B���N�A�܁E�l�^�����N����ƌΓ�Ȃ̒����ʼn^����W�J���A1921�N�̋��Y�}�n�����ɌΓ�ȑ�\�Ƃ��ďo�Ȃ����B�܁E�O������(1925)�Ȍ�͌Γ�̔_���^���̎w���ɂ�����A��������(1927)�Ȍ�͈䛼�R�ɑނ��č����n�����݂��A��ɐ����Ɉڂ��Ē��\���B�G�g���a�����������Ď�ȂƂȂ���(1931)�B�����Ē����r��̏��`��c(1935)�œ}���ɂ�����w�������m�����A�g�R��蝐��Ȗk���ɓ������B
1935�N8��1���A�����r��̒������Y�}�͔��E��錾(�����ɂ́u�R���~���̂��߂ɑS���E�ɍ����鏑�v�Ƃ���)�\�����B���E��錾�͓��{�̐N���ɑ��ē���̒�~�ƍR���̂��߂̖����������̌������Ăт��������̂ŁA�����̖��O�ɑ傫�ȉe����^�����B
1935�N11���A�������{�͕����ً}�߂��A�������v��f�s�����B���̉��v�ɂ���č������{�n�̒����E�����E��ʂ�3��s�̔��s�����s���݂̂��@��(�@��ʉ�)�ƂȂ�A���܂Ŏ�Ɏg���Ă�����Ƒ��̋�s�����s�����s���̎g�p�͋֎~���ꂽ�B�������v�ɂ���č������{�ɂ��S���I�Ȓʉ݁E���Z�̓��ꂪ�B������A�n���Ɏc������R���̗͎͂�߂�ꂽ�B�����ğ��]�����̎x�z����w���܂�A�Ӊ�̓ƍق���苭�����ꂽ�B
�g�R��蝐��Ȗk���ɓ����������A�ؖk�N���������{�͉͖k�ȓ����əb���h���������{�Ƃ������S�����𐬗�������(1935.11)�B
���������̒��ŁA1935�N12��9���A5000�l�ȏ�̖k���̊w�������́u���{�鍑��`�œ|�v�E�u�ؖk�������v�E�u������~���A��v���ĊO�G�ɂ�����v�Ȃǂ̃X���[�K�����f���ăf�����s�����B���̏\��E��^���͑S���ɑ傫�ȉe����^���A�R���~���^�����S���ɍL�܂����B�@ |
| ��6�@�R����������̐����Ɠ����푈 (2) |
   �@
�@
|
�������A�Ӊ��蝐��Ȗk���̋��Y�}�̍����n�ɑ���U���𑱂��A���w�ǂ̓��k�R�Ɨk�Տ�̐��k�R��h�����čU���𖽂����B
���w�ǂ̎w�����铌�k�R�́A���B���ςŌ̋���ǂ��ĉؖk�Ɉړ������R���ŁA���̏��������͖��B�ɂ��ǂ��ē��{�R�Ɛ키���Ƃ�]��ł����B�����~�E��v�R���ɌX�������w�ǂ͋��Y�}�Ƌ�������сA1936�N�O���Ȍ㓌�k�R�Ƌ��Y�}�R�͒���Ԃɂ������B
1936�N12���A�g�R�Ƃ̐퓬�ɏ��ɓI�Ȓ��w�ǂƗk�Տ��킷�邽�߂ɏӉ�͐����ɏ�荞��ŗ����B���w�ǂ͏Ӊ�ɓ����~�ƍR���̕K�v�������i�������Ӊ�͂�������ۂ����B
���Ɉӂ����������w�ǂ́A1936�N12��12�������A�����x�O�̉ؐ��r(���@�c��Ɨk�M�܂̃��}���X�ŗL���Ȓn)�ɂ������Ӊ�̏h�ɂ��R���ŏP�����A�Ӊ��߂炦�Ċċւ����B
���w�ǂ́A�����}�̉��g�E�����~�E�����Ƃ̎ߕ��Ȃ�8���ڂ�錾���A�Ӊ�ɐ���̓]���𔗂������Ӊ�͂���ɉ������A�V���ȓ���̊�@���������B���̎��A�������Y�}�͎������𐼈��ɑ����ďӉ��������A�����̕��a�I�ȉ����ɑ傫�Ȗ������ʂ������B���ǁA�Ӊ�͐����ɉ����ē���̒�~�Ȃ�8���ڂ�F�߂邱�Ƃ����25���Ɏߕ�����ē싞�ɋA�����B���ꂪ�L���Ȑ��������ł���B
���̐����������_�@�Ƃ��āA1927�N�ȗ�10�N�ɋy����͒�~����A�����푈���u������Ƒ�������삪�Ȃ�(1937.9)�A�R�����������������������B
���w�ǂ͐��������̐ӔC���Ƃ��ďӉ�̌��ǂ��ē싞�ɕ����đߕ߂���A���ƌ�����ċւ����߂ɂ�蒦��10�N�̔��������B���w�ǂ͗��N���͂ɂ���Ė��߂ƂȂ������Ȍ��֏�Ԃɂ�����A���j�̕\���䂩��p���������B
1946�N�ɏd�c�����p�Ɉڂ��ꂽ��������ւ̐��������������A1990�N6����90���j���a���p�[�e�B�[����k�s�ŊJ����A���w�ǂ͖��I�Ԃ�Ɍ��̏�Ɏp�������Đ��E�����璍�ڂ��ꂽ�B�����ANHK�͒��w�ǂƂ̃C���^�r���[�ɐ������A��1991�N��NHK�X�y�V�����u���w�ǂ����܌��-�����푈�ւ̓��v�Ƃ��ĕ��f�����B���炵���ԑg�ł������̂ŁA���͎��ƂŕK�����k�Ɍ������B���w�ǂ͂��̌�n���C�Ɉڂ�Z�݁A2001�N10����100�Ŗv�����B
1937�N7��7���A�k���x�O��ḍa���t�߂Ŗ�ԉ��K�����Ă������{�R�̓����10�����̏��e�e����B�N�����C�������ɂ��Ă͕s���ł��邪�A���{�R�͗�8���Ɉ�������Ƃ��̎��ӂ̒����R�ɍU���������A����ɒ������������R�����B����ḍa�������������푈(1937.7�`45.8)�̔��[�ƂȂ�A�Ȍ���������͑S�ʐ푈�ɓ˓������B
7��11���ɂ͒�틦�肪���ꂽ�B�������A�ŏ��͕s�g����j��\��������1���߉q���t(1937.6�`39.1)�������A�R���̉ؖk�h�������F�����̂Ŗ������͍���ƂȂ����B����������ł����Y�}��7��8���ɑS�����̍R����Ăт����A�Ӊ��7��17���ɍR��̌��ӂ�\�������B
���{�R�́A7��28���ɑ��U�����J�n���A�V�ÁE�k�����̂��A8��13���ɂ͏�C�ł���[���J�����B����ɉؖk�̗v�n���̂��A12��13���ɂ͓싞���̂����B���̎��A���{�R�͑����̒����l���s�E��(�������̎����ł�30���l�ȏ�)�A���D�E�\�s�E�����s���A���E����������т�(�싞�s�E����)�B
���̊ԁA1937�N9���ɒ����ł͑�2���������삪�������A�g�R�͔��H�R�Ɖ��̂��ďӉ�̓������ɓ���A�R�����������������������B
���{�R�́A1938�N10���ɂ͍L���ƕ������̂������A�������{�͐��{��싞���畐���ցA����ɏd�c�ֈڂ�(1938)�A�A�����J�E�C�M���X�E�\�A�̉������čR�킵���̂Ő푈�͒������E�D�������A���������͕s�\�ƂȂ����B
�߉q���t�́A1938�N1���ɒ����Ƃ̒�틦���ł���A���S�����𗧂Ă���j���ł߁A�u�������{��ɂ����v�Ƃ̋߉q�����\���A�푈�����̓�������������B������1940�N3���A�d�c��E�o���Ă��������}�̗L�͎҂ł��韊����(�����q�A1883�`1944)�ɐV���������点�A�d�c���{�ɑR���ē싞�ɂ�����̍������{�����������B�������A���̐����͓��{�̘��S�����ɂ����Ȃ������̂Œ������O�̎x����ꂸ�A���ʂ������邱�Ƃ͏o���Ȃ������B�܂����N11���ɂ͓����V�����̌��݂𐺖����A�N���푈�𐳓������悤�Ƃ����B
���{�́A1938�N���܂łɂ͉ؖk�E�ؒ��̑啔���ƍL�����Ӓn����̂������A����͏d�v�ȓs�s�Ƃ�������Ԍ�ʐ����m�ۂ����ɂ������A���ӂ̔_���͋��Y�}�⍑���}�R�̎x�z���ɂ���A���{�R�̓Q������ɋ�������A��ǂ̌��ʂ����܂����������Ȃ��Ȃ����B���̂��߂��̏�ŊJ���邽�߂ɓ���ւ̐i�o����āA1941�N12���ɂ͑����m�푈�ɓ˓����Ă������B |
| ��7�@�X�y�C������Ɛ����̌���
|
   �@
�@
|
�X�y�C���͑�ꎟ���E���ɒ�����ۂ��čD�i�C�����������A���s�i�C�ƂȂ�A�����s���ɉ����ĘJ���^�������������B
���������̒��ŁA1923�N9���A�v�������f�����x�����R(1870�`1930)���N�[�f�^�[���N�����A�����A���t�H���\13��(��1886�`1931�A�u���{�����Ō�̍���)�̏��F�̂��ƂɌR���ƍِ������������A�������h��e������Ȃǔ����������s�����B
���E���Q�̉e���ŃX�y�C���Љ�����Ɋׂ�ƁA�m���l�E�w���E�J���҂�̔��ƍى^�����N����A1930�N1���Ƀ��x�����R�͎��E�ɒǂ����܂�A�ƍِ����͕����B�ƍِ��������͋��a�h��Љ��`�҂ɂ�锽�����^��������ƂȂ����B
1931�N4���ɍs��ꂽ�n���c��I���ŋ��a�h���叟�����B���a�h�͍����̑ވʂ�v�����A�����A���t�H���\13���͗��X���ɍ��O�ɖS�����ău���{���������A���a������������(�X�y�C���v���A�X�y�C�����a�v��)�B
�X�y�C���v���ɂ���Đ��������A�T�[�j�����t(1931�`33)�͖����`���v��i�߁A���N12���ɂ̓h�C�c�̃��@�C�}�����@�ɂȂ��������I�ȋ��a�����@�����肳�ꂽ�B�������A�ő�̉ۑ�ł������y�n���v���s�O�ꂾ�����̂ŃA�T�[�j�����t�͍��h�ƉE�h�̗�������U������A1933�N9���ɑ����E�����B
������1933�N11���ɍs��ꂽ�I���ł͒n��E�R���E�J�g���b�N����E���{�ƂɎx�����ꂽ�E�h���͂��ߔ������߁A�Ȍ㔽�������i�݁A������u�Â�2�N�ԁv���n�܂����B
���̂��߁A�E�h���͂ɑR���邽�߂ɃX�y�C���ł����h���a��`�����}�E�Љ�}�E���Y�}�̊ԂŐl���������������(1936.1)�A1936�N2���̑I���ł͐l������h���叟���A�l��������t�����������B
�A�T�[�j�����A�����ő哝��(�C1936�`39)�ɑI��A�l��������t�͓y�n���v�E����̓������D�Ȃǂ̉��v�ɒ��肵���B
����ɑ��Đl��������t�ɔ�����R���E�n��E����Ɏx�����ꂽ�t�����R���R�́A1936�N7���ɃX�y�C���̃����b�R�Ŕ������N�����A�X�y�C������(�X�y�C�������A1936.7�`39.3)���n�܂����B
�t�����R(1892�`1975)�͗��R�m���w�Z�𑲋ƌ�(1910)�A�����b�R�̖����^�������ɏ]�����A30�̎Ⴓ�ŏ����ƂȂ����B1935�N�ɂ͎Q�d�����ƂȂ������A���N�l��������t����������ƃJ�i���A����������i�ߊ��ɍ��J����A�����b�R�Ŕ������N�������B
�t�����R���R�������b�R�Ŕ������N�����ƁA�X�y�C���{�y�ł��e�n�Ŕ������N����A���{�R�Ƃ̐퓬���n�܂����B�}�h���[�h��o���Z���i�Ȃǂł͐��{�R��J���҂ɂ���Ĕ����͒������ꂽ���A�����R��7�����܂łɂ̓����b�R�E�X�y�C���암�E�X�y�C���k���ȂǍ��y�̖�3����1���̂����B
�����8���ɓ���ƁA�h�C�c�E�C�^���A�̃t�@�V�Y�������̉������t�����R���R���{�y�ɏ㗤���A9�����ɂ̓}�h���[�h���͂��A�����R�̓X�y�C���S�y�̖�3����2���̂����B
���̃X�y�C������ɑ��āA�C�M���X�ƃt�����X�͐푈�̊g�������āA�܂��X�y�C���̋��Y��������ĕs��������Ƃ����B1936�N9���ɃC�M���X�ƃt�����X�̎哱�ɂ���ăX�y�C������s���ψ���������A�p�E���E�ƁE�ɁE�\�A�Ȃ�27�J�����Q�������B
�������A�h�C�c�ƃC�^���A�͕s����������Č��R�ƃt�����R���R���ɌR���������s�����B���Ƀh�C�c�͂��̃X�y�C�������V����̎�����Ƃ��A1937�N4���ɂ̓X�y�C���k���̏��s�s�Q���j�J����R�ɂ�閳���ʔ����ɂ���ēO��I�ɔj���B�X�y�C�����܂�̉�ƃs�J�\(1881�`1973)�́u�Q���j�J�v�͂��̏o������f�ނƂ��Đ푈�ւ̑��������߂ĕ`���ꂽ��i�Ƃ��ėL���ł���B
����ɑ��ă\�A�͐l��������{�̉����𐺖���(1936.9)�A���ۋ`�E�R�ƂƂ��ɐ��{�R�����������B���ۋ`�E�R�ɂ͐��E�e�n����t�@�V�Y���Ɛ키���߂ɑ����̎��R��`�҂Ȃǂ��Q�������B���ł��A�X�y�C�������w�i�ɕ`���ꂽ�w�N�����߂ɏ��͖�x(1940)�̒��҂ł���A�����J�̍�ƃw�~���O�E�F�[(1899�`1961)��C�M���X�̍�ƃI�[�E�F���A�����ăt�����X�̍�ƃ}�����[�炪�L���ł���B
�������ăX�y�C������͍��ې푈�����A����E���̑O����ƂȂ����B���{�R�͊拭�ɒ�R�𑱂������A�C�M���X�ƃt�����X�͍Ō�܂ŕs������𑱂����̂ŁA�h�C�c�ƃC�^���A�̉������t�����R�����D���ƂȂ�A1939�N1���ɂ̓o���Z���i���̂��A3���ɂ͂��Ƀ}�h���[�h���ח����A�X�y�C������̓t�����R���̏����ɏI������B
�t�����R�͍��Ǝ�ȂƂȂ�A���̌㑍��(���Ǝ�Ȍ���)�ɏA�C���ēƍّ̐����������A1975�N�Ɏ��ʂ܂ł��̒n�ʂ��ێ������B
�q�g���[�ƃ��b�\���[�j�́A�G�`�I�s�A�N���E���C�������g�i���E�X�y�C������Ȃǂ�ʂ��Đڋ߂��A1936�N10���ɂ̓x�����������[�}���������������B
�h�C�c�͓��{�Ƃ��A�R�~���e�����̊����ɑ���������⋤���h�q��āA1936�N11���ɓ��Ɩh����������B
��1937�N11���ɂ́A�C�^���A�����Ɩh������ɎQ�����ē��ƈɎO���h������ƂȂ�A�C�^���A�͓��N12���ɓ��E�Ƃɑ����č��ۘA����E�ނ����B
�������ē��{�E�h�C�c�E�C�^���A�̃t�@�V�Y�����Ƃɂ��u�x�����������[�}�����������v�����������B �@
�@ |
| ��1930�N��A�����J�勰�Q�̃��J�j�Y�� |
   �@
�@
|
���͂��߂�
1930 �N��̐��E�勰�Q�́A��ނ̂Ȃ���K�͂Ȃ��̂������B�勰�Q�̒��S�������A�����J�ł́A�}1 �Ɍ���悤�ɁA1929 �N10 ��24 ���A�Í��̖ؗj�������Ƀj���[���[�N�̊�������\�������B29 �N����32 �N�ɂ����čH�Ɛ��Y��50%�߂������A����GNP ��35���ȏ㉺���A����������30%�ȏ㉺�������B���Ɨ���29�N�ɂ�3.2%�ł��������A33 �N�ɂ�24.9%�܂ŏ㏸�����B����ɃA�����J�́AGNP��29 �N�̃s�[�N���̐����ɉ�����܂łɁA11 �N�Ԃ��v�����̂ł���B���̑勰�Q�ŁA�A�����J�݂̂Ȃ炸���[���b�p�����A���{�A����ɂ͒���ď���������ȑŌ��������B
1930 �N��̐��E�勰�Q�́A���{�o�ς̌�����l�����ł������̎����ɕx��ł���A���̌������l�@���A���P�����o�����Ƃ͗L�Ӌ`�ł���B�����ł̓A�����J���ނɁA�Ȃ��勰�Q���N�����̂��A�Ȃ����Q����̒E�p�ɒ����N����v�����̂��Ƃ���2 �_�ɏœ_�����ĂāA�勰�Q�̃��J�j�Y�����l�@���Ă������ƂƂ���B
�܂��A�勰�Q�̌����m�ɂ��邽�߂ɁA���̗v���������I�v���Ƌ��Z�I�v����2�ɑ�ʂ���B�����ł��������I�v���Ƃ́A1�f�ՋK�͂̏k���A2����E�ݔ������E�Z����̗����݁A3���{�x�o�̌����ł���A���Z�I�v���Ƃ́A1�����̖\���A2�}�l�[�T�v���C�̌����ł���B�Ȃ��A��s�j�]�̑�����FED �̋��Z����ɂ��ẮA2�}�l�[�T�v���C�̌����Ɩ��ڂɊW���Ă��邽�߁A2�ō��킹�čl�@����B
�勰�Q�̗v���ɂ��ẮA���݂Ɏ���܂ŗl�X�ȋc�_���s���Ă��Ă���B�ȉ��ł͂܂��A�����I�v���Ƌ��Z�I�v���̂��ꂼ��ɂ��āA����܂ōs���Ă����c�_���f�[�^�����Ȃ��猟���Ă������ƂƂ���B�܂��A�A�����J�勰�Q�̓����ł���A�����ɂ킽�鎸�Ɨ��̍��~�܂�̗v���ɂ��Ă��l�@���邱�ƂƂ���B
|
��1�D�����I�v���̍l�@
��(1)�@�f�ՋK�͂̏k��
���C�X(Lewis�A 1949)�A�����c�@�[(Meltzer�A 1976)��́A�勰�Q�̌����̓X���[�g���z�[���[�Ŗ@(1930 �N6 ���ɐ��������Ŗ@�B�勰�Q��w�i�Ɋł�啝�Ɉ��グ������)�ɂ���āA�f�ՋK�͂��k���������Ƃɂ���Ǝ咣�����B
���̐��ɑ��锽�_�Ƃ��āA�A�C�P���O���[��(Eichengreen�A 1989)�͎��̂悤�Ɏ咣�����B�Ő���͖{���A�g���I�Ȑ���ł���A���v���O�����獑���̐��Y�҂ւƈړ]����B���̂��ƂŔ�����������邩������Ȃ����A���̉e���͓I�Ȃ��̂ł���B�X���[�g���z�[���[�Ŗ@�͍��O���ɑ���A�o���ɑŌ���^�������낤���A�ł��勰�Q���Ă̂��Ƃ���Ȃ�A�ł͊O���̕ł��������Ƃō��O���̗A�o�����炵���A�Ƃ����b�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�h�[���u�b�V�����t�B�b�V���[(Dornbusch and Fisher�A 1986)���A�ł̉e��������I�ɑ����A���̂悤�Ɏ咣���Ă���B���O���̗A�o��29 �N�ȍ~�傫���������Ă��邪�A���̎����ɂ͗l�X�ȗv������N���������E���v�̗������݂��������ɈႢ�Ȃ��A���̉����̑S�Ă��X���[�g���z�[���[�Ŗ@�ɑ���ɋA���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A�������̎���GNP ���傫���ቺ���Ă��邱�Ƃ���A�A�o���v�̗����݂̌o�ςɑ���e���́A�搔���ʂ��l���Ă��S�̂̂������Ȉꕔ���ł���A�łɂ�鍑�����v�̐L�т܂Ōv�Z�ɓ����ƁA�ł̌o�Ϗk�����ʂ͂����������B
�ȏ�̋c�_�ɂ��āA�勰�Q���̗A�o���̐��ڂ��m�F����B�}2 �Ɍ���悤�ɁA�����A�o��28 �N����32 �N�ɂ����Ė�50%�����A�����A����29 �N����32 �N�ɂ�����40%�ȏ㌸�����Ă���B�܂��}3 �Ɍ���悤�ɁA�A�����J�̗A�o��29�N����GNP ��5%�����߂Ă������A33 �N�ɂ�3.9%�ɂȂ����B���̊Ԃ̎���GNP�́A�s�[�N��29 �N����{�g����33 �N�ɂ�����35%�ȏ㉺�����Ă���B
�A�o���̓�����GNP �ɋy�ڂ��e�����A1���A�o�A2�搔�̓�ʂ�̍l�����ɂ���Č���B1�́AGNP �̒�`�ɂ�菃�A�o�̑�����GNP �����Ƃ����l�����ł���B���A�o(1972 �N���i)�͐}2 �Ɍ���悤�ɁAGNP �̃s�[�N�ł���29 �N��3 �l�����ł�31.9 ���h���ł��������AGNP �̃{�g���ł���33 �N��1 �l�����ɂ�9.3 ���h���Ɍ��������B���̊ԏ��A�o(1972 �N���i)��GNP ��́A�}3 �Ɍ���悤�ɁA0.99%����0.45%�Ɩ�0.5 �|�C���g�������Ă���B���A�o�̌����́A35%����������GNP �S�̂̂ق�̈ꕔ���ɉ߂��Ȃ��B���������āA�A�o���̓������勰�Q�ɗ^�����e���͑傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�܂��A33 �N�ȍ~GNP �͉Ɍ������Ă��������A�O�f�}2 �Ɍ���悤�ɁA����ɂƂ��Ȃ��ėA���������������ʁA���A�o��35 �N�܂Ō������Ă���B���̂��Ƃ�����A���A�o�̌����͌i�C��傫����ނ�����v���ł͂Ȃ������ƍl������B
2�́A�A�o�̌������搔�ߒ���ʂ���GNP ������������Ƃ����l�����ł���B�O�f�}2 �Ɍ���悤�ɁA�A�o(1972 �N���i)��1929 �N��3 �l�����ł�163.2 ���h���ł��������A33 �N��1 �l�����ɂ�91.1 ���h���܂Ō��������B���̊Ԃ̌����z�ł����70 ���h���́A�搔��2 �Ƃ���ƁAGNP ��140 ���h���������������ƂɂȂ�B29 �N��3 �l�����̎���GNP ��3236.9 ���h���ł��邩��A�A�o�����̏搔���ʂ�GNP ��4.3%�����������v�Z�ɂȂ�B�������ԂɎ���GNP ��35%�ȏ㌸�����Ă��邩��A�A�o�����̏搔���ʂ́A����GNP �̌����̒��ł݂����قǑ傫�Ȋ����ł͂Ȃ��������Ƃ��킩��B
���������āA���C�X�A�����c�@�[�̐��͓K�łȂ����Ƃ��킩��B�X���[�g���z�[���[�Ŗ@��A�f�ՋK�͂̏k���͑勰�Q�����傫�Ȃ��̂Ƃ�������ł����Ă��A������Ђ�������������Ƃ͂����Ȃ��B
��(2)�@����E�ݔ������E�Z����̗�����
����E�ݔ������E�Z����̗����݂ɂ��āA���[���g��(Moulton�A 1935)�͎��̂悤�ɘ_���Ă���B���Y�@�\���̂��̂ɂ͏d��ȏ�Q�͂Ȃ��������A�����s���������i�W�������ʁA������v�͏�������Y�\�͂ɒǂ������Ƃ��ł��Ȃ������B�������������ґw�ɏW���������Ƃ͒��~���̏㏸�����݂����A�S���Y�\�͂��z�����邾���̎��v������o�����Ƃ��ł��Ȃ��������߁A��v�Ȑ��Y�����20%���̐��Y�\�̗͂V�x���c�����ƂɂȂ����B
�܂��A����ɂ��ăn���Z��(Hansen�A 1941)�͎��̂悤�ɘ_���Ă���B1921�N����25 �N�ɂ͖��\�L�̌��z�����A20 �N�����ɂ́A����܂����\�L�Ƃ����Ă悢�قǂ̊��S�Ȍ��z���̈ꎞ�I�O�a��ԂɒB�������ʁA���̒��O�a�̎������o��̂ɒ����N����v�����B1930 �N��̑勰�Q�̌����́A���z�z�̉��~�ǖʂƎ�z�̈�v�A�Z�p�i���E�V�̓y�J���E�l�������̂��ꂼ��̒�ɂ�铊���@��̏��łł���B
���̎����̏���E�ݔ������E�Z����̐��ڂ��A�}4�A�}5 �Ŋm�F����B�ϋv���������́AGNP �̌����ɐ�s����29 �N�̑�1 �l���������2 �l�����ɂ����Č����������A��3 �l�����ɂ����Ď�����Ȃ����Ă���B���̌��GNP �̌����ƂƂ��ɋ}���Ɍ������Ă������B�ݔ�������29 �N��2 �l�����܂ő���������A��3 �l�����ɂ����đ傫���������A��4 �l��������30 �N��1�A��2 �l�����ɂ����Ă͎����Ȃ��������̂́A���̌�͑傫���������Ă���B�Z�����28 �N�̑�2 �l�������s�[�N�ɂقڈ�т��Č������Ă������B
�����勰�Q�ɂ�����s�[�N�ƃ{�g���Ō���ƁA29 �N����33 �N�ɂ����đϋv�������50%�ȏ�ቺ���A��ϋv�������20%�ȏ�ቺ�����B�܂��ݔ������͓������ɖ�1/5 �ɒቺ���A�Z�����28 �N����33 �N�ɂ����Ė�1/8 �ɒቺ�������ƂɂȂ�B
�������ɁA���[���g����n���Z���̎w�E����悤�ɁA�勰�Q���ɂ�����ϋv������A�ݔ������A�Z����̌����͔��ɑ傫�������B�����́AGNP ���}���Ɍ������n�߂�29 �N��3 �l���������O����A���X�Ɍ����̌X���������n�߂Ă����B
�������AGNP ����������Ȃ��ŁA�ϋv������A�ݔ������A�Z����Ȃǂ̑ϋv���̎x�o����������͎̂��R�ł���A����͑勰�Q�̌����ł���ƂƂ��Ɍ��ʂł���B�����̎x�o���X�p�C�����I�Ɍ��������A�ϋv�������1/2 �ȉ��ɂ��A�ݔ�������1/5 �ɂ��A�Z�����1/8 �ɂ܂Œቺ������������A�ߏ�����⏊���̕s�������A�i�C�z�A�����@��̏��œ��̖��ɂ��ƍl����͖̂���������Ǝv����B
��(3)�@���{�x�o�̌���
�勰�Q�Ɋւ��鏔���̒��ɂ́A���̌�������������ɋ��߂���̂�����B����������邽�߂ɁA�܂��A�}�Ő��{�x�o�̐��ڂ����邱�Ƃɂ���B
���ڐ��{�x�o�́A�}6 �Ɍ���悤��31 �N���܂ő������A���̌�33 �N���܂Ō������Ă���B�܂��A���ڐ��{�x�o�̑�GNP ��́AGNP �̃s�[�N�ł���29 �N��3�l�����ɂ�8.3%�ł��������AGNP �̃{�g���ł���33 �N��1 �l�����ɂ�15.9%�܂ő������Ă���B���������āA���̊ԁA���{�x�o��GNP ��7.6%���x�����Ă������ƂɂȂ�B
���{�x�o�������l�Ō���ƁA�}7 �Ɍ���悤�ɐ��{�x�o��32 �N�܂ő������A���̌�͂킸���Ɍ������Ă���B�������{�x�o�̑�GNP ��́AGNP �̃s�[�N�ł���29 �N��3 �l�����ɂ�12.7%�ł��������AGNP �̃{�g���ł���33 �N��1 �l�����ɂ�20.6%�܂ő������Ă���B����ɂ��A���{�x�o��GNP ��7.9%���x�����Ă������ƂɂȂ�B
�ȏ���A�勰�Q���̍�������͌i�C�̑����������Ă����̂ł͂Ȃ��A�i�C�����x��������ʂ����������Ƃ�������B�u���E��(Brown�A 1956)�́A31 �N�x�̊��S�ٗp�\�Z�͂��Ȃ�g���I�ł���A29 �N�x�\�Z�������v�傳���AGNP��2%�����v���g�債���Ƃ��Ă���B��������͑勰�Q��������̂ɏ\���Ȑ����ł͂Ȃ������Ƃ����c�_�͂��肦�邪�A�ُk�I��������ɂ�苰�Q��勰�Q�ɓ]���������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�������I�v���̂܂Ƃ�
����܂Ō��Ă����悤�ɁA�f�ՋK�͂̏k�������A�����̌����͑勰�Q���ɂ����Ĕ��Ɍ����Ɍ���ꂽ�B�������A�����̎����I�v���̒��ɂ́A�勰�Q���\���ɐ����ł�����̂͂Ȃ������B���ꂼ�ꂪ�勰�Q�̈���ł͂��邪�A�i�C�̈������X�p�C�����I�ɐi�s�����铮���ł͂Ȃ������Ɨv��ł���B
����ł͂��̓����͉��������̂��낤���B���͂̋��Z�I�v���̍l�@�ŁA�������l���Ă������ƂƂ���B
|
��2�D���Z�I�v���̍l�@
�����ł́A�勰�Q�ɂ�������Z�I�v���̍l�@���s���B�܂��A�勰�Q���̌o�ς̗����݂�@���ɕ�����Ă��銔���̖\�����猩�Ă����B
��(1) �����̖\��
1929 �N10 ��24 ���Í��̖ؗj���Ƀj���[���[�N�̊������\�����A��������Ɋ����s�ꂪ�������A����ɑ勰�Q�̌��������߂�c�_������B�K���u���C�X(Galbraith�A 1961)�́A�����s��̖\�����勰�Q�̒��{�l�ł���Ƙ_�����B
����ɑ��A�e�~��(Temin�A 1976)�A�~�V���L��(Mishkin�A 1978)�A���[�}�[(Romer�A 1993)�͊����\���̉e��������I�ɑ����A���̂悤�Ɏ咣���Ă���B29�N�̊����\�������̉e���͂������Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A�����̖\���ɂ��l���Y�͖�10���ڌ��肵�A����҂̎��Y�ɑ��镉�̊����͏㏸���A�����ɑ������҂̕s���͑��債���B�����āA�����̂ǂ�������v�����������A�o�ς������������A�勰�Q�������N���������̂Ƃ܂ł͂����Ȃ��B
�e�~��(Temin�A 1989)�́A29 �N�ȍ~���݂܂Ŋ����s��͉��x���������������A���ꂪ�勰�Q�Ɠ��l�̓����������炵�����Ƃ͂Ȃ��Ǝ咣���Ă���B�e�~���́A29 �N�̊����\���Ƃ悭��������������1987 �N�̊������ɋ����āA���̂悤�Ɏ咣���Ă���B87 �N�ɂ�����l���Y�ɐ�߂銔���̊����́A29 �N�̂�������������������A87 �N�ɂ����Ă�29 �N�����͂邩�ɑ����̐l�����������L���Ă������A���E���̊����s�ꂪ�͂邩�ɋٖ��ɓ������Ă����B����ɂ�������炸���E�o�ς��s���Ɋׂ�Ȃ��������Ƃ́A�����s��̖\�����͕̂s���������炷�قǑ傫�ȏo�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ă���A�Ƃ��Ă���B
�O�f�}1 �Ɍ���悤�ɁA������29 �N����32 �N�ɂ����Ė�1/5 �ɒቺ�����B���̑�K�͂������Ԃ̊����\�����A�i�C�ɂȂ�炩�̌�ވ��͂����������Ƃ͖��炩�ł���B��������������ŁA�e�~��(Temin�A 1989)�̎咣����悤�ɁA�����̉������勰�Q���Ɨގ����Ă��鎞��������������B�Ⴆ�A�e�~���̂���1987 �N9 ������11 ���̊����́A1929 �N�̓����Ԃ̊����ƁA���̐��ڂƖ\���̋K�͂��悭���Ă��邪�A87 �N�ɂ�30 �N��̂悤�ȉ�œI�ȋ��Q�͋N����Ȃ������B������A30 �N��̋��Q�ɂ��������A�������̉����́A�����̖\���ȊO�̗v���ɂ���ċN���������̂ł��邱�Ƃ��킩��B�����͊�Ǝ��v�̗\�z�̌��ʂł����āA�����̉������i�C��ނ������炵�������ł���Ƃ܂ł͂����Ȃ��B
�ȏ�̍l�@���A�����̖\���͑勰�Q�̌����Ƃ��Ă̓K���u���C�X�̎咣����قǑ傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�e�~��(Temin�A 1976�A 1989)�A�~�V���L��(Mishkin�A1978)�A���[�}�[(Romer�A 1993)�̎咣����悤�ɁA�勰�Q���ԐړI�Ɍ������������̂Ƃ��đ�����ׂ��ƍl������B
��(2) �}�l�[�T�v���C�̌���
�勰�Q���ɂ̓}�l�[�T�v���C���}���Ɍ������Ă���A�t���[�h�}�����V���E�H�[�c(Friedman and Schwartz�A 1963)�́A�����勰�Q�̌����ł���Ƃ��Ă���B
�t���[�h�}�����V���E�H�[�c���ȑO�ɁA�P�C���Y(Keynes�A 1931�A 1933)�����ɂ���ɋ߂������������Ă����B�P�C���Y�́A�勰�Q���Ƀf�t���I�Ռ���^�����ُ̂͋k�I�ȋ��Z����ł���A���̏Ռ��͓����ւ̉e����ʂ��āA�o�ϑS�̂ɓ`�d�����Ƃ����咣��W�J���Ă���(Temin�A 1989)�B
�}�l�[�T�v���C�̑啝�Ȍ�����勰�Q�̎���Ƃ���l�����́A�e�~��(Temin�A1989)������ǂݎ���B�e�~���̓P�C���Y�̐����āA���̎����ُ̋k�I�ȋ��Z���勰�Q�̎���ł���Ƃ��Ă���B
�����̐������ƂɁA�ȉ��łُ͋k�I�ȋ��Z����ɂ��}�l�[�T�v���C�̌������A�ǂ̂悤�ɂ��đ勰�Q�������炵���̂����l���Ă����B
���}�l�[�T�v���C�̐���
�}�l�[�T�v���C�̌����̉e�����l�@����ɂ�����A�n�C�p���[�h�}�l�[(M0)�ƃ}�l�[�T�v���C(M2)�̐��ڂ����Z����ƂƂ��ɊT�ς��Ă����BM0 ��M2 �̑ΑO�N������̐��ڂ́A�}8 �Ɍ���Ƃ���ł���B
28 �N���ȑO�́AFED �̊ɘa����ɂ��M2 �̑ΑO�N������͏㏸���Ă������A28 �N�ɓ���ƁAFED �͊����s��̉ߔM�Ƌ��̗��o��}���邽�߂ɁA����������ߊ�ɓ]�������B���̐���ɂ��M0 �̑ΑO�N������͒ᐅ���ɗ}�����AM2�̑ΑO�N������͒ቺ���Ă������B���̌��ʁA29 �N10 ���̊����\����o�ς̏k�����n�܂������A�ɘa����͂Ƃ��Ȃ������B
30 �N���ɂȂ�ƁA�j�]�����s���o�͂��߁A31 �N�Ăɂ͋�s�j�]���������ɒB���āA�������s���Q�����������B�������AFED �͂Ȃ�����̊��ς����A31 �N9 ���ɂ̓h�����l�̈ێ��̂��߂Ɉ����߂��s���A31 �N�����瑝�₵�Ă���M0 �̑ΑO�N��������Ăї}���������߁A�}9 �Ɍ���悤�ɗ��q���̋}�㏸���N�������B���̈�A�ُ̋k�I�Ȉ��͂ɂ��AM2 �̑ΑO�N������͋}���Ɍ������Ă������B
32 �N�ɓ���ƁAFED �͊ɘa��������݂����������������O�ꂹ���A33 �N�ɓ����Ă悤�₭�ɘa�̓�����������悤�ɂȂ�A���N4 ���ɋ��{�ʐ����~���Ė{�i�I�ȋ��Z�ɘa�ɓ]�������B����ɔ����AM2 �̑ΑO�N��������㏸�Ɍ������A34 �N�ɓ���ƃv���X�ɓ]���A�����Ɍ��������B
���}�l�[�T�v���C�̌����͂ǂ̂悤�ɂ��đ勰�Q���Ђ�����������
���̂悤�ȃ}�l�[�T�v���C�̌����́A�f�t���X�p�C������ʂ��đ勰�Q���Ђ����������B�f�t���X�p�C�����̓X�g�b�N�ƃt���[�̗��ʂŌo�ϊ��������k�����邪�A�O�҂̃v���Z�X�́A�}�l�[�T�v���C�������������������̎������l�㏸����s�ݏo�����E���Z�V�X�e�����}�l�[�T�v���C�����̏z�ł���A��҂̃v���Z�X�́A�����̉��������������㏸������E�����������i�C��ށ����������̏z�ł���B
�勰�Q���̉��������́A�}10 �Ɍ���Ƃ���A29 �N����33 �N�ɂ�����30%�ȏ���������Ă���B����ҕ����������Ԃɖ�25%�������Ă���B������A���̎����̃A�����J�o�ς́A�}�l�[�T�v���C�̌����ɂ�范�����f�t�����͂��Ă������Ƃ��킩��B
29 �N��3 �l�����ȍ~�̃A�����J�o�ςɂ����ẮA�}�l�[�T�v���C�̌����ɂ���ăf�t���X�p�C�������i�s���A�勰�Q�̔����ɂȂ������̂ł���B
���Ȃ��}�l�[�T�v���C�͂���قnj��������̂�
31 �N���Έȍ~�A�}�l�[�T�v���C���}���Ɍ������A�A�����J�o�ς͏d�x�̃}�l�[�s���Ɋׂ������A�����31 �N�Ă̋�s�j�]�̑����������������Ƃ���Ă���B���Ƃ��}���L���[(Mankiw�A 1992)�́A���̎����̋��Z�����̂悤�ɐ������Ă���B
�勰�Q���ɂ����ă}�l�[�T�v���C�͑啝�Ɍ����������A����̓n�C�p���[�h�}�l�[�̌����ɂ����̂ł͂Ȃ��A�����E�a���䗦�Ə����E�a���䗦�̒������㏸�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�B���̉ݕ��搔�̒ቺ��1930 �N�㏉���̑�K�͂ȋ�s�j�]���A��s�Ɨa���ґo���̍s����ω������āA�}�l�[�T�v���C�������������ƍl������B�܂�A��s�j�]�͌��O�̋�s�ւ̐M����ቺ�����āA�a���E��s�䗦���㏸�������ƂƂ��ɁA��s�Ƃ����T�d�ɂ��āA�����E�a���䗦�����߂��̂ł���B
�}���L���[�̎w�E����A��s�j�]�̑�������s�ݏo��ቺ���������A�}11 �̋�s�ݏo�̐��ڂŊm�F���Ă����B��s�ݏo��29 �N���܂ł͑������Ă������A���̌�͌����ɓ]���A31 �N�ɂ͂���ƌ��������������B33 �N�ɓ���Ƌ}���Ȍ����͂����܂������A���̌��35 �N�܂ł��肶��ƌ������������B��s�ݏo�́A�ŏI�I�ɂ�29 �N��1/2 �ȉ��ɂ܂ŗ�����ł���B
1930 �N�㏉���̋�s�j�]�̑����́A�O�f�}8 �̐M�p�搔�̒ቺ������킩��悤�ɁA��s�̐M�p�n���@�\��ቺ�����A�ݏo���}���Ɍ����������B���̑ݏo�̒ቺ�ɂ��A31 �N��M0 �̑�����M2 �̑����ɂȂ���Ȃ������B������A�}���L���[�̎����Ƃ����s�ݏo�̒ቺ�ɂ���ă}�l�[�T�v���C���}���Ɍ������Ă��������Ƃ��m�F�ł���B
���M�p����R�X�g�ɂ���s�j�]�̉e���̍l����
��s�j�]�ɂ��Ă͕ʂ̊p�x����̍l�@������A����������Ŏ����Ă����B
�o�[�i���L(Bernanke�A 1983)�͐M�p����R�X�g�Ƃ����T�O�����A���̂悤�Ɏ咣�����B��s�͐��ݓI�ȑݎ肩������W�߁A�X�̎؎�̃��X�N��]�������R�X�g�̒���҂ł���B��s���Q�ɂ��ł������I�Ȓ���T�[�r�X�̒�����A���̃R�X�g���Ђ��Ă͑ݕt�R�X�g���㏸������B�ł��e������̂́A�ƌv�A�_���A�@�l������Ă��Ȃ���ƁA���K�͊�Ƃł���B�勰�Q�ɂ����ẮA�����̑�K�͖@�l�͏\���Ȍ����Ɨ����I�ȏ�������ۗL���Ă���A���Z����R�X�g�̏㏸�͑��Ƃ����ƌv�Ə���ƂɌ��������̂ƂȂ����B
����ɑ��āA�e�~��(Temin�A 1989)�͎��̂悤�ɘ_���Ă���B�o�[�i���L�́A���Z����R�X�g�̏㏸�����Ƃ����ƌv�Ə���Ƃ�ɂ߂��A�o�ς������������Ƃ��Ă���B�������A�勰�Q����1937 �N����38 �N�ɂ����Ă̕s���̗��҂ɂ��āA���Ƃ̑����Y�ƂƏ��K�͌o�c�̑����Y�ƂƂŐ��Y�̗����݂��r���Ă݂Ă��A���҂̊Ԃő卷���Ȃ��B�܂�A�ǂ̎Y�Ƃ����ނ��邩�����肵���̂͐M�p�̎₷���ł͂Ȃ������B
�x(Hori�A 1999)���A�Y�ƕʁA�K�͕ʁA�n��ʂ̐��Y�Ƌ�s�ݏo���r���āA���l�̌��_�Ă���B
�M�p����R�X�g���勰�Q�ɗ^�����e���́A���߂̋�s�j�]�̍l�@�ōl���Ă������ƂƂ���B
����s�j�]�̑����͑勰�Q�̎���Ȃ̂�
��s�j�]�̑����͋�s�ݏo�����������A�}�l�[�T�v���C�������������B�ł́A��s�j�]�̑����͑勰�Q�̎���������̂��낤���B���_���猾���A����͎���ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A��s�ݏo�������Ȃ��Ă�M2 �͑��₷���Ƃ��ł��邵�AGNP ���㏸�����邱�Ƃ��ł��邩��ł���B
��s�j�]�̑����́A�}�l�[�T�v���C�̌�����M�p����R�X�g�̏㏸����āA�o�ςɋ����k�����͂��������B�������A��s�ݏo��M2 �̑�����GNP �̏㏸�ɂƂ��ĕs���ł���Ȃ�A�勰�Q����̉́A��s�����A���邢�͐M�p����R�X�g�����퉻���A��s�ݏo���������ă}�l�[�T�v���C����������A�Ƃ����ߒ��ɂ���Ă����炳�ꂽ�͂��ł���B
�Ƃ��낪�A��ɂ݂��悤�ɁAGNP ��������33 �N��1 �l�������{�g���Ƃ��ĉɌ������AM2 ��33 �N��2 �l�������{�g���Ƃ��đ����ɓ]�������A��s�ݏo��35 �N�܂Ō����������A���̌������قǑ傫�����������킯�ł͂Ȃ������B��������A��s�ݏo�̑����̓}�l�[�T�v���C�̑����ɂƂ��Ă͕K�v�����ł͂Ȃ��AGNP �̏㏸�ɂƂ��Ă��K�v�����ł͂Ȃ��������Ƃ��킩��B
��s�j�]�̑����́A�m���ɑ勰�Q�̎������}�l�[�T�v���C�̌����������炵���傫�ȗv���ł���B�������O�Ɏ������悤�ɁA��s�ݏo���������Ă��A�}�l�[�T�v���C�̌����������~�߂邱�Ƃ͉\�ł���B��s�j�]�̑����́A�勰�Q�̎���ł͂Ȃ������̂ł���B
��FED �͉����Ȃ��ׂ���������
����ł́AFED �̓}�l�[�T�v���C�̌�����}���邽�߂ɉ����Ȃ��ׂ��ł������̂��B����ɂ��āA�}���L���[(Mankiw�A 1992)�͎��̂悤�ɐ������Ă���B
�勰�Q����FED �̐����ᔻ����l�X�́A���̓�̘_�_���咣����B�ЂƂ͍Ō�݂̑���Ƃ��ċ�s�j�]����ɂ����ƐϋɓI�Ȗ������ʂ����ׂ��ł������Ƃ�����ł���A�����ЂƂ͉ݕ��搔�̒ᗎ�ɑΉ����ăn�C�p���[�h�}�l�[�������Ƒ��₷�ׂ��ł������Ƃ�����ł���B���̂ǂ��炩�̐��̂��Ă���A�ݕ������̑啝�Ȍ����͖h�����Ƃ��ł������낤���A��s��������قǂЂǂ��͂Ȃ�Ȃ������A�ƌ��_�Â���̂ł���B
��s�j�]�ɂ���ă}�l�[�T�v���C�͑啝�Ɍ����������AFED �����̂悤�Ȑ���ɂ���ăn�C�p���[�h�}�l�[������ɋ������Ă���A�}�l�[�T�v���C�̋}���Ȍ����͖h�����Ƃ��\�ł������B
���Ȃ�FED �͏\���Ȋɘa������Ƃ�Ȃ�������
�勰�Q���ɂ����āA��s�j�]�������������ʑݏo���啝�Ɍ������A�}�l�[�T�v���C���}���Ɍ������������ɂ�������炸�AFED �͏\���Ȋɘa������Ƃ�Ȃ������B���������āA�勰�Q�̓���������́A�Ȃ�FED ���\���Ȋɘa������Ƃ�Ȃ��������𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ���B
���̓_�ɂ��ăA�C�P���O���[��(Eichengreen�A 1992) �́A�e���̋��Z���ǂ����{�ʐ��ɌŎ��������Ƃ��勰�Q�̖{���I�Ȍ����ł���Ƙ_���A�勰�Q�̖{���I�Ȍ����͋��{�ʐ��̑��g�ł���Ƃ���̂�����ƂȂ��Ă���B���̎����̃A�����J�̋������͖L�x�ł������B�������A31 �N9 ���ɃC�M���X�����{�ʐ��𗣒E�����ہA�A�����J�ł͋��̗��o���͂����܂������A���{�ʐ��̉��AFED �͂����}���邽�߂Ɉ����ߐ�����Ƃ����B�勰�Q���̃A�����J�ł̓}�l�[�T�v���C���}���Ɍ������A�i�C���}���Ɉ������Ă������ɂ�������炸�AFED �͏\���Ȋɘa������Ƃ�Ȃ��������A����͂��̂悤�ȋ��{�ʐ��̑��g�����������Ƃɂ��B
�������̐��ڂ̓���
�勰�Q���ɁAM2 �̉����ɂ���ĕ������啝�ɉ��������������Ƃ́A�O�Ɏ������Ƃ���ł���B�����ł́A�勰�Q���̕����̓������A����GNP�AM2 �Ƃ̔�r�ɂ����čl�@���Ă������ƂƂ���B
�}10 �Ɍ���悤�ɁA����GNP�AM2�ACPI�AWPI �́A28 �N����37 �N�ɂ����Ă͓����悤�ȓ��������Ă���B�������A27 �N�ȑO��38 �N�ȍ~�ɂ��ẮA����GNP ��M2 �̓����͎��Ă��邪�A���̗��҂ƕ����̓����͎��Ă��Ȃ��B��̓I�ɂ́A27 �N�ȑO�ɂ��ẮA����GNP ��M2 �͓����I�ɏ㏸���Ă��锽�ʁACPI�AWPI �͌������Ă���B38 �N�ȍ~�ɂ��ẮA����GNP ��M2 ���}���ɏ㏸���Ă��锽�ʁACPI�AWPI �͂��炭�����𑱂��A39 �N�ɂȂ��Ċɂ₩�ɏ㏸���Ă������B
�܂蕨���́A�勰�Q���ɂ̓f�t���X�p�C�����̔}��Ƃ���GNP ��M2 �ƘA�����Ă������A�勰�Q����̉ߒ��ɂ����ẮAM2 ��������GNP ���Ɍ��������ɂ�������炸�A����قǏ㏸���Ȃ������Ƃ��������������Ă���B
|
��3�D�����E���Ɨ�
�A�����J�̑勰�Q�́A1933 �N��1 �l�������Ƃ��ċ}���ɉ��A37 �N��2�l�����܂ŔN��8%�ȏ�Ő��������B37 �N����38 �N�ɂ����Ẵ}�C�i�X�����̂��ƁA�o�ς͍Ăы}���ɐ��������ɂ�������炸�A���Ɨ��͍��~�܂�A38 �N�ɂ����Ă����Ɨ���20%�߂������ɂ������B���Ɨ���10%����������̂́A�푈�o�ς��{�i������41 �N�ȍ~�̂��Ƃł���B�Ȃ����Ɨ��͂��̂悤�ɍ��~�����̂��낤���B
�勰�Q���̎��������y�ю��Ɨ��ɂ��ăe�~��(Temin�A 1989)�́A�A�����J�̒�����29 �N���s�[�N��32 �N�܂ʼn����������A���̌�̃j���[�f�B�[�����ɂ�����NRA(National Recovery Administration�F�S���Y�ƕ����@�ɂ��A�Y�Ƃ̍s���K��̍���Ǝ{�s���ē���@�ցB�J�����Ԃ̐����ɂ��ٗp�g���A�����̏㏸�ɂ��J���ʂ̍팸����}����)��A���[�O�i�[�@(�S���J���W�@�F�J���g���̕ی�琬�A�J�g�Γ��̌��͂̕t�^��ړI�Ƃ��A���̂��ߘJ��3�����m�F���A�s���J���s�ׂ��ւ��A�S���J���W�ψ����ݒu����)���ɂ��������}�㏸�������Ƃ́A���Ƃ�����������v���ɂȂ����Ƃ��Ă���B
�}12 �Ɍ���悤�ɁA����������25 �N����29 �N�܂ŏ㏸������A29 �N��100�Ƃ����32 �N�ɂ�86 �܂ʼn������Ă���B���̌��37 �N�܂ŏ㏸���A38 �N�Ɉ�U�����������A39 �N�ɂ͍Ăя㏸�Ɍ��������B
���Ɨ��́A24 �N����29 �N�ɂ�����5%�ȉ��Ő��ڂ��Ă������A30 �N�ȍ~�}���ɏ㏸���n�߁A33 �N�ɂ�24.9%�ɒB�����B����ɂ��̌������E���̒��O�܂ō������Ő��ڂ����B
������A���Ɨ��̍��~�܂�������炵�������́A29 �N�܂ŏ㏸�������������̌㉺���d���I���������ƂƁA32 �N�ȍ~�̒����̋}�㏸�ł��邱�Ƃ��ǂݎ���B33 �N���Ɏ���GNP ���}�����ɂ�������炸�A�勰�Q�������������Ƃ����C���[�W��������Ă���w�i�Ƃ��ẮA���̎����I�ȍ����Ɨ�������B
|
��4�D�܂Ƃ�
1930 �N��̃A�����J�勰�Q�ɂ��ẮA�����܂Ō��Ă����悤�ɐ��X�̋c�_���s���Ă����B�������f�[�^�Ō����邱�Ƃɂ���āA�勰�Q���������A�����Ē������������Ƃ̎���́A�}�l�[�T�v���C�̋}���Ȍ����ł���Ƃ������Ƃ����������B���[�}�[(Romer�A 1992)�́A1933 �N�ȍ~�̌i�C���ɂ����āA�}�l�[�T�v���C�̑����͌i�C�ɂƂ��Č���I�ȗv���ł������Ƃ��Ă���B�}�l�[�T�v���C�̋}���Ȍ����̓A�����J�o�ςɑ勰�Q�������炵�����A���ʁA�勰�Q����̉̓}�l�[�T�v���C�̑����ɂ���Ă����炳�ꂽ�̂ł���B
�勰�Q�̌����̂����ɂ́A�ߏ�Ȑݔ������⏊�����z�̍\���I���Ƃ��������̌o�ς̖���A�������@�̉ߔM�A�����≿�i�̉����d�����Ƃ������������R���邾�낤�B�������A���̒��ł��o�ς���w�����ւƓ������̂̓}�l�[�T�v���C�̕s���ł���A���Z����������ߐ���ɕ点�����{�ʐ��Ƃ����̐��ł������ƌ����悤�B
|
��(�N�\)�勰�Q�̐i�s�ߒ�
1928 �A�M������s�ɂ��i�C�k������(���������グ�A���q���㏸�ɂ�鐶�Y�̌���)
1929 �A�����J�̍H�Ɛ��Y�������ݎn�߂�A�A�M������s�ɂ��i�C�k������
1929.10 �����\���@/�@�A���[���`���A�u���W���A�I�[�X�g�����A�������̈ێ�������@/�@�A�����J�A��K�͂ȏ���̗�����
1930.6 �A�����J�A�X���[�g���z�[���[�Ŗ@�����@/�@�j���[�W�[�����h�A�x�l�Y�G�����A�������̈ێ������
1930.7 �h�C�c�A�ב֊Ǘ��������A������̋��{�ʐ�����̗��E
1930.12 �A�����J�A�ŏ��̋�s���Q
1931.5 �A�����J�A��s�|�Y�̋}��
1931�ăA�����J�A��s���Q���������ɁA���[���b�p�̒ʉ��Q
1931.9 �A�M������s�ɂ��i�C�k������(�h���h�q�̂��ߊ��������グ�A���q���㏸�ɂ�鐶�Y�̌���)�@/�@�C�M���X�A���{�ʐ���~(���A�o��O���ב֎���𐧌����A�ʉ݂�؉����鍑���ꋓ�Ɋg��)
1932.2 �A�����J�A�������Z����(RFC)�ݗ�
1933.3 �A�����J�A���[�Y���F���g�哝�̏A�C�A��s�x�ƁA���A�o�֎~
1933.4 �A�����J�A���{�ʐ����~
1933.5 �_�ƒ����@(AAA)�����A�e�l�V�[�k�J�J������(TVA)�ݗ�
1933.6 �S���Y�ƕ����@(NIRA)�����A���@�̂��ƑS��������(NRA)�ݗ�
1934.2 �A�����J�A��������؉���
1935.7 ���O�i�[�@���� �@
�@ |
| �����E���Q 12 / ���E���Q�̌��� |
   �@
�@
|
�o�ϊw�ҒB�̊����ȋc�_�̎��ƂȂ��Ă���A����͍L������Όo�ϊ�@�Ɋւ���c�_�̈�ł�����B������ʓI�ɂ́A���E���Q��1929�N�̊�����\���ɂ������N�����ꂽ�ƐM�����Ă���B���E���Q���ɋN�����X�̌o�ϓI�������O��I�Ɍ�������Ă���: ���������������ɂ́A���Y�⏤�i���i�̃f�t���A���v�ƐM�p�̋}�~���A�f�ՖԂ̕���A�����ċ��ɓI�ɋN���鎸�ƂƂ���ɑ����n���Ȃǂ�����B�������Ȃ���A���Q�������N�����A���邢�͋��Q����̉������炵�����{�̌o�ϐ���ƌX�̎����Ƃ̈��ʊW�͗��j�Ƃ̊Ԃňӌ��̈�v���݂Ă��Ȃ��B
�ߔN�ł́A���_�͓�̎嗬�h�Ƃ������ِ̈��ɑ傫����������B
�܂��A�P�C���Y�o�ϊw��x�h�o�ϊw�ɂ����v�哱���f���̗��_�ł́A�s�i�C�͏���s����(����ɂ���ăo�u���o�ς������N�����ꂽ�Ƃ����)�ߏ蓊���ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�Ǝ咣�����B���v�哱���f���̗��_�ɂ����ẮA�M�p���傫�����Ȃ�ꂽ���Ƃŏ���E���������̋}���Ȍ������N�����Ƃ������Ƃňӌ�����v���Ă���B�ꂽ�э����E�f�t�����N����ƁA�����̐l�X�͎s�ꂩ�狗����u�����Ƃł���ȏ�̑�����������悤�Ƃ���Ƃ����̂ł���B���̂��߂ɕ����͉����葱���A���ʂ̂����ł������̕��i����悤�ɂȂ�B���̌��ʁA�����~�ɉ��Ƃ��L���ƂȂ�A�X�Ȃ���v�����Ɍ������邱�ƂɂȂ�B
���ɁA�}�l�^���X�g��ɂ��A���E���Q�͒ʏ�̕s�i�C�Ƃ��Ďn�܂����̂����A���̎��̒ʉݓ���(���ɘA�M�������x)�ɂ��d��Ȑ���̃~�X�����Z�����߂Ƃ������ʂ������A����ɂ���Čo�Ϗ��ɒ[�Ɉ����������߂ɒʏ�̕s�i�C���琢�E���Q�Ɏ������Ƃ����B���̐����́A���f�t���ɂ���Ď��͎����I�ɂ�葽���̍������ƂɂȂ�Ǝw�E����l�X�Ɗ֘A������B
���̂ق��ɂ������ِ̈�������A�������x�����ăP�C���W�A����}�l�^���X�g�̐�����ے肷��҂�����B�V�����ÓT�h�}�N���o�ϊw�҂̒��ɂ́A���Q�����ɉۂ��ꂽ�l�X�ȘJ���s�ꐭ�����[���Ȑ��E���Q�������Ǝ咣����҂�����B�I�[�X�g���A�o�ϊw�h�́A������s�̌��肪�ǂ̂悤�ɂ��Č듊�����������ƃ}�l�[�T�v���C�̃}�N���o�ϓI�e���ɒ��ڂ���B
|
|
����ʗ��_�ɂ�����
|
���嗬��
���P�C���W�A��
�����̌o�ϊw�҂����̊������咣����Ƃ���̎��ȏC���@�\���s�i�C�ɓ����Ȃ����Ƃ����闝�R�͕��������1936�N�Ɍo�ϊw�҃W�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y���咣�����B�����w�ٗp�E���q����щݕ��̈�ʗ��_�x�ɂ����ăP�C���Y�́A���E���Q��������邽�߂̊T�O�������B�s�i�C���ɂ�����s����`����ɑ����̎咣�Ƃ��āA�������~�ɂ���ď���������ނȂ�Β��~�͗����̒ቺ�������炷�Ƃ������̂�����B�ÓT�h�o�ϊw�҂ɂ��A�Ⴂ�����͓����̊g��������炵���v�������I�ɂȂ�Ƃ����B
�������A�������ቺ���Ă��������K�����������ɂȂ�Ȃ����Ƃ̗ǂ�����������ƃP�C���Y�͎咣����B���v�����҂��Ă̓����͎��Ƃɂ���Ă����炳���B����䂦�A����̗������݂������ɂ킽��Ȃ�A���Ƃ̕��͂̌X���Ƃ��ď����̔���グ�̊��҂͒Ⴂ���̂ƂȂ�B���̂��߁A�ᗘ���ɂ���Ď��{�������ɂȂ��Ă������̐��Y�ʂ傳����悤�ȓ����͍ł��S�������Ȃ����̂ƂȂ�̂ł���B���̏ꍇ�A����̌����ɂ���Čo�ς͈�Ĉ��Ɋׂ�B�P�C���Y�ɂ��A���̎��ȋ����I�������������Q���ɔ��Ɋ����ɂȂ�A�|�Y���p������(�����ɑ���y�ϓI�Ȋ��҂��K�v�ł���)�������قƂ�NjN����Ȃ��Ȃ����̂��Ƃ����B���̐��͌o�ϊw�҂ɂ���Ă����Z�C�̖@���ɔ�������̂Ƃ��ē����Â����A���ɃI�[�X�g���A�o�ϊw�h�ɐl�C������B
���{�����̌��������Q�̌����ł���Ƃ������͒�����ؘ_�̒��S�I�Ȏ��ł���B
���}�l�^���X�g
1963�N�̒����w�č����Z�j 1867�N-1960�N�x�ɂ����āA�~���g���E�t���[�h�}���ƃA���i�E�V���E�H�[�c�͔ނ痬�̐��E���Q�̐������J�����B�ނ�̍l���ɂ��A�{���I�ɂ́A���E���Q�̓}�l�[�T�v���C�̌����ɂ���Ă����炳�ꂽ�B�t���[�h�}���ƃV���E�H�[�c�͎��̂悤�ɏ����Ă���: �u1929�N8���̎����I�ȎR����1933�N�̎����I�ȒJ�܂ł̊ԂɁA�ʉݗ��ʗʂ�3����1���ɂ܂ŗ������B�v ���̌��ʂ��t���[�h�}���������́u����k�v�\���Z�������߂̒������ʂɂ������E�����E�ٗp�̌��ށ\�ł���B ���̍��A�A�M�������x������������ȏ�ɐl�X�͂�����~���Ă����̂��ƃt���[�h�}���ƃV���E�H�[�c�͎咣����B���̌��ʐl�X�͏�������炷���Ƃł����~�����B�܂��A�����͑����ɉ�������قǗZ�ʂ������Ȃ����߂ɁA���ʂƂ��āA�ٗp�Ɛ��Y�̎��k���N�����B�A�M�̉߂��͉����N�������̂�������Ȃ��������Ƃ�����Ή������Ȃ��������Ƃɂ���B
���Q�ȍ~�A���̎�v�Ȑ����̓}�l�[�T�v���C�̏d�v��������X�����������B�������A�}�l�^���X�g�ɂ��A���Q�́u������A���Z�̌��ʂ̏d�v���̔ߌ��I�ȏؖ��ł���B�v �ނ�ɂ��A�A�M�������x�̐��E���Q�ɑΏ������ł̎��s�́A���Z�����͂ł��邱�Ƃ̕\��ł͂Ȃ��A�A�M�������x���Ԉ������������s�������Ƃ̕\��ł���Ƃ����B�ނ�͘A�M�����Q���u�N�������v�Ǝ咣���Ă���̂ł͂Ȃ��A�s�i�C�����Q�ɂȂ�̂�h��������g�����˂��ƌ����Ă��邾���ł���B
��k�푈�ォ��20���I�����ɂ����āA�A�����J���O���ƃ��[���b�p�͐��{���K�肷��`�̋��{�ʐ����̗p���Ă����B���̎����̃A�����J�o�ς͎����I�ȍD�s���̔g���Ă����B�s�i�C�͂�����s�s���ɂ���Ĉ����N������Ă����Ƃ݂��A���ɏd�v�Ȃ��̂�1873�N�A1893�N�A1901�N�A1907�N�A1920�N�ɋN�����Ă���B�A�M�������x��1913�N�ɐ�������ȑO�̃A�����J���O���ł͋�s�V�X�e���������̙[�������~���邱�Ƃł�������(1907�N���Q�̂悤��)��@�ɑΏ����Ă����B1893�N�ɊJ�n���Ĉȍ~�A���Z�@�ւ�r�W�l�X�}���ɂ�鐬���w�͂�����������@�ɉ�݂��A���t���ɚb����s�ɗ������������炵�Ă����B1907�N�̋�s���Q�̍ہAJ�EP�E�����K���̏��W�������̏����̘A�������̕��@�ł��܂�������A����ɂ���ċ��Q���Ւf����Ă���A���̂��ߒʏ��s���Q�ɑ����ċN����勰�Q�����̎��ɂ͋N����Ȃ������̂��Ƃ����B���{������������������Ƃ邱�Ƃ��v�����ꂽ���߂ɘA�M�������x���ݗ�����邱�ƂƂȂ����B
������1928�N-1932�N�ɂ́A�A�M�������x�͎��t���ɂ�������s�ɗ������������炷���Ƃ͂Ȃ������B���ۂɂ͂��̐���̓}�l�[�T�v���C�̋}���Ȏ��k���������Ƃŋ�s��@�ɉ����Ă����B������20�N��ɂ́A������s�͑��̖ڕW���u�����̈���v�ɒ�߂Ă������A����̓j���[���[�N�A�M������s�̑��كx���W���~���E�X�g�����O���A�����̈�������Z�ڕW�Ƃ������ɒ����Ȍo�ϊw�҃A�[���B���O�E�t�B�b�V���[�̒�q������Ƃ������Ƃ�����B��������������璆����s�͎Љ�̕��������肷����x�Ƀh���̗��ʗʂ�ۂ����B1928�N�ɃX�g�����O�����ɁA�ނ̎��ƂƂ��ɂ��̐��I�����A�S�Ă̒ʉ݁E�،��͔w��Ɏ��ۓI�ȕ��i�𗠕t���Ƃ��Ď����Ă���ׂ����Ƃ����^����`�w��������đ������B���̐���ׂ̈ɃA�����J���O���̃}�l�[�T�v���C��1929�N����1933�N�̊Ԃ�3����1�ȏ�Ɍ������邱�ƂɂȂ����B
���̒ʉ����ɂ���ċ�s�ւ̎��t�����N�����Ă��A�M�͐^����`�w����ێ����A1907�N���Q���Ղ����Ƃ��̕��@�ŋ�s�ɑ݂��t���邱�Ƃ����ۂ��A����Ɋe��s��j�œI�Ȏ��t���ɂ������܂܂ɂ������S�ɖv���������B���̐���ɂ���ĘA���I�ȋ�s�̓|�Y���N����A�������݂�����s��3����1�����ł����B�B�x���E�o�[�i���L�ɂ��A�����ċN�������M�p��@�ɂ���Ă���ɓ|�Y�̔g���N�������B1907�N�Ɠ�������1930�N�I���̋�s���Q�̍ۂɂ��̗p����Ă������ɂ���ĕ����������̎��Y�̗������̋����̈������A�����h�������낤�ƃt���[�h�}���͏q�ׂ��B�������Ă���A1893�N��1907�N�ə[������~�ɂ���ē����̗�������@�������Ɏ~�̂Ɠ������A1931�N�A1932�N�A1933�N�̋�s���Q�͋N����Ȃ������ł��낤�Ƃ����̂ł���B
�}�l�^���X�g�ɂ������̓T�~���G���\���̒����w�o�ϊw�x�ɂ����Ĕے肳��Ă���A�u�A�M�������x�̋��Z������i�C�z�𐧌䂷�閜�\��Ƃ݂Ȃ��o�ϊw�҂͍����ł͂قƂ�ǂ��Ȃ��B�����ɋ��Z�I�ȃt�@�N�^�[�͌����ł���̂Ɠ�����������ł���ƍl������A������������ʂ��Ă��芮�S�ɖ������ׂ��ł͂Ȃ�����ł͂��邪�B�v�Əq�ׂ��Ă���B�P�C���Y�o�ϊw�҂̃|�[���E�N���[�O�}���ɂ��A�t���[�h�}���ƃV���E�H�[�c�̒����1980�N��܂łɎ嗬�h�o�ϊw�҂̊ԂŎx�z�I�ɂȂ������A1990�N����{�́u����ꂽ10�N�v�̉��ɍčl�����ׂ��ł���Ƃ����B�o�ϊ�@�ɂ�������Z��@�̖����͐��E���Z��@ (2007�N-)�Ɋւ��銈���ȋc�_�ň����Ă���B
|
���ِ�
���I�[�X�g���A�w�h
���E���Q��1920�N��̘A�M�������x�̋��Z����̔������Ȃ����ʂ������ƃI�[�X�g���A�o�ϊw�h�͎咣���Ă���B�ނ�̈ӌ��ł́A���̒�����s�̐���͎����s�\�ȐM�p�ɂ��ɂ킩�i�C�������炷�u�����ȐM�p����v�ł������B�I�[�X�g���A�w�h�̍l���ł́A���̎����̃}�l�[�T�v���C�̃C���t�������Y���l(�L���،�)�Ǝ��{���̗��҂ɂ����Ď����s�\�ȃo�u���������N�������Ƃ����B�A�M�������x��1928�N�ɒx��ċ��Z�������߂��s���܂łɂ́A�[���Ȍo�ό�ނ������ɂ͎�x��ɂȂ��Ă����B1929�N�̑�\���̌�̐��{�̉���ɂ���Ďs��̒��߂��x��A���S�ȉ���荢��ɂȂ铹���J���ꂽ�ƃI�[�X�g���A�w�h�͎咣���Ă���B
���E���Q�̎匴���Ɋւ���I�[�X�g���A�w�h�̐���������邱�Ƃ̓}�l�^���X�g�̐����̔ے������邱�ƂƗ�������B�w�A�����J�̐��E���Q�x(1963�N)�̒��҂ŃI�[�X�g���A�o�ϊw�h�̃}���[�E���X�o�[�h�̓}�l�^���X�g�̐�����ے肵�Ă���B������s�̓}�l�[�T�v���C���\���ɑ��₷�̂Ɏ��s�����̂��Ƃ����~���g���E�t���[�h�}���̎咣�����X�o�[�h�͔ᔻ���A����ɁA1932�N�ɘA�M�������x��11���h���̕č�������ď��L���ʂ�18���h���Ƃ����ہA�A�M�������x�̓C���t�������Nj����Ă����̂��Ǝ咣����B������s�̐���ɔ����ăf�t�����[���������̂́u�}�l�[�T�v���C���ʂ�30���h���ɒB�����̂�(����)��s�̏������̑��ʂ�2��1200���h���ɗ��܂����v���߂ł���A����̓A�����J�̑�O����s�g�D�ɕs�M��������Ă���ɑ����̗a������s��������o���ޑ������Ƃ����A������s�̐����傫�������闝�R�ɂ����̂��Ɣނ͎咣����B���X�o�[�h�̎咣�ɂ��ƁA��s�ɑ����t�̂�����ׂ̈ɒn��͏������݂̑��o���ɂ���ɏ��ɓI�ɂȂ�A���̂��߂ɘA�M�������x���C���t�����N�����Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�B
���X�o�[�h���}�l�^���X�g�̐�����ᔻ�������Ƃɑ��āA������l�̑�z�����I�[�X�g���A�o�ϊw�h�̃����o�[�t���[�h���q�E�n�C�G�N�͔������B�n�C�G�N�́A���g��1930�N�ɒ�����s�̃f�t������ɔ����Ȃ��������Ƃ�����Ă�����1975�N�ɔF�߁A�B���ȑԓx���Ƃ������ƂɊւ��Ďߖ�����: �u�������́A�����Z�����Ԃɂ�����f�t���̉ߒ��́A(�o�ς��@�\���邱�ƂƗ����s�\���Ǝ����l���Ă����Ƃ����)�����̍d������j����̂��ƍl���Ă����B�v 1978�N�ɂ͔ނ́u�ꂽ�ы}�����N����ƘA�M�������x�͋����ȃf�t�������Nj�����悤�ɂȂ�Ƃ������ƂɊւ��ă~���g���E�t���[�h�}���Ɏ^������v�Əq�ׂă}�l�^���X�g�̌����Ɏ^�����A�f�t���ɔ����ăC���t���Ɏ^�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���̗��������ŁA�}�l�[�T�v���C�̋����������߂������悤�ȋ��Z����ƃn�C�G�N�̌i�C�z���_�͖�������ƌo�ϊw�҂̃��[�����X�EH�E�z���C�g���咣���Ă���B
���}���N�X��`
�}���N�X��`�҂͊T���āA���{��`���f���ɌŗL�̕s���萫�����E���Q�������N�������̂��Ǝ咣����B �@ |
| �������Ɋւ���X�̗��_
|
   �@
�@
|
�����f�t��
�A�����J���O����GDP�ɑ��镉�̊����͐��E���Q�̎��܂łɂ�300%�ɒB�����B���̊�����20���I�I���܂ʼnz�����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�W�F���[��(1934�N)�͐�Ԋ��̎Y�Ƃ̑唭�W���\�ɂ���������ԂɊւ��錴�T�s���̈��p�����Ă���:
���炭�������Ă��̍��ł���قǂ̗ʂ̍�������قǒႢ�����A����قǒ������Ԃɂ킽���ďo���ꂽ���Ƃ͂Ȃ������B
����ɁA�X�^���_�[�h�E�X�^�e�B�X�e�B�b�N�X�Ђɂ��60�x�̍��̎w����1923�N��4.98%����4.47%�ɂȂ����ۂɂ͐V���Ȏ��{���s�̗ʂ�1922�N����1929�N�̔N���ς���7.7%���������ƃW�F���[���͏q�ׂĂ���B
1920�N��ɂ͓��Ƀt�����_�B�ŕs���Y�E�Z��̃o�u�����N��������1925�N�ɔj���B1920�N��̏Z��݂͐l�������̐�����25%�����Ă����ƃA�����B���E�n���Z�����q�ׂĂ���B
�A�[���B���O�E�t�B�b�V���[�́A���E���Q�������N�������匴���͕��ߑ��ƃf�t�����Ǝ咣�����B�t�B�b�V���[�͐M�p�̒ቺ�ߑ��ƌ��т��A���ߑ������@�M�Ǝ��Y�o�u�����h�������̂��Ƃ��Ă���B���E�f�t���Ƃ������ő��ݍ�p���A�o�u�����N�������d�g�݂���肾������̗v����ނ͊T�����Ă���B������s����o�����̘A���͈ȉ�:
1. ���̗������Ɛ�L���̔��p
2. ��s���[���Ƃ��Ẵ}�l�[�T�v���C�ُ̋k�����Z�����
3. ���Y���i�����̒ቺ
4. �S�̂Ƃ��Ă̏��Ɖ��l�̐[���Ȓቺ�A�ˑR�̔j�Y
5. ���v�̒ቺ
6. ���ƁE�ٗp�ɂ����鐶�Y�ʂ̒ቺ
7. �M�p�̌����ƃy�V�~�Y��
8. �����̎���
9. ���ڋ����̒ቺ�Ɨ����ɂ��킹���f�t���̊g��
���E���Q�ɐ�s����1929�N�̋}���̍ہA�؋����K��z��10%�ɂ����Ȃ������B�܂�A���������Ǝ҂͓����Ђ�1�h���a���邲�Ƃ�9�h���݂��t�����B�s�ꂪ�}�������ہA�Ǝ҂͂����������[����������悤�Ƃ������A����͕Ԃ��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ������B���҂����s���s���N�����A�a���҂���Ăɗa����������悤�Ƃ��邱�ƂŎ��t���������N����A��s���|�Y���n�߂��B��������������H���~�߂邽�߂̐��{�̕ۏ�A�M�������x�ɂ���s�̋K���͌��ʂ��Ȃ����g���Ȃ������B��s�̔j�Y�ɂ�萔�\���h���̎��Y������ꂽ�B
�����Ǝ�����20-50%�������Ă���̂ɕ��͓����i�ł��邽�߁A�������̕����d���̂����������B1929�N�̍����̌�A1930�N�ŏ���10�����Ԃ�744�̃A�����J���O���̋�s���j�Y����(1930�N��ɂ͑S����9000�قǂ̋�s���j�Y����)�B1933�N4���܂łɁA3���̋�s�̖@��x���̌�ɖ����i�̗a����j�Y������s��70���h���̗a�����������ꂽ�B
��]������s�Ƃ��A��肪�Ԃ������E���Ԃ����ĂȂ��قǂ̐����őݕt���̉�����s���ƂƂ��ɋ�s�̓|�Y���A���I�ɋN�������B�\�����v���Ⴂ���̂ł��������߁A���{�����⌚�z��������B�s�Ǎ��⏫���̌��ʂ��̈����ɒ��ʂ��A�����̂�������s�͑ݕt�ɂ����ɓI�ɂȂ����B��s�͊�{��������������ƂƂ��ɑ݂��t�������炵�A����ɂ���ăf�t���������߂��B�������z���i�݁A���~�X�p�C���������������B
���̗������͎��g�������N�����������̉��~��H���~�߂��Ȃ������B���g�̎��Y�𗬓������悤�Ƃ�����O�̏Փ��I�s���̑�ǓI���ʂɂ���ăf�t�����������A���Y�ʌ����̉��l�ɉe�������B���g�̕������炻���Ƃ���X�l�̓w�͂����������セ��傳���Ă����B�t���I�����A���҂������Ε����قǁA�ނ�͕��𑽂������邱�ƂɂȂ����B���̎��Ȉ����̉ߒ���1930�N�̕s�i�C��1933�N�̐��E���Q�֕ς����B
�A�M������s�̑��كx���E�o�[�i���L�̂悤�ȃ}�N���o�ϊw�҂��t�B�b�V���[�ɗR�����鐢�E���Q�̕��f�t�������������B
�����ȊO�̌����ɂ��f�t��
���f�t���ɉ����āA19���I�Ō�̎l�����I�̑�f�t���ȍ~�ɋN���������Y���f�t���̍\���v�f�����݂����B��ꎟ���E���ɂ���ċN�������C���t�������߂��������炭�p�����Ă����B
48�B�Ō����������ł��ő�̖��c�A���e�L�T�X���c�����Ƃ��āA1930�N��ɂ͌������i�����ň��l�ɒB���Ă����B�����s��ɂ�����ߏ苟���̂��߉��i��10�Z���g/�o�����ɂ܂Œቺ���Ă����B
�����Y�ɑ���Ռ�
20���I�ŏ���30�N�ɂ͎��{�����ƌo�ϐ��Y�����d���E��ʐ��Y�E�A���@�ւ̓d�����E�_�Ƃ̋@�B���ƂƂ��ɗN���N����A���Y���̋}���ȑ����ɂ��A�����̍H��̕��╨���̉����ƂƂ��ɗ]�萶�Y�\�͂̑��傪����ꂽ�B���ʂƂ��āA���E���Q�̑O��10�N�ɂ͈�T�̘J�����Ԃ��͂��Ɍ������Ă����B���E���Q�ɂ���Ă���ɑ����̍H�ꂪ�������B
�u��X�̏q�ׂ�(���Y���A���Y���A�ٗp��)�X����1929�N�ȑO�Ɋ��S�ɖ������������Ƃ����܂�ɒ[�ɋ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̌X���͂��̋��Q�̌��ʂł͌����ĂȂ����A���E���̌��ʂł��Ȃ��B�����ł͂Ȃ��āA���̋��Q�͂��������������ɂ킽��X���̌��ʋN����������Ȃ̂ł���B�v �}���I���E�L���O�E�q���[�o�[�g
�S�Čo�ό������̉����ɂ��o�ł��ꂽ�W�F���[���w�Y�Ƃ̋@�B���x(1934�N)�ɂ́A�@�B�������Y���傳����X�������̂��J���͂����ق���X�������̂��͐��Y���̗v���̒e�͐��Ɉˑ�����Əq�ׂ��Ă���B�܂��A���Y�R�X�g���ۂ͕K����������҂ɊҌ�����Ȃ��B����ɁA��ꎟ���E���ȍ~�E�}��o�����̓��͂Ɏ���đ�����ƂƂ��ɉƒ{�����̎��v���������Ĕ_�Ƃ͕s���ȉe���������Əq�ׂ��Ă���B�u�Z�p�I���Ɓv�Ƃ����p��͐��E���Q���̘J������\���̂Ɏg����Ƃ��w�Y�Ƃ̋@�B���x�ɋL����Ă���B
�u��Ԋ��A�����J���O���̓����ł��鎸�Ƃ̑���̊������͔�e�͓I���v�ɉ��������i�Y����Y�Ƃ̋@�B���������ł���Ƃ����邾�낤�B�v �t���f���b�N�EC�E�E�F���Y�A1934�N
1923�N�̌i�C�z�̒��_���炵�炭��A�ߏ�ȘJ���҂��ٗp�n���Ɣ�r���Đ��Y�����W�ɂ�����đ����Ă���A1925�N�ȍ~�̎��Ƃ̊g��������N�������B
�A�����J���O���̎�v�Y�Ƃ̐��Y���̌��I�Ȋg��Ƃ��̐��Y�i�A�����A�J�����Ԃɑ���e�����A�u���b�L���O�X�������̎x���ɂ��o�ł��ꂽ���Ђ̒��ŋc�_����Ă���B
�엿�A�@�B���A�i����ǂ�ʂ������Y���V���b�N�������_�Y�����i�̒ቺ�������N�������̂��ƃW���Z�t�E�X�e�B�O���b�c�ƃu���[�X�E�O���[���E�H���h���咣�����B�_�Ƃ͉ߏ�ȘJ���͋������������y�n�ɉ������߂��Ă����̂��Ƃ����B
�_�Y�����i�͑�ꎟ���E����ɒቺ���n�߂��B���ʓI�ɑ����̔_�Ƃ������Ƃ��Ĕ_�Ƃ𐬂藧�������Ȃ��Ȃ�A���S�̏��K�͂Ȓn��̓|�Y���������B�g���N�^�[�A�엿�A�G��g�E�����R�V�ɂ��_�Ɛ��Y���͖��̈ꕔ�ɂ����Ȃ�����; ���̖��Ƃ̓E�}�E���o������R�͗A���@�ււ̓]���ł������B�E�}�E���o�̐��͑�ꎟ���E���ȍ~�������n�߁A�ƒ{�����Y���Ă�����ʂ̓y�n���]��悤�ɂȂ����B
�����ԁE�o�X���d�Ԃ̔��W���~�߂�悤�ɂȂ����B
���x�Ǝ����̕s�ύt
�E�H�f�B���E�L���b�`���O�Y�A�E�B���A���E�g�D���t�@���g�E�t�H�X�^�[�A���b�N�X�t�H�[�h�E�^�O�E�F���A�A�h���t�E�o�[��(�A�����Č�ɂ̓W�����E�P�l�X�E�K���u���C�X)�Ƃ������o�ϊw�҂̓t�����N�����E���[�Y�x���g�Ɋ������̉e����^�������_�y�������B���̗��_�Ƃ́A�o�ς��A����҂ɏ\���Ȏ������Ȃ��ɂ�������炸�A����҂��w���ł���ȏ�̏��i�Y���Ă��܂����A�Ƃ������̂ł���B���̐��ɂ��A1920�N��̒����̏㏸���͐��Y���̏㏸����������Ă����̂ł���B���Y�������債�����Ƃɂ�鉶�b�̂قƂ�ǂ͗����ƂȂ��Ă��܂��A����͊����s��o�u���������N���������̂́A����҂̍w���s���ɂ͌q����Ȃ������B���̂悤�ɁA1920�N���ʂ��ĕx���s�����ɕ��z���ꂽ���Ƃ����E���Q�������N�������Ƃ����B
���̐��ɂ��A���E���Q�̍��{�I�Ȍ����́A�Ɨ���Ƃɂ������E�����̐������\���ȍw���͂ݏo���ɒB���Ă��Ȃ��ɂ�������炸�s��ꂽ���E�I�ȉߏ蓊���ł���B�܂��A���{�͕x�T�w�ɑ���ېł��d�����邱�ƂŎ�������蕽���ɂ��ׂ��������A�Ǝ咣�����B���{�́A�Γ��̑����𗘗p���Č������Ƃ��s���Čٗp�������邱�ƂŌo�ς��u�R���Ďn���v������ꂽ�A�Ƃ����B�����A�����J���O���ł�1932�N�܂ŁA����Ƃ͐����̌o�ϐ��s���Ă����̂ł���B�哝�̑ޔC�O�N�̃n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�ɏЉ��t�����N�����E���[�Y�x���g�ɂ���č̗p����邱�ƂɂȂ���<1932�N�Γ��@>��������ƌv�悪�A�w���͂� ������x�ĕ��z���邱�Ƃɐ��������̂ł���B
�����{�ʐ�
���E���Q�̋��{�ʐ����_�ɂ��A���Q�̌����͎�ɁA��ꎟ���E����̐�����������O�̒l�i�Ɋ�Â����{�ʐ��ɕ��A���悤�Ƃ������Ƃɂł���B���̐��ɂ��A����ɂ���ċ��Z���f�t���u���ɂȂ�10�N�Ԃɂ킽���ă��[���b�p�̑����̍��̌o�ς̌��S�����Q���������Ƃ����B
���̐�㐭��ɐ�삯�ăC���t�����Ƃ��Ă�����ꎟ���E��풆�ɂ́A�����̃��[���b�p�����͐��̌����ɂ����{�ʐ���p�~������Ȃ������B���̌��ʁA�V�������ꂽ���̋������C���t���𒆘a�����鐶�Y���ւ̓����ł͂Ȃ����Ɏg��ꂽ���߁A�C���t�����N�������B���̐��́A��ʂɓ������ꂽ���̗ʂɂ���ăC���t���������܂�A����䂦�C���t���֓������Ƃ��A�j��I�E����I�ł����Čo�ϐ������Ȃ��ړI�̂��߂ɑ���ꂽ�V�ݕ��̑��ʂ�����������Ƃ������̂ł���B
���A�����J��[���b�p���������{�ʐ��ɕ��A�����ہA�����̍��͐�O�̐����̋�-�ʉ݃��[�g���Ƃ����B�Ⴆ�C�M���X�ł�1925�N�ɋ��{�ʖ@�������ʉ߂��A����ɂ���ċ��{�ʐ��ɕ��A�����ہA�����O���ב֎s��Ő�O���������ƒႢ���i�Ń|���h���������Ă����ɂ�������炸�X�^�[�����O�E�|���h���O�Ɠ����ɐݒ肷��Ƃ����v���I�Ȍ�����s�����B�����W�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y��́A���{�͂������邱�Ƃɂ���Ēނ荇�������Ă��Ȃ��悤�Ȓ����Đݒ�������Ă���̂��Ǝ咣���Ă��̌����ᔻ�����B�E�B���X�g���E�`���[�`�������{�ʐ��ɕ��A���������Ƃɑ���P�C���Y�̔ᔻ�͂�����ÂɃ��F���T�C�����̌��ʂƔ�r������̂ł������B
��O�Ɠ����ɂ��悤�Ƃ����X�������܂ꂽ���R�Ƃ��Ĉ�́A�f�t���͊댯�ł͂Ȃ��̂ɑ��ăC���t���́A���Ƀ��@�C�}�[�����a���Ɍ�����C���t���͑ς���댯�ł���Ƃ��������D���ł������ӌ����������B������̗��R�Ƃ��āA�z�ʉ��z�ő݂��t���Ă���҂͎��g���݂��t�����̂Ɠ����l�̋����ł�����҂��������Ƃ������̂�����(citation needed)�B�t�����X�Ɏx����Ȃ���Ȃ�Ȃ����z�̔��������x�������߂̊O�݂��l������̂ɏ\���ȏ��i��A�o�E�̔����邽�߂ɁA�h�C�c�͐M�p���]���ɂ��������̎���ɓ������B���E�̋��̗��܂�ꏊ�Ƃ��ẴA�����J���O���̓h�C�c���t�����X�ɏ��҂��邽�߂̊�ՂƂ��ĎY�Ɖ����邽�߂̎�����݂��t���A�t�����X�̓C�M���X����уA�����J�ɏ��҂����B���̗���̓h�[�Y�Ăɖ��������ꂽ�B
���ɍ����̎؋������čėZ�����ł��Ȃ���Ԃɂ��邩�A�ᗘ���ł͂Ȃ��Ƃ��Ɏ��{���ɗZ�����邽�߂݂̑��t���Ɉˑ����Ă���ꍇ�A�_�Ƃ̂悤�ȎY�ƕ���ɂƂ��ăf�t���͐h�����̂ƂȂ肤��B���̎����I���l���������Ă���̂ɑ��ĕ����̓f�t���ɐZ�H����Ă����B���Y�������ŕێ����Ă���҂�A���Y�𓊎��E�w���ɏ[�Ă��莑����݂��t�����肵�悤�Ƃ��Ă���҂ɂƂ��Ă̓f�t���͗L�v�ł���B
�s�[�^�[�E�e�~���A�x���E�o�[�i���L�A�o���[�E�A�C�P���O���[���Ƃ������o�ϊw�҂ɂ����ߔN�̌����́A���E���Q���ɋُk���Ƃ��Ă������Ƃɒ��ڂ��Ă���B���̍l�����ɂ��A��Ԋ��̋��{�ʐ����łُ̋k�͍ŏ��̌o�ϓI�V���b�N���g�債�A���Q��H���~�߂邠����s���ɑ��đ傫�ȏ�Q�ƂȂ����Ƃ����B�ނ�ɂ��A�ŏ��̕s���艻������Ռ��̓A�����J���O���̃E�H�[���X��\���ɋN�����邪�A�O���ɖ���`�d�������̂͋��{�ʐ��ł���Ƃ����B
�ނ�̏o�������_�ɂ��ƁA��@�̎���̐���҂����͋��Z����E����������ɘa���悤�Ƃ������A���̂悤�ȍs�����A�_���̗��ŋ�����������`�����ێ����鍑�Ƃ̔\�͂����������Ƃ����B�O���̎��Y�����Ŕ������Ƃ��鍑�ۓI�����Ƃ������t���邽�߂ɁA���{�ʐ��͍��������ێ����邱�Ƃ�v������B���̂��߁A���{�ʐ���p�~���Ȃ�����A���{�͌i�C�̋}���ɂ�������܂˂��Ă���ق��Ȃ��B���{�ʐ����Ƃ�S�Ă̍��̌����䗦���C�����邱�ƂŁA�O���ב֎s�ꂪ�����̕��t��ۂ������͕ۏ����B���Q����������Ƒ����̍������{�ʐ���p�~���n�߁A��葁���p�~�������X�͂�菭�Ȃ��f�t���̉e�����Ă�葁���f�t���������X�����������B
���R��s���h�o�ϊw�҂ɂ��ă~���g���E�t���[�h�}���̒�q�̃��`���[�h�E�e�B���o�[���C�N�͎��g�̗�����w�A�����J���O���̋��Z����ɂ݂�����{�ʐ��Ǝ�����`�����x�Ŗ��m�ɐ����������A���̘_���ł̔ނ̎咣�ɂ��ƁA�A�M�������x�͎��͋��{�ʐ����ɂ����Ă��Ȃ�̗]�T�������Ă���A���̂��Ƃ��j���[���[�N�A�M������s���كx���W���~���E�X�g�����O�ɂ��1923�N����1928�N�̕������萭��ɂ���ďؖ����ꂽ�Ƃ����B������1928�N�㔼�ɃX�g�����O���v����ƁA�j���[���[�N�A�M������s�̎x�z���������p�����h�����A�S�Ă̋��͎��ۂ̏��i�ɂ���đ�\����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���������`���������������B�h����30%�̃f�t���������ē��R���O���o�ςɑ��Q��^�������̐���͜��ӓI�ŁA����������̂ł����āA���{�ʐ��͂���Ȃ��ɑ����ł����ƃe�B���o�[���C�N���q�ׂĂ���:
���̊Ǘ��ɂ����邱�̈ڍs�͌���I�ł������B�X�g�����O�͑O�C�҂ɏ]���ċ��{�ʐ��Ƃ����������ɓڒ������ɕ������萭������s���A������`�����̎x���҂͎��g�̗��z�Ƃ��鐭������s�����œ��l�ɑ��������ɍςB1928�N-1929�N�̃V�X�e���|���V�[�͌��ʓI�ɕ������肩��I�Ȏ�����`�Ɉڍs�����B�u���́v���{�ʐ��͂��ꂪ�ďo������̂ɍD�s���Ȏ���҂`���I�Ȍ����|���ł����Ȃ��ꏊ�Ŏc�������B
�����Z�@�ւ̍\��
�o�ώj��(���Ƀt���[�h�}���ƃV���E�H�[�c)�������̋�s���|�Y�������Ƃ̏d�v������������B�|�Y�͎�ɃA�����J�̒n���ŋN�������B�n��o�ς̍\���I�ȐƎ㐫�ɂ���Ēn�₪���ɕn��ɂȂ��Ă����̂ł���B�_�Ƃ͊��ɑ��z�̕�������Ă���A1920�N��ɔ_�ꉿ�i���}������̂ƕ��̗\�z�����䗦�����ˏオ��̂Ƃ�ڂɂ����B
�ނ�̓y�n��(1919�N�̒n���o�u���̌��ʂƂ���)�ߏ�ɖ@�I�`���킳��Ă���A�����̉��i���Ⴂ���߂ɔނ�͏��L���蕥�����Ƃ�������ꂽ�B����s�A���ɔ_�ƌo�ςƌ��т�������s��1920�N��ɂ͓ˑR�̎��������̏㏸�ɂ��ڋq�̍��s���s�̂��߂ɏ�Ɋ�@�I�ɂ�����; ��������������s�̊Ԃɂ�20�N���ʂ��Ċ��ɓ|�Y�̔g�������Ă����̂ł���B
�s����܂��V���b�N�ւ̎コ�������炷�\���I�Ǝ㐫�ɋꂵ��ł����B�����ő�̋�s�̒��ɂ͓K�ʂ̏�������ێ������ɁA�����s��ő�ʂ̓������s�����胊�X�N�̍����݂��t�����s�����肷����̂��������B�j���[���[�N�s��ɂ��h�C�c��e���A�����J�ւ݂̑��t���͓��ɍ����X�N�ł������B�܂�A��s�@�\�͑�s�i�C�̃V���b�N��ጸ����悤�ɏ\���ɏ�������Ă��Ȃ������̂ł���B
�E�H�[���X��\���Ɋւ��鎖�����ǂꂾ������ł��邩�o�ϊw�ҁE���j�Ƃ��c�_���Ă���B�����͖��炩�ł���B; �����̗��v�ɑ�����҂ւ̏Ռ��͐r��ł������B1928�N-1929�N�̎s��̓t�@���_�����^���Y�ɂ���Ē�߂�ꂽ�����ɒ[�ɕ����������u�o�u���v�ł������ƂقƂ�ǂ̃A�i���X�g���l���Ă���B���̂��Ƃɉ��炩�̓_�ŐӔC�����邪�A�ǂꂾ���ӔC�����邩�𐄗ʂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƌo�ϊw�҂����͔F�߂Ă���B�u1929�N�̊����s��̕��ŏ��̕s�i�C�ɖ������ʂ��������Ƃ͕Ў����^���Ȃ��v�ƃ~���g���E�t���[�h�}�������_�t���Ă���B
�c�_�͎O�̃O���[�v�ɕ�����Ă���: �ŏ��̃O���[�v�́A�}���������̗\�z�̌��I�Ȓቺ�Ƒ�ʂ̎��{�����̓P�ނƂɂ���ċ��Q�������N�������Əq�ׂ�; ���̃O���[�v�́A1929�N�ĂɌi�C�����藎���ċ}���������ǔF�����Əq�ׂ�; ��O�̃O���[�v�́A�ǂ���̃V�i���I�ɂ����Ă��}���͕s�i�C�������N�����ȏ�̂��Ƃ͂Ȃ����Ȃ��Əq�ׂ�B�s���1930�N4���ɂ͈�U�������A����ȍ~�����͍Ăщ����葱���A1932�N7���ɂ���ƍŏI�I�Ȓ�l�ɒB�����B����͂ǂ��v���Ă��A�����J���O���ōŒ����Ԃ̎s��̐��ނł���B1930�N�̕s�i�C����1931�N-1932�N�̑勰�Q�ւ̑J�ڂׂ̈ɁA�S���قȂ�v�����������ʂ������̂ł���B
���ی�f�Վ�`
�X���[�g�E�z�[���[�@�ɂ݂���悤�ȕی�f�Վ�`�́A�ی�f�Վ�`������Ƃ��Ă��̌��ʋߗ��R������Ɏ��������X�ƂƂ��ɁA���E���Q�̌����Ƃ��Ă�����������B�X���[�g�E�z�[���[�@�͔_�Ƃ̍��s���s�������Ă���A���ɔ_�Ƃɑ��ėL�Q�ł������B���̏o�����ɂ�蒆��������ł̎��t�����N���������������������āA���̌��ʋ�s�@�\�������B1000�l�ȏ�̌o�ϊw�҂����������Q�菑���A�M���{�ɒ�o����A���̒Q�菑���ŃX���[�g�E�z�[���[�@���o�ςɉ�œI�ȉe���������炷�Ƃ����x�����Ȃ��ꂽ; �������A����ɂ���ăX���[�g�E�z�[���[�@�̋c��ʉ߂����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�ϓ����ꐧ�ł͂Ȃ����{�ʐ����Ƃ鍑�ŕی�f�Վ�`���̗p���ꂽ���Ƃ��ӂ݁A�ی�f�Վ�`�͋��Q�̌����ł͂Ȃ����Q�ɑ���u�����v�ł������Ǝ咣����o�ϊw�҂�����: ���{�ʐ����Ƃ鍑�X�͗�����艺������Ō�݂̑���ƂȂ����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������A�Ƃ����̂͂����̍��X�͂��������炷���A���{�ʐ������Ȃ����X�͗�����艺���ĕs��������������邱�Ƃ��ł��邩��ł���B���̉��߂̉��ł́A�ی�f�Վ�`�́A���Z�����{�ʐ��ɔ����Ă��鍑�X�̖f�Տ�����ω�������̂Ɉ�����Ƃ�����B
�����ۓI�ȍ��\��
1918�N�ɏI����}����ƁA���[���b�p�̍��ŃA�����J���O���ƒ�g���Ă��鍑�͑S�ăA�����J�̋�s���瑽�z�̎؋������A���̎؋��̑��z�͂����̍��X�̑��œ��s���ꂽ���ɂł͎x��������Ȃ��قǂɂȂ����B���ꂪ�A�A�������h�C�c��I�[�X�g���A�E�n���K���[�ɑ���(�E�b�h���E�E�E�B���\�������Q�������قǂ�)��������v���������R�̈�ł���B�A�����̐M����Ƃ���ɂ��A�������̂������ŘA�����͕��𐴎Z����ړr�����͂��������B�������A�h�C�c�ƃI�[�X�g���A�E�n���K���[���g�����ɐ[���Ȍo�ϊ�@�Ɋׂ��Ă���; �A�����������x�����Ȃ��ȏ�Ƀh�C�c�ƃI�[�X�g���A�E�n���K���[�����������x�����Ȃ��Ƃ����ł������B
������1920�N��ɃA�����J���O���ɕ��̖Ə������Ȃ��Ƃ����̌y�����s�����Ƃ������v�������B����A�����J���{�͂��̗v�������ۂ����B����ɁA�A�����J�̋�s�����B�����ɑ��đ�K�͂ȑ݂��t�����n�߂��B���̂��߁A����(�Ɣ�����)�͌Â����z�����ĐV��������ςݏd�˂邱�Ƃɂ���Ă̂ݎx������B1920�N��㔼�ɂ́A���ɃA�����J�o�ς�1929�N�ȍ~�Ɏ�̉����Ă���́A���B�������A�����J���炳��ɋ������̂�����ɂȂ����B�����ɁA�A�����J�̍����łɂ���āA���B���������i���A�����J�s��Ŕ���̂����ɍ���ɂȂ����B�؋����߂����߂ɖf�Ղɂ���Ď����邱�Ƃ��ł����A���B�����͍��s���s���N�����n�߂��B
1920�N��㔼�ɂȂ�ƁA���[���b�p�̃A�����J�ɑ��鏤�i���v�͌������n�߂��B����́A���[���b�p�̎Y�ƁE�_�Ƃ̐��Y��������������Ƃ����̂����邵�A�������̉��B����(�ł������Ȃ̂̓��@�C�}�����a�����̃h�C�c)���[���Ȍo�ϊ�@�ɂ������ł��ĊO���̏��i���]�T���Ȃ���������Ƃ����̂�����B�������A1920�N��㔼�Ƀ��[���b�p�o�ς�s���艻�������匴���́A��ꎟ���E���̗]�g�̒��ŋN�������ۓI���\���ł���B
�X���[�g�E�z�[���[�@�̂悤�Ȋŏ�ǂɂ���Đ푈���̎x�������v���I�ɖW�Q���ꂽ�B�A�����J���O���̍��ł̌��ʁA�����̏z�݂̂ɂ���Ĕ�������푈�x�����̑��s���Ȃ��ꂽ�B1920�N��ɁA���Ă̘A�����͎�Ƀh�C�c�̔������x�����ɂ���ē���ꂽ�����ɂ���Đ푈�����x�������A�h�C�c�̓A�����J���O���ƃC�M���X����̎��I�Ȏ؋��ɂ���Ă̂ݎx�������Ƃ��ł����B���l�ɁA�A�����J���C�O�ɓ��������h���݂̂ɂ���ď��O�����A�����J�̗A�o�i���w�����邱�Ƃ��ł����B
1929�N�̊����s��}���ɑ����������̒D�������̒��A���[���b�p����A�����J�֎������������A���[���b�p�̐Ǝ�Ȍo�ς��ӂ��U�����B
1931�N�܂łɁA���E�͋ߌ���ōň��̋��Q�ɂ���Ă������A��������푈���̍\���S�̂������B
���W�c���͊w
1939�N�ɁA�����Ȍo�ϊw�҃A�����B���E�n���Z�������Q�ƘA�����Đl������������������Ǝ咣�����B ��������1978�N�̎G���L���Ń}�j�g�o��w�̌o�ϊw�҃N�������X�E�o�[�o�[�ɂ���Ď咣���ꂽ�B���̃n���b�h�E�h�[�}�[���f����p���Đ��E���Q�͂��A�ނ͂����q�ׂĂ���:
�u���̃��f���ł́A�n���b�h�̎��R�������̌����ݏo���ɁA����̓I�ɂ͐l���������A�J���͑������A���Y���E�Z�p���W���̑������������Ȑ������ȉ��ɂ܂Ō������Ă��钆�ɁA�[���ȋ��Q�̋N����T�邱�ƂɂȂ�B
1920�N��́u���Y���������v�̌����́u�͂����肵���؋��͂Ȃ��v���A�������̐l�����������ۂ́u�͂����肵���؋��v�͂���ƃo�[�o�[�͏q�ׂĂ���B�[���ȋ��Q�������N���������ŏ\���d�v�ȁu���R�������v�̌����͐l�����������ۂɂ���ċN�����̂ł��낤�Ɣނ͏q�ׂĂ���B
�o�[�o�[�́A�����炭�l���������̌������Z����v�ɉe�������̂��낤�Əq�ׁA���ꂪ1920�N��ɋN���������Ƃƌ�����Ǝ咣���Ă���B����͂������_���Ă���:
�u�_�ƈȊO�̉ƒ�̋}���Ŕ��ɑ�K�͂ȑ������������������炩�ɁA1926�N�ȍ~�̃A�����J���O���̏Z��z�E�ɋN���������Ƃł���B�����Ă��̌������A�{���`�ƃs���O�������咣�������Ă���悤�ɁA1929�N�̓s�S�̑勰�Q�ւ̓]���̍ł��d�v�Ȉ�v���Ȃ̂ł��낤�B�v
1920�N��̐l�����������ۂ̌����̒��ɂ�1910�N�ȍ~�̏o�Y���ቺ��ږ��̌���������B�ږ��̌����͎��1920�N��ɑ啝�Ȉږ��}���Ƃ�ꂽ���Ƃɂ���B1921�N�ɋً}�ږ������@���c���ʉ߂��A������1924�N�ږ��@�����肳�ꂽ�B
|
| ���o�ϐ���̖���
|
   �@
�@
|
�����C���Z��`
�����̎嗬�h�o�ϊw�h�̍l���ł́A���{�͍L�����ڏ�̗v�����肵�������X���ɗ��߂Ă����悤�w�͂��ׂ�������(�V�����ÓT�h��}�l�^���X�g�ɂƂ��āA��͖��ڃ}�l�[�T�v���C�ł���; �P�C���Y�o�ϊw�h�ɂƂ��āA��͖��ڑ����v���ꎩ�̂ł���)�B���ڃ}�l�[�X�g�b�N�Ƒ����ڎ��v���}�����Ȃ��悤�ۂ��߂ɁA���Q���ɂ́A������s�͋�s�@�\�ɗ������𒍓�����ׂ��ł���A���{�͐ŗ���艺������𑣐i���ׂ��ł������B
�A�M���{�ƘA�M�������x��1929�N-1932�N�ɂ�����s�킸�A���E���Q�ւƊׂ����B�o�ώj�Ƃ̊Ԃň�ʓI�ɂȂ��Ă��Ă�����ł́A�A�M�������x�̐���҂����̐��Z��`���_�ւ̎������j�œI�Ȍ��ʂ��������Ƃ����B�u���Z��`�v�̑��݂����E���Q�Ƃ����h�}�Ɛ��Ȃ�������������肷�铮�@�Â������邤���ŏd�v�Ȗ������ʂ������B�t�[���@�[�哝�̂͂��������Ă���:
�g���������������ɗ�����ꂽ���C���Z��`�҂�����...���{�͎���o�����ɃX�����v���Ȑ��Z����̂ɔC����ׂ����Ɗ����Ă���B���������͂�������̕���������Ă���: �u�J���𐴎Z����A�����𐴎Z����A�_�Ƃ𐴎Z����A�s���Y�𐴎Z����v...�u����ɂ���ăV�X�e�����畅�s���r�������B���z�̐����A���������͒ቺ����B�l�X�͂�蓭���A��蓹���I�ɐ�������悤�ɂȂ�B���l�ς����߂���A�l�X���y���܂��邱�Ƃ������͂ɗ��l�X�̔j�ł�h���B�v �h
�u�P�C���W�A���v���v�ȑO�́A���̂悤�Ȑ��Z��`���_���o�ϊw�҂̂Ƃ��ʓI����ł���A�t���[�h���q�E�n�C�G�N�A���C�I�l���E���r���Y�A���[�[�t�E�V�����y�[�^�[�A�V�[���A�E�n���X�Ƃ������o�ϊw�҂ɂ���Ă��̗��_���咣�E���W������ꂽ�B���Z��`�҂ɂ����Q�͗ǖ�ł���B���Q�̋@�\�́A�Y�I�Ȏg�p���琶�Y�̗v��(���{�ƘJ��)��������邽�߂ɁA�Z�p�I���W�̂��߂Ɏ���x��ƂȂ莸�s���������E�r�W�l�X�𐴎Z���邱�Ƃ��Ƃ��ꂽ�B�����̗v���͋Z�p�I�Ɋ����Ȍo�ϕ���ɉꂽ�B�ނ��1920�N-1921�N�̋��Q�Ɍ��y���āA���̋��Q��1920�N��㔼�̔ɉh�̊�b��z�����Ǝ咣�����B�ނ��(1921�N�Ɋ��Ɏ��s����Ă���)�f�t��������Ƃ邱�Ƃ�v�����A���̐���͎��{�E�J���͂�Y�I�Ȋ������������ĐV���Ȍo�ϓI�o�u���̊�b��z���̂Ɏg�����̂��Ǝ咣�����B�o�ς̎��Ȓ��߂���ʂ̓|�Y���N�����Ƃ��Ă��A�����Ȃ�̂ɔC���Ă����ׂ����Ɛ��Z��`�҂����͎咣�����B�Ƃ����̂́A���`�ߒ����������邱�Ƃ͓k�ɎЉ�I�R�X�g�傳���邾�����Ɣނ炪�l���Ă�������ł���B�V�����y�[�^�[�̒���ɂ��A�����
�g...�́A�ЂƂ�łɋN�������Ƃ��ɂ̂��S�ł���Ǝ������ɐM�������Ă����B�l�H�I�Ȏh���݂̂ɂ�邢���Ȃ镜�����A�\���ɋ��Q�̓������s���͂��Ȃ��������c���A���s�K����������������������炸�Ɏc���������ɑ��Ă��ꎩ�̂̐V���Ȋ��s�K�����������A���ꂪ�܂����Y��K�v�Ƃ���悤�ɂȂ�A��X�ɕʂ�(��舫��)��@�ɂ���ď��Ƃ��������̂ł���B �h
���Z��`�҂̊��҂ɔ����āA�������{�̑啔���͐��E���Q��N�ڂɓ]���E��������Ȃ������B�I�����B�G�E�u�����`���[�h�ƃ��[�����X�E�T�}�[�Y�̌����ɂ��A1933�N�܂łɕs�i�C�ɂ����1924�N�ȑO�̃��x���̎��{�~�ς��N�������B
�W�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y��~���g���E�t���[�h�}���Ƃ������o�ϊw�҂́A���Z��`���_����A��������u���E���Q�̐[�����Ɏ������Ǝ咣���Ă���B�P�C���Y�͚}�̃��g���b�N�ɂ���āA�n�C�G�N�A���r���Y�A�V�����y�[�^�[���ȉ��̂悤�ɕ\�����ƂŐ��Z��`�v�z�̐M�p�����킹�悤�Ƃ����B
�g...�֗~�I�E�����k�I�ȐS����(���E���Q��)...�ނ�̌����Ƃ���́u�ߖc���v�ɂ�������s���ɂ��Ė]�܂����Ƃ��Ĉ���...�B����́A�ߏ�Ȕɉh�������S�̓I�ȓ|�Y�ɂ���ăo�����X���Ƃ��Ȃ������Ƃ��ɁA�s���ȕx�ɑ��ċN���鏟�����Ɣނ�͊����Ă���B�������������d�ɂ��u�������ꂽ���Z�v�ƌĂԂ��̂����������𐳂��Ă���邱�Ƃ�]�ނƔނ�͏q�ׂĂ���B�ނ炪��X�ɏq�ׂ�Ƃ���ɂ��ƁA���Z�͖����������Ă��Ȃ��B�������₪�Ă͊�������B�����Đ��Z����������̂ɏ\���Ȏ��Ԃ����ĂA�S�Ă͍Ăщ�X�ɂƂ��ėǂ��Ȃ�... �h
�~���g���E�t���[�h�}���́A�����������u�댯�ȃi���Z���X�v�̓V�J�S��w�ł͌����ċ������Ă��Ȃ����ƁA�Ȃ�(���̃i���Z���X���������Ă���)�n�[���@�[�h�ŎႭ���q�Ȍo�ϊw�ҒB�����������̎t�̃}�N���o�ϊw��ے肵�ăP�C���W�A���ɓ]������̂��������͕������Ă��邱�ƁA���q�ׂ��B�ނ͂��������Ă���:
�g�����v���ɃI�[�X�g���A�w�h�̌i�C�z���_�͐��E�ɑ傫�Ȉ��e���������炵���B���Ȃ����L�[�E�|�C���g����1930�N��ɖ߂�A�����h���ɃI�[�X�g���A�w�h���͂т����Ă���̂������āA�n�C�G�N��C�I�l���E���r���Y�ɐ��E���i�C�̒�ɂ���̂���u����ƌ����邾�낤�B���Ȃ��͂���ɏ]���Či�C�����ȉ���ɔC���邱�ƂɂȂ邾�낤�B����ɑ��ĉ��������邱�Ƃ͋�����Ȃ��B�������Ă���舫���Ȃ邾���Ȃ̂�����B...�����v���ɂ��̎�̕��u��ɕ����t�����āA�C�M���X�ł��A�����J�ł��ނ�͊Q���ׂ����̂ł���B�h
�o�ϊw�҃��[�����X�EH�E�z���C�g�́A�n�C�G�N�ƃ��r���Y��1930�N�㏉���̃f�t������ɐϋɓI�ɂ͔����Ȃ��������Ƃ�F�߂����A����ɂ��ւ�炸�A�n�C�G�N�����Z��`�̏����҂ł������Ƃ����~���g���E�t���[�h�}���A�W�F�[���Y�E�u���b�h�t�H�[�h�E�f�����O���̑��̎咣�ɒ��킵���B�n�C�G�N�ƃ��r���Y�̌i�C�z���_(��ɍ����m���Ă���悤�ȃI�[�X�g���A�i�C�z���_�ɔ��W����)�͎��̓}�l�[�T�v���C�̋����������߂������悤�ȋ��Z����Ƃ͖���������̂������ƃz���C�g�͎咣����B����ɂ�������炸�A���E���Q�̍ۂɂ̓n�C�G�N�́u1929�N-1932�N�̋����f�t���Ɩ��ڎ����̈ޏk�ɞB���ȑԓx���Ƃ����v�ƃz���C�g�͏q�ׂĂ���B1975�N�̍u�b�ŁA�n�C�G�N�͎��g��40�N�ȏ�O�ɒ�����s�̃f�t������ɔ����Ȃ��������Ƃ̔��F�߁A�B���ȗ��R���Ƃ������Ƃ̗��R���������: �u�������͂�����x�Z���Ԃ̃f�t���̉ߒ��́A�o�ς��@�\���邱�ƂƑ��e��Ȃ��Ǝ����l���Ă��������̍d������j��ƐM���Ă����B�v ���̎O�N��A�n�C�G�N�͐��E���Q�����̘A�M�̓ˑR�̃}�l�[�T�v���C�̈������߂ƘA�M����s�ɗ���������������̂Ɏ��s�������Ƃ������ᔻ����:
�g�u�ꂽ�ы}�����N����ƘA�M�������x�������ȃf�t������ɑ������Ƃ����_�Ɋւ��Ď��̓~���g���E�t���[�h�}���ɓ��ӂ���B���͒P�ɃC���t���ɔ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�f�t���ɂ������Ă���B������A������x�A�Ԉ���Čv�悳�ꂽ���Z�����Q�����������B�h
|
| ���I�[�X�g���A�w�h�̐��{�c���_
|
������̑���
�t�[���@�[���A�M���{�̏����50%�����グ���̂͌��ʓI�������B�قƂ�ǂ̑��傪1932�N�ɋN����A����ɓ������Ē����s�i�C���������ƏI�����}�����B�I�[�X�g���A�o�ϊw�h�̒��ł����R��s���h�ɑ�����o�ϊw�҃X�e�B�[�����E�z�[�E�B�b�c�́A�Z���s�i�C�������͂��̂��̂������āu�勰�Q�v�ɂ��Ă��܂����Ƃ��ăt�[���@�[�̏����ӂ߂Ă���:
�Z���s�i�C�ɏI���͂����������̂��A���[���ŁA�����ƒ����勰�Q�ɕς��Ă��܂����Ƃ����ᔻ���n�[���@�[�g�E�t�[���@�[�͂��܂��J���Ă���...�ނ͋��Q�Ɛ키���߂ɐ��{�̖�����傫���g������...���̌��ʂ́A�s�K�Ȃ��Ƃ�(�����������ׂ����Ƃł͂Ȃ�)�A�Ə�肭������Ƃ��������ނ��뉊��������B
�f�C���B�b�h�E���C���o�[�K�[�́A���̃A�v���[�`���A�E�B���\���̋����A�M���{�������N���������Q�̉��Ōo�ς����I�Ɏh�������Ɣނ��q�ׂ�(�����ȃ`���[�g�ɂ����Ă�������)�N�[���b�W�������̏���E�ŁE�Ԏ��̐艺���ƑΔ䂵���B�N�[���b�W�����̏��������Ƃ��ăt�[���@�[�������ƃN�[���b�W�̉��ł̋K�������サ�����A�����̕�����1929�N�ɔގ��g�����s�������Ƃɔނ͒��ڂ���BGDP�ɐ�߂�A�M�̏�������������Ă������Ƃ����������_���E�O���S���[�E�z���R�����q�ׂĂ���悤�ɁA�t�[���@�[�̉��ł̂��̑听���̓t�[���@�[�ɂ��i�C���~�ōΓ������炵���Ƃ��Ă������A�M�������x�̉��ňȏ�̎����Ȃ��ꂽ���Ƃ͖��炩���Ƃ����B
���V���Ȍ��I�K��
�����w�A�����J�̐��E���Q�x�A�w�n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�̋��Q�x���̑��ɂ����āA�}���[�E���X�o�[�h�́A�t�[���@�[���������Y�ƁE�_�ƁE�ٗp�Ƃ���������ɂ�����V���ȘA�M�K���̈ꗗ��������A�ނ͂���𐢊E���Q�������炵���A�M�������x�̊���`�ƌ��т��ďq�ׂ��B
���ŗ��̈����グ
1932�N�Ƀt�[���@�[�͍Γ��@�𐧒肵�Đŗ������I�Ɉ����グ���B�ނ͂�����w�ɑ���ł������グ�A�ŕn���w�ɑ���ł��O�{�ɂ��ĕx�T�w�ɑ���ŗ���25%����63%�ɏグ���B���̍����̐ł͉�v�N�x�ł��蒷���s�i�C���I������N�ɓ������Ďx����ꂽ�B
�@ |
| �����E�勰�Q�ƃj���[�f�B�[������ / ����}�N���o�ϊw�̎��_���� |
   �@
�@
|
��1929�N�̊�����\���Ɏn�܂������E�勰�Q
1930�N��̐��E�勰�Q��1929�N10��24���̕č��E�H�[���X�ł̊�����\������n�܂����B�č�GDP�͔����߂��A������2���ɁA���Ɨ���25���ƂȂ����B���{�̃o�u�������u����ꂽ10�N�v�Ɣ�r����ƁA���̃C���p�N�g�̑傫�����킩��B���{��GDP�͕����������l���ɓ��ꂽ�����ł͔����A���Ɨ��͍ň�����6����ɂ����Ȃ��B���݂̃��[������@�Ɣ�r���Ă��A���[�����S�̂ł�GDP�͔����A���Ɨ��͍ň����̃X�y�C������͂�25�����x�ł���A�h�C�c�Ȃǖk�������̎��Ɨ���10������Ă��邽�߁A���[�������ς�11�����x�ł���B���{�̊����͎���ꂽ10�N�ȍ~�����𑱂��Ă���Ƃ͂����A���̎S��������A���݂̕s���Ƃ͔�r���ׂ����Ȃ����\�L�̑勰�Q�Ƃ������Ƃ��ł���B���̌�̃i�`�X�h�C�c�̑䓪����{�̌R����`��U��������E�������������Ƃ��l����A���Ȃ����������X�ƂȂ���邱�Ƃ͕s�v�c�ł͂Ȃ��B
�勰�Q��1929�N����n�܂�A�s���������Ȃ��A���E�o�ς͑���E���ɓ˓��������߁A���]�Ȑ܂�����B�����TVA�ɂ��_�����݂ȂǂŒ����ȃj���[�f�B�[������́A���Ȃ����V�ȃC���[�W��^���錾�t�ł���A���I�o�}�哝�̂́u�O���[���E�j���[�f�B�[���v����Ƃ������̂ɂ������p����Ă���B�������j���[�f�B�[������͌��݂̍����x�o�K�͂ɔ�ׂĊi�i�ɏ������A���[�Y�x���g�č��哝�̂��̗p��������̑��̂ł���A���[�Y�x���g���̂��m�ł���l�����������Ď��s�����Ƃ�������A�u�����邱�Ƃ����ł��������v�ƕ]���������̂��B���̂��߁A���݂ł���������]���ɂ��āA�_���������Ă���B�{�e�ł͋ߔN�̋ߑ�o�ϊw�I�����̒m�����܂߂Ȃ���A�������̘_���_�ɕ��ނ��Ȃ���A�l�@���Ă䂱���B
|
���j���[�f�B�[������̎����敪
�勰�Q���̗����̂��߂ɂ́A�������̎����敪���s���K�v������B
�m1�n�����\��(1929�N)����̃t�[�o�[�哝�̊��ł����1���ł́A�ύt������`�ɂ���ꌋ�ʓI�ɑ��ł���Z�������߂Ƃ����t�s���鐭����s���A�勰�Q���������Ƃ����B
�m2�n���[�Y�x���g�哝�̏A�C�����2�N(1933–par 34)�ł����2���ł́A
�E33�N4�����{�ʐ����~����ȂǁA���E�o�ς̒n��u�u���b�N���v�𑣂������̂́A
�E��s��@�ւ̑Ή��Ǝ��v�n�o����̂�A����������H���~�߂�ȂǁA���̐��ʂ��������B
�m3�n�����đ�3��(1935-36)�ł́A���[�Y�x���g�͎Љ�ۏᐧ�x�̊m���ƘJ���ی�̂��߂̃��O�i�[�@�𐧒肵���B�}�N���o�ς�1933�N���Ƃ�1934�N�Ȍ�͉X���ɂȂ�A���[�Y�x���g�哝�͍̂L�͈͂̎x�����W�߂����̂́A�J���e���e�F���܂�NIRA( �S���Y�ƕ����@National Industrial Recovery Act)��AAA(�_�ƒ����@Agricultural Adjustment Act)�Ȃǖڋʐ���̂��������ō��قŁu����������j�Q����v�Ƃ���ጛ�������o���ꂽ�B
�m4�n37�N�Ăɂ͍Ăьi�C��ނɌ����������A�i�`�X�h�C�c�̑䓪�̂��ƂŁA�R���x�o�𒆐S�Ƃ����K�͂ȍ����x�o���i�C��̒��S�ƂȂ�A�펞�̐��Ɉڍs���Ă������B
���̎l�̎����敪���������Ƃ�
�E�����̋}���Ȉ����������Ƃ߂�u���}�[�u�v�ɂ��ẮA�t�[�o�[���ɂ͎��s�������̂̃��[�Y�x���g���͈��̐��ʂ����������A
�E���̉��}�[�u�ւ́u�����v�������A�ŏI�I�ɂ͐푈�����������߁A���̋A�����킩��Ȃ����Ƃł���B
|
���܂̘_���_ �����ێ�����ƃP�C���Y�I��������
�ȏ�̎����敪����A�u���}�[�u�v�Ɓu�����v�ɗ��ӂ��āA�_���_�����Ă݂悤�B
�m1�n�����\��
�@�@ ��
�m2�n��s��@�Ƌ��Z����
�@�@ ��
�m3�n�����x�o����Ɩ���
�@�@ ��
�m4�n���{�ʐ��ƑΊO�W
�@�@ ��
�m5�n�����ƒ�����ăt�@�V�Y��
��5�����邱�Ƃ��ł��悤�B���̘_���_�𗝉����邽�߂ɂ́A�ߑ�o�ϊw��̊w�h�̍l�����̈Ⴂ�ɓ���Ă����Ƃ킩��₷���B�ߑ�o�ϊw�A�Ȃ��ł��}�N���o�ϊw(GDP�⎸�Ɨ��Ƃ������W�v���ꂽ�蕽�ϓI�Ȍo�ϐ����̑��݈ˑ��W��ϓ����J�j�Y��������)�ɂ͑傫�������Ĉȉ��̓�̍l����������B
�ma�n���R���C����Ƃ���(�V)�ÓT�h�o�ϊw
�mb�n���v�s���̏�Ԃ���{�Ƃ����{����F����P�C���Y�h�o�ϊw
�O�҂��č��ɂ����鋤�a�}�I�A�V���R��`�I�ȍl�����ɂȂ���̂ɑ��A��҂͖���}�I�ȍl�����ɂȂ���B���ہA���[�Y�x���g�哝�̂̎x���҂����́u�j���[�f�B�[���A���v�Ƃ����鐭���I�ȃO���[�v�ƂȂ��āA�č��̎哱�����������B2012�N11���̑哝�̑I���ŁA���݂̕s�������郍���j�[���(���a�}) �ƃI�o�}�č��哝��(����})������L�����_���������čl����Ƌ����[���B�����đ勰�Q���̐�����O�҂�������ʂ�ے肵�����ł���̂ɑ��A��҂͑傫���]������Ƃ����Ⴂ������B�勰�Q���̌o�ϐ����_���͍��Ȃ������Ă���̂ł���B
���Ę_���_�����Ɍ������Ă䂱���B�܂��`���ɏq�ׂ��悤�ɁA�_���_�̑�1��
|
���m�_���_1�n1920�N��̍D������M���銔���s��̔����Ƃ��āA�勰�Q���Ƃ炦����̂��B
�Ƃ������o���_������|�C���g�ł���B��ʂɃo�u���I�Ȋ����㏸��D���̔����Ƃ��đ勰�Q���Ƃ炦��K���u���C�X(The Great Crash 1929)�Ȃǂ̒��삪�m����̂ɑ��A�ߔN�̌����ł́A�����̌��ʂ͂��قǂł��Ȃ��A���{�̊����\���ƕs��������̑Ή��̌�肪�傫���A�Ƃ������ӌ��������B���͌��݂ł����Z����̂�����ɂ��ẮAFed View��BIS View�Ƃ�����悤�ɁA�����o�u���ɑ��ĈقȂ�ӌ�������B�O�҂͊����͊O���I�ɏ㏸���邽�ߋ��Z����Ő��䂷�邱�Ƃɔ������A��҂͊����o�u�������Z�������s�ɂ����čl�����ׂ��Ǝ咣����B |
���m�_���_2�n��s��@�ւ̑Ή��Ƌ��Z����
�_���_�̑�2�͊����\������̐ٗ�ȋ��Z����ł���B�勰�Q�͋��Z����̎��s�������炵���Ƃ����ӌ��͂��Ȃ�̃R���Z���T�X�Ă���B�w�I���̎��R�x�Ƃ����x�X�g�Z���[�Œm����~���g���E�t���[�h�}���̓A���i�E�V�������c�ƂƂ��Ɂw���O���̉ݕ��j1867-1960�x�Ƃ����_�j�ȏ��������M���A
�E��s��@�ɂ���ă}�l�[�X�g�b�N(�L�`�̉ݕ��ʁF�ȑO�̓}�l�[�T�v���C�Ƃ��邱�Ƃ���������)�̌��������������Ƃ������A���������̏㏸�Ȃǂ�ʂ��Đ��Y�̒�������炵�����Ƃ�_�����B����A
�E��FRB�c���x���E�o�[�i���L�̈ȑO�̌����́A���Z��@�͋�s���j�Y������A��s�ݏo�̗��p�\����ቺ�����邱�Ƃɂ���Ē��ړI�ȕ��̌��ʂ������Ƃ��������B(Bernanke�A Ben �gNonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression�h American Economic Review)
�܂�t���[�h�}����͋����������Ȃ����Ƃ����u���i�ʁv�������������A�o�[�i���L�͂��������݂��Ă��炦�Ȃ��Ƃ����u���ʖʁv���d�������̂ł���B�܂�1930�N��̕č��̑勰�Q�ɂ��āA�o�[�i���L�c����1929〜1�N�ɂ����Ă̍ŏ���2�N�ԂŁA�j���[���[�N�A�₪�����ƐϋɓI�ɋ��Z�s��Ɏ������������Ă�����Q�̖������͖h�����Ǝ咣���Ă���(�����̋��Z����̓��V���g���ɂ���FRB�ł͂Ȃ��A�j���[���[�N�A�₪�哱)�B�o�[�i���L�c���́A����ꂽ10�N�ɂ�������{��s�̑Ή���ᔻ���A����̓P�`���b�v���悢�A�Ƃ܂Ō��������A����͑勰�Q�̌o�����O���ɂ���B���̂��߃��[�}���V���b�N��̋��Z��@�ɂ����āA�ނ͂킸�����N��3.25����FF(�t�F�f�����t�@���h)���[�g�������������B�ȏ�̓_������̋��Z��@�ɂ����Ă��A��s�~�ς��d������闝�R�ł�����B�����̐��E���Z���Q�ɂ����Ă̓��[�}���V���b�N���̓�����s�j�]������Z�ʂ̓��h�����������A���[�}���u���U�[�X�~�ςɎ��s�����Ƃ͂����A���E�e���̋��Z���ǂ́A���I���������Ȃǂŋ�s���M�p�V�X�e���ێ��ɓ������B
�������j�]�ɕm�������Z�@�ւ����ł��~�ς���悢���A�Ƃ��������ł͂Ȃ��B�����郂�����n�U�[�h�̖�肪���邩��ł���B�������n�U�[�h�͖{���A���x�I�ȋ~�σ��J�j�Y��������ꍇ�A���X�N����s����ӂ�ꍇ�������o�ϊw�p��ł���B�댯�ȗZ���ɂ̂߂荞���Z�@�ւ�M�p�����ێ��̂��ƁA���ł��~�ς��Ă��܂��Ύ��~�߂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����ŁA�킪���̎���ꂽ10�N�ɂ����āA�ŏ��ɔj�]�������Z�@�ւ�������M�g����(�������a�M�p�g���A���S�M�p�g��)�Ƃ�����ł́A���_�̔��ɂ����I���������͂��炭�^�u�[������A��͌����ɉ�����B���̌��ʎO�m�،��j�]����A1997�N�ɂ͑傫�ȋ��Z�V���b�N�����{�����������̂ł���B |
���m�_���_3�n��������ƃ������n�U�[�h
��3�̘_�_�Ƃ��āA�����x�o�����ł���B�t�[�o�[�������ł͍�������͊��p����Ȃ������B�ѕq�F(1988)(�w�勰�Q�̃A�����J�x��g�V��)���w�E����悤�ɁA���{�̎x�o���傪�}�N���o�ςɃv���X�ɂȂ�Ƃ����F�����t�[�o�[�ⓖ���̌o�ϊw�҂������Ȃ������킯�ł͂Ȃ����̂́A���ʓI�ɂ͐��{�̍��������x�����s�����킯�ł͂Ȃ��B���̔w�i�ɂ́A�����g��͒n�����{���s���ׂ��ł���Ƃ����M�O���t�[�o�[�������Ă�������ł���B�t�[�o�[�哝�̂�1932�N�ɂ͐Ŏ����A�����Ԏ��g����āA�Γ��@�ɂ��呝�łɏ��o�����قǂł���B�勰�Q���[���ɂȂ������R�̈�́A���̌���������������߂ɂ���B
�t�[�o�[�哝�̂����ʓI�ɖ���ł������̂ɑ��A1930�N��ɕč��哝�̂ɏA�C�������[�Y�x��
�g�̃j���[�f�B�[������́A���{�������҂̃P�C���Y�I�ȍl�����ɋ߂��Ǝw�E����Ă���B��������
�ETVA(�e�l�V�[�여��J������)�Ȃǂ̌�������
�ECCC(���Ԏ����ۑ���)�ɂ���K�͌ٗp�Ȃǂ͒����ł���A
�E1935�N�ɂ�WPA(�������Ƒ��i��)��ݗ����A���Ǝ҂̑�ʌٗp�ƌ����{���݂�������Ƃ�S�ĂɍL�����B�j���[�f�B�[���Ƃ��������̐�����v���o���قǂł���B
���������ۂɂ́A���[�Y�x���g�������ɂ����Ă������g���͏��K�͂ŁAGDP��1〜2���ɂ����Ȃ������B���[�}���V���b�N���2009�N�ɂ͖������t�͑��z2���~�̒�z���t������t���A����ɑ��z15���~�̕�\�Z��g���A����͓��{��GDP500���~���炷��Ɣ䗦��3���ł���B����A�č��̃I�o�}�����͒���ɖ�8000���h���̑�𐬗��������B���̋K�͈͂�l������ł͖�3200�h��(���{�~�Ŗ�30���~)�ƂȂ�A�č�GDP�̖�6���Ƃ��Ȃ�B���z�Ƃ����A2008�N11���Ɍ��肳�ꂽ�����̍�������͂���ɋ��z�ł������B60���~�Ɗ��Z����邪�AGDP��12���ɂ����B�܂���{��GDP��3���A�č���6���A������12�����̋��z�̍����x�o���s���A���̌��ʁA���E�o�ς͔j�]����Ƃꂽ�Ƃ�������B�������Ȃ��璆���o�ς̕ϒ��ȂǁA�����x�o�̉i���I���ʂɂ͌��E�����邱�Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���[�Y�x���g�����͂����邱�Ƃ��s�����A�Əq�ׂ����A�����x�o�̑���̔��z�̓P�C���Y�o�ϊw�Ƃ������A���������ƌv�̏������ێ����邱�Ƃɂ������B�t�[�o�[�������ɂ͏����ƕ������X�p�C�����I�ɉ����������A�Ȃ��ł��_�Ƃ̋ꋫ�͌����������B������
�EAAA(�_�ƒ����@)�ɂ�鐶�Y����
�͒��������A���̔w�i�ɂ͑�ꎟ���E��펞�Ɋg�債���_�Ɛ��Y�͉��B�����ƂƂ��ɉߏ萶�Y�Ɋׂ������Ƃ�����B���̂��߃J���e���I�Ȑ�������F���A������u�L��n�R�v������邽�߂ɐ��Y�������s�����̂ł���B
���̐��Y�����Ə����ێ��Ƃ����ϓ_���炷���
�ENIRA(�S���Y�ƕ����@)�ɂ��J�����Ԃ̒Z�k������̊m��
�E���O�i�[�@�u�S���J���W�@�v�ɂ��J���҂̌����g���
�Ȃǂ̘J��������������₷���B�J���̉ߏ苟��������A�����ێ���}�����킯�ł���B |
���m�_���_4�n�ʉݐ��x�Ɛ��E�o�ς̃��[�_�[�V�b�v
�勰�Q�Ȍ�A���ےʉݐ��x�͋��{�ʐ�����Ǘ��ʉݐ��x�ֈڍs�����B���̗��R�͕č��ŋN��������s�������{�ʐ��̂��ƂŁA���E�e���ɓ`�d��������ł���B���{�ʐ��ł͊e���͎����ʉ݂Ƌ��Ƃ̌����䗦�����肵�A������������������肳���B�e���ʉݓ��ǂ͋��������ێ����邽�߂ɁA�����̋��Z������g���B
���̃V�X�e���̂��ƂŁA�č��ŋ������㏸����ƁA�������獂���������߂ċ�����������͂��ł���B�������A������������e���͋��m�ۂɑ���A�����o��h�~���邽�߁A�Ӑ}�I�ɋ����������グ�āA���ꂪ���Z�������߂ɂȂ������B���{�ʐ��������ŁA�č��Ő������ݕ��I�V���b�N�����E�I�ȋ��Z�������߂ɂȂ������킯�ł���B���ʓI�ɁA�����͋��{�ʐ������X�Ɨ��E���A1944�N�ɂ̓u���g���E�b�Y�̐��Ƃ�����Ǘ��ʉݐ��x�����������B
���̂悤�ȋ��{�ʐ��̖��͕č��̌Ǘ���`�I�X���̖��ɂȂ���B�L���h���o�[�K�[�w��s�����̐��E 1929-1939�x(�M��͓�����w�o�ʼn�A1982)�͐��E���Q���A�p������č��ɔe��������ւ��邱�Ƃɔ����ߌ��ƂƂ炦�A������e������_�̐��݂̐e�Ƃ���Ă���B�ɉh�����č��́A�{��
�E���{�ʐ��̂��Ƃŋ��Z����������鏔���ɕč��͓������ׂ��ł���A�����łȂ��Ɛ��E�I�Ȏ��v�s���Ɋׂ�B����ɕč���
�E�ی�f�Վ�`������Đ��E�f�Ղ��k�������A
�E���ۘA���ɂ͎Q�����Ȃ��ȂǁA�Ǘ���`�I�s����������B
���̂悤�ȍ��ۊԂ̖��̓��[�}���V���b�N��̋��Z��@�ł��w�E���ꂽ�B�O���[�o���E�C���o�����X�Ƃ��邪�A��������{�̒��~�ߏ肪�č��ɂ�������Z�����ߏ�ɉ�����Ƃ������ł���B�܂����݂̃��[������@�ɂ����Ă��A�f�Ս������g�傳���Ă����h�C�c�̓M���V����X�y�C�����~�ς��ׂ��ł���Ƃ����ӌ����݂��邪�A�����͐��E�o�ς̎����o�����X���d������_�ŁA�勰�Q�̌o���ƂȂ����Ă���B |
���m�_���_5�n�_���̔g�y�ƌ���o�ςւ̊܈�
1939�N�ɂ���ꂽ�w�X�~�X�s�֍s���x�Ƃ����t�����N�E�L���v���ē̒����ȉf�悪����B���V���g���ɏ�荞�V�ď�@�c���̃X�~�X�����A��������(�_���J��)�ɂ������@�c���̖�����e�N����Ƃ����؏����ł���B�t�����N�E�L���v���̂���f��(��s�Z�����������w�f���炵���ƁA�l���I�x�⎸�Ƒ���l�����w�I�y���n�b�g�x�Ȃ�)�͓����A�j���[�f�B�[���E�R���f�B�Ƃ���ꂽ���̂́A���́w�X�~�X�s�֍s���x�͎��̓j���[�f�B�[������ɔᔻ�I�ȓ��e�ƂȂ��Ă���B���̗��R�́A���{�̒��ډ���͕��s�ނ���ł���A�L�`�̃������n�U�[�h�Ƃ�������B�����Ă��ꂪ�u�����v�ނ킯�ł���(�������_���J���ɑ���X�~�X���̒�Ă͎��R�̂Ȃ��ŏ��N�������L�����v����Ƃ������̂ŁA����̓��[�Y�x���g�̃A�C�f�A�ɂ��ƂÂ����ۂɍs��ꂽCCC(���ԍ��y�ۑS����)�Ƀq���g�����̂�������Ȃ����Ƃ͕t�������Ă����K�v������)�B |
��������
�{�e�ł͂������̘_�_�ɕ����āA�勰�Q���̐����Ή����l�@���Ă����B�č��ɂ����Ă͓��{�ł͍l�����Ȃ��قǂ́A����}�E���a�}�̑Η����������B�����Ė���}�n�̍l�������A�j���[�f�B�[��������g����߂��A���̉e�����ߑ�ɂƂ炦�����Ȃ̂ɑ��A���a�}�n�̍l�������j���[�f�B�[��������ߏ��]�����A�勰�Q�����Z����̃~�X�ɋN������ƌ��肵�����ł���Ƃ܂Ƃ߂��邾�낤�B����Ɂu���}�[�u�v�͂�����x�̌��ʂ͔F�߂��邪�A���́u���}�[�u�v�I�P�C���Y����͌������Ƃɂ����鉘�E������Ȃǃ������n�U�[�h��ŁA�u�����v�������B�܂��Љ�ۏ�̏[���́A�N���~�����Ƃ����ی��͈̔͂̊m������߁A�r�O��`�Ɍ��т��B�܂�u�����v�͂��ϗ��I�ȕ����ɐ����邽�߁A���͐����ȃP�C���Y��`���S�̎�`�ɂȂ��鑤�ʂ��炠��B�����������v���Z�X���l����ƁA�ߔN�̐��E�����s���͂��|�낵�����Ԃ������A�Ƃ����z�����\��������Ȃ��B���ہA�������(2006)(�w���f�B�A�Љ�x��g�V��)�͉f��̂Ȃ��ŃX�~�X�����x�����鏭�N�������i�`�X���N��(�q�g���[���[�Q���g)�ɗގ����Ă���Ǝw�E���Ă���B �@
�@ |
| �����E���Q�A���̌����ƌ��� |
   �@
�@
|
���v�����[�O
���@�Ƃ́A��Ƃ̒����ȗ���ɕ����ԖA���Ƃ��ĂȂ�A���̊Q���^���Ȃ��ł��낤�B�������A��Ƃ����@�̉Q�����̂Ȃ��̖A���ƂȂ�ƁA���Ԃ͏d��ł���B1 ���̎��{���W(the capital development)���q����̊����̕��Y���ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�d���͂��܂����������ɂȂ��B�V�������������v���猩�čł������ޕ����Ɍ����邱�Ƃ�{���̎Љ�I�ړI�Ƃ���@�ւƂ��Ē��߂��ꍇ�A�E�H�[���X�̒B�����������̓x�����́A���R���C��(laissez-faire)���{��`�̌����ȏ�����1 �ł���Ǝ咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��c�@
John Maynard Keynes�A The General Theory�A Chapter 12�A 1936�B
���Q�́A�˂ɁA���������̏������̈ꎞ�I�Ȗ\�͓I�ȉ����ł����Ȃ��A�������ꂽ�ύt����u�ԉ���\�͓I�Ȕ����ł����Ȃ��B�@
Karl Marx, Das Kapiral, B. �V-Ab. 3-Kapitel. 15, 1894.
���́A���j�I��Ԃ��s�f�ɕω�����Ƃ��������ł����āA���j�I��Ԃ͂܂��ɂ���ɂ���ė��j�I���Ԃɂ����ė��j�I�̂ƂȂ�B�����̕ω��͂��������������悤�ȏz���`��������̂ł��Ȃ���A�܂�1 �̒��S���߂���U�q�^���ł��Ȃ��B����2�̎���͎��̑��̎����Ƃ����܂��āA�����ɎЉ�W�̊T�O���`�����邱�ƂɂȂ�B���̎����Ƃ����̂́A��������j�I��Ԃ͂���ɐ�s�����Ԃ���K�ɗ���������Ƃ������ƁA���������ČX�̏ꍇ�ɂ��Ă��ꂪ�����ɂȂ���Ă��Ȃ��Ƃ��ɂ́A�����͂����ɉ����s�\�Ȗ�肪���݂���̂łȂ��A�������̖�肪���݂���Ƃ݂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�@
Joseph A. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 2. Aufl., 1926.
�����������̕n���̌������A�Q�[��n�k��푈�ɂ���̂Ȃ�A���Ȃ킿�A����ꂪ�����I���Y���ƁA����Y���鎑���ɂ��ƌ����Ă���̂Ȃ�A�����́A�d�J���Ɛߖ�Ɣ����̂Ȃ��ɂ����A�ɉh�ւ̓������o�����Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤�B�������A���ۂɂ͂����̍����́A�悭�m���Ă���悤�ɁA�ʂ̎�ނ̂��̂ł���c�ނ��낻��́A���d�ȈӖ��Ōo�ϊw�̖��ł���B�����Ƃ��܂��\������A�o�ϗ��_�ɐ����I��r���������������o�ϊw�̖��ł���B�@
John Maynard Keynes, The Means to Prosperity, 1933. |
��1.�@���E���Q(world crisis�A world depression)�̍Č���
�u�A�����J�o�ς́A2007 �N�O���Ɉ�ʓI�ɍD���ł�����������Ɨ���4�B5%�ɂƂǂ܂��Ă���c�R�A�E�C���t���[�V����(�G�l���M�[�ƐH�����i������)��2006 �N�Ƃقړ����ɂƂǂ܂��Ă���B�v2007 �N7 ��18 ���ɂ��̏����o������͂��߂��A�M�������x�������Monetary Policy Report to the Congress �����O���Ă����}�N���o�ϖ��͂����ς�G�l���M�[�ƐH�����i�̏㏸�ɂ���܂����B�������A���̔��N��ɏo���ꂽ�����A��́̕A�u�A�◝����O���Monetary Policy Report to the Congress ���o������N7���ȗ����Ȃ����Ă��Ă���v�Əq�ׂ�Ɏ���܂����B����2007 �N7 ���ɓ�����sBSC(Bear Stearns)�P���̃w�b�W�t�@���h���j�]���A8 ����BNP Paribas �P���̃w�b�W�t�@���h�̉����肩��T�u�v���C�����[���،�(MBS)��g�ݍ���CDO(Collateralized Debt Obligation ���S�ۏ،�)�̑��������ƂȂ�A�A���8 ��17 ����0�B5���ً̋}���������s���Ă����̂ł��B
���̌�A�e��������s�ɂ�鎑�������ɂ�������炸���ċ��Z�s��ْ̋��͉������ꂸ�A3 ���ɂ�BSC ��JP �����K�����~�ϔ������܂����A7 ���ɂ�Fannie Mae�A Freddie Mac �̌o�c��@�����݉��A9 ���Ƀ����������`�ƃ��[�}���̊�@���A���[�}���̔j�Y�ƃ����������`�̃o���N�E�I�u�E�A�����J�ɂ�锃���ɏI���ACDS(Credit Default Swap)�𑽗ʂɕ�������AIG �̋~�ϖ�肪�������A�������i�̖\���A���Z�s��̋ɓx�̋@�\�s�S�A�����ċ}���ȏ���̗₦���݂ƌٗp�̈����������炳��A����͂܂��O���[�o���Ȍo�ϊ�@�����Q�ւƂȂ������̂ł��BNBER(National Bureau of Economic Research)���A�i�C��ނ�2007 �N��12 ������n�܂��Ă����ƔF�肵���̂�2008 �N12 ��1 ���̂��Ƃł����B
12 ���ɂ͒�E�����߂Ȃ�����p�[�g�J���Ɍg��鐔���܂܂Ȃ��A�����J�̊��S���Ɨ���7�B2���A110 �����AIMF �̍T���߂ȑ����v�Z�ł�9 ���ɐ��E�̋��Z���Y��1�B3 ���h���ɋy�ԂƂ���܂����B�g���^��GM ���Đ��E��1 �ʂ̐��Y��ƂƂȂ�܂�������㏉�̉c�ƐԎ��ɂȂ�C�O�Ő��Ј��팸�����{����ɁA�}�C�N���\�t�g��5�A000 �l�ɋy�Ԍٗp�팸�ɒǂ����܂�A�������ꌅ�����ɗ������̂ł��B����܂Ōi�C�z���A���Y���𒆐S�Ƃ��ċ��������炾���������Ă������ǂ́A��ĂɁu���v�s���v���咣����Ɏ���A�u�s��Ɉς˂Ă����̂͊ԈႢ�������v�Ƃ̕��������܂�Ă��܂����B
10 ���܂ł́A�u���Z��@�́A1929 �N�̂悤�Ȑ��E���Q�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤���A���̌o�ςɉe�����y�Ԃ��낤���v�Ƃ����c�_���Ȃ���Ă��܂������A�����ł͂��̂悤�ȋc�_���̂��]��Ɋy�ϓI�ȁu��@���v�̕\���ł��������Ƃ����炩�ł��B |
��2.�@�A�����J��2001�|02 �s���Ȍ�̐���
�z�́A�����قǂɂ܂œT�^�I�Ȍo�߂�H���Ă��܂��B�����Minsky-Kindleberger �̃��f��1���獱�����O��Ă͂��܂���B�����A���Z�I�s���萫�̍\���̊�ՂɏZ��o�u��������A���Z�I���Y�E���������ƌv�Ǝ��Y���i�㏸�ƌ������Ă��܂����B
2001-02 �s������̒E�o�́A�u�ٗp�Ȃ���jobless recovery�v������Ƃ��Ă��܂����B2000 �N��570 �����x�ł��������Ƃ�03-04 �N��800 �����A4�B0%�ł��������Ԃ̎��Ɨ���4�B0%����03 �N�ɂ�6�B0%�ւƊg�債�܂����B���̂悤�ȏ���̒E�o�́A90 �N�ォ��͂��܂����Z���(�y�ъ֘A������̊g��)�A�Z��i�㏸�������炷���Y���ʂɂ�����̊g������Ƃ��܂����B
�Z���(new housing units started)�́AReaganomics �̊g��̒��ł͎ア���̂ƂȂ��Ă��܂����B�s�[�N��86 �N�ł����A��s����78 �N��200 ���˂�傫�������180 ���˂ɂƂǂ܂�A91 �N��100 ���˂�������Ƃ���܂ŗ������̂ł��B92 �N����V����Kuznets �z�Ƃ������ׂ��㏸���n�܂�A����90 �N��㔼�ɂ�150 ���˂�����̂ƂȂ�܂����B�Z��̔��Ɋւ��Ă�96 �N�ɑO�̃s�[�N�ł���86 �N��75 ���˂��A98 �N�ɂ�76 �N�̃s�[�N�ł�����82 ���˂���88 ���˗]�肪�L�^���ꂽ�̂ł��B�N���̏Z��i�㏸����S&P/Case-Shiller 10 city index ��96 �N����}���ɏ㏸��2000 �N���ɂ�14%�̐����ɂ܂ŒB���܂����B01-02 �s���ɐ旧���̔���99 �N����A���݂�2000 �N���猸���ɓ]���A�Z��i�㏸����01 �N��ʂ���7�B5%���x�܂ʼn������A�T�u�v���C�����[���̋}�g��Ɖƌv�̍��㏸�͏Z��z�̓��\�������܂����B
���́A�ȑO�̊w���2�ŁA�Z��݂����E�ɋ߂Â��āA�ƌv�̃o�����X�V�[�g�̒������K�v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E���A�u���_�A��������Z����̈ێ����\�ɂ��A�₪�ĉ����Ǝ��v�����Ɠ�������������̗������݂�}������\�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�����A���̏ꍇ�ɂ͒��~���ቺ�������炷�}�N���s�ύt���ʂ̖��ݏo���\�������݂���v�Əq�ׂ��̂ł����A�A���2003 �N��FF ���[�g��1���ɂ܂ʼn����A�����������}�C�i�X�ɓ����܂����B�����ŁA�Z��݂�03 �N����}���ɏ㏸���܂����B80 �N��̏Z��z���ア���̂ł��������Ƃ�Kuznets �z�Ƃ������錚�ݏz��Jugler �z��(�ݔ������z��)�ɔ䂵�Ē������̂ł��邱�Ƃ���A�Z������p���������Ƃ͕s�v�c�ł͂Ȃ��Ƃ�������������܂����A�����Ƃ͌����Ȃ����������݂��܂��B
��1 �ɁA�l���̖ʂ���݂�A�����J�̐l����1 �̐����ɂ��������đ������Ă���A�Z����̋}�g���������邱�Ƃ͍���ł����AShiller �̌����ɂ����3�A�Z��݃R�X�g������Z��i���ɓx�ɘ������ď㏸�������Ƃ����炩�ƂȂ��Ă��܂��B����͈�ʂł͂���܂ŃA�����J�ɂ��܂茩���Ȃ������y�n���i�㏸�f���Ă��܂����A�����ł̓o�u���̕\���ł�����܂��B��2 �ɁA�Z����̋}�g��́A3 �̗v���ɂ���Ďx����ꂽ�ƌ����܂��B�܂�A1�T�u�v���C�����[�����Z��ɓK�p����K���ɘa�ɂ���đ��i����A�܂��A2 ���o���b�W���������A��O�ł̃T�u�v���C����W�����{���[���̏،���(non-agency MBS)�Ƌ��Z�H�w�̏��͂čď،���(CDO)��}����������s�̊����|�T�u�v���C�����[����01 �N��1�A450 ���h������05 �N�ɂ͑��ݕt��20%����6�A250 ���h���ɑ����A����������80%���炢�̕ʂ̍��ƕ������킹�đg������CDO �Ȃǂ̔̔��͊����ȂǂƂƂ��ɐ��E�̋��Z���Y��90 �N�㔼�̐��E��GDP ���x����2006 �N�ɂ́A�f���o�e�B�u�����O���Ă�140 ���h���Ɋg�債���̂ł����|�A�܂���Z�I�~�ςɂ���đ��i����܂����B�����āA���Ɏw�E�����悤�ɁA32000 �N����A�₪�s�����A���I��FF ���[�g�����Ȃ��ɂ͏Z����̊g��͂��蓾�܂���ł����B�܂�A�ߏ����͋��Z�ʂő������ꂽ�̂ł��B��3�ɁA�Z��i�㏸�Ƌ��Z�ɘa�́A�Z��i�͉�����Ȃ��Ƃ����u�Z��i�_�b�v�������܂��āA�Z��i�㏸�ɂ��L���s�^���E�Q�C����ړI�Ƃ���Z��w���������炵�܂����B�Z�J���h�n�E�X�ȂǓ����ړI�̍w����40%�ɂ܂ŋy�ƌ����Ă��܂��B���̌��ʁA�Z�����Housing bubble �ɓ]�������̂ł��B
�Z��o�u���͐������������܂����B�ݔ��������}�C�i�X�����̂܂܂ł�����02 �N�ɏZ��ݓ�����4�B8%�A03 �N�ɂ�8�B4%�A04 �N�ɂ�10�B3%�Ɗg�債�A����ɂ���͏Z��֘A�̑ϋv���̏�����h�����܂����B�ٗp�̖ʂł����̐��Y��2000 �N����2005 �N�ɂ����đ��ٗp��250 ���ȏ㌸�����A�����ƌٗp�ł͖�300 ���ቺ�������ŁA���݂ł�50 ���̌ٗp����(90 �N�ɔ䂵�Ă�200 ��)�������܂����B���ɒ��ڂ���ׂ��́A���Y���i�̏㏸�ƂƂ��ɏ���g�債�����Ƃł��B���������ɑ���Z��Y��1�B5 �{�ɋ}�㏸����ƂƂ��ɁA�������ɑ�������95%����㏸����100%���z���A���ɖ��ԉƌv���~����05 �N��3�l�����Ƀ}�C�i�X�ƂȂ�܂����B92 �N��3�A000 ���h�����z���Ă������ԉƌv���~��2000�N��1�A685 ���h���A05 �N��325 ���h���ɒቺ�����̂ɑ��āA�ƌv�����00-05 �N��2 ���h���������܂����B���̗����͉ƌv�̍��̏㏸�ł���AIT �o�u���̍��ɉƌv���̑�GDP �䗦�̓��[�K�m�~�b�N�X�ȑO��50%�ȉ��ɔ�ׂď㏸��65%�ƂȂ��Ă������A�Z��o�u���̒���95%���z����Ɏ������̂ł��B
�Z��o�u�������Z�ʂŎx����ꂽ���Ƃ͊��Ɏw�E���܂������A���Z�I�~�ς��܂��Z��o�u���̒��ŋ}�������܂����B04 �N��11�B7���h����GDP �̒��ŋ��Z�T�[�r�X��2�B4 ���h���B���z���A00-04 �N�ɑ�������GDP2 ���h���㕪��25%�A4�A800 ���h���͋��Z���傩������炳��܂����B00-07 �N���Ƃ�Ƌ��Z�����9�A000 ���h���������Ă��܂��B90 �N��ɔ{���������Y�Ƃ̕t�����l��������00-04 �N�ł�800 ���h�����x�ł���A00-07 �N�ł�1�A900���h����̐����A�����Ƃł�00-04 �N�ł͎�������A00-07 �N�ł�1�A900 ���h�����x�̑����ł��������Ƃ��l����A�A�����J�̐����͋��Z�I�~�ςɌX���Ă����̂ł��B07 �N���݂܂��ƁA����ʂ̕t�����l�z�ŁA�����Ƃ͋��Z�����1 ���h���ȏ������錋�ʂƂȂ��Ă��܂��B80 �N��̑O���ɂ͋��Z���傪�����Ƃ��邱�Ƃ��Ȃ��������Ƃ��l����ƁA�����Ƃ̒n�ʂ̒ቺ�Ƌ��Z����̏㏸�����m�ƂȂ�܂��B�������A�A�����J���Z�Ƃ́A���̌������O������̗��������ɋ��߂Ȃ���C�O����̋��Z�ʂł̎��v�������Ă��܂����B
�A��́A���̊ԁA�o�u���ɑ��ċ��Z�����K�p���鍢�����������ƂƂ��ɁA�T�u�v���C�����[���̊g��ɂ��Z������m�肵�܂����B�A��ɂƂ��Ă̖��̓C���t�����Ɍ��肳��Ă����̂ł��B�Z����̏㏸�͋��Z�C�m���F�[�V�����ɂ���ĊJ���ꂽ�V�����@��ł���A���i�㏸�͐��Y���㏸�̐��ʂƂ������Ȃ���܂���ł����B�����I�s�ꉼ���ƃ}�l�^���X�g�A�����I���Ҍ`�������Ȃǂɂ���čS������Ă����̂ł��B���́A�O�ɐG�ꂽ�w��ŁA��C���t�����ł̎��Y���i�㏸�Ƃ��ꂪ�o�����X�V�[�g���g�������邱�Ƃɂ���ē����Ə���ɗ^����e�����l�������}�N���o�ϊw�̊m���Ɛ���̓W�J���K�v�ł��邱�Ƃ��w�E�����̂ł����A�A��́A���ǁA���{�̃o�u���A���A�W�A�̃o�u���AIT �o�u���̌o���������̂ł��B
�A�����J�̏Z��o�u���Ɖߏ����̓}�N���̒��~�E�����s�ύt�����g�債�܂����B���~(�����Ԓ��~�{���{�������x)���瓊�����������z�͌o����x�ƍP���I�ɓ��������Ƃ͂悭�m���Ă��܂��B91 �N��81 �N�ȗ��̍����Ɉ�U�]�����A�����J�̌o����x��IT �o�u���̉ߏ����̒���4�A000 ���h���̐Ԏ��ɓ]�����Ă��܂������A03 �N�ɂ͐Ԏ���5�A000���h���B���z���A04 �N�ɂ�6�A680 ���h���A05 �N�Ȍ��7�A000 ���h���ȏ���v�サ�Ă܂��BGDP ��5%����Ԏ������܂ꂽ�̂ł��B�u�o�q�̐Ԏ��v���[�K�������1987�N�̌o����x�Ԏ���3�B5%���x�ł��������Ƃ��l����ƁA���̋K�͂͑傫���c��̂ł��B�A�t�K�j�X�^����C���N�ł̐��v�コ�ꂽ���Ƃ���p���Ă��܂����A���~�s��������ŋK�肵���̂́A��ƒ��~�������ɂ�������炸�ƌv���~���}�C�i�X�ƂȂ������Ƃɂ���܂��B���̐Ԏ��́A���̑��������Z�̃A�����J�����ȏ،��w���̌`�Ԃ��Ƃ钆���ȂǓ��A�W�A�ł̊O�ݏ����̑����ƎY�����A���{�̎��{�ɂ���Ė��߂��܂����B�r�㍑�̒�������GDP ��45%�ɋy�ԓ��������Ȃ���50%���钙�~���s���ăA�����J�Ɏ��{���������A1 �l������GDP �ł͐��\�{�̖L���������A�����J������Ɉˑ����Ē�����Ɛ�������������Ƃ����u���̍��v�����܂ꂽ�̂ł��B�����āA�}�����鐻���Ɛ��i�A�o�̔��Έȏ���O���n��Ƃ̗A�o�Ɉˑ����钆�����͂��ߓ��A�W�A�́A�A�o�哱�^�������p�������̂ł��B�A�����J�̉ߏ������G���W���Ƃ��鐢�E�o�ϊg�傪80 �N��A90 �N��ƂƂ��Ɋg�債�čČ����ꂽ�ƌ����Ă悢�ł��傤�B
|
��3.�@02�|07 �z�̏I��
�Z��i�̑啝�ȉi���I�㏸�͂��肦�܂���B�ƌv�̍��̖c���Ƌ��Z�@��(��s�A������s�A�w�b�W�t�@���h�Ȃ�)�̎����Ɋ�Â��ˋ�̋��Z���Y�̉i���I�c�������肦�܂���B���~�E�����s�ύt���܂��i�����܂���B�Z��o�u���Ɋ�b��u�������͎����s�\�Ȃ��̂ł����B
����܂ł̋��Q�Ɠ��l�ɁA���Z�E���{�s��̊�@�̑O�Ɋ��Ɏ��̖ʂŎ����s�\�ł��邱�Ƃ́A����ɐ旧���āu�x���v����Ă��܂����B�Z��i�㏸����05 �N����06 �N�ɂ����Ē������ቺ���A06 �N�ɂ͏Z��H���������A02 �N��9%���炢������ቺ���Ă����T�u�v���C�����[���̕s��������05 �N�̌㔼����㏸���A06 �N�I���ɂ�10%�ɁA07 �N�ɂ�20%�ƒP�����������̂ł��B
�]���_�ƂȂ����̂́A9�B11���Ƀo�[����������25�h�����x�ɗ�������ł����������i���A�C���N�푈��A�W�A�ł̎��v�g���w�i��04 �N��40 �h�����A����ɋ}���ɏ㏸�������Ƃɂ���܂��B�C���t���ɕq���ȘA��͏����݂ȗ��グ�ɓ��ݐ�܂����B1����FF ���[�g��06 �N5 ��10 ���ɂ�5%�܂ŏ㏸���A�s���Y��ݕt�����͏㏸���܂����B���̂��Ƃ���A�������i�Ȃ�����i�̏㏸���������Z��@�̊�ՂƂȂ����Ɖ��߂���͈̂�ʓI�ł��B�������A���Y���i���^�[�Q�b�g�Ƃ����Ƀo�u������u�����A��̐��̂�����Ȃ���Ȃ�܂��A���Z�I�����͏Z��s��̒�E�����ɂ͋��Z�@�֎��̂���@�ƂȂ�O�܂ł͏Z��s�ꂩ�猴���s��⍒���s��ł̓��@�Ɍ�����������ł��B
2007 �N�̉Ă���͂��܂���CDO ���͂��߂Ƃ���،������i�̉��i�����A���ꂪ�����N���������Z��@�́A�T�u�v���C�����[���̋}���ȏł��t���Ɣj�Y����ՂƂ��Ă��܂����B���X�N���U���\�Ƃ����،��������X�N���g�債�Ă������Ƃ����炩�ƂȂ����̂ł��B
�����ƌv�Z���Ă݂܂��ƁA2007 �N�̃A�����J�̏Z��[���c����10�B5 ���h���A�����،�������6�B4 ���h���ŁA���̓��T�u�v���C���،���2�B1 ���h���A���{�n�G�[�W�F���V�[�،���4�B3 ���h���ƂȂ�܂��B�T�u�v���C�����[���̎x�����s�\��(delinquency rate)��20���ł���ő�4�A000 ���h�����x�Ɛ��@�ł��܂��B�������A���̊z��������07 �N���_�ł̑����ɂȂ�킯�ł͂���܂���B07 �N�ɑ����Ƃ��Č����͈̂ȑO�̃T�u�v���C���j�Y���Ȃ̂ł��B��������A��ƍ����Ȃ�07 �N��11 ���i�K�ł͑�����1�A000 ���h�����x�Ɍ��ς���AFF ���[�g�̈��������A�ً}�Z���A������s�Ǝs����s�̊Ԃ̒����ȂǂŊ�@�̉���͉\�Ɣ��f�����悤�Ɏv���܂��B�䂪���ł�����،���Ќn�̌��������T�u�v���C���j�Y���͂����傫���Ȃ��ƌ����Ă��܂����|�����Ƃ��A�����������������̑�����،���Ђ̑������傫�������Ƃ������Ƃ�������ɔ��������̂ł����B
�����A��@�͌p�N�I�ɐ����A08 �N�H�́u����v�Ɍ��ʂ��܂����B����P�B Samuelson�́ANBER �̃R���t�@�����X�ŁA�勰�Q�̂悤�ȕ�����܂łȂ������Ƃ��납��Minsky ���u�T���N�v�ɂ��Ȃ��炦���̂ł�����4�AMinsky-Kindleberger ���f���̒ʂ�Ɍ����͐i�s�����̂ł��B�������AIT-�X�g�b�N�E�o�u���̌�̕s������̒E�o���Z��o�u���ɂ���Ď������A�A�����J��������ق��Ă����s�ύt�����邱�Ƃ��Ȃ����������ɁA��@�̋K�͂͊g�傹��������Ȃ������̂ł��B |
��4.�@�z�Ƌ�ʂ����\�����|80 �N��Ȍ�̐����\���̕���
���Z�K���ɘa�Ǝ��R����w�i�ɂ����،����{��`�̊g���A�A�����J�̒��~�E�����s�ύt�Ɖߏ����A������t�@�C�i���X�����̎s��Ɉˑ�����A�W�A�����|�����́A����̏z�ɂ͂��߂ēo�ꂵ�����̂ł͂���܂���B����́A�P�C���Y�I�Ȏ��v�ʂ��d�������ٗʐ���Ɛ���IMF �̐����@�\�s�S�ƂȂ�X�^�O�t���[�V���������������ƂɊ�Â��\���ω����A���Z���R���A�ϓ����ꐧ�ƍ��ێ��{�ړ��̎��R���A�����ăC���t���}������{�Ƃ���}�l�^���X�g�I���Z����Ƌ����d���̌o�ϐ������Ƃ���82 �N�Ȍ�̐V���Ȑ����̌n�ݏo���Ĉȗ��AReaganomics �ɂ��u�����v�ɂ����Ă��A90 �N��㔼��IT �o�u���������ɂ����������̂ł��B
�܂��A�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA���Y���i�̏㏸������ݏo���A�ݕ����ʂƕ����𒍎�����}�l�^���X�g�I�Șg�g�݂̋��Z���o�u�����ʼn߂������Ƃ��A80 �N��㔼�̓��{�̃o�u���A�A�W�A�ʉ݊�@�ɏI��铌�A�W�A�̐����A90 �N��㔼��IT �o�u���ȂǂŌJ��Ԃ���Ă��܂����B
�����̏z�̏I���́A80 �N��ȗ��̐��������{�~�ς̃p�^�[�����ɓx�ɂ܂Ŋg��Đ��Y���ꂽ���ʂƂ��Đ����A���������ĐV���ȍ\���ω����A82 �N�ȗ��̍\���̏I�����邢�͐V���ȗ��j�I���Ԃ̒��ł̍\���ω��̎n�܂董�����Ă���̂ł͂Ȃ����傤���B�P�C���Y��`�ƍ������̎l�����I�̌�A70 �N��̉ߓn�����o�āA82 �N���猻�݂Ɏ����2 �̎l�����I�̍\�������ݏo���ꂽ�̂ł����A���ꂪ�I�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
2009 �N1 ���Ɍ��\���ꂽ�u�b�V�������Ō�́u�哝�̌o�ϕv�́A1��@�̌����͓��A�W�A���͂��߂Ƃ���ߏ蒙�~(saving glut)��������ƃ��X�N�̉ߏ��]���������炵�A�Z��u�[���𑣐i�������Ƃɂ���A�Ƃ�����ŁA2�Z����Z�̃C�m���F�[�V�����͈�ʂł͗L�v�ł��������A�Z��w�����ߓx�ɗe�Ղɂ��A�Z���֘A�،��͒Z���̎����ւ̈ˑ��Ƌ��Z�@�ւ̍L�͂ȕۗL��ʂ��Ċ�@�������炵���A�Əq�ׁA32009 �N�͒���邪10-11 �N�͊g�傷��Ɣ��f���Ă��܂��B���z�̊�{���i��������Ă������ł͂Ȃ��\�������ʼn߂��Ă���A�o�ϊw�I�ɂ͊ӏ܂Ɋ����镶���Ƃ͓��ꌾ���Ȃ����Ƃ͏g�ɖ��炩�ł���܂��傤�B
�K�v�Ƃ���Ă���̂́A1�����I�s�ꉼ�݂��ʋύt�ɑ�������Ȃ�����ɓK�Ȏ��v�Ǘ��ł���A2���Y���i�̕ϓ��ɑΉ�������Z���x�E����̊v�V�ł���A�A�����J�̒��~�E�����s�ύt���o����x�̒����ł���A3���ێ��{�ړ��̓K�ȊǗ��Ə،����{��`�����Z�Ǔ��x�z�̗}���ɂ�錻��́u�����݂��v�̒Ǖ��ł���5�A4�A�����J�ȊO�̏����ɂ�������I�����o�H�̍\�z�Ȃ̂ł��B
�����̉ۑ�́A�������80 �N�㏉������̐����o�ύ\���̕ω���v�����Ă��܂��B�Ƃ��Ă��A����͂��������I�s�ꉼ���Ȃ�V�ÓT�h�I����Ⳃ��L���łȂ�����u�P�C���Y��`�v�Ɂ|����̓P�C���Y�̎v�z�◝�_�Ƃ͈قȂ�ł��傤���A�܂��u�P�C���Y��`�v�ɂ��l�X�Ȏv�z�◝�_������̂ł����|�A���Ă̏���Ⳃɖ߂�悢�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�܂���B�V���ȍ\���ω��́A���[���́A�܂����L���̈�ł̍\���ω���v����ۑ���������܂܂�������Ȃ��̂ł��B
���̑�1 �́A�O���[�o�������s�t�ł���Ƃ���A����ɂӂ��킵�����ۓI�s�ύt�������ł́u���ۋ���international collaboration�A co-operation�v�̍č\�z���K�v�ƂȂ�܂��B�u���g���E�E�b�Y�̐��́A���j�I�ɂ݂č��ی��������͂��߂Ĉӎ��I�ɋ�������V�X�e���ł������A���̕����ɍ\�z���ꂽ�T�~�b�g�̐��ł́A���R���C�Ƌ������������A���E�āE��3 �ɂ̊Ԃ̒����͗e�Ղł͂Ȃ��A���ۋ����́u��@�Ǘ��v�I�ɂ������������܂���ł����B�킯�Ă�1999 �N�̃P�����E�T�~�b�g�ɂ����ăO���[�o���E�G�R�m�~�[�̖��_���w�E���ꂽ�ɂ�������炸���Z�E���{�s��ւ̋�̓I�ȑ[�u����������Ɏ���Ȃ��������Ƃ́A���݂̊�@�̔w�i���Ȃ��Ă��܂��B�������A��@�̓W�J�ߒ����݂Ă��A���ۋ��������ۊW�̎�v�ȍ\���v�f�Ƃ���post-modern state �Ƃ͈قȂ�modern states�A�܂�BRICs ���͂��ߐV�������܂܂Ȃ������ɂ͌��E�����݂��邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă��܂��B���ی����������V�X�e���Ȃ背�W�[���̍ĕҁE�č\�z�͋i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��A���_�̂��ƁA��O�E�풆�̈ב֊Ǘ���O��Ƃ���Bretton Woods �̐��E��1929�N���Q�̍ۂ̂悤�ȕی��`�A���ʎ�`�A�o����`�ւ̉�A�͖��ɂȂ�܂���B�O���[�o���E�G�R�m�~�[�̌����̊�Ղ̏�ɓK�ȍ��ی������������Ȃ���Ȃ�������Ȃ��̂ł��B
��2 �́A�A�����J���͂��ߐ�i���Ői�s���鏊�����z�̕s�ύt�̉����ł��B70 �N��́u���������v�̒����������āA70 �N��㔼���珊�����z�̕s�������ƘJ�����z���̒ቺ�����X�ɐi�s���Ă��܂������APiketty and Saez �̌����ɂ���6�A�A�����J�ł́A90 �N��Ƀg�b�v10���̏�����40����ɁA��Ƀg�b�v1���̏�����70 �N���8���O�ォ��15%�܂ő������܂����B����P�B �h���b�J�[�͊�ƃg�b�v�̋��^�͕��ϘJ���҂̒�����20 ����25�{����ׂ��ł͂Ȃ��ƌ������̂ł����A���݂̂����300 �{���͂邩�ɒ����Ă��܂��B�킯�Ă��A���̊ԂɐL�т����Z�ƂƏ��Y�Ƃł̍��z��V�͋����قǂł��B
�܂��A90 �N��ɓ���AAutor�A Katz & Kearney ��Acemoglu ��̌����Ŗ��炩�Ȃ悤��7�A������������u�n���v�J���҂Ƃ���ȊO�́u�s�n���v�J���҂̒����̊i�����}���ɍL����A�����Ɍٗp���̑������ɂ��i���������܂����B���Y���㏸���������㏸�Ɍ��т��Ȃ��ꍇ�Ƀ}�N���o�ϕs�ύt�������邱�Ƃ�Pasinetti �����炩�ɂ����v���ł���8�A90 �N��Ɍ����ƂȂ��������i���ƘJ���s��̕��ɉ��̓}�N���o�ϋύt�̎�����[�����瓮�h�����Ă��Ă���̂ł�9�B����������A��ʓI�ɒP��̘J���s�ꂪ���݂���Ƒz�肵�A�����ł̘J���_��̉��P��W�]����]���̐����o�ϊw�ɂ͌��E�����݂���̂ł��B�}�N���o�ϊw�̍ł���{�I�Ȃ��̉ۑ�������ɉ�������ׂ����A���ꂪ����Ă��܂��B
�Ȃ��A���������������z�̖��́A���Z�I�~�ς��傫�Ȗ������ʂ��������ƂƂ��W���Ă��܂��B���Z�E�́u�×~��greed�v���ŋ߃A�����J�ł͔ᔻ����Ă���̂ł����A�،���Ђ�30 ��̃g���[�_�[��$180�A000 �̃T�����[�����炢�A�{�[�i�X�Ƃ���$5mil�B������Ă����͓̂��ʂȂ��Ƃł͂���܂���ł����B���ُ̈킳�́A�������u�×~�v�ɋN������Ƃ��������A���Z�I�Ȗc���A�~�ς��A�����J�̐������x�����\���̒����琶�܂ꂽ���̂ł��B�����S�̂̋��琅�����㏸���A�X�L���̊i�������Ȃ����A�����������n���͂����Z�݂̂łȂ���X�̕��ʂɔz�������K�v������̂ł��B
��3 �́A�K�Ȏ��v�Ǘ�����������ɂ��Ă��A�����̐��{�́AThe General Theory �̊��s���Ƃ͈قȂ�A���{�̑��K�͂ƍ����Ԏ����c�����A�����̈ړ]�x�o��`���I������(���S�ۏ�A����A��������)�������ꎞ�I�ɂ���g�����邱�Ǝ��̂ɂ��A�܂����̌��ʂɂ����E�����݂��܂��B���[�K���哝�̂�T�b�`���[���u�����Ȑ��{�v���X���[�K���ɂ��Ȃ���AGDP �ɐ�߂鐭�{�̔�d�͏k�����܂���ł����BOECD �����̍����Ԏ��̑�GDP�䗦�́A70 �N��̏����������ɂ�����0�B4������2�B5���Ɋg�債�A���ꂪ�l�I�E���x�����̑䓪�������炵���̂ł����A80 �N��ɂ͐Ԏ��͂����3�B5���ւƊg�債�A�Γ��̋K�͂�30%��O������㔼�ւƊg�債�܂����B90 �N��ɂ�����炪�����������Ƃ͌����܂ł�����܂���B���{�̑��x�o�́A��O�I�ɔ䗦�̒Ⴂ�A�����J����{�ł�35�����z���AEU15�ł�50%���z���Ă��܂��B�d�ő̌n�̍ĕ҂ƍ����x�o�̗D�揇�ʂ̕ϊv���Ώo�\���̉��v�A����������Αd�ō��Ƃ́u�E�\�z�v�����߂��Ă��܂��B
��4 �ɁA�T�X�e�i�r���e�B��肪����܂��B82 �N����̃l�I�E���x���������́AIT �v���ɂ݂�C�m���F�[�V�����ƂƂƂ��Ɍ������i�̒�����ɂ���Ďx�����܂����B���̒���BRICs ���͂��߂Ƃ���V���H�Ə����̑䓪�Ɛ�i���ł̉ߏ����́A���̊Ԃɐi�Y�ƍ\���̓]����ȃG�l���M�[�Z�p�A��փG�l���M�[�J���ɂ�������炸�A���炽�߂ăT�e�i�r���e�B�Ƃ������Y�́������ʂł̐����l�ނɉۂ��Ă��Ă��܂��B�������i�⍒�����i�̍����́A���Z�I�ȓ��@��ʂɂ��Ă��A����̐��E�o�ς̕s���萫�������Ă��܂��B�������A���̉ۑ�́A��ʂł͋Z�p�v�V�ɂ������ƂƂ��ɁAG�B Hardin �̎w�E�����u���L�n�̔ߌ��v�������悤�ɁA�s��̊O�ł́A�킯�Ă����ۓI���ʂł̋�����K�v�Ƃ��Ă���̂ł��B |
��5.�@�ւ̓�
�o�u���̕��琶�����z�I����̉́A�}�N���o�ϐ���|���Z����ƍ�������̓K�Ȏ��H��ʂ��Ďx���邵������܂���B�������i�����}���Ɉ�������̂ɑΉ����ĉy�I�ɐv���ȑ[�u���K�v�ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B�����炭����͍����I���S���}��������ł��낤���A������K�v�ł��B���_�A�����ɁA���z�I����͐V���ȍ\���ω���K�ɓ��������ƒ��a�I�łȂ���Ȃ�܂���B
���������Z���ƒ����́A�z�ƍ\���̊W�����́A70 �N�㖖����80 �N��ɂ����Ă̍\���ω��̍ۂ�������ƂȂ��Ă��܂��B�^�C�g�ȋ��Z����Ƌ����d���̐���ŃX�^�O�t���[�V�����ɑΏ������ۂɂ́A�u��������ⳁv��K�p���邱�Ƃňꕔ�̉ۑ�͒B�������܂����B�ܘ_�A����ŏ\���ł͂Ȃ����������߂ɁAReaganomics �́u���Łv�ɂ��u���v�Ǘ��v�����H���܂����B����ł����v�T�C�h����u���ċ����T�C�h�ɏœ_�����āA�C���t���[�V�����̗}����D�悷�邱�Ƃ͉\�ł���܂����B�����A�����ʂ��Ă���\���ω��́A���n���I�ȗ����Ɛ����I�͔\��s���Ƃ���̂ł��B
��1 �ɁA�������A���z�I����͐V���ȍ\���ω��̏��ۑ�Ƌْ��W��L���Ă��܂��B���Ƃ��A�A�����J�̉ߏ����ƒ����̉ߏ蒙�~�A�܂�u���̍��v����̒E�o�́A�u���̍��v�̏Z���Ɉ��͂�������B�h���̈ב֑���̖\���Ɛ��E�o�ς̉�̂͒N�����������Ă���댯�ł��B
��2 �ɁA���ۋ����̍č\�z�A���Z����̊v�V�A�d�ō��Ƃ̒E�\�z�A�����J���s��ł̓K�ȏ������z�Ɣɉh�̎����A�T�X�e�i�r���e�B�̊m�ۓ��X�|�����́A�o�ϊw�́A�����ɐ����w�̊v�V�𔗂��Ă��܂��BSchumpeter �́w�o�ϔ��W�̗��_�x�ŁA���j�I�u�́v����������A���̏�ł͗��j�I�\���̕�������́A�����I�z��U��q�̉����ł͗���s�\�ł邪�A��s�����Ԃ��痝���\�ł���A�������̑O�́u�����s�\�v�ł͂Ȃ��u�������v�̖�肪����̂��ƌ������̂ł����A�܂��ɂ��������u�������v�̖�肪����܂��B�܂��V����political economy �̉ۑ肪����܂��B�]���̒m���ƌo���ɍS�����ꂸ�ɁA�V�������j�I�\���ω�����������̕K�v�������݂���̂ł��B
|
����
1�@Charles P. Kindleberger, Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, John Wiley & Sons, 1st in 1978, 4th in 2000.
2�@���X�ؗ����u�O���[�o���E�G�R�m�~�[�Ɛ��E�s���|�s���ƍ\���ω��Ɋւ���o���v�A���{���یo�ϊw���61��S�����ʘ_��w�O���[�o���[�[�V�����̐��ʂƉۑ�x�A���k��w�A2002 �N10 ��5 ���B
3�@Shiller, Robert J., The Subprime Solution, Princeton University, Press2008.
4�@Feldstein, M.(ed), The Risk of Economic Crisis, NBER with The University of Chicago Press, 1991.
5�@�u���g���E�E�b�Y��c�ŃA�����J�̍��������ł��������[�Q���\�[�́A��������ۋ��Z�̐_�a���獂���݂�Ǖ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���Əq�ׂ��B
6�@Piketty�AT. and E. Saez�AIncome Inequality in the United States�A1913-1998�ANBER Working Paper 8467�A2001.
7�@Autor, D. H., Katz, L. F. and M. S. Kearney, The Polarization of the U.S. Labor Market, NBER Working Paper 11986, 2006. Acemoglu, D., Technical Change, Inequality, and the Labor Market, Journal of Economic Literature, Vol. XL, 2002.
8�@Pasinetti, L. L., Growth and Income Distribution: Essays in Economic Theory, Cambridge University Press, 1974, and Structural Change and Economic Growth: A theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations, Cambridge University Press, 1981.
9�@���̖��ɂ��Ă͖{���{���ɏ������ٍe�u�����J���o�ςƃ}�N���o�ϋύt�v���Q�l�̂��ƁB�@
�@ |
| ���勰�Q�̌����̓t�����X�ɂ����� |
   �@
�@
|
�u�勰�Q(Great Depression)�Ɋւ�����I�Ȍ����̑����͑勰�Q�̐[���������{�ʐ��ƌ��ѕt���Ę_����X���ɂ���B����܂Ōo�ώj�Ƃ͑勰�Q�̈������ƂȂ��������Ƃ��ăA�����J�ɂ����Z�������߂ɒ��ڂ��Ă������A�勰�Q�̉ߒ��Ńt�����X���ʂ����������ɑ��Ă͏\���Ȓ��ڂ������Ă��Ȃ��B���E�S�̂ɑ��݂���������̂����t�����X���ۗL���銄����1926�N�̎��_�ł�7�����������A1932�N�̎��_�ł�27���ɂ܂ŏ㏸�������邱�ƂɂȂ����̂ł���B1930�`31�N�̊Ԃɐ��E�S�̂ŕ�����30���������邱�ƂɂȂ������A���̂������悻�����̓t�����X�ƃA�����J�ɂ���ʂ̋��̕ۑ�(���ߍ���)�ɂ���Đ����ł���\��������̂��B�v
1930�N��ɔ��������勰�Q(Great Depression)�Ɋւ���o�ϊw�̐��I�Ȍ����̑����́A�����̌i�C��ނ̒����Ƃ��̐[���������{�ʐ��ƌ��ѕt���Ę_����X���ɂ���B���{�ʐ����̗p���Ă������ł͈בփ��[�g���Œ肳��邱�ƂɂȂ�A���̂��ߊ�@�ɑΏ����邽�߂ɋ��Z��������R�ɉ^�c���邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����킯�ł���(�ڂ�����Temin(1989)��Eichengreen(1992)�ABernanke(1995)�Ȃǂ��Q�Ƃ̂���)�B
�������Ȃ���A1929�N����1933�N�܂ł̊��Ԃɋ��{�ʐ����ǂ����Ă���قǂ܂ł̃f�t���[�V�����𐢊E�K�͂ň����N�������ƂɂȂ����̂����̗��R�ɂ��Ă͂͂����肵�Ȃ��ʂ�����B�Ƃ����̂��A1920�N�ォ��1930�N���ʂ��Đ��E�S�̂ł̋������̗ʂ͒����ɑ��������Ă����̂ł���B�ǂ����ċ��{�ʐ��͎����̂��H�@�ǂ����ċ��{�ʐ��͂���قǂ܂ł̑匃�k�𐢊E�o�ςɂ����炷���ƂɂȂ����̂��낤���H
���勰�Q�Ɋւ���W���I�Ȑ���
1930�N��̑�S����������悤�Ǝ��݂钆�ł���܂Ōo�ώj�Ƃ͒�����s���̗p��������ɒ��ڂ��Ă����B�勰�Q�̋N��������W���I�Ȑ����ɂ��ƁA1928�N�����ɃA�����J�Ŏ��{���ꂽ���Z�������߂������勰�Q�̈������ƂȂ����������ƌ����X���ɂ���(Friedman and Schwartz 1963�A Hamilton 1987)�B1928�N������FRB�������������グ�����Ƃő��̍��X����A�����J�ւƋ����������邱�ƂɂȂ������AFRB�͂���ɂ��킹�Ĕ���I�y���s�����̗�����s�ى������B���̂��߃A�����J�ł͋��̗����ɂ�������炸�}�l�^���[�x�[�X�͑����邱�Ƃ͂Ȃ��A���̈���ŋ��̗��o�Ɍ�����ꂽ���X�͋��Z�������߂�]�V�Ȃ�����邱�ƂɂȂ����B�������Đ��E�o�ς̓f�t���V���b�N�Ɍ������邱�ƂɂȂ�A���̉e���Œʉ݊�@���s�p�j�b�N�������N������A����ɂ��ꂪ�����ƂȂ��ĕ����̉����X�p�C�����Ɉ�w�̔��Ԃ�������i�D�ƂȂ����E�E�E�Ƃ����킯�ł���B
���V���ȉ���
�������Ȃ���A���̂悤��(�勰�Q�Ɋւ���)�W���I�Ȑ����ɂ����Ă͂����Ύ��̎��������߂�����Ă���B�t�����X���A�����J�Ɣ��Ɏ��ʂ����s���ɏ��o���Ă����Ƃ�������������ł���B���̂Ƃ���A�t�����X�̓A�����J������X�s�[�h�ŋ������𗭂ߍ��ނƂƂ��ɂ���(�����ɗ������Ă�����)��s�ى����Ă����̂ł���(�ڂ�����Johnson(1997)�����Mouré(2002)���Q�Ƃ̂���)�B1926�N�Ƀt�������艺����ꂽ���Ƃ�����ƂȂ��đ�ʂ̋����t�����X�ɗ������n�߂邱�ƂɂȂ邪�A���̌��ʃt�����X��s���ۗL����������̗ʂ͋}���Ȑ����ő��債�n�߂邱�ƂɂȂ����B �ȉ��̐}1�Ɏ�����Ă���悤�ɁA���E�S�̂̋������̂����t�����X���ۗL���銄����1926�N�̎��_�ł�7���ɉ߂��Ȃ��������A1932�N�ɂ�27���ɂ܂ŏ㏸���邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@�@�@�} 1�B ���E�S�̂̋������ɐ�߂�e���̃V�F�A
���̂悤�ɂ��ăt�����X��A�����J�ɋ��������W���������ʁA����ȊO�̍��X�͑傫�ȃf�t�����͂ɎN����邱�ƂɂȂ����B1929�N����1931�N�܂ł̊Ԃ�(�A�����J�ƃt�����X������)����ȊO�̍��X�͐��E�S�̂̋������̂���8��������������i�D�ƂȂ����킯�����A1928�N12���̎��_��(�A�����J�ƃt�����X������)����ȊO�̍��X���ۗL����(���E�S�̂̋������ɐ�߂�)�������̊�����15�����������Ƃ��l����ƁA���̂قƂ�ǂ���������ƂɂȂ����킯�ł���B�������Ȃ���A�A�����J�ƃt�����X�����̗�����s�ى����邱�Ƃ��Ȃ�����̂悤��(�t�����X�ƃA�����J�ւ�)�������̏W�������E�o�ςɂƂ��Ė��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��������Ƃ��낤�B�A�����J�ƃt�����X�����̗�����s�ى����Ȃ���A���̗��o�Ɍ�����ꂽ���X�����Z�������߂�]�V�Ȃ������̂ƈ��������ɁA�A�����J�ƃt�����X�ł͋��̗����ɔ����ċ��Z�ɘa���i�߂��邱�ƂɂȂ�B���ׂĂ̍����ÓT�I�ȋ��{�ʐ��́u�Q�[���̃��[���v�ɏ]���čs������ꍇ�͓��R�����Ȃ�͂��ł��������A��Ԋ��̋��{�ʐ��ɂ����Ă͂��ׂĂ̍������ӂ���u�Q�[���̃��[���v�͊m�����Ă��炸�A�t�����X���A�����J���Ƃ��ɋ��̗��������Z�ɘa�ɂȂ���Ȃ��悤�ɋ��̗�����s�ى����Ă����̂ł���B
�t�����X�ɂ��(���̗�����)�s�ى��̎��Ԃ͈ȉ��̐}2�̐��ݏ������̐��ڂɕ\��Ă���B���ݏ������Ƃ����̂͒�����s��(��s�����s�c���{�����a���c��)�ɑ���������̊������w���Ă��邪�A�����ł��t�����X���H�����i�H�͑��̍��Ɣ�ׂčۗ����Ă���B�t�����X��s�̐��ݏ�������1928�N12���̎��_�ł�40����������(�@���ł͐��ݏ������͍Œ��35�������悤��߂��Ă���)�A1932�N12���̒i�K�ł�80���߂��ɂ܂ŏ㏸���Ă���̂��B1928�N����1932�N�܂ł̊ԂɃt�����X�̋�������160���������������̂́A���̈���Ń}�l�[�T�v���C(M2)�͂܂������ƌ����Ă����قǕω����Ȃ������B�����̐l�X�̒��ɂ̓t�����X���w���āu���̗��r(���̋z���@)�v(�ggold sink�h)�ƌĂԐ����������Ƃ������A����������Ƃ��Ȃ��Ƃ��ƌ����邾�낤�B
�@�@�@�} 2�B ��v������s�̐��ݏ�����(1928�N�`1932�N)
���A�����J�ƃt�����X(�ɂ����Z����)�����E�o�ςɋy�ڂ����f�t�����͂͂ǂ̒��x���H
1928�N����N�Ƃ��đI�ꍇ�A(�s�ى����ꂽ���Ƃ�)�����p�̂܂܂ɒu����Ă���1���̗ʂ����̂悤�ɂ��ċ��߂邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���̔N(��B1931�N)�Ɏ��ۂɒ�����s���ۗL���Ă����������̗ʂ��炻�̔N(��B1931�N)�̒�����s��(�}�l�^���[�x�[�X)��1928�N���_�̐��ݏ��������|�����킹������2�����������̂ł���B���̂悤�ɂ��Čv�Z���ꂽ�u�����p�̋��̗ʁv���O���t�ɂ����̂��ȉ��̐}3�ł���A���E�S�̂̋��X�g�b�N(�c��)�ɑ��銄���Ƃ��ĕ\�킳��Ă���B
1930�N�̎��_�ł̓A�����J�ƃt�����X�͗������킹�Đ��E�S�̂̋��X�g�b�N�̂��悻60����ۗL���Ă����킯�����A���̓����N�ɗ��������킹��Ɛ��E�S�̂̋��X�g�b�N��11���𖢗��p�̂܂܂ɒu���Ă������ƂɂȂ�B1929�N��1930�N�Ɋւ��Ă̓A�����J�ƃt�����X��(���̗�����s�ى����A���𖢗��p�̂܂܂ɒu���Ă������Ƃ�)���E�o�ςɑ��ē����̃f�t�����͂��y�ڂ����ƍl�����邪�A1931�N��1932�N�Ɋւ��Ă̓t�����X�̕����A�����J���������Ƒ傫�ȃf�t�����͂𐢊E�o�ςɋy�ڂ����ƂɂȂ����ƍl������B������1928�N����1932�N�܂ł̊��ԑS�̂Ŕ��f����ƁA�t�����X�̓A�����J������f�t�����͂𐢊E�o�ςɋy�ڂ����ƂɂȂ����Ƃ������ƂɂȂ�B����1928�N�Ɠ������ݏ��������ێ��������ł���A�t�����X�͐��E�S�̂̋��X�g�b�N��13�B7%�ɑ��������������ɍX�Ȃ���Z�ɘa�ɏ��o�������̂ł���A�A�����J�͐��E�S�̂̋��X�g�b�N��11�B7���ɑ��������������ɍX�Ȃ���Z�ɘa�ɏ��o�����Ƃ��\�������̂��B
�@�@�@�} 3�B �����p�̋��̗�(1929�N�`1932�N)
�������ɋy�ڂ����e��
1752�N�Ƀf�C���B�b�h�E�q���[���́u�ݕ��ɂ��āv(�gOf Money�h)�Ƒ肳�ꂽ�G�b�Z�C�̒��Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă���B�u�d��(�ݕ�)�����̒��ɂ��܂����܂��ƁA���̌��ʂƂ��ĉ��i�ɂ͍d�݂����̐�������ł����ꍇ�Ɠ��l�̌��ʂ������邱�ƂɂȂ�v�B���āA�A�����J�ƃt�����X�����𖢗��p�̂܂܂ɒu���Ă������ƂŐ��E�S�̂̕��������ɂ͂ǂ̂悤�ȉe�������������낤���H�@�����g�����ŋߍs�����������ʂɂ���(Irwin 2010)�A���E�S�̂̋��X�g�b�N��1������������Ɛ��E�S�̂̕���������1�B5�������㏸����Ƃ̊W�����藧���Ƃ��m�F����Ă���B�A�����J�ƃt�����X�����킹���(1930�N�̎��_�ł�)���E�S�̂̋������̂���11���������p�̂܂܂ɒu����Ă���3�i�D�ƂȂ�킯�ł���A����䂦��̊W�ɓ��Ă͂߂�Ɛ��E�S�̂̕������������悻16��������������ʂ��������Ƃ������ƂɂȂ�4�B1930�`31�N�̊Ԃɐ��E�S�̂ŕ�����30�����������킯�����A���̒P���Ȍv�Z���ʂɏ]���Ƃ��̂���(30���̂���)�̂��悻������FRB�ƃt�����X��s�ɂ����Z����ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�ƌ��_�t�����邱�ƂɂȂ낤(Sumner(1991)�͈قȂ�v�Z��@��ʂ��ē��l�̌��_�ɒB���Ă���)�B
��������f�t���X�p�C�����Ɍ����Ď��Ԃ������o���ƁA���̗v�����֗^���Ă��ĕ����̉����X�p�C�����Ɉ�w�̔��Ԃ������邱�ƂɂȂ�Ƃ����̂͊m���ł���B�Ⴆ�A�A�[���B���O�E�t�B�b�V���[(Irving Fisher)���w�E�����f�b�g�E�f�t��(���f�t��)�̃��J�j�Y����ʂ��Ĕj�Y�������A���̌��ʂƂ��ċ�s�̓|�Y�����������(��s��t�Ȃǂ�ʂ��ėa���̈����o���������錋��)�����a���䗦���㏸���邱�Ƃʼnݕ��搔���ቺ����\��������B�������Ȃ���A�����������o�����͓����̃f�t���V���b�N����Ɨ����Ĕ����������̂Ƃ͌��Ȃ������A����䂦���������̂����u�������ꂸ�Ɏc���Ă���v����5�ɂ��Ă����̈ꕔ��FRB�ƃt�����X��s���ԐړI�ɐӔC���Ă���ƌ����邾�낤�B
�܂Ƃ߂邱�Ƃɂ��悤�B����܂Ōo�ώj�Ƃ͑勰�Q�̈������ƂȂ��������Ƃ���1928�N�����ɃA�����J�Ŏ��{���ꂽ���Z�������߂ɒ��ڂ��Ă����B�������Ȃ���A���E�S�̂��f�t���X�p�C�����Ɋׂꂽ�����Ƃ������ƂŌ����ƃt�����X���ʂ����������ɂ�����܂ňȏ�ɂ����Ƒ傫�Ȓ��ڂ������Ă�����ׂ��Ȃ̂��B�@
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
�����{�̋��Q |
   �@
�@
|
| �����a���Q�̎��ԁA���̔����ߒ� |
�����a���Q�Ƃ�
���a���Q�́A1929�N�H�ɃA�����J���O���ŋN���A���E������������ł��������E���Q�̉e�������{�ɂ�����сA1930�N(���a5�N)���痂1931�N(���a6�N)�ɂ����ē��{�o�ς���@�I�ȏɊׂꂽ�A��O�̓��{�ɂ�����ł��[���ȋ��Q�B
���Ȃ����a���Q�����������̂�
���a���Q�̔����̌�����T��ƁA�u���{�ʐ��v�Ƃ����L�[���[�h�ɍs�������܂��B���{�ʐ��Ƃ́A�ۗL������̗ʂɂ���Ĕ��s����ʉݗʂ���������鐧�x�̂��Ƃ������܂��B���݂ł͂������A�ʉ݂̔��s�ʂ͒ʉݓ��ǂ��Ǘ�����Ǘ��ʉݐ��x�ɂȂ��Ă��܂��B�������A�����͋��{�ʐ��ł����B
��ꎟ���E���̖u���ɂ�萢�E�e���͐��E�e���͑��z�̌R���x�o���K�v�ƂȂ�A�e���͋��{�ʐ��̈ێ����ł����A�����Ԓ��ɋ����C�O�ɗA�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�����Ԓ��ɋ���A�o���邱�Ƃ��֎~���A���{�ʐ��͎������~����邱�ƂɂȂ�܂��B
�������A���̋��{�ʐ��̒�~�́A�����Ԓ��̈ꎞ�I�ȑ[�u�Ƃ����ʒu�Â��ŁA�₪�Ă͋��̗A�o���e�������ւ��A���{�ʐ��ɕ��A���Ă����܂��B
����A���{�͒����ł̌��v������֓���k�Ђ̕����̂��ߑ��z�̎x�o���K�v�ɂȂ�A���A�o�̉��ւɏo�x��Ă��܂��̂ł��B1928�N���_�ŁA��i���ł͓��{�݂̂������ւ��s���Ă��Ȃ��ł����B�e���͓��{�ɋ����ւ���悤�Ƀv���b�V���[�������Ă��܂��B
1929�N�ɕl���Y�K���t�������ւ̒f�s������̂��Ɣ������܂��B���̑�����㏀�V���͂��̂Ƃ��A�������A���Ȃ킿���{�����A�o�֎~����ȑO�̌������[�g�ŁA�����ւ��邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��܂��B���̓����̈בփ��[�g��100�~=46.5�h���O��ň�㑠���́A100�~=49.85�h���Ƃ������֗A�O�̋������ł̉��ւ������Ȃ������߁A�����I�ɂ͉~�̐�グ�ł����B
���́A�������ł̕��A�̂��߁A��㑠���͗\�Z5%�팸�A���������^10%�팸�A���Z�̈������߂Ȃǂ̃f�t��������s���܂��B�f�t���ɂȂ�Ɖ~�̉��l�����܂�A�~���ɂȂ邩��ł��B
�������A���̂悤�ȋُk�����̌��ʁA���{�o�ς͋����ւ��s����1930�N�ɂ͍�������������7%���������鋭��ȃf�t���Ɋׂ�܂����B�A�����J�ł̊�����\���[�Ƃ��鐢�E�勰�Q�������������A�~�������ڂɏo���̂ł��B�A�o�Y�Ƃ͉~���ɂ���s�U�ɁA���͑�ʂɊC�O�ɗ��o���܂����B�܂��A�s�s���ł͎��Ǝ҂����ӂ�A�_���ł͉쎀�҂��o����A���̐g���肪���s���Ă��܂����̂ł��B���ꂪ��O�ő�̋��Q�ł��鏺�a���Q�̎��Ԃł��B�@
�@ |
| �����a���Q |
   �@
�@
|
�����{�ʐ����߂��鏺�a���Q�̔����ߒ�
�� ���{�ʐ��̒�~
���{�ʐ��Ƃ́A�ۗL������̗ʂɂ���Ĕ��s����ʉݗʂ���������鐧�x�̂��ƁB��1�����E���̖u���ɂ���Đ��E�e���͑��z�̌R���x�o���K�v�ƂȂ�A�e���͋��{�ʐ��̈ێ����ł����A�����Ԓ��ɋ����C�O�ɗA�o���邱�Ƃ��֎~���A��������{�ʐ��͒�~���ꂽ
���������A���̋��{�ʐ��̒�~�́A�����Ԓ��̈ꎞ�I�ȑ[�u�Ƃ���A�₪�Ă͋��̗A�o�����ւ��A���{�ʐ��ɕ��A����Ƃ����̂����E�̒����������B
�� ���{�ʐ��ɕ��A�ł��Ȃ����{
���{�͒����ł̌��v������֓���k�Ђ̕����̂��ߑ��z�̎x�o���K�v�ƂȂ�A���Z�o�̉��ւɏo�x��Ă��܂���
��1928�N���_�ŁA�����ւ��s���Ă��Ȃ������̂͐�i�����œ��{�݂̂������B
�� �������ł̉��ւ�ڎw����㏀�V��
1929�N�ɐ��������_���Y�K���t�̌���͋����ւ̒f�s�������B���̑呠��b��㏀�V���́A�������A�܂���{�����A�o�֎~���s���ȑO�̌������[�g�ł̋����ւ�ڎw����
�������̌o�Ϗ�Ԃł́A�������ŕ��A���邽�߂ɂ́A�בփ��[�g���~�������ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ������B
�� ��㑠���̃f�t������
�������ł̕��A�̂��߁A��㑠���͗\�Z5%�팸�A���������^10%�팸�A���Z�̈������߂Ȃǂ̃f�t��������s����
�� ���s�������ُk����
�ُk�����̌��ʁA���{�o�ς͋����ւ��s����1930�N�ɂ͍�������������7%���������鋭��ȃf�t���Ɋׂ����B�A�o�Y�Ƃ͉~���ɂ���s�U�ɁA���͑�ʂɊC�O�ɗ��o�����B�܂��A�s�s���ł͎��Ǝ҂����ӂ�A�_���ł͉쎀�҂��o����A���̐g���肪���s����
�������́A�A�����J�ł̊�����\���[�Ƃ��鐢�E�勰�Q�ŁA�~�������ڂɏo���B
���̌�A1931�N12���Ɉ�㑠���͎��r���A���������̓o��ɂ����{�̌o�ϐ���͑傫���]�����邱�ƂɂȂ�B
|
���������������ɂ����{�o�ς̉�
�� ���������ɂ��o�ω�
����������1931�N�Ɉ�㏀�V���ɂ����A�呠��b�ɏA�C�B�����͂܂����̗A�o���Ăђ�~���A�R����̊g���������Ƃ̊g��A�����̈��������ȂǁA�ϋɓI�ȍ����x�o�g����s��
����㎞���15���~�ォ��20���~��܂ō��Ɨ\�Z�͑������B
�� ���������̍���
�������p������i�́A���̓��Ⓖ�ڈ����A���Ȃ킿����ɂ����s�����A����������Ƃ��ėp����
�������́A�u�����̋ύt�Ƃ͒P�N�x�ł͂Ȃ��A���̊��ԂŌ���K�v������v�Ǝ咣���A��㎞��ُ̋k�ŏk�������߂������Ȃ���Ȃ��ƍl�����B
�� ���������̃C���t����
���₪������������̍������������Ė��Ԋ�Ƃɔ��p���邱�Ƃɂ���āA�ʉ����̖��v��Ȗc����h����
�� ���������̐���
�����ɂ���Đϋɍ����ɓ]���Ă���̓��{�̃C���t������2%����6.5%�ł���A�u�n�C�p�[�C���t���v�Ƃ͂قlj��������B���{�o�ς͐��E�̐�i���̒��ōł������勰�Q���̃_���[�W�������
�� ���������̍Ō�u���Q���H���v
1935�N�ɂȂ�ƁA�o�ω��قڒB�����ꂽ�ȏ�A���̑����̓C���t���̍��i���������ƂɂȂ�ƍl���A�����́u���Q���H���v��ł��o���A�R������팸���悤�Ƃ����B�������A���̂��Ƃ����������ŁA2.26�����ŌR�̐N���Z�ɏP������A82�Ŗ��𗎂Ƃ���
|
����㏀�V�������Ɍ����鐴�Z��`�Ƃ́H
�� ���Z��`�Ƃ́H
�����������̌��ʁA������I�Ȋ�Ƃ�J���҂�ϋɓI�ɓ������邱�Ƃɂ���āA�������I�ŗD�ꂽ��ƁA�J���҂������c��A���̌��ʌo�ς����W����Ƃ����l����
�� �A�����J�勰�Q���̍��������A���h�����[�E������
�������́u�J���𐴎Z���悤�B�����𐴎Z���悤�B�s���Y�𐴎Z���悤�v�Ƃ������j�̂��ƁA�O��I�Ȑ��{�x�o�̍팸��f�s���A����ɂ���ĕs����f�s���悤�Ƃ����B�������A���Ɨ�����25%�AGDP����������
���O��I�Ȑ��{�x�o�̍팸�͈�㑠���̐���Ɠ����A�܂����Ɨ�������o�ϕs�U�����l�̂��ƁB
�� ���Z��`�ɂ�������v�Ƌ����̃o�����X
�܂��u��Ƃ�J���҂𓑑�����v�i�K�ł́A���v�Ƌ����͌�������B���̌�A���Y���ɗD�ꂽ�A��Ƃ�J���҂������c��B�������A�����c�������Y���ɗD�ꂽ���҂��������g�傷�邩�͕ʖ��B���̂Ƃ��̌o�ϏɈˑ�����B���Ƃ����҂ł����Ă��A����ɔ����l����v�������߂Ȃ��ł́A����Ⓤ���𑝂₷���Ƃ͓���B�ň��̃V�i���I�Ƃ��ẮA�u��҂̓����ɂ�鋟�����v�̌����v�݂̂��������A�o�ς��k�����������Ƃ������Ƃ����肦��
����㑠�����u��������ς������A���{�o�ς͗͋�����������v�Ƃ����M�O�������Ă��Ă����悤�ɁA���{�l�́u����������ς������Đ��������߂�v������D�ނ��A���E���Q�Ƃ������E�o�ς̏�Ԃŋُk�������s�������Ƃ����{�̋��Q��ł��܂����B�@
�@ |
| �����a���Z���Q |
   �@
�@
|
���{��1927�N(���a2�N)3�����甭�������o�ϋ��Q�ł���B�P�ɋ��Z���Q(����䂤���傤����)�ƌĂ�邱�Ƃ�����B���Z���Q�͖{���͒��ۓI�Ɍo�ϓI���ۂ��w�����t�����A���{�ɂ����Ă͓��ɒf��Ȃ��ꍇ�͂���1927�N(���a2�N)�̌o�ϋ��Q���w�����Ƃ������B���a���Q�Ƃ͓��`�ł͂Ȃ�(��q)�B
���{�o�ς͑�ꎟ���E��펞�̍D��(���i�C)�����]����1920�N�ɐ��s���Ɋׂ��Ċ�Ƃ��s�͕s�Ǎ���������B�܂��A1923�N�ɔ��������֓���k�Ђ̏����̂��߂̐k�Ў�`���c��ȕs�Ǎ��Ɖ����Ă����B����ŁA�����̋�s�͐܂���̕s�����Čo�c��Ԃ��������A�Љ�S�ʂɋ��Z�s���������Ă����B1927�N3��14���̏O�c�@�\�Z�ψ���̒��ł̕Љ����������́u�����v�����������Ƃ��ċ��Z�s�����\�ʉ����A������s�𒆐S�Ƃ��Ď��t�����������������B��U�͎���������̂�4���ɗ�؏��X���|�Y���A���̐��������p��s���x�Ƃɒǂ����܂ꂽ���Ƃ�����Z�s�����ĔR�����B����ɑ��č������������͕Жʈ����200�~����Վ��ɑ������Č����̋����Ɏ��s�����A��s�������X���ɐςݏグ��Ȃǂ��ĕs���̉����ɓw�߁A���Z�s���͎��܂����B
���a���Z���Q�́A��N�N�������a�_�Ƌ��Q(1929�N�̐��E���Q�̉e�����Ď�ɔ_�ƂɌo�ϓI�Ō�����)�ƍ��킹�ď��a���Q�ƌ����邱�Ƃ�����B
|
|
���w�i
|
|
���a���Z���Q�̌����Ƃ��āA���n�ȋ��Z�V�X�e���ƁA�o�ϓI��@�ɐ������Ώ������Ȃ��������n�Ȑ���������B
|
������
���Z�V�X�e���̐��������S�ł͂Ȃ��������Ƃ��甭�������s�Ǎ��̏������K�ɂȂ��ꂸ�A���Z�s�����N�����Ɏ������B�吳�����炱���V�X�e���̕s���͔F������Ă������A�[���Ȏ蓖�Ă��Ȃ����O�ɋ��Q�����������B
����s
�����ېV���ɐݗ����ꂽ��s�̒��ɂ́A��\���v�ɂ�������Z����(���\���E���\����)�����{���Ƃ��Đݗ����ꂽ���̂������������B�ݗ��̈Ӑ}���������v�ɉ�����o�ϓI���R�ɂ�炸���̎������@�Ƃ����A����Ȃ�䂫�ł��������߂ɋ��Z�̎���ɕs�ē��Ȏ҂���s�o�c�ɓ����邱�Ƃ����������Ǝw�E����Ă���B�܂��A���{�������ۂɕ������܂�Ă��Ȃ����̂����������Ƃ����B
���I�푈��ɂ͌o�ς����B���A����ɉ����邽�߂ɋ�s�̐ݗ����������ꂽ�B1890�N(����23�N)�ɉ������ꂽ��s���ł́A��s�Ƃ͈�ʂ̎���ƂƂ݂Ȃ��ꎑ�{���z�̐������P�p����A�K���������邢���̂ł������B���̎����A���Y�Ƃ���s��ݗ����邱�Ƃ�A�����ɗ]�T�̂��鎄��Ƃ���s�Ƃ����Ƃ��邱�Ƃ��s��ꂽ�B�܂��A����̊�Ƃւ̗Z���z�𐧌�����K���������P�p����A�Z���悪�����������B
�����Ƃƌ��т��̋�����s���w���đ��ɋ@��s�Ƃ����B���Y�Ƃ��L�x�Ȏ���������ɐݗ�������A����Ƃ̌��ƂŐݗ�������s�ŁA�W�߂��a��������Ƃ̋Ɩ����s�ɏ[�āA�オ�������v�ŗ����x������d���B���������̊�ƂɏW�����ėZ�����邱�Ƃ���A���̊�Ƃ̋Ɛт����������ꍇ�ɂ͒��ڋ�s�o�c�����e���������ނ�B�܂��A�ݏo���Ƃ̕s�����Ȍo���̉e����ւ��Čo�c���������邱�Ƃ������������B
�܂��A���B�̋�s�����֏��Ɏn�܂�Y�Ƃ̔��W�ɔ������Z�@�\�̗v���ɉ����ċ�s�Ƃ����B���Ă������̂ɑ��A���{�ł͊C�O�̋��Z�V�X�e�������f���Ƃ��Đ�ɋ�s���ݗ����ꂽ�Ƃ��납��A�����͋��Z�̎��v�����Ȃ���s���g�����Ƃ������Ď��v�����o���X���ɂ������B���������̊�Ƃ֑݂��o������v���ƂȂ����B
�������n�Ӌ�s
���\��������s�Ƃ��Đݗ�����A��\����s���o��1920�N�ɓ����n�Ӌ�s�Ɖ��̂����B�o�c�҈ꑰ�̊֘A��Ƃɑ��z�̑ݕt���s���@��s�Ƃ��Ă̐��i�������������A�����̗Z�������s���ŏł��t���֓���k�Ќ�Ɍo�c�����������B
����p��s
1895�N�̑�p������ɓ��{���{�̍���Őݗ�����A�������s�����������s�ł������B��p�ɂ�����Y�Ƃ̈琬�Ɏ�����Ƃ��납��n�܂������A���]�̎������ė�؏��X�ƊW��[�߂��B���̍�����������������嗤�ւ̗Z�����k�����V���ȗZ������J�Ă����Ƃ���ł�����A��؏��X�ւ̗Z���𑫂�����Ƃ��ē��n(���{�{�y)�ɂ��o�c���L�����B�����ɗZ���z���c��݁A�@��s�Ƃ��Ă̐��i�����߂��B�������A���s���ŗ�؏��X�̌o�c����������Ƒ��z�̗Z�����ł��t���A�ǂ��݂����s���悤�ɂȂ����B���̌�A���q���g���؏��X�̌o�c����r�����A�Z�����k������ׂ���������s�ɏI����Ă���B�Ȃ��A��p��s�͂����Όo�c��@�ɕm���s�x����̓��Z��呠�ȗa��������̗Z�������ł����B1920�N��ɓ���Ǝؓ����ւ̈ˑ��x�������A���Z�E�a�����̗Z���ɉ����A�R�[���s��̗Z�ʋ��ɂ��傫���ˋ�����悤�ɂȂ��Ă����B
���Y�ƍ\��
�B�Y���ƍ�̉��ɎY�ƐU�����傢�Ɋ��߂�ꂽ���A�吳���Ɏ����Ă����{�o�ς͂��̑������Ȃǂ̌y�H�Ƃɕ������B���S�③�D�Ȃǂ̏d�H�Ƃ��u��������A��ꎟ���E��풆�ɂ͉��B��i���̎Y�Ƃ��������̂��ւ���܂łɎ����������i�̎��ł͖����Ɉ������A���B���������ɎY�Ƃ�����ƃA�W�A�Ɋl�������s���D�ꂽ�B����͐��̑唽��(1920�N)�̈���ƂȂ�B
1874�N�ɊJ�Ƃ�����؏��X��1899�N�ɑ�p�̏��]�̔̔������l�����A���̍ۂɌ㓡�V���ƊW��[�ߐ��E�ɂ��ڋ߂����B��ꎟ���E�����ɂ͊C�O�d�����g���Đ푈�̒�������\�����A����ɔ����Ċ�Ɣ����Ⓤ�@���s������ȗ��v���グ���B�Ɩ��ɕK�v�Ȏ����͋�s�A���ɑ�p��s����̒Z���I�ȗZ���𒆐S�Ƃ��Ęd�����B�����ɂ�鎑���l���ł͊���̈ӌ���r���ł��Ȃ����Ƃ����������q���g�̕��j�ƌ����邪�A���ꂪ�o�c��@�ɂ����đ����Ɏ�����Ɋׂ�������ł���Ƃ�����B
�܂����q���g�̐����Ƃ��āA�o�c�g��ɂ͎�r���������s�̎Z�Ȏ��Ƃ���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������Ƃ�����B����ŁA�o�c�g��͓��{�̎Y�Ɣ��W���肤���q�̈Ӑ}�ɏo�����̂Ƃ�������B
|
���߈�
����ꎟ���E���
1914〜1918�N�ɐ��ꂽ��ꎟ���E���ɂ����ē��{�̎Q��͌���I�ł���A���ڂ̔�Q��Ƃꂽ�B����œ������E�̐��Y�̒��S�ł��������[���b�p�����ƂȂ萶�Y��A�o���������݁A���O�̊e�������E�̎��v��S�����ƂƂȂ����B�����ɐ푈�ɋ����镨���E����̎��v�����܂�A���{����͑D���̋����A�C�^�Ɩ��𒆐S�Ƃ��镨���E�T�[�r�X�����ꂽ�B���̉e���ł�����u�D�����v�����܂��ȂǓ��{�o�ς͍D����悵���B���̂Ƃ��A�����ȗ������ł��������̂������ɓ]���A���݂��傢�ɒ~�ς��ꂽ�B
�푈���I�����A�푈�������I���Ɣ����ŕs���ɂȂ邱�Ƃ��뜜���ꂽ�B���{�ɂ����Ă͓����푈����I�푈�̌�̔����s���̌o��������\���x�����ꂽ���Ƃ���d�Ăȕs���Ɋׂ炸�A���悻��㔼�N�Ŕ����s������E�����B�܂��A���B�ł͐��̕����̂��߂̎��v��������A����Ɍ����ėA�o���s��ꂽ���A��͂��ЂڎȂ������č��̌i�C�͍D���ŁA��������܂��Či�C�͊g�債(���u�[��)�N�ƁE���Y�ɂނ��Ă̓���������ɍs��ꂽ���A���̓��e�͂₪�ē��@�ւƕώ����A��풆�̍D���Ŏ�����~������s���ϋɓI�ɑ݂��o�����s���Ă�����x�����B���̎��ɂ͊����E�n�����㏸�����B
1920�N�ɓ���ƌo�ςɕϒ��𗈂���3��15���ɓ����̊����s�ꂪ�\���������A4���ɂ͑��̑��c�r���E�u���[�J�[��s���j�]���A�o�ϓI�������犔���s��E���i�s�ꂪ�b�����ɒǂ����܂�鎖�ԂƂȂ����B���B�ł̐��Y������Ɠ��{�̗A�o���������݁A�܂�7���ɂ͕č��̌i�C����ފ��ɓ��������Ƃ����炩�ƂȂ�A�D����O��Ɏ��Ƃ��g�債�Ă�����Ƃ͈�]���ĕs�Ǎ��������(1920�N�̑唽��)�B�g��H�����Ƃ��Ă�����؏��X������ȕs�Ǎ����������Ƃ̈�ł���B
�U��Ԃ���̕s���͏d�Ăł��������A�����͌i�C�z�̒��̂���ӂꂽ���Z�b�V�����ł���ƌ����s�Ǎ����������鍪�{�I�ȑ��ӂ����̂������̎��s�ƍl�����Ă���B
���֓���k��
1923�N�ɔ��������֓���k�Ђœ����E�_�ސ�Ŕ�Q������Ƃ��U��o���Ă�����`�ɂ��Ă͌��ϕs�\�ƂȂ邱�Ƃ��뜜����A�����Ƀ����g���A���߂��o����A�����ē��₪��`�̍Ċ������s��(�k�Ў�`)�A���ύ���Ȏ�`�ɗ�������t�^���邱�ƂŌo�ϊ����̒��h���ׂ��Ή��������(������Z)�B�������A�������܂ꂽ�����̎�`�̒�����k�Ў�`�Ƃ��ăX�^���v���������̂�I�ʂ����ʂɂ����āA�^�ɐk�Ђ̔�Q���ē����̎x�����ɍ����������͓̂����ɐ��Y��i��S�ۂƂȂ鎑�Y���r�����Ă��邱�Ƃ��������X�N���傫���Ƃ��Čh�����ꂽ�B����Ŕ�Ђ̒��x���y�����S�ȕ������D�悳�ꂽ�ق��A�܂���̕s���Ⓤ�@�̎��s�ŕs�Ǎ��ƂȂ�����`�͈ꉞ�̒S�ۂ��m�ۂ���Ă��邱�Ƃ�����S�ȕ����Ƃ݂Ȃ���A�������Ċ����̑ΏۂƂ��Ď���邱�Ƃ��������Ǝw�E����Ă���B���̉ߒ��Œ��ڐk�ЂɊW�Ȃ���`���������ꍞ�ރ������n�U�[�h���������A���s���ɋN������s�Ǎ������{�I�ȉ��������邱�ƂȂ��c��Â����B
�܂��A�k�Ђ���̕����ɍۂ��ĊC�O����̕����A�������債�בւʼn~�̉����������Ƌ��ɍɂ��ؗ����A���ꂪ�����̐��Y���������ĕs���ɗւ��������B
�Ȃ��A�k�Ў�`�ɂ��~�ύ�̎��{�ɂ́A��؏��X�̋��q�̓����������������Ƃ�������������A������Z���p��s�̖����ώ�`�̌����߂ɗ��p����Ӑ}�ł������ƌ�����B�܂��A���{����������m�ŗ��p��ٔF���Ă����Ƃ�������B
�k�Ў�`�Ƃ��čĊ���������`�̎x��������2�N�Ƃ��ꂽ���A���̓��e�͑O�q�̂悤�ɔ�r�I���S�Ȃ��̂ƁA��ӂ͈��S���Ă��邪���ۂɂ͓��@�̎��s�ł��͂����̌����݂̂Ȃ������Ȃ��̂Ƃ��������B1924�N3���̎�t�����܂łɓ��₪�����������`�͐��{�⏞�z�ł���1���~����4��3�疜�~�ɒB�������̂́A�ŏ��̐������͗\�z�����������ς��i�B���������X�Ɍ��ς���悤�ɂȂ�A�P�\�������������鍠�ɂ͌��ς̐i�W���قƂ�nj����Ȃ��܂ܓ��@�Ŏ��s�����s�ǂȕ����𒆐S��2���~�������Ŏc��A���Z�̕s����v���ƂȂ�u���E�̊��v�Ƃ��Ăꂽ���A��ނȂ��x������1�N������2��J��Ԃ�1927�N9���܂ŗP�\�����B
�����{�ʐ��ƈב֕ϓ�
19���I��������{�ʐ��ɂ����Ց̐����m��������A���{�������푈�̔������Ƃ��ē��������������ɏ[�Ă�1897�N�ɉݕ��@���{�s���A��������0.75mg=1�~(100�~=49.875�h��)�ƒ�߂Ė{�i�I���{�ʐ����m�������B�Ȍ�20�N�͕����E�בւ��ێ����ꂽ�B
��ꎟ��풆���n�܂�Ɖ��B�e���͑��X�Ƌ��{�ʐ����~���A1917�N�ɕč����������̈ꎞ��~�\�����̂ɒǐ����ē��{����������������~���A���ɋ��{�ʐ��֕��A(������)����@����M�����B�������A���̑唽���̌o�ύ����̒��ł��̋@������o�����A�֓���k�Ђ̌�̗A�����߂��āA����܂ŊT�˕���(100�~=49.875�h��)���ێ����Ă������̂�1924�N���ɂ�40�h�������荞�ނ܂łɂȂ����B���{�͍��E�̐���(���ۋD�D�E���N��s�E��p��s�̐���)���s���A�o�Ϗ����P���邱�ƂŎ��R�Ɉבւ������ɖ߂�悤�Ɋ�}�������A������ǂ݂������@�ɂ��1925�N���ɂ�49�h���ߕӂ܂ŋ}�����A�Ȍ㗐���������B
���ܑ卑�̈�ɐ�������悤�ɂȂ����Ƃ͂����܂����{�̌o�ς͏��K�͂ł���A�[�����~�����̗��t���̂Ȃ��ʉ݁u�~�v�͔����Z���i�Ƃ��ē��@�̑ΏۂƂ��ꂽ�B���̂悤�Ɉבւ��s����ŁA���@�̎v�f�ŗ��������邱�Ƃ͌o�ςɂƂ��čD�܂������̂ł͂Ȃ��A���ՋƂ���Z�Ƃ𒆐S�Ƃ��Čo�ϊE����בւ̈���̂��߂ɋ����ւ��s�����Ƃ����߂�ꂽ�B�܂��A���O���͐��ɑ��X�Ƌ��{�ʐ��ɕ��A���A1922�N4������5���ɂ����ĊJ���ꂽ�W�F�m�A��c�Ő��̉ݕ��o�ςɂ��ĂȂ��ꂽ�c�_�̒��œ��{�ɑ��Ă����{�ʐ��ւ̕��A�����߂�ꂽ�B
����ŋ����ւ̂��߂ɂ�1920�N���̕s�Ǎ��A�����Đk�Ў�`�����{�I�ɐ����E�������邱�Ƃ��O��ƂȂ�A���̏������傫�ȉۑ�Ƃ��Ă�����ꂽ�B���邢�͋����ւ����s����Ί�Ƃ̌o�c�̎�������邱�ƂƂȂ�A�s���S�Ȋ�Ƃ͎��R�ɓ������ꎩ���ƕs�Ǎ��͉�������Ƃ̌�����������(���Z��`)�B
�Ȃ��A���{�ʐ��ɕ��A����ɂ�����A����̌o�Ϗɉ��������[�g(�V����)�ŕ��A������������A�Ⴆ�t�����X�͒ʉ݂�1/5�ɐ艺���A�h�C�c�A�C�^���A��������ύX�����B���{�ł��֓���k�Ќ�̉~�����̍��Ɉꉞ�̈בֈ�������Čo�Ϗɉ������V����(100�~=40�h���O��)�ŕ��A���ׂ��Ƃ̈ӌ����������B�������A1919�N�ɂ����������A�����č���A���E�̋��Z�̒��S�ł������p����1925�N�ɕ��A�����ۂɂ́A��O�̕������ێ����Ă���A���̒��ɂ����Ă悤�₭�ɖ���A�˂�Ɏ��������{���~��艺����͍̂��͂̒ቺ�������ɂ�����̂ł��荑�Ƃ̈АM�Ȃ��u���J�v�ł���Ƃ�����������A������(��49.875�h��)�ł̕��A��]�ވӌ����吨���߂��B�܂��A�����͖@���ŋK�肳��Ă���Ƃ���ŁA���ɊO���E���Ղ��d���������ւɐϋɓI�Ȍ�����\���ȓ}���̂Ȃ��܂܂ɖ@�����ɗՂ߂c���̍����������\��������ύX�͗e�Ղł͂Ȃ��Ƃ݂Ȃ���Ă����B���Nj������ł̕��A���u�����Ĉב�������������̒���������̒����ňבւ�U��������A�����������t���_���Y�K�������ُk�������Ƃ�Ȃnjo�ϐ�����o�ĊԐړI�ɗU�����鐭�Ƃ�ꂽ�B�������A�ُk�������̂��A�܂��~�����ێ����ꂽ���Ƃ���A�o���U��킸�A���������������{�����̌i�C�͈��������B
�����E
�吳�������ɂ͌�����Ɨ������F��̓�吭�}������A�̂��ɐ��������v�V��y���������Č쌛�O�h�ƌ���ꂽ�B1922�N�ɗ������F��̍����������v�悵�����t�����̓��e�������ē����ŕ������A�����l����D�悷�鏰���|��Y�炪1924�N�ɐ����������Y���t���x�����āA�������F���E�}���Đ��F�{�}���������Ă��B���̂Ƃ����F�{�}�͍ő����ƂȂ��đ��}�ƂȂ������A���R���t���x���������Ƃ���1924�N�̑��I���Ŕs�k���ċc�Ȃ����炵�A����ŗ������F��͐�����Ԃ����B���Y���t���|��Č쌛�O�h�������������t�𗧂Ă���A������Ɨ������F��̑Η��A�������F��Ɗv�V��y���̍����ɂ���Č쌛�O�h����̂����1925�N8���Ɍ�����P�Ɠ��t�ƂȂ�ƁA���F��Ɛ��F�{�}�̊ԂŘa���̓���������A����1926�N�Ă̖p�����@�ɂ��̌X���ɔ��Ԃ����������B���N���ɂ͌㓡�V���̈����ŗ������F��Ɛ��F�{�}�̒�g����������(���{��g)���A1927�N2���Ɉ�]�A�������F��̐����l���j�~��}���Č�����Ɛ��F�{�}�̒�g(���{��g)���閧���ɐ���A�������F��͌Ǘ������B
������ɂ͎O�H�o�g�̎҂��Q�����A����ŗ������F��͎O��Ɖ����[���O������̏o�g�҂��Q�����Ă����B���̓_����A���ɗ������F��k�Њ֘A��@���U�����邱�Ƃɂ��ĎO��Ƌ��������؏��X�������I�ɋ~�ς���@���j�~��_�����Ƃ��錩��������B�܂��A�k�Ў�`�̎��Ԃ���؏��X���݂ł���Ɣc���������E�W�҂��^�}��������U������ޗ��Ƃ��ė������F��ɏ��𗬂����Ƃ�������������B
������Ɨ������F��͋��Ɍ쌛�h�ł���A���̑��̐��}�̂��̂Ɣ�r������̐���E�咣�͑������Ă����B��쌛�^���ŕ��ʑI�����������A�܂����Y���t��œ|����܂ł͈�v���ċ��͂������A���̖ړI���B������Ƒ傫�Ș_�_�������A�����������l���̂��߂ɂ͎��}�̎咣�藧�ĂĎx�����W�߂˂Ȃ炸�A�͂��ȍ��ق�傫�����グ�p���đΗ������Ƃ�����B
�܂��A�����͐��}�����ɂ����錛���̏퓹�Ƃ��āu���t�������ɂ���ē|�ꂽ���́A���ɖ�}���}�����t��S������v������オ���K�Ƃ��čs���Ă����B��������A��}�ɗ��������͌��݂̗^�}�̎�����˂���������ǂ����Ƃ��āA���̐������l�����邱�Ƃ@�̈�Ƃ��ė^�}���U�����邱�Ƃ��s��ꂽ�B
�����������ŁA���}�̊Ԃ̐���̍��ق������ƂȂ����B������͉����Ȃ��������O�𐭍�����A�o�ϓI�ɂ��C�O�Ƃ̌��Ղ��d�������B���̊�{�ƂȂ���{�ʐ��ւ̕��A(������)��ڎw���A������������邽�߂ɋُk�������u�������B����̗������F��͐ϋɊO�𐭍�����A�������k���̌��v����邽�߂ɌR���\�Z�̑����𒆐S�Ƃ����ϋɍ������u�������B�܂��A�R����m�ۂ̂��߂Ɏ؊����s���K�v��������ւɂ͔��̗����������B
����ɁA1925�N�A�c���`�ꂪ���R���琭�E�ɓ]�����F��قɌ}�����A�c���ɋ߂���؊�O�Y��v���[�V���Ȃǂ����}�������A�ނ�͐e�R�h�E������`�҂ɋ߂��A�쌛�h�ɑ��锽��������Ă����B���ق̌������������F��ɂ����ēc���Ƃ��̎��ӂ��}�̎���������悤�ɂȂ�ƁA�}���̗v�E�͏��X�Ɍ쌛�h����e�R�h�Ɏ���đ�����悤�ɂȂ��Ă������B
���R�k
�鍑�C�R�͂��˂Ă���͊͂̑����ƍX�V��}�邢���锪���͑��v��𐄐i���Ă���A��풆�ɍŏ��̒i�K�ł��锪�l�͑��Ẳ��Ŏ�͊͒���E�����E����E�y���E�V��E�ԏ�����Ē߂��͂��߂Ƃ���͒��̌������J�n���Ă����B���������D�i�C��������1920�N�Ɂu���h���v���͑�ꎟ�����v�̗\�Z���������A�����͑��̎����Ɍ����Ēlj��̐�́A���m��͂𒆐S�Ƃ����K�͂Ȋ͒������ɒ��肵���B��؏��X�����v�ׂ̍������ԑD�����猚�͎��v�g�傪�����܂��R����̎���o�c�̎������ڂ��Ă������A����ɑ唽���Ɍ�����ꂽ�B��͂�i�C�̌�ނ����č��ł��s���̒��Ŋg�傷��R���\�Z�Ƒ����A���ł����{�̌R�g���莋���ĕč��哝�̃E�H�����E�n�[�f�B���O���R�k��c����A�����̕��S�ɂ��������B���������Q������1921�N��胏�V���g����c���J�Â��ꂽ�B�����ŌR�͂ۗ̕L�E�V���𐧌�����R�k�����A���̎�茈�߂ɉ����Ē鍑�C�R�̐��ʑ������팸����邱�ƂƂȂ�A���ɑ��D����ł͐V���̎��v�����������B����ɑ����{����͑��D��Ƃɑ��Ĉ��̕⏞�����x����ꂽ���A�C�R���ł����z�̎�����s���Ă�����؏��X�͎���z�������ă_���[�W�������B�܂��A��؏��X�P���̐_�ː��|��W�̐[����葢�D�������炵�ċƐт����������B
|
�����O�̏�
1924�N6���Ɍ쌛�O�h�A�����t�Ƃ��ĉ����������t�������������A1925�N8���Ɍ�����P�Ɠ��t�ƂȂ���(�������2���������t)�B���̓��t�͋����ւ��w�����A���������̋}���������ė�1926�N1���ɐ���������Γ��t�����̕��j�������p�����B���̎�������͏����^�}�ł���A�c��^�c�ɍ���\�z���ꂽ�����猻��ŊJ�ׂ̈ɑ��I���ɑł��ďo�鎖�����߂�ӌ����}�����炠����A��ɑ喽���~��������悤���v���������������������҂����B������͑I�����a�茋�Ǐ����^�}�̂܂܂ŋc��^�c�ɓ����邱�ƂƂȂ����B
1926�N�̑�51��鍑�c��ɂ��Ă͐��F�{�}�̋��͂ď��������A�Ă���H�ɂ����Ėp���A�����ď����V�s�^���̑������N�����B�p���ł͗\�R���̒j����^�҂����������ʐ^�����J���ꐢ�_�����R�ƂȂ�A�i�@��b�]�ؗ����\���ɂ���ĉ����𓊂������鎖�����������B�i�@���ǂ̔\�͂Ђ��Ă͐��{�̓����\�͂ɋ^�`�������߂邱�ƂŎ�Γ��t�]����}�����k��P��̉A�d�ɂ��Ƃ�����B����A�����V�s�����ł́A�V�s�̈ړ]�������ĕs���Y�Ǝ҂��琭���Ƃɉ^����n���ꂽ�Ƃ����^�f�������オ��A����X���Y�����E�̑�����b�ł���Ȃ���\���R����A�܂��U�؍߂ō��������ȂǁA�O�㖢���̎��ԂƂȂ����B�����͑�52��鍑�c��`���Ŗ�}�����{���U����������ƂȂ����B
1925�N9���ɑ呠��b�ƂȂ����Љ������͑��������֘_�҂ł���A���˂Ă����ƂȂ��Ă�����s�@�����A�s�Ǎ��̉����A�����Ă��̑������������p��s�̐������s���ċ����ւ̏����𐮂���ׂ��ӗ~�I�Ɏ��g�B��̓I�ɂ�1927�N�č��̋����ւ���}���Ă����Ƃ̂��ɏ،����Ă���B�s�Ǎ������{�I�ɏ�������k�Ў�`�W��@��鍑�c��ɏ������ɍۂ��Ă��炩���ߖ�}�������F��̓c���`�ꑍ�قƔ閧���Ɍ����A���͂��Ƃ����Ȃǒ��ӂ��Ă����B�������A�c���͗������F��������ł͂Ȃ��A�܂����R���琭�E�ɓ]���Ă܂��Ȃ��}���̗L�͎҂��܂Ƃ߂���Ȃ������B
�呠�Ȃ́A��s�@�̉����̏������s���Ă����B�܂��A�o�c�̊낤����s���������ׂ��o�c�҂ɒ�����s���Ă����B�����n�Ӌ�s�����̈�ŁA������4�s�����������ĐV��s�ɕҐ����Ȃ������Ƃ��v�悳��Ă����B���̉ߒ��œ����n�Ӌ�s�̓�������l���呠�Ȃ͔c�����Ă���A3��14���ɐꖱ���o���������Ƃɂ��āA�\�f��^�����Ƃ�������B
���{�o�ς�1920�N�̑唽�����瑱�������I�ȕs�����甲���o���Ȃ��ł����B�J�Ԃł�1920�N�A1922�N�A1923�N�ɂ����t���������N����ȂNj��Z�s���������Ă���A���̒��ɂ����Ă��k�Ў�`�̗��s�Ǎ��̑��݂��s��������Ă����B
�����嗤�ł́A1926�N7������Ӊ�������鍑���}�ɂ��k�����s���A���{�����v�������Ă������B����������������B����ɑ��^�}������̎�Γ��t�͉�����������A�ڗ������Ή������Ȃ������B����͐����@�̔������A�̂��Ɏ�Γ��t�����ߔ��z���������ۂɋ��₷�錴���̈�ƂȂ�B
|
|
����52��鍑�c��
|
1926�N12��24���ɏ��W����A��25���ɑ吳�V�c�����䂵�A�c���q�T�m�e�����H�N���ď��a�ɉ��������B
�c���26���ɊJ��A�����ď��a2�N(1927�N)�ɔN�����܂������A���E�ł͖p���Ȃ�тɏ����V�s���������荬���������Ă����B
����A�o�ϏƂ��Ă͉~���E���������̕s�����ɂ���A�܂��A1920�N�̑唽�����ɐ������s�Ǎ����k�Ў�`�Ɏp��ς��āA�Ȃ��������Ԃ葱���Ă����B�����ɁA�k�Ў�`���{���̋@�\���ʂ��������͓��萭���̋~�ρE�����ɗp�����Ă���ƌ����������͔ᔻ������A��������e���Ă������{�ɑ��Ă��ᔻ���������B���Ƃɗ�؏��X�̕����o�c�֑����݂��t�������̂��ł��t������p��s�������̐k�Ў�`������Ă���Ƃ̉������Ȃ�����̖ڂ��������A���ɂ����l�ɐk�Ў�`���������s�̌o�c����Ԃ܂�Ă����B
���{�͂����̐k�Ў�`�̏������}���A�����̋����ւ�����������j���Ƃ����B�������A���{��ᔻ���闧�����F��͖p���Ȃ�тɏ����V�s�����̔��炵�Ď�Γ��t�e�N��t�Ă��o���Ό��p���𖾂炩�ɂ����B
��Ύ͗������F��ٓc���`��Ɛ��F�{�}���ُ����|��Y��ҍ��ɏ����A�V��H�N�̐܂ł����萭���͔�����ׂ��Ɛ����A�Âɕ��̑ސw�������Ƃ��č���̋c��^�c�ɂ��ċ��͂����t����(�O�}���k)�B
�����āA�Љ����c���ɒ��k�����ċ��͂����t����ȂǏ����𐮂�����ŁA1��26���ɁA����9��30���������ƂȂ�k�Ў�`��S�z�������邽�߂ɍ��s���A10�N�����ď��҂���k�Ў�`�W��@���c��ɏ�������B�����͗������F����ӂɉ����ē��t�e�N��t�Ă�P�������ŐR�c�ɉ��������Ƃ���A�@�Ă�3��4���ɏO�c�@�ʼn����������ċM���@�ɑ��t���ꂽ�B
�������̗��ł́A�O�}���k�Ŏ���ƒf�Ő��G�ƑË����A���܂����T��������Ƃ������v��Ȃ�������̗L�u�����S�ƂȂ��Đ����ێ���}��A���F�{�}�ɐڋ߂���2��26���ɒ�g���Ȃ���(���{��g�A�܂��͌��{�A���A���{�����Ƃ�)�B�������Ď�����̐V�}�ƂȂ��Ď��̑g�t�̑喽���邱�Ƃ���}���A���ɂ��ꂪ���Ȃ�Ȃ��܂ł����F�{�}�����������悤�ɐ}��A�������F��������ڂ邱�Ƃ�j�~���邽�߂ł������B���R�閧��ۂׂ����̂ł��������A��������̕s���ӂ��炱�̒�g�̑��݂��I�悵���B
|
|
���O���̋��Q
|
3���n�߂Ɍ��{��g���\�I����A���̖ړI�������ێ��ɂ���Ƃ킩��ƁA�������F��͑ԓx���d���������B�c���͐l����ĕЉ��ɈȌ�̋��͂��o���Ȃ��|��`���A���ɓ��t�e�N��t�Ă���艺���Ă���A���߂Ē�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ���A����Ȍ㗧�����F��͐k�Ў�`�W��@�𐭑��̋�Ƃ��čU���ɂ܂�����B���̎��A��̓I�ɐk�Ў�`�̓����c�����A���̏��𗬂��čU���ޗ�������͍̂��E�ł���Ƃ�����B
������͓����k�Ў�`�W��@�̖ړI�������܂ł����Z�̈��S��}�邽�߂Ɛ����������A�������F��͂��˂Ă���k�Ў�`�Ɋւ�������Z�������I�ɂ͓���̐����̋~�ύ�Ƃ��ėp�����Ă���Ƃ����^�f���w�E���A������u�����̖����v�ƍU�����ĕs�Ǎ��̋�̓I���e�Ƌ��z���������Ƃ�v�������B�����āA�{�@�Ă̖ړI�̎��ۂ���؏��X�ւ̑��z�݂̑��o�����ł��t��������p��s�̋~�ςɂ���A�Ђ��Ă͗�؏��X���������邱�Ƃɂ���|�𖾂炩�ɂ���悤�ɔ������B
�����̖@�Đ�����ڎw���^�}������͐k�Ў�`�̓���ɂ��ď��������炩�ɂ��A�̂��ɂ͋M���@�ɂ����Ĕ閧���k����J���ċ�̓I�ȓ��e�Ɩ@�Ă̐^�ӂ��}���ɓ`���Ė@�Đ����ւ̋��͂����߂����A���̓���@�ւɓ`��荑���̒m��Ƃ���ƂȂ����B���˂Ă���k�Ў�`�̓��e�ɂ��đ�p��s�������̐k�Ў�`�������ƁA�����đ�p��s�Ɨ�؏��X�̖����Ԃ肪�J�Ԃł��\����Ă������A���ꂪ�^���ƕ�����A����̓I�ȕs�ǎ�`�̊z�Ƃ��Đk�Ў�`2���~���̂�����p��s����1���~�ŁA����7�����؏��X�֘A�̂��̂���߂Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�o�ϓI��@����w�̐^�����������Ď���A�~���ɂ��i�C����Ƒ��܂��ĕs���͈�w�������B
���Љ������̎���
3��14���A�O�c�@�\�Z�ψ���ɂĐR�c�̎n�܂钼�O�A�����̌��ς̂��߂̎����J��ɍ���ʂĂ������n�Ӌ�s�̓n�ӘZ�Y�ꖱ�炪�ߌ�1�������ɑ呠�����̓c��(�ł� ������)�ɒ�A�u���炩�̋~�ς̎蓖�Ă��Ȃ���Ȃ���Ζ{���ɂ��x�Ƃ\������Ȃ��v�Ɛ��������B�c�͑Ή���Љ������ɑ��k���ׂ��c��ɕ��������R�c���Œ��ډ���A��������ʂɂ������߂ĕЉ������Ɍ��t�����B�Ȃ��A�n�Ӑꖱ�͋~�ς����߂�Ӑ}�Œ�����A�呠�Ȃ̑��ł͏]�O�̒����œ����������c�����Ă���A�x�Ƃ̕ɗ������̂Ɨ������Ă����Ƃ����B���ۂɓc�͗\�Z�ψ���R�c���Ɍ������ɍۂ��Č��M������������n�Ӑꖱ�ɏЉ�u��s�x�Ƃ̑P���v�ɂ��葱�����𑊒k����l�Ɏw�����Ă���B
����œ����n�Ӌ�s�͑呠�Ȃ���̏��͂錩���݂������Ȃ������̂ʼn��߂ċ���ɑ���A��S��s���玑�����蓖�Ă��邱�Ƃɐ������ē����̌��ς��ɍς܂����B���̎|��呠�Ȃɂ��d�b�œ`���A�������̒m�点�������A�c�͊��ɋc��ɕ����Ă���A�����ɂ͓`���Ȃ������B
�\�Z�ψ���ł͖�}���k�Ў�`�������@�����߂ċꋫ�Ɋׂ��Ă����s�̏������₢�������A�k�Ў�`�������s�Nj�s��A�Ɛт̈�����Ƃ̖��𖾂炩�ɂ���悤�ɋ��߂��B
����ɑ��A�X�̊�Ƃ̏𖾂������Ƃ͐M�p�s���ɂȂ���Ɗ뜜�����Љ������́A�������獷�������ꂽ���ʂɂ����������n�Ӌ�s�x����~�̏��(���߂Ɏx�������~�����|�ƁA�a���c�����̏���ʂɋL�ڂ���Ă���)�������A�j�]������s�ɂ��Ă͍��Y�����Ĉ����������ē�������葱�����b�̐ӔC�ɂ����Ē����ɍs���|�̉ɂƂǂ߂����A���̒��Œ��߂̔j�]��s��Ꭶ����ɂ�����A
�E�E�E���ɍ������ߍ��ɉ��ēn�Ӌ�s�������j�]��v���܂����A������(�܂���)�Ɉ⊶�疜�ɑ����܂����E�E�E �Ɣ��������B
�����ł����ċ�̓I�ɔj�]��s�̎���ɂ��ĐG�ꂽ�̂́A��������Ɍ��������_�������ĐR�c�������邱�Ƃ͑Ή���x�点�A���̂悤�ɋ�s��j�]�ɒǂ�����Ԃ����������錋�ʂɂȂ�A�Ƃ��������̈Ӑ}����o���Ƃ����w�E������B
����ŁA�Љ��ɕt���Y���Ă����呠�ȕ����ے��̐ؓ��O�͋c�ꂩ��呠�Ȃɖ߂��ē����n�Ӌ�s�̋������Ƃ������A���s�ɓd�b�������ĕ���ʂ�c�Ƃ𑱂��Ă��邱�Ƃ��m�F�����B�͕Љ��̔���������Ă������Ƃ�m��A���ꂪ�����̂�h���ׂ��A�����~�߂̌������������Ȍx�ۋǒ��̑����ɂ������������A�����͕Љ������̂悤�Ȕ����������ȏ�͂���������~�߂邱�Ƃ͏o���Ȃ��Ƃ��ėv�������ۂ����B�������ĕЉ��́u�����n�Ӌ�s�j�]�v�����͗������ꂽ�B�܂��A�c��ł̂����ړ`���������a���҂��I�Ɗԍۂ̓����n�Ӌ�s�ɎE�����A���t���������N�������B
�|���āu�j�]��鍐�v���ꂽ�����n�Ӌ�s�̓n�ӘZ�Y�ꖱ�́A�������@�ɕ����ĕЉ��̔������ԈႢ�Ȃ��Ɗm�F����Ə݂��ׂ��Ƃ������A�ِ��ɂ́A���̐ꖱ�̐l�����猾���Ă���͂��肦�Ȃ��Ƃ������A�Љ�������ɂ͋^�������Ă���B
������ɂ���A�����n�Ӌ�s�̎�]�w�͓���Ɏo���s�̂��������~��s���X��������x�Ƃ��邱�Ƃ����肵���B�ˑR��@�I�o�c��E���Ă��炸�A���Ӌx�Ƃ͔������Ȃ��Ƃ���ł���A�����̎����ɂ������ċx�Ƃ��A���̐ӔC��]�ł����̂��Ǝ���Ă���B
������u���܂��o�c���Ă����s�ɂ��Ĕj�]��鍐���A�������������v���Ƃɂ��ĐV���͕Љ��̔������u�����v�Ǝ��グ�A��}���u�x�Ƃ������̋�s������ɑ���͕̂s���R�v�ȂǂƎw�E���āu�����v�ŋ�s��j�]�ɒǂ����ƍU�������B�������A�Љ��͂����܂ł��u14���ɓn�Ӌ�s���x�Ƃ̕ɗ����v�Ƃ���ԓx���т��A�̂��ɂ���𗠕t���铯�s�ꖱ���M�̓^�����������Ď��Ԃ̎��E��}�����B�Ȃ��A���̒��M�̓^�����ɂ��Ă��A����ɕЉ���̈ӂɉ������e�Őꖱ���������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����w�E�����邪�A�ꖱ�͉�������Ă��Ȃ��B
���e��
���̋K�͂������������n�Ӌ�s���˔@�x�Ƃ������Ƃ��V���œ`������Ƌ��Z�s�����L�܂�A�֓��𒆐S�Ɏ��t���������N�������B�����͐k�Ў�`�𑽂����L���Ă���Ɩڂ��ꂽ��s�����t���ɑ����A����Ɋ��ɂ���щ��āA�����s�E���E�c��s�E���\�l��s�E�����s�E�����s���x�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B����ɑ����₪21�������ݏo�����{���Ē��É��ɋ߂��B����ŁA��}���͕Љ��̐ӔC��₢�A����͕������ė��������ɂ܂Ŕ��W���邪�A�k�Ў�`�W��@���̂́u��p��s�̐����v�Ƃ����t�ь��c������23���ɋM���@�ʼn����ꎖ�Ԃ͒��É������B������26���ɒ鍑�c��͕���B
|
|
���l���̋��Q
|
3���̎��t�������͎��܂������̂́A�ˑR�Ƃ��đ�p��s(���)�������̐k�Ў�`������A���̑��ɂ��o�c���낤����s���������Ƃɕς��͂Ȃ������B
���͂��˂Ă����؏��X�ɑ��z�̑ݕt���s���Ă���A1920�N�̑唽���ŗ�؏��X�̌o�c�����������ۂɕs�Ǎ��Ɖ������B�k�Ў�`�̌`�œ����̎������l�����邱�Ƃɐ������������̌��ς͑����B�Ƃ͂����A���͐��{�̐ӔC�Őݗ����ꂽ�����s�ł���A���ꂪ�j�]���邱�Ƃ͓��{���{�̑ΊO�I�ȐM�p�ɂ��������d����ł������B���ۂɂ���܂ł���₪�ꋫ�Ɋׂ�s�x�A���{���呠�Ȃ̎�����Z�ʂ���Ȃǂ��ċ~�ς��邱�Ƃ��J��Ԃ���Ă���A����ɂ��Ă��j�]�����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��Ƃ����̂�����̌����ł������B��؏��X�����d�������q�������ǂ�ő��Ɨ�؏��X�Ƃ̊Ԃɐ[���W��z���グ���Ƃ�������B�܂��A�ꎞ���͎O��������킷���������L�^������̋K�͂��炵�āA�����|�Y�����鎖�ɂł��Ȃ�Α����̎�����Ƃ��ɍ�����������s�𑽐��������ݓ��{�o�ςɑ���Ȉ��e�����y�ڂ����琭�{�������f�s�ɓ��ݐ炸��⋤�X�~�ς����葼�ɂȂ��Ƃ����̂����q�̊��҂��鏊�ł������B
�����Ď��ۂɐk�Ў�`�W��@�������������ƂŁA���{�̐ӔC�Ŗ����ς̐k�Ў�`�ɍ������Ă����Č����߂����A�ŏI�I�ɂ��̃c�P��[�Ŏ҂ɉ��Ƃ����܂����B����ɂ�������؏��X���ꑧ����ƂȂ�A���̖ʂł͋��q�̗\�z�ʂ�̓W�J�ƂȂ����B
�������A�k�Ў�`�W��@�Ɋ�Â��⏞�����{�����̂�O�ɁA����R�c�̂Ȃ��ő�₪�����ςł�����2���~�]��̐k�Ў�`�̖��ɏ��1���~���̍�������A�܂���؏��X�ւ݂̑��o�������z�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��������A�k�Ў�`�W��@�Ɏ�X�u��p��s�̐����v�Ƃ����t�ь��c��������ꂽ���ŁA���̌o�c�ɑ���s�����g�債�A�R�[�������������グ���A�����J�肪���������B����ŗ�؏��X����������������グ���A�����₤�����̗Z�ʂ��p��s�ɋ��߂����Ƃ���A����ɓ��s�̌o�c�͈������ꂽ�B
����3��26���ɂ�ނȂ���؏��X�Ƃ̐≏�����ӂ��A27���ɈȌ�V�K�̗Z�������Ȃ��A�Ɠ`�����B��₪�≏�ɓ��ݐ����̂́A���{����~�ς̈Ӑ}�������ɂ��߂��ꂽ���炾�Ƃ�������B���Ƃɋc��̓��_�̒��Ɂu��؏��X��|�Y�����Ă����͈ێ�����v�Ƃق̂߂������̂����������Ƃ������Ƃ����Ƃ����B�������A���Ɨ�̐≏�̏��4��1���ɕ����Ɨa���҂ɓ��h��������t���������N���A4��5���ɗ�؏��X�͐V�K����̒�~�\��������x�Ƃ����B
���̎��_�ő��͗�؏��X��3��5�疜�~�̗Z�������Ă���A���ꂪ�ł��t���ƂȂ�Α��ӑ��͔j�]����Ƃ݂��e�s�͈�ĂɃR�[���s�ꂩ��Z���������グ�A�܂����Ɏ����Ă������̉���ɂ��������B�R�[�������ɑ傫���ˋ����Ă������͑����ɍs���l��A���{���{�ɋ~�ς�v�������B
���{�͓��{��s�ɑ��đ��ւ̓�����Z���s���悤�ɑ������B����͂���܂ł̋�s�~�ςɍۂ��ēs�x���Z�ɉ����Ă������A���ɂ��Ă͋K�͂��傫�����Ƃ�����⏞�̗��Â��̂���@���ɋ���Ȃ���ΗZ�ʂ͂ł��Ȃ��Ƃ����B���ɒ鍑�c��͕�Ă����̂Ő��{�͌��@70���̋K��Ɋ�Â��A�@���ɑウ�ċً}���ߟД������������A�����@�͂�������@�ᔽ�ƒf��17���ɔی������B�����@�ږ�炪�o�ϓI��}�̎��Ԃł���Ƃ����F�����Ȃ������Ƃ������邪�A���̓����ɂ͕�����d�Y�O����b�̊O�𐭍�(�����O��)�ɋ�������������ɓ����㎡�E�����u��Y�Ƃ������L�͂Ȑ����ږ⊯�炪�������F��ƒʂ��ē|�t�ɓ������A�d���������B���̐ӔC���Ƃ�`�Ŏ�Γ��t��4��20���ɑ����E���A�g�t�̑喽���������F��̓c���`��ɉ������B
����œ��₩��̓��Z���Ȃ���������18���ɓ��n�y�ъC�O�̎x�X��߂�Ɣ��\�����B�����s�ł��萭�{�����炩�̋~�ς��s���ƌ����Ă����ɂ�������炸���Njx�Ƃ��Ă��܂������ƂőS���e�n�ɓ��h������A���t�������͊g�債���B
18〜19���A���̗L�͍s�ł���ߍ]��s�A��z��s���������ŋx�Ƃ����ق��A������s(����)�A������s(�L��)���x�Ƃ\�����B20���ɂ́A���`����s(���R)�A�L���Y�Ƌ�s���x�ƁA������21���ɂ͓����̑��s�ł������\�܋�s�܂ł����x�Ƃ����B�\�܋�s�͉ؑ�����̏o�������A�܂��{���Ȃ̉�v��S�������p��s�Ƃ��āu�����������Ɍ������J�����Ă��������a�������Ă��������邾���ł����h�v�Ɨ_�ꍂ���u�������x�Ƃ��邭�炢�Ȃ瑼�̋�s���Ƃ��ɋx�Ƃ��Ă���v�Ƃ�����قǂɍ����M�p�Ă����B�������A���̓���͏]�O�z������������s�������Ă������`�n��Ƃ̍����ł��t���A�s�Ǎ��Ɖ��������Ƃ���x�ƂɎ������B
��A�̍����̒��œ���͔��ݏo�𑱂��Č����̋����ɓw�߂����A�݂��o���K�͂��O�㖢���̊z�ɂ̂ڂ�A���Ɏ����̍ɂ�����������鎖�Ԃɒǂ����܂ꂽ�B���ɔ��s���I�����ĉ���ς݂̌Â�������A���Ďg�p�ɑς����Ȃ��Ƃ��ĉ�����������܂ł����o�������A�Ȃ��s�����A���ɂ͊e��s����̌��������o���v���ɑ��ďo�����a��悤�ɂȂ����B
���̊ԁA�g�t�̑喽���������������F��ق̓c���`��͍���������呠��b�ɔC������21���ɑg�t���A���Z���Q�̉�����}�����B
�����͑S���Ń����g���A��(�x���P�\��)�����{���ׂ����@8���̋K��ɂ��ً}���߂̟Д������₵�A�����@�������͑ԓx��ς��Ē��ߟД���e�F�����B�܂��A�����g���A���̌���(���ߟД�)����{�s�܂ł̎葱���ɂ�2���Ԃ�v����Ƃ݂āA��`�����������������˂�O���s�̒r�c���j�Ƌ�s�W���߂�O�H��s�̋��c������ʂ��đS���̋�s�ɑ�4��22��(��)��23��(�y)��2���Ԃ̈�ċx�Ƃ�v�����A��s���͂���ɉ������B
�����Ɍ����̋����ɑS�͂�s�����A�Жʂ�����������������}����200�~�D�̗l�����}篐��肵��500�����ȏ���点�A��s�x�Ɠ��ɂƂǂ܂炸���j���ł���24���ɂ���s�ɓ͂����B��s�͏���ɋ������ꂽ������X���ɐς݁A�x�����ɑ肪�����Ȃ����Ƃ��A�s�[�������B25������500�~�ȏ�̎x������P�\���郂���g���A�����{�s���ċ�s���J���A���t���ɗ����l�͓X���ɐς܂ꂽ���������Ĉ��S�����Ƃ����B�����āA3�T�Ԃ̃����g���A�����Ԃ��I������5��12���܂łɒlj���200�~����750���������ċ�s�ɓ͂��A�����g���A���I����������Ȃ����Z���Q�𒾐É��������B
|
|
�����㏈��
|
|
�x�Ƃ�����s�́A���̂܂ܑ��̋�s�ɋ~�ύ����������̂Ɛ�����ɉc�Ƃ��ĊJ�������̂Ƃ����������A�a���̊z�͍팸���ꂽ�B
|
���]��
��ʓI�ȋ��Q�ɑ��āA�l(�a����)�̋��Z�ɑ���s��������t���������N�������Y�Ƃ��̂��̂���łɂ͎���Ȃ������_�����قł���ƌ�����B
�O�q�̂悤�ɋ��Z�V�X�e���̕s���ƁA��@�ւ̑Ώ���������_�Ńo�u���i�C�Ƃ̗ގ��_�������邱�Ƃ�����B
|
���e��
���̎��t�������ɍ����͏����ȋ�s�ɗa����a���Ă��Ă͊�Ȃ��ƍl���A�����n�Ȃǂ̑��s�ɑ��ėa����a����悤�ɂȂ����B���̂��߁A���s(���Ɍܑ��s�Ƃ��Ă��O��E�O�H�E�Z�F�E���c�E���)�ɗa�����W������悤�ɂȂ�A�����̗͂͂���ɋ��剻�����B
�o�ϓI�����������ċ����ւ͉������ꂽ�B
���E�ł́A���{��g����6���ɖ{�i�I�ɗ��������}�����������B�@
�@ |
| �����a���Q |
   �@
�@
|
1929�N(���a4�N)�H�ɃA�����J���O���ŋN���A���E������������ł��������E���Q�̉e�������{�ɂ�����сA1930�N(���a5�N)���痂1931�N(���a6�N)�ɂ����ē��{�o�ς���@�I�ȏɊׂꂽ�A��O�̓��{�ɂ�����ł��[���ȋ��Q�B
��ꎟ���E���ɂ��펞�o�u��(�����{�̑��i�C)�̕���ɂ���ċ�s���������s�Ǎ������Z�V�X�e���������A�ꎞ�͎���������̂́A���̌�̋��{�ʐ���ړI�Ƃ����ُk�I�ȋ��Z����ɂ���āA���{�o�ς͐[���ȃf�t���s���Ɋׂ����B
|
|
���w�i
|
���a���Q�̔��[�́A��ꎟ���E���ɂ��펞�o�u��(�����{�̑��i�C)�̕���ɂ���B��ꎟ���E��풆�͑��i�C�ɕ��������{�ł��������A��ト�[���b�p�̐��i���A�W�A�s��ɖ߂��Ă����1920�N(�吳9�N)�ɂ͐�㋰�Q���������A���ꂪ�I���Ɍ��������Ƃ��Ă������A1922�N(�吳11�N)�̋�s���Q�A1923�N(�吳12�N)�ɂ͊֓���k�Ђ����X�ƋN�����čĂы��Q�Ɋׂ���(�k�Ћ��Q)�B���̂Ƃ���Вn�̊�Ƃ̐U��o������`����{��s(����)���Ċ������Đk�Ў�`�Ƃ������Ƃ͂������Ď��Ԃ̈������܂˂��Ă���B
�܂��A��ꎟ���E���Œ���1917�N(�吳6�N)9���A���{�̓A�����J���O���ɑ����ċ��A�o�֎~�������Ȃ��A������A���{�ʐ����痣�E���Ă����B�A�����J�́A��풼���1919�N(�吳8�N)�ɂ͑��������A�o������(������)���A���{�ʐ��ɕ��A�����B���������{�́A�����1919�N(�吳8�N)���ɂ͓��n�E�O�n���킹�Đ��ݏ�����20��4,500���~�ɂ̂ڂ�A���ێ��x�������ł������ɂ�������炸�A�����ւ��s��Ȃ������B
1920�N��(�吳9�N-���a4�N)�ɂ͐��E�̎�v���͂����ɋ��{�ʐ��ւƕ��A���A���ב֖{�ʐ���啝�ɓ����������ۋ��{�ʐ��̃l�b�g���[�N���Č�����Ă���A���E�o�ς͑�O����Љ���ނ����A�u�i���̔ɉh�v��搉̂��Ă����A�����J�̍D�i�C�ƍD���ȑΊO�����ɂ���đ��ΓI�Ȉ�������Ă����B
���{���{�́A���̂悤�Ȑ��E�I�Ȓ����ɉ����ĉ��x�������ւ����{���悤�Ƌ@����M�������A1920�N��(�吳9�N-���a4�N)�̓��{�o�ς͏�q�����悤�ɖ����I�ȕs���������Ċ�@�I�ȏ�Ԃɂ���A�܂��A�������F����ɉ�������Ƃ�������ւɓ��ݐ邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����1927�N(���a2�N)�ɂ́A�Љ����������̎����ɂ����t���������甭���������Z���Q(���a���Z���Q)���N����A�ב֑���͓��h���Ȃ��牺��������������B1928�N(���a3�N)6���ɂ̓t�����X���V����(5����1�؉���)�ɂ����A�o����(������)���s�����̂ŁA��v���ł͓��{�݂̂��c���ꂽ�B���̂���A���{�̕��A�v�f�������ʼn~�̈ב֑���͗������������߁A�����ւɂ��בւ̈���́A�A�o�ƎҁE�A���Ǝ҂̋�ʂȂ��A���E�S�̗̂v���ƂȂ����B
���̂悤�ȏ��Ő����������������}���_���Y�K���t�́A�u�����ցE�����ُk�E���ƌ��v�Ɓu�Ύx�O�����V�E�R�k���i�E�ĉp�����O���v���f���ēo��A���{�ʐ��̕��A�����f���A���{���i�̍��ۋ����͂����߂邽�߂ɁA����������������̗p���A�s��Ƀf�t�����͂������邱�ƂŎY�ƍ������𑣂��A���R�X�g�ƍ������̖����������悤�Ƃ����B����͑����̒�����Ƃɒɂ݂���������v�ł������B�l�����t�̈�㏀�V�������́A�O�ꂵ���ُk���������i�߂����Ő��݂�~���A���A�o���ւ��s�����Ƃɂ���ĊO���ב֑���̈���ƌo�ϊE�̔��{�I������}�����B
1929�N(���a4�N)12��7���t���̑�㖈���V���́u����E���镨�� �悢���������ł���Ƃق������ރT�����[�}���v�Ƃ������o���ŁA���{�ʐ����A�ɂ��f�t�������}�����B
���{�ʐ����A��̓����̐V���L���̌��o���ł́u���Z���������v(��㎞���V�� ���a5�N(1930�N)1��12��)�A�u������̍��E�͎��ɗǍD�v(��㒩���V�� ���a5�N(1930�N)1��22��)�Ɨ�^���ꂽ���A��J����ɂ́u�����ւŎY�ƊE�͍������Z����v(���O���ƐV�� ���a5�N(1930�N)2��17-19��)�A�u��ʕ����ɔ䂵�ĉ��͐r�����������v(��㒩���V�� ���a5�N(1930�N)2��20��)�Ƃ������V���L���̌��o�����o�n�߂��B
���a���Q�����̑�\�I�ȃ��f�B�A�ł���V���E�����G���ł́u�s�i�C��O�ꂳ����v�ƗE�܂����X���[�K������яo���Ă����B
|
|
�����a���Q�̔���
|
�����E���Q�Ƌ�����
�ُk�����Ƌ��Z�������ߍ�ɂ���Ė�3���~�̐��݂���������A�בւ��}���ɉ������߁A���{���{��1929�N(���a4�N)11��22���A���N��1��11���������ċ����ւɓ��ݐ�呠�ȗ߂����z�����B�������A�O�N��10���ɃA�����J���O���j���[���[�N�̃E�H�[���X�ŋN�����������̑�\���Ɏn�܂������Q�����E���イ�ɔg�y����(���E���Q)�B���{�o�ς́A����ɂ������ւɂ��s���Ƃ��킹�A��d�̑Ō����邱�ƂƂȂ����B
�����֑O�̈ב֑���̎�����100�~=46.5�h���O��̉~���ł��������A��㑠���́A100�~=49.85�h���Ƃ������֗A�O�̋������ł̉��ւ������Ȃ������߁A�����I�ɂ͉~�̐�グ�ƂȂ����B�~���������炵�ē��{�̗A�o���i�������Ċ����ɂ��A�Ђ��Ă͓��{�o�ς��f�t���[�V�����ƕs���ɂ݂��т�������̂��鋌�������ւ����{�����̂́A�~�̍��ېM�p�𗎂Ƃ������Ȃ��v���ɉ����āA���Y���̒Ⴂ�s�NJ�Ƃ𓑑����邱�Ƃɂ���ē��{�o�ς̑̎����P���͂���K�v������Ƃ̔��f���ꂽ���߂ł������B���Z�E�ɂ����Ă��A���Z���Q��̎����̏W���ɂ���đ̎��������͂����Ă����̂ŁA�f�t������肫�鎩�M��������Ă����B�בւ̕s����ɔY�܂���Ă������Ђ��܂������ւɎ^�����A�C�O����������ւ𔗂��Ă͂����B
�������A����Ӗ��ŁA1930�N(���a5�N)1���́A�����ւ̎����Ƃ��Ă͍ł������^�C�~���O�ł������B���{�������ւ��}�����̂́A1929�N(���a4�N)�܂ł̃A�����J�̔ɉh���݂����߂ł��������A�E�H�[���X��\�����₪�ċN���鐢�E�勰�Q�̑O�Ԃ�ł��邱�Ƃ�\���������E�̎w���҂͒N�ЂƂ肢�Ȃ������̂ł���A��㑠�����܂��A�ĂуA�����J�o�ς�������悷�邾�낤�ƍl�����̂ł���B�Ƃ��낪�A���ɂ���ē��{�̋����ւ͐��E���Q�̖������ė��Ƃ��ꂽ���̎��Ɏ��s�Ɉڂ��ꂽ�̂������B�����ւ����z���ėA�o�������𑁂߁A�A������x�������J�艄�ׂ�u���[�Y�E�A���h�E���O�Y�v�ɂ���č��ێ��x�̍D���ƈב֑���̏㏸���ꎞ�݂�ꂽ���̂́A����͈�]���ċt���ƂȂ����B
�����ݗ��o�Ə��a���Q�̔���
��R�X�g�ɂ���ėA�o���g�傳���悤�Ƃ�����㑠���̂˂炢�Ƃ͗����ɁA�ΊO�A�o�͌��������B���̂����ۂ��œ��{�����ř[�����ꂽ���݂͊C�O�ɑ�ʂɗ��o�����B������킸��2�����Ŗ�1��5,000���~���̐��݂����o�A1930�N(���a5�N)��ʂ���2��8,800���~�ɂ���B���ݗ��o��1931�N(���a6�N)�ɂȂ��Ă������܂炸�A�ނ��댃�����𑝂����B
���{�̗A�o��́A�����ɂ��Ă̓A�����J�A�Ȑ��i��G�݂ɂ��Ă͒������͂��߂Ƃ���A�W�A�����ł��������A�����̍��X�͂Ƃ�킯���E���Q�̃_���[�W�̋����n��ł������B�������������Ƃ���A1930�N(���a5�N)3���ɂ͏��i�s�ꂪ��\�����A�����A�S�|�A�_�Y�����̕����͋}���ɒቺ�����B�����Ŋ����s��̖\�����N����A���Z�E�������B����ɁA�����Ɗ����̉����ɂ���Ē�����Ƃ̓|�Y�⑀�ƒZ�k���������A���Ǝ҂��X�ɂ��ӂ�A������ʂ̍w���͂��������Ă������B1930�N(���a5�N)���ɂԂꂽ��Ђ�823�Ђɂ���сA����������Ђ�311�ЁA���U�������z��5��8,200���~�ɂ����ł���B�J���^�������������B�܂��A�S�̂�3���ɂ������3���̏��������铦�����Ă���B�����A�H���ł������͂��̑�w�E���w�Z���Ɛ��̂�����3����1���E���Ȃ���Ԃł���A�w�m���E�ɂ�����Ȃ������ȗ��ٕ̈ς������āu��w�͏o������ǁv�����s��ƂȂ����B1930�N(���a5�N)�̎��Ǝ҂͑S����250���l�]�Ɛ��肳��Ă���A���̂悤�Ȗ��]�L�̕s���́u�����y������v�Ə̂��ꂽ�B
1929�N(���a4�N)��100�Ƃ����Ƃ���1930�N(���a5�N)�E1931�N(���a6�N)�̌o�Ϗ��w�W�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
���ځ@/�@1929�N / 1930�N / 1931�N
�������� 100�@/�@81�@/�@77
�������� 100�@/�@83�@/�@70
�ĉ� 100�@/�@63�@/�@63
�Ȏ����i 100�@/�@66�@/�@56
�������i 100�@/�@66�@/�@45
�A�o�z 100�@/�@68�@/�@53
�A���z 100�@/�@70�@/�@60
�Ȃ��A1930�N(���a5�N)���_�ł̓��{��1�l�����荑������(GNI)�́A�A�����J�̖�9����1�A�C�M���X�̖�8����1�A�t�����X�̖�5����1�A�x���M�[�̖�2����1�ɂ����Ȃ������B
���_�Ƌ��Q
���a���Q�ŁA�Ƃ�킯�傫�ȑŌ������͔̂_���ł������B�����̑ΕėA�o�������������Ƃɉ����A�f�t�������1930�N(���a5�N)�̖L��ɂ��ĉ������A���N�A��p����̕Ă̗����ɂ���ĕĉߏ肪���債�A�_���͉�œI�ȑŌ������B
|
�����a�_�Ƌ��Q
2
1930�N(���a5�N)����1931�N(���a6�N)�ɂ����Đ[����������s��(���a���Q)�̔_�Ƃ���є_���ɂ�����W�J�B�P�ɔ_�Ƌ��Q(�̂����傤���傤����)�Ƃ������B
���a���Q�ŁA�Ƃ�킯�傫�ȑŌ������͔̂_���ł������B���E���Q�ɂ��A�����J���O�������̋��R���ɂ�萶���̑ΕėA�o�������������Ƃɂ�鐶�����i�̖\���ΐ��Ƃ����̔_�Y�������X�Ɖ��i�������A��㏀�V���呠��b�̃f�t�������1930�N(���a5�N)�̖L��ɂ��ĉ������ɂ��A�_�Ƌ��Q�͖{�i�������B���̔N�͔_���ł͓��{�j�㏉�Ƃ�����u�L��Q����v���������B�ĉ������ɂ͒��N���p����̕ė����̉e�����������Ƃ�����B�_���͉�œI�ȑŌ������B�����A�ĂƖ��̓�{���Ő��藧���Ă������{�̔_���́A���̗����̎�������₽��邠�肳�܂������̂ł���B
��1931�N(���a6�N)�ɂ͈�]���ē��k�n���E�k�C���n������Q�ɂ��勥��ɂ݂܂�ꂽ�B�s���̂��߂Ɍ��Ƃ̋@������Ȃ��Ȃ��Ă��������ɁA�s�s�̎��Ǝ҂��A�_�������߁A���k�n���𒆐S�ɔ_�ƌo�ς͔敾���A�Q�쐅���̋��R�Ɋׂ�A�n���̂��܂蓌�k�n���Ⓑ�쌧�ł͐c���肪���s���Č��H�����⏗�q�̐g���肪�[���Ȗ��ƂȂ����B���w�Z�����̋����s���������N�������B�܂��A���q�n�тƂ���n��𒆐S�ɏ��쑈�c�����������B
1933�N(���a8�N)�ȍ~�i�C�͉ǖʂɓ��邪�A1933�N�����ɏ��a�O���Ôg���N����A���k�n���̑����m���ݕ��͐r��Ȕ�Q�������ނ����B�܂��A1934�N(���a9�N)�͋L�^�I�ȑ勥��ƂȂ��Ĕ_���o�ς̋ꋫ�͂��̌���Â����B �_�앨���i�����Q�O�N�̉��i�ɉ���̂�1935�N(���a10�N)�ł������B�@ |
|
�����{���{�̑�
|
�_�����t�́A�_�Ƌ��Q�ɑ��ẮA�_���ւ̒ᗘ�����̗Z�ʂ�āA�����̎s���ێ�����Ƃ������A�ُk�����̘g�̂Ȃ��ł͂܂������s�\���ɂ����s���Ȃ������B�����ۂ��H�Ɩʂł́A1930�N(���a5�N)6���ɗՎ��Y�ƍ����ǂ�݂��Ă���B
�_�����t�́A�ΊO�I�ɂ͋����O����i�߁A1930�N(���a5�N)4���Ƀ����h���C�R�R�k�����B�������A���N11���A����������Ƃł���Ƃ��Ĕ������鈤���Ђ̍��������Y�ɂ���ē����w�ő_�����ꂽ�B�_���͈ꖽ�����Ƃ߂����A1931�N(���a6�N)4���A���t�s��v�ő����E�����B���{�͓���4���ɍH�Ƒg���@�A�d�v�Y�Ɠ����@�𐧒肵�āA�A�o������Ƃ𒆐S�Ƃ�����������J���e���̌����𑣐i�����B�d�v�Y�Ɠ����@�́A�w��Y�Ƃł̕s���J���e���̌�����e�F������̂ł��������A���ꂪ�����o�ς̐悪���ƂȂ����B
�_���̌�p�Ƃ��Ă͓������������}�̎���X���Y����ǂƂ����2����Γ��t�������������A31�N(���a7�N)9���A�֓��R�ɂ���Ė��F���ς��u�������B�܂��A����9���ɂ̓C�M���X�����{�ʐ����痣�E�������Ƃɂ��A��ʂ̉~����E�h��������U�������B�h��������i�߂������ɑ��ẮA�u�����v�u���v�Ƃ��čU�����鐺�������̂������ɍ��܂����B
���F���ςɑ��ẮA��Ύ͎��ϕs�g��𐺖��������A�֓��R�͂�������Đ�����g�債���B�������Ď�Γ��t�́A���Q�ɑ��L���ȑ���u���邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A���ό�̎��Ԃ̎��E�ɂ䂫�Â܂��đ����E�����B1931�N(���a6�N)12���A�������F��̌��{�B�����t��g�D�����B
���{���t�̍������������́A31�N(���a6�N)12���A�������ɋ��A�o���ċ֎~���A���{�͊Ǘ��ʉݐ��x�ւƈڍs�����B���������͖����}�������s���Ă����f�t�������180�x�]�����A�ϋɍ������̂�A�R����g���ƐԎ������s�ɂ��C���t���[�V����������s����(��������������Ƃ����R�g����́A�i�����P����A�����z���]���ƍ��ۋ�������}�����R�k�̎��݂ɂ�������炸�p�������B����ɂ��A���F���ρE�x�ߎ��ς�ʂ��ČR���̔����͂������Ă������ƂɂȂ�)�B
�������āA���{�̋��{�ʐ����A�͂킸��2�N�̒Z���ɏI������B����2�N�Ԃ̐[���ȋ��Q�͎Љ�I��@�����������A�_���Y�K�A��㏀�V���A�O������̑单���ł������c��������P�����e�����Y���ƂȂ��Ė\�����A�푈�ƌR����`�ւ̓����������錋�ʂƂȂ����B���̈���ŋ��A�o�ċ֎~�ɂ��A�~����͈�C�ɉ������A�~���ɏ������ē��{�͗A�o���}���������B�A�o�̋}���ɂƂ��Ȃ��i�C���}���ɉ��A1933�N(���a8�N)�ɂ͑��̎�v���ɐ�삯�ċ��Q�O�̌o�ϐ����ɉ����B
|
|
���e��
|
���������ɂ���āA���{�͉~���𗘗p���ėA�o���}�����������A�ĉp�Ȃǂ���́u�\�[�V�����E�_���s���O�v�ł���Ɣᔻ�����B�ĉp���ȂǑ����̐A���n�������́A���{�ɑR���邽�߁A����̐A���n���Ŕr���I�ȃu���b�N�o�ς��\�z����(�p�F�X�^�[�����O�E�|���h�E�u���b�N�A�āF�h���E�u���b�N�A���F�t�����E�u���b�N)�B�u���b�N�o�ω����i�ނƁA��]���ċ��n�ɗ������ꂽ���{�������ɑR���邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����A�����x�~�u���b�N�\�z��ڎw���ăA�W�A�i�o�����������邱�ƂƂȂ�B���{�Ɠ����㔭���{��`���ł���A�A���n�ɖR�����h�C�c�E�C�^���A�������̐��͊g���ڎw���Ėc������ւƓ]�����B���������u���Ă鍑�v�Ɓu�������鍑�v�Ƃ̓�ɉ��͑���E���u���̉����ƂȂ����B�@
�@ |
| �����a���Q�̍��� / ���������ƌi�C�� |
   �@
�@
|
���P�@���E���Q����̗�������
1929(���a4)�N10��24���̃A�����J�̊����\�����_�@�Ɏn�܂������E���Q�́A1930�N�ɓ��{�ɂ��g�y����( ���a���Q)�B�������͉������A�f�t���s���ƂȂ����B�q�O���t�P�r�́A�����̍H�Ɛ��Y�z�̎w���ł���B���E���Q���g�y����1930�N���琶�Y�z���������Ă��邱�Ƃ��킩��B
�������A�ӊO�ɂ�1933�N�ɂ�1929�N�̐��������A���a���Q�͔�r�I�Z���Ԃō������Ă���̂ł���(����͑S���I�ɂ����l�ł���)�B���̂悤�ɐ��E���Q�̒��A���{�͑��̐�i���ɐ�삯�Či�C���ʂ������A����͂Ȃ��Ȃ̂ł��낤���B
���a���Q���n�܂������̕l���Y�K���t�ɑ���A���{�B���t(1931)�ƂȂ�ƁA1927�N�̋��Z���Q�Ŏ�r�������o���҂̍����������呠��b�ƂȂ����B�����͌��{���܁E�����(1932)�œ|�ꂽ��̐ē������t�E���c�[����t�ł��������߁A��E��Z����(1936)�ō������g���ÎE�����܂œ��{�o�ς̑ǎ����s�����B�����́A�l�����t����Ɏ��{���ĕs���̌����ƂȂ��Ă��������ւ��ɒ�~���A���{�ʐ��x����Ǘ��ʉݐ��x�ɓ]���������B����ɂ��A��r�I���R�ɒʉ݂s�ł���悤�ɂȂ�ȂǁA���{�ɂ���������̎��R�x�����܂����̂ł���B
|
��2�@�������Ƃɂ��i�C��
�q�j���P�r�́A�����������s�������Nj��~���ƂƂ��鐭��Ɋւ�����̂ł���B�T������ǂނƁA���̐���͎�Ɍ������Ƃ��s���A�i�C�������悤�Ƃ������Ƃ��킩��B���̌������Ƃ̎����́u�lj��\�Z�v�ƂȂ��Ă��邪�A���̍����͊Ǘ��ʉݐ��x�ɂ�蔭�s�ł���悤�ɂȂ����Ԏ�����(����)�ł������B�����́A����܂ŕl�����t�ōs���Ă����Y�ƍ������ɂ��f�t�������180�x�]�����A�Ԏ�����(����)�s���ăJ�l�̗ʂ𑝂₵�A�f�t���Ɋׂ��Ă������{���C���t���ɓ]���������̂ł���q�O���t2�r�B���̐���́A�P�C���Y�̗��_����肵�����̂ł���(�P�C���Y�̎咘�w�ٗp�E���q����щݕ��̈�ʗ��_�x��1936�N�o��)�A�����̐�i�I�Ȑ���ł������B
�Ăсq�O���t�P�r�ɖڂ�߂����B1936�N���܂ő����Y�z�Ɠ��l�̐��ڂ������Ă���̂��A�@�ې��i�̐��Y�z�ł���B�܂��A�q�j��2�r�́A�@�ۍH�Ǝ����ꂪ���ڂ��A�����̋��͂ɂ���Ď�Ɍ������n��Ő��Y�����悤�ɂȂ����A����A�W�A�ȂǂŎg��ꂽ�u�T�����v�Ƃ���ȐD���̗A�o�����A�s�������ɍv�����Ă���l�q��������Ă���(�Ȃ��A�ȐD���̗A�o���͑S���I�ȌX���ł�����)�B
|
��3�@�Ǘ��ʉݐ��x�Ɩf��
�l���Y�K���t�ɂ������ւ́A������(���{�����{�ʐ��x�ƂȂ���1897�N�̉ݕ��@�Œ�߂�ꂽ�Œ�ב֑���)�ōs�������߁A���ۂ̉��l�����~���h�����̈ב֑���ƂȂ��Ă����B���������������̋��A�o�ċ֎~(���{�ʐ��x�𗣂��)�ɂ��A������Ǘ��ʉݐ��x�ɂȂ������Ƃ���A�����ɉ~���̐�����ۂK�v���Ȃ��Ȃ����~�h������͎��ۂ̉��l�ɋ߂Â����ƂɂȂ�A�}���ɉ~���h�������i�̂ł���B
�~���͗A�o�ɗL���Ȃ��߁A�T�����̗A�o���~�����ǂ����ƂȂ��ċ}���ɐL�т��̂ł������B�������A���������~���h�����ւ̈ב֗U���ɂ��A�o�����͏��O������x������A�C�M���X��I�����_�̐A���n�ł͗A���������s����悤�ɂȂ��āA�A�o�͎���ɓ��ł��ƂȂ����B
�Ƃ�����A���̂悤�ȍ��������̍�������(���������Ƃ���)�ɂ��s���͍�������Ă������A���̐���𑱂���ΐԎ����������Ă��܂��B���̂��ߌi�C���N���ɂȂ���1936 (���a11) �N�x����A�����͐ϋɍ�������ُk�����ւƐ����]�����悤�Ƃ����B�������A���������̂��Ƃő����Ă����R������팸���ꂻ���ɂȂ������R���A��E��Z����(1936)�ō������ÎE���A�ĂѐԎ����̔��s�ɂ��R�����������Ƃ̊g�傪�i�߂��A1937�N����n�܂�����푈�ɓ˓����Ă����̂ł���B���̌��ʁA�q�O���t�P�r������킩��悤�ɍD�i�C�͈ێ������B�������A����̓e����푈�A����l��J���҂̒Ꮚ���Ƃ��������̗v���ɂ��x����ꂽ�D�i�C�������̂ł���B�@
�@ |
| �����a���Q���߂���o�ϐ���Ɛ���v�z / �����֘_�� |
   �@
�@
|
���v ��
������{�̃f�t���s���̐i�s�ƂƂ��ɁA�ߋ��̃f�t���s���ւ̊S�����܂��Ă���B�{�_���ł́A���a���Q���炻�̒E�o�Ɏ�����{�o�ςɂ��āA�����̌o�Ϗ����łȂ�������l�̔����E�v�z��ǐՂ��邱�ƂŁA�o�ώv�z�ƌo�ϐ���̊֘A�ɂ��čl�@����B
�{�_���͓����̍ł��d�v�Ȑ����_���ł�������֘_���A�Ƃ��ɏ��a���Q�̒��O�ł���1927 �N�ȍ~���狰�Q����̒E�o���\�ɂȂ���1932 �N�̒i�K�ɏœ_�����Ă�B
�_���̌��ʂ́A���̓_�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B���ɁA�l�X�̊��҂̘_��ւ̉e���͂͑傫���B�ŏ��̓C���t����A���Ɉב։�A�בֈ����Ƃ��đł��o���ꂽ�����ւ��A1927 �N�̏��a���Z���Q��ɂ́u���r�����v�������{�o�ς̍Đ���Ƃ��Ċ��҂��W�܂����̂́u�s�i�C����̑ŊJ��v�����߂��l�X�̊��҂ɂ��Ƃ��낪�傫���B
���ɁA�o�ϐ����_���̏�Ƃ��āA�����o�ϊw�I�Ș_�_���������ɂȂ����̂ł͂Ȃ������B���{�ʐ��̂����܂��܂ȁu�ǂ��v���l�ς��_���ɂ͐F�Z�����f���Ă����B�܂��u���E�����v�����̎���̃L�[���[�h�ɂȂ����̂́A���Z��`(�s�i�C���D�i�C�̔����Ƃ݂Ȃ��A�s�����ɂ͕s�ǎ��ƁE��Ƃ̓O�ꓑ�����i�C�]���ɂ͕K�v�s���Ƃ��錩��)�������I���͂������Ă�������ł������B
��O�ɁA�ߋ��̋L���͖����ł��Ȃ��B�h�C�c��(�n�C�p�[)�C���t���[�V������A�����̃C���t���[�V�����̋L�������X���������Ƃ��ɁA�V�������ցA�����Ă��̌�̃��t������ւ̎x���͂Ȃ��Ȃ������Ȃ������B
��l�ɁA�w�E���܂߂āA�_�d�̈��|�I�����͋��������֔h�ł���A�V�������֔h���邢�́u�ċ֎~�o�����v�A���t���h���_�d�ő������߂����Ƃ͌����ĂȂ������B�������A���ւƂ���ɔ������a���Q�ɂ���āA�V�������֔h�ւ̊S�Ǝx���͔���I�ɍ��܂��Ă������B�w�҂̋c�_�́A�����ꕔ�̐V�������֔h�������ċ��{�ʐ��C�f�I���M�[�Ɛ��Z��`�ɂƂ���Ă����B�}���N�X�h�͖T�ώғI�ԓx�ɏI�n���邩�A���Z��`�̊ϓ_�ɗ����Ă����B����̐V�������֔h�Ɏ��s���낪�Ȃ������킯�ł͂Ȃ������B����ǂ��납���s����͔ނ�ɂ����������B�������A�ŏI�I�ɕ������������������͔̂ނ炾�����B
��܂ɁA��@�͈ꕔ�̐l�X�ɋ@��������炵��(���E���b�l�A�R���A���H�����A�呠����)�B����ɂƂ��Ȃ��āA���Q���͍����钆�ŕʎ�̌o�ώv�z���͂Ă������B
�Ō�ɁA�o�ϊ�@�ւ̑Ώ��͌���I�ɏd�v�ł���B�����]���������炷�̂ɐ����̖����͑傫�����A�����]���͗e�Ղł͂Ȃ��B�����Ƃ̖{�̂͌o������w�Ԃ��Ƃɂ���͂������A�s�K�ɂ��ē����̐����S���҂͋��{�ʐ��ɂƂ��ꂷ�����B��@�ɂ����ẮA���s���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂�������Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA��@�̉��ł̐���ɂ͏�ɕs�m�����������A���f���K�v�ł���B
|
|
��I. ���_�F�o�ϐ���ƌo�ϐ���v�z |
��I.1. ���Ǝ��p
������{�̃f�t���s���ւ̊S����A�ߋ��̃f�t���s���ɒ��ڂ��W�܂��Ă���B���̒��Ŕ�r�̑ΏۂƂ��ĈӋ`������̂́A1930 �N��̃f�t���s���A���Ȃ킿���E�勰�Q���ł���B�ނ��A���j�͒P���ɂ͌J��Ԃ��Ȃ��B���E�勰�Q���ƌ���ł͖����ł��Ȃ����܂��܂ȈႢ������B�������A�����̓���Љ�Ȋw�ɂ����ẮA���j�I�o���̌����͗L�v�ȏ���^���Ă����B��i�����ł͂���70 �N�قǁA�����ɂ킽�镨���������o���������Ƃ��Ȃ��Ƃ��������ɂ��݂�ƁA���߂̃f�t���s���ł���1930 �N��Ɋw�ԈӋ`�͂���ƍl����B1
�{�_���ł́A���a���Q���炻�̒E�o�Ɏ�����{�o�ςɂ��āA�����̌o�Ϗ����łȂ�������l�̔����E�v�z��ǐՂ��邱�ƂŁA�o�ώv�z�ƌo�ϐ���̊֘A�ɂ��čl�@�������B
�o�ϐ��ǂ̂悤�Ɍ��܂�̂��́A�ŋ߂̌o�ϊw�A�Ƃ��ɐV�������ؓI�����o�ϊw(new positive political economy)�̑傫�ȉۑ�ł���B2�����ł́A����͌o�ϊw���z�肷��I���̗��_�ɂ����āA�����S���҂����̖ړI���������Ȃ���A���ʂ��邳�܂��܂Ȑ���̒����琭���I������Ƒz�肳��Ă���B
���͐����S���҂̒��ʂ��鐧��̓��e�A�Ƃ��ɏ��W���ł���B�����I���җ��_�Ȃ�ΐ����S���҂͌o�ςɂ��Ắu�^�̗��_(true theory)�v��L���Ă���Ɖ��肷�邪�A���̗��_���̂����j�I�ɕϑJ�𐋂��Ă������Ƃ��l����ƁA���̗��_�����̂܂ܓK�p����킯�ɂ͂����Ȃ��B�{�_���ł͌o�ϊw�j�̊ϓ_����A�o�ϐ�����߂�����W��(�m��)�ɒ��ڂ��Ă݂����B�����S���҂����̎��X�ɂ����Ăǂ̂悤�ȃ��f���A���_�A�v�z�A�\�z�A�M���������Ă�������₤�ׂ��ł���A���̉𖾂ɂ����o�ϊw�j�����p���邱�Ƃ��ł���ƍl������B3
���̍�Ƃ܂��邱�Ƃł͂��߂āA�����̐����]������K�Ȏ��_��������ƍl����B�Ȃ��Ȃ�A����̕]���ɂ��Ă͂��̌��ʂ̑��肾���łȂ��A���p�\�ł��������̐����I�����ƏƂ炵���킹��K�v�����邪�A���������I�����͂��̓����̏��W���ɏƂ炵���킹�邱�Ƃɂ���Ė��炩�ɂ��邱�Ƃ��ł��邩��ł���B
�������I���ɂ́A�����łȂ��A�ړI�������ɂȂ�B���v�̒Nj��͌o�ϊw�̑�ꌴ���ł���B�o�ϐ���͌��ǁA�����S���҂����v��Nj����錋�ʂƂ��Č��肳���̂ł͂Ȃ����낤���B�{�_�������v(�ړI��)�����m��(�������)���d�����闝�R�͎O�_����B���ɁA�����S���҂����𗘉v�Ƃ��Ă��邩�͊O������͂��������m��Ȃ����Ƃ������B�������̗��v��Nj����Ă���Ƃ��Ă��A������o�ώ�̂����m�ɕ\�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B���������Ӑ}���B�����Ƃ��܂����v�ƂȂ邩�炾�B���ɐ����Ƃ⊯���Ƃ����������S���҂����s��������ɑ��ĐӔC����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ����A���ۂɂƂ�ꂽ���痘�v�𐄑�����̂́A�_�_���̊댯�����������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B���ɁA���v�ƒm���͑��݂Ɍ��т��Ă��邱�Ƃ������B�����ɂƂ��Ă̗��v�����ł��邩�𗝉�����ɂ́A���̒m�����K�v�Ƃ���邩�炾�B�o�ϐ���j�̊ϓ_��������֘_�����߂��闘�Q�ɂ��Č��������O�a2003�́A�u���Q�ӎ��v�Ƃ����p���p���āA���Q���̂��ǂ��ӎ�������邩����ɂ��Ă���B�O�a�͂���ɁA�u��ϓI���Q�ӎ��v�Ɓu�q�ϓI���Q�ӎ��v����ʂ��Ă��邪�A����������ʂ�������̂́A���v���̂��̂����̈ӎ��ɒ������Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B��O�ɁA�Љ�Ȋw�̊�{�̈�́A���v�Nj��̌��ʂƂ��ĈӐ}���ʌ��ʂ����܂�邱�Ƃł���(�u���������v)�B����́A�O�a�̂����u��ϓI���Q�ӎ��v�Ɓu�q�ϓI���Q�ӎ��v�̋�ʂ��������̗��R�ł�����B4
�{�_���ł́A���a���Q���ނɂ��āA�o�ϐ����S���҂ƌo�ϐ�����߂���v�z�E�\�z�Ƃ̊W���l�@����B���Ƃ�菺�a���Q�Ƃ����o�ϊ�@�͑����̌o�ύ\�z�ɋ@���^�����̂ł���A���̓����̐����_���͑��ʓI�ł���B���̒��ł��{�_���͏��a���Q�ɂ�����ł��d�v�Ȑ����_���ł�������֘_���A�Ƃ��ɏ��a���Q�̒��O�ł���1927 �N�ȍ~���狰�Q����̒E�o���\�ɂȂ���1932 �N�̒i�K�ɏœ_�����Ă����B
|
��I.2. ��������
�����ցA���a���Q�ɂ��Ă̌��������͖c��ł���A�����̌o�ϐ���A����v�z�Ɍ��y���Ă��Ȃ����̂͏��Ȃ��̂ł��ׂĂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ŋ߂Ɍ����Ă��A�����E����1989�A����1989�A����1989 �ɂ��T���A�ΊO���Z�ɏœ_�����Ă�����1989�A���{��s�̋��Z����ɏœ_�����Ă����������W�]�ł���Έ�2001 �������邱�Ƃ��ł���B
�Ȃ��A�ߔN�ł͌�����{�̃f�t���s���̐i�s�ƂƂ��ɁA1980 �N��㔼�ȍ~�̃A�����J�勰�Q�����̐��ʂ�������A���Z����̃��W�[���]���ɗ͓_���������������łĂ���(���c��2002a,b�A�x2002a)�B���̎��_�͖{�_���ł��傢�ɎQ�l�ɂ��Ă���B
�{�_���̑ΏۂƂ���o�ϐ���Ɛ���v�z�̊W�Ɏ傽��͓_�����������͍̂���1954- 5�A����1967�^1994�A��1994�^2001�A���X1999�A�O�a2003 �ł���B���̂����A�_���̓����ҏ،��A�c��Ȏ����̏W�ςƂ����_�ł͍���1954- 5 �͑��̒ǐ��������Ȃ����A�����҂̔����Ƃ����Ӗ��ŗ��p�ɒ��ӂ��K�v�ł���(�Ȃ��A�����҂̏،��ɂ��Ă͈���1968 ���Q�l�ɂȂ�)�B����1967�^1994 �͂��̎��ɂ��Ă̐��I����]�̂���T�����ł���B��1994�^2001 �́A�����̓��O�̌o�ώv�z�Ƃ̊֘A���������Ă���A���̑�IX �͂ł̓}���N�X�o�ϊw�҂̋��Q�_���A��_�ł͎�Ƃ��ĉp���̌o�ώv�z�Ɠ��{�̂���Ƃ̑Δ��`���Ă���B�܂����X1999 �́w���m�o�ϐV��100 �N�j�x���M�ɉ�������o�������āw���m�o�ϐV��x�̘_���𒆐S�ɋ����֘_�������ǂ��Ă���B�����ɂ������O�a2003 �́A���̂���܂ł̌o�ϐ���j�����̏W�听�ł���A���̑�6�A7�͂ŋ�������ѐ���ߒ��ɂ����闘�Q�ӎ��ɂ��āA��9�A10 �͂ł͍��������ɂ��Ă̕]�����s���Ă���B�Ƃ��ɗL�v�Ȃ̂́A��7�͂ł���A�����ł͍��E�A�o�ϒc�̗̂��Q�ӎ��ɂ��Č������Ă���B�Ȃ��A�����֘_���̎����Ƃ��ẮA���{��s������1968 ���ԗ��I�ł���A�ďC�ғy�����Y�ɂ������֗��ł���B
|
��I.3. �\��
�{�_���̍\���͈ȉ��̒ʂ�ł���B���̑� II �߂ł́A���a���Q�ւȂ��鐭���_���j�Ƃ��āA�����֘_�����T�ς��A���{�ʐ��̏d�v������������ŋ߂̑勰�Q�����̊ϓ_��������֘_���̈Ӌ`�����炽�߂Ċm�F����B����ɑ�III �߂ł́A���a���Q���̋����֘_���ɂ��Ę_����B��IV�߂ł͏��a���Q����̒E�o���߂���_���̍ŏI�ǖʂɂ��Č�������B�Ō�ɑ�u�߂͌���ł���A���a���Q�ɂ��Ă̌�������o�ϐ����̋��P���o���B
|
|
��II. ���Q�ւ̑O�t�ȁF�����֘_�� |
��II.1. �_���̈Ӌ`
���a���Q�𗝉�����ɂ́A����ɐ旧�����֘_���𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����֘_���́A���̋A���ɓ��{�̖��^���������Ă����Ƃ����Ӗ��ŁA�����炭�ߑ���{�j��ő�̌o�Ϙ_�킾�����B���{����������{�ʐ��𗣒E���Ă��������́A1917(�吳6)�N9 ��12 ���̋��A�o�֎~����A1930(���a5)�N1 ��11 ���̕l�����t�ɂ�鋌���������ւ܂ŁA���悻13 �N�ɋy�ԁB�������A�����֘_���Ƃ����`�ŁA���{�ʐ����A���߂���_�킪�n�܂����̂́A��ꎟ���E�����1919(�吳8)�N6 ��9 ���ɕč��������͂₭���{�ʐ��ɕ��A�����ȍ~�ł���B���̌�A�_�펩�̂͂��̎��X�̏Ŕ��̉ۑ�Ɗ֘A���Ȃ��瑱���Ă��������A�l�����t�ɂ������ւɂ���Ę_�������������킯�ł͂Ȃ��B�ނ��돺�a���Q�̌����ƂƂ��ɘ_���͕ω����Ȃ�����p�����A1931(���a6)�N12 ��13 ���̌��{���t�ɂ��ċ֎~����A32 �N�㔼�̖��m�ȃ��t������ւ̓]���܂ŁA�����ւ���ы��{�ʐ��̐���A�����ċ��Q�Ƃ̊֘A���߂����Č������_������킳�ꂽ�B�{�_���Ō���13 �N�Ƃ͎��1919 �N����32 �N����Ƃ����Ӗ��ŗp���Ă���B
�����֘_���̈Ӌ`�͓�_����B���ɁA���������������t�͂Ȃ��������̂́A���̘_���͓��{�Ƃ������S�̂̌o�ω^�c�̕������߂���u�}�N���o�Ϙ_���v�ł������B���ɁA�ŋ߂̑勰�Q�����ł͋��{�ʐ��̖����̌��������i��ł���A���̊ϓ_����́A���{�ʐ��ւ̕��A�������勰�Q�̉����ł��������Ƃ���������Ă���B
���āA�}�l�^���X�g�[�P�C���W�A���_���̗]�g�������Ē���Ă����勰�Q�����́A80 �N�㔼�Έȍ~�ɍ��۔�r���d������_��(���ۊw�h)���䓪�������Ƃɂ���Ĕ���I�ɑO�i���A���̍��ӂ��`�������悤�ɂȂ����B
���̍��ӂ̊j�́A�����̍��یo�ϐ��x�̗v������{�ʐ��x�̈Ӗ��̌��Ȃ����ł���B���{�ʐ��Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��A���ƈꍑ�̒ʉ݂̉��l��A�������鐧�x�ł���A����͌Œ葊�ꐧ�ł������B�Ƃ���ŁA���ۋ��Z�ɂ́A���ۊԂ̎��R�Ȏ��{�ړ��A�בփ��[�g�̈���A����ƍ��������̈���Ƃ����O�̖ڕW���ɂ͒B���ł��Ȃ��Ƃ������肪����(�u���I�ȎO�p�`�v)�B�Œ葊�ꐧ���Ƃ����A�ꎞ�I�ɂ͍��������̈���͋]���ɂ���������Ȃ��B
�܂��A��ꎟ���E����ɍČ����ꂽ���{�ʐ��͑傫�Ȗ�������Ă����B����́A���ێ��x�̍������ƐԎ����̊ԂɁA��Ώ̐������邱�Ƃł���B���Ȃ킿�A���ێ��x�̐Ԏ��ɂ���ċ����s������Ƃ��̍��͎����̒ʉ݉��l�̈ێ����ł��Ȃ��Ȃ�̂����A�����ɂ���ċ���~�ς������ɂ͂Ȃ��y�i���e�B���Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�����č��ێ��x�Ԏ����͈בփ��[�g�̈����I�����邩���ɁA���������̈�����]���ɂ���������Ȃ������̂ł���(�ʉ݉��l�̉����A�f���@�����G�[�V�������������̉����A�f�t���[�V������I��������Ȃ�)�B
��ꎟ���E����́A�Ƃ��ɂ��̖�肪�[���ɂȂ����B���̌����͎�Ƃ��ĕč��̋��Z����ł���B���ɉp���������ɓ]���������ŁA�č��͐��E�卑�Ƃ��Ă̈ʒu���߂������B�������A�o����x�����ɔ������̗����ɂ�������炸�A�č��͂���ɑΉ�������Z�ɘa���s�킸�A���Z������������ߓI�ɉ^�c����B����ɂ���āA���̍��X���������ߓI�ɉ^�c����������Ȃ��Ȃ�B�Ȃ��Ȃ�A���̍��X�́A���{�ʐ��ɂƂǂ܂����A�בփ��[�g��ăh���ɑ��ČŒ�I�Ɉێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B���{�ʐ���ʂ��ăf�t�����͂����E�o�ς�`�d����B�����āA���̃f�t�����͂̐ςݏd�˂��A�ŏI�I�ɐ��E�K�͂ł̕s���A�勰�Q�̈��������������ƂɂȂ�̂ł���B
���������������o���[�E�A�C�P���O���[��(�J���t�H���j�A��w�o�[�N���[�Z����)�͋��{�ʐ��́u�������v�Əq�ׂ��B�����ŏd�v�Ȃ̂́A���́u�������v���������A����̊�{�I�ȑ�g�����炩���ߌ��܂��Ă��܂����Ƃł���B���{�ʐ��̂��Ƃł́A���Z�ɘa����������I�ɑ����邱�Ƃ͂ł����A������͋��ۗ̕L�ʂɐ���Ă��܂����炾�B���̑�g����̓I�ȌX�́u����v�Ƌ�ʂ��āA�u���W�[���v�ƌĂԂȂ�A���{�ʐ��́A�f�t�����͂��܂�ł���u�f�t���E���W�[���v���̂��̂ł������B5
���̌ʂ̐���Ƌ�ʂ��ꂽ�A����̑�g�A���Ȃ킿�u���W�[���v�̖�肱���A1930 �N��̑勰�Q�⏺�a���Q����w�Ԃׂ��ő�̘_�_�ł���B���۔�r���������炩�ɂ����悤�ɁA���̋��{�ʐ����瑁���E�o�����W�[���̓]�����ʂ��������قǁA�勰�Q����E�o�����̂ł���B
�u���W�[���v�Ƃ��Ă̋��{�ʐ��ɂ��Ă͂���ɒ��ڂ��ׂ��_������B���ɁABordo and Kydland 1995 ����������悤�ɁA1880 �N�ォ��1914 �N�܂ł̋��{�ʐ�(�ÓT�I���{�ʐ�����)�́A���́u�t�я����t���[��(contingent rule)�v�ł������B�u�t�я����t�v�Ƃ́A�푈��o�ϊ�@�ɂ����Ă͈ꎞ�I���E���F�߂��Ă����Ƃ����Ӗ��ł���A����͍d�������₷���������{�ʐ��̃��[���Ɉ��̏_���ۏႵ���B
���ɁA�ÓT�I���{�ʐ�����ɂ����āA���{�ʐ��ɎQ���ł��邩�ǂ����́A���̍��̃}�N���o�ω^�c�̗ǍD���������u�F���(Seal of Good Housekeeping)�v�Ƃ��Ď~�߂��Ă���(Bordo and Rockoff 1996)�B���{�ʐ��ɑ����邱�ƂŎ��{�A�o��(�C�M���X)����̎��{�����͗e�ՂɂȂ邩��ł���B�����ɁA���_�̂悤�Ɂu�����v�����邱�ƂŁA�푈��o�ϊ�@�Ƃ������Ó��ȗ��R�ȊO�ŋ��{�ʐ����痣�E����Ƃ����@���`�I�s���̖h�~���\�ɂ����B���������āA��ꎟ���E���Ƃ��������I����痣�E�����e�����A���̍��یo�ϒ������Č�����\�z�̂Ȃ��ŁA���{�ʐ��Č����d�������͎̂��R�Ȃ��ƂƂ�����B
��O�ɁA��ꎟ���E����̍Č��\�z��S�����̂́A�e���̒�����s�ƁA�Ƃ�킯�C���O�����h��s���ك����^�M���E�m�[�}����j���[���[�N�A��كx���W���~���E�X�g�����O�������B���Ԋ��́u�O���[�o���[�[�V�����̎���v(James 2001)��K�ɉ^�c���邽�߂ɂ͒�����s�Ԃ̋������s���ł���A���̈Ӗ��ł��łɁu������s�Ƃ̎���v���������Ă����B
��l�ɁA�����鐧�x���l�ɁA���{�ʐ��ɂ͎v�z�I���ʂ��������B���\�N�ɂ킽���č��یo�ϐ��x�̍����Ƃ��ċ@�\���Ă������{�ʐ��́A����I�Ȃ��́A���S�Ȃ��́A�]�܂������̂̑㖼���ł������B���̂悤�ȋ��{�ʐ��̎v�z�I���ʂ����{�ʐ��C�f�I���M�[(Temin 1989)�A���邢�͓����̓��╛���ِ[��p�܂̕\������āu���{�ʐ��S���v(�[��1938)�ƌĂԂȂ�A���ꂪ����x��ɂȂ����Ƃ��A����͐����S���҂̍s��������u�������v�ƂȂ����B
��܂ɁA���{�ʐ��̋@�\�s�S���w�E���A���̌��E������o�ϊw�҂����������B���Ԋ����\����o�ϊw�ҁA�X�E�F�[�f���̃O�X�^�[�t�E�J�b�Z���A�A�����J�̃A�[���B���O�E�t�B�b�V���[�A�C�M���X�̃W�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y�́A���ׂċ��{�ʐ��̏d��Ȗ��_���w�E���Ă����B���ہA��Ƀ}�N���o�ϊw�ƌĂ����̂͂��̑��Ԋ��̌o�ϕϓ��ɑ���o�ϊw�̎��g�݂̌��ʂƂ��Ēa�����Ă���̂ł���B
���������āA�����̋��{�ʐ��������h�o�ϊw�̋��`�ł������Ƃ��Ă��A���̐����h���g�����h���������Ă������Ƃ͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��BLaidler1999 �����炩�ɂ���悤�ɁA�����̌o�ϊw�͈��̋�ʊ��ł���A���܂��܂ȗ��_���������Ă����B���̎����́u�����h�w���v�̗v��Ƃ������̂��u�呠�Ȍ����v�ƌĂ�Ă���̂͏ے��I�ł���B6���́u�呠�Ȍ����v�̂���ɔw��ɂ���Ƒz�肳��Ă����̂͋ύt�\�Z(�u���S�v����)�A���R�f�ՁA���{�ʐ�����Ȃ�u�����������f���v�������B�������߂ł��邩��A�o�ω^�c�ɂ��Ă̊�{�I�ӔC�͐��{�ɂ͂Ȃ����ƂɂȂ�B
�����āA���{�ʐ��C�f�I���M�[�ȊO�ɂ����܂��܂Ȏv�z�I�S���߂��������B���Z��`������ł���B���Z��`�Ƃ́A�i�C�ϓ���(�D�����̉ߏ蓊���ɂ��ߏ�ݔ����s�����ɔp�������悤��)�����I�Ȓ����ߒ��̈�Ƃ݂Ȃ������ł���A���̎����I�ߒ��ɋɗ͉�����Ȃ����Ƃ������Ăł��邾���i�C�̑��₩�ɉ�}��Ƃ������̂ł���B7�i�C�������A���{�ʐ��C�f�I���M�[�Ɛ��Z��`�݂͌��Ɋ֘A���Ă����B���{�ʐ��͎������߃��J�j�Y����O��Ƃ��Ă���A���Z��`�͂��̎������߃��J�j�Y���ւ�(�ߏ�Ȃ܂ł�)�M������̉��������̂�����ł���B8
|
��II.2. �_���̔w�i
���Ԋ��̓��{�ɂ��ẮA�����o�ς̗��ʂ��痝������K�v������B���̎���́A���}�����̗h�Պ��ł���A�����ނ˓�̐��}���������߂����ċ������J��L���Ă����B�������I�����͌��������肳��Ă���A����E����ɕ��y���������`����Ƃ���A���E�����邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B������1927 �N�ɂ͂��������̕��ʑI�������{����A���s�Ƃ��������܂��܂Ȗ����͂�݂Ȃ�������}�����͔��W�𐋂��Ă����B���̈Ӗ��ŁA�����֘_���̂悤�Ȍ��_�킪���̈Ӗ�������������ɂ������Ƃ����悤�B
�o�ς̖ʂł́A��ꎟ���E���ŗA�o���}�L���A�d���w�H�Ƃ̉肪�o�n�߂����{�́A���ɑ傫�ȕs���ƒ���o�����Ă����B�č��̎Q����@���1917 �N9 ���ɋ��{�ʐ��𗣒E���Ă������{�ł́A�č��͂��߁u�e���v�����{�ʐ��ɕ��A����̂����ڂɂ݂Ȃ���A����ɏő���������Ă���B���̏ő����̕\�ꂪ�u�����֘_���v�ł������B
�ő����̌����́A1920 �N��̓��{�o�ς��u�����s���v�Ɋׂ��Ă������Ƃɂ���B9���̈���Ƃ��āA1926 �N�ȗ��f�t���������Ă������Ƃɒ��ڂ������B�s���Ƃ�ׂ邩�ǂ����́A�������������v���X�ł��������Ƃ���c�_�����邩������Ȃ��B�������A1990 �N��̓��{�ɂ����Ă����肦���悤�ɁA�}�C���h�ȃf�t���̂��Ƃł��������������v���X�ɂȂ邱�Ƃ͂��肦��B�܂��A1927�N�ɂ͊֓���k�Ђ�����A��������̕������v�����������ߎ����������͈ꎞ�I�Ƀv���X�ɓ]�������Ƃ�����B������1920 �N��㔼�̐������͂���ȑO�̌X���ɔ�ׂ�ƒႭ�A�l�X�̊ԂɁu�����s���v���������炵�Ă����B
�Ȃ��A���̓����̐l�X�́A�������Z����������Ă��Ȃ��ƍl���Ă����킯�ł͂Ȃ��B���̐����ł���B�������F��̕��������ɂ������Ԏ��ƁA���a���Z���Q��̓��{��s���ʗD��������`(�����������Z)�̔��s�ɂ�����̋~�ϋ�s���͂Ƃɔᔻ�̓I�ƂȂ��Ă����B����ɂ�������炸�A���{�o�ς��u���r�����v���Ă��邱�Ƃ����ł������B
�f�t���̌����́A�����֏����ɂ������ƍl������B1926 �N9 ���ɂ͐ϋɓI���֘_�҂Ƃ��Ēm����Љ��������o�ꂵ�A�O�N��1925 �N4 ���ɂ͋��{�ʐ��̖{�ƃC�M���X�����A�������Ƃ��āA�����֏����ɓ����Ă����B�������֓���k�Ђ��Ȃ���A���̎����ɉ��ւ��Ă�����������Ȃ��B�Ƃ���1920 �N��㔼�ɂ́A���a���Z���Q�Ȃǂ��₦����f�t�����͂������炵�Ă����B
|
��II.3. �_���̓����҂���
���E�A���E�A���E�A��ʃ��f�B�A�A�o�σ��f�B�A�A�����̈��|�I�����h�͋��������֔h�������B���E�ɂ����ċ��������ւ̘_�q�Ƃ����A�����ւ����s�����l�������}���t�̑呠��b��㏀�V������\�ł������B���͏A�C���O�ɂ͋����֏����_�������Ă����̂ŁA�����ւ�����ɂ����l�����t�̑����ɏA�C�����Ƃ��ɂ͈ӊO���������ꂽ���A�A�C���ォ��e��̃p���t���b�g�Ȃǂ�ʂ��ċ��������ւ̂����Ƃ��Y�قȒ҂ւƕϖe����(���)�B�������A���������֔h�̐����Ƃ͔ނɌ����Ă����킯�ł͂Ȃ��B���ہA1920 �N���ʂ��ċ����ւ̕K�v���́A���O�㐭�}�̕ʂ��킸�������ꑱ���Ă������A���̏ꍇ�����ւƂ͋��������ւ��Ӗ����Ă����B�������A1920 �N��̓�吭�}���ׂ�ƁA���F��͏��ɓI�ȂǁA���������������Ƃ͎����ł���B10
���̗A�o�֎~���呠�ȗ߂ɂ���ĂȂ���A��㏀�V�����呠��b�ł��������Ƃ���킩��悤�ɁA�����ւ̐���̒����͑呠�Ȃł������B�������A���̑呠�Ȃ́A�_��ł͂قƂ�ǑO�ʂɏo�Ă��Ȃ������B���ɂ͋����ւɂ������ĕč�����̃N���W�b�g��ݒ肷�ׂ��h�����ꂽ���Ē��ݍ������Ó�����̂悤�Ɂu��̐艺���v���]�܂����ƍl���Ă������̂����Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B11�������A���̈ӌ��͌��ɂ͂Ȃ炸�A�呠�����͈��̃p���t���b�g�ɉ����������ȂǁA���������֔h�ɂ����ĕ⏕�I�Ȗ����ɓO���Ă���B12
�_���̒��Œ��ڂ��ꂽ�͓̂��₾�������A����ɂ͐[��p�ܕ����ق̑��݂��e�����Ă���B�[��͑����̊O����ɏK�n���m�[�}����X�g�����O�h���鍑�۔h�ł���A������s�Ԃ̍��ۋ����Ɉӂ��ӂ��Ă����B���̈Ӗ��ŁA���{�ʐ��ւ̐M�O�͋��������B�ނ͋����֖���ʉݖ��Ƃ��Ĕc�����A�ʉݗʂƁA�����A�ב֑���̊W�ɂ��Ă͒P�������ȗ����������Ă���B���Ȃ킿�A�������ɂ������ւ͒ʉ����ʂ̎��k�ƌi�C�̈������ƍl���Ă����̂ł���(�[��1928�A1929)�B13�������A�ꎞ�I�ȕs�i�C�̌�̉ɂ͋^�O���Ȃ������̂����A�����������ɂ͋����ւ��u�s�i�C�ŊJ��v�Ƃ��Ĕ��荞�܂�Ă������Ƃɂ͌��O������Ă���(�[��1929�A7 ��)�B��ɐ[��͋����֎��s�̗��R�Ƃ��č����̗���s���������邱�ƂɂȂ�(�[��1938�A322-4�ŁG�[��1941)�B
���E�ɂ��ẮA���̎嗬�h�͂قڋ��������֔h�������Ƃ����邾�낤�B�Ȃ��A���̎����̍��E�̎v�z�𗝉�����ɂ́A���{�H�Ƌ�y���A���H��c���A���{�o�ϘA����Ƃ������o�ϒc�̂�A�O��A�O�H�Ƃ������������A�����V���A�r�c���j�A����L���Y��u���E���b�l�v�����ɒ��ڂ���ׂ���������Ȃ��B���Y2002 ����������悤�ɁA1920 �N��̌o�ϊ�@�̎���A���܂��܂ȍ����Ȃǂ̏��������Ă����̂́A�ȏ�́u���E���b�l�v�ƌĂ��l�X�������B���Y�ɂ��A�u���E���b�l�v�Ƃ͐������͂ɉe���͂������o�σV�X�e���̈ێ��E���v�ɖ��m�Ȍo�ύ\�z��L����l�I�l�b�g���[�N�̂��Ƃł���A�P�Ȃ鐭����u���[�J�[�Ƃ͈قȂ�(���Y2002�A��)�B���̑�\�i�́A���E�ɓ]����O�̈�㏀�V�����̐l�������B���Ȃ݂ɁA�o�ϒc�̂̒��ɂ͈ӌ��W�ł��Ȃ��ꍇ�����������A�������P����Ƃ̗��Q�Η��̂������A�ӌ��W��͂Ȃ�����(�O�a2003�A��7 ��)�B14����ɔ�ׂāA�u���E���b�l�v�����͗�O�Ȃ����������֔h�������B15
�w�E�ɂ��ẮA�m���� I�E�t�B�b�V���[�̂��ƂŔ��m�����Ƃ�������原�Y(�c���`�m��w����)��A��������Y(���É��������Ƌ���)�ȂǁA�V�������֔h�̊w�҂����Ȃ������킯�ł͂Ȃ������B���������|�I�����͋��������֔h�������B16���Ƃ��A�y������(�����鍑��w�o�ϊw�������F��ɕ���l�w�ʼn͍��h���Y�Ƃ��ǂ��Ǖ������)�́w�����ցx(���{�]�_�ЁA1929 �N)�Ȃǂ���\�I�ł���B�y���͋��������ւ��ُk�I�Ȍ��ʂ������Ƃ��ÂɎw�E���Ȃ���A���Ƃւ́u��v����������B�܂�f�t���s����O��Ƃ�����ŁA��𗧂Ă�Ƃ����̂ł���B17
�܂��A1920 �N����\����o�ϊw�҂́A���c���O(�������ȑ�w����)�Ɖ͏㔣(���s�鍑��w����)�������B���c�́A1925 �N���炢�����ɋ������h�ɓ]������B���㗬�Ɍ����A�s�Ǎ�������Ȃ��œ���̋��Z����͌����Ȃ��A������u���E�̐����v��f�s����A�Ƃ����_���ł���B���R�u�����؉������֘_�v(�V�������֔h)�ɂ͔ᔻ�I�ł���B�ނ�́u���R�o�ׂ���ɂ�������āA�������ւ̈ꎖ����������Ƃ�����̂ł���B�o�ׂ���ɂ͉��炩�̌`�ɉ��āA�K���o�˂Ȃ�ʁB�����������邱�Ƃ͑����ɉЍ���ق����ƂƂȂ�B�v�͂��̋�ɂ��A����̑ς�������x�ɁA�����A��ʉ����A�Q��������ɂ���B�ُk��`�͍��̂Ƃ��낻�̊��A�Q�����̂����Ƃ��Ó��Ȃ���@�ł���ƐM����v(���c1930�A242 ��)�B����ɐV�������֔h���p���̃P�C���Y��J�b�Z������w��ł��邱�Ƃɂ��āA���̂悤�Ȑh��Ȕᔻ�����Ă���B�u�p���̎��Ɩ��́A�p�������̖��ł����āA���E�̖��ł͂Ȃ��B�����Ă�A����{�̖��ł͂Ȃ��v�B���̖{���͓��{�o�ϊE�̋@�\�ω�(�X�g���N�g�D�[�A�E���@���f��)�ł���B�u�B��M�ɂ́A�P�[���Y�m�}�}�n�A�J�b�Z�������̖ӖړI�M�ҏ����炸�A��M���ʂ̖�肽��֗A���ւɂ��Ă��A�P�[���Y���̉E�����q�܂��J�b�Z�������̍w���͕��������A�w��ǁw��o���x�I�ɑ��āA�����؉������֘_�̍����Ƃ���_�҂���v(222-3 ��)�B18
�͏�̏ꍇ�͂���ɋ����[���B�͏�͂��Ƃ��� 1913(�吳2)�N����̉ݕ��E�����_����I�E�t�B�b�V���[����{�ɂ����čŏ��ɏЉ����l�������B���ꂪ�A�}���N�X�o�ϊw�ɖv�����邱�Ƃő傫�ȓ]���𐋂��Ă����B��ɐ��Ƃ̑Ό��Ŗ��炩�ɂȂ�悤�ɁA�}���N�X�o�ϊw�ɓ]��������̉͏�ɂƂ��āA�s���͎��{��`�̕K�R�ł���A�s����͖��Ӗ��ł���B�s���ɂ����Ă����s�ǎ��Ƃ����Z�����̂ł���B����ɋ��{�ʐ��͎��{��`�ɂƂ��ĕs���ł���A���̔p�~�͎��{��`�̘g���ł͕s�\�ł���A�ƁB19���Ȃ݂ɁA�}�M���Y(�匴�Ќ��������A��ɒ����V��)���͂��߂��̎����̃}���N�X�h�̔����͂����Ȃׂĕs���́u���Z���ʁv������������̂������B20
��ʃ��f�B�A�A�o�σ��f�B�A�ɂ��Ă�����͓����ł���B���ƂɁw��㖈���x�A�w���������x�A�w��㒩���x�A�w���������x�Ƃ����������傫�Ȕ̔��������ւ��Ă����V���́A���������֔h�ł������B21�����Ƃ��T�^�I�Ȃ̂́w���������V���x�o�ϕ����q��P�q�ɂ�鎟�̔������낤�B�u�䍑�ɂċ����ւ��s�ӂ��Ȃ�Έꎞ�I���ۂƂ��ĕs�i�C�͍X�ɐ[���ɂȂ邩���m��ʁv�B�������u����͛߂ނ��邱�Ƃł���v(�u�ב։����Ƌ����ցv�w���Ƃ̓��{�x��5 ����10 ���A1926(�吳15)�N10 ���A���{��s�����Ǖ�1968�A23 ���A16 ��)�B22
�u����������ނ����Ȃ��v�B��������Ȃ������l�X�������B���ꂪ�V�������֔h�������B�ނ�͏����h�������B�����ɂ́A��ɏq�ׂ�����原�Y��A��������Y�Ƃ������w�҂��������A���E�l�ł��A���a�В������R���A�����C���e�����g�A��ꐶ���В���윑���Ƃ������L�͂Ȑl�X���������Ƃ͎����ł���(�����͂��ċ��������֔h�ł��������A�V�������֔h�ɓ]����)�B����ǂ����ۂ̘_��̎��ʂɑ����Ă����A���̒��S�́u�X�̌o�ϊw�ҁv�A���邢�́w���m�o�ϐV��x��h�ƌĂꂽ�A�o�σW���[�i���X�g�A�]�_�Ƃł������B
���݂ł����A���̎����̎咣��ʂ��Ĕނ�̗ߖ��͍������A�����ނ�̎Љ�I�n�ʂ͕K�������������̂łȂ��������Ƃ͒��ӂ��ׂ��ł���B����͐̏،�������f����B�v����ɁA�����̓��{�ł͎㏬���f�B�A�̈ꕔ�ŏ������Ă�����x�̔F���������̂��낤�B23
���̒��S�͂����܂ł��Ȃ����X�R�ł���B���́A1924(�吳13)�N12 ������1946(���a21)�N5 ���܂Łw���m�o�ϐV��x�劲�̍��ɂ������B�劲�͎�M�ƎЎ�����˂�B��M�Ƃ��Đ��́A�����֘_����ʂ��Ă��̓����̓��{�̌o�Ϙ_�d���x�z������̑傫�ȃC�f�I���M�[�ƑΌ������B���ɁA���Z��`�ł���B�l���A���̌o�ϐ���ɂ́A�D�i�C���u��i�C�v�A�Ԉ�������̂Ƃ݂Ȃ��l��������B�ނ�́u�������N�Ȃ�o�ύ����͕s�i�C�Ɉ˂��č����ƕT�z�v���Ă���(�u�s�i�C�͐l�ԎЉ�ő�̍߈��v1930(���a5)�N7 ��7 ���t�����s���}�Ёw���یo�ϖ��u������x��2 ���A�w�S�W7�x�A517�|9 ��)�B�������A�s�i�C�Ƃ́A�x�̗B��̌���ł���J����L���ɗ��p���Ȃ����Ƃ��Ӗ����邩��u�l�ԎЉ�ő�̍߈��v�ł���B�ł́u�l�ԎЉ�́A�@���ɂ��D�i�C���p�������邩�v�B�u�܂��ʉ݉��l�̕ϓ����������邾���ŁA�D�i�C�������͕s�i�C�r���͑����ɏo��������̂ƍl����v(519 ��)�B
���͋��A�o�ċ֎~��������u����ʼn䍑�̈�̖��͉���������Ǝv���Ă���v(�u�s�i�C��̌����v1930(���a5)�N9 ��6 �������ʘ_���A�w�S�W7�x�A365 ��)�킯�ł͂Ȃ������B�u������A�o���֎~�����A�ʉݐ��x�ɉ��v���s����Ɖ]�����ƂɂȂ����Ȃ�A����Ƒ������āA������o�ς����{�I�ɍ��������A�����S�N�̑�v�����鎖�ɓw�͂��˂Ȃ�ʁv(366��)�B�N���̎咣�ł���u���琧�x��A�n�����x�A�Y�Ƒg�D���̉��v���܂��͖��_�̘b���A�ׂ������Ƃɘi���Ă͕s�NJ�Ǝҕs�Nj��Z�Ǝ҂Ȃǂ��������錵�d�̝|����邱�Ƃ��������ׂ��炴��ꍀ�Ƃ��ĉ����˂Ȃ�ʁv�B
�����āA���ɋ��{�ʐ��I�S���ł���B���́A���{�ʐ��ɂ͖{���I�ɖ]�܂������R�͂Ȃ��ƍl����(�u������������]����T�z�v1927(���a2)�N1 ��1 ���E15 �����А��A�w�S�W6�x�A10�|�P�P��)�B�{���͊Ǘ��ʉݘ_���]�܂����B���{�ʐ��͂��܂��܂���܂ŋ@�\���Ă��������ł���B24�������ɊǗ��ʉ݂̂��ƂŁA�K���������邱�Ƃւ̌��O�͂��邩������Ȃ��B�������A����ɂ͒ʉ݁u�����@�ւ�K���ɑg�D����A���͂Ȃ��v(367 ��)�B���́u�����@�ւ����A���{�̏���ɂȂ�ʂ��̂ɂ��Ă����A���{�ʂłȂ��Ƃ��A�ʉ݂̉��l�͗��h�Ɉ��肹����v�B�����āA���̒ʉݓ����@�ւ�ݒu����ɂ͐��{�̑��̍����K�����d�v�ł���B�u���߂������������ړI�Ƃ���悤�Ȑ��{�ł����ẮA���@�ւ̐ݗ����ނ��������v�B
�劲���̋��݂́A�Ў�Ƃ��āw���m�o�ϐV��x�Ƃ�����̃��f�B�A�����S�ɏ������Ă������Ƃɂ���B�٘_���ڂ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B����ǂ��납�A�٘_�����}���Čf�ڂ��Ă���B�������A�ނ����̑唼�����M�����u�А��v���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�ҏW���j�͏�ɖ��m�������B����ɊC�O�̘_���̖|���ϋɓI�ɍڂ��A���̐��m�ȕ��y�ɓw�߂Ă���B
�ނ͂܂��o�Ϙ_���ϋɓI�Ɏd�|���Ă������B���Ƃ��u�V��������4�l�g�v���v�����[�g���ׂ��A�w�V��x�̎��ʂ���A�܂��e�n�ł̍u�����ϋɓI�ɑg�D�����B�����Ę_�q���u�̒��ڑΌ��̏�Ƃ��āA���_����J�Â����B
���ɗD��Ƃ���炸�d�v�Ȃ͍̂����T�g(1891�|1977)�ł������B1926 �N�Ɂw���m�o�ϐV��x�ҏW�����Ō�ɑގЂ����ނ́A���̌�o�ϕ]�_�ƂƂ��Ċ���B����������̂ɔ��ɉs�������́A���̎��X�̎�v�Ȗ��̂قƂ�ǂ��ׂĂɔ������A���̂��߂������т��Ă��Ȃ����Ƃ����X����B���Ƃ��A�w�i�C�̓h�E�Ȃ�x(1931(���a6)�N5 ���F����1931)�́A���㗬�ɂ����u�\���I�f�t���_�v���q�ׂĂ���B�����ɂ��A���ݐi�s���̕����̉����́u�v���v�ł���A��ꎟ���E��킩�畜���������B�A���V�A�v���ȗ��̍��������o�Đ��E�s��ɍĎQ���������V�A�A�����Ĉ����Ȓ����������͂ɂ��Ė��i�ڊo���������̐��Y�͑���ɂ����̂Ȃ̂Łu�P�v�I�̂��́v�ł���(�u��3 �͕��������̊v���ƌo�ϊE����̊��v)�B25����̓��{�͕��������ɑς���̐������ׂ��ł���A���̂��߂ɂ͎��f�Ȑ����ւ̓]�����s���A�u���E�����v���s���ׂ��ł���A�ƁB
����ǂ��A���̕]�_�ƂƔނ�����I�ɈႤ�̂́A�~�N���I�ȑ��ʂł̉��v�����łȂ��A26�V�������ւƂ����`�Ń}�N���o�ς̈���ɗ��ӂ������Ƃł���B���m�̂悤�ɁA�������������֘_�������Ă������X�R��������ĐV�������ւɓ]���������̂́A�����������B27���́w�i�C�̓h�E�Ȃ�x�ł��Ō�ُ͋k�����ᔻ���A�����؉���(�V�����o�����_)����Ă��邵�A�ނ����̎����̎��M��Ƃ݂Ȃ����w���A�o�ċ֎~�_�F�s�i�C�ŊJ�̊�{��x(����1930a)�́A�s�ǎ��Ƃ̓����Ƃ����Ӗ��ł́u���E�����v�̏d�v���͋������Ȃ�����A�f�t���s���̂��Ƃł͂��́u���E�����v�ł���i�܂Ȃ����낤����A���A�o���ċ֎~�����t������ɓ]����ׂ����Ƙ_�w���Ă���B28
����ȊO�ɂ��A�V�������֔h�ɂ͏���(1889�|1972)��R�����(1894�|1966)�������B����́w���O���ƐV��x(���݂̓��{�o�ϐV��)�o�ϕ����A�w�X���o�ϊw�x(����1931)����TV�ł̒����ԑg�u�������k�v�Œm����悤�ɁA�킩��₷�����t�ɂ��o�ω���Œm����B���̏���́A�ŏ�����V�������֔h�ł͂Ȃ������B�ނ͏��a4�N�t���납��V�����h�ւƓ]�������A29���̂��������͐[��p�܂̑���s�W��ł̍u���ł������Ƃ����B������w���O���ƐV��x�ɑS���f�ڂ����ނ͋��������ւ̂����炷�u�ɂ݁v�A�s�i�C���ʂ𗝉����A�u�s�i�C�ŊJ��v�Ƃ��Ă̋��������ւɉ��^�I�ɂȂ����̂ł���(���q��1955�A516 ��)�B30
������l�̎R��́w�����V��x�o�ϕ��L�҂���A�w�ǔ��V���x�o�ϕ������C�����B�����ƒm�荇���ł���A�������ɐV�������֔h�ւ̓]���𐋂��Ă���B��ɏЉ��悤�ɁA�s�����@�Ɩ����ȕ��͂Œm����B�Ȃ��A�w���O���ƐV��x�A�w�ǔ��V���x�Ƃ��ɓ����͔��ɕ��������Ȃ������B31
|
��II.4. �_���̘_�_
�����֘_���͒����ɂ킽��_��ł���A���̊Ԃɘ_�_�͈ړ������B��{�I�ɂ́A�בւ̗�������A�����̏㏸�Ƃ������A1920 �N��̂��̂Ƃ��ǂ��̖��ɑ���u���{�I������v�Ƃ��ċ����ւ͑������Ă����Ƃ����邪�A1927 �N�̏��a���Z���Q�ȗ����҂����������̂́A�u�s�i�C�̑ŊJ��v�Ƃ��Ăł������B�܂��A������̗v�����傫���B���݂���т��Č������n�߂��̂ł���B�����ւ͔������Ȃ��B����ƁA�_�_�͕��A�̃^�C�~���O�ƕ����̐ݒ�Ɍ����Ă���B
��II.4.1. ���������֔h�̎咣
�Ȃ��������ɂ������ւ͖]�܂����̂��H�����_���̉ߒ��ł��̗��R�͈ړ��𑱂������A��Ƃ��Ďl�̗��R�������邱�Ƃ��ł��悤�B���Ɉבւ̈���ł���B�����������A�_����ʂ��Ă���ɑ��锽�͊F���ɓ����������B���{�ʐ����e���ōČ������ȑO�ɂ́A���{�ʐ������Ǘ��ʉݐ��x���]�܂����ƍl���锭�z���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��P�C���Y�����̂悤�ȋc�_�������B���������̃P�C���Y���A�w�ݕ����v�_�x�ȍ~�͊Ǘ��ʉݐ��x���Ă��Ȃ��Ȃ����B
���ɁA�����̉����ł���B���������ւ͈בւ̐�グ���Ӗ�����B����͍����E���Z�̈������߂ɂ���ĕ��������������A�����̐��Y���ቺ�����邾�낤�B�Ȃɂ���A���{�̕����́u���ۓI���������v���������̂�����A�����ւɂ��f�t���́u���ۓI���������ւ̏����v(�������Ɖ�c���u���A�o���֖��Ɋւ���Q�l�����v���a2 �N1 ���F�͏㔣�����l�̔F���������Ă���)��}����̂ł���B���̔w�i�ɂ́A�����̓��{�ł́A�o����x�̐Ԏ��Ɍ�����悤�Ɂu���ۋ����́v���ቺ���Ă���Ƃ������O���������B���̉̂��߂ɂ́A���Y�������������Ӑ}�I�ȕ����������]�܂����Ƃ����̂ł���B����ɁA���̎���́A��ꎟ���E����̍����ɂ����鍂�C���t���A�h�C�c�E���������ɂ�����n�C�p�[�C���t���̋L�����܂��V��������ł��������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����������̌��͐����_�c��傫�����E����B
��O�ɁA�u����Ƒ̖ʁv(�[��p�܂�1928(���a3)�N11 �����o�ω�ł̍u��)����������B���{�ʐ��ւ̕��A�́u���E�̑吨�v�ł���B1925 �N�ɃC�M���X�y�у|���h���������������ŋ��{�ʐ��ɕ��A���A�t�����X��1926 �N�ɐV�������A�����肵�A28 �N�ɕ��A���Ă���́A������e�������ׂĕ��A������ԂɂȂ��Ă����B����ɋ��{�ʐ���]�܂����Ƃ݂Ȃ��C�f�I���M�[�����т��A����O���[�o���E�X�^���_�[�h�ɓ��{�����X�ƕ��A����ɂ͋��������ւ����Ȃ��Ƃ����C�����������̂ł���B
��l�ɁA�������ɂ������ւ��s�i�C�������炷���Ƃ͂悭��������Ă���(���Ƃ��ΐ�Ɍ������c���O�̔���)�B�����Đ��Z��`�̉e���������Ƃ������Ɍ�����̂͂��̓_�ł���B
��������A�����玸�Ƒ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ꂪ���肤��B��̓y�� 1929 �̋c�_������ł���B�����ւɔ����u�ɂ݁v�ɂ͏\���z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����c�_�ł���B
���������̈���ŁA�R����������j�����悤�ɁA�����ߒ��̒x�����悢�ƍl������̒����_�҂������B�u�ꂵ�ނ��悢�̂ł���B���{�̍��E�͐펞�ȗ����܂�ɕs�^�ʖڂ������B������傢�ɋꂵ��ő����Ɏn�߂č��E�̍���������������悤�v(�R��1929b�A95 ��)�B���Z��`�ɂ́u�����I�A�s�[���v�������Ă����B
���ꂪ����ɁA���ۂɏ��a���Q�Ɏ����Ă���́A���c�原(�쑺暌��o�ϒ����������玞���V��i�C��������)�̂悤�Ƀp�j�b�N�̐��Z���ʂ���������c�_���������B�u���E�����v��O��I�ɐi�߂邽�߂ɂ́A���������ێ����Ȃ���p�j�b�N���N�����A����ɂ���Đ��Z���ׂ��ł���Ƃ����咣�ł���B�ނ́A���a���Q�̂��Ȃ��Ɂu�勰�Q��傢�ɑ��i�������v�Ɣ������邱�ƂɂȂ�(�w���m�o�ϐV��x��1418 ���A23 �ŁB���{��s�����Ǖ�1968�A��23 ���A621 ��)�B
��II.4.2. �V�������֘_�҂̘_��
����̐V�������֘_�҂̘_���͎��̂Ƃ���ł���B���ɁA�בւ̈���͏d�v�ł���B�������A���̂��߂ɂ����A�������[�g�ɋ߂��V�����������Ƃ��]�܂����B�������ւƈ����グ�Ă������Ƃ͈���Ȃ����ꂪ����B
���ɁA�C���t���Ɠ����Ƀf�t�����Q���ł���B���̓_�������Ƃ������Ɏw�E�����̂����X�R�ł���B�����̉�������]����̂́u�T�z�v�ł���(���X�R�u������������]����T�z�v1927(���a2)�N1 ��1 ���E15 �����А��A�w�S�W6�x3�|11 ��)�B�����̒��߂͗\�z�ȏ�ɒ��������낤���A����͊�Ǝ��v�������A�����̌ٗp�Ə��������ނ�����B���������u���ۋ����́v���l����ۂɁA�������h�͑Γ����l(�����ʉݕ\��)�ƑΊO���l(�O�ݕ\��)�ɂ��č������Ă���B�V�����ɂ�����(�f���@�����G�[�V����)�́A��������������(�f�t���[�V����)�������ɁA�u���ۋ����́v���ł���B���̎��_���A��{�I�ɃP�C���Y�́w�ݕ����v�_�x(1923 �N)�ɑ�\����鉢�Ă̌o�ϊw�̍ŐV������O��ɂ��Ă��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
��O�̋c�_�ɂ��āA�R��͐V�������ււ́u�B��́A�����Ƃ����͂Ȕ��_�v�Ƃ��Ă���������B����͋��������֘_�ɂ́u�o�ϓI���R�v���Ȃ����Ƃ𝈝��������̂��낤���A�������A�R��́u���p�̖ʖژ_�v�Ƃ��đނ���(�R��1929a�A148 ��)�B�t�����X�̗�Ɍ�����悤�ɁA����ɍ������V�������ւ͔F�߂��Ă����B���{�̏ꍇ�A�푈�Ńt�����X�̂悤�ɑ�Ō������킯�ł͂Ȃ��������A���łɋ���������O���10 �N�ȏオ�o�߂��Ă���B�����̋}���Ȉ����グ�͌o�ςɑ�Ō���^���邾�낤�B
��l�ɁA�u��������������A���{�̎Y�Ƃ��ǂ��Ȃ�Ƃ����l���́A�Y�ƊE�����Q�؎̂đ����̏��ɐ�����K�v�Ƃ��鎞��ɉ��Ă̂ݐ^���ł����āA�ϋɓI���������g�D����@�̑������K�v�Ƃ��鎞��ɂ͊������ěƂ܂�Ȃ��B�Ⴕ����Ȃ��Ƃ������ł��]�ւ�Ȃ�A�K�������������ɕ��A�������łȂ��A���X�V���������@�蕽���ɉ��ς��邱�Ƃ��A�䂪�Y�ƂB�����߂�ł��낤�Ɖ]�Ӌc�_���������킯�ł��邪�A���炭����Ȕn���������Ƃ�M����l�͂���܂��v(151�|2 ��)�B��Q����͎̂Y�ƂƎY�Ɛl�ł���B�u�������ɂ���ċꂵ�މ��ւ����邱�Ƃ��ꌩ���`�̔@���Ɍ����āA���̎��ł����`�ɔ�������̂ł��邱�Ɓv�ł���(148 ��)�B������A�����T�g�̗��ꂪ�T�^�I�����A���Ƃ��u���E�����v�̕K�v����F�߂��Ƃ��Ă��A��������s����ɂ͓��{�o�ς�����Ă���Ƃ����l����������B�u���E�����v�ɕK�v�Ȃ��̂����A�V�������ւƂ����̂��A�����̗���ł������B
|
��II.5. �_���̕]��
�_���̕]���́A�ǂ̂悤�ȏ��W����O��ɂ��邩�ŕς���Ă���B���Ƃ��A���ł�1910�N�ォ��A�t�B�b�V���[��ɂ��V�����o�ώv�z���萶���n�߂Ă�����(Laidler 1991)�A���{�ł��ݕ��E�����_���Ƃ����`�Ŋw�E�ɂ͋z������������B�����Đ�Ԋ����\����o�ϊw�҂����́A�J�b�Z���A�t�B�b�V���[�A�P�C���Y�A�z�[�g���[�ł������B���̏��W���ɏƂ炵���킹��Ȃ�A�V�������֔h�̗D�ʂ͓����Ȃ��B
����ǂ��A�� I �߂ł݂��悤�ɁA�����̗����͐Z�����Ă��Ȃ������Ƃ����l���͂��肤��B�����̉��Ăł͋��{�ʐ��ɔ������o�ϊw�҂����ł͂Ȃ��A�^�������o�ϊw�҂���������ł���(���Ƃ���LSE �̃O���S���[�A���r���Y�Ȃ�)�B�������A���������֔h�͖ړI�ɂ����č������Ă����̂������ł���B�K�v�Ȃ̂͋��{�ʐ��ւ̕��A�ł���A����ɂ���Ĉבւ̈���A�����̈����B������̂��ړI�Ȃ�A�V�������ւ̂ق����D��Ă������낤�B�܂��A�Γ����l�ƑΊO���l�̋�ʂ́A�K�������ŐV�̋c�_�������o���Ȃ��Ă��킩���{�I�Ȍo�ϊw�I�m���ł���������A���̓_���������Ă������������֔h�͊�{�I�ȊԈႢ��Ƃ��Ă����B32
����Ǝc��̂́A�������̂��u����ƑΖʁv�Ɛ��Z��`�ł���B�ǂ�������ł��邪�[���Ȃ̂͐��Z��`�ł���B���Z��`�ɂ͐����_�Ƃ��Ēv���I�Ȍ��ׂ�����B���Z��`�́A�Z���ɂ����Ă͒ɂ݂�K�v�s���Ƃ݂Ȃ����A�����ɂ����Ắu�₪�āv���W�������炷�Ƙ_����B���́A�����ł����������ǂꂭ�炢���w�������܂��������m�ł͂Ȃ����Ƃł���B
De Long 1990 ���_����悤�ɁA19 ���I�̖��܂Ōi�C�z�͉s���u���^�œ����t�����Ă�������A���̂Ƃ��ɂ͐��Z��`�͑Ó������\���͂���B�������A���{�ʐ��Ɠ��l�A���ċ@�\���Ă������̂��@�\���Ȃ��Ȃ����ɂ�������炸�ێ������Ƃ����̂́A�܂������C�f�I���M�[����䂦��ł���B
|
|
��III. ���a���Q�F�����ւ̋A�� |
��III.1. ���Q�̌���
�������ł̋����ւ� 1929 �N11 ���Ɍ��肳��A��1930 �N1 ��11 ���Ɏ��{�����B�����l�X�͋����ւɔM�����A�����s����㏸�����B�����������Ɋ����s��͉������A1930 �N�̎����������͂ق�0���ɗ������ށB���Ɨ��͏㏸����B�Ȃ��A���̂Ƃ��̓��{�̎��Ɨ���1931 �N1 ���ɂ�����5.3���A�s�[�N����32 �N 7 ����7.2���ł���B331933 �N�� 25���߂��ɒB�����A�����J��A����ȏ���L�^�����h�C�c�Ɣ�ׂ�ƒႢ�B�������A���{�͂܂��A�J���o�ϊw�ł���������u�]���_�v�z�������Ă��炸�_�ƕ���̔�d���傫���������ƁA����Ɏ��ƕی������݂��Ȃ��������Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_���̂����ނ�����Ō����l����ƁA�������������ȏ�Ɏ��Ԃ͐[���������ƍl����ׂ��ł���B
�����ւɂ��āA���E���Q�Ƃقړ����ł������^�C�~���O�̈������w�E����ӌ�������B��㎩�g�����̂悤�ɕٖ����Ă��邪(���1930)�A����������͋��������֔h�̂��������̗���Ɛ����I�ł͂Ȃ��B���Z��`�I���ꂩ�猾���A���E���Q�͐���������ɑ��i������̂Ƃ��Ăނ��늽�}���ׂ������炾�B���ہA���̖{���͈�������Ƃ́A���ɉے��ł��������ق̂߂����Ă���B34
|
��III.2. ���Q��
���Q�ɑ��āA���{�A�Y�ƊE����͂��܂��܂ȋ��Q�u��v���ł��o���ꂽ�B�܂��A���E���b�l�����ɂ���Ċe���Ƃ̌o�c�����A�z�����������i�����B����Ɠ����ɐ���n���Z�@�ւ��u����v���邱�ƂɂȂ�B�ӂɉ���Ȃ����{���Ƌ�s���ق͍X�R����A��C�ɐ��b�l�̈�l�ł��錋��L���Y���A�C���A�~�ϗZ�������s�����(���Y2003�A�Ƃ��ɑ�3 ��)�B
����A���{�����ł͏��H�Ȃ��䓪����B1929 ����30 �N�ɂ����āA�ꋓ��19 ���̃J���e�����`�������B����̓J���e���j�������A�E�g�T�C�_�[�̑��݂����e���Ă���������E�͐��{�ɋ����̐�����v�������B1931 �N�ɐ��肳�ꂽ�d�v�Y�Ɠ����@�́A�J���e���j�������J���e�����̂��߂̖@���ł�����(���{1989�A117 ��)�B�u���E�v�̗��Q�Ɗ����̗��Q����v�����̂ł���(����ȏ�̓����g��ɂ͍��E�͔�����)�B
������v�z�I�Ɏx�����̂͐V�����C�f�I���M�[�ł������B���̎�������}���ɎY�ƍ������Ƃ������t�����s����B���Ƃ��Ƃ̓h�C�c�� 1920 �N�㏉���ɁA���[�e�i�E������h���t�������T�O�ł���(����1996)�B���̍����{�ł͂��قǒ��ڂ���Ȃ��������A���Q�̓����ƂƂ��ɒ��ڂ��W�߂��̂́A�Y�ƍ������������z����J���e�������Ӗ����Ă������Ƃł�����B�������H��c����1930 �N11 ������Y�ƍ��������������s�������ŁA1930 �N12 ���ɂ͓��{���H��c���̉����Ƃ�ŎG���w�Y�ƍ������x���n�������B�Y�ƍ������ƂƂ��ɁA�����o�Ϙ_������ɂȂ�B
|
��III.3. �]���_
1931 �N�́A���E�o�ςɂƂ��Ă̑傫�ȓ]���_�������B1930 �N�̌i�C��ނ͋}�����������A�s�������E�勰�Q�Ɉ������钼�ڂ̂��������́A1931 �N�ɐ��������Z��@�ƒʉ݊�@�̘A���ɂ�����(James 2001)�B���{�ʐ��͌Œ葊�ꐧ�ł���A�Œ葊�ꐧ�̏�Ƃ��Ēʉ݊�@���������₷���B���Ό��̓I�[�X�g���A�������B5 ���ɃN���f�B�[�g�E�A���V���^���g���|�Y���A7 ���Ƀh�C�c�̋��Z�V�X�e����s���艻��������A�C�M���X�ɓ��@�U�����W������B�C�M���X�́A�|���h�h�q��������߁A9 ��21 ���ɋ��{�ʐ����痣�E����B�A�����J�́A�����ʉݖh�q�̂��߁A���q���̈����グ�őΉ����A�����o�ς��}���ɗ₦���܂���B
�C�M���X�̋��{�ʐ����E�̎��ɕW�I�ɂȂ����͓̂��{�������B���@�U�����W������B����ɑ��Ĉ��͉~�h�q�ɖ��߂邪�A���݂̌������������B���̂Ƃ����͓��@�I�v�f����̃h���������I�ɔ����B���̔�����(���ɎO��)�Ɍ�����ꂽ���Ƃɂ���āA���̌�̍����ᔻ�̘_�������܂�A���ʂƂ��Ēc����(�O�䍇���В�)�̈ÎE�Ȃǃe�����Ƃ͂���߂Ĕ���ł���B�ނ��A���̓��@���I�O��ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�����T�g�͓����A�h�������͌o�ύ����I�ȍs���ł���Ɓ\�����ɂ��\�_���Ă���B
�C�M���X���l�A���{�̋��{�ʐ��ė��E��s���ɂ����̂͂��̒ʉ݊�@�������B�������A�C�M���X�̏ꍇ�ƈقȂ��Ă����̂́A�C�M���X�ł͋��{�ʐ����A��A���{�ʘ_�����قڎ������Ă������_�Ŋ�@���}�����̂ɑ��āA���{�ł͘_�d�ɂ����ċ����֘_�����܂����킳��Ă������Ƃł������B
�����āA�����S���҂ł����㏀�V������Ƃ��Đ����]���ɉ����Ȃ��������Ƃ��قȂ�B�������A9 ��18 ���ɂ͖��B���ς��N���Ă����B���Ɖ����m�Ɏu������Ό��Ύ��ƌR���̈ꕔ���A�ΊO��@�����o���ׂ����������o�����ł��邪�A���̎����𐭍��]���̍D�@�Ƃɂ�l�X�͑��������B���̐M�����镔���ł������呠�ȍ��ɉے��؈�j�́A��@�ɂ����Đ����]�����s���͓̂��t���b�̐ӔC�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ɛi���������A���͕�������Ȃ�����(��1994�^2001�A142 ��)�B
|
��III.4. ���f�B�A�̘_��
���̍��̃��f�B�A�̘_���ɂ͑傫�ȕω���������B����܂ŋ����ւ��^�����Ă������A�u���Q�Ƃ����������P�v���A�����̃��f�B�A�̈ӌ���ς����B���Ƃ����āA�����͂܂����m�ɐV�������ցA�Ȃ����͋��ċ֎~�ɑg�݂���܂ł͂����Ȃ��B���܂��܂ȋ��Q�u��v��v�����邾���ł���B�V�������֔h�̎咣�́A�u���v�������ꂽ�܂܂������B
�������A�_�d�ɂ͏��c�原�̂悤�ȁu�����ȁv���Z��`�҂������B���̎����̘_����ǂ������Ă���̂�1930 �N9 ��1 ���E8 ���ɊJ�Â��ꂽ�u���A�o�ċ֎~��蓢�_��v�ł���(�w���m�o�ϐV��x��1418 ���A1421 ���B���{��s�����Ǖ�1968�A��23 ���A613�|31 �łɎ��^)�B���_��ɏW�߂�ꂽ�̂�8 �l�B�V��������4 �l�g�͂��ׂĎQ�����Ă���B�_�d�ł͏����h�̂͂����A���̓��_��̐l�I�ł͌݊p�ɂ݂��邠����A����߂ċ����[�����̉��o�ł���B����ȊO�́A�ԏ�����(�Љ��O�}���L��)�A���c�^�l�Y(�_�C�������h��M)�A���c�原�A�X�c�v(�����V��o�ϕ���)�Ƃ�������Ԃ�ł���(�Ȃ��A2 ��ڂ̓��_��ɐԏ��͌��ȁA����Ɏ����V��o�ϕ��̐����^��Ɠ��m�o�ϑO�劲�̎O�Y�����Y���Q������)�B�ԏ��������āA����������������֔h�ł���B
���_��͓��m�o�ϐV��Ђ��犧�s���ꂽ����̕����R���w��㑠���̍��o�x�̍��]����n�܂�A������s��̂Ƃ��ē���͐M���ł��邩���_����ꂽ�B�R������͐V�������֘_�Ƃ̑Ό��p��������Ȃ�����A�Ƃ��ɐ[��p�܂ւ̕s�M���������ɂ��邪�A�������͓���A�Ƃ��ɐ[���M�����A�呠�Ȃ̕��j���ς��Γ�����ς��Əq�ׂĂ���B���̌�A�V�������ւ́A�f�t���̃`�F�b�N�ƂȂ�̂��A���邢�͂��ꂾ���Ōi�C�͂悭�Ȃ�̂��A����ɂ̓C���t���ƍ��E�����̊W�A�V�����́u�؉��\�z�_�A�����A�؉��_�܂ōs�����Ԗ��v�A�ċ֎~���s�̕��@�A�����A���ʂȂǑ��ʓI�Ȗ�肪���_����Ă���B
���̎��_�ŐV�������ւ͌����̃f�t���s���A���a���Q����E�o���邽�߂̈��̕������艻�ڕW����Ƃ��đ������Ă����B����ǂ��A���̓��_��ł̏��c�̎咣�̂悤�ɁA���Z��`�͍����������B�ނ͋��Q����Ƃ��Ă͂Ȃ炸�A���E��������i�Ɛi�߂�ׂ����Ǝ咣����B�V�������ւɂ��~�ύ�ɔ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�������A�~�ύ�͐i�s���̍��E������j�Q���邩��A�~�ς���Ƃ��Ă�������łȂ���Ȃ�Ȃ��B�u�勰�Q��傢�ɑ��i�������̂ł��v(�w���m�o�ϐV��x��1418 ���A23 �ŁB���{��s�����Ǖ�1968�A��23 ���A621 ��)�B
���̎����A�e��A���P�[�g�������悤�ɋ��ċ֎~�ւ̊S�͍��܂��Ă����B�������A�܂��������߂Ă��Ȃ������B35�����炭���̂܂ܑ����Ă��Ă��Ō�܂ő������߂Ȃ�������������Ȃ��B
|
|
��IV. ���Q����̒E�o�F�����֘_���̏I�� |
��IV.1. �����]���̉ߒ��F2 �i�K���W�[���]��
���a���Q����̒E�o�́A�����]���ɂ���ĂȂ��ꂽ���A����� 2 �i�K�\���{�ʐ�����̗��E�ƈ�w�̋��Z�ɘa����\����Ȃ��Ă����B���̐����]�����\�ɂ����̂́A���ɓI�ɂ͐��ǂ̕ω��������B�������F���c�m���1931 �N11 ��10 ���ɋ��ċ֎~���c���s���Ă����B36�����������A��㑠���͋��A�o�֎~�Ɋւ��鐺�����\���A���{�ʐ��̈ێ����ӂ�\�����Ă����B37
���Ǖω��̂��������͊t���s����ɂ���āA��Γ��t�������E�������Ƃ������B���F��Ƃ̋�����v���t���u������������B������������������ł���B���F��Ƃ̘A���͌o�ϐ���̓]�����Ӗ�����B���B�͋��ċ֎~�h�������B
12 ��13 ���ɐ����������{���t�̑����ɏA�C�������������́A�[��p�܂̌��������āA�������{�ʐ�����̍ė��E�����肷��(�[��1941)�B�������ċ��{�ʐ�����̗��E�Ƃ������W�[���̓]�����}��ꂽ�B�������A�o�ϊ�@�ɑ��鍂�������A�[��p�܂̔F���ɂ͊Â��Ƃ��낪�������B�����͋��A�o�ċ֎~���i�C�]����ł͂Ȃ��A����ȏ�ɋ��Z�ɘa���s�����߂̃��t������ł��Ȃ��Ɩ�����������ł���B���{�ʐ�����̍ė��E����A���S�Ȑ����]���܂ł͂�������]�Ȑ܂��o�邱�ƂɂȂ�B
���ʂƂ��āA�����͍Ăщ������A���Ƃ͐[��������B�ꎞ�����������Ɨ���31 �N�������炳��ɏ㏸����B����ɏՌ��I�������̂́A5.15 �����ł���B���̎��R���ɂ���ĈÎE�����Ƃ������Ԃɐ��{�͐����]����]�V�Ȃ����ꂽ�B
�����������g�̌o�ώv�z�ɂ��ẮA�Ƃ��ɃP�C���Y��`�Ƃ̊W�ł���܂Ō����̑ΏۂƂȂ��Ă����B�������A�ނɌo�ϊw�I�ɖ��m�������тƂ����v�z�����҂���Ǝ��]���邱�ƂɂȂ�(����1936)�B�������A�V�������֎l�l�g�̘_����m��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B����ǂ��A����I�łȂ������o�ϗD��̎v�z�A�o������w�ԃv���O�}�e�B�Y�����ނ̖{�̂ł������B
����I�Ȑ����]���Ɍ����āA���{�����A�Ƃ��ɑ呠�ȂƓ���̋������͍������悤�ɂȂ�B���B2003 �̐}�\�������悤�ɁA11 ��26 ���̓���ɂ��Γ���U�����́A�呠�ȂƓ���̂������������̌��ʂł������B���̎��_�܂ŋ��{�ʐ��̗��E����͂قڈ�N�A5.15 ��������͂��悻���N���܂肪�o�߂����B38
|
��IV.2. ���t���h�̑䓪
���̍��A�V�������֔h�͍ċ֎~�h����A����Ƀ��t���h�ւƓ]���𐋂��Ă����B�e�������{�ʐ����痣�E���Ă��錻�݁A���{�ʐ��̈ێ��͂��łɎ���x��ł���B���̋��Q���炢���ɒE�o���邩�B���t���h�͂���Ɉ�i�̍������Z����ɂ�郊�t���[�V����������A���m�Ȑ����]����v������B���̎����ɐ��X�R�́u���{�ʂ̒�~�ƍw���͂̑��i�v�A�����āu�C���t���[�V�����̈Ӗ����@�y���ʁv�Ƃ������ނ̌o�Ϙ_���̍ō�������������ƂɂȂ�B39���t������Ƃ��ĕK�v�Ȃ��̂́A1.���q�����������A2.���J�s�ꑀ��A������3.���c(����)���Ƃ̐��i�ł���B���̂����A3.�͎��Ƃ̎��ƋK�͂����ɂ߂�̂�����Ƃ��ċ��Z����Ɋ��҂�������B���������͍��������P�Ƃł͕����㏸�ɂȂ���Ȃ����Ƃ��m�����Ă����B��������ɂ���ĉ��傳��Ȃ�����A�ʉݗʂ��������A�ʉݗʂ������Ȃ���C���t���[�V�����͈����N������Ȃ�����ł���B�����ŁA������s�ɂ���̐���Ɋ��҂������A���҂Ƃ��L�p�Ƃ��Ȃ�����A���ړI�Ȃ̂͌�҂̌��J�s�ꑀ��ł���ƍl�����B
���̗v�_�́A�O��I�Ȓʉ����ɂ��C���t�����҂̏����ł���B�ŏ��A���̌��ʂ͗e�Ղɂ͔�������Ȃ���������Ȃ��B�������A���҂̕ω��ƃC���t�����̂��̂̌��ʂ��u�݂��Ɉ��ƂȂ�ʂƂȂ�āA�����ݐϓI�ɍ�p����v(�w�S�W8�x�A457 ��)�B�Ƃ����̂��A�ʉݖc�����u�拭�ɑ�������Ȃ�v�A�ǂ�ȁu��s�ł������Ɏ�����V���Ă����킯�ɂ͂����ʁv���炾�B�͂��߂̓R�[���s��Ɏ������o�邪�A�����̎s������������邩��A���ꂩ��͊����y�ѐV���s�̏،��ɓ������邱�Ƃ�]�V�Ȃ������B�w���͂́A�͂��߂͊����،��ɑ��邻��Ƃ��āA���ꂩ��V���s�̏،��A�����ē��Y�E�s���Y�ɑ��邻��Ƃ��Č���������B���̌o�߂������̑��ʂ���݂�A�Z�������A�����Ē������������������邱�Ƃɂ���āA�����͑������邾�낤�B��������������A���ƘJ���ւ̎��v���N���邱�ƂɂȂ�B���t���h�́u���̌��ʂ�����܂ŁA�拭�ɃC���t���[�V�����𑱂��ׂ��Ɛ����̂ł���v(458 ��)�B�ʉݖc�����u���ǁA�����đ������ɉ��Ċ�������͋��炭�ӊO�ɋ}���ɁA�������M��U�����ׂ��́A���̓��R�ɂ��āA�����^�f�����ޗ]�n�͂Ȃ��v�Ɛ��͌��_�t���Ă���B
�����ɐ��̓��t������ւ̔ᔻ�ɂ������Ă���B�u�ꂽ�уC���t���[�V�������n�߂�ƁA�����ɔV�𑱂��˂Ȃ�Ȃ��v����A���̌��ʑ�ꎟ����̃h�C�c�̂悤�ȃn�C�p�[�C���t�����N���邾�낤�Ƃ����ᔻ���������B���́A�n�C�p�[�C���t���́u��펞�̐��{�̍�����̕K�v�v����N������̂ł���Ǝw�E���A�����̒���C���t���ɂ́u���߂��疾�ĂȌ��x������v�Ƃ����B���̃��t���̓n�C�p�[�C���t���̂悤�ȁu�푈�Ƃ����@���O�I�������甗��ꂽ����ƈقȂ�A���{���͒�����s�̗~����܂܂ɓ���������B����ɉ��̊댯�����낤�B�ꂽ�уC���t���[�V�������n�߂�A�~�ߓx���Ȃ��ɓ��낤�Ȃǂƌ��ӎ҂́A�v���S�����炴��҂ł���v(463��)�B
|
��IV.3. �����]���̐���
����̊��S�]����̐��ʂ͂߂��܂������̂������B�������[����Z�����̂��ƁA���{�o�ς͋��ٓI�ȕ����𐋂���B�����͌������f�t������}�C���h�ȃC���t���ɓ]������B�������㏸���A���Y���L�т�(�����������̕��ώ�����������7���ȏ�ɒB���A���̍��x�������ɂ��C�G����قǂł���)�B�בւ��������A�N�ǂ��Ă����d���w�H�Ƃ͑��𐁂��Ԃ��A�Y�ƍ\���̓]�����}���ɐi�B����ɁA�����̏㏸�ɔ����A��Ƃ̎������B�\���̓]�����}���ɐi�ނ��ƂɂȂ�B���{�o�ς̍\���ω��𑣐i�����̂̓f�t������̒E�p�ł������B
�Ȃ��A���̕����̌������������̐��ʂɋ��߂錩�����Ȃ��ł͂Ȃ��B�ُk�Ƌ��Q�ɂ���č��E�������i�݁A���{�o�ς̐��Ԃ���̎������P���ꂽ���߂Ɍ�̃��t������͐��������Ƃ��������ł���B40���̌`��ς������Z��`(���Z��`�}�[�NII)�́A�����������؉\�Ȗ��肩�ǂ����^�킵�����A���Q�̂��Ȃ��Ɂu���E�����v���i�����������邱�Ƃ͂ł���B���Ƃ��A�I�[�o�[�o���L���O���(��s�ݏo�̑���������)�́A���a���Q�ɂ���Ă͉�������Ă��Ȃ��������A�����������Z�̎c���́A���Q�ɂ���Ă��܂����Ȃ�c���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B41
|
|
��V. ����F�o�ϊ�@�̋��P |
��V.1. ���a���Q���̌�F����I�Ȋ�H��
���E���Q�̌�A�E�o��Ƃ��Ď��݂�ꂽ�̂́A�u�����̍��ł̎Љ��`(socialism in many countries)�v(Temin 1989)�������B�����̍��ō��Ƃɂ�铝���A��������傷��B�i�`�X�h�C�c�Ȃǂ̓����o�ς��̂��̂͂����܂ł��Ȃ��A�A�����J�̓j���[�f�B�[��������@�ɘA�M���{�̖��������債�A�C�M���X�ł��u�Y�ƍ������^���v�A�����ĕ������ƌ��݂Ƃ����`�ŁA���{����������B
���{�́A���������̂��Ƃ��낤���Ċ�@�����������̂悤�ɂ݂������A���Q�u��v��͍����钆�ŁA�R���A������`�������̑̐��ɑ��閣�͓I�ȑ�ֈĂƂ��ĕ��サ�Ă���B���B�������́A�����̒��ŊJ���邽�߂̕��@�Ƃ��č����ɔM���I�Ɋ��}���ꂽ(Young 1998)�B�������ÎE���ꂽ��A�R���ւ̎��~�߂��Ȃ��Ȃ�A�R���哱�ɂ��̐��̓]���������炳�ꂽ�B���X�R�Ȃǂ͂��̌���w���m�o�ϐV��x�����_�ɉʊ��ɌR����ᔻ�����������A����͎��s����B
�R�������ł͂Ȃ��B���}�����̌�ނƂƂ��ɁA�����̖����͊g�傷��B�\�Z���߂���呠�����̌����͑��債�A���Q��Ƃ��ē������ꂽ�Y�Ɛ���ɂ���ď��H�����̌��������傷�邱�ƂɂȂ�B�܂��Ɂu�o�ϊ�@���Y�Ɛ���ݏo�����v(Johnson 1982, p.114;�M��123 ��)�B���̉ߒ��͐������̐₦������̌��ʂł���������A�u1940 �N�̐��v�Ƃ�������I�ȊW�������������Ȍ��t�͕s�K�����낤���A���Q�����ɂ��Đ������̃o�����X�����̑��ɌX�����͎̂����ł������B
�����ɐ������̂͌o�ώЉ�\�z�̂��߂������ł������B�ŏI�I�ɂ͋��{�ʐ��C�f�I���M�[�A���Z��`�͌�ނ��Ă������A�ʂ̃C�f�I���M�[���䓪���Ă���B�J����`�����̈�ł���B
�������ɂ����{�ʐ����A�Ƃ����Ӑ}�I�ȃf�t������́A���}�������吳�f���N���V�[����������Ă��܂����B���ʂƂ��āu1940 �N�̐��v�������炵���̂́A�\�����ɂƂ���ăf�t�����Ӑ}�I�ɑ��i�����}�N���o�ς̎����ƁA����𐳓����������鐭��v�z�������B
|
��V.2. ��̋��P
�o�ϐ�����߂���m���Ƃ����ϓ_����́A�����֘_�����牽���w�ׂ邾�낤���B
���ɁA�l�X�̊��҂̖�������������B�����֘_���̐�킳�ꂽ13 �N�Ԃ͓����̐l�X�ɂƂ��āu����ꂽ13 �N�v�������B���i�C��́u�����s���v�ɂ����āA�����́u�����v�����A�����s�ɂ������Ԏ����P��I�ł���A���Z�͓�����ʗZ�����s�ɂ���ē���͋~�ϋ�s�������ƍl�����Ă����B�ŏ��̓C���t����A���Ɉב։�A�בֈ����Ƃ��đł��o���ꂽ�����ւ��A1927 �N�̏��a���Z���Q��ɂ́u���r�����v�������{�o�ς̍Đ���Ƃ��Ċ��҂��W�܂����̂́u�s�i�C����̑ŊJ��v�����߂��l�X�̊��҂ɂ��Ƃ��낪�傫���B
���ɁA�o�ϐ����_���̏�Ƃ��āA�����o�ϊw�I�Ș_�_���������ɂȂ����̂ł͂Ȃ������B���{�ʐ��̂����܂��܂ȁu�ǂ��v���l�ς��_���ɂ͐F�Z�����f���Ă����B�u���E�����v�����̎���̃L�[���[�h�ɂȂ����̂́A���Z��`�������I���͂������Ă�������ł������B����Ɋ֘A���āA�o�Ϙ_���ɂ͂�����u���`�v�A���z�̊ϓ_�����܂Ƃ��B�V�������ւ̎咣�́A���i�C�ő�������������A�����~�ς���̂��A�Ƃ����������_�҂̌���Ɠ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
��O�ɁA�ߋ��̋L���͖����ł��Ȃ��B�h�C�c��(�n�C�p�[)�C���t���[�V������A�����̃C���t���[�V�����̋L�������X���������Ƃ��ɁA�V�������ցA�����Ă��̌�̃��t������ւ̎x���͂Ȃ��Ȃ������Ȃ������B
��l�ɁA�w�E���܂߂āA�_�d�̈��|�I�����͋��������֔h�ł���A�V�������֔h���邢�́u�ċ֎~�o�����v�A���t���h���_�d�ő������߂����Ƃ͌����ĂȂ������B�������A���ւƂ���ɔ������a���Q�ɂ���āA�V�������֔h�ւ̊S�Ǝx���͔���I�ɍ��܂��Ă������B
�w�҂̋c�_�́A�����ꕔ�̐V�������֔h�������ċ��{�ʐ��C�f�I���M�[�Ɛ��Z��`�ɂƂ���Ă����B�}���N�X�h�͖T�ώғI�ԓx�ɏI�n���邩�A���Z��`�̊ϓ_�ɗ����Ă����B
����̐V�������֔h�Ɏ��s���낪�Ȃ������킯�ł͂Ȃ������B����ǂ��납���s����͔ނ�ɂ����������B���X�R����O�ł͂Ȃ��B�ŏ��ɋ����ւ𑣂����͓̂��m�o�ϐV�������A���������ւ���V�������ււƘ_�����]�������̂͐��������B�������A���͈ꎞ���A�V�������ւ�f�O�������Ă���(�u���A�o���֖��̑O�r�v1927(���a2)�N9 ��24 �����А��A�w�S�W6�x�A100�|1 ��)�B�������A�ŏI�I�ɕ������������������͔̂ނ炾�����B
��܂ɁA��@�͈ꕔ�̐l�X�ɋ@��������炵��(���E���b�l�A�R���A���H�����A�呠����)�B������Ƃ����āA���v��Nj����邽�߂ɔނ炪��@�������N�������Ƃ܂ł͂����Ȃ��B�@��𗘗p�����Ƃ������Ƃ��낤�B�������A���v����т��Ă��邩�ǂ����͌������Ă݂�K�v������B���Ƃ��Α��s�����������ւ�]��ł����Ƃ����̂͂悭�����邱�Ƃł��邪�A���������ւɎ^�������̂́A���s�����ł͂Ȃ������B�����̋�s�A�Y�ƊE���^�������B�،��n�G�R�m�~�X�g�Ƃ������ׂ����c�原���Ȃ��ُk����Ɏ^�������̂��B�܂���㏀�V���̋������ւ̌Ŏ����ǂ��݂邩�B
�Ō�ɁA�o�ϊ�@�ւ̑Ώ��͌���I�ɏd�v�ł���B�����]���������炷�̂ɐ����̖����͑傫�����A�����]���͗e�Ղł͂Ȃ��B�����Ƃ̖{�̂͌o������w�Ԃ��Ƃɂ���͂������A�s�K�ɂ��Ĉ�㏀�V���͋��{�ʐ��ɂƂ��ꂷ�����B�V�������֔h�������ł������悤�ɁA���������A�[��p�܁A���[�Y���F���g�Ƃ����������S���҂��������s�����]�V�Ȃ����ꂽ�B��@�ɂ����ẮA���s���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂�������Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA����ɂ͏�ɕs�m�����������A���f���K�v�ł���B
|
����
1�@�_�҂ɂ���Ă͂��������Ⴂ�̈�Ƃ��āA1930 �N��̃f�t���s���͋ɂ߂Č��������̂ł��������A������{�͂���قǂł͂Ȃ����Ƃ��w�E���邩������Ȃ��B�������x2002a �����炩�ɂ��Ă���悤�ɁA�����Ȃ���Γ���ꂽ�ɂ�������炸����ꂽ�f�c�o�⎑�Y���l�̗v�Ō������A������{�̂ق����傫�����A����ɂ��̃f�t���s�������ݐi�s�`�ł���o�����猩���Ȃ����Ƃ́A����̂ق����[���ł���Ƃ�������B
2�@�������������̈��Ƃ��� Dixit 1996 ���Q�Ƃ̂��ƁB
3 ���̎��_�ɂ��Ă�Laidler 2001 ����w�B����ɁA����E����̈��艻������ɂƂ��Đ����S���҂̌o�ςɂ��Ă̐M���Ɛ���̑Ή��ɂ��Ę_����Romer and Romer 2002 ���L�v�ł���B���l�̎��_��������āA�A�����J�勰�Q����FRB�ƌo�ώv�z�ɂ��Č��������̂���c��2003d �ł���B
4�@���Ƃ��A���̂悤�ȗ���l���Ă݂悤�B1930 �N�����Ƀh�C�c�̎ƂȂ����n�C�����b�q�E�u�����[�j���O�́A�勰�Q�̂��Ȃ��ɂ����ăf�t����������s�����B���̔ނ́A���������������邽�߂Ƀh�C�c�o�ς̔j�Y��_���Ă����Ƃ���(Temin 1989)�B���̐����������Ƃ��Ă�����Ȃ�^�₪�킭�B�Ȃ��A�ނ͍��Ɣj�Y�����Ă܂Ŕ������̉�����D�悳�����ƍl�����̂��낤���B�h�C�c�ł̓i�`�X���䓪���A�u�����[�j���O���g�������̍�����������ꂽ���Ƃ��l����A�Ȃ��ނ��f�t������̓O��I�ȒNj������e�����ƍl���Ă�������₤�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�����ł����ƂȂ�̂͋��{�ʐ�����̗��E���\�ł��������ǂ����ł���B���̓_�A�����̃h�C�c�ɂ������@�̉���\�����߂���A�o�ώj�����Ƃ̊Ԃɂ����钘���Ș_��������A���̖��ɂ��Ă͍��ۓI�Ȏ��_�ł̔�r�������\�ł���B
5�@���ۊw�h�̌ÓT�� Eichengreen 1992 �ł���B�܂�Temin 1989�ABernanke 2000 ��James 2001 ���L�v�ł���B�܂��ŋ߂̑勰�Q��������{�Ő��͓I�ɏЉ��Ă���͖̂x�딎���ł���B�x2002a, b ���Q�Ƃ��ꂽ���B���̑��ɒ���2002�A����2003 ���Q�Ƃ��ꂽ���B�Ȃ��A�č��ƃt�����X�̋��Z���������ߓI�ł��������Ƃ��勰�Q�̈���ł��������Ƃ́A�����̐l�X�ɂ͂悭��������Ă����B���̓_�ɂ��Ă͓��t�{�̃Z�~�i�[�ł̍��������̎w�E�ɂ��B���������đ勰�Q�̍ŐV�����̈Ӌ`�͂ЂƂɂ͓����̓��@�͂ɕx�l�X�̓��@�����炽�߂Ċm�F�������Ƃɂ���Ƃ����悤�B
6�@�u�呠�Ȍ��� the Treasury View�v�́u���������͐M�p�̊g�����Ȃ�����A�ٗp�̑����������炳�Ȃ��v�Ƃ��Č��������ɂ�閯�ԓ����̊��S�ȃN���E�f�B���O�E�A�E�g���咣����B���Ƃ͂Ƃ����A�P�C���Y�̔ᔻ�ɂ���ăC�M���X�̑呠��(The Treasury)��1920 �N��㔼�ɖ��m�������������j�ł���A1929 �N�̑����`���[�`���̗\�Z�����Ɛ��{�����ɂ���Ė��炩�ɂ��ꂽ�B�������A���̌����̒莮���ɂ������ẮA���Ԋ��ɍł��e���͂̂������o�ϊw�҂̈�l�����t�E�z�[�g���[�̉e�����݂���(�ނ͑呠�ȗB��̃G�R�m�~�X�g������)�B����1999�A����1999 ���Q�Ƃ̂��ƁB
7�@���Z��`�ɂ��ẮADe Long 1990 ����ђ|�X2002 ���Q�Ƃ��ꂽ���B�V�����y�[�^�[�A���r���Y�A�n�C�G�N�A�V�[���A�E�n���X�Ȃǂ���\�I�Ȍo�ϊw�҂ł���B���ʓI�ȓ����́A�������v�����ߑ�]��������ƉƂɂ�铊�����D���������炷���A���ǂ��̓��������҂͂���ɏI���ĕs�����ɓ˓�����Ƃ����z���f���ɂ���B�Ȃ��A���㗝�_�ł̓��A���E�r�W�l�X�E�T�C�N�����_�Ȃ����͓��w�I�}�N���o�ϊw�̋����ɔ����A�`��ς������Z��`���������Ă���B�ᔻ�I�ȕ����W�]�ɂ��Ă�Aghion and Howitt 1998, pp.239-43 ���Q�ƁBDe Long1990 �́A�Z�p�ϓ��̂悤�Ȏ����I�v�����������錻��ł����������҂̍���Ɋ�Â��ߋ��̐��Z��`�̂ق����o�ϗ��_�Ƃ��Ă͗D��Ă���Ƃ����]���������Ă���B�������A���_�I�����͂Ƃ������A�|�X���Љ�Ă���Cabarello and Hammour 2000 �̌����������悤�ɁA���Z��`�ɂ͎��ؓI�ȍ������R�����B
8�@�A�����J�̑勰�Q�̕����ɂ����ẮA����ɋ�s�w�h�I�u���_�v��t�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���{�ʐ��C�f�I���M�[�A��s�w�h�I�u���_�v(�e�q�a���_)�ƃA�����J�̑勰�Q�Ƃ̊֘A�ɂ��ẮA��c��(2003��)���Q�Ƃ��ꂽ���B
9�@1920 �N����{�o�ς̊T���Ƃ��ẮA���c2003�A�����E����1989�A�O�a2002 ���Q�Ƃ̂��ƁB�܂�����2003�A��3�͂��L�v�ł���B
10�@���F��̂ق����A�����ււ̎����͋����Ȃ������Ƙ_���邱�Ƃ͂ł��悤�B�������A�c���`����t�̑呠��b�O�y�����������ւ�ژ_��ł����悤�ɁA���̑ԓx�͉��ււ̌����I���ł͂Ȃ������B
11�@���� 1965�A��A63 �łł̏،����Q�ƁB
12�@���Ƃ��A���ɂ��w�����o�ς̗������Ƌ����ցx�ɂ́A�呠�Q�^���������ɂ���������Ă���B���̉���́A���X�R����u�����ւ̏����������A����͂Ɖ]���ׂ��m���������Ă���v�Ƃ����茵�����ᔻ�������ނ����B�А��u���H�̈����ւ̂���͂��u���v�w���m�o�ϐV��x1929 �N9 ��14 �����A�w���X�R�S�W��7 ���x�A69�|72 �ŁB
13�@������ I�E�t�B�b�V���[�́w�ݕ����o�x�M��(����E���R�{�Ď���B1929 �N5 �����s)�ɏ�������ȂǁA�����̌o�ϊw�̐�[�����ɂ��Ă̗������L���������B
14�@���{�H�Ƌ�y���A���{�o�ϘA���͈ӌ����ꂪ�ł��Ȃ������B����A�ӌ�������������H��c���̂悤�ɁA���v�����炢�����������ւɔ����Ă����������Ȃ��Ƃ��낪�^�����Ă���B�Ȃ��A�O��A�O�H�Ƃ����������ł��ӌ�����͂Ȃ���Ȃ������BCf.�O�a2003�A202�\7 �ŁB
15�@�r�c���j���A1929 �N11 �����W�i���h�E�}�b�P���i(�C�M���X�̐����ƁB�呠��b���o�āA�~�b�h�����h��s����)�Ɖ�k�����Ƃ��ɁA�u���{�͂Ȃ����ւ��}���̂��A����Ȃɋ}���K�v�͂Ȃ��ł͂Ȃ����B���́A�C�M���X�͉��ւ��}���Ŏ��s�����v�ƌ���ꂽ�Ƃ�����b�͗L���ł���B��2001�A97 �ŁB���̃}�b�P���i�ɂ́A�C�M���X�̋��{�ʐ��ւ̕��A�̒��O�A�P�C���Y�ƂƂ��ɑ����`���[�`���Ɖ�k���A�������ł̋��{�ʐ����A�ɔ��������A�����̐����Ɏ��s�����Ƃ����o�܂�����B��c��2003a�A��11 �́B
16�@�o�䐷�V(����c��w����)�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���̗A�o���ւs���ׂ��Ƃ����c�_�́A�ߍ��킪���ɂ�����펯�ƂȂ����ς�����B�������̘_�ɑ��A�ِ������Ă邪�@�����̂�����Ȃ�A����ْ͈[�҂ł���ƌ��Ȃ����܂łɗ��������Ă���v�u���s�ɂ͔��v(�w��m�V���x1928(���a3)�N11 ��22 ���A���{��s�����Ǖ�1968�A23 ���A388�|91 ��)�B
17�@�Ȃ��������������߂ɁA���ƕی�����������Ă��Ȃ������ł̓y���̔����͌��ݕ�����������͂邩�ɐ�i�I�Ȃ��̂��������Ƃ͎w�E���Ă��������B
18�@���c�� 1925 �N�Ƀ\���B�G�g�A�M�ɏ�����ă��X�N���ɕ����A�����œ����������ꂽ�P�C���Y�Ƙ_��������Ă���B�P�C���Y�̘_���́w�`���[�`�����̌o�ϓI�A���x�Ɍ�����悤�ȃ}�N���I�ϓ_����̋��������֔ᔻ�ł������̂ɑ��āA�X�E�F�[�f�����珵�ق��ꂽ�w�N�V���[�͎^�ӂ�\���������A���c�͌o�ς̍\���ω����������闧�ꂩ�甽�����Ă���B���c1930�A��2��3�u�o�ϋ@�\�̕ω��Ɛ��Y�͕��ɐl���̖��\1925 �N���X�N���@�ɉ�����u���Ɠ��_�\�v���Q�ƁB
19�@�͏�ɂ��ẮA�� 1994�^2001�A��IX �́A��c��2003c ���Q�Ƃ̂��ƁB
20�@������q�́A����E����� 1965 �N��(������،��s��)���_�ł̍��k��ł��A���Z��`�I�ȍl�����q�ׂĂ���B����͌����̕s������u�����ق����A���{��`�Ƃ��Ă��u���S�v�ɂȂ�Əq�ׂĂ���B�u�������A�����Ă����A���Q(�N���C�V�X)�����܋N����Ƃ������Ƃ͂��蓾��B�����̏o���͂���B����͌���������̂�����A�N����̂͂��������Ȃ��B�ߏ�̐��Y�ݔ��͋��Q�ɂ���Ă��̐ݔ��̈ꕔ��j��悢�B���ꂪ�o���ł��邪�A����ɂ���ċ����ȁA�s���Y�I�Ȑݔ����Ԃ����Ƃ͂悭�Ȃ�B����ȊO�ɂ�����Ȃ������@�͂Ȃ��B�����ŋ��Q���N����Ȃ�A���܋N�������ق��������B����͏����N����˂Ȃ�Ȃ����Q�Ɣ�ׂ�A�����ȋ��Q�ōςނ��炾�B����������ȏ�A�M�͗}���Ȃ������悢�A�A�������Ȃ������悢�B���R�Ö@��������悢�v�B�g��2003�A30 �Œ�30 �Ɉ��p����Ă���B
21�@��ʐV���̑Ή��ɂ��ẮA���� 1998�A��4 �͂��Q�ƁB��ʐV���ɂ��Ă͒����@�x�A�o�σ��f�B�A�ɂ��Ă͓c���G�b�ɂ�錤�����i��ł���B
22�@�q��P�q�́A�����鍑��w����o�ϊw���m�����擾���������ʂƂ��Ēm���Ă����B��v�� 2003 ���Q�ƁB
23�@���̂������A�V�������ւȂ�咣���̂��̂��Ȃ������Ɠ�������z�������E�l(���{���Ƌ�s���ٗ�ؓ��g)�������Ƃ̂��Ƃł���B���̍����������T�g�͕�������߂ċL�^���Ă���B����1955�C���A884 �ŁB
24�@������A���͋��Z������߂���u����v�Ƃ��Ό����Ă����B�����A���c���O�ɓT�^�I�Ȃ悤�ɁA������Z�ɂ����Z���@�\�s�S�Ɋׂ����ƍl����_�҂͑��������B�����T�g�������l���Ă����B����ɑ��āA���͌��Ǖ��������߂�̂͒ʉݗʂł���A���������ւ��������邽�߂ɕ����̉������K�v�Ȃ̂ŁA���̂��߂ɂ͒ʉ����ʂ����炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă����B���̓_�ŋ��Z�������߂𐳖ʂ��炤����Ȃ��l�����t�̌o�ϐ���́u��͂���v�ł���Ɣᔻ���Ă���(�u�����֏����͒�͂���v1929(���a4)�N8 ��10 �����А��A�w�S�W7�x51�|5 ��)�B
25�@���j�I��Ƃ��ĂƂ肠����ꂽ�̂́A19 ���I����̃f�t���ł���B�u���B�ɉ���1874 �N������1897 �N������20�N�ԁA�Y�b�g�������ᗎ��������̏�����Ƃ܂��������ꂾ�Ɖ]���Ă悢���A����ǂ����Ă���v(����1931a�A110�|�P��)�B
26�@�ނ́w������ЖS���_�x�͂����������I�Ȃ�����A������Бg�D�ɐ��ݓI�ȃ������E�n�U�[�h�����w�E�������̂ł���B
27�@���́w��z�x�ł� 1924(�吳13)�N3 ��15 �����А��u�~���̕����Ƒ���v(�w�S�W5�x�A209�|13 ��)����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���(�w�S�W15�x)�B�������ɁA���̘_���ł͋������ɂ����āA�������[�g�ɋ߂������ݒ�̗��_��������Ă���B����ǂ��A���m�Ɂu�V�������ցv�Ƃ������t���o�Ă���܂ł͎��Ԃ��������Ă���(1924�N11 ��29 �����A12 ��6 �����А��́u�בֈ���̉��}��Ɖi�v��v�A��Ɂw�����ւ̉e���Ƒ�x�ɏ����B�w�S�W6�x�A307�|15 ��)�B
28�@����������E����Ɏ��M�����L�O��I�咘�w�吳���a���E�ϓ��j�x(����1954�|5)�́A��ꎟ���E��킩������֘_���A���a���Q�A�����Ă��̌�̓������ς܂ł̓��{�o�ς̐����_���j�����K�{�̕����ł��邪�A�������g�̓����̔����ɂ��Ă͎���I�ȁu�ҏW�v���܂܂�Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
29�@����́u�����ɋ����ւ��s�ӂɂ͕����؉����̊O�Ȃ��v��1929(���a4)�N3 ��16 ���t�w���m�o�ϐV��x1340���Ɍf�ڂ��ꂽ(���{��s������1968�A23 ���A60�|5 �łɎ��^)�B
30�@�Ȃ��A��ɏ���z���Ă���悤�ɁA���a 6�C7 �N����A���͔ނ������������Ƃ������Ƃ�����B���̂Ƃ��ɁA���͋������Ⴂ�Ə���ɂ���ꂽ�Əq�ׂĂ��邪�A����͓��u�͈�ӏ��Ɍł܂�Ȃ��ق����悢�ƍl���Ă����Ƒł������Ă���B���̐^�U�͂Ƃ������A�����̐V�������֔h�́u���u�I�����v������b�ł���(���q��1955�A514 ��)�B���Ȃ݂ɁA���͏��c�原�ɂ��Ă͓��Ђ�f���Ă���B
31�@1927 �N�̎��_�Łw�ǔ��V���x��10 �����A�w���O���ƐV��x��10 �����������B���Ȃ݂Ɂw��㒩���x126 �����A�w���������x40 �����A�������킹��166 �����A�w��㖈���x�w���������x�͂��ꂼ��116.6 �����A45 �����̍��v161.6�����B�ȉ��A�w�����V��x�w��㎞���V��x�����킹��70 �����A�w��m�V���x��25 �����ł���B�����̐V���̔��s�����ɂ��ẮA�R�{1981�A�ʕ\6���Q�ƁB
32�@�������A����������ʂ��ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂́A�Γ����l�ƑΊO���l���Œ�I�Ɍ��т�����{�ʐ��C�f�I���M�[�̕��Y���������\���͂���B
33�@�Ȃ��A��O�̎��Ɨ��ɂ��Ă͈�т������̂��Ȃ��B�u��O���ł͗B��A���Ǝ҂̎��n��I�ω��������ƂɂƂ炦�Ă���v�Ƃ����Љ�Ǎ쐬�w���Ə��茎��x�́A���v�ł��藘�p�ɂ͂��Ȃ�̒��ӂ��K�v�ł���(����1997�A5 ��)�B�����ł͈��B�����쐬�������̂��Q�l�ɂ����B
34�@���� 1965�A��A76�|7 �ŁB
35�@���{��s�����Ǖ�1968�A��23 ���Ɏ��^����Ă���e�퐢�_�������Q�ƁB
36�@���c�����ɂ͍����T�g�A�R��A���ւ��A�������͍��������Ă��N�������B���H 1992�A141 �ŁB
37�@���łɑO�N 30 �N11 ���ɕl�����_������āA31 �N4 ���ɓ��t�̎�ǂ͎�Η玟�Y�ɑ����Ă������A���͑����ɗ��C���Ă����B
38�@���� 1955�A���A��13 �͑�3 �߂̏��q���Q�Ƃ̂��ƁB
39�@�����́w�C���t���[�V�����̗��_�Ǝ��ہx�Ƃ��ďo�ł��ꂽ(�w���X�R�S�W�x��8 ���ɏ���)�B���̋c�_�ɂ��ďڂ����͎�c��2003e ���Q�Ƃ��ꂽ���B
40�@��� 2001�A241 �ŁB�����T�g�����������ӌ���\�����Ă���Ƃ��낪�ʔ����B����1955�C���A1415 �ŁB
41�@���B 2002�A��c��2003d�A170 �Ő}�\���Q�Ƃ̂��ƁB����ɕ�I�Ȃ͈̂��B2003b �ł���A�P)���a���Q�����̕s�Ǎ��K�͂͏��a���Z���Q���ɕC�G����K�͂ł��������ƁA2)���a���Q�����̕s�Ǎ��Ə��a���Z���Q�����̕s�Ǎ��͂��̔����������قȂ�\�����������ƁA3)���̂����A���a���Q�����̕s�Ǎ��̓f�t���������ƂȂ��Ă���\�����������ƁA�𖾂炩�ɂ��Ă���B�@
�@ |
| �����E���Q�ƌo�ϐ��� / �w�J�������x���{�̌o���ƌ��� |
   �@
�@
|
|
��1�D �͂��߂� |
�{�ł́A�w���E���Q�ƌo�ϐ���F�u�J�������v���{�̌o���ƌ���x(���{�o�ϐV���o�ŎЁA2009�N)�̓��e���Љ��2)�B
���́A2000�N5���ɓ��{��s���Z�������ɒ��C���Ĉȗ��A10�N�قǂ̊ԁA�����Ԋ��Ƃ�킯�u���������v���O��̓��{�̌o�ϐ���Ɋւ��錤���Ɍg����Ă����B���̌������n�߂����������́A1990�N��ȍ~�̓��{�o�ς̒���āA���j���琭�����ǂɂƂ��Ă̋��P��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������ӎ��ɍ����������̂ł������B������i�߂�ΐi�߂�قǂɁA�����ۑ�̉��[����g�ɂ��݂Ċ����Ă���B���̊ԁA2006�N4������2�N���ɂ킽��A�_�ˑ�w�o�όo�c�������Ō�������@���^�����A�����Ȃ�ɒ�����[�߁A���������܂Ƃ߂邱�Ƃɂ����B����Ȃ��_�͑��X���낤���Ǝv�����A�{���͂��̓��e�����Љ�A���ᔻ������K�r�ł���B
���̎ʐ^��1933�N6���Ƀ����h���ŊJ�Â��ꂽ���یo�ω�c�ɂ�������{��\�c�ƕW�҂̋L�O�ʐ^�ł���B���̉�c�́A�勰�Q�̍Œ��ɐ��E�e���̐����S���҂��ꓰ�ɉ�āA�勰�Q�ւ̑Ή��ɂ��Ęb���������߂̂��̂ł������B���{������A�������{��s�̕����قł������[��p��(�O��E����7�ԖځA���X�q��G�ɏ悹�Ă���l��)�ȂǁA��l���̑�\�c���o�Ȃ��Ă����B�������Ȃ���A���E�e���̑�\���W�܂����ɂ�������炸�A�L���ȑΉ���͑ł��o���ꂸ�A���E�͂��̌�u���b�N�o�ω��̓r��H��A��2�����E���ւƓ˓����Ă�����3)�B
�����āA�����̓��{����芪������U��Ԃ��Ă݂����B
�ߑ���{�ɂƂ���1�̑傫�Ȍ_�@�͖����̊J�`�ł������B�]�ˎ���̍����̐����̓��{�́A����◮���A�Δn�Ȃǂ������̖f�Ղ̑����͑��݂����ɂ��Ă���{�I�ɕ��o�ςł��������A1859�N�̊J�`���_�@�ɊJ���o�ςɈڍs�����B
�����̐��E�����͉p���𒆐S�Ƃ���Pax Britannica �ƌĂ����̂ł���A����ɕC�G����悤�ȃO���[�o���[�[�V�����̎���ł������Ƃ����B������������w�i�̒��ŁA���{�̓y���[���q���_�@�Ƃ��Đ��E�����ɋ����I�ɎQ��������ꂽ�Ƃ������Ƃ��ł���B
���{�́A�f�Ֆʂł�1911�N�܂ŊŎ��匠���Ȃ��A���R�f�Ղ̏ɒu����A19���I�㔼�̃O���[�o�����̒��ō��ۋ����ɂ��炳��Ă����B�܂��A1897�N�ɋ��{�ʐ������A����ȍ~�A���Z�ʂł��{�i�I�ɊJ�����ꂽ��ԂƂȂ�A�C�O�̋��Z�s��ւ̈ˑ������߂��B�Ⴆ�Γ��I�푈���ɂ́A�������������S�ƂȂ��ĊC�O�s��ő�ʂ̊O�s�����B�������ē��{�́A�f�Ֆʂł����Z�ʂł��ΊO�I�ɊJ�����ꂽ�o�ςƂȂ����B
|
�\1 �o�ϐ������ƃC���t����(�N����)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����GNP�@�@�@�@ GNP �f�t���[�^
1914�|19�N�u��1�����u�[���v�@6.2�@�@�@�@�@13.6
1920�|29�N�u�����s���v�@�@�@�@�@1.8�@�@�@�@ �|1.3
1930�|31�N�u���a���Q�v�@�@�@�@�@0.7 �@�@�@�@�|10.3
1932�|36�N�u���������v�@�@�@�@�@6.1 �@�@�@�@�@1.5
1937�|40�N�펞�����o�ρ@�@�@�@5.0 �@�@�@�@11.9 |
��1���������痼���Ԋ��ɂ́A�p�����S�̐��E���������h�𗈂����A���Z����юY�Ƃ̒��S���C�M���X����A�����J�Ɉڂ��Ă������ŁA�e���͐��E�����̓��h�ւ̑Ή��𔗂�ꂽ�B���{�̏ꍇ�ɂ́A��1�����ɂ�艢�ė��푈��Ԃɓ��钆�ŁA���Č����≢�Ċe���̐A���n�����̗A�o��L���A�}�����𐋂�����A���̔����Ƃ������ׂ�������1920�N��ɋN�����B1920�N��͓��{�ɂƂ��ăf�t��(��������)�̎���ł���A�����1929�N�̃j���[���[�N�����s��̖\��(������u�Í��̖ؗj���v)���o�āA����1930�N��ɂ͐��E���Q�ւ̑Ή��𔗂�ꂽ�B
��1����풆���痼���Ԋ��̓��{�̌o�ϐ������ƕ����ϓ������݂��(�\1)�A��1�����(1914�`1918�N)������19�N�܂ł̎���GNP ��������6���AGNP�f�t���[�^�Ō����C���t������14�� �ƂȂ�A�������E���C���t���̎���(�u��1�����u�[���v)�ł������B
1920�N��̎���GNP ��������2���AGNP �f�t���[�^�ł݂������ϓ����̓}�C�i�X�ƂȂ�A�ᐬ���E�f�t���̎���(�u�����s���v)�ł������B���̎����ɂ͋��Z�V�X�e�������h���A1920�N�́u��㔽�����Q�v�A�u1922�N���Q�v�A1923�N�̊֓���k�Ђ��͂���ŁA1927�N�́u���a���Z���Q�v�����������B
1930�N����31�N�ɂ����āA���{�͋��{�ʐ��ɕ��A�����B���A���͕̎l���Y�K�A�呠��b�͈�㏀�V��(�����{��s����)�ł���A�܂���̐��E���Q�Əd�Ȃ�A����GNP �̓[�������AGNP �f�t���[�^�ł݂������ϓ�����2�N�A����2�P�^�̃}�C�i�X�ƂȂ���(�u���a���Q�v)�B
1931�N12���A����������5�x�ڂ̑呠��b�ɏA�C���A1936�N2���ɓ�E��Z�����ňÎE�����܂ł�4�N���ɂ킽��A��_�Ȍo�ϐ�����̗p�����Ƃ����B1932�`36�N�ɂ����Ă̓��{�́A����GNP ������6���AGNP �f�t���[�^�ł݂��C���t����1�D5�� �ƁA�������E��C���t���̗ǍD�Ȍo�σp�t�H�[�}���X��������(�u���������v)�B
�����ÎE��̓��{�͐펞�����o�ς̎���ɓ���A�������E���C���t���ƂȂ�A��2��������������C���t���̎��オ�������B
���߈ȉ��ł́A�����Ԋ��̓��{�̐����Ή��ɂ��ďq�ׂ�B���̂����A2�߂ł�1920�N��̋��Q�ւ̑Ή��ɂ��ďq�ׂ�B2�߂̌��_����肷��A���̎����̐���ۑ�́A�����̋��Z�V�X�e�����ւ̑Ή��ł������Ƃ������Ƃ��ł���(����[2009a] ��5��)�B3�߂ł́A1930�N��̋��Q�ւ̑Ή��ɂ��ďq�ׂ�(����2�͂����4��)�B3�߂̃|�C���g�́A��1�ɁA���{���u�J�������v�ł���A�����̐���^�c���C�O�̓����ɉe�����₷���o�ςł������Ƃ������Ƃł���B��2�ɁA�u���a���Q�v�Ɓu���������v�̊W�ł���B�u���a���Q�v���ɂ́A������(��1�����O�̈בփ��[�g)�ŋ��{�ʐ��ɕ��A�������Ƃɔ����~���̉e���ƁA���E���Q�̔g�y�Ƃ����ӂ��̗v�����d�Ȃ�A���{�o�ςɋ����f�t���E�C���p�N�g��^�����B����ɑ��A�呠��b���A��̍��������́A�܂����{�ʐ����痣�E���A�����āA�בփ��[�g����A��������A���Z������܂ޑ����I�ȃ}�N���o�ϐ���𗧈Ă��A���s���Ă������B��3�ɁA�u���������v���̃C���t���\�z�̕ω��̗v���ł���B��4�ɁA�����K���Ɓu���������v�̊W�ł���B4�߂́A�܂Ƃ߂ł���B
|
|
��2�D 1920�N��̋��Q�Ƃ��̑Ή�4) |
|
1920�N��̓��{�ł́A��s���t�������Z���Q�����������Ă������A1927�N�́u���a���Z���Q�v���_�@�ɕs�Ǎ������Ƌ�s�ĕ҂��i�W���A���Z�V�X�e�����͎����Ɍ�������(�\2)�B
|
�\2 1920�N��̋��Z���Q�֘A�N�\
1920(�吳9)�N�@/�@4��7���@/�@���c�r���u���[�J�[��s�A�j�]
1922(�吳11)�N�@/�@2��28���@/�@�Έ�莵���X�A�j�]
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@10��19���@/�@���{���H��s(���s)�x��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@11��29���@/�@���{�ϑP��s(���s)�̋x�Ɣ��\�ɂ�苞�s�E�ޗ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���ɋ�s���h����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@11��30���@/�@��B��s(�F�{)�x�Ɣ��\
1923(�吳12)�N�@/�@9��1���ց@/�@����k��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@9��27���@/�@�k�Ў�`���������⏞�߁A���z
1927(���a2)�N�@�@/�@1��26���@/�@�k�Ў�`2�@�āA�鍑�c��ɒ�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@3��14���@/�@�Љ������A�O�c�@�\�Z�ψ���œ����n�Ӌ�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�]�����Ɣ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@3��23���@/�@�k�Ў�`2�@�A����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@3��30���@/�@��s�@�A���z(1928�����a3���N1��1���A�{�s)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@4��17���@/�@�����@�{��c�A��p��s�W�ً̋}���߈Ă�ی�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@4��18���@/�@��p��s�A��p�����̖{�x�X�E�o�����������x��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@4��21���@/�@�\�܋�s�x�ƁA�e�n�̋�s��t���s�[�N
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@4��22���@/�@�x��������(�����g���A��)���z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@/�@5��8�����@/�@�{��s���ʗZ�ʋy�����⏞�@�A��p�m���Z�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�X�������Z�ʃj�փX���@���A���� |
1920�N�́u��㔽�����Q�v�̌_�@�́A���c�r���u���[�J�[��s�̔j�]�ł������B����ɑ��āA���{��s�����ʗZ�ʂ����{���A���Z�s��ɗ��������������đΉ������B
���̌�A1923�N�̊֓���k�Ђɍۂ��ē��{��s�́A�֓���k�ЂŔ�Q��������Ƃ̎�`(�k�Ў�`)�̌��ς���ʂɗP�\����[�u���̂����B1927�N�ɐk�Ў�`�̌��ϗP�\�[�u���I�������邽�߂̖@�Ă��c��ɏ�����ꂽ���A�R�c���������A���̉ߒ��ő呠��b�̕Љ��������u�����n�Ӌ�s���j�]�����v�Ɣ��������B���ۂɂ͂��̎��_�œ��s�͔j�]���Ă��Ȃ��������A�Љ������̔����ɂ���Ĕj�]�ɒǂ����܂�A��1���̋��Z�p�j�b�N���N�����B��������E���邽�߁A���{�͓����傫�ȕs�Ǎ�������Ă�����p��s�ɐ��{�⏞�t���œ��{��s�̓��ʗZ�ʂ����{���钺�߈Ă𐕖��@�ɒ�o����(�c���̂���)�B�Ƃ��낪�����@�̐R�c���������A���̒��߈Ă��ی����ꂽ���Ƃɂ��A���t�����S���ɔg�y�����B
���̊Ԃ̌o�܂ɂ��āA�������疯�ԃG�R�m�~�X�g�Ƃ��Ċ��Ă��������T�g�́A1920�N��̋��Q�̍��{�I�Ȍ����͕s�Ǎ��ƕs�̎Z��Ƃ̐������s�O��ł��������߂ł���A�u�吳9�N�������Q�ȍ~�ɂ�����ߋ��̑n�w�ɑ���Гh�\�D���A���܂��܁A�c��ɂ�����k����̕����ɂ���Ė\�I�����A���ꂪ���Γ_�ƂȂ��āA�����ɑ勰�Q�̔����ƂȂ�Ɏ������v�Əq�ׂĂ���5)�B
�����ō����������ꎞ�I�ɑ呠��b�ɕ��A���A�����g���A��(��s�x�Ƒ[�u)�����A����ɁA���{��s���ʗZ�ʋy�����⏞�@�Ȃ�тɑ�p�m���Z�@�փj�X�������Z�ʃj�փX���@���ɂ��A���{��s�̑ݏo�ɑ��č��v7���~�̐��{�⏞��t�^���邱�ƂƂ����B7���~�Ƃ����z�́A������GNP �̖�7�� �ɑ�������B�Ȃ��A�u���a���Z���Q�v�̉ߒ��ł́A��s�̑����ɗa���҂��E�����A�ꎞ�I�ɋ�s���̔��s�c�����}���ɖc��݁A��s���̈�����Ԃɍ���Ȃ��Ȃ������߁A�}篁A�\�ʂ���������ꂸ���������̋�s���s�����Ƃ����G�s�\�[�h��������6)�B
�ŏI�I�ɂ́A��L�̍����ʂ̑[�u�ƍ��킹�A1927�N��s�@(1928�N1���{�s)�̉��ŋ�s�����Ƌ�s�K���E�ē̋������s���A���Z�V�X�e���̓��h�͎��������Ƃ����Ă���B���{��s����s�ɏo�����čl�����s���悤�ɂȂ����̂����̎����ł���B
��s�����݂�ƁA1920�N�㏉�ɂ�2�A000�����s�����݂��Ă������A1928�N���_�@�ɋ�s���������������A1920�N��I���ɂ����ċ}���Ɍ����Ă���(�}1)�B�呠�Ȃ̌�������{��s�̍l���̌��ʁA�o�c��Ղ��ア�Ɣ��f���ꂽ��s������������Ȃǂɂ��A���Z�V�X�e��������������̂�ꂽ���߂ł���B���̔w�i�ɂ́A1927�N�Ɂu���a���Z���Q�v�Ƃ�����@���������A���{�I�ȉ��v�𐄐i����Ƃ����C�^������オ�����Ƃ����ʂ��������ƍl������B
��s�ԂŒZ�������̗Z�ʂ��s���R�[���s��̋���(�R�[���E���[�g)�̐��ڂ��݂��(�}2)�A1920�N��O���ɂ͍��~�܂肵�Ă����B����́A�����̏o���肪���̃��X�N�ɕq���ɂȂ��Ă���A���X�N�E�v���~�A���������������Ă������Ƃ��������Ă���B1927�N�́u���a���Z���Q�v�Ƌ�s�@������_�@�Ƃ��āA�R�[���E���[�g�͒ቺ���Ă������B���̌�A1930�N�㏉���́u���a���Q�v���Ɉꎞ�I�ɏ㏸���邪�A�����ɒቺ����B���̂��Ƃ�����A1920�N��O���ɂ����Ă͋��Z�V�X�e���̓��h�����{�o�ς̑傫�Ȗ��ł���A���ꂪ1927�N���_�@�Ƃ��Ď����������Ƃ��M����B
�ȏ������ƁA1920�N��̓��{�o�ςɂƂ��Ă̑傫�ȉۑ�́A�Y�ƊE�̎��Ɛ����Ƌ��Z�@�ւ̕s�Ǎ��������s���S�ł��������Ƃł���A���̌��ʁA1927�N�́u���a���Z���Q�v���������A���ꂪ��s�E�̍\�����v�ƎY�ƊE�̎��Ɛ����𑣂����Ƃ������ʂ�����B�Ȃ��A�����T�g�́A�u���a���Z���Q�v�ɂ���ċ�s�E�A�Y�ƊE�̐����E���v���i�W�������Ƃ��A1930�N��̐��E���Q�ւ̑Ή���e�Ղɂ����ʂ�����|�q�ׂĂ���7)�B
�@�@�@�}1 ��s���̕ϓ�
�@�@�@�}2 �R�[���E���[�g(����)�ƌ������
|
|
��3�D�u���a���Q�v�Ɓu���������v
|
��(1)�u���a���Q�v�Ɓu���������v�̊J�n
���{�������̋��Z�V�X�e�������������A���ێЉ�ւ̊��S���A���ʂ����ׂ����{�ʐ��ɕ��A���Ă���1930�N����31�N�ɂ����āu���a���Q�v����������8)�B
���{�͑�1����풆��1917�N�ɁA�����ɒǐ����ċ��{�ʐ����痣�E�����B���������{�ʐ��ɕ��A���钆�A���{�͍����̋��Z�V�X�e����肩�畜�A���x��Ă������A�悤�₭�������������Ƃ���1930�N1���ɋ������ŋ��{�ʐ��ɕ��A�����B�������Ȃ���A���̃^�C�~���O�͐��E���Q�Əd�Ȃ�A�������ɂ����{�ʐ����A�ɔ����~���Ƃ̑�����ʂɂ���āA�����o�ς��傫�ȒɎ���Ă��܂����B
�C�M���X�̋��{�ʐ����E(1931�N9��)���_�@�ɁA���{�͑ΊO���{���o�Ɍ������A1931�N12���ɂ͓��{�����{�ʐ����痣�E����B
�@�@�@�}3 ���ĉp3�����̕����Ɖ~�בփ��[�g
���ĉp3�����̉��������̐��ڂ��݂��(�}3)�A��1�����O�ɂ͈��肵�Ă������A��1����풆�ɋ}���ɏ㏸���A��1������ɋ}���ɉ��������B���̍ہA�ĉp�ɔ�ׂē��{�̉����̒��x�͏������A��1�����O����ɂ���ƁA���{�̕����͕ĉp�ɔ�ׂĊ����ɂȂ��Ă����B���{���������ŋ��{�ʐ��ɕ��A���A���A������������ێ����邽�߂ɂ́A�ĉp�Ɠ����x�܂ŕ���������������K�v������A���ꂪ1920�N��̓��{�̏d�v�Ȑ����ڕW�̈�ɂȂ��Ă����B��̓I�ɂ́A1929�N���_�ő�1�����O�ɔ��1�`2�����x�̊����ƂȂ��Ă����B���̂��߁A���{�ʐ����A���ł܂�A�����Ď��ۂɋ��{�ʐ��ɕ��A���������ɂ́A���O���i�������邽�߂̃f�t�����͂������Ă����B����́u�\�z���ꂽ�f�t���v�Ƃ������Ƃ��ł���B
��L�́u�\�z���ꂽ�f�t���v�ɉ����A���{�����{�ʐ��ɕ��A����1930�N����31�N�̎����ɂ́A���E���Q���������A�ĉp���͂��߂Ƃ���C�O�������}���ɉ����������߁A���{�̕����͊C�O�̕��������Ɉ��������邩�����Łu�\�z����Ȃ��f�t���v���N���Ă��܂����B������̌��ʂ����܂��ċ}���ȃf�t�����N�����Ƃ����̂��A1930�N����31�N�̏ł������B
����ɑ���Ή���Ƃ��ē��{�͋��{�ʐ����痣�E���A���E�O�̋������Ƃ̔�r�ʼn~�בփ��[�g��1931�N������1932�N���ɂ�����40�� ���x���������B���̌��ʁA�C�O�̕���������钆�ŁA���{�̕����͏㏸�����B
�����Œ��ӂ��ׂ��́A�u���������v���̓��{�͊��S�ɕϓ����[�g���Ɉڍs�����킯�ł͂Ȃ��A���������בփ��[�g�����ōĂу|���h�Ƀy�b�O�����Ƃ������Ƃł���B1931�N������1933�N���܂ł̎����ɂ����ē��{�́A1�����̈בփ��[�g�������s���A����ɂ���ĕ�����1932�N�`33�N�ɂ����ď㏸���A���̂��Ƃ͈��肵���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
|
��(2)�u���������v�̖{��
�u���������v�̖{���ɂ��ẮA�������p���̐��I�Ȍ��������邪�A���{�ʐ��𗣒E���邱�Ƃɂ��בփ��[�g�̉����A�������̓��{��s�����������x�o�g��A�����ċ��Z�ɘa�Ƃ����A�}�N���o�ϐ����S�̂Ƃ��đ�����K�v������B�����3�̐���́A��������P�C���W�A���I�Ȍi�C�h����ł���A������_�ɐi�߂邱�Ƃɂ��A���E���Q���Ŋe�����f�t���ƕs���Ɋׂ钆�A���{�o�ς͔�r�I�����ɂ�������E�p���Ă������ƂƂȂ����B�P�C���Y���w��ʗ��_�x���o�ł����͍̂����������ÎE���ꂽ1936�N�ł���A�����́w��ʗ��_�x�ɐ�삯�Ă��̃G�b�Z���X�����H���Ă����Ƃ������Ƃ��ł���B
�����3��(�בփ��[�g�E�����E���Z)�̐���̂����A�ǂ̐��ł����ʂ����������������ؓI�Ɋm�F����̂́A�Ȃ��Ȃ�����B�~�c��M���̌����ɂ��A�����̕����ɑ��ẮA�C�O�����ƈבփ��[�g�̉e����������������A�����������Z����̉e���͎ォ�����Ƃ���Ă���9)�B�܂�A�f�t������̓]���Ƃ����Ӗ��ł͈בփ��[�g�̓������d�v�ł������Ƃ������ʂ�������Ă���B����A�ѓc�הV���Ɖ��c�����̌����ɂ��A���{�ʐ�����̗��E�ƒ������̓��{��s���ɂ���āA���Z����̃��W�[���]�����s���A�C���t���\�z���]�����ꂽ���Ƃ̉e�����傫�������Ƃ���Ă���10)�B
�ȉ��ł́A�u���������v���̈בփ��[�g����A��������A���Z��������۔�r�������Ȃ���T�ς���(�}4)�B
���{�A�Ȃ�тɓ��{�Ɠ��l�Ɂu���Ӎ��v�Ɉʒu�Â�����e���̈בփ��[�g�̐��ڂ��݂�ƁA�u���������v�����̓��{�̈בփ��[�g�����̓x�����́A�����ɔ�ׂđ傫���������Ƃ�������B�܂��A�������{�̍����o�����X���݂�ƁA�u���������v���̓��{�̍����Ԏ��́A�����ɔ�ׂđ傫�������B
����A���Z����ɂ��ẮA�u���������v���̓��{�́A�p���ɒǐ����邩�����Ō�����������������Ă��邪�A�p�������������͏����������B1�����̈בփ��[�g�̈��������̌�A�p�|���h�Ƀy�b�O���钆�ŁA���{�̋��Z�ɘa�͊C�O�̓�������Ɨ����Ď����I�ɍs���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�Œ背�[�g�����ʼnp���̋��Z����ɒǐ����čs���Ă����ƍl������11)�B���̊ԁA�ʉ����ʂ��݂�ƁA�����ÎE��͑����ɔ�ׂč����L�т��������ƂƂȂ邪�A�u���������v���ɂ́A�p�|���h�������ɂقړ������N��6�� ���x�̊ɂ₩�ȑ����������Ă���B���������āA�u���������v���̋��Z����͉p���ɒǐ����ɂ₩�Ȋɘa���s���Ă����Ƃ����̂����Ԃƍl������B
�@�@�@�}4 �}�N���o�ϐ���̍��۔�r
�ْ��ł́A���{�̋����ƊC�O�̋����̘A�����������Ă���(��2��)�B��s�����Ŏg���Ă��闼���Ԋ����{�̒Z�������w�W�́A��`�����Ȃǖ��Ԍ��������ł��邪�A������C�O�̖��Ԍ����Z�������Ɣ�ׂĂ݂�ƁA�A�����Ă��Ȃ��B���̗��R�́A1920�N��̓��{�ł͋��Z�V�X�e�������h�����Ԍ����̋����ɍ����M�p���X�N�E�v���~�A�����t������Ă������������邱�Ƃ���A�������������͊��ԂɊ܂߂Ă��܂��ƘA���W������Ă��܂����߂ƍl������B
�����Őْ��ł́A���{�ƊC�O�ɂ��Ĕ�r�\�ȋ����Ƃ��Ē�����������V���ɓ��o���������ŁA���{�ƕĉp�����̋����̘A���W�������Ă݂�(�}5)�B���̌��ʁA�����Ԋ���ʂ��ē��{�̋����͉p���̋����ƘA�����Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B���������āA���{�̋��Z���p���ɒǐ����Ă������Ƃ����ؓI�Ɋm�F���ꂽ�ƍl���Ă���B
�@�@�@�}5 ���ĉp3�����̒�������
�u���������v���̓��{�o�ς̃p�t�H�[�}���X�Y�ƕ����ɂ��Ă݂�ƁA�z�H�Ɛ��Y�A���������Ƃ��ɑ��̑����̍��ɐ�삯��1932�`33�N�ɂ����ăv���X�ƂȂ��Ă���(�}6)�B���ꂪ���������̖��O�𐢊E�I�ɗL���Ȃ��̂ɂ����B2003�N�ɓ��{���Z�w��ōs��ꂽ���ҍu���̒��ŁABen Bernanke ��(��FRB�c���A������FRB ����)�́u���������͓��{��勰�Q����~�����v�Əq�ׂĂ���12)�B
�@�@�@�}6 ���Y�ƕ����̍��۔�r
|
��(3) �C���t���\�z�Ɓu���������v
�ْ��̒��ł́A�u���������v���Ɏs��W�҂̗\�z���f�t������C���t���ɕω��������_�@�ɂ��Č������Ă���B�O�q�̔ѓc�E���c�_���ł́A�p�������{�ʐ��𗣒E����1931�N9���ƁA�������̓��{��s���������ꂽ1932�N��3���ɁA�\�z�C���t�������啝�ɏ㏸���Ă���Ƙ_���Ă���B�ނ�̕��͂ł́A���ۂɊϑ����ꂽ���������Ɩ��ڋ������g���Ď���I�Ɋϑ����ꂽ���������𐄌v���A���ڋ������玖��I�Ȏ��������������������邱�Ƃɂ���ăC���t���\�z�𐄒肵�Ă���B���Ȃ킿���ۂɊϑ����ꂽ�������������O�ɗ\������Ă����ł��낤�Ƃ������Ƃ�O��ɂ��Ă���B�������Ȃ���A���̑O�Ó��Ȃ��̂ł��������ǂ����͌�����Ă��Ȃ��B����ɁA�ނ炪���͂Ɏg�p���Ă�������f�[�^�͖��Ԃ̏؏��ݕt�����ł���A��قǏq�ׂ��悤�ɁA1920�N��̖��ԋ����ɋ��Z�V�X�e���̓��h�f�����M�p���X�N�E�v���~�A�����t������Ă������Ƃ܂���ƁA���̕��͌��ʂɂ͑傫�ȗ��ۂ��K�v�ƂȂ�B�����Őْ��ł́A���̂悤�Ȏ��ؕ��͏�̘_�_�܂��A�C�[���h�E�J�[�u���͂���я��i�敨�s��̓����Ƃ���2�̖ʂ���Č����s���Ă݂�(��3��)�B
�@�@�@�}7 �C�[���h�E�J�[�u�̓���(1931�N8���`1933�N1��)
��1�ɁA���܂��܂Ȏc�����Ԃ̍������o���A�C�[���h�E�J�[�u��`���Ă݂�(�}7)�B���̌��ʁA���̐����������ɂ���ď㉺�ɃV�t�g���Ă������Ƃ��m�F���ꂽ�B�t�@�C�i���X�_�̕���ł́A�C�[���h�E�J�[�u�̐����̃V�t�g�͎s��Q���҂̃C���t���\�z�̕ω��f���Ă���A����V�t�g�̓C���t���\�z�̋��܂���A�����V�t�g�̓C���t���\�z�̎�܂�(�Ȃ����f�t���\�z�̋��܂�)�������Ƃ���Ă���13)�B
�p�������{�ʐ����痣�E���钼�O��1931�N8��������{���p���ɒǐ����邩�����ŋ��{�ʐ����痣�E����1931�N��12���ɂ����āA�C�[���h�E�J�[�u�͑啝�ɏ���ɃV�t�g���Ă���A�C���t���\�z�̋}���ȍ��܂肪�N�����Ă����ƍl������B���̔w�i�ɂ���X�g�[���[�́A�u�p�������{�ʐ����痣�E���Ă��܂����̂ŁA���{���߂������ɋ��{�ʐ����痣�E����ɈႢ�Ȃ��B��������ƁA���{�͋��{�ʐ��Ƃ��������̃A���J�[�������Ă��܂��̂ŁA�����㏸�Ɏ��~�߂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂���������Ȃ��v�Ƃ������̂ł���B�C�[���h�E�J�[�u�̏���V�t�g�́A�s��Q���҂����̂悤�ɗ\�������Ƃ��������Ɛ����I�ł���B
���ɁA�������̓��{��s������̉����������A���Ȃ킿1932�N3���ɍ������������߂Ă��̂��Ƃ����Z�W�҂Ɍ�����Ƃ���鎞������A���N6���ɐԎ������s�̂��߂̗\�Z�ĂƖ@�Ă��c���ʉ߂��A���ۂɓ��{��s�ɂ���Ĉ������{����铯�N11�����܂ł̎����̃C�[���h�E�J�[�u�̓������݂�ƁA�����ɃV�t�g���Ă���B���̂��Ƃ́A�������̓��{��s���̃A�i�E���X�������̃C���t���Ɍq����Ǝs��W�҂��l�����Ƃ����ѓc�E���c�����Ƃ͐����I�ł͂Ȃ��B�ނ���A1932�N���Ɂu���������v�̓��e����̉�����ɂ�A���{���{�͏������~�߂̂Ȃ��C���t���ɂȂ�Ȃ��悤�Ȍo�ϐ�����s���ł��낤�Ǝs��W�҂��l����悤�ɂȂ�A�C���t���\�z�����É����Ă������Ƃ��������Ɛ����I�ł���B
��2�ɁA���i�敨�s��̎Q���҂̕����ϓ��Ɋւ���\�z�������Ă݂��B�����̓��{�ł́A�āA�����A�Ȏ��A�ȉԁA�����Ƃ��������܂��܂ȏ��i�ɂ��Đ敨������s���Ă����B�敨����͓��Y���i�̏������i��\�����čs���A�C���t���\�z�̕ω��͏��i�敨���i�ɉe����^���Ă����ƍl������B1931�`32�N�̏��i�敨�s��̎Q���҂̃R�����g���E���Ă݂�ƁA�p�������{�ʐ����痣�E����1931�N9��������{�����E���铯�N12���ɂ����Ă̎����ɂ́A���{�����ӗ��E���C���t���ɂȂ邾�낤�Ƃ����\����������Ă���B����A1932�N���̃R�����g���E���Ă݂�ƁA���Ȃ��Ƃ��������̓��{��s���Ɋւ���́A�s��W�҂̊Ԃł͂قƂ�ǒ��ڂ���Ă��Ȃ��B���������āA���i�敨�s��W�҂́A�������̓��{��s�����f�t������C���t���ւ̑傫�ȓ]�@�ƌ��Ă����Ƃ͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl������14)�B
�ȏ�̎��ؕ��͂���A���{�ʐ�����̗��E�́A�l�X�̗\�z���f�t������C���t���ɕω�����傫�Ȍ_�@�ɂȂ�������A�������̓��{��s���͂��������_�@�ł͂Ȃ������Ƃ��������Ɛ����I�Ȍ��ʂ�����ꂽ�B
|
��(4)�u���������v�ƍ����K��
�ْ��ł́A�u���������v�ƍ����K���Ƃ̊W���������Ă���(��4��)�B
�w�E��{�W�҂̊Ԃɂ́A��2������̋}���ȃC���t���Ɏ��邫���������u���������v���ɂ����钷�����̓��{��s���ɋ��߂錩��������A�������̓��{��s���������K�������킹�Ă��܂����Ƃ̌��y�������Ȃ����B�Ⴆ�A1947�N�����@�́A���{��s�ɂ�鍑�̈��������֎~���Ă���B�����̑呠�Ȃ̖�c�K���v�ǒ��́A���@�Ă̒�ė��R�����̂Ȃ��ŁA�u���{��s�ɍ�������������ƍ����C���t���������N�������ƂɂȂ�v�Əq�ׂĂ���15)�B�܂��A���ގO���́A�������̓��{��s���Ƃ������x�ɂ́A�������ߐ���ւ̓]��������Ƃ�����肪�����Ă����Ƃ̎|��_���Ă���16)�B
Michael Bordo ��Hugh Rockoff �����̌����ł́A���ۋ��{�ʐ��ɂ͍����K�����ۂ����J�j�Y�������݂��Ă����Ƙ_���Ă���17)�B���Ȃ킿�A���ۋ��{�ʐ��ɎQ�����邽�߂ɂ͈בփ��[�g������I�ɐ��ڂ���悤�ɓw�߂�K�v������B�����K��������ꂽ��Ԃł͌Œ�בփ��[�g�����ێ��ł��Ȃ��B���������āA���{�ʐ��ւ̎Q���ɂ���āA���{�ɍ����K�����ێ�����C���Z���e�B�u�����܂��Ƃ�����|�ł���B����𗠕Ԃ��ƁA���{�ʐ�����̗��E�ɂ������K���̃��J�j�Y���������Ȃ��Ȃ�Ƃ����ʂ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�B
�ْ��ł́A�u���������v���ɂ͐��x�Ƃ��č����K�����ۂ����J�j�Y���������Ă����Ƙ_���Ă���B�������̓��{��s���ɐ旧���āA���{�͋��{�ʐ����痣�E�����B���̔w�i�ɂ́A����܂ō��ۋ��{�ʐ��̗v�ł������p�������łɋ��{�ʐ����痣�E���Ă����Ƃ�������������B���������āA���ۋ��{�ʐ��̉��ŋ@�\���Ă��������K�����J�j�Y���������Ă����B�������Ȃ���A���ۋ��{�ʐ��ɑ��郁�J�j�Y���͓������ꂸ�A���x�Ƃ��Ă̍����K�����J�j�Y���͊m������Ȃ������B�����������ŁA�������̓��{��s���Ƃ������x���������Ƃ��A�����I�Ȋϓ_����݂�ƍ����K���̒o�ɂɂȂ������ƍl������B
�����̈ێ��\���v�I�Ɍ�������@�Ƃ���Bohn ����Ƃ�����@������18)�B����́A�P���ɂ����ƁA�O�N�x���̍��c�������������ꍇ�ɐ��{����b�I�������x(���̔��s�����ƌ����������������������x)�����P�����č������������߂����A���c�������������ꍇ�ɂ͍������ɂ߂�Ƃ��������^�c���s���Ă���A�����͈ێ��\�ł���A�Ƃ�����ł���B
Bohn ����̎�@��}��������ƁA�����ɑO�N�x���̍��c���A�c���ɓ��Y�N�x�̊�b�I�������x���̂����ꍇ�ɁA���҂��E�オ��̊W�ɂȂ��Ă���A���c�������������ꍇ�ɂ͊�b�I�������x�����P�����Ă��邱�ƂɂȂ�A�����͈ێ��\�ł���Ƃ����B����A���ꂪ�E������ɂȂ��Ă���ƁA���c���������Ă���̂ɍ����Ԏ��𑝂₵�Ă��邱�ƂɂȂ�A�����͈ێ��\�ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�����Ԋ��̓��{�ł́A1931�N�x�܂ł͑O�N�x���̍��c���Ɠ��Y�N�x�̊�b�I�������x�Ƃ̊ԂɉE�オ��̊W���ۂ���Ă������A1932�N�x����E������̊W�Ɉڍs���Ă��邱�Ƃ��A���v�I�Ɋm�F�ł���(�}8)�B���v�I�ɂ݂�ƁA���{�̍����^�c��1932�N�x����ێ��\�ł͂Ȃ��Ɋׂ��Ă������ƂɂȂ�B
�@�@�@�}8 �O�N�x�����c���Ɗ�b�I�������x(��GNP ��)
�Ƃ���ŁA1932�N����36�N���܂ł́A���{��s�͈��������̂قڑS�z��I�y�ɂ���ċ��Z�@�ւɔ��p���邱�Ƃ��\�ł������B����������A������{��s����w�����Ă������Z�@�ւ́A���{�̍������j�]���ď��������\������댯���͂���قǍ����Ȃ��Ɣ��f���A�����w�����Ă������ƂɂȂ�B����́A�����������g�������̍����K���Ƃ��ċ@�\���Ă���Ǝs��Q���҂����f���Ă���A����Ύs��Q���҂������̍����^�c��M�F���Ă������Ƃ̌����ƍl������B���ۂɍ����́A�R���̗\�Z�v����g������ė}�����A�����c����}���āA�����~���ɏ��������悤�Ȋ��𐮂��悤�Ɠw�͂��Ă����B�������Ȃ���A���̌��ʁA��E��Z�����ŌR���ɂ���ĈÎE����Ă��܂��A�����Ƃ����l�̔\�͂ƈӎv�Ɉˑ����������K���͎����Ă��܂����B
���{��s���Z�������A�[�J�C�u�ɂ́A���������ق߂Ă����[��p�܂����M���A1934�N9���ɑ呠�Ȃ̐؈�j�����ǒ��ɒ�o�����Ƃ����u�������̓j�փX�������كm�ӌ��v�Ƃ��������̕��ʔł��c����Ă���B���̃����ł́A�s��W�҂̊Ԃō����҂ɋ^�`��������ꍇ�A������������Ȃ�\�������y����Ă���B
�ł��J�����ׂ��͍����җ͂ɑ���^�f���͉ݕ����l�̉����ɑ��錜�O��藈�鍑�̕s�����Ȃ�B�V����������Ƃ��͍�����̍���𗈂����݂̂Ȃ炸�o�ϋ@�\�y�юЉ�@�\��̗R�X���������N���ׂ��B�ݕ����l�̉����ɑ��錜�O����Ƃ��͋��炭�͋����\���𗈂����ׂ��B���̕s�����͉E���^���̌��ʂ���Ɠ����ɍX��ɑ��̋^������������̌����ƂȂ�ē]�X�ݑ����ׂ��B�����܂ł͍K�ɂ��Ďz����s�˂̒���Ȃ����̂ɍ��ɂ��ĔV���]�ׂ���͖��p�̞X�J���邪�@������x���̐�����Ƃ��͐i�s�}���ɂ��đ����鍢��Ȃ�ׂ����Ȃė\�߉��S������ׂ��炸�B����ł�荑�Ƒ�ǂ̖��̈ꕔ�Ȃ�ǂ���������A�ʉ��Z����A�ב���̎O���ʂɉ��ďo���邾���T�d�ɍl�������v���B���Ɉב�����]�ׂ���͉ݕ����l�����̌��O���בւ̕��ʂ�萶����ꍇ�������ȂĂȂ�B�ォ��U��Ԃ��Ă݂�ƁA�����ÎE��Ɍ��ǂ͍����K���������č������Ɏx��𗈂������킯�ł��邪�A���������̒���(1934�N)�̒i�K�ŁA�������ǂ̒��ɂ͍����K���̖��Ɋ�@��������Ă����l���������Ƃ������Ƃ͋L���ɒl����B
|
|
��4�D ������ |
�{�̘_�_������ƈȉ��̂Ƃ���ł���B
1920�N��̓��{�o�ςɂƂ��Ẳۑ�́A�������Z�V�X�e���̓��h�ւ̑Ή��ł������B1927�N�́u���a���Z���Q�v�̌�A�����ʂ̑[�u�Ƌ�s������K���E�ē̋�������ʂ�����s����̍\�����v���i�W�������Ƃɂ��A���Z�V�X�e�����͉����̕����Ɍ��������B
1930�N��̓��{�o�ςɂƂ��Ẳۑ�́A�������ɂ����{�ʐ����A�Ɛ��E���Q�̔g�y�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�f�t���Ȃ�тɕs���ւ̑Ή��ł������B����ɑ��鍂�������̏���Ⳃ́A�ב։~���A�����g��A�����ĉp���ɒǐ�����`�ł̋��Z�ɘa�Ƃ����P�C���W�A���I�ȑ����v�Ǘ�����ł���A����͗L���ɍ�p�����B
�u���������v���̓��{�ɂ����āA�l�X�̗\�z���f�t������C���t���ւƓ]�������錮�ƂȂ����͈̂ב։~���ł���A�������̓��{��s���ł͂Ȃ������ƍl������B�u���������v���ɂ����āA�������̓��{��s�����C���t���\�z����N�����؋��͂Ȃ�19)�B
�Ō�ɁA�u���������v�ƍ����K���̊W�ɂ��ẮA�u���������v���ɂ͋��{�ʐ��ɑ�������K�����J�j�Y�����m������Ȃ����ŁA���������l�̔\�͂ƈӎv�Ɉˑ����Ȃ���A�������̓��{��s�������Ă��������Ƃ��A�����I�Ȋϓ_����݂�ƍ����K���̑r���Ɍq�����Ă��܂����̂ł͂Ȃ����ƍl������B
|
����
1)�@�{�e�́A2009�N12��5���ɍs��ꂽ�����w�o�ό�������68��u����ł̍u���̓��e�������N���������̂ł���B�����Ɏ����ꂽ�ӌ��͎��M�҂ɑ����A�K���������{��s�̌������������̂ł͂Ȃ��B
2)�@��L�ْ̐�(�ȉ��A����[2009a])�̂ق��A���ډ�l[2009b]�u�����Ԋ��̓��{�ɂ����鋰�Q�Ɛ����Ή��F���Z�V�X�e�����Ɛ��E���Q�ւ̑Ή��𒆐S�Ɂv�w����r���[�x2009-J-1 ���Q�ƁB
3)�@2009�N4���ɁA���������h����G20 �̉���J�Â��ꂽ�BG20 ��̑O��̕��݂�ƁA76�N�O�̎��s���J��Ԃ��Ȃ����߂ɂǂ�������悢���Ƃ����c�_���Ȃ���Ă����B
4) �{�߂̋L�q�ɂ��ẮA����[2009a] ��5�͂̂ق��A����[2009b] pp. 2-3 ���Q�ƁB
5)�@�����T�g[1955a]�w�吳���a���E�ϓ��j�x����p. 739�B
6) ���{��s���Z�������ݕ������كz�[���y�[�W�Q�ƁB
7)�@�����T�g[1955b]�w�吳���a���E�ϓ��j�x����pp. 1315-1316�B
8)�@���{�ʐ����A�̌o�܂ɂ��ẮA�O�f����[2009b] pp. 4-5 ���Q�ƁB
9)�@�~�c��M[2006]�u1930�N��O���ɂ�������{�̃f�t���E�p�̔w�i�F�בփ��[�g����A���Z����A��������v�w���Z�����x��25����1���App. 145-181�B
10)�@�ѓc�הV�E���c��[2004]�u���a���Q�Ɨ\�z�C���t�����̐��v�v��c�K�v�j�ҁw���a���Q�̌����xpp. 187-217�B
11)�@�בփ��[�g�Ƌ��Z����̊W�ɂ��ẮA���ۃ}�N���o�ϊw�̕���Łu�}�N���o�ϐ���̃g�������}�v�Ƃ��Ēm����L���Ȗ��肪����B����́A�������z�������{�ړ��̊��S�Ȏ��R�A�Œ�בփ��[�g�A(�����o�ς̈��艻�̂��߂�)�����I�ȋ��Z����A��3�̐����ڕW�͓����ɂ͒B���ł��Ȃ��A�Ƃ������̂ł���B
12)�@Bernanke�A Ben S. [2003] �gSome Thoughts on Monetary Policy in Japan�A�h Remarks by Ben S.Bernanke�A Member�A Board of Governors of the Federal Reserve System�A Before the 60th nniversary Meeting�A Japan Society of Monetary Economics�A Tokyo�A Japan�A May 31.
13)�@Dewachter�A Hans and Marco Lyrio [2006] �gMacro Factors and the Term Structure of Interest Rates�A�h Journal of Money�A Credit and Banking�A 38 (1)�A pp. 129-138.
14) �ڍׂ͒���[2009a] pp. 113-128 ���Q�ƁB
15) 92��鍑�c��O�c�@�ɂ������ė��R�����v���䕽��[1947]�w�����@��������x��m�ЁAp. 161�B
16) ���ގO�u�����鍂�������ɂ��āv�w���Z�����x��2����2��pp. 83-124�B
17) Bordo�A Michael D.�A and Hugh Rockoff [1996] �gThe Gold Standard as a Good Housekeeping Seal of Approval�A�h Journal of Economic History�A 56 (2)�A pp. 389-428.
18)�@Bohn�A Henning [1998]�A �gThe Behavior of U.S. Public Debt and Deficits�A�h Quarterly Journal of Economics�A 113 (3)�A pp. 949-963.
19)�@���̔w�i���l����ɓ������ẮA�����̓��{���u�J�������v�ł������Ƃ����_���d�v�ł���B�f�Ֆʂł́A�A�o�ɂ��ĊC�O�s��ɑ傫���ˑ����A�A���i��ʂ����C�O������בփ��[�g�̉e�����傫�������B����A���Z�ʂł́A���{�������h����j���[���[�N�̎s��ʼnߋ��ɔ��s�������̗������z�͂��Ȃ�傫���������߁A�בփ��[�g�͈��̐����ň��肳����K�v���������B���������āA���{�̐������ǂ́A�ϓ��בփ��[�g���Ɉڍs����̂ł͂Ȃ��A�Œ�בփ��[�g����I�������B������������^�c���W�[���̉��ł́A���{�̋��Z����͊C�O����Ɨ����Ď����I�ɉ^�c����Ă����킯�ł͂Ȃ��A������p���ɒǐ����Ă����B���̈Ӗ��ł́A����̃G�}�[�W���O�����̏ɋ߂��Ƃ������Ƃ��ł���B�@
�@ |
| ���l���Y�K���t�Ə��a���Q |
   �@
�@
|
�����j�Łu�������v���l���邱��
���͂悤�������܂��B��낵�����肢���܂��B�u���j��if(������)�͂Ȃ��v�ȂǂƂ����܂��B�u�����͎����Ƃ��Ă�������ƔF�����ׂ����v�Ƃ����Ӗ��łȂ炱�̌��t�͐������ł��傤�B���������j�w�́u�Ȃ�����Ȕn���Ȃ��Ƃ������̂��H��x�Ɠ����ԈႢ�����肩�����Ȃ����߂ɂ͂ǂ����ׂ����H�v���̖₢�ɂ������悤�Ƃ��Đ��܂ꂽ�w��Ƃ������i�������Ă��܂��B���j�̒��ɂ��낢��ȉ\�����l���邱�Ƃ́u�Ђ���Ƃ�����Ⴄ�����������̂ł͂Ȃ����v�u�ԈႢ�͂ǂ�����N�������̂��v�Ȃǂ��l���邱�Ƃ��d�v�ł���A�uif(������)�v���l���鎋�_�͑�ł��B�������Ă��鎞���ł����u�푈�ւ̓��͕K�R�������̂��v�u�Ȃ��~�߂��Ȃ������̂��v�u�����~�܂�A�����Ԃ��`�����X�͂��������̂��v�u�ǂ�ȕ��@���������̂��v�u�Ȃ��`�����X���Ă��܂����̂��v�ȂǂȂǂ�₢�A���{���푈��I�������ɂ��\����T�邱�Ƃ́A�������l�����ł���Ȏ��_���Ǝv���܂��B���j��K�R�Ƃ��ĂƂ炦��̂ł͂Ȃ��A���܂��܂ȑI���̒��ŁA���܂��܂ȗv���̐ςݏd�˂̒��ŁA���݂����邱�Ƃ��w�Ԃ��Ƃ���Ǝv���̂ł��B�u���j�Ɂw�������x�͂Ȃ��v�ƈ��ՂɌ��A�_�j�ł����悤�ȋC�ɂȂ��Ă���ƁA���̗��j�����͎����̌�ǂ��ƂȂ��Ă��܂��A���邢�͗��j�̉\�����������Ƃ��A���j�̐[�����������鎖�͂ł��Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B
|
���l���Y�K�Ƃ����l��
1929(���a4)�N�ɐ��������l���Y�K���������}���t�A���̓��t���푈�ւ̓��������Ƃǂ߂闝�O�ƋC���������Ă����ƍl����l�͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B�l���́A���a�V�c�̎��ӂŕ����c���`����t�ɑ����ē��t��g�D���܂����B���������}�́A��������F�{�}�ƍ������Đ����������}�ŁA�������i�}�̗���������s�s�Ɋ�Ղ�u�����}�ł��B�O�g�̌�����}��ł����������������O�H�����̖����ł������悤�ɁA�l�����O�H�Ƃ͑����p�C�v�������A�I�������̑������O�H����o�Ă���Ƃ��������Ƃ̊W���[�����}�ł��B ��O�̐��}�����͂��̂悤�Ȗʂ������Ă��܂����B���������}�́A���{�̍H�Ɖ��A�s�s���ɂƂ��Ȃ��x���w���g�債�A�����Ƃ����ʑI���̉��b���₷�����}�ł�����܂����B�l���͍��m���̏o�g�B�呠�Ȃ̊����o�g�ł����A�u�y���̃C�S�b�\�E�v�Ƃ�����悤�Ȋ�łŐ��`���̋������i���Ђ��ďo���͒x�ꂪ���ł����B�������A���̐l�����������l�����̂����߂Ő��E�ɐi�݂܂����B���R�����^���̉e�����������Ƃ̎w�E������܂��B�{���͍K�Y�Ƃ������̂͂����A����т��������D�������܂ܖ���ɓ͂����o�������߁A���O�̏㉺���ԈႦ���Ƃ����G�s�\�[�h���c���Ă��܂��B�����̍D���Ȑl�̑������m���炵���b�ł��ˁB���������G�s�\�[�h�A�u���C�I���ɑ��v�Ƃ���Ɠ��̕��e�A���H���������ʂ��琽���Ɏ��g�ݎp���A����Ƀ��W�I�����Ȃǂŗ����ɍ����ɑi��������p���������āA�����̑�O���爤����܂����B�V�c�̂��C�ɓ���ł��������݂����ł��B
|
���l�����߂���������
�l���̍l�����̊�b�ɂ́u������R�����g�����Ă����͂̍�����p�ĂƐ���ď������邱�Ƃ͕s�\�ł���v�Ƃ������A���Ȍ����F��������܂����B�ł����獑�ۘA���Ȃǂ𒆐S�ɐ��E�Ƃ̋������邱�ƁB�Ƃ��ɒ����Ƃ̊W�C���ɂ��ْ��ɘa���R���k���ɂȂ���A�f�Ղ̊������ɂ��Ȃ���ƍl���Ă��܂����B�܂��A�f�Ղ����������A���������肳���邽�߂ɁA��v�������łɕ��A���A���N�̌��ĂƂȂ��Ă������{�ʐ����A���߂����A�����ւ��v�悵�܂��B���̉ߒ��ŁA�s�̎Z��Ƃ�ޏo�������A�Y�ƍ\�������x�����āA�����ƂƖȖa�ыƒ��S�̌o�ς���d���w�H�ƂȂǂɂ������u���o�ς֕ς��Ă������ƍl���܂����B����ɋ����ւ������߂�ɂ́A���S�ȍ����^�c���K�{�ł���A���ꂪ�R���̂킪�܂܂ȌR�g�v�������ۂł���傫�ȃJ�x�ɂȂ�Ƃ��l���Ă����Ƃ����܂��B���̂悤�ɕl���͌R����`�I�ł͂Ȃ��A���{�̂��������ѐ������������_�Ő����i�߂悤�Ƃ��Ă��܂����B�l�������́A���{�o�ς𗧂Ē����A�c���`����t�Ői�R����`���ւ̓����ْ��ɘa�ɂ�镽�a�ւƈ����߂����Ƃ����̂ł��B
|
���u�j�q�̖{���v
�������A�l���̖ڎw�������́A�����ɂ�������ꌠ�v�̊g���R���g�傱�������{�̈��S�Ɨ��v�ɂȂ���ƍl����R����E�����͂ƑΗ�������̂ł����B�����ւɂƂ��Ȃ��\�����v���s�i�C�������炵�J���҂⒆����ƌo�c�ҁA�_���Ƃ������l�X�̕s�������߂���̂ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B �l���͎���̍s�����Ƃ�����v������̖����댯�ɂ��炷���Ƃ�m���Ă��܂����B �l���̌��Ȃ́u�j�q�̖{���v�ŁA���ꂪ�\���ɑ_�����ꂽ�Ƃ������̌��t���Ԃ₢���Ƃ����Ă��܂��B���������ČR����`�ւ̓��ɊƂ������ƁA���ꂪ�l���ɂƂ��Ắu�j�q�̖{���v�ł����B�����ĕ�����d�Y���O����b�ɁA����قł�������㏀�V����呠��b�Ƃ��܂��B�h���}���Ɍ����u�ꏏ�Ɏ���ł���v�Ƃ��������ł��ˁB
|
�������Ƃ̊W���P
������̓I�ɂ݂Ă����܂��B�������ۋ����O���A�Β��������������܂��B�����Ƃ̊W�C���������߁A�ĉp�ƂƂ��ɒ����������{�����F�A������x���������͂���F�D���͕��j���Ƃ�܂��B���������������Ă����s�������̉������x���A���{�̊�Ƃ̗��v�����Ŏ��匠�̏��F�ɂӂ݂���A���O�@���ɂ��Ă��i�K�I�ȉ����̕��j���߂����܂��B�������Ē����Ƃ̊W�͉��P�̕����ɐi�݂܂����B�����\�z�O�������̂́A�����ł̖����^�����v�����ȏ�ɐi��ł������ƁB����������������{�͗�������▞�S���s���~�݂ȂǓ��{�̌��v�ɂӂ�铮���������߂Ă���A�ĉp�Ȃǂ�����ɋ��͓I���������Ƃł��B�������������͓��{�����̐��_���h�����A���R��E���Ȃǂ̐��͂́u���{�̌��v�����Ȃ��w���O���x�ł���v�ƁA��}���F��Ƃ�����Ŕᔻ�����߂܂��B
|
�������h���R�k��c
���Ɏ��g�̂��A�R�k���ł��B���V���g���C�R�R�k���͎�͊�(���)�ۗ̕L�������߂��܂����B����ƁA�u��͂Ƃ������������낤�v�Ƃ���ɁA�e���͏��m�͂Ƃ��A�����͂Ȃǂ̐�͈ȊO�̌R�͂𑝂₵�܂����B������Ȃ�Ƃ���������1927(���a2)�N�W���l�[�u�R�k��c���J�Â���܂��������s�ɏI���܂����B�R���g���́A�e���ɂƂ��Čo�ϕ��S�ƂȂ邾���łȂ��A�݂��̋^�S�ËS�����߁A�ْ����܂��A����Ȃ�R�g�ɂȂ���܂��B����������Ԃ����P���悤�ƁA1930(���a5)�N�����h���R�k��c���J�Â���܂��B�l�����t�͌��V�̐�������V�c���߂Ƃ��ł����킹�̂����ʼn�c�ɗՂ݂܂��B���̉�c�ɁA�ł��_�o���ɂȂ��Ă����̂́E�E�E�����܂ł��Ȃ��C�R�ł��B�C�R�͉�c�ɗՂ�ŁA�l����ɓB���h���܂��B�u�Εĉp70���ȉ��ł͍���B���̃��C���͎��炵�ė~�����v�ƁB�Ƃ��낪�A���̌��_��69.75%�B�u�������炢�����Ă��ꂽ��悩�����̂Ɂv�Ƃ̂��̓W�J��m��Ǝv���̂ł����A�u�A�����J�c��̏��F���Ȃ��v�Ƃ���������ނȂ��Ɣ��f���܂��B�����Ō��n�̊C�R��b���͂��߁A�C�R�̑吨�̗��������āA�l���͓��t�̐ӔC�ŏ���������܂����B�Ƃ��낪���l�̊C�R�W�҂͔[�����Ă��܂���ł����B���ꂪ���������Ɩ��Ƃ��ĕ��サ�܂��B���̓_�ɂ��ẮA���ƂŐG��邱�Ƃɂ��܂��傤�B
|
|
�������ւƏ��a���Q
|
���Ǘ��ʉݐ��x
�l���̐���̂�����̒��u�����ցv������݂Ă����܂��傤�B���̓����A���E�̑吨�����{�ʐ��x�ɕ��A���Ă����ɂ�������炸�A���{���Ƃ��Ă����̂͊Ǘ��ʉݐ��x�ł����B���݂̐��E���̗p���Ă�������ł��B�Ǘ��ʉݐ��x�ł́A���ꂼ��̍��������̔��f�Œʉ݂s�ł��܂��B���������Ď����̋��ɂ̒��ɂ������Ȃ��Ƃ��A�K�v�ȑ�ʂ̂����s���邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B�����߂��Ⴍ����ɒʉ݂s����C���t���ɂȂ��č����Ԃ�܂��̂ŁA�ǂ̂悤�Ɏ�j���Ƃ邩�A�Ȃ��Ȃ��ʓ|�Ȑ��x�ł��B�����s���́A�����Ƃ��č����O������Ƃ����؋��Ō����߂����܂��B���z������C�ɂ������[��������ŃN���W�b�g�J�[�h�Ŕ����������銴���ł��ˁB�푈�Ȃǂő傫�Ȃ���������Ƃ��͓s���������ł����A�ǂ����Ă���(����)�g�����r���Ȃ�A��x�͂��߂Ă��܂������Ƃ͎~�߂�ꂸ�A�؋����d�˂Ă��܂������ł��B�����Ȃ�ƁA�C���t�����N����₷���A���ېM�p���ቺ���A�f�Ղɂ��x�Ⴊ�o�܂��B
|
�����{�ʐ��x�ƕl���E���̂˂炢
����ɂ������āu�w�g�̏�x�ɍ������z�̒ʉ݂������s���Ȃ��v�Ƃ������x���{�ʐ��x�ł��B���̏ꍇ�́w�g�̏�x�́A���ꂼ��̍��������Ă�����܂��͋�̗ʂł��B���̏ꍇ�����{�ʐ��A��̏ꍇ����{�ʐ��ł��B�����ւ�f�s�����Ƃ��A���{��13��6�疜�~���̋��������Ă��܂����B���̊z�����ƂɌv�Z���āA���s���ׂ��ʉݗʂ����߂�̂ł��B�����āA�ʉ݂���{��s�Ɏ����čs���Ƃ��ł����ƌ������Ă��炦�܂�(���[�����x)�B���D�ɂ�����������܂��B���Ȃ݂�100�~�̒ʉ݂́A��75���O�����ƌ������Ă��炦�܂��B���Ȃ݂ɋ�75�O������49.845�h���ł��B�ł�����~�͂��ł��h���ƌ��܂������[�g�Ō����ł��A���S�ł��B�l���ƈ��͂��������d�g�݂Ōo�ς����艻���A�f�Ք��W�ɂ��𗧂ƍl�����̂ł��B���{�ʐ��͍��������肳���܂��B�w�g�̏�x�ɍ������z�̒ʉ݂������s���Ȃ��v�̂ł�����A�����K�͂́u���{�������Ă�����̗ʁv�ɋK�肳��܂��B����ɂ��A�u�����Ƌ�������v�Ƃ����R����}�Ȃǂ̗v�������ނ��Ƃ��ł��܂��ˁB�l����̂˂炢�́A�����ʂ���R�������������ޓ_�ɂ��������Ƃ������Ă��܂��B�������A�傫�Ȗ�������܂��B���s����ʉ݂�����Ƃǂ�Ȍo�ό��ۂ��������܂����H�E�E�E�����A�f�t���ł��B�����ɑ��ă��m�̒l�i���Ⴍ�Ȃ�Ƃ������ہA����Ă�����Ȃ��Ƃ�����ԂɂȂ肪���Ȃ̂ł��B���R�s�i�C�ɂȂ�܂��B�l����͂������ނȂ��ƍl���Ă��܂����B�f�t���ɂȂ邱�ƂŁA���̈������i�A���Y���̈����ݔ��A�O����̎����ʼn������Ă����Ƃ��p���������Ƃ͎d�����Ȃ��ƍl�����̂ł��B�����A�f�Ղ����肷��ΓS�z��ȉԂƂ��������ޗ��̗A�������₷���Ȃ�A�Ƃ��ɏd���w�H�Ƃ̔��W���������B����ɂ���āA�u���������������Ƃ��ċؓ����ɂȂ������{�͖ʖڂ���V���Đ��E�̎s��ɏ��o���Ă�����v�ƍl���Ă��܂����B�����ȂǑ��Ƃɓs�����悭�A������Ƃɂ͌���������Ƃ����ᔻ�͓�����Ȃ��ł��傤�B�����ŘJ���g���@�⏬����~�ς���悤�ȎЉ����������Ă��܂����B����ɁA�A�����J�̋�s�̕ۏ����t���܂����B���͑S����V���������ւ̈Ӌ`������A�����̔[����w�͂����܂����B���̎����A�l�X�͕l�����M�����Ă��܂����B������1930(���a5)�N1��11���A�������J�n����܂����B
|
�����a���Q�̔���
���āA���̋����ւ��n�܂����N�A1930�N�A�����C�����܂��B���̑O�N�A1929�N�A��������܂���ł������B���E�j���邢�͒��w�Z�́u�����v�ɂ��̔N�����łĂ����̂ł����E�E�E�B�����A���E���Q(�勰�Q)�����������N�ł��B�܂�A�����ւ́A�j���[���[�N�E�E�H�[���X�̊�������Ŋ����̑�\������������2��������Ɏ��{���ꂽ�̂ł��B���̊��Ԃ������ł��ˁB��Q���g�債����Ƃ��������ŁA�ň���Ԃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B���E�����s�i�C�ɂȂ肩���̂Ƃ��B�{���͖��ɂ�������a���������ǁA�@���ׂɂł������������ȁA���������������ł����B���Ƃ��猩��ƍň��̃^�C�~���O�ɍł�����Ă͂����Ȃ����Ƃ���������Ƃ��킩��܂��B�����̂��A�s�i�C�ɂȂ�ƈ��莑�Y�Ƃ��ċ����Ȃǂ��W�߂܂��B�����Ȃ̃o�U�[���ł͂����璆�ŋ��̃l�b�N���X�Ȃǂ��Ă��܂��B�Ȃ����킩��܂����B�����o�ς��s����Ȓn��ł́A���莑�Y�Ƃ��ċ�����g�̂ɐg�ɂ��Ă����A�K�v�ɉ����Ĕ��p���邽�߂Ȃ̂ł��B����������i�����������̂ł��B�s�i�C�ɂȂ�o�������Ƃ�S�z�����l�X���Ƃ͋��Ƃ������Y���茳�ɒu�����ƍl���܂��B���̐^���Œ��ɁA���{���u�����Ă��A�����������Łv�ƌ����o�����̂ł��B���E�����璍�����E�����܂��B���͂���悠���Ƃ����Ԃɗ���o���܂��B�\��ɔ����ėA�o���L�тȂ��������Ƃ����܂��āA�����֎���13��6�疜�~����������2�N���1932�N4���~�Ɍ����Ă��܂��܂����B�厑�{�Ƃł�����M���@�c���������܂����B�u�r�ꋶ���\���J�̂��Ȃ��ɉJ�˂��J���������悤�Ȃ��̂��v�ƁB���̗Ⴆ�͎��Ԃ��݂��ƂɌ����\���Ă��܂��B�������ď��a���Q���n�܂�܂��B���a���Q�́A���E�I�Ȍ��ۂƂ��Ă̐��E���Q(�勰�Q)�ƕl�����t�̎����Ƃ��Ă̋����������N���������̂ł����B
|
���A�o���ނƃf�t���̐[����
�����Ă�����̗ʂ����~�s�ł��Ȃ��A���ꂪ���{�ʐ��ł��B������A�莝���̋�������Δ��s�����~�̗ʂ�����܂��B����ɂ��A����ȃf�t�����������܂����B�����͋����ւ���2�N�Ԃ�30�������A�����Ɏ����Ă�66���̉����ƂȂ�܂��B�����ƕ��Ԃ�����̎�v�A�o�i�̖Ȏ��E�ȕz�́A���A�o��̒����ƃC���h�������Y�Ƃ���邽�߂Ɋŗ��������グ�A��͂�A�o���������܂����B�����ւɂ���ėA�o���D���ɂȂ�Ƃ����v�f�͊O��A���{�̗A�o�z��43���Ƃ����啝�Ȍ����ƂȂ�܂����B
|
�����a���Q�Ɣ_��
���E���Q�̓A�����J����n�܂�܂����B�����A�����J�͐��E���ɋ����t����u���E�̋�s�v�ł����B�A�����J���h�C�c�ɋ���݂��A�h�C�c���������Ƃ��ăC�M���X��t�����X�ɂ��̋��̈ꕔ���x�����A�C�M���X��t�����X���A�����J�̑�풆�̎؋���Ԃ��A�Ƃ����V�X�e�����ł������ƂŁA1920�N��̃��[���b�p�␢�E�������Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�����J���R�P�܂����B�ǂ��������Ƃ�������܂����H�A�����J�̋�s�̓h�C�c�ɋ���݂��Ȃ��Ȃ�܂��B����ǂ��납���E���̍��Łu�݂�������Ԃ��v�Ƃ����o���܂��B�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��N����ł��傤�H ���E���̍��ł��������Ȃ��Ȃ�A�������s�i�C�ɏP���܂��B���E���Q�̋���ׂ��Ӗ���������ł��傤�B���̖L���ȃA�����J�́A�L���Ȑl�Ɏx�����Ă����̂��A���{�̗A�o�i�́u�s���̎l�ԃo�b�^�[�v�A�����ł����B�l�́A�i�C���������ґ�i����ߖ���͂��߂܂��B���̂����ґ�i�ł��鐶���⌦�D���̔���s���������A�����̉��i��2�N�Ԃ�66���̉����A��N�O��1�^3�̒l�i�ƂȂ����̂ł��B����ł͎�Ԓ��ǂ��납�A������ɂ��Ȃ�܂���B�����̌����̖��́A�_���ł����܂��B�����琶���A�o�̌����͔_���֑傫�ȃ_���[�W��^���܂����B����ɉ^�̈������Ƃ�1930(���a5)�N�͋L�^�I�ȕĂ̑�L��ł����B�L����Ă��ꂵ���͂��ł���B�ł����ۂ͂�������Ȃ��̂ł��B�킩��܂����B�s�ꉿ�i�͎��v�Ƌ����̊W�Ō��܂�Ƃ����b�A���w�Z�ŏK���܂����ˁH���̔N�͕Ă̋��������ɑ��������̂ł��B����ɂ��Ă̒l�i�͖\���A8����1������30�~�ł������ĉ���10���ɂ�19�~��2�^3�Ɩ\���A�L��n�R�Ƃ����܂����B�Ƃ��낪��1931(���a6)�N�͈�]���đ勥��A����ɗ��N�����삪�Â��܂��B�_�Ƃ�������؋��͔N�ԏ�����1.5�{���܂����B���w���ɂƂ��Ē��x�݂͂��ꂵ���͂��ł��B���������̂���̏��w���A�Ƃ��ɓ��k�̎q�ǂ������ɂƂ��Ă͐h�����Ԃł����B���x�ݎq�ǂ����������낼��Ƌ�������łĂ������Ƃ��A���Ȃ��݂̕��i�ł����B�ٓ��������Ă����Ȃ������̂ł��B�ނ���u���H�����v�Ƃ�сA�S����20���l�ɂ̂ڂ�܂����B�u���̐g����v���ꂪ��������悤�ɂ���Ȃ�܂����B
|
���u�f�t���X�p�C�����v
�s�s�ɂ����Ă����Q�̔�Q�͐[���ł����B�A�o�ʂ̌����ƕ����̉����͍H����A��Ƃ����X�Ƌꋫ�Ɋׂ点�܂��B�ŏ��͔��l�������͂��߂܂��B�����̈���������J�����Ԃ̒Z�k�A����ɂ́u���X�g���v(�l���̍팸)�⎖�Ə��̐����������݂܂��B�ǂ����悤���Ȃ��Ȃ�����Ƃ��x�Ƃ�|�Y�ɒǂ����܂�܂��B�o�c�҂̖铦��������s�����Ȃǂ����ʂ�������܂��B�������Đl�X�̎����͒ቺ�A�����Ɏ��Ǝ҂����ӂ�܂��B����ȏ�ԂŐV���ɐl���ق���Ђ͒������B��Q�͎�҂ɂ��y�т܂��B�����̗��s�ꂪ�u��w�͏o������ǁv�f��������܂��B��J�ɋ�J���d�˂Ă���Ƒ�w�𑲋Ƃ��Ă��A�ߐ悪�Ȃ��Ƃ������Ԃ��������܂��B�݂�Ȃ̐��N�O�̐�y�̂���u�A�E�X�͊��v�Ȃ�Ă��������ǁA���̂Ƃ��������B���ƂƓ����ɖ��E�҂̌Q��̒��ɐg�𓊂��邱�ƂɂȂ�A�������������ł��B�吳���{��`���x���Ă����T�����[�}���ȂǐV���ԑw�Ƃ�����l�X�ɂ���@������A������|�p�Ȃǂɂ��s�����]�����f���o����܂��B�d���������A�V���Ȏd�����������Ȃ��l�X�́A������s���̂ǂ��ɂ���ӂ邳�Ƃł���_���A���Ă����܂��B���Ɣ_�Ƃ̌��Ƃ����܂��B�����̒n�傽�����y�n��Ԃ��Ă��炨���Ƃ��āA���쑈�c���}�����܂��B������������Ă���l����������A���̋������������Ă����ƁA����ɍw���͂�������܂��B�����͂�������������A�|�Y�������ݎ��Ǝ҂������A����ɂ��̂̒l�i��������B���̂悤�Ȍi�C�̈��z���f�t���X�p�C�����Ƃ����܂��B�݂�Ȃ����܂ꂽ���A�悭�����Ă������t�ł��B�����Ă��̃f�t���̉Q�̒��ɐl�X�����ݍ��܂�Ă����܂����B���̒��͈ꋓ�ɕs���ȋ�C�ɕ�܂�Ă����܂��B�������������f���āA�u���͗܂����ߑ����v�Ƃ��u�e��炢�āv�Ƃ��������������т����s�̂��ꐢ���r����悤�ɂȂ�܂����B���������Ă݂܂��傤�B��Ȃ����͖̂�����w���w���o�g�̌Éꐭ�j�A�u�e��炢�āv�͎��E���悤�Ƃ����{�錧�̎R���Ō����[�z����C���X�s���[�V�������Ƃ����Ă��܂��B
|
���J�����c�E���쑈�c�̌���
���āA���������s���̒��A�l�X�͂��ƂȂ�������������������ꂽ��A�N�r�ɂ���Ă������肵���̂ł��傤���B�_�������͍��܂Œʂ�ɖق��ď��엿���x�������̂ł��傤���B�����ł͂���܂���ł����B��������邽�߂ɗ����オ��܂����B����܂ł̘J���g����������J�����c���͐�O�ō����L�^����悤�ɂȂ�A�J�����c�͒��������グ�Ȃǂ̗v�������S�ł������A���������E���ٔ��A����ɂ͉��َ蓖�x���Ƃ������A���؎��ȓ��e�ƂȂ��Ă����A���̐����A�Q���҂��}�����܂��B�Љ�V�X�e���̒x�ꂽ�\����w�i�ɒ�����E��������Ԃɂ����ꂽ�a�я��H�����̊Ԃł����c���������܂��B��Ђ͕��e�����A�u�`�`�L�g�N�v�Ƃ������d���ł����ď��H��A��߂�����ȂǁA�^���̐�������s���܂����B���������̈������������߂����҉^�������������܂����B�_���ł��A���쑈�c���}�����܂��B�����{�����S�ł��������쑈�c�́A��������k�֓��ւƍL����A���ɂ͋��Q�̔�Q���ł��[���ł��������k�����c�ő����n��ƂȂ�܂��B����܂ł̏��쑈�c�̗v���̒��S���u���엿���Ɓv�ł������̂ɑ��A�u����n�����グ���v�����S�ۑ�ƂȂ�A�K�͂̏����ȑ��c�������A�������܂���Ƃ����X�������܂�܂����B�_�����Ȃ�Ƃ����Ȃ���Ƃ����^�����L���肾���Ă��܂��B�{�����u�J�ɂ��������v�̎����������̂͂��̂���̂��Ƃł��B
|
���}���N�X��`�̍L����ƃt�@�V�Y��
�Љ�̖����̐[�����Ƒ��c�̊������̒��A�}���N�X��`��@�g�D�ł��������{���Y�}�̉e���͂��g�債�Ă����܂��B�Ⴂ�m���l�̊Ԃł̓}���N�X��`���L����������A�w��͂��Ƃ��A�v�����^���A���w���͂��߁A������f��Ȃǂ̕���ɂ��e�����������܂��B�X���f��ƌĂꂽ�Љ�h�̉f����o�Ă��܂����B������ƌ��Ă݂܂����B�u�����ޏ����������������v�Ƃ�����i�ł��B�T�C�����g�f��ł��B�������������ɋ��|���o���������x�@�Ȃǂɂ��������������܂����B�܂��Љ�̍�����_���̔敾�͍����ȂǑ厑�{�ƁA����ƌ����}�����̐ӔC�ł���Ƃ��������Ђ낪��A���̉����ɌR���𒆐S�Ƃ����S�̎�`�̐������߂鐺���A�R����ݖ�̉E�����͂̒����琶�܂�Ă��܂����B�N�[�f�^�[���v�悳��A�e�������s���鎞��ƂȂ��Ă����܂��B
|
���u�����ցv�Ƃ������
���̂悤�Ȏ��ԂɂȂ����ɂ�������炸�A���̐���ɐ��������������Ă���l������͋��C�ł����B���E���Q�͈�ߐ��ł���A���E�͂����ɗ�������B���A���̐h���������䖝�����邱�Ƃŋُk�̌��ʂ�������A���{�̎Y�Ƃ͋ߑ㉻���A�f�Ղ����W����B���̓������Ȃ��B�ƌ����M���Ă����̂ł��B����ɁA�������v�����i�߂悤�Ƃ��܂����B���������p���ɑ��A���F��͋c��Ō��������t�̐ӔC��₢�܂����B���̓��ق̓��W�ŕ������Ȃ���Ԃł����B���������������悤�ɁA��������͖��炩�Ȍ��ł����B�A�����J�Ŕ�������������\�������Q�̒�����߂����i�K�ŁA�E�C����P�ނ��s��Ȃ������̂́A��͂莸���Ƃ��������Ȃ��ł��傤�B�u�����ւ𒆎~���������ƂȂǂŗL�����v���g�傷�ׂ��v�Ƃ������F��̑��ɗ������������Ƃ́A���݂ł͖��炩�ł��B�������A�ނ�̎������U������̂̓t�F�A�łȂ���������܂���B�����A���E���Q�̎����Ă����Ӗ��𗝉����Ă����o�ϊw�҂������Ƃ͂��܂���ł����B�����Ƃ��Ă��������\���҂��������ꂽ�̂��ւ̎R�������ł��傤�B�L�����v�������邱�ƂŌo�ς̗��Ē�����}��Ƃ����o�ϐ��������C�M���X�̌o�ϊw�҃P�C���Y�̒����͂܂���������Ă��܂���ł����B�����̌o�ϊw�̐����Ƃ������E�̒��ɔނ�͂����̂ł��B
|
�����������Ɩ��
���Q�ɂƂ��Ȃ������⏫���̕s�����L����Ƃ����s���ȋ�C�̂Ȃ��A���F��͌������U�����d�|���Ă��܂����B��Ɍ����悤�Ƀ����h���R�k���ɂ����āA�l���͊C�R�̈ӌ����Ȃ�����t�̐ӔC�ŏ������F���܂����B�Ƃ��낪�A�C�R�̒��ɂ͕l���̂����͔[���ł��Ȃ��ƍl����l���������܂����B�u�R���́A�R���̍��ɂ����������e�Ȃ̂ŁA���ɂ������R�ߕ��̏��F���K�v���B�Ƃ��낪�R�ߕ��̐ӔC�҂̐����ȏ��F�����������t������ɒ����̂́A�V�c���R�����w������Ƃ������@�̓����̌��Ɉᔽ����v�Ƃ����������̂ł��B�l�����t�ɔ����������Ă������F��͂���ɔ�т��āu���������Ɩ��v�Ƃ��ē��t���U�����܂��B���F��ɂ�邱��������A�̍U���́A���}�����Ƃ����݂�����̊�Ղ����@������u�ւ���v�ł����B�ɂ�������炸�A���G�����}��ǂ����ނƂ����ڐ�̖ڕW�����̂��߂ɂ��̂悤�ȍs���ɂł��̂ł��B����Ӗ��A���}�����A�Ƃ��ɓ�吭�}���̕��Q���o���ƌ����Ă����̂�������܂���B�l�����t�̕��������O�������������ɔ������Ă��鐨�́[�R�����d�h�E�E���E�ꕔ�}�X�R�~�A�����Đ��F��[���A�����āA�l�����t�ɑ�U�����d���ĂĂ��܂����B�l���͋����֒���Ɏ��{�����O�c�@�I���Ŋl�����������}�̐�Α�����w�i�ɁA���ʓ˔j�����{�A�V�c�Ƃ��̑��߂̎x�������Ȃ���A�����h���R�k�̔�y(���F)����ɓ���܂����B
|
���l�����t�̏I��
1930(���a5)�N11���A�c��ł̘_�����i�������Ēn���V���Ɍ������l���������w�Ŗ\���ɕ���������܂����B���̏����������ƂȂ��ĕl���͑̒����������A�×{�����ɂ͂���܂��B���̊ԁA�O�c�@�ł͐��F���U�����|���Ă���A���ƂȂ鐭�F��̔��R��Y�́A�l���ɍ���ɏo�Ȃ��ē��ق��邱�Ƃ������v���A�ӔC���̋����l���͍���قɗ����܂����A���̖������������ĕa������������܂����B������1931(���a6)�N4����������Η玟�Y�ɏ���A8���ɂȂ��Ȃ�܂��B�������āA�푈�̓���������悤�Ƃ��鐭��ƗE�C�������A���}�����̒��_�Ƃ�����l�����t�̎��オ�����܂����B
|
���\�ܔN�푈�̊J�n��
�l�����t�I����5������A�l���̎���1�������1931(���a6)�N9��18���̖����Ύ��������������ɖ��B���ς��������܂����B�����\�ܔN�푈���n�܂�܂��B�R���A��������R�̈ꕔ���ɉ߂��Ȃ��֓��R�̍s�����A���t���A�c����A����ɂ͓V�c��V�c����芪���O���[�v���A�R���������炪����ł����A����ǔF�����肩�������ƂŎ��Ԃ����������Ă����܂��B�l���̎���́A�����������䂪���肬��\�ł���������ł������̂�������܂���B���邢�͐���̉\�����Ȃ�Ƃ��T���Ă������ゾ�����̂�������܂���B���F��́u���������Ɓv�Ƃ����U���͌R���ւ̃u���[�L������j�A���̖\�����~�߂��i��������悤�Ƃ������̂ł����B����̗����Ȃ��Ȃ����R���͖\�����J��Ԃ��A����ɂ��炽�Ȑ퓬�s�ׂ��͂��߂܂��B�������ē����\�ܔN�푈���W�J���Ă����܂��B�����ėL���Ȏ��ł�������ǔF���J��Ԃ����t��c��͍����̐M���������܂��B�����̐��䂷�痘���Ȃ��R���͖\�������肩�����A�����ƃA�W�A�̖��O���A���E���A�푈�ւƓ����Ă����܂��B�u���������Ɓv�𐺍��ɋ����F��ٌ��{�B���R���̖\����}���悤�Ƃ��Č܁E������̃e���ɓ|�ꂽ�̂͗��N�̂��Ƃł����B�u�����A�l���������������������ێ����Ă�����v�Ƃ����悤�ȁu����(������)�v�́A�l����ׂ��łȂ��̂ł��傤�E�E�E�B�@
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
������̋��Q�@ |
   �@
�@
|
 �o�u�� �o�u�� |
| �����Q2008�N |
|
�����E���Q1929�Ƃ̔�r |
���r�b�O�X���[�V���b�N
�V���^����ɗA�n��ɗ������鋐��覐�ڌ�������A10����ɉ����N���邩�H�n���̑�C�������߂��������A�����̖ϑz�Ȃ�A�債�����Ƃ͂Ȃ��B���E�͍��܂łǂ��肾�B���������A�n���ɏՓ˂�����A�n���Ō�̓��ɂȂ邩������Ȃ��B10����ɂ́A�������Ƃ��Ȃ��ٌ`�̐��E �E�E�E ��X�͍��A����ȏɗ�������Ă���̂�������Ȃ��B
2008�N12��11���A�A�����J�����ԑ��r�b�O�X���[�̋~�ϖ@�Ă�������p�ĂɂȂ����B3�Ђ̌o�c��Ԃ͍ň��ŁA���ł��f�l�A�N���C�X���[�́A1������ɂ͎������V���[�g����Ƃ����B����A�V���Ȗ@����K�v�Ƃ��Ȃ����Z���艻�@�Ɋ�Â��x������������Ă���(2008�N12��13��)�B����ɁAFRB(�A�����J�A�M����������)�̓��ʗZ���g���g���\��������B
����̃r�b�O�X���[�V���b�N�ŁA�A�����J�̊����͌������l�������݂����B�p�Ă̔��\��A�}���A�����āA���Z���艻�@�ɂ��x�������\�����ƁA�}�㏸�B���̎������Ƃ��Ă��A�A�����J���ǂ�قǍ������Ă��邩���킩��B����Ȕ��\�Ŋ������߂邱�Ǝ��̂��������̂��B�A�����J�̊��͂����Ɖ�����B
����̃r�b�O�X���[�~�ϖ@�ẮA���@�͒ʉ߂������̂́A��@�Ŕp�ĂƂȂ����B���̊ԁA�A�����J�����͋c�_�S�o�B�j�]���O�̃r�b�O�X���[�������~���ׂ����ۂ��H
�u���Ƃ̌o�c�̎��s���A�����̐ŋ��ŐK�ʂ�������̂͊Ԉ���Ă���v
�u�r�b�O�X���[���j�]����A���Ǝ҂������A���ǁA�A�����J���ɂށv
�����A���̋c�_�͏��߂��Ԉ���Ă���B�r�b�O�X���[�́A�j�]���O�ł͂Ȃ��A���łɔj�]���Ă���̂��B���̐₦���g�̂ɁA������A�O�Ȏ�p���{����҂����邾�낤���H�r�b�O�X���[���̊j�S�́A�����J��ɂ���̂ł͂Ȃ��B�����A�����Ȃ�A���I�����𓊓�����Ζ��͉�������B�����A���̖{���́A
�u����鎩���Ԃ����Ȃ��v
�ɂ���B�̂��Ȃ��̎�A�����̂ł��Ȃ��R�b�N�ɁA���J�l���҂Ȃǂ��Ȃ��B
�����A�n����ŁA�����ԃ��[�J�[���r�b�O�X���[�����Ȃ�A��݂�����\���͂���B�Ƃ��낪�A�����ԃ��[�J�[�͐��E���ɎR�قǂ���B�������A�����ԋƊE�́A�����ɕ��S�������Ȃ����^�ԁA�d�C�����ԂփV�t�g������B�r�b�O�X���[�́A�K�\���������Ԃ����łȂ��A���̐��E�ł������͂��Ȃ��̂��B���o�ňꐢ���r�������j���A�R��ɒ��킷�邩��J�l��݂��Ă���A�ƌ����Ă���悤�Ȃ��̂ł���B�Ƃ������ƂŁA
�u�r�b�O�X���[�͂�������ł���v
��̃r�b�O�X���[�̘_�c�ɂ́A������ԈႢ������B�r�b�O�X���[���~�ς���悤������܂����A��ʎ��Ƃ͔������Ȃ����Ƃ��B����A�~�ς��ꂽ�Ƃ��Ă��A�����̐ŋ����g������O�A��Ђɂ͒ɂ݂��Ƃ��Ȃ��B�僊�X�g���A���^�̌��z�A���������̃J�b�g�A�����炭�A�j�Y�@�̓K�p����̂Ƒ卷�͂Ȃ����낤�B�������A������Ђ����l���B�H���A���̒��_�ɗ���Ƃ��|���A�s���~�b�h���̂��̂�����B�܂�A
�u��ʎ��Ƃ�����邽�߂ɁA�r�b�O�X���[���~�ς���v
�͊Ԉ���Ă���B
|
���M�p��@(�N���W�b�g �N�����`)
�T�u�v���C�����[�����A���[�}���E�u���U�[�Y�j�]�AAIG��@��ʂ��āA���E�͔��X�̏�ɗ����Ă��邱�Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B
�u�݂��1�h�����ƐM�p���Ă��邩��1�h���Ȃ̂ł����āA���̓^�_�̎���v
���t��������A���Z�͐M�p�����Ő��藧���Ă���B
�����ŁA�������悤�B�X�͕��G�����A�S�̂͂������ăV���v�����B�g�Ȃ�̂����Z�[���X�}�����A�u100�~�{50�~�v�Ə����ꂽ����肳���Ă����B
�H���A
�u���̏؏���100�~�ōw������ƁA1�N��ɂ�150�~�ɂȂ�܂���v
�u�W�߂��J�l�ŕ����āA����Ŏx��������ł��v
�u���v�����āH�v
�u���S�z���p�B�ی��������Ă���܂�����v
�u���ɂ͂���Ă��A�ی���Ђ������Ă���܂���v
�������āA�Z�[���X�}���͂��̎�����A���E���ɔ��肳�������A�^�����H���͂͂���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���Ăɂ��Ă����ی���Ђ́A�z���������ĕ����Ȃ��Ƃ����B���Z�̍Ō�̍Ԃ������킯���B���ꂪ�A2008�N9���ɋN������AIG ��@�ł���B�M�p��h�邪���Ƃ����_�ł́A��s��،���Ђ̔j�]�̔�ł͂Ȃ��B���[�}���E�u���U�[�Y�����̂Ă��A�����J���{���AAIG���~�����̂́A���̂悤�Ȏ���ɂ��B���E���n���������܌����u�Ԃ������B
����ɖ��G�ɂ����̂́A�u100�~�{50�~�v�؏������ɁA�����Ǝ�̍��C���`�L�؏������A�]�������҂��������Ƃ��B�܂�A�܂��I�����Ă��Ȃ��u100�~�{50�~�v�؏�������ł��邱�ƂɂȂ�B�N���ǂꂾ�������Ă��邩�N��������Ȃ��B�M�p�s������C�ɕ��o�������R�͂����ɂ���B
|
���M�p��@�̌���
����̋��Z��@�ŁA�ł����Q�������ނ����̂́A�J�W�m���Z�̌����u�w�b�W�t�@���h�v���낤�B�w�b�W�t�@���h�Ƃ́A���Z�@�ւ�x�T�w����W�߂��J�l�ŁA�����A���A�ʉ݁A���i�敨�A�C���`�L�؏������ė��v�Ă���g�D�ł���B���J�l��݂��ċC���ɗ������Ƃ�킯�ł��A�x���`���[��Ƃɓ������Ė���ǂ��킯�ł��Ȃ��B�����Ă��܂��A�����o�N�`�B�l���オ��Ƃ݂�Δ����A�オ��Δ���B�l��������Ƃ݂�A��ɔ�����(�J������)�A���������Ƃ��ɔ����B�����́u������v�B
2008�N9�A10�������ŁA�w�b�W�t�@���h�̉^�p���Y�́A20���~��������Ƃ����B�^�p�����ƌڋq�̉�������B���ʁA�w�b�W�t�@���h�͌������m�ۂ��邽�߁A�����悩�玑�Y��������邱�Ƃ𔗂�ꂽ�B�������������x������A���ڋq�ւ̕ԋ��A�Ј��̋��^���A�u100�~�{50�~�v�C���`�L�؏��ŕ����킯�ɂ͂����Ȃ��B���̃p�j�b�N�I�����ɂ��A���i�敨�s��⊔���s�ꂩ��A��ĂɎ����������グ���A�����⊔����\�������̂ł���B�����A����ŏI������킯�ł͂Ȃ��B
�����������̂́A�h���͊�Ȃ��̂Ń��[���ցA���[�����s���ɂȂ�A���͉~�������Ă���B���ٓI�ȃX�s�[�h�ʼn~�����i��ł���̂́A���̂��߂ł���B���̂܂܉~�����i�߂A���{�̗A�o��Ƃ͑�Ō��������A�₪�āA�u���{���~�v�������邾�낤�B�ł́A���ɉ���������̂��H���S���Ĕ�����ʉ݂͂����Ȃ��B���̂悤�Ȓʉݕs���ł́A��(Gold)��������͂������A���܂����������݂��B�A���A�s�C���ɍ��l����A�V�����p���_�C�������܂��̂�������Ȃ��B
���E�̋��Z���Y�́A�����s��A���i�敨�s��A�ב֎s����ړ����邽�тɁA�z�����炵�Ă���B���E�̊����s�ꂩ��A���ł�3000���~��������ƌ�����B���{�̍��Ɨ\�Z�ł����A�l�b�g��200���~�B����A�w�b�W�t�@���h�́A�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�u���Y��Ҕ����Ă���v�ɂ����Ȃ��B�{���̎g���H���l����A�����I�ȏŁA�w�b�W�t�@���h�̖����͌���Ȃ��Â��B�����A�p��ς��A���O��ς��A����Ƀp���[�A�b�v���đh��\����50������B
����A����ȑ厖�������N�������̂͒N���H�ƁA�Ɛl�{�����n�܂��Ă���B�����o�N�`�ɖ�����ꂽ�w�b�W�t�@���h�͂��Ƃ��A�匳�̃C���`�L�؏��⏤�i�敨����܂ł��ʂɋ������Ă���B�����A���i�敨����́A�{���A��������̃��X�N�w�b�W�̂��߂̎d�g�݂ŁA���ꎩ�̂������킯�ł͂Ȃ��B�������ƊW�̂Ȃ��J�W�m�}�l�[�������������Ƃ����Ȃ̂��B
�}�N�����_�ł݂�ƁA����̋��Z��@�́A���E�K�͂̋��]��A�ߏ�ȗ������ɋN������B2007�N�̐��E�̋��Z���Y�̍��v�͖�20�A000 ���~(2���~)�ŁAGDP�͖�5�A400���~�B�܂�A���̌o�ς�4�{��̃J�l�����Ԃ��Ă���킯���B����A1980�N�A���̔䗦��1�D1�{�������B�܂�A�u���Z���Y��GDP�v�B����]�����J�l���A�}�l�[�Q�[���ɗ��ꍞ�ނ͕̂K�R�ł���B
����A���Z���Q(�M�p���k)�ɉ��������A���͂ǂ��܂ōs�����B����o�ϐ�历�ɂ��ƁA
�u�����N�����Ă��A�o�ς͂Ȃ��Ȃ�Ȃ����A���E���j�ł���킯�ł͂Ȃ��B����́A1929 �N�̑勰�Q���ؖ����Ă���B�m���ɁA�q�h�C���������A���̌�݂��Ƃɉ����ł͂Ȃ����v
�����A���j�������J��Ԃ��Ƃ͌���Ȃ��B
|
�����E���Q1929
���Q�́A���{��`�ł͔����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���j���݂Ă��A�Y�Ɗv�����{�i������19���I�ȍ~�A�Ђ�ς�ɋN�����Ă���B1929�N�̃A�����J�E�E�H�[���X�̊��̑�\�����N���Ƃ���u���E���Q�v�́A���E���Ɋg�債�A����E���̉����ɂ��Ȃ����B���{�̑���1931�N�ŁA���Q�O�ɔ�ׁA�H�Ɛ��Y����8���_�E�������B�A�����J�́A1932�`1933�N�����ŁA�H�Ɛ��Y���͋��Q�O�ɂ���ׂقڔ��� �E�E�E �M�����Ȃ��悤�Ȑ����ł���B����A�\�A�͓������A�t��1�D8�{�ɑ����Ă���B
�\�A�́u���Y��`���v��o�ρv�Ȃ̂ŁA���_��A���Q�͂��肦�Ȃ��B��Ō����������A�����J�́A������80���������A���Ɨ���25���ɒB�����B�ߏ萶�Y���ۗ����A�����ɂ�����ґ�i�̔䗦��������������ł���B�A�����J���O���哝�̂̃t�[�o�[�́A���ז���Ŏ��Ԃ��Ԃ��A���\�Ă�肳�ꂽ�������A�C�������ŁA�₵�����E���������B
���̌���p�����̂��A�t�����N�����E���[�Y�x���g�哝�̂ł���B���j�ɂ��o�ꂷ��L���ȃj���[�f�B�[������ň�C�ɉ����I�Ƃ͂����Ȃ������B�j���[�f�B�[������́A�h�C�c�̃q�g���[�̐������l�A�Љ��`�I�Ȃ��̂��������A�h�C�c�̕����܂��܂��������B���ہA1936�N�A�h�C�c�̍H�Ɛ��Y���͋��Q�O��95���܂ʼn������A�A�����J��75���ɂƂǂ܂����B
�����Ƃ��A(������)�h�C�c�ƈႢ�A�A�����J�������`�̍����������Ƃ��������ɂȂ����B���[�Y�x���g�̐���̂������́A�ō��ق���ጛ�������o������ł���B�Ƃ͂����A���̃n���f�B���l�����Ă��A�j���[�f�B�[������͐��ʂ��グ���A�Ƃ͌����Ȃ��B�A�����J���{���ɋ��Q��E�����̂́A����E����A�܂�A�푈�o�ςɂ���Ăł���B
����A���������݂�A���{�̃_���[�W���ӊO�ɏ��Ȃ��B���R��2�l������B��1�ɁA�ϋɓI�ȐA���n������ɂ��A�A���n��GDP����悹�ł������ƁB��2�ɁA�H�Ɛ��i�ɐ�߂��ґ�i�̔䗦���������A�������݂����Ȃ��������ƁB
|
�����E���Q2008
�����ŁA���N�����Ă��鐢�E�����s���ƁA1929�N�̐��E���Q���ׂĂ݂悤�B��Ԃ̈Ⴂ�́A���E�̎Y�ƍ\���ɂ���B1929�N�̐��E���Q�ł́A�H�Ɛ��i�ɐ�߂鐶���K���i�̔䗦�͍���荂�������B���̂��߁A��������炷�ɂ����x������A���̕��A�������݂����Ȃ������B
�Ƃ��낪�A���ł́A�H�Ɛ��i�̎嗬�̓p�\�R���A�t���e���r�A�f�W�J���A�P�[�^�C�ATV�Q�[���A������ �E�E�E �u�Ȃ��Ă������Ă����鏤�i���K���N�^�v���قƂ�ǁB���Q���{�i������A�N�����H�����Ƃɋ��X�Ƃ��A�K���N�^���v�͌������邾�낤�B�����A�ʂ̖�������B�K���N�^�Y�Ƃɏ]������l���䗦���������A���Ǝ҂������邱�Ƃ��B
�Ƃ���ŁA�ǂ������o�܂ŁA����Ȃ��тȎY�ƍ\���ɂȂ����̂��낤�B�������Ȃ��A�e�N�m���W�[�̐i���̂������B���āA�l�ނ́A�A�J�l����90�����H�Ɛ��Y�ɏ]�����Ă����B�Ƃ��낪�A����10���ɂ������Ȃ��B
�u�e�N�m���W�[�̐i�� �� �_�Ƃ̐��Y���̌���v
�̂������ŁA1�l��10�l���̐H�ƂY�ł���悤�ɂȂ�A�c��9�l�����C�y�Ȏd�����ł���悤�ɂȂ����̂��B���ꂪ�A
�u�Ȃ��Ă������Ă��遁�K���N�^���i�v
�Ƃ������ƂŁA�u���E���Q2008�v�́u���E���Q1929�v���A��ʂ̎��Ǝ҂��o��\���������B������Î�����j���[�X������B2008�N10���`2009�N3���̊ԂɁA�K�J����(�h������ԍH)3���l�����Ƃ���Ƃ����B�Ƃ��낪�A���Ј�����O�ł͂Ȃ��B�O���n���R���s���[�^��Ƃ����Ј�1000�l�̐l���팸�\�������A���Ј��팸�͓d�@�ƊE�ɂ��L�������B����قǐ��܂������X�g���́A����x���N�����Ă��Ȃ��B
���{���\�����Ƃ��A���߂��ꂽ�悤�Ƀ��X�g����i�߂Ă���B
�u�d������������ �� ���X�g���v
�Ȃ�A�N�ł���Ќo�c�ł���B���āA���{��Ƃ͐Ԏ��ł��ٗp����������A���͍����ł����X�g������B���{�́A��̂ǂ��Ȃ����̂��H
�o�u�������A���{��Ƃ̋����͂͏オ�������A���̂��炭��́A
�u�l������Œ���ϓ���ɕς����v
�ϓ���Ƃ́A���㍂�ɔ�Ⴗ����́A�Ⴆ�A���ޗ���B����A�Œ��Ƃ́A���㍂�ɂ�����炸�A���̂��́A�Ⴆ�ΐl����B���{��Ƃ́A����т��āA
�u�l����Œ��v
�Ōٗp������Ă����B�Ƃ��낪�A����10�N�A���Ј�����K�J���҂ɃV�t�g���A�d��������Ƃ������ٗp����悤�ɂȂ����B�܂�A�l����͕ϓ���ɕς�����̂ł���B���ꂪ�s���ɋ�����Ƃ̐��̂��B
�Ƃ͂����A���X�Ɩ��炩�ɂȂ鋰�낵���������݂�A��Ƃ��ǂ�قǐ[�����킩��B���[���̂āA�{�ۂ����Ȃ���A�S�ł���\��������̂�����B�������A�ٗp�́u�l�̐����v�ɂ�������肾�B�o�c�g�b�v�́A������V�ƌ��茠���^�����Ă���B�l�̏�ɗ��҂́A�ǂ�ȍ���Ȗ��ɂ������������ׂ����B�l�̐����Ɋւ��������@�����ՂɑI�ԂȂ�A�T�����[�}���ƕς��Ȃ��B
|
�����Q�O��
����A�O�ԃf�B�[���̉c�ƃ}���Ƙb�������B
�c�ƃ}���F
�u�[���[������Ȃ���ŁA�c�Ƃ�5�l����2�l�Ɍ���܂�����v
�u�ւ��[�A�ł��A�~�~�����g����Ȃ��ł����v
�c�ƃ}���F
�u���ꂪ�A������l���邩�� �E�E�E�v
�u�����A���悢�挈����ł��ˁv
�c�ƃ}���F
�u����A�[���[�����Ȃ��ł���v
�ŋ߁A����ȁu���肦�Ȃ��b�v���������ɂ���B�܂��́A�n���ŁA
�E�Ԃ̔̔��X�ŁA�y���̗��q���[���B�c�ƃ}���H���A�u�h�b�L���v���Ǝv�����B
�E���E�L���̋@�B���[�J�[�̉�������Ђ��A��D������1�����ŁA�d���������B
�EU�^�[���œ��肪�o���̂ŁA��Ђ����߂���A������������ꂽ�B
�E�����ŁA����(����Ɗ܂�)���A1�N�Ԃ�3�Ђ��|�Y�����B
���ɁA�S����(2008�N12��)�B
�E���������Ԕ̔�(�y�����Ԃ��Ȃ�)��11���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��27�D3�����B
�E�H��@�B�z�́A�P���Ƃ��ĉߋ��ő��62�D2�����B
�E2008�N10�`12���̍z�H�Ɛ��Y�͐Ζ��V���b�N��������10�����B
�E���������ɑ������x�o�̊�����10�����Œ����J�n�ȗ��Œ��77�D2���B
�����̏������猩���Ă���̂́A
�u���Y������ �� ���Ǝ҂����� �� ������� �� ���Y�������v
�܂�A���̃X�p�C�����B
�厖�̑O�ɂ͏�������������B����ȏł́A�h�������������������\�����A���\�L�̎��Ǝ҂��o�����������A�Љ�V�X�e�����̂��̂�����̂ł� �E�E�E �m���ɁA���̉\��������B�����A���������������B����܂œ��l�A�J�W�m���Z���������関�����B���̍����́H���̐��E�̎x�z�҂��A���̃��[�������炵�悤�Ƃ��邩�炾�B����́A���{�l����D���ȁu�A�d�l�^�v�ł͂Ȃ��A�N�����m����Ɋ�Â��Ă���B
�@ |
| ���勰�Q�̌��� |
   �@
�@
|
�����Q�Ƃ�
�o�u������͍��g�A���Q�͒Ôg �E�E�E 2004�N�A�X�}�g�����Ŕ��������Ôg�̉f�������Ă����v�����B�������C�̂��˂肪�A�Ԓf�Ȃ��A���ɉ����A�������Ԃ��l�����������Ă����B���g�Ƃ͌��Ⴂ�̃G�l���M�[�A�j��͂��B���g�͖ʂ̃p���[�A�Ôg�͗��̂̃p���[��������Ȃ��B���̒Ôg��28���l���]���ɂȂ������A���g�ł͂��肦�Ȃ���Q���B���g�ƒÔg�͓����Ɍ����āA���͕ʂ��̂Ȃ̂ł���B�����āA�o�u������Ƌ��Q�� �E�E�E
2008�N�A�T�u�v���C�����[�����ɒ[���A���[�}���V���b�N�AAIG�����Ƒ��������Z��@�A����ɁA�r�b�O�X���[�V���b�N�́A���E���Q���Î����Ă���̂��낤���A����Ƃ��A�����̃o�u������H
���A����҂͕K�v���Ȃ��K���N�^���i���ʂɔ��킳��Ă��邪�A����ɋC�Â��Ă��Ȃ��B������A�������\�����A���Z��@���N����A����҂͕s�����o���A�K���N�^���i��Ȃ��Ȃ�B����ł������Ă����邱�ƂɋC�Â�������҂́A�܂��܂��K���N�^��Ȃ��Ȃ�B�R�̂悤�ȍɂ�������Ƃ́A��@�����o���A���Y�����炷�B�H��͕�����A�J���҂���ʂɉ��ق���A�܂��܂����m������Ȃ��Ȃ�B
��Ƃ́A���łɂ��鐶�Y�ݔ��܂Ō��炷�̂ŁA�V�K�̐ݔ������͐��܂�Ȃ��B���ʁA�ݔ��Y�Ƃ͑�Ō���������B�����Ԃ̂悤�ȍ��z�ȑϋv������͔��㔼���A�Ɠd���i�͌����ł��ނ��A�ݔ��Y�Ƃ͌���Ȃ��[���ɋ߂Â��B�ł������̎��Ǝ҂��o���̂́A���̋ƊE���B����A�ݔ�����������A�������v������A���Z�@�ւ��s���Ɋׂ�B�������āA�������������z�ɂ̂ݍ��܂�A����ȕ��̃X�p�C�����ݏo���B���Y�E���ʁE����͌��I�ɗ������݁A�o�ϊ����͑傫������A�e�Ղɔ����o���Ȃ��Ȃ�B���ꂪ���Q�ł���B
�����ŁA���Q�ƌ�����r���Ă݂悤�B�ȉ��A�������Q�A�E������ł���B
1�D�������\�������o���ϊ����́A��N������44�������B
2�D���Y����������2009�N�V�Ԕ̔��䐔��39�N�Ԃ��500���䊄��B
3�D���Ǝ҂��}����2008�N10�����甼�N�ԂŁA8��5000�l������ �B
4�D��Ɠ|�Y���}����2008�N�̏���Ƃ̓|�Y�����͐��ő��B
5�D��s�̎��t���������A�����J�ňꕔ�������������B
���̒��ŁA�܂��N�����Ă��Ȃ��̂́A�u5�D��s�̎��t�������v�����ł���B������_�ǂ݂���A�Ôg�A�܂�A���Q�ł���\���������B�܂��A�l�I�ɋ��Q���^���Ă��邪�A���̗��R��3�B
1�D�i�C��ނ��܂��������Ă���
�E�i�C���ǂ݂ł���L���ƂƐݔ������Ƃ��܂��������Ă���B
�E�������Â��ƁA�u����s�\ �� ���Q�ւ̕��̃X�p�C�����v���n�܂�B
2�D�u�Ȃ��Ă������Ă����遁�K���N�^���i�v�̏A�J�l��������
�E��s���ł́A�K���N�^���i�̔��オ��������B
�E���{�̊�Y�Ƃ͂قƂ�ǃK���N�^���i�Ȃ̂ŁA��ʂ̎��Ǝ҂��o���B
3�D���Z��ʔj��CDS
�ECDS(�N���W�b�g�E�f�t�H���g�E�X���b�v)�́A��Ђ̍��ɑ���ی�����B
�E��Ȃ���Ђ̍�(�ЍȂ�)�����L����ꍇ�ACDS���A�ی������B
�E���̏ꍇ�A��Ђ��j�]���Ă��A������U���Ă��炦��̂ŁA���X�N�w�b�W�ɂȂ�B
�E�A���ACDS������Ђ��j�]����ƁA�u�j�]�̘A�����j����v���n�܂�B
�E�����Ȃ�A���Z�V�X�e�����̂��̂����A���m�̐��E���Q�ɓ˓�����B
�EAIG���~�ς��ꂽ�̂́ACDS���ʂɕ�������ł������߁B
|
���o�u�������Q��
�����A�����͂��ׂď؋��B�ł́A���E�͂ǂ����Ă���̂��낤�B�܂��́A�A�����J�̒�����sFRB(�A�����J�A�M����������)�B2008�N12��17���AFRB�́A�[�������ƗʓI�ɘa�\�����B�s��ɁA��ʂ̃}�l�[�𗬒ʂ����A��Ɠ|�Y��h�����߂ł���B���ɁA�[����������̓A�����J�j�㏉�̑�Z�B
�h�����[�������ƂȂ������߁A�h�����āA�����̍����~�����������������B�܂�A�~���h�����B�~���͓��{�̗A�o��ƂɂƂ��đ�Ō������A�h�����̓A�����J�̋��Z�����������\��������B����ł��A�i�C��D�悵�AFRB�͌��f�����B�����Ƃ��A���Ă̋����������ŁA�h���������A�~�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�A�����J������������Ԏ��E�f�ՐԎ��A�܂�A�h���ɑ���s�M�������ɂ���B
�Ƃ��낪�A�u�[�������v�J�[�h��������Ō�A�A�����J�̋��Q��́u�h����������܂��v�����c����Ă��Ȃ��B�������A�h���̑呝���́A�ی��̂Ȃ��h�����������A1�h��50�~�������������тĂ���B�����Ȃ�A�A�����J�̐����Ƃ͕������邾�낤���A�A�����J�̋��Z�Ƃ͑�Ō���������B�h�����ł́A�A�����J�Ƀh���������������Ȃ��Ȃ邩�炾�B�Ƃ������ƂŁA�X�ɂ͗\���\�����A����݂����G�Ȃ̂ŁA�S�̂Ƃ��ĉ����N���邩������Ȃ��B
����A�����s��͋����قNJy�ϓI��(2008�N12����)�B���̊����s��́A�Z���������ړI�A���邢�́A���Q�͂Ȃ��ƐM����҂������x�z���Ă���B�ނ�́A���̑�s�����Ôg�ł͂Ȃ����g�ƌ��Ă���킯���B�łȂ���A���łɁA�ă_�E�H�ƕ��ς�6000�h����A���o���ς�7000�~�����荞��ł���͂����B�������A���Q���n�܂�A���̒��x�ł͍ς܂Ȃ��B
�X�p�i�C�͂ǂ����낤�BTV���ςĂ���ƁA���������ʈ�a����������B�K�J���҂���ʂɉ��ق���A�H���ɖ����f���̌�ɁA���ɂ����Ȃ��o���G�e�B�B�v���J�[�h�����ĂɁA���ٓP���i����J���҂̉f���̌�ɁA�s�т̎g���̂Ĕԑg�B����Ȋi���Љ�P�퉻����A�ƍ߂�\�����������A�Љ�s�����������낤�B
����ɁA���낵���f�[�^������B���{�̘J���҂�34�����N��200���~�ȉ����Ƃ����̂��B���̑唼�́A�K�J���ҁB�e�Ɠ����Ȃ�܂������A�s��ň�l��炵�Ȃ�A�����邩���ʂ��B�������Ă��q��������Ȃ��B����́u�Љ�v�Ƃ������́u���v���B����Ȑ��E�ŁA�ǂ�����āA�����]�����Ăƌ����̂��낤�B���̃K�o�i���X(����)����ɕK�v���B
|
�����{��`�͏���������
���͎�`�A�����g/�����g�A�����Љ�A����ȗE�܂������t������������A��X�́A���{��`���剻�����Ă����B���{��`�̃��C�o���A���Y��`����������p��Ă���B���Y��`�́A
�u�\�͂ɉ����ē����A�K�v�ɉ����Ď��v
�Ƃ������z�������������A�����Ɏ��s�����B�����āA20���I���ɂ́A���{��`�̏��������X�Ɛ錾���ꂽ�̂ł���B�����A���{��`�͖{���ɏ��������̂��낤���H
���ꂾ���n�x�̍����g�債�A�������܂ŋ��������悤�Ȃ�A�����u�Љ�v�Ƃ͌ĂׂȂ��B�͂��������̂��������@�n�т��B�܂��A���{��`��搉̂��Ă��������g�����f�ł��Ȃ��B�ƂƂ��ɁA�\�͂͗����A�ߋ��̎��т��Y����Ă����B�����g����]�A�����g�ɓ]������̂����̐��E�Ȃ̂��B�ŋ߁A���͂ł���ȋt�]����p�ɂɌ���悤�ɂȂ����B�܂�ŁA�W�����O���ł���B
�n���͊�{�A������H�B������A
�u�\�͂ɉ����ē����A���ʂɉ����Ď��v
�Ɉ٘_�͂Ȃ��B�����A���������Ă��A�u�ߐH�Z���������v�����́A���l�ɕۏ��ׂ����B�l�ނɂ́A���ꂮ�炢�̗]�͂͂���B���_�ɐ����Q����E���ɂ��ӂ�Ă��邩��B����1000m�̒����w�r���A���H��232���~�̕����ŕ������h�o�C�E�o�u�����A�����̖\���ƂƂ��ɕ����B�����A������C�̓łɎv���l�͂��Ȃ����낤�B
���͎�`�E���ʎ�`����������A�Љ�̓W�����O���Ɖ����B���Y��`�E���{��`�ȑO�̖�肾�B�ق�̂�����ƁA�@���Ɏ�������邾���ʼn����ł���̂ɁA�Ȃ����Ȃ��̂��H���ꂪ�ł���l�ɂƂ��āA���l�������炾�낤�B���̐��E�ɁA��]�������Ȃ����R�͂����ɂ���B���E�́A�V�����Љ�V�X�e�������߂Ă���B�������������͖̂��ӁA���̏�ɏ���������p�Y�ł���B���j�͂��̂悤�ɑn���Ă����̂�����B
|
�������Ƃ��̂Ă��A�����J
100�N�Ɉ�x�̌o�ϊ�@�́A�Ȃ��N�������̂��H������A���{�ł������ł��Ȃ��A�A�����J�ŁB
1988�N�A�A�����J���O���B���̍��A�A�����J�ł́A�W���p���E�o�b�V���O(���{������)�������r��Ă����B�����́A���{�̖f�ՐԎ��B�r�b�O�X���[�̑�^�Ԃ́A���{�̒�R��ԂɎs���D���A��Ō����Ă����̂ł���BTV�ł́A��^�n���}�[�œ��{�Ԃ��A���͊����Ă��ߌ��ȃV�[�������f���ꂽ�B���ĊW�́A���ň��ƂȂ����B
����ɁA�ǂ��ł����������̂��A�A�����J�̃X�[�p�[301���ł���B�s�����Ȗf�Ղ��s�����ɑ��A�A���ł������グ��Ƃ����������B�����I�����A������ς���A�A�����J�͂܂��u���Â���v�Ɏ������Ă����ƌ�����B�Ƃ��낪���̌�A�S�|�A�����ԁA�Ɠd�ȂǃA�����J�̊�Y�Ƃ͎��X�Ƌ����͂��������B�����Ƃ��������A�����J�́A�V���ȎY�ƃ��f�����K�v�ɂȂ����B���̂܂܂����A�C�M���X�Ɠ������H�����ǂ�B���E�ŋ�������A2�����ցB
�A�����J���ڂ������̂́A���ăC�M���X���x�z�������Z�Ƃ������B������A�����̋��Z�Ƃł͂Ȃ��B�A�����J���Ƀp���[�A�b�v���ꂽ�V����̋��Z�V�X�e���������B
�|�C���g��3�B
1�D�莝�������̉��{�A���\�{���̎�����ł���M�p���(���o���b�W)
2�D���X�N���א�ɂ��ď،����������Z�h�����i(�f���o�e�B�u)
3�D���ǂ�݂ǂ�̋��Z���i�𑵂������Z�s��(�A�����J���c�J�W�m)
�܂�A���������Ắu�J�W�m���Z�����v�ɑ������̂ł���B�ړI�͂�����A���E���̃h���������A�����J�ɋz���グ�邱�� �E�E�E
|
���J�W�m���Z�����Ƃ�
�A�����J�͐����Ƃ�������߁A�~�������m�͗A���ł܂��Ȃ����Ƃɂ����B���{�⒆�����͂��ߐ��E�����烂�m���܂������̂ł���B�x�����́A��ʉ�(���ێ���̌��ϒʉ�)�̃h���B�Ƃ��낪�A�h���̓A�����J�̒ʉ݂ł�����̂ŁA�s��������A���邾���ł����B�܂�A
�u�֓]�@��������Ή��ł��D���Ȃ���������v
�����������A�u�����ʉ݁���ʉ݁v�̂������A�܂��ɁA�ł��o�̏���(���Â�)�ł���B
�Ƃ͂����A
�u�A�o���A���v
�ł́A�f�ՐԎ����c��ވ�������A��������ł́A��ʂ̃h�������o���A���E���Ńh�������ӂꂩ����B���ꂪ�Ȃ�ł����Ă��A�����������̂قlj��l�͉�����B�܂�A�h���̉��l�͔���A�h�����ɓ����B�����h�����߂ɂ́A�A�����J���痬�o�����h����������邵���Ȃ��B
�A�����J���h�����������ɂ́A������A�o���āA����Ƃ��ăh�������K�v������B�Ƃ��낪�A�A�����J�ɂ͔��郂�m���Ȃ��B�����ȃA�����J�����ł́A�����Ԃ�Ɠd���i�̗A�����͂܂��Ȃ��Ȃ��B�����ŁA�A�����J�͖��Ă��v�������B�ΕėA�o�ʼn҂������ɁA�A�����J���킹��̂ł���B�A�����J���Ƃ́A�A�����J���O���̍����Ȃ����s��������B�܂�A�A�����J�́A�A�����J������邱�ƂŃh������������̂ł���B
���ہA���{�̊O�ݏ����̂قƂ�ǂ��A�����J�����B�O�ݏ����Ƃ́A�����ۗL���鎑�Y�ŁA�A�������O���ւ̎ؓ����ԍρA�ב։���̂��߂̏������ł���B���̊O�ݏ������̐��E�i���o�[1�͒����A���ŁA���{�B�f�Ղł��ߍ������Ƃ����Ă������B
�Ƃ���ŁA�Ȃ��A���E�̍��X�̓A�����J�����̂��H�h���������ł����Ă��Ă��A���������Ȃ�����B�Ƃ͂����A�h�����ɂȂ�A���Y�͖ڌ��肷�邵�A���ہA���̂Ƃ���A�����ƃh�������B��(Gold)�̕������S�ł́H�A�����J���ł����R�͂ȂɁH���Ԃ�A����ԈႢ�Ȃ��A�A�����J�̋����ł���B
�����A�ǂ����̍����A�����J���肠�т���A
�u���������v�v
�ŁA�����i�͖\������B���l�̉������������Ă��炤�ɂ́A�������ɂ��邵���Ȃ��B���ʁA���̋����͏㏸����B�Ƃ��낪�A���̋������オ��A�����Ȋ����A���̂��܂݂������B�܂�A���͖\������B�A�����J�ɂƂ��āA�ǂ����Ƃ͈���Ȃ��̂��B���̂��߁A�A�����J�́A����ȌR���͂�w�i�ɁA�A�����J���킹�A����Ȃ��悤�w�����Ă���(�Ǝv��)�B����ɋt�炤�x��������̂͒������炢���낤�B
��ɁA�A�����J�ɂ͔��郂�m���Ȃ��Ə��������A���͈����B���������f���o�e�B�u(���Z�h�����i)���B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���E���̊�ƁA���Z�@�ցA�����Ƃ��A���̃f���o�e�B�u���܂������̂��B���ʁA���E���̃h���������A�����J�̋��Z�s��ɗ��ꍞ�B�܂�A�A�����J�͂����ł��h���̉���ɐ��������̂ł���B�A�����J�̍��s��A�����s��A�����E�����Ȃǂ̏��i�敨����s��A�s���Y�s��̓}�l�[�ŏ����A�����������l�オ�肵���B
�����A�����Ƃ��������Ƃ����߂Ƃ͂����Ȃ����̂��B�f���o�e�B�u�̈�u�T�u�v���C�����[���،��v���ł��t���A���Z�s�������������̂ł���B���ʁA���E�����s�����n�܂����B�������āA�A�����J�̃J�W�m���Z�����͔j�]���O�ɒǂ����܂ꂽ�B
|
���f���o�e�B�u�Ƃ�
�����A�f���o�e�B�u�́A���[���X�N�E�n�C���^�[���Ɍ������B�����炱���A���E���̓����Ƃ���Z�@�ւ��A�������Ĕ������̂ł���B�n�C���^�[���ł���A���̕��A���X�N���傫���B�����ŁA���X�N����̂��߂̍I���Ȏd�|�����g�ݍ��܂ꂽ�B���x�Ȑ��w����g�������Z�H�w�A�m�[�x����҂��J���A�l�X�ȎE�����傪�f���o�e�B�u���z�����m�Ɍ����������B
�m���ɁA�X�Ɍ���A�f���o�e�B�u�̃��X�N�͍I�݂ɉ������Ă���B�����A���Z�̐S���u�M�p���ی��@�\�v��������ׂA���Z�V�X�e���S�̂�����B�S�̂�����A�ǂ�ȗD�ǂȌł����Ă����݂ł��Ȃ��B�������A�f���o�e�B�u�̊J���҂́A
�u����Ȃ��Ƃ܂ŐS�z���Ă���A�����ł��Ȃ���v
�Ɣ��_���邾�낤�B���̂Ƃ���B�Ƃ���ŁA�f���o�e�B�u�̓C���`�L�A�z�����m�H
�f���o�e�B�u�̗��j�����������̂ڂ��Ă݂悤�B���Ԃ�A�f���o�e�B�u�̐�c��̓W�����N���B�ȑO�́A�p�ꂻ�̂܂܁A�W�����N�{���h(Junk Bonds)�ƌĂꂽ�B�W�����N�Ƃ́A�M�p�x���Ⴍ�A���{����̉\���̍������̂��Ƃł���B���Ƃ��A�|�Y���O�̉�Ђ̎ЍB���ʂ́A�N������Ȃ��̂ŁA���̕��A�������ł���B�܂�A�n�C���X�N�E�n�C���^�[���B����A�M�p�x�̍������́A���S�Ȃ̂ŁA���̕��A����肪�Ⴂ�B�܂�A���[���X�N�E���[���^�[���B���Ƃ��A���{��A�����J�̍����B
���ꂾ���Ȃ�A�����Ȑl�̓��[���X�N�E���[���^�[���A�����łȂ��l�̓n�C���X�N�E�n�C���^�[���A�Ƃ������ݕ����ɗ��������B�Ƃ��낪�A���鎞�A���[���X�N�E�n�C���^�[���Ƃ������̋��Z���i���o�ꂵ���̂ł���B�����͂������ăV���v���A
�u�A�u�i�C���ł��A���������A�S�ł��郊�X�N�͌�������v
�܂�A�����̃W�����N���u�����h���邱�ƂŁA���X�N�U�����̂ł���B�������A�ʂ̃W�����N�͍������Ȃ̂ŁA���ʂƂ��āA���[���X�N�E�n�C���^�[���ɂȂ�B�����A���Z���w�́u���Ғl�v���o���Ă���l�Ȃ�A���H�Ǝv���͂����B�܂��A�����ȓ˂����݂͂��Ă����A���ꂾ���͕ۏł���B
�u�W�����N��1�{�ނ���A�u�����h�E�W�����N�̕����A���w�I���^�[���l�͑傫���v
�������A�W�����N����肭�u�����h�ł�����̘b�����B
�Ƃ������ƂŁA�u�����h�E�W�����N�̐��ۂ́A�ЂƂ��ɁA�u�����h���@�ɂ������Ă���B�ǂ̃W�����N���ǂ������䗦�Ńu�����h���邩�H�������A�l�Ԃ̌o����J���ɗ���̂ł͂Ȃ��B��������߂�̂́A���w(�|�[�g�t�H���I���_)�ƃR���s���[�^���B�����A�u�����h�E�W�����N�̐��ۂ����v�ɂ���Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂�A�S�̂Ƃ��Ă̐������͕ۏ��Ȃ��ł��Ȃ����A�ʂł͕ۏ����˂�B���ꂪ�A�u�����h�E�W�����N�A�܂�A�f���o�e�B�u�̐��̂ł���B
�܂��A�f���o�e�B�u�ɂ́A�����Ƃ�����������̎d�|��������B�莝�������̉��{�A���\�{���̓������\�ɂ���M�p���(���o���b�W)���B�Ⴆ�A���҂ł��闘��肪5���̃u�����h�E�W�����N�ł��A10�{�̃��o���b�W��������A���җ����́A
5���~10 �� 50��
�ɂȂ�B�������A��������A���Q��10�{���� �E�E�E
�������āA�W�����N�s��́A���s��ɕC�G����K�͂ɐ��������B�����A���̃J���N���́A
�u�݂�ȂŃ��X�N���������v
�Ȃ̂ŁA�j�]���Ǐ��I�Ȃ�@�\���邪�A�j�]����K�͂Ȃ�j�]�̃h�~�m���n�܂�B�܂�A�V�X�e���S�̂�����B���ꂪ�A����̃T�u�v���C�����[���ɒ[�������Z��@�ł���B
|
�����Q�����������@
�����ŁA��������B�A�����J���u�J�W�m���Z�����v�ɑ������͕̂K�R�ł���A�A�����J�݂̂Ȃ炸�A���E�������������B�A�����J���؋��Ђ��Ń��m���̂́A�J�߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ����A�������ŁA�ΕėA�o���͂��邨�����B����Ă��铖�l�ł����A
�u����Ȃ��̕K�v���Ȃ��H��̒N���g���H�v
�Ǝv���悤�ȏ��i�܂Ŕ��ꂽ�B���E���̓����Ƃ����́A�A�����J�̋��Z�s��ł���Ȃ�̗��v���グ���B�ΕėA�o�����҂����h�����A�A�����J�ɉ�������͕̂s�{�ӂ����A���ʁA�h���̖\���͂܂ʂ��ꂽ�̂ł���B
�h�����\������A�A�����J�����邪�A�ΕėA�o��������B���Ƃ��A1�h���̏��i���A�����J�ɔ������Ƃ��āA
�u1�h��100�~ �� 1�h��90�~�v
�̉~���h�����ɂȂ��������ŁA����́A
�u100�~ �� 90�~�v
�Ɍ���B�����������Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂� �E�E�E
���ɂȂ��Ďv���A�A�����J�́u�J�W�m���Z�����v�ŁA���E�����n�b�s�[�������̂��B���X�Ɩ��炩�ɂȂ鋰�낵���o�ώw�W���݂�A���E���Q�̗\��������B�����A�ꕔ�̐S����l�X�������āA�N�������]��ł��Ȃ��B�ł́A�ǂ�������Q������ł���̂��H�A�����J�ɑ�ʏ���𑱂��Ă��炢�A�h�������肳���邵���Ȃ��B�܂�A
�u�J�W�m���Z�v���ێ����邵���Ȃ��B
�t�ɁA�J�W�m���Z���Ԃ��A�ԈႢ�Ȃ��A���E���Q�ɓ˓����邾�낤�B��X����剻���������{��`�́A�J�W�m���Z�Ȃ��ł͐������Ȃ��̂ł���B�@ |
| ���勰�Q�̑� |
   �@
�@
|
���ň�
�ň��̎��Ԃ����͍ň��ł͂Ȃ��A����Ɉ������Â����@�`J�EK�E�K���u���C�X�`
20���I���\����o�ϊw�҃K���u���C�X�́A1929�N�̐��E���Q�������]�����B�����̂قƂ�ǂ̓����Ƃ��A�u���Q�v���u�o�u������v�ƌ�������̂ł���B
1929�N10��24���A�j���[���[�N�����s��Ŋ�����\�������B�����͒l��߂������̂́A���̌���\���͑����A11���ɂ̓_�E���ς�224�h���܂ʼn����B3�����ԂŔ��l�Ƃ������܂����������B�������ɁA�����܂ʼn�����Β�l���낤�ƁA�݂�Ȃ��v�����B�Ƃ��낪�A�����͂��̌�������葱���A���ł����̂́A3�N���1932�N7���������B���̎��̊�����58�h���A�݂�Ȃ����ƐM����1/4�B
�����Č��݁A�j���[���[�N�̃_�E���ς́A1�N�O�̍��l���甼�l�܂ʼn����������A���̂Ƃ���A�����~�܂��Ă���(2009�N1��12��)�B1929�N11�����l�A�u���l����l�v�ƌ��Ă���̂��낤���B�����A���̂�����������l�Ƃ͌���Ȃ��B
����Ƃ��A�I�o�}�V�哝�̂̑�ՐU�镑���Ɋ��҂��Ă���̂��낤���B�����A�ی��̂Ȃ����������́A�A�����J�̍����Ԏ������������邾�����B�Ԏ���Ђ��M�p����Ȃ��̂Ɠ��l�A�A�����J�̐M�p�����Ă��A�C�O����̓���������B���ʁA�A�����J���Z�Ƃ̕s���͂���ɐ[���ɂȂ�B
|
���ی�f��
�I�o�}�V�哝�̂́A���m�ɖ������^�̐l�ԂȂ̂ŁA�����ʂł͊��҂ł��邾�낤�B�����A�哝�̌��������������O���ƂȂ�ƁA�b�͕ʂ��B�Ⴆ�A�����ɂȂ��Ă���u���b�N�o�ρB�u���b�N�o�ςƂ́A�����ƐA���n�A�܂��͓���o�ό�����̃u���b�N�Ƃ��A����ȊO�̍��ɑ��č����ł��ۂ��A���������̎Y�Ƃ���邱�Ƃ��B���ꂪ�u�ی�f�Ձv�ŁA���Ό��t�́u���R�f�Ձv�ł���B
�i�C�́A�O��(�A�o�������v)�Ɠ���(�����������v)�Ɏx�����Ă���B���{�̏ꍇ�A����l�������邽�߁A�����͊��҂ł��Ȃ��B���̂��߁A�u�O�����A�o�v�����������Ȃ�����A�i�C�͍D�]���Ȃ��B�܂�A���{�ɂƂ��ĕی�f�Ղ͓V�G�Ȃ̂��B
1930�N�̏��a���Q�ł́A���{�͎����̌o�σu���b�N���g�傷����@��I�B�A���n�𑝂₵�A�������g�債�悤�Ƃ����̂ł���B���ʁA���E�̗ƏՓ˂��A�啽�m�푈���u�������B�������A���[���b�p�ł������悤�ȃv���Z�X�Ő푈���n�܂�A�ŏI�I�ɂ͐��E���������ޑ���E���������N�������B�ی�f�Ղ��푈�̉Ύ�ɂȂ�͖̂��炩���B
2008�N11��15���A�ً}��]�(���Z�T�~�b�g)���J����A
�u�ی��`�͂��Ȃ��v
�Ɨ͋����錾���ꂽ�B80�N�O�̋��P�Ɋw�̂ł���B������A���{�̐V�����A
�u����͑傫�Ȑ��ʂ��B80�N�O�̐��E���Q�̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�v
�ƕ]�������B
�Ƃ��낪 �E�E�E
����1�������2008�N12��12���A�f�Պg���ڎw��WTO�̑��p�I�ʏ����̑�g���ӂ�������ꂽ�B���ꂪ�Ӗ�����̂́A���m�ɁA
�u�ی�f�Ղ͂��v
����ɁA2008�N12��23���ɂ́A���V�A�̃v�[�`���́A�����Ԋł������グ�A�����ɍ��Y�Ԃ��悤�i�����B��������m�ɁA�ی�f�ՁB
���R�f�Ղ̐��E�ł́A���ۊԂ̃q�g�E���m�E�J�l�̌𗬂��[�܂�A���݈ˑ������܂�̂ŁA�������N�����Ă��������₷���B����A�ی�f�Ղ����܂�A�e���͎��������o�ςɃV�t�g���A�O���Ƃ����A�������G�����Ȃ��Ȃ�B�Ƃ͂����A���E���Q������ɓ��������A�א��҂͕ی�f�Ղɑ��炴��Ȃ��B���ꂪ���̌����Ȃ̂ł���B
|
������
2009�N1��4���A���������V�i�C�̃K�X�c�̌@����J�n�����B���{���́A2008�N6��18���̍��ӂɔ�����s�ׂ��Ɣ����B��t�����ȂǁA���̎�̗̓y�E�̊C��肪�}�����Ă���B�����́A�����m�ۂ����ƈ��S�ۏ�Ɋ֘A�Â��A���͍s�g�������Ȃ��\�����B
�����́A���̂܂܂����A���E�ŋ����ɂ̂��オ��B���|�I�Ȑl���Ɛ��Y�ݔ���L����̂ŁA���{�����āA�n�C�e�N����肷��A�A�����J�ȂǓG�ł͂Ȃ��B����A�낤���ʂ�����B�����̗��j�́A
�u�_������ �� �����ŖS�v
�̗��j�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
���ہA
�E���E���L�̗����`���ŖS
�E���Ђ̗����㊿���ŖS
�E�����̗��������ŖS
�E�g�Ђ̗��������ŖS
�E���@���k�̗��������ŖS
��`�A���܂����l���p���[�B����ɏ]���ȓ��{�l�͌��K���ׂ��H
���݁A�C���^�[�l�b�g�����y�����������ŁA��ĖI�N���ȒP�ɂȂ��Ă���B���ہA���[�}���E�V���b�N�ȍ~�A�����̌i�C�͋}���Ɉ������A�\�����������Ă���(2009�N1��)�B�������Y�}�ɂ��Ă݂�A�A���Ėł��������A�\�A����̓�̕��͂��Ƃ��낤�B�L��ȍ��y�A10���l���閯�O�𑩂˂�̂́A�����̂��Ƃł͂Ȃ��B�������{���l�������̋��d����Ƃ�͕̂K�R�Ȃ̂��B�c��_�_���ʼnE���������A���q���̖��������܂�Ȃ����{�ɏ����ڂ͂Ȃ��B
���{�l�̑����́A
�u�O���Ɛ푈�͈�́v
�Ƃ��������ɖڂ����ނ��Ă���B�����A���q���͌R���ł͂Ȃ��ƌ��߂���]�_�Ƃ�TV�̊�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɋ����B�ނ�́A���܂��āA�����̐����ƍ��Y����鎩�q�����Ȃ�������ɂ���B���q�������������P���Őg�ɂ��������^���p���[�ƃX�L����F�߂Ȃ��B����ł́A�C��⏬���ǂ��납�A���{�{�y�܂ŕ�������邾�낤(���ؐl�����a���E���{��)�B��@����邾���̔ߊϘ_�͊댯�����A��@�����Ȃ��y�Ϙ_�͖����ɂȂ�B
�������̂Ȃ����_�𐁒�����]�_�Ƃ́A���j�Ɋw�Ԃׂ����B�Ȃ��Ȃ�A���j�Ɏ�ς͂Ȃ��A����̂͋q�ϓI�����̂݁B�����āA�����ɋL����Ă���̂́A
�u���͂ȌR�����Ȃ��ƁA�����͎E����邩�A�z��ɂ���邩�ł���v
�o�J�o�J�����A����Ȃ��Ƃ�����ɋN����͂����Ȃ��H�ł́A20���I�����̃`�F�R�X���o�L�A�A1956�N�`�x�b�g�����́H
|
�����V�A
����Ă��邱�Ƃ̑P�������͂Ƃ������A�꓁���f���[�h�ŗ����������̂́A���������ł͂Ȃ��B�v�[�`�������郍�V�A��������B2008�N9���A�O���W�A�̎����B��I�Z�`�A���߂���A���V�A�ƃO���W�A���Η��A���V�A�̓O���W�A�ɐN�U�����B���Ă̌��������Ȃǎ���ɂ������Ȃ������ȑԓx�́A���Ă̋���(���킨����)�̃\�A��f�i������B���̖��́A������`�ɕă��̔e��������ނ̂łǂ����������͈Ӗ��������Ȃ��B�O���Ƃ͂��ׂāA�����������̂ł���B
�܂��A���V�A�́A2009�N1��1���A�E�N���C�i�ւ̓V�R�K�X�̋������~�����B�\�����̗��R�͉��i���̂��ꂾ���A�e���ẴE�N���C�i�ɑ��鈳�͂ƌ����Ă���B�\�A�����A�ă\���͏I�����A���E�̓A�����J��Ɏx�z�ւƃV�t�g�����B�\�A���p�������V�A�́A��U�A���剻�Ɍ����������̂́A���݁A���f�B�A�����A�Y�Ɠ��������߂Ă���B����ɁA���E��L�x�Ȏ�����ɁA�A�����J�哱�̐��E�����ɗh���Ԃ�������Ă���B
�v�[�`���́A���̂Ă��瑫�̂ܐ�܂Ń��A���X�g���B����������]�݁A�������ׂ�����m���Ă���B�����āA�ǂ�Ȕ��𗁂т悤���A���܂킸�f�s����B��{���n��
�u���̐l�́@�����Ȃ�Ƃ��@���͂Ό��ց@�킪�Ȃ����Ƃ́@���݂̂��m��v
(���̎��͉��Ƃł������Ă���A�ǂ����A���̂�邱�Ƃ́A�������������)
��f�i������B�v�[�`���̐��̂͊v���ƂȂ̂��B
�ȑO�A�v�[�`���ƃ��V�A�s���̑Θb���ATV�ŕ��f���ꂽ�B���鏗�����A
�u�A���i�̂����ŁA���V�A�Y�Ƃ��ꋵ�ɗ����Ă��邪�A����Ȑ���͊Ԉ���Ă���v
�ƃv�[�`���ɋl�ߊ�����B���{�̎Ȃ�A�ی�f�Ղ͐��E�����ɔ�����Ƃ��Ȃ�Ƃ��A�����̐������ɏI�n�������낤�B�Ƃ��낪�A�v�[�`���̓����͋����ׂ����̂������B
�u���Ȃ��̌������Ƃ͐������B���́A����������肾�v
���̌�A���V�A�͎����Ԃ̊ł������グ�A���Y�Ԃ����Ƃ����サ���B�v�[�`���͐^�̈����҂��B�����ɂƂ��Ă͍Г�Ȃ̂����B
���̃��V�A�͓��{�̖����ېV�Ɏ��Ă���B�����͍ō��l����70�����������A���ƂƋ����x�z�Ōo�ς͍������A�P�ƈ��A�U�P�҂ƈ����ҁA�����Ɩv�����A���߂������Ă���B�l���̓A�����J�̔����ɂ��������A�H�Ɛ��i�̗ʎY�Z�p�������Ȃ��B����ŁA���G�A�����J�ƐL�������������ɑR���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ېV���v���A���ǂ�Ȏw���҂��K�v���͖��炩���B�v�[�`����邪�A���V�A�ɌN�Ղ��闝�R�͂����ɂ���B
|
����l
���̂悤�Ȑ��E����݂�A���ʂ̊�@�́A
�u���E���Q���N���邩�ۂ��v
�ɋA������B���E���Q�͑���E���������N�������O�Ȃ����邩�炾�B�����āA���́u�\���v�ƂȂ�̂��A�����B���A������\������A1929�N�̂悤�ȋ��Z���Q�ł͂��܂Ȃ��B�Љ�V�X�e���S�̂����A���m�̋��Q�ɓ˓�����\��������B�����ŁA����̊����\�� �E�E�E
�悸�A�����͉��Ō��܂邩�H����������Ǝv���l��������Ί��͉�����A���̋t�Ȃ�A���͏オ��B���ꂾ���B�s�������犔��������킯�ł͂Ȃ��B���̗ǂ��Ⴊ�A2009�N�����̊������B��ƋƐт̈����A��Ɠ|�Y�A���Ǝ҂̋}���ȂǁA���̌o�ς͓]��������ǂ��납�A��ח��Ƃ��Ȃ̂ɁA�����͈ӊO�Ɍ����B���̂��Ƃ͂Ȃ��A�����㏸�ɓ]����Ǝv���Ă���l���������炾�B���̍����́H
��Ƃ̌o�c��Ԃɔ�ׁA����������������B���̎w�W�ƂȂ�̂��uPBR�v���B
�uPBR��������1��������̏����Y�v
���̎�����APBR���Ⴂ�قǎ��Y�����銄�Ɋ������Ⴂ���ƂɂȂ�B�܂�A�����B
���݁A���؈ꕔ��Ƃ�PBR�̕��ϒl�́A0.7(2009�N1��)�B70���~���̊����A���̉�Ђ̎��Y100���~���̌��������L���邱�ƂɂȂ�B�����A��Ђ����U���āA���Y����������A�P���v�Z�ŁA
100���~�|70���~��30���~
�̗��v��������B�{���A���������̓��X�N���āA��Ђ̐��������̂Ȃ̂ɁA���U��������Ɍ������� �E�E�E �����܂ŒP���v�Z�����A����ɂ��Ă��A�ُ�Ȉ��l���B
�ł́A���������H�����O�ɁA�`���̃K���u���C�X�̌��t���v���o�����B�{���ɍ�����l�H
|
�����
���I�����𓊓����悤�����܂����A�A�����J�̃r�b�O�X���[�������c�関���͂Ȃ��B����قǁA�����ԎY�Ƃ͎Ηz�����Ă���B����܂ŁA5�N�O��ŎԂ���芷����l�������������A����7�N�O��A�₪��10�N�ȏ�ɂȂ邾�낤�B���ꂾ���ŁA�V�Ԕ̔��䐔�͔�������B���������A�����Ԃ�10�`20�N�͑���B���㔼���Ȃ�A�����c�鎩���ԃ��[�J�[�������H���E�Ő����c�鎩���ԃ��[�J�[��6�ЂƂ�����������B�g���^�A�z���_�ABMW�A�t�H���N�X���[�Q���A�_�C�����[�A�v�W���[�E�V�g���G�� �E�E�E �ăr�b�O�X���[������]�n�͂Ȃ��B
�r�b�O�X���[�V���b�N���̐��E���Q���n������A���������܂߁A��ʂ̎��Ǝ҂��o�邾�낤�B�Ƃ͂����A�A�����J��GDP�ɐ�߂鎩���ԎY�Ƃ̔䗦�͂킸��0.8���B�Ƃ��낪�A���Z�̑�ʔj��CDS(�N���W�b�g�E�f�t�H���g�E�X���b�v)�ɉ�������A�����ł͍ς܂Ȃ��BGDP�䗦��20�����߂���Z�E�ی��E���[�X�E�s���Y�Ƃ͑�Ō�����B�����Ƃ��A���Z�V�X�e�����̂��̂�����A�Ǝ�͊W�Ȃ����B
���������Ȃ�A�A�����J�l�́A�؋������S����������߁A�K���N�^���i�Ȃǔ���Ȃ��Ȃ邾�낤�B���ʁA���i���v�͌�������B
�u���Y�� �� ���Ǝҋ}�� �� ��� �� ���Y���v
�̋���Ȉ��z�����܂�A��Ƃ̋Ɛт͋}���Ɉ�������B���̎��_�ŁA�\������銔���́A�ă_�E����6000�h���A���o����7000�~�B
�����܂Ŋ�����������ƁA�ʂ̖�肪��������B�����̌��N�Ɛ����ƘV����������u�����̑�ʔj��v�ł���B�����ی���Ђ́A���Ђ̎��Y�̈ꕔ�����ʼn^�p���Ă��邪�A���̕\�͊e�Ђ������w���������̓��o���ϊ����ł���B
��Ж��@/�@�����擾���̓��o���ϊ���
�����@/�@12,750
�Z�F�@/�@10,400
�O��@/�@9,400
�x���@/�@9,300
���@/�@8,800
���z�@/�@8,270
�哯�@/�@8,000
���{�@/�@7,600
�������c�@/�@7,400
�Ⴆ�A�������c�����̏ꍇ�A���o���ϊ�����7400�~�Ńg���g���A�����艺����A���ő������邱�ƂɂȂ�B�����A��̗\���A7000�~�܂ʼn�������A���ׂĂ̐��ۂ��A���ő�������(�܂ݑ�)�B�����̊܂ݑ��́A��Ђ̎��Ȏ��{���獷��������邽�߁A�ی����̎x�����]�͂�������B���������Ȃ�A�����ی���Ђ̐M�p�s�����N����A�����҂̌��N�Ɛ����̕ۏႪ��������B��s�̓|�Y�ǂ���ł͂Ȃ��B
���\���͔N������������B�������[�߂����I�N�����^�p���Ă���̂��A�N���ϗ����Ǘ��^�p�Ɨ��s���@�l(GPIF)�B���[�}���E�V���b�N�Ɏn�܂銔�������ɂ��AGPIF�̉^�p�����͏㔼���Ƃ��Ă͉ߋ��ő��2��9000���~�ɒB����(2008�N)�B����ɁA�^�p�������ݐς���A�ی����̈����グ��x���z�̌��z�͔������Ȃ��B�����琭�{�ł��A�Ȃ����͕̂����Ȃ��B�N���́A�J���҂̎����A�N�������҂̐������ɂ����E����B�������A�A�����J������͓����B
���̑�\���́A�ی��ƔN�������A���ׂĂ̐����҂́u���S�ƈ��S�v�����ꂩ��h���Ԃ�B�[���ȎЉ�s�����������邾�낤�B���̂悤�ȏł́A�����Ƃ͕s���ɂ����A�����Ɗ��͉�����ƍl���A����ɉ��B���R�A�����̊�����������B���̃t�F�C�Y�ł́A���������̃e�N�j�J�����͂͗p���Ȃ����A��l�͗\���s�\�ɂȂ�B��l�������Ȃ��قNj��낵�����Ƃ͂Ȃ��B�����Ƃ̓p�j�b�N�Ɋׂ�A�Ō�̓������肪�n�܂�B�����Ȃ�A���o���ς�6000�~�����荞�ނ��낤�B���̌㉽���N���邩�͗\���s�\�E�E�E
|
������
���݁A�}�X���f�B�A���\�����関����2����B
1�D1�`2�N��ɒ�������ĉɓ]����(�����h)�B
2�D1929�N�̐��E���Q�Ɋׂ�(�����h)�B
�t�����X�̌o�ϊw�҃W���O���[�́A���Q���i�C�z�ɑg�ݍ���ł���̂ŁA�L���Ӗ��ŁA�u1�D�v���u2�D�v���z�I�Ȃ��̂ƌ����邾�낤�B�ł��A�Ђ���Ƃ����� �E�E�E ����̑�s���͏z�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ���������Ȃ��B����܂ł̐��E�Ƃ͕s�A���̑�j�ǂ������Ƃ����� �E�E�E
�����ԁA�d�b�A�J�����A�R���s���[�^��1�l1�䏊�L���邱�Ƃ����z���Ƃ�����H50�N�O�܂ł́A�قƂ�NjƖ��p�������̂�����B���������Ȃ�A���N�A���\�N�҂��Ă��A�i�C�͉��Ȃ��B�Ƃ͖{������ׂ��p�ɖ߂邱�ƂȂ̂�����B����́A�Љ�S�̂��܂���ψقł���A�ʂɑΏ����Ă����ʂ͂Ȃ��B���z�̑�ԗւ��A���ׂĂ��ۓۂ݂ɂ��邩�炾�B
�����ŁA�l�\���B������2����B
1�D���N��A���������u�J�W�m�o�ρv�ɋt�߂肷��(�m��60���H)�B
2�D���m�̐��E���Q�ɓ˓����A�Љ�̃X�N���b�v���r���h���N����(�m��40���H)�B
�悸�́u1�D�v�B�J�W�m���Z�ɂ�鐢�E���Q���ӂ������߁A���S�ȋ��Z�����߂��A���̌o�ς����� �E�E�E ���҂��\�����邱��Ȑ��E�́A���ԂȂ��B����܂ł̎��{��`�ɖ߂�Ȃ�A�J�W�m�o�ς����̂܂ܕ�������B���̎��{��`�́A�J�W�m�o�ςȂ����Đ��藧���Ȃ����炾�B��̓I�ɂ́A�A�����J���؋��Ђ��ő�ʏ���A���̑�����A�A�����J���Z��(�A�����J���c�J�W�m)���������B�K���N�^���i���݂̎��{��`���ێ�����ɂ́A���ꂵ���Ȃ��B
���Ɂu2�D�v�B���̑�\�����A�ی����N���V�X�e����j�A�����҂̈��S�͏�����сA�^�S�ËS�����E���������悤�ɂȂ�B�����K���i��������Ȃ��Ȃ�A�����̊�Ƃ��|�Y���A���Ǝ҂��X�ɂ��ӂ��B�^�A�A�O�H�Ȃǂ̃T�[�r�X�Ƃɂ��킦�A�x�@�E���h�Ȃǂ̌��I�T�[�r�X������A�s�ւȐ��̒��ɂȂ�B�����A����ȏ�Ԃ͒����͑����Ȃ��B�Љ�v���A�܂�A�V�����Љ�V�X�e�������܂��B
|
���V��
�����A�u2�D�v�������ɂȂ����Ƃ��āA�����̂�����Ȃ��A�������H���Ԃ��Ȃ��A�[�����������Ȃǂ��邾�낤���H���Ԃ�A����B��X���z���グ���f���炵���e�N�m���W�[���A������\�ɂ��Ă����͂����B
�l�Ԃ������Ă�����Ō������Ȃ��̂��A�G�l���M�[�ƐH���Ɛ��B���́A�ŐV�̃e�N�m���W�[���g���A���ׂĎ��������ł���B����ɁA�G�l���M�[�ɂ������ẮA���z�����d���g���A�����j���O�R�X�g�͂قڃ[���B�K���N�^���{��`�ɉ��S���āA��������K�v�ȂǂȂ��̂��B�l���Ă݂�A�G�l���M�[�A�H���A���͎��R�E�ɂ��ӂ�Ă���B
���ċƖ��p�ɂ����g���Ȃ�����������A���ł͓Ƃ��߂ł���悤�ɂȂ����BTV�A�V���A���ЁA�Q�[���A�ʐM��������B�R���e���c�ƃR�~���j�P�[�V�����̂��߂ɁA����قǂ�������̃��f�B�A��C���t�����K�v���낤���H���ׂāA�C���^�[�l�b�g�ł܂��Ȃ���̂ɁB������H���Ԃ��A�K���N�^���ʐ��Y���A�|�C�̂ĂŃS�~�̎R�H�������Ԉ���Ă���B
�C���^�[�l�b�g�́A�l�ނ����߂Ď�ɂ����u�����̓����c�[���v���B���A�R���e���c�A���i�̔��A�R�~���j�P�[�V�����A����ɁA�S���V�����T�[�r�X�����܂��\��������B�������A
�u���t�@�C�o�[ �{ ���[�^�[ �{ �[���v
�Ƃ����܂��������ō\�z�ł��邵�A���p�҂̕��S�����Ȃ��B����肩���āA������ƐU����������ł����B�����ɂ́A�����ŁA�G�R(ECO)�ŁA���N���N����y���݂͂�����ł�����B
��������c�ɂ�U�^�[�����āA�C�Â������Ƃ�����B���R�̖L�������B�l�����x���Ⴂ�̂ŁA��l���Ɛ�ł��鎩�R�������B����͓V�̌b�݁B�����́A����Ȑl���A�C���t�����������邪�A�ЊQ�Ɏキ�A�H�ƍɂ�1���������Ȃ��B�������A�u�h����v�ŘI�������悤�ɁA���Ƃ���A�����܂����Ƀ��[�`��������B���ł�����������̊y�����A������H�̃R���N���[�g�W�����O���Ɖ����Ă���B
�����A���E���Q���n�܂�A�s�ցA�s���R�ǂ��납�A��������Ȃ��Ȃ�B�����A���j���݂�A�����ƃq�h�C������������B�����m�푈�����̗������̋ʍӁB���\�{�A���S�{���̉Η͂����A�����J�R�Ɍ�����A�Ă���A����ł��������m�����B�n���̋ꂵ�݂Ƌ��|�̐�ɑ҂��Ă���̂́A�m���Ȏ��B����ȏ�̋ꂵ�݂͂Ȃ����낤�B�`���̃K���u���C�X�̌��t��ǂ݂����悤�B
�u�ň��̎��Ԃ����͍ň��ł͂Ȃ��A�����ƈ������Ƃ��������v
���E���Q�ł���Ȃ�ł���A�l�Ԃ��Ƃ����߂��Ȃ�A�K���C���ł���B����܂ł́A���������A�h���d���ł��A�[�����ē����B���͂Ƃ肠�����������т�����A�Ɗ����̂ł���B���̂����A�V�����p���_�C���A�V�����Љ���܂�邾�낤�B����͋C�x�߂ł͂Ȃ��A�l�ނ̗��j���ؖ����Ă���B
�ł́A�ǂ���������̂��H
1�D�C�̍������ԂŁA�R�~���j�e�B������B
2�D�c�����k���A�H��������������B
3�D���z�����d���[�d�V�X�e���ŁA�G�l���M�[��������������B
4�D�K���N�^���������A�����ƒm�I��ECO���C�t�ցB
�ŋ߁A ����ȃn�C�e�N���������R�~���j�e�B���Ă���B�@
�@ |
| ���A���Ă����勰�Q�o�� |
   �@
�@
|
The Return of Depression Economics (1999)
�בփ��[�g�����Ȃ��Ă�����(�בփ��[�g����萅���Ɉێ����Ȃ��Ă����A�Ƃ����Ӗ�)���́A�s�i�C��������邽�߂ɂ́A������K�v�Ȃ�����������������B�[���ɂ܂ł����ĉ�������B�ł��A���������[���ł��܂�����Ȃ��Ƃ�����H�@�[���ɂȂ��Ă��܂��A����҂����~�������Ԃ�Ƃ��Ȃ������̓���������Ȃ�������H�@���ꂪ���|�́u��������㩁v�Ƃ�����ŁA�����Ȃ������Ō�A���Z����Ȃ�āu���������v�悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B�����݂̑��������ɂ��Čo�ς��g�傳���悤�Ƃ��Ă������ڂȂ��B��s������҂��A���X�L�[�ŗ��������Ⴂ����犔�Ȃɓ���������́A���S��——�܂藬�����̍����������茳�ɂ����Ƃ��ق���I�Ԃ��炾�B
�܂��͂��߂�1930�N��ɁA�A�����J�ƃC�M���X�̌o�ς��������g���b�v�ɂ͂܂���������݂����B�A�����J�̒Z�����̕��ϋ����́A1939 �N�ɂ͂�����0.023 �� �������B�ł������ɉ��l���̌o�ϊw��——�L���Ȃ̂̓~���g���E�t���[�h�}���ƃA���i�E�V�����[�c���Ă����肾����——�������ɂ́A���ǂ������Ƃ��������肳�����Ă�����A1930 �N��ɂ�����ς���Z����͗L���������͂��ȂƁB�܂�����l�́A�������g���b�v�Ȃ�Ă��̂��������������I�ɂ��肤��̂��ǂ������Ă��Ƃ��^��ɂ��Ă�B�ǂ�ȃP�[�X�ł��A���̂��Ƃ͗��j�I�ȋ����̑ΏۂƂ��Ă���(�܂葼�l���ƂƂ��Ă���)���Ă��炦�Ȃ��݂������ˁB1990 �N�̎��_�ł́A�������g���b�v�Ȃ�ċN���������Ƃ͂Ȃ����A���ꂩ����N����Ȃ����낤�A�Ƃ����̂���ʓI�Ȍ����������B
���Ă����œ��{�̏o�Ԃ��B�u�o�u���o�ρv�� 1991 �N�ɒe�������ƁA���{�̋��Z���ǂ̓o�u�����܂��ӂ���ނ̂�����Ă�����ŁA�͂��ߋ�����������̂ɏ��ɓI�������B�ł��A 1996 �N���̂����Z��������1�����͂邩�ɉ�����Ă��邵�A���܂ł� 0.25% �܂ł��藎��������Ă�B����ȋɒ[�ɒႢ�����ł��A�s�������Ă̊��~�͂Ƃ߂��Ȃ����A���{�o�ς� 1992 �N�ȗ����邵��ł�i�C������Ђ�����Ԃ��Ȃ�āA���b�ɂ��Ȃ�Ȃ����炢�B�Ō�Ɏc���������_�ȉ������炩�̋����������肨�Ƃ��ă[���ɂ���A�����傫�Ȃ�����������͂����A�Ȃ�čl���Ă�o�ϊw�҂͂قƂ�ǂ��Ȃ�����A���{�͂ق�ƂɌÓT�I�ȃg���b�v�ɂ͂܂��Ă����B�����Ȃ�Ƌ����[���ł��܂�����Ȃ��Ȃ����Ⴄ�킯���B
(�ق�Ƃ͂����ɒi����5�͂��܂��Ă��B�����ł͎�ɓ��{���{�̌i�C���グ���ĂāA����炪����t���Ȃ��������R���q�ׂ��Ă��炵���B�ł����ȏ��̃y�[�W�̂����ŃJ�b�g����Ă�)
���{�̌o������킩��̂́A���W�����ߑ�o�ς��������g���b�v�ɂ͂܂肤����Ă��Ƃ�������Ȃ��B��������ɂ���Čo�ς����̃g���b�v����~���o����Ȃ�āA���C�y�ȉ����ŊÂ��ɂ��قǂ�������Ă��Ƃ��A���{�̌o���͎����Ă�̂��B�f�ł���s�����Ƃ�Ȃ��������爫�������Ƃ������āA���{�̎w���҂�l�|����l�����邩������Ȃ��B�ł������悤�ȉ߂����A�����J��[���b�p�ŔƂ��ꂽ���āA����s�v�c����Ȃ���B
1930�N��̖S�삪�܂����n���������Ă���Ă̂��ق�Ƃ��Ƃ��Ă��A�Ȃ����A����Ȃɒ����N�����u�ĂāH�@���Ă̂��������^�₾��ˁB����ɑ��ẮA���R�s��ł̓�����O�̃��[���ɏ]��Ȃ������c�P���Ă鍑������A�Ƃ����̂��W���I�Ȃ��������B�Ƃ��ɃA�W�A�o�ς́A�Ȃꂠ�����{��`�Ƃ����߂ɑ��锱�������Ă���B�ŁA�g���u���Ɍ�����ꂽ���݂͂�ȁA���̊�@�̂������Ő��ЂƂ��уX�|�b�g���C�g�𗁂т����ƂŁA����܂łł������܂���������炩���Ă����Ƃ������̉��ɂ��炳�ꂿ�Ⴄ�Ƃ����킯�B���Ƃ���s�ɂ̓��X�L�[�Ȍo�c���`�F�b�N�������ɋ����A����ł͐�ΓI�Ȑ��{�x����������A��Ƃɂ͂Ƃ�ł��Ȃ��z�̎؋������サ���A�ȂǂȂǂ̂܂������ˁB
�ł��A�o�ς͂��̎�_�̂����łЂǂ��ڂɑ����Ă�Ƃ����l�����́A���߂Ă����Ə��Ȃ��Ƃ�2�̓_�ʼn�������B�ЂƂɂ́A���̓�������̃X�P�[�����߂̑傫���Ƃ���ނ荇��Ȃ��悤�Ɏv����B�������f�̃w�}���A�P�Ȃ鐬���̌����ɂȂ��邾������Ȃ��āA�ǂ����Đ��Y�ƌٗp�̑����܂ň����N�������Ⴄ�̂��ȁH�@����ɁA���������͍̂��ȂƂ�����A������̂�������Ȃɑ����̍��������Ƃ��Ɉ�ĂɃg���u�����̂́A���������ǂ����ĂȂH
�����ł͂��Ƃ��b���킩��₷���Ǝv���B���H�̂����ԂŁA�����ŋ߂ňُ�Ȑ��̎��̂��N�����Ƃ��Ă݂悤�B�Ƃ��ɒ��ӂ��ׂ����́A������܂������ǎ��̂ɂ��������l�������B�قƂ�ǂ̃P�[�X�ł́A���̂̔�Q�Ҏ��g�ɂ��܂��������_��������Ă��Ƃ��킩��B�������݉߂��Ă��Ƃ��A�^�C�������茸���Ă��Ƃ��A���낢��B���ׂ̂��l�́A�����͓̂��H����Ȃ��ĉ^�]�肾�ƁA�������Č��_�Â��Ă��܂��B
���̌��_�̂ǂ������������낤�H�@�����A����͓�d�ɂ܂������Ă�B�܂����ɁA�ǂ�ȎԂɂ����ĉ^�]��ɂ����āA���������グ��Ό��ׂ̂ЂƂ�ӂ��A��������������͂��ł���B���̔�Q�҂ɂ͕��ς�薾�炩�Ɍ��ׂ������A�Ȃ�Ă��ƌ�����̂��ȁH�@���ɁA�ӂ��̉^�]���肿���Ƃ̓_���ȂƂ��낪�������ɂ���A�ނ�̂�������Ȃɑ����̐l�������A�ق��̂ǂ��ł��Ȃ������Ŏ��̂����Ƃ�������ɂ́A�����̂͂܂����H������Ă��ƂɂȂ�͂��B����ƑS���������Ƃ�B
�܂肱���������ƁF���Â��̃A�W�A�o�ς͐����I�E���x�I�Ȍ��ׂ������������Ă���Ă��Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����̂�����ǁA�ł������A�����J�����[���b�p�����N���ė��N�ɂł��g���u���ɂԂ������Ƃ�����A�A�i���X�g�����͉ߋ���U��Ԃ��āA���m�̉��l�ςƂ����x�̂��Ƃ����ē����悤�ɂ������낷�Ɍ��܂��Ă���Ă��ƂˁB������ 1990 �N��̃A�W�A�̋��Z���A���̑O��10�N�Ԃ��ǂ��������Ȃ����Ȃ�Ă��Ƃ́A�قƂ�ǂȂ��B����Ȃ�A�Ȃ�����Ȃɍŋ߂ɁA����ȂɂЂǂ��ɂȂ���������́H
�����͂����B���E�����݂����g���u���Ɏキ�Ȃ��������́A�o�ϐ����v����Ȃ��������Ƃ���Ȃ��B����ǂ��납�A���v���s��ꂽ�̂������Ȃ�B���E���̍��X�́A�勰�Q�Ȍ�̌��ׂ��炯�̑̐����C���ɂȂ��āA�勰�Q�ȑO�̎��R�s�ꎑ�{��`�̉��b�ɂ��������悤�ȑ̐��ɂӂ����ѕ������ǂ����킯���B�ł��A����x��̎��{��`�̉��b�������A�낤�Ƃ���A���̌��ׂ����Ď����A�邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��ł�������C������ׂ��͎��̂ӂ��ŁA�s����ȏ�ԂɊׂ�₷���Ȃ�A���ꂩ��s�������������₷���Ȃ���Ă������ׂ��B
�����ł͂Ƃ���4��ނ̐�����v�ɂ��čl���Ă݂悤�B�܂��͂��߂́A���ێ���̎��R���ɂ��Ă��B1930 �N��� 40 �N��ɂ́A�I�[�X�g���A�Ȃ̌o�����ӂ܂������ƂŁA���ێ��{�ړ���}���悤�Ƃ����������قƂ�ǑS���E���ɍL�܂����B�����͈ב֊Ǘ��̐��̈ꕔ�Ƃ��ĂˁB���Ƃ��Ƃ̃u���g���E�E�b�Y�̐��́A���@����̍U���ɔ������בփ��[�g�̌Œ艻��h�����Ƃ���Ǘ��̂�肩���ɁA���͊����Ɉˑ����Ă����B�ł����������āA�ב֊Ǘ��Ȃ�Ă��������Ƃ������ǂ��납�A�C���Z���e�B�u�͂䂪�߂�핅�s�͌ĂԂ�A���������̍��������Ă��Ƃ��킩���Ă����B����ł܂��͐�i���A�Â��ēr�㍑�̑������A���S�ʉ������Ǝ��R���{�ړ��̕��������Ă������ނ��ƂɂȂ����킯���B�ł��������邱�Ƃł�����́A���@���̍U���Ƃ����s����v���ɑ��ẮA�܂����Ă��キ�Ȃ���������̂ˁB
�ӂ��߂́A�������Z�s��̎��R���ɂ��āB1930�N��̈Â��e�̂��Ƃɂ����āA�قƂ�ǂ̍��͌������K���Ƃ������肵���o�b�N�A�b�v���̋�s���x�������Ă����B�����������x�͈��S�ł͂����Ă������������Ȃ肪���ŁA�a���҂ɂ͂�����Ƃ̂����������o���Ȃ����A�������������������悭�^�p����̂����������肾�����B���������ċK�������߂���ƁA���Z�V�X�e���͑O��肸���Ƌ����I�Ō����I�ɂȂ����B�ł�����Ɠ����ɁA1997�N�H�ɃA�����J�o�ς�E���������̂Ǝ����悤�ȋ��Z�p�j�b�N���N����\������������������A�Ƃ����킯�B
�݂��߂́A��������̗��Ē�����B�قƂ�ǂ̍��͐��Ɏ����I�ȃC���t�����o�����Ă��āA1970 �N��� 80 �N��͂��߂ɂ͕����̑唚�������E�K�͂ŋN�����B���̃C���t���͗}����K�v�������āA���������Ȃ����B�������ō��قƂ�ǂ̍��ł͕����͂т����肷�邭�炢���肵�Ă邵�A���������������ێ��������邾�낤�Ƃ����M�p���ł܂��Ă�B�ł��A�C���t���ɂ͎��͂������v��ʃ����b�g������Ƃ������Ƃ��킩���Ă����B�ЂƂɂ́A���Ƃ������ɂł�������������Ă鍑�́A�C���t���������Ă��̊z���Ȃ�Ƃ��Ȃ���x�ɂ܂ŁA����ɖڌ��肳��������Ă��Ƃ�����B�Ђǂ��s���Y�݂��t��������Ă� 1970 �N��̓��{��������݂����ɂˁB�����Ă����Ƒ厖�Ȃ̂��A�s�i�C�ގ��̂��߂ɋ�����������悤�ȂƂ��A�C���t����5���ŋ���8���̍��́A���������肵�Ăċ�����3���̍������A�����Ɨ]�T��������Ă��ƁB����������A����1980�N��ɕ�������̂��߂ɂ���قǃN�\�^�ʖڂɂ�����ĂȂ������Ƃ�����A��i���͗������g���b�v�ɑ��Ă����Ƃ����Ƌ����������낤���Ă��ƂȂB
�Ō�ɁA���������̍Č�����B1970�N���80�N��ɂ́A���z�̐Ԏ��\�Z��g��ł鍑�������ς��������B���ʂƂ��āA�����̐ӔC�������Ɖʂ������Ƃ����傫�ȓ�����1990�N��ɋN���Ă����B���[���b�p�ł́A�͂��߂̓}�[�X�g���q�g���ɂ���āA���܂͂d�l�t�����Ȍ�́u���苦��v�ɂ���āA�Ԏ��x�o����߂��邱�ƂɂȂ������A�A�����J����Ƃ��Ƃ��Ԏ��\�Z�������ĂȂ��Ȃ�Ƃ���܂ł����Ă���B�ł��s���̂������ŐԎ��x�o�ɂ͂܂肱���{�́A��������߂��ăo�����X�����悤�Ƃ��邾���w�͂���——����Ōo�ς�s���̂ق��։������ǂ����ʂɂȂ���������ȁB
�v����ɁA�勰�Q�o�ς����܂ɂȂ��ċA���Ă����̂́A���{�����������Ƃ����Ȃ��������炶��Ȃ��āA���������Ƃ���������炾�A�Ƃ����̂��{���̂Ƃ���Ȃ́B������邱�ƂȂ��P�s�͂Ȃ��A���Ă̂͐^������ˁB
�����Ȃ��Ă���ƁA���{�̃R���g���[�����Ƃ��C���t�����Ƃ��̖��ɑ���ӔC�҂̑ԓx�ɂ́A�Ȃ��ςȖ������łĂ���B1997�N�ɃA�W�A�o�ϊ�@���N����ȑO�A�r�㍑�̑S�������{��������R���ł���킯����Ȃ������̂́A�قƂ�ǒN�ɂƂ��Ă����ꂵ�����ƂȂB�Ƃ��ɒ����Ȃ�āA�c�C�Ă��ȁA��[�����̎��{���肪���܂��ɂ������B�ł��A�}���[�V�A���Ɏ��{���������ɖ߂�̂́A�������Ȃ����Ƃ��Ǝv���Ă�B����Ɠ����ŁA�A�����J�ɂ���̂�2���̃C���t����5���̋����ł����āA���肵��������3���̋�������Ȃ����Ă��Ƃ�m���Ă�A�݂�Ȃ͖������ǂ��Ȃ�킯�B����ǁA���{���C���t����3���Ƃ�4����ڕW�ɂ��Ă����ׂ����Ȃ�āA����ς�Ƃ�ł��Ȃ����b�B���t��������A�����ɂ���̂͂������ǁA������ڎw������_���A�Ȃ��Ă��B
����ł��A�����������_������Ēʂ�̂͂ނ��������B�x���ꑁ����ڂ���͎��v�̐j���A���Ȃ��Ƃ��r���܂ł͖߂��Ȃ�����Ȃ�Ȃ��Ȃ邾�낤���Ă��ƁB���Ƃ��A�ʉݓ����Ǝ��R�ϓ����ꐧ�ʉ݂̂ǂ���ɂ��K���Ȃ����ւ̎��{�̗���𐧌�������Ƃ��A���Z�s��ɂ���Ă��ǂ܂ŋK����������������Ƃ��A�����̈�������Ⴂ���ǒႷ���Ȃ��C���t�����̂ق���ڎw������Ƃ��B�ڂ���͑勰�Q�o�ς̋��P�̑O�ɓ��𐂂�Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B��������A�h�������܂����܂Ȃ�����Ȃ�Ȃ��Ȃ�悤�Ȗڂɂ́A��������Ȃ��ł��ނ͂�������B
�@ |
| ��2009�N���E���Q�̍��{��� |
   �@
�@
|
|
���T�D�͂��߂�
|
2007�N�ȍ~�A�����J�Ō��݉������T�u�v���C�����Z��@�����E�ւƍL����A�o�ςƂ�킯���O�̐����ɑ傫�ȉe����^�������Ă���B�u�S�N�Ɉ�x�̊�@�v(�O���[���X�p���O�A��c��)�Ƃ��]����A1929�N�̐��E�勰�Q�ɔ䌨����鎑�{��`�̐[���Ȋ�@�Ƃ������Ă���B���̔��[�̓A�����J�̑�蓊����s�n�w�b�W�t�@���h�̎����I�j�]��2007�N6�����납�瑊���������Ƃł���B�����w�b�W�t�@���h�́A�T�u�v���C���E���[�����W���E�g�������،���(���Z)���i���ʂɕۗL���Ă����B
�Ƃ��낪2006�N�Ă�����s�[�N�ɏZ��i���������n�߁A�����،������i�̐M�p�s�������������Ƀw�b�W�t�@���h�̌o�c�͍s���l�܂�A�e��Ђł��铊����s�̌o�c��@���\�ʉ������B�u�T�u�v���C����@�v�������n�߁A2008�N3���ɂ͑�蓊����s�x�A�E�X�^�[���Y�������I�j�](FRB��300���h���̎���������JP�����K���E�`�F�[�X�ɂ��~�ύ���)�A���N9���ɂ̓��[�}���E�u���U�[�X���j�]�A ���ی���Ђ�AIG(American International Group�A Inc.)���A�����J���{�̊Ǘ����ɓ���ȂǁA�T�u�v���C����@�͑S�Ă�h�邪���n�߁A���E���Z���Q��U�������̂ł���B�����̊W�ケ�̌o�܂��ڂ����q�ׂ�킯�ɂ͂����Ȃ����A�ǎ҂ɏ��e�𗝉����Ă����������߂ɁA�w�i�E�o�܂ƃT�u�v���C����@�ɂ��Ă͊ȒP�ɂł��G��Ă������B
�悸�w�i�ɂ��āB�f�Ղƍ����́u�o�q�̐Ԏ��v�ɔY�ރA�����J�́A�o��Ԏ��̍팸�̂��߂ɐ�i�����Ɂu���́v�����߂��B�Ƃ�킯�f�ՐԎ��팸�̂��߂ɍő�̖f�ՐԎ����荑�ł��������{�ɑ��āA�������ɓ������������A�o�̗}��(����K�����\�����c������c)�ƈבփ��[�g�̉~���E�h������v�������B���̌��ʂ��A�����o�u��(�u�Ԍ����o�ρv)�̔����ƕ���(�����s��)�ŁA���m�̂Ƃ��肻�̌���(��������`�̋@�\��Q)�ɓ��{�͔Y�܂��ꑱ���Ă���(�u����ꂽ20�N�v)�B
�����A�����J�͑Γ��A����h矂��A�����Ƃ́u�Y�Ƌ����́v�̉�ژ_�̂ł��邪�A�A�����J�͎Y�Ƌ����͂��ł��ʂ܂܁A�~���h�����������i�݁A1995�N4���ɂ�1�h��79�~�ɂ܂ʼn~�����i�B���̂܂܂ł̓h���ւ̐M�F���h�炬���˂Ȃ����ԂɃA�����J�͒��ʂ����B�������u����A�A�����J�ւ̎��������Ƀu���[�L����������肩�A�������č������瓦���o���A�A�����J�����̊����E���s�ꂪ�����͕̂K���ł���B���������܂�A�O�N1994�N12�����̕ϓ����ꐧ�ւ̈ڍs�E�y�\�艺������n�܂��������L�V�R�̒ʉ݊�@�́A���������s�������������~�����Ă��B���L�V�R�ւ̓A�����J�̃~���[�`���A���E�t�@���h(�����M��)����̓��@���������ꍞ��ł������߁A���L�V�R�̒ʉ݊�@�̓A�����J�����̋��Z�s������鋰�ꂳ���������B�A�����J�́A�����Ȏ����̗������m�ۂ��A����������h���藧�Ă��Ƃ�K�v�ɔ���ꂽ�B1985�N�v���U���ӈȗ�10�N�Ԍp�������e���ʉݍ��E�h��������͓]�����ꂽ�B1995�N4����7�J�������E������s���ى�c(G7)�́u�ב֑���́w�������锽�]�x�v���ւāA8��15���A���Ƃ̗������ƕĂ̗��������Z�b�g�Ƃ���������ێ��̋��������Ɠ��ē�3���̈ב�������ɂ���āA�u�}���N�E�~�����h�����v��ڎw���u�t�v���U�v�����s���ꂽ�B�A�����J�́A�������v�ƃh�����n���ł̈ב֍��v��ۏ��āA�A�����J�ւ̃h���җ������鐭��������������̂ł���B
���E�̃h���͎����������߂Ė��悤�ɃA�����J�Ɍ����A�������s��ɗ��ꍞ�̂ł���B�܂����Windows95�Ŗ{�i�������u�C���^�[�l�b�g�u�[���v�ɉ����A�ݔ������u�[���ɕ���IT�֘A�Y�Ƃ���ꂷ��i�X�_�b�N�̊������@�֎Ԃɂ��āA�ݗ��Y�Ƃ̊���(�j���[���[�N�،������)���}�������B�l�b�g�o�u���ł���B�������A2000�N3��10���̃i�X�_�b�N�ō��l�ڂ�IT�o�u���͂͂����Ĕ�B���̌o�܂ƌ����́A�G�������������ے����Ă���B���N�́u9�E11���������e�������v�ɂ��o�ϊ����̒ቺ��w�i�ɁA��2001�N10���A�o�ώ����G�������Ǝq��Ђ̖�����\�����̂���ɁA������v�ȂǕs���Ȋ�������̎��������X�Ɣ��o���A���̃X�L�����_���ɂ���Ċ����͑�\���B�����z�����Ȃ��Ƃ�160���h��(��1��9600���~)����A�����̃A�����J�j��ő�̊�Ɣj�]�ƂȂ����B2001�N3�����s�[�N�ɁA1991�N3���ȍ~9�N�Ԍp�������A�����J�̌i�C�㏸�́AIT�o�u������ƂƂ��ɏI������̂ł���B
�u�b�V���哝�̂́A�����������Ԃ��A�i�C�h�����ł��o���K�v�ɔ���ꂽ�B�u�b�V���͎����Ƃ̑��i���f���A�Z��ł�Ꮚ���Ҍ������[���̗D�����ł��o�����B�u2010�N�܂łɁA�������́A�}�C�m���e�B�[�̎���L�҂��A���Ȃ��Ƃ����Ƃ���550�����ё��₳�Ȃ���Ȃ�܂���B����L�̊i�������邽�߂ɁA�A�����J�͉���ȖڕW���f���A�������̒��ӂƎ��������̖ڕW�B���̂��߂ɏW�����Ȃ���Ȃ�܂���B�v1)�ƁB
2001�N��6.5���ł������t�F�f�����E�t�@���h���[�g(�U���ڕW)�͐����ɘj��Ђ������̖��A�N���ɂ�1.75���ɂ܂Œቺ�����B�Z��[��������30�N���Œ�ŔN6�������j�I�ᐅ���ɂ܂ʼn�����A2002�N7�A8�����ɂ͐V�z��ˌ��Ă̏Z��̔��ː��͉ߋ��ō����L�^�����B�܂��A�N�����Z��1600����Ȃ�������Ƃ���鎩���Ԕ̔��䐔���A�̔����i�̃[�������ɂ���āA������1800��������B�A�����J���{�͂��������̏Z��擾����𐄂��i�߂��B�Z��[��������Ŋz���獷�������Ő��D���[�u�����{���A�Z��s�s�J���Ȃ͏��߂ďZ����w������}�C�m���e�B�[(�����h)�œ������x�����Ȃ��Ꮚ���҂ɏ��������x��2)����Ȃǂ��āA�Z��擾�𑣐i�����̂ł���B�������āA�W���[�i���X�g�����Ď��̂悤�Ɍ��킵�߂��B�u�����̕č��l�ɂƂ��āA��ȓ����Ώۂ͊��ł͂Ȃ��Z��ł��v3)�ƁB
�l�b�g�o�u������ōs����������Ă��������ݕ����{�E�h�������́A��Ăɉ��i�������������Ƃ��Ȃ��u���S�v�ȓ����恁�Z��ւƌ��������̂ł���B�A�����J�̃o�u����IT����Z��ւƃ����[����A�A�����J�̌i�C��8������(2001�N3���`11��)�̒Z���Ԃ̃��Z�b�V�����̌�ӂ����я㏸�ɓ]���A2008�N9���̃��[�}���E�V���b�N�܂ŁA�Z��o�u����w�i�Ƃ����ߏ�Ƃ��������i�C�ɕ������ƂɂȂ�B2004�N�̃s�[�N���ɂ͑S�Đ��т̂��悻7�������Ƃ����L���A����܂ŏZ��L�Ȃǖ��̂܂����ł������}�C�m���e�B�[�̏Z��ۗL�����S�̂�5�������B���ƂƂ����A�����J���E�h���[���͌��閲������ݓ��錻���ƂȂ������A��������̓T�u�v���C���������������Ƃ��đł��ӂ���Ă����B
�u�A�����J���E�h���[���v�Ƃ́A�N�����@��āA�\�͂��\�Ȍ��蔭�����A���[�������L���Ȑ�����Nj����Ă�����Ƃ����u�����̖��v����ł���B�u�A�����J���E�h���[���v�̓A�����J�u�Ɨ��錾�v�ł�����ꂽ����(�K����Nj����錠���A���R�ȋ����A�@��̋ϓ��Ȃ�)������ǂ���Ƃ��A�l�I�~�]�ƃA�����J�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�[��A�������Ă���Ƃ���ɁA�u�A�����J���E�h���[���v���鏊�Ȃ�����B�l�̐����̒Nj��Ƃ����ƁA���������ӎU(������)�L�����A���ꂪ�Ɨ��錾�̐����ȗ��O�ƌ��ѕt�����ČӎU�L�������������Ă���B���̓_�Łu�A�����J���E�h���[���v�̓A�����J���L�ȁu���l�ρv�ł���A���̃��g���b�N�Ƃ����悤�B���̃h���[�������ӂ��ꂽ�̂ł���B�������̔w��ɂ́A�������n�U�[�h�Ƃ�������u���D�I�ݕt�v�u���Z���\�v�s�ׂ��܂���ʂ��Ă����̂ł���B�x�@�������e�����܂��Ȃ���A������������ꂽ�Z��ɓ˓�����j���[�X�f���͐��E�ɏՌ���^�������A����́u���D�I�ݕt�v�u���Z���\�v�s�ׂ��ے�����f���Ƃ�������̂ł���B���̓��e�͎��̍�(�㔼)�ŏq�ׂ�B
|
| ���U�D�T�u�v���C���E���[���̑g���ߒ��Ɛ��E�ւ̊g�U
|
   �@
�@
|
|
�T�u�v���C�����Z��@��29�N���Q�ɔ䌨�����[���Ȋ�@�𐢊E�ɋy�ڂ��Ă���B���̖��̖{�����ǂ��ɂ��邩�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�ȒP�ɂł��A�����J���琢�E�ւ̊�@�̘A���̌o�܂ɂ��ĐG��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
|
��1�D�T�u�v���C�����Z��@���ǂ̃��J�j�Y��
�A�����J�ł̓J���g���[�E���C�h(Countrywide Financial Corporation)�A�E�G���Y�E�t�@�[�S�E�z�[�����Q�C�W(Wells Fargo Home Mortgage)�A���邢�͑�菤�Ƌ�s�P���̏Z����Z����Ђ���ɏZ��[���Z�����肪���Ă���B���Ă͗a��������ɗZ�����钙�~�ݕt�g��(S&L�GSavings and Loan Association)����͂ł��������A1980�N��ɏ��Ƌ�s�Ƃ̋����ɔs��A������S&L���|�Y�����B����ɑ����āA1990�N��ɂ����قǂ̏Z����Z����Ђ��䓪���Ă����̂ł���B(�ȉ���1�}�Q��)�����Z����Z����Ђ݂͑��t�����Z��[���́u�ԍό����Ɨ��q�v���A���ʖړI���Ɖ��(�����͓�����s�̎P��)4)�Ɂu���v�Ƃ��Ĕ��p����B����ɂ���ďZ����Z����Ђ́A�ݕt��(�Z��[��)���������B���ʖړI���Ɖ�Ђ͂��������Z��[������5000���قǂ܂Ƃ߁A���Z�H�w����g����MBS5)�u�Z��[���S�ۍ��v��g������B�u�،����v�ł���B�e���Ɖ�Ђ́A���̏،��ɔ��t�������u���S�ȋ��Z���i�ł���v�Ƃ������Ƃ��A�s�[�����邽�߂ɕی���Г��ɕۏؗ����āACDS6)�Ƃ������̕ی���t����B����ɂ���ɃX�^���_�[�h���v�A�[�Y�Ƃ������i�t����ЂɁu��v���āA�i�t�����Ă��炤�B�������āu���S�Ō��{���z���������ɂ킽���ĕۏ����v���Z���iⒶ���g�������B���̏��iⒶ�ɂ���ɁA��قǂƓ����悤�Ȏ�@���g���āA�����ԃ��[���A�N���W�b�g�J�[�h��[�X�Ȃǂ̍�(ABS)���g�ݍ��܂�A���Z���iⒷCDO7)���o���オ��B
���G����ɂ킽��،������i��g�����A���S�Ƃ����܂莆���Ő��E���ɔ̔����ꂽ���Z���iMBS��CDO�̒��ɁA�s�Ǎ��A�������Ⴍ�M�p�͂ɖR�����l�����̃T�u�v���C���g�����Z���i���������Ă����̂ł���B
�i�C��̈�Ƃ��đ哝�̂̊̂���Ő��i���ꂽ�u�Ƃ����Ƃ����A�����J���E�h���[���v�͑ł��ӂ���Ă����B1990�N�㔼����AIT�o�u���ɂ���Đ��E����z�����Ă������ӂ�����̃h�������́A�A�����J�̒����������ɂ��J�l�]��������A�u�ߏ藬�����v��Ԃ��Ђ��N�����Ă����B�N�ł����������Ƃ����Љ����������Ă����B�T�u�v���C��(�Ꮚ����)�A�I���g�`(���^���ׂ�[�ŏؖ��ނ��Ȃ���)�ւ݂̑��o���z�́A2004�N�ɂ�7300���h���S�ݕt�z��10���A2005�N�ɂ�1��50���h��32.2���A������2006�N�ɂ�1���h��33.6��8)�ɒB���Ă����B�S�Ă̎����Ɣ䗦��2004�N�ɂ�69���ɒB���A�u�b�V���哝�̂����āu�킪���̗��j�㍡�قǑ����̍������}�C�z�[�������������Ƃ��Ȃ��v�ƌ��킵�߂����������̂ł���B
�������T�u�v���C���E���[���̉��Ɣj�]�́A���ƂɌ��킹��u�Z��i�̏㏸��O��Ɏ��̐g�̏�ɍ���Ȃ��ߏ�ȏZ��[����g�݁A�t�C�[�m�萔���n��������ŋƖ����������Ă��܂����D�I�ݕt�s��(Predaor Lending)�v9)�̌����������̂ł��顏Z����Z����Ђ͏Z��[�����u�،����v���Ĕ��蕥���킯������A���[���̏ł��t����S�z���邱�ƂȂ��A�u�萔���v���҂����Ƃɖz������悤�ɂȂ�B�u���S�ȏ����ؖ��Ȃ��ɗZ���ɋy���̂�43�`50���A�����O�ԍς��s�����ꍇ�Ƀy�i���e�B���ۂ�����Z����70��(�v���C�����[���̏ꍇ��2���ɉ߂��Ȃ�)�A2006�N�Z�����ō��l�ƃq�X�p�j�b�N�����T�v�v���C�����[���́m�����ؖ��Ȃ��n75���Ɓm�����O�ԍσy�i���e�B�n40.7��(���l������22.2���ɉ߂��Ȃ�)�Ƃ����悤�ɁA���D�I�ȈӐ}�������ďZ��[���̃I���W�l�[�V�������s���Ă����v10)�̂ł���B�Z��i���㏸���Ă���Ԃ́A�ʂ̋��Z�@�ւŏ㏸�����Z��i��S�ۂɐV���[����g�����A�O�̃��[����ԍς���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��ł���B����ɏZ����Z����Ђ̓��[����g�݂₷�����邽�߂ɁA����2�A3�N�͒�����ł̗Z�����s�����B�u2004�`2006�N�Z�����ŁA�}���ɋ������㏸���郊�Z�b�g�����t��(7������12����)�Z����89�`93�����߂�v11)�悤�ɂȂ��Ă����Ƃ����B���[�������㏸�O�ɏZ��i�㏸�ǖʂł���A���蔲���邱�Ƃ��ł��A���p�v�邱�Ƃ��ł����ł��낤�B�������A�S�ďZ��i��2006�N���s�[�N�ɉ������n�߂�B�Ɠ����ɉ��ؗ��͋}�����Ă������B���������Z��́A�������������邱�ƂɂȂ�B���ꂪ�`���q�ׂ����e���\���Ȃ���x�@�����Z��ɓ˓�����f���ɂȂ�킯�ł���B
���������u���D�I�ݕt�v�u���Z���\�v�s�ׂ͏Z��Ɍ��������Ƃł͂Ȃ������B�A�����J�̎����ԃ��[�J�[��IT�ƏZ��o�u���i�C�̂��ƁA��^��(SUV�GSports Utility Vehicle)�̔̔��D���Ɏx�����ă��o�C�o�����A����́uGM�GGeneral Motors�̊�Ձv�Ȃǂƌ���ꂽ�B�������A�������ɍD�i�C�Ɏx����ꂽ�ʂ��������Ƃ��Ă��A���́u�����v�ɂ����́u���D�I�ݕt�v�u���Z���\�v�s�ׂ��w��ɂ�����Ă����̂ł���B���̎d�|���͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
GM�̓f�B�[���[��ʂ��Čڋq�Ɏ����Ԃ�̔�����B�ڋq�́AGM�̋��Z�q���GMAC�GGeneral Motors Acceptance Corporation�Ń��[����g�����A������x�����B�ڋq�͍�(�����ԃ��[��)�������B�ʏ�ł���Όڋq�͏����ɏ]���Č������A���N����ɂ̓��[�������ς������Ԃ����L����B�ʏ�Ȃ�A�������ė��҂̍����W�͏��ł���B�����ڋq�̃��[������GMAC�ɂƂ��Ă͏����u�ݕt�����Ɨ��q�v���L���b�V���t���[�������߂���ł���BGMAC�͂������������ԃ��[�����𑩂˂đg�������Z���i�Ɏd���Ē���(�u�،����v)�A �o���N�E�I�u�E�A�����J�ABNP�o���o��V�e�B�[���̋��Z�@�ւ�ʂ��ē����Ƃɔ������̂ł���B���̋��Z���i�ɂ������قǂ�MBS�u�Z��[���S�ۍ��v�ɑg�ݍ��܂�ACDO(���Y�S�ۏ،�)�Ƃ��Ĕ��p���ꂽ�̂ł���B���̋��Z���i�������ɔ��p����Ă��邩����AGMAC�̓��[�����������悤������܂����C�ɂ��邱�ƂȂ��A���[����g��Ōڋq�Ɏ����Ԃ葱���邱�Ƃ��ł����̂ł���B���[���̐\�����ɂ�1���O2�Z��3���N����4�Љ�ۏ�ԍ�5�E�Ƃ�5���ڂ������L�ڂ���A�N����[���̏Ȃǎx�����\�͂��������ڂ͋̂܂܂������Ƃ����B�f�B�[���[�͓�����U��Ԃ��āu�������f�B�[���[��GM�������Ŏ��������܂��Ă����̂ł��B�c���[����Ђɂ́m���q�ɂ́n�ڂ��������Ȃ��ł���A�ƌ����Ă��܂����B�c���[����g�l�̒��ɂ͋�r���W�߂ĕ�炵�Ă����l�������Ǝv���܂���B����Ȑl�ł����[���_�����߂Ă��ꂳ��������[����g�߁m�����Ԃ��n���̂ł��v12)�Ə،����Ă���B�����̃T�u�v���C�����E���Z���Q�̍��������G�s�\�[�h�ł��邪�A�Z��ɂ��Ă������Ԃɂ��Ă��A�����̂Ȃ��A���邢�͒Ⴂ�l�ɂ��M�p�n�������A���̎؋����،������A�i�t�������āu���Z���i�v��g�����A���E���ɔ��肳�����̂ł���B���ꂪ�����̃T�u�v���C�����Z��@�����E���Z���Q�ւƓ]�����邱�ƂɂȂ�킯�ł���B���Z�ƌo�ώ��̂�2�ʂɂ킽��[���ȑŌ��́A�k���n�̃A�����J���琢�E�ւƁA���̂悤�Ɋg�債�Ă������B
1�A�����J������MBS(�Z��S�ۏ،�)�ɃN���W�b�g�J�[�h�⎩���ԃ��[���Ȃǂ̗l�X��ABS(���Y�S�ۏ،�)�������E�g������A���E�Ƃ��Ƀ��[���b�p�̋��Z�@�ւɓ]������A�ݐς����B���̂��߁A�T�u�v���C���֘A����L�������������Z���i�̉��i�����A�s�Ǎ����A����ɂ͂���Ɋ֘A������|�Y�ی��Ȃǂ̋��Z�h�����i�̉��i������j�]���A���[���b�p�̋��Z�@�ւɐ[���ȑŌ���^���Ă������B���Ƃ���2007�N8���ɂ̓t�����X�̍ő���sBMP�p���o(�P���̃w�b�W�t�@���h�j�])���o�c��@�Ɋׂ�A�܂�9���ɂ̓C�M���X�̒�����s�m�[�U���E���b�N�����t���������N����������s�ً̋}�Z�����s��ꂽ�B���̌���X�C�XUBS�A�p���C�����E�o���N�E�I�u�E�X�R�b�g�����h(RBS)��h�C�c��s�ȂǁA�e���ő����Z�@�ւ̊�@�ƌ��I�~�ώ����̓����̎��Ԃ��������B�����ɁA���B�ł��A�����J�̕s���Y�o�u���ƘA������悤�ȏZ���݁A�s���Y�̓��@�I�����������Ă������A���]���͂��܂�A���Z���Q���������ꂽ�B
2���̎��k�ߒ��ŁA���B��i���̋��Z�@�ւ́A�\�A�����s��o�ςɉ�A�A���[�����������E���������ɑ݂�����ł��������������g���n�߂��B���̂��߁A����珔���̌i�C��ނ��N���ƂȂ����B
3���E�ő�̏���҂Ƃ���1990�N�㉛�ȍ~���E�i�C�̃G���W������S���Ă����A�����J�̎����̓T�u�v���C�����Z��@���_�@�ɑ啝�ɏk�������B���{�A�h�C�c�̂悤�ɗA�o�Ɍi�C���ˑ����Ă��������͂��̉e�����܂Ƃ��ɎA���E���Q�Ɋ������܂ꂽ�B
|
��2�D���E���Z���Q�̌��߂Ƃ��Ă̋��Z�H�w�u�،����v
��2������A���x���̋��Z���Q13)��̌������A�����J�ł��邪�A�T�u�v���C�����Γ_�Ƃ��������̋��Z��@�́A�A�����J�{�̂̐M�p���k�Ǝ��̌o�ςɗ^�����e���̐[���Ɛ��E�����������_�ŁA����܂ł̂��̂ƈ���Ă����B
���̍��{�ɂ�����̂́A���Z�H�w���u��g�v�����u�،������_�v���̂��̂ɂ���B�g�U�̉ߒ��͂��������ꗱ�̉������ꂽ�R�������ꍞ��ł������߁A�������ǂ��ɕ��ꍞ��ł�����������Ȃ��������߂ɁA���ׂĂ̕đ܂̃R������������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����M�p�s���̘A���ƂȂ����B���́u�،����v�̉ߒ��́A���ɇT�Ŏ��Ԃɑ����ďq�ׂ����A�����ł͂���Ɂu�،����v�𐄂��i�߂��u���Z�H�w���_�v�̌��߂𖾂炩�ɂ��悤�B���_���̂��u���D�I�ݕt�v�u���Z���\�v�Ƃ������鐫�i�������Ă����̂ł���B
�������Ɂu�،����v���ꎩ�͍̂����̃T�u�v���C�����Z��@�ɂ͂��܂������Ƃł͂Ȃ��B��ʓI�ȈӖ��Łu�،����v�Ƃ�1���Z�s��ɂ����鎑�����B�̌`�Ԃ����Z�@�֎ؓ�(�Ԑڋ��Z)����،����s(���ڋ��Z)�ɃV�t�g���邱�ƁB2�ݕt���┄�|���̂悤�ɗ��������ɂ������Y�����Y�S�ۏ،��̔��s�ɂ���ė��������邱�ƁA�������B�A�����J�̏ꍇ��҂́u�،����v��1970�N�̐��{�n���Z�@��GNMA(���{�����)�ɂ��N�����̎n�܂�Ƃ����Ă��邪�A����MBS(���Q�[�W�S�ۏ،�)�͌��������̌��I�ۏ������A�M�p�x�̍����،��ł������B����ɑ��č�����ƂȂ����u�،����v�́A������s�����ʖړI���Ɖ�Ђ����s����悤�ɂȂ����M�p�x�̒Ⴂ�T�u�v���C���E���[���A���ႢAlt�|A14)���[���A��������z�߂����W�����{�E���[����S�ۂƂ��Ĕ��s���ꂽMBS�ł���A����ɃN���W�b�g�J�[�h�A�����ԃ��[���A���[�X�ȂǗl�X��ABS(���Y�S�ۏ،�)���W���E�g�������Ƃ����u�،����v�ł���B�{���ł���ɂ߂ă��X�N�̍����،��ł���B1999�N�Ɂu�،����r�W�l�X�v�����ԊJ��15)����A���Z�H�w�̗��_�ɂ���āA�u�،����v�����ʖړI���Ɖ�Ђ�Z����Z����ЂȂǒN�ɂł��ł���悤�ɂȂ�A���X�N�̍����،����u���S�ȏ،��v�ɉ������̂ł���B���́u�،������_�v�Ƃ͎��̂悤�ȁu���_�v�ł���B
���́u���_�v���T�C�R�����g���Đ���16)���悤�B�ݖ�͈ȉ��̂Ƃ���B20�ʑ̂̃T�C�R����5000�����ɐU�������A�u1�̖ځv�������ɏo��m���͉��p�[�Z���g�ɂȂ邩�B20�ʑ̂̃T�C�R���Ƃ݂͑��|�ꗦ��20����1(5%)��\���A5000�̃T�C�R���͏W�����ꂽ�Z��[����5000���[�����邱�Ƃ��Ӗ�����B�u1�̖ځv�͉���s�\�ɂȂ�Z��[����\�����Ă���B�v�Z����Ɓu1�̖ځv��10�����ɏo��m����100%�A200�����ɏo��m����99.96%�A250�����ɂł�m����50.65%�A������300�����ɏo��m����0.11%�A�ƂȂ�B��������u1�̖ځv�Ƃ��Ă���킳�ꂽ300�܂ł̏Z��[����BB(���G�N�C�e�B�[)��������AA(�ǁ����U�j�A��)�Ƃ��ċ�ʂ��ĕ����߁A����͂���Ńn�C���X�N�E�n�C���^�[����MBS�Ƃ��Ĕ���B�����ȊO��AAA(�D�ǁ��V�j�A)��MBS�Ƃ��Ĕ���B���ꂪ���Z�H�w�́u�،������_�v�ł���B�،����������ɂ���ă}�j���A��������PC�\�t�g�ƂȂ�A����܂ŃJ���ƌo���ɗ����Ă����Z��[���̃��X�N�Ǘ����N�ɂł��ł���悤�ɂȂ����B����ɂ���đ�ʂ̏،������Z���i�����݂�����A���E���ɔ̔�����g�U���Ă������̂ł���B���́u�،����v���������̃A�����J�E�T�u�v���C�����Z��@���A����܂ł̋��Z���Q(70�A74�A82�A84�A87/89)�ƈ���Ă���_�ł���B���Z�H�w���u���\�I�ݕt�v���\�ɂ��A�A�����J�̋��Z���i�𐢊E���i�Ɏd���ďグ�邱�Ƃ��ł����u�d�|�����閧�v�������ɂ���B
�����������̉ؗ�Ȃ���Z�H�w�̐����ɂ�2�̌�����O�g�ݍ��܂�Ă���B���̈��20�ʑ̂̃T�C�R���������u�݂��|�ꗦ5�p�[�Z���g�v�ł���A�������300�܂ł̃��[�����ǂ������BB�AAA�ɒ��a�E���ʂ�����̂��A�ł���B�O�҂̒��|���͂���܂ł̌o�����Ɋ�Â�����o���ꂽ�����ł����ĕs�ϐ��ł͂Ȃ��B��҂͂��łɎw�E�����悤�ɁAAlt�|A��T�u�v���C���E���[���͏����ؖ��Ȃǂ���o�s�\���邢�͕ԍϔ\�͂̂Ȃ��l�ւ̃��[���ł������BAA��BB�ɕ����߂悤�Ƃ��Ă��A�����������̃f�[�^���Ȃ��̂ł���B�܂������u���D�I�ȈӐ}�������ďZ��[���̃I���W�l�[�V�������s���Ă����v17)�̂ł���B |
| ���V�D�R���C���t���~�σ��J�j�Y���̋@�\�s�S�Ƃ��Ă̐��E���Z���Q
|
   �@
�@
|
��1�D���(��)���̐����̒~�ϗl���̋@�\�s�S
�ł͂Ȃ��A�����J�͋��Z�H�w����g���Ă܂ŁA���������u���Z�I���\�v�s�ׂ�Ƃ��˂Ȃ�Ȃ������̂ł��낤���B��4�}�������������������B�����ɂ�1950�N�ȍ~�̐�i���{��`���́u�����v(GDP�x�[�X��2���Y��)�̋O�Ղ��`����Ă���B10�N���ƂɔN��ʂɌ����1960�N��7.2%�E70�N��3.5%�E80�N��2.2%�E90�N��2%�A������2000�N��͍����̐��E���Z���Q�̉e�����܂Ƃ��Ɏ}�C�i�X0.4%�̐����ł������B��܂��Ɍ��Ă��O���t�̌X���������悤�ɁA20�N�̃X�p���Ő���������ɒ�ؕς���Ă������l�q���f����B��������1990�N��2000�N��̐�i�����̒�̒��ŁA�A�����J�̉E���オ��̐����ƃh�C�c��2000�N��̐�������тʂ��Ă���B���ꂪ��i��(�f7)�̕��ϐ������������グ�Ă���̂ł��邪�A�����2���̐����́A����v���Ƃ��Ă����̂ł��낤���B�A�����J�̐����́A���ɏq�ׂ��悤��IT�ƏZ��Ƃ���2�̃o�u������������������ł���A�h�C�c�̐�����1990�N��ȍ~���{��`���E�ɕ��A���s�ꉻ�������E���������ւ̗A�o�Ɠ����ɂ����̂ł���B�����A�h�C�c�̗A�o�ˑ��x���A2001�N30%�E2003�N36%�E2008�N47%�ƐL�тĂ���̂ɑ��āA�l����x�o�̑�GDP���2003�N59%�E2008�N57%�Ƃ��̊����������Ă���B�h�C�c�̐������A�����̏���Ɏx����ꂽ�����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B�A�����J��h�C�c�̐����́A����������\���n���ߒ�(�A�����J���̐�����)�ł́A�o�u����O�����̂���Γ���v���Ɏx�����Ă̐����������킯�ŁA���������������ΐ�i��(G7)�́u����ꂽ20�N�v�Ƃ�����̒��ɂ���Ƃ����悤�B
���́u����ꂽ20�N�v�́u20���I�����E�I�s���v18)�Ƃ������邪�A20���I������21���I�����ɂ����Ă̐�i���̒�͂ǂ����ċN���Ă���̂ł��낤���B�����1970�N�㔼�Έȍ~�A���j���悷��o�������n�܂��Ă�������ł���A�u����ꂽ20�N�v�͂��̋A���ł�����B�G���W�j�A�����O�E�v���X�e�B�b�N�ɑ�\�����悤�ȑf��(�J���Ώ�)�v���ƃ}�C�N���R���s���[�^�ɑ�\�����J����i�Ɋv�����N�����B�Ƃ�킯��҂́u�V���R���̏��Ёv�́A�W�ϓx���グ��ɘA��āA���i���̂Ɛ��Y�ߒ����}�C�N���G���N�g���j�N�X�����A���ɂ̓p�[�\�i���E�R���s���[�^�[�̃l�b�g���[�N���A�C���^�[�l�b�g�ւƐ����𐋂����B���̂킸�����~���p�̃V���R���`�b�v�̏��́A�A�W�A�l�̒�������f���ȘJ���͂ƌ������A�A�W�A���ނȂ������͂Ƌ����͂����u���E�̍H��v�ւƉ����グ�čs�����B���̐��̌R���E�����I�K�v����A�C���t���[�V����(�h���U�z)�ɂ̂��Đ��܂�o���A�W�A�̍H�Ɛ��Y�͂͂��̃C���t���[�V�������f�t���[�V�����ɂ����Ă��܂��قǂ̔����I�ȍH�Ɛ��i�̋����͂����������B�u���\100�{�E���i100����1�v�Ƃ����V���R���`�b�v�̖{���́A����ɂ���ĎY�ݏo���ꂽ�H�Ɛ��i�ɂ����ڂ�A��i�H�ƍ��̍H�Ɛ��Y�͂��u���v�����A���i�ƌٗp�j��Ƃ������E�s��v����20���I���ɂ����炵���B��i���{��`��20�N�ɂ킽��u��v�̔w�i�ɂ́A�n�����j�������I�Ȑ��Y�͔��W������̂ł���A�����Ă��̐��Y�͂́u�������Ƃ̘g�g�݁v�����A���O�i���������E��̐��Y�͂ƌ�����B
�u�A�W�A�H�ꉻ�v�A�����E�C���h�Ȃǂ̐V���H�ƍ��̋}�����Ƌ��ɐ�i�����̐��Y�͂͑�3�}�Ɍ�����悤�ɁuGDP(����)�M���b�v�v�ƂȂ��ĕ\��Ă���B���n��I��1990�N��ȍ~���v�s���E�ݔ��ߏ��Ԃ������Ă���B����������u����ꂽ20�N�v�́A�ߏ萶�Y���Q�Ƃ�������̂ł���A�����ɍ����T�u�v���C�����E���Z���Q�́A���̉ߏ�����Ă̂悤�ɋ��Q�ɂ���Ė\�͓I�ɔj��ł����ɁA���Z���{�́u��肭��v�ɂ���āA�摗�艄�����悤�Ƃ��������Ƃ�������̂ł���B
|
��2�D�T�u�v���C�����E���Z���Q�̗��j�I�Ӗ��ƈʒu
�ł̓T�u�v���C�����E���Z���Q�̌����Ɨ��j�I�Ӗ��͉��Ȃ̂��B�����̃T�u�v���C�����Z��@�ɒ[�������E���Z���Q�́A��㐢�E���{��`�̕ϗe�̓]���̎n�܂�������A�����E�u�~�σ��J�j�Y���v�̋@�\�s�S�̕\��ł͂Ȃ��̂��B�܂����̓_�����Ă݂悤�B����ɂ�19���I��20���I�����A�����́u�\���I�s���v�ɋꂵ��ł����ق�1���I�O�̐��E�̎p���Q�l�ɂȂ�B
���C�D���R�����V�X�e���̋@�\�s�S�ƓƐ�̌`��
�u�����甼���I�O�Ƀ}���N�X���w���{�_�x������������ɂ́A���R�����͈��|�I�����̌o�ϊw�҂ɂƂ��Ắw���R�@���x�Ǝv���Ă����B�}���N�X�́A���{��`�̗��_�I����ї��j�I���͂ɂ���āA���R�����͐��Y�̏W�ς݂����A�����Ă��̏W�ς͈��̔��W�i�K�œƐ�ɓ������Ƃ��ؖ��������A�c����Ɛ�͎����ƂȂ����v19)�B1873�N���Q���N�_�Ƃ�1896�N�܂ł�23�N�ԁA���[���b�p�͒����́u�\���I�s���v(Ernst Wagemann)�̒��ɂ����B���R�������J�j�Y���͋@�\�s�S���N�����Ă����B���{��`�̓J���e����g���X�g�Ƃ����V�����@�\�E�@�\��҂ݏo���A�Ɛ藘�����m�ۂ��邱�Ƃɂ���āA���́u�\���I�s���v���������̂ł���B���{��`�͎��R�����i�K�̌Â����{��`����A�Ɛ莑�{��`�Ƃ����V�����i�K�̎��{��`�֑J�ڂ����B
���R�����i�K�̎��{��`�ɂ����閵��(�ߏ萶�Y)�̉�����i�Ƃ��Ă̋��Q�̋@�\�͖�Ⴢ��A�����̉������푈�Ƃ��������I�E�o�ϊO�I��i�Ɉς˂�ꂴ������Ȃ��Ȃ����B19���I���́u�鍑��`�I���g�v�ƌĂ��R�g�i�C(1896-1913�N)�ȍ~�A���{��`�o�ς̏������́A�����I���Q�̔����ɂ���Čo�ϓI�ɉ��������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ȃ�A�����͉s�������I�����ɓ]�����A���E�s��ɂ����鏔�̑R�E�鍑��`�푈�ɂ��\�͓I�����Ɉς˂��Ă����B���̉����̂��߂ɁA���Ƃ̌o�ωߒ��ւ̑S�ʓI�ȉ���͕s���ƂȂ�A�Ɛ莑�{��`�́A���ƂƗZ���E����������Ȃ��Ȃ�A���I�Ȍo�ςւ̉��(�J���e���E�g���X�g�E�R���c�F����)�͍��Ƃ��������Ɛ�A����(�Ɛ�)���{��`�ւƋ}���ɕϗe���Ă������ƂɂȂ�B���̍ŏ��̉ߒ��͒鍑��`���̑��͐�ł����1�����E�������Ă̐펞�o�ϑ̐��̍\�z�ł��������A1929�N�勰�Q�Ƃ���ɑ���30�N���s���̉ߒ��ŁA����(�Ɛ�)���{��`�́A���{�E�J���E�ʉݓ������Ƃ̐����I�Ǘ����ɂ����A���{��`�̂���Ί�@�Ǘ��E�펞�̐��Ƃ��čP�퉻���Ă����B���̉ߒ��̓A�����J�̃j���[�E�f�B�[������i�`�X�E�h�C�c�̂悤�ȓO�ꂵ���R�����Ɖ��܂ŁA���܂��܂Ȍ`���Ƃ��ēW�J���ꂽ�B
�i�`�X�E�h�C�c�̏ꍇ�ɂ́A���������`���̓����ɂ�鎸�Ƒ��A�E�g�o�[��(�������H��)���݂Ȃǂ̑�K�͌������Ƃ̓W�J�A����ɂ͋ߗ����ւ̌R���i���E�N���ɂ��A��(���Ǝ҂̋z��)�Ȃǂ��}��ꂽ�B���̌��ʃh�C�c��1937�N�ɂ͂قڊ��S�ٗp��B�������B1930�N��̃h�C�c�́u�o�ϊ�ցv�́A������̃A�����J�A�C�M���X�̋��Q����̒E�o�A�������ɖ��ł����������ɒ��ڂ��ꂽ�B���{�����A�W�A�ւ̐N���E�A���n�A���D�ɂ���ċ��Q����̒E�o��ڎw�����̂ł���B
�h�C�c�Ɠ��l1929�N����1933�N�ɂ����čł����������Q�Ɍ�����ꂽ�A�����J�ł́A�h�C�c���i�`�Y���̂��ƂŊ��S�ٗp�𐬂������Ă������̂ɑ��A�j���[�E�f�B�[���J�n�N��1933�N�ł�1300���l25���̎��Ǝ҂�����āA���Q����E�o�ł����ɋꂵ��ł����B���ǃA�����J��1941�N�́u����ݗ^�@�v�ɏے������o�ς̌R�����ɂ���āA�͂��߂ċ��Q����E�o(1943�N���S�ٗp�̒B��)���邱�Ƃ��ł����̂ł���B
���Q��̍������܂��Ȃ����߂Ɋe�����{�͌��������������]�V�Ȃ�����邱�ƂɂȂ�B�Ƃ�킯�h�C�c�A���{�A�C�^���A�Ȃǂ̌㔭�����́A�����ς獑�ƍ����̐Ԏ��̂����ɑ�K�͌��������A�R���g�[����]�V�Ȃ����ꂽ�B�������������Ԏ����ŏI�I�ɉ������邽�߂ɁA�ٖ����ɑ��鋭���J������Y�̖v���A�A���n���D���s�Ȃ�ꂽ�B���̂��߂̐A���n�͕K�v�s�������A�n����̐A���n�͊��ɕ������������Ă�������A�ƁE���E�ɂ̏����͂��łɗ̗L����Ă���A���n��D�����āE�ĕ����̂��߂̐푈�ɓ˓����Ă������̂ł���B�����܂ł��Ȃ���2�����E���ł���B�������ċ��Q�Ƃ����o�ϖ��͐������R���̖��ւƓ]�����A���[�j�������j�����悤�ɁA���{��`�̖����̔������S�@�\�k���́A���Q����푈�ւƈڂ����̂ł���B
�u�\���I�s���v�u�����v�̋@�\�s�S�ւ̑Ή��E�Ɛ莑�{��`�ւ̕ϐg�̌��ʂ́A2�x�ɂ킽�鐢�E�푈�������킯�ł���B���E�̎S�邽��L�l�ɁA���ׂ����t�͂Ȃ��B��u�����������Ɍ�����i�`�X�E�h�C�c�̑Ή������A�s�펞���c����3872�����C�q�X�}���N�AGDP��6.5�{�ɒB���Ă����B
�����D���{��`�̐��ێ��̂��߂̌R���C���t���[�V�����I�~��(����)�̐��̋@�\�s�S
�鍑��`�̐��E�����x�z�E�A���n�̐��͊�{�I�ɂ͉�̂����B�����A��2�����E���I�����@�ɁA���E�͎��{��`�̐��Ɓu�Љ��`�v�̐��̓�̑̐��ɕ��Ă����B�A�����J�ƃ\�A�݂͌��ɑ���������z�G���Ƃ��A��ɕă\�S�ʐ푈�ւ̊댯�����������u�V���Ȏ�ނ̐푈�v���n�܂����B�u�O���[�o���ȊK�������v�̌n�̎n�܂�ł���B�A�����J�̓A�C�[���n���[���������낪����قǂ̍��Ǝ������R�Y�w�����̂Ƃ����R���Y�Ƃɂ����݁A���ۓI�ɂ͌R���E�o�ω������p���������̂ł���B�A�����J�͂���ȍ~���I�ɂ킽���āA2�x�̑��ł����W�߂��x�������Ƃ��āA���E���Ƀh�����U�z�����B����ɂ���Ă��Ă̗͕������Ƃ��A�Ƃ�킯�h�C�c�Ɠ��{�́A���ꂼ��u���C���̊�Ձv�u���x�����v�ƌĂ��u�����v���Ƃ����̂ł���B���ꂪ��4�}�Ɍf����1970�N��܂ł̐����A�O���t�̋O�Ղł���B
�h���͐��E���ɁA�Ƃ��Ƀ��[���b�p�ɑ͐ς��Ă������B�C���t���[�V�����͕K���ł���B���ł�1958�N�̍��ێ��x�̈���(1958�N12��8600���h���̐��3�x�ڂ̌o����x�Ԏ�)�ŕ\�ʉ������h����@�́A�����̑��ʓI�ȃh���h�q��ɂ�������炸���݉����A��{�I�ɂ͍�������Ȃ������B�������A�A�����J��1950�A60�N��A����ȍ~���ǒn�푈�ɓ������Ƃ��ĎQ�킵�Ă����B�h���͐��E���ɗ��܂��Ă������B���ɃA�����J��1971�N8��15�����h��������~�\�����̂ł���B���̃h���V���b�N�A���ےʉݕs���ɂ���āA�܂����B�e���͊O���ב֎s���������B���̌��i�e���͈בւ̕ϓ��ɋ��͂������a�m���聁�X�~�\�j�A���̐����ւāA�u���S�ϓ����ꐧ�v(IMF��GATT�̐��̉�̊J�n)�ւƈڍs�����B�A�����J�E�h���𒆐S�Ƃ������[���E�J�����V�[�̎s�ꂾ���ł��A���̋K�͂́A1970�N��1130���h���A10�N���1980�N�ɂ�13.5�{��1��5250���h���A1990�N�ɂ�4��9386���h��20)�ցA�����2000�N9��21)�ɂ�11���h���Ɩc��B���݂ł͂��̋K�͂�K���ɑ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ɒB���Ă���B���݂ł́u���E�̃h���ۗL���́w���K�łȂ������x�ɒB���v22)�Ă���A�ƃ{���J�[��FRB�c���͌x�����Ă���B���̑���͗e�Ղł͂Ȃ����AISDA�ɂ��ACDS�A���q�f���o�e�B�u�A�G�N�C�e�B�[�f���o�e�B�u�̑z�茳�{(Notional amount)��2009�N���ɂ�426.8���h��23)�ɒB���Ă���A�Ƃ����B���̐��\�z�A�Љ��`�̐��������߂̃R���g�[���[���[(�R���o�ω����ƒ��ړ���)�������h���́A���h��������~�ɂ���āA���Ε��̑̐���̂̃E�C���X�ɓ]�������B���E���ɑ͐ς����h���͗L���ȓ���������߂Đ��E����p�j���邱�ƂɂȂ����̂ł���B
|
| ���W�D�܂Ƃ�
|
   �@
�@
|
�A�����J���T�u�v���C�����Z��@�̐��E���Z���Q�ւ̓]�������������Ƃ��āA��i���{��`�����̒�A�ߏ萶�Y���Q�͒N�̖ڂɂ���������̂ƂȂ����B�A�����J��G20(2009�N9��)�Łu�č����݂̏���͎~�߂悤�v�ƌĂт����A�u���E�o�ς̃G���W�������~�肽���v24)�ƕ\�������B20���I����s���E�ߏ萶�Y���Q�́A��2�����E����̐��E���{��`�̒~�σ��J�j�Y���̋@�\�s�S�̕\��ł���ƂƂ��ɁA1���I�O�E19���I���u�\���I�s���v�ɗޔ�ł��鎖�ԂȂ̂ł͂Ȃ����B1���I�O�ɂ͎��{��`�͐V�����i�K���Ɛ�i�K�ւƒʘH���J�����B�������̌����͐��E�푈�������ɂ��Ă��A�ł��邪�B�������������{��`�͐V�����X�e�[�W�ւ̌��ʂ��������Ă��ʂ܂܂ł���B
20���I����s���̍ŏ��̒���A1970�N��̃X�^�O�t���[�V�������A���~�ϗl���E�u�����v�̋@�\�s�S�̔��ǂł͂Ȃ����A�Ƌ^�����̂̓t�����X�̌o�ϊw�҂����������B���m�̂Ƃ���A���x�[���E�|���C�G�𒆐S�Ƃ������M�����V�I��(����)�w�h�̌����ҒB�ł���B�����ł̓��M�����V�I�����_��S�ʓI�Ɏ��グ��킯�ɂ͂䂩�Ȃ����A�O���|�o���[�[�V�����A���Ȃ킿�u�����o�ρv�u�ꍑ�Đ��Y�\���v�̗n����ނ炪�ǂ��l�������A�ɍi���Č��Ă݂悤�B���M�����V�I���w�h�́A���̂悤�ɍl�����B�X�^�O�t���[�V�����ȑO�́u�������v����̎��{��`�́A�N���|�Y�h�ȍ����o�ς̘g�g�݂̒��ŁA�J���g���̒c�����E�c�̌�����w�i�ɂ��č������グ���������A���ꂪ����(�l����)���g�債�A���{�E��Ƃ̐��Y�g���U�����A�ꍑ�̌o�ϐ����𑣂����B���Ȃ킿�k�J���҂̏����㏸�����{�̐�����~�ρl�Ƃ����������������A�o�ς͍D�z���`�������B�����������͐Z�����̂悤�ɂȂ����B�u�q�g�E���m�E�J�l�v����������O���[�o���o�ς̘g�g�݂̒��ł́A�J���҂̍������������㏸�͋t�ɍ��ۋ����͂�j�Q���鍂�R�X�g�v���ɓ]������B1970�N��̃X�^�O�t���[�V�����̕a����ނ�͂����������A�V���Ȓ~�ϗl��(�{���{�C�Y���E�g���e�B�Y���c)��͍������B�������A�ނ�͗Տ���E�����Ƃł͂Ȃ������B
�����ɗՏ���E�����ƂƂ��ēo�ꂵ�Ă����̂��A�������E�T�b�`���[�E���[�K����ł���B�����ƂɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ƃ́A�a���̌�����葦�����̂��鐭���ł��o�����Ƃł���B���ꂼ��̍��̌o�ς̋@�\�s�S�ɑ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o�ϒ�Ɛ[���ȘJ�����c�̉Q���ɂ������C�M���X�ł́A���Ԃ��[���ő҂����Ȃ��ł������B�u�p���a�v�Ƃ������a������A1976�N�ɂ͍�����@�Ɋׂ�AIMF�ɋ~�ς����߂˂Ȃ�ʂقǁu�a��v�͈������Ă����B���̕a�C�̎厡��Ƃ��ēo�ꂵ���̂��T�b�`���[�ł���B�u�\�A�E�Љ��`�v�̐��ɑR���邽�߂ɁA�u��肩��������܂Łv�́u�����Љ�v��ێ�E�J���}��2�吭�}���̒��Ŗڎw���Ƃ����u���R���Z���T�X�v���T�b�`���[�͑Ŕj�����̂ł���B
�A�����J�����l�������B�j�N�\�����ł��o�����u�V�o�ϐ���v(1971�N)������t�����A���̌�̃C���t���[�V�����Ŏ��������������}�C�i�X���L�^���鎖�ԂɁA�{���J�[�͒Z��������20���߂��Ɉ����グ����Z�������߂̍r�Î�(1979�N)�Œ��킵���B�����Ă��Ƀ��[�K���́u�����ĖL���ȃA�����J�v���X���[�K���ɁA�\���d�H���������R�����g�傷�����ŁA�Љ���x�o��}�����A���K���ɘa�Ƒ啝�Ȍ��ł��s���Ȃǁu���[�K�����v�v�����s�����̂ł���B
�P�C���Y��`�I�������Z����͐V���R��`�I�}�l�^���Y������ւƓ]�����ꂽ�B�������āu���{�̎��s�̍����v��1979�N�C�M���X�E�T�b�`���[�����A1981�N�A�����J�E���[�K�������A��82�N�̓��{�E���]�������Ƃ����ێ�F�̋��������̒a���ƂȂ����B�ʂȕ�������ł��邪�A�����ł́u�Љ��`�v�o�ό��݂Ƃ������{�̎��s���A�u�s��o�ρv�����ė��Ē������Ƃ������������u���v�E�J���v(1978�N)��ł��o�����B
���̗���́A�P�C���Y�́u�ݕ��͎��̌o�ςɉe�����y�ڂ��Ȃ��v�Ƃ����l����ے肵�A�Љ�o�ϒ����Ǝ��R�������������s��o�ςɂ����Ă͊��S�ٗp�ύt�����������������J�j�Y���������B�����ėǂ����̂���������Ύ��v�͑��傷��A�Ƃ����l�����������B���̂��߂Ɋ�Ƃ͋����͂̋����ɓw�߂˂Ȃ炸�A���{�͓K�����ŁE�Љ�ۏ�̈��k�E�K���̊ɘa�P�p�Ȃǂ�i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ�����̂ł������B���{�̌o�ω�����ŏ����ɗ}���A�o�ς��s��ɔC���ċ����𑣐i���邱�Ƃ������A�����̌����I�z���ƎЉ�I�x�̑���A���Ȃ킿�o�ϐ�������������őP�̕��@�ł���Ƃ����u�s�ꌴ����`�v�ł���B
�������u�����Ă������̂��������悤�v�Ƃ��Ă��A��i���{��`���͍��ۋ����͂������ł͉ł��Ȃ������B��i���{��`���̌ʎ��{�E��Ƃ͍��ۋ����͂������邽�߂ɁA���������{�����Ɏ����Ȃ����Ƃ��K�{�����ɂȂ����B���̊�Ƃ̐����c���́A��i�����́u�Y�Ƃ̋��v�u�ٗp�̑r���v�ɋA������B��i�����ł͐��Y�͐��藧�����ݔ��ߏ�����������܂܁A�L�����v�������o���Ȃ��ł���B���̉ߏ�͌ٗp�j��A���ƂƂȂ��ĕ\��ꍑ�����ꂵ�߂Ă���B���ɃA�����J�ł͍����̐����͗A���i�ɗ��炴��Ȃ��Ȃ��Ă���A���ێ��x�̖f�ՐԎ����ςݏオ���Ă������B�����̃T�u�v���C�����E���Z���Q�͂����������ێ��x�̃o�����X�����Ƃ���肭�肵�悤�Ƃ��Ďd�|����ꂽ�A�����J�̎藧�ā����Z�I�Ώ��̔j�]�ł���B�L�̂Ɍ����A��i�������r�㍑�̋ꊾ�J���ɐ��Y���䂾�˂���Ȃ��Ȃ��Ă���A���̘J���̉ʎ������Z����ɂ���ė��D���A����悭�Ώ�O�����͂˂悤�Ƃ����p��̌����ł���B����͂܂��A���悻20�N�ԋ߂��ɂ킽��E�H�[���X�E���Z���{�Ɉˑ������u���Z�����v�A�����J�Ƃ��̒ǐ��҂����i���̍s���l�܂�ł���B
19���I�܂ł̎��R�����̎���A20���I�O���̒鍑��`(���E���ƓƐ�)�̎���A20���I�㔼�̗��\��(�̐��Ɛ�)�̎���Ƃ������{��`�̐��U�̕��݂��猩�āA20���I�S�̂���ߏグ�A���E���ƁE�̐��Ɛςݏオ��L�������u�Ɛ�v���@�\�s�S�Ɋׂ��Ă���B�����Ɏ��I�Ɏn�܂����Ɛ肪���Ƃ��������݁A���E����������Őςݏグ�����E�Ґ��x�z�̍\�}�����ꂩ�����Ă���B�����̂̐��i�A�u���\100�{���i100����1�v���ے�����悤�ɁA�Z�p�Ɛ�ɂ��ƂÂ��Ɛ藘���̈���I�m�ۂ�����Ȃ��Ă���B20���I����ߏグ���u�K���Ɠ����v�E�u�Ɛ�v�̋@�\�s�S��H���~�߂悤�Ƃ����藧�Ă��A�����J�́u���Z�ɂ�郊�J�o���[�v���Z���v�����������A���ꂪ�s���l�����A�Ƃ����킯�ł���B����͂܂��A��2�����E����̗��R�̎�i�Ƃ��Ă̐��E�P�C���Y����̔j�]�E�R���C���t���~�ϋ@�\�̋@�\�s�S�ł�����B
����������ɂ��Ă������B�m�[�x���o�ϊw�܂���܂����u�ؗ�Ȃ���Z�H�w���_�v�Ƃ��̗��_�����H�������s�E�،��E������ЁA�����Ă�����M�p�����l�X�ɁA�ł���B�u���̌�����v�Ƃ������̂�����B�L���X�g(��)�̈Ќ������܂˂����E�ɍL�߂邽�߂̂��̂ŁA�����ŏ��藧�Ă��Ă���B�����E�ߐ��̐l�X�͂���ɕ��������B����������ƁA���Z�H�w���_�Ƒ���Z�@�ւ̑s��Ȓ����w�r���́A�s�ꌴ����`�Ƃ����@���́A����ɂ�݂��������u���̌�����v�����m��Ȃ��B
|
1) 2002�N6��17���̃u�b�V���哝�̂̈ӌ��\���B
2) 2004�N6��9���A�Z��E�s�s�J����(HUD)�̓}�C�m���e�B�[���������⏕���x�𒌂Ƃ����̍�����\����(�u���o���Z�V���v2004�N6��9���A9�y�[�W)�B
3) �ăE�H�[���X�g���[�g�E�W���[�i���ҏW���|�[���E�X�^�C�K�[(�u���o�Y�ƐV���v2002�N10��30���A32�y�[�W)�B
4) Gramm�|Leach�|Bliley Act(�O�����E���[�`�E�u���C���[�@)���A1999�N11���ɐ��������B����ɂ��ABanking Act of 1933(1933�N��s�@�A�ʏ̃O���X�E�X�e�B�[�K���@)�̋�s�Ə،��̊_����66�N�Ԃ�ɓP�p����A��s�A�،��A�ی��̑��ݎQ�������i����邱�ƂɂȂ�A���̌��ʂ�����u�،����r�W�l�X�v�����R������邱�ƂɂȂ����B
5) MBS�Ƃ�Mortgage-Backed Securities�̗��ŁA�Z��[���S�ۏ،��B�،��w���҂͏Z��[������̖����̌����ԍςɑΉ����闘���ƌ��{�̏��҂ɉ�����(�z��)������邱�Ƃ��ł���B
6) CDS�Ƃ�Credit Default Swap�̗��ŁA��Ɠ|�Y����s���s�̍ہA����ۏE�����肷��d�g�݂ŁA�Z������Ȃǂ̃f�t�H���g(�ŕt��)�ɑ���ی��̂悤�Ȃ��́B���ꎩ�̂����Z���iCDS(���j�]�ۏ؏،�)�Ƃ��Ĕ��������B����ɂ���āA�ۏ��Ăق���(�S�ۂƂȂ�)���������Ȃ��҂��A�ۏ���������悤�ɂȂ�A�������s���s���N����Τ�킸���ȕی����̎x�����Ť�傫�Ȍ��{����\�������܂�顂��Ƃ���A�Ђ̍�100���h���̕ۏؗ�(CDS)�����N1���Ƃ���ƁA1���h���̕ۏؗ������l�ͤA�Ђ��|�Y������100���h������ɓ���邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����d�g�݂ł���BAIG�͂�������CDS�̍ŏI������ł������B
7) CDO�Ƃ�Collateralized Debt Obligation�̗��Ŏ��Y�S�ۏ،��B�Ѝ�ݏo��(���[��)�Ȃǂ���\������鎑�Y��S��(Collateralized)�Ƃ��Ĕ��s����鎑�Y�S�ۏ،�(ABS�GAsset Backed Security)�̈��B�}���ł�Ⓑ�B
8) ����O�v�u�č��Z��[���s��̌���Ɖۑ�A�����Ɛ���ƏZ����Z�A�Z��l�̕]���Ɗ��p���l����v�B
9) �O�f�_���A69�y�[�W�B���D�I�ݕt�s�ׂ�2003�N�����瑽�����Ă����A�Ƃ����B�m�@�n���̕����͈��p�җO��̑}��(�ȉ�����)�B
10)�O�f�_���A74�y�[�W�B
11)�O�f�_���A75�y�[�W�B
12)�uNHK�X�y�V�����A�A�����J�����E�����Ԋ�@�v(2009�N2��2�����f)�B�u2000�N�Ƀg�b�v�ɏA�������`���[�h�E���S�i�[�͋��Z�q���GMAC�Ɋ��H�����߂�B�����ԃ��[�X��ی��A�J�[�h�A�Z��[���c�c�BGMAC�Ɏ����ԃ��[����Јȏ�̊��҂��������B2000�N�AGMAC�̊i�t���͐e��Ђ�GM����ɂȂ����B�����Ԏ��Ƃ�04�N����Ԏ��BGMAC�̍����v���A�����Z�̒��K�����킹���B�]�@��05�N�t�B�K�\�������ŔR��̈���GM�Ԃ̔̔��s�U����i�Ɛ[�����B���Z�����U���Ȃ��Ȃ��B�cGMAC���M�p�͂̒Ⴂ�l(�T�u�v���C��)�w�ւ݂̑��o���𑝂₵�A��Ȃ�����n���Ă����B08�N�āA�L�̓f�B�[���[���݂��|��}���Ŕj�]�B9���̃��[�}���E�V���b�N��GMAC�������J��ɋ������B�cGM�͈ꎞ���L���k2009�N7��10���l����A���{�Ǘ����ł̕����E�Đ��ߒ��ɓ������v
13)��4�}�ɉ��M�������A���A�����J�̋��Z���Q�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B�u�A�����J�ɂ��Č���A1966�N�ɐM�p�N���������A70�N�A74�N�A82�N�ɂ͂��ꂼ����Z���Q�������������A84�N�ɂ͑勰�Q�ȗ��̗a����t�����������N�������B�c1987�N����89�N�ɂ����Ė��N200�s�����鏤�Ƌ�s���|�Y���A90�N�O��ɂ͓|�Y�̉\������Ƃ�������s��1000�s�����v
14)Alternative A-paper�̗��BA-paper�͈���������M�p�x�̍����������ۏ؏��B
15)��4�Q�ƁB
16)���̃p���O���t�̉���̘_�|�́A2009�N9��17�����f��NHK�u�}�l�[���{��`(4)�V�˒B������o�����g�֒f�̉ʎ��h���Z�H�w�v�ɉ��������̂ł���B�����ł͔ԑg���̑O����������̂܂܂ɂ��āA�ǎ��������ʂ��L�q���Ă���B
17)�O�f�A���_��75�y�[�W�B
18)�u�w20���I�����E�I�s���x�Ƃ����ꍇ�A�����1980-82�N�̐��E�����s��������w���̂��A���邢��1990�N�Ȃ���91�N����̊e��(���ɐ����[���b�p�E���{)�̐��E�I�s�ϓ��s���݂̂��w���̂��́A�_�҂ɂ���Ĉӌ��̈قȂ�v�Ƃ���ł���B
19)���F�E�C�E���[�j���A������T�w�鍑��`�_�x
20)���{��s�w�O���o�ϓ��v�N��x(���{��s�A1994�N)425�ŁB
21)���ی��ϋ�s(BIS)���ƁA���ۋ�s�Ǝs��̋K�͂́A2000�N9�����A���ۍ����z11��4094���h���A���ۍ����z11��1509���h���ŋ�s�ԍėa���������l�b�g���z�ł�5��5714���h���ƂȂ��Ă���B����͎�v���[���b�p�����A�A�����J�A�J�i�_�A���{���݂̋�s�ƃI�t�V���A�E�Z���^�[���݂̋�s�̊O���A�����ʉ��̍��ۍ��A���̐��v�ł���A����܂ł̃��[���E�J�����V�[�s��̐��v���Ώ۔͈͂��g�傳��Ă���B
22)�u���C�^�[(�C���^�[�l�b�g��)�v2009�N12��10��
23)ISDA Publishes Year-End 2009 Market Survey Results�AInternational Swaps and Derivatives Association�A Inc�@Home Page(2010�N7��13��)�B2010�N7��2��(��)�ߌ�10�����f��NHK�u�_��ꂽ���A�M���V�����E���E�ւ̏Ռ��v�́A���E�̃}�l�[��7���~(700���h���F1�h����100�~���Z)�Ɠ`�����B
24)�u�����V���v2009�N9��27���A����2�y�[�W�B
�@ |
| �����݂̌o�Ϗ�͏��a���Q�O��Ɏ��Ă����@2011/2 |
   �@
�@
|
���j�͌J��Ԃ��ƌ����Ă��邪�A�吳�Ə��a�����ɋN�������ƂƁA����Ƃ����ʓ_�������B���j����������w��ł�����A�o�u���Ƃ��̕���ɂ��o�ς̍���������邱�Ƃ��ł����̂ɂƂ����v����������������B
�o�u���ƌĂ��o�Ϗ��1989�N���ȊO�ɑ吳����ɂ��������B���̃o�u����������A�����f�t���̎��オ����A���̕s���̐^�������ɐ��{�ُ͋k�������s���āA���a���Q�Ɋׂ������Ƃ͗L���ł���B���݂̃}�X�R�~�̘_������Ƃ̔����ŁA�f�t���̒��ŋُk����������Ƃ̎咣���䓪���Ă��āA���a���Q�O��ɍ������Ă��Ă���A�댯����ɓ������悤�Ɏv����B
����ǂ��Ęb����i�߂邽�߁A1914�N���̔w�i����n�߂�B���{�̓A�����J�A�C�M���X�A�C�^���A�A�t�����X�ɕ��Ԑ��E�ܑ卑��1�ł������B�����̑Η������吭�}�ُ͋k�����̖����}�Ɛϋɍ����̐��F��ł������B���̍��͓��{���i�ɍ��ۓI�����͂����Ă��炸�A�f�ՐԎ��������A�O������̎؋����ςݏオ��A������������Ȃ��������B1913�N�ɍ����������呠��b�ɏA�C���ϋɍ�����W�J���A�f�ՐԎ��͊g�債�����A��K�͂ȊO�������łȂ�Ƃ��d���Ă����B�܂肱�̍��͊O������̎؋����ςݏオ��A�M���V���̂悤�ɂȂ낤�Ƃ��Ă����B
�������A������~�����̂�1914�`1918�N�̑�ꎟ���E��킾�����B���{�͐��ɂȂ炸�A�H���E���p�i�E�R���i�̋�����n�ƂȂ�A�W�A�s���Ȋ������B���C�o���ł��������[���b�p�����͐푈�ŗA�o�̗]�T�������Ȃ�A���̑���ɓ��{���i���i�o���Ă������B�C�^�ɂ����Ă��^�����̖\���ŋ��z�̗��v���B1914�N�ɂ�500���~�̖f�ՐԎ����������̂��A1915�N�`1918�N��4�N�Ԃ̌o����x�����v�z��27���~�ƂȂ����B���̍���GNP��47���~�ł��������Ƃ���A���̊z���@���ɋ��z����������������B���[���b�p�̐푈�ɂ����{�͍������珃�����ɂȂ�1919�N�ɂ͐��ݕۗL����20���~�ɒB�����B
���ڂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���̗A�o���ł���B�����͋��{�ʐ��ɂ���̂��A���{�ʂ��痣�E����̂��ŁA���̌o�ς̖��^���Ă����B���{�ʐ��x�Ȃ�A�����s������ƒʉ݂��\�����s�ł����A�f�t���Ɋׂ��Ă��܂������A���E����ƈבւ��s����ɂȂ�������ł���B1917�N���A�o���֎~���ꂽ�B�܂���{�ʐ�����̗��E�ł���B�f�ՐԎ��ŋ��̗��o�������Ă�����O�ƈႢ�A��C�ɐ푈�����ŋ��ۗL�𑝂₵�����ɋ��A�o�̋֎~���s�����͖̂�������悤�Ɏv���邪�A�A�����J���֗A�o�̋֎~���s�����̂ɑ����𑵂݂��Ă̋֎~�[�u�������B
�푈�����ŊO��(�����͋�)���҂��Ă悩�����Ǝv����������Ȃ����A���������ɂ��x�����ϋɍ����ŃC���t���ƃo�u���������Ă��܂����B1919�N�̏���ҕ�����1915�N��2�D37�{�ɂȂ����B���̃f�[�^�͉��������w���ł���B
|
|
�@�@�@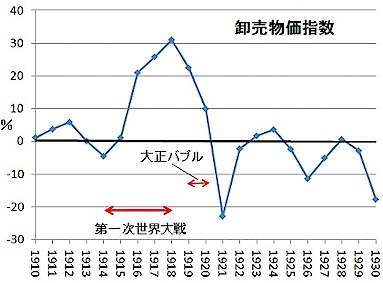 |
�Ă�ȉԓ��͂����ƌ������l�オ�肵�A1919�N�ɂ͑��O�ɔ�וĉ���3�D6�{�A�ȉԂ�7�{�ɖ\�����Ă���B�Ȃ����̂悤�ɕ������オ�����̂��Ƃ����A�푈�����ŊC�O�ʼn҂����O�݂��~�Ɋ��������߂ɁA���{�����ŏo��邨�������������Ƃɉ����A�����A�����������������ƂŁA�X�ɒʉݔ��s�̃e���|�������Ȃ������Ƃɂ���B�������A���̋��͕ĂƂ��ȉԓ����@�̑ΏۂɂȂ���̂Ɍ������A�������߂��Ēl�オ���҂������߁A�푈�����̉��b���Ȃ����������ɂ͋t�ɐ������ꂵ���Ȃ��Ă���B1919�N�ɂ͑S�R���\�Z����ʉ�v��45�D8���ɏ���Ă���A���������̂��߂ɂ������g���Ă��Ȃ��B
���݂̓��{�⒆���ł��O���ŋ����҂��ł��邪�A�C���t���ɂȂ�Ȃ��̂͂Ȃ����낤�B���݂̓��{�̏ꍇ�A�҂����h���͓��{�Ɏ����A��Ȃ��B���{�����œ����ł�����̂��������炾�B�Ă�ȉԂ��Ă��l�オ��̌����݂������B�y�n���@���l�����肪�����Ă��ĂƂĂ������C�ɂȂ�Ȃ��B��������ł́A�C���t����h�����߂ɗa�����������グ�āA��������s����o���ɂ���������A�������グ�Ă�������ɂ���������A����I�y�ł������z��������A�ߗ����Ɍ��������ʉ݂Ƃ��ĕۗL���`���Â����肵�Ă���B
|
�@�@�@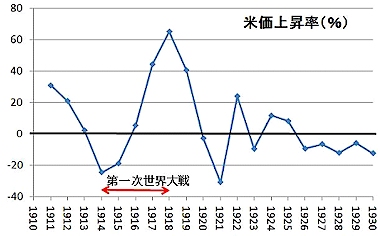 |
�吳����̓��{�͂��̂悤�ȓw�͂͑S�����Ă��Ȃ��B����ǂ��납1916�N3���ɂ͌�������̈����������s���Ă���B�푈�����ő听���������M�ŁA����Ȃ����W��������{���C���[�W���Ă���A�C���t�����C�ɂ����ϋɍ����𑱂��Ă���B�R�������ď����̐푈�ɔ����邱�Ƃ��O���ɂ������̂��낤�B�������A�C�O����̎��v�̋}���ɐ��Y���Ԃɍ��킸�A�{�^�����Еt�����������̈ߕ���A�o�����Ƃ̃G�s�\�[�h�����邭�炢�ŁA�e���i�ł����ł����ꂽ�B���̔�����1918�N11���̋x��ɂ��A���[���b�p�̊�Ƃ��߂��Ă��ċ����ɏ��ĂȂ��Ȃ�A�C�O���v�̌����A�����̉����Ōo�ς͑傫�ȑŌ������B
�Ƃ��낪�A���N��1919�N�ɂ́A�Ăьo�ς͍����̖����M���I�ȃu�[���ɂȂ�A�n���A�����A���i����Ȃǂ��ُ�ȍ������������B�w�Z�̐搶��T�����[�}���ȂǁA����Ƃ�����l�X�����Ȃǂ̓��@�ɔM�����Ă����B������38915�~�̍ō��l������1989�N�ɂ������肾�B���d�ɂ���s���ݔ������ɐϋɓI�ɉ������B���̊�ƐV�y�ъg���v�掑���̃O���t���݂�A���ُ̈킳��������B
|
�@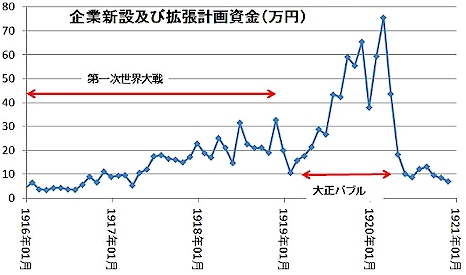 |
|
�������I���O�����������A�ݔ��������ߏ�ɂȂ��Ă����̂�����A���̑吳�o�u���͊Ԃ��Ȃ��I���A���̔�������C�ɂ���Ă���B�����ŃC���t���ɂȂ����̂Ƌt�̂��Ƃ��o�u������ŋN�����B�A�o�����ōĂіf�ՐԎ��ƂȂ�A�A�����ێ�����ɂ͉~���O�݂Ɍ������Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂�����A�~���s����������Ă����f�t���ƂȂ����B���A���i���ꓙ����\�������B���@�ɑ����Ă����l�A��Ƃ����X���Ȕj�Y�A�|�Y�����A��s�̎��t���������������A�x�Ƃ����������B�����͗a���ҕی�̎d�g�݂����������̂ŋ�s����Ȃ��Ȃ�����Ɏ��t�������ƂȂ����B����ɑ����{�ً͋}�Z���őΉ������B���̍��̌o�ς���������w�K���Ă�����A1989�N�̃o�u���Ƃ��̌�̃o�u������ɔ����s�Ǎ����̔����͖��������낤�B����1920�N�s���ɂ��_���[�W�͏��a���Q���傫�������Ƃ����̂���ؐ��r���w���a���Q�Ɋw�ԁx�̎咣�ł���A���̔�r�͎��̕\�ŕ�����B
|
�@�@�@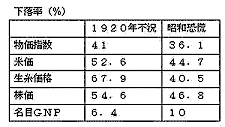 |
1920�N�s����[���ɂ����̂́A�u�ޏꂷ�ׂ���Ƃ͑ޏꂷ�ׂ��v�Ƃ����l���ł���A����E�|���H���ł��������B���{�̎����ɂ��o�u���������A�����ɂ��o�u������ƂȂ����̂ɁA��Ƃ��ׂ��̂͊�ƂɐӔC������Ɛ��{�����߂����B���̂��߁A�s����[���ɂ����i�C������ɂ����B���ۂ͐���̎��s�̂��߂ɑޏꂳ����ׂ��łȂ�������Ƃ𑽐��ޏꂳ���Ă��܂����B
1904�`1905�N�̓��I�푈�A1914�`1918�N�̑�ꎟ���E���A1931�N�̖��B���ςƑ����A���̎���͏�ɐ푈�ƌ������킴��Ȃ��ŁA�R���x�o�����債�₷�������B���Ȃ��Ƃ��吳����ɂ͊O������̎؋��͋C�ɂȂ��Ă��A���c���̑���ɂ͂���قNjC�ɂȂ��Ă��Ȃ������悤�Ɍ�����B���̐}�͍�(�����s�c��)��GNP��ł���B
|
�@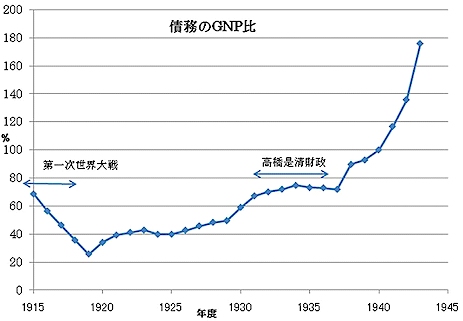 |
�i�C���悭�A�ϋɍ������s���Ă�����ꎟ���E��풆�ɂ͍���GNP��͌����B�������A�f�t����������1920�N�`1930�N�̊Ԃł́A����GNP��͏��X�ɑ������Ă���B���������̐ϋɍ���(��ʂ̍����s)�Ōo�ς�����������1931�N�`1936�N�ɂȂ�Ƒ����͎~�܂�A�����ɓ]���Ă���B��������Ă��A�i�C����������̎؋�(�����s�c���̂f�m�o��)�͑����Ă����A��ʍ����s�Ōi�C��������Ύ����I�Ɏ؋��͌���̂��ƕ�����B
�吳�o�u���Ŕ��������ߏ�ȓ������A���̌�̓��{�o�ς̑��������������B�X�Ɉ������ƂɁB1923�N�ɂ͊֓���k�Ђ��������A���{��GNP�̖�3����1��45���~�̑��Q���o�����B����Ɋ֘A���Ĕ��������������Z���Q�̐k���n�ɂȂ����B
1927�N�ɂ͑�p��s�̉c�ƒ�~�����������ɑ�K�͂Ȏ��t���������N�����B���a���Z���Q���������A�������������͈�㏀�V������قƋ��͂��A3�T�Ԃ̎x���P�\�[�u(�����g���A��)���s�����B�S���I�ȋ��Z�p�j�b�N�����߂邽�߂Ɏ����������B������Ԃɍ��킸�A�Жʂ�����������}����200�~�D���ʂɔ��s���ċ�s�̓X���ɐςݏグ�Č����āA�a���҂����S�����ċ��Z���Q�𒾐É��������B���݂͒ʉ݂��a�������S�ł���A�a��������Ă�����蓯�l�ȋ��Z�p�j�b�N�͋N���肻�����Ȃ��B
10�N�ȏ㑱�����s�i�C�E�f�t���̍ŏI�͂ō��S�̂����낵���W�c�Ö��ɂ������Ă��܂��B�f�t���̒��Łu�ُk�����v����ɐ���オ�����̂��B�����́q���O���f���A�����f���r�q���ꂵ���ւƂ���܂Łr�Ɓu�ُk���S�v(���\�쎌�A���R�W����ȁr���̂��ċ����ւ����}�����B1930�N�͍����s�z��0�ɂ��邽�߂̒��ُk�\�Z�ƂȂ����B�����������̈����������s��ꂽ�B
�Ȃ����̕s�i�C�̒��ŋُk�������s���̂��Ƃ����ƁA�f�ՐԎ��������Ă���A��������P����Ƃ������Ƃ������B�Ȃ�������(�܂���{�ʐ��ւ̕��A)���K�v���ƍl���Ă����̂��Ƃ����ƁA���O�������X�Ƌ��{�ʐ��ɕ��A���Ă������ƂƁA���ꂪ�בւ̈���ɂȂ���f�Ղ𑣐i�Ɍo�ϔ��W�ɕK�v���ƍl��������ł���B��㏀�V��������IMF�ɉe�����Ă����̂��낤�BIMF�͎����Z���̌��Ԃ�ɁA�o�ςُ̋k�����v������B�܂�ُk�����ɂ���č��ێ��x�̋ύt��}�낤�Ƃ���B�f�t�����łُ̋k�����ɉ����A1929�N�Ɏn�܂������E�勰�Q�����Ԃ��X�Ɉ��������A���{�o�ς͏��a���Q�ւƓ˓����Ă������B
���a���Q�O��̂��̊댯�ȏW�c�Ö��Ɋւ��Ă͌��݂̓��{�Ƒ����̋��ʓ_������B
1�@�o�u�������f�t������������B
2�@�f�t���Ȃ̂ɑ��ŁE�Ώo�팸�̋c�_������ł���B
3�@�ُk����ɍ����������������Ă���B
4�@IMF�̉e���𐭕{���Ă���B
5�@���������^�̍팸���咣���Ă���B
6�@��s�̌o�c��@�͉��x���o�������B
7�@�����s��}���悤�Ƃ��Ă���B
8�@�s���Ŋ������������Ă����B
9�@�~���e�F�̐������������B
10 �؋��ōΏo���v���Ă͂����Ȃ��Ƃ����_���B
�ȉ��Ɋ����̓����������B���������ɂ���Čo�ς����������O�́A�����͉������Ă����B |
�@�@�@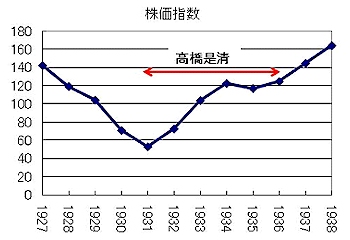 |
��㑠���ɂ��A1930�N1���ɋ������ł̋����ւ��f�s���ꂽ�B�������Ƃ������Ƃ́A�~���ɂ���Ƃ������Ƃ��B�ʉݔ��s�����ۂ��鐛���t�͎�����~���e�F�Ƃ������ƂŁA��㑠���̐���Ǝ��Ă���Ƃ�������B�~���ɂ���Ƃ������Ƃ́A���{���i�̂��ׂĂ���Ăɒl�グ���邱�Ƃɑ������A�����łȂ��Ă������͂̎ア���{���i�������킯���Ȃ������B���ہA���N��1931�N�ɂ́A�A�o�͉��֑O�̔����ɗ������B�����ւɔ����������T�g�́u���E�����߁v�Ōx�@�Ɉ�������ꂽ�B�}�X�R�~�͔ނ��u���v�����ɂ����B�}�X�R�~�̕Ό��͌�����ς��Ȃ��B
�����ւƂ������ƂŁA�l�X�͂��������ɑւ��n�߂��B����̐��ݏ����͌�����1931�N����4�D7���~�Ƌ����ւ̑O�ɔ�ה��������B���{�ʐ��ł͋��ۗL��������A�ʉ݂�����ɔ�Ⴕ�Č��炳�Ȃ���Ȃ炸�A�f�t�������������B�����o�čs�����R�͊ȒP�ɐ������Ă݂悤�B�����ł̋����ւƂ������Ƃ́A������(�h��)�������肷��Ƃ������ƁB���������͋����������������Ă��Ȃ��B�ƂȂ�ƁA��������S�����낵�āA��(�h��)���Ă����A�Ԃ��Ȃ����͑��������~�߂�B��������A��(�h��)�͒l�オ�肵�A�����ŋ�(�h��)��A����������ł���B���ۃh�����������Ėׂ����̂͏Z�F�A�O��A�O�H�Ȃǂ̍����������B���Nj��{�ʐ���2�N��ŏI������B
1931�N12���A���F��̌������t���������A�V�����A�C�����������������͋��A�o���֎~�A���{�ʐ����痣�E�A�����Đϋɍ����ɂ��o�ς̗��Ē������v�����B����ɂ��A���{�͐��E�ōł��������E�勰�Q���痧�����邱�Ƃ��ł����B
|
�@�@�@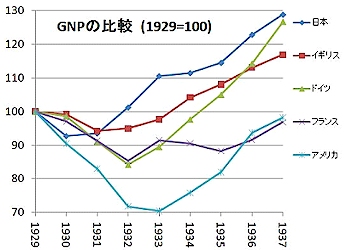 |
�Ō�ɋ������������́A�f�t���o�ςōΏo�팸��łȂǂُ̋k�������s�����Ƃ́A�ɂ߂Ċ댯�ł���Ƃ������Ƃ��B�����̍���������ő��łɎ^�����Ă���Ƃ������Ƃ́A���a���Q�O��Ɠ����悤�Ȕ��Ɋ댯�ȏɓ��{���ׂ��Ă���ƌ�����B�@
�@ |
| �����E���Q�͋��Z��������Ă�@2011/12 |
   �@
�@
|
���͓��{���̊i�������u�i�t�����v�Ɏx�z���ꂽ���E�o��
����EU(���B�A��)�̊i�t���܂Łu�����������ʂ��v�Ɏw�肳�ꂽ�B���{���̊i�������O�����܂��Ă���B�u�����������Ƃɂ͑a���v(�����l�O��)�Ȃǂƌ����Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B
�\�������o
�u�T�u�v���C�����[���֘A�̋��Z���i�ɍ����i�t�����o���Ă������ƂŁA�i�t����Ђ̐M���͒n�ɑ������A�M���V���Ɏn�܂鐢�E�e���̍���@�ɏ悶�āA���̊Ԃɂ��������Ă����B�i�t����Ђ����E�ŋ����ł���A�����J�̍����i��������ƁA���ꂪ�g���K�[(������)�ƂȂ��Đ��E���������ւƔ��W�A���B���̊i�������b�V���ł����̉e���͂̋������֎����Ă���v(������OB)
�e���̐��{��]�������A���܁A�i�t����Ђ̈ꋓ�����ɖ|�M����Ă���B
�S�����o�ϕ��L�҂������w�E����B
�u12��5���̇����B���i�����\�����̓C���p�N�g���傫�������B�đ��i�t����Ёw�X�^���_�[�h�E�A���h�E�v�A�[�Y(S&P)�x���˔@�Ƃ��ăh�C�c�A�t�����X���܂ރ��[��15�����̒������̊i�t������������������Ō������Ɣ��\����ƁA���E�̃}�[�P�b�g�������]�������B���͂��̔��\�̐����ԑO�ɁA�����R�W(�h�C�c�̃����P���ƃt�����X�̃T���R�W�哝��)�������ʼn���J���A���B�̍���@�ɑ���V���Ȕ��{����u����\�肾�Ɣ��\���Ă����B������D���A���[������͏グ��Ŏn�܂��Ă����̂ɁA�i���������̔��\���Ĉ�C�ɔ��肪��s�A�������J�n�����B���{�̊����s��ł����B���O���ĔR���A�߂�n�߂Ă������o���ς������A8���Ԃ�̉��������L�^�����v
���Ɍ����������P���̏Ί�͈�]�A��ɘc�B�i�t����Ђɂ��▭�ȃ^�C�~���O�ł̇���������A�s��ɍL�܂鉢�B�s�����Ώ������邽�߂ɊJ���������R�W��ɐ����������i�D���B
���[�}���E�V���b�N��ɖ����߂Ă����w�b�W�t�@���h�A�i�t����ЂƂ������u���Z���v�������A���B��@��w�i�ɂ��āA���̑��݊������߂Ă���B��T���Ń��|�[�g�����悤�ɁA�ꕔ�̃w�b�W�t�@���h�͊�@�𗘗p���Ėׂ��悤�Ɠ����o���Ă���B
�j���[�W���[�W�[�B�ݏZ�̕č��l�w�b�W�t�@���h�t�@���h�}�l�W���[�́A�ډ����B�ōL���鍑��@�ɏ悶�������ŁA�u�N��20%�v�Ƃ������ٓI�ȗ�����@���o���Ă���Ƃ����B
���l�����B
�u���B��@�̂������Ŗׂ��邱�Ƃ��ł��܂����B���͍����������ӂŁA��N�M���V����@���N���[�Y�A�b�v����Ă���APIIGS(�|���g�K���A�C�^���A�A�A�C�������h�A�M���V���A�X�y�C��)�̍��̃V���[�g(�J������)�|�W�V�������d���B���āA�M���V���̋~�ύ܂Ƃ܂�Ƃ̕����������͍����l�オ�肵�đ��������������Ȃ���ʂ����������ǁA�قƂ�ǂ͉�X���J�����肷��x�ɍ����\�����Ă��ꂽ����ˁB�g�[�^���ł͔N��20%�̐��т��c�����B�w�b�W�t�@���h����@������Ă���?����Ȃ��ƒm�������Ƃ���Ȃ��B���N�̓t�����_�̕ʑ��ɂ��s�����A�O��ő������������������B�ꐶ�����������l����������͓̂�����O�̂��Ƃ��v
���n������s�������A���������B
�u����A�C�^���A���̔j�]���X�N�������w���������������R���Ȃ��A�c��オ�������Ƃ��������B�Ȃɂ��������̂��ƌ��Ă���ƁA�x�����X�R�[�j(����)�̏�����肪�o�Ă����B����Ȓs�b�b�����Ŏw�����オ��̂͂��������ȂƎv���Ă���ƁA�s��ł���ȉ\�����ꂽ�B�w�A�����J�̃w�b�W�t�@���h����ʂɃC�^���A���̃V���[�g�|�W�V�����������Ă��āA����ŗ��v���o�����߂ɏ����������f�B�A�Ƀ��[�N�����炵���x---���̐^���͂킩��Ȃ��B�������̂悤�Ɏw�����I�݂ɓ��������|�����́A�K���ł�����߂ɂ���Ă�������Z�@�ւɂ͂ł��Ȃ��B�ǂ����̃w�b�W�t�@���h�̎d�ƂɈႢ�Ȃ��v�@
�@ |
| ���pEU���E�Ő��E���Q�ٔ� �g���ɗ��E���鍑�h�́H�@2016/6 |
   �@
�@
|
���E�o�ς�h�邪�����˂Ȃ��g�R���̓��h���߂Â��Ă���B23��(��)�A�p���łd�t���E��₤�������[�����{�����B���E�h�Ǝc���h�͌��������߂������A�ǂ���ɓ]��ł����������Ȃ����B
16���Ɏc���x���̏����c�����E�Q���ꂽ���ƂŁA���E�h�̐����͂����ꂽ�B18���ɔ��\���ꂽ�T�[�x�C�V�����Ђɂ�鎖���㏉�̐��_�����ł́A�c���h��45���ɑ��A���E�h��42���ɂƂǂ܂����B�E�Q�������N����O�́A�c���h42���A���E�h45���Ɨ��E�h���[�h�������̂ŁA�`���t�]���B
�u�p�����͂��Ȃ�����Ă���̂ł��傤�B�����牽���L�b�J�P������A����̓K�����ƕς��܂��B�Ⴆ�A��K�̓e���ł��B�d�t����̐l�̍s�����𐧌������ق��������Ƃ���������C�ɍ��܂�A���E�h�͑��𐁂��Ԃ��ł��傤�B���E�h�̏����́A�d�t�����A�z�����邾���ɕs�C���ł��v(�����]�_�Ƃ̑q���T�V����)
���Z�}�[�P�b�g�ł͑������u�p���̎��ɂd�t�𗣒E����̂͂ǂ����v��������n�߂Ă���B
�ăs���[�E���T�[�`�E�Z���^�[������7���ɒ��������u�d�t�̌o�ϐ���ɑ���s�x�����v�������[���B�d�t�̎�v10�J�����ΏۂŁA�s�x�������ł����������̂̓M���V����92���ŁA�ȉ��A�C�^���A68���A�t�����X66���A�X�y�C��65���A�X�E�F�[�f��59���A�C�M���X55���������B
�u�C�M���X���s����������5������܂��B�����������͉p�̂d�t���E�ɑ����m���������ł��傤�v(�s��W��)
���Z�s��́A�u�p�d�t���E���|���h�}��(���[���}��)���p���\��(�d�t�e���̍��\��)�����Z��@�����E���Q�v���x������B
���̗���ɏ悶�āA�w�b�W�t�@���h���\�����d�|���Ă���Ƃ����w�E������B
�u���������̓`���X�y�C����C�^���A�̍��\����_���Ă���ł��傤�B���ۂɗ��E���邩�ǂ����͖��ł͂���܂���B�}�[�P�b�g�����E�̉\������Ɣ��f�������_�ŁA�����̍��͑�\�������˂܂���B���Z�s��̓p�j�b�N�Ɋׂ�܂��v(�����A�i���X�g�̍����)
�d�t�̖�莙�M���V���Ȃǂ́A�d�|�����Ȃ��Ƃ����łɍ��͉������n�߂Ă���B�_���������ꂽ��A�f�t�H���g(���s���s)�ւ܂������炾�B�@
�@ |
| ���h�C�c��s�ɓ|�Y�̉\���@2016/2 |
   �@
�@
|
LIBOR�������Ńf�t�H���g����Ɛ��E���Q��
�����������ɓ��o���ϊ������\�����Ă��܂����A��͂�h�C�c��s�̓|�Y�̉\������������Ă��邱�Ƃ������Ƃ��čl�����Ă���悤�ł��B
�h�C�c��s���|�Y(�f�t�H���g)����\����2015�N�̉Ă��炢����w�E����Ă��܂������A���ꂩ�甼�N�قǂ��������݂ɂȂ��ē|�Y�̊�@���[�������Ă����̂�������Ȃ��ł��ˁB
���������h�C�c��s�̊������̂���\�����Ă��܂��̂ŁE�E�E���̊����̐��ڂ����邾���ł��|�Y����m�������Ȃ荂�����Ƃ��킩��Ǝv���܂��B
���[�}���E�V���b�N�ȍ~�̑�K�͂ȋ��Z�ɘa�ɂ���Đ��E���Q�͉�����ꂽ�悤�Ɍ����܂������A���͂���K�͂Ȋ�@���K��錴���ɂȂ����̂�������܂���ˁB
���h�C�c��s���|�Y(�j�])�̌����́H
�h�C�c��s���|�Y����Ɖ\����邩��ɂ͌���������̂ł��B
���̈���f���o�e�B�u���i�ł����A���Ȃ��ʂ̃f���o�e�B�u������s���Ă���悤�Ȃ̂ł��ˁB������M���V�����݂̊�Ȃ����c�ł��B
�f���o�e�B�u���i���ǂꂾ��������Ă����̂��͊O������͕�����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����A�h�C�c��s�������傫�����Ă��������Ƃɂ��ĉ��̋K�����s��Ȃ������h�C�c���{�̐ӔC���d��Ȃ��̂ƂȂ�ł��傤�B
����Ƀh�C�c��s��LIBOR��TIBOR�ɂ��Ă̕s�����s���Ă������Ƃ��瑽���̑i�ׂ�����Ă���킯�ł����A���̂��Â�ɂ����Ă�����Ȕ����𐿋�����Ă���̂ł��B
�܂��A�t�H���N�X���[�Q���̔r�C�K�X�̋K������̕s���ɂ���Ĕj�]�������ɂȂ��Ă����̂ł����E�E�E�����P���̎w���ɂ���ăh�C�c��s���t�H���N�X���[�Q���~�ς̎����̑啔�����o�����ƂɂȂ����̂ł��B
�����̗v������h�C�c��s�̊�������\�������킯�ŁA����ɂ���ē|�Y(�j�])����Ƃ����\���傫���Ȃ��Ă��������ɂȂ����̂ł��B
���h�C�c��s�̔j�]�Ő��E���Q�ɂȂ闝�R
�h�C�c��s���ĂƂĂ��Ȃ��K�͂̑傫���Ȃ̂ł����A�������j�](�f�t�H���g)���Ă��܂��ƋK�͂��傫�������ɒN�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ�����ԂɂȂ��Ă���̂ł��B
�Ȃ�Ƃ����Ă����E��4�ʂ̋K�͂��ւ��s�ł�����E�E�E�����|�Y�Ȃ�Ă��ƂɂȂ���[�}���E�V���b�N�����̐��E���Q����������\���͐��������̂ł��B
�h�C�c�ő�̋�s���j�]���Ă��܂����ꍇ�͋~�ς���̂̓h�C�c���{�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���̂ł����A�t�H���N�X���[�Q���������ɂ���ĕ��Ă���h�C�c���ȒP�ɋ~�ςł���Ƃ͓���v���Ȃ����Ƃ����R�̈�ɂȂ��Ă��܂��B
���āA�h�C�c��s�̊���������Ƃ������Ƃ͑S���E�̋��Z�֘A��Ƃ⏤�i�̉��l�̒ቺ�������N�����L�b�J�P�ƂȂ�܂��B
���ۂɃh�C�c��s�̊����\���������ƂȂ��ē��{�̋�s�����啝�ɉ������Ă���̂ł�����ˁB
���������Ƃ�������Z�֘A�����������Ă������Ƃ����Z�s���������N�����āA���ʓI�ɂ͐��E���Q�ւƌq����\������������Ă���̂ł��B
���h�C�c��s�f�t�H���g�Ɛ��E���Q
����́u�h�C�c��s�ɓ|�Y�̉\���ILIBOR�������Ńf�t�H���g����Ɛ��E���Q�ɁI�v�Ƃ������e�ł������A���Ƃ��Ƃ̓h�C�c�o�ς̓��[���b�p�̒��ł��D�����I�ȑ��݂������̂ł��B
��������54�����[���ɂ��Ȃ�f���o�e�B�u�������Ă��邪���߂ɁA�M���V���̔j�]�ɂ���ăh�C�c���j�]���邱�ƂɂȂ�킯�ł��ˁB
�M���V���̔j�]��EU�̉�̂Ɍq����댯�Ȃ��̂Ȃ̂ł����E�E�E�����Ȃ�Γ��R�A���E�o�ςɂ��傫�ȉe����^����͕̂K���ł�����ˁB
���Ă��āA�h�C�c��s�͐V�^�n�C�u���b�h��CoCo(�R�R)�̗����̓L�`���ƍs����̂ł��傤���H
�\�ł̓t�H���N�X���[�Q���|�Y�̊�@������Ă��܂��̂ŁA�����ǂ���Ƃ����l����悵�Ă��܂����ˁB�@
�@ |
| ��������Z��@�ƃ}���N�X���_ |
   �@
�@
|
|
���͂��߂�
|
2007�N�ĂɎn�܂������[���b�p�ɂ�����T�u�v���C����@�́A2008�N�ɂȂ肻�̑匳�ł���A�č����Z�@�ւ������B2008�N9��15���ɂ́A�č�������s���̈�A���[�}���E�u���U�[�Y�̓|�Y�Ƃ������Ԃɔ��W�����̂ł���B�č������s����͂��ߐ��E�̏،��s��́A1929�N10���̊������Q�ȗ��̑卬�����i�����B�܂��A���Z��@�́A�č��͂��ߑ����̍��̎��̌o�ςɉe��������ڂ��n�߂��BGM�A�t�H�[�h�A�N���C�X���[�̕Ď����ԑ��3�Ђ��o�c��@�Ɋׂ�A���I�@�ւ̋~�ςȂ����Ă͔j�Y�Ƃ����[���Ȏ��ԂɓW�J�����B�ƐїǍD�Ƃ���ꂽ���{�̃g���^���}���Ɏ��v�����������A���N�̌o�험�v�̓}�C�i�X�ƂȂ����B�J�ɂ́A1929�N���Q�̍ė����Ƃ��A100�N�Ɉ�x�̋��Z��@���Ƃ��A���܂��܂ȏ����ɑ���\�����q�ׂ��Ă���B
�{�e�́A�}���N�X�o�ϗ��_�̗��ꂩ��A����o�ϕ��͂̎��_���������Ƃɂ���B�Ƃ�킯�A���ݐi�s���̋��Z��@�ɂ��āA�}���N�X�M�p�_�̂ЂƂ̓K�p�����݂悤�Ƃ�����̂ł���B�����܂ł��Ȃ��A�}���N�X�̌o�ϗ��_�́A19���I�����̃C�M���X�o�ς�Ώۂɂ��č\�z���ꂽ�B������A����21���I�ɂ����āA���̗��_���ʗp����Ƃ���{�e�̎��_�ɂ́A�����̈٘_�����낤�B�����A�����ł́A���ݓW�J����Ă��鐢�E�I�ȋ��Z��@���͂̊�{�I���p���}���N�X�M�p�_�̓K�p�ɂ���Ă����炩�ɂ������B���̏ꍇ�A�킽�����́A�����̋��Z��@���}���N�X�̗��_�ɂ���ĕ��͂���ɂ́A3�̒i�K�I�c�_�ނ��Ƃ��d�v�ƍl����B�Ȃ��Ȃ�A�}���N�X�̋c�_���璼���ɍ����̋��Z��@���͂������Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ����炾�B
|
|
������1�@�}���N�X�w���{�_�x���牽�𒊏o���邩 |
�����܂ł��Ȃ��A�}���N�X�w���{�_�x�́A�o�ϋ��Q�ɂ��Ę_���������ł͂Ȃ��B�܂��A�}���N�X�̋��Z��@���͂Ƃ����̂���������Ď�����Ă���Ƃ����킯�ł��Ȃ��B�������A�����̋��Z��@���͂Ƃ������p����A�{����ǂݕԂ��A�������d�v�Ș_�_�𒊏o���邱�Ƃ��ł���B���ڂ��ׂ��́A���̑�3����5�сu���q�Ɗ�Ǝҗ����Ƃւ̗����̕���B���q���ݎ��{�v�ł���A�܂����̑�27�́u���{��`�I���Y�ɂ�����M�p�̖����v�ł���B�����Ń}���N�X�́A�M�p���x�̈�ʓI�_�_������̂����A���M�p�ɂ��ݕ��̐ߖƂ����@�\�ɂ͒��ڂ��ׂ����낤�B�܂�A�ݕ��͐M�p�ɂ����3�ʂ�̎d���Őߖ��Ƃ����B��1���u����̈�啔���ɂƂ��āA�ݕ����S���K�v�Ƃ���Ȃ��Ȃ邱�Ƃɂ���āv1)�B��2���u�ʗ�����}��k���ʎ�i�l�̗��ʂ����߂��邱�Ƃɂ���āv2)�B�����đ�3���u�����ɂ����ݕ��̑�ʁB�v3)�ɂ���Ă��Ƃ����̂��B�܂菤�ƐM�p����b�Ƃ��A��s�M�p�ɔ��W����A���{��`�o�ς̐M�p���x�́A�ݕ���ߖA���ʑ��x�������߁A���ݕ���K�v�Ƃ��Ȃ��V�X�e�������肾���̂ł���B�ݕ��Ȃǂ͋ȊϔO�I�ȉ��l�ɉ߂��Ȃ��Ȃ�̂��B���������āA�u���ʂ܂��͏��i�ϑԂ́A����ɂ͎��{�̕ϑԂ̌X�̋ǖʂ́A�M�p�ɂ������A�܂����̂��Ƃɂ��Đ��Y�ߒ���ʂ̉����v���N����A�u�M�p�́A�w���s�ׂƔ̔��s�ׂƂ��r�I�����Ԃɂ킽���ĕ������邱�Ƃ������A����䂦���@�̓y��Ƃ��Ė𗧂v�Ƃ����i�C�g��A�����ǖʂ����o����̂Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ��v���ƂȂ�B
�����A�����ł̃}���N�X�̌�����Z��@�ɂȂ���_�_�́A�������x�ɂ��Ę_�����ӏ����낤�B�����܂ł��Ȃ��A�������x�́A���{��`�̐����̂��̂̊�b��ł̎��{��`�I���I�Y�Ƃ̂ЂƂ̎~�g�ł���B�����炱���܂��A�}���N�X�́A���@����������Ƃ����̂��B�u�M�p�́A�X�̎��{�Ƃ܂��͎��{�ƂƂ݂Ȃ����l�ɁA���l�̎��{����ё��l�̏��L�A����䂦���l�̘J���ɂ�������A���̐������ł̐�ΓI�ȏ����������v4)�B�����瑼�l�̏��L�ɂ��ƂÂ����{�Ƃ̓��@�����́A��_�ɂȂ�A���̐��������s���A�����{�̏W���ɓ����A���D�ւƓW�J����B�u�M�p�́A���̏����҂ɂ܂��܂����R����R�t�̐��i��^����B���L�͂����ł͊����̌`�ԂŎ�������̂ŁA���L�̉^������шړ]�́A��������@�̏��R���錋�ʂƂȂ�̂ł���A�����ł͏��������͎L�����ɂ̂ݍ��܂�A�r�����͎�����T�����ɂ̂ݍ��܂��v5)���ƂɂȂ�̂��B
���{��`�Љ�ł́A���̐�����e�͓I�ȍĐ��Y�ߒ����A�M�p���x�ɂ���ċɌ��܂ʼn����L������B�܂�A�M�p���x���A�ߏ萶�Y�⏤�Ƃɂ�����ߓx�̓��@�̎�v�Ȟ��q�ƂȂ邩��Ȃ̂����A�����Ȃ�̂́A�Љ�I���{�̈�啔�����A���̎��{�̔L�҂����ɂ���Ďg�p����邩�炾�B�u�M�p���x�́A���Y���͂̕����I���W����ѐ��E�s��̑n�o�𑣐i����̂ł���A�����̂��̂��A�V���Ȑ��Y�`�Ԃ̕����I��b�Ƃ��Ă�����x�̍����܂ł��肠���邱�Ƃ́A���{��`�I���Y�l���̗��j�I�C���ł���B����Ɠ����ɁA�M�p�́A���̖����̖\�͓I�����A���Ȃ킿���Q���A����䂦�Â����Y�l���̉�̂𑣐i����v6)���ƂɂȂ�B
�����A���̋��Q�𑣐i����M�p�A�Ƃ�킯�������x�́A�ǂ̂悤�ɂ��Ď��{��`���ߓx�ȓ��@�����ւƒǂ����̂��낤���B�����ł����́A�܂��A�������x�̉��Ō`������遃�ˋ{���̌`�����J�j�Y���֕��͂̃��X�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�}���N�X�͌����B�u�ˋ{�̌`���́A���{�Ҍ��ƌĂ��B�K���I�ɔ�������鏊���́A��������A���ϗ��q���ɏ]���Čv�Z���邱�Ƃɂ���āA���Ȃ킿�A���̗��q���ő݂��o���ꂽ���{�������炷�ł��낤���v�Ƃ��āA�v�Z���邱�Ƃɂ���āA���{�ɊҌ������v7)�̂ł���B������A�u���̏،��̎��{���l�́A�����Ɍ��z�I�Ȃ��̂ł���v8)�B���̏،��̎s�ꉿ�l�́A�������{�ɉ��l�ω����Ȃ��Ă��A�Ǝ��̓�����������̂��B���銔���̖��ډ��l��£100�Ƃ��悤�B��ʂ̕��ϗ��q����5���̂Ƃ��ɂ��̊�����10���̎��v��������Ƃ���A£200�ɓ��M���邾�낤�B�Ȃ��Ȃ�A���v£10�ϗ��q���ŏ����Ă��Ƃ߂��l���A£200�ƂȂ邩�炾�B����ɁA���̏،��̎s�ꉿ�l�́A�ꕔ�͓��@�I�ɂȂ�B�Ȃ��Ȃ�A���̊����̎s�ꉿ�l�́A�����̎��v�݂̂Ȃ炸�A�����̊��҂������v�ɂ���Ă��e������邩�炾�B�������̂����Ɗ������i���}������̂́A�����������@�̓ǂ݂������Ă��邩��ł���B�u���������āA�ݕ��s��̕N�����ɂ́A�����̗L���،��̉��i�́A��d�ɉ�������ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A���ɂ́A���q�����オ�邩��ł���A���ɂ́A�����̏،����A�����̂��߂ɑ�ʂɎs��ɓ����o����邩��ł���v9)�B�������A�d�v�Ȃ��Ƃ́A�����߂�����A�����،��̎s�ꉿ�l�́A�j�Y��Ƃ₢�����܊�Ƃ̂��̂ł��Ȃ�����A�Ăт��Ƃ̐����ɓ��M����̂��B���Q���̉��l�����́A��ׂ���������ޓ��@�Ƃ̊i�D�̓����^�[�Q�b�g�ƂȂ�B������A���̉��l�����́A�ݕ����Y�̏W���̋��͂Ȏ�i�Ƃ��č�p����Ƃ����킯���B�Ƃ������Ƃ́A�����̏،��̉��l�����≿�l�������A�������{�̉��l�^���Ɖ��̂��������Ȃ��Ƃ���A�ꍑ���̕x�̑傫���ɂ͕ω��͐����Ȃ��B�u�����͖��ړI�ݕ����{�̂����̃V���{���ʂ̔j��ɂ���ẮA�т��ꕶ�n�����͂Ȃ�Ȃ������v�Ƃ������ƂɂȂ�B
���{��`�̔��W�Ƌ��Ɍ������{�̌����؏��Ƃ��Ă̏،��ނ̒~�ς������Ȃ���B�����̏،��́A�����炩�Ɍ������{�Ƃ̊֘A��L���Ă��邪�A���ꎩ�g���i�Ƃ��Ď�������ꍇ�A���ꎩ�g���{���l�Ƃ��ė��ʂ���̂��B�����̉��l�z�́A�������{�̉��l�^���Ƃ͑S���W�Ȃ���������B�������āA�����̏��L���؏��̉��i�ϓ��ɂ�闘���Ƒ����́A���i��A�q���̌��ʂƂȂ�B�}���N�X�͌����B�u���̓q���������{���L���l������{���̕��@�Ƃ��ĘJ���ɑ����Č����A�܂����ړI�\�͂ɑ����ēo�������̂ł���B���̎�̑z����̉ݕ��I���Y�́A�l�̉ݕ����Y�̔��ɑ傫�ȕ������Ȃ�����łȂ��A���łɏq�ׂ��悤�ɁA��s�ƎҎ��{�̔��ɑ傫�ȕ��������Ȃ��Ă���v10)�B
�������x�̔��W���}���ɓW�J�����ƁA�ݕ����{�Ƃɂ��ݕt�\���{�̒~�ς����i�����B�����āA�ނ�ɂ��~�ς̌���́A�Y�Ǝ��{�ƂƏ��Ǝ��{�Ƃ��]���ɂ��čs����̂��B�Ȃ��Ȃ�A���q�̂悤�ɁA�s���ǖʂɂ�����،����i�̉������ɁA�ނ�ɂ��،��̑�ʔ��t�����s�Ȃ��邩��ł���B�����̏،��́A���̌�̌i�C�ǖʂōĂт��̐���ȍ�������т���ȏ�̉��i�ɓ��M�����Ƃ��ɔ��蕥����B�������āA�ݕ����{�Ƃ̎�ɁA�c��ȃL���s�^���E�Q�C�����]���荞�ނƂ����Z�i���B�����������v���ݕ����{�Ƃ����́A�Ƃ肠�����ݕt�\���{�ɓ]��������Ƃ������ƂɂȂ�B�������A�ݕ����{�Ƃɂ�闘�v�������A�ݕt�\���{�̌���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�Y�Ǝ��{�Ƃ⏤�Ǝ��{�Ƃɂ����āA�~�ςɗ\�肳��Ă��闘�������́A���������莩�����g�̎��Ƃ̒��Ŏg�r���Ȃ���Αݕt�\���{�ƂȂ邾�낤�B�܂��A����ɗ\�肳��Ă��闘�������ł����Ă��A��͂�ꎞ�́A�ݕt�\���{�̌���ƂȂ肦�悤�B������Y���v�f�̉��i����������A���{�͈ꎞ�V������邵�A���Ƃ̒��f�ɂ���Ă����{�͗V������B�܂��A�Đ��Y������ނ��鑽���̐l�X�ɂ���Ă��A�ݕt�\���{�̒~�ς��s�Ȃ���B
���������āA�u�f�ޓI�x�̑���ɂ�āA�ݕ����{�Ƃ����̊K���͑傫���Ȃ�B����ł́A���ނ��Ă��鎑�{�Ƃ����A���Ȃ킿���������҂����̐��ƕx�Ƃ����傷��B�܂��A���ɂ́A�M�p���x�̔��W�����i����A����ƂƂ��ɋ�s�Ǝ҂����A�ݕ��ݕt�Ǝ҂����A���Z�Ǝ҂����Ȃǂ̐�����������B�\�\���R�ɗ��p�ł���ݕ����{�̔��W�ɂ�āA���q���ݏ،��A���،��A�����Ȃǂ̑��ʂ��A��ɏq�ׂ��悤�ɑ�������B�������A����Ɠ����ɁA�����̗L���،��̓��@������s�Ȃ��،�����Ǝ҂������ݕ��s��Ŏ����������̂ŁA���R�ɗ��p�ł���ݕ����{�ɂ���������v����������v11)�B���̏،�����Ǝ҂����̉ݕ����{���v�ɉ�����̂��A���Ƌ�s�ł���B�������āA�u�M�p���x�̔��W�ɂ�āA�����h���̂悤�ȑ傫�ȏW�����ꂽ�ݕ����s�ꂪ���肾����邪�A�����͓����ɂ����̏،��̎���̒��S�n�ł�����B��s�Ǝ҂����́A�����̏��l�k�،�����Ǝҁl�A���Ɍ��O�̉ݕ����{���ʂɗp���Ă�̂ł���A�������ēq���ꖡ�����傷��v12)�B
�C�M���X�ɂ����鎑�{��`�̔��W�́A�Y�Ƃɑ��ċ��Z�̗D�ʐ��𐧓x�I�ɍ��o���Ă����B���̂ЂƂ̋A����1844�N�̋�s�@�ɂ��������Ƃ͂悭�m���Ă���B�}���N�X�́A�u������ݕ����_�ɂ��ƂÂ��A�����ĉݕ�����Ǝ҂ł���I�E���@�X�g������т��̈ꖡ�̗��Q�W�ɂ���č����ɉ���������v13)�Ƃ������A����͂ǂ̂悤�ȈӖ��Ȃ̂��낤���B1844�N��s�@�́A�C���O�����h��s�����Ƌ�s���̓�ɕ��������B�������́A�啔�����{�ۏ؍ɂ���ė��t����ꂽ£1�A400���ƍō�4����1�܂ł͋�ł悢�̂����A�S�z���ŕۏ��ꂽ��s���s����B�����̋�s���͌��O�̎茳�ɂ���̂łȂ�����A��s���ɒu����A���O�Ƃ̎���͋�s�����s�Ȃ��B�������ƌ��O�Ƃ̎���́A���Ƌ�s���Ƃ̎���Ɍ�����B�܂�A��s�����������邽�т��̋��z�ɓ������s�������s����A���o���邽�тɂ��̋��z�ɓ������s�����j�����ꂽ�B��s�����ʂ����S�ɋ������ʂɏ]��������Ƃ����̂����̋�s�@�̊�{�I�����������B������A�������o����ƁA��s�������ʂ��炻�̕������グ��ꂽ�B���̌o�ς��ߏ萶�Y�Ɋׂ��Ă���悤�ȏꍇ�A���������C���O�����h��s�̍s���́A���Z�N���ƁA�o�ϋ��Q�̈��������������ƂɂȂ�B�����܂ł��Ȃ��A���̎��������x����i�����z�K�v�Ƃ��ꂽ�B�����͋������ꂸ�A���q���͋}�����A�܂��߂Ȏ��Ǝ�͍���ʂāA��Ɠ|�Y�����������B�������A���Z�Ǝ҂́A���̋����㏸�����܂����p�����B1844�N��s�@�ɂ���č��o���ꂽ���Q���ɂ�������������́A�ނ炪�\���Ȏ��v���グ�A���{�̏W���ɂ���āA�����h���̑�ݕ����{�ƂɂȂ肠�����Ă�����D�̃`�����X�������Ƃ����悤�B�}���N�X�͂��������Ă���B�u����ɁA�W���ɂ��Č�낤�I �����鍑�ƓI����s�ƁA��������芪����ݕ��ݕt�Ǝ҂�������ё卂���݂������Ƃ𒆐S�Ƃ���M�p���x�́A����ȏW���ł����āA����͂��̊K���ɁA�P�ɎY�Ǝ��{�Ƃ������ʂɎ����I�ɔj�ł����邾���łȂ��A�댯����܂���@�Ō����̐��Y�ɂ�������r�����Ȃ��͂�^����\�\���������̈ꖡ�́A���Y�̂��Ƃ͂Ȃɂ��m�炸�A�܂����Y�Ƃ͂Ȃ�̊W���Ȃ��B1844�N�����1845�N�̖@�́A���Z�Ǝ҂����Ƈ����������l�������Ƃ�����������̓����ǂ��̗͂����債�����Ƃ̏؋��ł���v14)�B
���E���Q�́A���ׂĂ̍����A���������A�����ɗA�o�������邱�Ƃɂ���ċN����B���̎����́A�����̍������{�ʂ��邢�͋�{�ʁA������ɂ��Ă��������ݕ����ʂ̊�b�ɂ������B�M�p���ł������^���A�ł����Ȃ���C�M���X�ŁA��ʓI�Ȗf�Ս��z�͏��ł����Ă��A�������Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̏��x�������z���t�ɂȂ�ƁA���Q�̑O���Ƃ��Ă̋����o�́A�܂��C�M���X�ŋN����B�������A�����o�Œ����ɋ��Q�ɓ˓�����킯�ł͂Ȃ��B�u�����̋��Q�͂����A�ב֑��ꂪ���]�����̂��͂��߂āA���Ȃ킿�A�M�����̗A�����ĂїA�o���D���ɂȂ�Ƃ����ɖu�������v15)�̂��B�Ȃ��Ȃ�A�����o���N����A�C���O�����h��s�ɂ���ċ�s���̔j�����܂��s�Ȃ���B���q�����㏸���A�ݕ��N�����N�������B�ב֑��ꂪ���]���A�M�����̗��o�������ɂ����̂����A�����ɃC�M���X���o�ϋ��Q�֓˓�������Ƃ����킯�ł���B�Â��āA�����C�M���X�֗��o���������ŁA��͂藘�q�����㏸���A�ݕ��N�����N����B�M�����̗������D���ɂȂ�Ɠ����ɁA���̍����o�ϋ��Q�ւƓ˓�����̂ł���B�e�ޔ��˂̏ꍇ�̂悤�ɁA�x���̏��Ԃ�����Ă���̂ɉ����āA�˂Ɋe���������X�Ƌ����o�������N�����A�Â��ė����Ɠ����Ɍo�ϋ��Q�ւƓ˓�����B���E�o�ϋ��Q�́A�C�M���X�����Ƃ��āA���E�e���֎��X�Ɣg�y���Ă����̂ł���B���̌��ʁA�u��ʓI���Q���R���s���Ă��܂��₢�Ȃ�A����͂ӂ����с\�\�Y�o��������̐V�Y�o�M�����̗����͕ʂƂ��ā\�\���ꂪ���܂��܂ȏ����̓��ʂ̏������Ƃ��ď����ɋύt��ԂŎ������Ă����̂Ɠ��������ŁA�z�������v16)�B���̎����́A�M�������ݕ��̊�b�ɂ���������ł́A���̊m�ۂ̂��߂ɁA���Q�Ƃ����\�͓I�ύt��p�������A�c��ȕx���]���ɂ��ꂽ���Ƃ������Ă���B�M�p��`����d����`�ւ̓]���́A�K�R�I�Ȃ̂����A�u��}�̏u�Ԃɋ����I��b���ێ����邽�߂ɁA�����̕x�̍ő�̋]�����K�v�v17)�ł������ƃ}���N�X�͎w�E�����B
|
|
������2�@�Ȃ����Z��@�͉e����߂��� |
|
�ȏ�A�}���N�X���_�������E�o�ςɂ�������Z��@�̖u���́A1929�N�勰�Q�ɂ�����܂ŁA���܂��܂ȋ�̓I�l����悵�Ȃ���A�z�I�������I�Ɉ����N������Ă����B�������A��2�����E����A���Ȃ��Ƃ�1971�N�č����{�ɂ����ƃh���Ƃ̌�����~�A1973�N�Œ葊�ꐧ�̕���ɂ�����܂ŁA�����������Z��@�̖u���͉e����߂����Ƃ͒N�������F�߂�Ƃ��낾�낤�B�Ȃ������������Ԃ����������̂��낤���B
|
��1�@���Z��@���É��̍����v��
����́A�}���N�X���w�E�����u����Z�Ǝ҂Ɗ��������l�����v�̗͂����߂邱�Ƃɐ�����������ł���B�K���u���C�X�͎��̂悤�Ɍ����Ă���B�u����@�l��Ƃɂ����Ċ���̎x�z�͂�����ꂽ���ƁA�Ɛт̏����Ȗ@�l��Ƃł́A�o�c�w�̒n�ʂ�����߂Č��łł��邱�ƁA��s�Ƃ̎Љ�I�Ȗ��͎͂���Ɏ�܂���邱�ƁA�A�����J���E�H�[���E�X�g���[�g�ɂ���Ďx�z����Ă���Ȃǂƌ����Ί�Ɋ������邱�ƁA�Y�ƊE�ł̐l�ޒT�����܂��܂����͓I�ɂ����Ȃ���悤�ɂȂ������ƁA���炨��ы���҂̈АM���V�������܂������Ɠ��A������ł���v18)�B�܂��AP�BA�B�o������P�BM�B�X�E�B�[�W�[�����̂悤�Ɍ����Ă���B�u������s�Ǝ҂̌��͂́A�n��������A�ŏ��̐����i�K�̏����ɂ����銔����Ђ́A�O�����Z�ɂ�������ِȕK�v����b�ɂȂ��Ă����B���̌�A�Ɛ藘���̂䂽���Ȏ��n������Ƃ��������Ђ��A�������ɁA�����I�ɒ��B���ꂽ�����ɂ���āA���̎������v���܂��Ȃ����Ƃ��ł��邱�ƂɋC�Â��ƂƂ��ɁA���̂悤�ȕK�v�͏d�v�ł͂Ȃ��Ȃ�A���邢�͂܂��������ł����B�c�c�������āA��r�I�傫�Ȋ�����Ђ́A�������ɋ�s�Ǝ҂�����A�L�͂Ȋ��傩����܂��܂��Ɨ�����悤�ɂȂ�A���������āA���̐���́A����c�̗̂��Q�ɏ]����������ނ���A�܂��܂��傫�Ȓ��x�ŁA���ꂼ�ꎩ�Ȃ̗��Q�ɂނ��т�����悤�ɂȂ����v19)�B
�����Ƃ̍s�������Z���Q���玩�R�ɂȂ����Ƃ����̂��A���Z��@�u�����e����߂��~�N���I�v���Ȃ̂��B�A�C�N�i�[�́A�������������Ƃɂ́A3�̓���������Ƃ����B��ꂪ�A�o�c�̏��L����̕������B���̓_�Ɋւ��ẮA���ł�1930�N��A�o�[���ƃ~�[���Y�������炩�ɂ��Ă���20)�B�܂�A�ނ�͌��㊔����Ђ̎x�z�͂��܂⊔�傩��o�c�w�Ɉڂ��Ă���Ƃ����̂��B����͖��`��A���̊�Ƃ̏��L�҂ł����Ă��A���劔����Ђ��������ɉ^�c�����ɂ͗L�\�Ȑ��I�o�c�҂��K�v�Ƃ����킯���B������A������Ђ̎�����̌��茠�́A�ō��o�c�ӔC��(CEO)�Ȃǂ���\�������o�c�����O���[�v�Ɉڍs���A���U���A�w���͂��������傽���́A�I�ȋ��������҂ɐ��艺�����Ă��܂����̂�21)�B
���́A�����H��̑��ƂƌŒ�I�Z�p�W���ł���B�A�C�N�i�[�ɂ��A�����Ƃ̑����Y�\�͂́A�����̍H�ꂩ��`������Ă��邪�A���{�ݔ��̌����^�]�̂��߂̌��ޗ��̕��ʂ�@�B���^�]���邽�߂̌����I�l���z�u�́A�����͂Ƃ������A�Z���I�ɂ͋Z�p�H�w�I�Ɍ��肳��Ă���Ƃ����̂��B������A�]���̐V�ÓT�h�o�ϊw�����R�Ƃ��Ă���U ���^��p�Ȑ��ɂ��œK�����_�͒ʗp���Ȃ��B���ۂ̊�ƂɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A�����ɉ��т���p�Ȑ������ł���A�����Ȃ���v�ɂ��Ή��ł��鐶�Y�\�͂��K�v�Ƃ��ꂽ�̂�22)�B
��O�́A�ǐ��Ƃł���Ƃ������Ƃ��B�����Ƃ́A�ނ�̐��Y�����s��ɒP���ɓ����o������͂��Ȃ��B�ނ�́A�s��K�͂��l�����Ȃ���A�ڕW�������������ł��鉿�i�ݒ���s�Ȃ��A�̔������ɏ]������23)�B������u�Ǘ����i�v�Ƃ�������̂��B��Ƃ��s�ꃁ�J�j�Y���Ɉˑ����A�ǂ�ȉ��i�������悤�����̎Y�o�����s��ɋ������A�s��ɉ��i������܂�����Ƃ������Ƃ͂��Ȃ��̂��B
�������������Ƃ��x�z���鐢�E�o�ςł́A��s���ˑR�Ƃ��ĎY�ƂƊ֘A��L���Ă��悤�����܂����A���Z�́A�������������Ƃ̎��{�~�ς��x����T���߂Ȗ�����S�킳��Ă������Ƃ͎����������B�č��ɂ����邻�̑̐����A�킽�����́A���u�P�C���Y�A���v�Ɩ��������B�P�C���Y�A���Ƃ́A���Y�I�����ɗ��Q��L���鐶�Y�K���̘A���ł���B��̓I�ɂ́A�č��ɂ�����x�z�I�ȉǐ莑�{�K���ƘJ���K���Ƃ̍L�͂ȘA���ł���A���̊�b�́A�ǐ�s�ꂩ�琶���钴�ߗ����Ƒg�D�J���҂̍������ɂ�����24)�B
|
��2�@���Z��@���É��̍��ۗv��
�Ƃ���ŁA�����Z��@���É��̍��ۓI�v���͂ǂ��ɂ������̂��낤���B�킽�����́A��������ۓ��@���{�̕������߂ɐ��������A���̍��ےʏ��Ȃ�тɍ��ےʉ݃V�X�e���̎����ɋ��߂����B���̍��یo�σV�X�e���́A��2�����E����A1973�N�܂ŋ@�\�����̂��B���̍��ےʏ��V�X�e���́A�}�N���I�o�ψ�������ۖf�Ղ̊������ɂ���Ď������悤�Ƃ����B����́AGATT �O����ǂ߂Έ�ڗđR���낤�B�����ɂ́A���̂悤�ɋL����Ă���B�u�f�Ջy�ьo�ς̕���ɂ�������Ԃ̊W���A�������������߁A���S�ٗp���тɍ��x�̂������ɑ���������������y�їL�����v���m�ۂ��A���E�̎����̊��S�ȗ��p�W�����A���тɉݕ��̐��Y�y�ь������g�傷������Ɍ�������ׂ��ł��邱�Ƃ�F�߁A�ł��̑��̖f�Տ�ǂ������I�Ɍy�����A�y�э��ےʏ��ɂ����鍷�ʑҋ���p�~���邽�߂̑��ݓI���b�I�Ȏ��ɂ߂�������邱�Ƃɂ��A�����̖ړI�Ɋ�^���邱�Ƃ���]���āA���ꂼ��̑�\�҂�ʂ��Ď��̂Ƃ��苦�肵��25)�v�Ƃ���B���̑O�����A�P�C���Y��`�Ɋ�Â��Ă��邱�Ƃ͖��炩���낤�B�܂�A�P�C���Y�́A�e�������̎��含�Ɋ�Â����S�ٗp���������ׂ��A�����E���Z�����W�J�������̊��������s�Ȃ��A���E�f�Ղ͊g�傳��A���E��GDP �����̏㏸�Ƌ��ɐ��E�I���Ƃ͖h����Ƃ������炾�����B������A�P�C���Y�͎��̂悤�Ɍ����̂��B�u��������������������ɂ���Ċ��S�ٗp�������ł���悤�ɂȂ�Ȃ��(���̂����A�����ނ炪�l�������ɂ����Ă��ύt��B�����邱�Ƃ��ł���Ȃ�A�ƕt�������Ȃ���Ȃ�Ȃ�)�A�ꍑ�̗��v�����̕s���v�ɂȂ�ƍl������悤�ȏd�v�Ȍo�Ϗ��͕͂K���������݂��Ȃ��̂ł���B�K���ȏ����̂��Ƃō��ە��Ƃ⍑�ۑݕt���s�Ȃ���]�n�͈ˑR�Ƃ��Ă���B�������A�ꍑ���������甃�����Ɨ~������̂ɑ��Ďx��������K�v����ł͂Ȃ��A�f�Վ��x�������ɗL���ɂ���悤�Ɏ��x�̋ύt�����Ƃ��閾���ȖړI�������āA�������i�𑼍��ɋ���������A���̔��荞�݂����ނ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������������@�͂��͂⑶�݂��Ȃ��Ȃ�ł��낤26)�v�����������E�o�ς͂�����̗��z���낤�B�ގ���u�����̎v�z�̎����͖��̂悤�Ȋ�]�ł��낤���v�Ƃ��q�ׂĂ���B
�����A�P�C���Y�͂��̍l�����u���̂悤�Ȋ�]�v�ɏI��点�邱�ƂȂ��A��2�����E���I����̍��ےʉݑ̐��Â���ɁA���̎��������݂�B���m�̂悤�ɐ�㍑�ےʉݑ̐��́AIMF�Ɍ�������B�o���R�[���ɂ��ƂÂ����ې��Z�����̎������u��]�v�����P�C���Y�ɂ��Ă݂�Ύ��ۂ̌����͕s�����ł������ɈႢ�Ȃ��B�������A�킽�����́A���ۓ��@���{�����߂邱�Ƃɐ��������Ƃ����Ӗ��ł́A�P�C���Y�I�l�������Ȃ������Ă���Ɣ��f����BIMF �́A���{����̎��R�Ɋւ��ẮA����߂ĐT�d���������炾�B���ۓI���{����̎��R�ɂ́A���{�̓��@�I�ړ]�⎑�{������e�F����댯��������������ł���B�P�C���Y�́A�o����x������琶����ύt�������炷�Z�����{�ړ��ƕs�ύt���������鋰��̂���Z�����{�ړ����s�ʂ��A��҂̋K����K�v�Ƃ����̂������B�o����x����̎��R�̎����ō��ۖf�Ղ̑��i��}��Ƃ����̂��P�C���Y�̍l���������BIMF �́A���{�ʐ��ł����ב֖{�ʐ��ł��Ȃ������B���{�ʐ��̂��Ƃł́A�e���̎����ʉ݂́A���ԃ��x���ɂ����ċ��̈��ʂƂ��ł������\�������B�����ʉ݂ƊO���ʉ݂Ƃ̌����́A���̋��Ƃ̌����䗦����������B�O���ʉ݂Ƃ̌����͎��R����������A�O���ב֑���́A���̋���������ɋ��̗A������l�������A���A���_�A���A�o�_�̋����͈͂Ɉ��肵�Ă����B�����A�����̎x�������z�����A�܂��撴�߂ƂȂ�A�����ʉ݂̌����䗦���㏸����B���ꂪ�A���A���_���z����A�x��������O���l�́A���������ʉ݂킸�ɁA�����w�����A����𑗂��Ďx�����s�Ȃ�����A�����ɋ������������B�t�ɁA�����̎x�����z���t�A�܂�x�����߂ƂȂ�A�����ʉ݂̌����䗦�͒ቺ����B���ꂪ�A���A�o�_�������A���������ʉ݂ŊO�݂킸�ɁA�����w�����A����𑗂��Ďx�����s�Ȃ�����A��������������o�����̂ł���B����́A���q�̃}���N�X�̎���̘b�ł���B
�P�C���Y��`�I�ɍl�Ă��ꂽIMF �́A���{�ʐ����Ƃ炸�A�����ʉ݂Ƌ��Ƃ̖��ԃ��x���ɂ����鎩�R�Ȍ����𐬗������Ȃ������B�M�����ɂ���č����o�ς̌o�ϐ��������Ƃ������{�ʐ��̍d��������̎��R���߂����ꂽ���炾�B���������āA�����ʉݑ��݂̌����́A�S�ʓI���R���琧�����ꂽ���̂܂ŁA���낢��Ȑ��x�v���\�������B�܂��A���̌����䗦���ב֑���Ɋ��S�ɂ䂾�˂�ϓ����ꐧ����A�Œ�I�Ȉב֑���܂ŁA���܂��܂ȕ��@���z�肳�ꂽ27)�BIMF �́A�����ʉݑ��݂̌����ɂ��āA�f�ՂȂǂ̌o��I�x���̐�����p�~���邱�Ƃɏd�_��u���A��8���ɉ������͌����Ƃ��Čo��I�x���ɐ������ۂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƒ�߂��B�܂��A�בւ̌����䗦�́A�Œ葊�ꐧ���̗p�����B����́A����̕ϓ��𗘗p���ē��@�I���v�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���u���@�I�����Ɓv�̏o����j�~���鑕�u�������B�����́A��������P�C���Y��`�I���z�����s�Ɉڂ������̂������B�P�C���Y�́A���@�̊댯���ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ����Ƃ�����B�u���@�Ƃ́A��Ƃ̒����ȗ���ɕ����ԖA���Ƃ��ĂȂ�A�Ȃ�̊Q���^���Ȃ��ł��낤�B�������A��Ƃ����@�̉Q���̂Ȃ��̖A���ƂȂ�ƁA���Ԃ͏d��ł���B�ꍑ�̎��{���W���q����̊����̕��Y���ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�d���͂��܂����������ɂȂ�28)�v�BIMF ����́A��4���Łu�e�������̒ʉ݂̕����́A���ʎړx������ɂ��A�܂���1944�N7��1�����݂̗ʖڋy�я�����L���鍇�O���̃h���ɂ��\������v�Ƃ����B��1�I���X��35�h���A�܂��e���ʉ݂ƃh���Ƃ̌����䗦(����)�́A��U�o�^�����Ƃ��̕ύX�ɂ�IMF �̏��F���K�v�Ƃ��ꂽ�B�ʉ݂̈ב֕ϓ��ɂ����ẮA�����̏㉺1���͈͓̔��Ɉێ����邱�Ƃ��`���t����ꂽ�̂ł���B
|
|
������3�@�Ȃ��������Z��@���p������̂� |
|
�����A���Z��@���p�����鎖�ԂƂȂ��Ă���B1980�N�㖖�č����~�ݕt�g���j�]�A1997�N�A�W�A�ʉ݊�@�A98�N���V�A�E���[�u����@�A�܂����{��1997�N����8�N�ɂ����Đ[���ȋ��Z��@�ɑ�������B2002�N�ɂ́A�s����v�E�������Z�ɒ[����Ċ����s������A������2007�N�Ă��猻�݂Ɏ���T�u�v���C�����ɂ�鍑�ۓI���Z��@�ł���B���̂��тɁA�u29�N���Q�̍ė����v�Ƒ�����A��@�̂��A�A��������ΔM����Y��A�܂��ĂсA���Z��@�����E���P���Ƃ����L�l���B�Ȃ��A�������Ċ�@�͌J��Ԃ����̂��B
|
��1�@���Z��@�p���̍����v��
����͑��ɁA�}���N�X���w�E�����u����Z�Ǝ҂Ɗ��������l�����v�̗͂��������A����ǂ����ƂɁA�ނ�̐����o�ϓI�͂����債�Ă��邩�炾�B�������A����͂ǂ̂悤�ɂ��ĉ\�ƂȂ����̂��낤���B���āA1844�N��s�@���A����Z�Ǝ҂̎��{�̋��~�ςɉʂ��������x�I�����ɂ��ẮA�}���N�X���_�����Ƃ��肾�B�����Ř_���ׂ��́A1929�N�勰�Q���_�@�Ƃ��ċ��Z�ɂ������Ă����K�����ǂ̂悤�ɂ͂�����Ă��������ł���B���̕č��o�ςɂ����ċ��Z��@�������߂��̂́A���[�Y���F���g�����ɂ����Z�������߂������������炾�����B���[�Y���F���g�������ō������������߂��w�����[�E���[�Q���\�[�́A�č����Ȃ���Ƃ���P�C���Y�I���Z�V�X�e���̍\�z�Ɏ��g�ݐ�������B�j���[�f�B�[������̖ړI�́A���Z���{���u�o�ς̎�l�v����u�o�ς̏��g�v���Ȃ߂邱�Ƃ�����29)�B����́A1933�N�O���X�E�X�e�B�[�K���@�ƂȂ�A�܂�1935�N��s�@�ƂȂ��Ď��s���ꂽ�B�O�҂́A���Ƌ�s�Ɠ����֘A��Ђ�藣���A��҂́A�ʉݐM�p�̒����W���I�Ǘ������߁A�����ȂƘA�M������s�Ƃ̖��ڂȋ����W��搂����B�����A���̂́A�����ȂɘA�₪�]�����邱�Ƃ������B���Ƌ�s�̋����K����ƑԋK���A���܂��܂ȋK���ɂ���āA�č����Z�@�ւ́A������߂̏ɒu���ꑱ�����B�����A���̋��Z�K���́A1980�N�ォ�猀�I�Ɏ��R������Ă����B���̑�ꂪ1980�N���Z���x���v�@(1980�N�a�����Z�@�K���ɘa�E�ʉ݊Ǘ��@)�������B���̖@�́A����E���~�a���̋�������K����P�p�����B�܂��A���~�a���ɏ��؎蔭�s��F�߁A���~���Z�@�ւ̎��Y�^�p�͈͂��L�����B1982�N�a�����Z�@�֖@(1982�N�K�[�����Z���g�E�W�����C���a�����Z�@�֖@)�́A���~���Z�@�ւ̉c�Ɣ͈͂��g�債���B���̋��Z�K���P�p����́A�č��̒��~���Z�@�ւ̉c�Ɣ͈͂����L���A�����̎��R���́A���v�d���̃��X�L�[�ȑݕt�ւƔނ��U�����B����̉ʂĂ��A1980�N�㖖�̕Ē��~�ݕt�g���̕������B
1991�N12�����̋��Z��@���o�āA�A�M�a���ی����Љ��P�@�����������B���̖@�́A�a���ی����x�̍č\�z�������B�Ȃ��Ȃ�A���z�̌��I���������Z�@�ւɂ����܂�������Ȃ����Ԃɂ܂œW�J�������炾�B�����Œ��ڂ��ꂽ�̂��A��s�ւ̐V�������Ȏ��{�䗦�K���̎��{�������B���ی��ϋ�s�ł́A���Ȏ��{�䗦8���ȏオ��Ƃ����B���̘A�M�a���ی����Љ��P�@�ł́A���Ȏ��{�䗦�ɂ��ƂÂ���s��5�ތ^�ɕ����A10���ȏ�����Ȏ��{�䗦���[��������s�Ƃ����B���Ȏ��{�䗦��������s�ɂ́A���ʂɏ،��ƂȂǐV�K���Ƃ�F�߂�Ȃǂ̑[�u���Ƃ�ꂽ�̂��B����ɂ���āA�č����Ƌ�s�͂��܂܂ňȏ�ɏ،����r�W�l�X�ɂ͂܂荞��ł����̂ł���B1990�N��ɕč����Ƌ�s�́A����I�Ȏ��I�]���𐋂����Ƃ����悤�B1999�N�ɐ��������O���������[�`���u���C���[�@�́A���Ƌ�s�A������s�A�ی���ЁA�M����s�A������̋��Z�@�ւ����܂�������Z������Ђ̑n�݂����ւ����B�������āA�p���h���̔��͊J����ꂽ�B�Ђ��Ȃ�ʏ،����Z�r�W�l�X�����E�o�ς���绂��鎞�オ�����J�����̂��B
�č����Z�@�ւƂ�킯���Ƌ�s�̏،��������܂��������Ői�s���Ă����B���Ȃ킿�A����͋�s�ݕt�̏،����Ɣ���������Ɉˑ�����I�t�E�o�����X����̊g�傾�����B�����ł́A��s�ݕt�̏،����E�]���ɂ��Đ������悤�B��ʂɁA���Ƌ�s�͈�U�݂��t����A�ԍς����ׂĊ�������܂ō���ɂ����Ă����B��s�ݕt�̓]���Ƃ́A���̑ݕt�������̎萔��������ē����Ƃɔ��蕥�����Ƃ��B�K�����ǂ́A���Ƌ�s�����Ȏ��{�䗦�̏㏸��������B���̂��߁A�����̋�s�́A���Ȏ��{���[����������A�ݕt�������̎萔��������ē]�����邱�Ƃ��l����B�������ɂ���Ď��Ȏ��{�䗦���㏸�����悤�Ƃ���킯���B
��s�ݕt�̏،����Ƃ͂����Ȃ���̂Ȃ̂��B�����ł́A���j�I�ɌÂ����炠�郂�[�Q�[�W�S�ۏ،��s��ɂ��Đ������悤�B���[�Q�[�W�Ƃ́A�Z��E���ƁE�_�Ɨp�s���Y��S�ۂƂ���ݕt���̂��ƂŁA���ꂪ�،������ꂽ���̂��w���ꍇ������B���R���̃��[�Q�[�W�́A�Z����w�������l���Z������ۂɂ��̏Z���S�ۂƂ��č������������̂�����{���Z�����s�Ȃ������Z�@�ւ��ۗL���邱�ƂɂȂ�B�������A�č��ł́A���̃��[�Q�[�W�����@�ցA�A�M�Z������(FNMA�F�t�@�j�[�E���C)��1938�N�ɐݗ�����A���̔�����肪�s�Ȃ��邱�ƂƂȂ����B�������A���̔�����肪����ɂȂ����̂́A1970�N��ȍ~�̂��Ƃ����A���̃t�@�j�[�E���C�́A������������[�Q�[�W���v�[�����A���[�Q�[�W�S�ۏ،��s���A���肳�����Ƃɂ���̂��B���̔��肳���́A�E�H�[���E�X�g���[�g�̑�蓊����s���A���̒S�ۏ،��������s�Ȃ����ƂɂȂ�B���������āA�،��̑���̍w���҂̒��ɂ́A�ő勉�̔N�������ی���Ђ��܂܂�A�č��̏Z����Z�́A���܂�n���̏��K�͂ȋ��Z�s�ꂩ�甲���o���A�č��̋���ȏ،��s��̈�p�ɑg�ݍ��܂�邱�ƂɂȂ����̂ł���B�Z����Z�����ۂɍs�Ȃ����Z�@�ւ́A�n���ŁA�Z��̔��⌳���̎旧�Ă��̑��̋��Z�Ɩ��ɂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���[�Q�[�W�S�ۏ،����w�������ŏI�����Ƃ́A���炻�������Ɩ��ɔς킳��邱�Ƃ͂Ȃ��B
���������A���[���̏،����́A�č��ł́A�Z��[���ɓT�^�I�Ɍ��邱�Ƃ��o���邪�A�����ԃ��[���A������ƒ��̑ݕt�A�R���s���[�^��g���b�N�̃��[�X�ȂǂȂǁA�ɘ_����A�����シ�ׂĂ̑ݕt���琶��������،������錻�ۂ��N�����Ă���̂��B�]���A���Ƌ�s�́A�a�������Ƒݕt�������琶���闘������ɂ���ĉc�Ƃ��Ă����B�������A���݂ł́A�萔������������߂đ傫�Ȋ������߂�Ɏ������B1999�N���ɂ����āA�č����Ƌ�s�S�����̂Ȃ��43����������^�̎����ɂ���Đ�߂�ꂽ�B������^�萔���Ƃ́A�N���W�b�g�E�J�[�h�萔���A���[�Q�[�W�E�T�[�r�X��t�@�C�i���X�萔���A�~���[�`�����E�t�@���h�̔��T�[�r�X�萔���A�،������ꂽ�ݕt���琶����萔��������B����ҐM�p�̏،������}�L���Ă���A�č��̏��Ƌ�s�͂܂��܂��A�،��s��Ƃ̊֘A���������Ă���̂�30)�B
2007�N�Ă��烈�[���b�p�ɋN����2008�N9��15�����[�}���E�u���U�[�Y�j�]�ň�C�ɋ��Z���Q�ƂȂ������ݐi�s���̊�@�́A���̌o�ς̏،����ɂ��̊�{�v�������߂邱�Ƃ��o���悤�B�����܂ł��Ȃ��A��@�̔��[�́A�T�u�v���C�����[���̏ł��t���ɂ������B�T�u�v���C�����[���Ƃ́A�N���W�b�g�E�J�[�h�̎x�����o�����A�����J��Ԃ��悤�ȐM�p�͂̒Ⴂ�l��Ꮚ���ґw��Ώۂɂ����Z��[���̂��Ƃ��B2003�N��������č��o�ς͖{�i�I�i�C�ǖʂւƓ����Ă����B�C���t�����x������A��́A�]���̋��Z�ɘa������Z�������ߐ���ւƑǂ��B�ᗘ���[���Ń��t�@�C�i���X���J��Ԃ�����͉ߋ��̂��̂ƂȂ����B�����ŁA�ݕt��ɍ��������~�ȋ��Z�@�ւ��ڂɕt�����̂��T�u�v���C�����[���Ƃ����킯���B�ԍϔ\�͂̒Ⴂ�l�����̂��߂Ə̂��āA�ŏ��̓�A�O�N�́A��z�̕ԍϊz��ݒ肵�A���̌�A�˔@�ԍϊz���}�㏸������Ƃ������\�܂����̗��D�I���@�ɂ���đݕt���g�債���B�݂��t����ꂽ�T�u�v���C�����[���́A�����Z�@�ւ��������A���[�����،������āA�P���̃T�u�v���C���֘A���i�ɓ����������ړI���(SIV)�ɔ̔�����B�T�u�v���C�����[���ؓ������A�O�N�́A�ł��t���͔������Ȃ��B���̏،������i�́A���Ύ��������i�t����Ђ̕]�����K�v���B�g���v��A�ȂǂƂ����]���Ƌ��ɁA���E�̓����@�ւ֑�X�I�ɔ̔����ꂽ�Ƃ����킯���B�������A��A�O�N�o�ĂT�u�v���C�����[�����ł��t�����Ƃ͖��炩�������B2007�N�ĂɌ��݉������̂͂����������R���炾���A���Ă���{���܂߂đ����̋��Z�@�ւ��T�u�v���C�����[����g�ݍ����[�Q�[�W�S�ۏ،��ɑ��z�̓������s�Ȃ��Ă�������A���[���̎x���s���s���琶�������Z��@�́A���E�I�ɔg�y�����̂��B
���q�̂悤�ɁA�}���N�X�̎�������E���Q���A�C�M���X��k���n�ɐ��E�ɔg�y�������Ƃ��������B�ߏ�A���E�ߏ�A�o�������ŁA�e�ޔ��˂̂悤�Ɏ��X�Ɗe�������E���Q�Ɋ������܂�Ă������킯���B�܂�A�}���N�X�̎���́A���{�ʐ��̉��ŁA���ۖf�Ղ̉ߏ肩�狰�Q�����E�������B�����A�ŋ߂̋��Z��@�ł́A���ێ��{�����̏ł��t������@�������N�����Ă���̂��B�f�Վ��x�E�o����x��̖��ł͂Ȃ��A���{���x��̖��Ȃ̂��B�Ȃ������Ȃ̂��B�߂����߂Ę_���Ă݂悤�B
|
��2�@���Z��@�p���̍��ۗv��
����̋��Z��@�����E�I�ɔg�y����̂́A���ۓI���{����̎��R���ƂƂ��ɁA���ۓI���@���{�̊����̎��R�����i�W��������ł���B1971�N8��15���̋��ƃh���Ƃ̌�����~�A1973�N�ϓ����ꐧ�ւ̈ڍs�A�����ĕč��ɂ�鍑�ۓI���{����̎��R���́A���̐��E�o�ϑ̐�������A����ɂȂ���V���R��`�I���E�o�ϑ̐����߂��������j�I����Ƃ��Ĉʒu�Â��邱�Ƃ��o����Ƃ킽�����͍l����B���E�o�ςɂ�����č��̖����Ƃ����ϓ_���猩��A���ۖf�Ղ𒆐S�Ƃ���u���E�̋�s�v���獑�ۓI���{����𒆐S�Ɍ`�����ꂽ�h������Ƃ���u���E�̓�����s�v�ւ̓]�����Ƃ����邾�낤�B���ێ��x�ɂ����鎑�{����̎��R���́A�ϓ����ꐧ�ւ̈ڍs��K�R������B�Ȃ��Ȃ�A���{����̎��R����F�߂Ȃ���A�Œ葊�ꐧ���ێ����邱�Ƃ́A���{�̗��o���ɑ��Ēʉݓ��ǂ́A�˂Ɉב։������������Ȃ����炾�B�����Ȃ�ƍ����̃}�l�[�T�v���C�ɑ���Ȃ�e����^�����˂Ȃ�����A���Z����̎��������ێ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���{����̎��R���ɂ���āA�č��o�ς̍��ێ��x��ɂ͂ǂ̂悤�ȕω������ꂽ�Ƃ�����̂��낤���B
���{����̎��R���́A�o����x�������ɑ��āA���{���x�������̋}���������炵���B���āA���[�j���́A�w�鍑��`�_�x�Ŏ��̂悤�Ɏw�E�������Ƃ�����B�u���R���������S�Ɏx�z����Â����{��`�ɂƂ��ẮA���i�̗A�o���T�^�I�ł������B�����A�Ɛ�̂��x�z����ŐV�̎��{��`�ɂƂ��ẮA���{�̗A�o���T�^�I�ƂȂ����v31)�B���̃A�i���W�[�ɏ]���A�킽�������́A���̂悤�Ɍ������Ƃ��o���邾�낤�B�u�P�C���Y��`���x�z���Ă����Â����{��`�ɂƂ��ẮA���i�̗A�o���T�^�I�ł������B�����A�V���R��`���x�z����ŐV�̎��{��`�ɂƂ��ẮA���{�̗A�o���T�^�I�ƂȂ����v�ƁB
���č��̃j�N�\���������A���ێ��{����̎��R���ւƁA�č��̑ΊO�o�ϐ���������Ă������̂��B1980�N��ɂȂ�ƁA�����o�ς̌��͂́A���č��o�ς̎x�z�I�K���ł���������Y�Ɗ�ƂƘJ���g������Ȃ�u�P�C���Y�A���v����A�č������Њ�ƂƋ�s����Ȃ鐢�E�I���Z�e���ւƈڍs�����B���āA�č����������w�����[�E���[�Q���\�[�́A���E�̋��Z���S�n�������h���ƃj���[���[�N����č������ȂɈڂ����ƂɐS�����������A�����݂������ۋ��Z�́u�_�a�v���炽�����o�����Ƃɐ��������B�������A���ꂩ��ق�50�N�A����͌��I�ɕω������B���ۋ��Z�́u�_�a�v���炽�����o���ꂽ�͂��̋��Z���{�́A�j�N�\�������ȗ�����ɗ͂����A�o�ϗ݂͂̂Ȃ炸�������͂����D�҂���܂łɐ��������B
����ł́A�č��ɂ����āA�������͂�D�悵�����Z���{���A���ۓI�ȋ��Z���R���ɂǂ̂悤�ɏ��o���Ă������̂��B���̎����̕č����{�́A�u�h���̗́v��ɓԂ��邢�͈���I�ȊO�����ɂ���āA���Z�̎��R�����������Ă������B�����ł͂킪�����{���ɂƂ�A�����������悤�B���{�Ƃ̌��́A1983�N�A�č��哝�̃��i���h�E���[�K�����K�������Ƃ��Ɏn�܂�B���̔N��11���Ɂu���āE�~�h���ψ���v���ݒu����A��̓I�ɓ��{���Z�s��̎��R�����c�_���ꂽ�B�č��`�[���́A�����ȁA���s�A�،���Ђ̑�\����Ȃ��|����Ȃ��̂������B�����ɂ́A�č����Z���{�̈ӋC���݂�������ꂽ���A�ނ�̗v���́A�ב֎���̎��������Ɖ~�]���K���̓P�p�������B
�ב֎���̎��������Ƃ́A�����ɓ��@��ړI�Ƃ���敨�ב֎����}�����邽�߂ɐ����{���Ƃ��Ă����[�u�������B���̑[�u�́A�o����x�̎���ɔ����ȊO�̎��̎���Ɋ�Â��Ȃ��敨��������������������̂��B���P�C���Y�I�ȍ��ےʉ݃V�X�e���ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂������B�Ȃ��Ȃ�A���@��ړI�Ƃ���敨�ב֎�����������Ȃ�A���̎���Ɋ�Â��Ȃ�����҂��̍��ۓI���@���{��������绂���ƂȂ邩�炾�B�������A����͂��łɕϓ����ꐧ�ւƈڍs���Ă����B�č��̓����t�@���h�͂��ߋ��Z�@�ւ́A����̕ϓ��𗘗p�����r�҂��ɑ傢�Ɋ��҂������Ă����̂��B1984�N4��1���A�����������͂ɍR�����ꂸ�A���{�͈ב֎���̎���������P�p����̂������B
�~�]���K���Ƃ́A�C�O����̓��@�����̍���������h���ړI�Ŏ��ꂽ���̈ב֊Ǘ������̈�������B�����A�C�O���痬�����A��Џ������j�Y���O�̉�Ђ̊����̋�ɂ���đ�ׂ����A�C�O�Ɏ��v���������邢����n�Q�^�J�E�t�@���h���b��ɏ�邪�A�����������@��������{�̐��ۂŌ��ނ���ɂ͍D�s���̃V�X�e���������B�����A���̋K�����A�č����̋����v�]�œ��N6���A�p�~����邱�ƂƂȂ����B
���ێ��{����̎��R���ɂ���ĕč��́A���Z��ʂ��ċ���Ȍo�ϓI�e�����m�����铹����ݎn�߂��B1980�N��㔼����90�N��ɂ����Đ��E�I�ɓW�J���ꂽ���ێ��x�ɂ����鎑�{���x����̎��R��������������Ă���B���A�W�A�ł́A�C���h���͂��ߑ����̔��W�r�㍑�����{���x�������̎��R���A1991�N12���A�\�A�M���Ō�A���̌X���̓O���[�o���ɓW�J���A�����̍��ō��ێ��{����̎��R�����i�W�����B�킪�����{�ł́A1998�N4���Ɂu�O���בy�ъO���f�Ֆ@�v���{�s����A�O���ב��F��s�y�ї��֏��̔F���x��p�~���A�O���בƖ��̎Q�������R�������B�܂��A�C�O���������R�ɂ��A�C�O�Ƃ̊O���ב֎���ɂ����鎖�O������p�~�����B�����������ێ��{����̎��R���́A�������n��ւ̎��{�̐��E�I�K�͂̏W���I�����ɂ��o�ϓI�����Ɠ��@�̍s���߂��������炵�A���Z��@�U���̗v���ƂȂ�̂��B�������A�č������Њ�ƁE��s�ɂƂ��ẮA���{�����ۓI�ɓ������A���v��������܂��ƂȂ��@��ƂȂ�B�Ƃ�킯�A�č����Ƌ�s�́A�،������ꂽ�s�ꂩ�甜��Ȏ��v�������Ă���A�܂����E�I�ȋ��Z�̏،����́A�č����Z�@�ւ̌o�ϓI�e���̊�ՂƂȂ��Ă���̂��B
�������āA����̊O���ב֎s��ɂ����ẮA���̌���v���Ƃ��āA���ۊԂ̎��Y�^�p���d�v�ȃt�@�N�^�[�ƂȂ��Ă����B���܂�A�O���ב֎s��ɂ����ăh���̎��v�����́A�f�Ղɂ���č��o����镔���ɔ�r���āA���ێ��Y�^�p�ɂ���č��o����镔��������߂đ傫���Ȃ����̂��B�������A���̍��ێ��Y�^�p�ɂ́A�č��ɂ�����،����̋}���Ȑi�W����������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�č��o�ς̋}���ȏ،����́A�܂��ɕč��^���Z�V�X�e���̌`�����Ӗ�����̂����A����́A�č��̏،��s��̒n�ʂ��e�i�ɏ㏸�������B���āA�Y�Ƌ��Z�̍T���߂Ȓ���҂ł������č����Ƌ�s���،��s��ƌ��т��A���܂�č��،��s��ɂ́A���E����̓����������W�����A�č��،��s��ɂ����Č`���������Z���{���Y�s�ꂪ�h���̈בփ��[�g�����肵�Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
���̋��Z���Y�s��ŁA�����Ƃ͂ǂ̂悤�ɍs������̂��낤���B�P�C���Y�ɂ��A�����̕]����ĕ]���́A���̊��s(convention)�ɗ����čs�Ȃ���B�����s���́A�Z���Ԃ̔��f�̘A���ƂȂ�̂ŁA���Ȃ�u����v�������̂ɂȂ肦��B�Љ�S�̂Ƃ��Ă����Ȃ���肵�������������炷���Ƃ��o����ƃP�C���Y�͂����B�������A�����ɂ��̓����Ƃ̊��s�́A�������̗v���ŕs����◊��Ȃ��������Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�Љ�̓������z���������钆�ŁA�o�c�ɎQ�����Ȃ��ŁA����̎��Ƃ̌��݂Ə����ɂ��ē��ʂ̒m���������Ȃ��l�X�̏��L���������āA���������̕]���ɒm���̌��������l�тƂ̕]�����d�v���������Ă��邩�炾�B�����A�����͈͂͐��E�I�Ɋg�����Ă���B�Ⴆ�A�n���̗����̂��鍑�̍����A���̍��̎�����m�炸�ɗ����̗ǂ����甃���Ă��܂����ƂȂǂ���������B�܂��A�ꎞ�̌i�C���炠���Ђ̊����̎s��]�����}�����邱�Ƃ�����B�����̖��m�Ȍl�̌Q�W�S���̎Y���Ƃ��Ă���グ��ꂽ���s�ɂ��]���́A�����m�M���鍪��������Ȃ��߁A�������ϓ��ɎN����邱�Ƃ�����B���݂̎��Ԃ������Ɏ�������Ƃ������Ƃ����������������Ȃ��Ă���ƁA�����̓����Ƃ͋}���ɔߊϓI�ɍs��������̂��B���݁A�����������Ԃ����ۓI���Z��@�Ƃ��āA������u�`�����ʁv�����o���Ă��邱�Ƃ͂悭�m����B�T�u�v���C�����ɒ[����č����Z��@���A�S�ʓI�h���������o���Ă���Ƃ��������̎��Ԃ��A���Y�s��̍��ۉ����h������ɐ[���ȉe����^���Ă�����Ƃ�����̂��B
�P�C���Y�́A�u�������A�����̒��ڂɒl����Ƃ�킯�����I�Ȃ��Ƃ�����v�Əq�ׂāA���s�̗���Ȃ��ƁA���I�Ȍ��l�̓����ƂⓊ�@�Ƃ̍s���l���Ƃ̊֘A�ɒ��ڂ���B���Ȃ킿�A�u�����̐l�X�̑命���̎傽��S�́A�����������炻�̑S�������Ԃɂ킽���ē�����W�R�I�Ȏ��v�Ɋւ��Ă����ꂽ�����\��������̂ł͂Ȃ��A��ʑ�O�ɋ͂��ɐ�ĕ]���̊��s�I�Ȋ�b�̕ω���\�����邱�Ƃɂ���v�Ƃ����B�������āA�u���l�̓����Ƃ́A�o����s��S���ɍł������e������悤�Ȏ�ނ́A���╵�͋C�́A�����������ω����ė\�z���邱�ƂɊS��������������Ȃ��̂ł���32)�v�ƂȂ�B�����Ԃɂ킽�铊���̗\�z���v��\������Ƃ��������Ɩ{���̎d������A�ނ����A�O�����̊��s�I�]���̊�b��\�����悤�Ƃ��鋕�X���X�̋삯�����̐킢�ƂȂ�̂��B
�������āA�����s��̑g�D�̉��P���Ȃ����ɂ�āA���@���D�ʂ��߂�댯�����債�Ă���B���E�I�Ɏ��R�ȓ����V�X�e�����`�������ɂ��������āA���ۓI�ɓ��@���{��������绂���댯�����債�Ă����̂��B���R�s��̖��̂��Ƃɂ����ɔ�����I�o�σp�t�H�[�}���X���s���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����Ȃ̂ł���B�������A�����������ۓI���@���{�̎��R�ȓW�J�𐧓x�I�ɑn�炴��Ȃ��Ƃ���ɁA�����A�č����u���ꂽ���E�o�ϓI������邱�Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�č��������s�ꂠ�邢�͂����ƍL���������Z���Y�s����E�̎������W�������邱�Ƃɂ���āA�h���̈בփ��[�g���ێ����A����E����z�����h���x�z�̐������������悤�ƍl���Ă��邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��B
|
|
���܂Ƃ߂ɂ�����
|
�����A���E�o�ϓI�ȏ̈Ⴂ������Ƃ͂����A�}���N�X���w���{�_�x�ŋc�_�������Z���Q�̔����̏����́A�����Ă���Ƃ������Ƃ��ł��悤�B�u����Z�Ǝ҂Ɗ��������l�����v�̌o�ϓI�͂́A����߂đ傫���Ȃ��Ă��邵�A���ۓI���@���{�����́A�͂Ȃ͂������ɓW�J���Ă��邩�炾�B���������āA���Z���Q���N����ƁA�u����勰�Q���I�v�ƂȂ�̂��B�����A�}���N�X�̎���ƈقȂ錈��I�����������B��ꂪ�A���݂́A���{�ʐ��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�������ɁAIMF �ɂ��Œ葊�ꐧ����ł́A���ۓ��@���{�����������݁A���Z�̉��\���R���g���[���ł��Ă����B����ɔ�r���A���݂̕ϓ����ꐧ�̎���ł́A���ۓ��@���{�̊����ȓ���������A���Z�̉��\���ڂɕt�����ԂƂȂ��Ă���B������A�}���N�X���_�����悤�ɁA���݂ɂ����Ă����Q���̐M�p��`����d����`�ւ̓]���͋N����̂��B�������A���{�ʐ��̎���������������ꂽ������s�́A���̍Ō�̑ݎ�@�\�𑶕��ɐ������A���Q�~�ς̎����������ً}�ɍs�Ȃ��Ă���B���ݐi�s���̋��Z��@�ɂ����Ă��A�e��������s�̍s����������ꂪ�悭�����ł��邾�낤�B��A�o�ςɂ����鍑�ƍ����̋K�͂��}���N�X�̎���Ƃ͌��Ⴂ�ɑ��債�Ă��邱�Ƃ��B�V���R��`�́u�����Ȑ��{�v�ɂ����Ă��A���Ƒ���Z�@�ւƂ������ƂɂȂ�A���Ƃ́A���I�������ӂ�ɂ����݂Ȃ���~�ς����s����B�������āA���Z���Y���i�̋}���E�\���Ƃ������Z�s���萫�́A�\���I�ɂ��������ɒ��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�J��Ԃ���邱�ƂƂȂ�B�������A���̋}���E�\���̐U�����ŋ߂ɂȂ�i�i�ɑ傫���Ȃ����B���������āA���Z���Y�̓������A����Y�Ɗ�Ƃ̉^�������E����悤�Ȏ��Ԃ������N�����܂łɂȂ����B����ҐM�p�ɑ傫���ˑ������č��r�b�O�X���[�̌o�c��@�A���邢�́A�}���ɐi�ރh�����E�~���ɂ���āA�A�����Z���}���Ɉ����������g���^�����Ԃ̌o�c�ȂǁA�����̂悢�Ⴞ�낤�B
����ꂪ���܂Ȃ��ׂ��ً}�̉ۑ�́A���ۓI���@�����̕������߂ł���B���㐢�E�o�ς���@�Ɋׂ��t�@�N�^�[�́A�\�����鎩�R�ȓ����V�X�e���ɂ���̂��B�����ł킽�������w�E�������̂́A���R�s��̖��̂��Ƃɂ����ɔ�����I�o�σp�t�H�[�}���X���s�Ȃ��Ă������Ƃ������Ƃł���B���̃V�X�e����ϊv���邱�Ƃ͂�����₷�����Ƃł͂Ȃ��B�������A���Z���P�Ȃ�o�u���̕���ł͂Ȃ��A���̌o�ςɐ[���ȉe��������ڂ��n�߂����܁A���̔�����Ȏ��R�ȓ����V�X�e���̎~�g���ɋ��߂��Ă���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤33)�B
|
����
1)�@�J�[���E�}���N�X�A���{�_�|��ψ����w���{�_�x�I�A�V���{�o�ŎЁA1987�N�A754p
2)�`17)�@�����
18)�@J.K.�K���u���C�X���A�s���d�l�Ė�w�V�����Y�ƍ��Ɓx��2�ŁA�͏o���[�V�ЁA1972�N�A85p
19)�@P.A.�o�����AP.M.�X�E�B�[�W�[���A�����h�m��w�Ɛ莑�{�x��g���X�A1967�N�A23�|4p
20)�@A.A.�o�[���AG.C.�~�[���Y���A�k�����j��w�ߑ㊔����ЂƎ��L���Y�x���듰���X�A1958�N���Q�Ƃ̂��ƁB
21)�@A.S.�A�C�N�i�[���A����O�Ė�w�����ƂƉǐ�\�}�N�����w�̃~�N���I��b�\�x���{�o�ϕ]�_�ЁA1983�N�A41p
22)�@����A55�|67p
23)�@����A68p
24)�@�ْ��w�A�����J�o�ϐ���j�x�L��t�A1996�N�A64p
25)�@�u�ŋy�іf�ՂɊւ����ʋ���v�R�{����ق��ҁw���ۏ��W�x�L��t�A1996�N�A352p
26)�@J.M.�P�C���Y���A����J�S���w�ٗp�E���q����щݕ��̈�ʗ��_�x���m�o�ϐV��ЁA1995�N�A385p
27)�@�O��`�v���w���x��g�V���A1968�N�A7p
28)�@�P�C���Y�A�O�f�A157p
29)�@Richard N. Gardner�A Sterling-Dollar Diplomacy�A The Origins of Our International Economic Order�A McGraw Hill Book Company�A New York�A1969.p.76.16 �w�Љ�V�X�e�������x(��18��)
30)�@William F. Bassett and Egon Zakrajsek�A �gProfits and Balance Sheet Developments at U.S. Commercial Banks in1999�A�hFederal Reserve Bulletin�A June2000�A pp.379�|80
31)�@���[�j�����A������T��w�鍑��`�_�x�������ɁA1961�N�A80p
32)�@�P�C���Y�A�O�f�A154p
33)�@�ڍׂ́A�ْ��w�č��͂����ɂ��Đ��E�o�ς��x�z�������x���ЁA2008�N�A221�|4p
�@ |
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
�����b |
   �@
�@
|
 �@ �@
���u�s���Ȃ̂Ɋ������オ��v���낵�� |
�u�o�ϐ��������E���Q�v�̃��J�j�Y��
���������i���ɏ㏸�������邱�Ƃ͂Ȃ�
���{�o�ς́u����ꂽ20�N�v�������N�������̂́A1989�N�̊����\���Ɏn�܂�o�u������ł����B�������ۂ��A�u�I�����_�̃`���[���b�v�E�o�u���v�u�C�M���X�̓�C�o�u�������v�A�����āu1929�N�̐��E���Q�v�ł��N�������̂ł��B
��ꎟ���E���ŘA�����������ɓ����A�������{�������ɂȂ�Ȃ������A�����J���O���͋�O�̌o�ϑ卑�ɐ������A���E�ő�̍����ɂȂ�܂��B���[���b�p�o�ς͂܂��������炸�A�č�����̗A�o�͍D���ł����B�f�Ս����ɉ����A��풆�ɔ����Ă��������[���b�p�����̐펞���̏���(�x����)���n�܂�A��ʂ̎������j���[���[�N�̃E�H�[���X�ɗ��ꍞ�݂܂��B
�E�H�[���X�̋��Z���{�́A�����̎�������Ƃɒᗘ�ő݂����܂��B��Ƃ̌o�c�҂́A�H��̐��Y���C���Ȃǐݔ������Ɏ����𓊉����܂��B
�t�H�[�h�����Ԃ́A�ŏ��̏���������p�Ԃł���s�^�t�H�[�h��̔����A�[�l�����E�G���N�g���b�N��(�f�d)�̗①�ɁE����@�E���W�I����ʉƒ�ɕ��y�����̂����̎���ł��B���{�ł�1960�N��Ɏn�܂�����ʐ��Y�E��ʏ���Љ�A1920�N��̃A�����J�ł͂��łɎ������Ă����̂ł��B
�������㏸���A�����͉Ɠd��N���}�����߁A��������A�y�n�ɓ�������悤�ɂȂ�܂����B�����̊�������w�̘b��ɂȂ�A�}�X�R�~����������܂����B
�������A�v���̓����Ƃ����\��s��،���Ђɂ͂킩���Ă����̂ł��B�������i���ɏ㏸�������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��c�c�B
|
���o�ϐ����̓X�g�b�v�B�����������͏㏸�B�Ȃ����H
1920�N��㔼�ɂ̓��[���b�p�o�ς��������A�A�����J����̗A�o�̓s�[�N���Ă��܂����B����ɔ����Ċ�Ƃ͔���c�������i�̍ɂ�����A���v���}�C�i�X�ɓ]���A�o�ϐ������͑��ꂵ����܂����B
�܂�A���̌o�ς̕s���͂��łɎn�܂��Ă����̂ɁA�����m��Ȃ������������Ɏ���o���Ă������߁A�����������ُ�ȏ㏸�𑱂��Ă����̂ł��B�܂��Ƀo�u���ł��B
�u�E�H�[���X�̌C�����̏��N�����̘b�����Ă���̂��āA����̓��o���Ǝv�����v�ƌ�����͓̂����Ƃ̃p�g���b�N�E�P�l�f�B�ł��B�ނ͖\�����O�Ɋ��蓦���A����ȗ��v�܂����B
�ނ͂��̎��������鐭���Ƃɓ������܂��B1932�N�̑哝�̑I���œ��I�����e�E���[�Y���F���g�ł��B�p�g���b�N�͌��J�҂Ƃ��Đ��E���肵�A���p��g�ɔ��F����܂����B�哝�̂ɂȂ�Ƃ����p�g���b�N�̖��́A���j�̃W�����E�e�E�P�l�f�B�Ɉ����p����܂��B
1929�N1���A����������w�i�ɁA�t�[���@�[�哝�̂��{�����j�����̒��Łu�A�����J�͕n�������������v�Ǝ��掩�^���܂������A�j�]�͂������������������̂ł��B
�j���[���[�N�A�E�H�[���X�̊����s��ł́A���N9�����s�[�N�Ƃ��Ċ����͏��X�ɉ�����n�߂܂����B�����āA�^���̓����K��܂��B
|
���u�o�ϐ��������E���Q�v�̌����Ƃ́H
10��24���A�u�Í��̖ؗj���v�ɑ�\�����n�܂�܂����B������7����1�ɉ����A�\������1�T�ԂŊ����s���300���h���̑������o���܂����B����͓����̃A�����J�A�M���{��10�N���̍��Ɨ\�Z�ɕC�G���܂��B
�j�Y�҂����o���A�������������낻���Ɛl�X����s�ɎE���������߁A��s���������͊����ĉc�ƒ�~�ɒǂ����܂�܂��B��s���玑���B�ł��Ȃ��Ȃ�����Ƃ̘A���|�Y���n�܂�A�|�Y���Ȃ�������Ƃ���K�͂Ȑl�����ق��n�߂܂��B4�l��1�l�����Ƃ���Ƃ����ُ펖�Ԃ̒��A1932�N�̑哝�̑I���ł͌��E�̃t�[���@�[�哝��(���a�})����s���A�j���[���[�N�B�m���������e�E���[�Y���F���g(����})���哝�̂ɓ��I���܂��B
��ꎟ���E���̔s�퍑�h�C�c�́A�A�����J����̓����Ōo�ϕ�����i�߁A�������x�������s���Ă��܂����B���������E���Q���n�܂�ƁA�A�����J�̋��Z���{�͊C�O�ɓ������Ă�����������ĂɈ��������Ă��܂��܂��B
�h�C�c�͓_�H���O���ꂽ���҂̂悤�Ȃ��̂ł����B�����܂������̊�Ƃ��|�Y���A���Ɨ���50���ɔ���܂��B����܂ŁA�������̎x�����Ƌ����O����i�߂Ă����Љ��}�����́A�����̎x���������܂����B
����Ȓ��A�������x���������ۂ��A�A���n�ĕ�����v�����鐭���Ƃ��A�~����̂��Ƃ��o�ꂵ�A�h�C�c������M�������܂��B�A�h���t�E�q�g���[�ł��B �@ |
 �@ �@
�������\���j |
   �@
�@
|
��1929�N�@�E�H�[���X��\��
�_�E�H�Ɗ����ς�6�N�ԏオ�葱���ē�����5�{�ɂȂ�A1929�N9��3���ɍō��l381.17��t������ŁA�s���1�����ԋ}�~�����A�������߂��猩���17%���������B�����͂��̌��1�T�Ԉȏ�ɂ킽���ĉ������̔������������A���̒���ɂ܂��������邾���������B������͉������A��\�������ƂȂ���1929�N10��24���́A������u���b�N�T�[�Y�f�[���}�����B���̓��͓����̋L�^�j��ƂȂ�1�A290������������ꂽ�B
���E���Q���A�����J����N�����������Ƃ��Ă͎��̂悤�Ȃ��Ƃ���������B
�����ԁE���w�E�d�C�Ȃǂ̐V�����Y�Ƃ̔��W�E�Y�Ƃ̍������ɂ��H�Ɛ��Y�͂̑���E����ɂƂ��Ȃ��ߏ�Ȑݔ������Ȃǂɂ���čH�Ɛ��i�����Y�ߏ�Ɋׂ��Ă������ƁB
���Ő���̉e���ō��ۖf�Ղ��L�єY��ł������ƁB
�_�ƕ���ł��A�푈������̑��Y�ɂ���Ĕ_�Y���̋������}�����Ă����Ƃ���ցA��ト�[���b�p�̕����ɂ���ă��[���b�p�̎��v���������A�_�Y�����i���}�����Ĕ_�ƕs�����[�������Ă������ƁB
�_�ƕs���ɂ���Ĕ_���̍w���͂��ቺ���A�܂����Y���̐L�тɔ�ׂĘJ���҂̒������Ⴍ�}����ꂽ�̂ō����̍w���͂��ቺ�������ƁB
�v����ɁA���Y�ߏ�ƍ����̍w���͂̒ቺ�ɂ���Ď��v�Ƌ����̃o�����X���傫�����ꂽ���Ƃ������ł������B�����āA��㐢�E�̎��{���A�����J�ɏW�����A���ꂪ�y�n�⊔���̓��@�Ɏg���A�ߏ�ȓ��@�u�[�����N�����Ă������Ƃ�������\���̒��ڂ̌����ƂȂ����B
���n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�哝��
�n�[�o�[�g�E�t�[���@�[�哝�̂́A�f�Օs�U�𐢊E���Q�̌����Ƃ݂Ȃ��A�f�ՐU���̊ϓ_����t�[���@�[�����g���A������A��ꎟ���E���̔������̎x�����P�\�����������ŁA�呝�Ŗ@�Ă�ʂ��ė������ލΓ��𑝂₻���Ƃ��A�ی��`�̃X���[�g�E�z�[���[�Ŗ@�ɏ����������A����̓J�i�_�A�C�M���X�A�h�C�c�Ȃǖf�Ց��荑�̕��ĂB�A�����J�o�ς͕s���Ɋׂ����B1932�N�܂łɎ��Ɨ���23.6���ɂ��Ȃ����B�͏d�H�ƁA���ދƁA�A�o�p�_�Y��(�ȉԁA�����A�^�o�R)����эH�Ƃň��������B�z���C�g�J���[��y�H�Ƃł͂���قLj����Ȃ�����
�����E���Q�ƃ��[�}���V���b�N��r
�u�����v�́E�E�E���E���Q���̉�������3�N�ԂŖ�87���ł��B���̋L���ł͖�1�N�ԂŖ�27���ł��B����������͂�����ƑO�̋L���ł��̂ŁA���݂̓}�C�i�X40�����炢�����B
�u���Ɨ��v�́E�E�E���E���Q���͖�4�N�ԂŖ�3�������25���ɏ㏸���܂����B����͖�1�N�Ԃ�4.7������6.1%�ɏ㏸���܂����B���E���Q���ɂ͋�s�̎�t���������������߂ɋ��Z�@�ւ��X�g�b�v���A���ꂪ���Ɨ��̌����Ɍq����܂������A����͂���ȑ������N�����Ă��܂���B
|
��1971�N�@�j�N�\���V���b�N
1971�N8��15���ɁA�e���r�ƃ��W�I�őS�ĂɌ����ĐV�o�ϐ���(���łƍΏo�팸�A�ٗp���i��A���i����̔����A���h��������~�A10���̗A���ے����̓���)��d���I�ɔ��\���A���̒��́u���h��������~(���ƃh���Ƃ̌Œ�䗦�ł̌�����~)�v�̂��Ƃ���Ɏw���B���̋��h��������~�́A�č��c��ɂ����O�ɒm�炳��Ă��炸�A�ɂ߂đ傫�ȋ�����^���A�܂����ꂪ���E�o�ςɐr��ȉe����^�������Ƃ���u�h���V���b�N�v�Ƃ��Ă��B
���j�N�\���E�V���b�N�ƗA�o�Y�Ƃ̑Ō�
���̎������N����܂ŁA�h���͋��ƃ����N���A�܂�1�h����360�~�ɌŒ肳��Ă��܂����B1971�N8��15���A�j�N�\���哝�̂́A���E�ɍ��܂�h���s���ɑΏ����邽�߁A���ƃh���Ƃ̌������~����ƂƂ��ɁA�ꗥ10���̗A���ے�����ݒ肵�܂��B�������\��A�����e���͓I�m�Ȕ����������A�����̈ב֑�����A�ϓ����ꐧ�ɒ����Ɉڍs�����܂��B���{�́A�����ɂ��ڍs���x��A8��26���ϓ����ꐧ�ɂȂ�܂�(���̂��߁A�����̕x���s���ɊC�O�ɗ��������ƌ����܂�)�B
�~����́A�����𑱂��܂��B���������E���邽�ߓ��N12���A�A�����J�̃X�~�\�j�A�������قɂ������i10����������c���J�Â���܂��B��c�ł̓h���̐؉����A�~�ƃ}���N�̐؏グ���s���A1�h��308�~�ƌ��肳��܂����B(���̌�1973�N2�����S�ȕϓ����ꐧ�ɖ߂�܂��B)
���̎����ɂ���āA�A�o�Y�Ƃ́A��Ō����܂��B���ɁA���D�ƊE�́A�A�o�D�̌����_�h�����ł��������߁A��2400���~�̈ב֍����������ނ�܂��B
���u�h����308�~����ϓ����Ɂv�@�ב֗��j�̐ߖ�
1971(���a46)�N8��15���̃j�N�\���V���b�N�̌��12��19���A��㒷���������u���g���E�Y�̐�������1�h��360�~����ɏI�����������B���{�͓����A�~����̏㏸��h���ׂ��ăh���̔����x�����s�������A8��28���ɂ͉�����~�A8�����ɂ̓t�����X��������v���͂��ׂČŒ葊�ꐧ���痣�E���A12���ɕăh���̐艺�����܂ޑ��p�I�ʉݒ����ō��ӂ��݂�ꂽ(������X�~�\�j�A���̐��̐���)�B
���j�N�\���V���b�N
�j�N�\���E�V���b�N�ɂ��A�h����GOLD�Ɍ����ł��Ȃ��Ȃ邱�ƂŁA���{�ʐ��x�͏I�����}���܂����B�j�N�\���E�V���b�N�����\�����O��A��ʂɃh������~�����̎�����Ȃ���܂����B�C�M���X��h�C�c�Ȃǎ�v�����ב֎s���������̂ł����A���{�͗��V�Ɉב֎s����J�������A�h�����x�����܂����B��ʂ̃h�������߂̉~�����ɔ��s�������̂ł��B���̌��ʁA��ʂ̉~���s��ɋ������邱�ƂƂȂ�A�����̓��{�̕�����傫���グ�邱�ƂƂȂ�܂����B
���j�b�|���̕���_
71�N8��16���B���~�x�ݖ����̌��j���ŁA�̂�т肵�����[�h���Y���Ă����呠��(��������)���������ɁA�ݓ��č���g�ق���1�{�̓d�b���������̂͌ߑO9�����߂��̂��Ƃ������B�u�ߑO10������j�N�\���哝�̂��d�v�ȉ������s���\�肾�v�d�b�����̂́A�����������������s�V�L�Y(82)(�����ےʉ�����������)�B��ɓ��{���\����u�ʉ݃}�t�B�A�v�ƌĂ��s�V�͑����Ɉٕς��@�m�B�����ɍ������̍���犲���ɘA���A1��̃��W�I���͂ݎ����X�����B
|
��1987�N�@�u���b�N�}���f�[
1987�N10��19��(��)�A�j���[���[�N�،�������ŕ��ϊ�����508�h����������(22.6��)�Ƃ����j��ő�̑�\��������A���E���Q�̈������ɂȂ���1929�N10��29��(��)�́u�u���b�N�T�[�Y�f�C�v�����鉺�����Ƃ������ƂŁA���E�����푈�ł��N����̂ł͂Ȃ����Ƒ��R�Ƃ��܂����B
���̖\���̔w�i�ɂ́A�����A�����J�̍����Ԏ���f�ՐԎ����g��X���ɂ���X�ɂ̓h�����ŃC���t�����O�����������Ȃǂ�����܂��B�A�����J�̓C���t�����9��5���Ɍ��������0.5�������グ6���ɂ��܂������A10��14���ɔ��\���ꂽ�f�Վ��x���\�z��傫������Ԏ��z�ł��������Ƃ���A��Ɛ��тɑ���s���������܂����B
����������ɂ��Ă������܂ł̂Ƃ�ł��Ȃ��������ɂȂ�قǂ̗v�f�͖��������Ƃ����܂��B���̃u���b�N�}���f�[���N�����ő�̌����́A��������Ƃ́u�v���O��������v�ł����B
���u���b�N�}���f�[����
����Ƃ����������͍����ɕ������Ă��Ȃ��炵���̂ł����A�������茾���ƃp�j�b�N����A���肪������ĂԂƌ����������ł��傤���A�v���O�����ɂ�锄���͍��ƂȂ��Ă͓�����O�ł����A�����͂܂����j�����{�Ȃǂ����܂����c�����ĂȂ������悤�ł��B���ʃu���b�N�}���f�[�̉e���͐��E�̊����s��ɂ�����A���{�ł������،�������͊�����3836.48�~(14.9��)������\���B
|
��1991�N�@���{�o�u������@�@
���o�u���̔���
80�N��㔼�A�n���⊔���̏㏸���啝���p���I�Ȃ��̂ƂȂ�ɂ�A�����S�̂ɁA����Ȃ�l�オ����҂����܂��Ă������B���̉��i�㏸���҂��A�������@�ɂ����e�N�u�[����n�グ�Ȃǂɂ��ߓx�ȓy�n���@�ɂȂ���A���ȑ��B�I�Ɏ��Y���i���㏸�������B���Y�c���̒����������́A����ʂł͎��Y���ʂɂ��ϋv������𒆐S�ɏ���z�������A��ƂɂƂ��Ă͎��Y�̒S�۔\�͂̑���ɂ��V���Ȏ��ƓW�J��ݔ������̂��߂̎������B��e�Ղɂ����B
���o�u���̕���
�i�C�ߔM�ɂ��C���t�������𖢑R�ɖh�����߁A���������89�N5������5��ɂ킽���Ĉ����グ��ꂽ�B�܂��A�Ő��̌�������y�n�֘A�Z���̑��ʋK�������s���A�����̐���ɂ��A�����E�n���͋}�����A�o�u���̕��n�܂����B
�o�u���̕���́A�t���Y���ʂɂ��������������A�|�Y���������ق��A90�N��S�ʂɂ킽�钷���̌i�C����������炷���ƂƂȂ����B
|
��2001�N�@IT�o�u������@�@
������IT�֘A�x���`���[�͓|�Y�ɒǂ����܂�A2002�N�̕č�IT�֘A���ƎҐ���56���l�ɒB�����B�V���R���o���[�𒆐S�Ƃ����N�Ǝx���t�@���h�͈ꎞ�I�ɂł͂���k����p�~��]�V�Ȃ�����A�O�[�O���A�A�}�]���E�h�b�g�R����e-�x�C�ȂLjꕔ�̃x���`���[�݂̂������c�����B�����̕s���̍Œ��A2001�N9��11���ɓ��������e�����������A�A�����J�͐[���ȕs���֓˓������B�}�C�N���\�t�g��C���e���A�f����q���[���b�g�E�p�b�J�[�h�ȂNJ�����IT�֘A���ƎҁA���邢�̓x���C�]����AT&T���r���e�B�ȂǒʐM���Ǝ҂Ȃǂ̊������啝�ɉ����������A�{�Ƃ��^����ꂽ�e���͌y���Ȃ��̂ł������B���P�[�u���̉ߏ�~�ݖ��(�_�[�N�t�@�C�o)�̍ĔR�����O���ꂽ���A���ł�90�N��㔼�̉ߏ蓊���̌o������}���I�ɓ�������Ă������Ƃ�����AIT�o�u������ɂƂ��Ȃ��_�[�N�t�@�C�o�̕s�Ǎ����ɂ��Ă͌��O�����قǂ̖��͐����Ȃ������B |
��2006�N�@���C�u�h�A�V���b�N�@�@
2005�N7���ȍ~�A���o���ς�7����1��2000�~�䂩��1��6000�~��ɂ܂ʼn���ȂǁA���{�o�ς̕������ے����邩�̂悤�ȁA�����㏸�����ڂ���Ă����B�����s��͐V�K�̌l�����Ƃ��ʂɈ������ꊈ����悵�Ă���A�ʏ�A���������X�I�Ɉ������Ƃ̂Ȃ��X�|�[�c�V���Ɂu�o�u���ė����H�v�̌��o�����x��ATV�ԑg�ł͊��������Ƃ̂Ȃ��|�\�l���u���ł�����ׂ����邩�H�v�Ȃǂ̓��W���g�܂��ȂǁA1980�N��㔼�̂�����o�u���i�C�����f�i�������Ԃł������B���̂悤�ȏɂ����ă��C�u�h�A�ɂ�镲���^�f���������o���A�V���s������̋}���Ɗ����s��S�̂̍������������B���C�u�h�A��1�����S�~���x���甄���ł��閣�͂��瑽���̌l�����Ƃ������Ă������Ƃ�����A2006�N1��16�����Ђւ̋����{���͎Љ�I���ۂƂ��ĘA�����f�B�A�Ŏ��グ��ꂽ�B
|
��2007�N�`�@���E���Z��@
��2008�N�@���[�}���V���b�N�@�@
���E���Z��@�́A�T�u�v���C�����[�����(�T�u�v���C���Z��[����@)�����������Ƃ���2007�N�̃A�����J�̏Z��o�u������ɒ[���A2013�N���݂Ɏ���܂ő����Ă��鍑�ۓI�ȋ��Z��@�̂��Ƃł���B����[�Ƃ����o�ϕs���̐��E�I�A���͐��E�����s���Ƃ��Ă��B
2008�N9��29���ɃA�����J���O�����@���ً}�o�ψ��艻�@�Ă���U�ی������̂��@�ɁA�j���[���[�N�،�����s��̃_�E���ϊ����͎j��ő��777�h���̖\�����L�^�����B
���T�u�v���C�����
�D�i�C�ɕ����A�����J�ŏZ��u�[�����N���܂����B�������A�Ƃ��ɂ͍��z�̔�p���K�v�Ȃ��߁A���[����g�ޕK�v������A���̃��[�����Ԃ����Ă̖����l�ɂ݂͑����Ƃ��ł��Ȃ����߁A�w������Z���S�ۂƂ�������݂����x���ł����̂ł��B�ŏ���2�`3�N�͋������Ⴂ�̂ł����A�N�����o�߂���ɂ�ċ������㏸����Ƃ����V�X�e���ŁA��X�̎x�������ꂵ���Ȃ�͖̂ڂɌ����Ă���̂ł����A���̍��ɂ͏Z��l���㏸���邽�߁A���̉��l�̕��܂����[����g��ŕԍςɂ܂킹��Ƃ����Z�i�ł����B �������A���ۂɂ͏Z��l���オ�邱�Ƃ͖����A���ʂƂ��ďZ��w���҂̓��[�����x�������Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B
|
�� 2010�N�`�@�[����@�E�M���V���V���b�N�@
���[����@�Ƃ́AEU(���B�A��)�̋����ʉ݂ł��郆�[���̒ʉ݉��l�������@�̂��Ƃł���A�M���V���̌o�ϊ�@�����̌����ł���ƌ����܂��B���XEU�ɉ������Ă��鍑�͍����Ԏ������Ȃ����������ł����B�ł����A�M���V���͂����̕�����EU�ɉ������Ă��܂����B
����͐�������サ�����Ƃɂ�蔻�������̂ł����A���̃M���V����EU�S�̂ʼn����悤�Ƃ����̂����[����@�̌����ł��B�M���V���͉ǂ��납�A����ɏ�͈����Ȃ�A����ɔ������[���̉��l�͋}�����Ă��܂��Ă��܂��B���̉e���͓��R�A�h�~�h�ɂ��^���A���ł͂��Ȃ�̉~���ɂȂ��Ă��܂��ˁB�@ |
 �@ �@
������̋��Q�ƃ}���N�X���Q�_ |
   �@
�@
|
|
��1 �����I�ߒ��̎����ɂ����镪�� |
�����̓}���N�X�o�ϊw�͌��㎑�{��`�̌����ߒ��̕��͂̂��߂ɗL���ł���A��{�I�Ȏ��_������������̂��ƍl���Ă���B���������㎑�{��`�̌��������̓}���N�X���Q�_�ɏd��ȓ_�œ����N���Ă���Ƃ�����B����͌��㎑�{��`�_���Ƃ������O�ł�ڂ�A�����\�N�ȏ�_�c����Ă�����̎�v�ȕ������������Â����Ă���B��O�̓�Z�N�Ԃɂ���ׂāA���̓�Z�N��̋��Q�ƎY�Əz�̗l���͕ω����Ă���B���ɂ����Ď��{��`���E�Ŗ��炩�Ɂu�s���v�̌��ۂ������ꂽ�N�̈��ܔ��N�ł��A�H�Ɛ��Y�̒ቺ�����������̂́A�A�����J�A���i�_����уx���M�[�ŁA���̍��X�ł͍H�Ɛ��Y�̃X���[�E�_�E�\�����������ɂ����Ȃ������B�܂��ł��T�^�I�ɍH�Ɛ��Y�̒ቺ�����������A�������ł��A����Z�|�O�Z�N��̋��Q�̂Ƃ��ɂ���ׂāA�H�Ɛ��Y�̒ቺ�̋Ђ͂͂邩�ɏ������A�ቺ�̑��������Ԃ͂͂邩�ɒZ�������B���̂悤�Ȉ�A�̎��Ԃ̕ω��ɂ��ƂÂ��āA�ߑ�o�ϊw�̑�����̓}���N�X���Q�_�͌��㎑�{��`�ɂ������ėL���ł͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����咣������A�}���N�X�o�ϊw�҂̂������ł͐��̋��Q�ƎY�Əz�ɂ��Ă̌����̑���Ƙ_���Ƃ�����Ă���B�����̃}���N�X�o�ϊw���߂���ᔻ�Ƙ_���Ƃ��������Ċ�����̂́A�B���ꂪ���ە��͂ƌ��ۉ��߂ɂƂǂ܂��Ă��āA�@�}���N�X���Q�_�̊�b���_�Ƃ̊֘A�����ɂ����Ȃ��Ă��邤��݂����邱�Ƃł���B�@���Ƃ��Ă����A�@�����̃}���N�X�o�ϊw�҂͐��̋��Q�ƎY�Əz�ɂ�����a���I���Ǐ���Ƃ炦�āA����ɐ�O�̐f�f���K�p�ł��邩�ł��Ȃ�����_���Ă���悤�Ɍ���������B�������}���N�X���Q�_�͂���a���_�ł͂����āA���{��`�I���Y�̉^���̐����w���������Ă���͂Âł���B�����͐��̌����ߒ��ɂ�������f�f�͐�㎑�{��`�̐����w�̂����ɂ��ׂ����ƍl����B�����Ă���ɂ����̂ۂ��Ă����ρA��㎑�{��`�̋��Q�ƎY�Əz�̕��͂̂��߂ɂ́A���Q�ɂ��Ă̊�b���_���̂��̂��m������˂���Ȃ��B
�����ɋ��Q�̊�b���_�ɂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�}���N�X�͊������ꂽ���Q�_�������Ă��炸�A���̌�p�҂����̋��Q�_�ɂ��Ẳ��߂͂����炸������v���Ă��Ȃ��̂ŁA�M�҂̋��Q�_�ɂ��Ă̌����̗v�_���ׂ̂Ă������Ƃ��{�e�̎��Ƃ̊֘A�ŕK�v�ɂȂ�B�}���N�X�̍l�����ɂ������ċ��Q�Ƃ͉����Ƃ������Ƃ�ł����A����͎��{�̉��l�j��ɂ�鎑�{��`�I���Y�̋ύt�̉ł���B���{��`�I���Y�̐��i�͉��l���B�ߒ��ł���A���{�ɕ�ۂ���鉿�l�ʑԁE���l�͏u�̎������̉^���͑��B�ߒ��ɁA�����Ė�����ݐς�����B���̖����̔����ł���A�����ɖ�����\�͓I�ɉ���������̂����Q�ł���B�}���N�X�͋��Q�����̂悤�ɂƂ炦�āA�Đ��Y�ƒ~�ς̉ߒ��ɂ����Ă������̓I�ɉ𖾂��邽�߂Ɏ��{��ʂ̎����Ə����{�̋����̎����Ƃ���@�_�I�ɁA��ʂ��Ă���B���{��ʂ̘_���\���̂��ƂŁA�������̌X���I�ቺ�������Ď��{��`�I���Y�̓��I�����������I���Q�������邱�Ƃ����o�����B���Q�͏��i�̉ߏ萶�Y�Ƃ��Ď����̏�Ŕ������邪�A���̍ʑԂɂ����Ĕ������閵���͎��{�̑��B�ߒ��ŗݐς�����̂ł���B���{��ʂ̎����ł͋��Q�͂܂����ۓI�ȉ^���̉ߒ��Ƃ��Đ�������ɂ����Ȃ����A����ƂƂ��Ɂ[�Y�Ǝ��{�̉^���Ƃ��Ă̎��{��`�I���Y�̈�ʓI�A�{���I�ȗv���Ƃ��Ă̋��Q�A���Ȃ킿���{��`�̊�{�I�����̔����ł���A���{�̉^���̊�{�I�ߒ��ł���Ƃ���̋��Q�̑��ʂ������炩�ɂ����B���ɏ����{�̋����̎����ŁA�m��I���v�̕ϓ��Ƃ���ɂ��s��W�̕ϓ��Ƃ����ĎY�Ǝ��{�̉^�����Nj������B�����ł͎Y�Ǝ��{�̉^���͐��Y���{�i���邢�͌������{�j�Ɖݕ����{�̑��ݍ�p�Ƃ��Ă�����A�����ƒ���̂ق��ɁB���q�������̔͐��Ƃ��Đ������A�������́A���s��ɂ����鏤�i���i�A���q�A����̕ϓ��ɂ���ċK�������s�ꗘ�����̌`�Ԃ��Ƃ�悤�ɂȂ�B�����Ă����̉��i�A�����̏��͐��̕ϓ��ƎY�Ǝ��{�̉^���Ƃ̑��ݍ�p�Ɂ[����ĎY�Əz�̉^���`�Ԃ��������A���Q�͎Y�Əz�̈�̋ǖʂƂ��Ĕ���������̂ƂȂ�B���Q�͂��̎����Ŏs��̋K�����������̓I�Ȏ��{��`�̉^���ߒ��ƂȂ�A����ɐ��E�s��ɁB�����鏤�i�Ɖݕ��̉^�����ӂ��߂čl����Ƃ��A���E�s�ꋰ�Q�Ƃ��Ĕ������A�����ߒ��̕��͂̕����Â����������闝�_�I�ȋ�̐������T�O�ƂȂ�B
��������ꂪ�����ߒ��͂���ꍇ�A�Ƃ��Ɍ��㎑�{��`�ɁB�����錻���ߒ��͂���ꍇ�A������̗��_�I��Ƃ��̂�����Ă���悤�ɂ�������B�����̓}���N�X�̕��@�ɂ���āA��̗��_�I��������ʂ��ċ��Q���𖾂�����̂����A���̐��ʂ��鏔�K�肾���ł������ɐ��̋��Q�ƎY�Əz�͂���킰�ɂ͂����Ȃ��B�}���N�X�o�ϊw�҂̈ꕔ�̐l�X����㋰�Q�͂���ꍇ�A���i���i�̉����������I���Q�̖{���I�����Ƃ��āA���i���i�̉����̂Ȃ��������Ƃ�������I���Q���������Ă��Ȃ��Ɣ��f�����͈̂�̗�ł��邪�A����͋��Q�ƎY�Əz�q�̌��ی`�Ԃ��ω����邱�Ƃ��l�����Ȃ��Ō������͂�������݂����̂ł���B���̂悤�ȍl�����ŁA���̌����ߒ����Ƃ肠�����ꍇ�A���Q�ƎY�Əz�Ƃ��Ă������ۂ͂��͂�ǂ��ɂ����o���ꂸ�A���Q�͏��ł����Ƃ������_�ɂ������邱�Ƃɂ��邾�낤�B�����͋��Q�ƎY�Əz�̌��ۍʑԂ��ω���������̂ł���Ƃ����O����݂Ƃ߂˂Ȃ�Ȃ��B�@�������Ȃ��猻�ی`�Ԃ̕ω��Ƃ����Ă��A�@���ی`�Ԃ͂˂ɕω���������̂ł��邵�A�܂��ω��𗅗������ł͌��ۋL�q�ȏ�̂��̂͏o�Ă��Ȃ��B���̌����ߒ��̕��͂ł́A���Q�ƎY�Əz�̕ω��̊�{�I�ȕ����������炩�ɂ��A�^���l���ɂ��Ĉ�ʓI�ȋK����������邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ�B���̗��_�I�ȉۑ���A���Q�̊�b���_�̂���Ƌ�ʂ���Ƃ���ځA����������I�ߒ��̎����ɂ����鋰�Q���͂Ƃ�Ԃ��Ƃ��ł���B�X�^�[���\�͂��̔ӔN�̒���u�\�A�ɂ�����m���`�̌o�ϓI�����v�ŁA���㎑�{��`�̊�{�I�o�ϖ@���Ƃ��������N�����B����́A�Ɛ莑�{��`�ɂ�����Đ��Y�ƒ~�ς̉^���l���ɂ��ēƐ�i�K�Ƃ��Ă̈�ʓI�ȋK������Ƃ߂�Ƃ����Ӗ��ɉ�����ρA���F���Ă悢��Ă��ӂ���ł����B���������ő�������̖@���Ƃ����X�^�[���\�̃e�[�[������I�ɐ�`����A�o�ϊw�I�ɂ͐[�߂�ꂽ���܂܂ɁA���ɂ����悹���X�^�[���\�ᔻ�̔g�ɂ���đ��肳���Ă��܂����B���㎑�{��`�ɂ����鋰�Q���͂ł́A�X�^�[���\�̌��_�͕ʂƂ��āA���̒i�K�ɂ����錻�ۂ̎�v�ȕω��ɂ��������ʓI�K���Nj����ׂ����Ƃ������z�͍ĔF������Ă�����ׂ��ł���B
�@ |
| ����@�~�ωߒ��ɂ�����u���Ǝ��{�v�@ |
   �@
�@
|
���[�j�\�͒鍑��`�i�K�A�����킿�Ɛ莑�{��`�̑��̓����Ƃ��Đ��Y�̏W�ςƓƐ�������A�u�H�Ƃ̋���Ȑ��ʂƁA�܂��܂���K�͉����Ă�����Ƃւ̐��Y�̏W���̂��ǂ낭�قNj}���ȉߒ��Ƃ́A���{��`�̂����Ƃ������I�ȓ����̈�ł���v�Ƃׂ̂Ă���B�H�Ƃ̐����Ƒ�K�͊�Ƃւ̐��Y�̏W���Ƃ͐��ɂ����Ă����{��`������Â����{�I�ȌX���ł���A���̏Ռ��̂��������̔��W�͐��̒~�ωߒ��ɂ������邵���\���I�ȕω����Ђ��������Ă���B����͓m��I�����{�̂Ȃ��ł��߂�u���Ǝ��{�v�̔�d�����債�Ă��邱�Ƃɂ�����Ă���B�����ɂ��������̂́A�`�E�}�f�B�\�\�́u���m�ɂ�����o�ϐ����v����̈��p�ł��邪�A���ꂩ������N�ɂ�����e�����������z�ɂ������鍑�Ɓi���{����ь�����Ɓj�̌Œ蓊���̔䗦���݂邱�Ƃ��ł���B���̔䗦�͓Ɛ�i�K�ɂ͂����Ĉ�Ⴕ�đ������A�Ƃ��ɐ��̎����ɂȂ�Ƒ����̕��������߂Ă���B�����Ƃ����ď����̈����Ƃ��Ă݂�ƁA���Ƃ̌Œ蓊���̂��߂�䗦�͂��ꂼ��̍����o�ς̓`���I����Ɛ��̐���̍���ɂ���Ă�����傫�Ȃ����������X�̂������ɂ݂Ƃ߂���B�Y�Ƃ̍��L���������Ȃ��Ă���C�M���X�ł͎l�O�E�こ�ɂ̂ڂ�A�S���E�d�M�d�b�܂ł�����Ƃɂ���Čo�c����Ă���A�����J�ł͈�Z�E�ł���A�������邵�������������߂��Ă���B�����������̐��x�I�ȑ���ɂ�������炸���{�K�͂̑�^���Ǝ��{�̏W���ɂ�āu���Ǝ��{�v�̔䗦�͑S�ʓI�ɑ��債�Ă���B�u���{�̓m��{�v�̂������Ă��鎑���Ɂ[���A�A�������ł����Ƃ̌Œ蓊���������e�Œ蓊���̂Ȃ��ł��߂��d�́A���܈�N�̈�O�E�O����Z�Z�N�̈ꎵ�E���ɑ��債�Ă���B
�u���Ǝ��{�v�̔�d�̑��������Ɏ��I����ɁB���������������̊W�̕ω��Ƃ��Ď��{�̍\���Ȃ����`�Ԃ̕ω������ɒ��ڂ���Ȃ�ڕ\�ʓI�Ȋώ@�ɂƂǂ܂邱�ƂɂȂ邾�낤�B���̌X���͂܂��ɍH�Ƃ̐����Ɗ�Ƃ̑�K�͉��̉ߒ������ݏo�����Ƃ���̂��̂ł���B�H�ƓI���Y���܂��܂����剻����Ɛ��Ƃ̎�ɏW������ɂ�āA���̒��ړI���Y�ߒ��͍L�ĂȊ֘A����ւ̑�K�͂ȓ�����K�v�Ƃ���B�����ԎY�Ƃ̔��W�����H�Ԃ̐�����K�v�Ƃ��A�Ζ��Y�ƂƐΖ����w�Y�Ƃ̔��W���`�p�ݔ��̋��剻��K�v�Ƃ��A��R�\�r�i�[�g�̌��݂��H�Ɨp�n�̊J����K�v�Ƃ���̂͂��̎���ł���B���̂��߂̓����͍��Ƃ̌��ɂ䂾�˂���B���̌X���͂��łɏ\�㐢�I�̏I��ɓƐ��Ƃ��o�������Ƃ��ɂ�����Ă����B�G�\�Q���X�́u���f���[���\�O�_�v�ŁA���̌X���ɂ��Ď��̂悤�ɂׂ̂Ă����B�@�u�Ƃق����Ȃ����債�Ă䂭���Y���͂��A���̎��{�I�����ɂ������Ă����Ȃ����̔��R�A���̓m��I�{���̏��F�����܂邱�̂����܂��Ă������v�����́A���{�ƊK�����̂��̂ɂ������āA���{�W�̓����ł��悻�\�Ȃ�����ŁA�܂��܂��A�����̐��Y���͂�m��I���Y�͂Ƃ��ĂƂ肠�������Ƃ���������̂ł���B�@�������̐M�p�c�����Ƃ��Ȃ��Y�ƍ��������A�@���傽���{��`�I��Ƃ̓|�炭�鋰�Q�~���g���̂��̂��A�Ȃ��������������̐��Y��i�����āA����̊�����m�ɂ݂���悤�ȓm��̌`�Ԃ��Ƃ邱�Ƃ��悬�Ȃ�������B�����̐��Y�P�P��ʎ�i�̂Ȃ��ɂہA�S���̂悤�ɂP�A���Ƃ��Ɣ��ɑ�K�͂Ȃ��߂ɁA���̂����Ȃ鎑�{��`�I���`�Ԃ����������Ȃ����̂������B�Ƃ��낪������̔��W�i�K�ɂ�������ƁA���̌`�Ԃł��������͂₶�䂤�Ԃ�ł͂Ȃ��B���{��`�m��̌��̑�\�҂ł��鍑�Ƃ��A���ǁA���Y�̊Ǘ������˂ڂȂ�Ȃ����Ƃɂ���B���̍��L�ւ̓]���̕K�v�́A�܂Ñ��ɁA��K�͂���ʎ{�݁A�����킿�X�ցA�d�M�A�d�b�A�S���̏ꍇ�Ɍ�����B�v�@�����̋���ȋK�͂̌Œ莑�{��K�v�Ƃ��镔�傪���Ƃ̊Ǘ��ɂ䂾�˂���̂́A�������̒ቺ��j�~���悤�Ƃ��鎑�{�̗v���ɂ��ƂÂ����̂ł���B�Ɛ莑�{��`�i�K�̏����ɂP���łɌ��v�Y�ƂƂ�ڂ�镔��͍��Ƃ܂��͒n�����{�̌o�c�ɂ䂾�˂���̂����ʂł������B��㎑�{��`�̋Z�p�v�V�ɁA���V�����Y�Ƃ̔��W�́A����Ɛ�ɓ����̍L��ȕ��������B�������w�Y�ƁA�d�q�Y�Ƃ���ёϋv������Y�Ɠ��͂���ł��邪�A�����̕���ł̎Y�Ɠ����̑���ƂƂ��ɁA������[���邽�߂̓��������Ƃ̖����傳���Ă���̂ł���B���܂��̕���̎��{�́u�m��{�v�Ƃ�ڂ�A���̎�ނ̓����̊g�[�̕K�v���������ڂ�Ă���B���̕���̎��{���S���@�\�͂��̌������A�m��ɂ���Ƃ����Ă��邪�A�@�u�m��{�v�̎g���́A���I���{�̊�ƍ̎Z���炷��ڗ������̒ቺ���������悤�Ȕ�����I��������������Ƃ�������������̂ł��邱�Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̕����������ڎ��̂悤�Ȃ��̂ɑ�ʂł��邾�낤�B��A��b�Y�Ƃ̍��L�A���ގY�Ƃ̍��L�A��A���H�`�p�̌��݁A���y�ۑS�A�n��J���A���q���̂��߂̎��ƁA�O�A���v����ь�ʎY�ƁA�l�A���炨��ѓm����A�܁A�����J���A�Z�A���h�Y�ƁB�ȏ�͂��Ȃ炸���g�債���邱�̕���̂��ׂĂ�ԗ����Ă͂��Ȃ���������Ȃ��B���������������Ď��̂悤�ɂ������Ƃ��ł���B���㎑�{��`�̎Y�Ƒ̌n�́A�Ɛ莑�{�̎x�z����ʐ��Y�A��ʔ̔��̕����̂����ɐ������Ă���A�����J�Ŕ��W���A���܁Z�N��ɂ͂���Ɖ��B�A�ږ{�œ����傤�ȑ̌n�ƕ��������W������B���̓Ɛ莑�{�̎Y�Ƒ̌n���[�����邢�͏��������邽�߂ɁB�u���Ǝ��{�v�̌n�}���ɔ��W������̂ł���B���̓�̌n��͎��{�~�ς������鐶�Y�̓m��̕����𐄐i���邽�߂̈�̑̐����`�����A���̑��݊W���x�z������̂͗��������ł���B�ߑ㉻����A��]���l���̍����V���Y�ƕ��傪���I�Ɛ�̕���ɂ䂾�˂���̂ɂ������āA���������A��r�I�ɏ�]���l���̒Ⴂ��b�Y�ƕ���A�Ƃ��ɓS�|�E�ΒY�Y�Ƃ͍��L�������B�܂��V���Y�ƕ���̂����A���q�͎Y�ƁA�F���Y�Ƃ̂悤�ɁA�����ƊJ���̂��߂ɋ���ȓ�����K�v�Ƃ��A�������̒Ⴂ���삪����B���̌��������E�J�������̕���͍��Ƃ̎�ɂ䂾�˂���B�������璆������ђn�����{�̓y�؎��Ƃł��������H�E�`�p���̌��݂́A�Y�Ɠs�s�̔��W�A�l���̓s�s�W���ɂ���āA�܂��܂���K�͉����A�Y�Ƒ̌n�̔��W�Ɍ����ׂ��炴����̂ƂȂ�B�Ɛ莑�{��`���̎Y�ƓI���W�́A���Ɠ�����~�ωߒ��̂Ȃ��ɂ��݂���A���������̍��ƕ���̋K�͂��������邵�����剻����B�������č��ƓƐ莑�{��`�̍��������肠������B���ƓƐ莑�{��`�̓����͂���ɍ��Ƃ̊Ǘ����鋐��ȕ��I���{�̌n��������Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��B����ƂƂ��ɍ��ƍ������A�~�ωߒ��̉ݕ��ʂɂ����Ă��傫�Ȗ���������B���L��Ƃ����łȂ��A���I�Ɛ��Ƃ̉ݕ����{�����ƍ����Ɉˑ�����i�⒐�j�B���ʉߒ��ł̍��Ǝx�o�̖����̑���́A�ߑ�o�ϊw�����㎑�{��`�̓����Ƃ��Ďw�E����Ƃ���ł���A��������Ǝ��{��`���邢�͓�d�o�ςƂ��ł���B���Ƃ̎x�o�̖����̑���͐�㎑�{��`�̓����ł���A���Ǝx�o�̔�d�̑���͓m��I���v�����ƍ����Ɉˑ����邱�Ƃ��Ӗ����Ă��邪�A�����͍��Ƃ̓m��I���v���o�̋@�\�������݂�̂ł́A���̌o�ς̉^���̑ԗl�͉𖾂ł��Ȃ��ƍl����B���{�̏W���ɂ��~�ωߒ��̕ω��Ƃ������_�ɂ����āA���ʉߒ��̕ω��͂��Ȃ���ςȂ�Ȃ��B
���㎑�{��`�̒~�ςƍĐ��Y�̉ߒ����l����ꍇ�A���ƓƐ莑�{��`���邢�͍��ƓƐ莑�{��`�i�K�Ƃ������O�Ō��㎑�{��`����Ԃ��Ƃɂ���B���Ɠ�������э��Ə�������{����ё����v�̂Ȃ��ő傫�Ȗ���������������ł���B���������̖��O�Ō��㎑�{�{��`�����ł��A����͓Ɛ莑�{��`�Ƌ�ʂ��č��ƓƐ莑�{��`����̑S���V�������x�A�V�����i�K�Ƃ��ĂƂ肠�������̂ł͂Ȃ��B���ƓƐ莑�{��`�͓Ɛ莑�{��`�ł���A���̒i�K�ɂ�����m��I�����{�̉^�����x�z������̂́A���I�Ɛ莑�{�̑��B�̉^���ł���B�Ɛ��̋����ɋK������鎑�{�̑��A�̏Փ��������̗U�����ʐ����A���I���{�̒~�ς������ނƂ��A������[���邽�߂ɍ��Ƃɂ��Œ蓊���A���ƍ�����������ݕ��I���{�̒~�ς̑��傪�K�v�Ƃ����̂ł���B���̒i�K�ł͓m��̑����{�̍\���͓�̎�v�Ȏ��{�n��A���I�Ɛ莑�{�ƍ��Ǝ��{�Ƃ����ɂ���ƍl������B���̓�̎��{�n��̉^���́A��������ڂɗ�����Nj����鑝�B�̏Փ��Ɏx�z����Ă���̂ɁA�������āA�����͂��̏Փ����玩�R�ł���Ƃ�����B���������Ǝ��{�����I�Ɛ莑�{���[������̂ł���ȏ�A���̋�ʂ͖{���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B��̌n��̎��{�̉^���̂������͂���𐧖�ݕ��I�����ɂ���ƍl������B�M�p�̗v�����̂����Ă����ځA���I�Ɛ�̓����𐧖�ݕ��I�����͒��ڂɗ����ł���A���Ɠ����𐧖���͓̂m��I���l���Y���Ƃ��̎����ւ̔z���ł���B���Ɠ����̍����͏I�ǓI�ɁB�͑d�łł���A�d�ł͓m��I���l���Y���̑傢���Ƃ��̎����ւ̔z���ɂ���Đ����B����ɁB�������Ď��I�Ɛ莑�{�̓����̍����͎��{���擾���闘���ł���B�����͗������̌X���I�ቺ���l����̂ɁA���������Ƃ��������������Ƃ��ł���Bp�͗������Am�͏�]���l���Ac�͕s�ώ��{�Av�͉ώ��{�Ƃ���B����ɂ���č��ƓƐ莑�{��`�̂��Ƃł̎��{�̑��B�ߒ��������ɋK������邩���l���Ă݂悤�B���Ǝ��{�͂��̎���c�̍\������͂̂������B���������Ă��ꂾ��p��ቺ������c�̗ݐς͂ӂ�����邱�ƂɂȂ�B���������̂��Ƃ͗������ɁB�W�̂Ȃ��Œ莑�{�̒~�ς̕��@�����ꂽ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�Œ莑�{���������Ƃɂ���Ă����Ȃ��邽�߂ɂ́A���Ƃ͂��̂��߂̉ݕ��I������d�ł܂��͕��A�ɂ��Ƃ߂˂Ȃ�ʁB�����Ă��̉ݕ��͓m��I���l���Y������Ƃ肽�Ă���B���Ȃ킿�m��I���l���Y���͏�]���l�����ƕK�v�J���ɁB�A�����鉿�l�s���A��p�����ƂɁB�킩���ƍl����ځA���Ƃ̌Œ莑�{�����͏�]���l���������܂��͔�p�����h�����ꂾ�����k���邱�ƂɂP�Ȃ�B���������ā��������͂��ꂾ���ቺ����X�������߂��̂ł���A����c�̑����ɂ�钼�ڂ�p�̒ቺ��������Ȃ������ł���B�����͎��̂悤�ɂ������Ƃ��ł���B���ƓƐ莑�{��`�i�K�̓m��I�����{�̒~�ύ\���̂��ƂŁA�s�ώ��{�A�Ƃ��ɌŒ莑�{�̑���͂�����Ƃ��Ď��{�̉��l���B�ߒ��𐧖�X�����ӂ���ł���B���̐���ɂ�������炸�A���l���B�����{�̉��l�j����Ђ����������ƂȂ��ɂ����Ȃ��邽�߂ɂ́A���Ǝ��{�ɂ���ĕ����鎄�I���{�̑��傪�J���̓m��I���Y�������グ�A��]���l�����̐��Y�����Ǝ��{�̑���̂��߂̒lj��ݕ���������������ɏ\���ȂقǑ��傷�邱�Ƃ��K�v�ł���B����͒��ړI���Y�ߒ��ɂ��čl�������{�̉��l���B�̂��߂̕K�v�����ł���B���������̏������݂�����邩���Ȃ��́A����g�p���l�̐��Y�ߒ��ɂ����鐶�Y���̖��ł͂����A�����Ɨ��ʂ̉ߒ��ɂ����鎑�{�̏z�Ƒ��B�̏��W�����ӂ����̂̉ߒ��̂Ȃ��ōl�����˂Ȃ炽���B
�@ |
| ���O�@���ʉߒ��ɂ����鍑�Ǝx�o�@ |
   �@
�@
|
�������K������Ɛ�s��ɂ����闬�ʉߒ��ɂ��Ă͖��m�ɂ���˂ڂȂ�Ȃ����_��̖��_�������B���������̂悤�ȊT���I�ȋc�_�����Ă���ꏊ�ł���ɂ��킵���ӂ�邱�Ƃ͕s�\�ł���B���̂��Ƃ�O�Ă����͎��̂悤�ɍl����B���ƓƐ莑�{��`�̂��Ƃł̎����͓Ɛ艿�i�̎x�z����s��̏������ɂ���ċK�������B����͂�����ׂĂ̏��i���Ɛ��Ƃɂ���Đ��Y����A�̔�����邱�Ƃ�z�肷����̂ł͂Ȃ��B�����ł͑����̔�Ɛ菤�i���ӂ��ޓm��I���l���Y���̉��i���Ɛ艿�i���厲�Ƃ���̌n���`�����A���̉��i�̌n�̋@�\�������ĉ��l�����������Ȃ���̂ł���B���̂悤�ȉ��i�̌n����������ȑO�̋������i�̌n�̂��Ƃł́A�s�ꉿ�i�͐��Y���i���w�����ĉ^�����A���i�͂��̔�p���i�v���X���ϗ����̐����ʼn��l�����������Ȃ��Ƒz�肷�邱�Ƃ��ł����B���i���Y�҂̂������ɔ��R�ȋ����������Ȃ��Ă���s������ɂ����ẮA��]���l�͐��Y�҂̏[�p���鎑�{�ɔ�Ⴕ�Ă킯�Ƃ��A���i�̎s�ꉿ�i�͐��Y�ɂP�v������l�v���X��]���l�̔z���z�ɂ���Č��肳��A���̉��i�ɂӂ��܂���]���l�̔z���z�̂Ȃ�����Y�Ǝ��{�Ƃ͗��q�A�n��A�d�ł��x�������̂ł������B���Ȃ킿��]���l�̔z���ɂ���������ёd�ł̏��͎��͗�������̍T�����ł���A���i�ʐ��ɂ͎Q�������������B����ɂ������ēƐ�s��ł͓Ɛ菤�i�̉��i�͐��Y���i�ɂ���Ă͌��肳�ꂽ���B�Ɛ��Ƃɂ��s��̎x�z�́A�����̋���Ȏ��{�K�͂�����Ƃ��������A�����̊�Ƃ����i�s��ł͉��i�����������Ȃ킸�A���i�ɂ��ċ��肵�A�����𑀍삷���ԂƂ��đz�肵�Ă悢���낤�B���̂悤�ȏ����̂��Ƃł́A�Ɛ菤�i�̉��i�͐��Y���i�ȏ�ɂ肠�����A�Ɛ��Ƃ͕��ϗ����ȏ�̓Ɛ藘�����擾����B�Ɛ�̎x�z����s��ł́A�����ߒ��������ēƐ��Ƃ͏�]���l�̕��O���A�[�p���{�ɔ�Ⴗ�镔���ȏ�ɍ��߂邱�Ƃ��ł���B�Ɛ莑�{��`�̂��ƂœƐ��Ƃ̗����̌���͗��ʉߒ��������炭�ݏo�������̂ł͂Ȃ��B�������Ɛ艿�i�A���Ȃ킿���Y���i�ȏ�ւ̉��i�̂�グ�ɂ�闘�����Ɛ莑�{�̗����̈�̎�v�Ȍ���ł��邱�Ƃ͂������ł���A���̂悤�ȉ��i�̌n�������Ă����Ȃ�������ߒ��Ƌ������i�̌n�̂��Ƃł̂���Ƃ̍�����l���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�Ɛ艿�i�����Y���i�ɂ���Č��肳��ʂƂ���ځA���̉��i�͉��ɂ���Č��肳��邩�B�Ɛ肪���i�����グ�邱�Ƃ��ł���Ƃ����Ă��A����ɂ͌��x������B���i�������V���������҂����Ă��̎Y�ƕ���ɂ����点��قǍ����Ȃ�ρA�Ɛ肪�������Ȃ��Ȃ�B������Ɛ艿�i�͋����҂̎Q����j�~���鐅��������Ƃ���B���������̏���͓Ɛ艿�i�`���̈�̗v���ł���A�Ɛ艿�i�`���̎�v�ȓ����͎��̓_�ɂ���ƍl����ׂ��ł���B����́A�����s�����A��Ǝҗ����A���Ȃ킿�{���̎Y�Ǝ��{�̗�������z���A�m�����ۂ̂ق��ɁA��]���l�̕����Ɂ|����Đ�������������̔͐��A���q�A�n������킦�A����Ɋ�Ǝҗ����ւ̑d�ŕ��ۂ������킦�Č��肳��A���ꂪ��p���i�ɏ�ς݂���ĉ��i���������肷�邱�Ƃł���B�Ɛ艿�i�`���̓����́A��]���l�̕����ɂ���Đ������鏔�͐����Œ艻���A���ꂪ��p�ƂƂ��ɉ��i�����肷�邱�Ƃɂ���B�������i�̏ꍇ�ɂ́A���{��̋����ɂ���ĕ��ϗ����������܂�A���Y���i���s�ꉿ�i�����肵�A����ɂ���ė������擾�����B���q�A�n�㓙�͘_���I�ɁB�͂��̌�ɁA�����āA��������̍T����������ї����̕��������Ƃ��Đ���������̂ł���B����ɂ������ēƐ�s��ɂ����ẮA�V�K�����҂̎Q�����j�~����Ă��邩����@�i���������ĎQ���j�~���i�͓Ɛ艿�i�̏���������̂ł��邪�j�A���Y�ʂ͉��i�������z���A���q�A�n��A�d�ŁA����ɐV�����̂��߂̓m�����ۂ��ӂ��ޗ����̋Ђ���������悤�ɒ��������B�����̏�]���l���鐫�i�������͝��͎��O�ɉ��i�����ɂӂ��܂�A���̈Ӗ��ʼn��i�̌���v���Ƃ���̂ł���B����������͌Œ�I�����i�������A�܂����l���Y���̂܂��܂��傫���������킯�Ƃ�悤�ɂȂ�B�Ɛ��Ƃ͂��̓����̂��߂ɊO���̋��Z�@�ւ̑ݕt���Ə،����s�ƂɈˑ�����x���������A���Ȃ̗�����m���ɗ��ۂ��āA�����V�����ɂ��Ă�悤�ɂȂ�B�܂����Ƃ̓����Ə���̑���ƂƂ��ɁB�A���̍����̈�ߗ����ŁA�@�l�����ł̌`�ʼn�m���v�ɂ��Ƃ߂�悤�ɂȂ�B�m�����ۗ����Ɖ�m�ېł͓Ɛ藘���̌Œ�I�Ȑ��i�傳���A���i�����͔�p�̂ق��ɂ��̌Œ�I�ȗ����������ӂ��܂˂ڂȂ�Ȃ��Ȃ�B���̉��i�`���̑ԗl�͓Ɛ�̎s��x�z�͂����ݏo�����V�����X���ł��邪�A�����ɂ���͉��l�����̉ߒ��ɐV������������킦����̂ł���B
���̂悤�ȓƐ艿�i���ӂ��ޓƐ�i�K�̉��i�̌n�͂��ꔒ�̂Ƃ��Ă������邵���s�ύt�����ӂ��ނ��̂ł���B���̕s�ύt���͎��v�̏k�����Ɂ[�Ƃ��ɖ��炩�ɘI�悳���B����ɂ͓Ɛ艿�i���������傪����A�����ɂ͔�Ɛ艿�i���������傪����B�O�҂̕���͎��v�̏k���ɂ������āA���Y�𐧌����āA���i���i�̕�����ӂ����A�������̒ቺ�����Ђɂ����Ƃ߂邪�A��҂̓s��͋���������͂��������A���i�̒ᗎ��j�~���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����ڂ���łȂ��A�Ɛ蕔��Ɣ�Ɛ蕔��Ƃ̂������ɂ͑����̏ꍇ���Y�͊r��������B����������Ƃ��悭���߂����̂́A�ߑ�I�����H�ƂƔ_�ƂƂ̂������̊r���ł���B���i�̒ᗎ�ɂ������āA�����H�ƕ���͘J�����Y���̈��グ�ɂ���Ĕ�p�s�������k���Ă���ɑΉ������i�������Ă��邪�A�_�ƕ���͂����_���Ɣ_�ƘJ���҂̐��������̈������ɂ���đΉ�����ق��͂Ȃ��B�Ƃ͂������v�̏k���ɂ��Ō��ɂ������ēƐ��Ƃ͖Ɖu���������̂ł͂Ȃ��B�Ɛ��Ƃ͐��Y�𐧌����邱�ƂɁ[����ēƐ艿�i���ێ����傤�Ƃ���B���Y�����ɂ���Ĕ�p�����̂������ڔ�͍팸����邪�A��ڔ�͐��Y�����ɔ�Ⴕ�ĉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ɛ��Ƃ͕���傫�Ȗ�ڔ�I�x�o���ڂS���Ă���A���̕��S�͏k�����ꂽ���Y�z�ɁB�������Ă���B�Ɛ艿�i�̐����͋��Q���ɘa������̂ł͂Ȃ��B����O�̓�Z�N��̋��Q�̗��j���݂�ƁA���Q���ɂ�����H�Ɛ��i���i�̒ቺ�͂���ȑO�̎����������Ђł��������A���Y�̒ቺ�̓x���͂��傫�������B����͓Ɛ艿�i�̌n�̋��Q�ǖʂɂ������p�ł��邪�A���Q�ǖʂɂ����炸�Y�Əz�̑S�ߒ��������Đ��Y�̐����Ɂ|����Ďs��ɂ����鋟�������A���i�������ێ����悤�Ƃ��鋭���X���������炷�Ƃ������Ƃ��ł���B���������ċ@�B�ƍH��̗��p�x�͒ቺ���A�Ɛ��Ƃ̌v�Z���炷��A�Ԑڔ�̈������˂ɗ������ɂ�����A�m��I���Y�S�̂��炷��ځA�ߏ萶�Y�\�͂Ɖߏ�J���͂����݂��邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ͐V���������̊g���j�~���A��̌X������B�܂�����͓Ɛ��Ƃ���݂Ď��v�̕s���Ƃ��Ċ�������B
�Ɛ��Ƃ͎��v�̂��傫�����O�������Ƃ邾���ł͂Ȃ��A�\���I�Ɏ��v�����N���A���v�n�o�Ƃ������ׂ�����𐄐i����B��ʐ��Y�����͑�ʏ��������O��ɂ��A��ʐ��Y�̂��߂̐��Y�Z�p�ƃ��f���E�`�F�[�\�W�A����V�M�p�A�̔��X�̌n���̔̔��Z�p�Ƃ͕��s���Đi������B�������A�����̔̔�����̗��Â���������́A�ϋv����������ł���悤�ɁA����ɂ�������v�̐V�������������o���Ă͂��邪�A�����ƌٗp�̑����ɂ�đ�Ђ����������߂����̂ŁA�@����I�Ȏ��v���ʐ�������̂ł͂Ȃ��B�@�Ɛ莑�{��`�͂��̎��{�̉��l���B�̂��߂Ɉ��肵�����v�̊g���K�v�Ƃ��A���̕K�v�ɂ���������̂Ƃ��č��Ƃ̎x�o���d�v�����܂�����B�����͂��̐߂̂͂��߂ɁA���Ɠ����̌��㎑�{��`�ɂ���������ɂ��Ăׂ̂����A���̒~�ωߒ��ɂ����鍑�Ƃ̖����Ƃ����ŁA���̍��Ƃ̖����A�����ߒ��ɂ�������������ƓƐ莑�{��`������Â���B���̒~�ωߒ��Ǝ����ߒ��ɂ����鍑�Ƃ̋@�\�̋�̓I�Ȏ��Ԃ������炩�ɂ��邱�Ƃ͌��㎑�{��`�̌������͂̎�v�ȉۑ�ł��邪�A���̘_���ł����������݂�킰�ɂ͂����Ȃ��B��̉ߒ��ɂ����鍑�Ƃ̋@�\�̑���͂��ׂĂ̍��X�ɂ�����Ă��鋤�ʂ̌X���ł��邪�A���ɂ���Ă��̌����̍ʑԂ͂������Ă���A���̈�ʐ��Ɠ��ꐫ�𐳊m�ɏ��q���邱�Ƃ͂��ꂾ���ő����̎�����K�v�Ƃ��邩��ł���B���������Ă����͂��̉ۑ�ɂƂ肭�ނ��Ƃ����ɁA���Ƃ̌o�ϓI�����ɂ��Ď��̂悤�ɊT������ɂƂǂ߂�B�~�ωߒ��ɂ����鍑�Ǝ����̖����ɂ��ẮA���łɁu�m��{�v�����������Ƃ��ɂ���ɂӂꂽ�B���̍��Ƃ̌Œ蓊���̑���ƂƂ��ɉݕ����{�̖ʂɂ�����~�ςƓ����̑��i�̂��߂̍��Ƃ̖��������債�Ă���B�����ɂ����͑��i�Ƃ������t�����������A����͂���ɍ��Ƃ���ړI�ȑ[�u�Ŏ��{�~�ς𑣐i����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA���ƍ����������Ē��ڂɉݕ����{��n�o����������ɂȂ��悤�Ɂ[�Ȃ������Ƃ������_�̓����ł���B�d�ŁA�����A�N����v�������Ĉ���������ꂽ�ݕ����u�m��{�v�̌`���A�Z��z�����ł����A��Y�Ƃ̓Ɛ��Ƃɒ���邱��
�ł���B�~�ωߒ��ɂ���������ƂƂ��Ɏ����ߒ��ɂ����鍑�Ƃ̖��������債�Ă���B����͒~�ωߒ��̕ω��̌��ʂƂ�����X���ł���A�������ƁA�Z��z�A���Y�ݔ����ւ̎��{�̓����͂��ꂾ�����Y��i����јJ���J�w�̎��v�ƂȂ��Ă�����邩��ł���B��ʓI�s����̎x�o�A�R���x�o������ɂ��킦��A���{�x�o�͍��������Y�̈�Z������ꎵ���ɂ̂ڂ�A����ɂ���ɕ⏕���A�����q�A���̑��U�֎x���������킦��ځA�����O�Z���ɂ܂ł̂ۂ��Ă���B���̐����́A�A�����J�ƃ��[���b�o�̏����̐��x�I�Ȃ������ɂ���č��Ǝx�o�̉����Ă�������ɂ͑����̌y�d�����邱�Ƃ�邪�A�������m��I���v�̔��ɑ傫�Ȋ��������Ǝx�o���`������悤�ɂȂ������Ƃ͎����ł���B
���̂悤�ȓm��I���v�̍\���ɂP������ω��́A���ʉߒ��Ɖݕ����{�̉^���ɂP�������A�̏d�v�ȕω����Ƃ��Ȃ��Ă���B����͎s�ꉿ�i�̑̌n�A�����،��s��̍\���A���Z�@�ւ̕ω��ɂ݂��邪�A�Ƃ��ɉݕ����x�ɂ����ċ��{�ʐ����p�~����A�@�u�Ǘ��ʉݐ��v�ɂ���������Ƃ́A���i���ʂƉݕ����{�̉^���Ƃɂ�����ω����W���I�ɁA���x�I�ɕ\�����Ă���B�����̏��ω������ĊǗ��o�ϐ��x�����܂ꂽ�Ɣ��f���A�Y�Əz�A���ƂɍĐ��Y�̋ύt�����鋰�Q�̋@�\�͏��������Ƃ����������A�ߑ�o�ϊw�ł��A�}���N�X�o�ϊw�̂Ȃ��ł��L�͂ƂȂ��Ă���B���̐߂̏I�ǂ̌��_�����̂悤�Ȍ����̐��ۂɂ��Ĕ��f�����������Ƃł���B���̏ꍇ���Ƃ̎x�o�̔�d�̑���Ƃނ��т������ʉߒ��̕ω��ɂ���āA���̎Y�Əz����O�Ƃ���ׂĂ������邵���ω������߂��Ă��邱�Ƃ�_�c�̑O��Ƃ��ׂ����낤�B�`�E�}�f�B�\�\�͐��̎Y�Əz�̃s�[�N�����܂ł̂f�m�o�̍ő�̒ቺ�����O�̓�̎����̂���Ɣ�r�����\�����߂��Ă���B�@���̕\�ɂ���Ă��A�@���̋��Q�ǖʂɂ����鐶�Y�̒ቺ�����������邵�����������Ƃ͂����炩�ł���B�������������̎Y�Əz�̕ω��͈�̗��R�����ɂ���Ă͐�������Ȃ��B����̍��̓���̏����ƈ�ʓI�ȏ����Ƃ���ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̋�̓I�ȏ����̕��͂ɂ������邱�ƂȂ��ɁA�����Ŋm�F�ł���̂́A��ʓI�ȋ��ʂ̏����Ƃ��Ă͍��Ǝx�o�̓m��I���v�̂Ȃ��ł��߂��d�����債�����Ƃł���B�ł����ځA�m��I���v�̑���������A���i�̉ߏ肪���������Ƃ��A���Ǝx�o�𐭍��I�ɑ��傳���邱�Ƃɂ���āA���v�̒ቺ���������邱�Ƃ��ł���B���̎��I�Ȏ��v���������̒ቺ�̉e���̊O�ɂ����Ƃ��ł������̂ɂ������āA�����x�o�ɂ�鍑�Ǝ��v�͎Y�Əz�̐������瑊�ΓI�ɓƗ��̓��������߂����Ƃ��ł���B���������Ď����ߒ��ɂ����č��Ǝ��v�����́A�z�E������ʂ����߂����̂ł���A���ꂪ���̎Y�Əz�̕ω������������̂ł��邱�Ƃ��݂Ƃ߂˂ڂȂ�Ȃ��B�������ꂾ���Ő��̎Y�Əz�Ƌ��Q�̕��͂�����点��킰�ɂ͂����Ȃ��B�����̌o�ϊw�V�͂��̓_����b�ɂ��ĊǗ����x�̗L�������m�肷��B������������Ǘ����x��������~�ςƎ����̉ߒ����Ӑ}���ꂽ�R�[�X�ɂ����ĉ^��������̂ł��邩�A���邢�͂�����Ƃ��ĈӐ}���ꂴ��R�[�X�A���_�I�ȉ��l�@���Ɏx�z����A�O�I�K�R�I�ȋK���ɂ��������ĉ^��������̂ł��邩���A��㎑�{��`�̔��W�ɂ��Ă̏I�ǓI���Ƃ��Ă̂���̂ł���B�@
���ƓƐ莑�{��`�̗��ʉߒ��̓����́A�Ɛ艿�i�𒆐S�Ƃ��鉿�i�̌n�Ǝ��v��⑫���鍑�Ǝx�o�̖����Ƃɂ���B���̂悤�ȓ��������������ʉߒ��ł͕����͂˂ɁB�㏸����X���������Ă���B����͈�ɂ͋��������ɂ��Ɛ��Ƃ̉��i�����̑��삪�A���v���k�����鎞���ɂ����Ă��A���i���Œ肳���邱�Ƃɂ����̂ł��邪�A���傫�����R�́A���Ǝx�o�ɂ����v�⑫�̋@�\�������㏸���Ђ����������Ƃɂ݂��������B���Ǝx�o�͓m��I���l���Y���ɂ���������v���`�����邪�A���̔��ʑd�ŁA�����������ꂩ�̌`�ԂŎ����̏��͎�����̍T���ɂ��̉ݕ��I���������Ƃ߂Ȃ���ڂ���Ȃ��B���Ǝx�o�̑������S���̉ݕ��I������d�łɂ��Ƃ߂�Ƃ���ځA�x�o�����ɂ��lj����v�͑d�łɂ��ݕ����グ�ɂ���đ��E����Ă��܂��B���Ǝx�o�Ɂ|�����v�n�o�͓m��I���l���Y�ɂ�鐧����܂ʂ������̂ł͂Ȃ��B�����x�o�ɁD�����v�̕�[���v�������̂́A�s�ꗘ�������ቺ���A���������ቺ���A�m��I���v���k�����鎞���ł���B���������Ă��̎����Ɏ��v��[�̐�����Ƃ邽�߂ɂ́A�o�튨��̎��x�̐Ԏ����Ђ��������Ȃ���ڂȂ�Ȃ��B�o����x�̐Ԏ��͍��Ƃ̎ؓ����ɂ���ĕ�U����A�ؓ����̏����Ɨ������͏����̓m��I���l���Y���ɂ�������d�ł̒����ɂ���Ă����Ȃ���B�Ԏ������͌��Ǎ��Ƃɂ��M�p�̓������Ӗ����A�����̗�������ђ����ɂ�������d�ŕ��S�̑�����Ђ��������B�Y�Ǝ��{�Ƃ��M�p�������ꍇ�A����ɂ���ď�]���l���Y���������A���������ė������������A���҂Ɨ������𗠂����邱�Ƃ��O��Ƃ����B���{�������擾���闘������M�p�̏��҂Ɨ������������Ȃ����Ƃ͐M�p��]�̕K�{�����ł���B���������Ƃ̐M�p�����͂��Ȃ炸�������̂悤���S���������Ȃ��B���̂���荑�Ƃ̑d�Ŏ����ɂ������鐿�����A���҂Ɨ������̐������𐬗������A���������č��Ƃ̐Ԏ������͋[�����{�A�����ɂ������鐿�����̎��{���̑���ɂ݂��т��B���Ƃ̎��v��[����ɂ���ċ[�����{���ݐς��A���ꂪ�m��̑����{�̑��B�𐧖�Ƃ������ʂ����܂��B���̐���͓Ɛ艿�i�̏㏸�ƂȂ��Ă������B
���Ƃ̐M�p�����ƂƂ��ɁA�����ōl���Ă݂�ׂ��͏���ҐM�p�ł���B����ҐM�p�������̔��̐��x�ɂƂ��Ȃ��ĐM�p���x�̂Ȃ��ŏd�v�����܂��Ă��邱�Ƃ͎��m�̂Ƃ���ł���B�����̔��͏���҂̏����̎�������̕����x�������������Ăɂ����Ȃ��̔��ł���A�ϋv������Y�Ƃɂ������ʐ��Y�̔��W�͂��̔̔������̂����ɂ����Ă���B����������͏���҂̕��̗ݐς�����o�����̂ł���A���ɂ������闘�q���S�͉��i�̂Ȃ��ɂӂ��߂��A���ꂾ�����i�����グ����ʂ����B���Ƃ̐Ԏ������Ə���ҐM�p�Ƃ́A���ƓƐ莑�{��`�ɂ����Ď��v�g��̎�v�Ȏ�i������o���Ă��邪�A����ҐM�p�́A�Y�Əz�����肳������v������o�����̂Ƃ͍l����ꂽ���B�ȕ��Ȃ����͏���҂̎����̕ϓ��Ɉˑ�������̂ł���A�ٗp���ቺ���A�������ቺ����ꍇ�A����ҐM�p���܂��k�����A����ɕ��̗��s�s�\�A�����킿�������̒�~�������肤�邩��ł���B���������ƓƐ莑�{��`�͍��Ƃ̐Ԏ������ɂ���A����ҐM�p�ɂ���A���̗ݐςɂ��m��I���v�̕�[�̐��x������o���A�܂����̂悤�ȕ�[�I���v���g�傷�邱�Ƃ��悬�Ȃ������̂ł���B���̌��ʂ͕��̗ݐϓI�ȑ���������炷���̂ł���B���Ƃ̐Ԏ������Ə���ҐM�p�Ƃ́A��{�I�ɂ͌���ɂ�����ݕ����{�̌_�@�̐V���������Ƃ݂�ׂ��ł���A�@�m��I�����{�̉^���̂Ȃ��Ɉʒu�����Ă��̋@�\�͂��ׂ��ł���B�@�ł����ό���ɂ���������̐���ɂ��m��I���v�̊Ǘ��Ƃ�������̂́A�@�ݕ����{�A�@���̑傫�������͋[���I�Ȏ��{�A���Ȃ킿��������̍T���A�����ɂ������鐿�����̎��{���ɂ���Đ������鎑�{�̗ݐςɂ݂��т��B���̂悤�Ȑ��i�����������{���m��I�����{�̑��B�ɂ�����A���������ꂪ����̌X�������Ƃ��A�m��I���l���Y���̔z���͂��̋[�����{�̂��߂ɕω�����B�z���̋@�\�͓Ɛ�p�i�̌n�ɂ���Ĕ}���邪�A�Ɛ�I���ʍ\���͋[�����{�ɂ��������]�̕��z�ɂP�����鉿�l���������i�ɓ]�ł�����B�[�����{���ݐς���Ƃ��A���i�́A���̓]�ŕ��̑���ɂ��A�ݐϓI�ɏ㏸���邱�Ƃ��܂ʂ���Ȃ��B��������ɂׂ̂����i�㏸�̃��J�j�Y���͌���̃C�\�t���[�V���\�̂��ׂĂ����������̂ł͂Ȃ��B���������哫�M�̌X���̎�v�ȓ����Ƃ��Ă����͎��v��[�������������̂ł���B
�@ |
| ���l�@���Q�ƎY�Əz�̕ω��@ |
   �@
�@
|
���ƓƐ莑�{��`�i�K�ɂ�����Đ��Y�ƒ~�ς̉ߒ��̓������ȏ�̂悤�ɍl����Ƃ��A���Q�ƎY�Əz�͂ǂ̂悤�ȑԗl�����߂������������悤�B���Y�Ǝ��{�̏W���E�W�ς��i�s���Ɛ�̎x�z����܂�ƂƂ��ɍĐ��Y�ƒ~�ς̉ߒ��œƐ���[���邽�ߍ��Ƃ̖������������邵���傫���Ȃ������Ƃ��݂��B���̍��Ƃ̕�[�I�Ȗ������Ӑ}�I�ȁA�����I�Ȓ��������Ƃ݂�̂�����̉��߂ł��邪�A�����͂����͍l���Ȃ��B���ƓƐ莑�{��`�i�K�ɂ����Ă��m��I���Y�̊�ؓI���i�͉��l���B�ߒ��ł���A���̒i�K�̐V�����X��������o�����Ƃ̓����Ə���Ƃ͎��{�̑��B�̈�̌_�@�ȊO�̂��̂ł͂Ȃ��A���l���A�ߒ��̖@���I�ȋK������������̂ł���B�����͗������̒ቺ�̌X���Ƃ��Ă�����鎑�̉ߏ肪���Q�̌����ł���A�������̒ቺ�̌X�����ӂ��ޓ��I���������i�̎����I�ߏ萶�Y�ƂȂ��ēW�J���A���Q�̋@�\�͎��{�̉��l�j��ɂ�鉿�l���B�̋ϊX�̉ł���Ƃ������_�������̂ł���B�܂����̎��{�̉ߏ�Ɖ��l�j��͂���Ɏ����I�ȋ��Q�ƂȂ��Ĕ������邾���łȂ��A��蒷���I�ȁA�\���I�ȕϓ��ƂȂ��đQ���I�ɊѓO������̂ł��邱�Ƃ̓}���N�X���w�E����Ƃ���ł���B���̊ϓ_���炷��Ƃ��A����ꂪ���̐߂Ŋm�F�������Ƃ̌o�ϓI���������{�̉ߏ肨��щ��l�j��Ƃǂ̂悤�Ȋ֘A����������������˂Ȃ�Ȃ��B���̓_�ɂ��Ăׂ̂�܂��ɁA�}���N�X�̂��Ƃڂ����p���悤�B
�u���̗����̌����́A���ړI�J�����Đ��Y�����炽�ɎY�o����Ώۉ����ꂽ�J���̑傫���ɂ������钼�ړI�J���̊������������邱�ƂƓ��Ӌ`�ł��邩��A��ʂɎ��{�̑傫���ɂ������Đ������J���̊����̏��������ƁA���������đO�ꂽ���{�ɂ������āA�����Ƃ��ĕ\�����ꂽ�ڂ����̏�]���l�̊����̏������_���A�K�v�J���ɂ������镪���O�����炷���ƁA�����đS�ٗp�J���ɂ��ď�]�J���̕��ʂ�����ɂ��������g�傷�邱�Ƃɂ���đj�~���悤�Ƃ��邽�߂̂����鎎�݂����{�ɂ���ĂȂ����ł��낤�B����䂦���Y�͂̂����Ƃ����x�̔��W�́A�����̕x�̍ő�̊g��ƂƂ��ɁB�A���{�̌����A�J���҂����p�A�����Ă��̐����͂̂����Ƃ������炳�܂ȏ��s�Ǝ��������Ă�����ł��낤�B�����̏������͔����A��ϓ��A���Q�ɂ����邪�A���������Ƃ��ɂ͂��������̘J���̈ꎞ�I�Ȓ�~�Ǝ��{�̑傫�ȕ����̔j�낪�����Ȃ��A���{�����ł��邱�ƂȂ��A���̐��Y�͂��\���ɉғ��ł���_�ɂ܂Ŗ\�͓I�Ɉ������ǂ����B�c�c�����A�����̋K���I�ɉ�A����j�ǂ́A��荂���K�͂ł̔����ցA�����čŌ�ɂ͂���̂����{�u�̖\�͓I�ȓ]���ւƂ݂��т��B���̉^�������܂����鏔�_�@���A���Q�ɂ����̂Ƃ͕ʂɎ��{�̔��W�����^���̂Ȃ��ɂ���B���Ƃ��ځA�������{�̈ꕔ���̂������鉿�l�r���A���{�̈�啔���ړI���Y�̍�p���Ƃ��Ă͓����Ȃ��Œ莑�{�֓]�����邱�ƁA���{�̈�啔����s���Y�I�ɐH���Ԃ����ƁA���B�@�i���Y�I�ɏ[�p����鎑�{�͂˂ɓ�d�ɕ�U�����B���łɂ݂Ă����悤�ɁA���Y�I���{�̉��l�Y�o�͈�̑Ή���O�Ă���A�A���{�̕s���Y�I����͈�ʂł͂�����₵�A���ʂł͂����j��B�Ȃ��܂������̗��̒ቺ����������̌����̍T������肳�邱�ƁA���Ƃ��ڑd�ł̌y���A�n��̌����Ȃǂɂ���đj�~�����Ƃ������Ƃ́A���ꂪ�ǂ��ۓI�Ӌ`�����Ƃ��Ă��A�{�������ɑ����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炱��͂��ꔒ�g��������O�ł̗����̑������ł���A���{�Ǝ��g�Ƃ͕ʂ̐l�X�ɂ���Ď擾����Ă�����̂�����ł���B���l�ɁA���{�ɔ�Ⴕ�Ē��ړI�J������葽���K�v�ȁA���Ȃ킿�J���̐��Y�͂��܂����W���Ă��Ȃ��V�������Y����̑n���ɂ���āA�ቺ�͂���������B�j�i���l�ɓƐ�j�v
�}���N�X�ɂ��ځA���{�̐�l�j��͋��Q�ɂ���Ă����Ȃ��邪�A���Q�Ƃ͕ʂɁA���{�̊`�l��r����������_�@�����̉^���̔��W�ɂ���Đ����B���Ƃɂ��Œ莑�{�����̑���A���Ǝx�o�ɂ��m��I���l���Y���̍w���̑���͂܂��Ɂ[����ł���A���{�̏W���E�W�ς̌��ʐ����������{��`�̓Ɛ�i�K�ɂ����Ď��{�̍\���I�ω�����т���ɂƂ��Ȃ����{�̉^���̑ԗl�̕ω��ɂ���Đ������Ƃ���̌X���ł���B�Œ莑�{�̑傫���������삪���Ƃ̎�ɂ䂾�˂��邱�Ƃɂ���āA���I�Ɛ莑�{�͂��̕���ւ̎��{�����̒��ړI�ȕ��S��Ƃ����A���̂�����ŗ������̒ቺ�͑j�~�����B�܂��R���x�o�ɂ��m��I���l���Y���̍w���A�R���͎��{�̕s���Y�I����̓T�^�I�Ȃ��̂ł���A�R���i�̉��l�͕�U����邪�A�g�p���l�͍Đ��Y�͈̔͂̊O�ɂ��������̂ł���B���Ƃ����{�Ə��i�̉ߏ��j�~���邽�߂ɉ���������ɂ��Ă����ɋ�x�I�ɂׂ̂�K�v�͂Ȃ����낤�B�����d���������Ĕ����邱�ƂȂ��ׂ̂Ă����ׂ��͍��Ƃ̖����̐��i�ɂ��Ăł���B���̍��Ƃ̋@�\�͈Ӑ}�I�A�����I�������̗v�����s��o�ϓI�ȍĐ��Y�ߒ��ɓ���������̂Ƃ����Ă���B�����������͍��Ƃ̋@�\�́A�}���N�X���ׂ̂Ă���悤�ɁA�ܖ{�̔��W�����^���̂Ȃ��ɂӂ��܂����̂ł��邱�Ƃ��w�E���Ă����˂ڂȂ�Ȃ��B���Q�ɂ�鎑�{�̉��l�j��́A�������̒ቺ�X���ɂ�����鉿�l���B�ߒ��̓��I�����̔����̈�ł���A���̖����̔����͑��l�ł���B���{��`�I���Y�̍\���̕ω��ɁB����ē��I�����̔����̌`�Ԃɂ��V�����_�@���W�J����B�Ɛ莑�{��`�ɂ����鎑�{�̏W���E�W�ς͍��Ƃ̍����I�@�\�����{�̑��B�ߒ��̂Ȃ��ɕ�ۂ��A�����I�@�\�����̖����̔����̌_�@�Ƃ�����̂ł���B���Ƃ̐����I���@�\�͖ړI�ӎ��I�ȗv�����Đ��Y�ƒ~�ς̉ߒ��ɓ������邱�Ƃ͔ے肷�ׂ����Ȃ����A���������l���B�ߒ��̖@���Ƃ��ē����K���͍��Ƃ̐����I�ȋ@�\�����x�z������̂ł���B���Q�ƎY�Əz�ɂ���ۂ����Ƃ̉e�����܂����̊ϓ_���番�͂���˂Ȃ�Ȃ��B
�����͂��łɁA���Ǝx�o�ɂ����v��[�����Q�ɂ����鐶�Y�̒ቺ��j�~���A�܂����̂悤�ȍ��Ǝx�o�̋@�\�������㏸���Ђ����������Ƃ��ׂ̂��B���̂悤�Ȍ����ߒ��̕ω����A�����Ɋm�F�������Q�̐��i�A�����A�@�\����l���ĉ����Ӗ����邩���������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B�܂����ɂ����炩�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂́A�������̒ቺ�ɂ݂��т����{�̉ߏ���Ђ����������v���͏������Ă͂��Ȃ����Ƃł���B���ƓƐ莑�{��`�̂��ƂŁA�Œ莑�{���������ƍ����̕��S�ɂ���Ă����Ȃ��邱�Ƃ́A�Ɛ莑�{�̌o�c�v�Z���炢���A���ꂪ�����̒ቺ��j�~���邱�Ƃɂ���B���������Ɠ����̉ݕ��I�����͑d�ł����ɂ�������Ƃ߂˂ڂ��炸�A����͌��Ǘ����ƒ�������T�������̂ŁA�������̒ቺ���Ђ����������Ƃ͂��łɂׂ̂��Ƃ���ł���B������Y�Əz�̏������̂��Ƃōl����ڎ��̂悤�ɂȂ�B�z�̋ǖʂ̂��ׂĂ������āA���ƍ����ݕ��s����������Ă���A�܂���Ђȑd�ł����i����Ǝ����Ƃ𐧖Ă���B���Q�ƒ�̋ǖʂł͍��Ǝx�o�͎��v��lj������Y�̒ቺ���ӂ������D���ǖʂ������ނɂ�Ĕ��ɍ�p����悤�ɂȂ�B���Ԋ�Ƃ��M�p�����Ƃ߂�Ƃ��A�ݐς������ƍ��̑��݂͐M�p�̊g����S������v���ƂȂ�A���v�̑����������Ƃ��A��Ƃ̗����ɂ�������d�ł͕��S�����d����B�������ቺ�̍�p����o�H�͕ω����邪�A�ቺ�̌X���͂�����Ƃ��č�p����̂ł���B�������̒ቺ���s��̃����j�Y���������Č���������Ƃ��A�Ɛ��Ƃ͉��i���������邱�Ƃɂ���Ĕ̔�������������@���Ƃ�Ȃ��B�ނ��됶�Y�����ɂ���ĉ��i�������ێ�����B�Ɛ��Ƃ̎s��ɂ�������x�z�́A���������ĉ��i��������邱�Ƃ��\�ɂ���̂ł���A���̂��Ƃ͓Ɛ��Ƃ����ė����̋}���Ȓᗎ���܂ʂ��ꂳ���邱�Ƃɂ͂���Ȃ��B��ڔ�p�͐������ꂽ���Y���ɂ�����A�����͋}���ɒቺ����B
���̂悤�ȋ��Q�ǖʂɂ����闘���̋}���Ȓቺ�����������͍̂��Ƃ̎x�o����ł���B���ƍ����͗��������ɒ��ڍS������Ȃ��B���������Ď��v�̏k���ɂ������āA�x�o�����邱�Ƃɂ���Ă�����[���邱�Ƃ��ł���B���Q�ǖʂ̗l���́A���ƓƐ莑�{��`�̏����̂��Ƃł͕ω�����B�ł���������ځA�������̒ቺ�ɂ���Ď��{�̉ߏ肪���i�̉ߏ�ɓ]�����邱�Ƃ����Ƃ̎��v��[�ɂ���đj�~�����̂ł���B���̂悤�ȊT���I�ȋK��Ɂ|�͑����̕⑫�������K�v�ł���B�����͓Ɛ��ƂƂȂ��Ŕ�Ɛ��Ƃ����݂��Ă���A���Q�ǖʂł����̊�Ƃ̂������ł͏��i�̉ߏ�A���i�̒ᗎ�A�j�Y���̂���ڌÓT�I�ȋ��Q���ۂ�������̂����Ă���B�����̉ߒ��͕��G�ŁA�s�ϓ��������ۂ̕����ł��邪�A�����ߒ��̒U�n�̓I�ȗl���������炩�ɂ��邱�Ƃ͂��̏��e�͈̔͂������Ă���B�����͍��ƓƐ莑�{��`�̏������̂��Ƃł̋��Q�̌��ی`�Ԃ̓����������炩�ɁB����̂ɕK�v�Ȍ��x�ɂƂǂ܂�˂ڂȂ�Ȃ��B
���Ƃɂ����v��[�͎��{�̉ߏ肻�̂��̂��������Ȃ��B�ނ���Ԏ������ɁB��鍑�ƍ��̗ݐς��������Ď��{�̉ߏ�������������d������X���������Ă���B����䂦�ɋ��Q�ǖʂ������A�����ǖʂ��J�n����܂łɉ�݂����؋ǖʂ͂���������������邱�ƂɂȂ�B���Q�����{�̉��l�j��ɂ���āA���l���B�̉ߒ��̍ĊJ�̏���������o���@�\�͏\���ɉʂ���Ȃ��B���Ǝx�o�ɁB�����v�̕�[�ɂ���āA���i�̉��l�����̉ߒ��ɁB��������v�Ƌ����̋ύt�͉����B���������ĉߏ菤�i�ɂ����������A���Y�̒ቺ�͒�������B����ɐ��Y�͏㏸�ɂނ������Ƃ��\�ł���B�������Ȃ���ߏ莑�{�̑��݂͗������̏㏸�����܂�����B���������ĐV�����Y�Ɠ����ɂ���Ď��{�̑��B���ĊJ���A����ɂ���Ďs��ƌٗp�Ƃ��g�債�A�s�ꗘ�����Ɨ��q���Ƃ̊W���B���Y�̊g��𑣐i��������͂���o����Ȃ��̂ł���B�Y�Əz�͏㏸���͂܂�A���Y�͒���A�ٗp�͒ᐅ���Ɂ|�Ƃǂ܂�B����͍��ƓƐ莑�{��`�̎Y�Əz�̏d�v�Ȗ��_���Ȃ��A��������Ƃ������O�ł��̒��ŊJ����[�u���u�����Ă���B����͎Y�Ǝ��{�̗��������߁A�����𑣐i���邱�ƂɋA�����邪�A�Œ莑�{�̂��肠�����p�𑣐i���邽�߂̑d�ł̌��ƂƓ������i�̂��߂̉�m�����ɂ�������ېł̒ጸ�Ƃ͍L���̗p����Ă���[�u�ł���B�����̑[�u�́A�ߏ莑�{�̐�����d�ő[�u�ɂ�董�i���A���邢�͗������̂��̂ɂ�������d�łڂɌy�����邱�Ƃɂ���ė����������߂���̂ł���B��̈��p���Ń}���N�X�͑d�ł̌y���͗�������̍T�������̎擾�̒����ł���A�{���I���Ӌ`�������ʂƂ����Ă���B���������Ƃ̍��������{�̌_�@�Ƃ��鍑�ƓƐ莑�{��`�i�K�ł́A�d�ł̌y���͌i�C�h������Ƃ��ďd�v�����������邵�����߂�B����ƂƂ��ɂ��̐���ɂ���č��ƍ��̑͐ςƑd�ł̐���Ƃ��Y�Əz�ɂ݂��т�����A���ꂪ�D���ǖʂŗ������̒ቺ���������������������̂ł���B
�����͂��̍e�̂͂��߂ɂ����āA���ƓƐ莑�{��`�ɂ�����m��I���Y�̓������ɂ���Ƃׂ̂��B����́A�Y�Əz�̏��_�@���܂��l���ɂ��ꂸ�A�Ɛ�I�Y�Ǝ��{�̉^���Ƃ��̉^���ɂ����鍑�Ƃ̕�[�I�@�\�Ƃ������l���邱�Ƃɂ���ē��B�������_�ł��邪�A�Y�Əz��O��ɂ��킦�Ă��������Ƃ�������B���Q�ǖʂɂ����鎑�{�̉��l�j�j�~����邱�Ƃɂ���āA�Y�Əz�̗l���͒�̌X�������߂��̂ł���B�Y�Əz�̎����ɂ����Ă̒�،X���́A�Y�Ǝ��{�̉^���̋K�������łȂ��A���Y���{�Ɖݕ����{�̉^���̑��݊W�ɂ��K���̌��ʂł���B���ƓƐ莑�{��`�̏����̂��Ƃł̎Y�Əz�̓����͋��Q�ǖʂ̌`�ԕω������ɁC�݂Ƃ߂��ׂ��ł͂Ȃ��āA�ނ���Y�Əz�̑S�̂���̗l�������߂����Ƃɂ���_���������킯�ɂ͂����Ȃ��B����ƂƂ��ɂ��̒i�K�ɂ�����Y�Əz�̂�����̓����́A�ݕ����{�̗ݐςɂ��C�\�t���[�V���\�ł���B���{�̉^���̌_�@�Ƃ��č��ƍ�������[�I�ȋ@�\���ɂȂ����ʍ��ƍ��̗ݐς������邱�Ƃ͂��łɂׂ̂��Ƃ���ł���B���ƍ��͋[���I�ȉݕ����{�Ƃ��ċ@�\���A�^������B�����Ă��̋[�����{�̗ݐς��C�\�t���[�V���\���Ђ����������ݓI�����͂��`������B���ƍ��͋��Q�ǖʂő������A�D���ǖʂł͂���Ɏ��I������ς݂���āA�ݕ����{�̖c���Ɛ��Y���{�̊g��Ƃ̂����������𑁂߂�̂ł���B�C�\�t�����ۂ͌��݉����A�ߓx�ْ��������炵�A���Q�ǖʂɓ]��������B�������C�\�t���[�V���\�͋��Q�ɂ���Đ��Z���ꂸ�A�P��I�ɗݐς���B
�����̍P��I�ȏ㏸�ƃC�\�t���v���̍\�����͐��z���̈�̓������ʐ�������̂ł��邪�A����ƂƂ��Ɏ��{�̉ߏ�𐴎Z���邱�ƂɁB�v������������ɁB�Ȃ����Ƃ��������Ȃ��B�C�\�t���[�V���\�̐i�s�͉ݕ��̌������Ӗ����A���̂�����ŗݐς�������̍����펞�I�ɏk���������p�����ƂȂށB���������Đ��Y���{�͉ݕ����{�̗��\���S���C�\�t���[�V���\�ɂ���Čy������A��Ǝҗ����Ƃ��Ă̗����͒ቺ�X���ɔ������̗v���̉e���������Ă��邱�ƂɂȂ�B�܂������ŕ������M�́A�Y�Ǝ��{�ɂƂ��āA���̔�p�̏����ځA�����A�R����A������̏㏸���Ӗ����A��ƍ̎Z�ɂ����鑹�v����_���㏸������B���v����_�̏㏸�́A�Ɛ��ƂƔ�Ɛ��ƂƂ̂������ɂ����������ʂ������炷�B�Ɛ��Ƃ́A���Y�H���̍������ɂ��A���邢�͐��i���i�̈��グ�ɂ���āA�@��p�̏㏸�ɑΏ������i�������Ă���B�@��������Ɛ��Ƃ͕������M�̂Ȃ��Ŕj�Y�ɂ��������B�������ĕ������M�͔�Ɛ��Ƃ̎��{�̉��l�j��A��ƂƂ��Ă̍Đ��Y�ߒ�����̗��ށA���{�̏W��������
�炷�̂ł���B���ƓƐ莑�{��Ƃ̒i�K�ł͂��̂悤�ȓ��������ď펞�I�Ȏ��{�̉��l�j��������Ȃ��A���{�̉��l���B���������郁���j�Y���������Ă���A����̓C�\�t���[�V���\�ɂ͂�����Ȃ��B�����͂��łɑd�ő[�u�������đ����ɌŒ莑�{�̌������p�������Ȃ킹�鐭�Ƃ��邱�Ƃ��ׂ̂��B���̑[�u�͓Ɛ莑�{�̂��߂ɑI�ʓI�ɂƂ��A�厑�{�͂��̓��T�I�[�u�𗘗p���Ă��̋@�B�ݔ������\���̍������̂ł���������B�����ɂ܂�����͓��Y��ƂɂƂ��Ă͋����{��p�����āA���{�̉��l���B�����Ȃ������̂ł���B�C�\�t���[�V���\�ɂ��ݕ����{�̉��l�r���A���v����_�̏㏸�ɂ���Ɛ��Ƃ̔j�Y�ƍ����A�Œ莑�{�̂��肠���������p���A���ƓƐ莑�{��`�i�K�ł́A���{�̉��l�j��͎����I���Q�ɂ�邾���łȂ��A�z�̏��ǖʂ������ď펞�I�ɂ�����������̂ł���B�@�@�@�@�@�D
�펞�I�Ȏ��{�̉��l�j�����Ȃ��邱�Ƃ͎����I���Q�̒��ԕω����\�ɂ��Ă����̗��R�ł���B�������펞�I�Ȏ��{�̉��l�j�낪�����I���Q�ɂ܂��������������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B���{�̑��B�Փ��ƓƐ�⋣���͍D���ǖʂƎ��{�̉ߏ������o���A�����I���Q���Ђ�����������ł���B�����͐���Z�N�̌����ߒ��̊ώ@����A���Q�ǖʂ̊ɘa�ƎY�Əz���S�̂̒�ؓI���i�����ƓƐ莑�{��`�i�K�̓����ƍl����B���������̂悤�Ɍ��_���邱�Ƃ́A���㌃�����`�̋��Q�������炽���Ɨ\�f������̂ł͂Ȃ��B���̒i�K�ɂ�����Y�Əz�̕ω��͈��ƍ��̗ݐς������炵�A���̌��ʂ������C���t���[�V���\�����i�����Ă���B�C�\�t���[�V���\�̐��i�͖����I�ł���A���̉e���͕s�ϓ����W��ݐς����Ă���B�s�ϓ����W�͓Ɛ��ƂƔ�Ɛ��ƂƂ̂������ɁB���i�s���Ă��邪�A�����łƂ��ɂƂ肠���Ďw�E���ׂ��͍��ۖ�̕s�ϓ����W�̌����ł���B����Z�N��܂ł́A���{�ʐ����@�\���Ă���A���̐��x�̂��Ƃł̋��ړ������ۖ�̋ύt�̒����قƂ��č�p�����B�e���̎Y�Əz�̍D���ǖʂō��ۖ�̕s�ϓ��Ȕ��W���ݐς��A���Q�ǖʂł͌��������̗��o��������A�ݐς����s�ϓ����̋ύt���������Ȃ���B�ύt���̍�p���ł��������`���Ƃ�ꍇ�ɂ́A�{�ʉ��Q���Ђ��������A�ݕ����l�̐艺���ɂ݂��т����B���Ȃ킿���E�ݕ����Q�������āA����S�̂̏��i�D���{���l�̔j�낪�����Ȃ��A����ɂ���č��ۖ�̏��i�E���̎�����Ăъg��ɂނ���������������̂ł���B���ƓƐ莑�{��`�i�K�ł͗��ʉߒ��͕ω����A���{�ʐ��x�͂�����u�Ǘ��ʉݐ��x�v�ɂ���ĂƂ��Ă�����Ă���B���ւ̎E���ɂ�鍑�ۖ�̋ύt���̖\�͓I�ȊѓO�͂��͂�ÓT�I�Ȍ`�ł͍�c�삵�Ȃ��B���̍��ۖ�ύt����藣����邱�ƂɁA����āA���ƍ��������{�̉^���̌_�@�Ƃ������������o���ꂽ�̂ł���B�������C�\�t���[�V���\�̍��i�ƂƂ��ɍ��ۖ�̕s�ϓ����W�͗ݐς��Ă���A����͍��ۖ�̖f�ՂƋ��Z�̊g���j�Q����B���łɒ�J�������̍��ێ��x�̊�@�����łȂ��A��ʉ݂���h������у|�\�g�̊�@�Ƃ��č��ےʉݐ��x�̊�@�ɂ܂ň�����i���Ă���B���̍����C�\�t���[�V���\�ɔ}��ꂽ���ۖ�̕s�ϓ����W�����㐢�E�ݕ����Q�������ď��i�D���{�̉��l�j��ɂ݂��т��\�����݂Ƃ߂�ׂ��[���̗��R������Ƃ����͍l����B���̉\�����݂Ƃ߂邱�Ƃ͈��O��N�̃|�\�h�̋��{�ʒ�~���_�@�ɂ��Ă��������j�ǓI�Ȑ��E�ݕ����Q��\�z������̂ł͂Ȃ��B���l��N�̒ʉ݉��l�̒������ނ��덡�エ���肤�ׂ����Q�̌`�Ԃł��邪�A����͎�v���̎��{�̉ߏ�̌��ʂł���A�܂����l�j��ɂ�鎑�{�ߏ�̐��Z���������鐢�E�s�ꋰ�Q�̐��i�������낤�B
�����̌���̋��Q�ƎY�Əz�ɂ��Ă̌����͈ȏ�ɂ���B�����ŗv��A���Q�ǖʂ̊ɘa�A�Y�Əz�S�̂̒������ł���B���̂��ƂɊ֘A���Ăׂ̂�K�v������̂́A����Z�N��̌����ߒ����݂�ƁA���̂悤�ȓ����̂��Ă͂܂�ʈ�̃O���[�v�̎Y�Əz�����邱�Ƃł���B��v�Ȏ��{��`���̂Ȃ��ŁA�A�����J�ƃC�M���X�̂���͒�̗l�������߂��Ă��邪�A�����嗤�����Ɠ��{�̂���͂����̓����Â��Ƃ͂��������l�������߂��Ă���B��҂̃O���[�v�̍��X�͐������̍����z�̏㏸�ǖʂ��Â������Ƃ����̓����ł���A�Ƃ��ɐ��h�C�c�ł͋��Q�ǖʂ̓T�^�I�Ȍ��ۂ�������Ȃ������Ƃ���������B���̂悤�Ȍ����ߒ��������炩�ɂ��邽�߂ɂ͎����ƌv���ɂ��ƂÂ������͂��K�v�ł��邪�A�����͂��̃O���[�v�̍��X�́A��̓I�ȁA�����ߒ��̓���Ȍ����ɂ���Ē����̍��x�����̊�������������̂ƍl����B����͑�ʐ��Y�����̐V�Y�Ƃ̔��W�ɂ�鍂���̌Œ莑�{�����ƍ��O�s��̊g��̏����������Ă������Ƃł���A���̏������Ȃ��Ȃ�ځA��ؓI�ȎY�Əz�̗l����������邾�낤�Ƒz�肳���B���������ɃA�����J�ƃC�M���X�͈��܁Z�N��㔼�ɂ��̏������������B���h�B�c���܂��������������Ƃ�������B����������͑z��ł����āA�����ɂ���ė��Â����邩�ǂ����͍���Ɂ[�������Ă���B��㎑�{��`�̌����ߒ��ɂ��Ă͑����̌������ׂ���肪����B���������̍e�̖ړI�́A���ƓƐ莑�{��`�i�K�ɂ����鋰�Q�ƎY�Əz���}���N�X���Q�_�̗��ꂩ��𖾂��邽�߂ɁA��A�̗��_�I�����N���邱�Ƃ͈̔͂��o����̂ł͂Ȃ��B
�@ |
 �@ �@
�����㋰�Q�_�ւ̃v�������[�h(�O��)�@2016/10 |
   �@
�@
|
|
���[�}���V���b�N�ň����N�����ꂽ���E�I���Z��@��1929�N�Ɏn�܂�勰�Q�Ƃ̔�r�_�����肪�������A���҂͌���I���Q�Ƃ��Ă̓��������ʂɎ����̂́A���Ԃ͂��Ȃ�Ⴄ�B���̓_�̍l�@�ƁA����܂��Č����_�ł̃A�x�m�~�N�X�̕]���ɂ����y����B
|
��1�D �z�����Q���R��`�i�K~��ꎟ���E���O��܂�
�D�����̉��ւ̎��{�~�ρ����{�\���s�ς̒~�ς�ʂ��āA�J���͋������N���A�J�����M�ɂ�闘�����̒ቺ�ƐM�p�g��ɂ�闘�q���̍������Փ˂�(1)�A���{�~�ς̓ˑR�̒�~�A���Q�ւƌ��I�ɓ]������B���Ǝ��{�ɂ��M�p���K�͂ɗ��p���Č`�����ꂽ���@�I�ɏ��i�̓�����ɂ��A���i���i�̕����A��`�M�p���Q�Ƃ���Ɋ�Â��Y�Ɗ�Ƃ̍L�͂ȓ|�Y��ʂ��āA�ߏ莑�{�̐������\�͓I�ɐi�s����B(2)���Q�Ƃ���ɑ����s�����������̋������ʂ����Q�ɑς����ꕔ���{�̌Œ莑�{�̍X�V���ʎ��{�I�Ȓ~�ςɂ��i�݁A�ᗎ������ʏ��i���i�ƘJ���͏��i���i����ї��q��������O��ɍ��x�����ꂽ���{�\���̎��{�~�ς���������A�s������D���ǖʂֈڍs�����炽�̏z���J�n�����B
�����������猩��Ȃ�A�D������ʂ��Ă̎��v�̋����g��ɑ����s�������̑S�ʓI�ȓ��M�X�����A�D�������ɓ��ɖ\�������鏤�i�����o���A�����ɓ��@�I�Ɍ`�������邱�ƂƂȂ�B�����ɘJ�����M�Ƃɋ�������A�������̋}���ƌ��ώ����̕���ɂ�闘�q���}���ɂ��A�M�p�̊����߂������s����A�N������M�p���ςɈ��������āA�ɑ؉݂̓�����A���i���i�̖\����������B���{�~�ς̓ˑR�̒�~�ɂ�萶�Y�ߒ������ʂ̘J���҂��r�o����A�J���͏��i���i�̋}���Ȓቺ�������ɐ�����B
���D�������Q���s�����D�����E�E�E�̏z�����Q�B
�����{�\���s�ς̒~�ρ�(���Q)�����x�����ꂽ���{�\���ɂ�邠�炽�Ȓ~�ρB
�J���͂̋z����(���Q)���J���͂̔r�o
�������̌X���I�㏸���ꕔ�����N�����i�̋}���Ɠ��@�E�J�����M�����@����A�ɓ�����A���������A�J������
��������19���I���t���̃C�M���X�𒆐S�Ƃ����i�C�z�ł́A�J�����M�͂���قǂł͂Ȃ��A�ނ��뎑�{��`�̎��ӂ��狟�������_�Y�����i�̓��M��������ƂȂ��Ă���B(3)�J���͏��i���̖����Ƃ͉F��̍��グ���_�b�B(4)
���M�p���K�͂ɗ��p�������@(���o���b�W)�Ƃ��̕���͂����鋰�Q�ɐ������镁�ՓI�_�@�B�B��(�H)�̗�O�̓`���[���b�v���Q(�I�����_1636-1637)�ŋ����ɂ��O�������L���s��ꂽ�Ƃ����B
�C�M���X���̏z�����Q��1873�N���Q�ȍ~���ł��A�l�����I�ȏ�ɂ킽���s�������f�t���o�ςɐ��E���{��`�͈ڍs���邪�A���̊Ԃ����20���I�ɓ����đ�ꎟ���E���O�܂ŁA�A�����J��h�C�c���̎�ɓS�����@�̔j�]���_�@�Ƃ���z�����Q�͐����Ă����B�C�M���X�͎���ɎY�ƓI�ȗD�ʂ�r�����Ă������A���E�f�ՂƐ��E���{��`�̋��Z�Z���^�[�Ƃ��Ă̒n�ʂ͗h�邪���A���Q�̐��E�I�g�y�Ƌ��̍Ĕz���@�\���ʂ����Ă����B���̉ߒ��ŃC�M���X���̂ɂ͋��Q�������ɂ͐������A���̂��Ƃ���s�����Ɍ`�����ꂽ�ߏ�Œ莑�{�̔p���ٍX�V������A�A�����J�A�h�C�c�̎Y�ƓI�䓪���������ʂƂȂ����B���{�ʐ��̂��Ƃł̃X�^�[�����O�|���h��ʉݑ̐��B(5)
(1)�@���ۂɂ́A�C�M���X���猩���f�Վ��x�̋t�����Z���蒷���݂��̊��ԃ~�X�}�b�`�Ƃ����܂��ăC�M���X����̓ˑR�̋����o�������A�������h�q�̂��߃C���O�����h��s���}篗��q���������グ��ɂ����ł����B�܂��M�p���Q�ɑΉ������s�[������~�Ɓu�Ō�݂̑���v�ɂ��Ă̓E�H���^�[�E�o�W���b�g�u�����o�[�h�X�v(��O����̉F��O���邪�C���O�����h��s���u�p����s�v�ƋL���ȂǁA���ԗ�R�Ȃ̂�2011���oBP�N���b�V�N�X�ł����E�߂���B�u�����Ɏ������Ǘ�����\�͂͂Ȃ��B���ꂪ�����������o�[�h�X���ɂ͑�ʂɑ͐ς��Ă���v)
���̊��̃C�M���X�𒆐S�Ƃ������Q�ߒ��ɂ��Ă͗�؍���Y�ҁu���Q�j�����v(���{�]�_��1973)�ȂǎQ�ƁB�i�C�z���哱�����Y�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��ȍH�Ƃ����A�{���ŐG�ꂽ�ȉԈȊO�̔_�Y�����@(�����Ȃ�)�������ł��������ƁA�܂����@�I�ɕ~�݂��ꂽ�S���ƂƓS�H�Ƃ̔j�]�����Q���i�v���Ƃ��ĕ������Ȃ��Ă��邱�Ƃɂ����ӁB
(2)�@���Ǝ��{�ɂ��M�p���K�͂ɗ��p�������@�I�Ɍ`���Ƃ��̕�������Q�̌������̎�v�Ȍi�C�Ƃ��Ĉʒu�Â��������Ƃ��āA��؍���Y�ҁu�o�ϊw�����_(��)�v(������w�o�ʼn�1960)����шɓ����u�M�p�Ƌ��Q�v(������w�o�ʼn�1973)�Q�Ƃ̂��ƁB
(3)�@�u���Q�j�����v�Q�Ƃ̂���
(4)�@�Ƃ͂����F��O���u���Q�_�v(��g���X1953��g����2010)�͕K�NJ�{�����B
(5)�@�������s�����ɂ����鐢�E�I�i�C�z�̕ϗe�ɂ��Ă͗�؍���Y�ҁu�鍑��`�����v(���{�]�_��1964)�Q�Ƃ̂��ƁB�܂��z�����Q�̂��̊��ɂ�����p�����ɂ��Ă̍l���̔͘����F�u���E���{��`�v(���{�]�_��1980)���Q�ƁB
|
��2�D ���E�勰�Q���㋰�Q�̚���
�@������(1)�̑r���ƃ����@���b�W�o�ς̑S�ʉ�
��ꐢ�E���̌��ʂƂ��āA�A�����J���{��`�����|�I�n�ʂɗ��B���E�̋��ۗL�̉ߔ����߁A���ő�̍����ɂȂ�オ��B�C�M���X�͑ΊO���̑���������r������ƂƂ��ɁA�|���h��̉��ɋꂵ�ށB���{�ʐ��ւ̓A�����J�ɂ͂邩�ɒx����Ƃ�1925�N���d�ɂ��������ŕ��A�B�P�C���Y�͋��{�ʐ����̈�ƒɔl�B(2)
����1918�N�ɏI�����邪�A�A�����J���{��`����l��s����1919�N�ɋ��{�ʐ��ɕ��A�B��㏈���̂��߂̐Ԏ������ɔ������u�[����1920�N���Q�������ďI�����}���A�r���ł����x���̃��Z�b�V�������܂݂Ȃ�����A��������勰�Q���܂ł��炽�Ȍp���I�i�C�g��ǖʂɈڍs����B���炭1920�N���Q���j��Ō�̏z�����Q�ŁA�풆���Ɍ`�����ꂽ�������̌n�����Z�b�g����A�ߏ莑�{�̐������s����B
�u�i���̔��f�v�Ƃ��Ă��D�i�C�ɕ��������A���ԕ��ςł͔N��3�����ł����Ă����鍂�x�����Ƃ͈قȂ�B������ɂ��撆�������p�������ɂ��S�炸�A��������16���㏸�ɂƂǂ܂�J�����Y����21���㏸�������āA��ʕ����������S���㏸�̋C�z���Ȃ������B����͓Ɛ�̂𒆐S�Ƃ�����ǓI�ݔ������Ǝs��x�z�͂̍��܂�̌��ʂł������B���̊Ԏ��Ɨ���7�D6������2����ɂ܂Œቺ�B
�����i���͒������i�W���A�Ɛ��(����170����)�ƈꕔ�o�c�҂����ȂǕx�T�w�ɕx���蒆�B�l����5����90���̕x������B(3)
�Ɛ�̂ɂ�����J���}���Ƃ��������A���Ƃ��Ƃ̃t�H�[�h�ɑ�\����鍂�����h�N�g����������A�����v�ɂ�������炸�A���łɒ����͍��ʂɂ���Ƃ̌o�c�҂̔F�����������B
�D�����O���܂ł͏Z��u�[�����������������㔼�͉Ɠd���i�⎩���ԂȂǑϋv������u�[���ɂ킫�A����ҐM�p���j�㏉�߂Ď����Ԃ̊����̔��𒆐S�ɕ��y����B
�Ɛ�́E�x�T�w�ɑ͐ς����]�莑�����A�ꕔ�͓������ۂ���ݔ������ɉ���������������̓u���[�J�[�Y���[���̌`�Ŋ����s��ɗ��ꍞ�݃o�u���������邱�Ƃɂȋ�s������Y�Ɗ�Ƃ����ȋ��Z������Ȃ��A�V���Ȏ��x����Ƃ���ɋ��߂��B�d�@�E�d�M�E�f��E�d�͂ȂǐV���Y�Ƃɍŏ��͌����Ȋ����㏸����ꂽ���A����ɑS�ʉ���29�N�ɓ����Ă���͓�����Ђ̐ݗ����o�u���̏�Ƀo�u�����`������悤�ȏ�ɂȂ�A10��24���́u�Í��̖ؗj���v���}���邱�ƂɂȂ����B�����͂���ɐ旧��9��3���Ƀs�[�N�A�E�g��(381�h��)�A����Ȍ�_�o���Ȓl�����������A���ڂɂ̓L���s�^���Q�C�������߂ė��ꍞ��ł����|���h�Z�����|���h�h�q�̂��߂ɂЂ����Ɉ����グ���Ă����̂����������ɁA�ꋓ�ɕ������邱�ƂɂȂ����B
�����s��̓����ɂ������āA�i�C�����͑ϋv������u�[���������Ԑ��Y�ł݂�Ȃ��29�N8���Ƀs�[�N�A�E�g���Ȃ��炩�̌�ދǖʂɓ���������Ƃ�����B
(1)�@����́u���ƓƐ莑�{��`�v(������w�o�ʼn�)����̃Z���g�����h�O�}�͖��_�u�ǂ�ȋ��Q�ł����Ă��K����������B�v�ł���B�Ǘ��ʉݐ��̍��q���C���t������ɂ����������}���ŋ��Q����Ƃ���̂́A�S�����j��m��Ȃ��c�_�B
(2)�@J.M.�P�C���Y�u�ݕ����v�_�v1923
(3)�@�`���[���Y�ER�E�K�C�X�gWall STREET �FA History
�啨����̈�l��J�EF�E�P�l�f�B�̕��e�ł���A�W���[�t�EP �E�P�l�f�B�ŃC���T�C�_�[����▧�����Ȃǂŋ��z�̕x���`���B�t�����N�����E���[�Y���F���g�̎Q�d�̈�l�B
���f�t�����ݐϓI���k�ߒ��̍ی��Ȃ��i�s(1)
�������i�����ɂ��A������S�ۂɌ`������Ă������̕ԍς��}����A�����̓�����ɂ��Ȃ���w�̊��������������݁A���x�͓y�n�A�����A���i�Ȃǂ̎��Y���i���������A����ɂ�荡�x�͎��Y�𓊔��肵�Ă̍��ԍςƂ��������z�������A���Y���i�S�ʂ̍ی��Ȃ��ݐϓI�����ƁA�x�o�̌������Ȃ킿�L�����v�̏k���ɂȂ���A������̂��Ƃ������ԎY�ƂȂǑϋv���������̋���Ɛ�̂̌����Ȑ��Y�����ɔg�y���A���̂��Ƃ��J���҂̃p�[�g�^�C�����A���قƂ��ď�����v�Ɠ������v�̌��ނɂȂ���A��w��ʕ����̒ᗎ���ĂыN�����A���̂��Ƃ��܂����̎������l�����߁A��w�̎x�o���ނɂȂ���A���Y���i�̕����͋�s�̒S�ۂ̗��A��s�o�c���̂̓��h�A�݂��o���p���̕ێ牻���ĂсA��w���Y�Ə���x�o�̏k�����A��蕪���Ĕ_�Ƒݏo�ɓ��������n����s�o�c�̋����������ƂȂ�A���̕��ʂ���a�����t�������Ƌ�s�j�Y���������A�Ɠ����ɏ���x�o�����ɂ����ɔ_�ƌo�c���������A���ςݑ�����Ă������̕ԍς��������Ƃ���y�n�̍����������ɂ��A�����_�Ƃ�������(�u�{��̕����v)��Ԃ����o���A�H�ꂩ��r�o���ꂽ�J���҂̑�ʂ̈�Q�ƂƂ��ɁA����͕s���̈�r���ǂ�?�܂��ɖ\�����e�n�Ŕ������鎖�Ԃɂ܂Ŏ���A�����̂��߂��ɍ��R�����ƂȂ�A���̐擪�ɗ����Ă����̂��}�b�J�T�[�������肵�āE�E�E
1929�N����33�N�ɂ����āA�����ǂ��A�₪��s�~�ύ�Ƃ���5���h���K�ً͂̋}�~�ϗZ�������{���邪�A��s�Ƃ��Ă������t���ɂ���������Ȃ���ɁA�ԍς̌����߂�Z������Ȃ����Ƃ���A���ǘA��ɗa������(���{�I�ɂ̓u�_�ς�)���ق��Ȃ��A����������ʂ͂�����ꂸ�ɏI���A�t�[���@�[�����̂��Ƃ̃t�����N�����E���[�Y���F���g�A�C����̑S����s�x�Ƃɂ܂œ˂��i�ށB���ǂ���������A�̋�s�j�����ʂ��č��̐��������Ζ\�͓I�ɋ��s����A�悤�₭�L�����v�ɕ����̒����������n�߂��̂�������_�@�Ƃ��ĂȂ̂������B
�ǂ��ł�GDP�̓s�[�N�̖��A������10���A���Ɨ���25���Ƃ��������܂����ł������B(�����x�[�X)
(1)�@���f�t���ɂ��Ă�A�E�t�B�b�V���[������B�����\���O�Ɋy�Ϙ_��f���Ėʖڂ����������A����ɂĒ��������B
���[�Y���F���g�����ɂ�邢����j���[�f�B�[�������GDP���5�����x�̐Ԏ������o���ł����Ȃ��A�L�����v�n�o��Ƃ��Ă͌��ʂ͌���I�ł��������A�_�ƕی��J������ɂ��Z�[�t�e�B�l�b�g���悤�₭�`������Ă��������Ƃ��l�X�ɂ����炵�����S�����傫�������̂��낤�B���ꂩ��a���ی�ɂ�邽�a�������s�a���ւ̊җ�����s�݂��o���X�^���X�ɂƂ��Ă͑傫�������B
���[�Y���F���g���g�͋ύt�����_�҂ŁA37�N�ɍ����K�͏k���Ƌ����������߂ɂ��Ă�29-33�N���Q��范�����������݂������Ă��܂��B���S�ɃA�����J�o�ς���������̂͑���E���ɂ����Ă̏��펞�E�펞�o�ϑ̐����̋��z�̌R����x�o��҂��ƂƂȂ�B(�R���P�C���Y��`�̚���)
�勰�Q�́A�A�����J�ꍑ�̌i�C�z�ɂƂǂ܂炸�A��̉��������ےʉ݃|���h�̓��h���I�[�X�g���[���Z���Q(1931�N)�Ɏn�܂鉢�B���Z���Q�ɂ����ɋ��{�ʐ��𗣒E����Ɏ���A��ʉ݂Ȃ����یo�ς̕��f�A�ב؉��������A�ŏ�ǂɂ�鑊�ݕƂ����u���b�N�o�ω��ւ̓���i�݁A����E���ւƂȂ����Ă����B���̈Ӗ��Ŏj���O�̎��{��`���E�̊�@�̌_�@�ƂȂ����B
|
��3�D�T�u�v���C�����Z���Q100�N�Ɉ�x�̊�@(�O���[���X�p��)
�w�i
��2000�N��IT�o�u����n���Ƃ��Ă̒�����̌p��
�������Ɛ���̐��i�ږ��E�Ꮚ���ґw����~�n�x�̊g��̃r�z�E�I��
����҂̃Z�J���h�n�E�X���v�A�x�r�[�u�[�}�[�̏Z��擾�N�
���Z�K���ɘa���V���h�[�o���L���O���Ƌ�s�O�̎������BMMF�ȂNj��Z�H�w�Ȃǂɂ��A�T�u�v���C���w�ւ̏Z��[���g��B
�،����ɂ��I�t�o�����X����
�������͊�ƗV�x����(�������_�E���T�C�W���O)��N���ȂNj@�֓����ƁA�C�O����(�V�����A���{�A�h�C�c�A���ߓ��Ȃ�)
�Ƃ��낪�A2000�N���̃f�t�H���g�f�[�^�Ɖ��i�㏸�X���p������ɂ��郊�X�N�]���ɊÂ�����A�Z��i�̓��ł�(2006)�ƕԍϗD�����Ԃ̏I���ƂƂ��Ƀf�t�H���g�������B�T�u�v���C���،��͐F�X�̋��Z���i�Ɏp��ς��āA�A�����J�����݂̂Ȃ炸���[���b�p�e�n�̋��Z�@�ւ�n�������c�̂ɂ܂Ŋg�U���A���E�I�ȋ��Z��@��U���B
����2008�N9���̃��[�}���u���U�[�X�j�]���_�@�ɁA���Z�V�X�e���S�̂���ჁB
FRB�AECB�A�C���O�����h��s�͑�K�͗����������ƂƂ��Ɏ��Y����Ȃǂ������Ȃ��s���A�勰�Q����j�~�B�V�X�e�~�b�N���X�N����͑勰�Q�̋��P�B������FRB�c���̃x���E�o�[�i���L�͑勰�Q�����̑��l�ҁB
�� ���Z�K���ɘa
���Ă̋�s���F�X�g���C�v�̃_�[�N�X�[�c�𒅂āA�u363�v�̌��������ދ��Ȏd���B3��3���̉����ы����A6��9���ɏo�Ђ���3���ɏオ��6���ԋΖ�3���ߌ�O������͗D�ǎ����ƃS���t�B���ꂪ�n�C���X�N�E�n�C���^�[��������O�̐����n�̖ڂ��ƊE�ɁB��Ƃ̋�s����ɂ��A�����������Ԋ|����B
�� �،����Z�p
�悤�͑吔�̖@���̉��p�B�Z����𑽐����˂�A�f�t�H���g�������肷�邩��A���X�N�W�����q�ω�����B����ɂ�����K�w�������[���X�N�E���[���^�[���A����n�C���X�N�E�n�C���^�[���ɎO���ށB�v�Z��̓n�C���X�N�ł��f�t�H���g�m����10���N��1��H�H
|
��4�D �A�x�m�~�N�X�َ����ɘa�̖��Ӗ���
�勰�Q�ł�����ꂽ�悤�ɁA�s����s���Z������������Ȃ��Z���������Ȃ��Ƃ��ɂ�����}�l�[�T�v���C���₵�Ă��A�u�_�ς݂ɂȂ��Ē�����s�ɖ߂��Ă��邾���B�勰�Q�̂Ƃ��݂͑��o�����X�N���]��ɑ傫���A���t���ɂ�������������Ȃ����ɂ����Ă̂��Ƃ��������A���݂̓��{�̏ꍇ���Ƃ͂��Ȃ���t�]�莑��������Ă��āA�Z���Ă܂œ�������Ӗ����Ȃ��B�����s��͖O�a���Ă���B�u�_�ς݂�j�~����ׂ��}�C�i�X�����ɓ��ݍ������ʔ����ł��Ă��Ȃ��B�s����s�̌h������Z����̈�ł���s���Y�����ɉI��I�ɗ���Ă���̂����m��ȁB
���Ẵo�u���i�C�̎��ł���ACPI�͔N��1.7%�ł��������Ƃ��v���ƁA2%�̃C���^�Q�̖�����������������B�����̓��ł��A���{�o�ϐ�s�����ʂ��̕s�������A�N�����^�̍���Ȃǂ���A��������ȒP�ɏ�����Ƃ͎v���Ȃ��B
�ꕔ�D�Ɛё��Ƃ��A����̃C�m�x�[�V�����⍇�������ɂ��s�ꕗ�i�̌��ςɔ����ď]�ƈ����^�̈��グ�ɑO�����ɂȂ�悤���Ȃ��B
�������v��I�����s�b�N���݂ւ̍����o������ߐ��ɏI��肩�˂Ȃ��B���i�v�I�ȋ��^�⏞���x�[�V�b�N�C���J�����������f�s���ׂ����낤�B�@ |
 �@ �@
���o�u�������̋��Q / ��������X�N�Ǘ� |
   �@
�@
|
|
���T �� |
2007�N�ĂɌ��݉������č��ɂ�����M�p�͂̒Ⴂ�l�����Z��[��(�T�u�v���C���E���[��)�̍��s���s���A�����u�T�u�v���C�����v�́A���[�}���E�u���U�[�Y���̉��Ă̋��Z�@�ւ̔j�]��S���E�̊����s��̖\�����̋��Z��@����N���A���E���Q�̌��O�����w�E�����Ɏ����Ă���B�����������A1970�N��ȍ~�̋��Z���R���A���Z�Z�p�v�V�A���Z�V�X�e���̎s��^�����̋��Z�s��E�V�X�e���̕ϖe(�ȉ��A�u���Z�v���v�ƌĂ�)�����ʂ̋��Z��@�̎���Ƒ����āA���Z��@�Ĕ��h�~��ړI�Ƃ����啝�ȋ��Z�K�������߂铮�����V�������≢�B�嗤�����𒆐S�ɋ��܂��Ă���B���̂悤�ȑ啝�ȋ��Z�K���͋��Z�v�����J�Ԃ����悤�Ƃ��Ă������ݓI�ȏ��@�\(���X�N���S�@�\�A���{�����@�\��)���x���̉��E�ݎ���Ă��܂��댯�������邪�A���Z�v�����̌��㎑�{��`�o�ς����ʂ̋��Z��@�����������悤�ȃo�u���̔����ƕ���ɑ��ď\���Ȗh�~����������Ȃ��̂ł���Α啝�ȋ��Z�K���̓������Î���Ȃ��B�R�����A�o�u���c���𖢑R�ɐH���~�߂鎖�O�I�h�~��ƃo�u�������̎��̌o�ςւ̔g�y���ŏ����ɐH���~�߂鎖��I�h�~��ɑ���l�ނ̉p�m�͑勰�Q��䂪���́u����ꂽ�\�N�v���̑傢�Ȃ鎸�s�o���ƌo�ϊw�I���͂̒~�ς�w�i�ɒ����Ɍ��サ�Ă���Ƃ݂���B�����̖h�~��̂������O�I�h�~��ɂ��Ă͍e�����߂Č������邱�ƂƂ��āA�{�e�ł́A���Z�v�����̌��㎑�{��`�o�ς��o�u�������̎��̌o�ςւ̔g�y�����Q�Ⓑ����Ɏ����O�ŐH���~�߂鎖��I�h�~������Ă���̂��ǂ�������������B���ʂ̋��Z��@��̋��Z�K���݂̍���Ɋւ���c�_�Ɏ�����ޗ�����邱�Ƃ��{�e�̖ړI�ł���B
�{�����ɂ����ĎQ�l�ƂȂ鎖��́A�o�u������̏Ռ��x�����ʂ̋��Z��@�ɕC�G���鎖��ł���B20���I�ȍ~�̐�i���ɂ����Ċ������������s�̕s�Ǎ��䗦�ɂ݂���o�u������̏Ռ��x�����ʂ̋��Z��@�ɕC�G���鎖��́A�勰�Q���̐�i�����A1990�N�㏉���̖k���Ɖ䂪���́u����ꂽ�\�N�v�̎���ł���B�����̎���̂����A�o�u��������GDP ���s�[�N��20���ȏ㌸��������܂ł̌i�C�̒J�̐[���s��(�ȉ��A�����ۂ���ʖ����Ƃ��āu�勰�Q�v�ƌĂ�)����������͑勰�Q���̕č��Ɖ��B�̋��u���b�N�������̎�����x�ł���B�勰�Q���̉p����䂪���A1990�N�㏉���̖k���̎���͌i�C�̒J�͑��ΓI�ɐA�䂪���́u����ꂽ�\�N�v�Ɏ����Ă͌i�C�̒J�̐[���͖w�ǖ��ɂȂ�Ȃ������ł���B�܂�A1990�N�㏉���̖k���Ɓu����ꂽ�\�N�v�ł͏��Ȃ��Ƃ��勰�Q�h�~�ɂ͐��������Ƃ݂���B����A�o�u�����i�C�̒J�̒����s������������́u����ꂽ�\�N�v�݂̂ł���B�ȉ��ł́A�勰�Q�̗v���A���Q�Ĕ��h�~��A�u����ꂽ�\�N�v�̗v���ƍĔ��h�~������Ɍ�������B�@ |
| ���U �勰�Q�̗v�� |
   �@
�@
|
|
�{�͂ł́A�勰�Q�h�~�Ɏ��s�����č��Ɖ��B�̋��u���b�N�������̎���Ƒ勰�Q�h�~�ɐ�������1990�N�㏉���̖k���Ɓu����ꂽ�\�N�v�̎���̔�r�Ɋ�Â��勰�Q�̗v������������B
|
��1�D�勰�Q���ƋߔN�̎����r
�č��ɂ����銔���o�u�������̕s�����勰�Q�ɂ܂Ŏ������v���ɂ��ẮA�t���[�h�}����̃}�l�^���X�g�͘A�M������s���ݕ������ʂ������������Ƃ������Z�v�����A�V�����y�[�^�[������I�i�C�z�_�҂͋Z�p�v�V�̒�Ƃ��������v�������ꂼ�ꋭ������B�����A�����̌����͔@���ɂ������t��̊����ۂ߂��A����̗v�����P�Ƃő勰�Q�������N�������ƌ��ɂ͖���������ƌ��킴��Ȃ��B���݂ł�����I�Ȍ����͖������A���̂悤�Ȑ������L�͂ƂȂ��Ă���悤�Ɍ�����B���Ȃ킿�A�����o�u�������A���̌o�ς��������A�M�p�s�����g�����Ă䂭���A��s���t�����K�͂�傫�����Ȃ���g��U���I�ɊԐڋ��Z�V�X�e�����P�������ʁA���Z�V�X�e�������X�ɕ��A�M�p���k�������B�����������A���Z�V�X�e���̕���⎸�Ƒ��哙�̎��̌o�ς̈����߂Ă̕s�m�����̑�������ւ��Đݔ��E�Z�����ϋv���������𒆐S�ɑ����v���������A�f�t��(�p���I�ȕ�������)����N�B�f�t�����ŘA�₪�\���ȋ��Z�ɘa���s��Ȃ��������Ƃ��瑍���v����w�������A�f�t���������A�����v������Ɉ�w��������u�f�t���E�X�p�C�����v�Ɋׂ����B���̌��ʁA�f�t����10�����ɂ��B�������ߎ���������15�����Ƃ������������ɍ��~�܂肵�ݔ�������ϋv����������₦���܂��A����GDP ���s�[�N��30���ȏ㌸������勰�Q�ɂ܂Ŏ������A�Ƃ��������ł���B
�܂��A���B�̋��u���b�N������(���A�ɁA����)���勰�Q���������v���Ƃ��ẮA�ĉp�������̐�i�������{�ʐ����E�E�����ʉݐ艺���A�ň����グ���̃u���b�N�o�ω��ɑ��钆�A3���{�ʐ��ێ��ւ̌Ŏ��������ʉݍ�(���������בփ��[�g�̑���)�Ƌ����̍��~�܂�����������߁A���A�o�Ɛݔ������𒆐S�Ƃ��鑍���v�̌����ƗA�����i���������ւ��ăf�t����i�s�����A�f�t���E�X�p�C�����Ɋׂ����Ƃ݂���B
����A�ߔN�̖k���Ɖ䂪���ł́A�勰�Q���̕č��ɏ�������x�̃o�u������̏Ռ������ɂ��S�炸�勰�Q�����̌i�C�����͐H���~�߂邱�Ƃ��ł����B�ߔN�̎��Ⴊ�勰�Q���ƈقȂ�_�Ƃ��āA���̎��_����������B���Ȃ킿�A���Z�V�X�e���̈��萫��ێ����鐧�x�Ƃ���[1]�a�����t����h�~���邽�߂̗a���ی����x���m�����Ă��邱�ƁA���Z�V�X�e�����艻��Ƃ���[2]������s�ɂ��ϋɓI�ȗ������̋���(�u�Ō�݂̑���@�\�v�̔���)�A[3]���{�ɂ���s�ւ̌��I�������������{���ꂽ���ƁA���Z�V�X�e���̈��萫�ێ��ƃf�t���E�X�p�C�����̖h�~��ړI��[4]���Z�̑啝�Ȋɘa�����{���ꂽ���ƁA[5]�i�C�ߒ��ɂ����Ď��������בփ��[�g�������������Ƃ��珃�A�o�̑�����������ƁA[6]�������x�̊g���I�������̂�ꂽ���ƁA�ł���B�܂��A�k����䂪���̎���ł͐��E�I�ȋ��Z��@�ɔ��W���邱�Ƃ��Ȃ��������߁A���ۋ������̂���K�v�͖����������A���ʂ̋��Z��@�ł́A�勰�Q���Ƃ͈قȂ�A���Z�V�X�e������A�����E���Z����̔����A���R�f�Ռ����ɂ�����7���ʓI�ȍ��ۋ������̂��Ă���B
|
��2�D�勰�Q�̗v���Ƒ勰�Q���X�N
�勰�Q���ƋߔN�A���ʂ̋��Z��@�̎����r����A�勰�Q�̗v���Ƃ��āA���Ȃ��Ƃ����̘Z�v�������ł��悤�B���Ȃ킿�A���Z�V�X�e�������ɓ�����[1]���Z���x�̕s���A���Z��@����[2]�s�ꗬ������@��[3]��s�V�X�e�����ւ̑�̕s�݁A�啝�ȋ��Z�ɘa�ɓ��ݐꂸ�����v��������������בփ��[�g�����ɋN������f�t���E�X�p�C�����̐i�s��j�~�ł��Ȃ�����[4]���Z����̎��s�A���l�Ƀf�t���E�X�p�C�����̐i�s��j�~���邽�߂̊g���I��������ɓ��ݐ�Ȃ�����[5]��������̎��s�A������[6]���ۋ����̎��s�A�ł���B������o�ϐ��x�E����̖��ł���A�]���č��Ƃ̌o�ϊ�@�Ǘ��\�̖͂��ł���B�����̑S�v���ɑ��A�ߔN�̖k���Ɖ䂪���A���ʋ��Z��@�̎���ł͕�I�ȑ{����Ă��邱�Ƃ���A���㎑�{��`�o�ς��o�u������^�s����勰�Q�ɂ܂Ő[���������郊�X�N�͔��ɒႢ�ƍl������B
�R��A���㎑�{��`�o�ςɂ����āA�o�u������^�s�����勰�Q�ɂ܂Ő[�������郊�X�N�͔��ɒႢ�Ƃ��Ă��A�勰�Q�ɔ�ׂ�Όi�C�̒J�͐�����ł��Ȃ��[���ȕs���A�Ⴆ�A����GDP ���s�[�N��10���ȏ㌸������悤�ȑ�s��(�ȉ��A�u���Q�v�ƌĂ�)���������X�N�͂ǂ̒��x�ł��낤���B�܂��A���㎑�{��`�o�ς͂����������Q���X�N�ɑ��@���ɔ�����ׂ��ł��낤���B���͂ł́A�����̖�����������B
�@ |
| ���V �o�u�������̋��Q�������X�N�Ɩh�~�� |
   �@
�@
|
|
���㎑�{��`�o�ς��o�u������^�s�������Q(����GDP ���s�[�N��10���ȏ㌸�������s��)�ɐ[���������Ȃ��h�~��������Ă���̂��ǂ�������������ɍۂ��ẮA�勰�Q�̗v���Ƃ��ē��肵����L�Z�v���̎��̌o�ςւ̉e�����ڍׂɌ�����K�v������B�O�q�̒ʂ�A���㎑�{��`�o�ς͍��ʂ̋��Z��@���̑Ή��ɂ݂���悤�ɁA��L�Z�v���ւ̑Ή����ł���͂��邪�A��������\�ł͂Ȃ��A�����Z�v���̎��̌o�ςւ̈��e�������S�ɖh�~���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����߁A�����̗v�����������x�̋K�͂Ō��݉����A�����p������`�ŋ��Q����N����\���͔ے�ł��Ȃ��B�]���āA���㎑�{��`�o�ςɂ����Ċ��҂����鐭�������ꂽ�ۂɂ����̗v�����ǂ̒��x�̋K�͂Ō��݉������邩�����ɂ߂�K�v������B
|
��1�D���ۋ����E��������̎��s
��(1)���ۋ����̎��s
���ʂ̋��Z��@�ł́AIMF�A���ⓙ�̍��ۋ@�ւ�G8�AG20���̍��ۉ�ŁA�����I�ȋ��Z�V�X�e�����艻�[�u�A�����E���Z����̋����I�����A���R�f�Ռ����̍Ċm�F�Ȃǂ��ׂ����ȂǁA���ۋ����͑������x�I���@�\���Ă���悤�ł���A���ۋ����̎��s�����Q�̈���ƂȂ�\���͔��ɒႢ�悤�Ɏv����B�����A����̋��Z��@�Ĕ��h�~��ɂ��ẮA�V�������AEU �����A���Ă̊Ԃł͎v�f�ɑ����Ȋu���肪����A�\�f�������Ȃ��ɂ���B
��(2)��������̎��s
�����`���Ƃł��邩�ۂ��ɍS��炸�A�����̌i�C��ւ̋����v�]�����㍑�Ƃ̐���ɑ���Ȉ��͂�������d�g�݂ƂȂ��Ă���ȏ�A�����o���̋K�͂��ߏ��Ɏ~�܂�A���Q�̈���ƂȂ�댯���͔��ɏ������Ǝv����B�J�돫���I�Ɍx�����ׂ��́A���{�������債���ƍ����̌��S�����������ቺ���Ă��܂����X�N�ł���B���������Ɋׂ�A�o�ϊ�@���Ɋg���I��������������Ă����Ԃ͏����̑��ł�\��������E���������S�O���邽�߁A�i�C���g���ʂ͖w�NJ��҂ł��Ȃ��Ȃ邩��ł���B�䂪���̍����́A���ɗ\�f�������Ȃ��ɂ���B�����̋��Q��@���ɔ����Ċg���I��������̗L�������m�ۂ��Ă������߂ɂ����}�ɍ��ƍ����̌��S���ɓw�߂�K�v������B
|
��2�D���Z�V�X�e���̋@�\�s�S
���Z�V�X�e�����@�\�s�S�Ɋׂ�v���Ƃ��ẮA�a�����t���ɂ���s�̑�K�͔j�]�����͌��σV�X�e����ʂ��Ă̘A���j�]�A�M�p�s����w�i�Ƃ�����Z�s��ɂ����闬������@�A���Ȃ킿�A��s�̒Z���������B�E�^�p�s��A��Ƃ̎������B�s��A�l�������B���邽�߂̃N���W�b�g�J�[�h�E�����ԃ��[����Ђ̎������B�s��ɂ����闬������@�A�s�ǎ��Y�̑����w�i�Ƃ����s�݂̑��a��E�ǂ��݂��ɂ����Z����@�\�̒ቺ�A����������B
��(1)��s�̑�K�́E�A���j�]
�a�����t���ɂ���s�̘A���j�]�ɑ��ẮA�a���ی����x����������Ă���ق��A���Z��@���ɂ͐��{�ɂ��a���ۏ؊z�̈����グ��S�z�ۏ��̂���B�܂��A���Z�@�ւ̔j�]�����σV�X�e����ʂ��ĘA���I�ɔg�y���錈�σ��X�N��h�~���邽�߁A�����O���X���σV�X�e���������̍��X�œ�������Ă���B�]���āA�a�����t���⌈�σV�X�e����ʂ��Ă̋�s�̑�K�͔j�]��A���j�]�̃��X�N�͔��ɏ������ƍl������B
��(2)���Z�s��ɂ����闬������@
�M�p�s����w�i�Ƃ����s�̒Z���������B�E�^�p�s��A��Ƃ̎������B�s��(CP�E�Ѝs��)�A�l���������B(�N���W�b�g�J�[�h�E�����ԃ��[��)���s�����߂̃N���W�b�g�J�[�h�E�����ԃ��[����Ђ̎������B�s��(���Y�S�ۏ،��s��)�ł̗�������@�́A���u���Ă����ƁA�������s���ɋN��������Z�@�ւ�
�j�]�A�s������̍��~�܂�A���{�s��̏k���A�����߂Ă̋�s�݂̑��a�蓙�̗l�X�ȕ��Q�����B���̂悤�ȗ�������@�ɑ��āA���ʂ̋��Z��@�ɂ����āA������s�E���Z���ǂɂ�鎟�̂悤�ȑΉ����̂�ꂽ�B��s�̒Z���������B�E�^�p�s��(��s�Ԏs��)�ɂ����ẮA�e������s����s�Ԏs��ɑ���h�������̑�ʋ�����M�p�ۏɂ��Ή��B�܂��A��Ƃ̎������B�s��(CP�E�Ѝs��)�ɂ����ẮAFRB�A�ĘA�M�a���ی�����(FDIC)�����ꂼ��D��CP �̍w���A�D�ǎЍ̐M�p�ۏɓ��ݐ����B����ɁA���Y�S�ۏ،�(ABS�AAsset Backed Securities)�s��ɑ��Ă��A���ʂ̋��Z��@�ɂ����āAFRB ��ABS�ۗL�����Ƃɓ��Y�،���S�ۂɑݏo���s�����x�������B�����̈�A�̗����������[�u�ɂ݂���悤�ɁA����̒�����s�E���Z���ǂ͗�������@�ɑ���F���������̂ŁA��������@���������x�̋K�͂ƂȂ��Ċg����A���Q�̈���ƂȂ����������ƍl������B
��(3)�ǂ��݂��E�݂��a��ɂ����Z����@�\�̒ቺ
�����ŁA�ǂ��݂��Ƃ́A�s�Ǎ����B����������s�o�c�҂̐ӔC���I���@�Ȃǂ����s���s�Ǎ����j�]�����Ȃ��悤�ɑ݂��o���𑱂���A�Ƃ������ł���B����������s�̒ǂ��݂��E�݂��a��ɑ��ẮA�䂪���́u����ꂽ�\�N�v�̌o�����L���ȋ��Z�V�X�e�����艻����������Ă���B�Ƃ�킯�A2002�N10���ɋ��Z�������\�����u���Z�Đ��v���O�����v�́A���v���O�������\�O�̎�v�s�s�Ǎ��䗦��2002�N3������8�D4������2005�N3������2�D9���ւƑ啝�ɒቺ�����A�o�u������ȍ~�̒��N�̌��Ăł������s�Ǎ����̉����ɍv����������ł���A�L�����������Ǝv����B�u���Z�Đ��v���O�����v�ł́A�ߋ�2��̋��Z�V�X�e�����艻��(1997�N����́u���Z�@�\���艻�@�v�A1998�N����́u�������S���@�v�u���Z�Đ��@�v��)���s�\���ɂ����@�\���Ȃ��������Ƃ܂��� 1) �A[1]���Y����̌��i���A[2]���Ȏ��{�̏[���A[3]�K�o�i���X�̋����A�̎O�̒����ł��o����Ă���B����͎��̂悤�ȗ��R�Ɋ�Â����̂ł���B���Ȃ킿�A���Y����̌��i�����s���Ȃ���A�K�Ȍ��I���{���������{�ł��Ȃ����A���Ƃ����Y��������i�Ɏ��{�����Ƃ��Ă��A�ǂ��݂�����N����قNj�s���̌o�c�K���@�\���o�ɂ��Ă���Ƃ݂���ň��ՂɌ��I���{���������{���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ɁA���I���{���������{����A���Ȏ��{�䗦�����シ��ƁA���X�o�ɂ��Ă�����s���̌o�c�K���@�\����w�o�ɂ���댯��������ق��A�����s��̌o�c�K���@�\���o�ɂ���댯��������B������2�ł́A���ȑ����w�͂����߂�ꂽ�ق��A3�̃K�o�i���X�̋����Ƃ��āA�O���č��@�l�ɂ�錵���ȐR���A���������[�u�̌��i���y�ё����x�����x�̊��p�A���I���{�����s�ɑ���K�o�i���X�̋����A���ł��o���ꂽ�̂ł���B���ɁA�s�Ǎ�������D�悵�������Z���̎v�f���猵�i�ɂ͓K�p����Ȃ������u�������S���@�v�ɂ�����u�O�����[���v(��1�Q��)�����i�����A���I���������s�ɑ��ĕs�Ǎ������Ǝ��v�͂̋������ɒNjy��������j���ł��o���ꂽ�B���̂悤�ȎO�̒�����Ȃ���I���������ȊO�̋��Z�V�X�e�����艻��Ƃ��āA�s�ǎ��Y�̔������E������ 2) ���s�̈ꎞ���L�����s���A�������x�̐��ʂ��������悤�ł���B�܂��A��s�̕s�Ǎ��������o�c�s�U��Ƃ̍s�߂����j�]�������Ȃ��悤�A�Y�ƍĐ��@�\�̊��p�ɂ��A�Đ��\�Ȋ�Ƃ̍Đ����}��ꂽ�B�ȏ�̋��Z�V�X�e�����艻����l������ƁA�ǂ��݂��E�݂��a��ɂ����Z����@�\�̒ቺ�����Q�̈���ƂȂ�댯���͒Ⴂ�悤�Ɏv����B
|
��3�D�f�t���E�X�p�C�����E���X�N
�f�t�������Q���\�������ɂ߂邽�߂ɂ́A�f�t���E�X�p�C�����̔����@�\��F������K�v������B�f�t���E�X�p�C���������̌����Ƃ��ẮA���ڒ����̉����d�����ƃ[���������w�E����Ă���B
��(1)���ڒ����̉����d����
���ڒ����ɉ����d����������ꍇ�A�f�t���ɂ���Ď����������㏸���邽�߁A�J�����v���������A�ٗp����������B���̌��ʁA�ٗp�������������邽�߁A������𒆐S�ɑ����v���������A�f�t������������Ƃ������z��������A�Ƃ����o�H�ł���B�R���A�u����ꂽ�\�N�v�̊Ԃł́A���ڒ����̉����d�����́A1997�N�����͊ώ@�������̂́A�f�t�����[��������1998�N�ȍ~�͊ώ@����Ȃ��Ȃ����A�Ƃ̎��،��ʂ�������Ă���(���c�E�R�{(2004))�B����ォ��1970�N�O�������A��i�����ł́A�������A���C���t���A�����J���g���̒������͓���w�i�ɖ��ڒ����͈�����x�����d���I�ł������悤�Ɏv���邪�A���̌�̓��ƈɂ𒆐S�Ƃ����������̒ቺ�A��ꎟ�Ζ���@��̒�����s�̕����Ǘ�����̋�����w�i�Ƃ���C���t�����̒ቺ�A�J���g���̒������͂̎�܂�Ȃǂ�w�i�ɖ��ڒ����̉����d�����͔������悤�Ɍ�����B����A��i�����ɂ����āA�����������傫���ω����Ȃ�����A���ڒ����̉����d�������f�t���E�X�p�C�����E���X�N����N����댯���͒Ⴂ�ƍl������B����ABRICS ���̐V�������ł́A��������w�i�ɃC���t�����͍��߂Ő��ڂ��Ă��邽�߁A�f�t�����̂Ɋׂ�댯�����������ƍl������B
��(2)�[����������
�[����������ɋN������f�t���E�X�p�C�����Ƃ́A���ڋ����̓[���ȉ��ɉ������Ȃ����Ƃ��疼�ڋ������[���ɓ��B������̓f�t���̉��������������̏㏸�������N�����A���ꂪ�����v�����������A�f�t������w���������A�f�t���E�X�p�C�����������N�����A�Ƃ����_���ł���B������ɋN������f�t���E�X�p�C������h�~�����Ƃ��ẮA���₪�f�t������2001�N3���ɍ̗p�ɓ��ݐ����u�ʓI�ɘa����v�����j��A�B��̐���ł���B�ȉ��ł́A�ʓI�ɘa���f�t���E�X�p�C������h�~������̂��ǂ�����ʓI�ɘa����̗��_�I���ʂƉ䂪���̌o���܂��Č�����B
���₪�̗p�����ʓI�ɘa����͎��̓��ނ̐���\������Ă���B���́A���Z����̖ڕW����s�Ԏs��̒Z�������ł���R�[�����[�g���疯�ԋ�s�̓��ⓖ���a���c���Ƃ����ʂɕύX���A�����a���c���ڕW�������グ�A����Ȏ����������s�����Ƃł���A���́A����ҕ����w���̑O�N��㏸��������I�Ƀ[�����ȏ�ƂȂ�܂ŗʓI�ɘa���p������Ƃ����ł������B���̐���́u������s�̍w�����鎑�Y�\���̕ω��ɂ����ʁv 3) �Ɓu�ʊg��̌��ʁv 4) ���A���̐���́u���Ԏ����ʁv�����ꂼ���}��������Ƒ�������B�����̌��ʂ̂����L���Ɗm�F�����̂́A����(2008)���咣����悤�ɁA�[�������p������邱�Ƃɂ���Ė��Ԃ̊��ҒZ��������ቺ�����A��Ⓑ�ڂ̋�����ቺ�����鎞�Ԏ����ʂ���}���������ł���B����ɂ��S��炸�A�f�t���̓f�t���E�X�p�C�����ɔ��W���邱�Ƃ͂Ȃ��ɂ₩�ȃf�t���Ɏ~�܂����B
�f�t���E�X�p�C�����Ɋׂ�Ȃ��������R�Ƃ��āA���Ȃ��Ƃ��A�ʓI�ɘa����̎��Ԏ����ʂ��@�\�������ቺ��ʂ��Đݔ������A�Z����A�ϋv���������傳�������Ƃɉ����A�f�t���ɔ������������בփ��[�g�̌����ɂ�菃�A�o�����債�����ƁA�̓�_���������悤�B�����A��҂͍��ʂ̋��Z��@�̂悤�Ȓn���K�͂̃o�u�����ɂ͊��҂ł��Ȃ��B
����ł͉��ɁA��҂̌��ʂ����҂ł��Ȃ��悤�ȏŃo�u�������Ƀf�t���ɓ˓������ꍇ�A������s���ʓI�ɘa����ɂ܂œ��ݐ����Ƃ��Ă��f�t���E�X�p�C�����Ɋׂ�댯��������̂ł��낤���B���̂悤�ȓ��ɉ����邽�߂̍ŗǂ̔��f�ޗ��͂����Η��j����^������BBordo and Filardo (2005)�́A�{�e�ł͎˒����y��ł��Ȃ�19���I�ɂ܂ők��A19���I�ȍ~�̐��E�̗l�X�ȃf�t���̎���������������ʁA�u�����Y�ʂ̑啝�Ȍ������f�t���͊ł���A���������������Ȏ���̑唼�͑勰�Q���ɏW�����Ă���v 5) ���Ƃ��u��^�����ꂽ�����v�Ƃ��ĕ��Ă���B�����āA�u���j��A�f�t���͂����Βꌘ���o�ϐ��������Ă����B�����1990�N��̓��{�ɂ�����f�t����勰�Q�ɂ�����f�t�������ʓI�Ɉ����o����鋌���̉p�m�Ƃ͑ΏƂ��Ȃ��Ă���v�Ǝ咣���A�J�ԃf�t���E�X�p�C�����E���X�N����������߂��Ă��邱�Ƃ��������Ă���B
�ȏ�̋c�_�����Z�߂�ƁA���̎b��I���_�������悤�B�[����������ɋN������f�t���ɑ��ẮA�O�q�̋��Z�V�X�e�����艻��̔����ɂ����Z�V�X�e���̋@�\�s�S��h�~������ŁA�f�t���E�p�܂ŗʓI�ɘa���p������Ɩ���ʓI�ɘa������̂�A�f�t���E�X�p�C�����E���X�N�Ɋׂ郊�X�N�͏������B���ɁA���������בփ��[�g�̌����ɂ�鑍���v�̉��x�����ʂ����҂ł���ꍇ�̓f�t���E�X�p�C�����E���X�N���ŏ����Ɏ~�ߓ���B�]���āA���㎑�{��`�o�ςł̓f�t���������Ƃ��鋰�Q���X�N���������ƍl������B
�@ |
| ���W �u����ꂽ�\�N�v�̗v���A��������X�N�ƍĔ��h�~�� |
   �@
�@
|
|
�{�͂ł́A�䂪�����o������������ł���u����ꂽ�\�N�v�̗v���Ɠ������E�p������I�Ȑ����O���ɏ悹�鐭��ɂ��āA����ؒ��ɌJ��L����ꂽ�_����������A�������̒�����ؒE�o�E�����i�C�g��ߒ����Q�l�ɂ��Ē�����̗v���ƍĔ��h�~�����������B
|
��1�D�u����ꂽ�\�N�v������_��
�u����ꂽ�\�N�v�Ɋւ��ẮA1990�N�㖖����2005�N�����A�����̘_�҂ɂ��l�X�Ȍ�����������Ă������A�c�_��}���I�ɐ������邽�߂ɁA�����̌����������ĎO�ɑ�ʂ���ƁA�ȉ��̒ʂ�ł���B���Ȃ킿�A���ɓI�����E���Z����(���ɏ��ɓI���Z����)�Ƌ�s�݂̑��a�肪��N���������v�s���ɋN������f�t���E�X�p�C����������Ƃ݂ăC���t����ڕW�Ƃ����ϋɓI�ȗʓI�ɘa����Ƌ��Z�V�X�e���̋@�\����}������s�ւ̌��I�������������u���t���h�v 6) �ƁA�Y�ƍ\�������̒x�����ꎟ�I�v���A���Z�V�X�e���̎��{�����@�\�ቺ���I�v���Ƃ݂ĎY�ƍ\�������𑣐i���邽�߂̍\�����v(�啝�Ȍ����x�o�팸�E�s�������v�E�K���ɘa����)�Ƌ��Z�V�X�e���̋@�\��}�邽�߂̕s�Ǎ����������u�\�����v�h�v 7) �A�f�t���ɉ������Z�V�X�e���̎��{�����@�\�ቺ�ƎY�ƍ\�������̒x��������Ƃ݂邪�A�s�Ǎ������ƍ\�����v�͒Z���I�ɂ͎��̌o�ς�����������Ƃ̊ϓ_����A�f�t���E�p�̂��߂̃C���t���E�^�[�Q�b�g�t���ʓI�ɘa�����s�Ǎ������E�\�����v�ɐ�s�����邩�A�����̓C���t���E�^�[�Q�b�g�t���ʓI�ɘa����ƕs�Ǎ������E�\�����v���ɐ��i���ׂ��A�Ƃ���h(�{�e�ł́A�u���t���\�����v�h�v 8) �ƌĂ�)�ł���B�����O�h�́u����ꂽ�\�N�v�Ɋւ���f�f�ƒ�����ؒE�p�̂��߂̏���Ⳃ͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
��(1)���t���h�̐f�f�Ə����
���t���h�́u����ꂽ�\�N�v�̗v�������̂悤�ɐf�f����B�o�u�������A�t���Y���ʂ�s�m�����̑��傩�瑍���v���������Ă������A���Z�ɘa�̒x������GDP �M���b�v����N��1994�N��4�l�����ɂ͌y���Ȃ���f�t��(GDP �f�t���[�^�E�x�[�X)�������B���̌�A���₪95�N�̉Ă���H�ɂ����Ă̑啝�ȋ��Z�ɘa�ɓ��ݐ������Ƃɂ���Ĉꎞ�I�Ɍi�C�͉����B�R���A97�N�̋��{�������ُ̋k�I�����ւ̓]���A�����Z�@�ւ̑������j�]�ɂ����Z�s������GDP �M���b�v���g�債�f�t�����{�i�������B�f�t�����ŁA���ڒ����̉����d�����ƃ[����������ɋN�������̌o�H�ɂ�閯�Ԏ��v�̉��������ʂɉ����A�s�Ǎ��̑���Ɗ����̑啝�����ɔ������Ȏ��{�䗦�̒ቺ�ɒ��ʂ�����s�݂̑��a��������āA�f�t���E�X�p�C�����Ɋׂ����B�ȏ��v��ƁA�o�u������ɔ��������v�s���Ƃ����{���͒Z���I�Ȗ��ɑ��A�����E���Z���\���Ȏ��v�n�o������̂�Ȃ��������߁AGDP �M���b�v���g��A�f�t���������N���������Ƃɉ����A��s�̎��Ȏ��{�s���ɋN������݂��a��������āA�f�t���E�X�p�C�����Ƃ����[���ȑ����v�s��������������Ɋׂ����A�Ƃ̐f�f�ł���B
�ȏ�̐f�f�Ɋ�Â��A�[���ȑ����v�s���ł���f�t���E�X�p�C��������E�p���邽�߁A�啝�Ȏ��v�n�o����}�����A�搔���ʂ̍��������I�Ȋg���I��������ƃC���t���E�^�[�Q�b�g�t���ʓI�ɘa����ɓ��ݐ�ׂ��A�Ƃ̏���Ⳃ��������B�����ŁA�C���t���E�^�[�Q�b�g�t���ʓI�ɘa����Ƃ́A���₪�f�t���E�p�Ɏ~�܂�Ȃ��N��1�`3���̃C���t���E�^�[�Q�b�g���f���āA���ڕW�B���̂��߁A1�������̔�����I�y�̑啝���z�̂ق��A2�O���ď،��̔�����I�y�̑啝���z�A3�����M���E�s���Y�����M�����̑�ʍw�����ɓ��ݐ邱�Ƃ�\�������s�Ɉڂ��ׂ��A�Ƃ������̂ł���B
��(2)�\�����v�h�̐f�f�Ə����
�\�����v�h�́u����ꂽ�\�N�v�̗v�������̂悤�ɐf�f����B�䂪���͑����A��i���Ŋm������Ă�������̐��i�E�����ߒ���͕�E���P���邱�Ƃɂ��o�ϐ����������ł��闧��ɂ���V�����Ƃ��āu�J���^�v�̎Y�ƍ\�����m�������B�R��ɁA1970�N��㔼�ɂ͓��{�o�ς͊J���i�K���T�ˊ����������߁u��i�^�v�̎Y�ƍ\���ւ̓]�����K�v�ƂȂ���(�r��(2006))���Ƃɉ����A1980�N��㔼����O���[�o���[�[�V������IT �v���ɂ��n���K�͂̎Y�ƍ\���̓]�����i�ݎn�߂����Ƃ���A�Y�ƍ\�������̈�w�̒x�������݉�����悤�ɂȂ����B���̊ԁA���ƂƊ��Ƃ̊W�ɂ����Ă��A�u�J���^�v�o�ςɂ����Ă͈�����x�̖������ʂ����Ă����Ƃ݂���X���E�����E���{�n���Z�@�ցE����@�l�������Ԃ���z���グ�����z�����������I�Ȑ��{�n���哙�ɓ�������d�g�݂Ɖ�������A���Ƃ̖��ƈ����̕��Q���w�E�����悤�ɂȂ����B����ɁA���Ԃ̋��Z�V�X�e���ɂ����Ă��A�u�J���^�v�o�ςł͈�����x�@�\���Ă����Ԑڋ��Z�D�ʂ́u���Ό^���Z�V�X�e���v�ɂ��Ă��A�u��i�^�v�o�ςƂ̓K���x�������Ƃ����s��^�Ԑڋ��Z����荞�u�s��^���Z�V�X�e���v�֏d�S���ڂ����Ƃ����߂��n�߂�(�r��(2006))�B
�����������A80�N��㔼�ɔ��������o�u�����~���s�����ɒ�����i�߂悤�Ƃ��Ă�����Ƃɒ�����x�点��U����^�����ق��A�o�u�������̌������ƒ��S�̊g���I��������TFP(Total Factor Productivity�A�S�v�f���Y��)�㏸���̒Ⴂ�����x�o�֘A�Y�Ƃ̎������ێ���������ɍ�p�������ƂȂǂ���Y�ƍ\����������w�x�点��(�r��(2006))�B
�܂��A���{�n���Z���܂ߊԐڋ��Z�D�ʂ̉䂪���̋��Z�V�X�e���ɂ����āA��s���s�Ǎ����ʂɕ����邱�ƂɂȂ������߁A�����̑啝�����Ƃ����ւ��Ď��Ȏ��{�䗦���ቺ���A���X�N���e�x�̒ቺ�����玑�{�����@�\���ቺ�������ߊԐڋ��Z�D�ʂ̋��Z�V�X�e���S�̂̎��{�����@�\���ቺ�����B�����������A���Ȏ��{�s���Ɋׂ�����s�����C���E�o���N���̉��A�o�c�҂̕s�Ǎ��B�����@�Ƃ����ւ���TFP �㏸���̒Ⴂ�����ɑ��ǂ��݂��𑱂��A���w�����̈��S�^�p�ɑ���ATFP �㏸���̍����V��������Ɠ��̃n�C���X�N�E�n�C���^�[���̗Z���Č��ɑ��đ݂��a�������߁A��w�̎Y�ƍ\�������̒x���������̂ł���(��(2008))�B
���������Y�ƍ\�������̒x���TFP �㏸�����Ⴂ�Y�Ƃ��獂���Y�Ƃւ̎����Ĕz�����x�̒ቺ���Ӗ����Ă��� 9) �A���̌��ʁA�o�u�������̓��{�o�ς�TFP �㏸���͒ቺ�� 10) ������Ɋׂ����̂ł���B����ɁA���̂悤�ȍ\�������̒x���ɂ��S�炸�A�\�����v���i�ɓ��ݐ�Ȃ������ɑ���s�M����w�i�Ƃ�����{���肪�������̎��Y���i�̈�w�̉��������������Ƃ���A�t���Y���ʂɂ����v�ʂ�����i�C�̑��������������̂ł���B
�ȏ��v��ƁA1980�N��������Ɂu��i�^�v�ւ̓]�����K�v�ƂȂ��Ă����䂪���̎Y�ƍ\���́A80�N��㔼����i�ݎn�߂��O���[�o���[�[�V������IT �v���ւ̓K���A�����疯�ւ̓]���A�Ԑڋ��Z����u��i�^�v�o�ςւ̓K���x�������s��^�Ԑڋ��Z�ւ̓]�����̈�w�̓]�����v�������悤�ɂȂ����B�����������A80�N��㔼�ɔ��������o�u���ƃo�u�������̊g���I�������Y�ƍ\�����ێ���������ɍ�p�������ƂȂǂ���Y�ƍ\����������w�x�点���ق��A�Ԑڋ��Z�D�ʂ̉䂪���̋��Z�V�X�e�����s�Ǎ���肩�玑�{�����@�\��ቺ���������߈�w�̎Y�ƍ\�������̒x���������B�܂��A�\�����v�ɓ��ݐ�Ȃ������ɑ���s�M������w�̎��Y���i�̉����������A���v�ʂ�����i�C�̑��������������A�Ƃ̐f�f�ł���B
�ȏ�̐f�f�Ɋ�Â��A���Z�V�X�e���̎��{�����@�\��}�邽�߂̕s�Ǎ������ɉ����A�Y�ƍ\�������𑣐i���邽�߂̑啝�ȍs�������v(�����x�o�팸�A�X�����c���A���{�n���Z�@�֓��̓���@�l���c���E���p��)�ƋK���ɘa����Ȃ�\�����v�����{���ׂ��A�Ƃ�������Ⳃ��������B��҂̍\�����v�ɂ��ẮA�����x�o�팸���͒Z���I�Ɏ��v�����������锽�ʁA�����̂��̑��̉��v 11) �͒Z���I�ɐ��ݓI���v���@��N�������Ƃɂ��Z���I�Ȍi�C�g����ʂ����҂ł���ق��A�������I�ɒx�����Ă����Y�ƍ\�������𑣐i���A���{�o�ς�TFP �㏸�������߂�A�Ƃ����������I�Ȍo�ϐ������ʂ����҂ł���B��҂̌��ʂɑ��ẮA�����ʂ��ǂ݂���s��Q���҂͊��҂�����C�����邱�Ƃ���A������f�������Y���l�̏㏸�ɂ�鎑�Y���ʂ����҂�����B�]���āA�����̒Z���I���ʂɂ����{�o�ς���r�I�����ɒ��������E�o���A�������I���ʂ�����{�o�ς������O���ɏ�邱�Ƃ�W�]�ł���B
��(3)���t���\�����v�h�̐f�f�Ə����
���h�́A�u����ꂽ�\�N�v�̗v���Ƃ��āA�f�t���A���Z�V�X�e���̋@�\�s�S�A�\�������̒x���̉���̗v�����d������B�����̂����A���Z�V�X�e���̋@�\�s�S���d�v�ȗv���Ƃ݂邱�Ƃɂ��Ă͊T�˔F������v���Ă���悤�ł��邪�A�f�t���ƍ\�������̒x���̉�������d�����邩�ɂ��ẮA�_�҂ɂ��f�f��������Ă���͗l�B�R����A������ؒE�o�̏���Ⳃ��T�ˋ��ʂ��Ă���̂́A�s�Ǎ������ƍ\�����v�͒������I�Ȍo�ϐ��������L���Ȑ���ł��邪�A�Z���I�ɂ͕s�Ǎ������E�\�����v�ߒ��Ŋ�Ɠ|�Y�⎸�Ɣ�������ʂ��Ĉ�w�i�C�����������镉�̌��ʂ����邽�߁A�f�t�����ŕs�Ǎ������ƍ\�����v�𐄐i����͕̂s�K�A�Ƃ̋��ʔF�������邩��̂悤�ł���B���F���Ɋ�Â��āA�f�t���E�p�̂��߂̃C���t���E�^�[�Q�b�g�t���ʓI�ɘa�����s�Ǎ������E�\�����v�ɐ�s�����邩�A�����́A�C���t���E�^�[�Q�b�g�t���ʓI�ɘa����ƕs�Ǎ������E�\�����v���ɐ��i���ׂ��A�Ƃ�������Ⳃ��������B
|
��2�D�u����ꂽ�\�N�v�̗v��
��L�_������u����ꂽ�\�N�v�̗v���̌��Ƃ��ẮA���Z�V�X�e���̋@�\�s�S�������s�Ǎ������̒x���A�o�u�������̋t���Y���ʂ���Z�V�X�e���̋@�\�s�S�ɋN�����鑍���v�s���ɑ�����ɓI�����E���Z����A�\�������̒x���̎O����������B�����̎O����u����ꂽ�\�N�v�̗v������肷��ɍۂ��ẮA�������ŁA�u����ꂽ�\�N�v����E�p���A�u�����Ȃ��i�C�v������Œ��̌i�C�g��������v����T�����邱�Ƃ����f�ޗ���^����B
�������ł́A�s�Ǎ������̒x���ɂ����Z�V�X�e���̋@�\�s�S�������鐭��Ƃ��āu���Z�Đ��v���O�����v���A�f�t����E�p���鐭��Ƃ��ē��₪���{�����ʓI�ɘa���A�\�������𑣐i���鐭��Ƃ��Č����x�o�̍팸�A�s�������v(����@�l�̓��p���E�Ɨ��@�l���E���c��)�A�K�����v(�N�Ƒ��i����}�����Œ᎑�{�����x�̓���[�u�̓����A�u�Γ��������i�v���O�����v�̍���A�l�ޔh���s��̋K���ɘa�A�����q��̋K���ɘa�A���������ϑ��萔���̎��R����)�̎O�̐�����܂ލ\�����v�����ꂼ��̂�ꂽ12)�B�]���āA�u����ꂽ�\�N�v����E�p�������i�C�g������������v�����Ƃ��āA�u���Z�Đ��v���O�����v�A�ʓI�ɘa����A�\�����v�A�̎O����������B�܂��A�������������v�����ȊO�ɁA[1]�f�t���ƗʓI�ɘa���Ŏ��������בփ��[�g���ቺ�������A���E�i�C�̊g������ւ��ď��A�o�����債�����Ƃɉ����A[2]�u�בփ��[�g�v�̌����ɔ����ΊO�����Y�̑����ɂ�鎑�Y���ʂ��瑍����E�����傳�������ƁA[3]���Ԋ�Ƃ̌o�c�w�͂ɂ����v��Ղ̋����A�̎O���w�E�����B�ȉ��ł́A�����̐���ȊO�̗v����������������ŁA�����v��������������B
�@ |
| ���v�����
|
   �@
�@
|
��1�D����ȊO�̗v�����
��(1)���������בփ��[�g�̒ቺ�ɂ�鏃�A�o����
���������בփ��[�g(���⎎�Z�l�ŁA1973�N3����100�Ɋ���A���l�������قlj~���ł��邱�Ƃ�\��)�̐��ڂ��݂�ƁA1999�N12����148�D1�_�ɊT�ˈ�{���q��2002�N4����115�D2�܂ʼn~�����i�s�������A���̌��2005�N3���܂�115�`125�̒�ʐ���������I�ɐ��ڂ��Ă���B�����������A����GDP�������̊�^�x�������݂�ƁA2002�N��2�l�������瓯��4�l�����܂ł͊O���̊�^�x���傫�����̂́A2002�N��1�l�����ȍ~�͊�{�I�ɓ����哱�̌o�ϐ����𑱂��Ă���B�]���āA���������בփ��[�g�̒ቺ�ɂ�鏃�A�o����́A�u����ꂽ�\�N�v����E�p��������Ƃ݂邱�Ƃ͂ł�����̂́A�u�����Ȃ��i�C�v������Œ��̌i�C�g��̎���ł͂Ȃ����Ƃ��M����B
��(2)�u�בփ��[�g�v�̌����ɔ����ΊO�����Y�����ɂ�鎑�Y����
�ΊO�����Y���������u�בփ��[�g�v�́A���������בփ��[�g�ł͂Ȃ��A�u�ʉݕʂ̑ΊO�����Y���l�ŏd�ݕt����ꂽ�בփ��[�g�v�ł��낤�B���בփ��[�g�̃f�[�^�͎茳�ɖ������A�䂪���̏����Y�̉ߔ����h�����Y�ł��邱�Ƃ��l�����āA�~�h���E���[�g�̐��ڂ��݂�ƁA��������2002�N������1�h��130�~���鐅���܂ʼn~�����i�s����B�R���A���̌�͉~�������ɔ��]���A2003�N���ɂ�1�h��110�~�����荞�ސ����܂ʼn~���ɐU�ꂽ��A2005�N�����T��1�h��110�~��̂��~���̐����Ő��ڂ��Ă���B���������~�h���E���[�g�̐��ڂ��琄�����āA�u�ʉݕʂ̑ΊO�����Y���l�ŏd�ݕt����ꂽ�בփ��[�g�v�̌����ɔ����ΊO�����Y�����ɂ�鎑�Y���ʂ́A�u����ꂽ�\�N�v����E�p��������Ƃ݂邱�Ƃ͂ł�����̂́A�����i�C�g��̈���ł͂Ȃ��Ɣ��f�����B
��(3)���Ԋ�Ƃ̌o�c�w�͂ɂ����v��Ղ̋���
��ʂɁA���Ԋ�Ƃ̌o�c�w�͂ɂ����v��Ղ̋����́A�s���������p�̈�ł���A���ꂪ�����̗͋����i�C�g��������Ƃ́A�ǂ��w�E����Ă���B���ʂ̌i�C���ɂ��A���Ԋ�Ƃ��o�u�����ɕ����Ă������A�ݔ��A�ٗp�̎O�̉ߏ肪��������Ă��邱�Ƃ���A�o�c�w�͂ɂ����v��Ղ̋������ׂ���Ă��邱�Ƃ����ĂɉM����B���Ԋ�Ƃ̌o�c�w�͂ɂ����v��Ղ̋����́A�u����ꂽ�\�N�v����E�p�������i�C�g��������v���ł���ƍl������B
���́A�����������Ԋ�Ƃ̌o�c�w�͂�����Ȃ���A���{�o�ς�������Ɋׂ��Ă��������ł���B����́A�����������Ԋ�Ƃ̌o�c�w�̗͂����ŁA������̌o�c�j�]��Ԃɂ���Ȃ����s�̒ǂ��݂����Ă������Ԋ�Ƃ�g���I��������̉��b�ɗa�����Ă��������x�o�֘A�̖��Ԋ�Ƃ��i�C�̑������������Ă�������ł͂Ȃ��̂��B���ǁA�O�҂̊�Ƃɑ��Ắu���Z�Đ��v���O�����v���A��҂̊�Ƃɑ��Ă͌����x�o�팸����̒��Ƃ���\�����v�����ꂼ��s�ꂩ��̑ޏo�𔗂�A�Y�ƍ\�������𑣐i�������炱���A���{�o�ϑS�̂̊�Ǝ��v��Ղ̋������}��ꂽ�ƍl������B����́A�u����ꂽ�\�N�v�̗v�����s�Ǎ������̒x���ƎY�ƍ\�������̒x���ł��邱�Ƃ��������Ă���B
|
��2�D�����v��
��(1)�u���Z�Đ��v���O�����v�ɂ��s�Ǎ������̑��i
�u���Z�Đ��v���O�����v������A�s�Ǎ����������i���ꂽ���Ƃɂ��ẮA�O�͂Ő��������B�����A�s�Ǎ����̉����͌i�C��ł���A�������ߒ��ő݂��o�����ቺ���Ă��邱�Ƃ���A�s�Ǎ����̉����͒��ڂɌi�C�����������̂ł͂Ȃ��B�J��A�u����ꂽ�\�N�v�ɂ�������̌i�C�g�傪���Z�s���̍ĔR�ɂ��Z���Ԃō��܂ꂵ�Ă��邱�Ƃ��l������ƁA�s�Ǎ����̉����͌i�C�̒����g��ɍv�������Ƃ݂���B
�R��A�s�Ǎ����̉������i�C�̒����g��ɍv�������o�H�͔@���Ȃ���̂ł��낤���B���̋^��ɑ��錵���ȉ́A����̎��ؕ��͂̌��ʂ�҂��ďo�����K�v�����邪�A����܂ł̌������画�f���āA��s���s�Ǎ����������A���{�����@�\�������邱�Ƃɂ���āA�Z���悪�]����TFP �㏸���̒Ⴂ�悩��n�C���X�N�ł͂��邪����TFP �㏸���������܂��V��������Ɠ��ֈڍs���Y�ƍ\�������𑣐i�����A�Ɖ��߂�����B����́A��L1�D(3)�̌��_�Ɠ��l�ɁA�s�Ǎ������E�Y�ƍ\�������̒x�����u����ꂽ�\�N�v�̗v���ł��邱�Ƃ��������Ă���B
��(2)�ʓI�ɘa����
�ʓI�ɘa����ɂ��ẮA�O�͂Ő��������ʂ�A�u������s�̍w�����鎑�Y�\���̕ω��ɂ����ʁv�Ɓu�ʊg��̌��ʁv����}��������͗L���ł͂Ȃ��A�[�������p������邱�Ƃɂ���Ė��Ԃ̊��ҒZ��������ቺ�����A��Ⓑ�ڂ̋�����ቺ������u���Ԏ����ʁv����}��������݂̂��L���ł������ɉ߂����A�f�t����E�p�ł����̂��i�C��3�N�ȏ�o��2005�N11��(����ҕ����w���x�[�X)�ł������B���Ȃ킿�A���t���h��ꕔ�̃��t���\�����v�h���咣���Ă����悤�ȁA�u�f�t���E�p�������Či�C�����v�ł�������A�u�f�t���E�p�ɂ͗ʓI�ɘa���L���v�ł������������ƂɂȂ�B�]���āA�f�t���ƃf�t�����������ɓI�ȋ��Z����́u����ꂽ�\�N�v�̗v���Ƃ��ĕs�K�ł���ƍl������B
��(3)�\�����v
��A�̋K�����v(�N�Ƒ��i����}�����Œ᎑�{�����x�̓���[�u�̓����A�u�Γ��������i�v���O�����v�̍���A�l�ޔh���s��̋K���ɘa�A�����q��̋K���ɘa�A���������ϑ��萔���̎��R����)�͒Z���I�Ȏ��v���@��N�����A�Y�ƍ\�������𑣐i�����Ƃ݂���B�܂��A�Y�ƍ\�������𑣐i�����{�o�ς�TFP�㏸�������߂�A�Ƃ����������I�Ȍo�ϐ������ʂ��ǂ݂���s��̊��҂̏���C�����f�������Y���l�̏㏸�ɂ�鎑�Y���� 13) �ɂ��Ă��A����������̓��o���ϊ����̐��ځA���ɏ����u�X�����U�I���v�Ȍ�̓������̏㏸�ɕ\��Ă���B�\�����v���i�C�E�����g��̗v���ł��邱�Ƃ��M����B���̊ԁA�i�C���ɂ����Ă��A���̌�̌i�C�g����ɂ����Ă��A�������I���{�`���͎���GDP �������̊�^�x����т��ĕ��ł������B�ȏ�̋c�_���A���ɓI��������́u����ꂽ�\�N�v�̗v���Ƃ��ĕs�K�ł���A�Y�ƍ\�������̒x�������v���ł��������Ƃ������Ă���B
�ȏ�̌����Ɋ�Â��A�o�u�������̒�����̎���́A���Z�V�X�e���̎��{�����@�\���������s�Ǎ������̒x���Ɠ��{�o�ς̐��Y�����������Y�ƍ\�������̒x���ł���ƌ��_�t������B
|
��3�D��������X�N�ƍĔ��h�~��
��L�����ɂ����肳�ꂽ������̓�v���̂����A�s�Ǎ������̒x���ɂ��ẮA�u����ꂽ�\�N�v�̌o�����瑬�₩�ɓK�ȋ��Z�V�X�e�����艻�ł���邱�Ƃ����҂ł���B�܂��A��҂̎Y�ƍ\�������̒x���ɑ��Ă��A�s��o�ς̎����I�Ȕ��W�𑣂��悤�A���{���剻�������A�K�X�K�Ȏ��R���𐄐i����A�Y�ƍ\���������x���Ɋׂ郊�X�N�͏������ƍl������B
�R���c�O�Ȃ���A�����ɑ���Љ�̈�ʓI�ȔF���͖����ɒႢ�ق��ARajan and Zingales (2003) ���w�E����悤�ɁA���{��`�Љ�ł́A�u�Љ�I�����v��͂ݎ��Ȃ������l�X��i���I�m���l���s��̓�����v���������łȂ��A���Љ�Łu�Љ�I�����v�����߂��͂��̌o�c�҂�����Ȃ̕ېg���@����Q����Ǔ��̋K��������v������X��������B���������s��o�ϓ����̐����I���͂��P��I�ɓ����Ă���ȏ�A��������X�N��������Ƃ݂���Y�ƍ\�������x�����X�N�́u�������X�N�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̂悤�Ȏs��o�ϓ����̍P��I�������͂ɑR���A�u�������X�N�v���y�����邽�߂ɂ��A�{�e�ł͏\���ȉ𖾂ɂ܂ł͎����Ă��Ȃ��Y�ƍ\�������̒x���ƒ�����̈��ʊW���𖾂��邱�Ƃ�����̉ۑ�ł���B |
����
1)�@�u���Z�@�\���艻�@�v�ł́A13���s��ꂸ�A�܂��ABIS ��Œ��j�I���{�Ƃ݂͂Ȃ���Ȃ����E��ネ�[���𒆐S�Ƃ�����I���������ł������ق��A�ߏ����{�Ɋׂ��Ă����s�����Ȃ̉ߏ����{�̏��I�悷�邱�Ƃ���ĉߏ��\�����s�������߁A2�̎��Ȏ��{�̏[���ɂ��q����Ȃ������B1999�N�́u�������S���@�v�u���Z�Đ��@�v���ł́A�]�����t���D�抔���𒆐S�Ƃ�����I���������ɕύX���邱�Ƃɂ���āA�u���Z�@�\���艻�@�v�̏�L����ɑΏ�����ƂƂ��ɁA���I����������̃K�o�i���X�Ƃ��āA�o�c���S���v��̗��s�̕����A�D�抔���̕��ʊ����ւ̓]�����s�g�ɂ��c�����l���̂ق��A���I���������s�ɂ����āu�v��(���v�ڕW)�Ǝ��тƂ̑������x�̘����v�����ꍇ�A�Ɩ����P���߂̔������܂߂��ē�̑[�u�̔��������������A�Ƃ����ʏ́A�u�O�����[���v���ł��o���ꂽ���A1�̎��Y����͊�{�I�ɋ�s�̎��ȍ���ɂ����̂ł������ق��A�u�O�����[���v�́A�s�Ǎ�������D�悵�������Z���̎v�f���猵�i�ɂ͓K�p����Ȃ������B2001�N�ɁA������s���s�Ǎ��ɂ͕��ނ��Ă��Ȃ����������X�[�p�[�̃}�C�J�����o�c�j�����ق��A�ؑ������ɂ���v�s�̑���Z����ɑ�������Ă̊Â����u���O�\�Ж��v�Ƃ��Ďw�E����A��s�̎��ȍ���̊Â��ƈ����ĕs���ɂ�鎩�Ȏ��{�s�������O����邱�ƂɂȂ����B
2)�@���Y�������ɂ����ẮA�Ώێ��Y�������E����������،����̎�@�Ɠ��s��̐������v�����邱�Ƃ����҂ł���B
3)�@��ʂ̗ʓI�ɘa����œ����ʂ���������Ƃ��ẮA�]���ɔ�ב��ΓI�ɐM�p�x�̒Ⴂ��`�̔����I�y����������B���I�y�ɂ��A���ΓI�Ƀ��X�N�̍������Y�̐M�p�X�v���b�h���k����������ʂ�����A���Z�V�X�e���̈��萫�ێ��ɂ͍v�������Ƃ���Ă��邪�A�f�t�����ɘa��������A���v�����N�����肷����ʂ͖��������悤�ł���B
4)�@�ʊg��̌��ʂƂ́A�}�l�^���[�E�x�[�X�̊g�傪�ݕ������ʂ������A�i�C�g��E�����㏸�����A�Ƃ����}�l�^���X�g�I�Ȍo�H��ʂ������ʂł���B�R�����A��ʂ̗ʓI�ɘa����ł́A�����������ʂ͊ώ@����Ȃ������B
5)�@����(2008)��388�Ő}19�\4�\1���Q�Ƃ���B
6)�@�|�X�A������A��c���炪�u���t���h�v�ɕ��ނ����Ǝv����B
7)�@�r���A��{�A����I�I�Y�A�{��炪�u�\�����v�h�v�ɕ��ނ����Ǝv����B
8)�@�ɓ����q�A�ɓ����d�A��c�A�N��A�|���A�сA���c�A�[���A���炪�u���t���\�����v�h�v�ɕ��ނ���悤���A��c�A���c�A�[���A���̓��t���h�ɋ߂�����ł���A�ɓ����q�A�ɓ����d�A�N��A�|���A�т͍\�����v�h�ɋ߂�����ł���悤�Ɏv����B
9)�@���c�E�쑺(1997)����E�����E���c(2003)�̎��ؕ��͂Ŋm�F����Ă���B
10)�@Hayashi and Prescott(2002)�ł́AHansen(1985)�̘J���̕����s�\����D�荞��ʋύt���w���f����p�������ؕ��͂ɂ��1990�N��̓��{�o�ς�TFP �㏸�����ቺ�������Ƃ�������Ă���B
11)�@�Ⴆ�A�������̍\�����v�Ŏ��{���ꂽ�A�N�Ƒ��i����}�����Œ᎑�{�����x�̓���[�u�̓����A�u�Γ��������i�v���O�����v�̍���A�l�ޔh���s��̋K���ɘa�A�����q��̋K���ɘa�A���������ϑ��萔���̎��R��������������B
12)�@������́A�u�\�����v�h�ɋ߂����t���\�����v�h�v�̎咣���F�Z�����f���Ă��邱�Ƃ��M����B
13)�@�����ł̑����v�g��o�H�̘_���W�J�́A �����Ɍ����A ���̂悤�Ɉׂ����ׂ��ł���B���Ȃ킿�A�����I�Ȍo�ϐ������ʂ��ǂ݂���s��Q���҂́A���҂�����C������ق��A����܂ŕ����Ă��������̕s�m�����ɑ���x���x��ቺ������B�O�҂͎��Y���l�̏㏸�ɂ�鎑�Y���ʂƃ��X�N���e�x�̏㏸��ʂ���ԐړI�Ȍo�H�ŁA��҂͒��ړI�Ȍo�H�ő������E����傳����A�Ƃ����Z���I�Ȍi�C�g����ʂ����҂�����B�����O�̌o�H�̂����A�悭�w�E�����͖̂{���ŋ��������Y���ʂ݂̂ł���B�R���A�c��̃��X�N���e�x�̏㏸��ʂ���ԐړI�Ȍo�H���A�s�m�����̌����ɔ����s�m�����x���x�̒ቺ���A�ߔN�̕s�m�������̌��p���_�̔��W�܂���ƁA���R�̌o�H�ł���A�������������x�̌��ʂ�����Ƃ݂���B�@
�@ |
 �@ �@
���w���{�_�x�ƃ}���N�X�o�ϊw |
   �@
�@
|
|
���͂�����
|
���{��`�Љ�̌o�ϓI�^���@�����𖾂��A�Љ��`�ւ̈ڍs�̕����I�K�R���𖾂炩�ɂ����w���{�_�x��1�����ł���������Ă���A100�N���̔N�������ꂽ�B���̊ԁA���E�͑傫���ω������B ����ł͎��{��`�͂��̍ō��ɂ��čŏI�i�K���Ȃ��鍑��`�i�K�ɓ˓����A�����ł̓}���N�X�����U���̎����̂��߂ɏ�M�������ނ����Љ��`�������̂��̂ƂȂ�A�S�n���̎O���̈���������Ɏ������B�����̐A���n���͊o�����A��������Ɨ��^���́A�鍑��`�����������ǂ��߂Ă���B ���{��`�����ɊK���Η����݂��A���̊K���Η��̍��ۓI�W�J���Љ��`���Ύ��{��`���̑Η��ł���A�鍑��`���ΐA���n���̑Η��ł���B ���E�j�̂��̂悤�ȕω��́A�w���{�_�x�ʂ��ɂ͂Ƃ��Ă������ł����A�w���{�_�x�͌Â��Ȃ����ǂ��납�A�����������Ɩ��ł��Ă���ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B
�l�ԉ���̏��A���{��`�Љ�̍����̏��A�v���̏��w���{�_�x�̔���100�N���L�O���āA���E�e���ŋL�O�s��������Ђ낰��ꂽ(1)�B�w���{�_�x�����̐���Ȃ킪���ł�����ꂪ�m�邩����A���̂悤�ȎG�����w���{�_�x100�N���W�A�������݁A�w���{�_�x�ɊW���鑽���̗͍���f�ڂ��āA�}���N�X�̈̋Ƃ���������(2)�B
�k1�l�u�B���j�ρv1967�N4�����A��4��
�k2�l�u�v�z�v1967�N5�����A��515��
�k3�l�u�o�ρvl967�N6�����A��37��
�k4�l�u�O�c�w��G���v1967�N9�����A��60����9��
�k5�l�u�����ٌo�ϊw�v1967�N10�����A��16����:3�E4��
�k6�l�u�o�ϊw�_�W�v(����)1967�N10�����A��33����3��
�k7�l�u�o�ϕ]�_�v1967�N11�A�����A��16����12��
�k8�l�u�o�Ϙ_�W�v(����w)1967�N12�����A��17����5��
�k9�l�u�o�ϊw�G���v(���s��)1968�N5�����A��58����5��
�k10�l�u�o�Ϙ_�p�v(����)1968�N11�B �����A��102����5��
�k11�l�o�ϊw�j�w��w�u���{�_�v�̐����x1967�N11��(��g���X)
(�������k11�l�͏����ł���A�k9�l�Ɓk10�l�̓}���N�X���a150�N�L�O���ł���B �܂��k2�l�́u�w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�v�Ƒ肳��Ă���B)
�ȏ�̓��W���Ɍf�ڂ���Ă��鏔�_���́A���e��A��{�I�ɂ͎��̌܂̃O���[�v�ɕ��ނ�����ł��낤�B 1�B�w���{�_�x�̊��(�v�z�j�I�E�N�w�I�w�i�A�����}���N�X�A�w���{�_�x�����ߒ�)�Ɋւ�����́AII�B�w���{�_�x�̕��@�E���e�Ɋւ�����́AIII�B �鍑��`�A���㎑�{��`�Ɋւ�����́Arv�B ���{���{��`�_�AV�B ���̑�(�Љ��`�_�A���z�A�N�\�A���k��A�}���ژ^�Ȃ�)�B �}���N�X�o�ϊw�͂��̎g�����炵�ē��R�A�Љ�ϊv�̕����I���������邢�͎Љ�ϊv�̂��߂̋q�ϓI���@������T������Ȋw�łȂ���Ȃ炸�A���̂悤�Ȋϓ_���炵�āA�����́w���{�_�x100�N���}���Ă킪���̃}���N�X�o�ϊw�E�ł͂ǂ̂悤�Ȗ�肪�_�����A�������炩�ɂȂ�A��������̉ہA��Ƃ��Ďc����Ă��邩�A�킪���̃}���N�X�o�ϊw��̌���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�𖾂炩�ɂ������Ǝv���B ���ꂪ�{���_�̖ړI�ł���B �{���_�́A�w���{�_�x100�N�A�}���N�X���a150�N�L�O���W����̏��_���������ɂ����Ȃ����A���_���͓����ɓ��{�̃}���N�X�o�ϊw�̌��������\���Ă���ƍl�����邩��A�����Ŗ��炩�ɂ������Ƃ͓����Ƀ}���N�X�o�ϊw�̌���ɂ����Ă͂܂�ƍl���Ă����ł��낤�B
(1)�@�퐣�A���{��`���A�{�{�`�j�u�w���{�_�x��1�����s100�N�ɂ������Ă̕]����h�C�c�A�\���F�g�A�p��-�v�w�o�ό����x1968�N10����; ���i����u�w���{�_�x100�N�ՂƃA�����J�o�ϊw���Љ�Ƙ_�]��v�w�o�ϊw�G���x1968�N5�����A��58����5���A�Q�ƁB
(2)�@�w���{�_�x100�N�Ɋւ�����O�̒����A�_���ɂ��Ă̂܂Ƃ܂��������ژ^�ɂ��Ắw�o�Ϙ_�p�x�k10�l�̊������Q�Ƃ��ꂽ���B�@ |
| ��1 �w���{�_�x�̊�� |
   �@
�@
|
�}���N�X�̓��]�������ɑn���I�ł���A�w���{�_�x�������ɓƑn�I�ȏ����ł������Ƃ��Ă��A�����̌o�ϊw�A�v�z�A�N�w�ȂǂƂ������Ȃ��ɁA���R�ƓV����~���Ă����悤�ɐ��܂ꂽ�킯�ł͂Ȃ������B ���̂��Ƃ́w���{�_�x�̕���u�o�ϊw�ᔻ�v�ɔ@���Ɏ�����Ă���B ���������āA�w���{�_�x���a�ɒ��ځA�ԐڂɊ�^���������̌o�ϊw�ҁA�v�z�ƁA�v���ƂȂǂƁw���{�_�x�Ƃ̂�������T�����邱�Ƃ��A���ɏd�v�Ȏd���ƂȂ��Ă���B ���̉ߒ��𐋍s���悤�Ƃ����̂��w�u���{�_�v�̐����x�ł������B ���̑�1���ł̓��J�[�h�h�Љ��`�ҁAJ�B S�B �~���A�V�X�����f�B�A�v���[�h���A�ֈ�Q���A�w�X�Ƃ̊֘A�Łw���{�_�x�����̎v�z�j�I�w�i���������Ă���B �V���_���͂Ƃ���John Francis Bray�𒆐S�Ƀ��J�[�h�h�Љ��`�҂̎��I���L�A�J���a�O�A��]���l�A���_���A���{��`�ŗL�̖�����^���ɑ���l�������l�@�������̂ł���B �����_���͓����C�M���X�̐A���n�ł������A�C�������h���ɑ��ĂƂ���J�B S�B �~���̑ԓx�ƃ}���N�X�̑ԓx�Ƃ��r�������A���̈ٓ��𖾂炩�ɂ��Ă���B �����̊S���Ƃ��ɂЂ��̂́A���ΓI�ߏ�l���̈��Ƃ��Ắw���{�_�x��1����7�ё�23�͑�5�߁u�A�C�������h�v���u���{�����Y�l���̖v���̕K�R����_������24�͑�7�߂ɘA���v(p�B 58)�����ė�������Ƃ����w�E�ł���B �g���_���́A����܂ł́u�����j��̋v���Ȃ��Ă���V�X�����f�B���}���N�X�̌o�ϊw�̌n�`���Ƃ̂������ōl�@�������̂ł���B �}���N�X��40�N��ł́A�V�X�����f�B�ɏ��u���W���@�Љ��`�҂��݁A50�N��ɂ͎��{�́u�l�K�e�B�u�Ȉ�ʐ��v���w�E���ČÓT�h��ᔻ�����ÓT�h�́u�I���̕⊮�ҁv���݁A60�N�ȍ~�́u���{�̌����̉^��(�����ƐM�p)�v�ɂ����閵���̓E�o�҂��݂��Ƃ����̂ł��邪�A�Ō�̓_�͓��ɂ����̋������Ђ��B ���ڍׂȑS�ʓI�ȉ𖾂��܂����B �X��_���͂܂��v���[�h���́w���L�Ƃ͉����x�A�w�n���̓N�w�x�̓��e�𖾂炩�ɂ��A���Ń}���N�X�̃v���[�h���ᔻ�̂������̓_��:�𖾂������̂ł���B
���_���́A�}���N�X�Ƃֈ�Q���Ƃ̘A�������A�u�t�]�v��ʂ��Ă̌p����~�g�Ƃ��Ă��ޗ��ꂩ��A�܂��}���N�X�ɂ��w�[�Q���~�g�̉ߒ��̊T�ς�ʂ��ė��҂̑Η����m�ɂ��A���ŘA�����A���ʐ��𖾂炩�ɂ��A�����āu�}���N�X��`����їB���ُؖ@�Ƃ͂Ȃɂ��v���𖾂��悤�Ƃ������݂ł���B �����w���{�_�x�S3���́w�_���\���x���𖾂����ӏ��ɂ͎�m�ł��Ȃ���A�O�̓_������B ���Ƃ��Ύ��͑�1�͑�1�A2�߂ł̌������l�� ���l�� �J���� �J���̓�d���ւ̉����ɂ����Ă̓u���W���A�Љ��=�u�����I�����ߒ��̑S�̂����k����Ă���v(p�B 138)�Ɨ�������Ă��邪�A����͖����ł���B�w���{�_�x�ɂ��������I�W�J�́A����ɐ旧���čs�Ȃ�ꂽ�����I���͂����q�ɂ������ċt�s�������̂ɂق��Ȃ�Ȃ�����A�w�����I�����ߒ��̑S�́v�Ƃ͋t�\������w���{�_�x�̏���ߒ��S�́A���Ȃ킿�w���{�_�x�̌n���̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B ���������āA�w�����I�����ߒ��̑S�́v����1�͑�1�A2�߂Ɂw���k����Ă���v�Ƃ͂Ƃ��Ă��������Ȃ��ł��낤�B��1�͑�1�A2�߂ł͂������ɕ��͓I�����@���Ƃ��Ă��邪�A���͂͏��i�̕��͂ɂ��Ă��Ă���̂�����A����͂Ȃ��s�v�c�ł͂Ȃ��B����Ƃ����ǂ��e�͂ɂ����镪�͂������͓̂��R�̂��Ƃł���B��2�ɁA�w��1����1�A2�т́A���̂����ɒ��ۂ����̂ւ̉�㈓I�W�J(��1�͑�3�߈��4��)���܂݂Ȃ�����A�w���{�_�x�̌n�̑S�̓I�֘A�̒��Ő�߂�n�ʂ́A���ʂ��璼�ړI���Y�ߒ��ցA���ۂ���{���ւ́A�_���I�����̉ߒ��ł���v(p�B138�B�T�_��M��)�ƌ����Ă���̂́A�čl�̗]�n�����낤�B�������ɁA���i�A�ݕ����玑�{�̐��Y�ߒ��ւ̐i�s�́A�w���ۂ���{���ցv�ւ́w�_���I�����̉ߒ��v�Ƃ��l�����悤�B�����������A���{�̐��Y�ߒ��̖{���͏�]���l�̐��Y�ɂ���A���̏�]���l�͘J���͂Ɖݕ��Ƃ̌�����O������ɂ��A���̉ݕ��͏��i��O��ɂ��Ȃ���Ƃ��Ȃ��̂ł��邩��A���i��ݕ��ꎑ�{�̐��Y�ߒ��Ƃ����_���̕��݂́A���P���Ȃ��̂����蕡�G�Ȃ��̂ւƐi�ޘ_���I����̉ߒ��Ƃ��l�����邩��ł���B�܂��ẮA��4�}(P�B 138)�̂悤�ɁA��1�A2�т��E������꒼���̉����ߒ����Ƃ͒P���ɍl�����Ȃ��B���i�ɔ䂵�ĉݕ��͖��炩�ɂ���̓I�ȍ����̔��e�ł��邵�A��2�т̏I�́w�ݕ��̎��{�ւ̓]���v�͂���̓I���G�ȁA�����̓��e�������́B�ł���B ��3�ɁA�w���{�_�x1���A�U���AIII���̘_���\�����A1��=�w�w�V�Љ�̌`���I���v�f�Ƌ��Љ�̕ϊv�I���_�@�x�̒ǐՋ����v�A���_�͑�24�͑�7�߁w���{��`�I�~�ς̗��j�I�X���v�AIII��=�w���Y�ߒ��Ɨ��ʉߒ��Ƃ̓���ɂ����đS�̂Ƃ��Ă̎��{�̉^���ߒ����l�@�v�AIII��=�w�S�̂Ƃ��čl�@���ꂽ���{�̉^���ߒ����琶�����̓I���`�Ԃ̔����A���q�v�Ɨ��������̂��s���m�ł��낤�B ����ł�1���������ϊv�̗��_��ŏo���A�U���AIII ���͕��^�ɂȂ邩��ł���B�w���{�_�x�S�����w�V�Љ�̌`���I���v�f�ƕϊv�I���_�Ђ𖾂炩�ɂ������̂ƍl����ׂ��ł���B ���Ƃ��A��III���̗������ቺ�@���́w���{��`�I�~�ς̗��j�I�X���v�̓��e������̓I�ɋK�肵�����̂ƕ]�����ׂ��ł���B �܂��AII����III���̓��e��v����̕��͂��A���҂�
���ɓ����ɂ݂��s���m�Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�R���_���́A�܂��w�X�̎v�z���l�Ԏ�̐��̉Ƃ��̑S�ʓI�J�Ԃɂ��邱�Ƃ��݁A���Ńw�X�̎Љ��`�v�z�̐ϋɓI���e���}���N�X�́w�o�N��e�v�w�ֈ�Q���@�N�w�ᔻ�����v�ɐێ悳��Ă���Ƙ_����B
�w�u���{�_�v�̐����x�͂����ő�2���Łw���{�_�x�������Ȃ�ߒ����o�Č`�����ꂽ����1840�N��A1850�N��A1860�N��ɂ��Ė��炩�ɂ��邪�A�����̓s���ŏȗ����A�����P�Ǝ��̏��](�w�o�ό����x1969�N4����)�ɂ䂸�肽���B
�ђ����w�����}���N�X�ɂ�����w���{�_�x�̐����v(�w�o�ρx)�́A1840�N��̃}���N�X�o�ϊw���̔��W�ߒ������������ƕ`�ʂ��A�w�w���{�_�x�ւ̐��n�̊�{����W�]�v�����D�_���ł���B�a�O�_���d�����邠�܂�A�����}���N�X���w���{�_�x�Ɛ�͂Ȃ��A�O�҂𐳂����Ƃ��A��҂��ނ��둭���Ƃ݂�l�����ꕔ�ɂ���A�܂��A���̂悤�ȍl���Ɍĉ����āA���{��`�Љ�̐^�̉Ȋw�I���͂�q�ϓI�ȍ��@�����A�v����̔F���ʂ��ɁA����ɑa�O�_�����ŎЉ�ϊv�����ԏ��s���I�}�i��`���ꕔ�ɂ݂��錻�݁A�{�_���̂悤�ȁw���{�_�x�֎��q���Ă����ߒ��Ƃ��Ă̏����}���N�X�̕]���͉��߂ĉ��l�����ł��낤�B
�����F�A�r��Ձu�}���N�X�ɂ�����w���Ƃƌo�ρx�v(�w�o�Ϙ_�p�x)�́A���C���V������w�O�����h���b�Z�x�Ɏ���܂ł̎j�I�B���_�̊m���ߒ��ɏœ_�����킹�āA���Ƃƌo�ς̊W�Ɋւ���}���N�X�̍l�������_�C�i�~�b�N�ɒT�����d���Ș_���ł���B �哇���u�w���{�_�x�ւ̓��v(�w�B���j�ρx)�́A�w���J���Ǝ��{�v�ł́w��]���l�A�����A���{�̗L�@�I�\�����ɂ����Ċ�{�I�Ȕc�����݂��A����ɂ���Ď��{�̐��Y�ߒ��ɂ��Ă̕��͂����Ȃ�[�߂���ɂ������Ă���v(p�B39)���Ƃ�_���A�w�O�����h���b�Z�x�ł́A�w���l�`�Ԕc���Ɗ֘A���Čo�ϊw�ᔻ�̌n�̊�Ƃ��Ă̘J���͂̏��i���ɂ����āv(p�B 29)�l�@�����J��ł���B ���ɏ����}���N�X�������������̂ɉ���h���u�����}���N�X�̌o�ϗ��_�ɂ��Ĉ�w�o�ϊw=�N�w��e�x�𒆐S�Ƃ��āv(�w�����ٌo�ϊw�x)������B�o���E���u���Y�͂Ɛ��Y�W�Ƃ̘_���I�ȊW�v(�w�o�Ϙ_�p�x)�́A���҂̊W���ُؖ@�ł����u�ُؖ@�I�Η��v�̊W�ɂ��邱�Ƃ�_�������̂ł���B�@ |
| ��2 �w���{�_�x�̕��@�Ɠ��e |
   �@
�@
|
�w���{�_�x�̕��@����e��1���I�����������ڂł������\���ɂ���߂��Ă��Ȃ��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���̉𖾂͓Ɛ艿�i�A�Ɛ藘�����ǂ��Ƃ����A�Ɛ莑�{��`�̖����͉����Ȃǂ��Ƃ������̗L�͂ȕ�������B
���c�Ή�w�w���{�_�x�̗���ƕ��@�v(�w�o�ρx)�́A�܂��w���{�_�x�̗���ƕ��@�Ƃ��ُؖ@�I�B���_�Ǝj�I�B���_�ł��邱�Ƃ��m�F���A����ɂ̓J�e�S���[�́u�ǂ��܂ł������̖͎ʁv�ł���Ƃ������ƂƂ��̃J�e�S���[�̏��q�A�����́u���ׂĂ��^���̗���ɂ����āA���W�ɂ����Ă݂�v���g���璊�ۂ����̂ւ́u�^���̉ߒ��ɂ����āA�܂������̃J�e�S���[�̑��v�ɂ����Ă���������v(p�B 253)���Ƃɏ�̕��@�̓��F�����邱�Ƃ��݂āA��ˋv�Y�w�Љ�Ȋw�̕��@�x(��g�V��)��ᔻ����B ��ˎ��̌����́A�l�Ԃ͎��R�Ȉӎu�������A���I�A�\���s�\�ȍs�ׂ��s�Ȃ�����A�Љ�̗��j���܂����R�A���R�I�A���I�ł����āA���R�ߒ��̂悤�ɋq�ϓI�ȍ����I�ߒ��Ƃ݂邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�����ŏ�̎��R�ӎu�œ����l�Ԃ̓��@��Ǒ̌����A���j�𗝉����ׂ��ł���A���ꂱ���Љ�Ȋw�̕��@�ł���Ƃ����̂ł���B ���c���͑�ˎ��̌��������悻�ȏ�̂��Ƃ��v�A�����Ď��̂��Ƃ��ᔻ����������B ���̗��j�ς́A(1)�����u�����̈ӎ��ƈӎu����Ɨ������q�ϓI�ȍ��@���I�ȉߒ��v�ƍl�����A�u���̍��@������ُؖ@�I�Ȏ��ȉ^���v�Ƃ݂��A�u�B���_�I����ѕُؖ@�I�ȓ�̊�{�I�ȓ��F�����{����ے肷�錩���ł���v(p�B254)�B �܂��}���N�X�ȑO�̗B���_���j�w�̐����Ɠ����ł���B (2)�u�l�Ԃ����j���`�����邽�߂̒n�ՂƑO��v�����A�l�Ԃ��̂��̂��A�Љ����j��K���̊O�łƂ炦�A�u�܂������ϔO�I�A���ۓI�v(P�B 258)�����ł���B (3)�u���R�j�I�ߒ��v�����i���Y���L�̂�����J���̎��ȑa�O�̈ꌻ�ۂƂ��Ă���܂��ĂƂ炦�Ă���B(1) �����́A���c���̂��̑�˔ᔻ�ɑS�ʓI�Ɏ^���ł���B �E�F�[�o�[�����ՂɃ}���N�X�Ƃ��Ȃ����@�́A���ǃ}���N�X���E�����ƂɂȂ邨���ꂪ���邱�Ƃ̋��P�������ɂ݂邱�Ƃ��ł���B ��ˎ��قǂ̗��j�w�҂ɂ��Ă����ł��邩��A�}���N�X�̕��@�̐��m�ȗ������w�E�������Ċm�肷�ׂ��ł��낤�B �Ȃ��A�w�o�ρx�Ɂw���{�_�x��1���u��2�ł̌㏑���v�ɂ����ă}���N�X�������]�����A�����̈��p���Ȃ��Ă���C�E�C�E�J�E�t�}���u�J�[���E�}���N�X�̌o�ϊw�ᔻ�̌��n�v�̖{�M���̂��Ă��邪�A���ɋM�d�ł���B �J�E�t�}���̃}���N�X�̕��@�̐[�З����ɂ��ǂ납��������Ȃ��B
���䐴�u�o�ϊw�ᔻ�̌n�Ɛ��E�s�ꋰ�Q�v(�w�o�Ϙ_�p�x)�́A���̂���܂ł̃v�������ɂ��Ă̍l���������A�㔼�̎O���ڂ̗��_����ʂ��Đ��E�s�ꋰ�Q�ւ̓W�]���݂����̂ł���B �����A�\��ɂ�������炸�A���E�s�ꋰ�Q���G���X�i�[�̏Љ�ł��܂���Ă���͎̂c�O�ł���B ����͂ނ�������̉ۑ�ł͂��邪�B
��؍���Y�u�B���j�ςƌo�ϊw�v(�w�o�ϊw�_�W�x)�́A�B���j�ςł������Y�͂Ɛ��Y�W�̖������Ȃ킿���{��`�̗��j�I���E�̘_���F��h�o�ϊw�̌n�̍ŏI�����Ȃ��u������ЂƂ��Ă̎��{�̏��i���v�ɋ��߂����j�[�N�Ș_���ł���B ���Ȃ킿�A���Y�͐����̏㏸�ƂƂ��ɌŒ莑�{�́u���剻�v���A���Q�ɂ���Ĕj��Ȃ��u�ߏ莑�{�v�Ɖ����B ���̂悤�Ȗ����s���̂��Ƃł͗������̋ϓ����́u�������{�Ƃ��Ă̎��{�̏��i���v�ɂ�銔�������̋ϓ����ɂ���ĒB�������ɂ������A���́u���{�̏��i���v�́u���{�݂����炻�̐��Y�͂Ɛ��Y�W�̑Η��������������Ă������Ƃ�����ɂȂ������Ƃ̎��ȍ����ɂق��Ȃ�v(P�B 9)���A�����Ɏ��{�����i�ɖ߂�Ƃ������݂Łu���{�̍Ō�̋��ɂ̌`�ԁv(P�B 9)���Ȃ��̂ł����āA�����Ɂu���i�ɂ͂��܂鎑�{��`�I�o�ωߒ��̐����̘_���͑̌n�I�ɏI��邱�ƂɂȂ�v(p�B 9)�A�u���{��`�̗��j���v�́u�����I�ɐ��v����邱�ƂɂȂ�Ƃ����̂ł���B ��؎��͌����u���̂Ȃ�A����Ɏ��{��`���i�v�ɂ������̂Ȃ�A���{��`��ΏۂƂ���o�ϊw�́A�Ώۂ̉i�v���ƂƂ��ɖ����ɂ��̌����I�W�J��]�V�Ȃ������A�o���_���Ȃ����i�ɍĂыA���Ă���Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��c�c�B ���̈Ӗ��ŁA���i�ɂ͂��܂��čĂя��i�ɂ��ǂ�Ƃ����o�ϊw�̑̌n�\���́A���ꎩ�̎��{��`�̗��j���������I�ɐ������̂ɂȂ��Ă���v(P�B 9)�B �����āA���͂��̂悤�Ȏj�I�B���_�Ō������{�����Y�W�����̒i�K�ł͐��Y�͂̔��W�ɂƂ��ė��_�ɂȂ�Ƃ������{��`�̗��j���́A���s�́w���{�_�x�̌n�ł͘_���ꂦ���A������u�����v(p�B 10)�����F����،o�ϊw�ɂ���Ă͂��߂Ę_�����Ǝ��掩�]���āA����ɂ��Ă�����B�����_�̌n�́u�������{�Ƃ��Ă̎��{�̏��i���v�ɏI����A���i�ɂ͂��܂��ď��i�ɏI���Ƃ����咣���̂͂��˂��ˎ��ׂ̂̂��Ă����Ƃ���ł���A�����ڂ����炵�����ƂłȂ����A���x�͂��̂��Ƃ������ɗB���j�ςł����u���{��`�̗��j���v�̘_�ɂȂ�Ƃ����_�Ŗڂ����炵���B
�����͂��̂悤�Ȏ咣�ɑ��đ����̋^����ւ����Ȃ��B ��1�̋^��͌����_�̌n�̂�����ɂ��Ăł���B �����_�̌n�͂Ȃ����i�Ɏn�܂菤�i�ɏI���Ȃ�������Ȃ��̂��A���i�Ɏn�܂菤�i�ŏI��邱�Ƃ��ǂ����Č����_�̊��������Ӗ����邱�ƂɂȂ�̂��A������~�@�����o���Ă������_���Ȃ��~�@���Ƃ�˂Ȃ�Ȃ��̂��s���ł���B �Ƃ��ɉF�쎁�Ƃ������Ď��̂悤�ɁA�����_�Ƃ́u���{��`���Y�l���̐����A�����A���n�����̓������猴���I�ɖ͎ʂ����q�������̂ł���v����؍���Y�ҁw�o�ϊw�����_�x��Ap�B 17)�Ƃ���Ȃ�A�����_�����i�Ɏn�܂菤�i�ɏI���Ȃ���Ȃ�Ȃ��_���I�K�R���͖ѓ��Ȃ��ł��낤�B ���Ƃ��Ǝ��́w�o�ϊw�����_�x�ɂ������2�сu���{��`�I���Y�v�����3�сu���ߒ��v�ւ̏�����邢�͊e�ѓ����͍̏\���͐��E���{��`�́u�����A�����A���n�v�́u�͎ʁv�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B ��2�̋^��́u���{�̏��i���v�̘_���ɂ����Ăł���B ���͐�ɂ́u���{�\���̍��x�����Ƃ��Ȃ�Ȃ��~�ς̕����p���Ē~�ς́w��ʓI�@���x���Ȃ��v(p�B 7)�ƍl���A�w���{�_�x��1����23�͂̑��ΓI�ߏ�l���� �J���҂̋��R�������R�Ƃ����_����ے肳�ꂽ�̂ɁA�����ł͈���I�Ɂu���Y�͐����̍��x���v(P�B 9)��Œ莑�{�́u���剻�v�������o���A��������u���{�̏��i���v���̂͘_�������ł͂Ȃ��낤���B�u���Y�͐����̍��x���v��Œ莑�{�́u���剻�v�͎��{�\���̍��x�����Ƃ��Ȃ��̂��Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��B ����ɂ͌Œ莑�{�����剻�����Q�ɂ���Ĕj��Ȃ��ߏ莑�{�ƂȂ�A�����s�����o������Ƃ����_���_�ʂ��ŕs���ł���B �܂������s���̂��Ƃł͌Œ莑�{�̐���ɂ��A�������̋ϓ�������������Ȃ��Ƃ����̂��������������B �����������{�ړ��Ƃ͊����Œ莑�{�����Ĉړ�����Ƃ������́A�������p����A��]���l�����ړ�����Ƃ������Ƃł���B ��������Ίg��Đ��Y�ߒ��ɂ����Ă͌������p�������̍ē������]���l����̐V�����̊e���Y����ɑ���z���䗦���ω�����Ƃ������Ƃł���B �Ō�ɗ������̋ϓ������u�������{�Ƃ��Ă̎��{�̏��i���v���Ƃ����Ă̊��������̋ϓ����ɂ��B�������Ƃ����̂����ł��낤�B �������Ɨ����͂����܂ŕʂ̔��e�ł��邵�A�������������{�I�ɂ͊�Ƃ̂����鑍�������Ɉˑ����Ă���ȏ�A���̋ϓ����͎��{�ړ���ʂ��Ă̑��������̋ϓ����Ɉˑ�����������Ȃ��ł��낤�B ��3�̋^��́A�����_�����i�Ŏn�܂菤�i�Ŋ�������Ƃ��Ă����ꂪ�Ȃ����{��`�̗��j�����ؖ����邱�ƂɂȂ�̂��Ƃ������{�I�ȋ^��ł���B ����ł͌����_�̊������ł����Ď��{��`�̏I����_���邱�ƂɂȂ�A�{���]�|�ł���A���̊ϔO�_�ƂȂ낤�B �����_�͌����̗��j�ߒ��̐i�s�́u�͎ʁv�ł������͂��Ȃ̂ɁA���x�͎�q���]�|���Č����̗��j�ߒ����F�쌴���_���u�͎ʁv���Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂߂ɂȂ�B �F�엝�_���ǂ��������悤�ƁA���{��`�o�ς͂��ꎩ�̘̂_���Ŋ�������ق��͂Ȃ��B ���̘_���������{��`�̑������̔����Ƃ��Ă̋��Q�A��荂�������������߂Ă̎��{�̒~�ύs�����S�̂Ƃ��ė��������߂Ă����Ƃ������Ȗ����̕\���ł��闘�����ቺ�@���ł���A���Q�̑�֕��Ƃ��Ă̐푈��C���t���A�o�ϐ����̒�Ȃǂł��낤�B�w���{�_�x�̌n���I�Ɂu�����v������A���q�_�ƒn��_�̏�������ꂩ���Ă݂�ƁA����Łw���{�_�x�ł͘_�ł��Ă��Ȃ��B���j�ς̍��{����A���Y�͂Ɛ��Y�W�̖����A���Y�W�����Y�͂ɑ��ĖÞ��ƂȂ邱�Ƃ��_�����Ƃ����̂ł͎v���������Ă���Ƃ����Ă��v�����Ȃ��ł��낤�B
����G���u�w���{�_�x�Ə������{��`�v(�w�o�ϊw�_�W�x)�́A�������F�엝�_�̗��ꂩ�珃�����{��`�̈Ӌ`���l�@�������̂ł��邪�A�F�엝�_�̒P�Ȃ锽���ɏI����Ă���B �������ˌ��l�Y�u�w���{�_�x�ƏC����`�_��-���{�~�Ϙ_�𒆐S�Ƃ���-�v(��)���A�F�엝�_�̗��ꂩ��A�x�����V���^�C���Ȃǂ̏C����`�_���ŕ���_�̊�b�ƂȂ����w���{�_�x��1����23�͂̎��{�~�Ϙ_��ᔻ�������̂ł���B �ᔻ�̗v�_�́A���̂Ƃ���ł���B (1)��23�͂ɂ͒����㏸�ꗘ�����ቺ���Q�̘_���Ɓu�ʌn��̘_�����������v�A�u�������_���W�J���j�Q�v(p�B 63)����Ă���B (2)�Œ莑�{�̑��݂䂦�Ɏ��{�\���̏㏸�́w�s�f�x�ɂ͂��肦���A�s�����ɏW������B (3)��4�߂́u��v�ȑΏہv(p�B 67)�́A�����Ȏ��{��`�Љ�Ŏ��{�~�ς����ݏo�����ΓI�ߏ�l���ł͂Ȃ��A�ނ��낻�̊O���ɑ��݂��钆�ԑw�̕������甭��������j�I�Ȃ���ł���B(4)�u���j�I�ȎY�Ɨ\���R�ɂ݂�ꂽ���R���̎������������Ɂw���{��`�I�~�ς̐�ΓI�Ȉ�ʓI�@���x�Ƃ���v�A�u�����_�̂����ɒi�K�_�ȉ��̋�̓I�ȋK�肪�����v(p�B 67)���Ă���B (5)�ʎ��{�̏W���͒~�Ϙ_�̎����ŏؖ��ł����A���Q��̉ߏ莑�{�����Ƃ̊֘A�łƂ���Ă��Ȃ��W�A���𑣐i����M�p�͏��ƐM�p�����s�M�p�ւ̓W�J�Ƃ��ĂƂ���Ă����A�ݕ����{�Ƃ��@�\���{�Ƃɋ��^���邩�����łƂ���Ă��邪�A�u���{�s��A�����g�i�[�I�����Ƒw�́A�����Ȏ��{��`��z�肷�錴���_�ł͑z��ł��v��(p�B 70)�A�W���@�\�Ƃ��Ă̊�����А��x�́A�u�i�K�_�v�łƂ��ׂ��ł���B (6)���Z���{�i�K�̐V���ۂ́A�q���t�@�[�f�B���O��[�j���ɂ���ĉ𖾂��ꂽ���A�u���@�_�I�ɂ͂Ȃ��s���m�v�ŁA�u������������Ď����т����邽�߂ɂ́v(P�B 73)�A�w���{�_�x�̏����ƒi�K�_�̌`�����K�v�ł���B
�݂���Ƃ���A�F��H���ɏ]�����A�F�엝�_�̒����Ȓʑ��I������^�����Ă���B �����A��1����23�͂̒��ێ����Ōi�C�z�_���Ƃ��Ȃ����Ƃ͉������薾�炩�ł���A�ނ���F�엝�_�����u�ʌn��̘_��]���u�����v�����Ă���̂ł���B �i�C�z�_�ł̏d�v�ȃJ�e�S���[�ł���s�ꉿ�i���v�Ƌ������q���A�����ƐM�p�Ȃǂ��Ƃ��O�ɁA���ړI���Y�ߒ��łǂ����Či�C�z�_������ł��悤���B ���{�̗L�@�I�\���̍��x�����������鋣���̈��͂͂������ɕs�����ɂ͈�����A�������D�����ɂ�����V�����A�ݔ��̍X�V�ɂ����Ď��{�͉��������̋Z�p���̗p����K�v�͂Ȃ��A��荂����������ڎw���čŐV�̋Z�p���̗p����ł��낤�B �Ƃ��ɘJ���͂��Ђ������Ă����Ԃ̉��ł͂����ł��邵�A�D�����ɂ����Ă������{�ԂɋN�钴�ߗ������߂����ẴR�X�g�؉����������W�J�����̂�����V�Z�p�̗̍p�͎��㖽�߂ł���B �������āA�i�C�z���̏ۂ��������I�ȕ��ωߒ����l�@����A�u�s�f�v�̎��{�\�����x���̑z�肪�\�ɂȂ�B���������Ă������玑�{��`���g������̃��J�j�Y���Ő��ݏo�����ΓI�ߏ�l�����Ƃ�o����ł��낤�B ���ꂪ�u��v�ȑΏہv�ł���B ���{��`�������J���͂̋�����{��`�I���̕����Ɉˑ�����Ƃ���A���{��`�͂���������ɐ��ꎩ���I�ɑ����������A�v�����܂܂ɉ����x�I�~�ς������i�߂��ʂ��ƂɂȂ낤�B �܂��A�ʎ��{�̋����A�i�C�z�ߒ����̏ۂ�������̒��ې��̂��ƂŒ��ړI���Y�ߒ��ɂ�����~�ς̈�`�ԂƂ��Ă̏W�����Ƃ��Ă����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B �܂��A���{�s��A�ݕ����{�ƂƋ@�\���{�Ƃ̕����A�e�X�̑��݁A������ЂȂǂ������_�łƂ��Ă�邢�킯���܂������Ȃ��B�u�������鎑�{�������Ȃ��痘�q�邾���Ŗ�������悤�Ȏ��{�Ɓv�́u���݂̗]�n�v(p�B 72)���Ȃ�����A�Ǝ��͌����邪�A�ނ��낻�̂悤�Ȏ��{�Ƃ������ɑ��݂��邩��A����������_�ɔ��f�����˂Ȃ�Ȃ��B �J�e�S���[�͌����̖͎ʂł���B �����Ă����A�ˌ����̋c�_�́A�~�Ϙ_�̒��ێ����A���@�A���e�ɑ������ƕΌ��̎Y���ł���B
�˖{���u�Љ�I�Ԑڎ��{�ɂ��āv(�w�B���j�ρx)�́A�w���{�_�x�ɂ�������̋K����������A�Љ�I�Ԑڔ�p�̕��ނ��s�Ȃ������̂ł���B ��؊�v�v�u���q�_�̕��@�v(����)�́A�F�싳���Ɓw���{�_�x�̗��q�_�̕��@��Δ䂵�čl�@���A�F�엝�_�̓�_���w�E�������̂ł���B �V���v���u���i�_�̐����v(�u�O�c�w��G���v)�́A�w���{�_�x�`���̏��i�_���Ȃ��A�܂������ɂ��Čo�ϊw�̌n�̎n���̒n�ʂɂ����������w���{�_�x�̐����ߒ��ɂ��Ă����炩�ɂ����_���ł���B
���̑������錴���_�W�ł́A���䐳���u������w�s���Ăȉӏ��x-�}���N�X�̎s�g���l�_�ɂ���-�v(�w�o�Ϙ_�W�x)�A�������u�w���{�_�x�ɂ����鏤�Ǝ��{�v(�w�o�ϊw�_�W�x)�A�g����u�}���N�X�����_�̕��@�ƍ\���v(�w�o�ϊw�G���x)�A���r��V�u�w���{�_�x�ɂ�����y�n���L�̘_���v(�w�O�c�w��G���x)�A�ѓc�T�N�u�M�p�Ƌ��Q�Ƃ̘A�q�ɂ��āv(����)�A�F��O���u���{�̕��_���v(�w�B���j�ρx)�Ȃǂ����邪�A�����̓s������e�ɗ�����Ȃ��B ���̑��A�ꃀ�E�o���F���N�́w���{�_�x�ᔻ�ƃq���t�@�[�f�B���O�̔��ᔻ�����������̂Ɏ퐣�u�w���{�_�x�ւ̔ᔻ�Ɣ��ᔻ�v(�u�o�ρx)�A�T�~���G���\���̃}���N�X�ᔻ�ᔻ�������̂ɕ��c���v�u�T�~���G���\���̃}���N�X�ᔻ�v(�w�o�ϊw�_�W�x)������B
�v�z�j�I�ϓ_����w���{�_�x���݂��_���Ɂw�v�z�x����̕��c�����u���j���_�Ƃ��Ắw���{�_�v�v�A�����l�Y�u�J���a�O�_�Ɓw���{�_�x�v�A���������u�w���{�_�x�ɂ����镨�����v������B ���c���͍ŋߐ��͓I�ɂ��̎�̘_���\����Ă��邪�A�S�ڂ������炩�ɂȂ鎞�_�܂Ř_�]�͂����Ђ��������B
(1)�@���A���悤�Ȋϓ_�����ˎ���ᔻ���A���̍������ˎ��̊K���I����ɂ݂����̂ɗђ������̏��]������(�w�w���V���x1966�N11��16����)�B�@ |
| ��3 �w���{�_�x�ƒ鍑��`�E���㎑�{��` |
   �@
�@
|
�w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�Ƃ͂ǂ̂悤�Ș_���I�֘A�ɂ����A�͍ŋߓ��ɂ�����ɂȂ����e�[�}�̈�ł���B �������O�Y�̘_���u�w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�v(�w�v�z�x)�̗v�_�͎��̂Ƃ���ł���B (1)���҂�A���I�Ȃ��̂ƍl����P���ȁu�A�����v�́u�w�_��=���j���x�ɑ���f�p�ȐM�v(pp�B 29-30)�Ɋ�Â��Ă���A���ǂ͗��҂̊W�𐳂����Ƃ炦�邱�Ƃ��ł��Ȃ����肩�A�u���j��`�v���u�_����`�v���́u�Ό��v�ɂ������炴������Ȃ��B (2)�u���j��`�v�I�Ό��̑�\��́w�o�ϊw���ȏ��x�ł���A�w���{�_�x��Ɛ�O�̎��{��`�̗��_�A�w�鍑��`�_�x��Ɛ莑�{��`�̗��_�Ƃ���B �������A���̐}���ł́w���{�_�x�́u����̗��j�i�K�Ƃ��Ă̎Y�Ǝ��{�i�K�̗��_�ƒP���ɓ��ꎋ����A����ɏx���������v(p�B31)�B (3)�u�_����`�v�I�Ό��̑�\��͋{��҈ꎁ�̌����ł���A�鍑��`�i�K�̏��������ׂāw���{�_�x�̉�������ɁA�o�ϊw�ᔻ�̌n�v������Ɉʒu�Â��A�w���{�_�x�̋�̉��Ƃ��đ̌n�����ׂ��ł���Ƃ����B �������A����ł͎Y�Ǝ��{��`�i�K�ƒ鍑��`�i�K�Ƃ́u���j�I�����̑��Ⴊ��������v(p�B 34)�邱�ƂɂȂ낤�B (4)�w�o�ϊw���ȏ��x�ł́w���{�_�x������ɁA�{�莁�ɂ����Ắw�鍑��`�_�x����ʂɉ�������Ă���B (5)�����̋��ʂ���u���{�I���ׁv�́A�u��̓I�E���H�I�ϓ_�̌��@�v(p�B 34)�ł���B�w���{�_�x�͓������E�v�����w�����A�w�鍑��`�_�x�͈ꍑ�Љ��`���w�����Ă���A�O�҂����҂ւ̗��_�I�W�J�́u�d��Ȏ��H�I�]����Ƃ��Ȃ����v(p�B 36)�B���u�A�����v�͂��̂��Ƃ��u�Y�p�v���Ă���B
�������ɁA�����ł́w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�Ƃ�P���Ɋ֘A�Â���ʑ��I�������s���ᔻ����Ă���B �������A���������悤�Ɏv����B�w���{�_�x�͒鍑��`�i�K�ɂ��Ó����鎑�{��`�̈�ʗ��_�ł��邪�A�����ɒ鍑��`�i�K�Ƌ�ʂ��������i�K�ł���Y�Ǝ��{��`�i�K�̓��ꗝ�_�ł�����B ��ʂ͂��v���~�e�B�u�Ȓi�K�ł͎f���ɓ���ł�����B ��ΓI��]���l�̐��Y����]���l���Y��ʂł����邵�A���ΓI��]���l���Y�ɑ��Ĉ�̓���I���Y���@�ł���̂Ɠ��l�ł���B ���̂悤�Ȃ��Ƃ����炩�ł��邩����A�w���{�_�x=�Y�Ǝ��{�i�K�̗��_�A�w�鍑��`�_�x=�Ɛ莑�{��`�i�K�̗��_�Ɖ]���Ă����������Ȃ��ł��낤�B�w�o�ϊw���ȏ��x�͂������炸�A���ꂪ�����̗�������}���ł���B
�o�ϊw�̗��_�́A�������������𖾂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̌����͓���O�������邮��܂���Ă����A�ނ���点���ɕω����𗙓I���W���Ƃ���B �����ŁA���̗��j�I���W(�����ł͓Ɛ莑�{��`�̂��Ƃł���)���ǂ����q���邩�����ƂȂ邪�A����ɂ͓�̕��@������Ƃ����͍l����B ��1�̕��@�́A�w�鍑��`�_�x�̂悤�ɁA���{��`��ʂ̗��_�͂��łɁw���{�_�x�ŗ^����ꂽ���̂Ƃ��đO�A�Ɛ莑�{��`�̓��ꐫ�����͂��A���q������@�ł���B ����ɂ��A�w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�Ƃ̘_���I�W�́A���炩�Ɂu�A�����v�ɂȂ�A�܂����j�̔��W�ɏƉ�������̂ƂȂ낤�B ��2�̕��@�́A�Ɛ莑�{��`�����̓��ꐫ�ɂ����Ă̂ݕ��́A���q�����ɁA���̓��ꐫ��Ɛ莑�{��`���̂����̊�b�ɂ����Ă��鎑�{��`�̈�ʐ��ƂƂ��ɓ����ɕ��͂��A���҂���̑̌n�Ƃ��ď��q������@�ł���B ���̕��@�́w���{�_�x��Ɛ莑�{��`�̑S�̂̈�ʓI���_�Ƃ��ĕҐ��������A�Ɛ莑�{��`�ɓ���ȌL�̏����e�A���@���𒆐S�ɂ����āA���̍��݂���w���{�_�x�ł̏����e�⏔�@�������P���Ȃ��́A��s�҂Ƃ��Ĉʒu�Â��Ȃ������@�ł���B �����ŁA���{�A�o�_�A�h����@�A�Ǘ��ʉݐ��Ȃǂ��������߂ɁA�O�����āw���{�_�x�̌n�̌�ɗ\�肳��Ă���v�����̌㔼3���ڂ̓��e�����͂����Ă����˂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B �{�莁�͂Ƃ������A�����̍l����v�����̋�̉�����ɒ鍑��`�_���\�z����Ƃ������Ƃ́A���̂悤�ȈӖ��ł���B �������̘_�����������A���̐ϋɐ����S�ڂ������炩�ɂȂ邱�Ƃ��̂��݂����B(1)
�{�ԗv��Y�u�w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�v(�w�o�ϕ]�_�x)�́A�w���{�_�x�̌p�����W�́u�i�K�_�I�A���ꗝ�_�I��̉��Ƃ����`�ł������肦�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�c �c �ǂ����Ă���ʗ��_���̂��̂̌��Ɗg�[�����Ƃ������ʂ�������������Ȃ��v(P�B 37)�A�w���{�_�x�́u���R�����i�K�̒i�K���_�Ƃ��Ă̑��ʂ����v���A�u�w���{�_�x�͈�ʗ��_�A�w�鍑��`�_�x�͓���i�K���_���Ƃ���ɂ�肫��v���Ƃ͂ł��Ȃ�(p�B40)�A�Ɖ]�����A����ꂪ��ɂׂ̂��Ӗ��ł͂��ȂÂ��悤�B ��m���G�v�u�w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�v(�w�o�ρx)�́A�u���{��`�̉^���v�Ƃ����ϓ_���痼�҂̌p���W���l�@�������̂ł���B
����́u����ɂ�����w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�v(�w�v�z�v)�́A�����̌���I�Ӌ`���l�@�������̂ł��邪�A���̓��e�͑啔���F�엝�_���炷�鑊������炸�́w���{�_�x�ᔻ�ƏC���̎咣�ɂ��Ă��Ă���B���l�ɉF��O���E�~�{���ȁu�Βk�E�w���{�_�x�Ɓw�鍑��`�_�x�v(�w�v�z�x)�ł��A�F�쎁�͂��łɂ��肩(2)�����ׂ̂����Ƃ��ނ��������Ă�����B ���B��͑���͂Ƃ̑Βk�u���㐢�E�ƃ}���N�X�o�ϊw�v(�u�o�ϕ]�_�x)�ł́A�F�엝�_���鍑��`�i�K�ɂȂ�Ǝ��{��`���u�s�����v���A�����I�ɂƂ��Ȃ��Ȃ�Ƃ����̂ɑ��āA���̕ω��́u�������ċ��R�̂��̂ł͂Ȃ��A���{��`���̂��̂̌����ɂ�锭�W�v(P�B 12)�ł���A�i�K�Ԉڍs�̘_���A���W�̘_�����u���{��`�̌����_�ɂ͂���v(p�B 14)�Ƃׁ̂A�F�엝�_�𐳂����ᔻ���Ă͂��邪�A�����ł́u�w���{�_�x�E�w�鍑��`�_�x�E����v(�w�v�z�x)�ł́A������u19���I���t�A20���I�����ƂȂ�ԑ�3�̒i�K�ƋK�肷�鉼���v(p�B 17)���o����Ă���̂͂ǂ��ł��낤���B �i�K�K�肪�\�������I�ɗ^�����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B ��{�a��u19���I���t�ɂ����鎑�{�̒��ړI���Y�ߒ��v(�w�o�Ϙ_�p�x)�́A���R�����i�K�ƓƐ�i�K�Ƃ̒i�K�敪�����{�̒��ړI���Y�ߒ��ɂ�����ω��ꗬ���Ƒg�D�A���������Ƌ@�Ȃǂ̓����m��-�ɂ���ċK�肵�悤�Ƃ������̂ł���B ���̓_�A�Ɛ藘���̌���Y�ߒ��ɂ�����u���߂�ꂽ�J���v�ɋ��߂锒�����_�Ƃ������ł��낤�B ��{���̍���̏ژ_���܂��܂Œf��I�Ȃ��Ƃ��]���̂͂����Ђ����������A���ړI���Y�ߒ��̕ω��͏�]���l���Y�̕��@�ɂ�����邱�Ƃł���̂ɔ����A�Ɛ�̒i�K�K��͋����̓Ɛ�ւ̓]���Ƃ����u�����_�v�ŁA���i�`���A��]���l�̍ĕ��z�������u���ߒ��v�ŗ^������̂ł͂Ȃ��낤��(���Ƃ��A�J���e���A�g���X�g���l���Ă݂�)�B
���ɍ��ƓƐ莑�{��`��_�����_���ɖڂ�]���悤�B �u���M�Y�u���ƓƐ莑�{��`�Ǝ��{�j��v(�w�v�z�x)�́A��т����_���ō��ƓƐ莑�{��`���𖾂����͍�ł���B ���̍��q�͂��悻���̒ʂ�ł���B (1)�l���̕s�ύt-���Y�\�͂Ə���̕s�ύt(���������Y�\�͂�����)�A�J���̎����̕s�ύt�A���l�Ɖ��i�̕s�ύt�A���嗘�����̕s�ύt��́A�D���ߒ��ŗݐς���A���Q�ɂ���Ė\�͓I�ɋύt�������B�u���{�j�낪�傫�Ȗ������ʂ��v(p�B 126)�̂ł���B (2)�Ɛ肪��������ƁA�Ɛ艿�i�̐ݒ�A���͂Ȏ��{�͂̂��߂Ɏ��{�j��A�s�ύt�̋ύt���͏\���s���Ȃ��Ȃ�A�s���͂Ȃ��т��B (3)�u�Ɛ莑�{�ɏ]�����A�o�ςɐ[���������v(p�B 128)���Ƃ́A�L�����v����������Ƃ邪�A����ɂ���Ă��J���͋����̐������邢�͎����������̐������E�܂ł̉����E�Փ˂Ƃ������Ԃւ̐i�s�͕s���ł���B (4)���Q�ɂ��Ȃ����{�j��͍D���ߒ��ɂ����鍑�Ƃ̉���Ɛ藘���̊m�ۂ�ۏႵ�A�������p��F�߁A�Ɛ莑�{�̍����𑣐i���A���Z�p�グ���肷��ɂ���Ă͂������B
�s�ύt�̗ݐςƘJ���͋��������Ƃ����V��ݒ�ɂ�
��t�]�ɂ��ẮA���łɕʂ̋@��ɔᔻ�������Ƃ�����̂ł����ł͂ӂ�Ȃ����A(3)�����ł��A��̘_�������ƓƐ莑�{��`�̉𖾂ɂƂ��Ăނ��낳�܂����ɂȂ��Ă���Ǝv����B ����������1�Ɏ��̘_���ł͋��Q���ߏ萶�Y���Q�ƂȂ炸�A��2�ɗL�����v�����Y�Ə���̖������ɘa���邽�߂̕���ł���Ƃ������Ƃ��킩�炸�A����䂦�J���͋��������A�����������̉����ւ̏Փ˂Ƃ������Ԃ̉����ɂȂ�Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł��낤�B ����ɂ��Ă����_���͍��ƓƐ莑�{��`�ɐ^���������肭���_�ł���A���݂̊w�E���炵�Ă����͍����]���������B
����́u���ƓƐ莑�{��`�Ƌ��Q�v(�w�B���j�ρx)�́A���ƓƐ莑�{��`�̐����ɂ���đ勰�Q����������A���Q�̌������������Ȃ��������̕s���ɂȂ����̂͂Ȃ����A�������Z�k���ꂽ�̂͂Ȃ����Ȃǂ��l�@�������̂ł��邪�A�S�ʓI�ɃX�P�b�`�I���i�����B�����L���u����̋��Q�ƃ}���N�X���Q�_�v(�w�����ٌo�ϊw�x)�́A�c�O�Ȃ���M�Җ����ł���B �c���T��Y�u�\�����v�_�ᔻ�v(�w�B���j�ρx)�́A�\�����v�_�҂̍��ƓƐ莑�{��`�_���A���Y�W�̗����A���Ǝ��{�Ǝ��I��s�ƎY�Ǝ��{�̂䒅�����u���ƓƐ莑�{�v�̐ݒ�A���ƓƐ莑�{��`������o�����ɂ͂����Ȃ����Y�̗͂����Ȃǂ̔ᔻ��ʂ��āA�����������̂ł���B �]�c�O�Y�u�V�����Љ��`�Ɠ��{�̌����v(�w�o�ϕ]�_�x)�́A���a�v�������B��_�A���{��`�����ł̍\���I���v�A�s�s���A���ۑ̐��̉����Ȃǂ�_����B �������A���͑��̖\�͋@�\�������Ȃ����߂ɂ́u���ΐ��͂̌Ǘ����v(P�B 105)�����ł����̂��A���a�v�������ƌ��݂́u����N�ρv�̈������͖������Ȃ��̂��A�������_�Ȃǂɋ^�₪�̂���B
(1)�@�{�_���̌�ɏo��2�_�����Ƃ��Ɏ��^�������̐V���u�w���{�_�x�ƉF��o�ϊw�v�ł��u�����v(p�B266)�ł���B
(2)�@�F��i�K�_�̏G�ꂽ�ᔻ�Ƃ��Ă͌��c�Ή�w�F�엝�_�ƃ}���N�X��`�o�ϊw�x������B
(3)�@���Ώ��F�u���{�~�ςƋ��Q�v�w�ꋴ�_�p�x����44�N4�����A��61����4���B�@ |
| ��4 �w���{�_�x�Ɠ��{���{��`�E���� |
   �@
�@
|
�牮�T�Y�u��O�̓��{���{��`�����Ɓw���{�_�x�v(�w�o�ρx)�ɂ���������Ƃ���A��O�̃}���N�X�o�ϊw�́A���̖{���̎g�����炵�ē��R�̂��Ƃł��邪�A�Љ�ϊv�₻����g���Ƃ���v�����}�̍j�̂̂�����Ƃ̂������ŁA���{���{��`���ǂ��K�肷�邩��^���ɍl���A�����̘J������ݏo�����B �Ƃ��낪����ɔ����A���̃}���N�X��`�o�ϊw�́A���{�̌����Ǝ��H�I�ɂ�����낤�Ƃ����ɁA�ނ���u��Y�v�Ɉ��Z���A�ӑĂ��ނ��ڂ��Ă����悤�ɂ݂���B ���������w�E��f���āA���{���{��`�ɂ��Ę_�������̂͂��������ɂ����Ȃ������B �����͂��̊w�E������S�ɔ��Ȃ������B
�䑺���q�u�w���{�_�x�Ɩږ{���{��`���͈�Đ��Y�\���_���߂����āv(�w�v�z�x�́A�k���E���ƂƂ��ɎY�ƘA�֕\�𗘗p���Đ����{���{��`�̍Đ��Y�\���̕��͂ɐ��͓I�Ɏ�g��ł����䑺���́u���ʂ��Ă�������ꉞ�������ᔻ�����������Ƃ�����́v(P�B 188)�ł���B(1)�w���̗v�_�͎��̂Ƃ���ł���B (1)�w���{�_�x��II����3�эĐ��Y�\���_�́A���̒��ې����炵�āA(�C)���Ǝ��{�A�ݕt���{�A�y�n���L�A��]���l�̋�̓I���`�ԁA�T�[�r�X�ƁA���ƁA�O���f�ՂȂǂ��̏ۂ��A(��)���l�Ɖ��i�̈�v�A�h���A�s�ύt�̂Ȃ����ϓI�ߒ���z�肵�Ă���B (2)�Đ��Y�_�̋�̉��̂��߂ɂ́A(��)�̑z��͓��R�ێ�����邪�A(�C)�͕\���ɓ������ׂ��ŁA�����ł͂������߂܂���1�ɓ������Œ莑�{�̉��l�ړ]���ƍX�V�����Ƃ̍��zD-R��\���ɓ������A�܂��u��1����̂Ȃ����w�J����i���Y����x�̓Ɨ����𒆐S�Ƃ��āw�J����i�W�̌��ޗ����Y����x�A�w�����i�W�̌��ޗ����Y����x�ɍĕ�������v(P�B 193)�B ��2�ɃT�[�r�X����⍑�Ƃ͋��z�̌Œ�ݔ��◬���I����(�R���i���܂�)���v��n�o���邩��A�u�T�[�r�X����v�A�u�T�[�r�X����p���ݐ��Y����v�A�u�R���I����v�A�u��R���I���ƕ���v�A�u�R���i���Y����v�A�u��R���I���ƕ���p���ݐ��Y����v��6�����n�݂���B (3)�A(1)��(��)�̑z��ɂ�������炸�A�����̍Đ��Y�͌i�C�ϓ��̉ߒ��ł������肦�Ȃ�����A����N�̌��͈͂�ǖʂ̕��͂ł������肦���A�����ŕ��͂̎��́A�u�N�X�̕ω��A�z�I�ϓ��̂Ȃ��ɂ���ʂ���Ă���A����\���I�����E���������o���邱�Ɓv(p�B 199)�ł���B ���炽�߂āA���Q�_�ƕ\���_�̘A�q�̉����ɂ��܂��Ă���B
����́u�w���{�_�x�Ɩږ{���{��`�_�v(�w�o�ϊw�_�W�x)�́A��O�̓��{���{��`�_���ɂ�����w���{�_�x�̗��p���@��ᔻ�������̂ł���B�w���{�_�x�̗��p���@�̈�́A�w���{�_�x�̑ΏۂƂ��鏃�����{��`�����u���^=���z���Ƃ��Ă����A���{���{��`�̖{���Ȃ���ꐫ�Ȃ���A�������Ƃ��ĉ𖾂���v(p�B75)���@�ł��邪�A�������{��`�Ȃ���̂͂������������ɂ͂������đ��݂��Ȃ����̂ł��邩��A�u�����鎑�{��`�ɌŗL�ȋ����Ȃ���ꘗ�v���u���ׂē��{���{��`�̓����Ƃ���v(p�B 79)�Ă��܂����ƂɂȂ�B ���̗��p���@�́u���������d��Ȍ��ׁv(P�B 79)�́A1930�N��͒鍑��`�E���Ǝ��i�K�ł���̂ɁA�u�i�K�_�v���ӎ����Ȃ��������Ƃł���B ���̂悤�ɂ��āA�u���h�����{�̓��ꐫ�ƍl�����������́A���{'�ƓI�y�n���L���ǂ��̍��ł��x�z�I�ɂȂ炸�A������������鍑��`�i�K�ł́u��̂���X���������v(P�B82)����A�u�i�K�_�I�ɂ݂�A���{��`��ʂɌŗL�Ȍ��ہv�ł���A�u���{�̓��ꐫ�ł��Ȃ���A�����╕�����ȂǂƂ������̂ł͂Ȃ��v(P�B 82)(��2�̗��p���@�A�}�j���_���ւ̊��͏ȗ�)�B �݂���Ƃ���A�F��O�i�K�_���炷��ɗ�Ȕᔻ���s���ă�'��B ������1�ɁA�w���{�_�x=�������{��`�Ɠ��{�̌����Ƃ̍��́u���ׂĂ̎��{��`�ɋ��ʂ̖��ł���v�Ƃ����̂ł́A���ꂪ�Ȃ��Ȃ�ł͂Ȃ����B ��2�ɁA�鍑��`�i�K���l�����ׂ��ł���Ƃ����̂͐��������A��ɂ��ׂ̂��悤�ɁA�鍑��`�Ƃ����ǂ����{��`��ʂɊ�b�������Ă���̂ł��邩��A���̂�����ł́A���̒��ې��ɂ����ẮA�w���{�_�x�ł����Č��͂��s�Ȃ����Ƃ��ł���̂ł���B ���i��ݕ��̕��́A�u�ݕ��̎��{�ւ̓]���v�c �c���X�́A������ēƐ�i�K�̖ږ{���{��`�̌��͂ł�����B�u�w����{�_�x��'���ɓ��{���{��`���͂ɒ��ڗ��p�����Ȃ��v(p�B 79)�Ƃ����̂́A���̓_��Y�ꂽ�c�_�ł���B �����ɎO�i�K�_�̎�_���I�悵�Ă���B
�u���h�̓��{���{��`���͂́A�������ɓ��{���{��`�̓��ꐫ=�������������������������炢���������B ���{���{��`�͔������I�y�n���L����̓I�ɗ��p���A����ݑ�ɂ��Ĕ��B�������Ƃ͎����ł��邪�A������u���v�Ƃ��Ĕ��B�����Ɖ]���A���{���{��`���g�������̒��ړI���Y�ߒ��ŘJ���҂���悵�A���ʉߒ��A�u���ߒ��v�ŊO���I�Ȏ��D���s�Ȃ��A�������Ă�����]���l�◘�������{�~�ςɓ]�����ē��ꐶ�I�A�����I�ɔ��B���Ă������ƁA�]��������Γ��{���{��`�������̑��ŗ����A�������g�̋@�\�ł����Ď��{�~��=���W���Ƃ��Ă������Ƃ��ߏ��]������邫�炢������̂ł͂Ȃ��낤���B ���{���{��`�̑S�̑��͂��̈�ʐ��Ɠ��ꐫ�Ƃ̗����ɂ����Ė��炩�ɂ���˂Ȃ�Ȃ��B
���̂ق��ɁA���{�̓Ɛ莑�{�̐E��������Ƃ��̈Ӌ`��_�������̂ɉ��c����_���A��Ô����_�������̂ɋg�c�k���Y�_��(�Ƃ��Ɂw�B���j�ρx����)������B
(1)�@�䑺���q�A�k���E���̋����J���m�邩���肠����Ύ��̂Ƃ���ł���B�u���{���{��`�̍Đ��Y�\�����͎��_�ꏺ�a35�N�u�Y�ƘA�֕\�v���肪����Ƃ���-(1)�A(2)�A(3)�A(4)�v�w�O�c�w��G���x��57����12���A��58����7���A��9���A��10��;�u���{���{��`�̍Đ��Y�\�����͎��_�U-���a30�N�ȍ~�̊g��Đ��Y�ߒ���(1)�A(2)�A(3)�A(4)�v�w�����x��59����6���A��10���A��60����5���A��7��;�u�w���x�����x�ߒ��ɂ�����Đ��Y�\����A���v�w�o�ϕ]�_�x1967�N9���A10�����B�@ |
| ���ނ���
|
   �@
�@
|
�ȏ�����́A�w���{�_�x100�N���L�O�������W���⏑���ɂ̂��Ă��鏔�_����W�]�����B �ȏ�̂ق��ɁA�Љ��`�o�ςɊւ������(�����u�J���ɉ��������z�ɂ����āv�w�o�ϕ]�_�x�A�u�J���ɉ��������z�ƃu���W���@�I�����v�w�v�z�x�A���c���u���i���_���Ɓw�Љ��`���i�x�_�v�w�o�ϊw�G���x)�A���k��Ȃǂ����邪�A�ȗ�����B
�ȏ�̃T�[���F�C��ʂ��ĒɊ��������Ƃ́A�����̘_���������Ƃ̑Ό��������A����ȍs���������Ă���Ƃ������Ƃł���B �������A�}���N�X�o�ϊw�̓U��������Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B �����́A�v�z�j�A�����}���N�X�A�a�O�_�A�w���{�_�x�`���ߒ��̌����������ɏd�v���ƍl���邪�A����ɂ��Ă����ƓƐ莑�{��`�A���{���{��`�A���͂Ȃǂ̌������]��ɂ����Ȃ��������Ƃ��c�O�Ɏv���B �܂��A�C���t���A�����㏸�A���Q�A�Z���A�s�s���A��ʐ푈�ȂǍ����������������Ă��鏔���A�J���g���^�����������Ă������ɂȂ��Ă��镟�����Ƙ_�C�f�I���M�[�A�Љ�ϊv�̂��߂̋q�ϓI�ȕ����I�������A���X���܂������Ƃ舵���Ă��Ȃ��������Ƃ́A�����̊w�E�f���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B �}���N�X�o�ϊw��������x���S�ɂ��ǂ��A�ϊv�̗��_�Ƃ���-���ꂪ�w���{�_�x100�N��^�ɏj���őP�̕��@�ł��낤�B�@ |
 �@ �@
�����̐g����͏��a���Q���ɑ������̂� |
   �@
�@
|
���v�|
���a���Q���ɂ���Ĕ敾�������{�̔_���ł́A���̐g���肪�������A���ꂪ�����Ŕj���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������_�����߁A���]�Ȑ܂̂������A�푈�ɂ܂œ˂��i��ł��܂����Ƃ����c�_������B���̐g���肪���������Ƃ����b�́A���Z�̓��{�j�̋��ȏ��ɂ��ڂ��Ă���B�������A����͖{���Ȃ̂��낤���B�e�Ђ̋��ȏ��́A���̐g���肪�������Ƃ������ƂɊւ��Ă͈�т��Ă��邪�A���ꂪ���a���Q���ɑ��債���Ƃ����f�[�^�͎�����Ă��Ȃ��B
�{�e�́A���̐g����̑����Ƃ������ێ��̂��A�����������ۂɋN�������̂��A�N�������̂��Ƃ�����A���N�������̂����w�x�������v���x����쐬�������n��f�[�^��p���Č������B
���̌��ʁA���a���Q���ɖ��̐g���肪�傫���������Ă��������͂Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ����B�������A���a�_�Ƌ��Q���ɖ��̐g���肪�����Ă����\���͂���B�܂��A���a���Q���ɓ��k�̈ꕔ�Ŗ��̐g���肪�����Ă����Ƃ�����A����͕l�����t�̊��L�n�������ɂ��\�������邱�Ƃ����炩�ɂ����B
����A1906�N����7�N�ȍ~�A���k�Ŗ��̐g���肪�������Ă������Ƃ����������B�ɂ�������炸�A����ɂ͂܂������G����邱�ƂȂ��A�����̂Ȃ����̐g����̌������Ɠ��k�̍����Ɛ푈�Ƃ����ѕt����̂͊�Ȃ��Ƃł���B
|
��1�D �͂��߂�
���a���Q���ɂ���Ĕ敾�������{�̔_���ł́A���̐g���肪�������A���ꂪ�����Ŕj���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������_�����߁A�N���Z�̕����������A���]�Ȑ܂̂������A�푈�ɂ܂œ˂��i��ł��܂����Ƃ����c�_������B���̐g���肪���������Ƃ����b�́A���Z�̓��{�j�̋��ȏ��ɂ��ڂ��Ă���B��O�A���{�̕n��������ɖ��̐g����|�؋��̂����ɔN�G����ŏ��W�ɔ�����Ƃ������Ƃ͂������B�������A���a���Q���ɂ��ꂪ�}�����A�������A�p���I�ɑ��債�Ă����Ƃ������Ƃ��������̂��낤���B
�e�Ђ̋��ȏ��́A���̐g���肪�������Ƃ������ƂɊւ��Ă͈�т��Ă��邪�A���ꂪ���a���Q���ɑ��債���Ƃ����f�[�^�͎�����Ă��Ȃ��B�܂��A���N�������̂��ɂ��Ă��L�q�ɗh�ꂪ����B���a���Q�̒��ړI�ȉe���Ŗ��̐g���肪�������̂��A���a���Q��ɋN�����_�Ƌ��Q�ɂ���đ������̂��A���ȏ��ɂ���ċ����_�̈Ⴂ�����邪�A���҂̉e�������܂��Ė��̐g���肪���������Ƃ���Ă���B
�{�e�́A���ȏ��ɂ�������Ă��閺�̐g����̑����Ƃ������ێ��̂��A�����������ۋN�������̂��A�N�������̂��Ƃ�����A���a���Q�A���a�_�Ƌ��Q�̂ǂ���̌����ɂ���ċN�������̂����f�[�^�Ɋ�Â��Č�����B
|
��2�D ��s����
���{�o�ώj�̑דl�ł��钆�����p�́A1930�N�㏉���̏��a���Q���ɂ����閺�̐g����ɂ��Ĉȉ��̂悤�ɏ����Ă���B
�؋����ꂵ�݂ʂ����_�Ƃ͖���V���ɐg����\�\���S�~�̑O�؋��ŔN�G���������قǂ̋ꋫ�ɒǂ����܂����̂����������B1
�����āA
���̐g����ɑ�\�����悤�Ȕ_���̋��R�͓��R�S�Љ�I�Ȕ������ĂыN�������B���a�Z�N�O�������Ɏn�܂�N���Z�̃N�[�f�^�Q�����A�_���o�g�̐V�������炷�邤���ɁA���̏o�g�ƒ�̋�����Ă���ɓ���A�܂����̂܂܂ł͌�ڂ̗J�����傫�����ċ����R���͂ł��ʂƂ����f�p�Ȑ��`���ɔ�������̂����������B2
�Ƃ������Ă���B
�܂��A���Z�̓��{�j�̋��ȏ��ɂ�
�ĉ���1920�N�ォ��A���n�Ĉړ��̉e�����Ē�����Ă������A���a���Q����������ƃR�����͂��ߊe��_�Y���̉��i���\�������B���Q�ŏ���k�������A�����J�ւ̐����A�o�͌������A���̉e���Ŗ����͑傫�����������B1930(���a5)�N�ɂ͖L��̂��߂ɕĉ��������������āu�L��n�R�v�ƂȂ�A��31�N(���a6)�N�ɂ͈�]���ē��k�E�k�C�����勥��ɂ݂܂�ꂽ�B�s���̂��߂Ɍ��Ƃ̋@������Ȃ��Ȃ��������A�s�s�̎��Ǝ҂��A�_�������߁A���k�n���𒆐S�ɔ_�Ƃ̍����͒�����(�_�Ƌ��Q)�A���H�����⏗�q�̐g���肪���o����3�B
�Ƃ���B���Ȃ킿�A���݂̋��ȏ��ł́A���a���Q�����łȂ��A����ȑO����̕ĉ��̒���A�A�����J�勰�Q�ɂ�鐶���A�o�̌����A����A���a���Q�ɂ��s�s�Ŏd�����������l�X�̋A�_�ȂǁA���Q�Ɋւ���v���Ƌ���ɂ��v�������܂��Ė��̐g����������炵���Ɛ������Ă���B���ȏ��ɂ���āA�����̗v���̋���ɑ����̃j���A���X�̈Ⴂ�����邪�A�قƂ�ǂ̋��ȏ��������v�������̗p���Ă���悤�ł���B�����ŁA�{�e�ł́A���̐g����Ɋւ���v�����̂����A�����������a���Q�v�����A���݂̋��ȏ��̐������a���Q�E����v�����ƌĂԂ��Ƃɂ���B������̗v�����A�����̗v�������̐g�����������(����܂łقƂ�ǃ[���ł��������̂�傫�Ȑ��ɂ�����)�A�܂��͑����������Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��Ă���B�������A���̂悤�ȊW�𗠕t����f�[�^�͑��݂���̂��낤���B�������A�e�Ђ̋��ȏ����A��������f�[�^�������Ă��Ȃ��B
�e���ɑ��݂�����́A�������ɏ��a���Q���A���邢�͏��a�_�Ƌ��Q���ɖ��̐g���肪�������Ƃ���������`���Ă���B�\1�͂��������f�ГI�Ȑ������܂Ƃ߂����̂ł���4�B�������A1930�N�ȑO�̃f�[�^�͂Ȃ��̂ŁA���̐g���肪1930�N�̏��a���Q���A31�N�̔_�Ƌ��Q���ɑ����������ǂ����͕�����Ȃ��B�������A�X���������32�N�ɐg���肪�����Ă���̂ŁA31�N�̋���ɑς��Ă����_�Ƃ�32�N�̏t�ɑς����ꂸ�A�g����ɓ��ݐ����Ƃ������ʊW���ǂݎ��邩������Ȃ��B�������A�X���A�H�c���A�R�`���ŁA34�N�ɐg���肪�����Ă���B34�N�ɂ͓��k�ő勥�삪������5�̂ŁA����͂��̉e���ƍl���邱�� ���ł���B���Ȃ킿�A�g���肪���a���Q�ő��������Ƃ����f�[�^�͑��݂��Ȃ����A34�N�� ���k�̋���ő��������Ƃ������Ƃ́A�e���̒f�ГI�ȃf�[�^���玦���ł���̂�������� ���B
�@�@�@�\1�@���̐g����(�|���W���v)
���a���Q�͕�����3 ������������Ƃ����f�t���s���ŁA�_�Y�����i���H�ƕi���i�����傫�����������Ƃ����s���ł���B�_�Y�����i�̍H�ƕi���i�ɑ���䗦��29 �N�̐����ɖ߂����̂�1935 �N�̂��Ƃł��邩��6�A�_���ɂ����ĕs���������Ă����͎̂����ł���B�������A���̉��i�䗦�͏��X�ɉ��Ă����̂ŁA���a���Q�ɂ����34 �N�ɐg���肪���������Ƃ��������͓̂��(�O�q�̂悤�ɁA����ɂ���Đ������邱�Ƃ͉\�ł���)�B
�\1 �̏o���ɏグ�������̈ꕔ�ɂ���f�ГI�ȋL�q�ȊO�ɁA���̐g����ɂ��ē��k�S�̂̐�����ΏۂɌ���������s�����́A�����炭�H�c��c�q�ɂ�錤��7�ȊO���݂��Ȃ��B �H�c��́A1931 �N10 ��30 ���́w��㒩���V���x�����p������ŁA���̐g���肪�n�܂����̂́A���a���Q�ȍ~��1931 �N�ł͂Ȃ��A1929 �N�ł���A����N�Ƃ�����������Ă���Ǝw�E���A�܂��A���̐g����̂��������͋���ł͂Ȃ��A������̊��L�n�������ɂ���ĕK�v�ƂȂ��������B�����i�Ƃ��Ăł������Ƃ��咣���Ă���B�����āA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�����܂ł��Ȃ��u���g����v���̂��̂́A���̎����̓��k�_���Ɍ��炸�A���������珺�a��O����ʂ��đS���e�n�ŋN�����Ă������ۂł���B�������A���łɊm�F�����ʂ�A���̂Ƃ����ꂽ�u���g����v�͋���ɒ��ڂ̒[�������̂ł͂Ȃ������B�ɂ�������炸�A���̕ȍ~�A�u���k�_���̖��g����v�͉₩�ɐ��Ԃ̒��ڂ���Ƃ���ƂȂ�A ���̎������傤�Nj���ɂ��炳��Ă������k�_���̋��R��ǎ҂ɋ�����ەt����ƂƂ��ɁA���k�_���̋�����Ƃ�킯�u���g����v�Ƃ������ۂɌ��т��A�����������ꂪ���k�_���ɌŗL�̎��ۂł��邩�̂悤�ȃC���[�W�𗬕z������ʂ��������Ƃ�����B8
�܂�A���̐g���肪�ŏ��Ƀ}�X���f�B�A�ŕ��ꂽ�̂́A1929 �N�̊��L�n�������ȍ~���̐g���肪�����I�ɑ������Ƃ���A1931 �N10 ��30 ���́w��㒩���V���x�ɂ��ł���A���Ƃ��Ɠ��k�̋���Ƃ͒��ړI�ȊW���Ȃ������Ƃ����̂ł���B����𖺂̐g����ɂ��Ă̑�3 �̉����A���L�n���������Ƃ��悤�B
�H�c��͊��L�n���������̓��e���̂��̂ɂ��Ă͏ڂ����������Ă��Ȃ����A��{�R�P�w�R�`���̕S�N�x(�R��o�Ŏ�)�ɂ͔�r�I�ڍׂȋL�q������B����ɂ��A�S��85�������L�т���߂Ă���ŏ�S�̔_���������A���L�ш�܁Z�����J�����A�_�n�Ƃ��ė��p���Ă����Ƃ���A���a4 �N(1929 �N)�ɕl���Y�K���t���ُk������Ƃ������Ƃɂ���āA�呠�Ȃ͍��L�n�̐������咣���A�u�W�_���ɐ��c�ꔽ�O�Z�Z�~�E���n��܁Z�~�E�R�юO�Z�~�ŕ���������ƍ������A�����������ɔ[�����Ȃ���Ί����n����O�҂ɋ�������ƒʍ������v9 �Ƃ������Ƃł���B�����āA���ɍŏ�S��������(���ŏ㒬)�ł́A���̉e�����r��ŁA�ȉ��̂悤�ȏɊׂ����Ƃ����B
�Ƃ�킯�ː�����O�ˁE�l���܌O�l�l�̍ŏ�S��������(���A�ŏ㒬)�ł́A�����������L�n�̍w�����������邽�߂ɔ_�Ƃ̖����������W�Ƃ��ĎO��l�A�ޕw�Ƃ��Ĉ�ܐl�A�|�W�Ƃ��Ĉ��l�A�����Ƃ��ē�Z�l������ꂽ���߁A��������Ⴂ�������p�������Ƃ������ԂɂȂ����B10
�H�c��́A�܂��A�����ȎЉ�ǎЉ�u�|���W�ޕw�����̖{�Вn���ҋƒn�ʐl�����v(���a10 �N2 ��1 ��)����ɗp���āA1935 �N(���a10 �N)�Ƃ����ꎞ�_�݂̂̃f�[�^�ł͂�����̂́A�e���ݏZ�̌|���W�̖{�Вn�ʃf�[�^����A���W�ł͓��k�n���o�g�҂̑S���ɂ�����䗦���������ɍ������A��B�n���o�g�҂̔䗦�����l�ɍ����A�|�W�A�ޕw�A���H�ɂ��ẮA�����������k�n���o�g�҂̔䗦�������킯�ł��Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B�������A�H�c��́u�|���W�ޕw�����̖{�Вn���ҋƒn�ʐl�����v��p���������́A�����܂�1935 �N�Ƃ����A���a���Q�̏����������ꎞ�_�ɏœ_�Ă����̂ł���A���ۂɑ������Ă��邩�ǂ����𑨂������̂ł͂Ȃ��B�������A�H�c��́u�������Ȃ��ꂽ1935 �N�́C���k�n���� 2 �x�ɂ킽��勥��(1931 �N�C34 �N)�����������ɓ��k�_���́w���g����x���Љ��艻���������ł���v11�Ə����Ă���B���Ȃ킿�A�Љ��艻�������䂦�ɒ��������̂����A���ꂪ���n��I�ɂǂ̂悤�ɓ����Ă����̂��͕�����Ȃ��܂܂ł���12�B�����ŁA ���������V���ɔ����������n��f�[�^��p���āA��蒷���I�Ȍ|���W���̕ϓ��𑨂��邱 �ƂŁA�{���ɏ��a���Q���⏺�a�_�Ƌ��Q���ɂ����Ė��̐g����̌����ȑ������������̂� ��������B
|
��3�D �f�[�^�̐���
�\1 ���̐�s�������܂߁A���̐g����Ɍ��y���Ă�����̂́A�ޕw�⏗���A���H�Ȃǂ��܂�ł���ꍇ���������A�{�����ł͏��W�ƌ|�W(�|���W�ƌĂ��)�ɑΏۂ��i���āA���̐g����̑㗝�w�W�Ƃ��Ă���B�Ȃ������ŁA�g����Ƃ́A�|���W�ɂȂ�ɂ������đO�����Ȃ����O�������ĘJ���_������Ԃ��ƂŁA���̘J�������W�܂��͌|�W�ɂȂ邱�Ƃ𖺂̐g����ƌĂԂ��Ƃɂ���13�B
�{�e�̕��͂ł�2 ��ނ̃f�[�^��p����B�܂��A�|���W���ɂ��ẮA��ʓI�ɍL�����p����Ă��Ȃ�2 �̃f�[�^�A�w�x�������v���x�Ɓw�����Ȍx�@���v�x�ɂ��14 15�B�����̓��v���́A�|���W�̐��ׂĂ�����̂ŁA���̐g����̐��ׂĂ��̂ł͂Ȃ����A�����̌|���W���g����̌`�Ō|���W�ɂȂ��Ă���ƍl�����邽��16�A���̐��̕ω��𖺂̐g����̐��Ɛ���ł���B�g����ɉe����^�����Ǝv����o�ώw�W�ɂ��Ă͊e���̓��v���Ɓw����{�隠���v�N�Ӂx�ɂ��B�����ɂ��Ă�4�D���͂̓����ݏZ�̏��W�E�|�W���Ɛ������Ƃ̌o�ϕϐ��̍��Ő�������B
�w�����Ȍx�@���v�x�́A�e���ŏ]�����Ă���|���W�̐��ׂĂ�����̂ł���B����́A�H�c�삪�u�w�x�@���v�x(�e�N�x)�ł́C���{�����̂����̏]���Ґ����L�ڂ���Ă��邪�C�����܂ł����ݐ��ł���C�o�g�n��̒����͂���Ă��Ȃ��v17�ƏЉ�Ă�����̂Ɠ����Ǝv���邪�A���a���Q���A���a���Q�E�_�Ƌ��Q���̕����A�H�c��̂�������w�x�������v���x�̑��݂��w�E���Ă��Ȃ��B�w�x�������v���x�́A�����ݏZ�̌|���W�݂̂������Ă�����̂́A���n��Ɍ|���W�̐���ǂ���V�����ƍl������18�B
�w�x�������v���x�́A�����ŏ]�����Ă���|���W�̐����o�g���ʂɒ��ׂĂ�����̂ŁA�w�����Ȍx�@���v�x�A�w�x�������v���x�ǂ���̃f�[�^���A����33 �N�����ȗߑ�44 ���Ƃ���1900 �N10 ��2 ���ɔ��z���ꂽ�u���W����K��19�v�Ɋ�Â��āA�ݍ��~20���ƂƂ��ɔc������Ă��鐔�����ƍl�����A����������Ɍ����Ă���Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�A�������܂ނƂ������ӏ����̂���u�|���W�ޕw�����̖{�Вn���ҋƒn�ʐl�����v�ƁA�w�x�������v���x�ɂ�����1935 �N(���a10 �N)�̓����ݏZ���k6 ���o�g���W�̐������ׂ�ƁA�O�҂ł�4693 �l�A��҂ł�3865 �l�ƁA828 �l�̍�������A���̍��������̐l���Ɛ����ł��邩��ł���21�B�܂��A�u�|���W�ޕw�����̖{�Вn���ҋƒn�ʐl�����v�Ɓw�����Ȍx�@���v���x�̓��k6 ���ɂ����鏩�W�̐����O�҂̐��������Ȃ��Ă���A��͂肱�̍��������̐l���ł͂Ȃ����Ǝv����B���������āA�w�����Ȍx�@���v�x�A�w�x�������v���x�Ƃ��ɁA�����̐��݈̂����Ă���Ɛ�������邪�A����͖{�e�̕��͂ɑ��đ傫�ȏ�Q�ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B�{�e�͐�ΐ��̐��m�������A�����Ƃ������ۂ��������̂��Ƃǂ����ɏœ_�ĂĂ���̂ŁA������x�S�̂̐��𐄑��\�Ȏ��n��f�[�^�ł���Ύx��͂Ȃ��ƍl������22�B�x�@���v�́A���̌��ɍݏZ�̌|���W���������邪�A�o�g��������Ȃ��̂ŁA���k�̌o�ϓI���������̐g����������炵�����ǂ����͕�����Ȃ��B�o�g��������̂́A�x�����̃f�[�^���A�H�c�삪�p���Ă���1935 �N1 ���_�̃f�[�^�������݂��Ȃ��B
|
��4�D ����
�������ݏZ�̏��W�E�|�W���Ə��a���Q
�O�q�̂悤�ɁA�w�x�������v���x�́A�����ɂ���|���W�ɂ��āA�����ɂ��̐����s���{���ׂ��f�[�^���ڂ��Ă���(�|�W�ɂ��Ă͖{�Гs���{��23�ŁA1929 �N����̃f�[�^ �����Ȃ�)�B����̓X�g�b�N�̓��v�ł��邪�A�p�ƂȂ����͓����ȊO�Ɉړ������҂̐����� �N���肵�Ă���Ƃ���A���̍����́A�V���ɏ��W�Ƃ��Đ������瓌���ɏ��W�Ƃ��ė��� �҂̐��̎w�W�ƂȂ�B�����̐������A�S���̐������\�ł���Ƃ���A���̍����͖��� �g����̑㗝�ϐ��ƂȂ�B���̐��������W�ɂ��Đ����������̂��\2�A�|�W�ɂ��Đ��� �������̂��\3 �ł���B
�@�@�@�\2�@�����ɂ����鏩�W�̐����ʐl��
�@�@�@�\3�@�����ɂ�����|�W�{�Г��{���ʐl��
�\2�̏��W���́A1920�N�őS��5499�l�A�����A�X29�l�ƂȂ��Ă���B����͓����̏��W5499�l�̂����A�����X�̎҂�29�l����Ƃ����Ӗ��ł���B21�N�̑O�N��������ƁA�S��223�l�A�X82�l�ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A���̕\�őS���Ƃ���̂́A�����ɂ�����S������W�܂������ׂĂ̏��W�A�|�W�̐��ł���B�����ɂ́A�p�Ƃ܂��͓����ȊO�Ɉړ��������̂��������A�S�����瓌����223�l�ȏ�A�X����82�l�ȏ�̎҂��W�܂����Ƃ������ƂɂȂ�B�e���̍����͑傫���ϓ����Ă���̂ŁA���k���v�̐������A���k�̍����̓x������\���ƍl���邱�Ƃɂ��悤�B1921�N���炱�̐��������Ă����ƁA1923�N�ɑ傫���������Ă��邱�Ƃ�������B����͓��R�A�֓���k�Ђɂ���ē����ł̏��W�̎��v�������������Ƃ������Ă���̂��낤�B���̂��Ƃ��Ӗ�����̂́A�o�g�n�̍����̓x�����Ƃ��������v���ȊO�ɁA�����̎��v�Ƃ����v�����l����K�v������Ƃ������Ƃł���B�֓���k�Ќ��1924�N�ȍ~�͑傫���������A����x�[�X�ɖ߂����ƍl������B
�����̐����́A�\1�̐�����肸���Ə������B���Ƃ��A���̐g����̑㗝�ϐ��ƍl���Ă��鍷���̐����́A�Ⴆ�A�X����1931�N�̐���������Ə��W20�l�A�|�W19�l�ō��킹��39�l�ł���B����A�\1�̐X���̐��l��641�l�ł���B���̗��R�͈ȉ��̂悤�ɍl������B
��1�ɂ͕\2�A�\3�̐������������̂��̂ł��邱�Ƃł���B���������ɂ��ƁA30�N�̌|�W�E���W�̐��͂��ꂼ��7��6639�l�A4��8839�l�ō��킹��12��5478�l�A40�N�ł͌|�W�E���W�E�ޕw�̐���15��342�l�ł���B���Ȃ킿�A�ޕw�̐����ł���Ƃ���ƁA30�N����37�N�ɂ����Ă̌|�W�E���W�̐���12�|15���l���x�ł������B�������ԂɁA�����̌|�W�E���W�̐��͕\2�A�\3�̐��������v����1.7�|1.9���l���x�ł������B������7�{���S���̌|�W�E���W�̐��ƂȂ낤�B���������āA�Ⴆ�ΐX�����ƁA����7�{���S���ւ̐g����̐��ł��낤�B�������A�\2�ƕ\3�̐X�o�g�̏��W�ƌ|�W�𑫂���39�l��7�{���Ă�273�l�����Ȃ�Ȃ��B����A�\1�̐X�̐g����̐���641�l�ł���B
�������A�V�K�̏��W�܂��͌|�W�̐��͂���ɑ����ƍl���邱�Ƃ̂ł��������̗��R������B�����̏��W�̐���S0�A�����̏��W�̐���S1�A�p�Ǝ҂̐���0.2�~S0�A�V�K�̏��W�̐���N �Ƃ���ƁAS1��S0�{N�|0.2�~S0 �ƂȂ�B�p�Ɨ�0.2 �Ƃ�5 �N�Ŕp�Ƃ���Ƃ������Ƃł���B����͍l�����鐔�l�ł��낤24�B�X��S0 ��300�AS1 ��350 �ɑ������Ƃ���ƁA350��300�{N�|0.2�~300 ����AN��110 �ƂȂ�B���Ȃ킿�A�X�g�b�N�̍����̔{�̐V�K�̏��W�E�|�W�����Ă����������͂Ȃ��B����ƁA273 �l��2 �{����546 �l�ƂȂ�A�X�̐g����̐��ɋ߂Â��B�����āA���ɐG�ꂽ�����Ǝ����̍��ɂ��e�����l������B�\1 �͎������܂�ł��邪�A�\2�A�\3 �͂����炭�܂�ł��Ȃ�25�B���������āA���������v�Z�ƌ����Ǝ����̍����l������A�\2�A�\3 �̍����̐��l�́A�V�K�ɏ��W�E�|�W�ɂȂ���̂̐���\���Ă���ƍl���Ă��ǂ��ł��낤�B
���a���Q���Ɋւ��āA�܂��A�\2 �̏��W�̐������Ă݂悤�B���ɂ����̂ŕ\2 �̏��W�̐��̍������O���t�ɂ������̂��}1 �ł���B
�@�@�@�}1�@�����ɂ����鏩�W�̂������k�o�g�҂̍����̓���
�}1 �ō����̐�������ƁA���a���Q�ȑO��28 �N�ɑ������A���̌�A���a���Q����1930 �N�A31 �N�Ɍ������A���a���Q���I�����32 �N�ɂ͌������Ă���B30 �N�̏��a���Q��2 �N�̃��O��������32 �N�̐g����̑����������炵���ƍl���邱�Ƃ͉\�ł��邪�A31 �N�ł����Q�͑����Ă����̂ł��邩��33 �N�ɖ��̐g���肪�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A33 �N�ɂ͌������Ă���̂ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ͍l���ɂ����B����A31 �N�ɂ͋��삪�N���Ă���̂ŁA���̉e����32�N�Ɍ��ꂽ�Ɖ��߂��邱�Ƃ͉\�ł���B�܂��A33�N�ȍ~�͌������A���k�S �̂ł��A33�N�ɂ�5�l�A34�N�ɂ�92�l�A35�N�ɂ�9�l�A���̌�̓}�C�i�X�ƂȂ��Ă���B ���̐g����͏��a���Q���ɂ͑��������A���a���Q����̉�����A���{�̔ɉh�ƂƂƂ� �ɋ}���Ɍ������Ă����B���Ȃ킿�A���̐g���菺�a���Q���͌��ŁA�_�Ƌ��Q���͐����� �\��������26�B
�H�c��̕��������������邽�߂ɎR�`���̍����̐��l������ƁA���W��29 �N����30 �N�ɂ����đ������Ă���B���L�n��������29 �N����s��ꂽ���Ƃ��l����ƁA�H�c����͐������\��������B�������A���L�n���������ǂꂾ���̋K�͂ōs��ꂽ�̂��ȂǁA����Ɍ�����K�v������B
�������Ƃ�\3 �̌|�W�ł����Ă݂悤�B�\3 �̌|�W�̐��̍������O���t�ɂ������̂��}2 �ł���B������͓����ɂ���|�W�̖{�Гs���{�����������̂ł���B���l�ɍ���������ƁA���k�S�̂ł́A���a���Q����30 �N��6 �l�A31 �N��40 �l�A32 �N��22 �l�A33 �N��89 �l�A34 �N��35 �l�Ƃ킸���Ȑ��ł������B�������A35 �N�ȍ~�A���a���Q���I�������ɑ������Ă���B
�}2�@�����ɂ�����|�W�̂������k�o�g�҂̍����̓���(�o��)�w�x�������v���x-200 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 �X�H�c���R�`�{�镟�����k���v
�ȏ�̊ώ@���番���邱�Ƃ��܂Ƃ߂悤�B���a���Q����E����1932 �N����37 �N�܂ŁA���{�̎�������͔N��4.1���ő������Ă���27�B�������A�_�����ł̉͒x��Ă������A ��f�}3����}8�Ɍ���悤�ɁA�͂��Ă����B���Ȃ킿�A���̐g���肪�K�v�ɂȂ�� �ǂ̍��������{����点���Ƃ������j�̃X�g�[���[�͑S���������Ȃ��B���{�͔ɉh���Ă� ��A���̐g���肪�}�����钆�ŁA���{�͐푈�ɓ˓����Ă��܂����Ɨ������邵���Ȃ��B�� �{�͏��a���Q���炢�������E�p���Ĕɉh���Ă���A���̒���1936�N��2.26�������N���� �̂ł���B
�������ݏZ�̏��W�E�|�W���Ɛ������Ƃ̌o�ϕϐ�
���ɁA�����ɂ��鏩�W�E�|�W���Ɛ����̌o�ϕϐ��̊W�����Ă݂悤�B�o�ϕϐ��͊e�����v���Ɓw����{�隠���v�N�Ӂx�̊e�N�ł𗘗p���Ă���28�B�w����{�隠���v�N�Ӂx�ɂ��ẮA�_�Ɛ��Y�z�݂̂��g�p���Ă���B
�}3 �́A�X���o�g�̏��W�E�|�W��(�\2�A�\3 �̍����̐��l)�Ɓw�X�����v���x�ɂ���āA�X���̐��Y�����z�A�_�Ɛ��Y�z���������̂ł���29�B���Y�����z�A�_�Ɛ��Y�z�Ƃ����ڂ̐����ł���̂ŁA���a���Q�ɂ��f�t���[�V�����̉e���������̂ł���B���v���A�o�ϕϐ��̐����́A�ȉ��̓��k�e���ɋ��ʂ̂��̂ł���B�_�Ɛ��Y�z������ƁA�f�[�^�̂��邷�ׂĂ̌���31 �N�A34 �N�ɗ������݂�����A���̗��N�ɋ��삪���������Ƃ��m�F�ł���30�B
�}3 �Ɍ���悤�ɁA�X���o�g�̏��W�͊֓���k�ЂŌ������A�k�БO�̃��x���ɖ߂�����A�ϓ����J��Ԃ��Ȃ���g�����h�I�Ɍ������Ă���B�m���ɁA���a�_�Ƌ��Q���A���Y�����z�Ɣ_�Ɛ��Y�z���ቺ����31 �N�̗�32 �N�A���W�����������Ă��邪�A���̌�͌X���I�Ɍ������Ă���B�|�W����29 �N���炵���Ȃ����A�o�ϕϐ��̉ƂƂ��ɁA�g�����h�I�ȑ����������Ă���B���a���Q���|�W�����������Ƃ͌�����B
�@�@�@�}3�@�X���̐��Y�z�Ɠs���X���o�g���W���Ȃ�
�}4�͏H�c���ɂ��Č������̂ł���B�H�c���ł͌o�ϕϐ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A���W��1932�N���s�[�N�Ɍ������Ă���B�������A�|�W���ɂ��Ă̓g�����h�I�ȑ�����F�߂邱�Ƃ��ł���B
�@�@�@�}4�@�H�c���̐��Y�z�Ɠs���H�c���o�g���W���Ȃ�
�}5�̊�茧�A�}6�̕������ɂ����Ă��͓����ł���B���W��32�N�ȍ~�A35�N�ɂ�⒵�ˏオ�肪���邪�A�g�����h�I�Ɍ������Ă���B����A�|�W���͌o�ϕϐ��̉ƂƂ��ɐL�тĂ���B����́A���a���Q�ɂ���đ��������Ƃ͌����Ȃ��B
�@�@�@�}5�@��茧�̐��Y�z�Ɠs����茧�o�g���W���Ȃ�
�@�@�@�}6�@�������̐��Y�z�Ɠs���������o�g���W���Ȃ�
�}7�̋{�錧�ł́A�����Ƃ͂��قȂ�A32�N�ɁA����܂ł̃g�����h�𖾂炩�ɏ��鏩�W���̑����������邪�A����ȍ~�A�������Ă���B�|�W���͌o�ϕϐ��̉ƂƂ��ɑ������Ă���B
�@�@�@�}7�@�{�錧�̐��Y�z�Ɠs���{�錧�o�g���W���Ȃ�
�}8�̎R�`���ɂ����Ă��A���W����32�N�ȍ~�A�������Ă���B�o�ϕϐ��͉��Ă��邪�A�|�W���͉����ł���B
�@�@�@�}8�@�R�`���̐��Y�z�Ɠs���R�`���o�g���W���Ȃ�
�ȏ���܂Ƃ߂�B�X���A�H�c���A��茧�A�������A�{�錧�̂�����ɂ����Ă��A���W����32�N�ɑ���������A�傫���������Ă���B�|�W���͉������������͂킸���ɑ������Ă��邪�A����͌o�ωƂƂ��ɋN���Ă���B32�N�̏��W�̑����́A31�N�̔_�Ƌ��Q�ɂ����̂ƌ����邾�낤�B�������A���̌�̏��W�̌����́A���{�����E�勰�Q���炢�����������Ƃ��������Ɛ����I�ł���B�܂��A�|�W�̑����́A���{�o�ς̉ƊW������̂�������Ȃ��B���Ȃ킿�A�|�W�͍����ȃT�[�r�X�Ƃł��邩��A�o�ς����ď��߂ċ��߂���T�[�r�X��������Ȃ��B
�����܂ł̕��͂ɑ��āA�\���ȏ؋��ł͂Ȃ��Ƃ����ᔻ�����邩������Ȃ��B�������A���a���Q���̓��k�ŁA�o�ϓI�������疺�̐g���肪�}�����A���ꂪ�Љ�s���̗v���ƂȂ����A�܂��͂��̏ے��ƌ��Ȃ���؋��͖R�����Ƃ������Ƃł���B���k��S�ʓI�ɂ݂�A���k�o�g�̏��W�͏��a���Q�ȑO����g�����h�I�Ɍ������Ă������A���ꂪ31 �N�̔_�Ƌ��Q��32 �N�ɑ���������A�傫�����������B1930 �N��̓��{�́A���E�勰�Q����ꑁ����������A���E�̒��̔ɉh�̌Ǔ��������B1931 �N�̎���GNP �͉����ł��������A���̌�͏����ɉ��A2.26 �����̋N����1936 �N�̑O�N��35 �N�ɁA����GNP ��1930 �N�ɔ�ׂ�32.3�������債�Ă���31�B�|�W�Y�ƂƂ́A����߂č����ȃT�[�r�X�Y�Ƃł��邩��A�|�W��33 �N�ȍ~���������̂́A���{���ɉh���Ă������炩������Ȃ��B
|
��5�D ���a���Q�ȑO�̖��̐g����̑���
���̐g����̋}������̑��ւȂ��邫�������ɂȂ����Ƃ����A���Ђ����发�⋳�ȏ��ɂ��L�q���A���������K���������m�ȍ����̂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ă����B���������L�q�ɂ͊��ɕ��͂������Ƃ��画�������悤�ȋ^��_�����ł͂Ȃ��A�X�Ȃ���_������B���{�́A���a���Q�ȑO�ɂ����x���̕s���⋥����o�����Ă����B���a���Q�ȑO�A�s���⋥��ɂ���Ė��̐g���肪���������̂��낤���B�܂��A���a���Q�ȑO�̖��̐g����Ə��a���Q�ɖ��̐g����ɈႢ�����邾�낤���B�ȉ��A���̂��Ƃ��l���Ă݂����B
�}9 �́A���a���Q�ȑO�̖��̐g����ɂ��āA�}1 �Ɠ����悤�ɐ������쐬�������̂ł���B����ƕs���ƂɊW�����邾�낤���B
���쐳�O�Y�w���{�̌i�C�z�x32�ɂ��A��O�̕s����(�i�C�̒J)��91 �N10 ���A98 �N11 ���A1901 �N6 ���A09 �N1 ���A14 �N12 ���A21 �N4 ���A30 �N11 ���A1921 �N4 ���Ƃ���Ă���(��������i�C�̒J�̎���)�B�������A�}9 �ɂ����āA01 �N�ɂ́A���k�o�g�̏��W�̐����������Ă��邪�A98 �N�A09 �N�A14 �N�A21 �N�ɑ��������Ƃ����W�͂Ȃ������ł���B�������A�i�C�̒J���̂ł͂Ȃ��A���̑O��̌i�C��؊����d�v�ł���ƍl����ׂ���������Ȃ��B��������Ɠ��I�푈��̕s��(1907 �N)�́A���̐g����ɉe����^�����\��������B�������Ȃ���A���W���̋}���ȑ����́A06 �N�ɂ��łɎn�܂��Ă���A���O���l������A����ɈȑO����̏o�����ɂ��e�����ƍl�����A�s���́A���̎���ɂ����Ă��A��͂蒼�ړI�Ȍ������̂��̂Ƃ͍l���ɂ����B
�@�@�@�}9�@�����ɂ����鏩�W�̂������k�o�g�҂̍����̓���
�܂��A���̐}�ƑO�f�}1����A���k���瓌���ւ̏��W�̋������������Ƃ����������̂́A���a���Q���ł͂Ȃ��āA1906�N����09�N�ɂ����Ă̊��Ԃł������Ƃ������Ƃ�������B�}9�̍����̓����������(�t�\1����v�Z�ł���)�A���Ƃ��A�ł������̌������R�`���ł́A1905�N��40�l����06�N�ɂ�198�l�A07�N183�l�A08�N128�l�Ƒ������Ă���B����A���a���Q�ł́A30�N101�l�A31�N83�l�̌�A32�N�ɂ�138�l�Ƒ������邪�A33�N�ɂ́|15�l�ƂȂ�B���a���Q�������A1906�N����09�N�̊��Ԃ��������ƌĂԂɑ��������B
��ɑ吳���ɔp���^�����s���Ă����R���R���͂��̏����삪�����ƌ��Ă���A�u�\�N�O(1904�N�̂��Ƃł���|�M��)�̓��k����ȗ��A�{��A�����A���̑��̒n������A�㋞���ď��W�ƂȂ�҂̐����}�ɐB�����̂́A�߂��ނׂ����ۂł���v33�Ə����Ă���B�����āA����ɑ����āA����35�N(1902�N)�A40�N(1907�N)�A�吳���N(1912�N)�̓��k�o�g�̓����ݏZ�|���W�����ڂ��Ă���34�B�܂��A���̐g����̐����̓����ƎR���̂�������Ƃ͎���������Ă��邪�A��������������Ƃ��Đg���肪�����A���ꂪ���������Ƃ����\���͏\���ɍl������B
����ɁA�C�M���X�̐V�����A���̎����̓��k�y�іk�C���ɂ�����Q�[�ɂ��āA�u�k�C���y�ѓ��k�̋Q�[�́A�ꔪ�Z��N�ȗ��̑�S���ɂ��āA�_���͋Q���ɋ����Ȏq�����ė]���A���͂�����ƂȂ��B���̑��ނׂ����������ƂƂ��Č��F���鍑�́A���Ȃ킿�䂪��p�鍑�̓������Ȃ�B���m���������Ēm������{���Ȃ�v35�Ɠ`���Ă���Ə����Ă���B
�������A�C�M���X�ɔᔻ����Ă����ɂ�������炸�A���̂��Ƃ͓��{�ɂ����đ傫�Ȗ��Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B����A���a���Q�Ə��a�_�Ƌ��Q�̉e���Ŗ��̐g���肪���������Ƃ����b�́A�f�[�^����͂܂��������t�����Ȃ������j�̋��ȏ��ɂ��f�ڂ���Ă���B�x�����̓��v�́A�����̊w�҂�W���[�i���X�g���m���Ă����͂��̓��v�ł���B
�R���ɂ��A���k����̏��W�����������̂�1904 �N�ȍ~�ł���B�������̃f�[�^���A�����͂��قȂ邪�A����𗠕t���Ă���B����ƁA1900 �N��̏����ɖ��ɂȂ�Ȃ��������Ƃ��A�Ȃ�1930 �N��ɖ��ɂȂ�悤�ɂȂ����̂��낤���B����́A���{�ߑ�j�̗��j�Ƃ��A���a���Q�Ə��a�_�Ƌ��Q�ɂ���āA���ɓ��k�n�����������A���ꂪ�����̕s���艻�������A���ɂ͐푈�ɂ܂łȂ������Ƃ����X�g�[���[�����߂Ă�������ł��낤�B�������A���̂悤�Ȏ����͂Ȃ������B�n��������ɖ��̐g����Ƃ����ߎS�Ȏ������������͎̂����ł��邪�A���ꂪ���a���Q���ɑ��債�Ă����Ƃ����؋��͂Ȃ��B�ނ���A1900 �N����30 �N�����ĖL���ɂȂ������{�l(��l���������GNP �͂��̊��Ԃ�52.4������36) ���A���̂悤�ȔߎS�Ȏ����ɋ��������Ƃ����̂������ł͂Ȃ����낤���B
�������A�g���肳�ꂽ�������������ȊO�̓��{���ɔ���ꂽ�Ƃ����\�����l������B�������A������ɂ��Ă��f�[�^�̕\�������́A�����ǂ��납�A�ނ���͂�����ƌ������Ă���X����������B�\5 �ƕ\6 �́A���{�S���̏��W�A�|�W�����݂����̂ł���(�\�̓s���{���͏o�g���ł͂Ȃ��āA�����ɍݏZ�̏��W�A�|�W�̐��ł���)�B�\5 �͏��W�A�\6 �͌|�W�ł���B�����Ŋ��Ԃ�24 �N����37 �N�Ƃ����̂́A���̓��v�̊J�n��24 �N�ł��邱�ƁA�܂��A�I���N��37 �N�Ƃ����̂́A37 �N�܂ł����Ȃ��x�������v�ɍ��킹������ł���B
����ɂ�铌�k�̔_�Ƌ��Q���ł����������Ƃ�����1934 �N�́A�S���ɂ����鏩�W�̐����A1924 �N����37 �N�̊ԂōŒ�̔N�ɂȂ��Ă���(45,705 �l)�B�܂��A���̌㐔�N�̏��W���̑������A�S���ł�������1000�`2000 �l�̑����ł���A���̊��Ԃ���͂范�������Ƃ͂����Ȃ��B���������āA�����ȊO�̑����{���ɓ��k���炻��܂łɌ����Ȃ��悤�ȑ�ʂ̏��W������ꂽ�Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ��B�����āA���k�ݏZ�̏��W�̐���1925 �N���s�[�N�ɁA����ȍ~�͖��炩�ȉ��~�g�����h�������Ă���B���������f�[�^����g����ɂ���ē��k����̑�ʂ̏��W�����a���Q���ɐ��ݏo���ꂽ�Ƃ͌����Ȃ��Ɣ��f�ł���B
���ɂ��A1935 �N��1���_�����ł��邪�A�ǂ̓s���{���ɂǂ̓s���{���o�g�̏��W�����l�����������������ȎЉ�ǎЉ�u�|���W�ޕw�����̖{�Вn���ҋƒl�ʐl�����v(���a10 �N2 ��1 ��)�ɂ����Ă������ɔ䌨����قǑ����̏��W�������ȊO�ɓ��k���狟������Ă���Ƃ������Ƃ͂Ȃ�37�B���Ƃ��A���́u�|���W�ޕw�����̖{�Вn���ҋƒl�ʐl�����v�ł́A�����ɂ����鏩�W��(�������܂ނƂ����)��9250 �l�A���ɂ����鏩�W����8444�l�ƁA���ɂ������Ɏ����ő����̏��W�����݂������Ƃ������邪�A���ҋƏ��W�̓��k�o�g�Ґ��́A�X52�l�A�H�c198�l�A���15�l�A����29�l�A�{��23�l�A�R�`60�l�� ����A�H�c�͂�⑽�����A�����ҋƏ��W�̓��k�o�g�Ґ�(�X615�l�A�H�c1051�l�A���144�l�A����760�l�A�{��637�l�A�R�`1486�l)��S���ő傫��������Ă���A��͂蓌 �������k����̏��W�̋�����ł��邱�Ƃ����炩�ł���B���̎��ɑS�̐����������s���A ���k�o�g�Ґ��͂�������2���ł���B���⋞�s�ɂ����鏩�W�̎�ȋ����n�͋�B�n���� ����A������l������ƁA�S���ɂ����鏩�W�y�o���͓��k���肪�ˏo���Ă���킯�ł� �Ȃ���B������38�B����͉H�c��́u�Ȍ�����v�����Ɏw�E���Ă���39�B�����ɑ��� �ē��k�o�g���W���������̂́A���m��_�ސ�ł���B���m�́A�X243�l�A�H�c303�l�A ���40�l�A����137�l�A�{��131�l�A�R�`142�l�ƁA���k�o�g���W���������Ɏ����ő� ���B�������A���̐��́A�����̐�����1����10����1���x�ł���A��͂蓌�����ˏo���� ����B
�܂��A�S�̓I�ȌX���͕t�\3 ������Ε����邪�A���m�͓����s�Ɠ����悤�Ɋɂ₩�ȑ����X���ɂ��邪�A���ɕ��͂��Ă���悤�ɁA�����ł��猃�����Ă���Ƃ͂����Ȃ����߁A��͂肱�̊Ԃɓ��k�o�g�҂��������Ă���Ƃ͍l����B�_�ސ�́A��������1920 �N�ォ��S�̂̏��W���������X���ɂ���A���̊Ԃɓ��k�o�g�҂����������Ƃ͍X�ɍl����B
�@�@�@�\4�@�S���ɂ����鏩�W��(�S�N��)�A�o�g���ł͂Ȃ��āA���̌��ɍݏZ�̏��W��
�@�@�@�\5�@�|�W��(�S�N��)�A�o�g���ł͂Ȃ��āA���̌��ɍݏZ�̌|�W��
|
��6�D���W�����s���{���̐���
�����ȗ��̏��W�̋����s���{�����ǂ̂悤�ɐ��ڂ������́A���q�̌x�������v���ɂ���āA�����ւ̋����s���{�������ł��邪���炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���B�}10�A�}11�͓����̏��W�̐����s���{�����Ƃ̐l��(�X�g�b�N)���������̂ł���B
�}10�Ɍ���悤�ɁA�����ɂ����鏩�W����5000�l����8000�l�ł��邪(1891�N�A92�N�̏��W�������Ȃ��̂͏\���ɑΏۂ𑨂��邱�Ƃ��ł��Ȃ������䂦�ł���Ǝv����B1923�N�̗������݂͑O�q�̂悤�Ɋ֓���k�Ђɂ����̂ł���)�A�����̏��W��3����1���������܂�ł��邪�A���X�ɒቺ����B���s�͂���ɐ旧���Ēቺ���Ă���B1890�N�ォ��O�d�A�V���������Ȃ邪�A�����1910�N�ȍ~�ቺ����B
�@�@�@�}10�@�����ɂ����鏩�W(18�Έȏ�)�����ʐl��(1891�`1937�N)
�}11�ŁA���m�A�͓����Ƃقړ������������Ă���B�R�`�A�����A�{��A�H�c��1907�N�O�ォ��A1920�N�O�ォ��͖k�C���A�X���傫���L�тĂ���B���͂���قǑ傫���͐L�тĂ��Ȃ��B����͓����A���s�A�O�d�A���m�A�������Ɍo�ϔ��W���A���W����������n�������甲���o���Ƃ������Ƃ������Ă���̂��낤�B�V���������̌��ɂ͒x�ꂽ�����W���A�Ō�ɓ��k�Ɩk�C�����o�ϔ��W������c����Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B���k�S�̂̓�����20�N��ɑ������Ă��邪�A30�N��ɂȂ��ē��ł��ƂȂ�A�㔼�������Ă���B
�}10�A�}11���痝������邱�Ƃ́A���a���Q�ȑO�ɂ����W�̋������������������������Ƃ������Ƃł���B�����́A1890�N�㖖�̎O�d���A1890�N�㖖����1900�N�㏉�̐V�����A1900�N�㏉�̎R�`���A1920�N�㏉����̎R�`�A�H�c�A�����A�k�C���A�{��A�X�̓��k�E�k�C���ł���B�������A���̐g����Ƃ������ۂ��r���𗁂т��̂�1930�N�ゾ���ł���B����́A�L���ɂȂ������{�l�����̔ߎS�ɖڂ�������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@�@�@�}11�@�����ɂ����鏩�W(18�Έȏ�)�����ʐl��(1891�`1937�N)
|
��7�D ���_
�������͖{�e�ɂ����āA���a���Q���ɖ��̐g���肪���ۂɌ��������̂��A���ɂ����̂ł���A�ǂ̎����Ɍ��������̂����A�w�x�������v���x����쐬�������n��f�[�^��p���Č��������B���̌��ʁA����⋳�ȏ����x�����邱�Ƃ͂ł����A���a���Q���ɖ��̐g���肪�傫���������Ă��Ȃ������A�ނ���32�N���s�[�N�Ɍ������Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�������A���a�_�Ƌ��Q���ɖ��̐g���肪�����Ă����̂͂����炭�m���ł���B�܂��A���a���Q���ɓ��k�̈ꕔ�Ŗ��̐g���肪�����Ă����Ƃ�����A����͕l�����t�̊��L�n�������ɂ��\�������邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���������āA���̐g����̌����Ȃǂ����ۂɋN����A���̂悤�Ȃ��Ƃ����������k�_���̍������A��̑��ɓ������Ƃ����悤�ȗ��j�̃V�i���I�������ɖR�������Ƃ����炩�ɂȂ����B����͓V��ɂ����̂ł��邩��A��������{��`�̖����Ƃ����ɂ͖���������B����̑�́A�s�s�̐Ŏ���p���Ĉꎞ�I�ɕn���n����~�ς��邱�Ƃł����Ȃ��B
����A1906�N����7�N�ȍ~�A���k�Ŗ��̐g���肪�������Ă������Ƃ����������B�ɂ�������炸�A����ɂ͂܂������G����邱�ƂȂ��A�����̂Ȃ����̐g����̌������Ɠ��k�̍����Ɛ푈�Ƃ����ѕt����̂͊�ł���B�������̗p�����f�[�^�ɂ͐����邪�A���������A���a���Q���ɖ��̐g���肪���������Ƃ����؋��͂܂��������݂��Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ɂł����B
|
����
1�@�������p�w���a���Q�ƌo�ϐ���x�u�k�Њw�p���ɁA1994�A115�ŁB
2�@�����w���a���Q�ƌo�ϐ���x116�ŁB
3�@�w�ڐ����{�j �����Łx�R��o�ŎЁA2007�N�A320�ŁB���ɎQ�Ƃ������ȏ��́w�V���{�j�a�x�ˌ����X�A2004�N�A�w���{�j�a�x�������Њ�����ЁA2004�N�A�w���{�j�a �V���Łx�����o�Ŋ�����ЁA2008�N�A�w���{�j�a �����Łx�O�ȓ��A2008�N�A�w�V���{�j�x�R��o�ŎЁA2014�N�ł���B
4�@�����̐����̂����X���͕w���q�g����Ƃ���Ă��邪�A�H�c���͗������q�A��茧�͌|���W�ޕw�����̋���(�͏o)�l���A�R�`���͌|�W���W�ޕw�Љ�l���ƂȂ��Ă���B�������q�͌|���W�ޕw�����Ƃ��ė������A�܂��A�Љ��Č|�W���W�ޕw�ɂȂ�ɂ������Ă��O���������Ɛ��@����A�����͖��̐g����Ɖ��߂ł���B�|���W�ޕw�����̋���(�͏o)���g����Ɖ��߂ł��邩�͕s���Ȃ̂ŁA����ɂ��Ă͂���ɒ������ł���B�ˋ����������́A�X���_�n���v�j�Ҏ[�ψ���ҁw�X���_�n���v�j�x1952�N�A212��(1935�N��1�|5���̂�)�A�H�c���́A�c������Y�w�H�c���̕S�N�x�R��o�ŎЁA1983�N�A192�ŁA�R�`���Ɗ�茧�ɂ��ẮA��{��O�w���Q���̓��k�_�� �㊪�x�s��o�ŁA1984�N�A93�łł���B
5�@�w���E��S�Ȏ��T ��2 �Łx���}�ЁA1998 �N�B
6�@����i���ҁw����(�����o�ϓ��v8)�x��10 �\ �_�Y�����������N�w���A��15 �\ �H�Ɛ��i���v�A���m�o�ϐV��ЁA1966 �N�A���m�o�ϐV��ЁA1967 �N�A�ɂ��v�Z����ƁA1929 �N�̔_�Y�����i/�H�Ɛ��i���i�w��(1934-36 �N����=100)��29 �N95.6 ��30 �N��77.8 �ɒቺ���邪�A���̌㏙�X�ɉ���1935 �N��102.3 �ƂȂ�29 �N��������B
7�@�H�c��c�q�u�Ȋw������⏕���������ʕ��v2009 �N(����21 �N5 ��15 ������)�B
8�@�H�c��u�Ȍ�����v5 �ŁB
9�@��{�R�P�w�R�`���̕S�N�x�R��o�ŎЁA1985 �N�A182 �ŁB
10�@��{�w�R�`���̕S�N�x182-183 �ŁB
11�@�H�c��u�Ȍ�����v3 �ŁB
12�@�����V���E�ǔ��V���̓d�q�ł�1929-37 �N�ɂ��āu�g����v���L�[���[�h�ɂ��ċL������������ƁA29-33 �N�͂قƂ�nj�������Ȃ��̂ɑ��āA34 �N�A35 �N��10 ���ȏ�q�b�g����B
13�@�����ނ����W�ɍi���Đg������`���Ă���̂��ʗ�ł���B�u1 �g�̑���ƈ��������ɁA�̈����Ԃ��߂邱�ƁB�����A�V���E���W(���傤��)�ɂ����B�v(�w�厫��x���w�فA1998 �N)
14�@�x�����ҁw�x�������v�� �S50 ���x�N���X�o�ŁA1999 �N�`�B
15�@�����Ȍx�ۋǁw�����Ȍx�@���v�� �S18 ���x���{�}���Z���^�[�A1993 �N�`�B
16�@�����E�ƏЉ���ǁu�|���W�ޕw�Љ�ƂɊւ��钲��(�吳15 �N)(1926 �N)�v(�J�쌒��w�ߑ㖯�O�̋L�^3�x�V�l�������ЁA1971 �N�A373-438 ��)�ɂ��A�F��V�s�̏��W1602�l��Ώۂɂ����u���W�ƂȂ�錴���v�̒����ł́A�u�n���Ȃ�ƌv�⏕�̂��߁v��42.39���A�u�O�؋��������ɉƌv�⏕�̂��߁v��54.43���A�u���Ȑ��v����̂��߁v��3.18���ƁA�����̌�����100���ƂȂ��Ă��� �B����͂����܂ŏF��V�s�ł̒����ł���A�u�����I�����ɉ߂�����̂ł��邪�A�V�𐄂��S�̂�m��v(�J��ҁw�ߑ㖯�O�̋L�^3�x411 ��)���Ƃ��ł��A�|���W������т��̐��̕ω��𖺂̐g����̑�֎w�W�Ƃ��čl���邱�Ƃ͑Ó����Ǝv����B���Ȃ݂ɁA�|�W213 �l��Ώۂɂ��������ł́A����痝�R�ɉ����āA�u���Ȋ�]�Ɉ˂�v��16.43������B
17�@�H�c��u�Ȍ�����v3 �ŁB
18�@�����܂ł��Ȃ����A�s���{���S���̌x�@�̂����A�����S���̌x�@���x�����Ƃ����B
19�@�u�攪�� ���W�҂͊����̋�������ݍ��~���ɔ�ΔV���ׂ����Ƃ��v
20�@�ݍ��~�u�s�����Ȍ�A����(�������傤)���W�O(���낤)�̍��~����ĉc�Ƃ����Ƃ��납��t�V�����B���Y���B�v(�w�厫��x���w�فA1998 �N)�B
21�@�u�|���W�ޕw�����̖{�Вn���ҋƒn�ʐl�����v�ɂ����铌�k6 ���o�g���W�̓���́A�X615 �l�A�H�c1051 �l�A���144 �l�A�R�`1486 �l�A�{��637 �l�A����760 �l�ł���(�w�����t��莑���W���\��O�� (��22 ��)�x�s��o�ŁA2003 �N�A217-227 ��)�B�w�x�������v���x�ɂ��������́A�X508 �l�A�H�c952 �l�A���128 �l�A�R�`944 �l�A�{��636 �l�A����697 �l�ł���B���ق̑������R�`���o�g�҂Ő����\�ł���A�R�`���o�g�҂Ɏ������������݂����Ɛ��������B
22�@�����āA�}�[�N�E�����U�C���[�́A�u�����͔N����������B�c20 ��㔼��30 ��O���̏����ɐ�߂銄���́A�����Z�N�^�[�̕����F�Z�N�^�[�������������v�Ǝw�E���Ă���(�u�|���W�_��\���Y�Ƃɂ�����u�M������R�~�b�g�����g�v�|�v(�]��T�v��)�w�k��@�w�_�W�x44 ����3 ���A1993 �N�A634 ��)�B�����̔N�������A�g����ł͂Ȃ��\���������B
23�@�����s���{���Ɩ{�Гs���{���̈Ⴂ�͖{���v���ɐ�������Ă��Ȃ����A�������̂Ǝv����B
24�@�����U�C���[�́u�����͈�ʓI��6 �N�Ԃ̌|���W�_��œo�^���A�c���w�̑�����3 �N����4 �N�Ŏ؋������ς��A�����p�Ƃ����̂ł���B�v�Ə����Ă���(�u�|���W�_��v607 ��)�B
25�@�������A�\1 �̎R�`�̐l���͖��炩�ɏ��ȉ߂���Ǝv����B
26 �Ȃ��A1933 �N3 ��3 ���ɎO����n�k�Ƒ�Ôg���������Ă���A���ꂪ���̐g����ɂȂ������\�����l������B���̔�Q�͊��(����1316 �l�A�s���s����1397 �l)�A�{��(170 �l�A138 �l)�A�X(23 �l�A7 �l)�ő傫������(���ҁA�s���s���҂́w��茧���a�k�Ў��x1934 �N10 ���A�ɂ��B���p�́A�R�����j�u�Ôg�ɂ�����u�����g�̋��|�v�]���a�O���Ôg�̎��Ґ��ƍs���s���Ґ��̔䗦�̈Ӗ�������́]�v�w���j�n�k�x��18 ���A2002 �N�A183-187 ��)�B�������A��Q�̑傫�����������3 ���ŁA33 �N����ї�34 �N�ɖ��̐g���肪���ɑ������Ƃ������ۂ͌����Ȃ�(�{�e�}3�C5�C7�Q��)�B
27�@����GNP �ł͐푈�o�ς̂��߂ɌR����Ŗc���ł���̂ŁA�����������l���邽�߂ɂ͎�������Ō���ׂ��ł���B����GNP ��40 �N�܂ő����𑱂��邪�A���������37 �N���s�[�N�ł���B����i�E�����M���E�R�{�L���w�����o�ϓ��v1 ���������x��18 �\�A���m�o�ρA1974 �N�B
28�@�X�����v�ہw�X�����v���x�A�H�c���w�H�c�����v���x�A��茧�w��茧���v���x�A�������m�����[�A�������������w���������v���x�A�{�錧�m�����[���v�ہA�{�錧���������v�ہw�{�錧���v���x�A�R�`�������������ەҁw�R�`�����v���x�A���t���v�Ǖҁw����{�隠���v�N�Ӂx�������v����B
29�@�X���ƕ������ɂ��ẮA�����̓��v�����w����{�隠���v�N�Ӂx��蒷���̔_�Ɛ��Y�z�̌n����f�ڂ��Ă���̂ŁA�w����{�隠���v�N�Ӂx���g�p���Ă��Ȃ��B
30�@�Ȃ��A�\���i�̉��������k�ɂ����Ă͉e�����傫�������̂ł͂Ȃ����Ƃ��l�����邪�A��{�I�ɁA�����i�͔_�Ɛ��Y�z�Ƃ̑��ւ������A�_�Ɛ��Y�z�ő�\����Ă���Ǝv����B
31�@����i���ҁw��������(�����o�ϓ��v1)�x��18 �\�A���m�o�ϐV��ЁA1974 �N�A���v�Z�B���̎����̎���GNP �͉ߑ各�v�ł͂Ȃ����Ƃ����c�_�����邪�A������l�����Ă�3 �����x���債�Ă����悤�ł���(���c�ׁE��������w���a���Q�Ƌ��Z����x��5 �́A���{�]�_�ЁA2012 �N�A�Q��)�B
32�@���쐳�O�Y�w���{�̌i�C�z�x�������[�A1965 �N�A35 �ŁA��2-4 �\�B
33�@�R���R���w�Љ�f���_�x�������_�ЁA1977�A66�ŁB
34�@�x�������c�����Ă��鐔���ł��낤�Ƒz���ł��邪�A�}9�̏o���ł���x�����̃f�[�^�Ƃ͈�_�����ꗂ�����B����35�N(1902�N)�R�`�̐l�����w�x�������v���x�ł�98�l�ƂȂ��Ă��邪�A�R�����ł�58�l�ƂȂ��Ă���B���͑S�Ĉ�v����̂ŒP���ȊԈႢ�ł��낤�B
35�@�R���w�Љ�f���_�x66-67 �ŁB
36�@����i���ҁw��������(�����o�ϓ��v1)�x��32 �\�A���m�o�ϐV��ЁA1974 �N�A���v�Z�B
37�@�w�����t��莑���W���\��O�� (��22 ��)�x222-223 �ŁB
38�@���Ƃ��A�F�{�o�g�̏��W���́A���974 �l�A���s438 �l�ƁA���Ȃ�̐��ɏ��A���k�o�g�҂����|�I�ɏ����Ă���B
39�@�H�c��u�Ȍ����v3-4 �ŁB �@ |
 �@ �@
�����E�s�ꋰ�Q�j�_�@�T�� |
   �@
�@
|
|
������
|
|
���ċ{��҈ꋳ���͋��Q�j�̕��@�����Ƃ��āu���Q�j�ɂ��A���o�ϊw���̕���ɑ����ׂ��@���I���Q�j�ƁA�ŗL�́��o�ώj���̕���ɑ����ׂ������I���Q�j�Ƃ̓�킪����A���҂̌����͂��������Đi�߂���ׂ��͓��R�ł��邪�A�c�c�o�ϊw�̑̌n�ɂ����āA�����Q�_���̌����͕��@�̑Η����܂߂Ė����ɍ��������߂Ă��镪��ł��邩��A���@���I���Q�j�����Ȃ킿�����Q�_���̌������A���Q�j�����ɂ��Ӌ`�́A���������ł���v(1) �Ƙ_����ꂽ���A�ȉ��̏��_�́��@���I���Q�j���Ɍ����������₩�ȑ����A�����ǂ���̎��_�ł���B�c�K��= �o���m�t�X�L�|�̕���Łw�C�M���X�ɂ�����Y�Ƌ��Q�x���w�p�����Q�j�_�x�Ɩ�o���ꂽ�̂͌��{�����̑쌩(2) �ł��邪�A���@���I���Q�j���Ƃ́u���E�s�ꋰ�Q�j�_�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�\����u���E�s�ꋰ�Q�j�_�T���v�Ɩ��Â������Ȃł���B
|
(1)�@�{��҈ꢋ��Q�j���@�-ģ��s���d�l�ďC�w�V���������o�ϊw�����߂āx��2�W��������[�1968�N�47��-�ޡ
(2)�@���{�� �w�p�����Q�j�_�x����{�]�_�Ф1931�N�
|
|
���T ���E�s��Ƌ��Q�E�Y�Əz�̐��� |
��1. ���{��`���E�s��̐���
������܂��܂��o�ς̍��ۉ���{�|�_�|���X�����邢�̓O���|�o���Y�������܂т���������Ă��邱�Ƃ́A�V����G������˂��������Ŗ��炩�ł���A����̗��s��̊����炨�ڂ���Ƃ���ł��낤�B�������A���{��`�ɂƂ��āA�ЂƂ܂��e�������ƂƂ��āu���ƌ`�Ԃł̑����v���o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͂����A���ې��͂����������̗��j�I�����ȗ��̕K�{�����ł��������Ƃ����A�͂����ĈӊO�ł��낤���H���{��`�Ɛ��E�o�ς͓������_���̗��ʂł���16���I�ȗ��u���{��`���E�o�ρv�́u��̗��j�I�V�X�e���v�Ƃ��đ��݂��Ă����Ƃ��ċߔN���ڂ����A�����J�̎Љ�w�҂h�D�E�H�|���|�X�e�C���̎咣���A���̈�ł���B���̎咣�́A���{��`�͂��́u�S�̐��v�ɂ����Ă͐��E�s��Ƃ��ď��߂đ��݂�����Ƃ����}���N�X�̔F���ɑ��ʂ�����̂Ƃ����Ă悢�B�܂��ɐ��E�s��́A�ߑ㎑�{��`�ɂƂ��āu�S�̂̑O����Ȃ��A���̒S������Ȃ��v�iGrundrisse.,S.139.���؊Ė�w�o�ϊw�ᔻ�v�j�x�T��匎���X1959�N�146��-�ށj�̂ł���A�u���E�s�ꂱ���͈�ʂɎ��{��`�I���Y�l���̊�b���Ȃ����̐��������Ȃ��Ă���v(Das Kapital �V,MEW Bd.25,S.589 )�̂ł���B
�͂邩��q�C����A�A�����J�嗤�̔����Ƃ���ɑ����A���́A�}�j���t�@�N�`�@����𑣐i�����E�s��`���̋N�_���Ȃ��Ă���B���̌�17���I�̎s���v����ʂ���y�n�v����18���I�Y�Ɗv���Ƃ��o��1820�N��Ɋm�������C�M���X�ȍH�Ƃ���Ƃ���Y�Ǝ��{��`�́A�A�����J��C���h�̈����Ȍ����ljԋ����Ɉˑ�����Ɠ����ɁA�܂����̖Ȑ��i�����Ԃ�i�Ƃ��ăC�M���X�֗�������^�o�R�E���E�R�|�q�|�E���h�����ƂƂ��ɐ��E���i�Ƃ��Ă̐��i�����тĂ����Ƃ����Ӗ��ɂ����āA���߂��琢�E�s��I�A�ւ̂��Ƃɂ�����Ă����B���̖ȍH�Ƃɑ�\�����@�B����H�Ƃ́u�g��\�͂͂��������Ɣ̔��s��ɂ������̐������݂������Ȃ��v���߁A�u�V���ȍ��ە��Ƃ����肾����v�A�n���̈ꕔ���i���|���b�p�A���ɃC�M���X�j���u�H�Ƃ���Ƃ��鐶�Y��ʁv�Ƃ����̕����i���C���h�E�I�|�X�g�����A���X�j���u�_�Ƃ���Ƃ����ʁv�ɕς��Ă��܂����̑��݈ˑ��������߂�B�Ƃ�킯�u���E�̍H��v�Ƃ��ẴC�M���X�́A�u���E�̊C�^�Ǝҁv�ł�����A�܂������ɃC���O�����h��s�_�Ƃ��郍���h�����Z�s��ɂ����Đ��E���i�̗��ʂɂƂ��Ȃ��ݕ��E�M�p�W�������鍑�ۋ��{�ʐ��̂��ƂŏW�闧��ɂ��������Ƃɂ����ē��M�����B
|
��2. ���Q�E�Y�Əz�̎n���Ƃ��̈Ӌ`
�����������E�s��̌`���E�m���ƂƂ��ɁA�ЂƂ܂��Y�Ǝ��{�̍����I�Ґ��̎w�W�Ƃ���1825�N�C�M���X�ɍŏ��̎��{��`�I�����I�ߏ萶�Y���Q���u�������̂��A�t�����X�E�h�C�c�E�A�����J�ȂǑ��������������Ƃ̎��{��`���W�ɂƂ��Ȃ����E�s�ꋰ�Q���s���ƂȂ��Ă����̂ł���B���j��̓I�ɂ́A1857�N�ɃA�����J�E�t�����X�E�C�M���X���قړ����ɏP�������Q�����̍ŏ��̂��̂ł������B�����̋��Q�̌o�܂𒍎��������Ă����}���N�X��1870�N�㒆���ɂ����Ď��̂悤�ɁA���̊Ԃ̎�����Ȍ��ɋL���Ă���B�u�@�B���H�Ƃ��[���������낵�č����̑S���Y�ɗD���ȉe�����y�ڂ��悤�ɂȂ����Ƃ��A�@�B���H�Ƃ̂������ŊO���f�Ղ��������Ƃ�ǂ��z���n�߂��Ƃ��A���E�s�ꂪ�V���E�k�A�����J�l��A�W�A��I�[�X�g�����A�ōL��Ȓn������X�ƕ��������Ƃ��A�Ō�ɁA�����ɉ����H�ƍ��̐����\���ɑ����Ȃ����Ƃ��A���̎��ȗ����߂āA���̐₦���Đ��Y�����z�͎n�܂����̂ł���B���̏z�̌p�N�I�ȏ��ǖʂ͐��N�Ԃɋy�сA����͂�����ʓI���Q�ɁA��̏z�̏I�_�ł�����܂��V���ȏz�̎n�_�ł������ʓI���Q�ɋA������̂ł���B����܂ł̂Ƃ��낱�̏z�̎����̒�����10�N��11�N�ł��邪�A���������̔N����s�ςƂ݂Ȃ��ׂ����R�͂܂������Ȃ��v�iDas Kapital,Bd.�T,MEW Bd.23b,S.662 �j�B
�����ɂ́A�ߑ㎑�{��`�̐����Ƌ��Q�E�Y�Əz�̊J�n�Ƃ̕s�������w�E����Ă���̂ł��邪�A���炩����19���I�����ȗ��̌i�C��ނ̔N��\�i�N���m���W�|�j�����Ɍf���������Łi�\1.�Q�� �j�A���̎w�E�̊܂ޏd�v�����Ċm�F���Ă��������B�܂���P�ɁA��ʓI�Ȏ����I���Q�̓C�M���X�Y�Ɗv���������ȍ~�̋K���I�Ȍ��ۂł����āA����ȑO�̕����I�ŕs�K���I�Ȍo�ϝ�����p�j�b�N�Ƃ͈قȂ邱�Ƃł���B�z�ꐧ�Љ�╕�����Љ�ɂ����鋥��E�u�a�E�푈���ɂ��k���Đ��Y�͂������̂��ƁA���i���ʂ̈��̔��W�̂��Ƃɂ�����A���@�I����ɂ��1634-7�N�̃I�����_�u�`���|���b�v���Q�v�⊔�����@�ɂ��1720�N�́u��C�̖A���v�A�V�N�푈�̉e���ɂ��1763�N�̖k���|���b�p�M�p���Q�A����ɑ嗤�����ƌ��т���1810�N�̃C�M���X�̋��Q�Ȃǂ͑����ɐl�דI���邢�͋��R�I�Ȍ��ʂł������B�����A1825�N���Q�ȗ��A���Q�E�Y�Əz�͋@�B���H�Ƃɗ��r����Y�Ǝ��{��`�̐��Y�͂̋}���Ȕ��W�Ɛ��Y����я���̖җ�ȑ���Ƃ��A�s��I�ɔ����Ƃ���̎����I�Ȍ��������k�ƍĐ��Y�̊h���Ƃ����Đ��Y�ߒ��ɍ����������{��`�V�X�e���̕K�R�I�Ȍ��ʂƂȂ����̂ł���B
��2�ɁA���E�s��̐����Ƌ��Q�E�Y�Əz�̎n���Ƃ̕s�����ł���B19���I�O���̋��Q�́A��Ƃ��ăC�M���X��Ƃ���ꍑ�I�Ȃ��̂ł������B1825�N�̋��Q�͖k�h�C�c�A�I�����_�����ăA�����J�ɉe�����y�ڂ����Ƃ͂����A�C�M���X�ɔ������̏����ɔg�y�������̂ł����āA����1836�N���Q��L�͂ȍ��ۓI�g�y������1847�N���Q�ɂ����Ă����l�ɁA�C�M���X�ȊO�̍��ł͖������Q�̖u������\���ȓ��I�K�R���������Ă����̂ł���B1846�N�̍����@�P�p��1849�N�̍q�C���̔p�~�Ƃɏے������C�M���X���R�f�Վ�`�̐i�W�̂��ƂŁA�C�M���X�̓S�H�ƂɎx����ꂽ���[���b�p�ƃA�����J���O���ɂ�����S�����݂̐i�W�́A�J���t�H���j�A�i1848�N�j�ƃI�|�X�g�����A�i1851�N�j �ɂ�����V���z�����ɂ��h������āA����珔���̋ߑ�I�H�Ɖ��𑣐i�����{��`�I���Y�l���̎x�z�I�m�����\�Ƃ�����ɂ������āA1857�N�ɏ��̐��E�s�ꋰ�Q���قړ����ɖu�������̂ł���B���̌�N������1866�N���Q��1873���Q�Ƃ́A���O�サ�Ċe�����������_�ł܂��������E�s�ꋰ�Q�ɂق��Ȃ�Ȃ��������A���Ɍ�҂͂��̕���A�h���X�e�B�b�N�Ȑ[�����A���ۓI�L����ɂ����Ă݂̂Ȃ炸�A���̔����̒��S���䂪�C�M���X�ł͂Ȃ��㔭���{��`������h�C�c�A�I�|�X�g���A�A�A�����J���O���ւƈړ��������Ƃɂ����Ă������I�ł������B
|
��3. �Y�Əz�̎������Ə��ǖ�
���ɖ��ƂȂ�̂́A���������Y�Əz�̎������Ə��ǖʂ̌p�N���ł���B�܂��A�������ł��邪� �Y�Əz�̍ŏ��̔����҂ł���}���N�X���g���ώ@���_�ɂ���Ă܂��܂��ł����āA�{�i�I�Ȍo�ϊw�����ɑł����ޑO��1852�N�ɂ́u5���N�Ȃ���7���N�̎����I�z�v�iMEW,Bd.8,S.367 �j�ɂ��Č��A�w���{�_�x���M���_��1860�N��ɂ́A�����u10���N�̏z�v�iKapital,�T.MEW,Bd.23,S.661���j�ɂ��Č��Ȃ���A1870�N�㒆���ɂȂ�ƁA��Ɉ��p�����悤�ɁA�u���̔N����s�ςƂ݂Ȃ��ׂ����R�͂܂������Ȃ��v�Əq�ׂ�ƂƂ��ɁA����ɑ����Ă����t�������Ă���B�u���ɁA����X���W�J���Ă����悤�Ȏ��{��`�I���Y�̏��@������́A���̔N���͉ϓI�ł���A�z�̎����͎���ɒZ���Ȃ�ł��낤�Ɛ��_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƁB���Y�e�N�X�g�ӏ��́A�w���{�_�x��1���u��23�͎��{��`�I�~�ς̈�ʖ@���v�́u��3�ߑ��ΓI�ߏ�l���܂��͎Y�Ɨ\���R�̗ݐi�I���Y�v���̂��̂ł��邪�A���̂Ƃ���A�����ɂ����u���{��`�I���Y�̏��@���v�������w���Ă���̂��A�܂��Ȃ����̂悤�ɐ��_�����̂��́A�肩�ł͂Ȃ��B
�Ȃ�قǁu�o�ϊw�ᔻ�̌n�v�̍\�z������Ă�������̃}���N�X���u�@�B�ݔ����X�V����镽�ϊ��Ԃ́A��H�Ƃ��m������Ĉȗ��Y�Ƃ̉^�����ʂ鑽�N�ɓn��z����������ł̈�̏d�v�Ȍ_�@�Ȃ̂��v�Ƃ��āA�Y�Əz�̊m��I�������@�B�ݔ��̍X�V���Ԃɂ���Đ������Ƃ���Ӑ}�������Ă������Ƃ͊m���ł��邪�A�����������ɂ܂��ނ́u���Q�̌o�߂͂��̍Đ��Y���Ԃ���݂ĂȂ��S���ʂȏ��_�@�ɂ���ċK�肳���v���Ƃ��F�����Ă����B�����Ŗ��ƂȂ�̂��A�Œ莑�{�̎����ƎY�Əz�̎������Ƃ̊֘A���Ɍ��y�������̗L���Ȉ�߂ł���B���������ł͂��邪�A���m���������߈��p���Ă������B
�u������A���{��`�I���Y�l���̔��W�ɂ�ď[�p�����Œ莑�{�̉��l�ʂƁ@�����Ƃ����傷��̂Ɠ����x�����ŁA�Y�Ƃ̐������X�̓����ɂ�����Y�Ǝ��@�{�̐��������N�ɂ킽����̂ɁA�Ⴆ�Ε��ς���10�N�Ƃ����悤�Ȃ��̂ɂȂ�B����ŌŒ莑�{�̔��B�����̐�������������Ƃ���A�����ł́A���l�Ɏ��{�@��`�I���Y�l���̔��W�ɂ�Đ₦���i�W���鐶�Y��i�̕s�f�̕ϊv�ɂ���Ă��̐������Z�k�����B���������Ă܂��A���{��`�I���Y�l���̔��W�ɂ�āA���Y��i�̕ω����A����͓��̓I�ɐ������I�����������ƑO���疳�`�́@���Ղ̂��߂ɐ₦����U�����K�v�����傷��B��H�Ƃ̍ł�����I�ȏ�����@�ɂ��ẮA���̐����z�͍����ł͕��ς���10�N�̎����������̂Ɛ��肵�@�Ă悢�B�Ƃ͂����A�����ł͓���̔N�������Ȃ̂ł͂Ȃ��B�����A���̂��Ƃ��@�@���͖��炩�ł���B���̂悤�ȘA���I�ȁA�������̉�]���܂�ł��đ��N�ɂ�@����z�ɁA���{�͂��̌Œ�I�����ɂ���Ĕ�������Ă���̂ł��邪�A���@�̂悤�ȏz�ɂ���āA�����I�ȋ��Q�̈�̕����I�Ȋ�b��������̂ł����āA���̏z�̒��Ŏ��Ƃ͒o�ɁA���ʂ̊����A�ߓx�̔ɖZ�A���Q�Ƃ����p�N�I�@�@��������ʂ�̂ł���B�Ȃ�قǁA���{�̓�������鎞���͋ɂ߂Ď�X�l�X�Ł@�@����B�Ƃ͂����A���Q�͏�Ɉ�哊���̏o���_���Ȃ��Ă���B���������Ă܂��A�Ё@��S�̂Ƃ��Č���A���Q�͑����ꏭ�Ȃ��ꎟ�̉�]�z�̂��߂̈�̂́@�V���ȕ����I�Ȋ�b���Ȃ��̂ł���B�v
����Ɋ֘A����J.A.�V�����y�[�^�[�́A���ʂ̑@�ۋ@�B�̑啔����30�N����40�N�A����ȏ㒷���g����ɂ�������炸�A�����̊�Y�ƂƂ��Ėa�ыƂ�O���ɒu���Ă����͂��̃}���N�X���u�ǂ����Ă��̎Y�Ƃ̌Œ莑�{��10�J�N�����z�ɂ��Č�邱�Ƃ��ł����̂��A�����ɋꂵ�ށv�Ɣ�]���Ă��邪�A����͎Y�Əz�̎����ƌŒ莑�{�̎����Ƃ����������ł���B�}���N�X�����Y�ӏ��ŔO���ɒu���Ă����͓̂S�����ł���A�����ł̃��[���A�w�ɁA�S���A�@�֎ԁA�ԗ����X�Œ莑�{���v�f�̎G���ȕ����I�������������čX�V���Ԃ̑��l�������ڂ���A����瑽�l�ȌŒ莑�{���v�f�����Q�̌��ʂƂ��Ď��R�O�́u���Ȃ�ʍX�V��������������ԂɍX�V�����W�����邱�ƂɂȂ�Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�u���Q�͏�Ɉ�哊���̏o���_���Ȃ��Ă���v�Ƃ����̂����̐^�ӂł��낤�B
�܂��p�N�����Ă��A�}���N�X�́A�u���ʂ̊����A���Y�̔ɖZ�A���Q�A���̊e�����v�iKapital,�T.MEW,Bd.23,S.661 �j���̈��p�����́u�o�ɁA���ʂ̊����A���́A���Q�A�Ƃ����p�N�I�������v�iKapital,�U.MEW,Bd.24,S.185�j�A���邢�́u���Ï�ԁA���C�̑���A�ɉh�A�ߏ萶�Y�A�����A��A���Ï�ԓ��X�A�Ƃ����z�v�u���ʂ̊����A���Y�̔ɖZ�A���Q�A���̊e�����v�iKapital,�T.MEW,Bd.23,S.661 �j��u�o�ɁA���ʂ̊����A���́A���Q�A�Ƃ����p�N�I�������v�iKapital,�U.MEW,Bd.24,S.185�j�A���邢�́u���Ï�ԁA���C�̑���A�ɉh�A�ߏ萶�Y�A�����A��A���Ï�ԓ��X�A�Ƃ����z�v�iKapital,�V.MEW,Bd.25,S.372 �j�Ȃǂ̂ق������̋L�q���c���Ă��邪�A�K��������`�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�Ƃ͂����A���Q�́u����Y�Əz�̏I�_�ɂȂ�v�iKapital,�T.MEW,Bd.23,S.697 �j�ƂƂ��Ɂu�˂Ɉ�哊���̏o���_���Ȃ��v�iKapital,�U.MEW,Bd.24,S.185-6�j���Ƃ����́A�͂�����Ɗm�F����Ă��邱�Ƃ���A�Ƃ肠������̏z�͕s���E�D���E�ɉh�E���Q�̂S�̋ǖʂ𐄈ڂ����̍ۂɋ��Q�ǖʂ�����߂ďd�v�Ȗ�����������Ƃ����͌����Ă悢�悤�Ɏv����B����Ɋ֘A���āA��Ɂu�V�������|�w�h�o�̗��_�ƂŌ��E���p�w�h�o�g�̗��j�Ɓv(E.Salin)�Ƃ����h�C�c�̂`�D�V���s�|�g�z�t�͋��Q�̊ώ@����Ǝ��́u�o�ϕϓ��i�K�v���\�����}�����Ă���̂ŎQ�l�ɂȂ邾�낤�B�������A�}���N�X�Ƃ͈قȂ�V���s�|�g�z�t�ɂ����ẮA���Q�ǖʂ́u�M�p�̕���A�p���I�Ȏx����~�v�Ɠ���Ɍ��肳��Ă��邽�ߏz�̕s��I�\���������Ȃ����̂ł͂Ȃ��A1837�N����1937�N�̃h�C�c��100 �N�Ԃŋ��Q�͂킸��1857�N��1873�N�̂Q�x�����L�^����Ă��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邪�A�u���{�s���������Q�ǖʂƍl��������ꗂ͈ꉞ���������B
�����ŁA�ʗደ�Q�u���N�Ƃ��ċL�^����Ă���N�x�̊Ԋu��ʂ��ďz�����̖��ɗ����Ԃ��Ă݂悤�B1825�N�ɃC�M���X�ŏ��߂Ėu�������ߑ㎑�{��`�I���Q��1836�N�A1847�N��11�N�̊Ԋu�������ăC�M���X�𒆐S�Ƃ��Ĕ���������A10�N���1857�N�ɐ��E�s�ꋰ�Q�Ƃ��Đ����e�����قړ����Ɋ������ނ悤�ɂȂ������Ƃ͐�ɏq�ׂ��B���̌��Q�����E���܂ł̋��Q�u���N�����A1866�N�A1873�N�A1882�N�A1890�N�A1900�N�A1907�N�A1920�N�A1929�N�A1937�N�ɐ��E���Q���������Ă���A���������Ă��̊Ԋu�͂��ꂼ��V�N�A�X�N�A�W�N�A10�N�A�V�N�A��P�����E��������łX�N�A�W�N�ł������B�܂�A�z�����͂V����11�N�̉ϐ��ł���A�������u���ԋ��Q�v�ƌĂ��e���̓��ꎖ��ɋN�����镔�����Q����������A��蕡�G���Ƃ������Ƃ͐�̕\�P������ǂݎ���ł��낤�B�����A���͂����������ۂ̐[���ɉ������B�@ |
|
���U �Ɛ�Ƌ��Q�E�Y�Əz�̌`�ԓ]�� |
��1. 19���I���u��s���v�Əz�ϗe
1873�N���Q�Ȍ�̏z�`�Ԃɂ͂���܂łƔ�ג������ω������ꂽ���Ƃ́A������l�̏،���������̌�̌o�ώj����������m�F����Ă���B���Q�E�Y�Əz�̔����҂ł������}���N�X�́A�܂����̌`�ԕω��ɍŏ��ɋC�Â�����l�ł��������B�ނ́A�ӔN��1879�N�t�Ɂw���{�_�x�����̊��s�𗯕ۂ���u���R�v�Ƃ��āu���ʂ̎Y�Ƌ��Q�v�́u���ِ��v�������āA�����q�ׂĂ���B�u���O�����A�����J��h�C�c��I�|�X�g���A�Ȃǂł������ɂقƂ�ǂT�N�������Ă��鋰�낵�����Q���C�M���X�̋��Q�ɐ悾���Đ��������Ƃ͂��܂������ĂȂ��������Ƃł��v�i4��10���t����ƴٿ݈��̎莆 �j�A�ƁB���̂P�N�T������ɂ��A�C�M���X�ňȑO�Ɍ���ꂽ�u�����h��������ł̑�\���v���ݕ����Q�̌��@���u�܂������ُ�Ȏ����v�Ƃ��Ďw�E���Ă���i1880�N9��12���t����ƴٿ݈��̎莆�j�B�������ԂɊ֘A���Č�̌o�ώj�Ƃ͎��̂悤�ɋL���Ă���A�u��ϊv���A1873�N�̑�\���ƂƂ��ɁA���邢�͂����Ɛ��m�ɂ����A����ɂЂ��Â��s���ƂƂ��Ɏn�܂��B���̕s���́A80�N��̏��߂̂قƂ�ǖڂ����Ȃ��قǂ̒��f�ƁA1889�N����ُ̈�ɗ��A�������Z���ȁw�u�|���x�Ƃ������������ŁA22�N�ɂ킽�郈�|���b�p�̌o�ώj���[�����Ă���v�i̫-��ټ���݁j�A�ƁB���Ȃ킿19���I���u��s���v�ł���B
�z�`�Ԃ̕ϗe�́A�@��̂S�ǖʂ̂����D���ǖʂ̒Z�k�Ȃ����͒E���A�A�C�M���X�ɂ�����ݕ����Q�̌��@�A���������ċ��Q�̋}���I���i�i�p�j�b�N�j�̏����A�B���E�s�ꋰ�Q�́u���S�I�����̍��v�̐攭���{��`���C�M���X����㔭���{��`���h�C�c�E�A�����J�ւ̈ړ���ցA�C�Y�Ƌ��Q�ɐ�������\���I�Ȕ_�Ƌ��Q�̑��݁A�@�ہ��ȖэH�ƂƂ�������傩��ΒY��L�S��S�|�Ƃ������Y������ւ̏z�̎哱����̓]���Ȃǂɗv��悤�B���������z�ϗe�Ƃ��Č��ۂ��鎖���̔w��ɂ́A�e���̎Y�ƍ\���Ɛ��E�s��Ґ��̍��{�I�ȓ]�����A���{��`���̂��̂̎��I���W����������Ă����B���̃L�[���[�h�́A"���R��������Ɛ��"�ł���B
|
��2. �Ɛ�ƌÓT�I�鍑��`
���I���u��s���v�܂ł�19���I�̐��E�s�������Â���̂́A�C�M���X���u���E�̍H��v�Ƃ��Đ��I�O���̖ȍH�Ƃ���S�����݂̐i�W���_�@�ɒ�������S�H�ƂɎ厲���ړ������Ȃ��瑼�̉��ď����̎��{��`�I�H�Ɖ��𑣂��A�����ŖȐ��i�̂���є_�Y���⌴�ޗ��̊m�ۂ̂��ߑ��̒n����̌�i�n���A���n�E�]���������邢��Ή~���^���E���Ƃ̒��_�ɗ����Ă������Ƃł������B���̍ہA���E�s����x�z���錴���͎��R�����ł���A���R�f�Վ�`�ł���B�����A������А��x�̓����ɂ��S�����݂��o�l�Ƃ����㔭���{��`�����̎Y�ƓI�}�ǂ́A���Y�̏W�ςݏo���ăC�M���X�̐��E�s��x�z���������A���ۋ����̌����͎��R�f�Ղ���̗��E�ƕی�f�Վ�`�����Ē鍑��`�I����ւ̓]������������ɂ��������̂ł���B�u��s���v���ɐi�s���Ă����̂͂����������Ԃł���A��̏z�ϗe�Ƃ͂��̔��f�ɂ����Ȃ��̂ł����āA���̓]���͍ŏI�I�ɂ�20���I�����ɂ����Ċ�������B
���̏ꍇ�A�ی�ł����R�f�Ղ��Ƃ����_�ł̌X�̎��{��`���̊Ԃ̑���͖{���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�d�v�Ȃ̂́A�u���Y�̏W�ςɂ��Ɛ�̐��a�́A�����Ď��{��`�̔��W�̌��݂̒i�K�̈�ʓI�����{�I�Ȉ�@���ł���v�i�-�݁w�鍑��c�_�x���g���ɤ35��-�ށj�Ƃ����_�̊m�F�ł���B���{��`�I�Ȏ��R���������{��`�I�ȓƐ�ɂƂ��đւ��ꂽ���Ƃ�{���Ƃ���鍑��`�ɊȌ��Ȍo�ϓI�K���^����Ƃ���A���̒����Ȓ�`���z������̂͂Ȃ��ł��낤�B�u�鍑��`�Ƃ́A�Ɛ�Ƌ��Z���{�Ƃ̎x�z���������A���{�̗A�o�������ȈӋ`���l�����A���ۃg���X�g�ɂ�鐢�E�̕������n�܂�A�ő�̎��{��`�����ɂ��̓y�̕��������������A�Ƃ����悤�Ȕ��W�i�K�ɂ����鎑�{��`�ł���v�B
����20���I�����̌ÓT�I�鍑��`�i�K�ȍ~������Â���̂́A�Ɛ�ɋN�����锭�W�̒�E�����Ɣ��̕s�ϓ����ł���A����͂܂��Y�Əz�̌`�Ԃɂ����R�e���������炳���ɂ͂��Ȃ��B���ΓI�ɒ����̕s���𐏔���,�ɖ�����ȗ����������C�M���X�E�t�����X�^�̐���I�z�Ƌ}���Ȕ��W�ƒZ���̋}���I���Q���h�C�c�E�A�����J�^�̊��͓I�z�Ƃ̑ΏƂɎ������悤�ȁA�e���z�̕s�ϓ����Ƌ��Q�̓������̑r��������ł���B�Ⴆ�A1900�N�̋��Q�̓h�C�c�𒆐S����Ƃ����s�Ȃ��̂ł���p�ĕ��ɂ����Ă͔���Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ��������A1907�N�̋��Q�̓A�����J�ɂ����ē��ɐ[��������ł������̂ɑ��ĉp�Ƃł͌y���ł������B�܂���P�����E�����1920-1�N�̋��Q�͉p�ē����P�������̂́A�h�C�c�E�I�|�X�g���A�͂��̌��O�ɂ��������A����1929�N�̑勰�Q�ɂ����Ă����t�����X�͗�O���Ȃ��Ă����B��Q�����E���˓��̑O����Ȃ�1937-8�N�̋��Q�͉p�ĕ����P�������A�펞�o�ϑ̐����̓��{�E�h�C�c�E�C�^���A�̐������͂��̉e����ւ�Ȃ������̂ł���B
|
��3. �����E���Əz�̋@�\���
�����������Q�E�Y�Əz�̕s�ϓ����Ɠ������r���́A���E�s��̑��D���������o�ς̌R�����ƂQ���ɂ킽�鐢�E�푈�̑��͐�Ƃɂ���Ă����������߂�ꂽ����ł͂Ȃ��A����͂���Ŏ��R�����i�K�̎��{��`�ɂ����Ă̖����̌o�ϓI�����`�ԂƂ��Ă̏z�̋@�\����Ⴢ��āA�푈�Ƃ��������I�o�ϊO�I��i�ɖ����������ς˂�������Ȃ��Ȃ������Ƃ̕\���ł�����B����������A19���I���́u�鍑��`�I���g�v�ƌĂ��R�g�i�C�i1895�`1913�N�j�ȗ����{��`�o�ς̏������͌o�ωߒ��̓����Ŏ����I�ɉ�������邱�Ƃ͕s�\�ƂȂ����Ƃ������Ƃ��A���Ȃ��Ƃ�19���I�ɂ͑��݂��Ă����z�̎������̊��S�Ȃ�j��Ƃ����`��ʂ��ĕ\������邱�ƂɂȂ����B�܂�A���̒i�K�ɂ�����o�ϓI�������͂��͂�����I���Q�̔����ɂ���Ĉꎞ�I�ɉ��������悤�Ȑ����̂��̂ł͂Ȃ��A�����O�ʼns�������I�E�a瀂������������E�s��ɂ����鏔�̑R�ƒ鍑��`�푈�ɂ��\�͓I�����ɐȂ�������̂ƂȂ����̂ł���i8�j�B���������o�ϓI�ɉ��������Ȃ��������̑��̂́A�������o�ς́u���ƌ`�Ԃł̑����v�ɐV���Ȏ���v������������Ȃ��B������u���ƓƐ莑�{��`�v�̓o�ꂪ����ł���B
���Ƃ̌o�ωߒ��ւ̑S�ʓI�ȉ�����s���ƂȂ�̂́A�ŏ��͒鍑��`���̔��̑��͐킽���P�����E���̑������̐��Ƃ��Ă̐펞�o�ϑ̐��Ƃ��Ăł������B���̌�1929�N�勰�Q�Ƃ���ɑ���30�N���s���̉ߒ��ō��ƓƐ莑�{��`�́A�A�����J�̃j���|�E�f�B�|������ɑ�\�����悤�ɁA�i�C�E�J���́E�ݕ��������Ƃ̐����I�Ǘ����ɂ������Ƃ��鎑�{��`�̂���Ί�@�Ǘ��̐��Ƃ��čP�퉻���A��Q�����E����ɂ͗��̐��̂��Ƃŕ����ɂ����Ă���ʓI�ɒ蒅���݂��̂ł���B�����ċ��Q�E�Y�Əz�́A���̖{���̎����I�Ȗ@�����������A�܂��܂��l�דI�ȁu�����I�i�C�z�v�ւƕώ����邱�ƂɂȂ炴������Ȃ��B��Q�����E����̌���̋��Q�E�Y�Əz���ۂ��������Ă���B
|
(1)�@�ٸ�=�ݹ�ٽ�w���{�_���ȁx(2)���莟�Y��匎���X1971�N�323-4��-�ޡ
(2)�@����w���{�_���ȁx(2)�338��-�ޡ
(3)�@T.Vogelstein,"Die finanzielle Organisation der kapitalistis chen Industrie und die Monopolbildungen",in Grundriss der Sozialokonomik,�W.Abt.,Tubingen 1914,S.222f.�-�݁w�鍑��c�_�x� �F�������g���X 1956�N�35-6��-�ޡ
(4)�@���̉ߒ��̓I�m��Ȗ��ȋL�q�Ƃ��Ĥ���]�ߎ��Y�w�鍑��`�̉𖾁x(�V�]�_ 1979�N)�̑�1�� ��鍑��`�Ƃ͉�������L�v�ł���
(5)�@�-�݁w�鍑��c�_�x��O�f�35��-�ޡ
(6)�@����146��-�ޡ
(7)�@�F����㢐��E���Q�j���䋂���ҁw�u������Q�_�x�W����m�o�ϐV��@��1959�N�81-2��-�ޡ
(8)�@���̓_�ɂ��ďڂ����ͤ�Ð�N�w��@�ɂ����鎑�{��`�̍\���ƎY�Əz�x(�L��t 1970�N)���Q�Ƃ��ꂽ���
|
|
���V ����̋��Q�E�Y�Əz�ƃX�^�O�t���|�V���� |
���P. ��㐢�E�ĕ҂̓���
��P�����E��킪�������ɃC�M���X�̒����ƃA�����J�̑䓪�������炵�A��㐢�E�́u���E�̕����v�ƍČ����i�בցj�{�ʐ��̂��ƂɃ��F���T�C���̐��Ƃ��čĕ҂��ꂽ�̂ɂ������āA��Q������( �s�퍑�Ɛ폟�����킸) �Q�x�̑��̎���ƂȂ������|���b�p�̖v���ƐA���n�̐��̕���A�����Ď��{��`���E�̏d�H�Ɛ��Y�̂U���Ƌ������̂V�����߂錆�o�����o�ϗ͂Ɓu���E�̕��폱�v�Ƃ��ċ���ȌR���͂����A�����J�̔e���������炵�A��㐢�E�̓A�����J�哱�̂��Ƃɗ��̐��Ƃ��čĕ҂���邱�ƂɂȂ����B���̍ہA��O�̐��E�s��̃u���b�N���Ƃ��̋A���Ƃ��Ă̐��E�푈�̔��Ȃɗ����āu���R�E�����ʁE���p�v�I�Ȑ��E�s���n�o���ׂ��A�A�����J�̒���I�ȗ͂�w�i�ɔ��������̂��h�l�e���f�`�s�s�̐��ł���B����ɂ��A�����J�́A���łɐ�Ԋ��ɍ����I�ɕs��������Ă��������ʉ݃h��������I�ɋ��ƂȂ�Ԑ��E�ݕ��Ƃ��Đ��E�s��ɎU�z����@�\��ƂƂ��ɁA������́u���卑�v�\�A�ɑΛ�����������{�̎��{��`�I�����ɓw�߂邱�Ƃ��ł����B
����ɐ�㐢�E�ĕ҂̓����Ƃ��ċ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��̂́A�A�����J���{��`�̌o�ς̌R�����ł���B1929�N�`33�N�Ƀh�C�c�ƂȂ��ł����Ƃ������Q�Ɍ�����ꂽ�A�����J�ł́A�h�C�c���i�`�Y���̂��Ƃ�1937�N�ɂ͂قڊ��S�ٗp��B�������̂ɂ������āA�j���|�E�f�B�|������̃X�y���f�B���O�E�|���V�|���Ԏ������������Ă��Ă����N�Ȃ��V�V�O���l�A�P�S���̎��Ƃ𐔂����܂܂ł���{�i�I�ȉ�1941�N�̕���ݗ^�@�̐����ɏے������o�ς̌R������҂��˂Ȃ�Ȃ������B�A�����J�̌R�����1938�N�ɂP�O���h���łf�m�o����ꊄ����Ă�����1943�N�ɂ͂U�R�Q���h���ƒ������f�m�o��͂R�V������߂�ɂ��������B���h�x�o�͂������ɑ����1948�`50�N�ɂ͂P�R�O���h����ւƌ����������A���N�푈�ɂ����1953�N�ɂ͂T�O�U���h���ւƌ������A���̌��U�������Ă���1961�N����Q�����x�g�i���푈�ɂ��1969�N�ɂ͂W�P�Q���h���ւƑ��債���������Y�̂قڈꊄ���߂Â��Ă����̂ł���(1) �B�ߔN�ɂ����Ă̓��|�K�m�~�N�X�ɂ��1980�N�ɂ͂P�U�S�O���h���ƘA�M�x�o��22.7���A�f�m�o��łT�����߂Ă������̂��A1987�N�ɂ͂Q�S�Q�U���h���ŘA�M�x�o��27.8% �A�f�m�o���6.4%�����߂�ɂ�����A���̂������̊Ԃ̐��{�����J����(�q���c) ���P�S�X���h������S�O�R���h���ւƌ������Ă���(2)�
��㎑�{��`���E������A�����J�o�ς̌R�����͐��ĕ҈ȗ��̍\���I�����Ƃ����Ă悢���A1947�N�̑\�������ߐ헪( �g���|�}���E�h�N�g����) �ȍ~�̗��R�̂Ȃ��ł���������������A�����J�݂̂Ȃ炸���E�̌o�Ϗz�𐧖������̂ł���B����̓A�����J�ꍑ�ɂƂ��Ă͐�O���̑�s������̉̌o���Ɋw�R���x�o�ɂ��ߏ莑�{�Ƒ�ʎ��Ƃ̓��������Ƃ������P�̐��ɂ����鐧�x�I�蒅�ł��������B�t�B�X�J���E�|���V�|�̌��ʂ͕s���Y�I�ȌR���ɂ����āu���Y�Ə���̖����v���������҂��ꂽ����ł���A�����Ă����ɂh�l�e�̐���ʂ���[���I���E�ݕ��h���̎��~�߂Ȃ��U�z�ɔ}���Đ�㌻�㎑�{��`���E�̋��Q�E�Y�Əz���K�肷��A�����J�哱�̌R���C���t���|�V�����I�~�ϑ̎����h���Â����̂ł���B
|
��2. ��Q�����E����̋��Q�ƃX�^�O�t���|�V�����̔���
���ۓI�ɂ͂Q�O���I�ɂ����āA���ꂪ�p�j�b�N���Ȃ킿�ݕ��E���Z���Q���Ƃ����Ӗ��̌ꊴ����ސ��ł���悤�ȋ��Q�́A1907�N���Q��1929�N���Q�A�킪���ł�1927�N���a���Z���Q�̑��ɂ͐����Ă͂��Ȃ��
��㒷�炭�A���Q�͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ă������A����͈ꍑ�S�̂����ꂩ��k��������悤�ȃh���X�e�B�b�N�ȋ��Q�Ƃ����Ӗ��ł͂������Ƃ��Ă��A���Q���̂��̂��Ȃ��Ȃ����킯�ł͂������ĂȂ��B�A�����J�ɂ��Ă݂�A1966�N�ɐM�p�N���������A1970�N�A74�N�A82�N�ɂ͂��ꂼ����Z���Q�������������A84�N�ɂ͑勰�Q�ȗ��̗a����t�����������N�������B���{�ɂ����Ă�1965�i���a40�j�N�ɂ͐[���ȏ،����Q���������Ă���B�����͐�㍑�ƓƐ莑�{��`�̂��Ƃł���������{�ɂ��~�ϑ[�u�ɂ���đS�ʓI�ȃp�j�b�N�ɂ܂Ŕ��W���邱�Ƃ����͖W����ꂽ�̂ł���B����ɁA�A�����J�ł�1987�N����89�N�ɂ����Ė��N�Q�O�O�s�����鏤�Ƌ�s���|�Y���A�X�O�N�O��ɂ͓|�Y�̉\������Ƃ�������s�͂P�O�O�O�s�����B�ߔN�ɂ킩�Ɂu�]������݂Ȃ�"���Z���僊�|�h�̌i�C���"�i"�����s��"�j�v(3) �A���邢�́u�i�C�g�����̃s�|�N�O�ɔ���������Z���Q�v(4) �Ƃ��Ē��ڂ���Ă��鎖�Ԃ�����ł���B����������A���̃A�����J�Ɠ��{�̌i�C��ނ̃N���m���W�|���f���Ă������i�\�Q�Q�Ɓj�B
���\�A�̌o�ϊw�҃����V�R�t�͋��Q�������I���Q�ƒ��ԋ��Q�Ƃɋ�ʂ��ׂ����Ƃ��咣���āA�A�����J�ɂ��Ă�1948�`9�N�1957 �`8�N�1966�`�V�N�A1973�`�T�N�������I���Q�A1953�`�S�N�A1960�`�P�N�A1969�`1971�N�𒆊ԋ��Q�Ƃ��ꂼ��K�肵�A���{�ɂ��Ă�1953�`�S�N�A1962�`�R�N�A1973�`�T�N�������I���Q�A1957�`�W�N�A1964�`�T�N�A1970�`�P�N�𒆊ԋ��Q�ƋK�肵�Ă���B�܂�����Ƃ͈���āA����������ʎ��̂�ے肵�āA���̂��ׂĂ��u���ƓƐ莑�{��`�I�Θ߂����Ƃ���̎����I���Q�v�Ƃ݂Ȃ��A���̐��ɂ���������Z�k���咣����_�҂�����(5) �B�������A��ʓI�ɂ̓N���m���W�|( �\�Q) �ɕ\������Ă���i�C��ނ̂����ŋ��Q�Ƃ����Ă���̂́A1957�`8�N�̌i�C��ނ�1974�`�T�N�V����ł���A1980�N�̂���͐��E�����s���Ə̂���Ă��邪�A���Q�ƋK�肳���O�Q�҂��߂����Ă��������ꂪ�����I���Q�Ȃ̂��A���邢�͒��ԋ��Q�Ȃ̂����̂Njc�_�̈�v���݂Ă��Ȃ��̂�����ł���B
���́A���̎������̖��́A�{�e��P�͂ɂ����ĐG�ꂽ�悤�ɁA���łɂP�X���I����o�ꂵ�����܂Ŏ����z����Ă������̂ł����āA���ԋ��Q�̑��ݔے���A�����I���Q�̂P�O�N�����s�ϐ��A���ԋ��Q�̉�݂ɂ��z�ϗe���A���Q�̎����Z�k���A�����I�ߏ萶�Y�i�K�ڍs���A�z���Ő����X�A���܂��܂ȃo���G�|�V�����Ō���Ă������̂ł���B�����̐S�Ȃ̂́A�������̂��̂����z�̓����̂ق��ł���B���̓_�ŁA��Q������̌i�C��ނ́A��O�܂ł̂���Ƃ͖��Ăɗl����ς��Ă���B�A�����J��1957�`�W�N�̌i�C��ނ��炵�āu���Z�b�V���i���|�E�C���t���|�V����(re-cessionary inflation)�v �ƌĂ��悤�ɁA��O���܂ł̋��Q���ɓ��L�̉��i�\�����݂��Ȃ��������Ƃ����̓��ِ��Ƃ��Ē��ڂ���Ă����B�P�W�Q�T�N�̋��Q�ȗ����Q�̂����Ƃ���ʓI�Ȍ��ۂ́A�u���i���i�̒����̈�ʓI���M�ɑ����ēˑR���Ƃ���邻�̈�ʓI�����v(6) �ł���������ł���B���̌�1960�N��̌i�C��ނɂ����ĉ��i�͖\���ǂ��납�t�ɓ��������߁A�o�ϕs���͕������M�Ƌ�������悤�ɂȂ����B������X�^�O�t���|�V�����̔����ł���B�������́A�����Ɠ��{�̐�㕜���Ƃ��̌�̃A�����J���܂ސ��E�o�ς̌o�ϐ����������ł�����1950�`�U�O�N��ɂ����Ă͂܂����ĂȌ��ۂł͂Ȃ��B�X�^�O�t���|�V�����͓��ɉ��Ă𒆐S�ɒᐬ���֓]�������P�X�U�O�N�㖖����P�X�V�O�N��ɂ����Đ[�������݉�����悤�ɂȂ�A���Ɨ��ƕ������M���Ƃ̑��a�Ƃ��ĕ\�������u�X�^�O�t���|�V�����x�v(7)��1974�`�T�N�̌i�C��ފ��Ƀs�|�N�ɒB����ɂ������āA�ɂ킩�Ɍ��㎑�{��`�̋ƕa�Ƃ��Đ[���Ɏ~�߂���悤�ɂȂ����̂ł���B
|
���R. �X�^�O�t���|�V�����̊�{�I�v��
���Ƃ���Stagnation�i�o�ϒ��j��Inflation �i�������M�j�Ƃ̍�����ł���Stagflation�́A�����̎����I�Ȉ�ʓI���M�Ƃ��̈�ʓI�����̌�ւƂ����ÓT�I�ȎY�Əz�ł͑������Ȃ��q�o�ϒ��؉��̕������M�r�Ƃ����V���Ȏ��Ԃ��A����������Ώz���ۂƂ͋�ʂ����\���I���ۂ���肷�邽�߂ɗp����ꂽ���̂ł���B���������l�דI�Ȗ��ړI�������M�Ƃ��ẴC���t���|�V�������̂��̂��炵�Ď������]���������Ȃ��Ƃ����Ӗ��ō\���I���ۂȂ̂ł��邪�A�P�C���Y����ɂ��1950�`�U�O�N��ɍ����������N���|�s���O�E�C���t���|�V�����Ƃ��Ďn�܂莟��Ƀn�C�p�|�������������M�́A1970�`�W�O�N��̒ᐬ���ւ̓]���ɔ����[���Ȏ��Ƃ̔����𐏔�����ɂ������ăC���t���Ƃ͋�ʂ����V���Ȗ��̂�^����ꂽ�킯�ł���B�u�X�^�O�t���|�V�����v�Ƃ����P���\��Ɍf����M��_������Ăɓo�ꂵ���̂́A1971�N�ȍ~�̂��Ƃł���A���ꂪ1975�N�ȍ~80�N��ɂ����Ă��т����������ɏオ�����Ƃ������Ƃ́A�����I���Ԃ̔��f�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
������A�����������̂Ƃ��ẴX�^�O�t���|�V�����̊�{�I�v����₤�Ƃ���A����͐悸������ʓI�ɂ́A��Q������̎��{��`�e���̍��ƓƐ莑�{��`�I�Ȑ������i��Ƃ��ẴC���t������̋A���ł���Ƃ����Ă悢�B���̂�����ł́A�X�^�O�t���|�V�����̔����́u���ƓƐ莑�{��`�̐������j�]�ɓ]�����A���Ƃɂ�钲�����|���@�\���Ȃ��Ȃ����Ƃ������ق����v(8) �Ƃ��Ă悢�Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł͊e�����t���b�g�Ɉ�����㐢�E�Ґ��̖�肪�������Ă���_�Œv���I�ȕs�\������Ƃ�Ȃ��B���E�I�C���t���|�V�����Ƃ����Ă����̐k���́A���j�{��`���E�ĕ҂̖���Ƃ��ČR���C���t���I�~�ϑ̐����ɂ����ꂽ�A�����J�ł����āA�������甭�����C���t�����l�h�e�̐��̂��Ɗ�ʉ݃h������āA����Ő�㕜������������Ƃ鐼���E���{�ցA�܂������ŐA���n���������ꂽ��J�������ւƒn����ɔg�y����͕̂K���ł������B���������āA�Ƃ�킯�A�����J�ɂƂ��ăX�^�O�t���|�V�����́A���R�̂��Ƃŋ������ꂽ�j�E�~�T�C���E�ʐM�E�d�q�𒆊j�Ƃ���V�s�R���Y�Ɓi�R�Y�����́j�̑n�o�A����ёO���W�J��͂̈ێ��Ƃ����⊮����ΊO�R�������Ȃ����؊��p�̃h���E�X�y���f�B���O����́A�v����ɌR���C���t���I�~�ϑ̐��i9 �j�́A���������ւ̓]���ɔ����K�R�I�ȋA���ł������B�Z�p�v�V�Ɏx����ꂽ�P�X�T�O�N��܂łƂ͈قȂ�A�R���p�V�s�Z�p�͖��������ꂦ�����Y���̒ቺ�ƃP�l�f�B���W�����\�������̐������i����̌��ʁA�����������̃X�p�C�����ȏ㏸�ɂ���ăA�����J�ݗ��H�Ɛ��i�́A�U�O�N��ȍ~�ɐ����E���{�̐��E�s��ւ̕��A�i�u�f�ՁE�בւ̎��R���v�j�ƍ��ۋ�����̌����̂��Ƃŋ}���ɋ����͂������A�A�����J�����s��͎\�H����āA�T�O�N��ɑ@�ہE�G�݂���n�܂����f�Ֆ��C�͓S�|�E���D�E�d�@�����Ď����ԂƂ������ݗ������ɂ܂ōL�����Ă������̂ł���B
����Ɠ������s�I�ɁA���z�̃h���U�z�͂U�O�N��Ɍ����ƂȂ�A�����J��Ƃ̑����Љ��i�ΐ����W�J�j�̐i�W�Ƃ����܂��ĂU�O�N���ʂ��Ċ�ʉ݃h���́u���Ƃ̓��ꐫ�v�ɂ�������M�F��h�邪���t�������A�u�h����@�v���i�s�����i1961�N���v�|���̌�����1968�N���̕���j�B���ۋ��Z���͂ƃh���h�q��ɂ�������炸�A�����J��1971�N�W�����Ƀj�N�\�������ɂ����E�h��������~�ɒǂ����܂�A�X�~�\�j�A�����ӂɂ��ʉݒ����i���N�P�Q���j�����P�X�V�R�N�ɂ͌Œ�ב֑��ꐧ���̂��̂����������Ɏ������B���Ȃ݂ɁA�Q�x�ɂ킽���Đ�i���{��`����k���������u�Ζ��V���b�N�v�i1973�N�H�A1979�N���j�Ƃ́A50�N��ȍ~���������Ă����ꎟ�Y�i�̒ቿ�i�ƃh�������ɂ�������n�o�d�b�i�Ζ��A�o���@�\�j�ɂ�锽���ɂ����Ȃ��������A����͂���ʼn��ē��{�̐Ζ����ʏ���̃R�X�g�㏸�v���Ƃ��ăC���t�������������̂ł���B�킪���ł́A�����i�C�ɕ������Ȃ��Łu���������v�Ƃ��đ����ꂽ���Ԃ�����ł���B
�������Ă݂�ƁA�X�^�O�t���|�V�����́A�A�����J�哱�̌R���C���t���I�~�ςɂ����1950�`60�N��Ɍ`������B������Ă����\���I�Ȍ������{�̉ߏ萶�Y�\�͂��z�I�Ȍi�C��ދǖʂɂ����Č������������M�ƂƂ��Ɍ��݉��������Ԃł����āA���������Ӗ��ɂ����đ�Q�����E���㌻��j�{��`�̓���1970�`80�N�������Â��鋰�Q�̓Ǝ��̔����`�Ԃł������Ƃ����Ă悢�ł��낤�B�ߏ莑�{�́A���ł�1957�`�W�N���Q�ɍۂ��ăA�����J�S�|�Ƃɂ݂�ꂽ�悤�ɑ��Ɠx�̒ቺ�Ƃ���ɂ��R�X�g�㏸���̉��i�]�łƂ����`���Ƃ�A���R�����i�K�ɂ�����悤�ɉݕ��M�p���Q���Ĉꋓ�E�S�ʓI�ɉ�������邱�ƂȂ��������ꂽ���߁A�����ɂ킽�茵�����s���E���ƁE�C���t���������i�s����������Ȃ����ƂɂȂ����̂ł���B������̔����ԗl�͊e�����ƂɈقȂ��Ă������A���̃X�^�O�t���|�V��������̒E�o�����l�ł͂Ȃ��������A���ꂪ���̌�̓��ɉ��ē��̐�i���{��`�����𒆐S�Ƃ���Q�O���I�����E�s���̋��ʂ̔w�i�ƂȂ������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��o�u���̔����Ƃ��̔j�]�́A���́u�`���|���b�v���Q�v�̗p�ɁA�W�O�N��㔼�ȍ~�ɓˑR���邢�͋��R�I�ɏo�������킯�ł͂������ĂȂ��̂ł���B
|
(1)�@�ȏ�̐��l�ͤ����͕ҁw���ƍ����x(������w�o�ʼn�1976�N)�159-60��-�ނ�蓾���
(2)�@T.Kemp,The Climax of Capitalism: The US Economy in the Twentieth Century,London & New York 1990,pp.221-2.���̌������ͤStatistical Abstract of the United States,1988�ł���
(3)�@�{��`��w�����s���x��������_�Ф1992�N�250��-��
(4)�@M.H.���̿ݤ�쉺����c���c��w���Z���Q:����ض�̌o���x����{�o�ϕ]�_�Ф 1995�N6��-�ޡ
(5)�@��������w���㎑�{��`�̏z�Ƌ��Q�x� ��g���X 1981�N�92-3��-�ޡ
(6)�@K.Marx,Zur Kritik der politischen Okonomie,1859,MEGA 2.Abteilung Bd.2,Dietz Verlag Berlin,1980,S.241 (�w�ٸ����{�_���e�W�x�B��匎���X1984�N�423��-��)�
(7)�@��������w���㎑�{��`�̏z�Ƌ��Q�x� �O�f�98-9��-�ޡ
(8)�@��� �́w���ƓƐ莑�{��`��j�]�̍\���x��䒃�̐����[�1983�N� 322��-�ޡ
(9)�@�� ���Ȣ���̐���̂�ME=���v���(�w�y�n���x�j�w�x���147���1995�N4��)�ͤ�������鍑��`�̒~�ϗl����Ɠ����Â��Ă��顂���Ɋ֘A���Ĥ����j�����鍑��`�̍\���ƽ�����-��ݣ(��C��w�w�Љ�Ȋw�N��x��19���1985�N)���Q�Ƃ̂��ơ
|
|
���W �Q�O���I�����E�I�s���ƌ���̃o�u���E�����s�� |
��1. �Q�O���I�����E�I�s���̔w�i
�u�Q�O���I�����E�I�s���v�Ƃ����ꍇ�A�����1980�`2�N�̐��E�����s��������w���̂��A���邢��1990�N�Ȃ���91�N����̊e���i���ɐ����E���{�j�̕s�ϓ��s���݂̂��w���̂���(1)��_�҂ɂ���Ĉӌ��̈قȂ�Ƃ���ł���ɂ��Ă��A���̔w�i�ƂȂ鎖�Ԃ̋N�_���P�X�V�O�N�㏉���̃u���g���E�b�Y�̐��̕���ł������Ƃ����_�ɂ����Ă͂����炭�٘_�̂Ȃ��Ƃ���ł��낤�B
��������1971�N�W���̃A�����J�̈���I�ȋ��E�h��������~�����́A���ۋ����͂̎㉻�̂��Ƃł̌p���I�ȃh���U�z�ɂ�鍑�ێ��x�̈����ɒ��ʂ��āA��ʉݍ��̐ӔC����������̐������Ď����̃X�^�O�t���|�V��������E�o���悤�Ƃ���j�N�\���u�V�o�ϐ���v�̈�ł������B�����낱��1971�N�́A�A�����J�f�Վ��x���S���I���ȗ�78�N�Ԃ�ɐԎ��ɓ]�������A�����J�o�ς̐��ނ��ے�����N�������̂ł���B���̌�̋��a�}�t�H�|�h����і���}�J�|�^�|�����ɂ����Ă��A�����J�o�ς̒�����؊�͕����ׂ����Ȃ��A��Q���Ζ��V���b�N�̉e���������ăC���t���|�V�����͂܂��܂������������͂Q����̏㏸�����������B1981�N�P���哝�̂ɏA�C�������a�}�u��h�v���|�K���́u�o�ύĐ��v��v�́A���̑单���Ƃ��ĘA�M�����K�͂̏k���i������u�����Ȑ��{�v�j�E�����Ō��ŁE���{�K���̊ɘa�E�ʉߋ����ʂ̗}����ł��o�����Ƃɂ���āA�P�C���Y��`�ƌ��ʂ������d���̌o�ϐ���i�u���|�K�m�~�N�X�v�j��W�Ԃ�����̂ł������B���|�K�������̓��ʂ̉ۑ�͂Ȃɂ����C���t���|�V�����̒��É��ł���A�������14���A�P�����20���O��Ƃ����}���ȋ��Z�����ߐ���ɂ��m����1981�N�ȍ~�C���t���͗}������A1983�N�ɂ͕����̖ʂ��猩�����X�^�O�t���|�V�����͏I���������Ɍ��������A����͓����Ɍ����Ȑ����Ɛݔ��ғ����ቺ�i�S�Y�Ƃł�69�5���A�S�|�Ƃ�37�6���A�����ԎY�Ƃł�36�6���j�Ɛ�㏉��1000���l���鎸�Ǝ҂̔���(2) �Ƃ����[���ȕs���������炵���̂ł���B����̓��|�K�������ɂ�鐭���s���Ƃ����܂��Ɂu�����I�i�C�z�v�ł���ƋK�肵�Ă������A�ߏ莑�{�Ɖߏ�J���͂̓��������Ƃ����Ӗ��ɂ����ẮA�ÓT�I��`�ɏƂ炵�Ă���������A�����J�ő�̌o�ϋ��Q�ł������Ƃ����悤�B
�����A���|�K�������O���̍������E�h�����������炵�������Əd��Ȍ��ʂ́A�A�����J��Ƃ̃O���|�o���ȑ����Љ��ƃA�����J�����Y�Ƃ̋��̐i�W�ł���A���z�̍����Ԏ��ƌo����x�Ԏ��̗ݐςł������B���̊��̃A�����J�o�ς́A���Z�E�T�[���B�X�ɉߓx�ɌX�������ō����ł̌������{�̗ݐς�����������������߂ɐ����Ƃɂ�����ΊO�����͂�����������߂����Ƃɂ���āA�������Ɂu��O�I�Ɂv�����͂������������{�̖��C�E�a瀂��܂��܂����߂Ă������̂ł���B���Ȃ݂ɁA1983�N�̃A�����J��Ƃ̐V�K�ݔ������́A�����Ƃ�1173���h���ɑ��Ĕ��Ƃ�1294���h���ł��������A1989�N�ɂ����Ă͑O�҂�1836���h���ɑ��Č�҂͖�2293���h���ł������B(3)
�Q�O���I�����E�I�s���̑�P�̔w�i�́A�P�X�W�O�N��Ɉ�i�Ɛ�s��������i���{��`�����ē��Ԃ́A�Ƃ�킯���ĊԂ̕s�ύt�̊g��ł���B���{�́A�V�O�N��̐Ζ��V���b�N���_�@�Ƃ���d������Y�Ɓi�S�|�E�Ζ����w�E�q�Ɓj�ɂ�����ȃG�l��������ݗ��@�B�H�ƂƓd�q�H�ƂƂ̐V�������Ȃ킿�m�b�H��@�E�Y�Ɨp���{�b�g�E�����ԁE�u�s�q�E�n�`���X�l�d�֘A�@��̓����ɂ���āA�p�Ă͂��Ƃ��h�C�c�ł��獎���ł��Ȃ������ꋫ�����z���āA�W�O�N��ɂ����Ē�������i���{��`�����̂Ȃ��ł���Έ�l���̗l����悵�A��l�̃A�����J�̎w���I�m���l�����āu�W���p���E�A�Y�E�i���o�|�����v(4) �Ƃ��킵�߂��قǂł������B���{�̎����ԁE�����́E�l�d�@��̏W�����J�ɂ����Ƃ���ꂽ�A�o�}���͋��Z�����ߍُ̈�ȃh�����ɂ���ĉ�������A���{�̌o����x�̍����]���ƑΕĖf�Ս����̗ݑ����A���������ăA�����J�̋��z�̖f�Վ��x�Ԏ����Y�ݏo�����B�A�����J�̌o����x�͂P�X�W�O�N�ɂ͂킸���P�W���h���Ƃ͂����܂������ł��������A�W�T�N�ɂ�1230���h���Ƃ����c��ȐԎ����L�^���A���������N�A�����J��1914�N�ȗ��V�P�N�Ԃ�ɍ����֓]�������̂ł���B���̓_�ł́A���{�́u�A�o�ˑ��I�����v���A�����J�Y�Ƃ̒�Ɉˋ������A�����J�s��̐Z�H�ɂ���Ď������ꂽ�Ƃ����咣(5) ���A���Ȃ����֒��ł͂Ȃ��B�Γ��f�Ֆ��C�͒��_�ɒB���č��c��͕ی��`�I�X�������ߑΓ����ّ[�u������肴�������Ȃ��A�A�����J���{�͕č��P�Ƃł̑Ή���f�O����v���ɋ��������v�����邱�Ƃɂ���ē�ǂ�ŊJ���悤�Ƃ����B���̌��ʂ��W�T�N�X���ɋً}�ɊJ�Â��ꂽ�f�T�i���E�āE���ƁE�p�E���T��������E������s���ى�c�j�̃v���U���ӂł���A���ꂪ�o�u�������Ɣj�]�́A���������ĂQ�O���I���s���̒��ڂ̔w�i�ƂȂ����̂ł���B
|
���Q. �o�u�������ƕ���
1990�N�Ȃ����X�P�N����̐��I���s���Ƃ��̈�ł���킪���́u�����s���v�̔w�i���Ȃ��Ă���̂́A�W�O�N��ɐi�s�������E�o�ς̍\���ϊ��ł���B���̑�P�́A��Ɍ�����i���{��`���Ԃ̕s�ύt�g��ł���A��Q�ɁA�����ɐi�W�������E�I�X�P�|���ł̋}���ȋ��Z�̎��R���ł���A��R�ɃA�W�A�m�h�d�r� �`�r�d�`�m� �����̋}�����ł����āA�����͑��ݐZ�������݂����ēW�J���Ă���B
�ȉ��ł͎�Ƃ��ăo�u���̔����ɒ��ڊ֘A������P�̎���ɏœ_���i���Ă݂Ă������Ƃɂ������B�h���������ň�v���݂��v���U���Ӓ��O�̉~�̑h������͂P�h����243�~�ł��������A���̂Q�N��ɂ͂P�Q�O�~��܂ō��������B��v���������̃h�������Ƌ����������͂W�T�N�ȗ����ē��ɂ����ē����Ɋ����E�s���Y�𒆐S�Ƃ��鎑�Y�C���t���|�V�������������B���̐��E�������Y�C���t���͉��ĂɊւ��邩����W�V�N�P�O���̃j���|���|�N�s��́u�u���b�N�E�}���f�|�v�i�����\���A��37���E����40���E�p35���E��22���j�ɂ��ꉞ�I������̂ɂ������āA���{�ł͂Ȃ���������Q�D�T���̒���������ێ�����}�l�|�T�v���C���S�J�N�ɂ킽�葝�債���������߂ɁA�W�V�N�ȍ~����Ƀo�u�����c�������̂ł���B���ʁA�y�n���Y�������z�̑f�m�o�䗦�́A�P�X�W�U�N��3.7�{����6.7�{�ɁA�����������z�̑f�m�o�䗦��1.3�{����2.2�{�ւƖc����A�Z��s�s�̒n���͂W�Q�N����s�|�N�̂X�O�N�X���܂łɕ��ς�3.7�{�A���ƒn��5.4�{�ɒB�����B���̊��̍��e�N�E�t�B�|�o�|�Ԃ�͂Ƃǂ܂�Ƃ����m�炸�A���@�Ώۂ̓S���t��������獜���i�A�G��A����i�ɂ�����Ԉُ킳�ł������B
�Ƃ͂����A�W�T�N�ȍ~�̓��{�o�ς̓��������ׂĎ��̂�Ȃ����̂ł������킯�ł͂Ȃ��B�o�u���͓����ɓO�ꂵ���ȗ͉��A���t�����l����Nj�����V�s�H��̌��݂�ŐV�ݔ������Ƃ������������{�̒~�ς����������Ă����B������A�o�u������́A���������č����s���̒��ړI�_�@�͂W�X�N�T���ȍ~�̓���ɂ�鐔���ɂ킽���������i�X�O�N�W���ɂ́A6.0 ���ցj�̈��グ�ƂX�O�N�S���̑呠�Ȃɂ��y�n�Z�����ʋK���������Ƃ��Ă��A���̔w��Ɏ��{�ߏ艻�̐i�s���݂Ȃ��Ȃ�Έ�ʓI�ɂ�����Ƃ��킴������Ȃ��B
|
���R. �u�����s���v�̐��i
1989�N�A�������N�P�Q�����ɓ����،��������P�����ϊ�����38�915�~�̎j��ō��l���L�^������A�����s��̖\���͂P�X�X�O�N���߂���R�g�ɂ���тX�Q�N�W����14�309�~�܂łU�R�����}�������B����������݂邩����ŁA�����1929�N�A�����J�勰�Q�̂W�X���A�킪�����a���Z���Q��67���������Ƃ͂����A���̊Ԃ̎����]���z�͓��ؑ�P��������Ă�330���~�̌��ł���A1990�N�H����̒n���������X�P�N�������ł�200���~�̌����������炵���Ƃ�����(6)������ǂ���V���{���ʂ����ł͂������̂ł���B�Ȍ�P�X�X�P�N�S���ȍ~���{�o�ς͕s���̒J�Ԃə�Ⴕ�����A���x���\�z���ꂽ�i�C�����̓s�x���ҊO��ɏI����Ă���B���Ȃ킿1992�N�W���ȗ��X�T�N�X���܂łɑ��z59���T�牭�~���̋��z�̌����������lj�����A��������������͑O�㖢����0.5 ���ɂ܂ň����������Ȃ���A�Ȃ��X�T�N11���̓��{�̊��S���Ɨ��͋�O��3.4 ���ɒB���A���ɂQ�S�Έȉ��̎��Ɨ���96�N�R�����_�ʼnߋ��ō���8.1 ���ɂ܂ŏ㏸���Ă���(7)����Ƃ̉��Đ�i�������ۂ̐i�s�Ƃ����Ă悢�B�����o�όv�Z��p���Ă݂��ꍇ�A�X�O�N����X�T�N�ɂ����Ĕ��������y�n�Ɗ��������v�����L���s�^�����X�͖�1000���~�Ŗ��ڂf�c�o�̂Q�{�ɒB����Ƃ����邪�A�W�O�N��㔼�̓y�n�Ɗ����̃L���s�^���Q�C����1700���~�ł�����(8) �Ƃ���A�Z����Z����Ж��ɏے�����鋐�z�̕s�Ǎ��̎c���͂ނ��듖�R�Ƃ����ׂ���������Ȃ��B�o�u���͂Ȃ��A�͂��������Ă��Ȃ��Ƃ��������ł���B�Ƃ�킯���������鍡���s��������Â��Ă���̂́A�����Ə]�ƎҐ��̌����ɓT�^�I�Ɏ�����Ă���Ƃ���̉ߏ�ݔ��̑��݂Ǝ��Ƃ̑��傻���ē��{��Ƃ̊C�O�i�o�E�����Љ��A���{�Y�Ƃ̋��̐i�W�ł���B
�Ƃ���ŁA�W�O�N��ɐi�s�������E�o�ς̍\���ϊ��̓������Ȃ����̂Q�̎��Ԃɂ������G��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�悸���Z�̎��R���ł��邪�A�����1983�N�̕č��ɂ�����a���������R���ɒ[���A���{�ɂ��Ă͗��N�́u���{�~�h���ψ���v��ʂ��ċ������ꂽ���̂ł��������A���Z����ɂ�����R���s���|�^�|�֘A�̂l�d�Z�p�v�V�Ƃ����܂��ĊO���ב֓��̍��ێ���͐��N�̊ԂɂQ�O�{�ɂ��}�g�債�Ă����B���Ȃ݂ɁA1995�N�̐��E�f�Պz�͂v�s�n�i���E�f�Ջ@�ցj�ɂ��S��8000���h���ł���̂ɂ������āA��v��������s�ɂ��W�v�ŊO���ב֎�����͔N�Ԗ�T�O�O���h���Ɛ��肳���Ƃ���(9)������ł́A���̋��Z���R���ƃJ�W�m������̃o�u�������̂��܂ЂƂ̔w�i���Ȃ��Ă������Ƃ�t�������Ă����ɂƂǂ߂����B
�܂��W�O�N�㐢�E�o�ς̍\���ϊ��̑�R�ɋ��������A�W�A�o�ς̋}�����́A���ɂW�O�N��㔼���猰���ƂȂ������̂ł��邪�A���ꂪ��i���{��`�����i���ɃA�����J�A���{�j���̎Y�Ƌ��ƗL�@�I�Ɍ��т��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B1994�N�̓��{�̑ΕĖf�Ս����͂U�T�Q���h���ł���A���A�W�A�̑ΕĖf�Ս����͂U�X�T���h���ł��������A���{�̓��A�W�A�ɑ���f�Ս������U�R�U���h���ł������Ƃ������l�Ɏ��������{�E�A�����J�E���A�W�A�̂R�҂̊W(10)�͂Ƃ�킯���ڂɒl����B����ɓ��{��Ƃɂ��A�W�A�ł̌��n���Y���}�����@�B�E�@��𒆐S�Ƃ����t�A���̑����ɂ��A�X�T�N�x�̗A�����z�ɐ�߂�A�W�A����̐��i�A���̔䗦�̓h���x�|�X��40�����z���č���25.6���A�d�t��21.2����傫�����������A���̌��ʂX�T�N�x�̓��{�����ٗp�͂P�P���l���������Ǝ��Z����Ă���(11)�������\���Ɏ~�ڂ���Ă悢�B
������ɂ���A�W�O�N�㐢�E�o�ς̍\���ϊ��������炵����i���{��`���Ԃ̕s�ύt�g��A���E�I�X�P�|���ł̋}���ȋ��Z�̎��R���A���A�W�A�̋}�����Ƃ������Ԃ́A���{��`�̃O���|�o���Y���̓W�J��@���ɕ������̂ł���A���ꂪ�Q�P���I����{�I�ɋK�肵�Ă������ƂɂȂ�̂͊ԈႢ�Ȃ��B�����āA1974�N�`5�N��1980�N�Ƃ̌i�C��ނ̓������ɂ����Ă݂�ꂽ���E�z�̓��ꐫ������ɂ������̃v���U���ӈȍ~����āA�W�O�N��㔼�ȍ~�e���z���������Ă��������s�ϓ��������߂Ă���Ƃ����������A���E�o�ς̍\���ϊ��̔��f�ɂق��Ȃ�Ȃ����̂Ƃ��ďd������悤�B
|
(1)�@����j�20���I���s���̕��͎��p-�{��`��w�����s���x���߂����ģ(�w��C�o�ϊw�_�W�x��28��2���1993�N11��)�ͤ90�N�㏉���𢐢�E�����s���̗l����悵�Ă���(35��-��)�Ƃ��Ă��邪����c���ɂ����ĎQ�Ƃ����ׂ��ł��顂��̌�̌o�߂ͤ�����s���ɋꂵ�ޓ��{��96�N1���ɓ����ň���415���l�̎��Ƃ��L�^�����Ƃ͑ΏƓI�ɤ�91�N�t�Ɏn�܂�6�N�߂��}�����č��̌i�C�g��͂��������ɐ�����C�z���Ȃ�������͉������Ƃ̎��v�����������w���{�o�ϐV���x�1996�N5��6���t��Ɠ`�����邲�Ƃ����E�z�͔����ƕs�ύt���̌����������Ă���
(2)�@�����L���Y�w��ض�o�ϐ���j�x��L��t�1996�N�239��-�ޡ
(3)�@���㏑�243-4��-�ޡ
(4)�@E.F.Vogel,Japan as Number One,Havard Univ.Press(�L����ؖ{��w�ެ��ݥ��ޥ����-�݁x�TBS����ƶ�1979�N)����{�𢋭�������哱�̍��ƣ�Ƴޫ-��ق�ď����Ȃ̌����ɂ������Ģ��Ж{�ʎ�`���Βu����̂ͤ�����G�w��Ж{�ʎ�`�͕���邩�x(�⏑�X�1992�N)�ł���
(5)�@�䑺���q�w������{�o�Ϙ_�x��L��t�1993�N���6�͂��Q�Ƃ̂��ơ
(6)�@����B�Y����{�o�ό�����70�N���T�ς��飤�w���нāx�n��70���N�Վ��������1993�N5��17���37��-�ޡ
(7)�@�w���{�o�ϐV���x�1996�N4��12�������5��17���t�
(8)�@�w���{�o�ϐV���x�1996�N5��28���t�
(9)�@�� ���ꢓ��ĉ��̑勣���ŋN��������Ĥ��ޱ�ւ̎����ģ��w���нāx�1996�N6��4���74��-�ޡ
(10)�@��r �q����̐��̉�̂Ɠ��{���{��`�̊�@���w��C��w�Љ�Ȋw����������x�No.391(1996.1.),22-3��-�ޡ
(11)�@�w���{�o�ϐV���x�1996�N5��15���t�[��
�@ |
 �@ �@
���u���{�_�v 1 |
   �@
�@
|
�J�[���E�}���N�X�̒���B�h�C�c�ÓT�N�w�̏W�听�Ƃ����w�[�Q���ُؖ̕@��ᔻ�I�Ɍp�����������ŁA����܂ł̌o�ϊw�̔ᔻ�I�č\����ʂ��āA���{��`�I���Y�l���A��]���l�̐����ߒ��A���{�̉^�����@���𖾂炩�ɂ����B�S3��(�S3��)���琬��B�T�u�^�C�g���́u�o�ϊw�ᔻ�v�B�`���ɁA�u�Y�ꂪ�����킪�F�E���A�����A�����ȃv�����^���A�[�g�O�q��m���B���w�����E���H���t�ɂ������v�Ƃ̌������L����Ă���B2013�N�ɋ��Y�}�錾�ƂƂ��Ɏ��{�_���ő�1�������l�X�R�L����Y�ɓo�^���ꂽ�B
1867�N�ɑ�1�������߂Ċ��s����A1885�N�ɑ�2�����A1894�N�ɑ�3�����������ꂽ�B��1���́A�}���N�X���g�ɂ���Ĕ��s���ꂽ���A��2���Ƒ�3���́A�}���N�X�̎���A�}���N�X�̈�e�����ƂɁA�t���[�h���q�E�G���Q���X�̌��g�I�Ȑs�͂ɂ���ĕҏW�E���s���ꂽ�B
�u��4���v�ƂȂ�\�肾�����ÓT�h�o�ϊw�̊w���ᔻ�Ɋւ��镔���́A�G���Q���X�̎���A�J�[���E�J�E�c�L�[�ɂ���Č������ꂽ���A�w���{�_�x�Ƃ����\��Ɋւ���Ō��̖��A�J�E�c�L�[�́u�Ǝ��̌����v�Ȃǂɂ��A�w���{�_�x��4���Ƃ��Ăł͂Ȃ��w��]���l�w���j�x(3��4����)�̕\��Ŋ��s���ꂽ�B���̌�A�\�r�G�g�̃}���N�X�����[�j����`�������ɂ���ĐV���ȕҏW�ɂ��ł����s���ꂽ�B(�A�J�f�~�[��)����͂���ɏC�������Marks-EngelsWerke�̑�26���T�`�V�Ƃ��Ċ��s���ꂽ�B(���F���P�ł܂��͑S�W�ŁA���݂̓��{���̑����͂���ɂ��ƂÂ��Ă���)
|
�}���N�X�́A�u�V���C���V���v�̕ҏW�҂Ƃ��āA�����I�ȗ��Q�W�������ߒ��ŁA����ɁA�Љ�ϊv�̂��߂ɂ͕����I���Q�W�̊�b���Ȃ��o�ςւ̗����̕K�v����F�����A�o�ϊw�����ɖv�����Ă������B
1843�N�ȗ��A�}���N�X�͌o�ϊw�̌������J�n����B�S����̃p���ł̌�������n�܂�A9���́w�p���E�m�[�g�x�A6���́w�u�����b�Z���E�m�[�g�x�A5���́w�}���`�F�X�^�[�E�m�[�g�x�ȂǂƂ��Ă��̐��ʂ��c���Ă���B�Ȃ��A�����̃m�[�g�́A��������w���{�_�x���e�ł͂Ȃ��B
1849�N�A�}���N�X�̓����h���S����A��p�}���قɒʂ��Č����𑱂��A1850�N-1853�N�܂ł̐��ʂƂ��āw�����h���E�m�[�g�x24���������グ���B����̓}���N�X�̃m�[�g���A�ő啪�ʂ��߂�o�ϊw�m�[�g�ł��邪�A���̎����̃m�[�g�̓��e�ɂ͍��Ɗw�A�����j�A�����j�A�C���h�j�A�����j�A�܂��������ȂǁA���e�̈قȂ鑽���̘_���������Ă���A���̎����Ƀ}���N�X�̌������o�ϊw�ᔻ�ɓ��������Ƃ͂����Ȃ��B
�}���N�X���o�ϊw�ᔻ�Ɋւ��鎷�M�ɂƂ肩�������̂�1857�N����ł���B����͏��i�E�ݕ���_���邲���ꕔ�̂��̂ɂƂǂ܂�A�w�o�ϊw�ᔻ�A��ꕪ���x�Ƃ���1859�N�Ɋ��s���ꂽ�B�܂��A���̎����̌��e�́w�o�ϊw�ᔻ�v�j�x�w��]���l�w���j�x�Ƃ��āA�}���N�X�̎���ɏo�ł��ꂽ�B
�w���{�_�x���̂��̂̑��e�ōł����S�I�ƂȂ������̂́A1863�N����1865�N���܂łɎ��M���ꂽ���e�Q�ł���B�����Ń}���N�X�͂����܂��ȑS3���̑��e�̂������������I�����B�������A����͖��ӎ��Ɋ�Â��������I������Ƃ����Ӗ��ɂƂǂ܂�A������ċᖡ�E�č\�����A���͂Ƃ��ď��q�������A��������Ƃ�����Ƃ͂܂�܂�c���ꂽ�B���́u1863�N����1865�N�܂ł̑��e�v�̂��Ƃ�VMEGA�ҏW�ψ��͂܂Ƃ߂āu��3�̎��{�_���āv�ƌĂ�ł���B���������̑��e���������̂��̂ł���A�}���N�X�͂��̂��ƂɎ��o�I�ł������B���̑�2���Ƒ�3���̑��e�ɂ��ă}���N�X��1866�N�̒i�K�ŃG���Q���X�Ɉ��ĂāA�u�ł��オ�����Ƃ͂����A���e�́A���̌��݂̌`�ł͓r�����Ȃ����̂ŁA�l�ȊO�̂���ɂƂ��Ă��A�N�ɂƂ��Ă������o�łł�����̂ł͂Ȃ��v�Ǝ莆�ɏ������قǂł������B
1867�N�ɑ�1�������s���ꂽ���A���̌���}���N�X�͏��q�̉��P������Ԃ��A�u�܂������ʌ̉Ȋw�I���l�����v�Ǝ����ŏ̂���قǂɔ[���ł���łƂȂ����u�t�����X��Łv���o�ł��ꂽ�̂͂悤�₭1872�N-1875�N�ł������B���̂悤�ɁA�}���N�X�͑�1�����s��������ɉ������d�ˁA��2���Ƒ�3���̍�Ƃ͑啝�ɒx��A�n���ƕa��̒��Ŗc��Ȗ��������e���c�����܂܁A1883�N�ɐ����������B�}���N�X�͑�ςȈ��M�ł������̂ŁA��e�̓G���Q���X�����ǂ߂��A�ҏW��Ƃ͔ނɂ����s�����Ƃ��ł��Ȃ�����(��Ƀ}���N�X�̕����̓ǂݕ����J�E�c�L�[�ƃx�����V���^�C���ɓ`��)�B�G���Q���X�́A�}���N�X���₵���c��ȑ��e�ƈ��M�̑O�ɁA��Ԃׂ̍�����Ƃ�]�V�Ȃ�����A�ڂ����������Ƃ����B�Ȃ�2004�N�ɂ́A�w���{�_�x��2���̕ҏW�ɍۂ��Ă̓G���Q���X�ƂƂ��ɁA���܂Łu�G���Q���X���e�ҏW�̌��q�M�L�ҁv�Ƃ��Ĉ����Ă����I�X�J���E�A�C�[���K���e�����������x���̕ҏW��ƂɊ֗^���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B
�w�o�ϊw�ᔻ�x�Ƃ�����Ń}���N�X���ŏ��ɍ\�z���Ă����̂͑S6�҂ł��������A����͌�Ɂw���{�_�x�S4���\���ɕύX���ꂽ�B�}���N�X�́w���{�_�x�\�z�͗��_�I�W�J���琬���1��-��3���ƁA�w���j���琬���4���ł������B�������}���N�X�̐��O�Ɋ��s���ꂽ�̂͑�1��(���ł�����A�ƌꏉ�ŁA������2�ŁA�}���N�X�Z�{����ŁA���V�A���)�݂̂ŁA���ƂɎc�����͖̂c��Ȍo�ϊw�ᔻ�Ɋւ���m�[�g�ނł���B���݂����̑��e�̑����̓A���X�e���_���Љ�j���ی������A���邢�̓��X�N���̌���j�����ۊǁE�������V�A�Z���^�[�ɕۊǂ���Ă���B
|
����1��
��1���͎��{�̐��Y�ߒ��̌����ł���B
�@�����i�Ɖݕ�
���{�_�̖`����������{���Y�}�����ψ�����Љ�Ȋw���������{�_�|��ψ��������ɖ|���B
���{��`�I���Y�l�����x�z���Ă���Љ�̕x�́A����ȏ��i�W���̂Ƃ��āA�X�̏��i�͂��̕x�̗v�f�`�ԂƂ��Č�����B������A���́A���i�̕��͂��珖�q���J�n����B
�}���N�X�́A����Ȏ��{��`�o�ς��\������A�ł��P���ł���ӂꂽ�v�f�ł��鏤�i�̕��͂���o������B
���i�́A�l�Ԃ̗~�]���݂����g�p���l(�ߑ�o�ϊw�Ō����Ƃ���̌��p�̑ΏۂƂȂ����)�ƁA���̂��̂Ƃ̌����䗦�ł���킳���������l(���W�����ݕ��\���Ƃ��Ă͉��i)�����B�����W�ɂ����ꂽ�i�́A�Ȃ����l���������ƌ�����̂��B�g�p���l������������ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�g�p���l���قȂ邩�炱�������̈Ӗ������邩��ł���B�ł͏��i����g�p���l����苎��Ɖ����c�邩�B����́A���i�Ƃ́A���R���ɂȂ�炩�̐l�Ԃ̘J�����t����������J�����Y���ł���A�Ƃ������Ƃ����ł���B��̏��i�������ł���Ƃ����Ƃ��A���̏��i�̐��Y�ɔ�₳�ꂽ�J���̗ʂ��������B���������̘J���́A�V���c��ȕz�Ƃ�������̓I�Ȏg�p���l���`������悤�ȁA�ٖD�J����D�z�J���Ƃ�������̐��̂���J��(��̓I�L�p�J��)�ł͂Ȃ��B�J���̋�̐����͂��Ƃ�ꂽ���ۓI�ȘJ���A�P�Ȃ�l�Ԃ̔\�͂̎x�o�Ƃ��Ă̒��ۓI�l�ԘJ���A���̂悤�ȘJ���̐��Y���Ƃ��ē�̏��i�͓������Ƃ����B���ۓI�l�ԘJ���̋Ìŕ��A���ꂪ���l�̎��̂ł���B���l�̗ʂ��Ȃ킿���ۓI�l�ԘJ���̗ʂ́A��{�I�ɂ͘J�����Ԃɂ���Ă͂����A���̍ۂɘJ���̋��x��J���̕��G�����l�������B
����ɁA���l�ʂ��K�肷��J�����Ԃ́A���̏��i�Y����̂ɕK�v�ȌʓI�A���R�I�ȘJ�����Ԃł͂Ȃ��A�Љ�I�ɕK�v�Ƃ���镽�ϓI�J�����Ԃł���B���Ƃ��A����Љ�ɁA1��8���ԘJ����1���̃V���c�����鏤�i���Y��A�ƁA1��8���ԘJ����7���̃V���c�����鏤�i���Y��B������Ƃ���A�Љ�S�̂Ƃ��Ă�16���ԘJ����8���̃V���c�����Y����A���ς���A1���������2���ԘJ������₳��Ă��邱�ƂɂȂ�B���i���Y��A����ɂ���̂�2���ԘJ�����̉��l�A���i���Y��B����ɂ���̂�14���ԘJ�����̉��l�ł���B���������Ă悭��������悤�ɁA�ӂ��҂���������킯�ł͂Ȃ��B
���i�̉��l�́A���̏��i�̐��Y�ɔ�₳���Љ�I�ɕ��ϓI�ȘJ���ʂɂ���Č��܂�B���ꂪ�}���N�X���A�A�_���E�X�~�X��J�[�h����p�����W�������J�����l���̂���܂��ł���B
�������A���i�͎���̉��l�����������ŕ\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���鏤�i�̉��l�ʂ́A���̏��i�̎g�p���l�ʂɂ���ĕ\�������B���ꂪ�ݕ��̋N���ł���B���i�Љ�ŁA�����̏��i�̎g�p���l�ʂɂ���đ��̂��ׂĂ̏��i�̉��l�ʂ�\�����邱�Ƃ��Љ�I���ӂƂȂ����ꍇ�A���̓���ȏ��i���ݕ��ƂȂ�̂ł���B�ݕ����i�̑�\����(gold)�ł���A���̎g�p���l�ʁA���Ȃ킿�d�ʂ��ݕ��̒P�ʂƂȂ����B
�܂��A���i�̉��l���ݕ��ŕ\���������̂����i�ł���B���鏤�i�̉��i�͎��v�����̕ϓ��ɂ��A���l�Ɨ���ĕϓ����邪�A���l�͂��̉��i�ϓ��̏d�S�ɑ��݂��A�����I���ϓI�ɂ́A���i���܂ޘJ���ʂɂ���āA���l�ɂ���ĉ��i�͋K�肳���B
���i��ݕ��́A���{��������邽�߂̘_���I�O��ł���B��ʂ̏��i���ʂ́A�����̏��L���鏤�i�Ƒ���̂����i�Ƃ̊Ԃ́A�ݕ���}��Ƃ��������̉ߒ��ł���A���i�|�ݕ��|���i�ł���B���̗��ʂ́u�������߂ɔ���v�A�܂�~�������i����ɓ���A���̎g�p���l������邱�Ƃɂ���ďI���B����ɑ��āA���{�Ƃ��Ẳݕ��̗��ʂ́u���邽�߂ɔ����v�A�c�ݕ��|���i�|�ݕ��c�ł���B���̗��ʂ̖ړI�͉��l�A�������A��葽���̉��l�邱�Ƃł���A���{�Ƃ��Ẳݕ��̗��ʂ͏I��邱�Ƃ̂Ȃ������̉ߒ��ł���B���{�Ƃ́u���ȑ��B���鉿�l�v�ł���A���ꂪ�ŏ��̎��{�T�O�ł���B���{�𗝉����邽�߂ɂ́A���l�Ƃ͉����A�ݕ��Ƃ͂Ȃɂ��A���i�Ƃ͂Ȃɂ������_�I�ɖ��炩�ɂ���Ă���K�v�����������߂ɁA���{�T�O�̑O�ɏ��i�A�ݕ��A���l�Ȃǂ̊T�O����������Ă����킯�ł���B
�@���ݕ��̎��{�ւ̓]���A��]���l�̐��Y
�ł́A���{�͂ǂ̂悤�ɂ��ĉ��l���B���A�ׂ���̂��B���̓����́A���牿�l�Y�������ȏ��i���Ȃ킿�J���͏��i�����L����A�����J���҂���̍��ɂ���Ăł���B
�@�B�Ȃǂ̐��Y��i��ݕ������̂܂��{�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��B������j�I�����̉��Łu���{�v�ɓ]������B���̌���I�ȏ����Ƃ́A���Y��i�����L����u���W���A�W�[(���{�ƊK�������Y��i�̏��L��)�ƁA�����I�g����������Y��i�̏��L��������R�ƂȂ����A�J���͏��i�ȊO�ɔ���ׂ����i�����������Ȃ������J���҂̑��݂ł���B�}���N�X�͎Y�Ɗv�������̃C�M���X�ł悭����ꂽ���b�_�C�g�^�����@�B�Ȃǂ́u�����I�Ȑ��Y��i�v�ł͂Ȃ��A���́u�Љ�I�ȍ��`�ԁv���U�����ׂ����Ɣᔻ�����B
���{(���̐l�i���Ƃ��Ă̎��{��)�́A�J���҂���J���͏��i���w������B�J���҂͂��̑Ή��Ƃ��āA���������B�����͘J���͏��i�̉��i�ł���B�J���͏��i�̉��l�͂��̍Đ��Y�̂��߂ɕK�v�Ȕ�p�A���Ȃ킿�J���҂ƉƑ��̐�����ɂ���Č��܂�B�J���͏��i�̎g�p���l�́A�J�����ĉ��l�ݏo�����ƁA���������{�ƂɂƂ��Ă̎g�p���l�́A�������鉿�l�ݏo�����Ƃł���B�������ĘJ���҂����ݏo�������l���u��]���l�v�ł���A���{�Ƃ�������擾����B——���ꂪ�}���N�X�����炩�ɂ������(�J���҂����ݏo�������l�|��������]���l)�̔閧�ł���A���{�ׂ̖��̔閧�ł���B���Ƃ��Γ���1���~�̘J���҂�2���~���̉��l�ݏo���Ȃ�A��������1���~���̏�]���l�����{�Ƃ̂��̂ƂȂ�B�t�Ɍ����A��]���l�����܂Ȃ��J���ҁA�����̒����ȏ�̉��l�ݏo���Ȃ��悤�ȘJ���҂́A���{�ɂƂ��Ă͍w������K�v�����@���Ȃ��B
���{�͎g�p���l�������ړI�̂��߂ɐ��Y���s���̂ł͂Ȃ��A�����̏�]���l(�Ώۉ����ꂽ�s���J��)�̒Nj��A���Ȃ킿�u�������v�̂��߂ɐ��Y���s���B���������āA�Ⴆ������Q�삪�����A�H�Ƃ̐��Y���K�v�ł����Ă��A�������������Ȃ���Ύ��{�͐��Y�͂��Ȃ��B�t�ɕ���ȂǎЉ�ɂƂ��ėL�Q�Ȃ��̂ł��A���������o��Ύ��{�͐��Y����B�}���N�X�͂��̂��Ƃ��w���{�_�x�̒��ŁA�u�܂����Ɏ��{��`�I���Y�ߒ��̐��i�I�ȓ��@�ł���K��I�ȖړI�ł���̂́A���{�̂ł��邾���傫�Ȏ��ȑ��B�A���Ȃ킿�ł��邾���傫����]���l���Y�A���������Ď��{�Ƃɂ��J���͂̂ł��邾���傫�ȍ��ł���v�Ə������B
�@����]���l���Y�̓�̕��@��ΓI��]���l���Y�Ƒ��ΓI��]���l���Y
���{���擾�����]���l��������ɂ͓�̕��@������B���ɁA�J���͂̉��l(�܂��͂��̉��i�\���ł������)�����ł���Ȃ�A�J�����Ԃ����������邱�Ƃł���B����1���~�̘J���҂�8���ԘJ����2���~���̉��l�ݏo���Ƃ��A12���ԘJ���ɉ��������3���~���̉��l�ݏo���A��]���l��1���~����������B������ΓI��]���l���Y�Ƃ����B�������A���̕��@�ɂ͌��E������B�܂�1����24���Ԃ����Ȃ��B����ɒ����J���҂͘J�����Ԃ̒Z�k�����߂ĘJ���g����g�D���Ď��{�Ƃɒ�R����B
�����ŁA�Ƃ�����̕��@�́A�J�����Ԃ����Ȃ�ΘJ���͂̉��l�܂��͒��������炷���Ƃł���B��قǂ̘J���҂̓�����������1���~����5��~�ɔ���������A��]���l��2���~����2��5��~�ɑ��傷��B����𑊑ΓI��]���l���Y�Ƃ����B�������A���O��ɘJ���͂̉��l�����炷���Ƃ͂ł��Ȃ��B�J���͂̉��l�܂��͒����́A�J���͏��i�̍Đ��Y��A�܂�J���҂Ƃ��̉Ƒ��̐�����ɂ���Č��܂��Ă���B���{�̑��������I�ɒ��������炷���Ƃ́A�J���҂��s�\�ɂ��A�J���͏��i�̍Đ��Y��s�\�ɂ�����B�����J���҂Ȃ����Ď��{�͏�]���l���Y�ł��Ȃ�����A�Z���I�ɂ͂Ƃ����������I�ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͕s�\�ł���B�ł͂ǂ����邩�B����͐��Y�͂̏㏸�ɂ���ĉ\�ƂȂ�B���Y�͂��㏸�����A�J���҂̐�����i���\�����鏤�i�̉��l�������Ȃ�A�J���҂̐�����������Ȃ�A�J���͏��i�̉��l���ቺ���A���������������Ă��J���͂̍Đ��Y���\�ƂȂ�B�����������邽�߂ɂ́A���Y�͂���{�ƂȂ�悢�̂ł���B�X�̎��{�͂������ȏ��i��ڎw���Đ��Y�͂��㏸�����邽�߂ɁA���݂ɋ������Ă���B���̋����������{���������A�X�̏��i�����������A����������������A����������������O��ݏo���Ă���B
���Y�͂��㏸�������i�ɂ́A���ƁA���ƂɊ�Â����ƁA�����J���@�B����H�Ƃ�����A�}���N�X�͂��ꂼ��ɂ��ĕ��͂��Ă���B
���{���{��`�ɂ����鐳�Ј��̒����ԉߖ��J���͐�ΓI��]���l���Y�̊T�O�ɂ���āA�Ј��̒�����͑��ΓI��]���l���Y�̊T�O�ɂ���āA�悭�������邱�Ƃ��ł���B
�@�����{�̒~��
�����J���҂���悵�Ď��{��������]���l�́A���{�Ƃ̏��L����Ƃ���ƂȂ�B���{�Ƃ͂����S�ď���邱�Ƃ��\�����A�u���{�̐l�i���v�Ƃ��Ă̎��{�Ƃ͌l�I�����ߖāA��]���l���Ăю��{�ɓ]�����A���{�~�ς������Ȃ���(��]���l�̎��{�ւ̓]��)�B�������玑�{�Ƃ́u�֗~�v�̌��ʁA�x���~�ς����Ƃ����Љ�I�ӎ��������A�֗~��P�Ƃ���v���e�X�^���e�B�Y�������{��`�̐��_�ƂȂ�(�}�b�N�X�E���F�[�o�[�w�v���e�X�^���e�B�Y���̗ϗ��Ǝ��{��`�̐��_�x)�B
���{�̒~�ς̉ߒ��́A�܂��܂������̒����J���҂����{�ɕ�ۂ���邱�Ƃł���A���{�|���J���W�̊g��Đ��Y�ł���B���j�I�Ƀ��[���b�p�ł́A�r�ѐ��Y�̂��߂ɕ����̎傪�_����y�n����ǂ��o���͂����݂ɂ���āA�_������쒀���ꂽ�_�����A�Y�Ɠs�s�ɈڏZ���v�����^���A�[�g�ɓ]�������B���{��`�̏����Ɍ����A���Ƃ̖\�͂𗘗p�����v�����^���A�[�g�̑n�o��{���I�~�ςƂ����B
�܂��A���ΓI��]���l���Y�ɔ������Y�͂̑���́A��]���l����]������鎑�{�ɂ��āA�s�ώ��{(���Y��i�w���ɓ�����ꂽ���{)�ɑ���ώ��{(�J���͍w���ɓ�����ꂽ���{)�̔䗦�𑊑ΓI�ɏ��������Ă���(���{�̗L�@�I�\���̍��x��)�B�������Ē����J���҂̂܂��܂������̈�蕔�����A���ΓI�ߏ�l��(���Ǝ҂┼���Ǝ�)�ɓ]������B���{��`�I���Y�̂��Ƃł́A����Ŏ��{�Ƃ̑��ɂ͕x���~�ς���A�����Œ����J���҂̑��ɂ͕n�����~�ς���Ă����B������}���N�X�́u���{�~�ς̓G�v�ƌĂѐ��Y�W�̊ϓ_���炩�炱�̌��ۂ͂��������́w�N�w�̕n���x��2�͑�1�߂����p���Ă���B
���{�~�ς̔��W�ɔ����āA���Y�͎���ɏW�ς��A���R�����͓Ɛ�ւƓ]������B�����J���҂ɂ���ĒS���鐶�Y�̎Љ���i�ވ���ŁA�ˑR�Ƃ��ĕx�̎擾�͎��{�ƂɈς˂��Ď��I�Ȃ܂܂ł���A���{�ƒ��J���̊Ԃ̖����͂܂��܂��傫���Ȃ�B���̖��������{��`�́u�����̏��v�ƂȂ�A�ƃ}���N�X�͑�1�������ԁB
��1���ł́A��]���l�����Y�ߒ��ɂ����Ē����J���҂���̍��ɂ���Đ��ݏo����Ă��邱�Ƃ��������B��]���l�͗����A���q�A�n��̖{���A���̂ł���A�����A���q�A�n��͏�]���l�̌��ی`�Ԃł���B�����ɂ��ẮA��3���ŕ��͂����B
����2��
��2���͎��{�̗��ʉߒ��̌����A���Ȃ킿�A���{���I���Y�l���̍Đ��Y�Ɋւ��錤���ł���B��1�����}���N�X���g���\���⏖�q�̎d�グ�A���s�܂Ŋւ�����̂ɑ��A��2���́A�}���N�X�̎���A�c����Ă����������̑��e(��2���̃G���Q���X�ɂ�鏘�����Q��)���G���Q���X���ҏW�A���s�������̂ł���B
��1�тƑ�2�т͎��{�̏z���]�Ȃǂ������Ă���A�ʎ��{�̗��ʉߒ��ł̉^�����l�@�����B����Ύ��{�Ƃ��o�c�̏�Ŏ��{�̓��������鎞�Ɠ������_�ł���B���ہA�}���N�X�́A�H��o�c�҂ł������G���Q���X�ɂ����Ύ��{�̉�]���Ȃǂɂ��ďƉ�̎莆�𑗂�A�o�c�̃��A���Ȍ����ɂ�����������w�сA���̑��e�ɔ��f�����Ă���B
��3�т͎Љ�S�̂ɂ����鎑�{�̗��ʉߒ��̌����ł���B�u�Đ��Y�_�v�ƌĂ�闝�_����ŁA�Љ�I�����{�̊ϓ_����A���{���I���Y�l�����ێ��E�������邽�߂ɁA���{�̐��Y�E���ʁE�ē������A�ǂ̂悤�Ȑ���E�����̉��ł����Ȃ��Ă��邩���l�@�������̂ł���B�}���N�X�̓t�����\���E�P�l�[�̌o�ϕ\�Ɏh�����Ȃ���u�Đ��Y�\���v�Ƃ��郂�f�������肠���A�}�N���I���_���玑�{�̗��ʁE�z��_�����B
����3��
��3���́A���{��`�I���Y�̑��ߒ��̌����ł���B��3������2���Ɠ��l�ɁA�}���N�X���g�̎�Ŋ��s���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�}���N�X�̑��e���G���Q���X���ҏW(��3���̃G���Q���X�ɂ�鏘�����Q��)�������̂ł���B
��3���͑�1���Ƒ�2���̌������ӂ܂��A���{��`�o�ς̈�ʓI�E���ՓI�ȏ����ۂł����p���i�A�����A���ϗ������A�������̌X���I�ቺ�̖@���A���q�A�n��Ȃǂ������A���{��`�o�ς̑S�̑��̍č\�������݂��B
|
���w���{�_�x�̕��@
�}���N�X���w���{�_�x�ŗp�������@�́A���{��`�Љ�S�̂̍��ׂƂ����\�ۂ�O���ɂ����A���͂Ƒ����ɂ���Ď��{�T�O���m�肵�A�L���ȕ\�ۂ͂��Ȃ�����������{�T�O��L���ɂ��Ă������Ƃ�ʂ��āA���{��`�Љ�̑S�̑����T�O�I�ɍč\������Ƃ����A���͂Ƒ�������b�Ƃ���ُؖ@�I���@�ł���B
�u�\�ۂ��ꂽ��̓I�Ȃ��̂���A�܂��܂����Ȓ��ۓI�Ȃ��̂ɂ����݁A���ɂ́A�����Ƃ��P���ȏ��K��ɂ܂œ��B����ł��낤�B�������炱��ǂ́A�ӂ����т��Ƃ��ǂ�̗����n�܂�͂��ł����āA�Ō�ɍĂѐl���ɂ܂œ��B����ł��낤�B��������Ǔ��B����̂́A�S�̂̍��ׂƂ����\�ۂƂ��Ă̐l���ł͂Ȃ��A�����̏��K��Ə��֘A���Ƃ��Ȃ����L���ȑ��̂Ƃ��Ă̐l���ł���v(�}���N�X�w�o�ϊw�ᔻ�����x)�B
���ꂪ�}���N�X���w���{�_�x�ŗp�����u�㏸�E���~�v�ƌ�������@�A�w�[�Q���ُؖ@�̔ᔻ�I�p���Ƃ���Ă�����̂̊j�S�̈�ŁA���̕��@�̊j�S�́A�B���_����b�Ƃ��镪�͂Ƒ����ɂ��Ώۂ̊T�O�I�č\���ł���B�w���{�_�x�̃T�u�^�C�g�����u�o�ϊw�ᔻ�v�ł���̂́A�����̎嗬�ł������ÓT�h�o�ϊw�Ƃ�����p�����o�ϊw(�}���N�X�̈����ɂ��u�����o�ϊw�v)�ւ̔ᔻ��ʂ��Ď�����ł����Ă�����ł���B
�}���N�X���w���{�_�x�ɂ����āA�ÓT�h��ᔻ�������̒��S�_�́A�ÓT�h�����{��`�Љ���j�I���i�������Ƃ������ɁA�u���R�Љ�v�ƌĂ�ŁA������������ՓI�ȎЉ�̐��ł��邩�̂悤�Ɍ��Ȃ����Ƃ����_�ɂ���B���Ȃ킿���{��`�Љ�͗��j�̂��鎞�_�ŕK�R�I�ɐ������A���W���A�₪�Ď��̎Љ�x�ւƔ��W�I�ɉ�������Ă����A�Ƃ����u���j���v�����Ă��Ȃ��Ƃ����̂��B
�}���N�X�́w���{�_�x��1���́u���Ƃ����v�ɂ����āA���̂��Ƃ��w�[�Q���ُؖ@�Ɍ��y���Ȃ���A�����q�ׂ��B�u���̍����I�Ȏp�Ԃł́A�ُؖ@�́A�u���W���A�W�[�₻�̋�_�I��َ҂����ɂƂ��ẮA���킵�����̂ł���A���낵�����̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A���ُؖ̕@�́A����������̂̍m��I�����̂����ɁA�����ɂ܂��A���̔ے�A�K�R�I�v���̗������܂݁A�ǂ̐��������`�Ԃ����^���̗���̂Ȃ��ŁA���������Ă܂����̌o�ߓI�ȑ��ʂ���Ƃ炦�A�Ȃɂ��̂ɂ���Ă��Ј�����邱�ƂȂ��A���̖{����ᔻ�I�ł���v���I�ł��邩��ł���v�B
�}���N�X�o�ϊw��}���N�X��`���قډ��(�H)�����悤�Ɍ����錻�݁A���̃}���N�X�o�ϊw���w�ׂȂ���Ȃ�Ȃ����Ɩ����Ȃ�A�������{��`�ɖ@��������Ȃ�A�����Ă����F�߂�Ȃ��(���邢�́A���邩���m��Ȃ��Ǝv���Ȃ�)�A���l�_(���{�_�ł̉��l�_�ɍS��K�v�͖���)���猤�����n�߂鑼�͖����A�]���Ď��{�_�̌������X�^�[�g�ɂȂ邾�낤�B
���w���{�_�x�̒��̋��Y��`�_
�w���{�_�x�́A���{��`�I���Y�l���Ƃ���ɏƉ����鐶�Y�E���Տ��W��������������ł���A���Y��`�̖������f����`��������ł͂Ȃ��B�������A�}���N�X�͎��{��`�̏��������A���{��`�ȑO�̐��Y�l��(�������A�z�ꐧ�Ȃ�)�̏ꍇ��A�����̋����Љ�(���Y��`�Љ�)�̏ꍇ�Ƃ����ΑΔ䂵�Ă���B
�w���{�_�x�S3���̒��Łu���Y��`�Љ�v�ƋL�ڂ���Ă���ӏ��͑�ꕔ�́u���Y��`�Љ�łͤ�@�B�ͤ�u���W�����Љ�Ƃ͂܂������قȂ��������͈͂����v�Ƒ�́u���Y��`�Љ�ł͎Љ�I�Đ��Y�Ɏx�Ⴊ�o�Ȃ��悤���炩���߂�����Ƃ����v�Z���Ȃ���邾�낤�v�̂킸��2�ӏ��ł���B�}���N�X�͎��{��`�Ƃ͈قȂ鋦���I�Ȑ��Y�l�����A�u�����I���Y�l���v�A�u���������J���̗l���v�A�u�����I���Y�v�A�u�Љ���ꂽ���Y�v�Ȃǂƕ\�����Ă���B���ڍׂȋK��Ƃ��ẮA�u�����I���Y��i�ŘJ�������������̑����̌l�I�J���͂����o�I�Ɉ�̎Љ�I�J���͂Ƃ��Ďx�o���鎩�R�Ȑl�X�̘A���́v(��1����1��)�A�u�J���҂������������g�̌v�Z�ŘJ������Љ�v(��3����1��)�A�u�Љ�ӎ��I���v��I�Ȍ����̂Ƃ��đg�D�v(��3����6��)�Ȃǂ�����B
�܂��A�w���{�_�x�ɂ����č��Ƃ͏d�v�ł͂Ȃ��A�u�ӎ��I�v��I�Ǘ��v(��1��)�u�ӎ��I�ȎЉ�I�Ǘ�����ыK���v(��3��)�Ƃ������`�Ŏs��́u�����{���v�𗝐��ɂ���ċK������Ƃ�����ʘ_���q�ׂ��Ă��邾���ł���B
�}���N�X�́w���{�_�x��3���ŁA�u���R�̍��v(���R�̉����Ƃ�)�Ɓu�K�R�̍��v�̖��ɐG��A���Y��`�v���̖ړI���q�ׂĂ���B���Ȃ킿�A�o�ς����{��`����]���l(������)�̒Nj�����������A�Љ�̍����I�ȋK���̉��ɕ����ĎЉ�̕K�v�ɑ��鐶�Y�Ƃ����o�ϖ{���̂���������邪�A����ł����Y�͐l�Ԃ��������Ă�����ŕK�v�ȕx�����肾�����߂̍S���I�ȘJ��(�K�R�̍�)���v��B�������A���̎��Ԃ͎��ԒZ�k�ɂ���Ď���ɒZ���Ȃ�A�]�Ɏ���(���R�̍�)���g�傷��B�w���{�_�x��3���ł́A���̎��Ԃ̊g��ɂ���Đl�Ԃ̑S�ʔ��B�������Ȃ��A�l�Ԃ���������ƃ}���N�X�͎咣�����B
���w���{�_�x����
���X�̃}���N�X�̃v�����Ɋ�Â��w���{�_�x�̕����ɂ��Ă͗l�X�ȋc�_�������Ă���B���݁A�}���N�X�ƃG���Q���X�̑S�Ă̒��앨�����s����VMEGA�̎��݂����ۓI�ȋ�����Ƃōs���A���̒��Łw���{�_�x�̍\���ɂ��Ă��ᖡ����Ă���B���̐VMEGA�ɂ������II���u�w���{�_�x����я����J��v�S15��24�����̕ҏW��L�E�~�V�P�[���B�`�AL�E���@�V�[�i�AE�E���@�V�`�F���R�A��J���V��AC�EE�E�t�H���O���[�g�AR�E���[�g�AE�E�R�b�v�t�A�呺��AM�E�~�����[�ȂNJe���̌����҂ɂ��A�i�߂��Ă���B
�����̓��{���͍����f�V��ɂ����̂ŁA���������������̗��w�����Љ��`�E���Y��`�𒆍��Ɏ����A�����ƌ�����(�Ȃ��A�����ւ̔����ł��銿�w�҂̒����[(�[��)���A���{���ɐ�Ċ�������s�������̂́A���e�͖ʔ��������͂������ł���Əq�ׂāA���̂܂ܕ������Ă��܂����ƌ����Ă���)�B���{�_�̓ǂݒ����́A�t�����X�̃��C�E�A���`���Z�[������{�̜A���A�����m�i�A���J�s�l��ɂ���čs���Ă���B
���ᔻ
Questionbook-4.svg���̐߂͌��؉\�ȎQ�l������o�T���S��������Ă��Ȃ����A�s�\���ł��B�o�T��lj����ċL���̐M��������ɂ����͂��������B(2016�N1��)
�}���N�X��`��ʂ�ᔻ���������w�h�͑������邪�A�w���{�_�x���̂��̂�ᔻ������\�I�Ș_�҂̈�l�ɃI�[�X�g���A�̌o�ϊw�҂ŃE�B�[���w�h�̃I�C�Q���E�t�H���E�x�[�����o���F���N������B�x�[�����o���F���N�́A�w�}���N�X�̌n�̏I���x�̂Ȃ��ŁA�}���N�X����1���ł͉��l�͓����J���ʂɂ���Č��܂�Ƃ����Ă���̂ɁA��3���ł͂���Ƃ͕ʂ́A�����ϓ��ɂ��ƂÂ����Y���i�ƕ��ϗ������̗��_�������o���Ă���Ƃ��āA������w���{�_�x�̑�1���Ƒ�3���̖����Ɣᔻ�����B
�܂��A���̖��Ɋւ���āA���l�����i�ɓ]������ۂɁA�����l�������Y���i���т����Ƃ���}���N�X�̗����ᔻ�����h�~�g���E�G�t�E�{���g�P���B�b�`�Ȃǂ�����B�����̂��āu�]�`���_���v�Ƃ����B
�����̑�
�\�ۂ��ꂽ��̓I�Ȃ��̂̓O��I�ȕ��͂���c�_���i�ނ��߁A�}���N�X�̐��������̐����K���i��l�X�Ȃ��̂̉��i�̋L�ڂ������A�����̈�ʘJ���҂̐������f�������Ƃ��Ă��M�d�ł���A�Ƃ�������������l������B(����Ԃ�Ԋ��A�ځA�w���{�_�x�[�~�i�[���Q��)
2013�N6���ɂ͂��̃h�C�c��ŏ��ő�1�����A1848�N�́w���Y�}�錾�x�̑��e�Ƌ��Ƀ��l�X�R�̐��E�̋L���ɓo�^���ꂽ�B
|
�����{�_�̗v��
�u�l�Ԃ̘J����������x�̌���ł���A���{�Ƃ́A�J���͂�����ĘJ���҂����A�V���ȉ��l���t�����ꂽ���i��̔����邱�Ƃɂ���ė��v���グ�A���{���g�傷��B���{�Ƃ̌����������ɂ�薳�����Ȑ��Y�͋��Q�������N�����A�J���҂͐�������������B�J���҂͑�H��œ������Ƃɂ��A���l�Ƃ̒c���̎d�����w�сA�g�D�I�ȍs�����ł���悤�ɂȂ�A�₪�Ċv�����N�����Ď��{��`��]��������B�v
�u�l�Ԃ̘J����������x�̌���ł���A���{�Ƃ́A�J���͂�����ĘJ���҂����A�V���ȉ��l���t�����ꂽ���i��̔�����v
�J����������x�̌���ł��闝�R�́A�����������i�����o���ɂ͘J�����K�v������ł��B
�앨�����n����ɂ��l�̎�Ŏ��n���Ȃ�������܂��A�@�B��ɂ��Ă��J�����K�v�ɂȂ�܂��B���l�̂��鏤�i�ݏo���ɂ́A�K���J�����K�v�ł��邱�ƂɋC�Â����}���N�X�́A�J���ɂ���ď��i�̉��l�����܂�ƍl���܂����B�����ď��i�̉��l�͂����ɕς��邱�Ƃ��ł���̂ŁA�J���̉��l�������ɕς��邱�Ƃ��ł��܂��B�܂菤�i���J���������Ƃ����������藧���܂��B
�����܂ł��A�J����������x�̌���ł�������ł��B
���ɁA���{�Ƃ́A�J���͂�����ĘJ���҂����A�V���ȉ��l���t�����ꂽ���i��̔�����̐����ł��B
���{�Ƃ́A���{�������Ƒ��₵�����Ǝv���Ă���l�Ԃł��B���{�𑝂₷�ɂ́A�J���͂��g���ď��i�ݏo�����A���݂��Ă��鏤�i�ɐV���ȕt�����l��t���Ĕ��肾���K�v������܂��B
�Ⴆ�A�J���͂��g���ď����������o�����Ƃ��܂��B���ꂾ���ł����l�͂���܂����A���̏��������g���ăp���ɂ��邱�Ƃŕt�����l�����A�����������������l���t���܂��B�������ĘJ���͂��g�����ƂŁA���i�̉��l�𑝂₵�Ă��������ł���̂ł��B�܂��A������O�ł���ˁB
�u���{�Ƃ̌����������ɂ�薳�����Ȑ��Y�͋��Q�������N�����A�J���҂͐�������������B�v
���{�Ƃ́A���ׂ��̂��߂Ɏ��{�Ɠ��m�Ō������������n�߂܂��B���̌����������ɂ͕t�����l��t���邱�ƈȊO�ɂ��A�J���҂�O��I�ɓ������A���������i�ݏo�����Ƃ��n�܂�ł��傤�B
�������i�Ƃ����̂́A���i�̉��l���������Ă���Ƃ������Ƃł��B���i�̉��l��������Ƃ������Ƃ́A�J���͂̉��l��������Ƃ������Ƃł�����A�J���҂̒����̒ቺ�Ɍq����܂��B
�܂�A�ߓx�̐��Y�́A���i�̉��l�������A�J���҂̉��l��������̂ł��B
��Ђ̂��߂ɃT�[�r�X�c�ƂȂǂ����Ĉꐶ���������Ă���̂ɁA���̓����������̎����̉��l�������邱�ƂɌq�����Ă���Ȃ�ĐȂ��ł��ˁB
�u�J���҂͑�H��œ������Ƃɂ��A���l�Ƃ̒c���̎d�����w�сA�g�D�I�ȍs�����ł���悤�ɂȂ�A�₪�Ċv�����N�����Ď��{��`��]��������B�v
�J���҂��H��œ���������ق����@�B��H�����ɏW�������邱�Ƃ��ł���̂ŁA���{�Ƃ͑����̗��v�ݏo�����Ƃ��ł��܂��B���̂����A�吨�œ������ƂŁA���C���h�����\�͂����߂邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�����āA��H��œ����Ă���吨�̘J���҂́A���l�Ƃ̒c���̎d�����w�јJ���g�����������A�X�g���C�L�ȂǑg�D�I�ȍs�����ł���悤�ɂȂ�A�c�����������̘J���҂��A�₪�Ċv�����N�����Ď��{��`��]�������܂��B
�����܂ł��}���N�X�����������{�_�̊ȒP�ȗ���ł��B
���܂Ƃ�
���{��`�̎d�g�݂Ƃ��āA���{�Ɠ��m�ŋ�������������Ƃ����{��Ɛ肵�n�߂܂��B��������Ƃ͘J���҂𑽂��������邱�ƂɂȂ�܂����A�吨�̘J���҂��c�����邱�ƂŎ��{�ɕ����Ȃ��͂�̂ŁA���{��`���]�����Ă��܂��\��������B�ƃ}���N�X�͌����Ă��܂��B
������g�D�����J���҂��A���{��`�����V���Ȏ�`���ł��邱�Ƃ��}���N�X�͊���Ă����̂ł����A�g�D�����J���҂��v�����N�������Ƃ͂Ȃ��A�\�A�⒆���ł͘J���҂ł͂Ȃ��l�Ԃ��g�b�v�ɗ����A���Ƃ��J���҂��Ǘ�����Љ��`�����܂�Ă��܂��܂����B
�}���N�X��`�ƌ����Ă��܂����A�}���N�X������Ȃ��ƂɂȂ�Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�Ō�Ɏ��{�_�ɏ�����Ă��鎑�{��`�������炵���f�����b�g�������Ă����܂��B�h����A�T�[�r�X�c�ƁA���[�L���O�v�A�A�ߘJ���A���Ǝ҂̑����A�i���Љ�B |
 �@ �@
���u���{�_�v 2 |
   �@
�@
|
�����{�_
�u���{�_�v�̓J�[���E�}���N�X�ɂ����150�N�ȏ�O�ɏ����ꂽ�{�ł��B�}���N�X�͎��{��`���@���ɔ�l�ԓI�Ȃ��̂ł���̂��͂��A��������Љ��`�^���A���Y��`�^�����L�����Ă����A�₪�ă\�r�G�g�Љ��`���a���A�M���a�����A��������f���Ƃ��Ē��ؐl�����a���A���N�����`�l�����a�����ł��A�����[���b�p�̍��X�����X�ƎЉ��`�̍��ւƕω����Ă����Ƃ�����僀�[�u�����g�������z���܂����B���߂Ċm�F���Ă݂�Ƃ��������Ƃł��ˁB���E��ς����Ƃ����Ă��ߌ��łȂ��Ƃ������Ƃ��ǂ��킩��܂��B���́u���{�_�v��1867�N�̔��������͔��s����1000�����S�Ĕ����܂łɂ��̂��������Ԃ�v�����Ƃ����L�^������܂��B�����������o�Ė|��Đ��E�ɍL�܂�A���{��ł͗v��400�����̍��������ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B
���̂�������x�X�g�Z���[�ƂȂ�킯�ł����A����������������Ă��邩�Ƃ����̂́A���{��`�͂������e�ł��B���̏��Ղ̈�����Љ�܂��B
�u���{��`���Y�l�����N�Ղ���Љ�ł́A�Љ�̕x�́u����ȏ��i�W���́v�̎p���Ƃ��Č����A�ЂƂЂƂ̏��i�͂��̕x�̗v�f�`�ԂƂ��Č����B���������āA��X�̌����͏��i�̕��͂���n�܂�B�v
��������ݍӂ��Ċ�߂���Ɓu���{��`�Љ�ł͂��ׂĂ����i�ɂȂ��Ă���v�Ƃ������Ƃł��B�����Ȃ�ƂЂƂЂƂ̏��i���ǂ�Ȃ��̂����͂���ΑS�̑��������Ă��邾�낤�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B
���āA�ł͋��ɂ̖��ł��B
�u����͋��Ŕ�����̂��v
���̒r�コ��̉���͑�w�̊w����Ώۂɍs���Ă��̂ŁA���ۂɍu�`�̍ۂɊw���Ƃ��������Ă��܂����B���̒��ł�
�u���{��`�o�ς̉��ł͂��ׂĂ����i�ƌ������Ƃ͈�����ς����Ȃ����Ǝv���܂����B�v
�u������l�����邵�����Ȃ��l������Ǝv���܂��B���z����ł͂Ȃт��Ă��܂��ЂƂ����邩��B���͂Ȃт��Ȃ��Ǝv���܂��B�v
�Ȃǂ̈ӌ����o�܂����B��������҂̈ӌ��������������ɒr�コ�u���Ⴀ�D���Ȑl�͂ǂ�ȕn�R�ł������H�v�Ǝ��₳���ƏȂ���ق��Ă��܂��܂����B���Ƀ��A���ȑΉ����Ǝv���܂��B��
�ЂƂ���o���܂��B
�������ނ��f�[�g�̂��߂ɋ���ȃe�[�}�p�[�N��݂���ɂ��Ă��ꂽ�炻��͂���͊������v���܂��H�����̂��Ƃ������Ă���Ă��邩�炾�ƁE�E�E�B�������A��������z�̕x���Ȃ���Ȃ����Ȃ����ƁB�܂茋�ʓI�Ɉ�����Ƃ��������ƂɂȂ�̂ł��낤���E�E�E�B
���̍u�`�̒��ł͂��̖��ɂ��Ă̓����͏o�����ɏI���܂������A�r�コ�����������������̂��ƌ����ƁA����Ƃ������i�ɂȂ肦�Ȃ��悤�Ɏv�����̂ł��A�낤������ɂ���E�E�E�E���{��`�Ƃ͖{���ɑS�Ă����i�ɂȂ��ďz���Ă���Љ�Ȃ̂��Ƃ������Ƃł��B�����Ă��̏��i�́u�Ȃ����i�Ȃ̂��H�v�Ƃ������Ƃ����Ă����Ƃ������Ƃ��}���N�X�̎��{�_�̘_�����ĂɂȂ�̂ł��B
|
�����i�̉��l
�}���N�X�͏��i�̉��l���l�������ɓ�̉��l�����o���܂����B
��1�@�g�p���l
��ڂ̉��l�́u�g�p���l�v�B���̏��i���ǂ̂悤�Ɏg�p���邱�Ƃ��o���邩�Ƃ������Ƃɂ����鉿�l�ł��B�Ⴆ�����ȃu�����h���̃V���c�ɑ���u�g�p���l�v�Ƃ͉��ł��傤���B�V���c�̎g�p���l���l����u���邱�Ɓv���ł��邾���ł��̎g�p���l���܂��Ƃ��ł��܂��B�������u�����h���͍����ł���ˁB�����ɂ́u���S�n�������v�A�u���\�������v�A�u�u�����h�̃��S������v�Ȃǂ̎g�p���l������̂ł��B
��2�@�������l
��ڂ̉��l�͑��̏��i�ƌ����ł���Ƃ����u�������l�v�B���̌������l�ƌ����͕̂��ƕ��͂������A�����Ƃ��̂������ł��܂��B�����Ă����͋��ƌ����o���܂����B���ꂪ���̎���������������Ƃ��đ��݂��Ă��鏊�ȂƂȂ��Ă��܂��B
|
������
��͕̂��X���������Ă��̂B���Ă��܂����B���t�͓����H�ׂ����Ȃ�A�t�͋����H�ׂ����Ȃ�E�E�E���ʗ��҂��o��ƕ��X�������������܂��B�������A����͋��R���d�Ȃ�Ȃ��Ɣ������܂����ˁB�ł͂ǂ����邩�B�݂�Ȃ��~��������̂ɂƂ肠�����ς��Ă��������Ƃ����l���Ɏ���܂��B�����̂Ȃǂ͕����Ă��܂��܂�����ˁB�����ŊF���~������z��A�ۑ��̂�����Ȃǂ����X�����̒�����ɂȂ��Ă����܂��B�����ł͎q���L�����̒�����ɑI��Ă��܂����B������ے����邩�̂悤�Ɂu���Y�v��u�M�d�i�v�A�u�d�G�v�Ȃǂ����ɂ܂�銿���ɂ́u�L�v�������Ă��܂���ˁB���̒�����������ȂǂɂȂ�A�₪�Ă������a������̂ł��B
�e�Ղɑz���������Ǝv���܂����A�����̒a���ɂ���Ă��̕��X�����͔����I�ɃX���[�Y�ɍs����悤�ɂȂ�܂����B�������A�}���N�X�͂��ꂱ�����댯�ł���Ɛ����܂����B���i������A������Ă����Ɋ����܂��B�����Ă��̂����ɂ���Ă���ɏ��i���w�����܂��B���i�����������i�ƌ����T�C�N���ł��B�������A���̃T�C�N���ɋt�]���ۂ��N���Ă��܂��B�����������āA���i���A���̏��i�邱�Ƃł����悤�Ƃ��܂��B���������i�������̃T�C�N���ł��B����͂������̂𑝂₻���Ƃ��铮���ɑ��Ȃ�܂���B�܂莑�{�Ƃł��ˁB
|
���J���͂̒a��
�����A���̃V�X�e���ł͑O��艿�l�𑝂₳�Ȃ�������܂���B����͘J���͂������Ă͂��߂Ăł��邱�ƂȂ̂��Ƃ������Ƃ��}���N�X�͔������܂��B
�u���鏤�i�̏���牿�l�������o�����߂ɂ́A�ݕ������҂͗��ʌ��������Ȃ킿�s��ɂ����āA���̎g�p���l���̂����l�̌���ƂȂ�悤�ȓƓ��̐����������i���^�ǂ���������K�v������B���̏��i�́A�����ɂ��������邱�Ǝ��̂��J���̑Ώۉ��A���Ȃ킿���l�n���ƂȂ�悤�ȏ��i�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�����Ď����A�ݕ������҂͎s��ł��̂悤�ȓ���ȏ��i������B�J���\�͂��Ȃ킿�J���͂�����ł���B�v
���i�̏�������邱�Ƃł���ȏ�̉��l�����o�����߂ɂ͘J���͂��K�v�ƌ������Ƃł��B
���鎑�{�Ƃ����i����邽�߂ɂ������čH������݂��܂����A��������݂��������ł͂ł��܂���B�����ɘJ���͂������ď��߂ĖړI�̏��i�̐��Y���\�ɂȂ�܂��B����邱�ƂŐV���ȉ��l�ݏo�����́A���ꂪ�J���͂Ȃ̂ł��B�J���҂̒a���ł��B�J���҂́u�J���͂邱�Ɓv�����{�Ƃƌ_������т܂��B�ꌩ���X���������Ă���Γ��Ȉ�ۂ��܂����A���ꂪ�z��̂悤�Ȉ����݁A�i���Љ���`�����Ă����܂��B���{�Ƃ͏����ł��J���҂��������邱�Ƃɂ���ė��v���オ��܂��B���̂��ߒ����ԘJ����������悤�ɂȂ�A�J���҂͊w�Z�Ȃǂɒʂ����Ԃ������Ȃ��Ă��Ė��m���L����܂��B����ɂ���Ă���ɘJ���������邱�Ƃ��e�ՂȊ������܂�A���{�Ƃ͂ǂ�ǂ�x��~�ς���̂ɑ��ĘJ���҂͕n���Ɩ��m���~�ς��Ă����Ƃ������ɑ傫�Ȋi�������܂��Ƃ������Ƃł��B
�}���N�X�����{��`��ᔻ����~�\�̕����͂����Ȃ̂ł��B
|
���G���Q���X
�O�q�Ń}���N�X���i�������Ƃ��鎑�{��`�̈ł̕����͂킩��܂����B���āA�����ň�ʔ������Ƃ�����܂��B���̓}���N�X�ɂ��x�����Ă���Ă����F�l�ɃG���Q���X�Ƃ����v�z�Ƃ����܂����B���̐l�͌o�ϓI�Ƀ}���N�X���������A���{�_�̏o�ł��������Ƃ���Ă��܂��B�������A���̃G���Q���X�͕��e�����Ƃ̌���̌o�c�҂ł���A���ʓI�ɂ��̍H����p�����ƂɂȂ�܂��B�܂�A���{�_�Ō����Ƃ���̎��{��`�Љ�̍ő�̈����_�A�J���Ƃ������{�����o�����{�ƂƂ��Ċ������A���g�͎��{��`�o�c�����Ȃ��炢���Ɏ��{��`���Ђǂ����̂ł��邩���}���N�X�ɐ����Ă����̂ł��B����ɂ���ă}���N�X�͎��{��`�Љ�̎��ԂɃ��A���ɐG��邱�Ƃ��o�����̂ł��ˁB�������A���{��`�Љ�ł��邪�䂦�ɁA�����͏d�v�A�C�e���ɂȂ�܂��B����𑽂����ݏo���ɂ͎��{�ƂɂȂ�K�v������܂��B���̃G���Q���X�̐������Ƃ����͔̂��Ƀ��A���ŃV�r�A�Ŕ���I�Ȃ��̂ł��ˁB��
�u���{�_�v��3���\���ɂȂ��Ă��܂����A���̓}���N�X�����O�̍ۂɏo�ł��ꂽ�̂�1���̂݁B�}���N�X�̎���A���e���܂Ƃ߁A�ҏW����2���A3�����o�ł����̂����̃G���Q���X�Ȃ̂ł��B
|
���Љ��`�v��
�u���{�_�v�̈�������p���܂��B
�u���厑�{�Ƃ�(����)���������̗��v��D�����A�Ɛ肵�Ă����̂����A����ƂƂ��ɋ���ȕn�����A�}���������ė�]�Ƒ��ƍ�悪�������Ȃ�B�����܂��A���{���I���Y�ߒ��̃��J�j�Y����ʂ��ČP������A��������A�g�D������A�����������̘J���ҊK���̕��������������Ȃ�B(����)�@���{���I���I���L�̏I���������������B���D�҂����̎��L���Y�����D�����B�v
�u���{���I���I���L�̏I���������������B�v�Ƃ�������́A���_���E�L���X�g���́u�Ō�̐R���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂莑�{��`�̉��ŘJ���҂͗}������A���m�ɒǂ�����邾���ł͂Ȃ��A�F�Ŏd�������L���邱�Ƃœˏo�����\�͂�������̂����[�_�[�I���݂J��オ��A�g�D�I�Ȓ�R�^�������邽�߂ɔ\�͂����߂邱�Ƃ��ł��A���������J���҂��������{�Ƃ�����������A���̒����Ђ�����Ԃ����Ƃ��N����ƃ}���N�X�͌����Ă���̂ł��B
�}���N�X�̕��͂ɂ���āu���{��`�͋ɂ߂Ĕ�l���I�Ȍo�ϑ̐��v�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�������Ă��̎��{��`�Љ�Ƃ͕ʕ��ł���Љ��`�͂����Ƃ������̂ł���ƍl�����Ă��܂����B�������ĎЉ��`�v�����N�����Ă������ƂɂȂ�܂��B�������A���j�̐Ղ����ǂ���X�͂��̎Љ��`�ɕϊ����Ă��������Ƃ��ߎS�Ȏ��s�𐋂������Ƃ�m���Ă��܂���ˁH�ł́A�Љ��`�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȗ�肪�������̂��B
|
���Љ��`���Ƃ����s�������R
���\�r�G�g�Љ��`���a��(1917�N�`1991�N)
�^����Ƀ}���N�X�̍l�����ɂ���Ă���ꂽ�����\�r�G�g�Љ��`���a��(1917�N�`1991�N)�ɂȂ�܂��B���𗦂����̂̓\�A�̏���ō��ӔC�҂ł��郌�[�j���B���{��`�ւƐ�ւ�������݂̃��V�A�ɂ����Ă����̃��[�j���̓����Ȃǂ͂�����Ƃ���Ɏc���Ă��邻���ł��B
�u���[�j���̎���͂悩�����v�Ɗ��S�ɂӂ�����̂���������Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB
�����đ�2��̍ō��ӔC�҂ƂȂ����̂̓X�^�[�����B���[�j���̎���ɂ͂܂����R�ȕ������������Ă����̂ł����A�X�^�[�����ɐ�ւ���Ă���͓O��I�Ȍ��_�����̎Љ�ɕς���Ă����܂����B
���������ω��̓\�A���Ƃ�܂����{��`���Ƃ���̎��{��`�I�Ȏv�z�E�l�������������邱�Ƃɂ��A���v���I�ȓ������N���邱�Ƃ����ꂽ���ʂȂ̂ł��B�����ĎЉ��`�ɐ�ւ����\�A���o�ϓI�ɂ��D�ʂł��邱�Ƃ����͂Ɏ����K�v������܂����B
�����Œ��肷��̂��A�_�Ƃ̏W�c���B�S�Ă̔_�n�����L�����A�_�����ȁu�J���ҁv�ɂ��悤�Ƃ��܂����B���̂��߂ɑ�n��͎E���Ă��܂��Ƃ������u���Ƃ��āE�E�E�B�������ĘJ���҂Ɋi�������܂�Ȃ��J���҂̂��߂ɗ��z�̎Љ��搂����̂ł��B
�������A���̗��z�ƌ����͂����Ȃ�܂����B
�܂�A�{���y�n�������Đ��Y������ꍇ�́A���̒n�Ŋl�ꂽ���͎̂����̂��̂ɂȂ邽�߁A����𗘗p���Ă������҂����Ƃ����ӎ��������A�Ȃ�Ƃ��Ăł��앨������Đ��Y�����グ�悤�Ƃ����v�l�������܂��B
�������A�W�c�_��̏ꍇ�͔_�����u���ƌ������v�Ƃ��������ɂȂ�܂��B����Ɛ��Y���グ�Ȃ��Ă��Œ���̃R�A�^�C���ɘJ�������Ă���ΐ����͕ۏႳ��Ă��邽�߂ɁA���Y�����グ��H�v�͐�����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��B
����͒n���r����������������ɂȂ�܂����B�_�Ƃɑ��Ēm�����L�x�Ȑl�Ԃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B
���ʓI��1932�N�ɂ̓\�A�̈ꕔ�ł������E�N���C�i�ő�Q�[���N����A���҂�1000���l�ȏ�ɋy�т܂����B
��
�}���N�X�̕��͂ł͎��{��`�Љ�̉��ł͎��{�Ƃ������������������J��L���܂��B���̌��ʁu�ߏ萶�Y�v���N���܂��B���������̗��ŘJ���҂����͉ߍ��ȘJ�����������܂��B�����Ɏ��v�Ƌ����ɑ傫�ȍ����o�ĕs���Ɋׂ�ꍇ������A�ň��̍ۂɂ͋��Q���N����ꍇ������Ƃ��܂����B
����ɏK���A�Љ��`�ł͍��Ƃ��v��𗧂ĂđS�Ă��v�搶�Y��������ƍl���A���s���܂����B
�������A������܂����ڂɏo�܂��B
�u�u�[�c�����v�Ƃ����w�߂ɑ��A
�u�u�[�c���������v�ˁu�J�╗�ɂ��炳��Ȃ��C����������v�ˁu���C�ő�p�\�v
�Ƃ����v�l�ɂȂ�A���ʓI�ɊO�ςȂǂ͋C�ɂ��Ȃ��@�\�������ڂ���Ă��鏤�i���������܂��B�������A�w���҂Ƃ��Ă͂���ȃ_�T�����̂𒅗p�������͂Ȃ��킯�ł��B�܂萶�Y���ɋ������Ȃ��ׂɁA�u�������́v�����Ƃ����v�l�ɂȂ�Ȃ��̂ł��ˁB�������ď��i������c��܂��B
�킩��܂����H���ǁA���{��`�ł��Љ��`�ł��ߏ�ȋ����������A�����̖��ʌ������N����̂ł��B
��������1991�N�Ƀ\�A�͕���Ɏ���܂����B
|
�����ؐl�����a��(1941�N�`)
1949�N�Ɍ������ꂽ���ؐl�����a���B�������܂��Љ��`���ƂƂ��Ĕ��ɗL���ł��ˁB����ō��ӔC�҂͖ёB
�ё������̂͑���i����B
�\�A�̑�3��ō��ӔC�҂ł���t���V�`���t�́u15�N�ŃA�����J�ɒǂ����ǂ��z�����v�Ƃ����X���[�K�����f���܂����B
����ɑR�������͓������E2�ʂł���o�ϑ卑�ł������C�M���X�ɒǂ������Ƃ��܂��B�C�M���X�͓����S�|�Ƃɂ���ĉh���Ă��܂����B���̂��߁A�����̎w�j�Ƃ��ēS�|�Ƃɖڂ������܂��B
�������Ĕ_�����S�|���Y�ɒ��肷�邱�ƂɂȂ�܂����B�e�n�ɑ���ꂽ�͓̂y�ō��ꂽ�~�j���S���ł���y�@�F�B
����Ɏg�p����ω����K���K�v�Ȃ̂ł����A�����ɂ͂�������m��������܂���ł����B�����Ŗڂ�t����ꂽ�̂��������j���ւ钆���ō��ꂽ���@�Ɏg�p����Ă��郌���K�B
�܂��A�F�̔R���ƂȂ�X�т́B����ɂ���ĎR�X���͂��Ă��܂��܂����B�����������ł���Ƃ������́A���̎����̐X�є��̂ɂ��Ƃ��낪�傫���Ƃ���Ă��܂��B
�����Ă���ɖ��ƂȂ�̂́A�S�����o�����߂̓S�z�������ɂ͂���܂���B�����ł����璆�ɂ���S���i��F�̒��ɓ���ėn�����Ƃ�����Ƃ��N����n�߂܂��B�������Ĕ_�@��Ɏg�p����Ă���S��n�����̂ł��B
��
�ǂ��Ȃ邩�킩��܂����H�����B��������_�@��p�������̂ł��B
���炩�ɂ��������̂ł����A��ΓI�ȃJ���X�}���������Ă����ёɑ��Ă͔�����|�����Ƃ������ẮA�����Ă͂����܂���B�������Ē����̎ЊO��`���܂������ɖ������d�˂��Ă����̂ł��B
���ʂƂ��Ėё̎���A�������ɂ���Ď����I�Ɏ��{��`�ւƓ]�����Ă����^�тƂȂ�܂����B���������ۂɎ��{����Ă���o�ϑ̌n�́u�Љ��`�s��o�ρv�Ƃ����Љ��`�Ǝ��{��`�������������̂悤�Ȃ��́B
�܂苤�Y�}�̓ƍِ����̉��ł̎��R�Ȏ��{��`�o�ςł��B���ꂪ���݂̒����B
|
���g�}�E�s�P�e�B���u21���I�̎��{�v
���������Љ��`���Ƃ͐�ւ��������Ƃ��Ă͌o�ς����I�ɐL�т��Ƃ������j������܂��B�������A�����I�ɂ͑������Ƃ��o���Ȃ��̂ł��B
2008�N�̃��[�}���V���b�N�ɂ��Ăђ��ڂ����������悤�ɂȂ����}���N�X�́u���{�_�v�B���{��`�o�ς��܂��A�l�X�Ȗ���������Ă���o�ςł��B�������āA���{��`���܂��i���I�ȑ̐��ł͂Ȃ��̂ł́E�E�E�ƍl������悤�ɂȂ����̂ł��ˁB
�܂��A�g�}�E�s�P�e�B���u21���I�̎��{�v���o�ł��ꂽ���Ƃ����{��`�ɂ��čl�����������̗v���ƂȂ�܂����B�s�P�e�B��100�N�ȏ�ɂ킽���Ă̐��E�e���̃f�[�^���������ʎY�܂ꂽ�̂����̌����B
r > g�@/�@r�͊����Ȃǂ̎��{���瓾��ꂽ���{���v���Bg�͍��̌o�ϐ������B�܂荑�̌o�ϐ������������{�Ƃ�������v���̕�����ł��邱�Ƃ��Љ���̂ł��B
���̌o�ϐ������Ƃ����ƕn�����l�Ȃǂ��܂܂�Ă���f�[�^�ł��B���̐L�ї��������{�Ƃ̗��v�̑��嗦�̕����傫���Ƃ������Ƃ́A���{�ƂɈ���I�ȕx�̒~�ς�����Ƃ������Ƃł��B
�܂��Ƀ}���N�X�������Ă������Ƃ��̂��̂��f�[�^�ɂ���ė��������ƂɂȂ�܂��B�������}���N�X�͂��ꂪ�䂦�Ɏ��{��`�Љ�͑œ|���ׂ��Ǝ咣���܂������A�s�P�e�B��
�u���{�Ƃ̗��v�������ŋ��Ƃ��Ď��グ�悤�v
�ug������r���Ӑ}�I�Ɍ��炵�Ċi���������ł����炷�ׂ��v
�Ƃ����ӌ����q�ׂ�̂ł��B
�@ |
 �@ �@
���w���{�_�x���玑�{��`�Љ������ |
   �@
�@
|
���X�ɍs���ƁA�u�}���N�X�v�u���{�_�v�W�̏��Ђ�����������ł��܂��B������A�o�ϊw�̐�发�R�[�i�[����ł͂Ȃ��A��ʏ���r�W�l�X���Ȃǂ̃R�[�i�[�ɐς܂�Ă��邱�Ƃ�����������܂���B�������A������}���N�X��`�o�ϊw�҂ł͂Ȃ�����̐l�A���Ƃ��Βr�㏲����Ȃǂ�������Ė{����������܂��B��\���N�O�A�x�������̕ǂ���A�\�r�G�g�A�M����������́A�}���N�X�͐�Ŋ뜜��ł����B
�u�}���N�X�͎���x��A���{�_�ȂǓǂމ��l�Ȃ��v�ƌ����Ă��܂������A���̂܂ɂ�����͕ς���Ă��Ă��܂��B
�Ȃ��A�w���{�_�x�����ڂ𗁂т�̂ł��傤���B�w���{�_�x��ǂނƂȂɂ������邱�Ƃ�����̂ł��傤���B
|
���N���w���{�_�x��ǂ�ł����̂�
�w���{�_�x�Ƃ����ΘJ���ҊK���Ɍ����ď����ꂽ�{�Ƃ����C���[�W������Ǝv���܂��B�������A�{���ɂ����ł��傤���B�}���N�X�̑��̒���A���Ƃ��w���Y�}�錾�x�Ȃǂ͂����炩�ɘJ���҂Ɍ����ď�����Ă��܂����A�w���{�_�x�͂����Ƃ͌�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�Ȃ��Ȃ�A�����̘J���ҊK���̐l�X���ǂނɂ��Ă͓��e��������邩��ł��B���{�_��ǂ��Ƃ̂Ȃ��l�́A���݂Ɂw���{�_�x���J���Ă݂Ă��������B�|��̖�������ɂ���A���ɓ���Ȃ��Ƃ��킩��܂��B
�}���N�X�{�l�̈Ӑ}�͂Ƃ������Ƃ��āA���ʓI�ɘJ���ҊK���̐l�X�ł͓ǂ݂��Ȃ����Ƃ͂ł��܂���ł����B�ł́A�N���ǂ̂ł��傤���B����͍L���Ӗ��ł́u���{�Ƒw(�G���[�g��������Ƃ��܂�)�v�������̂ł��B
�ނ�́w���{�_�x��ǂ�łǂ��l�����̂��B�����炭�͂����������Ƃł��B
�u�ǂ����}���N�X�������Ă��邱�Ƃ͐������炵���B���̂܂܂����ƁA���{��`�Љ�͕��āA�Љ�͑卬���ɂȂ�A���������͂��܂̒n�ʂ���v������B�v
�����l�����ނ�́A���{��`�𑶑������A�}���N�X�̗\��(���Y��`�v�����N���āA�v�����^�[�A�[�g�ƍق���������)���������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂǂ���������̂��A�m�b���i�����̂ł��B
|
���w���{�_�x����ǂݎ�鎑�{��`�Љ�Ƃ�
�w���{�_�x�ɂ� �u�����Ȏ��{�Ƃ��J���҂����悷��̂ŎЉ�����Ȃ�v�Ə�����Ă���킯�ł͂���܂���B������Ă���̂� �u���{��`�o�ςŐl�X���o�ύ����I�ɍs��������A�K�R�I�ɑ勰�Q�⋇�R�����N����v �ł��B
��Ƃ͌�������}��A���v���ő剻���邱�Ƃ�ڎw���܂��B����͓��R�̂��ƂŁA��������Ȃ���Ƃ͎��{��`�Љ�̒��ł͐����c��܂���B���̂��߂ɁA��Ƃ͑�K�͂Ȑݔ����������đ�ʐ��Y���\�ɂ��A���i�P�����������邱�Ƃŋ����ɏ��Ƃ��Ƃ������ł��B
����ɁA��Ƃ̗��v�̌���́A�J���҂��A���������������ȏ�̉��l�ݏo���u��]���l�v�ł��B���́u��]���l�v��������Ƃ̗��v�ɂȂ�܂��B�ł�����A�J���҂̉��l��������A��̓I�Ɍ����ΘJ�������������邱�Ƃŗ��v���m�ۂ��悤�Ƃ��܂��B��������v�̍ő剻�Ƃ������Ƃ��猾���Γ��R�̂��Ƃł��B����ł��u�l����̍팸�v�͑����̊�Ƃʼnۑ�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����A�o�ύ����I�ȍs�ׂ��ƌ����܂��B
�������A�J���҂͓����ɏ���҂ł��B�J����������Ƃ������Ƃ͏���҂̍w���͂������邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�����Ȃ�Ώ��i�͔���Ȃ��Ȃ�܂��B���ʂƂ��ď��i�͗]��A��������鐶�Y�ݔ����ߏ�ɂȂ�܂��B���v�͌���A�ݔ����w������ۂɋ��Z�@�ւ���肽������Ԃ��Ȃ��Ȃ�܂��B��s�Ȃǂ̋��Z�@�ւ͕s�Ǎ��̎R������A�Ō�ɂ͋��Z���Q���N����܂��B
�S3���́w���{�_�x�̎�|��Z����������͍̂���ł����A�P�������Č��������������Ƃł��B�����Ă��̈�A�̗���́A�o�u������ȍ~�̓��{�o�ς�f�i�Ƃ�������̂�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����炱���w���{�_�x�Ƀq���g�����߂����Ƃ����C�����N���Ă��Ă���̂��ƍl�����܂��B
|
���w���{�_�x���炭�ݎ�邱��
���{��`�ɂ͑����̖�肪����܂��B�������A�����炭�͂���ꂪ�����Ă���ԂɎ��{��`�̃V�X�e�������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�낭�ł��Ȃ��V�X�e�����A�ƓłÂ����Ƃ���ŁA�l�ނ͎��{��`���܂��Ȍo�σV�X�e�������܂������邱�Ƃ��ł����ɂ��܂��B���Y��`�̒��킪���s�������Ɩ��m�ɂȂ������݁A�ȒP�Ɂu�|�X�g���{��`�v�̂悤�ȃV�X�e���ݏo�����Ƃ������ł��傤�B
���Ƃ���A�\�����Ă��܂������Ȏ��{��`�Љ�̒��ŁA�܂荇�������Đ����Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�܂��A�\�����Ă��܂�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̏������A�O������łȂ����{��`�������琶�ݏo���Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B
���̂��߂ɁA�ꌩ����ƌo�ύ����I�łȂ��s�ׂ��K�v�Ƃ���܂��B20���I�㔼�܂ŁA���E�͂�������Ď��{��`������Ă����̂ł��B�������Ƃ͂������Ēa�����܂����B�J�g�����H�����A��ҋ~�ς̂��߂̃Z�[�t�e�B�[�l�b�g���A�����̍ĕ��z�������ł��B
�Љ��`���Ƃ����X�ƕ��A���{��`�̏��������`����邱�ƂŁA�����������Ƃ͌o�ϓI�s�����A���ʂȂ��Ƃ��Ɣr�����������Ɍ������܂����B���̌��ʂ͂��܂̐��̒��ł��B�ꕔ�̐l�ɕx�͏W�����A�i���͊g�債�����Ă��܂��B���̂܂܂����A�}���N�X�̗\�������𐁂��Ԃ��Ă��܂����˂܂���B
���ĂƓ����{�L�����ǂ����͂킩��܂���B�������ǂ�Ȍ`�ł���A���{��`�Љ�̑����̂��߂ɁA��Ƃɂ��l�ɂ� �u�i�ʁv ��ۂ��Ƃ��K�v�Ƃ����Ǝv���܂��B���Ƃ��ACSR(Corporate Social Responsibility�E��Ƃ̎Љ�I�ӔC)��SRI( Socially Responsible Investment�E�Љ�I�ӔC����)�Ƃ����l�����́A�������������̒����琶�܂�Ă��܂����B���������l�����L�܂�Ȃ���A���{��`�̑������̂Ɋ댯�������܂��B���{��`���܂��ȃV�X�e�����������Ă��Ȃ���X�́A�����ƂЂǂ��V�X�e����ł��܂����˂܂���B
|
�������Ă���Ȑ��̒��Ōl�͂ǂ�������̂�
�ǂ�������H�����ς���Ȃ����A�Ƃ������Ƃ͂��ꂼ�ꎩ���ōl���邵������܂���B���ꂼ��l�ɂ���ď������Ⴂ�܂��B���{��`�̖{���𗝉�������ŁA�����̓������������Ă��������l���Ă�����������܂���B
���̏�ŁA�u�o�ύ������Ƃ͗��ꂽ���݈ˑ��I�Ȑl�ԊW������Ă����v���Ƃ�����Ǝ��͎v���Ă��܂��B�o�ύ������Ƌ�����u���B�������ꂽ�ꏊ�ɂ����ꏊ������Ă����Ăق��������Ǝv���܂��B
���������Ă��n���̂悭�m�������X�X���畨���B�������m�o�n�ȂǂɊ�t������B���K�I���^�[���̊��҂ł͂Ȃ����O�ɋ�����������������Ƃɓ���������B���ׂĂ������ɓq����킯�ɂ͂����܂��A�����ł������������X�N�������邱�Ƃ��A���L���Ȑl������ނ�������������Ă����͂��ł��B
�@ |
 �@ �@
���T�����[�}���́w���{�_�x�Ǝ��{��`�̃��[�� |
   �@
�@
|
|
��1 ���̐��Łu���v���߂̐���[��
|
�Q�[����X�|�[�c�Ɠ����ŁA���̐��ɂ������⓭�����̃��[��������B�������A�����̐l�͂��̃��[����m��Ȃ��B���{��`�̎d�g�݂���������w���{�_�x�́A���̐��������郋�[�������ł�150�N�O�ɉ����������Ă����B���̘A�ڂł́A����ȑ咘�w���{�_�x�̃|�C���g�����|�I�ɓǂ݂₷��������Ă����B
���Ȃ��N��1000���~�ł�����ǂ��̂��H�@���҂������m���Ă��邱�̐��̃��[��
����A�����V���Ђ����s���Ă���uAERA�v�Ƃ����G���ŁA�N��1000���~�ȏ�̐l�����̎��Ԃ���ނ����A�u�N��1000���~�̌����v�Ƃ������W���g�܂�Ă��܂����B
�����Ō���Ă����̂́A�u���̎d�����e�ŁA���̋����͊��ɍ���Ȃ��v�u����ǂ��v�Ƃ����Q���̐��ł����B���������āA�g�̂��Ă��܂����Ƃ����������܂����B
�u�N��100���~�v�̎�������蓾��Ƃ����₩��钆�ŁA�N��1000���~�͒��������ł��B�N��1000���~�ɓ͂��Ă���l�́A�킸��3.8���������܂���B���Ԉ�ʂ���l����A�u�ڕW�v�Ƃ���邱�Ƃ��������z�ł��B����Ȃ̂ɁA1000���~�v���[���[�����́A�K�������ł͂Ȃ��̂ł��B�Ȃ��ł��傤���H
�������A���������ōK���łȂ����R��������l�͏��Ȃ��ł��B�u����ǂ��v�Ƃ������o�l�͂قƂ�ǂ��܂���B�ǂ�����Ώ����₷���Ȃ�̂��A�ǂ�����g�����h�ɂȂ��Ă��܂��̂��A�g�����h�Ȃ����߂ɂǂ�ȌX���Ƒ���̂��A�w�т܂���B
�������������ɂƂ��ĉ����g�����h�ŁA�����g�����h���������Œm��܂���B�Ƃ������A������m�낤�Ƃ��锭�z�������Ă��܂���B
���[����m��Ȃ���A���̊��̒��œK�ɐU�镑���܂���B�Љ�̃��[����\����m��Ȃ���A�]�ތ��ʂ��o�Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł��B
�Ƃ͂����Ă��A���Љ�̓Q�[����X�|�[�c�Ƃ͈Ⴂ�܂��B���[���u�b�N����������Ă���킯�ł͂���܂��A�u���[�������̏�v������킯�ł�����܂���B
��Ђ̏�i���m���Ă���Ƃ�����܂���B�ꍇ�ɂ���ẮA��N���}����܂Ō��ǃ��[�����������킩��Ȃ������Ƃ����l������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���{��`�Љ�̃��[���́A�u�o�ϊw�v����ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B
���w���{�_�x�́A���̐��̐���[���������Ă����
�ڂ��͑�w�Ōo�ϊw���w�сA���Љ�̃��[����(�Ȃ�ƂȂ�)�������܂����B�Љ�l�ɂȂ��Ă���́A�d���̌���ŁA�o�ϊw�̗��_�����Ă͂܂��Ă��邱�Ƃ��m�F�ł����ʂ�����������܂����B
�����āA���̌o�ϊw�̒��ł��A���̓��{�o�ς́g���[���h���ł��s���A�������Ɏ����Ă���̂��}���N�X�́w���{�_�x���Ƃ������ƂɋC�Â��܂����B
���̓��{�́A�w���{�_�x�̗��_�Ő����ł���Ƃ��낪���ɑ����A�w���{�_�x��m���Ă��邱�Ƃ́A�J���҂Ƃ��ē��������ŁA�ƂĂ����͂ȕ���ɂȂ�܂����B
�ڂ���2001�N�ɑ�w�𑲋ƌ�A�x�m�t�C�����A�T�C�o�[�G�[�W�F���g�A���N���[�g���o�āA���͓Ɨ����ăr�W�l�X���s���Ă��܂��B�x�m�t�C�����͂Ƃ������A�T�C�o�[�G�[�W�F���g�ƃ��N���[�g�͔��Ɂg���{��`�I�h�ȉ�Ђł��B
����������Ђɋ߂Ă����ڂ����w���{�_�x�̘b�������o���ƁA������邱�Ƃ������ł��B����́A�w���{�_�x�ɑ��āu���Y��`�̌o�ϊw�v�u�v���̖{�v�u���͂�A�������Ŗ��ɗ����Ȃ��v�Ƃ����C���[�W���������̕����������炾�Ǝv���܂��B
�ł����A�����̃C���[�W�́A�g�ԈႢ�h�ł��B�w���{�_�x�́A���Y��`�̌o�ϊw�ł͂Ȃ��A���{��`�o�ς̖{�����������Ă���{�ł��B�w���{�_�x�ɂ́A�ڂ��炪�������Ă��鎑�{��`�Љ�A�ǂ�ȃ��[���Ő��藧���Ă��邩��������Ă��܂��B
��������A�J���҂��Ȃ�����ǂ������ɒǂ����܂�Ă��܂��̂��A�Ȃ���Ƃ��ꐶ�����ɊJ���������i�������ɃR���f�B�e�B�ɂȂ�A�l�����肵�Ă��܂��̂��A�Ȃ�����̒����Ƃ��Ă��Ă͂₳�ꂽ��Ƃ��A�����Ȃ胉�C�o����Ƃɋt�]����Ă��܂��̂��A��ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B�����āA�������甲���o�����@���ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B
�w���{�_�x���u�������ł��͂�g���Ȃ��o�ϊw�v�Ƒ�����l�����܂����A���ɂ��������Ȃ��Ǝv���܂��B
�����Љ�Ŗ��ɗ��o�ϊw�@����ȑ咘��3�̃|�C���g����ǂ�
�ڂ��͋ƊE1�ʂ̊�Ƃ�3�Ќo�����Ă��܂����A�ǂ̉�Ђœ����Ă���Ƃ����A�w���{�_�x�̗��_�����p���邱�ƂŁA�K�Ɂg�j���h���Ƃ��ł��܂����B�܂��Ɨ���������A�w���{�_�x�Ō���Ă��鎑�{��`�̖{����O���ɒu���A�r�W�l�X�����Ă��܂��B���ۂɁA�ڂ��́w���{�_�x���r�W�l�X�Ɋ��p���Ă��܂��B
�����āA���̒��Ō���Ă��鎑�{��`�̌����A���[���́A���l�̃r�W�l�X�ɓ��Ă͂܂�A���l�̓������ɉ��p�ł���ƍl���Ă��܂��B
�������A�w���{�_�x��ǔj���邱�Ƃ͂��Ȃ荢��ł��B�ƂĂ�����ł����A�ƂĂ������ł��B�l�ɂ���Ă�1�N�ȏォ���邱�Ƃ�����ł��傤�B
�܂��A�w���{�_�x�ɏ�����Ă��邱�Ƃ̂��ׂĂ��K�v�Ȃ킯�ł�����܂���B���́A�w���{�_�x�̃G�b�Z���X�́A3�ɏW��ł��܂��B����3�𗝉�����A�w���{�_�x�̏d�v�ȃ|�C���g�A�܂�����Љ���j�������ł̕K�{�|�C���g���������邱�Ƃ��ł��܂��B
�y�|�C���g1�z�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v�̈Ӗ��𗝉����A���̋�ʂ����邱��
�y�|�C���g2�z�u��]���l�v�̈Ӗ��𗝉����A���ꂪ���܂��v���Z�X��m�邱��
�y�|�C���g3�z�u��]���l�v���A�₪�Č����Ă������Ƃ𗝉����邱��
����3���������Ă͂����܂���B�����ē����ɁA�w�҂�ڎw���̂łȂ���A����3�ŏ\���ł��B����3�𗝉����Ă���w���{�_�x���g�����Ȃ����Ƃ��ł��܂��B
���̂��яo�ł����w������ ���{�_�x�ł́A3�̃G�b�Z���X��1�͂���4�͂ɂ킽���ĉ�����Ă����܂��B�܂��A5�͂���7�͂ł́A���̐�A���{��`�̃��[���̒��łڂ��炪�ǂ��킢�A�����c���Ă��������̂����A�w���{�_�x�̊��p���@�ƂƂ��ɉ�����Ă����܂��B
���̖{��ǂݏI������Ƃ��A���̒��̌������ς��A���������ݏo���ׂ������������Ă���͂��ł��B
���́A�ڂ��炪���炭�Y��ł����^��́A150�N�O�ɂ��łɃ}���N�X���������Ă����̂ł��B
|
|
��2 �Ȃ������Ă������Ă��A�������オ��Ȃ����H
|
�Ȃ��J���҂͂���ǂ��̂��H �Ȃ������Ă������Ă��������オ��Ȃ��̂��H ���̓����́A150�N�O�Ɏ��{��`�̎d�g�݂��������������w���{�_�x�ɂ������B���{��`�̃��[����m��ɂ́A�܂����i�̉��i�̌��܂���𗝉����邱�Ƃ���n�߂悤�B
���J���҂́A�Ȃ�����ǂ��̂��H �w���{�_�x�ɂ��̓���������
���{�o�ς́A����ꂽ20�N�Ƃ�������s���ɋꂵ��ł��܂��B2012�N12���A�����}���{�������a�����A������u�A�x�m�~�N�X�v���X�^�[�g���܂����B�ꕔ�ɂ͌i�C�����Ă����g�؋��h������悤�ł����A�����̑唼�͂�����������Ă��܂���B
����ŁA���Ȃ�������Ȃ��d���́A�ォ��ォ��N���Ă��܂��B���{�͌o�ϐ�i���ł��B�����ɔ����ꂽ�Ƃ͂����A���E3�ʂ̌o�ϑ卑�ł��B�L���ȍ��̂͂��Ȃ̂ł��B
�������A���́u�L���ȍ��v�Ő�����ڂ���́A���̖L�������������Ă��܂���B�ނ��뎞�オ�i�ނɂ�āA����Ɏd���������ԂɂȂ�A����ǂ��Ȃ��Ă���悤�Ȉ�ۂ������܂��B����͈�̂ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���H
�w���{�_�x�ɂ��̓���������܂����B
���i�C���ǂ��Ȃ��Ă��A�Ȃ������͏オ��Ȃ��̂��H �u�J���҂́A�Ȃ�����ǂ��̂��H�v
���̑傫�ȗ��R���߂Ă���̂́u�����v�ł��B�܂�A�����ł��B�����Ă������Ă��������オ��܂���B�ނ���A����15�N�́A�����͉������Ă��܂��B
1997�N����2013�N���l����ƁA�T�����[�}���̕��ϔN����2007�N��2010�N�ɂ��オ���������ŁA���N�܂ŌX���I�ɉ������Ă��܂��B2002�N����A���[�}���V���b�N���N����O��2007�N�܂ŁA���{�͒ʏ́u�����Ȃ������v�̐��Œ��̌i�C�g����ƌ����Ă��܂����B���̌i�C�g����ł������A�����͉������Ă������̂ł��B
�i�C���ǂ��Ȃ��Ă���A�������オ���Ă������ȋC�����܂��B�������A�����͂Ȃ��Ă��܂���B�������̊�Ƃ����������Ă���̂ł���A�[���͂ł��܂��B�������A���̒��S�̂��������Ă���̂ł��B
�Ȃ����H ���̓�����m�邽�߂ɂ́A�܂��u���i�̉��i�̌��܂���v�𗝉�����K�v������܂��B
���i�̒l�i�͂ǂ̂悤�Ɍ��܂��Ă���̂��H
�u�����̏��i���������肽���v�u�����肵�����Ȃ��v
�����̕������������Ă���Ǝv���܂��B�����Ƃ��ẮA�ł��邾���������肽���ł��ˁB�������A����肪�����炻���l���Ă��A���ۂɔ����̂͏���҂ł��B�l�t�������邾���Ȃ炢����ł��\�ł����A���ۂɔ����Ă���Ȃ���ΈӖ�������܂���B
����҂������Ă����ɂ́A�Ó��ȉ��i��t���Ȃ�������܂���B�ł́A���́u�Ó��ȉ��i�v�Ƃ́A��̂�����Ȃ̂ł��傤�H
�������A���̏��i�ɂ���ĈقȂ�܂��B�������A�w���{�_�x�̗��_��ǂ݉����ƁA�l�t���̌������ǂݎ��܂��B�܂�A�u����҂��Ó��Ɗ����Ă���鉿�i�v�Ƃ́H �������Ă���̂ł��B�}�[�P�e�B���O��L���b�`�R�s�[�����Ŕ��낤�Ƃ���O�ɁA��{�ƂȂ闝�_��m���Ă����ׂ��ł��B
���Ȃ��A���̃W���[�X��150�~�Ȃ̂��H�@�ˑR�ł����A����ł��B
�݂Ȃ���́A�ӂ��炢���ȏ��i���Ă��܂��B���Ƃ��A�������y�b�g�{�g���̃W���[�X������������܂���B���̃W���[�X��150�~�ł����B�ł́A�Ȃ�150�~�Ȃ̂ł��傤���H
���ꂪ���ꂾ����H �ł́A���̑���͒N�����߂��̂ł��傤���H �Ȃ��A150�~�ƌ��߂��̂ł��傤���H
�u150�~���̖����������邩��v
�ߑ�o�ϊw�ł́A���̂悤�Ɍ���܂��B�}�[�P�e�B���O���_�ł��������Ƃ������Ă��邩������܂���B�������A�{���ɂ����ł��傤���H
���Ȃ��̓W���[�X���Ƃ���150�~���̖����������邱�Ƃ��������Ĕ����Ă��܂����H �����炭�����ł͂Ȃ��ł��傤�B
�܂��A��������A�^�Ă��^�~���A�y�b�g�{�g���̃W���[�X�͓���150�~�Ŕ����Ă��܂��B���̎��X�Ŗ������͈Ⴄ�͂��ł����A�l�i�͈ꏏ�ł��B����͂��܂������܂���B
�u����҂́A�����������閞�����Ɣ�ׂď��i���v�u���̏��i���瓾���閞���������z���Z���A�����������Δ����v�ƌ����܂��B�������A���́A�����ł͂Ȃ��̂ł��B���i�̒l�i�͂܂������ʂ̃��W�b�N�Ō��܂��Ă����̂ł��B
�����{��`�ł́A���i�͂������܂�
�w���{�_�x�ɂ́A�������d�v�ȗ��_������܂��B
1. ���i�ɂ́A�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v������
2. ���v�Ƌ����̃o�����X���Ƃ�Ă���ꍇ�A���i�̒l�i�́u���l�v�ʂ�Ɍ��܂�
���ꂪ��1��ŏЉ���A�w���{�_�x�̂ЂƂڂ̃|�C���g�ł���A�u���l�Ǝg�p���l�̈Ⴂ�v�ł��B���ԂɂЂ������Ă����܂��傤�B
1. ���i�ɂ́A�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v������
�}���N�X�́A�����������̂́u���ׂāh���i�h�ł���v�Ƃ��܂����B�݂Ȃ������H�ׂ��p�����A��Ђōw�������p�\�R�����A���ԂԂ��ɓ������X�^�[�o�b�N�X�̃R�[�q�[�����ׂāu���i�v�ł��B
����ŁA�u���i�v�ɂȂ�Ȃ����̂�����܂��B���[�ɗ����Ă��鏬�͏��i�ɂ͂Ȃ�܂���B�R���̃L�����v��̋߂��ɗ���Ă��邫�ꂢ�ȏ���̐����A���i�ł͂���܂���B�ڂ����`�����G�����i�ɂȂ�܂���B
�����������珤�i�ɂȂ�Ȃ��̂ł͂���܂���B�������ł��p���[�X�g�[���Ƃ��Ĕ����Ă��邱�Ƃ�����܂��ˁB�傫���̖��ł͂���܂���B
�������珤�i�ɂȂ�Ȃ��̂ł͂���܂���B�R���r�j�ł́u�����������v�������Ă��܂��ˁB�܂��A�ڂ����`�����G�͔���Ȃ��Ă��A�L����Ƃ��`�����G�͏��i�ɂȂ�܂��B
�܂�A������ނ̂��̂ł��A���i�ɂȂ�����Ȃ�Ȃ������肷��̂ł��B���̈Ⴂ�͉��Ȃ̂ł��傤���H
���ꂪ�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v�Ȃ̂ł��B�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v�������Ă���A���̃��m�͏��i�ɂȂ�A�����Ă��Ȃ���Ώ��i�ɂ͂Ȃ�܂���B
�ł́A���́u���l�v�Ƃ́H �u�g�p���l�v�Ƃ́H
�܂��A�������₷���u�g�p���l�v�ɂ��Đ������܂��B�u�g�p���l�v�Ƃ́A�u�g���Ċ����鉿�l�v�Ƃ����Ӗ��ŁA������u�g�������b�g�v�̂��Ƃł��B�܂�u�g�p���l������v�Ƃ́A�u������g�����烁���b�g������A��������A�L�Ӌ`�ł���v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�܂��B
���Ƃ��A�p���̎g�p���l�́u���������v�u�����������v�ȂǂŁA�������ŗ����ďĂ������m���g�p���l�����̂́u�l�������H�ׂāA����������邩��v�Ȃ̂ł��B
���́u�g�p���l�v�́A���ɏo�Ă���u���l�v�Ƃ͑S�R�Ⴄ�Ӗ��ł��̂ŁA���ӂ��Ă��������B
���ɁA�u���l�v�ł��B���̌��t�͗v���ӂł��B�}���N�X�������u���l�v�́A�ӂ���ڂ��炪�g���Ӗ��ł͂���܂���(�ڂ��炪�g���u���l�v�Ƃ������t�́A�}���N�X�������u�g�p���l�v�̂��Ƃł�)�B
�w���{�_�x�̒��Łu���l�v�Ƃ������t�́A�u�J�͂̑傫���v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă��܂��B�܂�A�u���̏��i�̉��l���傫�������̏��i������̂ɑ����̘J�͂��������Ă���v�Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł��B�u���������̂ɂǂꂾ����Ԃ������������v���v��ړx�Ȃ̂ł��B
�u���l�v�̑傫���͐l�����������̂ɂǂꂾ����J������(�ǂꂾ������ɑ��ĘJ��������)�ɂ���Č��܂�A�܂�u���l���傫�����i�v�Ƃ́A�u���̏��i�́A�����l�Ł������Ԃ����A�������J�͂������Ă������v�Ƃ������Ƃ������Ă���̂ł��B
���鏤�i�́u���l�v�̑傫���́A���̏��i�ɂ����܂ꂽ�u�l�Ԃ̘J���̗ʁv�ɂ���Č��܂��ł��ˁB������1���Ԃł������p�����A10���Ԃ����Ă������p���̕����u���l���傫���v�B�v���O���}�[��3���Ԃ����Ă������X�}�[�g�t�H���̃A�v���P�[�V���������A10���Ԃ����Ă������ؒ���̒u���̕����u���l���傫���v�̂ł��B
�u�u���Ȃ�Ă���Ȃ��I�v�Ǝv����������܂��A����͊W���Ȃ���ł��B���̃��m���L�����ǂ����́u�g�p���l�v�Ƃ������t�Ōv��܂��B�ړx���ʂȂ̂ł��B
�P���ɂ��������J�͂ɔ�Ⴕ�āu���l�v�͑傫���Ȃ�܂��B���ꂪ�A�}���N�X�������Ă���u���l�v�ł��B�u���l�v�Ƃ́A�ӂ���ڂ��炪�g���Ӗ��ł́u�J�`�v�ł͂���܂���B���ꂪ��̓I�ɂǂ�Ȃ��̂��Ƃ��������A����ɂǂꂾ���̘J������₳�ꂽ���ɂ���Č��܂��āA�����̘J������₳���قǁu���l�v���傫���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�ȒP�Ɍ����ƁA���Ԃ������Ă��������̂́u���l�v���傫���A�Ƃ������Ƃł��B�����b�Ŏg���u���l�v�́A�}���N�X�o�ϊw�ł����u�g�p���l�v�̏ꍇ�������A�����������ł��ˁB
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�ӂ���A�ڂ��炪�g���u�J�`�v�Ƃ������t�̈Ӗ��Ƃ͈Ⴂ�܂��B���̈Ӗ������Ⴆ�Ă��܂��ƁA�w���{�_�x�̓��e���܂����������ł��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�����ӂ��������B
|
|
��3 �ڂ���́u�l�i�v�́A���{��`�̃��[���Ō���
|
���i�̒l�i�́u�����b�g�v�ł͂Ȃ��A���̂ɂǂꂾ���u��Ԃ����������v�Ō��܂��Ă���B�����b�g�ōl���邱�ƂɊ��ꂽ�r�W�l�X�p�[�\���ɂ͈ӊO�Ɏv���邪�A���ꂱ�����{��`�o�ς̃��[���ł���B�����āA�J���҂́g�l�i�h���܂������d�g�݂Ō��߂��Ă����B
���u���l�v�����ł��A�u�g�p���l�v�����ł��A���i�ɂȂ�Ȃ�
��1��ŏЉ���悤�ɁA�}���N�X���咣�����̂́A�u���i�ɂ́A�g���l�h�Ɓg�g�p���l�h������v�Ƃ������Ƃł����B����͋t�Ɍ����ƁA�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v���Ȃ���A���̃��m�́u���i�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�O��̂����炢�ł����A�g�p���l�Ƃ́u�g�p�����b�g�v�̂��Ƃł���A���l�Ƃ́u�J�͂̑傫���v�̂��Ƃł��B�Ⴆ�A�p���́u���������v���g�p���l�ł���A�u���̂ɂǂꂭ�炢��Ԃ������������v�Ƃ����̂��u���l�v�ł����B
���i�Ƃ́A(�����ȊO��)���l�ɔ�����̂ł��B����������ƁA�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v���Ȃ����̂́A���l�ɔ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
��̗�Ő������܂��傤�B���Ƃ��A�u�g�p���l(�g�������b�g)�v���Ȃ����̂͏��i�ɂȂ�܂���B�g�������b�g���Ȃ���A�N�������Ă���܂���B���[�ɗ����Ă��鏬��A�ڂ����`�����G�����i�ɂȂ�Ȃ��̂́A�u�g�p���l�v���Ȃ�����ł��B
���ɗ����Ȃ����͔̂����Ă��炦�Ȃ��Ƃ����̂́A������O�̘b�ł��ˁB�ł��A���̓�����O�̘b���A�ƂĂ��d�v�Ȃ̂ł��B
�}���N�X�́A���Y�������m�����i�ƂȂ邽�߂ɁA�u�������̒���v�����Ȃ�������Ȃ��Ɛ����܂����B
���i�ɂ́A�u�g�p���l�v���K�v�ł��B�������A���́u�g�p���l�v�����邩�ǂ��������߂�̂́A���l(���q����)�ł��B�ł��オ���Ă݂Ȃ��ƁA���q����͂��̏��i���g�����Ƃ��ł��܂���B����ǁA�����Ă��܂���������ύX�ł��܂���B
�����̎v�����݂ŁA�u����͎g�p���l������͂��I�v�ƍl���Đ��Y���܂����A���ۂ́u�������킹�v�͏��i���ł��オ���Ă���Ȃ̂ł��B
�����āA���̃e�X�g�ɍ��i���Ȃ���A���m�̓��m�ŏI���܂��B���i�ƂȂ邱�Ƃ͂ł����A�N����������Ă��炦���I���̂ł��B���̃e�X�g�ɍ��i���Ȃ���A���i�ɂȂꂸ����ł��܂��̂ł��B���ꂪ�u�������̒���v�ł��B
�g�p���l���Ȃ����m�́A�����Ӗ��Ȃ��̂ɂȂ�̂����{��`�o�ςȂ̂ł��B
�����i�ɂ́u���l�v���K�v
�������A�u�g�p���l�v��������Ώ��i�ɂȂ邩(���l�������Ă���邩)�Ƃ����ƁA�����ł͂���܂���B�ڂ���r�W�l�X�p�[�\���́A���������낤�Ƃ��Ă��郂�m�E�T�[�r�X�́u�����b�g�v��O��I�ɍl����悤�A������Ă��܂��B
�u���q�l�ɂǂ�ȃ����b�g������̂��H�v�u�ڋq���_�ɗ��āv�u���q�l�Ɋ��ł��炦��A�K���I���v
���̂悤�ȃt���[�Y���I�t�B�X�̒��ŕp�ɂɌ��킳��Ă��܂��B�����͂܂�u�g�p���l�v���l����Ƃ������Ƃ������Ă���킯�ł��B�����A�����̏ꍇ�A�����ł́u�g�p���l��������A���q����ɔ����Ă��炦��v�Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B
�������A�u�g�p���l�v�����Ń��m�͏��i�ɂȂ�܂���B�u���l�v���Ȃ�������Ȃ��̂ł��B���̃��m�ɐl�̎肪������Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B
�u�g�p���l�v�Ƃ��킹�āu���l�v�������Ă��Ȃ���Ώ��i�ɂ͂Ȃ�܂���B���Ƃ��A�L�����v��̋߂��ɗ���Ă��邫�ꂢ�ȏ���̐�������Ȃ����R�������ɂ���܂��B�R���̂��ꂢ�ȏ���̐��́A���N�ɗǂ������Ȃ����ł��ˁB�~�l�����������Ղ�܂�ł������ŁA���ރ����b�g�͏\���ɂ���܂��B
�ł�������A�����ׂ̃L�����v��Ŕ��낤�Ƃ��Ă��A�ԈႢ�Ȃ�����܂���B�Ȃ����H�u���l�v���Ȃ�����ł��B
�N���o�Ă���ׂŔ���u�R���̂��ꂢ�ȏ���̐��v�ɂ́A�قƂ�ǘJ�͂��������Ă��܂���B�Ƃ������Ƃ́A����(���q����)���Ȃ�̋�J�������Ɏ�ɓ���邱�Ƃ��ł��܂��B������킴�킴����Ȃ��̂ł��B
�u���l�v���Ȃ�(�J�͂��������Ă��Ȃ�)���̂́A������g�p���l�������Ă��A������̂ɂȂ�Ȃ���ł��ˁB���̃|�C���g�����ɏd�v�ł��B�ނ���A������̕����厖��������܂���B
���i�ɂ�����̒l�i�������A����ɁA�ڂ���̋������Ȃ����̋��z�Ȃ̂�������Ă����̂́A���͂��́u���l�v�Ȃ̂ł��B���̔��ɑ�ȃ|�C���g�𗝉����邽�߂ɂ́A���̖@�����𖾂��Ȃ�������܂���B
��3���Ԏύ��J���[��30���ł������J���[�A�����̂͂ǂ����H
�}���N�X�́w���{�_�x�̒��ŁA���i�̒l�t���ɂ��Č���Ă��܂��B���ꂪ�A��1��ŏЉ���ӂ��ڂ̗��_�ł��B
2. ���v�Ƌ����̃o�����X���Ƃ�Ă���ꍇ�A���i�̒l�i�́u���l�v�ʂ�Ɍ��܂�
���i�ɂ́A�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v������܂��B�����ӂ��̗v�f�������āA���߂Ĕ�����̂ɂȂ�܂��B�������A���i�̒l�i�����߂Ă���̂́u���l�v���ƃ}���N�X�͍l���܂����B���l�̑傫�����x�[�X�ɂȂ��Ēl�i�����܂��Ă���Ƃ������Ƃł��B
����͈ӊO�Ȏ咣���Ɗ����܂��H�r�W�l�X�p�[�\�����d�v�����Ă���̂́A�u���q�l�̃����b�g�I�v�ł��B���q����Ƀ����b�g�����鏤�i(�܂�u�g�p���l�v�����鏤�i)����邱�Ƃ����ׂĂ��Ɗ����Ă��܂��B����������������Ă��܂��̂́A���q����ւ̃����b�g���s�\�������炾�A�ƁB�܂�u�g�p���l�v���Ȃ����炾�A�ƁB
�ł����}���N�X�́A�����͍l���܂���ł����B���i�̒l�i�́A�g�p���l�ł͂Ȃ��A���l�Ō��܂�ƍl�����̂ł��B�܂�A�u�ǂꂾ���J�͂������Ă��������v�Œl�i�����܂�A�u�J�͂������������ق�(���l���傫���Ȃ�Ȃ�ق�)�A�l�i���オ���Ă����v�ƍl�����̂ł��B
�u����Ȃ��Ƃ͂��蓾�Ȃ��B����ς�}���N�X�͎�����낾�v
��ǂ���ƁA���������邩������܂���B�ł��A����҂̖ڐ��Ō��Ă݂�ƁA�ڂ���͎������g�ł��}���N�X�̎咣�̒ʂ�ɍl���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�r�W�l�X�p�[�\���Ƃ��ĉ�Г��Ō����Ă��邱�ƂƁA�S�R�Ⴄ���f�����Ă���̂ł��B
����҂̗���ɂȂ��āA�l���Ă݂Ă��������B���Ƃ��A
�E30���ł������J���[
�E3���Ԏύ��J���[
�ɁA���ꂼ�ꂢ����̒l�i���Ó����Ǝv���܂����H �����炭�唼�̕����u3���Ԏύ��J���[�v�������ݒ肷��ł��傤�B�u3���ԁv�̕��������ē��R�A�Ɗ����܂��B���ɂ��Ă͉��������Ă��܂���B�u3���ԁv�̕��������������Ȉ�ۂ������܂����A�����܂ł��u��ہv�ł��B
�����Ă����炭�A�ډB�������ăN�C�Y���o���ꂽ��A�����̏���҂ɂ́A�u30���v���u3���ԁv���ꏏ�ŁA���̋�ʂ͂ł��܂���B�������A����ł��u3���Ԏύ��J���[�v�ɍ����l�t��������̂ł�(���N�N�n�Ƀe���r�ŕ��������u�|�\�l�i�t���`�F�b�N�v�ł��A�ō����i�ƈ�����i�̖�����ʂł��Ȃ��^�����g���吨���܂��ˁB�u���܂�Ⴂ���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł�)�B
����͂܂�A�g�p���l(�J���[�̂�������)�ł͂Ȃ��A���̃J���[������̂ɂ��������J��(���l)�Ŕ��f���Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�u�p���v�����u��Â���p���v�̕����������Ɋ����܂��B���ɍׂ����h�J���قǂ����ꂽ�z��������ꂽ�Ƃ��A�u�������v�Ǝv���܂��B�ł����A���ꂪ��҂݂��������Ƃ������Ɓu�����`�`��!!�v�Ɗ����܂��B�ڂ̑O�ɂ�����͕̂ς��Ȃ��̂ɁA���ꂪ�@�B�����萻���ŁA������d�݂��ς���Ă���̂ł��B
�܂��A�����̏K�����ɍs���Ƃ��A����ԂŊ����E�����f���邱�Ƃ�����܂��B�u10���~�����ǁA���N�Ԃ����������ˁv�u2���10���~�͍����I�v�Ƃ����悤�ɁB
�{���C�ɂ��Ȃ�������Ȃ��̂́A�����ɒʂ��ĖړI�̃X�L�����g�ɂ����ǂ���(���̍u���̎g�p���l)�ł��ˁB�����ƌ����Ă��܂��ƁA1��ł��ׂẴX�L�����g�ɒ��������������I�Ń����b�g������܂��B
�ł��A�����͍l�����A�����(���肪�����̂��߂ɔ�₵�Ă���鎞�ԁA�J��)�Ŕ��f���Ă���̂ł��B
���킩�肢�������܂����ł��傤���B�ڂ���͏���҂Ƃ��ď��i���u���l�v�Ŕ��f���Ă��܂��B�����āu���l�v���x�[�X�ɑÓ��Ȓl�i���l���Ă���̂ł��B�܂�A���̒��̏��i�́u�g�p���l�v�ł͂Ȃ��A�u���l�v�Œl�i�����߂��Ă���̂ł��B
�����l�ɍl�������̂́u�Љ�ρv
�u��Ԃ��������Ă���Ή��l���傫���Ȃ�v�u���̏��i������グ��J�͂������ƁA���l���傫���Ȃ�v�̂ł��B
�����A�������������ƁA�ЂƂ����������܂��B���������������Ԃ����Ă��������i�́A��ۗǂ����������i�����u���l���傫���v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B���Ƃ�����A�킴�Ƃ������A���ʂ𑽂����ď��i������A�u���l���������i�v���ł��オ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���R�Ȃ��炻��Ȃ��Ƃ͂���܂���B�������������Ă���悤�Ɏv���܂��B�����͂ǂ���������̂ł��傤���H
�}���N�X�́A���i�̉��l�̑傫���́u�Љ��ʓI�ɂ����镽�ώ��ԁE���ϘJ�́v�Ō��܂�Ƃ��Ă��܂����B
���i������グ��̂ɂ������Ԃ�K�v�ȘJ���ʂ͌l�l�ňႢ�܂��B�ł����A���i�̉��l�͂��̂悤�Ȍʂ̎���ɂ���Č��܂�̂ł͂Ȃ��A���̏��i�̉��l�́u���̎Љ�ŕ��ϓI�ɍl���āA�K�v�Ȏ�Ԃ̗ʁA���Ԃ̗ʁv�Ō��܂�̂ł��B
�E���̏��i������ɂ́A�ʏ킱�ꂭ�炢�̘J�͂�������
�E���̏��i�̌��ޗ��́A��ʓI�ɂ��ꂭ�炢�̗ʂ��K�v
���������u���̎d����������A���ꂭ�炢�����肻���v�Ƃ������o�l�������Ă��܂��B����Ɠ����ŁA�Љ��ʓI�ɔF������Ă���u�K�v�ʁv������̂ł��B
�d����m�ɂ���āA�Љ��ʓI�ɕK�v�ȘJ���ʂ��z�肳��Ă��܂��B���̕K�v�J���ʂ��u���i�̉��l�v�Ƃ��Ă݂Ȃ����̂ł��B
�ł�����A�킴�ƌ������������āA�J�͂������Ă��u���i�̉��l�v�͏オ��܂���B�܂��A�Љ�ς�2���ԂŏI���d�����A������10���Ԃ������čs���Ă��A�u5�{�̉��l�ݏo�����v�Ƃ͂Ȃ�܂���B�����܂ł��Љ�ςōl������̂ł��B
�u���m�̉��l�́A�Љ�ϓI�ȘJ�͂̑傫���Ō��܂�v
�����ǂ�Łu�����牽�H�v�ƕ��������Ȃ��Ă���l�����邩������܂���ˁB�������A���ꂱ�����݂Ȃ���̋����̌��܂���𗝉����邤���ŁA�܂������ɗ]�T���o�����߂ɁA���ɏd�v�ȃ|�C���g�Ȃ̂ł��B
�����i�̑�������߂�̂́u���l�v�A�������牿�i���㉺������̂��u�g�p���l�v
�u���i�̒l�i�́w���l�x�Ō��܂�Ȃ�āA���蓾�Ȃ��I �w�g�p���l�x(���肪�����郁���b�g)�̕����d�v���I�v
��ЂŁu���q�l�ւ̃����b�g���l����I�v�ƌ���ꑱ���Ă����ڂ���ɂ́A�w���{�_�x�́u���l���l�i�����߂�v�Ƃ������W�b�N�͂ɂ킩�ɐM�����܂���B
���������ʂ�A�u�g�p���l�v�͏d�v�ł��B�����āA�g�p���l�����i�ɉ����e�����y�ڂ��Ȃ����Ƃ����ƁA�����ł͂���܂���B�o�ϊw�I�Ɍ����ƁA�u�g�p���l�v�́A���v�E�����̖@����ʂ��āA���i�̒l�i�ɉe����^���܂��B
�g�p���l���������̂́A��葽���̂��q���ق�����܂��B���v���傫���킯�ł��B�u�����ƍ����Ă��ق����I�v�ƍl���Ă��邽�߁A���ʓI�ɒl�i��������������Ȃ�̂ł��B
���ɁA�g�p���l���Ⴂ���̂́A�u�����ƈ����Ȃ��Ɣ���Ȃ��v�ƌ����Ă��܂��A�����Ȃ��Ă���̂ł��B�������A������g�p���l�������Ă��A���R�b�v��10���~���邱�Ƃ͂܂�����܂���B���ɁA������g�p���l���Ⴍ�Ă��A�W�F�b�g�@��100���~�������Ȃ邱�Ƃ��l�����܂���B
����́A���l���l�i�̊�������Ă���A���̎�̂��̂́A�����������ꂭ�炢�̒l�i����ȁA�Ƃ�������������Ă��邩��Ȃ̂ł��B�ʂ̏��i�̒l�i�́A���̑������ɂ��āA�l�i�����܂��Ă��܂��B���������̂͂����܂ł��u���l�v�A�����āA���̊����l�i���㉺������̂��u�g�p���l�v�ł��B
�����͋������Ă������������邱�Ƃ͂���܂���B�������A�u�g�p���l�v���Ȃ���A���i�ɂȂ�܂���B�����Ă��炦�܂���B������g�p���l(���i�̃����b�g)��Nj�����͓̂��R�ł����A�K�v�s���ł��B
�������A����͏��i�̈ꑤ�ʂł�������܂���B�g�p���l�������(���q�l�Ƀ����b�g�������)�A���Ȃ���Ђ������ɂȂ邩�Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��̂ł��B
�g�p���l������A���q����͔����Ă����ł��傤�B�������A�u���l�Łv�Ƃ͌���܂���B���`�������悤�ɁA���i�̒l�i�́u���l�v����ɂȂ��Č��܂��Ă���Ƃ����̂��o�ς̌����ł��B�ł�����A���������̂ɘJ�͂��������Ă��Ȃ�(�債���J�͂�������Ȃ�)�Ǝv����悤�ȏ��i�́A�����l���t���Ȃ��̂ł��B
|
|
��4 ���Ȃ��̋����̌��߂���
|
�u���ʂ��グ�Ă��������オ��Ȃ��v�u�撣�肪�F�߂��Ȃ��v�ƒQ���l�͑����B�������A���{��`�̃��[�����炷��A����͑傫�ȊԈႢ�ł���B�����͂ǂ̂悤�Ɍ��߂��Ă���̂��H�Ȃ��E�Ƃɂ���ċ����ɍ����o��̂��H���̔閧�́A150�N�O�ɏ����ꂽ�w���{�_�x�ł��łɉ�����������Ă����B
�����Ȃ��̋����́A�������܂��Ă���
����܂ŁA���i�̒l�i�̌��܂���̃��[����������Ă��܂����B�l�i�́A�u���������v�Ƃ����u�g�p���l�v�ł͂Ȃ��A�ǂꂾ���u�J�͂��������̂��v�Ƃ����u���l�v�Ō��܂��Ă��܂����B
�}���N�X�́A���������̂͂��ׂāu���i�v�ł���Ɛ����܂����B�����l����ƁA���Ȃ��̘J���͂��u���i�v���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Ȃ��́A��Ђ̂��߂Ɏ��ԂƑ̗͂Ɛ��_�͂��g���ē����܂��B�����đΉ��Ƃ��ċ��������܂��B����͗��h�Ȏ���ł��ˁB�܂�A�J���͂��u���i�v�Ȃ̂ł��B
�Ƃ������Ƃ́A�u�J���͂̒l�i�v���A���i�Ɠ����悤�Ɍ��܂��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂�A�ڂ���̋����́A���i�̒l�i�̌��܂���Ƃ܂����������悤�ɍl���邱�Ƃ��ł���̂ł��B
���i�̒l�i�́A���i�́u���l�v����ɂȂ��Č��܂��Ă��܂����B���̏��i������̂ɁA�ǂꂭ�炢�̘J�͂��������Ă��邩�A�ǂꂭ�炢�̌��ޗ����K�v���A�ǂꂾ���̌������������Ă��邩�Łu���l�v�����܂�A�������ɒl�i�����܂��Ă���̂ł��ˁB
�ڂ���̘J���̒l�i���ꏏ�ł��B���������������Ō��܂��Ă��܂��B���Ƃ�����A�݂Ȃ���̋��������߂Ă���̂́A�u�݂Ȃ���̘J���͂����邽�߂ɕK�v�ȗv�f�̍��v�v�ƍl������̂ł��B
���i�̉��l�́A���i�Y����̂ɕK�v�ȗv�f�̍��v�ł��B�܂肱��́A���̏��i�́u���Y�R�X�g�v�ł��B�����悤�ɁA�J���͂̉��l���A�J���͂́u���Y�R�X�g�v�Ō��܂�Ƃ����킯�ł��B
�������́A���Ȃ����������邽�߂Ɂu�K�v�ȃR�X�g�v�Ō��܂�
�ł́A���́u�J���͂�����̂ɕK�v�Ȑ��Y�R�X�g�v�Ƃ͉��ł��傤���H �l�Ԃ������ɂ́A���̎d��������̗͂ƒm��(�m���E�o��)���K�v�ł��B�J���҂ɑ̗͂ƒm�͂��Ȃ���Γ����Ă��炤���Ƃ��ł��܂���B
���Ƃ��A�}���\���𑖂�I���ăG�l���M�[���[���ɂȂ��Ă��܂����l�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�J���҂Ƃ��ē����Ă��炤���߂ɂ́A�H�������āA����(�x��)���Ƃ��āA�ĂуG�l���M�[�^���ɂ��Ă����Ȃ�������܂���ˁB
���̂Ƃ��ɂ�����R�X�g(�H��A�����̂��߂̏Z����Ȃ�)�́A�J���͂�����̂ɕK�v�ȁu���Y�R�X�g�v�ł��B�����悤�ɁA�ƊE���o���̐l����ЂɘA��Ă��āA�݂Ȃ���Ɠ����悤�ɓ����Ă��炨���Ƃ��Ă������ł��B�d���ɕK�v�Ȓm����o�����Ȃ�����ł��B�����̒m���E�o����g�ɂ��Ă����Ȃ�������܂���B
���̂Ƃ��ɂ�����R�X�g��J��(�w��E���C��A�����ԂȂ�)���A�J���͂�����̂ɕK�v�ȁu���Y�R�X�g�v�ł��B�����āA�����́u�J���͂̐��Y�R�X�g�v��ςݏグ�����̂��A���̂܂ܘJ���͂̉��l�ɂȂ�A���̘J���͂̉��l����ƂȂ��āA�݂Ȃ���̋��������܂��Ă����̂ł��B
�̗͓I�ɃL�c���d���́A�����łȂ��d���ɔ�ׂāA�G�l���M�[����������K�v�Ƃ��܂��B���̂��߁A�G�l���M�[�⋋�̂��߂̃R�X�g�������K�v�ł��B������A���������d���͂��̕����������������Ȃ�܂��B
���ɏd�v�ȃ|�C���g�ł��̂ŁA���߂Đ������܂��ƁA�����������Ƃł��B�J�b�v���[����������̂ɂ́A
�u�߂���ނ��d�����v�u�X�[�v���d�����v�u�e���t�^���d�����v�u�e����f�U�C�����Ă��炤�v
�Ȃǂ��K�v�ł��B����Ɠ����悤�ɁA�݂Ȃ��u�J���́v������ɂ�(������悤�ɂȂ�ɂ�)�A�H�������Ȃ�������܂���B�H�������܂��B�̗͂������Ȃ�������܂���B�Z������ݔ����K�v�ł��B�Z��������܂��B���𒅂Ȃ�������܂���B�ߕ��オ������܂��B�X�g���X���U�̂��߂ɋC���炵���K�v�ł��B��y�������܂��B�d�������邽�߂̒m�͂��K�v�ł��B���̂Ƃ��ɒm���K���������܂��B
�����̍��v���J���͂̉��l�ɂȂ�A�݂Ȃ���̋��������߂Ă���̂ł��B���炦��̂́u�Љ�ϓI�Ɂv�K�v�Ȍo������K�v�o��Ƃ����Ă��A���R�Ȃ���u�������K�v�������炢����ł��o���Ă����v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B
���i�̉��l�́u�Љ�ϓI�ɂ݂ĕK�v�Ȏ�Ԃ̗ʁv�Ō��܂�Ɛ������܂����B�u���Ԉ�ʂōl���āA���̏��i������ɂ́A���ꂭ�炢�̌��ޗ����Ԃ��K�v���ȁv�Ƃ����ʂ��A���i�̉��l�ɂȂ�܂��B
�J���͂̉��l�����l�ł��B�J���͂̉��l�Ƃ��ĔF�߂���̂́A�u���Ԉ�ʂōl���ĕ��ϓI�ɕK�v�Ȕ�p�v�����ł��B�l�I�Ɂu�����ƐH�����ݑオ�K�v�I�v�u���̓u�����h�̃o�b�O���Ȃ��Ɛ����Ă�����Ȃ��́I�v�ƌ����Ă��ʗp���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���������ׂ�������ؖ����Ă���
���́w���{�_�x�̗��_�𗝉����Ă��������������ŁA�����g�̋��^���ׂ̍��ڂ���x���Ă݂Ă��������B�u�蓖�v�������Ӗ����Ă���̂��A����������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�ʋΎ蓖�́A�u���Ȃ����������������߂ɂ́A�d�Ԃɏ���ĉ�Ђ܂ŗ��Ȃ�������܂���ˁB���̔�p����Ђ����S���܂��v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�Z��蓖�́A�u�������������߂ɂ͏Z�ޏꏊ���K�v�ł��ˁB������Z���p�ӂ��܂��傤�v�Ƃ����āA��Ђ��݂Ȃ���ɂ������x�����Ă���̂ł��B
�Ƒ��蓖�́A�u���Ȃ����������������߂ɂ́A�Ƒ��������Ɨ{���Ă��Ȃ�������܂���B������A�}�{�Ƒ����������炻�̕�����悹���Ďx�����܂��傤�v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�q������蓖�́A�v����Ɏq�ǂ��̋����ł��B�u�q�ǂ��Ɋw�������܂��ˁB���̕����x�����܂��傤�v�Ƃ������Ƃł��B���i�蓖�́A�u���̎��i(�m��)��̂ɂ�����J�͂����������ł��傤�B�����炠�Ȃ��̘J���͂̐��Y�R�X�g���オ��܂����B���̕����x�����܂��傤�v�ł��B
��E�蓖�A�c�Ǝ蓖�������ł��B��E�ɏA���u���ꂾ���K�v�Ȑ��_�I�G�l���M�[�������܂��ˁB�ł́A���̕����v�u�c�Ƃ�����A���̗͂����Ղ��܂��ˁB���Ⴀ�A���̕����v�Ƃ����āA��Ђ��x�����Ă���̂ł��B
���ꂱ�����A���܂̓��{��ƂŁA�w���{�_�x�̗��_�ʂ�ɋ��������܂��Ă��邱�Ƃ̏Ȃ̂ł��B
���Ȃ���҂̋����͍����̂��H
�J���͂̉��l�ɂ́A���̎d��������̂ɕK�v�ȃX�L����g�ɂ���J�͂��܂߂čl�����Ă���Ɛ������܂����B�Ƃ������Ƃ́A���̃X�L����g�ɂ���J�͂��傫���d���́A�J���͂̉��l�������Ȃ�A����ċ����������Ȃ�̂ł��B
���Ƃ��A��҂̎����͂�������1���~�Ƃ����܂��B����A��ʊ�Ƃł͎���1000�`3000�~�ł��B
�Ȃ��A��҂̎����͍����̂��H ������u��҂̎d���̕����A��ʓI�Ȏd�������������v�u�l�������Ă������߂̏d�v�Ȏd�����Ă��邩��v�ƍl���Ă͂����܂���B
���ۂɈ�҂̎d���͑�ςł����A����Ɩ����Ǝv���܂��B���ȁA�畆�ȁA�����ȁA��ȁA�ǂ���Ƃ��Ă��l�����N�ɐ����Ă������߂̏d��Ȏd���ł��B
�������A�u���x������A�d��Ȏd�������狋���������v�̂ł͂���܂���B�����u����d���v�ɂ������x������̂ł���A�T�[�J�X�̒c���͂����ƍ������ł����Ă����͂��ł��B�u�l�������Ă������߂̏d��Ȏd���v�ɍ���������������̂ł���A���m�̋����������x�ɍ����Ȃ�͂��ł��B
�����������J���Ȃ̓��v(2012�N)�ł́A��҂̕��ό�������88���~�Ȃ̂ɑ��A���m�͖�21���~�ł��B���m�������悤�Ɂu�l�������Ă������߂ɕK�v�Ȏd���v�ł��B�ł��������傫���Ⴄ�̂ł��B
��҂̋����������̂́A��҂̎d�������Ȃ����߂ɁA�c��Ȓm����g�ɂ��Ȃ���Ȃ炸�A���̂��߂ɒ����ԏ��������Ă�������Ȃ̂ł��B��҂ɂȂ�܂ł̏�������ςŁA�݂�Ȃ�����𗝉����Ă��܂��B�����狋���������̂ł��B
���m�͔��ɏd�J���ŁA�Љ�I�Ӌ`�������d���ł��B�������A���m�ɂȂ邽�߂̏����́A��҂ɂȂ邽�߂̏����������Ȃ��čς݂܂��B���̍��������̍��ɂȂ��Ă���̂ł��B
�t�ɁA�N�ɂł��ȒP�Ɏn�߂���d���́A�u�g�ɂ���ׂ��X�L���v���Ȃ��̂ŁA���̕������������Ȃ�܂��B������撣���Ă��A�����琬�ʂ��グ�Ă��A�u�܂����������d�����ȒP�ɂł��Ă��܂��v�̂ł���A���R�A�K�v�o��͏��Ȃ��Ȃ�܂��B
�����l����ƁA�P����Ǝ҂̎��������Ȃ��̂́u�K�R�v���Ƃ����܂��B�u�̗͓I�ɃL�c���v�Ƃ��u���������ԘJ���v�Ƃ��͊W���Ȃ��̂ł��B���́u�J���́v�����邽�߂̌��ޗ�����Ȃ����߁A���������Ȃ��̂ł��B
���u�撣���Ă��]������Ȃ��c�c�v�ƒQ���̂͋؈Ⴂ
�J���͂́u���i�v�ł��B���̂��߁A��ʂ̏��i�Ɠ����悤�ɁA�u���l�v�Ɓu�g�p���l�v������܂��B����܂Ő������Ă������e���A�J���͂́u���l�v�ɂ��Ăł����B
�ł́A�u�J���͂̎g�p���l�v�Ƃ͈�̉��ł��傤�H �J���͂̎g�p���l�́A�u�J���͂��g�����Ƃ��̃����b�g�v�ł��B�v����ɁA�u��Ђ��A�ڂ���J���҂��g�����Ƃ�(�ق����Ƃ�)�̃����b�g�v���J���͂̎g�p���l�Ȃ̂ł��B
�����āA��ЂɂƂ��Ẵ����b�g�Ƃ́A�������ڂ��炪�҂����v�ł��B�܂�A
�E�g�p���l�������J���҂́A�\�͂������A��Ђɑ��đ傫�ȗ��v�������炷�l
�E�g�p���l���Ⴂ�J���҂́A�\�͂��Ⴍ�A���ʂ��グ���Ȃ��l�ł��B
�t�ɍl����ƁA��Ђɗ��v�������炷�l(���ʂ��グ��l)�́A�u�g�p���l�������l�v�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����ōl���Ă��������B�g�p���l�́A���̏��i�̒l�i�ɒ��ړI�ȉe�����y�ڂ��܂���ł����B�g�p���l���������̂́A���v�Ƌ����̖@���ɂ��������đ����l�i���オ��܂��B
�������A2�{�̎g�p���l�������Ă��A�l�i��2�{�ɂ͂Ȃ�܂���B�オ��̂͂��Ƃ��u1.2�{�v���炢�������肷��̂ł��B�J���͂ɂ��Ă��������Ƃ������܂��B����������ɒu��������ƁA�u2�{�̐��ʂ��o���Ă��A������1.2�{���炢�����オ��Ȃ��v�ƂȂ�܂��B
���ʂ��グ���̂ɋ������オ��Ȃ��ƒQ���l�͑����ł��B�u�����̉�Ђ͎Ј������Ă��Ȃ��v�u�撣���Ă��]������Ȃ��v�ƁB�������A���{�̎��{��`�o�ς̃��[�����l����A�����Q���̂́u�؈Ⴂ�v���������Ƃ��킩��܂��B���ʂ��グ���狋�����オ��Ɗ�����̂́A������������������̂ł��B
�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���ʂ��グ�Ȃ��Ă����͂����Ȃ��I�v�����������_������Ǝv���܂��B�ł��A�ڂ��́u���ʂ��グ�Ȃ��Ă������v�ƌ����Ă���̂ł͂���܂���B
�ނ���A�u�J���́v�Ƃ������̂��u���i�v�ɂȂ邽�߂ɂ́A�g�p���l�����邱�Ƃ���Ώ����ł��B���ʂ��グ���Ȃ��J���҂́A�g�p���l���Ȃ��̂ŁA��ƂɌق��Ă��炦�܂���B���ʂ��o�����Ƃ͕s���ł��B
�g�p���l���オ��A�u���̏��i���ق����I�v�Ǝv���l�������܂��B��ʂ̏��i�ōl����A�g�p���l������A����҂ɑI��ł��炦�܂��B�����āA�p�����Ĕ����Ă��炦�܂��B
�����J���͂ōl����ƁA�u�J���̎g�p���l�������(���̐l���D�G�ŁA��Ƃɗ��v�������点��)�A��ƂɑI��ł��炦��A�p�����Čق��Ă��炦��v�ƂȂ�̂ł��B
���C�Â��ł��傤���H �J���҂Ƃ��ėD�G�ɂȂ�A��Ƃɗ��v�������炷���Ƃœ�����̂́u�ق������Ă��炦�邱�Ɓv�Ȃ̂ł��B�������オ�邱�Ƃł͂���܂���B2�{�̐��ʂ��o����悤�ɂȂ��Ă��A������2�{�ɂ͂Ȃ�܂���(��قǂ̘b�̒ʂ�A1.2�{���炢�ɂ͂Ȃ邩������܂���)�B
�����������̂Ȃ̂ł��B���ꂪ���{��`�o�ςɂ����鋋���̃��[���Ȃ̂ł��B
�������J���Ȃ̓��v���ؖ����Ă���
����͊���̋�_�ł͂���܂���B�����ɂ����Ȃ��Ă���̂ł��B�����J���Ȃ����\���Ă��铝�v(����25�N�Œ��������������)�ɂ��ꂪ�\��Ă��܂��B����́A��{���̋��z�����߂Ă���v�f�ł��B��{���S�̂�100�Ƃ����Ƃ��A���ꂼ��̗v�f���ǂ̂��炢�l������邩��\���Ă��܂��B
1. �N��E�Α����c�c14.4��
2. �E���E�\�͋��c�c31.3��
3. �ƐсE���ʋ��c�c4.9��
4. �������f�c�c49.4��
�ƐсE���ʋ���4.9����������܂���ˁB���ꂪ���Ԃł��B���Ƃ��A�����̌�����z�����Ă��������B����40���~���Ƃ��܂��傤�B���̌����J���Ȃ̃f�[�^����l����ƁA�����̒��ŁA��ԗD�G�Ȑl�͌���42���~(�v���X5��)�A��Ԑ��ʂ��オ��Ȃ��l�́A����38���~(�}�C�i�X5��)�ƂȂ�܂��B����͂��Ȃ蔧���o�ƍ����Ă���A�[���ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ł����u�\�́v�Ƃ̓X�L���ł͂Ȃ��A�Љ�l�Ƃ��Ă̊�b�̂���
�u�ƐсE���ʋ���4.9�������A���̏�́w�E���E�\�͋��x��31.3��������B��͂�J���҂̔\��(�g�p���l)������Ă���̂ł́H�v�Ɗ����邩������܂���ˁB
�ł�������́A���t�̈Ӗ���������Ă��邾���ł��B�u�E���E�\�͋��v�Ƃ́A�J���҂��グ�����ʂł͂Ȃ��A�Љ�l�Ƃ��Ă̊�b�I�Ȍo���ƁA�Љ�l�Ƃ��Ă̊�{�Ɩ������Ȃ��\�͂��w���Ă��܂��B
���Ƃ��A�d�������邤���ŕK�v�ȗ�V�A���t�Â�������X�P�W���[�������\�́A�i���́A�����E�v���[���́A���̑��Љ�l�Ƃ��ĕK�v�Ȓm�����{�ƂȂ�o�����u�\�́v�ƒ�`���A����ɉ����Ă������Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�����āA���̊�b�I�Ȍo����Љ�l�Ƃ��Ă̊�{�Ɩ������Ȃ��\�͂́A�u�Љ�l���ɔ�Ⴕ�Đg�ɂ��v�ƍl�����Ă��܂��B���̂悤�Ȕ\�͎͂d����ʂ��āA�o����ʂ��Ē~�ς���Ă����܂��B�ʏ�A�o����ς߂ΐςނقǑ����Ă����܂��B�����āA��̓I�Ȏd�����e���ς���Ă�������̂ł͂���܂���B
���Ƃ��A�Љ�l10�N�ڂ̐l���A���S�ɖ��o���̋ƊE�ɓ]�E�����Ƃ��܂��B4��1���Ɋw�Z�𑲋Ƃ����Ă̐V���Ј��Ɠ����ɓ��Ђ��܂����B���̋ƊE�̂��Ƃ��܂������m��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł́A�V��1�N�ڂ��A10�N�ڂ݂̂Ȃ���������ł��B
�������A�݂Ȃ���̕������|�I�Ɏd�����ł���ł��傤�B�Ȃ����H �d���̂������킩���Ă��邩��ł��B10�N�̌o����ςݏd�˂Ă���̂ŎЉ�l�Ƃ��Ẵx�[�X�̗͂����邽�߁A�V���Ј��ƈႤ�̂ł��B
���ꂪ�u�E�\���v�ɔ��f����Ă���u�\�́v�Ȃ̂ł��B����͐�قǂ��炨�`�����Ă���u�J���͂̉��l�v�ɑ��Ȃ�܂���B�݂Ȃ���Ɠ������x���́g�n�́h��g�ɂ��邽�߂ɂ́A�Љ�l�Ƃ���10�N�̌o�����K�v�ł��B���ꂪ�����̋��z�����߂�傫�ȗv�f�ɂȂ��Ă���̂ł��B
|
|
��5 �Ȃ��N��1000���~�ł��A�������ꂵ�����H
|
�u�����Ă������Ă��������オ��Ȃ��v�u���܂ł����Ă��������y�ɂȂ�Ȃ��v����������l�͑������낤�B�������A����͊撣�肪����Ȃ��킯�ł��A��Ƃ��u���b�N�����Ă���킯�ł��Ȃ��A���{��`�̃��[���Ɋ�Â��ċ������x�����Ă��邩��B��ɐ������J�c�J�c�ƂȂ�{���̗��R�Ƃ͉����H
����������������ɂ́H
����܂�4��̘A�ڂ�ʂ��ĉ�����Ă����Ƃ���A�����͘J���҂��o�������ʂŌ��܂��Ă���̂ł͂Ȃ��A�J���͂̉��l�A�܂�u���̘J���҂��������d�������邽�߂ɕK�v�ȃR�X�g�v�Ō��܂��Ă��܂��B
���́u�K�v�ȃR�X�g�v�ɂ́A�H���E�Z���Ȃǂ̗̑͂��E�ێ������邽�߂ɕK�v�Ȃ��������łȂ��A���̎d�������邽�߂ɕK�v�Ȓm���E�o���E�Z�p�𑵂��邽�߂ɂ�����R�X�g���܂܂�܂��B
�O��ŁA��҂�ٌ�m�ȂǁA���I�Ȓm���Ⓑ�N�̌o�����K�v�Ȏd���́A���̂��߂ɕK�v�Ȓm�͂�g�ɂ���̂ɖc��ȃR�X�g�ƘJ�͂�������A���̂��߈�҂�ٌ�m�̋����͍����A�Ƃ����b�����܂����B
�����āA����̌����J���Ȃ̓��v�f�[�^������A�}���N�X�̗��_�����Ă͂܂��Ă��邱�Ƃ��m�F���܂����B�܂�A�������������邽�߂ɂ́A�u�J���͂̐��Y�R�X�g�v�������グ�邱�Ƃ��|�C���g�Ȃ̂ł��B
�`����̎d��������̂ɂ́A���x���`�̒m����Z�p�����߂���Ƃ��܂��B�����Đ��Ԉ�ʓI�ɁA���x���`�̒m����Z�p��g�ɂ���̂ɁA100���Ԃ�����Ƃ��܂��傤�B
����A�a����̎d��������̂ɂ́A���x���a�̒m����Z�p�����߂��܂��B������̃��x���a�̒m����Z�p��g�ɂ���ɂ́A200���Ԃ�����Ǝv���Ă��܂��B���̏ꍇ�A���_�I�ɍl����Ƃa����̕��������������Ȃ�܂��B
���i�̌��ޗ��ɁA���̏��i�����邽�߂̃X�L���K����܂܂��̂Ɠ��l�A�J���͂Ƃ��Ă̏��i�ɂ��A�u���̎d�������邽�߂ɕK�v�ȃX�L���v��g�ɂ��邽�߂ɁA������������(�J����)���p���l������܂��B�H��A�ƒ��A�m����A�X�g���X���U�̂��߂̈��ݑ�̑��ɁA�Z�p�K����u�J���͂̉��l�v�Ƃ��čl�������̂ł��B
���X�g�����̃V�F�t�ɂȂ邽�߂ɂ́A�����t�Ƌ������A�C�Ƃ��Ȃ�������܂���B���̏C�Ƃ������āA���߂ăV�F�t�Ƃ��ē������Ƃ��ł��܂��B�܂�A���̏C�Ɗ��Ԃ��u�V�F�t�Ƃ��ē����v�Ƃ����J���͂́u���ޗ��v�ɂȂ��Ă���킯�ł��B������A�V�F�t�̘J���͂̉��l�ɂ́A���X�̃V�F�t�̘J�������łȂ��A���̏C�Ɗ��Ԃɂ������ߋ��̘J�͂��܂܂��̂ł��B
�����悤�ɁA��w�̐搶�ɂȂ邽�߂ɂ́A��啪��̒m����g�ɂ��邽�߂ɕ����A�_���������Ȃ�������܂���B���̕����Ԃ�_���������̂ɔ�₵���J�͂��u��w�̐搶�̘J���͂̉��l�v�ɉ��Z����܂��B
�܂��A�Ƌ����Ȃ���ł��Ȃ��E�Ƃ�����܂��B�����A���̖Ƌ������̂�100���~���������Ƃ�����A���̂Ƃ��������������́A���̎d��������J���͂̉��l�ɉ��Z����܂��B
�������A100���~�������Ď��i�E�Ƌ����擾���Ă��A����̎d���ł����Ȃ�100���~�S�z���u�J���͂̉��l�v�Ƃ��ď�悹�����킯�ł͂���܂���B���̎��i�E�Ƌ��̗L�����Ԃ��l�����A���̊��ԓ��Łu100���~�v���ϓ����肵�ĘJ���͂̉��l�ɏ�悹�����悤�ȃC���[�W�ł��B
������ɂ��Ă��A���̎d�����ł���悤�ɂȂ邽�߂ɕK�v�ȏ������ԁA���̏����ɔ�₵���J�͂��u�J���͂̉��l�v�Ƃ��ĉ��Z�����̂ł��B
�������́u�K�v�o��v�̂�
�ڂ���J���҂̋����́A�u�J���͂̉��l�v�Ō��܂��Ă��܂��B�܂�A�J���͂��Đ��Y���邽�߂�(�������������߂�)�A�K�v�Ȃ����������Ƃ��Ă�����Ă���킯�ł��B
�Ƃ���A�����ɂȂ�Ƌ�s�c�����Ȃ��Ȃ��Ă���̂��A�܂������s�v�c�ł͂���܂���B����1�����ԁA�������āA�d�������邽�߂ɕK�v�Ȃ����������Ƃ��Ă�����Ă���̂ŁA�����ɂȂ����炨�����Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ����̂́A�ނ���u������O�̂��Ɓv�Ƃ������܂��B
�t�ɍl����ƁA�J���҂́u�����������߂ɕK�v�ȕ��v����������Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��킩��܂��B
�u�Ђƌ��ɐ���͈��݂ɍs���ċC���炵�����Ȃ��ƁA����Ă��Ȃ��v�ƍl�����Ă����Ƃ�����A���̈��ݑ���u�K�v�o��v�Ƃ��ċ����ɏ�悹���Ďx������܂��B
�����A������u���_�q������邽�߂̕K�v�o��v�Ȃ̂ł��B�K�v�����炭���킯�ł����āA�����ĘJ���҂��u�撣��������v�ł��u���ʂ��o��������v�����킯�ł�����܂���B
�ڂ���̋����́A���̂悤�ɕK�v�o������Ō��܂��Ă���̂ł��B������A�u�T�����[�}���͂��܂ł����Ă�����ǂ��v�̂ł��B�l�ɂ���āA������Ă��鋋�����Ⴂ�܂��B�V���Ј����A30�N�ڂ̃x�e�����Ј��̕��������͍����ł��傤�B
�������A�����30�N�ڂ̎Ј��̕����������т��o���Ă��邩��ł͂Ȃ��A30�N�ڂ̎Ј��̕����}�{�Ƒ����ł�����A�N�����̐g�Ȃ�����Ȃ�������Ȃ������肵�āA�������������Ȃ̂ł��B�������A�V���Ј����30�N�ڂ̎Ј��̕����A�d���̐��ʂ��������낤�Ǝv���܂��B
�������A�K�������N������̐l�����ʂ��o���Ă���킯�ł͂���܂��A�������x�����Ă���u�J���͂̎g�p���l�v(�J���҂���Ђɂ����炷���v)�ł͂���܂���B�����܂ł��u�J���͂̉��l�v�ɑ��āA�Ȃ̂ł��B
�Ƃ������Ƃ́A�������オ�����Ƃ��Ă��A����́u�����Ă������߂̕K�v�o�����������v�Ȃ̂ł��B�����͏�ɃJ�c�J�c�Ȃ̂ł��B
�}���N�X�́A�u���������肷��ۂ́A���ꂾ���͊O���Ȃ��Œ���̊�́A�J�����Ԓ��̘J���҂̐������ێ��ł��邱�ƂƁA�J���҂��Ƒ���}�{�ł��A�J���҂Ƃ����푰�����ɐ₦�Ȃ����Ƃɒu�����v(�w�o�ϊw�E�N�w���e�x��ꑐ�e�E��D����)�Ƃ������t���c���Ă��܂��B
�u�A�_���E�X�~�X�ɂ��A�����̐l�ԂƂ��Đ����Ă������ƁA�܂�A�ƒ{���݂̐����Ɍ������Œ���ɗ}�����Ă���v�Ƃ������Ă��܂��B(��)�N��ɂ�炸�A�Љ�l�o���ɂ�炸�A�݂�ȁu�����Ă������߂ɕK�v�ȍŒ���̋����v�������炦�Ȃ��̂ł��B
�u�Œ���̋����v�̈Ӗ��͏����ς���Ă��܂��B�쎀��������O�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A����̐����ɏƂ炵���킹�āu�ӂ��v�Ǝv���鐶�����ł��邾���̋��z�ł��B
����������Ă���̂ɁA�Ƒ����{���{���̕��𒅂āA�����������������Ă�����A����́u���������C�ɓ������Ɓv�͂ł��Ȃ��ł��傤�B�ł��A�����瓭���Ă��A������o����ς�ł��u�L���ɂȂ邽�߂̂����v�͂��炦�܂���B�����琬�ʂ��o���Ă��A�ł��B
�J���҂Ƃ��ċ������グ��Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���K�v�ȃR�X�g���₷�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�J���҂̋������オ��̂́A���ʂ��グ������łȂ��A�����Ă݂�u������オ��������v�ł��B�������́A�u�X�g���X������������v�ł��B
�Ƃ����̂́A�J���҂̋����ɂ́A�u�d���ɂ���Ď���ꂽ���_�I�G�l���M�[�v�����邽�߂̔�p���܂܂�Ă��邩��ł��B�܂�A�X�g���X������Z����Ă���̂ł��B
���̂��߁A�v���b�V���[�̍����d���ɏA���A���ꂾ���������オ��܂��B�ӔC���d����E�́A���̕������������ł��B������t�ɍl����ƁA�u�X�g���X����������A���̕������������v�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�܂�A��Ƃœ����J���҂��������グ�邽�߂ɂ́A���ꑊ���̑Ή����x����Ȃ�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���i�ɂ��Ƃ���A���l��1���~�����ł��Ċ��ł�����A���͌�����1���~�オ���Ă��āA�����̎�蕪���ς���Ă��Ȃ������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł��B
�ƂȂ�ƁA������҂��ł��A�L���ɂ͂Ȃ�܂���B�N������������A�ǂꂾ���L���Ȑ������҂��Ă��邾�낤���Ɩϑz����l�͑����ł��B
�����������I�ɂ́A�����Ɠ����ɕK�v�o�������̂ł��B�܂��A�N������^�̋������E���オ��Ȃ̂����������ł��B������x�N������āA�Ƒ���{���̂ɂ����������邩��A���̕������ɏ�悹����܂��B������u�����v�Ȃ̂ł��B
�ł������R�A���̐l���������Ă����A�Ƒ���{�����߂ɕK�v�ȋ��z��������Ă��邾���Ȃ̂ŁA�����ɂȂ�u���̊Ԃɂ��������Ȃ��Ȃ��Ă���v�̂ł��B
�����̌��܂���̃��[�����ς��Ȃ�����A����͕ς��܂���B�������ł����A���ꂪ�����Ȃ̂ł��B
������ǂ����甲���o�����߂ɁA�݂�Ȃ�����Ă��邱��
�u�������オ��Ȃ��v�u���܂ł����Ă��������y�ɂȂ�Ȃ��v�u�d�����Z��������v
�����̐l�����������Ȃ��瓭���Ă��܂��B�����āA�Ȃ�Ƃ����̏�ŊJ���悤�Ƃ��Ă��܂��B�������A���́u��v���Ԉ���Ă���̂ł��B
���̂���ǂ���ŊJ���邽�߂ɉ������Ă��邩�ƌ����A����l�́A��萬�ʂ��グ�邽�߂ɁA�����ԘJ�����܂��B�܂�����l�́A�X�L���A�b�v�̂��߂Ƃ����āA���i���擾���悤�Ƃ��܂��B
�ł����A�����͉�����ɂȂ�܂���B�܂��A��萬�ʂ��o�����Ƃ��Ă��A���قNj����͏オ��܂���B�����́A�J���͂́u�g�p���l�v�ł͂Ȃ��A�u���l�v�Ō��܂��Ă��܂��B���̂��߁A�g�p���l(��ЂɂƂ��Ẵ����b�g)���グ�Ă����ʂ͔����̂ł��B
�O�ɏЉ���ʂ�A���ʋ��͊�{���̂���5�����x�ł��B���ꂭ�炢�����l������Ȃ��̂ł��B�J��Ԃ��܂����A�J���͂̎g�p���l�͕K�v�ł��B���i�ɂ́u���l�v�Ɓu�g�p���l�v���Ȃ�������܂���̂ŁA���ʂ��グ�Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł͂���܂���B
�ł́A���i���擾����̂͂ǂ��ł��傤���H����́A����Ɂh�������w�́h�ł��B�Ƃ����̂́A�J���͂́u���l�v�̎��_�������Ă���\�����傫���A�܂��u�g�p���l�v�̎��_�ɂ��ẮA���S�ɔ��������Ă��邩��ł��B
���i����낤�Ƃ���̂́A���i����肳������A�������オ��Ǝv���Ă��邩��ł�(���Ȃ��Ƃ��A�����̎菕���ɂȂ�Ǝv���Ă��܂�)�B�ł����A�����̋��z�́A���̎d���𑱂���̂ɕK�v�Ȃ��̂������l�����Ă��܂��B
�d���ɂ܂������W�Ȃ����i������Ă��Ӗ�������܂���B�܂��A�{���́A���̎d���ɕK�v�Ȓm����X�L����g�ɂ��悤�Ƃ������z�ŕ������ׂ��ł��B�u���i����肳������v�Ɗ����Ă��鎞�_�ŁA�������t�ł��B����ł́A���i���擾���邱�Ƃ��ړI�ɂȂ�A���ꂪ�d���Ɏg���邩�A�܂莩���́u�J���҂Ƃ��Ă̎g�p���l�v���グ�邩�ǂ����͂킩��܂���B
�]�E�ɗL���ƍl���Ď��i���擾����l�����܂��ˁB���̃p�^�[�����ꏏ�ł��B�]�E�ɗL���Ȏ��i������Ƃ͎v���܂��B���i���Ȃ���ł��Ȃ��d��������܂��B
�ł��A����ȊO�́u���i�������Ă���A���d�����ł���v�Ƃ������̂ł͂���܂���B���i�Ƃ��̎��i�����Ƃ��ɐg�ɂ����m���E�X�L���́A�����܂ł��⏕�ł��B���i�������ꂾ���ʼn��Ƃ��Ȃ�킯�ł͂���܂���ˁB
���{�͌o�ϐ�i���ł��B�L���ȍ��̂͂��ł��B�������A���́u�L���ȍ��v�Ő�����ڂ���́A���̖L�������������Ă��܂���B�ނ��뎞�オ�i�ނɂ�āA����Ɏd���������ԂɂȂ�A����ǂ��Ȃ��Ă���悤�Ȉ�ۂ������܂��B
�J���҂����܂ł����Ă��L���ɂȂ�Ȃ��̂́A�u�K�v�o��v����������Ă��Ȃ�����ł����B�܂��A�ǂ�����������オ�邩�Ƃ����|�C���g���������Ă��邱�Ƃ������A�Ԉ�����w�͂��Ȃ���Ă��܂��B������A�u���܂ł����Ă�����ǂ��v�̂ł��B
��Ԃ̔���́A�u�J���҂́A�Ȃ�����ǂ��̂��H�v�Ƃ������̎���ɑ��铚�����A�}���N�X��150�N���O�ɂ��łɐ����Ă����Ƃ������Ƃł��B
|
|
��6 �J�����Ԃ͑����A�����͉�����
|
���J�Ȃ��������������Ă���u�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����v�B�ŋ߂悭���ɂ��邯�ǁA�ǂ��������̂��悭�킩��Ȃ��l�͑����͂��B�ʂ����ă��[�N�E���C�t�E�o�����X�̉��P�ɂȂ���̂��낤���H ����Ƃ��A�܂��܂��J���҂��ꂵ�߂鐧�x���H 150�N�O�ɏ����ꂽ�w���{�_�x�ł��\������Ă����A���{��`���K�R�I�Ɍ������J���҂̉ߍ����Ƃ́H
����A����ȃj���[�X������܂����B
�����J���Ȃ�(5��)23���A�������̐��E�Ɍ���A�������Ԃ����ȍٗʂƂ������Ɏc�Ƒ�̎x�����Ȃǂ̘J�����ԋK����K�p���Ȃ��u�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����v����������Ō����ɓ������B(�Y�o�V��)
����́A�v����ɁA����̃z���C�g�J���[�l�ނɂ́A�c�Ƒ���x����Ȃ��Ă������悤�ɂ���Ƃ����Ӗ��ł��B
���Z�@�ւ̃f�B�[���[�ȂǁA�J�����Ԃ������̍ٗʂŌ��߂₷���E�킪�u�c�Ƃ�Ȃ��Ă����Ώہv�ƂȂ錩�ʂ��ł��B
���̐��x�͈ȑO�������������������A���̓s�x�ᔻ�̑ΏۂɂȂ��Ă��܂����B�����āA���̃j���[�X���\��A�܂����c�������Ă��܂��B
�c�����v���J���͋L�҉�ŁA�u���ʂ��͂���A�����I�ɓ������Ƃ��A���[�N�E���C�t�E�o�����X�̉��P�ɂȂ���v�A�Ƃ�����|�̃R�����g�����Ă��܂��B
�܂�A�J�����Ԃł͂Ȃ��A���ʂŋ��������Ƃ��A�J���҂̃����b�g�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃł��B
�������ɁA���̑��ʂ͂���ł��傤���A�J���҂��猩����u�J�������̉����v�ł��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��ł��傤�B�J���g�������A�J�����Ԃ������Ȃ�Ƃ����������O���o���Ă��܂��B
�������A���̐��x�ŘJ���҂��C�����Ȃ�������Ȃ��̂́A�u�����ԘJ���v�����ł͂���܂���B���ł��A�܂Ƃ��Ɏc�Ƒ���Ă����Ƃ͏����ŁA������O�̂悤�Ɏc�Ƒ�Ȃ��̒������ԘJ�����܂���ʂ��Ă��܂��B
�����l����ƁA�u���ƕς��Ȃ��v�Ƃ��v���܂��B�������A����̐��x�́A�C�����Ȃ���ΐV���ɘJ����������������\����s��ł��܂��B
�w���{�_�x���������J�[���E�}���N�X���A150�N�O�ɁA���łɂ��̊댯�����w�E���Ă��܂����B
�܂�A�����������Ƃł��B����b��ɂȂ��Ă��鐧�x�͂܂�A�u�J�����Ԃł͂Ȃ��A���ʂŕ]�����܂���v�Ƃ������Ƃł��B����̓}���N�X���w�E�����u�o�����������v�ɒʂ��܂��B
���̐��x�ł́A�J���҂́A�^����ꂽ�Ɩ����I���܂Ŏd�������Ȃ�������܂���B�܂�A�d�����I���Ȃ���������x����Ȃ��Ă����Ƃ������ƂɂȂ蓾�܂��B���̂��߁A�J���҂ɒ����ԘJ���������鐧�x�Ɣᔻ����Ă���̂ł��傤�B
�������A����ɕ|�����Ƃ�����܂��B����́A���ʂ��オ�������ǂ����͊�Ƃ����ӓI�Ɍ��߂邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����_�ł��B
�}���N�X�́A���̓_���w�E���Ă��܂����B�P�Ɂu�c�Ƒ��Ȃ��Ă悭�Ȃ�������A�������������Ⴆ�v�ł͏I��炸�A�J���҂����Y�������ʕ����u���������B����B�B����ł�50���̎d���������ɂ����Ȃ��B�����狋����50�����������Ȃ��v�ȂǂƂ����āA�������̂������邱�Ƃ��ł��Ă��܂��̂ł��B
�܂��A�m���}�̊���グ�邱�ƂŁA�u�K��̐��ʂ�30�������������Ȃ���������A������30���ɂȂ�܂��B��낵���ł���ˁv�ƂȂ蓾�Ă��܂��̂ł��B
����A�s��ɂ͏��i�����ӂ�A���i�邱�Ƃ�����Ȃ��Ă��܂��B����������ŁA�l����͌Œ�I�ŁA�d����Ɠ����悤�ɂ͏_��ɕω������邱�Ƃ͂ł��܂���B���i�邱�Ƃ�������Ȃ��Ă������̒��ŁA�l�����}�����悤�Ƃ��铮���́A������ǂ�ǂ��Ȃ��Ă����܂��B
����̃z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����́A�ꕔ�̐E��Ɍ����܂����A����A���ׂĂ̐��Ј��ɓK�p����悤�Ɍ��������ł��傤�B
���̗���͕K�R�ł����A��Ƃ������c���Ă������߂ɁA�����Ă��̊�Ƃ��J���҂ɓ��������邽�߂ɂ�ނȂ����f���ƁA�l�I�ɂ͊����Ă��܂��B
�������A�}���N�X���w�E�����_�́A��ɔO���ɒu���Ȃ�������܂���B�܂�A��Ƃ����ӓI�Ɂu���ʕ��̎��v�u�m���}�̗ʁv��ς��Ȃ��悤�ɂ��Ȃ�������Ȃ��̂ł��B
�����āA���ʂ��o�Ȃ�����Ƃ����ċ����ӓI�Ɉ��������鎖�ԂɂȂ��Ă͂����܂���B
����̐��x�����ɑ��A�J���҂��l����ׂ����Ƃ́A�����ԘJ����h���Ƃ������Ƃ����A�����P�����̂������������Ȃ��ɂ��邱�Ƃ��ƁA�}���N�X�̎w�E���犴���܂����B
|
|
��7 ���ɂȂ����狋���͏オ��̂�
|
�j���[�X�ŁA�i�C�̉A�x�[�X�A�b�v�A����ҕ����w���̏㏸�ɂ��Ă悭���ɂ��邪�A���ۂ̂Ƃ��닋�����オ���Ă���l�͏������낤�B��̂��ɂȂ�����ڂ���̋����͏オ��̂��낤���H 32�N�Ԃ�̕����㏸�𑱂�����{�ŁA�T�����[�}�����m���Ă����ׂ��A���{��`�̗⍓�ȃ��[���Ƃ́H
�����Ȃ́A6��27���A5���̑S������ҕ����w��(���N�H�i������)�\���܂����B����ɂ��ƁA�O�N������3.4���㏸��103.4�ƁA12�����A���ŏ㏸���܂����B�G�l���M�[���i���㏸�������Ƃƍ��킹�āA����ŗ���8���Ɉ����グ��ꂽ�e������������ƕ��͂���Ă��܂��B
���̕����㏸���́A32�N1�����Ԃ�̑傫���B���ɑ�2���Ζ���@���1982�N�ȗ��ł��B
��ʓI�ɍl����ƁA�����͌i�C���悭�Ȃ�ɂ�āA�オ��X��������܂��B���̂��߁A����32�N�Ԃ�̕����㏸���u�f�t���E�p�Ɍ������O�i�v�ƕ]�����鐺������܂��B
�������A���R�̂��ƂȂ��畨�����オ�邾���ōD�i�C�ɂȂ�킯�ł͂���܂���B�u�����㏸�������㏸��������v�ƂȂ�Ȃ���Όi�C�͏�����Ă����܂���B
�������オ��ꍇ�A�����������ɏオ��Ȃ���Ύ��������͉�����܂��B3.5��������ҕ������オ���Ă�����A����҂̍w���͂͌���܂��B
�����J���Ȃ̓��v�ɂ��ƁA1���ѓ�����̕��ω��������͖�430���~�ł��B�P���v�Z����ƁA��15���~���A�w���͂��������Ȃ������ƂɂȂ�܂��B���z1���~���ł��B�����Ȃ�ƁA�������ꂵ��������l���o�Ă��܂��ˁB
�����ŊS���W�܂�̂́A�u�������オ�����������A�������オ�邩�v�ł��B
�w���{�_�x�̗��_�ōl�����ꍇ�A�������ǂ̂悤�Ɍ��܂��Ă��邩�A����܂ł̘A�ڂł��łɉ�����܂����B�����āA���{��Ƃ̋����̌��܂���́A���̎��{�_�̗��_�����S�ɍ��v���Ă��邱�Ƃ�������܂����B
���߂ĊȒP�Ɍ����ƁA���{��Ƃł͋����͎��̂悤�ȍl�����Ō��܂��Ă��܂��B
���Ȃ킿�A�u���̘J���҂����������C�ɓ������߂ɕK�v�ȃR�X�g�v���l���A���̍��v���z�������Ƃ��ēn���Ă���̂ł��B
�H��A�Z����A�ߕ��A�X�g���X���U��ȂǁA�����������Ă��炤���߂ɕK�v�Ȃ��̂̍��Z�������Ȃ̂ł��B
�����l����ƁA�������オ��A���̕��������オ���Ă������ƂɂȂ�܂��B�����A�����͕����ɘA�����ďオ���Ă��܂���B����͂��������ǂ��������Ƃł��傤���H
����ɂ�2�̗��R������܂��B
(1)�@�������オ��^�C�~���O�͌����Ă��邩��
�����͔N��1��A��������2��̊�Ƃ��唼�ł��B�����A�}�ɕ������オ���Ă��A�����ɏ��������킯�ł͂���܂���B
(2)�@�����͐�����u�����v�ł͌��܂��Ă��Ȃ�����
��Ƃ́u�������������߂ɕK�v�Ȃ��́v�����z���Z���ċ����Ƃ��ēn���Ă��܂��B�����Ă������Ƃ�����A�d�����̗͓I�E���]�I�Ɋy�ɂȂ�A���́u�K�v�Ȃ��́v������܂��B
���Ƃ��A�d������ɋ@�B��e�N�m���W�[����������āA�d�����y�ɂȂ�ƁA���������������鈳�͂��������ƂɂȂ�̂ł��B
���āA19���I�����̃C�M���X�Łu���b�_�C�g�^���v�Ƃ����J���҂̖\�����N���܂����B�@�B�����Y����ɓ�������A����ɂ���ĐE���������J���҂������A���Y�ݔ���j�ĉ�����̂ł��B�@�B�����������ƁA�l�Ԃ̘J���҂͕s�v�ɂȂ�̂ł��B
����́A�����Ɍ������b�ł͂���܂���B����ł����Y���C�����@�B������A�����̘J���҂��E�������Ă��܂��B
����ɂ����A���Y���C���ɗ����Ă��Ȃ��z���C�g�J���[���E�⋋������������܂��B�z���C�g�J���[���s���Ă����d���́A�₪�ăe�N�m���W�[���㗝�ōs����悤�ɂȂ�ł��傤�B
���łɁA��Փx�������E�l�Z���@�B�E�e�N�m���W�[�ɂ���đ�ւ���Ă��܂��B���̌��ʁA�J���҂�����܂Ŕ|���Ă����u�o���v�����l�������Ă��܂��B
�e�N�m���W�[���ł���̂ł���A�u�E�l�v�͕s�v�ł��B�E�l�ł͂Ȃ��A�@�B�𑀍삷��I�y���[�^�[���V�����A������Ōق��܂��B���܂�A�r�W�l�X����ɋ@�B��e�N�m���W�[���ǂ�ǂ���荞��ŗ��Ă��܂��B�����āA�ڂ���̘J���͂ǂ�ǂ�u�y�v�ɂȂ��Ă����܂��B
���������̈���ŁA�J�����y�ɂȂ�A�������������Ă��܂��\��������܂��B�u�d�����y�ɂȂ�������A���������Ă�������ˁv�ƁB
������͏㏸���܂����B�����������ɁA�e�N�m���W�[�����B���邱�ƂŁA�d���͂ǂ�ǂ���������y�ɂȂ��Ă��܂��B������A���Ăقǁu���ς݁v������Ȃ��Ȃ�A���Ăقǒm�́E�̗͂��g��Ȃ��Ă��悭�Ȃ�܂����B
���̕��A�������������Ă��܂��B�������͂��̕��A�オ���Ă����͂��̋��������炦�Ȃ��Ȃ�A�̂ł��B�P�ɕ������オ��������オ��킯�ł͂���܂���B����łЂƈ��S�Ȃǂ��Ă����܂���B
�܂��A�u�d�����y�ɂȂ����v�Ɗ��ł���͂����܂���B�ڂ��炪�������グ�Ă������߂ɂ́A�d�����u�y�v�ɂȂ������ߍ��킹�A����ɂ���ȏ�ɑ̗͓I�E���]�I�Ɋ撣��Ȃ�������Ȃ��̂ł��B
�ڂ��炪��炵�Ă��鎑�{��`�́A�����������[���œ����Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂����܂���B
�@ |
 �@ �@
��1929�N�A�����J�勰�Q�ƃA�[�T�[�E�~���[
�@2008�N�̃A�����J�����Z��@�Ƃ̊֘A����
|
   �@
�@
|
���͂��߂�
�{���̂��̍ŏI�L�O�u�`�̃^�C�g���ł����A�������A�����̃A�����J�ɂ�������Z��@�̏�1929�N10���ɋN�������A�����J���̑勰�Q�Ƃ����ւĂ���̂ŁA���X�ɓK�����e�[�}�ł���Ƃ̎v���������đI�т܂����B�����m�̂悤�ɁA����̃A�����J���̋��Z��@�̐��������ɋ����Đ��E�����o�ϕs���Ɋׂ��Ă���܂��B29�N�̑勰�Q�̎��ɂ́A�A�[�T�[�E�~���[��14�ł���A���e�̕w�l�������H�ꂪ���̑勰�Q�����ڂ̌����œ|�Y������ڂ̓�����ɂ��܂����B���̃V���b�L���O�ȑ̌���ނ̓~�V�K����w�݊w���Ɍ��܉����i�Ƃ��ď������w���l�ł͂Ȃ��x�i1936�j�Ƃ�����i�ɕ`�������ł��B���̍�i�͌����A�܂āA���̌ケ����Q�������ĉ�����d�˂܂����B�����͂��̎�l���̖��O�������āw�G�C�u�E�T�C�����Ƒ����O����x�Ƃ��Ė��o�łł͂���܂����A�~���[�����Ƃ̊Ԃł͒m���Ă��܂��B����Ȍ�A�~���[�͑勰�Q�ځE�Ԑڂ̕ʂ͂���܂����A����i�ŕ`�����ƂɂȂ�܂��B
���ڂɕ`������i��N��ʂɕ��ׂ�Ɓw��̌��j���̎v���o�x�i1955�j�A�w�㉿�x�i1968�j�A�w�A�����J�̎��v�x�i1980�j�ƂȂ�܂��B�勰�Q�́A����܂ł̓`���I�ȃA�����J�̃G�g�X�ł���u�A�����J�̖��v�gAmerican Dream�h �ɑ傫�ȗh���Ԃ���������Ƃ����Ӗ��ł��A�厖���ł����B���̑勰�Q�Ɓu�A�����J�̖��v������e�[�}�Ƃ�����i�ɁA�~���[�̋L�O���ׂ��u���[�h�E�F�C�i�o����ڂƂȂ����w�K�^��Ƃ��߂ɂ����j�x�i1944�j�Ƃ�����i������A����ɂ��Ă͂��b���̌㔼�ŐG��邱�ƂɂȂ�܂��B���āA���̍u�`�ł́A�܂������̃A�����J�����Z��@�̔w�i�A��Q�ɂ����29�N���̃A�����J�勰�Q�Ƃ̊֘A���A��R�Ƀ~���[�̑勰�Q�̌��A��S�ɑ勰�Q����������L�̃~���[�̍�i��������ǂ̂悤�ɕ`���Ă��邩�l�@���A��T�ɂ����̍�i�������ꂽ���ꂼ��̎���w�i�ƃ~���[�����̃e�[�}�����������R�A��U�ɑ勰�Q�Ɓu�A�����J�̖��v����Ƃ̊W�A�����čŌ�ɁA�勰�Q�Ɓu�A�����J�̖��v���e�[�}�Ƃ����i�ɂ�����~���[�̌x���Ȃ����͌x���̃��b�Z�[�W��ǂ݉����Ă݂����Ǝv���܂��B
|
���P�D2008�N�A�����J�����Z��@
�T�u�v���C���E���[�����Ɏn�܂�A���[�}���E�u���U�[�Y�̔j�]�Ŕ���������N���̐��E�I�ȋ��Z��@���������邱�Ƃ��Ȃ��A���E��2009�N���}���܂����B��N�X���̃��[�}���E�V���b�N�ōő�̊�@�Ɋׂ����E�H�[���X������Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�s�ꌴ����ӓ|�̎��{��`�́A���͂���E�ɒB���Ă��銴������܂��B�����̒����͕���Ďs��͂܂��ɃJ�I�X�Ɖ����A���{���܂ސ��E�̂�����g�g�݂��h�炢�ł��܂��B���]���N�O�����u�č��̌o�ϐ���ł̎��R���C��`�͐l�Ԑ��������Ă��Ȃ��B����������A��̂Ȃ����{��`�Ƃ������̂������B����̊�@�ł��̌��E���킩�����v�i�u��g���ɗ����������X�v�A�w��̐V���x�A2009�N�P��11���A�P�y�[�W�j�Əq�ׂāA���̔����w�E���Ă��܂��B���ʂ̓A�����J�̌o�ϗ��Ē������A�o���N�E�I�o�}�A�A�����J�V�哝�̂ɂƂ��Ă̍ő�̐����ۑ�ɂȂ�܂��B
�Ƃ���ŁA�j���[�E���[�N�̃E�H�[���X�̂ǐ^�ɑ傫�ȋ��̓���������̂��F����͂����m�ł��傤���B���̋��̓E�H�[���X�̔ɉh���肤�����ŁA�p�ꌗ�ł́u�����s��̋��C�v���gbull�h �ƌ����܂��B���Ȃ݂Ɂu��C�v�́gbear�h �������ł��B�ӂ���Ȃ�Ί��Ŗׂ����l���A���̓����ɂ��₩���Ă��̌���w�����Ȃł�̂ł����A2008�N�̏H�͈Ⴂ�܂����B�gArrest Bush�A�h �gGreed Kills�A�h �gBailout=Bullshit�h �ȂǂƏ������v���J�[�h���������l�������A���̋��̑����ɐQ���ׂ��Ă���p������ꂽ�̂ł��B�ޓ��͕ʂɊ��ő呹�����l�����ł͂Ȃ��A�E�H�[���X�̋�����Ђ����I�����ŋ~���ʂȂ�A���̑O�Ɏ����B�̕�炵������Ă���Ƒi���āA���{�̋��Z�@�~�ςɔ�����s�������ł����B�A�����J���{�����Z�x���@�Ăőz�肵�����o�z��7000���h���ƌ����Ă��܂��B������A�����J�̑��l���̂R���Ŋ���ƈ�l������2000�h���A���{�~�ł��Ɩ�20���~�ɂ��Ȃ�B�[�Ŏ҈�l������Ȃ�A5000�h���ȏ�̕��S�ƂȂ�܂��B�����̎s���́A������������Ȍ��I�������g�����~�ϖ@�ɒf�ŁA�v���e�X�g�����̂ł��B
����̋��Z��@�̒��ڂ̌����ł����A����͗v����ɁA�����Ȃ��؋��̏ؕ��ɁA�u���͖��������ǁA�����͕����܂���v�Ƃ������o���ڋq�ɋN�������ăT�C��������V�X�e���ł��傤�B�u�����́A�������������ɂȂ��Ă���v�ƐM�����܂��ꂽ�A���邢�͐M���邱�Ƃ��ł����l�Ԃ́A�������������̐g�̏�ɍ���Ȃ��؋�������B���������A�T�u�v���C���E���[���Ƃ����̂́A�Ⴂ�Љ�I�]�������Ă��Ȃ��l������ΏۂɁu���̂��Ȃ��ւ̊O���]���͕s���ɒႢ����ǂ��A�{���̂��Ȃ��͂����ƍ����]�����đR��ׂ��ŁA�����͕K�������Ȃ�܂���v�Ƃ����Â������������炷�V�X�e���������̂ł��B����ɓ��{�ł����ɂȂ����y�n�_�b�����B�u�����Ȃ������L���Ă���y�n�̕]���͕s���ɒႢ����ǂ��A������{���̕]���ɂȂ�͂��ł���v�ƁB�������āA�A�����J�̋��Z�ƊE�́A���̃T�u�v���C���E���[���̃V�X�e�����\�z����ɓ������āA�O���]�����Ⴍ�A���ȕ]���������l�Ԃ������u�A�����J�̖��v��̌��ł���Ƃ����_�b�𐁂����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
���l���R���Ƃ��ċ����ɏ����ĖL���ɂȂ邱�ƁA���ꂪ�u�A�����J���̖��v���Ɛ��������鋣���Љ�A�����J�̓`���I�ȍl�������ЂƂ܂��e�ɒu���Ƃ��Ă��A����̋��Z��@�̍ő�̌����͔��_���o��Ō����A�����ɂ킽��u�b�V�������̋K���ɘa�Ǝ��R���C����ɂ���Ƃ����̂��A����̌����ł��B2000�N�̑哝�̑I���Ŗ���}���̃A���E�S�A�ɐڐ�̖��A���������߂đ哝�̂ƂȂ����W���[�W�E�v�E�u�b�V���ł������A2001�N�P���̏A�C���ォ�獡�ЂƂx�������L�т�������Ă������ɁA���9.11���������e�����N���܂����B�ނ͂������܁A�p�̌����ʃe���W�c�ɐ��z�����A����ȗ��A�����J�͐퓬��Ԃɂ���͎̂��m�̎����ł��B�u�b�V���哝�̂��C���N�ƃA�t�K�j�X�^���ł̐푈�ɂ��܂��Ă���ԂɁA�o�ς́u���K�~�v�ggreed for money�h �ɋQ�����s��C���̏�Ԃ������A�܂��ɁA�u�s�ꌴ����`�v�̈��|�I�x�z�̏�Ԃɂ���ƌ�����ł��傤�B
�s�ꌴ����`�͐��{���ߓx�Ȗ��ԉ���������A�l�̎��R�ƐӔC�Ɋ�Â������Ǝs�ꌴ�����d������V���R��`�Ƒ������ǂ����Ƃ�����A���ɗ��̋��a�}�����͂��̎s�ꌴ�����d�����ė��܂����B���������o�܂������Ă��A���{������Ƃ������K�������Ȃ��̂ŁA���̊Ԍ���D���Ďs�ꂪ��Ɠ����̊T�O�������o���Ĕ��������炯�̋K����݂��āA���ׂ��ɑ������B���̌��ʁA�f���o�e�B�u�ƌĂ��e��̋��Z�h�����i�̉��s���������B�Z��o�u���̌����ƂȂ����T�u�v���C���E���[���̍���g�ݍ��،����܂߁A�����������Z�h�����i�́A���ׂĒZ������^�������̂ŁA�l������O�ɔ��蓦������̂��������Ƃ������z���܂���ʂ����̂ł��B
����͔����������ۗL���āA��Ƃ̐����Ƃ��̔z�����y���݂ɂ���Ƃ�������܂ł̒����^�̓����Ƃ͑S���t�̔��z�Ȃ̂ł��B�u�b�V�����哝�̂Ƃ��ČN�Ղ��Ă�����̂�2008�N���܂łȂ̂ŁA����܂łɂȂ�ׂ��������蓦������Η��v���m�ۂł���Ƒ����̓����Ƃ͍l�����B�����A�����ɂ����N�����j�]���K�ꂽ�B���ꂪ����̋��Z��@�̐��̂Ƃ����킯�ł��B
|
���Q�D1929�N10��24���̃A�����J�勰�Q
�����̏ɂ��ăA�����E�O���[���X�p���O�A�M�������x������c���́A�u100�N�Ɉ�x�N���邩�ǂ����̐[���ȋ��Z��@�v���ƌ����܂����B���ۂ̘b���A����̎��Ԃ�1929�N10��24���Ƀj���[�E���[�N�،�������Ŋ�������\���������Ƃ���|���ɐ��������Z���Q�ɑ�����{�ʐ��ł��邪�̂̃V�X�e���I�ȕs���Ɠ����̊e���̓����҂̑Ή��̂܂����������ŁA���̌�33�N���܂ő��������E�I�o�ϑ勰�Q�Ɠ����Ȃ̂ł��B����̎��Ԃ��A�u�勰�Q�Ȍ�̍ő�̊�@�v�ƌĂ�鏊�Ȃł��B����ł́A29�N�ȑO�̏͂ǂ��������̂��B��ꎟ���E����A20�N��̃A�����J�́A���ւ̗A�o�ɂ���Ĕ��W�����d�H�Ƃւ̓����A�A�ҕ��ɂ��啝�ȏ���̊g���A���[�^���[�[�V�����ɂ�鎩���ԍH�Ƃ̖��i�A���[���b�p�̔敾�ɔ����ΊO�����͂̑��ΓI�㏸�Ɠ��n��ւ̗A�o�̑����Ȃǂɂ���ē����̑哝�̃t�[�o�[���u�i���̔ɉh�v�ƌĂo�ϓI�D������ɓ���Ă����̂ł��B
�Ƃ��낪�A�勰�Q���N�O�ɂ́A���ɂ��̗\�����������B�A�����J�̔_�����ł͔_�Ƌ��Q���N�����Ă����̂ł��B�ߏ萶�Y���_�Y���̉��i�����������A�A�����J�����ł͐��Y�̏���͂��ቺ���Ă����B����ł��A20�N��̃A�����J�́A��ʐ��Y�E��ʏ���̎���Łu�i���̔ɉh�v��搉̂����ʖ��O�ɂ́A�_�����̌i�C��ɂ͖��S�������̂ł��B�����āA����20�N��O���ɂ�����]��_�앨�́A���[���b�p�ɗA�o�Ƃ��ĐU����������ߖ��͔������Ȃ������B�������A�_�Ƃ̋@�B���ɂ��ߏ萶�Y�ƃ��[���b�p�̕����A�������ُ�C�ۂ���_�Ƌ��Q�����X�ɐ[���ɂȂ��čs�����̂ł��B��̓I�ɂ́A��ꎟ���E���̍r�p������Ă��Ȃ��e���̍w���͂��ǂ������A�Љ��`���ɂ��\�A�̐��E�s�ꂩ��̗��E�Ȃǂɂ���āA����ɃA�����J�����̑��̐��Y���ߏ�ɂȂ��čs�����B�܂��A�_�ƕs���ɉ����ēS����ΒY�Y�ƕ�����s�U�ɂȂ��Ă����B����ɂ��ւ�炸���@�M�ɐ����A���̐��{���K�ȗ}���[�u�����Ȃ������̂ł��B
�������āA�A�����J�̊����s��́A1924�N�������瓊�@�𒆐S�Ƃ��������̗����ɂ���Ē����㏸�X���ɓ����čs�����B�Ƃ��낪�A20�N��㔼�ɂȂ�ƃ��[���b�p�̌o�ς�������A�܂���i���ɂ�����H�Ɖ��̐i�W�A�\�A�o�ς̕����Ȃǂɂ��A���E�I�Ȑ��Y�ߏ��Ԃ����܂�A�A�����J�ł����������̍D�i�C�������A�����̏�����L�т��A�q�ɂɂ͔���Ȃ����i�����܂�n�߂Ă����̂ł��B�D�i�C�ɂ���Ă��Ԃ������������ׂ̖��b���������@���s��ɗ������A�܂��܂����@�M�����܂�A�_�E���ϊ����͂T�N�ԂłT�{�ɍ������A29�N�X���R���ɂ̓_�E���ϊ���381�h���Ƃ����ō����i���L�^�����̂ł��B�s��͂��̎����璲���ǖʂ��}���A�����P�����Ԃ�17���������A���̂P�T�Ԃʼn������̔������قǎ������������̂́A���̒���ɂ܂��㏸������������Ƃ����ُ�ȓ������������̂ł��B
���̂悤�ȏ��A29�N10��24���ߑO10��25���A�[�l�������[�^�[�Y�̊�����80���������A���̒���̊��t���͕����������̂ł����A�܂��Ȃ����肪�c��݊����s��͔��蒍���������A�O��̂Ȃ��������Ŋ�������\�������̂ł��B11���ɂ́A�S�A�����J�̊��������̓X���甄�蒍���������A��p�j�b�N�ƂȂ����B�E�H�[���X���͕͂s���ȋ�C�ɕ�܂�A�x�������o�����Čx���ɓ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������悤�ł��B�ߌ�R���Ɏ�����I�����A���̓��̊����������́A����𒆐S��1289�����Ƃ����V�L�^�������B���ꂪ�A�S���E�̖w�ǂ̎��{��`���Ƃ����������E���Q�̎n�܂�ł��B���@�Ǝ҂Ŏ��E�����҂́A���̓������ł�11�l�ɋy�ƌ����Ă��܂��B���̓��͖ؗj�����������߁A��Ɂu�Í��̖ؗj���v�gBlack Thursday�h �ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B��25���A�E�H�[���X�̑�芔�����l�Ƌ�s�Ƃ��������c���A�����x�����s�����Ƃō��ӂ��܂����B���̃j���[�X�ł��̓��̑���͕��Â����߂��܂������A���ʂ͈ꎞ�I�������B�T���ɑS�Ă̐V�����\�����X�I�ɕ����Ƃ������āA28���ɂ�921��2800���̏o�����Ń_�E���ς������13��������Ƃ����\�����N����A�����10��29���ɂ�24���ȏ�̑�\�������������̂ł��B�����Ƃ̓p�j�b�N�Ɋׂ�A���̑����߂邽�ߗl�X�Ȓn��E���삩�玑���������グ�n�߂��B���̓��͉Ηj�����������߁A��Ɂu�ߌ��̉Ηj���v�gTragedy Tuesday�h �ƌĂ��悤�ɂȂ����̂ł��B
�������āA29�N�̃E�H�[���X�̖\���͕č��o�ςɑ傫�ȑŌ���^�����B�������A�����͍����ƈ���Ċ����s��̖������������������߂ɔ�Q�̑����̓A�����J�����ɗ��܂��Ă���A�����̕č��o�ς͏z�I�s���ɑς��Ă������т��������B�s�����勰�Q�Ɍq�������̂́A���̌�A��s�|�Y�̘A���ɂ����Z�V�X�e���̒�~�ɁA�A�����J�A�M�������x������̋��Z����̌�肪�d�Ȃ������߂ł����B�t�[�o�[���a�}�A�����J�哝�͎̂��ԂɊy�ϓI�ԓx����葱���A�o�ϓI��b�����S�Ő��Y��������������s���Ă���̂ő��v�ƒf���������ł��B�ނ͌ÓT�I�o�ϊw�̐M��҂ł���A�u�b�V�����l�A�����o�ςɂ����Ď��R���C�������葱���A���̈���ŕی�f�Ր�����������A���E�e���̋��Q�����������čs�����̂ł��B���Ǝ҂�30�N�ɂ�400���l�ɒB���A32�N�ɂ͎���1250���l�𐔂����ƌ����Ă��܂��B32�N�㔼����33�N�t�ɂ����Ă��A���Q�̃s�[�N�������悤�ŁA���Q�������O�Ɣ�ׂĊ�����80���ȏ㉺�����A�H�Ɛ��Y�͕��ςłP/�R�ȏ�ᗎ���A1300���l�Ƃ�����ꂽ���Ǝ҂ݏo���A���Ɨ���25���ɒB�����ƌ����Ă��܂��B�����ꂽ��s�͂P���s�ɋy�сA33�N�Q���ɂ͂Ƃ��Ƃ��S��s���Ɩ����~�A�v�����N����̂ł͂Ȃ����ƌ��O���ꂽ���ł��B
�����������A�o�ꂵ���̂�����}�̃t�����N�����ED�E���[�Y�x���g�哝�̂ł����B�ނ͏]���̎��R���C�o�ς���A�e�Y�Ƃ�J�g�W�܂ō��ƌ��͂̊��������铝���o�ςƁA��O�̍w���͑��i�Ƃɂ���Či�C�̉�}�낤�Ƃ���C�����{��`�Ɋ�Â����j���[�E�f�B�[��������f���ē��I�����̂ł��B����ʂ�Y�Ƃɓ����������A���i�E�Œ�����E�ō��J�����ԂȂǂ����߂��S���Y�ƕ����@�ƁA�_�Y���̐��Y�𐧌����ĉ��i�̈����}�낤�Ƃ����_�ƒ����@�A����Ɍٗp�𑝂₵���Ǝ҂̋~�ς�}�邽�߂̃e�l�V�[�여��J�����Ђ�ݗ����܂����B�����A�j���[�E�f�B�[�������1930�N��㔼�̌i�C��O�ɋK�͂��k�������Ȃǂ������߁A30�N��㔼�ɂ͍Ăъ�@�I�ȏƂȂ����̂ŁA������͂ǂ�قnj��ʂ����������ɂ��Ă͍����ł��^�ۗ��_������悤�ł��B���ǁA�A�����J�̕s���E�o�ƌo�ς̖{�i�I�ȉ́A���̌�̑���E���ɂ�锜��Ȑ푈�����܂ő҂��ƂɂȂ����̂ł��B�܂�A�勰�Q�����ۂɏI����������̂́A�h�q�x�o�Ɛ푈���o�ςɊ��C��^����1941�N�ɓ����Ă���ł����B
|
���R�D�A�[�T�[�E�~���[�Ƒ勰�Q
�������玄�����N�A�����̑ΏۂƂ��Ă����A�����J�̌���ƁA�A�[�T�[�E�~���[�Ƃ��̑勰�Q�Ƃ̊֘A�Ɋւ���b�ł��B���������A��ƂƂ������̂́A�����ƁA���l�A����Ƃ�����ł���A���̑n�슈��������I�ɑ��������炩�̐l����̑̌��������Ă�����̂ł����A�~���[�̏ꍇ�A���̑n�슈���̌��_�ƂȂ����̌��́A�܂���29�N���̑勰�Q�ł���܂����B�ނ�1915�N���܂�ł�����A����14�������B�ނ͌�N�A������U��Ԃ��āu�勰�Q�͎��̖{�ł������v�i�u�_�X�̉e���v�A�w�A�[�T�[�E�~���[�����_�W�x�A177�y�[�W�j�ƌ����Ă��܂��B�����āA���̗l�ɑ����Ă��܂��B�u1929�N�܂ŁA���͎��Ԃ͂��Ȃ茘�łȂ��̂Ǝv���Ă����B�Ƃ��ɁA�����̃A�����J�l�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�N���ӔC�҂�������̂Ǝv���Ă����B���m�ɂ͂킩��Ȃ����A���Ԃ���ƉƂ��낤�B�E�E�E�E�@���ۂɁA1929�N�܂Ō����A�Ȃ���Ă������Ƃ́A���Ƃ��Ƃ��܂₩���ł��邱�Ƃ��킩�����B�ӔC�҂Ȃǂ��Ȃ������̂��B���ɂ��Ďv���A���̓����A�����������͖̂ڂɌ����Ȃ����E�̊��o�ł������B������̂��A���̉B�ꂽ�@���ɂ���Ă��̃N���C�}�b�N�X�𖧂��ɗp�ӂ��Ă��āA�܂��ɂ��̓K�Ȏ��@�ɖ��ς�j�����̂��B���̈Ӗ��ŁA1929�N�͉�X�̃M���V���̔N�ł������B�_�X���x�����Ă����̂��v�i�u�_�X�̉e���v�A176�|77�y�[�W�j�B
���̂悤�ɁA�勰�Q���~���[�Ɍ���I�Ȏv�z��̉e����^�������Ƃ�������܂��B�����A��ꎟ����̐푈�i�C�ɐ�������Ă����l�X�́A���̑勰�Q�ɂ���ėl�X�ȈӖ��ő傫�ȑŌ����邱�ƂɂȂ�B�~���[�ɂƂ��āA���������͉����u�ڂɌ����Ȃ����E�v�ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ǝv�����̂ł��B29�N�̓~���[���o�������u�ڂɌ����Ȃ����E�̊��o�v��u�B�ꂽ�@���v�̔F���Ƃ́A�i���Ǝv��ꂽ20�N��̔ɉh���x�����o�σV�X�e����29�N10��24���̃E�H�[���X�̊�����\���Ɍ�����悤�ɁA���ɂ��ĕ���Ƃ����~���[���g�̔������Ӗ����Ă��܂��B����͒[�I�Ɍ����āA���̌�32�N�܂ł�500�𐔂����s��|�Y�����A1300���Ƃ�������l�X�����Ƃ����A�w��ɂ����Ă���܂ł́A�͂�����Ɩڂɂ͌����Ȃ������V�X�e���̑��݂̔F���ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B���N�����߂������勰�Q�̎���́A����ƂƂ��Ẵ~���[�ɂƂ��āu�B�ꂽ�@���v�����̌��̌��ƂȂ�A�₪�đ�Ȃ菬�Ȃ�ނ̏���i�̔w�i��e�[�}�ƂȂ�܂��B
����ɁA���̎���̏Ɋւ��āA�~���[��1987�N�ɏo�ł������`�œ����̐l�X�̕n���������ǂ������̓�����M���Đ���t�������ޓ��̋C�T�����̗l�Ɍ���Ă��܂��B�u�l���͎v���ʂ�ɍs���Ȃ������m��Ȃ����A�ʔ����h���I���B�l�X�͑ދ����Ă���悤�ɂ͌����Ȃ��B����́A�������ƂȂ��i�������肻�������炾���A��������������ɂ������̓w�͂��K�v�����炾�v�i�w���̂��˂�\����l���\�x�A64�y�[�W�j�B�܂��A�u���Ƃ͎��ɒP���������\�������͊�]���������������B��]�Ƃ���A���������Ă����A���z�ł��悩�����B�����͑ς������������\���Ǝ҂̍P��I��R�A������܂����A�����J���_�A�l�퍷�ʂ̒����A���ׂĂ̋M�d�Ȃ��́\���Ɏ�҂̉\���̘Q��B���[�Y�x���g�͊m���ɓV�g�̑��ɂ����ɂ���A����I�ȕ���̓���摗�肷��̂�����Ƃ������v�i71�y�[�W�j�Əq�ׂĂ��܂��B���̂悤�Ɂu���Ǝ҂̍P��I��R�v�A�u������܂����A�����J���_�v�A�u�l�퍷�ʂ̒����v�A�u��҂̉\���̘Q��v������������������A��]�����킸�Ɏ���H�������Č����ɏ����������̐l�X�̑̌�������Ă���̂ł��B�����̂�����w�G�C�u�E�T�C�����Ƒ����O����x�Ɓw��̌��j���̎v���o�x�́A�܂��ɂ����ŏq�ׂ�ꂽ��s�����ɂ�����ގ��g�̎��̌��ڂɕ`�������̂ł��B�����ɂ́A�~���[�̑勰�Q�̑̌���U��Ԃ�̂ł͂Ȃ��A�����֏�ɗ����߂��ăA�����J�Љ���_�I��@�Ɋׂ������ɁA�����Ŋw�o����l�X�ɒm�炵�߂�ނ̎g���������Ď��܂��B
|
���S�D�勰�Q���������~���[��i
�勰�Q���A�A�����J�l�ɗ^�����Ō��͌v��m��Ȃ����̂�����A�A���t���b�h�E�P�C�W���ɂ��A����́u�l���̊���A����A�l�����x���Ă���ӎ����̂��̂��A�����܂��ɂ��Ă��܂�ɂ���������̂Ɍ��������߂ɁA���ׂĂ̓`���I�ȉ��l���ˑR���₳��A���̑����������ۂ����̂Ɏv��ꂽ���炢�������v�i�w����A�����J���w�j�\����A�����J�U�����w�̈���߁x�A423�y�[�W�j�̂ł��B�~���[�́A������u�������鐢�E�̊��o�v�ƌĂ̂ł���A���̏Ռ��̐��܂���������Ă����̂ł��B������ɂ��Ă��A30�N��ɓ����Ď��{��`�̊�@�Ƃ��Ă̋��Q���A�A�����J�Љ�ɏd�ꂵ���̂��������Ă���ƁA���{��`�@�\���̂��̂̒��ŗ}�����ꂽ�l�Ԃ̖��͊���o�ϓI�j�]���痈���]���A���������I�ɂȂ�B�{���A�ɂ߂Čl�I�A�S���I�ȁu�a�O�v�Ƃ������A�������ĎЉ�\���I�F�ʂ�тт�̂ł��B���̂悤�ȏ��w��̌��j���̎v���o�x�̔w�i�ł���A�܂��ɂ��������ɂ���l�Ԃ̓T�^�I�ȗ���A���ɃK�X�Ƃ����l���Ɍ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�܂��A�~���[�́w��̌��j���̎v���o�x�Ƒ勰�Q�Ƃ̊֘A���Ɋւ��āA���̍�i��30�N����ʂ����[�h���ł���A�u�l�Ԑ��v���Y�ꋎ���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�Ɂu���l�ւ̓���v�Ɓu���ʂ̉^�����������ӎ��v�̕K�v������������̂������Əq�ׂĂ��܂��B�܂��A���̍�i�́u�����́v�gcommunity�h �̑��݂Ƃ�����ێ����邽�߂ɁA�����Ɂu�A�сv�gsolidarity�h ���d�v�ł��邩��\���������̂ł���ƌ����̂ł��B
����ɁA�~���[�͌�N�Ɏ��`�ŁA���������A���̑�ނ�I�̂́A�ނ����̍�i�������������̉₩�i�C�ɗN���ȃA�����J�Ƃ͈قȂ�A�m���Ȍ����ɐG���K�v�����������炾�Əq�ׂĂ��܂��B���̖L������搉̂��铦����`�̎���ɂ����ĒN���������悤�Ƃ��Ȃ����A���Ȃ킿�u�勰�Q�Ɛ����̂��߂̓����v�i�w���̂��˂�\����l���\�x�A353�y�[�W�l�Ɏ��g�Ƃ����킯�ł��B���ہA��s���ƃT�o�C�o���̊W�́A�o�ς̕���͌l�̑����̊��o�Ǝ��M�����킹�A�Љ�̗��z�ƍ��Ƃ̐_�b�͉�̂��A�B��̎��㖽�߂́u�����c�邱�Ɓv�ł������ƌ����܂��B��������s�����T�o�C�o�����邽�߂̏d�v�ȃt�@�N�^�[�����Ȃ�ʘA�шӎ��ł���A���ꂪ��̃~���[��i�ŌJ��Ԃ���������čs�����ƂɂȂ�܂��B
�~���[���w��̌��j���̎v���o�x�ňӐ}�����e�[�}�́A�܂��A�勰�Q�̉��A���������A�A�т�������30�N��̌o�ϕs�����������l�X�̃T�o�C�o���̖��Ƃ����Ɋ_�Ԍ����錻��Љ�̐l�ԑa�O�̖��ł���A����͎�l���o�[�g�̃C�j�V�G�[�V�����̖�肾�����̂ł��B�勰�Q�̃T�o�C�o��������u�A�сv�̖��͐�Ɉ��p�����~���[�̐����ŁA���łɏ\�����炩�ɂȂ����̂ŁA�u�a�O�v�Ƃ̊֘A�����q�ׂĂ݂܂��B�O�q�����~���[�̌����ɂ��A�ނ��Y�Ǝ�`�ƕ��������ɒ��킷��l�X�̐��_�̊�]�ƒ��O���A���̎����ԕ��i�q�ɂƂ����d�����ɂ��āA�`�����͖̂����ł��B�Ƃ���ŁA���̎����Ԃ̕��i�Ƃ����͔̂��ɏے��I�ȈӖ������������Ă���ƌ�����ł��傤�B��́A���i�Ƃ������̂́A���ꎩ�̂����ł͉��̖��ɂ��������A�܂����Ղ��đʖڂɂȂ�ΐV�������̂Ɨe�ՂɌ��������̂ł��B�����ŕ`�����o��l���́A�����������Ƃ̎��ւ��ɂ���ĊȒP�Ɍ����\�ȕ��i�̔@�����݂Ȃ̂ł��B�܂�A������l�ԂƂ��Ă̑��݂�D��ꂽ�A������u�a�O�v���ꂽ�l�B�̓K�Ȕ䞾�ƂȂ��Ă��܂��B
�����܂ł��Ȃ��u�a�O�v�Ɋւ���T�O�́A�}���N�X�����߂Ƃ���F�X�Ȏv�z�Ƃɂ���Ē�`���Ȃ���Ă��܂������A�v����Ɂu�l�Ԃ��̂����̂ɂ���Ă���v�A�u�l�ԕs�݂́v�A�u�l�Ԃ������v�A�u��l�ԓI�ȁv�Ƃ����悤�ȍL���Ӗ��Ƃ��ĉ��߂ł���ł��傤�B���ă��X�p�[�X�́A1930�N��܂ł̎Љ�ɂ����Ė��炩�ɂȂ��Ă����l�X�Ȑl�ԑa�O�̕a�����ۂ͂��Č����܂����B�ނɂ��A�������Ƌ@�B�����厲�Ƃ����Ȋw�Z�p�̔��B�ƏW�c�̋@�\���ɔ����l�Ԃ̑�O���̌��ʁA�l�Ԃ͋@�\�̒��őg�D����A�l�ԂƂ��Ă̓Ǝ����������A�P�ɐ��Ƃ��Ă����Ӗ��������Ȃ����X�}�X���鑶�݁A���邢�͋@�\�Ƃ����@�B�̕��i�ƂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł��B�u�a�O�v���ꂽ�l�Ԃ��@�B�̕��i�ƌ��郄�X�p�[�X�̊T�O�́A���̌��ŕ`�����J���҂̓I�m�Ȕ�g�ł���A���S�̂̒ꗬ�Ƃ��Ĉӎ�����Ă���ƌ����܂��B�ȏ�A�勰�Q�Ƒa�O�̖����֘A�����ďq�ׂĂ��܂������A���Ɂw�㉿�x�ŕ`���ꂽ�勰�Q����Ɍ���ꂽ���l�ς̑Η��ɐG��Ă݂����Ǝv���܂��B
�~���[�́w�㉿�x�ŁA���B�N�^�[�E�E�H���^�[���Z�킻�ꂼ��̐S���⓹���I���l�ς��Љ�̃W�����}�̐^�����őΗ��E��������l��`���A�܂����̂悤�ȉ��o��]��ł��܂��B�勰�Q�������炵�������M�����������Ƒ��W�̒��ŁA�Ƃ���邱�ƂɊւ��Ă��̐ӔC�̏��݂������ă��B�N�^�[�ƃE�H���^�[�ɁA���ꂼ��̉��l�ς�Η�����������������ł��B�~���[�̂��̂悤�ȗ��Z��ɑ��鋤���̕����v�z�̔w��ɂ́A30�N��̑�s���Љ�̒��ŕ\�ʉ������Ƃ���щƑ��ɑ���A�����J�I���l�ς̑Η�������A������~���[�͗��Z��̑Η��̒��ɏے��I�ɕ`�����̂ł��B�����āA�����ɂ͔ނ������̉��l�ςɓ����̉��l�̏d�݂������������Ƃ���Ӑ}�������Č����܂��B
���āA�Z�E�H���^�[�ɑ�\�����Ƃ��Ȃ݂Ȃ����l�ς́A�ɉh��20�N�ォ�瓪���������n�߂������ςƊW������܂��B������u�����̖��v�ł��蕨���I�����ւ̐��q�v�z�ł��B�勰�Q�Ō��݉������u�����̖��v�̖O���Ȃ����]�ł��B�E�H���^�[�͂��̎x���҂ł���A�����A���B�N�^�[�͂��̔��Ύ҂ł��B�������ė��҂́A�Ƒ��̉��l�ςƐ����̎v�z�������đΗ����܂��B���e�̔j�Y�ŁA���ꂱ���̂Ă�ꂽ�H�ו����������ĐH���Ȃ����Ƃ����Ƒ��̐M���W���A���B�N�^�[�̎��Ȑ������̎x���ɂȂ��Ă���̂ł��B�E�H���^�[�͂�������z���ƌ��ߕt���A�ނ�̉ƒ�ɂ͌��X����Ȃ��̂͑��݂��Ȃ������ƍ��ꂵ�܂��B�q���B�����ɏo�Đ������邱�Ƃ��A���e���]��ł������l�ςł���A�����͂���ɏ]�����������A�ƃE�H���^�[�͌����̂ł��B�������Č���ƁA���e�̈ꌩ���������������A���Z��̐l���ɈقȂ����I����^�����ƌ����邩���m��܂���B
���B�N�^�[�́A���e�������ɖ]�̂́A�A���n�������J��̃A�����J�l���z�����ϗ��I�����A���Ȃ킿���ӂ̖������������̒��œy�n�ƉƂ���蔲�����Ƃ������c�_���I�ȉƑ��ӎ��̓`���ł������Ǝv���̂ł��B�����A�E�H���^�[�́A�Ƃ��̂Đe�����ے肵�Ȃ���A�ނ��땃�e����͑��h���ꂽ�B����́A�����҂������ɑ���邩��@���ɕ\���Ă��܂��B�ނ̐����̉��l���傫���̂́A�s���ƌ����n���f�B�����̏o���_�Ƃ�������ł��B19���I�㔼�̓s�s���ƎY�Ɖ��̒��ŏ������ꂽ�����ς́A�E�H���^�[�̐������̒��ŁA�O�҂Ƃ͋t�Ɏ��c�_���I�ȉƑ��ӎ�����l��`�̔����ݏo���܂����B�`���I�ȉƂ̊ϔO����������20���I�����̒��ŁA�Ƃ���30�N��͓����̎�҂ɉƂɑ��ē�ґ���𔗂������Ƃł��傤�B�������āA���B�N�^�[�͌Â��`���I�ȏ]���̉ƈӎ��ɌŎ������̂ɑ��āA�E�H���^�[�͐V�������j�̗���ɏ悶�Đ��������̂ł��B�������Č���ƁA��l�̑Η����ɂ߂ďے��I�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B���B�N�^�[�͉ߋ��̐��E�̉��l�ςɐϋɓI�ɃR�~�b�g���A���̋��ƂƖłт�^���ɂ���l�ԑ����ے����A�E�H���^�[�͐V�������㊴�o�ł�����Čl��`�I�ȉ��l�ςɐϋɓI�ɃR�~�b�g�����l�ԑ����ے�����̂ł��B����͂��傤�ǁA�e�l�V�[�E�E�C���A���Y���w�~�]�Ƃ������̓d�ԁx�ŁA�V���암�̉��l�ς��X�^�����[�ƃu�����`�ɏے��������̂��v���N�������܂��B
�|���čl���Ă݂܂��ƁA���Z��̒S�������l�ς́A�A�����J�Љ���ݏo������̖��������嗬�̐��������\���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�����āA����炪���݂��r���������Ɠ����ɁA�䂩�ꂠ���Ă�����̂ł��B�悤�₭���ɂȂ��āA�x�@���Ƃ��ăR�~���j�e�B�[�ɕ�d���郔�B�N�^�[�̐������ɉ��l�����o���A���l�Ƃ̘A�т̒��ɐ������т����o�����̂́A���Ȃ�ʃE�H���^�[�ł��B�����A���B�N�^�[���A�E�H���^�[�̍����I�Ȍ����F���A���Ȏ����d����l��������ς������Ă������̂ɁA���N�̜x����������̐����ɊÂ���Ȃ������B�E�H���^�[�̎���̐�[���s���v�z�ɂ́A���B�N�^�[�����Ȃ��炸�A�A�]�̔O����������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��ł��傤�B�����������҂̍l�����͑��Η�������̂́A���҂Ƃ��Љ��������ɂ͌������Ȃ����̂ł����āA�������ă��B�N�^�[�ƃE�H���^�[�̑Η����ے��I�ł��鏊�Ȃł��B���B�N�^�[���̌����鈤�glove�h �Ɠ��`�gloyalty�h �Ɋ�Â��Ƒ��̘A�т̌����ƃE�H���^�[����\���鐬���̌����́A�������đ���������̂ł͂���܂����A���̑Η��͈�ʎЉ�̌���������ł���A�܂��Љ�@�\�����ŁA�K�v�s���ȗv�f�ł�����܂��B�����āA���Z��̑Η��̍���������`�҂Ǝ��ȒB���҂̊ϔO��̈Ⴂ�ɂ���ƌ��邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�Ƃ���ŁA�~���[�͂��̓`�L�̒��ŁA60�N��̐푈�Ԑ��i�x�g�i���푈�j�A���l�̖ڊo�߁i�������^���j�A����̑a�O���̒��ɂ����āA�ނ͗���ׂ����ł̎�������Əq�ׂĂ��܂��B�����āA����50�ɂ��Ĕނ́A�ߋ��̐��Ȃ�킢�̎c�����Ւf���悤�Ƃ����̂�����ǂ��s�\���ƌ��A���̖��͊���U�蕥�����߂̂���Έ��������Ƃ��āw�㉿�x���������Ǝ��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B�u�w�㉿�x�͂���_�ł́A���̌J��Ԃ��̖��C�͊���U�蕥�����悯�Ƃ�������B��l�̌Z��\�ЂƂ�͏����A�����ЂƂ�͐��������O�Ȉ�\���A���N�̌��ܕʂ�̂��ƍĉ��B���e�����ɁA���Y���������邱�ƂɂȂ�������ł���v�i�w���̂��˂�\����l���\�x�A542�y�[�W�j�B���̒���m�萬�l�������Z��ɂ́u�ߋ��̗���v�𐅂ɗ����ĐV�����W��ł����Ă邱�Ƃ��\�Ɏv��ꂽ�̂�����ǂ��A�ߋ��̎v���o�̕i�X�i�ÉƋ�j���A�������ĈȑO�̓{���s����~�����Ă邱�ƂƂȂ�A�Ăь��ܕʂ�ɏI���̂ł��B�������A���E�͗��҂���\��������A���Ȃ킿���B�N�^�[�ɑ�\�����u�����̒����Ȏ���v�ƃE�H���^�[�ɑ�\�����u��S�I�ŗ��ȓI�����V�������Ö@�̔����ҁv�����K�v�Ƃ��Ă���̂��A�Ƃ����̂��~���[�̌Z�튋���̐����ł��i�O�f���A542�y�[�W�j�B�����F���ł����A���ς�炸�J��Ԃ���邱�̊����́A�O�q���������̃A�����J�Љ�Ɍ���ꂽ�V���̈قȂ��̉��l�ς̑Η���ʂ̊p�x��������������̂Ɖ��߂ł��܂��B
�Ō�́w�A�����J�̎��v�x�̃e�[�}�́A�O�ɂ��q�ׂ܂����悤�ɑ勰�Q���̂��̂ł���A�Ɍ��ɂ���l�Ԃ��A������ǂ̂悤�ɏ����ăT�o�C�o�����čs���������̊j�S�ł��B���̃e�[�}�́A�ΏƓI�ɕ`�����o��l����ʂ��āA�u�A�����J�̖��v�̕���Ƃ�������������i�Ƃ��Ắu�A�����J�I�����`���_�v�̊m�F�ɂ�関���ւ̊�]�Ƃ����`�Ŕ��W���܂��B��̓I�ɂ́A���@�ɂ��������E�l�B�̖��H�ƔE�ϋ����������������[�̕�e���[�Y�ɕ`����Ă��܂��B���E�l�̒��ɂ́A���ƂɎ��s���Đ��_�I�ɗ�������Ŏ��E������̂��o�܂����A����ɑ��āA������������̕ω��ɂ���ǂ��������A�������ׂ������ł͂Ȃ����`�I�Ȑ��������u������N�E�B����o�[�g�\���̂悤�ȍ��E�l�����s���ĕ`����Ă��܂��B�@�B�I�Ŕ�l�ԓI�Ȏ��ƊE�E���E�ɍR���āA�l�Ƃ��Ă̐l�Ԑ���i�삵�����ރN�E�B����o�[�g�\���̎p�Ɂu�l�̉��l�v�u�@�l�^���Ɓv�̐}�������Ď�邱�Ƃ��ł���ł��傤�B���̃~���[�����ӂ̗ϗ��E�����Ɛ��`�Ɋւ��鍡�ЂƂ̗ǂ���́A�_�v�e�C���[�ł��B�ނ͋����̏�ʂŒ��Ԃ̏�������Ď����̔_������߂��܂����A�����킹�������ɓD�_�Ă�肳����߂����ƍ߈����������܂��B�������A�@�������ɂƂ��Đ��`��U�肩�������Ƃ��锻����o�ꂳ���Ȃ�����e�C���[�����̑ɂɒu���āA�l�Ƃ��Ă̖{���̐��`�͂ǂ��ɂ���̂��낤���Ɗϋq�ɖ₤�~���[�̎p�������ɂ͓����Č����܂��B���̍�i�́A�w��̌��j���̎v���o�x�̃o�[�g���l�A���[�̃C�j�V�G�[�V�������`����A��҂ɑ勰�Q���^�����C���p�N�g����������Ă���̂ł��B
|
���T�D�勰�Q�̃e�[�}��������i�Ƃ���炪�����ꂽ����w�i
�w��̌��j���̎v���o�x���Ⴉ�肵�~���[�̑勰�Q����̎���̑̌���D�荞�݁A���̎���̐l�X�����������T�o�C�o�����邽�߂ɂ́A�����ɘA�шӎ��A���҂Ƃ̋��ʊ��o��l�ԓI�Ȍq���肪�d�v�ł��邩������������i�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂������A�������ɖ��o�łŏ�����́w�G�C�u�E�T�C�����Ƒ����O����x�Ŏ�舵�������̑勰�Q�Ƃ����e�[�}�́A�~���[�ɂƂ��ĕ����ʂ�v���Ƒn��̌��_�ƂȂ�A�Ȍ�A�ނ͂��̃e�[�}�ځE�ԐڂɎ��グ�čs�����ƂɂȂ�܂����B�����ŁA�勰�Q���������O�̍�i�Ƃ��ꂪ�����ꂽ�N����l�@���A�~���[���Ȃ��勰�Q����������i�������˂Ȃ�Ȃ������̂��A���̕K�R�������Ă����܂��B55�N�́w��̌��j���̎v���o�x�ɑ�����68�N�́w�㉿�x��80�N�́w�A�����J�̎��v�x�ɂ��A���ځA�勰�Q�����C���E�e�[�}�Ƃ��Ď��グ���Ă��܂��B���̈Ӗ��ŁA�w��̌��j���̎v���o�x�́A�勰�Q���e�[�}�Ƃ����v��i�̐�삯�ƂȂ����킯�ł����A�勰�Q�������������̍�i�������ꂽ�N�A55�N�A68�N�A80�N�ɒ��ڂ���ƁA�����ɂ����̋��ʍ��������ė��܂��B���Ȃ킿�A�X�̍�i�ɂ���炪�����ꂽ����̐������f����Ă���Ƃ������Ƃł��B���ꂼ��̎���̓A�����J�����̓����ɖ�������Ă��������ł���A�~���[�͍�i��ʂ��Ă������������A�x��������Ȃ������B���̂��тɁA�ނ͂��݂��̊Ԃɒʂ������M���̕K�v���Ƃ��̉��肢�Ȃ���A�A�����J�ɑ傫�ȋ��P��^���Ă��ꂽ�勰�Q�ւƖ߂��čs�����ƌ�����̂ł��B
��̓I�Ɍ����܂��ƁA55�N�́A��Q������̌o�ϔɉh�̐Ⓒ���ŁA���̂��߂������Đl�X�̐S�̓����������ɂ����Ȃ��Ă��܂����A�C�[���n���[�哝�̂̎���ł��B����͊������オ��A�h�������E�ŗB��܂��Ƃ��Ȓʉ݂ƂȂ�������ł���A���ׂ��ɑ���A�����J�ւ̒ɍ��̎v�����A�~���[�Ɂw��̌��j���̎v���o�x�����������̂ł��B�����ɂ͐l�Ԃ̘A�ѐ�����������Ă���A�ނ͂��̂��Ƃ��u���̂悤�Ȍ��́A�������������ƂȂ̂ł����A�����ɂ͕\�����Ă͂��Ȃ����̂̐l�Ԃ̘A�ѐ�����������Ă��āA����͗y���߂����肵����̎v���o���Ƃ��Ă��A���ׂ��ȊO�ɂ��厖�Ȃ��Ƃ��������Ǝ咣�����̕��@�Ȃ̂ł��v�i�w���̂��˂脟����l�����x�A35�y�[�W�j�Əq�����Ă��܂��B�܂��A55�N�̓~���[�ɂƂ��Čl�I�ɂ炢�����ł�����܂����B�ŏ��̍ȂƂ̗�������͕ʂɂ��Ă��A�}�b�J�[�V�Y���̐���������Ĕ�Ċ����ψ���̒����ɌĂ�A�R�~���j�X�g�̏W��ɓ��Ȃ������Ԃ̖��O�𖾂����̂����ۂ��č���J�߂ɖ���܂����B���������o������Ɍl�ƎЉ�̊W���⎩��̗ǐS����ɎЉ�����ߒ������Ƃ���ӎ����A�~���[�̐S�ɉ萶���A���ꂪ�w��̌��j���̎v���o�x�ɑ�Ȃ菬�Ȃ蔽�f���ꂽ�̂͊m���������Ǝv���܂��B
���Ɂw�㉿�x�������ꂽ68�N�́A�x�g�i���푈�����I���Ƃ��m�ꂸ�A�펀�҂̐������X�����ɂ�āA��ʂ̐l�X�̊Ԃɉ}��ӎ������g�����W�����\���哝�̐��������̎����ł����B�~���[�͂��̍�i���M�̈Ӑ}���A�����A�D���������x�g�i���푈�Ƒ勰�Q�̗ގ��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ���A���̍������łɉߋ��ɂ����āA�ߋ��͌J��Ԃ����Ƃ��������A���̌����ɓ��݂���ߋ��̑��݂ɖڂ��Ԃ�l�Ԃ̋����A�������Г�̍��{�����������Əq�ׂĂ��܂��B�勰�Q�ŃA�����J�l���w�͂��̈��ʗ���w�i�ɁA�~���[�͂��̌��Ƀx�g�i���푈�̋�������勰�Q�������Ŕj�Y�������e�̏���������E�H���^�[�ƃ��B�N�^�[�Z��̖��Ӗ��Ȋm���ɏے��������̂ł��B�܂��A�푈�������č���������l�����āA�ނ͑�s������̐l�X�����������������̐��_�̑������Ƃ��ɁA���B�N�^�[��ʂ��đi�����������ɈႢ�Ȃ��̂ł��B
�Ō�Ɂw�A�����J�̎��v�x�ł����A���̍�i�����\���ꂽ80�N�́A�J�[�^�[�哝�̂̔C���R�N�ڂł������B�x�g�i���푈��E�H�^�[�Q�C�g�������o���l�X�͐����Ɍ��ł��A77�N�ɐ��{�ƍ����̑a�O�W���C�����ׂ������̍��ɒ������J�[�^�[�哝�̂ɖ����̕ω������߂��̂ł����B�����A�X�^�O�t���[�V�����ɂ��o�ς͈������A���Ɨ����㏸�A�G�l���M�[��@�ɂ��������A�ނ̐l���O�������ڂɏo�āu�ア�A�����J�v�A�u�Â��A�����J�v�Ƃ����l�K�e�B�u�ȕ]����蒅�����܂����B�������������ɂ����ă~���[���勰�Q���ނƂ����Ӑ}�́A�v����ɁA���ӊ�����������Ȃ��������Ɏ��Ȓ��S�I�ȃ~�[�C�Y�������s��������70�N��̐l�X�Ɂu�l�Ԃ̓���T�O�v��u�l�I�ȐS���ʂƎЉ����Ƃ̌��ѕt���v�Ɓu�Љ�̕���Ƃ����q�ϓI�����v��i���邽�߂ł������B���ꂱ�����A���̍�i�����������R�Ȃ̂ł��B
�����A�ǎ��̂���A�����J�l�̊Ԃɂ́A���R�Ȃ��玩�����g�Ƃ��݂������`���Ă���R�~���j�e�B�[�ւ̔F�������܂��������ł�����܂��B�~���[�̓r�b�O�Y�r�[�Ƃ̃C���^�r���[�ŁA�勰�Q����ɂ͕\�ʂ����ꋎ���Ă����̉��ɂ͂�������Ƃ����u�l�ԊW�̍��i�v�i�w����A�����J�h���}�@1945-1990�x�A116�y�[�W�j���������̂ł���A���ꂱ���������`�������������ƂȂ̂��ƌ���Ă��܂��B���̎���̃~���[�ɂƂ��ď����ׂ����́A�܂����Ă���s����������������҂Ƃ̋��ʂ̉^������������{�I�ȃA�����J���_�̗̏g�ł������̂ł��B�������w�A�����J�̎��v�x�ɂ́A�s��o�ς����l�ԘA�т̎Љ������l�X�̐������f����Ă���̂ł��B
|
���U�D�勰�Q�Ɓu�A�����J�̖��v�̕���
�����ŁA�勰�Q�Ɓu�A�����J�̖��v�̊֘A���Ɋւ��āA���̃e�[�}���ŏ��Ɉ������w�K�^��Ƃ��߂ɂ����j�x�ɂ��ďq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B�O�q�����悤�ɁA1929�N10��24���̃j���[�E���[�N������\���́A����Ȍ�30�N��n�߂܂ł̃A�����J�Љ�ɏ��Ȃ���ʕω��ƍ����������炷�勰�Q�̈������ƂȂ�܂����B�勰�Q�͊����̉��l�̌n�̕���������炵�����̐l�X�̉��l�ςɑ傫�ȉe�����y�ڂ��܂������A�����A�`���I�ȃA�����J�̃G�g�X�ł���u�A�����J�̖��v�Ɋ�Â��ނ�̐�������ԓx������������������^���邱�Ƃɂ��Ȃ����B���̓����܂őS�A�����J�l�𑩂˂Ă����ƍl�����Ă����u�A�����J�̖��v�̗ϗ��I�E�����I�ȑ��ʂ̍čl�ł��B�Ƃ���ŁA�u�A�����J�̖��v�ɂ́A��̎�ނ�����܂��B��ڂ͍��ƂƂ��Ă̖��A���邢�͎Љ�I�̈�ɂ����閲�ł���A�A�����J�l�S�̂̍����I�ȗ��z�Ɋւ����̂ł��B��ڂ͌l�I�ȗ̈�ɂ����閲�ł���A�A�����J�l�X�̗~���Ɋւ����������o�ϓI�����̖��ł��B
�l������̍K�������߂錠��������搂����u�Ɨ��錾�v�̗��O�́A��ʃA�����J�l�́u�����̖��v�ɖ��m�ȋ���ǂ����^���A���̖��ɔ��Ԃ������܂����B��k�푈������҂�������o�ċ}���ɐi�H�Ɖ��Ɠs�s���̒��ŁA�������\�A���K���q�̕���������������x�����`�⓹���������̂�������̌�A��ꎟ���̐푈�i�C���o��1920�N��ɓ���ƕx�����߂�l�X�́u�����̖��v�́A�ۉ��Ȃ��ɖc���������܂����B�������A29�N�̑勰�Q�͂��̔ɉh�ɗ␅�𗁂т��A����܂ł̊y�ϓI�ȁu�A�����J�̖��v�́A�������ĕϖe��]�V�Ȃ����ꂽ�̂ł��B�勰�Q�͌��ǁA���ʂ̓y��̏�ɔ|��ꂽ�d�v�ȕ����I�E�E�ƓI�ȃA�����J�I���K�A���Ȃ킿�u�A�����J�̖��v�ɋɂ߂đ傫�ȉe�����y�ڂ����̂ł���A���Ȃ��炸�����̍�ƒB�����̉e�����A���̑�s���Ɋւ����i���c���Ă��܂��B���_�A�~���[�����̗�O�ł͂���܂���B
�����A�~���[�̍ŏ��̃u���[�h�E�F�C�i�o��i�w�K�^��Ƃ��߂ɂ����j�x�́A���̎����w�i�Ƃ����u�����̖��v�̃e�[�}�����������̂ł����B�����āA�ނ̂��̌�̍�i�̊�����A�A�����J�́u�����̖��v�ɂƂ��Ē���I�ł�������@�I�ł��������̎���̗l�X�Ȗ������グ�Ă��܂��B�w�K�^��Ƃ��߂ɂ����j�x�́A�܂��ɑ勰�Q�Ɓu�A�����J�̖��v�̕��G�ȊW�����A���X�e�B�b�N�ɁA10�N�ɂ��y�ԑ�s���ɂ���Ă����炳�ꂽ�����̃A�����J�Љ�̖��͊����悭���f������i�Ȃ̂ł��B���Ȃ킿�A���̍�i�́A��ꎟ����̎Y�Ǝ�`�E���{��`�����_���ɂ߂����̂̑勰�Q�ɂ���ď���ς��A����܂ł̐��_�����d���`���I�ȁu�A�����J�̖��v�������I�E�����I�ȉ��l�ς��d�����邱�Ƃŕϖe��]�V�Ȃ����ꂽ�u�����̖��v�Ƃ����ɂ߂ă��A���X�e�B�b�N�ȃe�[�}�����������ƌ�����̂ł��B
|
���V�D�A�����J�Љ�ւ̃~���[�̌x���ƌx��
���āA�Ō�ɁA����܂ł��b���Ă����勰�Q�Ɓu�A�����J�̖��v�Ƃ����~���[�̓��e�[�}�̔w�i�ƃe�[�}���݊Ԃ̊֘A�����܂Ƃ߁A�����Ɍ�����ނ̃A�����J�Љ�ɑ���x���ƌx����ǂݎ���Ă݂����Ǝv���܂��B�~���[��1915�N�Ƀj���[�E���[�N�̃��_���l���Z�n��̃n�[�����Ő��܂�A�b�܂ꂽ�ƒ�Ɉ炿�܂������A14�̎��Ƀj���[�E���[�N�̊�����\�������[�ƂȂ��Đ��E�I�ɍL�������o�ϑ勰�Q�̐���������āA���e�̈ߕ��H�ꂪ�|�Y���܂����B���̑̌������̌�̃~���[�̐l���ςɐr��ȉe����^���A�ނ̎v���Ƒn�슈���̌��_�ɂȂ����̂ł��B���ɏq�ׂ܂������A���̈�Ƃ̋�X�����̌��́A�ނ��~�V�K����w�݊w���Ƀz�b�v�E�b�h���܉����i�Ƃ��ď������w���l�ł͂Ȃ��x���n�߁A���̌�A����������āw�ނ���܂������オ��x�Ɓw���Ȃ���x�ƂȂ����A������w�G�C�u�E�T�C�����Ƒ����O����x�ɕ`�����܂�A�w��̌��j���̎v���o�x�Ɓw�A�����J�̎��v�x�Ƃ������`�I�ȍ�i�Ɍp�����ꂽ�̂ł��B�ԐړI�ɂ́A�w�K�^��Ƃ��߂ɂ����j�x�A�w�݂�ȉ䂪�q�x�A�w�Z�[���X�}���̎��x�A�w�]���̌�Ɂx�A�w�㉿�x�Ȃǂ̍�i�̔w�i�ƂȂ�A�������đ勰�Q�̑̌��́A���ځE�Ԑڂ̈Ⴂ�͂�����̂́A�ނ̎�v��i�̈��e�[�}�ƂȂ��Ĕ��W�����̂ł��B
�A�����J�́A��k�푈��A�t�����e�B�A�̏��ł��o�Đ��Q�^�����I������19���I������20���I�����ɂ����āA����ȎY�Ǝ�`�̑䓪�����܂����B���ꂪ�`���I�ȁu�A�����J�̖��v�ɕω����y�ڂ��A�勰�Q�ォ�珙�X�ɗϗ������������r�W�l�X��̐������ō��̉��l�Ƃ���u�����̖��v���o�����܂����B�������C�ɉ����������̂��A�勰�Q�ł��B����������u�ɂ��Đl���̂ǂ��ɓ˂����Ƃ��ꂽ�����̗l�q�����ۂɌ����t����ꂽ�Ⴉ�肵�~���[�́A�]���́u�A�����J�̖��v�̕����m��A�ڂɌ����Ȃ��͂ɑ�����l�Ԃ̕s�𗝂�F�������̂ł��B���������Ől�X���ە������̂��A�܂��Ƀr�W�l�X�ł́u�����̖��v�ł���A���̃e�[�}����������i���A������u�����̖��O����v�Ƃ��̂�����w�K�^��Ƃ��߂ɂ����j�x�A�w�݂�ȉ䂪�q�x�Ɓw�Z�[���X�}���̎��x�������̂ł��B
�Ƃ��Ɂw�K�^��Ƃ��߂ɂ����j�x�́A�u�_�X�̉e���v�ŏq�ׂ����̃~���[�̑勰�Q����z���錾�t�𗠏���������̂ł��B�u�����������ɂ���āA���͑������疳�ӎ��Ȃ���A�S�ߒ����̂��̂ɂ������苻���������悤�ɂȂ����B�����͂ǂ̂悤�ɊW�������Ă��邩�A�l�̐����̌��͂܂��̐��E�ɂ���Ăǂ̂悤�ɕς����邩�B�����Ɠ����肾���A�l�̕����A���E���ǂ̂悤�ɕς��邱�Ƃ��ł���̂��Ƃ��������Ƃł���B����͊w��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B�ŏ��͕��w�I�E�����I�Ȗ��ł��Ȃ������B�l������ݑ����邽�߂ɂ͉���M����ׂ����Ƃ������ۂ̖��ł������B���Ƃ��A�l�͐������^���ׂ��ł���̂��\���������A�������Ă���l�X�������̂�����B���邢�́A�l�͏�ɐ��������z�ɉ߂��Ȃ��ƊŔj���ׂ��ł���̂��B�E�E�E�@�����͕s�����Ȃ��̂ł͂Ȃ������̂��\�ߏ��̂ق��̐l�X�݂�Ȃ��A�r���C�b�N�����Ԃ������Ă��Ȃ����肩�A���т����Ȃ��ł������ɂ́B����M���ׂ����v�i�u�_�X�̉e���v�A178�y�[�W�j�B
���Ɍ������悤�ɁA�~���[�́u�勰�Q�͎��̖{�ł������v�Əq�ׂĂ��܂��B�勰�Q�́A�܂��Ƀ~���[�̎v���̌��̌��ł���A�A�����J�́u�����̖��v�̕���A�T�o�C�o���A�A�тȂǁA��A�̃~���[�I�e�[�}�́A���̎v���Ɋ�Â��Ă���̂ł��B�ނ̈�匆��w�Z�[���X�}���̎��x�́A���}�Ȑl�Ԃ̖��ƍ��܂�`���A�u�A�����J�̖��v���u�A�����J�̔ߌ��v�ɓ]���镨��ŁA�����ɂ̓~���[�̃A�����J�Љ�ւ̋ꂢ�ᔻ���_�����邱�Ƃ��ł��܂��B�~���[�́u�A�����J�̖��v�Ɓu�����̖��v�ɑ���x�����l���邱�Ƃ́A�����A�d�v�ȈӖ������Ǝv���܂��B
|
��������
�{���̍u�`���I���ɓ������āA����x�A1929�N�̑勰�Q�ƍ����̋��Z��@�Ƃ̊֘A����U��Ԃ��Č��܂��傤�B29�N10���̊�����\���̌�A�P���ȏ�̋�s���|�Y���A�J���҂�25�������Ƃ����o�ϑ�s���Ƃ�����@�I��Ԃɂ����āA�t�����N�����E�c�E���[�Y�x���g�哝�̂́A����33�N�̏A�C�����ŕϊv�����̗l�ɑi���܂����B�u�܂����̐M�O���q�ׂ܂��傤�B��X���������̂͗B��A���ꂻ�̂��̂ł��B�����Ȃ����s�s�Ŗ����������|�ł��B�ދp����O�i�ւ̐芷�����A���̋��|�̂��ߐi�܂Ȃ��̂ł��B��X�����ʂ��Ă��鍢��́A�����I�Ȃ��̂���ł��B�����ʂĂ��Y�Ƃ̖S�[�����������ɓ]����A�_�Ƃ͍앨�����ꂸ�A����Ƃ������т����~�������܂����B���Ǝ҂̑�Q�������邷�ׂ����߂Ă��܂悢�A�d��������҂������͏��Ȃ��d���͂����B���̈Â�������ے肷��҂́A���߂ł����y�V�Ƃł��B�ӂƂǂ��ȋ��݂������̍s���ɐ��_�̐R��������A�l�̗ǐS�ɔw���҂��Ɣ��ꂽ�B�������̕����̐_�a������݂������͓����������B�������×��̐^���Ɋ�Â��A�_�a�����Ē������B�䂪���͍s����K�v�Ƃ��Ă���B�������s���̂Ƃ��ł��B��s�Ƃ�M�p�ݕt�Ɍ������Ď����K�v���B���l�̋����g�������@�ɂ͏I�~����łׂ��ł��B�ʉ݂��ߕs���Ȃ����S�ɋ�������V�X�e�����K�v�ł��B���ꂪ����̍U���ڕW�ł��B�ڍׂȍ����������ɐR�c����悤�V�c��ɗv�����܂��B���}�Ȏx�������ׂĂ̏B�ɗv�����܂��v�ƁB
���̂悤��75�N�O�A���[�Y�x���g�͎��{��`�V�X�e�������댯����i���A�����̍����ɍ��{�I�ȉ��v�����߈��|�I�Ȏx���܂����B���ꂪ�哝�̏A�C��100���ԂŎ��X�ƐV���������ł��o���đ���v�����s�ł������R���Ǝv���܂��B���̉����͋��K�~�ɖڂ�����ݕ�����`�ɂ܂݂�Ĕj�]�������{��`�V�X�e���x����炵�����h�ȓ����_�ł��B�~���[�����オ�����������������тɐl�X�ɂ��̑勰�Q�̋��P���v���o�����A�������̂��߂Ɍx����炵���̂ł���A���炩�Ƀ��[�Y�x���g�Ƃ̋��ʐ������o�����Ƃ��ł��܂��B�~���[��2005�N�Q���ɐɂ��������̐�������܂������A�������Ă���Ăё勰�Q����������i��J�l�܂݂�̘c�u�A�����J�̖��v��簐i����l�X��ᔻ������i�������āA���]�L�̊�@����w�Ԏp�����w�������A���̓��`�I�ӔC��V�����ϓ_����Njy���������m��܂���B
�J��Ԃ��܂����A�~���[�̋����́A�A�����J���ϗ��I�E���`�I�Ɋ�@�Ɋׂ邽�тɁA�勰�Q�ŘI�悵���A�����J�^���{��`�̉߂��Ƃ��̌��ʂƂ��Đ������A�܂��Ɉ����Ɖ������u�A�����J�̖��v�̕���Ƃ������̈�Y�Ɠ����ɍ��̖�����M���Ă��̊�@���������l�X�̔E�ϗ͂��v���N�����K�v��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B�����̎�����T�o�C�o�������勰�Q���̃A�����J�̐l�X�̎v����s�����������g�̖��Ɉ����āA���邪�܂܂ɒH���Ă݂邱�Ƃ̕K�v���ƁA�����Ƃ͕ʂ̎�ނ̔Y�݂���������̎��ǂ��̃A�����J�Љ�ɁA������x���̎���̂��ƁA���Ȃ킿�����̎���Ɍ����ɐ������A�����J�̋O�Ղł���勰�Q����̑����̐l�X�̖���߂����]��g�������v���o���Ă��炢�����ƃ~���[�͂Ђ����������ƌ�����̂ł��B
����̋��Z��@�ɘb��߂��܂��ƁA������������邽�߂ɂ͉�X�͑勰�Q���瑽�����w�ׂ�̂ł���A�w�Ԃׂ��Ȃ̂ł��B����A�����J�́A�����Ă��̑��̍��X�����̗ϗ�������Ă���̂ł��B����ɁA���݂̊�@�I�͋��Z�ʂ݂̂Ȃ炸�A���A�H���A�G�l���M�[�A���A�����Ƃ������삩����x����˂������Ă��܂��B���{��`�o�ς����j�I�]���_�ɂ��鍡�A���E�͂��̕s������E�o������ȎЉ�ɕ��A�ł���̂��A���j�Ɏc�閼�������������[�Y�x���g�哝�̂Ɠ����u�`�F���W�v�Ƃ����ϊv���f���ē��I�������V�ȃC���[�W�����I�o�}�����哝�̂�������P�T�Ԍ�A�A�C�����łǂ�ȑ��搂��グ��̂��A�傢�ɒ��ڂ������Ƃ���ł���܂��B�@ |
 �@ �@
����2���勰�Q�Ɓu�O���[���X�p�����v�̓W�J |
   �@
�@
|
2007 �N�A����܂ŏZ��o�u���̊g�傪�w�E����Ă����A�����J�ŁA�T�u�v���C���E���[����@���N�������B�����2008 �N9 ���Ƀ��[�}���E�u���U�[�Y�ɑ��������b�|�[���\���̔�~�ό���ɔ��W����ƁA�S���E�ɏՌ���^�����B��A�̌��ۂ́A�勰�Q�ȗ��̃_���[�W���A�A�����J�����łȂ����E�ɂ��^������B���܂̒i�K�ł͂��̑S�e�����łɕ���ꂽ����Ƃ��ď��q���邱�Ƃ͕s�\�ł���B�勰�Q�̍ł��[���ȗ]�g�͕s���ł͂Ȃ���2 �����E���ł������B1929 �N�̃N���b�V���̒���ɒn���ƌ��������̂��A�̂��ɗ����ɂ����Ȃ��������Ƃ����������B���̐����Q�l�ɂ���ƁA�����炭���܂��炠�Ƃɋꂵ�݂��҂��Ă���ƌ���̂����R�ł��낤�B
���Q�͉��炩�̎s��ɂ����錀�I�ȈÓ]�����A���̂��Ƃ�������߂��镪�͂����Â���D������B����ǂ��A�o�ϊw�̐��ƂƂ������̂͂������Ȃ�ꍇ�ł���т������_�I�������疵���Ȃ��o����������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������O��𗧂Ă���ŁA�{�e�ł͎��̂悤�Ȏ菇�ŋc�_��i�߂�B��T�߂ł́A�����o�ϊ�@�̐^���������A���ۗv������_������B��U�߂ł́A��@��̃O���[���X�p���ٖ̕��A9/11��̕��j�]���Ƃ��̋A���ɑ��鏀���A�ނ̋���������������{��������B��V�߂ł́A�u�B��I�[�X�g���A�w�h�v�ł���O���[���X�p���̎d���ɑ���I�[�X�g���A�w�h�̃R�����g�A�O���[���X�p���ٖ̕��ɑ���嗬�h�̌������T�ς��A�u���v�iconundrum�j���������f��p�ł��邱�Ƃ�_����B��W�߂ł́A�ȑO�莮�����Ă������u�O���[���X�p�����v���A���̌�̎��Ԃ̐��ڂ܂��Ă��������₷��B
|
|
���T ��2 ���勰�Q�Ƃ��̌��� |
���T. 1 ���Q�̐^��
�T�u�v���C���E���[����@�ɂ��ẮA�����̔������ォ�瑽���̕��͂��s���A���ł�5 �N�ȏソ�������݂ł͈�i��������������B�������A�����̕��͂́A���������Ƃ����_�ł͏\���Ȃ��̂Ƃ͌������˂�B
�����̏����͏Z����Z�s��ɂ�����،����Ȃǂ̋��Z�Z�@�̉���Ƀy�[�W�̑唼���₵�Ă��邪�A���̏ꍇ�ɒ��S�I�Ȗ��Ƃ����̂́A�،����ɂ���ďZ����Z�@�ւ��Ƃ̔���ɂ�郍�[�����ϑO�ɏ،��s�ꂩ�烍�[���S�z���̌��������Y���[������A���ꂪ���̃��[���ɉ�Ƃ��������݂ł���B�Z��[���͂���߂ĕ������s������Z�@�ւɗ^���邪�A���ꂪ�ʏ퐔�\�N�Ƃ��������ɂ킽�����ł��邱�Ƃ́A��Ƌ��Z�����������܂��͋��Z�@�֎��Y�̉�]����ቺ������\�������B�،����Ƃ������Z�X�L�[�����A���̖������������Ă����Ƃ����_�ő傫�ȈӋ`�������̂ł��������Ƃ͊m���ł���B�������A���̑O�j�͒����A���Ƃ��Ɛ��{�n�Z����Z�@�ցiGovernment Sponsored Enterprises : GSEs�j���l�Ă������̂ł���B2000 �N�㔼���납��}���ɖ��ԋ��Z�@�ւ������������n�߂��͎̂����ł��邪�A���ꂪ�ʂ̉����̌��ʂł������\�����l������B��A�̏o�����̈��ʊW�̖��̌������ǂ̂悤�ɑ�����ׂ����́A�����đ����Ȃ��ł��ޖ��ł͂Ȃ��B�������A�{�e�ł͂����������Z�Z�p�̐V�@���Ɋւ���c�_�������Ď̏ۂ���B���ǂ̂Ƃ��낻��͋��Q�̐^���ł͂Ȃ�����ł���B���Q�̂��тɐV��̋��Z���i�����ڂ���邪�A����炪���Q���N�������ƍl����̂́A���͕s�����Ȏv�����݂ł����Ȃ��B
����̋��Q�Ɋւ��錴�����͂��w�h���f�I�ɊT�ς���ƁA�勰�Q�̑O�Ⴊ�قƂ�ǂ��̂܂܍Č�����Ă��邱�ƂɋC�Â��B���Ȃ킿�A�}���N�X�h��P�C���Y�h�Ȃǂ̎Љ��`�҂͍s���߂������@�����e���ċ��Z�@�ւ̐��{�~�ςƃ��t�����������A�}�l�^���X�g�͊�@��̃}�l�[�T�v���C���\���ȗʂ������悤�ɐ����A�I�[�X�g���A�w�h��2000�N�㏉�߂�FRB �̒�����Ɍ��������߂č���̕��C������Ă���B
���ꂭ�炢�̑�g�����N����ƃ��f�B�A��w�҂͑呛�����邪�A���͋��Q�̌����͂��������Ȃׂē����ł����āA�����1990 �N��̑啽������̌o�܂����ԂɌ��Ă����A����͂ނ���N����ׂ����ċN���������̂ɂ����Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
����o�ϊw�̋��ȏ�������ƁA���ɂ��܂��܂Șb�肪���グ���Ă���̂ŁA�ǎ҂͂��������������邱�Ƃɒǂ���B�������A����������Ƃ���i�����Ă悭�悭�l���Ă݂�ƁA���ȏ��ɂ͂��鋤�ʂ̓��������邱�ƂɋC�Â��B����́A�����̌o�ς�ΏۂƂ��Ă���Ƃ����_�ł���B�ł́A�o�ό��ۂɂ����āu�L���v�ɓ�����͉̂����B�ނ��͋��Q�ł���B�������͌��݂��̐^�������ɂ���B�ɂ�������炸�A���i�̐����ɋy�ڂ����̉e���͂ނ���\�ʓI�ɂ͖ڗ������A���ɓ��{��́u���Q�v���udepression�v�̕s���m�Ȗ��ł��邱�Ƃ���`���āA���ʉ��ɐ����Ă���悤�ȂƂ��낪����B���ȏ��͋��Q�Ƃ��̌����_���d�v�Șb��̈�Ƃ͂��Ȃ����A��舵���Ă��ӂ��u�V���b�N�v�Ƃ����f���C�Ȃ��ꌾ�ŕЂÂ��悤�Ƃ���B�������A����͂������ɂ����܂������ł͂Ȃ��B�����������Q�Ƃ͎s��Q���҂����炩�̌o�ϕϐ��̓˔��I�ȕϓ��A�܂�V���b�N�ɏP���錻�ۂ̈����ł��邩��A���Q�̌������V���b�N���ȂǂƏq�ׂ邱�ƂɈӖ��͂Ȃ��B�u�V���b�N�ɏP��ꂽ���A�����̓V���b�N���v�������ꂪ�w��I����ł��낤���B�p���������قǓ�����O�̂��Ƃ��Ċm�F����ƁA���_�o�ϊw�̎d���́A�ނ��낻�̃V���b�N�̌������������邱�Ƃł���B���̉ۑ�ɉ����Ȃ������錾��́A�����Ƀm�[�x����҂�L����w�����ɂ���ďq�ׂ��Ă��悤�Ƃ��A�Ƃǂ̂܂�́u���V����V�j�t�B�A���v�ɂ����Ȃ��B
����̎嗬�h�o�ϊw�̗��_�͈ꌩ�k���ɍ\������Ă��邩�Ɍ����āA���̎����Q�̂悤�Ȑl�X�̊S��������������������ۂ��A�����܂ő̌n�̒�������������邱�ƁA����������Ε����o�ς���L���o�ςւ̘A���I�ڍs��������邱�Ƃ��܂�łł��Ă��Ȃ��B�o�ς̂��ƂȂ牽�ł��C���Ă����Ƃ���ɓ�����Ȋw�I�Ȍ��t����ח��Ă�o�ϊw�҂��A�L���ɂ͎�̂Ђ��Ԃ����悤�ɒ��ق�ۂƂ������Ƃ̊�����ɂ́A�����炭���Ȃ���ʑf�l�����Â��Ă���B�����ɂ͗��_�ƌ����̔ߊ쌀�I�ȕ�����B�L�͂ȉe�����y�ڂ������ŋ��Q�ɑ���l�X�̊S�͋������A�s�K�ɂ����̌����ɂ��Ă̊S�͗e�Ղɖ�������Ȃ��B���̌��ʁA�����Ȍ��ۂ��s���ƂȂ�B���Ȃ킿�A��w��I�ȋ��Q�_�����X�̒I�ߐs�����̂ł���B���Q���߂���c�_�͌o�ϊw�҂̎���͈͊O�ł���B�����āA�܂��������̂��߂ɁA�c�_�͗��ꗬ��Ă�����u�A�d�_�v�Ƌ���ڂ���W�������ɂ��ǂ���B
�u�A�d�_�v�Ƃ������̂́A�����ɂ��l�����������B�ߑ�I�Ȋw��Ƃ��Ă̌o�ϊw�́A�Љ�̒��̌o�ώ�̂̍s�ׂ���g�ݗ��ĂāA�����o�ς␢�E�o�ςȂǂ̑傪����ȑΏۂ��������m�ł��邱�Ƃ�W�Ԃ��Ă���̂ɁA���Q�̂悤�ɍL�͂Őr��ȉe�����Љ�ɋy�ڂ����ۂɂ��ẮA�N���������Ȃ��Ƃ���Ŏ�j�������Ă���Ƃ������ނ̐����ɂȂ邩��ł���B�������������Ɛ����̖����́A�}�̂Ƃ��ɂ͂����������𗧂Ăč������l�X���~�ς��ׂ��ł���Ƃ����ꌩ�����Ƃ��Ȏ咣�ɂ���āA���܂��čI���ɕ����B�����B�ӂ���͐����ɑ��Č������A�������ً}���ɂ͌����ɑ��Đ�����D�悷��Ƃ����̂��ʔO�ƂȂ��Ă��܂��Ă���B���Q�͌����Ɋ�Â��������Ɋ�Â������ɂ����Ƃ��܂łɎ�ۂ悭�u�������Ă��܂��B
�勰�Q�̌����_�Ƃ��čł�����ɂ���Ă���̂́A���̓t���[�h�}���ł���B������肩�A������{�̕s���̌����_�ł������ł���B�}�N���o�ϗ��_�ł͐V���ÓT�h���A���Z����̃��[���_�ł̓e�C���[���ނ��ߋ��̐l���ɂ������Ɍ���邱�Ƃ����邪�A���Q�̌����𐭍�ɋ��߂�^�C�v�̋c�_�͑O�҂ɂ͂��܂�Ȃ��A��҂ɂ͂����Ă��s���˓���̑��_�͎蔖������A����I�������Â炵�����_�̕����ً͋}���ԂƂ����˕��ɂ���Ă₷�₷�Ɛ��������A����t���[�h�}���Ƃ������n�����������B�������A�t���[�h�}���̑勰�Q�_�͎��͉A�d�_�ł���B�ނ́u���������f���v�͗]���g���f���ł��邽�߂ɐ������i�C�̔g�̏㉺���̂��������g�ɕ��Ă���i����2013 a�j�A�o�u���̃v���Z�X�Ɋւ�������͂͏\���ł͂Ȃ��B�����A�ނ̋��Q�_�̒��S�e�[�[�͕s����������s�̎d�Ƃ��Ƃ����f��Ȃ̂�����A��͂肻��͈��̉A�d�_�ł��邱�ƂɈ٘_�̗]�n�͂Ȃ��ł��낤�B�������A���̈ꌩ�Ȋw�I�ȑ����̂��߂��ʏ킱�̓_�����̓I�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��A���܂�ʐ��̍��ɋ������Ă���B�勰�Q�����_�̒ʐ��������̉A�d�_�ł���̂ɋ^�₪��N����Ȃ��̂́A�����[���t���ł���B
�P�C���Y�̗��_����{�I�ɞN�O�Ƃ��Ă���B���{�̌��E�������}�����Đl�X�̊Ԃ���u�M���v�����������A�u���K�v���ς��̂����Q�̌������Ƃ������A�ł͂Ȃ������Ȃ�̂��B�P�C���Y�́u�M���v������l���Ƃ��ē����ΏۂƂȂ��Ƃ̎��тɖ��S�Ȏs��Q���҂����߂���z�肵�Ă���A�u�f�l�v�Ɓu�v���v�̋�ʂ���������͓������邭���ɁA����ɑS�����f�l���R���Ƌ��ق��邩��A�u�M���v�Ƃ͎��ɞB���Ȋ���ɂ����Ȃ��Ȃ�B����Έ��́u�C���v�ł���B�C�����D���������炵�A�C�������Q�������炷�B���̂悤�Ȑ������A�{���Ɍo�ϗ��_�̖��ɒl����̂��B���{�Ƃ��×~�����Q�������炷�ƍl�����}���N�X���P�C���Y�͂��܂葸�h�����悤�ɂ͌����Ȃ����A��ƉƂɓ\��ꂽ�u�A�j�}���E�X�s���b�g�v�Ȃ�ʒ��F�̃��b�e���́A�ނ��}���N�X�̗אl�ł���\����Z���ɂ��Ă���B
�s��Q���҂́u�×~�v�Ɍ��������߂�^�C�v�̐��́A�m���ɋ��Q�ɐ旧�o�u�����ɂ͉H�U��̂悢�l�������҂�s������炵�ɓM���̂Ŗ{���炵����������B�������A�ł͂Ȃ����̂悤�ȕ�炵���ł���̂��Ƃ����_�ɂȂ�ƁA�����͈��ʂ̍�������Ɍ����̕����ɑk��n�߁A�r������Èł̒��ɓ˓����Ă��܂�Ȃ����낤���B�e��̋c�_�ɋ��ʂ̖��́A���ʂ̍��̒[�_���͂����肹���A�����Ƃ������̂ɂ���Ɍ��������肻���Ȉ�ۂ��c��Ƃ����_�ɂ���B
���āA�I�[�X�g���A�w�h�̋��Q�����_�́A��{�I��ABCT�i�I�[�X�g���A�w�h�i�C�z�_�j�Ɉˋ����Ă���i����_���j�B�Ƃ��낪�A���̗v�_�͒�����s�̉ߓx�̗��������o�u���́A�����ăo�u�������Q�̌������Ƃ������Ƃł��邩��A������A�d�_�ɕ��ނ����\��������B���Q�͂���߂ē���I�Ȍ��ۂł͂Ȃ����̂́A�\���N���琔�\�N�Ɉ�x�͋N�����Ă�������A�n���[�a���̗��K��F�����H�̔��������͂邩�ɕp�x�̍���������I�Ȍ��ۂł���B�o�ϊw�͂��łɐ��S�N�̗��j�����w�₾���A�����������ۂ��\�S�ɐ����ł��Ȃ����Ƃ́A���ꂪ�܂��܂��J���r��̒m�ɂ����Ȃ��\������������B�����Ő��Ԃɂ́u�A�d�_�v�����ӂ�錋�ʂɂȂ邱�Ƃ͐�ɏq�ׂ����A�s���Ȃ͉̂A�d�_���u��Ȋw�I�v�Ƃ��Ĕr�����Ƃ���҂��A�Ȃ����������̒�`�����Ȃ��Ƃ����_�ł���B
���ۖ��A���������ꕔ�̐������������肪�Љ�S�̂�����Ɋׂ�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���m���A�d�_�Ȃ̂��Ƃ���A���Q�̌����_�͕K�R�I�ɉA�d�_�ɂȂ�B���ɁA�Љ�����قڈ�l�ɍv�����Ė�肪�������Ƃ����咣��z�肷��ƁA����͖��炩�ɕs���R�ł���A��͂����_����S�̂ɖ�肪�g�U���Ă���ƍl����������R�ł���B�������A���ӂ��闘�v�W�c���Ӑ}�I�ɎЉ�ɍ���������Ă���Ƃ̎咣���A�d�_���ƍl����Ȃ�A����͋��Q�̌����_�Ƃ��Ă͐������Ȃ��B������s���ق͂ӂ��Ӑ}�ǂ���o�ς��R���g���[�����邱�ƂȂǂł��Ȃ��B�I�[�X�g���A�w�h�̋��Q�_�͒�����s�����_�ƌ��āA���̈Ӑ}�ɊW�Ȃ����ʂ�_���I�ɍl�@���闝�_�ł���B
���܃o�u�����N�����Ƃ���B�o�u���Ƃ́A�������Ȃ���ʓI�ߏ萶�Y���n�܂�Ƃ��Ɍ����錻�ۂł��邪�A�ŏI�I�ɂ͐��Y�v��̂����ꕔ�����������Ȃ��B���̈Ӗ��ł́A�����킯�̂Ȃ����̂�ʎY���悤�Ƃ��Đ�����듊���imalinvestment�j�ł���B�������A���͔���܂��͂߂������[�j���O�̒j���^�琶�ݏo������̂ł͂Ȃ��B���������ɂ͕K�����J�l���v��B�o�u����������ʓI�ߏ萶�Y�ւ̏��߂̒��ڂ̑O�œW�J�����̂Ȃ�A���̂Ƃ��͕K���ߏ�Ȃ��J�l���^����ꂽ�ƒf���ł���B��������ɔ����锭��������Ȃ�A���̎҂͊�Ƃ���i�Ő��i���������Ƃ��A�T���^�N���[�X���钆�ɑ���͂��Ă��ꂽ�Ȃǂƌ����Ă�������R�ł����āA�w�₩��͂�������Ă��܂��B���J�l�������Ȃ���A�����ăo�u���͋N���Ȃ��B�����Ƃ����肷���邱�Ƃ͂��肦�邪�A���̂Ƃ��͂��̐��i�̉��i���������ăo�u���ɂ͂Ȃ炸�A���̉�Ђ́i���v�̒e�͐��ɂ���邪�j����Ɏs�ꂩ��P�ނ��邾�낤�B�����āA�Z�������Ԃ̐l�X�͂₪�Ă����Y�ꋎ��ł��낤�B���̂悤�Ȋ�Ƃ��������̂��s��̑�Ȗ�ڂł���B�Ɛ��Ƃ̏ꍇ�́A���ߑ����̔��㑝�͌����߂Ă��A���̕�����҂̍��z�͌y���Ȃ邩��A�ʕ���̊�ƂƋ����W�ɓ���B���ǁA���ꑱ���邱�Ƃ͂Ȃ��B����ɁA���̂�������҂ɖO�����邾�낤�B�������A���J�l���������ꍇ�́A�ǂ̊�Ƃ����肷���邱�Ƃ����肦��B����҂̍��z���d���𑝂����Ƃ�������x����B�o�u���ł���B�ߏ�Ȑ��Y�ɓr���Ő���������悤�Ȍ_�@���s��̒����@�\�ƍl����Ƃ���A���̂Ƃ��s��̒����@�\�͂��łɖ�Ⴢ��Ă���B���ɂ���Ă��낤���B�����܂ł��Ȃ��A�ߏ�ȃ}�l�[�T�v���C�ɂ���Ăł���B�l�דI�ȃ}�l�[�T�v���C���͉ɐ����������ɂނ�����𒍂��B�����āA����̖@�߉ݕ����̂��Ƃł��̂悤�Ȃ��Ƃ��s����̂́A������s�ȊO�ɂ͐�ɑ��݂��Ȃ��B
�܂�A���ʂ��猴���ւƘ_���̃X�e�b�v���オ���Ă�����㈐��_�ɂ���āA���Q�̌����͒�����s���Ɠ���ł���̂ł���B�~�[�[�X�͉ݕ��̋N���ɂ��āu�k�y�藝�v�Ƃ������̂��l�Ă������i����2013 d�j�A����͋��Q�_�ɂ��K�p�ł��邾���łȂ��A�K�p�����ׂ��ł�����B�u�k�y��㈖@�v�Ƃł��ĂԂׂ����̂悤�ȋt�s�^�̐��������s�����A�����Ȃǂ̃p�����[�^���������Ď��{���_��������A�t���o�[�W������ABCT�ɂȂ�B�������������@�͌����_���ł����āA���_����ɂ͂���ȊO�̌�������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̂悤�Ȃ��Ƃɐ��������҂͂��Ȃ��B
�嗬�h�o�ϊw�ł́A�ݕ��͂܂����l�ړx�Ƃ���A���ꂪ�v���ԓI�Ȍ�����}��������i�Ƃ݂Ȃ����B�����A�唼�̊w�҂��u������i�@�\�v�̈Ӗ���������Ă���B�������Ȃ�͒P�Ȃ�����̔}��c�[���Ȃǂł͂Ȃ��A�{���͉��ł��܂���u�čw���́v�A�܂肠�����������T�[�r�X�Ƃ̑�ʉ\�������g�p���l����������ł���A���̌��ʌ���������ɂȂ�ƗʓI�䗦����艻���邩�炠�������u���l�ړx�v�ł��邩�Ɍ�����ɂ����Ȃ��i����2013 d ; 2014 a�j�B�����āA�ݕ���L���ԓI�Ɂi�������������āj�g�����߂ɏ���ґ�������~����Ɗ�Ƒ������p�ł��邩��A�ݕ��́u���l�����@�\�v�́u���{�@�\�v�ɂ��Ȃ�B�@�߉ݕ����̂��Ƃł͉ݕ��͒��~���o�R������s���Ƃ����Ă����Ȃ莑�{�@�\�����B���Ƃ���A���̑��ʂ��o�ϑS�̂��������܂��ɂ��މ\���ȂǍl�����Ȃ��B�嗬�h�o�ϊw�́A�����ɒ��z����Ƃ����ݕ��̓��ꐫ�̑��ʂ݂̂����āA���ꂪ�����Ɠ����������ϓ��ɎN����Č����ɂ͎ړx���Ȃǎ������Ȃ����߂ɐ����鏔���ۂɖڂ��ǂ��ł��܂��B�������A�V�K�Ɍo�ςɒ������ꂽ�ݕ��ɉ��l�ړx�@�\�Ƃ��̊��ɂ���������̂��߂̌�����i�@�\�݂̂������A���{�@�\�͌��ʓI�ɎE���ł��܂����@�ȂǑ��݂��Ȃ��B������A���������肳���邽�߂̉ݕ����ʂ͂��̂܂ܕs��I�Ɍo�ς̋ύt�����ꂩ��h���Ԃ�N���܂ɂȂ��Ă��܂��B����Ȃ̂ɁA�o�ϊw�҂����͂��̖��X���X�Ȏ�������ڂ����炷�B�������āA�K�R�I�ɉݕ��ɏo��������Ă��܂��B
����o�ϊw�́A�}�N�����_�ł͊�{�I�ɃP�C���Y�^�̊��_�I�Șg�g�ɓ������Ă��邪�A���̑n�n�҂܂��͏d�v�Ȑ�s�҂̓t�B�b�V���[�ł���A�t���[�h�}�����܂߂Ă��̘g�g�P���Ă���B�����A�}�N���o�ς̈�ʗ��_�̓P�C���Y�ȑO�Ƀ~�[�[�X�ɂ���Ē�o����Ă���iMises 1980�m1912�n�j�A���̂��߈ꎞ���ނ̗��_���嗬�h�̒n�ʂɂ������B���[�J�X���n�C�G�N�̃P�C���Y�ᔻ�ɕ֏悷��`�Ń}�N���o�ϊw�Ɋ��җ��_�������Ƃ����o�������A�����܂ł�����������A�̌o�܂̉�����ŗ��������ׂ��ł���B�I�[�X�g���A�o�ϊw�͒����ȗ��̒����`���������i����2014 a ; 2014 b�j�A����̑�w�̌o�ϊw�̐��E�ł͊�{�I�ɔr������Ă���Ƃ����s�K�ȏɂ���B�������A�{�e�ł͊w�j�S�̂܂��������̂Ȃ����_����A�L�v�ȉ𖾂͂��ׂė��p���ċc�_��i�߂Ă��������B
|
���T. 2 ���ۗv���̔�d�v��
����̊�@�̎傽��v���̓O���[���X�p���̒������ł���B����ɑ��锽�_�́A�ȏ�ɏq�ׂĂ������Ƃ�����قƂ�LjӖ����Ȃ��B�܂��A�ʂ̗v������������ꍇ���A�M�����̒�����̊�^�͔ے�ł��Ȃ��ł��낤�B�{�߂ł͍��ۗv�����̑�\�Ƃ��ăO���[�o���ߏ蒙�~�����������A���̖������w�E����B����́A�A�����J�̋��z�̌o��Ԏ��ƃA�W�A�V�����̋��z�̌o�퍕���̃O���[�o���E�C���o�����X�̂��ƂŁA��҂̑�ʂ̒��~���O�҂ւƗ��ꍞ��ł����Ƃ������ł���B���������c�_�̒��ڂ̔��[�ƂȂ����̂́A2005 �N3 ���ɓ���FRB �����������o�[�i���L�����@�[�W�j�A�B���b�`�����h�ōs�����u���ł���B
�����̖ʂŃA�����J�o�ς̏�Ԃ͏�X�Ǝv���܂��B�Y�o�̐L�т͌��S�Ȑ����ɂ܂ʼn��A�J���s��͌����ŁA�C���t���͂��܂��}������Ă���Ǝv���܂��B�������Ȃ���A�A�����J�o�ς̏�Ԃ̂����̖ʂ́A���܂Ȃ��G�R�m�~�X�g���̃v���̊S���䂢�Ă��܂��B����́A�킪���̑傫�Ȍo��Ԏ��ł��B�c�c���E�ő�̌o�ϋK�͂��ւ�A�����J�o�ς��A�Ȃ����ێ��{�s�ꂩ�瑽�z�̎���Ă���̂ł��傤���B�݂��Ă��������莩�R�ł͂Ȃ��̂ł��傤���B�A�����J�̌o��Ԏ��ƊO���M�p�ւ̈ˑ����A�����J�o�ς̏�Ԃ�f�Ց��荑�̏�Ԃɑ��Ă����Ȃ�Ӗ������̂ł��傤���B���̏ɑΏ�����̂ɉ��炩�̐��L�����Ƃ��āA�ł͂����Ȃ鐭�p������ׂ��ł��傤���B�����̂��b�ł́A���������₢�ɑ��ĉ��̓������o���Ă݂����Ǝv���܂��B���̕ԓ��́A���̓_�ł��^�j��Ȃ��̂ł��B���Ȃ킿�A�ߔN�̌o��Ԏ��̈�������{�I�ɃA�����J���g�͈͓̔��ł̌o�ϐ���₻�̑��̌o�ς̐��ڂ̂������Ƃ����A�悭���錩���Ɉًc����������̂��Ƃ������Ƃł��B�����o�ς̐��ڂ����̖������ʂ������Ƃ��Ă��A�ߔN�ɂ�����o��Ԏ��̑�����������ɂ́A�A�����J�̊O�ł̏o�����������Ə\���Ɏ���ɓ��ꂽ�O���[�o���Ȏ��_���K�v�ł��邱�Ƃ�_���܂��B�����Ɠ��肷��Ȃ�A�����\�N�قǂł��܂��܂ȏ��͂��O���[�o���Ȓ��~�����̑啝���ݏo�����Ƃ������Ƃł��c�c�B�iBernanke 2005�j
�O���[�o���E�C���o�����X�̌����������̐���ɋ��߂�̂���ʓI�Ȍ����ł��邱�Ƃ�����F�߂Ȃ���A����ɂ����Ĉًc�������悤�Ƃ����̂ł���B�����āA�c���A�C���2007 �N�̃x�������u���ł́A������������������ɔ��W�����悤�Ƃ����B
2005 �N3 ���̍u���k��L�u���l�ł́A�O���[�o���o�ς̒��ŋN���Ă���d�v�ő��݂Ɋ֘A���������W�J����������_���܂����B�A�����J�ɂ�����o��Ԏ��̑啝�g��A���X�̐V���o�ςɂ����铯�����ڂ�������o�퍕���̑����A���E�I�Ȓ����������q���̒ቺ�Ȃǂł��B�_�����Ƃ���A���������W�J�̈ꕔ�́A�O���[�o���Ȓ��~�ߏ�̑䓪��������ł��܂��B����𐨂��Â������̂́A�����̐V���o�τ����Ƃ�킯�A�}���W���铌�A�W�A�o�ςƎY�����o�τ������A���ێ��{�s��ɂ����ăl�b�g�ł̍������狐��ȃl�b�g�ł̍����ɕϖe�������Ƃł��B�iBernanke 2007�j�����h�ƃ~�[�[�X�̗����Ɏt���������C�X�}���́A�������̓_�ł��̂悤�ȍl�����ɔ��_���Ă��邪�iReisman 2009�j�A�c�O�Ȃ��炻�̋c�_�͓���Ȃ̂ŁA�M�҂Ȃ�ɂ��̒��~�ߏ���̋^��_���������Ă݂悤�B
�v�_�́A�{���ɒ��~�ߏ肪����A���ꂪ�P��I�Ɏ����𗬓������Ă���̂��ł���B�V�������́u�Ō�̔���v�ibuyer of last resort�j�ł���A�����J�ւ̗A�o�ɐ����o�����A���̑���̏��Ȃ���ʕ������h���Ŏ��B�A�����J�ɂƂ��Ă���͍݊O�h���ł��邪�A�A�W�A�����͂�������Nj��Z�@�ւɗa�����A�����͗a�������ȏ���҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��̎������^�p����B�����A�A�����J�ɓ������ꂽ�����́A�A�����J�̐M�p�c���Ɋ�^����ł��낤�B�o�[�i���L�͗A�o�����^�H�ƍ��������A�W�A�������A���̒��~���̍����䂦�ɉߏ莑���̌���ɂȂ��Ă���Ɛ������A�A�W�A����̎����͍��w���Ɍ����������������A�A�����J���炷��ΊO����s���������ƂŎ����o�ς��c������Ƃ͍l�����Ȃ��B�O��͘A�M�����P���̉����s�ł͂Ȃ��B
�����A���������h���̑��ʂ��������Ƃ��ɂ͂��ꂪ�N���邩������Ȃ��B���܁A����ɍ~���Ɖ͐�Ő��̗���������10 ���P�ʂ���A�͐��8 ���A������2 ���̐��̗��o������Ƃ���B����N�ɒn�k���N���Ēn�Ւ����̂��߂Ɍ��g�債�Ėʐς������A�~����������1 ���������Ƃ���B�̐��t���[���x�̑��z�́A�n�k��10 ������11 ���ɑ��������ƂɂȂ�B�ł́A�O���[�o���E�C���o�����X�̊g��ɂ����āA�n�k�ɂ��Ζʊg��ɑ���������͉̂����B���ێ��x�ɂ����Čo����x�Ǝ��{���x�͑��₢�����W�ɂ���A�o��Ԏ��͎��{�������Ӗ�����B�����āA�o����x�̐Ԏ��ƍ����̐��E�S�̂ł̍��v�z�́A�덷�E�R�������ƈ�v����͂��ł���B20 ���I������̃O���[�o���E�C���o�����X�̊g��ŁA�A�����J�ꍑ�����E�̌o��Ԏ��̑唼���v�シ��\�������������B����́A�n�k�Ōΐ��t���[���z���C�����A�E�g�����������Ƃɑ������A�h���̗��o�������������Ƃ��Ӗ�����B�ł́A�����͉����B���̂Ƃ���̓��A�W�A�����o�ς̋}�L�͊m���ɖڂ���������̂����邪�A�����Ȃǂ̑卑�͊J�������ł͂Ȃ��B�ނ炪������GDP��L�����Ƃ��Ă��A�o�퍕���͂���5�� �O��ł���B���̕������}�L�����Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł̓O���[�o���E�C���o�����X�͊g�債�Ȃ��B
�����������ɂ��ׂ��́A�Ȃ��A�����J�l���ȑO��肽������A���ł���悤�ɂȂ������ł���B�A�W�A��������������Ă��A�A�����J�ɂ��J�l���Ȃ���Ύw�����킦�Č��Ă��邵���Ȃ��͂��ł���B���ۂɂ́A�A�����J�ŐM�p�c�����N�����Ă��邩��A�����J�l���A�W�A���i�𑽂�������悤�ɂȂ��Ă��邵�A�A�W�A���A�����J�������Ă���邩������Ă���̂ł���B�����A�����J�̉ݕ��ʂ����Ȃ�A���������Y���Ă�����c�邾���ł���B
�@�@�@��1 �}�O���[�o���E�C���o�����X�̕���
�@�@�@��2 �}�A�����J�o����x�Ԏ��̕���
�܂��A��@�ナ�p�g���G�[�V�����i�����̖{����A�j���N�������A���炭����Ƃ�����x�A�����J�Ɏ����������߂��Ă����i��1 �}�j�B�������A���ꂾ���ŃA�����J���ēx�o�u���ɕ����Ă���Ƃ����b�͕����Ȃ��B
�A�����J�͊�{�I�ɕ��I�Ȍo�ςł����āA�O���[�o���Ȏ����̋K�͂͂��̌o�ϋK�͂ɑ��Ă������m��Ă���B���ƂȂ�2000 �N�㔼����̌o��Ԏ��̑�GDP ��́A�����Ȃ̓��v�����ƂɎZ�o����ƍő�ł�5�� ��ɂ����Ȃ��i��2 �}�j�B���Ƃ���A���ۗv�����́A���ΓI�ɏ����Ȏ����ő傫�ȍ��������Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��B�����܂ł��Ȃ��A�������@�̎�v���Ƃ��邱�Ƃ͕s�\�ł���B
���ێ��x�ɒ��ڂ��錩���͑勰�Q�Ɋւ��Ă������邪�A�o�ϋK�͂ɑ��鍑�ێ����t���[�̖������ߑ�]�����A������s�V�X�e���ɂ�����M�p�c���̖������ߏ��]�����邱�ƂɂȂ���₷���B����͐��l���ł��邩�猵���Ɍ�����Ƃ����t���[�o�ϊw�̓����������炷���e�ł��낤�B�������A�����̋N�_��A�M�����_�Ƃ���A�����J��s�V�X�e���ɂ�����M�p�c���ɋ��߂Ă��A�ȏ�̌��ۂ͐��������B�������A��萮���I�ɐ����ł���B���Ȃ킿�A�܂��A�����J�ŐM�p�c�����N����B�h���͊�ʉ݂�����A���̂܂ܐ��E�Ŏ�̂����B��������ƁA�A�����J�l�͈ȑO���A���𑝂₹��B�A���ɂ͎��{����ϋv�����܂܂�邾�낤�B�������A���̑���Ƃ��ĕ������h���̏��Ȃ���ʕ�������q�̊җ��v���Z�X�ɂ���č����ɖ߂��Ă���B�M�p�c���̊z�͔N�X�����邩��A�ȏ�̃��J�j�Y�����N�x���ƂɃt���[���z�𑝂��Ȃ���i�s����B��������ƁA�O���[�o���Ȍo����x�M���b�v���g�債�Ă���Ƃ������v�ƂȂ��ĕ\��邾�낤�B�������āA���v�������Ɏ��W���邪���̔w�i�ɂ���o�ϊw�I���J�j�Y�������������_�������Ȃ��w�҂�A�i���X�g�������A�A�����J�͐Ԏ����v�サ�Ȃ�����ȑO������𑝂₵�Ă���Ƒi����_����ʎY���邾�낤�B
�ł́A����̓A�W�A�����̒��~�ߏ�̂����ł��낤���B�A�W�A�ł͗��j�I�Ȍo�܂Ȃǂ���`���I�ɒ��~���������B�A�����J�̒��~�����Ⴗ����ƌ�����������������������Ȃ����A������ɂ��撙�~���ɊJ��������B�������A���܃A�����J���M�p�c�����N�����Ȃ������Ƃ���ƁA���N�قړ��������Ŏ��������ۈړ�����ƍl�����A���ꂪ�g�傷��\���͒Ⴂ�B�����g�傷��A���̕��A�W�A�����ł͓����̌��������邩��A�����ɐ������邾�낤�B�������A�A�����J�͏�����A�A�W�A�͐��Y���g�債�Ă����B�ƂȂ�ƁA�A�����J���M�p�c�������Ă������炾�Ƃ����̂��B��\�Ȑ����ɂȂ�B�A�W�A�̒��~�����������ƂƁA�A�����J�ւ̎����������������ƂƂ́A���͕ʖ��ł���B�܂��A���~�u���v�ƒ��~�u�z�v���ʊT�O�ł���B�����A�W�A�̒��~�����Ⴍ�Ă��A�A�W�A�����E�̍H��ł�����ƂŃA�����J���M�p�c����i�߂�A�W�A�̒��~�z�͑����A���ێ��x�M���b�v�͂�͂�g�傷��ł��낤�B
�O���[�o���E�C���o�����X�������ɂȂ�n�߂��̂�1990 �N�㖖����ł��邪�A�����1980 �N�㖖�̎Љ��`�o�ό��̕���A����ɐ旧���Čo�ώ��R����I�����������̔��W�A����A�W�A�����̐����A�C���h��A�t���J�Ȃǂ̑䓪�Ȃǂ����X�Ɛ������鎞��ł��������B�O���[���X�p���͂��̉e�����u�f�B�X�C���t���v�Ƃ����^�[���ŌĂ�ł��邪�A�����IT �Y�Ƃ��擱���������o�ςɂ����鐶�Y���̌���ƂƂ��ɁA�P�ʓ�����̃}�l�[�T�v���C���ɑ������ҕ����w���iCPI�j�̏㏸�y�[�X��݂点����ʂ��������ł��낤�B�������āA�l�ގj�ォ�ĂȂ��قǂ͈̔͂ƋK�͂ł̃O���[�o�������i�W����̂ƕ��s���đ啽�����O���ɏ��n�߂����߂ɁA�A�M�����͐��E�̒�����s�Ƃ������i�����߂Ă����̂ł���B
���鍑�ł͓����Ɏ�s�ƒ�����s������A���܂肨���߂��ɏ�������Ȑl�X���Z��ł���B���̂��Ȃ萼���ɁA���̂Â���ɗ��ł��܂肨�J�l���g��Ȃ��l�������Z�ޒn��������B���܂��̍��̈�یo����x�̓��v�����A�����ڏo���߁A�����ړ����߂ƂȂ낤�B������s���ݕ��������s���Ƃ��A���̍��ł͂܂������̋�s�̏����a���ɂ��J�l������Ƃ���ƁA���ŐM�p�c�����N���邩��A����Ɉ�ێ��x�̃M���b�v���g�傷��B�ނ��A�����̋�s�ɂ��ݕ����s���n����̕s�ϓ����v���Z�X�͎~�ނ��낤�B�������A���炩�̗��R�ōs���n��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���A��ەs�ϓ��͊g��̈�r�����ǂ邾�낤�B���������v���Z�X���������Đ��������̂��O���[�o���E�C���o�����X�ł���i�������A�A�M�����͊O��ɂ͍Ō�̑ݎ�ƂȂ�Ȃ��j�B���V���g���͓��ɁA�h�����O�݂Ƃ��đ�ʕۗL����A�W�A�����͐��Ɉʒu���A���҂̌o�ϓI�Ȃ���͐[�����O���ǂ���������A���݂��̎���͈�ێ��x���v�ł͂Ȃ����ێ��x���v�Ɍv�コ���B�������āA�A�M�����̕���������̂܂ܐM�p�c���ƂȂ�A���ꂪ���E����������ł������̂ł���B
����̍��یo�ϊw�ő��p�����}���f����̃��f����IS-LM ���f���Ƃ����P�N�x�t���[�o�ϊw�����ۉ��������̂ɂ������A���̘g�g�ň�A�̏o�����𗝉����邱�Ƃɂ͂��̂��ƌ��E������B���������O������̎��{�����̏��Ȃ���ʕ����͌������ǂ�A�����J�Ő��������ꂽ�M�p�ł��邩��A�t���[���v���獑�ۗv�����������Ă��܂��ƁA�A�M�������s���Ă��邱�Ƃ̐ӔC�]�łɎ��݂��Ă��܂������ł���B���ێ��x�M���b�v�̊g�傻�ꎩ�̂͋��Q�̌����ł͂Ȃ��B�����A�A�M�����̐M�p�c���������I�Ƀo�u���Ƌ��Q���N�����A���̉e���͓��R���E�Ɋg�傷��B�����āA�J�E���^�[�p�[�e�B�i��O�ҁj���X�N�ɑ���^�S�ËS���̕K�v�������̂���ƁA�ĂуM���b�v�͏����Ɋg�傷��B�������A���ꂪ���������̃o�u�����@���ĂԂ��Ƃ͂Ȃ��B�v����ɁA���O����̎��������̓A�����J�̌i�C�z�̎�v���ł͂��肦�Ȃ��B
|
|
���U ��@�̂��Ƃ��� |
���U. 1 ��@��̃O���[���X�p��
�O���[���X�p���̎咘�w�g���̎���x��2007 �N���ŁA�T�u�v���C���E���[����@�Ɠ��N�ł���B�o�Ō��̃y���M���Ђ́A���Ԃ̋}�ς��āA�ނɒlj����e�̎��M���˗������B�����2008 �N9 ���Ɂu����y�[�p�[�o�b�N�Łv�Ƃ��Ċ��s����A���╔���́w���ʔŃT�u�v���C���������x�Ƃ��Ė�o����Ă�����B�Ƃ��낪�A�^�C�g������͏\���ȃR�����g�����҂ł������Ɍ�����̂ɁA���͂��܂�j�S���ɂ͂ӂ�Ă��Ȃ��B�����炭����́A�����ꂽ��������@�̒��シ���邽�߂ł��낤�B�������̃O���[���X�p�����A���[�}���E�V���b�N�̗]�g���^����e�������͂��邢�Ƃ܂��Ȃ��܂܂ɋ}���Ŏ��M�������╔���ɁA��@�̕�I�Ȍ���}�����߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�����ŕʂ̎�����T��ƁA�������̗Ⴊ������B��\�I�Ȃ̂�2010 �N4 ���Ƀu���b�L���O�Y����������o���ꂽ�u��@�v�iThe Crisis�j�Ƃ����V���v���ȃ^�C�g���̘_���ł���B�܂��͂��ꂩ��T�ς��悤�B�_���́A���̂悤�Ɏn�܂��Ă���B
2008 �N9 ���̃��[�}���E�u���U�[�Y�̔j�]�́A���܂���U��Ԃ�Ɖߋ��ň��̃O���[�o����@�Ɣ��f�����Ǝv����}�]�����������炵���B���ۂɂ́A���̎��k�̎n�܂�̏�ʂł���ɑ����Đ������o�ϊ����̎��k�́A1930 �N��̕s���ɔ�ׂ�Ƃ͂邩�ɏ������B�Ƃ͂����A���ԒZ���M�p�������I�Ɉ����グ���A���������ꂪ�O���[�o���ȋK�͂ɒB�������Ƃ����Z��@�̐�삯�ƂȂ����킯�ŁA����͂킪���̋��Z�j�ɂ����ĊȒP�Ɍ�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B����܂ʼn��\�N���I�݂ɔ���������Ă������Ԃ̃J�E���^�[�p�[�e�B�M�p�Ď������A����ɃO���[�o���ȋK���V�X�e�����j�]�������ߐ��{�ɂ��O�ꂵ�����������K�v�ƂȂ�A����͂��܂Ȃ������Ă���B�iGreenspan 2010�A 3�j
�܂�A�K�͂ɂ����Ă͑勰�Q�قǂł͂Ȃ����A�C���^�[�o���N�̒Z���s��i�v���ǂ����̎���̏�Ȃ̂ŕ������ƂƂ��ɍ��x�ɗ����I�j���痬���������オ�������ƁA����т��͈̔͂��������z�������Ƃ͗e�Ղɂ͐M�����Ȃ����ۂł���A�V���b�N�̑傫����[�I�ɕ����Ƃ����̂ł���B
�v���Ƃ��ċ������Ă���̂́A��q����u���v�����ōL���F�m�����悤�ɂȂ����O���[�o���Ȓ��������̒ቺ�̂��Ƃł̎��Y�����̊g��A�������O���[�o���Ȓ��~�ߏ�Ȃǂɂ�郊�X�N�v���~�A���̒ቺ�Ɋւ�����̂������B���������ǖʂł́A�e��Ƃ���Z�@�ւ́A���S�㏸�ǖʂ������ɑ����\���͂Ȃ��Ɣ��f���Ă��Ă��V�F�A���m�ۂ��邽�߂ɂ����ă��X�N�����ɍs���icf. AOT 521�G���ʔ�36�j�B���̂��߁A���j���牺�~�ǖʂւ̓]����\������\�͂��ቺ���A���̂��Ƃ��x�d�Ȃ�o�u���Ƃ��̔j��̃T�C�N���������炷�B���Z�H�w�ɂ�郊�X�N�̊Ǘ��́A���ꂪ�R���s���[�^�ɓ��͂���f�[�^����������30 �N�قǑO�܂ł̂��̂ł����Ȃ��A���̒��x�̊��ԂɑO�Ⴊ���������X�N�ɑ��Ă����ϐ���ۏ��Ă���Ȃ������B
�̐S�̒������ƃo�u���̊֘A�ɂ��ẮA�Z��Z���Ɋւ��̂͒��������ł����ĒZ����FF ���[�g�ł͂Ȃ��A�܂����̒��������̒ቺ�͕s�R�͂ŁA�Z�������Ƃ̃����N��21 ���I���߂ɂ͏������Ă����Ƃ��������������Ă���B�ȒP�Ɍ����A2001 �N���납��̗��j�I��FF ���[�g�̈������͖Ɛӂ����Ǝ咣�������̂ł���B��Ƃ��Čf�����Ă���̂͋��Z�@�ւ̎��{�g�[�ł���B�u���{���\���Ȃ�A��`�ɂ���č����f�t�H���g�Ɋׂ邱�Ƃ͂Ȃ��A�ł������`�����j�~�����v�Ƃ����̂���Ă̍��q�ł���A���ׂ����́A�����̏،�����@�I�ɋK�����邱�Ƃ���Ă��Ă���B�������A�K���Ђ��ɂȂ邱�Ƃɂ͎��~�߂����߂Ă���B
�������A�K���I���v�p�b�P�[�W�̈�Ƃ��Č��ʂ����u�V�X�e�~�b�N�ȋK�����ǁv���l���邱�Ƃ͌������Ăł���B���݂̌o�ϗ\���͔߂�����Ԃɂ���A���{�͂��̖��ɂ͓�̑��ނׂ��ł���B���Ȃ�lj��v�f����ꂽ���̂������Ƃ����Ӗ��ŃX�^���_�[�h�ȃ��f���ł͍���̊�@��\�z�ł��Ȃ��������A���̐[���ƂȂ�Ƃ����Ɠǂ�����B�iGreenspan 2010�A 48−49�j
���ꂾ���łȂ��A����̒����I�ȗ\�z�������Ă���Ă���B�w�g���̎���x�̑��╔���̍Ō�ł́A����͒����������オ��A���炭�͎��̃o�u����S�z����K�v�͂Ȃ��Ƃ��Ă��邪�iAOT 532�G���ʔ�57�j�A1 �N����́u��@�v�ł́A�ނ̕M�͎��̃o�u���̌���}�ɂ܂ŋy��ł���B
���̊�@�́A�ԈႢ�Ȃ��R�قǂ̐V��̊v�V�I���Y���o���Ă��邾�낤�B���̈ꕔ�͈Ӑ}�������ēŐ��������A�N���O�����Ă����\�z�ł��Ȃ����낤�B����ǂ��A���{�ƈ������\���Ȃ�A�����͎������،��ۗL�҂Ɍ�����B�ނ�ُ͈�Ȏ��v�����߂邪�A�������邤���Ɉُ�ȑ�������̂ł���B�[�Ŏ҂̓��X�N�ɎN����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�iGreenspan 2010�A 49�j
�������āA�u��@�v�͋��Z��@�ւ̎��O�I�Ή��̌��E���w�E���Ď���I�ȃ��X�N�Ǘ���`���f���Ă�����������̉�����ɁA����قǂ̋K�͂̋��Z�����ɂ��Ή��ł���悤�ȑ傪����ȊǗ��V�X�e���̓������������ďI����Ă���B���ӂ��ׂ��Ȃ̂́A�ނ��K���̋���������ł��Ȃ��A���̑�K�̓o�u�����N����̂�����Ȍi�C�z�̐i�s�ɂ�����o�������ƒB�ς��Ă���_�ł���B����́A�`���ł��܂�ɋ}���ȗ������̊��オ��ɋ�����\�����Ȃ�����A����̊�@���u�ÓT�I�ȓ����^�o�u���v�ƌĂ�ł��邱�Ƃɂ��\��Ă���B�܂�A�ނ̓��̒��ł͂��́u100 �N��1 �x�v�iAOT 526�G���ʔ�46�j�̑勰�Q������قǂ̃V���b�N�ł͂Ȃ��悤�Ȃ̂ł���B
�����Ƃ��A���[�}���E�V���b�N����1 �N�ȏソ���Ă���_���̌`�ʼn��߂Ĕ��\���ꂽ���̂����ɁA�����₷���Ԃ����������̂Ɛ��@�����B�Ƃ��낪�A���ăp�[�N�X�Ɖ�b�����킵����ł�����i����2012 b�j�j���[���[�N�o�σN���u��2009 �N2 ��17���ɍs�����u���i�^�C�g���Ȃ��j������ƁA�͂����肵���T���Ԃ肪����������B���u���ł́A�����������������R�����g��������B1950 �N��ɃV�J�S��w�̃}�[�R�[�E�B�b�c���g�D�I�ȃ��X�N�Ǘ��_��W�J���n�߁A���Z�ƊE��E���������e�������A2007 �N�Ɍ����ɊǗ��̐��ɂЂт��������B
�������ꂽ���x�Ȑ��w��R���s���[�^�̃E�B�U�[�h�́A��{�I�ɁA���钆�j�I�O��Ɉˋ����Ă��܂��B���Z�@�ւ̏��L�҂�o�c�҂̌[���I�ȗ��ȐS���A�����̊�Ƃ̎��{��X�N�����Y�̎��������Ď��E�Ǘ����銈���ɂ���āA�ނ�ɍ��s���s�ւ̌����I�ȃo�b�t�@���ێ�������悤�d�����邾�낤�Ƃ����O��ł��B2007 �N�̉Ăɂ��ꂪ�j�]�����Ƃ��A���͐[�����낽���܂����B�iGreenspan 2009�j
�s��Q���҂�����ɉۂ��K���̈�����g�ɓۂ܂�Ă����Z�V�X�e���̒����͂��o�b�t�@�ɂȂ肦���͂��Ȃ̂ɁA���̈�����j��ꂽ�_�ɖ��̍��[��������B�Ⴆ��BIS�K���̂悤�Ȏ��{�v�������ʂɏI������B�u�傫�����Ēׂ��Ȃ��v�Ƃ����O���ɉ��i�Â���D�ʂɐi�߂����Ďs���c�߂��B�������āA���ǂ͈���Ŏs�ꌴ���ɉ����������̉��A�����Ŏ��{�g�[�ɂ��o�b�t�@�̋��������߂�̂ł���B�w�g���̎���x�̊j�ƂȂ郁�b�Z�[�W���A�啽���̂��납�琢�E��̎s��ŃX�~�X�́u���������v���@�\���n�߁A�傫�ȊO���V���b�N�ɂ��ς��Ď��R�s��o�ς������Ɉ���Ă������R��T��Ƃ����_�ɂ���Əq�ׂĂ��邾���Ɂi����2012 d�j�A���[�}���E�V���b�N�Ŏ��Ռ��͔ނ����낽��������قǑ傫�������B�����āA1 �N�������u��@�v�ł͂���ÂȎp�������߂��Ă���B��̔�������͂������@�ł���B
2009 �N�̍u���ɂ́A����������������_������B����́A�����ƃ}�N���o�ς̊W�ɂ��Ă̏����ł���B
���Z����̔j�]�́A�������\�N�ő����̌o�ς����߂����܂����B�ł��ڗ��̂�1990 �N��̓��{�ł��B�Ƃ��낪�A�������o�ςɗ^����e���̕��������炭�����ƒ��ړI�ł��B�������͊����̕ϓ����u����́v���v�⑹���Ƃ����������ő����A�����I�Ȑ��E�Ƃ͂���Ӗ��łȂ��肪�Ȃ��ƍl�������ł��B����ǂ��A���́u����̍��v�̉��l����������ƁA�O���[�o���Ȍo�ϊ����ɐ[���ȃf�t���I�e�����y�ڂ��܂��B�l����x�o�ɑ���ƌv�̕x���ʂɂ��Ă͑�����������Ă��܂��B�ł����A�����͖��Ԏ��{�����ɂ��傫�ȉe����^����̂ł��B1959 �N�ɔ��\�����_���ŁA�A�����J��Ƃ̊������Y�̎s�ꉿ�l�A�܂芔�����A�����̎��Y�̍Ď擾���i�Ŋ����Ĕ䗦�����߂܂����B����́A1920 �N��ɑk���ċ@�B�̔������ƍ������ւ�����܂����B�ŋ߂��̕��͂��A�b�v�f�[�g���āA���̒P���ȊW���Ȃ������ɗL������m���ċ����܂����B�����̂Ƃ���̎������Ԏ��{�����̋}���ȕϓ����炱��Ŏ�����̂ł��B�iGreenspan 2009�j
�勰�Q���݂̋��Z��@�̗]�C����߂��ʊԂɁA�u�����Ǝ��{���l�]��v�̋c�_�����傤��50 �N��ɍĐ����Ă���̂ł���iGreenspan 1959�G����2013 a�j�B�O���[���X�p���͕�������̂��߂ɒ��������V�K�ݕ������l�����E���{�@�\�������ƁA�����Ă��̂��߂ɋ��Z����̐��i�ɂ����Ċ�b�I�g�g�ƂȂ�}�N���o�ϊw�Ɏ��{���_���s���ł��邱�Ƃ��͂�����ƈӎ����Ă���B���̓_�ɋC�Â��ʂ܂ܔނ�ᔻ���邱�Ƃ͂��낻��~�߂ɂ��Ȃ���Ȃ�܂��B1990 �N��̃A�����J�o�ς�1950 �N��Ƃ͂��Ȃ�قȂ邪�A����ł��Ȃ���҂�y��ɍ\�z�������f�������������͂������Ă��Ă͂܂�B
������A���̌o���ł́A���������k�����Ƌ��|���J��Ԃ������s��́l�}�b�́A�����̌o�ϊ�����\����������̂ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�o�ϊ����̏d�v�Ȍ����ł��邱�Ƃ������̂ł��B�����͌i�C�z�̑唼��ʂ��ė��v���҂ƌo�ϊ����Ŏx�z����Ă��܂��B����́A�i�C�z�̓]���_�ɂ����Ă܂��܂��o�ϊ�������Ɨ��Ɍ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�o�ς̐�s�w�W���Ƃ����Ƃ��̈Ӗ��ł���A�i�C�z���͂̑������������_����킯�ł��B�iGreenspan 2009�j
�啽���̂�������1990 �N�㔼�����̓]���_�ł������B���������ς��Ƃ��ɓ�ɂȂ�悤�ɁA�����ł͊����͈ꌩ�����������������i��3 �}�j�B����ǂ��A���̊Ԃɂ����̃o�u���ւ̃J�E���g�_�E�����n�܂��Ă���̂ł���B
�O���[���X�p���̃}�N���o�ϕ��͂��A�C�܂���Ƃ͐����ȁA����߂č�����ѐ�����������̂ł��邱�Ƃ����킩�肢��������ł��낤�B���������Ǝ��̎�@�́AABCT�̘g�g�ɓ��v�I�~�N���o�ϊw�Ƃ������e�荞��ŁA���ł�30 ��O���Ɋm������Ă���̂ł������i����2013 a�j�B������A�ނ͍������Z��@�̋K�͂ɋ����Ȃ�����A����ł͎��̏グ�g�ւ̈ڍs������ɓ����ÂɎ~�߂Ă���̂ł���B
�@�@�@��3 �}�����̕��݁i�I�l�j
|
���U. 2 ���X�N�Ǘ��p���_�C��
���Q�́A�����N�����Ă�����_�I�ϓ_����捹�������B�������A�d�v�Ȃ̂͌������͂ł���B�����Ɋ�}�̎��ԂɂȂ��Ă��悤�ƁA���邢�͊�}�̎��ԂɂȂ��Ă���قǁA�I���Ɍ����Ă������ɑk�s���邱�Ƃ���Ȃ̂ł���B�������̐����Ă��錻��o�ς́A���J�l�ȊO�̈�ʏ����ɂ��Ă͊�{�I�ɓƐ��ǐ�𐧌����悤�Ƃ���̂ɁA���J�l�Ɋւ��Ă͓Ɛ������^��Ȃ��V�X�e���ł���B���̂悤�ȑ̐��̂��ƂŃo�u��������悤�Ƃ��邱�Ǝ��̂��A�y�䖳���Șb�ł���B����o�ς͂��������o�u�����Y�I�ł���B������A�O���[���X�p�����u�O���[���X�p�������v�Ɩ������ꂽ���X�N�Ǘ��@�̕K�v��������̂͂����Ƃ��ł���B�������A����̓o�u�������ɂ�����ߓx�̗������̌p���Ȃǂ��܂ނ��̂ł͂Ȃ��B���ہA1987 �N�̃o�u������̂Ƃ��A�ނ͒���ɂ͋��Z�@�ւ�ی삷��[�u����������̂́A����ɗ��グ�ɓ]�����B�Ƃ��낪�A2000 �N��IT �o�u�������́A�ނ͗������ɓ]����B���̗��R���u���Z����ɂ����郊�X�N�ƕs�m�����v�Ɏ������B
�O���[���X�p���̍l���ł́A1994 �N����܂łɃC���t�����͂����X�ɍ��܂�A�\�h�I�Ȉ������ߍ��������B���̌��ʁA1995 �N�ɖc���͎~�݁A����ɐ�������B�Ƃ��낪�A���̐������̂����̖��B����́A�i�C�z�̔g���������Ȃ�A���������肷����ƂŁA���X�N�v���~�A�����ቺ�������Ƃł������B���ہA���̎����ɍ��̗����͏��X�ɒቺ���Ă���B1999 �N����͂�����x�\�h�I���グ�����݁A�������ă{���J�[�ȗ��̎��݂�����t�����B�C���t������̂����ɓE�ݎ�鎎�݂����������͖̂������������A���ꂪ�����̏㏸�������炵���B�����ɁA�����̓��v�ɂ͂Ȃ��Ȃ��\��Ȃ��������A���Y�����}�㏸���Ď��v���҂����܂������Ƃ������㏸�Ɋ�^�����B���̂悤�Ȏ��Ԃւ̑Ώ��@���l���邽�߂̎Q�l��Ƃ��Ă͓��{�����Ȃ��A���ǃo�u���Ƃ��̕���ɑΏ����鏀����i�߂邵���Ȃ������B
���������v��������グ�ɂ��������߂����Ă����1990 �N��㔼�̃o�u����h���悤�Ȓ������ł��A�o�ψ�����ێ��ł��Ă����Ƃ̍l���́A�ԈႢ�Ȃ����ł��B
�قƂ�Ǘ\���ł��Ȃ����ʂ��̂Ɏv�������������������đz�肳���o�u����}�����ނ̂ł͂Ȃ��A1999 �N���̋c��،��ŏq�ׂ��Ƃ���A�u���~�������̂��̂ƂȂ����炻���a�炰�A�ł��邱�ƂȂ玟�̖c���ւ̈ڍs��e�Ղɂ���v���Ƃ��������k�A�M�����l�͑I�����܂����B�iGreenspan 2004�j
�Ƃ��낪�A9/11 �Ƃ����v�������Ȃ��V���b�N���A�����J�o�ς��P���B�O���[���X�p���̎咘�w�g���̎���x�́A���ۉ�c�ŏo�����Ă����X�C�X����A���s�@�ł��̃j���[�X�������Ƃ�����ʂ���n�܂邪�A����͐Q���ɐ��������B���R�ł͂��낤���A�A�M�����͗������őΉ������B���̉�������5�� �߂��ɒB��������A���Ȃ�啝�Ȃ��̂ł������B2003 �N�ɂ́A1950 �N�㖖�ȗ���1�� �����ɒB�������A������O���[���X�p���́u���ɂȂ��U���I�v�iunusually aggressive�j�ƌĂ�ł���B���������w�i�ɂ́A�C���t�����҂����Ȃ菬�����Ƃ����ǂ݂��������B
�o�u���̏��U�A�O���V���b�N�������āA1980 �N��܂łɔ�ׂ�ƃ}�C���h�ȕs�������N���Ȃ����Ƃ��킩�����B�O���[�o�����̐i�W�Ōo�ς͖��\�L�̒i�K�ɒB���A���M�ɒl����_����l�������B�t�����N�E�i�C�g�́u���X�N�v�Ɓu�s�m�����v����ʂ������A���ۂɂ͖ڂ̑O�ɂ��関�m�̗v�f���ǂ���ɑ����邩���ʂ�����@�͑��݂��Ȃ��B
���E�����������Ƃ͕s�\�ł���B���ǁA�\�ȑΉ��Ƃ��ẮA�����Ƃ����Ƃ��ɍŌ�̑ݎ�@�\�����邱�Ƃ𒆐S�Ƃ��郊�X�N�Ǘ�������݂̂ł���B����́A���X�N��\�ߓǂݍ��݁A�ł��邱�ƂȂ琔�ʉ����Ă�����@�ł���B����́u�x�C�Y�^�ӎv����v�����p������@�ł���B
2003 �N�ɋ�����1�� �Ɉ����������̂́A�f�t�������̃��X�N�ɐ����������邽�߂ł������B�܂��f�t���͌���Ă��Ȃ���������A����͕s�m�������[���̐��E�łȂ�ɂ߂���������ƂȂ낤�B�������A������u���X�N�Ǘ��p���_�C���v���炷��ΐ����������B����A �͂悭�ړI��B�������Ă���邪�A�o�ς̐^�̍\�����ǂ݂ƈႦ�Ό������t���ʂ݁A����B �͂��܂�ړI��B�������Ă���Ȃ����A�o�ςɊւ���ǂ݂��O��Ă��傫�ȃV���b�N�������炳�Ȃ��B2003 �N�����A����������l�ʂ��ĘA�M������
���X�N�𐧌����鐭����̂����i�����炭B ��������Ƃ����Ӗ��j�B���X�N�Ǘ��p���_�C���Ƃ́A�v����Ƀo�W���b�g���莮�������u�Ō�̑ݎ�@�\�v�̔����ł���B
������s�Ƃ��Ă����������Z�̓����I�����ɂ������ܑΉ������@�́A��ʂ̗������𒍓����邱�Ƃł��������Ȃ킿�A1 ���I�ȏ�O�ɃC���O�����h��s�̂��������������������E�H���^�[�E�o�W���b�g�ɂ��ƁA�C���O�����h��s�͋��Q�̂Ƃ��ɂ͂���߂č����Łu�D�ǂȏ،��������Ă���҂ɂ͂��₭�A�����Ȃ��A���₷���v�ݕt������ׂ��Ȃ̂ł��B�����炭���ꂪ���������ɂȂ��ꂽ������s�̃��X�N�Ǘ�����̕\���ł��B�iibid.�j
�Ƃ��낪�A���̃��X�N�����܂��\������m���Ȏ�@�͑��݂��Ȃ����ƂɋC�Â��B����ɑ��郊�X�N�Ǘ��A�v���[�`��Nj����钆�ŁA��������ꂽ���̃��X�N�����m�M�������Đ��ʉ��ł��Ȃ��Ƃ��������ɒ��ʂ��܂����B�������A�����������X�N�ł���A���������Ȃ��Ƃ����̏d�v�Ȗʂł͉ߋ��Ɏ��Ă���Ƃ����O���F�߂�Ƃ��ɂ̂݁A��ʓI�Ȍ`�Ő��ʉ��ł���̂ł��B�iibid.�j
���̂��߁A������s�́A���X�N�����P�ł���ƐM���Ă��鐭������s���邱�Ƃ₵�Ȃ����Ƃ�I�ԁB���̈Ӗ��ŁA���E���ǂ��������Ɋւ��鉼�������ɁA���f�����āA�܂����w�I�������ŗ�邱�Ƃ͏��m�̏�ōs�ׂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����ɁA�������̌v�ʌo�ϊw�����\���̂قƂ�ǂ̊�b�ɂȂ�P���Ȑ��`���́A�K�Ȍo�ϓI�ώ@�����܂�͈͂̊O�ł͐��藧���Ȃ��Ƃ킩���Ă��܂��B�c�c���ہA�Y�o�ƃC���t���̃^�[�Q�b�g�����炩�̌`�Ŕz�u���Ă��ꂩ��̘����ɍ��킹�ăt�F�f�����E�t�@���h�E���[�g�����߂�Ƃ������[���́A����15 �N�قǂŎ����������Ă������Ƃ̑�G�c�ȗ֊s�𑨂�����̂Ɍ����܂��B�c�c����ǂ��A�ŋ߂̐���j�Ō���ꂽ�悤�Ȍ���I�ȃ|�C���g�i1987 �N�̊����s��̕���A1997�`98 �N�̊�@�A2001 �N9 ���̂��ƂɋN�����o�����j�ɂ����ẮA�P���ȃ��[���͐���̏���ⳂƂ��Ă������Ƃ��Ă��s�\���Ȃ̂ł��B�iibid.�j
���̎咣���e�C���[�ɑ���ᔻ���܂ނ��Ƃ́A���悻�������悤���Ȃ��B�������A���̃��X�N�Ǘ��@�Ɋ�Â����f�ɂ���Đ��N��ɐ��ݏo���ꂽ�A�����v���̂ق��d��Ȃ��̂ł��������߁A���̘_�_���e�C���[�ɂ���Ď��グ���A���̘_���ɔ��W����B�������A���̖��͂̂��Ɏ��グ�邱�Ƃɂ���B
|
���U. 3 �V�����[�f�B���K�[�̔L�̎��S
�M�҂̓O���[���X�p���̋��Z������uRGS�v�i�[�����{�ʐ��j�Ƃ��ē����Â������i����2012 b ; 2013 a�j�A�e�j���A�㔼�̃O���[���X�p���́A�����炭����uRGS �̏o���헪�v�̂悤�Ȃ��̂ɔY��ł����ɈႢ�Ȃ��B����͐搧�U���i�\�h�[�u�j���������ł���ꍇ�̕������ƂȂ�͓̂��R�����A���グ�ł���ꍇ�ł��炠����x���ƂȂ�B�啽���̂���́A���Y�����}�L�����̂ŕ�������̂��߂ɉݕ������𑝂₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�Ƃ�킯�A1990 �N��㔼�ɂ͂����ł������B�������A�K���ɂ����̐V�K�ݕ��������炵��IT �o�u���͑�K�͂ł͂Ȃ������B���̂��ߊy�σ��[�h�͍��ꂩ�畢��͂��Ȃ������B9/11 �͋��Ђł��������A���ǂ���ł���ꎞ�I�ł������B���̂��߈���͌p�����A����ɐV�K�ݕ��������Ă������B
RGS �̖{���ɂ��ččl���悤�B����Ӗ��ł���́A�M�p�c����K�x�ɗ}���A�s����������R�����ɋɗ͋ߎ�������Ƃ�������w�j�ł���B
�܂��A�ݕ������s�ꂪ���S�Ȏ��R�s��ł���u���W�Q�s��v��z�肷��B���R��s���Ȃ̂ŁA�ނ����s�͑��݂��Ȃ��B�����ԑI�D�����܂��Ă����Ƃ���ƁA����͏��������Ƃ������ƂƓ��`�ł��邩��A���~�������Ă����B�����Ȃ�ƁA���R�Ȃ�������ɏグ���͂�������B�܂�A����܂ł͒��������ɐ����Ă����ǂ��������X�Ɏ�܂��Ă����킯�����A���炭���Ԃ��o�߂���ƌ��������ɕω����邾�낤�B�������Ď��v���Ƌ������̖c���x�͊e���Ƃ��K���ɓ������A���R�s�ꂪ���̒����͂�����B���̒����́A���{�ʂ̎��R��s���̂��Ƃł͎s�ꂪ�����I�ɒS���ł��낤�B�Ƃ��낪�A�@�߉ݕ������̂�Ƃ��́A�u�ʉ��������߂悤�ƂƂ߂鐭�{���Ȃ��ƁA���{�ʐ������ʓI�ɂ�������Ƃ��ꂩ�����o���̂͂ƂĂ�����v���̂ƂȂ�B�����ŁA������s��������S�����������u�����ʂ����v�Ƃ���̂�RGS �ł���B�������A�ł͂ǂ�����Ĉ����ʂ������̂ł��낤���B���̖₢�ɑ���q���g�́u���ƌo�ϓI���R�v�ɂ��łɏ�����Ă���B���Ȃ킿�A���W�Q�s��ł͓����̎��v�����݂̒ቺ�����v����Ċe���R��s���o�c���f�Ƃ��ė��グ�����邱�Ƃōs����̂ł������B�������A�@�߉ݕ����̂��Ƃł͂���𒆉���s���P�Ƃő�s����ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��B�����āA�����������߂�~�N���I�����ł��銔�����Q�l�ɒ�����s��������s���Ƃ������H�ɂȂ�̂ł���B�s�ꂪ�������V�O�i�������Ƃɂ��A�����傫���ǂ�邱�Ƃ��Ȃ�����A���̕��j�ɂ���Ă����ނ˖��W�Q�s��̋����ł��鎩�R�������ߎ��ł���B���グ���Ȃ���ΐ����Ă����͂��̃o�u���͖��R�Ɂi�\�h�I�Ɂj�j�܂�A���{�\���̍������ƒ������͗}������B�M�����\�����O���[���X�p���̋��Z������قڂ��̂悤�Ȃ��̂Ɨ������Ă���iGarrison 2007�j�B
�Ƃ��낪�A�����ɂ͂����炭�@�߉ݕ������L�̂�����̖�肪���ށB����́A���R��s���ƈ���ĕ����������Ƃ邽�߂ɁA�M�p���z���c�����Ă���Ƃ������Ƃł���B���R��s���̂��Ƃł́A�������������i�c�������Ⴂ�j�قǕ����̕ϓ����͏������Ȃ�ƍl������B���ꂪ�O���[���X�p���̂������n��I�Ȋe�������v�]�������́u�ϐ��v�ibalance�j�ł���iGreenspan 1986�A 104�G�M��118�j�B����́A�i�C�z�̔g���̍ŏ��������Ӗ�����B�������A����ł͕�������_�Ƃ����������ȐM�̂悤�ȋc�_������̊�{�I�ȑO��n��̕M���ɐw����Ă���A������s���ɂ͎����I���Y�����̊g��y�[�X�ɍ��킹�ĉݕ��𒍓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������A�����Ɏ��R������^���Ă݂Ă��A�V�K�����ݕ��̎��Y�s��ւ̉���Ƃ����A���R��s���̂��Ƃł͂��܂�l���Ȃ��Ă悢���ɕs��I�Ɍ����������ƂɂȂ�B�������A�����̍\���v�f�ɂ̓C���t�����҂��A���������ă��X�N�v���~�A�����܂܂�A����͏��o�ϓI�v���݂̂ŕϓ�����킯�ł͂Ȃ��B���������̕s����̓A�����J�̂悤�Ȑ�i���ł͍������������ł͂Ȃ����A�O���[�o�������i�W���������̏ł́A�����̐����s���̐�����Ă��܂��B������A���R�����ւ̋ߎ�����͂����낤���o�����X�̏�ɗ����čs����ق��͂Ȃ��B���������u���ɂȂ��U���I�v�ɂ��ׂ��ł���Ƃ����|�X�g9/11 �̌��f�́A���̃o�����X������Ă��܂����u�Ԃ������̂ł͂Ȃ��낤���B
�����l���Ă���ƁA�u�����Ȃ��M���v�u���̃e�[�}�ɍĂѕ����߂邱�ƂɋC�Â��B���R�����Ƃ́A��`�ɂ���Ē�����s�̑��݂��Ȃ���s�V�X�e���̂��Ƃʼnݕ��̎����W�݂̂����܂鐅���̋����̂��Ƃł���B������A������s��������莩�R�����͌����I�ɒm��悤���Ȃ� �B������s���u�K���ȁv������������낤�Ƃ��ăe�C���[�����ɏ]���Ă��A�����̎w��������������R�����ł��邱�Ƃ͒N���ؖ��ł��Ȃ��B
�ʎq�͊w�ɂ́u�V�����[�f�B���K�[�̔L�v�Ƃ����L���ȃp���h�N�X������B���̒��ɐ������L�����A���ː�����������˔\���o��ƃn���}�[���쓮���Đ_�J������ꂽ�r������A�L�����ʂ悤�Ȏd�|��������A�L�̗l�q���u�ώ@�v���悤�Ɠd���g�Ă�ƁA���̍s���̂��L���E���Ă��܂��Ƃ����̂ł���B�������\������f�q�̐U������m��̂ɓd���g���Ǝ˂���ƁA���Y����������ɂ���Ċ����Č��̏�Ԃ������A�����̎��R�ȏ�Ԃ͌����I�Ɋώ@�ł��Ȃ��B���̘_���ł́u�ώ@�v�Ƃ����s�ׂ�����ɑ�������B���R�����Ƃ͂���Ε��C���ꂽ��Ԃł̋����̐U�����ł���A������u�����v���悤�Ƃ����Ӑ}�����낤���Ȃ��낤���A������s�������s��ɉ�����Ă��܂����Ƃ��̂��̂ɂ���āA�s��I�K�R�I�ɂ���������֒ǂ�����Ă��܂��̂ł���B
20 ���I���̃A�����J�ɁA���j��O�Ⴊ�Ȃ��قǂ̎�r�����ߎ��̖��肪�����B���E�̎�s�ł��铇�ɐ��܂�A���E�Ő�[�̎��{��`�����̐^���������Ōċz���đ�l�ɂȂ����B���R��������傫�����炵�Ă�������܂ł̋c���Ƃ͑ł��ĕς���āA�ނ͋ߎ��̃v���ł������B����ǂ��A21 ���I�������Ă��炵�炭����ƁA�苖�������Ă��܂����B�v������肷�邱�Ƃ́A���ǕM�Ҏ��g���܂߂ĒN�����R������m�肦�Ȃ��ȏ�A���s�s�\�Əq�ׂ�ق��Ȃ����A���ʂ���k�y����ߎ����삪���Ȃ莸�s�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�V�����[�f�B���K�[�̔L�͎���ł��܂����̂ł���B�O���[���X�p�����g�A�u��@�v�̒��Ŏ����̋P�������ߋ��̎��т���ڂ��āA����Â��������Ă���ƌ�����ӏ�������B�u��@�v�̒��́u����͖h�������v�Ƒ肷��߂ł���B
�O���[�o���ȋ��Z�s�����������ł���������͖h�����ł��낤���B���Z����@�ւ̎��{���s�K�Ȃ܂łɒႭ�i�ߏ�ȃ��o���b�W������j�A20 �N�ɂ킽����ۑO��̂Ȃ��ɉh�A�Ⴂ�C���t���A�Ⴂ����������������Ƃł́A���͂���߂ċ^�킵���Ǝv���B���������o�Ϗ������́A�����R���̎��Y�o�u���̕K�v�����ł���A�����炭�͏\�������ł�����B�m���ɁA������s�̓o�u���I�Ȏ��Y���i���x����L���b�V���t���[�̉肪�����ł��������炻�̔w����܂�\�͂������A����͂قڊm���Ɍo�ς̎Y�o�����������k������Ƃ����]�������߁A�m���ɂ͂킩��Ȃ��A�����B�c�c
�������A�����߂͕K�v�ł͂Ȃ��̂��B���̒m�����A�ɉh�ɐ����������Ƀo�u�����U�炷�����߂����܂�������������͑��݂��Ȃ��B������s�����܂������߂��s���ăo�u�������X�ɎU�炷�ɂ́A�Z���̃t�B�[�h�o�b�N�I�������K�v�ł���B�������A�����1 �N����2 �N�ɂ��킽�钷���I�ŕϓ����܂ޒx�����Čo�ςɉe�����y�ڂ��B���X�Ɉ����߂����߂Ă����Ƃ��A���K�v�Ƃ���y�[�X�Ōo�ςɉe����^���Ă��邱�Ƃ��A�Ⴆ�ǂ̂悤�ɂ���FOMC �����A���^�C���Œm��Ƃ����̂��B�o�ς�s��ɂ��邱�ƂȂ��o�u�����U�炷�ɂ́A�O�����Ăǂꂭ�炢�����߂��s��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂��B�������A���d�v�ȓ_�ɂȂ邪�A�A�M�����̈����߂����X�N����i�ƒ��������j��啝�Ɉ����グ�邩�A���ƂȂ鎑�Y���i���x����L���b�V���t���[��������x�Ɍo�ς�s��ɂ��邩���Ȃ�����A�����̖]�݂͂قƂ�ǂȂ��Ǝv���B�iGreenspan 2010�A 44−45�j
���|�I�ȕ���ڂ̑O�ɂ��āA���������̈����������Ă��܂������Ƃ��ǂ����ňӎ����Ȃ���A����ł����ɕ��@�͂Ȃ������Əq�ׂĂ���̂ł���B�������A������@�ɃO���[���X�p���͉ߋ��̐���ɂ��Ă������I�ɃR�����g���n�߂��͗l�ł���B�A�M�����̈����߂̎��݂Ŏ��s�������̂������B1994 �N�̏��߁A�����C���t�����͂���������Ɗ����Ă����B���̖��ɒ��ʂ��āA300 �x�[�V�X�|�C���g�̈����߂ɒ��肵���B�c�c
�������́A1993 �N�ɂ͖��炩�ɂȂ��Ă����G���Ԃ̃o�u�����U�炷�̂Ɏ��s���������łȂ��A�����炭��������߂Ă��܂����B�o�ς�1994 �N�̌��������Z�����߂�ς����������Ƃ́A���܂�������D�����s��̗\����苭�����Ƃ��v�������������Ă����B�����āA���̌��ʁA�_�E�W���[���Y�H�Ɗ����ς̋ύt�����������グ���B���ꂪ�������̂́A1994 �N�̑}�b���͂邩�ɋ��������߂�2000 �N�̈����߂��s���Ă���A�o�u���ׂ����ł��Ă������낤�Ƃ������Ƃł���B2000�N���ɍs����6.5�� ���͂邩�ɍ���FF ���[�g���K�v�������̂��B
�ǂ�ȃo�u���ł����Z�������ׂ���������ǂ����ɂ���B6.5�� �ő���Ȃ���A���̂Ƃ���20�� ��50�� �ɂ��Ă݂邱�Ƃ��B�ǂ�ȃo�u���ł��ׂ��邪�A�ɉh�̏�Ԃ��K���]���ɂȂ�B2005 �N�ɘA�M�����̎������͍����𑨂��Ă����Z��o�u���̓��������čl�������ɂ��ĐS��Y�܂��Ă����B���N�Ɏ��͏q�ׂĂ���B�u�c�c���j�́A�Ⴂ���X�N�v���~�A���������Ƒ��������Ƃ̒u���y�Y��D���������Ă͂��܂���ł����v�B
����ǂ��A�����ɑ҂��Ă��郊�X�N�ɂ��ď\�������m�M�͌����ĂȂ������B�c�c1987 �N�̊����s��̕����h�b�g�R���E�u�[���̂Ƃ��ɂق�̂킸�������o�ςɕ��̉e�����Ȃ������Ƃ��������ŁA������ԂɊÂĂ����B���j������ƁA�Z��i��������Ƃ����炻��͂������ɂȂ邾�낤�ƐM���Ă����B�iibid.�A 46−47�j
���̂�����́A�����炭���Ȃ藦���ɖ{����f�I�������̂ł��낤�B�Ƃ�킯�A���]�݂Ȃ������50�� �ɂ��ł��A��������Ίm���Ƀo�u���ׂ͒��邾�낤�Ə�݂����镔���ɂ͎v�킸����ۂށB�ނ��A���ۂɂ���Ȃ��Ƃ�����Ίe���ʂ���O��I�ɒ@�����ł��낤�B�������A�ł�0 ����50 �܂ł̈�̂ǂ����K���Ȑ����ŁA��̂ǂ�����Ă����m��A��̂��ǂꂭ�炢�̏グ���ʼn���ɂ킽���Ă����Ɏ����Ă����悢�̂��B���������₢������ɔ�������B�ނ��A�N�������Ă���Ȃǂ��Ȃ��B�x���M�[�u�����v���N�������B�����ł́A�M�p��^�������Ă��^���Ȃ������Ă���肪�����邩��A������s�͂������̊Ԃɂ���͂��̓K���Ȑ�����T�������˂Ȃ�Ȃ��Əq�ׂ��Ă����̂ł������B�܂��u�����Ȃ��M���v�u�����v���N�������B�����ł́A��������ĕ��������肳�����܂ł͂������A���̂��Ǝ��̂��K�R�I�Ƀo�u�����ĂԂ��Ƃ��莮������A���A�����ł���̂ɒN��������킩���Ă���Ȃ����낤�A�Ƙ_�f���Ă���b���o���Ă����̂ł������B
����̊�@�̂��Ƃ̃o�[�i���L�̗����������ɂ��ẮA�o�ψ���Ɋ�^�������Ƃ͖������Ƃ��āA�O���[���X�p���͎��̂悤�ɂ��̐߂�����ł���B
�_�C�i�~�b�N�Ȏs��ƃ��o���b�W��������ĉ��炩�̌`�̏W���v������߂�Ƃ����Љ�I�ȑI�����Ȃ���Ȃ�����A�o�u���̖h�~�����ǎ��s�s�\���Ɣ�������̂ł͂Ȃ����Ɗ�ԂށB�o�u���̉e���̊ɘa���]�݂���ŗǂ̎����ł���Ǝv���B���ԃ��x���ł����{���x���ł��A����̓f�t���I�Ȋ�@�������炷������ꋫ�̒��x�����������邱�ƂɏW�����ׂ��ł���B�������A���o���b�W����邱�ƂŐ�����o�u�����o�ϐ����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����Ɍ��ʓI�ɎU�炷���@���A���{�̑啝�����ȊO�ɔ��������A����͎������̎s��o�ς�O�i�������ł̑傫�Ȉ���ɂȂ邾�낤�B�iibid.�A 47�j
����͖@�߉ݕ����܂��͒�����s���̂��Ƃł͕K�R�I�Ȍ��_�ł���A�n���Ƃ����f���ŌJ��L�����Ă���ߑ�Ƃ����s��s���œ����ӔC�҂����Ȃ��s��Ȏ����̒��Ől�ނ��ς�ł������܂��܂Ȍo���A����ъw�m���҂ݏo���Ă������܂��܂ȗ��_����w�ю��鎊��̒m�b�ł��낤�B
|
|
���V �ᔻ�Ɖ��� |
���V. 1 �I�[�X�g���A�w�h�̕]��
�����h�h�ł���A�O�ꂵ�����o�[�^���A���ł�����O���[���X�p�������A���������ƁA���̃��o�[�^���A���w�c����������̔ᔻ�����Ă���B����2013 a �Ŏ��グ���{�X�^�t��M�����\���͗�O�I�ł���A�����̏ꍇ�A�I�[�X�g���A�w�h������ᔻ���W�����Ă���ƌ����Ă悢�B�����ł́A���̂������̎�������グ�悤�B��1 �ɁA�����h�̃A�p�[�g�ŃO���[���X�p���Ɗ�����킹���\�����������X�o�[�h�ł���B�ނ�1995 �N�ɑ��E�������A1990 �N��Ɂw�o�ϊw�I�Ȍ����x�ŃO���[���X�p���ɂ��Ę_���Ă���B
���̓A������30 �N�O����m���Ă���A�ȗ������Ƌ����������Ĕނ̕��݂�ǂ��Ă����B�c�c�O���[���X�p�����{���ɓK�ނȂ̂́A�G�X�^�u���b�V�������g�̃{�[�g�������ėh���Ԃ�Ȃ��ƐM���ł��邩��ł���B�c�c�ނ͒��N���a�}�G�R�m�~�X�g�̑��̐l�����̑唼�Ɠ������ێ�I�ȃP�C���W�A���ł���A�����ł͖���}�w�c�̃��x�����h�P�C���W�A���ƂقƂ�nj����������Ȃ��B�iRothbard 2008�m1995�n�A339−340�j
���X�o�[�h�ɂ��ƁA�O���[���X�p���������h�h�Ȃ̂̓��j�[�N�����A����͓N�w�I�Ȗʂ����ŁA�u�v���O�}�e�e�B�X�g�v�ɖ���A�˂�ނ̓N�w�ƍs�ׂɂ͕s��v������B�b���킩��ɂ����̂��ނ����m�肾�Ƃ�����ۂݏo���Ă���A���ꂪ�������ďd��Ă���B���̋c�����o�ςɂ��čł����m��̐l�Ԃ������Ƃ͓���v���Ȃ��B�l����m���̎��̍�����FRB �̋c�����������s���ň�����鑶�݂ɂ��Ă�����̂łȂ��Ȃ�A�������������Ă���̂��B�G�h�����h�E�q�����[�����Ȃ��G�x���X�g�R�ɓo�邱�Ƃɂ������̂��q�˂�ꂽ�Ƃ��̓���������������Ȃ�A������FRB �̋c�������邩��ł���B�iibid. 342�j
�����A���X�o�[�h�̓O���[���X�p�����ł��ނ炵���d�������n�߂�����ɑ��E�����B��̃R�����g�́A���Ă̓��u�������h�h�̎v���`�����̂Ƃ͐����̐��E�Ŋ����邱�Ƃ����܂���ɕ��h�������̂ŁA���͓I�Ȑ[�݂ɂ͌�����B
��2 �ɁA�����������h�̂��Ƃɏo���肵�Ă��ăO���[���X�p����m���Ă��郌�C�X�}���̌��������悤�B�ނ̏ꍇ���ڍׂȃO���[���X�p���_�������Ă���킯�ł͂Ȃ����A�����h�ƃ~�[�[�X�̊ւ��ɂ��Ă̘_���Ō��y���Ă���B
���Ȃ�̔��f�ł́A�~�[�[�X����h�̒���́A���{��`��i�삷���œ������d�v�ł���B�~�[�[�X�����������Ȃ��ƁA�ŗǂł�F. A. �n�C�G�N�����K���l���ɂȂ����x�ł���B�����h�����������Ȃ��ƁA�ŗǂł��A�����E�O���[���X�p�������K���l���ɂȂ����x�ł���B�iReisman 2005�j
���{�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ����A�n�C�G�N�̓A�����J�̌���I�[�X�g���A�w�h�ɂƂ��Ă͂��ѐF�̈Ⴄ���݂ł���A���͂��̖{���Ɉʒu����l���Ƃ͑S�R�݂Ȃ���Ă��Ȃ��B��̔����͂��̎�����[�I�ɔ��f�������̂ł���B�����āA�ނ͂��̂�����Ɏ��̂悤�Ȓ������Ă���B
1957 �N�ȗ������悻15 �N�Ԃɂ킽���āA��ɋq�ώ�`�҂̂��܂��܂Ȍ𗬂̏�ŁA���͕p�ɂɃA�����E�O���[���X�p���ɉ���Ęb�������B���̑O�Ń~�[�[�X�̒����ǂ�Ŋw���Ƃ���������b�����ɂ������Ƃ͂Ȃ������B���̋C�Â�����ł́A�ނ̒��q��u��������������������͓����Ȃ��B1969 �N����T��1 ��A�ނ̉Ƃ��琔�}�C�������Ȃ��ꏊ�ōs���Ă���~�[�[�X�̑�w�@�[�~�ɏo�����Ƃ͂���Ǝv�����A�����1 ���ŁA�����h������o������ł���B�iibid.�j
���C�X�}���̏ꍇ���A���ږʎ������邽�߂ɐh���ł͂����Ă����͓I�ł͂Ȃ��R�����g�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���B�����A�~�[�[�X�̃[�~�ւ̏o�Ȃɂ��Ă͋c��،��Ŗ{�l���q�ׂ����Ƃƈ�v���邩��A���łɗ��j�I�ȏo�����ƂȂ����j���[���[�N�̃��o�[�^���A���E�R�l�N�V�����̈��i�𗠂Â���؋��Ƃ��Čf���Ă����B
��3 �ɁA�Z�N���X�g�̘_���u�A�����E�O���[���X�p�����������h�A���a�}�A�I�[�X�g���A�w�h�̔ᔻ�ҁv�����悤�B�ނ́A2000 �N����ɏ����ꂽ�O�̕]�`�����Ƃɓ��_���������Ă���B����́A���łɂӂꂽ�i����2012 b�j�E�b�h���[�h�A�}�[�e�B���A�^�b�V���̂��̂ł���B�ނ�̒���͖Ȗ��Ȓ����Ɋ�Â��Ă͂��邪�A�o�ϊw�̐��Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�O���[���X�p���̋��Z����ɂ��ė����𑣂����̂ł͂Ȃ��B�Z�N���X�g�͂��̓_���l������ABCT �̉���Ȃǂ����Ȃ���c�_��i�߂Ă���B���ڂ��ׂ�����������Ɉ������B
�I�[�X�g���A�w�h���w�E����Ƃ���A��x�����s�\�̖c�����Y�ݏo�����ƁA�u����v�Ȃ���̂͂��肦�Ȃ��B�듊�������������Ƃ��A�����Ă��̂Ƃ��ɂ̂݁A�o�ς͉���B����ɂ́A�����ς�l�דI�Ɉ���������ꂽ�����̂������Ŏ��v��������Ǝv�����v���W�F�N�g���ׂĂ𗬓�������K�v������B�����āA���̂��Ƃɂ͂��ꂪ���Y���z�̌����A���Ƃ̑�����A���Ȃ��Ƃ��ꎞ�I�ɂ͋��߂�B�iSechrest 2005�j
�����ABCT �̉���ł͂��邪�A�^���I�ɂ�����B���R��s�Ƃ̌����҂ł�����ނ́A����̖@�߉ݕ������u������s���v�i���ɂ���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ����������\���ł���j�ł���A���̂��Ƃł͐M�p�c�����n�܂�����Ō�A��x�ƌ�߂�ł��Ȃ��Ƃ����ϓ_�ɗ����Ă���B�������A���̍ۂɃ}�N���o�ςɂ��čׂ��Ȑ��I�c�_���ȗ����Ă���A�啽���������炵��RGS �ɏ\�����������̂Ƃ͌����Ȃ��ł��낤�B�������Q�Ǝw�W�ɂ��āu����v�炵�����̂����������͎̂����ł���B�ނ��A����𑱂��邱�Ƃ͌듊�����u�����v���邱�Ƃł͂Ȃ����炷���Ƃɂ������A�c�肾���ł��~�ς����ƌ��ǃo�u���������Ƃ����Ӗ����Ɖ��߂ł��Ȃ����Ȃ��B�Ƃ͂����A�ނ̋c�_�͂��������i�K�܂ł�z�肵�����̂Ƃ͎v���Ȃ��B
��4 �ɁA�J�[���\���̔ᔻ�����悤�B��@�コ�܂��܂Ȍ������͂��o�Ă������A�v���͕����I�ŁA���ł��嗬�h��IT �o�u�������̃O���[���X�p���̒�������d�������A�K���ɘa�̍s���߂��Ȃǂ��w�E����B�������A�����Ƃ���Ȃ����Z���i�����w�i�ɂ́A�ϔN�̐��{����̗��j������BGSE �͐��{�n�̏Z��Z���@�ւł��邵�A�܂��A�C���X�̃u���b�N�E�}���f�[�ȗ��̃O���[���X�p���ɂ��x�C���A�E�g���������n�U�[�h�������炵�Ă����B�Z��o�u����2001 �N�Ɏn�܂�AIT �o�u�������͕s���Ȃ̂ɏZ�����������n�߂��B�����2005 �N4 �l�����Ƀs�[�N���}���A�^�C�����O���l������Ƃقڗ�������}�l�[�T�v���C�����̓����Ő����ł���i��4 �}�A��5 �}�j�B
�@�@�@��4 �}�ݕ��W�v�l�̕���
�@�@�@��5 �}FF ���[�g�̕���
�܂��A1994 �N�̉��v�ŏ����a�����x�̑ΏۊO�ƂȂ钙�~�a����MMF �ɋ�s�����J�l���ڂ��A�v�������̂��߂Ɏ苖�ɒu���z���ŏ����ł���ٗʂ���s����ɂ����B�����a���͗��t�������ł͂Ȃ��A���̑[�u�ŋ�s�͑ݕt�̌����𑝂₹��悤�ɂȂ�A�܂��܂����o���b�W�����ɍs�����B�ߏ�Ɂu�M�p�n���v���s���ďł����Ă��A���ɂ͘A�M�������T���Ă��Ċm���Ƀx�C���A�E�g���Ă����B�������āA���Z�s���ɂ�����ߕی�ƌo�ϐ���ɂ�����Z��[���̗D���Ƃ����^�l�ɒ�����ɂ��ߏ藬�����Ƃ��������T����ăo�u�����ԊJ�����B�iKarlsson 2008�j
�J�[���\���͂܂��A�ʂ̊ϓ_������c�_��W�J���Ă���B�O���[���X�p���̘͐̂_���ŋ��{�ʐ��̃}�N�����艻��p��͐����AFRB �c���A�C���RGS ��ڎw�������A1987�N�̏A�C����2005 �N11 ���܂łɃx�[�X�}�l�[��235�� �������Ă���A�N��6.8�� �������������ƂɂȂ�BCPI �͓����Ԃ�174�� �㏸���A���~���������Ė��ԍ����c��B�܂��A�����̌��ۂ̗��ʂł����邪�A������u�O���[���X�p�������v�ōŌ�̑ݎ�@�\�����ł����������Ƃ̈��S�������Z�@�ւ̃�������ቺ�������_�͖��炩�ɋ��{�ʐ��ƑΏƓI�ł���B
�O���[���X�p�������炩�ɃI�[�X�g���A�o�ϊw�ɒʂ��Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�ނ͏��m�̏�ŕs�����Ȃ��Ƃ������ƌ��_����ȊO�Ȃ��BFRB �c���Ƃ��Ẵe�j���A�ɂ����āA�O���[���X�p���͎�����1966 �N�ɍU������������s�ƂƐ��m�ɓ����悤�ɐU�������B�O���[���X�p������̕s���̈�Y�́A���z�̕x�̖v���ƌo�ς̕s�ύt�ƂȂ邾�낤�B�����āA�����͂��ׂđ��l�̂����ɂ���邾�낤�B�iKarlsson 2005�j
�ނ��A���̌��_�́u���ƌo�ϓI���R�v��O�����̂ł���B���_���������Ƀ��o�[�^���A���̊ԂōL���ǂ܂�Ă��邩�Ƃ������Ƃ����߂Ďw�E���Ă��������B�����ɁA����̊�@�ł��������ꂽ�I�[�X�g���A�w�h�̎��ɓI�m�ȗ\���͂ɂ����߂Ē��ڂ𑣂��Ă��������B
��5 �ɁA�E�b�Y�̔ᔻ����������B��@���p�����Ɏ��R��`��K���ɘa�������Ƃ��čU�����錾�������o�������A�����͂��ׂēI�O��ł���B�ނ��됭�{���������@�̐^���ɂق��Ȃ�Ȃ��BGSE �����łȂ�CRA�iCommunity Reinvestment Act�F�n��Đ��@�j�ō��l���Z����܂ޒn��ɏd�_��������悤�ɗU�������̂����{�ł������BIMF�̋@�\�����A�d�ʼn��n�̋K�������A��Ƃ̏d���V�̍팸�Ȃǂ̑�͂��ׂĖ�D��ɂ������A����炪�t�����Ċ�@������ł���\���͂Ȃ��B2008 �N9 ���Ƀ��[�}���E�V���b�N���ĉ��@��ʉ߂����u�ً}�o�ψ��艻�@�v�̓u�b�V���̍Ō�̎d���ƂȂ������A����̓t�[�o�[�̉�����v���N��������B�I�o�}������������p���ł���A��吭�}���������I�ȋ@�\�������Ă���؋��ł���B
���ꂩ�猩�Ă������A�A�M�������x�̌o�ςւ̉�����o�u���Ƃ��̔j�z����\��������A����͕s���Ȃ̂ɂ���܂ł͔ɉh��搉̂����Ă����B���܂��Ď��R�s�ꂪ����̌����Ƃ��ċ��e�����B���V���g���ƘA�M�����̕����w�������ƍl���Ă݂�҂��炢�Ȃ��B���ꂪ����ƂȂ��Ď��Ԃ͔閧���ɐi�s����B�iWoods 2009�A 9�G�M��37�j
�o�u���ތ����͒�����s�ɂ��邪�A���ꂪ���_�ɒB�����Ƃ��̍��������Đl�X�����R�Ƃ��A�܂������������̂��̂����čĐ��Y���Ă��܂��̂ł���B�����āA���ꂪ�s����������B���̎��㏈���̂܂������A�u��s���v�̌����ł������B�����āA����̊�@�Ńo�[�i���L�����ȂɊ�Â��ē����Ȃ��ׂ��������ƐM���鎖�㏈�������Ă��邪�A�V���E�H�[�c�͂�������ƒf�����̂ł������i����2010�j�B�������̂��܂��x�z���闄��C���A������ؖ����Ă���B
�E�b�Y�ɂ��ƁA���̊�@�̌�����6 ���ڂ���B��1 �Ƀt�@�j�[���C�A�t���f�B�}�b�N�Ȃǂ�GSE �ł���B�����͎s��Ɉ�C����Ă���Ύ��v���̂Ȃ����ݏo���A����Ɏ������U���Ă����B�����������̂́AGSE �͑勰�Q�ւ̑Ή���Ƃ���1930�N��ɎY�����グ�����Ƃł���B�܂�A���{����돂�ɂȂ��ċ��Z�@�ւ�ی삷��쑗�D�c�����̃A�����J�łł���B��2 ��CRA �Ƙc�D�����x�ł���B��3 �ɐ��{�̏Z��[������̂��炵�Ȃ��ł���B����������ƁA�ݕt�̐R����͏��X�Ɋɘa����A���̌��ʍ������Ҍ����̏Z��[���ɂ��ߏ�ȐM�p�����^���ꂽ�i�����炭�]���ړ��Ă̍����Z��s��̔��B�̔w�i�j�B�������Ҍ����̃v���C���E���[���̕��������������ł̓T�u�v���C���E���[����菭�Ȃ����L�ї��ł͍��������B�܂��A�ϓ��������ʂ����������ɂ͒��ڂ��W�܂��Ă��邪�A���̓K�p���̓v���C���E���[���̕��ō��������B
��4 �ɏZ��擾�ɑ���D���Ő��ł���B�l�ސE���N�������401 k �͊����������㉟�����Ă��邪�A�Z��[���ւ̐ōT�����A�����J�l���Ȃ邾���ˌ��Z����悤�Ɏd�����Ă���B��5 �ɘA�M�����̒������ł���i����ɂ��Ă͌�q�j�B��6 �Ɂu�傫�����Ēׂ��Ȃ��v�iToo Big to Fail�j�Ƃ����_�b�ł���B�A�M�������������s��ɒ�������ƂƂ��ɁA��}�̂Ƃ��ɂ̓x�C���A�E�g���Ă����Ƃ������S�����u�O���[���X�p���E�v�b�g�v���A����͑���|�Y�����Ȃ�����V�X�e�~�b�N�E���X�N�͐����Ȃ��ƐM�����ގp���ƕ\����̂ł������B�iWoods 2009�A chapter 2�j
�E�b�Y�̔ᔻ�̖���͈ȏ�̎��O�I�ȑ��ʂ����łȂ��A����I���ʂ��܂߂āA���{�����ʂɌ������Ă���ichapter 3�j�B����̊�@�ł�5 �哊����s�����ׂď��ł��A�A�M�����̊ē��ɓ������B�����A���ꂪ�����I�Ȍ��ʂ����ƍl����̂͌��ł���B���̑[�u�͎����I�ɏ،���Ђɑ�������u������s�v�Ƃ����ƑԂ����Ƌ�s���݂ɘA�M�����ً̋}�Z��������悤�ɂ��������ł���B�E�H�[���X�̊�ł�����A�����ɂ��A�����J�I�ȓ�����s�Ƃ����ƑԂ��A���Y���̏㏸�Ƒ啽���̋������������㎑�{��`�ɂ���ē������ꂽ���Ƃ́A�Ռ��I�ȏo�����ł���B����́A�A�����J���Z�j��ł��ő勉�̒n���茻�ۂł���B�����āA����͂��Ƃ��Ɗe�ƊE�̒��ł��ڗ����ĎЉ��`�I�ȋ��Z�ƊE�����悢��Љ��`�����Ă��܂����B���̓_���l����ƁA�E�b�Y�̔ᔻ�͂��قǐh���Ȃ��̂ł��Ȃ��A�ނ���펯�I�Ȃ��̂��Ƃ������悤�B
�������ăI�[�X�g���A�w�h�̃O���[���X�p���_���T�ς��ċC�Â��̂́A���ꂪ���_�I�ɂ͐������Ƃ������Ƃł��邪�A�����ɔނ�̑唼���u�C���T�C�_�[�Ƃ��Ď��R�s�ꎑ�{��`�̔��W�ɐs�������v�ƌ��S�����O���[���X�p���̗���ɂقƂ�Ǘ������������A�����_�I�Ȋϓ_����ނ�RGS ���嗬�h�Ɉ�����̂��Ƃ��ďW���C�𗁂т��Ă���Ƃ�������B�O���[���X�p�������o�[�^���A���ł���ƌ����Ƃ��A�ނ�̊܈ӂ͋��܂��܂ށB�T�^�I�ȃ��o�[�^���A����������s�ɑ��Ď����p���́A�ŏI�I�ɂ͂����p�~���ׂ����Ƃ������̂ł���B����̋��Z������߂���c�_�̔w�i�ɂ͂������������̏o����s���ɂ��钆����s���L�̖�肪���邱�Ƃ��w�E�ł���B�o�ϗ��_�͂��܂��ɒ�����s���K�ɍ�p���Čo�ς����萬���������@���m���ł��Ă��Ȃ��̂ł���B����2012 b �łӂꂽ�p�[�N�X�̒���Ƀu���[�u�i�{�̗��\���̃R�����g�j����悤���߂�ꂽ�t���[�h�}���́A��������Ǝ��̂悤�ɕԎ����Ă���B
���̓u���[�u�������͂Ȃ��B�O���O��������B�iParks 2000�A iv ;blurb�j
���̊�e���ۂ̕ԓ������̂܂܃u���[�u�Ɍf�ڂ���Ă���̂ɂ͋�������邪�A������ɂ���A���̂悤�Ȑl�������㒆����s�Ɩ��̎w�j�ɂ��đ傫�ȉe���͂������Ă���̂ł���B
�O���[���X�p���́A�N���[�O�}����V���[�̂悤�ȑe�G�ȍ��h�����łȂ��E�h������p���`�𗁂ё����Ă���i�t���[�h�}���͏����j�B����Ӗ��ŁA�ނ�FOMC �̒������łȂ��A�����J�̌o�Ϙ_�d�S�̂̒��ł��Ǘ����Ă���B�������A�M�҂͂��̂��Ǝ��̂����A���ꂪ�����炷���ʂɂ��čl�@���Ă����B�ȉ��ł����̕��j���т��B |
���V. 2 �嗬�h�̕]��
��ɂӂꂽIT �o�u�������̗������ɑ���e�C���[�̔ᔻ�ɖ߂낤�B�_���̊T�v�́w���Z����̒E���x�iTaylor 2009�j�̖M��҂̉�����`���Ă��邪�A�e�C���[�̌������͂ƂĂ��킩��₷�����̂ŁA�v�_�͂������ꖇ�̐}�ŕ\���ł���B����́A2002�N���납���FF ���[�g������܂ł̃��[������啝�ɊO��Ă���A���������s���߂����Ƃ��Ƃ������}�ł���i��6 �}�j�B
�e�C���[��́u���[���v��1990 �N��O���܂ł̃O���[���X�p���̎��т��琄�v����Ă��邱�Ƃ͈ȑO�q�ׂ��i����2013 b�j�B�����A���̓_���l����ƁA���̔ᔻ�̈Ӗ��͕��G�ł���B�����Ă݂�A�e�C���[�̓O���[���X�p���̑O���e�j���A�ɂ���ăO���[���X�p���̌㔼�e�j���A��ᔻ���Ă��邱�ƂɂȂ邩��ł���B�܂�A�N���N��ᔻ���Ă���̂����琳���킩�肩�˂�̂ł���B�u�e�C���[�E���[���v�́u�O���[���X�p���O�����[���v�Ƃ��u�O���[���X�p�����ցv�ƌ��������Ă��悢�̂ɁA���������E�����㔼�̋���������u�ٗʁv�ł���Ɣᔻ����Ȃ�A�e�C���[�͂������đO���Ƀ��[�������������Ƃ�����F�߂錋�ʂɂ��Ȃ�B�O���ɂ����Ă͍ٗʂ������ʂ������A����ł����\�L�̑f���炵�����т��}�[�N�����̂ł��̔閧��T�낤�Ƃ����嗬�h�o�ϊw�҂��A��v�}�N���w�W�Ԃɂ��鑊�ւ����o���B�������ʘA�ւɂ͊S���������u���ʐ��Ȃ����ցv�̂܂܁A���̂��Ƃ����̑��ւɉ���������^�c������悤���߂�B�Ƃ��낪�A���ς�����Ƃ��ɐ�̑��ւ̑̌��҂́i�����҂ł͂Ȃ��j���ꂩ���E���鐭����Ƃ�n�߂�B������A���ւ̔����҂����̈�E���w�e����B���Ԃ͂��Ȃ蕡�G���Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@��6 �}FF ���[�g�̎��ےl�ƌ����l
����ǂ��A���_�̃v���Z�X�ɂ�����e�C���[�̍��[���_�������ɉ��ɖڂ��Ԃ�A���ʓI�ɂ��̔ᔻ�ɂ͈Ӗ�������B���������āA��ɂ݂��E�b�Y�̔ᔻ�ƌ��ʓI�ɂقƂ�Ǖς��Ȃ��Ƃ��l�����邩��ł���BIT �o�u�������łȂ�9/11 �Ȃǂ̔�o�ϓI�v������Ɏ����荇���ăf�t�����O���������Ƃ����̂͂����Ƃ��ł��낤���A�������͂��̗������̂����炵���A�����܂��܂��ƌ��������Ă���B�������Ȃ��T�u�v���C���E���[����@���˔��I�ɐ������ȂǂƂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���܂��ꂪ�ڂ̑O�ɐ������Ȃ�A�����͎��Y�s��ɉߏ�ȗ������𑗂荞�O���[���X�p���̐���ɋ��߂˂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
����ɂ��čl����O�ɁA�܂��e�C���[����̔ᔻ�ɑ���O���[���X�p���̔��ᔻ�����Ă������B����͐�ɂӂꂽ�_���u��@�v�ɏڂ����B�_�_�́A��ɎO�ɐ����ł���B
��1 �ɁA�e�C���[�E���[���̓C���t�����Ə���ҕ�����ϐ��ɗp���Ă��邪�A���Y���i�͍l�����Ă��炸�A���Z����̓K���ȕ��j�������Ă������̂ł͂Ȃ��B���́u�E���v���Ԃł���2002 �N����2005 �N�܂łɌ����l�ɋ߂������ɒZ���������グ��\�����������Ƃ���A����͏���ҕ����̃C���t�������O�����ꍇ�ł��邪�A�����̏ł͂��̌��O�͂Ȃ������B������A�����ǂ���̋����ɂ��Ă���ނ������ҕ����̕s���艻�������炷�V�O�i���M���邱�ƂɂȂ��Ă������낤�B�iGreenspan 2010�A42−43�j
��2 �ɁA�Z��[���̑g���ɂ�����Q�l�����́AFF ���[�g�₻��ɘA�������Z�������ł͂Ȃ����������ł���B���Y���i�͏����t���[���z�������Ŏ��{�Ҍ����������Ɏ��ʂ��邪�A���̍ۂ̋����Ƃ͓��R���������ł���B21 ���I���߂܂�FF ���[�g�ƏZ��[�������̑��ւ͍����������A2002 �N����ɂ͗��҂̃����N�͎����AFF ���[�g���Z��i�ɉe����^�����Ƃ͍l�����Ȃ��B�������͓��{����w��Ńf�t���ɔ�����ی��̂���ł������B�����āA���ꂪ��������������ƕ����C���t�����N��������A�p�����Ԃɂ����ӂ��Ă����B�iibid.�A 38−40�j
��3 �ɁA���یo�ϊw�҂ł�����e�C���[���O���[�o�����~�ߏ�������S�ɔے肵�Ă���_�ɑ���ᔻ�ł���B��Ɍ������̐��́A�����炭�O���[���X�p���������̒҂̈�l���Ǝv���邪�A�e�C���[�̓f�[�^�������Ȃ���A�A�����J�ȊO�̍��ł̒��~����͂��������A������A�����J�ł̌����ő��E����āA���E�S�̂ł͓����ƒ��~�̃M���b�v�����Ɋg�債�Ă͂��Ȃ������Əq�ׂ�iTaylor 2009�A 6−7�G�M��16−18�j�B����ɑ��ăO���[���X�p���́A�u�e�C���[�͎��O�I�ɒ��~�Ɠ����̊Ԃɂ���ٖ��Ȋ֘A��ނ���̂Ɏ���I�ȃf�[�^��p���Ă��邪�A�G�R�m�~�X�g�̑唼���˘f���͂��ł���v�Əq�ׂĂ���iGreenspan 2010�A 44�j�B�O���[���X�p�����g���ʂ̉ӏ��ŁA2007 �N�̃O���[�o���Ȓ��~�]�����䗦�͎���I�ɂ�1999 �N���킸���ɏオ���������ŁA��i���Ɠr�㍑�ł荇����������X�������邱�Ƃ��w�E���Ă��邪�iibid.�A 5�j�A�ᔻ�̈Ӑ}�͂킩��₷���͂Ȃ��B�@����ɁA����͒��~�������Ă������ł͓����ւ̈ӗ~�����܂�A�����Ȃ�Ɠ����������Ă����̂ŁA����I�ɂ͗��҂̊J�����傫���Ƃ����f�[�^�͏o�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ���ł��낤���B
�����̔��_�ɃR�����g���Ă������B��1 �̔��_�ɂ��ẮA��Ɂu���ɂȂ��U���I�v�Ǝ��獐�����Ă��鐭�A����B �^�C�v�ł͂Ȃ�A �^�C�v�������ƌ����ׂ��ł��낤�B����͑�2 �̔ᔻ�Ƃ��֘A����B���̔ᔻ�͈ꌩ��Â����A�悭�l����Ƃ����ł��Ȃ��B�Z������������������Ƃ��ɘA�M�����͍��s��Ŕ����I�y���s���Ă���A����͎s����s�̏����a���ɏ�����ςݑ������ƂɂȂ邩��A��s�͂����ƃ��o���b�W������悤�ɂȂ�B�܂�A�M�p�搔�ɂ���ĐM�p�c���������N�����A���ʓI�ɒ������������������邱�Ƃ͔������Ȃ����낤�iReisman 2009�j�B�Z��[���g���̍ۂ̎Q�l�����ɒ��ڂ�����c�_�͖��̊j�S���璍�ӂ����炷���̂ł����Ȃ��B��3 �̔��_�ɂ��ẮA���łɏq�ׂ��M�҂̏�����������܂�Ӗ��̂�����̂Ƃ͎v���Ȃ��B
�ȑO�A�n�[�o�[�h��w�P�l�f�B�E�X�N�[���ł̌�����Ń}���L���[�������啽�����͂����グ���i����2013 b�j�B�O���[���X�p���ɂ��Ă̔ނ̊�@��̌����́A�_���u��@�v�ɑ���R�����g������킩�邪�A���̑O�ɏ�̕Ŕނ��_�����Ƃ����d�v�_�_���w�E���Ă����B����́A1990 �N��㔼�Ƀ}�l�[�T�v���C���}�����Ă���Ƃ����_�ł���i��4 �}�j�B�������A���ꂪ�������Ԃɐ����������̋}���̗v���ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���i��3 �}�j�B10 �N�P�ʂ̕��ϒl�ƕϓ��̌����ł́A1990 �N�オ�����Ɋւ��Ă������ƈ�������Ă����Ƃ����̂��ނ̌��_�ł��������A�L���l�����Y�t���Ă���͂��́u�h�b�g�R���E�u�[���v�Ɋւ��ď\���ȗ������������̂Ƃ͎v���Ȃ��B���̃u�[���Ƃ́A���Y���̋}�L�ɂ�������炸�啽�����ێ�������قǂ̉ݕ������̋A���ł��邱�Ƃ��ʼn߂���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����s�ꂪ�}�N���o�ς̕ω��̑O���ƂȂ�ɂ�����Z����̕������Ƃ͖��W���Ƃ̈���I�Ș_�f�́A�O���[���X�p���ɑ���ނ̊�{�I�ȔF���s����������B���̗��R�͈ȏ�̏��q�ɂ���Ă��܂�ɖ��炩�Ȃ̂ł����J��Ԃ��Ȃ����AFRB �����ł������������[�C���O���[���X�p�����璼�ڕ�������������ɂ���ĕ⑫���Ă������B
�k���܂́l1920 �N��㔼�Ƃ�����_�Ŏ��Ă��܂��B�������A1929 �N����1932�N�̊��ԂƂ̗ގ����ɂ����������ӂ��Ȃ�������܂���B���́A����1930 �N��1931 �N�ɕʂ̑Ή�������Ă�����A���������̑傫���̌i�C��ނ͂������ɂ���u�勰�Q�v�ƌĂ��[�����͌o�����Ȃ��������낤�Ƃ������Ƃł��B�iLindsey1999�A 36�G�M��59−60�j
�O���[���X�p�����啽���̂��Ȃ���1929 �N�̃N���b�V���̍ė���^���ɋ���Ă��邱�Ƃ��͂�����킩��B�܂��A�t�[�o�[�̕����E�����������s���i����ǂ���j�̌����ƌ��Ă�����B�����[�C�̓O���[���X�p�����u�t���艮�v�icontrarian�j�ƌĂ�ł���B����́A���Ԃ̒ʔO�Ƃ͐����̍s�ׂ�I������l���Ƃ����Ӗ��ł���B�ނ̐����ɏ��������X���Ă������B
�ωׂ��s�����Ă���ݕ��ԗ������邩�S�|�C���S�b�g�k����l���Y���}�����n�߂���A�Ɛl�Ƃ��čł��\���������͔̂���̕s���ł���B���ꂪ�o�ϑS�̂Ɍ�����Ǝv������A������͏���҂������Ɣ����A��Ƃ������Ɛݔ��������s�����߂̎h���Ƃ��ė��������s���B�����A�ωׂŖ������ꂽ�ݕ��ԗ����ƂĂ������Ȃ��ĉ^�����オ��n�߂邩�S�|�C���S�b�g��Ђ��㓾�ӂɂ����[�i���Ȃ��Ȃ�ƁA�t���艮�͂킸���ɗ��グ���n�߂�B
�����������������Đ����Ή�������̂��A�A�M����������̓��핗�i�ł���B�����A�O���[���X�p���͋}���Ȍo�ϐ����Ɓu�ߑ�ȁv���v����ʂ���̂ɍאS�̒��ӂ��B�u��{�I�ɂ́A�����o�ς͂��܂̂Ƃ���ƂĂ������y�[�X�Ŋg�債�Ă��܂��B�ł����A�����������ӂ��ׂ��Ȃ̂́A�o�ϓ����Ŗc��݂�����I�s�ύt�ł���A���̒���̓C���t���ł��v�B�O���[���X�p���́u1920 �N��㔼�Ƃ�����_�Ŏ��Ă��܂��v�Ƃ������������ł�����m��Ȃ��B�ނ͌��S�Ȍo�ςƃC���t���I�Ȍo�ς���ʂ��Ă��邪�A����������ł���B���̗��R�́A�����̊ώ@�ҁi�O���[���X�p�����܂ށj���N�����Ă���ƍl���Ă���̂��A�o�ς̌���͓`���I�ȃP�C���Y�h�̌������v�̒��߂�s���ɂ��i�C�z�ł͂Ȃ��A�����哱�^�̌i�C�z������ł���B�c�c�����哱�^�̌i�C�z�̓����́A�}���Ȑ����A�����̈���܂��͉����A������ȂNj��Z���Y�����M����s��ł���B�o�ώj�Ƃ̑����́A1920 �N��㔼�̓W�J���D�܂��������V���b�N�Ɉ�������ꂽ����̂�����̗Ⴞ�����Ǝw�E����B�iibid.�A 36−37�G�M��60−61�j
�ӂ��V���g���̃I�t�B�X�ŃO���[���X�p�������ɂ��Ă���f�B�e�[���̈Ӗ��������[�C���ǂ��܂ŗ����ł��Ă��邩�A�O���[���X�p����1990 �N���1920 �N��Ɣ�ׂ悤�Ƃ��闝�R���ǂ̒��x�@�m�ł��Ă��邩�͓ǎ҂̔��f�Ɉς˂�ق��Ȃ��B�����炭���̑��吨�̃G�R�m�~�X�g�̌�����͂܂���������\���̂Ȃ����t��ނ���������Ă��邱�Ƃ͎��������A���̐����̓v���̃G�R�m�~�X�g�ɂ����̂Ƃ��ĉ��Ƃ��㑫�炸�ł͂Ȃ��낤���B����ł��A�}���L���[�ɔ�ׂ�Ƃ܂������ł��Ă���悤�Ɍ�����̂́A�c���Ɠ��Ȃ������Ԃ��ނ�蒷�����������ł��낤���B
���̃}���L���[���O���[���X�p���Ɠ��Ȃ������Ƃ�����B�ނ́A2010 �N3 ���ɍs��ꂽ�u���b�L���O�Y�������̏W�܂�ŃO���[���X�p������L�u��@�v������ۂɓ��_�҂߂��B�����āA���̂Ƃ��̏����N3 ��19 ���̃u���O�Ō��\���Ă���̂ł���B
����͈̑�Ș_���ł���B�ߋ����N�ɐ������߂��̕�I�Ȍ��Ƃ��āA�����ǂ��ł��ŗǂ̈�ł���B�ߔN�̋��Z��@�ɂ��Ď����̊w���ɘ_������������{�����ǂނƂ����h����o��������A�����I�Ԃ̂��������낤�B�iMankiw2010�j
���̂悤�Ȏ^���Ŏn�܂�L���́A�܂����ӂł���_�������Ă���B��́u�ÓT�I�ȓ����^�o�u���v�Ƃ����`�ʂł���A������͏Z���Ȃǂ̐����v���Z�X�����X�N�������グ�Ă��܂��Ƃ����咣�ł���B�^���悵�Ă���̂́A���Z����ɂ����郌�o���b�W�̖��ł���B�O���[���X�p���̓��o���b�W�̒ጸ������Ă��邪�A�}���L���[�́u�قƂ�ǃ��o���b�W�����Ȃ���s�Ȃ���̂��v�������ׂ�͕̂s�\���Ǝv���v�ƌ����B�Ƃ��낪�A������u�i���[�o���N���v�����������ɏo���Ď��̂悤�ɏq�ׂ�̂ł���B
���̂悤�Ȍ��i�ȋK���̂��Ƃʼnc�Ƃ����s�V�X�e���Ƃ������̂��A���Z����Ƃ����d��Ȍo�ϋ@�\���\���ʂ�����悤�Ɏv����B���o���b�W�Ȃǂ͕K�v�Ȃ��̂ł���B
���������V�X�e�����̂�Ȃ�������̂̈���A���܂̋��Z�V�X�e�������u�����]���v�@�\�ł���B���Ȃ킿�A�����̋�s����Z�@�ւ͂��܁A�Z���Ŏ�Ē����ő݂��Ă���B�������܊i�����Ă���̂́A���̖����]���������ɋ@�\������Z�V�X�e���ɂƂ��ďd��ȓ����ł���̂��ǂ����ł���B�����̂��ꂪ���ʓI�ɏo�Ă��邪�A���ꂪ��s���Q����Z��@�̒��S�I�v�f�ł���Ǝv����B���̓��̒��ł܂��������o�Ă��Ȃ��₢�����A���܂̍������o���b�W�������Z�V�X�e���̉��l�͉��ŁA���̗��_�͂��܂�ɂ������Ȃ��̃R�X�g������̂��ǂ����ł���B�iibid.�j
�������āA���Ȃ�قȂ郋�[�g�����ǂ��Ă͂��邪�A����̎嗬�h�o�ϊw�҂̓I�[�X�g���A�w�h�ƂقƂ�Ǔ������_�ɂ��ǂ蒅���Ă��邱�ƂɋC�Â��B�ނ��A����̓O���[���X�p���̒�ĂɐG������Ă̂��̂ł���A�ނ��u�B��I�[�X�g���A�w�h�v�ł��邱�Ƃ��傫�ȗv���ł͂��낤���A�嗬�h�̋c�_�̓W�J�@�̓I�[�X�g���A�w�h�̂���߂ē���I�ȉ�㈑̌n�ɔ�ׂ�Ɗw�m�Ƃ��Ă͖��x�Ƌ��x�ŗ��悤�Ɏv�����A����ł����_�����Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl����ł��낤�B���������A�e�C���[�́w�E���x�̕���u���{�̓��������Ɖ���������ɋ��Z��@�������N�����A���������A�������������v�́A�E�b�Y�́w�����g�_�E���x�̕���u�Ȃ������s�ꂪ���A�o�ς͑�A���{�̃x�C���A�E�g�͎��Ԃ����������邩�Ɋւ��鎩�R�s��h�̌����v�Ƃ��Ȃ莗�Ă��邱�ƂɋC�Â��B���̂��Ƃ́A�w�h�Ԃ̑Θb�̕K�v���������Ă���悤�Ɏv����B
|
���V. 3 �u���v�����ƌ��f��p
���Q�̌����͂��łɃ~�[�[�X�ɂ���đg�D�I�ɉ𖾂���Ă��邪�A�ގ��g���o�u�������邩�\���ł���\���͂Ȃ��ƔF�߂Ă���B�O���[���X�p�����~�[�[�X�́w�q���[�}���E�A�N�V�����x��ǂ�ł��邱�Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ����A��@��̏����ł��A�o�u���͂��̐i�s���ɂ͌��o������A�܂��Ă��ꂪ���ǂ�Ȍ`�Ŕj�邩��̓I�ɒm����@�͂Ȃ����Ƃ��������Ă���B�����A�t�Ɍ����A�Z�N���X�g��J�[���\���Ɠ������A������o�u�����͂����邱�Ƃ��d�X���m���Ă��邩��A���肵�ă��X�N�Ǘ��p���_�C�����Ƃ����Ƃ�������B���̂��߁A�O���[���X�p����9/11 ��ɒ��������Ƃ����Ƃ��ɁA���㏈���@�����łȂ�����ٖ��̗��_���\�z���n�߂��ƍl������B
�u�����Ȃ��M���v�u���Ɍ�������ނ́u�\�h�I�ipreemptive�j���グ�v�́u�������œ������g����v�悤�ȁu�搧�U���v�ipreemptive strike�j�ł��邱�Ƃ��������Ă����̂ł������i����2013 b�j�B������Q�l�ɍl����ƁA��Ȃ����̓_�ɋC�Â��B���Ȃ킿�AABCT������������s�̉ߓx�̗������Ƃ́A�����ݕ������s��Ƀ��b�Z�t�F�[������������Ă���Ό���ꂽ�ł��낤���R���������Ⴂ���������𒆉���s���ݒ肷��Ƃ����등�̈����ł��邩��A����͂��Ƃ��Ɓu�\�h�I�������v�Ƃ��\���ł�����̂ł���B����6�� ���錳�̐������ێ����Ă���ΐ������ł��낤�i�C�����h�����߂ɗ����������悤�Ƃ����̂��O���[���X�p���̈Ӑ}�ł������B���ꂪ���R�����܂łɂƂǂ܂��Ă���������ɏI��肦���\�������邪�A�ŏI�I�ɂ��ꂪ���R����������������Ƃ͌��ʂ��猩�Ă��܂����Ȃ��B�i�C����͔��������̂ŗ��������������B�������A�ǂꂭ�炢�̊��Ԃɂ킽���Ăǂ̒��x������悢�̂��B���̖��ɑ���m���铚������@�͂Ȃ�����A�s��̔��������Ȃ����T��Ői�߂Ă����ȊO�ɂȂ��B���s�����Ƃ��̂��߂ɍl��������łK�v�͂��邪�A������������̂��߂̗��_��p�ӂ��邱�Ƃ���ɂȂ�B
�����炭���������l���̂��Ƃɔނ������o�����̂��A��@�̔��������A�M�������Ƃ�����������ڂ����炳����e��̐��ł������Ǝv����B��\�I�Ȃ��̂́A��ɂӂꂽ�O���[�o�����~�ߏ���ƁA���ꂩ��u���v�����ōL���m����悤�ɂȂ������������̓���s�\���_�ł���B�O�҂ɂ��ẮA�e�C���[�̔ᔻ��{�e�ł̕M�҂̋c�_�������������ł��邪�A��҂ɂ��Ă͐^�Ɏ�҂��ӊO�Ƒ����B�����ŁA���̔����̔w�i�Ɩ��_�����āA���ꂪ���f��p�̈�ɂ����Ȃ����Ƃ�_���悤�B
�u���v�Ƃ́A�O���[�o���ȃf�B�X�C���t�����͂̂��߂ɒZ�������ł���FF ���[�g���㉺�����Ă������������A�����Ȃ��Ȃ������ۂ��w���B�����肪�\���ɍs���Ă�����Z�s��ł͒��Z�����͎��ʂ���X���ɂ���B�����������Z���������啝�ɍ�����A�Z���̎�Ȃ��ō������������̎x��������铮���������A�Z�����v�������Ē������v�͌��邩��A���Z�����͎��ʂ���B�t�ɑ啝�ɒႯ��ΒZ�������ւ̎��v�͌����Ē��������ւ̎��v�����܂邩�痼�҂͎��ʂ���B�Ƃ��낪�A�A�M������FF ���[�g���グ�Ă������������オ��Ȃ��Ƃ����킯�ł���B���̌��ۂ��uconundrum�v�Ȃ�g�p�p�x�̒Ⴂ��b�ŕ\�������_�������ɂ��O���[���X�p���炵���B����́u��v�Ƃ����g�p�p�x�̍�����b�Ŗ�邪�iAOT �����A��20 �́j�A����ł͔����̐^�ӂ͓`���ɂ������낤�B�����Ŗ{�e�ł͂�����u���v�ƖB�O���[���X�p����2005 �N�~�̃n���t���[�]�z�[�L���Y�@�،��ł��̌��p���Ă���B
���̏̒��Œ��������͂����������ቺ�X���ɂ���A�A�M������FF ���[�g�̖ڕW�l�̐�����150 �x�[�V�X�|�C���g�グ�Ă������ł����B�c�c�\�A����ƒ�����C���h�̃O���[�o���f�Վs��ւ̓����ɂ��A���E�̐��Y�ݔ����ȑO���O���[�o���ȍ��ƃT�[�r�X�̎��v�������ƂɌ�������悤�ɂȂ������Ƃ͂قƂ�NJԈႢ����܂���B�����ɁA���Z�s��̓������i�̂ŁA���E�̒��~�v�[���̂����������z������Z�Ⓤ���ɏ[�Ă��镔���������邱�ƂɂȂ�܂����B�O���[�o���ȍ��ƃT�[�r�X�Ƌ��Z�@��A�L���͈͂̍��X�ŃC���t�����т�ǍD�ɂ��邱�ƂɂȂ���܂������A�^���Ȃ����ꂪ���̌�̃C���t�����҂ƃC���t���̃��X�N�v���~�A���������������ڂ��ʂ����܂����B�������A�ǂ���V�������̂ł͂Ȃ��A�ł����炱��9 �����̒��������̒ቺ���O���[�o���������X�ɐi�s�������߂Ƃ���͍̂���ł��B���炭�́A���E�̍��s�ꂪ������ǓI�Ɍ��ė\���̂��Ȃ��U�����͉��ł��葱����ł��傤�B�iGreenspan 2005�j
�܂�A�O���[���X�p���́u���v���O���[�o�����̂����ɂ��Ă͂��Ȃ��B�����A�{�e�́u���v�ƌĂꂽ���ۂ̌������𖾂���Ƃ����ۑ�Ɏ��g�܂Ȃ��B�d�v�Ȃ̂́A���̐����_�I�܈ӂł���B��Ɍ����_���u��@�v�ł��ނ͏Z��[����g�މƂ̔�����͒�����������邩�璷����������肾�Ƃ��������������Ă��邪�A����͋^�킵���B���������̘A�����̗L���Ɋւ�炸�AFF ���[�g�̈����������Ōo�ςɂ̓u�[�����N����B����ɁA���������̐���s�\�����O���[�o�����ɂ�����������i�E�����̗����Ɗ֘A�Â���A�������������s���߂��Ċ�@�������Ă��܂�����ӔC���C�O�ɓ]�łł���B�������������̓P�C���Y�h�I�Ȓm�I���E�ɑ�����w�҂ɂ͑i����Ƃ���傩������Ȃ����A�I�[�X�g���A�w�h�ɂ͂܂��ʗp���Ȃ��B
���܈�x�m�F���Ă����ƁA�N�ł��m���Ă���Ƃ���A�����J�͐��E�ő��GDP ���ւ鍑�ŁA���̊z��2000 �N��O����10�`13 ���h���ł���B�������̃}�l�[�T�v���C��M 1 ��1.2 ���h���O��AM 2 ��4.5�`6 ���h���AM 3 ��6.5�`10 ���h���ł���B����ɑ��Čo��Ԏ��ő������O���̏�������0.4�`0.74 ���h�����x�ŁA���z�ł͂Ȃ����z�Ō��Ă����}�l�[�T�v���C�ɂ͉����y�Ȃ��B���ۗv����M���v���Ƃ݂Ȃ���\���͂Ȃ��B�o�[�i���L�����ێ��x�M���b�v�ɂ��č����v��������ʓI���ƔF�߂���ō��ۗv�����������āu���́v�itentative�j�A�܂��u�^�j��ȁv�iunconventional�j�������Əq�ׂĂ��邱�Ƃɉ��߂Ē��ӂ𑣂��Ă����B�O���[���X�p���̋c��،���2005 �N2 ��16 ���ŁA�o�[�i���L�̍u���͓��N3 ��10 ���ł���B�ꗝ���������ނ��c���̘b��~�����悤�Ƃ������̂́A�b���o���i�K�Ŏ��͗��_�ɖ��������邱�Ƃ�����F�߂Ă���̂ł���B���ꂪ���Αg�D�I�Ȍ��f��p���ƍl���鏊�Ȃł���B
�A�M�����������ɏ���������p�Ɉ����������ăO���[�o���ȋK�͂ł̎��R����ᔻ����Ȃǂ̋c�_�́A��ʓI�ɍ������������Ƃ��ł��Ȃ��ȏ�P�Ȃ鑭���ł���B���ƂȂ�܂��������������f���̐_�`��S���͂��Ȃ����낤�ƐM�������B�V���R��`����@�Ƃ�������́A�����炭���㉽�\�N�Ԃ��A���邢�͉��S�N�Ԃł����Đ�������������g�b�v�l�C�̃r�f�I�ƂȂ�ł��낤�B������肩�A���҂����{�����삳��A�L���͈͂ɔz�M����邾�낤�B�ɂ�������炸�A���̖{���̓z���b�̈���o�Ȃ��B�d�˂ċ������Ă������A��@�̌����͎��R��`�ł͂Ȃ����R��`�̌��@�ł���B
|
|
���W �O���[���X�p����� |
�M�҂́A�{���O���Łu�O���[���X�p�����v�Ƃ������̂�莮�����Ă��������i����2013 b�j�A�����܂ł̋c�_���炱�̖�肪����̌o�ϊ�@���Ē��ڂɒl����W�J�������Ă��邱�Ƃ����炩�Ȃ̂ŁA��@��̏�i�܂��ĐV���Ȓi�K�ɓ������O���[���X�p���������̂悤�Ȍ`�ōĒ�N�������B
��1 ��啽���Ƒ�2 ���勰�Q�̊W���ǂ����邩�B
����̋��Z��@�ɂ���ăO���[���X�p���ɂ͊e���ʂ���ᔻ���W�����A�ނ͂قƂ�ǐj��䭂ƂȂ��Ă���B�������A�ᔻ�҂͑啽���ɂ��Ă͗�O�Ȃ��^���Ă���B�O���[���X�p���Ɋւ�����́A���܂��Đ_�������ɂȂ�������Ƃ��ēW�J����B�ł͖₤�B�啽���͑�2 ���勰�Q�ɉ�����^���Ȃ������̂��B���Ȃ������Ȃ�A�Ȃ��_��Ȃ����V����}�]�����ŗ����苿���悤�ȓW�J�ɂȂ����̂��B�M�҂̌����ł͑O�҂���҂B�����āA�O�҂ɂ͂��̂悤�ɂ������������Ȃ������B�Ƃ���ŁA�O�҂����߂Ă���̂̓n���t���[�]�z�[�L���Y�@�Ȃ̂ł��邩��A���@�͂���ɒ����ɐ���^�c�����{������Q���������̂��Ƃ������ƂɂȂ�Ȃ����낤���B����������A����̌o�ϖ@�́i�Ӑ}�I�ɂł͂Ȃ��Ă����ʓI�Ɂj���Q��ړI�Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�Ȃ����낤���B1990 �N�オ������_��1920 �N��Ǝ��Ă���Ƃ����O���[���X�p���̓����̈Ӗ����A�勰�Q�����j�̑S�̑��܂�����Ōo�ϊw�҂͂ǂ��]������̂��B
��2 ��Ȃ��O���[���X�p���̋��Z����̎��s�����ɊS�������Ȃ��̂��B��̖₢�Ƃ����ނ��A�N�����^�������Ǝv���ƒ���ɂ͔�掂���҂́A��ʂɂ��̐l���ɏ\���ȊS������Ă��Ȃ��B�ނ����������ɂ����炵�Ă������̂ɂ����āA���ꂪ���v�ł���Ԃ͖J�߁A�Q���ɓ]�����ƌ����l��B�l��Δނ���Â��������Ă��锻�f����̂͊ȒP�����A�J�߂Ă���Ƃ��ɂ���Âł͂Ȃ��ƌ������̂͊ȒP�ł͂Ȃ��B�������A�����͂����ł��낤�B�啽���͑f���炵���Ƃ����Ȃ�A���̌������u�K�^�v�̈ꌾ�ŕЂÂ����ɐ^���ɉ𖾂��ׂ��ł���B�������A���Q�̌������𖾂��ׂ��ł���B�u���v�Ƃ����M����@�I�ɂ�������e�ɒu���āA���������Ԃǂ���������đf�l�ł��킩��悤�ɋ��Q�̌�����_���ׂ��ł͂Ȃ��̂��B���������₢�ɓ�����ɂ́A�܂��O���[���X�p���̋��Z����Ƃ͉��ł����������������˂Ȃ炸�A���̂��߂ɂ͂܂��A�O���[���X�p���Ƃ͂��������N�Ȃ̂����������˂Ȃ�Ȃ��B
�����ɂ��đ啽�����B�����ꂽ�̂��킩��Ȃ��A�O���[���X�p���̎��т͂��������ٗʂɊ�Â����珫������ɂ͎Q�l�ɂȂ�Ȃ��ȂǂƁA�E�ϗ͂Ɍ�����q���̂悤�ɉۑ�����₷�������o���O�ɁA�{�l�ɂ������莿���Ă݂�悢�ł͂Ȃ����B�K�v�Ȃ炵����ׂ��R���T���e�B���O�����Ăł��B�o�c�R���T���^���g�Ƃ��Ęr���A���t�����h�̂������Ń}�N���o�ϊw�ւ̊S��[�߁A���ꂪCEA �ψ������ւ�FRB �c���Ƃ�������Ŏ��n�Ɋ������ꂽ�̂��ނ̃G�R�m�~�X�g�l���ł������B
CEA �Ƃ͌ڋq���哝�̂�������l�̃R���T���e�B���O��Ђ̂悤�Ȃ��̂��Əq�ׂĂ��邩��iAOT 64�G�㊪93−94�j�AFRB �Ƃ͌ڋq���A�����J�l�S���̃R���T���e�B���O��Ђ��ƍl���Ă����Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B�L����w�ɑ哝�̖̂�����������w�@��݂���̂Ȃ�A�Ȃ����l�Ɂu�O���[���X�p���E�X�N�[���v��n�݂��AABCT ���瓝�v�I�~�N���o�ϊw�܂ŁA�����Ƒ������\�����烊�X�N�Ǘ��p���_�C���܂ł��^�����Đ���ԓ`�B���悤�Ƃ��Ȃ��̂��B
��3 ��@�߉ݕ����̂��ƂŌo�ψ�����ǂ��m�ۂ��邩�B
���Ȃ��Ƃ�1990 �N��܂ł́A�O���[�X�p���͌���̖@�߉ݕ����̂��ƂŌo�ψ�����m�ۂ���Ƃ����ۑ�ɍł����������l���ł������B������A�f���ɍl����A�ނ̌o�ώv�z������w�Ԃ��Ƃ͂��Ȃ�d�v�Ȃ͂��ł���B�Ƃ��낪�A�嗬�h�o�ϊw�҂����́u�ٗʁv�̈ꌾ�ł��̖�肩��ڂ����炵�A�ނ���w�Ԃ��肪�Ȃ��Ɩ������Ă���B�L����w�����ɂ�邱���������m����`�̉��܂�����g�͑�ψ⊶�ł���B�e�C���[�^���[���_�̒҂́A�v����Ɏ���莮�������u���[���v���ٗʂł����炳�ꂽ�Əq�ׂĂ��邱�ƂɂȂ邪�A�������������ȓ����_�@���Ȃ����_�̏�Ŋʼn߂���Ă���̂������ɋꂵ�ށB�A�����J�̃��t����͂����炭�n�C�p�[�C���t���������{�^�̒����s���������炷�\�����������A�����Ȃ�Ƒ�s�����Č������͕̂K���ł���B�����������A�@�߉ݕ������ŕ����ƗL���ɂǂ��o�ς����肳����̂��Ƃ����₢�ɑ��铚�������܂�ɂ��s�\���Ȃ��ƂɋN������B��������Ƌ�ʂ��ꂽ�Ӗ��ł̌o�ψ�����ǂ��m�ۂ��邩�ɓ�����A�����ƗL���������^�ɑ̌n�I�Ȍo�ϊw�����߂��Ă���B
|
����
�P �ǎ҂͖{�e��2012 a ; 2012 b ; 2013 a ; 2013 b �̑��҂Ƃ��ēǂ܂ꂽ���B
�Q �ނ��ABCT �ɂ����_�͑������A�����͂���������S�_�_�Ɋւ����̂ł͂Ȃ��B�ڍׂ�Garrison 1990 ������B
�R ��ʘ_�Ƃ��āA����������Ԃ͌��S�Ƃ͂������˂�B�Ƃ͂����A�o��Ԏ��̊g�傾���Ńh����@���N����Ƃ��������̐M�ߐ��ɂ��Ă͑������₦�Ȃ��B���łɃu���g���E�b�Y����ɁA�g���t�B���̓h�C�c����{�̐�㕜���ŃA�����J�̗A���������A�����o�Ńh���̋�������������Ɨ\�������B���̕��͂̓h���̋���������~���ꂽ�ȏ㐳�������A�L���h���o�[�K�[�͂���ɔ��_���A�A�����J�����E�̋�s�Ƃ��ė����������^���Ă��邾���ŁA�h���͊җ����Ă��邩�����������~���������͂Ȃ��Əq�ׂ��B���Ƃ��ߓx�̂Ȃ�������ł��邪�A���́u���ۋ��Z������v�ȗ��_���͑����Ă���A���܂Ȃ��p�����ƌ�����B
�����ɂ����Č�҂��\����̂��đq�́w�h����@�̕����O���[���X�p���x�ł���i�đq 2007�j�B�đq�́A�P�C���Y�l�������邱�Ƃɗ]�O���Ȃ��킪���̃P�C���Y�������u�n���v�ƒf���A���̌����獑���̈�ʓI�ȃP�C���Y�����̊�{�I�Ό�����ɂ����i�đq2008 a ; 2008 b�j�B�B�����܂ނƎv�����A�P�C���Y�������]�X����O�ɃP�C���Y�{�l�ɖ�肪����B
������ɂ���A��L�̃O���[���X�p���_�͊�{�I��_�������B�h����@���̐w�c�́A�A�����J�o�ς̃t�@���_�����^���Y����̉�����ƃh����������Ƃ���������ڂ̑O�ɂ��āA�A�����J�̌i�C���ɒ[�Ɍ�ނ���ƃh�����������R�ɂȂ�Ƃ����\�}�ōl���Ă���B����ɑ��āA���Z������̐w�c�́A����������~����h���ȏ�ɔ�����ʉ݂��o�Ă��Ȃ�����h���̎x�z�͑����ƍl���Ă���B�{ �_���̎��͂��̓_�ł͂Ȃ��̂ŁA�o���Ƃ����ʼn߂��Ă����肾�����w�E���Ă����B����́A���Z��������M�p�n���_�Ɉˋ����Ă���A������s�V�X�e���ɓK�p�����Ƃ��̓��w���̖��_�����̂܂܍��ۏ�ʂōĉ�����Ă��邾�����Ƃ����_�ł���B��҂̐w�c�͂�����ӎ������A�O�҂̐w�c���قƂ�NjC�Â��Ă��Ȃ��B�M�p�n���_�͗a�Ɩ��ɂ�������Z����Ɖݕ��U������ʂ����ɑe�G�Ɉꊇ���Ă���_�ŁA��{�I�Ȗ�������Ă���i����2012 b�j�B�A�����J�����E�̋�s�Ƃ��āu�M�p�n���v���s���Ă��A�ꍑ�̎s����s�̏ꍇ�Ƒ卷�Ȃ���肪���シ��͓̂��R�ł���B�A�M�����̐M�p�c�����O���[�o���E�C���o�����X�݁A���ꂪ�T�u�v���C���E���[����@�ɍs���������Ƃ��A���ۃh���̈ב֑���͂��Ȃ艺�������B�����A�K���s�K�����{�����[���b�p����@�Ɍ������Ă���̂ŁA�m���ɂ��̂܂܃h���̒n�ʂ��h�邪�Ȃ��\���������B�����ASOMC�i�e��FOMC�j�̃����c�@�[�Ȃǂ͗ʓI�ɘa�̉ʂĂɂ̓n�C�p�[�C���t�����҂��Ă���Ƃ����������o���Ă���iMeltzer 2010�j�A����Ƃ��\�f�͋����Ȃ��B��֊�ʉ݂�����Ȃ��Ă��h���̍w���͂͑Q�����Ă���A�|�[���̂悤�ȃA�����J�l�͂��̂��Ƃ��c��Ŗ��ɂ��Ă���̂ł����āi����2010�j�A���ےʉ݂Ƃ��Ẵh���̒n�ʂ݂̂ɏœ_�Ă�Ӗ��͕s���ł��낤�B
��A�̏o�����̍���ɂ́A����������s���Ƃ������R�@�ɔ�����ݕ����x����������Ă���A�i�C�z�ɂ�����Z��@�ɂ���ב֑���̕s����ɂ���A�܂荑���O������Ŕ������Ă��邩���킸�A����I�Ȍo�ϖ��̂قƂ�ǂ��ׂĂ�����ɕ������邱�Ƃ����������������ׂ��ł���B���Z����ݕ��U�����A�A�M�����̐M�p�c�����h���̍w���͂����E������A�i�C�z���N�����č����o�ς��肩���E�o�ς����ɂ߂����肷�����A�h����@���������Ƃ������c�_�ɃV�j�V�Y���ȏ�̈Ӗ��͂Ȃ��B�Ȃ��h�������Ȃ��������A�h�������Ȃ�����ǂ̂悤�Ȗ�肪�N����̂����������Ƃ��ׂ��ł��낤�B
�S Greenspan 2007 ���uAOT�v�Ɨ��L����B
�T 2009 �N�u���̂����̂�����͐V���w�n�}�ƈړ���x�Ŗ�1 �y�[�W���ɂ킽���Ĉ��p����Ă���iGreenspan 2013�A 73−74�j�B
�U ���̘_���͑���2012 b �łӂꂽ�����h���a100 ���N�L�O�V���|�W�E���̈ꕔ�ł���B
�V �A�����J�̌ˌ��Z��s��͓��{�Ƃ͂��Ⴄ���������B�A�����J�ł́A���{�Łu�e���X�n�E�X�v�Ȃǂ̒ʏ̂ŌĂ�镡�����шȏオ��̌����̕ʂ̕����ɏZ�ނ��́i�ˌ��ƏW���Z��̒��ԁj�ƒP�ƂŌ��݂����u1 ���ь����ˌ��Z��v�����邪�A��҂��҂�s���������̂������B�A�����J�̕��ϓI�ȍx�O�Z��̕~�n�ʐς͂قړ��{��3�`4 �{�͂���B���{�̉Ɖ��ɂ́A��r�I������肪�Z�ފX��ł��L�̊z�قǂ̑O�낪����̂�����t�����A�A�����J�ł͉Ɖ��Ɠ������炢�L���O�낾���łȂ��A����Ɠ������炢�̗��낪���B���y�ʐς�����ł��邱�Ƃ͓��R�����A���ꂾ���ł͂Ȃ��B���{�ł͌Â��Ɖ��ɂ͂ӂ����i�����Ȃ��B���g�[��V���ނȂljƉ��̐ݔ��ʂɐV���������߁A�Â����������D���Ȃ������������̈���Ǝv���邪�A���{�̓s�s�͗e�ϗ����Ⴍ�A�ǂ����Ă��y�n�ɉ��l�̋��菊�����߂���Ȃ��Ƃ������������B�����̎����y�n���i���ُ�ɓ��M���₷���\���ɂȂ��Ă���B�Z��[�J�[������Ƃ͉����I���̔N����ς������悤�ɂ͐v����Ă��炸�A���{�l�̓X�N���b�v�E�A���h�E�r���h�^�̏Z��������B����ɑ��āA�A�����J�ł͑�s�s�x�O�Ȃǂň��̖ʐψȉ��ł͌ˌ��Z������Ă����Ȃ��@���x�������A�������̏Z���y�n�����Ƃ��]�����Ē��Âœ]�����Ă����悤���������x���m�����Ă���B�܂�A�Z��������ɂ���v���́A���v���̑I�D�A���{�̐���A����ɂ���炪���ւ��Č`�����ꂽ���s�ɂ���ƍl������B
�W �v�b�g�Ƃ͐敨�s��Ŗ����ɖ�艿�i�Ŏ��Y��I�������Ӗ�����i�s�g�͎��R�j�B�v����ɁA�O���[���X�p���̂������Ŋm���ł͂Ȃ��������m���ɂȂ�Ɛl�X���M���Ă����̂ł���B
�X �������A����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��B��1 �ɁA���Z��@�̐^���͖����̂���ɂ͂Ȃ��B���̍��͂ނ���M�p���ʂɂ���B�嗬�h�́u�M�p�n���v�Ɋ܂܂����Z����@�\�Ɗ�K�l���Y�@�\����ʂł��Ă��Ȃ��B�ނ�̏��_��19 ���I�̋��Z�_���ɂ������s�w�h�ɋ߂��A�������S���̓x���Ŏ��I�ɋ�ʂ��邱�Ƃ��\�ŁA����ɂ���ċ��Q���h���邩�ɐM���Ă���B�������A�~�[�[�X�͒ʉ݊w�h�𑊑ΓI�ɕ]�����A���̌�̃I�[�X�g���A�w�h�̓��J�[�h���C���O�����h��s���ɂ͊��S���������߂Ȃ���a���ʉ݂̑n������C���ĉݕ������s��ɐ��{�Ɛ���������Ƃ𒆓r���[���ƌ��Ă���iSalerno 2009�Axii�j�B��2 �ɁA�i���[�o���N���̓~�[�[�X�h��������{�ʂ̊��S�������R��s���Ƃ͈قȂ�B�O�҂͗a�ݕ����ɂ���ċ��Z�s���萫������悤�Ƃ��邵���݂ŁA�a�������ʼn^�p���ĕی삵�悤�Ƃ��邪�A���Z����@�\��ቺ������ƂƂ��ɑݕt����̎������B�o�H���獬�����N�����邾�낤�B��҂͐M�p�̗ʓI�Ǘ��i�a�����ݗʂ�����j�����߂邪�A��s�����Z����痘�v�銈������C����B�ʓI�Ǘ��͌o�ϓ����ł͂Ȃ��B�ނ����s�̊�K�l���Y����C���a�����݂ɑ���s������@�ŕی삷�邱�Ƃ��s���̏��L���ɑ��铝���ł���B�X�܂̑��l���Y�𓐂߂ΐޓ��������ɂ̑��l���Y�𓐂߂ΐޓ��ł͂Ȃ����R��_�ł���̂��BA ���̂��̂�A ���̂��́AB ����̂��̂�B ����̂��̂ł���B���̍����I�����������Ƃ��炷�ׂĂ̋��Q�A���ׂĂ̕s���A���ׂĂ̎E�C���n�܂�B����̋��Z�V�X• • �e���́AB ����̂��̂ӓI��A ���̂��̂Ƃ��錴���ɑ����Ă���B�ޓ������ł���B�����A�Ȃ�• • • • • • • �ʂ��̂͂Ȃ�ʁB��Ă̊�b���ߏ�ȐM�p�̂����炷�A���ł���_�͋��ʂ����A���ꂾ���������Č��_�̌����̑��������ۗ��B�Ⴂ�̗��R�͉����B�o�ϊw�̕���Ɍ���A���l�_�E�ݕ��@�\�_�E�ݕ��N���_�̎O�ғ����Ƃ�����{�I�ۑ�Ɏ��g�܂Ȃ��܂܍s�������������Ɏ����I�ȏo�����ɑΏ�����Ƃ����v�_�ؓI�A�f�p���ؓI�Ȏ嗬�h�o�ϊw�̐��i�ɍs��������i����2013 d�j�B�����w��@�w�ɂ�������g�傷��ƁA���L���Ƃ�����{���C�ŐN�Q���邱�Ƃ�e�F���錻�s�o�ϖ@�ɍs��������B
�@ |
| �@ |
   �@
�@
|
|
�@ |
 �@ �@
 �@ �@
 �@�@ �@�@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@ �@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 |
| �@ |
   �@
�@
|
|
���߂��@�@���߂�(�ڍ�)�@�@�@�� Keyword�@�@ |
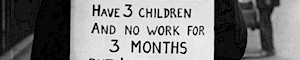 �@
�@ �@
�@




 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �o�u��
�o�u��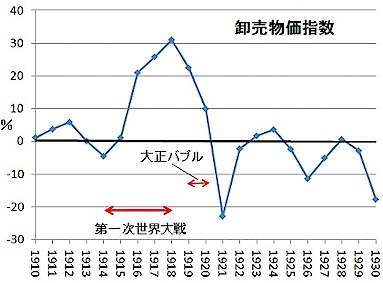
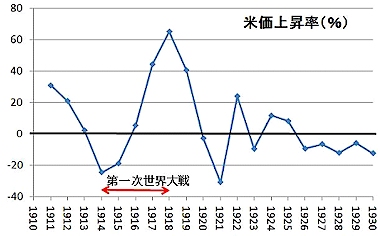
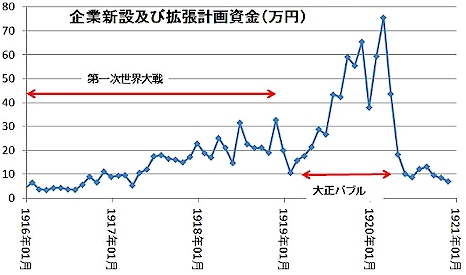
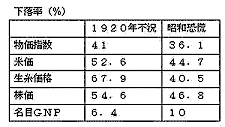
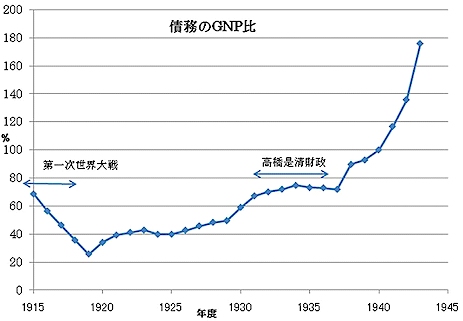
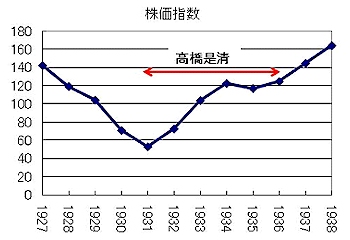
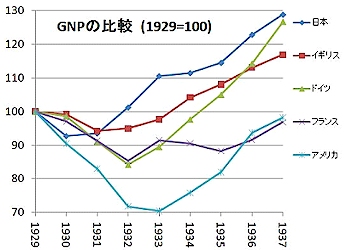
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@ �@�@
�@�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�@
�@ �@
�@
�@
�@
