| 仭僔儍儖儖丒傾儞僪儗丒僕儑僛僼丒僺僄乕儖亖儅儕丒僪丒僑乕儖 |
   丂
丂
|
(Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle丄1890-1970) 僼儔儞僗偺棨孯孯恖丄惌帯壠丅僼儔儞僗戞18戙戝摑椞丅戞擇師悽奅戝愴偵偍偄偰偼杮崙幐娮屻儘儞僪儞偵朣柦惌晎丒帺桼僼儔儞僗傪庽棫偟丄儗僕僗僞儞僗偲偲傕偵戝愴傪愴偄敳偄偨丅愴屻偡偖偵庱憡偵廇擟偟偨屻丄1959擭偵偼戝摑椞偵廇擟偟偰戞屲嫟榓惌傪奐巒偟丄傾儖僕僃儕傾愴憟偵傛偭偰崿棎偵娮偭偰偄偨僼儔儞僗傪棫偰捈偟偨丅
仭惗偄棫偪
僪丒僑乕儖偼僀僄僘僗夛妛堾偺峑挿(楌巎壢傪嫵偊偰偄偨)傪柋傔傞晝傾儞儕偺巕偲偟偰丄僼儔儞僗杒晹偺岺嬈搒巗儕乕儖偵惗傑傟偨丅
僪丒僑乕儖偺壠宯偼壓媺婱懓偱偁傞丅乽僪丒僑乕儖 (de Gaulle)乿偺乽僪乿(de) 偼杮棃偼慜抲帉偱丄乽僑乕儖(僈儕傾)岞乿乽僑乕儖嫧乿偲偄偭偨堄枴傪帩偮丅僪丒僑乕儖壠偺応崌偼柤帤偺堦晹偲尒側偝傟偰偄傞丅
僪丒僑乕儖偺慮慶晝偼儖僀16悽偺朄棩屭栤傪偟偰偍傝丄僼儔儞僗妚柦帪偵搳崠偝傟偰偄傞丅晝傾儞儕偼堛妛丒棟妛丒暥妛偺3偮偺攷巑崋傪帩偮愖妛丄擬怱側僇僩儕僢僋嫵搆偩偭偨偲偄偆丅傑偨丄慶晝僕儏儕傾儞傕挊柤側楌巎妛幰偩偭偨偲偄偄丄僪丒僑乕儖偼梒偄崰傛傝楌巎偵嫽枴傪妎偊丄乽僼儔儞僗偺柤梍偲揱摑乿偵屩傝傪書偔傛偆偵側偭偨偲偄偆丅偦偟偰丄僪丒僑乕儖偼丄揱摴巘傪栚巜偟偰偄偨傕偺偺丄挿恎憠嬰偲偄偆棫攈側懱奿偩偭偨偙偲偐傜孯恖偺摴傪慖傫偩丅
|
仭孯楌
仭棨孯巑姱妛峑帪戙
抧尦偺拞妛峑傪懖嬈屻丄1909擭偵僒儞丒僔乕儖棨孯巑姱妛峑偵擖妛偟偨丅僪丒僑乕儖偼棨孯巑姱妛峑撪偱偼乽梇寋乿(僔儔僲丅僼儔儞僗偺僔儞儃儖偺1偮偱傕偁傞)丄乽傾僗僷儔僈僗乿偦偟偰乽僐僱僞乕僽儖(Connétable丗乽戝彨孯乿偺堄)乿偲屇偽傟偰偄偨偲偄偆丅偙傟傜偺偁偩柤偼恎挿偑栺2m偁偭偨偲偄偆斵偺懱奿偵桼棃偟偰偄傞丅
仭棨孯巑姱帪戙
懖嬈屻偼丄曕暫戞33楢戉偵棨孯彮堁偲偟偰攝懏偝傟偨丅曕暫戞33楢戉偼僼傿儕僢僾丒儁僞儞(偺偪偺償傿僔乕惌尃偺巜摫幰)偺楢戉偩偭偨丅
戞堦師悽奅戝愴偱偼戝堁偲偟偰僪僀僣孯偲愴偄丄1916擭丄戝愴拞嵟戝偺寖愴抧償僃儖僟儞愴偱晹戉傪巜婗偟偨丅僪僀僣孯偺朇寕偱廳彎傪晧偄乽婥愨乿偟偨偑丄乽愴巰乿偲敾抐偝傟丄巰懱塣斃幵偵忔偣傜傟偨丅偟偐偟桝憲搑拞偵堄幆傪庢傝栠偟丄帠側偒傪摼偨偲偄偆丅
愴巰偲暦偐偝傟偨儁僞儞偼丄乽僪丒僑乕儖戝堁丅拞戉挿傪柋傔丄偦偺抦惈偲摽惈偵偍偄偰抦傜傟偨恖暔偱偁傞丅偍偦傞傋偒朇寕偵傛偭偰戝戉偵氺偟偄懝奞傪弌偟丄拞戉傑偨敧曽偐傜揋偺峌寕傪偆偗偨忬嫷壓偵丄偦傟偑孯偺岝塰偵偐側偆桞堦偺嶔偲敾抐偟偰暫傪傑偲傔丄撍寕傪姼峴丄敀暫愴傪揥奐偟偨丅崿愴偺偆偪偵愴巰丅岟愌敳孮乧乧乿偲偄偆屄恖揑側挗帿傪嶌惉偟偨偲偄偆丅
傑偨丄曔椄惗妶傕宱尡偟丄偦傟偼戞堦師悽奅戝愴廔寢傑偱懕偄偨丅僪丒僑乕儖偼5夞扙崠傪恾偭偨傕偺偺丄戝暱側懱偩偭偨偨傔5夞偲傕幐攕偟丄嵟傕尩廳側曔椄廂梕強偩偭偨僀儞僑儖僔儏僞僢僩忛偺楽崠乽揤彈偺廻乿偱曔椄惗妶傪宱尡偟偨丅偪側傒偵偦偺楽崠偵偼丄屻偵儘僔傾(僜楢)偺愒孯尦悆偲側傝丄僗僞乕儕儞偵傛偭偰弆惔偝傟偨僩僁僴僠僃僼僗僉乕偑偄偨丅僩僁僴僠僃僼僗僉乕偼僪丒僑乕儖偵懳偟丄乽枹棃偼変乆偺傕偺偩丄偔傛偔傛偡傞側乿偲曔椄惗妶傪堅傔偨偲偄偆丅
仭億乕儔儞僪孯帠屭栤帪戙
戞堦師悽奅戝愴廔寢屻丄僪丒僑乕儖偼億乕儔儞僪偺孯帠屭栤偲側傝丄摨崙傊晪擟偟偨丅摉帪億乕儔儞僪偼妚柦儘僔傾愒孯偺怤峌傪庴偗偰偍傝丄庱搒儚儖僔儍儚傑偱敆傜傟偰偄偨(億乕儔儞僪丒僜價僄僩愴憟)丅偦偺帪偺愒孯巌椷姱偼丄嫟偵曔椄惗妶傪夁偛偟偨僩僁僴僠僃僼僗僉乕偩偭偨丅僪丒僑乕儖偼偙偺愴偄偱妶桇偟丄乽億乕儔儞僪孯彮嵅乿偺徧崋傪摼傞偲嫟偵丄億乕儔儞僪惌晎偐傜孧復傕庼梌偝傟偨丅
仭棨孯戝妛峑帪戙
億乕儔儞僪偐傜婣崙偟丄僒儞丒僔乕儖棨孯巑姱妛峑偺孯帠巎扴摉嫵姱偲偟偰嬑傔偨屻丄1922擭偵僼儔儞僗棨孯戝妛峑偵擖妛偟偨丅摨妛峑偱偼丄乽嬑曌偵偟偰晀塻丄攷妛丅偟偐偟桭恖偲偺愜傝崌偄埆偔丄惈奿揑偵墌枮傪寚偔乿偲昡壙傪偝傟偰偄傞丅傑偨丄棨孯戝傪懖嬈偟偨傕偺偺丄僪丒僑乕儖偼乽傢偑摴傪峴偔乿偲偄偆庡媊傪嫮偔帩偭偰偄偨偨傔丄棨孯忋姱偲偺愜傝崌偄偑埆偔丄戝堁偐傜彮嵅傊偺恑媺偵10擭傕偐偐偭偰偟傑偭偨丅偟偐偟丄偙偺娫傕屻偵揋偲側傞儁僞儞偼僪丒僑乕儖傪偐傢偄偑偭偰偄偨偲偄偆丅
偦偺屻丄僪丒僑乕儖偼拞搶偵1夞晪擟偟丄1932擭偵偼拞嵅偲側傝丄僷儕偵偁偭偨孯帠嵟崅夛媍帠柋挿偵廇擟偟偰偄傞丅傑偨儁僞儞偺寁傜偄傕偁傝丄僪丒僑乕儖偼棨孯戝妛峑偵偍偄偰乽愴摤峴堊偲巜婗姱乿偲偄偆摿暿島墘傕峴偭偨丅偙偺島墘傪暥彂偵揨傔偨傕偺偑1932擭偵弌斉偝傟偨亀寱偺恘亁偱偁傞丅偨偩丄偙偺彂偼乽僼儔儞僗斉亀傢偑摤憟亁乿偁傞偄偼乽僪丒僑乕儖斉亀変偑摤憟亁乿(僪僀僣偺傾僪儖僼丒僸僩儔乕偺亀変偑摤憟亁偐傜)偲傕昡偝傟偰偄傞丅偮偄偱丄1934擭偵偼乽婡峛壔孯偵傓偗偰乿丄1938擭偵偼乽僼儔儞僗偲偦偺孯戉乿傪幏昅偟偨丅僸僩儔乕偼僪丒僑乕儖偺挊彂亀怑嬈揑孯戉傪栚巜偟偰亁傪撉傫偱姶柫傪庴偗偰偄偨偑丄挊幰偼傾儞儕丒僕儘乕偩偲姩堘偄傪偟偰偄偨丅
仭揹寕嶌愴偺悇恑
戞堦師悽奅戝愴偺償僃儖僟儞愴偺懱尡偐傜僪丒僑乕儖偼丄偙傟偐傜偺愴憟偼毻崍愴偱偼側偔丄婡摦椡偺偁傞愴幵傗旘峴婡傪嬱巊偟偨婡夿壔晹戉偵傛傞揹寕嶌愴偵側傞偙偲傪榑偠丄偄偔偮偐偺挊彂偺拞偱偦偺偙偲偵尵媦偟偨丅
偙偺尒夝偼丄儁僞儞傜僼儔儞僗孯偺庡棳攈偵偼庴偗擖傟傜傟偢丄偦偺屻旂擏偵傕僪丒僑乕儖傗僕儑儞丒僼儗僨儕僢僋丒僠儍乕儖僘丒僼儔乕偺挊嶌傪嶲峫偲偟偮偮尋媶傪峴偭偰偄偨僌僨乕儕傾儞偺偄偨僪僀僣孯偑愊嬌揑偵嵦梡偟偰偄傞(崙壠巜摫幰偑僸僩儔乕偩偭偨偙偲傕戝偒偄偲峫偊傜傟傞)丅
1939擭9寧偵戞擇師悽奅戝愴偑杣敪丄傑傗偐偟愴憟偲屇偽傟傞偵傜傒崌偄偺屻丄1940擭5寧偵僪僀僣孯偺僼儔儞僗怤峌偑巒傑傞偲丄僪僀僣孯偼杊塹曽恓傪寴帩偟偨僼儔儞僗孯偑崙嫬偵梡堄偟偨嫄戝梫嵡乽儅僕僲慄乿傪婡摦椡偺偁傞憰峛晹戉偱塈夞偟偰恑孯偟丄僼儔儞僗孯偼傢偢偐1偐寧娫偺愴偄偱僪僀僣孯偺揹寕嶌愴偵傛傝攕杒傪媔偟偨丅
奐愴捈屻偺5寧15擔丄僪丒僑乕儖戝嵅偼怴曇偺戞4婡峛巘抍挿偵擟柦偝傟偨丅偡偱偵庤抶傟偺帪婜偵側傝丄偟偐傕彫婯柾偱偼偁偭偨偑丄偙偙偱傛偆傗偔僪丒僑乕儖偼挿擭庡挘偟偰偒偨婡夿壔愴弍傪幚抧偵帋偡婡夛傪摼偨丅懠偺戞1偐傜戞3偺3屄婡峛巘抍偑摿偵尒傞傋偒妶桇傕側偔廔傢偭偨偺偵懳偟丄僪丒僑乕儖棪偄傞戞4巘抍偼巘抍挿偺捈愙偺巜婗壓偺傕偲偵愴幵偺廤拞塣梡傪峴偄丄堦帪揑偵偱偼偁傟丄僪僀僣孯晹戉偵嫼埿傪梌偊傞偙偲偵惉岟偟偨丅摿偵僜儞儉導傾僽償傿儖嬤曈偺斀寕偱偼丄揔愗側峲嬻巟墖偑摼傜傟側偐偭偨偨傔偵姰帏側惉岟傪廂傔傞傑偱偵偼峴偐側偐偭偨偑丄僜儞儉愳撿娸偺揋嫶摢毱3偮偺偆偪2偮傑偱傪庢傝曉偡妶桇傪尒偣偨丅偟偐偟偦偺屻娫傕側偔丄僪丒僑乕儖偼棨孯師姱偵擟柦偝傟丄晹戉偺巜婗傪棧傟傞偙偲偵側傞丅
|
仭乽帺桼僼儔儞僗乿帪戙
1940擭6寧偵偼丄摨擭3寧偺僄僪僁傾乕儖丒僟儔僨傿僄偺帿擟偵傛傝怴偨偵庱憡偵廇擟偟偨億乕儖丒儗僲乕棪偄傞怴撪妕偺崙杊師姱寭棨孯師姱偵擟柦偝傟丄僼儔儞僗孯巎忋嵟擭彮偺49嵨偱弝彨偲側偭偨丅僪僀僣孯偵傛傞僼儔儞僗怤峌偵懳偡傞僀僊儕僗孯偺嫤椡傪摼傞偨傔儘儞僪儞偵旘傃丄僂傿儞僗僩儞丒僠儍乕僠儖愴帪撪妕偲岎徛傪奐巒偡傞丅偦偺拞偱丄崌朄揑偵塸暓楢崌孯偺巜婗尃偺摑崌偲朣柦揑惈奿偺惌嶔丄塸暓楢崌(僼儔儞僗偲僀僊儕僗偲偺惌帯摑崌峔憐)偵杬憱丄僀僊儕僗懁偺妕媍寛掕屻丄僼儔儞僗惌晎偺旔擄愭儃儖僪乕偵岦偐偭偨偑儗僲乕撪妕偼塸暓楢崌偺埬審偲媥愴攈偺埑椡偱憤帿怑偟丄師姱怑傪夝偐傟傞丅
6寧15擔偵庱搒偺僷儕偑娮棊偟丄帺恎偵戇曔偺塡偑偨偭偰偍傝丄楢崌孯屭栤偺僀僊儕僗棨孯彨峑僗僺傾乕僘彨孯偺彚娨偵摨敽偟僀僊儕僗傊朣柦偡傞偙偲傪寛抐丅扙弌愭偺儘儞僪儞偵朣柦惌晎乽帺桼僼儔儞僗乿傪寢惉偟丄儘儞僪儞偺BBC儔僕僆傪捠偠偰丄懳撈峈愴偺宲懕偲拞棫惌尃偱偼偁傞傕偺偺恊撈揑側償傿僔乕惌尃傊偺掞峈傪僼儔儞僗崙柉偵屇傃偐偗偨丅僀僊儕僗媍夛傗妕椈偼帠傪峳棫偰傞偙偲傪嫲傟丄偦傟傪拞巭偝偣傛偆偲偟偨偑丄僀僊儕僗偺僂傿儞僗僩儞丒僠儍乕僠儖庱憡偺巜帵偵傛偭偰曻憲偼嫮峴偝傟偨丅偙偺曻憲偼偺偪偵僼儔儞僗偺斀寕偺偺傠偟偲偟偰崅偄壙抣傪梌偊傜傟傞偑丄摉帪捈愙偵暦偄偰偄偨傕偺偼傎偲傫偳偄側偐偭偨偟丄傑偨榐壒偝傟偰偄側偐偭偨偺偱嵞曻憲傕側偐偭偨丅偟偐偟丄梻擔偵偼傑偩偄偔傜偐偺帺桼偑巆偭偰偄偨償傿僔乕惌尃壓偵偁傞僼儔儞僗撿晹偺怴暦偺偄偔偮偐偑偙偺曻憲偵偮偄偰彫偝側婰帠傪宖嵹偟丄彊乆偵抦傜傟傞傛偆偵側偭偰偄偭偨丅 丂 梻1941擭10寧25擔偵偼僕儍儞丒儉乕儔儞偲夛尒丄堦偮偺戝偒側慻怐乽儗僕僗僞儞僗崙柉夛媍乿傪嶌傞偨傔儉乕儔儞傪嬌旈棤偵僼儔儞僗杮搚偵攈尛偡傞丅傑偨帺傜帺桼僼儔儞僗孯傪巜婗偟偰傾儖僕僃儕傾丄僠儏僯僕傾側偳偺僼儔儞僗偺怉柉抧傪拞怱偲偟偨杒傾僼儕僇愴慄偱愴偄丄懳撈峈愴傪巜摫偟偨丅偟偐偟丄暓椞僀儞僪僔僫傗儅僟僈僗僇儖傪偼偠傔偲偡傞怉柉抧傗僼儔儞僗杮崙偺僼儔儞僗孯偺懡偔偼丄拞棫傪堐帩偡傞偐償傿僔乕惌尃偵婣懏偟偨丅偦偺屻帺桼僼儔儞僗孯偼楢崌崙偲嫟摨偱僼儔儞僗怉柉抧偺僈儃儞丄儅僟僈僗僇儖傪峌棯偟偨丅1942擭偵偼傾儖僕僃儕傾偺僼儔儞僜儚丒僟儖儔儞戝彨偑楢崌崙懁偵偮偒丄杒傾僼儕僇偺僼儔儞僗庡惾偲側偭偨偑埫嶦偝傟偨丅偙偺埫嶦偺攚屻偵偼僪丒僑乕儖偺娭梌偑偁偭偨偲偄偆愢傕偁傞丅僟儖儔儞偺屻傪宲偄偩偺偼傾儞儕丒僕儘乕戝彨偱丄楢崌崙僼儔儞僗偺戙昞偲偟偰僪丒僑乕儖偲僕儘乕偑暲傃棫偮懱惂偲側偭偨丅1943擭1寧偵偼僼儔儞僗偺巜摫幰傪寛傔傞偨傔僇僒僽儔儞僇夛択偑奐偐傟偨偑寛拝偟側偐偭偨丅5寧偵僼儔儞僗崙撪偺儗僕僗僞儞僗慻怐慡崙掞峈昡媍夛偼僪丒僑乕儖傪儗僕僗僞儞僗偺巜摫幰偲寛掕偟偨偑丄6寧偵傾儖僕僃儕傾偱寢惉偝傟偨僼儔儞僗崙柉夝曻埾堳夛偼僪丒僑乕儖偲僕儘乕傪嫟摨戙昞偲偟偨丅偙偺擇摢懱惂偼11寧偵僕儘乕偑帿怑偡傞傑偱懕偄偨丅埾堳夛偼梻1944擭偵僼儔儞僗嫟榓崙椪帪惌晎偵夵慻偝傟丄僪丒僑乕儖偑戙昞偲側偭偨丅
僪丒僑乕儖偼偦偺撈嵸揑偐偮嫮尃揑側巔惃偐傜丄僠儍乕僠儖傗傾儊儕僇崌廜崙戝摑椞偺僼儔儞僋儕儞丒儖乕僘儀儖僩偲徴撍偡傞偙偲偑懡偔丄摿偵儖乕僘償僃儖僩偼僪丒僑乕儖偺偙偲傪乽宍幃偵偙偩傢傞媽悽奅揑恖暔乿丄乽慖嫇偱慖偽傟偨傢偗偱偼側偄偺偵巜摫幰偲偟偰孨椪偟傛偆偲偟偰偄傞乿乽偁偺傛偆側恖暔偵偼儅僟僈僗僇儖偺抦帠偱傕偝偣偰偍偗偽椙偄乿偲偟偰偁偐傜偝傑偵寵偭偰偄偨偲偄偆丅偲偼尵偊丄扗傢傟偨慶崙傪庢傝栠偡偨傔偵愴偆巔惃偵偼巟帩幰傕偍傝丄僠儍乕僠儖晇恖偼僪丒僑乕儖彨孯偺擬楏側僼傽儞偩偭偨偲偄偆丅
偦偺屻丄1944擭6寧偺楢崌孯偵傛傞儓乕儘僢僷戝棨傊偺嵞忋棨嶌愴丒僲儖儅儞僨傿乕忋棨嶌愴偑惉岟偡傞偲丄慶崙偵栠偭偰帺桼僼儔儞僗孯傪棪偄偰僀僊儕僗孯傗傾儊儕僇孯側偳偺楢崌孯偲偲傕偵愴偄丄摨擭8寧25擔偵僷儕偑夝曻偝傟偨丅僪丒僑乕儖偼梻26擔偵帺桼僼儔儞僗孯傪棪偄偰僷儕偵擖忛丄僄僩儚乕儖奙慁栧偐傜僲乕僩儖僟儉戝惞摪傑偱丄僪僀僣孯偺巆搣偑曻偮廵抏傪婥偵偡傞偙偲側偔奙慁僷儗乕僪傪峴偄丄僔儍儞僛儕僛捠傝傪杽傔恠偔偟偨僷儕巗柉偐傜擬楏側妳嵮傪梺傃偨丅
|
仭椪帪惌晎庡惾
仭嫮尃揑巜摫幰
僼儔儞僗夝曻屻丄椪帪惌晎偑僼儔儞僗偺摑帯傪峴偆偙偲偲側傝丄惂寷媍夛偼枮応堦抳偱僪丒僑乕儖傪椪帪惌晎偺庡惾偵慖弌偟偨丅僪丒僑乕儖偼帺桼僼儔儞僗帪戙偐傜戞嶰嫟榓惌偺媍夛惂搙偵偼寚娮偑偁傞偲庡挘偟偰偍傝丄柉廜偺惡朷傪攚宨偵懠偺巜摫幰丒惌搣偺堄尒傪柍帇偡傞偙偲偑懡偔側傝丄偲傝傢偗幮夛搣 (SFIO)丒嫟嶻搣偐傜撈嵸揑偲偺斸敾傪庴偗偨丅
1946擭1寧偵丄僪丒僑乕儖偼孯旛旓傪20僷乕僙儞僩僇僢僩偡傋偒偩偲偄偆幮夛搣偺梊嶼採埬偵斀敪偡傞偲偄偆宍偱丄撍擛庱憡傪帿擟偟偨丅偙偺帿擟偺恀堄偼丄媍夛偺桪埵傪庡挘偡傞惌搣懁偵懳偡傞晄枮偑偁偭偨偲偄傢傟偰偄傞丅
仭崙塩壔悇恑
僪丒僑乕儖偺庱憡帪戙偵偼丄僼儔儞僗夝曻屻偺1945擭偵戝庤帺摦幵夛幮偺儖僲乕傪崙塩壔偟偨傎偐丄僄乕儖僼儔儞僗峲嬻側偳懡偔偺婎姴婇嬈傪崙塩壔偟偨丅偙偺傛偆偵丄崙壠偺暅嫽傪悇恑偡傞偨傔傕偁傝孯廀丄僀儞僼儔娭楢偺戝婇嬈偺崙塩壔傪愊嬌揑偵悇偟恑傔傞偲偲傕偵丄岞嫟搳帒偵傕椡傪擖傟偨丅偙偺惌嶔偼屻偵僪丒僑乕儖偑戝摑椞偵側偭偰偐傜傕宲懕偝傟偨丅
仭嵼栰偺惌帯壠
惂寷媍夛偑惂掕偟偨憪埬偑斲寛偝傟丄嵞搙峴傢傟偨惂寷媍夛慖嫇偱恖柉嫟榓攈偑桇恑偡傞偲丄僪丒僑乕儖偼6寧16擔偺僶僀儐乕偱偺墘愢傪偼偠傔偲偟偰(僶僀儐乕墘愢(僼儔儞僗岅斉))丄帺傜偺寷朄峔憐傪昞柧偡傞傛偆偵側偭偨丅僪丒僑乕儖偼惌晎偲戝摑椞偺尃尷傪嫮壔偟丄惌晎撪晹偱偺摑堦偑恾傜傟傞傋偒偩偲庡挘偟偨偑丄幚嵺偵嵦戰偝傟偨僼儔儞僗戞巐嫟榓惌寷朄偵偼斀塮偝傟側偐偭偨丅
斵偼偙偺怣擮偐傜1947擭偵僼儔儞僗崙柉楢崌(棯徧RPF)傪寢惉偟偨偑丄偙偺抍懱傕傑偨1952擭偵偼堦晹偑暘楐偟偰惌憟偑敪惗偟偨丅偦傟傪寵偭偨僪丒僑乕儖偼RPF傪夝懱偟丄1955擭偵偼乽岞揑惗妶偐傜堷戅偡傞乿偲愰尵偟偨丅
|
仭戞屲嫟榓惂戝摑椞
仭嵞搊斅
僪丒僑乕儖堷戅屻傕惌晎偑彫搣棎棫偵傛偭偰婡擻晄慡偵娮偭偰偄傞偙偲偵偼曄傢傜偢丄傾儖僕僃儕傾偱偺柉懓帺寛傪媮傔傞斀棎偵傕桳岠側庤傪懪偰側偄偱偄偨丅1958擭5寧丄偙偺忬嫷偵晄枮傪帩偭偨傾儖僕僃儕傾偺僼儔儞僗怉柉幰(僐儘儞)偑丄傾儖僕僃儕傾偺撈棫塣摦偵懳峈偡傞偨傔丄傾儖僕僃儕傾挀棷孯偲寢戸偟偰杮崙惌晎偵斀婙傪東偟丄乽僪丒僑乕儖枩嵨乿傪彞偊偰僼儔儞僗杮搚傊偺怤峌寁夋傪棫偰偨丅尰抧挀撛偺棊壓嶱楢戉偑僐儖僔僇搰傪愯椞偟丄捔埑偵岦偐偭偨嫟榓崙曐埨戉傕摓拝屻斀棎孯偵摨挷偟丄僼儔儞僗杮搚偵嫼埿傪梌偊巒傔偨丅偙偺嬞媫帠懺偵丄廇擟捈屻偺庱憡僺僄乕儖丒僼儕儉儔儞偼側偡偡傋偑側偔丄恑戅嬌傑偭偨惌晎偼孯晹傪梷偊傞偙偲偺偱偒傞恖暔偲偟偰塀嫃傪愰尵偟偰幏昅妶摦偵偄偦偟傫偱偄偨僪丒僑乕儖偵弌攏傪梫惪偟偨丅
僪丒僑乕儖偼偙偺斀棎偵偼柍娭學偩偭偨偑丄偩偐傜偙偦惌晎偍傛傃儖僱丒僐僥傿戝摑椞傕僪丒僑乕儖偵弌攏傪梫惪偡傞偙偲偑偱偒丄斵傕偦傟傪庴偗傞偙偲偑偱偒偨丅僪丒僑乕儖偑庱憡廇擟偵嵺偟偰梫媮偟偨偺偼乽尰嵼偺嬌傔偰崲擄側忣惃偺拞偱峴摦偡傞偨傔偵昁梫側慡尃乿傪梌偊傞偲偄偆傕偺偩偭偨丅僪丒僑乕儖偼丄1946擭寷朄偼乽惌搣巟攝惈 Régime des partis乿偵懠側傜偢丄幏峴晎偵傛傝戝偒側埨掕惈偲尃埿偲傪梌偊傞偑丄偩偐傜偲偄偭偰柉庡揑偱偁傞偙偲傪傗傔側偄傛偆側怴偟偄惌帯懱惂偵丄嵗傪忳傞傋偒偱偁傞偲妋怣偟偨丅僪丒僑乕儖偼庱憡巜柤傪偆偗偨屻偺6寧1擔丄崙柉媍夛偵懳偟偰6儢寧娫偺慡尃埾擟傪梫媮偟丄怴寷朄憪埬傪採帵偟偨丅媍夛偼偙傟傪彸擣偟丄僪丒僑乕儖偼惓幃偵庱憡偵廇擟偟偨丅偙偺慡尃偼1958擭6寧3擔偺寷朄揑朄棩(僼儔儞僗岅斉)偵傛偭偰彸擣偝傟偨丅僕儍僢僋丒儅僔儏彨孯傗儔僂儖丒僒儔儞彨孯側偳挀棷孯庱擼晹偼偙傟傪巟帩偟偨丅偦偟偰6寧4擔偵偼傾儖僕僃偺傾儖僕僃儕傾憤撀晎偐傜乽巹偼彅孨傪棟夝偟偨両乿偲嫨傃丄斀棎傪捑惷壔偝偣偨丅
仭戞屲嫟榓惌偺惉棫
僪丒僑乕儖偼丄惓婯偺宍幃偵廬偄媍夛偐傜寷朄埬傪弨旛偡傞尃椡偺彸擣傪妉摼丄偦偺寷朄埬偼恖柉搳昜偵晅戸偝傟傞偙偲偵側偭偨丅僪丒僑乕儖偑帵偟偨寷朄憪埬偱偼丄戝摑椞偺尃尷傪嫮壔偟媍夛偺椡傪梷惂偡傞怴寷朄傪棫埬偟丄偨偩偪偵偙傟偼崙柉搳昜偵晅偝傟偨丅摨擭9寧偵峴傢傟偨崙柉搳昜偱搳昜幰偺80%嬤偔傕偺巀惉偵傛傝彸擣偝傟丄1958擭10寧4擔偵偼怴寷朄(僼儔儞僗戞屲嫟榓惌寷朄)偑岞晍丄惂掕偝傟丄僼儔儞僗戞屲嫟榓惌偑惉棫丄僪丒僑乕儖偼戞18戙戝摑椞偵廇擟偟偨丅僪丒僑乕儖偼丄埲屻1969擭偵戅恮偡傞傑偱偺11擭娫丄嫮尃揑偲傕尵傢傟偨惌尃塣塩傪傕偭偰僼儔儞僗偺撪奜惌嶔傪嫮椡偵悇恑偡傞偙偲偲側傞丅僪丒僑乕儖偼傑偨丄偐偮偰偺帺傜偺搣偱偁傞僼儔儞僗崙柉楢崌偺屻恎丒幮夛嫟榓攈側偳傪寢廤偟偰丄怴偨側梌搣偲偟偰怴嫟榓崙楢崌(Union pour la Nouvelle République丗UNR)傪寢惉偟偨丅
偙偺11擭娫偵弶傔偰僼儔儞僗偺惌嬊偼埨掕偟丄偦偺岻傒側宱嵪惌嶔偵傛偭偰僼儔儞僗偼崅搙宱嵪惉挿傪悑偘丄奜岎偺柺偱傕僼儔儞僗偺抧埵偼媫懍偵夞暅偟偨丅偟偐偟傾儖僕僃儕傾偵懳偟偰僪丒僑乕儖偼丄扴偓弌偟偨恖乆偺巚榝偲偼媡偵撈棫偼昁帄偲敾抐偟偰偄偨丅僪丒僑乕儖帺恎偑屻擭偺夞憐榐偱戞堦師僀儞僪僔僫愴憟偺攚宨偵偁傞柉懓帺寛偺摦偒傪棟夝偟偰偄偨偙偲丄傑偨摉弶偼姰慡撈棫偱偼側偄娚傗偐側楢朚惂傕柾嶕偟偨(幚嵺偵崙柉偵傕採埬偟偰偄傞)偙偲傪柧偐偟偰偄傞丅偙偆偟偰1959擭9寧偵偼僪丒僑乕儖偼傾儖僕僃儕傾恖偵柉懓帺寛傪擣傔傞敪尵傪峴偭偨丅偙傟偵僐儘儞偼寖偟偔斀敪偟丄1960擭1寧偵偼傾儖僕僃巗偱僶儕僎乕僪偺堦廡娫偲屇偽傟傞斀棎傪婲偙偟偨丅偝傜偵丄1961擭4寧偵偼傾儞僪儗丒僛儗乕儖丄儔僂儖丒僒儔儞丄儌乕儕僗丒僔儍乕儖丄僄僪儌儞丒僕儏僆乕偺4恖偺彨孯偵傛偭偰彨孯払偺斀棎偑杣敪偟偨傕偺偺丄僪丒僑乕儖偵傛偭偰懍傗偐偵捔埑偝傟偨丅寢嬊傾儖僕僃儕傾椞桳偺宲懕傪庡挘偡傞塃梼慻怐OAS偺僥儘偵傛傞斀懳傪墴偟愗偭偰丄1962擭丄撈棫傪彸擣偟偨丅僪丒僑乕儖偼偙偺娫丄偨傃偨傃OAS偺僥儘傗埫嶦偺昗揑偲側偭偨( 仺 徻嵶偼乽僕儍僢僇儖偺擔乿崁傪嶲徠)丅1962擭8寧偵偼僷儕峹奜偺僾僥傿亖僋儔儅乕儖偱丄忔偭偰偄偨帺摦幵偑OAS偵傛傝婡娭廵偱棎幩偝傟偨乽僾僥傿亖僋儔儅乕儖帠審乿偑婲偒偨偑丄僪丒僑乕儖偼嬨巰偵堦惗傪摼偨丅
傑偨丄傾僼儕僇偵巆偭偰偄偨僼儔儞僗椞惣傾僼儕僇媦傃僼儔儞僗椞愒摴傾僼儕僇偺峀戝側僼儔儞僗椞偺怉柉抧偵懳偟丄1958擭9寧丄僼儔儞僗嫟摨懱偺尦偱偺戝暆側帺帯傪擣傔偨戞屲嫟榓崙寷朄偺彸擣傪媮傔偨丅媫恑揑撈棫攈偩偭偨僙僋丒僩僁乕儗棪偄傞僊僯傾偼偙傟傪斲寛偟扨撈撈棫偺摴傪曕傫偩傕偺偺丄偦傟埲奜偺怉柉抧偼偡傋偰偙傟傪彸擣偟丄1960擭偵偼偙傟傜偺怉柉抧偼偡傋偰撈棫偟偰偄傞(偙偺偙偲偵傛傝丄1960擭偼乽傾僼儕僇偺擭乿偲傕屇偽傟傞偙偲偲側偭偨)丅偙傟偵傛偭偰丄僼儔儞僗偼撈棫摤憟偵傛偭偰崙椡傪偡傝尭傜偡偙偲側偔丄撈棫屻偺彅崙偵懳偟嫮偄塭嬁椡傪曐帩偡傞偙偲偑偱偒偨丅
仭撈帺楬慄
搶惣椉恮塩偺娫偱椻愴偑懕偔拞丄僪丒僑乕儖偼傾儊儕僇偲僜楢偺挻戝崙傪拞怱偲偡傞椉恮塩偲偼暿偵丄儓乕儘僢僷彅崙偵傛傞乽戞嶰偺嬌乿傪嶌傞傋偒偩偲偄偆堄幆傪帩偪丄僼儔儞僗傪偦偺拞怱偲偟傛偆偲偟偰偄偨偙偲傪丄堚嶌偲側偭偨夞憐榐偺拞偱傕弎傋偰偄傞丅斵帺恎偼儓乕儘僢僷奺崙偑楌巎傗暥壔揑攚宨傪柍帇偟偰摑崌偡傞偙偲偼柍棟偩偲峫偊偰偄偨偑丄奺崙偑嫟摨偟偰帠偵摉偨傞楢崌偵偼傓偟傠愊嬌揑偩偭偨丅
偦偙偱惣僪僀僣偲偼榓夝丒嫤椡傪恑傔傞斀柺丄傾儊儕僇庡摫偺杒戝惣梞忦栺婡峔(NATO)傗崙嵺楢崌偵偼斸敾揑側懺搙傪庢傝丄1966擭偵NATO偺孯帠婡峔偐傜扙戅(堦斒偺惌帯晹栧偵偼巆棷)偟偨丅偦偺偨傔丄NATO杮晹偼僼儔儞僗偺僷儕偐傜儀儖僊乕偺僽儕儏僢僙儖傊偺堏揮傪梋媀側偔偝傟偨丅偦傟偲暲峴偟偰崙楢暘扴嬥偺巟暐偄傪掆巭偟丄傾儊儕僇偲嬤偄棫応傪庢傞僀僊儕僗偺墷廈宱嵪嫟摨懱(EEC)傊偺壛柨嫅斲傕昞柧偟偨丅偙偺帪婜偵偼搶儓乕儘僢僷彅崙傕楌朘偟偰偄傞丅傑偨摉帪寖壔偟偰偄偨儀僩僫儉愴憟偵懳偡傞傾儊儕僇偺夘擖傪斸敾偟丄儀僩僫儉偺拞棫壔傪傾儊儕僇偵採埬偟偨偑丄庴偗擖傟傜傟側偐偭偨丅偙偺拞棫壔峔憐偼愴屻偵側偭偰傾儊儕僇懁偱傕嵞昡壙偑帋傒傜傟傞傛偆偵側偭偨丅
傑偨丄乽僼儔儞僗偺埨慡曐忈偑傾儊儕僇偺妀偺嶱偵埶懚偣偢偵嵪傓乿偲偺怣擮偱丄捠忢暫椡嶍尭偺戙傢傝偵僼儔儞僗撈帺偺妀暫婍偺奐敪傪悇恑偟丄1960擭2寧偵偼僒僴儔嵒敊偺儗僈乕僰幚尡応偱尨敋幚尡偵惉岟偟丄傾儊儕僇丄僜楢丄僀僊儕僗偵師偖妀曐桳崙偲側偭偨丅1964擭偵偼僀僊儕僗傪彍偔懠偺惣懁愭恑崙偱偼嵟傕憗偔丄嫟嶻庡媊惌尃壓偺拞壺恖柉嫟榓崙傪崙壠彸擣偟偨丅2擭屻丄拞崙偱暥壔戝妚柦偑婲偙偭偨丅1967擭7寧24擔偵偼丄儌儞僩儕僆乕儖枩崙攷棗夛朘栤偺偨傔偵朘傟偰偄偨僇僫僟偺働儀僢僋廈儌儞僩儕僆乕儖巗偱丄孮廤傪慜偵乽帺桼働儀僢僋枩嵨!乿(Vive le Québec libre!) 偲惡傪忋偘丄僇僫僟偲僼儔儞僗偲偺娫偺奜岎栤戣偵側偭偨偩偗偱側偔丄働儀僢僋撈棫塣摦偺壩偵桘傪拲偖寢壥偲傕側偭偨丅
仭屲寧妚柦
悽奅揑側妛惗塣摦偺崅傑傝偲嫟偵丄嵍攈揑側敪憐偐傜尰戙幮夛傪乽娗棟幮夛乿偲偟偰崘敪偡傞婡塣偑崅傑傞丅偦偺偝側偐丄彈巕椌傊偺怤擖傪嬛巭偝傟偨抝巕戝妛惗偺峈媍偐傜1968擭丄屲寧妚柦偑杣敪偡傞丅僼儔儞僗慡搚傪僗僩儔僀僉偺棐偑廝偄丄僪丒僑乕儖偼婋婡偵娮傞丅偟偐偟斵偼僕儑儖僕儏丒億儞僺僪僁乕庱憡側偳偺姪傔傕偁傝丄媍夛傪夝嶶偟偰崙柉偺堄巚傪栤偆偙偲傪昞柧偟偨丅偦傟偵屇墳偟偨僪丒僑乕儖巟帩偺戝婯柾側僨儌偑峴傢傟丄傑偨僆儕償傿僄丒僕僃儖儅儞僩儅偑僜儖儃儞僰戝妛戝島摪偱僪丒僑乕儖巟帩偺墘愢傪峴偆丅屲寧妚柦偼媫懍偵椡傪幐偄丄僪丒僑乕儖偼媍夛慖嫇偱傕埑彑偟偰婋婡傪忔傝墇偊傞丅
偟偐偟梻1969擭偵偼丄斵偑崙柉搳昜偵晅偟偨忋堾媦傃抧曽峴惌惂搙偺夵妚埬偑斲寛偝傟丄偦偺昁梫偑側偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢僪丒僑乕儖偼帿擟偟偨丅偙偺夵妚埬帺懱偼媍夛傪捠夁偝偣傞偙偲偑晄壜擻偱偼側偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄僪丒僑乕儖偑懁嬤偨偪偺斀懳傪墴偟愗偭偰姼偊偰崙柉搳昜傪峴偭偨恀堄偼柧傜偐偱偼側偄丅
|
仭堷戅屻
帿擟屻偼抧曽偺嶳懞僐儘儞儀丒儗丒僪僁丒僛僌儕乕僘偵廧嫃傪堏偟偰幏昅妶摦偵愱擮偟丄梻1970擭11寧偵夝棧惈戝摦柆釒攋楐偵傛傝79嵨偱巰嫀偟偨丅亀婓朷偺夞憐亁偲戣偟偨夞憐榐偑枹姰偺愨昅偲側偭偨丅
堚尵彂偵偼丄乽崙憭偼晄梫丅孧復摍偼堦愗帿戅丅憭媀偼僐儘儞儀偱丄壠懓偺庤偵傛傝娙慺偵峴偆傛偆偵乿偲婰偝傟偰偄偨偑丄僼儔儞僗惌晎偺婓朷傕偁傝丄寢嬊崙憭偑幏傝峴傢傟偨丅曟抧偼婓朷捠傝僐儘儞儀丒儗丒僪僁丒僛僌儕乕僘偵偁傞丅
丂 |
| 仭僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉 / 僫僔僆僫儕僗儅丒僇僞儔乕 |
   丂
丂
|
僇僞儖乕僯儍偵偝傜偵崅搙側帺帯傪媮傔傞丄傑偨偼僇僞儖乕僯儍偑姰慡偵撈棫崙壠偲側傞偙偲傪栚巜偡惌帯塣摦丅抧堟僫僔儑僫儕僘儉偺柤徧丅
僇僞儖乕僯儍偺楌巎丄僇僞儖乕僯儍岅丄僇僞儖乕僯儍撈帺偺柉朄偲偄偭偨楌巎揑尃棙偵崻偞偟偰偄傞丅尰嵼偺億儕僔乕偼丄1830擭戙偵偝偐傫偲側偭偨暥壔塣摦僇僞儔僯僗儌(es丄僇僞儖乕僯儍偼僗儁僀儞偲偼堎側傞楌巎偲暥壔傪帩偭偨懚嵼偱丄偦偺撈帺惈偺壙抣傪擣傔丄曐懚偟偰偄偙偆偲偄偆惌帯揑怣忦)偲偟偰惗傑傟偨傕偺偑丄1890擭戙偵柧妋偵側偭偨僇僞儖乕僯儍偺惌帯塣摦偲寢傃偮偄偰20悽婭弶摢偵娤擮揑偵宍嶌傜傟偨丅惌帯壠僶儗儞僥傿丒傾儖儈儔僀(en)偲抦幆奒媺偨偪偼偙偺夁掱偵嶲壛偟丄僇僞儖乕僯儍岅偺彸擣傪摼傞偺偲摨條偵帺帯傪暅妶偝偣傞偲偄偆怴偨側惌帯僀僨僆儘僊乕傪懙偊偨丅偙傟傜偺梫媮偼丄僇僞儖乕僯儍寷朄(es丄嵟屆偺傕偺偼1283擭偺僐儖僣偱惉棫)偺暅妶傪愢偄偨1892擭偺儅儞儗僓憪埬(es)偵梫栺偝傟偰偄傞丅
尰嵼丄嵍梼丄拞摴丄塃梼偺惌搣偍傛傃巗柉傪曪妵偡傞傕偺偲側偭偰偄傞丅
|
仭僫僔儑僫儕僘儉偺挭棳
仭柉懓帺寛尃
庡偲偟偰尰嵼僇僞儖乕僯儍柉庡廤拞(Convergència Democràtica de Catalunya丄棯徧CDC)偑棪偄傞丅偙偺惌搣偼丄僇僞儖乕僯儍偼崙(Nació)偱偁傝丄偝傜側傞帺帯偺奼戝傪妉摼偡傋偒偲榑偠傞丅偦偟偰丄僇僞儖乕僯儍恖帺恎偑丄僇僞儖乕僯儍偑彅柉懓偑摑崌偟偨扨堦崙壠丄偁傞偄偼楢朚惂崙壠偲偟偰偺僗儁僀儞偵巆棷偡傋偒偐丄撈棫偡傋偒偐傪寛傔傞柉懓帺寛尃傪桳偡傞偲偄偆偙偲傪擣傔傞傋偒偱偁傞偲偡傞丅
仭撈棫
僇僞儖乕僯儍嫟榓庡媊嵍梼(en丄棯徧ERC)偑宖偘傞丅CDC偺堦晹傕巟帩偟偰偄傞偑丄僇僞儖乕僯儍撈棫偺峔憐傪庣傝丄撈棫偵岦偗偰偺僗僥僢僾偲偟偰僇僞儖乕僯儍偺帺屓寛掕尃傪妉摼偟傛偆偲偡傞偙偺摦偒偼丄偝傜偵彮悢攈偲側偭偰偄傞丅
撈棫塣摦埲忋偵丄崙偲偟偰偺僇僞儖乕僯儍偼帺帯廈偩偗偵偲偳傑傜偢丄僇僞儖乕僯儍岅傗僇僞儖乕僯儍暥壔傪嫟桳偡傞僶儗儞僔傾廈丄僶儗傾儗僗彅搰丄傾儔僑儞廈偺搶晹偵偁傞僼儔儞僴抧曽丄杒僇僞儖乕僯儍偲傕屇偽傟傞僼儔儞僗偺儖僔儓儞丄僒儖僨乕僯儍搰偺傾儖僎乕儘丄傾儞僪儔岞崙偐傜側傞偺偑僇僞儖乕僯儍崙偱偁傞偲偄偆巚憐偑桪惃偱偁傞丅偙傟傜偺抧堟偼堦曽偱僇僞儖乕僯儍岅寳偺柤偑偮偗傜傟丄偙偺棳傟偺媶嬌偺慱偄偼崙楢崌傪偮偔傞偙偲偱偁傞丅
|
仭棟擮
僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偲撈棫塣摦偼丄僇僞儖乕僯儍暥壔偼僗儁僀儞(偡側傢偪僇僗僥傿乕儕儍)偺暥壔偲偼堎側傞偲庡挘偡傞丅1714擭偵僗儁僀儞丒僽儖儃儞壠偑晲椡偱僇僞儖乕僯儍傪愯椞偟偰偐傜丄埲屻梷埑偝傟懕偗偰偒偨崙偱偁傞偲庡挘偡傞丅僼僃儕儁5悽偑晍崘偟偨怴崙壠婎杮朄偵傛偭偰丄僗儁僀儞宲彸愴憟屻偨偩偪偵僇僞儖乕僯儍偺朄惂搙偼攑巭偝傟丄岞揑側応強偱偺僇僞儖乕僯儍岅巊梡偑嬛巭偝傟偨丅暥壔揑棫応偐傜丄僇僞儖乕僯儍偺僫僔儑僫儕僗僩偼丄僇僞儖乕僯儍偵偍偄偰偁傜備傞幮夛揑側応柺偱丄僇僞儖乕僯儍恖偼僇僗僥傿乕儕儍岅傛傝傕桪愭偟偰柉懓撈帺偺尵梩丒僇僞儖乕僯儍岅傪巊偍偆偲彠椼偡傞丅壛偊偰丄榖幰偺懡偝傗暥壔揑丒揱摑揑棫応偐傜丄僗儁僀儞惌晎巤愝丄傑偨偼儓乕儘僢僷奺崙偺巤愝偱僇僞儖乕僯儍岅傪榖偡尃棙傪庣傠偆偲偡傞丅
僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僗僩偲僇僞儖乕僯儍暘棧庡媊幰偼丄僇僞儖乕僯儍偼嵿惌愒帤傪杽傔傛偆偲偡傞僗儁僀儞崙壠偵傛偭偰宱嵪揑懝奞傪偙偆傓偭偰偄傞偲庡挘偡傞丅傑偨擺傔偨惻嬥傛傝傕丄庴偗傞傋偒壎宐偑彮側偄偲偡傞丅偙傟傜偺棟桼偐傜丄揱摑揑偵僇僞儖乕僯儍偼巌朄丄峴惌丄棫朄丄暥壔丄宱嵪偺奺棫応偐傜丄尰嵼傛傝傕偝傜偵崅搙側帺帯傪梫媮偟偰偄傞丅
徾挜揑側棫応偐傜偼丄僇僞儖乕僯儍偼僗儁僀儞慖庤抍偺峔惉偵壛傢傜偢丄僇僞儖乕僯儍撈帺偺慖庤抍傪帩偮傋偒偲榑偢傞丅僗儁僀儞慖庤抍偲偼柧傜偐偵嬫暿偟偰丄旕崙壠偱偁傞僗僐僢僩儔儞僪丄僂僃乕儖僘丄儅僇僆偺傛偆偵丄崙嵺揑側僗億乕僣僀儀儞僩偵岞幃偵嶲壛偡傋偒偲偄偆丅
僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偲僇僞儔僯僗儌傪嬫暿偟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄僇僞儖乕僯儍偺徾挜傗揱摑傪徿巀偟側偑傜僇僞儖乕僯儍岅偲偄偆暥壔傪庣傞偙偲偲丄偝傜偵戝偒側帺帯偺妉摼傪愢偔偙偲偼丄僫僔儑僫儕僘儉偺僷儔儊乕僞乕偺傕偲偱偼偦偺惌帯揑傾僾儘乕僠偑柧妋偱側偄偲偙傠偱偁傞丅偟偐偟懡偔偺挷嵏偵傛傟偽丄僇僞儖乕僯儍恖偺戝晹暘偑僇僞儖乕僯儍偑崙偱偁傞偲怣偠偰偍傝丄惌帯峴摦傪峴偆婡娭偱偼側偄偲偟丄僗儁僀儞崙撪偱偺僇僞儖乕僯儍崙偺姰慡摑崌傪愢偔丅僇僞儖乕僯儍撈棫塣摦偲偄偆慖戰傪攔彍偟偰偄傞偺偱偁傞丅僇僞儖乕僯儍撈棫塣摦偱偼丄僇僞儖乕僯儍幮夛庡媊幰搣(PSC)媦傃僇僞儖乕僯儍椢偺僀僯僔傾僥傿僽偲偄偭偨惌搣偼亀僫僔儑僫儕僗僩亁偲傒側偝傟側偄偑丄僇僞儖乕僯儍恖偲偟偰惓幃偵僇僞儖乕僯儍偼崙偱偁傞偲偄偆棟擮傪庣偭偰偍傝丄尰嵼偺帺帯廈偺榞慻傒傑偨偼楢朚崙壠偺掕懃偵偍偄偰僗儁僀儞偺堦堳偱偁傠偆偲偡傞丅
|
仭僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偺楌巎
僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偼丄僇僞儔僯僗儌偺曄堎偲偟偰丄20悽婭弶摢偵惌帯塣摦偲偟偰宍惉偝傟偨丅暥壔偲偟偰偺僫僔儑僫儕僘儉偺抋惗偼1830擭戙偱丄1890擭戙偵偼惌帯揑僫僔儑僫儕僘儉偲暘棧偟偨丅
仭儔僫僔僃儞僒
1830擭戙丄儘儅儞庡媊偺崅傑傝偐傜儔僫僔僃儞僒(Renaixença, 僇僞儖乕僯儍岅偱儖僱僒儞僗)偲屇偽傟傞塣摦偑惗傑傟偨丅儔僫僔僃儞僒偲偼抦幆揑偦偟偰暥壔揑側惙傝忋偑傝偱偁傝丄弶婜偵偼惌帯揑梫媮偼媮傔偢丄僇僞儖乕僯儍岅偺暅妶偲擣徹傪媮傔偰偄偨丅儔僫僔僃儞僒偺尮偼丄傂偲偮偼僶儗儞僥傿儞丒傾儖儈儔僀偑巒傔偨楢朚柉庡嫟榓搣丄偦偟偰傕偆傂偲偮偼僕儏僛僢僾丒僩乕儔僗偑棪偄偨僇儖儕僗僞塣摦偱偁偭偨丅斵傜偺梫媮偼丄1892擭偺儅儞儗僓憪埬偵惙傝崬傑傟偨丅
仭20悽婭
僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偑惌帯揑廳梫惈傪帩偭偰巒傑偭偨偺偼丄1901擭偺慖嫇偱抧曽惌搣丄柉懓庡媊惌搣丄曐庣惌搣偑彑棙偟偨偲偒偐傜偱偁傞丅1906擭丄孯偼僇僞儖乕僯儍岅偵嫟姶偡傞怴暦偺婲憪偵尵偄偑偐傝傪偮偗丄僫僔儑僫儕僗僩慡堳偺搟傝傪偐偒偨偰偨丅偦傟傪惌帯揑峔憿偵惙傝崬傫偩偺偑丄惌搣偺僜儕僟儕僞乕丒僇僞儖乕僯儍(僇僞儖乕僯儍楢懷)偱偁傞丅寢壥偲偟偰丄塣摦傪峔惉偡傞2梫慺丄暥壔偲惌帯偑寢傃偮偄偨丅1907擭偺慖嫇偺寢壥丄僇僞儖乕僯儍媍夛44媍惾偺偆偪41媍惾傪妉摼偟偨偺偱偁傞丅僶儖僙儘僫偺斶寑偺堦廡娫屻丄僜儕僟儕僞乕偼夝懱偝傟偨丅
1913擭丄曐庣揑側僄僪僁傾儖僪丒僟乕僩惌尃偼丄僇僞儖乕僯儍楢朚惂傪偮偔傝嵦戰偟偨丅偙傟偼丄抧曽惌搣偑棪偄傞4偮偺導媍夛傪娷傫偩丄帺帯惌晎偺堦庬偱偁偭偨丅1918擭埲崀僇僞儖乕僯儍偵偍偗傞戞堦搣偼丄僗儁僀儞媍夛偱懡偔偺媍惾傪妉摼偡傞偙偲偼側偐偭偨丅偦偺曐庣揑側巔惃偼暅屆庡媊揑側惌尃偲偮側偑傝傪帩偪丄1923擭偵惉棫偟偨僾儕儌丒僨丒儕儀乕儔惌尃偵斀懳傕偟側偐偭偨丅偟偐偟丄僗儁僀儞丒僫僔儑僫儕僘儉偲憡斀偡傞慡偰偺僫僔儑僫儕僘儉偵偮側偑傝偐偹側偄惌嶔偱偁偭偨楢朚惂偑丄崙夛偐傜庢傝壓偘傜傟偨丅堦曽偱丄CNT(es丄戞堦僀儞僞乕僫僔儑僫儖偵偮側偑傝偺偁偭偨傾僫儖僐僒儞僨傿僇儕僗儉偺楯摥慻崌)偵戙昞偝傟傞丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺戝懡悢偼傾僫乕僉僗儉傪巟帩偟偰偄偨丅
僾儕儌丒僨丒儕儀乕儔撈嵸惌尃偺捈慜丄僼儔儞僙僗僋丒儅僔傾乕偺庡摫偱弶偺恊僇僞儖乕僯儍撈棫惌搣丄傾僗僞丒僇僞儔乕(es丄僇僞儖乕僯儍崙壠)偑抋惗偟偨丅撈嵸惌尃屻丄傾僗僞丒僇僞儔乕偼嵍攈惌搣偵壛傢傝丄僇僞儖乕僯儍嫟榓庡媊嵍梼偲側偭偨丅偙偺惌搣偼丄僗儁僀儞戞擇嫟榓惌婜偵僇僞儖乕僯儍偺柨庡揑懚嵼偲側偭偨丅偙偺帪戙丄偦偟偰堦曽揑側僇僞儖乕僯儍嫟榓崙偺愰尵屻丄僇僞儖乕僯儍偺僫僔儑僫儕僘儉偼1932擭僇僞儖乕僯儍帺帯寷復(es)傪彑偪庢偭偨(僕儍僫儔儕僞乕丒僨丒僇僞儖乕僯儍傕暅妶偟偨)丅僗儁僀儞撪愴偱僼儔儞僐偑彑棙偡傞偲丄抧堟僫僔儑僫儕僘儉偼僗儁僀儞崙壠傊偺斀媡偱偁傞偲傒側偡丄梷埑偺帪戙偑巒傑偭偨丅僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僗僩偨偪偼抧壓傊愽暁偡傞偐丄崙奜傊朣柦偟偨丅1939擭丄僼儔儞僗傊摝傟偨123戙僕儍僫儔儕僞乕庱斍儕儏僀僗丒僋儞僷僯傿僗傜偵傛偭偰丄僷儕偱僇僞儖乕僯儍崙柉夛媍(ca)偑慻怐偝傟偨(僫僠僗偺僼儔儞僗怤峌屻偼儘儞僪儞傊摝傟偨)丅僋儞僷僯傿僗偺孻巰屻偼丄僕儏僛僢僾丒僀儖儔偑僕儍僫儔儕僞乕傪棪偄偨丅
帺桼偺側偄帪戙偱偁偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄1951擭丄1956擭丄1971擭丄1974擭偲暋悢夞偺楯摥幰僨儌偑慻怐偝傟丄夞傪廳偹傞偛偲偵婯柾偑戝偒偔側偭偨丅1958擭偵旕崌朄偵寢惉偝傟偨僇僩儕僢僋宯楯摥慻崌僇僞儖乕僯儍丒僉儕僗僩嫵楯摥幰楢懷偼丄1961擭偵僇僞儖乕僯儍丒楯摥幰楢懷偵柤徧傪曄偊丄媫恑攈偲拞娫攈傪書偊偨丅斀僼儔儞僐傪彞偊傞抍懱偲偟偰偼丄傾僙儞僽儗傾丒僨丒僇僞儖乕僯儍(ca)偑偁偭偨丅斵傜偼帺桼丄壎幫丄1932擭偺帺帯朄暅妶丄柉庡惃椡偺摑崌傪媮傔丄嵍塃椉攈偐傜峀偔嶲壛幰偑偁偭偨丅僼儔儞僐偑杤偟偨1975擭埲屻丄柉惌堏娗偑恑傔傜傟偨丅
1977擭丄僕儏僛僢僾丒僞儔僨乕儕儍僗棪偄傞僕儍僫儔儕僞乕偑丄挿偄朣柦婜娫傪廔偊偰僇僞儖乕僯儍傊栠偭偨丅1978擭僗儁僀儞寷朄偱偼丄僗儁僀儞偼懡偔偺崙偲抧堟偐傜側傞崙壠偱偁傞偲擣幆偝傟偨丅1980擭8寧11擔丄僇僞儖乕僯儍偼帺帯廈偲側偭偨丅摨擭偺帺帯廈慖嫇偱丄僕儑儖僨傿丒僾僕儑儖棪偄傞曐庣丒柉懓庡媊惌搣廤拞偲摑堦(棯徧CiU)偑戞堦搣偲側傝丄偙偺忬懺偼2003擭傑偱懕偄偨丅
仭21悽婭
2003擭11寧丄廤拞偲摑堦偼慖嫇偱攕戅偟偨丅帺帯廈媍夛偼嶰搣楢棫偲側傝丄僷僗僋傾儖丒儅儔僈僀偑僕儍僫儔儕僞乕庱斍偲側偭偨丅媍堳悢偱偼CiU偑嵟戝偱偁傞偑丄僇僞儖乕僯儍幮夛庡媊幰搣(es丄棯徧PSC)丄ERC丄PP丄ICV偑偙傟偵懕偄偨丅
2006擭僇僞儖乕僯儍帺帯廈慖嫇偱偼丄庡梫惌搣偑僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉惌搣偱愯傔傜傟偨丅僇僞儖乕僯儍柉庡廤拞丄僇僞儖乕僯儍柉庡楢崌(es丄棯徧Unio)丄僇僞儖乕僯儍嫟榓庡媊嵍梼偺嶰搣偱丄摼昜棪偼45.88亾偱偁偭偨丅偙傟傜偺惌搣偺拞偱偼堄尒偑暘嶶偟偰偄傞丅傛傝媫恑揑側恖乆偼丄暘棧偟偨僇僞儖乕僯儍崙壠庽棫偵枮懌偟偰偄傞偩偗偱偁傞丅懳徠揑偵丄傛傝壐寬側恖乆偼丄僇僞儖乕僯儍偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕偺曐岇偼僗儁僀儞崙撪偱憡梕傟傜傟側偄偲妋怣偟偰偍傝丄昁偢偟傕摨偠偲偄偆傢偗偱偼側偄丅傑偨懠偺恖乆偼峈媍偺堄枴偱偙傟傜偺惌搣偵搳昜偟偰偍傝丄慡懱揑側惌搣峧椞偲昁偢偟傕堦懱姶偼帩偭偰偄側偄(偨偲偊偽丄堦晹偺恖乆偼扨偵CiU偵朞偒偰偄傞偺偱丄嵍梼宯偺嫟榓崙惉棫傪朷傫偱偄側偔偰傕丄ERC偵搳昜偟偨偐傕偟傟側偄)丅
2006擭丄傛傝帺帯廈惌晎偺尃尷偑奼戝偝傟偨丄僇僞儖乕僯儍帺帯寷復夵惓偺廧柉搳昜偑峴傢傟偨丅栺73.24亾偺巀惉搳昜傪庴偗丄2006擭8寧偵巤峴偝傟偨丅偟偐偟丄48.84亾偺搳昜棪偼丄僇僞儖乕僯儍偺柉庡庡媊惌帯偺楌巎偺拞偱嵟傕崅偄婞尃偑峴傢傟偨偙偲傪堄枴偟偨丅偙傟偼丄堦斒戝廜偑夝偒曻偨傟偰偄傞徹偟丄傑偨偼僇僞儖乕僯儍偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕惌嶔偲偺憟偄偺椉曽偑堷偒崌偄偵弌偝傟偨丅
偟偐偟丄帺帯偱偼晄廫暘偱偁傞偲偟偰丄僇僞儖乕僯儍偱偼撈棫傪媮傔傞惡偑堦掕悢偁傞丅摿偵丄僜僽儕儞婋婡偵抂傪敪偡傞宱嵪婋婡偺忬嫷壓偱丄宱嵪惌嶔偵偍偄偰僇僞儖乕僯儍偑懠偺帺帯廈傛傝傕晄摉偵埖傢傟偰偄傞偲偺巚偄偐傜丄撈棫惃椡偼惃偄傪摼偮偮偁傞丅2012擭11寧25擔偺僇僞儖乕僯儍廈媍夛慖嫇偱偼丄撈棫傪庡挘偡傞4偮偺惌搣偑崌寁87媍惾偲丄慡懱偺栺3暘偺2傪妉摼偟偰偄傞丅9寧11擔偼丄僗儁僀儞宲彸愴憟偺嵟屻偺愴偄偱偁傞僶儖僙儘僫曪埻愴偱丄僇僞儖乕僯儍偑僗儁僀儞丒僼儔儞僗楢崌孯偵攕杒偟偨擔偱偁傝丄乽僇僞儖乕僯儍偺擔乿偲偄偆婰擮擔偲側偭偰偄傞丅偙偺擔偵偼撈棫傪媮傔傞僇僞儖乕僯儍巗柉偑100枩恖扨埵偱廤傑傝丄恖娫偺嵔傪嶌偭偰惌晎偵撈棫傪媮傔偰偄傞丅僇僞儖乕僯儍偱偼丄2014擭偵撈棫偵娭偡傞廧柉搳昜傪梊掕偟偰偄傞丅偟偐偟丄拞墰惌晎偺儔儂僀庱憡偼偙偺廧柉搳昜傪慾巭偡傞峔偊傪曵偟偰偄側偄丅堦曽丄撈棫斀懳傪彞偊傞僇僞儖乕僯儍廧柉傕彮側偔側偔丄2013擭10寧12擔偵偼丄撈棫斀懳傪彞偊傞悢枩恖婯柾偺僨儌偑峴傢傟偨丅僨儌偺嶲壛幰偼丄庡嵜幰敪昞16枩恖丄僶儖僙儘僫摉嬊偼3枩恖偲偟偰偄傞丅
2014擭11寧9擔偵幚巤偝傟偨僇僞儖乕僯儍廈撈棫傪栤偆廧柉搳昜偱偼僇僞儖乕僯儍廈偼崙壠偱偁傞傋偒偱偁傝丄撈棫傪朷傓惡偑80.76%偵払偟偨丅2015擭9寧27擔偵搳奐昜偝傟偨僇僞儖乕僯儍帺帯廈媍夛慖嫇偱偼僇僞儖乕僯儍廈撈棫巀惉攈偑135媍惾拞夁敿悢偺72媍惾傪妉摼偟丄2015擭11寧9擔丄僇僞儖乕僯儍媍夛偼僇僞儖乕僯儍撈棫庤懕偒奐巒愰尵傪嵦戰偟偨丅丂 |
| 仭僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉 |
   丂
丂
|
|
僀儞僪偵偍偗傞僫僔儑僫儕僘儉偼丄僀儞僪撈棫塣摦傪捠偠偰宍惉偝傟丄僀儞僪幮夛偵偍偗傞柉懓丄廆嫵揑懳棫偲摨條偵僀儞僪偺惌帯偵嫮偄塭嬁傪梌偊懕偗偰偄傞丅僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉偼偟偽偟偽1947擭偺僀僊儕僗偐傜偺撈棫埲慜偵擣傔傜傟偨丄僀儞僪暥壔寳偑僀儞僪垷戝棨傂偄偰偼傾僕傾偵梌偊偨塭嬁偲寢傃偮偗偰岅傜傟傞丅
|
仭僀儞僪偺崙壠堄幆
僀儞僪偱偼楌巎忋丄懡偔偺掗崙傗惌晎偵傛偭偰摑堦崙壠偑惗傑傟偰偒偨丅屆戙偺暥彂偵偍偄偰偼僶乕儔僞墹偺傾僇儞僟丒僶乕儔僞偑僀儞僪偺椞堟傪婯掕偟偰偍傝丄偙傟傜偺抧堟偑尰嵼偺僀儞僪暥壔寳傪宍惉偟偰偄傞丅儅僂儕儎挬偼僀儞僪慡堟偲撿傾僕傾丄儁儖僔儍偺戝晹暘傪斉恾偵壛偊偨嵟弶偺摑堦崙壠偲側偭偨丅埲屻丄僀儞僪偺奺帪戙偺崙壠偼僌僾僞挬丄儔乕僔儏僩儔僋乕僞挬丄僷乕儔挬丄儉僈儖掗崙丄僀僊儕僗椞僀儞僪掗崙側偳偑拞墰惌晎傪帩偮摑堦崙壠偲偟偰孨椪偟偰偒偨丅
仭斈撿傾僕傾庡媊
僀儞僪偺崙壠奣擮偼扨偵庡尃偺媦傇椞堟偺奼戝傪婎慴偲偼偟偰偄側偄丅僫僔儑僫儕僘儉偺婎慴偲側偭偰偄傞偺偼丄屆戙僀儞僪偵偍偗傞僀儞僟僗暥柧偲償僃乕僟帪戙丄偦偟偰悽奅偺庡梫廆嫵偵悢偊傜傟傞僸儞僪僁乕嫵丄暓嫵丄僕儍僀僫嫵丄僔僋嫵傪惗傒弌偟偰偄傞揰偵偁傞丅僀儞僪偺僫僔儑僫儕僗僩偼僀儞僪傪僀儞僪垷戝棨慡懱偺椞堟傪偝偟偰僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉傪榑偠傞偙偲偑懡偄丅
仭懠崙偺怤峌
僀儞僪偼夁嫀偺楌巎忋丄儅儔乕僞乕墹崙偵偍偗傞僔償傽乕僕乕丄僕儍乕儞僔乕偵偍偗傞儔僋僔儏儈乕丒僶乕僀乕丄儔乕僕僾乕僞乕僫乕偵偍偗傞僉僢僩僁乕儖丒僠僃儞僫儅傗僾儔僞乕僾丒僔儞僌(儅僴乕儔乕僫乕丒僾儔僞乕僾)丄僠儍僂僴乕儞挬偺僾儕僩償傿乕儔乕僕3悽丄僈僘僫挬峜掗儅僼儉乕僪傗僀僊儕僗偺僀儞僪巟攝傪攔彍偟傛偆偲偟偨僥傿僾乕丒僗儖僞乕儞側偳丄懠崙偺僀儞僪怤峌傗僀儞僪巟攝偵懳偟偰懡偔偺墹丄墹斳傪梚偟偰懳峈偟偰偒偨丅儅僂儕儎挬偺僠儍儞僪儔僌僾僞傗儅僈僟崙偺傾僔儑乕僇墹側偳丄屆戙僀儞僪偺墹偼廆嫵揑側姲梕偝傕偝傞偙偲側偑傜愴偺揤嵥偲偟偰屻悽偵岅傝宲偑傟偰偄傞丅
儉僗儕儉偺墹傕傑偨僀儞僪偺屩傝偺堦晹偲側偭偰偄傞丅儉僈儖掗崙嵟惙婜偺墹偱偁偭偨傾僋僶儖偼崙撪偺廆嫵揑懳棫傪夝徚偟傛偆偲偟丄崙撪偵僇僩儕僢僋嫵夛傪愝抲偡傞偙偲偱僸儞僪僁乕嫵搆丄暓嫵搆丄僔僋嫵搆丄僕儍僀僫嫵搆側偳偲嫟偵丄僇僩儕僢僋怣幰偲傕桭岲娭學傪曐偭偰偄偨偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅僸儞僪僁乕嫵搆偱偁傞儔乕僕僾乕僩偺墹偲寣墢揑丄惌帯揑寢傃偮偒傪嫮傔偨丅
傾僋僶儖埲慜偺僗儖僞乕儞偼懡偐傟彮側偐傟廆嫵揑偵姲梕偱偼偁偭偨傕偺偺丄傾僋僶儖偼偝傜偵恑傫偱丄崙撪偵偍偗傞僀僗儔乕儉嫵偺姰慡側怣嬄偺帺桼傪曐徹偟丄婛懚偺廆嫵偲偺崿崌傪帋傒偨丅傾僋僶儖偼廆嫵揑嵎暿傪揚攑偟丄僸儞僪僁乕嫵搆偺戝恇側偳傪搊梡偟丄墹偺慜偵偍偄偰廆嫵揑媍榑傑偱峴傢偣偨丅
|
仭僗儚儔乕僕
1857擭偵婲偒偨僀儞僪戝斀棎偵偍偄偰丄僀儞僪恖暫巑偲抧曽偺斔墹崙偺斔墹偼僀僊儕僗掗崙偵懳偟偰斀棎傪婲偙偟偨丅偙偺斀棎偼崙搚慡搚傪暍偆婯柾偵傑偱敪揥偟偨偩偗偱側偔丄彨棃偺僫僔儑僫儕僘儉宍惉偺婎慴偲側傝丄廆嫵揑丄柉懓揑側懳棫傕惗傒弌偟偨丅
帺帯傪堄枴偡傞乽僗儚儔乕僕乿偼僀儞僪偺姰慡側撈棫傪梫媮偡傞僶乕儖丒僈儞僈乕僟儖丒僥傿儔僋偵傛偭偰採彞偝傟偨偑丄戞堦師悽奅戝愴屻傑偱幚傪寢傇偙偲偼側偐偭偨丅1919擭丄儘乕儔僢僩朄敪晍偵懳偡傞峈媍偺偨傔偵廤傑偭偨旕晲憰偺僀儞僪恖巗柉偵懳偟僀僊儕僗孯偑柍嵎暿幩寕傪峴偭偨傾儉儕僢僩僒儖帠審偺屻丄僀儞僪崙柉偼搟傝傪敋敪偝偣丄僀儞僪崙柉夛媍偵偍偄偰僀僊儕僗偐傜偺撈棫傪柾嶕偡傞傛偆偵側偭偨丅
仭僈儞僨傿乕傜偵傛傞撈棫塣摦
儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕偼傾僸儞僒乕 (旕朶椡)偲巗柉揑晄暈廬傪宖偘丄墫偺峴恑偵戙昞偝傟傞僒僥傿儎乕僌儔僴塣摦傪峴偭偨嵟弶偺恖暔偱偁傞丅偙偺塣摦偵傛傝丄堦斒戝廜傕朶椡傗偦偺懠偺岲傑偟偔側偄庤抜傪梡偄傞偙偲側偔丄僀僊儕僗偵懳偡傞妚柦塣摦偵嶲壛偡傞偙偲偑壜擻偲側偭偨丅僈儞僨傿乕偼柉庡庡媊傗廆嫵揑丄柉懓揑暯摍偵偙偩傢傞偩偗偱側偔丄僇乕僗僩惂搙偵崻偞偟偨嵎暿偺揚攑塣摦傕揥奐偟丄僀儞僪偺楌巎忋弶傔偰晄壜怗柉偲屇偽傟傞恖乆偑妚柦塣摦偵嶲壛偡傞偙偲偵側偭偨丅
堦斒戝廜偑僀儞僪偵偍偗傞帺桼摤憟傊偲嶲壛偟偨偙偲偵傛傝丄妚柦塣摦偵嶲壛偡傞悢偼1930擭戙傑偱偵悢愮枩恖偵傑偱朿傟忋偑偭偨丅壛偊偰丄僈儞僨傿乕偼1918擭偐傜1919擭偵偐偗偰峴偭偨僠儍儞僷儔儞偲働僟偵偍偗傞僒僥傿儎乕僌儔僴偵傛傞彑棙偼丄僀儞僪偺惵擭憌偵懳偟僀僊儕僗偺巟攝傪懪攋偱偒傞偲偄偆帺怣傪梌偊偨丅償傽僢儔僽僶乕僀乕丒僷僥乕儖丄僕儍儚乕僴儖儔乕儖丒僱儖乕丄傾僽儖丒僇儔乕儉丒傾乕僓乕僪丄僠儍僋儔償傽儖僥傿乕丒儔乕僕儍僑乕僷乕儔乕僠儍乕儕乕丄儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕丄儔乕僕僃乕儞僪儔丒僾儔僒乕僪丄僴乕儞丒傾僽僪僁儖丒僈僢僼傽乕儖丒僴乕儞偲偄偭偨撈棫巜摫幰偼丄抧堟傗柉懓憌傪挻偊偰僀儞僪偺恖乆偵巟帩偝傟丄嫮椡側儕乕僟乕僔僢僾偵傛偭偰崙壠偺惌帯揑曽岦惈偺婎斦傪抸偄偨丅
|
仭僀儞僪恖偺榞慻傪挻偊偰
僀儞僪偼偦偺柉懓揑丄廆嫵揑側懡條惈偲摨條丄僫僔儑僫儕僘儉偵偍偄偰傕懡條側懁柺傪尒偣傞丅廬偭偰丄嵟傕塭嬁偺戝偒偄掙棳偵偁傞傕偺偼扨側傞乽僀儞僪恖乿偲偄偆榞慻傒傪挻偊偰偄傞丅僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉偵偍偄偰嵟傕媍榑偺揑偵側傝丄姶忣揑懳棫偑惗傑傟傞傕偺偑廆嫵偱偁傞丅廆嫵偼僀儞僪恖偺惗妶偵偍偄偰丄庡梫偐偮丄懡偔偺応崌偵偍偄偰崪巕偲側傞梫慺傪宍惉偟偰偄傞丅僀儞僪偵偼丄尵岅丄幮夛姷廗丄楌巎忋偺宱堒側偳偱嬫暘偝傟傞懡條側柉懓僐儈儏僯僥傿偑偁傞丅
仭僸儞僪僁乕丒僫僔儑僫儕僘儉
僀儞僪偵偍偄偰僀僗儔乕儉嫵巟帩幰偑巟攝幰憌偵偄偨帪戙偐傜丄僸儞僪僁乕嫵帥堾偺攋夡傗僀僗儔乕儉嫵傊偺嫮惂揑側夵廆丄僀僗儔儉嫵搆偵傛傞怤棯偼僸儞僪僁乕嫵偵廳戝側塭嬁傪傕偨傜偟偰偒偨丅
20悽婭偵擖傝丄僸儞僪僁乕嫵搆偼慡恖岥偺75亾傪挻偊丄僸儞僪僁乕嫵偼僫僔儑僫儕僘儉偺嫆傝強偲偄偭偰傕傛偄傕偺偲側偭偨丅尰戙偺僸儞僪僁乕嫵偱偼丄僇乕僗僩傗尵岅揑丄柉懓揑側堘偄傪挻偊偨僸儞僪僁乕嫵幮夛偺摑堦傪栚巜偟偰偄傞丅1925擭丄働乕僔儍償丒僶儕儔乕儉丒僿乕僪僎乕儚乕儖偼儅僴乕儔乕僔儏僩儔廈偺僫乕僌僾儖偵偍偄偰丄僸儞僪僁乕帄忋庡媊傪婎斦偵悩偊偨巗柉抍懱偱偁傞柉懓媊桬抍傪愝棫偟偨丅
償傿僫乕儎僋丒僟乕儌乕僟儖丒僒乕償傽儖僇儖偼僸儞僪僁乕丒僫僔儑僫儕僘儉傪懱尰偡傞崙壠偺妀偲側傞奣擮偲偟偰僸儞僪僁僩償傽偲偄偆梡岅傪摫擖偟偨丅偙偺奣擮偼僀儞僪恖柉搣傗償傿僔儏償傽丒僸儞僪僁乕丒僷儕僔儍僪偺傛偆側崱擔偺僸儞僪僁乕帄忋庡媊巟帩抍懱偺廆嫵揑丄惌帯揑側婎斦偲側偭偰偄傞丅
僸儞僪僁僩償傽偺巟帩抍懱偼僇僔儈乕儖偺傛偆側僀僗儔乕儉嫵搆偑懡悢傪愯傔傞抧堟偵偍偗傞敿帺帯揑側摿尃傪梌偊傞寷朄戞370忦偺攑巭傪庡挘偟丄儉僗儕儉偵懳偡傞摿暿側朄揑慬抲傪攑巭偟嬒堦側巗柉尃傪梌偊傞傛偆梫媮偟偰偄傞丅偙傟傜偺梫媮偼儉僗儕儉傊偺摿暿埖偄偵懳偡傞僸儞僪僁乕丒僫僔儑僫儕僘儉偺尰傟偲尒傞偙偲偑偱偒傞丅
仭僀儞僪寶崙
1906擭偐傜1907擭偵偐偗偰丄僸儞僪僁乕嫵搆偑懡悢傪愯傔傞僀儞僪崙柉夛媍傊偺儉僗儕儉偺夰媈怱偐傜僀僗儔儉嫵搆抦幆憌偵傛傝慡僀儞僪丒儉僗儕儉楢柨偑寢惉偝傟偨丅偟偐偟丄儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕偺巜摫椡偼儉僗儕儉偐傜傕暆峀偄巟帩傪廤傔偨丅傾儕乕僈儖丒儉僗儕儉戝妛偲丄僕儍乕儈傾丒儈儕傾丒僀僗儔乕儈傾偼摨偠僀僗儔乕儉嫵偺戝妛偱偁傝側偑傜丄撈棫偟偨戝妛偲側偭偰偄傞丅慜幰偼慡僀儞僪丒儉僗儕儉楢柨偺巚憐傪惀偲偡傞慻怐偱偁傝丄屻幰偼僫僔儑僫儕僘儉媦傃僈儞僨傿乕偺巚憐偵婎偯偔儉僗儕儉偺嫵堢傪峴偆応偲偟偰愝棫偝傟偨丅
儉僴儞儅僪丒僀僋僶乕儖傗儉僴儞儅僪丒傾儕乕丒僕儞僫乕偺傛偆側儉僗儕儉偑僸儞僪僁乕嫵搆偲僀僗儔儉嫵搆偼暿屄偺崙壠傪桳偡傞傋偒偩偲峫偊傞堦曽偱丄儉僼僞乕儖丒傾僼儅僪丒傾儞僒乕儕乕傗傾僽儖丒僇儔乕儉丒傾乕僓乕僪丄僴乕儞丒傾僽僪僁儖丒僈僢僼傽乕儖丒僴乕儞丄僴僉乕儉丒傾僕儏儅儖丒僴乕儞偼儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕偺巚憐傗僀儞僪偺帺桼摤憟傪巟帩偟丄僀儞僪偺儉僗儕儉偑暘棧撈棫偡傞傋偒偩偲偄偆峫偊偵斀懳偟偰偄傞丅屻幰偺峫偊偼僷儞僕儍乕僽丄僔儞僪廈丄僶儘乕僠僗僞乕儞廈丄儀儞僈儖抧曽偲偄偭偨丄慡僀儞僪丒儉僗儕儉楢柨偑惌帯揑偵嫮偄塭嬁椡傪帩偭偰偄傞抧堟傗僷僉僗僞儞偺暘棧撈棫偺塭嬁傪庴偗偨抧堟偱偼巟帩偝傟偰偄側偄丅
僓僉乕儖丒僼僒僀儞丄僼傽僼儖僢僨傿乕儞丒傾儕乕丒傾僼儅僪丄傾僽僪僁儖丒僇儔乕儉偼僀儞僪偺戝摑椞宱尡偑偁傞儉僗儕儉偱偁傞丅攐桪偺僔儍乕丒儖僋丒僴乕儞傗僫僔乕儖僨傿儞丒僔儍乕丄傾乕儈儖丒僴乕儞丄壒妝壠偺僓僉乕儖丒僼僙僀儞丄傾儉僕儍僪丒傾儕乕丒僴乕儞丄僋儕働僢僩慖庤偺僒僀僀僪丒僉儖儅乕僯乕丄僀儖僼傽儞丒僷僞儞丄僓僸乕儖丒僇乕儞丄儉僔儏僞僋丒傾儕乕丄儉僴儞儅僪丒傾僘僴儖僢僨傿乕儞偺傛偆側挊柤恖偺儉僗儕儉傕傑偨僀儞僪偺僔儞儃儖偲側偭偰偄傞丅
|
仭僫僔儑僫儕僘儉偲惌帯
僀儞僪偺嵟戝惌帯抍懱偱偁傝丄45擭偵傢偨偭偰梌搣偲偟偰惌尃傪塣塩偟偰偒偨僀儞僪崙柉夛媍偺惌帯揑側庡挘偼儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕偲僕儍儚僴儖儔乕儖丒僱儖乕丄偦偟偰斵傜偵楢側傞僱儖乕丒僈乕儞僨傿乕丒僼傽儈儕乕偵埶懚偟偰偍傝丄僀儞僪撈棫埲棃僱儖乕丒僈乕儞僨傿乕丒僼傽儈儕乕偑幚尃傪埇偭偰偒偨丅
1970擭戙慜敿傑偱僀儞僪崙柉夛媍偼僀儞僪撈棫塣摦惉岟偺壎宐傪庴偗傞宍偱惌尃傪塣塩偟偰偍傝丄僀儞僪偺帺桼丄柉庡庡媊丄摑堦傪庣傞偙偲偵懳偟偰偼僱儖乕偺帪戙偲摨條偺庡挘傪孞傝曉偟偰偄傞丅儉僗儕儉偼僱儖乕偑帵偟偨廆嫵嫵堢暘棧庡媊傪梚岇偡傞僀儞僪崙柉夛媍偺巟帩幰偱偁傞丅懳徠揑偵丄僀儞僪恖柉搣偼傛傝愊嬌揑側僫僔儑僫儕僘儉偵崻偞偟偨庡挘傪揥奐偟偰偒偨丅僀儞僪恖柉搣偼僀儞僪偺暥壔偲堚嶻傪庣傝丄僀儞僪恖岥偺懡悢傪愯傔傞僸儞僪僁乕嫵搆傪庣傞惌嶔傪柾嶕偟偰偍傝丄偙偺偙偲偑嬤椬偺嫼埿偲側偭偰偄傞拞崙傗僷僉僗僞儞偵懳偡傞崙嫬慄傊偺愊嬌揑側孯帠杊塹嫮壔偲偄偭偨僫僔儑僫儕僘儉偲寢傃偮偄偰偄傞丅
廆嫵揑側庡挘傪偟偰偄傞惌搣偲偟偰偼丄僔僋嫵搆偑懡悢傪愯傔傞僷儞僕儍乕僽廈偵婎斦傪帩偮傾僇乕儕乕丒僟儖傗丄儅僴乕儔乕僔儏僩儔廈偵偍偄偰儅儔乕僞乕墹崙偵偍偗傞僔償傽乕僕乕偺傛偆偵僸儞僪僁僩償傽傪巟帩偡傞僔償丒僙乕僫乕偑偁傞丅傾僢僒儉廈偱偼丄傾僜儉恖柉夛媍偑戞堦搣偱偁偭偨傕偺偺2011擭偺慖嫇偱嶴攕傪媔偟丄傾僜儉楢崌夝曻愴慄(ULFA) 偑傾僜儉恖偺僫僔儑僫儕僘儉傪戙曎偡傞宍偲側偭偰偄傞丅僞儈儖丒僫乕僪僁廈偱偼僪儔償傿僟恖嫤夛 (DK) 偐傜惗傑傟偨僪儔乕償傿僟恑曕搣 (DMK) 傗慡僀儞僪丒傾儞僫乕丒僪儔乕償傿僟恑曕搣 (AIADMK)丄楯摥幰搣(PMK)丄僪儔乕償傿僟暅嫽恑曕搣(MDMK) 偑庡梫惌搣偲側偭偰偄傞丅
僇乕僗僩惂搙偐傜偺夝曻塣摦傪峴側偭偰偄傞惌搣偲偟偰偼丄僂僢僞儖丒僾儔僨乕僔儏廈偲價僴乕儖廈偺傛偆側僀儞僪杒晹偺恖岥偺懡偄廈偵偍偄偰晄壜怗柉 (尰嵼偺巜掕僇乕僗僩) 傗僸儞僪僁乕嫵搆偺傛偆側昻崲憌傛傝巟帩傪庴偗偰偄傞戝廜幮夛搣傗儔儖乕丒僾儔僒乕僪丒儎乕僟償偺惌搣偑偁傞丅傎傏慡偰偺僀儞僪偺廈偵廈搚拝偺恖乆偺暥壔偐傜偺巟帩偺傒傪栚揑偲偟偰惌帯庡挘傪揥奐偡傞抧堟惌搣偑偁傞丅
|
仭僫僔儑僫儕僘儉偲晲椡徴撍
僀儞僪偺孯戉偼僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉偵偍偄偰昁偢榑揰偲側傞晹暘偱偁傞丅僀儞僪偺孯戉偵娭偡傞嵟屆偺婰弎偲偟偰偼償僃乕僟傗儔乕儅乕儎僫丄儅僴乕僶乕儔僞偺傛偆側彇帠帊偵尒傞偙偲偑偱偒傞丅僀儞僪偼楌巎忋懡偔偺墹崙偑嫽朣傪孞傝曉偟丄廫榋戝崙丄僔僔儏僫乕僈挬丄僈儞僈挬丄僫儞僟挬丄儅僂儕儎挬丄僔儏儞僈挬丄僇乕儔償僃乕儔丄僋僯儞僟墹崙丄僠儑乕儔挬丄僠僃乕儔挬丄僷乕儞僨傿儎挬丄僒乕僞償傽乕僴僫挬丄惣僋僔儍僩儔僷丄僋僔儍乕僫挬丄償傽乕僇乕僞僇挬丄 僇儔僽儔挬丄僌僾僞挬丄僷僢儔償傽挬丄僇僟儞僶挬丄惣僈儞僈挬丄償傿僔儏僰僋儞僨傿乕僫丄慜婜僠儍乕儖僉儎挬丄償傽儖僟僫挬丄僸儞僪僁乕丒僔儍乕僸乕挬丄搶僠儍乕儖僉儎挬丄僾儔僥傿乕僴乕儔挬丄僷乕儔挬丄儔乕僔儏僩儔僋乕僞挬丄僷儔儅乕儔挬丄儎乕僟償傽挬丄僜乕儔儞僉乕挬丄屻婜僠儍乕儖僉儎挬丄儂僀僒儔挬丄僙乕僫挬丄搶僈儞僈挬丄僇乕僇僥傿乕儎挬丄僇儔僠儏儕挬丄僨儕乕丒僗儖僞乕儞挬丄僨僇儞丒僗儖僞乕儞挬丄傾乕儂乕儉墹崙丄償傿僕儍儎僫僈儖墹崙丄儅僀僜乕儖墹崙丄儉僈儖掗崙丄儅儔乕僞乕墹崙丄儅儔乕僞乕摨柨丄僔僋墹崙側偳偑塰偊偰偼柵傫偱偄偭偨丅
尰嵼偺僀儞僪棨孯偼19悽婭偺僀僊儕僗椞僀儞僪掗崙偺孯戉偑尦偵側偭偰宍惉偝傟偨傕偺偱偁傞丅崱擔丄僀儞僪嫟榓崙偼100枩恖埲忋偺暫椡傪帩偪丄悽奅戞3埵偺孯戉晹戉悢傪帩偮丅岞幃偵敪昞偝傟偰偄傞崙杊梊嶼偼164415.19僇儘乕儖儖僺乕 (310.7壄僪儖)偱偁傞偑丄幚嵺偵偼偙偺嬥妟傛傝偼傞偐偵忋偱偁傞偲悇應偝傟偰偄傞丅僀儞僪棨孯偱偼媫懍側孯偺嬤戙壔偲孯旛奼挘偑峴傢傟偰偍傝丄僀儞僪抏摴儈僒僀儖杊塹僾儘僌儔儉傗愴棯敋寕婡丄戝棨娫抏摴儈僒僀儖丄愽悈娡敪幩抏摴儈僒僀儖傪巜偡屇徧偱偁傞妀暫婍偺嶰杮拰偺攝旛偑寁夋偝傟偰偄傞丅丂 |
| 仭擔杮偲崙壠庡媊 |
   丂
丂
|
戞擇師悽奅戝愴拞偺擔杮偼愴帪懱惂偵傛傝丄崙壠庡媊揑側孹岦偑嫮偔側偭偨偙偲偑巜揈偝傟偰偄傞丅
愴屻丄億僣僟儉愰尵偵婎偯偒丄愴拞偵幐傢傟偨柉庡庡媊偺暅妶嫮壔(擔杮崙惌晎僴擔杮崙崙柉僲娫僯墬働儖柉庡庡媊揑孹岦僲暅妶嫮壔僯懳僗儖堦愗僲忈釭儝彍嫀僗僿僔尵榑丄廆嫵媦巚憐僲帺桼暲僯婎杮揑恖尃僲懜廳僴妋棫僙儔儖僿僔)偑側偝傟丄孻帠慽徸朄傕丄慡柺夵掕嶌嬈偑峴傢傟丄椷忬庡媊傗嫮惂張暘朄掕庡媊偺摫擖丄曎岇恖埶棅尃偺嫮壔側偳偑峴傢傟丄1948擭(徍榓23擭)偵尰峴偺孻帠慽徸朄偑惉棫偟丄梻擭偐傜巤峴偝傟偨丅丂 |
| 仭宱嵪偲崙壠庡媊 |
   丂
丂
|
乽宱嵪揑崙壠庡媊乿偲偼丄乽崙桳婇嬈傗懠偺宍懺偵傛傞惌帯婡峔偵傛偭偰丄捈愙揑偵丄傑偨偼宱嵪婇夋偵傛偭偰娫愙揑偵丄崙偑宱嵪偵夘擖偡傞廳戝偱崌朄揑側栶妱傪帩偭偰偄傞乿偲偡傞尒曽傪嫮挷偡傞傕偺偱偁傞丅
乽崙壠庡媊乿偲偄偆梡岅偼帪偵崙壠帒杮庡媊傪巜偡偙偲偑偁傝丄傑偨崙壠偵傛傞懡検偺惌帯夘擖偵傛偭偰巗応傪娗棟偡傞宱嵪傪偝偡偙偲傕偁傞丅傑偨丄婇嬈丒嶻嬈傪崙桳壔偟偰丄崙壠偵傛傞摑惂傪嫮傔傛偆偲偡傞曽幃偺堄枴偱傕巊傢傟傞丅丂
丂 |
| 仭崙壠庡媊偺彅憡 |
   丂
丂
|
仭擔杮偱戜摢偡傞婋尟側崙壠庡媊丂2013/12
尃椡偺嵗偵曉傝嶇偄偰1擭偲側傞12寧26擔丄埨攞怶嶰庱憡偑丄擔杮偺愴杤幰傪釰傞恄幮偱偁傝丄戞擇師悽奅戝愴拞偺愴斊傪崌釰偟偰偄傞偙偲偱榑憟偺揑偲側偭偰偄傞恄幮桋崙傪嶲攓偟傑偟偨丅
拞崙偲娯崙偼捈偪偵偙偺嶲攓傪尩偟偔斸敾丄傾儊儕僇崌廜崙傕偙傟偵摨挷偟傑偟偨丅
彅奜崙偑擔杮偺怤棯庡媊丄偦偟偰怉柉抧巟攝偺徾挜偲傒側偡桋崙恄幮傊偺埨攞庱憡偺嶲攓偼丄偡偱偵嬞挘娭學偵偁偭偨懳拞崙丄懳娯崙偲偺奜岎娭學傪堦憌埆壔偝偣傞偙偲偵側傝傑偟偨丅傾儊儕僇崌廜崙戝巊娰偼丄乽擔杮偺巜摫幰偑嬤椬彅崙偲偺嬞挘傪埆壔偝偣傞傛偆側峴摦傪庢偭偨偙偲偵丄暷崙惌晎偼幐朷偟偰偄傞丅乿偲偺惡柧傪岞幃僂僃僽僒僀僩偵宖嵹偟傑偟偨丅
栤戣偼埨攞庱憡偑側偤崱丄桋崙傪朘栤偡傞偙偲傪寛怱偟偨偐偲偄偆揰偵偁傝傑偡丅慜夞擔杮偺庱憡偑桋崙恄幮傪嶲攓偟偰偐傜7擭偑宱偪傑偟偨偑丄拞崙偲娯崙偑偲傕偵偦偺懚嵼帺懱傪夣偔巚傢側偄恄幮偵丄嶲攓偡傟偽拞娯椉崙偲偺奜岎娭學偵昁偢埆塭嬁傪媦傏偡偲夝偭偰偄側偑傜丄側偤嶲攓傪峴偭偨偺偱偟傚偆偐丠
拞崙丄偦偟偰娯崙偲擔杮偺奜岎娭學偼丄2000擭戙拞崰傛傝尰嵼偺曽偑彯埆偔側偭偰偄傑偡丅
埨攞巵偑弶傔偰庱憡偵廇擟偟偨偺偼2006-7偺娫偱偟偨偑丄2012擭2搙栚偺庱憡偵側偭偨帪偐傜丄拞崙偲娯崙偺巜摫幰偼埨攞庱憡偲偺夛尒傪嫅斲偟懕偗偰偒傑偟偨丅
傂偲偮偼搶僔僫奀偵晜偐傇愲妕彅搰傪傔偖傞椞搚栤戣丄傕偆傂偲偮偼戞擇師悽奅戝愴拞丄擔杮孯暫巑偺惈揑搝楆偲偝傟偨娯崙偺廬孯堅埨晈偺栤戣偺偨傔偱偡丅媡愢揑偵丄拞崙丄娯崙偑偙偆偟偨懺搙傪柧妋偵偟偰埑椡傪偐偗偰偄傞偐傜偙偦丄埨攞庱憡偑桋崙嶲攓偵摜傒愗偭偨偲偄偆帠偑尵偊傑偡丅
愲妕彅搰栤戣偵偮偄偰拞崙懁偑揙掙偟偰懳寛巔惃傪偲偭偨偙偲偼丄擔杮崙柉偵拞崙偺孯帠揑嫼埿偵偮偄偰怣偠崬傑偣傞偨傔偵丄擔杮惌晎偵偲偭偰偼嬌傔偰岲搒崌側偙偲偱偟偨丅
埨攞庱憡偺栚昗摓払揰偺堦偮偼丄偳偙偱椞搚暣憟偑敪惗偟偰傕捈偪偵孯帠椡傪峴巊偱偒傞傛偆偵擔杮偺孯旛偺宍傪曄偊偰偟傑偆偙偲偱偡丅偦偺偨傔偵埨攞庱憡偼偙偺堦擭娫拞崙懁偑擔杮偵憲傝懕偗偨條乆側僒僀儞傪柍帇偟懕偗傑偟偨偑丄拞崙偺亀嫮峝巔惃亁傪撪奜偵傾僺乕儖偟懕偗傞偙偲偱丄偦偺帠幚傪塀偡偙偲偑弌棃偨偺偱偡丅
桋崙嶲攓偼丄偦偆偟偨崙柉偵懳偡傞愰揱岺嶌偑偆傑偔偄偭偰偄傞偐偳偆偐傪妋擣偡傞偨傔偺丄嶌嬈偺堦晹偩偭偨偲偄偆帠偑尵偊傑偡丅
擔杮偑廬孯堅埨晈栤戣偵恀潟偵岦偒崌偍偆偲偟側偄懺搙偵懳偡傞娯崙懁偺尩偟偄斸敾偑墑乆偲懕偄偰偄傞帠丄偦偟偰僷僋丒僋僱戝摑椞偑埨攞庱憡偲偺夛択傪嫅斲偟懕偗偰偄傞懺搙偼丄擔杮偺堦斒崙柉偵懳偟丄娯崙偵懳偡傞晄怣姶傪怉偊偮偗傞帠偵側傝傑偟偨丅偦傟偼悽榑挷嵏偺寢壥丄擔杮恖夞摎幰偺栺敿悢偑丄娯崙傕傑偨擔杮偵懳偡傞乽孯帠揑嫼埿乿偱偁傞偲偡傞寢壥偵昞傟偰偄傑偡丅擔杮恖桳尃幰偺偦偆偟偨堄幆偼丄埨攞庱憡偵拞崙惌晎傗娯崙惌晎偺斀墳偵偲傜傢傟傞帠柍偔丄巚偄捠傝偵怳傞晳偆帺桼傪梌偊傞帠偵側傝傑偟偨丅
擔杮偺庡梫側擔姧怴暦偱偁傞枅擔怴暦丄挬擔怴暦丄撉攧怴暦偺3巻偼丄埨攞庱憡偺廇擟埲棃丄桋崙嶲攓偵偼斲掕揑側榑挷傪懕偗偰偒傑偟偨丅傕偭偲廳梫側栤戣丄偦傟偼埨攞庱憡傗偦偺庢傝姫偒偺崙壠庡媊幰偵偲偭偰壗傛傝戝愗側偼偢偺懚嵼偱偁傞崱忋揤峜偑丄慜戙偺徍榓揤峜摨條丄桋崙恄幮嶲攓傪嫅斲偟偰偄傞帠偱偡丅
埨攞庱憡偑嵟廔揑偵栚巜偡傕偺丄偦傟偼尰嵼偺暯榓寷朄傪彂偒姺偊傞帠偱偡丅偙偺寷朄偼戞擇師悽奅戝愴屻偺傾儊儕僇孯偵傛傞愯椞婜娫偵岎晅偝傟偨傕偺偱丄崙壠偺岎愴尃傪嬛偠偰偄傑偡丅偦偟偰揤峜偼寷朄偺掕傔偵傛傝崙惌偵嶲壛偡傞尃尷偼帩偭偰偄傑偣傫偑丄崱忋揤峜傕傑偨擔杮偑愴憟偡傞帠傪擣傔偰偼偄側偄偺偱偡丅
埨攞庱憡偑桋崙恄幮嶲攓傪峴偆悢擔慜丄崱忋揤峜偼80嵨偺抋惗擔傪廽偆惾忋丄乽暯榓偲柉庡庡媊偺戝愗側壙抣乿傪庣傝懕偗傞偨傔丄1945擭偵暯榓寷朄傪惂掕偟偨恖乆偵懳偡傞乽怺偄姶幱偺擮乿傪昞柧偝傟偨偺偱偡丅
偙偺傛偆側忬嫷傪峫偊傟偽丄拞崙偲娯崙偼楌巎偺夝庍偺栤戣偵偮偄偰丄擔杮崙撪偵巀摨幰傪尒偮偗傞帠偼壜擻偱偡丅拞崙傕娯崙傕埨攞庱憡偲夛択偡傞婡夛傪愝偗丄惓柺偐傜棫偪岦偐偆傋偒側偺偱偡丅偙傟埲忋夛択傪嫅斲偟懕偗傟偽丄埨攞庱憡偑偝傜偵巚偄捠傝偺惌嶔傪幚尰偡傞偨傔偺岥幚傪梌偊傞偙偲偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
擔杮偺孯帠揑側朻尟偼丄傾儊儕僇偺巟帩偑柍偗傟偽壜擻偱偼偁傝傑偣傫丅傾儊儕僇惌晎偼埨攞庱憡偺傗傝曽偑丄杒搶傾僕傾抧嬫偵偳傫側壎宐傕梌偊側偄帠傪偼偭偒傝偲偝偣傞昁梫偑偁傝傑偡丅
傾僕傾偺寶愝揑側枹棃偼丄崙壠娫偺怣棅娭學傪抸偄偰偄偔帠偺拞偵偙偦偁傝傑偡丅埨攞庱憡偺峴摦偼丄偦偺怣棅偲枹棃偲傪師乆偲攋夡偟偰偄偔峴堊偵懠側傜側偄偺偱偡丅
|
Risky Nationalism in Japan丂DEC. 26, 2013
On Thursday, one year after coming to power, Prime Minister Shinzo Abe visited Yasukuni, the controversial Shinto shrine that honors Japan乫s war dead, including war criminals from World War II. China and South Korea swiftly criticized the move, as did the United States. Mr. Abe乫s visit will worsen Japan乫s already tense relations with China and South Korea, which see the shrine as a symbol of imperial Japan乫s wars of aggression and colonialism. The United States Embassy said America was 乬disappointed that Japan乫s leadership has taken an action that will exacerbate tensions with Japan乫s neighbors.乭
The question is why Mr. Abe decided to visit Yasukuni now. It had been seven years since a Japanese prime minister visited the shrine, a recognition at the highest levels that the site is symbolically repugnant to China and South Korea and that such a visit is detrimental to relations with them. Japan乫s relations with those two nations are worse now than during the mid-2000s. Both Chinese and South Korean leaders have refused to meet with Mr. Abe since he became prime minister in 2012 (his first stint as prime minister was 2006-7), in part because of issues over territory in the East China Sea and Korean comfort women, who were forced into sexual slavery by Japanese soldiers during World War II.
Paradoxically, it is Chinese and South Korean pressure on these fronts that has allowed Mr. Abe to think a visit to Yasukuni is a good idea. China乫s belligerent moves in the past year over Japanese-administered islets has convinced the Japanese public that there is a Chinese military threat. This issue has given Mr. Abe cover to ignore all the signals from China and to pursue his goal of transforming the Japanese military from one that is strictly for territorial defense to one that can go to war anywhere. The visit to Yasukuni is part of that agenda.
South Korea乫s continuing and sharp criticism of Japan乫s grudging stance on the comfort women issue and the refusal by President Park Geun-hye to meet Mr. Abe to discuss the issue have sown distrust of South Korea among Japanese citizens, nearly half of whom, polls say, also see South Korea as a military threat. Such views among voters have effectively given Mr. Abe license to act without regard to the reactions in Beijing and Seoul.
The three major national newspapers — Yomiuri, Asahi and Mainichi — have been editorializing against a prime ministerial visit to Yasukuni, especially in the year since Mr. Abe took office. And more important for Mr. Abe and his nationalist supporters, Emperor Akihito has refused to visit Yasukuni, as did Emperor Hirohito before him.
Mr. Abe乫s ultimate goal is to rewrite Japan乫s pacifist Constitution, written by Americans during the postwar occupation, which restricts the right to go to war. Here, too, Emperor Akihito disapproves, though he has no political power under the Constitution. A few days before Mr. Abe visited Yasukuni, the emperor, in comments marking his 80th birthday, expressed his 乬deep appreciation乭 toward those who wrote the post-1945 constitution in order to preserve the 乬precious values of peace and democracy.乭
So, if history is the problem, Chinese and South Korean leaders will find allies in Tokyo, and they should meet Mr. Abe to confront, to negotiate and to resolve these issues. Their refusal to meet will only give Mr. Abe license to do what he wants. Japan乫s military adventures are only possible with American support; the United States needs to make it clear that Mr. Abe乫s agenda is not in the region乫s interest. Surely what is needed in Asia is trust among states, and his actions undermine that trust.
丂 |
埨攞庱憡偺崱夞偺桋崙恄幮嶲攓偵偮偄偰偼丄崙嵺儊僨傿傾偵桸偔傛偆偵婰帠偑傾僢僾偝傟偰偄傑偡丅偙偺僯儏乕儓乕僋僞僀儉僘偺幮愢偼廏堩偱偟偨丅崙柉偵懳偡傞愰揱岺嶌丄堄幆傊偺嶞傝崬傒丄傕偭偲偄偊偽愻擼偑偆傑偔偄偭偰偄傞偐偳偆偐丄偦傟傪妋擣偡傞偨傔偵埨攞庱憡偼桋崙嶲攓傪亀嫮峴偟偨亁偲偼乧
偦偟偰戝愗側帠偑偁傝傑偡丅愲妕彅搰傪弰傞栤戣偵偮偄偰丄12寧3擔偺僄僐僲儈僗僩偼亀旕亁偼拞崙偵偁傝丄亀棟亁偼擔杮懁偵偁傞偲偄偆榑挷偱偟偨丅偲偙傠偑僯儏乕儓乕僋僞僀儉僘偺婰帠偱偼丄偦傟偑媡揮偟偰偟傑偄傑偟偨丅亀旕亁偼擔杮偵偁傞偺偱偡丅偙偺傑傑偙偺庱憡偵偮偄偰偄偭偨偺偱偼丄巹偨偪擔杮恖偼悽奅偺拞偱屒棫偡傞偽偐傝偱偡丅寵傢傟丄慳傑傟傞偽偐傝偱偡丅
摿掕旈枾曐岇朄傪惂掕偟丄尨敪傪師乆偲嵞壱摥偝偣丄傂偨偡傜孯旛傪奼挘偡傞丅偙傟偑巹偨偪擔杮恖偺婅偄側偺偱偟傚偆偐丠丂 |
仭崙壠庡媊偱偼崙偼敪揥偟側偄 2016/7
崙壠庡媊偑偄傠偄傠側偲偙傠偱棳峴偭偰偄傞傛偆偩偑丄恖椶偺楌巎偺拞偱偼丄偣偄偤偄丄堦帪揑側婥偺柪偄丄榚摴偵偡偓側偄偲巹偼峫偊傞丅側偤側傜偽丄偦偙偵偼丄嬸偐偝偼偁偭偰傕尗偝偼側偔丄柍抦偼偁偭偰傕塨抭偼側偄偐傜偩丅
悽奅偺悥惃偼丄幚偼丄憡屳偺娭學惈丄埶懚惈偑怺傑偭偰偄偔僾儘僙僗偱偁傝丄偙偺偙偲偼丄岎捠栐丄棳捠丄僀儞僞乕僱僢僩丄偦偟偰抧媴婯柾偺壽戣偺戜摢偵傛偭偰昁慠壔偟偰偄傞丅崙壠庡媊偼丄偦偺傛偆側摦偒偵懳偡傞乽斀摦乿偵偡偓側偄丅
偦傕偦傕丄乽崙壠庡媊乿偼丄僄僑僀僘儉偵懠側傜側偄丅偆偪偺崙壠偼悽奅堦丄偲巚偭偰婥帩偪傛偑偭偰偄偰傕丄懠偺崙偐傜尒偨傜抦偭偨偙偲偱偼側偄丅崙壠庡媊偼丄恖椶晛曊偺巚憐偵偼惉傝摼側偄丅偮傑傝丄抦揑側儅僀儗僢僕偑抁偄丅昁梫側塨抭傕愺偄丅
崙壠庡媊偼丄庛偄傂偲偨偪傪庝偒偮偗傞丅杮棃丄僌儘乕僶儖壔偺拞丄帺暘偨偪偺擻椡傪妶偐偟丄懠幰偺堎幙惈傪懜廳偟丄峀乆偲偟偨僱僢僩儚乕僋偺拞偱慻傒崌傢偣偺憂憿惈傪柾嶕偡傟偽偄偄偺偵丄晐傟丄晄埨偑傝丄暵偠偙傕傠偆偲偡傞丅崙壠庡媊偼丄偦偺杮幙偵偍偄偰乽抧壓幒偺庤婰乿偩丅
偳偺崙偵傕丄崙壠庡媊偵庝偒偮偗傜傟傞傂偲偨偪偼堦掕偺妱崌偄傞偺偱偁偭偰丄堦曽偱奐柧揑偱塨抭揑側恖偨偪傕偄偰丄偦偺僶儔儞僗偱偦偺崙偺敪揥椡偑寛傑傞丅屻幰偺妱崌偑崅偄崙偼敪揥偟丄慜幰偺妱崌偑崅偄崙偼杤棊偡傞丅
偮傑傝丄崙壠庡媊偼丄崙偺偙偲傪巚偭偰偄傞傛偆偱偄偰丄幚偼崙偺敪揥傪朩偘傞擣抦僶僀傾僗偵側傞偺偱偁偭偰丄偩偐傜偙偦丄杮摉偵崙偺偙偲傪戝愗偵巚偭偰偄傞恖偨偪偼丄寛偟偰崙壠庡媊傪怳傝夞偝側偄丅悽奅偵奐偐側偗傟偽丄崙帺懱偑敪揥偟側偄偲抦偭偰偄傞偐傜偩丅
埲忋偺崙壠庡媊偺惼庛偝丄斀抦惈揑杮幙偵偮偄偰偼丄抧媴忋丄奐柧揑側恖乆偵傛偭偰偁傑偹偔嫟桳偝傟偰偄傞乽忢幆乿偩偲巚偆偑丄崱挬偼丄姼偊偰丄儀乕僔僢僋拞偺儀乕僔僢僋傪嵞妋擣偡傞偨傔偵丄愘暥傪捲偭偰傒偨師戞偱偁傞丅 丂 |
|
丂 |
| 仭塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偼斀懳奣擮偱偼側偔丄撈棫奣擮偱偁傞
|
   丂
丂
|
愭擔偺乽僫僠僗偺乽25僇忦峧椞乿偼擔杮恖昁撉偱偼乿偼斀嬁偑戝偒偔丄僣僀僢僞乕偱傕丄偼偰側僽僢僋儅乕僋偱傕丄偨偔偝傫偺僐儊儞僩偑偁偭偨丅偦偙偱彂偒懌傝側偐偭偨晹暘側偳偵偮偄偰丄偄偔傜偐曗懌偟偨偄丅
惌帯偵徻偟偄恖偱偁傟偽丄巹偺僄儞僩儕偵懳偟偰丄乽僫僠僗偼崙壠幮夛庡媊側偺偩偐傜丄偦偙偵幮夛庡媊偑娷傑傟偰偄傞偙偲丄偮傑傝嵍梼揑側惌嶔偑娷傑傟偰偄傞偺偼帺柧偱偁傝丄尵偆傑偱傕側偄乿偲姶偠偨偐傕偟傟側偄丅
偁傞偄偼丄幮夛庡媊偵嫟姶偟偰偄傞恖偱偁傟偽丄乽僫僠僗偺栤戣偼傕偭傁傜崙壠庡媊偺懁柺偵偁傞偺偵丄幮夛庡媊偺懁柺偩偗庢傝弌偡偺偼僼僃傾偱偼側偄乿偲姶偠偨偐傕偟傟側偄丅
巹偑乽僫僠僗偺乽25僇忦峧椞乿偼擔杮恖昁撉偱偼乿偵偍偄偰丄僫僠僗偺乽崙壠幮夛庡媊乿偺偆偪乽幮夛庡媊乿偺懁柺偩偗傪庢傝弌偟偨偺偼丄僫僠僗偺乽崙壠庡媊(僫僔儑僫儕僘儉)乿偺懁柺偼偡偱偵傛偔抦傜傟偰偍傝丄尵偆傑偱傕側偄偲峫偊偨偐傜偩丅僫僠僗偺堦斒揑側僀儊乕僕偼丄乽崙壠庡媊乿偱偁傝丄乽孯崙庡媊乿偱偁傝丄乽塃梼乿偩傠偆丅
偄偭傐偆丄僫僠僗偺乽崙壠幮夛庡媊乿偺偆偪乽幮夛庡媊乿偺懁柺偵偮偄偰偼丄擔杮偱偼偦傟傎偳峀偔抦傜傟偰偼偄側偄傛偆偵巚偆丅偩偐傜丄偙偺僄儞僩儕傪彂偔堄媊偑偁傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偨偺偩偑丄幚嵺偵斀嬁偑戝偒偐偭偨偺傪尒偰傕(傕偪傠傫巀斲椉榑偩偑)丄偦傟側傝偵彂偔堄媊偑偁偭偨偺偩傠偆丅
偙偙偱柺敀偄偺偼丄側偤僫僠僗偺乽幮夛庡媊乿乽嵍梼乿偺懁柺偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偺偐丄偲偄偆偙偲偩丅偙傟帺懱丄廳梫側榑揰傪娷傫偱偄傞偲巚偆丅
側偤丄僫僠僗偺乽幮夛庡媊乿乽嵍梼乿偺懁柺偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偺偐丅偦偺棟桼偼丄
乽塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偼斀懳奣擮偲巚傢傟偰偄傞偑丄幚偼撈棫奣擮偱偁傞乿
偲偄偆偺偑戝偒偄傛偆偵巚偆丅
乽塃梼乿偲乽嵍梼乿偲偄偆偺偼丄尵梩偺忋偱偼斀堄岅偵尒偊傞偺偱丄斀懳奣擮偱偁傞偲巚傢傟偰偟傑偄傗偡偄丅傛偭偰丄僫僠僗偼乽塃梼乿乽崙壠庡媊乿偱偁傞偲偄偆僀儊乕僕偑屌傑傞偲丄僫僠僗偼乽嵍梼乿乽幮夛庡媊乿偱偼側偄丄偲偄偆擣幆偑帺慠偵宍惉偝傟傗偡偄偺偩偲巚偆丅乽塃梼乿偲乽嵍梼乿偼斀懳偺傕偺偱丄嫟懚偟偊側偄偲巚傢傟偰偄傞偐傜偩丅
偟偐偟幚嵺偺偲偙傠偼丄塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偲偄偆偺偼斀懳奣擮偱偼側偔丄撈棫奣擮側偺偱偁傞丅偦偟偰丄僫僠僗偲偄偆偺偼傑偝偵丄塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偑崌懱偟偨傕偺側偺偩丅僫僠僗偵偍偄偰丄塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偑嫟懚偟偰偄傞偲偄偆偙偲帺懱偑丄偦偺2偮偑斀懳奣擮偱側偔丄撈棫奣擮偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅
偙偺偙偲傪恾偱偁傜傢偟偰傒傞偲丄偙傫側姶偠偩丅
丂丂丂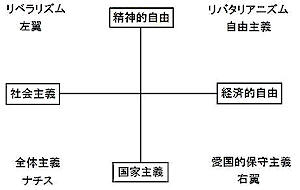
偙傟偼丄儕僶僞儕傾僯僘儉偺惌帯巚憐揑億僕僔儑儞傪愢柧偡傞偺偵偟偽偟偽巊傢傟傞乽僲乕儔儞丒僠儍乕僩(Nolan Chart)乿偵丄庒姳曗懌偟偨傕偺偩丅
儓僐幉偑乽宱嵪揑帺桼乿偺搙崌偄偱丄乽幮夛庡媊乿偼偄傢偽乽宱嵪揑晄帺桼乿偲埵抲偯偗傜傟傞丅乽幮夛庡媊乿偱偼丄惌晎偑巗応宱嵪偵夘擖偟丄崙柉偺僇僱傪惌晎偑庢傝忋偘偰丄偦偺巊偄曽傪惌晎偑寛傔傞丅
僞僥幉偑乽惛恄揑帺桼乿偺搙崌偄偱丄尵榑傗巚憐丄儔僀僼僗僞僀儖側偳偺帺桼搙傪帵偡丅乽崙壠庡媊乿偼偙偺懁柺偱偺帺桼傪扗偄丄柉懓揑傾僀僨儞僥傿僥傿偵慽偊偰丄崙柉傪摑惂偟傛偆偲偡傞丅
偙偺傛偆偵尒傟偽丄僫僠僗偲偄偆偺偼乽幮夛庡媊乿偲乽崙壠庡媊乿偑崌懱偟偨傕偺偱偁傞偙偲偑棟夝偟傗偡偔側傞丅偦傟偼乽宱嵪乿偲乽惛恄乿偺椉柺偱崙柉偐傜帺桼傪扗偄丄嫮惂偟偰丄傂偨偡傜惌晎偺尃尷傪奼戝偝偣傞丅偙傟偑乽慡懱庡媊乿偱偁傝丄恾偱偼嵍壓偵側傞丅
偙傟偲惓斀懳側偺偑塃忋偺儕僶僞儕傾僯僘儉偱丄屄恖偺乽宱嵪揑帺桼乿偲乽惛恄揑帺桼乿偺椉曽傪嵟戝壔偡傞偙偲傪巟帩偡傞丅偙偺椉曽偺帺桼偑惌晎偵傛偭偰怤奞偝傟傞偙偲傪寵偆偺偱丄惌晎傪偱偒傞偩偗彫偝偔偡傞乽彫偝側惌晎乿傪巟帩偡傞棫応偵側傞丅
嵍梼偼捠忢丄幮夛庡媊傪巟帩偟偰崙壠庡媊傪巟帩偟側偄偺偱丄嵍忋偵側傞丅偄偭傐偆塃梼偼捠忢丄崙壠庡媊傪巟帩偟偰幮夛庡媊傪巟帩偟側偄偺偱丄塃壓偵側傞丅
偦偟偰丄偙偙傑偱棟夝偡傟偽丄塃梼偲嵍梼偼傗偼傝斀懳懁偵埵抲偟偰偄傞偺偱丄愭傎偳偺
乽塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偼斀懳奣擮偲巚傢傟偰偄傞偑丄幚偼撈棫奣擮偱偁傞乿
偲偄偆尵偄曽偼丄惓妋偱偼側偄偙偲偑傢偐傞丅
撈棫奣擮側偺偼丄乽崙壠庡媊乿(僞僥幉)偲乽幮夛庡媊乿(儓僐幉)偱偁傞丅偦偟偰丄乽崙壠庡媊乿偲偄偆偺偼塃梼偺庡梫惉暘丄偄傢偽乽塃梼惈乿偱偁傝丄乽幮夛庡媊乿偲偄偆偺偼嵍梼偺庡梫惉暘丄偄傢偽乽嵍梼惈乿偱偁傞丅
偮傑傝丄僫僠僗偲偄偆偺偼乽塃梼惈(崙壠庡媊)乿偲乽嵍梼惈(幮夛庡媊)乿傪椉曽帩偭偨乽慡懱庡媊乿偩丄偲偄偆偙偲偵側傞丅愭傎偳丄僫僠僗偼乽塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偑崌懱偟偨傕偺乿偲彂偄偨偺偼丄偙偺偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅
偐傫偨傫偵尵偊偽丄僫僠僗偼乽塃梼偐偮嵍梼乿偱偁傝丄儕僶僞儕傾僯僘儉偼乽塃梼偱傕嵍梼偱傕側偄乿丅偙偺2偮偺棫応偼丄塃梼偲嵍梼傪1師尦揑偵斀懳奣擮偲偟偰懆偊偰偄傞尷傝丄側偐側偐棟夝偱偒側偄偩傠偆丅忋偺僲乕儔儞丒僠儍乕僩偺傛偆側2師尦揑攃埇偵傛偭偰偙偦丄偦傟偑棟夝偱偒傞偲巚偆丅
僫僠僗偺傛偆側斶寑傪孞傝曉偝側偄偨傔偵偼丄偦傟傪朰媝偡傞偺偱偼側偔丄偦傟偑偳偺傛偆側傕偺偱偁偭偨偺偐丄偳偺傛偆偵惉棫偟偨偺偐丄側偤巟帩傪廤傔偨偺偐傪抦偭偰偍偔昁梫偑偁傞丅摿偵擔杮偼丄屄恖偺乽帺桼乿偵懳偡傞堄幆偑婓敄偱偁傝丄乽懠恖偲堎側傞偙偲乿傊偺埑椡偑戝偒偄側偳丄慡懱庡媊偵捠偠傗偡偄惛恄揑搚忞偑偁傞丅幚嵺丄偄偪偳慡懱庡媊偑惗偠偨偲偄偆乽慜壢乿偑偁傞偺偩丅
擔杮偵偼丄栤戣傪乽峔憿乿揑丒乽僔僗僥儉乿揑偵棟夝偡傞偺偱偼側偔丄乽儚儖儌僲乿偺偣偄偵偟偰曅晅偗偰偟傑偄傗偡偄偲偙傠偑偁傞丅偙傟偩偲丄乽儚儖儌僲乿傪偄偔傜敱偟偨傝丄攔彍偟偰傕丄栤戣傪堷偒婲偙偡乽峔憿乿乽僔僗僥儉乿偑側偔側傜側偄偺偱丄偄偔傜偱傕乽儚儖儌僲乿偑弌偰偔傞丄偲偄偆偙偲偵側傞丅
僫僠僗偵偮偄偰傕丄帺暘偲偼娭學側偄乽儚儖儌僲乿偑堷偒婲偙偟偨偺偩丄偲擔杮偱偼峫偊傜傟偑偪偱偼側偄偩傠偆偐丅偙偆偄偆峫偊曽偼僫僀乕僽偱偁傝丄婋尟偱偡傜偁傞丅偦傟偼丄帺暘偼乽慞乿偱偁傝丄栤戣傪堷偒婲偙偡偺偼乽儚儖儌僲乿側偺偩偐傜丄帺暘偼娭學側偄偟丄帺暘偑栤戣偵壛扴偡傞偙偲偼側偄丄偲偄偆夁怣偺忋偵惉棫偟偰偄傞丅偙偺傛偆側峫偊曽丄帺暘偼乽慞乿偱丄栤戣傪堷偒婲偙偡偺偼乽儚儖儌僲乿偩偲埨堈偵慄堷偒偟偰偟傑偆峫偊曽偼丄幚偼僸僩儔乕偺峫偊曽偵偦偭偔傝偱偼側偄偩傠偆偐丅
偍偦傜偔傎偲傫偳偺恖偑丄帺暘偼乽慞乿偩偲峫偊偰偄傞偩傠偆偟丄幚嵺偵偨偄偰偄偺恖偑乽慞恖乿偩傠偆偲巚偆丅偟偐偟丄壗偑乽慞乿偐偲偄偆峫偊曽偼偄傠偄傠偁傞偟丄傑偨幚嵺偼乽慞恖乿側偺偵丄乽峔憿乿傗乽僔僗僥儉乿偺偨傔偵丄埆偄傆傞傑偄傪偣偞傞傪偊側偄応崌傕偁傞丅廳梫側偺偼丄(1)偝傑偞傑側乽慞乿偑偁傞偙偲傪慜採偲偟偰丄帺暘偺乽慞乿傪懠恖偵嫮惂偟側偄偙偲偲丄(2)屄暿偺斊嵾偱偼側偄幮夛栤戣偵偮偄偰偼丄乽儚儖儌僲乿偑堷偒婲偙偟偰偄傞偺偱偼側偔丄乽峔憿乿傗乽僔僗僥儉乿偵尨場偑偁傞偙偲丄偙偺2偮傪棟夝偡傞偙偲偩偲巚偆丅丂
丂 |
| 仭乽挻崙壠庡媊乿榑偼壗傪尒摝偟偨偐 |
   丂
丂
|
|
乽偐偔偰変傜偼巹惗妶偺娫偵傕揤峜偵婣堦偟丄崙壠偵曭巇偡傞偺擮傪朰傟偰偼側傜偸乿(恇柉偺摴)偲偄偭偰偄傞偑丄偙偆偟偨僀僨僆儘僊乕偼側偵傕慡懱庡媊偺棳峴偲嫟偵尰傢傟棃偨偭偨傢偗偱偼側偔丄擔杮偺崙壠峔憿偦偺傕偺偵撪嵼偟偰偄偨丅乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿娵嶳崃抝
|
仭1丂乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿
乽挻崙壠庡媊乿偼徍榓擔杮偺僼傽僔僘儉傗慡懱庡媊傪堄枴偡傞奣擮偲偟偰巊傢傟偰偄傞丅偨偲偊偽乽尰戙擔杮巚憐戝宯乿(拀杸彂朳)偵偼嫶愳暥嶰偺曇廤丒夝愢偐傜側傞亀挻崙壠庡媊亁(戞31姫)偺姫偑偁傞丅偦傟偼亀傾僕傾庡媊亁(戞9姫)亀僫僔儑僫儕僘儉亁(戞4姫)偲偼暿偵棫偰傜傟偨徍榓僼傽僔僘儉偲偦偺戙昞揑尵愢傪曇廤偡傞姫偩偲峫偊傜傟傞丅偲偙傠偱偦偺姫偺曇幰偱偁傞嫶愳偼偦偺夝愢偱乽擔杮偺嬤戙巎偵偍偄偰偼丄偨偲偊偽僪僀僣傕偟偔偼僀僞儕傾偵尒傜傟傞傛偆側丄柧妋側僼傽僔僘儉妚柦偲偄偆傕偺偑側偔丄偄傢偽側偟偔偢偟偺挻崙壠庡媊壔偑恑峴偟偨偨傔偵丄偦偺惌帯揑梫場偲偟偰丄堦斒偺塃梼巚憐丒崙壠庡媊巚憐偐傜嬫暿偝傟偨挻崙壠庡媊揑宊婡傪丄偦傟偲偟偰偲傝弌偡偙偲偑摿暿偵崲擄偱偁傞乿偲偄偭偰偄傞丅嫶愳偼偙偙偱娵嶳崃抝偑乽偳偙偐傜僼傽僢僔儑帪戙偵側偭偨偐偼偭偒傝偄偊側偄乿偲擔杮僼傽僔僘儉偺乽慟恑揑側惈奿乿傪偄偆尵梩傪堷偄偰偄偭偰偄傞丅巹偑偙偙偱拲堄偟偨偄偺偼乽挻崙壠庡媊乿偲偄偆擔杮僼傽僔僘儉偺摿惈偑僪僀僣傗僀僞儕傾偺偦傟偲偺嬫偐傜偄傢傟傞偙偲偱偁傞丅偙偆偟偨乽挻崙壠庡媊乿偲偟偰偺擔杮僼傽僔僘儉偺摿幙壔偼娵嶳偵傛傞傕偺偱偁傞丅
乽挻崙壠庡媊乿偲偄偆奣擮傪愴屻擔杮偵掕拝偝偣偨偺偼丄攕愴偺梻擭偵敪昞偝傟偨娵嶳偺榑暥乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偱偁傞偩傠偆丅偙偺榑暥偼愴屻擔杮偺巚憐揑尵榑悽奅偵傕偭偲傕戝偒側塭嬁椡傪傕偭偨傕偺偩偲偄偭偰偄偄丅愴屻20擭偵摉偨偭偰亀拞墰岞榑亁(1964擭10寧崋)偑乽愴屻擔杮傪憂偭偨戙昞榑暥乿偲偄偆摿廤傪傗偭偰偄傞丅挅栘惓摴丒塒堜媑尒傜偺慖峫埾堳偑18曆偺榑暥傪慖傫偱偄傞偑丄埑搢揑懡悢偺昜傪傕偭偰戞堦埵偵慖偽傟偨偺偼娵嶳偺偙偺乽挻崙壠庡媊乿榑暥偱偁偭偨丅偲偙傠偱娵嶳偼偦偺榑暥傪偙偆彂偒弌偟偰偄傞丅
乽擔杮崙柉傪塱偒偵傢偨偭偰楆廬揑嫬奤偵墴偟偮偗丄傑偨悽奅偵懳偟偰崱師偺愴憟傪嬱傝偨偰偨偲偙傠偺僀僨僆儘僊乕揑梫場偼楢崌崙偵傛偭偰挻崙壠庡媊僂儖僩儔丒僫僔儑僫儕僘儉偲偐嬌抂崙壠庡媊僄僋僗僩儕乕儉丒僫僔儑僫儕僘儉偲偐偄偆柤偱敊慠偲屇偽傟偰偄傞偑丄偦偺幚懱偼偳偺傛偆側傕偺偱偁傞偐偲偄偆帠偵偮偄偰偼傑偩廫暘偵媶柧偝傟偰偄側偄傛偆偱偁傞丅偄傑庡偲偟偰栤戣偵側偭偰偄傞偺偼偦偆偟偨挻崙壠庡媊偺幮夛揑丒宱嵪揑攚宨偱偁偭偰丄挻崙壠庡媊偺巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦偺暘愅偼変偑崙偱傕奜崙偱傕杮奿揑偵庢傝忋偘傜傟偰偄側偄偐偵尒偊傞丅乿
娵嶳偼乽挻崙壠庡媊乿偲偼擔杮傪愴憟偵嬱傝偨偰偨偲偙傠偺僀僨僆儘僊乕揑梫場偵楢崌崙偑壖偵柤偯偗偨屇傃曽偩偲偄偆偺偱偁傞丅偦偆偩偲偡傟偽乽挻崙壠庡媊乿偼擔杮偺僼傽僢僔僘儉側傝慡懱庡媊傪偄偆奣擮偲偟偰偡偱偵偁偭偨奣擮偱偼側偄偙偲偵側傞丅傓偟傠乽挻崙壠庡媊乿偼娵嶳偺偡傞暘愅揑擣幆嶌嬈丄偡側傢偪偦偺乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦偺暘愅乿嶌嬈傪捠偠偰偼偠傔偰擔杮偺撈帺揑側僼傽僔僘儉丄偁傞偄偼擔杮揑摿惈傪傕偭偨僼傽僔僘儉傪巜偡奣擮偲偟偰惉棫偟偨偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅乽挻崙壠庡媊乿偲偼丄偩偐傜娵嶳偺偙偺榑暥偑峔惉偡傞擔杮僼傽僔僘儉偺奣擮偱偁傞丅偩偑娵嶳帺恎偼偙偺榑暥埲崀丄乽擔杮僼傽僔僘儉乿偲偄偭偰乽挻崙壠庡媊乿傪偄偆偙偲傪偁傑傝偟偰偄側偄傛偆偵巚傢傟傞丅偩偑乽挻崙壠庡媊乿偼娵嶳偺偙偺榑暥偵傛傞奣擮峔惉偲偲傕偵丄擔杮僼傽僔僘儉偺戙柤帉偲偟偰堦恖曕偒偟偰偄傞丅
偱偼娵嶳偼偳偺傛偆偵乽挻崙壠庡媊乿傪擔杮揑僼傽僔僘儉奣擮偲偟偰峔惉偟偰偄偭偨偺偐丅娵嶳偑偄傑偟傛偆偲偟偰偄傞偺偼乽挻崙壠庡媊乿偺乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦偺暘愅乿偱偁傞丅傕偟偙偺榑暥偵傛偭偰乽挻崙壠庡媊乿奣擮偑峔惉偝傟偨偲偡傞側傜偽丄偦偺奣擮偼乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦偺暘愅乿傪捠偠偰峔惉偝傟偨傕偺偩偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟偼尒摝偟偰偼偄偗側偄戝帠側偙偲偩丅娵嶳偼偙偺暘愅丄偡側傢偪乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦乿偺暘愅偼偁傑傝側偝傟偰偄側偄偲偄偆丅偲偄偆偺偼丄偙偺栤戣偑乽偁傑傝偵娙扨偱偁傞偐傜偲傕偄偊傞偟丄傑偨媡偵偁傑傝偵暋嶨偱偁傞偐傜偲傕偄偊傞乿偐傜偩偲偄偭偰偄傞丅偁傑傝偵娙扨偱偁傞偲偄偆偺偼丄乽偦傟偑奣擮揑慻怐傪傕偨偢丄乽敧峢堦塅乿偲偐乽揤嬈夬峅乿偲偐偄偭偨偄傢偽嫨姭揑側僗儘乕僈儞偺宍偱尰傟偰偄傞偨傔偵丄恀柺栚偵庢傝忋偘傞偵抣偟側偄傛偆偵峫偊傜傟傞偐傜乿偩偲偄偆偺偱偁傞丅
娵嶳偑偙偙偱偙偪傜偺乽敧峢堦塅乿偲偄偭偨娙扨偡偓傞嫨姭揑側僗儘乕僈儞偵懳抲偟側偑傜丄偁偪傜偺僫僠僘儉丒僼傽僔僘儉塣摦傪戙昞偡傞傕偺偲偟偰嫇偘傞傕偺偼壗偐丅乽椺偊偽僫僠僗丒僪僀僣偑偲傕偐偔亀変偑摤憟亁傗亀擇廫悽婭偺恄榖亁偺擛偒悽奅娤揑懱宯傪帩偭偰偄偨乿偙偲傪娵嶳偼偄偆偺偱偁傞丅偙偙偵尒傞偺偼娵嶳偺惌帯妛揑尵愢偵丄偦偺尵愢峔惉傪壜擻偵偡傞傕偺偲偟偰廔巒偮偒傑偲偆恾幃揑側搶惣偺懳斾揑巚峫偱偁傞丅側偤娵嶳偼僸僩儔乕偺亀変偑摤憟亁傗儘乕僛儞儀儖僋偺亀擇廫悽婭偺恄榖亁偵懳抲偡傞偺偵杒堦婸偺亀擔杮夵憿朄埬亁傗戝愳廃柧偺亀擔杮擇愮榋昐擭巎亁傪傕偭偰偣偢偵丄乽敧峢堦塅乿傗乽揤嬈夬峅乿偲偄偭偨嫨姭揑僗儘乕僈儞傪傕偭偰偡傞偺偐丅偙偙偱亀変偑摤憟亁傗亀擇廫悽婭偺恄榖亁偵懳抲偡傞偺偵杒傗戝愳偺挊嶌傪傕偭偰偡傞偙偲偺揔斲偑栤傢傟傞偙偲偱偼側偄丅栤戣側偺偼亀変偑摤憟亁傪傕偮偐丄傕偨側偄偐傜擔杮僼傽僔僘儉偺摿幙傪摫偄偰偄偔娵嶳偺惌帯妛揑暘愅偺偁傝曽偱偁傞丅
乽挻崙壠庡媊乿奣擮傪峔惉偟偰偄偔娵嶳偺擔杮僼傽僔僘儉傪傔偖傞暘愅帇妏偼丄亀変偑摤憟亁偺桳傞柍偟傪栤偆傛偆側搶惣偺懳斾揑暘愅帇妏偱偁傞丅偙偺搶惣偺懳斾揑暘愅帇妏偼栤傢傟傞傕偺偺摿幙傪梊傔婯掕偟偰偟傑偭偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅
乽崙柉偺怱揑孹岦側傝峴摦側傝傪堦掕偺峚偵棳偟崬傓偲偙傠偺怱棟揑側嫮惂椡偑栤戣側偺偱偁傞丅偦傟偼側傑偠柧敀側棟榑揑側峔惉傪帩偨偢丄巚憐揑宯晥傕庬乆嶨懡偱偁傞偩偗偵偦偺慡杄偺攃埇偼側偐側偐崲擄偱偁傞丅惀偑堊偵偼乽敧峢堦塅乿揑僗儘乕僈儞傪摢偐傜僨儅僑僊乕偲偒傔偰偐偐傜偢偵丄偦偆偟偨彅乆偺抐曅揑側昞尰傗偦偺尰幚偺敪尰宍懺傪捠偠偰掙偵傂偦傓嫟捠偺榑棟傪扵傝摉偰傞帠偑昁梫偱偁傞丅乿(朤揰偼巕埨)丂
亀変偑摤憟亁傪傕偨側偄傢偑僼傽僔僘儉丄偡傫傢偪乽挻崙壠庡媊乿偲偄偆奣擮偼偙偺傛偆偵乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦乿偺暘愅傪捠偠偰峔惉偝傟傞偺偱偁傞丅
|
仭2丂亀変偑摤憟亁偼偙偙偵偼柍偄
堦斒偵偼僼傽僔僘儉偲偄偆惌帯僀僨僆儘僊乕傪旛偊偨惌帯揑丄巚憐揑塣摦懱宯偑慻怐揑愰揱偲戝廜嫵堢傪捠偠偰僼傽僔儑揑偲偄偆摨挷揑怱棟傪戝廜偺娫偵嶌傝弌偟偰偄偔丅偙偆偟偰帪戙偲幮夛偲偼慡懱庡媊揑偵嵞曇惉偝傟偰偄偔偺偱偁傞丅偨偟偐偵偦偙偵偼帪戙偲幮夛偺僼傽僔儑壔傪庡摫偡傞僀僨僆儘僊乕偑偁傝丄偦偺僀僨僆儘僊乕傪扴偆庡懱偲慻怐偲塣摦偲偑偁傞丅偩偑擔杮僼傽僔僘儉偵偼亀変偑摤憟亁偼側偄偲娵嶳偼偄偆偺偱偁傞丅亀変偑摤憟亁偑偙偙偵偼側偄偲娵嶳偑偄偆偲偒丄偦傟偼壗傪堄枴偡傞偺偐丅
亀変偑摤憟亁偑擔杮僼傽僔僘儉偵偼側偄偲偄偆偙偲偼丄嵟弶偵堷偄偨嫶愳偺乽夝愢乿偑偄偆傛偆偵丄擔杮僼傽僔僘儉偵偼乽巒傑傝乿偑側偄偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅乽巒傑傝乿偑側偄偲偼丄巒傑傝傪夋偡傞愰尵偲偄偭偨尵岅揑昞柧偑側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅尵岅揑昞柧偑側偄偲偄偆偙偲偼丄巒傑傝傪崘偘傞傛偆側妋怣揑側昞柧庡懱偑側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偺傛偆偵娵嶳偑擔杮僼傽僔僘儉偵偼亀変偑摤憟亁偼側偄偲偄偆偙偲偼丄巹偑忋偵乽偙偙偵偼帪戙偲幮夛偺僼傽僔儑壔傪庡摫偡傞僀僨僆儘僊乕偑偁傝丄偦偺僀僨僆儘僊乕傪扴偆庡懱偲慻怐偲塣摦偲偑偁傞乿偲偄偭偨僼傽僔僘儉塣摦偺堦斒宍偲偟偰偼擔杮僼傽僔僘儉傪尒側偄偙偲傪堄枴偡傞丅娵嶳偼擔杮僼傽僔僘儉傪僼傽僔僘儉偺摿堎宍偲偟偰尒傞偺偱偁傞丅乽挻崙壠庡媊乿偲偼偙偺摿堎宍偲偟偰偺擔杮僼傽僔僘儉傪偄偆偺偱偁傞丅偙偺摿堎宍偲偟偰偺擔杮僼傽僔僘儉傪彇弎偡傞娵嶳偺榑暥乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偼丄偙偺擔杮僼傽僔僘儉偲偄偆摿堎宍丄偁傞偄偼傓偟傠婏宍偵懳偟偰寵埆姶傪娷傫偩僒僠乕儖傪偟偽偟偽梺傃偣偐偗傞丅乽怲傑偟傗偐側撪柺惈傕側偗傟偽丄傓偒弌偟偺尃椡惈傕側偄丅偡傋偰偑憶乆偟偄偑丄摨帪偵偡傋偰偑彫怱梼乆偲偟偰偄傞丅偙偺堄枴偵墬偄偰丄搶忦塸婡巵偼擔杮揑惌帯偺僔儞儃儖偲尵偄摼傞丅乿
擔杮僼傽僔僘儉偵偼巒傑傝傕側偗傟偽丄巒傑傝傪崘偘傞尵梩傕庡懱傕側偄丅偱偼壗偑偁傞偺偐丅偙偙偵偁傞偺偼擔杮揑摿堎宍偲偟偰偺崙壠丄偡側傢偪揤峜惂揑崙壠偑偁傞偺偱偁傞丅偙偙偱偼崙壠偺懚棫偦偺傕偺偑丄乽崙柉偺怱揑孹岦側傝峴摦側傝傪堦掕偺峚偵棳偟崬傓偲偙傠偺怱棟揑側嫮惂椡乿傪偲傕側偭偨傕偺偲偟偰丄偁傞偄偼偦偆偟偨怱棟揑側嫮惂椡傪偨偊偢惗傒弌偡尃埿揑尮愹偲偟偰偁傞偺偱偁傞丅擔杮僼傽僔僘儉偺摿堎惈偲偼擔杮揑崙壠偺摿堎惈偱偁傞丅擔杮僼傽僔僘儉偼偙偺擔杮揑崙壠偲崙壠庡媊偺摿堎惈偑惗傒弌偡傕偺偲偟偰乽挻崙壠庡媊乿亖嬌抂側崙壠庡媊偲偄傢傟傞偺偱偁傞丅
|
仭3丂崙懱榑揑崙壠
娵嶳偼摿堎宍偲偟偰偺擔杮揑崙壠傪丄椺偵傛偭偰搶惣偺懳斾揑帇妏偵傛傞摿幙壔傪傕偭偰偟偰偄傞丅偄傑惣偺乹崙壠椶宆乺偑娵嶳偵傛偭偰偳偺傛偆偵峔惉偝傟傞偐傪尒偰傒傛偆丅
乽儓乕儘僢僷嬤戙崙壠偼僇乕儖丒僔儏儈僢僩偑偄偆傛偆偵丄拞惈崙壠(Ein neutraler Staat)偨傞偙偲偵堦偮偺戝偒側摿怓偑偁傞丅姺尵偡傟偽丄偦傟偼恀棟偲偐摴摽偲偐偺撪梕揑壙抣偵娭偟偰偼拞棫揑棫応傪偲傝丄偦偆偟偨壙抣偺慖戰偲敾抐偼傕偭傁傜懠偺幮夛揑廤抍(椺偊偽嫵夛)擳帄偼屄恖偺椙怱偵埾偹丄崙壠庡尃偺婎慴傪偽丄偐偐傞撪梕揑壙抣偐傜幪徾偝傟偨弮悎偵宍幃揑側朄婡峔偺忋偵抲偄偰偄傞偺偱偁傞丅乿
娵嶳偼偙偙偱乹拞惈崙壠乺傪嬤戙崙壠偺棟擮宆偲偟偰婰弎偟偰偄傞偺偱偼側偄丅惣懁丒儓乕儘僢僷偺嬤戙崙壠傪乹拞惈崙壠乺偲偟偰摿幙壔偟丄婰弎偟偰偄傞偺偱偁傞丅偙偺婰弎偼偡偱偵嫊峔偱偁傞丅偙偺乹拞惈崙壠乺偺婰弎偼丄偦偺斀懳懁偵乹斀丒拞惈崙壠乺傪摫偔偨傔偺嫊峔偱偁傞丅搶惣偺懳斾揑帇妏偵傛傞搶偺崙壠丒幮夛偺摿幙壔揑婰弎偼嫊峔偺婰弎偲側傞偙偲傪柶傟側偄丅巹偼僇乕儖丒僔儏儈僢僩傪屇傃弌偟偰偡傞娵嶳偺乹拞惈崙壠乺偺棟擮宆揑婰弎傪撉傒側偑傜丄亀擔杮惌帯巚憐巎尋媶亁偱娵嶳偑峔惉偡傞壃惗渉渜偺乹嶌堊揑幮夛乺憸偺婰弎傪巚偄婲偙偟偨丅乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偺偙偺堦愡傪撉傒側偑傜丄偁偨偐傕亀擔杮惌帯巚憐巎尋媶亁偺渉渜榑偺堦愡傪撉傫偱偄傞偐偺傛偆側嶖妎傪巹偼偍傏偊偨丅惂嶌庡懱傪慜採偵傕偭偨乹嶌堊揑幮夛乺偲偟偰儓乕儘僢僷嬤戙幮夛憸傪棟擮宆揑偵峔抸偟丄偦傟傪渉渜偺乹愭墹偺摴乺傪傔偖傞庲壠揑惌帯巚憐偵撉傒擖傟丄嬤戙偵愭嬱偡傞渉渜偺乹嶌堊揑幮夛乺憸傪娵嶳偼偱偭偪忋偘揑偵峔抸偟丄婰弎偡傞偺偱偁傞丅偙偆偟偰傢傟傢傟偑亀擔杮惌帯巚憐巎尋媶亁偵撉傑偝傟傞偺偼丄渉渜偺乹嶌堊揑幮夛乺憸傪峕屗偵抲偒朰傟偰嬤戙壔偡傞擔杮崙壠幮夛偺慜嬤戙揑側崙壠幮夛峔惉偲巚堃條幃偺帩懕偱偁傞丅
柧帯偺孾栔婜偵儓乕儘僢僷乹嬤戙乺偺嫊峔揑棟擮宆揑峔惉偑堄枴傪傕偭偨偺偼丄嬤戙壔偺嫵偊偲偟偰偱偁偭偨丅暉戲偺亀暥柧榑擵奣棯亁側偳偼偦偺傕偭偲傕椙幙側椺偱偁傠偆丅偩偑嬤戙愭恑崙壠暷塸偲偺憤椡愴偵攕傟偨1946擭偺愴屻擔杮偵偲偭偰丄乕乕憤椡愴傪愴偄偆傞偲偄偆偙偲偼擔杮傕傑偨嬤戙愭恑崙壠偱偁偭偨偙偲傪堄枴偡傞乕乕儓乕儘僢僷乹嬤戙乺偺嫊峔揑棟擮宆壔偺尵愢偼側偍嫵偊偲偟偰偺堄枴傪傕偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅偦傟偼暉戲傪桞堦偺巘偲偡傞娵嶳偵傛傞嵞搙偺丄偦偟偰恀惓偺嬤戙壔偺嫵愢側偺偐丅偦傟偲傕偙傟偼娵嶳偵傛傞惣墷嬤戙偺懳嬌憸偲偟偰偺慜嬤戙崙壠擔杮偺庺鎓傪偙傔偨斲掕揑嵞峔抸偺尵愢偱偁傞偺偐丅
娵嶳偼儓乕儘僢僷偵偍偗傞嬤戙乹拞惈崙壠乺偺宍惉夁掱傪丄乽(惌帯偲廆嫵偲偺娫偺鄷楏側妋幏偼)偐偔偟偰宍幃偲撪梕丄奜晹偲撪晹丄岞揑側傕偺偲巹揑側傕偺偲偄偆宍偱懨嫤偑峴傢傟丄巚憐怣嬄摴摽偺栤戣偼乽巹帠乿偲偟偰偦偺庡娤揑撪晹偑曐徹偝傟丄岞尃椡偼媄弍揑惈奿傪帩偭偨朄懱宯偺拞偵媧廂偝傟偨偺偱偁傞乿偲婰弎偟偰偄偔丅儓乕儘僢僷嬤戙偺乹拞惈崙壠乺偺娵嶳偵偍偗傞棟擮宆揑惉棫偲偲傕偵丄偁傞偄偼偦偺惉棫傪慜採偵偟偰偼偠傔偰乹斀丒拞惈崙壠乺偲偟偰偺擔杮揑崙壠偑婰弎偝傟傞偙偲偵側傞丅娵嶳偵傛傞擔杮揑崙壠偺婰弎傪尒傛偆丅
乽擔杮偼柧帯埲屻偺嬤戙崙壠偺宍惉夁掱偵墬偰彟偰偙偺傛偆側崙壠庡尃偺媄弍揑丄拞棫揑惈奿傪昞柧偟傛偆偲偟側偐偭偨丅偦偺寢壥丄擔杮偺崙壠庡媊偼撪梕揑壙抣偺幚懱偨傞偙偲偵偳偙傑偱傕帺屓偺巟攝崻嫆傪抲偙偆偲偟偨丅乿
乽偦偆偟偰戞堦夞掗崙媍夛偺彚廤傪栚慜偵峊偊偰嫵堢捄岅偑敪晍偝傟偨偙偲偼丄擔杮崙壠偑椣棟揑幚懱偲偟偰偺壙抣撪梕偺撈愯揑寛掕幰偨傞偙偲偺岞慠偨傞愰尵偱偁偭偨偲偄偭偰偄偄丅乿
乽崙壠偑乽崙懱乿偵墬偰恀慞旤偺撪梕揑壙抣傪愯桳偡傞偲偙傠偵偼丄妛栤傕寍弍傕偦偆偟偨壙抣揑幚懱傊偺埶懚傛傝傎偐偵懚棫偟摼側偄偙偲偼摉慠偱偁傞丅偟偐傕偦偺埶懚偼寛偟偰奜晹揑埶懚偱偼側偔丄傓偟傠撪晹揑側偦傟側偺偱偁傞丅乿
乹拞惈崙壠乺偺懳嬌偵峔惉偝傟偰偔傞偺偼丄壙抣揑側幚懱偲偟偰偺崙壠偱偁傞丅偙偺壙抣揑幚懱偲偟偰偺崙壠偱偁傞丅偙偺壙抣揑幚懱偲偟偰偺崙壠偲偼丄19悽婭廔傢傝偺搶傾僕傾偱崙壠偺帺棫揑懚棫傪偐偗偨擔杮偑崙壠偵梌偊偰偄偭偨柍擇偺崙壠惈僫僔儑僫儕僥傿乕偱偁傞丅偙偺柍擇偺崙壠惈傪揤峜偲崙壠偲崙柉偺摨帪揑惉棫傪偄偆憂惉恄榖傪傕偭偰廋忺偟丄偦傟傪乽崙懱乿偲偟偰擔杮偺嬤戙崙壠懚棫偺棟擮揑婎斦偲偟偰偄偭偨偺偱偁傞丅
巹偑偄偄偨偄偺偼娵嶳偑偄偆乽壙抣揑幚懱乿偲偟偰偺崙壠丄偁傞偄偼乽崙懱乿榑揑崙壠偲偼柧帯擔杮偑憂傝偩偟偨崙壠偩偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦傟偼寛偟偰嬤戙擔杮偵惉棫偡傞崙壠偑帺偢偐傜旛偊傞惈奿偱偼側偄丅暉戲偼亀暥柧榑擵奣棯亁偱柧帯弶擭偺崙柉偼乹拞惈崙壠乺傪偲傞偐丄乹崙懱榑揑崙壠乺傪偲傞偐偺廳戝側慖戰傪敆傜傟偰偄傞偙偲傪偄偭偰偄傞丅1875擭偺暉戲偵偍偄偰乹拞惈崙壠乺偼側偍壜擻側崙柉偺慖戰巿偱偁偭偨丅偩偑1946擭偺娵嶳偵偲偭偰乹拞惈崙壠乺偼嬤戙擔杮偵偍偗傞乹崙懱榑揑崙壠乺偺塣柦揑側旍戝傪庺鎓傪埲偰昤偒弌偡偨傔偺嫊峔偺棟擮宆偱偁傞丅娵嶳偼擔杮崙壠偺崙懱榑揑懚棫傪擔杮偺嬤戙崙壠偺摿堎惈偲偟偰偲傜偊丄崙懱榑揑崙壠庡媊偺夁忚偺揥奐傪乹挻崙壠庡媊乺偲偟偰婰弎偟偰偄偭偨丅
乹挻崙壠庡媊乺偑擔杮揑慡懱庡媊偱偁傞偺偼丄偦傟偑乹崙懱榑揑崙壠乺傊偺崙柉偺恎懱揑丄惛恄揑摑崌傪嫮惂偟丄偁傞偄偼撪晹偐傜偆側偑偡崙壠庡媊揑巟攝偺懱宯偱偁傞偐傜偱偁傠偆丅偙偙偱娵嶳偺乹挻崙壠庡媊乺揑巟攝偺暘愅偺摿堎惈偼丄乹崙懱榑揑崙壠乺偺懚棫偦偺傕偺偑惗傒弌偡丄崙柉偺巟攝—暈廬偺摿堎側怱棟夁掱偺暘愅揑側婰弎偵偁傞丅娵嶳偼崙柉偺巟攝—暈廬偺怱棟夁掱傪棨孯撪柋斍偵徾挜揑偵尒側偑傜桳柤側乽梷埑偺堏忳乿偲偄偆尃椡巟攝偺偁傝曽傪昤偒弌偡丅
乽偝偰枖丄偙偆偟偨帺桼側庡懱堄幆偑懚偣偢奺恖偑峴摦偺惂栺傪帺傜偺椙怱偺偆偪偵帩偨偢偟偰丄傛傝忋媺偺幰(廬偭偰媶嬌揑壙抣偵嬤偄傕偺)偺懚嵼偵傛偭偰婯掕偝傟偰偄傞偙偲偐傜偟偰丄撈嵸娤擮偵偐傢偭偰梷埑偺堏忳偵傛傞惛恄揑嬒峵偺曐帩偲偱傕偄偆傋偒尰徾偑敪惗偡傞丅忋偐傜偺埑敆姶傪壓傊偺湏堄偺敪婗偵傛偭偰弴師偵堏忳偟偰峴偔帠偵傛偭偰慡懱偺僶儔儞僗偑曐帩偝傟偰偄傞懱宯偱偁傞丅乿
偙偺乽梷埑偺堏忳乿偲偄偆巟攝—暈廬偺懱宯偼揤峜惂崙壠偺巟攝—暈廬偺懱宯偵傎偐側傜側偄丅
乽揤峜傪拞怱偲偟丄偦傟偐傜偺偝傑偞傑偺嫍棧偵墬偰枩柉偑梼巀偡傞偲偄偆帠懺傪堦偮偺摨怱墌偱昞尰偡傞側傜偽丄偦偺拞怱偼揰偱偼側偔偟偰幚偼偙傟傪悅捈偵娧偔堦偮偺廲幉偵傎偐側傜偸丅偦偆偟偰拞怱偐傜偺壙抣偺柍尷偺棳弌偼丄廲幉偺柍尷惈(揤忞柍媷偺峜塣)偵傛偭偰扴曐偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅乿
娵嶳偺乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿傊偺恖傃偲偺徧巀偼丄傎偲傫偳偙傟傜偺揤峜惂崙壠偺巟攝—暈廬偺幮夛怱棟妛揑側婰弎傊偺徧巀偵峴偒偮偔丅恖傃偲偼憟偭偰偙傟傪堷梡偟丄偙偺堷梡傪傕偭偰擔杮僼傽僔僘儉傊偺捛媦傪巭傔偰偟傑偭偨丅偦偺偲偒恖傃偲偼娵嶳偲偲傕偵擔杮僼傽僔僘儉傪塀暳偟丄尒摝偟偰偟傑偭偨偙偲偵婥晅偐側偄丅
|
仭4丂擔杮僼傽僔僘儉偵偼巒傑傝偑偁傞
擔杮僼傽僔僘儉偵偼巒傑傝偑側偄偲娵嶳偼偄偆丅斵偼偙傟傪擔杮僼傽僔僘儉偵偼亀変偑摤憟亁偑側偄偲偄偆偄偄曽偱偟偰偄偨丅娵嶳偲偄偆尰戙擔杮偺戙昞揑抦幆恖偺偙偺廘傒偺偁傞偄偄曽偼丄擇偮偺偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅堦偮偵偼擔杮僼傽僔僘儉傪乹崙懱榑揑崙壠庡媊乺偺巒傑傝偺側偄慟恑揑側夁寖壔偲偟偰偲傜偊傞偙偲偱偁傞丅擇偮偵偼娵嶳偺擔杮僼傽僔僘儉偺婰弎偼擔杮揑摿堎惈偺婰弎偵廔巒偡傞偙偲偱偁傞丅偙偺擇偮偼擔杮僼傽僔僘儉傪娵嶳偑乹挻崙壠庡媊乺偲偟偰奣擮峔惉偡傞偙偲偺椉柺偱偁傞丅
娵嶳偼擔杮僼傽僔僘儉傪乹挻崙壠庡媊乺偲偟偰奣擮峔惉偡傞偙偲偵傛偭偰丄偡側傢偪擔杮僼傽僔僘儉傪乹崙懱榑揑崙壠榑乺偺栤戣偵娨尦偟偰偟傑偭偰丄1930擭偵偍偗傞悽奅巎揑慡懱庡媊偺惉棫偺栤戣偐傜愗傝棧偟偰偟傑偆丅僪僀僣丒僫僠僘儉偼娵嶳偵偍偄偰擔杮僼傽僔僘儉偺摿堎惈傪朶偒弌偡棟擮宆偵側偭偰偟傑偆丅偙傟偼娵嶳惌帯妛偺崻掙揑側娫堘偄偱偁傞丅
擔杮僼傽僔僘儉傪悽奅巎揑慡懱庡媊偲偺娭楢偺拞偱尒傞側傜偽丄擔杮僼傽僔僘儉偼徍榓僼傽僔僘儉偲偟偰惉棫偟偨帪婜傪偼偭偒傝偲傕偮偙偲偵側傞丅偦偺帪婜偲偼1931(徍榓6)擭偺枮廈帠曄偑婲偙偭偨帪婜偱偁傞丅憤椡愴傪壜擻偵偡傞擔杮偺慡懱庡媊揑懱惂壓偑偙偺帠曄偲偲傕偵巒傑偭偨偺偱偁傞丅慡懱庡媊壔偡傞徍榓擔杮偺偨偩拞偵惗傑傟偨巹偼傕偲傛傝偙偺曄壔傪抦傞偙偲偼側偐偭偨丅偩偑娵嶳偨偪偺悽戙偼枮廈帠曄偲偲傕偵巒傑傞擔杮偺懱惂揑曄壔偵婥晅偄偨偼偢偱偁傞丅偵傕偐偐傢傜偢娵嶳偼攕愴偺梻擭偵擔杮僼傽僔僘儉傪巒傑傝偺側偄乹挻崙壠庡媊乺偲偟偰丄僼傽僔僘儉偺擔杮揑摿堎宆偲偟偰婰弎偟偨丅乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偼戝偒側昡壙傪偊偨丅偩偑偙偺榑暥偺惉岟偲偲傕偵擔杮僼傽僔僘儉傪偦偺挘杮恖偳傕偲偲傕偵傢傟傢傟偼尒摝偟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅
傢傟傢傟偼偄傑埨攞偲擔杮夛媍偵擔杮僼傽僔僘儉偺21悽婭揑嵞惗傪尒偰偄傞丅偙傟偼悽奅揑偵尒偰懠偵椺傪傒側偄帠懺偱偁傞丅
側偤変乆偼悽奅偵椺傪尒側偄愴慜僼傽僔僘儉偺嵞惗暅妶傪嫋偟偰偟傑偭偨偺偐丅巹偼溚溋偺巚偄偱愴屻夁掱傪怳傝曉偭偰偄傞丅傢傟傢傟偼擔杮僼傽僔僘儉傪尒摝偟偰偒偨偺偱偼側偄偐丅娵嶳偺乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偼偙偺尒摝偟偺堦場傪側偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丅 |
| 丂 |
   丂
丂
|
|
丂 |
| 仭崙柉庡媊丂 |
   丂
丂
|
仭 崙柉偺恖尃傗帺桼傪懜廳偟偮偮丄柉庡揑偵崙壠傪宍惉丒敪揥偝偣傛偆偲偡傞巚憐丒塣摦丅僫僔儑僫儕僘儉丅
仭 崙柉揑摑堦偺傕偲偵崙柉偺惌帯傊偺嶲壛偵傛傞嬤戙崙壠偺宍惉丒敪揥傪栚巜偡棫応丅僫僔儑僫儕僘儉丅
仭 乧偙偺慜屻丆堜忋婤傜偺抦嬾傪摼丆僼儔儞僗偺斀妚柦庡媊幰J.M.de儊乕僗僩儖偺彂暔傪乻庡尃尨榑乼偺戣偱東栿弌斉偡傞丅88擭惌晎偺忦栺夵惓偲墷壔惌嶔偵斀懳偟偰帿怑丆扟姳忛傜偺墖彆傪庴偗偰4寧傛傝乻搶嫗揹曬乼傪敪姧偟丆摨寧憂姧偺惌嫵幮偺嶨帍乻擔杮恖乼偺乹崙悎庡媊乺偵屇墳偟偰丆乹崙柉庡媊乺傪彞偊傞丅偙偺怴暦偼梻89擭2寧夵慻偝傟偰乻擔杮乼偲側傞偑丆偨傑偨傑楻塳偟偨戝孏廳怣奜憡偺忦栺夵惓埬斸敾傪捠偟偰丆愎撿偺柤偼堦桇崅傑傞丅乧
仭 乧偙偺崲擄傪曗偆揰偱廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偺偑柉懓庡媊偱偁傝丆柉懓崙壠丆崙柉崙壠偑楌巎偺棳傟偲側傞側偐偱崙壠庡媊偼柉懓庡媊偲偺梈崌傪偲偘丆偦偺棟擮傪曗姰偡傞偙偲偵側偭偨丅幚嵺丆擔杮偱偼廬棃丆崙壠偲柉懓偲偺廳側傝偑傎傏帺柧帇偝傟偰偒偨偙偲傕偁偭偰丆崙壠庡媊丆柉懓庡媊丆崙柉庡媊丆崙悎庡媊偲偄偭偨尵梩偼傎偲傫偳摨媊偵梡偄傜傟偰偄傞丅偟偨偑偭偰偙傟傜偺岅偼崙壠庡媊偺戞2偺撪梕傪側偡偲偄偭偰傛偄丅乧
仭 乧傑偨擇梩掄巐柪傗摽晊錬壴側偳偵傛傞暥妛偺妚怴傪傕幚尰偝偣偨丅偙傟偵懳峈偟偨嶰戭愥椾丆巙夑廳峍傜偺惌嫵幮偼丆嶨帍乻擔杮恖乼偵傛偭偰棨愎撿偺怴暦乻擔杮乼偲偲傕偵乹崙柉庡媊乺傪彞偊偨丅乻擔杮恖乼偼崅搰扽峼偺岯晇偺楯摥忦審偺夁崜偝傪慽偊偰丆偄傢備傞儖億儖僞乕僕儏偺愭嬱偲側傝丆乻擔杮乼偼惓壀巕婯偺攐嬪嵞嫽偺晳戜偲側偭偰崙柉揑側傂傠偑傝傪傕偮抁帊宆暥寍姷廗傪掕埵偡傞側偳丆擔杮偺嬤戙暥妛偵峷專偟偨丅乧
仭 乧偐偮偰偼丆柉懓庡媊丆崙柉庡媊丆崙壠庡媊側偳偲栿偟暘偗傜傟傞偙偲偑懡偐偭偨偑丆嵟嬤偱偼堦斒偵僫僔儑僫儕僘儉偲昞婰偝傟傞丅偙偺偙偲偼丆僫僔儑僫儕僘儉偲偄偆尵梩偺懡媊惈傪斀塮偟丆偦偟偰偦偺懡媊惈偼丆偦傟偧傟偺僱乕僔儑儞nation傗丆偦偺僫僔儑僫儕僘儉偺扴偄庤偑偍偐傟偰偄傞楌巎揑埵抲偺懡條惈傪斀塮偟偰偄傞丅乧
仭 棨愎撿偺崙柉庡媊 / 惌帯偵墬偗傞崙柉榑攈偺戝梫 / 崙撪揑惌帯(僫僔儑僫儖亖億儕僠僢僋)偲偼奜偵懳偟偰崙柉偺摿棫傪堄枴偟丄帶偟偰撪偵墬偰偼崙柉偺摑堦傪堄枴偡丄崙柉偺摑堦偲偼杴偦杮棃偵墬偰崙柉慡懱偵懏偡傋偒幰偼丄昁偢擵傪崙柉揑偵偡傞偺堗側傝丄愄帪偵嵼傝偰偼枹偩崙柉偺摑堦側傞傕偺偁傜偢丄懘擵偁傞偑擛偒桞偩奜娤偵夁偓偢偟偰丄峏偵幚憡傪尒傟偽堦庬懓堦抧曽枖偼堦搣梌偺愱桳偨傞偙偲傪柶傟偞傞偁傫傝丅掗幒偺擛偒丄惌晎偺擛偒丄朄惂偺擛偒丄嵸敾偺擛偒丄暫攏偺擛偒丄慸惻偺擛偒丄杴偦崯摍偺帠暔偼奆杮棃偵墬偰崙柉慡懱偵懏偡傋偒傕偺偲偡丄慠傞偵愄帪偵嵼傝偰偼巣傞帠暔奆側崙柉拞偺堦晹偵擟偟偰懘偺巹椞偲堊偣傝丄惀傟崙柉摑堦偺幚側偒傕偺側傝丄崙柉榑攈偼撪晹偵岦偰崯偺曃悳媦暘楐傪嫥嵪偣傫偲梸偡丅偝傟偽崙柉揑惌帯偲偼崯偺揰偵墬偰偼懄偪悽懎偺強堗傞梎榑惌帯側傝偲堗傆傋偟丄亀揤壓偼揤壓偺揤壓側傝亁偲尵傊傞奿尵傪偽擵傪幚抧偵揔梡偟丄崙柉慡懱傪偟偰崙柉揑擟柋傪暘彾偣偟傔傫偙偲偼崙柉榑攈偺撪帯偵墬偗傞戞堦偺梫巪側傝偲偡丄崯棟桼偵傛傝偰崙柉榑攈偼棫寷孨庡惌懱偺慞惌懱側傞偙偲傪妋擣偡
丂
丂 |
| 仭乽崙柉庡媊乿偺栤戣 |
   丂
丂
|
仭1丄愇揷梇偺栤戣採婲
愇揷梇丒汭彯拞偵傛傞亀娵嶳恀抝偲巗柉幮夛亁傪丄傢傟傢傟撉幰偼偳偺傛偆偵撉傓傋偒側偺偱偁傠偆偐丅偙偺杮偼弮慠偨傞挊嶌偱偼側偔摙榑偺撪梕偑揨傔傜傟偨傕偺偱偁傞丅偦偟偰擇恖偺懳択偱傕側偄丅偙偺媍榑偺拞偱汭彯拞偼僎僗僩偱偁傝丄儂僗僩偼愇揷梇偱偁傞丅偙偺摙榑傪弶傔偐傜婇夋丒峔惉偟丄庡摫偟偰偄傞偺偼愇揷梇偱偁傞丅宍偼摙榑宍幃偱偁傞偗傟偳傕丄撪梕揑偵偼傎偲傫偳愇揷梇敘偺亀娵嶳恀抝偲巗柉幮夛亁偲側偭偰偄傞丅偦偙偵汭彯拞傪壛偊偨偺偼丄愇揷梇帺恎偺栤戣採婲傪儓儕姰寢偝偣傞偨傔偺栚揑揑側攝椂偐傜偱偁傞偲尵偭偰傛偄丅
偙偺媍榑偺拞偱丄愇揷梇偼偒傢傔偰廳戝側栤戣採婲傪擇偮偟偰偄傞丅偦偺堦偮偼丄娵嶳恀抝偺巚憐偺拞偵偼廜栚偑尵偆傛偆側乽巗柉幮夛乿偺昞尰丒尵媦偼側偄丄偦偆偟偨奣擮丒棟榑偼側偄丄娵嶳恀抝傪乽巗柉幮夛攈乿偲偟偰婯掕偡傞偺偼岆傝偱偁傞丄偦傟偼娵嶳恀抝傪乽嬤戙庡媊乿偲偟偰斸敾偡傞恖乆偵傛偭偰嶌傜傟偨僀儊亅僕偱偁傝僔儞儃儖偱偁傞偲偄偆巜揈偱偁傞丅偙偺巜揈丄栤戣採婲偺堄枴偼旕忢偵戝偒偄丅
傕偆堦偮偼丄偦偺巗柉幮夛偺栤戣偲傕娭楢偡傞偑丄亀楌巎堄幆偺脩w乿亁偵偍偄偰娵嶳恀抝偑榑偠偰偄傞擔杮擣幆丄尨擔杮憸攃埇偺慜採(摍幙揑丒嬒幙揑側擔杮恖偺崙柉惈丄擔杮恖崙壠亀偔偵亁偺楌巎巒尨揑惉棫)偼丄嬤戙揑側崙柉庡媊偺峫偊曽傪楌巎傪熻偭偰搳塭偡傞曽朄懺搙偱偁傝丄偦傟偼娵嶳恀抝偺乽桬傒懌乿偱偁偭偨偲偄偆媍榑偱偁傞丅傢傟傢傟撉幰偼丄愇揷梇偑娵嶳恀抝偺乽桬傒懌乿傪尵偆偺傪弶傔偰暦偔丅
偙偺戞擇偺栤戣採婲傪暦偄偨偲偒丄傢傟傢傟偼丄壗屘偦偙偵愇揷梇偑汭彯拞傪彽偄偨偺偐傪傛偔棟夝偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵巚傢傟傞丅偦傟偼偡側傢偪汭彯拞傜偵傛偭偰幏漍偵斸敾偝傟偰偒偨偲偙傠偺乽崙柉庡媊幰娵嶳恀抝乿偺巚憐憸偵懳偟偰堦愇傪搳偠傛偆偲偡傞帋傒偱偁傞偲尵偊傞偩傠偆丅擔杮崙柉撪晹偺堎幙惈傗廃曈傾僕傾彅崙偵懳偡傞擔杮偺怤棯偺帠幚偵攝椂偟傛偆偲偟側偄乽"嬤戙庡媊幰"娵嶳恀抝偺崙柉庡媊揑尷奅惈乿偲偄偆媍榑偼丄敧仜擭戙埲崀丄擭庒偄尋媶幰偨偪偺娫偱偺乭娵嶳恀抝斸敾乭偺掕斣僙僆儕亅偲側偭偰偒偨傕偺偱偁傞丅偦偺嬤戙庡媊斸敾偲偟偰偺崙柉庡媊斸敾偼丄娵嶳恀抝偺傒側傜偢柧帯偺暉戲桜媑傪幩掱偵悩偊偨傕偺偱偁偭偨丅
汭彯拞傪昅摢偲偡傞偦偆偟偨僆儕僄儞僞儕僘儉斸敾偺帇妏偐傜偺乽崙柉庡媊幰蹘R恀抝乿斸敾偺媍榑偵懳偟偰丄娵嶳恀抝帺恎偑壗傜偐斀榑傪傕偭偰墳偊傞偙偲偼側偐偭偨偑丄娵嶳恀抝偺巰嫀偺偁偲丄愇揷梇偑悑偵偦傟偵懳偡傞摦偒傪尒偣偨偺偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄偦傟偼摨帪偵亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁偵偍偄偰揟宆揑偵昞尰偝傟偰偄傞偲偙傠偺娵嶳恀抝偺乽擔杮揑尨憸乿偺擣幆曽朄傪乽桬傒懌乿偡側傢偪 mistake 偲偡傞丄撉幰偵偲偭偰偼堄奜側斀墳偲懳墳偱偁偭偨丅
傑偢丄抂揑偵丄傕偭偲傕栤戣偑偁傞偲巚傢傟傞売強傪堷偄偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅乽屆憌乿榑暥(亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁堦嬨幍擇擭)偺側偐偺堦愡偱偡丅
乽傢傟傢傟偺亀偔偵亁偑椞堟丒柉懓丒尵岅丒悈堫惗嶻條幃偍傛傃偦傟偲寢傃偮偄偨廤棊偲嵳媀偺宍懺側偳偺揰偱丄悽奅偺亀暥柧崙亁偺側偐偱斾妑偡傟偽傑偭偨偔椺奜揑偲偄偊傞傎偳偺摍幙惈傪丄抶偔傕屻婜屆暛帪戙偐傜愮悢昐擭偵傢偨偭偰堷偒懕偒曐帩偟偰棃偨丄偲偄偆偁偺廳偨偄楌巎揑尰幚偑墶偨傢偭偰偄傞乿
(拞棯)偦傟偵偟偰傕偙偺堦愡偼丄嬤戙擔杮偵偍偗傞丄偮偔傜傟偨揱摑偲偟偰偺摍幙惈偺恄榖偲偄偆傕偺傪屻婜屆暛帪戙傑偱熻傜偣偨偲偄偆揰偱丄柧傜偐偵娵嶳偵偲偭偰桬傒懌偱偁偭偨偲巹偼巚偄傑偡丅
(拞棯)偙偺乽屆憌乿偵戙昞偝傟傞愙嬤曽朄偵偮偄偰偼丄娵嶳帺恎偁傞庬偺晄埨傪姶偠偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅偦傟偼偙偺愙嬤偺拞妀傪側偡奣擮偺晄埨掕惈偵傕帵偝傟偰偄傑偡丅(拞棯)乽屆憌乿偱柧傜偐偵偝傟偨偦偺摿挜揑側巚峫條幃偼丄偄傢偽廻柦揑側傕偺偵側偭偰偟傑偄偐偹側偄丅(拞棯)偦偆偄偆憡懳壔傪敽傢側偄応崌偵偼丄偁傞庬偺暥壔揑寛掕榑偲偟偰廻柦榑偵棊偪崬傓婋尟惈傪傕偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅
愇揷梇偺偙偺媍榑偼丄偁傞晹暘丄偙傟傑偱偺汭彯拞傜偺娵嶳恀抝斸敾傪擣傔傞媍榑偱偁傞偲尵偊傞丅偦傟傪晹暘揑偵擣傔偮偮丄偦偺乽岆昑乿傪堦嬨幍仜擭戙偺乽擔杮揑尨憸榑乿偺廃曈偵巭傔丄娵嶳恀抝偺巚憐慡懱偐傜偡傟偽寛掕揑側栤戣揰偱偼側偄偲偄偆榑弎偑側偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅汭彯拞帺恎傕丄偙偺愇揷梇偺乽桬傒懌乿偺栤戣採婲偑堄奜側傕偺偱偁偭偨條巕偩偑丄屻偺斵偺曬崘偺晹暘偱偼丄娵嶳恀抝偺堦嬨巐嬨擭偺榑暥亀嬤戙擔杮巚憐巎偵偍偗傞崙壠棟惈亁傪庢傝忋偘丄娵嶳恀抝偺崙柉庡媊揑巚峫偑扨偵亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁偺屆戙巎擣幆廃曈偵尷掕偝傟傞傕偺偱偼側偔丄傕偭偲杮棃揑偱杮幙揑側傕偺偱偼側偄偐偲偄偆揰傪斀榑偟偰偄傞丅偙傟偼摉慠偺斀榑偱偁傠偆丅
傢傟傢傟撉幰偼丄偙偺愇揷梇偺乽桬傒懌乿榑偺栤戣採婲傪偳偺傛偆偵庴偗偲傔傞傋偒側偺偱偁傠偆偐丅
|
仭2丄崙柉庡媊偲抧媴幮夛庡媊
偙傟偼僫僔儑僫儕僘儉偺栤戣偱偁傞丅Political Theory 偲 Nationalism 偺栤戣偱偁傞
嵟弶偵巹帺恎偺姶憐傪尵偊偽丄偙偺愇揷梇偺乽桬傒懌乿榑偼丄偁傑傝愊嬌揑側堄枴傪擣傔傜傟傞傕偺偱偼側偄丅偦偙傑偱娵嶳恀抝偺乽擔杮揑尨憸攃埇乿傪斲掕揑偵尒傞昁梫偼側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆偺偑棪捈側報徾偱偁傞丅偦偙傑偱僆儕僄儞僞儕僘儉榑揑帇妏偐傜偺乽崙柉庡媊幰娵嶳恀抝斸敾乿偺媍榑偵旼傪孅偡傞昁梫偼側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆偺偑丄撉幰偱偁傞巹偺姶偠曽偱偁偭偨丅巹偼丄僆儕僄儞僞儕僘儉榑偐傜偺暉戲桜媑斸敾傗娵嶳恀抝斸敾偵偼 亅 偦傟偵偮偄偰傎偲傫偳柍抦偱偁傞偙偲偑棟桼偺戞堦偱偼偁傞偺偩偗傟偳 亅 壗偺愢摼椡傕姶偠側偄偺偱偁傞丅
愴拞愴屻偺娵嶳恀抝傗柧帯偺暉戲桜媑偵乽抧媴巗柉乿偺巚憐傪梫媮偡傞偺偼丄峕屗婜偺壃惗仩仩傗杮嫃愰挿偵乽巗柉妚柦乿偺巚憐傪婜懸偡傞偺偲慡偔摨條偺乽柍棟乿偱偼側偄偺偐丅偦傟偼丄岾摽廐悈偵乽慜塹搣偵傛傞擇抜奒妚柦乿傪媮傔傞偺偲摨偠旘桇偲尵偊傞偺偱偼側偄偺偐丅偦傟偙偦傑偝偵僴儖亅僩僁僯傾儞偺尵偆乽楌巎偐傜偺棧扙乿偦偺傕偺偱偼側偄偺偐丅傢傟傢傟偼丄儕儞僑偑栘偐傜棊偪傞偺傪尒偰乽枩桳堷椡偺朄懃乿傪敪尒偟偨暔棟妛幰僯儏亅僩儞偵懳偟偰丄偳偆偟偰偍慜偼乽憡懳惈棟榑乿偺敪尒傑偱摫偗側偐偭偨偺偐側偳偲僋儗亅儉傪偮偗偨傝偡傞偙偲偑偁傞偩傠偆偐丅偦傟偼偳偆峫偊偰傕乽柍偄傕偺偹偩傝乿偺乽柍棟側偍婅偄乿偲尵偆傋偒偱偁傞丅
幮夛壢妛偲偟偰偺惌帯妛偵偼丄帺慠壢妛偲摨偠傛偆偵偦偺帪乆偺梌偊傜傟偨楌巎揑壽戣偲偄偆傕偺偑偁傞丅偦偺壽戣傪惓妋偵暘愅攃埇偟丄偦偟偰偦偺偲偒嵟戝尷壜擻側揥朷傪巜偟帵偡偺偑幮夛壢妛幰偺栶妱偱偁傞偲尵偊傞偩傠偆丅強梌揑偱尷奅揑側偦傟偧傟偺楌巎揑娐嫬偺拞偱丄偳偙傑偱晛曊揑側棟擮傪尰幚壔傊偲摫偔偙偲偑偱偒傞偐丄偦傟偙偦偑梊尵幰偲偟偰偺巚憐壠偺壽戣偱偁傞丅壗帪偺帪戙偱傕恖偼棟擮偲尰幚偺嬞挘娭學偺拞偵棫偨側偗傟偽側傜側偄丅
偦偺僫僔儑僫儕僘儉(偨偲偊偽亀嬤戙擔杮巚憐巎偵偍偗傞崙壠棟惈亁偵尒傜傟傞)偼丄娵嶳恀抝偵偍偗傞尷奅惈偲尵偆傛傝傕傓偟傠楌巎惈偲尵偆傋偒偱偁傝丄楌巎惈偲偟偰愊嬌揑偵昡壙偱偒傞傕偺偱偁傞丅摿偵丄擔杮偺惌帯揑撈棫偑偒傢傔偰晄埨掕偱晄摟柧側娐嫬偵偁偭偨愴屻堦嬨屲仜擭戙偺帪戙傑偱偺棟榑偵偮偄偰偼丄柧妋偵偦偆抐尵偡傞偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅偦偺崰偺娵嶳恀抝偑乽抧媴巗柉榑乿傪揻偄偰偄偨偲偡傟偽丄傢傟傢傟偼惌帯妛幰偲偟偰偺娵嶳恀抝偺僙儞僗傪戝偄偵媈傢側偗傟偽側傜側偄偼偢偱偁傞丅
傑偨丄嵟斢擭偺嵗択夛偱偼丄娵嶳恀抝帺恎偵傛傞師偺傛偆側敪尵傪尒傞偙偲偑偱偒傞丅
愇愳 / 崙楢偵偮偄偰偼偳偆偱偟傚偆丅
娵嶳 / 庡尃崙壠偼晲椡偺惓摑惈傪撈愯偟偰偄傑偡丅偩偐傜崙楢偺慻怐偑庡尃崙壠傪桞堦偺扨埵偲偟偰偄傞偐偓傝丄偦偺摦偒偼戝崙偺棙奞偱嵍塃偝傟丄杮摉偺悽奅慻怐偲偟偰暣憟傪夝寛偡傞偺偵栶棫偨側偄丅戝懱丄崙柉崙壠偑庡尃傪傕偭偰悽奅拋彉偺扨埵偵側偭偨偺偼丄楌巎偼挿偦偆偵尒偊傞偗傟偳丄戞堦師戝愴埲屻偺偙偲偱偡傛丅偦傟傑偱拋彉傪堐帩偟偰偒偨庡梫側戝掗崙偑憡偮偄偱曵夡偟偰偐傜偱偡丅庡尃奣擮偑儓亅儘僢僷偵宍惉偝傟偰偐傜傕丄偣偄偤偄嶰昐擭梋傝偩丅恖娫偺巚峫偲偄偆傕偺偼懩惈偑嫮偔偰丄尰幚偺曄壔傛傝抶傟傞偺偑忢偱偡偹丅(拞棯)
愇愳 / 崱偺傑傑偱偼丄崙楢偺枹棃偼埫偄偱偡偹丅
娵嶳 / 崻杮夵慻傪偡傞偟偐側偄偱偡偹丅堦曽偱偼僾儖亅儔儖側幮夛抍懱偺丄崙壠偐傜偺帺庡惈傪嫮壔偟丄懠曽偱崙壠傪攠懱偵偟側偄偱捈愙偵崙嵺揑偵寢崌偟偰抧媴幮夛偺峔惉堳偵側傞傛偆側僔僗僥儉傪峫偊傞傎偐側偄丅傑偁丄擇廫堦悽婭偵傕偪偙偡壽戣偱偟傚偆偑丄寷朄嬨忦傪傕偮擔杮偼丄偙偆偄偆曽岦偱丄偮傑傝崙壠庡尃傪巚偄愗偭偰惂尷偡傞曽岦偱偺夵妚傪庡挘偱偒傞棫応偵偁傞丅(拞棯)
偙偙偱娵嶳恀抝偼嬤戙揑側庡尃崙壠偺尷奅傪尵偄丄偦偟偰抧媴幮夛偺崙楢峔憐傪弎傋偰偄傞丅汭彯拞偼娵嶳恀抝帺恎偺偙偺敪尵傪偳偺傛偆偵庴偗巭傔傞偺偱偁傠偆偐丅偙偆偟偨敪尵偼丄嬤戙庡媊幰偱偁傝崙柉庡媊幰偱偁傞娵嶳恀抝偺乽揮岦乿偱偁傞偺偩傠偆偐丅偦偆偱偼側偄偩傠偆丅偦傟偼揮岦偱傕曄愡偱傕側偄丅偦傟偼扨偵丄娵嶳恀抝偵傛偭偰尰嵼偺乽忢幆乿偑弎傋傜傟偰偄傞偵夁偓側偄丅汭彯拞偑挿擭庡挘偟丄崱夞愇揷梇偑堦晹擣傔傞丄偙偺娵嶳恀抝偺乽嬤戙揑側崙柉崙壠娤偺楌巎巒尨偺帪戙傊偺庡娤揑搳塭乿傊偺斸敾偼丄媡偵丄遁彯拞偲愇揷梇帺恎偺丄尰嵼偮偔傜傟梌偊傜傟偰偄傞屆戙巎娤丒屆戙巎擣幆偺乽忢幆乿傪楌巎傪熻偭偰擇廫屲擭慜偺娵嶳恀抝偵揔梡偟搳塭偡傞旕楌巎揑側曽朄懺搙偱偁傞偲偼尵偊側偄偺偐丅
|
仭3丄乽擔杮揑尨憸乿攃埇偺壽戣偲曽朄
愇揷梇偑尵偆偲偍傝丄娵嶳恀抝偺擔杮揑尨憸棟夝偼丄嬤戙揑側崙柉崙壠娤偺楌巎巒尨偺帪戙傊偺搳塭偱偁傞偲尵偊傞偺偐傕抦傟側偄丅偟偐偟丄摉帪堦嬨幍擇擭傑偱偺屆戙巎妛偵偍偄偰偼柍榑偺偙偲丄偦傟埲崀丄尰嵼傑偱偺擔杮偺楌巎妛傗峫屆妛偺壢妛揑巎椏揑惉壥傪尩枾偵捛愓偟偨偲偟偰傕丄偙偺娵嶳恀抝偺擔杮揑尨憸榑傪崻掙偐傜斲掕偡傞傑偱偺寛掕揑側崻嫆傪弨旛偟摼偰偄傞偲偼昁偢偟傕尵偊側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偨偲偊偽嵟嬤傑偱偺尋媶惉壥偺僗僞儞僟亅僪側曬崘偱偁傞偼偢偺娾攇彂揦亀娾攇島嵗 擔杮捠巎 戞2姫 屆戙1亁(堦嬨嬨嶰擭)側偳傪嬦枴惛撉偟偰傕丄偦偺婰弎偼埶慠偲偟偰乽屆戙崙柉崙壠乿揑側楌巎娤傪婎挷偲偟偨傕偺偱偁傞丅
丂丂丂婼摢惔柧 : 榋悽婭傑偱偺擔杮楍搰 亅 榒崙偺惉棫 亅
丂丂丂嶁尦媊庬 : 搶傾僕傾偺崙嵺娭學
丂丂丂媑懞晲旻 : 榒崙偲戝榓墹尃
偦傟偵偼棟桼偑偁傞丅
偦偺(屆戙崙柉崙壠揑側)楌巎擣幆丒屆戙巎擣幆偑丄戝擔杮掗崙偑曵夡偟丄峜崙巎娤偑柵傃嫀偭偨屻偵妋棫偝傟偨愴屻擔杮偺堦斒揑丒昗弨揑側屆戙巎娤偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅巹側傝偺尵梩偱昞尰偡傞側傜丄偦傟偼偡側傢偪乽擔杮崙寷朄偑嫋偡偲偙傠偺亀擔杮彂婭亁偺撉傒曽乿偵懠側傜側偄丅峜崙巎娤傪嫅斲偡傞擔杮崙寷朄偲偄偆忦審偲亀擔杮彂婭亁偺婰弎偲偄偆忦審偺擇偮偑尰嵼偺僗僞儞僟亅僪側乽擔杮恖偺楌巎揑尨憸乿傪僉亅僾偝偣偰偄傞丅寢榑偐傜尵偆側傜丄擔杮彂婭偁傞偄偼屆帠婰偺巎椏尋媶傪婎慴偲偟偰擔杮屆戙偺幚憸傪晜偐傃忋偑傜偣傛偆偲偡傞尷傝丄扤偺庤偵傛傞壖愢偵偍偄偰傕丄昁偢偙偆偟偨乽屆戙崙柉崙壠乿揑側楌巎擣幆偲偟偰寢壥偣偞傞傪摼側偄偩傠偆丅偦偺朄(偺傝)傪崕偊傞偙偲偑偱偒傞偺偼丄楌巎妛幰偱偼側偔丄楌巎擣幆偐傜壢妛揑曽朄傪攔彍偟偰怱傪捝傔傞偙偲偺側偄揘妛幰偺傒偱偁傞丅
廃抦偺偲偍傝丄擔杮巎妛偺悽奅偵偼丄幮夛壢妛偲偼堦枴堘偭偨撈摿偺揱摑揑側妛栤條幃偑懚嵼偡傞丅偦傟偼乽搶嫗妛攈乿偲乽嫗搒妛攈乿偲偄偆擇偮偺僌儖亅僾偵傛傞懳棫揑嫤嬈偺峔恾偱偁傞丅扨偵崙棫戝妛傗楌巎攷暔娰偺尋媶怑堳偩偗偱側偔丄峀偔嵼栰偺楌巎彫愢壠傑偱僀儞儃儖償偟偰偙偺懳棫揑峔恾偼擻摦揑偵婡擻偟偰偄傞偺偱偁傞丅堦斒揑側報徾傪尵偊偽丄搶嫗妛攈偑僆亅僜僪僢僋僗側壢妛偲峫徹偺婎弨傪庣偭偰僗僞儞僟亅僪側擔杮楌巎憸傪怲廳偵採嫙丄宲彸偟丄堦曽丄嫗搒妛攈偑帺桼杬曻偵偦偺榞傪攋偭偰怴愢丒捒愢丒婏愢偺椶傪棎敪偡傞偲偄偆峔恾偱偁傞丅儅僗僐儈傗弌斉幮傗楌巎儅僯傾偑旘傃偮偔偺偼嫗搒妛攈偺帺桼側憐憸椡偩偑丄堦扷丄楌巎嫵壢彂婰弎偲偄偆傛偆側怺崗側栤戣偵側傞偲丄楌巎妛偼壢妛偲忢幆偺僗僞儞僗偵尩弆偵棫偪栠傜側偗傟偽側傜側偄丅
娵嶳恀抝偺乽擔杮揑尨憸乿榑傪嬤戙庡媊揑側帺屓擣幆偺庡娤揑搳塭偩偲岥愭偱斸敾偡傞偙偲偼梕堈偱偁傞丅偟偐偟偦傟偱偼丄汭彯拞側傜偽堦懱偳偺傛偆側乽屆戙擔杮偺尨憸乿傪擔杮崙柉偵採嫙偟偰偔傟傞偺偐丅擔杮崙寷朄偑偁傝丄擔杮彂婭偲偄偆(偁傞堄枴偱愨懳揑側)巎椏偺婰弎傪慜偵偟偰丄壥偨偟偰汭彯拞偼偳偺傛偆側屆戙巎擣幆傪傕偭偰乽擔杮揑尨憸乿傪擔杮恖偵愢柧偟傛偆偲偡傞偺偱偁傠偆偐丅偁傞偄偼愇揷梇偼堦懱偳偺傛偆側乽擔杮揑尨憸乿傪傢傟傢傟偵梡堄偡傞偺偱偁傠偆偐丅
傕偟傕丄偦傟傪岆昑偱偁傝嫊憸偱偁傞偲偟偰丄壗傜偐暿偺屆戙擔杮偺尨憸傪昤偒忋偘傛偆偲偡傞側傜偽丄偦偺傾僾儘亅僠偼丄偨偲偊偽(嫗搒妛攈揑曽朄偺戙昞幰偱偁傞)攡尨栆偺乽傾僀僰=撽暥榑乿偺傛偆側億僗僩儌僟儞庡媊揑側怴僌儔儞僪僙僆儕亅偺峔抸偲側傞偙偲偩傠偆丅攡尨栆偺僽儗僀僋僗儖亅偼曽朄偲偟偰偒傢傔偰夋婜揑偱偁偭偨偲巹偼巚偆丅巹偼偦偺僽儗僀僋僗儖亅偵攺庤傪憲傝偨偄丅偟偐偟側偑傜丄偙傟偼偙傟偱丄乽屆戙崙柉崙壠乿揑楌巎憸偲偼慡偔暿偺宍偺丄帺慠庡媊揑丒儘儅儞庡媊揑側擔杮庡媊丄偡側傢偪怴偨側憰偄偺乽挻嬤戙揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺楌巎擣幆(=乽晛捠偺崙乿傪僀僨僆儘僊亅揑偵曎徹偡傞)偱偁偭偨偙偲偼娫堘偄側偄丅
梫偡傞偵丄偦偙偱栤傢傟偰偄傞偺偼乽擔杮恖偲偼壗偐乿側偺偱偁偭偰丄摎偊傞懁傕傑偨乽偙傟偑擔杮恖偺尨揰偩乿偲偄偆尨憸榑偺夝摎傪梡堄偟側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞丅擔杮恖帺恎偑擔杮恖帺恎偵懳偟偰乽偙傟偑擔杮恖偺尨憸偩乿偲偄偆夝摎傪梡堄偡傞偲偒丄偦偺楌巎憸偑壗傜偐乽崙柉揑側乿宊婡傪梌偊傜傟偢偵嵪傓偲偄偆偙偲偼偁傝摼側偄丅擔杮偺塃梼揑榑幰偨偪偐傜幤乆憚嬍偵偁偘傜傟傞娯崙抦幆恖偨偪偵傛傞乽擔杮恖偺尨憸乿榑偺孹岦傪尒傞側傜偽丄偦偺堄枴偲恀憡偑傛偔暘偐傠偆偲偄偆傕偺偱偁傞丅傢傟傢傟擔杮恖偵偲偭偰嬄揤偡傞傛偆側捒愢偑斵傜偵偲偭偰偼忢幆揑側楌巎揑帠幚側偺偱偁傞(偦傟偑娫堘偄偩偲尵偭偰偄傞偺偱偼側偄)丅
廬偭偰巹偼丄娵嶳恀抝偵傛傞亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁偺擔杮揑尨憸攃埇傪乽桬傒懌乿偲偼峫偊側偄丅傕偟愇揷梇偺尵偵廬偭偰丄娵嶳恀抝偺偦偺擔杮揑尨憸攃埇傪斲掕偟傛偆偲偡傞偺偱偁傟偽丄偦偺棟榑揑妀怱晹偱偁傞乽偮偓偮偓偵側傝備偔偄偒傎傂乿偺婎掙斖醗偺曽傕柍帠偱嵪傑偝傟傞偲偄偆偙偲偼側偄偩傠偆丅擔杮恖偺柉庡庡媊偵偲偭偰丄尰嵼傕丄彨棃傕偒傢傔偰廳梫側帺屓擣幆(偺嵿嶻)偱偁傞丄娵嶳恀抝偺亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁偺棟榑傪婋偆偔偟偐偹側偄愇揷梇偺媍榑偵丄巹偼惓捈側偲偙傠屗榝偄傪妎偊偞傞傪摼側偄偺偱偁傞丅
側偍丄偙偺乽擔杮揑尨憸乿偺栤戣偵偮偄偰峫偊傞忋偱丄嵟嬤偺嶌昳偱偼僒儞僩儕亅妛寍徿傪庴徿偟偨彫孎塸擇偺楯嶌亀扨堦柉懓恄榖偺婲尮亁(怴梛幮)偑嶲峫偵側傞丅撉彂偟偰旕忢偵柺敀偄丅傑偨擭戙揑偵偼屆偄帪戙偺嶌昳偱偁傞偑丄摿偵娵嶳恀抝偺乽屆憌乿偵懳偡傞偡偖傟偨栤戣堄幆偲偟偰庣杮弴堦榊偺亀擔杮巚憐巎偺壽戣偲曽朄亁(怴擔杮弌斉幮)傪嫇偘偰偍偒偨偄丅彫孎偼偙偺乽擔杮恖偺帺夋憸偺宯晥乿偺媍榑偵偍偄偰丄揤峜惂偺寣墢揑巟攝偺僀僨僆儘僊亅偵偮偄偰惓柺偐傜榑偠偰偄傞丅彫孎偑庣杮傪撉傫偩偙偲偑偁傞偺偐偳偆偐偼暘偐傜側偄偑丄庣杮埲棃丄偙偺乽揤峜惂偺寣墢揑巟攝偺僀僨僆儘僊亅乿偵怗傟傞媍榑傪丄巹偼媣偟傇傝偱栚偵偡傞偙偲偑偱偒偨丅
彫孎偺亀扨堦柉懓恄榖偺婲尮亁偵偍偗傞攡尨栆傊偺斸敾揑側娽嵎偟傕惓崝傪幩偨傕偺偲尵偊傞偱偁傠偆丅偦偺乽擔杮恖偺帺夋憸偺宯晥乿偺峫嶡偺帇妏傗曽朄偵懳偟偰慡柺揑側昡壙傪梌偊傞傕偺偱偼側偄偑丄堦嬨榋擇擭惗傑傟偲偄偆庒偝偲彮偟曄傢偭偨宱楌偵丄撉幰偲偟偰帺慠偵娭怱傪拲偑傟丄師夞嶌偑婜懸偝傟傞懚嵼偱偁傞丅巚憐巎偲偄偆妛栤偵僀僨僆儘僊亅暘愅偺帇妏傪帩偪崬傓偙偲偺偱偒傞丄崱擔悢彮側偄尋媶幰偺堦恖偲偟偰丅
|
仭4丄傾僕傾偵偍偗傞乽崙柉崙壠乿偺楌巎揑塣柦
嬤戙崙柉崙壠偲僫僔儑僫儕僘儉偺媍榑傪巒傔傞偲僉儕偑側偄偑丄嬤戙揑側崙柉崙壠偺棟榑偲偄偆傕偺偼丄傕偼傗悽奅巎偵姰慡偵偦偺楌巎揑巊柦傪廔偊偨傕偺偲尵偄愗傞偙偲偑偱偒傞偺偱偁傠偆偐丅傢傟傢傟擔杮恖偵偲偭偰偼丄抧媴巗柉側傝抧媴幮夛側傝偺棟擮傪擛壗偵偙偺抧忋偵幚尰偡傞偐偲偄偆偙偲偑擇廫堦悽婭偺壽戣偱偁傞偲尵偊傞偱偁傠偆丅偟偐偟丄偨偲偊偽偍椬偺娯崙偱偼丄崱傑偝偵傛偆傗偔丄偦偺挿偄挿偄柉懓偺楌巎忋弶傔偰偺嬤戙揑崙柉崙壠傪搊応(抋惗)偝偣傛偆偲偟偰偄傞偺偱偁傞丅娯崙柉偑嬤戙揑摑堦揑側崙柉崙壠傪帩偮偺偼偙傟偑弶傔偰偺宱尡偱偁傞丅
椬偺椬偺儌儞僑儖偼偳偆偐丅儌儞僑儖恖偑偄傢備傞嬤戙揑崙柉崙壠傪幚尰偝偣傛偆偲偡傟偽丄摉慠側偑傜丄拞崙丒撪栔屆帺帯嬫傪暪崌偟偰崙壠摑堦傪幚尰偟側偗傟偽側傜側偄偩傠偆丅椬偺椬偺椬偺僂傿僌儖恖丄椬偺椬偺椬偺椬偺僠儀僢僩恖丄斵傜偑嬤戙揑側崙柉崙壠傪帩偲偆偲偡傟偽丄拞壺恖柉嫟榓崙偐傜偺撈棫傪払惉偡傞埲奜偵側偄丅偦偟偰偦偙偵偼(堎幙側)戝検偺拞崙恖(娍恖)偑廧傫偱偄傞丅偳偆傗傜拞崙戝棨偺廃曈偱偼丄擇廫堦悽婭偵偍偄偰傕嬤戙揑偱摑堦揑側偄傢備傞崙柉崙壠(Nation State)宍惉偺栤戣偑夁嫀偺傕偺偲側偭偰偄傞傢偗偱偼側偄傛偆偱偁傞丅
偦傟偼拞崙戝棨撪晹偩偗偺榖偩傠偆偐丅杒偺戝棨晹偵偍偗傞拞壺僐儈儏僯僘儉掗崙偲傛偔帡偨僎僆億儕僥傿僢僔儏偺峔恾偑撿偺奀梞晹偵傕懚嵼偡傞丅擇壄偺恖岥偲擇枩偺搰涀傪書偊傞悽奅嵟戝偺奀梞掗崙丄僀儞僪僱僔傾僀僗儔儉掗崙偱偁傞丅僯儏亅僊僯傾搰惣敿晹僀儕傾儞僕儍儎偵偍偗傞暘棧撈棫塣摦偼埲慜偐傜抦傜傟偨偲偙傠偩偑丄尰嵼偺傢傟傢傟偵偼壗傕壜帇揑偵塮傜側偄僄僗僯僔僥傿(尵岅丒寣摑丒晽懎丒廗姷)偺嵎堎惈偺栤戣偼丄僗儔僂僃僔搰柉偲僕儍儚搰柉丄儃儖僱僆搰僇儕儅儞僞儞廧柉偲僕儍儚搰廧柉偺娫偵偼慡偔懚嵼偟側偄偲尵偊傞偺偩傠偆偐丅偦傟傜偺抧堟偵嬤戙揑帒杮庡媊揑側岺嬈惗嶻椡偑峀斖偵媦傫偱峴偭偨偲偒丄壥偨偟偰斵傜偼僀儞僪僱僔傾僀僗儔儉嫟榓崙柉偲偟偰堦偮偺懚嵼偺傑傑寢懇偟偰偄傜傟傞偺偩傠偆偐丅
尰嵼偺傢傟傢傟偺楌巎嫵壢彂偵偍偄偰丄儅僕儍僷僸僩墹崙偲偐僔儏儕償傿僕儍儎墹崙偲偄偭偨嬐偐側屌桳柤帉偺傒偱搑愗傟偰偄傞偦偺搶撿傾僕傾偺楌巎偼丄偍偦傜偔丄宱嵪敪揥偲嫟偵嵟怴偺楌巎壢妛偲峫屆妛偺惗嶻椡偵傛偭偰尰嵼偺悢攞丒悢廫攞偺 information 傪梌偊傜傟丄悽奅巎嫵壢彂偺儁亅僕悢偺惓摉側僔僃傾傪梫媮偡傞傛偆偵側傞偵堘偄側偄丅擇廫堦悽婭傕敿偽偵側傟偽丄僗儔僂僃僔搰柉偑僗儔僂僃僔恖偲偟偰偺嬤戙揑側帺屓擣幆傪帩偮擔偑傗偭偰棃傞偙偲偩傠偆丅崙柉崙壠偺宍懺傪揨偭偨掗崙偺拞偵怴偟偄崙柉崙壠偑惗傑傟偰備偔丅擇廫堦悽婭偵偍偗傞崙柉崙壠偺曎徹朄丅
擇廫堦悽婭敿偽偺傾僕傾傪傕偼傗傢傟傢傟偼尒傞偙偲偑偱偒側偄偑丄偦傟偑堦婥偵抧媴幮夛偺抧媴巗柉偺悽奅偲側偭偰偄傞偺偐丄偦傟偲傕怴偟偄僱亅僔儑儞僗僥亅僩偑悢懡偔惗傑傟偰尰嵼偺儓亅儘僢僷偺傛偆側巔偵側偭偰偄傞偺偐丄偦偺偳偪傜偐偑彨棃憸偲偟偰惓夝偱偁傞偲偡傞側傜偽丄巹偼屻幰偱偼側偄偐偲偄偆梊姶傪帩偮丅拞壺戝棨掗崙偺夝懱丄僀儞僪僱僔傾奀梞掗崙偺夝懱丄偝傜偵儘僔傾僔儀儕傾掗崙偡傜傕悑偵夝懱偟偰丄偦傟偧傟偺抧堟偵俙俽俤俙俶偺傛偆側俤倀宆偺崙柉崙壠楢崌懱偑宍惉偝傟傞彨棃恾偺梊姶偱偁傞丅
拞崙撪棨晹傗僀儞僪僱僔傾偺榖側偳墦偔偺榖偱儕傾儕僥傿傪姶偠側偄丄偲偄偆恖傕偄傞偐傕偟傟側偄丅椆夝丅偦傟偱偼傢傟傢傟偵偲偭偰嵟傕恎嬤側榖傪偟傛偆偱偼側偄偐丅壂撽偼偳偆偐丅壂撽偺擇廫堦悽婭偼嬤戙揑側崙柉崙壠偺奣擮傗棟榑偲壥偨偟偰柍墢偱偄傜傟傞偺偐丅壂撽偐傜暷孯婎抧傪揚嫀偡傞偨傔偵偼丄壂撽導柉偑壂撽崙柉偵側傞埲奜偵摴偼偁傞偺偩傠偆偐丅擔杮崙偐傜偺惌帯揑撈棫偺払惉埲奜偵丄擔暷埨曐忦栺偺偔傃偒偐傜帺屓傪夝曻偡傞庤抜偼偁傞偺偩傠偆偐丅壂撽偺恖乆偑朷傓壂撽偺旕晲憰拞棫偼丄壂撽恖偑壂撽偺庡尃幰偲偟偰帺屓傪妋棫偡傞偙偲偵傛偭偰偺傒弶傔偰幚尰偝傟傞偼偢偱偁傞丅偦偺偲偒壂撽偺恖乆偑崙嵺幮夛偵愰尵偟丄崙嵺幮夛偑彸擣偡傞偱偁傠偆惌帯揑撈棫偺偁傝曽偼乽嬤戙揑崙柉崙壠乿Nation State 偺宍懺埲奜偵偳偺傛偆側巔偑偁傞偺偱偁傠偆偐丅
僕儑儞儗僲儞偺尵偵廬偊丅僀儅僕僱亅僔儑儞偣傛丅
僫僔儑僫儖偼傕偆屆偄丄僄僗僯僔僥傿偲僕僃儞僟亅偺娽偱尒側偗傟偽怴偟偔側偄丄僂僅亅儔僗僥僀儞偑偙偆尵偭偰偄傞偐傜幮夛壢妛傕扙峔抸偩偲丄幮夛壢妛偵偍偗傞乽偮偓偮偓偲側傝備偔偄偒傎傂乿偵忔偭偰娵嶳恀抝偺乽嬤戙庡媊乿傪斸敾偡傞偺偼寢峔偱偁傞丅偗傟偳傕丄桪廏側惌帯妛幰偱偁傞汭彯拞偑杮摉偵崱傗傜側偗傟偽側傜側偄偙偲偼丄怴偟偔惗傑傟傛偆偲偡傞敿搰偺崙柉崙壠偑擇廫堦悽婭偺峳攇偵懴偊偰鐥偟偔惗偒敳偄偰峴偗傞傛偆偵丄嵞傃丄廬懏傗暘抐傗撪愴偺斶寑傪尒偸傛偆偵丄偦偺崙柉偲崙壠偵椙幙偱寬慡側 Political Theory 傪採嫙偡傞偙偲側偺偱偼側偄偺偩傠偆偐丅娯崙崙柉偼偦傟傪懸偭偰偄傞丅娯崙崙柉偵偼偦傟偑昁梫偱偁傞丅娯崙崙壠偲娯崙崙柉偺偨傔偺乽娵嶳惌帯妛乿傗乽戝捤巎妛乿偑崱媮傔傜傟偰偄傞偼偢偱偁傞丅
傢傟傢傟偼乽儃亅僟亅儗僗丒僄僐僲儈亅乿偲偐乽僌儘亅僶儖丒僗僞儞僟亅僪乿側偳偲偄偆乽壓晹峔憿乿偺尵梩偺棳峴偵娙扨偵忔偭偰丄懄帺揑丒柍帺妎揑偵乽抧媴幮夛乿傗乽抧媴巗柉乿偺昞徾偵僘儖僢偲妸傝崬傫偱偟傑偄偑偪偱偁傞丅偟偐偟丄偦偺慜偵傕偆堦搙扥擮偵悽奅抧恾傪挱傔捈偟丄堦偮堦偮偺崙乆傗抧堟偺楌巎偲尰幚傪儕傾儖偵僀儅僕僱亅僔儑儞偟偰傒傞傋偒偱偼側偄偺偩傠偆偐丅乽偮偓偮偓偵側傝備偔偄偒傎傂乿偺幮夛壢妛偑娙扨偵扙峔抸張棟偟偰偟傑偆傎偳丄崙柉崙壠偲偄偆尵梩偺帩偮堄枴偼寉偔偼側偄偺偱偁傞丅巗柉幮夛偲摨偠傛偆偵丅丂
丂 |
| 仭揤峜偲乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿 |
   丂
丂
|
偄傑撉傓偲妘悽偺姶偑偁傞偑丄1999擭偺榑暥偱搉曈帯偼乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偵傛傞懳峈塣摦偵偮偄偰丄師偺傛偆偵偦偺栤戣傪巜揈偟偰偄偨丅
仭
乽偙偙偱堦偮偩偗嫮挷偟偰偍偒偨偄偺偼丄巟攝憌偺偙偆偟偨僀僨僆儘僊乕偵懳偟巹偨偪偼丄偐偮偰娵嶳恀抝傜偑峫偊偨傛偆側崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉偱懳峈偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偱偼側偄偐丄偲偄偆揰偱偁傞丅
擔偺娵丒孨偑戙偺朄惂壔偑晜忋偟偨偲偒丄偦傟偵斀懳偡傞榑嫆偺堦偮偲偟偰丄擔偺娵傕孨偑戙傕丄寛偟偰偁偺僼儔儞僗嶰怓婙傗傾儊儕僇偺惎忦婙偺傛偆偵妚柦傗柉庡庡媊揑摙榑偺拞偐傜惗傑傟偨傕偺偱偼側偄偲偄偆揰偑丄彮側偔側偄榑幰偵傛偭偰偁偘傜傟偨丅擔偺娵丒孨偑戙惂掕偺宱堒偵偮偄偰偼丄偦偺捠傝偱偼偁傞丅偟偐偟丄巹偼丄偙偺斀榑偼寛掕揑庛揰傪桳偟偰偄傞偲巚偆丅偦傟偼丄偙偺媍榑偼丄崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉傕掗崙庡媊傪惗傫偩偲偄偆栤戣偵摎偊傜傟側偄偐傜偱偁傞丅抂揑偵偄偊偽丄偙偺媍榑偼丄擔偺娵丒孨偑戙偺栤戣惈傪嬤戙偺晄懌乵尨暥擇帤朤揰乶偵媮傔傞丅偟偐偟丄擔偺娵丒孨偑戙偑帩偮栤戣偺杮幙偼丄偦偆偱偼側偄丅嬤戙偺婣寢乵尨暥擇帤朤揰乶偲偟偰偺掗崙庡媊偺栤戣側偺偱偁傞丅乵拞棯乶
尵偄偨偄偙偲偼丄傕偪傠傫帺桼庡媊巎娤偺傛偆偵擔杮掗崙庡媊偺怤棯愴憟傪憡懳壔偡傞偨傔偱偼側偄丅偦偆偱偼側偔偰丄巹偨偪偑丄尰戙偵偍偄偰擔偺娵丒孨偑戙偺朄惂壔傪栤戣偵偡傞偺偼丄偁偺擔偺娵丒孨偑戙偵崬傔傜傟偨擔杮掗崙庡媊偺怤棯峴摦偑丄尰戙偺戝崙壔偺拞偱丄傛傝僜僼傿僗僥傿働僀僩偝傟偨宍偱偱偁傟嵞尰偝傟傛偆偲偟偰偄傞偐傜偱偁傝丄偦偺揰偱偼丄擔偺娵丒孨偑戙偑柉庡揑偵彸擣偝傟偰偙側偐偭偨偲偄偆栤戣偼丄尰戙偺擔偺娵丒孨偑戙栤戣偺徟揰偱偼側偄偺偱偁傞丅
偡偱偵偔傝曉偟嫮挷偟偨傛偆偵丄擇堦悽婭偺擔杮偑愴憟峴摦偵嶲壛偡傞応崌偱傕丄偦傟偼寛偟偰擔偺娵偲惎忦婙偑愴偆愴憟偱偼側偔丄擔偺娵偲惎忦婙偑暲傫偱乵尨暥嶰帤朤揰乶丄乽巗応柉庡庡媊乿傗乽恖摴傪庣傞乿偨傔偵峴傢傟傞愴憟偑傎偲傫偳偱偁傠偆丅乿丅
仭
偮傑傝丄尰忬偺栤戣揰傪嬤戙偺晄懌(亖乽崙柉庡媊乿揑妚柦偺枹払惉)偵傛傞傕偺偲懆偊傞乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺懳峈塣摦偱偼丄擔偺娵偑尰戙掗崙庡媊偺傕偲偱壥偨偡栶妱傪廩暘偵斸敾偱偒側偄丄偲偄偆庡挘偱偁傞丅擔偺娵丒孨偑戙偑崙柉偵墴偟晅偗傜傟傞丄偲偄偆懁柺偱偼側偔丄傓偟傠擔杮偺怤棯峴摦偺側偐偱擔偺娵丒孨偑戙偑偳偺傛偆側栶妱傪壥偨偟偰偒偨偺偐丄偦偟偰丄偄傑怴偨側怤棯峴摦偵偍偄偰偄偐側傞栶妱傪壥偨偦偆偲偟偰偄傞偺偐傪偮偐傑偊丄寕偮偺偱側偗傟偽丄巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偵懳峈偱偒側偄丅偙傟偑99擭偺搉曈偺庡挘偱偁偭偨丅
拞惣怴懢榊偼丄搉曈偺巜揈傪偆偗偰丄尰戙偺巟攝揑僀僨僆儘僊乕偵懳峈偡傞偵偼乽僐儘僯傾儕僘儉偵偨偄偡傞揙掙偟偨巚憐揑丒幚慔揑斸敾傪杮幙揑偵旛偊偨崙壠憸丄崙壠峔憐偺挙戶偑昁梫偱偁傠偆丅乵拞棯乶椻愴懱惂曵夡屻偺悽奅拋彉偵徠傜偣偽孯帠椡憹嫮側偳晄梫偲偄偭偨椶偺尰幚擣幆傗儘僕僢僋偵棅偭偰偄偰偼丄僌儘乕僶儖帒杮庡媊帪戙偺偄傢偽乽彑偪慻僫僔儑僫儕僘儉乿偵偼偲偆偰偄懢搧懪偪偱偒側偄乿偲巜揈偟偰偄傞丅
偄偢傟傕嬌傔偰廳梫側巜揈偱偁傝丄10擭埲忋傪宱偰偝傜側傞塃孹壔偑恑傫偩崱擔偙偦丄偙偆偟偨帇揰偼峀偔嫟桳偝傟傞傋偒偩偲巚偆丅傓偟傠丄偙偺10擭娫偺塃孹壔偼拞惣偺偄偆乽僐儘僯傾儕僘儉偵偨偄偡傞揙掙偟偨巚憐揑丒幚慔揑斸敾傪杮幙揑偵旛偊偨崙壠憸丄崙壠峔憐偺挙戶乿傪夞旔偟丄偙偺揰傪濨枂偵偟偨偐偨偪偱懳峈惃椡偑曐庣攈傗塃攈偺庢傝崬傒(幚嵺偵偼庢傝崬傑傟偨偺偩偑)偵憱偭偨寢壥偱偁偭偨丅榓揷傗戝徖丄杙桾壨傜偺乽崙柉婎嬥乿攈偑丄夁搙側擔杮斸敾偙偦偑擔杮傪塃孹壔偝偣偨偲偺愑擟揮壟偺尵愢傪孞傝曉偡偺偼丄嵞傃乽榓夝乿偺僾儘僕僃僋僩傪悇恑偡傞偨傔偺愰揱偱偁傞偲摨帪偵丄偙偆偟偨帺傜偺乽幐攕乿傪屭傒側偄偨傔偺曽曋偱偼側偄偐偲傕巚偆丅
偨偩丄崱偺搉曈偑偙偆偟偨擔杮掗崙庡媊斸敾傪岅傞偙偲偼傎偲傫偳側偄丅傓偟傠乽夵寷偵棫偪岦偐偆偨傔偺曐庣偲偺嫟摨丄抧堟偵崻嵎偟偨塣摦丄懳埬傪帵偟偨崙柉揑嫟摨偺峔抸偱昁巰偵婃挘傝敳偔偙偲傪慽偊乿偰偄傞(亀愒婙亁2014擭3寧30擔晅 )丅偙偆偟偨愴棯偼丄巹偵偼搉曈帺恎偑斸敾偟偨乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偵傛傞懳峈塣摦偦偺傕偺(偁傞偄偼偝傜偵曐庣揑側傕偺)偲偟偐巚偊側偄丅塃孹壔偺恑揥偵傛傝丄乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偱傕巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偵懳峈偱偒傞丄偁傞偄偼丄塃孹壔偑恑揥偟偨偄傑偼乽崙柉乿傪揋偵夞偡夁搙側擔杮掗崙庡媊斸敾偼嬛暔偱偁傞丄偲峫偊傞傛偆偵側偭偨偺偐傕偟傟側偄偑丄偙偺揰偱偼慜弎偺乽崙柉婎嬥乿攈偺恖傃偲偲摨條偺尰忬擣幆偵傑偱屻戅偟偰偍傝丄擔杮掗崙庡媊斸敾傪寚偄偨乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺斸敾幰偐傜丄悇恑幰傊偲揮姺偟偨偲偄傢偞傞傪偊側偄丅
偲偙傠偱丄偙偆偟偨擔杮掗崙庡媊斸敾傪寚偄偨乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偲娭傢偭偰拲栚偡傋偒栤戣偲偟偰丄揤峜偺埵抲偯偗偑偁傞丅慜弎偺榑暥偱丄搉曈偼尰戙擔杮偺巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偵偮偄偰師偺傛偆偵巜揈偟偰偄偨丅
仭
乽巟攝憌偑尰戙偺戝崙壔傪惓摉壔偡傞偵偼丄僀儞僞乕僫僔儑僫儕僘儉偲丄揱摑揑僫僔儑僫儕僘儉傪崙柉庡媊揑偵嵞曇惉偟偨僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉傪暪梡偡傞埲奜偵側偄偙偲偼娫堘偄側偄偲偄偆偙偲傪丄偁傜偨傔偰嫮挷偟偰偍偒偨偄丅偦傟傪揤峜偺庢傝埖偄偲偄偆揰偱偄偆側傜偽丄巟攝憌偺墴偟弌偡揤峜憸偼丄柧帯寷朄揑丒尃埿揑揤峜偐傜丄乽徾挜乿揑揤峜憸傊偺揮姺偲偄偆偙偲偵側傞丅偦偟偰丄崙柉摑崌偺棟擮偲偟偰偼丄柉庡庡媊揑棟擮偑墴偟弌偝傟丄揤峜偼偙偆偟偨柉庡揑側擔杮崙壠偺徾挜偲偟偰寲揱偝傟傞偵堘偄側偄丅寷朄夵惓偵傛傞帺塹戉偺奀奜弌摦懺惃偺惓摉壔傕丄僀僨僆儘僊乕偲偟偰偼丄乽崙嵺峷專乿偲丄乽悽奅偺暯榓拋彉宍惉傊偺愑擟乿丄偲偄偆媍榑偱峴傢傟傞偵堘偄側偄丅
憤偠偰丄怴偨側孯帠戝崙壔偼丄寛偟偰僇乕僉怓偺孯暈偲柉庡庡媊偺攋夡丄揤峜惂偵傛傞崙柉偺摑惂偲偄偆偍偳傠偍偳傠偟偄奿岲偱偼搊応偟側偄偙偲偩偗偼娞偵柫偢傋偒偱偁傞偲偄偆偺偑丄偙偙偱嵟傕嫮挷偟偨偄揰偱偁傞丅乿
仭
戞擇師埨攞惌尃傪抦傞棫応偐傜傒傞偲丄乽怴偨側孯帠戝崙壔偼丄寛偟偰僇乕僉怓偺孯暈偲柉庡庡媊偺攋夡丄揤峜惂偵傛傞崙柉偺摑惂偲偄偆偍偳傠偍偳傠偟偄奿岲偱偼搊応偟側偄乿偲偄偆巜揈偼偄偝偝偐妝娤揑偵偡偓傞傛偆偵傕巚偊傞偑丄傂偲傑偢偦傟偼慬偙偆丅廳梫側偺偼丄慜弎偟偨傛偆偵丄偙偙偱巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偲偟偰憐掕偝傟偰偄傞乽揱摑揑僫僔儑僫儕僘儉傪崙柉庡媊揑偵嵞曇惉偟偨僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉乿偑丄偄傑偱偼掗崙庡媊斸敾傪寚偄偨懳峈塣摦偵傛偭偰宖偘傜傟丄巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕傪曗姰偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅
偲傝傢偗揤峜偑廳梫側梫慺偲偟偰搊応偟偰偄傞偙偲偵拲栚偟偨偄丅偙偙偱搉曈偑巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偺廳梫側梫慺偲傒側偡乽柉庡揑側擔杮崙壠偺徾挜乿偲偟偰偺揤峜憸偼丄巟攝憌偵偲偳傑傜偢丄懳峈塣摦偵偍偄偰傕憡摉側塭嬁椡傪桳偡傞偲偄偊傞丅傓偟傠丄揤峜偙偦偑暯榓庡媊幰偱偁傞丄偲偄偭偨尵愢偼丄埨攞惌尃斸敾偺榑朄偲偟偰乽岇寷攈乿偺側偐偱偼偐側傝偺塭嬁椡傪帩偭偰偄傞丅嶐擭偺乽庡尃夞暅偺擔乿偺惌晎幃揟偵偍偗傞乽揤峜暶壓枩嵨乿偺彞榓偵偮偄偰丄幚偼揤峜帺恎偑堦斣寵偑偭偰偄傞丄偲偄偆榑朄偱偺乽斸敾乿傪傛偔尒偐偗偨(捈愙暦偄偨偙偲傕偁傞)偑丄偙傟傕摨庬偺傕偺偱偁傠偆丅傕偪傠傫丄揤峜偑尰峴寷朄傪弲庣偡傞偺偼摉偨傝慜偺偙偲偱偁傞偟(傕偪傠傫夵惓屻偺寷朄傕庣傞偩傠偆)丄傓偟傠揤峜偺壗傜偐偺乽堄巚乿偑寷朄夵惓榑媍偵壗傜偐偺塭嬁傪梌偊傞偙偲偺曽偑傛偭傐偳嫲傠偟偄偲峫偊偰偟偐傞傋偒偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄孨庡偺恖奿偵埶嫆偡傞乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺塣摦側偳搢嶖埲奜偺壗幰偱傕側偄丅
懠曽丄偙偆偟偨揤峜偲乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺枿寧偵娭楢偟偰婥偵側傞偺偑丄乽愴憟愑擟傪帺妎偡傞擔杮崙壠偺徾挜亖揤峜乿憸偺棳晍偱偁傞丅搉曈帯偼慜弎偺亀擔杮偺戝崙壔偲僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉偺宍惉亁偺側偐偱丄擔杮偺孯帠戝崙壔偵偼乽愴屻柉庡庡媊乿偲乽傾僕傾彅崙柉偺寈夲乿偲偄偆擇偮偺忈奞暔偑偁傝丄慜幰偼90擭戙偵憡摉庛懱壔偟偨偑丄屻幰偼擔杮掗崙庡媊偺夁嫀(乽戞堦偺怤棯乿)傊偺斸敾偵壛偊丄尰嵼偺擔杮婇嬈偺傾僕傾恑弌(乽戞擇偺怤棯乿)傊偺斀敪傕偁偭偰傓偟傠嫮傑偭偨偺偱丄偙傟傪娚榓偟偰孯帠戝崙壔偲崙楢埨曐棟忢擟棟帠崙擖傝傪擣傔偝偣傞偨傔偵壨栰択榖偑弌偨丄偲巜揈偟偰偄偨丅2000擭戙傪捠偟偰乽傾僕傾彅崙柉偺寈夲乿傊偺寈夲傕丄乽巟攝憌乿偺傒側傜偢懳峈塣摦偵傑偱奼偑偭偨偲峫偊傜傟傞偑丄嬤擭偺摦岦傪傒傞偲丄傓偟傠偙偪傜偺曽偑傛傝怺崗側栤戣傪娷傫偱偄傞偺偱偼側偄偐偲巚偊傞丅
偲傝傢偗徾挜揑偩偭偨偺偼2012擭偺棝柧攷尦戝摑椞偺揤峜幱嵾敪尵傊偺斀墳偱偁傞丅棝柧攷偑2012擭8寧丄揤峜偺朘娯偺忦審偲偟偰撈棫塣摦壠傊偺幱嵾傪媮傔傞敪尵傪偟偨偙偲偵懳偟丄亀挬擔亁傗亀撉攧亁偼乽擔娯娭學傪傂偳偔彎偮偗傞乿丄乽楃傪幐偟偰偄傞乿偲斸敾丄廜媍堾偼乽嬌傔偰旕楃側敪尵乿偲偡傞旕擄寛媍傪嵦戰偟偨偑丄偄偢傟傕揤峜偺怉柉抧巟攝愑擟偲偄偆娞怱側榑揰偵偮偄偰偼慡偔尵媦偣偢丄乽晄宧偱偁傞乿偲偱傕偄傢傫偽偐傝偺栤摎柍梡偺斀敪偵廔巒偟偨丅
傢偢偐偵嫟嶻搣偑乽旕楃乿榑偲偼堎側傞斸敾傪揥奐偟偨偑丄偦傟傕乽(偄傑偺)揤峜偲偄偆偺偼寷朄忋丄惌帯揑尃擻傪傕偭偰偄側偄丅偦偺揤峜偵怉柉抧巟攝偺幱嵾傪媮傔傞偲偄偆偙偲帺懱偑偦傕偦傕偍偐偟偄丅擔杮偺惌帯惂搙傪棟夝偟偰偄側偄偲偄偆偙偲偵側傞丅擔杮惌晎偵懳偟偰丄怉柉抧巟攝偺惔嶼傪媮傔傞側傜傢偐傞偗偳丄揤峜偵偦傟傪媮傔傞偺偼偦傕偦傕僗僕偑堘偆乿偲偄偆寷朄夝庍偐傜偺愢柧偱(亀愒婙亁2012擭9寧11擔晅 )丄寢榑偲偟偰偼摨偠偔棝柧攷敪尵斸敾偱偁偭偨丅
傕偪傠傫丄捈屻偵濨枂偵偝傟偨偙偲偐傜傕傢偐傞傛偆偵丄棝柧攷偺敪尵偑偳偙傑偱杮婥偩偭偨偐偼夦偟偄傕偺偱偁傞偑丄彮側偔偲傕偦偙偱栤戣偲偝傟偰偄偨偺偼丄挬慛撈棫塣摦偺抏埑傊偺揤峜偺愑擟丄偲偄偆怉柉抧巟攝偵娭傢傞廳梫側栤戣偱偁偭偨丅擔杮崙寷朄偵偍偗傞揤峜偺抧埵傗尃擻側偳偼丄偁偔傑偱擔杮懁偺帠忣偱偁偭偰丄彮側偔偲傕挬慛傗拞崙偐傜傒傟偽丄偦傫側偙偲偼嵄嵶側栤戣偵偡偓偢丄尰偵乽揤峜乿偲偟偰偦偺抧埵偑懚懕偟偰偄傞埲忋丄偐偮偰偺乽揤峜乿偺愑擟傪宲彸偟偰偄傞偲峫偊傞偺偑摉慠偩傠偆丅偟偐偟丄摉帪偙偺榑揰偵摜傒崬傫偩尵媦偼傎偲傫偳側偝傟側偐偭偨丅
偨偩丄椺奜揑側尵媦偲偟偰丄崙嵺惌帯妛幰偺嶁杮媊榓偵傛傞師偺傛偆側棝柧攷敪尵斸敾偑偁偭偨丅
仭
乽棝戝摑椞偑丄揤峜偺嬶懱揑側幱嵾峴堊傑偱媮傔傞敪尵傪偟偨偺偼丄柧傜偐偵幐尵偱偁傞丅擔杮偺愴憟愑擟傪擔杮偺堦斒偺惌帯壠傗崙柉埲忋偵捝姶偟偰偄傞揰偱丄巹傕宧垽傪惿偟傑側偄尰揤峜偵偮偄偰丄偁傑傝偵柍抦偱偁傝丄抪偢傋偒偱偁傞丅乿
仭
晛捠偵峫偊傟偽丄愴憟愑擟傪扤傛傝傕捝姶偟偰偄傞側傜偽幱傟偽傛偄偼偢偩偑丄嶁杮偺榑朄偩偲丄愑擟傪捝姶偟偰偄傞揤峜偵幱嵾傪媮傔傞偺偼乽柍抦偱偁傝丄抪偢傋偒偱偁傞乿偲偄偆偙偲偵側傞丅亀挬擔亁傜偑怉柉抧巟攝愑擟偺栤戣傪旔偗傞偐偨偪偱乽旕楃乿偲斀敪偟偨偺偲偼堎側傝丄嶁杮偼丄偙傫側偵愴憟愑擟傪帺妎偟偰偄傞揤峜偵撈棫塣摦壠傊偺幱嵾傪媮傔傞側偳抪抦傜偢偩丄偲暜偭偨偺偱偁傞丅嬃偔傋偒乽儕儀儔儕僗僩乿偱偁傞丅
壗傛傝栤戣側偺偼丄乽愴憟愑擟傪帺妎偡傞擔杮崙壠偺徾挜乿憸偑丄傾僕傾偐傜偺愴憟愑擟捛媦傪梷埑偡傞偨傔偵屇傃弌偝傟偰偄傞偙偲偱偁傞丅偙偆偟偨揤峜憸偼丄乽岇寷攈乿偺懡偔偑嫟桳偡傞愴屻崙壠憸(亖帺夋憸)偵揔崌偡傞傕偺偱偁傠偆丅忋偵傒偨傛偆偵丄傎偲傫偳偼揤峜偺怉柉抧巟攝愑擟傪榑偠傞偙偲帺懱傪旔偗偨偑丄幚嵺偵偼偙偆偟偨揤峜偵娭偡傞嶁杮偺傛偆側乽姶妎乿偼丄乽儕儀儔儕僗僩乿偺側偐偱偼憡摉掱搙嫟桳偝傟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偙偆偟偨揤峜憸偑丄慜弎偺乽柉庡揑側擔杮崙壠偺徾挜乿偲偟偰偺揤峜憸偲愗傝寢傃丄斸敾偺僀僨僆儘僊乕偲偟偰婡擻偡傞偲偒丄搉曈偺偄偆偲偙傠偺乽僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉乿偼撪偵偼彅惃椡傪摑崌偟丄奜偵偼乽傾僕傾彅崙柉偺寈夲乿偵旛偊傞巟攝揑側僀僨僆儘僊乕偲偟偰乽姰惉乿偡傞丅傗偼傝擔杮僫僔儑僫儕僘儉偼揤峜敳偒偵偼偁傝偊側偄丅
乽3.11乿埲屻丄擔杮崙撪偵偍偄偰偼偙偺僀僨僆儘僊乕偺乽姰惉乿偵嬤偯偒偮偮偁傞傛偆偵巚偆偑丄懠曽偱偙偆偟偨揤峜憸偺墴偟晅偗傪丄偦偆傗偡傗偡偲傾僕傾偺恖傃偲偑庴偗梕傟傞傢偗偼側偄丅偩偑丄傕偟偦傟偑側偝傟傞偲偡傟偽丄偍偦傜偔嵟傕愗傝曵偟堈偄嵼擔挬慛恖傗娯崙偑偹傜傢傟傞偼偢偱偁傞丅偦偆偟偨堄枴偱偼丄嵼擔挬慛恖傪娷傓挬慛柉懓偺嬤尰戙巎偵娭傢傞彅庬偺楌巎廋惓庡媊傊偺斸敾(亖擔杮掗崙庡媊斸敾)偼丄堷偒懕偒嬞媫惈傪桳偟偰偄傞偲摨帪偵丄尰嵼偺乽僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉乿斸敾偵偲偭偰傕嬌傔偰廳梫側埵抲傪愯傔偰偄傞偲偄偊傞偩傠偆丅丂
丂 |
| 仭柧帯僫僔儑僫儕僘儉乽崙柉庡媊乿 / 棨 愎撿(偔偑 偐偮側傫) |
   丂
丂
|
仭(堦)彉暥
棨愎撿(杮柤丒幚)偼丄柧帯擇廫擭戙偐傜嶰廫擭戙偵偐偗偰丄怴暦亀搶嫗揹曬亁媦傃亀擔杮亁偵幮挿丄庡昅偲偟偰幮愢傪彂偒懕偗偨丄惌榑婰幰丄僕儍乕僫儕僗僩偱偁傞丅愎撿偺彞偊偨乽崙柉庡媊乿偼丄撪偵崙柉揑摑堦傪丄奜偵崙壠偺撈棫傪媮傔丄椉幰偺敪揥傪偼偐傞偙偲傪栚巜偡傕偺偱偁偭偨丅愎撿偼崙柉慡懱偺楌巎丄宱嵪丄晽懎傪捠偟偰丄摴摽惈傪嫮挷偟側偑傜丄尩偟偄惌帯斸敾傪丄幮愢偲偟偰怴暦偵敪昞偟懕偗偨丅懄偪丄崙柉偐傜嫍棧傪妘偰偨乽巚憐壠乿偲偟偰偺愎撿偱偼側偄丄崙柉偲枾愙偵娭傢傝偁偭偨乽僕儍乕僫儕僗僩乿偲偟偰偺愎撿偑丄偦偙偵偼懚嵼偡傞偺偱偁傞丅杮榑偼偙偆尵偭偨娤揰偐傜丄愎撿偺柧帯僫僔儑僫儕僘儉乽崙柉庡媊乿偲偼擛壗側傞傕偺偱偁偭偨偐丄椫妔慄傪柧妋偵偟丄枖尒捈偡偙偲偱丄尰戙擔杮偺偁傝曽傪峫嶡偡傞傕偺偱偁傞丅
|
仭(擇)偙傟傑偱偺棨愎撿尋媶偲崻嫆帒椏
愎撿偼丄嶨帍亀擔杮恖亁傪庡嵜偟偨惌嫵幮儊儞僶乕偺巙夑廳濄(堦敧榋嶰乗堦嬨擇幍)丄嶰戭愥椾(堦敧榋仜乗堦嬨巐屲)傜偲暲傃丄柧帯拞婜僫僔儑僫儕僘儉傪戙昞偡傞懚嵼偲偟偰丄昡壙偝傟偰偒偨丅惌帯妛揑暘愅丒惌帯巚憐巎揑傾僾儘乕僠偵傛傞愎撿偺乽孯帠奜岎榑乿尋媶偼丄偙傟傑偱傕庡偵娵嶳恀抝丄怉庤捠桳偺椉巵傪昅摢偵婔恖偐偺尋媶幰偵傛偭偰峴傢傟偰偄傞丅巚憐壠丄僫僔儑僫儕僗僩偲偟偰偺愎撿偑戝偒偔昡壙偝傟偰偒偨強埲偱偁傞丅偦偺偨傔愎撿偺棟榑(揘妛)尋媶偼恑傫偩偑丄偦偺斀柺丄愎撿娭學偺榑暥偼丄拪徾揑偱擄夝側報徾傪梌偊傞孹岦偑偁傞偲傕丄尵傢傟偰偄傞丅
棨愎撿娭學偺帒椏偲偟偰偼丄傒偡偢彂朳偐傜惍棟偝傟偨亀棨愎撿慡廤亁(慡廫姫)偑姧峴偝傟偰偄傞丅慡廤偵偼丄亀擔杮亁偺慜恎偱偁傞怴暦亀搶嫗揹曬亁偲丄亀擔杮亁偺幮愢偑拞怱偵廂傔傜傟偰偄傞丅
亀搶嫗揹曬亁偼丄愎撿傪庡昅寭幮挿偲偟偰柧帯擇廫堦擭(堦敧敧敧)巐寧嬨擔憂姧偝傟偨怴暦偱偁傞丅梻擇廫擇擭擇寧嬨擔偵偼攑姧偝傟丄懕偄偰亀擔杮亁偑慜巻傪夵慻偟偨宍偱丄摨擭擇寧廫堦擔(戝擔杮掗崙寷朄岞晍偲摨帪)偵丄憂姧偝傟偨丅亀擔杮亁偼丄埲屻戝惓廫嶰(堦嬨堦屲)擭傑偱懕偄偰敪峴偝傟偨偑丄偙偺娫愎撿偼丄柧帯嶰嬨(堦嬨仜榋)擭榋寧偵丄昦婥偺偨傔丄埳摗嬙椇偵摨巻傪忳傝搉偡傑偱丄栺廫幍擭娫偵傢偨偭偰丄庡昅寭丄幮挿偲偟偰幮愢偺戝晹暘傪幏昅偟懕偗偰偄傞丅
彯丄亀擔杮亁幮愢偺拞偵偼丄懠幰偺彁柤偑婰偝傟偰偄傞傕偺傕崿擖偟偰偍傝丄(椺偊偽丄婰幰丒暉杮擔撿偲巚傢傟傞乽暯憼乿偺彁柤偺偁傞傕偺摍)偦傟傜偼柧傜偐偵丄愎撿偺挊嶌偱偼側偄丄偲敾柧偟偰偄傞丅偦偺懠偵柍婰柤偺幮愢偑偁傝丄偦傟傜傕愎撿埲奜偺恖暔偺挊嶌偱偁傞壜擻惈偑戝偒偄偑丄偦偺応崌偼彮側偔偲傕愎撿偑栚傪捠偟丄亀擔杮亁傊偺宖嵹傪擣傔偨傕偺丄偲敾抐偟丄昁梫偑偁傟偽嶲徠偡傞偙偲偲偟偨丅
|
仭(嶰)愎撿偺柧帯僫僔儑僫儕僘儉乽崙柉庡媊乿
愎撿偺彞偊偨乽崙柉庡媊乿偵偮偄偰丄偦偺掕媊偲夝庍偵偮偄偰偼丄婛偵偄偔偮偐偺尋媶偑側偝傟偰偄傞偑丄戝嬝偵偍偄偰亀擔杮亁憂姧偺帿偵偁傞傛偆偵乽堦扷朣幐偣傞崙柉惛恄傪夞暅偟丄妿偮擵傪搊梡偣傫偙偲傪乿栚揑偲偟偨傕偺偱偁傝丄乽崙柉偺撪偵丄尃棙媦傃岾暉偺曃孹側偐傜偟傔傞乿傛偆側崙柉揑惌帯傪朷傓傕偺偱偁偭偨偲偄偆偙偲偑悇嶡偝傟傞丅愎撿偼乽撪偵墬偰偼崙偺摑堦傪丄奜偵懳偟偰偼崙柉偺摿棫傪媮傔傞乿巚憐傪丄偙偙偵帺傜乽崙柉庡媊乿偲柤晅偗偨偺偱偁傞丅
嬶懱椺傪嫇偘傛偆丅
柧帯擇榋丄幍擭偺乽忦栺椼峴栤戣乿偲擇敧丄嬨擭偺乽愑擟栤戣乿榑憟偵偍偄偰傕丄偙偺婎杮巔惃偼娧偐傟偰偄偨丅椺偊偽丄忦栺夵惓埬偺栤戣偵娭偟偰丄愎撿偼丄乽忦栺椼峴榑乿傪巟帩偟偨偑丄偙傟偼忳曕偺懡偄晄姰慡側夵惓偱偼擔杮偺撈棫傪彅奜崙偵彸擣偝偣偨偙偲偵偼側傜側偄丅偲丄敾抐偟偨堊偱偁傞丅擔杮偺崙尃傪彅奜崙偵擣幆偝偣丄彯妿偮忦栺夵惓傪幚尰偡傞堊偵偼丄奜恖偑帺敪揑偵夵惓傪朷傓傛偆偵偟傓偗傞偙偲偑摼嶔偱偁傝丄尰峴忦栺傪嵼擔奜恖偵椼峴偝偣傞偙偲偵傛偭偰丄偙傟偑壜擻偵側傞偲峫偊偨偺偱偁傞丅
乽愑擟栤戣榑憟乿偵偮偄偰傕摨條偱丄乽奜偵懳偟偰崙柉偺摿棫(撈棫)傪媮傔傞乿乽崙柉庡媊乿傪撈棫崙壠偺棫応傪庣傝偒傟偢椛搶敿搰傪妱忳偟偰偟傑偭偨惌晎偵懳偟偰偦偺愑擟傪捛媦偡傞丄偲偄偆宍偱幚峴偟偰偄偨丅
偙偺傛偆偵愎撿偺榑愢傪捛偆宍偱妋擣偟偰傒傞偲丄擛壗偵乽崙柉庡媊乿偲尵傢傟傞傕偺偑丄偄傢備傞愴屻偵尵偆乽僂儖僩儔僫僔儑僫儕僘儉(挻崙壠庡媊)乿偲偐偗棧傟偨傕偺偱偁偭偨偐偑丄傢偐傞偩傠偆丅愎撿偺尵偆乽崙柉揑惌帯乿偺堊偺摑堦偲偼丄乽杴偦杮棃偵墬偄偰崙柉慡懱偵懏偡傋偒幰偼昁偢擵傪崙柉揑偵偡傞偺堗乿傪堄枴偟偨傕偺偱偁偭偰丄揤峜偼栜榑丄斔敶偵傛傞忋偐傜偺崙柉摑堦偲偄偆巚憐偲偼丄媡偺棫応偵埵抲偡傞傕偺偱偁偭偨丅愎撿偺乽崙柉庡媊乿偼乽柧帯偺僫僔儑僫儕僘儉乿傪戙昞偡傞懚嵼偺傂偲偮偱偼偁偭偨偑丄寛偟偰擔業愴憟埲崀偺摿偵徍榓弶婜偵偍偗傞孯崙庡媊丄崙壠庡媊側偳偲屇徧偝傟傞掗崙庡媊揑側怤棯傪峬掕偡傞巚憐偱偼側偐偭偨丅愎撿偺尵偆崙柉偲偼丄乽孨庡偲恖柉偲憡嫟摨偣傞惃椡丄懄偪崙柉惃椡(僫僔儑僫儖僼僅儖僗)乿傪巜偟偰偍傝丄揤峜偲崙柉偑堦抳嫤椡偡傞宍懺傪棟憐偲偟偰偄偨偺偱偁傞丅乽摑堦崙柉偼丄擻偔婱懓傪梕傟丄枖嫠柉傪梕傟丄崙壠偺栎昅偲屄恖偺怢挿偲傪愜拸偡傟偽側傝乿偲偄偆愎撿偺尵梩偼丄斵偺峫偊偰偄偨僫僔儑僫儕僘儉偺寬慡惈傪帵嵈偟偰偄傞丅
懄偪愎撿偼丄崙柉偲崙壠偺娭學傪怢弅帺嵼偱尰幚偵懃偟偨懳墳偺偱偒傞傕偺偱偁傞傋偒偲峫偊丄椉幰偺乽暲楍乿傪峫偊偰偄偨偺偱偁傞丅椺偊偽丄乽暥柧偺惌摴偼昁偢傑偢奺恖擻椡偺敪払傪杁傝丄偦偺敪払偵傛傝偰埲偰丄崙壠埿椡偺怢挘傪杁傞偵偁傝乿乽暥柧偺栚揑偼晉椡偺憹恑偵偁傜偢偟偰丄摽媊恖忣偺孾敪偵偁傞偙偲乿乽暥柧惌帯偺杮巪偼丄扨偵崙壠偺埿尩嫮屌傪挘傞偺傒偵偁傜偢偟偰丄枖丄幮夛奺恖偺岾暉埨擩傪曐岇偡傞偵偁傞偙偲乿偲偄偭偨敪尵偺拞偵傕丄愎撿偺乽屄恖乿偵懳偡傞峫偊曽偼塎偊傞丅
埲忋偺傛偆偵愎撿偺榑偵偼丄忢偵乽崙壠偲屄恖乿乽帺桼偲暯摍乿摍丄擇偮偺帠暱偵偍偗傞僶儔儞僗姶妎偑懚嵼偡傞丄偲偄偆摿怓偑偁偭偨丅偦偟偰偙偺僶儔儞僗姶妎偙偦偑丄愎撿傪帺崙帄忋庡媊偱偼側偔丄崙柉揑屄惈偺曐懚偲敪払偺擇柺惈傪暪桳偟偨乽崙柉庡媊乿幰偨傜偟傔偨偺偱偁傞丅傗傗棟憐庡媊偺怓崌偄偼偁傞傕偺偺丄崙柉揑屄惈偺妋棫偲摨帪偵丄偝傜偵敪揥偝偣偰丄悽奅揑側嫟懚傪媮傔偨偺偑斵偺乽崙柉庡媊乿偱偁偭偨偲尵偊傛偆丅
|
仭(巐)棨愎撿偲偼壗幰偱偁偭偨偺偐
乽愎撿偼僫僔儑僫儕僗僩偱偁傞乿偲偼扨弮偵妱傝愗傟偸傛偆偵丄乽愎撿偼巚憐壠偱偁傞乿偲偼抐尵偟擄偄丅斵偼偄偔偮偐偺杮傕弌斉偟偰偄傞偑丄偦傟偼怴暦幮愢傪壗夞暘偐傑偲傔偨憤廤曇偱偁傞応崌偑懡偔丄枖丄斵偺巇帠偺傎偲傫偳偼丄怴暦嶌傝偵偁偭偨丅摨帪戙恖偲偟偰愎撿傪尒偨帪丄傗偼傝乽棨愎撿偼怴暦恖偱偁傞乿偲偄偆昞尰偑嵟傕揑傪摼偰偄傞偲巚傢傟傞丅斵帺恎傕傑偨丄怴暦婰幰偱偁傞偙偲偵戝偄偵椙偄堄枴偱偺僾儔僀僪傪帩偭偰丄巇帠傪偙側偟偰偄偨丅椺偊偽丄斵偼憂姧偵偍偄偰丄亀擔杮亁傪媞娤揑側棫応偐傜丄摉帪偺怴暦奅偺忬嫷偺拞丄埲壓偺傛偆偵埵抲偯偗偰偄傞丅
乽怴暦巻偨傞傕偺偼惌尃傪憟偆偺婡娭偵偁傜偞傟偽丄懄偪巹棙傪幩傞偺彜昳偨傝丅婜娫傪埲偭偰帺傜擟偢傞偺偼丄搣媊偵曃偡傞偺鎺傝傪柶傟擄偔丄彜昳傪埲偭偰帺傜嫃傞傕偺偼丄埥偄偼棳懎傪捛偆偺殅傪彽偔丅崱偺悽偵摉偨傝怴暦巻偨傞傕偺偺埵抲枓偨崲擄側傜偢傗丅(拞棯)変偑乽擔杮乿偼屌傛傝尰崱偺惌搣偵娭學偁傞偵偁傜偢丅慠傟偳傕枓偨彜昳傪埲偭偰帺傜娒偢傞傕偺偵傕偁傜偢丅乿
偙偺乽擔杮乿憂姧偺帿偺棟擮偼戞堦復偺榑憟丄懄偪丄擔惔愴憟埲慜偺嵟戝偺栤戣丄忦栺夵惓榑憟偵偍偄偰傕丄枖愴屻偺嶰崙姳徛偵傛傞椛搶敿搰娨晅栤戣偵偍偄偰傕娧偐傟偨丅偙偆尵偭偨乽擔杮乿撈帺偺怴暦棟擮丒曇廤曽恓偺堦娧惈偼丄椺偊偽摨帪婜偺乽崙柉怴暦乿偑丄擔惔愴憟慜屻偵揮岦偟偨偙偲偲懳斾偝偣傞偲丄傛傝堦憌昡壙偱偒傞傕偺偱偁傞丅
偟偐偟丄怴暦奅偺棳傟偑丄惌榑僕儍乕僫儕僘儉帪戙傪棧傟丄惓妋丄恦懍側曬摴傪拞怱偲偟偨彜嬈僕儍乕僫儕僘儉帪戙傊偲堏偭偰備偔偲丄乽擔杮乿偺傛偆側偠偭偔傝偲幮榑傪庡挘偟偰備偔僞僀僾偺怴暦偼丄偦偺僥儞億偵偮偄偰備偗偢丄庢傝巆偝傟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅摉帪偺晽挭傪扱偒丄埲壓偺傛偆側婰弎偑巆偭偰偄傞丅
乽愄偺怴暦偼婰幰偺抦宐丄幆尒丄揤嵥傪攧偭偨傕偺偱偁偭偨偑丄崱偼墿嬥偺椡偱憿偭偨峀崘丄慀摦丄挧敪丄桿榝偱攧傞傛偆偵側偭偨丅(拞棯)怴暦婰幰偼揤壓傪巜摫偡傞婰幰愭惗偵旕偢偟偰嬥偱攦傢傟偨梑恖偵側傝壓偑偭偨丅怴暦傪撉傓傕偺傕丄怴暦傪憿傞傕偺傕婰幰偼桞偩曬抦傪廤傔偰曬抦傪彂偔婡夿偵夁偓側偄偲巚偭偰偄傞乿
條乆側娐嫬偺曄壔偵傛偭偰怴暦乽擔杮乿偼悐偊偨偑丄旂擏側偙偲偵愎撿偑乽怴暦婰幰榑乿偱彞偊偰偄偨乽晄曃晄搣乿偺惛恄偩偗偼怴暦奅偵庴偗宲偑傟偰偄偭偨丅偁傞堄枴偱偼丄尰戙偵偍偗傞怴暦偺偁傝曽偺尨揰偲傕尵偆傋偒慺抧偑丄乽擔杮乿偵偼懚嵼偟偰偄偨偺偱偁傞丅尰戙偺怴暦偵梌偊偨塭嬁傪峫偊傞偲偒丄怴暦婰幰丄惌榑婰幰偲偟偰偺愎撿偼丄傕偭偲昡壙偝傟傞傋偒恖暔偱偁傞偲偄偆偙偲偑弌棃傛偆丅
乽棨愎撿偼巚憐壠偱偁傞乿偲偄偆擣幆偑偁傞丅偙傟偼丄斵偑乽僫僔儑僫儕僗僩偱偁傞乿偲偄偆擣幆偐傜攈惗偟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅偩偑丄愎撿偺挊弎偟偰偒偨傕偺傪丄庡偵怴暦乽擔杮乿偺榑愢傪捛偆丄偲偄偆宍偱尒傞帪丄幚偼偙偺擇偮偺擣幆偑丄偳偪傜傕幚偵濨枂偱丄岆夝偺懡偄傕偺偱偁傞偙偲偑敾傞丅偦偺柺偱偼棨愎撿偼丄徍榓弶婜偺挻崙壠庡媊(僂儖僩儔僫僔儑僫儕僘儉)偺偁偍傝傪庴偗偰丄愴屻偵惓摉側昡壙傪庴偗傜傟側偔側偭偰偟傑偭偨恖暔偺堦恖丄偲偄偆偙偲偑弌棃傞丅(幚嵺丄棨愎撿偼挻崙壠庡媊傪斸敾偡傞棫応傪偲偭偰偄偨)偲摨帪偵丄巆偝傟偨悢懡偔偺乽擔杮乿幮愢傪撉傓偲丄愎撿偵乽巚憐壠乿偲偄偆傂偲偮偺儗僢僥儖傪揬偭偰偟傑偆偙偲偑丄旕忢偵婋尟側峴堊偱偁傞丄偲偄偆偙偲偑傛偔傢偐傞丅
愎撿偼乽怴暦婰幰乿偺懠偵傕乽宱嵪昡榑壠乿乽嫵堢榑幰乿乽楌巎壠乿偲偟偰懡條側壜擻惈傪旈傔偨恖暔偱偁偭偨丅嫵堢偵偮偄偰偼丄憗偔偐傜暥晹徣偵傛傞崙掕嫵壢彂斀懳偺榑傪彞偊丄傑偨彈巕嫵堢偵娭偟偰傕婔偮偐偺挊弎偑巆偝傟偰偄傞丅壛偊偰丄愎撿偺暥妛揑尒幆偵偮偄偰傕丄燍愇偺乽僷儕捠怣乿傪乽擔杮乿偵嵹偣丄惓壀巕婯偺偨傔偵戞堦柺傪妱偄偨偙偲傪峫偊崌傢偣傟偽丄柍帇偡傞偙偲偼弌棃側偄丅愎撿偺恖暱偼枖丄摨帪戙恖偵垽偝傟偰偄偨丅乽擔杮乿傪巟帩偟丄愎撿傪宧垽偡傞撉幰偺夛乽擔杮惵擭夛乿(巚憐抍懱偱偼側偄)偺懚嵼傗丄乽棨愎撿慡廤廫姫乿偵廂傔傜傟偨愎撿傪傔偖傞恖乆偺挊弎偑偦傟傪嫮偔暔岅偭偰偄傞丅婰幰埲奜偺棨愎撿憸偵偮偄偰傕丄偦偺壜擻惈傪捛偆偙偲偼堄媊偑偁傞偩傠偆丅
|
仭(屲)廔傝偵
乽傕偟偙偺帪戙偵棨愎撿偔偑偐偮側傫偺怴暦亀擔杮亁偑偁傟偽乧乿
戞擇師悽奅戝愴婜丄怴暦曬摴偑孯晹偵孅偟偰偟傑偄丄崙柉偵恀幚傪曬偠摼側偐偭偨偙偲傪扱偄偰丄亀怴暦偺楌巎亁偺拞偵偼偙傫側尵梩偑婰偝傟偰偄傞丅尰戙擔杮偺曬摴丒儅僗僐儈偺偁傝曽偵偍偄偰丄惌帯尃椡偲偺嫍棧偺抲偒曽傪峫偊傞帪丄柧帯婜僕儍乕僫儕僗僩丒棨愎撿偔偑偐偮側傫偺曇廤曽恓傗婎杮巔惃偵妛傇偲偙傠偼戝偒偄丅
崿柪偺尰戙偵偍偄偰丄擔杮屆棃偐傜偺暥壔偺偁傝曽丄峴偔枛傪巚偆帪丄寛偟偰崙壠尃椡偲寢傃偮偔偙偲偺側偐偭偨丄愎撿偺弮悎側乽崙柉庡媊乿偵偮偄偰偦偺堄枴偲廳梫惈傪峫偊捈偝偢偵偼偄傜傟側偄丅撪偵崙柉揑摑堦傪丄奜偵崙壠偺撈棫傪媮傔傞乽崙柉庡媊乿揑巔惃偼丄尰戙偵傕捠偠偰丄昡壙偝傟傞傋偒偩傠偆丅丂
丂 |
| 仭嬤戙偺壒妝 |
   丂
丂
|
仭19悽婭屻敿偐傜20悽婭傊
18悽婭枛偺僼儔儞僗妚柦偵傛偭偰惗傟偨帺桼偲暯摍偺惛恄偼丄奺崙偺巗柉奒媺偺拞偵怺偔怹摟偟丄僂傿乕儞懱惂偵懳偡傞斵傜偺掞峈偵偼崻嫮偄傕偺偑偁傝傑偟偨丅妚柦偺恔尮抧偱偁傞僼儔儞僗偱偼傕偪傠傫丄偦偺傎偐偺彅崙偵偍偄偰傕丄惌帯揑側曄摦傗幮夛懱惂偺曄壔偑憡師偄偱婲偙傝丄儓乕儘僢僷偩偗偱側偔丄悽奅慡懱偑偦傟偵傛偭偰梙傝摦偐偝傟傞傛偆偵側偭偰偄偒傑偡丅偦偺寖曄偡傞幮夛忣惃偼丄偦偺傑傑悽婭偺屻敿偵傑偱傕偪偙偝傟丄傗偑偰丄20悽婭慜敿偵偍偗傞2搙偺戝愴傪彽偔偵帄傝傑偡丅
僼儔儞僗偱偼1848擭偺戞2嫟榓惌帪戙偺偁偲丄僫億儗僆儞3悽偵傛傞掗惌帪戙偲桳柤側僷儕丒僐儈儏乕儞傪宱偰丄1875擭偵偼戞3嫟榓崙寷朄偑抋惗偟丄崱擔偺婎慴傪抸偒傑偡丅僪僀僣偼僾儘僀僙儞傪拞怱惃椡偲偟偰丄1871擭偵僪僀僣掗崙傪柤偺傞偙偲偵側傝丄僀僞儕傾偱偼1859-60擭偵傢偨傞摑堦愴憟偐傜僀僞儕傾墹崙偺抋惗傪尒傞偙偲偵側傝傑偡丅
奀傪妘偰偨僀僊儕僗偼償傿僋僩儕傾彈墹(嵼埵1837-1901)偺帪戙偱偁傝丄悽奅偵峀偑偭偨宱嵪寳傪懌応偵丄悽奅掗崙偲偟偰偺埿梕傪惍偊偮偮偁傝傑偟偨丅儘僔傾傕婛偵戝崙偲偟偰愭恑彅崙偲尐傪暲傋傞偵帄偭偨傕偺偺丄1861擭偺擾搝夝曻丄81擭偺傾儗僋僒儞僪儖2悽偺埫嶦帠審偲丄惌帯揑偵偼懡擄側摴傪曕傫偱丄傗偑偰儘僔傾妚柦傊偲偮側偑偭偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅傑偨丄僗僇儞僨傿僫償傿傾3崙傗僶儖僇儞敿搰偺彅崙丄儃僿儈傾傗億乕儔儞僪側偳偱偼丄撈棫塣摦偑惙傫偵峴傢傟偰偄傑偟偨丅堦曽丄奀偺岦偙偆偺傾儊儕僇偱偼1861-65擭偺撿杒愴憟偑丄63擭偺搝楆夝曻愰尵傪嫴傫偱峴傢傟丄65擭偵偼崌廜崙偲偟偰偺摑堦偑惉棫偟傑偡丅
偙偆偟偨儓乕儘僢僷幮夛偺摦偒偼丄寢壥揑偵丄偦偺屻偺楍嫮偺掗崙庡媊揑側摦偒傪彆挿偡傞偙偲偵側傝傑偡偑丄堦曽偱偼丄帺桼庡媊揑側峫偊偐偨偵婎偯偄偨巗柉奒媺傪拞怱偲偡傞柉懓塣摦傕崅傑偭偰偄偒傑偡丅偦傟偑崙柉庡媊偱偡丅偙偺帪婜丄偦偆偟偨孹岦偑壒妝偵傕偆偐偑傢傟傞偲偙傠偐傜丄偙偺帪戙偺壒妝傪崙柉庡媊壒妝偲傛傫偱偄傑偡偑丄媄朄揑偵偼儘儅儞庡媊壒妝偺墑挿忋偵偁傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅
|
仭崙柉庡媊偺嶌嬋壠偨偪
儘僔傾偺崙柉庡媊壒妝傪嵟弶偵憂憿偟偨偺偼丄壧寑乻僀償傽儞丒僗僒乕僯儞乼傗乻儖僗儔儞偲儕儏僪儈乕儔乼側偳偱抦傜傟傞僌儕儞僇(M. I. Glinka, 1804-57)偱偡丅斵偵懕偄偨偺偑僟儖僑儉僀僔僗僉乕(A. S. Dargomizhsky, 1813-69)偱丄偦偺偁偲偵儘僔傾屲恖慻偺恖偨偪偑尰傟偰偒傑偡丅
崙柉庡媊揑側偄偒偐偨傪嵟傕柧妋偵昞偟偨偺偑儘僔傾偺屲恖慻偵傛傞壒妝偱偟偨丅屲恖慻偵偼僶儔僉儗僼(M. A. Balakirev丄1837-1910)丄僉儏僀(C.A. Cui, 1835-1918)丄儃儘僨傿儞(A. P. Borodin, 1833-87)丄儕儉僗僉乕=僐儖僒僐僼(N. A. Rimsky-Korsakov, 1844-1908)丄儉僜儖僌僗僉乕(M. P. Mussorgsky, 1839-81)偑偄傑偡偑丄偙偺偆偪丄惓婯偺壒妝嫵堢傪庴偗偨偺偼僶儔僉儗僼偩偗偱偟偨丅傎偐偺恖偨偪偼崱傆偆偵偄偊偽丄庯枴偱壒妝偵嫽偠傞僨傿儗僢僞儞僩偵夁偓傑偣傫偱偟偨丅偦傟偩偗偵丄揱摑偵偁傑傝偲傜傢傟傞偙偲側偔丄尯恖偔偝偔側偄僼儗僢僔儏側壒妝傪惗傒弌偣偨偺偩偲偄偊傞偱偟傚偆丅
偙偺屲恖慻偺拞偱偼丄慻嬋乻僔僃僄儔僓乕僪乼偱抦傜傟傞儕儉僗僉乕=僐儖僒僐僼偑嵟傕嶌嬋棟榑偵桪傟丄乻娗尫妝朄乼傗乻榓惡妛乼偺挊彂傕堚偟偰偄傑偡丅傑偨丄儉僜儖僌僗僉乕偼戙昞嶌偲偟偰壧寑乻儃儕僗丒僑僪僲僼乼傗乻揥棗夛偺奊乼側偳傪彂偒丄偦偺揱摑偵懇敍偝傟側偄怴慛側壒妝偼丄屻偺壒妝壠偵偄傠偄傠側堄枴偱塭嬁傪梌偊偰偄偒傑偡丅
偟偐偟丄偦偺帪婜偺儘僔傾偱丄堦曽偱偼惣墷儘儅儞庡媊偵婎偯偔嶌昳傪彂偄偰偄偨嶌嬋壠傕偄傑偡丅傾儞僩儞(A. Rubinstein, 1829-94)偲僯僐儔僀(1835-81)偺儖價儞僔僥僀儞孼掜傗僠儍僀僐僼僗僉乕(P. I. Tchaikovsky, 1840-93)偑偦偺戙昞奿偱丄摿偵僠儍僀僐僼僗僉乕偼3戝僶儗僄嬋傪偼偠傔偲偡傞懡偔偺嶌昳傪彂偄偰丄媄朄揑偵偼惣墷揑儘儅儞僥傿僔僘儉偺榞傪庣傝側偑傜傕丄僗儔償揑側柉懓怓傪惙傝崬傫偱丄撈摿偺嶌晽傪妋棫偡傞偵帄傝傑偡丅
摨偠崰丄儃僿儈傾偵偼僗儊僞僫(B. Smetana, 1824-84)傗僪償僅儖僓乕僋(Dvořák, 1841-1904)側偳偑搊応偟傑偡丅偲傕偵丄儃僿儈傾偺柉懓怓傪嫮偔斀塮偟偨嶌昳偱抦傜傟丄慜幰偼壧寑乻攧傜傟偨壴壟乼傗岎嬁帊乻傢偑慶崙乼丄屻幰偼岎嬁嬋乻怴悽奅偐傜乼偦偺傎偐偺嶌昳偑桳柤偱偡丅儃僿儈傾偱偼斵傜偵懕偄偰丄儎僫乕僠僃僋(L. Janáček, 1854-1928)傗僗乕僋(J. Suk, 1874-1935)丄偝傜偵儚僀儞儀儖僈乕(J. Weinberger, 1896-1967)傗旝暘壒偱桳柤側僴乕僶(A. Hába, 1893-1973)側偳偑尰傟丄尰戙僠僃僐壒妝偺揱摑傪抸偒忋偘偰偄偒傑偡丅
僗僇儞僨傿僫償傿傾彅崙偱偼丄僲儖僂僃乕偵僌儕乕僌(E. H. Grieg, 1843-1907)丄僼傿儞儔儞僪偵僔儀儕僂僗(J. Sibelius, 1865-1957)偑尰傟丄偦傟偧傟偺柉懓怓傪惙傝崬傫偩柤嶌傪堚偟偰偄傑偡丅僌儕乕僌偼丄桳柤側乻僺傾僲嫤憈嬋僀抁挷乼丄晅悘壒妝乻儁乕儖丒僊儏儞僩乼傗懡偔偺僺傾僲嬋偱抦傜傟偰偍傝丄僔儀儕僂僗偼乻僼傿儔儞僨傿傾乼傪偼偠傔偲偡傞懡偔偺婍妝嬋偑桳柤偱偡丅
|
仭偦偺屻偺僪僀僣丄僆乕僗僩儕傾偲僼儔儞僗
崙柉庡媊壒妝偼19悽婭屻敿偵丄崙壠揑偵傕壒妝揑偵傕傗傗棫偪抶傟偰偄偨彅崙偵偍偄偰丄摿偵尠挊側棽惙傪尒偣傑偟偨偑丄廬棃偐傜偺壒妝崙偵偁偭偰傕丄懡偐傟彮側偐傟丄崙柉揑側壒妝傪彂偔偲偄偆峫偊偑惗傟偰偒傑偡丅
僪僀僣丄僆乕僗僩儕傾偱偼丄儚乕僌僫乕偺巰屻丄僽儖僢僋僫乕(J. A. Bruckner, 1824-96)丄償僅儖僼(H. P. J. Wolf, 1860-1903)丄儅乕儔乕(G. Mahler, 1860-1911)側偳偑偦偺棳傟偺忋偵妶桇偟丄堦曽丄僽儔乕儉僗宯偺嶌嬋壠偲偟偰偼丄儗乕僈乕(M. Reger, 1873-1916)傪偁偘傞偙偲偑偱偒傑偡丅
僽儖僢僋僫乕偼9偮偺岎嬁嬋傪拞怱揑側嶌昳偲偟偰堚偟傑偟偨偑丄偄偢傟偵傕丄儚乕僌僫乕怓偑嫮偔斀塮偝傟偰偍傝丄偳偺岎嬁嬋傕1帪娫偁傑傝傪梫偡傞戝嬋偲側偭偰偄傑偡丅償僅儖僼偼壧嬋嶌嬋壠偲偟偰丄僪僀僣丒儕乕僩偺摴傪傗傗堘偭偨妏搙偐傜楙傝捈偟丄撈摿偺悽奅傪揥奐偟傑偟偨丅儅乕儔乕傕岎嬁嬋偺嶌嬋壠偲偟偰妶摦偟傑偟偨偑丄壧嬋偱傕乻朣偒巕傪偟偺傇壧乼傗乻偝偡傜偆庒恖偺壧乼乻巕偳傕偺晄巚媍側妏揓乼側偳傪彂偄偰偄傑偡丅傑偨丄巜婗幰偲偟偰偺妶摦偵傕戝偒側懌壒傪堚偟傑偟偨丅傑偨丄儗乕僈乕偼僽儔乕儉僗偵孹搢偟丄屆揟宍幃傪懜廳偟偨嶌昳傪嶌傝弌偟傑偟偨丅
偙偺帪婜偵偼丄傎偐偵傕丄償傽僀僆儕儞嫤憈嬋偱抦傜傟傞僽儖僢僼(M. Bruch, 1838-1920)丄壧寑乻僿儞僛儖偲僌儗乕僥儖乼偱恊偟傑傟偰偄傞僼儞僷乕僨傿儞僋(E. Humperdinck, 1854-1921)丄僺傾僯僗僩偲偟偰妶摦偟偨儌僔儏僐僼僗僉乕(M. Moszkowski, 1854-1925)丄偦傟偵僾僼傿僢僣僫乕(H. Pfitzner, 1869-1921)側偳偑妶桇偟丄偦偺棳傟偺拞偵儕僸儍儖僩丒僔儏僩儔僂僗(R. Strauss, 1864-1949)偑搊応偟偰偒傑偡丅僔儏僩儔僂僗偺屻敿惗偼20悽婭偺慜敿偲廳側傝傑偡偑丄嶌晽偼偁偔傑偱傕儚乕僌僫乕傆偆偺棳媀偵偟偨偑偭偨嶌嬋壠偱偟偨丅偟偐偟丄尰戙壒妝揑側懡挷惈傗柍挷惈偺媄朄傕庢傝擖傟偨丄懡偔偺岎嬁帊傗妝寑丄壧嬋側偳傪堚偟偰偍傝丄尰戙僪僀僣壒妝偺婎慴傪抸偄偨岟愌偼偗偭偟偰彫偝偔偁傝傑偣傫丅
僼儔儞僗偱偼丄19悽婭慜敿偺漅忣壧寑慡惙帪戙偺偁偲傪庴偗偰丄屻敿帪戙偵側傞偲丄僼儔儞僋(C. Frank, 1822-90)偲丄偦偺棳傟傪偔傓僟儞僨傿(V. d'Indy, 1851-1931)丄僨儏僷儖僋(H. Duparc, 1848-1933)丄僔儑乕僜儞(E. Chausson, 1855-99)側偳丄偁傞偄偼丄偦偺僌儖乕僾偲偼懳徠揑側懚嵼偱偁偭偨僒儞=僒乕儞僗(C. Saint-Saëns, 1835-1921)丄僼僅乕儗(G. Fauré, 1845-1924)丄僔儍僽儕僄(A. E. Chabrier, 1841-94)側偳偑搊応偟偰偒傑偡丅斵傜偼壧寑柺偽偐傝偱側偔丄婍妝偺暘栰偱傕懡嵤側嶌昳傪彂偄偰丄嬤戙僼儔儞僗壒妝偺婎慴傪抸偒忋偘傑偟偨丅
僼儔儞僋偼儀儖僊乕弌恎偱偡偑丄僷儕壒妝堾偵妛傃丄偦偺惗奤偺傎偲傫偳傪嫵夛僆儖僈僯僗僩偲偟偰夁偛偟傑偟偨丅嶌昳揑偵偼壡嶌偱偁傝丄峔惉揑偵偼寴屌側偑傜丄傗傗抧枴側嶌晽傪傒偣偰偄傑偡丅乻僼儔儞僗嶳恖偺壧偵傛傞岎嬁嬋乼偱抦傜傟傞僟儞僨傿偼僼儔儞僋偺掜巕偱丄棟榑柺偱偺巇帠偵傕廳梫側嬈愌傪堚偟偰偄傑偡丅傑偨丄僨儏僷儖僋偼乻椃傊偺偄偞側偄乼偲偄偆壧嬋偵傛偭偰傛偔抦傜傟偰偄傑偡偑丄屻敿惗偼惛恄揑幘姵偺偨傔偵塀撡惗妶傪憲傝傑偟偨丅僔儑乕僜儞偼乻帊嬋乼偑傛偔抦傜傟偰偄傑偡丅
僒儞=僒乕儞僗偼丄偦偺挿偄惗奤傪惛椡揑偵妶摦偟偨恖偱丄傢偐傝傛偝偲傛偄堄枴偱偺崙嵺惈傪恎忋偲偡傞嶌嬋壠偱偟偨丅斵偺栧壓偱偁傞僼僅乕儗偵傕丄巘偲摨偠孹岦偑擣傔傜傟丄壧嬋傗幒撪妝嬋丄僺傾僲嬋側偳偵柤嶌傪堚偟偰偄傑偡丅偦偺僼僅乕儗偲摨帪戙偺僔儍僽儕僄偼丄嶌昳偺悢偼彮側偄傕偺偺丄嫸帊嬋乻僗儁僀儞乼偑桳柤偱偡丅
偙偆偟偨僼儔儞僗偺嶌嬋壠偨偪偼丄偦偺嶌晽偵偍偄偰偼偦傟偧傟堘偭偨摴傪曕偄偨偲偼偄偊丄崙柉揑側壒妝傪嶌傞偲偄偆揰偱偼摨偠峫偊傪傕偭偰偄傑偟偨丅斵傜偑廤傑偭偰丄1871擭偵偼崙柉壒妝嫤夛偑嶌傜傟丄偁傞堄枴偱崙柉庡媊揑偲傕偄偊傞塣摦傪偼偠傔傑偡丅偙偆偟偨妶摦偑婎慴偵側偭偰丄20悽婭偵偍偗傞僼儔儞僗壒妝偺棽惙偑摫偐傟偰偄偭偨偺偱偡丅
|
仭偦偺懠偺崙偱偼
僗儁僀儞偵偼丄慻嬋乻僀儀儕傾乼偱抦傜傟傞傾儖儀僯僗(I. Albéniz, 1860-1909)傗丄乻僑僀僄僗僇僗乼偑桳柤側僌儔僫僪僗(E. Granados, 1867-1916)偑搊応偟傑偡丅偄偢傟傕丄僗儁僀儞偺柉懓揑側怓嵤傪僼儔儞僗壒妝偐傜偺塭嬁偱偁傞報徾庡媊揑側媄朄偱曪傓嶌晽偑摿挜偱丄偦偺昞尰偵偍偄偰偼嬤戙揑偱偁傞傕偺偺丄撪梕揑偵偼崙柉庡媊揑偱偁傞偲偄偊傑偡丅偙偺2恖傛傝1悽戙偖傜偄偁偲偺僼傽儕儍(M. de. Falla, 1876-1946)偼丄僶儗僄壒妝乻楒偺杺弍巘乼傗乻嶰妏朮巕乼偑傛偔抦傜傟偰偍傝丄懡暘偵柉懓揑側怓嵤傪尒偣側偑傜傕丄偒傢傔偰嬤戙揑側嶌晽偑摿怓偱偡丅
僶儖僇儞敿搰偺彅崙偵傕崙柉庡媊揑側壒妝壠偨偪偑尰傟傑偟偨丅儖乕儅僯傾偱償傽僀僆儕僯僗僩偲偟偰妶桇偟偨僄僱僗僐(G. Enesco, 1881-1955)偼乻儖乕儅僯傾嫸帊嬋乼偑抦傜傟偰偄傑偡丅僴儞僈儕乕偵偼僪儂僫乕僯(E. v Dohnányi, 1877-1960)偑弌偰丄嬤戙僴儞僈儕乕壒妝偺婎慴傪抸偒丄偦偺摨擭戙偵僶儖僩乕僋(B. Bartók, 1881-1945)傗僐僟乕僀(Z. Kodály, 1882-1967)傕弌偰丄20悽婭偺壒妝偵戝偒偔峷專偡傞偙偲偵側傝傑偡丅僗僀僗偵偼丄儔僼(J.J. Raff, 1822-82)傗儅儖僞儞(F. Martin, 1890-1974)丄億乕儔儞僪偵偼丄償傽僀僆儕僯僗僩偲偟偰妶摦偟丄償傽僀僆儕儞嫤憈嬋偱恊偟傑傟偰偄傞償傿僄僯儍僼僗僉(H. Wieniawski, 1835-80)傗戝摑椞偵側偭偨偙偲偱桳柤側僺傾僯僗僩偺僷僨儗僼僗僉(I. J. Paderewski, 1860-1941)側偳偑搊応偟傑偡丅傑偨丄僀僊儕僗偱偼僄儖僈乕(E. Elger, 1857-1934)偑妶桇偟傑偟偨丅 怴偟偄崙壠偲偟偰偺傾儊儕僇偱傕丄19悽婭屻敿偵偼偄偭偰丄僴乕僶乕僩(V. Herbert, 1859-1924)傗儅僋僟僂僃儖(E. A. McDowell, 1861-1908)側偳偑搊応偟偰偒傑偡丅 丂 |
| 丂 |
   丂
丂
|
|
丂 |
| 仭柉懓庡媊丂[ethnicism] |
   丂
丂
|
仭 柉懓偺懚嵼丒撈棫傗棙塿傑偨桪墇惈傪丄妋曐傑偨偼憹恑偟傛偆偲偡傞巚憐偍傛傃塣摦丅偦偺嬌抂側宍偼崙壠庡媊偲傛偽傟傞丅僫僔儑僫儕僘儉丅懛暥偑彞偊偨嶰柉庡媊偺堦丅
仭 柉懓偺摑堦丒撈棫丒敪揥傪栚巜偡巚憐丅柉懓堄幆傪傕偲偵丄柉懓傪廳帇偟偰峴摦傗庡挘傪峴偍偆偲偡傞丅堦嬨悽婭僪僀僣丒僀僞儕傾偺柉懓崙壠摑堦塣摦丄戞堦師戝愴屻偺柉懓帺寛庡媊丄戞擇師戝愴屻偺斀掗崙庡媊撈棫塣摦側偳偵尰傟傞丅懛暥偺彞偊偨嶰柉庡媊偺堦丅
仭 乧嬤戙偵偍偗傞崙壠庡媊偺僕儗儞儅偼丆偙偆偟偨棟擮傗壙抣偵柍墢側奣擮傪摜傑偊偰丆側偍偐偮偦偺帄崅惈傪慽偊側偗傟偽側傜側偄揰偵偁偭偨丅丂偙偺崲擄傪曗偆揰偱廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偺偑柉懓庡媊偱偁傝丆柉懓崙壠丆崙柉崙壠偑楌巎偺棳傟偲側傞側偐偱崙壠庡媊偼柉懓庡媊偲偺梈崌傪偲偘丆偦偺棟擮傪曗姰偡傞偙偲偵側偭偨丅幚嵺丆擔杮偱偼廬棃丆崙壠偲柉懓偲偺廳側傝偑傎傏帺柧帇偝傟偰偒偨偙偲傕偁偭偰丆崙壠庡媊丆柉懓庡媊丆崙柉庡媊丆崙悎庡媊偲偄偭偨尵梩偼傎偲傫偳摨媊偵梡偄傜傟偰偄傞丅乧
仭 乧偐偮偰偼丆柉懓庡媊丆崙柉庡媊丆崙壠庡媊側偳偲栿偟暘偗傜傟傞偙偲偑懡偐偭偨偑丆嵟嬤偱偼堦斒偵僫僔儑僫儕僘儉偲昞婰偝傟傞丅偙偺偙偲偼丆僫僔儑僫儕僘儉偲偄偆尵梩偺懡媊惈傪斀塮偟丆偦偟偰偦偺懡媊惈偼丆偦傟偧傟偺僱乕僔儑儞nation傗丆偦偺僫僔儑僫儕僘儉偺扴偄庤偑偍偐傟偰偄傞楌巎揑埵抲偺懡條惈傪斀塮偟偰偄傞丅乧
仭 嶰柉庡媊 / 1905擭丄懛暥偑採彞偟偨拞崙妚柦偺婎杮棟擮丅拞崙崙柉搣偺惌峧偲側傝丄妚柦塣摦偺敪揥偲偲傕偵丄偦偺撪梕偼怺壔偟丄懛暥偺斢擭偵姰惉丅24擭丄崙柉搣夵慻埲屻丄怴嶰柉庡媊偲屇偽傟傞丅柉懓偺撈棫(柉懓庡媊)丄柉庡惂偺幚尰(柉尃庡媊)丄抧尃暯嬒丒帒杮愡惂偵傛傞宱嵪揑晄暯摍偺惀惓(柉惗庡媊)偺嶰尨懃丅懛暥庡媊丅丂
丂 |
| 仭柉懓庡媊 |
   丂
丂
|
帺傜偺柉懓傪惌帯丒宱嵪丒暥壔側偳偺庡懱偲峫偊丄壙抣娤偺帄忋偲偡傞巚憐傗塣摦丅僄僗僯僢僋丒僫僔儑僫儕僘儉(Ethnic nationalism)偲傕尵偆丅崙壠庡媊丒垽嫿庡媊丒抧堟庡媊偲偼憡屳偵娭楢偡傞偑丄摨堦偺奣擮偱偼側偄偙偲偵拲堄丅
堦斒偵岆擣偝傟偑偪偩偑丄杮棃偺柉懓庡媊偼崙壠偱偼側偔柉懓傪拞怱偵峫偊傞巚憐偱偁傞丅崙壠庡媊偲寢傃晅偔偺偼柉懓庡媊偺棟擮偐傜柉懓傪惌帯揑偵堦偮偵偟傛偆偲偡傞塣摦偑婲偙傝傗偡偄偐傜偱丄媡偵傾儊儕僇傗儐乕僑僗儔價傾偺傛偆偵崙壠傪懡柉懓偵傛偭偰宍惉偡傞崙偱偼丄偁傞偄偼僆乕僗僩儕傾傗僗僀僗偺傛偆偵丄椬偺戝崙(僪僀僣)偲懡悢攈偺柉懓偑嫟捠偡傞彫崙偺応崌偼丄傓偟傠奺柉懓庡媊偲崙壠庡媊偼懳棫偡傞丅摿掕偺柉懓傪桪嬾偡傞懡柉懓崙壠(僼儔儞僐惌尃壓偺僗儁僀儞丄僽儈僾僩儔惌嶔偑晘偐傟偨儅儗乕僔傾側偳)偺応崌偼丄偦偺桪嬾偝傟偨柉懓偺柉懓庡媊傪巟帩婎斦偵偡傞偑丄摉慠抏埑丒椻嬾偝傟傞懁偺柉懓庡媊偲偼懳棫偡傞丅垽崙怱傛傝偼傓偟傠嫿搚垽(垽嫿庡媊)偲偺恊榓惈偑嫮偄偲傕尵傢傟傞丅
堦曽丄塸岅偱偼垽崙庡媊偲柉懓庡媊偼 Nationalism 偲昞婰偝傟扨岅偲偟偰偺堘偄偼側偄丅悽奅揑偵傒偰傕丄20悽婭偵柉懓帺寛偺尨懃偑彞偊傜傟偰偐傜丄偙偺擇偮偺尵梩偺堄枴偺堘偄偼尭彮偡傞曽岦偵偁傞丅暋悢偺柉懓偱惉傝棫偭偰偄傞崙壠偑暋悢柉懓偺尃棙傪庡挘偡傞応崌偵僄僗僯僔僥傿乕偲屇偽傟傞丅偟偐偟崙撪偵懡柉懓傪撪曪偡傞崙偼埶慠偲偟偰懡偔丄奺抧偱彮悢攈柉懓偺撈棫塣摦偑寖壔偟偰偄傞丅摿偵椻愴廔寢埲崀偺墷廈偱偼抧堟庡媊偺悇恑側偳偱丄傛傝彫偝側柉懓廤抍偵暘偐傟偰憟偆孹岦偑怺傑偭偰偄傞丅
儅僀僲儕僥傿偵傛傞柉懓庡媊偼丄彮悢柉懓丒愭廧柉懓偑帺傜偺尵岅丒暥壔丒廆嫵側偳偺堐帩懚懕傪媮傔丄柉懓帺寛偺庡挘傪偲傕側偆偙偲傕偁傞偑丄暘棧庡媊側偳丄愴憟丒暣憟偺梫場偵側傝摼傞丅
摿掕柉懓偵傛傞崙壠偺宍惉丒弮壔丒奼戝傪庡挘偟丄懳奜揑偵帺柉懓偲偺嵎堎偲桪墇惈傪庡挘偡傞偙偲偑偁傞丅戝崙偵偁偭偰偼嬤椬彅崙偺帺柉懓嫃廧抧堟側偳偺暪崌丄彮悢柉懓偵偁偭偰偼暘棧撈棫傗懠柉懓偺捛曻側偳傪庡挘偟丄偟偽偟偽愴憟傗暣憟偑惗偠傞丅帺柉懓嫃廧抧堟偑嬤椬偵側偄応崌傕丄椞搚傪暪崌偡傞慜傗屻偵偍偄偰丄旐巟攝柉懓偲偺嬤墢惈丒堦懱惈(擔慛摨慶榑側偳)傪嫮挷偡傞偙偲偱惓摉惈傪庡挘偡傞応崌傕偁傞丅偙傟傜偼崙壠庡媊偵柉懓庡媊傪愙崌偡傞摦偒偲尵偊傞丅
僫億儗僆儞愴憟偵傛傞僼儔儞僗偺巟攝壓丄偙偆偟偨奣擮偵怗傟偨儓乕儘僢僷偺奺崙柉偼柉懓庡媊傪崅梘偝偣偨丅傾僕傾偵偍偄偰偼丄擔業愴憟偑摨條偺栶妱傪壥偨偟偰偍傝丄擔杮傊偺婜懸傪惗傫偩丅戞擇師悽奅戝愴屻偵偼丄懡偔偺傾僕傾丒傾僼儕僇偺崙壠偑柉懓庡媊傪崅梘偝偣偰撈棫傪壥偨偟偨丅
仭擔杮偵偍偗傞柉懓庡媊
擔杮偱偼悈屗妛丒崙妛偺塭嬁傪庴偗偨懜墹澋埼塣摦偲偟偰尰傟丄柧帯堐怴偺尨摦椡偲側偭偨丅
偟偐偟丄嬤戙擔杮偵偍偄偰偼丄柉懓庡媊偲崙壠庡媊偲偺堘偄偑堄幆偝傟傞偙偲偼彮側偐偭偨丅擔杮偺柉懓庡媊偲傾僕傾彅柉懓偺柉懓庡媊偲偺楢実傪柾嶕偡傞傾僕傾庡媊偺傛偆側摦偒偼偁偭偨傕偺偺丄掗崙庡媊偺帪戙偵偁偭偰丄擔杮偺柉懓庡媊偼崙壠庡媊偵堸傒崬傑傟偰偄偔丅擔惔愴憟丒擔業愴憟屻偺戝擔杮掗崙偼丄挬慛丒戜榩側偳傪椞搚偵壛偊偰懡柉懓掗崙傪巙岦偟丄擔杮偺崙壠庡媊偼乽敧峢堦塅乿傪宖偘傞戝搶垷嫟塰寳寶愝傪栚巜偟偨戝搶垷愴憟(懢暯梞愴憟)偱僺乕僋偵払偡傞丅
攕愴屻丄偦偺斀徣偐傜愴慜揑側(塃攈揑丒崙壠庡媊揑側)柉懓庡媊傊偺掞峈姶偑嫮傑偭偨堦曽丄斀暷傪宖偘傞嵍攈揑側柉懓庡媊偑崅梘偡傞丅嵍攈揑側棫応偐傜偺柉懓庡媊偼丄壂撽曉娨偺尨摦椡偲側偭偨傎偐丄(楍嫮偐傜偺帺棫傪栚巜偡)傾僕傾丒傾僼儕僇偺柉懓庡媊偵偼忣弿揑側嫟姶偑婑偣傜傟丄儀僩僫儉愴憟斀懳側偳偺斀愴塣摦偲傕寢傃偮偔偲摨帪偵丄嫟嶻庡媊偲寢傃偮偔惃椡偺夘擖偵傛傝丄崙壠偲柉懓偺暘棧偵棙梡偝傟傞堦柺傕帩偭偰偄偨丅
1960擭戙偵偼嵍梼宯妛惗塣摦偵懳偡傞懳峈偲偟偰柉懓攈妛惗慻怐偺塣摦偑妶惈壔偡傞丅斵傜偼恊暷丒斀嫟偵孹偒柉懓庡媊傪側偄偑偟傠偵偟偨愴屻塃梼抍懱傊偺斀敪偐傜柉懓庡媊傊偺夞婣傪巜岦偟丄怴塃梼(柉懓攈)偺尮棳偲側偭偨丅丂
丂 |
| 仭塃偲嵍偲柉懓庡媊 |
   丂
丂
|
堦楢偺偙偺僐儔儉偺暥復傪撉傓偲丄撉幰偺奆偝傫偼壥偨偟偰杔偑杮棃偼嵍婑傝偺恖娫側偺偐丄偼偨傑偨塃婑傝偺恖娫側偺偐丄偵傢偐偵偼敾傝偯傜偄偲巚傢傟傞偐傕抦傟側偄丅乽偁傞悽奅娤乿偱偼曃嫹側塃梼揑巚憐(偲屇傋傞傎偳棫攈側傕偺偱偼側偄偑)傪揙掙揑偵潏潐偟偰偄傞偐偲巚偆偲丄嵟嬤偺乽偪傚偭偲偍偐偟偄傛乿傗乽僐僪儌敹擇戣乿偺戞堦晹乽僐僪儌僲僋僯乿偱偼塃婑傝偩偲敾抐偝傟偰傕偍偐偟偔側偄媍榑傪揥奐偟偰傕偄傞丅偦傟傕摴棟偱丄杔偼傕偲傕偲帺暘偑塃梼偩偲偐嵍梼偩偲偐婯掕偟偨妎偊偼側偄偟丄偦傕偦傕乽僂儓僋乿乽僒儓僋乿偲偄偆暘椶偑幚偼偦傟傎偳堄枴傪帩偮傕偺偩偲偝偊巚偭偰偄側偄丅塃梼丄嵍梼偲偄偆尵梩偼妚柦摉帪偺僼儔儞僗崙夛偱丄壐寬側嫟榓庡媊幰偺僕儘儞僪搣偑塃懁丄屻偵嫲晐惌帯傪峴偄懪搢偝傟傞媫恑攈偺僕儍僐僶儞搣偑嵍懁偵嵗偭偰偄偨偲偙傠偐傜惗傑傟偨偲偄傢傟偰偄傞丅偄偢傟傕尰嵼偺塃梼丄嵍梼偺僀儊乕僕偲偼戝暆偵堎側傞搣攈偱偁偭偨丅尰嵼偱偼丄嵍梼偲偄偊偽嫟嶻搣傪嵟嵍梼偲偡傞幮夛柉庡庡媊惌搣傪巜偟丄塃梼偼曐庣丒帺桼柉庡庡媊偐傜嵟塃梼偺崙悎庡媊偵偄偨傞惌搣傪巜偡偙偲偵側偭偰偄傞丅杔帺恎偼丄慖嫇偺帪偵偼堦娧偟偰嵍梼惌搣偵昜傪擖傟偰偒偨偑丄傕偪傠傫斵傜偺庡挘偵慡柺揑偵巀摨偟偰偄偨傢偗偱偼側偄(慡柺揑偵巀摨偟側偗傟偽搳昜偱偒側偄偺偱偼丄巟帩惌搣偺側偄幰偼惌帯嶲壛傕偱偒側偔側傞)擔杮偺惌帯晽搚偱偼挿偄娫丄栰搣亖嵍梼惌搣偱偁偭偨偺偩偐傜偟偐偨偑側偄丅偦傕偦傕乽惌搣乿偦傟帺懱偵偝傎偳怣棅傪抲偄偰偄傞傢偗偱傕側偐偭偨偺偩丅戝愗側偺偼僶儔儞僗偱偁傝丄崙夛偵採弌偝傟偨朄埬傪傛傝懡妏揑偵嬦枴偡傞偨傔偵傕丄嫮椡側栰搣偼晄壜寚偱偁傞丅栰搣偵昜傪擖傟傞棟桼偼偦傟偩偗偱廫暘偩丅愄傛偔偄傢傟偨乽壗偱傕斀懳幮夛搣乿偲偄偆尵梩偼丄幚偼栰搣偺傕偭偲傕廳梫側懚嵼棟桼傪尵偄昞偟偰偄偨偺偱偁傞丅
杔偼帺暘偵嵍梼偺儗僢僥儖傪揬傜傟傛偆偑丄塃梼偺儗僢僥儖傪揬傜傟傛偆偑偦傟偼慡慠峔傢側偄丅偨偩傂偲偮丄揬傜傟偰偼崲傞偺偑乽柉懓庡媊幰乿偺儗僢僥儖偱偁傞丅傑偝偐偲偼巚偆偑丄乽僐僪儌僲僋僯乿偺敪尵偺傒傪庢傝忋偘偰偦偆偟偨儗僢僥儖揬傝傪峴偍偆偲偡傞攜偑尰傟側偄偲傕尷傜側偄丅乽柉懓庡媊乿偲偄偆尵梩偵偼偗偭偙偆峀偄堄枴偑偁傝丄偦偺偡傋偰傪斲掕偡傞傢偗偱偼側偄偑丄彮側偔偲傕乽乣乣庡媊幰乿偲屇偽傟傞傎偳杔偑柉懓庡媊偵擖傟偁偘偰偄傞傢偗偱偼側偄偙偲偼妋偐偩丅
乽庡媊乿偲偄偆尵梩傪帿彂偱堷偔偲丄乽寴偔庣傞峫偊曽乿偲偐乽忢偵庣傞峴摦忋偺曽恓乿側偳偲偄偭偨堄枴偑嵹偭偰偄傞丅偨偲偊偽乽柉庡庡媊乿偼乽柉庡乿偮傑傝乽尃椡傪愱惂孨庡偵偱偼側偔恖柉堦斒偵偍偔偙偲乿偑乽惌帯塣塩偺忢偵庣傜傟傞曽恓乿偱偁傞傢偗偩偟丄乽嫟嶻庡媊乿偼乽惗嶻庤抜傪嫟桳偡傞僾儘儗僞儕傾妚柦傪悇偟恑傔傞偙偲乿傪乽峴摦忋偺曽恓乿偲偡傞峫偊曽偱偁傞丅偝偰丄偱偼乽柉懓庡媊乿偲偼壗偩傠偆丅偙傟傑偱尒偰偒偨乽乣乣庡媊乿偺乽乣乣乿偼傒側丄摦帉傪柤帉偵偟偨奣擮傗棟擮偱偁傞丅偮傑傝丄偁傞棟憐傪峴摦偱幚尰偟傛偆偲偡傞偺偑乽乣乣庡媊乿偲偄偆偙偲偵側傞丅偟偐偟側偑傜丄乽柉懓庡媊乿偺応崌偺乽柉懓乿偼摦帉偱偼側偔丄巒傔偐傜柤帉偱偁傞丅偁傞峴摦傪傕偭偰摼傜傟傞傕偺偱偼側偔丄嵟弶偐傜乽忬懺乿偲偟偰懚嵼偟偰偄傞丅偙偺暥復傪撉傫偱偄傞偁側偨偑擔杮恖側傜丄婣壔偟偨傝丄寢崶偟偰屻揤揑偵擔杮崙愋傪摼偨応崌傪彍偗偽丄惗傑傟側偑傜偵擔杮柉懓偩偭偨偼偢偩偟丄嵼擔挬慛恖側傜傗偼傝慜弎偺傛偆側忬懺傪彍偒丄挬慛柉懓偲偟偰惗傪庴偗偨偼偢偱偁傞丅偙偆偟偨乽偱偁傞傋偒偙偲乿偱偼側偔丄偼偠傔偐傜乽偱偁傞偙偲乿偵偮偗傞乽庡媊乿偲偄偆尵梩偼丄偍偺偢偐傜杮棃偺堄枴偲偼旝柇偵偢傟偰偄傞偺偱偼偁傞傑偄偐丅偪側傒偵帿彂偵傛傞偲丄乽柉懓庡媊乿偲偼(1)摨偠柉懓偱崙壠傪宍嶌傠偆偲偡傞庡媊(2)帺暘偺懏偡傞柉懓偺帺棫偲敪揥傪惌帯揑丄暥壔揑側嵟崅偺栚昗偲偡傞庡媊丄偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞丅偳偪傜偺堄枴偵偍偄偰傕丄乽柉懓庡媊乿偲偼側偵傛傝傕乽柉懓帺寛乿(奺柉懓偼丄懠柉懓偺姳徛丒巟攝傪庴偗偢丄偦偺柉懓帺恎偵傛偭偰惌帯偦偺懠傪峴偆傋偒偱偁傞偲偄偆峫偊曽)傪幚尰偡傞偨傔偺乽峴摦忋偺巜恓乿偲偟偰婡擻偟偰偒偨偲偄偆偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅
乽柉懓庡媊乿偼僫僔儑僫儕僘儉偲傕尵偄姺偊傞偙偲偑偱偒傞偑丄塸岅偵偼帡偨傛偆側堄枴偺尵梩偲偟偰Nationalism偲偼暿偵Racism偲偄偆扨岅偑偁傝丄擔杮岅栿偲偟偰偼乽恖庬嵎暿乿乽柉懓揑桪墇姶乿偲偄偆斲掕揑僀儊乕僕偺偁傞尵梩偲側傞丅偟偐偟丄擔杮岅偱梡偄傜傟傞乽柉懓庡媊乿偺側偐偵偼丄Nationalism傛傝尷傝側偔Racism偵嬤偄巚憐傕偁傝偦偆側婥偑偡傞偺偩丅偨偲偊偽柉懓庡媊傪巪偲偡傞惌帯寢幮偼丄傎偲傫偳偑偄傢備傞塃梼抍懱偦偺傕偺側偺偩偑丄斵傜偺奜崙恖攔愃巚憐側偳偼柧傜偐偵Nationalism偺斖醗傪挻偊丄Racism偲抐偠偰傕夁尵偱偼側偄丅偁傞偄偼柧帯堐怴慜栭偺懜墹澋埼巚憐偵斖傪偲偭偰偄傞偮傕傝側偺偐傕抦傟側偄偑丄懜墹澋埼偑偁偔傑偱傕帿彂偵偁傞捠傝乽柉懓帺寛乿傪幚尰偡傞偨傔偺乽柉懓庡媊乿巚憐偦偺傕偺偲尵偊傞偺偵懳偟丄塃梼抍懱偺峫偊曽偼偼偭偒傝嵎暿庡媊揑偱偁傝丄乽柉懓揑桪墇姶乿偦偺傕偺偲偡傜尵偄愗偭偰傕偄偄丅偪側傒偵塃梼偲柉懓庡媊偑傎傏摨媊岅側偺偼偙偙偑擔杮偩偐傜偵夁偓偢丄偨偲偊偽儘僔傾偱偼丄嫟嶻庡媊偲柉懓庡媊偲偑寢傃偮偄偨怴偟偄宍偺嬌嵍朶椡庡媊側偳傕惗傑傟偰偄傞丅巚偊偽儗乕僯儞偑堦崙妚柦榑傪傇偪忋偘偨摉弶偐傜丄僂儓僋丄僒儓僋偲偄偆嬫暿偲柉懓庡媊偲偼傑偭偨偔暿偺儀僋僩儖偵懚嵼偟偰偄偨偺偐傕偟傟側偄丅
乽柉庡庡媊乿傕乽嫟嶻庡媊乿傕偲傕偵姰惉宍偺側偄丄傛傝崅偄師尦傪栚巜偝側偗傟偽側傜側偄揰偱丄乽柉懓帺寛乿傪栚巜偝側偗傟偽側傜側偄忬懺偵抲偐傟偨崙柉偵帡偰偄傞丅偟偐偟丄慜擇幰偑偄傢偽僑乕儖偺側偄愴偄傪嫮偄傜傟傞乽庡媊乿側偺偵懳偟偰丄乽柉懓庡媊乿偵偼偼偭偒傝偲偟偨僑乕儖偑偁傞丅懠柉懓偺巟攝傪棧傟丄帺傜偺庤偱惌帯傪扴偆偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞偲偄偆丄乽柉懓帺寛乿偑払惉偝傟偨帪揰偱丄斵傜偺乽柉懓庡媊乿偼姰惉偟偰偟傑偆偺偩丅媡偵尵偊偽丄懠崙偺姳徛傪庴偗側偄撈棫崙傪偡偱偵庤偵偟偰偄傞柉懓偵偼傕偼傗乽柉懓庡媊乿側傞巚憐偼丄尩枾偵偼晄昁梫側偺偩丅偦偺忬懺偵偍偄偰傑偩乽柉懓庡媊乿傪庡挘偡傞偙偲偼丄偡偱偵Nationalism偺斖醗傪挻偊丄Racism偺椞堟偵擖傝偐偗偰偄傞偲偄偭偰傕偄偄丅Nationalism偲Racism偺娫偺偳偙偵慄傪堷偔偐偼側偐側偐擄偟偄栤戣偩偑丄偨偲偊偽嫮峝側柉懓庡媊幰偲偟偰抦傜傟偰偄傞儈儘僔僃價僢僠尦僙儖價傾戝摑椞側偳丄僐僜儃暣憟偺屻偵柧傜偐偵側偭偨傾儖僶僯傾宯廧柉偵懳偡傞媠嶦傪傒傞偲丄Nationalist偲偄偆傛傝偼丄尷傝側偔Racist偵嬤偄恖暔偩偭偨偲巚傢傟傞丅寢嬊偺偲偙傠丄偦偺乽柉懓庡媊乿偑偳偪傜側偺偐傪敾抐偡傞偵偼丄屄暿偵斵傜偑峴偭偨峴堊偺寢壥傪尒傞傛傝側偄偺偩傠偆丅
奀奜偵栚傪揮偠傞偲丄尰嵼乽柉懓庡媊乿嫵堢偵擬怱側偺偼側傫偲偄偭偰傕偍偲側傝丄拞壺恖柉嫟榓崙偱偁傞丅婎杮揑偵懡柉懓崙壠偱偁傞拞崙偑柉懓庡媊嫵堢偵擬怱側偺偼偪傚偭偲曄側婥偑偡傞偑丄乽拞壺恖柉嫟榓崙乿崙柉偑偁偨偐傕堦偮偺柉懓偱偁傞偐偺傛偆側尪憐傪梌偊偮偮乽崙壠乿偲偟偰偺摑堦傪恾傠偆偲偄偆丄Racism偺怓嵤偑嬌傔偰擹偄Nationalism側偺偩偲偄偊傞偩傠偆丅偙偙偱偁偊偰Racism偲偄偆尵偄曽傪偟偨偺偼傕偪傠傫傢偗偑偁偭偰丄偙偲偺敪抂偼偄偆傑偱傕側偔揤埨栧帠審偱偁傞丅媫寖側柉庡壔偵懱惂曵夡傊偺婋婡姶傪曞傜偣偨拞崙嫟嶻搣惌尃偼丄嫮峝側曐庣壔楬慄傊偲惌嶔傪揮姺偟丄摨帪偵戝廜偺栚傪崙撪偐傜奀奜傊偲堩傜偡傋偔丄垽崙嫵堢傪堦抜偲嫮壔偡傞丅偦偺帪偄偪偽傫偍庤寉偩偭偨偺偑丄嫵壢彂栤戣傗桋崙栤戣偱壗偐偲偛偨偛偨偟偑偪側擔杮傪傗傝嬍偵嫇偘傞偙偲偩偭偨丅擔壺帠曄傗撿嫗戝媠嶦側偳偵娭偡傞90擭戙埲崀偺乽楌巎乿嫵堢偼丄柧傜偐偵惌帯庡摫偺嫮偄Racism怓傪懷傃偨傕偺偱丄偙偆偟偨弶摍嫵堢傪庴偗偰堢偭偨尰嵼偺庒擭憌偼擔杮偵懳偟偰嬌抂側揋堄傪書偄偨傑傑惉擭偟丄嵟嬤懡敪偟偰偄傞斀擔僨儌偱搳愇傪孞傝曉偟偨傝偟偰偄傞丅幚嵺偺偲偙傠丄2008擭偺杒嫗僆儕儞僺僢僋偵塭嬁傪梌偊偦偆側偙偆偟偨孹岦偵丄拞崙惌晎偲偟偰偼愴乆嫲乆側敜偩偑丄柉廜偺僄僱儖僊乕偑傒偢偐傜偵岦偔偙偲偺曽偑梱偐偵嫲傠偟偄偺偱丄寢嬊偺偲偙傠朤娤偡傞傛傝側偄偺偩傠偆丅偄偢傟偵偟傠丄偙偆偟偨偽偐偘偨峴摦偱懝傪偡傞偺偼拞崙帺恎偩偲偄偆偙偲偵丄惌晎偑婥晅偄偰偄側偄偼偢偼側偄(抁婜揑偵偼娤岝廂擖偺寖尭丄晄攦塣摦偵傛傞宱嵪惉挿偺撦壔丄挿婜揑偵偼崙壠丒惌尃偦偺傕偺傊偺怣棅搙偺掅壓傗帒杮堷偒偁偘側偳偵傛傞崙嵺嫞憟椡偺挊偟偄掅壓側偳側偳丄埆塭嬁偼寁傝抦傟側偄)悽奅奺崙偼拞崙偺偙偆偟偨姱惢暣憟寑偺撪枊傪偡偱偵抦傝恠偔偟偰偍傝丄傾儊儕僇偱偼怴暦偺幮愢側偳偱傕乽曃岦偟偨垽崙庡媊嫵堢偺摉慠偺寢壥乿偲彂偐傟偨傝偟偰偄傞偺偩丅壗傕敾偭偰偄側偄偺偼丄憶偄偱偄傞摉偺庒幰偨偪偩偗偩偲偄偆偙偲偩丅傑偁丄僨儌嶲壛幰偺條巕傪傛偔尒傞偲丄僨乕僩婥暘偲偟偐巚偊側偄條巕偺庒幰側偳傕偄偰偝傎偳愗幚偝偼姶偠傜傟偢丄偁傟側傜乽懪搢暷掗乿傪嫨傫偱僨儌偵柧偗曢傟偨傢傟傢傟偺悽戙偺曽偑丄梱偐偵婋尟偩偭偨傛偆側婥傕偡傞偑^^;堦恖偭巕惌嶔偱娒傗偐偝傟曻戣偵堢偭偨庒幰偨偪偑丄帺傜偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕傪椬崙傊偺Racism偵枮偪偨曃岦嫵堢偐傜偟偐摼傜傟側偄偲偟偨傜丄偳偺傒偪偙偺崙偵彨棃偼側偄偩傠偆丅杔偨偪偼偨偩嵗偭偰斵傜偑帺柵偟偰偄偔偺傪尒偰偄傟偽偄偄偩偗偩丅
榖偑偩偄傇堩傟偰偟傑偭偨偑丄梫偡傞偵乽僒儓僋乿乽僂儓僋乿偲偄偆尵梩偼憡懳揑側傕偺偱偟偐側偔丄偦偙偵愨懳揑側堄枴偼側偄丅偟偐傞偵乽柉懓庡媊乿偵偼偟偭偐傝偲掕媊偱偒傞堄枴偑偁傝丄彮側偔偲傕尰忬偺乽柉懓帺寛乿傪幚尰偟偰偟傑偭偰偄傞擔杮偵偼丄傢偞傢偞乽庡媊乿偲偟偰偙偲偝傜嫮挷偡傞昁梫偼側偄偲杔偼巚偭偰偄傞傢偗偩丅傕偪傠傫偦偆偼偄偭偰傕擔杮恖傪傗傔傞傢偗偵偼峴偐側偄偐傜丄恎偵晅偄偨僫僔儑僫儕僘儉傪斲掕偡傞偙偲偼偱偒側偄偟丄偦偺昁梫傕側偄丅偨偩丄愴慜偺擔杮恖傗尰戙偺偍椬偝傫偨偪傪斀柺嫵巘偵偟偰丄Racism偲偺嫬奅傪墇偊側偄傛偆丄忢偵堄幆偟側偑傜惗偒偰峴偙偆偲巚偭偰偄傞丅丂2005/4丂
丂 |
| 仭擔杮偺柉懓庡媊偼丄傾儊儕僇掗崙庡媊偺僨僐僀?丂2015/5 |
   丂
丂
|
擔杮偺埨攞惌尃偼丄傾儊儕僇偑憪峞傪彂偄偨擔杮寷朄傪廋惓偟丄擔杮偺孯偑愴憟傪峴偊傞傛偆偵偡傞偙偲傪慱偭偰偍傝丄偐偮偰偺掗崙庡媊揑孹岦偺暅妶傪嫲傟傞恖乆傕偄傞丅
擔杮偼愴屻偺暯榓寷朄傪曄偊傛偆偲偟偰偄傞丅擔杮偼丄愴娡傪寶憿偟丄愴摤婡傪峸擖偟丄媫懍偵寗側偔晲憰偟偮偮偁傞丅曞廤億僗僞乕偼帄傞強偵偁傞丅偦偺堦曽偱丄擔杮偼丄廬弴偐偮拤幚偵丄愯椞幰偱偁傝嵟傕恊枾側摨柨崙偱偁傞丄傾儊儕僇崌廈崙傪巟帩偟偰偄傞丅
忬嫷傪摜傑偊傟偽丄埨攞偺乪柉懓庡媊乫偲偼堦懱壗偐丄媈栤偵巚傢偞傞傪摼側偄丅斵偺拤惤怱偼丄墷暷丄偲傝傢偗傾儊儕僇崌廈崙偺曽偵岦偄偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅寛偟偰斵帺恎偺崙傗傾僕傾彅崙偵偱偼側偄丅
傾儊儕僇偑朷傓偁傜備傞偙偲傪擔杮偼巟帩偡傞丅儚僔儞僩儞偼丄偦偙偱儚僔儞僩儞偑寛掕揑栶妱傪墘偠傞乪懢暯梞偺悽婭乫傪柌憐偟偰偄傞丅儚僔儞僩儞偼梕幫側偔乪傾僕傾婎幉乫僪僋僩儕儞傪悇恑偟偰偍傝丄偦偙偱偼丄孯帠揑偵丄慀摦揑偵丄擔杮偼偑偭偪傝傾儊儕僇懁偱偄傞偙偲傪傕偔傠傫偱偄傞丅儚僔儞僩儞偼丄12儢崙偵傛傞丄娐懢暯梞愴棯揑宱嵪楢実嫤掕(TPP)傪幏漍偵捛媮偟偰偍傝丄擔杮偼攺庤妳嵮偟偰偄傞丅
仭杒曽椞搚偺僕儗儞儅
偦偙偐傜儘僔傾偺搰僒僴儕儞偑尒偊傞擔杮嵟杒抂偺搒巗丄抰撪偱偼丄孯帠儗乕僟乕傗娔帇僔僗僥儉偑壒傪偨偰丄楌巎揑側峘偱偼丄奀忋曐埨挕偺慏敃偑丄偄偮偱傕弌摦偱偒傞傛偆懸婡偟偰偄傞丅
壏愹傪朘傟偨抝惈媞偑丄傕偟彈搾偵擖傟偽婲慽偝傟傞偲偄偆寈崘偵帄傞傑偱丄巗撪昗幆偺傎偲傫偳慡偰偑丄擔杮岅偲丄儘僔傾岅偱彂偐傟偰偄傞丅
廻攽偟偰偄傞儂僥儖偺憢偐傜偼丄揤婥偑椙偄偲僒僴儕儞偑尒偊傞丅壞偺娫偼丄擇惽偺戝偒側慏偑丄抰撪偲僒僴儕儞搰偵偁傞儘僔傾偺挰僐儖僒僐僼偺娫傪擔杮恖娤岝媞傪嵹偣偰墲暅偡傞丅儘僔傾嫏慏偼昿斏偵杒奀摴傪朘傟丄暥壔岎棳傗杅堈偝偊峴傢傟偰偄傞丅
儁僠僇丒儗僗僩儔儞偱偼丄旤枴偟偄儘僔傾椏棟偑嫙偝傟丄價乕儖偑拲偑傟丄儘僔傾偺壧偑壧傢傟偰偄傞(恖婥偺壧偼乪昐枩杮偺僶儔乫偩)丅挀幵応偺岦偙偆丄暃峘巗応偵偼丄幚嵺丄愮搰楍搰偑丄慡偰擔杮偵強懏偟偰偄偨帪戙偺僒僴儕儞偺屆偄儌僲僋儘幨恀偑屩傜偟偘偵宖偘傜傟偰偄傞丅
杒曽椞搚偼丄夝寛晄擻忬懺偺栤戣偲側偭偰偄傞丅擔杮懁偺僾儘僷僈儞僟偼丄戞擇師悽奅戝愴枛偵丄僜楢偑杒曽椞搚傪忔偭庢偭偨偲偄偆庡挘偺孞傝曉偟偩丅壗廫擭傕丄擔杮偼丄曉娨傪梫媮偟偰偒偨丅
偩偑抰撪偵偍偄偰偝偊丄偙偺栤戣偱儘僔傾偑懨嫤偡傋偒偩偲偄偆偙偲偵昁偢偟傕慡堳偑擺摼偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偁傞彫宆擔杮嫏慏偺慏挿偼偙偆愢柧偡傞丅
乬擔杮偵偼丄嬌塃庱憡偑偄傑偡丅斵偼丄椉崙傪揋偵傑傢偟丄偦偟偰幚嵺丄儘僔傾丒拞崙椉曽傪攋夡偟偨偑偭偰偄傞壜擻惈偑嬌傔偰崅偄崙丄傾儊儕僇崌廈崙偲偒傢傔偰恊枾偱偡丅傕偟愮搰楍搰傗僒僴儕儞偑丄擔杮偵栠傟偽丄奆丄懄嵗偵丄傕偆堦偮偺壂撽偵曄偊傜傟偰偟傑偆偱偟傚偆丅儘僔傾杮搚偺偡偖偦偽偺傾儊儕僇嬻孯偲奀孯婎抧偩傜偗偵丅乭
栺3,000km棧傟偨応強偱丄尦偄偵偟偊偺壂撽墹崙偼丄愯椞偲丄偦偺屻偺孯挀棷偲偄偆埆柌偺拞偵偁傞丅壂撽偐傜丄壗愮傕偺傾儊儕僇偲擔杮偺峲嬻婡偑丄擭拞拞崙傗杒挬慛傪挧敪偟偰偄傞丅偦偺堦曽丄尰抧廧柉偼愯椞偵寖搟偟偰偍傝丄戝婯柾峈媍峴摦偱搰偼梙傟偰偄傞丅導柉偼丄傾儊儕僇孯挀棷廔椆傪梫媮偟偰偍傝丄傾儊儕僇孯婎抧揚嫀傪朷傫偱偄傞丅偩偑埨攞惌尃偼丄峏側傞傾儊儕僇憰旛昳丄峏側傞妸憱楬丄峏側傞嶌愴墘廗傪朷傫偱偄傞丅
巹偼壂撽偱擇搙巇帠傪偟偨偙偲偑偁傞丅嵟嬤偱偼丄2013/14擭丄撿暷偺曻憲嬊僥儗僗乕儖偺暷孯婎抧偵娭偡傞僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋乪壂撽愴乫偵娭梌偟偨帪偩丅
撨攅偱丄尦傾儊儕僇嬻孯僷僀儘僢僩偱丄尰嵼偼嶌壠偱嫵庼偺僟僌儔僗丒儔儈僗偑忬嫷傪偙偆愢柧偟偰偔傟偨丅
乬壂撽偼丄擔杮撪偺傾儊儕僇孯暫巑偲丄傾儊儕僇巤愝偺栺75僷乕僙儞僩傪梚偟偰偄傑偡丅暷孯暫巑傗婎抧偼丄杮搚偵曢傜偡戝敿偺擔杮崙柉偵偲偭偰丄慡偔尒偊側偄偺偱丄朰傟傜傟偰偄傑偡丅壂撽偼丄庱搒搶嫗偐傜壗愮僉儘傕棧傟偰偄傑偡偐傜丅壂撽導柉偲榖偟偰尒傟偽60擭埲忋偨偭偨崱傕丄婎杮揑偵丄傾儊儕僇-擔杮孯帠摨柨偺晧扴傪堷偒庴偗傞條丄梫媮偝傟偰偄傞偙偲偵丄斵傜偑丄搟傝幐朷偟偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅傾儊儕僇偲偺孯帠摨柨偼丄偁傜備傞柺偱丄儚僔儞僩儞偵懳偡傞斱孅側懺搙偲斸敾偡傞恖乆偑昞尰偡傞忬嫷傪傕傕偨傜偟偰偄傞丅奜岎惌嶔偵偮偄偰丄儚僔儞僩儞偑朷傓偙偲傪擔杮偑朩偘傞傛偆側偙偲偼傎偲傫偳側偄丅乭
婎抧偼丄曈栰屆榩偺條偵丄壂撽偺帺慠偺傑傑偺抧堟偵傑偱奼挘偟偮偮偁傞丅
壂撽偺妛幰丄桭抦惌庽弝嫵庼偼丄傾儊儕僇偲擔杮椉崙偺掗崙庡媊揑孹岦偲斵偑姶偠偰偄傞傕偺偵懳偟偰寈夲姶傪昞柧偟偰偄傞丅斵偼尰抧廧柉偺嬯擄偼廫暘傢偐偭偰偄傞丅
乬傾儊儕僇掗崙庡媊偼丄擔杮怉柉抧庡媊傪丄変乆偵懳偟偰棙梡偟偰偄傞偺偩偲巚偄傑偡丅擔杮惌晎偼丄傾儊儕僇崌廈崙偲埨慡曐忈忦栺傪寢傃丄偦偟偰丄傾儊儕僇崌廈崙偼丄擔杮傪棙梡偟偰丄変乆壂撽導柉偵丄傾儊儕僇孯帠婎抧傪庴偗偄傟傞傛偆嫮偄偰偄傞偺偱偡乭偲斵偼愢柧偟偨丅
婎抧偑丄拞崙傗杒挬慛傗儘僔傾偲揋懳偟丄挧敪偡傞堊偵丄偦偙偵懚嵼偟偰偄傞偺偼媈偄傛偆偑側偄丅戞嶰師悽奅戝愴偑丄壂撽偐傜巒傑傝偐偹側偄偲峫偊偰偄傞恖乆偼懡偄丅
戩墇偟偨僆乕僗僩儔儕傾恖楌巎妛幰偱挿嶈戝妛柤梍嫵庼偺僕儑僼儕乕丒僈儞偼丄偙偺抧堟偵偍偄偰丄塿乆峌寕揑偵側傝偮偮偁傞擔杮偺栶妱傪寽擮偟偰偄傞丅
乬埨攞惌尃偑愲妕/掁嫑[彅搰]傪崙桳壔偟偰丄慡偰偑曄傢傝傑偟偨丅擔杮偑丄偙傟傜偺偄傢備傞學憟拞偺彅搰傪弰偭偰丄幚嵺丄學憟偼側偄偲愰尵偟偨堊偵尰忬偑曄傢偭偨偺偱偡丅偦傟偱搶嫗偺惌尃偑拞崙傪搟傜偣偨偺偱偡丅拞崙偼丄偙偺尰忬曄峏偵暜奡偟偰偄傞偺偱偡丅乭
仭柕弬偺崙丄擔杮
挿擭丄擔杮偼丄怣偠傜傟側偄傎偳巚偄傗傝偺偁傞幮夛儌僨儖傪敪揥偝偣側偑傜丄嬥帩偪偲昻朢恖偲偺娫偺奿嵎偑丄悽奅偱堦斣彫偝偄偙偲傪屩傞偙偲偑偱偒偰偄偨丅巟攝幰払偺拞偵偼偳傟傎偳偺塃梼偑偄傞偐抦傟側偄偑丄條乆側揰偱丄擔杮偼丄傎偲傫偳乪幮夛庡媊乫崙偲偟偰捠梡偡傞偩傠偆丅
偩偑堦偮婎杮揑側栤戣偑偁傞丅擔杮偼丄帺崙柉偵偲偭偰偺傒丄幮夛庡媊幰側偺偩丅
擔杮偺戝婇嬈偼丄壗廫擭娫傕丄搶傾僕傾偺帄傞強偱丄怉柉抧庡媊偺嫮搻抍偺傛偆偵傆傞傑偭偰偒偨丅椺偊偽丄擔杮偺帺摦幵夛幮偼丄懡偔偺搒巗傪攋夡偟丄尰抧惌晎傪攦廂偟丄曪妵揑側岞嫟岎捠婡娭傪寶愝偟側偄傛偆偵偝偣偨偲壗搙傕暦偐偝傟偨丅尰嵼丄帺摦幵傗僆乕僩僶僀偺攔婥偱懅偑媗傑傝偦偆偵側傞僕儍僇儖僞傗僗儔僶儎摍偺柍悢偺嫄戝搒巗偼丄抧壓揝楬慄傗寉婳忦僔僗僥儉偑堦杮傕側偄丅
偙偺棟桼偼丄傾僕傾彅崙柉偵恊墷暷揑悽奅娤傪悂偒崬傓偲偄偆擔杮偺庢傝慻傒偵傛偭偰丄傎偲傫偳愢柧偱偒傞丅擔杮偺戝妛偼丄壗廫擭傕丄昻偟偄搶撿傾僕傾偺崙乆偺妛惗払偵乪彠妛嬥乫傪採嫙偟偰偒偨丅擔杮偺戝妛偼丄偙偆偟偨妛惗払偵丄恊墷暷嫵媊傪悂偒崬傒丄妚柦惛恄傪嵙偒丄庒幰払傪掗崙偺巊梡恖偲偟偰怳傞晳偆傛偆曄偊偰偟傑偆丅杮幙揑偵丄擔杮偵懳偟偰側偝傟偨偙偲傪丄懠偺傾僕傾恖偵懳偟偰峴偭偰偄傞偺偩丅
戞擇師悽奅戝愴偱攕杒偟偨屻丄擔杮偼寢嬊墷暷偺偛庡恖払偵丄拤幚偵側偭偨丅尦儅儗乕僔傾庱憡儅僴僥傿乕儖丒儌僴儅僪傪娷傓懡偔偺傾僕傾巜摫幰払偑乬擔杮偼傾僕傾偵婣傟乭偲梫媮偟偰偒偨丅擔杮偼寛偟偰栠傜側偐偭偨丅挬慛愴憟拞偵丄墷暷偺孯戉岦偗偺惢昳傗憰旛傪惢憿偟偰丄擔杮偼朙偐偵側偭偨丅儀僩僫儉愴憟拞傕丄擔杮偼摨偠偙偲傪偟懕偗偨丅擔杮偼尰嵼丄摨偠摴傪扝偭偰偄傞丅
傾僀儖儔儞僪恖偱丄搶嫗偵偁傞桳柤峑丄忋抭戝妛島巘偺僨僀價僢僪丒儅僋僯乕儖偼擔杮偺崙塩曻憲丄NHK偱傕巇帠傪偟偰偄傞丅斵偼丄怴偨側丄孯崙壔偟丄愻擼偝傟偨擔杮偵偮偄偰丄塿乆斸敾揑偵側偭偰偄傞丅
斵傜偼嫵壢彂傪彂偒姺偊偰偄傑偡丅斵傜偼戞擇師悽奅戝愴傪旘偽偟丄傢偢偐8儁乕僕偟偐偝偒傑偣傫...柉懓庡媊偼惙傝忋偑傝偮偮偁傝傑偡丅婌寑嶌壠偺昐揷彯庽偑丄乪塱墦偺僛儘乫偲戣偡傞恄晽愴巑偵偮偄偰偺彫愢傪姧峴偟傑偟偨偑 乧 彫愢偼丄500枩晹傕攧傟傑偟偨! 擔杮偱丄500枩晹傕攧傟傞杮側偳懠偵偁傝傑偣傫!
乬埨攞庱憡偼丄偦偺杮傪撉傫偱丄婥偵擖傝傑偟偨丅斵偼丄嶌壠傪NHK偺棟帠偵偟偨偺偱偡傛! 偦傟偵丄NHK棟帠挿傕丄塃梼偺僠儞僺儔偱偡丅乭
僨僀價僢僪偼丄塿乆暜奡偟偨條巕偱偙偆懕偗偨丅
乬尰嵼丄擔杮偺儅僗僐儈偱偼戝曄側帺屓専墈偑峴傢傟偰偄傑偡丅偦偟偰惌晎偼丄椺偊偽丄偄傢備傞乪僆儗儞僕丒僽僢僋乫偲偄偆乪僈僀僪儔僀儞乫傪敪峴偟偰偄傑偡丅乪峀偑傝傗偡偄傕偺乫...偁傞偄偼楌巎偵娭偡傞偁傜備傞偙偲傪丄偳偆埖偆傋偒偐偲偄偆傕偺偱偡丅嶌壠傗東栿幰偵懳偡傞巜帵偑偁傞偺偱偡丅椺偊偽丄乪撿嫗媠嶦偺條側尵梩偼丄奜崙恖愱栧壠偺敪尵傪堷梡偡傞応崌埲奜偵偼寛偟偰巊傢側偄偙偲乫丅偁傞偄偼乪桋崙恄幮偱偼丄偦傟偵偮偄偰乬媍榑偺揑偵側偭偰偄傞乭偲偄偆尵梩偼寛偟偰巊傢側偄偙偲乫丅変乆偼丄戞擇師悽奅戝愴偺乪堅埨晈乫偵偮偄偰偼丄彂偔偙偲偑偱偒傑偣傫丅乭
擔杮偺戝廜偼丄帪帠栤戣偵偮偄偰丄堦曽揑側夝庍傪悂偒崬傑傟偰偄傞偲傕尵偭偨丅儘僔傾丄僔儕傾傗拞崙偲偄偆榖戣偵側傞偲丄擔杮恖偼丄傕偭傁傜墷暷僾儘僷僈儞僟傪媧廂偝偣傜傟偰偄傞丅
乬偟偐傕丄斵傜偼幚嵺丄NHK偑尵偆偙偲傪怣偠偰偄傞偺偱偡乭偲僨僀價僢僪偼尵偆丅
崄峘偺乪塉嶱妚柦乫偺夋憸傪丄僲乕儉丒僠儑儉僗僉乕偲嶌偭偰偄傞塮夋偵庢傝崬傫偱偄傞嵺丄僼傿儖儉曇廤幰偺丄偼偨丒偨偗偟偼丄偙偆偄偭偰徫偭偨丅
乬擔杮偱偼丄崄峘偱偺丄偙偆偟偨乪僇儔乕妚柦乫傗嵟嬤偺弌棃帠偺攚屻偵墷暷偑偄傞偙偲傪恖乆偼棟夝偟偰偄傑偣傫丅擔杮偱偼丄崄峘偱偺摦偒偼丄帺桼偲柉庡庡媊偺堊偺塣摦偩偲偄偆偺偑丄慡堳偺崌堄側偺偱偡丅偦傟偼懠偵丄戙懼偺僯儏乕僗忣曬尮偑傎偲傫偳側偄偣偄偱偡丅乭
傾僽僟價傗儀僀儖乕僩偺條側応強偱偝偊丄RT偺條側僥儗價嬊偺曻憲傪丄偁傜備傞堦棳儂僥儖偱尒傞偙偲偑偱偒傞丅擔杮偱偼偦偆偱偼側偄丅偁傜備傞戝庤崙嵺僠僃乕儞偺儂僥儖偱偼丄傎偲傫偳偑丄擔杮偺曻憲嬊偲丄CNN丄BBC偲Fox掱搙偩丅
仭廬棃捠傝偺惌帯偵懳偡傞晄枮
擔杮偺尰嵼偺惌帯恑楬偵懳偡傞晄枮偼帄傞強偱尒偊傞傛偆偵側偭偰偄傞條巕偱丄偟偐傕偦傟偼丄堦晹偺丄彫偝側斀懱惂廤抍偵尷傜側偄丅79嵨偺尦戝庤寶愝夛幮暃幮挿丄Segi Sakashi偼丄嵟嬤斵偺搟傝傪巹偵岅偭偰偔傟偨丅
傾儊儕僇偲偺嬌抂偵恊枾側娭學偲丄儘僔傾丄拞崙傗懠偺崙乆偵懳偡傞揋懳揑懺搙偱丄埨攞庱憡偑丄擔杮傪嫮堷偵丄椬崙丄偮傑傝娯崙傗拞崙偲偺孯帠徴撍偵捛偄傗傝偮偮偁傞偺偵丄崙柉偼偙偺偙偲傪慡偔婥偑偮偐偢偵弅彫偟懕偗傞幮夛暉巸偵偟偑傒偮偄偰偄傞丅
乬嬤椬彅崙偺斀姶傪攦偆昁梫側偳慡偔奆柍側偺偱偡偐傜丄偙偆偟偨偙偲偼慡偔攏幁偘偰偄偰丄偲傫偱傕側偄偺偱偡丅拞崙偼丄擔杮偺庡梫杅堈憡庤崙偺堦偮偱偡丅娯崙傕偦偆偱偡丅変乆偼宱嵪揑偵丄偍屳偄偺懝塿偱丄惉挿(偁傞偄偼丄弅彫)偟偰偒偨偺偱偡丅棪捈偵尵偭偰丄埨攞庱憡偼丄1960擭偺傾儊儕僇偲偺埨曐忦栺備偊偵丄変乆偼偙偆偄偆晽偵峴摦偟側偗傟偽偄偗側偄偲巚偄崬傒丄幚偵嬸楎側僎乕儉傪偟偰偄傞偺偱偡丅乭
擔杮拞偺岞墍偺幣惗傗丄懠偺応強偵丄敀偄昗幆偑棫偭偰偄傞丅偄偔偮偐偺尵岅偱彂偐傟偰偄傞崟偄暥帤偼乬悽奅恖椶偑暯榓偱偁傝傑偡傛偆偵両乭
擔杮偺奜岎惌嶔傪峫偊傟偽丄偙偆偟偨尵梩偼婾慞偲夝庍偝傟偐偹偢丄旂擏偱偝偊偁傞丅墷暷偑丄悽奅傪丄拞崙傗儘僔傾偺條偵丄暯榓揑側偑傜傕丄嫮椡側崙乆偲偺攋柵揑側徴撍偵岦偗偰墴偟傗偭偰偄傞嵟拞丄擔杮偼偦偺墷暷傪巟墖偟傛偆偲婃挘偭偰偄傞偺偩丅
偦偙偱丄擔杮偺巜摫幰偼丄傾僕傾偺懡偔偺応強偱偼丄寖搟偝傟側偑傜丄墷暷偱偼丄戝偄偵巟帩偝傟丄徧巀偝傟傞傢偗偩丅執戝側擔杮偺揘妛幰丄壀憅揤怱偑丄100擭埲忋慜偵丄挊彂乪拑偺杮乫偵彂偄偨尵梩傪巚偄偩偡偺偼帪媂偵偐側偭偰偄傞偩傠偆丅
乬堦斒偺惣梞恖偼丄拑偺搾傪尒偰丄搶梞偺捒婏丄抰婥傪側偟偰偄傞愮昐偺婏暼偺傑偨偺椺偵夁偓側偄偲巚偭偰丄懗偺壓偱徫偭偰偄傞偱偁傠偆丅惣梞恖偼丄擔杮偑暯榓側暥寍偵傆偗偭偰偄偨娫偼丄栰斬崙偲尒側偟偰偄偨傕偺偱偁傞丅偟偐傞偵枮廈偺愴応偵戝乆揑嶦滳傪峴側偄巒傔偰偐傜暥柧崙偲屇傫偱偄傞丅乭
偲傝傢偗埨攞庱憡傪丄僀僨僆儘僊乕忋丄斵偑婣壔偟偨懢暯梞懳娸偺慶崙偵憲傝弌偟偨屻丄傕偟擔杮偑拑偺搾偵愱擮偟偰偔傟偨側傜丄傾僕傾戝棨偼戝偄偵傛傠偙傇偩傠偆丅
仭
偄偔傜丄堎忢側帠懺傪偰傫偙傕傝偵偟偰洓棟孅傪暲傋偰傕丄強慒偼廆庡崙怤棯愴憟暫鈰妶摦偺堊丄偙傟偐傜悽奅拞偵弌偰備偔丄廆庡崙怤棯愴憟巟墖嶌愴悇恑朄埬丅偆傑偄愢柧側偳偁傝偆傞偼偢偑側偄丅
乽惌晎偼柕弬偺側偄廫暘側愢柧傪偡傋偒偩乿摍偨傢偛偲傪撉傑偝傟偨偔偼側偄丅柕弬偺側偄廫暘側愢柧側偳嬥椫嵺晄壜擻偵寛傑偭偰偄傞丅
慶晝偼埨曐夵掶帪偺戝廜僨儌偺惙傝忋偑傝偱丄帿怑偣偞傞傪摼側偐偭偨丅懛偼丄尨敪帠屘傪傂偒婲偙偟偰偍偄偰丄愑擟傪偲傜偢丄曈栰屆婎抧戝奼挘傪悇恑偟丄TPP偱丄擔杮偺堛椕偐傜丄嫵堢丄岞嫟挷払丄偁傝偲偁傜備傞傕偺傪廆庡崙戝婇嬈偵嵎偟弌偟丄偁偘偔偺壥偰偵丄怤棯愴憟偵孯戉傑偱採嫙偡傞丅偙偺崙偑廔傢傠偆偲偟偰偄傞偺偩丅慶晝偺帪偺壗廫攞傕偺孮廜偑丄楢擔崙夛傪庢傝埻傫偱晄巚媍偼側偄偼偢側偺偩偑丅斵偺尵偆捠傝丄尨敪偱偼側偔丄戝杮塩峀曬晹偑姰慡偵傾儞僟乕僐儞僩儘乕儖偵偁傞偺偱丄埨怱偟偰朶惌偑峴偊傞丅
偄偔傜閤偟偰傕丄晛捠偺尒幆偑偁傟偽丄偙偺崙偑偲傫偱傕側偄丄廆庡崙梡偺偍偲傝僨僐僀偱偁傞偙偲偼捈偖傢偐傞丄偲偄偆椺偑丄偙偺婰帠丅丂
丂 |
| 仭乽嫟嶻庡媊乿偑搼懣偝傟乽柉懓庡媊乿偵帄偭偨拞崙偺晐偝
|
   丂
丂
|
乽1980擭戙丄拞崙嫟嶻搣偼偡偱偵乬攋嶻乭偟偰偄偨乿乗乗偦傫側偙偲傪尵傢傟偨傜丄乽偊偭丄杮摉偐丠乿偲巚傢偢丄帺暘偺栚傪偙偡傞岦偒傕彮側偔側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偟偐傕丄偦傫側婰帠傪宖偘偨偺偑乽挬擔怴暦乿偩偲抦偭偨傜丄偳偆偩傠偆偐丅
崱擔(2寧25擔)丄挬擔怴暦挬姧偺僆僺僯僆儞棑(17柺)偵丄嫽枴怺偄僀儞僞價儏乕婰帠偑宖嵹偝傟偨丅戣偟偰乽拞壺柉懓暅嫽乿丅傾儊儕僇偺暥壔恖椶妛幰丄僷僩儕僢僋丒儖乕僇僗巵(50)偑挬擔怴暦偺庢嵽偵墳偠偰岅偭偨傕偺偩丅巹偼丄偙偺婰帠偑丄偝傑偞傑側堄枴偱嫽枴怺偐偭偨丅
挬擔怴暦偑偙傟傪宖嵹偟偨偙偲帺懱偑偍傕偟傠偐偭偨偟丄1980擭戙偐傜拞崙偵棷妛偟丄挿偔拞壺柉懓偺尋媶傪偮偯偗丄崙嵺嫵堢岎棳嫤媍夛丒杒嫗僙儞僞乕挿傕柋傔傞傾儊儕僇恖尋媶幰偺撈摿偺帇揰偵戝偄偵嫽枴傪嬱偒偨偰傜傟偨偺偩丅
儖乕僇僗巵偺廗嬤暯崙壠庡惾偵懳偡傞暘愅偼儐僯乕僋偩丅偦傟偵傛傞偲丄廗嬤暯偼偙偺20乣30擭偺娫偱丄嵟傕乽柉懓庡媊揑側拞崙偺嵟崅巜摫幰乿偱偁傝丄偦偺棟榑偑乽拞崙偼摿暿偱偁傞乿乽拞崙偺廀梫偼懠幰傛傝戝帠偩乿偲偄偭偨摿挜揑側2偮偐傜乽惉傝棫偭偰偄傞乿偙偲偩偲偄偆丅
廗嬤暯偼丄乽執戝側傞拞壺柉懓偺暅嫽乿傪彞偊丄帺暘偨偪偑楌巎忋桪廏側柉懓偱偁傝丄傾僕傾偺拞怱偩偭偨尦乆偺抧埵偵栠傞丄偲尵偄偨偄偺偩偦偆偩丅偦偺棟榑偺婋尟惈傪儖乕僇僗巵偼丄乽垽崙庡媊偵偼寬峃揑側晹暘傕偁傝丄昁偢偟傕懠幰傪彎偮偗傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄柉懓庡媊偼偦傕偦傕偑嵎暿堄幆偱偁傝丄懠幰傪昁梫偲偡傞丅偦偟偰墲乆偵偟偰偦偺懠幰偵奞傪梌偊傑偡乿偲巜揈偟偰偄傞丅
偮傑傝丄拞崙偺乽柉懓庡媊乿傊偺寈忇偑丄偙偺僀儞僞價儏乕偺妀怱偲尵偊傞丅儖乕僇僗巵偼偦偺忋偱丄乽1980擭戙丄拞崙嫟嶻搣偼乬攋嶻乭偟偨乿偲暘愅偟偰偄傞丅嫟嶻搣偑屇傃偐偗傞嫟嶻庡媊偺僀僨僆儘僊乕傪丄扤傕怣偠側偔側傝丄偦偺偨傔偵丄乽嫟嶻搣偼丄巗柉偺怣擟傪摼傞偨傔丄壗偐怴偨側傕偺傪昁梫偲偟偨乿偲偄偆偺偱偁傞丅
巹偑戝妛帪戙傕娷傔丄枅擭偺傛偆偵拞崙傪朘傟偰偄偨偺偼丄摨偠1980擭戙偺偙偲偱偁傞丅梷埑偲撈嵸偑摿挜偩偭偨拞崙嫟嶻搣偲丄偦傟傪椻傔偨栚偱尒偮傔傞恖柉偺巔偑丄摉帪偺巹偵偼報徾揑偩偭偨丅恖乆偺暔幙揑側梫媮傪枮懌偝偣傞偨傔偵乽夵妚奐曻楬慄乿傪偲偭偨拞崙偼丄摉慠偺婣寢偲偟偰昻晉偺嵎偑奼戝偟偰偄偔丅偦偺崰偺偙偲傪儖乕僇僗巵傕撈摿偺帇揰偱娤嶡偟偰偄偨傛偆偩丅
嫟嶻搣偵偲偭偰丄昻晉偺嵎偑奼戝偡傞偙偲偼杮棃丄嫋偝傟側偄丅尩偟偄梷埑偵傛偭偰偦偺晄枮傪晻偠側偗傟偽丄摑帯偦偺傕偺偑梙傞偓偐偹側偐偭偨丅
嫽枴怺偄偺偼丄儖乕僇僗巵偑偙偺帪揰偱丄乽嫟嶻搣偼朮巕傪曄偊丄儅僗僋傪曄偊傞偙偲偵偟偨丅嫟嶻庡媊偼偄傢偽搼懣偝傟丄柉懓庡媊偑摑帯偵巊傢傟巒傔偨偺偩乿偲暘愅偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅
乽嫟嶻庡媊偺搼懣乿偲乽柉懓庡媊偵傛傞摑帯乿乗乗僀儞僞價儏乕偼丄偦偙偐傜偑偍傕偟傠偄丅儖乕僇僗巵偼丄1995擭慜屻偵巒傑偭偨摉帪偺峕戲柉崙壠庡惾偺垽崙庡媊嫵堢偵偮偄偰丄乽偙偙偱搊応偟偨偺偑乬旐奞幰偺暔岅乭丅偙傟偼嬌傔偰曋棙側傕偺偩偭偨乿偲偟偰偄傞丅偦偙偱乽揋乿偲偟偰搊応偟偨偺偑乽擔杮恖偲丄偦偺怤棯峴堊乿偱偁傝丄乽柉懓庡媊偲嫟偵丄偙偆偟偨乬婰壇乭偑屇傃婲偙偝傟偨乿偲偄偆偺偱偁傞丅
儖乕僇僗巵偼丄栄戲搶帪戙偵偼乽拞壺柉懓偑棫偪忋偑偭偨乬彑棙幰偺暔岅乭乿偩偗偱廫暘偱丄80擭戙傑偱丄乽摑帯幰偼乬旐奞幰偺暔岅乭傪昁梫偲偟側偐偭偨乿偲丄巜揈偟偰偄傞丅偮傑傝丄夵妚奐曻楬慄偵傛傞昻晉偺奼戝偼丄80擭戙偐傜90擭戙偵偐偗偰乬彑棙幰偺暔岅乭偩偗偱偼恖柉傪擺摼偝偣傜傟側偔側傝丄偦偙偵乽柉懓庡媊乿偲偦傟傪曗嫮偡傞乬旐奞幰偺暔岅乭偑昁梫偵側偭偰偄偭偨丄偲偄偆偺偱偁傞丅
栵夘側偺偼丄崱偱偼乽柉懓庡媊偺僷儚乕偑戝偒偔側傝偡偓偰丄僐儞僩儘乕儖偱偒側偄忬嫷乿偑惗偠偰偍傝丄偦偺偨傔偵乽拞崙惌晎偼懳奜揑偵堦悺偨傝偲傕忳傜側偄偲偄偭偨嫮峝巔惃乿傪懕偗偞傞傪摼側偔側偭偰偄傞偙偲偩丄偲儖乕僇僗巵偼尵偆丅乽惌帯偼偍屳偄偵忳曕偡傞傕偺丅偟偐偟丄奜崙恖偵忳曕傪偡傟偽丄惌晎傕斸敾傪柶傟側偔側偭偰偄傞乿偲丄崱偺拞崙偺婋偆偝傪岅傞偺偩丅
巹偼偙偺僀儞僞價儏乕婰帠傪撉傒側偑傜丄1985擭8寧丄偦傟傑偱栤戣偵偝傟偨偙偲傕側偐偭偨乽桋崙嶲攓乿傪恖柉擔曬傑偱乬摦堳乭偟偰奜岎僇乕僪偵巇棫偰忋偘偨挬擔怴暦偺曬摴傪巚偄弌偟偨丅偮傑傝丄乽拞崙偺柉懓庡媊乿傪慀偭偨摉偺挬擔怴暦偑丄偦偺柉懓庡媊傪斸敾偡傞僀儞僞價儏乕婰帠傪宖偘偨偙偲帺懱偑姶奡怺偐偭偨丅
僀儞僞價儏乕傪廔偊偨挬擔怴暦偺拞崙憤嬊挿偼丄婰帠偺嵟屻偵丄乽椬傝崌偆崙偺柉懓庡媊偑屳偄偵巋寖偟崌偆偙偲偼旔偗傜傟側偄丅摨巵偺巜揈偼丄変乆擔杮恖傕傑偨丄柉懓庡媊偺乬晧偺楢嵔乭偺側偐偵偁傞偙偲傪婥偯偐偣偰偔傟傞丅搶傾僕傾偺柉懓庡媊偺奼戝傪梷偊傞偵偼傑偢丄偙偺帺妎偙偦偑媮傔傜傟偰偄傞乿偲彂偄偰偄傞丅
偙傟偵偼丄偝偡偑偵悂偒弌偟偰偟傑偭偨丅偄偐偵傕乽挬擔怴暦傜偟偄乿偲尵偊偽偦偆偩偑丄憡庤偵奜岎僇乕僪傪梌偊偰擔拞偺桭岲娭學傪攋夡偟丄拞崙偺柉懓庡媊戜摢傪懀偡戝偒側栶妱傪壥偨偟偨帺暘帺恎偺憤妵偱偼側偔丄偙傫側乬偍寛傑傝偺寢榑乭偑撍慠丄弌偰偒偨偐傜偩丅
偦傟偼丄偙偺儐僯乕僋側僀儞僞價儏乕婰帠偵偼丄偁傑傝偵晄帡崌偄側傕偺偩偭偨丅乽媑揷挷彂曬摴乿偲乽堅埨晈曬摴乿偵偮偯偒丄乽拞崙曬摴乿偱傕挬擔怴暦偺乬憤妵乭偑巒傑偭偨偺偐丄偲巚偭偨偺偼憗寁偩偭偨丅偩偑丄挬擔傪偼偠傔丄怴暦儊僨傿傾偵偼丄僞僽乕傪嫲傟偢丄懡庬懡條側帇揰傪偙傟偐傜傕丄偳傫偳傫採帵偟偰梸偟偄偲巚偆丅丂2015/2丂
丂 |
| 仭嶰丂棖廎偺乽昐墹堦惄乿榑偲乽墹攅娭學乿榑丂 |
   丂
丂
|
偱偼丄棖廎偼偳偺傛偆偵徏壀暥梇亀恄摴妛懃擔杮嵃亁傪尒偰偄偨偺偩傠偆偐丅
亀棖廎堚峞亁偵偼丄師偺傛偆側堦愡偑婰偝傟偰偄傞丅
乽崰撉怴姧彂丄崋擔杮嵃丄嫗巘恖徧暥梇幰擵強堊栫丅(拞棯)崱梇埲堊変朚恖悇変朚懎丄夗弌搨嬹嶰戙擵忋擵堄丄恄摴壠幰擵巹尵栫丅懘彂戝棯埲昐墹堦悽堊屩挘擵嬶丄埲搨嬹慣忳丄搾晲曻敯丄堊晝巕擵悐丄孨巕擵懐幰丅懘堄旕晄旤栫丄慠晄抦摴丄晄抦揤丄桳強樳帶沔攍鎖帶涍丅梫旔擵壜後丄擳梸梌擵嫮榑懘嬋捈鄟丄懃寵墬旕変崙搣惸廈(拞崙傪巜偡亅昅幰)恇巕擵壜丄晄媂尵後丅悽庲娤崯彂丄猸岥晄曎丄媂後丅慠斾擵暔栁嫧丒懢嵣弮擵搆埲埼嘟懸変崙帺娒幰丄晄壜摨擔帶榑後丅梇枓桳壜娤幰丄慠庩晄抦変崙擵強埲昐墹堦悽丄搙墇枩崙幰丄惃擵強埲慟丄旕崙忢棫強梌栫丅晄慠懃摴嬀丒墴彑擵懏丄姣桳鍼鍻揤埵擵堄嵠丅梋彟挊昐墹堦悽榑徻擵丄屻擵孨巕惪徻鄟丅乿25)
偡側傢偪暥梇偺嬌榑偵懳偟偰丄堦斒偺庲幰偼傒側杮朚寉帇丒拞壺悞攓偺傕偺偲岆夝偝傟傞偙偲傪嫲傟偰斸敾傪峊偊偰偄偨偑丄棖廎偼偦偺晄曃晄搣偺棫応偐傜姼偊偰偙傟傪斸敾偟偨傢偗偱偁傞丅偦偺嵺丄渉渜傊偺斸敾傕堦尵側偝傟偰偄傞偑丄偦傟偼丄暥梇偺擔杮桪墇榑偺傎偆偑渉渜丒弔戜偺擔杮寉曁榑傛傝偼憹偟偩丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦傟偼妋偐偵杮壒偱偼偁傞偑丄懠曽偱偼悽恖偺旕擄偵旛偊偰挘偭偨梊杊慄偱傕偁傞偙偲偑柧傜偐偱丄偟偐傕偦偺拞偵暥梇斸敾偺宊婡傕娷傑傟偰偄傞偺偱偁傞丅棖廎偵傛傟偽丄擔杮桪墇榑偲偄偆偺偼丄渉渜堦棳偺拞壺悞攓丒擔杮寉帇偵懳偡傞恄摴壠偺乽嫺瀅幐捈乿丄偮傑傝嬋偑偭偨傕偺傪捈偦偆偲偟偰丄惓偟偄偲偙傠傪峴偒夁偓偨偙偲偵傛傞傕偺偱偁傞丅26)亀恄摴妛懃擔杮嵃亁偼偙偺傛偆側曃岦偺堦昗杮偲偝傟偰偄傞偑丄摨彂偺岆傝偼乽昐墹堦悽傪埲偰屩挘偺嬶偲堊偟丄搨嬹慣忳丄搾晲曻敯傪埲偰晝巕偺悐傊丄孨巕偺懐傂偲堊偡乿偙偲偵偁傞偲棖廎偑尒敳偄偨丅
偙偙偱偼丄傑偢丄棖廎偺乽昐墹堦惄乿榑偲乽墹攅娭學乿榑傪専摙偟偰傒傛偆丅
乽昐墹堦惄乿栤戣偵偮偄偰丄棖廎偼偨偩乽昐墹堦悽(惄)乿偼乽惃傂偺埲偰慟傓強偵偰丄偄傢備傞崙忢棫偺梌傆傞強偵旕偞傞側傝丅慠傜偞傟偽丄懃偪摴嬀丒(宐旤)墴彑偺懏丄姣偵揤埵傪鍼鍻偡傞怱偁傜傫傗乿偲偟偐榑偠偰偄側偄偑丄偟偐偟丄斵偺斸敾揑帇妏偑偙偺嬌傔偰娙寜側巜揈偵傛偔尰傟偰偄傞偲偄偭偰傛偄丅暥梇偼崙忢棫懜傪揤抧枩崙偺庡嵣恄偲偡傞偲摨帪偵丄乽堦惄埲偰丄柍媷偵揱傊傞乿峜摑偺崻尮偲傕偟偨偑丄棖廎偼偦偺昐墹堦悽偲偄偆尰徾偺宍惉偼乽崙忢棫偺梌傆傞強偵旕乿偢偲偒偭傁傝偲斲掕偟偨丅傑偨丄偄傢備傞乽曮婍堦偨傃掕傝丄墹巕峜懛偦偺埵傪妚傔偢丅恇弾阾柉偦偺怑傪幐偼偢乿偲偄偆偺傕丄巎幚偵斀偡傞恄榖偩偲棖廎偼峫偊偰偄傞丅側偤側傜偽丄楌巎忋丄摴嬀丒宐旤墴彑(摗尨拠杻楥)偺傛偆側棎恇懐巕偑妋偐偵偁偭偨偐傜偱偁傞丅斵偵傛傟偽丄昐墹堦悽偲偄偆尰徾偼乽惃傂偺埲偰慟傓強乿偱偁傝丄偄偄偐偊傟偽丄楌巎偺悇堏偺拞偱宍惉偝傟偨傕偺側偺偱偁傞丅
偱偼丄偙偙偺乽惃傂乿偲偼偳傫側傕偺傪巜偟偰偄傞偺偱偁傠偆偐丅
娵嶳恀抝巵偼丄偐偮偰乽偄偒傎傂乿傪擔杮恖偺楌巎堄幆偺婎掙奣擮偺堦偮偲懆偊丄乽娍岅偺亀惃亁偑擔杮岅偺亀偄偒傎傂亁偲揱摑揑梡朄偵偍偄偰丄傕偭偲傕恊榓惈傪懷傃偨偺偼丄傑偝偟偔亀惃亁偺偙偆偟偨僟僀僫儈僢僋側懁柺偱偁偭偨丅偙偆偟偨堄枴偱偺亀惃亁偑楌巎揑帪娫偺悇堏偵撪嵼偡傞偲娤擮偝傟傞偲偒丄偦偙偵乗 拞崙偺巎彂偱偝偊丄婬偵偟偐巊梡偝傟側偄乗 亀帪惃亁丄埥偼亀揤壓偺戝惃亁偲偄偆奣擮偑丄擔杮偺楌巎堄幆偍傛傃壙抣敾抐偵偍偄偰嬌傔偰棳捠搙偺崅偄斖醗傪宍惉偡傞傛偆偵側傞偺偱偁傞乿偲巜揈偟偰偄傞丅27)棖廎偵偍偗傞乽惃乿偺奣擮傕庡偲偟偰偙偺傛偆側堄枴偁偄偱巊梡偝傟偨偙偲偼丄師偺傛偆側榑弎偐傜塎傢傟傞丅
乽惃丄崯塢埳婔墦斾丄枖塢撨棦丄埳婔墦斾幰堗埿尃栫丄撨棦堗宍忬栫丄崱強埲宍忬尵丅乿
偡側傢偪屓偺偄偆乽惃乿偲偼丄乽埳婔墦斾乿(偄偒偍傂丒埿尃)偺堄枴偱偼側偔丄乽撨棦乿(側傝丒宍忬)偡側傢偪宍惃偺堄枴偱偄偭偰偄傞偙偲傪嫮挷偟偰偄傞傢偗偱偁傞丅
偱偼丄昐墹堦惄偺宍惃偼偳偺傛偆偵宍惉偝傟偰偒偨偺偱偁傠偆偐丅
乽(昐墹堦惄)屌濰峜摽峀戝強抳丄枓惃擵強巊慠丄惃栫幰丄嫤揤堄丄暈柉怱強惗栫丅乿
偙偺朻摢偺乽屌傛傝濰偔丄峜摽峀戝偺抳傞強乿偲偄偆暥復偼丄亀昐墹堦惄榑亁偑乽晻帠忬乿(偮傑傝屆戙拞崙偺恇壓偑枾晻偟偰揤巕偵嵎偟弌偡堄尒彂)偺暥懱偱彂偐傟偨偙偲偵偐偐傢偭偰偄傞偺偱丄幚幙忋戝偟偨堄枴傪帩偨側偄傛偆偵巚傢傟傞偑丄壓偺乽惃側傞傕偺偼丄揤堄偵嫤傂丄柉怱偵暈傂偰惗偢傞強側傝乿偼丄娞怱側偲偙傠偱偁傞丅偲偄偆偺偼丄偦傟偼丄昐墹堦惄偺宍惃偑扨偵堦屄偺弮媞娤揑夁掱偺帺慠揑嶻暔偱偼側偔丄恖娫(屻弎偡傞傛偆偵揤峜丄偲偔偵彨孯傪巜偡)偺堄幆揑嶲梌壓偵揥奐偝傟偨媞娤夁掱偺強嶻偱偁傞偙偲傪柧帵偟偨偐傜偱偁傞丅
怉庤捠桳巵偑丄乽峕屗帪戙偵梡偄傜傟偨亀揤柦亁丒亀揤塣亁丒亀帪塣亁偲偄偆尵梩偼丄恖娫偲偺寢傃晅偒偑梱偐偵嫮偄丅(拞棯)楌巎擣幆偺悽奅偵尰傟傞亀揤柦亁丒亀揤塣亁丒亀帪塣亁偼丄恖娫偵偲偭偰挻墇揑側偄偟奜揑側傕偺偲偄偆傛傝偼丄傓偟傠偁傞帪揰偵偍偗傞恖娫偵偼昁慠揑側偄偟塣柦揑傕偺偲偟偰梌偊傜傟傞偑丄偦傟偼偦傟埲慜偵偍偗傞恖娫偺峴堊偺愊傒廳偹偲偟偰偦偆側傞偺偱偁偭偰丄媷嬌揑偵偼恖娫偑摑屼偱偒傞丄彮側偔偲傕恖堊傪捠偠偰尰傟傞傕偺偵傎偐側傜側偄丅揤柦偼恖怱偵尰傟傞偲偄偆堄枴偼偙偺揰傪抂揑偵帵偡傕偺偲偄偊傛偆乿偲榑偠偰偄傞偑丄棖廎偺強愢傪傒傟偽丄傑偝偵偦偺捠傝偱偁傞丅28)
楌巎偵懄偟偰榑偠傞応崌丄棖廎偼恄晲掗偐傜岶尓掗傑偱偺挿偄娫丄乽墹壔丂恖怱偵煥乿偒偨傔丄慼変壼埼丒擖幁丒摗尨朙惉偍傛傃摴嬀偺傛偆偵乽媡杁乿傪恾偭偰傕偙偲偛偲偔幐攕偵廔傢傝丄暯惔惙丒懌棙媊枮偺傛偆偵愱尃偟偰偄偰傕乽姼傊偰恇埵偵堘偼偢乿偲巜揈偟偨偑丄偟偐偟丄偦偺椡揰偼傓偟傠墹丒攅偺娫偺憡屳埶懚娭學偺廳梫惈偵抲偐傟丄偲傝傢偗廃戙晻寶惂偵偍偗傞墹攅娭學偼堦偮偺戝偒側嫵孭偲偟偰懆偊傜傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅
乽惪埲廃幒歡鄟丄昉惄墹墬惸廈(拞崙傪巜偡乕昅幰)丄揱悽嶰廫丄杕擭敧昐丄瀚惸姾嫮攅丄壓攓忋庴丄晄姼旝愼巜丄懘懠栤揅惪悑丄奆堊尒陎丅橶巊惸晄幐攅嬈丄悢悽擻曭揤巕椷彅岒鄟丄懃恅瀚屨楾丄埨擻暪榋崙丄撣擇廃丅(拞棯)橈巊廃梚嫊婍墬忋丄塱晄憆墹崋墬壓丄墬惀屃昐墹堦惄丄壜婓朷墬廃壠丄惸枓壜昐悽埲攅揤壓丄榋崙擳壜埲塱曐懘晻醖丅惀揤壓戝惃丄旕嬫乆忢嶔強擻媡鍺後丅惀屘惸擵幐攅丄懄廃擵強幐墹栫丄惸擵幐攅丄惃擵嫀栫丅乿
偙偙偵偄偆乽惸姾乿偼丄搶廃偺慜婜偡側傢偪弔廐帪戙偺惸姾岞偱偁傝丄娗拠傪擟梡偟偰夵妚傪椼峴偟丄乽懜墹澋埼乿傪彞偊偰偼偠傔偰惂攅偟偨桳堊偺崙孨偱偁傞丅棖廎偵傛傟偽丄廃偺墹幒偼惸姾岞偲堦庬偺憡屳埶懚娭學偵偁傝丄惸姾岞偼嫮偄偑丄墹埵偵乽愼巜乿偟傛偆偲偼偣偢丄廃墹幒傕偦偺梚岇偱埨掕傪曐偮偙偲偑偱偒丄偦偙偐傜乽惃乿偑惗傑傟偰偒偨傢偗偱偁傞丅傕偟惸偑乽攅嬈傪幐偼偢丄悢悽擻偔揤巕傪曭偠偰彅岒偵椷乿偟丄廃偑乽嫊婍傪忋偵梚偟丄塱偔墹崋傪壓偵憆偼偞傟偽乿丄廃傕昐墹堦惄偺惓摑傪懕偗傜傟偨偼偢偱偁偭偨丅偦偆偩偲偡傟偽丄恅偺榋崙崌暪丄擇廃撣柵偑晄壜擻偲側傝丄恅埲崀偺墹挬峏揜偺昿敪傕桳傝摼側偄偙偲偲側偭偨偼偢偱偁偭偨丅偙偺傛偆偵堦尒偦傟偧傟揔惓偵埵抲晅偗傜傟偰偼偄傞偑丄寢榑揑偵偄偊偽丄偦偺廳怱偼傗偼傝惸崙偺曽偵抲偐傟偨偺偱偁偭偨丅廃偺墹尃傪乽嫊婍乿偲偄偄丄乽惸偺攅傪幐傆偼丄懄偪廃偺墹傪幐傆側傝丄惸偺攅傪幐傆偼丄惃偺嫀傞側傝乿偲偄偆偺偼丄偙偺偙偲傪抂揑偵帵偟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偱偒傛偆丅傑偨丄惸偵懕偄偰攅尃傪埇偭偨怶崙偺峴曽偵偮偄偰偺榑弎丄椺偊偽乽榋嫧乿愱尃傗乽嶰怶乿暘棫偵傛偭偰丄寢嬊惂攅晄擻偲側傝丄乽廃枓偨悘傂偰朣傇乿側偳傕摨條偺孹岦傪昞傢偟偰偄傞丅偟偨偑偮偰丄棖廈偺榑偠傞偲偙傠偺墹攅憡屳埶懚娭學偼攅杮埵偲偟偨傕偺偲尒傜傟傞偺偱偁傞丅
偙偺攅杮埵偺墹攅憡屳埶懚娭學傊偺廳帇偼丄摉戙惌帯偵娭偡傞棖廎偺媍榑偵堦憌柧妋側宍偱昞弌偝傟偨偺偱偁傞丅
乽嵼崱曐惃丄壗堗懃壜丅濰懜墹幒栫丄夰彅岒栫丄嬷挍柉栫丅崯嶰幰丄揤堄擵強梌丄柉怱擵強暈丄帶惃擵強懚栫丅宑尦擵嵺丄搶巘惣惇丄嵞夗岟惉丄孮梇嫇弲懘栺懇丄曵妏宮庱丄奺帺廇斔崙丅墬惀惓嶑庉埵弌槹墹幒丄棙婍枹慡橈恖庣惉丅(拞棯)奀撪濆慠丄奐愮枩擭柍媷懢暯丄幚変朚屆棃擵強柍丄擳戝惃墬惀屃掕丅(偟偐偟丄戝彫岒攲偼)晻撪擵擖丄晄懌埲嫙挬鍾摴楬擵旓丄擳妵柉嵿丅枖嬄媼嶰搒夛晉彜丄悘孹悘巟丅壛埲姱壠搚栘彆栶丄枖曭巊嫗巘丄枖嬂墹巊丄楪媦梎戜丄擳晎屔嬻嫊丄悑帄扗壠恇擵曨彯晄嬷丅垼嵠丅懘嬌昁帄岊柶挬阗丄鋺壜擵丄懃慶朄攑丄晄壜懃柍寁壜弌丅慠廫枩愇埲忋丄桺壜堊擵栫丄屲枩愇埲壓晄壜堊後丅媂愽尛棛恖丄専懘昻晉丄壥昻屃丄埥摿柶堦挬丄尩錃鋼嬛丄晄壽彆栶丄埲槷擵丅懃斔晎忋壓丄鈉摼慼懅丄懻曭帬帄丄墬惀屃戝惃塿掕丅揤壓昁堗丄桞搶徠孨遽帶壜堊彨孯丄桞峕屗壜攅揤壓丅擳廇擻屼擵丄夑嶧瀚戝丄壜埲梵巊丄墱斔瀚嫮丄壜埲曏攚丅曽崱墹攅憡堊怬帟丄壜梌姾暥暪埬丄惃擵強學丄懘戝後嵠丅乿
偮傑傝棖廎偵偟偰尒傟偽丄乽墹幒傪懜傇乿偙偲偼栜榑廳梫偩偑丄摉柺偺枊晎偲挬掛偲偼丄惸姾岞丒怶暥岞偲廃墹幒偲偺娭學偺傛偆偵乽怬帟乿摨慠偺椙岲娭學偵偁傝丄栤戣偼偄偐偵嵿惌擄傪書偊偰偄傞拞彫彅岓偵懳偡傞夰廮嶔(偦偺崲媷搙傪妋偐傔偰偐傜嶲鍾岎戙丒彆栶側偳偺媊柋傪堦帪揑偵柶彍偡傞偙偲側偳)偱恖怱傪廂澁偟丄惃傪曐偭偰偄偔偐偲偄偆偙偲偵偁傞丅偦傟偝偊偆傑偔夝寛偱偒傟偽丄乽戝惃塿乆掕傑傞乿偙偲偵側傝丄壛夑丒嶧杸丒愬戜側偳偺傛偆側奜條戝柤傪偄偮傑偱傕姰慡偵僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偑偱偒傞偵憡堘側偔丄偟偨偑偭偰丄枊晎偺惂攅偵偨傛偭偰偄傞挬掛傕塱懕偱偒傞傢偗偱偁傞丅偙偙偱偼丄枊晎偺惌尃扴摉丄惌嶔塣梡偼庡摫揑丄寛掕揑側傕偺偲偟偰埵抲偯偗傜傟偰偄傞偺偱偁傞丅偦傟偼偲傕偐偔傕丄昐墹堦惄偲偄偆揱摑偺宍惉尨場偵娭偡傞偙偺傛偆側楌巎庡媊丒恖娫拞怱庡媊揑夝庍偼丄暥梇偺恄拞怱(崙忢棫懜偺帓梌)揑夝庍偲偼崻杮偐傜懳棫偡傞傕偺偱偁傞丅丂 |
| 仭巐丂棖廎偺乽搾晲曻敯乿榑偲乽恄庲娭學乿榑丂 |
   丂
丂
|
慜弎偺傛偆偵丄亀恄摴妛懃擔杮嵃亁偵偍偄偰擔杮偺昐墹堦惄偑屩帵偝傟傞偲摨帪偵丄拞崙偺堈惄妚柦丄摿偵搾晲偺曻敯偑寖偟偔攔寕偝傟偨丅偙傟偵懳偡傞棖廎偺斀榑偼傗偼傝楌巎庡媊丒恖娫拞怱庡媊偺棫応偐傜敪偟偨傕偺偲尒傜傟傞丅
椺偊偽丄搾晲偺曻敯偵偮偄偰
乽恖庴揤抧擵拞埲惗丄擳桳奆強埲憡惗憡梴擵摴丅摑棟擵幰丄墹幰栫丅晄慠懃庛擵擏嫮擵怘丄憡憟梇憡撣柵丄惗柉杦煛愨丅惗柉煛愨丄懃揤摴婔屃懅丅曽崯擵帪丄孨恇擵媊堊寉丄搾晲擵強埲曻敯栫丅埼惸瀚尗丄抦恖枹抦揤丄桞抦恖帠丄晄抦惞恖桳嵸惉曘憡擵擟丅愝巊埼惸惀搾晲丄旕屃朶孨媠庡揜婲戙弌丄檣巊埲柵憡惗梴擵摴丄柉娮揾扽擵拞丄柍晄堊暪丄孨恇擵摴朣擵帶涍丄惞恖擵強晄擡嵖帇栫丅(拞棯)晇搾晲壜曻敯丄帶曻敯奆弴揤柦帶涍丅惀埲廃釴敧昐擭丄姾暥嫮攅丄廔慡恇愡丅乿29)
偲偁傞丅偙偺堦愡偼丄搨戙丒娯桗偺亀尨摴亁偵偍偗傞乽屆擵帪丅恖擵奞懡後丅桳惞恖幰棫丅慠屻嫵擵埲憡惗梴擵摴乿傗乽擛屆擵柍惞恖丅恖擵椶柵媣後乿側偳偺榑弎偵傛傞偲偙傠偑彮側偔側偄偑丄偟偐偟丄偨偲偊偽乽嵸惉曘憡乿丄乽曽崯擵帪丄孨恇擵媊堊寉乿側偳偺娤擮偺慻傒擖傟側偳偵帵偝傟偰偄傞傛偆偵丄慡懱偲偟偰偼偦偺乽搾晲乿丒乽埼惸乿榑偺揥奐偺偨傔丄尵偄姺偊傟偽暥梇偵斀敐偡傞偨傔偵峔抸偟偨撈帺偺榑棟峔憿偲偄偊傞丅30)
暥梇偼丄孨恇偺摴傪乽奐钃埲棃乿堦娧偟偰懚嵼偟偰偄傞嵟廳梫側椣忢偲尒側偟偨偺偱丄搾晲偺曻敯傪偦偺椣忢偵攚偔斀媡揑峴堊偲峫偊偰偄偨丅偟偐偟丄棖廎偼乽孨恇偺媊乿偼偙偺傛偆側愭尡揑斖醗偱偼側偔丄楌巎揑偵宍惉偝傟偨傕偺偱偁傝丄忋屆偵偍偄偰偼乽孨恇偺媊乿偼寉偔丄偦傟傛傝傕乽揤柦乿偺弴庣丄乽揤摴乿偺堐帩偺傎偆偑偼傞偐偵廳梫側堄媊傪傕偮傕偺偱偁偭偨偲巜揈偟偰偄傞丅偲偄偆偺偼丄傕偟壞瀧丄彜鉆偑乽惗柉乿偺惗懚傪嫼偐偟偨傛偆側偙偲傪曻擟偡傟偽丄偦偺寢壥丄惗柉偑偙偲偛偲偔愨柵偟丄乽揤摴乿傕懅柵偟偰偄偔壜擻惈偑偁傞偐傜偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄朶孨偺旕摴偐傜惗柉傪庣傞偙偲偼丄摉帪偵偍偗傞嵟戝偺壽戣偱偁傝丄偙偺堄枴偱彜搾偺壞瀧曻敯丒廃晲墹偺彜鉆摙敯偼乽揤柦偵弴傆乿惓媊偺峴堊偱偁偭偰丄偙傟偵懳偟丄偦偺摙敯傪娦巭偟傛偆偲偟偨乽埼惸乿偡側傢偪攲埼丒廸埼偺曽偼乽揤傪抦傜偢乿丄乽惞恖偵嵸惉曘憡偺擟偑桳傞偙偲傪抦傜乿偞傞柍幆尒側傕偺側偺偱偁傞丅偦偟偰丄乽晇隉弚擵慣忳丄搾晲擵曻敯儝揤柦偲塢僼僴丄壗儝徹暥僯僗儖僐僩僝乿偲偄偆暥梇偺丄恄婍揱庼偺娤擮偐傜敪偟偨媗擄偵懳偟丄棖廎偼丄寢壥揑偵廃墹挬偑敧昐擭傕挿懕偒偟丄乽嫮攅乿偺乽姾暥乿偮傑傝惸姾墹丒怶暥岞傕姼偊偰偦偺尃埿偵挧愴偟傛偆偲偼偣偢丄恇偲偟偰愡憖傪慡偆偟偨偙偲偐傜丄廃晲墹偺彜鉆摙敯偼揤柦偵廬偭偨堦斣偺徹嵍偱偁傞偲曎岇偟偨丅31)
偝偰丄偙偺乽搾晲曻敯乿榑偍傛傃忋婰偺乽昐墹堦惄乿榑偲娭楢偟偰丄棖廈偼摨帪戙偺恄庲榑憟偺側偐偱偳偺傛偆側巔惃傪庢偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅庲嫵偺棫応偵偨偭偨恄摴斲掕榑幰偲恄摴偺棫応偵偨偭偨庲嫵斲掕榑幰偺娫偵屓偺埵憡傪帺妎偡傞棖廎偼丄晄曃晄搣偺棫応傪偲偭偰偄偨傛偆偱偁傞丅
慜幰偵偮偄偰偼丄偦偺堦椺偲偟偰丄偨偲偊偽懢嵣弔戜偺師偺傛偆側榑弎偑偁傞偺偱偁傞丅
乽恄摴偼杮惞恖偺摴偺拞偵桳擵岓丄廃堈偵娤揤擵恄摴帶巐帪晄忒丄惞恖埲恄摴愝嫵丄帶揤壓丂暈後偲桳擵丄恄摴偲偄傆偙偲巒偰崯暥偵尒偊岓丅乿
乽擔杮偵偼尦棃摴偲偄傆偙偲柍偔岓丄嬤偒崰恄摴傪愢偔幰偄偐傔偟偔丄変崙偺摴偲偰崅柇側傞條偵怽岓傊嫟丄奆屻悽偵偄傂弌偟偨傞嫊択栂愢偵偰岓丅乿32)
乽擔杮偵偼尦棃摴偲偄傆偙偲柍乿偄偲偄偆榑棟傪傕娷傓堦晹偺庲妛幰偺拞壺桪墇榑偵懳偟偰丄棖廎偼乽嬤悽変朚庲惗丄懡搣懘強嗷丄懜娍埲堊拞壺丄埲変朚堊埼嘟丄湕慠埨擵丄桺晄宧懘恊丄宧懠恖擵椶乿偲偄偆傛偆偵丄恄摴壠偺尵梩傪庁傝偰偺峌寕偝偊偍偙側偭偰偄傞丅33)偟偐偟丄偙偺傛偆側峌寕偼丄斵偑恄摴桪墇偺榑棟偵巀惉偟偰偄偨偙偲傪堄枴偟偰偄傞偺偱偼寛偟偰側偄丅斵偑庲嫵揑晛曊庡媊偺棫応偵偁偭偨偙偲偼丄師偺傛偆側堦愡偵傛偔尰傟偰偄傞丅
乽(恄摴幰棳)嫺瀅幐捈丄鏺尵変朚慺桳恄摴嵼丄汌橈廃岴擵嫵丄懘慠丄姣懘慠屃丅愄幰愭峜揑抦嫵朄暥暔晄擛娍丄擳廋阗搨擵巊丄愝棷妛擵惗丄惞怱岞暯惓戝丄愨柍閬欏懺丅忋媨墹擵嶌寷朄栫丄戝堄庢彅榋宱榑岅丄晄枓媂屃丅晇摴悇曻巐奀帶弨丄恖惈屌柍斵崯擵暿丄玎庴彅揤丅隉弚廃岴丄姣崯堎恖丄屷壗溌嵠丅枩崙暘洺丄奺庡懘庡丄桳柤暘丄桳堦掕擵棟丄晄壜熇棎丅扐惸廈擵钃(惸廈懄娍亅尨暥偺妱拲)愭変丄醖搚枓戝丄晄擻晄悇堊忎恖丄峴惃栫丅屷姣鋺嵠丄娤幃巎擇嶔壜尒丅妿懘抧孮惞宲婲丄廋摴寶嫵丄戝峧嫇枩栚挘丄変朚擵強埲晄媦栫丅慠庒屆庲揟晄峲丄懃昁桳惞揘廝悈搚埲桳惂嶌丄晄搆猸栙嬄懠崙丅晇晄堘堿梲擇棟丄擇懜擵柧夲栫丅隉弚擵摴晄奜堿梲丄壗懡婒擵桳丅庲揟涍峲丄懘摴梌変懎晞丄擳媂桼巤峴鄟丅暅壗庉壩擵梡丅乿34)
偙偺榑弎偵傛傟偽丄乽晇偺摴丄巐奀偵悇偟曻傝偰弨偟丄恖惈屌傛傝斵変偺暿偪柍偟丄玎偟偔揤偵庴偔乿偙偲偐傜丄隉丒弚丒廃丒岴偺傛偆偵擔杮偺乽惞揘乿傕摴傪惂嶌偡傞擻椡偺帩庡偱偁傝丄乽庒偟屆偒庲揟峲傜偞傟偽丄懃偪昁偢惞揘桳傝丄悈搚偵廝傂丄埲偰惂嶌偁傝丄搆偩猸栙偟偰懠崙傪嬄偑偞傞乿偲偄偆偺偱偁傞丅偄偆傑偱傕側偔丄偙偺壖愢偼渉渜偑摴偺嶌幰傪隉丒弚丒鈀丒搾丒暥墹丒晲墹丒廃岞側偳偺幍恖偵尷掕偟偨偙偲傊偺斀榑偱偁傝丄偦偺嫮挷揰偼丄擔杮柉懓偑娍帤丒庲妛偺傛偆側棫攈側暥帤丒嫵愢傪憿傝弌偣側偐偭偨尨場偼丄寛偟偰憂憿椡偵寚偗偰偄偨偙偲偵偁傞偺偱偼側偔丄偨偩偙傟傜傪憿傠偆偲偟偨嵺偵丄愭恑暥壔偺桝擖偵傛偭偰嶌傞昁梫偑側偔側偭偨丄偲偄偆偙偲偵偁傞丅
斀柺丄恄摴壠偺乽変偑朚慺偲恄摴偁傞偙偲桳傝丅汌偔傫偧廃岴偺嫵傊傪橈傜傫傗乿偲偄偆傛偆側嬌榑偵懳偟偰丄棖廎傕斀敐偟丄偙傟傪乽閬欏懺乿偮傑傝偍偛傝偱傗傇偝偐側廥懺偲偟偰愃偗偨丅偦偺榑朄偵傛傟偽丄拞崙偺乽钃偒丄変偵愭傫偠丄醖搚枓偨戝側傝乿丄乽孮惞乿偺偨偰偨摴傗嫵偊傕乽変偑朚偺媦偽偞傞乿偲偙傠偱偁傝丄乽愭峜丂揑傜偐偵嫵朄丒暥暔丂娍偵擛偐偞傞偙偲傪抦傝丄擳偪搨偵阗傆偺巊傪廋傔丄棷妛偺惗傪愝偔乿丄乽忋媨墹偺寷朄傪嶌傞傗丄戝堄丂榋宱丒榑岅偵庢傞乿偺偱偁傞偲偄偆丅
偙偙偱偼丄偄偔偮偐偺億僀儞僩偵拲栚偡傞昁梫偑偁傞丅傑偢丄偦偺乽愭峜乿偺乽惞怱乿偑乽岞暯惓戝乿偲偄偆敾抐偱偁傞丅偮傑傝尛銨巊丒尛搨巊偺攈尛傪摉帪偺揤峜偺峀偄帇栰偲書夰偺斀塮偲偟偰丄奜棃暥壔傊偺偁傞傋偒巔惃傪採帵偟偨偙偲偱偁傞丅師偵丄偦偺惞摽懢巕偺昡壙偺暘楐偱偁傞丅偡側傢偪懢巕偺暓嫵彞摴側偳偵懳偟偰埆昡傪梌偊偨棖廎偑丄偙偙偱偼偦偺乽榋宱丒榑岅乿偵傕偲偯偄偨乽廫幍忦寷朄乿偺嶌惉(戞擇忦偺乽撃宧嶰曮乿傪彍偄偨偙偲偼忋弎偺捠傝偱偁傞)偵岲昡傪婑偣偨偺偱偁傞丅偦偟偰丄嫽枴怺偄偙偲偵丄堦晹偺庲妛幰偺拞壺悞攓傪斸敾偟偨偲偒偵巊傢傟偨丄乽恖惈屌傛傝斵崯偺暿偪柍偟丄玎偟偔揤偵庴偔乿偲偄偆庲嫵揑晛曊庡媊偺榑棟偼丄偙偙偱堦揮偟偰偦偺恄摴壠斸敾偺榑嫆偲傕側偭偰偄傞偺偱偁傞丅擔杮恖偲惈幙忋堎側傞偙偲偺側偄嬆丒弚丒廃岴偲偄偆拞崙偺愭惞偑嶌偭偨嫵偊傗摴偼丄乽変偑懎偵晞傆乿丄擇懜偺乽堿梲擇棟偵堘偼偢乿偲偄偆乽柧夲乿偵傕崌偆偺偱偁傞偐傜丄偙傟傪棙梡偟偰傕傛偔丄昁偢偟傕偙偺堎崙偺摴傪攔愃偟丄栰尨偵堦偐傜摴傪奐戱偡傞昁梫偼側偄丄偲棖廎偼偄偆偺偱偁傞丅
暥梇偑亀恄摴妛懃擔杮嵃亁偺枛旜偵丄孨恇摴偲偟偰偺恄摴傪乽曭儖儓儕奜丄変崙僯惗儗僔恖僲嵃僴僫僉僴僤栫丅屷忢僯崯摴僯巙僗恖僯丄扅崯擔杮嵃儝幐僸嬍僼僫僩丄僸僞僗儔僯嫵儖僴崯屘栫乿偲嫮挷偟偰偄傞丅偙傟偵偮偄偰丄棖廎偼丄偦偺撉屻姶偺側偐偱乽擔杮嵃幰丄弌尮岅壋彈曆丄懘尵濰丄戝掞恖埲嵥妛堊杮丄帿憯堊枛丄擳擔杮嵃擵梡墬悽桳梋桽丄惀愭掗擵強埲嫵岝(尮巵亅昅幰)栫丄堗恖怱帶涍乿偲丄乽恖怱乿(亖椙幆)偵偐偊偰恄摴傊偺柪怣傪乽擔杮嵃乿偺撪梕偲偡傞暥梇偺嬋夝傪嫮偔旕擄偟偨丅35)棖廎偺偙偺夝庍偼丄乽桺丄嵥傪杮偲偟偰偙偦丄戝榓嵃偺悽偵梡傂傜傞乀曽傕丄嫮偆帢傜傔乿偲偄偆亀尮巵暔岅亁乽壋彈乿曆偺暥復偵婎偯偄偰偄傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅36)偦偺拞偺乽嵥乿偼丄捠忢妛栤偲偔偵娍妛偲棟夝偝傟偰偄傞偑丄偙偙偱偼丄棖廎偼乽嵥乿偲乽戝榓嵃乿偲偺娭學偵偮偄偰偼榑偠側偐偭偨丅偟偐偟丄偦偺亀彸惞曆亁偵偍偄偰偼娭楢榑弎偑偁傞偺偱丄偙偙偱徯夘偟偰偍偒偨偄丅
乽梋昁偟傕暓傪偄偲偼偡丅偨偩傕傠偙偟偵偰丅巒傔偰憁偲側傞幰丅栟偵偔傓傊偟丅(拞棯)榘偺墿弶擭拞偵丅拞崙偺恖偼偟傔偰憁偲側傝偲尒偨傝丅傢偐崙偺摴傪偟傜偡偟偰丅懠崙偺朄傪傛偟偲偍傕傊傞幰丅愭栂恖偲偄傆傊偟丅傢偐擔杮偼丅恄偺摴偵悘傆傪傕偰傛偟偲偡丅慠傞偵丅懘嫵朄偺瀶栚偄傑偩嬶偼偸撪偵丅傕傠偙偟偺宱揟傢偨傝偨傝丅変摴偲偄傆偼丅埳淨戻懜堿梲偺偙偲傢傝偵廬偼偣媼傂偟傛傝丅崙偺儈偼偟傜偨偪偼偟傔偨傝丅傕傠偙偟偺摴傕堿梲偺奜側傜偹僴丅傢偐崙偺晽偵偐側傂偨傝丅備傊偵愭戙掗墹懘瀶栚偵傛傝偰丅偙傟傪梡傂媼傊傝丅偝傟偲丅恖偼擔杮偺恖丅尮偟傕偺偐偨傝偵偄傊傞丅傗傑偲偨傑偟傤偺偁傟僴丅帠偙偲偵傕傠偙偟偺擛偔偵偣傫偲偼偟媼偼偡丅揤巕惄傪偐傆傞側偳丅擔杮偺晽側傜偸備傊丅傪偺偮偐傜懘偙偲側偟丅乿37)
丂 |
| 仭偍傢傝偵丂 |
   丂
丂
|
朻摢偱弎傋偨傛偆偵丄棖廎偺亀昐墹堦惄榑亁偵尰傟偰偄傞偺偼丄庲嫵揑晛曊庡媊偲乽戝媊柤暘乿娤擮傪椉棫偝偣偨僶儔儞僗姶妎丄乽揤峜恄奿壔乿偲乽擔杮撈慞榑乿偲偄偆旕棟惈揑孹岦偵帟巭傔傪妡偗傛偆偲偟偨桬婥丄偍傛傃挬枊娭學偲枊斔娭學傪埨掕壔偝偣傞偨傔偺惌帯抦宐偱偁傞丅偙偺傛偆側僶儔儞僗姶妎丄桬婥偲抦宐偼斵屄恖偺暆峀偄妛怋偲怺偄幆尒偺帓暔偱偁傞偩偗偱側偔丄夰摽摪偲偄偆妛峑偺惈奿傗偦偺抲偐傟偨幮夛宱嵪揑丒妛弍暥壔揑娐嫬偺強嶻偱傕偁傞偲偄偊傞丅挰恖偺嵿椡偵埶懚偟丄枊晎偺姱嫋傕摼偨夰摽摪偼丄岞媀偲偼堦庬偺晄懄晄棧偺娭學偵偁偭偨丅偦偟偰丄揱摑揑側惌帯丒暥壔偺庱晎偱偁傞嫗搒偲傕怴嫽偺惌帯丒暥壔偺拞怱偱偁傞峕屗偲傕棧傟偰偄傞戝嶃偺抧棟揑埵抲偍傛傃偦偺宱嵪丒憜塣偵偍偗傞拞怱揑抧埵傕丄摨妛攈偺尰幚庡媊偺敪憐傗帺桼側敪尵傪壜擻偵偟偨丅
棖廎偺妛栤偲惌帯巚憐偺摿幙傪嵺棫偨偣傞偨傔偵丄杮峞偼庡偲偟偰恄摴壠徏壀暥梇偺強榑傪庢傝忋偘偨偑丄帠幚丄偙偺傛偆側斸敾傗斀榑偼摉帪偵偍偄偰懡偔峴傢傟偰偄偨丅偡偱偵棖廎偺惗擭偵偁偨傞1697(尦榎10)擭偵丄嶈栧偺恄庲寭妛幰梀嵅栘嵵(1658‒1734)偲丄栘(栘壓弴埩)栧偺庲妛幰幒數憙(1658‒1734)偲偄偆摨帪戙恖偺娫偵恄庲榑憟偑偍偙偭偨偑丄椉幰偺娫偺墲暅彂娙偼丄亀恄庲栤摎亁(堦柤偼亀恖暔榑亁)偲偄偆彂暔偵傑偲傑傝丄庡偵悅壛偺摨栧丄偲傝傢偗徏壀暥梇側偳偵傛偭偰揮幨偝傟丄悽偵抦傜傟傞傛偆偵側偭偨丅偦偺拞偱丄擔杮偵偼巐彂榋宱偺擛偒傕偺偑側偔丄楃妝孻惌丒揟復暥暔側偳拞崙惞恖偺朄偵傑偨側偄傕偺偼側偄偲偄偆數憙偺恄摴斲掕榑偵懳偟丄栘嵵偼丄変崙偼乽晽壔擵奐栫嵟抶乿丄偐偮堦墹堦摑偺惌帯側傞屘丄楃妝丒惂搙傪棫偰傞偵媯乆偨傜偢丄拞悽埲屻堎朚偲岎捠偡傞偵媦傃丄惂搙偺嵦傞傋偒傕偺傪梡偄丄乽帺壠惂嶌擵斚楯乿傪徣偄偨偑丄栜榑恄楈偺変崙偱偁傞偐傜丄斵崙偺朄傪嵦梡偟側偔偰傕丄帪傪懸偰偽帺傜惉廇偡傞偺偼摉慠偱偁傞偲榑偠偰偄傞丅38)偙偺栘嵵偲數憙偺榑曎偵偮偄偰丄拞堜抾嶳偼榑偠偨偙偲偑偁傞丅乽數憙僲暥帤儌昁桧僴峕屗孥洖儓儕弌僥丄墹幒儝栚忋僲釒僩僗儖僫儕丄嶳嶈壠僲恄摴儝嶨僼儖僴嫗孥洖僯僥丄晲壠儝旜戝僲惃僩僗儖僫儕丄徫僼儀僉僐僩僫儕丅幒巵丒梀嵅巵悢曉墲暅僲曎榑儌丄憃曽僣儛僯孥洖孉拞儝扙弌僙僘丄扸僘儖僯梋儕傾儖僐僩僫儔僘儎丅憤僕僥妛幰僲岞暯惓戝僲媍榑儝棫儞僯丄孥洖曃悳僲嵐懣僯媦僽僐僩僴傾儖儅僕僉僐僩僫儕丅僜僲忋杴僜変朚僯傾儖恖丄扤僇愮嵹堦墹僲戲儝嬄僈僓儔儞丄杴僜崱僲悽僯傾儖恖丄扤僇屼摉壠汅悽僲棽帯儝懻僇僓儔儞乿偲丅39)棖廎偺棫応偲榑挷傪宲彸偟偨抾嶳偺柺栚偑桇慠偲偟偰偄傞偲偄偊傛偆丅
偵傕偐偐傢傜偢丄乽巕惗杮挬丄挿杮挬丄帶晄曭恄摴丄廬奜崙廃岴擵嫵丄壗栫乿40)偲敆傞嬤悽偺崙悎庡媊傗僫僔儑僫儕僘儉偺晽挭偵懳張偡傞偙偲偼丄棖廎偑恎傪傕偭偰帵偟偰偔傟偨傛偆偵丄寛偟偰梕堈側偙偲偱偼側偄丅偙偺傛偆側晽挭偼丄嬤戙偵偍偄偰傕搙乆嵞惗嶻偝傟偰偄偨丅柧帯婜偺撪懞帠審偼慜弎偺偲偍傝偱偁傞偑丄徍榓愴慜婜偺偦傟偵偮偄偰丄娵嶳恀抝偼埮嵵妛攈傪暘愅偟偨嵺偵丄乽擔杮恖偲偟偰擔杮偺摴傪朰傟偰亀堎崙偺嫵亁偵廬偆偺偼丄晄拤晄岶偺亀堎朚恖亁偱偁傞偲偄偆岅挷偼丄幚偼偮偄偙偺娫傑偱傢傟傢傟偺廃埻偵寲乆殢乆偲柭傝傢偨偭偰偄偨嬁偒偱偁偭偨乿偲巜揈偟偰偄傞丅41)擔杮偵尷傜偢丄愴屻偺乽嵔崙乿忬懺壓偺拞崙偱傕丄帡偨傛偆側斶寑傕懡偔敪惗偟偨丅寛偟偰朰傟偰偼偄偗側偄嫵孭偱偁傞丅
仭
1) 摡摽柉乽嫵堢廆嫵徴撍榑憟偺攚宨偵懳偡傞嵞峫乗 堜忋揘師榊偺亀宧塅暥廤亁斸昡傪庤偑偐傝偵乿丄屷嵢廳擇丒墿弐寙曇亀崙嵺僔儞億僕僂儉丂搶傾僕傾悽奅偲庲嫵亁強廂(搶曽彂揦丄2005擭3 寧)傪嶲徠偝傟偨偄丅
2) 摽晉慼曯亀嬤悽擔杮崙柉巎丒曮楋柧榓曆亁(柉桭幮丄1936擭晛媦斉)嶲徠丅摨彂偼乽戝媊柤暘榑乿偺弌尰傪丄拞壺悞攓偺孹岦傪桳偡傞乽渉渜妛偺煀堨乿偵懳偡傞斀摦偲懆偊偰偄傞(118‒119暸)丅偙偺揰偵偮偄偰丄杮峞偱庢傝忋偘偨棖廎偺媍榑傕偦偺棤偯偗偲側偭偰偄傞丅嵟嬤丄慜揷曌巵偑乽嬤悽揤峜尃埿偺晜忋乿偺尨場傪丄庡偲偟偰尦榎婜埲崀偺彜昳壿暭宱嵪偺恑揥偱媷朢壔偟偨恖乆偑恄摴傗崙妛側偳偺攠夘傪捠偠偰惛恄揑側媬嵪庡傪媮傔偨寢壥偲暘愅偟偰偄傞丅亀暫妛偲庨巕妛丒棖妛丒崙妛乗 嬤戙擔杮巚憐巎偺峔恾亁戞巐復(暯杴幮丄2006擭)丅摨帪戙偵偍偗傞崙悎庡媊揑孹岦偼丄偍偦傜偔偙偺椉柺偐傜峫嶡偟偰偼偠傔偰慡懱憸傪攃埇偱偒傞偩傠偆丅
3) 亀棖廎堚峞亁(戝嶃晎棫拞擵搰恾彂娰強憼)忋姫丄屲幍挌丅嬪撉揰偼昅幰偵傛傞丅偙偙偱偼乽昐墹堦惄乿偲偼偡側傢偪昐墹堦宯丄偄傢備傞乽枩悽堦宯乿偲摨偠堄枴偱偁傞丅応崌偵傛偭偰丄棖廎偼乽昐墹堦悽乿偲傕偄偆偑丄偦偺堄枴傕乽昐墹堦惄乿偲摨偠偱偁傞丅彅嫶揙師亀戝娍榓帿揟亁偵傛傟偽丄乽堦悽乿偺堄枴偺堦偮偼乽堦墹挬偺偮偯偔娫丅枖丄堦寣摑偺偮偯偔娫乿偱偁傝丄偦偺弌揟偼庨巕偺亀榑岅廤拲亁偵偍偗傞乽墹幰堈惄庴柦堊堦悽乿偵偁傞丅傑偨乽昐墹乿偵偮偄偰丄亀恄峜惓摑婰亁偵偍偗傞乽昐墹乿巚憐偵娭偡傞愇栄拤巵偺暘愅(亀擔杮巚憐榑憟巎亁丄傌傝偐傫幮丄1979擭丄73暸)傪嶲徠丅
4) 屲堜棖廎乽憲埨払惛塸擛峕搒彉乿丄摨拲3 )丄壓姫丄擇巐亅擇屲挌丅
5) 摨拲3 )丄忋姫丄嶰乑挌丅
6) 戝嶃戝妛崙暥妛尋媶幒亀岅暥亁戞廫廠丄1954擭1 寧丅
7) 拞懞岾旻乽屲堜棖廎偺暥妛娤乿丄亀拞懞岾旻挊弎廤亁戞堦姫(拞墰岞榑幮丄1982擭)強廂丅
8) 惣懞帪旻曇亀棖廎洫榖亁(徏懞暥奀摪丄1911擭)忋姫丄擇嬨挌丅
9) 屲堜棖廎乽寋榏曆乿(夰摽摪暥屔杮)姫堦強廂丅
10) 戝寧柧乽屲堜帩尙偺妛栤偲巚憐偵娭偡傞庒姳偺峫嶡乿丄摨亀嬤悽擔杮偺庲妛偲梞妛亁(巚暥妕弌斉丄1988擭)強廂丄16暸丅
11) 屲堜帩尙亀恄摴堚彂亁丄戝嶃晎棫拞擵搰恾彂娰強憼丅堷梡偺嵺丄戝寧柧巵偺東帤(摨拲10)傪嶲徠偟偨丅
12) 屲堜棖廎亀擔杮彂婭恄戙姫島媊亁(戝嶃晎棫拞擵搰恾彂娰憼)丄嶰挌丅尨暥偵偼撉揰偑側偄偺偱丄堷梡偺嵺丄昅幰偑揔媂巤偟偨丅
13) 摨拲12)丄嬨亅廫挌丅
14) 杮揷嵪栿拲亀堈亁(拞崙屆揟慖丄挬擔怴暦幮丄1966擭)丄97亅98暸丅
15) 暯廳摴乽嬤悽偺恄摴巚憐乿(娾攇彂揦亀擔杮巚憐戝宯39亁強廂)丄545暸丅
16) 摨拲12)丄廫敧亅廫嬨挌丅
17) 嶳嶈埮嵵乽恄戙姫島媊乿(娾攇亀擔杮巚憐戝宯39亁強廂)丄162暸丅側偍丄嬍栘惓塸偺愢偼扟愳巑惔亀擔杮彂婭捠徹丒堦亁(椪愳彂揦丄1978擭)丄189暸嶲徠丅
18) 摨拲12)丄壓嶜丄堦亅擇挌丅
19) 亀擔杮彂婭恄戙島弎玮亁丄亀恄摴戝宯亁(榑愢曇幍丒埳惃恄摴壓)(摨曇櫽夛敪峴丄1982擭)丄272暸丄321暸丅
20) 摡摽柉乽娷悏摪偺恆摴娤偲屆媊妛乗 懌戙峅摴偲搚嫶廆怣傪拞怱偵乗 乿亀夰摽亁65崋丄1996擭丅摡摽柉亀擔杮娍妛巚憐巎榑乗 渉渜丒拠婎偍傛傃嬤戙乗 亁(娭惣戝妛弌斉晹丄1999擭3 寧)偵傕廂榐丅
21) 彫椦寬嶰亀悅壛恄摴偺尋媶亁(帄暥摪丄1940擭)丄403亅410暸丅暯廳摴乽嬤悽偺恄摴巚憐乿丄摨拲15)丄555亅556暸丅
22) 摨拲21)丄412丄414暸丅媑嶈媣乽徏壀拠椙偺栧恖曤乗 嫗搒戝妛憼亀熡惉摪栧恖柤曤亁乗 乿(亀恄摴巎尋媶亁21姫6 崋)丅
23) 徏壀梇暎亀恄摴妛懃擔杮嵃亁(亀擔杮巚憐戝宯39亁強廂)丄258暸丄252暸丅摨妛懃偼杮暥偲栤摎偺擇晹偐傜側偭偰偄傞丅埲壓偺娭楢堷梡傕偙傟偵傛傞偺偱丄昁梫側尷傝偟偐拲婰偟側偄偙偲偵偟偨丅側偍丄彫椦寬嶰乽摱栔擖妛栧偺尋媶丒忋乿偵偍偗傞乽妛懃偲偼壗偐乗 渉渜妛懃偲擔杮妛懃偲偺斾妑乗 乿偲偄偆愡(亀恄摴巎尋媶亁19姫3 崋)傪嶲徠丅
24) 摨拲23)丄260暸丅側偍丄454暸曗拲乽恄膺乿忦傪嶲徠丅
25) 摨拲3 )丄敧堦亅敧擇挌丅
26) 摨拲3 )丄屲嬨挌丅
27) 娵嶳恀抝乽楌巎堄幆偺亀屆憌亁乿(亀楌巎巚憐廤亁丄拀杸彂朳丄1972擭)強廂丄26暸丅
28) 怉庤捠桳乽峕屗帪戙偺楌巎堄幆乿丄摨拲27)亀楌巎巚憐廤亁強廂丄79暸丅
29) 摨拲3 )丄敧擇挌丅
30) 娯桗乽尨摴乿(惔悈栁栿拲亀搨憊敧壠暥丒忋亁(挬擔怴暦幮丄1966擭)強廂丄214‒220暸丅
31) 峕屗帪戙偵偍偗傞乽曻敯乿榑偲乽妚柦乿榑偵娭偟偰丄堖妢埨婌亀嬤悽庲妛巚憐巎尋媶亁(朄惌戝妛弌斉嬊丄1976擭)戞擇復戞擇愡偺乽搾晲曻敯榑乿丄娵嶳恀抝乽埮嵵妛偲埮嵵妛攈乿(亀擔杮巚憐戝宯31亁強廂)丄栰岥晲旻亀墹摴偲妚柦偺娫乗 擔杮巚憐偲栃巕栤戣乗 亁(拀杸彂朳丄1986擭)側偳傪嶲徠丅
32) 摨拲21)丄38暸丄42暸丅
33) 摨拲3 )丄屲嬨挌丅偙傟偼丄嵅摗捈曽乽摙榑昅婰乿(亀嵅摗捈曽慡廤亁強廂丄擔杮屆揟妛夛丄1941擭丄12暸)偵揱傢偭偰偄傞師偺傛偆側恄摴壠偺榑挷傪堦晹庁梡偟偨偲尒傜傟傞丅擔杮帺恄戙埲棃丅桳摴摑擵揱丅帶懘揱庼旈愢丅嶶尒槹恄戙姫丅拞恇釶丅媦彅壠揱婰丅帺庲妛惙峴丅変恄摴擵媊丅崿嶨帶晄柧丅恟懃愱廬墬庲嫵丅怣阤怘擵搆丅攚変恄崙擵嫵丅晄抦懜曭恄幮幰丅墲乆桳擵丅晇惗槹変崙丅帶懜堎朚擵摴丅桺晄宧懘恊丅帶宧懠恖丅朰恄柧擵壎丅幐孨恇擵媊丅晄岶晄拤丅敎夁墬崯後丅岵懍夵帶斀懘杮屃丅
34) 摨拲3 )丄屲嬨挌丅
35) 摨拲3 )丄敧堦挌丅
36) 亀尮巵暔岅丒擇亁(娾攇彂揦亀擔杮屆揟暥妛戝宯15亁)丄277丄460暸丅
37) 屲堜棖廎亀彸惞曆亁(夰摽摪暥屔強廂)忋姫丄擇嬨挌丅
38) 暯廳摴乽悅壛妛幰偲偟偰偺梀嵅栘嵵乿(摨亀嬤悽擔杮巚憐巎尋媶亁媑愳峅暥娰丄1969擭強廂)丄282丄236乣237暸丅
39) 拞堜抾嶳乽摎戝幒戞堦彂乿丄亀抾嶳崙帤喁亁壓姫強廂丅棖廎偼嶈栧偺孨恇娭學榑偺幚幙偵偮偄偰師偺傛偆偵巜揈偟偨偙偲偑偁傞(亀奲怺榐亁巐巐乣巐屲挌)丅嶳嶈愭惗恄摴儝庡挘僗儖僯栿傾儕丅岴巕亀弔廐亁傪弎僥丄旝乆僞儖廃墹儝懜悞僔僥丄孨恇僲柤暘儝惓僗丅嶳嶈愭惗崯堄僯廬僸丄擔杮僲揤峜僴昐墹堦悽僲恄懛僫儖帠儝揤壓僲恖僯抦儔僔儊丄揤峜儝懜悞僔僥孨恇僲暘儝惓僗堄栫丄懘屻鉊嵵愭惗亀桋專榐亁儝挊弎僔僥丄屆愄僲拤怣僲恖儝嫇儔儗僞儕丄僐儗枖嶳嶈愭惗僩懘庢儖檤僴堘僿僩儌丄拤怣僲恖儝嫇僥孨恇僲暘儝惓僔僥丄揤峜儝懜悞僗儖僲堄僴堦僣栫丄孖嶳愭惗僲亀曐寶戝婰亁儝挊弎僗儖儌丄枖摨堦堄栫丅庨巕僴峧栚僯僥惓摑晄惓摑儝惓僒儖丅
40) 偙偺愝栤偼丄屲堜棖廎亀寋榏曆亁(戝嶃戝妛夰摽摪暥屔強憼)姫堦強廂偺恄摴斸敾偺戝峧亀廫栵榑亁偺朻摢偵偁傞傕偺偱偁傝丄拲33)偵堷梡偺嵅摗捈曽偺暥復傪嶲徠偝傟偨偲尒傜傟傞丅嬪撉揰偼昅幰偑揔媂巤偟偨丅側偍丄戝嶃晎棫拞擵搰恾彂娰強憼亀寋榏曆亁(亀屲堜棖廎堚峞丂堧亁)姫堦強廂偺亀廫栵榑亁傪嶲徠偟偨丅
41) 娵嶳恀抝乽埮嵵妛偲埮嵵妛攈乿丄娾攇彂揦亀擔杮巚憐戝宯31亁強廂丄630暸丅丂
丂 |
| 仭巙夑廳偵偍偗傞崙悎庡媊偺娤擮 / 丂奣擮偺椉媊惈偲榑棟偺崿棎 |
   丂
丂
|
|
仭彉榑丂 |
巙夑廳偺巚憐偺慡懱憸偵偮偄偰偼偡偱偵壗搙偐庢傝忋偘偰偒偨偑(1)丄偦傟傜傪傕偲偵杮峞偼斵偺崙悎庡媊偺娤擮偵偮偄偰偁傜偨傔偰嵞峔惉丒榑昡偟偨傕偺偱偁傞丅巙夑偺崙悎庡媊偼偐側傝壙抣偺偁傞庡挘傪娷傫偱偄傞偑丄斵帺恎偑奣擮惈傗榑棟惈偵庛偄偙偲丄傑偨丄杮暔偺揱摑庡媊幰偱側偐偭偨偙偲偑戝偒側尨場偲側偭偰丄廫暘偵揥奐偟偒傟側偐偭偨丅偙偆偄偆揰偵拲堄偟側偑傜丄斵偺崙悎庡媊傪嵞峔惉偟偰傒傞丅
仭
(1)愘峞乽崙悎庡媊偺忦審乗巙夑廳偺巚憐乿(亀柤屆壆妛堾戝妛尋媶擭曬亁10丄1997擭12寧)丄摨乽崙悎庡媊偺惉棫忦審乗巙夑廳偲嶰戭愥椾乿(亀柤屆壆妛堾戝妛尋媶擭曬亁12丄 1999擭12寧)丄摨乽巙夑廳偺崙悎庡媊乿(亀柤屆壆妛堾戝妛尋媶擭曬亁13丄 2000擭12寧)丄摨乽巙夑廳偺曐庣庡媊乗娵嶳恀抝偺棨愎撿榑偲偺娭學偱乿(亀柤屆壆妛堾戝妛尋媶擭曬亁15丄 2002擭12寧)丄摨乽巙夑廳偺巚憐乗崙悎庡媊埲崀乿(亀柤屆壆妛堾戝妛尋媶擭曬亁16丄2003 擭12 寧)丄摨乽嶰戭愥偺崙悎庡媊乗巙夑廳偲懳斾偟偰乿(亀柤屆壆妛堾戝妛尋媶擭曬亁17丄2004擭12寧)丄摨乽擔杮偵偍偗傞揱摑宆曐庣庡媊偼偄偐偵偟偰壜擻偐乗巙夑廳偲偺娭楢偱(忋)乿(亀柤屆壆妛堾戝妛榑廤(幮夛壢妛曇)亁戞巐嶰姫戞巐崋丄2007擭3寧)丄摨乽擔杮偵偍偗傞揱摑宆曐庣庡媊偼偄偐偵偟偰壜擻偐乗巙夑廳偲偺娭楢偱(壓)乿(亀柤屆壆妛堾戝妛榑廤(幮夛壢妛曇)亁戞巐巐姫戞堦崋丄2007擭7寧)側偳傪嶲徠丅丂 |
| 仭堦丂旤偲偟偰偺揱摑丂 |
   丂
丂
|
巙夑偼亀撿梞帪帠亁偱堦桇榑抎偺拲栚傪梺傃傞傛偆偵側偭偨偁偲丄惌嫵幮偱崙悎庡媊傪彞偊傞慜偵亀崙柉擵桭亁戞堦乑崋偵乽擛壗僯僔僥擔杮崙儝(僔僥)擔杮崙僞儔僔儉壜僉儎乿(柧帯擇乑擭堦乑寧)偲偄偆榑暥傪婑偣偰偄傞丅偙傟偼彫榑偱偼偁傞偑丄斵偑偺偪偵尵偆乽崙悎巪媊乿(崙悎庡媊)乗乽崙悎巪媊乿偲偄偆尵梩帺懱偼傑偩巊偭偰偄側偄偑乗偺庡挘傪傑偲傑偭偨宍偱昞柧偟偨嵟弶偺傕偺偱偁傝丄傑偨丄揱摑傪傔偖傞嬯擸偑惓捈偵弌偰偄偰拲栚偝傟傞丅
傑偢丄巙夑偼偙偺彫榑偺朻摢偱擔杮偲偼側偵偐丄擔杮偺屌桳偺傕偺偲偼側偵偐偵偮偄偰丄偦傟偼旤偟偄晽搚偱偁傞偲柧妋偵摎偊偰偄傞丅
乽栱朷堦怓弔奀僲擛僋丄枮濻僲嶗庽僴峠敀擹扺憡岎儕僥暣斺僔湌僩僔僥嵺奤僫僉張丄夛儅壴涰僲寚僞儖娫儓儕晣梪曯摢儝朷儈丄愮樋僲妜忋挬彨僯徃儔儞僩僔僥敿揤峠儝敪僔丄慚乆唷乆僩僔僥搶奀僲攇摀曽僒僯怓儝曄僔墕塮埶婬僩僔僥慟僋墦僉僯愙僗儖僲晽怓儝忷朷僗儗僶丄墿恛懲棥僯杬憱僔丄墿嬥桞惀儗悞攓僗儖柍忣椻扺僫儖峴彜僩瀚儌丄桺妿儝掆儊僥鏢鏞僔丄妎僿僘乽欆歭旤僫儖晽怓僫儖嵠丄昐枩僲墿嬥僯儌姺傊擄僔乿僩扸徿僗儖僐僩僫儔儞丄帶僔僥崯壴僴擔杮屌桳僲儌僲僫儕丄崯嶳僴擔杮屌桳僲儌僲僫儕丄崯悈僴擔杮屌桳僲儌僲僫儕僩抦椆僗儗僶丄扤儗僇擔杮晽搚僲桪旤僫儖儝扱徿僙僓儖儌僲傾儔儞儎丄嫷儞儎擔杮僲搚抧僯惗儗僞儖戝榓柉懓儝儎丄強堗乽晘搰偺戝榓怱傪恖栤偼乁丄挬擔偵崄傆嶳嶗偐側乿(拞棯)僩僴嬼慠帺慠僯敪婗僔僞儖姶忣儝捈幨僔僞儖儌僲僯旕儔僘儎丄帶僔僥梊僴崯姶忣儝棙梡僔僥丄塀栺僲娫僯擔杮僲崙婎儝栎屌僙儞僐僩儝榑僛儞僩僗儖儌僲僫儕丄乿(1)
嶗偺壴偲晉巑偺曯傪椺偵嫇偘偰丄偙偺桪旤側晽搚偙偦擔杮偺屌桳偺傕偺偱偁傞丄晽搚傊偺垽傪崙壠偺慴偲偟偨偄偲丅嶗壴傕晉巑傕擔杮旤偺椺偲偟偰偼偼側偼偩捠懎揑偱偁傞偑丄傗偑偰崙悎庡媊傪彞偊傞偙偲偵側傞摉恖偑丄彮側偔偲傕偙偺彫榑偱偼崙懱榑傗晲巑摴偵堦愗尵媦偣偢丄嶳壨偺旤傪揱摑偺妀怱偲偟偰柧夣偵庡挘偡傞揰偱棨愎撿傗懡偔偺擔杮宆曐庣庡媊幰偲偼傑偭偨偔堘偆丅
偗傟偳傕巙夑偼偙偺揱摑偵懳偟孅愜偟偨姶忣丄傓偟傠僐儞僾儗僢僋僗偵嬤偄婥帩偪傪書偄偰偍傝丄尵梩偲偼棤暊偵恀偺垽拝偑帩偰側偄偺偱偁傞丅偦偺暋嶨側姶忣偼偙偺彫榑偵憗偔傕尰傟偰偒偰偄傞丅擔杮偺偙傟偐傜偺曽岦傪榑偠偨埲壓偺晹暘偑偦偆偱偁傞丅
乽妿強堗夵椙榑幰僴屌儓儕垽崙僲巚憐僯晉儉儝埲僥擔杮幮夛僲夵椙僯擬怱杬憱僗儖儌僲僩僙僶丄壗屘僯彅巕僴乽儈儈僋儕乕乿(椶宍)僲帠嬈僯僲儈擬怱杬憱僔僥丄弮慠僞儖惃椡曐懚僲帠嬈僯廃慁焢椡僙僓儖儎丄擔杮僲擛僉昻庛崙僯墬僥強堗崱擔捈愙僯僔僥妿媫柋僫儖惃椡曐懚僩僴丄惀儗抳晉僲曽嶔僯僔僥丄強堗怋嶻嫽嬈惀儗僫儕丄慠儗僪儌梊僴崱擔僴姪擾媦價彜嬈奼挘僲島榑儝巄僋巭儊丄懠僯擔杮僲崙婎儝栎屌僗儖僲曽嶔儝榑僛儞僩僗儖儌僲僫儕丄懘幰擛壗丄濰僋擔杮僲嶳悈晽搚壴捁僲桪旤僫儖儝扱徿僗儖僲姶忣儝憌堦憌熂梴僔丄僐儗儝攟怋僔丄埲僥柣乆僲娫僯塀慠僩擔杮崙搚儝垽曠僗儖僲娤擮儝栕拁僙儞僩僙僔儉儖儌僲僫儕丄乿(2)
巙夑偼擔杮恖偺嵦傞傋偒曽岦偲偟偰嶰偮偺慖戰巿傪採帵偟偰偄傞丅
(1)丂奜崙昳偽偐傝傪悞攓偡傞乽儈儈僋儕乕乿丄偮傑傝惣梞偺柾曧
(2)丂晉崙側偄偟怋嶻嫽嬈
(3)丂擔杮崙搚傊偺垽
斵偑悇彠偡傞偺偼丄傕偪傠傫(3)偺乽擔杮崙搚傊偺垽乿偱偁傝丄(1)偺乽奜崙悞攓乿偼斲掕偝傞傋偒傕偺丄(2)偺乽怋嶻嫽嬈乿偼嫮椡偵悇恑偡傋偒偱偁傞偑丄偲傝偁偊偢偙偙偱偼媍榑偟側偄偱偍偔傕偺丅
棫榑偺庯巪偐傜(3)偺乽擔杮崙搚傊偺垽乿傪嵦傞偺偼摉慠丄(1)偺乽奜崙悞攓乿傪惣梞偐傇傟偲攔愃偡傞偺傕梊憐偳偍傝偩偑丄栤戣偼(2)偺乽怋嶻嫽嬈乿偱偁傞丅(2)偵偮偄偰巙夑偼嫮偄娭怱傪帵偟側偑傜偙偙偱偺媍榑偼懪偪愗偭偰偄傞丅乽怋嶻嫽嬈乿偲乽擔杮僲嶳悈晽搚壴捁乿揑旤堄幆偑偳偆偟偰娙扨偵堦抳偟傛偆丅嬤戙暥柧偺捛媮偲揱摑偺曐帩偑偨傗偡偔偼憡梕傟側偄偙偲傪擣傔偞傞傪摼側偐偭偨丅偙偆偄偆惓捈側擣幆偼丄嬤戙暥柧偲揱摑偺曐帩偑柕弬偟側偄偐偺傛偆偵尵偄挘傞敿擭偁偲偺亀擔杮恖亁偺媍榑傛傝偼傛傎偳岲姶偑帩偰傞丅
偟偐偟丄偦傟偱傕側偍偐偮丄巙夑偼嬤戙壔偵嫮偄枹楙傪巆偟偰偄傞丅乽崙婎儝栎屌乿偵偡傞曽朄偼側偄傕偺偐偲尵偄偝偟偰丄嶻嬈怳嫽偺曽嶔偵偮偄偰偺媍榑傪傗傔偨偲偙傠偵巙夑偺嬯擸偑椙偔尰傟偰偄傞丅巙夑偺枹楙偼(2)偺乽怋嶻嫽嬈乿傪乽惣梞壔乿偲偼尵傢偢偵丄乽惃椡曐懚僲帠嬈乿偲彂偄偰偄傞偲偙傠偵傕傛偔弌偰偄傞丅乽惣梞悞攓乿偼僟儊偱偁傞偲抐偭偨偰傑偊丄乽怋嶻嫽嬈乿傪乽惣梞壔乿側偳偲偼尵偊側偄丅偦偙偱乽惣梞壔乿偱偼側偔乽惃椡曐懚乿偱偁傞偲偟偰偍偗偽丄揱摑庡媊偺棫応偐傜傕乽怋嶻嫽嬈乿傪庡挘偱偒傞梋抧偑偄偢傟弌偰偔傞丅斵偼偙偆寁嶼偟偨偺偱偁傠偆丅偟偐偟丄嶻嬈棫崙偼棫攈側嬤戙壔丄杮奿揑側惣梞偐傇傟埲奜偺側傫偱偁傠偆偐丅
偲偼偄偊丄巙夑偑(2)偵偮偄偰偺媍榑傪偙偙偱偼懪偪愗偭偨偙偲傪傗偼傝朖傔偰傗傞傋偒偱偁傠偆丅(2)偺乽怋嶻嫽嬈乿傪柍忦審偵捛媮偡傞偲(3)偺乽擔杮崙搚(揱摑)傊偺垽乿偲偺惍崌惈偑寛掕揑偵攋抅偡傞丅偦偆偄偆攋抅傪柍棟偵偛傑偐偦偆偲偡傞榑暥偼屻偱偄偔偮傕弌偰偔傞丅柕弬偵婥偑偮偄偰媍榑傪懪偪愗偭偨偲偙傠偵丄斵偺嬯擸偑偐偊偭偰惓捈偵尰傟偰偟傑偭偨偲傕尵偊傞丅
傑偨丄巙夑偑媍榑偵峴偒媗偭偨偺偼揱摑傪擔杮偺晽搚偺旤偲掕媊偟偨偙偲偵傕婲場偡傞丅旤偼杮棃丄崙壠幮夛偺偁傝曽傪帵偡傕偺偱偼側偄丅旤偐傜偨偩偪偵擔杮偺恑傓傋偒曽岦傪峔憐偡傞偙偲偼偱偒側偄丅擔杮偺揱摑偑旤偱偁傞偲偟偰丄変乆偼堦懱偳偆偡傟偽傛偄偺偐傢偐傜側偄偱偼側偄偐丅巙夑偼揱摑丄揱摑偲尵偄側偑傜丄撪怱丄擔杮偺揱摑偼偙偺掱搙偺傕偺側偺偐丄傕偆彮偟壗偐側偄偺偐偲渪渹偨傞巚偄偵嬱傜傟偨偱偁傠偆丅偨偩丄斵偺媍榑偼傗偑偰傗傗怺傑傝傪尒偣丄旤傪挷榓丒暯榓偲夝庍偟丄偦偙偵楌巎惈傗幮夛惈傪惙傝崬傓偙偲偵傛偭偰丄偙偺峴偒媗傑傝傪偁傞掱搙忔傝墇偊傛偆偲偡傞偺偱偁傞丅
偄偢傟偵偟偰傕丄斵偼偄偭偨偄揱摑傪暅尃偟偨偐偭偨偺偐丄偦傟偲傕嬤戙壔傪栚巜偟偰偄傞偐丅杮怱傪梷偊偰丄恖娫娭學偐傜崙悎庡媊偺恮塩偵搳偠偨偨傔丄斵偺榑棟偼戝偒側崿棎傪偒偨偡偙偲偵側傞丅
仭
(1)乽擛壗僯僔僥擔杮崙儝(僔僥)擔杮崙僞儔僔儉壜僉儎乿丄亀崙柉擵桭亁戞堦乑崋(柧帯擇乑擭堦乑寧擇堦擔)丅
(2)摨丅丂 |
| 仭擇丂崙悎庡媊偺巚憐 / 奣擮偺椉媊惈偲榑棟偺崿棎 |
   丂
丂
|
仭(堦)惌嫵幮偺惉棫
亀撿梞帪帠亁偱堦桇桳柤偵側偭偨巙夑偼丄柧帯擇堦(堦敧敧敧)擭丄惌嫵幮偺寢惉偵壛傢傝丄庡昅偲側偭偨丅敿寧娫偺嶨帍亀擔杮恖亁戞堦崋偺敪姧偼摨擭巐寧嶰擔丅惌嫵幮偺恖柆偼擇偮偁傞丅傂偲偮偼悪塝廳崉偲媨嶈摴惓偑愝棫偵恠椡偟偨搶嫗塸岅妛峑(屻偺擔杮妛墍拞妛丒崅摍妛峑)娭學幰偱丄悪塝偦偟偰媨嶈傪拞怱偵巙夑廳丒崱奜嶰榊丒徏壓忎媑丒媏抮孎懢榊丄傕偆傂偲偮偼堜忋墌椆傪拞怱偲偡傞揘妛娰(偺偪偺搶梞戝妛)娭學幰偱壛夑廏堦榊丒搰抧栙棆丒扖枻彫師榊丒嶰戭愥椾丒悪峕曘恖丒扞嫶堦榊傜丅偲偒偁偨偐傕丄幁柭娰偺墷壔庡媊壺傗偐側傝偟偙傠偱丄偙偺晽挭傪桱偊傞恖偨偪偑惌嫵幮偵廤寢偟偨丅庡媊庡挘傪摨偠偔偡傞棨愎撿偑崙柉庡媊偵嫆偭偰怴暦亀擔杮亁傪巒傔傞偺偑丄梻摨擇擇(堦敧敧嬨)擭丅偡偱偵丄暯柉庡媊傪彞偊偰摽晉慼曯棪偄傞柉桭幮偼摨擇乑(堦敧敧幍)擭偵嶨帍亀崙柉擵桭亁傪憂姧偟偰偍傝丄摨擇嶰(堦敧嬨乑)擭偵偼亀崙柉怴暦亁傪敪姧偡傞偙偲偵側傞丅
惌嫵幮偵壛傢偭偨巙夑偱偼偁傞偑丄巚憐揑偵尒傞偲丄怱偐傜偺揱摑庡媊幰偱偼側偔丄亀擔杮恖亁僌儖乕僾偲偼憡摉偺堘偄偑偁傞丅偨偲偊偽丄恖柆偺拞怱偵偄偨悪塝廳崉傗堜忋墌椆傜偼杮幙揑偵崙懱庡媊幰偱偁傞偲尵偭偰傛偄丅傕偪傠傫丄懠偺暥柧揑尨棟傪攔彍偟側偄丄悪塝側傜惣梞偺棟妛傪丄堜忋側傜暓嫵傪怣曭丒昡壙偡傞偲偙傠偵偄傢備傞崙懱榑偲堘偆奐柧惈傗廮擃惈偑偁傞偑丄偟傚偣傫崙懱榑傪拞怱偵偟偨嵦挿曗抁庡媊幰丒愜拸庡媊幰偱偁傞丅棫榑偺偆偪偵偝傜柧傜偐偵側傞傛偆偵丄巙夑偺揱摑娤偲偼偐側傝堘偄偑偁傞偟丄側偵傛傝傕巙夑偼杮幙揑偵墷暷悞攓幰偱偁傞丅
偵傕偐偐傢傜偢丄斵偼亀擔杮恖亁偺拞怱揑摨恖偩偭偨傢偗偱偁傞偑丄偦傟偼斵偑妛傫偩搶嫗戝妛梊旛栧傗嶥杫擾妛峑丄偦偟偰撿梞偐傜偺婣崙屻偵嬑柋偟偨搶嫗塸岅妛峑偺恖柆揑娭學偵傛傞偲偙傠偑戝偒偄偱偁傠偆丅惌嫵幮偺屻墖幰悪塝廳崉偼傕偲搶嫗戝妛梊旛栧挿偩偭偨偟(巙夑偼偡偱偵嶥杫偵椃棫偭偰偟傑偭偰偄偨偑)丄亀撿梞帪帠亁偺帺戣偺乽墔帉乿偵斸暥傕婑偣偰偔傟偨丅媨嶈摴惓偼擾妛峑帪戙偺壎巘偱丄悪塝偲偲傕偵塸岅妛峑傪愝棫丒宱塩偟丄巙夑傪偦偙偵悇慐偟偰偔傟偨恖偱偁傞丅惌嫵幮摨恖偺媏抮孎懢榊偲崱奜嶰榊偼擾妛峑偺偦傟偧傟摨媺偲堦媺壓偱丄偲傕偵搶嫗塸岅妛峑偺嫵巘偱偁偭偨丅
巙夑偼擔杮偺揱摑偵偦傟傎偳偺垽忣傪帩偭偰偄偨傢偗偱偼側偄偑丄悽榖偵側偭偨悪塝傗媨嶈丄偁傞偄偼摨憢惗偲偺恖娫揑鉐偵傛偭偰丄懡彮怱側傜偢傕丄惌嫵幮偺拠娫偵偼偄偭偨偲峫偊傜傟傞丅傑偨丄巙夑偑巚憐幰偲偟偰偼鉱枾側榑棟傗奣擮偑嬯庤偱丄傛偔尵偊偽崑曻猁棊側惈奿偱偁偭偨偨傔偵丄摨恖偨偪偲偺僘儗偑偦傟傎偳婥偵側傜側偐偭偨偺偐傕抦傟側偄丅偦偟偰丄斵偼柧帯惌晎偵懳偟偰傕帺桼柉尃塣摦偵偮偄偰傕姶幱偲斀姶丄昡壙偲斀敪偲偄偆暋嶨側姶忣傪帩偭偰偄偨丅姱椈偵傕側傜偢丄偦偆偐偲偄偭偰斀惌晎偵傕夞傟側偄拞娫揑側棫応傕崙悎庡媊傪慖傇戝偒側尨場偵側偭偰偄傞偑丄偙偆偄偆恖娫娭學傗懡彮僀僨僆儘僊乕揑棫応偐傜偺婙涱偺慖戰偑杮棃偺揱摑庡媊幰偱側偄巙夑偺巚峫偵奣擮偲榑棟偺嫸偄傪惗偠偝偣傞偙偲偵側傞丅
仭(擇)崙悎庡媊偺巚憐 / 奣擮偺椉媊惈偲榑棟偺崿棎
揱摑庡媊偲偟偰偺崙悎庡媊丂巙夑偼亀擔杮恖亁戞擇崋(柧帯擇堦擭巐寧堦敧擔)偵宖嵹偟偨乽亀擔杮恖亁偑夰書偡傞張偺巪媊傪崘敀偡乿偺朻摢偱乽崙悎庡媊(巪媊)乿偲偼側偵偐傪師偺傛偆偵掕媊偟偰偄傞丅
乽墌悕宍偺捔壩嶳丄廏慠偲偟偰奀傪敳偒丄洣棫堦枩梋樋丄愮擭枩擭偺昘愥丄岖乆偲偟偰懘曯椾偵懲愊偡傞傕偺僴丄幚偵晉巑偺曯偵旕偢傗丄帶偟偰婔懡偺嶳宯擵傪柸榡偟悏傪嬻偵憓傒暽傪塤偵墶傊丄墦偔樔朷偡傟偽恀屄偵堦暆偺妶夋偺擛偔丄揮偨恖傪偟偰抦傜偢幆傜偢旤弍揑偺娤擮傪敪婗偣偟傔丄帶偟偰慟偔偙傟偑敪堢傪桿抳偟偨傞傕偺僴丄奧偟嬼慠偵旕偞傞壜偒栯丄枖堦曽傛傝娤傟偽丄変擔杮偺奀搰僴壏懷寳棥偺拞墰偵揰捲偟丄懘増娸僴嬒偟偔惀傟壏抔挭棳偺愻傆張偲側傝丄揤岓榓鄨丄晽搚弫戲側傞傪埲偰嶗壴崯張偵啵敪偟埉擔偲憡塮偢傞張丄堦憃偺扥捀掃偑懘娫偵隳偡傞偺忬傪樿帇偡傟偽丄恖傪偟偰帺偐傜桪沀崅彯側傞娤擮傪梴惉偣偟傓傞帠側傜傫丄帶偟偰枖擔杮偺奀搰傪娐銋偣傞揤暥丄抧暥丄晽搚丄婥徾丄姦壏丄憞幖丄抧幙丄悈棨偺攝抲丄嶳宯丄壨宯丄摦暔丄怉暔丄宨怓摍偺枩斒側傞埻奜暔偺姶壔偲丄壔妛揑偺斀墳偲丄愮擭枩擭偺廗姷丄帇挳丄宱楌偲偼丄奧偟攪棥偵惗懅偟攪嵺偵棃墲偟攪斒傪鍺暦偣傞戝榓柉懓傪偟偰丄柣乆塀栺偺娫偵堦庬摿庩側傞崙悎(Nationality)傪檶惉敪払偣偟傔偨傞偙偲側傜傫丄奧偟攪斒偺強堗崙悎側傞傕偺僴丄擔杮崙搚偵懚嵼偡傞枩斒側傞埻奜暔偺姶壔偲丄壔妛揑斀墳偲偵揔墳弴廬偟丄埲偰泱戀偟惗嶻偟惉挿偟敪払偟偨傞傕偺偵偟偰丄妿偮傗戝榓柉懓偺娫偵愮屆枩屆傛傝堚揱偟棃傝壔弳偟棃傝丄廔偵摉戙偵摓傞傑偱曐懚偟偗傞傕偺偵偟偁傟偽丄惀傟偑敪堢惉挿傪桗傛懀抳彠椼偟丄埲偰戝榓柉懓偑尰嵼枹棃偺娫偵恑壔夵椙偡傞偺昗弨偲側偟婎杮偲側偡僴丄惓偟偔惀傟惗暔妛偺戝尮懃偵弴揔偡傞傕偺側傝乿(1)
擔杮恖偑偦偺撈帺偺晽搚楌巎偺拞偱屆棃曐帩偟懕偗偨摿幙丄偲傝傢偗丄旤偟偄嶳壨偲壏抔側婥岓偺拞偱偼偖偔傑傟偨旤堄幆偑乽崙悎(Nationality)乿偱偁傞丅偙傟傪枹棃偵傢偨偭偰宲彸敪揥偝偣偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偲丅揱摑偺堐帩敪揥偑崙悎庡媊偱偁傞偲偄偆巙夑偺愢柧偼偲偔偵偡偖傟偨摯嶡傪娷傫偩傕偺偱偼側偄偑丄崙悎庡媊傪掕媊偡傞応崌偵昁偢尵傢側偗傟偽側傜側偄帠暱偱丄変乆偑忢幆揑偵帩偭偰偄傞崙悎奣擮偵崌抳偟丄椆夝偱偒傞丅
傕偆傂偲偮偙偺傛偆側掕媊偺椺傪嫇偘偰偍偔丅乽擔杮崙棥偺棟憐揑帠戝搣乿(亀擔杮恖亁戞屲崋丄柧帯擇堦擭榋寧嶰擔)偵傕乽崙悎乿偲偼戝榓柉懓偺揱摑揑旤堄幆偱偁傞偲彂偄偰偄傞丅乽欆歭梊攜偑強堗崙柤偲僴崯偺桪旤側傞擔杮朚搚傪栚巜偡傞幰側傝丄崙壠偲僴擔杮崙搚偲丄寭偰擔杮崙柉偑惃椡傪憤暪偡傞偵嵟廳嵟戝嵟宱嵪揑側傞斵偺掗幒傪柤徧偡傞傕偺側傝丄崙悎偲僴戝榓柉懓偑屌桳摿棫偺惛恄偲丄懘嵟挿強偨傞旤弍揑偺娤擮傪彞摫偡傞傕偺側傝丄欆歭崯偺崙柤丄崯偺崙壠丄崯偺崙悎傪塹岇偟擵傪曐懚偡傞偼丄姣偵晇傟梊攜戝榓柉懓偑帄戝帄崉側傞杮暘偵旕偢偟偰壗偧傗乿(2)
巙夑偼摉慠峜幒傪懜廳偟偰偄傞偑丄崙悎庡媊偺愢柧偵嵺偟丄忋婰堷梡偵傕昞傟偰偄傞傛偆偵丄崙懱偺娤擮偵傛偭偰偙傟傪杽傔恠偔偡偲偄偆傛偆側偙偲偼偟側偐偭偨丅慜宖偺乽亀擔杮恖亁偑夰書偡傞張偺巪媊傪崘敀偡乿偱傕崙懱揑側娤擮偑偁傞掱搙嫮偔弌偰偔傞偑丄偦偺応崌偱傕悈屗妛幰棳偐傜帺暘傪帺妎揑偵嬫暿偟偰偍傝丄揤峜偵懳偡傞愨懳晄曄偺拤媊偩偗偑傢偑崙偺惛壺偱偁傞偲偄偆傛偆側尵偄曽偼偟偰偄側偄(3)丅峜幒惂搙傪娷傔偰丄晽搚偲柉懓偺惗妶丄偲偔偵旤堄幆偑崙悎偺撪梕傪側偟偰偄偨丅
惃椡曐懚偲偟偰偺崙悎庡媊丂巙夑偼偙偺傛偆偵旤堄幆傪拞怱偲偟偰晽搚偲柉懓惗妶偺偍傝側偡揱摑偺堐帩敪揥傪崙悎庡媊偲愢柧偟偰偍傝丄変乆偑忢幆揑偵僀儊乕僕偡傞崙悎庡媊偺奣擮傕傎傏偙偆偄偆傕偺偱偁傠偆丅偲偙傠偑丄斵偑亀擔杮恖亁偵嵹偣偨崙悎庡媊傪傔偖傞彅榑暥傪撉傫偱傒傞偲丄暿偺崙悎庡媊偺奣擮偑懚嵼偟偰偄傞丅乽擔杮慜搑偺擇戝搣攈乿(亀擔杮恖亁戞榋崋丄柧帯擇堦擭榋寧堦敧擔)偱偺愢柧偼偙偆偱偁傞丅
乽乽擔杮巪媊乿偲偼壗偧傗丄乽惃椡曐懚巪媊乿惀傟側傝丄惃椡曐懚偲僴壗偧傗丄帺屓偑摿桳偺惃椡傪曕乆拝乆敪婗恑挩偟偰丄懘婎慴傪栎屌偵偟丄懘廳怱慄傪悅捈側傜偟傔丄慟師偺娫偵戝惃椡偲壔惉偡傞傕偺傪塢傆丄慠傟偽崯偺巪媊僴乽墷廈巪媊乿懄偪柾曧巪媊偲慡慠斀懳偡傞傕偺偵偟偰丄擔杮崙柉偑尨惈丄杮嵥丄摿擻丄惛恄丄廏悎傪梴惉拁愊偟丄搼懣夵椙偟丄埲偰擔杮崙婙偺柦柆塰梍傪塱媣枩戙偺娫偵曐堐偣傫偲偡傞傕偺側傝乿(4)
崙悎庡媊(乽擔杮巪媊乿)偲偼乽惃椡偺曐懚乿(僐儞僒乕償僃乕僔儑儞丄儝僽丄僄僫僕乕)偱偁傞丄柉懓丒崙壠偺敪揥偙偦崙悎偺敪婗偩偲尵偆偺偱偁傞丅乽惃椡曐懚乿偑乽崙悎庡媊乿偩偲尵偄偐偹側偄婥攝偼乽擛壗僯僔僥擔杮崙儝(僔僥)擔杮崙僞儔僔儉壜僉儎乿偵傕偁偭偨偑丄慜宖堷梡榑暥偱偼偭偒傝偲弌偰偒偨丅偙偺愢柧偼傑偙偲偵嫮堷偱栤戣偑偁傞丅傑偢丄崙悎庡媊偼揱摑偺堐帩敪揥偱偁傞偲偄偆巙夑偺傕偲傕偲偺掕媊偲戝偒偔怘偄堘偄丄傕偪傠傫丄変乆偺忢幆揑側奣擮偐傜傕姰慡偵堩扙偟偰偄傞丅偦偟偰丄偦傕偦傕偙傟偱偼崙悎庡媊偲嬤戙壔偺嬫暿偑晅偐側偄丅
柉懓崙壠偑椡傪怢偽偟偰偄偔偙偲側傜偽丄崙壠偺敪揥偲偐嬤戙壔偲偐晉嫮壔偲偐暿偺尵梩傪巊偆傋偒偱偁傞(傕偟丄乽崙悎庡媊乿偲偄偆尵梩偱巙夑偼懳棫偡傞擇偮偺娤擮傪摨帪偵昞偟偨偺偱偁傞偲曎岇偡傞恖偑偄傞偲偡傟偽丄偦傟偼嫮曎偱偁傞)丅偦偟偰丄摉慠側偑傜惃椡偺曐懚丒敪揥(柉懓傗崙壠偺敪揥)偺偨傔偵偼丄堦斒偵偼揱摑偼幾杺偱丄惣梞壔偡傞傎偆偑傛偄丅傕偭偲傕丄揱摑偲尵偭偰傕懡庬懡條偱偁傞偐傜丄側偐偵偼嬤戙壔偵斾妑揑寢傃偮偒傗偡偄傕偺傕偁傠偆丅偨偲偊偽丄擔杮恖偼揱摑揑偵婍梡偱偁傞偑丄偙傟偼岺嬈棫崙偵戝偒偔峷專偟偨丅偟偐偟丄嬤戙壔偵桳棙側揱摑偲偄偆偺偼傓偟傠椺奜偱偁偭偰丄懡偔偺応崌丄揱摑偺曐帩偲崙壠偺敪揥偑懄嵗偵寢傃晅偔偼偢偑側偄丅偨偄偰偄偺嬤戙壔偲偼揱摑偵挧愴偟攋夡偡傞偙偲偱偁傞丅偲偙傠偑丄巙夑偼揱摑偺曐帩傕崙壠偺敪揥傕崙悎庡媊偱偁傞偲偄偆傛偆側幚偵偍偐偟側愢柧傪偟偰偟傑偭偨偨傔偵丄揱摑偲嬤戙偑傑偙偲偵嫮堷偵寢傃晅偗傜傟偰偄傞丅乽亀擔杮恖亁偑夰書偡傞巪媊傪崘敀偡乿偐傜堷梡偡傞丅
乽屻幰(崙悎庡媊乗昅幰)僴擔杮傪擔杮偲偟丄帶偟偰屻惣梞妛栤偺挿強傪埲偰懘抁強傪曗僴傫偲偡傞幰側傝乿(5)
乽妿偮晇傟乽擔杮暘巕懪攋乿榑幰偺強愢傪悢棟妛忋偵挜偡傟偽丄擔杮偺奐壔僴屻恑側傞傪埲偰壖傝偵1234 偲側偣偽惣梞偺奐壔偼12345678910 側傝丄屘偵擔杮崙棥偵惣梞偺奐壔懄偪10 傪桝擖偣傛偲彠椼偡傞偵夁偓偢丄鄟傫偧抦傜傫擔杮嵼棃偺暘巕傪懪攋偟偰0偲側偟丄帶偟偰绡慠10偺奐壔傪桝擖偣偽丄0傛傝10偵旘墇挼桇偡傞幰偵偟偰懄偪懘娫偵懢偩嬻寗傪惗偠丄堊傔偵崻瀜婎慴僴曃偵惼庛偵偟偰娫潨搢偡傞偺堌傟柍偲偣偢丄擩傠1234傪慟師偵憹恑偟棃傝丄5678910偲側偡偺埨慡栎屌側傞偵庒偐偞傞側傝乿(6)
乽扅懽惣偺奐壔傪桝擖偟棃傞傕丄擔杮崙悎側傞堓姱傪埲偰擵傪欚殣偟擵傪徚壔偟丄擔杮側傞恎懱偵摨壔偣偟傔傫偲偡傞幰栫乿(7)
擔杮揑偵欚殣偡傞偙偲偵傛偭偰暥柧壔偑偆傑偔偄偔丄擔杮偺揱摑偺忋偵惣梞壔傪恾傟偲偄偆媍榑偱偁傞丅偟偐偟丄偙傟偱偼乽崙悎庡媊乿偱偼側偔丄乽嵦挿曗抁乿傗乽愙栘乿偱偁傞丅
偟偐傕丄巙夑偺尵偭偰偄傞傛偆偵偄偮傕偄偔偼偢偑側偄丅擔杮偺揱摑傪嬤戙壔偺拞偵偆傑偔惗偐偣傞応崌偑偁偭偨偲偟偰傕丄偦傟偼傓偟傠彮悢椺偱偁傞丅(傕偟丄偁傞偲偄偆偺側傜丄偤傂帵偡傋偒偱偁傞丅擔杮偺揱摑傪捠偟偰杮摉偵嬤戙壔偱偒傞偺偐丄偳偆偡傟偽壜擻側偺偐傪偐側傜偢岅傜側偗傟偽側傜側偄丅偲偙傠偑丄巙夑偼偦傟埲忋側傫偺愢柧傕偟偰偔傟側偄偱偼側偄偐丅)偩偄偄偪丄暥柧奐壔偺帪戙偵偁偊偰擔杮庡媊丄崙悎庡媊傪彞偊傞偲偄偆偙偲偼丄杮摉偼嬤戙壔傪憡摉媇惖偵偟偰丄偁傞偄偼廋惓偟偰偱傕揱摑傪庣傟偲偄偆庡挘偱側偗傟偽側傜側偄丅偦偆偄偆妎屽偙偦崙悎庡媊偱偁傠偆丅偲偙傠偑丄巙夑偼偙偆偄偆揱摑偲嬤戙偺憡崕偲偄偆偒傢傔偰廳梫側栤戣傪偮偒偮傔偰峫偊偰傒傛偆偲偣偢丄偠偮偵娙扨偵崙悎庡媊偲嬤戙壔傪寢傃晅偗偰偟傑偭偨丅摉帪偺撉幰偐傜傕丄偙傟偱偼崙悎庡媊偲暥柧壔偺嬫暿偑偮偐側偄偱偼側偄偐偲偄偆斸敾偑婑偣傜傟偰偄傞(8)丅偨偟偐偵偙傟偱偼擔杮揑奐壔偲惣梞揑奐壔偼偨傫側傞敪揥抜奒偺堘偄偱偟偐側偔側偭偰偄傞丅幁柭娰偵徾挜偝傟傞惌晎偺惣梞壔傕巙夑偑斸敾偡傞傛偆偵愺敄偱偁偭偨傠偆偑丄斵帺恎偺揱摑偲嬤戙偺寢崌偺巇曽傕傑偙偲偵埨堈偱偁傞丅
偙偺椶偺嫮堷側榑朄傪傕偆傂偲偮嫇偘偰偍偔丅
乽梊攜僴乽崙悎曐懚乿偺帄棟帄媊側傞傪妋怣偡丄屘偵暯摍巪媊傪夰書偡傞幰側傝丄屘偵挷榓巪媊傪夰書偡傞幰側傝丄屘偵夵妚庡媊傪夰書偡傞幰側傝丂榑偠嫀傝榑偠棃傝偰崯張偵摓傟偽丄梊攜偼曃偵乽崙悎曐懚乿偺宱嵪棙塿揑側傞傪妋抦偡傞幰側傝丄婛偵宱嵪棙塿揑側傟偽丄懄偪攪斒僴幚偵塅撪戝惃偺惓棳偵弴揔偡傞幰側傞傪挜徹偡傋偟丄慠傝帶偟偰斵偺乽揾枙巪媊乿偲乽擔杮暘巕懪攋巪媊乿偲偼宱嵪棙塿揑偺杮尮杮棳偵旕傜偞傞傪埲偰丄擔杮嵟戝悢偺柉恖偑嵟戝岾暉僴幚偵攪斒偺椉巪媊傛傝桸弌偡傞幰偵旕偞傞傗晇傟柧偐栫丄乿(9)
乽崙悎曐懚乿偑暯摍庡媊偱丄挷榓庡媊偲尵偆偺傕旘桇偑偁偭偰暘偐傝偵偔偄偑丄夵妚庡媊偱丄宱嵪揑棙塿偵崌抳偟丄悽奅偺戝惃偱偁傞偲尵偆偵帄偭偰偼丄埨堈慹嶨傪捠傝墇偟偰傕偼傗巟棧柵楐偱偁傞丅偳偆偟偰揱摑偺梚岇偑偨偩偪偵夵妚庡媊傗宱嵪揑棙塿偵側傞偺偐丅偳偆偟偰悽奅偺戝惃側偺偐丅巚憐幰偲偟偰傑偙偲偵柍愑擟偱杤榑棟揑側敪尵偱偁傞丅
傕偲傛傝丄偄偐偵揱摑偺曐帩傪嫨傏偆偲丄擔杮偺嬤戙壔偼愨懳偵昁梫偱偁偭偨丅揱摑庡媊幰偲偰傕嬤戙暥柧偵娭怱偑峴偔偺偼摉慠偱偁傞丅嬤戙壔偺拞偵揱摑傪丄揱摑偺拞偵嬤戙壔傪偳偆埵抲偯偗傞偐偲偄偆擄栤偵惤幚偵摎偊傞偺偑偦傕偦傕崙悎庡媊幰偱偁傠偆丅偲偙傠偑丄巙夑偼惣梞暥柧偺庴梕偵偁偨偭偰丄擔杮偺揱摑傪惗偐偟丄擔杮揑偵欚殣偟側偗傟偽側傜側偄偲尵偆偩偗偱丄側偵傪惗偐偟丄偳偆欚殣偡傞偺偐偵偮偄偰傛偔峫偊偰偄側偄偟丄庤偑偐傝偝偊梌偊偰偔傟側偄偱偼側偄偐丅偙偆偄偆崲擄偱偁傠偆偲傕傕偭偲傕廳梫側嶌嬈偑偱偒側偄偐傜丄擔杮揑揱摑偵側傫偲側偔惣梞暥柧傪愙栘偡傟偽傛偄丄傑偨丄偱偒傞偲偄偆傛偆側尵偄曽偱栤戣傪偛傑偐偟偨偺偱偁傞丅
懠崙偺崙悎丂偙偺傛偆側奣擮偺崿棎傪懠崙偺崙悎傪榑偢傞応崌偵傕帩偪崬傫偱偄傞椺傪嫇偘偰偍偒偨偄丅乽崑廎楍崙偺崌廲撈棫偣傫偲偡傞(偺)堦戝孹岦乿(亀擔杮恖亁戞擇堦崋丄柧帯擇擇擭擇寧嶰擔)偑偦傟偱偁傞丅摨榑暥偼柧帯擇擇擭堦乑寧偺戞嶰斉埲崀偺亀撿梞帪帠亁偵戞敧復乽崐廎楍崙僲崌廲撈棫僙儞僩僗儖堦戝孹岦乿偲偟偰傕廂榐偝傟偰偄傞丅巙夑偼僆乕僗僩儔儕傾偺撈棫栤戣偵娭楢偝偣偰丄乽崙悎乿偺廳梫惈傪埲壓偵榑偠偰偄傞丅偙偺榑暥偁偨傝偑偲傕偐偔傕乽崙悎庡媊乿傪榑偢傞嵟屻偺傕偺偱偁傞丅偪側傒偵僆乕僗僩儔儕傾楢朚偺惓幃愰尵偼堦嬨乑堦擭丄惓幃撈棫偼堦嬨嶰堦擭偱偁傞丅
乽崐廎怋柉偺幚椡婛偵巣偔偺擛偟丅偙傟傪堦恖偵鏍傆傞偵桺傎彮憇偺慟偔帺屓偺尒幆傪棫偰丄抦傜偢幆傜偢摿棫摿峴偺娤擮傪奐敪偡傞傕偺偵帡偨傝丅崐廎偺怋柉幚椡傪拁愊偟偰帺偐傜堦尒幆傪棫偰丄擵傟偲嫟偵強嵼枩斒側傞埻奜暔偼斵摍偺娫偵慟偔堦庬摿庩側傞崙悎傪敪払偣偟傔丄崯偺崙悎桗乆敪払偟偰杮崙偺帠暔偲桗乆憡妘棧偟丄杮崙偺棙奞偲桗乆憡徴撍偡丅崯偺崙悎傗堦婲偟偰乬Australia for the Australians乭(乽崐懢棙僴崐懢棙恖偺崐懢棙偨傜偞傞傋偐傜偢乿偲塢傆媊側傝)偺歗惡偲側傝丄嵞婲偟偰乬National Party乭(撈棫搣)偺抍寢偲側傝丄嶰婲偟偰崐廎楍
崙偺崌廲撈棫偲側傞丄乿(10)
乽斵傟偲塢傂崯傟偲塢傂枓埲偰撈棫巪媊偺婥傪挜抦偡傋偟丅慠傝帶偟偰懘婲場偡傞張幚偵崐廎怉柉偑桳宍忋偺幚椡傪拁愊偟偨傞偲丄柍宍忋堦庬摿庩側傞崙悎傪敪払偟偨傞擇戝尦慺偵嵼傝丅恀屄偵崙悎偺敪払僴柉懓撈棫偺娤擮偑敪払偲椉乆憡峴偡傞偺鏆嵍偲側偡偵懌傟傝丅(拞棯)恑壔偺恄偼擆攜傪欒岇偣傝丅乿(11)
偙偙偱傕丄巙夑偺崙悎奣擮偺寚娮偑惀惓偝傟偢偵丄偦偺傑傑業掓偟偰偄傞丅堷梡晹偺乽崙悎乿丒乽摿棫乿偲偼丄崙壠柉懓偺惉挿敪揥偲丄偦偺寢壥偲偟偰偺撈棫丒帺屓尃塿偺梫媮偱偁偭偰丄揱摑偺曐帩偲偼偲偔偵娭學偑側偄丅偩偄偄偪丄僆乕僗僩儔儕傾偺撈棫偼(偙偺榑傛傝偁偲偺偙偲偩偑)丄偄傢偽傾儊儕僇偺撈棫偲摨偠偱丄崙壠柉懓偺敪揥偐傜弌偰偔傞庡懱惈偺庡挘偱偁傝丄偦偺堄枴偱偺惌帯揑僫僔儑僫儕僘儉偺栤戣偱偼偁傞偑丄椉崙偑撈棫偵娭楢偟偰偲偔偵暅屆傪嫮挷偟偨偲偄偆榖傕暦偐側偄丅傕偲傕偲僆乕僗僩儔儕傾傗傾儊儕僇偼揱摑傪塢乆偡傞偵偼楌巎偑愺偡偓傞丅偟偨偑偭偰丄揱摑偺曐帩偲偄偆堄枴偱偺乽崙悎乿傪峫偊傞嵺偵丄僆乕僗僩儔儕傾偺撈棫栤戣傪椺偵弌偡偺偼偼側偼偩晄揔愗側偺偱偁傞丅偲偙傠偑丄崙壠偲偟偰偺帺妎敪揥傕崙悎庡媊偱偁傞偲偄偆偙偲偵偟偰偟傑偭偨偐傜丄堷梡偺傛偆側偍偐偟側媍榑傪偟偰偟傑偆偺偱偁傞丅
偙偺傛偆偵巙夑偺崙悎庡媊偼揱摑偺堐帩敪揥偲崙壠偺嫮惙偺椉媊惈傪帩偭偰偄偨丅崙壠偺嫮惙傪栚巜偡偲偡傟偽丄嬤戙壔偼旔偗偰捠傟偢丄偦偺曽岦偼杮幙揑偵揱摑偲徴撍偡傞丅偙偺傆偨偮偼偲偆偰偄娙扨偵偼暲棫偼偱偒側偄丅偵傕偐偐傢傜偢丄斵偼椉幰傪嫮堷偵摍抲偟丄偛傑偐偟偰偟傑偆偲偄偆廳戝側寚娮偑偁偭偨丅偦傟偼傑偨揱摑偲嬤戙偺憡崕偐傜栚傪偦傜偟丄寢嬊偼揱摑偑幪偰嫀傜傟偰廔傢傞偲偄偆寢壥傪彽偔偙偲偵側傞丅
偙偆偄偆偙偲偵側偭偨偺偼丄巙夑偺榑棟惈偺慹偝偵壛偊丄崙悎庡媊偺壓偵墷暷庡媊偺杮壒偑塀偝傟偰偄傞偐傜偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄崙悎庡媊偼揱摑庡媊偱偁傞偲偄偆偟偛偔傕偭偲傕側愢柧傪偟偰偍偒側偑傜丄偄偭傐偆偱丄崙悎庡媊偼惃椡偺曐懚敪揥(寢嬊墷暷壔)偲摨偠偱偁傞偲偄偆傛偆側婏夦側愢柧偵側偭偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅
仭
(1)乽亀擔杮恖亁偑夰書偡傞張偺巪媊傪崘敀偡乿丄亀擔杮恖亁戞擇崋(柧帯擇堦擭巐寧堦敧擔)丅
(2)乽擔杮崙棥偺棟憐揑帠戝搣乿丄亀擔杮恖亁戞屲崋(柧帯擇堦擭榋寧嶰擔)丅
(3)乽亀擔杮恖亁偑夰書偡傞張偺巪媊傪崘敀偡乿丄亀擔杮恖亁戞擇崋(柧帯擇堦擭巐寧堦敧擔)丅
(4)乽擔杮慜搑偺擇戝搣攈乿丄亀擔杮恖亁戞榋崋(柧帯擇堦擭榋寧堦敧擔)丅
(5)乽亀擔杮恖亁偑夰書偡傞張偺巪媊傪崘敀偡乿丄亀擔杮恖亁戞擇崋(柧帯擇堦擭巐寧堦敧擔)丅
(6)摨丅
(7)摨丅
(8)摗尨廐媊乽崙悎榑傪敐偡(懘堦丒懘擇)乿丄亀搶嫗宱嵪嶨帍亁戞巐堦嬨乣擇乑崋(柧帯擇堦擭屲寧堦嬨丄擇榋擔)丅偙傟偼崅栰惷巕亀慼曯偲偦偺帪戙乗傛偣傜傟偨彂娙偐傜乗亁(1994 擭丄拞墰岞榑幮)丄堦幍幍暸偵徯夘偝傟偰偄傞丅側偍丄巙夑偺斀榑偲巚傢傟傞乽姶椳傪揌傟偨傞傕偺乿(柍彁柤)偑亀擔杮恖亁戞榋崋(柧帯擇堦擭榋寧堦敧擔)偵嵹偭偰偄傞偑丄榑棟揑偱偼側偄丅
(9)乽擔杮慜搑偺崙惀偼乽崙悎曐懚巪媊乿偵愶掕偣偞傞傋偐傜偢乿丄亀擔杮恖亁戞嶰崋(柧帯擇堦擭屲寧嶰擔)丅
(10)乽崑廎楍崙偺崌廲撈棫偣傫偲偡傞(偺)堦戝孹岦乿丄亀擔杮恖亁戞擇堦崋(柧帯擇擇擭擇寧嶰擔)丅
(11)摨丅丂 |
| 仭嶰丂旤偺幮夛揑惗妶 / 偦偺夁嫀偲枹棃 |
   丂
丂
|
偲偙傠偱丄巙夑偼偄偭偨偄揱摑(旤)偐傜偳偺傛偆側崙壠幮夛憸傪摫偒弌偦偆偲偡傞偺偐丅斵偺嫮堷側榑朄偺偨傔偵丄傎傫傜偄揙掙揑偵峫偊偰偍偐偹偽側傜側偄偙偺傕偭偲傕廳梫側揰偑傎偲傫偳晜偐傃忋偑偭偰偙側偄丅旤堄幆偺傛偆側寍弍揑娤擮偼偦傕偦傕惌帯幮夛榑偵側傝偵偔偄偲偄偆堄尒傕偁傞(1)丅偟偐偟丄偙偺揰偱庤偑偐傝偵側傞榑暥偑傢偢偐偩偑懚嵼偡傞丅旤堄幆偼夁嫀偵偳偺傛偆側惗妶偲側傝丄枹棃偵偳偺傛偆側幮夛傪昤偙偆偲偡傞偺偐丅
仭(堦)旤偺幮夛揑惗妶 / 偦偺夁嫀
巙夑偼亀擔杮恖亁戞幍崋(柧帯擇堦擭幍寧嶰擔)偵乽戝榓柉懓偺愽惃椡乿偲偄偆榑傪嵹偣偰偄傞丅偙傟傕偝偟偰挿偔偼側偄丅傑偨丄椺偵傛偭偰榑棟偑慹偄偲偄偆斵偺庛揰傕尠挊偱偁傞丅偟偐偟丄擔杮偺旤偺摿幙偼壗偐丄偦偙偐傜弌偰偔傞擔杮恖偺惗妶偲偼偳偺傛偆側傕偺偐丄傛偆偡傞偵擔杮恖偺杮幙偲偼壗偐丄偲偄偆僥乕儅偵偲傕偐偔傕惓柺偐傜挧傫偩傕偺偱偁傞丅摨帪戙偺崙悎庡媊幰偨偪偼堦懱偵揱摑偺曐帩傪嫨傇傢傝偵丄揱摑偺杮幙偲偼側偵偐偵偮偄偰傑偭偨偔掕媊傕愢柧傕偟側偐偭偨傝丄濨枴側愢柧偱嵪傑偣傞恖偑懡偄丅亀擔杮恖亁偵偍偗傞崙悎庡媊偺奣擮偦偺傕偺傪傔偖傞偒傢傔偰廳梫側媍榑偼掅挷偵廔傢偭偰偟傑偭偨偑丄偙傟偼崙悎庡媊幰偨偪偑擔杮偺揱摑傪崙懱偱偁傝丄暘偐傝偒偭偨傕偺偲峫偊偰偄傞偙偲傗丄揱摑偵埬奜帺怣傪帩偰側偄偙偲偑戝偒側尨場偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅偦偺堄枴偱惓柺偐傜擔杮恖偺惗妶偺杮幙傪栤偍偆偲偟偨巙夑偺乽戝榓柉懓偺愽惃椡乿偼拲栚偵抣偡傞丅偦偟偰丄榑棟偺嫮堷偝傗愢柧晄懌偵栚傪偮傇傞偲丄尵傢傫偲偡傞偲偙傠偼擔杮恖偺惛恄惗妶偺妀怱傪傛偔偲傜偊偰偄傞丅偦偺拞怱晹暘偼偙偆偱偁傞丅
乽晇傟惣梞偺奐壔僴悢棟妛傛傝桼棃偡丄悢棟妛偺尮棳僴暘愅側傝丄屘偵惣梞偺挿張偨傞壢妛偼奆暘愅朄偵場傜偞傞傕偺側偟丄壔妛丄棟妛丄惗暔妛丄惎妛丄抧妛偺擛偒懄偪惀傟側傝丄慠傝帶偟偰攪斒暘愅揑偺姶壔僴懽惣幮夛偺帠乆暔乆偵怹擖偣偞傞側偔丄懘嬌張偵帄傟偽堿尟偲側傝丄帺垽偲側傝丄幩棙偲側傝丄攓嬥偲側傝丄廔偵椣棟摴摽偺夡攕傪懍偔傗晇傟柧偗偟丂擔杮偺奐壔僴偼懽惣偺奐壔偲懳妏慄揑偵憡斀懳偣傞傕偺偵偟偰丄懘尮棳僴挷榓傛傝桼棃偡丄挷榓僴懄偪旤弍偺杮尦側傝丄旤弍偲僴暘愅偟偨傞帠乆暔乆傪廤崌揰捲偟丄擻偔嫤崌挷榓偟偨傞傕偺乀堗偵偟偰丄壖椷偽堦恖巑偺柺杄傪暘愅偟偰旣栚傕旤側傝丄旲岥傕旤側傝丄帹傕銰傕幓偔惀傟旤側傝偲偰丄懘恖偺梕巔昁偢偟傕桪旤側傝偲塢傆傋偐傜偢丄枓埲偰旤側傞娤擮僴暘愅偟偨傞帠乆暔乆傪嫤崌挷榓偟偰丄帶偟偰屻敪婲偡傞傕偺側傞傪挜抦偡傞偵懌傟傝丄婛偵慠傝戝榓柉懓偺旤張丄挿張丄悎張僴旤弍揑偺娤擮偵嵼傝丄屘偵巼幃晹偺彫愢偲側傝丄庪栰棳偺奊夋偲側傝丄摡婍惢憿偲側傝丄幗揾偲側傝丄巋恎偲塢傂丄岥庢傝偲塢傂丄帠乆暔乆奆惀傟旤弍揑偺嬻婥傪曪娷偣偞傞傕偺側偟丄慠傟偳傕懘嬌抂偵摓傟偽丄堹辔側傞榓壧偲側傝丄堩妝側傞婥徾偲側傝丄埥僴拑偺搾偵捑揗偟丄憓壴偵峉幏偟丄曐庣偲側傝丄曻楺偲側傝丄懹懩偲側傝丄悋柊偲側傞偺孹岦側偒偵偟傕偁傜偞傞側傝丂梊攜僴丄姼偰崘敀偡丄強堗擔杮偺崙悎僴丄旤弍揑偺娤擮偵懚嵼偡偲丄慠傟偳傕攪斒偺娤擮偼摗尨巵幏尃偺摉戙偵擃庛偲側傝丄愴崙偺帪婜偵戅曕偟丄摽愳巵偺帯悽嶰昐擭偺娫偵曄懃揑偺敪払傪嶌堊偟偨傞傕偺側傝丄慠傜偽戝榓柉懓偺婥晽偑曐庣側傝丄曻楺偲側傝丄懹懩偲側傝丄悋柊偲壔惉偟偨傞僴丄偙傟旤弍揑偺娤擮偑堦帪幾楬偵峴曕偟偨傞偺傒丄惓摴傛傝妘棧偟偨傞傕偺乀傒丄壗傫偧攪斒傪惓懃揑偵敪払偣偟傓傞偺婓朷側偟偲偣傫傗丄乿(2)
巙夑偼挷榓偙偦旤偺杮幙偱偁傝丄擔杮偺揱摑偺妀怱偱偁傞偲尵偆丅旤偺杮幙偑挷榓偵偁傞偐偳偆偐偼偐側傝傓偢偐偟偄栤戣偱偁偭偰丄偡偖傟偨寍弍嶌昳偼偙傟傑偱偺挷榓傗捠擮傪攋傝偮偮丄傛傝崅偄怴偨側挷榓傪嶌傝弌偟偰偄偔偲偙傠偵偦偺恀悜偑偁傞偲傕巚偊傞丅偟偨偑偭偰丄挷榓偩偗偑旤偺杮幙偲偼尵偊側偄丅偟偐偟丄擔杮偺晽搚偼偍偩傗偐偵挷榓偟偨憡杄傪帩偪丄攋揤峳側宨娤偑彮側偔丄傑偨丄変偑崙柉偼偲偐偔彫偝偔傑偲傑偭偰慇嵶側傕偺傪垽娺偡傞孹岦偑偁傞偐傜丄擔杮恖偺旤堄幆丒惛恄偺摿挜偲偟偰偼偐側傝懨摉偱偁傞丅巙夑偵傛傟偽偙偺旤偙偦擔杮偺揱摑偺妀怱偵偁傝丄偦傟偼幮夛惗妶偲偟偰偼挷榓偱偁傞丅嫤挷揑偱傗偝偟偄偲偙傠偑屆棃擔杮恖偺寛掕揑摿挜偱偁傞丅偦偺偐傢傝丄偳偆偟偰傕埨堩暯壐偵棳傟傞丅偮傑傝丄堄巙傗桬婥傗庡懱惈偵朢偟偄偺偱偁傞丅
偙偺揱摑夝庍偼擔杮恖偺挿強摿挜偲丄偁偨傝傑偊偺偙偲偩偑偦傟偲昞棤堦懱偺寚娮庛揰傪側偐側偐傒偛偲偵偲傜偊偰偄傞丅斵偼崙懱傗晲巑摴傪堌宧偟側偑傜丄偟偐偟丄偙偙偱偼懡彮梊憐偲偼堘偭偰偄偭偝偄帩偪弌偟偰偄側偄偺傕傛偄丅擔杮恖偺偍偩傗偐側婥幙偼崙懱巚憐傗晲巑摴傪帪娫揑偵傕奒憌揑偵傕偼傞偐偵挻偊偨挿偔峀偄揱摑偩偐傜偱偁傞丅
嵶偐偔尒傞偲丄巙夑偑偙偺擔杮恖偺摿挜偑椙偐傟埆偟偐傟傕偭偲傕傛偔敪婗偝傟偨偺偼暯埨帪戙偲峕屗帪戙偩偲尵偭偰偄傞偺傕惓妋偱偁傞丅暯埨偺慜婜偲峕屗帪戙偼暯榓偑懕偄偨丅愴崙帪戙偵偼戅曕偟偨偲尵偆偺傕擺摼偱偒傞丅崌愴偑忢懺壔偟偰偄傞帪偵丄晲巑偑偍偩傗偐偱偼巇帠偵側傜側偄偐傜偱偁傞丅
傑偨丄乽幗揾乿丒乽巋恎乿丒乽岥庢傝乿丒乽榓壧乿丒乽拑偺搾乿丒乽憓壴乿偺傛偆側椺偺偁偘曽傪尒傞偲丄巙夑偼擔杮偺暥壔偼偲偐偔彫婍梡偱丄埆偔尵偆偲徕彫偱偁傞偲偄偆昡壙傪壓偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偨偟偐偵丄擔杮恖偼傕偺偯偔傝偑偦偺揟宆偱嵶晹偵偙偩傢傝丄慇嵶偱偰偄偹偄偱偁傞丅偦偺偐傢傝丄戝偒側峔憐椡偵庛偄丅巙夑偼柧帵揑偵尵偭偰偼偄側偄偑丄偦偆偄偆椺偲偟偰偁偘偰偄傞偲偡傟偽丄偙傟傕揑妋偱偁傞丅
偟偐偟丄擔杮恖榑偲偟偰偼杮幙傪撍偄偨巙夑偺榑偵偄偔偮偐偺晄枮偑巆傞丅傑偢丄抁偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅巙夑偺崙悎庡媊偵偮偄偰偺榑暥偼忢偵抁偄丅偣偭偐偔崙悎庡媊幰偑擔杮偺揱摑偺妀怱偵敆傠偆偲偡傞偺偩偐傜丄傕偆彮偟偨傫偹傫側峫嶡偑偤傂偲傕昁梫側偲偙傠偱偁傞丅偨偲偊偽丄擔杮恖偑挷榓揑偩偲偡傟偽偦傟偼側偤側偺偐丄偳偙偐傜棃偰偄傞偺偐偲偄偆峫嶡偑側偄丅巙夑偺偙傟傑偱偺峫偊曽偐傜尵偊偽丄擔杮偺晽搚偑偦偺庡梫側尨場偲偟偰嫇偘傜傟偰傛偄偼偢偱偁傞偑丄晽搚惈傊偺尵媦偼側偄丅傑偨丄柉懓偺嫽朣偑側偔丄扨堦柉懓偱惉傝棫偭偰偄傞偲偄偆擔杮恖撈摿偺楌巎偲惛恄惈偲偺娭學偵傕巚峫傪媦傏偡傋偒側偺偱偁傞偑丄偦偆偄偆尨場暘愅傕側偄丅擔杮偺揱摑偺桼棃婲尮偵偮偄偰偺峫嶡偑偁傟偽偙偺彫榑偺怺偝傗岤傒傕憹偟偨偱偁傠偆偑丄杮棃偺揱摑庡媊幰偱側偄偲偄偆庛偝偑偙偺彫榑傪彫榑偺傑傑偵偲偳傔偰偟傑偭偨丅
傑偨丄榑棟傕慹偄丅偨偲偊偽堷梡晹偱丄惣梞暥柧偺婎慴偼悢棟妛偺暘愅揑側庤朄偵偁傞偲尵偭偰偄傞偺偼偄偪偍偆棟夝偱偒傞偑丄偦偺悢棟揑庤朄偑棙屓庡媊偵側傝丄攓嬥庡媊偵側傝丄晽懎摴摽偺戅攑傪彽偔偲尵偆偵帄偭偰偼棟夝晄擻偱偁傞丅悢棟揑庤朄偑側偤攓嬥庡媊偵側傞偺偐偦偺巇慻傒丒僾儘僙僗傛偆側傕偺偼傑偭偨偔愢柧偝傟偰偄側偄丅偙偺傛偆側榑棟揑丒奣擮揑巚峫偺庛偝偼偲偔偵偙偺彫榑偺嵟屻偵尠挊偱丄椺偵傛偭偰揱摑偲嬤戙傪柕弬偟側偄偐偺傛偆偵嫮堷偵愙懕偡傞榑棟偺旘桇偲偄偆傛傝偛傑偐偟傪傗偭偰偄傞丅偦傟偼師偺傛偆側屄強偱偁傞丅
乽慠偳傕梊攜偼姼偰懽惣偺奐壔傪桝擖偡傋偐傜偢偲榑愢偡傞傕偺偵旕傜偢丄擩傠塻堄掟恑偟偰偙傟傪擔杮崙棥偵棙摫偟丄埲偰擔杮崙悎傪惓懃揑偵敪払偣偟傔丄懘崻嫆傪偟偰桗乆栎屌偨傜偟傔傫偲偡傞傕偺側傝乿(3)
乽崱傗戝榓柉懓偑摿惈拞偺旤張丄挿張丄悎張傪銅愢偟丄攪斒傪曐懚偟妿敪払偣偟傓傞僴擔杮崙婙偺柦柆傪摉戙偺桪彑楎攕応棥偵曐堐偡傞嵟戝寁嵟挿嶔側傞傪愢榑偟偰丄崯張偵崙悎榑偺昅恮傪擺傔傫偲偡傞傕偺側傝乿(4)
屻幰偺堷梡偵偮偄偰尵偆偲丄揱摑傪曐帩偡傞偙偲偑偳偆偟偰偨偩偪偵惗懚嫞憟偵桳棙偵摥偔偱偁傠偆偐丅傕偲傛傝丄揱摑偲偄偊偳傕懡庬懡條偱偁傞偐傜丄側偐偵偼偦偆偄偭偨傕偺傕偁傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄柉懓偺惗偒巆傝傪搎偗傞側傜慡懱偲偟偰偼嬤戙壔偡傞偟偐側偄丅偦偆巚偭偰丄擔杮偼奐崙奐壔傪慖傫偩偺偱偁傞丅媡偵丄揱摑偺曐帩偼堦斒揑偵偼惗懚嫞憟偵晄棙側偺偼柧傜偐側偼偢偱偁傞丅偲偄偆傛傝傕丄偁偊偰偙偺帪戙偵崙悎傪彞偊偨偺偼惗懚嫞憟揑側嬤戙壔偲偼堘偆崙壠幮夛偺曽岦傪柾嶕偡傞偨傔偱偼側偐偭偨偺偐丅揱摑偺堐帩偑惗懚嫞憟偱偺彑棙偵娙扨偵寢傃偮偔傢偗偑側偄丅偦傟傪桪彑楎攕偵傕桳棙偩側偳偲尵偆偺偼丄偄偮傕偺偙偲側偑傜丄巙夑偺抳柦揑側偛傑偐偟偱偁傞丅
偦偟偰丄嵟屻偵丄巙夑偑擔杮偺揱摑偵偦傟傎偳偺垽拝傪帩偭偰偄側偄偙偲偑偙偺榑暥偐傜傕姶偠庢傟傞偙偲傪巜揈偟偰偍偒偨偄丅崙悎庡媊幰偨傞幰丄柍斸敾偵揱摑傪峬掕偟偰偼側傜側偄偑丄寵埆丒斸敾偡傞偩偗偱側偔丄摨帪偵怺偄垽忣傪帩偭偰偄側偗傟偽側傜側偄丅彮側偔偲傕斸敾偲垽忣偺椉幰偑側偗傟偽崙悎庡媊幰偨傞帒奿偑側偄丅偲偙傠偑丄偙偺榑暥偼揱摑偺昡壙偡傋偒偲偙傠傪庢傝弌偦偆偲偡傞庯巪偱彂偐傟偰偄傞偼偢側偺偵丄慡懱揑側報徾偲偟偰偼垽拝傛傝傕寵埆偺姶忣偑嫮偄傛偆偵尒偊傞丅偩偐傜偙偦丄寢榑偺晹暘偱揱摑偵嬤戙傪嫮堷偵愙栘偡傞傛偆側榑朄偑暯婥偱弌偰偔傞偺偱傕偁傝丄偙傟偱偼揱摑傪怱偐傜垽偟恀偵妶偐偡偙偲偼晄壜擻偱偁傞丅怴暦亀傒偐偼亁偺榑愢偺応崌丂擔杮恖偺偍偩傗偐偱挷榓偺庢傟偨幮夛惗妶偵懳偡傞巙夑偺崅偄昡壙傪怴暦亀傒偐偼亁偺榑愢偐傜傕曗嫮偟偨偄丅斵偼亀撿梞帪帠亁偺挊幰偲偟偰丄傑偨亀擔杮恖亁偺摨恖偲偟偰榑抎偵擣傔傜傟偨偡偖偁偲丄偄傢偽屘嫿偵嬔傪偐偞傞宍偱丄壀嶈偺抧曽巻亀傒偐偼亁偺巟墖傪埶棅偝傟丄柧帯擇擇擭堦乑寧偐傜堦擭娫丄嵼嫗偺傑傑偱偦偺庡昅偺栶妱傪堷偒庴偗偨(5)丅摨巻偼怴暦偲偼偄偭偰傕擔姧偱偼側偔丄敿寧姧巻偱偟偐側偄偑丄巙夑偺嫤椡偑巒傑傞偲巻柺偑夵椙偝傟丄寧嶰夞偺敪峴偲側偭偨丅亀傒偐偼亁(戞幍崋丄柧帯擇擇擭嬨寧堦擔)偼堦乑寧偐傜偺巙夑偺嫤椡偲巻柺嶞怴傪戝偒偔愰揱偟丄堦乑寧堦擔偺戞嬨崋偵乽嶰壨抝帣壧乿傪娷傓榑愢傪戞堦柺偵宖嵹偟偨丅偙傟偼柍彁柤偱偁傝丄嶰愡偵嬫暘偝傟偰偄傞偑丄堦愡栚偺偙偺壧偼巙夑偺嶌偲偟偰傛偔抦傜傟偰偍傝丄擇愡栚偑偦偺彂偒壓偟偱側偍偐偮慡懱偑憡屳偵楢娭偟偰偄傞偐傜丄戞嶰愡傕斵偑彂偄偨傕偺偲尒偰娫堘偄側偄偱偁傠偆丅
偙偺戞嶰愡偱巙夑偼悽奅偵屩傞傋偒擔杮恖偍傛傃嶰壨恖偺帠嬈偵偮偄偰偙偆愢柧偟偰偄傞丅
乽姼僥栤僼擔杮恖庬僴悽奅僲楌巎忋僯壗摍僲惉愓儝堚僔僞儖僇丅擔杮恖庬僴悽奅桞堦柍擇僲帠嬈儝惉廇僔僞儖僐僩傾儖僇丅濰僋嵼儕丅巐摏僲桞堦柍擇僫儖帠嬈儝惉廇僔僞儕
丂丂戞堦丂寏懓儝嫏椔僗儖寔滣儝悽奅僲奺恖庬僯愭僠弶儊僥惢憿僔僞儖僐僩
丂丂戞擇丂嶰昐擭僲挿嵨寧娫懽暯徍悽(擇嶰僲彫堦潉儝彍僋)儝惉廇僙僔僐僩
丂丂戞嶰丂擇昐擭娫僯昐屲廫枩僲恖岥儝曐桳僙僔戝搒儝(峕屗)憂愝僙僔僐僩
丂丂戞巐丂慡悽奅僯僥嵟儌嬥嬧儝銅儊僞儖寶抸暔(擔岝昣)儝憿儕弌僙僔僐僩
慠儕帶僔僥寏懓儝嫏椔僗儖寔滣儝弶儊僥惢憿僔僞儖幰儌嶰壨僯惗嶻僔僞儖恖巑僫儕僉丅
嶰昐擭娫僲懽暯徍悽儝惉廇僙僔幰儌嶰壨僯惗嶻僔僞儖恖巑僫儕僉丅擇昐擭娫僯昐屲廫枩僲恖岥儝曐桳僙僔戝搒儝憂愝僙僔幰儌嶰壨僯惗嶻僔僞儖恖巑僫儕僉丅慡悽奅僯僥嵟儌嬥嬧儝銅儊僞儖寶抸暔拞僯昣釰僙儔儖儖幰儌嶰壨僯惗嶻僔僞儖恖巑僫儕僉乿(6)
巙夑偵傛傟偽丄(堦)曔寏梡偺儌儕偺椶偺奐敪丄(擇)峕屗帪戙偺暯榓丄(嶰)昐屲廫枩搒巗峕屗偺憂愝丄(巐)擔岝昣丄偙偺巐偮偑嶰壨恖丄擔杮恖偺悽奅偵屩傞帠嬈偱偁傞丅崙悎庡媊幰偑枩悽堦宯偺崙懱傪嫇偘側偐偭偨偺偼丄偝偡偑偵斵偺傆傞偝偲嶰壨偲偄偆搚抧暱傪峫偊偨偐傜偐傕偟傟側偄丅戞堦偺曔寏梡儌儕偺奐敪傗戞巐偺擔岝昣偼偳偆偐偲巚偆偑丄戞擇偺嶰昐擭偵嬤偄暯榓偲丄偦傟偵枾愙偵偐偐傢傞戞嶰偺昐枩搒巗峕屗偺憂愝偼丄嶰壨恖偺偍崙帺枬揑梫慺偑弌偰偄傞偲偟偰傕懨摉偱偁傠偆丅偙傟偼巙夑偺尵偆傛偆偵悽奅巎揑偵尒偰傕擔杮恖偑屩偭偰傛偄偙偲偲巚傢傟傞丅晲巑摴偩偺崙懱巚憐偩偺偲尵偆傛傝傕偼傞偐偵晛曊揑壙抣偑偁傞丅嶰壨恖側傜偤傂偲傕晲巑摴傪弌偟偨偄偲偙傠傪丄巙夑偼擔杮恖偺悽奅偵摿昅偡傋偒揱摑偲偟偰偦偺暯榓惈傪偁偘偨偺偱偁傞丅
仭(擇)旤偺幮夛揑惗妶 / 偦偺枹棃
偦偟偰丄崙悎庡媊偼偄偐側傞枹棃傪丄崙壠幮夛峔憐傪帩偮偺偱偁傠偆偐丅巙夑偼摉慠幁柭娰偺晳摜夛偵徾挜偝傟傞傛偆側埨庤偺墷壔庡媊偑晄枮偱丄搶嫗傗搒夛偑斏塰偟丄抧曽偑崲媷偟偰偄傞忬嫷傪桱椂偟丄堦斒偺崙柉偺岾暉傗斏塰偙偦崙悎庡媊偵偐側偆丄偟偽偟偽偦偆偄偆岥傇傝傪傕傜偟偰偄傞(7)丅偟偐偟丄偦偺偨傔偵採彞偝傟偨偺偼怋嶻嫽嬈偱偁傝丄奀奜傊偺恑弌偱偁傝丄杅堈傗堏柉偱偁偭偨丅偙偆偄偆曽朄偵傛偭偰崙柉偺惗妶傪朙偐偵岾暉偵偡傞偙偲偼傓傠傫壜擻偱偁傞偲偟偰傕丄偦傟偼惣梞偺柾曧丒嬤戙壔偦偺傕偺偱偁偭偰丄崙悎庡媊偱偼側偄丅偦傟偱偼揱摑偐傜枹棃傪愗傝奐偄偨帠偵偼側傜側偄丅揱摑偐傜枹棃傪峫偊傞偲偄偭偨偄偳偆偄偆幮夛偑弌偰偔傞偺偐丄偙偺揰偵偮偄偰巙夑偼傎偲傫偳摎偊偰偔傟偰偄側偄偑丄亀擔杮恖亁憂姧崋(柧帯擇堦擭巐寧嶰擔)宖嵹偺乽乽擔杮恖乿偺忋搑傪镾偡乿偵偦偺庤偑偐傝偑懡彮偁傞丅偙傟偼帪娫揑偵偼愭弎偺乽戝榓柉懓偺愽惃椡乿(亀擔杮恖亁戞幍崋丄柧帯擇堦擭幍寧嶰擔)傛傝傕彮偟慜偱偁傞丅偙偺乽乽擔杮恖乿偺忋搑傪镾偡乿偼師偺傛偆側愰尵傪偟偰偄傞丅
乽桞檅偔僴斵偺乽僇僤儔乿偺崻丄榥偺栞丄堦嵨堦夞捔庣嵳楃偺愡丄敒姛傪歍傞傪埲偰恖惗戞堦偺夣妝偲側偟丄擔梉嵜慸偺泔棛偑幠栧傪澣偔枅偵換偪怱傪棎偟鋄傪棊偟丄埥僴旐堖傪揟偟偰擵偑撀愑偵廩偰丄曣僴昦彴偵夌偟偰帣僴婹姦偵嫨傃丄宱塩嶴郬丄堄彔惁慳偨傞偙偲桺傎
丂丂乬Give me three grains of corn, mother,
丂丂丂丂Only three grains of corn;
丂丂丂It will keep the little life l have,
丂丂丂丂Till the coming of the morn,
丂丂丂I am dying of hunger and cold, mother,
丂丂丂丂Dying of hunger and cold,
丂丂丂And half the agony of such a death
丂丂丂丂My lips have never told.乭
丂丂乬The king has lands and gold, mother,
丂丂丂丂The king has lands and gold,
丂丂丂While you are forced to your empty breast
丂丂丂丂A skeleton babe to hold, 乗
丂丂丂A babe that is dying of want, mother,
丂丂丂丂As I am dying now,
丂丂丂With a ghastly look in its sunken eye,
丂丂丂丂And famine upon its brow丏乭
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乗Miss Edwards丏
偺擛偒丄懡悢柉恖傪偟偰愑偰偼榋擔偺嬑曌堦擔偺媥宔傪妉偣偟傔丄妴傕岲偟崯梉懞棊偺弔塉丄枥乆偲偟偰巺偺擛偔漗傪銋傞偺揰揌丄惡嬚拀偵帡偨傞棥丄旣愥偺晝榁偑柰枋嬀傪攃傝堦梩偺怴暦巻傪揥傋棃傝丄壠懓偺帣懛傪楩曈偵廤傔擵傪島撉偟偗傞屻丄嫟偵実偊偰斢巂偺怘戩偵廇偒丄墺沎丄晇晈丄帣懛抍烺偲偟偰憡梚偟丄枮斦偺涿漪塉傪懷傃偰悏怓揌傫偲偡傞張丄妿堦偺寋擏傪徿枴偟旊傫偱丄嵗傠偵朞偒棃傟偽丄旐敮峠壴偺擛偒敧嵥偺彫懛僴墺沎偺彠椼偵廬弴偟偰換偪婲棫偟丄壜垽偺壒嬋傕偰堦嬋偺乽孨偑戙乿傪楴彞偡傟偽枮幒偺妳嵮桹偔偑擛偔丄堊傔偵嵮宭抾膺偺轾數傪偟偰嬃婲偣偟傓偰傆寁傝偟偒偺惔暉夣妝偲丄抭椡棙曋偲傪攷庢偣偟傔傫偲梸偡傞幰側傝乿(8)
塸帊傪娷傓堷梡晹偺慜敿偼尰忬傪崘敪偟偨傕偺丄屻敿偼栚巜偡傋偒棟憐嫬偲偄偆峔惉偵側偭偰偄傞丅堦斒崙柉偺斶嶴側惗妶傪崘敪偟偰偄傞偺偲丄塸帊(Miss Edwards 偲偄偆嶌幰丄帊恖傜偟偒彈惈偵偮偄偰偼傛偔傢偐傜側偄偑)傪尨岅偺傑傑堷梡偟偰偄傞偺傪尒傞偲丄亀擔杮恖亁偵堦擭傎偳愭棫偭偰悽偵弌偨亀崙柉擵桭亁憂姧崋傪忺偭偨摽晉慼曯偺乽歭屇崙柉擵桭惗傟偨傝乿(亀崙柉擵桭亁戞堦崋丄柧帯擇乑擭擇寧堦屲擔)傪柧傜偐偵嫮偔堄幆偟偨彂偒曽偱偁傞丅
慼曯偼偙偺婰擮偡傋偒榑愢偺拞偱乽変偐晛捠偺恖柉偼庘澍偨傞屒懞丄姖壆偺棥丄攋憢偺壓丄巻摃塭敄偔丄楩壩扽椻偵丄擇嶰偺晝榁憡懳偟偰戺庰傪孹傞偵夁偒偡丄乿(9)偲丄暥柧奐壔偺壎宐偵偁偢偐傟側偐偭偨堦斒偺崙柉偺昻偟偔傢傃偟偄惗妶傪昤偒弌偟偰丄柧帯惌晎傪斸敾偟丄傑偨丄廔傢傝偺曽偱儈儖僩儞偺亀幐妝墍亁偺堦愡傪尨岅偺傑傑敳偒弌偟偰丄擔杮偺崿撟偨傞忬嫷偵偨偲偊偨丅
巙夑偼慼曯偺傗傝曽傪偳偆傗傜恀帡偨傛偆偱偁傞丅Miss Edwards 偺帊偼婹偊偲姦偝偱巰偺偆偲偡傞幰偑丄曣傛丄偣傔偰僩僂儌儘僐僔嶰棻傪丄偦傟偱梻挬傑偱業柦傪偮側偛偆偲婅偆偒傢傔偰斶嶴側岝宨傪塺偭偨傕偺偱偁傞丅恖乆偺嫻偵嫮偔慽偊傞丄偄偝偝偐愵摦揑側忣宨傪梡堄偟丄傑偨僴僀僇儔偵塸帊傪尨岅偱堷梡偟偰傒偣傞偲偄偆傗傝曽偼慼曯傪堄幆偟偨傕偺偱偁傠偆丅偲傕偁傟丄慜敿偼愵忣揑偱偼偁傞偑丄斾妑揑偁傝偒偨傝側尰忬斸敾偱丄偲偔偵怴慛枴偼側偄丅
偟偐偟丄枹棃恾偵偁偨傞堷梡晹偺屻敿偼巙夑偺撈帺惈偑弌偰偄偰側偐側偐柺敀偄丅巙夑偑棟憐偲偟偰昤偄偨傕偺偼丄懡偔偺擔杮恖偑怱偺尨晽宨偲偟偰忢偵婣偭偰偄偔偲偙傠偱偁傞丅偦傟偼丄傑偙偲偵偍偩傗偐偱丄抔偐偔丄偮偮傑偟傗偐側壠懓偱偁傝丄偺偳偐偱旤偟偄懞棊偺晽宨偱偁傞丅偔傢偊偰丄拞崙偺壠懓娭學偑恊偵懳偡傞巕偺岶傪尩偟偔梫媮偡傞偺偵懳偟丄擔杮偺応崌偼恊偑巕傪偄偮偔偟傓偙偲傪戝曄楉偟偄傕偺偲偟丄偦傟傪摴摽揑媊柋偵傑偱崅傔偰偄偭偨偲尵傢傟傞偑丄偦偺堄枴偱傕慶晝曣傗恊偺巕(懛)偵懳偡傞帨垽偑堨傟傞壠懓偺昤幨偼偄偐偵傕擔杮揑偱偁傞丅
偙偆偄偆偝偝傗偐偱丄偟偐偟丄暯榓偱偁偨偨偐偄丄恊巕偺忣偑堨傟傞惗妶偙偦擔杮恖偺揱摑偱偁傞偙偲傪丄傕偟巙夑偑塻偔帺妎偟偨偆偊偱丄偙偺恖乆偺惗妶傪柧帯惌晎偺嬤戙壔偵懳偟偁偔傑偱傕庣傠偆偲偟偨偺偱偁傟偽丄斵偼傒偛偲偵揱摑傪枹棃偵搳塭偡傞偙偲偵惉岟偟偨偲尵偊傞丅偙偆偄偆偍偩傗偐側偮偮傑偟偄惗妶偺梚岇偐傜偼丄暯榓偲偐挷榓偲偐偁傞庬偺暯摍偲偐庛幰偺曐岇偲偄偆傛偆側崙壠幮夛揑尨棟偑斾妑揑柍棟側偔摫偒弌偣傞偱偁傠偆丅偦傟偼丄孯旛傪憹嫮偟丄庛幰傪媇惖偲偡傞傛偆側柧帯惌晎偺嬤戙壔偵懳峈偡傞棫攈側幮夛崙壠偺峔憐偵堢偰忋偘傞偙偲偑偱偒傞丅傑偨丄嫮堷側暥柧壔傗搒巗壔偵懳偟丄擾懞偺曐岇丄偁傞偄偼搒巗偲擾懞偺挷榓偺庢傟偨敪揥偲偄偆庡挘偵傕揥奐偱偒傞丅恎偺忎偵崌傢側偄嬤戙壔偼偡傞側丄崙柉偺惗妶偵攝椂偣傛偲偄偆崙悎庡媊幰偺庡挘偑擔杮恖偺揱摑揑惗妶傪摜傑偊偮偮怴偟偄崙壠幮夛偺棟擮偲偟偰戀摦偟偰偄傞偱偼側偄偐丅巙夑偼偙偆偄偆宍偱揱摑傪怴偟偄幮夛偺拞偵惗偐偟丄柧帯惌晎偺嬤戙壔偲偼偪偑偭偨崙壠偺枹棃傪峔憐偟偰傒傟偽傛偐偭偨偺偱偁傞丅
偨偩丄栤戣偼偍偩傗偐偱偮偮傑偟偔帨垽偵枮偪偨懞棊偺惗妶傪庣傟偲偄偆庡挘偑丄偨傫側傞枹棃恾偱偼側偔丄傑偝偟偔揱摑(挷榓)傪枹棃偵搳塭偟偨宍偵側偭偰偄傞偙偲傪巙夑偑偳傟傎偳怺偔帺妎偟偰偄偨偐偱偁傞丅偙偺揰偵嫮偄媈栤偑巆傞丅擔杮偺揱摑傪堄幆偼偟偰偄偨偱偁傠偆偑丄偦傟傪惗偐偦偆偲偄偆塻偄帺妎偺傕偲偵彂偐傟偨傛偆偵偼撉傔側偄丅崙悎庡媊幰偼丄偨傫側傞枹棃恾偱偼側偔丄揱摑傪枹棃偵惗偐偡帋傒傪怺偔堄幆偟偰彂偐側偗傟偽側傜側偄丅偦傟偱偙偦崙悎庡媊幰偱偁傞丅偟偐偟丄巆擮側偑傜偦偆柧夣偵偼撉傔側偄偺偱偁傞丅傓偟傠丄偨傑偨傑偙偆偄偆庡挘偑惗傑傟偨偩偗偲偄偆婥攝偑擹偄丅偩偐傜偙偦丄偣偭偐偔偺枹棃恾傕傆偨偨傃庢傝忋偘傜傟傞偙偲偼側偐偭偨丅傕偟丄巙夑偑杮暔偺揱摑庡媊幰偱偁偭偨側傜偽丄偙偺峔憐傪娙扨偵曻婞偡傞偙偲偼側偐偭偨偱偁傠偆丅揱摑傪枹棃偵妶偐偡偙偺帋傒傪孞傝曉偟孞傝曉偟採埬偟丄怺壔偝偣偰偄偭偨偼偢偱偁傞丅
寢嬊丄巙夑偼偙傟埲崀丄揱摑偲枹棃傪寢傃偮偗傞嶌嬈傪偮偒偮傔偰峫偊傞偙偲偑側偐偭偨丅偦傟偼斵偑擔杮偲擔杮恖偺偨傔偵偝傑偞傑側採埬傗峔憐傪偟側偐偭偨偲偄偆堄枴偱偼傑偭偨偔側偄丅斵偼廔惗丄擔杮偺彨棃偺偨傔偵偠偮偵惛椡揑偵峴摦偟敪尵偟偰偄傞丅偨偩丄枹棃偵偮偄偰偺偝傑偞傑側採埬偑偳偆揱摑偲寢傃偮偔偺偐丄偳偆揱摑傪惗偐偟偨傜朙偐側枹棃偑峔憐偱偒傞偺偐偲偄偆娤揰偐傜峫偊偰偄傞傛偆偵偼尒偊側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟偼丄寢嬊偺偲偙傠丄揱摑傊偺垽拝偑埬奜愺偔丄偟偨偑偭偰丄揱摑傪惗偐偡偙偲偵偙偩傢傝傪帩偭偰偄側偄偐傜偱偁傞丅偦傟偼惣梞暥柧傊偺斸敾偑庛偔丄偮偄惣梞傪慉朷偟偰偟傑偆偙偲偲棤暊偱傕偁傞丅巙夑偼偮偄偵崙悎庡媊幰丒揱摑庡媊幰偵側傝偒傟側偐偭偨偺偱偁傞丅
巙夑偼亀撿梞帪帠亁偺拞偱擔杮恖偼朻尟怱偑庛偄偲扸偄偰偄傞(10)丅偙傟偼擔杮恖偑偍偩傗偐偱暯榓惈偑偁傞偲偄偆偙偲傪丄媡偐傜昞偟偨傕偺偲尒傞偙偲偑偱偒傞丅偮傑傝丄傛偔尵偊偽丄挷榓傗傗偝偟偝傪岲傓幰偼丄偳偆偟偰傕戝抇偝偵寚偗丄朻尟怱偵傕朢偟偄偆傜傒偑偁傞丅偟偐偟丄擔杮恖偼朻尟怱偑朢偟偄偲尵偭偰廔傢偭偰偟傑偭偰偼崙悎庡媊幰偵偼側傟側偄丅朻尟怱偼朢偟偄偑丄偍偩傗偐偱偁傞丄暯榓惈偑偁傞丄偦傟傪枹棃偵惗偐偦偆偲峫偊傞偲偙傠偵崙悎庡媊偺壜擻惈偑弌偰偔傞偺偱偁傞丅偦偙偱偼偠傔偰丄揱摑偲枹棃傪寢傃偮偗傞抂弿偑尒偊偰偔傞丅巙夑偵偼偦偺抂弿偑偁傞偑丄揥奐偟偒傟偰偄側偄丅
仭
(1)怉庤捠桳乽亀崙柉擵桭亁丒亀擔杮恖亁乿丄徏杮嶰擵夘曇亀惌嫵幮暥妛廤(柧帯暥妛慡廤丂37)亁(1989擭丄拀杸彂
朳)丄巐乑嬨暸丅
(2)乽戝榓柉懓偺愽惃椡乿丄亀擔杮恖亁戞幍崋(柧帯擇堦擭幍寧嶰擔)
(3)摨丅
(4)摨丅
(5)巙夑廳乽嶰壨怴暦巻忋僯墬働儖梊乿丄亀傒偐偼亁戞嬨崋(柧帯擇擇擭堦乑寧堦擔)丅亀傒偐偼亁怴暦偵偮偄偰偼丄挿嶁堦徍乽廳偲亀傒偐偼怴暦亁乗巙夑廳偺恖偲巚憐傪媮傔偰(嘦)乗乿丄亀搶奀垽抦怴暦亁(1981擭10寧28擔)丄塅堜朚晇亀巙夑廳丂恖偲懌愓亁(1991擭丄尰戙僼僅儖儉)丄嶰幍乣嬨暸嶲徠丅
(6)乽柍彁柤(巙夑廳偲悇掕)榑愢乿丄亀傒偐偼亁戞嬨崋(柧帯擇擇擭堦乑寧堦擔)丅
(7)乽擔杮慜搑偺崙惀偼乽崙悎曐懚巪媊乿偵愶掕偣偞傞傋偐傜偢乿丄亀擔杮恖亁戞嶰崋(柧帯擇堦擭屲寧嶰擔)丄乽怴撪妕憤棟戝恇偵強朷偡乿(柧帯擇堦擭屲寧嶰擔)丄亀慡廤亁戞堦姫丄嬨乗堦乑暸側偳嶲徠丅屻幰偼亀慡廤亁偱偼亀擔杮恖亁戞嶰崋(柧帯擇堦擭屲寧嶰擔)強嵹偲側偭偰偄傞偑丄摨崋偵偼尒摉偨傜偢丄弌揟偼晄柧偱偁傞丅
(8)乽亀擔杮恖亁偺忋搑傪镾偡乿丄戞堦師亀擔杮恖亁戞堦崋(柧帯擇堦擭巐寧嶰擔)丅
(9)摽晉慼曯乽歭屇崙柉擵桭惗傑傟偨傝乿丄亀崙柉擵桭亁戞堦崋(柧帯擇乑擭擇寧堦屲擔)丅
(10)亀撿梞帪帠亁(弶斉)丄幍屲乣榋丄堦嬨乑乣堦暸丅丂 |
| 仭寢榑 / 曐庣庡媊偵偍偗傞揱摑棟夝偺寚擛偲榑棟惈偺晄嵼 |
   丂
丂
|
巙夑偺崙悎庡媊偺娤擮傪尒偰偒偨偑丄偦偺庡挘偼偐側傝偡偖傟偨撪梕傪帩偪丄偦偟偰丄揱摑傪枹棃偵妶偐偦偆偲偡傞帋傒偵傕傑偙偲偵嫽枴怺偄晹暘偑偁傞丅偙傟傜偺揰偱斵偼懠偵敳偒傫弌偨曐庣庡媊幰偱偁偭偨偲尵偭偰傛偄丅偟偐偟丄斵偼奣擮惈丒榑棟惈偑庛偔丄傑偨丄偄偐偵傕偨傑偨傑揱摑庡媊幰偵側偭偨偩偗偲偄偆偲偙傠偑偁傞偨傔丄偦偺崙悎庡媊偼搑拞偱曻婞偝傟偰偟傑偭偨丅揱摑傪揑妋偵棟夝偟(偙偺揰偱偼巙夑偼傑偟偱偁傞偑)丄偦傟傪榑棟揑偵昞尰偡傞巚憐幰偺晄嵼偑丄擔杮偺揱摑庡媊傪傑偙偲偵昻偟偄傕偺偵偟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅
丂 |
| 仭乽擔杮夛媍乿 |
   丂
丂
|
仭1. 乽擔杮夛媍乿偲偼
乽擔杮夛媍乿(柤梍夛挿丗 尦嵟崅嵸敾強挿姱 嶰岲払丄 夛挿丗奜岎昡榑壠丒埱椦戝妛柤梍嫵庼 揷媣曐拤塹丄 暃夛挿丗搶嫗戝妛柤梍嫵庼丒昡榑壠 彫杧宩堦楴丄恄幮杮挕憤挿 揷拞湋惔傎偐)偲偄偆擔杮嵟戝偺峜幒梼巀塃梼崙悎庡媊抍懱偑懚嵼偟傑偡丅
1997擭5寧30擔偵憂愝丄楌戙夛挿偼丄弶戙偵儚僐乕儖憂嬈幰捤杮岾堦丄戞2戙偵愇愳搰攄杹廳岺嬈夛挿堫梩嫽嶌丄戞3戙偵尦嵟崅嵸敾強挿姱 嶰岲払丄 偄偢傟傕峜幒悞攓巚憐傪帩偮婃柪側塃攈暅屆曐庣庡媊幰偱偡丅
崙夛媍堳慻怐偵乽擔杮夛媍崙夛媍堳崸択夛乿丄抧曽媍堳慻怐偵乽擔杮夛媍抧曽媍堳楢柨乿傪帩偪丄慡搒摴晎導偵妶摦嫆揰傪抲偔丅偝傜偵乽峜幒偺揱摑傪庣傞崙柉偺夛乿側偳傪愝棫偟丄摨孹岦偺巚憐傪帩偮懡悢偺抍懱偲偺楢実傪怺傔偰偄傑偡丅
偟偐偟丄巹偼偙偺抍懱偺巚憐傗妶摦偵偼偍偧傑偟偝偡傜妎偊丄旕忢偵嫮偄寽擮傪書偐偞傞傪摼傑偣傫丅 抐屌偲偟偰斀懳偺棫応傪偲傝傑偡丅擔杮偺彨棃傪晄岾偵偡傞偦偺婋尟搙丒埆幙惈偼丄抦傜偸娫偵憹怋揮堏偡傞埆惈庮釃(娻)偦偺傕偺偱偡丅
壛偊偰巒枛偑埆偄偺偼丄夛堳傗巟墖幰偑堦掕悈弨埲忋偺幮夛揑塭嬁椡傪帩偮惌帯壠丒抦幆恖丒暥壔恖丒昡榑壠摍偱偁傝丄扨弮側塃梼抍懱偲偼堎側傞偲偄偆偙偲偱偡丅
|
仭2. 乽擔杮夛媍乿偺揹榖庢嵽
9寧28擔丄偙偺婰帠傪彂偔偵嵺偟乽擔杮夛媍乿偺帠柋嬊偵揹榖庢嵽偟傑偟偨丅 偟偐偟墳懳偵慖偽傟偨楅栘朸巵偼偁傑傝偵柍擻側偺偐丄柉娫抍懱偱偁傞偙偲傪弬偵丄夞摎晄梫偲幷傞偺偑惛堦攖偺抰愘側懳墳偵廔巒丅 偙偪傜偺庡挘傗巜揈偵丄偒偪傫偲斀榑丒曎柧傪偟側偄偲摉曽偺偦傟傜傪擣傔偨偙偲偵側傝傑偡傛偲偺嵞嶰偺妋擣偵懳偟丄乽偟傚偆偑側偄偱偡偹偳偆偧偍岲偒側傛偆偵乿偲偺庯巪偺敪尵偑摨巵偐傜傕悢夞偁傝傑偟偨丅偦偺寢壥丄僂僃僽僒僀僩忋偺栤戣売強偺婰嵹撪梕偼帠幚偱偼側偔嫊婾偩偲乽擔杮夛媍乿帺恎偑擣傔偨偙偲偵側傝傑偟偨丅偳偆傗傜乽擔杮夛媍乿偼丄夛堳丒巟墖幰偺悽榖傗弾柋丒懳奜愜徴傪扴偆帠柋曽僗僞僢僼偵偼丄桪廏側恖嵽偑廤傑傜側偄傛偆偱偡丅
堦曽丄乽媨撪挕乿偵傕壗搙偐揹榖庢嵽偟偨偙偲偑偁傝傑偡偑丄偄偢傟傕桪廏側僗僞僢僼偑惤幚偵懳墳偟偰偔傟偨偨傔丄怺傒偺偁傞桳堄媊側堄尒岎姺偑偱偒傑偟偨丅
|
仭3. 乽擔杮夛媍乿偺栚揑偲峴摦尨棟丂峜幒傪拞怱偲偟偨崙壠宍惉傪栚巜偡
埲壓偑乽擔杮夛媍乿偑栚巜偡傕偺偱偁傝丄峴摦尨棟偺崻姴偵偁傞嵟傕婎杮揑側峫偊曽偱偡丅
乽峜幒傪宧垽偡傞崙柉偺怱偼丄愮屆偺愄偐傜曄傢傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅偙偺峜幒偲崙柉偺嫮偄鉐偼丄婔懡偺楌巎偺帋楙傪忔傝墇偊丄傑偨朙偐側擔杮暥壔傪惗傒弌偟偰偒傑偟偨丅懡條側壙抣偺嫟懚傪擣傔丄恖娫偲帺慠偲偺嫟惗傪幚尰偟偰偒偨傢偑柉懓偼丄堦曽偱揱摑暥壔傪懜廳偟側偑傜奀奜暥柧傪愊嬌揑偵媧廂丄摨壔偟偰妶椡偁傞崙傪憂憿偟偰偒傑偟偨丅125戙偲偄偆桰媣偺楌巎傪廳偹傜傟傞楢柸偲偟偨峜幒偺偛懚嵼偼丄悽奅偵椶椺傪傒側偄傢偑崙偺屩傞傋偒曮偲偄偆傋偒偱偟傚偆丅巹偨偪擔杮恖偼丄峜幒傪拞怱偵摨偠柉懓偲偟偰偺堦懱姶傪偄偩偒崙偯偔傝偵偄偦偟傫偱偒傑偟偨丅偟偐偟丄愴屻偺傢偑崙偱偼丄偙偆偟偨旤偟偄揱摑傪寉帇偡傞晽挭偑挿偔偮偯偄偨偨傔丄摿偵庒偄悽戙偵側傟偽側傞傎偳丄偦偺壙抣偑擣幆偝傟側偔側偭偰偄傑偡丅巹偨偪偼丄峜幒傪拞怱偵丄摨偠楌巎丄暥壔丄揱摑傪嫟桳偟偰偄傞偲偄偆楌巎擣幆偙偦偑丄乽摨偠擔杮恖偩乿偲偄偆摨朎姶傪堢傒丄幮夛偺埨掕傪摫偒丄傂偄偰偼崙偺椡傪戝偒偔偡傞尨摦椡偵側傞偲怣偠偰偄傑偡丅崙嵺壔偑恑傒丄幮夛偑戝偒偔曄摦偟傛偆偲傕丄忢偵梙傞偑偸屩傝崅偄揱摑偁傞崙偑傜傪丄柧擔偺擔杮偵揱偊偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅巹偨偪偼偦傫側婅偄傪傕偭偰丄峜幒傪宧垽偡傞偝傑偞傑側崙柉塣摦傗揱摑暥壔傪戝愗偵偡傞帠嬈傪慡崙偱庢傝慻傫偱傑偄傝傑偡丅乿
偲偙傠偑丄偙偙偵弎傋傜傟偨偙偲偼丄偙偲偛偲偔帠幚偵斀偡傞傕偺偱偡丅椺偊偽暥拞偵偁傞
1乽峜幒傪宧垽偡傞崙柉偺怱偼丄愮屆偺愄偐傜曄傢傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅偙偺峜幒偲崙柉偺嫮偄鉐偼丄婔懡偺楌巎偺帋楙傪忔傝墇偊丄傑偨朙偐側擔杮暥壔傪惗傒弌偟偰偒傑偟偨丅乿
2乽巹偨偪擔杮恖偼丄峜幒傪拞怱偵摨偠柉懓偲偟偰偺堦懱姶傪偄偩偒崙偯偔傝偵偄偦偟傫偱偒傑偟偨丅乿
3乽峜幒傪拞怱偵丄摨偠楌巎丄暥壔丄揱摑傪嫟桳偟偰偄傞偲偄偆楌巎擣幆偙偦偑丄摨偠擔杮恖偩偲偄偆摨朎姶傪堢傒ゥゥゥ乿
偙傟傜123偼壥偨偟偰恀幚偱偟傚偆偐丠
幚偼偙偆偟偨峫偊偼丄峜幒悞攓幰傗峜崙巎娤怣曭幰偵偁傝偑偪側丄峳搨柍宮側栂憐(斵傜偺摢偺拞偵偩偗懚嵼偡傞乽偍壴敤乿)偵夁偓傑偣傫丅乽擔杮夛媍乿偼丄柌憐揑側揤峜怣嬄傪峴摦尨棟偲偡傞丄夦偟偘側僇儖僩怣嬄廤抍偲偄偆傋偒偱偡丅偦偺捁敡偺棫偮傛偆側敄婥枴埆偝偼丄壗偵傕偨偲偊傛偆偑偁傝傑偣傫丅偦偟偰摉慠偺偛偲偔乽擔杮夛媍乿偼丄乽桋崙恄幮乿偲偦偺晅懏巤愝偱偁傞愴巎攷暔娰乽梀廇娰乿偺庡挘傗妶摦傪巟墖偟傑偡丅
|
仭4. 惌帯傊偺嫮偄夘擖丂埨攞撪妕偺戝恇 8妱嬤偔偑乽擔杮夛媍乿怣幰
偙偺夦偟偘側僇儖僩怣嬄廤抍偑丄惌帯偺悽奅傪彊乆偵偱偼偁傞傕偺偺拝幚偵怤棯偟偮偮偁傝傑偡丅堦椺傪嫇偘傟偽丄乽擔杮夛媍乿偺惌奅怤峌傊偺嫶摢毱偲偟偰乽擔杮夛媍崙夛媍堳崸択夛乿偑偁傝丄夛挿丗暯徖驵晇丄 夛挿戙峴丗妟夑暉巙榊丄 暃夛挿丗埨攞怶嶰丒愇攋栁丒彫抮昐崌巕傎偐丄 姴帠挿丗壓懞攷暥偲偄偭偨嬶崌偱偡丅偦偟偰290恖嬤偄崙夛媍堳偑嶲壛偟偰偄傑偡丅
偝傜偵椺傪嫇偘傟偽丄壓婰偺捠傝尰嵼偺戞3師埨攞撪妕20柤偺妕椈拞丄15柤偺妕椈偑乽擔杮夛媍乿偵擖夛偟怣幰偲側偭偰偄傑偡丅
1.埨攞怶嶰憤棟丂2.杻惗懢榊暃憤棟鄸睉妬@3.崅巗憗昪憤柋憡丂4.娸揷暥梇奜憡丂5.壓懞攷暥暥壢憡丂6.墫嶈嫳媣岤楯憡丂7.朷寧媊晇娐嫬憡丂8.拞扟尦杊塹憡丂9.悰媊執姱朳挿姱丂10.抾壓榡暅嫽憡丂11.嶳扟偊傝巕岞埨埾堳挿丂12.嶳岥弐堦壂撽丒杒曽憡丂13.娒棙柧宱嵪嵞惗憡丂14.桳懞帯巕彈惈妶桇憡丂15.愇攋栁抧曽憂惗憡
婛偵乽擔杮夛媍乿偼丄帪偺惌尃偵偑偭偪傝偲怘偄崬傫偱偄傞偺偱偡丅
側偍丄擖夛偟偰偄側偄偺偼丄忋愳梲巕朄柋憡丂懢揷徍岹崙搚岎捠憡丂椦朏惓擾椦悈嶻憡丂媨郪梞堦宱嵪嶻嬈憡偺4妕椈偺傒丅墦摗棙柧僆儕儞僺僢僋扴摉憡偼晄柧丅
偙偺傛偆偵庱憡偲懡偔偺妕椈丄崙夛媍堳偑偙偺乽擔杮夛媍乿偲怺偄娭學偵偁傝丄偙傟偱偼梌搣帺柉搣偲埨攞惌尃帺懱偑偦偺嫮偄塭嬁壓偵抲偐傟丄擔杮偺惌帯偑乽擔杮夛媍乿偵傛偭偰媿帹傜傟偰偟傑偆晐傟偑偁傝傑偡丅乽擔杮夛媍乿偺傛偆側僇儖僩怣嬄廤抍偑丄岞尃椡偵怘偄崬傒偦傟傪枴曽偵偮偗偰偟傑偆偲丄慡偔庤偵晧偊側偄婋尟側忬嫷偵擔杮傪捛偄崬傒傑偡丅 偦偺揰偱偼岞尃椡偵揋懳偟偨僆僂儉恀棟嫵偺曽偑傑偩傑偟偩偭偨偲偝偊尵偊傞偱偟傚偆丅
偝傜偵乽擔杮夛媍乿偼丄惌帯壠偩偗偱側偔丄昡榑壠丄妛幰丄儅僗僐儈娭學幰偲傕屳偄偵塭嬁傪梌偊崌偆恊枾側娭學偵偁傝傑偡 丅
偙偆偟偨揰傪峫偊傟偽丄乽擔杮夛媍乿栤戣偼丄埨曐朄惂傗尨敪傪傕偼傞偐偵椊偖戝偒側惌帯栤戣偱偡丅偁傑傝栚棫偨側偄摦偒偩偗偵丄梋寁偵婋尟偱偡丅
|
仭5. 乽擔杮夛媍乿偑傕偨傜偡彨棃傊偺婋尟惈丂愴慜偺崙壠懱惂傊偺夞婣
偙偆偟偨乽擔杮夛媍乿偑惌帯傊偺塭嬁椡傪憹偟懕偗傞偲丄偄偮偟偐寷朄傗惌帯懱惂偑丄愴慜偲摨條側傕偺偵暅屆偟丄乽晄宧嵾乿傗乽帯埨堐帩朄乿偑嵞惂掕偝傟丄尵榑昞尰偺帺桼傗巚憐怣忦偺帺桼偑戝偒偔惂尷偝傟傞帠懺偵側傝偐偹傑偣傫丅偦偆側偭偨傜丄巹偺偙偺傛偆側婰帠傕彂偗側偔側傝傑偡丅
偦偟偰嵞傃揤峜偑恄梎(傒偙偟)偵扴偓忋偘傜傟丄揤峜傊偺拤惤偑嫮惂偝傟丄偦偺柦椷偵偼愨懳暈廬偲偄偆宍偱嫮尃揑側惌帯偑峴側傢傟傞婋尟惈偑偁傝傑偡丅偮傑傝愴慜偺揤峜傪捀揰偵偟偨崙壠懱惂乽戝擔杮掗崙乿傊偺夞婣偱偡丅柧恗傗摽恗丄暥恗偼丄乽扴偖恄梎偼寉偔偰僷乕偑偄偄乿(彫戲堦榊偑庱憡慖弌偵嵺偟偰弎傋偨柤尵)偵僺僢僞儕偺偼傑傝栶偩偗偵丄梋寁偵儕僗僋偑崅偄偲尵偊傑偡丅偦偟偰嵞傃乽戝搶垷嫟塰寳乿偺幚尰偲偄偆尒壥偰偸柌偵岦偐偭偰丄柍杁側崙壠塣塩傪嫵嵈丒梼巀偡傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅
乽擔杮夛媍乿偺夛堳傗巟墖幰偺拞偵偼丄偁偐傜偝傑偵媽寷朄(戝擔杮掗崙寷朄丒柧帯寷朄)傊偺夞婣傪庡挘偡傞攜偑戝惃偄傑偡丅傑偨僕僃儞僟乕僼儕乕偵偼愨懳斀懳偺棫応偱偁傝丄愴慜偺壠懓惂搙丒嫵堢惂搙偺暅屆傪慱偭偰偄傑偡丅斵傜偺庡挘傪昞偡僉乕儚乕僪偼丄峜幒拞怱庡媊丄桋崙恄幮丄崙壠庡媊丄帪戙嶖岆(傾僫僋儘僯僘儉)側偺偱偡丅
垽偡傞擔杮傪彨棃晄岾偵偟側偄偨傔偵偼丄傒側偝傫偼傑偢偼乽擔杮夛媍乿偺懚嵼傪抦傝丄偦偺幚懺偲婋尟惈丒埆幙惈傪廫暘棟夝偟偰偄偨偩偔偙偲偑廳梫偱偡丅斵傜偼丄峜幒曭廽峴帠傗奺庬島墘夛丒曌嫮夛丒彂愋丒恖揑僱僢僩儚乕僋摍傪妶梡偟丄嬌傔偰岻柇偵惃椡奼戝偺偨傔偵偦偦偺偐偟傪峴側偄傑偡丅
偙偺乽擔杮夛媍乿偺姪桿偺埆鐓偝偼暲戝掞偱偼偁傝傑偣傫丅奆偝傫偺恎嬤偵傕擡傃婑偭偰棃傑偡偺偱廫暘偛拲堄偔偩偝偄丅摿偵婇嬈僩僢僾偐傜偺乽柦椷乿偲偟偰丄幮堳偑夛崌傗島墘夛丄慖嫇妶摦偵嫮惂揑偵摦堳偝偣傜傟傞働乕僗傕懡偄傛偆偱偡丅
傕偟乽擔杮夛媍乿偑丄乽擔杮偼愮屆偺愄偐傜忢偵崙柉偼峜幒傊偺宧垽偺擮偵枮偪偰偄偨乿側偳偲嫊婾偺榖傪偡傞偙偲偵傛偭偰丄擖夛姪桿傗婑晅嬥廤傔傪偟偨側傜丄偦傟偼傕偼傗嵓媆偱偁傝斊嵾偱偡丅 傑偨夛幮偺乽嬈柋柦椷乿偺宍傪偲偭偰幮堳偵妶摦傪嫮梫偡傞偺傕丄傕偪傠傫廳戝側斊嵾峴堊偱偡丅
|
仭6. 壽戣
埲忋偼乽擔杮夛媍乿偺乽巚憐偲恖偲偦偺塭嬁乿偵娭偟偰偺傕偺偱偡偑丄崱屻偼摉慠乽僇僱偺棳傟乿偺埮偵傕岝傪摉偰傞昁梫偑偁傝傑偡丅
傑偨丄偙傟傎偳戝偒側栤戣偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄僥儗價丒戝怴暦側偳儊僕儍乕側儅僗儊僨傿傾偑媦傃崢偵側傝丄乽擔杮夛媍乿偺偙偲傪庢傝忋偘傛偆偲偟傑偣傫丅
丂 |
| 仭乽擔杮夛媍乿巎娤偺忔傝墇偊曽 |
丂 |
仭1丄偦偺惈奿偺朶業偱側偔丄庡挘傊偺斸敾偑戝帠偱偁傞
擔杮夛媍偲偼壗偐丅傒偢偐傜尵柧偟偰偄傞傛偆偵丄乽崙柉摑崌偺徾挜偱偁傞峜幒傪懜傃丄崙柉摨朎姶傪熂梴偡傞乿丄乽変偑崙杮棃偺崙暱偵婎偯偔乽怴寷朄乿偺惂掕傪悇恑偡傞乿偙偲側偳傪塣摦曽恓偲偟偨抍懱偱偡丅
擔杮夛媍偑庡挘偟偰偒偨尦崋朄傗垽崙怱傪柧婰偟偨嫵堢婎杮朄夵惓側偳偑幚尰偝傟偰偄傞偙偲丄尰嵼偺埨攞撪妕偺妕椈偺8妱偑擔杮夛媍偵壛柨偟偰偄傞偙偲側偳偐傜丄擔杮夛媍偑埨攞惌尃傪摦偐偟偰惌嶔傪幚尰偝偣偰偄傞側偳偲尵偆恖傕偄傑偡丅柧帯寷朄壓偺擔杮傪尰戙偵嵞尰偡傞偲偄偆恀偺偹傜偄傪塀偟偰嶔摦偡傞嬌塃廤抍丄僇儖僩廤抍丄堿杁廤抍偩偲巜揈偡傞恖傕偄傑偡丅
巹傕丄擔杮夛媍偺塭嬁椡傪偳偆偍偝偊偰偄偔偐偲偄偆偙偲偵丄廳戝側娭怱傪婑偣偰偄傑偡丅堦曽丄偦偺塭嬁椡偑丄尃椡偲偺偮側偑傝傗塀偟帠偺岻傒偝丄堿杁側偳偵傛偭偰峀偑偭偰偄傞偲偼巚偄傑偣傫丅擔杮夛媍偼丄偠偮偵惓乆摪乆偲傒偢偐傜偺庡挘傪揥奐偟偰偍傝丄偦偺庡挘偺撪梕偑崙柉偺怱傪懆偊傞偙偲偵傛偭偰塭嬁椡傪奼戝偟偰偄傞偲偄偆偺偑丄儕傾儖側傕偺偺尒曽偩偲峫偊傑偡丅
偮傑傝丄彮側偔側偄崙柉偼擔杮夛媍偺塃梼揑側庡挘傪梕擣偟偰偄傞偺偱偁偭偰丄偦偺塃梼揑側惈奿傪偄偔傜朶業偝傟偰傕斵傜偵偲偭偰偼捝偔傕偐備偔傕側偄偺偱偡丅偦傟偩偗帪戙偑塃偵婑偭偰偟傑偭偨偙偲偺斀塮偱偟傚偆丅
偄傑戝帠側偺偼丄斵傜偺庡挘偺拞恎傪斸敾偟偰偄偔偙偲偱偡丅偟偐傕丄斵傜偺庡挘偑巟帩傪摼偨棟桼傪愻偄弌偟丄崻尮揑側斸敾傪揥奐偡傞偙偲偱偡丅
仭2丄塭嬁椡傪奼戝偟偰偒偨偺偼楌巎擣幆傪傔偖偭偰偱偁傞
斸敾偡傋偒庡挘偺側偐偱丄傕偭偲傕戝帠側傕偺偺堦偮偑楌巎擣幆傪傔偖傞栤戣偱偡丅擔杮夛媍(慜恎偺乽擔杮傪庣傞崙柉夛媍乿乽擔杮傪庣傞夛乿傕娷傔)偑崙柉偺側偐偱塭嬁椡傪帩偪巒傔偨偺偼丄傑偝偵楌巎擣幆偵娭偡傞尵榑傪捠偠偰偺偙偲偩偭偨偐傜偱偡丅
擔杮偺愭偺愴憟傪乽怤棯愴憟乿偩偲偟偨1993擭偺嵶愳岇鄦庱憡偺敪尵丄怤棯偲怉柉抧巟攝偵懳偟偰偍榣傃偲斀徣傪昞柧偟偨懞嶳晉巗庱憡択榖偵懳偟偰丄擔杮夛媍偼栆楏側斸敾傪揥奐偟丄偦偺屻傕宲懕揑偵摨條偺庡挘傪偟偰傑偟偨丅偦偺婎挷偼丄乽擔杮偺愴憟偼帺懚帺塹偺愴偄偩偭偨乿乽擔杮偼傾僕傾偺夝曻偵婑梌偟偨乿乽擔杮偼挬慛敿搰偺恖傃偲傪戝愗偵偟偨偺偱偁偭偰丄墷暷偺夁崜側巟攝偲偼堎側傞乿乽搶嫗嵸敾偼彑幰偺嵸偒偩乿側偳偲偄偆傕偺偱偟偨丅
偙偆偟偨庡挘偼丄塃攈偺側偐偱偼愴屻柆乆偲庴偗宲偑傟偰偒偨傕偺偱偡偑丄偁偺愴憟傪怤棯偩偲偼擣傔側偐偭偨楌戙帺柉搣惌尃偺傕偲偱偼丄偁傑傝昞柺壔偡傞偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅嵶愳敪尵丄懞嶳択榖偑弌偝傟丄惌帯偺儗儀儖偱帺柉搣棳偺愴憟擣幆偑媡揮偟偦偆偩偭偨偺偱丄塃攈偑懚嵼堄媊傪偐偗偰摤偄傪奐巒偟偨偺偱偡丅
尵榑柺偩偗偱偼偁傝傑偣傫丅偙偺崰偐傜丄擔杮夛媍偑庡摫偟偰丄塃梼揑側庡挘傪宖偘偨奨摢僨儌傕峴傢傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅媍夛傊偺惪婅側偳傕慻怐揑側傕偺偲側偭偰偄偒傑偡丅愴屻偺擔杮偱偼丄乽塣摦乿偲尵偊偽嵍攈丄妚怴攈偑傗傞傕偺偲偄偆偺偑偍寛傑傝偱偟偨偑丄擔杮夛媍偼偦偙偵曄壔傪傕偨傜偟偨傢偗偱偡丅
偦偺寢壥丄擔杮偺悽榑偼丄戝偒偔塃傊偲摦偒傑偟偨丅堦曽偱幮夛搣偑徚柵偟丄幮柉搣傕媍惾偑尭傝懕偗偰偄傞偙偲丄懠曽偱埨攞怶嶰巵偺傛偆側楌巎娤傪帩偮恖娫偑崙惌慖嫇偱楢愴楢彑偟偰偄傞偙偲側偳丄嵍偺戅挭偲塃偺怢挿偼柧傜偐偱偡丅
偱偼擔杮夛媍偺庡挘偺壗偑崙柉偺怱傪懆偊偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅変乆偼壗傪慽偊傞傋偒側偺偱偟傚偆偐丅
仭3丄搶撿傾僕傾偱偼乽懳擔嫤椡幰乿偵斲掕揑側僀儊乕僕偑側偄棟桼
偦偺栤戣傪峫偊傞忋偱丄乽懳擔嫤椡幰乿偲偄偆尵梩傪庢傝忋偘偰傒傑偟傚偆丅偙偺尵梩偑丄娯崙傗拞崙偱偼丄怤棯幰偱偁傝巟攝幰偱偁傞擔杮偵壛扴偟偨恖傪巜偡傕偺偲偟偰丄姰帏偵斲掕揑側堄枴偱巊傢傟偰偄傞偙偲偼榑傪樦偪傑偣傫丅椉崙偱偼丄擔杮偺怤棯傗怉柉抧巟攝傪斸敾偡傞偺偵丄壗偺徹柧傕晄梫偱偡丅
偟偐偟丄偱偼丄搶撿傾僕傾偼偳偆側偺偱偟傚偆偐丅偨偲偊偽丄價儖儅巎偵徻偟偄崻杮宧巵偼丄亀掞峈偲嫤椡偺偼偞傑亁(娾攇彂揦)偱師偺傛偆偵岅偭偰偄傑偡丅
乽塸崙偺怉柉抧偩偭偨價儖儅偱偼丄廆庡崙偺塸崙傗愴帪拞偺愯椞幰偱偁傞擔杮偵懳偟嫤椡偟偨惌帯丒峴惌僄儕乕僩偑丄偦偺偙偲偺偨傔偵愴屻偵儅僀僫僗偺僀儊乕僕傪攚晧傢偝傟偨傝丄旕擄偝傟偨傝丄斲掕偡傋偒婰壇偲偟偰崙壠偵傛偭偰嫮挷偝傟偨傝偡傞側偳偺帠幚偼尒傜傟側偄乿
変乆偼丄拞崙偱偁傟搶撿傾僕傾偱偁傟丄擔杮偼怤棯偟偨崙壠偩偲偄偆擣幆傪傕偭偰偄傑偡丅偦偺擣幆偼惓偟偄偺偱偡丅偟偐偟丄摨偠怤棯偱偁偭偰傕丄撈棫崙壠偱偁傞拞崙偵懳偡傞怤棯偲丄偦傟埲慜偵墷暷偺怤棯傪庴偗偰怉柉抧巟攝偝傟偰偄偨搶撿傾僕傾偵懳偡傞怤棯偲偱偼丄偍偺偢偐傜惈奿偑堘偭偰偄傑偡丅
偙偙偱偼徻偟偔彂偒傑偣傫偑丄搶撿傾僕傾偺恖傃偲偺側偐偵偼丄墷暷偵傛傞怉柉抧巟攝偐傜敳偗弌偡偨傔偵丄怴偨側巟攝幰偲側偭偨擔杮傪棙梡偡傞偲偄偆傛偆側巚榝傕偁傝傑偟偨丅幚嵺偵傕丄愴憟偑廔傢偭偰嵞傃巟攝幰偲偟偰栠偭偰偒偨墷暷傪懪偪搢偡偨傔丄擔杮偵傛偭偰偄偭偨傫偼墷暷偺巟攝偐傜扙偟偨帠幚傪棙梡偟偨偺偱偡丅偦偺偨傔丄搶撿傾僕傾偺恖傃偲偺側偐偐傜傕丄擔杮偺愴憟偑傾僕傾偺夝曻偵偮側偑偭偨偲偄偆惡偑惗傑傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅
擔杮夛媍偼丄偦偆偄偆搶撿傾僕傾偺惡傪棙梡偟偰丄擔杮偺愴憟傪峬掕偡傞尒曽傪峀偘傛偆偲偟傑偡丅偦傟偵懳偟偰丄擔杮偺怤棯傪廳帇偡傞恖偨偪偼丄偦偆偄偆惡偑偁傞偙偲傪柍帇偟偨傝丄斲掕偟偨傝偡傞傗傝曽傪偲偭偰偒偨偲巚偄傑偡丅偟偐偟丄偦偺惡偑偁傞偙偲偼帠幚偱偡偐傜丄柍帇偟偨傝丄斲掕偡傞傗傝曽偱偼丄擔杮夛媍偺塭嬁椡傪嶍偖偙偲偼偱偒側偐偭偨偺偩偲巚偄傑偡丅
仭4丄岝偲塭傪摑堦偟偨楌巎偺尒曽傪採帵偡傞偙偲偑戝帠偩
偙傟偼丄傎傫偺堦椺偱偡丅懠偵傕摨偠傛偆側帠椺偑偨偔偝傫懚嵼偟偰偄傑偡丅
偦傟傜傪娧偔傕偺偼壗偐丅扨弮壔偡傞偙偲偵側傝傑偡偑丄擔杮夛媍偼丄擔杮偺楌巎偺側偐偺乽岝乿偺晹暘傪庢傝忋偘丄偦傟偑擔杮偺楌巎偺慡懱憸偱偁傞偐偺傛偆偵昤偄偰偒傑偟偨丅堦曽丄偦傟傪斸敾偡傞恖傃偲偼丄乽塭乿偺晹暘傪擔杮嬤尰戙巎偺杮幙偱偁傞偐偺傛偆偵庡挘偟偰偒傑偟偨丅偙偆偟偨峔恾偺側偐偱偼丄崙柉悽榑偲偄偆偺偼丄暦偄偰偄偰婥帩偪偺傛偄乽岝乿偺嫮挷偺傎偆偵孹偔偙偲偵側偭偰偟傑偭偨偺偩偲姶偠傑偡丅
擔杮偺嬤尰戙巎偑丄偨偩塭偽偐傝偺楌巎偩偭偨偐偲偄偆偲丄偦傟偼帠幚偵斀偟傑偡丅墷暷偑傾僕傾慡懱傪怉柉抧偵偟傛偆偲婇傫偱偄偨側偐偱丄擔杮偑撈棫傪庣傝敳偄偨偲偄偆堦揰偩偗偱傕丄屩傞傋偒偙偲偩偲巚偄傑偡丅偨偩丄偦偺岝傕丄傒偢偐傜偑挬慛敿搰傪巟攝偡傞偙偲偵側偭偨偲偄偆塭偲枾愙晄壜暘偩偲偄偆偙偲側偺偱偡丅
偄傑媮傔傜傟傞偺偼丄岝偲塭傪摑堦偝偣傞曽朄榑偩偲姶偠傑偡丅挊柤側楌巎妛幰偱偁傞媑揷桾巵傕丄師偺傛偆偵巜揈偟偰偄傑偡(乽愴憟愑擟榑偺尰嵼乿)丅
乽愴屻楌巎妛偼丄愴憟愑擟栤戣偺夝柧偲偄偆揰偱偼妋偐偵戝偒側尋媶惉壥傪偁偘偨丅偟偐偟丄崙嵺揑宊婡偵怗敪偝傟傞宍偱尋媶僥乕儅傪愴憟愑擟栤戣偵堏峴偝偣傞偙偲偵傛偭偰丄偦傟傑偱偵愊傒偁偘傜傟偰偒偨廳梫側榑揰偺宲彸傪懹偭偨偙偲丄愴憟愑擟栤戣丄摿偵愴憟斊嵾尋媶偵杤擖偡傞偙偲偵傛偭偰丄曽朄榑揑側栤偄捈偟傪扞忋偘偵偟偨偙偲側偳丄愴憟愑擟栤戣傊偺岦偒崌偄曽帺懱偺撪偵丄廳梫側栤戣揰偑偼傜傑傟偰偄偨偙偲傕帠幚偱偁傞丅愴憟愑擟栤戣傪楌巎妛偺壽戣偲偟偰偄偭偦偆怺傔偰備偔偨傔偵偼丄偙偺栤戣偺夝柧傪拞怱揑偵扴偭偰偒偨愴屻楌巎妛偦偺傕偺偺偁傝曽偑丄崱偁傜偨傔偰丄斸敾揑偵峫嶡偝傟側偗傟偽側傜側偄偺偩偲巚偆乿丂
丂 |
| 仭塃梼 1 |
   丂
丂
|
仭塃梼抍懱
塃梼巚憐傪宖偘傞惌帯抍懱傑偨偼惌帯揑惃椡偱偁傞丅
塃梼揑傑偨偼曐庣揑巚憐傗抍懱偼丄屆棃傛傝偁傜備傞帪戙丒抧堟偵懚嵼偟偰偄傞丅17悽婭埲崀偺孾栔巚憐傗丄18悽婭埲崀偺嶻嬈妚柦偵傛傞嬤戙壔偵傛傝丄恑曕庡媊傗帺桼庡媊傗屄恖庡媊側偳偺巚憐偲丄惌帯揑丒宱嵪揑偵偼帒杮庡媊傗幮夛庡媊側偳偑恑揥偡傞偲丄偦傟傜偵媈栤傪帩偪斀懳偡傞懳峈惃椡偲偟偰塃梼巚憐傗曐庣庡媊傪宖偘傞抍懱傕柧妋壔偟偰偄偭偨丅
塃梼抍懱偺懡偔偼丄偦偺崙傗抧堟偺暥壔揑丒楌巎揑丒揱摑揑側壙抣娤傗丄偦傟傜偵婎偯偔幮夛拋彉傗幮夛懱惂傪巟帩偟偰偍傝丄僫僔儑僫儕僘儉傗柉懓庡媊傗崙壠庡媊偁傞偄偼抧堟揑側嫟摨懱傪廳帇偟偨懡悢偺巚憐傗塣摦偑懚嵼偟偰偄傞丅
偟偐偟乽塃梼抍懱乿偺岞幃側掕媊傗斖埻偼懚嵼偟偰偍傜偢丄帺徧偡傞抍懱丄帺徧偟側偄偑偦偆懠徧偝傟傞応崌偑懡偄抍懱丄偁傞偄偼惌帯抍懱偲偟偰偺幚懺傪敽傢側偄偑朶椡抍側偳偑揈敪夞旔偺偨傔婾憰偟偰偄傞抍懱丄峏偵偼妚怴攈傗嵍梼抍懱偐傜儗僢僥儖挘傝偝傟偨抍懱傕彮側偔側偔條乆偱偁傞丅惌帯揑僗儁僋僩儖忋偺埵抲偯偗偱偼丄捠忢偼曐庣庡媊丄尃埿庡媊丄慡懱庡媊丄孨庡庡媊丄廤抍庡媊丄偁傞偄偼斀嫟庡媊側偳偺巜岦傪帩偮応崌偑懡偄丅
斀嫟庡媊偵偮偄偰偼丄 崙嵺彑嫟楢崌亖摑堦嫵夛( 暥慛柧巵偺愝棫)偲嫟摤偡傞晹暘傕偁傞丅
|
仭擔杮偺塃梼
擔杮偺塃梼抍懱偼丄捠忢偼娤擮塃梼丄惓摑塃梼丄恗嫚塃梼丄妚怴塃梼(崙壠幮夛庡媊)丄奨愰塃梼丄廆嫵塃梼丄怴塃梼(柉懓攈)丄峴摦偡傞曐庣側偳偵暘椶偝傟傞丅傑偨乽塃梼抍懱乿偺屇徧偼偁偔傑偱嵍梼偲偺斾妑偵偍偗傞柤徧偱偁傞偨傔丄帺傜塃梼抍懱偲昗炘偡傞偙偲偼側偔堦斒偵偼乽垽崙幰抍懱乿偲偄偆昞尰傪偡傞(楢棈婡娭偺抍懱柤偵傕乽垽崙乿偺暥帤偑尒傜傟傞)丅
揱摑揑側堄枴偺塃梼巚憐偼丄揱摑傗暥壔偺壙抣傪廳帇偡傞曐庣庡媊偱偁傝丄擔杮偺塃梼偑巚憐揑側尮棳傪庡挘偡傞偺偼嬤悽偺崙妛傗丄柧帯堐怴偺嶰寙偲栚偝傟側偑傜傕巑懓偺斀棎偱偁傞惣撿愴憟傪婲偙偟偨惣嫿棽惙側偳偱偁傞丅偙傟傜偼丄惣梞壔偵偮側偑傞嬤戙壔傗丄偦傟傪悇恑偡傞拞墰惌晎傪寈夲偟丄抧堟偺廆嫵傗楌巎傗廗懎偺撈棫惈傗宲懕惈傪廳帇偡傞丄曐庣揑丒揱摑揑丒抧曽庡媊揑側塃梼挭棳偲偟偰丄埲屻偺惌晎傗帒杮壠偺梡怱朹揑側乽娤擮塃梼乿傗丄幮夛庡媊偵懳峈偟丄崙撪偺晠攕傪彍嫀偡傞乽妚怴乿傪懪偪弌偡乽妚怴塃梼乿偲偼暿偵懚嵼偟偰偄偔偙偲偵側傞丅
擔杮偱偼丄幵椉傪梡偄偰墂慜傗奨摢丄姱岞挕嬤曈傗峌寕懳徾偲側傞婇嬈傗廤夛応偺廃曈摍偱戝壒検偵傛傞峈媍丄愰揱妶摦傗岞摴傪戝壒検偺壒妝傪棳偟偰憱峴偡傞乽奨愰塃梼乿偑峀偔抦傜傟乽揟宆揑側塃梼乿偲尒傜傟偑偪偱偁傞偑丄偙偺妶摦曽朄偼1970擭(徍榓45擭)撪奜偵偁傜傢傟偨傕偺偱偁傝丄堦晹偺抍懱偼朶椡抍偲昞棤堦懱偺塃梼抍懱(恗嫚塃梼丄塃梼昗炘抍懱)偱偁傝丄巚憐柺偱偺惌帯塣摦偵偼愊嬌揑偱偼側偔丄婇嬈嫲妳傗惌帯壠桳柤恖嫲妳側偳傪栚揑偲偟偨偄傢備傞婾憰塃梼抍懱偺応崌偑偁傞丅
|
仭楌巎
仭柧帯埲崀
擔杮偺塃梼巚憐偑妋棫偡傞偺偼柧帯帪戙偱偁傞偑丄偦偺尮棳偼丄峕屗帪戙屻婜偺崙妛幰偺堦晹偑昗炘偟偨崙悎庡媊傗峜崙巎娤側偳偑嫇偘傜傟傞丅傑偨擔杮偺塃梼抍懱偺婲尮偼丄1868擭(柧帯尦擭)1寧3擔偺柧帯堐怴(墹惌暅屆偺戝崋椷)偩偲栚偝傟傞丅偙傟傪14擭慿偭偨1854擭(埨惌尦擭)3寧31擔偵丄峕屗枊晎14戙彨孯摽愳壠掕偑嵔崙傪揚攑偟偨帪丄嬑墹斀枊偺惌帯壠偑惃椡傪憹偟偨丅枊枛偵惗傒弌偝傟偨戝検偺懜墹攈偺巙巑偺慻怐妶摦偼丄堐怴偺惉岟偵傛傝偄偭偨傫偼惌尃偵慻傒崬傑傟徚幐偡傞丅
夋婜偲側傞偺偼惇娯榑帠審傪嫬偲偟偨嬨廈丒嶳岥偱偍偙偭偨堦楢偺巑懓斀棎偱偁傞丅惣嫿傪宧垽偟崙妛丒庨巕梲柧妛偺幚慔傪婅偄側偑傜傕巰偵偦傃傟丄偁傞偄偼庢傝巆偝傟偨幰偨偪偺嵼栰廤抍偑1881擭(柧帯14擭)偵摢嶳枮傜偑寢惉偟偨尯梞幮偱偁傝丄偙傟偑擔杮偺娤擮塃梼偺偼偠傑傝偲偝傟偰偄傞丅
1880擭戙偵帺桼柉尃塣摦偑敪惗偟丄寖偟偄斀惌晎塣摦偑惙傝忋偑偭偨丅柧帯惌晎偼帺桼柉尃塣摦傪岞尃椡偱庢傝掲傑傞偲偲傕偵丄偟偽偟偽擟嫚廤抍偵惌帯抍懱傪寢惉偝偣丄柉尃塣摦壠偺妶摦傪朩奞丒抏埑偡傞庤抜偲偟偨丅偦偺屻丄幮夛庡媊塣摦偺崅傑傝偲嫟偵楯摥憟媍丄彫嶌憟媍偑奺抧偵峀傑傞偲丄惌奅丄嵿奅偐傜偺梫朷偵傛傝丄擟嫚宯偺惌帯抍懱偑偦傟傜偺塣摦朩奞丄抏埑塣摦偵戝偒側栶妱傪壥偨偟偨丅偙偺宯摑傪堷偔抍懱偼丄乽擟嫚塃梼乿(朶椡抍宯塃梼)側偳偲屇偽傟傞丅
1910擭戙偵側傞偲幮夛庡媊巚憐偑擔杮偵傕攇媦偟偰偒偨丅惌晎偼偙傟偵帺桼柉尃塣摦埲忋偺嫅斲斀墳傪帵偟丄岞尃椡偲擟嫚廤抍偱庢傝掲傑傝傗朩奞傪峴偭偨丅偙傟傜偺擟嫚廤抍偼柧帯尦孧偨偪偲傕寢傃偮偒偑嫮偔丄帺桼庡媊傗幮夛庡媊偵懳峈偟偰丄崙壠傪梚岇偡傞塃梼抍懱傪寢惉偟偨丅
傑偨丄嬤戙壔偺夁掱偱惗偠偨彅柕弬傪夝寛傪栚巜偡惌帯抍懱偲偟偰丄暯摍傪栚巜偡2偮偺棳傟偑惗偠偨丅堦偮偼幮夛庡媊妚柦偵傛傝暯摍傪栚巜偦偆偲偡傞棳傟丅傕偆堦偮偼揤峜偺壓偵枩柉偼暯摍偱偁傞偲偡傞棳傟偱偁傞丅偙傟偼丄擔惔愴憟傗擔業愴憟傪攚宨偵丄拞壺柉崙偺惉棫傗棝巵挬慛偺嬤戙壔偵娭梌偟偨戝傾僕傾庡媊偺挭棳偵忔傞丅傑偨丄幮夛庡媊偺塭嬁傕偲偱崙壠庡媊偵傛傞傾僕傾偺嬤戙壔偺幚尰傪栚巜偟偨偨傔偵幮夛庡媊偲偺愙嬤傪傕婲偙偟丄偦偺巚憐挭棳偼偄傢備傞崙壠幮夛庡媊傗幮夛庡媊偲偺暋嶨側塭嬁偺尦偵偁偭偨丅巚憐揑孹岦偼丄昁偢偟傕斀嫟庡媊偱偼側偔丄斀墷暷怓偑嫮偐偭偨丅偙偺宯摑傪堷偔抍懱偼丄乽惓摑塃梼乿側偳偲徧偝傟傞丅
嵿奅偺梫朷偵棫偪楯摥塣摦傪抏埑偡傞乽擟嫚塃梼乿(朶椡抍宯塃梼)偲丄棟憐傪宖偘偰杴傾僕傾揑妶摦傪峴偆乽惓摑塃梼乿偼丄愴慜偺塃梼抍懱偺2偮偺戝偒側宯摑偱偁偭偨丅偙傟傜偼棙奞偑堦抳偡傞嵿奅丄孯晹偐傜帒嬥墖彆傪庴偗偰妶摦傪偟偰偄偨偲揷拞棽媑偼弎傋偰偄傞丅
悽奅嫲峇帪戙偵偼丄塃梼傕幮夛庡媊偐傜嫮偄塭嬁傪庴偗丄堦晹偺崙妛偺宯摑傪堷偔擔杮偺曐庣巚憐壠傗嵍梼偐傜偺揮岦慻偺拞偐傜崙壠幮夛庡媊巚憐傪帩偮僌儖乕僾偑尰傟偨丅偙偺宯摑偼妚怴塃梼偲尵偄丄棨孯偺峜摴攈偵嬤偄柉懓庡媊揑側娤擮塃梼偲丄棨孯偺摑惂攈偵嬤偄妚怴塃梼偑懳棫傪婲偙偡傛偆偵側傞丅偙傟傜偼擔撈埳嶰崙孯帠摨柨掲寢帪偺棨奀孯偺懳棫傗丄屲丒堦屲帠審丄擇丒擇榋帠審側偳偵傕塭嬁傪梌偊偨丅塃梼偼戝搶垷愴憟(懢暯梞愴憟)捈慜偵掲寢偝傟偨擔撈埳嶰崙孯帠摨柨偵偮偄偰偼巟帩偡傞棫応傪嵦偭偨偑丄僀僞儕傾偺僼傽僔僘儉傗僪僀僣偺僫僠僘儉偵懳偟偰偼丄帺桼庡媊傗幮夛庡媊偲摨條偺奜棃巚憐偲庴偗巭傔傜傟丄搶曽夛側偳偺堦晹偺抍懱傪椺奜偲偟偰戝敿偐傜偼柍娭怱傕偟偔偼攔愃偺懳徾偲偟偰懆偊傜傟偰偄偨丅
仭戞擇師悽奅戝愴廔寢屻
1945擭(徍榓20擭)偵擔杮惌晎偼崀暁暥彂偵挷報偟偨(戞擇師悽奅戝愴偱偺擔杮偺崀暁)丅GHQ偵傛傝懡偔偺塃梼抍懱偼孯崙庡媊偺壏彴偲尒側偝傟丄抏埑傪庴偗偨丅傑偨丄塃梼抍懱偺僷僩儘儞偱偁偭偨孯晹偺徚柵丄嵿敶偺夝懱丄擾抧夵妚偵傛傞抧庡憌偺杤棊偵傛傝丄帒嬥柺偱傕尩偟偄嬊柺偵捛偄崬傑傟偨丅偙傟偵傛傝妚怴塃梼偺棳傟傪媯傓柉懓攈塃梼(棨孯宯)偼悐戅偟丄恊暷塃梼偺棳傟偑憹偊偰偄偭偨丅
仭椻愴帪戙
傾儊儕僇孯傪拞怱偲偡傞楢崌崙孯偺愯椞壓偵抲偐傟偨愴屻崿棎婜偵偼丄GHQ庡摫偱忋偐傜偺柉庡壔偑恑傔傜傟偨傕偺偺丄搶嫗嵸敾偑廔傢傞偲崱搙偼椻愴偑巒傑傝斀嫟庡媊偵傛傞乽媡僐乕僗乿偑恑傒丄岞怑捛曻傪庴偗偨幰偑懕乆偲惌奅偵暅婣偟偨丅偡傞偲丄擔杮偺嵞孯旛壔偑専摙偝傟傞傛偆偵側傝丄岞怑捛曻夝彍傗挬慛愴憟傊偺擔杮偺嫤椡偲偟偰媽孯恖傊偺朄柋晎摿暿怰嵏嬊偺暦偒庢傝側偳偑偍偙側傢傟丄偦傟傑偱捑栙傪曐偭偰偄偨媽孯恖傗塃梼妶摦壠傕敪尵傪偍偙側偆傛偆偵側偭偨丅嵞孯旛偵傓偗偨媽孯恖偺慻怐揑側妶摦偼1951擭(徍榓26擭)8寧偺戝検偺捛曻夝彍埲崀偵妶敪壔偟丄偍偍傓偹埲壓偺5攈偑揥奐偝傟偨丅
1. 峜孯暅妶傪庡挘偟偨恀嶈恟嶰榊傜偺乽峜摴攈乿
2. 嬶懱揑嵞孯旛埬傪採帵偺偆偊楢崌崙懁偵嫤椡傪採帵偟偨壓懞掕傜偺乽惓媊攈乿
3. 楢崌崙偲偺嫤椡傪曄愡幰偲尒側偟偙傟偵懳峈偟偨娾斎崑梇傜偺乽摑惂攈乿
4. 斀嫟墖徲偺偨傔偵戜榩攈暫傪寁夋偟偨壀懞擩師偺乽曞暫攈乿
5. 惂奀丒惂嬻尃傪廳帇偟偨嵞孯旛寁夋傪採埬偟偨栰懞媑嶰榊尦奀孯戝彨傪拞怱偲偟偨乽奀孯攈乿
嵟弶偺慻怐壔偼慜擭偵岞怑捛曻傪夝偐傟偨愒旜晀偵傛傞丄1951擭(徍榓26擭)10寧偵寢惉偝傟偨戝擔杮垽崙搣偱偁傞偑丄偡偱偵偦偺敿擭慜偺2寧偵偼戞堦夞垽崙幰抍懱崸恊夛側偳偑偱偒偁偑偭偰偍傝丄傑偨1952擭(徍榓27擭)偐傜偼塃梼抍懱偑懕乆偲愝棫偝傟偨丅
偙傟傜偼椻愴偵偲傕側偆乽杊嫟偺嵲乿偲偟偰偺擔杮偺杊塹偵婋婡姶傪帩偭偨GHQ偺堄岦偵揔偆傕偺偱偁傝丄嵍梼巚憐傪摑惂偡傞乽媡僐乕僗乿偲傕屇偽傟偨丅1951擭(徍榓26擭)偵偼丄擔杮崙悎夛弶戙夛挿丒怷揷惌帯偺怽偟弌傪庴偗偰丄栘懞撃懢榊朄柋晎憤嵸(屻偵朄柋戝恇)偑摉帪偺嬥妟偱3壄悢愮枩偺梊嶼傪偮偗丄僥僉壆丄朶椡抍丄塃梼傪傑偲傔偨巹暫乽斀嫟敳搧戉乿傪惌嶔偲偟偰棫埬偟偨偑丄媑揷栁庱憡偵憡庤偵偝傟偢偵撢嵙偟偨丅
愯椞婜偑廔傢傞偲奺塃梼偼揤峜拞怱庡媊丒斀嫟庡媊丒斀幮夛庡媊丒嵞孯旛懀恑丒寷朄夵惓側偳偺偦傟偧傟偺庡挘傪昗炘偟丄妶摦傪嵞奐偟偨丅偙傟傜愴屻偺塃梼抍懱偺戝偒側摿挜偲偟偰偼乽斀嫟恊暷乿楬慄傪嫇偘傞偙偲偑偱偒傞丅
埨曐摤憟拞偺1960擭(徍榓35擭)偵偼僪儚僀僩丒D丒傾僀僛儞僴儚乕暷崙戝摑椞棃擔傪娊寎丒巟墖偡傞偨傔偵丄帺柉搣埨慡曐忈埾堳夛偑丄慡崙偺僥僉壆丄朶椡抍丄塃梼傪慻怐偟偰乽傾僀僋娊寎幚峴埾堳夛乿傪棫偪忋偘丄嵍梼偺廤夛偵墸傝崬傒傪偐偗偝偣偨丅偙傟傜偺摦偒偵敽偄丄崟揾傝偺奨愰幵偱戝壒検偺孯壧傪棳偡丄揟宆揑側乽奨愰塃梼乿偑搊応偟偨丅1992擭(暯惉3擭)偺朶椡抍懳嶔朄巤峴埲崀偼丄朶椡抍慻怐偑塃梼抍懱偵帒嬥傪採嫙丄傕偟偔偼惌帯抍懱偵堖懼偊偡傞帠椺偑懕敪偟丄塃梼偑崙壠偵懳峈偟斀尃椡傪庡挘偡傞忬懺偵側偭偰偄傞丅奨愰塃梼偼丄憡庤傪乬斀擔乭偲抐偠偨側傜偽奨愰傪偐偗傞偲偄偆偦偺惈幙偐傜丄條乆側斸昡偑偝傟偰偄傞丅
擟嫚塃梼偺宯晥偲偟偰偼丄愴屻偟偽傜偔偟偰奀孯偲嶰旽嵿敶偺棳傟傪媯傓棙尃偵寢傃偮偄偨嶳岥慻宯塃梼偺妶摦偑栚棫偭偨丅斵傜偼奀孯丒嶰旽偲嫟偵挿嶈偐傜慏偵忔偭偰峀搰丄恄屗丄墶昹側偳憿慏強丒峘挰傪揱偭偰慡崙傊峀偑偭偨丅揤峜傪棫偰偨庡挘偑嬤偄偨傔椉幰偺幆暿偼擄偟偄偑巚憐丒妶摦栚揑丄帒嬥尮偼慡偔堎側傞丅奣偹恊暷偐斀暷偐偱嬫暿偱偒傞丅愴屻偐傜徍榓婜偵偐偗偰偼帣嬍梍巑晇偺傛偆偵惌嵿奅偺崟枊偲偟偰棙尃惌帯傗択崌偵娭梌偟丄偁傞偄偼憤夛壆傗巇庤嬝側偳偲偟偰埫桇偡傞傕偺傕偄偨偑師戞偵戅挭偟偨丅惓嬈傪帩偨偢帒嶻壠偺帒嶻傪庣傞梡怱朹傑偑偄偺偙偲傪偟偨傝丄怘媞傑偑偄偺幰傕偁傞丅
懠曽偱偼丄1960擭戙屻婜偐傜丄乽怴塃梼乿傗乽柉懓攈乿偲屇偽傟傞丄奨愰幵傪梡偄側偄偐堦斒幵偺傛偆側奜尒偺奨愰幵偱墘愢傪偡傞妶摦偵愗傝懼偊傞塃梼妶摦壠偑尰傟巒傔偨丅斵傜偼乽斀嫟乿堦曈搢偺巚憐傗朶椡峴堊傗戝壒検偵傛傞愰揱妶摦偵廬棃偺娤擮塃梼傗奨愰塃梼偵斀敪偟丄僩乕僋僙僢僔儑儞偵弌墘偟偨傝榑抎帍偵悢儁乕僕偺楢嵹傪帩偭偨傝偡傞榑棟揑側尵榑妶摦偱擔杮傗柉懓傪慽偊傞妶摦傪偟偰偄傞丅偙偺攚宨偵偼丄廬棃宆偺塃梼偺崟枊偱偁傞帣嬍梍巑晇偺儘僢僉乕僪帠審偱偺懡妟偺拁嵿偺敪妎傗丄嶰搰帠審丄宱抍楢廝寕帠審側偳傪宊婡偲偟偨丄懱惂婑傝偺晠攕偟偨乽婛惉塃梼乿傊偺斀敪偑偁傞丅斵傜偼乽斀嫟斀暷斀懱惂乿傗丄応崌偵傛偭偰偼乽柉庡庡媊丄巗柉庡媊乿傪庡挘偟丄巚憐揑偵偼愴慜偺乽惓摑塃梼乿偲偺嫟捠揰傕戝偒偄丅
仭椻愴屻
椻愴帪戙偵偼朶椡抍偲偮側偑偭偨懱惂婑傝偺恊暷塃梼偑懡偐偭偨偑丄椻愴廔椆屻偵巤峴偝傟偨朶椡抍懳嶔朄傗奺抧偺朶椡抍攔彍忦椺偵傛傝悐戅偟丄斀懱惂揑側斀暷塃梼傕憡懳揑偵栚棫偮傛偆偵側偭偰偄傞丅
21悽婭偵擖偭偰偐傜偼嵼擔摿尃傪嫋偝側偄巗柉偺夛偵戙昞偝傟傞丄寵拞(斀拞)丒寵娯(斀娯)傪幉偲偟偨巗柉塣摦揑僗僞僀儖偺乽峴摦偡傞曐庣乿偑戜摢偟丄奨摢僨儌傗僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偟偨乽攔奜庡媊乿揑側愰揱妶摦偱丄崙楢偺恖庬嵎暿揚攑埾堳夛傪弶傔丄崙撪奜偐傜斸敾偝傟偰偄傞丅
|
仭暘椶
仭愴慜(惛恄攈丒棟榑攈)
愴慜偼慻怐丒峴摦偲偄偆暘椶偱偼側偔丄乽弮惓擔杮庡媊乿偲乽崙壠幮夛庡媊乿偲偵暘椶偝傟丄慜幰偼乽惛恄攈乿丄屻幰偼乽棟榑攈乿偲偝傟偰偄傞 丅
仭愴屻(慻怐塃梼丒峴摦塃梼)
慻怐塃梼傕峴摦傪敽偆偑丄搱拞帠審偺嵺偵寈嶡挕偑乽帯埨忋拲堄傪梫偡傞抍懱乿偲偟偰慻怐塃梼偲峴摦塃梼偲偄偆2暘椶傪偟偰偄傞(亀塃梼娭學抍懱梫棗亁丄1972擭丅強嵼抧婰嵹偺側偄傕偺偼搶嫗強嵼)丅
慻怐塃梼偼戝搶弇丒晄擇壧摴夛丄崙柉憤楢崌丄戝擔杮惗嶻搣丄崙柉摨巙夛丄擔杮惵擭楢柨丄崙柉幮夛搣丄崌桭夛(柤屆壆)丄擔杮摨巙夛(壀嶳)丅
峴摦塃梼偼戝擔杮垽崙搣丄岇崙抍丄帯埨妋棫摨巙夛丄杊嫟掟恎戉丄崙悎夛丄徏梩夛丄媊恖搣(擔偺娵惵擭戉)丄戝擔杮崙柉搣丄戝擔杮撈棫惵擭搣丄巘嵃妚怴摨柨(柤屆壆)丄寶崙惵擭摨柨(垽抦)丄垽崙惵擭摨巙夛(榓壧嶳)丄徠崙夛(幁帣搰)丅
乽峴摦塃梼乿偺岅偼朶椡抍偑塃梼偵嶲壛偟偨1960擭(徍榓35擭)慜屻偐傜堦斒壔偟偨丅傛偭偰堦晹偼朶椡抍偺嶱壓抍懱(塃梼昗炘朶椡抍)偱偁傞丅
|
仭慻怐
揱摑揑側曐庣塃梼丄恊暷塃梼丄奨愰塃梼丄娤擮塃梼側偳偲偼暿偵丄1960擭戙偵偼妛惗塣摦側偳夁寖側嵍梼宯塣摦偺懡敪偵懳峈偡傞宍偱丄柉懓宯塃梼偺戝婯柾側慻怐壔偑峴傢傟偨丅塃攈妛惗傜偑棫偪忋偘偨柉懓攈妛惗慻怐偺偆偪丄擔杮妛惗夛媍丒擔杮妛惗摨柨(2007擭夝嶶)丒慡崙妛惗帺帯懱楢棈嫤媍夛側偳偼丄柉懓庡媊偺棫応偐傜斀暷傪娷傔偨乽YP懱惂懪搢乿傪宖偘丄戝偒側塭嬁椡傪帩偭偨丅偟偐偟懳峈惃椡偱偁偭偨嵍梼偺妛惗塣摦偺戅挭傗慻怐偺暘楐偵傛傝丄柉懓攈妛惗慻怐偺塣摦傕戅挭偟1990擭戙埲崀偼栚棫偭偨妶摦傪傎偲傫偳偟偰偄側偄丅
尰嵼偱偼丄愴慜偐傜偺宯晥傪堷偔擟嫚塃梼傗奨愰塃梼偱傕峔惉堳悢偑嶰寘偵払偡傞偲偙傠偼奆柍偲偄偭偰傛偄丅偨偩偟丄擟嫚宯偼偁傞掱搙慻怐偑戝偒偔側傞偲晹壓偵撈棫傪懀偟暿抍懱傪寢惉偝偣傞偨傔丄屄乆偺慻怐娫偺楢実偼枾偵庢傟偰偄傞応崌偑懡偄丅偙傟傜丄擟嫚塃梼傗奨愰塃梼偺峔惉堳偵偼丄彮偐傜偸悢偺嵼擔娯崙丒挬慛恖偑懚嵼偡傞慻怐偑偁傞偺傕摿挜偱偁傞丅
|
仭妶摦
懏偡傞宯摑偵傛偭偰棫応偑堘偄丄抍懱偵傛偭偰妶摦撪梕傗曽恓傕堎側傞丅條乆側塃梼側偄偟曐庣庡媊幰抍懱傪傑偲傔傞楢棈婡娭偲偟偰丄乽慡擔杮垽崙幰抍懱夛媍乿(慡垽夛媍)丄乽戝擔杮垽崙抍懱楢崌丒帪嬊懳嶔嫤媍夛乿(帪懳嫤)丄乽惵擭巚憐尋媶夛乿(惵巚夛)丄帺柉搣媍堳傕懡偔強懏偡傞曐庣庡媊幰抍懱偺乽擔杮夛媍乿側偳偑偁傞偑丄昁偢偟傕巚憐摑堦傪峴偭偰偄傞傢偗偱偼側偄(摿偵丄擔杮夛媍偵偼峴摦塃梼偼慡偔壛柨偟偰偍傜偢丄媡偵慡垽夛媍傗帪懳嫤偵偼媍堳丒昡榑壠丒幚嬈壠丒廆嫵壠偲偄偭偨恖暔偼嶲壛偟偰偄側偄丅岎棳側偳偑偁傞偺傒)丅
懠偵偼擭傪昞偡嵺偵偼惣楋偱偼側偔丄尦崋傗峜婭傪桪愭揑偵巊偭偰偄傞(尦崋朄惂掕慜偵偼尦崋偺朄惂壔偺悇恑塣摦傗徍榓51擭偐傜惣楋傪桪愭昞婰傪偡傞傛偆偵側偭偨怴暦幮傪斸敾偟偨)丅
仜 柧恗(摉帪峜懢巕)偲峜岪旤抭巕(摉帪偼乽惓揷旤抭巕乿)偺寢崶偵嵺偟丄徏暯怣巕丒媨嶈敀楡偺摥偒偐偗傪庴偗偰崶堶斀懳塣摦傪揥奐偟偨(擖峕憡惌擔婰傛傝)丅
仜 擔杮嫟嶻搣丄幮夛柉庡搣丄擔杮嫵怑堳慻崌丄慡擔杮嫵怑堳慻崌側偳傪乽擔杮偺愒壔傪婇傓朶椡妚柦廤抍乿偲偟丄慻崌戝夛丒嫵堢尋媶慡崙廤夛傗愒婙傑偮傝丄尨悈敋嬛巭擔杮崙柉夛媍悽奅戝夛摍傊偺峈媍2008擭(暯惉20擭)2寧偺擔嫵慻戝夛偵嵺偟偰偼丄慡懱廤夛夛応偵梊掕偝傟偰偄偨僌儔儞僪僾儕儞僗儂僥儖怴崅椫偑丄梊栺傪庴棟偟偰偄側偑傜峈媍峴摦偵傛傞憶忥偺嫲傟傪棟桼偵僉儍儞僙儖偟丄峈媍峴摦傪偡傞慜偵拞巭偝偣傞岠壥傪惗傫偩丅柉帠夘擖朶椡傕嶲徠丅
仜 愴屻傕丄抍懱偺懡偔偼楌巎揑側宱堒偱妛惗塣摦傗嵍梼僥儘偺捔埑偵寈嶡偺摦堳悢偑晄懌偟偨堊丄帣嬍梍巑晇偑朶椡抍偵傕梫惪偟偨帠偐傜尰嵼偱傕朶椡抍偲娭學偑偁傞丅傑偨擟嫚宯偱偁傝丄宱塩幰偺埶棅傪庴偗楯摥幰偺僗僩儔僀僉捵偟傗慻崌捵偟丄岞奞昦姵幰偺僨儌捵偟傗嫼敆(嵍梼宯僌儖乕僾偑娭梌偟偰偄傞堊)傗丄巗柉抍懱傪昗炘偡傞嵍梼僨儌傊偺朩奞丄塃攈惌帯壠偺堄傪渦搙偟偰偺曻壩丄姅庡憤夛偺乬墌妸側恑峴乭側偳丄帒杮壠丒尃椡憌偑捈愙庤傪壓偣側偄乬墭傟巇帠乭傕峴偆丅朶椡抍懳嶔朄偵傛傞掲傔晅偗傪庴偗丄柤栚忋丄巚憐抍懱偲偟偰塃梼巚憐傪昗炘偟偰偄傞偩偗偲偄偆尒曽傪偝傟傞働乕僗傕尒庴偗傜傟丄偙偺応崌偼奨愰妶摦傪捠偠偨嫲妳峴堊丒寵偑傜偣側偳偱丄偁傞嬈柋傪庢傝巭傔偝偣偨傝嬥昳傪偣偟傔偨傝偡傞偺偑庡側栚揑偲偝傟傞(幮夛塣摦昗炘僑儘)丅
仜 尦岞埨挷嵏姱偺悰徖岝峅偼乽嵼擔娯崙丒挬慛恖傗旐嵎暿晹棊偑朶椡抍堳偺9妱傪愯傔丄塃梼妶摦偵傛偭偰廂塿傪忋偘偰偄傞乿偲偺尒夝傪帵偟偰偄傞丅傑偨丄帺恎傕嵼擔娯崙恖偱偁傞昡榑壠偺恏廼嬍偼塸岅斉傾僒僸僐儉偵偍偄偰"Many, in fact, are Koreans, she said" ((斵彈偺榖偵傛傟偽塃梼偺拞偵)懡悢偺嵼擔娯崙丒挬慛恖偑偄傞)偲弎傋偰偄傞丅
仜 塃梼巚憐偵婎偯偔抍懱偱側偔偰傕嵍梼抍懱傗嬤椬彅崙偵斸敾揑偱偁偭偨傝偡傞偲偦偆屇偽傟傞偙偲偑偁傝丄乽塃梼抍懱乿偺屇徧偵懳偡傞寵埆姶丒僗僥儗僆僞僀僾側僀儊乕僕偐傜丄偁傞庬偺儗僢僥儖偲偟偰婡擻偟偰偄傞働乕僗傕尒傜傟傞(拞崙偺儊僨傿傾偼帺崙偵斸敾揑側擔杮偺抍懱傗恖暔傪乽塃梼乿丒娯崙偱偼嬫暿柍偔乽嬌塃乿偲昞尰偟偰偄傞)丅
|
仭屇徧
乽崱忋揤峜乿偵愨懳揑宧堄傪帵偟丄乽揤峜暶壓乿傑偨偼乽崱忋暶壓乿偲徧偡傞偺偑晛捠偱偁傞丅楌戙揤峜偱偼徍榓揤峜偺帠傪乽愭掗暶壓乿丒柧帯揤峜偵偼乽柧帯戝掗暶壓乿傗乽戝掗暶壓乿丒徍榓揤峜傗戝惓揤峜丒柧帯揤峜傪乽(尦崋)偺揤峜暶壓乿偲徧偡傞傕偺幰傕偄傞(偨偩偟徍榓揤峜偺傛偆偵巰屻偵晅偗傜傟偨屇徧偼丄偦傟帺懱偵宧堄偑崬傔傜傟偨捛崋偱偁傞偺偱乽徍榓揤峜乿偲屇徧偡傞幰傕偄傞)丅懠偺峜懓偵偼乽揳壓乿傪晅偗偨傝乽偝傑乿傪晅偗偨傝條乆偩偑丄乽偝傑乿偱偼宧堄偑帵偣側偄(傑偨偼幐楃)傗峜幒揟斖偵婎偯偄偰乽揳壓乿傪梡偄傞曽偑懡偄(峜懓傊偺宧徧傪晅偗偨屇傃曽偼丄峜懓偺儁乕僕傪嶲徠)丅 懠偺揤峜偵娭偡傞屇徧偱偼乽揤峜惂乿傗乽揤峜壠乿傪斀揤峜岅(桼棃偑揤峜偵斸敾揑側幰偑嶌偭偨尵梩偱乽揤峜壠乿偺桼棃偼峜幒傪嶲徠)偲偟偰巊傢側偄幰傕偄傞丅
懠偵偼慜弎偺條偵乽懢暯梞愴憟乿傪乽戝搶垷愴憟乿偲屇傫偩傝偡傞(乽懢暯梞愴憟乿偵偼傾儊儕僇偺惓媊愴憟偲偄偆堄枴傕偁傞偲偟偰)丅
拞壺恖柉嫟榓崙傪斸敾偡傞嵺偵偼乽拞嫟乿(拞崙嫟嶻搣傊偺斸敾偱傕巊傢傟傞)丒乽僔僫丒巟撨乿丒乽僔僫(巟撨)拞嫟乿丄娯崙傗杒挬慛傪斸敾偡傞嵺偵偼乽挬慛乿(娯崙傪乽撿挬慛乿)丄擔杮嫟嶻搣傪斸敾偡傞嵺偵偼乽擔嫟乿偲徧偟偨傝偡傞丅
尰嵼偺廽擔朄偵掕傔傜傟偰偄傞廽擔偼GHQ偵傛偭偰曄峏偵偝傟偨傕偺偑懡偄堊偵丄擔杮偺塃梼抍懱偼尰嵼偺柤徧偱尵傢偢偵愴慜偺柤徧偱尵偆応崌偑懡偄丅
仜 尦擔仺巐曽愡
仜 寶崙婰擮偺擔仺婭尦愡
仜 暥壔偺擔仺柧帯愡
仜 揤峜抋惗擔仺揤挿愡
仜 弔暘偺擔仺弔婫峜楈嵳
仜 廐暘偺擔仺廐婫峜楈嵳
仜 嬑楯姶幱偺擔仺怴彟嵳
|
仭惌帯揑庡挘
擔杮偺塃梼偺庡側惌帯揑庡挘偲偟偰丄揤峜惂岇帩丄斀嫟庡媊丄帺庡寷朄惂掕榑丄崙婙宖梘丒孨偑戙惸彞偵巀惉丄懢暯梞愴憟(戝搶垷愴憟)偺峬掕丒YP懱惂懪攋丒桋崙恄幮嶲攓丄崙杊惌嶔偺嫮壔丒嫮峝揑側奜岎惌嶔偺巟帩偺巟帩側偳偑嫇偘傜傟傞丅惌搣偵娭偟偰偼丄愴屻嵟戝偺曐庣惌搣偱偁傝丄挿婜娫惌尃傪曐帩偟偰偄傞帺柉搣傗柉庡搣偺塃攈(庡偵媽怴惗搣丒柉幮搣宯)傪巟帩偡傞幰偑懡偄偑丄揤峜恊惌偺棫応偐傜媍夛惂柉庡庡媊懪搢傪彞偊偨傝撈帺偺柉懓庡媊惌搣(堐怴惌搣丒怴晽摍)傪慻怐偡傞媫恑攈傕堦晹懚嵼偡傞丅傑偨丄寷朄夵惓榑媍偱偼丄儂儚僀僩僴僂僗偵傛傞乽墴偟晅偗寷朄榑E埨慡曐忈忋偺栤戣揰摍傪巜揈偟偰夵寷傪庡挘偟偨傝丄寷朄柍岠榑傪彞偊傞幰傕懚嵼偡傞丅
懳奜揑偵偼丄摉帠崙傗擔杮偺嵍梼惃椡偑乽偦偺愑擟偼擔杮惌晎偵偁傞乿偲偡傞2005擭(暯惉17擭)偺斀擔僨儌傗慜弎偺桋崙恄幮栤戣丄愲妕彅搰偺椞搚栤戣側偳偐傜拞壺恖柉嫟榓崙偲拞壺柉崙(戜榩)丄摨偠偔斀擔僨儌傗桋崙恄幮栤戣丄抾搰偺椞搚栤戣側偳偐傜娯崙丄擔杮恖漟抳栤戣側偳偐傜杒挬慛丄僜楢偺懳擔嶲愴偺宱堒傗丄偦傟偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨杒曽椞搚栤戣偐傜儘僔傾(1991擭)傑偱偼僜價僄僩楢朚)偺5崙傪斸敾偡傞帠偑懡偄丅偝傜偵丄斀嫟偺棫応偲楌巎擣幆偺妺摗偐傜儀僩僫儉傗丄斀嫟偺棫応偐傜僉儏乕僶丄恊暷偺棫応偐傜拞搶彅崙丄僷僉僗僞儞丄搶僥傿儌乕儖側偳傕斸敾偺懳徾偲側傞偙偲傕偁傞丅
偨偩偟丄傾儊儕僇傗娯崙偵懳偟偰偺擣幆偼抍懱偵傛偭偰堎側傞丅斀嫟偺棫応偐傜傾儊儕僇傗娯崙傪巟帩偟偰棃偨塃梼抍懱傕偁傞偑丄椻愴屻偼桋崙恄幮偵懳偡傞懺搙傗丄1945擭埲慜偺悽奅傪弰傞楌巎擣幆摍傪弰偭偰丄傾儊儕僇傗娯崙傪斸敾偡傞塃梼偑憹偊偰偄傞丅摨條偵丄惣懁惃椡偵偲偭偰嵟戝偺嫼埿偱偁偭偨僜價僄僩楢朚偑徚柵偟偨偨傔丄尰忬偺擔暷埨曐懱惂偼懳暷廬懏傪悇恑偝偣傞偩偗偩偲偟偰斀暷偺棫応傪嵦偭偨抍懱傕偁傞偑丄拞壺恖柉嫟榓崙偲杒挬慛偺孯帠揑嫼埿傗丄儘僔傾偲偺娫偱書偊偰偄傞椞搚栤戣偱擔杮偑晄棙側棫応偵棫偨偝傟偰偄傞帠傪庡挘偟偰丄埶慠偲偟偰恊暷偺棫応傪嵦傞抍懱傕偁傞丅
廬棃偐傜斀嫟偺僗僞儞僗偱拞壺恖柉嫟榓崙傪斲掕偟丄拞壺柉崙傪拞崙傪戙昞偡傞惌晎偲偡傞偺偑懡偔偺塃梼偺棫応偱偁傝丄僠儀僢僩撈棫塣摦丄搶僩儖僉僗僞儞撈棫塣摦丄撪儌儞僑儖撈棫塣摦傪巟帩偡傞帠偑懡偄(撈棫塣摦偼妶敪偱偼側偄偑枮廈偺撈棫傪巟帩偡傞抍懱傕偁傞)丅偟偐偟丄拞壺柉崙偼戞擇師悽奅戝愴偺楢崌崙偺堦堳偱偁傝丄1945擭(徍榓20擭)埲慜偺悽奅傪弰傞楌巎擣幆偱偼擔杮偺塃梼偲妺摗偡傞棫応偱偁傞揰偐傜丄嬤擭偼拞壺柉崙帺懱傪斲掕偟丄戜榩撈棫塣摦傪巟墖偡傞摦偒傕尒傜傟傞(側偍拞壺柉崙偑惉棫偡傞傑偱戜榩偼戝棨偵偲偭偰恖奜丒枹奐偺抧偱偁傝丄堦崙偲偟偰擣幆偝傟偰偼偄側偐偭偨)丅偙傟傜妶摦偺崻嫆偲偟偰柉庡庡媊丒恖尃丒拞崙嫼埿榑丒柉懓帺寛側偳傪彞偊偰偄傞丅
嵍攈宯儊僨傿傾偺孹岦偑偁傞偲偝傟傞挬擔怴暦傗枅擔怴暦偵懳偟偰偼丄1990擭戙偺堅埨晈偵娭偡傞堦楢偺曬摴側偳偐傜摿偵斸敾揑偱偁傞丅傑偨抧曽巻偱偼杒奀摴怴暦傗拞擔怴暦丄棶媴怴曬丄壂撽僞僀儉僗偑揋帇偝傟偰偄傞応崌偑懡偄丅曐庣揑榑挷偺孹岦偑偁傞撉攧怴暦傗嶻宱怴暦偵懳偟偰偼丄峬掕揑側峫偊傪帵偡偙偲偑懡偄偑丄応崌偵傛偭偰偼斸敾偡傞偙偲傕偁傞(撉攧怴暦偑2004擭偵採尵偟偨寷朄夵惓埬偱乽揤峜乿偺崁栚傪戞堦復偱偼側偔丄戞擇復偵偟偨帠傪斸敾偟偨帠傕偁傞)丅傑偨丄擔杮宱嵪怴暦偵懳偟偰偼丄嬤擭偵偍偗傞戝婇嬈偺拞崙傊偺恑弌偐傜丄拞崙傊偺峬掕揑側曬摴巔惃傗恑弌偟偨擔杮婇嬈偑僠儍僀僫儕僗僋偱惗偠傞擔杮宱嵪傊偺塭嬁傕偁傞偨傔丄斸敾揑偱偁傞偙偲偑懡偄丅擔杮宱嵪怴暦偺榑挷偱偁傞恊暷曐庣揑側怴帺桼庡媊傗僌儘乕僶儕僘儉偲丄擾杮庡媊側偳偺柉懓庡媊巚憐偼婎杮揑偵憡梕傟側偄傕偺偱偁傞丅
|
仭楌巎擣幆
仜 揱摑揑側塃梼偺楌巎擣幆偼丄崙懱岇帩偺棫応偐傜峜崙巎娤傪庡挘偡傞丅偟偐偟嬶懱揑偵偳偺傛偆側崙壠懱惂傪棟憐偲偡傞偐偼懡悢偺棫応偑偁傝丄屆戙側偳偺揤峜恊惌傗婱懓惂搙偺暅妶丄揱摑揑側崙壠偺傛傝偳偙傠偲偟偰偺峜幒傪嫮挷偟徾挜揤峜惂傪堐帩偡傋偒偲偡傞堄尒丄柧帯揤峜偺傛偆側孾栔愱惂宆偺揤峜恊惌偺暅妶丄峏偵偼杒堦婸側偳偺嬤戙崙壠偺摑崌偺偨傔偺揤峜婡娭愢偵嬤偄崙壠懱惂側偳偑懚嵼偡傞丅
仜 屲丒堦屲帠審丄擇丒擇榋帠審側偳偺僋乕僨僞乕偵娭偟偰偼丄揤峜恊惌偺拞墰廤尃揑側怴崙壠傪憂棫偟傛偆偲偟偨傕偺偲偟偰昡壙偡傞棫応傗丄揱摑揑側曐庣庡媊傗朄帯庡媊傗柧帯寷朄偺棫寷孨庡惂傪懜廳偡傞棫応偐傜斸敾揑側棫応傕懚嵼偡傞丅
仜 娯崙暪崌傗枮廈帠曄傗擔拞愴憟側偳偺擔杮偵傛傞戝棨恑弌偵娭偟偰偼丄懡偔偺栤戣偑偁傝慡偰傪峬掕偼偱偒側偄傕偺偺丄儘僔傾掗崙傗僜價僄僩楢朚偺撿壓傪杊偓丄嬤椬崙偺嬤戙壔傪懀恑偟丄擔杮偺惗懚寳傪杊塹偡傞偨傔偺昁梫惈偼斲掕偱偒側偄偲庡挘偡傞棫応偑懡偄丅偨偩偟廆嫵塃梼偺堦晹偼丄奺柉懓偺揱摑揑側暥壔傗廆嫵側偳傪懜廳偡傞棫応偐傜丄嫮惂揑側嬤戙壔傗峜柉壔嫵堢側偳偺怉柉抧惌嶔傪斲掕偟偨丅
仜 戞擇師悽奅戝愴(懢暯梞愴憟)偵娭偟偰偼丄捠忢偼戝搶垷愴憟偲屇傃丄帺塹揑側愴憟偱偁偭偨偲庡挘偡傞丅傑偨丄愴憟偼栄戲搶傗僐儈儞僥儖儞偺堿杁偵傛傝奐巒偝偣傜傟偨丄偲偺嫟嶻庡媊堿杁榑傪庡挘偡傞幰傕偄傞丅懠曽偱偼堦晹偺曐庣庡媊傑偨偼帺桼庡媊揑側塃梼偼丄摑惂攈偑庡摫偟偨崙壠憤摦堳朄傗尵榑摑惂傗摑惂宱嵪側偳偺愴帪懱惂偼1庬偺幮夛庡媊偱偁傞偲偺棫応偐傜丄偙傟傜傪斸敾偟偨丅偄傢備傞乽撿嫗戝媠嶦乿傗乽堅埨晈嫮惂楢峴乿側偳偵娭偟偰漵憿側偄偟偼屩挘偝傟偨僾儘僷僈儞僟偱偁傞偲庡挘偡傞孹岦偑偁傞丅
仜 戞擇師悽奅戝愴屻偺擔杮偵娭偟偰偼丄揱摑揑塃梼丒恊暷塃梼丒斀嫟塃梼偺懡偔偼丄嫟嶻庡媊偺塭嬁傪庴偗偨嵍梼偵傛傞帺媠巎娤偑嫵堢尰応傗儅僗僐儈偱墶峴偟偰偄傞偲庡挘偟丄戝搶垷愴憟媦傃戝擔杮掗崙峬掕丒愴屻柉庡庡媊斲掕丄擔杮嫵怑堳慻崌傗挬擔怴暦(嵍梼宯)側偳傊偺斸敾丄僗僷僀杊巭朄丄孯旛椡偺憹嫮丄擔暷埨曐忦栺偺嫮壔側偳傪庡挘偟偰偄傞丅懠曽偱偼柉懓攈塃梼偼愴屻偺擔杮傪丄傾儊儕僇偲僜楢側偳偵傛傞帠幚忋偺擔杮偺怉柉抧壔偱偁傞乽YP懱惂乿偲偺棫応偐傜丄斀嫟庡媊偲摨帪偵斀暷傪庡挘偟偨丅
|
仭庡側斸敾懳徾彅崙
擔杮偺懡偔偺塃梼抍懱偱偼丄斀嫟庡媊偺棫応偐傜僜楢曵夡傑偱偺僜價僄僩楢朚傗丄拞崙傗杒挬慛側偳偺崙壠丒懱惂丒惌晎傗嫟嶻庡媊惌搣傪斸敾偟偰偄傞丅傑偨拞崙偵抏埑偝傟偰偄傞僠儀僢僩丒搶僩儖僉僗僞儞丒撪儌儞僑儖側偳偺帺帯撈棫塣摦傪巟帩偡傞棫応傕偁傞丅椻愴婜偵偼丄戝擔杮垽崙搣側偳偺戝敿偺塃梼抍懱偼斀嫟偺棫応偐傜恊暷丒恊娯丒恊戜榩丒恊懱惂(恊暷塃梼)偱偁偭偨偑丄怴塃梼側偳偼斀嫟丒斀暷丒斀懱惂(斀暷塃梼)偱偁偭偨丅
崙壠庡媊傗柉懓庡媊偺棫応偐傜丄夁嫀偺撿壓惌嶔傗杒曽椞搚栤戣側偳偱儘僔傾傪丄抾搰栤戣側偳偱娯崙傗杒挬慛傪丄愲妕彅搰栤戣側偳偱拞壺恖柉嫟榓崙傗戜榩(拞壺柉崙)傪斸敾偡傞棫応傕偁傞丅傑偨嬌搶崙嵺孯帠嵸敾傗GHQ偵傛傞擔杮愯椞惌嶔傗桋崙恄幮栤戣側偳傪崙嵺朄堘斀偺撪惌姳徛偲偟偰丄摉帪偺楢崌崙傪斸敾偡傞棫応傗丄墷暷偺怴帺桼庡媊側偳傪宱嵪怤棯傗暥壔怤棯偲斸敾偡傞棫応傕偁傞丅
峏偵擔杮傗搶梞偺暥壔揱摑傗楌巎傪廳帇偡傞曐庣庡媊傗柉懓庡媊偺棫応偐傜偼丄墷暷宆偺屄恖庡媊丒柉庡庡媊丒帺桼庡媊側偳傪斸敾偟丄嬤戙壔傗丄抝彈暯摍傗巰孻栤戣側偳偺恖尃栤戣丄曔寏栤戣傗娐嫬曐岇塣摦丄偙傟傜傪娷傓嫵堢栤戣側偳偱丄傾儊儕僇崌廜崙丒墷廈楢崌丒僆乕僗僩儔儕傾丒僯儏乕僕乕儔儞僪側偳偺墷暷彅崙傗丄偦偺棫応傪斀塮偟偰偄傞偲偟偰崙嵺楢崌傗奺庬偺旕惌晎慻怐側偳傪斸敾偡傞棫応傕偁傞丅傑偨廆嫵柺偱偼僉儕僗僩嫵傗僀僗儔儉嫵側偳偺桞堦恄嫵偵懳偟丄懡恄嫵偺恄摴傗丄偁傞偄偼暓嫵丒庲嫵側偳偺桪埵揰傪庡挘偡傞棫応傕偁傞丅丂
丂 |
|
仭塃梼 2 |
丂 |
仭塃梼偵偮偄偰
仭1 塃梼偺掕媊
塃梼偲屇偽傟傞寢幮偺偡傋偰偵嬤偄懡偔偼峜幒宧嵹傪杮媊偺戞堦媊偲偟偰偄傞丅偦偟偰丄嫟嶻庡媊丒幮夛庡媊偺懪搢杘柵傪栚巜偟偰偄傞丅柉懓偺揱摑丒暥壔偺岇帩偲奜棃丒曄幙暥壔丒巚憐傊偺寈夲丅偟偐偟丄偦偺庡媊丄偦偺巚憐丄偦偺庡挘偼暆峀偔恊暷偲儎儖僞億僣僟儉懱惂懪攋偺條偵恀媡偺儌僲傕懡偄偨傔塃梼偼堦恖堦搣偲尵傢傟傞桼墢偱傕偁傞丅
庡媊庡挘傕懡婒偵暿傟丄柉懓庡媊丄崙懱庡媊丄擔杮庡媊丄惛恄庡媊丄戝傾僕傾庡媊丄崙悎庡媊丄挻崙壠庡媊丄崙壠幮夛庡媊摍偑偁傞丅娙扨偵掕媊偟偒傟側偄傎偳暋嶨側巺棈傒偺條側嶨懡側梫慺偺楢寢偱偁傝丄峜幒丒斀嫟埲奜偼扨弮偵偼傂偲妵傝偼弌棃側偄丅
柉懓庡媊 / 惣梞楍嫮偺擔杮巟攝偵懳峈偡傞懜峜澋埼塣摦傪尮棳偲偟丄柉懓帺寛偺惛恄傪宖偘懠崙壠(暷拞業)偺姳徛傪攔彍偡傞塣摦丅
戝傾僕傾庡媊 / 摢嶳枮摍偑傾僕傾偲偺楢懷傪栚巜偟丄墷暷楍嫮偺嫼埿偐傜偺扙媝傪巚峫偟偨偑丄屻擔惔愴憟偵暯榓嫤挷楬慄傪曻婞偟擔杮偑柨庡偲側傞怤棯宆偲側偭偨丅
崙悎庡媊丒崙壠庡媊 / 帺崙柉偍傛傃帺崙偺暥壔丒揱摑傪懠崙傛傝桪傟偨傕偺偲偟偰丆攔奜揑偵偦傟傪庣傝峀偘傛偆偲偡傞峫偊曽丅
崙壠幮夛庡媊 / 擔杮揑崙壠幮夛庡媊偲偼丄揤峜傪拞怱偲偟偰幮夛庡媊偺堦晹傪庢傝擖傟丄崙壠傪傛傝嫮恱側懱惂偵偮偔傝偐偊傛偆偲杒堦婸傪拞怱偵巚峫偟偨丅
仭2 塃梼偵僶僀僽儖偼昁梫偐丠
嫟嶻庡媊偵偼亀帒杮榑亁偲偄偆棟榑偺僶僀僽儖偑偁傞丅傛偔塃梼偵偼棟榑偺僶僀僽儖偑側偄偲尵傢傟傞偑丄杒堦婸偺乽擔杮夵憿朄埬戝峧乿偵傛偭偰徍榓堐怴(愴慜塃梼)偺僶僀僽儖偑抋惗偟偨偲尵偊傞丅偟偐偟崙懱偺杮媊偵婎偯偔塃攈丒堐怴攈丒柉懓攈偵嵶偐偄棟榑偑偼偨偟偰昁梫偱偁傠偆偐丠枩悽堦宯偺揤峜偺傕偲擔杮屆棃偺暥壔丒晽廗丒摴摑傪庣偭偰偄偔偙偲偙偦偑栶栚偱偼側偄偱偁傠偆偐丅婘忋偺嬻榑偱偟偐側偄悽奅偺幮夛庡媊崙偺枛楬傪尒傟偽棟夝偱偒丄幚慔偺拞偵偙偦妶楬傪尒偄偩偟偰偄偔摴傕傑偨惓榑偱偁傠偆丅垽崙塣摦偵掟恎偡傞偵偼丄婥暣傟偩偗偱偼懕偗傜傟側偄丅峀偄抦幆偲廋梴偑昁梫偱偁傞丅巚椂怺偔尒幆傪梴偄偺惤堄傪帩偪婥敆傪曐偪懕偗側偗傟偽側傜側偄丅擔杮崙懱偺杮媊偱偁傞枩悽堦宯偱楢柸偲揤峜暶壓傪懜悞偟丄変偑崙撈帺偺揱摑傗暥壔偺傕偮惛恄傪婎慴偲偟偰崙壠偺斏塰傪栚巜偡塣摦偵掟恎偡傞幚慔妶摦傪捠偠偰懡偔傪妛傫偱偄偔傋偒偱偁傞丅
仭3 曐庣拞摴偲斀摦
曐庣丒拞摴偼尰嵼偺懱惂傗拋彉傪廳傫偠丄斀摦偱偁傞塃梼偼丄夁嫀偺忣惃傗懱惂偵旤堄幆傪尒弌偟暅屆傪栚巜偡偲尵傢傟偰偒偨丅丂斀摦偱偁傞嵍梼偼丄夁嫀偐傜懕偔揱摑傗崱惉傝棫偭偰偄傞尰幚傪寉曁偟尰幚傗夁嫀傪斲掕偡傞偙偲偱崻嫆側偒傛傝椙偒枹棃偵柌傪尒傞嬻拞極妕傪嶌傝忋偘傛偆偲偟偰偄傞條側傕偺偱偁傞丅
悽奅忣惃丒崙柉惗妶摍偑媫寖偵曄壔偟偰偄傞尰嵼偵偍偄偰崙柉堄幆偺曄壔傕摉慠偺忬嫷偱偁傞丅丂幮夛曄妚丒幮夛夵妚傪慟恑揑偵恑傔傞庤朄傪慖傇曐庣攈偲懳洺偡傞惃椡偼媫恑揑丒妚柦揑庤朄偱崙壠夵憿傪峴偍偆偲偟偨偺偱偁傞丅丂 |
仭塃梼(塃攈)偺尮棳偲楌巎
仭柧帯帪戙
柧帯堐怴帪丄嶧挿斔敶偵傛傞愱惂惌晎偑惉棫偟奺斔偺晲巑偼晄枮偑朶敪偟丄嵅夑偺棎丒恄晽楢偺棎丒廐寧偺棎丒攱偺棎丒惣撿愴憟偲斀棎偑懕敪偡傞丅暉壀斔偼拀慜嬑墹搣偲偟偰嬑墹攈彅斔偺拞偵偁偭偰懚嵼姶傪帵偟偰偄偨偺偩偑丄枊晎偺埑椡偵孅偟丄憤惃昐巐廫柤偺戝検偺張孻偲偄偆乽壋塏偺崠乿偲屇偽傟偨戝抏埑傪壛偊丄嬑峜攈偼夡柵偟偨丅偦偺寢壥丄柧帯怴惌晎憂寶偲偄偆戝帠嬈偵丄堦恖偨傝偲傕嶲夋偡傞偙偲偑弌棃側偐偭偨丅弇惗偵偼丄摢嶳枮丒晲晹彫巐榊丒敔揷榋曘丒墇抭旻巐榊丒恑摗婌暯懢丒撧椙尨帄丒媨愳懢堦榊傜偑妛傫偩丅柧帯8擭丄摢嶳枮摍偵傛傝乽嫺巙幧乿偑寢惉偝傟傞偑丄恄晽楢偺棎丒攱偺棎偵楢嵗偟幮堳惻堳偑戇曔偝傟偨丅
柧帯堐怴帪丄嶧挿斔敶偵傛傞愱惂惌晎偑惉棫偟奺斔偺晲巑偼晄枮偑朶敪偟丄嵅夑偺棎丒恄晽楢偺棎丒廐寧偺棎丒攱偺棎丒惣撿愴憟偲斀棎偑懕敪偡傞丅暉壀斔偼拀慜嬑墹搣偲偟偰嬑墹攈彅斔偺拞偵偁偭偰懚嵼姶傪帵偟偰偄偨偺偩偑丄枊晎偺埑椡偵孅偟丄憤惃昐巐廫柤偺戝検偺張孻偲偄偆乽壋塏偺崠乿偲屇偽傟偨戝抏埑傪壛偊丄嬑峜攈偼夡柵偟偨丅偦偺寢壥丄柧帯怴惌晎憂寶偲偄偆戝帠嬈偵丄堦恖偨傝偲傕嶲夋偡傞偙偲偑弌棃側偐偭偨丅
壓崠屻偺柧帯10擭偵乽岦昹弇乿傪寢惉偟丄10枩梋捸偺嶳椦奐戱偵忔傝弌偡丅柧帯12擭偵慡崙偺墷壔斸敾攈偑寢廤偟戝嶃偱奐嵜偝傟偨乽垽崙幮乿偺戝夛嶲壛屻丄弇傪夝嶶偡傞丅摢嶳枮傗暯壀峗懢榊丒敔揷榋曘摍偑乽岦梲幮乿傪寢惉偟丆3擭屻偵乽尯梞幮乿偲夵徧偟偨丅
幮堳偵偼丄戝孏廳怣敋嶦帠審(寁夋偼幐攕偟塃懌愗抐偺廳彎)偺棃搰峆婌傗弿曽抾屨丒拞栰惓崉丒撪揷椙暯丒峀揷峅婤乧傪攜弌偟偨丅
乽尯梞幮乿偺婎杮惛恄偱偁傞乽幮寷懃嶰忦乿偼丄
戞堦忦丂峜幒傪宧懻偡傋偟
戞擇忦丂杮崙傪垽廳偡傋偟
戞嶰忦丂恖柉偺尃棙傪屌庣偡傋偟
宯晥偵偼丄乽崟棿夛乿乽戝搶弇乿乽戝擔杮惗搣乿乽搶曽夛乿乽楺恖夛乿
仭戝惓帪戙
戝惓婜偵擖傞偲丄擟嫚宯丒峴摦塃梼偑搊応偡傞丅偙偺宯摑偵偼丄乽娭搶崙悎夛乿乽戝擔杮崙悎夛乿乽戝榓柉楯夛乿乽戝惓愒怱夛乿乽峜摴媊抍乿乽戝擔杮惓媊抍乿乽愒壔杊巭抍乿乽揝寣抍乿乧
戝惓8擭丄枮愳婽懢榊丒戝愳廃柧丒嶳揷塏懢榊摍偵傛傝乽桺懚幮乿偑寢惉偝傟偨丅庡挘偼戝垷嵶垷庡媊偵壛偊崙壠妚怴傪彞偊偨丅偦偺屻拞崙忋奀偵偄偨杒堦婸傕婣崙偟嶲壛偟丄杒偺乽擔杮夵憿埬戝峧乿偺敪峴椞晍偟偨丅
庡側摨恖偵偼丄幁巕栘堳怣丒埨壀惓撃丒惔悈峴擵彆丒娾揷晉旤晇丒搱栰嶰榊丒惣揷惻丒埢愳晲帯丒埈旤彑摍偲偄偭偨屻偺徍榓堐怴塣摦偺巜摫幰払偑寢廤偟偨丅宯晥偵偼丄乽戝妛椌乿乽戝壔夛乿乽戝峴幮乿乽峴抧幮乿乽嫽垷妛弇乿乽搶嫽楢柨乿乽巑椦憫乿乽慡擔杮嫽垷摨巙夛乿乽寶崙夛乿乽崙柉愴慄幮乿乧
仭徍榓慜婜偺帪戙
戝惓枛婜偐傜偺晄嫷偵壛偊徍榓偵擖傞嬥梈嫲峇偑婲偭偨丅幐嬈幰偼200枩恖傪挻偊丄擾懞偼旀暰偟偰偄偨丅丂偙偺條側悽憡傪攚宨偵崙壠幮夛庡媊傪庡棳偲偟偨崙壠妚怴塣摦偼媫懍偵偦偺惃椡傪惉挿偝偣偨丅偦偟偰寣偵揾傜傟偨僥儘儖偲僋乕僨僞乕懕敪偟丄嫸婥偺帪戙偲側偭偰偄偭偨丅
丂徍榓 5擭丂嵅嫿壆棷梇偵傛傞昹岥梇岾慱寕帠審
丂徍榓 6擭丂媍夛媫廝枹悑偺3寧帠審丒庱憡姱揁廝寕枹悑偺10寧帠審
丂徍榓 7擭丂寣柨抍帠審丄5.15帠審
丂徍榓 8擭丂恄暫戉帠審
丂徍榓 9擭丂巑姱妛峑帠審丄塱揷孯柋嬊挿巋嶦帠審
丂徍榓11擭丂2.26帠審
丂徍榓18擭丂搶曽摨巙夛帠審丄嬑峜傑偙偲傓偡傃丒堐怴岞榑幮帠審
仭攕愴偲愯椞偺帪戙
攕愴偵傛傞僔儑僢僋偵壛偊丄愯椞孯(俧俫俻)偺亀峜崙巎娤乿偺斲掕丄塃梼恖偺愴斊巜掕丄抍懱偺夝嶶柦椷偵傛傝塃梼恮塩偼夡柵偟偨丅夝嶶柦椷傪庴偗偨抍懱偼300嬤偔偵偺傏傝丄庡側偲偙傠偼乽戝擔杮惗嶻搣乿乽戝搶弇乿乽尯梞幮乿乽戝壔夛乿乽帪嬊嫤媍夛乿乽搶曽夛乿乽寶崙夛乿乽崟棿夛乿乽崙悎戝廜搣乿乽揤峴夛乿乧
攕愴偺崿棎偺拞丄朰傟偰偼側傜側偄斶偟偄帠審傕懕敪偟偨丅
丂8寧22擔丄懜澋摨巙夛堳垽搯嶳帺寛帠審
丂8寧23擔丄柧楴夛媨忛慜帺寛帠審
丂8寧25擔丄戝搶弇戙乆栘楙暫応帺寛帠審
戝搶弇宯偱偼丄3擭屻偺4寧8擔偵塭嶳彲暯偺掜丒娾抝偑乽愯椞壓偺嫵堢偵斶扱偟帺恘丅30擭屻偺徍榓54擭5寧25擔弇挿偺塭嶳惓帯偑乽尦崋朄惂壔偺幚尰傪擬禱偟曭傞乿偲堚彂偟丄愗暊屻対廵怱憻傪懪偪敳偒帺巰偟偨丅
仭愴屻偺徍榓帪戙
徍榓21擭偺戞夞憤慖嫇偵偼丄戝惌搣偵崿偠傝乽揤峜惂曭岇摨柨乿乽擔杮斀嫟楢柨乿乽擔杮妚怴搣乿 摍偺塃攈惌搣偑400埲忋柤忔傝傪忋偘偨丅愴慜偐傜偺宯晥傪崘偖抍懱傕乽媬崙惵擭楢柨乿乽擔杮崙柉搣乿乽媏婙摨巙夛乿乽怴擔杮搣乿乽慡崙嬑楯幰摨柨乿摍傗丄暅堳孯恖宯偺乽媏悈夛乿乽擔杮愴桭抍懱楢崌夛乿摍傕摦偒弌偟偨丅挬慛愴憟屻偵塃攈恮塩傕捛曻夝彍偵側傝丄暉揷慺尠丒峳尨杚悈偵傛傝乽垽崙幰抍懱崸恊夛乿傗杮娫寷堦榊偺乽怴惗擔杮崙柉摨柨乿傗媽搶垷楢柨宯傪摑崌偟偨乽嫤榓搣乿摍偑寢惉偝傟偨丅
徍榓30擭戙偵偼巎忋嬻慜偺婯柾偺斀惌晎丒斀暷塣摦偺埨曐摤憟偑孞傝峀偘傜傟嵍攈惃椡偺朶椡偺棐偑悂偒峳傟偨丅擔偛偲偵崅梘偡傞惌帯摤憟偺偆偹傝偺拞偱丄塃梼攈婋婡姶傪曞傜偣擔杮摨柨丒徍榓堐怴楢柨丒惗嶻搣丒擔擳娵惵擭戉丒弣崙惵擭戉摍偵傛傝乽慡擔杮垽崙幰抍懱夛媍(慡垽夛媍)乿丄帣嬍梍巑晇宯偺乽惵擭巚憐尋媶夛(惵巚夛)丄暉揷慺棼宯偺乽戝擔杮垽崙抍懱楢崌帪嬊懳嶔嫤媍夛(帪懳嫤)乿摍峴摦塃梼偺楢崌懱偑師乆寢惉偝傟偨丅 丂 |
仭擔杮偺崙懱傪庣傞夛 / 惓榑幮
仭峧椞
1 惵擭偺抦堢偲摽堢傪楙惉偟丄慶崙傪垽偡傞惓偟偄柉懓垽惛恄偺姭婲偵偮偲傔傞丅
2 峀偔摨桱偺巑偲摨巙懱傪寢惉楢崌偟丄椡傪崌傢偣偰乽堐怴乿偺巚憐揑尋鑢偲摑崌傪恾傞丅
3 巚憐傪嫮屌偵偟丄擔杮偺楌巎偲摴摑偵斀偡傞嫺寖側傞崙嵺嫟嶻惃椡傪攔寕偟恀惓擔杮偺尠尰偵昁梫偲怣偢傞幚慔妶摦傪幚慔偡傞丅
仭峴摦巜恓
暰夛偼恀惓擔杮庡媊偵婎偯偒丄昳奿傪傕偭偰妶摦偡傞傕偺偲偡傞丅夛堳奺帺偼丄杮怑(惗嬈)傪嵟桪愭偲偟丄尋媶夛丒曭巇妶摦丒奺塣摦偼偦偺梋壣帪娫偵嬌椡嶲壛偡傞傕偺偲偡傞丅
仜 婎杮棟擮
恀惓擔杮庡媊傪宖偘丄擔杮崙懱偺杮媊偱偁傞枩悽堦宯偱楢柸偲懕偔揤峜暶壓傪懜悞偟丄変偑崙撈帺偺揱摑傗暥壔偺傕偮惛恄傪婎慴偲偟偰崙壠偺斏塰傪栚巜偡塣摦偵掟恎偡傞丅
倄俹(儎儖僞丒億僣僟儉)懱惂偵傛傝峳攑偟偨嫵堢丄攓嬥揑帒杮庡媊懱惂傪惀惓偟柉懓帺寛偺尃棙傪庢傝栠偡丅
擔杮柉懓偺惗偒曽偲偟偰揤峜惂傪棙梡偟巊偆惌帯惃椡傪寛偟偰嫋偟偰偼側傜偢丄揙掙懳寛偡傞丅
仜 寷朄偵懳偡傞棟擮
愯椞壓偵墴偟晅偗傜傟偨尨暥塸岅偺孅怞揑寷朄傪懄帪夵惓偟恀偺撈棫崙偲偟偰偺帺庡寷朄偺惂掕傪栚巜偡丅
仜 椞搚栤戣偵懳偡傞棟擮
擔杮屌桳偺椞搚偱偁傞杒曽椞搚(帟晳丒怓扥丒崙屻丒戰懆搰媦傃愮搰楍搰)丄抾搰偺懄帪曉娨傪嫮屌偵悇恑偡傞丅
仜 杊塹栤戣偵懳偡傞棟擮
暅妶掗崙庡媊揑亀儘僔傾亁媦傃攅尃庡媊揑挻撈嵸崙壠拞嫟亁偺怤棯媦傃嫸將崙壠亀愒怓挬慛亁暲傃偵崙嵺僥儘慻怐偵懳偡傞抐屌偨傞杊塹懱惂偺妋棫傪栚巜偡丅
仜 嫵堢栤戣偵懳偡傞棟擮
擔嫵慻偺懄帪夝懱偲嫵堢捄岅傪廋惓暅妶偟丄惵彮擭偵惓偟偄抦幆尒幆偲惤堄傪帩偮恀偺擔杮惛恄傪峀傔傞丅
仜 楌巎娤偵懳偡傞棟擮
惓偟偄専徹傕偣偢擔杮傪怤棯崙壠丒埆嬍偲堦曽揑偵抐嵾偡傞乽搶嫗嵸敾巎娤乿偺懪攋丄惓偟偄楌巎娤偺庽棫偡傞丅
仜 桋崙偵懳偡傞棟擮偲妶摦
崙偺偨傔偵愴偄丄懜偄柦傪媇惖偵偝傟偨屼塸楈偺屼楈偵懳偟垼搲偺惤傪曺偘丄懜悞偺擮傪朰傟偢丄屼楈埨傜偐側傟偲偛柣暉傪偍婩傝偡傞曭巇妶摦傪偡傞丅丂 |
|
丂 |
| 仭億僺儏儕僘儉 [populism]丂 |
   丂
丂
|
仭 恖柉庡媊偲栿偝傟傞偑丄偦偺堄枴偼揔梡斖埻偵傛偭偰堎側傞丅 19悽婭屻敿偺儘僔傾偵偍偄偰敪惗偟偨僫儘乕僪僯僉塣摦偼僣傾乕懱惂懪搢傪栚巜偡抦幆恖偨偪偑擾懞傪嫆揰偲偟偰揥奐偟偨幮夛庡媊塣摦偱偁傞丅
仭 (Populism)19悽婭枛偵暷崙偵婲偙偭偨擾柉傪拞怱偲偡傞幮夛夵妚塣摦丅恖柉搣傪寢惉偟丄惌帯偺柉庡壔傗宨婥懳嶔傪梫媮偟偨丅堦斒偵丄楯摥幰丒昻擾丒搒巗拞娫憌側偳偺恖柉彅奒媺偵懳偡傞強摼嵞暘攝丄惌帯揑尃棙偺奼戝傪彞偊傞庡媊丅戝廜偵寎崌偟傛偆偲偡傞懺搙丅戝廜寎崌庡媊丅
仭 柉廜偺忣弿揑巟帩傪婎斦偲偡傞巜摫幰偑丄崙壠庡摫偵傛傝柉懓庡媊揑惌嶔傪恑傔傞惌帯塣摦丅1930擭戙埲崀偺拞撿暷彅崙偱揥奐偝傟偨丅柉廜庡媊丅恖柉庡媊丅惌帯巜摫幰偑戝廜偺堦柺揑側梸朷偵寎崌偟丄戝廜傪憖嶌偡傞偙偲偵傛偭偰尃椡傪堐帩偡傞曽朄丅戝廜寎崌庡媊丅
仭 堦斒揑偵丄乽僄儕乕僩乿傪乽戝廜乿偲懳棫偡傞廤抍偲埵抲偯偗丄戝廜偺尃棙偙偦懜廳偝傟傞傋偒偩偲偡傞惌帯巚憐傪偄偆丅儔僥儞岅偺億僾儖僗(倫倧倫倳倢倳倱)亖乽柉乿偑岅尮丅偙偆偟偨峫偊偺惌帯壠偼億僺儏儕僗僩偲屇偽傟傞丅暋悢偺廤抍偵傛傞棙奞挷惍偼攔彍偟丄幮夛偺彮悢攈偺堄尒偼懜廳偟側偄孹岦偑嫮偄丅乽戝廜寎崌乿乽戝廜愵摦乿偺堄枴偱傕巊傢傟傞丅偨偩丄桳尃幰偺娭怱偵墳偠偰庡挘傪曄偊偨傝丄婋婡姶傪偁偍偭偨傝偡傞庤朄偼丄億僺儏儕僗僩偲傒側偝傟側偄惌帯壠傕梡偄傞丅
仭 惌帯偵娭偟偰棟惈揑偵敾抐偡傞抦揑側巗柉傛傝傕丄忣弿傗姶忣偵傛偭偰懺搙傪寛傔傞戝廜傪廳帇偟丄偦偺巟帩傪媮傔傞庤朄偁傞偄偼偦偆偟偨戝廜偺婎斦偵棫偮塣摦傪億僺儏儕僘儉偲屇傇丅億僺儏儕僘儉偼彅恘偺寱偱偁傞丅弾柉偺慺杙側忢幆偵傛偭偰僄儕乕僩偺晠攕傗摿尃傪惀惓偡傞偲偄偆曽岦偵岦偐偆偲偒丄億僺儏儕僘儉偼夵妚偺僄僱儖僊乕偲側傞偙偲傕偁傞丅偟偐偟丄戝廜偺梸媮晄枮傗晄埨傪偁偍偭偰儕乕僟乕傊偺巟帩偺尮愹偲偡傞偲偄偆庤朄偑棎梡偝傟傟偽丄柉庡惌帯偼廜嬸惌帯偵懧偟丄弾柉偺僄僱儖僊乕偼帺桼偺攋夡丄廤抍揑擬嫸偵岦偐偄偆傞丅椺偊偽丄嫟嶻庡媊傊偺嫲晐傪攚宨偵偟偨1950擭戙慜敿偺暷崙偵偍偗傞儅僢僇乕僔僘儉側偳偑偦偺戙昞椺偱偁傞丅柉庡惌帯偼忢偵億僺儏儕僘儉偵懧偡傞婋尟惈傪帩偮丅偦偺傛偆側応崌丄栤戣傪扨弮壔偟丄巚峫傗媍榑傪夞旔偡傞偙偲偑偳偺傛偆側奞埆傪傕偨傜偡偐丄崙柉偵岅傝偐偗丄峫偊偝偣傞偺偑儕乕僟乕偺栶妱偱偁傞丅
仭 戝廜偺巟帩傪婎斦偲偡傞惌帯塣摦丅堦斒弾柉偺慺恖(偟傠偆偲)姶妎傪棅傝偵丄惌尃傗摿尃奒媺丄僄儕乕僩憌丄姱椈丄戝抧庡丄戝婇嬈側偳偺晠攕傗摿尃傪惓偡惌帯僄僱儖僊乕偲側傞偙偲傕偁傞偑丄堦曽偱恖婥庢傝偵廔巒偟丄戝廜偺晄枮傗晄埨傪偁偍傞廜嬸惌帯偵娮傞偙偲傕偁傞丅偙偺偨傔乽恖柉庡媊乿乽柉廜庡媊乿側偳偲峬掕揑偵栿偝傟傞応崌傕懡偄偑丄擔杮偱偼乽戝廜寎崌庡媊乿乽廜嬸惌帯乿側偳偲斲掕揑偵巊傢傟傞偙偲偑偁傞丅側偍丄傾儊儕僇偱偼峬掕揑偵丄儓乕儘僢僷偱偼斲掕揑側堄枴偱巊傢傟傞孹岦偑偁傞丅億僺儏儕僘儉偺摿挜偼丄(1)棟惈揑側媍榑傛傝傕忣擮傗姶忣傪廳帇偡傞丄(2)惌帯晄怣傗婛懚偺幮夛惂搙傊偺斸敾傪攚宨偵峀偑傞偙偲偑懡偄丄(3)廤抍揑擬嫸丄壖憐揋傊偺峌寕丄柉庡庡媊偺斲掕側偳偵岦偐偄傗偡偄丄(4)桳尃幰偺娭怱偵墳偠偰庡挘偑曄傢傝堦娧惈偑側偄丄(5)懡偔偺応崌堦夁惈偺塣摦偱偁傞丄側偳偱偁傞丅儔僥儞岅偺乽億僾儖僗(恖乆丄恖柉)乿偑岅尮偱偁傞丅傕偲傕偲偼19悽婭枛偵傾儊儕僇撿惣晹偱擾柉憌傪拞怱偵寢搣偝傟丄柉庡壔丄宨婥懳嶔丄搚抧強桳惂尷丄戝婇嬈偺壡愯杊巭丄強摼嵞暘攝丄昻晉偺嵎惀惓側偳傪梫媮偟偨恖柉搣(People's Party丄Populist Party)偺惌帯塣摦傪偝偡丅1930擭戙埲崀丄搒巗壔偺恑傫偩拞撿暷彅崙偱憡師偄偱弌尰偟丄儊僉僔僐丄僽儔僕儖丄傾儖僛儞僠儞丄儁儖乕丄儃儕價傾側偳偵峀偑偭偨丅1950擭戙慜敿偵傾儊儕僇偱婲偒偨斀嫟嶻庡媊塣摦乽儅僢僇乕僔僘儉乿傗丄僆僶儅惌尃傪斸敾偡傞憪偺崻曐庣塣摦乽僥傿乕僷乕僥傿乕塣摦乿側偳偼丄億僺儏儕僘儉偺堦庬偲偝傟偰偄傞丅擔杮偱偼2000擭戙弶摢偺彫愹弮堦榊惌尃偺抋惗埲崀丄億僺儏儕僘儉偲偄偆偙偲偽偑懡梡偝傟傞傛偆偵側偭偨丅掞峈惃椡偲偺懳寛傪宖偘偨彫愹惌尃偺峔憿夵妚楬慄傗丄戝嶃巗挿偺嫶壓揙(偼偟傕偲偲偍傞)(1969乗丂)傪拞怱偲偡傞乽堐怴偺夛乿偺摦偒側偳偑億僺儏儕僘儉偵偁偨傞偲偝傟傞丅偙偆偟偨億僺儏儕僘儉偺摦偒偼丄婛懚惌帯僔僗僥儉傊偺晄枮傗斸敾偽偐傝傪孞傝曉偡儅僗僐儈傗抦幆憌傊偺晄怣偺昞傟偱偁傞偲偄偆巜揈傕偁傞丅
仭 乧塸岅偱偼億僺儏儕僘儉Populism偲偄偆丅戝廜傪巟帩婎斦偲偟偨惌帯塣摦丅乧
丂
丂 |
| 仭億僺儏儕僘儉 |
   丂
丂
|
堦斒戝廜偺棙塿傗尃棙丄婅朷丄晄埨傗嫲傟傪棙梡偟偰丄戝廜偺巟帩偺傕偲偵婛懚偺僄儕乕僩庡媊偱偁傞懱惂懁傗抦幆恖側偳偲懳寛偟傛偆偲偡傞惌帯巚憐丄傑偨偼惌帯巔惃偺偙偲偱偁傞丅擔杮岅偱偼戝廜庡媊傗恖柉庡媊側偳偲栿偝傟傞傎偐丄惌帯巜摫幰丄惌帯妶摦壠丄妚柦壠偑戝廜偺堦柺揑側梸朷偵寎崌偟偰戝廜傪憖嶌偡傞曽朄傪巜偟丄戝廜寎崌庡媊偲傕栿偝傟傞丅
傑偨丄摨條偺巚憐傪帩偮恖暔傗廤抍傪億僺儏儕僗僩(塸: populist)偲屇傃丄柉廜攈傗戝廜庡媊幰丄恖柉庡媊幰丄傕偟偔偼戝廜寎崌庡媊幰側偳偲栿偝傟偰偄傞丅
偙偙悢悽婭偺妛弍揑掕媊偼戝偒偔梙傟摦偄偰偍傝丄乽恖柉乿丄僨儅僑乕僊乕丄乽挻搣攈揑惌嶔乿傊傾僺乕儖偡傞惌嶔丄傕偟偔偼怴偟偄僞僀僾偺惌搣傊偺儗僢僥儖側偳丄偟偽偟偽峀偔堦娧惈偺柍偄峫偊傗惌嶔偵巊傢傟偨丅塸暷偺惌帯壠偼偟偽偟偽億僺儏儕僘儉傪惌揋傪旕擄偡傞尵梩偲偟偰巊偄丄偙偺條側巊偄曽偱偼億僺儏儕僘儉傪扨偵柉廜偺堊偺棫応偺峫偊偱偼側偔恖婥庢傝偺堊偺寎崌揑峫偊偲尒偰偄傞丅偵傕娭傢傜偢嬤擭怴偨偵妛幰偵傛偭偰億僺儏儕僗僩偺尒暘偗曽傗斾妑暘椶偺堊偺掕媊偑傑偨嶌傜傟偰偄傞丅Daniele Albertazzi偲Duncan McDonnell偼億僺儏儕僘儉偺掕媊傪乽嬒堦揑(恖庬丒廆嫵側偳偑嫟捠偺)椙柉傪丄僄儕乕僩憌偲婋尟側亀堘偆恖乆亁傪椉幰嫟偵庡尃幰偨傞恖乆偐傜尃棙丄壙抣娤丄繫塰丄傾僀僨儞僥傿僥傿乕丄敪尵椡傪扗偆(傕偟偔偼扗偍偆偲偡傞)傕偺偲愢偒丄柉廜偲懳寛偝偣傞乿棟擮偲偟偰偄傞丅
嬤擭偱偼丄乽暋嶨側惌帯揑憟揰傪扨弮壔偟偰丄偄偨偢傜偵柉廜偺恖婥庢傝偵廔巒偟丄恀偺惌帯揑夝寛傪夞旔偡傞傕偺乿偲偟偰丄億僺儏儕僘儉傪乽戝廜寎崌(庡媊)乿偲栿偟偨傝丄乽廜嬸惌帯乿偺堄枴偱巊梡偡傞椺偑憹壛偟偰偄傞丅懞忋峅偵傛傟偽丄屄恖揑側恖婥傪旛偊偨惌帯壠偑惌搣慻怐側偳傪宱偢偵捈愙戝廜偵慽偊偐偗傞偙偲傗丄扨弮壔偟偡偓傞僗儘乕僈儞傪宖偘傞偙偲傪巜偡偲偡傞丅
柉庡庡媊偼柉堄傪婎慴偲偡傞傕偺偺丄柉廜慡懱偺棙塿傪埨堈偵憐掕偡傞偙偲偼彮悢幰傊偺梷埑側偳偵偮側偑傞婋尟惈傕偁傞偲偄偆堄枴偱偼丄廜嬸惌帯偵揮偠傞婋尟惈偼懚嵼偡傞偑丄偦傟偼柉庡庡媊偺杮幙偱偁偭偰丄億僺儏儕僘儉偦偺傕偺偺栤戣偱偼側偄丅柉庡惂偼恖柉庡尃傪慜採偲偡傞偑丄娫愙柉庡惂傪娷傔偨婛懚偺惂搙傗巟攝憌偑丄廫暘偵婡擻偟偰偄側偄応崌傗丄捈柺偡傞婋婡偵懳墳偱偒側偄応崌丄晠攕傗晄惓側偳偱怣梡偱偒側偄偲戝廜偑峫偊偨応崌偵偼丄億僺儏儕僘儉傊偺捈愙巟帩偑奼戝偟偆傞丅偦偺嵺偵偼億僺儏儕僗僩偑戝廜偵捈愙慽偊傞柉夛丒弌斉丒儅僗僐儈側偳偺儊僨傿傾偺懚嵼偑廳梫偲側傞丅
僲乕儔儞丒僠儍乕僩偵傛傞掕媊偱偼丄屄恖揑帺桼偺奼戝偍傛傃宱嵪揑帺桼偺奼戝偺偳偪傜偵偮偄偰傕怲廳側偄偟徚嬌揑側棫応傪嵦傞惌帯棟擮傪億僺儏儕僘儉偲埵抲偯偗丄尃埿庡媊傗慡懱庡媊偲摨媊偲偟偰偍傝丄屄恖揑帺桼偺奼戝偍傛傃宱嵪揑帺桼偺奼戝偺偳偪傜偵偮偄偰傕愊嬌揑側棫応傪嵦傞儕僶僞儕傾僯僘儉(帺桼帄忋庡媊)偲偼懳嬌偺奣擮偲偟偰偄傞丅
|
仭楌巎
乽億僺儏儕僘儉乿偺梡岅偼乽儔僥儞岅: populus(柉廜)乿偵桼棃偟丄捠忢偼乽僄儕乕僩庡媊乿偲偺懳斾偱巊梡偝傟傞丅
屆戙儘乕儅偱偼乽populus乿偼乽儘乕儅巗柉尃傪帩偮幰乿偺堄枴偱偁偭偨偑丄億僺儏儕僗僩払偼乽柉廜攈(戝廜攈)乿偲傕屇偽傟傞帠幚忋偺搣攈偲側傝丄僥傿儀儕僂僗丒僌儔僢僋僗丄僈僀僂僗丒儅儕僂僗丄僈僀僂僗丒儐儕僂僗丒僇僄僒儖丄傾僂僌僗僩僁僗側偳偼丄尦榁堾傪夞旔偡傞偨傔偵柉廜偵捈愙慽偊偰巗柉廤夛偱搳昜傪屇傃偐偗偨丅
19悽婭偵儓乕儘僢僷偱敪惗偟偨儘儅儞庡媊偼丄廬棃偺抦幆恖拞怱偺崌棟庡媊傗抦惈庡媊偵懳峈偟丄戝廜偵僫僔儑僫儕僘儉傗億僺儏儕僘儉偺塭嬁傪梌偊偨丅1850擭偐傜1880擭偺儘僔傾掗崙偱偼丄抦幆恖(抦揑僄儕乕僩)偵懳棫偡傞塣摦偲偟偰尰傟偨丅
19悽婭枛偺傾儊儕僇崌廜崙偱偼丄恖柉搣(捠徧億僺儏儕僘儉搣)偑婛惉偺巟攝憌偱偁傞揝摴傗嬧峴傪峌寕偟丄惌帯巚憐偲偟偰偺乽億僺儏儕僘儉乿偑峀偔抦傜傟傞傛偆偵側偭偨丅埲屻傕傾儊儕僇偱偼丄儅僢僇乕僔僘儉傗丄2000擭戙偺僥傿乕僷乕僥傿乕塣摦側偳偑億僺儏儕僘儉偲屇偽傟偰偄傞丅
1930擭戙偺僀僞儕傾偺僼傽僔僘儉塣摦丄僪僀僣偺僫僠僘儉丄傾儖僛儞僠儞偺僼傾儞丒儁儘儞惌尃側偳偼丄婛懚偺僄儕乕僩憌偱偁傞戝婇嬈丒奜崙帒杮丒幮夛庡媊幰丒抦幆恖側偳偵嫮偔斀懳偟丄戝廜偵懳偟偰屬梡傗楯摥忦審岦忋傪幚尰偡傞曄妚傪捈愙慽偊偨偨傔丄億僺儏儕僘儉偲屇偽傟傞応崌偑懡偄丅丂 |
仭閤傝偺抧暯丂嫊忺偺惓媊
億僺儏儕僘儉偲偄偆偺偼丄戝廜寎崌庡媊偲栿偝傟傑偡偑丄偦傕偦傕偼丄僄儕乕僩庡媊偲偼懳棫偡傞奣擮偲偟偰丄19悽婭偐傜20悽婭偵偐偗丄傾儊儕僇偱惗傑傟偨惌帯庤朄偺偙偲偱偡丅
戝廜偑惌帯偺拞怱偵埵抲偡傞偨傔偵丄戝廜偑婜懸偡傞惌帯傗惌嶔傪傾僺乕儖偟丄偦傟偵傛偭偰丄暆峀偄巗柉塣摦傪宍惉偡傞偨傔偵丄儅僗僐儈傪摦堳偟偨戝廜偺孾敪偲慻怐壔偑偦偺杮棃偺堄枴偡傞傕偺偱偡丅
戝廜傊偺忣曬奐帵傗揱攄傪偦偺拰偲偟丄僄儕乕僩廤抍偩偗偱堄巙寛掕偝傟傞惌帯偐傜丄戝廜傪峀偔庢傝崬傫偩惌帯傪宍惉偡傞偲偄偆峫偊曽偱偡丅
偡側傢偪丄柉庡庡媊偵偼丄偙偺億僺儏儕僘儉偲偄偆偺偼愗偭偰傕愗傝棧偣側偄娭學偵偁傝丄柉庡庡媊偑揮傇偲偒偵偼丄摨偠傛偆偵丄偙偺億僺儏儕僘儉偑廳梫側梫場偲側傝傑偡丅
偨偲偊偽丄傾儊儕僇戝摑椞慖嫇側偳偵尒傜傟傞丄儅僗僐儈偺妶梡偼偦偺揟宆偱偡偟丄惗傑傟偨偲偒偐傜僱僢僩幮夛偵偁傞丄僨僕僞儖僱傿僥傿僽偺庒幰偨偪偑丄僀儞僞乕僱僢僩偺忣曬傪捠偠偰丄悽奅拞偱楢懷偟丄僄僀僘杘柵偺偨傔偺廤夛傗僨儌傪慻怐偡傞偲偄偆偺傕丄偙偺庤朄偵傛傞傕偺偱偡丅
婛惉偺壙抣娤傗婛摼尃偺暻傪夡偟丄怴偨側塣摦傪婲偙偟丄戝廜傪慻怐偡傞偲偄偆揰偱丄偦偙偵偼丄斀婛惉尃椡偲偦偺尃椡傪巟偊偰偄傞丄姱椈傊偺斀僄儕乕僩庡媊偑偁傝傑偡丅
偟偐偟丄偙傟偼丄摨帪偵恖婥庡媊偵傛傞丄廜嬸惌帯偲傕側傞彅恘偺寱偱偡丅
愴慜偺僪僀僣偱偼丄僸僩儔乕偑尃椡傪帺暘堦恖偵廤栺偡傞偙偲偱丄僼傽僔僘儉偑宍惉偝傟傑偡偑丄偙傟傪巟帩偟丄巟偊偨偺偼戞堦師悽奅戝愴偱悽奅偱桞堦偺攕愴崙偲側傝丄惗妶偑旀暰偟偰丄帺怣傪憆幐偟偰偄偨僪僀僣恖偺崙柉姶忣偱偡丅
僸僩儔乕偼偙偺柉廜偺惗妶傊偺晄枮丄懠崙傊偺晄枮丄偦偟偰丄帺怣傪憆幐偟偨傗傝応偺側偄姶忣傪岻傒偵撉傒丄偦偙偵僎儖儅儞柉懓庡媊傪嫮偔慽偊丄偙傟傪戝廜壔偡傞偙偲偱丄僼傽僔僘儉傪宍惉偟傑偟偨丅
傑偨丄僀僞儕傾偱偼丄儉僢僜儕乕僯偑斀僄儕乕僩庡媊傪彞偊丄擔杮揑偵尵偊偽丄嫏巘偺慻崌偺偍偭偮偀傫偑楺壴愡揑偵丄乽嬥帩偪傗僄儕乕僩偵惌帯偼擟偣傜傟僱僃乿偲丄惗妶偵崲媷偡傞昻偟偄楯摥幰傪庢傝崬傓偙偲偱丄柉暫慻怐傪偮偔傝丄偙傟偑暥柉惌帯偵埑椡傪妡偗傞偙偲偵側傝丄僼傽僔僘儉傪宍惉偟傑偟偨丅
摨偠傛偆側僼傽僔僘儉偱偁傝側偑傜丄僪僀僣偲僀僞儕傾偺偦傟偵偼戝偒側堘偄偑偁傝傑偡丅
僸僩儔乕偺僼傽僔僘儉偼斀僄儕乕僩庡媊偼側偔丄揙掙偟偨僄儕乕僩庡媊偲傕尵偊傞傕偺偱丄僸僩儔乕帺恎丄僎儖儅儞柉懓偺桪埵惈傪屰晳偡傞偙偲偱丄曃嫹側僄儕乕僩庡媊傪崙柉姶忣偵怉偊晅偗傑偟偨丅偦偺偨傔偺揋偲偟偰丄斀儐僟儎庡媊傪採彞偡傞傢偗偱丄偁傞堄枴丄僸僩儔乕偺僼傽僔僘儉偵偼柧妋側堦娧惈偲榑棟惈偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄偦偺椻揙側榑棟惈備偊偵丄擔杮丄僀僞儕傾傪彍偔丄悽奅偡傋偰傪揋偵夞偟偰偟傑偭偨偲偄偆嬸偝偑偁傝傑偡丅
偟偐偟丄僀僞儕傾偺偦傟偼丄嵍攈傕塃攈傕側偔丄媊棟恖忣傗怱忣偵傛偭偰丄乽昻偟偄偍傜偨偪偑丄怴偟偄丄偄偄崙偵偡傫傋乿偲偄偭偨椶偺傕偺偱丄儔僥儞宯傜偟偔丄旕忢偵姶忣揑偱丄捈忣揑側僼傽僔僘儉偱偡丅尵偄姺偊傟偽丄旕忢偵柍拋彉偱丄柍嫵梴側傕偺偱偡丅
擔杮偺愴慜丄愴娫婜偺僼傽僔僘儉偼丄堦斒偵僪僀僣偺僼傽僔僘儉偺宍懺傪柾曧偟偨偲尵傢傟偰偄傑偡偑丄尰幚揑偵偼丄偙偺僀僞儕傾宆偵帡偰偄偰丄徍榓15擭偵嬤塹暥枦憤棟戝恇偵傛偭偰丄巜摫丄敪埬偝傟丄濨枂側傑傑抋惗偟偨丄戝惌梼巀夛偲偄傢傟傞嫇搣懱惂傕丄傑偝偟偔偙傟偱偡丅
尰嵼傕偦偆偱偡偑丄愴慜偵偍偄偰偼丄尰嵼傛傝側偍丄墷暷偵斾傋丄惌帯偺惉弉搙偑旕忢偵抶傟偰偄偨擔杮偱偼丄悽奅奺崙偺摦岦偲巚榝傪廂廤偱偒傞忣曬椡傕側偔丄傑偨丄攃埇偱偒偰偄偨偲偟偰傕丄偙傟傪暘愅偱偒傞摢擼傕側偔丄揔愗側崙嵺嫤挷傗楢懷偑偱偒傞丄崙嵺姶妎偲僶儔儞僗姶妎傪帩偭偨丄嫮椡側儕乕僟乕丄惌帯壠偑慡偔偄傑偣傫偱偟偨丅
偦偺偨傔丄徍榓6擭偺娭搶孯偵傛傞枮廈怤棯埲屻丄崙惌丒奜岎偵偍偄偰嫮偄敪尵尃傪帩偮傛偆偵側偭偰偄偨丄棨孯撪晹偺岎愴攈(偄傢備傞丄摑惂攈偲屇偽傟偰偄偨楢拞)丄娙扨偵尵偆偲丄崙搚奼挘攈(怤棯偲尵偆傛傝偼乽奼挘榑乿偺屇徧偺曽偑戝搶垷嫟塰寳峔憐偺婎杮奣擮偵嬤偄偨傔)偲懳洺偡傞偨傔偵丄堦崙堦搣庡媊偲偄偆僪僀僣傗僀僞儕傾丄僜價僄僩偺傛偆側摑惂崙壠峔憐偑晜傃傑偡丅
奐愴傪慾巭偱偒側偐偭偨憤棟戝恇偲偟偰斸敾偝傟傑偡偑丄嬤塹偵偟偰傒傟偽丄戝惌梼巀夛偲偄偆嫇搣懱惂傪庢傞偙偲偱丄孯晹傪庢傝崬傒丄偦偺朶敪傪杊偖偲偄偆慱偄傕偁偭偨偺偱偡丅
偟偐偟丄寢嬊偼丄懢暯梞愴憟傊岦偗丄暥柉姱椈(攚峀)慻傕丄棨孯偺姱椈慻傕丄朶憱偡傞棨孯撪晹偺岎愴揑側摑惂攈(崙搚奼挘榑攈)傪梷偊傞偙偲偑偱偒偢丄嬤塹偑昤偄偨孯晹偺僐儞僩儘乕儖偼偱偒側偔側傝傑偡丅偐偮丄摉帪偺柧帯寷朄偱偼丄揤峜傪捀揰偲偡傞枩悽堦宯偺峜崙巎娤偲傕丄揤峜偺摑悆尃偲傕丄堦崙堦搣峔憐偼柕弬偡傞偨傔丄崿棎偟丄暔媍傪忴偡偺偱偡丅
側偤側傜丄嬤塹暥枦偑崙夛偐傜巗挰懞媍夛傑偱傪摑崌偡傞戝惌梼巀夛偺憤嵸偲側傟偽丄揤峜傪捀揰偲偡傞孯偺巜婗宯摑偲柕弬偡傞偐傜偱偡丅
偲偙傠偑丄傾儊儕僇偲偺奐愴偑旔偗傜傟側偄忣惃偵側偭偰丄忬嫷偑昇敆偟偰偔傞偲丄惌帯壠傕孯晹傕丄僷僯僢僋忬懺偵側傝丄揤峜偺摑悆尃偼扞忋偘偟丄棟孅偼偲傕偐偔丄庡媊庡挘偼偲傕偐偔丄偲傝偁偊偢丄愴帪壓偵偍偄偰偼嫇崙堦抳偱側偗傟偽偲偄偆扨弮側巚榝偐傜丄忔傝抶傟偰偼儎僶僀偲嵍攈傕塃攈傕拞摴攈傕偙傟偵嶲壛偡傞偲偄偆偰偄偨傜偔傪尒偣傑偡丅
偲偙傠偑丄偙偆偟偨惌搣傗孯晹偺摦偒偵楢摦偟丄巟帩偟偨偺偑丄乽懪偨傟偨傜丄懪偪曉偣両乿偲埿惃偺偄偄妡偗惡偱寢廤偟偨丄塆崌偺廜丄岎愴傛偟偲偡傞嫵梴偺側偄丄戝廜偱偟偨丅椙幆偁傞抦幆恖偨偪偺惡傕丄孯晹偵傢偢偐偵偄偨崙嵺姶妎傪帩偮僄儕乕僩姱椈偨偪偺惡傕丄偡傋偰丄偦偺柍抦丄柍嫵梴側惡偵偐偒徚偝傟偰偟傑偄傑偡丅
偦偺寢壥丄惂暈慻偵傛傞暥柉摑惂(僔價儕傾儞僐儞僩儘乕儖)偼慡偔婡擻偟側偔側傝丄擔杮偐傜巔傪徚偟傑偡丅偦偟偰丄戝擔杮嶻嬈曬崙夛丒擾嬈曬崙楢柨丒彜嬈曬崙夛丒擔杮奀塣曬崙抍丒戝擔杮晈恖夛丒戝擔杮惵彮擭抍偲偄偭偨丄崙柉偺偁傜備傞奒憌傪庢傝崬傫偩崙壠嵟桪愭丄棨孯偺崙搚奼挘榑嵟桪愭偺孯晹庡懱偺惌嶔傪巟帩偡傞懱惂偑弌尰偟偨偺偱偡丅
偄傢偽丄乽傾儊儕僇偑僔乕儔僀儞傪晻嵔偡傞側傜丄偙偭偪傕傗傝曉偣両丂偱側偒傖丄偍傜偨偪偺惗妶偑傑偡傑偡嬯偟偔側傞偩偵両乿偲偄偭偨忬嫷偺拞偱丄乽偁偭偪偺懞偱傕傗傞傫側傜丄偍傜偨偪偺懞傕丄偦偺側傫偨傜偭偰偄偆抍懱偵擖偭偰偍偐偹偉偽丄庢傝巆偝傟偪傑偆偩両乿乽偁偲偱丄僆儊僆儊摢壓偘偰丄擖傟偰偔傟偭偰偄偭偨傜丄徫傢傟偪傑偆偧両乿偲偄偭偨惃偄偱丄愴憟傊傑偭偟偖傜偺戝惌梼巀夛偑抋惗偟偰偟傑偆偺偱偡丅
偙偺揰偑僀僞儕傾偺捈忣揑側僼傽僔僘儉偲旕忢偵椶帡偟偰偄傑偡丅
徍榓13擭丄枮廈帠曄埲屻丄拞崙戝棨傊偺弌暫傪懕偗傞娭搶孯偵傛偭偰揇徖壔偟偰偄偨擔拞愴憟傪宲懕偡傞偨傔偵丄崙壠憤摦堳朄偑丄傗偼傝嬤塹暥枦偵傛偭偰抋惗偟傑偡偑丄偙傟傕丄偙偆偟偨戝廜怱棟偵巟偊傜傟偰偄傑偟偨丅
偦偙偵偁偭偨偺偼丄悽奅嫲峇偵傛偭偰崙撪宱嵪偑旀暰偟偨拞丄捛偄摙偪傪偐偗傞傛偆偵丄棨孯偺堦晹偑巒傔偰偟傑偭偨枮廈怤棯偵傛偭偰丄偝傜偵惗妶偑崲媷偟偰偄偨崙柉偺惗妶晄埨偲僕儗儞儅偑偁傝傑偟偨丅
怤棯偵傛偭偰丄崙搚偺奼挘偵傛偭偰丄崙壠宱嵪偑傛偔側傞偲峫偊偨偺偼丄棨孯偺摑惂攈丄崙搚奼挘榑攈偽偐傝偱側偔丄崙柉姶忣傕偦傟傪屻墴偟偟偰偄偨偺偱偡丅偟偐傕丄棨孯偺摑惂攈偲屇偽傟傞孯忋憌晹偼丄僄儕乕僩偲尵傢傟偨丄巑姱妛峑丄棨孯戝妛弌恎幰偺拞偱傕惉愌偺怳傞傢側偐偭偨搶忦塸婡傜丄棊偪偙傏傟廤抍偱偡丅
偙偙偵僀僞儕傾揑僼傽僔僘儉偺峔憿偑惉棫偟偰偟傑偭偨偺偱偡丅
偮傑傝丄孯晹傪僐儞僩儘乕儖偟偰偄偨僄儕乕僩姱椈傪榚偵抲偒丄埿惃偺偄偄妡偗惡傪忋偘傞丄棊偪偙傏傟偺孯恖偨偪偑丄斀僄儕乕僩庡媊傪庡挘偡傞偙偲偱丄孯偺拞悤傪埇傝丄偐偮丄偦偺屇傃偐偗偵丄偪傑偪傑偟偨僄儕乕僩惌帯壠傗姱椈偵寵婥偑嵎偟偰偄偨戝廜偑寎崌偟偨偺偱偡丅
偦偙偵偁偭偨偺偼丄攕愴偵傛偭偰業掓偟偨丄嫊忺偺惓媊偱偟偨丅
孯偺椡偺屩帵側偔偟偰丄奜岎偼偱偒側偄偲偄偆塕傪偮偒丄晲椡偵偼晲椡偵傛偭偰棫偪岦偐偆偟偐夝寛偺摴偼側偄偺偩偲崙柉傪閤偟丄楢屇偟懕偗偨堦晹偺崙嵺姶妎側偒丄塸岅傕傑偲傕偵偟傖傋傟偢丄彂偗偢丄墷暷恖偲傑偲傕偵夛榖傕偟偨偙偲偺側偄丄柍抦柍擻偺崙悎庡媊幰偨偪偱偡丅
偄傑僥儗價傗堦晹嶨帍偱丄愕抪怱傕側偔丄愭偺愴憟愑擟偼擔杮偵偼側偐偭偨偲嬸偐側偙偲傪閤傝懕偗偰偄傞丄尦峲嬻帺塹戉嬻敋挿偺揷曣恄弐梇偲偦傟偵摨挷偟偰偄傞丄乽怴偟偄楌巎嫵壢彂傪偮偔傞夛乿夛挿偺惣旜姴擇丄偝傜偵偼丄斵傜傪丄柍擻偺戝廜傛傠偟偔丄巟帩偟偰偄傞丄戝惌梼巀夛嶨帍WiLL偺傗偭偰偄傞偙偲偼丄傑偝偵丄偙偺斀僄儕乕僩庡媊傪庡挘偟丄乽暥柉惌帯壠偵惌帯偼擟偣偰偍偗側偄偐傜丄揷曣恄偺傛偆側恖娫偵惌帯偺拞悤傪埇傜偣傠両乿偲摨偠僯儏傾儞僗偱丄寢壥揑偵僼傽僔僘儉傪慀傝懕偗偰偄傞偺偱偡丅
徍榓13擭崰偺擔杮偺惌帯宱嵪忬嫷偲尰嵼偼旕忢偵傛偔帡偰偄傑偡丅惗妶奿嵎傪書偊偨宱嵪忬嫷丄偵傕偐偐傢傜偢丄婇嬈偼奿嵎傪傛偟偲偟偰恖傪愗傝幪偰丄惌帯偼柍擻偱丄崙柉偺偨傔偺嬶懱嶔傪採帵偱偒側偄忬嫷丄偦傟傜偑旕忢偵椶帡偟偰偄傞偺偱偡丅
尰幚偵丄WiLL偺憤寛婲廤夛偵偼丄揷曣恄偺島墘偵擬楏側攺庤偲巀摨偑暒偒婲偙傝丄傑偝偵丄柧擔丄杒挬慛偵岦偗丄帺塹戉偑弌暫偟偰丄僐僥儞僐僥儞偵懪偪偺傔偟偰偟傑偊偲偄偆傛偆側擬婥偵曪傑傟偰偄傑偟偨丅
偩偐傜丄妀晲憰傕摉慠偲偄偆嬻婥偑夛応傪曪傒傑偟偨丅偙偺愵摦偺愑擟偼堦懱丄偩傟偑偲傞偺偐丅
偟偐偟丄弎傋偰偒偰偄傞傛偆偵丄鉱枾偵夁嫀偺楌巎傪昍夝偗偽丄揷曣恄偺尵偭偰偄傞楌巎娤傗乽怴偟偄楌巎嫵壢彂傪偮偔傞夛乿偺榑挷偑丄偄偐偵庤慜彑庤偱丄偆偡偭傌傜偄傕偺偐偑傢偐傝傑偡丅
揷曣恄傪峲嬻帺塹戉偺尰応偺僩僢僾偺恖帠偵偝偣偨帺塹戉偺懱幙傗杊塹挕(摉帪)偺尒幆偺側偝傕旕擄偝傟傞傋偒偱偡偑丄揷曣恄偼杮棃丄偦偆偟偨棫応偵棫偰傞傛偆側僉儍儕傾傪愊傫偱偒偨僄儕乕僩姱椈偱偼偁傝傑偣傫丅傑偝偵丄搶忦塸婡偺傛偆偵丄惉傝忋偑偭偰傗偭偲僩僢僾偺嵗傪庤偵擖傟偨恖娫偱偡丅
偦偺抝偑島墘偱暯慠偲丄惂暈慻傪柍抦柍擻屇偽傢傝偟丄杒挬慛偲偺壏偄奜岎岎徛偱偼偩傔偱丄岎徛偑寛楐偡傟偽丄帺塹戉偑弌暫偟偰揙掙揑偵扏偔昁梫偑偁傞偲傑偱尵偄愗偭偰偄傑偡丅
帺塹戉偑寷朄偱偦偺棫応傪曐徹偝傟偰側偄塢乆傪斵偼尵偄傑偡偑丄斵偺閤傝偺撪梕偼偦偺栤戣偲偼傑偭偨偔娭學偑偁傝傑偣傫丅斵偺尵摦偦偺傕偺偑偡偱偵寷朄傪柍帇偟偰偄傞偐傜偱偡丅
斵偼帺塹戉偺愑擟幰偺堦恖偱偁傝丄崙柉偑慖傫偩暥柉惌帯壠偵傛偭偰摑妵娗棟偝傟傞棫応偺岞柋堳偵夁偓傑偣傫丅傑偟偰丄崙偺杊塹偲偄偆巇帠偵摉偨傝丄寷朄偵峉懇偝傟傞恖娫偑丄屄恖偺堄尒偩偐傜壗傪尵偭偰傕偄偄崻嫆側偳偦傕偦傕側偄偺偱偡丅
偦傟偼尵榑摑惂偱偼側偔丄寷朄偵峉懇偝傟傞棫応偺恖娫偑崙柉傊偺摉慠偺愑柋偲偟偰慡偆偟側偔偰偼側傜側偄偙偲偱偡丅夝擟丄峏揜偑尵傢傟偨偺傕偦偺偨傔偱偡丅
斵偺棟孅偼丄戝摑椞偠傖棅傝偵側傜側偄偐傜丄妀偺僗僀僢僠傪帺暘偨偪孯恖偵帩偨偣傠偲尵偭偰偄傞偺偵摍偟偄偙偲偱偡丅
寷朄偼崙柉偑摑帯幰丄尃椡幰傪敍傞偨傔偺嵟崅婯斖偱丄揷曣恄偺傛偆側岞柋堳偼偙傟偵廬偆丄岞杔偲偟偰偺愨懳偺媊柋偲愑擟偑偁傞偺偱偡丅側偤側傜丄斵偼巹偨偪偺寣惻偵傛偭偰惗妶傪曐徹偝傟偨恖娫偱丄偦傟埲忋偺懚嵼偱偼偁傝傑偣傫丅
嬤戙寷朄偺惉傝棫偪偵偮偄偰丄偙偺恖偼傑偢曌嫮偡傋偒偱偡丅
偦偟偰丄壗傛傝丄斵偑岤婄柍抪側偺偼丄偦偆偟偨斀惌晎丄斀暥柉摑惂傪庡挘偟側偑傜丄億僗僩偵偟偑傒偮偄偰丄帺屓偺庡挘傪偟丄柉庡庡媊偺尨棟傪傑偭偙偆偐傜斲掕偟偰偄傞偙偲偱偡丅
偦偙傑偱偺偙偲傪岞柋堳偑岅傟傞尃棙偼偁傝傑偣傫丅寷朄傪棟夝偡傞擻椡偑側偄側傜丄傑偢丄崙壠岞柋堳朄偐傜曌嫮偡傋偒偱偡丅偝傕側偔偽丄帺傜寜偔怑傪帿偡傋偒偩偭偨偺偱偡丅擔杮抝巕偲偄偆尵梩傪斵偼楢屇偟傑偡偑丄側傜偽丄棪愭悇堏丄怑傪帿偟丄擔杮抝巕偲偟偰偺屩傝偲柤梍傪帵偡傋偒偩偭偨偼偢偱偡丅偦偺忋偱丄帩榑傪揥奐偡傟偽偄偄丅偦偺婥崪傕側偄偲偙傠偱丄帺暘偱偼側偄庒幰偺柦傪媇惖偵偡傞愴憟傪岅傞帒奿側偳偁傝傑偣傫丅
偟偐傕丄偦傟偽偐傝偐丄巹偨偪偺寣惻偐傜擯弌偝傟偨丄戅怑嬥傕偟偭偐傝傕傜偄丄偐偮丄僥儗價傗嶨帍偵搊応偟丄崙悎庡媊傪慀傝丄愵摦偡傞偙偲偱嬥傪壱偄偱偄傞丅偙偺巔偼廥偄偲偟偐尵偄傛偆偑偁傝傑偣傫丅
斵偺島墘偵嶲壛偟偰偄偨恖乆偺懡偔偑50戙埲忋70戙慜屻偺楢拞偩偭偨偺偼媬偄偱傕偁傝傑偡偑丄摨帪偵丄婋尟偱傕偁傝傑偡丅偐偮偰丄愴憟傪傛偟偲偟偨嫮偄惡偼丄帺傜愴抧傊岦偐偆偙偲偺側偄丄偙偆偟偨儘乕僩儖偨偪偩偭偨偐傜偱偡丅
偟偐偟丄尰嵼偺傛偆偵丄惌帯丒宱嵪偑崿柪偟偰偄傞偲偒丄偐偮偰偺擔杮偺傛偆偵丄娫寗傪朌偭偰丄偙偆偟偨戝惌梼巀夛揑側嬻婥偑惃偄傪憹偡偺偼梊應偱偒傞偙偲偱偡丅
偦偟偰丄揷曣恄偺傛偆側恖娫傪棙梡偟偰丄巹梸傪朿傜傑偦偆偲偡傞攜偑埫桇偟傑偡丅
偦偺晅偗傪嵟屻偵暐偆偺偼丄偩傟側偺偐丅
偄傑尰幚偵婇嬈偑帺暘偨偪偺晅偗傪偩傟偵暐傢偣偰偄傞偺偐丅
偄傑丄偙偺崙偺惌帯偑惌帯壠偺晅偗傪偩傟偵暐傢偣偰偄傞偺偐丅
偦偺堦揰傪椻惷偵傒偮傔偰傕丄揷曣恄媦傃丄斵傪棙梡偟丄嵳傝忋偘偰偄傞攜偺攚屻偵偁傞幰偺愺傑偟偒巔偑尒偊偰偒傑偡丅
偟偐偟丄偙偆偟偨怺椂傕偣偢偵丄寍恖摨慠偵僥儗價偵業弌偝偣丄摨偠偔妛幆傕嫵梴傕側偄偍僶僇僞儗儞僩偵丄揷曣恄偺堄尒傊巀摨偝偣偰偄傞僥儗價惂嶌幰偨偪傛丅
偁側偨偨偪偼丄帇挳棪偺偨傔偵偼溳傞偙偲側偔丄恖傪棙梡偟傑偡偑丄偐偮偰丄300枩恖傕偺恖乆偑柦傪棊偲偟偨丄愴憟傊偺摴傪丄僼傽僔僘儉傊偺愵摦偺愑擟傪丄偁側偨偺柦偱孳偆妎屽偼偍偁傝側偺偱偡偐丠
|
仭巹偨偪偼億僺儏儕僘儉偺帪戙偵惗偒偰偄傞
愭恑僨儌僋儔僔乕偺崙乆偺懡偔偼丄億僺儏儕僘儉偺帪戙傪寎偊偰偄傞丅僀僞儕傾偺儀儖儖僗僐乕僯庱憡丄僼儔儞僗偺僒儖僐僕戝摑椞偩偗偱偼側偄丅傾儊儕僇偱偼愭偺拞娫慖嫇偱憪偺崻曐庣偲偟偰偺乽僥傿乕丒僷乕僥傿乿偑戜晽偺栚偲側傝丄埨掕偟偨惌帯傪宱尡偟偰偄傞偐偵傒偊傞杒墷彅崙偱傕嬌塃億僺儏儕僘儉(乽僫僔儑僫儖丒億僺儏儕僘儉乿)惌搣偺桇恑偑巭傑傜側偄丅擔杮偱傕摑堦抧曽慖嫇傪寎偊偰丄億僺儏儕僗僩揑側惌嶔傪懪偪弌偡乽庱挿怴搣乿乽抧堟惌搣乿偑婛懚惌搣偺堦妏偵怘偄崬傒惃偄傪傒偣偰偄傞丅偙偆偟偨僩儗儞僪偼丄嬼慠偺堦抳偱偼寛偟偰側偄丅
亀億僺儏儕僘儉傪峫偊傞丂柉庡庡媊傊偺嵞擖栧亁偱栚揑偲偟偨偺偼丄偙偺億僺儏儕僘儉偺儊僇僯僘儉傪棟夝偡傞偙偲丄偮偓偵偦傟偑側偤惗偠傞偺偐偺僟僀僫儈僘儉傪拪弌偡傞偙偲丄偦偟偰壗傛傝傕丄億僺儏儕僘儉傪捠偠偰尰嵼偺柉庡惌帯偑書偊偰偄傞崲擄傪柧傜偐偵偡傞偙偲偱偁傞丅
乽億僺儏儕僘儉乿偲偄偆尵梩偼昿斏偵巊傢傟傞擔忢梡岅偱偁傝丄晛捠曁徧偱梡偄傜傟傞偙偲偑懡偄丅偟偐偟丄偦偺嬶懱揑側堄枴撪梕偼昁偢偟傕柧妋偱偼側偄偲偙傠偵摿挜偑偁傞丅偼偨偟偰丄億僺儏儕僘儉偲偼偄偭偨偄壗偱偁傠偆偐丅
仭億僺儏儕僘儉亖戝廜寎崌側偺偐丠丂
傛偔偄傢傟傞偺偼丄億僺儏儕僘儉偑乽戝廜寎崌庡媊乿偵偡偓側偄偲偄偆傕偺偩丅偩偑丄偦傕偦傕乽恖柉偺丄恖柉偵傛傞丄恖柉偺偨傔偺摑帯乿偲偄偆丄偐偺桳柤側儕儞僇乕儞戝摑椞偵傛傞柉庡惌帯偺掕媊傪庴偗擖傟傞側傜偽丄偙偺乽恖柉亖恖乆(僺乕僾儖)乿傪壙抣懱宯偺嵟忋埵偵偍偔乽億僺儏儕僗僩惌帯乿偵榑敐偡傞偺偼擄偟偄丅
億僺儏儕僘儉偼乽戝廜寎崌庡媊乿偵偡偓側偄偲壖偵懪偪幪偰偨偲偙傠偱丄尰戙偺柉庡惌帯偱偼僄儕乕僩傗愱栧壠偵傛傞巟攝偼摓掙庴偗擖傟傜傟傞傕偺偱偼側偄丅偮傑傝丄乽恖乆乿偵庡尃偑偁傞偲偄偆乽恖柉庡尃乿偺尨懃偑揙掙偟丄媍夛偺栧偑乽嵿嶻傕嫵梴傕側偄乿戝廜偵奐偐傟傞傛偆偵側傟偽丄乽恖乆乿偑媮傔傞偙偲傪丄偙偺乽恖乆乿偺乽戙昞乿偨傞惌帯壠偑廩懌偡傞偺偼傓偟傠媊柋偱偡傜偁傞偺偩丅偙偺尨棟尨懃傪曎偊偰偄側偄億僺儏儕僘儉斸敾偼丄揤偵懥偡傞偺偵摍偟偄偺偱偁傞丅
傕偭偲傕丄偙偆偟偨尨棟尨懃榑傪榚偵偍偄偰傕丄偦傕偦傕尰戙偺柉庡惌帯偼億僺儏儕僘儉傪惗婲偝偣傞傛偆側峔憿偵側偭偰偒偰偄傞偲偙傠偵擄栤偑偁傞丅
仭曄傢偭偰偟傑偭偨乽惌帯偺儌乕僪乿丂
傑偢丄愴屻惌帯幮夛傪巟偊偰偒偨條乆側惂搙傗婡娭(惌帯僄儕乕僩丄惌搣丄媍夛丄楯摥慻崌丄幮夛惃椡側偳)偼丄掅惉挿帪戙偲幮夛曐忈偺愗傝壓偘偵傛偭偰丄偙傟傑偱乽恖乆乿偐傜偊偰偄偨怣擟傪幐偆傛偆偵側偭偨丅
擔杮傪娷傔丄懡偔偺愭恑崙偱偼丄乽帺暘偨偪偺巕偳傕偼帺暘偨偪傎偳偺惗妶悈弨傪婜懸偱偒側偄乿偲峫偊傞崙柉偑懡悢偵偺傏偭偰偄傞丅偙傟偼丄愴屻偼偠傔偰捈柺偡傞忬嫷偱偁傝丄乽崙柉傪嬺傢偣傞乿偙偲傪栚揑偵偟偰偄傞偼偢偺惌帯壠傊偺晄怣傪惗偠偝偣傞丅
偙偆偟偰丄柉庡惌帯傪埻偭偰偄偨杊攇掔偼姠夝偟丄惌帯儕乕僟乕偼恖乆偲偺捈愙偺寢傃偮偒傪嫮傔傛偆偲偡傞丅乽戝摑椞宆乿偺惌帯傪壜擻偵偡傞擔杮偺抦帠偑丄抧曽媍夛傪傓偟傠攔彍偡傞偙偲偵傛偭偰乽恖乆乿傪摦堳偟傛偆偲偡傞偺偼丄傑偝偵偙偆偟偨峔恾偵摉偰偼傑傞偐傜偵懠側傜側偄丅偦偟偰偙偙偱偼丄傕偼傗乽棙塿偺暘攝乿傛傝傕丄乽暔岅乿傗乽壙抣乿傪傔偖傞惌帯偑庡偨傞懳棫幉偵側偭偰偄偔偙偲偵側傞丅
偟偐傕丄惌帯壠偼摉慖偟側偗傟偽側傜側偄偐傜丄桳尃幰傪埨怱偝偣傞偨傔偺條乆側栺懇傪偡傞丅偨偩偟丄僌儘乕僶儖壔偲幮夛偺暋嶨壔傪慜偵丄斵傜偼柍椡偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄偄傢偽乽嬻庤宍乿偑棎敪偝傟傞偙偲偱丄惌帯壠傊偺晄怣偼傑偡傑偡曞偭偰偄偔丅
傕偆傂偲偮偺棟桼偼丄尰戙惌帯偵偍偄偰偼條乆側愱栧壠傗撈棫愱栧婡娭偺夘嵼偵傛傞乽僈僶僫儞僗乿偑晄壜寚偵側偭偰偄傞偙偲偑偁傞丅愭恑僨儌僋儔僔乕偵偍偄偰偼彮側偔偲傕丄惌帯懱惂(僀僨僆儘僊乕)傪傔偖傞懳棫偑墦偺偒丄懡條側傾僋僞乕娫偺棙奞偺挷惍傪栚揑偲偡傞悈暯揑側摑帯偑慜採偲側偭偰偄傞丅
偙偆偟偨惌帯儌乕僪偑巟攝揑偵側傞側偐偱丄堄巚寛掕偼傓偟傠晄摟柧側偐偨偪偱堦晹偺僾儘僼僃僢僔儑僫儖偺庤偵傛偭偰壓偝傟傞傛偆偵側傝丄嵟嬤偺擔杮偺嬥梈惌嶔榑憟偱妋擣偝傟偨傛偆偵丄嫟摨懱峔惉堳偺岤惗傪懝側偆寢壥傪傕偨傜偟偐偹側偄丅偙偺傛偆側乽僈僶僫儞僗乿偵懳偡傞斀敪偲偟偰傕丄億僺儏儕僘儉偼惗婲偡傞偙偲偵側傞丅
偦偺晄怣姶傪暐怈偟偰丄偄傑堦搙惌帯偺幚峴椡傪屩帵偡傞偨傔偵丄惌帯傗峴惌偺乽夵妚乿偲偄偭偨斾妑揑寢壥偑栚偵傒偊傗偡偄惌嶔偑偮偓偮偓偲懪偪弌偝傟偰偄偔丅偙傟偑僱僆丒儕儀儔儖揑側億僺儏儕僘儉偺杮幙偱偁傞丅
懠曽偱丄偦偆偟偨忬嫷壓偱偼丄惌帯偺柍椡偝傪崘敪偡傞偙偲偑丄桳尃幰偺娊怱傪桿偆偙偲偵傕側傞丅撪妕傗姱椈偺柍擻偝傪偁偘偮傜偄丄斵傜偼崙柉偺偙偲傪峫偊偰偄側偄偲偡傞偺偱偁傞丅偙傟偑丄尰壓偱傒傜傟傞乽億僺儏儕僘儉乿偲偄偆偙偲偵側傞偩傠偆丅
丂 |
| 仭戝廜寎崌庡媊偑彽偔廜嬸惌帯偺嫲晐 |
   丂
丂
|
仭億僺儏儕僘儉慁晽偑悽奅偵悂偒峳傟偰偄傞
儔僥儞岅偺乽populus(恖柉)乿傪岅尮偲偡傞億僺儏儕僘儉偼丄尦棃丄婛懚偺巟攝憌傗抦幆恖側偳偵傛傞乽僄儕乕僩庡媊乿傪斸敾偟偰丄堦斒戝廜偺婅朷傗晄埨丄晄枮側偳偺乽幚姶乿傪廳帇偡傞惌帯巚憐丄惌帯懱惂偺偙偲偱偡丅
柉堄傪懜廳偡傞偲偄偆堄枴偱偼旕忢偵柉庡庡媊揑側奣擮側偺偱偡偑丄恖乆偺梸媮晄枮傪慀偭偰巟帩傪廤傔傞庤朄偼丄偟偽偟偽廜嬸惌帯傪彽偒傗偡偔側傝傑偡丅偙偺偨傔尰戙偵偍偄偰偼丄億僺儏儕僘儉偼戝廜偵寎崌偟偰恖婥傪摼傛偆偲偡傞乽戝廜寎崌庡媊乿偲偄偆僱僈僥傿僽側堄枴偱巊傢傟傞偙偲偑懡偔側傝傑偟偨丅
|
仭億僺儏儕僗僩偨偪偺岞栺偺塕傪尒敳偗側偄桳尃幰
仭儔僥儞傾儊儕僇丄儀僱僘僄儔偺億僺儏儕僘儉亖僠儍儀僗丄儅僪僁乕儘
億僺儏儕僘儉偐傜廜嬸惌帯偵娮偭偨揟宆椺偑儀僱僘僄儔偱偁傞丅僠儍儀僗慜戝摑椞偲偄偆嬌傔偮偒偺億僺儏儕僗僩偑搊応偟偰丄乽21悽婭偺幮夛庡媊乿傪宖偘丄昻崲憌岦偗偺柍椏恌椕強傗柍彏廧戭偺寶愝側偳僶儔儅僉幮夛暉巸惌嶔傪悇恑偟偨丅僠儍儀僗慜戝摑椞偼2013擭偵娻偱巰嫀偟偨偑丄僠儍儀僗偺屻傪宲偄偩暊怱偺儅僪僁乕儘戝摑椞傕楬慄傪宲彸偟偨丅
僶儔儅僉偺尮愹偼悽奅嵟戝偺杽憼検傪屩傞愇桘帒尮偱偁傞丅偟偐偟丄1僶儗儖亖120僪儖埲忋偱側偗傟偽惉傝棫偨側偄傛偆側崙壠梊嶼傪慻傫偱柍懯尛偄偟懕偗偨寢壥偼偳偆側偭偨偐丅1僶儗儖亖40僪儖掱搙偵傑偱愇桘壙奿偑朶棊偟偨偨傔偵愇桘嶻嬈偼夡柵丄僴僀僷乕僀儞僼儗偵廝傢傟偰儀僱僘僄儔宱嵪偼攋抅忬懺偵捛偄崬傑傟偰偟傑偭偨丅
側偄懗偼怳傟側偄偲偽偐傝偵惌晎偼嬞弅楬慄偵愗傝懼偊偨偑丄岞柋堳傪憹傗偟偡偓偰丄偄偔傜嶍尭偟偰傕捛偄偮偐側偄丅偲偆偲偆廡媥2擔偱偼側偔廡媥5擔惂偵偟偰丄岞柋堳偺媼椏傪60亾僇僢僩偟偨傎偳偩丅庤偑偮偗傜傟側偄僴僀僷乕僀儞僼儗偱崙柉惗妶偼崲媷偟丄恖乆偼崱崰偵側偭偰惌晎傪嫮偔旕擄偟偰偄傞丅偟偐偟丄僠儍儀僗傗儅僪僁乕儘傪戝摑椞偵慖傫偩偺偼傎偐側傜偸崙柉帺恎側偺偩丅
仭墷廈丄僊儕僔儍偺億僺儏儕僘儉亖僠僾儔僗
偙傟偼儔僥儞傾儊儕僇偺搑忋崙偵尰傟偨摿堎側帠椺偱偼側偄丅柉庡庡媊偺惗傑傟偨崙偱偁傞僊儕僔儍傕廜嬸惌帯偵娮偭偰偄傞丅
僊儕僔儍偼嫄戝側嵿惌愒帤偺塀暳偑柧傜偐偵側偭偰宱嵪婋婡偵娮傝丄俤倀偐傜嬥梈巟墖偺忦審偲偟偰擭嬥偺4妱僇僢僩傗岞柋堳偺3妱嶍尭側偳偺尩偟偄嬞弅嵿惌傪媮傔傜傟偰偒偨丅偟偐偟丄曻枱嵿惌偺庴塿幰(偨偲偊偽擭嬥偺庴媼奐巒擭楊偼53嵨偱丄崙柉偺4恖偵1恖偼岞柋堳)偱偁傝側偑傜丄僊儕僔儍崙柉偲偟偰偼帺暘偨偪偺惗妶偑嬯偟偔側傞傛偆側嬞弅嵿惌偼庴偗擖傟偨偔側偄丅
偦偆偟偨乬柉堄乭偵寎崌偟偰丄乽俤倀偺尩偟偄梫媮傪嫅斲偟傛偆乿偲嫨傫偱惌尃偺嵗偵廇偄偨偺偑僠僾儔僗庱憡偩丅
俤倀偺嵿惌嬞弅嶔偺斲寛偲偄偆崙柉搳昜偺寢壥傪攚晧偭偰岎徛偵椪傫偩僠僾儔僗庱憡偩偭偨偑丄僨僼僅儖僩傪栚慜偵峊偊俤倀偺尵偆偑傑傑偵懨嫤傪敆傜傟偨丅偙傟偵柍愑擟側僊儕僔儍偺柉廜偼戝寖搟偟偰丄僠僾儔僗偵戅恮傪敆偭偰偄傞丅偟偐偟丄斵偑乽俤倀偺嬞弅嶔傪庴偗擖傟傞傋偒偩乿偲庡挘偟偰偄偨傜庱憡偵側傟側偐偭偨傢偗偱丄愑傔傜傟傞傋偒偼塕傪尒敳偗側偐偭偨崙柉側偺偩丅廜嬸惌帯偦偺傕偺偱偁傞丅
僊儕僔儍傎偳婋婡揑忬嫷偵偼帄偭偰偄側偄傕偺偺丄宱嵪婋婡偺壩庬偲擄柉栤戣傪書偊傞儓乕儘僢僷偼奺崙偱億僺儏儕僘儉偺戜摢偑栚偵偮偔丅
俤倀棧扙傗斀堏柉傪庡挘偡傞嬌塃惃椡傗斀嬞弅傪宖偘傞嬌嵍惌搣偑惃偄傪憹偟偰丄惌嶔偵傕塭嬁傪媦傏偟偰偄傞丅俤倀棧扙攈偑惂偟偨僀僊儕僗偺崙柉搳昜偵偟偰傕丄乽棧扙偡傟偽堏柉傪帺暘偨偪偱僐儞僩儘乕儖偱偒傞乿乽俤倀偺嵶偐側惂栺偵敍傜傟側偔偰偡傓乿偲偄偆棧扙攈偺億僺儏儕僘儉偵愭摫偝傟偨懁柺偑嫮偄丅
仭暷崙偺億僺儏儕僘儉亖僩儔儞僾丄僒儞僟乕僗
崱夞偺暷崙戝摑椞慖傪尒偰偄偰傕丄億僺儏儕僘儉偺戜摢偑挊偟偄丅梊旛慖偺榖戣傪偝傜偭偨僩儔儞僾尰徾傕僒儞僟乕僗尰徾傕億僺儏儕僘儉偺娤揰偱偼傑偭偨偔摨偠側偺偩丅嫟榓搣偺岓曗幰巜柤儗乕僗傪妋幚側傕偺偵偟偨僪僫儖僪丒僩儔儞僾巵偼戝廜偑暦偒偨偄偙偲傪僘僶儕偲尵偆揟宆揑側億僺儏儕僗僩偩丅
堏柉偵巇帠傪扗傢傟偨偲巚偭偰偄傞敀恖偺楯摥幰奒媺偵偼丄乽儊僉僔僐崙嫬偵暻傪偮偔傟乿偲偄偆僩儔儞僾敪尵偼怱抧傛偔嬁偔丅俬俽側偳僀僗儔儉夁寖攈偺僥儘偵嫲晐偟偨傝丄搟傝傪妎偊偰偄傞恖乆偵乽僀僗儔儉嫵搆偼擖崙嬛巭乿偲偄偆僩儔儞僾巵偺庡挘偼岲姶傪帩偨傟傞丅偟偐偟丄椻惷偵峫偊傟偽儊僉僔僐崙嫬偵枩棦偺挿忛偺傛偆側暻偑偮偔傟傞偼偢偑側偄偟丄儊僉僔僐偵暻偺寶愝旓傪暐傢偣傜傟傞傢偗傕側偄丅
偦傟偵丄偄偔傜僀僗儔儉嫵搆偺擖崙傪嬛偠偰傕丄崙撪偵偼栺600枩恖偺僀僗儔儉宯堏柉偑偡偱偵偄傞丅6寧偵僼儘儕僟偱50恖偑巰朣偡傞嵟埆偺廵棎幩帠審偑婲偒偨丅幩嶦偝傟偨梕媈幰偼傾僼僈僯僗僞儞宯偺暷崙恖偱丄僀僗儔儉夁寖攈偲偺娭學偑媈傢傟偨偑丄偳偆傗傜扨撈斊偵傛傞僿僀僩僋儔僀儉偺壜擻惈偑崅偄傜偟偄丅僀僗儔儉嫵搆偺擖崙傪嬛偠偰傕丄儂乕儉丒僌儘僂儞丒僥儘儕僗僩(崙奜偺夁寖巚憐偵嫟柭偟偰丄崙撪弌恎幰偑撈帺偵堷偒婲偙偡僥儘偺偙偲)偵偼壗偺岠壥傕側偄偺偩丅
僩儔儞僾巵偑乬塃偺億僺儏儕僗僩乭側傜丄乬嵍偺億僺儏儕僗僩乭偼柉庡搣偺巜柤憟偄偱慞愴偟偨僶乕僯乕丒僒儞僟乕僗巵偩丅帺傜乽柉庡幮夛庡媊幰乿偲柤忔傝丄庒幰悽戙傗敀恖偺昻崲憌偵夁戝側岞栺傪偟偰慁晽傪姫偒婲偙偟偨丅偟偐偟丄乽岞棫戝妛偺庼嬈椏柍彏壔乿偲偐乽崙柉奆曐尟乿偲偐丄攝傞惌嶔偽偐傝傪庡挘偟偰丄嵿尮偵偮偄偰偼傎偲傫偳壗傕尵偭偰偄側偄丅
偦傕偦傕楢朚惌晎偺峴惌挿偱偁傞戝摑椞偵側偭偰傕丄岞棫戝妛偺庼嬈椏傪柍彏壔偡傞尃尷偼側偄丅傾儊儕僇偺戝妛偺傎偲傫偳偼僐儈儏僯僥傿僇儗僢僕(2擭惂偺抁婜戝妛)偱丄庼嬈椏偑柍椏偵側偭偨傜塣塩偑惉傝棫偨側偔側傞偺偩丅惌晎偑庼嬈椏傪曗揢偟傛偆傕偺側傜丄惻嬥偑偄偔傜偁偭偰傕懌傝側偄丅
崙柉奆曐尟偵偟偰傕丄3000枩恖偵堛椕曐尟傪曗揢偟偨僆僶儅働傾(僆僶儅惌尃偵傛傞曐寬堛椕惂搙夵妚)偱偝偊尷奅偓傝偓傝側偺偵丄偦傟傪忋夞傞惂搙夵妚偑幚尰壜擻偲偼偲偰傕巚偊側偄丅
偮傑傝僩儔儞僾巵傕僒儞僟乕僗巵傕丄偱偒傕偟側偄岞栺傪暲傋棫偰偰丄庴塿幰偲偍傏偟偒恖乆偐傜擬嫸揑側巟帩傪廤傔偰偒偨偺偩丅偙傟傑偱偺戝摑椞慖嫇偱傕丄儘僗丒儁儘乕巵偺傛偆側億僺儏儕僗僩偼偄偔傜偱傕弌偰偒偨丅偟偐偟丄儅僗僐儈偺僠僃僢僋婡擻偑摥偄偰丄梊旛慖偱攔彍偝傟傞偺偑捠椺偩偭偨丅
偲偙傠偑崱夞偼朅枟岓曗偲巚傢傟偨億僺儏儕僗僩偑晄巚媍偲巆偭偨丅側偤偐丅儅僗僐儈偺僠僃僢僋婡擻偑庛偔側偭偨偺傕妋偐偩偑丄戝偒側棟桼偺堦偮偼丄婛懚惌搣偺摉偨傝慜偺庡挘偵朞偒朞偒偟偨傝丄晄枮傪帩偮恖乆偑憹偊偨偐傜偩傠偆丅偩偐傜杮柦帇偝傟偨僸儔儕乕丒僋儕儞僩儞巵偑忢幆揑側偙偲傪尵偊偽尵偆傎偳乽偮傑傜側偄乿岓曗偲偟偰恖婥傪棊偲偟偰偒偨偺偩丅
仭擔杮偼偳偆偩傠偆偐丠
乽掅惉挿偑挿偔懕偄偰傕幐嬈幰偼偁傆傟偰偄側偄偟丄媼椏偑忋偑傜側偔偰傕怘偄媗傔偰楬摢偵柪偭偰偄傞恖偼彮側偄丅擄柉傗幐嬈偺栤戣偑怺崗壔偟偰偄側偄擔杮偱偼億僺儏儕僗僩偺弌傞枊偼側偄乿偲巚偭偰偄傞側傜戝娫堘偄偩丅
巹偑弌攏偟偨1995擭偺搒抦帠慖偼惵搰岾抝巵偑乽偪傖傇戜傪傂偭偔傝曉偟偰傗傞乿偲偄偆堄枴晄柧側岞栺偱埑彑偟偨偟丄摨帪婜偺戝嶃晎抦帠慖偱慖偽傟偨偺偼屻偵嫮惂傢偄偣偮帠審偱帿擟偵捛偄崬傑傟傞墶嶳僲僢僋巵偩偭偨丅
搒巗攷傪拞巭偵偟偨偖傜偄偱壗偺巇帠傕偟側偐偭偨惵搰巵偺屻傪宲偄偩偺偼愇尨怲懢榊巵丅廡偵2丄3擔偟偐搊挕偟側偄愇尨巵傪搒柉偼4婜傕楢懕偟偰慖傫偱丄屻傪宲偄偩挅悾捈庽巵傗慍揧巵傕岞栺傜偟偄岞栺偼側偔丄偦傟偱傕慖嫇偼惓摑攈偺僀儊乕僕偩偗偱埑彑偟偨丅
偄偢傟傕戝偟偨巇帠傪偟側偄偆偪偵戝偒偔鏣偄偰丄搒惌偼掆懾偟偨傑傑偩丅
怳傝曉傟偽丄惵搰丄愇尨丄挅悾偲3戙懕偗偰嶌壠偑搒抦帠偵側偭偨傢偗偩偑丄嶌壠偼暔岅傪偮偔傞恖娫偱偁偭偰峴惌擻椡傪婜懸偡傞傎偆偑偍偐偟偄丅傕偭偲傕峴惌擻椡偑側偔偰傕乬帺摦塣揮乭偱柋傑傞偺偑搶嫗搒抦帠偲偄偆巇帠側偺偐傕偟傟側偄偑丅
儀僱僘僄儔傗僊儕僔儍偺傛偆偵丄暦偙偊偺偄偄億僺儏儕僘儉偵堷偒偢傜傟偨柉庡庡媊偑峴偒拝偔愭偼丄廜嬸惌帯偱偁傞丅
廜嬸惌帯傪旔偗傞偵偼丄乽me first(壌傪愭偵偟傠)乿偲偄偆峫偊曽偵愼傑傜側偄偙偲偑廳梫偩丅帺暘偺懝摼偱偼側偔丄僌儖乕僾慡懱偵偲偭偰丄僐儈儏僯僥傿慡懱偵偲偭偰偄偄偙偲側偺偐丄埆偄偙偲側偺偐偱敾抐偡傞丅帺屓拞怱偱偼側偔廤抍慡懱偵廳偒傪抲偔丅屄恖傛傝傕慡懱傪傛偔偟傛偆偲敪憐偱偒傞恖偑夁敿悢偄側偗傟偽丄柉庡庡媊偼惉傝棫偨側偄丅偙傟偼摦暔揑偵偼旕忢偵崅搙側敾抐椡丄抦惈偱偁偭偰丄恎偵偮偗傞偨傔偵偼岞柉嫵堢偑晄壜寚丅
18嵨偵側偭偨傜慖嫇尃傪梌偊傞偩偗偱偼側偔丄愑擟偁傞幮夛恖偲偟偰慖嫇尃傪偳偆峴巊偡傋偒偐偟偭偐傝嫵堢偡傋偒偩偟丄抦柤搙偩偗偱慖偽傟偰偟傑偭偨夁嫀偺慖嫇傪働乕僗僗僞僨傿偵偟偰岓曗幰偺尒暘偗曽傑偱妛偽偣傞丅
偮傑傝夁嫀傪憤妵偟偰揱偊傞嶌嬈傪偤傂堦搙傗偭偰傒傞傋偒偩丅丂
丂 |
| 仭尰戙億僺儏儕僘儉偺彅憡 |
   丂
丂
|
仭戝廜寎崌庡媊偵閤偝傟偰僩儔儞僾傪慖傫偩敀恖偺拞掅強摼昻崲憌 2016/11丂
堎椺偱偁傞丅NHK偑偢偭偲傾儊儕僇戝摑椞慖嫇偺懍曬傪棳偟懕偗偰偄傞丅
柉曻偼丄墦偄傾儊儕僇偺榖傛傝偼帇挳棪偺庢傟傞偲摜傫偩攷懡墂慜偺戝娮杤傪拞宲偟偰偄傞丅
乽嫮幰偲嫮幰乿乽嬥帩偪偲嬥帩偪乿偺懳寛偵側偭偨傾儊儕僇戝摑椞慖嫇偼丄堦曽偺嬥帩偪僪僫儖僪丒僩儔儞僾巵偑彑偭偨丅億僺儏儕僘儉(戝廜寎崌庡媊)偺彑棙偱偁傞丅
堦斒戝廜偺棙塿傗尃棙丄婅朷丄晄埨傗嫲傟傪棙梡偟偰丄戝廜偺巟帩偺傕偲偵婛懚偺僄儕乕僩庡媊偱偁傞懱惂懁傗抦幆恖側偳偲懳寛偟偰偄傞僸乕儘乕傪憰偭偨僩儔儞僾巵丅敀恖偺拞掅強摼昻崲憌偑書偔堦柺揑側梸朷偵寎崌偟偰戝廜傪憖嶌偡傞曽朄丄億僺儏儕僘儉偑惉岟偟偨偲偄偊傛偆丅
傾儊儕僇崙柉偺拞偱懡悢傪愯傔傞拞掅強摼昻崲憌偼丄戝摑椞偲偟偰偳偪傜偐偺嬥帩偪傪慖傇慖戰巿偟偐側偐偭偨丅偦偟偰丄敀恖昻崲憌偵偲偭偰偼丄僸儔儕乕丒僋儕儞僩儞偑僂僅乕儖奨傪愯嫆偡傞忋埵1亾偺晉桾憌偺拠娫偱偁傞偙偲偑偼偭偒傝偟偰偄傞丅
偲丄偡傟偽徚嫀朄偱丄傕偟偐偟偨傜帺暘偨偪偵嬥傪夞偟偰偔傟傞恊暘偐傕抦傟側偄乽傕偆傂偲傝偺嬥帩偪乿偵搳昜偡傞偟偐側偄丅偟偐偟丄僩儔儞僾戝摑椞傕傑偨丄幚幙偼忋埵1亾偺晉桾憌偺拠娫側偺偱偁傞丅
偮傑傝丄寢嬊丄昻崲憌偵偼嬥偼夞偭偰偙側偄丅偙傟偼娫傕側偔柧傜偐偵側傞偩傠偆偑丄偦偆側偭偨帪丄敀恖偺昻崲憌丄僸僗僷僯僢僋偺昻崲憌丄傾僕傾宯偺昻崲憌偲偄偭偨恖乆偼戝摨抍寢偟偰傾儊儕僇傪曄偊傞偙偲偼弌棃傞偺偐丠丂偼側偼偩怱傕偲側偄丅
戝廜偑戝廜寎崌庡媊偺僩僢僾傪慖傫偱傕帺傜偑彑偮偙偲偼寛偟偰側偄丅嫮幰偼偳傫側曽朄偱傕庢傝偆傞偑丄戝廜偑偲傝偆傞曽朄偼悢偺椡偱彑偮偙偲偺傒偱偁傞丅偦傟偑柉庡庡媊偩丅
柉庡庡媊偱嫮梸帒杮庡媊偵彑偮偟偐側偄偑丄偦傟傪傾儊儕僇偵朷傓偺偼偟偽傜偔偼柍棟偩傠偆丅丂 |
仭悽奅偺巗応暍偆戝廜寎崌偺儕僗僋丂2016/8
塸崙偺墷廈楢崌(俤倀)棧扙寛掕偵傛傞儅乕働僢僩偺崿棎偑傂偲傑偢廂懇偟丄悽奅偺姅幃巗応偼棊偪拝偒傪庢傝栠偟偰偄傑偡丅巟偊偵側偭偰偄傞偺偼夁嫀嵟崅抣寳偵偁傞暷僟僂岺嬈姅30庬暯嬒丅暷宨婥偺夞暅椡偼庛偄傕偺偺丄憗婜棙忋偘尒捠偟偑屻戅偟偨偙偲偑岲姶偝傟偰偄傑偡丅偦傟偱傕丄悽奅揑偵姅壙偺忋抣偼廳偄報徾偱偡丅
戝偒側棟桼偺傂偲偮偵暷戝摑椞慖傊偺晄埨偑偁傞偲巹偼峫偊傑偡丅偲傝傢偗丄嫟榓搣偺戝摑椞岓曗僪僫儖僪丒僩儔儞僾巵偺恖婥偑悐偊側偄偙偲偼悽奅偺姅幃巗応偵偲偭偰廳戝側儕僗僋偲側偭偰偄傑偡丅
僩儔儞僾巵偺庡挘偡傞惌嶔偼丄僌儘乕僶儖宱嵪偵攚傪岦偗傞屒棫庡媊偱偁傝丄帒杮庡媊傪斲掕偟偐偹側偄幮夛庡媊怓偺嫮偄惌嶔偲偄偊傑偡丅擔暷摨柨偵攚傪岦偗丄娐懢暯梞宱嵪楢実嫤掕(俿俹俹)偵斀懳傪彞偊丄儊僉僔僐偲偺帺桼杅堈嫤掕(俥俿俙)偺尒捈偟偵尵媦偡傞堦曽丄暷崙撪偱偼僶儔儅僉宆幮夛暉巸傪幚巤偡傞偲庡挘偟偰偄傑偡丅11寧偺杮慖嫇偱僩儔儞僾巵偑彑棙偡傞偲擔杮偩偗偱側偔丄悽奅偺姅幃巗応偵偲偭偰媡晽偲側傝傑偡丅
懳偡傞柉庡搣偺戝摑椞岓曗僸儔儕乕丒僋儕儞僩儞巵偼丄揱摑揑側帒杮庡媊丒擔暷摨柨傪懜廳偡傞巔惃偑尒傜傟傑偡丅偲偼偄偊丄僋儕儞僩儞巵偑彑棙偡傟偽姅幃巗応偵偲偭偰捛偄晽偐偲偄偆偲丄偦偆偲傕尵偄愗傟側偄晹暘偑偁傝傑偡丅
僩儔儞僾巵偺夁寖敪尵偵偼暷崙撪偱傕斀敪偑嫮偔丄嫟榓搣偼僩儔儞僾巵巟帩偱堦枃娾偵偼側偭偰偄傑偣傫丅偲偙傠偑丄僋儕儞僩儞巵傕暷崙撪偱偼晄恖婥偱丄柉庡搣偱偼梊旛慖偱嵟屻傑偱僋儕儞僩儞巵偲嫞傝崌偭偨帺徧幮夛庡媊幰丄僶乕僯乕丒僒儞僟乕僗巵偑庒幰偵愨戝側恖婥偑偁傝傑偡丅斵偺巟帩幰偼僒儞僟乕僗巵偑僋儕儞僩儞巵巟帩傪昞柧偟偨偙偲偵嫮偄晄枮傪書偒丄杮慖嫇偱偼僩儔儞僾巵偵搳昜偡傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅
僩儔儞僾巵偑戝摑椞偵側傟偽廳戝側儕僗僋偲側傝傑偡偑丄傕偟僋儕儞僩儞巵偑戝摑椞偵側偭偰傕丄暷崙撪偱斀帒杮庡媊偺棳傟偼廂傑傜偢丄戝摑椞偲偟偰嫮偄儕乕僟乕僔僢僾傪敪婗偱偒側偔側傞壜擻惈傕偁傝傑偡丅偙偺傛偆偵帺桼庡媊宱嵪偺婙摢偲偟偰悽奅傪偗傫堷偟偰偒偨暷崙偺媫曄偼丄廳戝側儕僗僋偲側偭偰偄傑偡丅
6寧23擔偺塸崙柉搳昜偱俤倀棧扙攈偑彑棙偟偨偺傕丄戝偒側僒僾儔僀僘偲側傝傑偟偨丅婯惂娚榓乽價僢僌僶儞乿偱愭峴偟丄墷廈偱嵟傕價僕僱僗偑傗傝傗偡偄崙偲側傞偙偲偱乽塸崙昦乿偲偄傢傟傞宱嵪晄怳偐傜婏愓偺暅妶傪壥偨偟偨崙偑丄僌儘乕僶儖宱嵪偵攚傪岦偗偰屒棫庡媊偵岦偐偆偙偲傪梊憐偱偒偨搳帒壠偼傎偲傫偳偄傑偣傫偱偟偨丅
俤倀傗堏柉傪埆幰偵偟丄掅強摼幰憌偺恖婥傪摼偰丄棧扙攈偺彑棙傪摫偄偨儃儕僗丒僕儑儞僜儞慜儘儞僪儞巗挿偺庡挘偼僩儔儞僾巵偺庡挘偲懡偔偺晹暘偱廳側傝傑偡丅塸崙偑億僺儏儕僘儉(戝廜寎崌庡媊)偵棳偝傟偰帒杮庡媊偵攚傪岦偗傞偺偐丄戝偒側婒楬偵棫偭偰偄傑偡丅
巹偼擔杮姅偺僼傽儞僪儅僱僕儍乕傪傗偭偰偄偨偲偒丄拞搶丒暷崙丒墷廈丒拞崙傊弌挘偟丄戝庤婡娭搳帒壠偲擔杮姅偺搳帒壙抣偵偮偄偰壗搙傕僨傿僗僇僢僔儑儞偟傑偟偨丅擔杮姅偵搳帒偡傞奀奜搳帒壠偵偄偮傕暦偐傟傞偺偼擔杮偺惌帯摦岦偱偡丅擔杮偺宨婥丒婇嬈嬈愌摦岦偵偮偄偰傕幙栤偝傟傑偡偑丄偦傟埲忋偵惌帯偵偮偄偰擬怱偵暦偄偰偔傞搳帒壠偑懡偄偲姶偠偰偄傑偟偨丅
奜崙恖搳帒壠偑擔杮偺惌帯傪昡壙偡傞愗傝岥偼僔儞僾儖偱偡丅幙栤偺巇曽偼搳帒壠偛偲偵堎側傝傑偡偑丄嫟捠揰傪堦尵偱偄偆偲乽擔杮偺惌帯偼帒杮庡媊偺嫮壔(宱嵪惉挿廳帇)偵岦偐偭偰偄傞偐丄幮夛庡媊偺嫮壔(幮夛暉巸廳帇)偵岦偐偭偰偄傞偐乿偵恠偒傑偡丅
彫愹弮堦榊尦庱憡偺峔憿夵妚偑惃偄傪摼偰偄偨2005擭偵奀奜搳帒壠偼乽擔杮偼帒杮庡媊傪嫮壔偟偰偄傞乿偲敾抐偟丄擔杮姅傪愊嬌揑偵攦偄傑偟偨丅偦偺屻丄09擭偵柉庡搣惌尃偑抋惗偟偨偲偒偼乽幮夛庡媊傪嫮壔偟偰偄傞乿偲尒側偟傑偟偨丅傾儀僲儈僋僗偑杮奿僗僞乕僩偟偨13擭偼嵞傃帒杮庡媊傪嫮壔偡傞惌尃偑搊応偟偨偲懆偊丄擔杮姅傪戝検偵攦偄傑偟偨丅
偦偺奜崙恖搳帒壠偺栚偱丄崱偺暷崙偲塸崙傪尒傞側傜偽椉崙偲傕幮夛庡媊婑傝偺惌嶔偑戝廜偺恖婥傪摼偰偄傞偙偲偑搳帒壠偲偟偰寽擮偝傟傞忬嫷偱偡丅暷崙丄塸崙偑偙偺傑傑帒杮庡媊偵攚傪岦偗懕偗傞偺偐丄偁傞偄偼億僺儏儕僘儉偺峴偒夁偓傪斀徣偡傞婡塣偑堢偪丄揱摑揑側帒杮庡媊偵栠偭偰偄偔偺偐丄拲堄怺偔尒庣偭偰偄偔昁梫偑偁傝傑偡丅丂 |
仭悽奅傪惾姫偡傞億僺儏儕僗僩慁晽偼丄偳偙傑偱峀偑傞偐丠
仭柉庡庡媊敪徦偺僊儕僔儍偱婲偒偨廜嬸惌帯
儔僥儞岅偺乽populus(恖柉)乿傪岅尮偲偡傞億僺儏儕僘儉偼丄尦棃丄婛懚偺巟攝憌傗抦幆恖側偳偵傛傞僄儕乕僩庡媊傪斸敾偟偰丄堦斒戝廜偺婅朷傗晄埨丄晄枮側偳偺乽幚姶乿傪廳帇偡傞惌帯巚憐丄惌帯懱惂偺偙偲偩丅
柉堄傪懜廳偡傞偲偄偆堄枴偱偼旕忢偵柉庡庡媊揑側奣擮側偺偩偑丄恖乆偺梸媮晄枮傪慀偭偰巟帩傪廤傔傞庤朄偼偟偽偟偽廜嬸惌帯傪彽偒傗偡偄丅偙偺偨傔尰戙偵偍偄偰偼丄億僺儏儕僘儉偼戝廜偵寎崌偟偰恖婥傪摼傛偆偲偡傞乽戝廜寎崌庡媊乿偲偄偆僱僈僥傿僽側堄枴偱巊傢傟傞偙偲偑懡偄丅
億僺儏儕僘儉偐傜廜嬸惌帯偵娮偭偨揟宆椺偑儀僱僘僄儔偱偁傞丅僠儍儀僗戝摑椞偲偄偆嬌傔偮偒偺億僺儏儕僗僩偑搊応偟偰丄乽21悽婭偺幮夛庡媊乿傪宖偘丄昻崲憌岦偗偺柍椏恌椕強傗柍彏廧戭偺寶愝側偳僶儔儅僉幮夛暉巸惌嶔傪悇恑偟偨丅娻偱巰傫偩僠儍儀僗偺屻傪宲偄偩暊怱偺儅僪僁乕儘戝摑椞傕楬慄傪宲彸偟偨丅僶儔儅僉偺尮愹偼悽奅嵟戝偺杽憼検傪屩傞愇桘帒尮偱偁傞丅偟偐偟丄1僶儗儖亖120僪儖埲忋偱側偗傟偽惉傝棫偨側偄傛偆側崙壠梊嶼傪慻傫偱柍懯尛偄偟懕偗偨寢壥偼偳偆側偭偨偐丅1僶儗儖亖40僪儖偐傜偣偄偤偄50僪儖掱搙傑偱愇桘壙奿偑朶棊偟偨偨傔偵愇桘嶻嬈偼夡柵丄僴僀僷乕僀儞僼儗偵廝傢傟偰儀僱僘僄儔宱嵪偼攋抅忬懺偵捛偄崬傑傟偰偟傑偭偨丅
側偄懗偼怳傟側偄偲偽偐傝偵惌晎偼嬞弅楬慄偵愗傝懼偊偨偑丄岞柋堳傪憹傗偟偡偓偰丄偄偔傜嶍尭偟偰傕捛偄偮偐側偄丅偲偆偲偆廡媥2擔偱偼側偔廡媥5擔惂偵偟偰丄岞柋堳偺媼椏傪60亾僇僢僩偟偨傎偳偩丅庤偑偮偗傜傟側偄僴僀僷乕僀儞僼儗偱崙柉惗妶偼崲媷偟丄恖乆偼崱崰偵側偭偰惌晎傪嫮偔旕擄偟偰偄傞丅偟偐偟丄僠儍儀僗傗儅僪僁乕儘傪戝摑椞偵慖傫偩偺偼傎偐側傜偸崙柉帺恎側偺偩丅
偙傟偼儔僥儞傾儊儕僇偺搑忋崙偵尰傟偨摿堎側帠椺偱偼側偄丅柉庡庡媊偺惗傑傟偨崙偱偁傞僊儕僔儍傕廜嬸惌帯偵娮偭偰偄傞丅僊儕僔儍偼嫄戝側嵿惌愒帤偺塀暳偑柧傜偐偵側偭偰偐傜宱嵪婋婡偵娮傝丄EU偐傜嬥梈巟墖偺忦審偲偟偰擭嬥偺4妱僇僢僩傗岞柋堳偺3妱嶍尭側偳偺尩偟偄嬞弅嵿惌傪媮傔傜傟偰偒偨丅偟偐偟丄曻枱嵿惌偺庴塿幰(偨偲偊偽擭嬥偺庴媼奐巒擭楊偼53嵨偱丄崙柉偺4恖偵1恖偼岞柋堳)偱偁傝側偑傜丄僊儕僔儍崙柉偲偟偰偼帺暘偨偪偺惗妶偑嬯偟偔側傞傛偆側嬞弅嵿惌偼庴偗擖傟偨偔側偄丅偦偆偟偨乬柉堄乭偵寎崌偟偰乽EU偺尩偟偄梫媮傪嫅斲偟傛偆乿偲嫨傫偱僩僢僾偺嵗偵廇偄偨偺偑僠僾儔僗庱憡偩丅
EU偺嵿惌嬞弅嶔偺斲寛偲偄偆崙柉搳昜偺寢壥傪攚晧偭偰岎徛偵椪傫偩僠僾儔僗庱憡偩偭偨偑丄僨僼僅儖僩傪栚慜偵峊偊EU偺尵偆偑傑傑偵懨嫤傪敆傜傟偨丅偙傟偵柍愑擟側僊儕僔儍偺柉廜偼戝寖搟偟偰丄僠僾儔僗偵戅恮傪敆偭偰偄傞丅偟偐偟丄斵偑乽EU偺嬞弅嶔傪庴偗擖傟傞傋偒偩乿偲庡挘偟偰偄偨傜庱憡偵側傟側偐偭偨傢偗偱丄愑傔傜傟傞傋偒偼塕傪尒敳偗側偐偭偨崙柉側偺偩丅廜嬸惌帯偦偺傕偺偱偁傞丅
僊儕僔儍傎偳婋婡揑忬嫷偵偼帄偭偰偄側偄傕偺偺丄宱嵪婋婡偺壩庬偲擄柉栤戣傪書偊傞儓乕儘僢僷偼奺崙偱億僺儏儕僘儉偺戜摢偑栚偵偮偔丅EU棧扙傗斀堏柉傪庡挘偡傞嬌塃惃椡傗斀嬞弅傪宖偘傞嬌嵍惌搣偑惃偄傪憹偟偰丄惌嶔偵傕塭嬁傪媦傏偟偰偄傞丅EU棧扙攈偑惂偟偨僀僊儕僗偺崙柉搳昜偵偟偰傕丄乽棧扙偡傟偽堏柉傪帺暘偨偪偱僐儞僩儘乕儖偱偒傞乿乽EU偺嵶偐側惂栺偵敍傜傟側偔偰偡傓乿偲偄偆棧扙攈偺億僺儏儕僘儉偵愭摫偝傟偨懁柺偑嫮偄丅
仭僩儔儞僾傕僒儞僟乕僗傕億僺儏儕僗僩偩
崱夞偺傾儊儕僇戝摑椞慖傪尒偰偄偰傕丄億僺儏儕僘儉偺戜摢偑挊偟偄丅梊旛慖偺榖戣傪偝傜偭偨僩儔儞僾尰徾傕僒儞僟乕僗尰徾傕億僺儏儕僘儉偺娤揰偱偼傑偭偨偔摨偠側偺偩丅嫟榓搣偺岓曗幰巜柤儗乕僗傪妋幚側傕偺偵偟偨僪僫儖僪丒僩儔儞僾巵偼戝廜偑暦偒偨偄偙偲傪僘僶儕偲尵偆揟宆揑側億僺儏儕僗僩偩丅堏柉偵巇帠傪扗傢傟偨偲巚偭偰偄傞敀恖偺楯摥幰奒媺偵偼丄乽儊僉僔僐崙嫬偵暻傪偮偔傟乿偲偄偆僩儔儞僾敪尵偼怱抧傛偔嬁偔丅IS側偳僀僗儔儉夁寖攈偺僥儘偵嫲晐偟偨傝丄搟傝傪妎偊偰偄傞恖乆偵乽僀僗儔儉嫵搆偼擖崙嬛巭乿偲偄偆僩儔儞僾巵偺庡挘偼岲姶傪帩偨傟傞丅偟偐偟丄椻惷偵峫偊傟偽儊僉僔僐崙嫬偵枩棦偺挿忛偺傛偆側暻偑偮偔傟傞偼偢偑側偄偟丄儊僉僔僐偵暻偺寶愝旓傪暐傢偣傜傟傞傢偗傕側偄丅
偦傟偵丄偄偔傜僀僗儔儉嫵搆偺擖崙傪嬛偠偰傕丄崙撪偵偼栺600枩恖偺僀僗儔儉宯堏柉偑偡偱偵偄傞丅6寧偵僼儘儕僟偱50恖偑巰朣偡傞嵟埆偺廵棎幩帠審偑婲偒偨丅幩嶦偝傟偨梕媈幰偼傾僼僈僯僗僞儞宯偺傾儊儕僇恖偱丄僀僗儔儉夁寖攈偲偺娭學偑媈傢傟偨偑丄偳偆傗傜扨撈斊偵傛傞僿僀僩僋儔僀儉偺壜擻惈偑崅偄傜偟偄丅僀僗儔儉嫵搆偺擖崙傪嬛偠偰傕丄儂乕儉丒僌儘僂儞丒僥儘儕僗僩(崙奜偺夁寖巚憐偵嫟柭偟偰丄崙撪弌恎幰偑撈帺偵堷偒婲偙偡僥儘偺偙偲)偵偼壗偺岠壥傕側偄偺偩丅
僩儔儞僾巵偑塃偺億僺儏儕僗僩側傜丄嵍偺億僺儏儕僗僩偼柉庡搣偺巜柤憟偄偱慞愴偟偨僶乕僯乕丒僒儞僟乕僗巵偩丅帺傜乽柉庡幮夛庡媊幰乿偲柤忔傝丄庒幰悽戙傗敀恖偺僾傾憌偵夁戝側岞栺傪偟偰慁晽傪姫偒婲偙偟偨丅偟偐偟丄乽岞棫戝妛偺庼嬈椏柍彏壔乿偲偐乽崙柉奆曐尟乿偲偐丄攝傞惌嶔偽偐傝傪庡挘偟偰丄嵿尮偵偮偄偰偼傎偲傫偳壗傕尵偭偰偄側偄丅
偦傕偦傕楢朚惌晎偺峴惌挿偱偁傞戝摑椞偵側偭偰傕丄岞棫戝妛偺庼嬈椏傪柍彏壔偡傞尃尷偼側偄丅傾儊儕僇偺戝妛偺傎偲傫偳偼僐儈儏僯僥傿僇儗僢僕(2擭惗偺抁婜戝妛)偱丄庼嬈椏偑側偔側偭偨傜塣塩偑惉傝棫偨側偔側傞偺偩丅惌晎偑庼嬈椏傪曗揢偟傛偆傕偺側傜丄惻嬥偑偄偔傜偁偭偰傕懌傝側偄丅崙柉奆曐尟偵偟偰傕丄3000枩恖偵堛椕曐尟傪曗揢偟偨僆僶儅働傾(僆僶儅惌尃偵傛傞曐寬堛椕惂搙夵妚)偱偝偊尷奅偓傝偓傝側偺偵丄偦傟傪忋夞傞惂搙夵妚偑幚尰壜擻偲偼偲偰傕巚偊側偄丅
偮傑傝僩儔儞僾巵傕僒儞僟乕僗巵傕丄偱偒傕偟側偄岞栺傪暲傋棫偰偰丄庴塿幰偲偍傏偟偒恖乆偐傜擬嫸揑側巟帩傪廤傔偰偒偨偺偩丅偙傟傑偱偺戝摑椞慖嫇偱傕丄儘僗丒儁儘乕巵偺傛偆側億僺儏儕僗僩偼偄偔傜偱傕弌偰偒偨丅偟偐偟丄儅僗僐儈偺僠僃僢僋婡擻偑摥偄偰丄僾儔僀儅儕乕(梊旛慖)偱攔彍偝傟傞偺偑捠椺偩偭偨丅偲偙傠偑崱夞偼柺敀偄傛偆偵朅枟岓曗偲巚傢傟偨億僺儏儕僗僩偑巆偭偨丅側偤偐丅儅僗僐儈偺僠僃僢僋婡擻偑庛偔側偭偨偺傕妋偐偩偑丄戝偒側棟桼偺堦偮偼婛懚惌搣偺摉偨傝慜偺庡挘偵朞偒朞偒偟偨傝丄晄枮傪帩偮恖乆偑憹偊偨偐傜偩傠偆丅偩偐傜杮柦帇偝傟偨僸儔儕乕丒僋儕儞僩儞巵偑忢幆揑側偙偲傪尵偊偽尵偆傎偳乽偮傑傜側偄乿岓曗偲偟偰恖婥傪棊偲偟偰偒偨偺偩丅丂 |
仭塃攈億僺儏儕僗僩偺戜摢丄僌儘乕僶儖壔斲掕偺挍偟偱偼側偄
愭恑彅崙偑1930擭戙埲棃嵟埆偺晄嫷婜傪懴偊擡傇拞丄奺崙偺桳尃幰偼崙奜偺恖乆偑帩偪崬傓捝庤傪旕擄偡傞億僺儏儕僗僩(戝廜寎崌庡媊幰)偵孮偑偭偰偄傞丅偙傟傪庴偗偰丄僌儘乕僶儖壔偑媡峴偟僼傽僔僘儉偑戜摢偟偨悽奅戝嫲峇偲斾妑偡傞晄壐側摦偒偑傒傜傟傞丅
偩偑徻偟偔嬦枴偡傟偽丄椶帡惈偺巜揈偵偼晄旛偑偁傞偙偲偑暘偐傞丅
墷廈戝棨偵傒傜傟傞拞摴塃攈偺億僺儏儕僗僩傗塸崙偺墷廈楢崌(EU)偐傜偺棧扙偵巀惉偡傞恖乆丄暷戝摑椞慖偱嫟榓搣岓曗偵巜柤偝傟傞尒捠偟偺僪僫儖僪丒僩儔儞僾巵側偳偵懳偡傞巟帩偼丄僌儘乕僶儖壔偵懳偡傞暆峀偄斀敪傛傝傕丄堏柉偲偄偆摿掕偺堦柺偐傜惗偠偰偄傞丅偙偺栤戣偑丄宱嵪柺偩偗偱側偔丄恖庬傗暥壔柺偱偺晄埨傪崅傔偰偄傞丅
僪僀僣偺椺傪傒傞偲丄2013擭偺慖嫇偱偼丄嬌傔偰恖婥偺崅偄儊儖働儖庱憡偑棪偄傞拞摴塃攈梌搣偑丄斀儐乕儘傪宖偘傞億僺儏儕僗僩惌搣偺乽僪僀僣偺偨傔偺慖戰巿乿(AfD)傪埑搢偟偨丅AfD偺摼昜棪偼傢偢偐4.7亾偩偭偨丅偲偙傠偑偦偺屻丄梌搣偺巟帩棪偼掅壓偟丄AfD偑巟帩傪戝偒偔怢偽偟偰偄傞丅
崱擭3寧偺廈媍夛慖嫇偵偍偗傞AfD偺摼昜棪偼丄僓僋僙儞丒傾儞僴儖僩廈偱24亾丄僶乕僨儞丒價儏儖僥儞僽儖僋廈偱偼15亾丄儔僀儞儔儞僩丒僾僼傽儖僣廈偱13亾偩偭偨丅偙偆偟偨摦偒偼宱嵪偲偼娭學側偄丅僪僀僣偺幐嬈棪偼儐乕儘婋婡埲慜偺敿暘偺悈弨偵側偭偰偄傞丅拞搶傪拞怱偵100枩恖挻偺擄柉棳擖傪嫋偟偨儊儖働儖庱憡偺敾抐偵懳偡傞斀敪偑攚宨偵偁傞丅廈媍夛慖嫇偱偼丄AfD巟帩幰偺敿悢埲忋偑擄柉偼柧傜偐偵栤戣偩偲巜揈偟偨丅宱嵪傪栤戣帇偡傞惡偼傢偢偐4暘偺1偩偭偨丅
楌巎揑偵傒偰丄嬥梈婋婡偼惌帯偺椉嬌壔傗抐曅壔偵偮側偑偭偰偒偨偑丄儐乕儘婋婡傕偦偺椺偵楻傟側偄丅墷廈慡懱偱婛惉庡棳攈惌搣偵懳偡傞巟帩偑掅壓偟偰偄傞丅偩偑丄帺摦揑偵嬌塃攈偺巟帩偵偼偮側偑偭偰偼偄側偄丅
暷僕儑乕僕傾戝妛偺僇乕僗丒儅僢僨弝嫵庼(惌帯妛)偵傛傞偲丄儐乕儘寳偱嬥梈巟墖傪庴偗偨5僇崙偱偼丄塃攈億僺儏儕僗僩偺摼昜棪偼暯嬒2亾枹枮偩丅嬞弅傊偺掞峈偑丄僊儕僔儍偱偼嵍攈億僺儏儕僗僩偵惌尃傪埇傜偣丄僗儁僀儞偱愭偛傠峴傢傟偨慖嫇偱2埵惌搣偺抧埵傪梌偊偨偑丄偳偪傜傕儐乕儘寳偐傜偺棧扙傪採彞偟偰偼偄側偄丅
偙傟偲偼懳徠揑偵丄億乕儔儞僪偲僴儞僈儕乕偱偼拞摴塃攈億僺儏儕僗僩偑惌尃偵偮偄偨丅椉崙偲傕儐乕儘傪摫擖偟偰偍傜偢丄儐乕儘婋婡傪柶傟丄掅偄幐嬈棪傪嫕庴偟偰偄傞丅僆儔儞僟恖偺儅僢僨弝嫵庼偼乽宱嵪忣惃偑慡偔娭學偟偰偄側偄偲偄偆偙偲偱偼側偄丅偩偑丄幮夛暥壔揑側堄枴丄偮傑傝墭怑傗斊嵾丄摑崌偵懳偡傞寽擮偵娭楢偟偨偙偲偲偟偰夝庍偝傟傞偲丄嬌塃攈偵桳棙偵摥偔孹岦偑偁傞乿偲岅偭偨丅
僼儔儞僗偺応崌偼帠忣偑偝傜偵暋嶨偩丅儐乕儘偲宱嵪偵懳偡傞尪柵姶偐傜嬌塃惌搣乽崙柉愴慄乿傊偺巟帩偑崅傑偭偨偑丄斀堏柉偺巔惃偼僼儔儞僗惌奅偵偍偗傞堦惃椡偲偟偰偄傑偵巒傑偭偨偙偲偱偼側偄丅
摨條側摦偒偑塸崙偱傕丄EU棧扙偺惀旕傪栤偆6寧23擔偺崙柉搳昜偑嬤偯偔偵偮傟偰栚棫偭偰偒偰偄傞丅儐乕儘夰媈攈偺拞怱揑側恖乆偼偐偹偰丄EU杮晹偺偍偣偭偐偄側姱椈傜偑塸崙偺柉庡庡媊傪彎偮偗偰偄傞偲晄枮傪楻傜偟偰偒偨丅偩偑丄悽榑挷嵏夛幮僀僾僜僗偵傛傞偲丄EU傪棧扙偟偨偄偲偡傞塸崙柉偺偆偪丄堏柉傪棟桼偵嫇偘傞惡偑49亾偩偭偨偺偵懳偟丄朄惂忋偺撈棫惈傪棟桼偲偟偨恖偼傢偢偐30亾偩偭偨丅
暷崙偺桳尃幰偼偄偮傕寽擮嵽椏偺戞堦偵宱嵪傪嫇偘傞偑丄僌儘乕僶儖壔偺嫅斲偵偼寢傃偮偄偰偄側偄丅慡懱偲偟偰丄帺桼杅堈偲堏柉偵懳偡傞暷崙恖偺巟帩偼丄07擭乣09擭偺儕僙僢僔儑儞(宨婥屻戅)埲崀偵掅壓偱偼側偔憹壛孹岦傪偨偳偭偰偄傞丅僩儔儞僾巵偼帺桼杅堈偵斀懳傪彞偊偰偄傞偑丄堏柉偵懳偡傞斀懳傗恖岥偺傎傫偺堦晹偵偍偗傞恖庬忋偺寽擮傎偳丄慖嫇塣摦偺惉岟偵偍偄偰拞妀傪側偟偰偄側偄傛偆偵巚傢傟傞丅
弌岥挷嵏偱偼丄堏柉傪栤戣偺戞堦偲偟偨嫟榓搣堳偼栺10亾偵偡偓側偐偭偨偑丄僩儔儞僾巵傪巟帩偟偨恖乆偺娫偱偼丄嫟榓搣堳慡懱傛傝傕偦偺斾棪偼偼傞偐偵崅偐偭偨丅僺儏乕丒儕僒乕僠丒僙儞僞乕偵傛傞偲丄僩儔儞僾巵傪巟帩偡傞恖偺69亾掱搙偑堏柉偼暷崙偵偲偭偰晧扴偩偲偟偰偄傞偑丄摨巵傪巟帩偟側偄嫟榓搣堳偺娫偱偙偆偟偨堄尒偼47亾偩偭偨丅
堘朄堏柉傪旕擄偡傞岦偒偺懡偔偼幚嵺偺偲偙傠丄崌朄揑側堏柉偑弴斣傪懸偪昁梫偲偝傟傞媄弍傪帩偭偰偄傞尷傝偵偍偄偰娊寎偟偰偄傞丅偩偑僩儔儞僾巵巟帩憌偺懡偔偼丄宱嵪柺偲摨偠偔傜偄暥壔柺傪怱攝偟偰偄傞丅僺儏乕丒儕僒乕僠丒僙儞僞乕偵傛傞偲丄僩儔儞僾巵偼摿偵丄暷崙偺恖岥偵偍偗傞敀恖偺斾棪掅壓傪栤戣帇偡傞嫟榓搣堳偺巟帩傪廤傔偰偄傞丅
擮偺偨傔偵尵偆偲丄偙偙偵偼宱嵪忋偺攚宨傕偁傞丅僩儔儞僾巵偵懳偡傞巟帩偼妛楌偺掅偄敀恖憌偵戝偒偔廤拞偟偰偄傞丅偙偺憌偼丄椙偄捓嬥偺巇帠偑奜崙偵堏偭偨傝丄帺摦壔偝傟偨傝丄戝懖幰偵堏偭偨傝偟偨偨傔偵晄掁傝崌偄偵嬯偟傔傜傟丄偄傑傗巇帠傪堏柉偲嫞偭偰偄傞丅
偩偑丄宱嵪慡懱偑斏塰偟偰傕丄暥壔傗恖庬傪弰傞惌帯揑側嬞挘偼昁偢偟傕娚傓傕偺偱偼側偄丅1960擭戙偼拞娫憌偺強摼偑旘傃敳偗偰偄偨偑丄撿晹偺敀恖幮夛偼岞柉尃朄傪弰傝柉庡搣偵栚傪岦偗側偐偭偨丅堏柉攔愃庡媊偺惌帯壠傜偑搶墷傗撿墷偐傜偺堏柉偵偼嫟嶻庡媊幰傗柍惌晎庡媊幰偑娷傑傟傞偲晄埨傪偁偍偭偰尩奿側堏柉婯惂傪墴偟偮偗偨偺偼丄悽奅戝嫲峇偺帪婜偱偼側偔乽嫸憶偺20擭戙乿偲屇偽傟傞岲嫷婜偩偭偨丅僥儘儕僗僩偑偄傞偐傕偟傟側偄偲偟偰僀僗儔儉嫵搆傪攔愃偡傞僩儔儞僾巵偺峫偊偵帡捠偭偰偄傞丅
宱嵪惉挿偑偝傜偵嫮傑傝暆峀偔嫟桳偝傟傟偽丄偄傑桳尃幰傪暘抐偟偰偄傞栤戣偺懡偔偐傜搟傝偑偁傞掱搙偼敄傟傞偩傠偆丅偩偑楌巎偑帵偡捠傝丄堏柉偼偦偺堦偮偵偼側傜側偄偩傠偆丅丂 |
仭僩儔儞僾巵偼僉儕僗僩嫵搆偐
悽奅偵栺12壄恖偺怣幰傪書偊傞儘乕儅丒僇僩儕僢僋嫵夛嵟崅巜摫幰丄儘乕儅朄墹僼儔儞僔僗僐偼18擔丄7擔娫偺儊僉僔僐朘栤傪廔偊丄儘乕儅傊偺婣搑偺婡撪偱姷椺偺婰幰夛尒傪峴偭偨丅偦偟偰暷嫟榓搣戝摑椞岓曗幰偺1恖丄晄摦嶻墹偺僪僫儖僪丒僩儔儞僾巵偵偮偄偰丄乽壦偗嫶偱偼側偔丄暻傪嶌傞幰偼僉儕僗僩嫵搆偱偼側偄乿偲巜揈丄堏柉僗僩僢僾傗僀僗儔儉嫵搆偺擖崙嬛巭側偳傪庡挘偡傞僩儔儞僾巵傪僉儕僗僩嫵搆偱偼側偄偲斸敾偟偨丅
僩儔儞僾巵傪梚岇偡傞偮傕傝偼側偄偑丄儁僥儘偺屻宲幰儘乕儅朄墹偼擛壗側傞棟桼偑偁傞偲偟偰傕丄乽偁側偨偼僉儕僗僩嫵搆偱偼側偄乿偲愗傝幪偰傞偙偲偼偱偒側偄偼偢偩丅朄墹偼丄乽暷戝摑椞慖偵姳徛偡傞峫偊偼側偄乿偲抐偭偰偄傞偑丄偦偺敪尵撪梕偼偐側傝惌帯揑偩丅
栤戣偼丄朄墹偑嫟榓搣戝摑椞岓曗儗乕僗偵姳徛偟偰偄傞偐傜偱偼側偄丅梤帞偄偺棫応偵偁傞儘乕儅朄墹偑丄梤偺怣幰偨偪偵岦偐偭偰丄乽偍慜偼僟儊乿乽偍慜偼偄偄乿偲崗報傪墴偡偙偲偼杚夛傪惞怑偲偡傞朄墹偵揔偟偰偄傞偺偐偩丅
朶尵傗栤戣敪尵傪偟側偐偭偨惌帯巜摫幰偼奆柍偩傠偆丅偝傑偞傑側朶尵敪尵偑惌帯壠傗巜摫幰偺岥偐傜旘傃弌偡丅偦偺撪梕偑僀僄僗偺椬恖垽偲崌抳偟偰偄側偄偲偄偆棟桼偱丄乽偍慜偼僉儕僗僩嫵搆偱偼側偄乿偲偄偆側傜偽丄悽奅12壄恖偺怣幰傪書偊傞僇僩儕僢僋嫵夛偱偳傟偩偗杮摉偺怣幰偑偄傞偩傠偆偐丅
惔昻傪愢偒丄尓嫊偲帨垽傪媮傔偰偒偨僼儔儞僔僗僐朄墹偐傜丄嵸敾姱偺傛偆側敪尵偑旘傃弌偟偨偺偩丅僉儏乕僶偱儘僔傾惓嫵偺僉儕儖1悽偲楌巎揑夛崌傪壥偨偟丄儊僉僔僐偱偼懡庬懡條偺楃攓丄僀儀儞僩偵嶲壛偟偰偒偨79嵨偺崅楊朄墹偼儘乕儅婣搑偺婡撪偱儕儔僢僋僗偟丄岥偑寉偔側偭偨寢壥丄旘傃弌偟偨偩偗偩傠偆丅
偦傟偵偟偰傕丄僼儔儞僔僗僐朄墹偵偼栤戣敪尵偑彮側偔側偄丅朄墹偼嶐擭1寧19擔丄僗儕儔儞僇丄僼傿儕僺儞朘栤屻偺婣崙搑忋偺婡撪婰幰夛尒偱丄悘峴婰幰抍偐傜旔擠栤戣偱幙栤傪庴偗偨帪丄乽奜晹偐傜壠懓寁夋偵偮偄偰姳徛偡傞偙偲偼偱偒側偄乿偲弎傋丄乽巚憐偺怉柉抧壔乿偲屇傫偱斸敾偡傞堦曽丄旔擠庤抜傪嬛巭偟偰偄傞僇僩儕僢僋嫵媊傪梚岇偟側偑傜傕丄乽僉儕僗僩幰偼儀儖僩僐儞儀傾偱戝検惗嶻偡傞傛偆偵丄巕嫙傪懡偔嶻傓昁梫偼側偄丅僇僩儕僢僋怣幰偼僂僒僊(帞偄僂僒僊)偺傛偆偵側傞昁梫偼側偄偺偩乿偲弎傋丄柍愑擟偵巕嫙傪嶻傓偙偲偵寈崘傪敪偟偨偺偩丅朄墹偺乽偆偝偓偺傛偆偵乧乿偲偄偆敪尵撪梕偑揱傢傞偲丄乽戝壠懓偺怣幰偨偪偺怱忣傪彎偮偗傞乿偲偄偭偨斸敾偩偗偱偼側偔丄梴揺嬈幰偐傜傕嬯忣偑旘傃弌偟偨偺偼傑偩婰壇偵怴偟偄(乽斸敾傪屇傇朄墹偺亀揺偺偨偲偊榖亁乿2015擭1寧22擔嶲峫)丅
慜朄墹傋僱僨傿僋僩16悽傕嵼埵婜娫(2005擭4寧乣13擭2寧)丄栤戣敪尵偑側偐偭偨傢偗偱偼側偄丅朄墹廇擟擭偺2005擭9寧丄朘栤愭偺僪僀僣偺儗乕僎儞僗僽儖僋戝妛偺島墘偱丄僀僗儔儉嫵偵懳偟丄乽儉僴儞儅僪偑傕偨傜偟偨傕偺偼幾埆偲巆崜偩偗偩乿偲斸敾偟偨價僓儞僠儞掗崙峜掗偺尵梩傪堷梡偟偨丅偦偺偨傔丄悽奅偺僀僗儔儉嫵搆偐傜寖偟偄僽乕僀儞僌傪庴偗偨偙偲偑偁偭偨丅
妛幰朄墹傋僱僨傿僋僩16悽偲撿暷朄墹僼儔儞僔僗僐偼丄栤戣敪尵偺撪梕傕偐側傝堎側偭偰偄傞丅撿暷婥幙偺朄墹傪抦傞僕儍乕僫儕僗僩偼朄墹偐傜柺敀偄敪尵傪堷偒弌偦偆偲晠怱偟偰偄傞偼偢偩丅
栤戣偵栠傞丅僩儔儞僾巵偼僉儕僗僩嫵搆偱偼側偄偺偩傠偆偐丅
摨巵偼僾儘僥僗僞儞僩宯偺挿榁攈嫵夛偵強懏偡傞僉儕僗僩嫵搆偩偑丄廤夛偱惞彂傪傕偭偰岅傝妡偗傞偙偲傕偁傞丅偟偐偟丄懠幰傪斸敾偟丄崲媷壓偵偁傞恖娫傊偺垽偺寚擛偼僀僄僗偺嫵偊偵偼堦抳偟側偄偙偲偼柧傜偐偩丅偑丄偦傟偼僩儔儞僾巵偩偗偱偼側偄丅僩儔儞僾巵傕帺恎偺敪尵偑栤戣傪屇傃丄儊僨傿傾偺拲栚傪梺傃傞偙偲傪抦偭偨忋偱岅偭偰偄傞偼偢偩丅偦偺堄枴偱丄僩儔儞僾巵偼娫堘偄側偔億僺儏儕僗僩偩丅
堦曽丄僩儔儞僾巵傪斸敾偟偨僼儔儞僔僗僐朄墹傕帺暘偺敪尵偑朄墹傜偟偔側偄偙偲傪廫暘抦偭偰偄傞偼偢偩丅朄墹傕僩儔儞僾巵偵晧偗側偄億僺儏儕僗僩偺柺偑偁傞偲偄偆傋偒偩傠偆丅
偩偐傜丄2恖偺億僺儏儕僗僩偺敪尵偵偮偄偰丄摉曽偺偙偺僐儔儉偺傛偆偵丄乽偁偁偩乿乽偙偆偩乿偲昡偡傞偙偲偼偁傑傝堄枴偑側偄偽偐傝偐丄偦傟偙偦億僺儏儕僗僩偺悌偵懧偪偄傞偙偲偵傕側傞丅丂 |
仭塸崙偺俤倀棧扙偼丄崙壠偺曵夡傊偺彉復!丠
仭塸崙崙柉偼崙柉搳昜偱乽俤倀棧扙乿傪慖戰
俤倀(墷廈楢崌)偐傜偺棧扙偺惀旕傪栤偆塸崙偺崙柉搳昜偼丄嬐嵎偱棧扙巟帩攈偑惂偟傑偟偨(巆棷巟帩攈偺摼昜棪48.1亾偵懳偟偰丄棧扙巟帩攈偼51.9亾丅搳昜棪偼栺72亾)丅帠慜偺悽榑挷嵏側偳偐傜愙愴偑梊憐偝傟偰偄傑偟偨偑丄乽嵟廔揑偵偼巆棷攈偑彑棙偟偰塸崙偼EU偵棷傑傞偙偲偵側傞偩傠偆乿偲偄偆尒曽偑戝惃偱偟偨丅偦傟偩偗偵棧扙攈偺彑棙偼寖恔偱丄崙柉搳昜偺奐昜擔偺搶嫗丄堦栭柧偗偨6寧24擔偺悽奅偺姅幃巗応偼慡柺埨偺揥奐偲側傝傑偟偨丅
堊懼巗応偱偼塸億儞僪偑攧傜傟偰1985擭埲棃偺悈弨偵壓棊丄1擔偺壓偘暆偲偟偰偼夁嫀嵟戝傪婰榐偟傑偟偨丅摉帠幰偱偁傞塸崙崙柉偵偲偭偰傕梊憐奜偺寢壥偩偭偨傛偆偱丄斵傜偺屻夨偺擮偼憡摉偵嫮偄傕偺偑偁傝傑偡丅
仭崙柉搳昜偱乽怣擟乿偲僞僇傪偔偔偭偰偄偨僉儍儊儘儞尦庱憡偺戝岆嶼
仭僉儍儊儘儞偑斊偟偨3偮偺儈僗
崱夞偺崙柉搳昜偱偼悽戙娫偺堄幆偺堘偄偑柧妋偵弌偨丅
乽We European乿偱堢偭偰偄傞庒偄悽戙偼埑搢揑懡悢偑俤倀巆棷傪巟帩偟丄媡偵崅楊悽戙偺懡偔偼棧扙傪巟帩偟偨偺偩丅嬌抂偵尵偊偽崅楊幰悽戙偼6懳4偱棧扙巟帩丄庒幰悽戙偼7懳3偱巆棷巟帩偲偄偆峔恾偵怓暘偗偝傟偨丅
偙偆偟偨暘愅寢壥傪庴偗偰乽塸崙偺塣柦傪帺暘偨偪偑寛傔偨偺偼娫堘偄偩偭偨丅庒偄恖偨偪偑偦傫側偵巆棷傪朷傫偱偄傞偺側傜丄変乆傕巆棷偵搳昜偡傋偒偩偭偨乿偲偄偆惡偑崅楊憌偐傜暦偙偊偰偔傞丅幚嵺丄塸崙媍夛偵偼崙柉搳昜偺傗傝捈偟傪媮傔傞彁柤偑嶦摓偟偰偄傞偑丄僉儍儊儘儞尦庱憡偼(堷偒宲偄偩儊僀怴庱憡傕)乽崙柉搳昜偺傗傝捈偟偼偟側偄乿偲柧尵偟偰偄傞丅
俤倀巆棷傪屇傃偐偗偰偒偨僉儍儊儘儞尦庱憡偼乽棧扙偵岦偗偰怴偟偄巜摫晹偑昁梫偩乿偲帿堄傪昞柧偟偨丅僉儍儊儘儞偲偄偆儕乕僟乕偼摢偼埆偔側偄偺偩傠偆偑丄埲壓偺傛偆側3偮偺儈僗傪斊偟偨偲巚偆丅
(1)僗僐僢僩儔儞僪撈棫偺惀旕傪栤偆廧柉搳昜傪擣傔偨偙偲
撈棫偼斲寛偝傟偨傕偺偺丄壓庤傪偡傟偽塸崙偲偄偆崙壠偺暘楐偺堷偒嬥偵側傝偐偹側偐偭偨丅
(2)崱夞偺崙柉搳昜
僉儍儊儘儞尦庱憡偼3擭慜偵崙柉搳昜偺幚巤傪昞柧偟偰丄乽変乆曐庣搣偑彑偭偨傜丄偙傟傪傗傝傑偡乿偲嶐擭偺憤慖嫇偱岞栺偵宖偘偨丅偮傑傝朄棩偵傕側偄崙柉搳昜傪惌尃墑柦偺摴嬶偵巊偭偨偺偩丅僉儍儊儘儞尦庱憡偲偟偰偼廧柉搳昜傗崙柉搳昜傪栺懇偟偰僈僗敳偒偡傟偽丄嵟屻偼乬椙幆揑乭側寢榑偵棊偪拝偔偲偄偆娒偄撉傒偑偁偭偨偺偩傠偆丅僗僐僢僩儔儞僪偺廧柉搳昜偱偼尰忬堐帩攈偑偒傢偳偔忋夞偭偨偑丄崱夞偺崙柉搳昜偼姰慡偵撉傒堘偭偨丅巆棷攈偺僉儍儞儁乕儞偱偼僕儑儞丒儊乕僕儍乕傗僩僯乕丒僽儗傾傜楌戙偺儕乕僟乕傪憤摦堳偟偰巆棷偺儊儕僢僩傪愢偒丄拞墰嬧峴偺憤嵸傑偱偑乽(棧扙偺)宱嵪揑側懝幐偼寁傝抦傟側偄乿偲慽偊偨丅偟偐偟惌奅傗嵿奅偺僄僗僞僽儕僢僔儏儊儞僩偑乽棧扙側傫偰僶僇側慖戰偼偁傝偊側偄乿偲岥傪懙偊傞傎偳偵僄儕乕僩巟攝偵懳偡傞斀敪偑嫮傑偭偰丄棧扙攈巟帩偵崙柉偑孹偄偨懁柺傕偁傞丅
(3)崙柉搳昜偺寢壥傪庴偗偰丄偡偖偝傑帿擟傪昞柧偟偨偙偲
帾偄偨庬偼帺暘偱姞傝庢傞傋偒側偺偵丄俤倀棧扙偵岦偗偨懬庢傝傪搳偘弌偟偰偟傑偭偨丅偨偩偟丄媍夛傪夝嶶(媍堳偺3暘偺2偺巀摨偑昁梫)偟側偐偭偨偺偼尗偐偭偨丅夝嶶偡傟偽憤慖嫇偩偑丄夝嶶偟側偗傟偽曐庣搣偼惌尃傪堐帩偟偨傑傑丄屻宲幰傪寛傔傜傟傞偐傜偩丅
仭崙柉搳昜偺寢壥傪暍偡媡揮僔僫儕僆偼偁傝偆傞偐
摉弶丄桳椡側屻宲岓曗偲栚偝傟偰偄偨偺偼棧扙攈傪庡摫偟偰偒偨儃儕僗丒僕儑儞僜儞慜儘儞僪儞巗挿偩偭偨丅偟偐偟懁嬤偺棤愗傝偵偁偭偰丄搣庱慖傊偺弌攏傪抐擮丅寢嬊丄搣庱慖傪惂偟偨僥儕乕僓丒儊僀慜撪柋戝恇偑怴庱憡偵廇擟偟偨丅儅乕僈儗僢僩丒僒僢僠儍乕埲棃26擭傇傝丄2恖栚偺彈惈庱憡偺抋惗偱偁傞丅
儊僀庱憡偼崙柉搳昜偱偼俤倀巆棷傪巟帩偟偰偄偨偑丄庱憡廇擟屻偼崙柉搳昜偱夁敿悢傪摼偨乽棧扙乿傪悇恑偡傞峫偊傪帵偟丄慻妕偱棧扙攈偺儃儕僗丒僕儑儞僜儞巵傪奜柋戝恇偵擟柦偟偨丅乽棧扙傪惉岟棤偵恑傔偨偄乿偲偟側偑傜傕丄乽俤倀偲偺岎徛愴棯傪嶔掕偡傞偨傔偵帪娫偑昁梫乿偲偟偰丄擭撪偼棧扙庤懕偒傪奐巒偟側偄偲偺棫応傪怴庱憡偼昞柧偟偰偄傞丅
偝偰丄壛柨崙偑俤倀傪棧扙偟偨慜椺偼側偄偑丄俤倀偺婎杮忦栺偱偁傞儕僗儃儞忦栺偺50忦偵棧扙偺庤懕偒偵偮偄偰婯掕偝傟偰偄傞丅
偦傟偵傛傟偽丄摉奩崙偑墷廈棟帠夛(俤倀偺嵟崅嫤媍婡娭)偵棧扙偺堄巚傪捠崘偡傞偙偲偐傜棧扙庤懕偒偼巒傑傞丅偦偺屻丄墷廈埾堳夛偲扙戅嫤掕傪掲寢偡傞偨傔偺岎徛傪峴偆丅崌堄偟偨扙戅嫤掕偑墷廈媍夛偱彸擣偝傟丄偝傜偵墷廈棟帠夛偱彸擣偝傟傟偽丄扙戅嫤掕偺敪岠擔傪埲偰惏傟偰俤倀棧扙偲側傝丄棧扙崙偵俤倀朄偼揔梡偝傟側偔側傞丅
傑偨丄岎徛偑擄峲偟偰扙戅嫤掕偑掲寢偱偒側偐偭偨応崌偼丄棧扙捠崘偐傜2擭偱俤倀朄偼揔梡彍奜偲側傞(慡壛柨崙偺摨堄偱墑挿壜擻)丅偮傑傝丄俤倀傪棧扙偡傞偵偼嵟掅偱傕2擭埲忋偐偐傞傢偗偩偑丄塸崙偼傑偩棧扙捠崘偡傜峴偭偰偄側偄丅捠崘傪偟側偗傟偽棧扙偺庤懕偒偼巒傑傜側偄偺偩丅
捠崘傪僟儔僟儔偲堷偒墑偽偟偰俤倀偵棷傑傝懕偗傞偲偄偆摴嬝傕側偔偼側偄偑丄崿棎偺奼戝傪婋湝偡傞俤倀懁偼塸崙偵懳偟偰乽棧扙偡傞側傜偝偭偝偲弌偰偄偗乿偲撍偒曻偟偰偄傞丅
塸崙偼帺崙捠壿偺億儞僪傪巊偭偰偄傞偟丄堟撪偺帺桼堏摦傪曐徹偡傞僔僃儞僎儞嫤掕偵傕壛擖偟偰偄側偄丅偡偱偵摿尃揑側棫応偵偁傞傢偗偱丄乽棧扙傪偪傜偮偐偣傞塸崙偵偙傟埲忋偄偄偲偙庢傝偼偝偣側偄丅棧扙偡傞側傜彑庤偵偡傟偽偄偄丅変乆偼27僇崙偱寢懇偟偰偄偔乿偲偄偆偺偑俤倀偺抐屌偨傞巔惃側偺偩丅
塸崙偲偟偰偼弆乆偲棧扙庤懕偒偵擖傞偐丄傕偟偔偼崙柉搳昜偺寢壥傪暍偡媡揮僔僫儕僆傕峫偊傜傟傞丅崙柉搳昜偼僉儍儊儘儞尦庱憡偑栺懇偟偨岞栺偵偡偓偢丄偦偺寢壥偵朄揑峉懇椡偼側偄丅朄揑側峉懇椡偑偁傞偺偼媍夛偱寛傑偭偨偙偲偱偁傞丅
巹偑塸崙偺庱憡偩偭偨傜媍夛偵偙偆屇傃偐偗傞丅
乽崙柉搳昜偺寢壥偼懜廳偝傟側偗傟偽側傜側偄丅偟偐偟丄偙傟偐傜偁傜備傞忣曬傪庢傝婑偣偰丄僀僊儕僗偵偲偭偰壗偑摼嶔側偺偐丄慖椙偱偁傞変乆偱傕偆堦搙媍榑偟傛偆偱偼側偄偐乿
媍榑偺僾儘僙僗偼偡傋偰崙柉偵岞奐偟偰丄棧扙偡傋偒偐巆棷偡傋偒偐丄媍夛偱寢榑傪弌偡丅偦偺偆偊偱夝嶶憤慖嫇傪峴偭偰崙柉偺怰敾傪嬄偖乗乗偲偄偆僔僫儕僆偩丅偙傟偼寛偟偰奊嬻帠偱偼側偄丅
1970擭戙偵巹偼壗搙傕塸崙傪朘傟偰偄傞偑丄摉帪偼枬惈揑偵宱嵪偑掆懾偟偰幐嬈棪偼11亾偵払偟丄乽塸崙昦乿偲偄偆尵梩偑儊僨傿傾傪擌傢偟偰偄偨丅偟偐偟丄崱偺塸崙偺幐嬈棪偼傢偢偐5亾丄墷廈偱嵟傕堏柉傪庴偗擖傟偰偄傞崙偺堦偮偑塸崙偩偑丄偦傟偱傕愄偺傛偆側幐嬈棪偵側傜側偄偺偼側偤偐丅側偤崱偺塸崙偵屬梡偑偁傞偐丅偦偆偄偆媍榑偑崱夞偺崙柉搳昜偺僾儘僙僗偱偼敳偗棊偪偰偄偨傛偆偵巚偆丅
偙偺30擭娫丄塸崙偑悽奅拞偐傜搳帒傪廤傔偰屬梡傪惗傒弌偟偰偒偨偺偼丄僒僢僠儍乕夵妚偺惉壥偽偐傝偱偼側偄丅塸崙偑俤倀28僇崙偺乬僿僢僪僋僆乕僞乕乭偲偟偰廳曮偝傟偰偒偨偐傜偩丅擔杮婇嬈偵偟偰傕塸崙偵墷廈杮晹傗岺応傪偮偔傟偽丄偦偙偐傜俤倀慡懱偵梕堈偵帠嬈傪揥奐偱偒傞丅儘儞僪儞偺僔僥傿偵偟偰傕俤倀偵擖偭偰偐傜悽奅偺嬥梈僙儞僞乕偲偟偰抐僩僣偵敪揥偟偨丅擔杮偺嬧峴傗徹寯夛幮偑僔僥傿偵嫆揰傪抲偔偺偼丄偁偦偙偑乬墷廈乭偩偲巚偭偰偄傞偐傜偩丅
塸崙偺斏塰偼俤倀偺拞偵偁偭偰偙偦偺斏塰偱偁傝丄棧扙偟偰傂偲傝傏偭偪偵側偭偨傜丄塸崙偼尦偺塸崙堦崙偵栠傝丄搳帒偺枺椡偼戝偒偔尭戅偡傞丅崱夞偺崙柉搳昜偱棧扙偺嫲晐傪敡偱姶偠偨塸崙崙柉偼彮側偔側偄偩傠偆丅悽奅宱嵪丄傂偄偰偼帺崙宱嵪偵梌偊傞僀儞僷僋僩傕丄億儞僪朶棊偺壜擻惈傕尒偊偨丅
偝傜偵偄偊偽丄巆棷攈偑懡悢傪愯傔偨僗僐僢僩儔儞僪傗杒傾僀儖儔儞僪偺摦岦傕尒摝偣側偄丅僗僐僢僩儔儞僪帺帯惌晎偺僯僐儔丒僗僞乕僕儑儞庱憡偼僗僐僢僩儔儞僪扨撈偺俤倀壛柨偵岦偗偨帎栤夛媍偺愝棫傪昞柧丄撈棫偵岦偗偨2搙栚偺廧柉搳昜偺弨旛傕巒傑偭偨丅杒傾僀儖儔儞僪偱傕俤倀巆棷偲傾僀儖儔儞僪偲偺摑堦偺摦偒偑壛懍偟丄棧扙攈偑懡悢傪愯傔偨僂僃乕儖僘偱傕撈棫傪柾嶕偡傞摦偒偑弌偰偒偨丅
偲偄偆偙偲偱丄塸崙偑棧扙偵岦偐偊偽僌儗乕僩僽儕僥儞偼嬻拞暘夝偟偐偹側偄丅棧扙屻偺倀俲偺塣柦丄偡側傢偪曵夡丄偲偄偆栤戣偼偄傑偩偵崙柉揑側媍榑偑側偝傟偰偄側偄偺偩丅
偙偺傛偆側僨儊儕僢僩傪夵傔偰僇僂儞僩偟偰偄偔偲丄棧扙偺摴偼墦偔夃傫偱偔傞丅俤倀偺嫮婥偺巔惃傪尒偰偄傞尷傝偱偼丄棧扙岎徛傪塸崙偑桪埵偵塣傋傞壜擻惈傕掅偄丅廬偭偰忋偵弎傋偨傛偆側媡揮僔僫儕僆傕廫暘偵偁傝偆傞丅塸崙偺棧扙偼塸崙偲偄偆崙壠偺廔傢傝偺彉復偱偼偁傞偑丄岼(偪傑偨)偱尵傢傟偰偄傞傛偆側乽俤倀偺廔傢傝偺巒傑傝乿偵側傞偙偲偼側偄偩傠偆丅
丂 |
仭僩儔儞僾偲僗儁僀儞偺媫恑嵍攈惌搣億僨儌僗偼帡偰偄傞偺偐
亙僪僫儖僪丒僩儔儞僾偲僗儁僀儞偺媫恑嵍攈惌搣億僨儌僗偼帡偰偄傞...丅丂帡偨傛偆側巟帩幰傪妉摼偟丄恖乆偺忣擬偵岅傝偐偗傞丅塃攈億僺儏儕僘儉傪巭傔傜傟傞偺偼嵍攈億僺儏儕僘儉偩偗側偺偐丠亜
暷戝摑椞慖偺寢壥傪庴偗丄僗儁僀儞偱偼丄億僨儌僗偺僷僽儘丒僀僌儗僔傾僗搣庱偲僪僫儖僪丒僩儔儞僾傪斾妑偡傞恖乆偑弌偰棃偨偺偱丄僀僌儗僔傾僗偼偙傟偵暜奡偟丄乽億僺儏儕僗僩偲偼傾僂僩僒僀僟乕偺偙偲偱偁傝丄帡偨傛偆側儊僜僢僪傪巊偆偙偲偼偁傞傕偺偺丄偦傟偼塃梼偱傕丄嵍梼偱傕偁傝摼傞偟丄僂儖僩儔儕儀儔儖偺応崌傕丄曐岇庡媊幰偺応崌傕偁傞乿偲庡挘偟偰偄傞偲僄儖丒僷僀僗巻偑揱偊偰偄傞丅
仭億僺儏儕僘儉偲偼戝廜寎崌庡媊側偺偐
僷僽儘丒僀僌儗僔傾僗偼丄乽億僺儏儕僗僩乿偺奣擮偵偮偄偰偙偆岅偭偰偄傞丅
乽億僺儏儕僘儉偲偼丄僀僨僆儘僊乕偱傕堦楢偺惌嶔偱傕側偄丅亀傾僂僩僒僀僪亁偐傜惌帯傪峔抸偡傞傗傝曽偺偙偲偱偁傝丄偦傟偼惌帯偑婋婡偵昺偟偨帪愡偵奼戝偟偰偔傞乿
乽億僺儏儕僘儉偼惌帯揑慖戰傪掕媊偡傞傕偺偱偼側偄丅惌帯揑帪愡傪掕媊偡傞傕偺偩乿
僗儁僀儞偼崱擭6寧偵嵞憤慖嫇傪峴偭偨偑丄嶐擭枛偺憤慖嫇摨條偵媍惾偑2戝惌搣偲怴嫽2搣偵暘楐偟偨傑傑惌尃庽棫偵帄傜側偐偭偨丅偦偺忋丄嵟戝栰搣偺幮夛楯摥搣偱撪晹僋乕僨僞乕偑婲偒傞側偳偟偰僑僞偮偒丄儔儂僀庱憡懕搳偺惀旕傪栤偆怣擟搳昜偱婞尃偟偨偨傔丄寢嬊偼崙柉搣偑惌尃偵曉傝嶇偄偰偄傞丅
僀僌儗僔傾僗偼幮夛楯摥搣偺傆偑偄側偝傪寖偟偔旕擄偟偰偍傝丄億僨儌僗偼栰搣戞堦搣偵側傞墿嬥偺僠儍儞僗傪捦傫偱偄傞偲傕曬摴偝傟偰偄傞丅乽懨嫤傪偟側偑傜崙壠惂搙偺側偐偱抧埵傪妋棫偡傞億僨儌僗乿偲乽嵍攈億僺儏儕僘儉偲偟偰偺億僨儌僗乿偲偺愜傝崌偄傪偳偆偮偗傞偐偲偄偆埲慜偐傜偁偭偨栤戣偑丄偄傛偄傛愗幚側傕偺偵側偭偰偒偨傛偆偩丅僀僌儗僔傾僗偼偙偆尵偭偰偄傞丅
乽偙傟偐傜偺悢僇寧丄媍榑偟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄億僨儌僗偼億僺儏儕僗僩偺儉乕償儊儞僩偲偟偰懚嵼偟懕偗傞傋偒偐斲偐偲偄偆偙偲偩乿
乽億僺儏儕僘儉乿偲偄偆尵梩偼丄擔杮偱偼乽戝廜寎崌庡媊乿偲栿偝傟偨傝偟偰摢偛側偟偵埆偄傕偺偺傛偆偵尵傢傟偑偪偩偑丄Oxford Learner's Dictionaries偺僒僀僩偵峴偔偲丄乽弾柉偺堄尒傗婅偄傪戙昞偡傞偙偲傪昗炘偡傞惌帯偺僞僀僾乿偲僔儞僾儖偵彂偐傟偰偄傞丅19悽婭枛偵暷崙偱擾柉偨偪偺朓婲偐傜惗傑傟偨惌搣偺柤慜偑億僺儏儕僗僩(恖柉搣)偩偭偨丅偙傟偼POPULACE偵桼棃偡傞尵梩偩丅堦曽丄POPULAR偐傜攈惗偟偨億僺儏儔儕僘儉偼嵟嬤傛偔惌帯婰帠偱巊傢傟傞傛偆偵側偭偰偒偨尵梩偩偑丄傓偐偟偐傜壒妝娭學偺塸暥婰帠傪撉傫偱偄傞恖偼栚偵偟偨偙偲偑偁傞偲巚偆丅僋儔僔僢僋偵戝廜壒妝偺梫慺傪崿擖偟偨傝丄僀儞僨傿乕宯偺抦傞恖偧抦傞傾乕僥傿僗僩偑億僢僾傾儖僶儉傪弌偟偨傝偡傞偲偒偵丄昡榑壠偨偪偼乽億僺儏儔儕僘儉乿偲屇傫偱偒偨丅
乽億僺儏儕僘儉偺峴偒夁偓偨傕偺偑億僺儏儔儕僘儉乿偲偄偆夝庍傕偁傞偑丄億僺儏儕僘儉偼戝慜採偲偟偰乽壓懁乿(僀僌儗僔傾僗晽偵尵偊偽乽傾僂僩僒僀僪乿)偺惌帯惃椡偨傜傫偲偡傞偙偲偱丄僥儗價偵弌偰偄傞桳柤側僞儗儞僩傪慖嫇偵弌攏偝偣偨傝偡傞庤朄偼扨側傞億僺儏儔儕僘儉(戝廜寎崌庡媊)偩丅偦偺僞儗儞僩偑壓懁(傾僂僩僒僀僪)偺惡傪戙昞偡傞偮傕傝偐偳偆偐偼傢偐傜側偄偐傜偱偁傞丅
仭嵍攈偲抧傋偨偺槰棧
EU棧扙丄暷戝摑椞慖偺寢壥傪庴偗偰丄怴偨側嵍攈億僺儏儕僘儉偺昁梫惈傪愢偄偰偄傞偺偼塸僈乕僨傿傾儞巻偺僆乕僂僃儞丒僕儑乕儞僘偩丅
乽摑寁偺悢帤傪尒傟偽掅強摼幰偑僩儔儞僾巟帩偲偄偆偺偼娫堘偄乿偲偄偆堄尒傕弌偰偄傞偑丄僕儑乕儞僘偼擭廂3枩僪儖埲壓偺嵟掅強摼幰憌偵拲栚偟偰偄傞丅懠偺廂擖憌偱偼丄2012擭偺戝摑椞慖偲崱夞偲偱偼丄柉庡搣丄嫟榓搣偲傕偵昜悢偺憹尭僷乕僙儞僥乕僕偼堦寘戜偟偐堘傢側偄丅偩偑丄擭廂3枩僪儖埲壓偺嵟掅強摼憌偱偼丄嫟榓搣偑16亾偺昜傪怢偽偟偰偄傞丅昜悢偱偼傢偢偐偵僩儔儞僾昜偑僋儕儞僩儞昜偵晧偗偰偄傞傕偺偺丄嵟掅強摼憌偱偼丄慜夞偼弶偺崟恖戝摑椞傪偙偧偭偰巟帩偟偨恖乆偺懡偔偑丄崱夞偼儗僀僔僗僩揑敪尵傪偡傞僩儔儞僾偵擖傟偨偺偩丅
塸崙偱傕丄壓憌偺奨偵曢傜偟偰偄傞偲丄奅孏偺恖乆偑(斵傜側傝偺庡媊傪嬋偘傞偙偲側偔)嵍偐傜塃偵搨撍偵僕儍儞僾偡傞姶偠偼敡姶妎偱傢偐傞丅偙傟傪乽壗傕峫偊偰偄側偄僶僇偨偪乿偲嵍攈偼斸敾偟偑偪偩偑丄幚偼偦偆攍搢偣偞傞傪摼側偄偺偼丄斵傜偺偙偲偑傢偐傜側偄偲偄偆帠幚偵儉僇偮偔偐傜偱偼側偄偩傠偆偐丅
乽儔僨傿僇儖側嵍攈偺僗僞僀儖偲暥壔偼丄戝懖偺庒幰(杔傕娷傓)偵傛偭偰宍惉偝傟傞偙偲偑懡偄丅(拞棯) 丒丒丒偩偑丄偦偺桪愭弴埵傗丄儗僩儕僢僋傗丄暔偺尒曽偼丄僀儞僌儔儞僪傗僼儔儞僗傗暷崙偺彫偝側挰偵廧傓擭忋偺儚乕僉儞僌僋儔僗偺恖乆偲偼寑揑偵堎側傞丅(拞棯)懡條壔偟偨儘儞僪儞偺奨偐傜丄愄偼岺応偑棫偪暲傫偱偄偨杒晹偺奨傑偱丄嵍攈偑儚乕僉儞僌僋儔僗偺僐儈儏僯僥傿乕偵崻嵎偝側偄偙偲偵偼丄偐偮偰偼嵍攈偺巟帩幰偩偭偨恖乆偵嬁偔尵梩傪岅傜側偗傟偽丄偦偟偰丄楯摥幰奒媺偺恖乆偺壙抣娤傗桪愭弴埵傊偺晭曁傪庢傝彍偐側偗傟偽丄嵍攈偵惌帯揑側枹棃偼側偄丅乿
仭塃攈億僺儏儕僘儉傪巭傔傜傟傞偺偼嵍攈億僺儏儕僘儉偩偗丠
僄儖丒僷僀僗巻偼丄億僨儌僗偲僩儔儞僾偼3偮偺僞僀僾偺帡偨傛偆側巟帩幰傪妉摼偟偰偄傞偲彂偄偰偄傞丅
1丏僌儘乕僶儖婋婡偺寢壥丄晧偗將偵偝傟偨偲姶偠偰偄傞恖乆丅
2丏僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞偵傛偭偰丄帺暘偨偪偺暥壔揑丄崙壠揑傾僀僨儞僥傿僥傿偑嫼偐偝傟偰偄傞偲巚偆恖乆丅
3丏僄僗僞僽儕僢僔儏儊儞僩傪敱偟偨偄偲巚偭偰偄傞恖乆丅
乽昳偑側偄乿偲尵傢傟傞價僕僱僗儅儞偺僩儔儞僾偲丄塸崙偱尵偆側傜僆僢僋僗僼僅乕僪偺傛偆側戝妛偺嫵庼偩偭偨僀僌儗僔傾僗偑丄摨偠憌傪巟帩幰偵庢傝崬傓偙偲偵惉岟偟偰偄傞偺偼嫽枴怺偄丅
儅僪儕乕僪帺帯戝妛偺儅儕傾儞丒儅儖僥傿僱僗亖僶僗僋僫儞偼丄億僨儌僗偲僩儔儞僾偑憡帡偟偰偄傞揰偼乽岅傝偐偗乿偩偲巜揈偡傞丅乽僩儔儞僾偵偼棟擮偑偁傞傢偗偱偼側偔丄斵偺尵梩偼丄僿僀僩傗丄僆僶儅戝摑椞偑徾挜偡傞偡傋偰傊偺斀摦偵婎偯偄偰偄傑偡丅恖乆偺姶忣傪楳傃丄嬌嵍傗嬌塃偑偡傞傛偆偵丄嫟捠偺傾僀僨儞僥傿僥傿傪憂弌偟傛偆偲偟傑偡丅栤戣偼丄恖乆偺忣擬偑偳偺傛偆偵棙梡偝傟偰偄傞偐偲偄偆偙偲側偺偱偡乿偲斵彈偼榖偟偰偄傞丅
姶忣偲尵梩偺懁柺偵偮偄偰偼丄塸崙偺僆乕僂僃儞丒僕儑乕儞僘傕偙偆彂偄偰偄傞丅
乽僾儘僌儗僢僔償側嵍攈偼丄僼傽僋僩傪暲傋偰嫨傋偽恖乆傪愢偒暁偣傞偙偲偑偱偒傞偲怣偠偰偄傞丅偩偑恖娫偼姶忣偺摦暔偩丅変乆偼姶忣揑偵撍偒摦偐偝傟傞僗僩乕儕乕傪媮傔偰偄傞丅堦曽丄僋儕儞僩儞偺墘愢偼丄嬧峴姴晹偺栶怑偵墳曞偟傛偆偲偟偰偄傞恖偺傛偆偵暦偙偊偨丅(棯)丒丒丒嵍攈傕姶忣傪摦偐偡償傿僕儑儞傪揱偊側偗傟偽側傜側偄丅偨偩帠幚傪弎傋偰傢偐偭偰偔傟傞偩傠偆偲婜懸偟偰偄傞偩偗偱偼丄塃攈偺惃偄傪撦傜偣傞偙偲傕丄僾儘僌儗僢僔償側惃椡偺楢崌傕抸偗側偄偲傢偐偭偨偺偩偐傜丅乿
億僨儌僗偺姴晹偨偪偼乽塃攈億僺儏儕僘儉傪巭傔傜傟傞偺偼嵍攈億僺儏儕僘儉偩偗乿偲尵偭偨儀儖僊乕偺惌帯妛幰丄僔儍儞僞儖丒儉僼偵塭嬁傪庴偗偰偄傞偲偄偆丅僄儖丒僷僀僗巻偵傛傟偽丄僗儁僀儞偼墷廈崙偲偟偰偼捒偟偔丄塸崙偺僫僀僕僃儖丒僼傽儔乕僕偺UKIP傗丄僼儔儞僗偺儅儕乕僰丒儖丒儁儞偺崙柉愴慄偺傛偆側塃攈億僺儏儕僘儉偑傑偩弌尰偟偰偄側偄丅
偪傚偭偲婓朷偺墴偟晅偗夁偓偱偼側偄偐偲傕巚偆偑丄僆乕僂僃儞丒僕儑乕儞僘偑乽億僨儌僗偑曵傟偨傜墷廈偺嵍攈偵枹棃偼側偄乿偲尵偆偺傕丄塃攈億僺儏儕僘儉傊偺梷巭椡偲偟偰婡擻偟偰偄傞嵍攈億僺儏儕僘儉偑懠偵尒偁偨傜側偄偐傜偩傠偆丅丂 |
仭崗乆偲擡傃婑傞両丠拞崙宱嵪婋婡偺懌壒
仭廗嬤暯 vs 棝崕嫮丂宱嵪惌嶔傪傔偖傝懳棫偑寖壔偐丠
偄傑拞崙偱偼丄廗嬤暯崙壠庡惾偲棝崕嫮庱憡偲偺娫偱丄宱嵪惌嶔傪傔偖傞懳棫偑寖壔偟偰偄傞偲偄傢傟傑偡丅
崙桳婇嬈曐岇惌嶔傪堐帩偟偰尃椡彾埇傪恑傔偨偄廗庡惾偵懳偟丄棝庱憡偑乽僝儞價婇嬈(宱塩偺峴偒媗傑偭偨崙桳婇嬈)偺搼懣乿側偳乽捝傒傪敽偆峔憿夵妚乿傪採彞偟偰偄傑偡丅乽崱擭慜婜偺宨婥偼椙岲乿偲偡傞棝庱憡偺尒夝傪廗庡惾偺懁嬤偑恀偭岦偐傜斲掕偟丄乽(偙偺傑傑側傜)拞崙宱嵪偼亀倁帤夞暅亁傕亀倀帤夞暅亁傕側偔丄亀俴帤宆亁偑懕偔乿偲庡挘偟丄捝楏偵斸敾偟偨偲恖柉擔曬偑曬偠傑偟偨丅
仭拞崙偺嵚柋巆崅偼2600挍墌埲忋丠
偙偺宨婥敾抐偵偮偄偰偼廗庡惾偺傎偆偑惓偟偄偲巚偆丅椺偊偽丄崱擭6寧偵拞崙幮夛壢妛堾偺妛晹埾堳偱崙壠嬥梈丒敪揥帋尡幒偺棟帠挿傪柋傔傞棝梘巵偑乽2015擭枛偺帪揰偱丄拞崙偺嵚柋巆崅偼168挍4800壄尦(栺2600挍墌)偲嫄妟偱丄俧俢俹(崙撪憤惗嶻)偺249亾偵払偟丄偆偪婇嬈暘偑156亾傪愯傔傞乿偲敪昞偟偨丅
敪尵偺庯巪偼丄拞崙偺嵚柋偼僐儞僩儘乕儖壜擻側斖埻偱丄嵚柋儕僗僋偵懳墳偡傞偨傔偺廫暘側帒嬥偑偁傞偙偲傪棟桼偵乽嵚柋婋婡偼懚嵼偟側偄乿偲嫮挷偡傞傕偺偩偭偨偑丄偙偺悢帤偼宱嵪婯柾偑堘偆偲偼尵偊丄擔杮偺庁嬥偺1000挍墌偺2.6攞偩偐傜丄傗偼傝姦婥偑偡傞傛偆側婯柾偱偁傞丅
棝梘巵偼乽庁嬥傛傝帒嶻偺傎偆偑懡偄乿偐傜埨怱偲尵偆偑丄幚偼拞崙偺庁嬥偑惓妋偵偼偄偔傜偁傞偺偐丄扤偵傕傢偐偭偰偄側偄偲巚偆丅
拞崙偺庁嬥偵偼戝偒偔4偮偺梫慺偑偁傞丅
(1)崙塩婇嬈
(2)柉娫婇嬈
(3)抧曽惌晎
(4)崙
乗乗偱偁傞丅
249亾偺偆偪丄婇嬈暘偑156亾偲偄偆偙偲偼丄抧曽惌晎偲崙偑巆傝偺93亾偲偄偆寁嶼偵側傞丅
偩偑丄15擭9寧偵婛偵巜揈偟偨傛偆偵丄偙傟傑偱抧曽惌晎偺晉偺尮愹偩偭偨擾抧傪彜嬈抧傗岺嬈抍抧偵梡搑曄峏偟偰棙塿傪摼傞晄摦嶻奐敪傗僀儞僼儔惍旛側偳偺搳帒僾儘僕僃僋僩偼偙偲偛偲偔峴偒媗傑傝丄抧曽惌晎偼敎戝側庁嬥傪書偊偰廂廍偑偮偐側偄忬嫷偵娮偭偰偄傞丅偍傑偗偵傾儕僶僶(垻棦攂攂)側偳偺僱僢僩捠斕偑棽惙偟偰偄傞塭嬁偱懡偔偺僔儑僢僺儞僌儌乕儖偼僥僫儞僩偑擖傜偢偵乽婼忛(僑乕僗僩僞僂儞)乿壔偟偰偄傞丅偦偺偨傔丄抧曽惌晎偑彜嬈抧側偳偺奐敪偵傛偭偰栕偗傞偲偄偆廬棃偺巇妡偗偼丄傕偼傗婡擻偟側偔側偭偰偄傞丅
崙傕丄柭傝暔擖傝偱僗僞乕僩偟偨俙俬俬俛(傾僕傾僀儞僼儔搳帒嬧峴)偵婥慜傛偔帒杮嬥1000壄僪儖偺3妱(栺3挍墌)傪弌帒偟偨偑丄奀奜僀儞僼儔僾儘僕僃僋僩偱棙塿傪弌偡偺偼帄擄偺嬈偱偁傞丅偟偐傕丄拞崙偼奀奜僀儞僼儔僾儘僕僃僋僩偺僲僂僴僂傪帩偨側偄丅奀奜僀儞僼儔僾儘僕僃僋僩偵偼丄僼傽僀僫儞僗傗僄儞僕僯傾儕儞僌側偳丄慡晹傪偒傔嵶偐偔僐乕僨傿僱乕僩偡傞僾儘僕僃僋僩儅僱乕僕儍乕偑晄壜寚側偺偩偑丄偦偆偟偨宱尡傕恖嵽傕僲僂僴僂傕帩偭偰偄側偄拞崙偑奀奜偱崅懍揝摴側偳偺戝婯柾側僀儞僼儔僾儘僕僃僋僩傪惉岟偝偣傞偙偲偑偱偒傞偲偼巚偊側偄丅偍偦傜偔丄俙俬俬俛偺僾儘僕僃僋僩偼尙暲傒幐攕偡傞偩傠偆丅
傑偨丄崙塩婇嬈傕崙撪宱嵪偺媫尭懍偵傛偭偰揝峾丄僙儊儞僩丄憿慏丄揝摴側偳偑朞榓忬懺偱丄惗嶻椡偑姰慡偵僟僽偮偄偰偄傞丅
椺偊偽丄拞崙偵偼揝峾儊乕僇乕偩偗偱100幮偔傜偄偁傝丄2015擭偺慹峾惗嶻検偼栺8壄僩儞偵払偟丄悽奅慡懱偺5妱傪愯傔偰偄傞丅擔杮傕偐偮偰揝峾惗嶻悽奅堦偺帪戙偑偁偭偨偑丄偦偺屻丄揝峾晄嫷(揝椻偊)偵捈柺偟丄摉帪偺捠嶻徣偑崙嶔偲偟偰惗嶻擻椡偺嶍尭偵戝僫僞傪怳傞偭偨丅憿慏丄慇堐丄愇扽側偳偱傕摨條偵捠嶻徣偑庡摫偟偰惗嶻擻椡傪寑揑偵嶍傝丄晄嫷傪崕暈偟偰偄偭偨丅
偦傟偲摨偠偙偲傪拞崙偑偱偒傞偺偐丠偄偔傜撈嵸幰丒廗嬤暯偱傕柍棟偩傠偆丅
側偤側傜丄拞崙偺抧曽帺帯懱偺懡偔偼丄偦偙偵棫抧偟偰偄傞揝峾丄憿慏丄僙儊儞僩側偳偺婇嬈偵傛偭偰惉傝棫偭偰偄傞偐傜偩丅偮傑傝丄婇嬈傪捵偟偨傜抧尦偺抧曽帺帯懱傕徚柵偟偰偟傑偆偺偱偁傞丅傕偟丄偦傟傜偺抧曽帺帯懱偺偆偪丄廗嬤暯偑擟柦偟偨庱挿傗彂婰偑偄傞抧曽偺婇嬈偩偗偑惗偒巆偭偨傝偟偨傜丄墔歭(偊傫偝)偺塓偱惌尃偦偺傕偺偑傕偨側偄偩傠偆丅
仭俵仌俙偲偄偆戝媊柤暘偱拞崙婇嬈偺宱塩幰偼崙傪尒幪偰奀奜偵乬崅旘傃乭
傑偨丄柉娫婇嬈偺宱塩幰偼懕乆偲奀奜偵扙弌偟偰偄傞丅7寧28擔偺乽拞崙怴暦栐乿偵傛傞偲丄2016擭偵擖偭偰偐傜偺拞崙婇嬈偵傛傞奀奜婇嬈偺俵仌俙(崌暪丒攦廂)憤妟偼栺15挍墌偵払偟丄偡偱偵15擭捠擭偺栺11挍墌傪忋夞偭偨偲偄偆丅
偩偑丄偦偺戝敿偼幚偼乬奀奜摝朣帒嬥乭偱偁傞丅偮傑傝丄俵仌俙偲偄偆柤栚偱偁傟偽丄婇嬈偺崙嵺壔偲偄偆偙偲偱惌晎偑擣傔偰偔傟傞丅偩偐傜宱塩幰偨偪偼暷崙偺搳帒嬧峴側偳偑帩偪崬傫偩俵仌俙埬審偵旘傃偮偒丄偣偭偣偲帒嬥傪奀奜偵帩偪弌偟偰偄傞偺偩丅
偐偮偰偼擔杮婇嬈偼媫寖側墌崅傗壵楏側杅堈杸嶤偵捈柺偟偨帪丄昁巰偵惗嶻惈傗晅壛壙抣偺岦忋丄僐僗僩嶍尭側偳偺僀僲儀乕僔儑儞傪廳偹偰惗偒巆偭偨偑丄拞崙偺宱塩幰偼偡偱偵崙傪尒幪偰偰奀奜偵乬崅旘傃乭偟偰偄傞傢偗偩丅
埲忋傪憤崌偡傞偲丄拞崙宱嵪偑崗乆偲攋嬊偵嬤偯偄偰偄傞偙偲偼柧傜偐偩傠偆丅
偱偼丄偙傟偐傜拞崙偼偳偆側傞偐丠偙傟傕16擭2寧偵婛偵彂偄偨傛偆偵丄拞崙宱惌晎偑恖審旓傪巗応偵埾偹偢偵嫮惂揑丒恖堊揑偵枅擭15亾偢偮堷偒忋偘偰偒偨偣偄偱拞崙婇嬈偺嫞憟椡偼掅壓偟偨偺偩偑丄偩偐傜偲偄偭偰捓壓偘偼恖柉偺斀敪偑晐偄偐傜偱偒側偄丅
偲側傞偲偍偺偢偲堊懼偼尦埨偵岦偐偆偺偱丄曄摦憡応偵偡傞偟偐側偔側傞丅曄摦憡応惂偵偟偨傜堦婥偵尦埨偑恑傒丄尰嵼偺1僪儖亖6丏6尦偑敿暘偺1僪儖亖13尦偖傜偄傑偱壓偑傜偞傞傪摼側偄偩傠偆丅偦偆側傟偽桝弌嫞憟椡偼夞暅偡傞偐傕偟傟側偄偑丄宱嵪偼僴僀僷乕僀儞僼儗偵側偭偰恖柉偺惗妶偼崲媷偡傞丅
拞崙宱嵪偑攋抅偡傟偽丄悽奅宱嵪偼戝崿棎偡傞丅傕偟偐偡傞偲丄1929擭摉帪偺怴嫽宱嵪戝崙暷崙偺僶僽儖曵夡偑堷偒婲偙偟偨戝嫲峇偺傛偆側忬嫷偵側傞偐傕偟傟側偄丅
偨偩擔杮偼丄僆乕僗僩儔儕傾傗僽儔僕儖側偳偺帒尮崙偵斾傋傟偽懳拞桝弌偵埶懚偟偰偄側偄偟丄尦埨偵傛偭偰拞崙偐傜桝擖偟偰偄傞怘椏昳丄揹婥惢昳丄堖椏昳側偳偑埨偔側傝丄拞崙偵恑弌偟偰偄傞擔杮婇嬈偺僐僗僩嫞憟椡傕嫮偔側傞偐傜丄擔杮偵偲偭偰偼儅僀僫僗傛傝傕僾儔僗偺傎偆偑戝偒偄偩傠偆丅
丂 |
仭嫟嶻搣僣乕僩僢僾偑偙偙傑偱懳棫偡傞偺偼嬤擭捒偟偄丂2016/7
丂廗嬤暯倴倱棝崕嫮丂拞崙峴惌偺尰応偑崿棎偟偰偄傞
乽撿堾偲杒堾偺憟偄偵姫偒崬傑傟偰戝曄偩乿丅7寧拞弡丄媣乆偵夛偭偨拞崙嫟嶻搣偺拞寴姴晹偑偙偆楻傜偟偨丅杒嫗巗拞怱晹偺惌帯偺拞悤丄拞撿奀抧嬫偵偼丄撿懁偵搣拞墰偺寶暔丄杒懁偵崙柋堾(惌晎)偺寶暔偑偁傞丅搣姴晹傜偼嵟嬤丄廗嬤暯憤彂婰(崙壠庡惾)偲棝崕嫮庱憡偺宱嵪惌嶔側偳傪傔偖傞懳棫偵偮偄偰丄朻摢偺傛偆側塀岅偱昞尰偟偰偄傞偲偄偆丅
崙桳婇嬈傪曐岇偟丄宱嵪偵懳偡傞嫟嶻搣偺庡摫傪嫮壔偟偨偄廗巵偲丄婯惂娚榓傪恑傔偰柉娫婇嬈傪堢偰偨偄棝崕嫮巵偺娫偱丄埲慜偐傜偡偒傑晽偑悂偄偰偄偨偑丄嵟嬤偵側偭偰懳棫偑杮奿壔偟偨偲偺尒曽偑偁傞丅
峕戲柉巵偺帪戙偼庱憡偺庨鐿婎巵丄層嬔煼巵偺帪戙偼庱憡偺壏壠曮巵偑宱嵪塣塩傪庡摫偟偨傛偆偵丄僩僢僾偺搣憤彂婰偑搣柋偲奜岎丄庱憡偑宱嵪傪扴摉偡傞栶妱暘扴偼埲慜偐傜偼偭偒傝偟偰偄偨丅偟偐偟嵟嬤丄尃椡彾埇傪恑傔偨偄廗嬤暯巵偑宱嵪暘栰偵愊嬌揑偵夘擖偡傞傛偆偵側偭偨偙偲偱丄扤偑宱嵪惌嶔傪庡摫偟偰偄傞偺偐尒偊偵偔偄忬懺偵側偭偨偲偄偆丅
搣婡娭巻丄恖柉擔曬偑5寧9擔晅偱宖嵹偟偨偁傞僀儞僞價儏乕婰帠偑戝偒側攇栦傪屇傫偩丅乽尃埿幰乿傪柤忔傞摻柤偺恖暔偑丄乽崱擭慜婜偺宨婥偼椙岲乿偲偡傞棝庱憡偺尒夝傪恀偭岦偐傜斲掕偟丄乽(偙偺傑傑側傜)拞崙宱嵪偼亀倁帤夞暅亁傕亀倀帤夞暅亁傕側偔亀俴帤宆亁偑懕偔乿偲庡挘偟丄捝楏偵斸敾偟偨丅
嫟嶻搣嵟崅巜摫晹撪偱彉楍2埵偺棝庱憡傪偙偙傑偱斲掕偱偒傞偺偼彉楍1埵偺廗庡惾偟偐偄側偄偲偺娤應偑峀偑傝丄乽廗庡惾杮恖偑僀儞僞價儏乕傪庴偗偨偺偱偼側偄偐乿偲偺尒曽傕堦帪晜忋偟偨丅
暋悢偺嫟嶻搣姴晹偵妋擣偟偨偲偙傠丄乽尃埿幰乿偼廗庡惾偺懁嬤丄棲掃丒搣嵿宱巜摫彫慻帠柋嬊挿偱偁傞偙偲偼偺偪偵柧傜偐偵側偭偨丅偟偐偟丄僀儞僞價儏乕偺撪梕偼廗巵偺峫偊偱偁傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅嵟嬤偺姅壙偺壓棊傗宨婥掅柪偺尨場偼丄棝庱憡偺宱嵪塣塩偺幐攕偵傛傞傕偺偩偲峫偊偰偄傞廗庡惾偼丄廃曈偵棝庱憡傊偺晄枮傪昿斏偵楻傜偟偰偄傞偲偄偆丅
廗庡惾偼7寧8擔丄杒嫗偱乽宱嵪忣惃偵偮偄偰偺愱栧壠嵗択夛乿傪庡嵜偟偨丅宱嵪妛幰傜傪廤傔丄帺傜偑採彞偟偨怴偟偄僗儘乕僈儞乽僒僾儔僀僒僀僪(嫙媼懁)廳帇偺峔憿夵妚乿偵偮偄偰択榖傪敪昞偟偨丅棝庱憡偼偙偺擔丄杒嫗偵偄偨偑夛媍偵嶲壛偟側偐偭偨丅嫟嶻搣姴晹偼乽乬棝庱憡奜偟乭偼偙偙傑偱棃偨偺偐乿偲嬃偄偨偲偄偆丅
偦偺3擔屻偺11擔丄崱搙偼棝庱憡偑乽宱嵪忣惃偵偮偄偰偺愱栧壠丒婇嬈壠嵗択夛乿偲偄偆傎偲傫偳摨偠柤慜偺嵗択夛傪庡嵜偟偨丅帺傜偺帩榑偱偁傞乽婯惂娚榓偺廳梫惈乿側偳偵偮偄偰婎挷島墘傪峴偭偨丅
棝庱憡廃曈偵嬤偄搣娭學幰偵傛傞偲丄棝庱憡偼廗庡惾偵戝偒側晄枮傪帩偭偰偍傝丄帺暘偑庡摫偡傞宱嵪夵妚偑偆傑偔偄偭偰偄側偄偺偼丄廗巵偵傛傞夘擖偑尨場偩偲峫偊偰偄傞偲偄偆丅
嫟嶻搣偺僣乕僩僢僾偑偙偙傑偱懳棫偡傞偙偲偼嬤擭偱偼捒偟偄丅乽揤偺惡乿偑2偮偁傞偙偲偱丄峴惌偺尰応偱戝偒側崿棎偑惗偠偰偄傞偲偄偆丅8寧偵壨杒徣偺旔弸抧偱奐偐傟傞搣偺廳梫夛媍丄杒懻壨夛媍偱丄搣挿榁偨偪偑2恖偺娫偵擖傝丄宱嵪惌嶔偺挷惍偑峴傢傟傞偲傒傜傟丄峴曽偑拲栚偝傟傞丅丂 |
|
丂 |
| 仭尰戙擔杮丂億僺儏儕僘儉偺彅憡 |
   丂
丂
|
仭嫶壓巵偺億僺儏儕僘儉丂2012/8
億僺儏儕僘儉偼椙偄嬁偒傪帩偮尵梩偱偼偁傝傑偣傫丅晛捠偼乽戝廜寎崌乿偲栿偝傟傞傛偆偵丄戝嬊揑丄挿婜揑懝摼傪峫偊偢丄偦偺帪揰偱懡悢偺恖偵庴偗擖傟傜傟傞惌嶔傪宖偘傞丅栚揑偼戝廜揑恖婥傪摼偰尃椡傪妉摼偡傞偙偲丅崙柉偺偙偲傛傝帺暘偺偙偲偟偐寢嬊偼峫偊偰偄側偄丅億僺儏儕僗僩偲惌帯壠傪屇傇偺偼丄嫮偄旕擄傪偙傔偰偄傞偺偼娫堘偄偁傝傑偣傫丅
嵟嬤丄嫶壓戝嶃巗挿偵懳偟億僺儏儕僗僩偲偄偆斸敾偑弌偰偄傑偡丅恖栚傪堷偔僥乕儅偱僗僞儞僪僾儗乕傪孞傝曉偡偑恖婥庢傝埲忋偺傕偺偱偼側偄丄偲偄偆偺偑斸敾偺棟桼偱偡丅帹栚傪廤傔傞偙偲偺懡偄嫶壓巵偱偡偑丄撉攧怴暦庡昅搉曈峆抝巵偼嵟嬤偺挊彂丄偦偺柤傕乽斀億僺儏儕僘儉榑乿偱嫶壓巵傪億僺儏儕僗僩偺揟宆偲埵抲晅偗偰偄傑偡丅
偲偙傠偑摉偺嫶壓巵偼億僺儏儕僘儉偵偦傟傎偳斲掕揑側僀儊乕僕傪帩偭偰偄側偄傛偆偱偡丅嫶壓巵偼僣僀僢僞乕偺拞偱師偺傛偆偵尵偭偰偄傑偡丅
乽偟偐偟惌帯峴惌偺杮幙偼懡悢偺堄尒偱恑傔傞偙偲偩丅億僺儏儕僘儉偲寉曁偝傟傛偆偑側傫偱偁傠偆偑丄柉庡惂偲偼偦偆偄偆傕偺偩丅偦傟偑寵側傜丄柉堄傪寉曁偡傞丄尗恖惌帯偵偡傞偟偐側偄丅偦傫側惌帯偼傑偭傄傜偛傔傫偩丅尗恖側偳偄傞傢偗偑側偄丅柉庡惂偼姰傌偒偱偼側偄偑偦傟偵懼傢傞惌懱偼側偄丅乿
幚偼億僺儏儕僘儉傪乽戝廜寎崌乿偲栿偡偺偼丄惌帯妛揑側堄枴偱偼惓偟偔偼偁傝傑偣傫丅妛栤揑偵偼億僺儏儕僘儉偼摿掕偺僄儕乕僩丄尃椡幰偑崙柉傪棪偄偰偄偔乽僄儕乕僩庡媊乿偲懳斾偝傟偰乽戝廜庡媊乿乽恖柉庡媊乿偲偡傞偺偑晛捠偱偡丅
嫶壓巵偼傑偝偵偦偺乽斀僄儕乕僩庡媊乿偲偟偰億僺儏儕僘儉偲偄偆尵梩傪庴偗巭傔偰偄傞傛偆偱偡丅嫶壓巵偼摨偠偔僣僀乕僞乕偺拞偱丄乽僀儞僥儕乿偲屇偽傟傞恖払偵塻偄斸敾傪梺傃偣傑偡丅椺偊偽丄嫶壓巵偼暥妝傊偺曗彆傪戝嶃巗偑尭妟偡傞偙偲傪専摙偟偰偄傞偙偲偵懳偟丄乽嫶壓巗挿偼揱摑寍擻傪棟夝偟偰偄側偄乿偲尵傢傟偨偙偲偵斀敪偟偰師偺傛偆偵弎傋偰偄傑偡丅
乽暥妝偵偮偄偰慺杙側媈栤傪傇偮偗傞偲丄偄傢備傞帺徧僀儞僥儕憌偑丄暥妝偺偙偲傪暘偐偭偰偄側偄両両揱摑寍擻傪暘偐偭偰偄側偄両両偲棃傞丅庱挿傗峴惌儅儞丄偦偟偰帺徧僀儞僥儕憌偼暥壔壒抯偲偄偆斸敾丄偙偺尵梩偑堦斣寵側傫偩偹丅偩偐傜暥壔偼戝愗偩丄暥妝偼廳梫偩偲偟偐尵傢側偔側傞丅乿
嫶壓巵偼乽僀儞僥儕乿偑條乆側宍偱娤擮榑偱惌嶔偺斸敾傪偡傞偙偲傪寖偟偔峌寕偟傑偡丅嫶壓巵偺拞偵偁傞偺偼丄惌帯偼堦晹偺抦幆恖丄儅僗僐儈偑柍抦側堦斒戝廜傪乽慞摫乿偡傞偙偲偱峴傢傟傞傋偒偱偼側偔丄尰幚揑側幚柋傪峀偔崙柉堦斒偺栚慄偱峴偆傋偒偩丄偲偄偆嫮偄怣擮偺傛偆偱偡丅
乽寢嬊怴暦側偳偵婑偣傜傟傞帺徧僀儞僥儕憌偺堄尒偼丄崙柉憤悢偐傜偡傞偲傎傫偺彮偟偺堄尒側偺偵丄怴暦巻柺偵偼懡偔傪愯傔傞丅偄傢備傞僨儌偲帡偰偄傞丅怴暦偺帺徧僀儞僥儕憌偺堄尒偑丄崙柉戝懡悢偺堄尒偩偲尒岆傞偲偊傜偄栚偵憳偆丅傕偪傠傫丄悢偩偗偑慡偰偱偼側偄偙偲偼暘偐偭偰偄傞丅乿
嫶壓巵偺柕愭偼昡榑壠揑側乽僀儞僥儕乿憌偩偗偱偼偁傝傑偣傫丅抧曽偵懳偡傞拞墰惌晎偵懳偟偰丄摴廈惂偵傛傞抧曽傊偺戝暆側尃尷堏忳傪媮傔偰偄傑偡丅偙傟偼丄拞墰偺惌帯壠丄姱椈偲偄偆擔杮偺僄儕乕僩憌偵懳洺偡傞杮棃偺堄枴偺億僺儏儕僘儉揑庡挘偲尵偆偙偲偑偱偒傑偡丅
嫶壓巵偵偲偭偰丄億僺儏儕僘儉偙偦柉庡庡媊偺杮幙偱偡丅惌帯偼堦晹偺僄儕乕僩偺傕偺偱偼側偄丅摉傝慜偺偙偺峫偊傪乽僀儞僥儕乿偼抦揑側橖枬偝偱丄撪怱偱偼斲掕偟偰偄傞丅斲掕偟偰偄傞偐傜偙偦揱摑寍擻丄暥妝傊偺曗彆嬥偺攑巭偲偄偆惌嶔寛掕僾儘僙僗傪乽暥壔傪棟夝偟偰偄側偄乿偲愗偭偰幪偰傛偆偲偡傞丅嫶壓巵偼偙偆峫偊偰偄傞傛偆偱偡丅
偙傟偼擔杮偺惌帯偺拞偱偐側傝儐僯乕僋側峫偊偲偄偆婥偑偟傑偡丅摨偠傛偆側懱惂懁偵懳偡傞挧愴偱傕丄埫偵乽堄幆偺崅偝乿傪屩傞懡偔偺巗柉塣摦壠傗丄乽巟攝偝傟傞懁乿偺棫応傪庢傞揱摑揑側幮夛塣摦壠偲偼惓斀懳偲尵偭偰傕椙偄偐傕偟傟傑偣傫丅
偟偐偟丄斀僄儕乕僩庡媊傪宖偘偰傕丄偦傟偩偗偱尰幚偺惌帯偑偱偒傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅嫶壓巵帺恎傕師偺傛偆偵巜揈偟偰偄傑偡丅
乽惌帯壠偑峴惌幚柋傪偱偒傞傢偗側偄丅偨偩偟棤傪曉偣偽丄姱椈慻怐偼丄崱傑偱偺傗傝曽傪戝偒偔曄偊傞偙偲偼偱偒側偄丄棙奞娭學幰丒婛摼尃幰傪怳傝愗傞偙偲偼偱偒側偄丄媍榑偑銹拝偟偨偲偒偵寛掕偱偒側偄丄惓夝偑暘偐傜側偄応崌偵偼崱傑偱傗偭偰偒偨偙偲傪摜廝偡傞丄偲側傞丅乿
嫶壓巵偺尵偆傛偆偵丄惌帯壠偼曽岦惈傪帵偟丄姱椈婡峔偑幚峴偡傞丅偙傟偼娙扨側偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅側偤側傜丄惌帯偼惌嶔傪朄棩偵偡傞偙偲偲丄幚峴偺偨傔偺梊嶼攝暘偑側偗傟偽婡擻偟傑偣傫丅偦偺擻椡側偟偱惌帯庡摫偲尵偭偰傕丄偦傟偼扨側傞妡偗惡偩偗偱偟偐側偄偺偱偡丅偦偟偰偦偺擻椡傪撈愯偡傞偙偲偱姱椈婡峔偼擔杮偺惌帯傪幚幙揑偵摦偐偟偰偒偨偺偱偡丅
嫶壓巵偺斀僄儕乕僩庡媊偑杮摉偺堄枴偺惌帯庡摫傪幚尰偟偰偄偔偙偲偑偱偒傞偐丅嫶壓巵偺壓偵廤傑偭偨乽堐怴偺夛乿偑丄夦偟偘側恖暔偺懡偄尵傢偽塆崌偺廜偩偭偨丄夁嫀偺怴惌搣偲杮摉偵堘偆偺偐丅偟偽傜偔尒庣偭偰偄偔昁梫偑偁傝偦偆偱偡丅丂 |
仭戝廜寎崌惌帯偑擔杮傪怚傫偱偄傞丂2012/9
丂亀斀億僺儏儕僘儉榑亁傪彂偄偨搉绯峆梇巵偵暦偔
乽廜嬸偺惌帯乿偲抐屌愴偆偲偄偆丄撉攧怴暦庡昅偵傛傞熡恎偺惌帯榑偲偼丅
仭悽偺拞偵億僺儏儕僘儉偑枲墑偟偰偄傞傛偆偱偡偑丅
亀峀帿墤亁偱偼戞榋斉偐傜丄億僺儏儕僘儉偵偮偄偰乽堦斒戝廜偺峫偊曽丄姶忣丄梫媮傪戙曎偟偰偄傞偲偄偆惌帯忋偺庡挘丄塣摦丅偙傟傪嬶尰偡傞恖乆傪億僺儏儕僗僩偲偄偆乿偲偄偆掕媊偑捛壛偝傟偨丅偟偐偟丄偙傟偱偼億僺儏儕僘儉偱偼側偔偰丄扨側傞柉庡庡媊偺掕媊傒偨偄偩丅側偤丄戝廜寎崌惌帯偲尵傢側偄偺偐丅嵟嬤丄挬擔怴暦偑乽柉庡庡媊傪抌偊捈偦偆乿偲戣偡傞幮愢偺拞偱丄扙尨敪僨儌偲偄偆捈愙柉庡庡媊傪楃巀偟偰偄傞丅偙傟偙偦乽億僺儏儕僘儉枩嵨乿偲尵偭偰偄傞傛偆側傕偺偩丅
仭1999擭偵傕挊彂亀億僺儏儕僘儉斸敾亁傪弌斉偟偰偄傑偡丅
億僺儏儕僘儉偵嫽枴傪帩偭偨偺偼愇嫶扻嶳尦庱憡偺塭嬁傕偁傞丅愇嫶偝傫偼傾儞僠億僺儏儕僗僩偩偭偨丅愴慜丄悽榑慡懱偑戝崙庡媊偵岦偐偭偰偄傞偲偒偵丄怉柉抧傪幪偰傛丄傓偟傠偄傜側偄偲庡挘偟偨丅帠幚丄擔杮偼孯帠椡傪巊偭偰怉柉抧傪摼丄寢壥揑偵攕愴偟丄愴屻偼怉柉抧傪幐偭偰捠彜崙壠偲偟偰暅嫽偵惉岟偟偨丅
嬱偗弌偟婰幰偺崰丄杔偼愇嫶揁偺嬤偔偵廧傫偱偄偰丄挬丄崙夛傑偱幵偵摨忔偝偣偰傕傜偭偨偙偲傕偁傞丅杔偼戝妛帪戙偼嫟嶻搣堳偱丄偦偺屻揮岦偟偨偑丄棟榑揑側婎慴偼愇嫶偝傫偨偪偺乽彫擔杮庡媊乿偩偭偨丅摉帪丄傑偝偵愇嫶偝傫偼億僺儏儕僘儉偺媡偵埵抲偟偰偄偨丅偦偺崰偼乽徍榓堐怴偺壧乿偑偼傗偭偰偄偰乧乧丅
仭惵擭彨峑偨偪偑岥偢偝傫偱偄偨偲偄傢傟傞乧乧丅
斵傜偼偙偺壧傪壧偄側偑傜屲丒堦屲帠審丄擇丒擇榋帠審傪婲偙偡丅10愡偁傞壧帉偺拞偵丄乽嵿敶晉傪屩傟偳傕幮鈒(偟傚偟傖偔)傪巚傆怱側偟乿偲偁傞丅尃椡偼晉偵閬傝崙壠傪巚偭偰偄側偄偲偟偰丄斵傜偼乽堐怴乿傊偲摦偔丅
晛捠偺恖偼堐怴偲偄偆尵梩傪暦偔偲柧帯堐怴傪楢憐偡傞偑丄杔偼丄巕偳傕怱偵婰壇偑慛柧側徍榓堐怴傪巚偭偰偟傑偆丅崱丄堐怴偲偄偊偽乽慞乿偺斖醗偱偲傜偊傜傟偰偄傞偑丄偦偙偑杔偺悽戙偲偺偢傟偩丅偩偐傜丄乽嫶壓揙偝傫丄戝嶃堐怴偲徍榓堐怴偼偳偆堘偆偺乿偲尵偄偨偔側傞丅
仭嫶壓戝嶃巗挿偺崙惌岦偗偺岞栺乽堐怴敧嶔乿偼億僺儏儕僘儉偺惌嶔偱偟傚偆偐丅
堐怴敧嶔偼丄偄偄偙偲傕尵偭偰偄傞丅柉庡搣偱傕帺柉搣偱傕偱偒側偐偭偨偙偲傪傗傞偲尵偄丄偍偐偟偄偙偲偼偍偐偟偄偲夵慞偵庢傝慻傕偆偲偟偰偄傞丅
媈栤傪帩偮偺偼丄徚旓惻傪慡晹抧曽惻偵偣傛偲偄偆偲偙傠丅偦偺戙傢傝丄抧曽岎晅惻岎晅嬥偼偄傜側偄偲偄偆偑丄尰幚揑偵柍棟偩丅斵偺廃傝偺僽儗乕儞偑埆偡偓傞丅僽儗乕儞偺堦恖偩偭偨戝慜尋堦偝傫偼尨巕椡偺愱栧壠偩偭偨偺偱嫶壓巗挿偵斸敾揑側暥復傪彂偄偰偄傞偑丄尨巕椡敪揹強傪壞応偩偗摦偐偣偲偄偆嫶壓巗挿偺敪尵偼丄尨巕楩偺峔憿偵懳偡傞柍抦偵傛傞傕偺偩丅廃傝偵偄傞恖娫偑丄恖婥庢傝偺偨傔偵丄斵偵扙尨敪丒斀徚旓憹惻偲惙傫偵尵傢偣傛偆偲偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丅斵偵偼桪廏側僽儗乕儞傪廤傔傞偙偲偑昁梫偩丅
仭尨敪傗徚旓惻傊偺庢傝慻傒曽偵傕億僺儏儕僘儉偑尒偰庢傟傞偺偱偡偐丅
偨偲偊偽丄扙尨敪偲堦岥偵尵偆偑丄尨敪偺壱摥傪拞巭偟偰傕丄偦偺屻傕椻媝偟懕偗側偔偰偼偄偗側偄丅偦偺旓梡傕朿戝偩丅偦偆偡傞傛傝傕丄嵟戝尷埨慡偵壱摥偝偣偰丄慜岦偒偵媄弍傪岦忋偝偣傞傎偆偑戝帠偱偼側偄偐丅偳偆偣愭偼側偄偺偩偲巚偆傛偆偵側傞偲丄堦強寽柦偵庢傝慻傓媄弍幰偑尭偭偰丄偐偊偭偰婋側偄丅
戝斞尨敪偱偼丄偡傋偰偺揹尮傪幐偭偨嵺偵尨巕楩傪椻媝偱偒傞帪娫偑丄嵞壱摥慜偼傢偢偐5帪娫偩偭偨丅拁揹抮偟偐側偐偭偨偐傜偩丅偦傟偑崱偼椻媝梡偺悈偺旛拁側偳偵傛偭偰丄慡揹尮偑幐傢傟偰傕16擔娫傕椻媝傪懕偗傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨丅摨偠傛偆偵夵慞偡傟偽丄嵅夑導偺尯奀尨敪偼婛愝偺揹尮傪幐偭偰傕65擔娫偵丄幁帣搰導偺愳撪尨敪偼104擔娫偵傑偱椻媝婜娫偑墑傃傞丅暉搰尨敪傪傔偖偭偰奺庬偺帠屘曬崘彂偑弌偰偄傞偑丄偄偢傟傕恖嵭偩偲寢榑偯偗偰偄傞丅恖嵭側傜恖娫偺椡偱杊偖偙偲偑偱偒傞偼偢偩丅
仭偱偼丄嵞惗壜擻僄僱儖僊乕傊偺揮姺傪偳偆昡壙偟傑偡偐丅
偨偲偊偽懢梲岝偵傛傞揹椡丅尨敪1婎暘偺懢梲岝僷僱儖偲偄偭偨傜丄搶嫗偺俰俼嶳庤慄偺撪懁慡懱偵憡摉偡傞柺愊偑昁梫偩偑丄偦傫側応強偼擔杮偵偼側偄丅偙偺慜丄懢梲岝揹椡傪1僉儘儚僢僩帪42墌偱攦偄忋偘傞偲崙夛偑寛傔偨偑丄偙傟偙偦傛偔峫偊傕偟側偄恖婥庢傝偺億僺儏儕僘儉偩丅壩椡敪揹偺僐僗僩偼1僉儘儚僢僩帪栺12墌偩偑丄擱椏戙偼偳傫偳傫忋偑偭偰偄傞丅儂儖儉僘奀嫭偱栤戣偑婲偒偨傜丄50墌偖傜偄偵僴僱忋偑偭偰偟傑偆偐傕偟傟側偄丅偙傟偵懳偟偰尨巕椡敪揹偼丄1僉儘儚僢僩帪栺9墌偱偱偒傞偺偩偐傜丄媄弍揑偵埨慡惈傪妋曐偟偨偆偊偱丄壱摥偟懕偗偨傎偆偑偄偄丅
仭徚旓惻憹惻偼柉庡搣撪偱傕摜傒奊偵側傝傑偟偨丅
憹惻斀懳偲尵偭偰偄傞偑丄憹惻暘偼壗偵巊傢傟傞偺偐丅庡偵幮夛曐忈旓偵巊傢傟傞偺偩丅
柉庡搣偺儅僯僼僃僗僩偵偁傞乽僐儞僋儕乕僩偐傜恖傊乿偼丄億僺儏儕僘儉偺徾挜偲偟偰屻悽偵巆傞尵梩偱偼側偄偐丅妋偐偵帺柉搣惌尃偼丄憡摉検偺岞嫟帠嬈傪恑傔偨丅怴姴慄傪憿偭偨傝丄崅懍摴楬傪憿偭偨傝丅傑偨丄岞嫟帠嬈偲偟偰揤嵭懳嶔傕峴偭偰偒偨丅帺柉搣偺傗偭偰偒偨偙偲偵斸敾偼偁傞偩傠偆偑丄偙傟傜傪傗偭偰偙側偐偭偨傜丄崱偳偆側偭偰偄偨偐丅
仭億僺儏儕僘儉偑枲墑偡傞拞偱偺怴暦偺栶妱偼壗偱偡偐丅
怴暦偼丄岆偭偨惌嶔傪悇偟恑傔傞惃椡傗晄惓傪斊偟偨幰傪偨偩偟偰偄偔丅斸敾偡傞応崌偼丄朄棩傗幮夛忢幆丒摴摽傪摜傑偊丄榑棟揑丒懱宯揑偵峴傢側偗傟偽側傜側偄丅怴暦偵偼丄偦傟偑偱偒傞丅彫慖嫇嬫惂偲儅僯僼僃僗僩帄忋庡媊偑丄擔杮偺惌帯傪寛掕揑偵埆偔偟偨丅偙傟傜偲偺寛暿偑丄億僺儏儕僘儉惌帯偐傜扙偡傞偨傔偵偼愨懳昁梫偩丅
仭乽拞宆楢棫惌尃乿傪悇彠偟偰偄傑偡丅
擔杮偺惌帯偑乽廜嬸惌帯乿偵懧偪偰偄偔偺傪怘偄巭傔傞偺偵丄偦傟埲奜偺摴偼偁傞偩傠偆偐丅彮側偔偲傕僊儕僔儍丄僗儁僀儞偼戝幐攕傪偟偨丅尨場偼億僺儏儕僘儉偩丅偙偺杮偱僊儕僔儍婋婡傪庢傝忋偘偨偺偼丄揟宆揑側戝廜寎崌惌帯偑偦偺尨場偩偭偨偐傜偩丅
擔杮傕怴偟偄惌帯偺曽岦偵峴偗偽挏棊偼柶傟傞丅柉庡搣偲帺柉搣偑丄戞擇偺曐庣崌摨偺偮傕傝偱堦偮偺惌搣偵側傞偙偲偩丅帺柉搣偲偺楢棫偱惌尃搣偲偟偰偺宱尡傪愊傫偱偒偨岞柧搣傕丄楢棫惌尃偵壛傢傞擻椡偑偁傞丅丂 |
仭擔杮偼乽億僺儏儕僘儉(戝廜寎崌)宆惌帯乿偐傜扙媝偡傋偒両丂2012/12
仭億僺儏儕僘儉惌搣乽擔杮堐怴偺夛乿偼乽戞擇柉庡搣乿偱偁傞
崱夞偺廜媍堾慖嫇偺摿挜偼丄怴搣寢惉傗惌奅M仌A偑婲偙傝丄惌搣偑棎棫偟偨偙偲偑嵟戝偺摿挿偱偡丅
摿偵丄乽擔杮堐怴偺夛乿偼乽栰崌偺僨僷乕僩乿偲徧偝傟偰偄傞捠傝丄乽扙尨敪乿傪宖偘傞嫶壓巵偲乽尨敪悇恑乿傪宖偘傞愇尨巵偑抪偢偐偟偘傕側偔丄乽惌嶔偑堦抳乿偟偨偲敪昞偟丄栰崌偟偨偙偲偼暚斞暔偱偡丅
擔杮堐怴偺夛偺杮幙偼丄柉庡搣偲摨偠乽棟擮側偒婑崌偄強懷乿偱偁傝丄惌嶔偑堦抳偟側偄幰摨巑偑乽晽乿偵忔偭偰媍惾傪妉摼偡傞偨傔偵廤傑偭偨乽栰崌惌搣乿偺嬌傒偱偁傝丄柉庡搣偲摨偠偔丄撪晹暘楐偼晄壜旔偱偡丅
幚嵺丄擔杮堐怴偺夛偺岓曗幰偼丄乽晽乿偵忔傞偨傔偵丄乽偳偺搣偵擖偭偨傜摉慖偱偒傞偐乿偲偄偭偨帺暘偺惌帯惗柦傪墑柦偝偣傞偨傔偺敾抐偱惌搣傪搉傝曕偄偰偄傞乽惌奅搉傝捁乿偨偪偑彮側偔偁傝傑偣傫丅
擔杮堐怴偺夛偼丄愇尨巵側偳乽曐庣偺婄乿傪慜柺偵墴偟弌偟偰偄傑偡偑丄幚嵺偼丄尦幮夛搣丄尦柉庡搣側偳偺摨榓宯傗楯慻宯丄奜崙恖嶲惌尃巀惉媍堳傕彮側偔偁傝傑偣傫丅
偡側傢偪丄乽擔杮堐怴偺夛乿偼乽柉庡搣乿偺娕斅傪偡偘懼偊偨丄扨側傞乽戞擇柉庡搣乿偵夁偓側偄偺偱偡丅
仭乽戝廜寎崌偺惌帯暥壔乿偐傜偺扙媝傪両
嫗搒戝妛丒嵅攲孾巚嫵庼偼丄11寧22擔嶻宱怴暦偺乽惓榑乿偱丄乽彫戲堦榊巵偵傛傞帺柉搣棧扙偐傜偼偠傑傞惌帯夵妚偼丄帺柉搣偵曄傢傞擇戝惌搣惌帯傪彞偊丄偦偺偙偲偵傛偭偰柉堄傪斀塮偡傞乿偙偲傪偹傜偭偨傕偺偱偁傞偲巜揈偟偰偄傑偡丅
偟偐偟丄乽柉堄傪斀塮偡傞惌帯乿偺棳傟偼丄擔杮偱偼乽億僺儏儕僘儉乿偵娮傝丄乽戝廜寎崌偺惌帯暥壔乿偺埆偟偒晽廗偑弌棃忋偑偭偰偟傑偄傑偟偨丅
偦偺徾挜偑丄堦晹偺儅僗僐儈偑曬摴偡傞乽崙柉偺憤堄偲偟偰偺扙尨敪乿偱偡丅
帺柉搣丒埨攞憤嵸偱偝偊丄昜偑尭傞偙偲傪嫲傟偰乽尨敪偺惌嶔乿偵偮偄偰偼偭偒傝尵偆偙偲偝偊弌棃傑偣傫丅偦傟偱偼偳偙傊崙柉傪摫偄偰偄偔偺偐偝偊丄晄埨偵側傝傑偡丅
仭惌帯壠偼惌嶔傪崙柉偵偟偭偐傝愢柧偣傛両
偦偆偟偨堄枴偱偼丄岾暉幚尰搣偼乽尨敪悇恑乿傪偼偭偒傝偲懪偪弌偟丄扙尨敪偑傕偨傜偡宱嵪偺杤棊傗崙杊柺偐傜尒偨尨敪悇恑偺棟桼傪崙柉偺奆條偵愢柧偟偰偄傑偡丅
惌帯壠偵昁梫側偙偲偼丄戝廜偵寎崌偡傞偙偲偱偼側偔丄偦偺戝廜偑慖傫偩慖戰偑晄岾傪媦傏偡偲偒偵偼丄偟偭偐傝偲愢柧偟丄帪偵偼媡晽傪撍偄偰惌嶔傪抐峴偡傞桬婥偑昁梫偱偡丅
愄偺惌帯壠偵偼丄娸怣夘尦憤棟偺傛偆偵丄戝婯柾側僨儌戉偵傛偭偰庢傝埻傑傟丄搳愇偲嫟偵乽娸傪嶦偣両乿偲偄偆搟崋偵曪傑傟傛偆偲傕丄乽愮枩恖偲偄偊偳傕屷墲偐傫乿偲偄偆抐屌偨傞婥奣偱擔暷埨曐夵掕傪惉偟悑偘偨傛偆側曽偑偄傑偟偨偑丄崱偺惌帯壠偵偦偺傛偆側恖暔偼尒摉偨傝傑偣傫丅
仭儅僗僐儈偑偮偔傝偁偘偨乽恖婥庡媊乿偲偺寛暿傪両
傑偨丄慜弌偺嵅攲孾巚嫵庼偼丄偙偆傕巜揈偟傑偡丅乽惌帯偼丄儅僗僐儈儊僨傿傾傪捠偟偨恖婥庡媊偵戝偒偔嵍塃偝傟傞偙偲偵側偭偨乿偲丅
惌嶔偼擇偺師偱丄尰嵼偺擔杮偺乽惌帯暥壔乿偼丄儅僗僐儈偑壒摢傪庢偭偨乽恖婥幰乿偑摉慖偡傞嬻婥偑弌棃忋偑偭偰偟傑偄傑偟偨丅
岾暉幚尰搣偼乽戝廜寎崌乿偱偼側偔丄惓乆摪乆偲擔杮崙柉偺岾暉丄擔杮宱嵪偺敪揥傪偳偺傛偆偵偮偔傞偺偐丄恀偭岦偐傜惓榑傪慽偊偰偄傑偡丅
崙柉偺奆條偵偼丄儅僗僐儈偑嶌傝忋偘偨乽恖婥乿偱偼側偔丄岾暉幚尰搣偺乽惓榑乿偙偦偑崙柉傪恀偵岾暉偵偡傞偙偲傪惀旕偛棗捀偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂 |
仭彫愹弮堦榊偺擔杮宆億僺儏儕僘儉
戝浽廏晇巵偼乽擔杮宆億僺儏儕僘儉乿偺僠儍儞僺僆儞偲偟偰偺彫愹弮堦榊傪丄傾儊儕僇偺儗乕僈儞尦戝摑椞偲斾妑偟側偑傜峫嶡偟偰偄傞丅傕偭偲傕偙偺杮(乽擔杮宆億僺儏儕僘儉乿拞岞怴彂)偑彂偐傟偨偺偼2003擭5寧埲慜偺偙偲偱偁傝丄彫愹偼庱憡偲偟偰擟婜敿偽偱偁偭偨忋偵丄斵偺億僺儏儕僗僩偲偟偰偺摿挜偼丄2005擭偺梄惌柉塩壔慖嫇偺嵺偵傕偭偲嬅弅偝傟偨宍偱敪婗偝傟偨偙偲偐傜偡傟偽丄拞娫揑側憤妵偲偟偰偺尷奅傪帩偨偞傞傪摼側偄偲偙傠偩偑丄偦傟偱傕丄彫愹偑懱尰偟偰偄偨擔杮宆億僺儏儕僘儉偺摿挜傪傛偔懆偊偰偄傞偲偄偊傞丅
億僺儏儕僘儉偵偼擇偮偺僞僀僾偑偁傞偲巵偼偄偆丅壓偐傜偺億僺儏儕僘儉偲忋偐傜偺億僺儏儕僘儉偱偁傞丅壓偐傜偺億僺儏儕僘儉偼傾儊儕僇偺惌帯揑側揱摑偺拞偱丄恖柉搣側偳丄柉廜偺堄巚傪懱尰偡傞塣摦偲偄偆宍傪偲偭偨丅偦傟偼墲乆偵偟偰丄戝廜寎崌揑側怓嵤傪懷傃傞丅堦曽忋偐傜偺億僺儏儕僘儉偼儔僥儞傾儊儕僇偺楌巎偵偍偄偰丄戝廜揑巟帩傪摼偨尃埿庡媊懱惂偲偟偰尰傟偨偺偑揟宆揑側椺偱偁傞丅偦傟偼愵忣揑側戝廜摦堳偲偄偆怓嵤傪懷傃傞揰偱丄僼傽僔僘儉偲偺嬤墢惈傪姶偠偝偣傞偙偲傕偁傞丅妛幰偵傛偭偰偼丄偙偺宍偺億僺儏儕僘儉傪僨儅僑僊乕偲屇傇幰傕偄傞丅
偙偺椉幰偺億僺儏儕僘儉偼嬤擭師戞偵廂澥偟偮偮偁傞偲峫偊傜傟傞丅偦傟偼丄偄偢傟偺宍偺億僺儏儕僘儉傕師偺傛偆側摿挜傪嫟桳偟偰偄傞偙偲偐傜棃傞帺慠偺悥惃偩偲偄偊傞丅(偙傟傜偺摿挜偼丄傾儊儕僇偺惌帯妛幰働僀僕儞偺尋媶傪傕偲偵摫偒弌偝傟偨傕偺偱偁傞丅埲壓偼戝浽廏晇乽擔杮宆億僺儏儕僘儉乿偐傜堷梡)
"億僺儏儕僘儉偲偼丄乽晛捠偺恖乆乿偲乽僄儕乕僩乿丄乽慞嬍乿偲乽埆嬍乿丄乽枴曽乿偲乽揋乿偺擇尦榑傪慜採偲偟偰丄儕乕僟乕偑乽晛捠偺恖乆乿偺堦堳偱偁傞偙偲傪嫮挷偡傞偲摨帪偵丄乽晛捠偺恖乆乿偺懁偵棫偭偰斵傜傪儕乕僪偟丄乽揋乿偵岦偐偭偰愴偄傪挧傓乽僸乕儘乕乿偺栶妱傪墘偠偰傒偣傞丄乽寑応宆乿惌帯僗僞僀儖偱偁傞丅偦傟偼丄幮夛塣摦傪慻怐偡傞偺偱側偔丄儅僗丒儊僨傿傾傪捠偠偰丄忋偐傜丄惌帯揑巟帩傪挷払偡傞惌帯庤朄偺傂偲偮偱偁傞丅"
儘僫儖僪丒儗乕僈儞偼丄偙偙偱掕媊偝傟偨傛偆側億僺儏儕僗僩揑側惌帯僗僞僀儖傪懚暘偵敪婗偟偨惌帯壠偩偭偨丅斵偼傾儊儕僇恖偺戝懡悢傪愯傔傞乽晛捠偺恖乆乿偑惌帯揑偵柍帇偝傟偰偒偨偲岅傝丄斵傜傪柍帇偡傞惌帯揑側僄儕乕僩傪揋偲偟偰丄晛捠偺恖乆偺戙昞幰偲偟偰愴偆巔惃傪帵偟偨傢偗偱偁傞丅偙偆偟偨傗傝曽偼丄僽僢僔儏傗僋儕儞僩儞傕堷偒宲偄偩丅斵摍傕傑偨丄乽晛捠偺傾儊儕僇恖乿偲乽儚僔儞僩儞丒僄僗僞僽儕僢僔儏儊儞僩乿偲偺擇尦榑偵埶嫆偟偰丄峀斖側戝廜偺巟帩傪摦堳偟偨偺偱偁傞丅
偦偺儗乕僈儞偲斾妑偟側偑傜彫愹弮堦榊偺億僺儏儕僘儉偺摿幙傪暘愅偡傞偲師偺傛偆偵側傞丄偲巵偼偄偆丅
戞堦偵丄儗乕僈儞偺惌嶔偺幉偵側偭偰偄偨偺偼丄怴帺桼庡媊偱偁偭偨丅偡側傢偪丄彫偝側惌晎偲巗応傊偺怣棅偱偁傞丅彫偝側惌晎偼丄姱椈側偳偺婛懚偺僄儕乕僩惃椡傪揋偵偟偰丄晛捠偺傾儊儕僇恖偺棙塿傪庣傞偲偄偆庡挘偵偮側偑傞傕偺偩丅偦傟偵懳偟偰彫愹傕丅乽梄惌柉塩壔乿側偳偵娭偟偰丄彫偝側惌晎傪庡挘偟偨偑丄儗乕僈儞傎偳惌嶔偑柧妋偱偁偭偨傢偗偱偼側偄偲巵偼尵偆丅儗乕僈儞偺応崌偵偼丄揋偼姱椈偲暲傫偱楯摥慻崌側偳偺嵍梼惃椡偵傕岦偗傜傟偨揰偱丄塃梼揑側怓嵤偑嫮偐偭偨傢偗偩偑丄彫愹偵偼儗乕僈儞偲斾傋偰嵍梼偲偺懳寛巔惃偑庛偄偲偄偆傢偗偱偁傞丅偦傟偼彫愹偺棫応偑怴帺桼庡媊揑巚憐懱宯偺嶻暔偱偼側偔丄姱椈斸敾偲尰幚偺嵿惌婋婡偐傜敪偟偨傕偺偱偁傝丄嬶懱揑側張曽獬偺儗儀儖傪弌偰偄側偄偙偲偵傛傞偲偄偆丅
戞擇偵丄彫愹偺億僺儏儕僘儉偼儗乕僈儞偲斾傋偰愵忣揑側柺偑彮側偄偲偄偆丅儗乕僈儞偼傾儊儕僇偑恄偵傛偭偰慖偽傟偨崙偱偁傞偲偄偆傾儊儕僇恖摿桳偺廆嫵堄幆偵慽偊偐偗傞堦曽丄奜晹偺揋偺嫼埿傪嫮挷偟偰僫僔儑僫儕僘儉傪慀偭偨丅彫愹偵偼擔杮恖偺帺懜怱傪慀傞傛偆側億僕僥傿僽側梫慺偼彮側偔丄揋傪峌寕偡傞偩偗偺僱僈僥傿僽側億僺儏儕僘儉偲偟偰偺柺偑嫮偄偲偄偆丅
戞嶰偵丄摨偠寑応宆偺惌帯偲偄偭偰傕丄儗乕僈儞偲彫愹偵偼偐側傝側憡堘偑偁傞丅儗乕僈儞偼攐桪弌恎偲偄偆偙偲傕偁偭偰丄梇曎偱榖傕偆傑偔丄乽彈惈揑乿側僀儊乕僕傪暪偣帩偭偨儕乕僟乕偩偭偨丅彫愹偺曽偼丄懘傟偲偼懳徠揑偵壡栙偱丄抝惈揑側僀儊乕僕偑嫮偐偭偨丅傑偨儗乕僈儞偑戝廜偺巟帩傪妉摼偡傞偨傔偵擖擮偱壢妛揑側弨旛傪偟偰偄偨偺偵懳偟偰丄彫愹偵偼偦偺傛偆側搘椡偺宍愓偼尒傜傟側偄丅彫愹偼撍擛丄巚偄偑偗偢偵戝廜偺恖婥傪妉摼偟偨偺偱偁傞丅
偙偆偟偨憡堘偼丄彫愹帺恎偺僉儍儔僋僞乕偲傕戝偄偵娭學偟偰偄傞偩傠偆丅巵偼偦傫側彫愹傜偟偄偲偙傠傪偄偔偮偐拪弌偟偰偄傞丅
傑偢丄愭偺戞嶰偺揰偲娭楢偡傞偑丄彫愹偼壡栙偱丄壗傪峫偊偰偄傞偺偐傢偐傜側偄偲偙傠偑偁偭偨偲偄傢傟傞傛偆偵丄巚憐丒怣忦傪偲傜偊傞庤妡偐傝偵朢偟偄偺偱偁傞偑丄尵偆偙偲堊偡偙偲偑楺壴愡揑偩偲偄偆偺偱偁傞丅偙傟偼彫愹偺壠宯偲娭學偑偁傞偺偐傕偟傟側偄丅
楺壴愡揑偩偲偼丄媊棟恖忣偵撃偄偲偄偆偙偲偱偁傞偑丄彫愹偵偼偦偆偱偼側偄偲偙傠傕偁傞丅彫愹偼恖娫娭學偵偮偄偰偼堄奜偲僪儔僀側柺傪暪偣帩偭偰偄偨丅
師偵丄彫愹偼姶忣傪偐側傝僗僩儗乕僩偵昞尰偡傞惌帯壠偱偁傞丅媡偵尵偆偲丄姶忣傪僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偑嬯庤偱偁傞丅偦偺偨傔丄尵摦偵忣弿揑側怓嵤傪敽偭偨丅
偙偺偙偲偺棤曉偟偩偑丄彫愹偼暋嶨側幮夛尰徾傪丄拪徾揑側儗儀儖偱懱宯揑偵巚峫偡傞擻椡偑庛偄丅偦偺偨傔丄惌帯栤戣傪丄嬌傔偰扨弮側儗儀儖偱偲傜偊傞丅
彫愹偺帩偮偙偆偟偨乽楺壴愡揑乿丄乽姶忣揑乿丄乽扨弮乿偲偄偭偨摿幙偑丄戝廜庴偗偡傞庤抜偲偟偰婡擻偡傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅
嵟婜偵彫愹偺怣忦偵偮偄偰丅晛捠億僺儏儕僗僩偲屇偽傟傞傛偆側惌帯壠偼丄揱摑夞婣揑偱僞僇攈揑側僀儊乕僕偑嫮偄傕偺偩偑丄彫愹偼昁偢偟傕偦偆偱偼側偄丅廃曈彅崙偺斀敪傪柍帇偟偰桋崙恄幮偵嶲攓偟懕偗偨偙偲偼丄彫愹偺揱摑懜廳傪暔岅傞椺偩偲巚傢傟側偄偱傕側偄偑丄偦傟埲奜偺僀僔儏乕偱彫愹偑揱摑庡媊幰偩偭偨偲嫮偔巚傢偣傞傛偆側徹嫆偼側偄丅傑偨奜岎偺柺偱傕僞僇攈傇傝傪敪婗偟偨偲偄偆宍愓傕杦偳側偄丅偦偺曈偺偲偙傠傪憤妵偟偰丄巵偼師偺傛偆偵尵偭偰偄傞丅
"斵偺怣忦偵偼丄擔杮偺旤晽丄偁傞偄偼峜幒傊偺宧垽偲偄偭偨揱摑庡媊偺梫慺偼庛偄偟丄杊塹惌嶔偱傕丄嫵堢惌嶔偱傕偲偔偵塃梼揑偱偼側偄丅僺儖夝嬛傊偺斀懳傕曐庣惌帯壠偑偟偽偟偽埶嫆偟丄彞偊傞岞彉椙懎榑側偳揱摑庡媊傪崻嫆偲偡傞庡挘偱偼側偄丅偦偺堄枴偱丄斵偺僞僇攈揑庡挘偼丄崻偺愺偄傕偺偱偁傞丅 丂 |
仭戝廜寎崌惌帯偼戝偒側儕僗僋丂2015/10
惌帯偑戝廜寎崌揑(億僺儏儕僘儉)偵側傞偲宱嵪揑偵娫堘偭偨惌嶔偑峴傢傟傞椺偼懡偄丅婰壇偵怴偟偄偺偼暷崙偺儕乕儅儞丒僔儑僢僋帪偵丄乽僂僅乕儖奨傪媬偆偨傔偵惻嬥傪巊偆偺偼偗偟偐傜傫乿偲偄偆悽榑偵偍偝傟偰丄嬥梈埨掕壔朄埬偑斲寛偝傟偨丅屻偵嵞壜寛偝傟偨偑丄斲寛偝傟偨偙偲偱嬥梈惌嶔傊偺晄怣姶傕堦婥偵崅傑傝丄悽奅拞偐傜乽怣梡乿偲偄偆怣梡偑徚柵偟嬥梈婋婡偼攋柵揑側儗儀儖偵撍擖偟偨丅儕乕儅儞攋抅帪傛傝傕嬥梈埨掕壔朄斲寛帪偺曽偑姅壙側偳偺朶棊傗嬥梈巗応偺崿棎偼寖偟偐偭偨丅
擔杮偱傕僶僽儖曵夡帪偵乽弾柉偑壠傪攦偊側偔側傞偺偼偗偟偐傜傫乿偲偄偆悽榑傗儅僗僐儈偺憶偓偵偍偝傟偰丄媫寖側堷偒掲傔傪峴偭偨偙偲偱丄僶僽儖傪攋柵揑偵扏偒捵偡偙偲偵側偭偨丅偦偺屻偺嬥梈婡娭傊偺帒杮拲擖偵嵺偟偰傕丄暷崙偺儕乕儅儞丒僔儑僢僋帪偲摨偠偔丄乽惻嬥偱嬥梈婡娭傪媬偆偺偼偗偟偐傜傫乿偲偄偆惡偵偍偝傟偰帒杮拲擖偑抶傟丄僶僽儖曵夡偺塭嬁偑偝傜偵挿婜偵媦傇偙偲偵側偭偨丅
偦偺帪乆偺暤埻婥傗悽榑偵偍偝傟偰惌帯偺堄巚寛掕偑峴傢傟傞偲丄宱嵪揑偵偼戝偒偔娫堘偭偨偙偲偑峴傢傟傞儕僗僋偑偁傞丅
杮暔偺惌帯壠偲偼崙柉偵恖婥偑側偔偰傕丄崙塿傗彨棃揑側娤揰偐傜傒偰惓偟偄惌嶔傪幚峴偱偒傞惌帯壠偩丅傎偲傫偳偺柉庡庡媊崙壠偱捈愙柉庡惂偱偼側偔娫愙柉庡惂偑儊僀儞偺堄巚寛掕僔僗僥儉偲偟偰嵦梡偝傟偰偄傞偺偼丄堦帪偺擬嫸偱曃傞乽攺庤偲妳嵮乿偺惌帯偱偼側偔丄慖椙偵傛傞尗柧側敾抐偺傎偆偑寢壥偲偟偰惓偟偄慖戰偑偱偒傞偲偄偆楌巎揑側宱尡偵婎偯偔丅
億僺儏儕僘儉偵傛傞宱嵪揑偵岆偭偨惌嶔偑幚峴偝傟傞儕僗僋偼忢偵懚嵼偡傞丅惌帯壠偼崙柉偺恖婥偵側偄偙偲傪峴偭偨偙偲偱師偺慖嫇偱棊慖偡傞偙偲傪嵟傕嫲傟偰偄傞偐傜偩丅
嵟嬤偱偼擔杮偺徚旓憹惻偺寉尭惻棪榑媍偑偙傟偵偁偨傞偲偄偊傛偆丅怘椏昳摍偵寉尭惻棪傪揔梡偡傞庛幰傗掅強摼幰偵桪偟偄惌嶔偲偄偆偲暦偙偊偼傛偄偑丄僔僗僥儉僐僗僩傗嬈幰偺僐僗僩傪峫偊傞偲寢嬊崙柉偺晧扴偑憹偊傞壜擻惈偑偁傞丅傑偨丄寉尭惻棪傪揔梡偡傞慄堷偑擄偟偔丄棙尃偺壏彴偲側傝偙偺僐僗僩傕崙柉偵挼偹曉偭偰偔傞壜擻惈偑偁傞丅丂丂
傑偨丄暷崙偱僸儔儕乕丒僋儕儞僩儞巵偑TPP偵斀懳偟偨傝丄嬥梈巗応偺婯惂傪堷偒掲傔傛偆偲偟偰偄傞偺傕億僺儏儕僘儉偺揟宆偲偄偊傛偆丅廬棃偺庡挘傪嬋偘丄戝摑椞慖偱彑棙偟傛偆偲偟偰栚愭偺恖婥庢傝偺庡挘傪偟偰偄傞偺偼偄偨偩偗側偄丅
寢嬊丄惓偟偄惌嶔偑峴傢傟傞偨傔偵偼丄崙柉堦恖堦恖偑堦帪偺悥惃偵棳偝傟偨傝儅僗僐儈偺慀傝偵忔傜偢丄椻惷偵惓偟偄惌嶔傪峫偊偰峴摦偡傞昁梫偑偁傞偑丄偙傟偼偙傟偱旕忢偵擄偟偄偙偲偩丅
帪戙偑曄壔偟偰傕丄柉庡庡媊崙壠偺戝廜寎崌惌帯偼戝偒側儕僗僋偲偟偰懚嵼偟懕偗丄偙傟傪旔偗傞桳椡側庤抜偼尒摉偨傜側偄丅丂 |
仭寷朄夵惓偱帺塹戉偼乬暷崙偺億僠乭壔偡傞丠
仭3暘偺2偺媍惾傪妋曐偟偰夵寷惃椡偺摦偒偑杮奿壔
夵寷惃椡偑3暘偺2偺媍惾傪妋曐偟偨偙偲傪庴偗偰丄偵傢偐偵夵寷媍榑偑崅傑偭偰偄傑偡丅埨攞怶嶰庱憡偼乽寷朄怰嵏夛偱偺媍榑傪桪愭偡傞乿偲偄偄傑偡偑丄偡偱偵乽戞9忦乿傗乽嬞媫帠懺忦崁乿側偳偵偮偄偰徻嵶側夵寷憪埬傪嶌惉偟偰偄傞帺柉搣偑乬悢偺椡乭偱媍榑傪庡摫偟偰偄偔壜擻惈偑崅傑偭偰偄傑偡丅
帺柉搣偺乽擔杮崙寷朄夵惓憪埬乿偼偳偙偑偳偆栤戣側偺偱偟傚偆偐丠暷崙偺摨柨崙偱偁傞塸崙偑暷崙偲傕偵僀儔僋怤峌偵帄偭偨宱堒傪挷傋偰偒偨撈棫挷嵏埾堳夛(僕儑儞丒僠儖僐僢僩埾堳挿偺柤慜偐傜丄捠徧乽僠儖僐僢僩埾堳夛乿)偑2016擭7寧偵柧傜偐偵偟偨儗億乕僩傪摜傑偊丄戝慜尋堦偑夝愢偟傑偡丅
仭帺柉搣儁乕僗偺夵寷媍榑偼婋尟偩偑丄夵寷慡柺斲掕偼帪戙抶傟
仭乽廤抍揑帺塹尃乿傪崌寷壔偡傞偨傔偺帺柉搣9忦夵惓埬
塸崙偑暷崙偲偲傕偵2003擭偵僀儔僋怤峌偵嶲愴偟偨宱堒側偳傪専徹偟偰偄偨撈棫挷嵏埾堳夛(僠儖僐僢僩埾堳夛)偼2016擭7寧丄7擭娫偵傢偨傞挷嵏偺寢壥丄僩僯乕丒僽儗傾尦庱憡偺嶲愴敾抐傗寁夋嶔掕偵悢乆偺岆傝偑偁偭偨偲偡傞曬崘彂傪敪昞偟偨丅
偝傜偵曬崘彂偼丄僽儗傾庱憡偑奐愴8偐寧慜偺2002擭7寧丄暷崙偺僽僢僔儏戝摑椞(摉帪)偵乽壗偑偁偭偰傕嫤椡偡傞乿偲晲椡峴巊偱偺楢実傪彂娙偱妋擣偟偨偙偲傕柧傜偐偵偟偨丅梫偡傞偵丄僽儗傾尦庱憡偺寛掕揑側儈僗僥乕僋偼乬暷崙偺億僠乭偵側偭偨偙偲偩偭偨偺偱偁傞丅
偙傟偼埨攞庱憡傊偺寈崘偲尵偊傞偩傠偆丅廤抍揑帺塹尃偺峴巊傪梕擣偟丄懠崙孯偺屻曽巟墖偺偨傔偵帺塹戉傪偄偮偱傕奀奜偵攈尛偱偒傞傛偆偵偡傞埨慡曐忈娭楢朄偼丄傑偝偵乽暷崙偵偍嫙偟傑偡乿偲偄偆愰尵偱偁傝丄偦傟偑偄偐偵婋尟側偙偲偐丄忋弎偟偨曬崘彂偑擛幚偵暔岅偭偰偄傞偐傜偩丅
忢偵暷崙偑擔杮傛傝傕惓妋側忣曬傪帩偪丄惓偟偄敾抐傪偟偰偄傞偺側傜丄暷崙偵捛廬偡傞偺偼巇曽偑側偄偟丄搶惣椻愴帪戙偱偁傟偽惣懁恮塩偺堦堳偲偟偰偺媊柋傕偁偭偨偲巚偆丅偟偐偟丄忋弎偟偨曬崘彂傪懸偮傑偱傕側偔丄暷崙偑偙偺20擭娫偵僀儔僋傗傾僼僈僯僗僞儞側偳偱揥奐偟偰偒偨拞搶惌嶔偼丄偙偲偛偲偔娫堘偭偰偄偨丅偦傟埲慜偺楌巎傪怳傝曉偭偰傒偰傕丄儀僩僫儉愴憟偲偄偆戝偒側夁偪傪斊偟偨偟丄拞撿暷偱傕僷僫儅怤峌側偳偺儈僗僥乕僋傪廳偹偰斀暷惃椡傪憹傗偟偰偟傑偭偰偄傞丅
偦偆偄偆敾抐椡側偒暷崙偲栍栚揑側孯帠摨柨傪寢傏偆偲偄偆偺偑丄2015擭9寧偵巤峴偝傟偨埨曐娭楢朄偱偁傞丅
偦偟偰崱丄慿忋偵嵹偣傜傟傛偆偲偟偰偄傞帺柉搣偺寷朄夵惓憪埬偼丄愴憟曻婞傪鎼偭偨戞9忦傪埲壓偺傛偆偵曄偊傛偆偲偟偰偄傞丅
戞2復丂埨慡曐忈
戞9忦丂擔杮崙柉偼丄惓媊偲拋彉傪婎挷偲偡傞崙嵺暯榓傪惤幚偵婓媮偟丄崙尃偺敪摦偲偟偰偺愴憟傪曻婞偟丄晲椡偵傛傞埿奷媦傃晲椡偺峴巊偼丄崙嵺暣憟傪夝寛偡傞庤抜偲偟偰偼梡偄側偄丅
2丂慜崁偺婯掕偼丄帺塹尃偺敪摦傪朩偘傞傕偺偱偼側偄丅
偙偺夵惓偺慱偄偵偮偄偰帺柉搣偺乽擔杮崙寷朄夵惓憪埬俻仌俙憹曗斉乿偱偼埲壓偺傛偆偵夝愢偟偰偄傞丅傑偢丄尰峴寷朄偺戞9忦戞1崁偵偮偄偰偼暥復偺惍棟偺傒偲偡傞丅偝傜偵2崁偱乽愴椡偺晄曐帩乿摍傪掕傔偨婯掕傪嶍彍偟偨偆偊偱丄夵傔偰乽慜崁偺婯掕偼丄帺塹尃偺敪摦傪朩偘傞傕偺偱偼側偄乿偲偟偰帺塹尃傪柧帵丅乽偙偺亀帺塹尃亁偵偼崙楢寷復偑擣傔偰偄傞屄暿揑帺塹尃傗廤抍揑帺塹尃偑娷傑傟偰偄傞偙偲偼丄尵偆傑偱傕偁傝傑偣傫乿丅
偙傟傑偱偺楌戙撪妕偼丄乽廤抍揑帺塹尃偺峴巊偼寷朄戞9忦偱嬛偠傜傟偰偄傞乿傕偺偲偟偰夝庍偟偰偒偨丅埨攞庱憡偼偦偺夝庍傪曄峏偟丄廤抍揑帺塹尃偼尰峴寷朄偺壓偱傕摉慠擣傔傜傟傞偲偄偆偙偲偱埨曐娭楢朄傪惉棫偝偣偨丅
廬棃偺寷朄偱偼擣傔傜傟偰偄側偐偭偨傕偺傪丄夵寷偟偨忋偱朄棩偵傕斀塮偡傞偲偄偆棟孅側傜暘偐傞偑丄幚嵺偼丄怴偨偵巤峴偝傟偨朄棩偵崌傢偣偰寷朄傪廋惓偟傛偆偲偄偆偙偲偵側傞丅偮傑傝丄帺柉搣偼丄戞9忦夵惓偵傛偭偰埨曐娭楢朄傪寷朄偵斀塮偝偣傞偲偄偆乽屻晅偗乿偱惓摉壔偟傛偆偲偟偰偄傞偺偩丅偦偙偵偼僽儗傾尦庱憡偑斊偟偨夁偪傊偺斀徣傗丄暷崙偑夁嫀20擭娫孞傝曉偟偰偒偨娫堘偄偩傜偗偺拞搶惌嶔偵偮偄偰偺斀徣偼旝恛傕側偄丅偙傟偼偁傑傝偵傕搈愶偱婋尟偩偲巚偆丅
摿偵丄擔暷僈僀僪儔僀儞偱偼丄擔杮偼屻曽巟墖偡傞偲偄偭偰傕丄尰抧偵攈尛偝傟偨孯戉偼暷孯偺巌椷姱偺巜婗壓偵擖傞偙偲偵側偭偰偄傞丅偮傑傝丄傂偲偨傃愴抧偵晪偄偨応崌偼丄崙夛傕撪妕傕帺塹戉偺摑惂尃傪幐偆婋尟惈偑偁傞偺偩丅塸崙偺帒椏偵弌偰偔傞偙偆偟偨揰偺媍榑傕丄擔杮偱峴傢傟偰偄傞偺傪壡暦偵偟偰抦傜側偄丅
埨攞庱憡偼寷朄夵惓偵岦偗偰丄戞1師惌尃帪戙偵崙柉搳昜朄傪惉棫偝偣丄嶐擭埨曐娭楢朄傪嫮峴嵦寛偟偨丅偦偟偰丄崱壞偺嶲堾慖偱夵寷偺3暘偺2埲忋偺媍惾傪夵寷惃椡偱妋曐偟偨丅偙偺惃偄偱堦婥偵夵寷傊丄偲峫偊偰偄傞偐傕偟傟側偄偑丄乽俧僛儘乿帪戙偵側偭偨崱偙偦丄偄偭偨傫棫偪巭傑偭偰暷崙偲偺愴屻70擭傪嵞峫偟丄崙嵺幮夛偺拞偱擔杮偼偳偆偁傞傋偒偐偲偄偆偙偲傪丄傕偭偲恀潟偵媍榑偟側偗傟偽側傜側偄丅
傕偲傕偲埨攞庱憡偼乽愴屻儗僕乕儉偐傜偺扙媝乿傪庡挘偟偰偄偨丅偟偐偟丄暷崙偲偺娭學傪尒捈偡偙偲偺擄偟偝偵捈柺偟丄拞崙丄娯崙偲偺娭學埆壔傪宱偰丄寢嬊丄暷崙偵嶤傝婑偭偨丅2015擭4寧丄楢朚媍夛忋壓堾崌摨夛媍偺墘愢偱乽擔杮偵偲偭偰丄暷崙偲偺弌夛偄偲偼丄偡側傢偪柉庡庡媊偲偺憳嬾偱偟偨乿側偳偲帟偺晜偔傛偆側偍傋傫偪傖傜傪尵偭偨偺偼婰壇偵怴偟偄丅梫偡傞偵埨攞庱憡偼丄幚偼崢偑掕傑偭偰側偄偺偱偁傞丅偩偐傜尰嵼偺擔杮偺忬嫷偼丄側偍偝傜婋尟偲巚偆偺偱偁傞丅
仭乽嬞媫帠懺忦崁乿偼乽崙壠憤摦堳朄乿偺嵞棃偱婋尟
埨攞庱憡偼2014擭偺廜堾慖偲2016擭偺嶲堾慖偱崙柉偺怣擟傪摼偨偲偄偆丅幚嵺偼柉恑搣側偳偺栰搣偑帺柵偟偨偩偗偩偑丄慖嫇偱偺彑棙傪丄埨曐娭楢朄傗傾儀僲儈僋僗側偳偺乬嬔偺屼婙乭偵偟偰偄傞丅
幚偼偙偺傗傝曽偼丄偐偮偰偺僫僠僗丒僪僀僣偲摨偠偱偁傞丅僫僠僗偺傾僪儖僼丒僸僩儔乕傕崙柉偑崲媷偡傞拞偱幐嬈丒宨婥懳嶔傗堏柉攔愃傪慽偊丄慖嫇偺偨傃偵崙柉偺巟帩傪奼戝偟偰嫮戝偵側偭偰偄偭偨丅
帺柉搣偺寷朄夵惓偺憪埬偵惙傝崬傑傟偰偄傞夵寷偺徟揰偲側偭偰偄傞乽嬞媫帠懺忦崁乿(乽擔杮崙寷朄夵惓憪埬乿戞9復)偼丄傑偝偵僫僠僗傪渇渋偲偝偣傞丅偦偺拞偱偼丄変偑崙偵懳偡傞奜晹偐傜偺晲椡峌寕傗戝婯柾側帺慠嵭奞側偳偑婲偒偨帪偵庱憡偑嬞媫帠懺傪愰尵偡傟偽丄朄棩偲摨偠岠椡傪帩偮惌椷傪撪妕偑掕傔偨傝丄嵿惌忋昁梫側巟弌傪庱憡偑寛掕偟偨傝丄抧曽帺帯懱偺挿偵懳偟偰昁梫側巜帵傪弌偟偨傝偡傞偙偲偑偱偒丄崙柉偼崙傗岞偺婡娭偺巜帵偵廬傢側偗傟偽側傜側偄偲偟偰偄傞丅偙傟偼1938擭偵惂掕偝傟偨乽崙壠憤摦堳朄乿偺傛偆側傕偺偱丄偡偙傇傞婋尟偩丅
帺柉搣偺寷朄夵惓憪埬偱庡梫側憟揰偲側偭偰偄傞晹暘傪尒偰偄偔偲丄摨搣偺儁乕僗偱夵寷媍榑偑恑傓偺偼嬌傔偰儕僗僋偑崅偄丅
偨偩偟丄偦偺堦曽偱栰搣丒岇寷攈偺夵寷慡柺斲掕傕丄偡偱偵帪戙抶傟偩丅妋偐偵戞9忦偑壥偨偟偰偒偨楌巎揑栶妱偼偲偰傕戝偒偔丄偦偺寢壥偲偟偰擔杮偑愴屻70擭娫偱旕忢偵椙偄崙偵側偭偨偺偼暣傟傕側偄帠幚偱偁傞丅偩偑丄崱傗崙嵺忣惃偼崿柪丒崿棎傪怺傔丄擔杮偼恖丒儌僲丒僇僱丒媄弍丒僲僂僴僂丒宱尡側偳條乆側柺偱悽奅偵峷專弌棃傞忬嫷偵側偭偰偄傞丅
偙偺怴偟偄帪戙偺拞偱帺暘偨偪偺崱屻悢廫擭傪婯掕偟偰偄偔寷朄傪偮偔傞偲偄偆嶌嬈偼愨懳偵昁梫偱偁傝丄扨偵尰峴寷朄傪乽晄杹偺戝揟乿偲偟偰悞傔曭傞偩偗偱壗傕怴偟偄傾僀僨傾傗懳埬傪弌偝側偄岇寷攈偼丄抦揑懹枬偺旑(偦偟傝)傪柶傟傞偙偲偑偱偒側偄丅丂 |
仭怴偨側崟揷僶僘乕僇偱惃偄晅偔墌庛婥攈罃{g儔儞僾夛択屻傕堦憌偵
奜崙堊懼巗応偺墌庛婥攈偑堦抜偲惃偄晅偄偰偄傞丅僪僫儖僪丒僩儔儞僾師婜暷戝摑椞偺宱嵪惌嶔傪愭庢傝偟偨暷崙偺嬥棙忋徃偑懕偔拞丄擔杮嬧峴偺崟揷搶旻憤嵸偑棙夞傝巜掕偺怴宆偺崙嵚峸擖偵摦偔側偳丄墌埨梫場偵側傝摼傞擔暷嬥棙嵎偺奼戝娤應偑堦抜偲嫮傑偭偰偄傞偐傜偩丅
暷10擭暔崙嵚棙夞傝偼18擔偵堦帪2.36亾偲擭弶棃偺崅悈弨傪晅偗丄暷戝摑椞慖偺寢壥偑敾柧偡傞捈慜偺悈弨傪50儀乕僔僗億僀儞僩(倐倫丄1倐倫亖0.01亾)忋夞偭偨丅摨擭尷偺擔杮崙嵚棙夞傝傕2寧埲棃偺崅悈弨偲側傞0.04亾傪晅偗偨偑丄嬥棙偺忋偘暆偼暷嵚偵斾傋5暘偺1掱搙偲彫偝偄丅僩儔儞僾巵偲埨攞怶嶰庱憡偑夛択屻偵桭岲娭學偺峔抸傊偺堄梸傪嫟偵帵偟偨摨擔偺擔暷10擭嵚偺棙夞傝奿嵎偼5擭埲忋傇傝偺悈弨偵傑偱奼戝偟偰偄傞丅
偙偺擔偺墌偺懳僪儖憡応偼堦帪1僪儖亖111墌12慘偲慜廡偵堷偒懕偒5寧31擔埲棃偺墌埨抣傪峏怴丅僩儔儞僾巵偑岞栺偟偨戝宆尭惻傗僀儞僼儔搳帒側偳偑暷崙偺宱嵪惉挿偲僀儞僼儗傪壛懍偝偣丄暷棙忋偘偑恑傓偲偺尒曽傪攚宨偵偟偨墌攧傝丒僪儖攦偄埑椡偼崻嫮偔巆偭偰偄傞丅儌儖僈儞丒僗僞儞儗乕偼丄墌偑乽偐側傝乿壓偘傞偲梊憐丅僶儞僋丒僆僽丒傾儊儕僇(俛倧倖俙)偼丄棃擭偼120墌掱搙傑偱墌埨丒僪儖崅偑恑傓壜擻惈偑偁傞偲撉傓丅
儊儕儖儕儞僠擔杮徹寯偺嶳揷廋曘僠乕僼俥倃乛姅幃僗僩儔僥僕僗僩偼乽僩儔儞僾巵偺摉慖偵敽偆暷嬥棙偺忋徃偵掁傜傟偰偄側偄偺偼擔杮偩偗偩丅崟揷憤嵸偑巜偟抣僆儁偺敪摦偱嬥棙偺梷惂傪懕偗傞偲堄巚昞帵偟偨偺偱丄暷10擭嵚棙夞傝偑偝傜偵忋徃偟偰傕崙撪嬥棙偑偳傫偳傫忋偑偭偰偄偔偲偼峫偊偵偔偄乿偲巜揈丅乽擔杮偱偼捛壛娚榓偟側偔偰傕丄嬥梈娚榓偺搙崌偄偑帺摦揑偵嫮傑偭偰偄偔乿偲傒偰偄傞丅
墌埨丒姅崅傪攚宨偲偟偨捛壛娚榓娤應偺屻戅傪庴偗丄擔杮偺拞婜嵚棙夞傝偑儅僀僫僗暆傪媫懍偵弅彫偟偨擔偺梻17擔丅擔嬧偼2擭嵚傪儅僀僫僗0.09亾丄5擭嵚傪儅僀僫僗0.04亾偱攦偄擖傟傞巜偟抣僆儁傪弶傔偰幚巤偟偨丅幚惃傛傝崅偄棙夞傝(埨偄壙奿)偲偄偆忦審偩偭偨偨傔丄嬥梈婡娭偐傜偺墳嶥妟偼僛儘墌偩偭偨偑丄巗応偼擔嬧偐傜偺偗傫惂媴偩偲庴偗巭傔偨丅
擔嬧偼9寧偵嬥梈娚榓嶔偺榞慻傒傪曄峏丅擔嬧摉嵗梐嬥偺堦晹偵儅僀僫僗0.1亾偺晅棙傪壽偡偺偵壛偊丄10擭嵚棙夞傝偑僛儘亾掱搙偱悇堏偡傞傛偆丄崙嵚傪峸擖偡傞乽挿抁嬥棙憖嶌乿傪拞怱偵悩偊偰偄傞丅崟揷憤嵸偼18擔偺廜堾嵿柋嬥梈埾堳夛偱丄拞婜僝乕儞偺嬥棙忋徃偑乽偐側傝媫僺僢僠乿偱揔愗偱側偐偭偨偲愢柧偟丄崱屻傕乽応崌偵傛偭偰偼偄偔傜偱傕柍惂尷偵攦偄憹偡乿偲岅偭偨丅
儌儖僈儞丒僗僞儞儗乕偺僠乕僼僌儘乕僶儖捠壿僗僩儔僥僕僗僩丄僴儞僗丒儗僨僇乕巵(儘儞僪儞嵼嬑)偼僀儞僞價儏乕偱丄擔嬧偼僀乕儖僪僇乕僽(棙夞傝嬋慄)傪朷傑偟偄悈弨偵桿摫偡傞偨傔偵乽旕忢偵尗柧偵懳張偟偰偄傞乿偲巜揈丅墌埨丒僪儖崅偑乽偐側傝偺惃偄偱恑傓偩傠偆乿偲偺尒捠偟傪帵偟偨丅
仭惗曐偼崙撪夞婣偣偢
惗柦曐尟嫤夛偺崻娸廐抝夛挿(柧帯埨揷惗柦曐尟幮挿)偼18擔偺婰幰夛尒偱丄擔嬧偑10擭嵚棙夞傝偺忋徃傪0.10亾掱搙傑偱偼梕擣偡傞偲巚偭偰偄偨偺偱丄尰嵼偺悈弨偱巜偟抣僆儁傪敪摦偟偨偺偼堄奜偩偲敪尵丅崙撪嬥棙偼廬棃偺墌嵚搳帒寁夋傪廋惓偡傞悈弨偱偼側偄偲偺擣幆傪帵偟偨丅偐傫傐惗柦曐尟傗擔杮惗柦曐尟側偳庡梫惗曐偼崱擭搙壓婜丄挻掅嬥棙偑懕偔崙撪嵚寯偺曐桳巆崅傪尭傜偡曽恓傪帵偟偰偄傞丅
僗僞儞僟乕僪丒儔僀僼丒僀儞儀僗僩儊儞僣偱僔僯傾擔杮傾僫儕僗僩傪柋傔傞僑價儞僟丒僼傿儞巵(崄峘嵼嬑)偼丄崱夞偺墌埨傪傕偨傜偟偨擔暷嬥棙嵎偺奼戝偼乽擔嬧偺僀乕儖僪僇乕僽丒僐儞僩儘乕儖偵傛偭偰妋幚惈偑崅傑偭偨乿偲暘愅丅乽崱屻偺徟揰偼柧傜偐偵丄擔嬧偑尰嵼偺悈弨偵摜傒偲偳傑傞偐斲偐偩乿偲傒偰偄傞丅
俰俹儌儖僈儞丒傾僙僢僩丒儅僱僕儊儞僩偺捤扟尩帯嵚寯塣梡晹挿偼乽擔嬧偑巆懚10擭掱搙傑偱偺棙夞傝傪帺傜偑朷傓悈弨偵梷偊偨偄偲偄偆巔惃偑巜偟抣僆儁偺敪摦偱慛柧偵側偭偨乿偲巜揈丅乽摉柺偼暷嬥棙偑偝傜偵忋偑偭偰墌埨丒姅崅偵側偭偰傕丄崙撪嬥棙偺忋徃偼尷傜傟傞乿偲撉傓丅暷10擭嵚棙夞傝偵偮偄偰偼摉柺2.5亾掱搙傑偱忋徃偡傞偑丄擔杮偼0.07亅0.08亾巭傑傝偱丄墌埨丒僪儖崅偑112亅113墌傑偱恑傓偲梊憐偡傞丅
僩儔儞僾巵偺惌嶔婜懸偱丄摨崙偺梊憐僀儞僼儗棪偼14擔偵嶐擭4寧埲崀偱弶傔偰2亾戜偵敆偭偨丅擔杮偺摨巜昗傕忋徃偟偰偄傞偑丄僩儔儞僾巵摉慖屻偺忋偘暆偼暷崙偺敿暘掱搙偵偲偳傑偭偰偄傞丅
憗愳塸抝尦擔嬧棟帠偼愭廡偺僀儞僞價儏乕偱丄僩儔儞僾巵偺摉慖傪庴偗偨暷嵿惌愒帤偺奼戝傗僀儞僼儗埑椡偺崅傑傝丄挿婜嬥棙偺忋徃偲僪儖崅丄曐岇庡媊偺嫮傑傝偲偄偆棳傟偼丄傑偢曄傢傝傛偆偑側偄偲巜揈丅擔嬧偼嫲傟偰偄偨墌崅偑墦偺偔偨傔丄乽壗傕偟側偄偱偙偺傑傑偛傠怮傪偟偰偄傟偽傛偄乿偲弎傋偨丅丂
丂 |
| 仭堦曕慜恑丄擇曕屻戅 / 媡恑偡傞悽奅偺柉庡庡媊偲偦偺尨場 |
   丂
丂
|
傾儊儕僇偺崙嵺栤戣愱栧帍亀僼僅乕儕儞丒億儕僔乕亁3/4寧崋偑丄椻愴屻奼戝偟偰偒偨僌儘乕僶儖側柉庡庡媊偑崱傗屻戅婜偵偼偄偭偰偄傞偲偄偆丄昞婰偺榑暥傪宖嵹偟偰偄傞丅偦偺尨場偼丄柉庡庡媊偺庡懱偲偟偰昡壙偝傟偰偒偨拞嶻奒媺偺庛懱壔偲柍婥椡偵偁傞偲偄偆丅昅幰偺僕儑僔儏傾丒僇乕儔儞僠僢僋偼崙嵺栤戣昡媍夛搶撿傾僕傾尋媶堳偱丄嬤挊偵亀屻戅偡傞柉庡庡媊丗拞嶻奒媺偺斀棎偲戙媍惂摑帯偺悽奅揑側悐戅亁偑偁傞丅
仭柉庡庡媊偺慜恑偑僺乕僋傾僂僩丄屻戅嬊柺偵丂乗丂2005擭埲崀
夁嫀2擭娫丄傾儔僽悽奅丄傾僼儕僇丄傾僕傾偵偍偄偰偙傟傑偱梊憐偝傟側偐偭偨媫寖側曄壔偵悽奅偺娭怱偑庝偒偮偗傜傟偰偒偨丅
價儖儅偱偼丄偨偭偨6擭慜傑偱棎朶側孯晹偑墿怓側憁堖傪揨偭偨憁椀傪奨摢偱幩嶦偟偨偑丄夁嫀2擭娫偵柉庡庡媊揑側柉惌傊偲惓幃偐偮杮暔偲尒偊傞堏峴偑恑傫偱偄傞丅
僠儏僯僕傾丄僄僕僾僩丄儕價傾偱偼挿婜偺愱惂惌尃偑恖柉妚柦偵傛偭偰懪搢偝傟偨偑丄偙傟傜偺崙偺巗柉偼柉庡庡媊偺棊偲偟寠傪幚姶偟偮偮偁傞傛偆偵尒偊傞丅亀僯儏乕儓乕僋丒僞僀儉僗亁偼丄傾儔僽偺恖柉偑乽変偑崙偑巟偊偰偒偨朶椡揑偱愱墶側惌尃偵懳偟偰帺傜偺夞摎傪帩偭偰棫偪忋偑偭偨乿偲彂偄偨丅
屩戝側愰揱傪怣偠偰偼側傜側偄丅尰幚偵偼柉庡庡媊偑屻戅偟偰偄傞丅傾僼儕僇偲傾儔僽悽奅偺堦晹偺崙偼夁嫀2擭娫偵傢偢偐偵夝曻偝傟偨偑丄偐偮偰惌尃岎戙偺柾斖偲偝傟偰偒偨懠偺崙偱偼丄棊抇偡傋偒柉庡庡媊偺儊儖僩僟僂儞偑嫟捠偟偰傒傜傟傞丅乽僼儕乕僟儉丒僴僂僗乿(昡幰拲丗巗柉揑帺桼傪昡壙偡傞奿晅偗曬崘傪枅擭敪昞偟偰偄傞崙嵺揑俶俧俷)偼丄偙偙7擭娫偵傢偨偭偰宲懕揑偵掅壓偟偰偒偨悽奅偵偍偗傞帺桼偑丄2012擭偵偼崱悽婭嵟掅偵懧偪偨偲偟偰偄傞丅
傑偡傑偡懡偔偺崙偱丄億僺儏儕僗僩(戝廜寎崌)揑嬌塃攔奜庡媊揑偱丄柉庡庡媊傪傎偲傫偳懜廳偟側偄惌搣偑恖婥傪攷偡傞傛偆偵側偭偰偄傞丅惌尃偵斸敾揑妶摦壠傪抏埑偟傛偆偲偡傞惌晎傕憹壛偟偨丅
乽傾儔僽偺弔乿偼丄堟撪偱僔儕傾偺僶僔儍乗儖丒傾儖丒傾僒僪傗僶乕儗僀儞傪巟攝偡傞傾儖丒僇儕僼傽堦壠傪捛偄媗傔偨偑丄斀柺偱悽奅拞偺愱惂揑惌尃偵嫮峝楬慄傪柉廜偵懳偟偰偲傜偣傞偙偲偵側偭偨丅
拞崙偼峈媍傪堄枴偡傞娫愙揑側昞尰傑偱傕専墈嶍彍偺懳徾偲偝偣偰偄傞偟丄儘僔傾偱偼怴偟偄崙壠斀媡嵾偑惂掕偝傟丄恖尃俶俧俷偑抏埑偝傟偨丅傾儔僽偺弔埲崀丄曄妚傪媮傔傞戝廜塣摦偵懱惂懁偑晀姶偵側傝丄岻柇偱尩偟偄梷埑嶔傪嵦傞傛偆偵側偭偰偄傞丅丂
傕偪傠傫丄偦偺愑傔傪傾儔僽偺弔偵晧傢偣傞傢偗偵偼備偐側偄丅柉庡庡媊偺悽奅揑側慜恑偺僺乕僋偼2000擭戙偺偼偠傔偵廔傢偭偰偄傞丅僌儘乕僶儖側柉庡庡媊傪曪妵揑偵挷嵏偟偰偄傞乽儀僥儖僗儅儞嵿抍乿偺曄壔巜昗偵傛傞偲丄乽奐敪搑忋崙偵偍偄偰慡斒揑偵柉庡庡媊偺幙偑掅壓偟偨乿偦傟偵傛傟偽丄偲偰傕杮暔偺柉庡庡媊崙偲偼巚傢傟側偄傎偳惂搙丄慖嫇丄惌帯暥壔偑楎壔偟偨崙偑52偵忋偭偨丅
仭孯晹偑尃椡偺拞悤傪埇傞崙偑嬤擭嵞傃憹壛孹岦
儘儞僪儞偺亀僄僐僲儈僗僩亁帍挷嵏晹偺戝偑偐傝側挷嵏偵傛傞偲丄2011擭偵挷嵏偟偰167儠崙拞丄48儠崙偱柉庡庡媊偑楎壔偟偨丅偦偺曬崘偼丄乽夁嫀5擭娫丄僌儘乕僶儖側巟攝揑僷僞乕儞偼屻戅偱偁傞乿偲弎傋偰偄傞丅
偙傟傜偑巜偟偰偄傞偺偼丄埆柤崅偄僂僈儞僟傗僷僉僗僞儞偩偗偱偼側偄丅斀懳攈偺惡偵婡夛偑扗傢傟丄朄偵傛傞摑帯偑寚偗丄戙媍惂偺婡擻偟側偄惌帯婡峔傪帩偮崙乆傪愱惂惌帯偲偁傑傝憡堘偺側偄乽嬌傔偰晄姰慡側柉庡庡媊乿偲曄壔巜昗偼暘椶偟偰偄傞丅
怴偟偄柉庡庡媊偺儌僨儖偲偟偰偟偽偟偽嫇偘傜傟偰偒偨崙偱偝偊傕丄夁嫀10擭娫偵媡恑偟偰偄傞丅僠僃僐丄僴儞僈儕傾丄億乕儔儞僪丄僗儘儀僯傾偼丄2004擭偵俤倀偵壛柨偟偨摉帪丄惉岟暔岅偲帩偰殥偝傟偨丅偟偐偟側偑傜丄俤倀壛柨屻10擭偵偟偰丄偦偺婸偒偑撥偭偰偟傑偭偨丅摿偵僴儞僈儕傾偼丄嫟嶻搣巟攝壓偲偁傑傝曄傢傜側偄傎偳丄曬摴偺帺桼偑戝暆偵屻戅偟偨丅
儓乕儘僢僷偺柉庡庡媊偑梙傜偄偱偄傞堦曽丄媽宆偺僋乕僨僞偑奺戝棨偱暅妶偟偰偒偨丅傾僼儕僇丄傾僕傾丄儔僥儞傾儊儕僇偵偍偄偰丄1990擭戙偵偼孯帠僋乕僨僞偑婬偵側偭偰偄偨丅偟偐偟丄2006擭偐傜2012擭偺娫偵僶儞僌儔僨僔儏丄僼傿僕乕丄僊僯傾丄僊僯傾乗價僜僂丄儂儞僕儏儔僗丄儂儞僕儏儔僗丄儅僟僈僗僇儖丄儅儕丄僯僕僃乕儖丄僞僀側偳偱孯晹偑尃椡傪埇偭偨丅僄僋傾僪儖丄儊僉僔僐丄僷僉僗僞儞側偳偺崙偱偼丄孯晹偼傓偒弌偟偺僋乕僨僞偙偦杁傝偼偟側偐偭偨傕偺偺丄惌帯偺拞怱揑棫栶幰偲偟偰尃椡傪夞暅偟偨丅
拞嬤搶偵偍偄偰傕慡斒揑偵偙偺孹岦偑傒傜傟傞丅傾儔僽柉廜偺朓婲偑孯晹偺椡傪庛懱壔偝偣丄戝婯柾側晄埨傪庝婲偟丄拞嶻奒媺儕儀儔儖偺崙奜扙弌傪彽偒丄僗儔儉庡媊幰偺戜摢傪懀偟偨丅僀僄儊儞偐傜僄僕僾僩偵帄傞彅崙偱峈媍塣摦偼桬姼偵巜摫憌偵挧愴偟偨偑丄巟攝幰偑巆傞偙偲偑偱偒偨偐偳偆偐偼孯晹偺巟帩偵傛偭偰寛傑偭偨丅
仭柉庡庡媊庛懱壔偺棟桼偼側偵偐 / 拞嶻奒媺偺惌帯揑曄幙偲柍婥椡
偳偆偟偰帠懺偑埆壔偟偨偺偐丅拞嶻奒媺偲偄偆丄堄奜側斊恖傪柤巜偟偡傞偙偲偐傜巒傔偨偄丅僒儉僄儖丒僴儞僠儞僌僩儞偺嬤戙壔榑偲偼媡偵丄僙僀儌傾丒儕僾僙僢僩傗傎偲傫偳偺惣墷偺悽奅揑儕乕僟乕偨偪偼丄奐敪搑忋崙偵偍偗傞拞嶻奒媺偺惉挿偑柉庡壔偺僽乕儉傪惗傓偲挿擭偵傢偨偭偰庡挘偟偰偒偨丅偲偙傠偑丄偦偆偼嶌梡偟側偐偭偨丅
棟榑揑偵偼丄拞嶻奒媺偑奼戝偡傞偵偮傟偰丄嫵堢悈弨偑偁偑傝丄宱嵪揑幮夛揑惌帯揑柉庡庡媊奼廩偺梫媮偑崅傑傞偼偢偱偁偭偨丅傂偲偨傃堦恖摉偨傝強摼偑拞娫揑強摼悈弨偵払偟偨崙偼丄愱惂揑惌帯偵屻栠傝偡傞偼偢偱偼側偐偭偨丅
乽(柉庡壔偝傟偨)傎偲傫偳偺崙偱丄柉庡壔偺傕偭偲傕愊嬌揑側巟帩幰偼拞嶻奒媺偱偁偭偨乿僴儞僠儞僌僩儞偼彂偄偨丅儘僔傾偺僄僐僲儈僗僩丄僙儖僎僀丒僌儕僄僼偼乽儘僔傾偺拞嶻奒媺偼旕忢偵傛偔嫵堢傪庴偗丄惗妶偺幙傪嫕庴偟傛偆偲堄梸揑側偺偱乿僾乕僠儞偺擡傃婑傞愱惂庡媊偱偼側偔乽晠攕偺嶍尭偲嶲壛婡夛偺奼戝傪梫媮偡傞偩傠偆乿偲崱擭2寧偵弎傋偰偄傞丅
偟偐偟丄斵傜偺塢偆捠傝偵側偭偰偄側偄丅拞嶻奒媺偑僌儘乕僶儖偵尒偰奼戝偟偰偄傞偺偼帠幚偱偁傞丅拞嶻奒媺偼丄悽奅嬧峴偺悇嶼偵傛傞偲丄1990擭偐傜2005擭偺娫偵傾僕傾偺奐敪搑忋彅崙偱3攞偵側傝丄傾僼儕僇奐敪嬧峴偵傛傞偲丄傾僼儕僇偱偼夁嫀10擭娫偵3暘偺1埲忋憹壛偟偨丅崱擔丄悽奅拞偱栺7000枩恖偑枅擭拞嶻奒媺擖傝偟偰偄傞丅
偟偐偟側偑傜丄偙偺僌儘乕僶儖側怴拞嶻奒媺偼丄壗傛傝傕埨掕傪慖戰偟偰偄傞丅傾儖僕僃儕傾偐傜僕儞僶僽僄偵帄傞拞嶻奒媺偼丄戝廜揑柉庡庡媊偵懳偡傞忈暻偲偟偰孯晹傪巟帩偟偰偒偨丅斵傜偼丄昻柉丄廆嫵幰丄柍嫵堢側傕偺傪嫲傟偨丅
夁嫀10擭娫偺奐敪搑忋悽奅偵偍偗傞僋乕僨僞(惉斲傪栤傢偢)傪挷嵏偟丄尰抧偺儊僨傿傾傗悽榑傪暘愅偟偨偲偙傠丄50亾偺働乕僗偱拞嶻奒媺偑帠慜偵僋乕僨僞傪慀傞偐丄帠屻偵慡柺揑偵孯晹傪巟帩偟偰偄偨丅傕偲傕偲拞嶻奒媺偼偙傟傑偱僷僉僗僞儞傗僞僀側偳偱孯晹傪惌帯偐傜攔彍偡傞塣摦偺愭摢偵棫偭偰偒偨偙偲偐傜尒傟偽丄偙傟偼嬃偔傋偒悢帤偱偁傞丅
懡偔偺崙偵偍偄偰丄朶椡揑峴摦偱偼側偔丄慖嫇傛偭偰惌帯巜摫幰傪岎戙偝偣傞柉庡庡媊偺尨棟傪拞嶻奒媺偑寉帇偟偰偄傞丅儃儕價傾丄儀僱僘僄儔丄僼傿儕僺儞側偳偱丄拞嶻奒媺偑慖嫇偱慖偽傟偨巜摫幰傪捛曻偡傞偨傔偵奨摢僨儌傗嵸敾摤憟傪偍偙側偭偰偄傞丅
偙偆偟偨孹岦偼嫮偔側傞偽偐傝偱偁傞丅懡偔偺奐敪搑忋崙偱偺悽榑挷嵏偼丄柉庡庡媊偺幙偑掅壓偟偰偄傞偩偗偱側偔丄柉庡庡媊偵偮偄偰偺堦斒戝廜偺尒曽偑屻戅偟偰偄傞丅垷僒僴儔抧堟偺傾僼儕僇丄拞墰傾僕傾丄媽僜楢偱偙傟偑摿偵挊偟偄丅嵟嬤偺悽榑挷嵏偱偼丄柉庡揑偵崙傪摑帯偡傞偙偲偑旕忢偵廳梫偱偁傞偲摎偊偨儘僔傾恖偼16亾偩偗偱偁偭偨丅
摨條偵丄僐儘儞價傾丄僄僋傾僪儖丄儂儞僕儏儔僗丄僌傾僥儅儔丄僯僇儔僌傾丄僷儔僌傾僀丄儁儖乕偲偄偆拞撿暷彅崙偱丄柉庡庡媊偑懠偺摑帯宍懺傛傝傕岲傑偟偄偲摎偊偨恖偼丄夁敿悢傪傢偢偐偵忋夞傞偐丄彮悢攈偵偡偓側偐偭偨丅
仭嬥梈嵿惌婋婡偱巗応庡媊偑柉庡庡媊傪埑搢
2008擭偺嬥梈婋婡埲屻偺僌儘乕僶儖側宱嵪揑掅柪偑柉庡庡媊偵懳偡傞巗柉偺巟帩傪庛傔偨丅奺崙丄摿偵搶墷偵偍偄偰丄偙偺宱嵪揑崿棎偑拞嶻奒媺偵懪寕傪偁偨偊偨丅2011擭偺墷廈暅嫽奐敪嬧峴曬崘偼丄怴俤倀壛柨10儠崙偡傋偰偵偍偄偰婋婡偑柉庡庡媊偵懳偡傞巟帩傪怺崗偵掅壓偝偣偨偲傒偰偄傞丅乽傛傝帺桼傪嫕庴偟偰偄傞傕偺偑丄婋婡偵傛偭偰懪寕傪栔偭偨帪偵丄柉庡庡媊傛傝傕巗応傪桪愭偟偨乿偲曬崘偼弎傋偰偄傞丅
悽奅偱嵟傕宱嵪揑偵妶婥偑偁傝丄僌儘乕僶儖壔偟偰偄傞抧堟偱偁傞傾僕傾偱偝偊傕丄悽榑偑柉庡庡媊偵晄枮傪帩偭偰偄傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅椺偊偽丄僀儞僪僱僔傾偼丄2000擭戙偵偍偗傞柉庡庡媊偺惉岟暔岅偲尒橍偝傟偰偄傞丅偩偑偟偐偟丄昜偺攦廂傗慖弌偝傟偨媍堳偺晠攕偑栤戣帇偝傟巒傔偰偄傞丅2011擭偺挷嵏偱偼丄夞摎幰偺嬐13亾偺傒偑丄柉庡揑偵慖嫇偝傟偨惌帯壠偑僗僴儖僩帪戙偺巜摫幰傛傝傑偟偩偲弎傋偨偵偡偓側偄丅
柉庡庡媊偑傕偭偲怺偔崻晅偄偰偄傞崙偱偝偊傕丄嬤擭丄惌帯偵偨偄偡傞尪柵偑晜忋偟偰偄傞丅僀儞僪偱偼壗廫枩偺恖乆偑惌帯晠攕偵峈媍僨儌傪峴偄丄僀僗儔僄儖偱偼婎慴揑側宱嵪栤戣傪惌帯壠偑寉帇偟偰偄傞偙偲偵懳偡傞峈媍偺嵗傝崬傒偑僥儖傾價僽偱懕偒丄僼儔儞僗偱偼惌晎偺嬞弅慬抲傪崙柉偑墴偟曉偡側偳丄拞嶻奒媺偼偦偺庡挘傪傑偡傑偡奨摢偱昞柧偡傞傛偆偵側偭偰偄傞丅
幐嬈棪偑50亾傪挻偊偨僗儁僀儞偱偼丄乽搳昜偵峴偔偺偼惌帯偺壎宐傪庴偗偰偒偨椉恊偨偪偩偗乿偲庒幰偑怴暦婰幰偵岅偭偰偄傞丅乽変乆偺悽戙偵偲偭偰搳昜偼柍堄枴乿偩偲丅
僆僶儅偼丄乽悽奅拞偺柉庡庡媊偺悇恑偵彆椡偡傞丄偲偙傟傑偱偺戝摑椞偲摨偠傛偆偵丄戞擇婜偺廇擟墘愢偱弎傋偨丅僆僶儅偺堄恾偡傞偲偙傠偼椙偄偑丄幚嵺偵偼傎偲傫偳弌棃摼傞偙偲偱偼側偄丅奐敪搑忋崙偵偍偗傞柉庡庡媊偺屻戅偼斶偟偄偑丄傾儊儕僇偑惂屼偟偆傞傕偺偱偼側偄丅傾儊儕僇偼傑偢帺崙傪惂屼偟側偗傟偽側傜側偄丅
仭
杮榑暥偑巜揈偟偰偄傞傛偆側丄柉庡庡媊傛傝傕惌帯揑埨掕偲巗応傪桪愭偡傞挭棳偑丄嶲媍堾慖嫇埲崀擔杮偱傕堦抜偲嫮傑傞偙偲偑寽擮偝傟傞丅擔杮偺柉庡庡媊偑崱屻偝傜偵媡棳偡傞偺傪嫋偣偽丄傕偭偲傕庡梫側愭恑嶻嬈崙偺堦偮偑偙偺孹岦傪弶傔偰尠挊偵帵偡偙偲偱丄21悽婭偺楌巎忋丄壭乆偟偄儔儞僪儅乕僋偲側傞偩傠偆丅
20悽婭枛偵僜楢偲偦偺嫟嶻寳偑曵夡偟偨偙偲偱椻愴偑廔傢傝丄僪儈僲揑偵懠偺惌帯撈嵸偑憡師偄偱徚柵偟偨丅撈嵸偺扴偄庤傕偟偔偼屻傠弬偱偁偭偨孯戉偼暫幧偵堷偒忋偘丄柉惌堏娗偑恑傫偩丅搶傾僕傾偵偍偄偰偼娯崙傗戜榩偑丄椻愴廔寢慜傛傝惌帯偺柉庡壔偺愭曏傪偮偗偰偄偨偺偱丄椻愴廔寢偵柉庡庡媊奼戝傪婲場偡傞偺偼抁棈偵偡偓傞丅僜楢偺曵夡偲椻愴偺廔寢偵偡傋偰偺柉庡壔偺崻尮傪傒傞丄僼儔儞僔僗丒僼僋儎儅棳偺扨弮側柉庡庡媊晛曊壔榑偼偝偡偑偵塭偑敄偔側偭偨丅嫟嶻庡媊偑曵夡偟偨偺偱丄柉庡庡媊偵挧愴偡傞惌帯棟榑偑柍偔側傝丄惌帯懱惂偼乽楌巎偺廔傢傝乿偵摓払偟偨偲偄偆傛偆妝娤揑偱丄僲乕揤婥側柉庡壔榑偼巔傪徚偟偨丅
抧媴偺娐嫬丒帒尮丒恖岥側偳偐傜尒偨惂栺傪柍帇側偄偟寉帇偟丄宨婥夞暅偲宱嵪奼戝丄偦偺偨傔偺宱嵪嫞憟椡奼戝傪桪愭偡傞乽傾儀僲儈僋僗乿揑嬤帇娽揑億僺儏儕僘儉偑丄柉庡庡媊偺崻掙傪梙傞偑偡乽惌帯揑夞婣乿偲惛恄揑棦婣傝孹岦偲寢崌偡傞偲偒偵丄嬌傔偰婋尟偐偮柍愑擟側愵摦宆惌帯壠偑搊応偡傞慺抧偑惗傑傟傞丅偙傟偼昁偢偟傕擔杮偩偗偵屌桳側尰徾偱偼側偄丅
僔儏儗僕儞僕儍乕丒僕儏僯傾偑丄偐偮偰杮帍偱徯夘偟偨亀僼僅乕儕儞丒傾僼僃傾乕僘亁偺榑暥偱寈崘偟偰偄偨傛偆偵丄忣曬偺棳捠偲惌帯僾儘僙僗偺僨僕僞儖揑壛懍壔偑恑傓偙偲偑丄懳榖偲偐専徹偲偄偆帪娫偺偐偐傞僾儘僙僗傪昁梫偲偡傞柉庡庡媊偵婋婡傪傕偨傜偡婋尟傪嫮偔幚姶偡傞傛偆偵側偭偨丅専徹偝傟側偄忣曬偑戝検偵儅僗僐儈偲僱僢僩忋偱悅傟棳偝傟丄斸敾揑媍榑偺僾儘僙僗敳偒偵峴傢傟傞乽悽榑挷嵏乿偱惗傑傟偨巚憐揑挭棳偑丄乽悽榑乿傪棳嵒偺傛偆偵晽師戞偲偟偰丄惌帯傪嵍塃偡傞壛懍揑棳摦傪偆傫偱偄傞丅
惌帯揑柉庡庡媊偑幮夛揑柉庡庡媊偲宱嵪揑柉庡庡媊偵傛偭偰曗嫮偝傟偰側偄幮夛偱偼丄柉庡庡媊偼乽傂庛側奜旂乿偵巭傑傝丄愨偊偢惌帯揑晄埨掕偵傛偭偰嫼埿偵偝傜偝傟傞偙偲偵側傞丅丂 |
| 丂 |
   丂
丂
|
|
丂 |
| 丂 |
   丂
丂
|
|
丂 |
| 丂 |
   丂
丂
|
|
丂 |
| 丂 |
   丂
丂
|
|
丂 |






